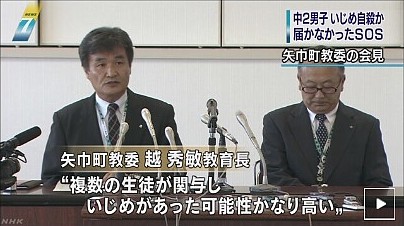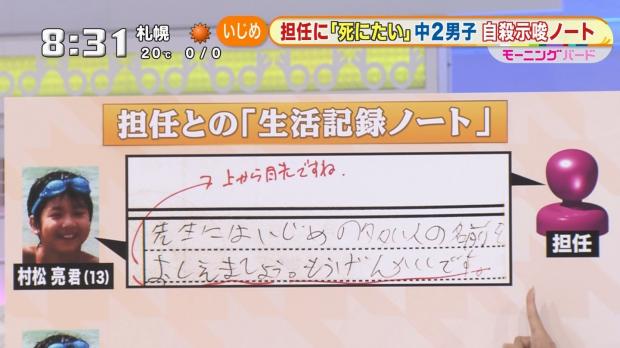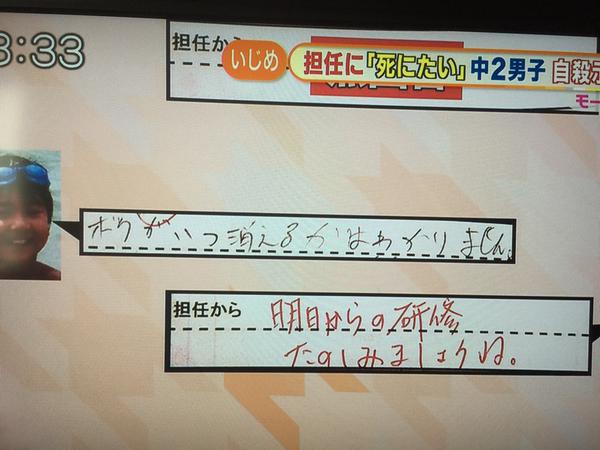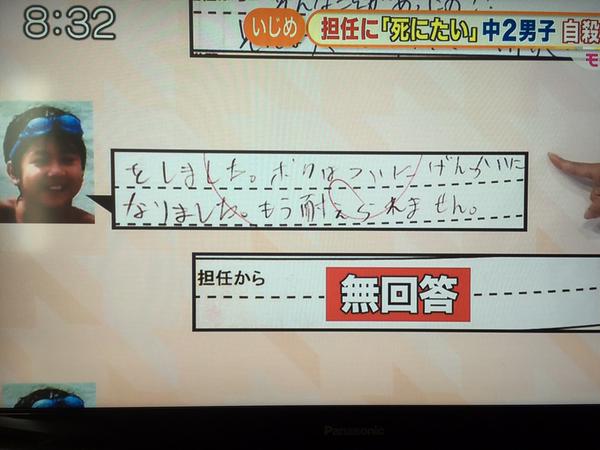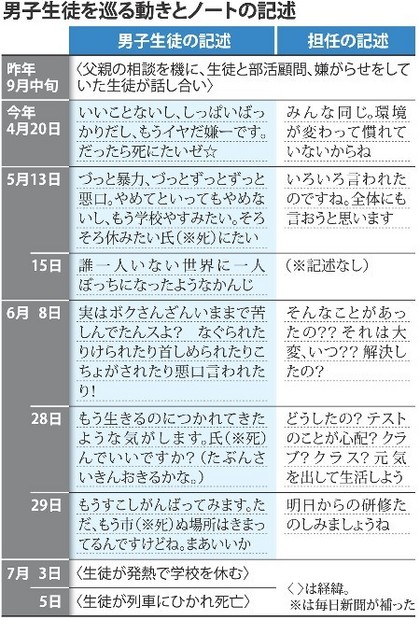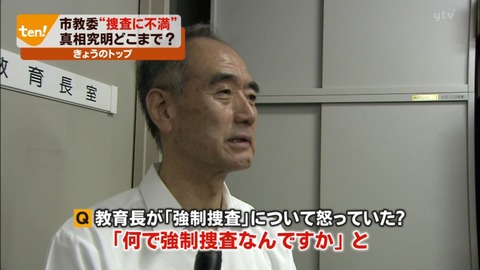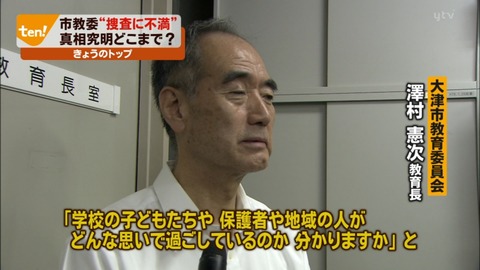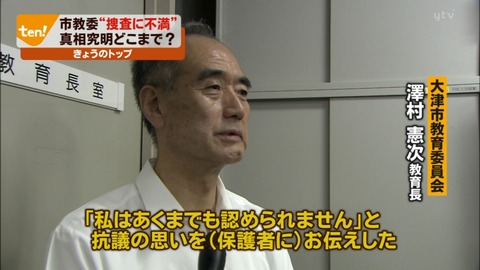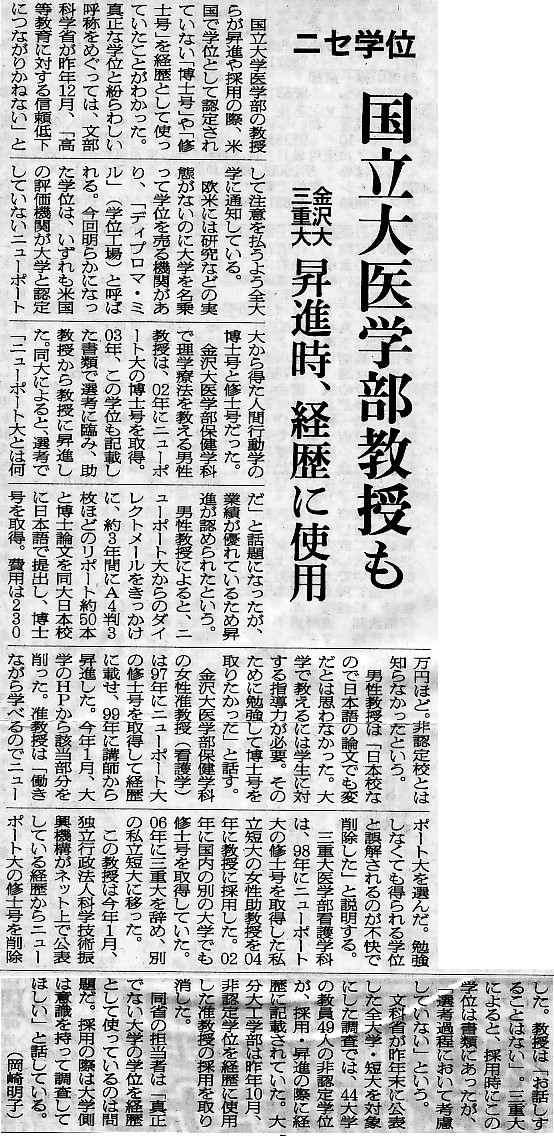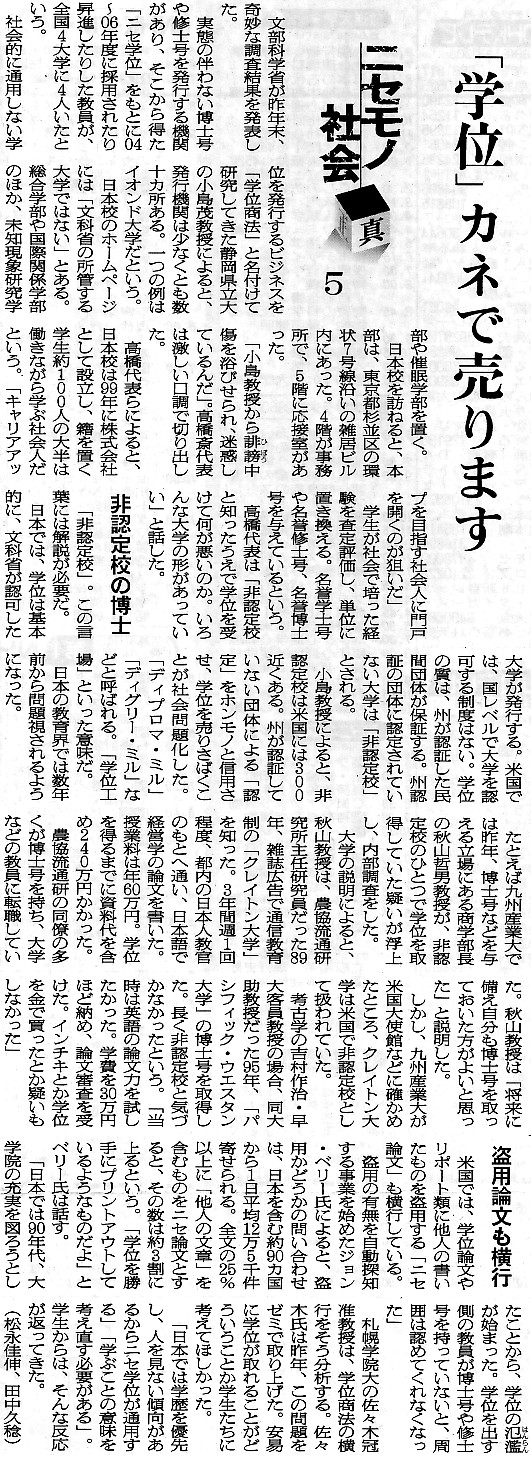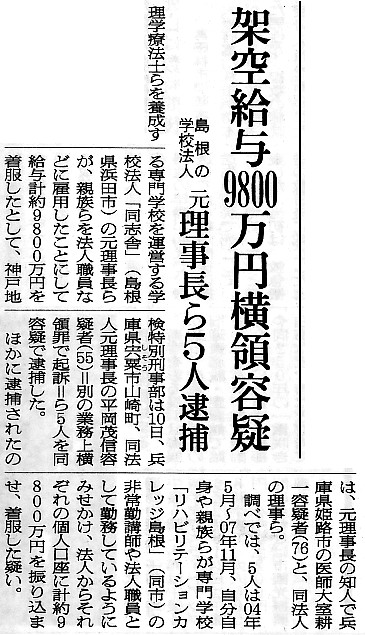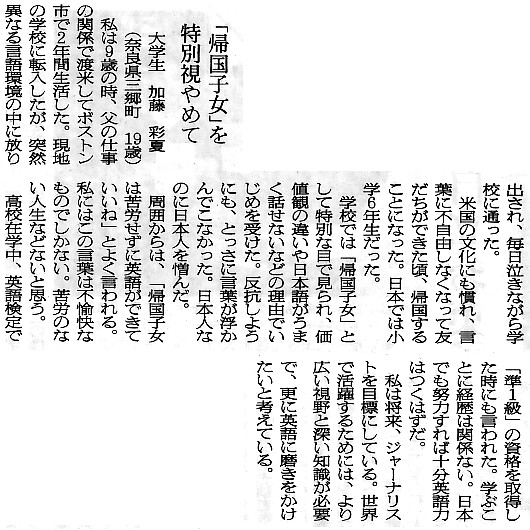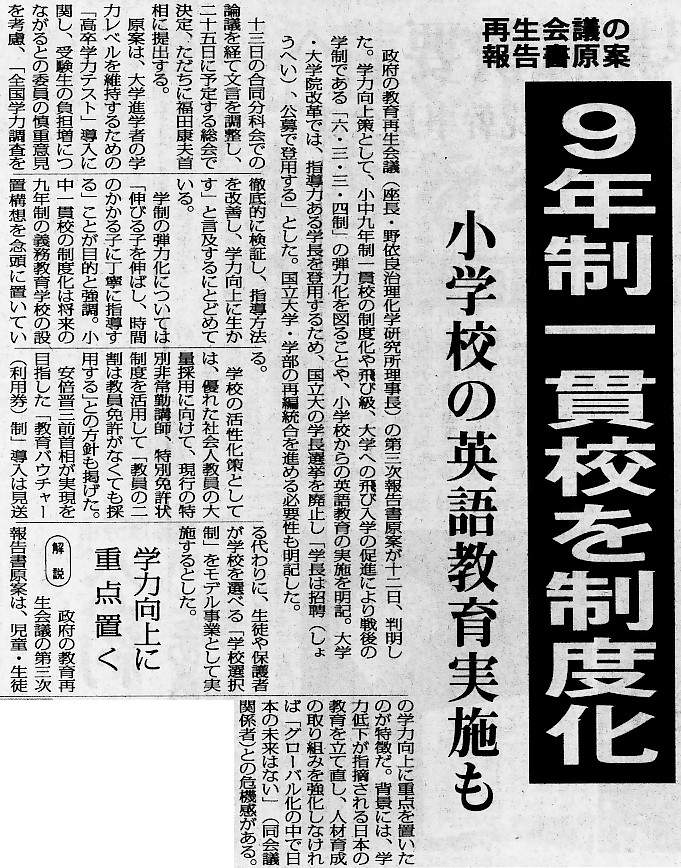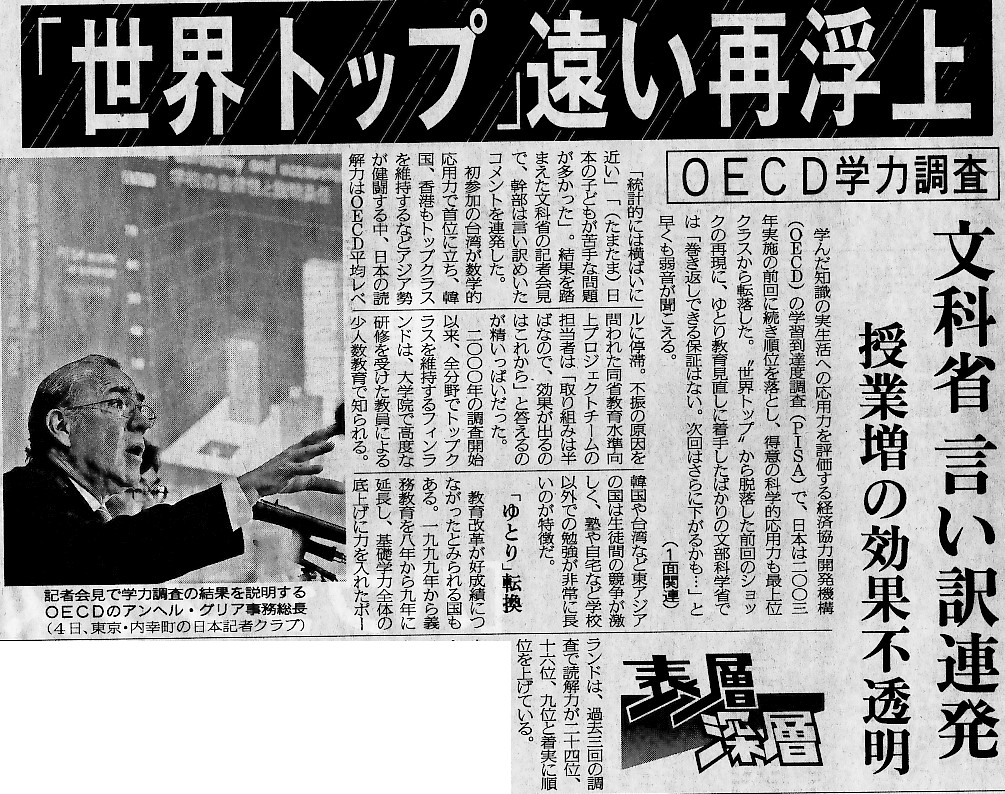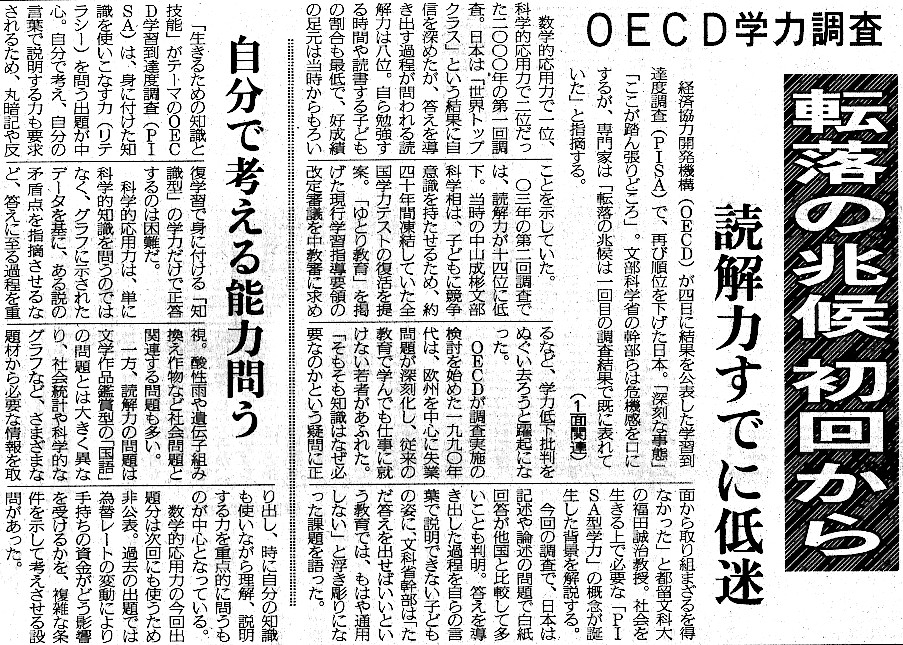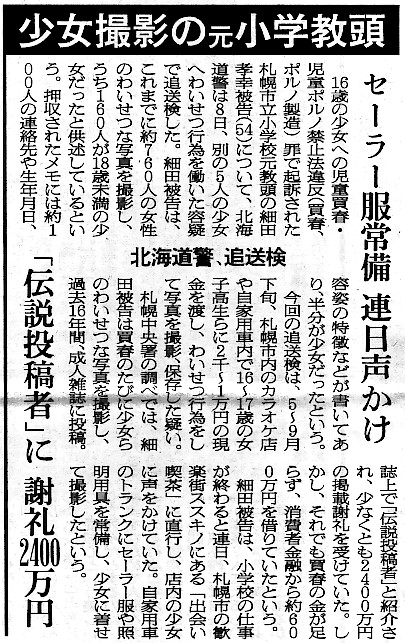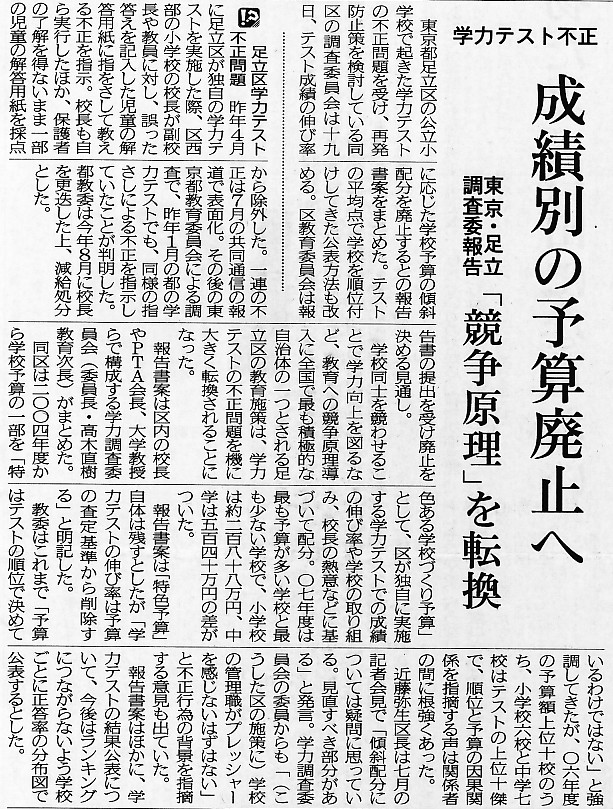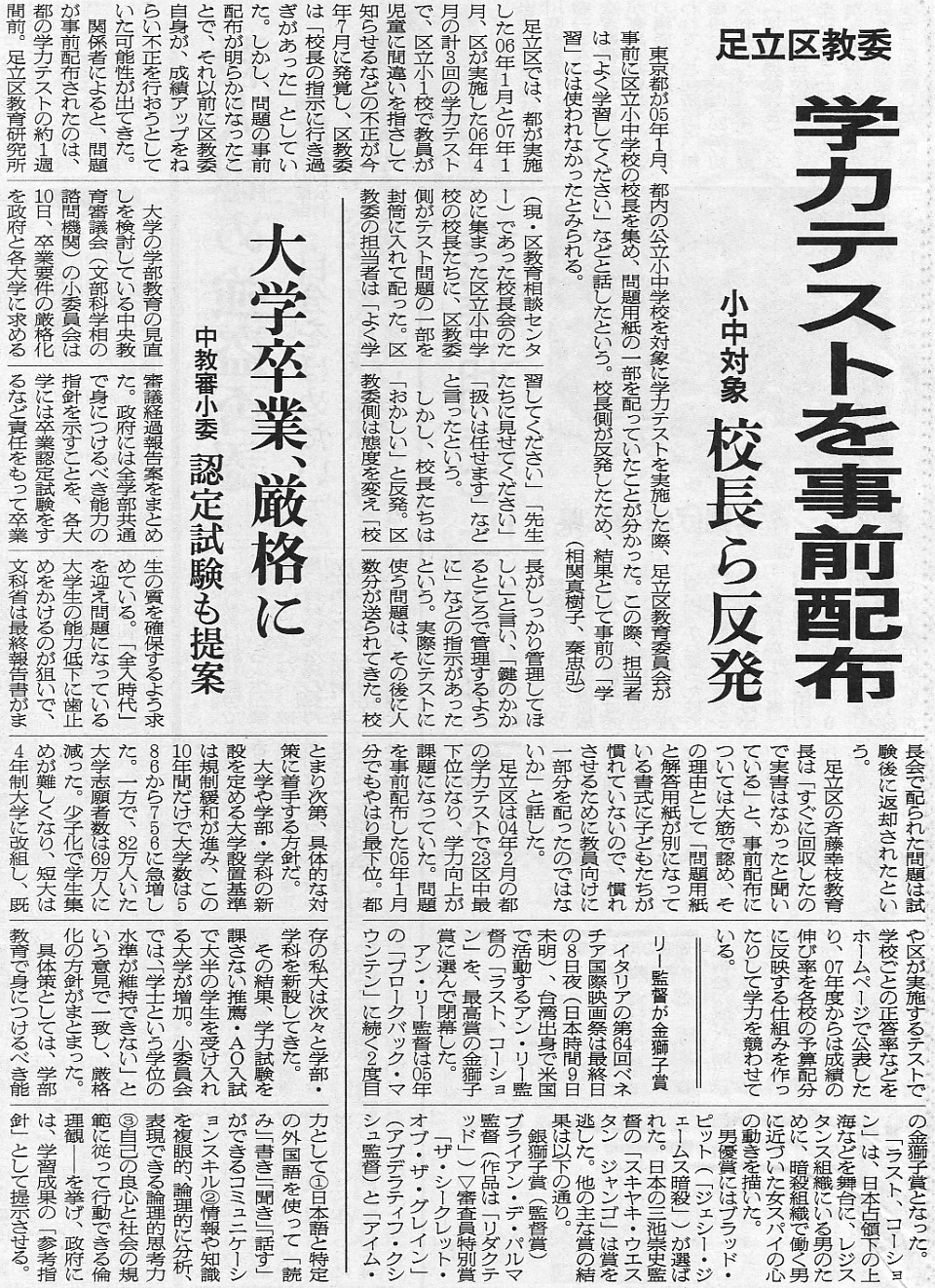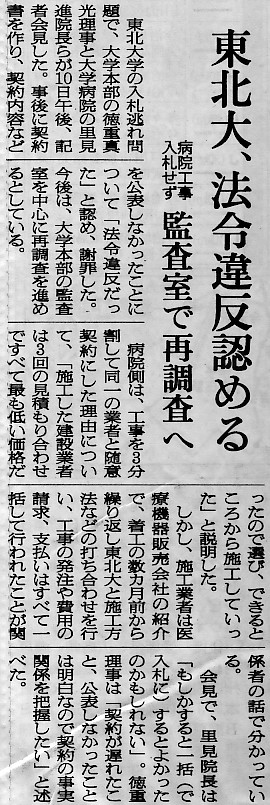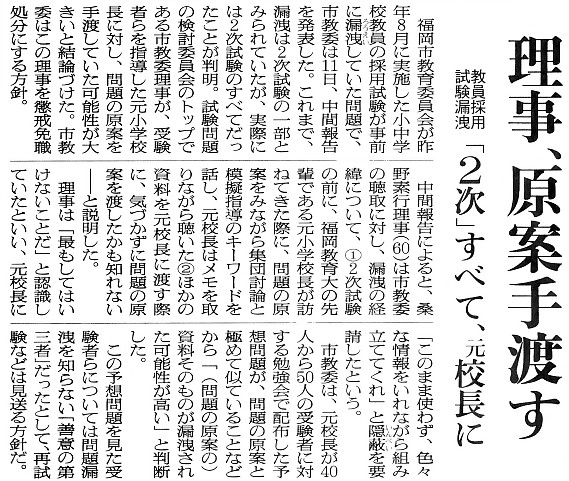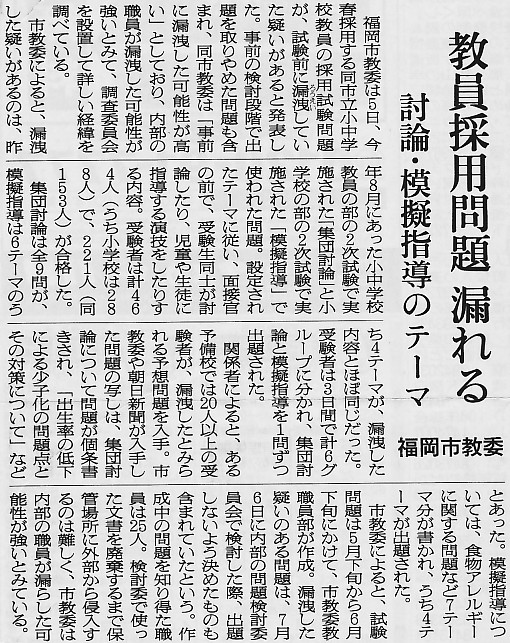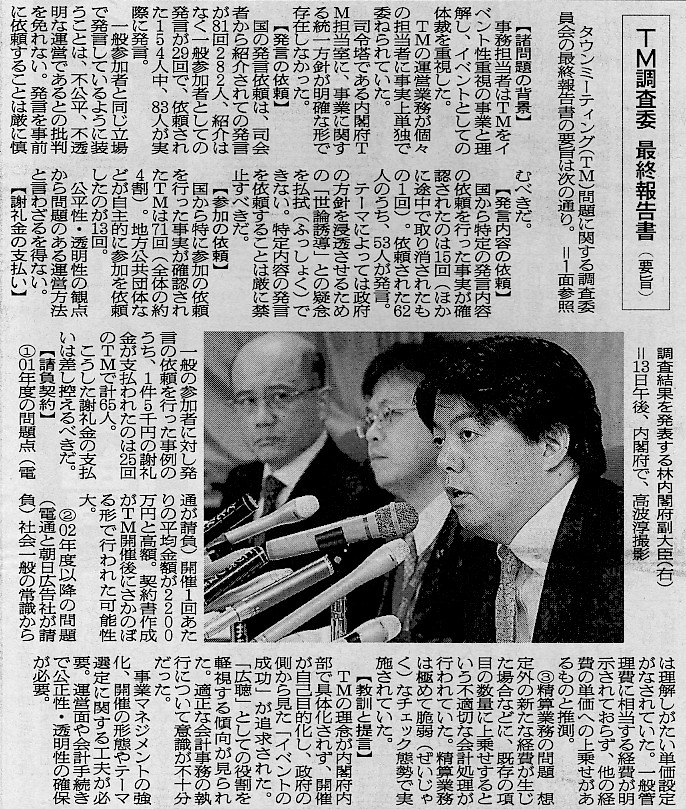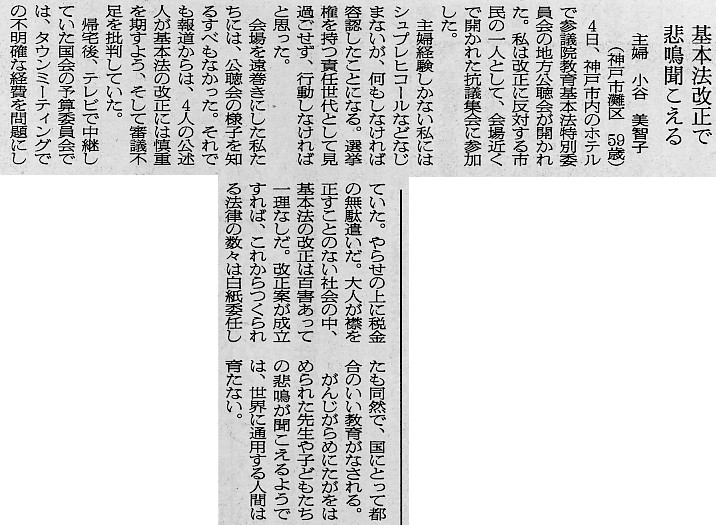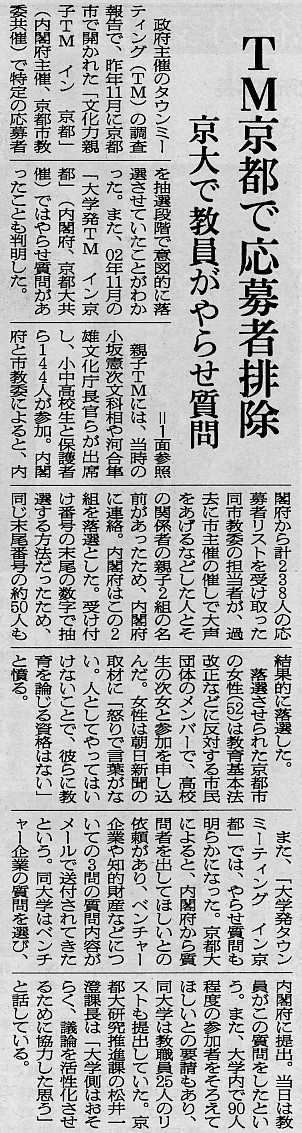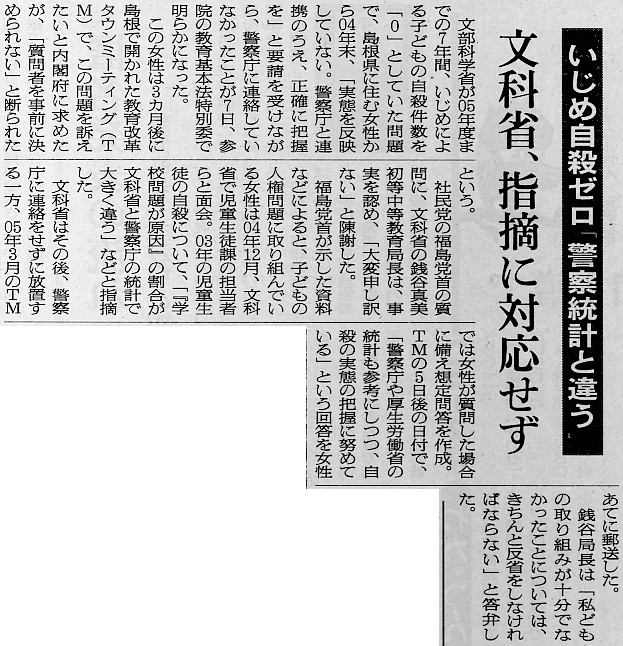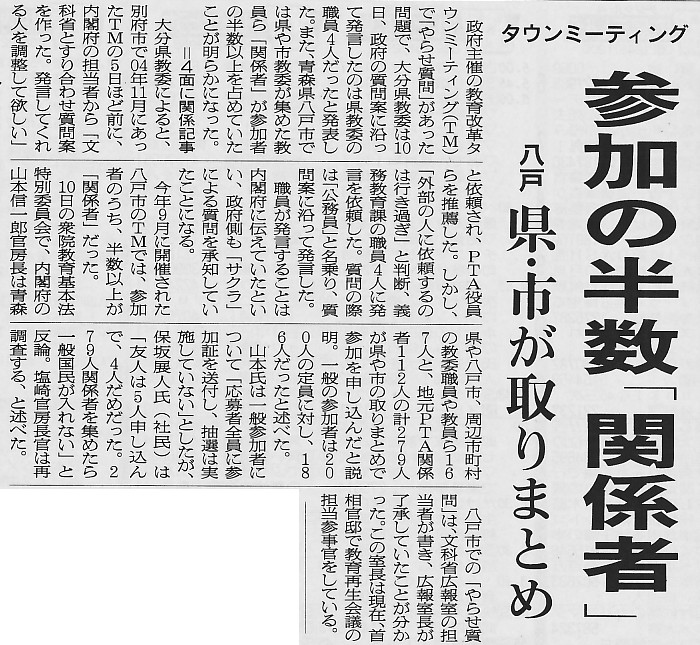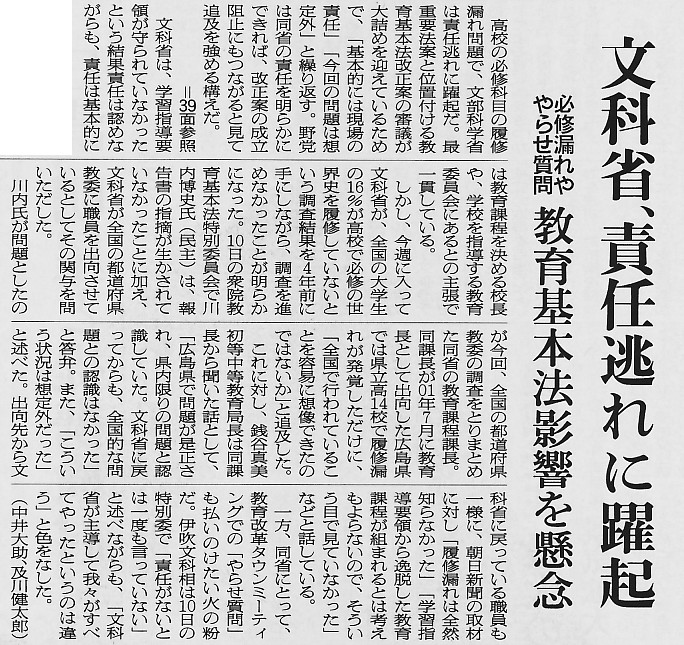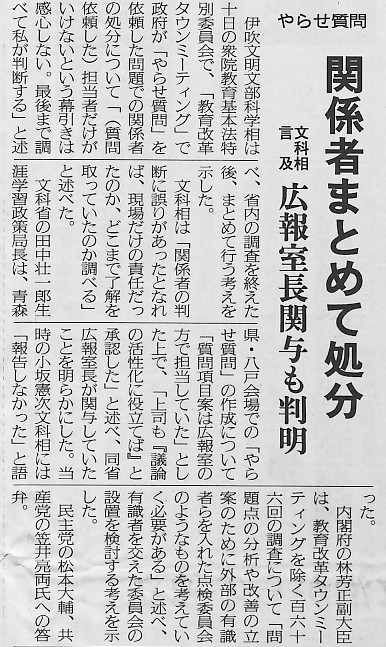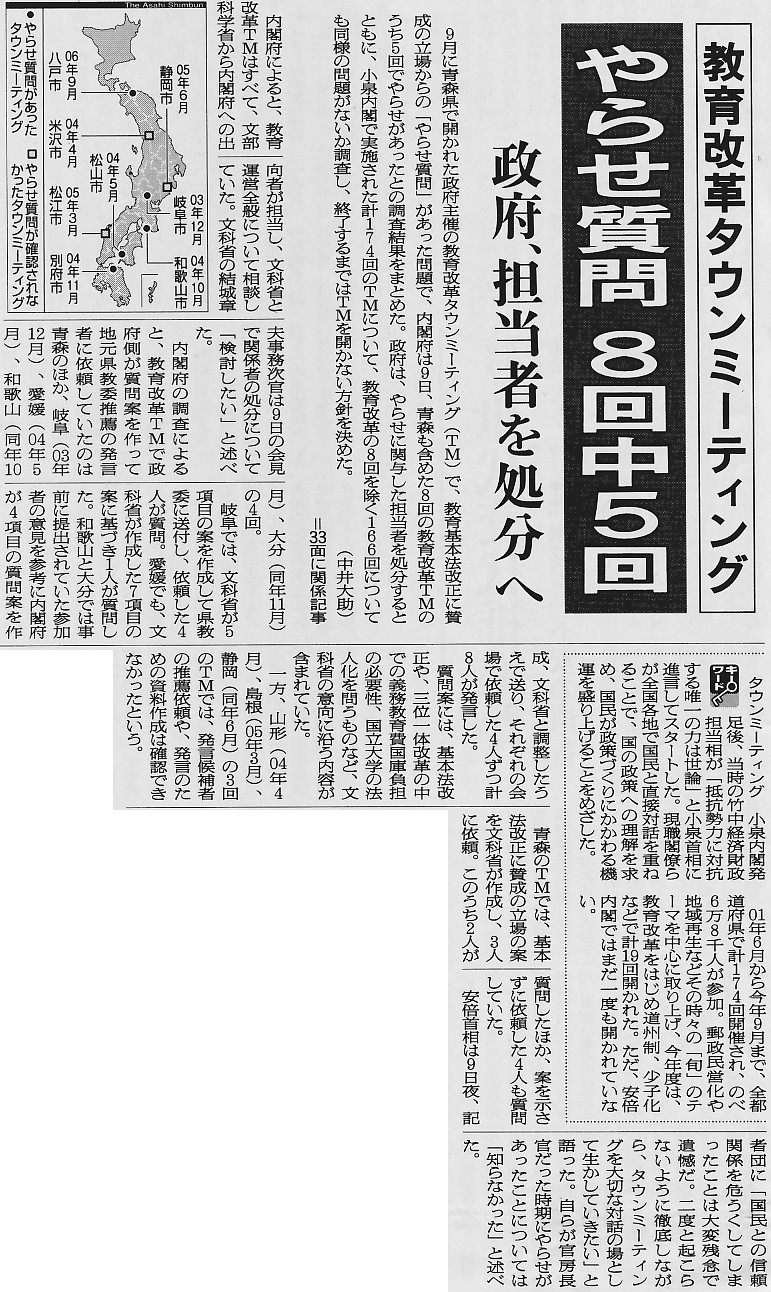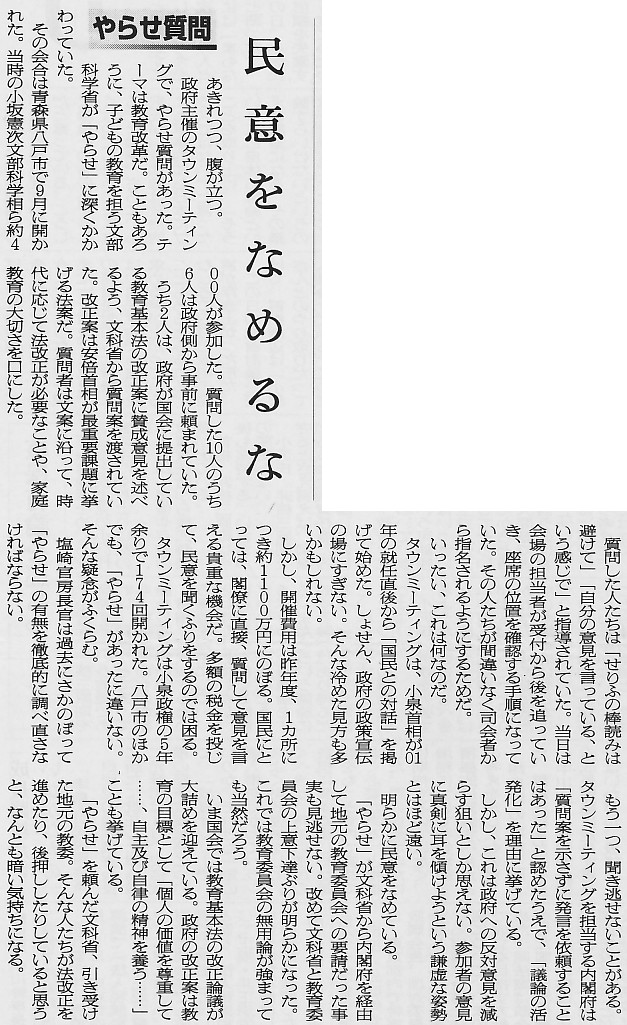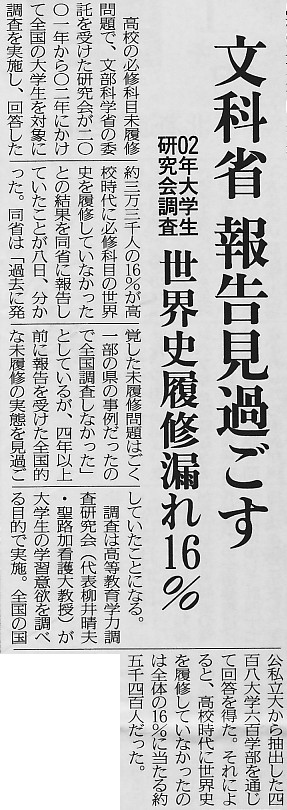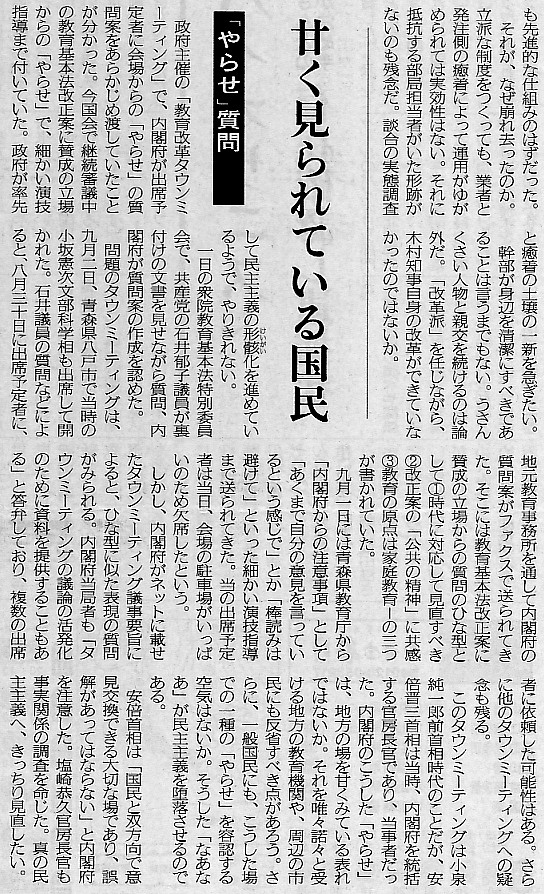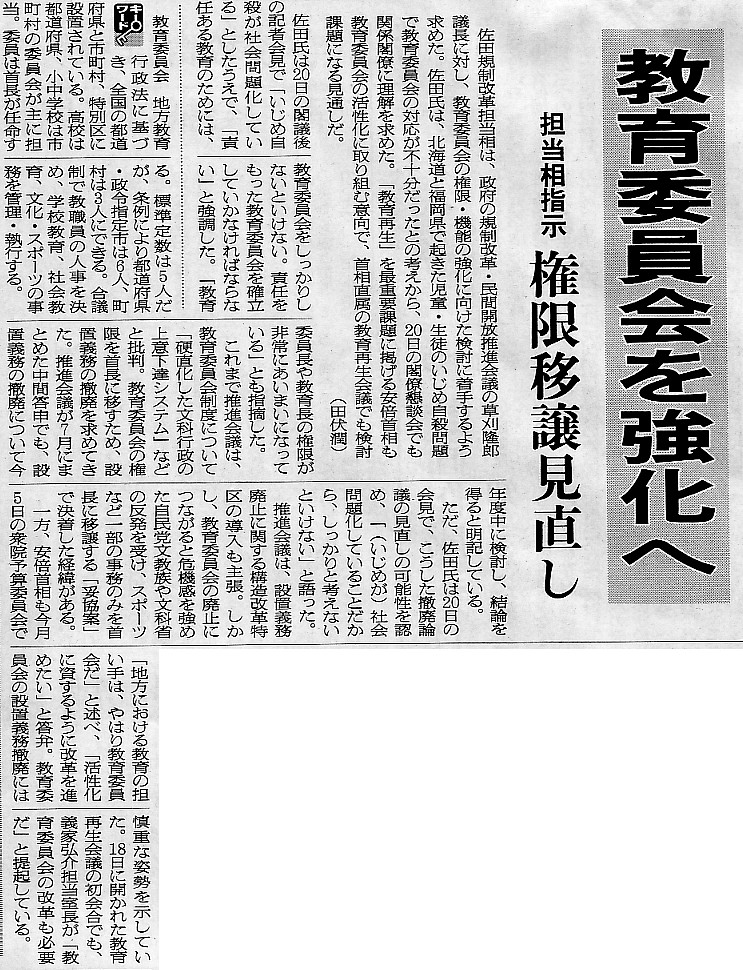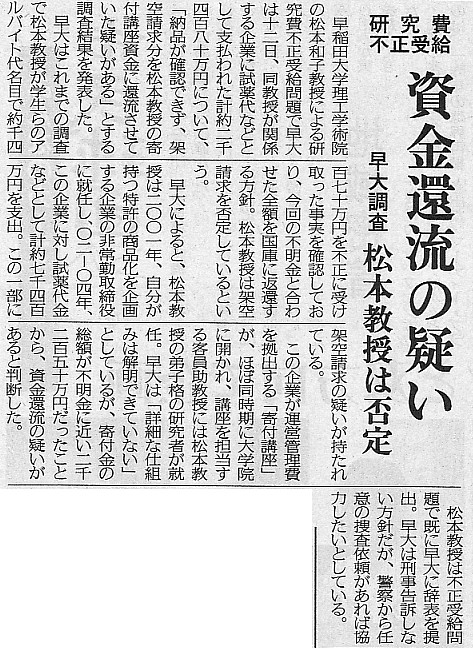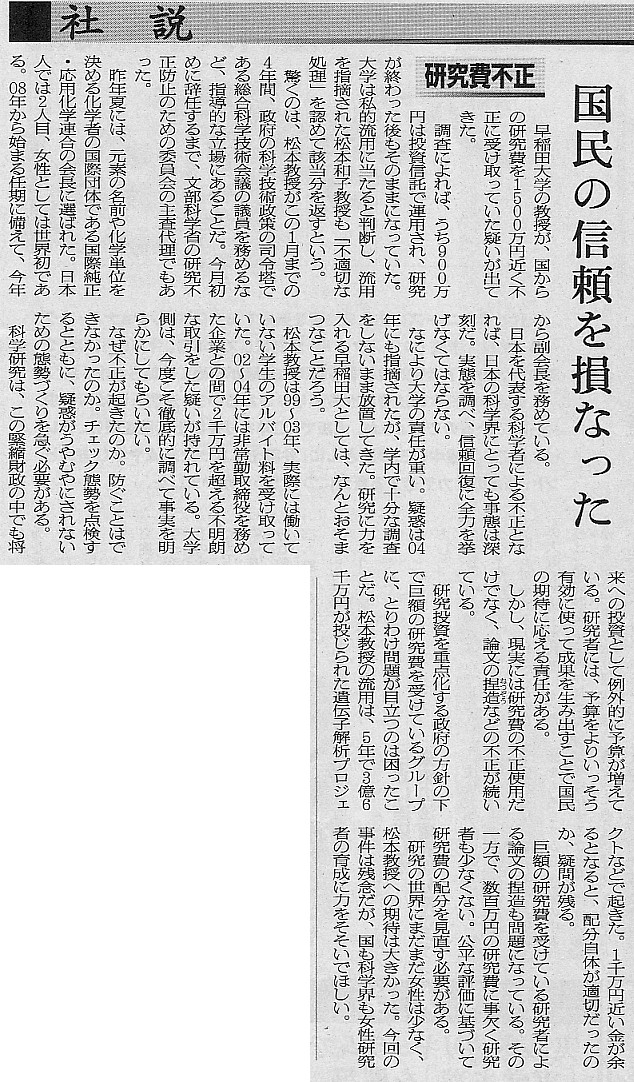文部科学省&教育の問題
★HOME
教育予算7兆増にしたから良い結果で出るわけではない。効率的に税金を使わなければならない。
「幼稚園、保育所は無償」でどのような結果を期待するのか?子供の数が増えるから、将来、
子供達から税金としてお金を取れば良いと思っているのか?先行投資とでも思っているのか?
もしお金(税金)だけを注ぎ込んで、良い結果がでなかったら負担が増えるぞ!なんでこんなに
政府のレベルは低いのか?
厚生労働省と
社会保険庁は
雇用促進事業団の無駄遣い:
私のしごと館 関西文化学術研究都市(京都府 精華・西木津地区)
を許した。多くの税金が使われ、良い結果は出ていない。文部科学省は真剣に考えるべきだ。
多額の税金を使った結果を考えなければ、一部の政治家と業者だけを喜ばす。もしかすると、
一部の政治家と業者だけを喜ばすためだけに国民は使われてきた。そして収入が減ると
キャリアや官僚達の詐欺師のような説明で国民に負担を押し付ける。このような仕組みになって
いるがそこそこに国民も良い思いもしたので誰も文句を言わなかったのかもしれない。
参考サイト
無駄遣い 私の仕事館
「私の仕事館」の段
タウンミーティングでやらせを計画した文部科学省を信じてはならない良い例だ。日本政府だって信用できない。
「社会保険庁職員と社会保険事務局職員は必要なし!」
を見てもわかるが、公務員の殺害は問題だが彼らがやってきたことについて責任を取らすべきだと思う。
事故米転売事件に関して職員に対する処分も甘い。
公務員は屁理屈や納得できない言い訳でごまかしたり、逃げたりする場合が多い。まあ、
東大を卒業する段階でも社会の矛盾や世の中の裏と表が存在することを知らない学生が存在することも問題だ。
勉強だけをしていれば将来が約束された時代は終わったのだろう。国民も卒業大学だけでなく、個人の経験や
その他の点を評価する社会になるように意識を変えるべきだろう。
外国船で検索したら興味を引かれるサイトを見つけた。理系だったので地理を選択したせいもあるかもしれないが下記について最近まで知らなかった。
大学生時代、英語の能力を伸ばすためにアメリカの大学で世界史を取ったことがある。日本で習った内容と違っている箇所も多くありショックを受けた。
自分が取っている世界史の内容を多くの日本人は全く知らないだろうについてだ。教授は、「事実は1つかもしれないが、勝国と敗国の違う立場で
書かれている歴史が違う。唯一の事実であっても見る角度、又は、書く者の立場で記載される内容は違ってくる。不都合な事実は削除、又は、抹消され、
歴史として記載される。多くの歴史は勝国の歴史であることを理解するべきだ。」と言っていた。「プロパガンダにも注意して個々が判断しないと間違った
方向へ進んでいくことをとめる事が出来ない。」とも言っていた。昔の事だから大体の内容しか覚えていない。受験勉強に必要な事しか教えられなかった
自分にとっては凄く新鮮で今でもいろいろな事を考えたり、判断する時に思い出す。
下記の情報がどこまで正しいのか調べていないので良くわからないが、少なくとも下記の内容は日本の権力を持つ人々や教育関係者達が知られなくないない内容
なのであろう。また、キリスト教関係者達もアメリカで原爆の投下が正当化されている事と同じで事実に触れたくないのかもしれない。アフリカから黒人が
奴隷としてアメリカや南米に移送されて事実を考えると、日本人やアジア人が奴隷として売られてもおかしくない。アメリカのインディアンの問題も
同じ次元であると思う。同じ人間と思っていないのでそのような扱いをしたのであろう。
同じ問題ではないが、推測させるような出来事は現在もある。
下記が事実であるようなので日本政府は日本の歴史についてもっと教えようとしているのなら、下記についても教えるべきである。
フロイスは、日本全国を歩き回って『日欧文化比較論』という報告書を本国に提出した。
宣教師達は、例外なく日本人女性に貞操観念がない事に呆れる所か嫌悪した。
「ヨーロッパでは未婚の女性の最高の名誉と尊さは貞操であり、またその純潔が冒されない貞潔さである。日本の女性は処女の純潔を少しも重んじない。それを欠いても名誉も失わなければ、結婚もできる」
男尊女卑の儒教観念が社会を息苦しく縛っていない時代、男と女はお互いが気に入れば結婚するが、夫は外で幾人の女性と関係を持ち、妻は夫が不在であれば不特定多数の男を家に忍び込ませて関係を持っていた。
そうした分別なき生殖本能で、日本の人口は減る事なく増え続けた。
事実。儒教倫理が日本社会を閉鎖的に支配した江戸時代、それ以前の性風俗が乱れていた時代に比べて人口は概ね安定していた。
省略
ミゲル千々石「旅先の先々で、売られて奴隷の境遇に落ちた日本人を親しく見た時には、道義を一切忘れて血と言葉を同じゅうする同胞を、さながら牛か馬の様に、こんな安い値で売り飛ばす我が民族への激しい義憤の念に燃え立たざるを得なかった」…後に、イエズス会を脱会し、キリシタンを捨てた。幾たびか命を狙われ、身を寄せていたキリシタン大名の有馬氏からも領地から追放された。
日本人は、奴隷として売られ、自由を奪われ、人間としての尊厳が踏みにじられていた。
省略
古代から、九州各地から朝鮮へ売られて行った女性や子供達を「唐行き」といわれ、海外に売る日本製品がなかった時代には日本人が奴隷として売られていた。
南蛮人が来るまで、九州の諸大名は、明国は陸禁海禁政策を取っていた為に日本人を奴隷として朝鮮に売っていた。
朝鮮は、正統派儒教から日本を文明度の低い野蛮人と見下していた為に、日本人を奴隷として購入し、自分の家僕にするか、中国人奴隷商人に高額で売っていた。
明国にしろ朝鮮にしろ、日本と交易してどうしても買いたいと思うような日本産はなかった。
ポルトガル商船で日本を訪れた東南アジア人達は、日本人は安いとして買って帰国し、地元で奴隷として高く売って金を稼いでいた。
東南アジアも、奴隷として日本人を買う意外で欲しい日本産はなかった。
朝鮮に売られる「唐行き」が途絶えた後、東南アジアへ売られる事が「唐行き」とされた。
豊臣秀吉も、徳川家康も、日本人を奴隷として売られて行く事を止める為に外交政策を行った。
省略
多くの大名は、南蛮人に最新兵器の購入を申し込み、引き換えに領地内での布教を許可した。
一部の大名は、より多くの武器を購入するべく驚喜して洗礼を受け、キリシタン大名となった。
コエリョ神父は、イエズス会の軍事力を誇示する為に豊臣秀吉に軍艦を見せたが、購入仲介の要請を拒否した。
オルガンティーノは、日本における布教活動の保護と引き換えに軍艦2隻を提供すると、豊臣秀吉に提言した。
鬼塚英昭著「天皇のロザリオ」(P249~257)は次のように述べている。
「徳富蘇峰の『近世日本国民史』の初版に、秀吉の朝鮮出兵従軍記者の見聞録がのっている。
『キリシタン大名、小名、豪族たちが、火薬がほしいぱかりに女たちを南蛮船に運び、獣のごとく縛って船内に押し込むゆえに、
女たちが泣き叫ぴ、わめくさま地獄のごとし』。ザヴィエルは日本をヨーロッパの帝国主義に売り渡す役割を演じ、
ユダヤ人でマラーノ(改宗ユダヤ人)のアルメイダは、日本に火薬を売り込み、
交換に日本女性を奴隷船に連れこんで海外で売りさばいたボスの中のボスであつた。
キリシタン大名の大友、大村、有馬の甥たちが、天正少年使節団として、ローマ法王のもとにいったが、
その報告書を見ると、キリシタン大名の悪行が世界に及んでいることが証明されよう。
『行く先々で日本女性がどこまでいっても沢山目につく。
ヨーロッパ各地で50万という。肌白くみめよき日本の娘たちが秘所まるだしにつながれ、
もてあそばれ、奴隷らの国にまで転売されていくのを正視できない。
鉄の伽をはめられ、同国人をかかる遠い地に売り払う徒への憤りも、もともとなれど、
白人文明でありながら、何故同じ人間を奴隷にいたす。
ポルトガル人の教会や師父が硝石(火薬の原料)と交換し、インドやアフリカまで売っている』と。
日本のカトリック教徒たち(プロテスタントもふくめて)は、キリシタン殉教者の悲劇を語り継ぐ。
しかし、かの少年使節団の書いた(50万人の悲劇)を、
火薬一樽で50人の娘が売られていった悲劇をどうして語り継ごうとしないのか。
キリシタン大名たちに神杜・仏閣を焼かれた悲劇の歴史を無視し続けるのか。
数千万人の黒人奴隷がアメリカ大陸に運ばれ、数百万人の原住民が殺され、
数十万人の日本娘が世界中に売られた事実を、今こそ、日本のキリスト教徒たちは考え、語り継がれよ。
その勇気があれぱの話だが」。
日本の歴史教科書はキリシタンが日本の娘を50万人
も海外に奴隷として売った事は教えないのはなぜか?
2006年1月27日 金曜日
◆日本宣教論序説(16) 2005年4月 日本のためのとりなし
わたしは先に第4回「天主教の渡来」の中で、日本におけるキリシタンの目覚ましい発展と衰退の概略を述べました。しかし、ここではキリシタンがたどった土着化の過程について考察してみたいと思います。後で詳しく述ぺますが、わたしの先祖はキリシタンでありました。わたしは伊達政宗の領地であった岩手県藤沢町大籠(おおかご)地区での大迫害で生き残ったかくれキリシタンの末裔です。
今はプロテスタントの牧師ですが、わたしの中にはキリシタンの血が流れていると思います。三年前の夏、父の郷里藤沢町を初めて訪問してこの事実を知ってから、キリシタンについてのわたしの関心は以前より深くなりました。そしてキリシタンについての知識も少し増えました。四百年前のキリシタンを知ることが現代のわたしたちと深く関わってくると思いますので、先ず追害の理由から始めたいと思います。
◆1.キリシタン遣害の理由
宣教師ルイス・フロイスが暴君と呼ぶ豊臣秀吉が「伴天連(ばてれん)追放令」を発したのは、1587年7月24日(天正15年6月19目)でした。これは天正(てんしょう)の禁令として知られる第1回のキリシタン禁止令です。それ以後徳川時代にかけて、次々に発せられた禁止令の理由をまとめると、次の五つになるでしょう。
(1)植民地政策
キリシタンの宣教は西欧諸国の植民地政策と結びついていました。それは、初めに宣教師を送ってその国をキリスト教化し、次に軍隊を送って征服し植民地化するという政策です。秀吉は早くもそのことに気づいて主君信長に注意をうながしています。
ポノレトガル、スペインのようなカトリック教国は強力な王権をバックに、大航海時代の波に乗ってすばらしく機能的な帆船や、破壌力抜群の大砲を武器として、世界をぐるりと囲む世界帝国を築き上げていました。その帝国が築き上げた植民地や、その植民地をつなぐ海のルートを通って、アジアでの一獲千金を夢見る冒険家たちが、何百、何千とビジネスに飛ぴ出していきました。
そうした中にカトリックの宣教師たちも霊魂の救いを目指して、アジアに乗り出して行ったのです。彼らが求めたのは、霊魂の救いだけではなく、経済的利益でもありました。
ザビエルがゴアのアントニオ・ゴメス神父に宛てた手紙から引用すると、
「神父が日本へ渡航する時には、インド総督が日本国王への親善とともに献呈できるような相当の額の金貨と贈り物を携えてきて下さい。もしも日本国王がわたしたちの信仰に帰依することになれぱ、ポルトガル国王にとっても、大きな物質的利益をもたらすであろうと神かけて信じているからです。堺は非常に大きな港で、沢山の商人と金持ちがいる町です。日本の他の地方よりも銀か金が沢山ありますので、この堺に商館を設けたらよいと思います」(書簡集第93)
「それで神父を乗せて来る船は胡椒をあまり積み込まないで、多くても80バレルまでにしなさい。なぜなら、前に述ぺたように、堺の港についた時、持ってきたのが少なけれぱ、日本でたいへんよく売れ、うんと金儲けが出来るからです」(書簡集第9)。
ザビエルはポルトガル系の改宗ユダヤ人(マラーノ)だけあって、金儲けには抜け目ない様子が、手紙を通じても窺われます。ザビエル渡来の三年後、ルイス・デ・アルメイダが長崎に上陸しました。この人も改宗ユダヤ人で、ポルトガルを飛ぴ出してから世界を股にかけ、仲介貿易で巨額の富を築き上げましたが、なぜか日本に来てイエズス会の神父となりました。彼はその財産をもって宣教師たちの生活を支え、育児院を建て、キリシタン大名の大友宗瞬に医薬品を与え、大分に病院を建てました。
(2)奴隷売買
しかし、アルメイダが行ったのは、善事ばかりではなく、悪事もありました。それは奴隷売買を仲介したことです。わた〕まここで、鬼塚英昭著「天皇のロザリオ」P249~257から、部分的に引用したいと思います。
「徳富蘇峰の『近世日本国民史』の初版に、秀吉の朝鮮出兵従軍記者の見聞録がのっている。『キリシタン大名、小名、豪族たちが、火薬がほしいぱかりに女たちを南蛮船に運び、獣のごとく縛って船内に押し込むゆえに、女たちが泣き叫ぴ、わめくさま地獄のごとし』。ザヴィエルは日本をヨーロッパの帝国主義に売り渡す役割を演じ、ユダヤ人でマラーノ(改宗ユダヤ人)のアルメイダは、日本に火薬を売り込み、交換に日本女性を奴隷船に連れこんで海外で売りさばいたボスの中のボスであつた。
キリシタン大名の大友、大村、有馬の甥たちが、天正少年使節団として、ローマ法王のもとにいったが、その報告書を見ると、キリシタン大名の悪行が世界に及んでいることが証明されよう。
『行く先々で日本女性がどこまでいっても沢山目につく。ヨーロッパ各地で50万という。肌白くみめよき日本の娘たちが秘所まるだしにつながれ、もてあそばれ、奴隷らの国にまで転売されていくのを正視できない。鉄の伽をはめられ、同国人をかかる遠い地に売り払う徒への憤りも、もともとなれど、白人文明でありながら、何故同じ人間を奴隷にいたす。ポルトガル人の教会や師父が硝石(火薬の原料)と交換し、インドやアフリカまで売っている』と。
日本のカトリック教徒たち(プロテスタントもふくめて)は、キリシタン殉教者の悲劇を語り継ぐ。しかし、かの少年使節団の書いた(50万人の悲劇)を、火薬一樽で50人の娘が売られていった悲劇をどうして語り継ごうとしないのか。キリシタン大名たちに神杜・仏閣を焼かれた悲劇の歴史を無視し続けるのか。
数千万人の黒人奴隷がアメリカ大陸に運ばれ、数百万人の原住民が殺され、数十万人の日本娘が世界中に売られた事実を、今こそ、日本のキリスト教徒たちは考え、語り継がれよ。その勇気があれぱの話だが」。
(以上で「天皇の回ザリオ」からの引用を終ります)
わたしはこれまで各種の日本キリシタン史を学んで来ましたが、この『天皇のロザリオ」を読むまでは、「奴隷」の内容について知りませんでした。しかし、こういう事実を知ったからには、同じキリスト教徒として真摯な態度で語り継いで行きたいと思います。
なお今年の1月30日に、第5版が発行された、若菜みどり著「クアトロ・ラガッツィ(四人の少年の意)」(天正少年使節と世界帝国)P.414~417」に奴隷売買のことが報告されていますが、徳當蘇峰「近世日本国民史豊臣時代乙篇P337-387」からの引用がなされているにもかかわらず、「火薬一樽につき日本娘50人」の記録は省かれています。
そして、「植民地住民の奴隷化と売買というビジネスは、白人による有色人種への差別と資本力、武カの格差という世界の格差の中で進行している非常に非人間的な『巨悪』であった。英雄的なラス・カサスならずとも、宣教師はそのことを見逃すことができず、王権に訴えてこれを阻止しようとしたがその悪は利益をともなっているかぎり、そして差別を土台としているかぎり、けっしてやむものではなかった」(p.416〉と説明して、売られた女性たちの末路の悲惨さを記しています。かなり護教的な論調が目立つ本です。
秀吉は準管区長コエリヨに対して、「ポルトガル人が多数の日本人を奴隷として購入し、彼らの国に連行しているが、これは許しがたい行為である。従って伴天遠はインドその他の遠隔地に売られて行ったすぺての日本人を日本に連れ戻せ」と命じています。
(3)巡回布教
更に秀吉は、「なぜ伴天連たちは地方から地方を巡回して、人々を熱心に煽動し強制し'て宗徒とするのか。今後そのような布教をすれば、全員を支那に帰還させ、京、大阪、堺の修道院や教会を接収し、あらゆる家財を没収する」と宣告しました。
(4)神杜仏閣の破壊
更に彼は、なぜ伴天連たちは神杜仏閣を破壊し神官・僧侶らを迫害し、彼らと融和しようとしないのか」と問いました。神杜仏閣の破壊、焼却は高山右近、大友宗瞬などキリシタン大名が大々的にやったことです。これは排他的唯一神教が政治権カと緒ぴつく時、必然的に起こる現象でしょうか。
(5)牛馬を食べること
更に彼は、なぜ伴天連たちは道理に反して牛馬を食ぺるのか。馬や牛は労働力だから日本人の大切な力を奪うことになる」と言いました。
以上秀吉からの五つの詰問にたいする、コエリヨの反応は極めて傲慢で、狡猪な、高をくくった返答でした。高山右近を初め多くのキリシタン大名たちはコエリヨを牽制しましたが、彼は彼らの制止を聞き入れず、反って長崎と茂木の要塞を強化し、武器・弾薬を増強し、フイリピンのスペイン総督に援軍を要請しました。
これは先に巡察使ヴァリニヤーノがコエリヨに命じておいたことでした。しかし、かれらの頼みとする高山右近が失脚し、長崎が秀吉に接収されるという情勢の変化を見てヴァリニヤーノは、戦闘準備を秀吉に知られないうちに急遽解除しました。
これらの経過を見れば、ポルトガル、スペイン両国の侵略政策の尖兵として、宣教師が送られて来たという事実を認めるほかないでしょう。これらの疑問は豊臣時代だけでなく、徳川時代300年の間においても、キリシタンは危険であり、キリシタンになればどんな残酷な迫害を受けるかわからないという恐怖心を日本人全体に植え付けることになり、キリスト教の日本への土着化を妨げる要因になったと言えるでしょう。(後略)
◆バテレン追放令 2002年7月9日 北國新聞
もう1つの国内向けとみられる法令は11カ条からなっている。一条から九条までの内容は▽キリシタン信仰は自由であるが、大名や侍が領民の意志に反して改宗させてはならない▽一定の土地を所有する大名がキリシタンになるには届けが必要▽日本にはいろいろ宗派があるから下々の者が自分の考えでキリシタンを信仰するのはかまわない―などと規定する。
注目すべきは次の十条で、日本人を南蛮に売り渡す(奴隷売買)ことを禁止。十一条で、牛馬を屠殺し食料とするのを許さない、としていることである。
以上の内容からは▽右近が高槻や明石で行った神社仏閣の破壊や領民を改宗させたことを糾弾▽有力武将を改宗させたのはほとんどが右近によってで、右近に棄教をさせることで歯止めがかかると見た▽バテレン船で現実に九州地方の人々が外国に奴隷として売られていること―などが分かる。秀吉の追放令は、ある意味で筋の通った要求だった。
さらに重要なのは、日本の民と国土は、天下人のものであり、キリシタン大名が、勝手に教会に土地を寄付したり、人民を外国に売ることは許されないということである。天下統一とは、中央集権国家の確立にほかならない。キリシタンは、その足元を乱す、かつての一向宗と同じ存在になる危険性があると秀吉が感じていたことがわかる。
「バテレン追放令」は、キリシタンが対象であるかのように見えて、実は日本が新しい時代を迎えるため何が課題かを暗示する極めて重要な出来事だったのである。
(私のコメント)
今年のNHKの大河ドラマは山内一豊が主人公ですが、信長、秀吉、家康の時代のドラマです。また同じNHKでは「そのとき歴史は動いた」と言う番組でも戦国時代のことをよく取り扱います。その中で秀吉とキリシタンの関係を扱ったものがありましたが、日本の娘などがキリシタンによって奴隷として売りさばかれた事は扱わなかった。
この事は、さまざまな文献資料によっても証明されているから事実なのですが、日本の歴史教科書でも、秀吉のキリシタン弾圧は教えても、日本女性が奴隷としてキリシタンたちが海外売りさばいた事は教えないのはなぜか。そうでなければ秀吉がなぜキリシタン弾圧に乗り出したかが分からない。
ましてや宣教師のザビエルなどが改宗ユダヤ人であることなどと指摘するのは歴史教科書やNHKなどでは無理だろう。しかしこのようなことを教えないからユダヤ人がなぜヨーロッパで差別されるのかが分からなくなる。彼らは金になれば何でもやるところは現代でも変わらない。
なぜこのような事実が歴史として教えられないかと言うと、やはりGHQなどによる歴史の改ざんが行なわれて、キリスト教や白人などへのイメージが悪くなるからだろう。もちろんキリシタン大名などの協力があったから日本女性を奴隷として売りさばいたのだろうが、彼らは日本人の顔をしたキリシタンだった。
おそらく大河ドラマでも高山右近などのキリシタン大名が出てくるだろうが、娘たちを火薬一樽で娘50人を売った事などはドラマには出てこないだろう。しかしこのようなことがキリスト教に対する日本国民のイメージが悪くなり、キリスト教は日本ではいくら宣教師を送り込んでも1%も信者が増えない。かつてキリスト教は人さらいをした宗教と言うDNAが埋め込まれてしまったのだろう。
歴史教科書などではキリスト教弾圧を単なる異教徒排斥としか教えていませんが、信長にしても秀吉にしてもキリシタンに対しては最初は好意的だった。しかし秀吉に宣教師たちの植民地への野心を見抜かれて、だんだん危険視するようになり制限を設けたが、神社仏閣の破壊や日本人を奴隷として売りさばく事が秀吉の怒りに触れて弾圧するようになったのだ。
現代にたとえれば竹中平蔵などがキリシタン大名として宣教師たちの手先となって働いているのと同じであり、日本の銀行や保険会社などを外資系ファンドなどに売りさばいてしまった。戦国時代に日本の娘を奴隷として売りさばいたのと同じ行為であり、竹中平蔵は高山右近であり、アルメイダのような改宗ユダヤ人が日本乗っ取りを狙っている。
ヤフーのコメントにいろいろなコメントがあるが、「制度などへの認識不足があり、不適切な説明」は隠ぺいしようとした側の言葉、嘘の説明以外の表現は正確な表現ではない。制度などへの認識不足な関係者は降格で良い。何らかの重い処分が必要だと思う。これだけの事をして、「制度などへの認識不足があり、不適切な説明」で逃げられると思っている人間達は排除した方が良いと思う。このような人間達はいなくならないが、明確になったケースでは排除するべきだと思う。教師不足とか関係ない。悪質な対応を取る教育関係者は少なくとも降格、そして、普通の教員から再スタートすれば良い。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
jsr*****
いつも思うが、いじめを隠す意味が分からない。
いじめはいじめた本人が悪いのであって、相談を受けたり報告をした教師が責められるようなことはあってはいけない。というか、責めることがそもそも間違っている。ただ、世論はそんなに責めていないと思う。
一部の被害者の親だったり、教育委員会や上司の教諭が責めているだけ。
一丸となっていじめっ子とその親に責任を押し付ければ良いものを、学校側が隠すから、学校もいじめに加担したことになる。
今のやり方や責める人を間違えているということに一体いつ気づくのでしょうか。
今回のように後から発覚するようなケースでは厳正に処罰することを望みます。
haj*****
>1年以上も国への報告を怠っていたことが明らかになった。被害児童の保護者に事実と異なる説明をし、第三者委員会による調査を拒否していたことも発覚。
報告を怠っていたのでなく、これは恣意的なので、隠蔽していたと言うのだと思う。
さらに当該生徒の保護者が文部科学省への報告の有無をきいたところ、報告済していると回答しているとの事だから悪質。
この対応では今後も改善されるはずがない。
いじめ問題よりも組織の保身に走る。本当に最低なレベルだと思う。
hir*****
これを最初に伝えた毎日新聞の記事によると、小学校を管轄する教育学部の副学部長で、ひたちなか市のいじめに関する委員も兼ねる人物が、第三者調査を求めた親御さんに「調査という言葉は使いたくない」「どこまで調べれば気が済むのですか」などと暴言を吐いたとのこと。
昨日、文書を読み上げる形で「謝罪」しようとして批判され、10分かかってやっと子どもに「ごめんなさい」と話しかけたという学校だが、その謝罪の場には学部長は出たそうだが暴言副学部長が出席したとの話はない。
ここから透けて見えるのは、いつも通りの隠蔽、事なかれ体質。口先では「子どものために」などと強調するくせに、子どもよりも自分達の都合を最優先させる態度がよくよく分かる話だ。
oohay***
>この経緯について、「制度などへの認識不足があり、不適切な説明だった」と説明
保護者が文科省への報告の有無をただしたところ、幹部は「報告済み」と事実と異なる説明をした、というのも相当に問題だと思うけど、教育のプロフェッショナルの集団である筈の学校の教職員が、組織ぐるみで隠ぺいしようとしたのかと疑わしくさえ思えるような「認識力のなさ」こそ深刻だと思う。いじめ得、逃げ得を許してはいけない。
aaa*****
いじめ防止対策推進法28条は重大事態が発生した場合に調査を義務としていますから、調査拒否は明らかに違法です。
茨城大学には、調査義務違反として賠償責任も生じます。
as0*****
国立大付属の小学校でも隠蔽するとは。しかも調査を拒否したり、発言で嘘つくとは疑っちゃうな。
捜査のメスを入れていただき、「逃げ得」一切不可で、学校関係者に厳罰を下していただきたい。
kua*****
そうか、茨城大学は、嘘の説明を不適切というのか。日本語として嘘と不適切の間には相当な乖離があると思うが。これで校長は逃げ切りですかね。
「重大事態」いじめ、1年も国に報告せず 茨城大付属小、調査も拒否 04/08/23(朝日新聞)
茨城大学教育学部付属小学校(水戸市)が、「重大事態」と認定したいじめについて、1年以上も国への報告を怠っていたことが明らかになった。被害児童の保護者に事実と異なる説明をし、第三者委員会による調査を拒否していたことも発覚。同大は7日、一連の経緯を発表し、統治機能に「深刻な問題」があったと認めた。
保護者の代理人弁護士によると、当時小学4年だった女児は2021年4月ごろから、同級生につきまとわれたり、命令されたりした。その後、学校を休むようになり、同6月には欠席の理由がいじめだと保護者が同校に伝えたという。
同大によると、同校は女児の欠席期間が長期に及んだことを踏まえ、同11月に、いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」にあたると認定した。
同法は国立大付属校で重大事態が認められた場合、文部科学省への報告を義務づけている。同大は、件数のみの回答で報告を終えたと誤解し、個別事案の報告はしないままにしていたと説明している。
女児の保護者は、状況が改善されないとして、今年1月に同校幹部と面談。この際、文科省への報告の有無をただしたところ、幹部は「報告済み」と事実と異なる説明をした。実際に文科省に報告したのは、面談後の2月になってからだった。同大はこの経緯について、「制度などへの認識不足があり、不適切な説明だった」と説明した。
保護者は1月の面談で、第三者委による調査を求めたが、学校側は後日、「被害児童の不登校解消に向けて心のケアを行う段階」にあるとして、第三者委による調査の必要はないと書面で回答した。
保護者の代理人弁護士は3月、「事実の解明が十分でない」などと改めて第三者委による調査を要請。大学側は4月5日になって、「保護者の納得が得られていない」などとして、いじめの調査と大学側の対応を検証するための第三者委を置くことを決めた。
同大の太田寛行学長は「ガバナンスに関する深刻な問題があり、厳しく受け止めている。深くおわび申し上げる」とのコメントを公表した。今後、再発防止に向けた課題の抽出と検証をしていくとした。(藤田大道、久保田一道)
茨城大附属小で「重大事態」のいじめ 1年以上国へ報告せず 04/07/23(NHK)
茨城大学の附属小学校がおととし、「重大事態」にあたるいじめがあったものの、法律で義務づけられている国への報告を1年以上にわたり行っていなかったことがわかりました。
学校側は保護者に対して、国には報告したと事実とは異なる説明をしていたということです。
茨城大学によりますと、おととし6月、教育学部附属小学校に通う当時小学4年生の児童の保護者から、子どもがいじめを受けていると連絡がありました。
小学校はこの年の11月、いじめ防止対策推進法に定められた「重大事態」にあたるとしましたが、その際、法律で義務づけられている文部科学省への報告をしていなかったということです。
その後も児童は学校に行けない状態が続き、保護者と小学校などとの間でやりとりが続いていましたが、文部科学省に事案を報告したのはいじめを「重大事態」としてから1年3か月後の、ことし2月だったということです。
この間、学校側は保護者の問い合わせに対して、「文部科学省にはすでに報告を済ませた」などと事実と異なる説明をしていたということです。
茨城大学は、第三者調査委員会を設置して調査を行うことを5日になって決め、6日、児童と保護者に小学校の校長らが謝罪したということです。
茨城大学の太田寛行学長は、「国の調査に対して『重大事態』の件数を回答したことで国への報告を済ませたと誤った認識をしていた。関係の皆様には深くおわび申し上げる。ガバナンスに関する深刻な問題があると考え、厳しく受け止め、問題の改善に真摯(しんし)に取り組んでいく」としています。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
asa*****
>学校側が謝罪文を読み上げる形を取ったため、母親や弁護士から「娘に分かるようにお話をしていただけたら」「普通の言葉で『ごめんなさい』って言っていただければ」と求められた。
ここは考えさせられた。
苦しい思いをしていたのは嫌がらせを受けたお子様で、学校側はその子のために取るべき対応を怠ったわけである。
そこから6日の謝罪の場まで、子供の方を向いていなかったことが象徴されているように思える。
学校側は子供に向けて「ごめんなさい」と声をかけた時点で初めてその子に向き合ったと認識すればいい。
そして教育とは何かを考え直せばいい。
nag*****
>学校側が謝罪文を読み上げる形を取った
いじめ被害者の親を前に、大本営発表かよw
ouq*****
こういうのは子供がメンタルヘルスがやられて登校できない診断書を医者に処方してもらって、傷害罪として刑事告訴すべき。
第三者委員会なんて捜査権がないので意味なし。
茨城大付属小いじめ未報告 第三者委で大学や付属小の対応検証へ 04/07/23(毎日新聞)
茨城大教育学部付属小学校(水戸市)が「重大事態」と認定した女児へのいじめについて、いじめ防止対策推進法に基づく調査や文部科学省への報告をしなかった問題で、永岡桂子文科相は7日の閣議後記者会見で「報道であるような対応がなされていたとすれば、極めて遺憾」と述べ、事実関係を調査するとした。一方、茨城大も毎日新聞の取材に対し、新設する第三者委員会で、教育学部や付属小の対応の誤りなどを検証することを明らかにした。
学校側は2021年11月、当時4年生の女児について、いじめを理由に長期欠席する「重大事態」と認定した。同法は重大事態と認定すれば、事実関係の調査と、国立大付属小の場合は文科省に報告することを義務づけている。だが、被害者側から求めがあった第三者委員会によるいじめ調査を拒否し、約1年3カ月にわたり文科省への報告もしなかった。その間、保護者には「重大事態と22年5月30日に文科省に報告した」と事実とは異なる説明を繰り返していた。
茨城大は7日、毎日新聞の報道などを受け、太田寛行学長名でホームページに談話を公表。文科省への報告の遅れなどについて「諸制度に対する認識が不足していた」と釈明し「これらの事態を招いた要因として、ガバナンス(組織統治)に関する深刻な問題があると考え、状況を厳しく受け止めている」などとした。
茨城大によると、学外の有識者らでつくる第三者委員会の人選を進めており、設置後はいじめの事実関係に限らず、大学や付属小の対応についても検証する。
また、付属小の校長・副校長、同大教育学部長は6日、被害女児と母親、代理人弁護士と面会して一連の対応を謝罪した。ただ、学校側が謝罪文を読み上げる形を取ったため、母親や弁護士から「娘に分かるようにお話をしていただけたら」「普通の言葉で『ごめんなさい』って言っていただければ」と求められた。
結局、面会が始まって10分以上たって、学校側の3人は「ごめんなさい」「安心して登校できるように、先生たちと一緒に考えて頑張っていきます」などとかみ砕いた言葉で謝った。【森永亨、深津誠】
【写真・図解】茨城大付属小から保護者に送られたメール
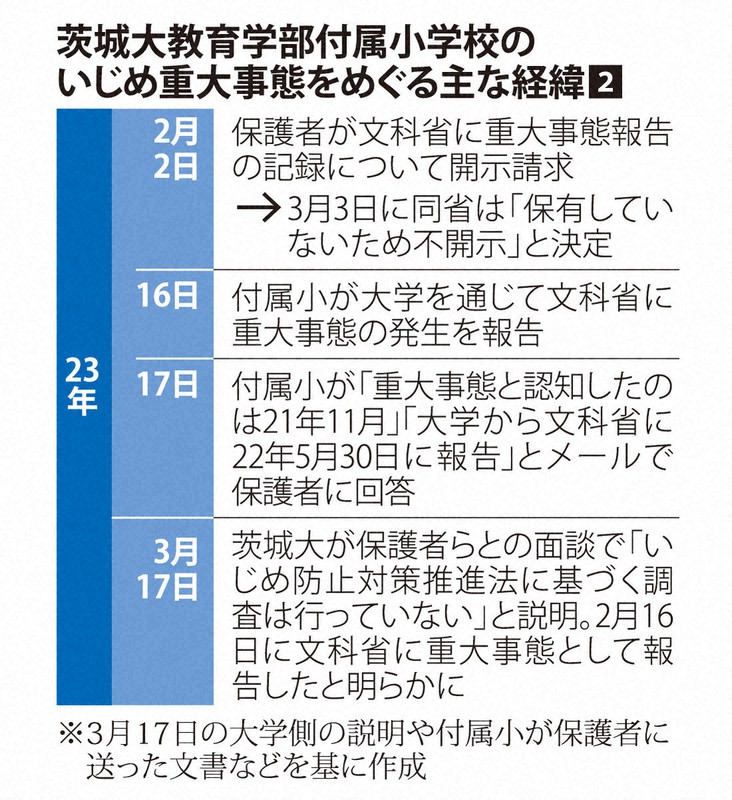
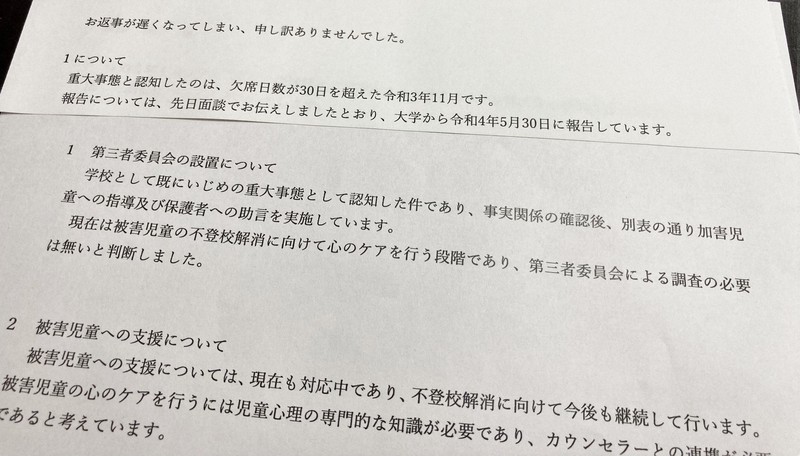
この教育学部副学部長は木村勝彦教授と三輪寿二両教授です。
母親との面談での音声データでは「調査って言葉使いたくない」「どれだけ調査したら気が済む」と発言し、三輪は「調査って言葉、僕もあんまり使いたくなくて、グチャグチャになっちゃうから嫌なんだけど」持論を展開。
上記のコメントが事実なら文科省が調査するべきだと思う。第三者委員会の調査は当てにはならない。基本的に公務員は信用しないが、このような事があるから文書で出せないと言う公務員は信用しない方が良いと再認識した。
国立大学法人の役員や職員は「みなし公務員」ですので、内外に嘘の説明文書を出していれば、虚偽公文書作成・同行使罪という重い犯罪が成立します。
いじめられた子供の保護者は刑事告発するべきだと思う。警察が介入すれば嘘は付きとおす事は出来ないと思う。まあ、警察がまともに告発状を受け取って捜査すればの話だけど!
「保護者にも誤った説明」とオブラートで包んだ表現を使うメディアも噓付き達の仲間だと思ってしまう。メディアはなぜ上記が事実ならニュースとして書かないのか?日本のメディアにもいじめ問題の責任があると思う。もし、文科省が踏み込んだ対応を取らないのなら、多分、日本のいじめ問題は建前のだけの対応で結果を出す意思がないと思う。ところで、文科省は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)のけんではしっかりと仕事をしているのか?
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
前田恒彦
元特捜部主任検事
いじめ防止対策推進法が施行されて久しいですし、現にいじめを苦にした児童や生徒の自殺が全国各地で起こってきたわけですから、この学校の関係者も法が求めるいじめに対する毅然とした対応について十二分に分かっていたことでしょう。
この報道の時系列が事実であれば、学校側の言う「認識が不足していた」という弁解など嘘であり、自己保身のために「隠蔽」を図ろうとしたものの、保護者によって文科省への情報公開請求まで行われた結果、嘘がバレてしまい、大慌てで取り繕っているとみるのが自然ではないでしょうか。
国立大学法人の役員や職員は「みなし公務員」ですので、内外に嘘の説明文書を出していれば、虚偽公文書作成・同行使罪という重い犯罪が成立します。第三者委員会の調査などあてになりませんし、学校関係者らによる証拠隠滅や口裏合わせのおそれも高いので、早い段階での刑事告発も視野に入れるべき事案ではないかと思われます。
京師美佳
防犯アドバイザー/犯罪予知アナリスト
法改正がされ子供を守る体制を整えてもそれを行う現場の人間が無視をしていれば何の意味もない。いつまで保身の為の隠蔽を続けるのか。自分の家族が同じ目にあっても、そのような隠蔽を行えるはずはない。
誤った行動をするいい加減な人間に任せて子供が真っ当に成長するとは思えず、加害者の子供達も不幸ですし、ある意味被害者です。傷害、暴行、名誉毀損、侮辱、器物損壊など、いじめの大半は犯罪です。
罪を犯せば謝罪して罪を償わせる。それを教えるのが教育者と学校のする事です。誤った対応をした現場の者には隠蔽した事を後悔するほど、また、同じ事が起こらない様に、厳しい処分を行うべきです。
*****
いじめは、いじめた側の家庭環境や人格に問題があるんだから、いじめた側を隔離することこそが必要。
いじめた側の家庭を訪問して、いじめ家庭自身に解決させること、いじめが止まない場合、退学や矯正のための学校に入れることを視野に、ということをしっかり親子共々認識させて、解決させること。それでダメなら本当に矯正施設送り。それくらい必要で、いじめる子の方が性格に問題を抱えているので隔離矯正が必要です。
potty***
いじめた側を退学か逮捕にするべき。日本はいつになったら被害者が守られるのか。。旭川の事件も犯人は逮捕されたのか?!メディアはしっかりと報道してほしい。
プチマロ
学校側はいじめをなかったことのように済ませることが多い。まさに事なかれ主義である。そういった体質がいじめを助長させ、さらにいじめを受けた側を追い詰めていくことになってしまう。
「いじめは犯罪である」ということを学校側がきちんと認識しなければならない。いじめに対しての対応があまりにも学校側があやふやで至らないがために多くの最悪の事態になっているということを忘れてはならない。
いじめに対する学校側の毅然とした対応が必要である。いじめを行った場合は厳しく処罰すること、退学などの処分も視野に入れていかねばならないと思う。
nejknv
四年生からイジメ発覚してから一年以上放置、という事は当事者達が卒業するのを待ってるのでは?
学校は卒業したら終わりと最初から調べる気持ちも無かったと思うし、無責任な対応に憤りを感じます。
教師は自分の出世に響くから知らんぷりかな?
学校は信頼出来ないから、イジメを犯罪と見なし警察介入案件にした方が良い。
tig*****
お母さん、頑張りましたね。
弁護士等のアドバイスが無かったとしたら、自分ならここまで校長や大学を追い詰められただろうか?
それにしても腹立たしい。
子どもの1年は返ってこない。
sta*****
この教育学部副学部長は木村勝彦教授と三輪寿二両教授です。
母親との面談での音声データでは「調査って言葉使いたくない」「どれだけ調査したら気が済む」と発言し、三輪は「調査って言葉、僕もあんまり使いたくなくて、グチャグチャになっちゃうから嫌なんだけど」持論を展開。
jsp*****
>保護者には、認定の半年後に文科省へ報告したと事実と異なる説明をしていた。
一番許し難いのは嘘の報告をしたこと。
犯罪と何ら変わらない。
ここは国立の小学校でしょう。
文科省が直接、指導もできるし個人的には懲戒免職でも
良いくらいの極めて悪質な対応だと思う。
kvv*****
しかし学校というのは、いまだ変わらない体質だということですね、子供のことを何も考えてない、ただの利権だけの機関でしかない、報告どころか調査そのものもしてないという、学校の驕りですね、文部科学省は、末端の学校までちゃんと指導してるのですか?お役所仕事と揶揄されても仕方有りませんよ、指導は厳しくやらなければいみがありません
E=m℃
認識が不足していたことと、嘘の結果を保護者に伝えることは全く次元が違う。
認識が不足していたのに、文科省に報告をしていたと嘘をつくことは矛盾している。
知っていたのに報告しなかったという方がすんなり理解できる。
そうで無いならば、認識がないのになぜ文科省に報告済みと保護者に対して嘘がつけたのか疑問が残る。この点はどのように説明が可能なのだろうか。
rai*****
はっきり言えばこんなの氷山の一角。重大事態に認定されるのも実際の半分に満たないと言われている。多くは隠蔽され闇に葬られる。
この調子では第三者委員会の設置を約束しても人選も仲良しや学校側の息のかかった人を入れてみたり、調査に何年もかける、最初からいじめは無かったとか学校に責任は無いという結論ありきの調査で終わる気がしてなりません。
こんなのが教育学部の付属校ですから学生たちは隠蔽術でも学んで卒業して現場で実践していくのではないですかね?
littlepork
国立の小・中学校は公立よりも腐りきっている。国立は文科省が管轄だ。それならば、戦前の文部省に置かれ、学事の視察、監督にあたった官職に視学を復活させ、国立の小・中・高等学校と特別支援学校を視察し、特にいじめ・不登校問題については警察と同じ権限を持たせるようにすれば、生温い対応や問題を棚上げにすることができなくなる。
視学が廃止されたのは教員の人事や思想統制に大きな影響力を持つ存在になり、視学の顔色をうかがう、視学に睨まれないように教員が画策するようになったからだ。
今回の視学の復活は事実上のスクールポリスだ。視学は警察からの出向者と文科省でいじめ・不登校問題のスペシャリストの職員がバディを組み、学校の諸問題に対処し、教員の懲罰も直接下せるようにする。教員経験者は除外とする。
視学は公立と私立にも置き、同様に警察からの出向者といじめ・不登校問題に長けた民間人(教員経験者は除外)がバディを組む。
茨城大付属小でいじめ不登校 「重大」認定も1年以上調査・報告せず 04/06/23(毎日新聞)
茨城大教育学部付属小学校(水戸市)が2021年11月、当時4年生の女児がいじめを理由に不登校が続く「重大事態」と認定しながら約1年3カ月にわたり文部科学省に報告せず、いじめ防止対策推進法に基づく調査もしていないことが毎日新聞の取材で判明した。保護者には、認定の半年後に文科省へ報告したと事実と異なる説明をしていた。学校側は6日、取材に「制度に対する認識が不足していた」などと対応の誤りを認め、同法に基づく第三者委員会を設け、いじめを調査すると明らかにした。
【写真・図解】小学校から保護者に送られたメール
◇第三者委を設置し調査へ
同法は、いじめによって児童生徒が「相当の期間」学校を欠席したケースなどを重大事態と定義。学校側が重大事態を認定した場合は、発生報告と事実関係を明確にするための調査が義務付けられている。文科省が策定した基本方針では、欠席日数について「年間30日を目安」とされている。
代理人弁護士らによると、被害女児は21年4月ごろから、同級生の女児から登下校時を含めて学校で一日中付きまとわれたり、悪口を言われたりした。同年6月から休みがちになり、不眠や腹痛、吐き気を訴えるようになった。母親が付き添って登校することもあったが、5年生になっても不登校が続いていた。
母親は、付属小に同級生への指導を求めたものの、状況が改善されていないとして、23年1月13日に校長らと面談。同法に基づいて学外の第三者による調査を求めたほか、文科省への報告状況も尋ねた。これに対して校長は「22年5月30日に大学から報告した」と説明。23年1月24日には文書で「第三者委員会による調査の必要は無いと判断しました」と調査を拒否した。
その後、母親が同法に基づく手続きが行われているのかを改めて確認したところ、付属小は23年2月17日、21年11月に重大事態として認知したとメールで回答。文科省への報告については1月の面談時と変わらず「22年5月30日」とした。
ところが、母親が文科省に対し、重大事態の発生報告の記録を23年2月2日に情報開示請求したところ、3月3日付で「保有していない」と学校側の未報告が疑われる通知があった。
母親は同17日に茨城大教育学部の副学部長2人と面談。この際、文科省への報告について改めて確認すると、実際の報告日は、開示請求後でメール前日の2月16日だったと認め、同法に基づいた調査を実施していないことも明らかにした。
茨城大は6日、毎日新聞の取材に「付属小及び教育学部において、いじめ防止対策推進法などの諸制度に対する認識が不足していたため法人及び文科省への報告などが不十分であった。不適切な内容を保護者に説明していた」などと文書で回答した。【森永亨】
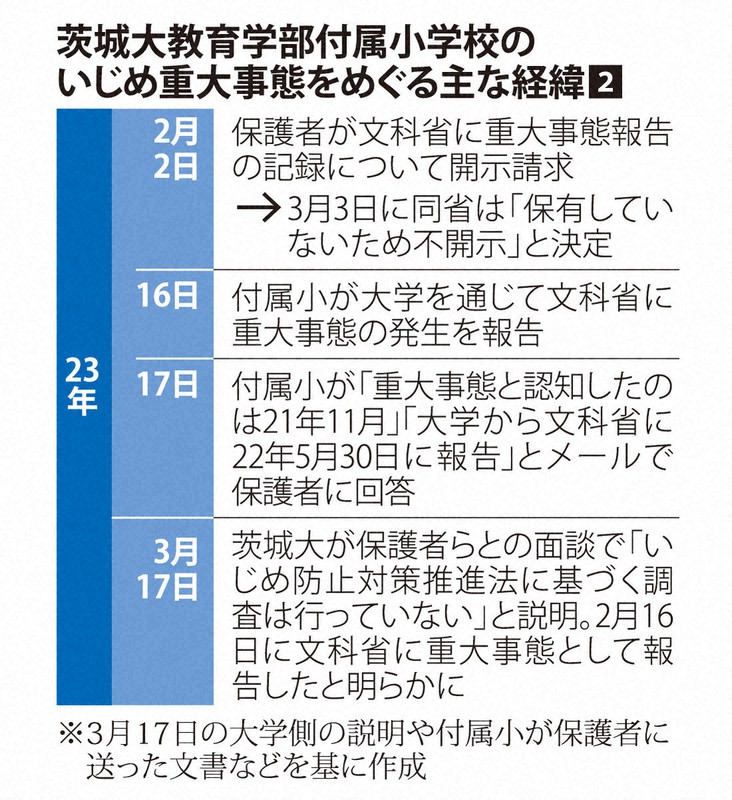
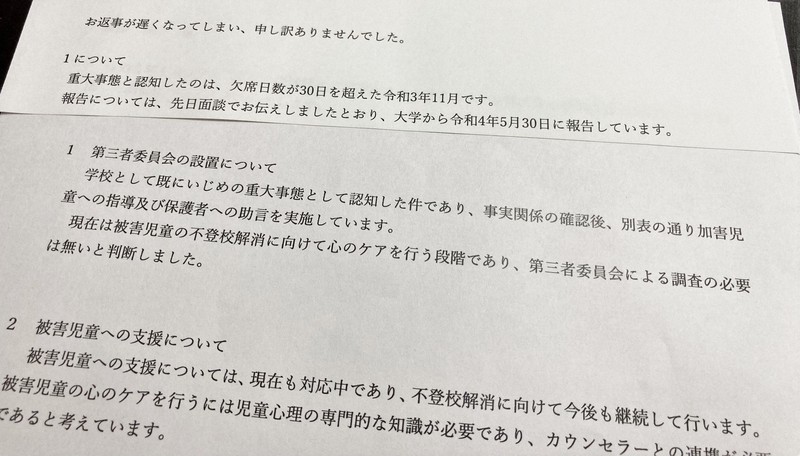
21年4月から発生した同級生からのいじめと6月からの不登校を、認知しながら翌年5月末に文科省に届けたと親にウソの報告。何の対応もされないので、今年2月にいじめられた親が文科省に問い合わせ、3月に届いていないと文科省が答えたので露見。
上記が事実なら完全に嘘。「保護者にも誤った説明」とオブラートで包んだ表現を使うメディアも噓付き達の仲間だと思ってしまう。メディアはなぜ上記が事実ならニュースとして書かないのか?日本のメディアにもいじめ問題の責任があると思う。もし、文科省が踏み込んだ対応を取らないのなら、多分、日本のいじめ問題は建前のだけの対応で結果を出す意思がないと思う。ところで、文科省は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)のけんではしっかりと仕事をしているのか?
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
ffh*****
21年4月から発生した同級生からのいじめと6月からの不登校を、認知しながら翌年5月末に文科省に届けたと親にウソの報告。何の対応もされないので、今年2月にいじめられた親が文科省に問い合わせ、3月に届いていないと文科省が答えたので露見。
学校の対応はあまりにも酷い。
ただ不祥事を隠そうとしたのか、それともいじめた方の親への忖度か?
これから第三者委員会設置されて対策がなされるのを期待したい。
しかし、少なくても校長をはじめ学校関係者は社会的責任を取る事になるだろう。隠すことは自分の為にも生徒の為にもならない事を肝に命ずるべきだ。
ko*****
またか。
全くこれまでの過ちが活かされていない。
事なかれ主義、ウチの学校にイジメなんて存在しないというテイを保ち、経営者や教員らが自らの保身に走る。
何と愚かで醜いのか?
学校側がイジメは無いとしていた事例で、後にイジメが発覚した場合には、関係者は懲戒免職になるくらいの法律を作るべきではないか?
残念ながらイジメは無くならない。
そして、教師や親の質も上がらない。
ならば、イジメを隠蔽することが自らの保身にならないようなシステムにしないと、この問題は解決しない。
xra*****
再発防止とかではない。
世の中これだけいじめ問題に対して取り組んでいるにも関わらず、認識の薄さは現場の教育者の問題でもある。
附属の小学校が何やってんの?と思う。
恥ずかしいことだよ。
meo*****
いじめた側の親や祖父母が、その土地のお偉いさんだったりしたのかな。
教育大附属の学校なんて、親御さんが医者や弁護士や教師やエリートサラリーマンだらけで、これ以上ないぐらい、勉強できる環境整ってるだろうに。
いじめ自体をこの世からなくすことは恐らく不可能なのだが、こんなエリート校ですら、およぴ腰にしてしまうものなんだな。
smile***
こんな学校は廃校にすべき。迷惑。
いじめで児童の不登校が続く「重大事態」文科省に報告せず 保護者にも誤った説明 茨城大学附属小学校 04/07/23(ABEMA TIMES)
茨城大学附属小学校が、いじめを理由に児童の不登校が続く「重大事態」があったにもかかわらず、文部科学省に報告していなかったことがわかった。
【映像】いじめ「重大事態」文科省に報告せず
水戸市にある茨城大学教育学部附属小学校は、おととし11月に児童がいじめを受け不登校になっている「重大事態」を認識していたにもかかわらず、文科省に報告していなかったという。いじめを受けた児童の保護者に対しても誤った説明をしていた。
茨城大学の太田学長は第三者委員会を速やかに設置し再発防止に取り組むとしている。
永岡文科大臣は閣議後の会見で「仮に報道であるような対応がされていれば極めて遺憾。事実関係を確認した上で必要な対応を取っていきたい」と話した。
(ANNニュース)
教育現場のトップや管理職達が腐っているから、このような事になる。嘘を付いてもバレなければ大丈夫と教育関係者が考えるから、問題のある教員達を切れない、真面目な教育者達が報われない。
北海道の女子中学生の凍死の件もあるし、今回は国立大学付属学校なので徹底的に調査して、隠ぺいしたり、口裏合わせをする人間は重い処分を下すべき。
嘘を付かない。能力とは関係なく、この基本が出来ない管理職やトップは必要ない。切るべきだと思う。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
asa*****
保護者の情報開示請求後の2/16に後追いで学校側から文科省へ報告が行ってるわけですよね。
報告書に現時点までの状況を時系列で記載してあれば言語道断の対応が明らかであるし、重大事態に至った経緯しか記されていなければ「何で今頃出してきたんだ!」と事態の経過も含めて学校側に確認を行うのが普通ではないでしょうか?
3/17に保護者が副学部長2人と面談して、重大事態への対応を怠り虚偽の説明をした不祥事が明らかになり、当然それも文科省に要報告の案件と思えますが、大臣の口ぶりだと把握出来ていない感じですね。
とっくに文科省が調査に乗り込んで不祥事を把握してなければ遅過ぎと言えるくらいです。
全国の学校に「いじめ防止対策推進法」制度の運用について一斉調査を実施する必要に迫られるくらいの不祥事のように思えますが。
tom*****
子供の都合ではなく、大人の都合でことが運ぶからこうなる。
いじめる側の家庭環境などにも大きな問題があるケースが多々ある。しかし、その親は自分の非は絶対に認めない。先生方も、自分の立場を守るために問題を避けて通る。
全員が「何かのせい」にしたがって、問題と向き合おうとはしない。
私も遠い昔の小学生時代にいじめを受けたが、担任の先生は見て見ぬふりだった。田舎の小さな小学校では私の居場所は無かった。
只野
大臣、本気で調査してください。これまでの附属学校で起きたいじめも全て調査してください。附属学校に期待して入学された全ての子どもと保護者が不安を感じています。
報告せずに隠蔽していた事実などあるのであればきちんと責任者を処罰すべき!謝って許されるなら警察入りません。
xra*****
深刻な問題として受け止める?
深刻な問題でしかないわ。
時すでに遅し。
隠蔽と思われてもしょうがないし、教育者としていじめに対する認識が低いのは間違いない。
ski*****
「文科省に重大事態として報告した」と事実と異なる説明をしていたのなら、報告の遅れではなく虚偽説明だろ。
茨城大付属小のいじめ未報告「極めて遺憾」 永岡文科相 04/07/23(毎日新聞)
茨城大教育学部付属小学校(水戸市)がいじめを理由に女子児童の不登校が続く「重大事態」を認定しながら、文部科学省に報告しなかった問題で、永岡桂子文科相は7日の閣議後記者会見で「仮に報道であるような対応がなされていたとすれば、極めて遺憾」と述べ、茨城大側への聞き取りなどをする考えを示した。
学校側が女児の保護者に示した文書などによると、2021年11月、当時4年生の女児について、いじめを理由に長期欠席する「いじめ重大事態」と認定。いじめ防止対策推進法は、重大事態と認定すれば、国立大付属小の場合は文科相に報告するよう求めるが、約1年3カ月にわたり報告しなかった。また、その間に保護者には「文科省に重大事態として報告した」と事実と異なる説明をしていた。
茨城大は7日、毎日新聞の報道などを受け、太田寛行学長名で、ホームページに談話を公表。文科省への報告の遅れなどについて釈明し「これらの事態を招いた要因として、ガバナンスに関する深刻な問題があると考え、状況を厳しく受け止めている」などとし、6日には、被害児童や保護者に謝罪したことも明らかにした。
【深津誠、森永亨】
テレビ朝日
茨城大学の太田学長は第三者委員会を速やかに設置し、再発防止に取り組むとしています。
第三者委員会の設置などたいそうな事をしなくても、誰の指示や判断でこのようになったのかわかっているだろう。広島県教育委員会みたいに税金を溝に捨てるような事をするな。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
aoz*****
政治より教育関係の方が隠蔽は悪質だね。
茨城大付属小 いじめ「重大事態」文科省に報告せず 04/07/23(テレビ朝日系(ANN))
茨城大学附属小学校がいじめを理由に児童の不登校が続く「重大事態」があったにもかかわらず、文部科学省に報告していなかったことが分かりました。
水戸市にある茨城大学教育学部附属小学校は、おととし11月に児童がいじめを受け不登校になっている「重大事態」を認識していたにもかかわらず、文科省に報告していなかったということです。
いじめを受けた児童の保護者に対しても誤った説明をしていました。
茨城大学の太田学長は第三者委員会を速やかに設置し、再発防止に取り組むとしています。
永岡文科大臣は閣議後の会見で、学校の対応について「極めて遺憾」「事実関係を確認したうえで必要な対応を取っていきたい」と話しました。
テレビ朝日
同大は昨年5月、不登校などに関する統計調査の一環でこの問題を計上していたが、同法に基づく内容の報告は今年2月まで怠っていたとしている。大学側は「統計調査の報告が重大事態の報告を兼ねると誤認した」と釈明。重大事態と認定後、保護者に対しても「文科省へ報告した」と事実と異なる説明をしており、6日に児童と保護者に謝罪したという。
「事実と異なる説明」とは簡単に言えば嘘を付いたと言う事。それを認めない茨城大学は国立大なのにFランレベルだと思う。能力に問題があるのではなく、担当者や関係者達の人間性に問題があって、結果としてFランレベルの対応になったのだと思う。
文科省はこの説明を受け入れるのではなく、詳細な経緯を把握するために茨城大学教育学部付属小学校(水戸市)にまじめな職員を派遣するべきだと思う。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
…………
誰もが安心して、義務教育を受けれるような
学校の意識改革は待ったなし。
少子化対策が出産率を上げる事がメインなら
その発想は、途上国レベル。
kua*****
保護者への嘘が説明の誤りになるのか。教育に係る者の日本語能力に問題ありだな。
yas*****
教師や教育委員会の意識改革が「重大事態」なのよ
茨城大付属小の「重大いじめ」文科省へ報告怠る…小4女児が不登校、詳細調査もせず 04/07/23(あいテレビ)
茨城大学教育学部付属小学校(水戸市)が、2021年11月、いじめを理由に当時同小4年の女子児童が不登校となった問題を「重大事態」と認定しながら、いじめ防止対策推進法に基づく文部科学省への報告を怠っていたことがわかった。同大は「今年2月に報告した」としているが、永岡文部科学相は7日の閣議後記者会見で「事案の報告というのは全く受けていない」とし、事実関係を確認する考えを示した。
同大はこれまで、いじめの詳細な調査もしておらず、今後、第三者委員会を設置して事実関係を調べる。
同大によると、女子児童は21年からいじめを理由に不登校が続き、学校側は同年11月に重大事態と認定した。同法では、いじめが疑われる児童が相当期間欠席した場合などを重大事態と位置付け、国立大の付属学校に対し文科相に報告する義務を課している。
同大は昨年5月、不登校などに関する統計調査の一環でこの問題を計上していたが、同法に基づく内容の報告は今年2月まで怠っていたとしている。大学側は「統計調査の報告が重大事態の報告を兼ねると誤認した」と釈明。重大事態と認定後、保護者に対しても「文科省へ報告した」と事実と異なる説明をしており、6日に児童と保護者に謝罪したという。
同大は7日、ホームページで「制度への認識不足と保護者への説明の誤りがあった」と謝罪した。
多様性を考えたり、同じスペックの人間はほとんどいないと言う事を考えれば、絶対的な正解はないと思う。また、英語教育に関しても目的や目標が違えばやり方が違ってくると思う。英語は話せた方が良いが皆が話す必要はないと思う。一般的な日常会話なら高校2年レベルで十分。後はスポーツと同じように繰り返していく過程、又は、慣れるとそれなり話せるようになると思う。英語を第二言語として学ぶ外国人生徒を見て思ったことだが、生徒の国の文化や生徒の積極性が能力が同じであるのなら上達に影響すると思った。基本的に、よく話す文化の生徒、そして、自分の思いや考えを主張する事が当たり前の国出身やよく話す生徒は英語の上達が早い。日本人や日本文化で育った日本人は、間違ったらだめ、目立ったら嫌われる、自分の意見や考えを否定されたり、批判されたくないから何も言わない、人と衝突したくない、人前で意見を言う習慣がないなどのために英語の授業でも発言する日本人は少ない。結果、能力が高い人以外は、英語の上達が積極的な文化の国出身の生徒達と比べると遅い。
日本は文法や試験を重視するので、英語をコミュニケーションとして使うための教育になっていない。子供が英語の文法について聞いてくるが、結構、答えられない。テレビ、他の人が話すとき、英語の本を読む時に、そのような表現を聞いたことがない、又は見たことがないから違うんじゃないのか程度しか言えない。また、日本に住んでいたころは英語が嫌いで、テストの点も悪かったので、日本語での文法に関してどのように表現するのか知らない。相手が英語で話してくるから、英語で理解して英語で話すだけで日本語に訳しながら話しているわけではない。何を言っているのか日本語で説明してほしいと言われれば、内容を説明するだけで一字一句を訳していない。日本語で一語で何と言うのかわからなくても別の言葉で説明すれば問題ない事は多いし、ある言葉を使ってこの事と聞かれて、その言葉の定義を聞いて合っている、又は、かなり近いと判断すればそう言う事だと思うと言えば良いだけ。通訳を仕事としているわけではないので十分だと思う。
英語のネイティブと話しても、アメリカ人、イギリス人、オーストラリア人と国籍が違えば使う英語の表現や発音が違う。慣れていないと聞き取れなかったり、分からない事がある。日本だって、特定の地方で使われている表現を使われたら、日本人であっても理解できないのと同じ。また、英語が母国語ではない外国人と話す時は表現や発音が違うので、英語の問題ではなく慣れないと聞き取りにくい事はある。
日本語でも同じだが、相手が使っている言葉が正確とは限らない。嘘や過大な表現を使っている事だってある。それを見抜くのは経験だったり、いろいろな質問をして相手が本当の事を知っているのか確認したりする必要がある。嘘を簡単に付く人は会話に矛盾があったり、おかしい回答をしたりする。
スポーツにしても、慣れ親しむ事から入ったり、基本を徹底的に教えたり、楽しいと思えるような指導をしたり、いろいろなやり方があるように英語教育にもいろいろなやり方があると思う。プロを目指す人、スポーツをやりながらプロや特待生待遇を選択する人、プロを夢見たが諦める人、別の生き方を選択する人、親が英才教育を好きとか思う以前の段階から始めるなどいろいろなパターンがあるように、いろいろなやり方が英語教育で行えると思う。
バイリンガルと言っても、バイリンガルの定義はあまり日本では言われていない。帰国子女と言っても、英語やその他の言語のレベルは違う。日本語と英語が話せるケースでも、日本語が日本に住んでいる日本人と比べれば劣っていると思う事が多い。日本語しか使っていない日本人と比べる方が間違い。日本語しか使わない日本人と英語と日本語を通常の生活で使っている日本人ではそれぞれの言葉を使う時間が違う。そして言語能力も影響すると思う。日本で生まれ、日本で育ったら同じレベルの日本語を話すわけではない。理系と文系の違いだけで日本語の能力が違う。
最近では、英会話や英語の塾に行く子供の数も昔とは違う。同じような教育を想定すること自体が間違いだし、無駄だと思う。日本は平等とか、これまでのやり方にこだわりすぎだと思う。英語の教育に限らず、多くの子供が塾に行く時代に同じような教育を考えること自体が間違い。また、学生の大学でも学び方も改革した方が良いと思う。教室や教授や講師の数の問題もあるだろうが、合格者や定員を増やし、アメリカのように勉強しない学生、又は、試験で勉強しない学生は退学にすれば良いと思う。地方だから、塾に行っていないから多少、入試の点が悪くても、継続して学ぶ意志があり実行すれば、大学は卒業できると思う。そのような環境に大学を変えても良いと思う。特に地方の国公立大学で敷地にゆとりがあれば、少子化であっても定員を増やせばよいと思う。そして勉強しなければ留年や退学処分で良いと思う。積極的に学ぶ、又は、興味を持って何かを学ぶ学生にはチャンスを与えればよいと思う。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
*****
小5から教科化されたことにより、今の中学生が習う英語の文法や語彙の範囲は難化し、かつ幅広くなっています。
その上、主体的・協同的な学びの推進とやらで、答えを一足飛びで教えてもらって覚えるのではなく、自分たちで理解したものを応用していくような授業構成となっていて、先生も生徒も時間的な余裕がないです。
なので小学生のうちから三単現や進行形、助動詞や過去形の簡単な知識くらいはつけられると、中学生での負担は軽減でき、英語嫌いも回避できると思います。
そうした意味で、そういう学びができる環境があるのであれば小1などの早い時期から英語授業をやるのは悪くない、と思っています。
lov*****
英語教師です。
低年齢から外国語に触れるのはとっても大切だと思います。耳も慣れ、違った文化に触れる機会にもなるでしょう。
しかしもっと大切なのは母語である日本語への親しみ、理解、正しい読み書き、表現やことわざの知識ではないでしょうか。国語が苦手な生徒は英語が好きでも伸び悩みます。
ggm*****
保守派とかタカ派とか言われる自民党の一部議員が事もあろうに自身の票獲得のために反日の統一教会を支え、統一教会に賛辞を捧げるなんてブラックジョークにも程がある。 それが今の自民党の姿でもある。
lll....
小5から学校の英語がわからなくて悩んでました。先生は外国人、担任は英語がわからず相談する人がいないと言ってました。他の学びにあててほしいと言ってました。
中学に入ると1学期の最初はABCを書いてたけど急にどんどん進むカリキュラムのようです。指導要綱準拠の学校でこれだから一貫校は相当なものだと思います。小学校からやるのはいいのですが遊びの範囲でなくやってついてけない子の対応もしてほしいです。
dx685222
私は旗から見ると、英語ペラペラで問題なく外国人の英語を100%理解しているように見えるらしいです。たしかに英検も1級とりました。
しかし、実際は外国人によっては半分くらいしか言っていることがわからないこともあるし。どう説明していいか言葉が出てこないこともあります。
そういうときは、どうでもいい会話はいちいち聞き返さずスルーするときもあるし大事な部分だけ何度でも聞き直して理解する。うまく説明出来ない事はジェスチャーや図&イラストなどに描いて説明する(紙と鉛筆常備です)を徹底してます。だからいつも会話はスムーズです。
コミュニケーションって言語の要素が小さくて別のところにあると思います。
本当はこんなに英語の授業を頑張らせなくても教育の仕方次第でなんとかなるんでは?といつも感じる。
inori
早い方が良いですよ。
今の中高生は、中学からの英語教育だったり、変わったもののコロナ禍でカリキュラム通りに学級運営が出来ず、
英語の授業が削られてしまった世代なので、
いきなり受験英語に突入し、
英語嫌いになるケースが多々あります。
何語もそうですが、
言葉はコミュニケーションツールなので、本来、その習得は楽しいものです。
楽しく始める入り口は、
昨今の公立高校受験事情と、
そこから派生する私立中学受験加熱のせいで
小学生低学年のうちからやらないと
楽しむ時間がありません。
先生が教えられないために
ネイティブの専門教師が教えている点も、
お互いの気分転換になり、
大変良いです。
coc*****
授業とはいえ、身につける目的ではないのてしょう。他国の言語を学ぶと言う事はその国の文化を知ることだと思う。幼い頃から他国の文化に触れるのは良い事でしょう。
身につけるための勉強は、仕事とか受験とか留学とか、結局必要に駆られた時にしか出来ないというか、やる気にならないと思う。
saz*****
専門家は、「英語を早くから学びさえすれば効果がでるわけではない」と指摘する。」
専門家の方々がおっしゃるならば、そうなんでしょう?
それよりも日本の英語教育は、実践ではほとんど役に立たない
のが問題点だと思います。外国の方とコミュニケーション取っても
訛りのない英語は聞く方は理解できますが、喋れない人が多く結果として
役に立たない現実がある。
kat*****
英語好きとしては、早くから導入してもらう今の子達が羨ましいわ。
ただそれで英語が身につくわけじゃない事、理解しないと。勘違いする親が少なくないから。
あと、日本人先生のカタカナ英語発音が身についたら、やばいね。
私は自分で小5から英語勉強して、中学は私立だったから、週1にイギリス人の先生が来て、正しい発音が早くけら聞けたのはラッキーでした。
小1から英語授業、都内半数の自治体で 専門家「早いだけでは……」 02/16/23(朝日新聞)
小学校でも英語を学ぶようになって10年あまり。現在は3年生から「外国語活動」として学ぶことになっているが、実際はさらに早い段階から採り入れている学校も多い。朝日新聞が東京都内の49区市に聞いたところ、約半数で1年生から英語を学んでいることがわかった。
【写真】小学生の学びで大切なことは 言語教育の専門家が語る
専門家は、「英語を早くから学びさえすれば効果がでるわけではない」と指摘する。早期の英語教育にどう向き合えば良いのか。
■港区では週2回、品川区では「英語科」設置
調査によると、1年生から一律に英語授業や英語に親しむ活動をしていたのは24区市。授業数は年4回程度から週2回まで幅があり、内容も様々だった。
時間数が最も多かったのは、港区の週2回。外国人講師を各校に置き、区独自のデジタル教科書を使う。週1回の品川区も独自に「英語科」を設置。授業では基本的に、英語のみ話す。中央区と荒川区も週1回程度の授業があった。
2020年度に全面実施された学習指導要領では、3、4年生は「外国語活動」、5、6年生は教科としての「外国語」を学ぶ。
英語は早くから学べば、効果が出るのか。
日本社会と英語の関係を研究する関西学院大の寺沢拓敬(たくのり)准教授によると、多くの実証研究の結果、早く始めるだけでは効果がないことはほぼ通説だという。早期教育のさまざまな意義は否定しないとした上で、「授業時間や動機付け、教員養成など他の要因のほうがより重要だ」と話す。
問題が起きた時に在籍していた教頭も出席。「1人の被害者の未来より10人の加害者の未来が大切」などと発言したと遺族から指摘されたことについて、初めて釈明しました。
中学校の教頭
「保護者に対し、当該生徒をないがしろにし、加害生徒を擁護するような発言を行ったと言われる不適切な発言ですが、そのような発言はしておりません。保護者に対する説明において、私の言葉が十分に伝わらず、誤解を招いた部分がありましたら、その部分は申し訳ないと考えている」
個人的には具体的に「1人の被害者の未来より10人の加害者の未来が大切」などと遺族が勝手に言っているとは思えない。ただ、会話を録音していないのなら、この教頭なら嘘を付き続けると思う。
個人的にあるトラブルを経験したが、担当者と話にならないので問題を上まで持って行った。するとそのような事は言っていないと嘘ばかり。嘘を付いていると証明したかったが、相手がこちらの提案を飲んだので圧勝する事に拘らずに妥協した。別の件では、相手は謝罪するが、文書で事実を認める事は出来ないとこちらの提案を拒否した。この世の中、嘘を平気で付く人間はたくさんいると言う事を理解しなければならないと思う。相手が嘘を付いていると感じたら直ぐに証拠を取る事を考えるべきだと思う。ある公務員はある人物がそのような事は言わないと話を聞かないので、会話を録音した。その後の展開はスムーズに進んだ。ただ、相手が最悪の行動を取るまで証拠がある事は黙っている方が良いと思う。相手に嘘を出来るだけ言わせて、ひっくり返す方が相手は悪い人間であると説明する方が、他の人間を説得するには良い。
個人的には旭川市はあまり良くない地域である印象を受けた。もし他の学校関係者や教育委員会の人達がまともであれば、教頭をこのように好き勝手にはさせないと思う。似たような体質、又は、似たような環境の人々が集まっている可能性は高い。まあ、個人的に経験からの推測なので事実は知らない。実際に旭川市に住んでいる人達の方がどのような地域なのか知っていると思う。特に他の地域や県外から引っ越してきた人達は違う基準を持っている可能性が高いので、何らかの意見を持っている可能性は高い。同じ地域に長くいると何が常識なのか、何が普通なのか判断できなくなる事がある。
旭川いじめ問題 凍死した女子中学生在籍した学校で説明会「10人の加害者の未来が大切」…教頭が初めて釈明 11/18/22(朝日新聞)
去年、旭川の公園で凍死した状態で見つかった当時中学2年の廣瀬爽彩(ひろせ・さあや)さんへのいじめ問題で、爽彩さんが在籍した中学校と旭川市教委による保護者説明会が開かれました。
2時間以上にわたった説明会で語られた中身とは…。
18日午後6時すぎ、旭川市内の中学校に50人の保護者が集まりました。
中学校と旭川市教委が開いたのは、廣瀬爽彩さんへのいじめ問題に関する保護者説明会です。
およそ1年半ぶりに開催された説明会の音声データをHBCは入手しました。
中学校の校長
「当時を振り返って最も反省しなければならない点は、法の趣旨に基づき学校いじめ対策組織による組織的な対応が出来ていなかったことです」
説明会では第三者委員会による最終報告書の概要のほか、いじめに関する組織的な対応やほかの機関との連携などの再発防止策が説明されました。
しかし、質疑応答では保護者から厳しい声が相次ぎます。
保護者の男性
「質問とか言いたいことはいろいろありますけど、まず黙とうとかしなくていいんですか?亡くなられた生徒さんに対して黙とうとかしなくていいんですか?」
保護者の女性
「肝心なことがまったく取り上げられていないと思い、すごく気になっていて、それが性についての問題だと思う。子どもたちはゆがんだ性の知識と認識を持ったまま野放しにされているがゆえに、こういう事態が起きているというのが明らかに分かっているはずなんですけど」
また、問題が起きた時に在籍していた教頭も出席。「1人の被害者の未来より10人の加害者の未来が大切」などと発言したと遺族から指摘されたことについて、初めて釈明しました。
中学校の教頭
「保護者に対し、当該生徒をないがしろにし、加害生徒を擁護するような発言を行ったと言われる不適切な発言ですが、そのような発言はしておりません。保護者に対する説明において、私の言葉が十分に伝わらず、誤解を招いた部分がありましたら、その部分は申し訳ないと考えている」
保護者からは、生徒への説明会も実施するべきだとの声もあがり、校長は来月1日に生徒向けの説明会を開く予定だと明らかにしました。
参加した保護者
「取り組むという姿勢は、それなりのことは言っていましたけど。(説明には納得した?)それはなんとも。人の感じ方なので」
旭川市教委 野崎幸宏 教育長
「たくさんの皆さんの思いをいただいて、これからもいじめ防止に向けて取り組んでいきたいと思ったところです」
ようやく開かれた保護者説明会。問題をめぐっては、今月から市長直属の新たな第三者委員会による再調査が行われる見通しです。
11月21日(月)「今日ドキッ!」午後5時台
北海道放送(株)
先生の問題と言うよりは真面目で悩むタイプだから悩んでいると個人的に思える。
教師特有の問題はあると思うし、教師の世界は知らないから何とも言えない。ただ、個人的な経験から言えば、例え、経験が増え、知識が増えても、問題が簡単に解決できるわけではないと思う。いろいろな問題や他の人達の選択を知ると、他の人が選んでいるのからそれで良いのか、まともに仕事をすると問題になる、同じ選択でも立場が違う人達にとっては、良い事と評価されたり、好ましくないと評価されたりするケースがあるので判断や選択に迷う事がある。一般的に正しい選択だとしても、全ての人がその選択を望んでいるわけではない。良くない選択であっても特定の人達には好ましいと思われることがある。そして結果に対する責任が発生した時に、他の人達はあなたの判断とか、あなたに選択責任があったと逃げるケースがある。
仕事、会社、そして部署が違えばそのような経験をしないで済むかもしれないが、仕事や会社を変えても全く同じ問題でないだけで、別の形の問題が存在するかもしれない。
仕事を変えたら問題が解決するのかを考えて判断すればよいと思う。逃げる事が正解の場合はあるし、逃げても別の問題にぶち当たるだけの事はある。そして最終的には運と結果次第だと思う。
「先生を辞めたい」小学校教員の悲痛な叫びに、鴻上尚史が贈った「オンとオフ」と「スルー力」という言葉〈dot.〉 (1/3)
(2/3)
(3/3) 11/22/22 (AERA dot.)
「先生は、勉強を上手に教えられて当然、クラスをまとめられて当然」とのプレッシャーに逃げ出したくなる、と悲痛な叫びを投稿した32歳の小学校女性教員。励みになるような詩や言葉をいただきたいとの相談者の要望に、鴻上尚史が贈った言葉と詩とは?
【相談164】「先生」に対する世間のイメージに押しつぶされそうなことがあります(32歳 女性 トトロ)
私は、大学卒業後から公立の小学校で働いています。大変なことの方が多くて、なぜこんな思いをしてまで続けるんだと自問自答する日もありますが、やはり子供たちと過ごす時間がかけがえのない宝物だから続けてきました。
でも、この仕事を辞めようかと思っています。「先生」に対する世間のイメージに押しつぶされそうなことがあるからです。先生は、勉強を上手に教えられて当然、クラスをまとめられて当然、など、誰に責められたわけでもないのに、プレッシャーで逃げ出したくなることがあります。クラス分けをし、子供に圧力をかけて小さな枠の中に押し込むような、教育のあり方にも疑問があります。
今は発達障害という言葉も一般的になってきています。あんなに狭い世界にいることを強制されて、ついてこられない子供がいるのも当然だと思います。でも、集団からはみ出る子が一人でもいることを、許せない教師もいます。どんな方法をとっても圧力をかけて自分の言うことは聞かせるように躾ようとする人もいます。私は、それは恐ろしいことだと思います。プレッシャーから逃げたい自分と、今は現状を変えられないけれどこういう考えを持っている人間が一人でも教育現場にいることで、誰かの力になれるのかもしれない、と考える自分の両方がいます。どちらかというと、辞めて逃げてしまいたい……という気持ちが勝っています。
でも、自分に力がないから自信が持てずに逃げ出したくなるのだとも思います。とにかく本を読んだり、研修に参加して力をつけることで見えてくるものがあるのかもしれないと、必死に今もがいています。教育とは一体何なんだろうと思い悩みながらも、できることを日々がんばります。以前、女性の医師の方に贈られた詩が私の宝物です。まとまらない相談ですが、もし、何か励みになるような詩や言葉をいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
【鴻上さんの答え】
トトロさん。大変ですね。苦しみ、葛藤されているようですが、僕はトトロさんの相談を読んで、トトロさんのような人こそ、学校の先生であって欲しいと思いました。
僕は演出家をかれこれ40年近くやっています。その間、いろんな演出家さんに会いました。自信満々に俳優に命令を出し続ける人もいれば、いつも不安で俳優の顔色を窺いながらお願いし続ける人もいました。
いろんなタイプの演出家を見て、僕がなりたいと思ったのは、演出の指示をちゃんと出しながら、常に自分の演出を疑い、俳優やスタッフの声を聞ける演出家です。
ちゃんと演出の指示を出し(時には自信満々に見えながらも)、これでいいのか、もっといい演出はないのか、もっといい伝え方はないのかと、常に試行錯誤を続ける演出家になれたらいいなと思っています。
その意味では、「絶対の自信と安心」はないですから、不安になったり、迷ったり、プレッシャーに押しつぶされそうになります。でも、それは、より良い方向に変わるために必要なことだと腹を括っています。
トトロさんが「教育とは一体何なんだろうと思い悩みながらも、できることを日々がんば」るように、僕もまた「演出とは一体何なんだろうと思い悩みながらも、できることを日々がんば」るだけなのです。
「本を読んだり、研修に参加して」トトロさんが力をつけようとするのは素晴らしいことだと思います。
ただ、僕が心配するのは、トトロさんの文章から、トトロさんがとても真面目なんじゃないかということです。ちゃんと生活でオンとオフを使いわけていますか? 仕事の時は、オンですが、休みの時はすべてを忘れてオフになっていますか?
俳優さんの中にも、とても真面目な人がいて、稽古休みの時も休演日の時もずっと芝居のことを考えている人がいます。あまりに深刻になったり、対象に対して距離が近くなると、見えなくなってくるものが生まれます。ですから、そういう人には、僕は「明日の休みは芝居のことはいっさい考えない。温泉でも海でも遊園地でも行って、どーんと遊べ!」と言ったりします。
あと、プレッシャーを意識しすぎる時は、穏やかにかわす「スルー力」も必要だと思います。トトロさんが書くように、「勉強を上手に教えられて当然、クラスをまとめられて当然」というプレッシャーを感じた時に、「がんばろう」と思う時もあれば、「そうねえ、そうなれたら素敵ですよねえ」とノンキに答えて、息をつけるテクニックを身につけられたらと思います。
僕は演出家として、あまりに大規模で「成功して当然、お客さんが入って当然」という大プレッシャーの作品を演出する時は、割と簡単に「僕一人の力では、完全に無理なので、どうか助けて下さいね」と各部署に言って回ります。言われた方は、演出家がわざわざ来るので驚いた顔を見せることが多いですが、悪い気はしてないと思います。
さて、トトロさん。「何か励みになるような詩や言葉」ですね。言葉は「オンとオフ」と「スルー力」です。
詩は、例えば、谷川俊太郎さんのこんな詩はどうですか?
冬に
ほめたたえるために生れてきたのだ
ののしるために生れてきたのではない
否定するために生れてきたのではない
肯定するために生れてきたのだ
無のために生れてきたのではない
あらゆるもののために生れてきたのだ
歌うために生れてきたのだ
説教するために生れてきたのではない
死ぬために生れてきたのではない
生きるために生れてきたのだ
そうなのだ 私は男で
夫で父でおまけに詩人でさえあるのだから
最後の二行を、
「そうなのだ 私は女で
(トトロさんの立場で、例えば)娘でおまけに教師でさえあるのだから」
と口ずさむ時に変えても、谷川俊太郎さんはきっと許してくれると僕は思っています。
■本連載の書籍化第4弾!『鴻上尚史のなにがなんでもほがらか人生相談』が発売中です。書き下ろしの回答2編も掲載!
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
*****
本来学校がここまではどっぷりと入る話ではないんだよな。内容からすれば警察が介入すべき案件だった。
今となっては学校がいじめや原因を認めるか認めないかという機関になってしまい、捜査権もないものだから答えが出ていない。
学校を守る、生徒を保護するという意識も働いたのだろう。中立的な視野に立てないことで火に油を注ぐこととなってしまっている。
今からでも遅くはないので、捜査を警察に預けて、加害者を特定する。偽証している人間もあぶり出す。いじめがあったかなかったかという話ではなく、刑事事件として扱う必要があると思う。
mih*****
学校内や学校外でも、その学校に所属する生徒間の問題については、原則として担任→校長→教育委員会→警察へ相談するルールがあるそうです。
子供が中学生の時、学年崩壊していつ誰が命を落としても不思議じゃない状況に陥り、担任へ相談しても埒が明かず、あまりの酷さに耐えかねて「今後は学校外で起きたことについては、加害生徒をその場で警察へ突き出す。」とはっきり言った時、担任と校長から言われました。
その後、学校内でうちの子含む2人の生徒が2週間以内に立て続けに自殺未遂したので、否応なく警察が介入することになりましたけど。
zaf*****
学校側より、すでに警察案件。
希死念慮の意味をわかっているのだろうか。
被害者がそんな事を望むのか。
まったくありえないだろ。
もし希死念慮という言葉を使うなら、希死念慮に至ったすべての原因は加害者だったと言えるのではないか。
また、今回の内容を拝見すると、全く他人事のようで、この関係者たちは人を教育できる能力、道徳がないと証明している。
参加者から黙祷を言われてしまうのもありえません。
何も反省していない関係者たちは、早く終わらせたい一心だろう。
まずは加害者をしっかり処罰する必要があるのでは。
教育者以前に人として、失格だろうと思います。
dnf*****
「第三者委員会はいじめの事実を認定。性的なイジメ、深夜の呼び出し、おごらせる行為など中学校の先輩7人が関与した6項目をイジメだった」
と書かれていますが、それは強要罪、恐喝罪など、犯罪行為に抵触しないのでしょうか?
「イジメ」の定義は曖昧で、その言葉で犯罪行為が雲隠れしてしまうのは問題です。
公務員は犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないとされています。
「イジメ」という都合のよい言葉により、告発する義務がないという解釈をしているのではないでしょうか?
それは「イジメ」という言葉に疑問を持たずに多用しているマスコミの責任もあります。
人を精神的に追い込む行為については傷害罪、更に自殺に追い込む行為については傷害致死などの判例がされれば、行為者のみならず、関係者各位の今後の対応も変わるのではないでしょうか?
feb*****
本来、いじめやハラスメントという言葉は、犯罪に触れない程度の「いやがらせ」を指すのだと思う。
傷害や強要、脅迫、逮捕監禁等、明確に刑法犯にあたるのに、それをごまかす意図で使うから、初動を誤るんだと思う。
学校は事態を把握したら、警察に相談したら良い。
ちゃんと刑事事件として警察が捜査して、学校は捜査に協力する立場で良いのに、自分たちだけでごまかそうとするから問題になる。
ray*****
「ゆがんだ性知識を持つ生徒が野放しに」との危惧は本当に深刻だと感じます。
旭川警察は触法少年を理由に一旦とはいえ幕引きが早過ぎます。
この事件と同時期に隣県で未成年による児童ポルノ強要事件が有り、加害者は刑事罰を問える15歳だったが警察はあまりに悪質だとして出来る限りの追及をしていました。
被害者と御遺族は早い段階で学校と市教委に相談していた事も、どのような対応をされてきたかも何度も報じられていて、状況が悪化してからの話し合いの場に弁護士の同席を拒否もされていました。
順番が違ったところで学校側が警察の介入を素直に許すとは考え難く「〜出来る筈だ」「〜すべきだ」を気楽に言える事件ではありません。
dop*****
学校側が警察の介入を素直に許すとは考え難く
↑
現行法では、学校が拒否しても警察は強制的に捜査できます。
tya*****
この問題は学校だけでなく、警察、いじめ相談、医療機関等も含め、さあやさんにかかわった大人たちになんらかの問題があったように感じる。これらの機関の連携の在り方や各機関の反省点も明らかにされるべきものだと思う(この調査委員会の枠内かどうかは不明だが)。
ただ、記事の「希死念慮」という言葉が気になってしまった。
さあやさんに「自殺願望があった」と判断した根拠は何なのだろうか?
自殺未遂も、ニュース記事によると自殺願望からではないと思われるのだが。
この言葉から報告書の信頼性に疑問が出てしまうのではないかな。
コメントには警察案件にするべきだったと多くの人が書いているが、自分の記憶が正しければ警察官件になっていたと思う。だから、閉鎖的な旭川市だから地元の有力者の子供が関与しているのではとか書いている人がいたと思う。警察が介入したがらないかったのか、管轄の警察署に誰かから圧力があったのか、その点については詳しい記事はなかったと記憶している。
旭川14歳少女凍死は本当に学校、教師達、そして教育委員会だけの問題なのか疑問だが、記事からしか判断できない。個人的には爽彩(さあや)さんが担任や教頭との会話を黙って録音していたらこのような状況にはならなかったかもしれないと思うが、公務員や警察は信用できないと強く思う経験をしていなければ、そのような事を思いつかない可能性は高い。人間、話せば分かりあえるは綺麗事。話せば理解しあえる人達はいるが、全ての人に言える事ではない。人が約束と言っても信用してはいけないと思う。誰がその言葉を言っているのか、その人の人間性を知っているのかなど条件がかけていれば嘘を付いている可能性を疑った方が良い。もし嘘を付いているのなら、いくらか質問したらつじつまの合わない回答が帰ってきたり、回答に息詰まると思う。もしそうなったら信用に値しない人間と判断した方が良いと思う。
個人的な経験から言えば、自分のサイドであると思えない人達は5割以上で嘘を付く。真面目な人だと嘘ではなく、コメントできないとか、その件では発言する必要はないとか言うケースが多い。運が悪いから自分のような経験や考え方になるのかもしれないが、爽彩さんのような最悪な事が起きてからでは遅い。基本的には性悪説を基本に対応すれば疑念を抱いた時点で次の行動を取れると思う。
《旭川14歳少女凍死》「ゆがんだ性知識を持つ生徒が野放しに」「彼女には希死念慮があった」ようやく開いた保護者会で学校と市教委が見せた“当事者意識ゼロ”【音声データ入手】 (1/3)
(2/3)
(3/3) 11/19/22 (文春オンライン)
《旭川14歳少女凍死》“被害者母”が明かした学校や加害者への“言葉にならぬほどの無念”「娘は軽い気持ちで死を選んだわけじゃない」【最終報告書公表も再調査へ】 から続く
【画像】爽彩さんは裸の画像をいじめグループによって拡散された
「学校からも市教育委員会からも終始、爽彩(さあや)さんへの謝罪の言葉はありませんでした。第三者委員会の調査の報告もただ資料をかいつまんで読み上げるだけ。当事者意識が一切感じられませんでした。この学校に子どもを通わせている身として、こういった学校と教育委員会の杜撰な対応は不安しかありません」
11月18日、北海道旭川市にあるY中学校で行われた保護者説明会に参加した保護者はため息をつきながら語った。
ようやく開かれた「重大事態」についての保護者説明会
2021年3月、旭川で当時14歳の廣瀬爽彩(さあや)さんが凍死して見つかった事件に関し、文春オンラインはその背景にあった凄惨なイジメについて報じてきた。第三者委員会はいじめの事実を認定。性的なイジメ、深夜の呼び出し、おごらせる行為など中学校の先輩7人が関与した6項目をイジメだったとした。しかし、爽彩さんの死は「自殺と考えられる」としたものの、イジメとの因果関係については認定しなかった。
そして18日、旭川市教育委員会は第三者委員会の調査報告を受け、「本件重大事態の事実経過とともに、学校のいじめ防止対策や生徒の安全確保の取り組みなどについて」保護者に説明する場を設けた。文春オンラインは約2時間に及ぶ説明会の音声を入手。その音声には、市教育委員会の対応に保護者の不信感が渦巻く険悪な空気が記録されていた。
午後18時過ぎ、既に凍えるような寒さの季節となった北海道旭川市のY中学校。昇降口には多くのマスコミ関係者がカメラを構え、校舎の回りでは男性教員が見回りをするなど物々しい雰囲気を醸していた。集まった保護者の多くは待ち構えるマスコミを避けるように足早に校舎の中へと消えていく。
説明会の会場には市教育委員会から4人、そしてY中学校の校長や教頭など5~6人が保護者を待っていた。第三者委員会の調査の結果に関する報告という趣旨であったが、教育委員会の説明はあまりにもお役所的な内容だったと前出の参加者は語る。
「受付で渡された160ページ以上の資料をかいつまんで読み上げていました。広い体育館の中で延々と約30分にわたって資料を読み上げる姿にはどこか他人事のような印象がありました。もちろん、言葉では我々保護者や生徒に『ご心配をおかけしていること』については謝罪していましたが、遺族や亡くなった生徒への哀悼の言葉はありませんでした」
教育委員会側はイジメと認定した6つの項目について説明するものの、それらが爽彩さんの死と関係しているとは断定できないとした。その理由として、「当該生徒には希死念慮があった。その希死念慮とイジメの因果関係を証明できなかった」と説明し、イジメと自殺との関係を断言しないままに終わった調査結果をなぞった。
続いて、Y中学校の校長が「ご遺族、保護者へのご心痛をかけたことを申し訳なく思っている。大変重く厳重に受け止め反省している」と語り、学校内のおける再発防止策について語った。
黙祷もしないんですか?
「再発防止策は4つの柱を立てています。一つ目は、いじめ事案の原因の調査と組織的な対応を行います。二つ目は、いじめ全校指導への取り組みを計画的に進めてまいります。三つ目は、生徒の自己優良感、自己肯定感を高め、思いやりの思考の充実を図ります。四つ目は、家庭、地域、行政との連携強化を図り、各方面との連携のもと組織的な対応を行っていきたいと思っております。
今回の報告書にあるいじめ防止等対策委員会の言葉を重く受け止め、いじめの対応に真摯に向き合い教育の充実に全力を尽くす所存です」
質疑応答では、最初に挙手した男性が怒りをこらえたような声でこういった。
「黙祷はしなくていいんでしょうか。反省しているとおっしゃっていましたが、それなら教育委員長が音頭をとってやるべきではないでしょうか」
これに対し、教育委員会は「大変失礼しました。それでは、亡くなった生徒に哀悼の意を示したいと思います」淡々と返答した。保護者の呼びかけにより、開始から50分以上経過してようやく爽彩さんへの黙祷がささげられた。
市教育委員会と学校が示した再発防止策に対して、不満を持つ保護者は「やっとひらいていただけた」と声を震わせながら語り出す。
「今回の再発防止策には性のことが一切書かれていません。今まで学校教育の中で性教育をきちんとやってきませんでした。今回、ゆがんだ性の知識を持った生徒が野放しになっていることが分かったと思うのですが、学校教育の中で学びなおすのを今後の課題に入れないともっとひどくなると思います。こういったことを教えていくことが、本当に子どもたちの命を守っていくことに繋がっていると思います」
加害生徒が爽彩さんにわいせつ画像を撮影して送るようSNSで強要したことなどを踏まえた発言である。これに対し、市教育委員会と校長はこう答えた。
「ここの中学生は白い目で見られる」
「昨年度から国が作った教材で性教育を始めたところです。より具体的に性に関することやSNSに関することを学べるプログラムを持つことを検討しています」(市教育委員会)
「保健体育やSNSに関する授業で性の尊厳を守る取り組みができる場面があると思うので検討していきたいと思います」(Y中学校校長)
保護者の中には「ちゃんと調査したのに再調査をしなければならないのか。Y中学校の生徒ということで白い目で見られる。いつ終わるのか」と平穏な日常を切望する声も挙がった。それに対し、直後に挙手した保護者は正反対の発言をしていた。
「(被害者が)自分の子供だったら悔やんでも悔やみきれない。この事件を解決しない限り、旭川からはいじめは撲滅できません。ぜひ徹底的にやっていただきたい」
文春オンラインでは、爽彩さんの母親が担任の教員にイジメについて相談したところ「デートなので」と断られたことを報じた。このことに対し、ある保護者は「一部の間違った認識の教員がいる」と指摘した。
しかし、市教育委員会はその発言の事実を否定していた。
「担任の先生については、デートを理由にして断ったことは、教育委員会は本人に確認しました。本人はそのようなことを言った事実はないと言っています」
また、加害生徒が所持していた爽彩さんのわいせつ画像を教頭が自らが確認し、自身の携帯で撮影したことや、遺族に対し、「10人の加害者の未来と、1人の被害者の未来、どっちが大切ですか。 1人のために10人の未来をつぶしていいんですか」と発言したことも文春オンラインは報じている。しかし、この発言についても学校は否定した。
説明会に出席していた教頭自らが回答していた。
「報道で誤解を与えたら申し訳ない」
「遺族や保護者のみなさんに多大なる心痛とご負担をかけた事をお詫びいたします。当該生徒の性的な画像を撮影したという事実はありません。報道を受けて警察にスマホを提出し、検査した結果、該当なしとなっています。遺族に対しての不適切な発言もしておりません。保護者への対応は複数の教員で対処し、その都度教育委員会に報告しています。
この件に関しては、第三者委員会にもあらゆる資料を提出しています。誤解を招いている分がありましたら大変申し訳ないと思います。いじめを把握し、適切に対応できなかったこと、教員を管理監督する立場にいながら指導の適切さを欠いたことは深く反省しています」
こう回答していた教頭の様子を、前出の参加した保護者が描写する。
「話を振られると用意された紙を読み上げていました。おそらく最初から回答を用意していたんでしょうが、聞かれなければ話すつもりはなかったのでしょう。機械的に読み上げている感じで、反省しているような印象は受けませんでした」
市教育委員会とY中学校は謝罪や反省の言葉は何度も口にしながらも、あくまでも組織的な問題点しか言及しなかった。教員をかばう姿勢は変えず、イジメと自殺の因果関係にも踏み込まない。前出の参加した保護者は最後に「これじゃあ、前の保護者会と変わらないよ」とため息をついていた。
被害者と遺族の無念が晴れる日はまだ遠い――。
「文春オンライン」特集班/Webオリジナル(特集班)
旭川・中2いじめ凍死問題、尾木直樹さんが第三者委メンバーに…11月中にも新たに立ち上げ、遺族の意向など受け再調査 11/17/22(HBCニュース)
北海道旭川市で、いじめを受けていた当時、中学2年の女子生徒が凍死した問題で、市は、再調査のために設置する新たな第三者委員会のメンバーに、教育評論家の尾木直樹さんらを起用する方針を固めました。
旭川市が起用の方針を固めたのは、法政大学の名誉教授で「尾木ママ」の愛称で知られる教育評論家、尾木直樹さん。
もう1人は、筑波大学の教授で、思春期、精神病理学を専門とし、いじめ問題の著書もある斎藤環(たまき)さんです。
2人の起用について市は、地元とのしがらみがなく、いじめ問題の調査経験や若年層の心理に詳しいためなどとしています。
尾木さんは、大津市のいじめ自殺問題でも第三者委メンバーを経験
尾木さんは、いじめを受けて自殺した、滋賀県大津市の中学2年の男子生徒をめぐる第三者委員会でも、メンバーを務めた経験があります。
公園で凍死していた廣瀬爽彩さんの問題では、調査した第三者委員会が最終報告書で、廣瀬さんに対するいじめは認めたものの、自殺といじめの因果関係は認めませんでした。
こうした結論を不服とする廣瀬さんの親族の意向を受け、市は11月中にも新たな第三者委員会を設置し、再調査することを決めていました。
いじめを受けていて、公園で凍死した廣瀬爽彩さん
一方、廣瀬さんがいじめを受けていた当時に通っていた中学校では、18日夕方、保護者向けに、第三者委員会の最終報告書についての説明会が開かれる予定です。
<第三者委員会が認定した、いじめ6項目>
1.性的な話題をくり返す、体を触る
2.深夜や未明の公園などへの呼び出し
3.飲食代をおごらせる
4.性的な画像の送信の強要
5.性的な行為の強要
6.性的なからかい
※関与したのは、同じ中学と他の中学の上級生の男女7人
11月17日(木)午後2時10分配信
北海道放送(株)
教員不足が深刻な都道府県はどれだけあるのか知らない。教員不足が深刻な都道府県は小規模な学校と大きな学校でオンライン授業が可能なのか文科省に問い合わせて問題ンがなければ実行するべきだと思う。
小規模な学校はタブレット端末やPCなどを都道府県の負担で支給して同じ県、又は、他の県で授業の動画をオンラインで提供してる場合は許可を取って生徒が見れるようにすれば良いと思う。特に算数、数学そして英語は生徒にやる気があれば問題なく学習できると思う。大きな学校では理解度や能力で受ける授業を決めれば良いと思う。
体育、音楽、そして実験が伴う理科や化学は教科によってはオンラインは難しいと思う。そのような教科はこれまで通りで良いと思う。
ただ、必要な教育が提供できない国の将来は暗いと思う。教員不足の問題は簡単には解決できないと思うので、オンラインとの実際の授業のハイブリッドで考えていくべきだと思う。
教員不足深刻 5月で小中高15人 さらに増加、教頭が担任の学校も 11/18/22(朝日新聞)
山梨県内の公立学校で教員不足が深刻となっている。県教育委員会の5月時点の調査では、小中高校の15校でそれぞれ教員1人が未配置で、前年同時期の2校から大幅に増えた。さらに年度途中で、産休や病休に入った教員の代わりが見つからずに、教頭や主幹教諭が担任を兼ねる学校も出てきている。
県教委の調査によると、本来必要な数の教員が配置できていなかったのは小学校3校、中学校8校、高校4校の計15校。それぞれ1人ずつ足りなかった。急な退職や休職などに対応できなかった例が多いという。ただ、担任が不在となったケースはなかったとしている。
前年度は、小学校1人、高校1人の計2人だけだった。
教員不足が生じる理由として、県教委は、代用を務める臨時的任用教員が見つからなかったことを挙げる。定年となる教員の継続希望者はすでに、再任用の形で配置計画に組み込まれている。そのため、教員採用試験で採用されなかった人たちの中から臨時的に任用するが、受験倍率が年々低下しているうえ、「すでに就職している」などと断られるケースもあって確保が難しいという。
この調査は5月時点のみで、その後の不足数は把握されていないという。そのため、教員が計画通り配置されても、その後教員不足が深刻化する例もある。
実際、前年度の途中に体調不良や家族の介護などを理由に57人(小学校42人、中学校13人、高校2人)が退職し、教頭や主幹教諭が担任を兼ねた学校もあった。
県内のある小学校では、教頭と主幹教諭が担任を兼任し、校長も一時は授業を担当した。この校長は「教頭や主幹教諭は担任の仕事が終わった後、本来の仕事もこなしている。臨時職員を見つけるのは校長の仕事だが、どこにいるのかわからず、闇を手探り状態」という。
新年度がスタートした時点では、教員の配置は定数通りだったが、心身の不調で担任が1人外れ、産休などで職場を離れた教員もいた。校長が代わりの臨時教員のなり手を探したが、「授業はできるが担任は無理」という人が多かった。ほかの校長に尋ねてもみたが、「うちがほしいぐらいだ」と手いっぱいの状態を説明されて断られたという。
教員不足は全国的な問題で、文部科学省は昨年度初めて山梨県を含む全国調査を実施した。その結果、公立小中高・特別支援学校で計2065人が足りなかった。千葉県は県内教員の不足数を毎月調べており、昨年5月時点で135人の不足だったのが、9月には倍以上の281人になり、この1月には324人にまで増えたという。
山梨県教委は5月時点以外の教員不足数を調査する予定はないというが、この校長は「山梨でも年間複数回の調査をして実態を把握し、対策を講じてほしい。このままでは数年後には学校が崩壊する」と危機感を募らせる。(米沢信義)
日本の教育は軍隊式の影響がある教育で圧力で締め付け、我慢を押し付けて、会社の歯車になるようなシステムだったと自分が読んだニュースや記事で思うようになった。そして古い体質と古い体質を経験し、体罰が許され経験してきた体育系の教師のように悪い事や間違っている事でも許されると思っているのと同じように、新しい事を取り入れない文科省、地方自治体の教育委員会、そして実際に教育する教諭や管理職の教育関係者が問題の一部だと思う。
試験の点で合否が決まる部分は公平かもしれないが、塾に行っている子供と塾に行っていない子供の環境まで考えると公平とは思えない。しかも塾はコストになる。
就職して働くまでを考えれば、純粋に学力が必要な仕事と能力や人間性を含む総合的な点で良い評価の方が重要な仕事があるので入試だけに時間、努力、そしてお金をかけるのはおかしいと思う。
スポーツは絶対に必要とは思わないが、スポーツと通して学ぶこと、勝ち負けがある事を学ぶこと、個々の能力だけではなく、戦略や情報分析で結果が違ってくること、努力や精神面のタフさが結果に影響する事ある事、努力よりも才能や遺伝が重要な事もある事など学ぶことが出来れば、将来に応用する事によって未来で良い結果をだせるかもしれない。スポーツに限らず、似たような事を学ぶことが出来る活動や経験をすれば、多少の偏差値の差よりも大切な経験かもしれない。
集団で動くような仕事、多くの人をまとめてある仕事を達成する仕事などはコミュニケーション能力、リーダーシップ、人と上手くやって良く能力などがより重要だと思う。多少、能力が高くても運悪く多少の苦労や辛い思いをして現場で乗り越える事が出来なければ、精神的、又は、身体的につぶれて行く可能性はある。
教師の不祥事は家庭の影響はあると思うが、日本の教育システムの問題の現れだと思う。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
mur*****
「小学校の平等教育は限界に来ている」から「親は躊躇なく塾探しに動いたり、インターナショナルスクールなど、わが子に最適な道を選びましょう」となる部分はあるのかもしれません。
もっとも、「塾探し」を通じて所得格差が学力に反映されるようになった結果、「小学校の平等教育」に限界をもたらしている可能性もありえます。
不平等を公金で是正しようにも、格差をめぐる競争を加熱する結果に終わることも予想されますので、中学受験の在り方を考え直した方がよさそうな気がします。
cho*****
教育先延ばしが子供にとって致命的、という部分は共感しますね。
致命的という言葉のチョイスは大袈裟ですが、小学生の時に先取りしていたから、中学生になって困らないということはあります。
期末テスト対策で、中1の子供の日本史の教科書を一緒に復習した時ですが。
例えば、大化の改新は、何年に誰が何を何の目的でしたことなのか、その結果どうなったのか、スラスラと言えるわけです。
子供に聞いてみると、中学で覚えたわけではなく、小学生の時に中学受験の塾で覚えたそうです。
そうすると、他の科目対策に時間をかけることができ、全体として、良い成績をキープできる。
進学先が公立中学なので、よけいに。
個人的には、何時間も集中して座って授業を受けられるというスキルがついたのが、中学受験の1番の収穫だったかもしれません。
そんなこと?と思われるかもしれませんが…結構この先、大事です。
中学受験は激化の一途、“教育先延ばし”が子どもにとって致命的なワケ 11/14/22(ダイヤモンド・オンライン)
2022年の首都圏中学受験者数は5万人を超えて過去最高となり、受験競争の激化が続く。開成、麻布、桜蔭、雙葉、筑駒、渋幕……東京・吉祥寺を中心に都内に展開する進学塾VAMOSは、「入塾テストなし・先着順」で生徒を選抜しないが、「普通の子ども」を有名難関校に続々と合格させると話題の塾だ。子どもの特徴を最大限に生かして学力を伸ばす「ロジカルで科学的な学習法」が、圧倒的な支持を集めている。本稿では、VAMOSの代表である富永雄輔氏の最新刊『ひとりっ子の学力の伸ばし方』(ダイヤモンド社)から、特別に一部を抜粋して紹介する。
● 中学受験を取り巻く環境は激変している
ひとりっ子の子育ての場合、兄や姉という比較対象がないため、親はつい「自分が子どもだった頃」と比べてものを考えてしまいます。しかし、そこにはおよそ30年の開きがあります。その間に、教育事情は大きく変化しています。
とくに、中学受験をめぐる環境は様変わりしました。親世代の頃は、中学受験にかける準備期間は約2年でした。5年生になってから塾に通い始めれば良かったわけです。しかし、今は3年から3年半が必要になっています。つまり、3年生のうちに塾に入ってなんとかギリギリというところです。
● 塾なしで中学受験は「無謀な挑戦」
こういう状況について、「過熱」を指摘する声もあります。本来、子どもの学びは学校で得るものであって、幼い頃からせっせと塾に通わせるのはおかしいというわけです。子どもに対する理想が高いひとりっ子の親は、「のびのびと育てたい」という気持ちから、こちらの方向に傾くケースも多々あります。
その意見は尊重しますが、中学受験を考えているなら、塾に通わせることはほぼ不可欠です。というのも、今の公立小学校のカリキュラムや授業の体制は、親の時代とは違い、中学受験にはおよそ対応できないものとなっているからです。
上の子を育てた経験がある親はそのことに気づいていますが、ひとりっ子の親はわかりません。だから、まず「自分たちの頃とは違うのだ」という認識を持って、さまざまな情報に接してください。
ちなみに、欧米諸国では、日本のような塾文化はありません。彼らの国では「飛び級・降級」が設定されていて、優秀な子はどんどん上の授業を受けられるからですしかし、日本の義務教育は、広く一般的な知識を与えること優先で、個々のレベルに合わせるのは不可能です。
そういう状況にあって、塾というものをいかに上手に使っていくかが、大事なポイントになってきます。大事なのは、自分の子どもに合った勉強方法や進路を考えることです。
● 教育機会は平等ではない
親の時代と比べ今は、働き方改革やパワハラ抑止策が大きく進んでいます。このことによって、子どもたちは親のときのような教育を受けられなくなっています。
勉強についていけない子がいたときに、先生が残って見てあげればサービス残業になってしまいます。授業中に騒いでいる子を怒鳴りつければ、パワハラだと保護者からクレームが入ります。
こういう状況にあって、小学校の平等教育は限界に来ているのです。現場の先生も頑張っていますが、世の中は変化し、子どもの進路も多様化しています。
そのことを認識し、親は躊躇なく塾探しに動いたり、インターナショナルスクールなど、わが子に最適な道を選びましょう。野球やサッカーなどのスポーツも、プロで活躍している選手の大半は、小学2年生くらいからクラブに入会して練習を積んでいます。勉強も同様で、スタートダッシュは非常に大事なのです。
(本稿は、『ひとりっ子の学力の伸ばし方』からの抜粋・編集したものです)
富永雄輔
【独自入手】《おな電をさせられ、秘部を見させるしかない》《自殺未遂しました》旭川14歳凍死少女「イジメ被害メッセージ」 (1/3)
(2/3)
(3/3) 04/25/21 (AERA dot.)

《市がイジメ再調査表明》「わいせつ強要の証拠LINEを教頭は写メで撮っていた。学校調書を調べて」旭川14歳少女凍死 遺族がコメント から続く
【画像】爽彩さんは裸の画像をいじめグループによって拡散された
亡くなる約1年前、廣瀬爽彩(さあや)さんは自分が受けた壮絶なイジメの実態について、ネットで知り合った友人に対して下記のようなメッセージを送っていたことが新たにわかった。「文春オンライン」取材班が独自入手した。
その一部を引用する。
《内容を簡単にまとめると
・会う度にものを奢らされる(奢る雰囲気になる)最高1回3000円合計10000円超えてる。
・外で自慰行為をさせられる。
・おな電をさせられ、秘部を見させるしかない雰囲気にさせられて見せるしか無かった。
・性的な写真を要求される。
・精神的に辛いことを言われる(今までのことバラすぞなど)etc……
ありまして、、
いじめてきてた先輩に死にたいって言ったら「死にたくもないのに死ぬって言うんじゃねえよ」って言われて自殺未遂しました》
今年3月、北海道旭川市内の公園で積もった雪の中で亡くなっているのが見つかった爽彩さん(当時14歳)。死因は低体温症で、警察も自殺とは認定しなかったが、「文春オンライン」では4月15日から7本の記事を公開。その死亡の背景に上級生らからの凄惨なイジメがあったことを報じた。
※本記事では廣瀬爽彩さんの母親の許可を得た上で、爽彩さんの実名と写真を掲載しています。この件について、母親は「爽彩が14年間、頑張って生きてきた証を1人でも多くの方に知ってほしい。爽彩は簡単に死を選んだわけではありません。名前と写真を出すことで、爽彩がイジメと懸命に闘った現実を多くの人たちに知ってほしい」との強い意向をお持ちでした。編集部も、爽彩さんが受けた卑劣なイジメの実態を可能な限り事実に忠実なかたちで伝えるべきだと考え、実名と写真の掲載を決断しました。
無理やり撮らせたわいせつ画像をイジメグループ内で拡散
2019年4月、市内のY中学校へ入学してからほどなくして、爽彩さんは、上級生のA子、B男、Z中学校に通うC男らからイジメを受けるようになった。イジメは日に日にエスカレートし、加害生徒らが爽彩さんに無理やり撮らせたわいせつ画像をイジメグループ内で拡散したことや、公園内でイジメグループが複数名で爽彩さんを囲み、自慰行為を強要したこともあった。
爽彩さんは同年6月に、イジメグループら十数名に囲まれた挙句「死ぬ気もねぇのに死ぬとか言うなよ」と煽られた末に、地元のウッペツ川に飛び込むという“事件”を起こした。この事件ののち、爽彩さんは長期入院を余儀なくされ、同年9月には市内のX中学校へ転校。しかし、X中学校へもなかなか通うことができず、家に引きこもりがちな生活を送るようになった。医師からはPTSDと診断され、イジメのフラッシュバックに悩まされていた。
校長は「爽彩さんの死亡と自慰行為強要は関連がない」
冒頭の爽彩さんのメッセージは2020年2月に書かれたものだ。この時期、彼女は引きこもりがちになり、依然としてイジメによるPTSDに悩まされていたという。
いかに悲惨な性被害にあったかについて、彼女自身の言葉で綴られている。こうした言葉を綴るだけでも、当時の場面がフラッシュバックし、つらかったのではないか。
取材班は爽彩さんがイジメを受けた当時通っていたY中学校の校長を直撃( #6 参照)。校長は「イジメはなかった」「(男子生徒が当時12歳だった爽彩さんに自慰行為を強要して撮影したことが)今回、爽彩さんが亡くなった事と関連があると言いたいんですか? それはないんじゃないですか」などと答えた。だが、少なくとも彼女が、自身が受けた行為を「イジメ」だったと認識し、そのトラウマに悩まされていたことは、今回のメッセージを読めば明らかだ。
爽彩さんは、ウッペツ川に飛び込んだ事件以降、精神的なショックから入院、2019年9月に退院した後はイジメを受けたY中学校からX中学校へ転校することになった。
「わいせつ画像が拡散された学校への復帰はありえない」
爽彩さんの親族が語る。
「Y中学の教頭先生は『うちの生徒なので戻ってきてほしい』と学校に復帰するよう爽彩に勧めましたが、わいせつ画像が、どれだけ学校中に拡散されたのかもわからない上に、加害生徒がまた近づいてくる可能性もあった。それで学校に復帰なんてありえない。そこでX中学校へ転校することにしました。その際に、自宅も引越ししたのですが、場所は以前の学区からはバスで1本では行けない、離れた場所にしました。しかし、それでも爽彩は外に出ることに怯え、新しい学校に行くことも拒んでしまったのです」
爽彩さんの「最後の声」を聞いたネット世界の友人
爽彩さんは、家に引きこもりがちになり、もともと関心があったネットやゲームに没頭するようになった。学校に通えなくなった爽彩さんにとって、そこだけが、家族以外にありのままの自分を見せることができる“居場所”だったようだ。
辛くて思い出すのさえ苦しかったはずの「イジメ」の内容について、あえて伝えたのも、相手が唯一心を開くことができるネットの世界の友人だったからだろう。
爽彩さんはそうしたネットの友人たちに、自身が受けたイジメについて相談をしていた。そして、再び学校に通えるよう努力し、なんとか明るい未来を見出そうと必死にもがき、苦しんでいた。
取材班はそんな彼女の「最後の声」を聞いた友人たちに接触した――。( #9 へつづく)
◆◆◆
「文春オンライン」では、旭川イジメ問題について、情報を募集しています。下記のメールアドレス、または「 文春くん公式 」ツイッターのDMまで情報をお寄せ下さい。
sbdigital@bunshun.co.jp
https://twitter.com/bunshunho2386
《今日死のうと思う 既読ありがとう》旭川14歳少女凍死 ネットの友人3名が明かした「イジメから最期までの600日」 へ続く
「文春オンライン」特集班/Webオリジナル(特集班)
「高校進学後も関係は続いた。断ることができなかったのは、幼い頃から『先生には従うもの』と教えられていたからだ。」
なんかそんな事を言われたことはあるし、学校は正しいと言われたことがあると思う。ただ、個人的にはそれは間違っていると大人になって思うので、子供には先生の言う事を聞けなんて言わない。先生や学校がおかしいと思ったら証拠を取っておけとは言ったことはある。子供達が先生を尊敬しない事に対しては教育委員会や文科省の自業自得だと思う。リーダーシップがない教師に生徒は従わないと思った方が良い。
大阪のデタラメ!市職員の5人以上の会食200件、千人以上参加の仰天「上司の強要、偽装工作」核心証言〈dot.〉(1/2)
(2/2) 04/24/21(読売新聞)や
校長ら31人、修了式後に懇親会 大阪のホテルで3月 04/15/21(朝日新聞)のケースを考えたら良い。言っている事とやっている事に矛盾がある人達を言う事を素直に聞く人は多いのだろうか?昔はありかもしれないが、今は、違うと思う。
【#許すなわいせつ教員】中学時代の「心の傷」破裂 私は性被害者だったんだ…(1/2)
(2/2) 04/24/21(読売新聞)
性的な被害は体にも心にも大きな傷として残る。それが子供の場合、その影響は甚大だ。被害がすぐには顕在化せず、「忘れよう」と蓋をしてきた記憶が大人になる過程で外れ、心の中で突然、よみがえるという。めまいや頭痛、極度の精神的な不安のほか、中には自傷行為を繰り返すケースもある。
「#しんどい 君へ」ジャングルポケット 斉藤慎二さんからメッセージ
中学校時代の教員からわいせつな行為を受け、その後、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状に悩まされてきた関東地方の20歳代の女性は、今年から児童虐待などに対応する仕事に就いた。
「子供の頃に受けた性被害で自分は大いに苦しんだ。同じように悩み、『心の傷』を持つ子供たちの手助けをしてあげたい」。女性はこう語り、現在は希望を持ち、仕事にまい進する。
行為から数年がたった2018年頃は、わいせつ行為を受けたことを頻繁に思い出し、涙が止まらなくなり、過呼吸の症状に見舞われることが続いた。精神科を受診したところ、「うつ病と複雑性PTSD」との診断を受けた。それまで、もやもやしていたが、治療やカウンセリングを受け、「私は性暴力の被害者だったんだと、ようやく自覚した」と振り返る。
求められたメール交換 ハートの絵文字に違和感
自然が豊かな西日本の町で女性は生まれ育った。中学時代は成績も良く、運動部の部長を務め、3年時担任の40歳代の男性教員からの信頼は厚かった。
ある時、携帯電話の番号とメールアドレスの交換を持ちかけられ、戸惑いながらも応じた。その後、教員からはハートの絵文字付きのメールを受け取ることもあった。妻子ある年齢の離れた教員のため、違和感を持ちつつも軽い冗談だと受け止めていた。
成績表には、教員から「学級役員に」という希望も書かれていた。高校への推薦入学も決まり、教員からの依頼で3学期は学級役員を務めた。卒業イベントの準備で、放課後に男性教員と作業をすることが増え、教員が車で自宅まで送ってくれることもあった。女性の両親も「いい先生だね」と喜んでくれていたという。
撮られた写真の悪用、うわさを不安視 性被害言い出せず
卒業間近の放課後、教員の車に乗せてもらったところ、見知らぬ場所で車が止まり、性的な暴行を受けた。女性はそれまで男性の体を見たことがなく、ぼう然となった。その後、自宅まで送ってくれたが、女性は親にも言えずに泣きじゃくった。
高校進学後も関係は続いた。断ることができなかったのは、幼い頃から「先生には従うもの」と教えられていたからだ。携帯でわいせつな行為の写真を撮られ、会わなくなったらそれが悪用されるのではないかという不安もあった。地元で教員をしている親の評判を落としてしまうのではないかなど、様々な理由で苦しんだという。
そうした悩みが心の中で抑えきれなくなったのか、高校3年のある日、教室で過呼吸を起こして保健室に運ばれた。そこで初めて、学校で生徒たちの相談に応じていた女性教員にこれまでの経緯を打ち明けたという。
教育委員会は教員を懲戒免職処分とした。読売新聞の取材に教委は事実を認めつつも、担当者は「二次被害を防止する観点から、詳細は答えられない」とする。
女性は「教員には自分がしたことの罪深さを知ってほしい。そして、狂ってしまった私の人生を返してほしい」との思いを今も抱える。
性被害は「魂の殺人」
性暴力被害者らでつくる一般社団法人「スプリング」(東京)などは昨年夏、性被害者にアンケート調査を実施した。5899人から回答を得たところ、わいせつ行為を受け、それを性被害だったと認識できるまでには平均で6~7年かかることがわかった。
父親から、長年にわたって性暴力の被害を受けた経験を持つ山本潤代表は、「顔見知りからの性被害の場合は、被害だと認識するまでに長い時間がかかってしまう。心身の負担も大きく、事実として受け止めるには相当のエネルギーと時間が必要だということを広く知ってもらいたい」と語る。
精神科医として性暴力の被害者を200人以上診療し、内閣府の「女性に対する暴力に関する専門調査会」で会長を務める小西聖子・武蔵野大教授によると、思春期の性暴力では、自分が被害に遭ったことを思い出さないように、記憶に蓋をする「回避」の傾向が強いという。
回避しようとしても、本当に記憶をなくすことはできないため、いずれ無理が生じてフラッシュバックが起こり、PTSDの発症につながることもある。
小西教授は「都市部では性被害の臨床にたけた専門医などもいるが、地方にはまだ少ない。幼少期に被害に気づくことができ、適切なカウンセリングや治療を受けることができる例は少ない。性被害は『魂の殺人』でもあり、その対策に国は本腰を入れてほしい」と指摘している。
教え子5人にみだらな行為 誓約書で口止めも 塾経営の男に懲役6年 鹿児島 07/28/20(鹿児島テレビ)
教え子である18歳未満の女子生徒5人に対して、複数回にわたってみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反などの罪に問われた学習塾経営の男に対する判決公判が28日、鹿児島地方裁判所の支部で開かれ、懲役6年の実刑判決が言い渡されました。
判決を受けたのは、鹿児島県内で学習塾を経営する55歳の男です。
判決によりますと、男は2014年1月から2020年1月にかけて、自分が経営する学習塾に通っていた18歳未満の女子生徒5人に対し、自分の立場を利用して性的なサービスをするよう指示し、自宅などでみだらな行為を30回以上繰り返しました。
また、そのうち1人のわいせつな画像137点を撮影・保存し、児童ポルノを製造しました。
男は犯行前、被害生徒らを「特に重点的な指導を行う対象者」として選抜していたほか、うち2人については「自分との会話や出来事は絶対に外部に漏らさない」という内容の誓約書に署名をさせ、口止めしていました。
判決公判で、鹿児島地裁支部の裁判官は「思慮分別が十分でない被害者らを自分の性欲を満たすための道具のようにもてあそんだ犯行で、卑劣で悪質」と指摘しました。
その上で「未成熟な被害生徒らの将来に悪影響を及ぼすことが強く心配され、刑事責任は重い」と述べ、検察側の懲役8年の求刑に対し、懲役6年の実刑判決を言い渡しました。
ヤフーのコメントで下記のようなコメントがあった。
友人が小学校の教師をしていますが、同僚が子供にわいせつ行為を行う常習者だと言っていました。
親からの訴えで問題となり、彼は別の市の小学校へ転勤して行きました。友人に、また彼は普通に教職に付くのか確認した所、そうだ、という返事でした。
大変驚きました。教育委員会はその事を知っているのか確認した所、知っている、と言っていて、異常だと思いました。これは10年程前の出来事です。
そんな同僚をそのままにしている友人に不信感が出て、今は疎遠になっています。
普通なら事件となり、逮捕されていなければならないと思ったし、海外では性犯罪者がどこに住んでいるか、居場所がわかるアプリも使われているのに、日本は何やってるんだと思いました。
神戸のイジメ教師達も、女性はお咎めなしの様だし、男性は、免許を再取得するかもしれないということですね。
早急にまともな法改正をしていただきたいです。
良くも悪くも政治家達や公務員達がこの問題を放置してきた。放置するぐらい自分達には甘いシステムを維持し、教員は大変だと騒いできた。自分達の待遇には敏感に
騒ぐが、自分達が加害者になる可能性がある件には関しては放置してきた。自己中心的な人達が多いから教員のわいせつ行為や性犯罪が起きるのではないのか?
法改正で「児童生徒へのわいせつ行為で教員免許が失効しても3年後に再取得を可能としている教員免許法」をどのように変えるのか?肝心なところが記事では抜けているが
方針に関する案は現時点ではないのか?
わいせつ教員対策で法改正方針 免許法、文科相表明 07/22/19(共同通信)
萩生田光一文部科学相は22日の衆院文部科学委員会で、児童生徒へのわいせつ行為で教員免許が失効しても3年後に再取得を可能としている教員免許法を改正する方針を示した。「私の責任で、できるだけ速やかに法案を提出することを念頭に進めていきたい」と述べた。自民党の池田佳隆氏への答弁。
文科省は、子どもたちにわいせつ行為をした教員は、原則として懲戒免職とするよう教育委員会などに要請。懲戒免職となったり、禁錮以上の刑が確定したりすれば、免許は失効するが、現行法では3年後に再取得できる。
政府は6月、性犯罪・性暴力対策の強化方針を決定。教員免許も見直しを検討するとした。
下記の記事の内容が正しいのであればこのような人物が中高一貫校の元副校長になれたのだろうか?過去の事件が発覚しなかったのはなぜか?北海道の教育委員会は過去の
事件に関して全く知らなかったのか?それとも証拠がないので処分しなかったのだろうか?
【辞令】道教委(令和2年6月3日付)▽教職員局教職員主幹(登別明日中等教育副校長)鎌田祐一 (北海道通信社 DOTSU-NET 日刊教育版)
寝ていた30代女性にわいせつ行為…3人目の被害者判明で"3度目"逮捕 54歳元副校長の男 余罪捜査へ 07/09/19(北海道ニュースUHB)
女性に睡眠導入剤を飲ませたなどとしてて2度逮捕されていた登別市の中高一貫校の元副校長の54歳の男が、寝ていた知人女性にわいせつな行為をしたとして再逮捕されました。
準強制わいせつの疑いで再逮捕されたのは、北海道登別市の登別明日中等教育学校の元副校長、鎌田祐一容疑者(54)です。
鎌田容疑者は、別の高校に勤務していた2013年11月14日から15日までの間に、石狩地方のホテルで、寝ていた30代の知人女性にわいせつな行為をした疑いが持たれています。
調べに対し鎌田容疑者は、「やったともやっていないとも言えない」などと話しているということです。
鎌田容疑者は2020年3月、自分の車に同乗していた別の30代の知人女性に睡眠導入剤を飲ませたとして、傷害の疑いで逮捕。
その後2014年に、寝ていた別の30代の知人女性にわいせつな行為をした疑いで6月に再逮捕されていました。
警察がさらに捜査を進めたところ今回の容疑が浮上。3人目の被害者が判明し、3度目の逮捕となりました。
警察はさらに余罪がある可能性が高いとみて調べを進めています。
<北海道>わいせつ行為で3回目の逮捕 道立校の前副校長 07/08/19(HTB北海道テレビ放送)
3回目の逮捕です。7年前に睡眠中の女性にわいせつな行為をしたとして、道立学校の前副校長が8日に逮捕されました。
道立の中高一貫校である登別明日中等教育学校の前副校長・鎌田祐一容疑者54歳は、幌加内高校の教頭だった2013年11月、石狩管内の宿泊施設で、30代の知人の女性が寝ている間に、服を脱がすなどのわいせつな行為をした準強制わいせつの疑いで逮捕されました。
鎌田容疑者は、2014年にも別の女性の睡眠中に、わいせつな行為をしたとして先月、逮捕されているほか、ことし3月には別の知人の女性に、自分の車の中で睡眠導入剤を飲ませた傷害の疑いでも逮捕されていて、今回、3人目の被害となりました。
鎌田容疑者は「やったとも、やっていないとも言えない」などと容疑を否認しているということです。
下記の記事の内容が事実だとすれば真面目すぎるし、完璧でいようとするからしんどくなるのだと思う。教師になりたいと思ったことはないし、教師の仕事をする事など想像を
したこともない。昔は、教師であるだけで生徒達もそれなりに言う事を聞くし、親だって言いたい事を言わなかったと思う。しかし平等とか、主張がする事が広がると教師には
カリスマとか、リーダーシップの能力が欠けていると生徒をまとめる事は出来ないと思う。生徒は子供であるが、人を見ている。教師だからとの理由だけで言う事は聞かないと
思う。教師も生徒を納得させるだけの説明や話をする能力や魅力が必要だと思う。ただ、採用試験にはそのような能力や魅力は重要ではないと思う。試験の平等性が強調され
評価しにくいカリスマ、リーダーシップや人間的な魅力は放置されているのだと思う。
人付き合い、知り合いを作るこは採用試験には関係ないが、仕事や人生の中では必要な能力である場合はある。知り合いや友達がいれば相談したり、アドバスを聞くことができる。
問題解決につながる場合もあるし、繋がらない場合もあるが、単純に、いろいろな意見を聞くだけで答えが見つかる場合もある。人とは関わりたくない。そのかわり自分で答えを
見つけるという人はいると思う。そのやり方でなんとかなるのならそれも選択の一つ。一人で問題の解決が出来る人と出来ない人がいる思うが、出来るのであれば問題ない。人には
いろいろなやり方がある。出来ない人は仕事を変えるのか、別のやり方を考えるのか、人付き合いを下手なりに、または、嫌な気分になるが、相談したりするしかない。
どうしても嫌なら仕事を変えればよい。パーフェクトな仕事はないが、合う仕事、合わない仕事、前の仕事よりはましと思える仕事など人によって選択は違ってくる。自分が
壊れる前に仕事を変えてみればよい。次の仕事も同じように問題があれば、また、次の仕事を見つけるか、自分を部分的に変える必要があると思うか、自分で決めればよい。
記事の人間が教師を辞めても、続けても、大きくは変わらない。辞めれば、別の人が採用されるだけ。人手不足になり、困れば、給料を上げたり、待遇を改善したり教育委員会や
県が考える。
兵庫県の教師のいじめやパワハラは教師の現場が古く、生徒の成長と教育を担当しながら、ダブルスタンダードの人間的に成長できない偽善者達の集団が建前のいつわりを
子供達に言っている事を部分的に証明している。
河井夫妻選挙違反事件 首長2人議員38人に1680万円提供の疑い 06/26/20(NHK)や
「先輩議員に“ちゃんと地元でお金を配ってるの?”と叱られた」豊田真由子・元衆議院議員が告白 06/26/20(ABEMA TIMES)を考えても表と裏が多くの人達が知らないだけで
存在すると言う事である。
この日本が簡単に良くなるはずがないと思う。
多忙で孤立「壊れる教員たち」の過酷すぎる現実 (1/5)
(2/5)
(3/5)
(4/5)
(5/5) 06/28/20(東洋経済オンライン)
教育現場で「教員の孤立」が進んでいるという。授業準備や書類作成、生徒・保護者との対応、休日をつぶしての部活顧問。業務量がただでさえ多いうえ、相談できる上司や同僚が職場内におらず、メンタルをやられてしまうケースが少なくない。
実際、文部科学省の調査によると、上司に仕事の相談ができる教員は35%にとどまっていた。「みんな忙しくて相談なんてできない。これ以上続けたら、自分が潰れてしまう」。そんな声があふれる現場を追った。
【写真】取材に応じた真金薫子医師など
■つねに孤独 ウソをついて教員を辞めた
北関東にある小さな飲食店で田中まさるさん(仮名)に会った。20代。5月の水曜日、夜7時。昼間は真夏のように暑かったのに、外は激しい夕立になっている。
「つらくて、教員を1年で辞めました。僕、この町にいないことになっているんです。『東北の実家に戻らなければならなくなった』とウソついて、職を辞めたんです。だから実名や写真は勘弁してください」
田中さんはなぜ辞めたのか。
「生徒指導で悩みがあっても誰にも相談ができないんです。担当している部活動では、言うことをきかない子もいて。昔みたく、ヤンキーってほどではないんですけど、周りと違う行動をし、かき乱す子が何人かいるんです。
『いい加減にしなさい』と生徒を自分のもとに引き寄せたことがあるんですが、『死ね死ね。わー、胸ぐらをつかまれた最悪』と言われ……。そうした子のために何ができるのか、悩んでいました。でも、同僚教員には、『誰しも直面していることだから。キツかったけど、俺らも乗り越えてきたから、君も乗り越えて』という雰囲気が根付いていました」
関東の大学を卒業し、出身地での教員を目指した。正規採用の試験は落ちてしまい、臨時採用の形で公立中学校の教員になった。
「40人ほどの教員がいました。自分は3年生のクラスで副担任。運動部の副顧問。先生になって2日後です。あれっ、と思った。研修もなく、すぐ現場に出されました。新人ですよ? 『わからなかったら聞いて』と言われたのですが、聞けないんですよ。
職員室ではみんな黙々と仕事をしていて、雑談のような会話はいっさい聞こえない。生徒は自分の言うことをなかなか聞いてくれないし、授業の内容はきちんと理解できているのか、と。保護者との対応も、これで大丈夫なのかと不安でした」
教員の仕事は「つねに1人で孤独だった」と田中さんは振り返る。当然、日々の仕事も忙しかった。
「部活の朝練があるので、朝6時には学校にいました。授業の準備などで夜は10時くらいまで。あと、先輩より先に帰れなかったんですよ。それが暗黙のルールとして根付いていました」
土曜と日曜はいつも部活に費やした。
「大会や練習試合で隣県へ行くときは大変でした。朝5時に顧問を車で迎えに行き、練習試合が終わると先生同士の懇親会。深夜2時に顧問を家まで送り、また朝5時に迎えに行く。週末はずっとそんな感じでした。先輩方は『これは当たり前。誰しもが通ること』と言っていて、相談なんてできなかったです」
■「50連勤」も。残業代はでない
1971年に制定された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)」により、教員には時間外勤務の手当は出ない。月額給与の4%加算が、それに代わるものとして支給されている。
田中さんの月額給与は手取りで約23万円だった。それに対し、1カ月の労働時間はほとんど400時間を超えていたという。「飲食店でバイトしていたほうがもっとお金をもらえたと思う」と田中さんは話す。食べることでストレスを発散しようとしたせいか、1年で体重が18キロも増加した。
「実際はそんなこと、ほとんどなかったんですが、仕事の悩みを相談できたとしても、毎日が忙しいから、仕事が終わった後。そんな時間から何かを相談するなら、家で寝たかった。
6月と11月がとくにつらかった。6月は中学3年の引退試合で忙しかった。中3の副担だったので、11月は卒業後の進路指導で忙しくて。50連勤くらいしたかな。自分が何を考えているのかわからないくらい、精神的に追い込まれていました。毎日仕事だから友だちとも会えない。食べることしか、楽しみがなかったです」
メンタルに関する面談はなかったのだろうか。
「新年度に1年間の教育達成目標を書いて、それに沿って学期始めと学期末に『目標をどれくらい達成しているのか』の確認をする面談があっただけでした。精神状況に関する面談はなかったです」
12月に入ると、校長から翌年も臨時教員を続けるかどうかの意向確認があった。限界だった田中さんは「東北の実家に戻らなければならなくなった」とウソをつき、継続しないと申し出たという。
「教員をこれ以上続けると、自分が壊れてしまう、と。校長は『あ、そうなの』と淡白でした。やりがいは感じていたのに、一方では、いつも『もう辞めなきゃ』と思うほど追い込まれていました。
3月に辞める前、生徒や保護者から『先生、ありがとう』と言われたときは『もう1年、頑張ればよかったかな』とも思ったんですが……。遅くまで仕事が続いていたとき、校長や教頭が『早く帰れ』などと職員室全体に強く言ってくれれば、変わっていたかもしれない。でも、この業界は上のことは絶対だから」
田中さんのような事例は特殊ではない。「若手が上司に相談できない教育現場」という実態は、文科省の調査でも浮き彫りになる。
2013年に公表された「教職員のメンタルヘルスに関する調査結果」(全国の小中高200校を無作為抽出、回答数約5000人)によると、管理職以外の「教諭」が、不安や悩みを含む「ストレス」の相談を上司に「よくしている」割合は4.7%。「ときどき」を含めても35%しかいない。
上司に相談できるか否かは、問題を具体的に解決できるかどうかが重要なポイントでもある。それなのに、これらの年代は自ら抱え込むか、同僚に相談するかなどの対応しかできなかった。その同僚相手に自らの相談をするかどうかについても、「よくしている」は16.2%しかない。上司にも同僚にも相談しない、できないという荒涼とした風景が見えるようだ。
精神疾患で休職する教員の数も高止まりしている。
文科省の「公立学校教職員の人事行政状況調査」(2018年度)によると、精神疾患を原因とする教員の休職者は、2007年度以降5000人前後で推移しており、2018年度は5212人を数えた。平成元年だった1989年度の1037人に比べると、今の水準はおよそ5倍。教員の採用抑制が続く中、高止まり傾向は顕著だ。
教員の自殺も同じ状況にある。厚生労働省が集計・公表をしている調査によると、自殺した教員数は2018年では93人に上った。「勤務問題」が最大の原因であり、次に「健康問題」と続く。「健康問題」でもうつ病が主な要因を占めた。自殺者全体の傾向で言えば、2013年から100人前後を行き来している。
■子どもをめぐる状況は複雑化しているのに…
こうした実態や各調査を踏まえ、東京都教職員互助会・三楽病院の真金薫子医師(精神神経科部長)は次のように訴える。
「教員の数を早急に増やすべきです。1990年代後半に『学級崩壊』が注目され、教育現場の実態が問われましたが、今のほうが現場は複雑で大変だと考えています。ここに訪ねてくるのは、40代が最も多い。その次に20代と50代。ベテランもストレスを抱えている一方、20代がここ最近、増えてきています。2000年代から教員の大量採用を行っており、母数が増えてきているからか、と。内容を順番付けすると、生徒指導について、職場での人間関係、授業での教え方と保護者対応でしょうか。
子どもをめぐる状況は複雑化しているのに、ほかの先生と問題を共有できていないと感じます。本来は『チーム学校』として問題解決に取り組まないといけないのに、個人プレーになっている。背景にあるのは、先生一人ひとり、仕事量が多いという現実です」
「ベテラン教員の意識改革が必要」と訴える専門家もいる。関西外国語大学外国語学部の新井肇教授もその1人。教員のメンタルヘルスについて研究を続けている。
「教員の仕事は『個業』と呼ばれています。1人ですべてやるという意識が、教育界に根付いているからです。もともと仕事量が多いうえ、ICT教育やプログラミング学習など、新しくやるべきことが次々と出てくる。保護者は教員を学習サービスの提供者としてどころか、子どもの面倒をみる何でも屋、あたかも学校を託児所のように、捉えている。
そうした事柄に対応ができなければ、『力不足だった』という自己責任論で片付けられてしまう。チームプレーで一つひとつ乗り越えていこうといった意識をまずベテランが持たなければならない」
およそ30年間、新井教授は埼玉県の公立高校で教壇に立っていた。その間に、長期派遣教員として、大学院で生徒指導の研究にも取り組んだ。今も、危機介入や研究協力で学校現場に入ることが多いが、そうした経験から言っても、教職の世界では、教員はつねに孤独な状況に立たされており、困ったときに「助けて」と言える職場環境もない。
新井教授には、教員になった教え子を自死で亡くした経験もある。
■どれだけ残業しても給料が変わらない現実がある
「うつ病から職場復帰して間もなくの出来事でした。そのことが私の研究の出発点になっています。教員のストレスには、人を相手にすることの難しさ、多忙や賃金のあり方、職場の人間関係などが複合的に絡んでいます。職場での孤立には、給特法の影響も大きい。どれだけ残業しても給料が変わらない現実があると、自分の仕事だけに集中し、他人のことには構わないという風潮が生まれてしまう」
「人手不足については、教員を増やすことが先決です。そのうえで、学校が何もかも背負い込むのではなく、部活動など、可能なところは外部へ委託することも必要でしょう。教員を孤立させず、チームで動けるようにするには、『仕事量を減らすことこそが仕事の質を高める』という教員の意識改革と、それを保障するための人材確保という構造的な改革が不可欠です」
<取材:フロントラインプレス(Frontline Press)>
大学の教育学部では教師になると言う事は一般の民間会社でサラリーマンとして働く以上に人間性を問われることを教えるべきだ。それで教師になるのをやめるのであれば仕方がないし、教師になって問題を起こすよりは良いと思う。
自制心があれば、多少の問題はコントロールできると思う。善悪や違法か違法でないかだけで興味があるないは決まらない。国が変われば法、規則、そしてガイドラインが違うことは普通にある。
だから自制心で対応するしかないと思う。
多くの人は人に見せている部分だけが全てとは思わない。自制心と自分の立場を考えて行動すれば、問題は起きないと思う。どのような立場になるかで、同じ事をしても批判や評価は
違う。権力や地位を持っていなければ、虐げられる事はあるが、注目される可能性は少ない。
逮捕されても示談にするとは思うけど、考えて行動すればよかったと思う。
酩酊女性に性的暴行 立命館慶祥教員の男を逮捕(北海道) 06/26/19(STVニュース北海道)
北海道江別市にある立命館慶祥中学・高校の教員の男が、酩酊状態だった知人の20代女性に性的暴行を加えたとして逮捕されました。
準強制性交の疑いで逮捕されたのは、立命館慶祥中学・高校の教員井内睦容疑者43歳です。井内容疑者は6月5日の深夜、札幌市厚別区のホテルの一室で酩酊状態だった知人の20代女性に対し、性的暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、井内容疑者と女性は事件前に飲食店で2人で食事をしていて、女性はこのときに飲酒をして酩酊状態になったとみられています。井内容疑者は行為を認めているものの「無理やりではなかった」などと容疑を否認しているということです。
アメリカに留学していた頃、日本のトップはアメリカのトップには勝てないと思った事がある。それは、勉強が出来る生徒の中に勉強と遊びを両立している割合が多いと感じたからだ。
勉強ばかりして来た日本人大学生と勉強と遊びを両立させているアメリカ人大学生が学力テストを受けたら日本人大学生がトップを占めると思うが、総合的な面で判断すれば、日本人学生は劣るのではないかと感じた。また、人生を楽しむという点では日本人は完敗すると思った。
昔、日本はアメリカの後を追っていると言われたことがある。国のサイズや文化が違うので正確な表現ではないが、部分的には参考になると思う。例えば、大学を卒業しても就職できない若者が増えた、就職出来ても低収入で学費の返済に困っている若者が増えた、低収入で結婚しない若者が親の家に住み続ける割合が増えたなどがそうである。結局、先進国であっても、経済成長が止まる、又は、平行線で他の賃金が安い発展途上国からの追い上げに苦しんでいる国が抱える共通点なのかもしれない。
まあ、日本の経済や生活は簡単には改善されないであろう。昔から存在する無駄を止め、現状や将来に合う形を見つけるしかないと思う。次の世代に負担を背負わせるのは狡いと思う。まあ、結局、出来た人間の方が少ないと思うのでなるようになるしかないと思う。
生徒“監禁”勤務先の中学校「誠実な先生」 06/26/19(日テレNEWS24)
25日、群馬県高崎市で女子中学生を監禁したとして27歳の教師の男が逮捕された事件で、男は女子中学生の担任だったことがわかり、中学校は「誠実な先生で驚いている」などと話している。
この事件は、群馬県安中市の中学校の教師、内田慎也容疑者が、女子中学生を自身の車の中に監禁した疑いで逮捕されたもの。
警察によると、25日午後1時過ぎ、女子中学生の母親から「娘がいない。家の中が荒らされている」と通報があり、警察が捜査したところ、午後4時半過ぎ、高崎市内の山中で2人を発見。女子中学生は軽いけがをしていた。女子中学生は2年生で、内田容疑者が担任を務めていたという。
内田容疑者が勤務する中学校の教頭「大変驚いていることと、大変残念でございます。(内田容疑者は)誠実で真面目な勤務態度も決して悪くない先生」
警察は内田容疑者が自宅から女子中学生を連れ去ったとみて、経緯などを詳しく調べている。
いくらテストで良い点が取れても、いくら偏差値が高い大学を卒業できても、人間的に成長で来ていない場合、ブレーキの利かないスポーツカーと同じで使えないので高馬力は不必要となる。つまり、文科省は知識や能力はそれを生かせる重要な部分が明らかに変えている場合、教育者や労働者としては使えない場合がある事を理解しなければならない。
女子生徒監禁疑い教員逮捕 自宅から車で連れ去りか 06/25/19(KYODO)
群馬県警は25日、県内に住む10代の女子生徒を車の中に監禁したとして、監禁の疑いで同県高崎市の私立学校教員内田慎也容疑者(27)を現行犯逮捕した。生徒はけがをしており病院に運ばれたが、命に別条はない。
県警によると、内田容疑者は「間違いありません」と容疑を認めている。県警は女子生徒の自宅から連れ去ったとみて、動機などを調べている。
同日午後1時ごろに帰宅した女子生徒の母親が「家の中が荒らされており、留守番をしているはずの娘がいない」と110番。防犯カメラの映像などを手掛かりに、捜査員が寺尾町の山林内の道で、車の後部座席に座っている2人を発見した。
心理学の授業を取っていた時、人間はある欲求が満たされると次のレベルの欲求を求める傾向があるとテキストに書いてあったと思う。
公務員としての収入の安定が保証され、それに慣れると、次は人間として幸せや恋(恋愛)の欲求が強くなったのだろうか?学生の頃は、学歴とか就職先とか重要だと思っていたが、最近はバランスと個々の価値観で人生の自己評価は違ってくるのではないかと思うようになった。ある人にはうらやましい仕事や実績でも、本人が同じような評価をしているとは限らないし、バランスがとれている方がある分野で成功するよりも幸せに感じる人達がいると思うようになった。
懲戒免職になった女性教諭は自分の人生についてどのように考えていたのだろうか?懲戒免職なる行為を後悔しているのだろうか、それとも、懲戒免職になるリスクを取りたくなるくらい幸せな一瞬があった事を良かったと思っているのだろうか?周りの意見や判断と本人の判断が違う事があるので何とも言えない。
「気持ち抑えきれず」TDLで中学男子生徒にキス、女性教諭を懲戒免職 千葉県教委 01/26/19(読売新聞)
千葉県教委は6日、2017年度に担任したクラスの男子生徒にわいせつ行為をしたとして、県北西部の市立中学校に勤務する女性教諭(44)を懲戒免職処分とした。女性は聞き取り調査に「好意があり、いけないことだと分かっていたが気持ちを抑えきれなかった」と話したという。
県教委によると、女性は17年12月~18年1月、東京ディズニーランドや校内のパソコン室などで生徒を抱きしめたりキスをしたりしたという。女性の監督責任を問い勤務先の当時の男性校長(61)も減給1カ月(10分の1)の懲戒処分とした。
生徒の親が18年11月に市教委に相談したが、市教委は県教委への報告を約2カ月にわたって怠っていた。県教委は今年1月に親から相談があり、初めて事態を把握したという。県教委は生徒側の意向を理由に刑事告発しない方針。【斎藤文太郎】
大学院教育学研究科の50歳代の男性講師がこのような非常識な指示をするのか?しかも50代の講師。人間的に人格が形成されているから欲求をコントロール出来るかもしれないが、人間性は変わらないと思う。
これまで非常識な指示を出しても問題にならなかったから調子に乗っていたのだろうと思う。教育学研究科の講師がこのような行動を取る。基本が間違っている人間は知識以上に教えられる事はないと思う。下手をすればパワハラやセクハラは権力を持ったら可能であることを伝えていたかもしれない。
男性講師、女子学生にミニスカート着用を指示 01/26/19(読売新聞)
広島大は25日、女子学生にミニスカートを着るよう指示するなどのセクハラがあったとして、大学院教育学研究科の50歳代の男性講師を停職3か月の懲戒処分にしたと発表した。
発表では、講師は2014年度から4年間にわたり、入学案内などに載せる写真を撮影する際に、複数の女子学生にミニスカートやホットパンツを着てくるよう指示。撮影した写真を女子学生の自宅に郵送した。女子学生の1人が大学に相談して発覚した。講師は事実を認めているという。
目標が高すぎるし、日本の英語教育に問題がある事を認識していない。そして、平等に同じように英語教育を行う考え方が間違っている。
選択制の導入やレベルわけも必要だと思う。日本は体裁や見栄にこだわる傾向が高いのでレベルわけや選択制に抵抗があるかもしれないが、
その点を考えて授業を行うべきである。
オランダのようにNHKは日本語のニュースの時は、字幕が英語、英語のニュースの時は日本語の字幕を入れるなどして学校の教材に使用してもらったり、
バイリンガルに向かうように文科省は政府やNHKと交渉するべきである。安上がりな英語教育だと思う。
国の英語力目標 中高の生徒・教師ともに達成できず 04/06/18(テレ朝news)
政府が英語力向上のため、昨年度までとして立てた目標を中学校、高校の生徒と教師ともに達成できませんでした。
文科省外国語教育推進室・金城太一室長:「生徒の英語力、また教師の英語力、いずれも目標に達成しなかったことを厳しく受け止めたい」
政府は2013年度から昨年度までの英語力向上の目標として、中学校で英検3級程度以上、高校で英検準2級程度以上の生徒をそれぞれ5割以上にするとしていました。しかし、中学校は40.7%、高校は39.3%で、2013年度と比べると8ポイント以上、増えているものの、いずれも目標に達しませんでした。また、教師の英語力についても英検準1級程度以上を中学校で5割、高校は75%としましたが、中学校で33.6%、高校で65.4%といずれも目標を達成できませんでした。
文科省、私立小中生の支援金滞る 見通し甘く想定の2倍申請 9億円分予算足りず 03/20/18(西日本新聞)
文部科学省が、私立小中学校に通う子どもがいる年収400万円未満の世帯に対し、経済的支援として年額10万円を支給する制度を本年度から始めたものの、申請を受け付けた昨年7月以降、約2万1千人の全国すべての対象者に未支給の状態が続いていることが、「あなたの特命取材班」への情報提供で分かった。申請者数について文科省の見通しが甘く、想定の約2倍の申請が寄せられて予算が足りなくなったため。文科省は対象世帯を絞った上で、今月中に支給する方針を明らかにした。
文科省によると、私立小中学校就学支援金は都道府県への補助事業で、前年の所得に応じた市町村民税の所得割額が10万2300円未満の世帯が対象となる。
子どもの貧困対策も関連した実証事業として、義務教育で私立校を選択した理由や家庭の経済状況についてアンケートに協力することが条件で、全国で1万2千人程度の申請を予想し、本年度予算に12億円を計上していた。しかし、実際には約2万1千人から申請があり、全対象世帯に支給するためには約21億円が必要であることが判明。約9億円分の予算が不足する事態に陥ったという。
同省高校修学支援室は「事前の調査を基に申請数を予想していたが、実態とずれがあった」と説明。補助事業のため補正予算では対応できず、他の財源を調整してある程度の予算を確保したが、全国で700人弱は支給を受けられない見通しになっているという。国会審議中の新年度予算案でも本年度と同額しか盛り込まれておらず「支給要件の見直しを検討する」としている。
私立校は経済的負担が大きく、比較的高年収の世帯の子どもが通うケースが多いが、地元の公立校でいじめを受けて転校するなどの事例もあり、所得に応じて授業料の負担を軽減する狙いがあった。私立高校の生徒については、低所得世帯への就学支援制度が導入されている。
福岡県私学振興課によると、対象世帯に支給決定通知すら出せない状態が続いてきた。複数の学校や保護者から「いつ支給されるのか」との問い合わせを受け、文科省に催促を重ねてきたという。今月16日になって文科省から内定通知が届き、近く各学校を通じて保護者に伝える。担当者は「ここまでずれ込むとは想定していなかった。文科省の見通しが甘かったと言わざるを得ない」と話した。
=2018/03/20付 西日本新聞朝刊=
「同校は『ただただ申し訳ない。2度とこのようなことがないよう、指導教育と同時に対策を取りたい』とコメントした。」
教頭は指導する立場、今更、指導教育は必要ない。今後も教頭として働かせるのか、降格させるかだけだと思う。
お酒を付き合いで飲んだのであれば、今後、お酒を飲まない可能性もあるが、お酒が好きであるのなら今後も飲酒運転をする可能性はある。
住んでいる場所が交通の便が良くなければ、お酒を飲んだから運転しないのは難しい。既に63歳であり、学校の教頭である。捕まった時の
リスクを考えていない新米の先生でもない。私立学校なので学校の方針や理念にも考慮して処分すれば良いと思う。
酒気帯び 63歳中学教頭を逮捕 容疑認める 福岡県警 02/04/18(毎日新聞)
福岡県警博多署は4日、私立博多女子中学校(福岡市東区)教頭、入江利昭容疑者(63)=同県志免町吉原=を道交法違反(酒気帯び運転)容疑で現行犯逮捕した。「ビールや焼酎などを飲んだ」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は3日午後11時40分ごろ、福岡市博多区豊1の市道で、酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転したとしている。
同署によると、近くの交差点を、信号が赤に変わる直前に右折したため、パトロール中の県警自動車警ら隊が職務質問して発覚した。呼気1リットルあたり0.46ミリグラム(基準値0.15ミリグラム)のアルコールが検出された。
同校によると、入江容疑者は昨年4月から教頭を務めており、この日の日中は学校で勤務していた。同校は「ただただ申し訳ない。2度とこのようなことがないよう、指導教育と同時に対策を取りたい」とコメントした。【宗岡敬介】
聖カタリナ高からミッション系の学校だと推測するが、キリスト教系でこのような事を放置するのか?
まあ、アメリカでも牧師が少年、少女に手を出すスキャンダルはある。人間である以上、過ちはあると言う事か?
「彼女にしてやる」セクハラ教諭を諭旨解雇 聖カタリナ高、校長減給 11/20/17(産経新聞 WEST)
松山市の聖カタリナ学園高は20日、女子ソフトボール部監督の男性教諭(30)が部員4人に「彼女にしてやる」などのセクハラ発言や体罰をしたとされる問題で、男性教諭を諭旨解雇処分にしたと発表した。
また、理事会への報告などが遅れたとして、校長を減給、教頭2人をけん責処分とした。
問題は、昨年12月に保護者からの連絡で発覚し、同校は男性教諭を校長訓戒の仮処分としていた。今月、理事会を開き、正式な処分が決定した。同校は「部内での人間関係などを考慮し、なるべく穏便に済ませたいという思いから、初期の対応を誤ってしまった」としている。今後、体罰やセクハラに関するガイドラインを改め、教員研修をするなど指導を徹底するとした。
「いきものがかり」に異変、学校の動物飼育崩壊 「卵、食べれるんですか」教師が驚きの質問 01/17/18(産経新聞)
子供の頃、学校で動物を飼育した経験がある方もいらっしゃるだろう。しかし、今、小学校や幼稚園など教育現場で飼育される動物に「異変」が起きていることをご存じだろうか。子供だけでなく教師も、動物の飼育に関する知識や経験がないため、ウサギは過剰繁殖し、けんかや餌不足で健康状態が悪化。ニワトリも卵の放置から、ひながふ化しすぎることがあるという。この状況に立ち上がったのが、獣医師らでつくる兵庫県学校動物サポート協議会。動物の適切な飼育方法を教師だけでなく、教師を目指す学生らに伝える活動を行っている。「いきものがかり」を育成するためにも、まずは教員の養成がカギになるのかもしれない。(山田太一)
「ウサギは高いところまで持ち上げてはいけない」「ウサギが驚くのでむやみに騒がないように」。関西学院大西宮聖和キャンパス(兵庫県西宮市)で昨年11月、教育学部の学生らを対象に実際のウサギを用いた動物飼育の体験授業が行われた。教師を務めたのは兵庫県学校動物サポート協議会所属の獣医師15人。「ウサギを触ったことがない人」との質問に手を挙げる学生もおり、教室と屋外を利用して丁寧な指導を行った。
平成27年に発足した同会は、県内の小学校などで教師を対象に飼育方法についての研修を行っている。同会会長で神戸市獣医師会副会長も務める物延了さん(64)は、以前に訪れた小学校で、狭い飼育小屋の中でウサギが約80匹にまで過剰繁殖している現場を目撃した。
「見た瞬間にこれは大変だと思った」。増えすぎた結果、オス同士のけんかが多発したり、餌不足によって健康状態が悪化したりするなど、深刻な状態だった。ウサギは去勢手術をした後に別の小学校に譲るなどして徐々に数を減らした。過剰繁殖しているウサギ小屋は、他にも多くの小学校でみられるという。
また別の小学校では、教師に「ニワトリの去勢手術をお願いできないか」と相談されたことがあった。事情を尋ねると、ニワトリの卵を処理できずにヒナがふ化して数が増えてしまっていた。
物延さんは「卵を食べてしまえばいい」と答えたが、「食べられるんですか」と聞き返され、面食らったという。衛生面を考えた上での反応だったものの、物延さんは「学校の飼育小屋の環境下で有害な菌が繁殖することはない」と指摘。そのうえで「子供に伝えるよりも、まず教師への教育が必要だ」と強調する。
そんな同会も大学での授業は今回が初めて。小学校などで飼育されるウサギやニワトリは新人教師が飼育担当になり、適切な飼育方法を知らないまま飼育されているケースが多いことから、教師を目指す学生にも指導対象を広げた。
同会の発起人の一人で獣医師の水沢栄雄(しげお)さん(58)は「教師が子供から動物について聞かれたときに答えに困るケースが多い」と指摘し、教育現場に出る前の指導の必要性を強調する。
そもそも学校で動物を飼育することで得られる教育効果とは、どのようなものがあるのだろうか。同会によると、海外では子供たちが教師に引率されて動物を飼育する施設を訪ねる「訪問型」が一般的で、教育現場で実際に動物を飼育するのは日本特有の文化という。日本に動物の飼育教育が導入された時期は定かではないが、明治時代末期に東京高等師範学校付属小学校の教員だった松田良蔵氏が導入に尽力したとの記録が残っている。
文部科学省が平成15年に作成し、全国の小学校などに配布されている教師用手引き「学校における望ましい動物飼育のあり方」には、「(動物の)成長の様子から感じられる生命力の素晴らしさ。これらは、飼い続けることによって得られる学びの内容である」などと記されている。
では、なぜ教師は動物の扱い方を知らないままなのか。教職員免許法では教師になるための学位などは定められているが、個別のカリキュラムについては規定がなく、文科省の担当者は「動物の飼育方法を学ばせることについては、各大学の担当教官に任せているのが現状」と説明した。
実際には、地域の獣医師が大学を訪れて指導するのが精いっぱいの状況という。物延さんは「それぞれの自治体の獣医師会で教師を志す学生向けに講義を行っているケースはあまりない」と語る。日本獣医師会も学生や教師に動物の飼育方法について学ばせる環境作りを進めるよう働きかけはしているものの、環境の整備には至っていない。
昨年11月に関西学院大で行われた動物飼育の体験授業を見守った理科教育が専門の湊秋作・関西学院大教授は「動物に触れるという経験がない学生が多かった。生き物についての感性を育てる意味でも授業は非常によかった」と振り返った上で、「自然について体験することは教師になる上での必須条件だ」と指摘する。
湊教授は大学内の教室の片隅にオタマジャクシやヤゴ(トンボの幼虫)などを展示し、触れることができる「理科コーナー」を設置した。「動物への慣れは一朝一夕では身につかない。日常的に学生が動物に触れる機会をつくることが必要だ」と話す。教師になる上で避けて通れない動物とのふれあい。教師の卵を育てる教育機関での環境整備が求められている。
「退院後、右耳がほとんど聞こえなくなり、自律神経を損傷した影響で突然めまいを覚えるようになったといい、12月に再度入院し治療を受けるなどしたが、完治は難しいという。」
偶然の事故、又は、男児が知的障害を持つ場合には対応に関して難しいが、故意に相手を傷つけようと思って回復が困難なケガを負わされた場合、
許せないのなら傷害で被害届を出せばよいと思う。立場が逆になった場合、同じように感じれるかは疑問であるが、許したから男児が反省して
成長するとも限らないので批判する人はいると思うが、自分が思うようにすれば良いと思う。
子供の全てが天使であるわけでもなく、天真爛漫でもない。既に歪んでいたり、社会や人に敵意を見せる子供のいるであろう。
全ての教諭が問題のある生徒に対応できる能力や経験を持っているとは思えない。不祥事を起こす教諭は問題外。
綺麗ごとではなく、問題のある生徒を更生させたいと思う教諭は多くはいないであろう。規則とか、勤務中とか関係なく、生徒が安心感を
持てる関係を築くのは難しい。普通の生徒以上に、不信感を抱き、精神的に安定していないと思うからだ。
大学でも問題のある生徒は存在する事を認識させるべきだと思う。また、県や教育委員会は問題のある生徒を扱える教諭には特別手当を与えるなど
差別化を図るべきだと思う。ただ、これを悪用して私腹を肥やす教諭、校長、や教頭は存在すると思うので、対応策は必要。
公務員ではあるが、皆が同じ、皆が平等はおかしいし、楽をしている教諭が同じ給料はおかしいと思う。
完ぺきな制度はなかなか存在しない。基準や優先順位次第だと思う。
児童館で小2男児が女性職員の首をバットで殴り後遺症、傷害で児相通告 被害届に「なぜ小学生を追い詰めるのか」と逆非難… (1/3ページ)
(2/3ページ)
(3/3ページ) 12/19/17 (産経新聞 WEST)
兵庫県内の児童館で今年5月、小学2年の男児が施設に勤務する20代女性の首をバットで殴って負傷させる事件があり、兵庫県警が傷害の非行内容で、男児を児童相談所に通告していたことが18日、関係者などへの取材で分かった。女性は右耳がほとんど聞こえなくなるなどの後遺症が出ており、現在も治療中という。
関係者によると、女性は今年5月下旬、勤務していた児童館で、男児に突然、施設にあった少年野球で使われるようなバットで後ろから首を殴られた。女性は意識もうろうとなり、約1週間入院。退院後、右耳がほとんど聞こえなくなり、自律神経を損傷した影響で突然めまいを覚えるようになったといい、12月に再度入院し治療を受けるなどしたが、完治は難しいという。
この男児は、事件の数日前にも別の児童に暴力を振るっていたといい、女性は6月、県警に被害届を提出。県警は捜査の結果、女性に対する傷害の非行内容で10月、男児を児童相談所に通告した。
女性は教員免許を持っており、この児童館で専門職として勤務する以外に別の小学校でも非常勤講師として教壇に立っていたが、事件以降、いずれも休職を余儀なくされている。
刑法は14歳未満を処罰対象から除外している。通告を受けた児童相談所が家庭裁判所に送致すれば、家裁は調査や審判を行う。
教育者は「被害者」になってはいけないのか
「後遺症が出るような傷を負っても、教育者は『被害者』になってはいけないのか」。被害を受けた20代女性は、産経新聞の取材に苦しい胸中を語った。
女性は大学時代に教員免許を取得。事件当時は、大学院で教育学の研究をしながら、小学校と児童館で勤務する多忙な日々を送っていた。「幅広い知識と経験を得て、子供の能力を最大限伸ばせる教諭になりたい」という思いが支えだったという。
事件後は、静かな場所なら相手の話が聞き取れるが、周囲が騒がしいと、ほとんど聞こえない状態になった。授業や課外活動で児童の発言を聞き落としてしまう可能性が高いため、学校での勤務を断念せざるを得なくなった。
だが、それ以上に女性を苦しめたのは、周囲の反応だった。10月、教育関係者が集まる交流会に出席すると、事件を「単なる事故」と切り捨てられ、「児童が感情をむき出しにするのはむしろ良いこと」「小学生をなぜそこまで追い詰めるのか」と、被害届を出したことを逆に非難されたという。
文部科学省が行った平成28年度の問題行動・不登校調査によると、全国の小学校で児童の暴力行為は約2万3千件発生。うち「対教師暴力」は3628件にのぼる。これに対し、警察や児童相談所などが何らかの措置をした児童は219人と、暴力行為全体の約1%にとどまっている。
女性は「児童から激しい暴行を受けても、我慢している先生はたくさんいるはず。教育現場であっても、『暴力は犯罪』という認識がもっと広がるべきだ」と訴えた。
◇
【用語解説】児童館
児童福祉法で定められた0~18歳未満を対象とする屋内型の福祉施設。集会室や遊戯室、図書室などが設けられ、専門の指導員が季節や地域の実情などに合わせて子供たちに健全な遊びを指導する。一般財団法人「児童健全育成推進財団」によると、平成27年時点で全国に約4600カ所あり、児童福祉施設としては保育所に次いで多い。
下記の記事は極端のような気がするが「本当にデキる人間」と書いているので、何とも言えない。少なくとも本当に出来る人間の定義又は、
記者の思うデキる人間を明確に書いてほしかった。
欠陥があるとしか思えない文科省の学校教育には改善の余地が多くあると思うので、下記の記事の中間点あたりのシステムが良いと思う。
制度として、高卒や大卒の給料基準が存在するから、高卒や大卒の意味があると思う。また、多くの企業がステレオタイプの考え方を持っているし、
日本の社会で育つと型にはまった人間になる確率が高いので、学歴を強調するのと、少子化で学校経営に問題を抱えた人々がメディアや政治家を
使って、教育の重要性や無償化のプロセスで教育の大切さを強調のような気がする。
最近は、学校で考える力の定着を繰り返しているようであるが、本当に知識を身に着け、考える力を身に着けると、教師、学校、その他の社会の
矛盾に気付くようになるのではないのか?そうなると、ごまかしたり、愚かな言い訳を使えないくなる。
将来、財務省が税金を吸い上げる働きアリと見下していると、逆襲を受けるかもしれない。今の現状では、残念だが恐れるような状況にはならないと思う。
教育制度に問題がありすぎる。もしかすると意図的に中途半端な歯車となる人間にすることが目的なのかもしれない。
一般的に完ぺきなシステムや選択は少ない。メリットとデメリットを考えて、適用する状況で一番良い結果を期待できそうな選択を選ぶしかない。
その中には恩恵を受けない人や犠牲になる人も存在する。その人達がデメリットの部分だと思う。
学校教育では「本当にデキる」人間は育たない (1/3)
(2/3)
(3/3) 11/19/17 (東洋経済 ONLINE)
子どもの可能性は、型にはめない多様な学びの中で生まれると、『「天才」は学校で育たない』を書いた白梅学園大学の汐見稔幸学長は説く。
■学校で身に付けたものはそんなに多くない
──原点に立ち返り「学び」を論じていますね。
自分が育ってきたプロセスを考えても、学校で育ててもらった実感がない。学生時代は僕にとって戦後のいい時代で、友人ができたことは大きな意味があったが、学校で身に付けたものはそんなに多くない。教育に世間が考えているほどの力があるのか、教育はそんなにいいものなのか、との疑問が、教育学を長年手掛けながら消えることはなかった。
古代までスパンを広げて眺めると、歴史上に優れた人物はたくさんいる。そういう人物はまず学校に行ってない。学校に行かなければ優れた人物は育たないと考えるのは現代的な幻想だ。人物を育てたのは何だったのか。その時代、時代においての向き合い方だったのではないか。
──向き合い方?
たとえば僕の父はかっぽう料理店の息子で、小学校しか出ていない。板前修業を強いられたが、当時生まれたばかりのラジオにほれ込み自作した。物づくりに執着があって、家を出てやりたかった機械いじりに転じ、戦前のテイチクの録音技師になって、戦後はレコードを作る仕事を手掛けた。
仕事のことを父から直接聞いたことはない。ただ、五味康祐という作家が雑誌にレコード製造技術について書く中で、ドイツ・ハルモニア・ムンディのレコードが随一としながら、1人だけ日本にも任せられる人物がいると紹介した。それが私の父親で、後で父本人に聞いたら、五味が会社に来たことがあったとか。
──職人気質で寡黙だった。
耳がいい男だったようだが、現代風に言えば発達障害だったのだと思う。音に対してはものすごく長けていたが、対人関係は得意でない。物を作らせたらすごいぞという人は昔からたくさんいた。彼らは必ずしも職人になれといわれたから職人になり、そして職人気質になったのではない。もともとそういう気質だったから職人になったらすごい仕事をする。
父は戦後テレビができたときに、大阪の日本橋の電気街に行って設計図を見つけ部品を買い、仕事から帰った後にはんだ付けからテレビを作った。完成前はブラウン管に映るかどうか1週間ぐらい家で調整したから、その間、家族はテレビが見られた。頼まれて市価の4分の1の値段で数十台は作ったようだ。
■仕事ができる人間と学歴は関係がない
──人には得手不得手があると。
もともとそう。誰もがそんなにいろんなことができるわけではない。むしろ可もなく不可もなしのことをいっぱいやり、満遍なくできる人間ほどつまらないものはない。それより、こっちは苦手だが、これをやらせたらすごいという人はたくさんいる。でも、「平均的な底上げ」を得意とし、「年相応の学び」を提供してきた学校教育は、そういう人間を伸ばせるシステムとはいえない。
──優れた大人のイメージは父親ですか。
印象的だったのは近所の大工の棟梁。その人のやっていることを見ていると、すごく格好いい。僕自身、自分用の大工道具一式を小学校に入る前には持っていた。父は仕事人としては一人前だが、学歴がないからNHKの音響技師に応募して断られたということもあったらしい。
本当に仕事ができる人間と学歴は関係がない。上手な手助けのシステムがあれば、人は勝手に育っていく。自分で自分の人生を作っていると実感できれば後悔もない。もちろん医学など大学に行かないと学べないことはたくさんある。だが、そこに行かないと研究できないのだから、それはほとんど職人仕事だとも言ってもいい。
──没頭できるものとの出合いが大切?
世の中、こういう枠組みがあるから、そこに入りなさい。その中で、点数取りの競争をして、それに向いているからと銘柄の大学に入って、それも末は博士か大臣かではなく大企業の課長止まり。今のリクルートシステムの主流はこう作られているが、教育はそんなつまらないものではない。
文学作品を読んで感動して、こういうものを書いてみたいと文学教室に入ってみる。いろんな人と出会い、切磋琢磨し合う。結局プロにはなれなくても、今でも自作に励んでいる。そうであれば人生に満足できる。文章ではなく、料理にはまってその世界に入っていってもいい。
本当の文化に出合い、そこで没頭する、凝ってみたいと高揚する。それこそが生きていくうえでのテーマなのだから頑張ってみる。そういうシステムがあったら、もっと面白く、アイデア豊かな人間が育つのでないか。
■教育の本来の姿
──師を選べ、ともあります。
歴史的に見て強制的に勉強させたのは古代ギリシャのスパルタぐらいしかない。教育は学ぶ側が主体で、本来は先生を選んで始まる営みなのだ。中でも宗教家は皆そう。こういうものになりたい、こういう力を身に付けたいとの初心が学ぶ側にあって、師を選ぶ。これが教育の本来の姿だ。
今の学校は小学校、中学校とも勝手に割り振られる。この先生に学びたいと選んでいない。ただ社会や国家が先に立ち、必要な人材になれ、税金でやるから来させよとなってしまっている。もっとラディカルに考え直したほうがいい。
──授業は午前だけで十分とも。
本来の教育は学ぶほうが優れた人や文化に出会い、あれをやってみたい、この人と語り合いたいと発起し、その取り組みを励ましていくことだ。今の教育は、基本的に指示に従って上手に点数を取れば安泰な人生が送れるとした「修練」に陥っている。指示からはみ出たやり方やオリジナルなやり方ができる人間はなかなか育たない。
最低限の読み書きそろばんは必要だとしても、それは学校の午前中だけで十分だ。午後は子どもがそれぞれ自分のやりたいことを見つけて、それを伸ばすことに専念する。そのやり方を学校が認めてくれないなら、その学校の存在意義は薄い。そうしたほうが、絶対面白い子が育つからだ。
特に、企業人に問いたい。経済のためと強制的に産業人予備軍を育てるサラリーマン養成学校のようなものが、本当にうまく機能しているかと。
塚田 紀史 :東洋経済 記者
法、規則、制度や体制が存在しても、運用する組織、管理部門や人材に問題があれば機能しない。結果として、ないよりはまし程度になってします。
行政や組織がこの事を理解していないと法、規則、制度や体制があるから問題ないと愚かな発言をする幹部が存在するようになる。
調査委員会はなぜ担任が助言を実行しなかったのか明確にする必要があると思う。担任が助言を無視したのであれば、担任の責任は重い。
無視した理由も重要。担任は教務主任を信頼していなかったのか、教務主任を嫌っていたのか?担任は人の話を素直に聞くタイプではなかったのか?
担任は自分の判断を優先するタイプだったのか?担任はメモや記録を取らないタイプで、単純に保護者に受診の件を言うのを忘れたのか?
同じ結果でも、理由がわかれば次回にフィードバック出来る。教員採用の面接で、どのようなタイプの人間が教師に向かないのかを判断する
資料やデータにも使える。
発達障害疑い、助言受けた担任ら放置…叱責自殺 11/18/17(朝日新聞)
福井県池田町の町立池田中学校で3月、2年生の男子生徒(当時14歳)が自殺した問題は、担任と副担任の厳しい叱責が原因とする調査委員会の報告書の公表から1か月が過ぎた。
報告書は生徒について「発達障害だった可能性がある」とし、担任も同僚からそう伝えられていた、と指摘した。特別な支援が必要な生徒を巡っては、国の指針などに基づき各都道府県で体制を整えている。だが、同校では今回こうした仕組みが全く機能していなかった。
「指導方法を考えるべきではないか」。今年2月頃、男子生徒の発達障害を疑った教務主任は、叱責を繰り返す担任の30歳代の男性教師を見かねてこう助言した。担任と、副担任の30歳代の女性教師は宿題の未提出などが続いた生徒を大声で怒ったり、執拗(しつよう)な指導を繰り返したりしていた。
先月15日に公表された報告書によると、主任は生徒の受診を保護者に勧めるよう担任に促したという。教員間でも、その疑いが話題になっていた。だが、担任は校長らに相談せず、家庭訪問時に保護者に伝えることもなかったという。
文科省!下記の記事の内容が事実なら文科省は教員免許が取得できる学部を持つ大学にどのような指導及び監督をしているのか?問題のある大学や
問題のある学部を持つ大学に決められた期間内に改善が見えなければ補助金、又は、その他の支援を打ち切りで、生き残れないのなら退場してもらうべきだ。
大学レベルでなくても、メンデルの法則は中学科学でもカバーしているだろう。
メンデルの法則は、 優性の法則、分離の法則、独立の法則の3つからなります。
優性の法則:遺伝子には、表現型が現れ易い遺伝子(優性)と現れにくい遺伝子(劣性)があり、同時に存在した場合、優性の形質のみが表現型として現れる。
分離の法則:両親から受け継いだ2対の遺伝子は融合せずに、次の代に伝わる際には分離する。
独立の法則:異なる2つ以上の形質が対立する場合、特定の組み合わせを成さずに、独立して遺伝する。
(【理科講師必見】メンデルの法則をわかりやすく説明するコツ!塾講師ステーション情報局)
こんな事を理解出来ない人間が教員免許を取得でき、教員採用試験にも受かる。過去にも他の件で試験や採用で不正が起きているが、大阪でもあるのではないかと疑ってしまう。
もし不正がないのなら、大阪の教員採用試験及び面接に適任者でない人間が合格できる欠点があると推測する。
「すると担任の先生に、『どこの血が入っていようが、なに人であろうが関係ない。これは市の決まり。普通は黒髪で生まれてくる。髪を染めてもらわなければ学校に来ては困る』と言われたんです」・・・
同じクラスには、アメリカ人と日本人の親を持つ生徒がいた。担任はその生徒の髪色に言及しながら、「ハーフが黒髪に近いのになぜ、クォーターのあなたの髪がこんなに赤いのか」とも注意をしたという。
個人的な意見だが、差別や無知はなくならない。ただ、無知な人間を教員採用試験で合格できないように改善すること、運が良く教諭になれたが、無知である
、又は、常識がない教諭に完全が見られなければ、分限処分にすることが出来るようにする事は可能だし、大阪府の行政次第で速やかに対応できる。
「同じような問題をなくすために、どんなことを教育関係者に知ってもらいたいのか。そう聞くと、女子生徒は言葉に力を込めた。」
記事に出てくる中学及び高校の教諭らが教員採用試験でに合格しない、そして、臨時採用の人間も含め、採用しないように大阪府知事に要請するべきだと思う。
問題を知ったところで、無視する教育関係者や教諭達は存在するし、無視しても処分されない。問題のはじまりから断ち切るしかない。それでも
問題は改善すると思うが、はなくならないと考えた方が良い。
今年、福岡の私立高校で教師を殴る生徒の映像が流れた。正当が理由がないのであれば、このような生徒は少なくとも公立では退学処分にするべきだと思う。
教諭だけでなく、問題のある生徒に対しても厳しい処分が必要。高校無償化にするのであれば、私立であっても同じことが言えると思う。
税金をつぎ込んで勉強をしたくない生徒を学校へ通わせる必要はない。他の生徒の中には迷惑に思っている生徒もいるはず。
「茶髪で生まれたら普通じゃないの?」 黒染めを強要された女子高生の想い (1/2)
(2/2) 10/28/17(BUZZFEED JAPAN)
髪の毛が生まれつき茶色いにも関わらず、教員から黒染めをするよう強要され、精神的苦痛を受けて不登校になったとして、大阪府立高校の女子高生が府に対して起こした裁判が、議論を呼んでいる。他人事ではないーー。この問題をそんな風に感じている人たちは、少なくない。自らも過去に「黒染め強要」を受けたことがある別の女子高生が、BuzzFeed Newsに思いの丈を語った。【BuzzFeed Japan / 籏智広太】
「普通は黒髪で生まれてくる」
「茶髪で生まれてきた私が、普通じゃないと言われているように感じて。本当に、涙が出るほど悔しかったです」
BuzzFeed Newsの取材にそう話すのは、大阪府内の公立高校に通う女子生徒(3年)だ。祖父がアメリカ人で、生まれつき、髪の毛が茶色い。
この女子生徒は、中学1年生のころ、担任から黒染めの強要を受けたことがある。入学当日のことだ。いまでもはっきりと覚えている。
「保護者やクラスメイトの前で、担任の先生から教室の前に呼び出され、髪色の注意を受けました。母は『私の父がアメリカ人なので娘は4分の1、つまりクォーターです。生まれつきの髪色です』と説明しました」
「すると担任の先生に、『どこの血が入っていようが、なに人であろうが関係ない。これは市の決まり。普通は黒髪で生まれてくる。髪を染めてもらわなければ学校に来ては困る』と言われたんです」
母親は教育委員会に足を運び、対応を依頼したが、その後も担任の態度は変わらなかった。別室や廊下に呼び出される日々が続いた。
「見世物みたいに教師たちに囲まれ、髪をかき分けられながら根元も調べられました。まるで不良少女扱いです。悔しくて、仕方がなかった」
「高校進学も諦めろ」
同じクラスには、アメリカ人と日本人の親を持つ生徒がいた。担任はその生徒の髪色に言及しながら、「ハーフが黒髪に近いのになぜ、クォーターのあなたの髪がこんなに赤いのか」とも注意をしたという。
さらには「高校進学や行事参加も諦めろ」とまで言われ、「我慢の限界」を感じた女子生徒は、母親とともに、再び教育委員会に訪れた。
教育委員会からは、「そのような決まりはない」との説明を受けた。すぐに学校側に連絡が行き、学年主任らから謝罪も受けたという。
その後、担任から幼少期の写真を持ってくるよう求められ、数枚を提出すると「やっと地毛だということが認められた」。それからは同じような強要を受けることはなくなった。
女子生徒は自らの経験を振り返りながら、こう言った。
「生まれ持ったものを否定するなんて、ひどいですよね」
差別がなくなれば…
毎日新聞によると、裁判を起こした女子高生は、文化祭や修学旅行には茶髪を理由に参加させてもらえなかった。また、教諭からは、「黒く染めないなら学校に来る必要はない」と言われ、2016年9月から不登校になったという。
いずれも、「生徒心得」で「染髪」を禁止した項目があるのが、その理由だ。
取材に応じた女子生徒は「とても他人事とは思えなく、悲しく、やりきれない気持ちでいっぱいです」と語る。黒染め強要が「差別」だとも。
「私が、黒染め強要を差別だと感じる理由は、生まれ持ったものを無理矢理変えなければいけないということです。髪色を好き好んで生まれてきたわけでもないのに、髪色のせいで人格まで否定されたり、なぜここまで地毛のせいで辛い思いをしなければならないのかと、疑問に思います」
いま通っている高校では、事前に髪色が黒ではないことやパーマであることを示す「地毛登録」をしており、黒染めの強要を受けたことはないそうだ。
同じような問題をなくすために、どんなことを教育関係者に知ってもらいたいのか。そう聞くと、女子生徒は言葉に力を込めた。
「人はみんな、持っているものがそれぞれ違うということです。肌の色も目の色も髪の色も、それぞれ違います。髪色一つで人格まで否定されるような社会は間違っています」
「どうか理解が広がって、私のような生徒も、ハーフやクォーターではないけど生まれつき黒髪ではない生徒も、みんなが辛い思いをせず学校生活を送れるようになることを、願います」
人によっては髪染めの化学薬品で皮膚が炎症や拒否反応を起こすので、絶対にと主張する府立懐風館高校はおかしいと思う。
生まれつき茶色い髪と嘘を付くケースもあるから、例外を作りたくなかったのかもしれないが、大阪府立懐風館高校の説明はおかしいと思う。
生まれつき茶色い髪と嘘を付く人間は他の点でも問題を起こす、又は、問題があるケースが多いと思う。明確に白黒付けれる事で処分すれば
良いと思う。女生徒が髪の色以外で問題がなければ信じても良いと思う。
まあ、大阪の人は自己主張が強く、自己中心的な傾向が他の地域よりも強いように思えるので、例外を作りたくないのだろうか?
大阪府立高校の校則について全く知らないが、府立高である以上、大阪府教育庁の指導や方針に従う必要があると思う。府立懐風館高校の判断は
大阪府教育庁の了解を取っているのだろうか?
「教諭らは『金髪の外国人留学生でも規則なので黒く染めさせる』と母親に告げ」について、学歴で判断できない事はあるが、教諭らはどこの大学を
卒業して、このような愚かな説明をするのか?ロジカルに物事を判断し、説明できなくても、教員免許が取得できるし、教員採用試験にも
受かる事が証明されたと思う。(教員採用試験では便宜を図った事、又は、不正がなかったと仮定する。)
文科省よ!教員養成の大学のプログラムに改善する必要がある事を意味している。大阪府は教員採用試験及び面接に関して改善する必要があると
思う。例え、規則を遵守する事を説明したいとしても、「外国人留学生でも黒く染めさせる」は余りにも思考能力が低く、常識が欠如し、
国際感覚も欠如していると思える。
外国人達にこのような間抜けな説明が通用すると思うか?外務省、英語教育の前に、教諭達の質の向上を同時に行う必要がある。英語が話せたら
こんな教諭達の欠点だらけの説明を受け入れる事は100%無理だと思う。英語が話せると言う事は、外国の考えを理解し、外国人と議論できる
能力を備えていると言う事になる。そうであれば、府立懐風館高校の一部の教諭達は愚かで、その愚かさにも気付かない愚かな教育者達と言う事だ。
府立懐風館高校がどの程度の高校か知らないが(みんなの高校情報)、私立なら学校経営者の方針が反映されたり、どのような学校したいかで
違いはあると思うが、公立でこのようなおかしな説明はないと思う。こんな学校でも高等教育無償で生徒が増えるのだろうか?文科省や自民党は
教育無償化も良いが、問題のある学校は生き残れないようにするべきだと思う。公立及び私立で問題のある学校は、残るべきではない。税金の無駄遣い。
要らない学校、教諭、学校経営のために勉強したくない生徒を受け入れる私立学校は退場させるべき。
「金髪外国人でも黒に」茶色の髪の女子高生に黒染め強要、府「事実と異なる点もある」 10/27/17(MBS)
大阪府立高校の女子生徒が生まれつき茶色い髪を学校から黒く染めるよう強要され精神的苦痛を受けたとして訴えを起こしました。
訴状によりますと、羽曳野市にある府立懐風館高校3年の女子生徒(18)は生まれつき髪が茶色で、入学時に母親が学校側に配慮を求めていました。ところが教諭らは「金髪の外国人留学生でも規則なので黒く染めさせる」と母親に告げ、黒く染めるよう繰り返し指導。女子生徒は、頭皮がかぶれるほど黒染めを繰り返してきましたが「黒染めが不十分」と指導され、去年9月以降、不登校になりました。
生徒側は「精神的苦痛を受けた」として、府に約220万円の賠償を求めています。一方、大阪府側は27日の第一回口頭弁論で請求の棄却を求めました。大阪府教育庁は、取材に対し「原告の主張は事実と異なる点もあるので、今後の裁判で明らかにしたい」としています。
生来の茶髪「黒く染めろ」…不登校に 女子生徒が大阪府を提訴 10/27/17(ABC)
大阪府立高校の女子生徒が、生まれつき茶色い髪を黒く染めるよう教師らに強要され、不登校になったとして、府に賠償を求める訴えを起こしました。
訴状などによりますと、羽曳野市の府立懐風館高校3年の女子生徒(18)は、生まれつき髪の色素が薄く、茶色く見えるため、母親が配慮を求めてきました。しかし、生徒指導の教師らは髪を黒くするよう繰り返し強要。女子生徒は市販の髪染めが肌に合わず、痛みなどを感じながら何度も髪を染めましたが、教師らから、「不十分」と言われ続けた上、授業の出席も禁じられ、去年9月から不登校を余儀なくされたということです。女子生徒は府におよそ220万円の賠償を求めて提訴。きょうの第1回口頭弁論で府側は請求の棄却を求め、争う姿勢を示しました。大阪府教育庁は、「原告の主張は一部、事実と違うところもあるので、訴訟の中で説明していく」としています。
「サンダルに仕込んだスマートフォンで撮影」は悪質だし、常習性があるように思える。
高校教師の前に男性であるのはわかるけど高校教師である事を自覚するべきだと思う。
実際は知らないが、被害届を出さない人達もいるから、リスクを負うメリットもあるけど、やはり教師はリスクが高すぎると思う。
「生徒の体触ってた」"知人"10代女性に性的暴行 逮捕の高校教師 保護者から苦情も 札幌市 06/11/17(北海道ニュースUHB )
10代の知人女性に乱暴したとして10月10日に逮捕された札幌市の高校教師が以前、保護者から、「生徒の体に触ることがある」と指摘を受けていたことが分かりました。
学校側:「誠に遺憾。関係者に深くおわびする」
札幌静修高校の教師、根塚司容疑者(34)が逮捕されたことを受け、学校側が報道陣の質問に答えました。
学校側は根塚容疑者の指導に対し、保護者から「生徒との距離感が近い」と指摘を受けていたと明らかにしました。
根塚容疑者は、女子生徒の肩に触れることがあり、嫌がる生徒もいたということです。
根塚容疑者は2017年6月、札幌市中央区の商業施設のトイレで、酒に酔って意識がもうろうとなった10代後半の知人の女性に乱暴した、準強姦の疑いが持たれています。
根塚容疑者は、容疑を認めています。
UHB 北海道文化放送
「トイレで介抱し興奮した」"知り合い"10代女性 性的暴行の高校教師 カラオケで 札幌市 06/11/17(北海道ニュースUHB )
2017年6月、札幌市・ススキノの商業施設で10代の知人女性に乱暴したとして札幌市の高校教師が10月10日に逮捕された事件で、男が酒に酔った女性をトイレで介抱していて興奮したと話していることがわかりました。
この事件は2017年6月、札幌市中央区の商業施設のトイレで、酒に酔って意識もうろうとなった10代後半の知人女性に乱暴したとして、札幌静修高校の教師、根塚司容疑者(34)が逮捕されたものです。
捜査関係者によりますと根塚容疑者は、当時カラオケ店で被害者の知人女性を含む数名で酒を飲んでいて、調べに対し、酒に酔った女性を介抱しようとトイレに連れて行ったところ、興奮したという旨の話をしているということです。
根塚容疑者は「事実です」と容疑を認めていて、警察では、カラオケ店で同席していた知人などからも話を聞く方針です。
"以前から知り合い" 10代女性 酒飲ませ性的暴行 34歳高校教師を逮捕 北海道札幌市 06/10/17(北海道ニュースUHB )
2017年6月、札幌市中央区の商業施設で知人の10代女性を酒に酔わせて乱暴したとして、札幌市の高校教師が10月10日、逮捕されました。
準強姦の疑いで逮捕されたのは、札幌静修高校の教師、根塚司容疑者(34)です。
根塚容疑者は2017年6月、札幌市中央区の商業施設で札幌市に住む10代の知人女性に酒を飲ませ、意識もうろう状態となった女性を、乱暴した疑いが持たれています。
警察によりますと、根塚容疑者は女性と以前から知り合いで、未成年であることも知っていたということです。
根塚容疑者は学校で、ハンドボール部の顧問を務めていました。
調べに対し、根塚容疑者は「事実です」と容疑を認めています。
学校は11日、集会を開き、生徒に事情を説明することにしています。
UHB 北海道文化放送
また不祥事 愛知県立高の男女教諭を懲戒 06/04/17(CBCテレビ)
愛知県教育委員会は、県立高校に勤務しながら万引きを繰り返し逮捕された女性教諭と、強姦未遂容疑で逮捕された男性教諭を、それぞれ懲戒処分にしました。
「申し訳ありませんでした」
(愛知県教育委員会 会見)
愛知県教育委員会によりますと、処分を受けたのは半田農業高校の29歳の女性教諭です。
女性教諭は、去年3月、通勤途中に名古屋市中区のコンビニエンスストアで、菓子などを万引きし、警察の調べを受けたうえ、ことし4月、同じ店でおにぎりを万引きし、窃盗容疑で逮捕されました。
女性教諭は、8日付で停職6か月の処分を受けました。
また、横須賀高校の27歳の男性教諭は、去年12月、出会い系アプリで知り合った当時14歳の女子中学生と会い、車に同乗させたものの、未成年と分かって怖くなり何もせずに別れたとして、強姦未遂容疑で逮捕されました。
この男性教諭は、停職1か月の処分です。
愛知県教育委員会は、「教職員の意識喚起に努め不祥事の根絶を図っていきたい」とコメントしています。
年の差を超えての純愛もあるのかもしれないが、教諭の立場を考えないといけない。もし、結婚したいのであれば、女性であれば16歳で結婚できるのだから
あと一年もしくは女性の誕生日まで待てばよかった。まあ、女性の親が賛成するかも問題があるが、少なくとも法的には問題なかった。
女性の気持ち次第であるが、結婚しない限り、教諭は同じ学校には残れないと思う。私立学校のレベル次第であるが、普通、又は、それ以上の中学校で
あれば、学校に残れないと思う。
カーテン付きの車中で…47歳中学教諭が15歳元教え子にみだらな行為 愛知・小牧市 06/04/17(東海テレビ)
愛知県の私立中学校に勤務する教諭の男が、車の中で元教え子にみだらな行為をした疑いで逮捕されました。
逮捕されたのは愛知県内の私立中学校に勤務する教諭・富永浩容疑者(47)で、3日午後4時ごろ小牧市内の駐車場に停めた車の中で、15歳の少女に対しみだらな行為をした疑いです。
その後、隣りの春日井市の駐車場でカーテンが閉まったままの車をパトロール中の警察官が発見し、富永容疑者に職務質問をしたところ犯行を認めたため逮捕しました。
調べに対し、富永容疑者は「相手を愛おしく思う気持ちがあった」と供述していて、警察によりますと少女は富永容疑者の元教え子で、2人は交際していたということです。
公立であってもスポーツに力を入れている学校や特定の部活だけ力を入れている場合がある。
日本は平等が好きだが同じ基準では考えない方が良い。スポーツに力を入れたい学校は申請して優先的に経験豊富な教師をくじで引くようにすれば良いのではないのか?
部活は勝てなくても体を動かす程度で良いと思っている学校に、部活動のスポーツに関して経験豊富な教師は必要ない。実際、平等にしようとしても
コストや人材で実現可能だろう。ゆとり教育の失敗や現在の早期の英語教育に現場の問題を考えれば理解出来るだろう。理想や理論と現場での実行
の段階になると難しい事がある。
教育の窓 部活指導員、根性論脱却を 内田良・名大大学院准教授に聞く 05/01/17(毎日新聞)
<kyoiku no mado>
スポーツなどに詳しい学校外の指導者が、学校職員と位置付けられる「部活動指導員」制度が4月に始まった。教員の負担軽減と部活動の安定運営などのため、中学・高校の部活動で技術的な指導をするほか、大会へ引率したり、顧問に就いたりできる。部活動の現場はどう変わるのか。学校問題に詳しい名古屋大学大学院の内田良・准教授に、子どもの立場からみた意義や課題を聞いた。
●子ども、負担減らず
--今回の制度をどう評価しますか。
国の部活動指導員制度の導入には大きく二つの狙いがあります。一つは教員の長時間労働の解消です。
ある教育誌に掲載された研究で、名古屋市の中学校新任教員の残業時間が、月平均90時間だったというデータがあります。国の「過労死ライン」の80時間を超えている。別に名古屋市が特異なわけではなく、どこも同じような状況でしょう。先生に代わって負担を減らそうとする点で、指導員制度を高く評価します。
一方で、子どもの負担軽減にはなっていません。休日もない、長時間の部活動は子どもたちにとっても大きな負荷がかかります。でも、国が掲げる指導員制度の二つ目の狙いは、子どもの技術力の向上です。むしろ「部活動を積極的にやるぞ」という姿勢を示しています。指導員は地域の熱いタイプの人が引き受けがちで、根性論で練習が過酷になることを危惧しています。
--子どもにとって指導員のメリットはないのでしょうか。
指導員の資質によってはあります。より高度な技術指導を受けられる点です。日本体育協会(東京都)の調査では、運動部担当の教員の約半数は、その競技の未経験者でした。運動部で素人が指導するのはとても危険なことです。事故につながるからです。
ただ注意しなければならないのは、ただの経験者では駄目だということです。経験則はかえって危険を招きます。必要なのはスポーツ指導の科学的知識なのです。しかも、時代に応じてきちんとバージョンアップされること。例えば、中途半端な知識の指導者は、長時間やれば強くなると考えます。しかし、プロは、本当に勝ちたいと思うなら週2日休むのは当然と考えます。
●定期チェック必要
--指導員の質を担保するにはどうしたらいいでしょうか。
指導員と指導内容をきちんと調査し、チェックすることです。どんな競技経験があり、大学などで何を学んだか、指導方法は適切か、などの点について年1回、あるいは2年に1回でも定期的にチェックします。国が人件費を出すのが一番いいと思います。そうでないと自治体任せになってしまい、地域によってばらつきが出るからです。国が指導員の資質の点検までするのは難しいので、予算を手当てするしかありません。
--教員、子どもの双方に無理を強いる「ブラック部活」という言葉も広がっています。
部活動は1980年代ぐらいから変容してきました。ペーパーテストだけではなく、生徒の多様な能力を評価する尺度の一つとして入試の成績に結びつきました。学校によっては看板にもなり、強豪校の校舎には「全国大会優勝」などの垂れ幕がかかる光景を目にします。
部活動が生徒や学校の評価手段となり、勝利至上主義に傾く中でブラック化が進んできました。本当は「勝つため」一心になっているのに、先生たちは「子どものため。ごらん、目がキラキラしている」と。教育の名がつくと、みんないいことになってしまう。
●長時間活動に疑問
--部活動は今後、どうあるべきだと考えますか。
部活動は、誰もが同等に低コストでスポーツや文化活動に触れられる、子どもに対する機会保証だと考えています。世界でも類を見ない制度で、残すべきだと思います。でも、学業に支障が出るような長時間の活動は必要ないし、教員の不払い労働が支えているのもおかしい。
教育現場や家庭が、部活動のあり方について根本的に考えを変えていかなければならないと思います。休養日を増やすだけでなく、大会数を減らすなど、評価や勝つことを前提とした考え方から脱却を図る必要があります。
「休養指針」実効性カギ
部活動指導員が学校教育法に盛り込まれ、学校職員として位置付けられるようになった背景には、国際的に日本の学校教員の長時間労働が問題視されたことに加え、教員自らも声を上げて署名集めなどの活動を始めた経緯がある。
日本は2013年に経済協力開発機構(OECD)が行った「国際教員指導環境調査」(TALIS、タリス)に初参加した。14年6月に結果が発表され、日本の中学校教諭の1週間あたりの勤務時間は53・9時間と参加34カ国・地域のうち最長で、中でも部活動など課外活動の指導時間は7・7時間と、参加国平均(2・1時間)の3倍超だった。世界一多忙な状況がデータで示され、教育関係者の間では、調査名をとって「タリスショック」と呼ばれたほどだ。
また、現場の過重労働の実態が明るみに出たのは、ウェブサイト「部活問題対策プロジェクト」の力も大きい。全国の現役中学校教員6人が15年12月、部活動の顧問を引き受けるかどうかの「選択権」を求めてネット上で署名集めを始めた。サイトには疲弊しきった若手教員たちの声がつづられ、3カ月間で約2万3500人の署名が集まり、文部科学省に提出された。現在も活動は続き、署名は3万1000人を超えている。
今年1月、文科省とスポーツ庁は、中学や高校の部活動の休養日を適切に設けるよう全国の教育委員会などに通知した。さらに、今年度中に実態調査を実施し、具体的な練習時間や休養日のガイドラインを策定する方針だ。
しかし、1997年に当時の文部省が部活動の休養日について「中学校は週2日以上」「高校は週1日以上」と目安を示した際には、現場にほとんど浸透しなかった。専門家からは「罰則規定がなければ、どの程度実効性があるのかわからない」という指摘も出ている。【太田敦子】
■人物略歴
うちだ・りょう
1976年生まれ。名古屋大経済学部卒、名大大学院教育発達科学研究科博士課程修了。教育社会学者。授業中や部活での体罰、事故など「学校リスク」に関わる問題について研究し、2011年から現職。著書に「柔道事故」「教育という病」など。
高校教諭児童買春の疑いで逮捕 04/06/17(BSN新潟放送)
新潟市の私立高校、東京学館新潟の30歳教諭の男がSNSで知り合った17歳の女子高校生に現金を渡しみだらな行為をしたとして逮捕されました。
児童買春の疑いで逮捕されたのは、東京学館新潟高校の英語教諭渡邉東雲容疑者30歳です。渡邉容疑者は、ことし1月中旬、SNSで知り合った新潟市内に住む当時17歳の女子高生に現金を渡し18歳に満たないことを知りながら、新潟市内のホテルでみだらな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、渡邉容疑者は「弁解することは何もありません」と容疑を認めているということです。東京学館新潟高校は取材に対し、「事実を確認中」とコメントしています。
文部科学省と上智大学言語教育センター教授、藤田保氏の考えは同じなのか?
同じ、又は、似た考えなら、学習指導要領の改訂は大間違いだと思う。
英語が出来ない日本人教師に英語を教えて、その教師が子供に英語を教える。なんと無駄な事であろうか?選択制として希望者だけが英語を
受ければ良いと思う。そのかわり、高校入試や大学入試で、合否の基準を変えるべきだと思う。
なぜ全ての先生が英語を話すことを楽しめると思うのか?ここで既に勘違い。英語を話せるメリットも教えるべき。そして、日本人は外国人と
比べると一般的に積極性に欠ける。英語教育の前に、又は、同時に、この点を変えていなければ英語を話すメリットはあまりない。
英語を話せればメリットになるが、どれだけのお金をかけて、子供が英語を話せるようになるのかを考えると、メリットがないと言う事だ。
英語が嫌いでも英語を話す必要がある、目標を達成する過程で英語を話さなければならない状況では、人は苦労すると思うが、英語を必死で
学ぶと思う。それで良いと思う。やりたいと思った時に、安く英語を勉強できる環境を提供する方がコストパフォーマンスははるかに高いと思う。
小学校からの英語教育は、「ゆとり教育」と発想が同じだ。結局、多くの税金を使って大きな効果もなく失敗するだろう。「ゆとり教育」は
本来の目的を達成できる人材不足の環境で形だけを実行した。結果、子供の探求心や社会の出来事と勉強の関連を教える事も出来ず、ゆとりの時間を
興味を持っている事を深く掘り下げるために使う事も出来ず、薄い教科書だけが結果となった。詰め込み勉強でなく、いろいろな事を深く学ぶことで
いろいろな関連性や実社会での応用出来る事に多くの子供が気付く事なく、学力低下でエンド!
教師の不祥事のニュースや記事を見ると、こんな教師達に何が出来るのかと思う。少なくともまともな生き方さえも見せる事が出来ない。
英語教育も同じ道をたどると思う。英語学校や英語塾が得をするだけである。そしてネイティブや外国人英語アシスタントを使うコストがかなり
無駄に使われるであろう。
小学3年からの英語教育 専門家「先生が楽しみながら英語を話す姿を見せていくのが大事」 04/06/17 (AbemaTIMES)
学習指導要領の改訂により、これまでは5年生からだった小学校の英語教育が3年生から始まることになった。
上智大学言語教育センター教授の藤田保氏は、これまで英語を教えていなかった先生にとって負担増につながる可能性も指摘したが「少なくとも知識という点においては、どう考えても先生のほうが子供たちよりは持っているわけですから。自分に自信を持っていただきたい」と話した。
またネイティブが英語を話したところで子供たちの関心は引き寄せられないとし「でも自分のクラスの担任の先生が楽しみながら英語を話している姿を子供たちに見せてあげれば、それが子供たちにとって大きな自信を与えていくことになるし、大人になって自分もそういう風に英語を話す人になっていくんだというロールモデル(手本)を与えることになる。そこが日本人の先生が英語を使うことの大切さだと思います」と説明した。(Abema One Minute Newsより)
児童福祉法違反容疑 教諭逮捕 03/14/17(NHK広島)
福山市の県立高校に勤める48歳の教諭が車の中で女子中学生にわいせつな行為をしたとして児童福祉法違反の疑いで逮捕されました。
教諭は「黙秘します」と話しているということです。
逮捕されたのは福山市の大門高校の教諭、宮地仁容疑者(48)です。
警察によりますと宮地教諭は先月25日の午後6時40分頃、福山市箕沖町の路上に駐車した自分の車の中で、15歳の女子中学生に対し18歳未満であると知りながらわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反の疑いが持たれています。
パトロール中の警察官が車の中で女子中学生とわいせつな行為をしている宮地教諭をみつけたということで、警察によりますと2人は面識があるということです。
宮地教諭は警察の調べに対し「黙秘します」と話しているということです。
県教育委員会の福嶋一彦教職員課長は「県立高校の教諭が逮捕されたことは誠に遺憾であり、生徒や保護者、県民の皆様におわび申し上げます。詳細の確認を行い、結果を踏まえて厳正に対処したい」と話しています。
文部科学省は天下り先さえ確保できれば、税金が無駄に、又は、非効率に使われようが、良い結果が出なくても
どうでも良いと言う事。
「英語が使えない英語教員」とは情けない --- 山田 肇 02/15/17 (アゴラ)
京都新聞の2月10日の記事「英語教員、TOEIC“合格”2割 京都府中学「資質」はOK?」(http://www.kyoto-np.co.jp/education/article/20170210000018)は衝撃的だった。京都府内の中学校英語科教員で、本年度にTOEICを受験した74人のうち730点以上を獲得したのは16人で、最低点は280点、500点未満も14人いたという。
TOEIC730点は英語検定準1級に相当する実力で、文部科学省が2014年に設定した英語科教員の能力目標(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/102/houkoku/1352460.htm)である。500点は簡単な会話ならリスニングできるレベル、280点は箸にも棒にもかからない。
文部科学省は毎年730点越えした英語科教員の比率を公表(http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/04/05/1369254_2_1.pdf)し、昨年の公表値は30.2%。都道府県別のデータも公表されているが、京都府の中学校教員の場合、対象675名のうち試験を受験した経験がある者は555名、このうち730点越えは80名、26.7%である。京都府の英語科教員の能力は全国平均よりも低く、大半は英語が使えない。これでは子供たちの英語力が向上するはずはない。
経済社会は急激に変化し、子供たちが養うべき能力も年々変化してきている。先の記事でも触れた情報活用能力もその一例(http://agora-web.jp/archives/2023953.html)であるが、英語も必要不可欠である。文部科学省も英語教育の改革を進めているが、現場は追いついていない。
教員免許更新制度は2009年に導入されたが、文部科学省の該当ページには、制度は「不適格教員の排除を目的としたものではありません。」(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/)という注釈がある。第一次安倍政権で「不適格教員の排除」を出発点に議論が始まったのだが、現場の反対で押し戻された結果である。朝日新聞の過去記事を検索したら、日教組の定期大会後、委員長が「政権交代したら民主党と話し合い、免許更新制をストップする方向でいきたい」と語ったという2009年7月31日の記事が残っていた。
免許更新制度と同じロジックでは、TOEIC280点の英語科教員にも再教育のチャンスを与えることになるのだが、本当にそれでよいのか。箸にも棒にもかからない教員に教えられる子供たちの悲劇を思うと、「不適格教員の排除」に進むべきではなかろうか。
山田 肇
「今回の早稲田大学の件でも、内閣官房のHPで毎年の再就職状況が個人名と再就職先を含めて公開されている
(http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/kouhyou_h280920_siryou.pdf)。
ここはネタの宝庫であるので、マスコミはこれを活用して、是非とも天下り問題をしっかり解明して欲しい。」
この点には同感である。マスコミは徹底的に調べて情報を公表してほしい。元文部科学事務次官 山中伸一は問題を知っていたのか?
元文部科学事務次官 山中伸一 在ブルガリア大使に聞く! 平成28年7月26日(火曜日)(文部科学省)
【天下り問題】事務次官のクビを一瞬で飛ばした安倍官邸「真の狙い」 震え上がる官僚たち (1/3)
(2/3)
(3/3) 01/23/17 (現代ビジネス)
天下りの起源
文部科学省が元高等教育局長の早稲田大への天下りを斡旋(あっせん)した、という問題が世間を賑わしている。この件の責任を取って、前川喜平文科事務次官が引責辞任した。
早稲田大学では、20日に鎌田薫学長が記者会見を開いて、「再就職等規制に関する本学の理解が不足していた」と謝罪。そして、早稲田大学に再就職していた元高等教育局長の吉田大輔教授は辞職した。
教育再生会議座長をはじめ、各種審議会で役所との繋がりが深く、しかも著名な法学者である鎌田学長の口から「再就職等規制の理解が不足していた」という言葉が出てきたのはかなり残念である。
世間一般では、天下り批判は、公務員が関連企業に再就職することをいう。しかし、いくら公務員であっても職業選択の自由があるので、再就職全般を禁止することはできない。
そこで、再就職活動に関連して、職員による再就職斡旋禁止、現職時代の求職活動禁止、退職後の元の職場である役所への働きかけ禁止の規制が行われている。
この天下り規制は、10年前の第一次安倍政権の時に筆者らが企画立案し成立した「国家公務員法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第108号)に基づくものだ。
筆者は、小泉・安倍政権下で、道路公団民営化、郵政民営化、政策金融改革、特別会計改革など、各省の既得権とぶつかる数多くの改革に携わってきた。そこでは幾度となく、官僚たちが自己の保身や出身組織の防衛に走る姿を見てしまった。
天下りに固執するのは、公務員個々人の資質によるものではない。組織そのものに内在する問題と言わざるをえない。
* * *
わが国の官僚制の起源は、明治初期にさかのぼる。
1893(明治26)年、文官任用令、文官試験規則が改正され、官吏は原則として公開試験によって任用されることとなった。1899(明治32)年、山縣有朋は公開試験制度を活用し、内務省などの省庁の高級官僚から憲政党などの政党員を締め出し、自分の配下となる官僚群を作った。
それが、難関な文官高等試験(高文試験)の合格者のみが特権的な任用を受ける「キャリア制」に連なっていったという見解もある。まさしくマックス・ウェーバーの言う通り、「権力の闘争とは官吏任命権の争い」なのだ。
ただ、天下りの起源はそれほど古くはない。
昭和初期から漸増し、組織的な天下りはいわゆる1940年体制下で確立された。戦時統制経済期に、経済統制機関や金融統制機関に官僚が送り込まれたのだ。当初は天下りというよりも、国策を徹底するための、官界からの人材派遣という側面が強かった。
こうして始まった天下りは、戦後の高度成長期にはある程度は社会に許容されたかもしれない。しかし、今ではきわめて厳しい批判にさらされている。
ちなみに、天下り先の政府法人を売却すれば、国債の大半はなきものになる。しかし、官僚はこの天下り先に世間の関心が向かうことを好まない。
このため、天下り先への資金供与である出資金、貸付金は政府の巨額な資産の一部であるにもかかわらず、財政問題ではもっぱらバランスシートの右側の負債(国債のストック残高)のみが強調され、左側の資産は無視される。
これは、天下り先への資金供与に国民の目が向かないようにとの配慮である。
「天下り規制」にブチ切れた官僚たち
さて、天下りは日本だけに特有なことではないというものの、先進国の中ではあまり類例がない。
官僚天国といわれるフランスでは「Pantoufle」といわれており、友人のフランス人に聞いたら、スリッパ、室内履きという意味に加え、「居心地がいい」という意味もあるそうだ。ただし、日本ほど広範に天下りは行われていないという。
そのような慣行のないアメリカでは対応する言葉がなく、日本語を直訳して「Descent from Heaven(天下り)」といい、最近では「amakudari」と言っても、日本にある程度詳しい学者の間では通用する。
官僚では年功序列を原則とするから、上級ポストが少なくなって肩たたきされた退職者にも天下りで高給を保証する構造になりがちだ。それをただすには、予算・許認可権限をもつ各省人事当局による斡旋を禁止するのがもっとも効果的である。
役人を長くつとめていれば、このシステムこそが各人に各省への忠誠心を誓わせる原動力になっていることは、誰でも知っていることだ。国民のための政策といいながら、結局、天下り先確保のために組織作りに汲々としている役所幹部の見苦しい姿を、筆者は何度も見てきた。
第一安倍政権において、筆者らが企画した天下り斡旋等の禁止は、官僚側から猛烈な抵抗を受けた。
当時の官僚トップとして官邸にいた的場順三内閣官房副長官(財務省OB)は、内閣府職員から天下り斡旋の禁止を盛り込んだ経済財政諮問会議の民間議員ペーパーの事前説明を受けると、机を叩いて激怒した。
そして、「欧米とは事情が違う。欧米には、再就職斡旋の慣行がないなんて言うな」といい、「欧米には再就職斡旋の慣行がない」というペーパーの注記を削除した。その注記は正しいにもかかわらず、削除されたのだ。
さらに、総理秘書官(財務省出身者)が民間議員ペーパーの事前説明を内閣府職員から受けていたが、それらの内閣府職員に対して「お前ら全員クビだ」と怒鳴ったという。
それほど、天下り斡旋等の禁止は組織の根幹を揺るがすものだったのである。
実際、各省の意思決定をしている幹部官僚ほど、天下りの確保は自分の人生の問題として切実だ。官僚が出身省庁に忠誠を尽くすのは、仮に出世競争に敗れても天下りによる給与が保証されているからであった。
役所の人事サイドから見れば、退職者に対し「退職依頼+天下り斡旋」のセット、退職者から見れば「依頼承諾+斡旋依頼」となって両者は満足だ。しかし、国民から見れば最悪なのである。
官僚の猛烈な抵抗にもかかわらず、10年前の安倍総理はぶれずに、「国家公務員法等の一部を改正する法律」を国会で通した。
ただ、その成立にあまりに多くのポリティカル・キャピタルを投入せざるを得なくなり、結果として第一次安倍政権は短命に終わった。それゆえといべきか、退任時の安倍総理は、記憶に残る仕事として公務員改革を掲げていた。
その間の様子をよく見ていたのが、現在の菅義偉官房長官である。そして、天下り斡旋等の禁止の威力を誰よりも理解していた。
選挙に備えてのにらみ?
実は、「国家公務員法等の一部を改正する法律」に基づき2008年12月に再就職監視委員会が設置されたが、当時の民主党などの反対で国会同意人事が行えず、発足後も委員長・委員不在で開店休業状態だった。
こうした事情を知っている筆者から見れば、民主党は公務員擁護の党であり、公務員改革に熱心でなかった。今、蓮舫代表が、天下り問題で安倍首相を責めるというが、民主党お家芸のブーメランにならなければいいが、と懸念してしまう。
結局、民主党政権末期の2012年3月にようやく再就職監視委員会の委員長・委員の国会同意人事が得られた。
第二次安倍政権は、一次政権時の国家公務員改革の成果をうまく使っている。2013年3月の国土交通省職員による再就職斡旋、2016年3月の消費者庁元職員による求職が、国家公務員法違反と認定されるなど、監視委員会はやっと本格的な活動を始めた。
第二次安倍政権では内閣人事局も発足させ、各省のトップ人事を菅官房長官がしっかりと掌握している。ここが、第二次安倍政権の絶対的な強みである。
今回、再就職監視委員会は、国交省、消費者庁に次いで文科省にメスを入れたのだが、今回の文科省はあまりに不用意だった。
ただし、他省庁でも、程度の差こそあれ、似たようなことはやっている。なにしろ、国家公務員法で違反としているのは、再就職のための情報提供、再就職依頼の禁止などである(国家公務員法第106条の2など)。これらは、事実行為であり、いわゆる天下りにはつきものなのは、国家公務員であれば誰でも知っているはずだ。
今回の文科省の一件で、他の霞が関官僚は震え上がったに違いない。なにしろ事務次官のクビがあっという間に飛んだわけだから、官僚としては大騒ぎだ。
10年前にあっさり倒れた安倍政権ではなく、今や空前の長期政権にもならんとしている安倍政権である。それも、知謀の菅官房長官が、内閣全体ににらみを利かしている。
10年前の第一次安倍政権崩壊時に祝杯を挙げたという霞が関官僚は、これから頭を高くして眠れないのではないか。もっとも、伝家の宝刀は抜かずに、その威光だけで官僚たちをひれ伏させることもできるので、宝刀の無駄振りはしないだろう。
こうなってくると、第一次安倍政権では横行したような、官僚発の「倒閣運動」はやりにくくなる。今年は総選挙の年になると言われているので、安倍政権は選挙がやりやすいように、しっかりと内部から固めているのだろう。
最後に、マスコミにその気があるなら、天下り問題について比較的簡単に調査報道ができることを示しておこう。「国家公務員法等の一部を改正する法律」では、天下りの斡旋禁止だけではなく、再就職状況を公表するようになった。
今回の早稲田大学の件でも、内閣官房のHPで毎年の再就職状況が個人名と再就職先を含めて公開されている(http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/kouhyou_h280920_siryou.pdf)。
ここはネタの宝庫であるので、マスコミはこれを活用して、是非とも天下り問題をしっかり解明して欲しい。
髙橋 洋一
今後は「おごり」と言う新たないじめが流行るかもしれない。
「教育委員会としては、法律に基づく専門委員会からの答申は尊重すべきであると考えており、専門委員会の結論をみても金品の授受のところにつきましては、それだけで『いじめ』と認定するということは、なかなか判断できないという趣旨でお答えしました。」
法律の点から判断したと言う事なので、法律のお墨付きだ。こらからはお金をくれじゃなくて「おごってくれ」と言っていれば良いと言う事だ。
ライブに行く途中、高齢ドライバーに奪われた女子高生の命 友人たちは立ち上がった (1/3)
(2/3)
(3/3) 01/23/17 (BuzzFeed Japan)
福島第一原発事故で横浜市に自主避難をした児童が「賠償金あるだろ」と言われ、ゲームセンターなどで150万円支払わされた。子どもを守るべき教育長が、これを「いじめと認定できない」と発言したことへの怒りが広がっている。【BuzzFeed Japan / 籏智広太】
批判を受けているのは、横浜市教育委員会の岡田優子教育長が1月20日、市議会常任委員会でした「関わったとされる子どもたちが『おごってもらった』と言っていることなどから、いじめという結論を導くのは疑問がある」という発言だ。
「おごってもらった」と言えば、小学生に150万円を払わせてもいじめにはならないのか。納得はできない。
BuzzFeed Newsは1月23日、横浜市で教育長に直接取材した。
なぜ、150万円払わされることがいじめではないのか。岡田教育長は、この件について調べた第三者委の判断を理由にあげた。
「(第三者委はおごりの)背景にいじめがあったことが推察できるという言い方をしています。第三者委員会の結論は第三者委員会の結論ですから、それを覆すことなんてできないじゃないですか」
つまり、背景にいじめがあったと推察できても、認定はできないということなのか。それでは、市教委としてどうすれば認定できるのか。
「市教委として認定できるのかは、再発防止委員会の中でしっかり議論して考えていく。ただ、あれだけ厳しい第三者委員会が出した結論を、そんなに簡単に覆すことは難しいですよ、という話を(市議会で)した」
第三者委の判断とは。経緯を振り返る。
BuzzFeed Newsが弁護側に提供を受けた横浜市の第三者委員会の報告書によると、男子生徒は震災の5ヶ月後、2011年8月に福島県から2年生で転校してきた。
直後から名前に「菌」をつけられるなどのいやがらせを受け、不登校に。小学5年生になった2014年には、「プロレスごっこ」と称して数人の児童から叩かれるようになった。
また、横浜駅やみなとみらい周辺のゲームセンターでの遊興費、食事代、交通費などをすべて、負担させられた。男子生徒の説明に基づくその回数は、計10回ほど。1回につき5万~10万円で、自宅にあるお親の金を持ち出していた。
これが、問題になっている「150万円のおごり」だ。担当弁護士によると、生徒側はこの金額が総額150万円にのぼるとしているが、学校側は8万円しか確認できていない、としているという。
男子生徒はその後、2度目の不登校に。2015年12月には生徒の両親が市教委に調査を申し入れ、2016年1月、第三者委員会が市の諮問を受けて、調査を開始。11月にその結果が報告書にまとまった。
一方、報告を受けた横浜市教育委は12月、検討委員会を設置。当時の対応の検証を始め、神奈川新聞によると、2017年3月にも結論をまとめる方針だという。
そして、1月20日、横浜市議会の常任委員会。
岡田教育長が、その進捗を報告する際に飛び出したのが、「関わったとされる子どもたちが『おごってもらった』と言っていることなどから、いじめという結論を導くのは疑問がある」という先述の発言だった。
おごりは、いじめではないのか。
なぜ、岡田教育長はこうした発言をしたのか。第三者委員会の報告書には、金銭の授受について「認定しうる事実」として、こう記載されている。
“A(男子生徒)は、「だれが出す?」「賠償金もらっているだろ?」とか「次のお金もよろしくな」などと言われ、今までにされてきたことも考え、威圧感を感じて、家からお金を持ち出してしまったという“
“関係児童の遊興費等を負担(いわゆる「おごり」)することで、それ以降はプロレスごっこ等のいやなことは一切されなくなり、更にAは他の児童に対し、友好感が生じることができたので、同様のことが多数繰り返されてしまったと思われる“
報告書はその上で、おごりが「『いじめ』から逃れようとする当該児童の精一杯の防衛機制(対応機制)であったということも推察できる」と分析。こう結論付けた。
“おごりおごられ行為そのものについては『いじめ』と認定することはできないが、当該児童の行動(おごり)の要因に『いじめ』が存在したことは認められる“
BuzzFeed Newsの取材に対する岡田教育長の答えから、問題の発言は、この点を念頭に置いたものだとも捉えられる。ただ、男子生徒側がそれを良しとしているわけではない。
発言の10日前、2017年1月10日。生徒側は「金銭要求行為がいじめとして認定されなかったこと」への横浜市長宛の所見を市教委に提出。報告書に対し、「悪しき前例とならないよう、いじめと認めて頂きたい」と求めていた。
その際、生徒自身も、こんな文書をしたためている。
「またいじめが始まると思って、何もできずにただ怖くて仕方なくて、いじめが起こらないようにお金を出した。お金を取られたことをいじめと認めて欲しい」
抗議で市教委の電話はパンクした。
そうした状況における岡田教育長の発言は、大きな波紋を呼んでいる。
「おごりと言えばいじめじゃないのか」「市教委は子どもを守れるのか」などとの批判が相次ぎ、署名サイト「Change.org」で、抗議の署名活動も始まった。
市教委の担当部署には抗議が殺到したのか、この日は電話が一日中つながらない状態が続いた。また、午前に開かれた市教委臨時会に合わせ、建物の外で「じゃあいじめって何ですか?」と掲げた看板を持つ人の姿もみられた。
臨時会には定員の20人を超えた傍聴人が集まり抽選となった(記者クラブに加盟していないBuzzFeed Newsも参加)が、公開部分の会議では問題に触れる発言はなく、参加者から「市民の怒りがわかってないのでは」などという声もあがっていた。
生徒側は「即時撤回を」と抗議した。
1月23日には、生徒側の弁護士が市教委に「被害児童を無用に苦しめる発言については、即時撤回されたい」などと申し入れをした。弁護士は報道陣に、両親や男子生徒が「大きく衝撃を受け、動揺して悲しんでいる」と説明した。
文書では、岡田教育長の発言について「金銭授受について、あたかもいじめとは無関係であるかのような内容となっている」と指摘。
第三者委員会の報告にある「いじめの要因があったという内容には全く言及されていない」としつつ、その内容を「大幅に後退させるものである」と批判した。
また、「関わったとされる児童」の「おごってもらった」という発言に依拠している点についても、「いじめられた児童生徒の立場に立つことを必要」としたいじめ防止対策推進法の趣旨に反しているとして、発言の即時撤回を求めた。
申し入れ後、市教委側の担当者が報道陣に「教育長の発言は言葉足らずだった。当時はいじめと認定できたかというと難しいという趣旨だった」との見解を発表。BuzzFeed Newsも会見に同席した。
この見解は奇妙だ。常任委員会でのやり取りは、当時のことを話す内容ではなかったからだ。当然、受け取った記者クラブ側からは「後付けの内容だ」「本当にこの見解で良いのか」と批判の声が上がった。
市教委側は批判の声に対し、持ち帰って検討すると、改めて見解を出し直す可能性を示唆した。だが、本当に出しなおすかどうかを含めて決まっていない。このことからも、猛烈な批判を受けた教育委員会の迷走が見て取れる。
BuzzFeed Newsは新たなコメントを入手次第、追記します。
更新 2017/01/23 21:53
市教委事務局は1月23日夜、「改めて確認」したうえで、岡田教育長のコメントを発表した。
発言は、第三者委の報告書を尊重し、「金品の授受がいじめだと認定することはなかなか判断できないという趣旨」であり、「丁寧にお伝えできず申し訳ありません」としている。
全文は以下の通り。
常任委員会において、金品のやりとりについて、専門委員会が「いじめ」と認定することが難しいと言っていても、教育委員会として総体として「いじめ」があったと認めることは可能ではないかといった趣旨の質問をいくつかいただきました。
これらの質問に対して、教育委員会としては、法律に基づく専門委員会からの答申は尊重すべきであると考えており、専門委員会の結論をみても金品の授受のところにつきましては、それだけで「いじめ」と認定するということは、なかなか判断できないという趣旨でお答えしました。
専門委員会の調査報告書でも、「おごり・おごられ行為そのものについては、『いじめ』と認定することができないが、当該児童のおごりの要因に『いじめ』が存在していたことは認められる」と記載されていることは受け止めています。
丁寧に趣旨をお伝えできず、申し訳ありませんでしたが、現在、再発防止検討委員会で課題や防止策について議論を重ねておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
文部科学省がこのような組織だから、学校や教育委員会が報告書や調査のデータについて虚偽報告をする。上がやっているのだから部下や下部の組織が
真似て当然。自分達が狡い事をやっているのだから、まじめな人ほどやる気をなくす。
道徳教育など必要はないと言う事。道徳教育を提供する組織がこのありさま。道徳教育は裏表の表の部分。結局、裏が存在するのだから
成績で評価する必要はない。上手く偽善者になるための練習が既に上手い生徒や本当の世の中を知らないまじめな世間知らずの生徒が好成績を取るだけ。
道徳教育なんて必要ない事を文科省が現実社会で証明している。国民を欺き、補助金と言う税金をチラつかせ、自分達だけが良い思いをする。
虚偽報告で隠蔽工作までおこなっている。道徳教育と平気で言っていること自体、道徳教育が形だけの必要ないものと言う事だ。
天下りあっせん10件認定=組織ぐるみ、国家公務員法違反―監視委 01/20/17(時事通信)
政府の再就職等監視委員会は20日、文部科学省が組織的に幹部の天下りをあっせんしていたと認定する調査報告を公表した。
元高等教育局長が在職中に人事課経由で早稲田大に経歴を伝えて求職行動した行為など10件について、国家公務員法に違反したとしている。他にも違反が疑われる行為が28件あった。
調査報告によると、こうした違反を隠すため人事課職員が虚偽報告を行っていた。前川喜平事務次官も、文科審議官当時の2015年にOBの再就職をめぐる情報提供で同法に違反していた。
この問題で政府は同日の閣議で、前川喜平文科事務次官を交代させ、後任に戸谷一夫文科審議官を充てる人事を決めた。
<文科次官辞意>天下りあっせん「他省庁でも」01/19/17(時事通信)
「国民の批判は強い」「やむを得ない」。文部科学省の「天下り」あっせん問題で同省事務方トップの前川喜平事務次官(62)が辞任の意向を固め、省内に衝撃が広がった。「他の省庁ではもっと大規模な天下りあっせんがあるのは霞が関では公然の秘密。文科省だけで収束するとは思えない」。他省庁への波及の可能性を指摘する声も出た。
関係者によると、文科省では以前から、人事課の幹部職員らが中心になって、個室が与えられる各局の幹部職員らの天下りをあっせんしてきたという。ある職員は「実際にあっせんに関わるのはごく一部だが、前から続いている」と明かした。
2007年の改正国家公務員法成立で天下りの規制が強化されたこと自体は多くの職員が認識しているが、再就職については定年退職が近くならなければ意識することは少ないため、細かな規制の内容について知る職員は多くはないという。
一方、この職員は「他省庁ではもっと大規模に天下りが行われ、人事課の課長級以下の職員までかかわっている役所もあると聞く。再就職等監視委員会に情報提供があって調査が始まったと考えられるが、『なぜ文科省だけが責められるのか』と多くの職員が感じているのではないか」と省内の“本音”を代弁した。
また、ある幹部職員は「首相官邸としては次官の辞任で幕引きを図りたいのだろうが、他省庁でも天下りがあるのは霞が関の常識で、他の役所にも問題が発展する可能性がある。その場合にも次官を辞めさせるのかどうか。あしき先例になる恐れがある」と話した。【佐々木洋】
◇最近の主な省庁トップの辞任・退任(※組織名、肩書は当時)
2011年8月 原発シンポジウムの「やらせ問題」の責任を取り、経済産業省の松永和夫事務次官ら関連省庁トップ3人が辞任
10年12月 元特捜検事の証拠改ざん事件後、大林宏検事総長が辞任
09年9月 公務員制度改革を巡り政府・自民党と対立した谷公士人事院総裁が辞任
07年8月 小池百合子防衛相と対立した守屋武昌事務次官が退任
02年1月 牛海綿状脳症(BSE)問題を受け、農林水産省の熊沢英昭事務次官が辞任
02年1月 小泉純一郎首相が国際会議でのNGO排除問題を巡り、外務省の野上義二事務次官を更迭
1999年11月 茨城県東海村の臨界事故とH2ロケット打ち上げ失敗を受け、科学技術庁の岡崎俊雄事務次官が辞任
98年11月 防衛庁調達実施本部の背任事件を巡る証拠隠滅疑惑を受け、秋山昌広事務次官が辞任
98年1月 大蔵検査官の接待汚職事件を受け、大蔵省の小村武事務次官が辞任
96年11月 社会福祉法人からの利益供与問題で厚生省の岡光序治事務次官が辞任
文科事務次官の辞任で幕引きでは困る。組織的に天下りに関与した職員の全てに重い処分を下すべきだ。豊洲問題では大噓付きの東京都職員達が誰が責任者なのか、
誰が指示を出したのかわからないとか逃げ回った。
家文科副大臣は小池東京都知事のようにふざけた報告書を受け取らず、徹底的に調べて処分してほしい。
文科次官、辞任へ=天下りあっせん問題で引責 01/19/17(時事通信)
文部科学省が幹部の再就職を組織的にあっせんしていた疑いがあるとして、政府の再就職等監視委員会が調査している問題で、同省の事務方トップである前川喜平事務次官(62)が引責辞任の意向を固めたことが19日、分かった。
「処分含め検討」=義家文科副大臣
監視委の調査結果を受け、文科省が正式発表する見通し。
松野博一文科相は同日午前、首相官邸で記者団に「大変遺憾。監視委からの指摘を踏まえ、厳正に対応を進めたい」と述べ、再発防止に向けた検討チームを設ける考えを示した。義家弘介文科副大臣も「しっかりと検証し、国民の信頼に応える体制をつくっていく」と語った。
義家氏は同日午前に開かれた副大臣会議で問題の経緯を説明し、「ご迷惑をお掛けしている」と陳謝した。
<天下りあっせん疑惑>文科事務次官、引責辞任へ 01/19/17(毎日新聞)
文部科学省が幹部の再就職を組織的にあっせんした疑いが浮上した問題で、文科省の前川喜平事務次官(62)が責任を取って辞任する意向を固めたことが関係者への取材で分かった。問題を調査している政府の再就職等監視委員会は19日中にも調査結果をまとめ、関与した文科省の幹部職員らの処分を求める方針。官僚の天下りを巡る一連の問題は、事務方トップの事務次官辞任に発展する見通しになった。
関係者によると、文科省の元高等教育局長(61)が2015年に退職した2カ月後に早稲田大に教授として再就職した際、省内のあっせんを受けていた疑いがある。官僚の「天下り」のあっせんを禁じた国家公務員法に違反する可能性があるとして監視委が昨年から調査している。
これまでの調べで、元局長のあっせんには人事課を中心に複数の幹部らが関与し、元局長の経歴などに関する情報を大学側に提供するなど、組織的に天下りをあっせんした疑いがあることが分かっている。元局長はあっせんを受けただけでなく、文科省在職中に自ら大学側と接触し、再就職に関する相談などをした疑いも持たれている。また、過去にも同様のあっせん行為が少なくとも数十件行われた可能性があるとみて、監視委が詰めの調査を進めている。
関係者によると、前川次官は一連の問題について事務方トップとして責任を取る必要があると判断し、辞任する意向を固めた。前川氏は初等中等教育局長、文部科学審議官を経て16年6月に事務次官に就任していた。
松野博一文科相は監視委の調査結果を踏まえ、近く前川次官や当時の人事課長など計7人の幹部と職員を懲戒処分とする見通し。【佐々木洋】
「保護者が問題視して学校に連絡。学校が担任に事情を聴くと、担任は当初、『相談を受けているわけだし、私は絶対にそういうことは言わない』と否定した。だが11月29日、別の教諭らがクラス全員に聞き取り調査をした結果、複数の児童が『自分もそう呼んでいた』『担任の先生もそう呼んだ』などと答えた。
この40代男性教諭は教師として失格だと思うし、学校にも「相談を受けているわけだし、私は絶対にそういうことは言わない」と否定する事は公務員そして
人間として失格だと思う。
このような人間は自己中心的で、自分のためなら平気で嘘を付くであろう。嘘を平気で付く人間達にたくさん会っているので嘘が人生、又は、生活の
一部となっていると思う。簡単には治らないと思う。困った状況に陥ると簡単に嘘を付くのである。
40代となると人格形成が終了しているので短期の研修を受けても直せないと思う。単に「菌」をつけて生徒を呼んだが反省しているのならまだましであるが、
聞き取りで嘘を言った事実は重大だと思う。もし、生徒達を恐喝、又は恫喝していたら、恐ろしくて事実を生徒達は言わないかもしれない。「分限免職」に
するべきだと思う。生徒達もばかではない。ニュースを見たり、又は、成長すれば、公務員になれば学校に嘘まで付いたけれど、軽い処分で済むと考えるかもしれない。
教諭の自業自得なので、「分限免職」にするべきだ。調子に乗っている似たように教師達に対しても戒めにもなるであろう。
原発避難の小4に担任が「菌」発言 いじめ相談の5日後 12/02/16(朝日新聞)
新潟市の小学4年の男子児童が、担任の40代男性教諭から名前に「菌」をつけて呼ばれ、1週間以上学校を休んでいることが、保護者や学校への取材でわかった。児童は5年前、東京電力福島第一原発事故で福島県から家族と避難していた。同級生からもそう呼ばれ、この担任に相談していたという。
保護者によると、児童は11月22日、担任から昼休みに教室で連絡帳を渡された際、ほかの児童がいる前で、自分の名前に「菌」をつけて呼ばれた。この日は早朝、福島県で最大震度5弱の地震が発生。児童は福島県で働く父親と連絡が取れないまま登校した不安感も重なり、強くショックを受けた様子だったという。祝日をはさみ、24日から学校を休むようになった。
児童は2011年の東日本大震災後、家族と新潟市に自主避難した。保護者によると、理由は定かではないが、小学3年のころから仲間はずれにされたり、一部の同級生から名前に「菌」をつけて呼ばれたりするようになったという。4年に進級すると、同級生に文房具を捨てられたり、傘を壊されたりもしたというが、児童は保護者に「守ってくれる友達もいる。大丈夫だよ」と話していた。
ところが、11月に横浜市に自主避難した中学生が名前に「菌」をつけて呼ばれて不登校になった問題が報道されると、落ち込んだ様子になったという。保護者らは「自分も深刻ないじめを受けていると自覚したためでは」とみている。
心配した保護者の勧めで、児童は11月17日、担任に「自分も名前に『菌』をつけて呼ばれている」と相談した。にもかかわらず、5日後、担任がその呼び方で児童を呼んだとされる。
保護者が問題視して学校に連絡。学校が担任に事情を聴くと、担任は当初、「相談を受けているわけだし、私は絶対にそういうことは言わない」と否定した。だが11月29日、別の教諭らがクラス全員に聞き取り調査をした結果、複数の児童が「自分もそう呼んでいた」「担任の先生もそう呼んだ」などと答えた。
校長によると「担任は『認識不足だった。何とかして謝罪したい』と話している」といい、学校側は発言に問題があったと認めている。新潟市教育委員会も問題を把握。詳しい経緯や状況について調査している。市教委教職員課の吉田隆課長は「福島は帰りたくても帰れない状況で、お子さん、ご家族につらい思いをさせているのは残念。適切な対応をしていきたい」と話している。(永田篤史、狩野浩平)
■今回の問題の経緯(保護者への取材から)
2011年3月11日 東日本大震災、その後、新潟市に自主避難
15年(小学3年) 仲間はずれや、「菌」との呼び方はじまる
16年(小学4年) 嫌がらせが続く
11月上旬 自主避難した横浜市の中学生のいじめ発覚。「菌」と呼ばれていたことがニュースに
17日 児童が担任に相談
22日 早朝、福島県で最大震度5弱の地震
昼休み、担任に名前に「菌」をつけて呼ばれる
放課後、保護者が学校に連絡
24日 学校に行かなくなる
29日 学校の調査で担任の発言確認
校長を含め、学校側がまぬけなのか、言い訳として「少しでも早く申請した方がいいと思った」と答えたのか?自殺だとお金が貰えず、「通学中の事故」だと保険が下りるのか。
これって申請した時点で学校側による詐欺?
保護者に説明なり、どのような対応を望むのか、確認するべきだったと思う。まあ、いじめにしろ、事故にしろ、子供を失くした親に連絡するのは気が進まないであろう。
文科省は学校が適切な対応を取れないのであれば、ガイドラインなり、マニュアルなり、対策を取るべきであろう。
いじめ訴え自殺 学校側、遺族に説明なく「通学途中の事故」と申請 11/04/16(フジテレビ系(FNN))
2016年8月に、いじめを訴えて自殺した、青森県の中学2年生・葛西りまさんについて、学校側が、遺族に説明なく、通学途中の事故として、給付金を申請していたことがわかった。
葛西りまさんの父・剛さんは「謝罪を求めているわけではなく、何があったのかを求めている」と話した。
文部科学省で会見した父親らによると、学校側は、遺族に十分な説明をしないまま、りまさんの自殺を「通学中の事故」として、日本スポーツ振興センターに、災害共済給付金を申請していた。
この制度では、学校の管理下で、子どもがけがをするなどした場合、保護者が医療費や見舞金を受け取れる。
申請は、事故後2年間有効だが、学校側は、FNNの取材に、「少しでも早く申請した方がいいと思った」としているが、遺族側は不快感を示している。
これで終わりなのか?
ダブル不倫の日教組委員長、直撃取材に愛人を切り捨て “もうお前は関わるな” (1/2)
(3/3) 10/27/16(デイリー新潮)
日本教職員組合(日教組)委員長、岡本泰良(やすなが)氏(56)に発覚したダブル不倫。10月3日から4日にかけ、池袋のラブホテルで3時間以上を過ごしたお相手は、夫と2人の子のいる、ホステス兼歌手の小谷彩花さん(44)=仮名=だった。
さらに10月7日には、彼女と日教組副委員長と共に居酒屋を訪れた後、彩花さんの働くガールズバーへと“同伴”。その後、2人でタクシーチケットを使い、帰路についたのである。
■「見てるだけじゃないか」
岡本氏に、ラブホテルでの彩花サンとの逢瀬について直撃すると、
「うん、知らない、知らない、俺、知らないよ」
彩花サンについても、
「知らないっすよ」
2人がホテルに入る写真を見せると、
「(ホテルの外観を)見てるだけじゃないか。知らないよ、そんなの。もう、やめてください」
では、今日の飲み会は。
「教育総研です。あなたに言う必要ない」
“聖職”の親玉にしては、また連合副会長を兼ねる労働界の大物としても、あまりにゲスな逃げ口上である。教師が、子供が、こんな御仁の鏡になるなら世も末だが、実家で留守を預かる小学校教員の妻も、
「私も公務員ですから、プライベートなことにお答えすることはできません」
と意味不明の回答だ。
■彩花さんは…
一方、彩花さんは当初、
「ホルモン専門店は行ったけど、ラブホテルに入る女性は私じゃない」
の一点張りだったが、その翌日、前言を撤回して、
「あれは私です、ホテルには入りました」
と話を始めた。
「主人も年下ですし、頼れる男性が欲しくて。岡本さんも“一緒にいるとリラックスできる”と言っていたと思います。付き合い自体は3、4年で、ラブホテルはここ2年くらい。月に1回、行くか行かないかです。でも信じないでしょうけど、肉体関係はなくて、並んで腰かけて他愛のない話をするだけなんです」
なのに、どうしてラブホテルなのか。
「2人きりになりたいから。岡本さんはすごく神経がすり減っていらっしゃるから、音が聞こえると休まらないみたいなんです」
ためしに2人が入ったと思しき403号室に入ると、埋め込み型のキングベッドとサイドテーブルが鎮座し、案外狭い。ベッド脇にはコンドームとバイブレーター。青や赤の仄(ほの)かな照明といい、やたらめったら淫靡である。学校関係者の岡本氏にふさわしく? セーラー服のコスプレのレンタルもある。
■「もうお前は関わるな」
それはともかく、岡本氏の“ご乱行”を日教組の広報担当にぶつけた直後、彩花サンから訂正の連絡が。
「本当は私が岡本さんに一方的に気持ちを寄せていて、池袋のホテルに行ったことがないから行きたいとお誘いしました。私が無理やり連れ込んだんです」
しかも、行ったのはそれ1回きりだと、奇妙なまでに岡本氏をかばいながら話すのである。しかし、こうも前言を撤回されてばかりでは埒が明かないので、彼女の母親に尋ねると、
「彩花は学生時代から彼氏も二転、三転して、ラブホにも行き慣れていると思う。お芝居したいから就職しないで赤坂でずっと働いてね。娘がウソをついた? 赤坂で大物のお客と丁々発止してきたのだから、この子は保身のためにそのくらい言うでしょう」
で、もう一度、彩花さんに聞いてみた。
「記者さんに話したことを岡本さんに電話で伝えると、“すべて情報を与えて、記事の裏づけをとられる形になってしまった”と絶句され、それから電話にも出てもらえなくて、やっと出ても“もうお前は関わるな”と言われて。一度は岡本さんを守ろうとウソをついたんですが、守ってくれないんだったら、ウソをつく必要もないなと思って」
実際、直撃にすっ惚けたあと、本誌(「週刊新潮」)の再三の取材に一切答えない岡本氏が、ゲスでクズであることはよく伝わる。丹野久広報部長も、
「質問に対して回答する必要はないと判断しました」
と、日教組のモラルが反映した回答をくださった。
■「望んだのは私」
それでも彩花さんは、岡本氏に遠慮して話すのだ。
「ホテルに行くのを望んだのは私で、8月の私の誕生日の2日後、お願いして初めて連れてってもらったんです。でも、期待して“よしっ!”と思ったけど、全然そんな(男女の)関係にならなくて。あとは9月と10月に1回ずつ行きましたけど、同じでした」
しかし、彼女の母親は、
「この子はおじさんは好きじゃない。年上と付き合ったことないんだから。この人の地位を利用してるだけだと思うけど」
彩花さんの発言が三転したワケは想像するしかないが、元神奈川県教組委員長で参議院議員も務めた小林正氏が言う。
「清く正しく美しく、と思われている日教組は、社会的信用が最も求められる労組。そのトップが組合費を愛人との飲み代に使っているのを、許せる組合員がどこにいるでしょうか」
ごもっとも。さらに言うなら、保身のために“愛人”も切り捨てる男に、子供を守れるはずもない。
特集「『銀座・赤坂』で豪遊を続ける日本一の『労働貴族』 色と欲『日教組委員長』のお好きな『池袋ラブホテル』」より
「週刊新潮」2016年10月20日号 掲載
感情的になってボールを投げたら顔に当たったと言うのはあるかもしれないけど、女子生徒の胸を触る行為に関して言い訳は出来ないだろう。
<懲戒免職>中学教諭、女子バレー部生徒に体罰や暴言 横浜 10/20/16(毎日新聞)
横浜市教育委員会は20日、顧問を務める女子バレーボール部の延べ26人の生徒に体罰や暴言、セクハラを行ったとして市立中学の田井哲彦教諭(49)を懲戒免職処分とした。田井教諭は2012年度にも別の中学で同様の行為により口頭注意を受けていた。
市教委によると、田井教諭は14年8月~16年2月、生徒11人に後頭部をつかんで引き倒したり、ボールを顔にぶつけたりする体罰を行った。また6人に胸を触るなどのセクハラ行為をしたほか、9人に対して「部活をやめろ」などの暴言があったとしている。
昨年11月に保護者から匿名の相談メールがあり、発覚した。市教委の調査にも生徒への謝罪はなかったという。【水戸健一】
27才だったらまだやり直せる可能性は高いが、本人次第。もう教師として働くのはかなり難しいと思う。
「熱心な教師」だから、性欲が強くてもコントロールできる人物とは限らない。校長は人を見る能力を持つ必要がある時代になったかもしれない。
胸触った女子生徒 “9人“に 逮捕の中学教師 懲戒免職 10/18/16(北海道文化放送)
女子生徒の胸などを触ったとして、札幌市の中学校教師が逮捕された事件を受けて、市教育委員会は教師の男を懲戒免職にすることを決めました。
懲戒免職が決まったのは、10月13日に女子生徒の胸などを触ったとして、準強制わいせつの疑いで逮捕された札幌の中学校に勤務する男(27)です。
札幌市教委によりますと、教師の男は2015年8月から2016年9月にかけて、4度の部活動の合宿で女子生徒が寝ている部屋に入り、8人の生徒の胸などを触ったほか、2016年6月の宿泊学習でも1人の胸などを触ったということです。
警察の調べに男は「体に触れたのは間違いないが、手を入れて胸に触れてはいない」と容疑を一部否認しています。
札幌市教委は、教師の男の管理監督が不十分だったとして、勤務先の50代の校長についても戒告処分としました。
UHB 北海道文化放送
生徒に慕われ人気者…わいせつ容疑の教師に何が?校長「熱心な教師」 札幌市 10/18/16(北海道文化放送)
生徒の模範となるべき教師に一体、何があったのでしょうか。札幌市の中学校に勤務する27歳の教師の男が、女子生徒の胸などを触ったとして、警察は男を準強制わいせつの疑いで逮捕しました。
「私の指導の前提は人として恥ずかしくない行動かどうか」「人を傷つける言動は許さない」
新人教師に向けた文章の中で、自らの信念を語っていた男…。しかし、このわずか2年後…、男は自らの言葉を裏切る形で逮捕されました。
記者リポート「いま身柄が警察署に入ってきました。車の外から姿を見ることはできません」
準強制わいせつの疑いで、逮捕されたのは、札幌の中学校に勤務する27歳の教師の男です。
男は先月17日深夜から18日朝にかけて、部活動の合宿中に女子生徒の部屋に入り、服の中に手を入れて胸などを触った疑いがもたれています。
警察の調べに、男は「体に触れたのは間違いないが手を入れて胸に触れたことはしていない」と容疑を一部否認しています。
生徒に親しまれ、人気があったという男…。勤務先の校長は…
校長:「本当に熱心に取り組む教師。生徒と接するところはオールマイティーに熱心に取り組んだ」
一方で、今月10日までに複数の女子生徒と保護者が警察に被害届を提出…そして3日後のきょう、逮捕されました。
現役教師が逮捕される事態に市の教育委員会は…。
札幌市教委職員:「私どもの責任を痛感しているのはまさに、その通り。被害に遭った生徒、保護者にあらためて、おわび申し上げたい」
警察は、余罪があるとみて捜査することにしています。
UHB 北海道文化放送
胸触った女子生徒 “9人“に 逮捕の中学教師 懲戒免職 10/18/16(北海道文化放送)
女子生徒の胸などを触ったとして、札幌市の中学校教師が逮捕された事件を受けて、市教育委員会は教師の男を懲戒免職にすることを決めました。
懲戒免職が決まったのは、10月13日に女子生徒の胸などを触ったとして、準強制わいせつの疑いで逮捕された札幌の中学校に勤務する男(27)です。
札幌市教委によりますと、教師の男は2015年8月から2016年9月にかけて、4度の部活動の合宿で女子生徒が寝ている部屋に入り、8人の生徒の胸などを触ったほか、2016年6月の宿泊学習でも1人の胸などを触ったということです。
警察の調べに男は「体に触れたのは間違いないが、手を入れて胸に触れてはいない」と容疑を一部否認しています。
札幌市教委は、教師の男の管理監督が不十分だったとして、勤務先の50代の校長についても戒告処分としました。
UHB 北海道文化放送
不登校の理由で「先生が原因」である調査報告書は学校や教育委員会からは出ない、又は、あっても過少報告であると考えて間違いないであろう。
真面目な人が調査を反映させたとしても、校長、教育長、そして教育委員会でもみ消される、又は、修正される可能性が高いと思う。文科省がこのような
リスクや傾向が存在する事を認識し、理解しているのだろうか?提出された報告書に記載されていないので、事実の再確認をランダムに抜打ち調査を行うことなく
そのまままとめるのであろうか?
文科省が本当に不登校を減らしたいのであれば 事実や現場の真実を把握し、理解し、そして対応を取らなければ期待したほど良い結果は現れないであろう。
公務員の不祥事は存在するのに教諭、校長、そして教育委員会職員の不祥事が存在しないはずはない。
公務員の不正・裏金問題&その他の問題
不登校「先生が原因」 認知されず ―学校調査と本人調査のギャップから考える 10/16/16(Yahoo!ニュース)
内田良 名古屋大学大学院教育発達科学研究科・准教授
■不登校の理由 本人への調査はナシ?!
学校における、いじめ、暴力行為、不登校、自殺などの現況が集約される「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」が、今年で50回目を迎える。
1966(昭和41)年度の「不登校」(当時は「学校ぎらい」)に関する調査に始まり、今日ではさまざまな項目が追加されている。毎年、秋頃に結果が発表されており、2015(平成27)年度の結果もそろそろ発表されるのではないかと考えられる。
さて、この長らく調査されてきた「不登校」について、気がかりなことがある。不登校の調査結果を見てみると、小中別、国公私立別、学年別の不登校児童生徒数といった基本的な数値にくわえて、各児童生徒が不登校になった理由や不登校を続けている理由など、実情により踏み込んだ分析がある。
ところが、不登校経験者たちに話を聞くと、「調査目的で不登校の理由を聞かれたことは一度もない」というのだ。調査されていないのに、数字が公表されている。これはいったいどういうことなのか? そして、その公表されている数字は、不登校経験者の認識とどれくらい合致しているのだろうか。
■不登校経験者が覚えた違和感
先に結論の一部を述べるならば、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」は、学校が回答したものである。したがって、不登校になった理由というのも、学校がそう判断したに過ぎないのであって、本人がどう思っているかとは、一致しない可能性がある。
私がこうした関心をもったのは、自らも不登校経験のある石井志昂氏(不登校新聞社編集長)から問題提起を受けたためである。石井氏は、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」において、不登校をした本人の意見が反映されないままに調査が実施され、不登校の理由が語られていくことに違和感をもったという。とくに学校側が、教師との関係を「不登校の理由」にあげる割合が、極端に少ないのではないか、というのだ。
じつは、不登校経験者に直接質問をした調査が存在する[注1]。調査では、かつて中学校で不登校を経験した生徒に追跡調査を実施し、不登校当時やその後の状況が尋ねられている。成果は、2014年7月に、『平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書』として公表されていて、そこには不登校になった理由について回答の結果が示されている。
■不登校になった理由は複数ある
はたして、学校が回答した「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」(以下、適宜「学校調査」)と、不登校経験者本人が回答した追跡調査(以下、適宜「本人調査」)との間には、どのようなちがいがあるのだろうか。
本人調査は、2006年度時点で公立の中学3年生であり不登校であった者を対象としている。したがってここで比較対象とすべきは、2006年度時点の学校調査(「平成18年度 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」)における公立中学校のデータである。
両調査の対象者や「不登校の理由」に関する質問内容は、厳密には同じものではないが、いくつかの点で十分に比較可能である[注2]。まず全体的な傾向として目につくのは、「不登校の理由」14項目全般において、本人調査の値が学校調査の値より大きい点である。つまり、不登校経験者のほうが学校よりも多く、複数の「不登校の理由」を選んでいるということになる。
本人調査では一人あたり2.8項目(4,486÷1,604)、学校調査では一人あたり1.2項目(115,411÷99,959)が、不登校の原因としてあげられている。大まかに言えば14項目のなかでは、本人は不登校になった原因を約3つ選び、学校はおおよそ一つに絞っているということである。
本人の目線からすると、不登校に至るにはさまざまな要因や問題がある。だが学校側は、そうした複合的な原因とはとらえていないようである。
■不登校の理由は先生にもある? 認識のギャップ
14項目の「不登校の理由」には、親、友人、教師との人間関係が含まれている。両調査ともに、人間関係のなかでもっとも数値が高いのは、友人との人間関係である[注3]。この点は想像に難くないが、この記事でむしろ強調したいのは、学校側と本人側との認識のギャップである。
図を見てほしい。まず「親との関係」を原因と考える割合を見てみよう。不登校の理由には、親の影響があると考えるのは、学校調査も本人調査もそれほど大きなギャップはなく、1.5倍の開きにとどまっている。次に「友人との関係」を原因とみるのは、3.2倍の開きがある。
ここまでであれば、学校と本人の間のギャップは、複数の原因を選ぶかどうかの範疇にとどまる。上述のとおり、不登校経験者は複数の原因を指摘する傾向(一人あたりで、本人調査では2.8個、学校調査では1.2個の原因)があるため、いずれの項目においても2~3倍の開きが出てしまうからだ。
だがその範疇を超えて問題なのは、「教師との関係」である。学校調査では教師が原因であるとの回答は1.6%(学校調査のなかでは、もっとも数値が小さい)にすぎないが、本人調査では26.2%にもなる。学校と本人の間に16.3倍の開きがある。本人としては、「先生のせいだ」と思っていても、学校側はまるでそのようには考えていないということだ。
「不登校は先生のせいだ」ということが言いたいのではない。大事なことは、認識のギャップを認識するということだ。本人と学校が、まったく異なる「不登校の理由」を思い描いていては、会話さえ成立しない。
子どもの声をちゃんと拾い上げること、これは学校や教育行政そして私たち大人全員に課せられた作業である。
[付記]
石井志昂氏からの問題提起を受けて分析した結果の一部は、すでに石井氏に回答済みである。その回答をもとに、不登校新聞においても記事が発表されている(10/15『不登校新聞』444号)。細かい点で数値の扱い方が本記事とは若干異なっているものの、基本的には同様の結果が示されている。
[注1]文部科学省が省内に「不登校生徒に関する追跡調査研究会」を設置して実施したもので、いじめや不登校の研究で日本の教育界をリードしてきた森田洋司氏(鳴門教育大学特任教授)が研究会の座長を務めた。
[注2]「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」に記載されているのは、不登校となった生徒全員である。他方で、追跡調査では、2006年度当時に中学3年生で不登校であった生徒のなかで、2011年に「調査の協力に応諾した者」(調査実施は2012年)である。また、不登校の理由については、両調査ともに14項目があげられており、各項目の類似性も高い。そのなかでも本記事が扱う、親/友人/教師との人間関係については、質問項目の類似性はとりわけ高いと考えられるため、比較検討の対象とした。
[注3]「友人との関係」の数値は、学校調査では「いじめ」と「いじめを除く友人関係をめぐる問題」の合計値、本人調査では「友人との関係」と「クラブや部活動の友人・先輩との関係」の合計値とした。また、「親との関係」の数値は、学校調査では「親子関係をめぐる問題」、本人調査では「親との関係」を参照した。「教師との関係」の数値は、学校調査では「教職員との関係をめぐる問題」、本人調査では「先生との関係」を参照した。
他の校長達が逮捕されていても止められない。男の性としてもロリ系の風俗に留めておけば逮捕される事はなかったと思う。仮に逮捕されるとしても、
校長と一般人では社会のとらえようが違うと思う。しかし、女子高生が警察に相談したと言う事は、相手に不愉快な行為をしたのだろうか?
それともしつこく会う事を迫ったのだろうか?
女子高生を買春容疑、中学校長を逮捕 SNSで知り合う 10/05/16(朝日新聞)
女子高校生に現金を渡してみだらな行為をしたとして、岩手県警は5日、宮城県気仙沼市の市立中学校長、菅原進容疑者(56)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
県警少年課によると、菅原容疑者は8月下旬ごろ、SNSを通じて知り合った岩手県内に住む女子高校生に対し、18歳未満と知りながら現金数万円を渡して同県内の宿泊施設で性行為をした疑いがある。女子高校生が警察に相談し、発覚したという。
人間は完璧でない以上、問題は起こす。性善説は理想であって、現実ではない事を理解して、件数を減らす努力をするしかないと思う。
被害者を優先するのか、加害者を優先するのか、判断基準の明確化、そして誰が判断するのかの明確化を文書として残して対応するべきだと思う。
それでも解決されないと思う。なぜなら、人間が関与するから。人間が関与するから、良くもなるし、悪くもなる。
【性暴力の実相】「前も教え子とできちゃったんですよね…」見過ごされた教師のわいせつ行為 (1/2)
(2/2)07/22/16(西日本新聞)
「前も教え子とできちゃったんですよねぇ。われわれも扱いづらくて…」
中学生の娘ミサ(仮名)が教師から性被害を受けたと知り、40代の母親トモコ(同)が学校に訴えると、校長はこんな言葉を漏らした。あぜんとして言葉が出てこなかった。
数年前のこと。中日本に住むミサが所属していた中学校美術部の50代顧問は、お気に入りの生徒を自宅に呼んで個人レッスンをしていた。「芸大に行かせてやる」と誘われ、通い始めたミサ。父親以上に年が離れた相手に警戒心はまったくなかった。2、3回通ったころ、顧問から数十分間、無理やりキスされた。
「もっとひどいことをされたはず」とトモコは思うが、ミサはそれ以上話そうとしない。別の個人レッスン生も同時期、急に不登校になった。学校の対応に不信感を抱き、知り合いを介して教育委員会関係者の元へ駆け込むと、返ってきたのは「あの先生、そういう癖があるんです。今までもずーっとですよ」。
結局、顧問は複数の生徒へのわいせつ行為を認め、懲戒免職になった。「学校や教委は問題を把握していたのに見て見ぬふりをしていた。泣き寝入りしたら間違いなく被害は繰り返されていた」とトモコは憤る。
トラブルを起こしても処分されなければ記録に残らない
問題行動を起こした教師への対応はどうなっているのか。
九州の小学校で数年前、女児の胸を触った教諭が、子どもたちから「セクハラ」と訴えられたことがあった。「Tシャツを指さしたら当たっただけ」と釈明したため、校長の判断で情報が教師間で共有されることはなかったという。
当時、この学校で教壇に立っていた女性は「被害児童の立場で考えたり、接し方を議論したりする機会もなかった」と振り返る。同僚から漏れ伝わってきたのは数カ月後のこと。直後、この教師は転勤になった。
福岡、佐賀、熊本などの県教委によると、懲戒処分を受けた事実は人事記録として文書で残る。だが、その具体的な内容は校長同士の口頭の引き継ぎに委ねられているという。トラブルを起こしても、処分されなければ記録にも残らない。
九州のある自治体で教育委員を務めるミドリ(同)は異動時の引き継ぎに疑問を抱き、不祥事の内容をすべて文書にして学校間で渡すよう、教委の会合で提案した。「教員の再起を妨げるようなことはすべきじゃない」と一蹴された。
子どもたちが傷つけられてからでは遅すぎる
教師によるわいせつ行為が相次いだ長野県教委は2013年、不祥事の引き継ぎを文書で行うなど46項目の再発防止策をまとめた。非公表だった当事者への指導状況や懲戒に至らない問題行動も文書で残し、学校や県、市町村教委で共有するようになった。教職員への研修や啓発も徹底させているという。「それでも不祥事はゼロにならない」と担当者は漏らす。
九州の実態を知るミドリは、自らの町で被害が起きないか、不安を募らせる。「起こる前提で対策を取らないと、子どもたちが傷つけられてからでは遅すぎる」
長野県の取り組み
不祥事が相次いだ長野県教委は2013年、46項目からなる「信州教育の信頼回復に向けた行動計画」を策定した。問題を起こした教諭の情報を文書で引き継ぐようにしたほか、不祥事に気付いた教諭が相談、通報しやすい体制を構築する▽管理職の選任要件に組織管理能力を加える▽感情のコントロールの仕方など専門的な研修を実施する-ことなどを盛り込んだ。弁護士や臨床心理士など外部の専門家から最低年1回、意見をもらいながら、不祥事防止に努めているという。
万引きして捕まるのが嫌だったら万引きなどしなければ良い。ストレスが理由と言うのであれば、ストレスの発散方法を変えればよい。
犯罪にならない発散方法はあると思う。まあ、逮捕された時点で、既に遅いけど!
体育の講師だから、他の講師と価値観が合わなかったのか?(岡山中学校・高等学校)
下記の記事を読むと最悪の捕まり方。教師を続けるのはかなり厳しいかも??

万引き中学講師が車で逃走、制止の3人をはねる 08/17/16(読売新聞)
岡山西署は16日、岡山市北区野殿東町、私立岡山中講師万代卓実容疑者(26)を強盗致傷、強盗殺人未遂の両容疑で再逮捕した。
発表によると、万代容疑者は14日午後0時5分頃、同区野殿西町の「ホームセンタータイム大安寺店」で扇風機1台(1万6800円相当)を万引きしようとして見つかり、車で逃走。立ちはだかった男性従業員(28)をはねるなど、制止しようとした3人に胸部打撲などのけがを負わせた疑い。
万代容疑者はその直後、同区内の民家に侵入したとして、住居侵入容疑で現行犯逮捕された。調べに対し、「とにかく逃げたいと思っていた。殺意はなかった」と容疑の一部を否認しているという。
岡山中によると、万代容疑者は昨年4月から勤務。体育の授業を担当し、今年6月から1年のクラス担任になった。勤務態度はまじめだったといい、金田好史教頭は「事件は痛恨の極み。事実関係を確認し、厳正に対処する」と話した。
住居侵入 中学校講師を容疑で逮捕 万引き注意され 岡山西署 /岡山 08/15/16(毎日新聞)
岡山西署は14日、ホームセンターで万引きをとがめられ、民家敷地に逃げ込んだとして北区野殿東町、私立中学校講師、万代卓実容疑者(26)を住居侵入容疑で現行犯逮捕した。店から車で逃げる際、従業員らにけがをさせたとして、同署は強盗致傷などの容疑でも調べる。
同署によると、同日昼ごろ、北区野殿西町のホームセンタータイム大安寺店で、扇風機1台を万引きしたとして保安員に声をかけられた男が、駐車場に止めていた車で逃走。従業員がボンネットに乗るなどして制止しようとしたが、振り切って逃げた。同署員が110番通報で駆けつけ、駐車場に落ちていた万代容疑者の財布を見つけたところ、戻ってきた万代容疑者が財布を奪って逃げ、間もなく見つかり逮捕された。【益川量平】
万引の中学講師、落とした財布を拾いに現場戻る 08/14/16(日刊スポーツ)
岡山西署は14日、岡山市の住宅敷地内に不法に入ったとして、住居侵入容疑で同市北区、私立中講師万代卓実容疑者(26)を現行犯逮捕した。
同署によると、市内のホームセンターでの万引について職務質問され、走りだしたという。
岡山西署によると、万代容疑者は正午ごろ、扇風機1台を持ち、代金(1万6800円)を支払わずに店を出たとして保安員が店舗内の事務所で事情を聴いたところ車で走り去り、制止しようとした保安員や店長ら3人が頭を打つなどした。
約10分後、落とした財布を拾いに徒歩で店の駐車場に戻り、駆け付けていた署員が職務質問したところ再び逃走。追跡中の署員が住居敷地を通過するのを目撃した。
逮捕容疑は14日午後0時20分ごろ、同市北区の住居2軒の敷地に不法に侵入した疑い。同署は強盗致傷の疑いもあるとみて調べる。(共同)
「文科省担当者はショックをあらわに」
なぜ? データーの共有は便利であるが、大量の情報の流出または取得が簡単になる事を理解できなかったのか??
セキュリティーを強化すると維持管理の費用が負担となる事さえも理解できなかったのか?かなり自信がない限り、流出またはハッキングされても問題ない
程度の情報にするべきだったと思う。
児童や生徒の学籍や成績などの情報をコンピューターで管理する「校務支援システム」に頼らなくても情報は共有する方法はあると思う。メリットばかり
見て、デメリットを軽視するからこのような事になる。自業自得!
ホテルで教え子にわいせつ行為…食料品を万引、教諭2人免職/県教委 07/13/16(埼玉新聞)
埼玉県教育委員会は13日、万引やわいせつ行為をしたとして、教諭2人を懲戒免職処分にした。
県教育局によると、県立越ケ谷高校の男性教諭(54)=不起訴処分=は2011年9月11日、越谷市内のショッピングセンターで食料品数点(計3千円相当)を万引し、今年2月7日には東京都大田区の店舗で、サポーターとスポーツソックス(計3300円相当)を万引した。
県東部の県立高校の男性教諭(50)は3月13日から14日にかけて、県内のホテルで担任する女子生徒の胸を触るなどのわいせつな行為をした。女子生徒から教諭に「家の事情で自宅に帰れない」などと電話があり、車でホテルに行ったという。女子生徒が保護者に相談し発覚。教諭は「胸は触っていない」と一部否認していたが、処分を受け入れたという。
また、無免許運転などをしたとして、三郷北高校の臨時的任用の男性教諭(29)を停職6カ月の懲戒処分とした。男性教諭は4月1~14日、通勤や出張の際に無免許で乗用車を運転した。教諭は12年に事故などにより免許取り消し処分を受けていた。13年に臨時教諭として採用されたが、無免許のまま通勤や出張で車を運転。通勤届を提出するため、運転免許証の写しを改ざんしていた。提出書類を不審に思った担当課が学校に問い合わせ、発覚した。
一方、車で交通事故を起こした県西部の県立高校の女性教諭(49)を戒告の懲戒処分にした。
関根郁夫教育長は「4件の不祥事が起きたことについて深くおわび申し上げる。学校と一体となって再発防止に取り組み、県民からの信頼回復に全力を尽くす」とコメントした。
「文科省担当者はショックをあらわに」
なぜ? データーの共有は便利であるが、大量の情報の流出または取得が簡単になる事を理解できなかったのか??
セキュリティーを強化すると維持管理の費用が負担となる事さえも理解できなかったのか?かなり自信がない限り、流出またはハッキングされても問題ない
程度の情報にするべきだったと思う。
児童や生徒の学籍や成績などの情報をコンピューターで管理する「校務支援システム」に頼らなくても情報は共有する方法はあると思う。メリットばかり
見て、デメリットを軽視するからこのような事になる。自業自得!
<不正アクセス>「最先端の佐賀県システム破られるとは」 06/27/16(毎日新聞)
◇文科省担当者はショックをあらわに
「ICT(情報通信技術)化が最も進んでいる佐賀県のシステムが破られた。とても驚いている」。佐賀県立高校の生徒の成績などが流出した事件で、文部科学省の担当者はショックをあらわにした。同省は27日、佐賀県教委に事実関係の早急な報告を求めた。
全国の公立小中高校の普通教室に設置されている電子黒板の整備率(2015年3月時点)は全国平均が9%なのに対し、佐賀県は76.5%で全国1位。パソコンの整備状況も生徒2.6人に1台と全国トップで、国が第2期教育振興基本計画(13~17年度)で定める目標の3.6人に1台を唯一超えており、ICT化の先進地域として知られていた。
同省によると、児童や生徒の学籍や成績などの情報をコンピューターで管理するシステムは「校務支援システム」と呼ばれ、各地の学校で導入が進んでいる。教職員同士が情報を共有することできめ細かな指導をしたり、教員の校務負担の軽減を図ったりするメリットがあるとされる。
佐賀県のシステム「SEI-Net(セイネット)」は全国に先駆けて13年度から導入された。学校側が授業支援のためのデジタル教材を提供し、児童生徒が家庭でダウンロードして予習や復習に利用したり、ネット経由で相談に乗ったり、学校行事の確認をしたりすることも可能にしていた。
佐賀県教委によると、このシステムには5月1日現在で小中学生3万4739人、高校や特別支援学校などの県立学校生5万6590人、教職員7987人の情報が登録されていた。
教職員が成績や住所などの個人情報にアクセスするには、校内ネットワークに接続したうえでIDとパスワードを入力する必要がある。児童生徒はIDとパスワードを入力すれば、校外からでもネットに接続して、自分のテスト結果や電子教材などは閲覧できるという。【佐々木洋、池田美欧】
不正アクセス容疑 数万人の情報流出か 17歳少年再逮捕 06/27/16(毎日新聞)
警視庁 佐賀県の教育情報システム侵入の容疑で
生徒の成績などを管理する佐賀県の教育情報システムに侵入したなどとして、警視庁サイバー犯罪対策課は27日、佐賀市の無職少年(17)=不正競争防止法違反容疑で逮捕=を不正アクセス禁止法違反容疑で再逮捕した。少年がシステムから盗み取った成績表や生徒の住所などの情報は数万人分にのぼるとみられる。
逮捕容疑は今年1月20日午前0時20分ごろ、県立高校1校の教育情報システムに無線LANから侵入し、他人のIDやパスワードを使って不正にアクセスしたとしている。少年はこの高校を含めて6高校のシステムに侵入し、成績表などが入った約21万ファイルを盗み出したとみられる。同課によると、少年は容疑を認めているという。
また少年は今年1月16日ごろから18日ごろまでの間、佐賀県が管理する県立中学・高校の生徒の成績や出欠状況などを記録する教育情報システム「SEI−Net」に不正にアクセスした疑いもある。県立高校6校の生徒や教員のIDを盗み取っていたとみられる。
少年は盗み取ったIDをインターネット上のサイトに掲載し、仲間数人に紹介していた。成績表などの個人情報は掲載しておらず、情報の転売や流出は確認されていないという。
同課は今月6日、有料デジタル放送の視聴に必要な「B−CASカード」を使わずにパソコンで無料視聴できるプログラムを開発してネット上に公開したとして、少年を不正競争防止法違反容疑で逮捕。その後、少年の自宅にあったサーバーを解析したところ、個人情報が保管されているのが見つかったという。
各校の教育情報システムには生徒の氏名や住所のほか、成績や出欠状況、生活態度などをまとめた調査票なども保存されていた。生徒が宿題や課題を提出したり、教材をダウンロードする際に利用することもあるが、成績や調査票などの情報にアクセスできるのは教員に限られていた。少年は友人のIDやパスワードを使用するなどしていたとみられる。【斎川瞳】
教え子とわいせつ行為…現金、ユニホーム盗む 教諭3人処分/県教委 06/23/16(埼玉新聞)
県教育委員会は23日、窃盗事件やわいせつ事案を起こした教諭3人を懲戒免職処分にした。
県教育局によると、越谷西特別支援学校の男性教諭(51)=不起訴処分=は昨年12月、東京都内のカプセルホテルで、床に置いてあったかばんの中の財布から現金1万1千円を盗んだ疑いで警視庁に逮捕された。
杉戸農業高の男性教諭(39)=窃盗罪などで起訴=は今月4日、千葉県印西市の順天堂大の体育館に侵入し、男性用のバレーボールユニホーム1枚を盗んだとして千葉県警に逮捕された。男性教諭は「順天堂大は高校のころから憧れの大学で、ユニホームを見て格好がよかったので取ってしまった」と話しているという。
県西部の公立中学校の男性教諭(34)は2012年4月から14年8月までの間、教え子だった当時18歳未満の女性(19)とみだらな行為をした。男性教諭は既婚者で、女性の卒業後に不適切な関係を持ったという。今年3月に女性の母親が気付き発覚した。
ほかにも、体罰に適切に対処しなかったとして、草加市立高砂小の男性校長(60)を戒告処分にした。
関根郁夫教育長は「不祥事防止に懸命に取り組む中、4件の不祥事が起きたことについて深くおわび申し上げる。信頼回復に向けて再発防止に全力を尽くす」とコメントした。
女子生徒と関係元男性教諭 懲戒免職取り消し 06/09/16(河北新報)
20年以上前に勤務していた福島県立高で、当時の女子生徒とみだらな行為をしたとして懲戒免職処分を受けた元教諭の男性(64)が県に処分取り消しを求めた訴訟の判決で、福島地裁は8日までに、処分の取り消しを命じた。
地裁は年月の経過や処分前に慰謝料50万円を払っていたことなどを踏まえ、処分は重すぎるとして「著しく妥当性を欠いており、裁量権の乱用」とした。男性の行為について「公教育に対する信頼を著しく失墜させた」と指摘した。
判決によると、男性は1986年から3年余り、女子生徒と関係を持ち、定年退職前年の2012年、県教委が元生徒からの相談を受けて懲戒免職処分とした。
鈴木淳一県教育長は「判決の内容を精査し、今後の対応を検討したい」との談話を出した。
生徒にわいせつ行為、窃盗 教諭と元校長処分 05/17/16(河北新報)
宮城県教委は16日、県北部の男性高校教諭(30)を免職、東部教育事務所管内の男性元中学校長(56)を停職12カ月の懲戒処分にしたと発表した。
県教委によると、教諭は3月下旬、勤務する学校の女子生徒に県内のホテルでわいせつな行為をした。生徒が学校に相談し、発覚した。教諭は生徒に対し、学校の事情聴取に事実を隠蔽(いんぺい)するよう電話やメールで指示していた。
元校長は2月13日、仙台市宮城野区のパチンコ店景品交換所で、他の客が取り忘れた現金2万円を盗んだ。3月27日に仙台東署に任意同行を求められるまで校長として勤務を続け、事実を把握した県教委が4月1日に学校以外の機関に異動させ、5月16日付で退職願を受理した。
高橋仁教育長は「服務規律の徹底を指示し、不祥事防止の取り組みをしてきたが、再びこのようなことが発生し、県民に深くおわびする」との談話を出した。
「京都府教育委員会高校教育課は15日、『高校には、それぞれの生徒の状況に応じて配慮するようにと繰り返し言っている。妊娠も、病気やけがと同様に配慮が必要』との見解を示した。妊娠した生徒の体育授業について『実技ではなく、リポート提出や軽微な体操で配慮できる』としている。」
京都府教育委員会高校教育課が批判を受けて対応を変えたのでなければ、京都府教育委員会高校教育課の管理・監督に問題がある。そして、生徒の人生を狂わすほどの間違った判断を下したのだから京都府立朱雀高の校長と副校長を処分するべき。
個人的には性行為および適切な避妊をしなかった事に対してのいましめとして、学校の方針で卒業させないと言うのであれば仕方がないと思う。同級生と一緒に卒業できなくても、
自己責任だと思う。
「スポーツ庁学校体育室は『体育の評価は実技だけではない』と、実技にこだわる朱雀高は認識不足と指摘する。学習指導要領にある評価の観点は運動技能含め知識や意欲など4点で、『妊娠や障害など考慮すべき一つ一つのケースを明記せずとも、現行の記述で生徒の人権に配慮した授業は行える。学習指導要領の趣旨が現場に周知されていないのなら残念』とした。」
権限を持つ組織が全く違う判断をしているので、京都府立朱雀高の校長と副校長を処分しなくてはならない。なぜなら彼らは権限を乱用し、生徒の人生を狂わせた責任がある。今回の事が全国規模の記事にならなければ
批判を受けることはなく、間違った判断が正当化され続けただろう。
広島県府中町の町立中学校3年の男子生徒が、誤った万引き記録に基づく進路指導を受けた後に自殺した問題と似ている。教育委員会の管理・監督の問題と校長の傲慢な判断。似たような問題は氷山の一角かもしれない。
妊娠生徒に体育実技要求 京都の高校に批判殺到、対応見直しへ 05/15/16(京都新聞)
京都府立朱雀高(京都市中京区)が1月、妊娠7カ月の3年女子生徒(18)に対し、卒業の条件として体育の実技をするよう求めていたことが分かった。保護者や本人の意向に反し、一方的に休学届も送りつけていた。学業か出産かの二者択一を迫る学校の対応に、文部科学省は「妊娠と学業は両立できる。本人が学業継続を望む場合、受け止めるべき。子育てに専念すべきとなぜ判断したか分からない。周囲の協力を得ながら育児するのは働く女性も高校生も変わらない」と批判している。
これに対し同高は15日、「学校の認識にかなり古い部分があった。見直さないといけない」として、今後、妊娠生徒への対応を改める意向を示した。
副校長は4月、妊娠生徒に体育実技をするよう求めた理由について、取材に「妊娠すると子育てに専念すべきで、卒業するというのは甘い」「全日制では妊娠した生徒は学業から離れないといけない。府民の要請がある」などと説明。補習の実技として「持久走などハードなこと」を例示した。
副校長の見解に対し、同高に苦情や問い合わせの電話が相次いでいるという。
生徒は同級生と一緒に卒業することを希望していたが、休学届を学校側から渡され、休学している。
また副校長は同日、「(妊婦にとって)学校が一つの壁だったのは認めざるを得ない。妊娠がマイナスイメージであってはならず、今後、改めないといけない」と述べた。
京都府教育委員会高校教育課は15日、「高校には、それぞれの生徒の状況に応じて配慮するようにと繰り返し言っている。妊娠も、病気やけがと同様に配慮が必要」との見解を示した。妊娠した生徒の体育授業について「実技ではなく、リポート提出や軽微な体操で配慮できる」としている。
スポーツ庁学校体育室は「体育の評価は実技だけではない」と、実技にこだわる朱雀高は認識不足と指摘する。学習指導要領にある評価の観点は運動技能含め知識や意欲など4点で、「妊娠や障害など考慮すべき一つ一つのケースを明記せずとも、現行の記述で生徒の人権に配慮した授業は行える。学習指導要領の趣旨が現場に周知されていないのなら残念」とした。
情報が少ないので何とも言えない。
ただ本人の意思に反して「妊娠7か月の高校3年生の女子生徒に対し、マラソンなど体育の実技の補習を求めていた」と言うことであれば、この校長の知識と常識を疑う。
「校長は、『卒業には補習が必要で、妊娠は特別扱いをする事情にはあたらない』としながらも、対応に問題があったと述べました。」
この校長、常識がないと思う。妊娠だからと言って特別扱いはしないので体育の実技の補修が出来ないから卒業させないと言うのであれば仕方のないこと。
女生徒が卒業を断念、または、延期するのは個人の判断だと思う。
妊娠の女子生徒に体育実技要求、京都の府立高校 05/15/16(TBS系(JNN))
今年1月、京都府の府立高校が、当時妊娠7か月の高校3年生の女子生徒に対し、マラソンなど体育の実技の補習を求めていたことがわかりました。
校長は、「卒業には補習が必要で、妊娠は特別扱いをする事情にはあたらない」としながらも、対応に問題があったと述べました。
「不測の事態が起きた時にどうなのかという思いが確かにございました。100%それがよかったかと言えば、そうとは言い切れない」(校長)
結局、女子生徒は卒業を断念し、今年4月に出産しましたが、現在も休学中です。
15年間「偽教諭」、男を書類送検=給与4000万円詐取疑い―大阪府警 10/21/14 (時事通信) や
<無免許教諭>給与1.8億円返還請求せず 03/10/16(河北新報)が過去に起きている。なぜ、偽造教員免許状が簡単にばれないのであろうか??
「県教委は過去の行政実例を踏まえ、『女性は適法に採用された教員と同じ勤務をこなした』と認め、労働の対価である給与の返還は請求しにくいと判断した。」03/10/16(河北新報)のような甘い対応もあるから、軽い処分だと安易に考えるのであろうか??
“偽造教員免許”の写し提出した疑い、元講師の女逮捕 05/10/16(TBS系(JNN))
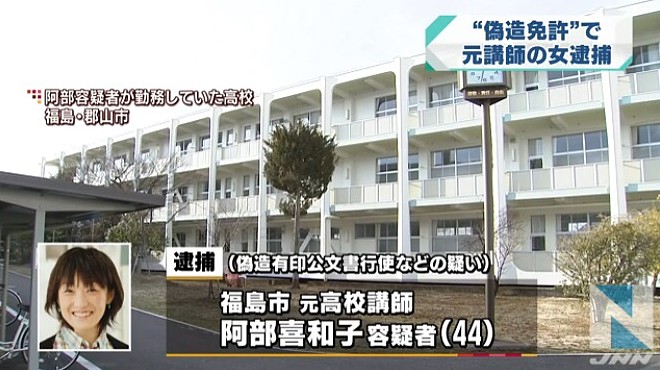
福島県郡山市の私立高校に偽造された教員免許状の写しを提出した疑いで、元講師の阿部喜和子容疑者(44)が逮捕されました。
阿部容疑者は4年前に、高校に偽造された教員免許状や、在籍していなかった大学のうその成績証明書を提出し、およそ2年半にわたり、美術などの講師として教壇に立っていた疑いがもたれています。警察などによりますと、阿部容疑者は容疑を認めているということです。
阿部容疑者は、ほかの福島県内の県立高校2校でも、偽造した免許状で講師を務めていたとして刑事告発されています。
県立高講師、採点ミス指摘の生徒殴る…訓告処分 04/21/16(読売新聞)
愛知県立高校の30歳代男性講師が3月、定期試験での採点ミスを指摘してきた男子生徒を拳で殴るなどしていたことが20日、県教育委員会への取材でわかった。
県教委は「体罰」と認定したが、総合的に判断し、文書訓告にとどめたという。
県教委によると、男性講師は3月2日、国語の答案を返却する際、成績が良くなかった男子生徒に「怠けているな」と言い、生徒の頭を平手でたたいた。
その後、席に戻って答案を確認した生徒が採点ミスに気づき、講師に採点をしっかりやってほしいとの言葉を投げかけると、腹を立てた講師が生徒の左手首を右手でつかみ、頭部を拳で殴ったという。生徒が保健室に駆け込んだことで発覚したが、けがはなかった。
県教委は3月29日付で講師を文書訓告にするとともに、校長を監督責任者として厳重注意した。講師は「教師としての自覚、配慮が欠けていた。深く反省している」と話しているという。
「調べによると吉岡容疑者は12日午前6時半ごろ、大洲市内のスーパーでおにぎりや酒など11点、合わせて1200円余りを万引きした窃盗の疑いが持たれている。」
万引きして捕まれば、「校長としての職を失う=給料がない=もっと金銭的に生活が苦しくなる」とは考えなかったのだろうか??本当にお腹が減ったのなら、お酒はやめておにぎりだけにしておけば良かったのに。
もう今の人生を終わらせたかったのかもしれない。
おにぎり万引き「生活苦しかった」校長逮捕 04/12/16(日本テレビ系(NNN))
スーパーでおにぎりなどを万引きしたとして愛媛県大洲市の中高一貫校の校長が窃盗の疑いで現行犯逮捕された。
逮捕されたのは帝京冨士中学校・高等学校、校長の吉岡行正容疑者(63)。調べによると吉岡容疑者は12日午前6時半ごろ、大洲市内のスーパーでおにぎりや酒など11点、合わせて1200円余りを万引きした窃盗の疑いが持たれている。
吉岡容疑者が商品をスーツのポケットに入れ、レジを通さず店の外に出たため、店員が警察に通報し駆けつけた警察官が現行犯逮捕した。
吉岡容疑者は12日は学校に出勤予定で、校長の逮捕を受け木村克人教頭は「ショックで信じられない、事情がはっきり分からないのでコメントできない」としている。
吉岡容疑者は「金銭的に生活が苦しかった」と容疑を認めていて、警察は余罪の有無についても調べを進める方針。
「教諭は市教委の聞き取りに『態度を改めてほしいという気持ちがあった。反省している』と話しているという。」
本当に反省しているのかは、市教委だけが知っている。子供でも嘘を付く。大人になればなおさら自己利益や自己都合のために平気で嘘を付く。反省していなくても、
反省していると言う事は良くある事。
この男性教諭、体罰をおこないながら、体罰で処分を受ける可能性を十分に理解し、自覚している。
市教委は教諭に問題があるのか、生徒にも問題があるのか調べる必要がある。生徒にも問題があれば、体罰を使わずに、生徒に対応する事は出来るのか、
問題のある生徒に対する対応についてマニュアルや学校が取れる選択などを事前に準備しておく必要があるだろう。
教諭に問題があれば、分限免職を適応する基準を明確にしておくべきであろう。
男児に体罰、「一生許さへん」=男性教諭を戒告処分―大阪市教委 04/05/16(時事通信)
昨年12月に大阪市東住吉区の市立小学校で、男性教諭(37)が当時5年生の男子児童に対し、壁に押し付けるなどの体罰を加え、「これで先生がクビになったら一生許さへんからな」と暴言を浴びせていたことが5日、市教育委員会への取材で分かった。
男児にけがはなかった。市教委は教諭を戒告処分にした。
市教委によると、教諭は昨年12月22日、放課後学習中に、注意に従わず教室内を立ち歩いていた男児のあごをつかんで壁に押し付けた。さらに襟首を持って振り回し、転倒した男児に暴言を浴びせた。帰宅後、男児は嘔吐(おうと)し、病院で検査を受けた。保護者が学校に問い合わせたことで発覚した。
また、この教諭は昨年10月、担任をしていた当時4年生の男児に対しても体罰を加えていた。
教諭は市教委の聞き取りに「態度を改めてほしいという気持ちがあった。反省している」と話しているという。
全額返納する命令処分後、強制的に回収する事は可能だろうか?
アメリカでは強制回収の対応策として、妻に資産や家を譲って妻名義に変更した後に離婚する場合がある。
このような事をさせないために速やかに強制回収する必要がある。神奈川県はどのように対応するのだろう。
退職金3千万円、初の返納命令 買春の元校長に 03/30/16(カナロコ by 神奈川新聞)
横浜市教育委員会は30日、フィリピンで少女とのみだらな行為の撮影を繰り返すなどしたとして有罪判決を受けた元市立中学校の男性校長(65)に対し、退職手当約3千万円を全額返納する命令処分を出した。
処分は県職員の退職手当に関する条例に基づいた措置。条例では在職中に懲戒免職相当の事案を起こした場合、退職金の返納を命じることができる。市教委としては返納命令を出すのは初めて。
多くの現役の教師などが今回の問題はありえないとブログで書いてある。しかし、世間からの必要以上の批判は良くないとも書いてある。そして、死ぬ選択を選ぶ必要もなかったとも書いてある。
個人的には死ぬ選択を取る必要はなかったと思う。しかし、自殺したからこそ、注目を浴び、メディアが取上げ、隠蔽される、又は、うやむやにされる問題の一部が公になった。多くの人々がこのような状態がありえるのかと驚いたはずである。生徒が自殺しなかったら、メディアが取上げなかったら、多くの人々が批判しなかったら、問題は公にならなかったに違いない。日本は、酷い結果又は犠牲者が出ないと動かない国である。文科省の特別チームも動かなかったであろう。
生徒が自殺によってこのような展開になる事を想像したとは思わないが、自殺した以上、問題の根っこまで調べるべきでる。事実の裏には理由がある。一方で、理由が公になる事を望まない人達も存在する。理由が明らかになると対応せざるを得ない状況になる可能性があるからだ。残念ながら他人事はどうでも良いと思う人達は多くいる。直接的であれ、間接的であれ、そのような人達が存在するから、今回の悲劇は起きた。
子供とか生徒とか言いながら、それは言葉だけで、本心はそれほど関心を示していない教諭達も存在するはずだ。だから、このような信じれない事実が出てきた。事実を理解し、受け入れないと、綺麗ごとや理想だけでは現状に対応する方針や活動を決める事など出来ないと思う。ゆとり教育の失敗は、綺麗ごとや理想、そして現状の教育現場の理解不足があると思う。もう、多くの人達はゆとり教育の失敗に触れない。責任や計画の甘さを認めなくてはならなくなるからだ。
今回の自殺ももう幕引き段階に来ていると思う。ここで幕引きすると言う事は、将来的に、問題を残す事になる。これが、現実。事件後にスクールカウンセラーの派遣で対応させるとか簡単に言う前に、生徒達にどのような影響を与えるのか、教育委員会や学校側は考えて対応するべきであろう。
「校長が給与の一部を自主返納へ」、結局、一部とは一割、2割、それとも3割?
「25日の同中での終業式で、坂元校長は『大変つらい思いをさせてしまい、申し訳ない』と、生徒に謝罪し、『無念と思って退くが、校長としてみなさんを見させてもらい、心から感謝している』とあいさつしたという。」
どこまで行っても体裁だけの人なのだな?なぜ、多くの問題が放置されてきた。最後なのだから、公表するべきだろ!
広島・中3自殺、校長が給与の一部を自主返納へ 03/27/16(読売新聞)
広島県府中町立府中緑ヶ丘中3年の男子生徒(当時15歳)が自殺した問題で、町教委は25日、3月末で定年退職する坂元弘校長が、給与の一部を自主返納すると申し出たことを明らかにした。
町教委によると、坂元校長は「責任をとりたい」との趣旨の説明をした。町教委は了承し、県教委に伝えた。県教委は今後、返納方法を検討するとしている。
25日の同中での終業式で、坂元校長は「大変つらい思いをさせてしまい、申し訳ない」と、生徒に謝罪し、「無念と思って退くが、校長としてみなさんを見させてもらい、心から感謝している」とあいさつしたという。
「『1年時に触法行為があっても、その後頑張っている生徒を評価するのが教育だ』。『1~3年時への拡大』という決定内容対して学校関係者から聞こえてくるのは、こうした批判の声がほとんど。下崎県教育長も『普通はありえないし、聞いたことがない』と批判する。」
このような状況となったから下崎県教育長がこのような批判をしたのか、本音で批判したのかわからない。
しかし、下崎県教育長の批判が事実であれば、なぜ坂元弘校長を誰も止められなかったのか?なぜ高杉良知府中町教育長は下崎県教育長と同じような考えを持たなかったのか?
府中町教育委員会は坂元弘校長の王様のような対応を知りえる事は出来なかったのか?知りえるような体制になっていないとすれば、なぜ問題を把握できるような体制をとらずにいたのか?
坂元弘校長の間違った判断に対して異論を唱える環境はなかったのか?坂元弘校長から威圧的な対応はあったのか?公開されなければならない事がたくさんあると思う。
冤罪で生徒を死に追いやった、あまりにも「ルーズ」学校…広島中3自殺、重いずさん教育指導責任(1/4)
(2/4)
(3/4)
(4/4) 3/27/16 (産経新聞 West)
「学校の組織がバラバラ」-。広島県の下崎邦明教育長が定例会見で語った言葉は、3年の男子生徒=当時(15)=が自殺した同県府中町立中学校の体質を突いていた。同校が町教委などの指導を受けながら作成した「調査報告書」は生徒指導面でも、進路指導面でも何もできていなかった「学校のルーズさ」を浮かび上がらせた。普通ならすべきことをしないという「学校の不作為」が、誤った万引記録による志望高への専願の道を閉ざし、男子生徒を自殺に追い込んだといえる。
学校側のケアレスミスで万引犯に
男子生徒が1年生の時にかかわったとされた万引事案は、同級生2人が起こしたものだった。コンビニからの通報を受けて万引事案に対応した教諭が生徒指導担当に口頭で伝え、生徒指導担当が万引事案の概要をコンピューターのサーバーに打ち込む際、男子生徒の名前を謝って入力してしまった。このケアレスミスが「冤罪(えんざい)死」の発端になった。
万引事案を議題にした平成25年10月の生徒指導推進委員会の席上、出席者の1人が「男子生徒ではない」と指摘した。しかし、配布資料が訂正されただけで、サーバー内のデータが訂正されることはなかった。以降、6回の推進委会議の配布資料でも、誤ったデータによって男子生徒の名前が載り続けたが、出席者から訂正を求める声は上がらず、データ内に名前が残り続けた。
昨年11~12月に行われた男子生徒への進路指導では、担任が万引記録を理由に私学専願の推薦ができないことを伝えた。3年の学年主任は「いつ、どこで、何をしたか」という具体的なことを生徒に確認するよう求めていたが、担任は生徒のあいまいな返答だけで「確認できた」と判断。この思い込みが志望校への専願の道を絶ち、生徒を自殺に追い込んだ。
数多くあった誤記録訂正のチャンスを生かすことができなかったのは、担任ら個々人の問題だけではない。学校組織から、チャンスを生かす土壌が失われていたことも大きな要因だ。
担任交代時に引き継ぎなし
万引事案のあった25年10月6日の翌日、同校では1年生による教諭に対する暴力事案が発生。多くの教諭がこの対応に追われたこともあり、「いつ、どこで、だれが」などを書き込む「事実確認票」は作られず、生徒と保護者、担任らによる五者面談など、問題行動に際して行うべき6つの作業や指導もすべて行われなかった。
仮に五者面談が行われていれば、男子生徒と両親はすぐに学校側に抗議、誤記録を正すよう求めたはずだ。データ内に名前が残り、2年後の進路指導時に「嫌疑」をかけられたとしても、生徒や両親が反論しただろう。
このような問題行動へのルーズな対応は、今回の万引事案に限ったものではない。報告書によると、生徒指導推進委の会議録は作られず、問題行動を起こした生徒の反省文や事実確認票を誰が管理するかも決まっていなかった。個人別に問題行動の内容や生徒、保護者と話したことなどを書き込む「個人カルテ」もなかった。
このため学年が上がって担任が代われば、過去の問題行動は引き継がれず、新しい担任は受け持ちの生徒たちが過去にどんな問題行動を起こしたかを把握しづらい。2年以上前に起きた万引の誤記録が見過ごされたのも当然だった。
唐突な推薦方針変更
このような学校のルーズさは進路指導面でも顕著だった。
同校では従来、私立専願の推薦をしない触法行為の範囲を「3年時」にしていたが、今春の受験から「1~3年時」に拡大することを決めた。その際、何を根拠資料とするかは決められず、いい加減に管理されていた推進委のデータが引っ張り出され、訂正されないままの男子生徒の名前が出てきてしまった。
だが、もっと大きな問題は、このような重大な決定を、受験校を決める直前の11月に決め、保護者や生徒への周知も怠ったことだ。
校長名で出された報告書には「1、2年時の触法行為を推薦基準に入れるのであれば、入学時から全生徒、保護者に明確に伝え、周知する必要があった」との記述がある。
しかし、3年生の担任らが11月、「1~3年時」への拡大案を報告しにきた際の校長の対応について、報告書には「校長は『これまでの説明会で1、2年時の触法行為が入らないとは明言していない』などと考えて了承した」とあり、校長の頭には入学時からの周知など全くなかったように記述されている。
「1年時に触法行為があっても、その後頑張っている生徒を評価するのが教育だ」。「1~3年時への拡大」という決定内容対して学校関係者から聞こえてくるのは、こうした批判の声がほとんど。下崎県教育長も「普通はありえないし、聞いたことがない」と批判する。
生徒の将来を左右する進路指導や個人記録の扱いについて、学校側のあまりにもずさんな対応の数々。悲劇は起こるべくして起きたといえる。
「王様のような坂元弘校長の独裁がなぜ許されたのか? 府中町教育委員会は学校の状況を定期的に知るような体制を取っていないのか?広島県府中町立府中緑ケ丘中学校での坂元弘校長の任期が何年だったのか公表されていないが、3年未満であれば、前の校長はどのような対応していたのか?このような事を調査するべきである。放置すると問題は残る。
府中町中学生自殺問題 義家副大臣が町教委に改善策要望 03/27/16(RCC)
府中町の男子中学生が誤った万引き歴に基づく進路指導を受けた後に自殺した問題で、文部科学省の義家弘介副大臣が教育委員会に改善策を要望しました。
義家副大臣は、今回の問題を受け文科省の特別チームがまとめた中間報告書を高杉教育長に手渡しました。
報告書は、学校側に校長のリーダーシップや推薦基準の見直しなどを求めています。
会談終了後 義家副大臣は、生徒の進路決定が機械的に判断されたことが問題だと強調しました。
(文科省 義家弘介副大臣)「一つ一つの失敗を裁くのが義務教育学校の責任ではないと思っています。いかにして成長を導くのか、町を飛び出して次のステージへとチャレンジさせるのか、まさに義務教育に問われている」
「市教委は『教育的配慮に欠ける発言』として、寺井校長を口頭指導したことも発表。『処分に該当する法令違反などはなかった』として、指導にとどめたとした。」
大阪市教育委員会が「処分に該当する法令違反などはなかった」と判断している以上、寺井寿男校長のような行動を取っても校長になれるし、再任用する判断に問題はないと言うことだろう。
「2人以上出産」発言の中学校長、退職へ…大阪 03/28/16(読売新聞)
大阪市教育委員会は28日、2月の全校集会で「女性にとって最も大切なのは子供を2人以上産むこと」などと発言した大阪市立茨田まった北中学校の寺井寿男校長(61)について、3月末の再任用の任期満了に伴い、校長を退職すると発表した。
寺井校長は昨年3月に定年退職し、再任用された。再任用は1年ごとの更新制で、市教委は寺井校長に来月以降の任期更新を通知していたが、本人が今月18日に辞退届を提出したという。寺井校長は辞退の理由について、「間違った発言はしていないが、学校や関係者に多大な迷惑をかけた」と話しているという。
市教委は「教育的配慮に欠ける発言」として、寺井校長を口頭指導したことも発表。「処分に該当する法令違反などはなかった」として、指導にとどめたとした。
「 文科省が公表した『中間とりまとめ』では、学校の対応について、万引き記録の際に名前を取り違えたことなど情報管理の不徹底▽1年時の触法行為のみによる機械的な進路決定▽触法行為があれば推薦しない範囲を『3年』から『1~3年』に広げたことを説明しなかった▽その変更を3年生にさかのぼって適用したことなどを要改善事項としてあげた。」
坂元弘校長の判断で決めた事。文科省が要改善事項とした以上、高杉良知府中町教育長は坂元弘校長に処分を出すべきだ。退職金はフルで支払うのか?
高杉良知府中町教育長は文科省の判断に関係なく坂元弘校長の判断は妥当であると思うのか?
広島中3自殺担任名前も嘘後から後から嘘発覚、全部嘘。嘘つき学校 03/19/16(news鹿)

広島府中町中3自殺で嘘バレたサーバーに訂正済み生徒資料、担任の篠永美代子廊下で進路指導 03/09/16(news鹿)
広島の中3自殺、文科省が学校側の問題点指摘 中間報告 03/25/16(朝日新聞)
高浜行人
広島県府中町の町立中学校3年の男子生徒が、誤った万引き記録に基づく進路指導を受けた後に自殺した問題で、対策を検討してきた文部科学省は25日、学校側の課題を公表した。男子生徒の1年時の万引き記録だけで推薦を認めなかったことなどを問題視している。この日、全国の学校に対し、適切な進路指導ができているか確認を求める通知を出した。
文科省が公表した「中間とりまとめ」では、学校の対応について、万引き記録の際に名前を取り違えたことなど情報管理の不徹底▽1年時の触法行為のみによる機械的な進路決定▽触法行為があれば推薦しない範囲を「3年」から「1~3年」に広げたことを説明しなかった▽その変更を3年生にさかのぼって適用したことなどを要改善事項としてあげた。
これを踏まえて出した通知では、学校や教育委員会に対し、記録の確認を徹底することや進路指導の説明責任を果たすことなど、6項目について確認するよう求めている。
文科省は今後も再発防止策などについて議論を続け、夏をめどに、どんな推薦基準が適切かなどについて結論を出すという。(高浜行人)
処分が甘い!この甘い処分が将来の不祥事に対する前例となる。
32年間無免許で指導、県教委が関係者8人処分 03/25/16(読売新聞)
山形県の県立高校で、教員免許を取得していない女性(55)が32年間指導していた問題で、県教育委員会は25日、教育長ら関係者8人を減給などの処分にした。
女性は問題発覚後、採用された1984年4月まで遡って任用を無効とされている。県教委は給与返還は求めないものの、教育職員免許法違反で告訴することを検討している。
県教委によると、2014年度に県内の公立校で一斉に実施した教員免許の確認が不十分だったとして、女性が当時勤務していた高校の教頭を減給10分の1(1か月)、菅野滋教育長ら6人を厳重注意。08年度に教員免許の番号を確認した際に十分点検しなかったとして、当時の校長を戒告とした。菅野教育長は給与の10分の1(1か月)を自主返納する。
ソフトランディングの幕引きだ!
「懲戒処分も検討しているが、『過去の事例などに照らすと難しい』との声が内部で出ており、見送られる公算が大きい。」
市民や国民からの批判が多く、懲戒処分を出したくは無いが、出す事も検討しなくてはならないので
寺井寿男校長と裏取引をしたのでは?
「校長は昨年度末に定年退職し、今年度は1年間の任期で再任用された。来年度も再任用の継続を希望していたというが、問題発覚後、『電話対応などで教員らが忙殺され、業務を停滞させた責任を感じた』などとして、市教委に進退伺を出していた。」
メディアに取上げられれば批判されるのは想定できたはず!しかしテレビで流されたある対応。想定できなかったのであれば、愚かな人物であったと判断出来る。
広島中3自殺事案で中間まとめ 情報共有・管理の不備指摘 03/25/16(教育新聞)
広島県府中町立府中緑ケ丘中学校3年生の男子生徒(当時15歳)が誤った万引記録に基づく進路指導を受けた後に自殺した問題について、文科省のタスクフォース(TF)が3月25日、新学期を直前にして早急な対応に向けた方向性を示した中間まとめを公表した。進路指導の情報共有・管理方法に関しての課題や「推薦・専願基準」の見直しなどが盛り込まれた。また同日、各中学校で生徒指導などの在り方について確認するよう、全国の教委に通知を発出した。
中間まとめでは、情報共有・管理の不備によって最悪の事態が起きたと強調した。
「生徒指導推進委員会でミスが発覚し、何度も訂正の機会があった」として情報管理が不徹底であったと非難した。万引の事実に学校と保護者、生徒の三者間で速やかに確認や事後指導が行われなかったとも指摘した。
この事案では、生徒の人生を決める進路指導が廊下でなされていた。こうした事実を踏まえ、進路指導の体制を整えるよう早急に措置を講ずるべきだとした。
「推薦・専願基準」の見直しも求めた。
触法行為だけをもって機械的に判断するべきでないとした。同校では、1年生から3年生までの間に起きた触法行為があった場合には、専願・推薦を認めないような基準であった。
このほか生徒指導などの重要会議に、校長が欠席していた。これについても言及した。
会議終了後、TFの座長を務める義家弘介副大臣が26日、府中町教委に出向くと表明した。
副大臣は「中間まとめを直接もっていく。今後は第三者委員会が立ち上がる。文科省としてできる限りのサポートをしていきたい」と語った。
<「2人以上出産」発言>校長、退職へ…大阪市教委方針 03/25/16(毎日新聞)
大阪市立中学校の男性校長(61)が2月末の全校集会で「女性にとって最も大切なことは子どもを2人以上産むこと」と発言するなどした問題で、市教委は校長を3月末で退職させる方針を固めた。懲戒処分も検討しているが、「過去の事例などに照らすと難しい」との声が内部で出ており、見送られる公算が大きい。
校長は昨年度末に定年退職し、今年度は1年間の任期で再任用された。来年度も再任用の継続を希望していたというが、問題発覚後、「電話対応などで教員らが忙殺され、業務を停滞させた責任を感じた」などとして、市教委に進退伺を出していた。【大久保昂】
「市教委は昨年9月に生徒の保護者から相談を受けるまで、この問題を知らなかった。」
校長が隠蔽したのか?校長まで問題が上がっていなかったのか?この違いを明確にするだけで問題がもっと明らかになる。
メディアは詳細を調べて記事にしてほしい。
「吐き気ぐらいで授業抜けるのか」白血病生徒に教師暴言 03/24/16(朝日新聞)
小北清人
神奈川県藤沢市の市立中学校で、白血病を患っている2年生の男子生徒に対し、教師が健康状態に関する暴言を吐いたとして、生徒が授業のボイコットを続けていることがわかった。23日に開かれた市議会で明らかになった。市教育委員会は生徒が大きなショックを受けたことについて、「認識が欠けていた」と陳謝した。
神村健太郎議員(自由松風会)が質問した。生徒は昨年4月、授業中に体調不良から保健室に行きたいと申し出たが、教師は「吐き気ぐらいで授業を抜けるのか」と返答したという。生徒は泣き出し、翌日から約2週間登校せず、通学するようになってからも、その教師の授業だけは受けずにいるという。市教委は昨年9月に生徒の保護者から相談を受けるまで、この問題を知らなかった。(小北清人)
「市教委の吉住潤教育部長は取材に対し、『教諭は生徒の病気について知ってはいたが、新年度が始まったばかりで、丁寧な対応ができなかった』と述べた。度替わりの4月に向け、『教諭間の引き継ぎをしっかり行い、各生徒の事情を学校全体で共有するよう指導する』としている。」
言い訳としか聞こえない。「引き継ぎ」と言えば、府中町の中3自殺の間接な原因だ。
公務員はしっかりするべきだ。
授業中、難病生徒に保健室行き許可せず…市立中 03/24/16(読売新聞)
神奈川県藤沢市立中学校で昨年4月、難病の治療中の生徒が授業中に「気分が悪くなった」と訴えた際、男性教諭が保健室に行く許可を出さなかったことが分かった。
同市教委が23日、市議会予算特別委員会で明らかにした。生徒は「自分の病気について理解されていない」とショックを受け、その後、約2週間欠席したという。吉田早苗教育長は「配慮に欠ける対応で、生徒を傷つけた」と謝罪した。
市教委によると、生徒は病気の影響で疲れやすいため、「保健室に行きたい」と申し出たが、教諭は「大事な授業なので、我慢できないか」などと応じたという。生徒は、机に体を預けるように伏せてしまい、授業が受けられなくなった。市教委は「難病を抱える生徒なので、すぐ保健室で休ませるべきだった」と、対応の誤りを認めた。
市教委の吉住潤教育部長は取材に対し、「教諭は生徒の病気について知ってはいたが、新年度が始まったばかりで、丁寧な対応ができなかった」と述べた。年度替わりの4月に向け、「教諭間の引き継ぎをしっかり行い、各生徒の事情を学校全体で共有するよう指導する」としている。
体調不良の訴え認めず 闘病中生徒に我慢強いる 03/24/16(カナロコ by 神奈川新聞)
藤沢市立中学校で2015年4月、白血病で投薬治療中の2年の男子生徒が英語の授業中に体調の悪化を訴えたにもかかわらず、50代の男性教諭が「吐き気ぐらいで大事な授業を抜けるのか」などと述べ、我慢を強いていたことが23日、分かった。生徒は心理的な重圧を理由に2週間にわたり登校できない状況になり、同市教育委員会の吉田早苗教育長は「配慮が足りなかった」と陳謝した。
市教委などによると、生徒は入学直前の14年3月に白血病と診断された。抗がん剤治療などを受けて15年2月に退院、3月から投薬治療を受けながら通学を始めたが、体調がすぐれない日もあった。
問題の対応は2年に進級後の4月中旬で、体調が悪化し保健室に行きたいと申し出た生徒に対し、同教諭は「大事な授業を抜けるのか」「後にしなさい」などと述べた。戸惑った生徒は涙を流しつつ、我慢して最後まで授業を受け続けた。
生徒は翌日から学校に通えなくなり、食事も固形物がのどを通らなくなった。生徒の病状は校内で情報共有を図ってきたが、同教諭は市教委の調査に「生徒と病状のことが頭の中ですぐに結びつかなかった」などと回答したという。
市議会予算特別委員会で、神村健太郎氏(自由松風会)の質問に市教委が答えた。
「平成11年 6月29日 県立学校長,市町村教育委員会に「教職員研修について」(通知)を出し,職員団体との話し合いにより進めてきた県教育委員会としての姿勢を見直し,任命権者としての権限と責任において適正に実施することを明確にする。・・・
10月19日 小中学校の学校運営等(主任等の任命・適格性・機能等の状況,職員会議の状況,教職員の勤務管理について,確認書等の状況等)に関するヒアリングの結果,及び高教組役員の授業時間数について公表する。」
国歌斉唱を適正に取扱わなかった県立学校長の件で今回の生徒の自殺とは関係ないが、市町村教育委員会の教職員研修の内容が適切で、適切に行われ、主任等の任命・適格性・機能等の状況,職員会議の状況,教職員の勤務管理について市町村教育委員会が定期的にチェックしていれば今回の問題は発見できたと思う。
文部省是正指導に関する経緯について(平成11年度の状況)(広島県ホームページ)
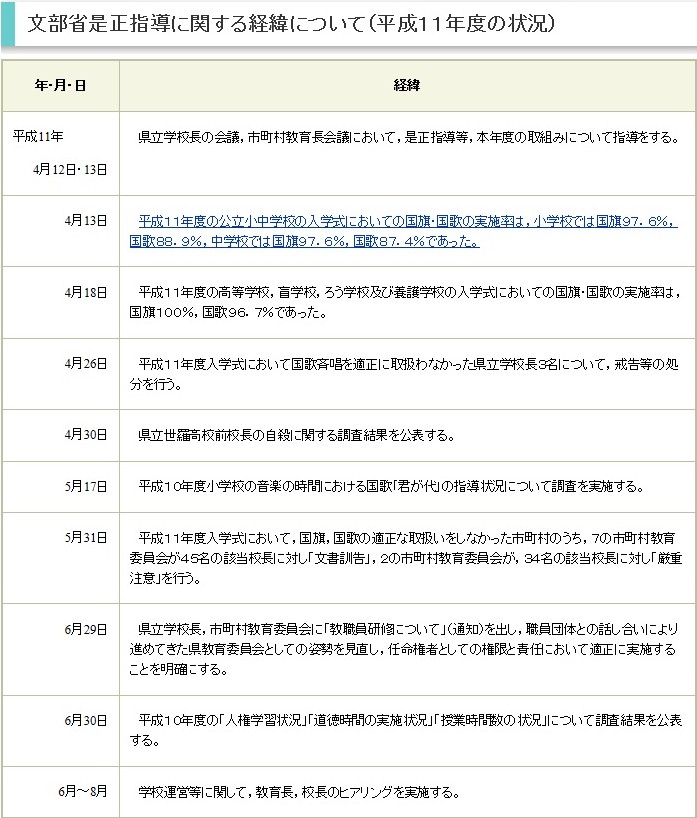
「報告書での2人のやりとりは、担任の記憶のみに基づいた口頭での聞き取りによるものだったことが判明。坂元弘校長は『正確な記録に基づいておらず、身内への甘い調査だと言われても致し方がない』と報告書の不備を認めた。」
「正確な記録に基づいておらず、身内への甘い調査だと言われても致し方がない」
致し方ないではなく、その通り。身内への甘い調査と言い直せと思う。調査で、証拠やサポートする資料や根拠が得られない場合、その趣旨を記載するべきである。もし、坂元弘校長が報告書でそのような記載の書き方を知らなかった、又は、中立的な調査報告書の作成の仕方を知らなかったのであれば、今月の3月に退職するようだが、校長として経験不足そして能力不足であったと判断する。そして、府中町教育委員会が校長の任命及び評価に関して問題がある事が疑われる。
もし坂元弘校長が故意に証拠やサポートする資料や根拠が提出できるのか確認せずに報告書を作成したのであれば、坂元弘校長は校長としてだけではなく、人間としても尊敬に値しない人物であると推測できる。
メディアは下記のサイトの情報が事実が記事で公表してほしい。
広島中3自殺担任名前も嘘後から後から嘘発覚、全部嘘。嘘つき学校 03/19/16(news鹿)

広島府中町中3自殺で嘘バレたサーバーに訂正済み生徒資料、担任の篠永美代子廊下で進路指導 03/09/16(news鹿)
<府中町の中3自殺>進路指導、記録残さず 担任、記憶のみで調査報告書 /広島 03/19/16(毎日新聞)
府中町立府中緑ケ丘中3年の男子生徒(当時15歳)が誤った万引き記録に基づく進路指導を受けた後に自殺した問題で、生徒との進路指導上のやりとりを女性担任がメモなどの記録に残していなかったことが18日、わかった。学校側が調査報告書の内容を再調査したところ、報告書での2人のやりとりは、担任の記憶のみに基づいた口頭での聞き取りによるものだったことが判明。坂元弘校長は「正確な記録に基づいておらず、身内への甘い調査だと言われても致し方がない」と報告書の不備を認めた。
同校によると、進路指導の際には、生徒との面談内容を教員自身がメモに残すのが通常だったが、担任はこうした作業を怠っていたという。さらに学校側も生徒の自殺後の調査を担任への口頭の聞き取りのみで行っており、担任が生徒との面談内容をメモに残しているかも把握していなかった。これらの調査内容は2月29日付で報告書としてまとめられ、遺族に提出された。
遺族の代理人弁護士によると、生徒の両親は報告書に記された担任と生徒のやりとりが正確なのか、以前から疑念を抱いていたという。代理人は「生徒が亡くなり、担任の一方的な記憶のみによる報告を信じること自体に無理がある。せめて担任が他の生徒にどんな進路指導をしていたのか情報が開示されなければ、信ぴょう性の議論は水掛け論になる」と指摘している。【石川将来】
坂元弘校長の単独の対応なのか、高杉良知府中町教育長と話し合っての対応なのか、時間稼ぎが上手いな!情報を小出しに出しながら時間稼ぎをしている。「学校側は記憶に頼った調査には限界がある」については担任と面談した時に判明しているはずである。人間的には信頼も信用も出来ない人間のように思えるが、汚れ役や後始末の役には適任かもしれない。護士などを入れた第三者委員会の設置の時間稼ぎは府中町教育委員会がナイスフォローの時間稼ぎに成功している。
これが教育現場の実態であれば、良くなるはずがない。
「誤った万引き記録」で中3自殺 第三者委設置へ 03/19/16(テレ朝NEWS)
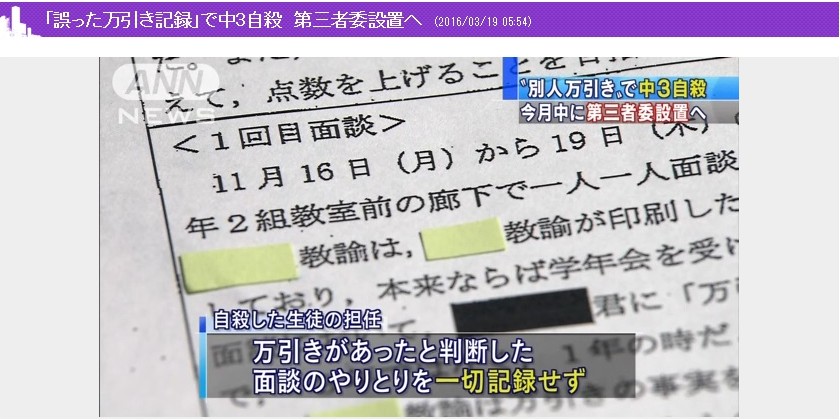

広島県の中学校で誤った万引き記録による進路指導の後に生徒が自殺した問題で、学校は保護者会を開き、今後の調査を第三者委員会に委ねたいと説明しました。
18日夜に開かれた2回目の保護者説明会で、学校側は指導と自殺との因果関係を認め、来年度から組織的に指導を行う「進路指導部」を設置するなどの改善策を説明しました。
保護者:「学校からの回答に対して納得がいかないという部分も結構あった」
学校は先月に報告書をまとめましたが、万引きがあったと判断した面談のやり取りを担任が一切、記録していないなど、ずさんな対応が次々と明らかになっています。学校側は記憶に頼った調査には限界があるとして、今後の調査は弁護士などを入れた第三者委員会に委ねたいと説明しました。今月中の設置を目指しています。
昔、仕事で事実と報告書が違っていたので、問合せた事がある。担当の言い訳は、メモや記録をとらずに事務所に帰って報告書を作成したので、覚え違いで報告書に間違いが起こったとの事だった。
嘘を付いているのか、単に仕事が出来ない人間なのかと言う事になる。嘘を付いていると個人的に思ったが、確認する事が出来ないので再発防止を要求した。
嘘か事実なのか確認出来ないのでこのように嘘であっても逃げる事も出来る。時間をかけて、もっと突っ込んで調べれば嘘なのか、事実なのか、確信の持てる推測まで
到達できるかもしれない。しかしそこまでする理由も時間もなかった。
広島・中3自殺の件では、直接的な問題ではないが組織的に多くの問題があることがいろいろな事実を通して明らかになっている。しかしながら、坂元弘校長や高杉良知府中町教育長の対応を見ていると幕引きと時間稼ぎに全力を注いでいるとしか思えない。これまでも他の地域で上手く幕引き出来たケースが多いから、同じようにしているのであろう。もういい加減に見逃すべきではないと思う。
嘘を付く人間は、辻褄を合わせるためにさらなる嘘を付く。事実を付き合わせ、パズルのような作業を行うと嘘がさらなる嘘の発見の手がかりになる。
面談メモ、存在せず 担任記憶で報告書 広島・中3自殺 03/18/16(朝日新聞)
泉田洋平、根津弥
広島県府中町の町立府中緑ケ丘中学校3年の男子生徒(当時15)が自殺した問題で、学校が調査報告書に記した生徒と担任教諭の5回にわたる面談のやりとりは、担任による面談時のメモが根拠とされていたが、メモは存在していなかったことがわかった。17日、坂元弘校長が明らかにした。すべて担任の記憶のみに依拠して作成されたことになり、報告書の信用性が問われそうだ。
担任と男子生徒は、昨年11月中旬から自殺当日の12月8日まで5回、進路について面談。学校が今年2月にまとめた報告書は、1回目の面談で担任が「万引きがありますね」「3年ではなく、1年の時だよ」と問うと、男子生徒は「あっ、はい」と答えたと記す。その後の面談も具体的な会話を交えて記している。
担任は一連のやりとりで男子生徒から万引きを否定する発言がなかったとして、1年時に万引きをしたとする誤った記録の確認ができたと誤認した、としている。
これは公務員が良く使うス
忍法モークスクリーン(英和辞典 Weblio辞書)ではないのか?
「坂元弘校長は会見で『進路指導が組織的計画的に行われていなかった』として、一元的に担当する『進路指導部』を来年度から設けると話した。」
メモを取って入力する。担当を決めておく。間違いを指摘されたら、直ぐに修正する。メモや記録を取る。確認の方法を確立する。引継ぎの手順を作成し、実行する。教諭が理解し実行しているか定期的にチェックするだけで問題は起きないし、防止効果がある。これは単に進路指導だけでなく、多くの項目で応用が可能である。
しかし、「進路指導部」の設立に絞ると、設立したら終わり。他の問題の対応や改善は放置出来るし、焦点に含まれないのでこれまで通りに出来る。次に他の問題が起きた時は、「進路指導部」意外に関しては指示や改善策は含まれて入ないなかった、又は、そこまで配慮が足りなかったと言い訳できる。
だからこれは公務員が良く使うス忍法モークスクリーン(英和辞典 Weblio辞書)
だと思う。つまり戦争で敵の視界を狭くして、相手を戦略的に騙して壊滅させるために使用する煙幕と同じで、批判をかわすために焦点や問題の原因究明から国民の目を逸らす高等手段。ずる賢い公務員が使うやり方。つまり、府中町教育委員会はずる賢い組織であるか、対応能力が不足していると考える事が出来る。
自分の子供が自殺したわけではないからこの程度の批判で済ますことが出来るが、府中町教育委員会や坂元弘校長の対応はテレビや新聞を見ていると気分が悪くなる。
坂元弘校長は今月末で退職なので、一日が終わる度にカレンダーに×でも付けて退職の日を待ちわびているのではないだろうか?
進路指導態勢を見直しへ 中3自殺、三者委は年度内 03/18/16(朝日新聞)
広島県府中町立府中緑ケ丘中の3年男子生徒=当時(15)=が昨年12月、1年生の時に万引をしたという誤った記録に基づいて進路指導を受けた後に自殺した問題で、同校が18日夜、2回目の保護者説明会を開き、進路指導態勢を見直す考えを説明した。
説明会後、記者会見した同町教育委員会の高杉良知教育長は問題を検証するための第三者委員会の設置について「年度内に立ち上げたいと思っており、日程調整を進めている」と述べた。
坂元弘校長は会見で「進路指導が組織的計画的に行われていなかった」として、一元的に担当する「進路指導部」を来年度から設けると話した。
担任は初回に続き欠席 保護者らに深まる不信感 2度目の説明会 03/18/16(産経新聞)
昨年12月、3年の男子生徒=当時(15)=が誤った万引記録による進路指導を受けた後に自殺した広島県府中町の町立中で18日夜、問題発覚後2回目となる保護者説明会が開かれ、出席した保護者からは学校への不満や全容解明を求める声が相次いだ。
午後6時半から始まった説明会は、予定より1時間遅れの同9時ごろに終了。出席者は生徒の遺族も含め初回の半数ほどの約240人だった。出席者によると、校長らは「生徒の命を無駄にしないことを約束します」などと話したという。
学校側が進路指導の不手際を保護者に明らかにして以降、学校の調査報告書や説明会の開催時期などをめぐり、遺族が不信感を募らせる実情が浮き彫りになっている。この日も学校運営の改善策を説明したという。
ただ、自殺した生徒の担任は初回に続いて欠席し、不満の声も漏れた。3年生の父親は「当事者が直接話さなければ信頼回復につながらない」と話した。
広島の中3自殺 外された信頼のはしご 03/18/16(東京新聞)
子どもと向き合うとはどういう意味か。広島県の中学三年生が自らの命を犠牲にして投げかけた重い問いではなかろうか。学校はもちろん、親たちもよく考えてみたい。悲劇を繰り返さないために。
府中町立中学校の男子生徒が自殺したのは昨年十二月。
一年時に万引したとのぬれぎぬを着せられたうえ、その誤った記録を理由に、志望する私立高校には推薦できないと担任の先生から伝えられていた。
万引したのは他の生徒だった。なのに、パソコンには誤って男子生徒の名前が入力されていた。生徒指導の会議では人違いと指摘されながら元データは修正されず、そのまま進路指導に利用されたという。学校の調査結果である。
子どもの将来を左右しかねない重大情報が、かくも乱暴に取り扱われていた実態に言葉を失う。管理責任者さえはっきりせず、人権意識の希薄さが強く疑われる。
なぜ学校は取り返しのつかないミスを重ねたのか。
職場の多忙や風通しの悪さも浮かぶが、それ以前に、子どもへの無条件の信頼や愛情が欠けていたのではないかと考える。成長を喜び、支えるという血の通った教育が見失われていた、と。
昨年十一月、学校は私立高受験の推薦基準を厳しくした。万引などの触法行為があれば推薦しないとする期間を、三年時のみから一年時からの三年間にまで広げたのだ。不幸にも、男子生徒は対象者にふくまれてしまった。
失敗しながら成長するのが人間だろう。ましてや、多感な中学生である。秩序の維持ばかりを重んじ、未熟な生徒を導くどころか切り捨てる。そうした負の評価を優先する風土があったとすれば、およそ学びの場とは呼べまい。
男子生徒がなによりも深く傷ついたのは、万引記録は“冤罪(えんざい)”であると、担任がとうとう信じてくれなかったことではないか。教育現場にはそう見る向きもある。
精神的なよりどころとする相手に裏切られたと感じたとき、子どもは強烈なショックを受ける。「どうせ言っても、先生は聞いてくれない」と、生前、親に打ち明けた言葉には悔しさや諦めがにじんでいるようだ。
生身の子どもは日々変わる。蓄積された記録は成績であれ、非行歴であれ、過去の一部でしかない。教育の足場は常に現在に置かれるべきである。全国の学校で、家庭で、目の前の子どもをあらためて見つめ直したい。
「さらに、同校では私立高校の推薦基準は昨年11月20日、対象とする非行歴を『3年時のみ』から『1~3年時を通して』に急きょ変えている。
なぜ、誰が、突然に推薦基準を変更したのか。坂元校長は『私が判断しました』と打ち明ける。
『3年時だけでいいのか、1年時まで遡るべきか、学年で意見が分かれて、ずっと協議しておったんですね。しかし、3年生になって急によくなった生徒だけを評価するのではなく、1年時から地道にまじめにやってきた子もいるので、やっぱりそちらにしたいと私が判断したわけです』」
生徒に厳しく、身内に甘い。こんな自分勝手で横暴な坂元弘校長に対して、高杉良知府中町教育長は事実を把握していたのか?これまでの記事を読むと教諭達に対する管理は甘いと思える。
坂元弘校長は退職しても管理責任者として十字架を背負って生きていくのか?このような人間に限ってその場限りのパフォーマンスの場合が多い。
中3万引き自殺、尾木ママ「かなり汚い校長と教育委員会」 03/16/16( 週刊女性PRIME)

坂元校長は報道陣の質問に淡々と答えるだけ(11日夕方)
広島県府中町の町立府中緑ケ丘中学校で、3年生の男子生徒が自殺した事件。事実とは異なる万引き記録をもとに、学校側が私立高校の専願を拒否した後に自殺したため、大きな問題になっている。
さらに、同校では私立高校の推薦基準は昨年11月20日、対象とする非行歴を「3年時のみ」から「1~3年時を通して」に急きょ変えている。
なぜ、誰が、突然に推薦基準を変更したのか。坂元校長は「私が判断しました」と打ち明ける。
「3年時だけでいいのか、1年時まで遡るべきか、学年で意見が分かれて、ずっと協議しておったんですね。しかし、3年生になって急によくなった生徒だけを評価するのではなく、1年時から地道にまじめにやってきた子もいるので、やっぱりそちらにしたいと私が判断したわけです」
町教委によると、推薦基準は各学校長が定めるもので、教委への報告義務はないという。坂元校長は「他校の基準は知りません」と話しており、受験する生徒の立場で考えれば公平性に欠ける。
Aくんは、どうして身に覚えのない万引きをきっぱり否定しなかったのか。
「うーん、それが私も不思議なんです。学力も高く、自分の意思をはっきり言う子ですからね。なぜ否定しなかったのかがねぇ。あとは第三者委員会の調査にお任せするしかない」(坂元校長)
淡々と他人事のように述べるだけだった。Aくんは家庭で「どうせ言っても先生は聞いてくれない」などと話していたという。
Aくん宅を訪ねると、母親がインターホン越しに「何もお話しすることはありません。いまは余裕がまったくありませんので」と答えた。
在校生らによると、Aくんはスラッとした長身で、陸上部の長距離ランナーだった。家族仲もよかったという。
「Aくんは物静かで男前。優しい性格だったから、反論するのを諦めちゃったのかもしれない。人違いだと言い返せなかったのかもしれません」(近所の主婦)
もしAくんが否定していたら、“真犯人”の同級生は推薦資格を失っていたはずだ。それもまた後味が悪い。
Aくんの遺族は自殺当初、高校受験が近いため同級生が動揺しないよう、しばらくは「急性心不全」で亡くなったことにしてくれるよう学校側に申し入れた。それから3か月。受験を終えて真相を知った同級生は12日に卒業した。
「死人に口なしで、学校側がストーリーをつくっている可能性があると思います。3か月ありましたからね。廊下で立ち話の進路指導なんてしませんよ。しかも5分ですよ。
それで“面談を5回やった”と言い張っている。かなり汚い校長と教育委員会だと思う。生徒の将来を一緒に切り開いていくのが教師の役目なのに、生徒の選別作業をしているみたいじゃないですか」(教育評論家の尾木直樹氏)
真相をウヤムヤにしてはいけない。
取材・文/フリーライター・山嵜信明と週刊女性取材班
one night standそれともfatal attraction?
多摩地域の小学校男性教諭はどのような理由で決断したのだろうか?真剣な愛?やれそうだったから?誘われたから?タイプだったから?
理由が公表してほしいですね!
校外活動で出会った児童母と性行為... 小学校教諭が懲戒免職処分 03/18/16(J-CAST)
東京都教育委員会は2016年3月17日、勤務校に在籍する児童の母親と性行為をしたとして多摩地域の小学校男性教諭(28)を懲戒免職処分とした。各種報道によると、男性教諭は校外活動で母親と出会い、関係を持ったという。
また都教委は同日、15年11月、出勤前に自宅玄関前で下半身を露出させ、公然わいせつ罪で罰金10万円の略式命令を受けた大田区立小学校の男性教諭(25)も合わせて懲戒免職処分とした。
今回の騒動、おもしろい!
たかが校長の地位で個人の自由選択や生き方まで支配しようとしている。寺井校長の価値観を校長としての権限を乱用してまで、人格形成が完了していない子供に
押し付けている。
「寺井校長は今月末で校長の再任用の期限を迎えますが、VOICEのこれまでの取材に不当な処分などを受けた場合徹底抗戦するとしています。」
寺井校長の行為は適切であったと思っているのか?不当な処分とは何か?再任用の条件内容次第であるが、再任用の契約が自動継続でなければ、大阪市教育委員会が
再任用を見送る判断をすれば、徹底抗戦する理由もないと思う。
国民は国のために犠牲にならなければならないのか?日本は民主主義国家なのか?社会主義国家ではないが社会主義に近い国家であるのか?
テレビのインタビューで、寺井校長は子供は2人以上いるのかとの質問に答えなかった。子供には自分の価値観を強要しておいて、子供の数についての質問にはデリケートな事なのでと逃げるような対応。おかしくないか?単なる詭弁家?人によっては視野の狭い考え方の人もいる。しかし、この寺井校長、ずる賢い詭弁家と思える。国語の教師なので少しばかり、言葉の操り方、言葉によるごまかし方は習得しているようだ。いくら言葉で着飾ったり、武装しても、ずるい人はめっきがはげるように問題がところどころに見える。
VOICE 2016年03月14日 『女性は子どもを2人以上産むこと 発言の校長 「問題ない」、「ヘイトスピーチ」条例に新たな問題 ほか』 1080i
寺井寿男の会見内容!娘や家族についての質疑応答とは?仰天校長の実態 [芸能] 03/18/16 (壷中天)
「女性は2人以上産むこと」発言校長に辞職求める方針 03/18/16(毎日放送)
「女性に最も大切なのは子どもを2人以上産むこと」などの発言をした大阪市立中学の校長に対し市の教育委員会は辞職を求める方針であることがVOICEの取材でわかりました。
「(女性は2人産むべきと話してきた?)もちろんです。二人産まないとあなたの年金が8分の1になるんですよ」(大阪市立茨田北中学校 寺井壽男校長)
中学校の全校集会で「女性に最も大切なのは子どもを2人以上産むこと」などと発言していた大阪市立茨田北中学の寺井壽男校長(61)。
関係者によりますと一連の言動を問題視した市の教育委員会が寺井校長に対して辞職を勧告する方針であることがわかりました。
市教委は今月14日に寺井校長を呼び出し発言が不適切だとし処分する方針をすでに伝えています。
寺井校長は今月末で校長の再任用の期限を迎えますが、VOICEのこれまでの取材に不当な処分などを受けた場合徹底抗戦するとしています。
女は子供産めの寺井校長「独演会見」教科書や黒板使ってわが教育論を授業 03/16/16(毎日放送)
全校集会の講話で「女性はキャリア積むより子供を2人以上産むことが大切」と話して、大阪市教育委員会から「不適切」とされた大阪市立茨田北中学校の寺井寿男校長(61)は15日(2016年3月)に会見して、批判に真っ向から反論した。黒板や教科書を使って、まるで授業風の熱弁で、記者たちは生徒扱いだった。
校長先生は子供は2人以上いるのですか?「家族のことはちょっと・・・」
会見では、始まる前から「空いてる先生呼んで、見に来いと。勉強になるから。どうやってしゃべったらいいか参考になる」と自信たっぷりに上から目線だった。ネットでの批判に「人物が特定できないのに謝罪は不可能。職務命令といえどもできないと(教委に)申し上げた」と開き直り、「卒業式での子供たちの目は澄んでいた。疑惑の目は1人もいなかった」と語った。
さらに、国語教科書の太宰治の「走れメロス」を広げて、「メロスが王城にたった1人で乗り込むように、私はたった1人で市役所に乗り込みます」とまるで英雄気取りだ。
記者から「発言は不適切だと思わないのか?」と問われても、「シリーズで話してますから、そこだけ切り取られたら言葉足らずと言われても仕方ないが、言葉は尽くしています」。全校集会で講話は年に30回ほど行うという。
もともと国語の教師で、3年前に校長になった。去年3月に定年退職となったが、4月に再任用で学校に残った。会見でも自らを「くせのある教師、教頭、校長である」と言い、独自の教育論をぶち、黒板に漢字を大書して見せたりした。しびれを切らした記者が「授業はあとどれくらい?」と皮肉る場面もあった。
「子育てが大事」「そのためには産むこと」「大変な価値のあることです」と一方的に語り、「子供はいますか。2人以上ですか」と質問されると、「ちょっと、家族のことはデリケートなので」と逃げた。
「男子生徒の同級生らは既に卒業し、坂元弘校長も3月末で定年退職する。・・・手続きでミスも起きている。町教委は3月上旬から4団体に委員の選定を電話で依頼し、広島弁護士会からは『正式文書で依頼してほしい』と頼まれたのに送付していなかった。」
うっかりミスを装った逃げ切り作戦ではないのか?坂元弘校長は3月末で定年退職は知っているので、3月末までに事実確認がはっきりしないようにのらりくらりとしていれば退職して、退職金を受け取る事が出来る。結果が出るまで退職金を受け取りの保留を提案出来るが、法的には処分を受ける前に退職してしまえば、退職金を受け取ることが出来るはず。
町教委は故意に選定作業を遅らしたとしても、故意である証拠は内部告発者がいない限り公になる事はない。逃げ切り作戦、大成功と言ったところであろうか?
府中町教育委員会及びその管轄の学校教諭に対する信頼や信用は地に落ちたであろう。子供達も内心、こんな教師が善人ずらしてと心の中で軽蔑するかもしれない。一部の人達のずるさがまともな教諭に対しても不信感や疑念を抱かせる結果となるかもしれない。まあ、今回の事件で教育委員会や学校に不信感を抱いた生徒がいれば、少なくとも教師など目指さなくて良いと思う。どこかでメスが入らないと組織は変わらない。
広島・中3自殺 真相究明難航も 第三者委設置遅れる 03/17/16(毎日新聞)
広島県府中町立府中緑ケ丘中3年の男子生徒が自殺した問題で、町教育委員会が設ける第三者委員会の設置作業が遅れている。第三者委設置のための要綱づくりを優先させたり、自殺の公表を生徒の死から3カ月後にしたため、第三者委メンバーの選定を外部団体に依頼するのが遅れたりしたからだ。男子生徒の同級生らは既に卒業し、坂元弘校長も3月末で定年退職する。教職員の人事異動も控えており、自殺の真相究明は難航が予想される。【石川将来、山田尚弘】
文部科学省は指針で「組織立ち上げには時間を要する」ため平時から体制づくりに努めるよう求めている。町教委は自殺直後から、原因究明と再発防止策を検討する第三者委の設置が必要と考えたが、事前準備を怠っていたため第三者委設置の要綱がなく、急きょ、作成作業を始めてさらに手間取った。町教委は準備不足を認めながらも、「人選方法や任期などについてルール化しておけば、後に理解が得られると判断した」と釈明している。
要綱作成に着手したのは、自殺から約1カ月後の今年1月中旬で、完成は2月9日だった。町教委は「学校が行う調査を支援するのに時間がかかった。並行して第三者委の準備も進めるべきだった」としている。
第三者委メンバーの選定を外部に依頼する手続きも滞った。町教委は「生徒への動揺を避ける」「遺族の意向がある」などを理由に、公立高入試が終わる今月8日に自殺を公表する考えだったからだ。
手続きでミスも起きている。町教委は3月上旬から4団体に委員の選定を電話で依頼し、広島弁護士会からは「正式文書で依頼してほしい」と頼まれたのに送付していなかった。弁護士会は選定作業に着手できなかった。同級生に行うアンケートも自殺から約3カ月後となり、学校は卒業式2日前の今月10日に用紙を配布し、翌日回収するという性急な調査となった。
文科省は特別チームを設けて学校の進路指導に問題がなかったか検証しており、今月中に中間報告を取りまとめる。担当者は「全国的に指導する必要があるか見極めたい」としている。
学校事故に詳しい喜多明人・早稲田大教授(教育法)は「自殺公表の遅れが第三者委の設置遅れにつながった。今回のような事案は初動調査が重要で、遺族の意向などを理由に隠し続けたのは、行政の責任の取り方としてふさわしくない」と指摘する。
府中町立府中緑ケ丘中学校の坂元弘校長をはじめ、府中町立府中緑ケ丘中学校は恥ずかしい教諭ばかりだ。
「学校側は『自分の思いが言えない生徒がいるとは考えていなかった』と釈明したが、生徒の思いにあまりに配慮にかける構図ができあがっていた。」はいろいろな問題を隠すための言い訳。
府中町教育委員会の管轄の教諭の多くは無責任な人間の集団とも判断できる。自己中心的な考え方をする人間は人格の一部となっている。同じ事を同じような状況で繰り返す。
「『それぞれが目の前のことに精いっぱいだった』(町教委)ために引き継ぎを怠り、ソフトを使える教諭がいなかったことを理由に、進路指導は先送りされた。」
先送りは誰の判断だったのか?引継ぎの教諭は決まっていたのか?決まっていなかったのであれば、誰が引継ぎを決める権限を持っていたのか?常識で考えて、ソフトが使えないと進路指導に影響する事が考えなかったのか?
「平成25年10月に実際に起きた万引について、対応した教諭から口頭で報告を受けた生徒指導部の担当教諭が作成した。
その際、誤って自殺した生徒の名を入力したのが最初のミスとなった。」(03/14/16 産経新聞)
この学校の体質は問題だらけだ。教諭や管理職である校長が問題を放置すると後で問題が大きくなる事を理解していない。府中町教育委員会の管轄の教諭達はこのような腐った組織に慣れきっているので問題とも考えないのだろうか。
経営者の放漫経営による倒産以外で倒産した会社の社員と何度か話す機会があるが、倒産した会社の従業員は存続している会社の従業員と比べると倒産する会社の社員だと思うことがあった。問題がある/あったのに人事で対応しない。放置すると後で問題が大きくなり、対応にも多くの時間を取られるのに直ぐに対応しない。言い訳ばかり考えて、問題を処理しようとしない。
今回の件に関する記事を読んでいて似ていると思った。公務員は自治体が破綻しない限り職を失わないし、給料は下がらない。だからと言って、今回のような怠慢が許されるのか?
府中町教育委員会は管轄の学校を訪問したりして、学校の管理状態をチェックはしないのか?しているのだとしたら事前に訪問を連絡して馴れ合いの形だけのチェックだったのか?この学校の問題は氷山の一角だと思う。安易に自殺する事は良くないと批判している人達もいるが、自殺しないとこれぐらいの問題は見逃され、隠ぺいされ、適当な言い訳で幕引きになっていたのではないのか?学校による自浄能力又は府中町教育委員会の介入により、この学校の問題が事前に発見され、改善されたと思うのか?
坂元弘校長のテレビでの対応や新聞記事を見ていると、隠ぺいや早期の幕引きが強く感じられる。
進路面談、例年より半年遅れで実施 背景に引き継ぎミスや怠慢 03/15/16(産経新聞)
広島県府中町の中学3年の男子生徒=当時(15)=が昨年12月、誤った万引記録による進路指導を受けた後に自殺した問題で、今年度は同11月に実施された進路に関する面談が、例年は半年前の5月に行われていたことが15日、同校への取材で分かった。遅れた背景には教諭間の引き継ぎミスや怠慢などがあり、短期間の面談で推薦の可否を判断するという無計画な進路指導につながっていた。
同校の調査報告書などによると、同校では従来、推薦受験できる高校を判断するため、生徒の成績を入力するコンピューターソフトを使用。結果をもとに5月には生徒との面談を行い、推薦の可否の見通しを伝えていた。だが今年度は、ソフトを使用できる担当教員が他校に異動。「それぞれが目の前のことに精いっぱいだった」(町教委)ために引き継ぎを怠り、ソフトを使える教諭がいなかったことを理由に、進路指導は先送りされた。
また、時間に余裕があったはずの夏休みになっても、進学先の高校に関する資料集めは進まなかった。「担当教諭に資料を作らなければという意識はあったが、どうしてよいのか分からない状況になっていた」(報告書)といい、この作業も2学期に持ち越された。さらに9~10月は、来校する高校の対応に追われたため、進路指導の作業が具体化していなかったという。
そのため、学校が推薦の可否に関わる重要な面談を始めたのは、例年の半年遅れの11月16日。男子生徒の担任は12月8日までの5回の面談で受けた一方的な印象から、誤った万引記録を疑うことなく、希望する私立高校への専願受験はできないと伝え、同日午後、生徒は自宅で自殺した。
府中町立府中緑ケ丘中学校の坂元弘校長をはじめ、府中町立府中緑ケ丘中学校は恥ずかしい教諭ばかりだ。
「学校側は『自分の思いが言えない生徒がいるとは考えていなかった』と釈明したが、生徒の思いにあまりに配慮にかける構図ができあがっていた。」
新米教師の集団じゃないんだから、そんな言い訳を言うなと言いたい。警察の誘導尋問や警察のシナリオによる自白を考えてみれば良い。質問された件について
やっていなくても、それ以外で全く悪い事をしていない限り気が弱い人間は緊張する事を知らないのか?そのような事が事実なら今までどのように学校で仕事をしてきたのか?
「3年の学年主任は各担任に日時などを本人に確認するよう求めたが、担任は、校内の廊下で行った5回の面談で得られたごく短い生徒の発言だけで、具体的な日時などを確認することもなく『確認できた』と思い込んだという。」
担任は記録があるのであれば、一年生の時のいつ、どこで、何を万引きしたのかの記録が残っているが間違っていないかと訊ねたのか?質問の仕方は適切だったのか疑問が残る。たぶん、この担任はこれまでに質問や確認方法について批判や問題の指摘を受けたことが無い、もし、受けたことがあるとすれば指摘されても直さない、又は、直せない教諭の可能性がある。
「担当教諭は修正されないままのデータを基に、触法行為者をリストアップし、生徒の名前も含まれることになった。作成時には、推薦基準を確認する根拠資料として使われるとは、校内の誰もが考えていなかったデータだった。」
推薦基準に使われないから、間違ったデータを残すのか?引継ぎがされなかったら、経緯を知らない人が見れば、触法行為者と判断するとは学校内の誰一人も思わなかったのか?この学校の教諭は生徒の将来を考えていないと思われても仕方が無い。教諭は移動するから少なくとも府中町教育委員会の管轄の教諭の多くは無責任な人間の集団とも判断できる。それとも、管理者である校長の認識が甘いと言うことなのかも知れない。言い訳ばかりの体質が個人的にはおかしいと思う。
「1年時に問題行動を起こし、本来は推薦に手が届かない立場だったという。一転した決定に驚いたが、すべての真相を知るのは今月、一連の問題が発覚してからだった。
『学校は3カ月も真実を隠していた』と生徒。推薦をもらえたことはうれしいが、男子生徒のことを考えると不信感は増す。『やっぱり学校には腹が立つ』と複雑な表情をのぞかせた。」
この学校は問題が大きくならないように学校の方針を変えた汚い学校又は校長だと思う。ずるさや汚さが感じられる。
「自分の思いが言えない生徒がいるとは」…学校側、初歩的「4つのミス」招いた〝人災〟 公表1週間 (1/3)
(2/3)
(3/3) 03/14/16(産経新聞)
広島県府中町の中学3年の男子生徒=当時(15)=が昨年12月、誤った万引記録による進路指導を受けた後に自殺した問題は、公表から14日で1週間。学校側の初歩的な「4つのミス」が、引き金になった「人災」の可能性が高くなっている。事実を誤認した指導で進路志望先の変更を余儀なくされた生徒は、悩みをどこにも打ち明けられないまま命を絶った。学校側は「自分の思いが言えない生徒がいるとは考えていなかった」と釈明したが、生徒の思いにあまりに配慮にかける構図ができあがっていた。
誤入力放置
自殺問題の調査報告書によると、一連の事案の発端となった誤った万引記録は「後に、推薦基準を確認する根拠資料として使われるとは誰も考えていなかった」というデータだった。
平成25年10月に実際に起きた万引について、対応した教諭から口頭で報告を受けた生徒指導部の担当教諭が作成した。
その際、誤って自殺した生徒の名を入力したのが最初のミスとなった。ただ、自殺後の調査でも、教諭の聞き間違いなのか、単なる入力ミスなのかさえ分かっていない。
同月8日の「生徒指導推進委員会」で、誤りが指摘されたが、校内のサーバーに残ったデータは修正されないというミスが続いた。報告書は「データ管理の役割分担が明確になされていなかった」と指摘する。
推薦基準
3つ目のミスは昨年11月、私立高校の専願受験の推薦基準を十分な準備もせずに厳しくしたことだ。推薦できない対象は従来、「3年時の触法行為」だけだったが、入学者の問題行動を嫌う進路先の高校への配慮もあり、「1~3年時」に拡大することを決定。担当教諭は修正されないままのデータを基に、触法行為者をリストアップし、生徒の名前も含まれることになった。作成時には、推薦基準を確認する根拠資料として使われるとは、校内の誰もが考えていなかったデータだった。
思い込み
そして事実確認のずさんさが決定的な最後のミスになった。3年の学年主任は各担任に日時などを本人に確認するよう求めたが、担任は、校内の廊下で行った5回の面談で得られたごく短い生徒の発言だけで、具体的な日時などを確認することもなく「確認できた」と思い込んだという。
担任に確認するよう指示を出した学年主任は「自分の思いが言えない生徒がいるとは考えていなかった」(報告書)と振り返った。
生徒の自殺後の昨年12月、同校は推薦基準を「3年時に触法行為をしていない」に戻した。いったん推薦できないと判断した18人のうち15人の推薦を認めた。
「自分にとって受験は推薦がないと厳しかった。最初はもらえないって言われていたけど、冬休み前に突然、先生から出せるって言われた」と、「救済」された生徒の一人は振り返る。
1年時に問題行動を起こし、本来は推薦に手が届かない立場だったという。一転した決定に驚いたが、すべての真相を知るのは今月、一連の問題が発覚してからだった。
「学校は3カ月も真実を隠していた」と生徒。推薦をもらえたことはうれしいが、男子生徒のことを考えると不信感は増す。「やっぱり学校には腹が立つ」と複雑な表情をのぞかせた。
「広島県府中町立府中緑ケ丘中3年の男子生徒が自殺した問題で、学校が推薦基準の厳格化を決めた当日に進路説明会を開いていたにもかかわらず、生徒や保護者に基準の変更を伝えていなかったことが、学校がまとめた報告書で分かった。年度初めの説明会でも具体的な基準を示さなかったことを理由に挙げ、『大きな違いはないという非常に甘い考えがあった。生徒は悩み苦しむものだという認識と生徒理解の姿勢が欠けていた』と釈明している。 」
学校、校長、そして3年生の担当教諭が生徒や保護者を軽視して、自分達の都合で自分達の権力を行使して傲慢に振舞ってきた事がよくわかる。自分達が間違っていると
言う事さえ気付かず、中3の生徒が自殺して多くの人達が事実を知るまで考えもしないほど、傲慢に振舞って来て外部から指摘をさせない、又は、ブラックボックス化して外部から見えない状態にしていたと言う事だ。
公平や社会性を教える学校で、学校、校長、そして3年生の担当教諭が生徒や保護者を無視して傲慢に振舞って来た背景は問題である。府中町教育委員会はどのように判断するのか?
広島・中3自殺 「推薦基準厳格化」学校側は生徒に伝えず 03/14/16(毎日新聞)
広島県府中町立府中緑ケ丘中3年の男子生徒が自殺した問題で、学校が推薦基準の厳格化を決めた当日に進路説明会を開いていたにもかかわらず、生徒や保護者に基準の変更を伝えていなかったことが、学校がまとめた報告書で分かった。年度初めの説明会でも具体的な基準を示さなかったことを理由に挙げ、「大きな違いはないという非常に甘い考えがあった。生徒は悩み苦しむものだという認識と生徒理解の姿勢が欠けていた」と釈明している。
報告書によると、同校は高校推薦の基準の一つとして「問題行動や触法行為がないこと」と規定。「いつからの問題行動や触法行為が対象になるのか」という具体的な基準は毎年、3年生の担当教諭が検討してきた。
今年度は、昨年5月の第1回進路説明会(保護者会)で、3年生の生徒や保護者に基準を伝えた。一方、同じ頃から3年生の担当教諭は学年会で「いつからを対象にするか」を協議。例年は触法行為などを考慮する年次を「3年生のみ」としてきたが、「1〜3年時」と広げることにし、11月20日午前に開いた校務運営会で正式に決まった。
同校は同日午後、第2回の進路説明会を開いた。だが、例年より対象年次を広げて厳しくした推薦基準は、生徒や保護者には報告されなかった。5月の説明会でも基準の対象年次を伝えていなかったため、従来の基準から変更したことを伝えなくても大差ないと考えたという。
結局、全生徒や保護者に基準変更の説明はされず、推薦できない生徒とその保護者にだけ11月末から12月初めにかけて伝えられた。報告書は「推薦できない生徒以外は関係ないと考えた。1、2年時の触法行為を推薦対象に入れるなら、入学時から全生徒や保護者に伝え、周知する必要があった」としている。【安高晋】
小川洋・聖学院大教授(教育学)の話
学校は推薦基準や基準変更を早く全生徒や保護者に示すべきだ。非行歴の扱いなど「何がどう評価されるのか」が分からないと、生徒や保護者は学校の顔色をうかがって萎縮してしまう。学校は基準をあいまいにすることで、品行を慎ませる思惑があったのではないか。だが、それでは信頼関係は築けない。
本人が死んでいる以上、確認出来ない。それに、これまでの学校の対応を考えると誠実さは感じられない。
担任・生徒のやりとりは事実か…第三者委設置メド立たず、検証作業が難航 (1/2)
(2/2) 03/14/16(産経新聞)
広島県府中町の中3年の男子生徒=当時(15)=が昨年12月、誤った万引記録による進路指導を受けた後に自殺した問題で、中学校側の対応を調べ改善策を提案する第三者委員会の設置作業が難航している。自殺直前の生徒と担任のやりとりなどをまとめた同校の調査報告書の信憑(しんぴょう)性などを検証するため、文部科学省も早急な設置を指示しているが、人選などの調整に手間取り、設置の見通しは立っていない。
誤記録などの経緯も根拠は「記憶」…あいまいな部分も
第三者委について町教委は、自殺問題について初めての記者会見を開いた8日の時点で、設置の方針を示していた。町教委は生徒指導や学校経営などに詳しい団体などに、すでに委員の選定や派遣を求めている。文科省も早期の設置を指導しているが、「(人選に)時間がかかる」との意向を示した団体もあり、設置のめどは立っていないという。
報告書は中学の坂元弘校長らによる校内のプロジェクトチームが、3年時の担任や、万引事案があった1年時の関係教員らからの聞き取り調査などをもとに作成した。だが自殺直前の担任と生徒との面談時のやりとりや、万引の誤記録がサーバーに入力された経緯などは、関係者による記憶が主な根拠となっており、事実関係があいまいな部分も少なくない。
遺族の代理人弁護士も「両親は、やりとりが事実かどうか疑問を持っている」と述べており、早急な検証が求められている。
同校の坂元校長は14日会見し、第三者委の検討内容を「平成28年度の学校の経営方針から反映させたい」と述べたが、第三者委の検討スケジュールについては「わからない」とした。
あともう少しで定年退職、ほんとに良かったと心の中で思いながら、泣き顔を作ったのだろうか?問題を抱える校長には演技力も必要な時代かもしれない。
自殺中3の両親に卒業証書…担任は式を欠席 03/12/16(読売新聞)

中学3年の男子生徒(当時15歳)が自殺した広島県府中町立府中緑ヶ丘中で12日午前、卒業式が行われ、亡くなった男子生徒に卒業証書が授与された。
式には男子生徒の両親も出席した。町教育委員会の担当者などによると、男子生徒の同級生が遺影を手に体育館へ入場。会場に設けられた男子生徒の席には生徒の制服と遺影が置かれ、全員で黙とうをささげた。卒業生218人の名が順々に読み上げられる際、男子生徒の名が呼ばれると、同じクラスの全員が「はい」と返事をしたという。
終了後に記者会見した坂元弘校長は「一緒に卒業したいという子供たちの思いが表れた式だった」と振り返り、「学校がきちっとしていれば、こういうことにはならなかった。本当に痛恨」と言葉を詰まらせた。
亡くなった男子生徒の担任は式を欠席した。同じクラスの男子(15)によると、式の後、教室で副担任から生徒の父親に卒業証書が手渡されると、拍手が起きた。その後、クラス全員で折った千羽鶴を受け取った両親は「ありがとう。(男子生徒のことを)忘れないでね」と呼び掛けたという。
推薦枠維持へ厳格基準に対して問題はないと思う。府中町立府中緑ケ丘中学校の坂元弘校長の判断に問題があった。
基準を厳格化するのであれば、入学式で生徒と保護者に事前に説明するべき。説明した上で、問題を起こしたのであれば、規則は規則なので仕方がない。
今回は、学校側の配慮の欠けた厳格基準の適応、文書やデーター管理の問題、教員の責任感の欠如、責任感が無い上にコミュニケーションが不足しているなどが
問題なのである。
府中町立府中緑ケ丘中学校の坂元弘校長はもしかするとエリートなのかもしれない。
「報告書は『規律維持を求めるあまり、過ちを犯した生徒を排除するような指導になっていたのではないかと猛烈に反省している』と結論付けた。 」
規律維持が原因ではないだろ。校長や教師達の軽率や対応及び怠慢が原因だろ。学校側のまとめた報告者は自分達のあやまちに触れていない。言い訳ばかり。基準を厳しくしても、間違いが修正されていれば、自殺した生徒の推薦は可能であり、自殺する理由はない。この報告書は加害者側の言い分として参考にして、利害関係のない人達が調査するべきだ。
篠永美代子先生と内藤博夫先生と判明、広島中3自殺問題-面談は廊下で立ち話 03/10/16(日刊時事ニュース)
広島・中3自殺 推薦枠維持へ厳格基準…報告書 03/11/16(毎日新聞)
広島県府中町立府中緑ケ丘中3年の男子生徒(当時15歳)が自殺した問題で、学校が昨年11月、非行歴評価の対象年次を広げて推薦基準を厳格化したのは、進学した生徒が問題を起こして高校から推薦枠を取り消されることがないよう、高校との関係維持を優先した結果だったことが学校側のまとめた報告書で分かった。報告書は「学校の規律維持を優先した。生徒一人一人の成長を考慮しなければならないという意識が足らなかった」としている。
報告書「成長考慮が不足」
基準変更は、昨年5月ごろから3年生の担当教諭で構成する学年会で協議された。学校では以前、推薦基準を緩めていた時期があり、進学した生徒が問題を起こして翌年から高校に推薦枠を取り消されたことがあった。
自殺した生徒が在籍した今の3学年は、入学当初から教師への暴力など多くの問題行動があった。学年会では「学校として推薦するのだから、触法行為は1回でもやってはいけないのではないか」「触法行為があっても、その後頑張っている生徒は対象にしたい」と意見が衝突。最終的に「3年間真面目に努力してきた生徒を推薦することが、高校の信頼に応えることになる」と厳格化を決めた。
報告書は「規律維持を求めるあまり、過ちを犯した生徒を排除するような指導になっていたのではないかと猛烈に反省している」と結論付けた。
加藤誠之・高知大教育学部准教授(生徒指導論)は「少年法でも問われない中学1年生の非行歴を高校の推薦基準にすることはおかしい。14歳未満の非行歴が将来を左右することがあってはならないし、他の生徒や高校への配慮が最優先であってはならない」と話している。【安高晋、高橋咲子】
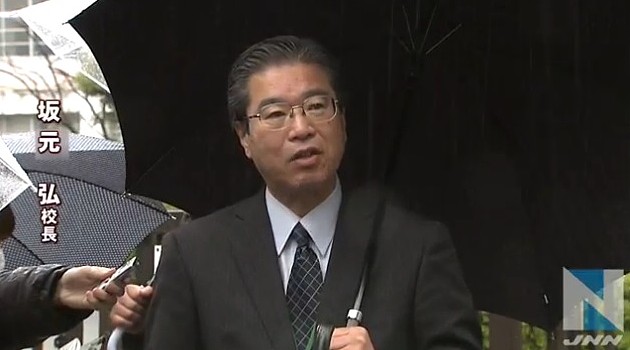 間違った進路指導後に中3生徒自殺、校長が全校集会で謝罪 03/09/16(TBS系(JNN))
間違った進路指導後に中3生徒自殺、校長が全校集会で謝罪 03/09/16(TBS系(JNN))
やはりこの学校は問題ばかり。ソフトには使用するためのマニュアルがあるはず。マニュアルを読んでも使える無いソフトであるのなら
誰が採用を判断したのか?入札なのか?それとも誰かの判断による決定なのか?入札であれば、価格優先で使い勝手、ユーザーフレンドリーは
考慮されなかったのか?
なぜ引継ぎが行われなかったのか?引継ぎが行われる事を確認する担当者はいなかったのか?担当者がいないのであれば、校長が指示するべきではないのか?
府中町教育委員会そして広島県教育委員会はどのような指導や監督を行ってきたのか?
進路指導が大幅遅れ、期間1か月のみ…中3自殺 03/11/16(読売新聞)
広島県府中町で昨年12月、町立府中緑ヶ丘中3年の男子生徒(当時15歳)が自殺した問題で、生徒の推薦校を決定する個人面談などの進路指導期間が1か月しかなかったことがわかった。
教諭間の不十分な引き継ぎや推薦基準の変更などが理由で、自殺した生徒の思いを十分にくみ取れなかった可能性がある。昨年度は1学期から面談を始めており、坂元弘校長らが2月29日付で作成した調査報告書は、こうした進路指導の不十分さを認めている。
報告書などによると、同校は、推薦を受けて受験できる高校を判断するため、成績などを入力するコンピューターソフトを使用。昨年度はこれを使い、1学期から生徒に対する個人面談などの進路指導が行われていた。
しかし、今年度は昨年度の担当教諭との引き継ぎが行われず、ソフトを使える教諭が不在となったため、指導開始が先送りされた。
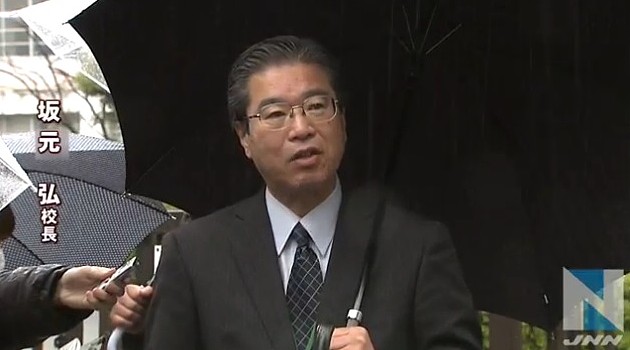 間違った進路指導後に中3生徒自殺、校長が全校集会で謝罪 03/09/16(TBS系(JNN))
間違った進路指導後に中3生徒自殺、校長が全校集会で謝罪 03/09/16(TBS系(JNN))
坂元弘校長のコメントをテレビで見ていると、直接的な原因ではないが、人事のような話し方にこの校長だと問題は解決できないであろうと
感じた。
また、府中町教育委員会の組織体質にも問題があったと思う。いろいろな問題は見過ごされ、放置され、他の原因と重なって問題や事故は起きる。
1つの原因だけで起きることは少ないと思う。他の記事では間違いを指摘したと書かれている。問題を指摘されて修正しないのは担当者の責任、そして、担当者に言っても意味が無い、又は問題を指摘できないような雰囲気を放置している校長の問題。
自殺問題に関連する事だけが記事になっているが、広範囲に調べるともっと問題が出てくるのではないかと思う。組織が腐っていれば、人もだめになっていくし、だめな人間が権力を握る。
府中町教育委員会が問題を解決及び改善できる能力があるのか、実行出来る人材を持っているのかも疑問?もし人材に問題がなければ、自殺事件が
起きる前に町立府中緑ヶ丘中学の体質問題は指摘されていたと思う。事件後にニュースで注目を受けて、パフォーマンスとしていろいろな防止策を提案するのは、府中町教育委員会そして広島県教育委員会がだめな証拠!
誤記書類、発覚後も6回にわたり配布…中3自殺 03/11/16(読売新聞)
広島県府中町で昨年12月、町立府中緑ヶ丘中学3年の男子生徒(当時15歳)が自殺した問題で、学校側が約2年前、万引きに関する記録の誤りに気付いた後も、誤ったままの記録を6回にわたって会議で配っていたことが分かった。
会議にはおおむね同じ教諭らが出席していたが、誰も誤りを指摘していなかったという。
学校側は2013年10月6~8日、非行事案を記録するパソコン上のデータに、別の生徒が起こした万引き事案を、男子生徒の名前で誤って記録。8日の生徒指導会議では、このデータを印刷した資料が出席した十数人の教諭に配布され、うち1人が誤りに気付いて指摘した。教諭らは各自の資料は手直ししたが、パソコン上の元データは、誰も修正しなかった。
府中町教育委員会、町教委の高杉良知教育長、広島県教育委員会、町立府中緑ヶ丘中学坂元弘校長と町教委の高杉良知教育長、担任、そして別の教諭から口頭で名前を聞き取ってデータ記入する際に誤記した教諭の全てに責任がある。
馳 浩文部科学大臣、無責任な関係者に対して退職金は出すべきではないでは?懲戒免職でも良いかもしれない。
人間は機会ではない。悩んでいるサインを出していないから悩んでいないと言う事ではない。嘘を付いても科学的に推測する事ができる程度で、100セント、嘘を付いているのか、いないのか、証拠がなければ判断できない。
教育者であるのだからしっかりするべきであった。
中3生徒自殺「万引きの現場にも居合わせず」 03/10/16(NHK)
広島県府中町の中学3年の男子生徒が自殺した問題について、学校がまとめた報告書が明らかになり、生徒が万引きの現場にさえ居合わせず、全く関係なかったことや、教職員の誰にも相談できなかった状況が分かってきました。さらに問題の背景として進路指導の際の取り組みが「子どもの可能性を信じ、最大限に引き出して伸ばすというには程遠い」ものになっていたとしています。
広島県府中町の府中緑ケ丘中学校の3年生の男子生徒が、万引きの非行歴があるという誤った情報が記載された資料に基づいて進路指導を受けたあと、自殺しました。
この問題を受けて、学校が先月まとめた調査報告書の内容が明らかになりました。それによりますと、平成25年に当時1年生だった別の2人の男子生徒が、広島市内のコンビニエンスストアで万引きをした際、自殺した生徒は現場に居合わせてさえいなかったのに、誤って資料に名前を記載されていたことが分かりました。
学校の教育相談体制についても不十分だったとしていて、自殺した男子生徒は、「どうせ言っても先生は聞いてくれない」という思いを保護者に話すなど、教職員の誰にも相談することができなかったとしています。
さらに、こうした問題が起きた背景として学校の進路指導の在り方について「子どもの可能性を信じ、最大限に引き出して伸ばすというには程遠く、生徒を一定の型にはめ、型にはまらない生徒は排除する」というやり方になっていたと指摘し、「報告書で示した事案が起きたのはすべて校長の責任」としています。
生徒の両親「報告書の内容に疑念」
自殺した生徒の両親の弁護士によりますと、学校が先月末に作成した調査報告書について、両親は「そもそも誰に向けて作られたものなのか分からず納得がいかない。また、報告書に書かれた担任との面談の会話が本当に、このとおりだったのか、疑念を持っている。学校の言い分は正確ではないと思う」と話しているということです。
また、両親は「息子の性格を考えると『万引きがありますね』などと決めつけられると、もめごとを起こしたくない性格から、明確に反論できないところがあると思っている。全くの想像にすぎないが、もしかしたら本当に万引きをした友だちの受験に影響が出ることを心配して、誰にも相談できず1人で悩んでいたのかもしれない」と話しているということです。
そして、今後に期待することとして、「担任との面談で本当はどんなことが話されていたのか、第三者委員会の場で調査され、より客観的で公平かつ中立な調査結果が出ることを期待したい」と話しています。
自殺当日に一緒に帰宅した友人は
自殺した生徒と小学校時代からの友人で、生徒の自殺当日、一緒に下校したという男子生徒がNHKの取材に応じ、そのときの生徒の様子について、「進路の話もしましたが、いつもと変わらない笑顔を見せていて、悩んでいるようには見えませんでした」と話しました。
取材に応じた友人の男子生徒は、生徒が自殺した当日の去年の12月8日について、「この日はテストがあって午後1時ごろに学校から2人で一緒に帰りました。ゲームの話題以外に進路の話もしましたが、彼はいつもと変わらない笑顔を見せていて、悩んでいるようには見えませんでした」と話しました。
そして自殺した生徒について、「走ることと理数系の科目が得意で、同じ陸上部だったのでよく一緒に帰宅していました。彼は高校に入学したら『軽音楽部に入ってギターを弾きたい』とよく話していました」と振り返っていました。
さらに、「彼の口から弱音を聞いたことがなかったので、『自殺』と知って、まわりの友人と『理由が知りたい』『相談してほしかった』と話しています。1つの間違いでこんなことが起こってしまってとても悲しいし、学校はするべきことをしていなかったので、これからはしっかりとやってもらいたいと思います」と話していました。
自殺した生徒の親友は
自殺した生徒と親友だという男子生徒は「優しくて誰からも好かれる人気者だった」とし、亡くなったことを知ったあとスマートフォンで「ほんとにありがとう」とメッセージを送って突然の死を悼んだということです。
男子生徒は「亡くなる2日前に自分の家で一緒に遊んだし、亡くなった当日も学校で会話をしたが、特別悩んでいる様子もなく、いつもどおりでした」と話しました。
さらに、スマートフォンの無料通話アプリ、LINEでも頻繁にやり取りをしていたということで、亡くなった当日の午後7時ごろから一緒に受ける予定だったという塾の模擬試験に、この生徒が来なかったことから、午後10時すぎ、「きょうはどうしたの」という意味の「今日とじたんな」とメッセージを送っていました。
しかし、このメッセージは読んだことを示す「既読」にはならず、その後、生徒が亡くなったことを知らされたということです。
生徒が自殺した翌日の12月9日、男子生徒は死を知りながらも、あえてLINEで「ほんとにありがとう」とのメッセージを送ったということです。
男子生徒は「読まれることがないことは、もちろん分かっていましたが『今まで仲よくしてくれてありがとう。ゆっくりと休んでね』という気持ちを込めてメッセージを送りました」と話していました。
そのうえでこの生徒について、「優しくて誰からも好かれる人気者で、何事にも一生懸命取り組む性格でした。部活の練習を毎日頑張っていて志望校に合格するために休まず塾にも通っていた。進路のことで悩みがあるなら相談に乗ってあげたかった。帰ってこないと分かっていてもできることなら、また一緒に遊んだり語り合ったりしたい。本当にショックでつらいです」と話しました。
そして、「進路は生徒にとって、とても大切なものなので学校は2度と同じ過ちを繰り返さないようにしてほしいです」と話していました。
広島中3自殺 報告書から浮かび上がる「負の連鎖」 学校のミスと担任の思い込みが原因か 03/10/16(読売新聞)
自殺した中学3年の男子生徒=当時(15)=が通っていた広島県府中町立中学校がまとめた48ページの報告書は、学校の課題を明らかにし、再発防止につなげようと、詳細な経緯が記された。行間からは教諭のミスや思い込みが重なり、生徒の死につながった「負の連鎖」が浮かび上がる。
報告書は万引の事実誤認理由について、2点の「不適切な対応」を強調した。
一つは平成25年10月7日の万引発生日の翌日、当初対応した教諭は生徒指導担当の教諭に生徒2人の名字を口頭で伝えた。報告を受けた教諭は生徒指導のデータを学校のサーバーに入力する際、うち1人の名字を誤り、男子生徒の名字を入れた。この教諭は誤記入を防ぐための「生徒指導ノート」への記録も怠った。
もう一つは同8日の生徒指導推進委員会で他の教員が誤りを指摘した後も、元データの修正が行われなかった点。誰が修正を行うか不明確で、管理職からの指示もなかったため放置された。
また、27年11月に生徒の進路を話し合う進路査定会議の資料を準備した教諭は、この時の誤った万引記録が含まれた資料が生徒指導推進委で使われたことから、「正確なはずだ」と信じた。推薦基準変更の際には、何を1、2年時の触法行為の根拠資料にするか検討すべきだったが、校長は指導・指示を怠っていた。
5回行われた男子生徒に対する担任教諭の面談は、いずれも廊下で行われ、配慮に欠けていた点も指摘した。
報告書では今後、生徒と教員の心の交流や教員間の信頼関係強化など改善点を列挙。学校は生徒指導上大変厳しい状況にあったことに触れ、「規律維持を求めるあまり、過ちを犯した生徒らを排除するような指導になっていたのではないかと、猛烈に反省する」と結んだ。
「同校の教諭が、万引きの問題に対処した別の教諭から口頭で名前を聞き取ってデータ記入する際に誤記したという。教諭らは『なぜ間違えたのか、覚えていない』と話しているという。」
問題は「なぜ間違えたのか、覚えていない」が焦点ではなく、間違いを指摘されたにも関わらず、その後に修正されていなかったことである。
また、推薦に過去3年間の記録を使用する事を決定した時に、記録に間違いが無いのか、確認するように指示を校長が出していないとすれば、
その点についても校長に確認するべきである。
自殺原因は「誤記録での進路指導」…町教委謝罪 03/09/16(読売新聞)
広島県府中町で昨年12月、町立府中緑ヶ丘中学3年の男子生徒(当時15歳)が誤った非行記録に基づき志望校に推薦できないと学校から伝えられた後に自殺した問題で、町教委は8日夜、記者会見を開き、万引きを行った生徒として誤って男子生徒の名前を記録するなどのミスが重なったことを認めたうえで、「誤った記録に基づく進路指導が自殺の原因となったと考えられる」と述べて謝罪した。
町は近く第三者委員会を設置し、経緯を詳しく調べる。
記者会見には、坂元弘校長と町教委の高杉良知教育長らが出席した。
坂元校長らの説明では、生徒が1年生だった時に作成された生徒指導の会議の資料データに、万引きをしたのは同学年の別の生徒だったのに男子生徒の名前が記される誤りがあった。
同校の教諭が、万引きの問題に対処した別の教諭から口頭で名前を聞き取ってデータ記入する際に誤記したという。教諭らは「なぜ間違えたのか、覚えていない」と話しているという。
「県教委は過去の行政実例を踏まえ、「女性は適法に採用された教員と同じ勤務をこなした」と認め、労働の対価である給与の返還は請求しにくいと判断した。」
山形県教委はずる賢いな!同じ勤務をこなしても資格がない状態で行うのでは大きな違いだ。運転免許を持っていない人が運転手として31年間働けば、
運転免許を持っている運転手と同じように車を運転し、送迎したから労働の対価として返還は請求しにくいと判断されるのか?
免許を持たない無線通信士が通信士として免許を持った人と同じ勤務をこなせば、労働の対価として返還は請求しにくいと判断されるのか?詭弁だな!
山形県教委が問題を長引かせたくないだけだと思う。
「新たな再発防止策も示した。採用時と人事異動時、免許状の写しを着任校に提出させるなどし、教員免許の有効期限の把握や確認作業の徹底を図る。」
山形県教委は学習能力がない、おろかな組織である。免許状の写しで不正は防げない事を理解していない。写しは印刷技術、ソフト、プリンターで簡単に偽造できる。
「教育の信頼損なう」 教諭免許偽造の“ニセ教師”に懲役1年6月求刑 大阪地裁 12/15/14 (読売新聞)を知らないのか?
問題を放置した山形県教委らしい再発防止策である。防止策を聞いた人達は何も疑問に思わなかったのか?本物を確認するべきだろ。
このままでは、ずる賢い人達がいればまた問題が起きるであろう。山形県は山形県教委の対応に関して何も言わないのであろうか?山形の閉鎖性を疑う?
<無免許教諭>給与1.8億円返還請求せず 03/10/16(河北新報)
教員免許を持たない女性(55)が約32年間、山形県内の公立高で授業をしていた問題で、県教委は女性に支払った給与計約1億8000万円の返還を請求しない方針を固めた。9日の県議会2月定例会文教公安常任委員会で明らかにした。
県教委によると、給与は1984年4月の採用時から、問題が発覚した2016年1月まで31年10カ月間支払った。女性は2月22日付で採用時にさかのぼり任用が無効とされた。
県教委は過去の行政実例を踏まえ、「女性は適法に採用された教員と同じ勤務をこなした」と認め、労働の対価である給与の返還は請求しにくいと判断した。退職手当や共済年金は、任用無効となり教職員でなくなったため、支払わない。
新たな再発防止策も示した。採用時と人事異動時、免許状の写しを着任校に提出させるなどし、教員免許の有効期限の把握や確認作業の徹底を図る。
県教委によると、女性は県外の大学で教職課程の単位を取得したが、免許申請時に体調不良で手続きしないまま82年度に卒業。翌年度の採用試験に合格し、これまで計4校で、延べ約7700人の生徒に保健体育を指導していた。
県教委は教職員免許法違反の疑いで、女性を刑事告訴するかどうか検討中。免許状の管理や事務手続きにも問題があったとして、本年度内に関係者を処分する。
坂元弘校長も含め、関係する教諭は全て平に格下げ。支払われる退職金から最低2割差し引け!懲戒免職にして終わらせるのも良いかもしれない。
生徒に進路査定会議で罰則的な処分として推薦をしなかった。この結果が間違いの情報そして内規の指導をすべて無視した事により起きたのであるから、
関係者は全て処分されなければならない。
1人の教育者ではなく、複数の教諭そして校長が関与しているのだから、根本的な問題は根が深い。挙句の果てに生徒の自殺を病死扱い。責任は全て学校側で
あるにも関わらず、この扱い。坂元弘校長はどのような人物であるのだろう。
「万引き」事実確認せず…内規の指導、全て怠る 03/10/16(読売新聞)
広島県府中町で昨年12月、町立府中緑ヶ丘中学3年の男子生徒(当時15歳)が自殺した問題で、学校が行った調査の報告書全文が9日、読売新聞の情報公開請求で開示された。
男子生徒の身に覚えのない万引き事案があった翌日、校内暴力が起き、学校はこの対応に追われたために、万引きした生徒本人への事実確認など、内規に定められた指導をすべて怠っていたことが一因だと指摘している。
報告書は2月29日付で、約50ページ。生徒が自殺した昨年12月8日以降、坂元弘校長ら5人が調査し、坂元校長名でまとめた。
報告書によると、2013年10月6日の日曜日、広島市内のコンビニエンスストアから、1年生男子2人が万引きをしたと学校に電話があった。たまたま出勤していた教諭が店に出向き、2人の保護者を店に呼んで謝罪させるなどした。
教諭は翌7日、生徒指導担当の教諭に口頭で報告。生徒指導担当教諭がパソコンに入力する際、うち1人の名前を誤り、男子生徒の名前を記入した。教諭は、手控えの生徒指導ノートにもメモを取っていなかった。
広島県府中町の町立府中緑ケ丘中の校長はまともな人間ではないと思う!
高杉良知・府中町教育長はこの事実を把握していたのか?知っていれば、この人間もりっぱな人間の仮面を被った偽善者。もし「学校側は生徒の死亡翌日、死因は急性心不全と説明していた。」事実を知らなければ管理能力のない教育長。どちらにしても、問題のある教育長だと思う。
<広島・中3自殺>「病死と聞かされたのにまさか...」同級生 03/09/16(毎日新聞)
男子生徒の自殺が発表された保護者会から一夜明けた9日、広島県府中町の町立府中緑ケ丘中では臨時の全校集会が開かれた。坂元弘校長は男子生徒は病死ではなく自殺だったことを報告し、学校側の誤った進路指導があったことなどを謝罪した。
◇
自殺した男子生徒は中学校では陸上部に所属していた。陸上部員だった男子同級生(15)は「まじめで優しく、決して他人の悪口を言わない子だった。病死だと聞かされていたのに、まさか自殺だったなんて信じられない」と驚いた様子で話した。学校側は生徒の死亡翌日、死因は急性心不全と説明していた。この同級生は「亡くなる前日も一緒に写真を撮ったり、とても元気だった。何があったのかと、みんな不思議がっていた」と振り返った。
高杉良知・府中町教育長は8日夜の記者会見で、男子生徒について「明るく学力も上位だった。自分の考えもしっかりしていて、友人が非常に多かった」と説明した。
同日夜に開かれた同校の保護者説明会には亡くなった生徒の遺族も出席していた。参加した保護者によると、遺族は「勉強も陸上もまじめにやる自慢の息子だった」と語り、「なぜ私たちに相談してくれなかったのか、私に相談できる雰囲気がなかったのか。なぜ、まじめにやっている子の進路を閉ざす方針が決定されたのか、その原因を明らかにしてほしい」などと訴えたという。【山田尚弘、植田憲尚】
自殺した生徒の両親は心が広いな!自分の子供に同じ事が起きたらこの程度では許さない!
間違った進路指導後に中3生徒自殺、校長が全校集会で謝罪 03/09/16(TBS系(JNN))
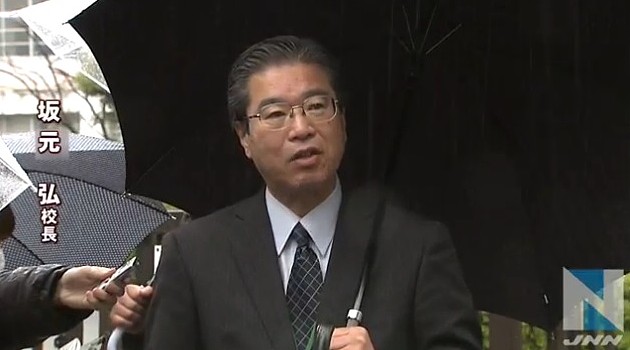
高校受験を控えた男子生徒が誤った万引き歴に基づく進路指導を受けた末に自殺した問題です。男子生徒が通っていた中学校で9日朝、全校集会が開かれ、校長が生徒たちに謝罪しました。
去年12月に中学3年の男子生徒が自殺した広島県府中町の府中緑ケ丘中学校では、9日午前8時半から9時まで全校集会が開かれました。集会には、およそ600人が出席し、坂元弘校長が経緯を説明しました。
「これまで病死であったということを伝えておりました。それは、保護者の意向によってそういうことをさせていただいたと。事実を伝えていなかったことに関しておわび申し上げました」(坂元弘 校長)
学校や町の教育委員会によりますと、自殺した生徒は、事実ではない万引き歴を理由に学校の推薦が必要な私立高校の専願受験はできないと担任から指導を受けていました。万引き歴は2年前に人違いだと判明していましたが、学校では、元データが訂正されないまま残されていました。
「進路指導に使う可能性あると判断していなかった。あまりに安易な資料の選定だった」(坂元弘 校長)
自殺した生徒の両親は、「ずさんなデータ管理、間違った進路指導がなければ、我が子が命を絶つということは決してなかったと親として断言できます」とコメントしています。
広島中3自殺、学校のずさん対応に批判 03/09/16(読売新聞)
同級生「万引きやるやつじゃない」
「自慢の息子でした」。父親は声を震わせ、母親は泣きじゃくった。広島県府中町で町立府中緑ヶ丘中3年の男子生徒(当時15歳)が自殺した問題で、同校が8日夜に開いた保護者説明会には男子生徒の両親も出席し、保護者らからは、学校のずさんな対応に厳しい批判の声が上がった。同校は9日朝、全校集会で生徒らに謝罪。友人らは「まじめで頼りになる子だった」と悲しみを新たにした。
保護者説明会には、自殺した男子生徒の両親を含む全学年の保護者約400人が出席。1時間半だった当初予定を大幅に上回り、午後10時過ぎまで続いた。
出席者によると、男子生徒の父親は「明るくて勉強もできて、陸上も頑張る自慢の息子でした」と声を震わせて発言し、「なぜ気付いて受け止めてくれなかったのか」とも訴えた。母親は、保護者からの質問に対する学校側のあいまいな回答に感情が高ぶり、泣きじゃくっていたという。
生徒と息子が同級生という父親は、「肝心のところを隠そうとしている感じで、イラッと来た。早く説明会を切り上げようという姿勢が見えた」と納得のいかない様子で話した。
その後に開かれた記者会見は、9日午前1時半まで約3時間に及んだ。記者からは、自殺した生徒と担任教諭との万引きを巡るやり取りに質問が集中。坂元弘校長が「第三者委員会の調査を待ちたい」などと繰り返した末、数分にわたって下を向いたまま沈黙する場面もあった。
同校は9日午前8時30分頃から体育館で全校集会を開き、今回の経緯を説明。終了後、取材に応じた坂元校長は「学校側の不適切な進路指導に関わる事実を話し、申し訳ないと伝えた」とし、生徒らは硬い表情で聞いていたという。
同校はこの日から、生徒の心のケアにあたるカウンセラーを緊急で配置。生徒にはこれまで男子生徒の死亡について「急性心不全」と伝えており、自殺に至った原因の究明を目的として、生徒への個人面談やアンケート調査も行うという。
生徒の間にもショックは広がる。男子生徒はスポーツが得意で、陸上部に所属。友人も多く、よくゲームを楽しんでいたという。
同じクラスだった男子生徒(15)は「まじめで面白くて、頼りになり、みんなに好かれていた」と振り返り、「自分の意見を曲げず、おかしいと思ったことはおかしいと言う性格。万引きをやるようなやつじゃない」と話した。
昨晩、両親とこの問題について話し合ったという別の男子生徒(15)は「誤記がなかったらこんなことにはならなかったはず。学校のやり方がおかしかったのでは」と語り、2年の女子生徒は「自分にも同じようなことが起こるかもしれないと思うと怖い」と話した。
教室前の廊下で「万引ありますね」…2年間も資料修正せず、別の生徒の万引記録 非常識の数々(1/2)
(2/2) 03/09/16(産経新聞)
広島県府中町立中3年の男子生徒(15)=当時=が昨年12月8日、自宅で自殺した問題で、1年生当時の生徒指導の会議で、配布された資料にある生徒の万引記録が誤っていることに気付いていたが、資料の内容を保存しているサーバーでの修正作業をしていなかったことが8日分かった。同校には万引などの行為があった際、校長推薦を認めないルールがあった。生徒と両親、学校側との三者懇談はこの資料に基づいて進められており、ずさんな管理態勢に非難が集まりそうだ。
■「間違った資料」のまま進路指導…保護者との三者懇談の当日、生徒は出席せず自宅で自殺
8日夜に会見した高杉良知教育長と学校長によると、生徒が1年生の時に万引をしたことがあるとの誤った記録を理由に志望校の推薦を出せないとの話を、学校側が三者懇談で両親に伝える予定だった。生徒は三者懇談の当日に亡くなった。万引の記録は自殺後の調査で別の生徒のものと判明した。
会見での説明によると、今回の進路指導では、サーバーに残っていた、誤った内容の資料がそのまま使われていた。
生徒は公立高校を第1志望とし、受験するために校長の推薦が必要な私立高校を第2志望にしていた。
担任教諭は、教室前の廊下で、生徒に対し「万引がありますね」と聞き、「えっ」との反応があった。さらに「3年の時ではなく、1年の時だよ」と確認すると、生徒は間をおいて「あっ、はい」と答えたという。
担任は生徒が否定したと認識せず、12月に入り、推薦できない旨を両親に伝えたかどうか生徒に確認。8日の三者懇談で両親と会ったが、生徒は姿を見せず、同日夕、自宅で自殺しているのを父親が見つけた。
自殺した男子生徒の両親は、代理人弁護士を通じ「ずさんなデータ管理、間違った進路指導がなければ、わが子が命を絶つことは決してなかった」とのコメントを出した。
中3男子生徒自殺 誤り判明後もデータ未修正で残る 03/09/16(NHK)
去年12月、広島県府中町の中学3年生の男子生徒が自殺した問題で、学校と町の教育委員会が8日夜、会見し、生徒の指導の際に使った「万引きの非行歴があった」との誤った資料について、誤りが判明したあとも学校のサーバーにデータが未修正のまま残っていたことを明らかにしました。会見で学校側は、情報管理に問題があったと謝罪しました。
去年12月8日、広島県府中町の町立中学校の3年生で15歳の男子生徒が自宅で自殺しました。学校や町の教育委員会によりますと、自殺当日までに5回行われた進路指導の際、生徒に万引きの非行歴があったとする誤った資料に基づいて、担任の教諭が、志望校への推薦は出せないと伝えていたということで、誤った資料に基づく指導が生徒の自殺につながった原因とみられるとしています。
8日夜の記者会見で、校長は誤った資料の作成について、「データ入力の過程で生徒の名前を誤ったことが原因と思われる。その後、ミスと判明したが学校のサーバーの電子データは未修正のまま残されてしまった」と述べたうえで、情報管理に問題があったと謝罪しました。また、学校が教育委員会に報告した別の資料では誤りが修正され、この生徒の非行歴は、誤りに気付けた可能性があったということです。
中学校は9日、全校集会を開き、校長が詳しい経緯を生徒に説明することにしています。
自殺した生徒の両親は弁護士を通じて、「ずさんなデータ管理、間違った進路指導がなければ、わが子が命を絶つということは決してなかったと親として断言できます」とするコメントを出しました。
記者会見の詳細
広島県府中町の中学3年生が自殺した問題を受けて、男子生徒が通っていた中学校と町の教育委員会は、8日午後10時半ごろから3時間余りにわたって記者会見を開きました。
この中で、自殺した男子生徒が通っていた中学校の校長は「生徒みずからが命を絶つようなことが起こったことについて、生徒を預かる学校の責任者として深くおわび申し上げます」と述べ、謝罪しました。そのうえで、公表が男子生徒の自殺から3か月後になったことについて、「亡くなった翌朝に遺族から『みずからの命を絶った事実を知らせると同級生の動揺が大きく進路にも影響があるかもしれないので進路が一段落するまで急性心不全で亡くなったことにしてほしい』と希望が寄せられた。公立高校の入学試験が終わったので公表した」と説明しました。
また、男子生徒に「万引きの非行歴があった」とする誤った資料については、「男子生徒が1年の時の生徒指導推進委員会の資料で触法行為をした生徒として名前があった。記録上のミスで、会議の席でミスであると確認したものの、サーバー上の電子データは未修正のまま残されてしまった」と説明しました。
誤った資料が作成された理由については、「当時、生徒が万引きをしたと連絡を受けた教諭が、資料を作成する生徒指導部の教諭に生徒の名前を口頭で連絡した。データの入力の過程で誤ったと思われる」としたうえで、「あくまで会議で使うための資料だったので、その後、ほかのことに活用するということは考えず、データも直されなかった」と述べました。
さらに校長は生徒を高校に推薦する際の基準について、それまで3年生の1年間で非行歴がある場合は推薦の対象としないとしていたものを、去年11月に1、2年生の時も含めて非行歴がある場合には推薦の対象にしないと改めたことを明らかにしました。そのうえで、こうした考えは生徒の成長を認め、生徒の意欲を高めるという観点に欠けていたと述べました。
一方、担任の教諭と男子生徒のやり取りについては、「担任は去年11月から自殺した日の朝にかけて5回、男子生徒と面談した。担任は1回目の11月16日の面談で触法行為があったことの確認を取ろうとしたが、具体的な事実を確認せず、生徒本人の不明確なことばで確認が取れたと思い込んでしまった。5回の面談を通しても担任は生徒が触法行為を否定したと感じなかったため、触法行為があったと確認が取れたとしていた」と説明しました。
保護者会開催も批判相次ぐ
中学校は8日夕方から緊急の保護者会を開き、これまでの経緯を保護者に説明しました。
緊急の保護者会は8日午後6時半から、およそ3時間半にわたって中学校の体育館で行われました。出席した複数の保護者によりますと、中学校の校長と町の教育委員会の教育長が、これまでの経緯を説明し、この中で、学校側は自殺した男子生徒に「触法行為」があったとする誤った資料に基づいて、担任の教諭が生徒に「志望校への推薦は出せない」と伝えたことが自殺に直接結びついた可能性が高いことを認め、保護者に謝罪したということです。
一方で詳しい当時の状況や原因の分析などの詳細な説明はなかったということで、保護者からは「説明が十分されていない」といった意見や批判が相次いだということです。
会には自殺した生徒の両親も出席しましたが、担任の教諭は出席せず、出席した保護者からは「担任が直接説明しないのはおかしい」とか、自殺の公表が今まで遅れたことに触れ、「なぜもっと早く説明しなかったのか」といった指摘が相次いだということです。出席した保護者の1人は「説明は体裁を整えているだけで、事実を伝えることから逃げているようだった。先生が生徒の味方になれば、自殺は起きなかったはずで納得がいかない」と話していました。
ISOでは文書の管理および保存に関するマニュアルを作成する事を要求している。ISOの認定を受けている企業であっても、従業員が文書の管理および保存について十分な理解をしていなかったり、
実際にはマニュアル通りに行われていない場合もある。
ISOの認定など受けなくても、マニュアルを作成し、担当者がマニュアルを理解し、実行し、定期的な
検証を真面目な正確の人が行えば、お金をかけなくても問題は防止できる。
このような事を府中町教育委員会の人間誰一人も指摘したり、現状の把握を提案しなかったのか?
<広島・中3自殺>サーバーに訂正済み生徒資料…知られず 03/09/16(毎日新聞)
広島県府中町立府中緑ケ丘中3年の男子生徒(当時15歳)が誤った万引き記録に基づく進路指導を受けた後に自殺した問題で、実際に万引きをした生徒の氏名に訂正した正式な生徒指導資料が、学校の共有サーバーに保存されていたことが9日、分かった。担任は進路指導の際に正しい指導資料を使わず、サーバーの別フォルダーにあった訂正前の資料を使用していた。
同校の坂元弘校長によると、2013年10月6日、「万引きをした生徒がおり、保護者に連絡してほしい」と被害店舗から連絡を受けた学校職員が、生徒指導部の担当教諭に万引きをした生徒の名字だけを口頭で伝えた。この教諭は生徒指導会議用に配布した資料に、自殺した男子生徒の氏名を誤って記載した。同8日の会議で氏名の誤りが指摘され、資料はその場では訂正されたが、学校の共有サーバーに保存されたデータは修正されなかった。
指導部の教諭は同月末、修正した記録を町教育委員会に提出した。その後、正式な記録は別フォルダーに保存されて教諭が閲覧できる状態にあった。進路指導の参考にした修正前の資料は3年生を担当する教諭の一人が学校のサーバー内から見つけ、3年担任の他の5人に配ったという。
坂元校長によると、学校が推薦基準に非行歴の勘案対象を3年時だけでなく1、2年時も含めると改めたのは昨年11月で、過去の資料の閲覧などはマニュアル化されていなかった。坂元校長は「進路指導に関しては各教師の裁量に任せていた。何の指示もなく、マニュアルなども決めていなかったことは大変問題だと認識している」と話した。
また、担任教諭は昨年11月16日から男子生徒が自殺した12月8日までの計5回、進路指導の際に男子生徒に万引きの事実を確認したが、「生徒の返事が曖昧で明確な否定もなかったため、確認がとれたと判断した」と釈明しているという。いずれも指導は廊下で5~15分程度だった。学校側は「生徒の非行歴を含む重要な進路指導が廊下で行われたことは非常に問題。来年度から準備室のような場での指導を教員に指示していく」としている。【石川将来、高橋咲子】
◇
男子生徒の両親は、代理人弁護士を通じて「ずさんなデータ管理、間違った進路指導がなければ、我が子が命を絶つことは決してなかったと親として断言できます」とのコメントを出した。【山田尚弘】
文科省はソーシャルカウンセラーを常勤化するよう法令を改正する方向で動いているが、このような学校が存在していては税金の無駄。
教員や学校関係者が楽をしたいだけで、生徒の事を思った上での対応とは思えない。
ビンタに頭突き約20分 教師が中1男子に12/15/15(日本テレビ系(NNN))
愛媛県の中学校で40代の男性教師が中学1年の男子生徒(12)に暴行を加えていたことが分かった。暴行は、頭突きやビンタなど20分にわたり、教師は生徒と母親に対して謝罪した。
暴行が発覚したのは愛媛県松山市の市立津田中学校。男子生徒は10日の放課後、教室で友人とふざけていたという。生徒の母親によると、担任の教師は男子生徒の頬をつかんだ状態でトイレに連れていき、カギを閉めた上で約20回にわたりビンタや頭突きなどの暴行を加えた。
「殺してやろうか。耳を聞こえんようにしてやろうか」などと言葉を浴びせ、暴行は約20分にわたり続けられたという。
担任から暴行を受けた直後に母親が撮影したとする写真には、男子生徒の腫れ上がった左の頬が写っている。つねられたような痕も残っている。
母親には、男子生徒が帰宅する前に、担任の男性教師から「ほっぺたをたたいてしまった。申し訳ありません」と電話があった。当初、母親はふざけていた息子が悪いため、1発2発たたくのは問題無いと思ったと話す。しかし、帰宅した生徒の様子をみて驚き、学校に抗議をするとともに、息子を病院に連れていった。
男子生徒は、顔面打撲や頭部打撲で、2週間の治療が必要だと診断された。
学校側は暴行の翌日に男子生徒の自宅を訪問。母親は、その時の音声を録音していた。
教頭「両方のほっぺたをギューっとつまんで。そこで平手打ち、だいたい17、8回ぐらい殴ってる」
校長「大変ご心配をおかけしていることに対して申し訳なく思っています」
学校側は、暴行を認めて謝罪した。
なぜ、担任の男性教師は暴行に及んだのか?
担任「お母さん、絶対信じてくれないと思うんですけど」
母親「話なんか聞きたくないわい」
担任「僕は(男性生徒が)大好きです」「これまでの半年の人間関係があると思っとったんで、甘えとったんですよ。すいません」「男同士であったりとか勝手に思ってた。申し訳ありません」
人間関係があると思って甘えていたと釈明した。
さらに--。
父親「(男子生徒)に対してじゃなくてもなんですけど、今までどれくらい(体罰を)」
担任「過去にはあります」
過去にも体罰を行ったことがあると話した。
今回の暴行について中学校の校長は、「普段より職員については重大な事案、こういった事案を引き起こさないよう指導してきたが、それが十分に至らなかったと、大変残念に思っています」
中学校は、暴行の当日に松山市の教育員会に報告したという。
暴行を受けて以降、男子生徒は学校に通っていない。
母親「今は学校に行きたくないと。教室にもたぶん怖くていけないと」「夜中も数回起きたり下痢してて、たぶん精神的なものだと思う」
母親は学校には、見て見ぬふりをしないでほしいと訴える。
母親「教師である資格がないと思っている。見て見ぬふりをした方も一緒」
警察は、男性教師から事情を聞くなど傷害の疑いもあるとして調べている。
就学支援の不正受給なしで学校運営できない学校は存続させなくて良い。
「就学支援金とは、年収約910万円未満の世帯に対し国が高校の授業料を肩代わりする制度。公立高は約12万円、私立高は約12万~30万円が支給される。株式会社立高は私立高の額が適用される。高校を卒業したり、在籍期間が3年を超えたりすると支給対象から外れる。
三重県によると、同校には昨年度、約1億5700万円の支援金が支給されたという。」
制度を悪用させる体制は税金の無駄使い。行政は制度の悪用を厳しくチェックし、厳しく処分するべきだ。
就学支援90万円を不正受給か 三重の高校、生徒3人分 12/09/15(朝日新聞)
東京地検特捜部の強制捜査を受けた株式会社立ウィッツ青山学園高校(三重県伊賀市)が、受給資格のない3人の生徒の就学支援金を申請し、計約90万円を国から受け取っていたことが、関係者の話で分かった。特捜部はこの3人についての詐欺容疑で調べている模様だ。
関係者によると、3人はいずれも20~40代の会社役員。2014年4月に同校通信課程に入学し、四谷LETSキャンパス(東京都千代田区)に所属していた。入学願書の学歴には「中学校卒業」と虚偽の記載をしていたが、実際には高校を卒業しており、受給資格がなかった。授業や試験の添削指導などを受けたこともなかったという。
国は同年5月~今年7月に3人分にあたる計約90万円の就学支援金を同校に支給した。3人の支援金は、四谷キャンパスの代表者と3人が交わした同意書をもとに、キャンパス側に渡っていたという。
就学支援金を不正受給した疑い 三重の高校など家宅捜索 12/08/15(朝日新聞)
高校授業料の実質無償化に合わせて導入された国の「就学支援金」を不正に受給していた疑いがあるとして、東京地検特捜部は8日、株式会社立ウィッツ青山学園高校(三重県伊賀市)や、運営する株式会社「ウィッツ」(同市)、その親会社の「東理ホールディングス」(東京都中央区)など関連先を詐欺容疑で捜索した。
関係者によると、同校では別の高校を卒業するなどして受給資格のない複数の生徒を通信制課程に入学させ、受給資格があるように装って就学支援金を国に申請し、受給した疑いがあるという。
同校では同日午後5時半すぎ、東京地検の係官とみられる男性らが段ボール箱をワンボックス車に運びこんだ。
同校は国が進める構造改革特区制度の「教育特区」を利用し、ウィッツが株式会社立の高校として2005年に開校。今年2月時点で全日制の生徒は29人、通信制は1158人だった。
就学支援金とは、年収約910万円未満の世帯に対し国が高校の授業料を肩代わりする制度。公立高は約12万円、私立高は約12万~30万円が支給される。株式会社立高は私立高の額が適用される。高校を卒業したり、在籍期間が3年を超えたりすると支給対象から外れる。三重県によると、同校には昨年度、約1億5700万円の支援金が支給されたという。
ウィッツ社の福村康広社長は同日、「就学支援金を受け取っていたことは知っているが、詐欺は知らない。現場にはタッチしていない」と話した。
「就学支援金」不正受給か 詐欺容疑で三重の高校など捜索 東京地検特捜部(1/2)
(2/2) 12/08/15(産経新聞)
国の「就学支援金」制度に絡み、三重県内の株式会社が運営する高校「ウィッツ青山学園高校」(同県伊賀市)の通信制課程に受給資格がない生徒が入学することで、支援金を不正受給していた疑いが強まったとして、東京地検特捜部は8日、詐欺容疑で同校や運営会社「ウィッツ」(同)、親会社の「東理ホールディングス」(東京都中央区)などを家宅捜索した。
就学支援金制度は昨年4月、高校授業料の実質無償化に代わって導入された。世帯年収に応じて生徒1人につき、最大で年間約30万円を国が生徒に代わって学校に支給。制度を定めた「高等学校等就学支援金の支給に関する法律」には、虚偽や不正な手段で支援金を支給させた場合の罰則規定がある。
関係者によると、同校の通信制課程に、すでに他校を卒業するなどして受け取る資格がない複数の生徒が入学、支援金が不正支給されていた疑いがある。
文部科学省によると、支援を受ける際の申請書には、在学期間を記入する欄はあるものの、高校を卒業したかどうかを確認する欄はなく、確認は取っていないという。就学支援金制度全体の今年度の予算額は3805億円。
伊賀市教育委員会や同校のホームページなどによると、市が平成16年、株式会社の学校運営を認める国の「教育特区」の認定を受け、同校は17年に開校した。全日制と通信制があり、28年度の募集要項では、学年の定員は全日制が20人、通信制が400人。
市教委の担当者は「運営は学校が独自にやっているので、経営に関しての学校評価などを除き、特に関わっていなかった」と説明。他校を卒業した生徒などが通っていることについて「初めて知り、把握できていなかった」と話した。
「就学支援金」で不正の疑い 高校など捜索 12/08/15(NHK)
高校の授業料の実質無償化に代わって新たに導入された「就学支援金」の制度を巡り、三重県にある株式会社が運営する高校の通信制に、受給資格がない複数の生徒が入学し、支援金が不正に支給されていた疑いがあることが分かりました。東京地検特捜部は詐欺の疑いで強制捜査に乗り出し、関係先としてこの高校や運営する会社などを捜索しています。
就学支援金制度は高校授業料の実質無償化に代わって去年4月から導入され、世帯の年収に応じて生徒1人当たり最大で年間およそ30万円を国が生徒に代わって学校に支給するもので、すでに高校を卒業している生徒などは支給の対象になっていません。
関係者によりますと、株式会社が三重県伊賀市で運営する「ウィッツ青山学園高校」の通信制の課程に、すでに別の高校を卒業するなどして受給資格がない複数の生徒が入学し、国から支援金が不正に支給されていた疑いがあるということです。
東京地検特捜部は8日、詐欺の疑いで強制捜査に乗り出し、生徒の自宅のほか、関係先として、ウィッツ青山学園高校や、高校を運営する株式会社「ウィッツ」、運営会社の親会社で東京・中央区にある「東理ホールディングス」などを捜索しています。
この高校は、株式会社の学校運営を認める国の「教育特区」となった伊賀市で平成17年に設立され、全日制と通信制がありますが、市によりますと、通信制の生徒は全国に広がり、その数は全日制の50倍以上の1100人余りに上っているということです。
東京地検特捜部は今後関係者から事情を聴くなどして、実態解明を進めるものとみられます。
捜索を受けていることについて、ウィッツ青山学園高校はNHKの取材に対し、「責任者が対応できず、現段階ではコメントできない」と話しています。また、東理ホールディングスは「捜索を受けているかどうかも含めてコメントできない」としています。
就学支援金とは
就学支援金は、高校の授業料を国が生徒に代わって学校に支給する制度です。民主党政権が平成22年度に高校の授業料を実質無償化した際、私立高校については、世帯の年収に応じておよそ12万円から24万円の就学支援金を国が高校に支給する制度が導入されました。
公立高校はおよそ12万円を国が負担していましたが、自民党政権になって制度が見直され、去年4月からは公立、私立ともに就学支援金を支給する制度に一本化されました。
支援を受けられるのは年収がおよそ910万円未満の家庭の生徒で、1人当たり年間およそ12万円が支給されます。
私立の場合は、家庭の負担が大きいとして加算があり、▽年収が350万円から590万円ほどの場合は1.5倍、▽250万円から350万円ほどの場合は2倍、▽250万円に満たないくらいの場合は2.5倍のおよそ30万円が支給されます。
また、法律では、高校を卒業している人や在学期間が通算で36か月を超える人はこの支援を受けることはできないと定められていて、不正に支給させた場合の罰則規定が設けられています。支援を受ける際には課税証明書と申請書の提出が必要で、申請書には高校などに在籍した期間を記入する欄がありますが、文部科学省によりますと、高校を卒業していないかどうかの確認は特に行っていないということです。
文部科学省によりますと、昨年度、新たな制度で就学支援金を利用したのはおよそ94万人で、今年度の予算額は3805億円となっています。
学校運営にこれまでも疑問の声
三重県伊賀市によりますと、10年前に設立された「ウィッツ青山学園高校」については、これまでも学校の運営をチェックする年2回の市の審議会の場で、学校での授業とともに全国にあるサポート校での指導の内容が適切かどうかを問いただす意見が出ていたほか、通信制の生徒の定員が最近になって1200人にまで増えたことで、少ない教員の数で対応できるかなど、学校運営を疑問視する声が上がっていたということです。伊賀市教育委員会の伊室春利教育次長は「市としては株式会社が運営する学校ができることで、地域の知名度の向上や生徒が通うことによる経済の活性化などを期待して、学校の設置を認可した」と話したうえで、今回の捜索について、「就学支援金の不正受給が事実なら非常に残念だ。学校などから話を聞いて早急に事実確認したい」と話しています。
文部科学省 「制度悪用なら遺憾」
就学支援金を巡り東京地検特捜部が詐欺の疑いで強制捜査に乗り出したことについて、文部科学省は、「就学支援金は家庭の経済状況にかかわらず子どもたちが進学できるように設けた制度で、悪用されたのが事実だとしたら大変、遺憾だ。制度が始まって以降、不正受給は報告されておらず生徒の申請を信用して支給していたが、審査の在り方含めて今後対応を検討したい」としています。
画像が本物なら自業自得!教師である事を考えるべき!まあ、自己責任が付いて回るという事は公務員として教師として理解しているはず?
AKBグループの未成年アイドルの一般男性との熱愛プリクラが流出、相手はなんと中学教師・・・ (暇つぶしーく)
「婚活支援」国の税金でやること?…指摘相次ぐ 11/12/15(週刊文春)
今年8月に結成されたAKBグループ「欅坂46」のメンバー・原田まゆ(17)が、男性と写ったプリクラ画像がネットに流出した問題で、週刊文春はそれぞれの父親に接触した。
画像の男性は原田の中学時代の教師M氏。画像で男性は原田の胸をまさぐっており、教師による未成年への淫行の決定的証拠ではないかと指摘されていた。現在、彼が勤める大田区内の中学校には抗議の電話が殺到。11月4日には全校集会と保護者会が開かれた。
「息子はほとんど連絡をよこさない。東京で真面目に中学教師をやっているとばかり思っていた。彼女の話は聞いてませんので」(M氏の父親)
一方、原田の父親は週刊文春の取材にこう話した。
「相手が先生だと聞いて最初は驚きましたけど、会ってみるとしっかりしていて、感じのいい青年だったので、交際を認めました」
M氏が勤務する中学の校長に取材を申し込んだが取材拒否。大田区教育委員会に見解を聞くと、「事案は把握しています。警察と連携して調査していきます」と答えた。
教え子アイドルと中学教師の胸揉み画像流出 学校や教委に電話、メールが相次ぎ大騒ぎ(1/2)
(2/2) 11/12/15(J-CASTニュース)
アイドルの少女(17)とキスする画像などがネットに晒された東京都大田区立中学の30代前半の男性教師について、学校や区教委に電話やメールが相次ぐ騒ぎになっている。
「ほんまにかわいい」「ちゅ~~~っ」。ツイッター上で2015年11月2日ごろに何者かが投稿したプリクラ画像では、こんな言葉とともに、教師が少女の胸を揉んだり、キスしたりするシーンが写っていた。
淫行処罰規定に触れる可能性があるが...
すぐにネット上で騒ぎになり、情報サイトなどに取り上げられた。少女が8月に結成されたAKBグループ「欅坂46」のメンバーとされたからだ。
事実関係ははっきりしなかったが、週刊文春が11月12日発売号で騒ぎを取り上げた。欅坂46のホームページでは、文春サイトで前日夕に同様な記事が出た直後に、少女は欅坂46の活動を自ら辞退したことを告知した。ただ、辞退の理由については触れられていなかった。
文春の記事によると、この教師は、独身で、少女が中学3年のときに赴任してきた。少女が学校の球技大会実行委員をしていたとき、教師が担当だったことから知り合い、2人は、学校でも親密そうにしていたという。
教師がした性的とも受け取れる行為については、都青少年健全育成条例第18条の淫行処罰規定に触れる可能性がある、とされた。それは、教師が性的欲望を満足させるためだけに少女と接していた場合だ。しかし、文春の記事では、少女の父親が取材に答え、教師に会ったうえで交際を認めたことを明かした。交際するようになったのは、高校に入ってからだという。
一方、プリクラ画像は、複数枚がネットに流出しており、少女の髪の長さが変わるなどしていることから、長い期間にわたって交際していた可能性がある。もしキス画像の1つが少女の中学在校時に撮られたものだとすれば、都教委の処分規定から、少女からの同意の有無を問わずに懲戒免職になる。過去には実際に、キスしただけで免職になったケースがあった。
ネットでは「親が認めてるなら良い」の声
大田区教委の指導課では、J-CASTニュースの取材に対し、ネット上で画像が流出したときから事案を把握し、プリクラが少女の中学在校時に撮られたものかどうかなどを調査していることを明らかにした。
流出画像が少女の中学卒業後のものであった場合、教師への処分については、保護者が交際を認めているかなど状況によって判断するとしている。
本当かどうか全く分からないが、教師は、在校中の複数の教え子にも声をかけていたとの情報もある。文春にも在校生の証言が出ており、区教委では、「ネット上の情報は把握しており、事実関係を調べています」と取材に答えた。
区教委や学校はまた、11月4日に全校集会や保護者会を開き、騒ぎについて生徒や保護者に説明を行ったと取材に明かした。今回の件については、学校や区教委に電話やメールで意見が相次いでいるともした。
区教委の指導課では、「こうした問題が出たことについては、本当に遺憾に感じています」と言っている。
文春の記事では、学校側は教師と少女が真剣交際をしていると生徒や保護者の前で話したとしている。教師は、発覚直後から学校を休んでいるという。
ネット上では、「教師はアウトでしょ」「こんな先生に自分の娘を預けれない」といった厳しい声もあるが、交際に理解を示す向きが多い。「親が認めてるなら良いだろ」「生徒と結婚した教師も結構いるから」「交際すら認めないとなれば16歳の結婚規定はどうなる」といったものだ。
「卒論を盗用した点について、教授は『資料やアイデアは自分が教えたもので、盗用ではない』と釈明した」が事実であれば、学生の論文に
クレジットとして教授の名前を記載させるべきだった。していない時点で、学術的には教授に問題があると言う事になるのでは?
教え子の卒論、ほぼ全文を無断引用…教授処分へ 11/06/15(読売新聞)
福岡教育大(福岡県宗像市)は5日、教育学部の50歳代の男性教授が2010~13年に発表した論文5本で無断引用などの不正があったと発表した。
年度内に教授の処分を決める。
同大学によると、不正論文は教員や学生の論文をまとめて掲載する「大学紀要」などで掲載された。外国文献の和訳や、かつて指導した学生の卒業論文などを盗用しており、12年の大学紀要では卒論のほぼ全文を引用していた。
昨年5月、独立行政法人・日本学術振興会(東京)に情報が寄せられ、同大学が教授の過去の論文について調査していた。
卒論を盗用した点について、教授は「資料やアイデアは自分が教えたもので、盗用ではない」と釈明したが、大学側は「卒論は学生のものであり、不正にあたる」と判断した。
校長ら4人、同時に懲戒免…わいせつ行為や横領 10/22/15(読売新聞)
千葉県教委は21日、わいせつ行為や横領などで校長ら6人を懲戒処分とし、うち4人を免職とした。
今年度の懲戒処分(監督責任と千葉市教委を除く)は計18人で、免職者は7人に上る。昨年度1年間の懲戒処分(同)の13人を既に上回っており、県教委は同日、市町村教委などに綱紀粛正を通知したほか、教育事務所長らを臨時に集めた会議で指導の徹底を求めた。
免職処分は、習志野市立小の男性校長(53)ら4人。校長は9月5日、船橋市の京成線船橋競馬場駅のエスカレーターで、女性のスカート内をデジタルカメラで盗撮。船橋署に任意同行され、今月8日、県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで千葉地検に書類送検された。
県立高校の男性教諭(28)は6月下旬~8月14日、顔見知りの県内の女子高校生にホテルなどでわいせつな行為をしたとされる。
このほか、9月23日に千葉市内の書店で女子中学生のスカート内をデジタルカメラで盗撮し、千葉北署に同条例違反(同)の疑いで逮捕された印西市立小の男性教諭(42)と、9~10月に担任クラスの学校徴収金約11万円を横領するなどした八街市立小の男性教諭(25)の2人が免職処分となった。
また、県立高校の剣道部顧問の男性教諭(30)は5~7月、部活動中に男子部員4人に対し、竹刀や木刀で腰や頭などをたたき、みみず腫れなどのけがを負わせたとして、停職1か月。県立高校の男性校長(57)は、男性教諭に対する監督責任を問われ減給1か月(10分の1)となった。
県教委は、免職処分が同時に4人出るのは「少なくともここ数年はない」とし、内藤敏也教育長が記者会見で「誠に遺憾。県民の信頼を裏切ることとなり、深くおわびする」と陳謝した。
公務員は副業を禁止されているので、どんな副業をしようが見つかれば処分されるので同じ事かもしれないが、中学校教諭の立場でなぜ売春クラブ?
売春クラブ主催の都立中教諭逮捕 女子高生あっせん容疑 10/21/15(朝日新聞)
女子高校生を客に引き合わせ、売春させていたとして、神奈川県警は、東京都立中学校教諭、坪内駿一容疑者(27)=板橋区坂下3丁目=を児童福祉法違反(淫行させる行為)や児童買春・児童ポルノ禁止法違反(周旋)などの疑いで逮捕し、21日発表した。「間違いありません」と容疑を認めているという。
少年捜査課などによると、坪内容疑者は別の男(54)=同容疑などで逮捕=と共謀し、複数の男女が同時に参加する売春クラブを主催。2013年9月、東京都文京区のホテルで、当時16歳で通信制高校1年生だった女子生徒=横浜市=を、18歳未満と知りながら売春相手として男(31)に引き合わせ、みだらな行為をさせるなどした疑いがある。男からは1万3千円を料金として受け取っていたという。
第三者調査委員会はまともな調査を行った可能性が高い?
調査委が「学校も問題」としたが、この判断の妥当性は誰が判断し、どのように反映されるのか?学校も問題と言うことは、責任者(校長)や担当者(担任)を処分すると言う事か?
いじめ自殺、学校「転校」と説明…教職員謝罪 10/07/15(読売新聞)
仙台市立中1年の男子生徒がいじめを受けて昨秋に自殺した問題で、同校は6日、全校集会を開き、初めて在校生に事実関係を説明した。
「男子生徒は転校した」と事実と異なる説明をしていたことについて、教職員全員で謝罪した。校舎2階に献花台を設ける方針を示したほか、動揺した生徒の心のケアにあたるスクールカウンセラーを2人に増員した。
全校集会後に記者会見した校長によると、集会では、生徒ら約300人が男子生徒に黙とうをささげた。校長が男子生徒の実名を明かし、「本人が心を痛めていたのに、学校が十分に対応できず、申し訳なかった」と話すと、涙ぐむ生徒もいたという。
市教委はこれまで、個人が特定されないことを望む遺族の意向を理由に、学校名や男子生徒の名前を伏せてきた。3日に遺族から在校生への説明について同意が得られたことから、全校集会を開いた。校長は「事実を共有し、本来取るべき行動ができるようになった」と述べた。
男子生徒の父親は6日、読売新聞の電話取材に「息子の死から1年経過してからの公表となり、生徒たちを動揺させて申し訳ない。からかいもいじめになる。保護者も含め、みんなで何がいじめなのかを考えてほしい」と話した。
「『男子生徒は転校した』と事実と異なる説明をしていたことについて、教職員全員で謝罪した。」
なぜ教職員全員で謝罪する必要があるのか?隠ぺい行為に協力又は黙認したからなのか?転校したと嘘を付いた事について明確な理由及び判断に至るまでの
説明はあったのか?
「男子生徒の父親は6日、読売新聞の電話取材に『息子の死から1年経過してからの公表となり、生徒たちを動揺させて申し訳ない。からかいもいじめになる。保護者も含め、みんなで何がいじめなのかを考えてほしい』と話した。」
残念ながらいじめはなくならない。差別や偏見がなくならないのと同じ。また、明確ないじめでない限り、セクハラと同じで当人がどう感じる次第でいじめとなるケースもあると思う。本人がいじめと感じた時に
教員や学校がどのように対応するかが重要だと思う。
中1自殺、主因はいじめ…調査委「学校も問題」 10/07/15(読売新聞)
山形県天童市の市立中学1年の女子生徒(当時12歳)が昨年1月、「いじめにあっていた」と書いたノートを残して自殺した問題で、第三者調査委員会(委員長・野村武司弁護士)は5日、いじめが自殺の主要な原因と認定した上で、「学校が適切な対応を取らなかった」とする報告書を市教委に提出した。
記者会見した野村委員長によると、報告書ではクラスや部活動で悪口や嫌がらせなどのいじめを受けていたと認めた。学校については「いじめの兆候などの十分な情報を関係教師は得ていた。しかし、教師の理解が十分ではなく、いじめのリスクを的確に評価できず、場当たり的な対応にとどまった」と指摘。女子生徒の母親は部活動での嫌がらせを担任に相談していたが、「情報が学校全体で共有されなかった」とした。
仙台市立中学校男子生徒いじめ自殺事件の学校名と担当教諭名 09/30/15(豊受真報臨時号)
たぶん、下記の記事は事実を書いているのだろう。
下記は建前だけで、生徒の事なんかは考えていない偽善者達のダイアログだろう。解決する意思などないのだから、税金の無駄そして時間との無駄。
評価のためだけのパフォーマンス。どんなシステムを導入しようが、スクールカウンセラーを増やそうが、問題を直視しない体質になっているのだから
税金の無駄そして時間との無駄。
「3点目の町内小中学校の児童・生徒、保護者、地域の方々等からの教育相談の実態と課題についてですが、各小中学校における教育相談窓口での対応のほか、教育研究所が平成24年度に受けた相談として、小学校の保護者から10件、中学校が14件となっております。
主な相談内容として、小学校については、教諭への指導の不満、児童間のトラブル、中学校については、不登校生徒の悩み、生徒間のトラブル、教諭への指導の不満等であります。相談を受けている研究所では、問題の実態を速やかに把握、確認し、学校長と連携を図りながら解決に向けて取り組んでいるところであります。
不登校については、家庭状況、生徒間のトラブル等、さまざまな要素と経過があります。学校では、校内はもちろんのこと、スクールカウンセラーや適用支援員の配置により、早期の問題解決を図っており、相談者の立場に立った個々の状況に応じ、
学校の相談室登校、学校だけでは解決できない場合の不適応支援教室こころの窓への入級なども選択肢に入れ、学校に戻れるよう復帰訓練等の対応をしながら支援体制を整えているところであります。」
平成25年第2回矢巾町議会定例会目次(矢巾町役場)
岩手県教育委員会も同じ問題を抱えているであろう。下記の研修もパフォーマンスだけであろう。
<教師といじめ>職員室の「雰囲気」次第 09/21/15(河北新報)
◎(上)情報共有
仙台市立中1年の男子生徒=当時(12)=がいじめを苦に自殺した問題では、男子生徒のSOSをくみ取れず、組織的な対応に至らなかった学校の課題が浮き彫りになった。教育現場はいじめ防止にどう取り組み、解決にはどんな壁があるのか。宮城県内外の教師たちに学校の実情を聞いた。(仙台・中1いじめ自殺問題取材班)
<人事評価で萎縮>
男子生徒の自殺を調査した第三者委員会は、生徒が通っていた中学校内の情報共有や連携の不十分さを指摘した。いじめの対応が担任ら一部教員にとどまり、学校を挙げての指導には結びつかなかった。
「情報共有が図られるかどうかは、職員室の雰囲気や人間関係が大きい」
学校の現状をこう話すのは仙台市内の中学校の男性教諭(59)。管理職の中には、いじめの情報を伝えても「担任の指導不足だ」と取り合おうとしない人もいるという。「人事評価を気にして、言うのをやめておこうと萎縮することはあるだろう」と語る。
教諭によると、同じ学年の教師間では情報交換を密にしても、学年が異なるとおろそかになる「学年セクト」も存在するという。
宮城県内の40代の女性講師は「報告しても無駄という雰囲気が強く、担任が1人で抱え込んでしまう」と憂う。いじめを認知したら学年主任に報告するルールが勤務先の中学校にはあるが「傷害や暴行など学校保険の対象となる事案でないと、校長や教頭には伝わらない。報告するようないじめがあれば(担任らは)翌年、高い確率で転勤になる」と話す。
<抱え込む担任も>
岩手県矢巾町では7月、いじめを受けていた中学2年の男子生徒(13)が自殺した。
同県の中学校に勤める女性教諭によると、男子生徒の自殺以降、いじめ対応について情報共有を心掛ける動きが広がっている。「なかなか言い出せない若手や、問題を抱えた生徒を任せられて多忙なベテランがおり、簡単なことではない。しっかり話ができる人間関係が重要だ」と風通しの良い職場づくりの大切さを指摘する。
宮城県内の60代の元小学校長も「全職員と保護者、教育委員会の情報共有が何より大切だ」と強調。「あるいじめ事案を担任が大したことないと判断しても、他の教師はそう思わない場合もある。担任が1人で抱え込んでしまうところに落とし穴がある」と訴える。
仙台市教委は今回の問題を受け、いじめに組織的な対応をするよう全市立学校に指示した。12歳の少年の悲劇を二度と繰り返さないためにも、情報共有を出発点にして学級や学年、立場の枠を超えた「学校力」の結集が求められている。
いじめ問題へのご意見をお寄せください。宛先は河北新報社報道部「仙台・中1いじめ自殺問題」取材班。ファクスは022(224)7947。メールアドレスはhoudou@po.kahoku.co.jp
学校だけの問題ではなく、町、市、そして県教育委員会の腐った体質に問題がある。校長にも問題はあると思うが、校長だけの個人的に問題ではないと思う。
<仙台いじめ自殺>説明責任果たさぬ学校 08/29/15(河北新報)
◎届かなかった叫び(上)沈黙
<具体名覆い隠す>
具体名をひたすら覆い隠す記者会見だった。
仙台市教委は21日夕、仙台市立中1年の男子生徒=当時(12)=が自殺していたことを明らかにした。
「昨年、市立中1年の男子生徒が自殺した」
「第三者委員会の調査で、校内のいじめが自殺と関連性があるとされた」
市教委が市役所で開いた会見で説明したのは、この2点がほぼ全て。男子生徒の氏名や年齢、学校名はもとより、実際には昨年9月下旬だった自殺の時期を問う質問にも答えなかった。
詳しい説明は拒み、公表遅れの理由なども含め「遺族の意向」と繰り返した。
情報管理は徹底されていた。市教委が宮城県教委に報告したのは20日。発表前日のことだ。
「県教委と市教委の意思疎通が十分でなかったのは大変残念」。村井嘉浩知事が24日の定例記者会見で苦言を呈するほどだった。
<生徒らも違和感>
市教委はその後、自主的に補足説明する場を設けていない。「事実は公表した」「遺族の意向もくんだ」という体裁を整えたことで責任を果たしたかのようにも映る。
具体名を消し去った「生徒の死」は事実の重さを揺るがしかねない。
24日朝、男子生徒が通っていた学校であった臨時の全校集会。校長が読み上げたのは、市教委が全市立学校に配布した再発防止を訴える緊急アピール文だけ。自校でのことには一切触れなかった。
「自ら命を絶ってはならない。私たち大人が必ず皆さんを守る」。抽象化された言葉は違和感を持って受け止められ「なんか違くない?」とささやく生徒もいたという。
学校側も「事実をつまびらかにしない」という姿勢では一貫している。
男子生徒の自殺後、担任の女性教諭は「(男子生徒は)家の都合で転校しました」とクラスメートに説明。学校はいじめに加わったとされる11人の生徒に実態調査の過程で事実を伝えたものの、他の生徒への説明はいまだにない。
<「先生たち怖い」>
市教委の発表後、学校周辺で取材する報道関係者らに対しては、同校の教諭らが「うちの学校だという証拠があるのか」と否定を装った。
校長は「市教委に聞いてほしい」の一点張り。28日夜の河北新報社の取材には「駄目、駄目。警察呼びますよ」と拒否した。
市教委と学校は説明責任を果たせているのかどうか。「遺族の意向」を理由にした沈黙の前で、生徒や保護者の間では「本当のことが知りたい」との思いが膨らむ。ある生徒は「先生たちの対応が怖い」とつぶやく。
男子生徒は「いじめが収まらない」と自殺の直前に言い残していた。12歳の少年が絞り出した叫び声が、実体を持って受け止められずにいる。
◇
仙台市立中1年の男子生徒がいじめを苦にして自ら命を絶った。学校や市教委の対応には問題点が次々と浮かび上がり、地域に疑問と不信が渦巻く。生徒の死は何を問い掛けているのか。経緯と現状を検証する。
(仙台・中1いじめ自殺問題取材班)
校長はどう考えているのか知らないが、もし自分が生徒ならこんな校長は必要ないです。
<仙台いじめ自殺>生徒ら「何を信じたら」 08/30/15(河北新報)
◎届かなかった叫び(中)混乱
<「かん口令」敷く>
三つの注意事項が生徒たちの心を再び波立たせた。
「臆測で物を言わない」「個人情報は出さない」「個人情報を出すと名誉毀損(きそん)になる」
いじめを苦に自殺した仙台市立中1年の男子生徒=当時(12)=が通っていた中学校。市教委による事実関係の公表から4日後の25日、教諭たちが生徒に示したのは真実ではなかった。「事実上のかん口令」と生徒、保護者の多くが受け止めた。
「うちと決まったわけではない」(教頭)。「本当の事が知りたい」という生徒や保護者の切実な願いに、学校側はかたくなな態度を崩さない。
校長が自校であったいじめ自殺に触れないまま、「命の重み」を説いた24日朝の臨時全校集会。ある生徒は、いじめに関与したとみられる生徒たちに反省するそぶりがないことを知り、「もう駄目」とショックで寝込んでしまったという。
保護者は「先生たちはまるで人ごとのような態度。子どもたちは何を信じていいか分からなくなっている」と嘆く。
インターネット上では、学校名や所在地など真偽不明のさまざまな情報が飛び交い始めた。真実を明らかにしない市教委と学校の対応が臆測に次ぐ臆測を呼び、ネット空間の過熱に拍車を掛ける。
自殺した男子生徒と同級の中学2年生たちの間でも、無料通信アプリLINE(ライン)でいじめに関する詳しい情報が出回り、動揺が広がっている。
<肩身狭い思いも>
塾などでは「○○中学の生徒」とレッテルを貼られ、肩身の狭い思いをしている。保護者の一人は「学校に行きたくないという生徒が大勢いる」と打ち明ける。
「地域に余計な動揺を与えるのを避けるため、公表したくなかった。要らぬ混乱を招いたのであれば大変申し訳ない」
自殺した男子生徒の両親は24日、あらためて談話を出した。混乱の責任を一手に背負おうとする痛々しさが文面ににじむ。
ある保護者は「愛する子どもが自殺した直後、親が冷静に対応できるはずがない。遺族の思いを、われわれは責めるべきではない」とかばう。
「昔からある学校側の事なかれ主義とその場しのぎの対応が、事態をより悪化させている」。住民の一人が地域の声を代弁する。
12歳の早すぎた死が問いかけた命の重み。混乱の渦中にある生徒、保護者、学校に疑心暗鬼が広がりつつある。
組織が腐ってしまうと再生は簡単ではない。腐った人間達は簡単には再生できない。再生や改善を望んでいない公務員を変えるのはかなり難しい。
思想や考え方を変えるのは難しい。民間でも難しいが、公務員はリストラ出来ないので仙台市エリアの教育は期待できない。子供がいじめられそうなら
仙台への引越しは避けるほうが良いであろう。
<仙台いじめ自殺>「死」伏せ説かれる「命」 08/31/15(河北新報)
◎届かなかった叫び(下)不信
<教訓生かされず>
電話の声は怒りで震えていた。
「いじめは報道された2件だけではない。学校では不登校やいじめが常態化し、(同級生が)怖くて教室に入れず、廊下で給食を食べている生徒もいる」
仙台市立中1年の男子生徒=当時(12)=が昨年9月下旬、いじめを苦に自殺した問題。仙台市教委が21日に事実関係を公表して以降、河北新報社には保護者や学校関係者から悲痛な叫びが続々と寄せられている。
校長は「相談事例は数件あるが、いじめと認識しているものはない」と現時点でいじめの存在を否定。生徒、保護者との現状認識の差は広がる一方だ。
「怒り、寂しさ、悔しさで体が震えた。息子の死が教訓になっていない」
「生徒の死後もいじめが続いていた」と報じた25日、両親が電話取材に応じ、苦しい胸の内を明かした。
両親は息子の死後、「くれぐれもこのようなことがないように」と学校側に念を押し、いじめ根絶に向けた取り組みを託していた。
学校はその後もいじめの連鎖を止められず、自殺した男子生徒へのいじめをエスカレートさせたとされる「謝罪の会」を本年度も開くなど、教訓を生かした形跡はない。
両親は「息子の時と同じ対応でいいのか」と不信感を募らせる。
<「まさか2度も」>
この中学校では1998年にも中1の男子生徒=当時(13)=が自殺し、学区内では「いじめが一因になった」と公然と語られていた。「同じ地域で子どもの自殺が2度もあるなんて…」と、絶句する住民は少なくない。
「学校が問題をうやむやにするため、いじめが止まらない。自校で自殺があったことを認めず、踏み込んだ指導ができるのか」と住民の一人は危惧する。
昨年秋の男子生徒の自殺は「遺族の意向」を盾に、この学校では「なかったこと」にされた。教員らは「新聞はでたらめ。信じないように」と、生徒たちに説明しているという。
自殺した男子生徒について、「転校した」と事実と異なる説明を受けていた同級生たち。今も友人の死を悼む機会を奪われたまま、校長や教員たちから「命の尊さ」を説かれている。
真実を直視しないまま、いじめをなくす学校再生の青写真を描けるのだろうか。不信が渦巻く学校に、きょうも生徒たちが通う。
淫行で逮捕の中学校教諭を懲戒免職 08/21/15(ABAニュース )
女子中学生にみだらな行為をしたとして7月27日に逮捕された八戸第2中学校の40歳の男性教諭が21日付で懲戒免職処分となりました。21日付で懲戒免職処分を受けたのは階上町に住む、
八戸第2中学校の倉谷幸伸教諭です。倉谷元教諭は2015年4月、相手が18歳未満と知りながら県内に住む女子中学生と五所川原市内のホテルでみだらな行為をしたとして7月28日に県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されました。
そして8月17日、罰金60万円の略式命令を受けました。県教育庁が8月6日に倉谷元教諭から直接事情を聴いて事実を認めたことから今回の処分を決めました。
岩手中2自殺のケースとは違い、かわいそうではあるが平田奈津美さんのケースはある意味では親と当人の責任だと思う。中学一年生が真夜中あたりから朝方まで
街中をふらついているのは問題だと思う。
「同中学によると、7月中旬の面談で担任教諭は、平田さんが夜間に外出していることを直接注意したが、夏休み中に野宿していたことは把握していなかった。」
野宿する事を知っていて注意しなければ問題であるが、野宿する事まで把握する必要は無いと思う。記事には書かれていないが、平田さんが夜間に外出している事を
彼女の親に伝えていたのか、当人だけだったのかが少し問題になりそう。彼女の親に夜間外出の問題を伝えていれば、教諭次第であるが、それ以上関わる義務はないと思う。
相次ぐ事件に教委「全ての子供の把握は困難」 08/19/15(読売新聞)
大阪府高槻市で、中学1年生の女子生徒が遺体で見つかるなどした事件は、学校の目の届きにくい夏休みに起きた。
川崎市の中学生男子殺害など児童生徒が巻き込まれる事件が相次いだことを受け、文部科学省や各地の教育委員会などは、夏休み前に安全確認や見守りを強化するよう呼び掛けてきたが、「全ての子供を把握することは困難」と頭を悩ませている。
大阪府警の調べでは、殺害され、遺体で見つかった同府寝屋川市立中1年、平田奈津美さん(13)と、行方不明となっている同級生の男子生徒(12)は12日夜から13日午後にかけ、2人で京阪寝屋川市駅付近などを行き来していたことが判明している。
同中学によると、7月中旬の面談で担任教諭は、平田さんが夜間に外出していることを直接注意したが、夏休み中に野宿していたことは把握していなかった。
懲戒免職で退職金はなし。小遣いと言うことは結婚している?退職金なしで大波乱かも??
小学校副校長、PTA会費など469万円着服 07/31/15(読売新聞)
PTA会費などを着服したとして、横浜市教委は31日、市立日吉台小学校の三戸さんのへ聡副校長(58)を懲戒免職処分にしたと発表した。処分は同日付。
市教委は刑事告発を検討している。
発表によると、三戸副校長は昨年6月~今年3月、PTA会費や学年費などの口座から十数回にわたり、計約469万円を引き出し、自身の借金返済に充てた。口座の通帳はいずれも三戸副校長が管理しており、3月末に当時の校長に打ち明けて発覚したという。引き出した金は、当時の校長から借りて弁済した。
市教委によると、三戸副校長は聞き取り調査に対し、「小遣いの不足分をカードローンで借りるようになり、返済額が数百万円に膨らんだ」と話している。学校は会計事務をすべて副校長に任せ、定期的な確認を怠っていたという。
「町教育委員会の越秀敏教育長は『調査報告書は詰めが甘い部分もあり、検証対象などは第三者委の調査で精査され増えるだろう』と話している。」
「調査報告書は詰めが甘い部分もあり」と言っているが、組織内での調査の限界、身内に甘い調査の現実、個々の関係者の独自の判断ではない可能性がある
背景での厳しい調査が暴露合戦になるリスクなどの理由で甘くなる理由しかないのではないのか?
岩手中2自殺:いじめ疑いさらに10件 生徒アンケートに 07/30/15(毎日新聞)
岩手県矢巾(やはば)町の中学2年、村松亮さん(13)がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、中学校のいじめ調査報告書で検証の対象になった行為13件以外にも、全生徒へのアンケートで「柔道のように投げていた」など、村松さんへのいじめが疑われる事例が約10件書かれていたことが明らかになった。学校側は「目撃が1件だけだと検証対象にはなりにくい」と説明しているが、8月にも設けられる第三者委員会で調査されることになりそうだ。
毎日新聞は、生徒に実施したアンケートの回答をまとめた文書を入手した。文書によると、直接見聞きしたことを尋ねた回答欄に「5、6月ごろ、男子が村松さんのことを柔道のように投げていた」「(6月ごろ、村松さんが)胸あたりをつかまれ突き飛ばされたり、髪の毛を引っ張られていた」など、報告書では触れられていない行為が約10件記されていた。
アンケートの回答を読んだ村松さんの父親(40)は「さらに調査が必要だということが分かった。第三者委でしっかり調査してほしい」と語った。
村松さんが通っていた中学校は村松さんの自殺を受け、今月7日に1〜3年生の生徒446人にアンケートを実施。さらに、教職員らへの聞き取り調査などから、校長をトップとした調査チームが、同級生らによる村松さんへの行為の中で検証すべきものを13件とし、うち6件をいじめと判断したとする報告書を26日にまとめていた。
校長は、13件を検証対象にした理由について「詳細は言えない。ただ、目撃が1件だけなら対象になりにくい」と説明。町教育委員会の越秀敏教育長は「調査報告書は詰めが甘い部分もあり、検証対象などは第三者委の調査で精査され増えるだろう」と話している。【二村祐士朗、近藤綾加】
<矢巾中2自殺>学校のいじめ判断 調査焦点 07/29/15(河北新報)
岩手県矢巾町で中学2年の村松亮君(13)がいじめを苦にして自殺したとみられ、通っていた中学校がいじめが自殺の一因と認めた問題で、町教委は8月初めにも、いじめの態様をあらためて検証し裏付ける第三者委員会を設置する。学校は調査報告書で6件のいじめを認定。いじめと自殺の因果関係や、学校がいじめと判断しなかったトラブルの調査が焦点となる。
学校は、調査でいじめが疑われた13事案のうち6件について「苦痛を感じていた」として、いじめと判断した。ほかの7件は「階段でズボンを下げられそうになった」「宿泊研修中のけんか」などだった。
校長は「(村松君の)当時の心境の裏付けが、生活記録ノートやほかの生徒の証言では得られず、判断を見送った」と説明する。
これに対して父親は「いじめは日常的な苦痛の積み重ねだと思う。これはいじめ、これはいじめじゃないという判断は納得いかない面がある」と反論する。
町のいじめ防止基本方針によると、第三者委は学識経験者や弁護士の5人で構成する。学校の調査報告書を参考に、新たに全校生徒と教員へのアンケートや聞き取りを実施する。
父親は委員の人選に関し、半数以上に遺族の意向を反映させることを要望。町教委は全面的に受け入れる方針を示している。父親は「第三者委は学校であったこと全てを明らかにしてほしい」と求めている。
問題が発覚するとどうなるのかわかっているのだから本望だろう。
女子生徒にみだらな行為など、高校2教諭を免職 07/24/15(読売新聞)
埼玉県教育委員会は23日、県南部の県立高の男性教諭(32)と、別の高校の男性教諭(52)の2人を懲戒免職、川口市立中の男性教諭(27)を減給10分の1(3か月)の懲戒処分にしたと発表した。
発表では、32歳の教諭は2014年秋から冬、副担任をしていた3年女子生徒と公園や自宅でキスなどをし、別の生徒に好意を伝えるメッセージを十数回送ったとされる。教諭は一部を否定している。52歳の教諭は12年夏から14年春、顧問をする部活動の女子生徒とホテルで数回みだらな行為などをしたとされる。
中学教諭は14年秋から15年春、学校行事の準備中、卓球をしていた1年男子生徒を平手打ちするなど計3回体罰を行ったとされる。
やっと警察の聴取。相手が警察だから嘘ばかり付くと偽証罪が適用されるかも??
あとは警察がどのような質問をするかがポイント?警察のさじ加減で質問が決まる。警察が突っ込んだ質問をするのか、形だけの質問をするかで
事実を簡単にいえるのか、黙秘するのか、決まるかもしれない。
岩手中2自殺、複数の生徒から県警が任意で聴取 07/24/15(読売新聞)
岩手県矢巾町の中学2年生の男子生徒(13)がいじめ被害を訴えて自殺したとみられる問題で、県警がほかの生徒らに対し任意で話を聞いていることが24日、わかった。
生徒は複数人に上るとみられ、県警は暴行などの行為がなかったかどうかなどについて確認を進めるとしている。
男子生徒の父親は12日、同級生から暴力をふるわれたなどとして県警に被害を届け出ていた。また、男子生徒が担任と日々やりとりをしていた「生活記録ノート」や、生徒の書き込みなどが残っていた携帯型ゲーム機などを県警に提出していた。
県警はすでに、教職員らから任意の事情聴取を進めており、学校での男子生徒の様子などを調べている。
担任に責任の全てを押し付けて幕引きか?
判断ミスとすれば、
「当時の校長によると、担任は生徒指導担当の教員や校長、副校長らにも相談。9月には別の教員とともに、村松さんやトラブル相手の生徒を交えて面談し、指導したという。当時の校長は『生徒がトラブルを抱えれば、学年の教員や管理職で絶対に共有する。村松さんのケースはいじめの前段階で対処し、一定の解決をみたと考えた』と説明。」岩手中2自殺:「いじめ」訴え昨春から 07/15/15(毎日新聞)
そして、
「学校では4月に校長が代わったが、当時の校長は『継続的ないじめはないと思い、引き継ぐ必要はないと判断した』という。」岩手の中2死亡、「いじめ訴え」引き継がず 1年時校長 07/16/15(朝日新聞)
が事実であれば、当時の校長、松村さんの件で相談を受けて現在も同じ学校にいる教員にも責任があることは明らかだ。
保護者向けのアンケート及び
<矢巾中2自殺>いじめ防止策 校内研修せず 07/16/15(河北新報)を実施しなかった校長にも管理及び監督の責任があると思う。
「学校側は、担任が校長に報告するなどの対応をしなかった点を「判断ミス」と認め」となっているから、学校側としては担任に責任を押し付けて、
学校の組織としては責任がないと言っているのだろうか?そうだとすれば、この学校は外部からの大きなメスが入らないと変わらない組織だと思う。
第三者委員会は学校とは独立して調査していると(勝手な勘違いかも?)思うので、どのような報告になるか次第で、第三者委員会の公平性と能力が
わかると思う。
岩手の中2死亡、担任対応「判断ミス」 学校側認める 07/24/15(朝日新聞)
岩手県矢巾(やはば)町で中学2年の村松亮さん(13)が自殺した問題で、村松さんが自殺をほのめかす記述を書いたノートを提出した際、担任は心配して声をかけたものの、その後に具体的な対策を取らなかったことが関係者の話でわかった。学校側は、担任が校長に報告するなどの対応をしなかった点を「判断ミス」と認め、26日に公表する調査報告書に盛り込む方針。
村松さんは担任に毎日提出していた「生活記録ノート」に6月29日、「もう市(死)ぬ場所はきまってるんですけどね」と書いた。
関係者によると、学校が担任から聞き取ったところ、これを読んだ後に村松さんに「大丈夫か」などと声をかけ、村松さんは「大丈夫」という意味合いの返事をしたという。
この応答から担任は「ふだんと変わらない」と判断。「明日からの研修たのしみましょうね」と、7月1日から行う宿泊研修についてコメントを書いた。村松さんは7月5日夜に自殺した。
学校調査に60人が「いじめ見聞きした」 07/16/13(産経新聞)
「岩手・中2自殺」学年主任いじめ証言の同級生脅し「余計なこと言うな」 07/13/15 ( J-CASTテレビウォッチ)
「余計な事を言うな」等を学校主任から言われたかどうか生徒に質問するべき。また、関与した
「同じ学級の4人」岩手の中2自殺、少なくとも4人がいじめ関与 07/23/15(朝日新聞)が他の生徒に対していじめの証言に対して圧力をかけていたのか
質問するべきであろう。
質問はいじめを見聞きした生徒からはじめるべきであろう。その後、学校主任および少なくともいじめに関与した4人に質問するべきであろう。
嘘を付いた場合、多くの証言と食い違いが出るはずだ。そうすれば証言の信頼性も推測できる。
県警、生徒聞き取りへ 暴行の有無を確認 07/23/15(産経新聞)
岩手県矢巾町の中学2年村松亮君(13)がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、岩手県警が月内に同級生や同じ部活の生徒らから、事情を聴く方針を固めたことが23日、捜査関係者への取材で分かった。いじめに関わった可能性があると名前が挙がった複数の生徒も含まれ、暴行容疑に当たる事案がなかったか慎重に捜査を進める。
捜査関係者によると、県警は村松君が担任に提出していた生活記録ノートの提供を受け、既に教職員からは聞き取りを始めた。ノートに同級生らからの暴力を示唆する記述があった上、村松君が机に頭を打ち付けられていたとの情報も得ており、目撃した生徒がいないか、村松君の学校での様子などを詳しく聴く。
学校はいじめがあったと認める内容を盛り込んだ調査結果を、26日をめどにまとめ、遺族や他の生徒の保護者に順次説明。町教育委員会は今後、第三者委員会を設置し、亡くなった原因を調べる。
「 2020年東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が22日、施設建設や交通インフラ整備など大会にかかる経費の総額について『最終的に2兆円を超すことになるかもしれない』と述べた。
森氏はこの状況を踏まえ、新国立競技場の建設を含めた大会にかかる経費の当初見積もりだった約7千億円も、約3倍に膨れあがると想定したとみられる。」
これでは詐欺商法と同じだ。嘘の誘い文句で引き込み、引くのも進むのも難しい状態に落として、迷っているうちに最悪の事態となる。
2兆円-約7千億円=約1兆3千億円 森氏が、新国立競技場で国はたかが2500億円も出せないのかと考えるはずだ。約1兆3千億円は
とてつもない額だ。
新国立競技場の予算は800億円そして新国立競技場の建設を含めた大会にかかる経費の当初見積もりだった約7千億円に戻せば、処分の必要はないのでは?
たぶん大会にかかる経費の約7千億円に戻せないので処分という事?
舛添知事「処分できぬなら文科相辞任しかない」 07/24/15(読売新聞)
2020年東京五輪・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の建設計画の白紙撤回を受け、東京都の舛添要一知事は23日、ツイッターへの書き込みで、最大の責任は文部科学省にあるとし、「担当役人の処分は免れない。組織の長にその処分ができないのなら、(下村文科相は)自らが辞任するしかない」との考えを示した。
さらに、「それが大人の世界の常識であり、役人一人の更迭もないのなら、国民は許さない」と続けた。
元教え子と飲酒、わいせつな行為…臨時講師免職 07/23/15(読売新聞)
兵庫県教育委員会は22日、女子生徒にわいせつな行為をしたとして、20歳代の県立高校臨時講師を懲戒免職に、体罰を行った明石市内の県立高校の男性教諭(39)を減給10分の1(3か月)の懲戒処分とした。
発表によると、臨時講師は、5月4日夜から、転校した元教え子の女子生徒が18歳未満であることを知りながら、飲食店でともに飲酒した後、翌5日にはカラオケ店でわいせつな行為をした。
女子生徒とは、同じ学校だった昨年9月頃から無料通話アプリ「LINE(ライン)」で相談を受けるなどし、好意を抱いていたという。県教委は同11月、特定の生徒とLINEなどでの必要以上のやりとりを禁止する通知を出している。
明石市の教諭は、顧問を務めていたサッカー部員ら7人の生徒に、備品や道具を忘れてきたことなどを理由に平手打ちした。この教諭は、別の学校に勤務していた時にも、体罰で厳重注意処分を受けていた。
「 学校側は、いじめ防止対策推進法がいじめの定義とする「苦痛を感じていた」かどうかを、それぞれの証言に当てはめて検討。いじめに該当するかどうかを判断する。」
学校側はこれまでの方針で苦痛に感じていないと判断したいと思う。
<矢巾中2自殺>いじめ証言十数件 07/23/15(河北新報)
岩手県矢巾町で中学2年の村松亮君(13)がいじめを苦にして自殺したとみられる問題で、亡くなった後に学校が実施したアンケートと聞き取り調査の結果、村松君へのいじめの疑いがある証言が十数件あったことが22日、町教委への取材で分かった。町教委は同日、学校がまとめる調査報告書を26日にも遺族に示すことを明らかにした。
町教委によると、アンケートは全校生徒445人に行い、村松君と同じクラスや部活の生徒には聞き取り調査をした。「悪口を言われていた」「体をたたかれていた」など、いじめの疑いのある証言が十数件に絞られた。
学校側は、いじめ防止対策推進法がいじめの定義とする「苦痛を感じていた」かどうかを、それぞれの証言に当てはめて検討。いじめに該当するかどうかを判断する。
学校が遺族に示す調査報告書は、村松君へのいじめの有無や生徒間トラブルへの全教員の対応状況の検証を盛り込む。町教委が設置する第三者委員会にも提出する。
第三者委の設置や人選について、村松君の父親は21日、町総合教育会議が主導するよう要望した。
高橋昌造町長は「教育長には遺族の気持ちを誠実に受け止め、寄り添った対応をするよう指示している」と述べ、引き続き町教委に対応させる意向を示した。
岩手の中2自殺、少なくとも4人がいじめ関与 07/23/13(朝日新聞)
岩手県矢巾(やはば)町で中学2年の村松亮さん(13)が自殺した問題で、村松さんへのいじめに関与した生徒が少なくとも4人いることが関係者の話で分かった。学校は26日にも公表する調査報告書に盛り込む方針だ。
学校は生徒や教職員へのアンケートや聞き取り調査をし、22日までに終えた。生徒の目撃証言などを精査し、村松さんが2年生になって以降、同じ学級の4人が関わったことが分かった。学校は、村松さんの遺族から「いじめに関わった生徒を特定してほしい」との要望を受けていた。
報告書では、村松さんが1年生時から、悪口を言われたり体をたたかれたりするなど、数件から十数件のいじめを受けていたことを認定する。村松さんが今月5日に自殺した大きな要因がいじめだったとも認定する方針だ。
学校は26日にも報告書を村松さんの遺族や、生徒の保護者らに公表する方向で調整している。(斎藤徹)
オリンピック招致に反対だったが、やはり騙されやすい日本国民は騙されていた。
「 2020年東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長が22日、施設建設や交通インフラ整備など大会にかかる経費の総額について『最終的に2兆円を超すことになるかもしれない』と述べた。
森氏はこの状況を踏まえ、新国立競技場の建設を含めた大会にかかる経費の当初見積もりだった約7千億円も、約3倍に膨れあがると想定したとみられる。」
これでは詐欺商法と同じだ。嘘の誘い文句で引き込み、引くのも進むのも難しい状態に落として、迷っているうちに最悪の事態となる。
2兆円-約7千億円=約1兆3千億円 森氏が、新国立競技場で国はたかが2500億円も出せないのかと考えるはずだ。約1兆3千億円は
とてつもない額だ。
オリンピックも白紙撤回してほしいぐらいだ。これで増税された分が迂回して予算に使われるのか、又は借金が増えて将来の国民の負担となるのだろう。
「五輪全体にかかる予算について『ロンドンで2兆5000億円、ソチで5兆円。東京は最終的に2兆円を超えるのではないか』との見通しを述べた。」
他を比較して正当化するのならロンドン五輪スタジアム(収容人数約8万人)、約800億円を超えないように新国立競技場を建設してほしい。
新国立で森氏「組織委に発言権なく、関係ない」 07/23/15(読売新聞)
2020年東京五輪・パラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長は22日、日本記者クラブで記者会見し、「計画白紙」となった新国立競技場について、「正直言って大変迷惑している。組織委には発言権はなく、どういうものを造ろうと関係ない」などと述べ、不快感を示した。
森会長は冒頭、「こんなことになるとは、夢にも考えていなかった」と予想外だった点を強調。一部で自身を含めた責任論が出ていることを念頭に、「よく間違われて報道されることがあって、決して愉快な話じゃない」などと話した。
ただ、責任の所在については、「どこにあるというのは難しく、犯人を出してもプラスはない」と述べるにとどめた。
今月末にはクアラルンプールで国際オリンピック委員会(IOC)の総会が開かれるが、「(IOCへの)説明は今、悩んでいる。みんなで考える」とした。
また、五輪全体にかかる予算について「ロンドンで2兆5000億円、ソチで5兆円。東京は最終的に2兆円を超えるのではないか」との見通しを述べた。
日本スポーツ振興センター(JSC)を今回のプロジェクトから外すべきだ。契約や建設の進め方に問題がある。
損害賠償と不安と煽るJSCと文科省の動きがおかしい。また、まったく違う構造やコンセプトだとザハ・ハディド氏の情報はほとんど役に立たないと
思う。1300億円がコスト圧縮の修正案でも2520億円となった明確な理由が説明されなければザハ・ハディド氏を使用する事はとても危険だ!
ロンドンのアクアティクス・センターが当初建設予算の3倍の結果となった。
【侍青の風】「新国立競技場」の建設費と維持費を、他のスタジアムと比べてみると 05/23/15(サムライブルーの風)
主にJリーグで使用される他のスタジアムの建設費である。
横浜にある日産スタジアム(7万人収容)が約600億円、
埼玉にある埼玉スタジアム(6万人収容)が約350億円、
東京の味の素スタジアム(5万人収容)が約300億円、
大阪の長居スタジアム(5万人収容)が約400億円、
愛知の豊田スタジアム(4万5千人収容)が約300億円、
新潟のビッグスワン(4万人収容)が約300億円、
神戸のノエビアスタジアム(3万人収容)が約230億円
新しく大阪にできる
ガンバ大阪のスタジアム(4万人収容)が約140億円。
上記のその他のスタジアムの建設費を考えれば、
8万人収容だとは言え、新国立競技場の建設に
1600億円~3000億円もかけるのは
いくらなんでもおかしいことが分かってもらえると思う。
この自分の意見に対して、
「いやいや、オリンピックは特別なんだ!」
「その他のスタジアムと一緒にしてもらっては困る!」
「オリンピックのスタジアム建築をケチるなんて、
節約するところを間違っている!」
そういった意見もあるかもしれない。
じゃあ、最近のオリンピックで作られた
各都市のスタジアムの建築費は
いくらだったのかを調べてみよう。
ロンドン五輪スタジアム(収容人数約8万人)、約800億円
北京五輪スタジアム(収容人数約9万人)、約500億円
アテネ五輪スタジアム(収容人数約7万5千人)、約350億円
シドニー五輪スタジアム(収容人数約11万人)、約680億円
直近のロンドン五輪スタジアムは
最も安く見積もった新国立競技場の建設費1600億円の
半分の値段の800億円であり、
8万人の新国立競技場よりも、
はるかに収容人数が多い11万人の
シドニー五輪スタジアムだって、
建設費は新国立よりも約1000億円も安く済んでいる。
ザハ氏側、新国立関わりたい…政府に交渉申し入れ 07/22/15(日刊スポーツ)
新国立競技場の計画案を白紙撤回された英建築家ザハ・ハディド氏の事務所が、政府に直接交渉を申し入れたことが21日、設計関係者への取材で分かった。デザインをゼロベースで見直す場合でも約2年間かけて行われた基本、実施設計を生かせるところは生かし、切迫する工期のリスク軽減などを提案する。
設計関係者によると、ザハ・ハディド氏を含めた事務所の総意は、新国立のプロジェクトに最後まで関わりたい意向。現時点で違約金などを求める段階ではないという。サッカーW杯招致のため、常設で8万席などの条件が出ており、このままでは総工費は下がらず、白紙撤回があまり意味をなさないとの見方もある。今週中にも政府関係者と直接対話をしたい考えだ。
また、ザハ事務所への白紙撤回の通知が簡易の書類1枚だった。安倍晋三首相が白紙撤回を表明した17日夜、契約を取りやめる旨の書類が添付されたメールが事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)から送付されたという。
「ハディド氏から損害賠償を求められる可能性もあり、JSCの鬼沢佳弘理事は『契約破棄について、近くハディド氏側と面談して交渉したい』と話した。」
ロンドンのアクアティクス・センターが当初建設予算の3倍の結果となった事を例に挙げて、もし損害賠償を求められたら、カウンター訴訟を起こすべきだ。
もし、日本スポーツ振興センター(JSC)とザハ・ハディド氏側と日本国民に知られてはならない隠し事があれば、JSCはカウンター訴訟は
しないであろう。相手も勝つため、又は、出来るだけ良い条件で示談にするために、いろいろな事を裁判で言う可能性はある。
日本スポーツ振興センター(JSC)が損害賠償を想定しない契約書を準備していたのであれば、日本スポーツ振興センター(JSC)にも責任はある。
責任を追及するべきだ。
21日の県教育委員会議で、八重樫勝教育委員長が矢巾町の中学2年の男子生徒がいじめを苦にして自殺したとみられる問題で「県中学校総体で(男子生徒が通っていた)
学校の生徒に『お前ら出る資格があるのか』などとやじを言った大人がいると聞いた」と指摘する一幕があった。同問題の影響は学校の内外に大きく広がり、生徒は学習や部活動などで不自由な学校生活を強いられている。
保護者からは子どもの状況を案じる声が聞かれ、学校への一層の支援が必要だ。
岩手県教育委員会はいじめを放置し、自殺者が出るとどのような影響や結果になるのか今回の事件を通して嫌でも学んだと思う。
「県中学校総体で(男子生徒が通っていた)学校の生徒に『お前ら出る資格があるのか』などとやじを言った大人がいると聞いた」について程度の問題ではないと
言えばそうかも知れないが、いじめを隠蔽した、又は、いじめがないように偽装した教諭達や校長に比べれば軽い。
東芝の不正会計を考えると、いじめに関与していなくともその学校の生徒であるだけでネガティブな影響や
不適切な対応を受ける事は不愉快な経験であるが、問題を先送りして最悪の結果となった場合、いじめに関していなくとも影響を受ける事を経験することは生徒がそこから
何かを学べば全てマイナスでは無いと思う。
この学校を卒業し教師になる生徒がいれば、何もなかった学校を卒業した生徒よりもいじめに対して深く考えられると思うし、いじめのサインを知りながら
いじめがなかった事にした教諭達や校長のようにはならないと思う。不愉快な経験であっても克服できれば将来に生かせる経験となると思う。
ただ、皆、同じ結果とはならないし、克服できない人もいるかもしれない、副作用のリスクのある予防接種のケースのように、自己責任と運次第と言う
場合もある。判断する力を段階を追って子供達に身に付けさせる事が重要。
多くの教育委員会は逃げる事ばかりの対応が多いと感じる。
中総体でやじ、生徒へ影響懸念 矢巾・中2自殺問題 07/22/13(岩手日報)
21日の県教育委員会議で、八重樫勝教育委員長が矢巾町の中学2年の男子生徒がいじめを苦にして自殺したとみられる問題で「県中学校総体で(男子生徒が通っていた)学校の生徒に『お前ら出る資格があるのか』などとやじを言った大人がいると聞いた」と指摘する一幕があった。同問題の影響は学校の内外に大きく広がり、生徒は学習や部活動などで不自由な学校生活を強いられている。保護者からは子どもの状況を案じる声が聞かれ、学校への一層の支援が必要だ。
心ないやじがあったこともあり、18~20日の県中学校総体の競技会場で同校は「校名」を出すことを控える様子がうかがわれた。
岩手日報社の取材や保護者らの証言によると、県央部の会場では自校の試合の時以外は学校の横断幕を掲げなかった。県南部の会場では選手以外の生徒の会場入りを見合わせ、県央部の会場では横断幕を掲げなかった。
校内では調査が始まった7日から、2学年や調査に深く携わる一部の教諭の授業が自習となることが多く、学習面への影響が出ている。報道各社の取材にいじめの実態などを証言した生徒がほかの生徒らに嫌がらせを受けていると話す生徒もおり、新たなトラブルの発生も懸念される。
「21日に町役場を訪れた父親は『第三者委の設置には、教育委員会だけでなく、町長にも関わってほしい』と話した。」
町長に関わってほしいと要望したのは良いアイディアだ。町長に対しても調査報告書に対して責任が伴ってくるので町長が良心的であるなら
おかしなことに目を瞑らないであろう。
しかし村社会的な構造であれば、公平な調査は難しいかもしれない。
<矢巾中2自殺>父親、教育会議が第三者委人選を 07/22/13(河北新報)
岩手県矢巾町で中学2年の村松亮君(13)がいじめを苦にして自殺したとみられる問題で、村松君の父親は21日、いじめの有無などを究明する第三者委員会の設置をめぐり「町教委への不信感が高まった」として、運営や人選は町長をトップとする町総合教育会議で行うよう町に要望した。
町教委は同日、弁護士会などに出した第三者委メンバーの推薦依頼を取り下げた。町議会が23日に審議する予定だった第三者委の設置条例案も提出を見送る。
村松君の父親によると、第三者委の人選に遺族の意向を反映するよう求める要望書を17日に提出した際、町教委は「既に委員選定の推薦を依頼しており変えられない」と難色を示した。その後、一転して遺族の意見を聞きながら人選をやり直す方針を示した。
越秀敏教育長は「遺族に不信感を抱かせてしまい申し訳ない。町長の回答をみてもう一度話し合いの場を持ちたい」と話した。
岩手県教委は同日の定例教育委員会で、全公立校が昨年度策定した「いじめ防止基本方針」の運用状況などに関する調査を7月中に始め、8月末にも結果を取りまとめる方針を示した。
8月初めに全小中学校長を対象に、いじめ防止研修会を開催することも報告された。昨年、滝沢市であった中学2年男子の自殺をめぐり、いじめとの関連性があったと結論付けた第三者委の報告書を全校長に配布し、対処策を検討する。
岩手中2自殺:「遺族の意向に沿った第三者委運営」要望 07/21/13(毎日新聞)
岩手県矢巾町の中学2年、村松亮さん(13)がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、村松さんの父親(40)は21日、いじめを調べる第三者委員会が設置された場合、遺族の意向に沿った運営や調査の透明化を求める要望書を同町に提出した。
同町は、第三者委設置に関する関係条例案を今週中にも町議会に提案する予定で、委員の人選も進めていた。しかし、設置に関して父親への相談がなかったことから、父親らは17日、「委員の半数以上を遺族が推薦する有識者から選んでほしい」と要望。同町は条例案の提案を先送りすることにした。
21日に町役場を訪れた父親は「第三者委の設置には、教育委員会だけでなく、町長にも関わってほしい」と話した。さらに、遺族側の要望を聞いてもらえるよう、臨時の町総合教育会議の開催も求めたという。【二村祐士朗】
「ハディド氏から損害賠償を求められる可能性もあり、JSCの鬼沢佳弘理事は『契約破棄について、近くハディド氏側と面談して交渉したい』と話した。」
ロンドンのアクアティクス・センターが当初建設予算の3倍の結果となった事を例に挙げて、もし損害賠償を求められたら、カウンター訴訟を起こすべきだ。
もし、日本スポーツ振興センター(JSC)とザハ・ハディド氏側と日本国民に知られてはならない隠し事があれば、JSCはカウンター訴訟は
しないであろう。相手も勝つため、又は、出来るだけ良い条件で示談にするために、いろいろな事を裁判で言う可能性はある。
日本スポーツ振興センター(JSC)が損害賠償を想定しない契約書を準備していたのであれば、日本スポーツ振興センター(JSC)にも責任はある。
責任を追及するべきだ。
新国立の旧計画、59億円契約済み…大半戻らず 07/22/15(読売新聞)
「白紙」に戻った新国立競技場の建設計画を巡り、事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)は21日、これまでに国内外の設計事務所やゼネコンと計約59億円の契約を結んでいたことを明らかにした。
2014年末で契約期間を終えたものは支払いが確定しており、今年分についても業務内容に応じて多くが支払われる見込みという。
JSCが民主党の会合に提出した資料によると、英国在住の女性建築家、ザハ・ハディド氏の事務所に対してはデザイン監修料として約14億7000万円の契約を締結。このうち15年度の1億7000万円分の支払いについては今後、調整する。ハディド氏から損害賠償を求められる可能性もあり、JSCの鬼沢佳弘理事は「契約破棄について、近くハディド氏側と面談して交渉したい」と話した。
契約したのに白紙撤回したのだから仕方のない事。ただ、1300億円で提示したコンペがコスト圧縮の修正案でも2520億円になった責任は明確に
しなければならない。安藤氏及びザハ・ハディド氏は予算を知っているのだから責任はあるはずだ。賠償「最大100億円」試算とも新聞記事に
書かれているが、カウンター訴訟を起こしたほうが良い。1300億円がコスト圧縮の修正案でも2520億円になったのだから責任はあるはず。
安藤氏はコンペの参加者に伝えてあると断言しているのだからカウンター訴訟は可能と思う。また、あえてコストが高くなる事が推測できる
デザインを選んだ安藤氏には責任があると思う。常識で考えても、曲線が多い建造物のほうが割高になる事は予測できる事。
新国立競技場の59億円契約済みの全てが戻らなくとも、1000億円以下で建設できる国立競技場であれば白紙撤回したメリットは必ずある。
本当はもっと安く出来たはずであるが、文科省、日本スポーツ振興センター(JSC)、安藤氏そして有識者達の責任のために税金の無駄遣いの
結果となった。1000億円以下で建設できる国立競技場にするべきだ。デザインさえ限定すれば絶対に出来るはずだ!
新国立競技場、59億円契約済み 相当部分戻らぬ見込み 07/21/15(朝日新聞)
新国立競技場建設の事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)は21日、ザハ・ハディド氏のデザインに基づく旧計画で、デザインや設計などで計約59億円の契約を結んでいると明らかにした。計画は白紙になったが、これらの業務は出来高払いのため、相当部分が戻らない見込みだ。
JSCがこの日、民主党の「東京オリンピック・パラリンピックに係る公共事業再検討本部」に提出した資料によると、ハディド氏のデザイン監修が約14億7千万円。日建設計、梓設計、日本設計、アラップ設計共同体の設計業務が36億5千万円。施工予定業者で設計にも携わった大成建設、竹中工務店の技術協力が約7億9千万円。
ハディド氏との契約は17日の同本部の会合では17億円と説明していたが、21日は、13億円を支払い済みで、さらに今年度分1億7千万円のうち契約解除前の業務の報酬が必要なうえ、業務中止のための追加費用が発生すると説明。損害賠償を請求される可能性もあるとした。また設計業務については「若干残っている部分があれば返還をお願いする」、技術協力は「一部削る余地があるかも」としており、関係各社と協議する。
新国立競技場をめぐっては、文部科学省が当初想定の2倍近い2520億円で建設する計画を6月29日に発表。JSC有識者会議も今月7日に了承した。しかし建設費が膨らんだことに批判が集中したため、安倍晋三首相が17日に計画を白紙に戻すと表明した。デザインや設計業務の約59億円とは別に、有識者会議の了承を受けて9日に大成建設と契約したスタンド部分の工事約33億円分については、JSC幹部は「資材調達していなければキャンセルできるはず」としている。(阿久津篤史)
「文科省は無能力」について同じである。たぶん、無能ではなく仕事をしないキャリア達。そして自分達が勉強してきた以外については
何も知らない税金泥棒。プライドだけはあるが勉強しかしてこなかったキャリアは、彼らが知らない世界や分野に関して素人。
1800億円の予算も多すぎ。IOC会長は「デザイン重要でない」と言っているのから平凡なデザインでも良いから、メンテナンスや維持に
お金がかからない構造にして内装の機能に少しお金をかけたら良いと思う。文科省は何にもわからないから検討を付ける事さえ出来ない思う。
ある程度の方針を決めないと予算など推測する事も出来ないはずだ。デザインに重視すると簡単な構造にならない場合が多い。建設し易い構造で
あればコストはかなり削減できるはずである。建設しやすい=コスト及び納期に有利になる。
メンテナンスや維持に関与する仕事をしている以外の人達には理解し難いかもしれないが、メンテナンスや維持が簡単な仕様で建設や建造されていれば
建設後の維持及び管理コストが安くなる。インターネットで検索すればいろいろな情報が得られると思うが、デザインと設計のコンペにすれば
決められた予算で実現可能なデザインに絞られるはずである。デザインだけのコンペを行い、予算だけを決めた時点で文科省が無能者の集団である、
または、追加が発生しても国民に負担させようと考えいたと推測できる。どちらであっても許せない事だ。
最後に建設額が大きければ、大きいほど儲けを出しやすい。建設費の何パーセントをごまかして誰かにあげるとか、迂回させて献金するとか、
プールするとか、いろいろ出来る。天下りの受け入れの予算も確保できる。悪いほうに取れば、文科省の人間は天下りの確保を考えていたのかもしれない。
舛添都知事「文科省は無能力」「密室の議論が原因」 ブログで提言公表 07/20/15(産経新聞)
東京都の舛添要一知事は20日、2020年東京五輪・パラリンピックのメーン会場となる新国立競技場建設計画の見直しに対する提言をブログで公表した。これまでの失策について責任の所在を明らかにし、関係閣僚による組織を立ち上げ、情報公開を進めることなどを求めた。
提言では「文部科学省は無能力・無責任で、これが最大の失敗の原因」と指摘。安倍晋三首相をトップに関係閣僚らによる「新国立競技場建設本部」を組織し、政治家のほか、中央官庁やゼネコンなど民間企業、アスリートらの作業委員会を立ち上げるべきだ、としている。
また、「失敗の第二の原因は、一部の政治家や関係者やゼネコンなどが密室で議論したことにある」とし、議論を公開して、国民を巻き込んでの合意形成が必要とした。
IOC会長は撤回評価…「デザイン重要でない」 07/19/15(読売新聞)
【セントアンドルーズ(英)=風間徹也】国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長は18日、ゴルフの全英オープンを開催中の英セントアンドルーズで記者会見し、2020年東京五輪・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の建設計画が白紙撤回されたことについて、「問題を先延ばしにせず決断したのは良かった」と評価した。
バッハ会長は五輪の競技場に求める条件について、「唯一の関心は選手と観客が使いやすい、最先端のスタジアムであること。デザインはあまり重要ではない」と語った。また、撤回の理由が建設費の高騰だったことについては「日本は妥当な金額で素晴らしい競技場を造ると確信している」と語り、5年後の五輪開催に問題はないという認識を示した。
「 村松さんについて2年生の教員の間では友人が少なく、配慮が必要な生徒だという認識は共有されていたということですが、いじめをうかがわせるノートの内容が伝わっていなかったことから、
町の教育委員会は、いじめがあったとした上で、基本方針にもとづいた校内での組織的な対応が不十分だったことを認め、今週中にもまとめる予定の調査報告書に盛り込む方針です。」
おかしな表現である。いじめの認識はないが「 村松さんについて2年生の教員の間では友人が少なく、配慮が必要な生徒だという認識は共有されていた」
配慮が必要な生徒であるならなぜ担任はいじめを疑わせる「生活記録ノート」について一切報告をしていないのか?また、友達が少なく、配慮が必要な
生徒との認識があれば、彼が所属するバスケットボール部の顧問とも情報を共有する必要があると思わなかったのか?
「岩手・中2自殺」学年主任いじめ証言の同級生脅し「余計なこと言うな」 07/13/15 ( J-CASTテレビウォッチ)との記事があるが、
なぜこの学年主任はこのような事を言ったのか?このような威圧的な教師に情報を言う生徒はいてもかなり少ないだろう。
「町の教育委員会は、いじめがあったとした上で、基本方針にもとづいた校内での組織的な対応が不十分だったことを認め、今週中にもまとめる予定の調査報告書に盛り込む方針です。」
「学校は、村松君が担任に提出した生活記録ノートのコピーの提供を警察から受けた。1年時のノートにも「まるでいじめられるような気分でいやです」(昨年5月1日)などと、いじめをうかがわせる記載があり、関係する生徒への聞き取りを行うとしている。」
岩手の中2自殺、学校が中1時のいじめ調査 07/16/13(日本経済新聞)の情報は共有されなかったのか。
「電車に飛び込んで自殺したとみられる岩手県矢巾やはば町の中学2年の男子生徒(13)が、1年時に担任とやりとりしていた『生活記録ノート』でもいじめ被害を訴え、『もうげんかいです』と書いていた。
担任らは当事者同士の話し合いなどで問題解決を図っていたが、学校は町教育委員会にいじめの報告をしていなかった。」「もう限界」ノート記述…昨年のいじめ報告せず 07/12/13(読売新聞)
これだけの事実があれば組織的な対応が不十分だったではなく、組織的に対応しない学校の体質があった、又は、口裏あわせでかなりマイルドな表現を
調査報告書に書こうとしていると思える。どうですか、越秀敏矢巾町教育委員会教育長そして松尾光則(元教育長)矢巾町教育委員会教育委員長!
ノートの内容 共有されず 07/19/13(NHK岩手)
矢巾町で中学2年生の男子生徒がいじめをうかがわせる内容を学校のノートに書き残し、自殺したとみられる問題で、ノートの内容が担任からほかの教員に伝わっていなかったことが学校の聞き取り調査でわかりました。
町の教育委員会は、校内での組織的な対応が不十分だったことを認め、調査報告書に盛り込む方針です。
矢巾町の中学2年生の村松亮さん(13)は、担任の教諭とやりとりする「生活記録ノート」にいじめをうかがわせる内容を記し7月5日に自殺したとみられています。
この問題を受けて中学校が、当時の学校や担任の対応について教職員34人から聞き取り調査を行った結果、いずれも、「ノートの内容について相談はなかった」などと答え、担任からほかの教員に伝わっていなかったことがわかりました。
中学校はいじめを防ぐための基本方針で、生活記録ノートなどを活用し、教職員の間で情報交換しながらいじめの早期発見に努めることなどを定めています。
村松さんについて2年生の教員の間では友人が少なく、配慮が必要な生徒だという認識は共有されていたということですが、いじめをうかがわせるノートの内容が伝わっていなかったことから、町の教育委員会は、いじめがあったとした上で、基本方針にもとづいた校内での組織的な対応が不十分だったことを認め、今週中にもまとめる予定の調査報告書に盛り込む方針です。
調査報告書、いじめ認める内容 矢巾の中2自殺 07/19/13(岩手日報)
矢巾町の中学2年の男子生徒がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、学校が今週中をめどにまとめる調査報告書にいじめを認める内容を盛り込むことが18日、関係者への取材で分かった。生徒アンケートや聞き取り調査を踏まえて判断した。いじめと自殺の因果関係の記載は結論を得ていないとみられる。第三者委員会の人選は白紙に戻し、遺族の要望を踏まえて再検討する。
学校は生徒死亡後、生徒445人にアンケートを実施。その後実施した生徒127人への聞き取り調査では、男子生徒と学級や部活が異なる生徒だけで、約60人がいじめを見聞きしたと回答した。
いじめに関与したとみられる生徒や教職員への聞き取りなども踏まえ、報告書の作成を進めている。いじめと自殺の因果関係に関する内容の報告書への記載は検討中だ。
男子生徒が担任とやりとりする生活記録ノートには「づ(ず)っと暴力、ずっとずっと悪口」「氏(死)にたい」などの記述があり、学校が6月に実施したアンケートでは「いじめられたりする時がよくあります」と回答していた。
岩手中2自殺 いじめ認める 学校が報告書記載へ 07/19/13(スポニチ)
岩手県矢巾町の中学2年村松亮君(13)がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、中学校が、いじめがあったと認める記述を、来週をめどにまとめる調査報告書に盛り込むことが18日、学校や町教育委員会への取材で分かった。
学校は村松君の死後、生徒や教職員を対象にアンケートや聞き取りによる実態調査を行った。少なくとも約60人の生徒が村松君へのいじめを見聞きしたことがあると回答した。同町の越秀敏教育長は「たとえわずかなことであっても、受けた側に心理的な影響があればいじめだ」と述べ、村松君のケースがいじめに当たるとの考えを示した。
越秀敏矢巾町教育委員会教育長は発言を修正せざるを得ない状況に追い込まれたのか?
中学校、報告書で「いじめ」認める方針 名前挙がった生徒にも確認 07/18/13(産経新聞)
岩手県矢巾町の中学2年、村松亮君(13)がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、中学校が、いじめがあったと認める記述を、来週をめどにまとめる調査報告書に盛り込むことが18日、学校や町教育委員会への取材で分かった。
学校は村松君の死後、生徒や教職員を対象にアンケートや聞き取りによる実態調査をした。少なくとも約60人の生徒が村松君へのいじめを見聞きしたことがあると回答した。名前の挙がった生徒らにも事実確認しており、こうした調査結果を踏まえて判断した。
町の越秀敏教育長は「たとえわずかなことであっても、受けた側に心理的な影響があればいじめだ」と述べ、村松君のケースがいじめに当たるとの考えを示した。町は同日、「いじめ問題対策連絡協議会」を開き、再発防止策などを検討。
村松君は7月5日夜、JR矢幅駅で列車にはねられ死亡した。担任に提出していたノートには、「もうつかれました」「死にたいと思います」などと書かれていた。
岩手の中2死亡、第三者委の委員選定に父親参加へ 07/18/13(朝日新聞)
岩手県矢巾町で中学2年の村松亮さん(13)が自殺したとみられる問題で、町教育委員会は18日、いじめの有無を検証するために設ける第三者委員会の委員選びに村松さんの父親(40)も参加してもらうことを明らかにした。
父親は「町が選ぶ委員だけで構成される第三者委は公平性に欠ける」として、遺族の声を反映するよう町教委に求めていた。18日に会見した越秀敏・町教育長は「遺族の意向を尊重することは大切で、要望に応えることにした」と述べた。
すでに委員5人について県教委や医師会などに推薦を依頼していたが、取りやめて白紙に戻すという。これにより第三者委の立ち上げは、8月以降にずれ込むとみられる。(角津栄一)
膨れあがった工費、背景に「無責任の連鎖」 07/18/15(読売新聞)
新国立競技場の建設計画の総工費が膨れあがった背景には、コストについての責任の所在があいまいな「無責任の連鎖」があった。国民負担が真剣に議論された様子は見られない。
「私も1300億円、どうかなと思っていた」
見直しが決まった英国在住の女性建築家ザハ・ハディド氏のデザインについて、国際デザインコンクール(コンペ)審査委員長だった建築家の安藤忠雄氏は16日の記者会見でそう話した。選考当時はデザイン重視でコスト面への意識が低かったことを認めたが、「私たちが任されたのはデザイン選定まで」と強調、責任はないとの主張に終始した。
デザインの決定を受けて計画の策定を進めてきたのは、文部科学省所管の独立行政法人「日本スポーツ振興センター(JSC)」だ。JSCの河野一郎理事長は今月7日、読売新聞の取材に対し、「文科省からハディド氏のデザインをもとに建設計画を進めるよう指示されていた」とし、JSCには計画を変更する権限がないと主張した。
政府内には「JSCが大規模施設の建設にかかわった経験は少なく、ゼネコンとの交渉など無理だ」という声もあった。特殊構造の「キールアーチ」に巨額の費用がかかるなどの理由で、今年春になって総工費は当初の1300億円から、3000億円を超えるまで膨れあがることが判明した。
下村文科相は、東京都と費用負担をめぐる協議に乗り出したが、舛添要一都知事は強く反発。5月18日に下村氏と会談後、記者団に「都が負担する根拠がない。誰が責任者で、誰に責任を問えばいいのか」といらだちをあらわにした。
舛添氏と論争を繰り広げた下村氏は6月9日の記者会見で、責任の所在について、「第一義的にJSCにある」としつつ、「明確な責任者がどこなのかわからないまま来てしまった」と反省の弁を口にした。与党内には「文科省の対応がずさんすぎた」(自民党中堅)との批判が強い。
文科省幹部は「首相や大臣が『国際的に信頼を失う可能性がある』と答弁してきただけに、覆した政府の判断は信じがたい」とぼう然としていた。
大体、文科省、お前達にも責任があるだろ!「国際的に信用を失う」だと?だったら鳩山元総理のCO2 25%削減の国際公約で既に信頼を失って
いるから問題ない!お前達の勝手な解釈を勿体付けるな。
文科省、お前らは基本設計もない段階で予算の1300億円を超えない事をただの絵だけでどうやって確認したのか?お前達が無能だから
こうなったとは思わない事が信じられない。申しわけと思わない、国民に負担を押し付ける事に関しても悪いとは思わないのだろう。
文科省が無能者達の集団である事を世界に発信したことははずかしくないのか?ザハ・ハディド氏デザインのロンドンオリンピックのために建設された
アクアティクス・センターが当初建設予算の3倍の結果となった事は知っているのか?お前らを見ていると腹が立ってくる。

最初の建設予算の3倍をかけて建造する価値を見つけられない。だから多くのイギリス人達からも批判を受けたのであろう。
もしかすると文科省は建設コストが予算オーバーになることをうすうす知っていたのではないのか?それを納期とか、国際的信用とか言いながら
天下り先の確保に動いていたのではないのか?責任者が明確でないのも確信犯的にしたのではないのか?エリートが揃っていながら考えられないわけがない。
岩手の中2自殺では学校がいじめゼロにするためにいろいろな抜け道を考えていた。そう考えると
文科省そしてそれに乗った安藤にかなり責任がある。安藤は建築士の資格も持っているそうだ。デザインだけのコンペ。しかし1300億円の予算は伝えたと
無責任な対応。何かが隠されていたのでは?
新国立、土壇場での「白紙」に歓迎と困惑 07/18/15(読売新聞)
2020年東京五輪・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の建設計画が17日、土壇場で白紙に戻った。
計画を批判し、撤回を求めてきた建築家らはこの日の安倍首相の決断を歓迎した。一方、一部契約が済み、走り始めた計画の突然の撤回に、驚きや困惑を隠せない関係者もいた。
首相官邸での会議を終えた下村文部科学相は「多くの国民の皆さん、アスリートから、ご心配や問題視する意見が出ていたので、約1か月前から(計画の)見直しをしていた」と切り出した。決断が17日になった理由については「ラグビー・ワールドカップには間に合わないが、五輪には間に合うことが今日確信できた」と説明した。ただ、責任問題を問われると「検証する中で適切に判断する」と言葉を濁した。
下村文科相に設計のやり直しを求める提言書を出した、東大名誉教授で建築家の大野秀敏さんは、安倍首相が白紙撤回を明言する映像を見ながら「これ以上、決断が遅れたら完成が間に合わない時期で、ラストチャンスだった。我々の主張が社会に浸透したという意味では良かった」とうなずいた。
今後の課題については「時間がないので、国は早急に、どのような施設にするのか方針を打ち出さなくてはならない」とし、「透明性を確保した上で案を決定し、東京の品格を上げるような施設にしてほしい」と注文を付けた。
同じく現行のデザインに反対していた1級建築士の森山高至さんも、「巨大な『キールアーチ』で屋根を支える特殊構造を続ける限り、非常に高額になることを首相は理解してくれたのだろう。問題が大きくなったことで、多くの人が計画に詳しくなり、疑問を持つようになった結果でもある」と話した。
その上で、「今からコンペになっても、間に合わせるためのアイデアは色々ある。多くの建築家が応募すればコンペが盛り上がり、再び五輪へのムードも高まるだろう」と期待を寄せた。
一方、白紙撤回に驚きの声も上がった。文科省幹部は「首相や大臣が『国際的に信頼を失う可能性がある』と答弁してきただけに、覆した政府の判断は信じがたい」とぼう然としていた。
現行案を捨ててやり直すことについて「要項作成や業者選定など、全てゼロからやり直しをする。本当に間に合うのか」と不安をにじませた。
「文科省はハディド氏側にデザイン監修料の一部として昨年度までに13億円を支払い済みで、契約解除時に違約金を支払う条項は設けていないと説明。ただ、政府の調査では、過去の判例から違約金や賠償金として『10億円から最大100億円』を支出せざるを得ないとの数字も出た。
巨額の賠償金を支払うことになれば、新たな批判を呼び起こすのは確実だ。」
文科省、ばかじゃないの!契約書の時に建設費用が例えば30%以上アップした時には損害賠償とか、解約の時には例えば10%とか決めておくのは常識。
その契約書に同意しなければ契約しなくても良いし、事前に納得した企業や建築家だけでコンペをすればよかった。
なんか日本人であることがはずかしくなるし、嫌になる。こんなにお金をどぶに捨てるような使い方をする公務員のために税金を払うのは空しい。
新国立「白紙」 首相、森氏説得したA4文書…国交省に作成指示 07/18/15(産経新聞)
■「私は現行計画見直す」
「2019年ラグビー・ワールドカップ(W杯)日本大会には間に合いませんが、お許しいただきたい」
安倍晋三首相は17日午後、首相官邸5階の執務室で、2020年東京五輪・パラリンピック組織委員会会長の森喜朗元首相にこう頭を下げた。
それでも不満そうな表情の森氏に首相が示したのが、建設計画を見直した場合の工期などを示した1枚の紙だった。
「ギリギリ間に合うと希望的なことを言ってできないとかえってまずいでしょう」
森氏は、内容を確かめると小さな声で応じた。
「それじゃ、やむをえませんね」
首相が示したA4の文書は、国土交通省などが作成したものだった。もう一度、コンペをやり直して半年以内に設計を決定し、20年春に完成させ、五輪には間に合わせるという計画見通しが示されていた。
首相が工期などの計画見直しを文部科学省に指示したのは6月2日頃だった。総工費や工期など現状計画の変更が可能かどうか検討するよう伝えた。
「計画の見直しを再検討してみてほしい」
これに対し、文科省の回答はかたくなだった。
「できません」
文科省は、国際オリンピック委員会(IOC)での首相演説などを根拠に、建築家ザハ・ハディド氏のデザインは「国際公約」と見なしていた。下村博文文科相も公の場で「既存計画を進める以外ない」と表明していた。
ただ、12年にデザインを国際公募した際に「1300億円程度」という条件の総工費はふくれ上がり、6月29日の文科省の正式発表では2520億円になっていた。ロンドンなどの過去の開催地に比べても高すぎるとの批判は強まった。
政府高官は「安全保障関連法案と違い、国立競技場問題では全部のマスコミが批判的だ」と警戒。首相も周辺に「アーチが無駄遣いの象徴のようになっている。世論が持たないかもしれない」と懸念を口にするようになっていた。
また、安保関連法案の審議を通じ、内閣支持率はじりじり下がっていた。さらに五輪にも建設が間に合わないかもしれないとの情報に、首相が下村氏を呼んでただしたが、下村氏は「努力する」と繰り返すのみ。しびれを切らした首相はついに文科省だけでなく、国交省にもこう指示した。
「では、私は現行計画を『見直す』。それを前提に検討してほしい」
■首相、最後まで悩み抜き…賠償「最大100億円」試算
安倍晋三首相が新国立競技場の計画見直しで、国土交通省や文部科学省に念入りに検討させたのは、2020年東京五輪・パラリンピックまでに建設が間に合うのかという工期と、現行計画より総工費を抑えられる見通しが立つのかというコストの問題だった。
加えて大きな問題となったのは、現行計画を白紙にした場合には、デザインしたザハ・ハディド氏側に支払うべき損害賠償などが発生する可能性があることだった。文科省はハディド氏側にデザイン監修料の一部として昨年度までに13億円を支払い済みで、契約解除時に違約金を支払う条項は設けていないと説明。ただ、政府の調査では、過去の判例から違約金や賠償金として「10億円から最大100億円」を支出せざるを得ないとの数字も出た。巨額の賠償金を支払うことになれば、新たな批判を呼び起こすのは確実だ。
このため首相も最終決断に踏み切るまで悩み抜いていたようだ。首相は9日夜の会食で、次世代の党の松沢成文幹事長に「下村(博文文科相)さんは『絶対大丈夫』と言っている」と話し、松沢氏が「見直さないと世論が持たなくなる」と指摘すると、首相は苦り切った表情を浮かべた。
また、計画変更の難関の一つは、五輪大会組織委員会会長の森喜朗元首相の説得だった。14日には自民党幹部から首相周辺に「森氏は変更に慎重だ」という情報が入った。今月末にクアラルンプールで開かれる国際オリンピック委員会(IOC)総会で森氏自身がメーン会場の説明をする予定になっているためだった。
森氏には自分が説明し、説得するしかない-。審議中の安全保障関連法案の衆院通過後に森氏と会談する日程も前から入っていた。
17日の首相と森氏の会談が終わり、下村氏や遠藤利明五輪相が執務室に招き入れられると、森氏はラグビーの合言葉を引用して言った。「首相が決めたことだ。みんなで団結してやろう。ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン(一人はみんなのために、みんなは一人のために)」 (水内茂幸)
矢巾町教育委員会はひどいな!越秀敏矢巾町教育委員会教育長の意向だけでなく松尾光則(元教育長)矢巾町教育委員会教育委員長も
了承している事なのか?
岩手県滝沢中2自殺…カッターナイフ向けるも「遊びの延長」 07/16/14(Girls Channel)
との報告書が昨年提出された。しかし
<滝沢中2自殺>第三者委「いじめあった」 03/26/15(岩手日報)で覆されている。
大津いじめ自殺事件の遺族が介入した事は村松亮さんの父親にとっては良い事であろう。経験がないと後手になってします。個人的な経験だが
公務員の言葉や約束をそのまま信用してはいけない。疑問に思ったら騙されていると想定して対応する事。相手が嘘を付いていると思ったら
メモでも録音でも良いから証拠を残しておく事。嘘を付く事になれている公務員であれば、忘れたとか、記憶にないとか、証拠がないとか
平気で言ってくる。証拠がなければ泥沼。言った、言わないの低レベルな戦いになってしまう。
裁判になっても同じ事が言える。事実であるのか、真実であるのかはそれほど重要ではない。証拠がなければ判断材料とならないので
悔しい思いをする、又は、証拠がない場合よりも時間がかかってしまう。
公務員の言葉や約束が信用できないについては裏切られたり、そのような経験がない人には理解できないかもしれない。
しかし、想定して対応したほうが良い。
矢巾町中2男子自殺・父親が大津いじめ自殺事件の遺族と対面(岩手県) 07/17/13(鹿児島読売テレビ)
矢巾町の中学2年の男子生徒がいじめを訴え自殺した問題で、この生徒の父親が17日、滋賀県大津市でいじめを受けて自殺した男子生徒の父親と対面した。矢巾町教育委員会にいじめの実態を調査するため23日に予定されている第三者委員会の設置について要望書を提出した。
要望書を提出したのは、いじめを訴え、今月5日に列車に飛び込み自殺した矢巾町の中学2年、村松亮さん13歳の父親と2011年10月に滋賀県大津市でいじめを受けて自殺した当時中学2年生の男子生徒の父親。大津市の中学2年生の自殺は、おととし6月のいじめ防止対策推進法の制定の大きなきっかけになった。
17日提出された要望書には、客観性と公平性が保たれる委員会を組織することや、第三者委員会が行うアンケートの調査結果について、学校側が修正を加えることができないようにすることなど7点が記されている。大津市の父親は「お父さんに第三者委員会の設置について、今までまったく説明していなかった。
何も言っていなかったら23日に決まってる。決まった後、事後報告するつもりでしたかと言ったら、教育長に声を荒げられて、ちょっと驚いた」と話していた。この父親は、このあと矢巾町の亮さんの自宅を訪れ、仏前に手を合わせた。
BBCニュースとtheguardianが取り上げている新国立競技場デザイン変更など計画見直しについての記事を読んだ。
イギリスはサッカーよりもラグビーが人気があるので、オリンピックの事よりもラグビーW杯の事で失望しているようだ。
ザハ・ハディド氏(British architect Zaha Hadid)のデザインは初期の予算よりも高額になった事(ロンドンオリンピック)が過去にもあった事が書かれている。
経験したイギリスとしては驚く事ではないのであろう。安藤は建築家であるのに、そのような情報や推測は出来なかったのだろうか?素人ではあるまい。
theguardianの記事に「Jim Heverin, project director at Zaha Hadid Architects, said the rising cost of the stadium was not a result of the design, instead blaming the increasing cost of materials.
“Our teams in Japan and the UK have been working hard with the Japan Sports Council to design a new national stadium that would be ready to host the Rugby World Cup in 2019,
the Tokyo 2020 Games and meet the need for a new home for Japanese sport for the next 50 to 100 years,” he said. 」
ザハ・ハディドアーキテクツのプロジェクトディレクター、Jim Heverinは建設費の高騰はデザインの結果ではないといっている。
ロンドンオリンピックで建設費高騰に一切触れていないし、根拠がない。外国人と仕事をしていて思うのが、彼らの言葉をそのまま信用してはいけない。
信用できる根拠が提示されている、経験から彼らの言い分に妥当性があると判断できる、又は、信用していないが拒否する選択肢がない場合以外は、
言葉をそのまま鵜呑みにすると、被害を被る、又は後悔する事になる。
プロジェクトディレクター、Jim Heverinは日本スポーツ振興センター(JSC)とかなり親密なコミュニケーションを取ってきたような表現をしている。
事実すれば日本スポーツ振興センター(JSC)は批判されていないが、かなりの責任があるのではないのか?
最後に、
森元総理「国がたった2500億円出せなかったのかね」( 07/17/15 (テレ朝ニュース)
は日本の財政問題に関心がない証拠だろうね。たった2500億円と言うのであれば、税金で年金受給額を上げればよいし、大学や高校の授業料の
無料化も良いだろう。ガソリン税も下げればよい。財政問題があるから出来ないのだろ!企業の非正規社員の増加はコストカットの結果。
ギリシャを見ていると政治も国民も人事だった。無視できない状況になって気がついた。港も売れ、空港も売れと言われる状況が日本のも着た時に
必要以上の税金を投入した新国立競技場はどれほどの価値が付くのか?
森元総理「国がたった2500億円出せなかったのかね」( 07/17/15 (テレ朝ニュース)
新国立競技場の建設計画見直しを受け、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の会長・森元総理大臣がコメントしました。
森喜朗元総理大臣:「ああいう、でかいものやったことないんだよ。スーパーゼネコンと話し合うような行為をしたことないわけですよ。
JSCだけじゃないですよ、文科省もそうですよ。国がたった2500億円も出せなかったのかねっていう、そういう不満はある。何を基準に『高い』と言うんだね。皆、『高い、高い』と言うけれど」
Japan scraps 2020 Olympic stadium design 07/17/15 (BBC NEWS)
The Japanese government has decided to scrap its controversial design for the stadium for the 2020 Tokyo Olympics and Paralympics.
Prime Minister Shinzo Abe said his government would "start over from zero".
The original design, by British architect Zaha Hadid, had come under criticism as estimated building costs almost doubled, reaching $2bn (£1.3bn)
Mr Abe says the new stadium will still be completed in time for the games.
However, the delay means that the stadium will no longer be ready in time for the 2019 Rugby World Cup, which Japan is also hosting.
World Rugby said it was "extremely disappointed" and was "urgently seeking further detailed clarification".
Japanese officials say the contract with Zaha Hadid's architecture firm will be cancelled, and a new design chosen within six months.
Zaha Hadid Architects said that the stadium the firm had designed could be built cost-effectively.
"It is not the case that the recently reported cost increases are due to the design," the firm said in a statement.
The real challenges were "increases in construction costs in Tokyo and a fixed deadline", it said, adding that building costs in Tokyo were higher than many other places as the risk of earthquakes meant that strict safety standards were needed.
Under the original plans, Tokyo's stadium would have been bigger and more expensive than any of its recent predecessors.
It drew increasing criticism as estimated costs spiralled from $1bn to $2bn.
The futuristic design of the stadium also drew attention, with architects likening it to a turtle or a bicycle helmet.
Announcing the cancellation on Friday, Mr Abe said: "I have been listening to the voices of the people and the athletes for about a month now, thinking about the possibility of a review."
"We must go back to the drawing board," he added. "The cost has just ballooned too much."
He said that he had made the decision after being assured that it was still possible to complete construction of a new design in time for the Olympics.
Dame Zaha Hadid has won several architectural awards, including the 2004 Pritzker Architecture Prize and the 2010 and 2011 Stirling Prizes.
She designed the London Aquatics Centre for the London 2012 Olympics and Paralympics, as well as Qatar's Al-Wakrah stadium for the 2022 football World Cup.
Commentators have described her projects as exuberant, extravagant and striking.
However, it is not the first time one of her designs exceeded the initial budget - the London Aquatics Centre's budget more than tripled from its initial budget of $116m (£75m).
Japan scraps Zaha Hadid plan for Olympic stadium 07/17/15 (theguardian)
Rugby authorities disappointed as they lose World Cup final venue due to decision to ‘start over from zero’ on Tokyo Games showpiece
The Japanese government has scrapped controversial plans for a dramatic Zaha Hadid-designed $2bn (£1.3bn) stadium envisioned as the focal point of the 2020 Tokyo Olympics, amid concern about rising costs and a growing public backlash.
The move sparked an immediate response from world rugby’s governing body, which was scheduled to host the 2019 World Cup final in the stadium and will now no longer be able to do so. It said it was “very disappointed” at the decision and would need to consider its options.
“We have decided to go back to the start on the Tokyo Olympics-Paralympics stadium plan, and start over from zero,” said the prime minister, Shinzō Abe, after a meeting at his office with Yoshirō Mori, chairman of the Tokyo 2020 organising committee. Organisers had already decided to scale back the original designs but they will now be scrapped altogether.
“I have been listening to the voices of the people and the athletes for about a month now, thinking about the possibility of a review,” he added. “We must go back to the drawing board. The cost has just ballooned too much.”
He said he had taken the decision after being reassured that there was still time to draw up new plans and complete the new stadium, on the site of the existing national stadium, before the 2020 Olympics. London began building its Olympic stadium in 2007, five years before the Games.
The ambitious design by the award-winning Iraqi-British architect Hadid, likened to a bike helmet, was due to not only host the opening game and final of the 2019 Rugby World Cup but also the 2020 Olympics and then become the new national stadium.
It was a key part of the bid that triumphed over Istanbul and Madrid in 2013 to win the right to host the 2020 Games. But the government has faced growing criticism as the estimated cost for the stadium almost doubled from original estimates to 252bn yen (£1.3bn).
Abe said he had obtained the consent of Mori, a former prime minister, and instructed the sports and Olympics ministers to conduct a review and draw up a new plan.
World rugby’s governing body immediately hit out at the decision and said it would seek urgent clarification of the plans for the 2019 World Cup, awarded as part of a push to grow the sport in new markets.
“World Rugby is extremely disappointed by today’s announcement that the new national stadium will not be ready to host Rugby World Cup 2019 matches, despite repeated assurances to the contrary from the Japan Rugby 2019 organising committee and Japan Sports Council,” said a spokesman.
Hadid, who has designed a similarly divisive stadium for the 2022 Football World Cup in Qatar, won the design contest for the Tokyo stadium in 2012, but faced a barrage of criticism over its appearance.
And amid growing international scrutiny of the costs and benefits of hosting a Games – something that the recently elected International Olympic Committee president, Thomas Bach, has promised to focus on – and domestic public pressure, organisers will now be forced to look for a more cost-effective solution.
Jim Heverin, project director at Zaha Hadid Architects, said the rising cost of the stadium was not a result of the design, instead blaming the increasing cost of materials.
“Our teams in Japan and the UK have been working hard with the Japan Sports Council to design a new national stadium that would be ready to host the Rugby World Cup in 2019, the Tokyo 2020 Games and meet the need for a new home for Japanese sport for the next 50 to 100 years,” he said.
“It is not the case that the recently reported cost increases are due to the design, which uses standard materials and techniques well within the capability of Japanese contractors, and meets the budget set by the Japan Sports Council. The real challenge for the stadium has been agreeing an acceptable construction cost against the backdrop of steep annual increases in construction costs in Tokyo and a fixed deadline.”
One Japanese architect, Arata Isozaki, described the design as “like a turtle waiting for Japan to sink so that it can swim away”. The Pritzker prize-winning architect Fumihiko Maki, 86, organised a symposium to protest against the scheme, and was joined by fellow leading Japanese architects Toyo Ito, Kengo Kuma and Sou Fujimoto. A petition was launched calling for the project to be scrapped.
Last year Hadid hit back at her peers’ complaints, telling Dezeen magazine: “I think it’s embarrassing for them. Many of them were friends of mine, actually the ones which I supported before like Toyo Ito, who I worked with on a project in London. I’ve known him for a long time.
“I understand it’s their town. But they’re hypocrites because if they are against the idea of doing a stadium on that site, I don’t think they should have entered the competition. The fact that they lost is their problem.
“They don’t want a foreigner to build in Tokyo for a national stadium. On the other hand, they all have work abroad. Whether it’s Sejima, Toyo Ito, or Maki or Isozaki or Kengo Kuma.”
The affair has echoes of the controversy that surrounded Hadid’s Aquatics Centre in London, where costs soared threefold to £269m as a result of the ambitious design, and certain elements had to be pared back.
The history of Olympic stadiums is chequered, due to the difficulties in planning for a future beyond the Games. The Beijing National Stadium, also known as the Bird’s Nest, is rarely used, although it will be pressed into action for the World Athletics Championships this summer, while the legacy issues with the venues built for the 2004 Games in Athens have become a symbol for the subsequent wider malaise in the country.
The the future of London’s Olympic Stadium, where total costs have now soared to £701m thanks to an ambitious plan to convert it into a multi-use venue that will become West Ham United’s home ground, has also proved controversial.
IOC vice-president John Coates, who is chair of the coordination commission that liaises with the host organising committee, said it had been reassured that the review would not affect the delivery of the stadium in time for the Games.
“The national stadium is a national project, which will serve the people of Japan for many years to come. This is why the Japanese government is best placed to decide on what is appropriate for this venue,” he said.
結局、これが現実。校長も人間だから失敗はある。隠す事自体、教育者としては問題ではないのか?違反すれば処分される事を身を持って子供達に
教えるべきだろう。
名城大付高の校長が酒気帯び運転の疑い 学校に報告せず 07/17/15(朝日新聞)
名城大付属高校(名古屋市中村区)の高須勝行校長が、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで、今月8日に愛知県警西尾署から交通切符(赤切符)の交付を受けていたことがわかった。高須校長は16日夜、取材に対し、「飲み会で酒を飲み、車を運転した」と事実関係を認めたが、学校には報告していなかったという。
本人や関係者によると、高須校長は8日午後10時ごろ、愛知県西尾市内で、酒気を帯びているにもかかわらず、乗用車を運転した疑いがある。パトロール中の西尾署員が停止を求め、呼気検査をした結果、アルコールが検出されたという。
高須校長は取材に対し、飲み会の出席者や酒量などについて明らかにしていない。学校に報告しなかった理由については「8月中旬に出頭を命じられている。その時点で報告し、進退をはっきりさせるつもりだった」と説明した。
高須校長は県教委高校教育課長や学習教育部長などを歴任し、2013年3月まで県立岡崎高校校長。現在は名城大学常勤理事で、付属高校校長を兼務している。
同校は17日、終業式だったが高須校長は欠席した。
実際の本音は別として、「見直した方がいい。もともとあのデザインは嫌だった」と森喜朗元首相はよく言った。
これで安く建設できるデザインを導入すればよい。違約金がいくらか知らないが、公表するべきだ。そして違約金の額を考えて
他のデザインしたほうがトータル的にかなり安くなるのか考えたほうが良い。
安藤よ、これでザハ・ハディド氏(64)の案に固執する必要は無い。選択した責任は安藤だ!
森喜朗元首相は「見直した方がいい。もともとあのデザインは嫌だった」とBS番組で言ったそうだ。
新国立、計画抜本見直しへ 森氏「生ガキみたいだ」 07/17/15(朝日新聞)
政府は17日、2020年の東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場の建設計画を抜本的に見直す方向で検討に入った。世論の強い反対を受け、総工費2520億円を削減し、現行計画の大幅な修正が必要だと判断した。同日午後、安倍晋三首相が見直しを表明する。東京五輪・パラリンピック組織委員会会長の森喜朗元首相も同日、見直しを容認する考えを示した。
政府は、競技場を19年のラグビーワールドカップ(W杯)で使う計画は断念して競技場が完成するまでの工期をのばし、デザインや工法などを大きく修正することで、総工費を圧縮する考えだ。
安倍首相は17日午後、森元首相と会談し、計画見直しへの協力を求める。森氏は17日、BS朝日の番組収録で、計画の見直しについて「した方がいい」と発言。「僕は元々、あのスタジアムは嫌だった。生ガキみたいだ。(現行案の2本の巨大アーチは)合わないじゃない、東京に」と語った。下村博文文部科学相は17日午前の記者会見で、安倍首相が下村氏とも会談し、記者会見するとの見通しを示した。
「僕は専門家じゃないけどキールアーチが問題なのは分かる。」
安藤、森喜朗元首相でもキールアーチが問題(コストアップ)になることぐらいわかるようだ。安藤は問題(コストアップ)はわからなかったのか?
わかっていたけど、選択したのか?
「それでも東京都が3000億円、組織委員会もトータルで7000億~8000億円はかかる。でも国は2520億円しか出さない。おかしいと思いませんか。3対8対2だよ。」
こういう考え方が日本の借金を増やしている。日本の借金を考え、将来に負担を減らすことを考えないから、日本の借金が増えていく。
格差が子供の教育に影響していると頻繁に記事になっているが、たいした問題でないのならなぜ取り上げるのか?自己責任で放置しておけばよい。
日本の財政がさらに苦しくなれば、良い仕事に就けない人達も含めて、増税して負担させればよい。蓄えのない老人は古い簡易宿泊所に押し込めておけば良い。
東京オリンピックのため、ラグビーW杯のために自慢できる新国立競技場を建設する方が優先されると言うことなのだろう!
森喜朗元首相 「新国立競技場の経緯すべて語ろう」(10/11ページ) 07/17/15(産経新聞)
僕は専門家じゃないけどキールアーチが問題なのは分かる。でもそれを前提にして基礎設計をやってるんですよ。キールアーチをやめるとなると全部やり直しだ。そうすると実施設計まで1年半かかり、プレ五輪に間に合わない。
それにキールの部材は7月中に発注しないと間に合わないそうだ。あまりに巨大だから全体を作って競技場に運べないから切断したのを運んで現場で接合するしかない。だから仮設工場もいるんですよ。
問題は総事業費だけど、そこは腹をくくって国家的事業だからということで納得してもらうしかないんです。大事なことは、五輪は国と東京都と組織委員会が協力してやることなんです。そして経費を徹底的に精査すること。僕が組織委員会にきて2000億円くらいはすでに圧縮したよ。
それでも東京都が3000億円、組織委員会もトータルで7000億~8000億円はかかる。でも国は2520億円しか出さない。おかしいと思いませんか。3対8対2だよ。
「現行案を撤回した場合のリスクは3点あった。まずザハ氏への違約金。『裁判になったら確実に負ける』(政府関係者)という懸念がつきまとった。」
心配する違約金はいくらだ?契約書の記載されているはずだろう。公表するべきだ!
建築家と呼ばれている安藤は1300億円の予算を全員に伝えていると言ったが、建設費用の1300億円の何パーセント以上の差が出た場合の損害金とか
契約に記載されいるのか?記載されていない、予算に関する責任の免除が記載されていないのであれば、デザインだけで決める無責任は誰の責任なのか、
安藤!曲線のアーチとアーチなしのデザインではどちらがコストがかからないか常識だ考えてもわかるよな!建築家でなくとも理論的な考えが出来る
人であれば理解できる。それをあえて、安藤が選んだ!基本設計前のステージまでと逃げているが、70歳にもなった建築家としてはお粗末。
メディアよ、誰が契約書を作成したのか?記事にしてほしい。
新国立競技場:「安保」衆院通過日、打開に動く 07/17/15(毎日新聞)
急浮上した2020年東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場の計画見直し論議は16日、新たな局面に入った。総工費2520億円に膨らんだ現行案に国民が猛反発する事態に、政府は現行案の抜本的見直しに踏み込む。現行案を維持して工期の調整などによる経費削減にとどめる慎重意見も残っているが、安全保障関連法案審議とともに、新国立競技場への対応が来夏に参院選を控えた政権の打撃となりかねない事態に安倍晋三首相の「政治決断」の段階となった。
16日朝、東京都内で開かれた自民党の議員有志でつくる新国立競技場勉強会。国民の猛反発に危機感を抱いた約70人が集まった会場は熱気に満ちていた。議論を主導した後藤田正純衆院議員は「文部科学省に聞くと、できません、間に合いません、国際公約ですという三つの答えが返ってきた。今までの進め方はいかがなものか」と口火を切ると、河野太郎衆院議員は「キールアーチをやめないと、この問題は解決しない。官邸はそれを外していいという議論をしていると理解している」と気勢を上げる。懸案だった安保法案が衆院通過したその日、政府は次なる懸案の打開に動いた。
キールアーチはイラク出身の建築家、ザハ・ハディド氏(64)による現行案の象徴でもある開閉式屋根を支える2本の弓状の巨大な構造物だ。それを外すことはデザインの抜本的な変更を意味する。その場合はザハ氏に新たなデザインを求めるのか−−。政府の判断は五輪招致の象徴と位置付けられながら、総工費高騰の代名詞となってしまった「キールアーチ」の撤回を辞さないものだった。
現行案を撤回した場合のリスクは3点あった。まずザハ氏への違約金。「裁判になったら確実に負ける」(政府関係者)という懸念がつきまとった。
続いて、文科省が設計のやり直しは完成まで61カ月を要すると試算した日程。それでは19年9月開幕のラグビー・ワールドカップ(W杯)に間に合わなくなる。横浜市の日産スタジアムの代替案も取りざたされたが、五輪組織委員会の森喜朗会長がW杯招致も尽力してきたこともあり「納得してもらえるか」(文科省幹部)と様子をうかがってきた。
また、現行案は安倍首相が東京五輪の開催が決まった13年9月の国際オリンピック委員会(IOC)総会でイメージ図を示したうえで建設を約束した。「総理が約束したことを撤回できない」(政府関係者)と、国際公約が独り歩きした理由だ。ただし、IOCはデザイン変更を「政府の判断次第」(ジョン・コーツ副会長)と公約とも思っていない。そこは安倍首相の判断次第だった。
しかし、現行案を推進した側は戸惑いを隠せない。事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)の関係者は見直しとなっても「そうですか。じゃあそうしましょうという話ではない」と話す。設計の全面見直しは見送り、キールアーチを備えた現行案のままで工期を延ばす選択肢もある。予定されている19年5月の完成時期を遅らせれば、資材や人材の確保に余裕ができ、総工費削減につながるという目算だ。政府内ではさまざまなシミュレーションが飛び交っている。
安保法案の審議で報道各社の世論調査では、安倍内閣の不支持が支持を上回っている。新国立への対応で選択を間違えば、さらに逆風が吹きかねない。今月末にはクアラルンプールでIOC理事会・総会が開かれ、新国立の状況を報告しなければならない。残された時間は少ない。【三木陽介、藤野智成、田原和宏、熊田明裕】
大きな借金を日本国民に負わせて何を言っているのか?安藤がはやく引退しないから、莫大な借金が追加されるリスクに曝されている。
経験がないのならもっと謙虚になれ。はずかしいほどの混乱の渦中にいる多くのギリシャ人に聞くと、こうなるのがわかっていたら
絶対にオリンピック招致に反対していた。そんな事をギリシャ経済が最悪になってから言ってももう遅い。年金を削減され
退職後の人生設計が狂った、無理して大学院まで行かせたのに子供が職を失い、援助しなければならない等の話を聞く。日本の
債務残高(対GDP比)はギリシャより悪い。ギリシャの国債の多くは外資や外国人により購入されているから違うといっても、
日本が大きな借金をしていることにはかわりない。そして、港や空港などは資産として考えられるとしても現在の評価額と
日本が危なくなってからの評価額では大きな違いが出てくるはずだ。結局、新国立競技場のように国民に負担を負わせようと考えて
多くのプロジェクトを企画し、姑息に国民が気付かないように負担を増やしている。
日本が、国際的信頼とか言うが、財政的に日本が行き詰るほうが将来的に日本の国際的な信頼を失うことになるとは考えないのか?
建築家としての小さい世界の話だろ!安藤は70歳まで生きてきて今回のような大きなプロジェクトは経験したこと無いのだろ?
自分の経験や価値観がいかに小さいのか、今回の経験を通してもまだわからないのか?
どれほどの人が困るのかは知らないが、安藤が引退しても困らないから、すみやかに引退してくれ!しかし、人生の最後で苦しい言い訳!
これまでの発言を帳消しにしてしまう!
建築家・安藤忠雄氏「80年以降に生まれた若者はダメ」「70、80の老人が引退したら日本は困る」 12/29/10(Quumu)
安藤忠雄の年収と妻について!建築作品と明言まとめ! 04/01/14(はづきちのまったりティータイム)
「有識者会議に出なかったから『すべて安藤の責任や』というのはちょっと、私はわからない。有識者は何十人もいる」
しかし、下記のリストで専門家は安藤だけではないのでしょうか?安藤は詳しく説明したのでしょうか?安藤は基本設計の前の段階で
建設費用は1300億円では納まらない可能性がある。基本設計前ではチェックのしようがない事を説明したのでしょうか?もし怠っていれば
責任はあります。安藤が建築家ではなく、文系の大学教授であれば言い分に妥当性はあるでしょう。しかし、安藤は建築家。他の有識者は
素人の集団。
逃げの言い訳をする事で人間性がわかる。テレ朝のやじうまプラスで萩谷順が安藤の説明についてコメントしていたが、この人間も何を言っているのか
わからない。安藤は必要ないので今後、一切出てくるな!責任があるのはデザイン選定までと言うのなら必要ない。
国立競技場将来構想有識者会議 委員名簿 (平成24年度)(日本スポーツ振興センター)
開けない人はここをクリック
安藤忠雄氏「2520億円、えーと思った」 07/16/15(読売新聞)
責任があるのはデザイン選定まで――。
新国立競技場の総工費が膨張している問題について、選考時の審査委員長を務めた安藤忠雄氏(73)が16日、初めて口を開いた。「2520億円と聞いて、『えー』と思った」と驚いたことを明かし、自身の責任は「デザイン選定まで」にとどまると繰り返し強調した。
■批判集中に不満
東京都内のホテルで午前11時過ぎから開かれた記者会見。安藤氏は、笑みを浮かべ、約250人の報道陣の前に姿を見せた。冒頭、「有識者会議に出なかったから『すべて安藤の責任や』というのはちょっと、私はわからない。有識者は何十人もいる」と自身に批判の矛先が向かっていることに不満を述べた。
安藤氏はさらに、デザイン選定から設計までの過程を記したパネルを示した。「私たちが任されたのは、デザイン選定まで」と強調し、「安藤に責任をなすりつけたらええんじゃないかと思うかもしれないが」とその後の費用高騰については責任がないとの認識を示した。
「安藤氏はグレーのジャケット姿で現れた。用意されたパネルを示しながら、2012年11月のデザイン選定以降は、調整に関わっていないと何度も述べた。総工費が2520億円に膨らんだことについて『もうからなくても国のためだ。それが日本のゼネコンのプライドではないか』と、建設会社との金額調整を求めた。」
「技術とコストについてはハディド氏と日本の設計チームによる次の設計段階でできるんじゃないかと思った」のは根拠のない安藤の勝手な判断。
その部分に関して責任がある。何も出来ないのなら、さっさと引退しろ!根拠のない勝手な判断で多くの金額が国民の負担となる。オリンピックなんて
必要ない。中止してもいいぞ、安藤!
新国立:「責任、デザイン選定まで」安藤氏コスト議論せず 07/16/15(毎日新聞)
「選んだ責任は感じるが、とりまとめはここまで。私は総理大臣ではない」。新国立競技場の基本デザインを選ぶ審査委員会で委員長を務めた建築家の安藤忠雄氏(73)が16日、東京都内で記者会見した。政府が計画見直しの検討を始める中、安藤氏はキールアーチと呼ばれる巨大な2本の弓状構造物が特徴のデザイン維持を求めつつ、批判が高まる総工費については自らの責任でないと強調した。
会見場の東京都千代田区のホテルには、200人を超える報道陣が詰めかけた。午前11時15分、安藤氏はグレーのジャケット姿で現れた。用意されたパネルを示しながら、2012年11月のデザイン選定以降は、調整に関わっていないと何度も述べた。総工費が2520億円に膨らんだことについて「もうからなくても国のためだ。それが日本のゼネコンのプライドではないか」と、建設会社との金額調整を求めた。
デザインが審査条件の1300億円で建設可能か検討したかについては「アイデアのコンペで、徹底的なコストの議論にはなっていない」と語った。今月7日の日本スポーツ振興センター(JSC)の有識者会議を欠席したことに関し「欠席しただけで全て私の責任と言われるのは分からない」と話した。
イラク出身で英国在住の建築家、ザハ・ハディド氏の作品が選ばれた経緯をたどると、審査の過程で安藤氏が強く推していた様子が浮かび上がる。
「日本の技術力のチャレンジという精神から17番がいいと思います」。12年11月7日。JSCが基本構想のデザインを募った国際コンクールの審査委員会で安藤氏は発言した。委員の一人であるJSCの河野一郎理事長が「いかがでしょうか」と尋ねると「賛成」の声が上がった。17番はハディド氏の作品だ。
情報公開請求で開示された議事録によると、2次審査に残った11点のうち、委員長を含む委員10人による投票では、ハディド氏の作品を含む3点が同点。だが、他の委員から「委員長の1票は2票か3票の重みがあると判断すべきかと思う」などと促され、安藤氏がハディド氏の作品を選んだ。審査委員会も、募集要項などを了承したJSCの国立競技場将来構想有識者会議も原則、非公開だった。
安藤氏はハディド氏の提案を「宇宙から舞い降りたような斬新な案に心を動かされた」と講評していた。【山本浩資、飯山太郎、武本光政】
「安藤氏は当時の審査について、『デザインの選定までが仕事だった。アイデアのコンペなのでコストについて徹底的に議論することはなかった。オリンピック招致に向け斬新でシンボリックなデザインということで選んだと思う。デザインを選んだ責任はあるが、技術とコストについてはハディド氏と日本の設計チームによる次の設計段階でできるんじゃないかと思った』と説明しました。」
デザインの部分だけで、コストについては議論していないと逃げるのであれば、安藤よ、お前は黙っていろ!それとも自費で足りない部分をだすのか?
新国立競技場 安藤氏「コストの徹底議論なし」 07/16/15(NHK)
新しい国立競技場の建設費が2520億円に膨らみ、政府内で設計自体の見直しなどを模索する動きが出るなか、最初のデザインを決めた審査委員会の委員長で建築家の安藤忠雄氏が初めて記者会見を開き、「デザインの選定までが仕事で、コストの徹底議論はしなかった」と説明しました。
新国立競技場の最初のデザインは2012年11月に安藤氏が委員長を務めた審査委員会で、1300億円の建設費の設定のもと、イラク人女性建築家、ザハ・ハディド氏の作品を最優秀賞として選びました。
安藤氏は、建設費が2520億円に膨らんだ改築計画を了承した今月7日の有識者会議を欠席しましたが、16日午前、都内のホテルで記者会見を開き、一連の経緯について初めて説明しました。安藤氏は当時の審査について、「デザインの選定までが仕事だった。
アイデアのコンペなのでコストについて徹底的に議論することはなかった。オリンピック招致に向け斬新でシンボリックなデザインということで選んだと思う。デザインを選んだ責任はあるが、技術とコストについてはハディド氏と日本の設計チームによる次の設計段階でできるんじゃないかと思った」と説明しました。
そのうえで、政府内で設計自体の見直しなどを模索する動きが出ていることについて、「ハディド氏のデザインは外す訳にはいかないと思うが、2520億円は高すぎ、もっと下がらないかなと思うので徹底的に議論して調整してほしい」と話しました。
デザイン変えないことが望ましい
安藤忠雄氏の記者会見のあと取材に応じたJSC=日本スポーツ振興センターの鬼澤佳弘理事は、政府内で設計自体の見直しなどを模索する動きが出ていることについて、「報道では理解しているが、正式に伝達や指示は受けていない」と述べました。
そのうえでザハ・ハディド氏のデザインを変更する可能性については、「これまでの決定の経緯や条件、それに約束などから国際的にも『変更は難しい』という判断があったので、変更しないことを前提に議論を進めていくのではないかと思う。
こうした判断に関係なく議論するということならば、変更という判断もありえないわけでない。ただ、安藤氏が言うように、基本的にはハディド氏のデザインで進まなければ日本の信頼や信用にも関わるという認識を持っている」と述べ、今後、何らかの見直しがあったとしてもデザインは変えないことが望ましいという見解を示しました。
「安藤氏は『選んだ責任はある。ただ2520億円になり、もっと下がるところがないのか私も聞きたい。一人の国民として何とかならんのかなと思った』と述べ、見直しを求めた。
その一方で『国際協約としてザハ氏を外すわけにはいかない。そうでないと国際的信用を失う』と強調した。」
安藤、お前は、引っ込め!国際的信用を失うとカッコつけるな!あんたの顔がつぶれるだけ。外国だって、自分の利害関係に関わることならあれこれと
言い訳を付けて覆す。日本がカッコを付けたがるのは知っているが、多額の費用が絡んでいるんだ。お前に何がわかるのか?選んだ責任があるのなら、差額をポケットマネーで何とかしろ!
日本国民はこんなコメントの安藤を許すのか?1200億円ものお金を他の分野に使ったらもっと良いことが出来る。学費で苦労している子供に未来を
与えられる。学費を下げるための助成金に使えば多くの人の将来をポジティブな方向へ導ける。国際的信用はこれからの子供達が築けばよい。
安藤は自分の面子のために、多くの可能性を犠牲にしようとしている。お金がないことはどう言う事なのか。ギリシャが良い例だ。
安藤よ、お前は70歳にもなって、自分の事しか考えられない人間なのか?子供の将来や教育の事などどうでもよいのか?人間的に最低な建築家として
残りの人生を過ごしたいのか?
<新国立>経費高騰「承知せず」 安藤氏、現行案継続を希望 07/16/15(毎日新聞)
総工費が2520億円に膨らみ、見直しを求める意見が高まっている2020年東京五輪・パラリンピックの主会場の新国立競技場の建設で、デザインを選定した建築家の安藤忠雄氏(73)が16日、東京都内で記者会見した。安藤氏は現行案を残しながら経費削減に向けた見直しは必要との認識を示したが、巨大な構造物を備えたデザインを選んだことが経費高騰を招いた関連性は否定した。
建設主体の日本スポーツ振興センター(JSC)が国際デザインコンクールを実施して12年11月、イラク出身の女性建築家、ザハ・ハディド氏のデザインに決めた際の審査委員会の委員長。安藤氏は「選んだ責任はある。ただ2520億円になり、もっと下がるところがないのか私も聞きたい。一人の国民として何とかならんのかなと思った」と述べ、見直しを求めた。その一方で「国際協約としてザハ氏を外すわけにはいかない。そうでないと国際的信用を失う」と強調した。
巨大な2本の弓状のキール構造で開閉式屋根を支えるデザインが経費高騰の要因となったが、五輪招致が決まった13年9月の時点で審査委員会と設計の関わりが終了しており、その後の総工費高騰には「消費税増税と物価上昇に伴う工事費の上昇分は理解できるが、それ以外の大幅なコストアップにつながった項目の詳細、基本設計以降の設計プロセスについて承知していない」と関与を否定した。
選定時は1300億円の予算を前提に決定。技術的に困難な構造である上、資材や人件費の高騰を受け、総工費は昨年5月の基本設計時の1625億円から2520億円に増えた。デザイン選定の理由について安藤氏は「アイデアがダイナミックで斬新でシンボリックだった。16年五輪招致に敗れ、20年は勝ってほしい思いがあった」と述べ、斬新なデザインが五輪を勝ち取る上で重要な役割を果たしたとの認識を示した。
安藤氏は実施設計を了承した7日のJSCの有識者会議を欠席しており、新国立競技場のデザインに対する批判が高まってから初めて見解を述べた。
菅義偉官房長官は16日午前の記者会見で、新国立競技場建設計画に関し「整備額が大きく膨らんだ理由について国民の皆さんに説明が足りなかった」と述べた。「国民負担ができるだけ生じないように(競技場運営の)民間委託など、いろいろな工夫を考える必要がある」とも指摘した。建設計画の見直しについては「現時点では決定していない」とした。【藤野智成】
「更なる説明求められる」 安藤氏が会見で配布した文書 07/16/15(朝日新聞)
安藤忠雄氏が記者会見場で配布した文書は次の通り(原文まま)
◇
新国立競技場改築について、国際デザイン競技審査委員長として、ザハ・ハディド氏の提案を選んだ審査の経緯をここに記します。
老朽化した国立競技場の改築計画は、国家プロジェクトとしてスタートしました。「1300億円の予算」、「神宮外苑の敷地」、オリンピック開催に求められる「80000人の収容規模」、スポーツに加えコンサートなどの文化イベントを可能とする「可動屋根」といった、これまでのオリンピックスタジアムにはない複雑な要求が前提条件としてありました。さらに2019年ラグビーワールドカップを見据えたタイトなスケジュールが求められました。
その基本デザインのアイディア選定は、2020年オリンピック・パラリンピックの招致のためのアピールになるよう、世界に開かれた日本のイメージを発信する国際デザイン競技として行うことが、2012年7月に決まりました。
2013年1月のオリンピック招致ファイル提出に間に合わせるため、短い準備期間での国際デザイン競技開催となり、参加資格は国家プロジェクトを遂行可能な実績のある建築家になりましたが、世界から46作品が集まりました。
デザイン競技の審査は、10名の審査委員による審査委員会を組織して行われ、歴史・都市計画・建築計画・設備計画・構造計画といった建築の専門分野の方々と、スポーツ利用、文化利用に係る方々、国際デザイン競技の主催者である日本スポーツ振興センターの代表者が参加し、私が審査委員長を務めました。グローバルな視点の審査委員として、世界的に著名で実績がある海外の建築家2名も参加しました。
まず始めに、審査委員会の下に設けられた10名の建築分野の専門家からなる技術調査委員会で、機能性、環境配慮、構造計画、事業費等について、実現可能性を検証しました。その後、二段階の審査で、デザイン競技の要件であった未来を示すデザイン性、技術的なチャレンジ、スポーツ・イベントの際の機能性、施設建設の実現性等の観点から詳細にわたり議論を行いました。2012年11月の二次審査では、審査員による投票を行いました。上位作品については票が分かれ、最後まで激しい議論が交わされました。その結果、委員会の総意として、ザハ・ハディド氏の案が選ばれました。
審査で選ばれたザハ・ハディド氏の提案は、スポーツの躍動感を思わせる、流線型の斬新なデザインでした。極めてインパクトのある形態ですが、背後には構造と内部の空間表現の見事な一致があり、都市空間とのつながりにおいても、シンプルで力強いアイディアが示されていました。とりわけ大胆な建築構造がそのまま表れたアリーナ空間の高揚感、臨場感、一体感は際だったものがありました。
一方で、ザハ・ハディド氏の案にはいくつかの課題がありました。技術的な難しさについては、日本の技術力を結集することにより実現できるものと考えられました。コストについては、ザハ・ハディド氏と日本の設計チームによる次の設計段階で、調整が可能なものと考えられました。
最終的に、世界に日本の先進性を発信し、優れた日本の技術をアピールできるデザインを高く評価し、ザハ・ハディド案を最優秀賞にする結論に達しました。実際、その力強いデザインは、2020年オリンピック・パラリンピック招致において原動力の一つとなりました。
国際デザイン競技審査委員会の実質的な関わりはここで終了し、設計チームによる作業に移行しました。
発注者である日本スポーツ振興センターのもと、技術提案プロポーザルによって日建設計・日本設計・梓設計・アラップが設計チームとして選ばれました。2013年6月に設計作業が始まり、あらゆる課題について検討が行われ、2014年5月に基本設計まで完了しました。この時点で、当初のデザイン競技時の予算1300億円に対し、基本設計に基づく概算工事費は1625億円と発表されました。この額ならばさらに実施設計段階でコストを抑える調整を行っていくことで実現可能だと認識しました。
基本設計により1625億円で実現可能だとの工事費が提出され、事業者による確認がなされた後、消費税増税と物価上昇にともなう工事費の上昇分は理解できますが、それ以外の大幅なコストアップにつながった項目の詳細について、また、基本設計以降の実施設計における設計プロセスについては承知しておりません。更なる説明が求められていると思います。
そして発注者である日本スポーツ振興センターの強いリーダーシップのもと、設計チーム、建設チームが、さらなる知恵を可能な限り出し合い一丸となって取り組むことで、最善の結果が導かれ、未来に受け継がれるべき新国立競技場が完成することを切に願っています。
2015年7月16日
新国立競技場基本構想国際デザイン競技
審査委員長 安藤忠雄
悪いけど安藤忠雄と呼び捨てさせてもらう。安藤忠雄は建築家であっても、プロジェクトを考えられる人間ではない事が明確になった。
能力がないのであれば僕には決められないと言うべきであった。
「選考時に『1300億円』の予算が示されていたと強調。」
専門家に見積もりの妥当性や根拠に伺いを立てる発想はなかったのか?相手の言い分をチェックもせずに鵜呑みにするのはばかだ。70歳にも
なってもそんな事もわからないのか?肩書きだけの人間は使えない良い例だ。
これでは日本はギリシャを笑う資格はない。無能者ばかりだ!謝罪ぐらいしろ!まあ、謝っただけで何百億もの税金を突っ込む事が許されるわけはないけど。
悪いと思うなら建築家を引退しろ!いい歳なんだから建築家だけで工事費予算1300億円で収まるのかチェックできないとはっきりと言うべきだった。
安藤忠雄氏、新国立の工費高騰「私も聞きたい」 07/16/15(読売新聞)
2020年東京五輪・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の総工費が2520億円に膨らんだことについて、デザイン選考時の審査委員長を務めた建築家の安藤忠雄氏(73)が16日、東京都内で記者会見し、「選んだ責任はあるが、なぜ2520億円になったのか私も聞きたい」と述べ、政府がさらなる見直しの検討を始めたことに「(現行案は)残してほしいと思うが、値段が合わないのなら、徹底的に討論してほしい」と述べた。
費用高騰などが問題化して以降、安藤氏が公の場で発言するのは初めて。安藤氏は今月7日、2520億円を承認した日本スポーツ振興センターの有識者会議を欠席。これに関し、「欠席したから責任があるというのはわからない」と自身に批判が集まっていることに疑問を呈した。
デザインが費用高騰を招いたとの批判には、選考時に「1300億円」の予算が示されていたと強調。その上で「デザインを決める場で、コストについて徹底的な議論にはなっていなかった」と釈明した。
安藤氏を巡っては、下村文部科学相が10日、「選んだ理由を堂々と発言してほしい」と述べるなど、その発言が注目されていた。
「ギリシャ政府の借金総額は国内総生産(GDP)の約1・8倍もあり、「財政は持ちこたえられない」と指摘した。」
そうだったら日本も破滅だね!
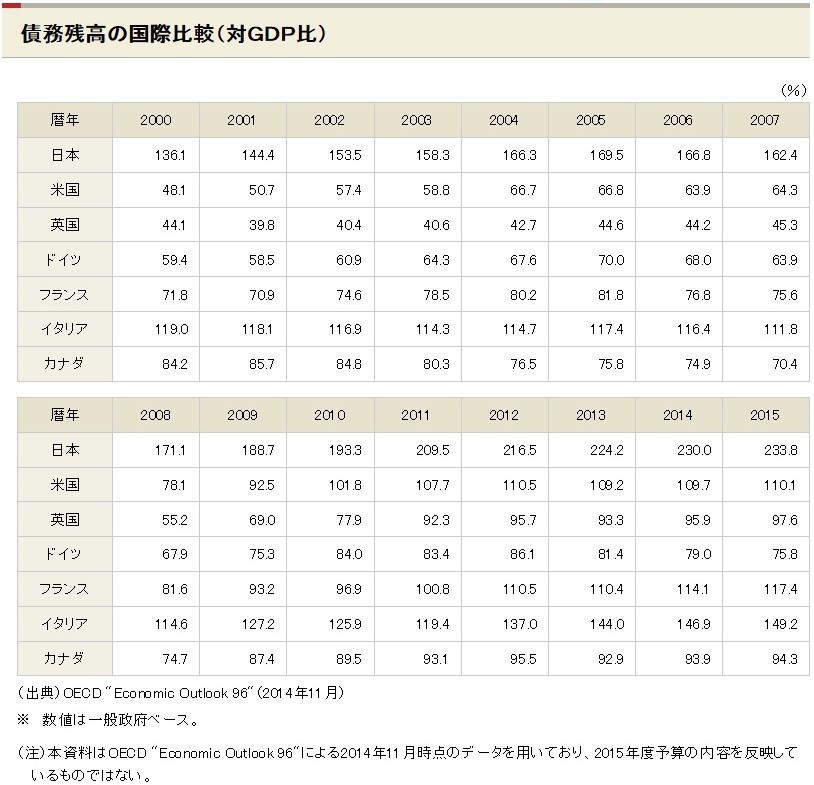
債務残高の国際比較(対GDP比)(財務省)
「ギリシャ持たない」米長官、EUに見直し要求 07/11/13(毎日新聞)
【ワシントン=安江邦彦】ギリシャの金融支援を巡り、ルー米財務長官は10日のニューヨークでの講演で、「ギリシャ政府が抱える債務を整理する必要がある」と述べ、ギリシャを支援している欧州連合(EU)に対して返済条件の見直しを改めて求めた。
ギリシャ政府の借金総額は国内総生産(GDP)の約1・8倍もあり、「財政は持ちこたえられない」と指摘した。
ギリシャ政府に対しても「持続可能な経済へ立て直すため、困難な手段を講じる必要がある」と強調し、改めて財政の緊縮策の導入など厳しい改革を求めた。
ギリシャ政府が、付加価値税(日本の消費税に相当)の増税や年金支給額の削減などを柱とする新改革案をEU側に提案したことについては「必要な構造改革を反映している。(交渉するギリシャとEUの)両者は近づいているように見える」と歓迎した。
世論調査 新国立競技場「納得できない」81% 07/11/13(スポーツ報知)
NHKの世論調査で、新しい国立競技場を、当初よりおよそ900億円多い2520億円をかけて建設する計画に納得できるかどうか尋ねたところ、「納得できる」と答えた人は13%、「納得できない」と答えた人は81%でした。
NHKは今月10日から3日間、全国の20歳以上の男女を対象に、コンピューターで無作為に発生させた番号に電話をかける「RDD」という方法で世論調査を行い、調査対象の67%に当たる1024人から回答を得ました。
この中で、安倍総理大臣が、戦後70年のことし発表する予定の談話の中に、「過去の植民地支配と侵略に対するおわび」を、盛り込んだほうがよいと思うか聞いたところ、「盛り込んだほうがよい」が31%、「盛り込まないほうがよい」が24%、「どちらともいえない」が34%でした。
また、東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムとなる新しい国立競技場を、デザインの大幅な見直しをせず、当初よりおよそ900億円多い2520億円をかけて建設する計画に納得できるかどうか尋ねたところ、「大いに納得できる」が1%、「ある程度納得できる」が12%で、合わせて13%でした。
これに対し、「あまり納得できない」が34%、「まったく納得できない」が47%で、合わせて81%でした。
一方、現在、停止している原子力発電所の運転を再開することについて、「賛成」が19%、「反対」が42%、「どちらともいえない」が33%でした。
「渋谷駅同様、使えない競技場を設計したザハ・ハディド氏には『デザイン監修料』として十三億円が支払われる。」
仕方がないから十三億円をどぶに捨てたと思い、ザハ・ハディド氏に支払い、普通の競技場を500億円以下でで建設しよう。
国民の負担はその方がはるかに軽い。
新国立競技場計画の破たんと“ごまかし” (1/5)
(2/5)
(3/5)
(4/5)
(5/5) 07/13/15 ( ITmedia ビジネスオンライン)
東京五輪・パラリンピックのメイン競技場となる新国立競技場の建設計画。抑制されたはずの建設コスト見積もりにも、建設完了後の収支計画の説明にも、明らかなごまかしがある。
2520億円に膨れ上がった総工費に対し財源確保の見通しはいまだに立っていない。1000兆円という空前絶後の負債を抱える国家でありながら、財政再建に取り組むどころか、不必要な巨額赤字をなお積み上げようとするのは世界中のもの笑い以外の何物でもない。
しかし見直しを求める世論を無視するように、事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)有識者会議が建設計画を了承したことに、各方面から批判が渦巻いている。
主な批判の論点は当初予算の倍近い金額に膨れ上がったこと。確かに当初の想定が大甘だったことは間違いない。
審議委員だった安藤忠雄氏は「コンペの条件としての予算は1300億円であり、応募者も認識しています」とコメントしており、当時の審議委員の1人であった建築家は「委員にはコスト見積もりを精査するようには求められなかった」とインタビューで述べていた。
つまり、建設コストの根拠がいい加減なままデザインを決め、基本設計や実施計画を詰めてみたら倍に膨れ上がったということだ。プロセス自体に問題があるとしか言いようがない。
これはまさに東京五輪向け整備に関し、小生が従来から指摘してきた懸念が現実化している事態だ。
無策のまま最悪の事態に至ることを避けるため、この問題に関し4つほど関係者の「ごまかし」を指摘しておきたい。
(1)最新の建設コスト見積もりに潜むごまかし
当初見積もりとの食い違いに関するJSCの今回の説明にはごまかしを感じる。建設計画の了承を発表した際にJSCは、当初予算から倍増した理由を次のように説明した。資材や人件費の上昇で350億円、消費増税分で40億円増、さらにアーチ2本で建物を支える「キールアーチ」というデザインの特殊性によって765億円増、と。
まるで途中から「キールアーチ」になったような説明である。しかし途中から環境条件が変わってしまった資材・人件費の上昇や消費増税と違い、「キールアーチ」のデザインは五輪が決定する前から分かっていた条件である。
もし「このデザインでは予算1300億円に収まるのは初めから無理なんです」と言いたいのなら、何としてもデザインを変えるべきだったという肝心の結論も伝えるべきだろう。
もしくは「このデザインでは建設経験が世の中にほとんどなく、正しいコストの見積もりが限りなく難しいんです」と言いたいのなら(建築家の幾多のコメントを拝見する限り、こちらが真実に近いだろう)、今回示されている「2520億円」という総額もまた信頼に値しないと言わざるを得ない。
しかも、この金額には五輪・パラリンピック後に設置を先送りした開閉式屋根の整備費や1万5千席の仮設スタンド設置分に加え、200億円超と見積もりされていた周辺整備費も含まれていない。これらを加えると結局、総額は3000億円前後になるのではないか。
しかしそれでは改めて批判が高まるため、今回は先送りした分の建設費などを除外して、一見コストが減額された印象を与えようとしたのではないか。実に姑息なやり方である。
(2)運営後の収益計画におけるごまかし
今回JSCが発表した収支目論見では、開閉式屋根を設置した場合という条件付きで、収入40億8100万円、支出が40億4300万円、締めて3800万円の黒字と試算している。この微妙な黒字額からは、いかにも無理矢理に黒字にした印象が強い。弊社が時々頼まれる事業見直し時に、担当部門がこんな事業計画案を出そうものなら、真っ先に疑って精査の対象となる。
既に各方面から、これらの収入の見積もりの甘さと支出の過小さを指摘されている。つまり、これは楽観シナリオに基づく見積もりだということである。
通常、事業計画の策定には悲観シナリオと(2つの中間に位置する)妥当シナリオも並行して検討し、その上で妥当シナリオの計画値を正式に上申する(楽観シナリオと悲観シナリオの予測数値は添付資料に回されることが多い)。楽観シナリオに基づく数値だけを提示するJSCのやり方は、ごまかし以外の何物でもない。
ちなみに、この収支計画には完成後にかかる修繕費が以前より多少増額して約1046億円と計上されているものの、50年間に必要な大規模改修費は別枠扱いとして、収支計画に組み込んでいない。これもまた「ごまかし」である。
しかもその年平均21億円という修繕費はまだまだ随分と過小だと言わざるを得ない。専門家の指摘によると、JSCが収支計画の前提としている開閉式の屋根というものは非常に故障しやすいものらしい。
実際、大分銀行ドームは前年の故障に応じて2011年に大規模な改修工事を終えたものの、2年後の2013年に再度、故障によって屋根が開いたままになり、大分県は予算措置に往生したそうである。また、豊田スタジアムは多額の改修費と維持費を理由に今年度から屋根を開けっ放しにしている(開き直った措置だが、問題が判明した時点で現実的な対処をしたといえる)。
これらのスタジアムでの改修工事費は5~15億円掛かっている。建築費がこれらの10倍以上掛かる上に、特殊構造となる「キールアーチ」に対応した新国立競技場の開閉屋根の改修工事となれば、100億円前後に上るのではないか。新しいうちはともかく、稼働後20~30年経てくれば故障が頻発することは避けられない。
ここで今ある情報に基づき妥当シナリオを想定してみよう。
建設当初の数年間は可動式の屋根ができていないため赤字になるとJSCはいう。毎年数~10億円程度の赤字としよう。
数年後に300億円ほどの追加費用を掛けて可動式屋根を追加設置、その後仮に20年ほど幸運にも故障なしに運用できたとして、既に見た通り楽観シナリオの下でギリギリの収支である。実際には1~2億円程度の赤字は避けられないのではないか。
その後は数年に一度の(しかも頻度は段々高まる)改修工事のたびに100億円ずつ吐き出すばかりか、故障期間は雨天時に使えない、工事期間は全く使えない、となれば収入はガクンと落ち込む。平均して毎年20億円近くの赤字を積み重ねることになるだろう。
こんな収支計画の事業をGOさせる経営者がいたら、お目に掛かりたいものだ。間違いなく負の遺産になろう。
(3)納期に関するごまかし
見直しをしない理由として、関係者は「今から国際コンペをやり直して設計を詰めてから建設するとなると、2020年の五輪に間に合わない」という。安倍首相もこのため変更を断念したという。本当にそうだろうか。
まず、国際コンペをやり直す必要はない。デザインコンペは既に実施されており、ザハ・ハディド氏のデザインがどうしても予算内に収まらないということで失格するとしたら、次点とされた作品を選ぶのが筋だ(もちろん予算内に収まるという条件の下ですが)。
これから基本設計そして詳細設計、さらに実施計画を詰めると五輪に間に合わないというのは本当だろうか。まだ5年あるのだ。
ザハ・ハディド氏のデザインに基づく特殊な構造の場合にはそうかも知れないが、もっとまともな構造であれば、日本の建設業界の設計力・実行力をもってすれば十分可能ではないか(ただし、工事ピーク時前後には周辺のあちこちに臨時の資材置き場を設ける、などの工夫も必要となるかも知れない)。
JSCのいう「間に合わない」対象は本当に東京五輪なのか、かなり疑わしい。本当は政界・スポーツ界に隠然たる影響力を持つ森喜朗・元首相がかねてご執心の、2019年9月からのラグビー・ワールドカップ日本開催に間に合わない、ということなのではないか。安倍首相と菅官房長官は関係者を問い詰めるべきだ。
(4)責任の所在に関するごまかし
下村文科相はデザインの審査委員長を務めた安藤忠雄氏に(先日の有識者会議を欠席したことに絡めて)「説明を求めたい」と批判している。当初見積もりが甘かったことに全ての責任を負いかぶせようという意図が透けて見えるものだ。確かに安藤氏に非がないとも思えないが、「第一級戦犯」ではなかろう。
本当に責任を取るべきは、過去に何度もあった見直しの機会に、当初のデザイン案をあきらめて基本設計を見直すという決断を先送りしてきた文科省とJSTの幹部である。とりわけ、最後のチャンスでありながら今また、見直しをせずに他に責任をなすりつけようとしている最高幹部の下村文科相の責任こそが重大ではないか。
改めて感じるのは、これほど「ごまかし」を重ねてでも関係者が基本設計の見直しに踏み切らないのには、よほどの理由があるのだろうということだ。
関係者や事情通は「国際的信用」や「無責任の構造」、先に触れた森・元総理への遠慮、などをいろいろと挙げる。しかしそれにしてもここまで政治問題化しながらも文科省とJSCが強引に世論に抗するのは、今一つ腑に落ちない。もしかすると我々の知らない巨悪の構造が隠れているのかも知れない。ジャーナリストの活躍を待つ所以である。(日沖博道)
新国立競技場2520億円をゴリ押ししたのは誰か (1/6)
(2/6)
(3/6)
(4/6)
(5/6)
(6/6) 07/11/15 (ダイヤモンド・オンライン)
二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、メインスタジアムとなる新国立競技場の工事費がようやく決まった――、というか、不可解だらけの疑惑を残し、二五二〇億円というべらぼうな工事費が有識者会議で了承された。
二五二〇億の内訳は、竹中工務店が担当する「屋根工区」が九五〇億、大成建設が担当する「スタンド工区」が一五七〇億になる。驚きなのは、昨年五月発表の建設費が一六二五億円(解体費用を除く)で、これだけでも額は膨大と言われていたのに、蓋を開けてみれば当初の予定より九〇〇億円も上乗せした二五二〇億に及んだことだ。
さらにアンビリーバボーなことに、現在、建設費に確保されている財源が六二六億円しかないと言われている(国が三九二億を負担、スポーツ振興基金が一二五億円、totoの売り上げ金から一〇九億円を供出)。
これに、新国立競技場のネーミングライツ(命名権)で二〇〇億、totoの売り上げから六六〇億を供出する予定だが、それでもぜんぜん足らず、文部科学省は東京都に五〇〇億を負担するよう言い出した。舛添要一都知事は寝耳に水だったようだが、おカネがなければ税金があるじゃん、とお役人さんが得意とする身勝手作戦がオリンピックでも展開されようとしている。
それでも、まだ五三四億円もの建設費が不足しているのだ。
何故、こんなことになったのか――? 文部科学省の役人たちが無能だからか。それとも、文科省傘下の独立行政法人『スポーツ振興センター(JSC)』の職員はほとんどが文科省からの出向者で占められているから母体が無能なら傘下団体もやっぱり無能になってしまうのか。JSCには文科省で使えないやつが放り出されているのだろうか? でも本当に使えないのだ、こいつら。
「JSCも文科省の官僚も最悪だ。都市計画の変更などは難しいと思っていたが、まさか本体をつくる能力もないとは」
政府関係者は呆れているそうだ。国民も呆れています。舛添さんも呆れている。
「文科相に任せていたらアウトです。一〇億や二〇億で学校をつくったことはあっても、一〇〇〇億以上の建物をつくった経験もない。責任能力がない」
二五二〇億という額に落ち着いたとき、JSC幹部はこんなことを言った。
「国が主導でやることで、JSCがやることではなかった」
文科省に劣らずJSCもぼんくら揃いな団体だが、しかし、彼らはぼんくらなりに計画は立てていた。それが、石原慎太郎都知事時代に行なわれた、二〇一六年の五輪招致活動である。当時を知る関係者が言う。
「二〇一六年の招致では、『世界一コンパクトな五輪』を掲げ、一九六四年の東京五輪のレガシー(遺産)である旧国立競技場とベイエリアを結ぶ晴海に新スタジアムをつくるというプランでした。旧国立競技場を残し、二つのスタジアムを併用する理想的なプランでしたが、招致失敗でこの案は消えた。二〇二〇年招致に向けて再始動する過程で、新国立競技場を建設するプランが浮上してきたのです」
当時のプランをスポーツ紙の記者が語る。
「JSCは、旧国立競技場に耐震補強を施し、改修して継続利用する“改修案”を検討していました。JSCは設計会社に依頼して、改修案が作成された。この案では、収容人員は約七万人(中略)予算は七七七億円でした」
オリンピックのメインスタジアム建設費は、アテネが約三〇〇億円、北京が約六五〇億円、ロンドンが約七〇〇億円と言われているから、七七七億は妥当な数字ではあった。バブルでもあるまいに、二五二〇億という額が異常すぎるのだ。
だから、二〇一六年の招致に成功していたか、当時のプランを踏襲していれば、予算は今回の三分の一以下で済んだのだが、それはいまさら言ってもしょうがない。滝川雅美ちゃん……、もとい、滝川クリステルさんの、お・も・て・な・し、が功を奏したかどうかはさておき、日本は二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック開催国になった。
そして、二〇一二年三月、各分野十四人のメンバーからなる『国立競技場将来構想有識者会議』が設立された。発足当時は「八万人収容」「開閉式の屋根」「可動式観客席の導入」等々の方針が決められた。問題となる国際デザインコンクール――、いわゆるコンペの実施を発表したのがその年の七月だ。審査委員長には建築家の安藤忠雄氏が就任するが、このときから新国立競技場建設をめぐる迷走が始まるのである。
コンペの発表が七月。応募の締め切りが九月二五日という異例のスケジュールが組まれた。オリンピックのメインスタジアムにして日本の国立競技場を決めるコンペなのに、応募期間がわずかに二ヵ月しかないというのは、実に不可解と言わざるを得ない。
不可解なこのコンペには、応募資格まで設けられた。首を傾げたのは東京電機大学の今川憲英教授だ。
「コンペの応募資格が、収容人数一万五〇〇〇人以上のスタジアム設計経験者と、国際的な建築賞を受賞したことのある人物に限定されており、そのこと自体かなり異例です」
応募は、海外から三十四点、国内から十二点の計四十六点があった。これをブラインドで一次審査にかけ、二次審査には十一点(海外七・国内四)が残った。二次審査は、各委員(日本人八・海外二)が良いものから順に三点を選ぶ方式が取り入れられたが、不可解なのは、この後の審査過程だ。
「ザハ案(今回採用された女性建築家)以外、豪州と日本の設計事務所の案が残りました。ここから安藤さんの意向で日本案が外され、最後は二案になる“決選投票”となったのです」(スポーツ紙デスク)
今回の審査委員には外国人建築家が二人、名を連ねていたが、何とも不可解なことに、彼らは一度も来日せず、一次審査にも投票しなかった。ではどうしたかというと、二次審査に残った作品をJSC職員が現地まで持参し、順位とコメントを聞き取り、審査に反映させたという。だから、外国人審査員の最終決選においての発言はない。
「決選投票は四対四で割れてしまい、その後もめいめいが意見を述べましたが、いったん休憩しようということになった。で、皆が席を離れた後、ひとりの委員が安藤さんに『こういうときは委員長が決めるべきでしょう』と話しかけたのです。実際、それ以上繰り返しても結果は変わりそうになく、安藤さんも『わかりました』と応じていました」
安藤忠雄氏は、さきの有識者会議のメンバーでもある。
「だから他の委員が詳しく知り得ない“上の意向”にも通じていたのでしょう。一時間ほどの休憩をはさみ、再び委員が席に着くと、安藤さんは『日本はいま、たいへんな困難の中にある。非常につらいムードを払拭し、未来の日本人全体の希望になるような建物にしたい』という趣旨のことを口にし、ザハ案を推したのです。そこで安藤さんは全員に向かって『全会一致ということでよろしいですか』と念を押し、誰も異論がなかったので、そのまま決まりました」
皆さんもザハ・ハディド氏がデザインした新国立競技場のイメージ像はご存じだろう。安藤氏曰く、あれが『未来の日本人全体の希望』だそうだ。呵々大笑。どーでもいいけど、安藤忠雄という建築家は、ぜんぜん使えない東急東横みなとみらい線の渋谷駅を設計した人です。乗り換えるのに五分も十分も歩かされる不便駅です。
「専門家が見れば、予算の範囲でつくれないのは審査段階でわかります。だいいち、建物の一部が敷地外に飛び出しており、本来ならば失格の作品を最優秀賞に選んでしまった。せめて招致が決まった段階で、ザハ案が違反であると公表し、十分な条件によるコンペを開いて仕切り直すべきでした。それをしなかったのは、安藤さんの責任でしょう」(今回、二次審査まで残った建築家の渡辺邦夫氏)
ザハ氏の作品は、昆虫の触角のように伸びたスロープがJR線をまたぎ、施設の高さも制限をオーバーしていた。応募条件から大きく逸脱していたにもかかわらず、安藤忠雄氏はコンペの優勝者としたのである。ホワイ?
ついでながら言えば、ザハ案は床面積を四分の三に縮小、高さも低く抑えるなど修正が必要だったのだが、どーいうわけか安藤さんはザハ案を選んだ理由のいっさいを説明しようとはせず、メディアにも口をつぐんだままだ。ホワイ? ただ、
〈コンセプトが強ければ後で修正できる〉
〈つくりあげるのはたいへん難しいが、日本の土木、建築技術は世界最高レベルにあり、乗り越えていける〉
とは言ってるみたいですけど。渋谷駅同様、使えない競技場を設計したザハ・ハディド氏には『デザイン監修料』として十三億円が支払われる。
「たしかに有識者会議でデザインは決めたけど、ぼくらは何の権限もなく、契約はJSCがやるわけだから、どうなっていくのかわかりません。五輪までに間に合ってほしいとは思いますけどね」
こんな無責任発言をしたのは、有識者会議・佐藤禎一委員長(元文部事務次官)だ。
未来の日本人全体の希望(安藤氏の発言)は、ぎりぎりの工夫をこらし、何とか一六二五億円で建設できるとの見通しを立てたが、やはり、使えない文科省とJSCだけあって甘かった。消費増税に加え、資材や人件費の高騰で、〈未来の日本人全体の希望(安藤氏の発言)〉には二五二〇億もの予算がかかることになったのである。
さらに言えば、本来なら昨年七月に始まるはずだった解体工事の入札で官製談合の疑いが浮上し、昨年十二月、三回目の入札でようやく業者が決まるなど、JSCがいかにお粗末な組織であるかも判明した。
また、東京オリンピック・パラリンピックに先んじて、二〇一九年にはラグビーのワールドカップが日本で開催される。このメインスタジアムも新国立競技場だから、JSCは工事を急がなければならないのだが、ザハ案のままでいくとW杯までに競技場の完成が間に合わず、開閉式の屋根工事は先送りすることになった(開閉式屋根の工事費一六八億円は今回の二五二〇億円に含まれず)。
屋根工区を担当するのは竹中工務店だが、同社はテレビのニュースを見て、初めて開閉式屋根工事が先送りになったことを知ったのだという。つまり、JSCから知らされていなかったということだ。JSCの担当者は文科省の出向者ばかりだから、民間のルールとか取引先との信頼関係というのがわからないのだろう。元文部事務次官も有識者会議の委員長だってえのに、あんな無責任な発言をするし。
私は思う。いったい誰がこんな滅茶苦茶なプランをゴリ押ししたのかと。
テレビ東京の『午後のロードショー』は今年二〇年目を迎えるが、今月の特集は「サメ」だ。残念なことだが、日本には「サメの脳みそ」と揶揄された元総理がいる。森喜朗氏だ。東京オリンピック・パラリンピックの実現には、ITを「イット」と読んで笑われたサメ頭の暗躍があるとも言われているのだ。
〈当初、五輪招致への再挑戦に消極的だった石原氏を口説き落としたのが森氏だった。スポーツジャーナリストの谷口源太郎氏は、「そこには森氏のしたたかな計算があった」と指摘する〉
「森氏は日本ラグビー協会の会長を長く務め、二〇一九年に日本で開催されるラグビーW杯招致に尽力していました。彼の狙いはまさにラグビーW杯の会場として新国立競技場を建設することでした。ラグビーW杯は準決勝と決勝の会場は集客人数八万人以上が望ましいとされているのですが、ラグビーW杯のために新国立を主張しても世論は動かせない。そこで、東京五輪のメインスタジアムにすることを口実にしたのです」
そして、こんなバックグラウンドも。
「石原氏が再立候補の狼煙を上げた日本体育協会とJOCの一〇〇周年事業のレセプションは、森氏自ら実行委員長を務めていました」
新国立競技場建設を既定路線としたのは、JSCが新体制になってからのことだ。
「新理事長に就いたのはラグビー協会の理事・河野一郎氏でした。彼は筑波大の教授で、五輪やラグビー代表のチームドクターでもあったドーピングの専門家。英語が堪能で弁も立つことから、森氏の強い意向で二〇一六年の五輪招致委員会の事務総長に選ばれた」(スポーツ紙記者)
が、彼が力を入れたのはラグビーW杯招致のほうで、二〇一六年の五輪招致には失敗する。
「ラグビーW杯招致にばかり熱心で、IOC委員にアタックできるチャンスをみすみす逃していたと招致委員会内部からも批判の声があがっていました。それなのに招致失敗の責任をとるどころか、スポーツ行政の鍵を握るJSCのトップに就任したので、周囲も驚いていました」
森喜朗氏の狙いがラグビーW杯の開催にあり、そのためにまずオリンピック・パラリンピックの東京開催を実現させ、JSCの理事長に息のかかったラグビー協会の理事をスライド就任させる。そして、W杯の準決勝・決勝戦を行なうため、八万人を収容できるよう国立競技場新しく建て替えさせた――、とすれば、森氏はたいしたマキャベリストではないか。
その森喜朗氏は、建設予算が二五二〇億と決まった直後、「これはあくまで国家プロジェクト」と言い放った。すごいぞ森喜朗! オリンピックをラグビーワールドカップの出汁にするなんて。
だから、もしかしたら、多くの人が森喜朗氏に踊らされていたのかもしれない。
週刊新潮の記者さんが、ザハ案を採用した安藤忠雄氏を自宅近くで直撃している。
「いや、ちょっと、私わからない。またね」
食い下がる記者さんに、安藤氏はキレたそうだ。
「いいから、来んといてくれや。はい、さいなら……、ええ加減にせえや! もう帰れよ! 」
紳士の振る舞いからは程遠い安藤氏だが、この人も、踊らされているのだろう。
ラグビー好きなひとりの思惑と文科省、その文科省から出向したJSCとが、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアム建設予算をアンビリーバボーな二五二〇億円にまで押し上げた。実にぼんくらな仕事ぶりである。
新国立競技場の工費は二五二〇億だが、ここには一万五〇〇〇席の仮設スタンド、開閉式屋根の工費(一六八億円)は含まれていない。べらぼうな費用がかかる新国立競技場は、しかし、完成した後も問題をはらんでいる。
競技場の維持管理費に、五〇年間で一〇四六億円が必要になるというのだ。年間収支の黒字見込みは約三八〇〇万円ほどで、すると、新国立競技場は、毎年二〇億円前後が赤字になる。文科省やJSCは、その赤字ぶんの補填すらも、私たちの税金で補う心づもりでいるのだろう。
ザハ氏のデザインは「キールアーチ構造」と言い、二本のアーチで建物を支える特殊な構造になっているらしい。安藤忠雄氏は、日本の技術ならキールアーチを完成できると言っている。
私も、そうであることを願っている。文科省とJSCの仕事ぶりはお粗末きわまりなく、計画が二転三転してきた。工事だけはしっかりと、見事な新国立競技場をつくってほしい。
ぼんくらなお役人のぼんくら仕事を民間企業がカバーする。それが、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックである。
参考記事:朝日新聞・東京新聞・毎日新聞7月8日他
週刊文春6月4日号 週刊新潮6月18日号
降旗 学
「「安藤忠雄建築研究所」の名前で、番組の司会を務めるキャスターの辛坊治郎さん(59)宛に出されたファクスでは『コンペの与条件としての予算は1300億円であり、応募者も認識しています。提出物には建築コストについても示すように求められていました。それは当然評価の一つの指標となりました』と明記。」

日刊スポーツ
上記がが事実ならデザイン決定後の基本設計や実施設計の責任なのか、コンペの与条件としての予算は1300億円であることを認識していたハディド氏の責任なのか、はっきりする。
ハディド氏の見積もりに問題があれば損害賠償を請求する事が契約書次第であるが可能ではないのか?早く検証して答えを出そう。
お高いの見積もりを比べるだけで結果を出せると思う。
安藤忠雄氏「何でこんなに増えてるのか、分からへんねん」…新国立問題で初コメント 07/11/13(スポーツ報知)
総工費の高騰が問題となっている新国立競技場のデザイン選考について、審査委員長を務めた建築家の安藤忠雄氏(73)が11日放送の日本テレビ系(読売テレビ制作)「ウェークアップ! ぷらす」(土曜・前8時)にコメントを寄せた。安藤氏がコメントするのは問題が浮上して以来、初めてとなる。
「安藤忠雄建築研究所」の名前で、番組の司会を務めるキャスターの辛坊治郎さん(59)宛に出されたファクスでは「コンペの与条件としての予算は1300億円であり、応募者も認識しています。提出物には建築コストについても示すように求められていました。それは当然評価の一つの指標となりました」と明記。下村博文文部科学相が10日の閣議後の会見で発言した「値段(総工費)とデザインを別々にしていたとしたら、ずさんだと思う」との言葉に反発した。
また、辛坊さんによると、安藤氏は「デザイン決定後の基本設計や実施設計には、審査委員会はかかわっていない」と話していたといい、最終的な計画概要の2520億円という金額に関しては「辛坊ちゃん、何でこんなに増えてるのか、分からへんねん!」と驚いていたという。安藤氏が7日の有識者会議を欠席した点に関して辛坊さんは「しゃべりたい気持ちは満々らしいが、周囲から止められているらしい」と聞いているとした。
下村文科相、欠席の安藤忠夫氏に注文「何らかの形で発言して」 07/10/13(産経新聞)
下村博文文部科学相は10日の閣議後会見で、新国立競技場建設をめぐる7日の有識者会議を欠席した建築家の安藤忠雄氏について、新国立のデザイン案を選んだ理由などに関し「何らかの形で発言してほしい」と述べ、説明責任を果たすべきだとの考えを示した。
安藤氏は新国立のデザインとして英国の女性建築家、ザハ・ハディド氏の案の採用を決めた平成24年11月の審査委員会の委員長を務め、日本スポーツ振興センター(JSC)が整備事業案を報告した今月7日の有識者会議での発言が注目されていたが、自己都合により欠席していた。
下村氏はこの日の会見で「(安藤氏は)堂々と自信を持ってなぜザハ氏の案を選んだのか。21世紀において、国内外にその重要性を何らかの形で発言してほしい」と述べた。
また、新国立のデザイン選考について、「(当初の総工費)1300億円がどの程度、公募の中で伝わっていたのか。値段とデザインを別々にしていたとしたら、ずさんだ」として検証する考えを示した。
「基本方針は、2013年施行のいじめ防止対策推進法で各学校に策定が義務付けられている。保護者向けのアンケートは学校の防止基本方針で6、10月の年2回実施することにしている。校長によると、前年度もいじめに特化した保護者アンケートは実施されず、本年度も実施予定はなかったという。」
越秀敏矢巾町教育委員会教育長、矢巾町の中学校の隠蔽工作はすごいよ。これじゃ、越秀敏矢巾町教育委員会が怠慢、又は故意にチェックしない場合は
いじめは自殺者が出るまで発覚しないシステムが確立している。
「保護者向けのアンケートは学校の防止基本方針で6、10月の年2回実施することにしている。」と対外的には公表し、実際は実施しないし、実施する予定もない。
権限を持っている人や組織が介入しないと、内部情報までは調査できない。学校ぐるみで口裏を合わせれば、自殺等の問題が発生するまでいじめを隠し通せる
システムだ。これは誰が考え出したのか、いじめの引継ぎはしてなくても、いじめの偽装工作又はいじめの偽装報告は引き継がれている。
岩手県教育委員会では常識なのか?それとも矢巾町には中学校が2つしかないが、矢巾町教育委員会の常識なのか?先生達が他の地区の学校にも
移動するので、このような手法は知られている、又は、拡散していても不思議ではない。文化や習慣も同じように伝わっていく。隣接する地域では
習慣、価値観、食文化、方言などが似ているのは同じ理由。人を通して拡散していく。今回は学校関係者達。
保護者アンケート、6月に未実施 矢巾・中2自殺問題 07/17/13(岩手日報)
矢巾町の中学2年の男子生徒がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、中学校が同校のいじめ防止基本方針に基づき行う早期発見のための保護者アンケートを、予定した6月に実施していなかったことが16日、校長への取材で分かった。昨年7月策定の町いじめ防止基本方針には関係機関の連携を図る連絡協議会設置が盛り込まれたが1年間開催されず、町教委は18日に初会合を開く。防止対策の形骸化が浮き彫りになり、実効性があらためて問われている。
基本方針は、2013年施行のいじめ防止対策推進法で各学校に策定が義務付けられている。保護者向けのアンケートは学校の防止基本方針で6、10月の年2回実施することにしている。校長によると、前年度もいじめに特化した保護者アンケートは実施されず、本年度も実施予定はなかったという。
同基本方針に定めた取り組みの中で、教職員の資質向上に向けて取り組み姿勢を評価する自己診断も6月の予定が未実施。いじめの早期発見を目的とした生徒対象のアンケートは年3回(5、11、2月)の実施予定だが、1回目は6月にずれ込んでいた。
町いじめ防止基本方針には学校や町教委、子育て支援センター、警察などの関係機関でつくる町いじめ問題対策連絡協議会の設置を明記。いじめ根絶への方策や情報交換が目的だが設置に至っていなかった。越秀敏教育長は「方針をつくり、すぐ設置すべきだったが怠っていた」と釈明する。
越秀敏矢巾町教育委員会教育長、この学校調査についてどうコメントするのか?前校長からも話は聞いたか?スクールカウンセラーや
教育研究所(監事 立花 常喜 矢巾町教育研究所長)は校長が
いじめを報告しなかったから介入できなかったのか?
現在の校長と前校長に責任があると思うのか?それとも担任だけの責任か?過去、2年間のいじめに関するアンケートの結果はどうだったのか?
前校長は「継続的ないじめはないと思い、引き継ぐ必要はないと判断した」と新聞記者には回答しているが、昨年の報告にはいじめとして
報告はしているのか?
幕引きしたいのだろうけど簡単に幕引きさせると同じ事を繰り返す。警察がしっかりと捜査するべきだと思う。
学校調査に60人が「いじめ見聞きした」 07/16/13(産経新聞)
岩手県矢巾町の中学2年村松亮君(13)がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、死亡後に学校が実施したアンケートに対し、クラスメートや同じ部活動の生徒以外で、約60人の生徒が村松君へのいじめを見聞きしたことがある、と回答したことが16日、町教育委員会への取材で分かった。学校は、クラスメートらからもさらに詳しい聞き取りを進め、死亡に至った背景を調べている。
アンケートは生徒445人を対象に実施。いじめを実際に見たり、村松君から聞いたりしたことがあるかを尋ねていた。
また、村松君が自殺をほのめかす投稿をした携帯ゲーム機や、亡くなる直前に参加した宿泊研修のノートを父親(40)が県警に提出したことも、関係者への取材で判明。県警は既に、村松君が「げんかいです」「死にたい」などと記した1年1学期から2年1学期の生活記録ノート計4冊の任意提出を受けている。
文部科学省のキャリアは高学歴でも使い物にならない人材ばかりか?インターネットで検索したらいろいろな情報は得られるだろう。何もしなかったのか?
こんなキャリアは必要なし!
専門家ではないが、建築家は構造や力学を考慮せずにデザインを優先させる、それを現実の建物にするのはエンジニアと理解している。
 国立競技場将来構想有識者会議に参加した人々、日本スポーツ振興センター(JSC)及び文部科学省の関係者は理解できないことがあれば建築家の安藤忠雄氏
に質問しなかったのか?また、1300億円は計画の予算だったのか、それとも決まったデザインの見積もりだったのか?この点を明確にするだけで
部分的な責任は誰にあるのか判るのではないのか?
国立競技場将来構想有識者会議に参加した人々、日本スポーツ振興センター(JSC)及び文部科学省の関係者は理解できないことがあれば建築家の安藤忠雄氏
に質問しなかったのか?また、1300億円は計画の予算だったのか、それとも決まったデザインの見積もりだったのか?この点を明確にするだけで
部分的な責任は誰にあるのか判るのではないのか?
「下村博文・文部科学相は10日、閣議後の記者会見で、新国立競技場の計画について『(当初予定した総工費の)1300億円がデザインする人に伝わっていたか。値段は値段、デザインはデザインということならば、ずさんだったことになる』」
こんな事、デザインを決定する前、又は、決定した後でも確認できただろ。確信犯的に時間稼ぎをしたとしか思えない。
文科相、いまさら、「ずさんだったことになる」とか言うなよ。もっと前に解決できる話だろ!
仕事柄、いろいろなギリシャ人と話す機会がある。ギリシャの財政問題について聞くと、お金がないと政府が公表していたらオリンピックなんかギリシャで
開催する必要など無かった。絶対に反対していたと質問をしたギリシャ人のほとんどが答えた。新国立競技場建設の巨額な費用を考えると
ギリシャと同じように「国立競技場将来構想有識者会議に参加した人々、日本スポーツ振興センター(JSC)及び文部科学省など
のマフィアに騙された!」と回答する日本人が将来増えるかもしれない。
新国立競技場:文科相「ずさんだったことになる」 07/10/13(毎日新聞)
◇ほかの閣僚から「デザイン決まったのは民主党政権時代」
下村博文・文部科学相は10日、閣議後の記者会見で、新国立競技場の計画について「(当初予定した総工費の)1300億円がデザインする人に伝わっていたか。値段は値段、デザインはデザインということならば、ずさんだったことになる」と述べ、2012年の国際公募や選考の過程を検証する考えを示した。ほかの閣僚からも「デザインが決まったのは民主党政権時代」と、総工費膨張の原因を民主党に責任転嫁するような発言が相次いだ。
実施計画で了承された建築家ザハ・ハディド氏の案は開閉式屋根を支える2本の巨大な弓状の構造物(キールアーチ)が特徴で、総工費をつり上げた。下村氏はハディド氏がデザインする際、当初予定していた総工費を「どの程度認識していたのか」と疑問を呈した。
安倍晋三首相は10日の衆院平和安全法制特別委員会で「民主党政権時にザハ案でいくと決まったが、その後、検討を重ねる中で費用がかさんだ」と答弁。麻生太郎副総理兼財務相は会見で「建設費用が決まった経緯がよく分からない。(12年当時の)野田内閣に聞いてください。政権交代のときに渡されただけで、我々は額も知らされていなかった」と述べた。【田原和宏】
問題のある公務員組織は実際のところ、こんなものだろう。いろいろと言い訳だけはすらすらと言うが、突き詰めると逃げる。それも受け入れらない
ような屁理屈やノーコメントで逃げる。
「いじめ防止のために町が実施する施策として、「いじめ問題対策連絡協議会」の設置を決めている。町内の6小中学校と町教委、町PTA連合会、スクールカウンセラーや紫波署などから構成され、各校でのいじめ防止の取り組み推進や、いじめの実態把握を行うとしていた。」
形だけの日本の特徴。新国立競技場建設費用問題と同じ。本質を無視し、国際的信頼、納期などいろいろと理由を探して正当化する。
下記の記事は矢巾町教育委員会だけの事であるが、今回の対応から推測して岩手県教育委員会の管理される学校の問題であると思う。
掘り下げて調べれば調べるほど辻褄の合わない問題が出てくると思う。紫波署が捜査の担当なのか知らないが(どこへ被害届が出されたのか知らない)
理論的に捜査すればいろいろと出てくると思う。見落とすのか、見つけるのかは、警察官の能力及び/又はやる気次第。
岩手県滝沢中2自殺…カッターナイフ向けるも「遊びの延長」 07/16/14(Girls Channel)は偶然ではないと思う。
町・学校のいじめ対策、未実施ばかり…中2自殺 07/17/13(読売新聞)
いじめ被害を訴えていた岩手県矢巾町の中学2年の男子生徒(13)が電車に飛び込み自殺をしたとみられる問題で、町と男子生徒が通っていた学校は、いじめ防止対策推進法に基づく対策を予定通りに実施していなかったことがわかった。
同法に基づき町と学校が定めている、いじめ防止の基本方針が形骸化している現状が浮き彫りになった。
町は2014年7月、いじめ防止対策推進法(13年9月施行)に基づき、「町いじめ防止基本方針」を策定した。このなかで、いじめ防止のために町が実施する施策として、「いじめ問題対策連絡協議会」の設置を決めている。
町内の6小中学校と町教委、町PTA連合会、スクールカウンセラーや紫波署などから構成され、各校でのいじめ防止の取り組み推進や、いじめの実態把握を行うとしていた。しかし、基本方針の策定以降、一度も設置されなかった。男子生徒の問題を受け、急きょ18日に設置することを決めた。越秀敏教育長は16日、「(協議会を)すぐ設置すべき所を怠っていた。申し訳ない」と話した。
また、生徒が通っていた学校は、いじめ防止のために教職員に行わせる「自己診断」を、予定していた今年6月に実施していなかった。学校は「なぜ実施できていなかったのか調査中」としている。
同法に基づき、同校が策定したいじめ防止基本方針では、教職員の資質を向上させていじめ防止につなげようと、毎年度6、11月にいじめ問題への取り組みについての自己診断の実施を定めている。しかし、今年はまだ実施されていない。
自己診断は、教職員が19の質問に対し「はい・いいえ」で答える。回答についての解説によって、自身のいじめに対する考え方や取り組み方を見直すことができる。校長は「実施しなかったことと、生徒が亡くなったことは、全く関係ないとは言いきれない」と話した。この学校は、方針で定めたいじめ早期発見のためのアンケート調査も、今年は計画より1か月遅れの6月に実施。6月に予定していた保護者アンケートも実施されていなかった。
一方、校長は16日、全校生徒約450人に対するアンケートと、一部の生徒への聞き取り調査をほぼ終えて、調査報告書の作成に着手したと明らかにした。
聞き取り調査は、男子生徒の同級生と所属していた運動部生徒約70人と、アンケート調査で「いじめと思われる場面を実際に見たか、男子生徒から聞いた」と答えた生徒ら約60人を対象に実施した。そのうえで、「男子生徒をいじめた」と指摘された生徒への聞き取りも行った。(福元洋平、安田英樹)
越秀敏矢巾町教育委員会教育長、この学校調査についてどうコメントするのか?前校長からも話は聞いたか?スクールカウンセラーや
教育研究所(監事 立花 常喜 矢巾町教育研究所長)は校長が
いじめを報告しなかったから介入できなかったのか?
現在の校長と前校長に責任があると思うのか?それとも担任だけの責任か?過去、2年間のいじめに関するアンケートの結果はどうだったのか?
前校長は「継続的ないじめはないと思い、引き継ぐ必要はないと判断した」と新聞記者には回答しているが、昨年の報告にはいじめとして
報告はしているのか?
幕引きしたいのだろうけど簡単に幕引きさせると同じ事を繰り返す。警察がしっかりと捜査するべきだと思う。
学校調査に60人が「いじめ見聞きした」 07/16/13(産経新聞)
岩手県矢巾町の中学2年村松亮君(13)がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、死亡後に学校が実施したアンケートに対し、クラスメートや同じ部活動の生徒以外で、約60人の生徒が村松君へのいじめを見聞きしたことがある、と回答したことが16日、町教育委員会への取材で分かった。学校は、クラスメートらからもさらに詳しい聞き取りを進め、死亡に至った背景を調べている。
アンケートは生徒445人を対象に実施。いじめを実際に見たり、村松君から聞いたりしたことがあるかを尋ねていた。
また、村松君が自殺をほのめかす投稿をした携帯ゲーム機や、亡くなる直前に参加した宿泊研修のノートを父親(40)が県警に提出したことも、関係者への取材で判明。県警は既に、村松君が「げんかいです」「死にたい」などと記した1年1学期から2年1学期の生活記録ノート計4冊の任意提出を受けている。
いじめゼロを達成するためにはいろいろな事が考えられる。アンケートを取らない。校内研修をおこなわない。教員にいじめを報告しないようにプレッシャーをかける。
校長がいじめと認識しないことを教員に間接的に伝えるなど。
例え、今回のように生徒の自殺となっても、理由を付けてアンケートが出来なかったという、研修を行っていないので周知徹底が出来なかったと言える。
全て準備していたようなシナリオや展開。だからこそ生徒が自殺しても逃げれる口実がドラマのように明らかになる。
岩手県教育委員会が本音はどうであれどう対応するか次第で将来に影響するであろう。
<矢巾中2自殺>いじめ防止策 校内研修せず 07/16/13(河北新報)
岩手県矢巾町で中学2年の村松亮君(13)がいじめを苦にして自殺したとみられる問題で、通っていた学校がいじめ防止対策推進法に基づき策定した「いじめ防止基本方針」を教員間に徹底させるための校内研修をしていなかったことが15日、校長への取材で分かった。学校側のいじめへの危機管理意識が低かった側面は否めず、村松君のいじめトラブルを教員間で共有できなかった遠因になった可能性がある。
いじめ防止基本方針は、学校ごとに策定が義務付けられている。校長によると、同校の方針は、いじめの疑いや生徒間のけんかを把握した場合、校長と町教委に報告し、教員全体で解決に当たると定めた。
校内では、いじめに関する教員間の情報共有、関係生徒の日常生活のサポートの在り方などについて、深い議論がなかったという。校長は「教員全体で方針の項目ごとに話し合ったことはなく、学年会議でも協議してこなかった。方針内容を検討するようあらためて指示はしなかった」と釈明している。
村松君は5、6月に学校の悩みアンケートに「悪口を言われている」「いじめられている」などと記入。同時期に担任に出したノートには「づっと暴力」「(特定の生徒を指し)あいつといるとろくなめにあわない」と記していた。
担任はアンケートを受け、5月に村松君とトラブルがあった男子生徒と面談したが、情報は組織的に共有されなかった。
校長は「(村松君のトラブル報告は)教員間の伝達系統のどこかで止まっていた可能性が高い。全教員に文書で報告するよう明確な周知はしてなかった」と説明している。
個人的には警察の捜査をを信用していないが、これほど注目を受ければ適当な捜査は出来ないと思う。
岩手県の権力者などから圧力かからない限り担当署の警察署長も出世とか考えると批判を受けるような捜査はしないはずである。
当時の校長が「継続的ないじめはないと思い、引き継ぐ必要はないと判断した」事実を越秀敏矢巾町教育委員会教育長が公表しなかった、又は、知らなかった
ことはとてもおかしい。いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)(文部科学省)
に関してこの校長は一切知らないのか?知らないとすれば、このような校長が他の学校で校長をしても良いのか?
矢巾北中学校から盛岡市立仙北中学校の校長になったのは高橋清之校長。この人物が当時の校長だろう?
「学校側がいじめを早期発見するため、全校生徒へのアンケートも5、11、2月の年3回するとしていた。」
昨年実施されたアンケートにはいじめが記載されていたのか?記載されていたとすれば、なぜ、越秀敏矢巾町教育委員会教育長は被害者が昨年にも
いじめを受けていたことを公表しなかったのか、それとも、いじめを知らなかったのか?辻褄があわなくなるので、メディアに突っ込まれるまで何も言わない何も言わないつもりか?
いじめが起きたら岩手県教育委員会の管轄の学校では適切な対応が出来ない可能性が高いので、ゆとりがあれば子供だけでも岩手から引越しさせる、又は、
他の県が推進している地方留学で新しいコミュニティーで再出発のほうが良いかも知れない。岩手の過疎や子供の数が減る問題があったとしても
それは岩手県庁や岩手県教育委員会の問題。
岩手の中2自殺、学校が中1時のいじめ調査 07/16/13(朝日新聞)
岩手県矢巾町の中学2年、村松亮君(13)がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、同町の越秀敏教育長は15日、村松君が1年生の時にもいじめられていた可能性が高いとの見解を明らかにした。学校も1年時のいじめの有無について調査を始めた。
学校は、村松君が担任に提出した生活記録ノートのコピーの提供を警察から受けた。1年時のノートにも「まるでいじめられるような気分でいやです」(昨年5月1日)などと、いじめをうかがわせる記載があり、関係する生徒への聞き取りを行うとしている。
学校はこれまで、2年時のクラスメートや同じ部活動に所属する生徒全員、教職員に対して聞き取りをしており、並行して1年時の調査もする。
矢巾町は14日から、村松君が亡くなったJR矢幅駅の線路脇に献花台を設置。15日もたくさんの花やジュースが供えられていた。〔共同〕
「 一方、村松さんの同学年の女子生徒(14)が「いじめを受けた」と訴えていたことについて、町教育長は15日の会見で『いじめはなかった』との認識を示した。」
越秀敏矢巾町教育委員会教育長に「いじめの認識」の定義を新聞記者は質問してほしい。定義が違えば議論の余地もないし、事実の検証にも食い違いが出てくる。
岩手県滝沢中2自殺…カッターナイフ向けるも「遊びの延長」 07/16/14(Girls Channel)
の前例もあるので、越秀敏矢巾町教育委員会教育長の認識が正かは利害関係のない第三者でなければ判断できない。
「学校では4月に校長が代わったが、当時の校長は『継続的ないじめはないと思い、引き継ぐ必要はないと判断した』という。」
継続的とはどのくらいの期間が開いていれば、継続的との言葉を使わないのか?少なくともいじめの報告書で使われる継続的の定義を新聞記者は
質問してほしい。
やはり矢巾町教育委員会の対応はおかしいと思う。完全に逃げの対応。校長達は岩手県教育委員会の研修を受けている。つまり
岩手県教育委員会の考えが反映されている生き物である。
いじめを受けたと訴えた女子生徒の不登校について教育研究所(監事 立花 常喜 矢巾町教育研究所長)
は相談を受けていたのか?相談を受けていたのであれば、いじめが原因ではない不登校と判断したのだろうか?
岩手の中2死亡、「いじめ訴え」引き継がず 1年時校長 07/16/15(朝日新聞)
斎藤徹、岡田昇
岩手県矢巾(やはば)町で中学2年の村松亮さん(13)が自殺したとみられる問題で、村松さんが1年生の時に「いじめ」を訴えていたが、当時の校長が「解決した」と判断し、現校長に引き継がなかったことがわかった。町教委は15日の会見で、1年生時もいじめがあった前提で調査する方針を示した。
村松さんが1年生だった昨年7月、担任に提出した「生活記録ノート」には「もうげんかいです」「クラスでいじめがまたいやになってきました」などの記述があった。
当時の校長によると、村松さんが所属した運動部で嫌がらせを受けたとの報告があり、部活動の顧問や担任と話し合いがもたれた。3学期ごろにも嫌がらせの報告があり、部員らに指導。当時の校長は「2度目の指導でいじめはなくなったと理解していた」と話す。
学校では4月に校長が代わったが、当時の校長は「継続的ないじめはないと思い、引き継ぐ必要はないと判断した」という。だが町教委はノートの記述などから、1年生の時もいじめがあったとみて調査する。
一方、村松さんの同学年の女子生徒(14)が「いじめを受けた」と訴えていたことについて、町教育長は15日の会見で「いじめはなかった」との認識を示した。(斎藤徹、岡田昇)
「 委員からは『生徒が継続してSOSを発したのに情報共有できなかったのは不思議』『岩手の教員の信頼が失われた』などの意見が出た。滝沢市で昨年、中学2年の男子生徒が自殺し、第三者委員会が自殺といじめの関連性を認定したことの教訓が生かされなかったとの指摘もあった。
県教委の八重樫勝教育委員長は『救いを求めたのに、助けられなかった13歳の苦しみやつらさを考えると胸が張り裂けそうな思い。遺族に寄り添った対応をすべきだ』と強調した。」
担当の教育委員会に責任があるのは当然だが、教育委員会が機能していない事を前提に岩手県教育委員会は対応するべきであった。その点では、岩手県教育委員会にも
責任はある。
「達増知事は『それぞれが自分たちの問題として対応することが未来につながる。事実関係を明らかにするため、(町教委の)第三者委員会に協力していく』と語った。」
達増岩手県知事はだめだな。適切に対応していないから問題が起きたことを理解していない。問題がある町教委が決めた第三者委員会に協力してどうするのか。
問題は解決されない。知事がこの程度の理解ではトップダウンの問題解決は出来ないだろう。
<矢巾中2自殺>教育会議、SOS見逃し批判 07/15/13(河北新報)
◎岩手知事「全県でいじめ防止」
岩手県矢巾町で中学2年の村松亮君(13)がいじめを苦にして自殺したとみられる問題で、県総合教育会議の臨時会が14日、県庁で開かれた。達増拓也知事は「岩手県からいじめをなくし、いじめで命を失うことがないようオール岩手で取り組む」と述べた。
委員7人が黙とうし、村松君の冥福を祈った。県教委は対応として、全公立校が昨年度策定した「いじめ防止基本方針」の実態調査や県のいじめ防止マニュアルの周知徹底、教員研修の充実を図る方針を示した。
委員からは「生徒が継続してSOSを発したのに情報共有できなかったのは不思議」「岩手の教員の信頼が失われた」などの意見が出た。滝沢市で昨年、中学2年の男子生徒が自殺し、第三者委員会が自殺といじめの関連性を認定したことの教訓が生かされなかったとの指摘もあった。
県教委の八重樫勝教育委員長は「救いを求めたのに、助けられなかった13歳の苦しみやつらさを考えると胸が張り裂けそうな思い。遺族に寄り添った対応をすべきだ」と強調した。
達増知事は「それぞれが自分たちの問題として対応することが未来につながる。事実関係を明らかにするため、(町教委の)第三者委員会に協力していく」と語った。
「高橋教育長は『(今年5月に)全市町村の教育委員会に情報提供したが、学校への具体の配布要請はなかった』と釈明。」
(今年5月に)滝沢市のいじめ自殺の報告書を全市町村の教育委員会に情報提供したのであれば、担当の学校に配布していない教育委員会を調べ、
配布していない理由を聞いて、問題があると疑われる教育委員会から訪問調査を始めるべきだ。それが終わったら、配布していない教育委員会を
訪問調査するべき。抜打ちで学校のいじめを受けた等のアンケートを実施するべきだと思う。事前通告だと、学校側が周到に準備する可能性がある。
矢巾・中2自殺:滝沢の報告書、周知なく 県教委、各校配布へ /岩手07/15/13(毎日新聞 地方版)
矢巾町の中学2年、村松亮さん(13)がいじめを苦に自殺したとみられる問題を受け、県総合教育会議は14日、盛岡市内丸の県庁で臨時会を開いた。県教育委員会は、昨年5月に滝沢市で中学2年の男子生徒が自殺したいじめの調査報告書が県内の学校に周知されていなかったことを明らかにし、各校へ配布する方針を示した。
会議は国の教育委員会制度改革の一環で今年度に設置された。達増拓也知事と高橋嘉行教育長のほか、八重樫勝教育委員長ら教育委員5人が参加した。
滝沢市のいじめ自殺の報告書が共有されていなかったことについて、委員から「あらゆる事実を明らかにするためにまとめた報告書だ。今からでも配って読んでほしい」と指摘された。
高橋教育長は「(今年5月に)全市町村の教育委員会に情報提供したが、学校への具体の配布要請はなかった」と釈明。「結果的に生かされなかったことはきわめて残念で深刻だ。今後は閲覧できる状態にしていきたい」と述べた。
一方、県教委はいじめ防止のため昨年度中に県内全公立校590校で策定した「学校いじめ防止基本方針」の運用状況を調査する方針も明らかにした。策定した方針が形式化していないかなどを検証する狙いがあるという。【浅野孝仁】
岩手県教育委員会少なくとも矢巾町教育委員会の教員や校長に対する洗脳教育はすばらしい。いじめゼロを達成するために
日本人として珍しい強引な解釈が徹底されている。これじあいじめによる不登校や自殺があるわけだ。
岩手県滝沢中2自殺…カッターナイフ向けるも「遊びの延長」 07/16/14(Girls Channel)との解釈も納得できる。目標のためには
黒に近い灰色だと白と言え、言っているようなものだ。
教員も一応、他の件の教員と同じような学科を取って教員になっているのに、誰も疑問に思わない事自体、驚くし、以上だ。心の中でおかしいと思っていても
言えない環境が出来上がっているのならとても恐ろしいことだ。
文部科学省も気付かないうちにこのような環境が完全に出来上がっているのであれば、とても恐ろしいことだ。
いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)(文部科学省)
で文科省がいじめの対策を指導しても強引な解釈で骨抜きにしてしまう強固な組織。「いじめの前段階」はいじめに近いが「いじめ」ではない。
「『死にたいと思ったときがけっこうありました』などの記述がある。『死にたい』との記述に対して担任は『どうしてそう感じるのかな? 何もかもダメと感じているの? 少し休んでリフレッシュできるといいなぁ』などと書いていた。」
矢巾町にはスクールカウンセラーがいるようだ。なぜカウンセラーがいるのにスクールカウンセラーを呼ばないのか?例え、生徒がネガティブに考えすぎていたとしても、
担任が勝手に判断するよりはカウンセラーの意見を聞いてみるべきである。スクールカウンセラーが使い物にならないのなら税金の無駄だから
廃止するべきだと思う。
「3点目の町内小中学校の児童・生徒、保護者、地域の方々等からの教育相談の実態と課題についてですが、各小中学校における教育相談窓口での対応のほか、教育研究所が平成24年度に受けた相談として、小学校の保護者から10件、中学校が14件となっております。
主な相談内容として、小学校については、教諭への指導の不満、児童間のトラブル、中学校については、不登校生徒の悩み、生徒間のトラブル、教諭への指導の不満等であります。相談を受けている研究所では、問題の実態を速やかに把握、確認し、学校長と連携を図りながら解決に向けて取り組んでいるところであります。
不登校については、家庭状況、生徒間のトラブル等、さまざまな要素と経過があります。学校では、校内はもちろんのこと、スクールカウンセラーや適用支援員の配置により、早期の問題解決を図っており、相談者の立場に立った個々の状況に応じ、
学校の相談室登校、学校だけでは解決できない場合の不適応支援教室こころの窓への入級なども選択肢に入れ、学校に戻れるよう復帰訓練等の対応をしながら支援体制を整えているところであります。」
平成25年第2回矢巾町議会定例会目次(矢巾町役場)
開けない人はここをクリック
メディアが騒ぎすぎているのかもしれないが、言っていること、書いてあることと、現状や事実と大きなギャップがある。これは組織に問題がある大きな証拠である。
文部科学省に対しても大きな期待は出来ないが、今回の事件について背景を含めて深く掘り下げて調査するべきである。
ところで教育研究所(監事 立花 常喜 矢巾町教育研究所長)は今回の問題を知っていたのか、報告を受けていなかったのか?
岩手中2自殺:「いじめ」訴え昨春から 07/15/13(毎日新聞)
◇学校側、「事前に解決」と認識
岩手県矢巾(やはば)町の中学2年、村松亮さん(13)がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、村松さんが1年生の時に当時の担任教員に提出した「生活記録ノート」にもいじめに関する記述が複数あることが分かった。担任は当時の校長らと情報を共有し、2学期には村松さんらと面談したという。学校側は「いじめが起きる前に解決した」と認識していたが、その後も記述は続いており、学校は昨年度の対応についても調べる。
村松さんが最初に「いじめ」という言葉を使ったのは昨年5月1日付。「まるでいじめられている気分でいやです。もうげんかいです」と記述。担任はノートに「みんなが仲良くできる方法を考えましょう。まずは、自分の気持ちを相手に伝えよう」と返事を書いた。
その後、村松さんは7月中に「先生にはいじめの多い人の名前をおしえましょう。もう限界です」「クラスでいじめがまたいやになってきました」と記述。担任は「三者面談で伝えますが、2学期、みんな変われるといいですね」などと返事を書いた。
当時の校長によると、担任は生徒指導担当の教員や校長、副校長らにも相談。9月には別の教員とともに、村松さんやトラブル相手の生徒を交えて面談し、指導したという。当時の校長は「生徒がトラブルを抱えれば、学年の教員や管理職で絶対に共有する。村松さんのケースはいじめの前段階で対処し、一定の解決をみたと考えた」と説明。町教委に毎月報告するいじめ件数はゼロとしていた。
しかし、ノートのやりとりはその後も続いた。12月8日付に「何十回も『死ね』って言われるんですけど」、今年2月には「死にたいと思ったときがけっこうありました」などの記述がある。「死にたい」との記述に対して担任は「どうしてそう感じるのかな? 何もかもダメと感じているの? 少し休んでリフレッシュできるといいなぁ」などと書いていた。
4月に赴任した現在の校長は今月13日の記者会見で、村松さんがいじめを受けていた可能性があることについて「聞いていなかった」と明言。2年生から受け持った担任や生徒指導担当者らに引き継がれていたかについては「調査している」と説明した。
【浅野孝仁】
下記のサイトの情報の全てが事実とは思わないけど、事実の部分があるとすれば岩手県は恐ろしいところだと思う。
これらの指示が越秀敏矢巾町教育委員会教育長や松尾光則(元教育長)矢巾町教育委員会教育委員長から発信されいるのか、
それとも校長から発信されているのだろうか?どちらにしても就職の約束の話が事実なら、教育委員からの指示のような気がする。
岩手県は村社会的な社会構造が残っているのだろうか?岩手に行った事がないのでわからない!
岩手県教育委員会が越秀敏矢巾町教育委員会教育長に任せずに介入するべきだろう。
岩手県教育委員会からの御意見 (文部科学省)を提出する前に、岩手県の教育委員会の構造改革を行うべきだろう。改革できない事実が
指摘している問題に関係しているのではないのか?
<矢巾中2自殺>女子生徒もいじめ被害、不登校に 07/15/15(河北新報)
◎学校、町教委へ報告せず「いじめ件数ゼロ」
岩手県矢巾町で中学2年の村松亮君(13)がいじめを苦にして自殺したとみられる問題で、同じ学年の女子生徒が昨年、「クラス内でいじめを受けている」と学校に相談していたことが14日、分かった。担任教諭は相手生徒を指導したが、学校の組織的対応はなく、町教委へも報告していなかった。女子生徒は取材に「学校が昨年度のいじめ件数ゼロとしているのはうそだと思った」と話している。
女子生徒は昨年4月中旬から、同じクラスの複数の生徒から無視されたり、掃除当番の教室に入れなくされたりなどのいじめ被害を受けた。5月に担任教諭に相談。担任は翌日、クラスの女子全員に注意した。
担任は7月、女子生徒がいじめを受けたと指摘した生徒たちと面談したが、嫌がらせは続いた。女子生徒は1年生の3学期に不登校になり、2年生になっても通学できていない。
女子生徒は「いじめだと学校に相談した。この学校のいじめについて全て明らかにしてほしい」と訴えている。
女子生徒は2年生に進級して、村松君と同じクラスになり、休日はゲームでよく遊んだという。「村松君からいじめの相談はなかった。心配を掛けたくなかったのだと思う。大事な友達だった」と振り返った。
女子生徒の母親は「娘が被害に遭ったとき、担任はよく対応してくれた。いじめは二度と起きないよう学校にお願いした。学校が対策を取っていれば、村松君が亡くなることはなかったと思う」と話した。
町教委は「いじめが要因で不登校になった生徒がいるとの報告は受けていなかった。調査して真偽を確かめたい」と説明した。
「県は14日、臨時の総合教育会議を開き、高橋嘉行・県教育長が、いじめ防止対策推進法に基づいて、各学校が定めているいじめ防止基本方針が守られているかを全県的に調査する方針を明らかにした。」
下記のような偉そうな事を書いて、去年の校長もいじめを報告せず、今年の校長(前職:岩手県教育委員会教職員課首席経営指導主事)もいじめを報告せず、
同じ学校でいじめられて不登校、学年主任はいじめを目撃した生徒を「余計なこと言うな」と脅す、
岩手県滝沢中2自殺…カッターナイフ向けるも「遊びの延長」 07/16/14(Girls Channel)を作成と驚くことばかりが起きている岩手県教育委員会エリアの学校。
自分の県の学校で何が起きているのか把握する事から始めよう。報告がないから知らないで済むのか?しかも、校長や教員が問題を悪化させているではないか?
学校関係者が自己都合で最悪のケースで生徒が自殺しても良いような対応を取っている。恥ずかしいとは思わないか?中学生ぐらいで考えることが出来る中学生は
校長や教員が何をしているのか理解できるぞ!校長や教員も自己を優先させ、他人がどうなっても良い対応を取る。問題が起きると詭弁で逃げる。このような
事実を見た生徒の中には正直者は馬鹿を見る、先生の中には生徒を見捨てる人がいる、先生は給料のため、出世のために他人を切り捨てる等と思うかもしれない。
岩手県教育委員会はこれで満足しているのか?これでは自己満足の世界かも?
 全校に調査を依頼しても正確な報告書が帰って来るとは思わないほうが良い。既に腐った学校が注目を浴びている。しかも、
日本年金機構の個人情報流出問題を巡り、パスワード設定などの安全対策が完了したとする虚偽の報告
が良い例である。安全対策が完了したとする虚偽の報告が4回も提出されている。越秀敏矢巾町教育委員会教育長はいじめの報告はゼロと回答したが、
実際はいじめはあったのか?いじめはあった。少なくとも2件。しかし越秀敏矢巾町教育委員会教育長はいじめはゼロとの報告に満足していた。
本当に調査を行いたいのなら、抜打ちで岩手県教育委員会が通知なしで学校を訪問し、いじめられた:はい いいえの簡単な質問だけ良いので行うべきである。
そうでなければ、まじめになっている校長、教員、そして生徒に負担をかけるだけのパフォーマンスになってしまう。日本が好きな形だけの
パフォーマンスで幕引きであれば、従来の方法で実施すればよい。考えるタイプの人達ははやり岩手県教育委員会はそのような体質だったのかと思うだけである。
全校に調査を依頼しても正確な報告書が帰って来るとは思わないほうが良い。既に腐った学校が注目を浴びている。しかも、
日本年金機構の個人情報流出問題を巡り、パスワード設定などの安全対策が完了したとする虚偽の報告
が良い例である。安全対策が完了したとする虚偽の報告が4回も提出されている。越秀敏矢巾町教育委員会教育長はいじめの報告はゼロと回答したが、
実際はいじめはあったのか?いじめはあった。少なくとも2件。しかし越秀敏矢巾町教育委員会教育長はいじめはゼロとの報告に満足していた。
本当に調査を行いたいのなら、抜打ちで岩手県教育委員会が通知なしで学校を訪問し、いじめられた:はい いいえの簡単な質問だけ良いので行うべきである。
そうでなければ、まじめになっている校長、教員、そして生徒に負担をかけるだけのパフォーマンスになってしまう。日本が好きな形だけの
パフォーマンスで幕引きであれば、従来の方法で実施すればよい。考えるタイプの人達ははやり岩手県教育委員会はそのような体質だったのかと思うだけである。
父親「調査すると約束、信じたい」…中2自殺 07/14/13(読売新聞)
いじめ被害を訴えていた岩手県矢巾やはば町の中学2年の男子生徒(13)が電車に飛び込み自殺したとみられる問題で、男子生徒の父親(40)は14日午前、町教育委員会を訪れ、徹底した真相究明を要望した。
応対した越秀敏教育長は、「13歳の生徒が自殺を選択するまで追い込まれ、救いの手をさしのべられなかったことは大変申し訳ない」と父親に謝罪した。
また、越教育長は学校の調査結果がまとまった後の今月下旬をめどに「(生徒の担任と父親の)話し合いの場を持つよう調整していく」と伝えた。父親は面談後、報道陣に対し、「謝罪があったことは評価したい。調査をしっかりやると約束していただいたので信じたい」と話した。
一方、県は14日、臨時の総合教育会議を開き、高橋嘉行・県教育長が、いじめ防止対策推進法に基づいて、各学校が定めているいじめ防止基本方針が守られているかを全県的に調査する方針を明らかにした。
顔出しNGだったがニュースで顔出しで謝罪した。
○○○○、○○○○!岩手県矢巾北中学校の加害者たちか!? [事故・事件] (ブチまけ小僧日記)
この学校の体質である可能性が非常に高くなってきた。
個人的な推測ではこの学校だけでなく、越秀敏矢巾町教育委員会教育長の地域の学校では多かれ少なかれ同じような問題が報告されていない可能性がある。
問題を起こした校長の前の肩書きは岩手県教育委員会教職員課首席経営指導主事。もし越秀敏矢巾町教育委員会教育長の地域の学校だけの問題であれば
校長達を指導する立場であったこの校長は矢巾町教育委員会教育長の問題を岩手教育委員会に報告するだろう。報告もせずに、それに従うのは基本的に
岩手県教育委員会の体質が同じである可能性が高い。それを推測させるケースは
岩手県滝沢中2自殺…カッターナイフ向けるも「遊びの延長」 07/16/14(Girls Channel)との報告書だ。
盛岡市立仙北中学校校長になった高橋清之校長(移動前は矢巾北中学校)にも聞き取りをした方が良い。関係者は早く幕引きを望んでいると思うが、
徹底的に調査し、警察は捜査しなければいけないと思う。警察も地元密着であれば間接的に甘い捜査をお願いされるかもしれない。あってはならないが、人間である
以上、可能性はないわけではない。
本当に一部の学校だけ、又は、校長の問題であれば校長が変われば、新しい人が他の組織から来れば変わるはず。変わらないのは、似たような人間達である
から問題と思わないし、疑問にさえ感じないと言う事。良い意味でも、悪い意味でも暗黙の了解があった、または、何も言わなくても組織の意思が
理解できるほどの洗脳が岩手県教育委員会のコントロールで確立されていると言う事かも知れない。
女生徒もいじめ被害か、昨年度不登校…中2自殺 07/14/13(読売新聞)
いじめ被害を訴えていた岩手県矢巾やはば町の中学2年の男子生徒(13)が電車に飛び込み自殺したとみられる問題で、同学年の女子生徒(14)も昨年5月頃から、「同級生からいじめを受けている」と学校に訴えていたことがわかった。
だが、状況は改善されず、女子生徒は不登校になったという。学校は男子生徒のケースと同様、町教育委員会に報告しておらず、町教委は13日、学校に速やかな調査と報告を求めた。
女子生徒とその母親によると、女子生徒は昨年5月頃から、同級生から嫌がらせを受けるようになり、教室の出入りの際に閉め出されたり、集団で無視されたりした。すぐに当時の担任に相談したが、1年の3学期以降は不登校になった。女子生徒は1年時、亡くなった男子生徒とは別のクラスだった。
「もう限界」ノート記述…昨年のいじめ報告せず 07/12/13(読売新聞)
電車に飛び込んで自殺したとみられる岩手県矢巾やはば町の中学2年の男子生徒(13)が、1年時に担任とやりとりしていた「生活記録ノート」でもいじめ被害を訴え、「もうげんかいです」と書いていた。
担任らは当事者同士の話し合いなどで問題解決を図っていたが、学校は町教育委員会にいじめの報告をしていなかった。
生徒が今月5日午後7時半頃、JR東北線矢幅駅構内で普通電車に飛び込んで死亡し、12日で1週間になる。2年生になってからの生活記録ノートなどに、いじめを受けていたような記述や、自殺をほのめかす内容が書かれていたことが明らかになり、町教委は今月末を目標に第三者委員会を設置し、学校の調査結果を基に検証を始めることにしている。
生徒は中学に入学した昨年4月から生活記録ノートに、「もうげんかいです」(5月1日)、「クラスでいじめがまたいやになってきました」(7月23日)などと記述。担任はノートに「みんなが仲良くできる方法を考えましょう」(5月1日)、「三者面談で伝えますが、2学期、みんな変われるといいですね(よい方向に)」(7月23日)などとコメントした。
昨年秋、父親が学校に相談し、関係する生徒で話し合いの場を持ったが、その後もノートには「さいきんなにもかもだめだし、死にたいと思ったときがけっこうありました」(今年2月26日)との記述が続いた。
いじめや自殺の撲滅に取り組むNPO法人「再チャレンジ東京」の平林朋紀事務局長は「大人は子供が置かれている苦しい境遇を理解し、『いじめは死に直結する』という意識を持つ必要がある」と話している。
「同署は父親に対し、『きちんと調べていきます』と回答したという。」
「余計なこと言うな」と恫喝した「岩手・中2自殺」の学年主任は当然、警察の調書を受けるのだろ!教員の立場を利用していじめを目撃した生徒を
威圧し、証言しないような行動を取った。捜査妨害に当たると思うがどうなのか?もし事件現場を見た目撃者に現場を見られたやくざの子分が目撃者に
対して「余計なこと言うな」と言えば、大問題だろ。それと同じではないのか?
刑事告発が受理されているのなら校長や教育委員会が隠蔽や口裏あわせを完璧にする前に捜査を始めて方がよい。謝罪をして相手を油断させて
時間稼ぎをする場合もある。ゲームじゃないけど、作戦勝ちというパターンもある。気を付けよう。
父親、学校に真相究明求める…岩手の中2自殺 07/13/15 (読売新聞)
岩手県矢巾やはば町で、いじめ被害を訴えていた中学2年の男子生徒(13)が電車に飛び込み自殺したとみられる問題で、男子生徒の父親(40)は13日午前、生徒が通っていた中学校に対し、真相究明のための調査を徹底するよう申し入れた。
また、12日には、男子生徒が同級生から暴力をふるわれたなどとして、県警紫波署に被害を届け出た。
父親は校長と面談し、「今回の件は起こるべくして起こった。学校で起きていたこと、息子がどんな生活をしていたのか、息子をいじめていたグループを特定して報告してほしい」と要望。校長は、「申し訳ございません」と父親に初めて謝罪し、「しっかり調べてお伝えします」と答えたという。
取材に対し、父親は「事実関係が全て明らかにならなければ、同じようなことは後を絶たない。徹底的に調べてほしい」と話している。また、「机に頭をたたきつけたり、大きな体でぶつかってきたりする行為は暴行にあたると思う。容疑などの詳細は今後、警察と調整していく」とも話した。同署は父親に対し、「きちんと調べていきます」と回答したという。
岩手県教育委員会は形だけの組織。表と裏がある事を証明している。問題を起こした校長の前の肩書きは岩手県教育委員会教職員課首席経営指導主事。
岩手県教育委員会の考えが染込んでいるはず。そしてこの様。
岩手県滝沢中2自殺…カッターナイフ向けるも「遊びの延長」 07/16/14(Girls Channel)との報告書が提出された背景が想像できる。
達増拓也岩手県知事(岩手県庁)、
どう思われますか?エリート過ぎて理解できない領域ですか?事件の学校は盛岡の県庁から近いですよね。情報収集は簡単ですよね!
「岩手・中2自殺」学年主任いじめ証言の同級生脅し「余計なこと言うな」 07/13/15 ( J-CASTテレビウォッチ)
いじめを訴えて自殺した岩手県の中学2年、村松亮君(13)の父親がきのう12日(2015年7月)、警察に被害届を出した。亮君の死から1週間、いじめていた生徒やその保護者からは接触も謝罪もない。そればかりか、学校やいじめ生徒たちの悪質な言動も浮かび上がってきた。
村松亮君の父親が被害届「警察も入って捜査してもらいたい」
亮君は1年生の時から学校に提出する「生活記録ノート」でいじめの事実を訴え、「死にたいと思ったときがけっこうありました」と記していたが、2年生のクラス替えでもいじめ生徒と同じクラスにされた。「死んでもいいですか」「もう死ぬ場所は決まっているんです」などの記述も、担任は校長や周囲に報告せず、生徒の命にかかわる情報が共有されなかった。父親にも話がなかったという。
父親は「担任だけが把握して、連絡をもらえなかったのはなぜか。自殺がどれだけ重いことか」と問いかける。祖父も「亮は明るくふるまっていたのだろう。学校から電話がきたことも1回もない」という。これでは家族は気づけない。
教育委員会は第三者委員会を設置して調査することを決めたが、父親は「校内暴力について警察も入って捜査してもらいたい」と話す。こんな学校や教委を信頼しろというのはどだい無理な話だ。
まったく反省ないいじめ生徒!証言同級生に舌打ち
いじめを証言した生徒に対しても、学校はおかしな対応をしている。この同級生は学年主任の教員から8日と9日に呼び出され、「余計なことを言うな」「反省したか」と問い詰められたという。亮君の訴えにきちんと対処しなかったたけでなく、事実を握りつぶそうとしたのか。これではいじめの共犯行為だ。
今度は「また余分なことをばらしたな」とでも脅すのだろうか。いじめをしたとされる生徒たちも、証言した同級生とすれ違ったざまに舌打ちをしたという。8日、9日、10日と日にちもはっきりしている。
司会の加藤浩次「勇気を持って言っている子どもに対して、これは何なんだと思ってしまいます。いじめ生徒も何も反省していないということですね」
こんな教師やいじめ生徒をいつまで放置しておくのか。うやむやにせず、厳正な措置が必要だ。
記事になっているのだから、いじめた生徒はバスケ部員と同じクラスメートに絞っての捜査だから検討が付け易いだろう。
話は変わるが、現在の校長は4月からの校長。いじめは去年から始まっていると言うことは、盛岡市立仙北中学校校長になった高橋清之校長にも
聞き取りをした方が良い。「学校側がいじめを早期発見するため、全校生徒へのアンケートも5、11、2月の年3回するとしていた。」と言うことは、
去年の11月及び今年の2月にアンケートが実施されているはずである。その時はどのようになっていたのか?
「学校側が、いじめとして町教委に報告していなかったことについて、町教委は10日の記者会見で『いじめの認知がゼロであることが、(いじめ防止の)成果という意識が教委や学校にあった』としている。」
これは新しい校長での学校側の認識なのか、それとも以前からの同じ認識だったのか?メディアはこの点についても取材して記事にしてほしい。
少年の母、憤りと悔しさ訴え 「ここまでひどいいじめとは…」「学校は『言うな』と箝口令」 (1/3)
(2/3)
(3/3) 04/30/15(読売新聞)
岩手県矢巾町(やはばちょう)の中学2年の村松亮君(13)がいじめを苦に列車に飛び込んで自殺したとみられる問題で、村松君の母親(44)が11日、産経新聞の取材に応じた。10日に初めて読んだ村松君のノートで、同級生からの暴力や悪口に苦悩していたことを知ったといい、「ここまでひどいいじめとは…。なぜここまで追い詰められる必要があったのか」と悔しさと憤りを露わにした。
元夫からの2年半ぶりの連絡が…
5年前の8月に(村松君の父親と)離婚しました。東京都内で中学1年と小学3年の娘(亮君の妹)と住んでいます。
初めは亮も(東京に)連れていったのですが、おばあちゃん子だったのですぐに「おばあちゃんが心配。岩手に帰っていいかな」と言い出したんです。本人の意思を尊重したら、こんなことになってしまいました。
(村松君が死亡したという)一報を受けたのは6日の午後5時18分でした。元夫とは2年半の間、連絡を取っていなかったので、びっくりしました。
久しぶりの連絡がこれかよと。7日にこちら(矢巾町)に来るまで、冷静でいられませんでした。悲しみ、驚き、戸惑い、(亮を預けた元夫への)怒りが入り交じり、言葉で言い表すことができませんでした。
遺体と対面し、現実を見て、何で死んだんだろうという疑問がわきました。なぜここまで追い詰められる必要があったのか。
相談あれば「行くな」と言ったのに…
(村松君と)連絡が取れていれば、いじめのことを言ってくれたかもしれない。私なら「行くな」と言いました。亮の姉も同じ中学校に通い、いじめを受けていました。「行くな」と言いました。所属していたバレーボール部の顧問が親身になってくれました。学校とは関係なくだったと思います。
10日に初めて(村松君の生活記録)ノートを見ました。子供たちがこう(死を示唆する内容)書いているのに、他の子でも「研修たのしみましょうね」と書いてしまうのでしょうか。
生徒が40人もいれば、面倒みるのは大変でしょう。先生も人だから。でも「死ぬかも」とか「生きているのが嫌になった」とかつづっているのだから、一言でいいから元夫か、おじいちゃんに電話してくれていれば…。(学校に対しては)不信感だけ。
1年生のときの担任はすごくいい先生でした。1年生のときの担任なら助けてくれたと思います。引き継ぎしていなかったのかなぁ。亮は「何とかしてほしい」と頼んだのでしょう。
いじめ、ここまでひどいとは…
ここまでひどいいじめとは思っていませんでした。(いじめていたという)子たちを恨んでもしようがないが、この先、どういう人生を歩むのでしょうか。
(同じ中学校で)他にもいじめられている子がいると思います。全国でいじめられている子には「死ぬな」と言いたいです。中学校では「(今回の件を報道機関などに)言うな」と(箝口令が)出ているらしいです。
(村松君は)最初は卓球部に入りたがっていたらしい。でも(ラケットで)ポンポンと20回以上できないと入れないと言われてバスケ部に入ったそうです。バレーボール部でも、文化部でも良かった。絵を描くのが好きだったんです。
(いじめた子は)バスケ部にも同じクラスにもいるそうです。「人の嫌がることをするな」。この子たちにそう言いたいです。亮が何をしていたか分からないが、うちの子が悪いことをしていたら、私は土下座でもします。世の中はおかしい。いじめはなくならない。だけど、何かしたら、いずれ返ってきます。
(了)
「学校側が、いじめとして町教委に報告していなかったことについて、町教委は10日の記者会見で『いじめの認知がゼロであることが、(いじめ防止の)成果という意識が教委や学校にあった』としている。」
ようやく原因の一部が出てきたようだ。つまり、担任の判断ではなく校長による圧力または校長による間接的な指示、そして最終的には教委からの直接又は間接的な指導があったと言うことだ。
個人的な意見であるが、これは岩手県教育委員会そして岩手県庁の組織的な問題であると思う。
岩手県滝沢の同校校長や市教育委員会関係者ら13人で組織された調査委員会は
岩手県滝沢中2自殺…カッターナイフ向けるも「遊びの延長」 07/16/14(Girls Channel)との報告書も同じ力や圧力が働いていたと推測する。
「矢巾町教委は『黒塗りが多く、読むのが大変』として配布を見送った。」事実は、教員がいじめを報告しなければならないのはないかと疑問を抱く、
または、教委及び校長の指示に従わなくなるリスクを抑えたかったのではないのか?教委の人間が岩手県教育委員会に一時的に籍をおいている事実は、
判断基準及び価値観は岩手県教育委員会のDNAから来ていると判断する。日本年金機構の個人情報流出問題を巡り、パスワード設定などの安全対策が完了したとする虚偽の報告
を考えれば、判断基準及び価値観が共有されていることが推測できる。たくさんの人間が組織内を往来して同じ判断基準及び価値観を共有し、
明確な指示を出さなくてもサインのようなメッセージで行動できるバージョンの悪いケース。
教員は働きすぎと言われるが、隠蔽のための活動、隠蔽のための会合、隠蔽のための資料作成、隠蔽のための偽装工作、隠蔽が発覚した時の口裏あわせ、
隠蔽が発覚した時の証拠抹消、隠蔽が発覚した後の歪んだ調査報告の作成などに関与していてはさらに忙しいであろう。日本年金機構の個人情報流出対策
の虚偽報告を見れば判るが、ばれなければ嘘のほうが簡単なのである。嘘がばれたとしても、処分するのも公務員。調査し、処分する権限を持つのも
公務員。反論されないような対応や防止対策を公表し、実際は実行しなくても、バレル可能性が低い環境が問題。
こんな校長、教育委員会そして教育関係者が存在するのだから、子供がまともに育つほうが不思議だ。たしかに子供の親の責任はある。しかし、
こんな対応を給料を貰い、権限を持っている教育関係者が存在するのだから、まともな方針が立てれないはずだ。めんどうな問題から目をそらし、
実際の社会の問題を無視して、理想の世界だけで通用する試みを実行する。子供達は学校を卒業すれば現実の社会に適応しなければ、
生きて行けなくなるか、敗北者としての命ある限り生きていくしかない。卒業してしまえば、子供達がどうなっても関係ないのである。
自殺しても関係ないような対応するのだからそうであるに違いないと思う。
文部科学省は今回の事件を単なる自殺事件ではなく、学校関係者及び教育委員会の問題として踏み込んで調査するべきである。本気で調査すれば
抵抗したり、協力しない関係者がいる事に気付くと思う。岩手県教育委員会を含め、厳しい制裁措置を取って対応するべきである。それでも、
隠蔽や抵抗はなくならないと思う。それは組織の体質が原因である証拠だと思う。
いじめ訴え、昨春からノートに…岩手中2自殺 07/11/13(毎日新聞)
岩手県矢巾やはば町で、いじめ被害を訴えていた中学2年の男子生徒(13)が電車に飛び込み自殺したとみられる問題で、男子生徒は中学1年のときから、当時の担任教諭とやりとりする「生活記録ノート」に、「(別の生徒から)何回も『死ね』って言われる」などと記載していたことが分かった。
学校から町教委に対し、いじめの有無を伝える報告は昨年度から今年6月末現在までゼロだった。
亡くなった生徒の父親によると、生徒は昨年春から、「生活記録ノート」に「まるでいじめられるような気分でいやです」(2014年5月1日)、「先生にはいじめの多い人の名前をおしえましょう。もうげんかいです」(同7月15日)などと書き込んでいた。
亡くなった生徒は昨年秋、「(別の生徒から)わざと体をぶつけられたりして困っている」と家族に打ち明けたことがあり、父親は学校に相談。関係する生徒を交えて当時の担任らで話し合いの場を設けたが、その後も「先生どうか助けてください」などの記載が続いた。
学校側が、いじめとして町教委に報告していなかったことについて、町教委は10日の記者会見で「いじめの認知がゼロであることが、(いじめ防止の)成果という意識が教委や学校にあった」としている。
「このアンケートとは別に、学校側は5月に2年生を対象にした学校生活に関するアンケートを実施していた。」
アンケートを実施する時間があるなら一緒に「いじめ防止基本方針」で定めた「こころのアンケート」もやればよかった。
問題を抱えていない生徒は適当に書くだけだからそんなに問題ないはず。生徒に負担になるとは思えない。
生活ノートにあれだけ書いているのだから、先生に負担になるというのであれば該当しような子に「いじめ防止基本方針」で定めた「こころのアンケート」
を記入させれば良かった。「こころのアンケート」がなければ学校や校長が動けないと言うのであれば、学校又は校長がいじめはないと報告したかったのではないのか?
公務員で嘘を付くやつ等は屁理屈や本当らしい嘘を平気で言う。録音が必要。
岩手中2自殺:6月調査で「いじめ」回答 町教育長が謝罪 07/10/13(毎日新聞)
岩手県矢巾(やはば)町の中学2年生の男子生徒(13)がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、学校が当初5月に予定していた全校生徒を対象にしたアンケートが6月に実施され、男子生徒が「いじめられている」と回答していたことが10日、分かった。同町教育委員会の越秀敏教育長は記者会見し、「いじめがあったという事実がかなり高く、自殺の一因と言わざるを得ない。手を差し伸べられず、心よりおわび申し上げる」と謝罪した。
アンケートは学校が昨年3月に策定した「いじめ防止基本方針」で定めた「こころのアンケート」。5、11、2月の年3回実施するとしていたが、今年は運動会などの学校行事の影響で約1カ月延期されていた。町教委などによると、男子生徒はその中でいじめを受けたと記載していたが、アンケートは生徒が亡くなるまで集計されず、校長らにも報告されていなかった。
また、このアンケートとは別に、学校側は5月に2年生を対象にした学校生活に関するアンケートを実施していた。男子生徒はこの際にも「悪口を言われる時がある」などと記していた。学校側によると、この時は担任が男子生徒と面談したといい、「他の生徒とのトラブルは収束した」と思っていたという。
文部科学省は同日、同町教委に聞き取り調査を実施し、同校の対応について適切に検証するよう求めた。【近藤綾加、春増翔太】
同じ事を繰り返すようになるが、「越教育長は、町内の小中学校からは月に1回、いじめの認知件数の報告を受けていましたが、村松さんが通っていた中学校を含め、今年度はゼロだったことを明らかにし、『学校と一緒に考えて行かなくてはと反省している』と述べました。また、担任の教諭が、教育委員会の聞き取りに対して、『村松さんにはトラブルがあったが、指導をして解決したと認識していた』と説明していることを明らかにしました。
越教育長は、『いじめ防止の方針を作っても、機能しなければただの紙と同じだ。情報共有できる職場環境を検討していかなければならない」と述べました。』
「学校側がいじめを早期発見するため、全校生徒へのアンケートも5、11、2月の年3回するとしていた。」
上記から考えると町内の小中学校からは月に1回、いじめの認知件数の報告を受けるシステムになっていても実際は「学校側がいじめを早期発見するため、全校生徒へのアンケートも5、11、2月の年3回するとしていた。」
越教育長の説明は明らかに何も知らない人、又は詳しい情報を知らない人を騙すような回答。アンケートが年3回実施なのに、月1回の報告の
信頼性の根拠はどこにあるのか?それもこれはNHKのニュースだ。
越教育長は平成25年6月11日(火)に開かれた平成25年第2回矢巾町議会定例会によると
5月1日、松尾光則(元教育長)矢巾町教育委員会教育委員長に越秀敏氏が教育長就任している。よって松尾光則氏(元教育長)矢巾町教育委員会教育委員長と
越教育長が矢巾町教育委員会の体質に関して責任があると思う。町議について一切知らないが、平成25年第2回矢巾町議会定例会に出席した議員は
齊藤正範議員、藤原由巳議員、村松信一議員、山﨑道夫議員、川村農夫議員、小川文子議員、谷上哲議員、廣田光男議員、
秋篠忠夫議員、芦生健勝議員、昆秀一議員、村松輝夫議員、藤原梅昭議員、川村よし子議員、米倉清志議員、髙橋七郎議員、長谷川和男議員、藤原義一議員となっている。
町内の小中学校からは月に1回、いじめの認知件数の報告は建前であり、張りぼての制度。越教育長は「学校側がいじめを早期発見するため、全校生徒へのアンケートも5、11、2月の年3回するとしていた。」
を知っていたのか?知らないのであれば管理責任者として失格。そして全校生徒へのアンケートが実地されていない事をチェックする事を部下に指示していなければ
管理責任者として失格。松尾光則(元教育長)矢巾町教育委員会教育委員長についても同じことが言える。元教育長であるのだから矢巾町教育委員会の体質及び教育長の仕事について
十分に精通していると思われる。越教育長が全てを仕切っているのであれば、松尾光則(元教育長)矢巾町教育委員会教育委員長は必要ない。そうでないのであれば、
松尾光則矢巾町教育委員会教育委員長にも責任がある。自殺した学校ではアンケートを取っていないのだから報告に上がるはずがない、本当にチェックしているのであればアンケートを行った日付も報告書に記載させるべきだ。
矢巾町教育委員会では詳細な情報を上げるような発想を考え付く人間が1人もいなかったのか?それとも最近の不適切な会計問題のようにトップからの何らかの
圧力があり、発言できるような環境ではなかったのか?報告されていないからいじめはゼロとは言えない。データ操作していると判断、又は、データ操作の疑うことが出来る。
日本年金機構の個人情報流出問題を巡り、パスワード設定などの安全対策が完了したとする虚偽の報告
と同じ。報告を集めるだけでチェック機能が欠如している。
平成25年第2回矢巾町議会定例会(矢巾町役場)を読むとスクールカウンセラーは矢巾町に
設置されているようだなぜ、スクールカウンセラーの事が記事に触れられていないのか??
「文部科学省初等中等教育局・平居秀一生徒指導室長は『いじめられているという記述があった』、下村文部科学大臣は『子どもがSOSを明らかに発している。
担任教師の対応の仕方は甘かった』と述べた。」
担任教師の対応が甘いではなく、なぜいじめとして校長に報告できなかったのかを調査するべきだ。校長が圧力をかけていたとすれば、「校長が聞き取りを始めた。」と新聞記事に記載されているので
校長による聞き取りを止めさすべきだ。第三者委員会に全てを任せるべきだ。
岩手県滝沢の同校校長や市教育委員会関係者ら13人で組織された調査委員会は
岩手県滝沢中2自殺…カッターナイフ向けるも「遊びの延長」 07/16/14(Girls Channel)とのすばらしい報告書を給料を貰いながら作成している。
責任を問われたくない関係者の隠蔽及び詭弁の努力が良くわかる。下村文部科学大臣は校長による聞き取りの中止を指示するべきだ。
岩手・中2自殺:いじめ調査間に合わず 行事で遅れ 07/10/13(毎日新聞)
岩手県矢巾(やはば)町の中学2年の男子生徒(13)がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、学校側が今春、いじめに関して実施する予定だった教職員や生徒への調査が終わっていなかったことが分かった。男子生徒の担任が生徒からのいじめの訴えを校長らに報告していなかったことが判明しているが、学校側の対応も不十分なため、いじめ情報を共有できなかった可能性が出てきた。【近藤綾加】
男子生徒の通っていた中学校は、2013年施行のいじめ防止対策推進法に基づき、同校独自の「いじめ防止基本方針」を策定している。
教職員のいじめ問題への取り組みに関する自己診断調査を6、11月の計2回実施すると規定。学校側がいじめを早期発見するため、全校生徒へのアンケートも5、11、2月の年3回するとしていた。いずれの調査も、これまでは結果がまとまれば町教委に報告されていた。
しかし、町教委によると、6月の教職員への自己診断調査は実施されていなかった。全生徒へのアンケートも運動会や中学総合体育大会を理由に実施が遅れたといい、町教委に結果の報告はきていない。
担任の女性教諭は4月から男子生徒のクラスを受け持っている。生徒と担任がやりとりをする「生活記録ノート」で、男子生徒は4月から何度もいじめを訴えたり、自殺をほのめかしたりしていた。町教委によると、男子生徒の自殺後に学校が全生徒に実施している調査でも、かなりの生徒がいじめを目撃したと回答しているという。
今春の教職員や生徒への調査が実施されていれば、男子生徒へのいじめの情報を学校や町教委内で共有する機会になったとみられ、同町教委幹部は「調査で生徒の自殺前に何か手がかりをつかめた可能性は否定できない」と話している。
興味があったので検索してみました。岩手県教育委員会及び幹部達はまともな人達ではないと思います。彼らにも子供がいるのかもしれませんが
どんな顔をして親をしているのでしょうか。
滝沢中2自殺に関して同校校長や市教育委員会関係者ら13人で構成された調査委員会のコメント
「去年には生徒2人が男子生徒にカッターナイフを向ける姿が目撃され、教員が2人を指導したことなどが説明された。ただ、調査委は『男子生徒に対する他の生徒の行為は遊びの延長と
考えており、今のところ、いじめという認識はない』と説明したという。」
調査委員会のメンバーの実名を公表しろと言いたい。納得しない被害者の親の要請で第三者委員会による調査が行われ「一部の行為はいじめに当たり、自殺といじめには一定の関連性があった」と結論付ける報告書
提出した。しかし、この報告書に対して岩手県教育委員会、少なくとも越秀敏教育長は良く思わなかったに違いない。なぜなら
「矢巾町教委は『黒塗りが多く、読むのが大変』として配布を見送った。」からだ。
今回の自殺が全国的に注目されたので「越秀敏教育長は『教員間の情報共有など参考になる点は多く、今後は毎月1度の町内小中学校長が集まる会議の資料などで活用する』と語る。」
実に公務員的でずる賢い対応だ。心にもないコメントだと思うが、形だけの言葉としては非難できない。まあ、形だけだから今回の自殺は防げなかったと思う。
「越教育長は、町内の小中学校からは月に1回、いじめの認知件数の報告を受けていましたが、村松さんが通っていた中学校を含め、今年度はゼロだったことを明らかにし、『学校と一緒に考えて行かなくてはと反省している』と述べました。また、担任の教諭が、教育委員会の聞き取りに対して、『村松さんにはトラブルがあったが、指導をして解決したと認識していた』と説明していることを明らかにしました。
越教育長は、『いじめ防止の方針を作っても、機能しなければただの紙と同じだ。情報共有できる職場環境を検討していかなければならない」と述べました。』
自殺した学校ではアンケートを取っていないのだから報告に上がるはずがない、本当にチェックしているのであればアンケートを行った日付も報告書に記載させるべきだ。
その場合、報告されていないからいじめはゼロとは言えない。データ操作していると判断、又は、データ操作の疑うことが出来る。
日本年金機構の個人情報流出問題を巡り、パスワード設定などの安全対策が完了したとする虚偽の報告
と同じ。報告を集めるだけでチェック機能が欠如している。
岩手県民でなくて良かった。岩手の学校に行かなくよかった。少なくともこれだけははっきり言える。
中2いじめ自殺で謝罪「いじめあった可能性が高い」 テレビ朝日【スーパーJチャンネル】(JCCテレビすべて)
07/10 17:58 テレビ朝日 【スーパーJチャンネル】
中2いじめ自殺で謝罪「いじめあった可能性が高い」
岩手県矢巾町の中学2年男子生徒がいじめを苦に自殺したとみられる問題。
男子生徒は5日、電車にはねられて死亡。
通っていた中学校が行った悩みについてのアンケートで「いじめられている」と回答していたことが文部科学省矢巾町教育委員会などへの聞き取り調査で分かった。
矢巾町教育委員会・越秀敏教育長が会見し、「いじめがあったという事実がかなり高いと認識している」、文部科学省初等中等教育局・平居秀一生徒指導室長は「いじめられているという記述があった」、下村文部科学大臣は「子どもがSOSを明らかに発している。
担任教師の対応の仕方は甘かった」と述べた。
教育委員会は第三者委員会に委ね、「調査の結果を待ちたい」としている。
「真相は明らかになるのか…公平な第三者の視点が不可欠」。
法政大学・萩谷順教授が「いじめ防止対策推進法がありながらいじめを公にしない圧力が学校現場にあるのかもしれない」とスタジオコメント。
教育評論家・尾木直樹は「第三者委員会は全員県外の人がいい」と指摘。
滋賀・大津の事件について言及あり。
町教育長らとの面談の映像。
教育長「いじめに複数生徒関与の可能性」 07/10/13(NHK)
岩手県矢巾町で中学2年の男子生徒がいじめをうかがわせる内容を学校のノートに書き残し、自殺したとみられる問題で、10日、記者会見した矢巾町の教育長は、「複数の生徒が関与し、いじめがあった可能性がかなり高い」と述べました。一方で、生徒が通っていた中学校からは、いじめの件数はゼロと報告を受けていたことを明らかにしました。
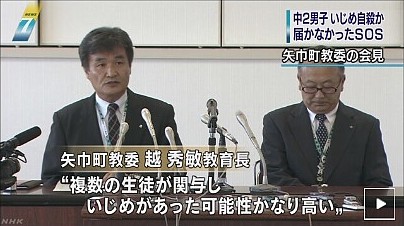
このなかで、矢巾町の越秀敏教育長は、「13歳の子を追い込み、手を差し伸べられず、亡くなった村松亮さんの遺族には心からおわびしたい」と述べたうえで、「複数の生徒が関与し、継続的ないじめがあった可能性がかなり高いと考えている」と述べ、外部の専門家などで作る第三者委員会で検証したいという考えを示しました。
そのうえで、越教育長は、町内の小中学校からは月に1回、いじめの認知件数の報告を受けていましたが、村松さんが通っていた中学校を含め、今年度はゼロだったことを明らかにし、「学校と一緒に考えて行かなくてはと反省している」と述べました。また、担任の教諭が、教育委員会の聞き取りに対して、「村松さんにはトラブルがあったが、指導をして解決したと認識していた」と説明していることを明らかにしました。
越教育長は、「いじめ防止の方針を作っても、機能しなければただの紙と同じだ。情報共有できる職場環境を検討していかなければならない」と述べました。
滝沢の自殺報告書、共有されず 矢巾町含む学校現場 07/10/13(岩手日報)
矢巾町の中学2年の男子生徒が同級生による暴力被害などを訴え自殺したとみられる問題で、矢巾町教委が昨年滝沢市で発生した中学2年男子生徒の自殺に関する第三者委員会の報告書を学校に配布していなかったことが9日分かった。岩手日報社の調べでは、同市以外の県内の小中学校にも配布されていない。同市の詳細な教訓が県内の学校現場でほとんど共有されず、今回の矢巾町の問題でも学校の対応に生かされていなかったことに、遺族は衝撃を受けている。
報告書は100ページで、4月に個人名など一部を伏せて公開した。県教委は全県で教訓を共有しいじめの防止を図る目的で、報告書を5月上旬に各市町村教委へ配布。具体的な取り扱いは各市町村の判断としている。
報告書にはいじめの経緯や提言のほか、記述式アンケートの結果も掲載し、「学校側が(いじめを)隠そうとした」など、学校の対応の問題点を記録。今回生徒が亡くなった矢巾町の中学校に配布されていれば、教諭らが参考にして対応することで、生徒の自殺を防ぎ得た可能性もある。
しかし矢巾町教委は「黒塗りが多く、読むのが大変」として配布を見送った。越秀敏教育長は「教員間の情報共有など参考になる点は多く、今後は毎月1度の町内小中学校長が集まる会議の資料などで活用する」と語る。
<滝沢中2自殺>第三者委「いじめあった」 03/26/13(岩手日報)
昨年5月に滝沢市の中学2年の男子生徒が自殺した問題で、いじめの有無などを調べるため市教委が設けた第三者調査委員会は25日、「一部の行為はいじめに当たり、自殺といじめには一定の関連性があった」と結論付ける報告書を市教委に提出した。
第三者委がいじめと判断したのは、いじめが疑われた7事案のうち(1)男子生徒がある生徒から「死ね、きもい」などと悪口を言われ頭をたたかれた(2)複数の生徒から筆入れを隠されトイレで泣いていた-の二つ。
いじめ防止対策推進法がいじめの定義とする「苦痛を感じていた」かどうかを当てはめて判断した。
自殺との因果関係については「いじめなどが複雑に絡み、学校生活に喪失感、失望感を深め自死に至ったと推認される」と指摘。「いじめが直接的原因になったと捉えることはできないが、一定の関連性があった」と結論付けた。
全校生徒約700人と教職員約50人へのアンケートも実施。生徒の約3割、教職員の約1割が「男子生徒がいじめや嫌がらせを受けていた」と答えた。
男子生徒が自殺した直後の学校調査は「いじめと疑われても致し方ない事案があった」としながらも、原因に関しては「判断できない」と説明。遺族の要望で昨年9月に第三者委を設け、計20回の会合を重ねた。
亡くなった男子生徒の父親は「いじめの報告を受けて、第三者委に対しては感謝の気持ちでいっぱいです」との談話を出した。
学校側は25日夜、保護者説明会を開催。参加者の一人は「学校が当初、いじめを認めなかったことについての説明が不十分。到底納得できない」と話した。
滝沢中2自殺:カッターナイフ向けるも「遊びの延長」 07/15/14(毎日新聞)
岩手県滝沢市立中学の2年生男子生徒(13)が自殺した問題で、いじめの有無を調査している調査委員会が男子生徒の父親(40)に「いじめがあったとは認識していない」と説明していたことが13日、分かった。
調査委員会は、同校校長や市教育委員会関係者ら13人で組織。説明は、中間報告として12日に学校で行われた。父親によると、男子生徒が亡くなる3週間前に筆箱やペンを隠されたりしてトイレで泣いていたことや、
去年には生徒2人が男子生徒にカッターナイフを向ける姿が目撃され、教員が2人を指導したことなどが説明された。ただ、調査委は「男子生徒に対する他の生徒の行為は遊びの延長と
考えており、今のところ、いじめという認識はない」と説明したという。
父親は「いじめがあったという他の保護者からの話もある。調査内容には納得していない」と話し、 第三者による調査を要望するという。校長は「説明内容については答えられない」としている。
調査委は最終報告をまとめて再度、父親に報告するという。【浅野孝仁】
校長が岩手県教育委員会教職員課首席経営指導主事の肩書きを持っているのであれば、県は嫌でも動くしかない。岩手県で十分な指導や研修を受けているはず。
岩手県は責任から逃げることは出来ないと思う。逃げたら岩手県教育委員会はそれだけの組織であることを全国に知らしめることになると思う。
【岩手中2自殺】矢巾北中・村松亮くん担任の女教師に関する衝撃的な事実判明!!!名前や顔を特定しろと叩いてた2ch「本当に悪いのは加害者犯人のいじめグループ生徒」【画像あり】 07/09/13(NEWSまとめもりー)

「担任は7月6日から体調を崩して休んでいたが、9日に出勤し、校長が聞き取りを始めた。町教育委員会は、調査のための第三者委員会を設置する方針を決めた。」
生徒の自殺により体調を崩して休んでいたのなら立ち直りが早すぎる。誰かに病欠で休めと言われたのでは?
複数の生徒が嫌がらせ目撃 岩手中2死亡、中学校が調査 07/10/13(朝日新聞)
岩手県矢巾町で5日、中学2年の男子生徒(13)が電車にはねられ死亡した事故で、学校の全校生徒へのアンケートに、複数がいじめを疑わせる行為を目撃したと答えたことが分かった。生徒は担任と交わしたノートに、自殺をほのめかす記述を3カ月にわたって残していた。生徒のSOSをすくい上げることはできなかったのだろうか。
学校は7日、全校生徒にいじめの有無を尋ねるアンケートを実施。関係者によると、複数の生徒が「砂をかけるなどの嫌がらせをされていた」「頭を小突かれていた」「たたかれていた」などの回答を寄せた。学校は回答した生徒に聞き取りをし、7月中にも調査結果をまとめる。
また、担任が6月上旬、男子生徒と面談したうえで、男子生徒とトラブルになった生徒とも面談し、嫌がらせをやめるよう指導していたことも分かった。ただ、その後も状況は改善されなかったとみられている。
担任は7月6日から体調を崩して休んでいたが、9日に出勤し、校長が聞き取りを始めた。町教育委員会は、調査のための第三者委員会を設置する方針を決めた。
生徒が担任に毎日提出していた「生活記録ノート」には4月からほぼ毎日、記述が残されていた。
4月7日は「今日は新しい学期と学年でスタートした一日です」と前向きな姿勢を示していたが、4月中旬に変化が生じた。4月17日に「最近○番の人に『いかれてる』とかいわれました」、5月13日に「もう学校やすみたい氏(死)にたい」とつづった。
「ある生徒は担任について、『優しくて、いい先生だった。生徒から慕われ、相談にもよく乗ってくれた』と取材に答えた。」
ある生徒と紹介されているので評価の1つでしかないが、もし多くの生徒も同じ意見であるならば、この学校の校長及び/または矢巾町教委
に問題がある可能性が高い。例えば、いじめがあると報告するなと校長及び/または矢巾町教委が指導していれば、担任は簡単には校長には
報告できないと思う。あくまでも推測なので警察、又は、岩手県の教育委員会(まともに調査できるのか疑問)が事実関係を確認する必要がある。
一般の公務員による調査だと嘘を付ける。偽証について厳しい罰則がない。警察だと偽証罪を問われるので、簡単に嘘を付けない。
特定のグループと何人かの生徒が証言しているので、このグループを特定するのは難しくないだろう。生徒には責任は取れないので、民事で
両親を訴える準備をしたほうが良いだろう。時間が掛かるので出来るだけ早く訴訟の準備をした方が良いだろう。弁護士の選定からになるのでは?
被害者の両親が事実解明だけでなく、加害者に対する償いを求めているのであれば、それぐらいしかない。あと、校長及び/または矢巾町教委の対応
や行動次第では、矢巾町にも損害賠償を請求できるかもしれない。
「別の生徒も特定のグループが男子生徒の机を蹴るのを見たが、『怖くて何も言えなかった』と話す。」
理解できる。善人ぶって何かを行ったり、行動を起こして恨まれたり、ターゲットにされた場合、助けてもらえる保障はない。例え、担任や
学校に相談しても、担任や学校にやる気がなかったり、対応できる能力不足の場合、問題を解決できない。文科省のキャリアのエリートは
そんな経験など勉強ばかりしていたので無いから理解できず、机上の空論で判断するのかもしれない。当事者に近い経験をすればきれいごとでは
すまないことは理解できるはずだ。まあ、日本の大人の社会でも弱いものいじめや、「見ざる、聞かざる、言わざる」が存在する。大人は
解決できるかといえば、ケース・バイ・ケースで難しい。学校だけの問題と捉えないほうが良いと思う。
クラス内で暴力行為、担任叱る…岩手の中2死亡 07/09/13(朝日新聞)
岩手県矢巾やはば町で5日、同県紫波しわ郡の中学2年の男子生徒(13)が電車に飛び込んで死亡した事故で、男子生徒を巡ってクラス内でトラブルが何度かあり、担任が仲裁や注意をしていたことが9日、同じ中学の複数の生徒への取材でわかった。
生徒の一人によると、死亡した男子生徒は4月以降、特定のグループから頭をたたかれたり、髪の毛をつかまれて机に打ち付けられたりしていた。担任がこうした行為を見つけ、グループの生徒らを注意したこともあった。取材に応じた生徒は「(担任が教室とは)別の部屋に連れて行って叱っているのを何度か見た」と話すが、グループの態度はその後もあまり変わらなかったという。
別の生徒も特定のグループが男子生徒の机を蹴るのを見たが、「怖くて何も言えなかった」と話す。死亡した生徒が、泣きながら担任に相談しているのを見たこともあるという。ある生徒は担任について、「優しくて、いい先生だった。生徒から慕われ、相談にもよく乗ってくれた」と取材に答えた。
さて、校長及び矢巾町教委(責任を持つ意味で名前を出せ)はどのような発言をするのか楽しみだ!
あるサイトの書き込みで責任を追及すると自殺者が出ると書いてあった。例え自殺しても申しわけないというよりは責任を追及される状況から逃避したいと言うケースが
高いのでは?個人的に思うのは自殺必要などない。責任を追及されるのが嫌なら、辞職すればよいのである。誤解しているかもしれないが、それで終わり。
矢巾町教委の誰かが対応しなければならないだけの事。被害者の家族としては納得いかないと思うが、辞職してしまえば、民事で訴訟を起こす以外、どうしようもない。
ただ、注目を受けて教育委員会の改革や校長の責任の明確化について議論されるであろう。矢巾町教委の管理エリアの学校ではスクールカウンセラーは1人も存在しないのか。
1人でもいるのであれば、教師が忙しければ電話でも相談すれば良い。スクールカウンセラーとして採用されているのだから、専門家だろ?もし、矢巾町に
スクールカウンセラーがいないとしても岩手県に1人もいないことはないと思うが???相談を受けるスクールカウンセラーが任命されていなければ、
岩手県及び岩手県の教育委員会の問題でもあるかもしれない。
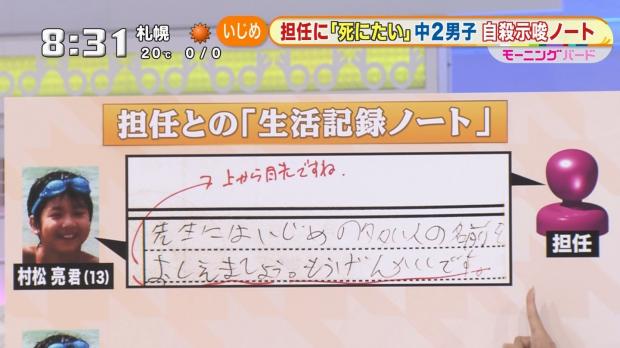
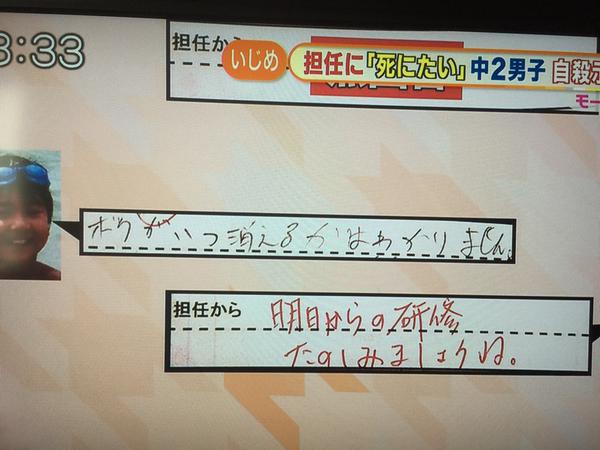
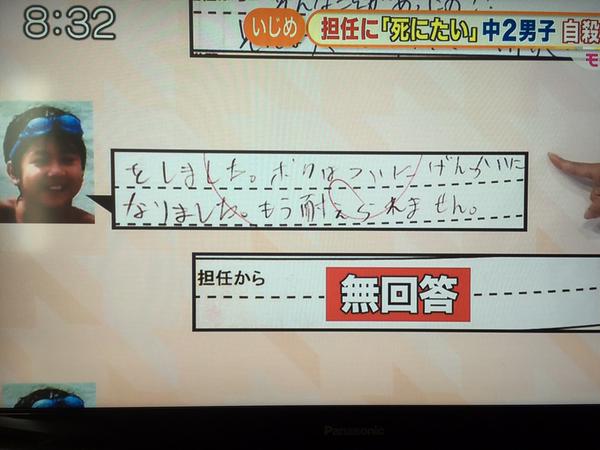
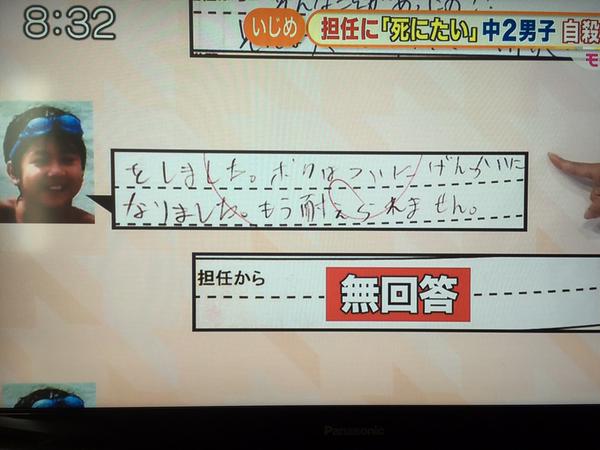
岩手中2自殺:多数生徒いじめ目撃「髪つかまれ机に強打」 07/09/15(毎日新聞)
◇全生徒対象のアンケートなどで回答
岩手県矢巾(やはば)町の中学2年の男子生徒(13)がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、自殺後に学校側が全生徒を対象に実施しているアンケートなどで、多数の生徒が男子生徒へのいじめを目撃したと回答していることが分かった。男子生徒は担任とやり取りしていた「生活記録ノート」でいじめを訴えていたが、日常的にいじめがあったことがこのアンケートでも裏付けられた。
男子生徒が5日に自殺したのを受け、学校側は7日からいじめの事実関係を調べ始めた。全校生徒にアンケートしたうえで、見たり聞いたりしたと回答した生徒には聞き取りを実施。また、男子生徒が所属していた運動部の部員と、同じクラスの生徒にも、聞き取りを進めている。町教委によると、これらの調査で、かなり多くの生徒がいじめを目撃したと回答しているという。
一方、同じ2年生の保護者が子供から聞いた話によると、男子生徒は同級生に髪をつかまれて机に頭を打ち付けられるなど悪質ないじめを受けていたという。今春の運動会の予行演習中には、複数の同級生から砂をかけられ、男子生徒が「やめて」と言っても、しつこく続いた。
また、クラスメートらによると、男子生徒が体をぶつけられて言いがかりを付けられたり、給食の配膳中に体を押されたりすることもあったという。
矢巾町教委は「暴行や悪口など具体的ないじめについては、アンケートや聞き取り調査の結果を見て精査したい」としている。【近藤綾加、二村祐士朗】
岩手中2自殺:生活ノートに記された気持ち…担任報告せず 07/09/15(毎日新聞)
岩手県矢巾(やはば)町の中学2年の男子生徒(13)がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、生徒がいじめを訴え自殺を担任教諭にほのめかしながら、学年主任や同僚教員も把握していなかったことが、町教育委員会への取材で分かった。2013年施行のいじめ防止対策推進法では、いじめが確認された場合、複数の教職員による対応を求めているが、実施されていなかった可能性が高い。
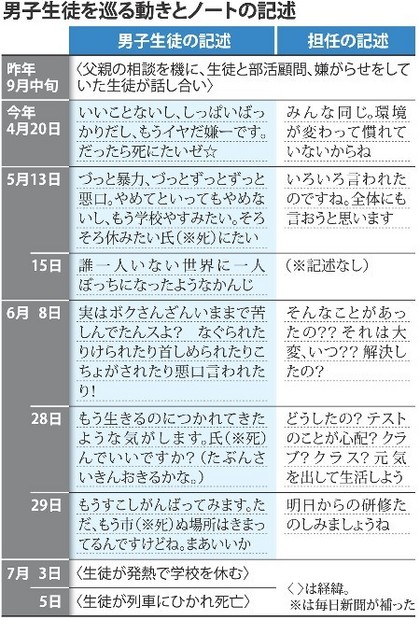
生徒が通っていた中学では、担任が生徒と「生活記録ノート」をやりとりし、生活状況を把握している。生徒は5月以降、他の生徒から蹴られたり、首を絞められたりしていることをノートに記していた。自殺前の6月末には「もう市(死)ぬ場所はきまってるんですけどね」などと自殺をほのめかす記述もあった。
中学は同法に基づき、「いじめ防止に関する基本方針」を作成。早期発見のため、生活ノートを活用するとしていた。さらに、いじめを発見したり、通報を受けたりした場合、校長らでつくる「いじめ対策委員会」を開き、校長以下全教員で共通理解を持って対応することになっていた。
しかし町教委によると、ノート内容については担任から学年主任への報告もなかった。同僚教員にも担任からいじめの可能性があると聞いた人はいないという。
同法やその基本方針を教員に周知させる研修などの実施に関し、町教委は関与しておらず、各校の判断に委ねられていた。町教委学務課の立花常喜課長は「他の教員らと情報共有し、ステップを踏んで対応すべきだった」と話している。【近藤綾加】
◇いじめ問題に取り組むNPO法人「ジェントルハートプロジェクト」の小森美登里理事の話
ノートは「死なないから助けて」という訴えに読め、誰も助けてくれない絶望が死のきっかけとなったように思う。法律はできても先生のいじめ対応スキルは上がっていないし、いじめがあること自体を問題視する風潮が抜けきれていないのではないか。
岩手県紫波郡矢巾町がどのような所か知らない。
「父親によると、生徒は4月上旬頃から『(別の生徒に)ちょっかいを出されてうざい。学校に行きたくない』などと話すようになったという。」
この時点で生徒に録音できるMP3プレーヤーを持たせ、録音させておけば良かった。自殺を防止できたかもしれないし、自殺しても、
担任や校長そしていじめた生徒の両親に対して損害賠償を要求できた。そして裁判になっても勝訴する可能性も高い。
いじめた生徒に対しては傷害等で警察に被害報告を出せたかもしれない。証拠は大事。事実であろうが、正しかろうが、証拠がなければ裁判では勝てない。
このような問題は簡単には解決できない。全てが同じ方法で解決できないが証拠集めを早い段階で準備する事は良いと思う。必要なければ消去すれば良い。
最悪の事態になれば、証拠を使えばよい。
生活ノート、担任への「叫び」記録…中2死亡 07/08/15(読売新聞)
岩手県矢巾やはば町で、同県紫波しわ郡の中学2年の男子生徒(13)が電車に飛び込んで死亡した事故で、男子生徒が4月からクラスの担任と交わしていた「生活記録ノート」の全容が8日、明らかになった。
別の生徒からの暴力や、体調不良を繰り返し訴え、助けを求める「叫び」が記録されている。SOSはなぜ届かなかったのか。学校側は死亡にいたった経緯などの調査を始めた。
クラス替えが終わり、2年生としてのスタートを切った4月。ノートの書き出しは7日で、「学年がスタートした1日。この今日を大切に、でだしよく、終わりよくしたい」と意欲的な記述で始まっていた。異変が起きたのは、4月中旬だった。
〈最近、「いかれてる」とかいわれ、けっこうかちんときます。やめろといってもやめない。学校がまたつまんなくなってきた〉(4月17日)
父親によると、生徒は4月上旬頃から「(別の生徒に)ちょっかいを出されてうざい。学校に行きたくない」などと話すようになったという。
その後、生徒は「イライラする」「だるい」「つかれました」と徐々に体調不良を訴えるようになる。具体的ないじめの記述と共に、心理的不安も書くようになる。暗闇の中で人が迷っているイラストを添え、孤立感を訴える記述も出てきた。
別の生徒からの仕打ちについて「しつこい」との記述が続き、6月3日には「けんかしました。ボクはついに、げんかいになりました」とつづった。
そして担任に直接助けを求める記述が現れる。 〈次やってきたら殴るつもりでいきます。そうなるまえに、ボクを助け……〉(6月5日)
〈実はボクさんざんいままで苦しんでたんスよ?なぐられたり、けられたり、首しめられたり、悪口言われたり!〉(6月8日)
6月中旬には、担任が「きのう話しができてよかったです」と記載し、生徒と話をした形跡もある。
しかしその後、テストに関する記述が続くが、約2週間後に突然自殺をほのめかす。
〈生きるのにつかれてきた。氏(死)んでいいですか?〉(6月28日)
最後の記述は死の6日前だった。
〈ボクがいつ消えるかはわかりません。もう市(死)ぬ場所はきまってるんですけどね〉(6月29日)
これに対し、担任は学校行事についてのコメントしか書いていない。
この日を最後に、記述は途絶える。7月5日、生徒は祖父に「買い物に行ってくる」と言って外出したまま、帰らぬ人になった。
校長は7日の記者会見で、「ノートの内容について担任から報告がなかった」と述べた。担任は体調不良だとして7日から休んでおり、生徒が記載した後にどう対応したかや、生徒との間でどんなやりとりがあったかなどについて、学校側は把握できていない。(盛岡支局 福元洋平、安田英樹)
「校長は7日夜に開いた緊急の保護者会の後、取材に応じ、ノートのやり取りについて『担任から聞いていない。いじめは否定できないが、あれば私に報告があるはずだ』と話した。担任は生徒の自殺後、病欠しているという。」
担任の病欠は本人の判断なのか、それとも、校長、又は教育委員からの証拠が残らないように口頭での指示なのか?刑事事件でない以上、誰かが真実を言わなければこのまま闇に
葬られる。
いじめがれば報告する事になっているのか?それともいじめと思われる事実があれば報告する事になっているのか?似ているが同じ意味ではない。いじめと断定できる
証拠がないと報告できない。しかし「いじめと思われる事実」であれば間違っていても報告する事が出来る。下記の記事を読むとこの校長は逃げているように思える。
なぜならいじめがあれば報告があると話している。取材に慣れていないのかもしれないが、管理能力がある校長の発言とは思えないし、管理能力があるのであれば
完全に逃げようとしているように思える。
公務員とやり取りをしていると時々、屁理屈や詭弁で逃げていると感じる。彼らは公務員の世界の価値観で生きている。退職する年齢まで公務員でいるつもりであれば、
公務員の世界で生きようとする。上からの強い指示がなければ変わらないか、変われない。
岩手・中2自殺:校長「いじめ知らなかった」 07/08/15(毎日新聞)
岩手県矢巾(やはば)町の中学2年の男子生徒(13)がいじめを苦に自殺したと見られる問題は、学校側の対応が不十分だった可能性が出てきた。生徒と女性担任が交換していたノートで、生徒は「もう市(死)ぬ場所はきまってるんですけどね」と書いたが、担任は「明日からの研修 たのしみましょうね」と翌日からの学校行事(合宿)に触れただけだった。6月30日ごろの記述とみられ、このSOSが生徒の最後のメッセージとなった。
◇父「なぜ連絡ない」
同校には生徒と担任がほぼ毎日交換する「生活記録ノート」があり、毎日新聞は生徒の父親を通じて全文を入手した。この中で生徒はいじめについて何度も担任に訴えていた。
日付が明確でない記述が多いが、今年5月以降、生徒が「なぐられたり、けられたり、首しめられたり」と書き、担任は赤ペンで「それは大変、いつ?? 解決したの?」と返事を書いていた。直後に生徒は「解決していません」などと書いたが、担任の欄は空白で、生徒の記述に二重丸がつけられていた。
その後、生徒が「もうつかれた。……。どうなるかわからない」と書いた時も担任からの記載はなかった。別の日に生徒が「ここだけの話。(中略)氏(死)んでいいですか(たぶんさいきんおきるかな)」と自殺をほのめかした時には、担任は「どうしたの? テストのことが心配? クラス? ××(この生徒の名前)の笑顔は私の元気の源です」などと応じていた。
校長は7日夜に開いた緊急の保護者会の後、取材に応じ、ノートのやり取りについて「担任から聞いていない。いじめは否定できないが、あれば私に報告があるはずだ」と話した。担任は生徒の自殺後、病欠しているという。
生徒の父親も生徒が自殺するまでノートの内容は知らされておらず、「ここまで書いていたのなら、なぜ連絡してくれなかったのか」と学校側の対応への不満を述べた。
7日夜の保護者会の出席者によると、学校側からいじめの有無について明確な説明はなく、生徒が死亡したことへの陳謝もなかったという。
町教委などによると、同校は7日、全校生徒(約450人)を対象にいじめを見聞きしていないかについて記名式のアンケートを実施したという。
【二村祐士朗、浅野孝仁】
「見殺しにしたも同然」「ダメ教師」 岩手中2自殺事件で学校に怒りの声多数 07/08/15(J-CASTニュース)
岩手県矢巾(やはば)町の中学2年の男子生徒(13)がいじめを苦に自殺したと見られる問題で、学校側への怒りの声が広がっている。
生徒は2015年7月5日、JR東北線矢幅駅で進入してきた電車に飛び込んだ。「いじめではなく暴行」「見殺しも同然」――有名人も、ツイッターやブログで報道に反応している。
尾木ママ「学校の体をなしていない」と激怒
最も批判が集まっている点は、学校側の対応だ。生徒は担任教師と交換していたノートでいじめの被害を繰り返し訴えていたが、教師はそれを「無視」して返答を書き続けた。また、生徒が通っていた中学校の校長もノートのやり取りについて「担任から聞いていない」と話し、 7月7日に開かれた保護者会でもいじめの有無を説明しないなど「知らぬ存ぜぬ」を決め込んでいるという。
そんな中、報道にいち早く反応したのが「尾木ママ」こと教育評論家の尾木直樹さん(68)だ。7日から8日にかけ、当件に関するブログ記事を連続で投稿。「生徒殺人学校」「許し難い事件」「担任の見殺し自殺も同然」と学校側を厳しく批判し、岩手県教育委員会には第三者委員会を設置して徹底的に真相解明するよう注文を付けた。
尾木さんは8日あさ放送の情報番組「モーニングバード」(テレビ朝日系)にも出演し、「学校の体をなしていない」と激怒、担任教師や校長へも「失格だ」と非難を続けた。
ツイッターにも
“「担任ってダメ教師だなあ」
「教師は役に立たない」
など怒りの声が寄せられた。
いじめじゃなくて「暴行」「恐喝」にすべき
一方、学校側を批判する以外の語られ方も見られた。情報番組「スッキリ!!」(日本テレビ系)に出演するコラムニスト・犬山紙子さん(33)が8日、「いじめなんかじゃなくて暴行」とツイッターで指摘、人気声優の白石稔さん(36)も「『いじめ』という単語は無くして、暴行とか恐喝とか、名称を変えるべき」と主張するなど、「いじめでなく暴行と呼ぶべき」という風潮はネット上で強い。
また、実業家の堀江貴文さん(42)は「大事なのは逃げてもカッコ悪くない雰囲気作り」と他とはやや異なる視点でつぶやいた。
ストレスのためだけにそんな事をするのか?仕事を失うリスクは小さいことなのか?仕事でストレスがたまっていたのだから
仕事にウンザリしていたのか?
「部活指導でストレス」教諭、女性宅侵入で免職 07/04/15(読売新聞)
堺市教育委員会は3日、女性宅に侵入して下着を撮影したなどとして、市立中教諭の男(26)を懲戒免職処分にしたと発表した。
市教委によると、男は2月13、23両日、同市東区の女性宅に侵入し、下着などを携帯電話で撮影した。男は、友人宅を訪れた際に隣人の女性に興味を抱いたといい、3月には別の女性宅にも上がり込むなどした。男はこの日の処分後、地裁堺支部で住居侵入罪で懲役10月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。
市教委に対し、男は「サッカー部の指導で休みがなく、ストレスがたまっていた」と話しているという。
53歳になって、なぜ、万引き。万引きのスリルが良いのか?見つかった時にリスクを考えないのか?
スリルが良いのあれば、他の方法もあると思うが?それともスリル以外の理由があるのか?
PC部品などパンフに挟んで盗む…小学教諭逮捕 06/14/15(読売新聞)
静岡県警静岡南署は13日、静岡市清水区宮加三、同市立清水岡小学校教諭遠藤誠一容疑者(53)を窃盗の疑いで現行犯逮捕した。
発表によると、遠藤容疑者は同日午後1時45分頃、同市駿河区のパソコンショップで、ケーブルやパソコン部品など計5点(販売価格計3700円相当)をパンフレットに挟んで万引きした疑い。店員に見つかり、店を出たところで声をかけられた。
調べに対し、「間違いない」と容疑を認めているという。高木雅宏・市教育長は「誠に遺憾。事実を確認し、厳正に対応する」とコメントしている。
福岡県にはそれほど教員が少ないのか?それとも将来の少子化加速のための教員調整の副作用なのか?
詳細には書けないかもしれないが、そこまで踏み込んで書いてくれないと問題の本質が見えない。
何が原因かわからないけど、こんな状態であれば国が進めている教員免状の国家資格制度が導入されれば一部の地域では問題が深刻化するのは
間違いない。
大学4年生、臨時免許で教壇に 福岡の中学、教員不足で 06/10/15(朝日新聞)
福岡県教育委員会は9日、同県みやこ町の町立中学校で、臨時教員免許を持つ大学4年生2人が、非常勤講師として勤務していることを明らかにした。教員不足を補うためで、現役の大学生を教員として任用する例は珍しいという。
県教委によると、2人は県内の私立大4年の男子。県教委は2人にそれぞれ数学と技術の臨時免許を出している。臨時免許は教育職員免許法に基づき、都道府県教委が出せる。
みやこ町教委などは町立中で働ける教員を探したが見つからなかった。大学に問い合わせたところ、教員免許取得見込みの2人を紹介されたという。受け持つ授業数は週5コマずつのため、大学側も学業に影響はないと判断したという。
県教委によると、昨年度には、理科の普通免許を持つ大学院生に技術の臨時免許を出し、県内の公立中学校で教壇に立ったという。(山下知子、渡辺純子)
使用した統計データが信頼できるのか、比較するに十分な誤差なのか知らないが、記事からだけで判断すると日本では「高学歴」でも若年無業者(ニート)
になる割合が高い。つまり、仕事に就く、又は、継続して仕事に従事することに関して、「高学歴」であるだけでは不十分であることを意味していると
思う。例えば、日本では精神的なタフさやいろいろな活動を通してのコミュニケーション能力を軽視して、学校のテストや入試試験の結果だけに重点を置いている
可能性がある。グラフでは2位に韓国となっている。コネ就職やコネによる出世が日本よりは浸透しているので、単なるデータではなく、その他の要素を
考慮するともしかすると実際は日本と同じ、または、上かもしれない。日本にしろ、韓国にしろ、学校のテストや入試試験を重視し、単に「高学歴」
であることは、仕事をしていく上でバランスが取れていないことを意味しているのかもしれない。
日本のニートは「高学歴」…OECD報告 05/28/15(読売新聞)
日本の若年無業者(ニート)は学力などに関する国際調査の成績が他国に比べて高いことが、経済協力開発機構(OECD)が27日に発表した若者の技能と雇用に関する報告でわかった。
OECDは「学校から仕事へと円滑につなげる仕組み作りが必要」と指摘した。
OECDが2011~12年に行った「国際成人力調査」(略称PIAAC)など複数の国際調査や統計データを基に分析した。
それによると、ニートはOECD加盟国全体で3900万人。日本のニートは、大学卒業以上の学歴を持つ人が、それ以外の人よりも多かった。PIAACの「読解力」では、成績が低いレベルだったニートは日本は3%にとどまり、他国に比べて好成績の割合が高かった。「数的思考力」も同様の傾向が見られた。
文部科学省の学習指導要領に問題がある事を示したケース。指導要領で問題が指摘されないほど人員構成や人員のバックグラウンドに問題があることも
考えられる。文科省のレベルはこの程度と言う事なのだろう。現実に直視して問題を乗り越える事を想定しているのであれば、明確にしたほうが良い。
悲劇や困難を乗り越えられたらその人達は精神的に強くなり、確実に成長するだろう。問題は問題を乗り越えられるようなサポートがあるのか、乗り越えられない人達は
副作用的な結果として考えるかであろう。
学習指導要領:文部科学省(文部科学省)
現行学習指導要領・生きる力(文部科学省)
小2生活科「生い立ち授業」に戸惑い 里親「子ども負担大きく」 05/08/15(静岡新聞)
学習指導要領に基づき、生活科で児童が自らの生い立ちを振り返る小学2年生の授業について、虐待などさまざまな理由で親と暮らせない児童を養育する里親らから戸惑いの声が上がっている。「一律の取り組みが、大きな負担になっている子どももいる」。切実な訴えに、専門家も「家族が多様化する中、学校側に配慮が必要」と指摘する。
「本当につらい作業だった」―。小学3年の女児を養育する静岡県中部の里親は、女児が2年生だった今年2月に取り組んだ生活科の授業に苦しんだ。担任から「名前をつけた理由」「1歳の時に初めてできたこと」などの質問が書かれたプリントを宿題で配られた。絵本の形にまとめるため、思い出の写真などを準備するようにも言われた。
女児が里親の元にやってきたのは小1の時。写真はあったが、実の親と連絡は取れない。担任に相談すると「ありきたりなことでいいから書いて」と返ってきた。名前の由来や乳幼児期の様子など「想像で書くしかなかった」と里親は話す。女児は直接的な拒絶の言葉こそ口にしなかったが、しばらくは表情が暗く、怒りやすい状態が続いたという。
教員向けの指導書によると、この授業は「これまでの自分の歩みを振り返ることで自身の成長を実感し、今後につなげていく」のが狙い。別の学校では、親への手紙などと合わせ、参観会で発表するケースもあるという。
ただ、里親家庭や児童養護施設で暮らす児童に配慮する学校もある。学区内に児童養護施設「静岡ホーム」(静岡市葵区)がある市立安西小では、生い立ちに固執せず、ここ1年間にできるようになったことを振り返りの中心にする。昨年度、2年を担任した教員は「施設の子どもに限らず各家庭にさまざまな事情がある。生い立ちを追わなくても、自身の成長を感じられれば授業の目的は達成されると思う」と話した。
◇「2分の1成人式」など 任意行事にも課題
小学校で自らの生い立ちなどを調べ発表する機会には、小学2年の生活科のほか、小学4年時、各学校がキャリア教育の一環などとして任意で行う行事「2分の1成人式」がある。実施する学校数については、県教委も把握していないという。
内容は「10歳証書」の贈呈、合唱の発表などさまざまだが、児童が生い立ちを巻物にして発表したり、親に宛てた感謝の手紙を読んだりする例もある。
生活科や「2分の1成人式」などで児童が生い立ちを振り返る活動について、静岡大教育学部の石原剛志教授(46)=児童福祉=は「極めて個別的な配慮が必要。やり方によっては子どもを大きく傷つける可能性がある。里親家庭に限らず、虐待、貧困、シングルなど多様な家庭があることを前提に行う必要があり、教師に力量がなければ成り立たない活動だ」と指摘する。
<メモ>小学校生活科の学習指導要領には「自分自身の成長を振り返り、多くの人々の支えにより自分が大きくなったこと、自分ができるようになったこと、役割が増えたことなどが分かり、これまでの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもつとともに、これからの成長への願いをもって、意欲的に生活することができるようにする」との記載がある。小学2年の生い立ちを振り返る授業はこの記載をもとに実施されている。
「フィリピンでは人格が変わった」買春1万2660人「元校長」は比政府から目をつけられ、日本警察に通報された (1/5)
(2/5)
(3/5)
(4/5)
(5/5) 04/20/15(産経新聞)
「仕事のプレッシャーが強く、倫理観のたがが外れたとき、より解放感を味わえた」。フィリピンで少女とのわいせつ行為を撮影したとして、神奈川県警が児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)容疑で元横浜市立中校長、高島雄平容疑者(64)=横浜市金沢区=を逮捕した事件。校長退職後も教諭として教壇に立っていた高島容疑者は、四半世紀ほどの間に延べ1万2660人の女性を買春し、「うち1割は18歳未満だったと思う」と供述した。「聖職者」の仮面を脱ぎ捨て、海の向こうでさらけ出したのは、女性の人権を踏みにじる本性だった。(岩崎雅子、小野晋史)
410冊のアルバムに女性の写真15万枚
「長年にわたって大勢の女性を買春している男がいる」。警察庁を通じてフィリピン政府から情報提供を受けた県警は昨年2月13日、高島容疑者の自宅に家宅捜索に入った。
書斎に踏み込んだ捜査員が目にしたのは、女性らの写真がびっしりと貼られ、平積みされた410冊のアルバムだった。
アルバムは1ページにつき写真が6枚。余白には女性ごとに1番から1万2660番までの番号を振り、それぞれの名前、年齢などを綿密に記録していた。写真は1人1枚とは限らず、“お気に入り”とみられる女性の場合は、1人で二十数枚もの写真を何ページにもわたって貼る気合の入れよう。写真総数は約15万枚にも達し、捜査員も開いた口がふさがらなかったという。
写っている女性の姿はさまざまで、番号の脇に貼られた1枚目の写真は洋服を着て正面から撮影。2枚目以降はその女性の裸や、性交中の様子、他の女性に撮影させたりした写真などもあった。動画は見つかっておらず、あくまで写真にこだわっていたようだ。
用いられたカメラも、昭和63年から平成26年までの26年間という長い年月を反映して、当初のインスタントカメラからデジタルカメラに変化。押収物には、データ保存用の「SDカード」も含まれていた。
県警は家宅捜索後、1年以上をかけて押収した写真を精査。このうち、26年1月ごろに買春して撮影した1人の少女について、小児科医から「13歳程度」との判定が得られたことから、児童ポルノ製造の容疑で逮捕に踏み切った。だが、女性を特定できなかったため、児童買春容疑での立件は断念せざるをえなかった。児童ポルノ製造の時効は製造の日から3年のため、他の女性についての立件も難しいという。
買春ペースは最少でも1日平均6人
行為のたびに写真を撮影していた理由について、「自分の思い出作りのため、記録として残しておいた」と供述する高島容疑者。フィリピンでの買春に目覚めたのは、37歳で首都マニラの日本人学校に派遣された昭和63年4月以降のことだった。
「女性が好きで、他人よりも性的好奇心が強い」と自らを分析しており、マニラ着任から間もなく、買春宿で遊びを覚えたとみられる。
捜査関係者によると、当時、女性1人あたりの買春代金は日本円でわずか400~500円程度。「安いな。これでもう、悶々(もんもん)とする必要はない」と喜んだ高島容疑者は、自らが教育者であることを忘れて快楽の泥沼にはまり込んでいった。
平成3年に帰国し、横浜市内の中学校で教壇に立つようになってからも、フィリピンでの買春に対する欲望は収まらなかった。毎年春、夏、冬の3回、学校が長期休暇となるたびに1回あたり2週間ほどの日程でフィリピンに滞在。渡航回数は、最後の26年1月までに65回にも達し、買春した女性の総数は延べ1万2660人にも達した。主に安ホテルに泊まって滞在費を抑え、最近は知人女性から女性の斡旋(あっせん)を受けていた。
フィリピン滞在中に毎日買春していたとしても、単純計算で1日平均6人を相手にしていたことになり、高島容疑者は「部屋に10人の女性を集めたこともある」と供述。アルバムには、ハーレムのように大勢の女性に囲まれて悦に入る高島容疑者の写真も貼られていた。
全員と性行為をしていたかどうかについて、捜査関係者は「性欲が強く、本当に全員と性交した可能性はある」としている。
教育誌にフィリピンのリポート寄稿
買春行為にのめり込む一方で、高島容疑者は帰国後の5年、日本人学校での勤務経験を元に、公益財団法人「横浜市教育文化研究所」が発行している「JAN(じゃん)」という雑誌に「『WHAT‘S SCHOOL?』 こどもたちは、いつも熱い視線で語りかけてくれた 海外教育事情-フィリピン・マニラ」と題する4ページのリポートを寄稿した。
リポートでは、冒頭でマニラ郊外のスラムについて「私には馴染(なじ)み深い場所だ。住民と共に寝起きしてみて非常なやすらぎを覚えた」と記し、スラムで出会った学校に行けない貧しい子供たちとの交流について触れていた。
「物質的に豊かになったことでなくしてしまった心の中の尊いものを、持たざる彼らの中に見つけた気がした」
「学校へ来る機会に乏しい子供たちに、学校は何かしてあげられないのでしょうか」
リポートからは、フィリピンで暮らす貧しい子供たちに心を寄せる、真面目な教師の姿が思い浮かぶが、高島容疑者が買春した少女たちこそ、このような貧しい境遇だったに違いない。
元教え子「裏切られた気分」
高島容疑者は逮捕翌日の4月9日、逃亡や証拠隠滅の恐れがないなどとして釈放され、在宅での捜査に切り替えられた。
横浜市金沢区の東京湾が望める高台にある自宅で、妻子とともに3人で暮らしている。周囲は閑静な高級住宅街で、窓にはステンドグラスもはめ込まれた大きな洋風の建物だ。車庫には高級車が止まっていた。市教委によると、退職金は約3千万円だったという。
玄関には「防犯連絡所」などの看板が掲げられ、手入れされた庭には品の良い木製の机や椅子が並べられている。玄関のチャイムを押しても返答はなく、近くの人々は「あまり関わりがないので」と、言葉少なに立ち去ってゆく。
20年4月から23年3月まで市立中学の校長を務め、朝礼や入学式、卒業式などで生徒らに語りかけてきた高島容疑者。当時、この中学の生徒だったという大学3年の男性(20)は「厳格な印象を持っていたからショック。(買春の)数の多さに、あきれればいいのか怒ればいいのか分からない。『校長なのに…』と裏切られた気分だ」と眉をひそめる。
県警によると、日本国内での児童買春は確認されておらず、高島容疑者は「フィリピンに行ってしまうと人格が変わってしまう。気分がとても高揚して抑えきれなかった」と供述したという。
教育者の立場にありながら女性を差別する行為を続け、多くの教え子らを欺いてきた「二重の罪」はあまりに重い。
この教諭も日本の教育全体にストレスを感じて衝動に駆られたのか?これはたいへんなことだ!そんな事などあるわけないか。
性欲は人間の基本的な欲望の1つ。オープンに出来ないだけで普通の人でも性欲はある。人間も動物。子孫を残すような本能が備わっている。動物と人間の違いは
感情や欲望をある程度コントロールできるかどうか。犯罪を犯すぐらいなら綺麗ごとはやめて風俗に行く様に指導したほうが良い。
「トイレ貸して」女性に抱きつく、教諭を再逮捕 04/10/15(読売新聞)
女性宅に上がり込み、わいせつ行為をしようとしたとして、大阪府警北堺署は9日、堺市立中学教諭の男(26)を強制わいせつ未遂と住居侵入の両容疑で再逮捕した。
容疑を認めているという。
発表では、男は3月15日未明、堺市内のマンションで20歳代の女性が自室に入ろうとした際、「トイレを貸してほしい」と声をかけ、部屋に上がり込み、室内で背後から女性に抱きついた疑い。
女性が抵抗したため、逃げたという。女性とは面識はない。
男は同月22日、別の女性をつけてマンション内に侵入したとして、同署に建造物侵入容疑で逮捕されていた。
「日本の教育全体にストレスを感じていて、解消したかった」
日本の教育制度が問題なんだって!文部科学省、
そして、大臣・副大臣・大臣政務官(文部科学省)、
どうするの?
「体の清潔さ新鮮で」少女ら12000人“買春”元校長 04/09/15(テレ朝news)
少女とのわいせつ行為を撮影したとして逮捕された中学校の元校長が、少女を買春していた理由について「清潔さに新鮮さを感じた」などと話していることが新たに分かりました。
横浜市立中学校の元校長・高島雄平容疑者(64)は去年、フィリピンのマニラ市内のホテルで、18歳未満の少女とのわいせつな行為を撮影し、データを保存していた疑いで9日朝に送検されました。高島容疑者はこれまで、フィリピンで少女ら1万2000人以上を買春していたとみられています。その後の捜査関係者への取材で、少女を買春していた理由を「体の清潔さに新鮮さを感じたから」などと話していることが新たに分かりました。また、「日本の教育全体にストレスを感じていて、解消したかった」などとも話しているということです。警察は今後、余罪がないかなどさらに詳しく調べる方針です。
実際、ここに至るまでに逮捕されないのだから普通は逮捕されないのだろうね!もしかすと、これでフィリピンに行く人が増えるかも?
フィリピンで少女のポルノ撮影 容疑で元校長逮捕 04/09/15(カナロコ by 神奈川新聞)
渡航先のフィリピンで少女とのみだらな行為を撮影したとして、県警少年捜査課と大船署は8日、横浜市金沢区富岡西1丁目、元市立中学校校長の男(64)を児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)容疑で逮捕した。県警の摘発で3件目となる同法の国外犯規定を適用した。
県警や市教育委員会によると、元校長は文部科学省からマニラ市内の日本人学校に派遣されていた3年間とも重なる1988年から2014年まで現地女性を買春し、ポルノ写真を撮影していた。18歳未満は約千人に上るという。
逮捕容疑は、14年1月、マニラ市内のホテルで10代前半の少女とみだらな行為をしている姿をカメラで撮影し、写真11枚を保存した、としている。県警の調べに対し、元校長は「思い出にするために撮影した」と容疑を認めている。旧知の現地女性が少女を周旋したという。
13年9月にフィリピン警察から警察庁に情報提供があった。県警によると、元校長は約2500円を渡してみだらな行為をしたが、少女が特定できなかったため、児童買春容疑での摘発は見送った。少女の年齢は、小児科医の鑑定で13~14歳と判断した。
男は横浜市立中学校の正副校長を歴任。11年の退職後から今年3月末まで公益財団法人・横浜市教育文化研究所に所属し、機関誌の編集長を務めていた。
市教委は「不祥事防止に取り組んでいる中、極めて遺憾な行為」との談話を発表した。
◆◇◆
「12660」。県警が元校長の自宅から押収した写真に記された最後の通し番号だ。県警によると、この「異常な数」(捜査幹部)はフィリピンで買春した10~70代の女性の総数だった。アルバム約400冊に計約14万7600枚の写真が収められていた。同容疑者は、うち1割ほどが18歳未満だったと県警に説明している。
買春は、マニラ市内の日本人学校に派遣された1988年に始まったという。帰国から3年後の93年に発行された市教育文化研究所の機関誌に現地の子どもについて、こうつづっていた。「物質的に豊かになったことでなくしてしまった心の中の尊いものを、持たざる彼らの中に見つけた気がしたのだ」
「明日をも知れぬ子供たち」(同誌)の貧困を憂う教育者の一方、元校長は性的搾取者という二面性を持ち合わせていた。風俗店で数百円を上乗せすれば性交できると知ると、「安いな。たくさんの女性とできるなと思った」(県警の任意聴取に対する供述)という。帰国後も年3回の休暇を利用して計65回、現地に渡っていた。1日10人ほどの女性を買春していた計算だ。
売春に従事させられている子どもはアジアだけで100万人、人身売買の産業規模は年間100億ドルともいわれる。日本は70年代の海外旅行ブーム以降、「買春ツアー」の送り出し国として、とりわけ国際的な非難を浴びてきた。122カ国が参加した96年の世界会議で対応の遅れが指摘され、3年後に児童買春・ポルノ禁止法が成立、国外犯規定が盛り込まれた経緯がある。
「日本の対策はまだまだ国際的な水準に達していない」。性的搾取の被害者支援に取り組むNPO法人「ライトハウス」の藤原志帆子代表は強調する。主要8カ国(G8)で日本とロシアのみが規制していなかった児童ポルノの単純所持は、14年7月の法改正でようやく禁じられた。
警察庁によると、全国の警察が14年の1年間に摘発した児童ポルノの製造や流通の被害者は746人。摘発も1828件に上り、統計が残る2000年以降でともに最多だった。藤原代表は「児童買春やポルノをめぐる日本人の規範意識の低さは、いまだに深刻な状況にある」と指摘している。
◆国外犯規定 日本国外での犯罪に対し、国内法を適用して処罰する規定。児童買春や児童ポルノ製造・提供などの行為は、刑法の殺人罪などと同様に、国外での犯行でも日本国民を処罰できる。
デビルマンの歌(今日もどこかでデビルマン)のようだ:「誰も知らない 知られちゃいけない デビルマンが誰なのか 何も言えない 話しちゃいけない デビルマンが誰なのか 」
元校長買春事件 フィリピンに赴任した際に「買春の快楽覚えた」 04/09/15(フジテレビ系(FNN))
神奈川・横浜市の中学校の元校長が、少女とのみだらな行為を撮影した疑いで逮捕された事件。元校長は、かつてフィリピンに赴任した際に、買春の快楽を覚えたと供述していることがわかった。
警察署の階段を下りて来た白髪の男は、時折、カメラの方を見たあと、目線を下に向けたまま、車に乗り込んだ。
児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕、9日に送検された横浜市立中学校の元校長・高島雄平容疑者(64)。
高島容疑者は「気分が高揚し、抑えきれなかった」と供述している。
高島容疑者は2014年1月、フィリピンの首都マニラで、少女ら2人に、みだらな行為をしたうえ、その様子を撮影し、画像11枚を保存した疑いが持たれている。
高島容疑者は、横浜市の自宅で、家族と暮らしていた。
近所の人は「(高島容疑者の印象は?)感じいいですね。『あの方、感じいいね』と言ったら、『あの方、先生をやっていた』と」と話した。
1975年に教員採用された高島容疑者が、マニラにある日本人学校に赴任したのは、およそ25年前。
3年間、理科を教えていた。
高島容疑者は、マニラ時代のことをコラムに「経済的理由で、学校に行くことができない子どもたちが多いこと。明日をも知れぬ子どもたちが街にあふれているのだ」と書いていた。
高島容疑者は、このマニラへの赴任中に、少女などの買春を始めたという。
高島容疑者は「買春の快楽を覚えた」と供述している。
日本に帰国したあとも、学校の夏休みなどを利用して、フィリピンに65回ほど渡航。
およそ25年間で、13歳から70歳くらいまでの女性1万2,600人以上と買春したという。
高島容疑者は「タガログ語や英語で話すと、自分が大胆になり、気分が高揚し、抑えきれなかった。仕事のプレッシャーが強ければ強いほど、倫理観のタガが外れ、開放感を感じた」と供述している。
知人の男性は「(フィリピンの話は?)全く聞いたことがない」と話した。
中学校の卒業生は「自分が中学生だった時も、そういう目で見られていたのかなと思うと、すごく怖い」と話した。
警察が高島容疑者の自宅から押収したものの中には、複数のカメラやDVD、児童ポルノの漫画のほか、買春した少女らの写真を保存したアルバムが410冊もあった。
写真には、通し番号が振られ、その数は、1万2,600人以上に及んでいた。
高島容疑者には、およそ3,000万円の退職金が支払われていて、横浜市教育委員会は今後、退職金の返還を求める方針だという。.
「動機については『仕事のプレッシャーが強ければ強いほど、倫理観のたがを外すことで開放感を味わえた』と話しているという。」
今回のケースと他の不祥事を同じと考えてはいけないが、仕事のプレッシャー=わいせつ行為、又は、生徒との不適切な関係となるのか?
埼玉、香川、大分などの教育委員会がLINE(ライン)」を使い生徒と私的なやりとりをすることを通知などで禁止
しているがあくまで手段であって、個々の教諭が自己抑制できなければ極端な話、逮捕された元横浜市立中学校校長と同じような問題を起こしても不思議ではない。
1万2000人以上の女性とやれば「『買春を繰り返している日本人がいる』とフィリピンの捜査当局」に指摘されても仕方がない。
元横浜市立中学校校長は校長としてどのような話をしていたのだろうか?立派な話をしていたら、とんでもない偽善者と言っても間違いないだろう。
元中学校長「1万2千人超を買春」 児童買春容疑で逮捕 04/08/15(朝日新聞)
興津洋樹
フィリピンで現地の少女の裸の写真を撮影したとして、神奈川県警は8日、元横浜市立中学校校長の高島雄平容疑者(64)=横浜市金沢区=を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノの製造)の疑いで逮捕し、発表した。
少年捜査課などによると、高島容疑者は1988年から3年ほど、フィリピンの日本人学校に勤務。その後、横浜市内の中学で校長などを歴任し、2011年に退職した。同課の調べに対し、容疑を認めたうえ、「現地に派遣されていた当時から買春を始め、帰国後も休暇を利用して買春目的でフィリピンに渡航していた」と供述。「現地でのべ1万2千人以上の女性と買春し、うち1割は18歳未満だったと思う」と話しているという。動機については「仕事のプレッシャーが強ければ強いほど、倫理観のたがを外すことで開放感を味わえた」と話しているという。
高島容疑者の逮捕容疑は、フィリピン・マニラのホテルで昨年1月、13~14歳くらいの少女とわいせつな行為をする様子など写真11枚をデジタルカメラで撮影し、SDカードに保存していたというもの。
「買春を繰り返している日本人がいる」とフィリピンの捜査当局から情報があり、県警が自宅などを捜索。フィリピンで撮影したとみられる女性の写真14万点以上を押収した。1万2千人以上の女性に番号がふられていたという。
高島容疑者は編集に関わった教育冊子に93年、「フィリピンで学んだ教育の原点」というリポートを掲載。「物質的に豊かになったことでなくしてしまった心の中の尊いものを、見つけた気がした」などと書いていた。(興津洋樹)
少なくとも1万2000人以上の女性とやったのは日本でもすごい記録になるのでは????
1年=365日と計算して、毎日1人とSEXしたとして1人X365日X30年=10950人
かなり遊んだと言う事だ!フィリピンの物価が安いとしてもかなりの額を使ったのでは??
遊び人とか言われる人でも1万2000人以上の女性とやった人は少ない、又はほとんどいないと推測する!
「倫理観のタガ外れた時、解放感味わえた」 04/08/15(日本テレビ系(NNN))
フィリピンで少女とわいせつな行為をし、その様子を撮影したとして、横浜市の中学校の元校長が逮捕された。フィリピンで1万2000人以上の女性を買春していたという。
児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、横浜市の公立中学校の元校長・高島雄平容疑者(64)。警察によると、高島容疑者は去年の元日、フィリピン・マニラ市内のホテルで当時13歳から14歳くらいの少女に金を払ってわいせつな行為をし、その様子を撮影した疑いが持たれている。
高島容疑者は27年前に教員としてフィリピンに派遣されて以降、帰国後もフィリピンに度々渡航して買春を繰り返していて、自宅からは14歳から70歳まで1万2000人以上の女性とのわいせつな写真を記録したアルバムが約400冊押収されたという。
校長在任中の知人「元々、向こう(フィリピン)に赴任した時に教育の原点というのかな、ちょこっと語られたことは聞いたことは当時少し覚えています。『向こうの子は一生懸命勉強することに飢えていた』とすごい話してましたね」
警察の調べに対し、高島容疑者は「倫理観のタガが外れた時、より解放感を味わえた。写真は思い出にするため」と容疑を認めているという。
比で児童ポルノ撮影、元校長逮捕…14万枚押収 04/08/15(読売新聞)
フィリピンで買春した少女の裸を撮影し、児童ポルノ画像を作成したとして、神奈川県警は8日、元横浜市立中学校長の無職高島雄平容疑者(64)(横浜市金沢区)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕した。
発表によると、高島容疑者は昨年1月1日頃、マニラ市内のホテルで、当時13~14歳とみられる少女とみだらな行為をしている様子をデジタルカメラで撮影し、データをSDカードに保存した疑い。県警は昨年2月、高島容疑者宅を捜索し、少女から70歳くらいまでの同国の女性のわいせつな写真約14万7600枚を押収した。
県警幹部によると、高島容疑者は逮捕前の任意の事情聴取で、1988年から3年間、同国の日本人学校に赴任した際に買春をするようになったと説明。その後も年に3回程度は同国に渡航し、「延べ1万2000人超の女性を相手に買春を行い、そのうち1割ほどが18歳未満だった」と話したという。
文科省はどのような基準で承認を出しているのか?これらの大学に補助金や助成金は出されているのか?もしそうだとすれば補助金や助成金を
ストップするべきだ。税金の無駄遣いだ。
「こうした実態について文科省の調査は「大学教育水準とは見受けられない」と指摘しており、改善を求めています。」
改善がなかったらどうするのか?時間稼ぎなのか?言い逃れの言い訳なのか?
設置計画履行状況等調査の結果等について(平成26年度) (文部科学省)
設置計画履行状況等調査の結果等について(平成26年度) (文部科学省)
開けない人はここをクリック
講義は中学レベル、入試は「同意」で合格 文科省がダメ出しした“仰天大学”とは? 02/21/15 (withnews )
「数学の授業は四捨五入から」「受験生と大学の『同意』で合格」「新入生が一人もいない」――。新設の大学や学部でこんな事例が相次ぎ、文部科学省が改善指導に乗り出しました。若者の減少とキャンパスの新増設で「大学全入」とも言われる時代。とりわけ知名度の低い地方大学で、教育の質の低下が懸念されています。
百分率や小数が分からない大学生?
文科省は今月19日、講義内容や運営方法などに不備があるとして、改善を求める大学253校を公表しました。新設された大学や学部を昨年度から調べており、対象となった502校の約半数に問題が。多くは学生の定員割れや、教職員の高齢化などでしたが、大学としての“適格性”が問われそうなものも少なくありませんでした。
千葉科学大(千葉県銚子市)は、一部の講義で“レベルの低さ”が問題視されました。たとえば「英語1」の講義。同大のシラバス(講義計画)によると、冒頭から「be動詞」「過去形」「進行形」と、中学校レベルの内容が並びます。「基礎数学」の講義でも、割合(百分率)や小数、四捨五入とは何か、から教え始めます。
つくば国際大(茨城県土浦市)でも、「化学」の講義で元素や周期表から教え始めたり、「生物学」で光合成やメンデルの遺伝法則を一から学ばせたり。
こうした実態について文科省の調査は「大学教育水準とは見受けられない」と指摘しており、改善を求めています。
開設以来、学生ゼロも
一方、入試を巡って、受け入れ数や選考基準が不明確だったりするケースも調査で明らかになりました。
太成学院大(大阪府堺市)では、書類と面接で合否を決める「アグリーメント入試」を実施しており、選考基準について「学生と大学が同意に達したら入学を許可する」と説明してきました。
しかし、文科省の調査は「同意以外の判断基準が明示されておらず、どのように合否を決定しているか不明」として、見直しを求めています。
北翔大(北海道江別市)では、大学院の募集要項に「可能な限り受け入れる」との表現があり、適切な選抜が行われていない印象を与えると指摘されました。
同大総務部によると、試験には論文と面接があり、「適正に競争原理に基づいて選抜している」とのこと。ただ、受験者には社会人が多く、合格しても入学を辞退する人が多いため、できるだけ志願者を集めたかった、と説明しています。
ほかにも、「併設校からの内部推薦など募集要項に記載されていない入試区分が存在」(大阪府守口市の大阪国際大)、「留年生が多数生じており、また、在籍学生の学年ごとの評定平均が下の学年ほど低くなっている」(兵庫県宝塚市の宝塚医療大)、「開設以来、学生が1人も入学していない」(千葉県我孫子市の川村学園女子大・観光文化学科)などの例が指摘されています。
教員はもう大人なのだから自己責任で自由に行動させればよいのではないのか?子供を指導するはずの教員が自己抑制出来ないのでは問題だ。
結果だけで不祥事が無いようにするのは小手先の対策。「教員と生徒の私的メール、14県市で禁止」は教員の質が下がったのか、公務員になったのは公務員採用試験に受かっただけで人格的に
問題の無い人材が公務員になっているわけではない事を意味していると思う。
教員と生徒の私的メール、14県市で禁止 02/08/15 (読売新聞)
公立中、高校などの教員がメールや無料通話アプリ「LINE(ライン)」を使い生徒と私的なやりとりをすることを通知などで禁止する教育委員会が、埼玉、香川、大分など11県、京都、岡山など3政令市に上ることが読売新聞の調査でわかった。
生徒へのわいせつ行為で処分される教員が増えており、メールなどのやりとりが不祥事につながることを防ぐためだ。
調査は、全都道府県、政令市を対象に行った。
埼玉県教委は昨年12月に県立高校、今年1月には公立小中学校に「電話、メールや無料通話アプリなどによる児童生徒との私的な連絡は絶対に行わないこと」とする通知を出し、教え子とのやりとりを禁止した。同県では2014年度、生徒へのわいせつ行為で5人の教諭が懲戒免職処分を受け、うち4人が生徒とメールやLINEのやりとりをしていた。
埼玉県の責任ではないのかもしれないが、埼玉県が下記のような小冊子を作成し教諭に指導しなければならない事実が文科省及び多くの自治体の教育方針に問題があったことを証明している。なぜなら、文科省及び多くの自治体の教育方針や教育の結果が教諭の不祥事なのだ。日本で教育を受けた子供が大人となり、教諭となったのだ。責任は文科省及び多くの自治体の教育委員会にある。ある程度、人格形成が最終段階になった時点では修正は難しいと個人的に思う。衝動や感情を抑える事が出来るのか、出来ないかの勝負(段階)だと思う。行動を起こさなければ上出来と考えるしかない。「教師とは、教育者とは」など奇麗事を言っても考え方を変えるのは非常に難しいと思う。
生徒とのLINE連絡「禁止」 埼玉、県立高教諭に通知 01/14/15(産経新聞)
埼玉県内で昨年、県立高校の男性教諭による教え子へのわいせつ行為が相次いだことを受け、県教育委員会が昨年12月、各県立高に「LINE(ライン)」などスマートフォン向け無料通信アプリによる生徒らとの私的連絡の禁止を通知していたことが13日、分かった。年明けに教職員に配布した冊子では「28歳で停職6カ月なら生涯賃金が550万円減る」などと懲戒処分の実例まで示し、犯罪の抑止効果を狙っている。
同県内では昨年、採用直後の男性教諭が部活動の女子生徒にLINEで連絡を取り、キスするなど計5件のわいせつ行為が発覚し、うち4件は教え子が対象だった。県教委は12月22日の通知で生徒との私的連絡を「絶対に行わないこと」とした上で、禁止項目に無料通信アプリも含めた。部活などで連絡を取る必要がある場合は、校長ら管理職の事前許可制とした。
さらに「信頼関係の確立をめざして」と題した小冊子を年明けに作成。「もしも、わいせつ行為を起こしたら…」とした項目では「報道があれば氏名・住所が公表される」「免職処分で退職手当は不支給」「示談金は数百万円かかることがある」などと“不利益”を列挙し、生涯賃金が減少することも強調している。
県教育局の担当者は「分析では、気軽に連絡を取れる無料通信アプリがわいせつ行為のきっかけとなっている。また、自分を見失わないよう懲戒処分による生活や経済面での現実を書き込んだ」と話している。
LINEで生徒に「抱かせろ」 都立高教員を懲戒免職 12/24/14(産経新聞)
スマートフォン向け無料アプリ「LINE(ライン)」を使って女子生徒に「抱かせろ」などと迫ったとして、東京都教育委員会は24日、都立高校の男性教員(30)を懲戒免職処分にしたと発表した。また、「スカートが短い」と生徒指導を装い、隠し撮りをした区立中学の男性教員(29)も懲戒免職にするなど教員計5人を処分した。
都教委によると、高校教員は昨年4~5月、同校の女子生徒にラインで計170件のメッセージを送信。「抱かせろ」「嫉妬すんなよ」などとわいせつな内容が含まれていたほか、別の女子生徒が自分の顔写真をネットに投稿したことに憤慨し、ラインで「おれが警察に言えば、停学退学になる」などと脅した。
また、中学教員は今年6月、「スカートの丈が短い」などと女子生徒を校内でひざ立ちにさせ、スマートフォンの動画機能を使ってスカート内を盗撮した。
高校教員は「立場をわきまえず、友人ののりで接してしまった」。中学教員は「ストレスがあり、スリルに満足感を得ていた」などと話したという。
このほか教育実習生に対するセクハラで中学教諭1人、体罰で小中教員2人を停職処分などにした。
神奈川県では過去に2回起訴されていても臨時教諭として採用されるらしい。
小学校臨時教諭、中3少女にわいせつ行為 01/08/15(日本テレビ系(NNN))
ツイッターで知り合った女子中学生にわいせつな行為をしたとして、小学校の臨時教諭の男が逮捕された。
警察によると、神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕された川崎市の小学校の臨時教諭・阿久沢恒生容疑者(23)は、去年9月、座間市の公園に駐車した車の中で、中学3年生の少女にわいせつな行為をした疑いが持たれている。阿久沢容疑者は少女とツイッターで知り合っており、初めて会ってすぐに人目につかない公園に連れて行き、犯行に及んだという。
警察の調べに対し、阿久沢容疑者は「好みのタイプだった」と容疑を認めているという。阿久沢容疑者は別の少女へのわいせつ行為で、過去に2回起訴されていた。
教員免状が無効になっていなければどこかでまた働くだろう。そして同じ事が起きる可能性も残る。
教え子にみだらな行為、県立高教諭4人を懲戒免 12/22/14 (読売新聞)
埼玉県教育局は22日、教え子の女子生徒にみだらな行為をした東部地区の県立高校男性教諭(26)ら4人を免職、わいせつ行為をした同局職員(44)を停職6か月とする懲戒処分を発表した。
5人とも行為を認め、同局職員も同日、依願退職した。
同局県立学校人事課によると、男性教諭は8月10日深夜から11日未明にかけ、部活動の大会のため宿泊した都内のホテルの自室で、女子部員にみだらな行為をした。痛めていた脚の具合の確認で呼び出したが、「気持ちを抑えられなくなった」と話しているという。
また、西部地区の県立高校の男性教諭(25)は6~10月、車内で教え子の女子生徒にキスしたり、川越市内のホテルでみだらな行為をしたりした。北部地区の県立高校の男性教諭(58)は複数の女子生徒に「キスしたくなる」と声をかけ、後ろから抱きつくなどした。いずれも生徒が養護教諭に相談するなどして発覚した。
17歳の女子高生へのわいせつ行為で今月4日に県青少年健全育成条例違反容疑で逮捕され、12日に罰金30万円の略式命令を受けた県立杉戸高校教諭(29)も今回の処分に含まれている。停職の同局職員は10月に同県鴻巣市内で強制わいせつ容疑で逮捕され、その後、被害女性との示談が成立し、不起訴になったという。
関根郁夫・県教育長は「不祥事の根絶に向けた取り組みを徹底し、信頼回復に努めます」とのコメントを出した。
最後の修学旅行になるのだろうか?
修学旅行先で、教諭が引率の女子高生を盗撮 12/15/14 (読売新聞)
京都府警下京署は13日、修学旅行先の京都市で引率していた女子高生の裸を盗撮したとして、青森市蛍沢、青森県立高校教諭・原子真輝容疑者(26)を京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕した。
発表によると、原子容疑者は12日夜、宿泊先の京都市下京区のホテルの女湯脱衣場で、女子生徒の裸をビデオカメラで撮影した疑い。
ホテル従業員が脱衣場のロッカーの上に、置き時計型のカメラが置かれているのを発見。周辺の防犯カメラの映像に不審な動きをする原子容疑者が映っていたという。
子供のころなぜ表紙に昆虫なのかと思った事はあった。
子供や子供の親が表紙に関してクレームを入れるのは個々の判断であるが、教師までもクレームを入れるのはおかしい。昆虫が嫌であれば、文科省に理科の廃止を求めるのか?昆虫よりも保健体育の人間の体の構造、骸骨のレプリカや標本の方が気持ち悪と思った。しかし、人間の体の構造や仕組みを学ぶ事は有益になるし、医師、薬剤師、生態や人体に関する研究者になる子供にとっては必ず知っておかなければならない事。
教師が教師個人の価値を子供に押し付ける事実には驚いた。メーカーにプレッシャーを与えるほどそのような教師が多いのにはもっと驚いた。そのような教師は子供にとって有害になる可能性もあるのではないか?文科省や地方自治体の教師の採用方針や採用基準、そして教育方針に問題があるのではないのか?法的に問題がなければ子供の個性や価値観を受け入れる事が出来ない教師が増えているのであれば問題だ。問題の解決には時間がかかるので文科省や地方自治体はすみやかに対応するべきだ。公務員である教師は一旦採用されれば簡単には首には出来ない。
ジャポニカ学習帳から昆虫が消えた 教師ら「気持ち悪い」 40年続けたメーカーは苦渋の決断 11/27/14 (withnews)
1970年の発売以来、累計12億冊を販売した「ジャポニカ学習帳」。表紙にカブトムシなどの大きな写真が入っているのが特徴でしたが、2年前から昆虫の写真を使うのをやめていたことが分かりました。きっかけは、教師や親から寄せられた「気持ち悪い」という声だったといいます。
30年以上、一人のカメラマンが撮影
文具メーカー「ショウワノート」のジャポニカ学習帳は、来年で発売45周年になるロングヒット商品。すべて富山県にある本社工場で作られていて、学年や科目ごとに異なる約50種類が販売されています。商品の形に商標権を認める「立体商標」として認められるなど、抜群の知名度を誇ります。
そんなジャポニカ学習帳の特徴の一つが、表紙を飾る写真です。1978年以降、カメラマンの山口進さんが撮影したものが使われています。
「アマゾン編」「赤道編」といった、様々なテーマがあり、山口さんは世界各地に滞在して数カ月かけて撮影してきました。
2012年に昆虫が消える 教師からもクレーム
ところが、2012年から表紙の写真に昆虫は使われていません。こんな意見が寄せられたのがきっかけでした。
「娘が昆虫写真が嫌でノートを持てないと言っている」
「授業で使うとき、表紙だと閉じることもできないので困る」
保護者だけではなく、教師からも同じような声が上がったそう。ショウワノートの開発部の担当者は「虫に接する機会が減ったということでしょうか」と推測します。
ショウワノートは苦渋の対応
こうした声は10年ほど前から寄せられたといいます。それほど多くはなかったそうですが、ショウワノートは昆虫写真を使わないことに決めました。
「学校の授業や、家に帰ってからの宿題。お子さんがノートを使う機会は多いです。もしかしたら友達と一緒にいる時間より長いかもしれません。学校の先生もノートを集めたり、添削したりと、目に触れる機会は多いと思います。そんな商品だからこそ、一人でも嫌だと感じる人がいるのであればやめよう、ということになりました」
多いときはジャポニカ学習帳の半分近くを占めていたという昆虫の写真。ショウワノートにとっては苦渋の選択でしたが、改版するたびに徐々に減らし、2年前に完全に姿を消しました。
世相を反映した対応とはいえ、表紙の珍しいカブトムシやチョウが大好きだった人からすれば、寂しく感じられるかもしれません。
「諮問の柱は、英語教育の抜本的な見直し。20年度に開催される東京五輪・パラリンピックに合わせ、外国人と交流できる実践的な英語力を身につけるのが目標だ。」
そんな目標のために多額の税金を注ぎ込むのか?止めろ!税金の無駄遣いだ。英語を勉強したい生徒だけ集中して勉強できる環境を整えれば良い。簡単な英語しか出来ないレベルで何が出来るのか?
平等を強調するがあまり、税金を無駄にして、費用対効果から目を背けている。増税するなら無駄な事は止めろ!
小学英語教科化も…指導要領改定、中教審に諮問 11/20/14 (読売新聞)
下村文部科学相は20日、幼稚園から高校までの教育内容を定める学習指導要領(幼稚園は教育要領)の全面改定を中央教育審議会(安西祐一郎会長)に諮問した。
時代の変化に迅速に対応し、国際的に活躍する人材を育成するため、小学校英語の教科化や高校での科目新設、日本史必修化などについて検討が行われる。
約2年かけて審議し、2016年度に答申される予定。これまで学習指導要領は約10年ごとに改定されており、次期改定は当初、幼小中学校が17年度、高校が18年度の予定だったが、文科省は社会のグローバル化などに迅速な対応が必要として、それぞれ1年前倒しで改定する方針。次期要領は幼稚園が18年度、小学校が20年度、中学校が21年度から、高校は22年度の1年生から順次実施される見通し。
諮問の柱は、英語教育の抜本的な見直し。20年度に開催される東京五輪・パラリンピックに合わせ、外国人と交流できる実践的な英語力を身につけるのが目標だ。英語教育の開始時期を現在の小学5年生から3年生に引き下げ、5年生からは正式な教科とする。
公務員を辞めたかったのか、それとも、自己抑制できなかったのか? 理解できない行動!
義援金も…911万円流用の中学事務職員を処分 11/14/14 (読売新聞)
宮城県教委は13日、中学校が管理する911万円を流用したとして、石巻市立飯野川中の事務職員・菅野裕貴主事(25)を懲戒免職処分にした。
同中の校長(58)は減給3か月(10分の1)、現在の教頭(50)と前任の教頭(52)も減給1か月(同)の懲戒処分とした。
県教委と市教委の発表によると、菅野主事は2013年8月から今年10月、各家庭から集めた教材費や給食費などを引き出し、家電製品の購入や消費者金融への支払いなどに充てたとしている。同中への義援金約14万円も流用したという。9月下旬、大会出場のため利用したバス代が支払われていないと業者から指摘され、発覚した。父親が全額を返済したが、市教委は刑事告訴も検討している。
市内の小中学校の事務職員はそれぞれ1人で、市教委の境直彦教育長は「管理体制の甘さがあった。深く反省している」と謝罪した。市教委は全校の会計を再調査する。
県教委はこのほか、県北の中学校の女性教諭(23)を停職6か月、県北の高校の男性教諭(43)を減給9か月(10分の1)の懲戒処分とした。女性教諭は仙台市内の商店で化粧品や入浴剤などを万引きし、男性教諭は女子生徒に性的な内容を含むメールを頻繁に送ったとしている。女性教諭は13日付で退職した。
他のエリアで講師として採用されたら同じ事を繰り返す可能性は高いだろう!
自宅で生徒にキス、別の生徒と性行為…懲戒免職 11/12/14 (読売新聞)
兵庫県教委は11日、女子生徒にわいせつな行為をしたとして、県立高校の20歳代の男性臨時講師を、同日付で懲戒免職にした。
県教委によると、臨時講師は7月下旬、自宅で女子生徒の進路相談に応じた際、生徒にキスをしたり、胸を触ったりしたほか、8月中旬には、自宅で別の女子生徒と性行為をするなどしたという。
本人の能力や努力もあるのかもしれないが、大学を卒業しなくても、教員免許がなくても疑惑を持たれないような授業を14年間も行う事が出来る事を証明したケースだと思う。問題を起こす教員や指導力のない教員の問題を考えると採用基準や教員に対する要求を見直す必要があると思う。
15年間「偽教諭」、男を書類送検=給与4000万円詐取疑い―大阪府警 10/21/14 (時事通信)
大阪府東大阪市立中学で教諭を務めていた男(45)=失職=が約15年間、偽の教員免許で教諭に成り済ましていた問題で、府警は21日までに、この男を詐欺や偽造有印公文書行使、教職員免許法違反の疑いで書類送検した。府警によると、成り済ましの事実を認め「給与は返す」などと供述しているという。
送検容疑は1999年4月~今年2月、教員免許を偽造して東大阪市立中など4校で教諭に成り済まして勤務し、2007年4月以降に給与約4000万円をだまし取った疑い。
大阪府教育委員会によると、今年1月の教員免許更新の際に偽造が発覚した。99年4月に府教委に教職員採用されたが、実際は大学を卒業しておらず、友人から借りた免許をコピーし、氏名などを書き換えて使っていた。府教委は採用時にさかのぼって失職扱いとし、詐欺容疑については公訴時効が成立していない07年4月以降の分で刑事告発していた。
「経済的な理由で大学や短大などを中退する学生が増えていることが、文部科学省の調査で分かった。」について経済的な支援が注目を集めている。
【貧困と中退】経済的な支日本は大学や短大に進学する割合はさほど高くない。(大学進学率の国際比較 文部科学省)開けない人はここをクリックデータの取り方により誤差はあるだろうが、日本の大学進学率は約50パーセントだ。この進学した数値よりも卒業生は少なくなる。
こんな状況で多額の税金を投入して英語教育を進める必要性はあるのか?英語を教えた事のない教師を教育するコスト、ALTのコストそしてその効果を考えると疑問な点が多くある。後ろ向きの考えではだめだと言う人もいるだろう。しかし、財政的に問題を抱える日本で、大学進学率が約50パーセントの状況で経済的な理由で大学や短大を中退する学生が増加している状況を無視していてはトータルに見ると問題が残る。英語の授業数は選択制で良い。全てを同じにする必要はない。特別校を指定したり、特別校を増やすだけで良いと思う。財政的にゆとりがあれば良いが財政的にゆとりが無いのだから考え方を変えるべきである。
大学や短大の生き残りの問題もある。とにかく生徒を増やしたいために入試を簡単しても、戦力にならない卒業生が増えれば大学や短大を卒業する意味が薄れる。とにかく大学や短大を卒業すれば就職できる時代でもなくなっている。大学や短大の教育課程や教育プログラムも現在そして将来に対応するような変化が必要だと思う。アメリカのように授業料の安いコミュニティーカレッジのようなシステムを作り、成績優秀な生徒が4大への編入を希望すれば簡単に編入できる制度を採用し、専門分野を4大で学ぶ事が出来るようにしてトータルのコストを抑える事を採用しても良い。
経済的な理由で中退する学生の増加=学費の免除=返済なしの奨学金と考えるのも良いが、大学や短大への助成金が効率的に使用されているのか、大学進学及び関連費用が減るシステムへの対応を考えるべきだと思う。文部科学省、しっかりしろ!
【貧困と中退】経済的な支援を惜しむな 10/13/14 (高知新聞)
経済的な理由で大学や短大などを中退する学生が増えていることが、文部科学省の調査で分かった。
経済格差が広がり、教育に深刻な影響を及ぼしている一つの例といえるだろう。貧しさゆえに学業をあきらめなくても済むよう、支援を拡充する必要がある。
調査によると、2012年度に大学や短大、高専を中退したのは全学生の2・7%に当たる約7万9千人で、そのうち経済的理由は20・4%と最も多かった。07年度の前回調査に比べ、6?余り上昇している。休学についても経済的理由が最多だ。
特に私立では経済的な理由による中退者の割合が国公立に比べて高く、授業料を滞納している学生も私立大が8割を占めている。
学費はここ数年、国立大では変化がないが、私立大は値上げの傾向にあるという。一方、厚生労働省の国民生活基礎調査によると、12年の1世帯当たりの平均所得は537万円と、10年前に比べ40万円余り減った。300万円に届かない世帯は3分の1に上る。
全国大学生協連の調査で、自宅外から通う学生への平均仕送り額が12年まで6年連続で減ったのも、家計の厳しさゆえだろう。奨学金やアルバイトでのやりくりが限界に達し、中退を余儀なくされた学生は多いに違いない。
中退者に限った問題ではない。意欲と能力がありながら、家庭の経済的な事情によって、大学や短大などへの進学をあきらめる若者は多いはずだ。
政府が8月に決定した「子供の貧困対策大綱」は、「貧困が世代を超えて連鎖しないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図る」ことを掲げる。経済的理由による大学などの中退や進学断念は、その根幹に関わる問題といえる。
高等教育を希望する若者が道を閉ざされないようにするためには、経済的な支援が欠かせない。国公立大の授業料の値下げ、授業料の減免枠の拡大、無利子奨学金の拡充や返済義務のない給付型奨学金の創設などだ。
だが、大綱では給付型奨学金の導入を見送った。財源のめどが立たないためだが、欧米では主流になっていることを考えると、安倍政権の本気度が問われよう。
教育は将来を担う若者や子どもたちへの投資だ。それを惜しむようなことがあってはならない。
皆、平等に英語を教えようとするからだめなんだ!全ての日本人に英語は必要ない。もちろん、英語が喋れて方が良いが、教師も対応できない、予算の問題もある。選択制にすれば良い。英語を取らない生徒は他の授業を多く取る。英語が必要だと思ったら受ける授業数を増やせば良い。話す及び聞く授業は、インターネット又はDVDを使えば少人数のクラスでも対応できる。本人が積極的に学ぶ意欲があれば、聞く事に関してはネイティブのALTがいなくとも学べる。よほど高度なレベルでなければ問題ない。話す授業にしても一人の生徒が話す時間はそれほどない。シュミレーションタイプのDVDでネイティブが英語で質問した事を英語で答える形式でも単純な質問であれば、即座に質問を聞き取り理解し回答する事が出来る生徒がどれだけいるのか。大学生でもレベルとしては低い学生が多いと思う。だから、お金のかかる方法など考えなくても良い。問題があるとすれば、違ったレベルで、授業数が違う生徒の成績をどのように評価するかだ。上のレベルであれば良い成績を付けるのか、生徒の達成度や取得レベルで評価するのか?中学受験や高校受験の英語のテストをどうするのかだ。中学受験や高校受験に英語を入れず、学校での成績を評価するのも良い。大学を卒業するまでに個々のレベルで英語を学ぶのであれば受験に英語を除外するのも良い。受験英語のための勉強は話したりする能力にはあまり関係ない。英語でコミュニケーションが取れる事を目的とするのであれば受験英語は廃止するべきである。まあ、役立たずの文科省だから彼らが考えた方向に進んでいくのだろう、ゆとり教育のように!
外国人教師からみた日本の英語教育の問題点「クソみたいな教科書を使っている」 09/29/14 (日刊SPA)
中学、高校と勉強したけど、結局英語は話せずじまい……そんな読者の方も少なくないだろう。なかなか成果のあがらない日本の英語教育だが、昨年、文部科学省は東京オリンピックに向けて2014年から改革をはじめるとぶち上げた。
◆「クソみたいな教科書を使っている」とバッサリ
今回の改革案では小学校3年生から英語教育を始めるなど、さまざまな方針が発表された。しかし、実際にこういった手法は効果的なのだろうか? 教える側の意見を探ってみると、英語圏の大手掲示板redditには「日本の英語教育を改善する」というそのものズバリのスレッドが。だが、書き込みを見てみると、外国人教師からの評価は辛辣なものばかりだ。
「ほとんどの生徒は選択形式のテストで高い点数をとることしか頭にないね。教わる文法もほとんど実生活じゃ役に立たないし、そもそも使われてないようなものばっかり」
「クソみたいな教科書をクソみたいなネイティブが校閲してる。授業で使えって言われた教科書は7歳児が書いたみたいだったし、本当に校正してんのかってクレームの手紙を送ったよ」
「1000時間のうち、いったいどれぐらい英語を聞いたり話してる? ほとんど日本語に訳したり、日本語で説明してるよな。これじゃ子供は一生英語で考えることはできないよ」
今回の改革案では高校の授業を英語で行うことや外国人教師の積極的な登用も盛り込まれているが、単純に授業を増やすだけでは解決にはならないとする意見が多かった。
「ALT(外国人指導助手)をやってたときにムカついたのは、ほかの授業とまるで協力しないこと。ある授業で文法をやって、オレの授業でスピーキングとリスニングをやって、別な授業じゃライティングをやって……何も重なるところがなかった。せっかく教わったことを別な授業に活かせてないよ」
「生徒の前でぐらいALTにも日本の教師と同じように敬意を払ってくれよ。生徒がALTにはお辞儀しなかったり、ちゃん付け・くん付けするのを許されてたら、絶対真剣に取り組む気にならないよ」
また、外国に行ったこともなければ、英語も話せない日本人教師が多すぎるという、根本的な問題を指摘する声も。学校側やカリキュラムとの溝が埋まらない限り、ネイティブの教師を使ったからといって、必ずしも成果があがるわけではないようだ。
◆部活などで手一杯の日本人教師
では、今回の改革案や外国人教師からの不満を日本人教師はどう思っているのだろう? 公立校で英語を教えている赤田保仁さん(仮名・30歳)に話を聞いた。
「改革案は中途半端ですね。入試のシステムから変えていかないと英語教育を変えるのは難しいです。いくつかの私立校が導入しているバカロレア(スイスに本部をおく財団法人の提供する教育プログラム)などはすごく効果的だし、公立でも積極的に取り入れるべきだと思います」
やはり量だけではなく質に関しても大規模な改革が必要なようだ。また、外国人教師が不満を感じている日本人教師との連携についても、英語教育のみならず、学校全体での変化がないと難しいという。
「外国人教師の不満にも一理ありますよね。こっちも困っていて、部活などほかの仕事が忙しく、ハッキリ言って満足に授業の準備をする余裕がないんです。一番力をいれて取り組みたいのが授業なんですけど……ただ、予算がおりたことで可能性は広がったと思います」
人員が増えることでそれぞれの負担が軽減されれば、授業の質も上げられるのではないかと、現場でも一定の評価はされているようだ。しかし、肝心の授業に注力できないなど、まだまだチグハグな印象は否めない。東京オリンピック開催決定を機に大きな改革の始まった英語教育。果たして日本は“英語の金メダル”を獲得できるのだろうか。 <取材・文/林バウツキ泰人>
面談した教職員に「人を殺してみたかった」と打ち明けていた事実がなぜここまで隠されていたのか?校長にも報告されていたから、校長が会見で悲しみよりも困ったといったような表情を見せたのか?
「人を殺してみたかった」と打ち明けていた事実を教職員と校長で隠蔽していた。「校長も深刻な状況と受け止めず、県教委に報告していなかった。」としか言い訳を重い使いないだろう。事実を隠蔽していましたと言えば責任を取らされる。全てを県教委に報告して県教委に判断をさせれば良かった。しかし全てを報告しない判断は校長が下した。校長の評価や出世にでも影響すると思ったのかもしれない。例え非難されても、疑われても「深刻な状況と受け止めず」としか言えないと思う。後は校長の言い訳を上がどう判断するかだけだ。
佐世保事件、少女の殺人願望を県教委に伝えず 09/25/14 (毎日新聞)
長崎県佐世保市で7月下旬に起きた高1女子生徒殺害事件で、逮捕された同級生の少女(16)(鑑定留置中)が3月に父親を金属バットで殴ったことについて、殴打の6日後、面談した教職員に「人を殺してみたかったので、父親でなくてもよかった。あなたでもいい」などと打ち明けていたことがわかった。
教職員が校長に報告したのは4月下旬で、校長も深刻な状況と受け止めず、県教委に報告していなかった。
県教委が教職員らから事情を聞くなどして判明し、26日の県議会文教厚生委員会で報告する予定だ。
とんでもない事実がはっかくした。建設会社は経営問題に直面する可能性が高い。もし建設会社が倒産すれば、国と「大同特殊鋼」が尻拭いをするのか?国が尻拭いすると言う事は、税金の無駄遣いとなる。どれぐらいの儲けになるのか知らないが、問題が発覚すれば大きな損害になるとは思わなかったのか?思わなかったからやったのだろうけど。
公務員で教師なのだから常識で考えれば何をしてはいけないのか理解できると思うが、セルフコントロールは出来なかったのだろう。
飲酒運転に詐欺、わいせつ…教職員3人を懲戒免 09/0714 (読売新聞)
福岡県教委は4日、飲酒運転や詐欺、女子高校生にわいせつな行為をした教職員3人を、いずれも懲戒免職処分にしたと発表した。
免職となったのは、直方市立直方北小の男性講師(26)、福津市立福間東中の男性教諭(56)、糸島市立南風小の女性教諭(28)の3人。
県教委教職員課によると、男性講師は4月下旬、無料通話アプリ「LINE」で知り合った女子高校生を18歳未満と知りながら、わいせつな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反(淫行などの疑い)容疑で逮捕された。
男性教諭は8月中旬、宗像市内の市道を酒気を帯びた状態で運転し、道交法違反(酒気帯び運転)の容疑で現行犯逮捕された。
また、女性教諭は6月中旬、郵便局員が誤って届けた他人あての宅配物を詐取したとして詐欺容疑で逮捕され、その後、不起訴処分となった。
今年度の免職処分は今回で4件。同課の原田靖課長は、同日の記者会見で、「不祥事防止の徹底を図ってきたにもかかわらず、相次いだことは大変遺憾。指導徹底を図っていく」と述べた。
「勉強が大変。睡眠時間が削られて疲れている」が自殺の理由だとすれば残念だ。多くの親は勉強が重要だから子供に勉強させると思う。学歴だけで仕事が出来ない人達も存在するが、学歴が低いために挑戦する機会まで自動的に失うことが日本では多い。
親が真剣に心配しようとも子供が勉強を苦痛と思えば意味が無い。学歴のない人の一般的な生き方、収入が低い仕事で働いている親、貧乏である経験を通して理解すれば教育や高収入を得る出来る仕事がどのような意味を持つのか理解できるのかもしれない。
子供と親の関係が良好であれば、また、出来る範囲でがんばれば失敗しても次をかんばれば良いと思える関係があればこのようなことにはならなかったのかもしれない。逃げてばかりいては多くの事は達成できないが、限界を超えた努力の強制や本人の意思とは関係なしに限界を超えた努力をさせると解放への逃げ道として自殺を選ぶのかもしれない。家族の恥になるかもしれないが、本当に同じような自殺を防止したいと両親が思うのであれば、事実を研究している大学教授や研究者に話すべきだと思う。残念ながら日本に子供の自殺を防止するために研究している心理学者や大学教授が存在するのか知らない。存在すればケーススタディーとして生かせると思う。両親としては子供に対する自分の接し方が間違っていたかもしれないなんて振り返りたくもないし、話したくもない人が多いと思う。
女児飛び降り自殺? 2人死亡 周囲に「勉強が大変」と訴え 09/06/14 (産経新聞)
5日午後3時35分ごろ、東京都大田区下丸子のマンション敷地内で、区立小学校6年の11歳と12歳の女児2人が倒れているのが見つかった。いずれも搬送先の病院で死亡した。女児らが書いたとみられる遺書のようなものが見つかっており、警視庁池上署は2人が一緒に飛び降り自殺を図ったとみて、詳しい経緯などを調べている。
同署や大田区教育委員会などによると、2人は同じクラスの友人。2人は9階建てマンションの駐車場付近で倒れ、真上にある非常階段の7階と8階の間の踊り場に靴が2組そろえておかれているのが見つかった。
女児らの同級生によると、2人とも中学受験を目指し、周囲に「勉強が大変。睡眠時間が削られて疲れている」などと訴えていた。5日はいずれも登校していたという。
遺書のようなものにいじめを示唆する内容は書かれておらず、区教委も「いじめの情報は把握していない」としている。
現場は東急多摩川線武蔵新田駅から南西に約600メートルの住宅街。
マンションから小6女児2人飛び降り?死亡 09/06/14 (読売新聞)
5日午後3時40分頃、東京都大田区下丸子のマンション敷地で、同区立小学校6年の11歳と12歳の女子児童が血を流して倒れているのを男性が発見し、119番した。2人は全身を強く打って病院に搬送されたが、2人とも死亡した。マンションの7階と8階の間の外階段の踊り場に2人のものとみられる靴2足がそろえて置いてあり、警視庁池上署は一緒に飛び降り自殺を図ったとみている。
同署幹部や区教委などによると、2人は同級生で仲が良く、5日も登校していた。11歳の女児はこのマンションに家族と住んでいるという。靴の近くで遺書らしきメモ用紙が見つかっており、同署が詳しく調べている。
この日、2人と学校で会った同級生の女子児童(11)は、「2人とも中学受験を控え、『疲れた』と言っていた。こんなことになるなんて信じられない」と泣きながら話した。
現場は、東急多摩川線武蔵新田駅の南西約500メートルの住宅街。
もう教授にはなれないだろう。教授や指導者を目指していながらこのような行為をするのなら教授になるような人物でもないと思う。
東大大学院生が中2買春 行為後カフェで数学教える 09/04/14 (スポーツ報知)
神奈川県警中原署は3日、女子中学生(15)に淫らな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで、東京都文京区の東京大大学院生で医学系研究科の杉本真人(まこと)容疑者(28)を逮捕した。
逮捕容疑は、3月26~27日、アパート自室で、川崎市に住む当時中学2年の生徒に2万円を渡す約束をして、淫らな行為をした疑い。容疑を認めているという。
同署によると、杉本容疑者は3月上旬、ツイッターで生徒と知り合い、無料通信アプリ「LINE」で本名を名乗ってやりとりをしていた。杉本容疑者は生徒に制服で自室に来るように指示。買春行為の後、一緒に生徒の自宅がある川崎市へ移動し、カフェで数学を教えていた。
同署はツイッターなどで「生徒が援助交際をしている」などという情報が流れたため、8月28日に生徒を保護。生徒から話を聞いて裏付け捜査をしていた。杉本容疑者は3日に逮捕されるまで、捜査されていることを知らなかったという。
杉本容疑者が生徒と会ったのは、1度だけだったが、生徒の裸の写真を撮っていたという。児童ポルノ映像を作成しようとしていた疑いもあり、同署では同法違反(製造)容疑でも調べを進めている。
杉本容疑者は医学部予備校で講師のアルバイトなどをしながら大学教授を目指していたという。
もう教授にはなれないだろう。教授や指導者を目指していながらこのような行為をするのなら教授になるような人物でもないと思う。
「お小遣いが欲しかった」職員室で窃盗容疑 横浜市の37歳男性教諭を書類送検 神奈川県警 09/04/14 (産経新聞)
神奈川県警神奈川署は4日、窃盗の疑いで横浜市立子安小学校の男性教諭(37)=同市=を横浜地検に書類送検した。
送検容疑は、7月初旬から中旬にかけて、職員室に置かれていた女性教諭3人のかばんから、それぞれ現金1万円を盗んだとしている。「お小遣いが欲しかった」と容疑を認めているという。
同署によると、7月下旬に同校から被害届を受けた同署が捜査を開始。校長に相談した男性教諭が、8月18日、校長とともに同署に出頭したという。男性教諭は平成22年から同校で音楽を教えていた。
公務員そして教員である自覚なし。昨年4月に採用されているとのこと。面接ではどんな事を言ったのだろうか?教育委員会は、公表してほしい。不可能であれば、どのような面接であったのか調べ、良い事を言っていれば、面接での対応は練習させすればなんとか上手くこなせる事を理解して、その他の部分で人格評価をするべきだと思う。
教員が17歳少女に売春させるなんて普通は考えない。本音を面接で言えば受からない。面接で受かるような対応が出来るのであれば、面接の評価及び評価の点数を変更すべきだ。面接で上手に対応できない、嘘を付けない人は採用レベルにも達していない事実はかわらないが。
小学校教諭が少女に売春あっせん、逮捕 送迎中に職務質問され発覚 08/26/14 (産経新聞)
愛知県警中川署は26日、18歳未満の少女による売春をあっせんしたとして、売春防止法違反と児童福祉法違反などの疑いで、名古屋市南区泉楽通、市立表山小教諭、近藤純平容疑者(24)を逮捕した。
逮捕容疑は7月23日、同県大治町の無職少女(17)を、インターネットで募った男性(36)と名古屋市内で引き合わせ、ホテルでの売春をあっせんした疑い。
中川署によると、売春後の少女をホテルまで迎えに行き、車に乗せていたところをパトロール中の警察官に職務質問され、あっせんが発覚した。少女とは4月、援助交際のサイトを通じて知り合った。容疑を認めている。
表山小によると、近藤容疑者は昨年度から同校で勤務し、5年生のクラス担任だった。中島誠校長は取材に「学級運営やクラブ活動に一生懸命取り組んでいたので、驚いた。児童に動揺が広がらないよう対応したい」と話した。
17歳少女に売春させた疑い、小学教諭を逮捕 08/26/14 (読売新聞)
愛知県警は26日、少女に売春をさせたなどとして名古屋市南区泉楽通、同市立表山小教諭近藤純平容疑者(24)を児童福祉法、売春防止法違反などの容疑で逮捕した。
発表によると、近藤容疑者は、インターネットのサイトで知り合った愛知県内の無職少女(17)が18歳未満と知りながら、7月23日に名古屋市中区の路上で自営業男性(36)に引き合わせ、同区のホテルで売春させるなどした疑い。近藤容疑者は調べに対し、「間違いない」と容疑を認めているという。
名古屋市教育委員会によると、近藤容疑者は昨年4月に採用され、表山小に勤務し、現在は5年生を担任。市教委は「事実とすれば、許せない行為で大変遺憾。事実を確認し、厳正に対処したい」としている。
「本野容疑者は今年4月に採用され、現在は同市都筑区内の中学校で保健体育を教えていた。」
体育会系ならおもしろさでナンパすればよかったのに?数打てばナンパも成功したかも?
「女子高生の後ろから近づき、突然口をふさぎながら『騒いだら殺すぞ。パンツちょうだい。体触らせて』などと脅して体を触るなどした」
これで起訴されたら犯罪者だし、教師も辞めることになる。どうしても襲う興奮を得たかったのだろうか?自己責任でリスクを負ってまでしたかったのなら仕方が無い。
「パンツちょうだい」 女子高生に強制わいせつ容疑 横浜市立中学教諭を逮捕 神奈川県警 08/25/14 (産経新聞)
帰宅途中の女子高生の体を触ったとして、神奈川県警捜査1課などは25日、強制わいせつの疑いで、横浜市立中学教諭、本野恵太容疑者(25)=同市西区霞ケ丘=を逮捕した。
逮捕容疑は、13日午後10時半ごろ、同市南区の路上で、歩いて帰宅していた高校3年の女子高生(17)=同区=の上半身を触るなどのわいせつな行為をしたとしている。「間違いない」と容疑を認めているという。女子高生にけがはなかった。
捜査関係者によると、本野容疑者は女子高生の後ろから近づき、突然口をふさぎながら「騒いだら殺すぞ。パンツちょうだい。体触らせて」などと脅して体を触るなどしたという。
同市内では、3月下旬以降、保土ケ谷、西両区を中心に、同様の手口の強制わいせつや暴行事件が14件ほど発生しており、同課で関連を調べている。いずれもけが人はなかった。
横浜市教委などによると、本野容疑者は今年4月に採用され、現在は同市都筑区内の中学校で保健体育を教えていた。市教委は「事実関係を確認した上で、厳正に対処したい」と話している。
常識もなく、教師としての自覚も無いならこのような事件を起こしたのだろう。
「脅迫容疑で逮捕された同市立七光台小学校教諭、藪崎正己容疑者(49)は、同小によると、教務主任で勤続25年目。土曜授業では、学年計画の集約や地域ボランティアの管理を担当し、『土曜日がつらい』とこぼすこともあったという。若手教員の指導にも熱心だったといい、同校の小松崎明教頭は『一人で抱え込んでしまったのかも』と語った。」
脅迫文を送った場合、最悪の場合、逮捕されることぐらい知っている事だろう。知らないのであればテレビや新聞を読んでいないような教師であったと言う事になる。
地域ボランティアの管理が望んで担当していたのであれば自己満足。地域ボランティアを行っているから、若手教員の指導にも熱心だったから、良い教師と断定するのも疑問。「『今すぐ土曜授業をやめろ』『無理やり土曜日に出勤させられて大変だ』『体の調子は最高に悪い。寝込んでしまう。病死してしまう』」との考え方はいかにも公務員的だ。ブラック企業で働く従業員や派遣社員に比べればはるかに恵まれた環境だが、公務員の優遇された環境しか知らないから不満に思うのだろう。
「市教委学校教育部の染谷篤部長は『現場の教員と聞き驚いている。教員がやりがいを持てる土曜授業にしなくては』と話した。」
市教委のコメントもだめだな。土曜授業導入は学力向上が目的ではないのか?学力だけが全てではないが劣悪な環境で育ったハングリー精神も持っている、又は、劣悪な環境でも耐える事の出来る発展途上国の人々との競争に勝つのは教育と資本(お金)だ。打たれ弱いハングリー精神がなく、劣悪な環境でも耐えられない子供が多い日本では教育を優先するべきだろ。勤続25年目の49歳の教諭でこのありさまだ。
「無理やり土曜日に出勤させられて大変だ」と書いているのに「教員がやりがいを持てる土曜授業にしなくては」のコメントは解決策になっていない。まあ、少なくても免職にすればよい。なぜ学力向上が必要なのか、国際競争に勝つために必要なもの、子供が就職出来、リストラされないようにするには教育と何が必要かを議論して、結果を教員に理解させるべきだろう。公務員だから安定している思い、自分のことばかり考えるからこのような極端な事を起こすのだろう。ゆとり教育に舵をきった文科省とこのような教員達が子供達をだめにしている。楽な方から厳しい方へ行くのは程度の差はあるが誰でも苦痛に思う。それを理解し対応できない文科省と市教委はだめだ。
「土曜つらい」学校でもこぼす…脅迫の教諭 08/20/14 (読売新聞)
千葉県野田市が今年度から導入した土曜授業を巡る脅迫事件。
県内唯一の取り組みで、市が浸透を図ろうとしていた中で教諭が逮捕され、関係者に困惑が広がった。
市教委によると、送られた脅迫文には、「今すぐ土曜授業をやめろ」「無理やり土曜日に出勤させられて大変だ」「体の調子は最高に悪い。寝込んでしまう。病死してしまう」などの記述があったという。
脅迫容疑で逮捕された同市立七光台小学校教諭、藪崎正己容疑者(49)は、同小によると、教務主任で勤続25年目。土曜授業では、学年計画の集約や地域ボランティアの管理を担当し、「土曜日がつらい」とこぼすこともあったという。若手教員の指導にも熱心だったといい、同校の小松崎明教頭は「一人で抱え込んでしまったのかも」と語った。
市教委によると、土曜授業導入後に行った教職員と保護者らへのアンケート調査では、「学力向上に役立つ」と肯定的な意見は、教職員が4割、保護者が8割だという。教職員の中には、少数だが、「疲労感がたまっている」との意見もあったという。
市教委は、土曜出勤の振り替え休日を夏休み中に取りやすくするなどしていたが、市教委学校教育部の染谷篤部長は「現場の教員と聞き驚いている。教員がやりがいを持てる土曜授業にしなくては」と話した。
推測であるが、
佐世保こども・女性・障害者支援センター
は加害者の父親が弁護士であり、過去の父の対応を考慮して理由を探した上で対応しなかったのではないのか?診察した精神科医だと、守秘義務や加害者の弁護士である父親から名誉棄損や人権侵害で訴えられるリスクを感じていたに違いない。それでも被害者が出る危険性を感じたために連絡したと思う。佐世保こども・女性・障害者支援センター長は長崎県教委が10年の長期に行って来た「命の教育」は子供だけのものだと思っていたのだろうか。それとも「命の教育」について全く知らなかったのだろうか。全く知らなかったのであれば、長崎県教委の「命の教育」は地域には浸透していなかったのだろう。
「市教委は『少女の進学先に事案の概要を伝え、中学や高校でも見守りは続けられていた』と説明している。
市教委及び加害者が在籍した学校は専門的な知識や技術が必要無いと判断して佐世保こども・女性・障害者支援センターに連絡していなかったのか?市教委は
佐世保こども・女性・障害者支援センターは存在や概要は知っていたのだろうか?メディアは徹底的に調べて公表してほしい。
佐世保こども・女性・障害者支援センターの概要
子どもに関すること
近年・子どもへの虐待は後を絶たず、子どもの命が奪われるといった重大な事件が発生しています。また、日頃から育児の悩みを持つ方もたくさんいらっしゃいます。 子どもの様子や子育て中の家庭の様子がおかしい、と感じたら、早いうちにお近くの窓口に連絡・相談することが大事です。18歳未満の児童の育児やしつけ、心身の発達の遅れ、非行、不登校、養育、虐待などの相談窓口は市町につくられていますが、特に専門的な知識や技術が必要な場合には、当センター職員が市町と連携して支援します。
女子生徒は「人を殺しかねない」 高1殺害、医師の相談生かせず 07/31/14 ( 共同通信)
長崎県佐世保市で高校1年の同級生を殺害したとして女子生徒(16)が逮捕された事件で、発生前の6月、県の児童相談窓口に寄せられた情報に「女子生徒は人を殺しかねない」との内容が含まれていたことが31日、県関係者への取材で分かった。県は具体的な対策を取らず、情報を生かせなかった。
県と、報告を受けた県議会は、当時の対応が適切だったかどうかを含め経緯を調べている。
県関係者によると、女子生徒を診察した精神科医が6月10日、相談窓口がある佐世保こども・女性・障害者支援センターに連絡。精神状態の不安定さを懸念し「このまま行けば人を殺しかねない」と相談した。
「殺しかねない」と精神科医 長崎県、相談電話放置か 実家を家宅捜索 07/31/14 (産経新聞)
長崎県佐世保市で高校1年の同級生を殺害したとして女子生徒(16)が逮捕された事件で、発生前の6月、県の児童相談窓口に寄せられた情報に「女子生徒は人を殺しかねない」との内容が含まれていたことが31日、県関係者への取材で分かった。県は生徒名が伏せられていたとして具体的な対策を取らなかったが、医師は名乗っていた。県と、報告を受けた県議会は、相談を放置した可能性もあるとみて対応が適切だったかどうか、経緯を調べている。
県関係者によると、女子生徒を診察した精神科医が6月10日、相談窓口がある佐世保こども・女性・障害者支援センターに電話で連絡。精神状態の不安定さを懸念し「小学生の時に薬物混入事件を起こし、中学生になって父を殴打した。小動物の解剖をしている。このまま行けば人を殺しかねない」と相談。対策を求めたが、女子生徒の氏名は明かさなかった。
県警は31日夜、殺人容疑で女子生徒の実家の家宅捜索を始めた。
長崎県教委の「命の教育」の10年間は何だったのか?
「結果として事件が起きたことで、我々の気持ちや教育が子どもたちの心の底まで届いていなかったという印象だ」
形だけの教育だったと言う事だ。全ての子供に伝わらなければ意味が無い。しかし、全ての子供に届く事は現実には不可能だと思う。しかし、届くと思っていたのなら原点から間違っていると思う。
「多くの子どもたちにトラウマが生じかねないような状況になっているとして臨床心理士や看護師らでつくる精神保健の専門家チーム(8人)を初めて派遣した。」
こう言う時こそ、命の大切さ、犯罪を犯したらどうなるのか、問題の先送りをしない事の重要性などを教えるべきである。進学校だから実際は、迷惑と思っている生徒も多いだろう。今は理解しないかもしれないが結婚とは何か、子育てについて話をしても良いかもしれない。目先の進学だけに焦点を置くのか、長いスパンで振り返る事が出来る話をするのか、学校の責任で判断するのか、長崎県教委の責任で判断するのか、考えた方が良いだろう。
遅かれ、早かれ人は死ぬ。努力しても、がんぱっても不幸は起きる事がある。その時にどうするのか?そう言う事を教えても良いかもしれない。ところで心のケアとは何か?アメリカで勉強した事を日本にそのまま導入する事なのか?個々の子供達が届かなければ意味が無いと思う。資格を持った臨床心理士や看護師は探せるが、実際に問題解決が出来るかは別問題だと個人的な経験から思う。大体、スクールカウンセラーの考え方がアメリカだろ。日本でのフィールド調査や他の調査が行われ調整や改善が行われているのか?トラウマとは何か?トラウマと言うのなら加害者はトラウマやネガティブな感情を抱えていたに違いない。なぜ、事件の前に対応できなかったのか?事件後に調査や実験のまとめ又は本や論文から偉そうなことを言っても、事件を防げなくては意味が無い。
佐世保高1殺害…長崎県教委、命の教育見直し 07/30/14 (読売新聞)
長崎県佐世保市の県立高校1年の女子生徒(15)が殺害され、同級生の少女(16)が殺人容疑で県警に逮捕された事件で、池松誠二・県教育長は28日、報道陣に対し、県教委などによる命に関する教育について、「再構築していきたい」と述べ、課題を検証したうえで見直していく考えを示した。
池松教育長は事件について、「ショックだった。胸が張り裂けそうな気持ちだ」と沈痛な表情を浮かべた。
命の大切さを伝える教育の効果については、「結果として事件が起きたことで、我々の気持ちや教育が子どもたちの心の底まで届いていなかったという印象だ」と述べ、「しっかりとした再発防止策を策定したい」と決意を語った。
心のケア専門家チームを初めて派遣
県教委は28日午後、2人が通っていた高校で、多くの子どもたちにトラウマが生じかねないような状況になっているとして臨床心理士や看護師らでつくる精神保健の専門家チーム(8人)を初めて派遣した。
チームは2003、04年にかけ、県内で未成年による重大事件が相次いだことを受け、05年に発足させた。活動は30日までで、ショックの大きい教職員や生徒への個別面談、保護者へのアドバイスなど、心のケアの視点から学校を支援する。
このほか、佐世保市も市子ども子育て応援センター(中央保健福祉センター4階)に心の相談窓口を開設。8月8日(8月2、3日を除く)までで、午前9時~午後7時に保健師が対応する。事件に関して悩みを持つ人を対象にした電話相談も受け付ける。相談電話は(0956・25・9718)へ。
命の教育「形骸化」の指摘も 県が臨時教育委員会 [長崎県] 07/30/14 (西日本新聞)
県教育委員会は29日、佐世保市の高1同級生殺害事件を受け、臨時教育委員会を開き、今後の対応を話し合った。池松誠二教育長は「命を大切にする教育や子どもの心と向き合う教育に取り組んできたが、このような事件が発生したことは痛恨の極み」と語った。
黙とうをした後、会合は非公開で実施。県教委によると、事件の概要や加害生徒が1人暮らしをしていること、小学校時代の問題行動などについて説明。命を大切にする教育について委員から「結果として、全ての児童、生徒の心に届いていなかった」「取り組みが形骸化しているのではないか」などと指摘する意見が出たという。
記者会見した池田浩教育次長は「事件の背景、課題をつかみ切れていない。これまでの取り組みに何が足りなかったのか、検証が必要だ」と語った。
長崎市では2003年、男子中学生が男児を誘拐して殺害する事件が発生。04年には佐世保市で女子児童が校内で同級生を殺害する事件があり、県教委は命を大切にする教育に力を入れていた。
=2014/07/30付 西日本新聞朝刊=
佐世保高1殺害…長崎県教委、命の教育見直し 07/29/14 (読売新聞)
佐世保市の県立高校1年の女子生徒(15)が殺害され、同級生の少女(16)が殺人容疑で県警に逮捕された事件で、池松誠二・県教育長は28日、報道陣に対し、県教委などによる命に関する教育について、「再構築していきたい」と述べ、課題を検証したうえで見直していく考えを示した。
池松教育長は事件について、「ショックだった。胸が張り裂けそうな気持ちだ」と沈痛な表情を浮かべた。
命の大切さを伝える教育の効果については、「結果として事件が起きたことで、我々の気持ちや教育が子どもたちの心の底まで届いていなかったという印象だ」と述べ、「しっかりとした再発防止策を策定したい」と決意を語った。
◆心のケア専門家チーム派遣
県教委は28日午後、2人が通っていた高校で、多くの子どもたちにトラウマが生じかねないような状況になっているとして臨床心理士や看護師らでつくる精神保健の専門家チーム(8人)を初めて派遣した。
チームは2003、04年にかけ、県内で未成年による重大事件が相次いだことを受け、05年に発足させた。活動は30日までで、ショックの大きい教職員や生徒への個別面談、保護者へのアドバイスなど、心のケアの視点から学校を支援する。
このほか、佐世保市も市子ども子育て応援センター(中央保健福祉センター4階)に心の相談窓口を開設。8月8日(8月2、3日を除く)までで、午前9時~午後7時に保健師が対応する。事件に関して悩みを持つ人を対象にした電話相談も受け付ける。相談電話は(0956・25・9718)へ。
「『命の教育』から善悪を教える『宗教教育』へ」の記事に賛成できない。子供達が命の大切さが理解できたのならそれで十分だ。宗教教育とはどの宗教を示しているか?キリスト教もあれば、イスラム教もある。同じキリスト教でも、イスラム教でも宗派が違えば争い合ったり、妥協できなかったりする現実がある。宗教教育とは仏教のことなのか?
子供の環境に問題があり、子供に届かなければ効果が出ない事を理解できなかった事が問題だと思う。コストや利益を重視すれば安全性のリスクが高まる。成績だけを重視すれば人間性が軽視される傾向が高くなる。教師の時間や努力にも限りがある。また、教師の採用方法や先輩教師の影響が時間と共に新人教師の質に関与してくるだろう。社会の個人の評価方法も長期的に影響する。人間的に良くても大手企業はそのような点よりは最終学歴を優先するだろうし、会社に採用されなければ非正規社員としての受難が待っているかもしれない。グローバリゼーションの中では国際競争も無視できない。お役所とは違う。赤字続きでは会社は存在できない。社会福祉とか人間の幸福とか言っても、国の財政が破たんすれば終わり。打ち出の木槌はない。ギリシャが良い例だ。
だからこそ教育がしっかりしなければならないのにこのありさま。宗教は人生の価値観を簡単に形成してくれるが、自分なりの哲学や価値観を客観的に持つ事が出来れば宗教など重視する必要はない。
「命の教育」から善悪を教える「宗教教育」へ 佐世保・高1女子殺害事件 07/29/14 (読売新聞)
高校1年の女子生徒が、同級生を殺害するという痛ましい事件が起きた長崎県で、これまでに取り組んできた「命の教育」のあり方を見直す動きが始まっている。
県教育委員会が29日に開いた臨時の会合では、出席者から「これまでの取り組みの検証が必要」などの声が上がった。県教委は今後、県内の各学校の校長を集めた会合を開き、再発防止のための教育のあり方について検討するという。
佐世保市では2004年6月にも、小学6年の女子児童が、校内で同級生にカッターナイフで切りつけて死亡させる事件が起きた。これを受けて文部科学省は、05年から全国で「命を大切にする心を育む」ことに重点を置く道徳教育の取り組みを推進。07年に改定した学習指導要領には、道徳の授業で「生命の尊さ」を重点的に指導するという内容を追加した。
この流れの中で、佐世保市の小中学校では毎年6月、「いのちを見つめる強調月間」を設けてきた。命の大切さに関する校長の講話や公開での道徳授業をはじめ、小動物や植物の生育、佐世保大空襲などを取り上げた平和教育などにも取り組んできた。
しかし、こうした道徳教育を通して「命を落とさないことの大切さや、その方法」を教えることはできても、「なぜ生命を奪ってはいけないのか」という根源的な問いに答え切ることは難しいだろう。
生命の本質やその尊さなど、目に見えないものの大切さを教えているのは、世界各地で説かれてきた宗教である。しかし、日本の学校教育からは「神、仏という存在がいる」「良いことをした人は天国へ、悪いことをした人は地獄へ行く」といった、基本的な宗教教育は日陰の存在として追いやられている。
教育基本法では、宗教に関する一般的な教養を教えたり、宗教に対して敬意を払うことは定めている。だが、社会問題への対応や生徒への指導、道徳教育において、宗教教育が根付いているとは言いがたい。
人間の本質は魂であり、肉体が死んでも魂は生き続ける、というのが霊的な真実だ。また、この世に生まれる理由は、「人生の様々な出来事を通して魂を磨き、成長させるため」である。殺人が罪なのは、他の人が幸福に生き、魂を成長させる機会を奪ってしまうからだ。
もちろん、家庭教育が大切なことは言うまでもないが、子供が一日の大半を過ごす学校での教育は、人格形成に大きな影響を与える。残虐な事件を二度と繰り返さないために必要なのは、現在の道徳教育を「宗教教育」のレベルに引き上げ、真の意味で生命の大切さを学び、善悪の判断ができる子供へと育てることである。(晴)
【関連書籍】
幸福の科学出版 『繁栄の法』 大川隆法著
http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=148
幸福の科学出版 『教育の法』 大川隆法著
http://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=49
【関連記事】
2005年5月号記事 子供が凶悪事件を起こさないために──命の大切さを教えるには
http://the-liberty.com/article.php?item_id=249
2014年7月28日付本欄 同級生殺害事件 長崎県佐世保市で繰り返されたのはなぜか
http://the-liberty.com/article.php?item_id=8213
助成金まで出し格安「反日」 大分県教組の「慰安婦ツアー」、交流目的で歴史館など見学 (1/3)
(2/3)
(3/3) 10/22/13 (毎日新聞 東京夕刊)
大分県教職員組合(県教組、大分市)が法に反し、韓国の「慰安婦」関連施設などを見学する旅行を募集していたことが明らかになった。その“反日教育ツアー”は、県教組が助成金を出し、親子2人が2泊で2万5千円という破格の旅行代金が売りだった。
「親子1組(2人)2万5千円で30組を募集!」
地元紙の大分合同新聞に掲載された2泊3日の「親子で学ぶ韓国平和の旅」の募集広告には、旅行代金が太字で強調されていた。一般の格安ツアーをはるかに下回る料金設定。これは「金額は明かせないが、うちが助成金を出しているため」(県教組担当者)だ。
県教組によると、「韓国平和の旅」は県教組独自の平和事業の一環で、今回が12回目だという。新聞広告で申し込みを受け付け、代金徴収も行うようになったのは2年前からだといい、今回を含めて少なくとも3回は違法行為を重ねていたことになる。
かつて旅行団長を務めたこともある県教組の岡部勝也書記長は「韓国の中学生との交流がメーンで、それもスポーツや芸能の話題が多い」と話すが、広告に書かれた通り、「日本軍『慰安婦』歴史館」や、反日運動家らの監獄として使用された「西大門刑務所跡」なども訪問する。そこでは、現地ガイドから、韓国側の主張に沿った一方的な説明を受けるのだという。
日本軍「慰安婦」歴史館には、平成5年の河野洋平官房長官談話発表を「慰安婦『強制』認め謝罪」と報じた朝日新聞のコピーなど多くの慰安婦関連資料が展示されている。
だが強制連行説の最大の論拠だった河野談話については、6月に公表された政府の談話作成過程検討チームの報告書で、元慰安婦への聞き取り調査終了前に談話の原案を作成したことや、裏付け調査を実施しなかったことなどが指摘され、「強制連行を直接示す資料はない」との政府見解が再確認されたばかりだ。
今回は広告を出した後、初めて10件以上、抗議電話があったという。岡部書記長は「反日や自虐史観を植え付ける旅行ではなく、日本の加害行為に向き合い、平和を模索する目的だ」と強調。「修学旅行として行くなら控えるが、希望する親と子が行く旅行なので問題ないと考える」と話す。
だが明星大の高橋史朗教授(教育学)は「慰安婦問題は国内的には決着がついた議論」とした上で「歴史教育については、義務教育の段階では自国の立場を教えるのが基本だが、旅行は極めて反日的で、韓国側の立場を学ばせるもので教育上不適切だ」と批判する。
県内の元小学校長(61)は「県教組はこれまでに何度も不祥事を起こしており、自浄能力がなさすぎる」と指摘した。
◇
【用語解説】大分県教職員組合
日本教職員組合傘下で、加入率(小中学校)が60%を超え、全国有数の「日教組王国」として知られる。平成13年には、「日本戦犯裁判」や「南京大虐殺」を載せた「平和カレンダー」を作製し、小中学校に掲げていたことが「偏向的」と批判されて撤去された。
同年には、特定の中学歴史・公民教科書の採択阻止を求める全面広告を大分合同新聞に掲載したことも、「採択の公正さを損なう」と批判された。20年には教員採用をめぐる汚職事件が表面化。県教組出身の県教委幹部や小学校長ら8人が有罪判決を受け、確定している。
「教育委員会で改めて調べたところ、男性教諭が教員免許を取得した記録が確認できず、免許がないまま勤務していた疑いがあると判断しました。
男性教諭に目立ったトラブルはなく授業にも熱心に取り組んでいたということです。」
教員免許を取得していなくとも教師はできるが、制度として免許が必要なだけ。逆に教員免許を保持し、採用試験に合格しても教師として不適格な人間もいる。
いい加減に教員の免許状と名刺サイズのIDカードを発給し、IDカードの番号で確認できるシステムを採用してはどうか?教員の免許状は携帯に問題あり。
教員免許無いまま14年指導 中学教諭が死亡 07/19/14 (読売新聞)
京都市の中学校で14年間にわたって保健体育を指導した男性教諭が、教員免許を持っていなかった疑いがあることが分かりました。男性教諭が教員免許の更新手続きをしないため、教育委員会が事情を聞こうと呼び出した当日に、電車にはねられて死亡したということです。
教員免許を持っていなかった疑いがあるのは、京都市右京区の中学校で保健体育を担当していた45歳の男性教諭です。
京都市教育委員会によりますと、男性教諭は京都市内の複数の中学校で保健体育の非常勤講師や正式な教員などとして、ことし3月まで14年間勤めました。
しかし、教員免許の更新手続きの期限をすぎても書類を提出しなかかったため、ことし3月に教育委員会が事情を聞こうと呼び出したところ、当日、電車にはねられて死亡したということです。
その後、教育委員会で改めて調べたところ、男性教諭が教員免許を取得した記録が確認できず、免許がないまま勤務していた疑いがあると判断しました。
男性教諭に目立ったトラブルはなく授業にも熱心に取り組んでいたということです。
これまで採用の時には教員の免許状のコピーを提出すればよかったということで、京都市教育委員会は「今後は原本を確認するなど再発防止に努めたい」としています。
経済協力開発機構(OECD)の2013年の「国際教員指導環境調査」を大義名分として利用しただけだ。英語が出来ない教師に英語を教えること自体、効率を考えば時間と費用の無駄。英語教育を先延ばしにして教員採用試験に英語を導入し、英語の能力があり、教員としての能力がある教員の給料をアップするほうが効率的だ。英語が出来ない教員のどれだけの研修を行い、どれほどの効果を期待するのか?教員にストレスを与え、英語教育の結果も期待できないばかげた考えを推し進める文部科学省は考え直すべきだ。また、教員が授業に専念出来れば子供の学力が飛躍的に向上する考える方がおかしい。机上の空論だ。進学率だけを考えれば学力向上は喜ばしことだが、学力だけが全てではない。選択Aを選ぶと結果Bとはならないのが子供だ。また、周りの環境、家族の影響、スポーツやその他の影響などで変わる子供もいる。短期の結果そして長期の結果もあり、簡単に評価できない場合もある。個人的には子供の心のケアを担うスクールカウンセラーは疑問だ。教員が基本的な知識があれば後は個々の経験で対応できると思う。アメリカの物真似で本質を見ていなければあまり効果がないと思う。日本は財政的に問題を抱えているのに、なぜ公務員や支出を増やそうとするのか理解できない。
文科省:教員の多忙対策 外部人材を大幅増員する方針 07/17/14 (毎日新聞)
文部科学省は、「世界一多忙」とされる日本の教員の勤務状況を改善するため、学校活動を担う外部人材を大幅に増員する方針を決めた。「チーム学校」と名付け、福祉の専門家のスクールソーシャルワーカー(SSW)や外部の部活動指導者、事務職員を増員し、教員の負担を軽減。授業に専念できる環境を整備し、子供のさらなる学力向上を図る。来年度予算の概算要求に盛り込んだ上で、今月中にも下村博文文科相が中央教育審議会に「チーム学校」の在り方を諮問する。
中学教員を対象にした経済協力開発機構(OECD)の2013年の「国際教員指導環境調査」では、日本の教員の勤務時間は週53・9時間と最長(参加34カ国・地域平均は38・3時間)で、事務作業や部活動指導の時間が参加国平均に比べ3〜2倍長かった。さらに、いじめや不登校、家庭環境への対応など授業以外の問題も教員が担うケースがほとんど。部活動がない小学校でも今後英語や道徳の教科化が想定され、負担軽減が急務になっている。
事態を重く見た同省は来年度から、教員以外のメンバーを増やしてサポート態勢を大幅に強化。「チーム学校」として▽家庭や児童相談所、警察と連携し、いじめや不登校の課題解決を図るSSW▽子供の心のケアを担うスクールカウンセラー▽地域スポーツの指導者などが教員に代わって生徒を教える部活動指導員−−などを想定する。
いずれも「専門家の非常勤職員」として、週に複数日学校に入ることが想定され、直接子供たちに関わる。これにより、教員が本来業務である「授業」に専念できる状況を作るとしている。
また、書類作りなど事務作業は、正規の事務職員を増員。さらに複数の学校で作業を共同化することも推進する。【三木陽介】
倫理研修や教育が解決方法で無い事が証明された一例だろう。倫理教育を受けていれば回避出来るケースはあるだろう。しかし、倫理研修や教育を受けても自制する能力が弱ければ欲求を優先するだろう。自制心や自省する能力は公務員採用試験では要求されない。規制するだけでなく、自由にさせて問題を起こす教員を早期に取り除く方が効率的だし、効果的だと思う。人格形成がほぼ終了した成人に対しての倫理研修は効果は無いとは思わないが、費用や時間に対して期待できる効果はないと思う。
「県教委は『倫理研修は繰り返し続けていくしかない。宿泊研修については、禁酒にするなど、対応を検討していきたい』としている。」こんなコメントするような県教委だから教員の不祥事が起きるのではないのか?根本の問題を見ていないのではないのか?
倫理研修後、個室侵入し女性教諭の体触り懲戒免 07/08/14 (読売新聞)
採用1年目の教員向け研修中に女性教諭の体を触るなどしたとして、静岡県教委は7日、県立特別支援学校の20歳代の男性教諭を懲戒免職処分とした。
今年度の懲戒処分は5件目。発表によると、男性教諭は5月30日未明、静岡県掛川市富部の県総合教育センターで宿泊研修中、女性教諭が寝ていた個室に侵入し、上半身を触るなどした。
男性教諭は今年度採用され、特別支援学校の小学部で担任を務めていた。女性教諭と所属校は異なるが、28日から2泊3日の日程で、同じグループで研修を受けていた。29日は午後5時に研修を終え、施設内の集会談話室で他の参加者も一緒に酒を飲んだ後、それぞれの宿泊室に戻ったという。男性教諭は県教委の聞き取り調査に対し、「トイレに行こうと起きあがり、衝動的に取ってしまった行動」と説明したという。
女性教諭が6月6日、所属校の教頭に相談し、学校が県教委に報告した。女性教諭が希望していないため、刑事手続きはとらないという。
男性教諭は宿泊研修の初日、倫理に関する研修も受けていた。
県教委は「倫理研修は繰り返し続けていくしかない。宿泊研修については、禁酒にするなど、対応を検討していきたい」としている。
男性教諭の氏名を公表しなかった理由については「被害者のプライバシーを守るため」と説明した。
アイディアとしては悪くない。しかし、絵に書いたモチだ。1年もインターンとして働いて教師になれなかった時のリスクがある。新卒採用が普通の日本で就職先を探すのは難しい。適性を判断する人の経験や洞察力に頼るしかない。チェックリストを作成したとしても、本当にチェックリストに基づいてチェックしないと形だけの適性となる。先生としての適性の基準を決めるのが難しい。試験だけではわからない経験や個性がどのように評価されるのか?また、学校が積極的であれば、学校や校長の方針でほしい教員が違ってくると思う。ほんとうに適性を判断する側に能力や経験があるのか疑問に思う。指導力やリーダーシップは個人の経験やスポーツなどで身に着く。勉強しかしていない、又は社交的でない教員候補は例え試験の成績が良くても簡単には実に付ける事は出来ない。採用されるために猫を被る人間もいるだろう。考えるほど簡単ではない。
教師の適性、1年かけて判断…現場研修後に免許 06/19/14 (読売新聞)
政府の教育再生実行会議(座長・鎌田薫早稲田大総長)が近くまとめる提言に、正式採用前に教員の適性を厳格に評価する「教師インターン制度(仮称)」導入の検討が盛り込まれることがわかった。
現在は大学卒業時に授与している教員免許を、1年程度の「インターン」期間中に適性を見極めた上で授与する仕組みについて、本格的な論議を求める。提言は来月上旬にも、安倍首相に提出される。
子どもが多かった1970年代~80年代に採用されたベテラン教員が退職期を迎え、各地の学校では経験の浅い若手教員が増加。指導力の向上が課題となっている。このため提言案では、正式採用前に教員としての適性を測る必要性を指摘している。
インターン制度では、大学卒業時に仮の教員免許を取得し、都道府県教育委員会に仮採用された人は、最低1年間学校現場で実習や研修を行った上で、教委などに評価を受ける。適性があると認められれば、教員免許を正式に授与され、正式採用される仕組みを検討する。
「米で学資ローン社会問題化…就職難」は少なくとも十何年前から存在する。以前よりも問題が悪化したのか?学生時代、大学を卒業したけど就職出来ないとか、大学卒業したけどレストランでウェイターやウェイトレスをしている話は良く聞いた。また、何年働こうが、給料がほとんど上がらない「Dead End Job(先のない仕事)」にうんざりしている話も良く聞いた。日本では最近「ブラック企業」と呼ばれる言葉が良く使われている。日本のブラック企業とは違うが、単純な仕事なので覚えてしまえば、難しくはない。問題は何年働いても給料が増えない。もっと給料をほしければ、大学や大学院に戻って学位を取得して、再就職するのが一般的な解決方法だった。しかし、働きながら夜間の授業を取るか、バイトをしながら大学に通う事になる。又は、お金を貯めておくか、ローンをするかに選択する事になる。
高校を卒業してローンで大学に進学する学生も多くいた。その割には将来就職に有利な専行をしない学生や、ローンしているくせに勉強をせず、パーティーに明けくれる生徒もいた。借金してまで大学に来ているのにと良く思ったものだ。人の人生だから自由な選択をして、その結果については自己責任らしい。専行を変えたり、大学を辞めていく生徒もいた。誰もそんなに驚かない。普通の出来事なのだろう。
思い出したが、クレジットカードを何十枚と作り、新しいカードで古いカードの支払いをしている奴がいた。日本人の彼女を作り、結婚して日本で英語を教えるとか言っていた。クレジットカードの支払いは、日本に行くので踏み倒すと言っていた。こんな奴から英語を習わないといけない日本人が哀れに思えた。今、奴はどこにいるのだろう。彼の知り合いは、世間知らずの日本人お嬢様と結婚した。英語だけを教えてもらえば良いのに結婚までとは。両親はどう思っていたのだろうか。大学に入学するために英語学校で勉強している時に結婚。人生、いろいろ。結果良ければ、すべて良し。
米で学資ローン社会問題化…就職難、若者返済できず 地方都市、支援で人材取り込み (1/3)
(2/3)
(3/3) 05/31/14(産経新聞)
【ニューヨーク=黒沢潤】大学の授業料が高額な米国で、学資ローンの返済滞納が社会問題化している。一方で、人口減少にあえぐ地方の自治体はローン返済を肩代わりして若く優秀な人材を次々と取り込む「ローン返済支援制度」を相次いで創設し、地域活性化につなげようとしている。
「僕は約8万ドル(約800万円)のローンを抱えている。『ニューヨーク大(NYU)卒』という学歴を手に入れたので就職できたが、そうでなかったら返済は大変だったろう」
ニューヨークのヤンキースタジアムで5月下旬に行われた同大の卒業式。エンジニアリング会社に就職が決まっているアレックス・アルメンダレスさん(22)がしみじみと語った。
米国の大学の授業料は高額なことで知られる。私立大は特に高く、2013~14年度の授業料や諸費用は年平均3万94ドル(約301万円)と約10年で倍増。充実した教授陣と施設を抱える名門ハーバード大やエール大では年間4万~6万ドル(400万~600万円)にもなる。
このため、年間約1200万人の若者らが大手金融機関などから借金し、大多数が負債を抱えて卒業する。1人当たりの平均ローン残高は約2万4千ドル(約240万円)。ところが、08年のリーマン・ショックによる景気後退を受け、就職できない若者らの返済滞納や債務不履行が続出し、13年には11・5%の若者がこうした「返済地獄」に陥った。
ニューヨーク連銀によれば、学資ローン残高の総額は1兆1千億ドル(約110兆円)以上に膨れ上がっている。延滞率の上昇で経済への悪影響も懸念され、消費者破産弁護士協会(NACBA)はこうした状況を「学生ローン爆弾」などと呼び、警戒を強めている。
■ ■ ■
自治体の中には、ローン返済にあえぐ若者を積極的に取り込む動きもある。
中部カンザス州は12年1月、州内の50郡に就職する若者に5年間、最大で1万5千ドル(約150万円)を提供する支援制度を創設した。35州の450人以上から申し込みがあり、優秀な数十人に資金を与えた。
東部のボストンカレッジ法科大学院を12年に卒業した後、同州ガーデンシティー(人口約2万6千人)に移り住んだコンピューター会社社員、モニカ・バルデスさん(27)も同制度を利用した一人だ。
ローン返済額は約5万ドル(約500万円)だったが、今では6千ドル(約60万円)まで減少。幼少のころシカゴなどで育った「都会っ子」で、「最初はこの町に慣れるのに戸惑った」と語るが、今では教会やジムで友人もでき、満足した日々を送っているという。
カンザス州では、50郡の人口が00~10年に1割も減少している。支援制度を通じて「優秀な若者を呼び込み経済振興を図るほか、家族らを呼び寄せてもらい人口増につなげたい」(州職員)ともくろんでいる。
■ ■ ■
同じような制度は、世界三大瀑布(ばくふ)の一つである「ナイアガラの滝」があるニューヨーク州ナイアガラ・フォールズ市にもある。
同市は昨年から年間約20人に対し、1人当たり最大7千ドル(約70万円)の支援を始めた。
世界有数の観光地とみられがちな同市だが、「世界中の観光客は実はこの町ではなく、滝の絶景が楽しめるカナダ側のナイアガラ・フォールズ市に殺到する。年々さびれるこちら側は、劣勢を盛り返すために支援制度を立ち上げた」(市職員)という。
同市によれば、10年時点の人口(5万106人)が20年に5万人を割り込んだ場合、連邦政府からの補助金を失う恐れがある。市の魅力を高め、人口を増やすことは最重要課題だ。
米国内ではこのほか、農業州の中西部ネブラスカ州など、過疎に直面する複数の州や市が同様の制度創設を検討しているという。
Listening:「仕事より家庭」は無責任か 息子の入学式出席の担任教諭 05/26/14 (毎日新聞)
埼玉県の県立高で4月、1年生を担任する女性教諭が入学式を欠席し、同じ日に別の高校であった息子の入学式に出席した。この事実が式典に参加した県議のフェイスブックや複数メディアで伝えられると、インターネット上で議論が沸騰。主な論点は「教師として無責任」か「教師も一人の親」か−−だが、二者択一で簡単に結論を出せるのか。子育てとの両立に悩みながら働く女性らは教諭に自らの姿を重ね、職場の理解が進まない現状を憂う。
関係者によると、女性教諭は高校受験でストレスを抱えていた一人息子が、高校生活を無事スタートできるか心配し、事前に校長に説明して休暇を認められていた。入学式当日、自らの生徒に欠席をわびる手紙も準備していたという。
「聖職」である以上、個人的理由の優先は許されないのか。同じ立場にある教師たちからは、同情する意見が聞かれる。
同県内の40代男性教諭は妻の出産前、病院から「不測の事態に備えて絶対に立ち会いを」と求められ、「職場の行事と重なったら」と悩んだ経験があるという。学齢期の子がいれば、学校行事への協力や部活動の送迎といった保護者同士の役割分担も必要だ。「近所や祖父母を頼れない家庭も多く、職場か家庭か日々迷いながら選択しているのは教師も他の職業も同じ」と訴える。
入学式の主役だったこの高校の新入生からも、女性教諭への理解を示す声が聞かれる。ある生徒は「自分が同じ立場なら子供の入学式に行きたい。教師も親だし」。別の生徒も「入学式は単なる儀式。担任が休んでも特に困らない」「どちらでもいい。(論争が)バカバカしく見える」と、ネット上の「熱さ」とは対照的な反応を見せた。
一方、今回の問題をフェイスブックで取り上げた江野幸一・同県議は「生徒は『これから担任に世話になる』という思いで入学式に来ている。担任は必ずいるべきだ」と力説。母子家庭に育ち、入学式に親が来た経験がないことから「(女性教諭が)過保護ではないかとの思いがあった」といい、「教師は親の他界などやむを得ない場合以外、職務に支障を来してはいけない」と指摘した。
「我が子の入学式と重なって欠席する場合、担任を外すべきだ」との意見もある。しかし、60歳超の再任用者が増える学校現場では担任の変更も容易ではない。
年金(報酬比例部分)の支給開始が段階的に65歳まで引き上げられるのを受け、教職員の新再任用制度が今年度スタート。各教委は再任用希望者を原則すべて採用することを義務付けられた。埼玉県教委によると、県立校の再任用教諭は教諭全体の1割近い824人(4月1日現在)で、前年度比176人の増となった。
再任用教諭の大半は短時間勤務を希望するため、多く受け入れる学校ほど担任のなり手がいない。ある県立高校長は「『この人が駄目ならあの人』と簡単にはいかないのが現実」と話す。
◇母親たち、常に選択迫られ
全国の多くの教育委員会は、次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と家庭を両立する「ワーク・ライフ・バランス(WLB)」の支援計画を策定している。
埼玉県教委の計画は「子どもの予防接種実施日や入学式、卒業式、授業参観日などの学校行事において、職員が休暇を取得しやすい職場の雰囲気づくり」を目標に明記。しかし、12年度調査で「子育てのための休暇が取りやすい」と答えた県立校の教職員は57%だった。
WLBに詳しい学習院大の脇坂明教授(経済学)は「昔はプロ野球の外国人選手がシーズン中に子育てのため帰国するとファンが憤慨したが、今は当然視している。WLBは時代や人によって受け止め方が変わるので、職場や顧客の信頼と理解を得る努力が重要」と指摘。今回の女性教諭のケースは「丁寧な対応だったのでは」とみる。
難しい選択を迫られるのは教師に限らない。「職場で『母親だから』は通用しない」と語るのは、東京の不動産会社に派遣社員として勤務する佐藤美穂子さん(34)=仮名=だ。夫(33)、長男(3)と3人暮らしだが、夫妻の実家はともに遠方で助けは望めない。
佐藤さんの勤務は週5日で午前9時〜午後5時。飲食店長の夫は立場上、休みを取りづらく、佐藤さんがほぼ1人で子育てを担う。勤務先はフレックスタイム導入などで子育て環境充実を図っているが「実際は『育児のため休みたい』とは言いにくい雰囲気がある」という。
保育園の遠足や保護者会など、事前に日程が分かれば調整しやすいが、最も困るのは子供の突然の発熱。同僚に次々と電話をかけて代理を必死に頼む。女性教諭を非難する声も多かった今回の論争はひとごととは思えず「とても切ない気持ちになった」と振り返る。【夫彰子、山寺香、奥山はるな】
………………………………………………………………………………………………………
◆論争の主な経過◆
4月 8日 埼玉の県立高校入学式を1年生担任の女性教諭が年次休暇(一般の有給休暇)で欠席。同日に別の高校であった息子の入学式に出席。
9日 入学式に参列した江野幸一県議が
フェイスブックに「私事の都合で簡単に職場を放棄する態度には憤りを感じざるを得ない」と記載。
12日 地元紙が報道。以降、各メディアで取り上げられ、Yahoo!ニュースは意識調査を開始。
14日 関根郁夫県教育長が記者会見で「保護者、生徒に不安を与えない対応が重要」との見解。欠席の是非については明言を避ける。
22日 Yahoo!ニュース調査終了。約35万票のうち「欠席は問題」が44.4%、「問題と思わない」が48.0%と拮抗(きっこう)。「どちらでもない」が7.6%。
採用されたばかりの新任教諭逮捕…酒気帯び容疑 05/19/14 (読売新聞)
宮城県警仙台中央署は18日、仙台市泉区、町立中学校男性教諭(22)を道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで現行犯逮捕した。
発表によると、教諭は18日午前1時20分頃、仙台市青葉区国分町の市道で、酒気帯び状態で乗用車を運転した疑い。教諭は信号のある交差点で出合い頭に同区の男性(39)の乗用車と衝突した。男性にけがはなかった。教諭は「飲んだ後に休んでいたから、酔いはさめたと思っていた」と供述している。
教諭は4月に教諭として採用された。
東大教授を解雇…受験の知人から祝儀受け取る 03/31/14 (読売新聞)
東京大学は31日、同大大学院入試を受験した知人から100万円を受け取ったとして、50歳代の男性教授を諭旨解雇の懲戒処分にしたと発表した。
3月28日付。教授は同大の調査に事実関係を認め、退職届を提出した。
発表によると、教授は2010年夏頃、教授就任の祝儀の名目で、大学院入試の受験を希望していた知人から100万円を受領。その後、教授の所属する研究科を受験する意向を伝えられたにもかかわらず、返還しなかった。さらに、翌11年秋の入試なら優遇できると受け取れる内容のメールを出すなどしたが、同年の入試の出願時期になると、「受け入れるのは難しい」などと態度を翻した。
教授は11年秋、口述試験で試験委員として質問し、採点に関わったが、知人は不合格となり、12年6月、学内のハラスメント防止委員会に訴えた。同大は「教授は入試で便宜を図っていない」などとして刑事告発は検討していないという。
個人的な憶測だが、本音が出たのでは??自殺問題に対して他人事と捉えていたら、自殺問題は早く片付いてほしいと思うに違いない。教育長であるがゆえに立場上、無視するわけにもいかない。はやく片付いてほしい。穏やかな日常に戻ってほしいと思ったのであろう。
教育長「片付くといい」 自殺小6女児の遺族抗議 03/01/14(朝日新聞)
いじめを受けていた長崎市立小6年の女児=当時(11)=が昨年7月に自殺を図り、その後死亡した問題で、同校の卒業式前に馬場豊子・長崎市教育長が「(問題が)片付くといい」と発言したことが23日、教育長への取材で分かった。遺族は「そんなふうに考えていたのかとショックを受けた」と述べ、文書で抗議した。
馬場教育長によると、田上富久市長の代理で19日の卒業式に出席した。式が始まる前、校長室で来賓から「(問題が)落ち着けばいい」と言われ、「片付くといい」と発言した。別の来賓から「今の言い方はあんまりでは」と指摘され、謝罪と撤回の意味を込めて「この言葉は良くなかった」と話した。
教育長は「丁寧に対応しなければならないとの意図で答えた。遺族の心情を傷つけたのなら申し訳ない」と釈明した。
教育委員会のメンバーの中には偽善者がいると思う事があるが、教育関係者の関与はおかしいと思う。暴力団との関係は教育関係者としては良くない。
名古屋の進学塾代表、山口組系風俗店に6億円融資 03/01/14(朝日新聞)
東海地方で私立小学校や進学塾を運営する名進研グループ(名古屋市)の豊川正弘代表(64)が2004年と05年、指定暴力団山口組弘道会の資金源とされる風俗店グループ側に3億円ずつ計6億円を融資していたことがわかった。風俗ビルの建設や賭けゴルフの借金返済に充てられたという。
豊川代表は朝日新聞の取材に融資の一部を認め、「小学校設立に出資を約束してくれたため、頼みごとを聞いた」と説明している。
名進研グループは、進学塾「名進研」40校を運営するほか、12年春には名進研小学校(同市守山区)を開校した。豊川代表は名進研を経営する「教育企画」社長で、小学校を運営する学校法人「名進研学園」の元理事長。
買春で懲戒免の教諭、免許「紛失」と次々教壇に 02/28/14(読売新聞)
昨年8月、教員免許が失効し、無免許で教壇に立っていた教育職員免許法違反の疑いで、2人の元教諭が埼玉、神奈川両県警にそれぞれ逮捕された。
いずれも採用時に未返納の教員免許状を悪用していたという。
文科省や各県教委などによると、埼玉県警に逮捕された50歳代の元教諭の男性は1985年、佐賀県教委から中、高教諭の免許状を授与された。福岡県内の市立中学校に勤務していた2005年、児童買春事件で懲戒免職となり、免許が失効した。
福岡県教委によると、男性は「紛失した」として免許状を返納せず、逮捕されるまでの間に、山口県内の私立高校や埼玉県内の市立中学校、群馬県の村立小学校などに無免許で勤務していた。
13年4月、埼玉県内の市立中に採用された際、住民の問い合わせで無免許が発覚したが、この時も免許状をすぐに返納せず、同年5月には群馬県の村立小に採用されていた。埼玉県教委は無免許が判明した時点で各都道府県教委に通知していたが、情報は生かされなかった。
性欲の問題と欲求を抑えられるかの問題だ。採用試験の結果だけではわからない事だし、面接で「性欲が強いですか」と質問をしたら、パワハラや個人のプライバシーに踏み込んでいると言われそうだ。不祥事の防止策としてそのような質問が出来たとしても、試験に受かりたい受験者が「性欲が強くて抑える自信がありません」なんて事は言うはずがない。
信頼される教職員となるように全力をあげるとはどのような事をおこなうことなのだろうか。オープンに問題を話し合える環境を整え、ロリコンの趣味があれば童顔の女性が働く風俗店を利用して何とか性欲を抑えろとかアドバスをするのだろうか。それとも不祥事を起こす前に、性欲が抑えられないのであれば教師そして公務員として働く事は難しい事を説得して転職を支援するのであろうか。公務員でなく教師でなければある程度の好みは許容範囲だと思う。ロリコンだから女子中学生に囲まれて人生を送りたいとの願望が無ければ、安定しているから公務員や教師になる選択を諦めるアドバイスを大学生時代にオリエンテーションか何かの機会で触れる事も考えた方が良いだろう。教師や公務員になってから不祥事を起こすと本人にも被害者にも良くない。ばかげた考えかもしれないが真剣に考えても良いかも??
男性教諭が児童買春で逮捕、臨時の校長会議 01/15/14(読売新聞)
女子児童に現金を支払って性行為をした疑いで富山市の中学校の男性教諭が逮捕された事件を受けて富山市教育委員会は、15日臨時の校長会議を開き、教職員の綱紀粛正を徹底するよう指導しました。
臨時の校長会議には富山市内の小中学校の校長や幼稚園の園長など102人が集まり、麻畠裕之教育長が「大人に対する不信感を抱かせる、絶対にあってはならない事件だ。信頼される教職員となるよう全力をあげて取り組んでもらいたい。」と呼びかけました。
この事件は、富山市立八尾中学校の教諭、寺尾真人容疑者(29)が去年8月、富山市でインターネットの出会い系サイトで知り合った県内の13歳未満の女子児童に現金3万円を支払い、性行為をした疑いで、今月11日に逮捕されたものです。
寺尾容疑者が勤務していた八尾中学校では14日からスクールカウンセラーを増員して、生徒個別の相談に応じています。
また寺尾容疑者の処分については県教育委員会が事実確認をしたうえで検討します。
大津いじめ自殺で確約書、市に30万円賠償命令 01/14/14(読売新聞)
いじめを受けた大津市立中学2年の男子生徒が自殺した問題を巡り、中学校から全校アンケート結果の内容を口外しないとの確約書をとられるなどして精神的苦痛を受けたとして、父親(48)が市に100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、大津地裁であった。長谷部幸弥裁判長は、市側の責任を認め、市に30万円の支払いを命じた。
訴状などによると、父親は生徒の自殺後間もない2011年10月下旬、学校から全校アンケート結果の資料を受け取る際、「個人情報が含まれるので部外秘にする」との確約書を求められた。父親は、確約書の存在が障害となり、自由な行動が制約されたと主張していた。
市側は父親の提訴後、「心情を損なったことをおわびする」とし、賠償責任は争わないとしていた。
父親らは市や加害者とされる元同級生らを相手取り、約7700万円の損害賠償を求める訴訟も大津地裁に起こしている。
自転車盗で懲戒免の女性教諭、それ以前も3回… 03/25/14(読売新聞)
群馬県教委は24日、前橋市立中学校の男性教諭(26)と、県立養護学校の女性教諭(60)を懲戒免職処分にした。
発表によると、男性教諭は2月1日午前6時45分頃、高崎市剣崎町の市道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、道交法違反(酒気帯び運転)容疑で高崎署に現行犯逮捕された。高崎区検は3月24日、同法違反で高崎簡裁に略式起訴した。
女性教諭は1月29日午後、高崎市内のスーパーの駐輪場で、他人の自転車を盗んだとして窃盗容疑で検挙され、高崎簡裁から罰金20万円の略式命令を受けた。県教委の調査で、2011年10月~13年7月、3回にわたって前橋市内で放置自転車を横領し、いずれも罰金の略式命令を受けたこともわかったという。
今年度に懲戒処分となった教職員は15人に上り、過去10年では最多。吉野勉教育長は「教育に対する期待を大きく裏切ることにつながり、深くおわびする」とコメントを出した。
児童の修学旅行費、部活動費…なんと校長が着服 12/26/13(読売新聞)
熊本県玉名、荒尾の両市教委は25日、合同で記者会見を開き、玉名市立小学校の男性校長(50歳代)と荒尾市立小学校の男性講師(30歳代)が、それぞれ学校の修学旅行費の積立金などを着服していたと発表した。
両市教委は窃盗や横領容疑で告発を検討している。
発表によると、校長は2009年3月から今年10月にかけ、教頭だった両市の小学校2校と、現在勤務している玉名市立小学校の計3校で、児童の修学旅行費の積立金や部活動費など計81万5000円を12回にわたって着服。個人の借金返済などに充てていた。
講師は9月から今月にかけ、休日に現在務める学校の職員室の書庫や同僚の引き出しから、児童の見学旅行費やPTAからの助成金など計33万円を7回にわたって抜き取るなどし、パチンコ代や生活費に使っていた。
両市教委は「教育界全体の信用を失墜し、誠に申し訳ない」と謝罪した。県教委は報告を受けており、2人の処分を検討している。
わいせつ行為が最多…昨年度懲戒免職の公立教員 12/18//13(読売新聞)
昨年度に懲戒免職になった全国の公立校教員は206人で、1961年度の調査開始以来最多だったことが17日、文部科学省のまとめで分かった。
訓告なども含む処分は1万827人で、前年度の2・5倍に増えた。このうち、体罰で処分を受けた教員は2253人で、前年度より1849人増えた。
同省によると、免職、停職、減給、戒告を含めた懲戒処分は968人(前年度860人)。免職は前年度より26人の増加。理由別で最も多かったのは、わいせつ行為の119人(同101人)。このほか、交通事故46人(同42人)、体罰3人(同0人)など。
体罰では、男子生徒が自殺した大阪市立桜宮高校で暴力行為を繰り返したバスケットボール部顧問の男性教員や、女子柔道部員に体罰を何度も加えた宮崎県の高校教員、特別支援学級の児童に体罰や嫌がらせを行った神戸市の小学校教員が免職。さらに、173人が停職、減給、戒告の懲戒処分を受けた。
女性音楽講師を校長が説得…免許無しで美術授業 12/18//13(読売新聞)
高知県内の町立中学校で、20歳代の女性音楽講師が男性校長(57)の指示を受けて今年4~6月、免許を持っていない美術の授業も担当し、町教委が7月に校長を文書で注意したことがわかった。
文部科学省によると、該当科目の免許を持たない教員が授業することは、都道府県教委が認めれば可能。
県教委によると、校長は3月、赴任のあいさつに来た講師に美術も担当するよう指示。講師は拒否したが校長に説得されたという。
同校の教頭は、美術の授業をすることが県教委に認められていた。県教委は、講師が教頭の授業計画に沿って授業し、教頭が補講を行ったことなどから、生徒の成績には影響がないと説明している。
文科省教職員課は「へき地などの小規模校では教員の確保が難しく、別の科目の教員が授業を担当する例はあるが、申請せずに授業すれば教育職員免許法に違反する」としている。
学校を水浸しに 店からレンズ盗む あきれた男性教諭2人懲戒免職 愛知県教委 12/17//13(産経新聞)
愛知県教育委員会は17日、窃盗の疑いで現行犯逮捕された東浦町立片葩小の滝沢太郎教諭(41)と、勤務する大府市立大府南中に侵入し、校内を水浸しにしたなどとして逮捕された吉川祐正教諭(27)を懲戒免職にした。
県教委によると、滝沢教諭は10月、名古屋市内の家電量販店でカメラレンズ2個を盗んだとして現行犯逮捕された。今月16日に名古屋地裁で懲役2年、執行猶予3年の判決を受けた。
吉川教諭は5~6月、大府市内の小中学校に複数回侵入。パソコンやファイルを校外に捨て、水道の蛇口を開け放して校内を水浸しにするなどして建造物侵入などの容疑で現行犯逮捕された。
また県教委は、8~9月、ソフトボール部の指導中に女子部員3人に平手打ちしたほか「死ね」などと暴言を浴びせたとして春日井市立中の男性教諭(26)を減給10分の1(1カ月)とした。
慶大准教授、児童ポルノ製造容疑 女生徒らホテルで撮影 12/10//13(朝日新聞)
女子中学生とのみだらな行為をデジタルカメラで撮影したなどとして、愛知県警は10日、慶応大学准教授で建築士の松原弘典容疑者(43)=東京都新宿区=を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)などの疑いで再逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
西署によると、松原容疑者は昨年11月4日、名古屋市中区のホテルで、当時中学1年だった女子生徒が18歳未満と知りながら、みだらな行為をし、デジタルカメラで撮影。また、今年4月には栃木県内のホテルで、中学3年の女子生徒に同様の行為をした疑いがある。女子生徒2人とはインターネットの掲示板で知り合ったという。
県警は11月19日、当時中学1年の女子生徒とみだらな行為をしたとして愛知県青少年保護育成条例違反の疑いで松原容疑者を逮捕。その際、家宅捜索で押収した大量のわいせつ画像を分析したところ、18歳未満とみられる女子生徒の画像が多数あったという。
松原容疑者は建築設計が専門で、中国やアフリカで多くの設計を手掛けている。慶応大学では2005年4月から准教授として勤務していた。
中学女子わいせつの慶大准教授、宇都宮でも 12/10//13(読売新聞)
名古屋市の女子中学生にわいせつ行為をしたとして逮捕された建築家で慶応大准教授の松原弘典容疑者(43)が、栃木県内の女子中学生にもみだらな行為をしたとして、愛知県警西署は、栃木県青少年健全育成条例違反と児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、10日午後にも再逮捕する。
同署によると、松原容疑者は4月5日、宇都宮市内のホテルで、インターネットの出会い系サイトで知り合った中学3年の女子生徒(当時14歳)にみだらな行為をし、動画を撮影した疑いなどが持たれている。
愛知県警は松原容疑者を、名古屋市の女子中学生(当時13歳)にわいせつ行為をしたとして11月に逮捕。自宅のパソコンから少女など約40人分のわいせつな画像や動画を押収した。県警は、松原容疑者が少女らにみだらな行為を繰り返していた疑いもあるとみて調べている。
松原弘典准教授逮捕 広がる衝撃と困惑......そのときSFCは 11/29//13(SFC CLIP)
11月20日(水)未明、複数のメディアによって松原弘典総合政策学部准教授(以下、松原准教授)が、愛知県青少年保護育成条例違反(淫行・わいせつ行為禁止)の疑いで、愛知県警西署に逮捕された。SFC CLIP編集部では、義塾の対応や今後の方針、ならびに学生の反応を聞いた。 逮捕までの経緯 メディア各社の報道によると、松原准教授は2012年11月4日(日)、愛知県名古屋市中区のホテルで、同市西区在住の女子中学生(当時13歳)が18歳未満であると知りながら、みだらな行為をした疑いがある。警察は現在、女子中学生と松原准教授の間に金銭のやりとりがあったとみて調査を進めているという。
SFC CLIPの調査では、逮捕が報道される前の11月18日(月)の夜には、捜査員とみられる集団とともに松原准教授がSFCのν棟(デザイン棟)にある松原弘典研究室に入っていくのを複数のSFC生が目撃していたことが分かった。
その日の2時限目には、松原准教授による授業「デザインスタディーズ」が開講予定であったが、予告なく突然休講になっていた。また、同日18:30から早稲田大学早稲田キャンパスの大隈記念講堂にて開催された「16th DOMANI・明日展プレイベント」にもパネリストとして参加予定であったが、「急病のため」という理由で欠席していた。
翌日、松原准教授は、11月19日(火)に愛知県警西署に逮捕され、本日11月29日(金)13:00現在、松原准教授は愛知県警西署に勾留されている状態だ。容疑の認否は留保しているという。
世界的建築学者として活躍していた経歴 松原准教授は70年生まれ。89年開成高等学校卒業後、東京芸術大学芸術学部建築科に進学。途中2度の世界旅行を経て25歳で卒業し、モスクワ建築大学研究生として1年間ロシアに渡った後、東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了。
卒業時の修士設計においては、有名建築家の原広司氏などに指導を受けて作品「全長4556mの住居」を発表し、優秀作品として顕彰された。
その後、伊東豊雄建築設計事務所に就職し「せんだいメディアテーク」等の実施設計を務め、01年から日本政府文化庁の派遣芸術家在外研修員として中国に渡り、北京大学で講師も務めている。
05年に個人事務所である北京松原弘典建築設計諮詢有限公司を設立、同時に総合政策学部に助教授として着任し、07年に同准教授となり、現職。11年には東京大学から博士学位(環境学)を授与されていた。
建築家としても活躍しており、北京を中心に世界各地で作品を残している。今年は研究室で設計した「コンゴ民主共和国日本文化センター」でグッドデザイン賞を受賞し、同時にベスト100作品に選出され、今月初頭に東京ミッドタウンでプレゼンテーションを行ったばかりであった。
海外にも及んだ逮捕の衝撃 松原准教授の逮捕については、北京でも波紋が広がっている。現地メディアは「对于松原弘典的被捕, 日本建筑学界相关人士惊讶万分, 身为那位泰斗的门生,竟然能犯下如此猥亵案件,简直是令人无法相信(編集部訳: 松原弘典の逮捕について、日本の建築学に関する人たちは驚いている。松原という高く評価される人がこのような性犯罪事件を犯すなんて、ただただ信じられない)」などと報じている。
広がる困惑、学生の声 報道各社によってこのニュースが明らかになったのが、SFC最大のイベントであるOpen Research Forum 2013(ORF2013)の2日前であったということもあり、SFC生の間では混乱が広がった。特に各社が一斉に報じた直後、SNS等には、学生たちによる疑問や怒りの声が多くみられた。
なお、ORF2013会場では、松原研究会で出展予定であったブース・展示物ともすべて別の教員名義に差し替えられており、セッションも松原准教授不在で進行した。
SFC CLIP編集部が、松原准教授の授業履修者に個別に話を聞いたところ、「事実なら残念」「信じられない」という声や、「社会的に許されないことなので、履修者に謝罪してほしい」「たった1人のせいで、大学全体が批判されて迷惑」などといった声も少なくなかった。
大学や各所の対応は? 今後の対応について、湘南藤沢事務室は「講義については、他の教員が受け持つなどの対応を含めて検討中」とし、その他のことは、事実調査中で未定の状態だとしている。
松原准教授は今年度、「グッドデザイン賞」を受賞している。同賞を主催する公益財団法人日本デザイン振興会事務局に、賞の取り下げなどを含めた何らかの対応を行うかを問い合わせたところ「現在は慶應義塾としての対応を問い合わせているところで、それが分かり次第検討する」とのことであった。
また、今月1日発売の雑誌「新建築」11月号にも、松原研究会の設計した建物が掲載されている。何らかの対応を行うか、 株式会社新建築社の新建築編集部に問い合わせたところ、「『新建築』11月号の発売時点では事件が発覚しておらず、発刊してから2週間以上経ってから発覚したことと、『新建築』は増刷しないことから、当該号に関する、ページの差し替えなどの対応は行わない方針」とのことであった。
本塾教員としてのみならず、建築家・建築学者としても活躍していた松原准教授の突然の逮捕に、現在もSFCでは波紋が広がっている。SFC CLIPでは、事実関係も含め、今後も調査を続けていく予定である。
女子中学生にみだらな行為の疑いで慶応大准教授を逮捕 名古屋市 11/20//13(FNNニュース)
慶応大学の准教授で建築家の男が、女子中学生にみだらな行為をしたとして、愛知県警に逮捕された。逮捕されたのは、東京・新宿区に住む建築家で慶応大学の准教授・松原弘典容疑者( 43 )。
松原容疑者は、2012 年 11 月、インターネットの掲示板で知り合った愛知・名古屋市西区の当時中学1年生の女子生徒( 13 )に、中区のホテルでみだらな行為をした疑いが持たれている。
2013 年 1 月ごろ、女子生徒の母親が携帯電話の使用料が増えていることに異変を感じ、事件が発覚し、メールの解析から、松原容疑者が浮上したという。
調べに対し松原容疑者は、「 その時は誰と会ったか、わからない 」と認否を留保しているが、自宅のパソコンなどには、ほかの女性と連絡をとった形跡があるということで、愛知県警は、余罪についても調べる方針。
都教委も仰天、AV女優だったエリート先生 (1/3)
(2/3)
(3/3) 12/08//13(産経新聞)
AV女優「真木麗子」は小学校の音楽教師だった-。無修正のアダルトビデオに出演したとして、東京都世田谷区の小学校に勤務する音楽科の女性講師(27)が逮捕され、教育関係者の間に衝撃が走り、インターネットでも一時“祭り”状態になった。面倒見のいい音楽の先生として生徒から慕われる一方、2つの名前を使い分けてAV作品に出演。名門・東京芸術大音楽学部を卒業した音楽界のエリートの素顔とは-。
■テレビ出演、オペラ歌手、華やかな経歴の裏で
女性講師は先月30日、無修整であることを知った上でわいせつ動画に出演したとして、わいせつ電磁的記録記録媒体頒布幇助(ほうじょ)の疑いで、静岡県警に逮捕された。
関係者や勤務先の音楽教室のプロフィルなどによると、女性講師は横浜市在住で、幼い頃から児童合唱団に所属し、テレビやラジオへの出演や、ソプラノのオペラ歌手など広い分野で活躍、AV女優のイメージとはほど遠い華やかな経歴。現在は、非常勤講師として、世田谷区内の複数の小学校で音楽の授業を受け持っているという。
都教育委員会によると、女性講師の勤務態度は良く「教育熱心で、生徒一人一人に個別指導を行うなど丁寧に授業をしていた。コミュニケーション能力も高く、周りの教員とも仲良くやっていた」と周囲の評価も上々だったという。都教委は「普通、こういう場合は事前に警察から連絡が入るものだが、今回は報道を見て初めて知ったのでびっくり仰天だった」と驚きを隠さない。
■低額出演料の“その他”女優
捜査関係者によると、女性講師は、中堅のAVプロダクションに所属。「純野静流」名で“表”のAV作品に出演する一方、有料の会員制無修整動画サイト「人妻斬り」に「真木麗子」として出演し、動画がインターネット配信されていたという。同サイトには、サンプル動画や裸の写真が掲載されており、「真木麗子」については「白い美肌とボリューミーなカラダつきがセクシーな若妻」と紹介されていた。
AV業界の事情に詳しい関係者の話によると、出演料の相場は、人気女優の場合で1本100万~200万、その他の女優は一本わずか3~5万円ほどで、「男優と同じくらいの出演料。お小遣い程度だ」と話す。女性講師も“その他”に含まれていたとみられ、これまでに複数の作品に出演していたとみられる。
そもそもなぜ県警は逮捕に踏み切ったのか。捜査関係者の話によると、県内で今年1月ごろ、無修正DVDと知らずに出演させられた20代女性が被害を訴えたのがきっかけ。県警では、女性への聞き取りなどからAV制作者を割り出した。その後、内偵捜査を続け、都内の喫茶店で女性講師が「無修整でインターネットに流れる」との一文が入った同意書にサインするのを確認。10月に制作者を逮捕し、動画と同意書の両方を抑えたことから女性講師の逮捕に踏み切ったという。
■生活苦か、ストレスか
AV出演の動機については、現在も取り調べ中で詳しいことは分かっていない。ある県警幹部は「カネか男のどちらからだろう。人間の欲望は無限大。好奇心で始めたのかもしれない」と話す。都内の小学校に務める男性教諭(34)は、「非常勤講師の給料は、20万円いけばいい方。生活苦か、それとも学校は閉ざされた社会なのでストレスがたまっていたのでは」と推測している。
ネット上では、小学校講師のAV出演で“祭り”状態に。「AVに芸術性を感じたのでは」、「音楽講師だけじゃ食えないんだろう。水商売というのはよくある話」などさまざまな憶測が飛んでいる。
都教委職員課は今回のAV騒動を受け「本人から事実関係を聞いた上で、出演が事実であれば厳正に対処する」とコメント。女性講師が勤めていた学校側は「コメントは一切差し控える」と沈黙を貫くが、近く保護者会を開き事情を説明をする予定だという。
現在、県内で勾留中の女性講師は容疑について「間違いありません」と認めている。取り調べに対しては、取り乱す様子もなく淡々と答えているというが、その胸中にはどんな思いがあるのだろうか。
「誤答を正答とし、点数を上乗せしていた。男性教諭は『頑張っている生徒の姿を見て情がわいた』と事実を認めているという。」
個人的な価値観や考え方があるので絶対に間違いとは言えない。しかし「情がわいた」から「誤答を正答とし、点数を上乗せしていた。」は間違っていると思う。
生徒が頑張っているとの判断で点数を上乗せしたのであれば、頑張っている度合いの評価で公平に評価出来たのか?学校以外や教諭が見ていないところで頑張った生徒の評価はどうなるのか?問題点が存在する。
頑張っても結果として表れなくても努力の継続の大切さを説明するべきだった。頑張っても結果としてなぜ表れなかったのか分析して個々の生徒に対する教え方や勉強法を考えるべきだった。残念ながら個人の能力には差があることを説明して、一層の努力によって結果は向上できる事を教えるべきであった。スポーツの世界が良い例だ。みんな、同じように努力しても同じ結果ではない。一位は一人だけ。
世の中は厳しい。生徒が世の中で生きていけるように教えるべきだ。
「頑張る姿に情が…」教諭が答案改ざん、正答に 11/20//13(読売新聞)
岐阜県各務原市立蘇原中学校で、2年生の数学を担当する男性教諭(29)が中間テストの生徒43人の答案を改ざんしていたことが20日わかった。
誤答を正答とし、点数を上乗せしていた。男性教諭は「頑張っている生徒の姿を見て情がわいた」と事実を認めているという。
同校によると、男性教諭は15日に行われた後期中間テストの5クラス178人の答案を自宅で採点。うち3クラス43人の答案の一部を書き換えるなどして2~10点かさ上げしていた。生徒が消しゴムで消していなければ正答だったはずの「惜しい解答」に正答を書き加えていたという。
返却された答案に疑問を感じた一部生徒が申し出て発覚。同校は19日に臨時の全校集会を行って生徒全員に謝罪した。県教委は男性教諭の処分を検討している。
道徳を教科化することには個人的には反対であるが、教科になった場合、教師の不祥事対しては今まで以上に厳しく処分する必要があると思う。
道徳を教える教諭が道徳の道から外れる事をするのはおかしいからである。厳しく処分する事によりどのような結果をもたらすのか示すべきであると思うからである。
スピード違反で検挙3回、女性教諭を戒告処分 11/19//13(読売新聞)
岩手県教育委員会は18日、9~10月に酒気帯び運転で運転免許を取り消された後、道交法違反(無免許運転)容疑で検挙されたとして、大船渡市立中の男性教諭(47)を懲戒免職処分にした。
また、同法違反(速度超過)容疑で検挙されながら報告を怠るなどしたとして、一関地区の小学校の女性教諭(49)を戒告処分にした。
県教委によると、男性教諭は9月5日、大船渡市内の市道を酒気を帯びた状態で運転、一時停止の標識で停止せず、同法違反(酒気帯び運転と一時不停止)容疑で検挙された。
運転免許は返納されたが、同教諭は10月23日に同市の国道を無免許運転し、再び検挙された。同教諭は、県教委の調査に対し、「今まで教えてきた生徒、卒業生や家族との信頼に傷をつけて申し訳ない」と謝罪の言葉を語っているという。
女性教諭は2005年9月、09年12月、12年7月の3回、釜石市や一関市内で同法違反(速度超過)容疑で検挙されたにもかかわらず、校長への報告を怠ったり、面談の際にうその報告を行ったりしていた。
今年7月下旬、女性教諭が校長と面談した際、所持していた運転免許証が「優良運転者」に交付されるゴールド免許ではなかったことから発覚した。
本当のクレームと金目当てのクレームは違うだろ!現金脅し取った両親が実刑を受けても仕方がない。
子ども叱った校長から現金脅し取った両親に実刑 11/10//13(読売新聞)
子どもが通う小学校で指導に言いがかりをつけ、校長から現金を脅し取ったとして、恐喝罪に問われた高松市の無職の男(49)と妻(36)に対する判決が8日、地裁であった。
片岡理知裁判官は「学校内での教育は教員の創意工夫に委ねられるべきで、親は一致協力すべきだ」などとして、男に懲役2年4月(求刑・懲役3年6月)、妻に同2年8月(求刑・同)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、2人は7月9日、高松市内の小学校で、前日に子どもを叱責した校長に対し「教育委員会やマスコミに言っていいんか」などと脅し、8万円を脅し取った。
片岡裁判官は「保護者に対して慎重な対応を求められる校長の立場につけ込んだ犯行」と指摘した。
女性教師の指導記録、コンビニで捨てた同僚教諭 11/09//13(読売新聞)
大分県教委は8日、同僚のパソコンなどを盗んだとして窃盗罪で罰金50万円の略式命令を受けた中津北高の黒田修司教諭(44)を同日付で懲戒免職にしたと発表した。
発表によると、黒田教諭は7月31日と8月4日、職員室などで20歳代の女性臨時講師の携帯電話や、貸与されていたノート型パソコンを盗んだ。県教委に対し、7月31日には女性の机の引き出しから生徒の出欠状況などを記した指導記録も盗み、翌日早朝、コンビニのごみ箱に捨てたと説明。指導記録は見つかっていない。
黒田教諭は「自分のことをどう思っているのか知りたかったし、困らせたかった」と話しているという。
前の盗み「無職」と偽った女教諭、今回は懲戒免 10/25//13(読売新聞)
埼玉県教委は24日、同県上尾市立中学校の女性教諭(49)を懲戒免職にした。
県教育局小中学校人事課によると、同教諭は9月21日午後2時15分頃、同市内のスーパーでおにぎりや果物など食料品18点(売価約4000円相当)を盗んだとしている。教諭は県警上尾署に現行犯逮捕され、大宮区検が10月22日、窃盗罪で大宮簡裁に略式起訴した。
県教委によると、教諭は昨年12月にも同県北本市内の書店で本を盗み、鴻巣署が書類送検したという。このときは起訴猶予になったが、同署などの取り調べで「無職」と偽り、当時勤めていた別の中学校の校長にも報告していなかった。
教諭は中学校の3年生の担任で、数学を教えていた。県教委の聞き取り調査で「ほかにも万引きをやった。生活に対する不安があった」と話しているという。
客の女性は知り合いだったのか、それとも面識があったのか?面識がない女性にそのような行為をしたのであれば解雇で良いのではないのか?外国の先進国だったら処分されて当然だから!本人も知っているはずだ!
外国語指導助手、店で女性の腰など触った疑い 09/02//13(読売新聞)
長崎県警佐世保署は1日、佐世保市高梨町、高校外国語指導助手(ALT)ガラス・リチャード・マックナーマラ容疑者(33)(アイルランド籍)を県迷惑行為等防止条例違反(卑わいな言動)容疑で現行犯逮捕した。
発表によると、8月31日深夜、同市栄町の飲食店で、客の女性(24)の腰や太ももなどを触った疑い。容疑を認めているという。県教委によると、マックナーマラ容疑者は7月29日に任用された。
どのような理由で留学生にホステスの仕事をあっせんしたのか書かれていないが、
国立大学(岩手大学ホームページ)の教授なのだから違法な事は控えるべきだ。留学生が金銭面で苦労して勝手に違法に働くのは、監督責任があるかもしれないが留学生のリスクだと思う。しかし教授から違法な仕事のあっせんは非常識すぎると思う。国立大学なのだから私立大学以上に違法であるかどうかについて判断するべきだったと思う。
教授、ロシア人留学生にホステスの仕事あっせん 08/26//13(読売新聞)
岩手県警は26日、女子留学生にホステスの仕事をあっせんしていたとして、
岩手大(岩手大学ホームページ)
の男性教授(59)を入管難民法違反(不法就労助長)容疑で盛岡地検に書類送検した。
同大も今後、処分を検討する。
発表によると、教授は昨年10月26日と今年2月9日、盛岡市内の喫茶店や国際交流イベントの会場で、スナックの経営者らに対し、就労資格がない同大の中国人1人、ロシア人3人の計4人の女子留学生をホステスとして紹介し、不法就労をあっせんした疑い。
教授は読売新聞の取材に対し、「一切説明できない」としている。
岩手大によると、教授は2004年4月から、外国人留学生の受け入れなどを行う同大国際交流センターに勤務している。
インターネットで検索するだけで、
「教職員の懲戒処分について 教諭・佐藤 美和・43歳・女性(埼玉県ホームページ)」
を簡単に見つける事が出来る。相模原市教育委員会及び相模原市は採用に関して適切なチェックを行っていなかったことは明白だ。
「教員免許の失効情報は全国の都道府県教委が通達を出して共有されている」
相模原市では誰も採用に関してチェックやダブルチェックはないと言う事なのか?担当者だけでなく、上司も一切何も質問もチェックもしなかったと言う事なのだろう。
公務員試験に合格して採用されれば、簡単には首にならないので仕事はルーズと言う事なのだろうか?
教員免許失効隠し小学校に勤務…44歳女を逮捕 08/26//13(読売新聞)
教員免許が失効しているのを隠して相模原市内の小学校に勤務したとして、神奈川県警相模原署は26日、同市緑区橋本、無職佐藤美和容疑者(44)を教育職員免許法違反容疑で逮捕した。
教員免許の失効情報は全国の都道府県教委が通達を出して共有されているが、同市は採用する際に確認していなかった。
発表によると、佐藤容疑者は4月1日から7月10日まで、教員免許がないにもかかわらず、同市南区の市立小学校で4年生の担任として勤務した疑い。
市教委によると、佐藤容疑者は2008年3月、福島県教委から、適性を欠くなどとして解雇する分限免職処分を受けた。この処分歴を隠して昨年4月に埼玉県教委の正規教員として採用されたが発覚し、同10月に懲戒免職となり、同時に教員免許が失効した。
埼玉県教委は、教員を採用する際、他の自治体で勤務歴があった場合に在職証明を出させているが、退職理由の記載を義務付けておらず分限免職処分となっていたことが把握できなかった。
相模原市教委に対しては、福島、埼玉両県教委での処分歴を隠し、教員免許状を提出して採用されていた。
文部科学省の責任でするべきだ。
「教員免許失効」データベース化 08/21//13(読売新聞)
教員免許が失効していた男が片品村や埼玉県で教員として働いていたとされる事件で、群馬県教委は20日、採用時の再発防止策として、全国の教員免許の失効情報をデータベース化する考えを明らかにした。
2005年度以降に各都道府県教委などが処分した約1500人分を対象とし、実際の採用業務にあたる教育事務所などと共有する。
吉野勉教育長は、20日の記者会見で「データベースの構築が、失効者(の採用)を防ぐには一番」などと述べた。事件では、埼玉県警が今月、教員免許の失効を隠し、同県秩父市内の中学校に勤務していたとして、片品村立北小で臨時教員をしていた古畑正仁容疑者(53)を教育職員免許法違反容疑で逮捕。古畑容疑者は、返納前の教員免許を群馬県教委に示し、5月から同小に勤務していた。
吉野教育長は「県民、保護者、子どもたちに申し訳ない事務作業をしてしまった」とも述べ、今後、埼玉県警などの捜査状況をみながら、採用担当者らの処分も検討する考えを示した。
埼玉県教委は採用前にしっかりとチェックするべきだった!対応が甘い!教師不祥事列伝の情報が正しいのであれば、教員免許が失効していながら他の学校でも働いていた。悪質だ。なぜこのような不正が簡単にできるのか??
教育委員会そして文部科学省は採用前に教員免状が失効していないか簡単に確認できるようなシステムを確立するべきだ。
執行猶予中だったから実刑確定だろう!
無免許で数学教え 53歳臨時教員逮捕、失効隠し 08/01/13 (毎日新聞)
教員免許が失効していることを隠して埼玉県秩父市の中学校で勤務したとして、埼玉県警は1日、教育職員免許法違反(無免許)の疑いで、群馬県片品村、公務員、古畑正仁容疑者(53)を逮捕した。
古畑容疑者は4月に失効が発覚し失職していたが、逮捕されるまでの間にも、無免許の状態で群馬県の村立片品北小で臨時教員として勤務していたという。
逮捕容疑は4月5日~12日までの間、無免許で、同県秩父市の市立影森中学校で臨時教員として数学の授業をした疑い。
県警によると、インターネットで古畑容疑者の名前を調べた保護者が「過去に有罪判決を受け失効しているのでは」と学校側に連絡し、無免許が発覚。4月中旬に埼玉県教委が採用を取り消し、刑事告発していた。
校長室に忍び込み、3万円盗んだ小学校臨時教諭 08/23/13 (読売新聞)
夏休み中の小学校の校長室に忍び込み、財布から3万円を盗んだとして、広島県警福山東署は22日、福山市の市立小臨時教諭の橋本航容疑者(25)を窃盗の容疑で逮捕した。
「遊ぶ金がほしかった」と容疑を認めているという。
発表によると、橋本容疑者は8日午前9時頃、校長室に入り、机の引き出しに入っていた川崎行輝校長(56)の財布から3万円を盗んだ疑い。現金がなくなっていることに気づいた川崎校長が20日に被害届を同署に提出。同僚らからの事情聴取で橋本容疑者の犯行が明らかになった。
事件当時、教職員が手分けして校内の清掃をしていた。校長室の机の引き出しはかぎがかかっていなかった。市教委によると、橋本容疑者は昨年9月14日に任用され、2年生のクラスを担当していた。
教職員の虚偽の事務処理372件、校長の指示で 08/23/13 (読売新聞)
大阪府高槻市立樫田小(同市田能)で2011、12年度、教職員12人が自家用車を使いながら、バスや電車などの公共交通機関で出張したとする虚偽の事務処理を372件繰り返していたことが、同市教委などへの取材でわかった。
出張の規定をよく理解できていなかった校長が、誤った指示を続けていたという。
同市教委などによると、正当な理由があれば、自家用車による出張は認められる。しかし、当時の校長は「どんな場合も車の出張は許されない」と誤解、教職員に「出張の際はすべてバスや電車で行ったように申請を」と指示していた。
交通の便が悪いため、同校は自家用車で出張申請しても認められる学校だった。372件のうち、自家用車の走行距離に応じて支給されたはずの旅費は、公共交通機関より高額になるケースが大半だったという。当時の校長は、12年度末で退職している。
同市教委は「虚偽の出張や旅費を余分に受け取るための行為ではなかったが、不適切だった」とし、各市立小中に実態に合わせた出張申請をするよう指導したという。
「福島・前教育長は取材に『全教育委員に諮らなければならない事例とは思わなかった。・・・』」とコメントしている。学校教育に長い間関わっているのに
会議もなし、報告もなしで決めたと言うのはおかしい。
島根には
島根原子力発電所(ウィキペディア)がある。広島みたいに極端に「核兵器反対や平和」と言わなくても良いが、原発や放射能のリスクだけは理解させる必要はあると思う。福島のようになってからでは遅い。
事実や現実から目を背けるのではなく、どのように問題を解決するのか、また、問題を防ぐ事が出来るのかを教える事が教育だと思う。ゆとり教育の失敗は現実や現場を理解しない高学歴のキャリア達に原因があったと思う。
聖心女子大学2年の益野友利香さんが学生団体アイセックのインターン先のルーマニアのブカレスト郊外でレイプされ殺害された事件は海外には日本の常識では対応できない国や現実があることを日本で学ぶ機会がなかった事と不運によるものだと思う。
過保護に子供達を育てるだけでは問題は解決しない。留学する生徒が減ってきている原因の1つはここにあると思っている。比較的に守られている環境で育った子供達が異文化の国で生活したいと思うのか。自己主張をしないと助けてくれない国に行きたいと思うのか?ハングリー精神を持った外国の子供達と競争出来るのか?同じ能力や資本力では負けてしまうと思う。困難を乗り越える事を経験した子供達に勝てるわけがない。
最後に人はそれぞれで考え方も違うが、自己主張(作品)や選択の自由を奪う判断が福島・前教育長と副教育長2人、市教委の課長2人の計5人で決定された事は驚いた。民主主義を理解していない市教育委員会が存在し、その一つが松江市教委だったと言う事であろう。
島根原子力発電所(ウィキペディア)のメリット及びデメリットについて学校で話し合う機会は与えているのであろうか?そのような機会がないのであれば情報操作された環境で子供達は育てられていると言って間違いない。

福島律子教育長さん(ギャラリーC 松江市宍道ふれあい交流館)
「はだしのゲン」を禁止本に指定した松江市教育委員会(福島律子教育長)の超非常識? 08/17/13 (タイムスタンプ「忘れな草」 )
はだしのゲン:閲覧制限 前教育長、教育委員に諮らず決定 08/20/13 (毎日新聞)
松江市教委が故中沢啓治さんが自らの被爆体験を基に描いた漫画「はだしのゲン」の閲覧制限を全小中学校に求めている問題で、当時の福島律子教育長が自身を含めた教育委員(5人)の会議に諮ることなく判断したことが19日、分かった。同市教委は22日の定例会議で委員に説明するが、委員から「少なくとも(委員に)報告するべきだった」との声があがっている。同市教委には19日夕までに1253件の意見がメールや電話などで寄せられ、9割が批判する内容だったという。
古川康徳・副教育長によると、昨年8月に学校図書室からゲンの撤去を求める陳情が同市議会に提出され、当時の前教育長と副教育長2人、同市教委の課長2人の計5人で対応を協議。旧日本軍がアジアの人々の首を切ったり、女性に乱暴するシーンなどを問題視し、12月の校長会で教師の許可なく閲覧できない閉架にするよう口頭で求めた。教育委員に説明しなかったという。
ある委員は「教育委員に報告するなり、会議にかけて決定する話だと思う」。別の委員も「これだけ全国的にも話題になっている。もう1回話し合う必要がある」と批判した。
福島・前教育長は取材に「全教育委員に諮らなければならない事例とは思わなかった。反省している。私も全巻を読んで性描写のショックが大きく、簡単に子供が閲覧できる状況にしてほしくなかった。作品を否定するつもりはなく、見せ方を工夫してほしいというつもりだった」との見解を示した。
一方、同市教委には19日夕までに全国からメールで979件、電話で205件などの意見が寄せられた。9割は苦情や抗議といい、子供の知る権利や表現の自由などを求める声が多かったという。【曽根田和久、金志尚】
松江市 (松江市ホームページ)は「はだしのゲン:閲覧制限」に関して市教委独自の判断が可能であったのか、それとも市教委による不適切な対応だったのか公表するべきだ。もし不適切であったら当時の前教育長と副教育長2人、同市教委の課長2人の計5人の処分を検討し、公表するべきだ。
「はだしのゲン」閲覧制限を再検討=撤回を視野-松江市教委 08/20/13 (時事通信)
2012年12月に死去した漫画家中沢啓治さんが自身の被爆体験を基にした漫画「はだしのゲン」について、松江市教育委員会が同月、市内の小中学校に閲覧制限を要請していたが、要請の撤回を視野に再検討する方針を決めたことが、20日までに分かった。
市教委などによると12年8月、「はだしのゲンは間違った歴史認識を植え付ける」として学校図書館からの撤去を求める市民からの陳情が市議会にあったが、市議会は同年12月に全会一致で陳情を不採択としていた。
しかし市教委は、作中にある女性への暴行場面や人の首を切る描写を問題視。同月中に市内の全小中学校に対し、作品を図書館の倉庫などにしまい、子どもから要望がない限りは自由に閲覧できない「閉架」措置とするよう要請した。要請は市の教育委員会会議で議論されずに、市教委の独断で2度にわたり行われていた。
清水伸夫松江市教育長は20日までの取材に、「手続き的にどうだったか調査する必要がある」と要請に至った過程の問題点を指摘。また、議会が陳情を不採択としたことや、市内外から反発の声が多数寄せられていることを受け、「今後は撤回も視野に、委員会会議の意見を聴いて再度検討したい」と話した。
22日には同会議が開かれ、閲覧制限が議題として取り上げられる予定。清水教育長は、「遅くとも月内に一定の結論を示したい」としている。
さすが韓国に不法占拠されている
竹島(ウィキペディア)
がある島根県の珍騒動だ。竹島が島根県にあり、日本の領土であるならなぜ韓国軍が駐留しているのか?
松江市教委事務局、独断で要請 「はだしのゲン」閲覧制限 08/20/13 (中国新聞)
松江市教委が、図書館を持つ市内の小中学校49校に要請した漫画「はだしのゲン」の閲覧制限。市教委事務局が幅広い意見聴取をせず、独断で学校現場へ閲覧制限を要請した経緯が19日、関係者の証言で浮き彫りになった。
「(制限は)市教委事務局の判断で構わないと考えたが、教育委員会議に諮るべきだった」。昨年12月に閲覧制限を決めた当時教育長だった福島律子・松江市総合文化センター館長は対応の不備を認めた。
学校図書館から「ゲン」の撤去を求める市民の陳情が市議会に提出された同8月以降、教育長たち幹部が協議。有識者の意見や他市の対応から「撤去は不適当」としたが、本棚から書庫に移す「閉架」や貸し出し制限を各校に求める対応は、内部協議だけで決めていた。
戦場で首を切ったり、女性に性的暴行を加えたり…。市教委は「暴力的な描写」を問題視する。古川康徳副教育長は「表現の自由よりも、子どもへの悪影響を防ぎたい思いが強かった。行き過ぎた制限とは考えなかったが、慎重さを欠いていた」と振り返る。
市教委から同11月、図書撤去の是非を尋ねられた島根県立大短期大学部(松江市)の石井大輔講師(図書館情報学)は「行政が『図書の表現に問題がある』と考える場合、可能なのは問題提起まで。今回の市教委の対応は、図書館運営への介入と受け取られても仕方がない」と指摘。「閲覧制限の可否は図書館が独自に決めるべき問題」と強調した。
市教委が「暴力的描写の悪影響」を懸念する一方、陳情者は別の観点から「ゲン」の記述を批判していた。陳情は「ありもしない日本軍の蛮行」「国歌に対しての間違った解釈」を指摘。「間違った歴史認識を植え付ける」と訴えた。
市議会は同12月、陳情を全会一致で不採択とした。だが、議長経験もあるベテラン議員の一人は「歴史上の事実関係に見解が分かれる内容や、天皇制批判の記述もある。妥当な対応だった」と閲覧制限を支持する。
著作の歴史観を問題視する陳情者や市議への配慮があったのではないか―。この疑問に、福島前教育長は「そうした主張に加担するつもりはない。市議との接触もなく、市教委独自の判断だ」と明確に否定した。
日本はいつも極端だ。まあ、これまでの経緯や過去については記事になっていないから何とも言えないが、これぐらいで退職なのか?
年齢的に退職しても退職金も対して変わらないし、校内にナイフを持ち込んで他の児童を脅した児童を頭をたたいたことで処分する学校組織に嫌気がさして辞めたのかもしれない。まあ、あまり規則で固めると複雑になって逆効果もあるし、不祥事を起こす教諭も増えているので、難しいところだ。
ナイフで脅した小6の頭叩いた校長処分…退職 08/01/13 (読売新聞)
大阪市教委は31日、児童7人の頭を手でたたいたとして、同市都島区内の市立小学校の校長(62)を25日付で戒告の懲戒処分にしたと発表した。
校長は「指導のつもりだった。深く反省している」として、31日付で依願退職した。
市教委によると、校長は5月、6年男子児童が校内にナイフを持ち込んで他の児童を脅し、一緒にいた同級生6人も先生らに知らせなかったことを知り、7人を別室に呼び出して頭を1発ずつたたいた。7人にけがはなかったが、市教委は「市立桜宮高の体罰自殺問題を受けて、暴力に頼らない指導を目指す中、管理職が手を上げた責任は重い」として懲戒処分とした。
女性養護教諭、生徒のカバンから現金を窃盗 08/01/13 (SANSPO.COM)
沖縄県石垣市の県立八重山高校で、30代の女性養護教諭が今年5月、体調不良で保健室で休んでいた生徒のカバンから現金1万5000円を盗んだことが30日までに分かった。
同校では他に6件の窃盗被害の報告があり、女性教諭が教室で生徒の持ち物を物色していたとの情報が一部の生徒から寄せられているため、八重山署に被害届を提出する準備を進めている。
同校によると、窃盗被害は5月31日から7月10日までに計7件発生し、被害総額は約5万1000円。保健室以外は、すべて教室に置いていた財布から現金が抜き取られていた。
女性教諭については、教室などで不審な行動がたびたび目撃されていた。生徒の間では窃盗していると噂になっており、女性教諭が生徒の持ち物を物色している様子を、ある生徒が動画撮影したという。
この映像を学校側が確認し、女性教諭に事情を聴いたところ、保健室での窃盗を認め、生徒に謝罪したうえで1万5000円を返金した。しかし、他の6件に関しては「自分は関係していない」と関与を否定しているという。
現在教諭は自宅謹慎中。今後、沖縄県教委が処分を決定する。本成浩校長は「信頼回復と、生徒の心のケアに当たりたい」と話した。
教諭、女子部員2人と同時交際・わいせつ行為も 07/26/13 (読売新聞)
埼玉県教委は25日、教え子の女子高校生にわいせつ行為をしたとして、県南部の県立高校の男性教諭(31)を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。
県教委によると、教諭は2011年12月~12年2月、複数回にわたり、顧問を務める部活の部員だった、当時高校3年の女子生徒に対し、乗用車内でキスをしたり、胸を触ったりした。
また、12年3~12月、同部員の別の女子生徒と自宅で3回性行為をした。
今年6月、同時に教諭と交際をしていることに気付いた2人が保護者とともに高校に申し出て発覚した。
教諭は県教委に対し、「同時に2人の元生徒を傷つけたという許されがたい行為をした。生徒、保護者に大変申し訳ない」と話しているという。
教職員の懲戒処分について 07/25/13 (埼玉県ホームページ)
1 処分内容 懲戒処分(免職)
2 処分年月日 平成25年7月25日
3 職名・年齢・性別 教諭・31歳・男性
4 地域・校種 南部地区・県立高校
5 発生年月日 平成23年12月下旬から平成24年12月24日までの間
6 事件・事故の概要
当該教諭は、当時所属校に在籍していた女子生徒に対して、平成23年12月下旬から平成24年2月頃までの間、同教諭所有の普通乗用自動車内において、複数回にわたり、唇にキスをし、胸を触るなどした。
また、当時在籍していた別の女子生徒に対して、平成24年3月上旬から平成24年12月24日(月)までの間、同教諭の自宅において、3回にわたり性行為を行った。
詐取した研究費、親族経営会社に移動か 07/26/13 (産経新聞)
東京大学などから研究費をだましとったとして詐欺容疑で逮捕された同大政策ビジョン研究センター、秋山昌範容疑者(55)が、詐取金を親族が経営する会社に移していたことが26日、関係者への取材で分かった。秋山容疑者は容疑を否認しているもようで、東京地検特捜部は詳しい動機について捜査を進める。
調べによると、秋山容疑者は、IT関連業者6社と共謀し、研究事業に使うデータベース作成を業者に発注したように装うなどして、東大と岡山大学に虚偽の納品書や請求書を提出。約2180万円を詐取した疑いが持たれている。
関係者によると、秋山容疑者は詐取した研究費を東京都杉並区の自宅と同じ住所にある医療情報コンサルティング会社に移動。同社の取締役は秋山容疑者の親族が務めており、資金は同社の運転資金として使われていたもようだ。一部の現金は自身の飲食費としても支出していたという。
秋山容疑者が詐取した研究費は、厚生労働省の科学研究費補助金や国立長寿医療センターの委託研究費など、すべて公的資金が支給された研究事業だった。東大などによると、秋山容疑者は平成24年度までの4年間で、外部から計約2億1500万円の研究費を受け取っており、特捜部は過去の研究でも不正がなかったか調べを進める。
東大教授を研究費詐取で逮捕 架空発注で2千万円 東京地検 07/25/13 (イザ!)
架空の研究費を請求して東京大学などから公金計約2180万円をだまし取ったとして、東京地検特捜部は25日、詐欺容疑で、東大政策ビジョン研究センター教授、秋山昌範容疑者(55)=東京都杉並区=を逮捕した。
特捜部は認否を明らかにしていない。秋山容疑者は詐取した現金を私的に流用しており、特捜部は使途などを捜査する。
調べによると、秋山容疑者は平成22年3月~23年9月の間、医療情報システム構築に関するデータベース作成業務などを業者に発注したように装い、約1890万円を不正に東大から引き出したほか、共同研究をしていた岡山大学からも同様の手口で約290万円をだまし取った疑いが持たれている。
捜査関係者によると、秋山容疑者は付き合いのあったIT関連会社やシステム開発会社など6社に、数十万~数百万円の架空の納品書と請求書を計8回、大学側に提出させ、研究費を引き出していた。
秋山容疑者は、業者側に入金された研究費の大部分を還流させて流用し、一部を手数料として業者側に渡していた。研究費は、厚生労働省が支出した科学研究費補助金などの公金だった。
特捜部は6月に東大など関係先を捜索し、捜査を進めていた。東大政策ビジョン研究センターは、多分野にわたるテーマを結んで研究を行う機関。秋山容疑者は21年8月から所属し、医療分野でのITの活用などを研究していた。
東大教授逮捕 断ち切れない「学業癒着」 浮かぶ欲で結びつく構図 07/25/13 (産経新聞)
研究者と取引業者の癒着をめぐっては、昨年も京都大学の元教授が逮捕されるなど相次いで表面化。架空取引で捻出した資金を業者側に管理させる「預け金」などの不正経理も絶えない。うまみを吸いたい「学」と教授に食い込みたい「業」が、欲で結びつく構図が浮かぶ。
「発注権限を持つ教授を1人囲い込むだけで、簡単に億単位の受注を生む。教授にどれだけ近づけるかは死活問題となる」。ある教育関係者は指摘する。
こうした癒着は昨年もあぶり出されていた。東京地検特捜部は昨年7月、収賄容疑で、京都大学大学院薬学研究科元教授、辻本豪三被告(60)=公判中=を逮捕。辻本被告は、物品納入に便宜を図った謝礼と知りながら、平成19~23年、飲食代金や海外旅行の費用計約643万円を業者側に負担させたとされる。
辻本被告はゲノム(全遺伝情報)創薬科学の第一人者。贈賄側の業者は、辻本被告の京大への転籍に合わせて、京都事務所を立ち上げるなど、長年近い関係にあった。「接待攻勢は日常茶飯事。自社のクレジットカードを渡して『自由に使ってくれ』ということも多い」(製薬業界関係者)。
こうした癒着は全国の研究機関に存在しており、文部科学省が今年4月に発表した調査によると、科学研究費補助金(科研費)など公的資金の不正使用は、46機関で計約3億6100万円に達していた。計139人が関与しており、多くは預け金を取引業者に管理させていた。
文科省は不正防止のガイドラインを作成しているが、機能しているかは疑問符が付く。捜査関係者は「国や自治体に比べて、研究機関と業者の癒着は度が過ぎており、自浄作用がないとしか言いようがない」と指摘している。
「女性気になった」小学校長、電車で痴漢容疑 07/22/13 (読売新聞)
電車内で女性の体を触ったとして、大阪府警阿倍野署は22日、同府河内長野市立加賀田小学校校長・杉田憲治容疑者(56)(大阪府富田林市向陽台)を府迷惑防止条例違反(痴漢)容疑で現行犯逮捕した。
杉田容疑者は「女性が気になった」と供述しているという。
発表では、杉田容疑者は22日午前7時45~50分頃、近鉄南大阪線矢田(大阪市東住吉区)―大阪阿部野橋(同市阿倍野区)間を走行中の準急車内で、20歳代の女性の尻を触った疑い。
大阪阿部野橋駅に到着した際、女性が杉田容疑者の腕をつかんで駅員を呼び、同署員に引き渡した。
同小によると、杉田容疑者は今春赴任。22、23両日は夏季休暇で、逮捕時は、「友人に会うため大阪市内に向かっていた」と言っているという。
中2転落死「死ね」発言 担任と生徒食い違い…第三者委調査難航か 07/16/13 (読売新聞)
名古屋市南区で市立明豊中学2年の男子生徒(13)がいじめを苦に自殺したとみられる問題で、男子生徒が死亡した10日昼頃の「帰りの会」(ホームルーム)の詳細が明らかになってきた。
ただ、生徒らの証言と担任教師の説明には食い違いもあり、市教委が近く設置する第三者委員会の調査は難航も予想される。
市教委の発表によると、男子生徒は10日昼過ぎに帰宅し、午後3時半頃、自宅近くのマンションから転落して死亡した。その直前の同日正午頃、教室で開かれた帰りの会で男子生徒が同級生から「死ね」と言われたとされるが、その際の担任教師の対応も焦点の一つとなっている。
12日に記者会見した担任教師は「帰りの会が始まったばかりで騒がしく、男子生徒が『死ね』と言われたことを認識していなかった」と説明。複数の同級生によると、クラスの生徒は約30人で、男子生徒の座席は廊下側の列の前から3番目だった。帰りの会で、近くの席の男子生徒と女子生徒から「死ね」と言われた時、担任教師は教壇付近にいたという。
当時、一部の生徒は教室を出入りするなど騒然としており、離れた席からは3人のやりとりが分からない状況だったという。しかし、男子生徒が「死ね」と言われていたことは「担任には聞こえていたはず」と複数の同級生が話している。
同校が全校生徒を対象に実施したアンケート結果について市教委は、「男子生徒が『死ね』と言われていた」との回答や、担任が「(自殺を)『やれるものならやってみろ』と言った」という記述があったと明らかにした。これに対し、担任は記者会見で「決して言っていない」と否定した。
同級生への取材では、「『そんなことできるわけないでしょ』と言っていた」との証言がある一方、「あの先生がそんなことを言うはずがない」との話も寄せられた。
アンケートでは他の生徒からの伝聞や、スマートフォン向け無料通話ソフト「LINE(ライン)」の書き込みでこうしたやりとりを知ったとする回答が多かった。今後、生徒らへの聞き取り調査を行うほか、第三者委員会を設置して、こうした認識のずれを埋めることになる。
大津市で2011年にいじめを受けた市立中学2年男子生徒が自殺した問題で、市の第三者調査委員会の委員を務めた教育評論家の尾木直樹さんは、「大津の件でも生徒へのアンケートの回答で伝聞情報が多かった。それでも、その後にねばり強く聞き取り調査を行い、誰から聞いた情報なのか確認すれば、必ず真相にたどり着く」と話す。
中学教諭の男逮捕=女子生徒にわいせつ行為容疑-和歌山県警 07/12/13 (毎日新聞)
中学2年の女子生徒にわいせつな行為をしたとして、和歌山県警少年課は12日、児童福祉法違反容疑で、和歌山市立中学校の教諭の男(25)=同市=を逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑では昨年8月ごろ、常勤講師として担任をしていたクラスの2年生の女子生徒=当時(13)=に、生徒の自宅でみだらな行為をした疑い。
県警によると、男と生徒はメールで連絡を取り合っていた。男は今年4月、市内の別の中学校に異動して教諭になった。生徒と保護者が今月初めに被害届を提出した。
脅迫:女性の裸撮影し脅す 容疑の小学教諭を逮捕 07/10/13 (毎日新聞)
女性の裸を写真に撮影して脅したとして、埼玉県警大宮署は10日、さいたま市北区、市立指扇(さしおうぎ)小学校教諭、大塚裕(ゆたか)容疑者(28)を脅迫容疑で逮捕した。同署によると「写真を撮ったことは間違いない」と供述しているという。
逮捕容疑は、9日午後9時5分ごろ、同区のホテルで、市内に住む女性(20)を「これからも会ってくれるよね。裸の写真撮ったからね」などと脅したとしている。女性はすきを見てホテルから110番した。同署によると、大塚容疑者は同日、市内の路上で帰宅途中の女性に声を掛けたといい、「電車内で見かけて気になった」と供述しているという。
同校の石井寛校長は「事実とすれば人間として許されない行為。対応を検討したい」と話した。【大島英吾】
結果次第だが、このような教諭が担当しているクラスでいじめによる自殺者が出たら、隠ぺいに走る可能性は高いだろう。
アンケに「いじめと書くな」と指導した女性教諭 07/10/13 (読売新聞)
栃木県栃木市の市立小学校で、いじめに関するアンケートを実施した際、3年生を担当する30歳代の女性教諭が、いじめの申告件数が多くならないように児童を指導したうえで、回答させていたことが分かった。
アンケートは、市がいじめの実態を把握するために市内の全小中学生を対象に無記名で行った。同小では今月4日に実施された。
同小によると、女性教諭は、アンケート記入に先だって、担当のクラス全員に「いじめは一方的なもの。みんながしているからかいなどはケンカ。いじめと書くと多くなるので書かないように」と指導したという。
また、女子児童の一人が、今年4月に同級生に鉛筆で腕を刺されたとして、「いじめあり」の欄に丸印をつけていたが、女性教諭はアンケート回収後に女子児童を呼び出し、いじめにあたらないなどと説明。ペンで「いじめではない」に丸印をつけ、本人が納得済みである旨も加筆したという。
仕事を失うリスクを取ってでも復縁したかったのだろうか??
元生徒に復縁迫るメール209件、高校教諭逮捕 06/15/13 (読売新聞)
群馬県警は2日、太田市龍舞町、高校教諭中沢亮容疑者(32)を脅迫とストーカー規制法違反の疑いで逮捕した。
発表によると、中沢容疑者は今年4月、教え子だった同県内の女性(19)の携帯電話のメールに「なめている。ぶっ飛ばしたくなる」などの内容を9回送って脅した疑い。6月には「よりを戻してくれ」と交際などを迫るメール209件を送るなどした疑い。
中沢容疑者が送ったメールは1000件を超えていた。調べに対し、中沢容疑者は「メールを送ったのは間違いない」と供述しているという。
残念ながら過労死問題はそう簡単になくならないだろう。
「命を絶ったのはそれから半月後だった。5年計画のプロジェクトも抱えていたのに2年以内の研究室閉鎖を大学から一方的に告げられ、心のバランスを崩した結果だった。」
過労も影響したかもしれないが、非常に厳しい環境でがんばってきた努力が報われなかった、夢や生きがいがなくなったのが大きいと思う。全ての人に当てはまるわけではないが、人は夢や希望があるからこそ今は報われなくてもがんばれるのだと思う。それらを急に失い、パニックに陥り、悲観的になれば、人によっては生きる意味を失うのではないかと思う。つまり自殺の選択を選ぶ人もいる。残酷なようだが、その時に家族と共にいたいと思わなければ自殺をするかもしれない。仕事だけが
全てでなければ留まれたのではないかと思う。ただ、日本の大学組織は古い体質を維持しているところが多く、実力よりは、人脈、コネ、派閥などいろいろな
負の部分があると聞いた事がある。そのような事実も大学組織の中にいる教員にマイナスの影響を与えた可能性も高いと思う。良く分からないが多くの日本人は
日本に住み続けたいと思っていると思う。それは良い事も悪い事も受け入れたうえでの判断なのか、それとも日本以外の世界を知らないから故の判断なのだろうか??
過労死:自死の大学教員遺族、根絶目指し法整備求める 06/15/13 (読売新聞)
東日本大震災で研究室が全壊した大学教員が、再開を目前に控えながら過労と絶望の末に命を絶った。労災だと認められたが、仕事上のストレスを原因とする2012年度の精神疾患の労災認定は475人で過去最多を更新するなど、心を壊す職場の荒廃が広がる。「働くことで命を失うことがあってはならない」。遺族らによる過労死根絶を求める声は共感を広げながら増え続けている。
仙台市青葉区の前川珠子さん(48)の夫英己(ひでき)さん(当時48歳)が自殺したのは12年1月のことだ。
英己さんは東北大工学部准教授でリチウム電池など先端材料の解析を専攻していた。博士課程を含む8人の学生を指導し、研究プロジェクトも多く抱えていた。しかし東日本大震災で研究室は全壊した。
水素ボンベなど危険物が転がる部屋からデータや実験機材を持ち出し、再開の日に向けて働いた。授業の傍らの国内外への出張は93日間。珠子さんは、ノートパソコンに頭を突っ込むようにして眠っている姿を何度も見ている。
再開のめどが立ったのは翌年の1月半ばだった。プレハブの研究室に珠子さんと一人息子の長男(14)を連れて行き、「これから始まるんだ」と満面の笑みを見せた。長男は科学のことを分かりやすく話してくれる英己さんが大好きで「将来は科学者になりたい」と憧れていた。
命を絶ったのはそれから半月後だった。5年計画のプロジェクトも抱えていたのに2年以内の研究室閉鎖を大学から一方的に告げられ、心のバランスを崩した結果だった。
体調を心配する珠子さんに向けた「ありがとう。大丈夫。息子をよろしくね」が最後の言葉になった。珠子さんは労災を申請し、昨年10月「過重労働の恣意(しい)的強制があった」と認められた。大学の教員で労災が認められるのは極めてまれだ。
ただ、長男は父の死に傷つき、科学者になる夢を口にしなくなったという。その姿に珠子さんは他の過労死遺族と「過労死防止基本法」制定を求める運動に加わった。「息子や夫の教え子たちを、働くことが尊重され人らしく生きられる社会に送り出したい。過労死根絶はその第一歩」と話す。
遺族や労働組合らによる基本法制定を求める動きは3年前から始まり、署名は46万人を超えた。こうしたうねりに、与野党9党の議員が参加し、「『過労死防止基本法』制定を目指す超党派議員連盟」が参院選後にも結成されることになっている。【東海林智】
夜道で女子高校生の下半身触った高校教師逮捕 06/15/13 (読売新聞)
神奈川県警緑署は12日、横浜市緑区十日市場町、私立高校教師大久保雄治容疑者(24)を強制わいせつ致傷容疑で緊急逮捕し、14日に横浜地検に送検した。
発表によると、大久保容疑者は12日夜、同区長津田みなみ台の路上で、歩いて帰宅中だった同区の女子高校生(17)に後ろから近づき、スカートの中に手を入れて下半身を触り、女子高校生の左手首に軽傷を負わせた疑い。大久保容疑者は「触りたいと思って触った」と供述しているという。
特任助教、駐車場でわいせつDVD32枚販売 06/12/13 (読売新聞)
わいせつDVDを販売したとして、徳島県警生活環境課と徳島東署は11日、徳島市助任本町、徳島大特任助教菊池淳容疑者(43)を、わいせつ物頒布容疑で逮捕した。
容疑を認めているという。
同署の発表によると、菊池容疑者は4月下旬~5月中旬、同市の大型レジャー施設の駐車場で、県内の成人男性3人に、無修整のわいせつDVD32枚を計1万5000円で販売した疑い。インターネット上の掲示板で買い手を募っていたという。
同大学総務課は「事実なら教員としてあるまじき行為で遺憾」とコメントした。
児童転落、揺れる説明 神戸市教委「経緯に取り違え」 06/12/13 (朝日新聞)
神戸市立小学校の5年生男児が自然学校として泊まっていた宿舎から転落して重傷を負った事故は、10日の発覚以降、事実関係に関する市教育委員会の説明が揺れ動いている。市教委は「学校とのやり取りの中で情報の取り違えなどがあった。今後は正確な情報の把握に努めたい」(指導課)としている。
市教委によると、男児は5月29日午前、宿泊先の養父市のロッジの2階で、同級生たち9人と柔道遊びをしていた際、二重窓のすき間に閉じ込められた。約30分後、男児は自力で脱出しようと外側の窓を開けて約4メートル下に飛び降り、背骨や両かかとを骨折した。
市教委は報道機関の取材が相次いだ10日、「柔道に負けた罰ゲームで二重窓の間に入れられた」と説明していたが、校長は11日、朝日新聞の取材に「我々の調査では罰ゲームをしていた事実はない」と否定。市教委も説明を訂正した。
几帳面な29歳女性教師 ホテヘル嬢になった“理由”と“収支決算” 05/17/13 (イザ!)
大阪府立高校の教壇に立つ29歳の女性教諭が、放課後にホテルヘルス(ホテヘル)嬢としてアルバイトに精を出していたことが発覚した。米国では過去にポルノ映画に出演していたことがバレて解雇された女性教諭もいたが、性風俗の最前線でバイトしていたという今回のケースは、国内では前代未聞の不祥事。府教委によると、買い物が過ぎてクレジットカードの支払いが滞り、さらに学生時代に受けていた奨学金の返済も重なったことが、「短時間で高収入」のバイトを始めたきっかけという。それにしても、なぜホテヘルだったのか。それは“先生”らしく理詰めで職を求めた結果だった。(平田雄介)
■女性教諭の肩が震えた
「なんか、報告することないか」。春休みが終わり、新学年を迎えた4月上旬の昼下がり、ある府立高で、校長立ち会いの下に行われた女性教諭への事情聴取は、府教委幹部のこの一言から始まった。
突然の呼び出しに怪訝(けげん)な表情を浮かべながら入室してきた女性教諭は、知らぬ顔を通した。
「いえ、別にありません」。何もやましいことなどない、とばかりに「しらばっくれた」(幹部)という女性教諭の反応を観察しつつ、手持ちの情報を少しずつぶつける幹部。そして、いよいよホテヘルの店名を切り出したとき、女性教諭の肩が震えた。
「とんでもないことをしました。申し訳ありません」と、観念した様子でホテヘル嬢としての副業を認めたという。
ホテヘルは、インターネットやビラなどを頼りに男性客が店舗へ出向き、指名した女性とホテルへ移動して性的サービスを受ける。全国的にみれば、過去にもホステスなど水商売のバイトで処分された教諭はいるが、今回は「性的サービス」をしていた点が際立っていた。
この女性教諭は昨年10月から今年4月までの105日間、放課後に大阪市内のホテヘル店で働き、計約160万円の収入を得たという。営利目的の副業を禁止した地方公務員法に違反している上、「著しく不適切で、信用を大きく失墜させた」として、停職6カ月の懲戒処分が下された。女性教諭は処分事実を認めた上で「生徒に申し訳ない」と述べ、5月2日付で依願退職したという。
■下着姿、挑発するポーズ
女性教諭がバレないと見込んだ風俗バイトが露見したのは今年3月中旬。府教委に届いた匿名の告発メールがきっかけだった。
「A高校のB先生が大阪市内のCホテルヘルスのD店で働いています。調査してください」。送り主が特定されないようフリーメールのアドレスから送信されていたが、女性教諭の氏名や勤務先の高校名、ホテヘルの店名が記載されていた。
「ほんまかいな」。担当者はにわかに信じられず、自宅のパソコンで家族に隠れてホテヘル店のホームページ(HP)を検索。告発の信憑性を見極めたという。
確かに店は実在しており、ホテヘル嬢の紹介ページには女性教諭らしき姿が…。顔をぼかした写真ながら、下着姿で挑発的なポーズを取っており、証拠としてページを印刷。そして、府教委による調査を開始したのだった。
■カードローン地獄?
なぜ、公立高校の教諭が禁止されている副業を、それも性風俗店で始めたのか。
「借金の返済に困っていたようです」。記者会見で、府教委幹部は苦渋の表情を浮かべながら動機について語り出した。
女性教諭は衣服や化粧品を買うのが好きだったという。普段の服装や化粧は派手ではなかったが、現金で支払えないほど購入する品数が多かった。2、3社のクレジットカードを使い回し、昨年10月には未払い金が200万円に達したという。
督促状が自宅に届くようになり、同居する家族に借金がバレるのを恐れた女性教諭はネットでこっそりバイトを探した。これが転落の始まりだった。
検索のキーワードは「短時間で高収入」。地方公務員法の副業禁止規定はもちろん認識しており、職場にも家族にもバレないことが条件だった。そんな条件をクリアできたと思い、たどり着いたのが、放課後に1、2人の客を取れば1日で1万円以上の収入を得られるホテヘルだった。
女性教諭は府教委の調査に「性風俗業は特定の客とだけ接すればよいので、多くの人に顔を見られずに済むと思った」と語ったという。先生らしく理詰めでホテヘルをバイト先に選んだことがうかがえるが、性風俗店で働くことに抵抗はなかったのだろうか。
府教委幹部は「抵抗はあったようだが、大学時代の奨学金の返済も抱え、切羽詰まっていたようだ」と明かした。
■几帳面な性格が「仇」
ホテヘルでのバイトを認めた女性教諭に対し、府教委は自宅謹慎を命じた上、事実関係を把握するために顛末書を提出するよう求め、さらに数回、事情聴取を重ねた。
几帳面な性格の女性教諭はバイトに出た日付と収入を詳細に控えており、事実関係の調査は思いのほかスムーズに進んだという。違法性の有無についても、バイト先が大阪府警に営業を届け出ていることを確認し、女性教諭から「売春防止法に触れる違法行為はなかった」という証言も取った。
だが、府教委の裏付け調査が十分だったとは言い難い。処分事実は女性教諭の説明を基に記述。府教委はバイト先の店とは一度も連絡を取らず、勤務実態を確認することもしなかった。
警察関係者によると、ホテヘル嬢は通常1日で2~3万円の収入があるといい、「女性教諭は自己申告額の160万円より多くを稼いでいたはずで、借金も実際には数百万円あったのではないか」と指摘する。
■背景は闇の中
事実確認が進むと、今度は懲戒処分の“量刑”が議論された。
副業が発覚した場合の処分基準は戒告や減給処分とされているが、府教委は今回、再び教壇に立つことは許されないと判断し、退職を前提に話を進めた。
ただ懲戒免職は、基準より極めて重い処分となるため、違法ではない性風俗店で働く人に対する職業的差別につながることが懸念されたという。
解決策として府教委が導き出した答えが、事実上の退職勧奨を行って女性教諭が自ら依願退職を求めるよう仕向けることだった。
「で、どうすんねん?」。語気を強めて今後の身の振り方を尋ねる府教委幹部に対し、女性教諭が「辞めます」と答えたことで、依願退職を前提に「停職6カ月」の処分が決まったという。
別の幹部は「服や化粧品を買うために風俗バイトするなんて問題外だ」と怒りをぶちまけるが、なぜ女性教諭がカードローンを組んでまで大量の衣服や化粧品を買い続け、借金苦に陥ったのか、という根本的な理由は、府教委の調査では明らかになっていない。
いわゆる「買い物依存症」だったのか、職場の人間関係で悩みやストレスを抱えていのか。そもそもクレジットカードの利用の仕方がまずかったのか…。高校教諭による前代未聞の不祥事は原因不明のまま、幕引きされた。
「性欲に負けた」性欲がなければ子供が生まれないわけだが、「路上で強制わいせつ」は必要ないと思う。まして「教諭」と呼ばれる
公務員なのだから行動する前に考えるべきだったと思う。「性欲に負けた」との理由が本当であれば、教師としての能力や実績とは
関係なく再犯の可能性は高いだろう。
「性欲に負けた」中学教諭、路上で強制わいせつ 05/12/13 (読売新聞)
埼玉県警捜査1課と浦和東署などは11日、さいたま市桜区白鍬、さいたま市立馬宮中教諭田村竜也容疑者(24)を強制わいせつ容疑で逮捕した。
発表によると、田村容疑者は1月27日午後7時55分頃、同市緑区の路上で、歩いて帰宅していた20歳代女性の後ろから素手で口を塞ぎ、胸や尻などを触った疑い。
調べに対し、田村容疑者は「性欲に負けてやりました」などと供述しているという。県警は防犯カメラの映像などから田村容疑者を特定。昨年秋頃から今年にかけて、周辺で十数件の強制わいせつ事件が起きており、県警が関連を調べている。
田村容疑者は同中1年の担任で、英語を担当していた。荻田哲男校長は「真面目に勤務していたので大変驚いている。事実であれば生徒や保護者に大変申し訳ない」とコメント。同市教委の桐淵博教育長は「教育公務員としてあるまじき行為で極めて遺憾。今後、事実を確認した上で厳正に対処する」としている。
「女子生徒を教科準備室に連れて行き、片手で突き飛ばしたほか、授業で使う指示棒や平手で頭を複数回たたいたり、太もものあたりを足で複数回軽く蹴ったりした」
行為は問題があるが、「授業中に金属の棒で机をたたき続けた女子生徒」にも問題があると思う。この場合、他の生徒の授業を受けることを妨害したので
教室から出る命令を出せるのか、問題のある生徒のも授業を受ける権利があるので教室から出ていく命令は出せないのか、そのようなケースについて
文部科学省/A>は検討して、速やかに明確な指導方針を出すべきだ。
体罰や暴力は良くないが、問題のある生徒達をつけ上がらせるのは良くない。
授業中机たたき続けた女子生徒たたいた教諭懲戒 05/06/13 (読売新聞)
栃木県教委は、生徒に体罰をしたとして、県南の中学校に勤務する男性教諭(50)を7日に戒告の懲戒処分にしたと発表した。
発表によると、男性教諭は2012年11月、授業中に金属の棒で机をたたき続けた女子生徒を教科準備室に連れて行き、片手で突き飛ばしたほか、授業で使う指示棒や平手で頭を複数回たたいたり、太もものあたりを足で複数回軽く蹴ったりした。生徒にけがはなかった。教諭は「今後二度とこのようなことのないようにしたい」と反省しているという。
今回の体罰は、文部科学省の通達を受けて児童生徒や教職員、保護者を対象に2~4月に実施したアンケート調査で把握した。調査では、12年度に県内で116件の体罰があったことが判明している。
明確に説明してほしい。「一種の催眠術にかかっていた」は受け入れられる説明ではありません。
仮定を立てて、仮定を説明する客観的な証拠で仮説が正しいと結論付けるはずではないのか?単独調査でもないはず。
他の人達も同じ考えだったのか?異論を言える環境ではないのか?東京大学だからかもしれないし、失敗を隠ぺいできなくなった時代なのかもしれないが、
東京大学の失敗や問題を最近よく聞くようになった。一部分ですごく優秀でも総合的に、客観的な判断できる能力について欠けている人達が多いのかもしれない。
「催眠術に…」立川断層の誤り、おわびの教授 03/28/13 (読売新聞)
「混乱を与えて申し訳ない」。人工物を岩石と取り違えるなどのミスが明らかになった立川断層帯の掘削調査。
28日の記者会見で研究者はおわびの言葉を繰り返した。地元自治体は冷静に受け止めつつ、「市民は引き続き警戒を」と呼びかけている。
「一種の催眠術にかかっていた」
立川断層帯の地質構造を見誤った佐藤比呂志・東京大学地震研究所教授は、会見で謝罪の言葉を重ねた。佐藤教授とともに現場で調査にあたった石山達也同研究所助教も、「住民、社会に混乱を与えたことを申し訳なく思う」と頭を下げた。
誤りの原因について、佐藤教授は「断層を予想していた場所に人工物があった」とした上で、「バイアス(先入観)があったと思う」と厳しい表情を浮かべた。
佐藤教授は東北電力東通原子力発電所の敷地内の断層調査にもかかわっており、調査チームは今年2月、「活断層の可能性が高い」との報告書をまとめている。辞任の意向を問われ、佐藤教授は「資質がないので辞めろというなら職を辞したいと思うが、引き受けた限り、研究者として責任は全うしたい」と述べた。
北里大の補助金不正受給、文科省分も不透明取引 03/26/13 (読売新聞)
北里大(東京都港区)が厚生労働省の補助金を不正受給していた問題で、研究の実質的責任者だった元医学部教授(53)が、文部科学省の補助金でも、研究の一部を自ら設立したNPO法人を介して下請けに丸投げする不透明な取引をしていたことがわかった。
同大はこの問題を把握しながら報告しておらず、文科省は25日、同大に調査を指示した。
読売新聞の調査や同大への取材によると、不透明な取引があったのは、臨床研究に携わる人材を育成する事業(2007~09年度)で、補助金計約5800万円を交付された。
元教授は、自身が理事長を務めるNPO「日本保健医療情報マネジメント機構」(東京都)にホームページ作成など事業の一部を約1900万円で委託し、その業務を個人や会社計7者に計約1680万円で丸投げ。約220万円の利益を得ていた。下請け先の中には、高校の同級生で、NPO理事を務める男性(53)の妻(費用約165万円)も含まれていた。
「子供、子供」と大義名分で言うが、本音はそれほど子供の事など考えていないのではないかと思う。「子供のために」とか「子供の将来が」とか
言っても、自分達が一番と考えているような態度を取る。確かにモンスターピアレントはいるかもしれないが、学校や教育委員会の対応を見ていると
徹底的にやってやらないと変わらないと思わせる事実がある。下記の記事について全く知らないが、報告書に関係した人間の名前を公表するべきだ。
悪質な対応を取っておきなが責任を取らないのは良くない。少なくとも名前を公表するべきだ。
19年前の小6自殺「体罰が原因」…市教委訂正 03/21/13 (読売新聞)
兵庫県たつの市で1994年9月、放課後に首をつって自殺した小学6年の男児について「事故死」として処理し、直前の教師の暴行との因果関係を否定していた市教委が、今月になって「体罰による自殺」と認めて両親に謝罪、文部科学省に訂正を報告したことがわかった。
教育現場の隠蔽体質に批判が強まる中、訂正せざるを得ないと判断したとみられる。
市教委が新たに「自殺」として報告したのは、龍野(現・たつの)市立揖西(いっさい)西小の内海(うつみ)平(たいら)君(当時11歳)。教室で運動会のポスターの作り方を質問した際、担任の男性教諭から「何回同じことを言わすねん」などと言われ頭や頬を殴打されたことにショックを受け、その日の夕方、自宅の裏山で首をつって死亡した。
警察は自殺と判断したが、学校は「事故による死亡(管理外)」「原因不明」と報告書に記載し、責任を否定していた。両親は市に損害賠償を求めて提訴。2000年1月、神戸地裁姫路支部は、自殺と暴行との因果関係を認めた上で、市に3792万円の支払いを命じた。市は控訴を断念。それでも訂正は「必要ない」との立場を変えなかったが、今月19日、市教委の苅尾昌典教育長が両親宅を訪れて謝罪、訂正を伝えた。
親から虐待された子供が苦痛を経験したにもかかわらず、親になると子供を虐待する。離婚した両親を持った子供は、離婚していない両親よりも
離婚しやすい傾向がある。体育会系で体罰を受けた選手は、同じように教え子達に体罰を与えるのでないのか??このような傾向が高いのであれば
やはり教員や指導者に対しての講義や教育が必要なのではないのか??
「文科省は、うつ病など精神的な病気になる公立学校の教員が過去10年間で約2倍に増えていることから、去年、有識者会議を設置し、原因や予防策などについて検討してきた。
・・・ また、教育委員会に嘱託の精神科医を配置し、学校を巡回訪問させるような施策も必要だとしている。」 03/23/13 (日テレNEWS24)
と精神科医をおけば問題が解決するとでも思っているのか?文科省はなんと愚かな組織なのか、それとも精神科医の組織と癒着でもしているのか?
教員を目指す生徒になぜ教員を目指すのか、教員になった時に遭遇するかもしれない問題、教員としてのモラル等などを大学などの教育機関で
講義の1つとして取らせるべきだ。ただ、安定しているからとか公務員になりたいとか安易に考えている生徒には他の選択を考えさせるべきである。
精神科医を置いても、教員の問題に精通していなかったり、子供の教育に対して知識や経験を持っていなければ、問題は解決しないと思う。
精神科医は最低限の資格だけであり、効果的な解決方法ではない。教員になる前に教員の適性や教員になる意思(意志の強さ、社交性)等をチェックする
ほうが良い。教員の資格と採用試験による合格だけでは問題は解決でない。精神科医を置く事によって問題解決を考える文科省自体、問題の原因かもしれない。
特集ワイド:愛ある体罰「ないですわ」 ラガーマンで教育者、大八木淳史さんが語る (1/3)
(2/3)
(3/3) 03/06/13 (毎日新聞)
大阪市立桜宮高バスケット部員の自殺、柔道全日本女子代表監督の辞任など体罰問題が議論を呼んでいる。スポーツの現場で体罰が相次ぐのはなぜなのか。昔は熱血ラガーマン、今は芦屋学園中学・高校で校長を務める大八木淳史さん(51)の「体罰論」を聞きに行った。【小国綾子】
◇富国強兵と意識変わらぬ 「げんこつ」ではなく涙、涙
大きい。身長190センチ、体重100キロは現役時代とほぼ変わらない。校長室の革張りソファも小さく見える。
体罰論議、どう思います?
「桜宮高の件はプレーの失敗で張り手を食らわせたと聞く。勝利至上主義が生んだ暴力であり、指導法として間違えている」。明快な答えとは裏腹に大八木さんはうかない表情。「ただし今の体罰論争もおかしい。体罰を定義しないまま、誰もが勝手なイメージで『体罰反対』『愛ある体罰はOK』と言っている。これでは答えは出ない」という。
確かに毎日新聞の世論調査(2月2、3日)では「一切認めるべきでない」(53%)と「一定の範囲で認めてもよい」(42%)で意見は真っ二つ。男性は「認めてもよい」が多い。連想する体罰の中身もバラバラなのだろう。
「体罰の歴史と目的を理解しないと。体罰は明治時代以降の富国強兵に使われた。目的は強い軍隊、つまり国益。では今は? スポーツ関連の国家予算を見ればわかる」
文部科学省によると、年間のスポーツ関連予算は今年度235億円。このうち約7割は競技スポーツに集中投下されている。学校の体育や国民の生涯スポーツは二の次だ。
「競技スポーツ、つまりメダル獲得プロジェクト。これも国益やないですか。富国強兵時代と一緒。国益や学校のブランド力のためのスポーツだから体罰が生まれる」
しかし、大八木さんは「スポーツは体罰の温床」という考えには反対だ。むしろ「スポーツの力で体罰やいじめをなくしていける。ドロップアウトした子の受け皿としてのスポーツにこそ税金を使うべきだ」。スポーツによる人間形成−−それが大八木さんの一生のテーマだ。
同志社大で大学選手権3連覇、神戸製鋼で7年連続日本一。87、91年のワールドカップにも出場した。36歳で現役引退後、生き方に迷った。「俺の生きるミッションは何や」。悩んだ末、大学院に進学。修士論文のテーマは「トップアスリートは青少年育成にどう関われるか」。6年前、実践の場として高知県の高知中央高に赴いた。スポーツ推薦で入学しながら挫折し退学寸前の生徒らを集め、「スポーツで傷ついた子をスポーツで救いたい」とラグビー部を創部した。
最初の年、ラグビー哲学をいくら熱っぽく語っても部員は辞めていく。ともに泣き、円陣を組んだはずの部員が、翌日部活をサボる。壁にぶつかった時、学問が役立った。思い出したのは、米国の心理学者マズローの「自己実現の法則」。人間の欲求は(1)生理的(食欲・睡眠)(2)安全(住居・健康)(3)社会的(仲間)(4)尊厳(他人からの評価)(5)自己実現−−の5段階あり、低次の欲求が満たされて初めて次の欲求が生まれる、と。
「3段階の哲学を語る前に1、2段階や」。合宿先などで共に寝起きし、風呂に入り、食事する時間を増やした。
創部2年目、全国大会出場切符を勝ち取った。無名チームがわずか数年で全国優勝を果たした軌跡を描いた80年代のテレビドラマを模して、「平成のスクール・ウォーズ」と呼ばれた。
ちなみに「スクール・ウォーズ」は実話が元になっている。「泣き虫先生」のモデルは、大八木さんの高校時代の恩師で当時、京都・伏見工高でラグビーを教えていた山口良治さんだ。
ドラマで「泣き虫先生」が泣き顔で部員たちを殴るシーンは有名だ。山口さんの著書でも、長野・菅平のラグビー合宿でいいかげんなプレーをしていた大八木さんを引っぱたく場面が登場する。
「あの日は足のねんざが痛くてイライラしてる時に怒鳴られ、売り言葉に買い言葉。『ほな、帰りますわ』と荷物まとめてグラウンドを去りかけた。そしたら山口先生が追いかけて、平手でパンパーンってね」
それから慎重に言葉を選び、言い添えた。「体罰を美談にするつもりはない。でも先生はあの時、僕を追いかけ叱責することで、俺に戻る場を与えてくれた。そのまま放り出されたらどうなったか。それに30年以上も前の話です」
でも気になった。自分の受けた体罰を肯定的にとらえた者が指導側に回った時、体罰を再生産する、という批判もあるではないか。大八木さん自身は高知中央高で生徒に手を上げたことは?
「ないです」。即答だった。
ならば「愛ある体罰」に訴えたくなったことは?
しばらく記憶をたどっていたが「やっぱり、ないですわ。たばこを隠し持っていた部員に『走ってこい!』と言ったことはありましたけど」。
ふと、数年前の新聞記事を思い出した。全国大会の初戦前、大八木さんは涙ながらに奮起を促し、選手もまた目を真っ赤にし、試合に臨んだという。試合前から涙、涙。彼らの間に「げんこつ」は要らなかったのかもしれない。
インタビュー後半、大八木さんは立ち上がり「スポーツ指導の現場に一番足りないのはこれや!」とホワイトボードに殴り書き。DIVERSITY(多様性)とある。
「まず、女性をもっと登用し、女性の視点を入れること。ナショナルチームの体罰問題を最初に訴えたのは女子柔道でしょう? それから指導者の視野を広げること。桜宮高の件でも、バスケしか知らん指導者と強豪チームを求めて入部した生徒が集まれば、価値観はバスケ一色。勝利至上主義に陥って当然。スポーツ指導者は年に1〜2カ月程度、現場を離れ、社会学や心理学など別の学問や価値観を学ぶ仕組みが必要なんです」
それから熱血先生、再びソファに体を預け、最後はしみじみと「『生徒のためにここまでやったのに』と教師が独りよがりになってはダメ。ラグビーを必死に教えても生徒は時には問題を起こすし、部や学校を辞めていく。彼らは教師の物差しで測れば『バツ』かもしれないが、まじめに生きてくれたら人間として『マル』でしょう? 大事なのは元気に生きてくれること。ラグビーの上手下手やない」。
「今でもね、ラグビー部や学校を辞めたヤツらが時々電話してきよる。それで十分やないですか」。熱血授業は、2時間半を過ぎていた。
越直美市長、大津いじめ自殺で校長処分など要請 02/04/13 (読売新聞)
いじめを受けた大津市立中学2年の男子生徒が自殺した問題で、越直美市長は4日、滋賀県の嘉田由紀子知事と河原恵・県教育長に対し、市の第三者調査委員会(委員長=横山巌弁護士)の報告書を受けて、校長らの処分と人事の刷新、教員の増員など学校への支援を要請した。
越市長は県庁で嘉田知事らに、「来年度に向け、(問題のあった)学校の体制を考える必要がある。県側でも学校を調査し、処分の必要性を検討してほしい」と述べた。
教員の人事権を持つ県教委には、市が学校運営により積極的に関わることができるように人事権を移譲することや、教員を増やして現場にゆとりをもたせることを要望。県が各校に配置しているスクールカウンセラーについても、業務の独立性を高めて、効果的に生徒の相談に応じられるよう運営を改めることを求めた。
全ての学校で同じことをする必要はない。この記事を読んで思う事はこのような経験をさせても良いと思う。そしてそれはその学校や
教諭のスタイルであって良いと思う。似たような授業を16年間を行って来たのだから入学する生徒もある程度情報を知っているはずだろう。
大人になっても自ら嫌な体験、不愉快な体験そして辛い体験から何かを学ぶかもしれないと思っていても誰かが背中を押してやらないと出来ない場合もある。
ある体験が何年後、何十年後にある出来事を考えさせる事もある。しかしその時になるまである特定の体験が後の考え方や生き方に影響するとは思わない事もある。
情報をある程度開示してどうしても嫌であるならばその選択を取らない選択もある。世の中には100セント、好き、嫌いで判断できるケースは少ないと思う。
今の学校では奇麗事がまかり通っているが、世の中は学校で言われた通り自由でも平等でもない。個人の実力、才能、人間関係、各々がいる環境、会社、地域、国、
そして時代によって数式のように同じ答えにならない。だから福岡県立筑水高等学校のようなケースがあっても良いと思う。テストや試験の結果が日本では
重要と考えられていると思う、しかし時代や社会構造が急速に変化している時はサバイバル能力や状況ごとに考えて行動する能力がある程度必要と個人的に思う。
日本人であっても様々な考え方の人間がいる。そして議論しても話し合っても妥協点に到達できない人間達も存在すると考える。だからまったく批判のない
状況はまれだと思う。自分が同じ事を進んで体験するかと言われれば、体験しない方を選ぶだろう。だが、この体験を経験すれば誰かが行った行為により
自分が直接手を下す必要がなかったことを強く認識すると思う。
女子高生が鶏を育てて解体して食べる 「命の授業」は残酷か? 03/05/13 (Business Journal)
ーー『カンブリア宮殿』『ガイアの夜明け』(共にテレビ東京)『情熱大陸』(TBS)などの経済ドキュメンタリー番組を日夜ウォッチし続けている映画監督・松江哲明氏が、ドキュメンタリー作家の視点で裏読みレビューしますーー。
今回の番組:2月24日放送『情熱大陸』(TBS)
カメラは鶏の首を持ち、ナイフを刺す生徒たちの表情を追う。嗚咽し、涙を流す少女たち。覚悟を決めた力強い意志を感じさせる男子生徒。そして、順番を待ってはいるものの、一歩を進めることさえ困難そうな塚本さん……。
この日の『情熱大陸』は福岡県立筑水高等学校の真鍋公士教師が主役だが、ディレクターの視点は彼女に向いていた。真鍋教師を軸に進めつつも、彼女の成長もしっかりと追う。そのように構成することで、番組の視点が視聴者に近くなる。そして首を切られる鶏を一切、映すことなく、しかしそれを見る生徒たちの表情を捉えることで、制作者が何を伝えたいのが明確になった。
このクラスでは食品流通科一年生の授業として毎年「命の授業」が行われている。鶏の受精卵を生徒一人ずつが飼育し、成長したそれを自らの手で解体し、食べるのだ。命の尊厳を肌で感じる授業はメディアにも取り上げられ、文部科学大臣奨励賞を受賞した。
だが、一方で批判もある。
学生にそんな残酷なことをさせなくても、という意見だ。しかし真鍋先生には直接体験することでしか伝えられない教育がある、と確信している。でなければこのような授業を16年間も続けられるはずがない。三カ月の最後、生徒たちは二つの選択を選ぶことになる。工場に出荷するか、自らの手で解体をするか。受精卵に名前を付け、愛着のある「子」を自らの手で「殺す」のには並大抵の覚悟ではないはずだ。
産まれた時から側にいて、今も安心して腕の中にいる鶏の命を選択するという授業。僕は『情熱大陸』という番組を通し、傍観する立場にいるが、ここに映る被写体たちの気持ちを思うと苦しい。しかし、それも想像でしかない。
僕は、卒業生の会話が印象的だった。ある女性は、学生の頃に妊娠し、周囲からは出産を反対されたが、「鶏の解体を経験したからこそ、堕胎という考えには至らなかった」と子供を抱きながら言う。「こんな時、真鍋は思う。自分のやり方は間違っていなかった」ーーそう、ナレーションが補足をするが、その思いは居酒屋で学生時代の彼女の写真を見つめ、笑う表情で十分に伝わった。
塚本さんは餌を上手く食べられない鶏の面倒を見る。養鶏場ならば切り捨てられてしまう、弱い命かもしれない。しかし、自ら名前を付けた命だからこそ助けられる。数カ月後には「食べられる」命だが、今はまだ違う。か弱い鶏を集団から離し、個別に餌を与える。一生懸命に食べる小さな鶏。その一生懸命な姿をカメラはローアングルで撮影する。
夕方、女性たちが「お友達つれてきた」と笑い合い、地面に直座りするさりげないカットがある。そこに重なる「学んでいるのは飼育だけではない。生徒たちは自分たちが生きている意味さえ突きつけられる」というナレーション。鶏も彼女たちの周囲を歩き回り、真鍋先生も加わる、よくある高校の放課後の風景だったが、何かかけがえのない瞬間を切り取っているようにも見えた。
いよいよ鶏を解体する時が近づいてきた。塚本さん自ら解体することに同意した。真鍋先生は「自分がかわいがってきたんだから、最後まで面倒をみてやろう」と思ったのではないか、とこれまで見てきた生徒と重ねて分析する。
冒頭にも書いたように、鶏の首を切る瞬間は、人間たちのアップで捉えられた。制作者はここまで丹念に真鍋先生と生徒たちに寄り沿い描いてきた。だからこそ彼らの苦しさが伝わる。しかし、この授業は命を頂き、調理するまで続く。真鍋先生が皮を剥ぎ、生徒たちは「おぉー」と驚きの声をあげる。スーパーや食肉店で見慣れた「肉」に変わると、生徒たちも仕事に没頭し始める。
真鍋先生は「必ず」という言葉を強く発する。
「人間は残酷で、必ず食べなきゃ生きていけない」「君たちが今、生きてるのも両親がいるからだ。それを絶対忘れちゃいけない」
「絶対」という言葉も、軽々しく使われてはいない。本当の事実だけを指す時に使う言葉なのだ、と思った。
番組は、塚本さんの作文で締められた。
「この命の学習を通して一つ一つの命の重さはもちろん、隣でずっと声をかけてくれた友達の大切さを改めて知る事ができました」と。命を扱うからこそ、それだけでない様々なことに気づける、そんなことを僕も気づいた。
『情熱大陸』のテーマ曲もいつもよりスローテンポで叙情的な雰囲気だった。番組スタッフも様々な発見があったんだろう。僕には真鍋先生と生徒たちへの感謝のように思えたのだが、考え過ぎだろうか。
(文=松江哲明/映画監督)
今回の「駆け込み退職」は公務員の中には自己中心的な人間達が多くいることを証明した出来事だ。国民のためでなく自分達のためには国民を税金を無駄にしても仕方がないと思っている。
自分達のため、天下り先確保のために無駄な事業の企画や発注も平気で行う公務員達がいることが理解できるだろう!
駆け込み退職「公認」の動き…3月限定で再任用 01/23/13 (読売新聞)
駆け込み退職を“公認”し、対策を講じる動きもある。
京都府警の場合、条例改正案が施行される3月1日以降に退職した場合、退職金は前年度の退職者より百数十万円安くなる。
府警ではこれに伴い、今春の定年退職予定者154人に対し、引き下げ前の2月末で駆け込み退職した場合に、3月の1か月間限定で「再任用」する案を提示している。定年退職予定者には署長ら管理職も含まれているため、府警は「駆け込みが相次げば警察業務の運営に支障をきたす」と判断したという。
再任用後は原則として退職前と同じ職場でフルタイム勤務するが、給与は減額される。早期退職、再任用の希望人数は現在取りまとめ中という。警察官の再任用は、後継者の指導や育成のために任期は1年とするのが一般的という。
駆け込み退職 埼玉ショック…茨城 01/23/13 (読売新聞)
改正国家公務員退職手当法が昨年11月に成立したのに伴い、茨城県は県議会3月定例会で県職員の退職手当を、3年間で約400万円引き下げる条例改正案を提出する。
すでに条例を改正した埼玉県では減額を免れるため、教職員らが定年退職前に自己都合で辞める「駆け込み退職」が相次いでおり、県内でも懸念が広がっている。
退職手当の引き下げは、官民の格差是正を目的に国が昨年11月に法改正を実施、総務省が全国の自治体に手当の引き下げを要請している。県は他県の状況を見ながら慎重に検討を続けていたといい、3月定例会で条例改正案を提出する。県議会で可決されれば、定年退職日の3月31日直前の同月下旬に施行される見通し。
県人事課によると、条例改正により退職手当は12年度は約140万円、13年度は約280万、14年度は約400万円の減額(いずれも11年度比)となる。県内では、条例施行日と定年退職日の間が短いため、自己都合で早期退職しても給与月額の目減り分が少ない。このため、施行日より1日早く退職すれば約140万円の減額を免れることができ、直前の駆け込み退職が相次ぐ可能性がある。
退職手当は自己都合の場合、通常は支給割合が2割ほど減るが、県では60歳以上の自己都合退職は定年退職と同じ扱いとしている。同課の担当者は「学級担任をしているような教職員や要職にある県職員が年度途中で辞めるのは道義的にいかがかと思うが、制度上、止めることはできない」と説明する。
県は25日に県職員組合との交渉で、退職手当引き下げに関する条例改正案を説明する。同組合の清水瑞祥委員長は「退職手当をあてにして生活設計を考えている職員もいる。駆け込み退職が相次げば、現場は混乱しかねない。4月からの施行にしてもらいたい」と話す。今年3月末に退職を迎える県職員は、知事部局約190人、教職員約460人、県警約150人の約800人。県職員の退職手当は1人平均約2740万円(11年度実績)。
市町村職員の退職手当については、市町村長や議長らが議員を務める県市町村総合事務組合で管理しており、今後、引き下げに関する条例改正案が出される見込みだ。
佐賀の教員は悪知恵がすごい!ほとんどの教員が臨時任用で年度末まで働くらしい。この方法だとニュースにならなければ、誰も気付かない。
このような事を行い、生徒には平等とか、公平とか言って来たのだろうか??モラルや専門職としての意識の欠如が学校崩壊の原因の一つかもしれない。
「駆け込み退職」佐賀県も 学級担任含む25人 01/23/13(読売新聞)
佐賀県教育委員会は23日、学級担任を含む県の教員計25人が退職手当引き下げ前に「駆け込み退職」していたことを明らかにした。手当引き下げ前の退職は、埼玉県で多くの教員が申し込み問題になっている。
手当を引き下げる佐賀県の改正条例は1月1日に施行。一方、3月に定年退職を迎える教員25人(小学校4人、中学校4人、高校14人、特別支援学校3人)が昨年12月末で退職していた。ほかに事務職員など11人も退職した。手当の差額は150万円程度という。
県教委は「教育の継続性を保つため、ほとんどの教員が臨時任用で年度末まで働いてもらっている」と説明。現在までに学校現場から混乱が生じたという声は上がっていないとしている。
学校の問題は教員の考え方や姿勢にも問題があるのではないのか?「子供達に人に迷惑をかけない、秩序を守る、自分勝手な行動をしない」と言っても
自分さえ良ければよい、面倒なことは避ける教員を子供達は信用するのか?先生の本性を見抜ける子供達の答えは「NO」であるに違いない。
問題のある教員や人格に問題のある教員は辞めさせる制度も考えるべきだと思う。駆け込み退職は制度的に可能であれば、子供達に迷惑をかけても
良いと考えている証拠。これだけ駆け込み退職をする教員が存在する事は、新たな制度が必要と証明しているようなものだ!
駆け込み退職:佐賀、徳島43人 教頭、担任も 本紙調査 01/23/13(読売新聞)
埼玉県内で100人超の教員が退職手当引き下げ前に「駆け込み退職」を希望している問題で、佐賀県と徳島県では教頭や学級担任を含む教員43人が既に駆け込み退職していたことが22日、毎日新聞の全国調査で分かった。学校事務職員や一般行政職員を加えると70人超が退職。高知県など4自治体でも退職希望者がおり教育委員会が対応に追われている。
埼玉県とさいたま市を除く46都道府県と19政令市の教委に聞き取りをした。佐賀県は退職手当を引き下げる改正条例を1月1日に施行したが、昨年12月末で教員36人(小学校8人、中学校5人、高校16人、特別支援学校7人)と一般職員16人が退職。同県教委は「子供の教育に支障がないよう臨時的任用で年度末まで継続するようお願いし、一部はまだ働いている」と話す。
徳島県も1月1日付で条例改正。昨年12月末に教員7人(小学校2人、中学校3人、高校1人、特別支援学校1人)と学校事務職員5人、一般職員7人が退職した。徳島市では中学教頭が辞め、現在も空席という。同県教委は「教員4人を臨時採用し、支障は出ていない」としている。
また、高知県は3月に改正条例を施行する予定で、教員2人が2月末の退職を希望。愛知県と兵庫県、京都市でも3月改正で、退職希望者がいるとみられるが「未集計」などとして詳細を明らかにしていない。
ほとんどの自治体は、まだ条例の改正を議会に提案していない。10自治体は既に議会で可決されているが、問題は出ていないという。【まとめ・加藤隆寛】
教員と言えど人間。平均約150万円の違いに動いた!
退職金減る…埼玉の教員110人が駆け込み退職 01/11/13(読売新聞)
埼玉県職員の退職手当が2月から引き下げられるのを前に、3月末の定年退職を待たず今月末で「自己都合」により退職する公立学校教員が、県採用分で89人に上ることが21日、わかった。
県費で退職手当が支払われるさいたま市採用の教員も、21人が同様の予定という。県教育局の担当者は「例年、定年退職者が年度途中で辞めることはほとんどない。異例の事態だ」としている。該当教員がいる学校では後任の確保の対応に追われている。
県によると、今年度の県の定年退職者は約1300人(県警を除く)。このうち1月末での退職希望者は教員が89人、一般職員が約30人の計約120人となっている。
改正国家公務員退職手当法が昨年11月に成立し、総務省が自治体職員の退職手当引き下げを自治体に要請。埼玉県では県議会が昨年末に改正条例を可決し、2014年8月までに平均約400万円が段階的に引き下げられる。改正条例は2月1日から施行され、今年度の定年退職者は3月末まで勤務すると、平均約150万円の減額となるという。2月1日の施行について、県人事課は「速やかな実施が必要」と説明している。
バレー部顧問、停職後も体罰…校長は「隠蔽」 01/11/13(読売新聞)
大阪市立桜宮さくらのみや高校の2年男子生徒(17)が、バスケットボール部顧問の男性教諭(47)から体罰を受けた翌日に自殺した問題に絡み、市教委は体罰で停職3か月の懲戒処分を受けた同高のバレーボール部顧問の男性教諭(35)が、復帰後にも体罰をしていたと発表。体罰が蔓延していた同高の実態が明らかになった。
10日の市教委の発表によると、同高のバレーボール部顧問の男性教諭は2011年に部員6人への体罰で停職3か月の懲戒処分を受けていた。3か月間の研修を受けた後、顧問に復帰したが、昨年11月になって同部員の1年男子生徒の頭を平手でたたく体罰をしていた。
バスケットボール部の男子生徒の自殺を受け、同高が今月9日に開いた非公開の保護者説明会では、保護者がバレー部顧問に対し、「まだ体罰をしているのではないか」と詰め寄る場面があったが、バレー部顧問は明言しなかったという。
終了後の記者会見で、この際のやりとりについて質問された佐藤芳弘校長の説明があいまいだったため、市教委の担当者が会見を中座してバレー部顧問に確認した。このとき、バレー部顧問が「処分を受けて以降は(体罰は)やっていない」と答えたため、その内容を記者団に伝えていた。
翌10日、市教委が改めて佐藤校長に事実関係を確認したところ、佐藤校長は体罰の事実を当時から把握していたと告白。市教委に対して佐藤校長は「顧問が反省しており、本人の将来への影響も懸念した」「次に体罰があれば伝えるつもりだった」と話したという。
市役所で10日夜に開かれた記者会見で佐藤校長は、虚偽報告について「生徒への注意喚起のために、頭をはたいていたもので、軽微な体罰だと判断した。報告すれば、停職処分を受けているので(次は)より重い処分内容になると心配した」と説明した。
市教委は、佐藤校長とバレー部顧問の行為について、「隠蔽ととられても仕方がない」として、懲戒処分を検討している。
スポーツ界では体罰の程度はあるけれど存在してきたこと。試合に負けて殴られたことも経験した。ただ、時代は変わっているし、
自殺した理由が明らかな証拠として残った事がなかったから注目を浴びなかったのだと思う。
多くの人間は強くない。たとえ未来の結果が良くなるとわかっていても自分の意思で自分を苦しめたり、苦しい選択を選ばない。
だから体罰による恐怖や苦しみを与え、恐怖や苦しみから解放されるためにに厳しい練習に耐えたり、何があっても試合に勝つようにさせると思う。
しかし極端なやり方は現代に育った子供には耐えられないと思う。多少の苦しみや悩むことが壁を乗り越える条件であっても、過保護に育てられた場合、
または、本人が望んでいない場合、壁を乗り越えられない。壁を乗り越えた者と乗り越えられなかった者の評価や結果への報酬をあいまいにしようとする
社会に進んでいる。過去と現在、昔の日本の考え方と西洋的な考え方、弱肉強食の時代とある程度満たされた時代、いろいろな要素が絡み合って
変わりつつある。間違っていることを黙認して少しでも変えていこうとしなかった結果が今回の自殺の形となって現れただけだと思う。
高2自殺で「意識甘い」、橋下市長が直轄調査へ 11/09/12(読売新聞)
大阪市立桜宮高校の2年男子生徒(17)が、所属するバスケットボール部顧問の男性教諭(47)から体罰を受けた翌日に自殺した問題で、橋下徹市長は10日、市教委や学校による調査を「ずさん。意識が甘すぎる」と批判し、市長直轄の調査チームを設置する方針を表明した。
同高だけでなく、全市立小中高校(計452校)で体罰の有無に関する一斉調査を実施するとし、「調査チームは100人規模にして、1000万円の予算を付ける」と述べた。
市役所で記者団の取材に答えた。同高のバスケ部顧問を巡っては2011年9月、「体罰が横行している」との電話が市の公益通報の窓口に寄せられたが、当時の校長はこの顧問を含む各運動部の顧問から話を聞いただけで、生徒には聞き取りをせず、「体罰はなかった」と判断していた。
昨年12月23日に男子生徒が自殺した後の市教委の調査についても、橋下市長は「遺族側の言い分と食い違いがある。責任者がわからない市教委の今の調査態勢では、実態解明は全くできない。僕が陣頭指揮をとらないとダメだ」と明言。市教委は既に弁護士5人による市の外部監察チームと共同調査に乗り出しているが、橋下市長は市教委に対し、人員の規模を拡大し、全校での一斉調査を指示した。
これが事実なら教育施設の指導者としては最低な人間だ!実力が全ての世界もあるが、指導者としては
彼のような人間を受け入れるべきでなかった。
内柴被告、後輩の警察官に騒動収束を依頼「性行為、見てないよな」(1/2ページ)
(1/2ページ) 11/28/12(産経新聞)
指導していた大学の女子柔道部員を合宿先で乱暴したとして、準強姦罪に問われた2004年アテネ、08年北京両五輪柔道金メダリスト、内柴正人被告(34)に対する被告人質問が、28日に東京地裁(鬼沢友直裁判長)で行われる。27日の第4回公判では、大学の後輩の警察官が証言。内柴被告から「事件を落ち着かせてくれ」と助けを求められたことなどを明らかにしたが、内柴被告本人がどんな発言をするか注目される。(サンケイスポーツ)
27日に証言した警察官の男性は、事件直前の焼き肉店での飲食、その後のカラオケ店で内柴被告、部員らと同席。事件後、内柴被告から「休みを使ってこっちへ来て、この事件を何とか落ち着かせてくれ」「カラオケで性行為しているところとか見てないよなあ」などと、助けを求める連絡があったという。
前日26日の第3回公判では、内柴被告が指導していた九州看護福祉大(熊本県玉名市)女子柔道部の男子コーチが証言に立ち「口裏を合わせてでも、本当も嘘も使ってでもかばってほしかった」と“恨み節”ともとれるメールを、事件後に内柴被告から送られたと証言している。
両日の2人の証言から、事件後の内柴被告が、後輩たちに自分に有利な証言をしてもらおうと必死だった様子が浮き彫りになった。
26日の後輩コーチの証言では、事件後に大学から解雇された内柴被告の夫人が、私物の荷物を引き取りに来た際、夫人から他の人を通じて「怪しいものは処分してくれないか」と頼まれたとしていた。
具体的にはシャワー室に隠してあったコンドーム、師範室に隠していた性的器具、放送室にあったわいせつなDVDなどのことで、後輩コーチが処分したという。
注目の被告人質問が行われる第5回、6回公判は28、29日の2日間、東京地裁で最大規模の104号法廷(関係者席含む傍聴席数98)で午前10時から開かれる。ロッキード事件、オウム真理教事件なども裁かれた大法廷で、内柴被告からどのような発言がなされるのか、注目される。
不況や就職難も問題を悪化させていると思うが、それ以外にも問題があるのではないのか。
好きな事を勉強するために大学や専門学校へ行く選択もあるが、就職に有利なため、時代と共に求められる知識や技術は変わるが必要とされる知識や技術を
学び、比較的に良い収入を得るために大学や専門学校へ行く選択があることを学生に高校入学時に説明するべきである。
大卒や専門学校卒だから簡単に就職できる時代は来ないだろう。グローバリゼーションが加速する事はあっても、交代する事はない。
企業だって、利益を出せる人材を求めるし、正社員を簡単に解雇できないのであれば、簡単に採用しないであろう。
多くの学生がどの大学や専門学校を卒業すれば支払った学費及び勉強に費やした時間の元が取れるのか真剣に考えるようになれば、必要とされない
大学や専門学校は淘汰される。文科省は必要とされない学校に補助金など支給する必要はない。厳しい競争の中では、企業は高卒とか大卒の肩書などは
必要としない、どの学校を卒業すればある一定の能力や知識が保証されるかのほうに関心があるだろう。
一部の天才を生み出す学校、平均的にある一定の能力を持つ卒業生を生み出す学校、いろいろなスタイルがあっても良いと思う。早い時期に生徒に
将来を考える機会を与えればよいと思う。将来についてあまり真剣に考えない生徒がいても良い。その生徒が大人になり、結婚して子供を持った時に
将来についてあまり考えなかったから今の自分の状況を受け入れないといけないと思えば、少なくとも子供に対しては同じ過ちをさせないように思うだろう。
何十年も時間が必要かもしれないがそれで良いだと思う。急に新しい取り組みをしてもすぐに結果として表れない事もある。奨学金問題を単に不況や就職難を
理由だと思って対応してきているから、現状のような問題のままではないのか。大学や専門学校を卒業しても卒業しない生徒と結果として変わらないのであれば、
奨学金を借りた生徒の問題と進学しない選択についても考えさせるべきでないのか。自己破産する若者が急増しているのなら、進学しない選択も選択の1つで
あることを説明した方が良い。
奨学金問題:全国組織が31日発足…返済苦しむ若者急増で 03/27/13(毎日新聞)
不況や就職難で奨学金が返済できず、厳しい取り立てを受けたり、自己破産したりする若者が急増しているとして、全国の学者や弁護士らが「奨学金問題対策全国会議」を31日に発足させる。背景には、学費高騰や学生支援組織の独立行政法人化などがあり、支援者らは「本人の努力だけでは解決できない社会問題だ」と訴えている。奨学金問題で全国組織が結成されるのは初めて。
独立行政法人・日本学生支援機構(旧日本育英会)によると、2011年度の同機構の奨学金利用者は128万9000人。大学や専門学校に通う学生の3人に1人が利用している。同機構の奨学金に給付型はなく、卒業後に返済が必要だが、就職難や非正規雇用の増加で返済が遅れる利用者が続出。延滞者は03年度末から11万人増え、11年度末で33万人にのぼる。
追い打ちをかけたのが、独立行政法人化による回収の厳格化だ。同機構は10年度から、3カ月滞納した利用者を銀行の個人情報信用機関に登録(いわゆるブラックリスト化)し、4カ月目から民間の債権回収会社(サービサー)に委託している。その後は裁判をし、11年度だけで給料差し押さえなど強制執行は135件にもおよぶ。
全国44の弁護士会が2月に実施した奨学金に関する初の電話相談には計453件が寄せられ「生活苦で返済できない」が42%で最多だった。対策会議設立の母体は80年代から多重債務者を救済してきた全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会。対策会議事務局長(予定)の岩重佳治弁護士は「学生の将来をひらくための奨学金が、将来をつぶすことになっている。学生支援のあり方を含め、社会全体で取り組む必要がある」と話す。
対策会議の設立集会と記念シンポジウムは31日13〜16時、東京都千代田区六番町の主婦会館プラザエフで。問い合わせは、東京市民法律事務所内の事務局(03・3571・6051)。【浦松丈二】
「大学減なら質向上」とは言い切れない。問題がある大学は廃止にすればよい。それが結果として「大学減=質向上」となる場合もあるだけである。
短大卒では就職できない→よって、4大に進学する人が増えた。結果として短大の需要がなくなった。
景気が悪い→よって卒業生の能力に期待できない4大からの生徒を取らない。就職できない学生が多い大学を敬遠する。
需要のない、必要のない大学の廃止→よって、大学職員、講師、教授そして関係者は職をなくす。(この状況を回避したい関係者が役所に泣きつく!)
大学に入学してくる生徒の基礎学力が低いから大学が困っているのなら、なぜ学生の基礎学力が低くなる政策をとった
文部科学省を批判してこなかったのか?自分達が被害を被るまで問題を放置してきただけだ。
生徒の進学率とか、学ぶ機会を与えるとか言うのであれば、短大卒の学生で成績優秀で4大に進学したい場合には、推薦の形で4大に簡単に
進学できるシステムを構築するべきだ。アメリカでは学費の問題、住居周辺で働きながら学びたい場合は、学費の安いコミュニティーカレッジで
基本的な授業を取り、3年生として4大で転校して学位を取れるシステムになっている。生徒が本気で学びたいのであれば、合理的で
経済的である。夢だけは大きいが、努力をしない生徒は4大に進学できなかったり、進学を諦める。自分に厳しくなければ目標を達成できない。
それで良いではないのか。大学の教授達が大学減に反対していることが実に滑稽である。生徒のためと大義名分を使いながら、
自分達のためにやっているように思える。
補助金で支えられた「大学バブル」の終わり 11/09/12(ニューズウィーク日本版)
田中真紀子文部科学相が来春開校する予定の3大学の設置を認可しなかった騒ぎは、一転して白紙撤回で収拾されたが、大学が大きな問題を抱えているという彼女の問題提起は正しい。学校教育は今や農業と並ぶ補助金産業であり、今年度は国立大学法人と私立大学に合計1兆4800億円の補助金が支給されている。農業と同じように、補助金は産業を腐らせるのだ。
人材の育成は政府の重要な仕事だが、今の大学がそういう役割を果たしているかどうかは疑わしい。教育の効果についての調査としてもっとも大規模な世界銀行の実証研究によれば、教育投資と経済成長率にはまったく相関がない。労働者の技能が上がらないのに大卒の賃金が上がるのは、大学が能力を示すシグナリングの装置として機能しているからだ。したがって学歴の私的収益率は高いが、大学教育は社会的には浪費だ、というのが多くの実証研究の示すところである。
大学で差別化できないと、大学院への進学率が高まる。アメリカではこのような大学バブルが問題になっており、ここ30年で高等教育への家計支出は4倍以上になり、学費のローンが自動車ローンを上回って家計を圧迫している。日本でも、学齢期人口が減少している中で大学が20年で260校も増えたのはバブルである。「大学院重点化」は無名大学から有名大学の大学院に入る「学歴ロンダリング」の温床になり、法科大学院は廃校が相次いでバブルの崩壊が始まっている。
これは大学の競争を促進しようとして設置基準が緩和されたためだが、新規参入は増えたが退出はほとんどなかった。定員割れになっている私大の赤字を私学助成で補填してきたからだ。また今回いったん不認可になった秋田公立美術大学のように、就職の当てのない大学を自治体が経営するケースも多く、この場合は赤字を地方税で補填している。
このように日本の大学は補助金に守られて競争がないため、教師にも学生にも競争原理が働いていない。世界的には、大学の教師は任期制で、終身雇用資格(テニュア)をもつのはごく一部だが、日本では准教授になると自動的にテニュアが与えられ、定年まで1本も論文を書かなくても授業さえやっていれば身分を保障される。成績評価も甘く、入学さえできれば卒業できるため、学生もまじめに勉強しない。
学歴を求めて大学生が増えすぎた結果、大卒の就職内定率が8割という状況が続いている。リクルートワークス研究所の調査によれば、2013年大卒に対する大企業の求人倍率は0.73倍なのに対して中小企業は1.79倍。全体では1.27倍と需要超過なのに、大学生が大企業に就職しようとするため「無業者」になってしまうのだ。
企業は大学で何を勉強したかにはほとんど関心をもたないので、大学1年の4月2日に内定を出すユニクロのような企業が合理的だ。大企業の人事部が採用するのはMARCH(明治・青山学院・立教・中央・法政)クラスまでで、定員割れになっているような私大に行くことは、機会費用(4年間の学費と賃金)を考えると、私的収益率もマイナスになるおそれが強い。
今のような劣化した大学は人材育成に役立たないばかりでなく、「大学教授」という非生産的な労働に多くの知的労働者を囲い込んで人的資本にマイナスになっている。もちろん哲学や天文学などには文化的な価値もあるが、そういう機能は今の大学の1割ぐらいだろう。大部分の大学はアカデミズムの飾りを捨て、実務教育に徹するべきだ。
人材育成のためには今のように大学に一律に補助金を投入するのではなく、学生に対して成績に応じた奨学金として出すことが望ましい。大学にも競争を導入し、教師にも一律に雇用を保障するのではなく、有期雇用にして業績評価を徹底すべきだ。田中文科相の問題提起を、政府も大学関係者も真剣に受け止める必要がある。
文科省が認可した大学でも、続々と定員割れになっている - 問題の本質は田中真紀子大臣の不認可ではない 11/09/12(みんなの心にも投資 … ソーシャルインベスター(社会投資家)への道)
日本では教育問題の議論が常に目先のことばかりで
利害関係者の方では必死に姑息な情報操作を行い、
しかもメディアや国民がそれを見抜けないという情けない状況にある。
(例えば「大学生の学力低下」「日本の教育予算は少ない」等は見え透いた情報操作)
今回問題になった中で看護系は確実にニーズがあるから別として
他の2大学はもとは地方の短大であり、四大になれるかどうかに
組織と職員の雇用の存亡がかかっている。
秋田と愛知で強硬な反発があった理由はそこにある。
どうしてメディアは地方短大の不人気や経営難を報じないのか。
特に秋田は90年代に公立美術短大を設置するという賭けに出たために
頑として誤りを認めない自治体の常として、何としても四大にし
自己の政治責任を問われないようにしたいのである。
秋田公立美短の実質倍率や就職率を見れば、
秋田県の抱く危機感は手に取るように分かる。
文科省や審議会をうまく抱き込んで面子を保てる筈だったのに、
最後に引っくり返されたからあれほど居丈高な怒りを見せたのだ。
文科省の審議会や認可が大学の質向上において
殆ど無意味に近いのは、議論の余地のない明白な事実である。
田中文科相の指摘する通り、審議会は教育界関係者に牛耳られており
原子力ムラと同様、ほぼ関係者の思惑通りに進行するのが常である。
だから文科省が認可した大学でも次々と定員割れと経営危機を起こしている。
最近では法科大学院の惨状は100%間違いなく文科省の制度設計に原因がある。
アメリカの大学の経営管理に詳しい諸星裕氏は、
これから日本では次々に大学が破綻する時代になると予言されている。
文科省はそもそも大学教育の質や大学運営の質を評価する指標を持たないし、
指標に基づいて政策調整しなければならないとの意識が全くない。
計量経済学や計量社会学の専門家を雇い、
若年人口の変動が大学経営に与える影響を測定し、
労働市場の変化と人材需要に基づいて政策決定をしなければ
日本の大学は悲惨な状況に追い込まれてゆくだろう。
日本より授業時間が少ない欧米と比較して日本の大学生の勉強時間が少ないとして
愚劣な責任転嫁を平然と行う中教審の議論の「猫の目ぶり」を見れば
文教政策が頭の悪い「モグラ叩き」でしかないことは明白だ。
↓ 参考
大学生に責任転嫁する中央教育審議会、自らの分析不足を認識せず -「勉強時間」しか判断基準がない貧弱さ
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/62943717b497b8613c43f5d980ed62b1
東大が海外留学生に蹴られ、欧米有力大学への劣後が明確に - 秋入学効果を盲信する愚かな論者に警鐘
http://blog.goo.ne.jp/fleury1929/e/326d77615f6ee0bfbc1f72f8f9c0c145
クローズアップ2012:文科相、3大学再審査へ 猛反発で一転「決断」 「問題提起」手法に疑義(毎日新聞)
http://mainichi.jp/opinion/news/20121107ddm003040066000c.html
”大学設置・学校法人審議会の答申を覆し、3大学の開設を不認可とした田中真紀子文部科学相の「政治判断」は、来春開学の準備を進めていた大学側から猛反発を受けている。田中文科相は6日、新基準で再審査する考えを示し、事実上救済する方針に転換した。文科省は早急に具体的な手続きを検討するが、従来の手続きを無視する強引な田中文科相の手法に各方面から批判の声が上がっている。【石丸整、田原翔一、福田隆、駒木智一】
田中文科相は6日、記者会見を終えた後、再び会見場に姿を見せ、一転して3大学の再審査に言及した。文科省幹部によると、同省12階の会見場からエレベーターで移動したところで森口泰孝次官から「言い忘れたことはありませんか」と問われ、思い返して会見場に向かったという。
田中文科相が3大学の不認可を表明したのは11月2日。省内では3大学の不認可を回避するため複数の案を作成し、5日に森口次官が大臣室に入ったという。混乱する事態の収拾を図ろうとしたとみられる。
同省幹部によると、新たな検討会は、今週中に財界人など幅広い分野からメンバーを人選。田中文科相の了承を得た上で今月中に発足させ、財務状況や学生の募集状況の見込み、地域から要請があるかなど、現行より厳しい基準を設ける。その後、田中文科相が認可を最終判断する。年内の判断なら、来春開学に間に合う目算だ。
だが、金子元久・筑波大教授(高等教育論)は「3大学を再審査するというが、認可されない可能性もある」と指摘する。
◇
田中文科相の「問題提起」は、大学数の多さや審議会の在り方だ。この日の記者会見でも「乱立に歯止めをかける」と述べた。「方法に問題はあるが、問題提起は正しい」という声もある。
規制緩和の流れを受け、03年度から文科省が大学新設の抑制方針を撤廃したこともあり、大学数は増加。00年に649校だった4年制大学は12年で2割(134校)増の783校となった。同省は今年度から財務情報や学生の就職情報を公開していない大学・短大への助成金を減額しており、定員割れなど経営難に陥っている大学の統廃合を促している。
検討会では来年度以降の大学設置・学校法人審議会の在り方についても検討。田中文科相が「メンバーのほとんどが大学の学長、教授で数カ月に1回しか開かれていない」と問題視したからだ。
同審議会の委員29人のうち、22人が大学関係者で占められ、秋田公立美術大など3大学についての審査は4~10月に計9回開催している。だが、同審議会委員でジャーナリストの柴崎信三(しばさきしんぞう)氏は「審議会は設置基準に適合しているかを審議する場。校舎を建設中でも、準備が間に合わないようなら認可を出さないケースも多い」と説明する。
今回の一連の動きに金子教授は「小規模な新規の大学を不認可とするより、既存の大学の教育の質を上げる方が大切で正当な方法だ」と、田中文科相の対応を批判する。〔以下略〕”
毎日新聞の記事が最も鋭い。
大学乱立は自民党政権時の愚かな規制緩和の必然の結果である。
進学先がなくなるかもしれない生徒の抗議の声ばかり取り上げて、
そもそも地方短大や地方美大の深刻な就職状況を無視するメディアも
教育政策のリテラシーが低過ぎると言わざるを得ない。
「既存の大学の教育の質を上げる方が大切」との主張は結構なことだが
そうすると大学の教職員の既得権をある程度破壊せざるを得ないのを
分かっているのだろうか。
▽ 北欧の大学は社会のニーズを見て大胆な再編を行い、教職員の解雇も日常茶飯事
私大の46%が定員割れ 東北では入学者1割減(朝日新聞)
http://www.asahi.com/national/update/0827/TKY201208270399.html
”今春、入学者が定員を下回る「定員割れ」となった4年制私立大学は全体の45.8%にあたる264校で、前年より6.8ポイント増えた。東北地方では、入学者が約1割減った。日本私立学校振興・共済事業団が調べ、27日発表した。
5月1日現在で、通信制などを除く577校が対象。全体の入学定員計45万5790人に対し、入学者は前年度比1.5%減の計47万4892人。定員に対する入学者数の割合を示す定員充足率は、過去最低の104.2%だった。
特に東北地方は、入学者が9.3%減の1万3313人と、落ち込みが目立った。同事業団は「東日本大震災の影響も考えられるが、明確な要因は分からない」としている。〔以下略〕”
これが周知のように定員割れ私大の悲惨な状況。
勿論、全て文科省が認可を出した大学である。
「既存の大学の教育の質を上げ」ても間に合う筈がない。誰にでも分かる話である。
法科大学院の次には教職大学院でも問題が発生するだろう。
今回認可が出された3大学にしても、喜ぶのは早計である。
10年後、20年後には悲惨な経営難に陥る可能性がある。
ただ秋田の美大だけは公立なので近隣の私立美大が生徒を奪われ潰れる可能性がある。
アイディアはすごく良いし、他の国立大学と同等の学費で英語の講義が受けられるのならお得だと思う。
ただ実施は無理だと思う。英語がかなり得意でないと授業について行けないだろう。英語の専門用語で理解した場合、
日本語で何と言うのかわからないと思う。外資系やグローバルな企業での就職を考えているのなら良いが、
それ以外の企業での就職を考えている場合、頑張って卒業しても英語の能力を使うことは希だろう。
講義を行う講師は英語が話せるのか、話せない講師や教授は大学を去ってもらうのか?
事前に英語で講義内容を準備して音読するだけでは意味がない。医学、工学、生命環境学、教育人間科学を英語で
学ぶだけの能力がある生徒はもっと知名度が高く、卒業生が活躍している大学を選択する可能性は高い。入学する学生の
レベルを下げれば、英語での授業は成り立たないだろう。英語の勉強だけでもオーバーロードになることは間違いない。
簡単に英語の授業を受けて理解できるのであれば、アメリカの大学に入学した日本人留学生達は苦労しない。
まあ、理系で全ての講義を英語で受けて卒業したとすれば、国際教養大(秋田市)の卒業生達よりもほしい企業にとっては
魅力的な学生達になるだろう!就職に有利どころではなく貴重な生徒達の奪い合いになるだろう。留学して英語を話せる
日本人留学生達よりも優秀であると考えられる。
ほぼ全講義を英語化する国立大…学生は「不安」 10/06/12(読売新聞)
山梨大(甲府市武田)は2016年度までに、ほぼすべての講義でテキストを英語の書籍とし、英語で講義することを決めた。
全学的な講義の英語化は、国際教育に特化した大学を除けば極めて珍しい。専門性の高い分野では、学生への負担増も課題となりそうだ。
同大総務課によると、英語化するのは、日本文学など日本語の使用が必須な科目を除く全講義。来春から段階的に導入し、4年後をめどに完全移行する。
段階的導入には、教員が英語で指導する準備期間を確保することや、一斉導入による学生のテキスト購入費の急増を避ける狙いがある。入試でも、早ければ16年実施の試験から、全学部の2次試験に英語を課すなど、比重増加を検討する。
英語化は、前田秀一郎学長や理事、学部長など10人で構成する「グローバル化推進会議」で10月に決定。既に大学院では、一部の講義の英語化を始めており、同課は「グローバル化に乗り遅れることなく、優秀な人材を育てる環境を整えたい」と説明する。
文部科学省大学振興課によると、全学的に講義を英語化し、英語の授業だけで卒業が可能な大学は、国際教養大(秋田市)の例があるが、「ほかには把握しておらず、珍しいのではないか」としている。
山梨大は医学、工学、生命環境学、教育人間科学の4学部。同大総務課は「元々英語の方が講義を進めやすい科目も多く、英語化はしやすい」としている。
これに対し、学内の意見はさまざま。ある男性教員は「日本語の教材よりレベルが高く適切な英語教材があれば、既に使っているはず。今の学生の英語力では、4年後の移行は正直難しいだろう。特に何も変えるつもりはない」と冷ややかだ。教育人間科学部4年の男子学生(23)は「英語を重視した特色のある大学として、就職の時に有利になるかも」と話し、工学部1年の女子学生(18)は「いきなり英語になっても、授業の内容を理解できるか不安」と漏らした。
生徒の月命日、市教委職員「パーティーですか」 10/06/12(読売新聞)
浜松市の自宅マンションから転落死した同市立中学2年の男子生徒(当時13歳)がいじめを受けていたとされる問題で、生徒の月命日にあたる9月12日、遺族宅を訪れた市教委の担当者が、集まっていた遺族や友人らに対し、「きょうはパーティーですか」と発言し、その後謝罪していたことが5日、わかった。
遺族によると、市教委の担当者2人が「手を合わせに来た」と遺族宅に弔問に訪れ、そのうちの1人が生徒の母親らに「きょうはパーティーですか」などと発言した。担当者は今月5日、遺族に電話で「申し訳なかった」などと謝罪したという。
この担当者は取材に「たくさん人がいたので、『パーティー』という言葉を使ってしまった。お母さんの心を傷付けて申し訳ない」と話している。
生徒の父親は「いじめについて、私たちが我慢して第三者委員会に調査を託している中で、学校の上にいる人たちからそういう発言が出るのは理解できない」と不快感を示している。
文部科学省「道徳教育実践研究事業」の指定を受けた滋賀県大津市立皇子山中学校の校長及び
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)は教育関係者達であっても偽善者で人間としては最低レベルであることが示したと思う。
偽善者である教育者が教育専門家として「子供のため」とか言い訳をつけながら実は自分達の都合や自己主義のために行動していることを
大人達でけでなく子供達にニュースを通じて認識させてくれた。「学校の校長だから信用できる。」とは言えないことを<
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)の職員達までが関与した隠蔽で多くの日本人に認識させたと思う。
また、教育委員会制度の廃止または改革の必要性を
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)を多くの日本国民に認識させた。組織ぐるみでの隠蔽。問題は深い!
「いじめ情報」学校放置? 大津 自殺直後の教師メモ 09/20/12(京都新聞)
大津市で昨年10月、中学2年の男子生徒が自殺した問題で、自殺直後、複数の生徒が「定規を割った」など男子生徒へのいじめを疑わせる情報を教師に伝えたにもかかわらず、放置された可能性が高いことが19日、市教育委員会への取材で分かった。
市教委によると、学校が全校アンケートを行う4日前の昨年10月13日から14日にかけ、2年生約20人が教師約10人に情報を寄せていたことが、教師のメモから明らかになった。学校は内容を市教委に報告していなかった。
うち4人の証言は「移動教室のときに荷物を持たされていた」「机の中の物を出して拾わせていた」「眼鏡を取って投げた」など、アンケートにも記述がない事案だった。当時、学校が4件について事実確認したかはわからないという。
また「10月5日 会議 いじめの可能性」と書かれた市教委職員のメモが残っていたことも新たに判明。男子生徒への暴力をめぐり、昨年10月5日夜に担任ら13人の教師が集まり、うち3人がいじめを疑う意見を述べた協議について、電話で聞き取ったメモとみられる。聞き取りは同17日に行われたが、情報共有されなかった。
滋賀県警に押収されていた資料のコピーを市教委が取り寄せた8月下旬以降、精査する中で明らかになった。
文部科学省は不法就労を目的とした留学生の受け皿となる以外で経営が成り立たない
山口福祉文化大学(ウィキペディア)
に税金をつぎ込むべきでない。留学生の失踪や不法就労が相次ぎ、広島入国管理局が中国人留学生127人に対し在留資格認定証明書を交付しないことを決定したことが
過去にもある。終わりにすべきだ!
サテライト教室不備で規制強化へ 09/04/12(NHK)
山口県にある私立大学「山口福祉文化大学」が東京に設置しているサテライト教室について、学生数に合った講義室や図書館が設けられていないなど、法令で定める要件を満たしていないことが分かり、文部科学省は大学に改善を指導するとともに、サテライト教室の規制を強化することになりました。
指導を受けたのは、山口県萩市に本校がある「山口福祉文化大学」です。
文部科学省によりますと、大学が東京・墨田区に設置しているサテライト教室には、萩市にある本校に通う学生171人の3倍を超える600人余りの留学生がいますが、学生数に見合った講義室や図書館、それに医務室といった法令で定める要件を満たしていないことが分かりました。
サテライト教室は、主に地方の大学が、社会人などが学びやすいよう利便性の高い都市部に設けていますが、この大学のサテライト教室の学生は、ほとんどが中国からの留学生だということです。
文部科学省は「サテライト教室が本来の目的に使われておらず、不法就労を目的とした留学生の受け皿になるおそれもある」として、来年にも大学の設置基準を改正し、規制を強化することになりました。
文部科学省は、近く中教審=中央教育審議会の分科会で議論を始めることにしています。
山口福祉文化大学とは
山口福祉文化大学は、地域活性化の切り札として、山口県と萩市から合わせて40億円の補助を受けて平成11年に開校しました。
開校当初から定員割れが続き、学生を確保するため、中国から大量の留学生を受け入れましたが、入学後に行方が分からなくなるケースが相次ぐなど経営状態が悪化し、平成17年に民事再生法の適用を申請しました。
その後、平成19年に名称を山口福祉文化大学に改め再建を目指しましたが、地元では学生が集まらないため、東京にサテライト教室を設けて留学生を受け入れていたということです。
それでも、ことし6月には資金繰りに行き詰まり、2度目の民事再生法の適用を申請し、現在、福島県郡山市の専門学校を運営する学校法人の支援を受けて再建に取り組んでいるということです。
東京サテライトに本校の3・5倍、606人在学 09/04/12(読売新聞)
山口福祉文化大(山口県萩市)が、文部科学省が定める校舎の要件を満たさない東京都内のビルに設置したサテライト教室に、606人の学生を通わせていることがわかった。
このうち605人は中国人など留学生で、文科省は改善を指導した。同省は都心部に開設されたサテライト教室が不法就労の受け皿になる恐れもあるとみて、他の大学が開く同教室の実態調査にも乗り出す方針を固めた。
同大は社会福祉系の4年制単科大。同大によると、5月現在、萩市の本校に171人、東京都墨田区と広島市内のサテライト教室にそれぞれ606人、43人が在籍している。墨田区のサテライト教室の学生数は本校の3・5倍に上り、606人のうち、中国人が536人と大半を占める。ほかはネパール人が27人、ベトナム人が11人など。
大津いじめが注目を受けて、県教委のずさんさが注目されるようになった。良いことだ。
「和歌山県の県立高校で、PTA会費などの保護者徴収金が、本来は公費を充てるべき教員の出張費や校舎修繕費などに支出されていた問題」に
ついて「西下博通教育長らは、『保護者の意向を受けてやってきた』」と会見で言った。どのようにして「意向」を確認したのか??
公式に公表したり、使途目的を説明したのか??行っていないなら西下博通教育長は詐欺師に近い人間だ。詭弁は詐欺師と似たようなもの。
PTA会費流用、「保護者の意向だ」と教育長 09/01/12(読売新聞)
和歌山県の県立高校で、PTA会費などの保護者徴収金が、本来は公費を充てるべき教員の出張費や校舎修繕費などに支出されていた問題で、県教委が実施していた調査結果が発表された30日、記者会見した西下博通教育長らは、「保護者の意向を受けてやってきた」などとして、過去の支出が不適正だったかどうかは明言は避けた。
一方、PTA会費からの支出を減らして保護者の負担を減らすために新たに使途基準を示したが、その運用にはあいまいな点が残った。
この日の記者会見で、県教委側は「学校の管理運営・教育活動に必要な経費については、設置者である県が負担することが原則」と基本的なスタンスを示した。その一方、2010年度に保護者徴収金から約3億円が学校運営などに支出されたことについて、西下教育長は「これまでの慣行。保護者の意向を受けてやってきたつもり」と弁解。他の県教委幹部も「(生徒のために使われており)特に問題はなかった」などと繰り返した。
こうした支出の8割程度は県費で賄えるとみて、今年度内の補正予算で不足分を補っていくとした。だが、全日制学校に通う生徒1人当たり平均約2万3000円の徴収金を減額できるかどうかについては、県教委幹部は「各校のPTAの判断」と明言を避けた。また、校長名で支払いを求めるなど、半ば強制的に行われてきた会費の徴収方法は、「今後学校に指導していく」と述べた。
新たな基準では、部活動の充実や地域交流など、特色ある事業に限って、PTAなどから自発的な提案があれば、支援を受けられるとした。クラブ活動や進学など各校が特色ある教育方針を打ち出せる余地を残したが、具体的な内容はまだ不明な点が多い。
県教委の関係者らからは、「あいまいな点も残り、出張費などで今まで通りの使われ方をする可能性もある」と心配する声もある。
一方、文部科学省財務課の担当者は「会費から支援を受けられる経費について、具体的な例を示したことは使途の透明化を図る上で評価できる」と話した。
大津いじめ:「調査委委員が家庭情報漏らす」遺族側抗議へ 08/24/12(毎日新聞)
いじめを受けた大津市立中学2年の男子生徒(当時13歳)が自殺した問題で、市が25日に初会合を開く外部調査委員会の委員に内定している滋賀県臨床心理士会会長の野田正人氏が、生徒の家庭に関する個人情報を入手し、第三者に漏らしていたとして、遺族側が24日、市に抗議文を提出することが、関係者への取材で分かった。委員としての適格性を問題視しており、外部調査委が開催延期を含め紛糾する可能性が出てきた。
外部委の委員は市と遺族側が3人ずつ推薦する異例の形式で設置され、野田氏は市側推薦の一人。外部委の設置目的は「学校で起きたいじめなどの事実解明」と要綱で定めている。遺族側代理人によると、漏らされた個人情報は県子ども家庭相談センター(児相)に生徒の父親が相談した内容といい、「調査に関係のない家庭の情報で先入観を持って調査にあたる委員の中立性は疑わしく、委員就任に際して市が公平・公正な調査を求めた要綱に違反する」などと批判している。
「市教委は当初、『故意ではなかった』などと説明していたが、事実と違った理由について、市教委幹部は『対応した職員がきちんと理解しないまま、説明してしまった』と釈明している。」
まともな言い訳を考えろ!
越 直美市長(大津市のHP)、
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)はいじめの対応に問題があるだけでなく、事実確認及び報告さえも出来ない職員達がいることは明らかだ。
このことを認識して対応して欲しい。
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)は対応した職員の能力を評価して、問題があれば諭旨免職にするべきだ。まともに仕事もできない職員を
抱えていては更なる犠牲者や被害者が生まれる。問題のある職員を免職にしても、新しい仕事を探せば良いだけの話。
大津いじめ、女性担任蹴り骨折「故意」と市教委 08/24/12(読売新聞)
昨年10月に自殺した大津市立中学2年の男子生徒(当時13歳)へのいじめの加害者とされる同級生の一人が今年5月、中学校内で担任に暴力を振るってけがを負わせた問題で、担任の女性教諭が同級生に蹴られるなどして左手小指骨折、脇腹や顔などの打撲傷で全治約1か月の重傷だったことがわかった。
市教委は当初、「故意ではなかった」などと説明していたが、事実と違った理由について、市教委幹部は「対応した職員がきちんと理解しないまま、説明してしまった」と釈明している。
市教委によると、5月下旬、学校の体育館で翌日に控えた修学旅行の事前指導が行われていたさなか、同級生が急に立ち上がり、帰宅すると言って暴れた。更衣室に向かい、追い掛けて止めようとした担任の女性教諭を蹴ったという。
担任が足を左手で止めようとして小指を骨折。同級生はその後も止められるまで脇腹や顔などを計10回、殴ったり蹴ったりした。市教委は当初、取材に対し、小指骨折は暴れていた男子生徒の足が偶然当たったためで、「担任を狙ったのでなく、故意ではなかった」などとしていた。
学校は6月上旬、担任を交えて協議した結果、被害届を出さないと決定。大津署には経緯を説明したうえで、「同じようなことがあれば、被害届を出す」と伝えた。市教委が今月中旬、改めて聞き取りをした際、担任は「3年生になって、クラスになじめてきつつある。(法的な措置を取るのでなく)担任として見ていきたい」と話したという。
暴力はよくないが、いろいろとシステムの中で守られ、逃げてばかりいる
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)にはレッスンとなったであろう。必殺仕事人ではないが、悪い奴らを裁きをと言ったとことだろうか。
ただ沢村憲次教育長ごときを怪我させたために逮捕されて人生を狂わせる価値はない。いじめた側(加害者)にも人権がある
のだから、相手の気分を害した沢村憲次教育長にも原因はある。行動をおこさないが沢村憲次教育長の対応に怒り、不満、または傲慢さを感じている
人は多いと思う。
大津市教育長、襲われけが 容疑の19歳「許せず」 08/15/12(朝日新聞)
15日午前7時50分ごろ、大津市御陵町の市役所別館2階にある教育長室で、出勤してきた沢村憲次教育長(65)が、若い男に突然、ハンマーで襲われた。教育長は頭を殴られ、右目の上を切る約3週間のけが。病院で手当てを受けたが、意識ははっきりしているという。
大きな声を聞いた市教委の男性職員(28)が男を取り押さえ、駆けつけた大津署員が殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。逮捕されたのはさいたま市の私立大学1年の男(19)。
沢村教育長は市立中学2年の男子生徒(当時13)が昨年10月に自殺した問題の対応をめぐり繰り返し会見を行い、「いじめも自殺の要因の一つと思っている」などと説明していた。
男は「大津市の中学生のいじめ自殺問題に関して、教育長が真実を隠していると思い、許せなかった。殺そうと思った」と供述。容疑を認めているという。
教育長襲撃の学生、どうやって侵入したのか 08/15/12(読売新聞)
大津市のいじめ問題への対応に当たってきた沢村憲次教育長が15日、市庁舎内で襲われるという事件が起きた。逮捕された大学生は「教育長は真実を隠している。許せないと思った」と供述しているという。
市や市教委に批判が相次ぐ中、教育行政トップを狙った今回の事件に、関係者らに衝撃が走った。
沢村教育長は午前7時50分頃、庁舎2階の教育長室に入った直後に襲われた。
大学生はどうやって侵入したのか。大津署によると、居合わせた市教委職員は「(大学生は)教育長の後を付けた」「待ち伏せしていた」などと証言しているが、内容が錯綜(さくそう)しており、はっきりしないという。
いじめ問題への対応で市などへの批判が強まるなか、県警は1日に数回、自殺した男子生徒が通っていた中学校と、市教委が入る市役所周辺をパトカーで巡回していたという。
事件の後、庁舎につながる通路2か所には規制線が張られ、大津署の警察官が現場保存のために立つなど物々しい雰囲気に包まれた。
黒川弥寿夫・教育部次長によると、市教委事務局は盆休みで出勤してきた職員は通常より少なかったが、沢村教育長はいじめ問題への対応などで出てきたという。
黒川次長は自宅にいた同8時15分頃、「教育長が襲われた」との連絡を受け、慌てて駆け付けた。すでに捜査員らが教育長室や周辺の通路などで鑑識活動を行っていた。
黒川次長は「詳しいことはわからないが、暴力は許されない。庁舎の安全管理を見直す必要がある」と言葉少なだった。
越 直美市長(大津市のHP)はいじめに関して徹底的に
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)の改革または廃止に関して国に働きかけるべきだ。
滋賀県大津市立皇子山中学校及び校長そして報告を受けた
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)の対応に問題がありすぎる。このまま問題を放置するべきでない。
〝加害〟同級生、教師にも暴力振るっていた 全治1カ月の重傷も警察に報告せず 08/10/12(産経新聞)
大津市で昨年10月、市立中学2年の男子生徒=当時(13)=が飛び降り自殺した問題で、男子生徒をいじめていたとされる同級生の1人が今年5月、女性教諭に暴行し、重傷を負わせたにもかかわらず、学校と市教委は警察に報告していなかったことが9日、分かった。
市教委関係者によると、5月下旬、同校の体育館で、同級生が暴れていたため、女性教諭が止めに入ったところ手を殴られ小指を剥離(はくり)骨折し、全治約1カ月の重傷を負った。学校側は当日と6月上旬の2回、女性教諭や校長ら複数の教員が集まり協議したが、同級生が反省しているなどとして警察に報告しないことを決めたという。
滋賀県警は7月11日、昨年9月の体育大会で、同級生3人が男子の両手をはちまきで縛り、口に粘着テープを貼ったとして、暴行容疑で、学校と大津市教委を家宅捜索し、関係資料を押収。しかし、学校と市教委はその後も県警に女性教諭が暴行を受け重傷を負ったことを告げていなかった。
市教委幹部は「いじめとは全く関係がない。(同級生の)生徒への指導もしっかり行った。警察に報告する必要はなかった」と話している。
県警は7月26日から男子へのいじめを調べるため生徒らへの聴取を開始。8月中に終え、9月以降に立件の可否を判断する。
女性担任にも暴行、けがさせていた加害者…大津 08/10/12(読売新聞)
いじめを受けていた大津市立中2年の男子生徒が昨年10月に自殺した問題で、加害者とされる同級生の1人が今年5月、中学校内で担任の女性教諭に暴力を振るい、けがを負わせていたことが、関係者への取材でわかった。
市教委によると、学校側は、「本人は反省し、生徒指導の範囲で対応している」として、被害届を出していないという。
県警はいじめに関する一連の捜査でこの暴行についても把握。けがが重傷だとして、担任に、傷害容疑で被害届を出すよう求めたが、「学校が被害届を出さないと決定した」などとして応じなかったという。
市教委によると、学校は、暴行があった当日と約1週間後に、それぞれ校長や生徒指導担当教諭らによる会議で対応を協議、市教委には、約3週間後に報告した。
「根性焼き」は合意による行為と認識…学校側 08/08/12(読売新聞)
仙台市の私立高校の男子生徒(16)が、同級生からたばこの火を腕に押しつけられる「根性焼き」などのいじめを受けたとして仙台東署に被害届を出した問題で、生徒が通う学校の教頭は7日、読売新聞の取材に応じ、「いじめの可能性を否定せず再調査する」と話した。
「他の生徒に動揺を与える」として生徒側に求めていた自主退学は保留扱いとした。
学校の説明では、生徒の保護者からいじめの相談を受け、7月中旬に校内に調査委員会を設置。いじめたとされる生徒に話を聞いたところ、被害生徒が自分でたばこの火を腕に押しつけたなどと説明を受けた。被害生徒も自分から頼んだと説明したとして、やけどは「自傷行為」、または「合意による」と認識したという。
その後、被害生徒が、やけどはいじめによるものと申し出たため、学校側は他の生徒から話を聞くなどしたが、いじめとは認めず、生徒側に今月6日までに自主退学するよう求めたという。学校側は、自主退学に応じなければ退学処分にするとしていたが、被害届が出された6日に行われた保護者との話し合いで、「保護者が納得していない」などとして、再調査と退学処分の保留を決めた。
学校側は、いじめたとされる同級生が7月31日付で自主退学したことも明らかにした。
いじめに関するニュースはテレビで見るが、
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)に対する批判のニュースはあまり見ない。なぜなのか??
教育委員会の問題についてもあまり取り上げられない。メディアよ、なぜ取り上げないのか??
大津の中2自殺、県警が生徒ら聞き取り開始へ 7/25/12(読売新聞)
大津市で昨年10月、市立中学2年の男子生徒が自殺した問題で、滋賀県警は25日、男子生徒が通っていた中学校の生徒らへの聞き取りを26日から始めると発表した。
全校アンケートでいじめの情報を寄せた283人のうち、実名で回答した116人(卒業生を含む)から重点的に話を聞き、必要に応じて、無記名の生徒らからも情報を集めるとしている。
県警によると、聞き取りについては、県警側がそれぞれ生徒側に日時を打診し、できる限り保護者立ち会いのもと行うという。面会場所は自宅など、生徒側の意向を踏まえて決める。希望があれば、少年課・少年サポートセンターの女性相談員を同席させるなど、心理的負担の緩和に努めたいとしている。
インターネットで注目を集め、マスコミからも注目を受けたからこそ、
「市教委が調べたところ、学校側は遺族に対し、全校生徒対象のアンケート結果を伝えただけで、全教諭を調査したことや結果を説明していなかったという。」
結果となった。簡単に学校が事実を隠蔽して
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)はチェックを行うことなく対応した。また、問題の指摘を受けると
市教委は読売新聞に対し、「事実確認は可能な範囲でしたつもりだが、
いじめた側にも人権があり、教育的配慮が必要と考えた。『自殺の練習』を問いただせば、当事者の生徒や保護者に『いじめを疑っているのか』と
不信感を抱かれるかもしれない、との判断もあった」と説明。結局、事実がつかめなかったとして、非公表にしたという。
平野文部科学相は
いじめに関する専門的な指導・助言を行う新組織を設置すると言っているが隠蔽体質の教育現場と適切な対応が出来ない教育委員会の問題とは
関係ない。いじめの問題自体を報告しない、適切に報告しなければいじめに関する専門的な指導・助言を行う新組織など税金の無駄遣い。
新組織の職員が適切なアドバイスを出来るのかも疑問。
大津いじめ、全教諭調査結果を遺族に伝えず 7/24/12(読売新聞)
大津市で昨年10月、市立中学2年の男子生徒(当時13歳)がいじめを苦に自殺したとされる問題で、自殺直後、学校側が全教諭に対し、男子生徒へのいじめの有無を調査していたにもかかわらず、その結果を遺族に伝えていなかったことが、市教委への取材でわかった。
文部科学省は指針で、自殺があった場合、1週間以内に調査し、遺族に説明するように求めているが、学校側は調査したことさえも知らせていなかったという。学校によるずさんな対応がまた浮かび上がった。
市教委によると、調査は自殺直後の昨年10月中旬、教諭約60人にいじめを見聞きしたかどうかをアンケートで質問。男子生徒の担任や2年生の担当教諭ら約10人については、校長らが直接聞き取り、記録していたという。文科省が昨年3月、自殺の再発防止に向けて策定した「子どもの自殺が起きたときの調査の指針」では、学校側の対応として「自殺から3日以内に全教師、数日以内に亡くなった生徒と関係の深い生徒から聞き取りを行い、1週間以内に遺族に説明する」との原則を示している。
しかし、市教委が調べたところ、学校側は遺族に対し、全校生徒対象のアンケート結果を伝えただけで、全教諭を調査したことや結果を説明していなかったという。市も近く設置する外部委員会で、説明しなかった理由や経緯を調べる。
市教委も、学校の遺族対応の不手際について把握はしていなかった。
教育委員の問題は
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)だけにとどまらない。教育委員会は異常なレベルで守られすぎている。教育委員の制度改革または廃止しかない。
生徒自殺、ずさんな教員聞き取り…愛知の県立高 7/21/12(読売新聞)
昨年6月に起きた愛知県立高校2年の男子生徒(当時16歳)の自殺をめぐり、同校と県教育委員会の実施した「初期調査」が不十分だったことが、関係者への取材でわかった。
文部科学省は、児童・生徒が自殺した場合、学校などに対し、できる限り全教員から迅速に聞き取り、再発防止につなげるよう求めているが、ごく一部の教員からしか聞き取りを行っていなかった。県教委はその後、第三者による調査委員会を設置、自殺の背景などを調べている。
関係者によると、野球部に所属していた男子生徒は昨年春、「部活をやめたい」と家族に話すようになり、同年5月下旬から部活を休むようになった。翌6月初旬には、部活に来ないことに気付いた顧問から呼び出しを受けたが、応じず、2日後に練炭自殺した。遺書は見つかっていない。
昨年6月、文科省が県教委などに通知した文書によると、児童・生徒の自殺があった場合、学校はできる限り全教員と、可能な範囲で自殺した子とかかわりの深い在校生から話を聞くよう求めている。
しかし、同校が聞き取りをしたのは、70人以上の在籍教員のうち、担任と部活の顧問の2人だけ。その後、県教委も追加調査したが、対象は担任ら2人に加え、校長と教頭、部活の別の顧問2人の計6人にとどまっていた。
読売新聞の取材に、県教委は「できる限り全教員から話を聞くように指示したが、学校側は自殺の事実が校内に広がることを懸念し、わずかな教員からしか聞き取らなかった」と説明。追加調査については、「遺族が『そっとしておいてほしい』という意向を持っていると考え、本人をよく知る教員の範囲にとどめた」としている。同校では、野球部顧問の1人が、別の生徒への体罰を行っていたことが調査の過程でわかり、県教委が昨年度、文書訓告の処分を行っている。
「越市長はこれまでの市教委の対応のまずさを改めて認めた上で、その遠因に教育委員会制度の矛盾があると指摘。
『市民に選ばれたわけではない教育委員が教育行政を担い、市長でさえ教職員人事などにかかわれない。民意を直接反映しない無責任な制度はいらない』と述べ、
国に制度改革を求める意向を示した。」
本音はどうなのか知らないが、越市長、よく言った。教育委員の独立性を主張しながら、
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)の対応は、不合理で横暴な対応は第二次世界大戦の日本軍のようだ。政治の教育への介入を軍事独裁政治を
例に挙げて拒んでいるが、今回のような隠蔽を平気で行う組織は異常なレベルで守られすぎている。教育委員の制度改革または廃止しかない。
大津市長「裏切られた…教育委員会制度は不要」 7/19/12(読売新聞)
いじめを受けていた大津市立中2年の男子生徒が自殺した問題を巡り、同市の越直美市長が読売新聞のインタビューに応じた。
「学校で何があったのか、なぜ不十分な調査になったのかを明らかにしたい」と述べ、市が設ける外部委員会での真相解明に意欲を見せた。
この問題では、全校アンケート結果の大半を市教委が公表していなかったことが、今月4日に発覚。越市長は「非公表のものがあるとの報告を市教委から受けておらず、報道で知った」と弁明した。
越市長は、自身も小学校と高校でいじめに遭ったことを明かしている。市教委から、まとめ資料ではなく、詳細なアンケート回答を取り寄せて読んだ。男子生徒が同級生から受けた被害がいくつも記されており、「いじめが自殺の原因だと確信した」という。
一方、市教委は男子生徒の自殺後、「全校アンケートは不確かな情報が多く、いじめとの因果関係は断定できない」と主張していた。
越市長は「市教委の説明を受け入れてきたけれど、前提となる事実の確認がいいかげんで信用できないとわかった。裏切られたように感じた」。アンケート結果の全面公表をしぶる市教委に対し、「事実はあなたたちが言ってきたことと違う。これは出すべきです」と押し切り、10日以降の公表につながったという。
さらに、越市長はこれまでの市教委の対応のまずさを改めて認めた上で、その遠因に教育委員会制度の矛盾があると指摘。「市民に選ばれたわけではない教育委員が教育行政を担い、市長でさえ教職員人事などにかかわれない。民意を直接反映しない無責任な制度はいらない」と述べ、国に制度改革を求める意向を示した。
クローズアップ2012:大津の中2男子自殺 学校・市教委、失態重ね 7/19/12(毎日新聞)
◇アンケート、聞き取り2割のみ いじめ目撃生徒の直訴、調べず
大津市で昨年10月、市立中学2年の男子生徒(当時13歳)が自殺した問題は、今月に入って学校・市教委の対応の不備が次々と明らかになっている。いじめの兆候を見逃し、自殺後の原因調査もずさんだった「二重の失態」の背景には、いじめに対する認識不足と身内への甘さがあった。
9カ月も前の自殺問題が再燃したのは今月4日。全校アンケートで「自殺の練習をさせられていた」と書いた生徒16人の回答を大津市教委が公表していなかったことが発覚した。「いじめと自殺の因果関係は判断できない」としてきた市教委へ批判が集中した。
その後も、男子生徒と同級生の金銭トラブルを指摘した回答を公表せず「葬式ごっこ」「首を絞める」という具体的記述を見落としていたなど、市教委の不手際が相次いで明らかになった。
アンケートは、男子生徒が自殺した後の昨年10、11月、学校が2回実施。1回目は約300件の回答があった。それを基に加害者とされる同級生らに聞き取りした結果、男子生徒に対する暴力などが判明し、市教委はいじめがあったと認めた。
「定例会で詳細な経緯が初めて報告されたのは12月15日になってから。自殺の6日前、同級生が担任に『トイレでいじめてる』と伝えていたのに最終的に学校側で
『けんか』として処理したことも説明された。しかし、公開されている議事録によると、教育委員からの意見や質問は一切なく、定例会は閉会した。」
大津・中2自殺事件でこのような状態になったのだから
越 直美市長(大津市のHP)は教育委員から聞き取りを行いなぜ質問や意見が一切なかったのか公表するべきだ。
教育委員、いじめ報告の場で質疑なし 大津・中2自殺 7/18/12(朝日新聞)
大津市立中学2年の男子生徒(当時13)が昨年10月に自殺した問題で、昨年11月と12月の市教委定例会に生徒へのいじめが報告された際、いずれの会議でも岡田隆彦委員長を含む5人の委員から意見や質問が出なかったことが議事録や市教委への取材でわかった。学校や市教委のずさんな対応が指摘されているが、教育委員のチェックも不十分だった可能性がある。
大津市教委の定例会は、地方教育行政法で原則公開と規定されている公式の「会議」にあたり、原則として毎月1回開かれる。会議では、教科書の取り扱いや学習指導のあり方など教育行政全般が幅広く話し合われる。学校でのいじめや暴力行為も検討対象で、これまでの定例会では件数の増減などが報告されていた。
男子生徒の自殺後の11月2日、市教委は全校生徒へのアンケートなどに基づき「(生徒が)複数の生徒からいじめを受けていた」と発表した。同月17日に開いた定例会では、沢村憲次教育長が男子生徒の自殺について触れ、臨時校園長会や生徒指導主任主事会を開いたことを報告した。
定例会で詳細な経緯が初めて報告されたのは12月15日になってから。自殺の6日前、同級生が担任に「トイレでいじめてる」と伝えていたのに最終的に学校側で「けんか」として処理したことも説明された。しかし、公開されている議事録によると、教育委員からの意見や質問は一切なく、定例会は閉会した。
和解は金額と条件次第だろうが、
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)、
平成21年 4月 1日 文部科学省「道徳教育実践研究事業」の指定を受けた滋賀県大津市立皇子山中学校
の対応の悪さを認めさしてから和解して欲しい。
「家庭的な要因も」と市教育長、遺族憤りあらわ 7/17/12(読売新聞)
大津市の沢村憲次教育長は17日、市役所で記者会見し、男子生徒が自殺した背景について「個人的、家庭的な要因もあったと、学校から聞いている」と述べ、いじめ以外の要因があったとの見方を示した。
具体的な内容については「個人情報であり、警察や市の外部委員会で調べていくものだ」と言及を避けた。
この発言に対し、遺族側は「責任の所在をすり替えようとしている」と憤りをあらわにしている。
また、沢村教育長は記者会見で、遺族が起こしている損害賠償請求訴訟について、「外部委員会の調査で、いじめと自殺の因果関係が示されるのではないか。それを受け、和解協議をさせてもらいたい」と話し、これまで「裁判を続行したい」としていた態度を修正した。
女児のいじめ問題対応中の新任校長、自殺 7/18/12(読売新聞)
津市立小学校の男性校長(54)が同市内の山中で首をつって自殺していたことが、津市教育委員会や津署への取材で分かった。
津市教委は18日午前、記者会見を開き、校長が校内のいじめ問題の対応にあたっていたことを明らかにしたうえで、自殺との関係を調査していると発表した。
津市教委などによると、校長は15日午後、自宅を出たまま行方不明となり、16日朝、山中で首をつった状態で発見された。状況から自殺とみられるが、遺書は見つかっていないという。
校長は3月まで別の小学校で教頭を務めており、4月から同校校長に就任していた。
就任後、女子児童が仲間外れにされるなどのいじめにあっていることが保護者の指摘で分かり、担任らと対応にあたっていたという。津市教委は、「いじめ問題と自殺との関係は現時点では分からない」としている。
今回の事件は、
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)、
平成21年 4月 1日 文部科学省「道徳教育実践研究事業」の指定を受けた滋賀県大津市立皇子山中学校
そして
文部科学省/A>
の対応の悪さを日本国中に広めた。残念ながらいじめたなくならないと思う。日本だけでなく多くの国でいじめや差別が存在するからだ。
ただ、状況の改善は期待できるし、
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)を含む教育委員会の改革または廃止が今回の事件によるきっかけになることを祈る。
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)や
文部科学省「道徳教育実践研究事業」の指定を受けた滋賀県大津市立皇子山中学校の校長の対応を見ていると公務員であり、
教育関係者でありながらここまで自己利益や組織の利益のためには明らかに非常識な対応を取ることが出来ることには驚く。
「『いじめ罪』という法律はない。学校の出来事を何でも摘発できるわけではない」
滋賀県警の発言は法律の改正の必要性を投げかけている。悪法でも法は法である。法やシステムが間違っていれば改正すればよい。
今まで、いじめの事件に関して「『いじめ罪』という法律はない。学校の出来事を何でも摘発できるわけではない」との発言が
大きく取り上げられたことはないと思う(もしかすると注意して見ていないだけ、または勉強不足かもしれない)。
法務省、滋賀県及び
大津市
が今回の事件を重く受け止めているのなら、法改正、または条例で対応するべきだ。そして、いじめだけでなく
いじめによる自殺の可能性ある件についての大津市、
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)や
文部科学省「道徳教育実践研究事業」の指定を受けた滋賀県大津市立皇子山中学校の対応はあまりにもひどい。
懲戒免職を含む罰則を明確に定めるべきである。個人的には嘘とも思える発言を公でするような行為は許せない。
文部科学省「道徳教育実践研究事業」の指定を受けた滋賀県大津市立皇子山中学校の校長は処分を受けるかもしれないが、
降格のような軽い処分しか受けないような気がする。懲戒免職でも良いと思う。そして
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)の責任者達及び関与した職員達も懲戒免職で良いと思う。これぐらいの処分を行わないと
今後も不適切な調査や隠蔽体質は改善されない。
大津・中2自殺:捜査、長期化の可能性…捜索から1週間 (1/3ページ)
(2/3ページ)
(3/3ページ)07/18/12(毎日新聞)
大津市で市立中学2年の男子生徒が自殺した問題で、滋賀県警が学校と市教委に異例の家宅捜索をしてから18日で1週間。県警は40人態勢の捜査班を作り、夏休み中に数百人に及ぶ生徒や卒業生から集中的に事情を聴く方針だ。ただ、刑事罰を科すことができない年齢の生徒も捜査対象であるうえ、全ての生徒や保護者の心情への配慮も求められ、捜査は長期化する可能性もある。一方、生徒からは「学校は真実に向き合って」などと、一日も早い解決を求める声が上がった。【村瀬優子、村山豪、石川勝義、加藤明子】
◇時間経過、物証乏しく
「『いじめ罪』という法律はない。学校の出来事を何でも摘発できるわけではない」。滋賀県警の幹部は捜査の難しさを強調した。
県警は今月11日、男子生徒に対する同級生3人の暴行容疑で、関連先として学校と市教委を捜索した。3人は昨年9月の体育祭で、男子生徒の手を鉢巻きで縛ったり、殴ったりした疑いがあるという。県警は教諭の日誌、学校の調査資料などを押収し、暴行容疑の裏付けを進めている。
学校のアンケートで多くの生徒が男子生徒に対するいじめを指摘する回答をした。ただ伝聞も多く、確認するのは容易ではない。物証に乏しく、生徒の自殺から時間が過ぎており、県警は生徒らの証言を組み立てて捜査を進めるとみられる。
14歳未満は刑事罰の対象外だが、捜査対象には13歳(当時)の同級生も含まれ、事情聴取の方法など、捜査手法には慎重さが求められる。県警は、保護者の同席を認めるなど、生徒らの聴取にあたり、配慮をする方針だ。
◇生徒、学校側に不信も
捜索は生徒らにも衝撃だったようだ。
女子生徒は「学校の雰囲気が以前とは違う。みんなそわそわしている感じ。私もニュースをよく見るようになった」。男子生徒は「捜索の後、先生が部活にほとんど来なくなった。みんな不安がっている」と明かした。
捜索翌日には校長が全校放送で「皆さんの安全は守ります。我々も努力しています」などと訴えたという。しかし生徒から「何を努力してるんやろ」と冷ややかな声も上がる。
多くの生徒が男子生徒に対するいじめを目撃したと取材に証言した。「自殺するまで、教職員にいじめの認識はなかった」とする市教委側の見解が生徒らの大人への不信を増幅させている。
別の女子生徒は「学校は正直になってほしい」と訴えた。
◇市教委へ抗議1万件超える
市教委に対する抗議が17日午後9時半までに1万件を超えたことがわかった。市教委によると、内訳はメール6155件、電話4791件。【千葉紀和】
NPO法人 全国いじめ被害者の会の/A>の理事長 大澤秀明氏が
いじめに関して
文部科学省に責任がある言っていた。
タウンミーティングでやらせを計画した文部科学省/A>
はエリートと勘違いしたキャリアが現場の状況も把握せずに対応しているからこのような結果となったのであろう。
平成21年 4月 1日 文部科学省「道徳教育実践研究事業」の指定を受ける(滋賀県大津市立皇子山中学校のHP)
と今回の事件とは全く関係ないとは言え、文部科学省/A>
の担当者はこの学校について何も感じなかったのだろうか?組織の雰囲気は事故が起こってもそんなに変わるとは
思えない。
越 直美市長(大津市のHP)が要請し派遣される文部科学省/A>職員
が何を調べどのような報告書を提出するのか興味深い。能力や経験がないが学歴だけがある職員が来たら適当な報告書を
書いて終わりかもしれない。
大津の中学生自殺は「校内犯罪」だ 暴行、恐喝を「いじめ」とすり替えるな 7/10/12(J-CASTニュース)
滋賀県大津市の中学校で2011年10月、男子生徒が自殺した「事件」は、同じ学校に通う生徒たちの証言から陰惨な犯罪の実態が浮き彫りになってきている。
教育評論家や、息子が自殺した父親はいずれも「いじめというより、これは犯罪だ」と厳しく断じている。
■いじめを理由とした出席停止わずか6件
「一方的に殴られていた」「火のついたタバコをつけられた」「金を脅し取られた」――。自殺した男子生徒の同級生は、学校側が実施したアンケートにいじめの様子を具体的に回答していた。最近では在校生がテレビの取材に対して、加害者による暴力についてコメントし、続々と詳細が明らかになってきた。
「これは犯罪です」。NPO法人「全国いじめ被害者の会」代表の大澤秀明氏は、J-CASTニュースの取材にこう断言した。大澤氏は1996年、「いじめ」が原因で息子が自殺に追い込まれるという悲劇に見舞われている。遺書には、同級生に殴られ続け、現金を要求された事実が記されていたという。これにより加害者の生徒2人は保護観察処分となった。
大澤氏は2012年7月6日に大津市を訪れて、自殺した生徒の父親と対面した。「地元警察から被害届の受理を3回も断られたことに、落ち込んだ様子でした」と話す。そこで滋賀県警に告訴状を持参するように助言したそうだ。
大津市のケースでは、加害者とされる同級生が「遊びの範囲内だった」と主張。学校側も「仲良しグループだと思っていた」と話したという。だが他の生徒からは、担任に「いじめ」の様子を報告したのに適切な対応をしなかったとの証言も出た。そもそも一方的に殴りつけるのが「遊びの範囲内」とは思えない。
大澤氏によると、かつては教育の場で「社会的人間の形成」が重視され、いじめが起きても教師が加害者の生徒を叱り、二度と繰り返さないような措置を施して「根元」を断ち切っていた。だが時代とともに「善悪」を教える風潮が薄まり、加害者への措置も講じられなくなったと指摘する。学校教育法では、教育上必要があれば加害者に対して懲戒(11条)や出席停止(35条)を命じられると定める。ところが文部科学省の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」(2011年8月4日付)を見ると、2010年度に全国の小中学校で出席停止が下された74件中、いじめを理由にしたのはわずか6件。最も多かったのが「対教師暴力」の21件だった。
文科省は1995年、「いじめの定義」として「自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」とした。これを2006年、「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」と改めた。暴行や恐喝といった犯罪行為が「『いじめ』という言葉にすり替えられ、しかも定義があいまいになっている」と大澤氏。深刻な犯罪の意味合いがぼかされて、「ふざけ合い」「単なるケンカ」として処理されうる流れになってしまっていると憤る。
■教師が隠ぺいに加担したら処罰する条例を
大澤氏は全国各地でいじめに悩む親子の相談を受けている。自身のつらい体験について、「息子がいじめられていたのを見ていた同級生が担任に報告したにもかかわらず、現場に行かずに放置していたのです」と振り返る。こうなれば、いじめの行為はますますエスカレートしがちだ。「いじめの実態を知ろうとしない。そうしておけば後から『学校側は把握していなかった』と言えるからです」と続け、「これは文科省の方針のせい」と怒りを隠さない。大津市の場合も、学校側は「見て見ぬふりをしていた」と生徒から声が上がっている。市教育委員会はいじめがあったことを認める一方で、自殺との因果関係は「判断できない」としている。
教育評論家の森口朗氏に聞くと、大澤氏と同様に今回の加害者側の行為を「校内犯罪」と断定する。一方で最近は未成年でも、加害者が罪に問われる事例が「ようやく出てきました」と話す。
本来であれば、悪質な「いじめ」が発覚したら被害者側と学校が連携して警察に被害届を出すのが望ましいと森口氏。そのうえで、実態を明らかにするために証拠を固めることが重要だという。複数の証拠に基づいて告発すれば、警察も動かざるをえなくなるからだ。
だが大津市のケースでは、学校側が協力的とはいえない。その場合に被害者側は、マスコミに訴えかけるなど別の方策をとる必要がある。さらに、「都道府県レベルで『いじめ防止条例』のようなものを制定し、教師がいじめの実態の隠ぺいに加担したら処罰する内容を盛り込んではどうでしょうか」とも提案する。学校側に腰を上げさせるためにも、ある程度強制的に「校内犯罪撲滅」への手段が必要というわけだ。
大津市教育委員会委員長の岡田隆彦氏は会見に出るべきだ。大津市教育委員会委員長の責任を果たせ!
「大津市教育委員会委員長は岡田隆彦氏(絶対にバッシングしないで下さい)ですが、一般論として地域の著名人や有力者等の持ち回りポストでたまに会議をやるだけです。
私も自治体のその手の委員をいくつかやっていましたが、『誰でもいいんです。』非常に不適切な表現をするなら、私が年配になったら任命されえるレベルのポストです(誰でもいいということ。)」
これがやはり一般的な教育委員会の実態であれば、改革や廃止するべきだ。
参考までに
片山さつき Official Blog
片山さつき先生、ブログに「皇子山中学校の藤本一夫校長」と大津いじめ事件の中学校明記…公開処刑?。大津市教育委員会と大津市教育長。
7/13/12(お気楽系・作家・評論家・コメンテーターの林雄介(元官僚)のライブドア(公式)ブログ。日本一、不真面目なトンデモ元キャリア官僚。」)
いつもありがとうございます。林雄介です。
参議院議員の片山さつき先生(元大蔵官僚、ミス東大?)が、「ブログとHPに大津市いじめ事件の大津市立皇子山中学校の藤本一夫校長(たまたま校長なだけですから、絶対に脅迫文を送らないで下さい。)」と明記されました…。まあ、大蔵官僚ですから、大丈夫なのかもしれません…。ちなみにデヴィ夫人(元大統領夫人)は、加害者の実名をブログに明記されましたが、アメブロに削除されました…。気持ちはわかりますが、推定無罪ですから、「加害者とその家族の名前」を明記しないで下さい。
大津市教育委員会委員長は岡田隆彦氏(絶対にバッシングしないで下さい)ですが、一般論として地域の著名人や有力者等の持ち回りポストでたまに会議をやるだけです。私も自治体のその手の委員をいくつかやっていましたが、「誰でもいいんです。」非常に不適切な表現をするなら、私が年配になったら任命されえるレベルのポストです(誰でもいいということ。)
教育委員会というより、教育行政は事務方トップの教育長の沢村憲次さん(年収1200万推計)が運営していますが、実際、経験上、責任の所在が市長も含めて不明確な場合が大半です。村社会ルールなのです。ちなみに片山さつき先生も教育長(沢村さん)と教育委員長(岡田さん)の誤記がありました。主計官(片山議員)が誤記するくらいですから、そんなもんですよ。
事務方トップの沢村さんも個人の意見ではなく(そもそも校長経験者なので教師)、教育委員会事務局の意見としての対応のはずです。知り合いにも、教育委員会の事務方がいますが、教育委員会には個々の苦情が大量に届き、物理的に処理できないのも事実です。大津いじめ事件は、たまたま、炎上して面に出ただけで氷山の一角です。あと、教育委員会にはモンスター保護者から苦情がバンバンきますから、優先順位や真相究明は難しい。それは一般論としてご理解頂き、大津市教育委員会や沢村さんを生け贄にしないで欲しいんですね。ただし、もし、担任が本当にいじめ放置の「ほどほどにしておけ」発言があったなら、適切な処遇は必要だと考えます。
林雄介拝。
藤本一夫校長は
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)の連中が
警察の強制捜査で逃げ腰になったから、やっと学校の責任者として出てきた感じた。しかし、国民をがっかりさせる対応だ。
いじめであると断定する藤本一夫校長の定義とは何か?
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)に提出した報告書でいじめの認識はないとの判断は誰がしたのか?校長は報告書に目を通して
問題はないと判断したのか?誰が事実確認して、「これはけんかだ」となったのか?この校長は報告能力があるのか、
それとも故意に曖昧な発言をしているのか?子供の学校では、誰が、どこで、何を、なぜしたかを説明できるように教えているぞ!
滋賀市では校長になるような人間にそのような能力が備わっていなくとも校長に任命するのか?
警察や検察は関係者の聞き取りをしっかりしてほしい。ここまで矛盾があれば嘘をついている人間達を見つけるのは難しことではないはずだ。
いじめ自殺、校長「けんかだと…判断甘かった」 7/15/12(読売新聞)
大津市立中学2年の男子生徒(当時13歳)が昨年10月、いじめを苦に自殺したとされる問題で、中学の校長が14日午後に行った記者会見での主なやり取りは次の通り。
――男子生徒がいじめを受けていたという認識は。
校長「(5日は)いじめという通報で始まったので、確認しているはず。ただ、(男子生徒と同級生に)確認したら、双方が手を出したけんかということだった。その段階で、いじめだという確実な認識はなかった」
――いじめがあったと全く疑わなかったのか。
校長「疑っていなかったというより、気付いていなかった。認識がなかった」
――協議で、いじめという言葉は出なかったのか。
校長「もちろん出ている。本人たちから事実確認して、『これはけんかだ』という話になった」
――いじめの可能性を切り捨てたのではないか。
校長「切り捨てていない。捨てていたら調査しない」
――自殺当日、校長は記者会見で「いじめはなかった」と断定した。なぜか。
校長「断定していない。いじめがあったとも、なかったともわからない、調査したいと(言った)」
――10月5日のトラブルは市教委に報告したのか。
校長「その時点では報告していない。指導の不十分さ、判断の甘さがあったと言わざるを得ない」
――けんかがあり、いじめの可能性を疑わなかったことについてどう思うか。
校長「生徒からもっと聞き取り、早期に調査すれば迅速な対応ができた。通報があったのに本人から事情を聞かず、それまでの情報で判断してしまった」
大津中2自殺、初会見の校長「いじめ認識せず」 7/14/12(読売新聞)
大津市立中学2年の男子生徒(当時13歳)が昨年10月、いじめを苦に自殺したとされる問題で、中学の校長が14日午後、全校アンケートの非公表問題が発覚後、初めて記者会見した。
担任ら複数の教諭が、男子生徒がいじめられているとの情報を受けていたことを認め、「同級生とのけんかと判断した。いじめを把握する機会があったのに見逃していたと言われれば、その通りだ」と陳謝した。しかし、「担任らは、この段階で確実にいじめだという認識はなかった」と説明、市教委が14日午前に「自殺前に担任らがいじめの可能性を疑っていた」とした説明とは違う見解を示した。
「(生徒の自殺まで)いじめというはっきりした認識はなかった。疑っていなかったというより、気付かなかった」。沢村憲次・市教育長とともに大津市役所で記者会見に臨んだ校長は、言葉を選ぶように釈明した。
一連の問題発覚後、これまで会見に応じなかった理由については、「生徒たちの心の安定を考えて避けていた」とし、「強制捜査などで学校全体が混乱する事態になり、十分責任を感じている」と話した。
校長は、男子生徒が昨年10月11日に自殺する前に2度、いじめに遭っているという情報が寄せられていたと説明。「教諭らから、生徒は同級生と力の差があり、けんかで負けることが多いと聞いていた」とも話した。
自殺6日前の同5日に、男子生徒と加害者とされる同級生がトラブルになった際には、担任ら5、6人で対応を協議したものの、双方の生徒がいじめを否定し、「大丈夫」と言っていたため、「これはけんかだ」と結論づけた、とした。
嘘と歪められた調査で幕引きしようとした
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)
教育関係者集団でありながら人間としてレベルの低い嘘つき集団であることが明らかになりつつあるようだ。
これだけ嘘で歪められた調査結果を公式に発表してきた事実を考えると、文部科学省は罰則規定をさだめるべきだ。
罰則があれば更なる隠蔽を招くと反対する人達もいるだろう。今回のように警察が捜査して、虚偽の発言や発表を行った
ことが判明した場合、懲戒免職や教職員免許の無期限の停止または剥奪などで処分するべきだ。罰則がなくとも、
ここまで事実を歪める教育委員会があるのだから罰則を設けるべき。
生徒への暴行、教諭が目撃か…大津いじめ自殺 7/14/12(読売新聞)
大津市で中学2年男子生徒が自殺した問題で、滋賀県警は14日も引き続き、自殺した男子生徒が通っていた中学校の教諭らから聞き取りを行った。
この日は、男子生徒に対する暴行などを目撃した可能性のある教諭ら数人から、聞き取りを実施。生徒からの聞き取りは、夏休み中に行う方針だ。
県警によると、任意で提出を受けた全校アンケートや、市教委と中学校から押収した資料などを調べた結果、いじめの加害者とされる同級生らが男子生徒に暴行した現場を目撃した可能性のある教諭がいることが判明。教諭らから、アンケート回答にあったいじめの実態の有無についても聞くとしている。
一方、県警は15日から、25人の専従捜査班に加えて20人を増員し、計45人態勢で捜査する。
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)の誰かが
虚偽(Yahoo!辞書)の発言を公表することを決めたはずだ。
誰なのか捜査し公表するべきだ。些細なことではなく、自殺事件でこのような判断をする公務員の名前は公表され、処分されなければならない。
公務員組織による調査がいかにずさんで不適切で歪められた報告を事実として公表し偽善者でありながら平然としていられることが
現実社会にあることを多くの国民そして子供達に知らせた。そう言う意味では
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)による調査が良い例になったと思う。
最低の人間達が教育関係者として存在し、いろいろな大義名分で守られてきた事実。教育委員会の問題がメディア等で指摘されながら、
抜本的な改革が行われず、放置されてきた事実。今回の事件は多くの隠された膿の一部を多くの国民に曝した。
<大津いじめ自殺>担任ら複数の教諭が話し合い 問題把握か 7/14/12(毎日新聞)
大津市の市立中学2年の男子生徒が昨年10月11日に自殺した問題で、生徒が亡くなる直前、「男子生徒がいじめを受けている」との情報を受け、担任ら複数の教諭がいじめの可能性について話し合っていたことが市教委への取材で分かった。情報は、昨年9月末ごろと10月5日、担任の男性教諭らに別の生徒が少なくとも2度伝えていた。【加藤明子、村山豪】
【自殺を強要されていた】アンケートで生徒ら回答
また、市教委学校教育課は14日、取材に男子生徒が自殺した10月11日にも学校がいじめについてアンケートをする予定だったことを明らかにした。そのうえで「いじめの指摘の認識については、(教諭らで)共有していた」と認めた。これまで学校は一貫して「いじめの存在は知らなかった」としていた。
市教委などによると、同年9月末ごろ、男子生徒が同級生からトイレで殴られているのを目撃したという女子生徒が別の教諭に「(男子生徒が)いじめられている。やめさせてほしい」と訴えた。この教諭が男子生徒に確認すると、「大丈夫」と答えたという。
また10月5日、別の生徒が担任に「いじめがある」と伝えていた。学校側は男子生徒が同級生とけんかをしたとして、両方の保護者を呼んで謝罪させた。このとき担任は、男子生徒1人を残し「本当はどうなんだ」と、いじめについて聞いたところ、生徒は「きょうはちょっとイヤやった」と答えたという。
担任や2年を担当する別の教諭らはその後、男子生徒について話し合い、その際「いじめかもしれないから、人間関係に気をつけていこう」という意見も出されたという。男子生徒はこの6日後に自殺した。
学校や市教委はこれまで一貫して「担任も含めいじめについては知らなかった」と話しているが、少なくとも自殺の直前に、いじめがあった可能性を認識していた疑いがある。
県警は、生徒約300人の事情聴取も視野に、いじめの有無について全容解明を目指す方針。
「 市教委学校教育課の担当者は『当時、明確にいじめられているとは認識できなかった。もう少し踏み込んだ対応をやるべきだった』としている。 」
市教委学校教育課の担当者は誰?
自殺6日前にいじめ対策会議 情報受け担任ら 大津 7/14/12(朝日新聞)
大津市立中学2年の男子生徒(当時13)が自殺した問題で、自殺6日前の昨年10月5日、生徒がけんかをしたり他の生徒から「いじめを受けている」という情報が教師に2度寄せられたりしたことを受け、担任らが対応策を考える会議を開いていたことがわかった。
市教委はこれまで、生徒が暴力を受けていることを把握していたが、「教師はいじめと認識できなかった」と説明している。この会議では「いろいろな可能性の中でいじめについても考えて対応する」ことを決めていた。
担任は10月1日と同5日に生徒に声をかけ、生徒は「大丈夫」という返事だったと市教委は説明。5日には、学校側は生徒の父親を学校に呼び、いじめられているという情報があったことを伝えたという。
市教委学校教育課の担当者は「当時、明確にいじめられているとは認識できなかった。もう少し踏み込んだ対応をやるべきだった」としている。
生徒か教諭達(少なくとも担任)のどちらかが嘘をついていることは明らかだ。警察や検察に対しての証言によっては偽証罪(刑法169条)と
なるのか?今後とも注目したい!もう一つ言えることは、生徒が正しいとすれば
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)は自己の利益のためにはモラルを逸脱し、人間としての良心のかけらもない集団の組織であると言う事だ。
組織の人間達を権力や地位を使い圧力で押さえ込もうとする姿勢は、第二次世界大戦の軍部と変わりないではないか。
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)など廃止してしまえば良い。職員が困るかは関係ない。自殺を組織的に隠蔽する人間達には
レッスンが必要。命まで取られるわけではない。
大津いじめ、「泣いて担任に電話」と2生徒回答 7/14/12(読売新聞)
大津市立中学2年の男子生徒(当時13歳)がいじめを苦に自殺したとされる問題で、市教委が昨年11月に実施した2回目の全校アンケートで、2人が「(男子生徒がいじめについて)泣きながら電話で担任教諭に相談したと聞いた」と回答していることがわかった。
1回目のアンケート結果でも教諭がいじめを知っていたことを示唆する回答があり、市は、近く設置する外部委員会で学校側の認識や対応の経緯などについて調査を進める。
昨年10月に実施した1回目のアンケートに続き、2回目は「今までに伝えられていないこと」を聞くことを目的に実施、約30人が回答した。うち2人が「男子生徒が泣きながら担任に、いじめられていることがつらいと電話をしたと聞いた」と記述。うち1人は「担任はいろんなことを聞いていたのに、行動を起こさなかったのはなぜか、説明したらどうなんですか」とつづった。
市教委はこの内容について「1回目のアンケート後に学校が担任に聞き取りをし、男子生徒から電話での相談があったことは確認したが、いじめではなく家庭内に関するものだったと聞いている」と説明。2回目のアンケートに記された2人の回答については新しい事実ではないと判断、調査は行わなかったという。
隠蔽体質と批判された滋賀県の大津市教育委員会。
「 ただこのアンケート結果には、実際に目撃した事実とうわさや伝聞内容が混在しているとみられ、警察は今後、
ひとつひとつの回答内容が事実かどうか慎重に調べる方針です。」
いじめの認識を認めた教師はゼロ。警察の確認作業でどのような結果になるのか興味深い。複数の目撃情報があれば、
教師達が口裏を合わせた、または、誰かの圧力で口裏を合わせたことになる。以前、警察官達が口裏わせをした事件があった。
警官達でもやったのだから、教師達が絶対にしないことはない。教師達の不祥事事件を考えると否定はできない。誰かが圧力を
かけた、または、隠蔽の打ち合わせがあったとすれば、大津市教育委員会が関与していたか、知っていた可能性が高いのでは??
「『ぼく死にます』と電話」悲痛な心情あらわ アンケート、市議会傍聴人にも異例の公表 (1/2)
(2/2) 07/14/12 (産経新聞)
大津市立中学2年の男子生徒=当時(13)=が自殺した問題で、市教委は13日に開かれた市議会教育厚生委員会で、学校側が生徒に実施した2回のアンケート結果を公表。市議のほか傍聴人にも配られた。自治体の内部資料が傍聴人に配布されるのは異例で、「先生も見て見ぬふり」「(自殺前日、加害生徒に)『ぼく死にます』と電話」などの記述もあり、男子生徒が追い詰められた状況や、他の生徒の心情が改めて浮かび上がった。
アンケートは、1回目は生徒の自殺直後の昨年10月、2回目は11月初めに実施。2回目のアンケートは初めて全体の内容が明らかになった。
2回目は、1回目で書き足りなかったことを問う内容で、全校生徒859人に対し188人が回答。市教委が今月10日に初めて存在を認めた際には「自殺の練習と言って首を絞める」「葬式ごっこ」の記述以外は明らかにしなかった。
「葬式ごっこ」などの記述は「いじめは本当にあった」と書き出す回答の中でいじめの内容の具体例として記され、ほかに「はちの死骸を食べさせる。粘着テープで縛る。(加害者が)お金を持ってこいと命令する」などの記載もあった。
他の生徒の回答では、死亡した生徒が「泣きながら先生(担任)に、いじめられていることがつらいと電話したと聞いた」とし、「亡くなる前にいろんなことを担任は聞いてたはずなのに、何も行動を起こさなかった。なぜか説明したらどうなんですか」と批判するものも。「いじめてた人がわかっているのなら全校生徒に全部伝えたほうがいい」と、学校側の対応に疑問を呈する回答もあった。
澤村憲次・市教育長は委員会で、2回目のアンケートでもいじめを強くうかがわせる記述があったにもかかわらず、見落としていたとしていることについて「調査が不十分だった」と陳謝。委員会後の会見では、傍聴人にも資料を配布したことについて「保護者から市民に情報が伝わる可能性もあり、配布を決めた」と述べた。
市議から市教委批判続出
「なぜ生徒が『SOS』を出していることを理解できなかったのか」。アンケートが配られた市議会教育厚生委員会では、出席した市議から疑問の声が相次いだ。
委員会は本会議と同じ議場で開かれ、計10人の市議が出席。澤村教育長ら市教委幹部から自殺の経緯の説明があった後、職員が出席した市議にアンケートを配布した。
市議からは「(学校の)取り組みに問題はなかったのか」「市教委は事の重大性を認識していない」と批判の声が続出。いじめと自殺との因果関係を聞かれた澤村教育長は「自殺の要因は一つに絞りきれるものではなく、この場で申し上げることはできない」と明言を避けた。
委員会は約3時間にわたって開かれた。市議と市教委とのやりとりを傍聴した大津市の40代の男性会社員は「特に新しいことは聞けずに残念。市教委はちぐはぐな答弁が目立った。真相究明を徹底してほしい」と話し、市教委の不誠実ともいえる態度に不満をもらした。
大津・中2自殺:アンケート結果公開…市教委、市議会で 7/14/12(毎日新聞)
大津市で市立中学2年の男子生徒が自殺した問題で、大津市教委は13日、自殺の背景調査のために実施した2回分の全校アンケート結果の公開を始めた。これまで報道陣の開示要求に「確証のない情報がある」として応じず、遺族に渡す際も、口外しないよう求める確約書に署名させていたが、同日の市議会常任委で委員10人に回答の一覧表を配布したほか、一般傍聴者15人にも同じものを配った。いじめの内容を記した内部資料が一般公開されるのは異例で、市教委によると、情報公開請求があった場合に公開すべき範囲の内容だという。
一般公開に踏み切った理由について、沢村憲次教育長はこの日の記者会見で「保護者に渡すと当然外に出て行くし、一般市民にも伝える必要がある」と説明。同中学の在校生約880人の保護者に対し「希望があれば学校で手渡す」という内容のメールを送り、生徒にも案内書を配った。希望する保護者に市議会で配布したのと同じ資料を配る。
公開された資料は、在校生が書いた回答を教員がパソコンで一覧表に整理したもの。昨年10、11月に実施した2回分で、加害者とされる同級生の名前などは白く消されている。
隠ぺい批判集中 いじめ全校アンケート 議会で公開 7/13/12(MBS毎日放送)
隠蔽体質と批判された滋賀県の大津市教育委員会はようやく…、
しかし、保護者ではなくまずは議員に公開でした。
いじめがあった学校で調査として行われた生徒たちへのアンケート結果の概要が、市議会の議員と傍聴していた市民に配られました。
大津市議会の教育厚生常任委員会。
午後3時45分ごろ、市の職員が議員と傍聴席の市民らにアンケート結果の概要を配りました。
全部で29ページ。
暴行容疑で捜査が行われている、9月29日の体育祭での記述は生々しい表現でした。
「体育大会のとき、蜂を食べさせようとしていた」
「手足をはちまきでしばって、粘着テープを口に張って身動きの取れないようにしていた」
「体育大会の時、死んだ蜂を食べさせられていた。口の中にいれて吐き出した」
回答からはその後、いじめがエスカレートしていったことが伺えます。
「トイレで暴力をふるわれていた」
「カエルを食べさせられた」
「両手を後ろで結ばれ、口に粘着テープを張られていた」
自殺の前日、男子生徒が同級生に連絡したという回答もありました。
「死ぬ前にいじめていた人に『死にます』とメールで送ったらしい」
「『もう俺死ぬわ』とメールして『死ねばいいやん』と送り返していた」
いじめをしていたとされる同級生たちが、男子生徒の死を知ったときの対応についても書かれています。
「『死ね、死ね。あっもう死んだか』といっていた」
アンケートからは男子生徒が夏休みまでは同級生3人と仲良くしていて、それが2学期が始まる9月になっていじめられるようになったことがわかります。
「9月頃からいじるようになり、下旬には殴るケルの暴行を加え、いじめるようになりました」
ただこのアンケート結果には、実際に目撃した事実とうわさや伝聞内容が混在しているとみられ、警察は今後、ひとつひとつの回答内容が事実かどうか慎重に調べる方針です。
滋賀県警、教師や市教委への聴取本格化 大津・中2自殺 7/14/12(朝日新聞)
大津市立中学2年の男子生徒(当時13)が昨年10月に自殺した問題で、滋賀県警は13日、中学校の教師や市教委学校教育課の職員らから事情を聴くなど本格的な捜査を始めた。いじめの犯罪性のほか、生徒がお金の使い方で家族に注意され、担任に相談した経緯についても調べる。
県警は11日に専従チームを設置。昨年9月29日の体育大会で生徒が鉢巻きで後ろ手に縛られたという暴行容疑で学校と市教委を捜索し、校長らから話を聴いていた。
教師への聴取では、暴行の様子を目撃したり、いじめの情報を聞いたりしていなかったか調べる。学校が昨年10月17~19日と11月1~4日、全校生徒を対象に実施した2回のアンケートをもとに、記名回答した生徒から聞き取った内容も確認していく。
「沢村教育長は『いじめがすべて犯罪行為との認識はない』と話した。」沢村憲次教育長はどのような人間なのか?
「市教委は『学校からの報告をうのみにし、チェックが甘かった』と認めた。」
学校からの報告をうのみにしたのなら、誰が報告書を作成し、市教委に送られる前に誰が報告書に目を通したのかも公表すべきだ。
そして、市教委の誰が報告書を読んだのか?一人なのか、複数なのかも公表すべきだ。全てを公表しないと問題は明確にならない。
陳謝だけで市教委や学校関係者を許してはならない。うやむやにするとまた同じことが繰り返される。
平成21年 4月 1日 文部科学省「道徳教育実践研究事業」の指定を受ける
平成18年 4月 1日 第十九代校長に澤村憲次就任 (滋賀県大津市立皇子山中学校のHP)
文部科学省「道徳教育実践研究事業」の指定を受ける学校はどのような学校なのか?
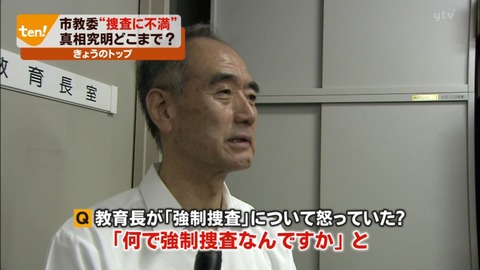
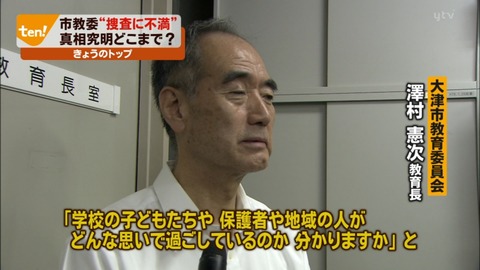
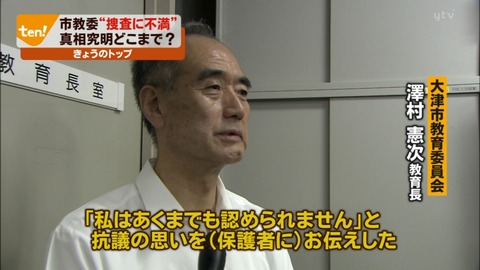
傍聴人にアンケート結果配布 中2自殺で異例の対応 7/13/12(毎日新聞)
大津市は13日、中2男子自殺で学校側が実施したアンケート結果の概要を市議会の教育厚生常任委員会で公表した。概要は市議のほか、傍聴人にも配布された。自治体が内部資料を傍聴人に提供するのは極めて異例だ。
沢村憲次さわむら・けんじ教育長は昨年11月に実施した2回目のアンケートで「葬式ごっこ」などといじめを強くうかがわせる記述があったにもかかわらず、見落としていたことについて「調査が不十分だった」と陳謝。「委員の皆さまにご心配をおかけした。ご報告が遅れて申し訳ない」と述べた。
アンケートは「(昨年9月29日の体育大会で)はちまきで首を絞められているのをみた」「(同日)死んだハチを食べさせていた」などの証言を列挙している。出席した10人の市議は黙々とページをめくった。
市議の一人は市教委の対応を「重大性を認識していないと言われても仕方がない」と糾弾。市教委は「学校からの報告をうのみにし、チェックが甘かった」と認めた。
いじめと犯罪行為の関係をめぐり、沢村教育長は「いじめがすべて犯罪行為との認識はない」と話した。
思ったよりも展開がはやい。同じ女性教諭なのか?違う女性教諭なのか?同じであればどうして発言が違うのか?
発言に関して誰かが圧力をかけたのか?警察の強制捜査で偽証罪(刑法169条)が怖くなり発言を変えたのか?
今後の展開はどうなるのか??
大津“いじめ”自殺 “暴行”女性教諭が目撃か 7/13/12(MBS毎日放送)
滋賀県大津市でいじめを受けていた男子生徒が自殺した問題で、同級生が男子生徒に暴行していたのを女性教諭が目撃していた可能性のあることがわかりました。
男子生徒の自殺をめぐり滋賀県警は、去年9月の体育祭で同級生3人が男子生徒に暴行を加えた疑いがあるとして11日、中学校などを捜索しました。
生徒へのアンケート調査で、男子生徒が体育祭のとき粘着テープなどで縛られていたのを複数の生徒が目撃していたことがわかっていましたが、市の教育委員会はこれまで目撃した教諭はいないとしていました。
しかし13日の会見では、「女性教諭が目撃した可能性を否定せず、この教諭は遊んでいるようにみえてやめるよう注意した」と話しているということです。
警察は夏休み中に生徒や教諭ら関係者から集中的に事情を聞き、来月中に立件するかどうかを判断するとしています。
滋賀県警、大津の中学教諭らから聞き取り始める 7/13/12(読売新聞)
大津市立中学2年の男子生徒がいじめを苦に自殺したとされる問題で、滋賀県警は13日、男子生徒が通っていた中学校の教諭らから聞き取りを始めた。
事実関係を解明するため、いじめがあったかどうかや、自殺前の男子生徒の様子などについて聞く。
県警は11日にも同校の校長や沢村憲次・市教育長から任意で事情を聞いており、今後は生徒や卒業生らからも話を聞く方針。
大津いじめ自殺:「訴訟は継続」大津市教育長 7/13/12(毎日新聞)

大津市の沢村憲次教育長は13日の記者会見で、自殺した生徒の遺族が起こしている損害賠償請求訴訟について「訴訟は続けるべきだと思います」と述べ、今後も争う意向を明らかにした。越直美市長はいじめと自殺の因果関係があるとの認識を示し、第三者委員会での調査を踏まえて和解を探る方針を表明している。
滋賀県警が捜査を始めた体育祭での男子生徒に対する同級生の行為について「その時間、そのエリアを巡回していたのは女性教諭1人だけ。その教諭は、その場面は見ていないと言っている」と強調した。【千葉紀和】
検察や警察が沢村憲次教育長に対してどのように対応していくかが重要だろう!話は変わるがアメリカ沿岸警備隊は
韓国人船長が海洋投棄の事実に関してフィリピン船員に虚偽の発言を強要したことを立証し、有罪にした。沢村憲次教育長対策が
上手くいけば、他の教諭達も真実を言うと思う。それとも証拠隠滅罪(刑法第104条)や偽証罪(刑法169条)を適用して、
嘘が明らかだと思える教諭から矛盾をついていくのか?一度嘘を付けば、嘘のつじつまを合わせるためにさらなる嘘を
つかなければならなくなるはず。そこを見逃すのか、見逃さないかが検察や警察の能力次第。
「ほんまにごめん」生徒心中吐露「苦しくて涙」 7/13/12(産経新聞)
大津市立中学2年の男子生徒(当時13歳)がいじめを苦に自殺したとされる問題で、生徒らが回答したアンケートの自由記載欄の内容がわかった。
それぞれが、仲間を失った悲しみ、助けられなかった自責の念を抱き、「全力で調査してください。お願いします」などと真相究明を求めていた。生徒らの痛々しいまでの心の叫びは、なぜ学校側に届かなかったのか。
自由記載欄の記述がわかったのは、昨年10月に男子生徒が自宅マンションから飛び降りた直後、全校生徒約860人に対して行われた1回目の調査アンケート。見聞きしたいじめの有無とは別に、「学校に伝えたいこと」「男子生徒への思い」を尋ね、635人が記入した。
ある生徒は、苦しい胸の内をこう記した。
「どれだけつらかっただろう。どんな思いで飛び降りたのだろう。そう考えると、悲しくて苦しくて涙が出る。相談に乗ってやれたらよかったのにと悔しい気持ちでいっぱいです」
男子生徒はクラスでも部活動でも、冗談を言って周囲を和ませるムードメーカー的存在。そんな彼が抱えていた苦しみに、多くの生徒は、仲間を失って初めて直面することになった。
ほかの生徒も「もっと早く気づいてあげればよかった。ほんまにごめんな、ゴメン。ゴメン。ゴメン」などと書き、いじめに気付いていた生徒は「見て見ぬふりをしてしまった」と、無念さをにじませた。
◆「先生も話して」◆
男子生徒の自殺直後、学校はいったん、報道機関などに「いじめはなかった」と公表した。これに対し、「絶対、先生とかも気付いていたと思う。いいかげん、隠さずに話してほしい」などと多くの生徒が違和感を持っていた。
自分たちが目撃したいじめが、自殺の原因だったのではないか。そんな思いで、徹底的な調査を期待する声も少なくなかった。
ある生徒は「絶対に真実を突き止めてほしい。事実がどうであっても、学校を守るために封印するのは絶対にやめてください」とクギを刺していた。
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)の対応は問題がある。強制捜査となって良かった!
証拠隠滅罪(刑法第104条)や偽証罪(刑法169条)があるから教育委員や教諭の逮捕だって場合によってはあるかも。
心当たりがある人間は心配しているかも?どのような結果になるかは検察の能力や経験次第だろう。
「未提出資料あるかも」 強制捜査の背景に市教委への不信感 7/12/12(産経新聞)
教育委員会や学校への異例の強制捜査に発展した大津市の中学2年生の自殺問題。捜査関係者によると、滋賀県警が本格捜査に踏みきった背景には、県警の市教委に対する不信感があったという。一方、自殺した生徒の父親が3度にわたって提出しようとした被害届を受理しておらず、「捜査が遅いのではないか」という批判への配慮もあったとみられる。
県警は数日前から市教委に対し、資料の任意提出を求めるなどしていたが、市教委は、いじめ調査のために学校側が実施したアンケートが2回行われていた事実について県警側に伝えていなかった。
捜査関係者によると、県警は家宅捜索を行った11日までに1回目のアンケートの原本や集約結果などの提出を受けていたものの、それが資料の全てなのかどうかは、はっきりしていなかった、と指摘する。
ある捜査幹部は「(アンケートが)2回と知ったのは(10日の)市教委の記者会見があってから。これまでに任意提出を受けた分が全てかどうか疑念を抱いた」と打ち明けた。
一方、県警側には焦りもあった。同級生からの暴行を受けているとして自殺した生徒の父親が3度にわたり、滋賀県警大津署に被害届を提出しようとしていたものの「被害者が死亡しているので立件するのが難しい」などとして受理しなかった経緯に対する批判もあったためだ。
また、捜査にあたり事情聴取の対象者は700~900人と膨大になることもあり、市教委だけの調査には限界があるという判断もあった。これまでに提出を受けた資料に加え、捜索で押収した教員の日記やノート、生徒の出欠簿などを精査し、事態の全容解明を目指している。
「学校に警察の人、信じられない」…生徒動揺 7/12/12(読売新聞)
いじめの実態はどこまで解明されるのか。
大津市立中学2年の男子生徒が自殺した問題は11日、教育現場が捜索を受けるという異例の事態に発展した。捜査員が入った市教委や中学では、教職員、生徒らが「これからどうなるのか」と、驚きと不安の表情を浮かべた。
亡くなった男子生徒が通っていた中学では午後7時20分頃、滋賀県警の捜査車両3台が到着、捜査員が正門を開け敷地内へ。カーテンを閉めた3階建て校舎の一室で約5時間、捜索を続けた。
報道で知り、友人と自転車で駆けつけた1年男子生徒は「学校に警察の人が来るなんて信じられない。どんどん大きなことになっているが、人が死んだのだから、当然なような気もする」と心配そうな表情。その後も帰宅していた生徒らが次々と集まり始めた。
その場にいた教職員らは、報道陣に対して「コメントすることはありません」とだけ話した。
一方、市教委のある市役所別館2階では午後7時30分頃から2時間余りにわたり、捜査員約10人が教育長室などを捜索。事務室では約50人の職員が残業中で、入り口のドアは内側から段ボールなどで目隠しされた。女性職員は「何が始まるんですか」と驚き、男性職員は「これからどうなってしまうのか」と不安そうに語った。捜索に立ち会っていた沢村憲次・教育長は「大変残念。一日も早い事態の収束と信頼回復に全力で取り組みたい」と話した。
保護者らにも動揺が広がった。同校1年の息子がいる男性(41)は「今回のいじめはもはや事件。市教委や学校の説明を聞いていても信じていいか分からず、息子を通わすのも不安だ。捜査で少しでも真実が明らかになれば」と願い、女子生徒の母親は「娘から『男子生徒へのいじめはやり過ぎだ。誰か止めた方がいいと話題になっていた』と聞かされた。学校からは生徒や保護者に説明がない」と不満げに語った。
「いじめた側にも人権」を主張する大津市教委が扱うケースなのだから当然だろ!「葬式ごっこをしていた」「『自殺の練習』と言って首を絞めた」などの内容を
見落とすようなレベルなのだから感謝こそすれ、問題はないだろう。
滋賀県警がどこまで捜査できるかは疑問だが、「いじめ=警察による捜査」の前例を作った
教育委員会 | 大津市(大津市のHP)の唯一の貢献を活かして欲しい。教育委員達が関係書類を隠したり、破棄したことが明らかになれば
証拠隠滅罪が適用できるのだろ?適用されれば懲戒処分か?
いじめ自殺、中学と市教委を捜索…滋賀県警 7/11/12(毎日新聞)
大津市立中学2年の男子生徒(当時13歳)がいじめを苦に自殺したとされる問題で、滋賀県警は11日、専従捜査班を設置し、男子生徒への暴行容疑の関連先として大津市教育委員会と同中学校を捜索した。
校長や市教委の担当者らからも任意で事情聴取した。
捜査関係者によると、捜索の容疑は、同級生数人が昨年9月、男子生徒に暴行した疑い。県警は、いじめと自殺の因果関係など事件の全容を解明するには、全校アンケートなどの資料の分析が必要と判断。非公開の資料もあるとみて強制捜査に乗り出した。
警察庁によると、いじめが背景にある事件の場合、学校や市町村の教育委員会から証拠の任意提出を受けるのが一般的で、捜索まで行うのは異例という。
大津・中2自殺、またも生徒に口止めか(TBS Newsi)(YouTube)
大津いじめ自殺、加害生徒に確認せず (YouTube)
相手の言葉を信用できなくなれば疑って動く。当然の対応です。疑って対応するからいろいろな情報を得ようとする。
大津市の教育委員会の判断に多くの人は疑問を抱かなかっただろうか?おかしいと思った人は多いだろう。
すると「なぜ」(理由)を知りたいと思う。日本では権力がある人間が問題を隠蔽する傾向は理解されていると思う。
東京電力の発言を多くの国民が信用しているのか?信用していないだろう。お金で学者、政治家そしてキャリアを操る。
もしかしたらいじめ事件でも圧力なり、権力が関与しているのかもと考えてもおかしくない。
大津市の教育委員会が適切でなきからこのような展開になったと思う。「いじめた側にも人権」と言った教育委員会。
結果として最悪の方向へ向かっている現状を考えると滑稽だ!
加害生徒の親族情報まで出回る いじめ事件対応と何か関係しているのか 7/11/12(J-CASTニュース)
滋賀県大津市立中学2年の男子生徒が自殺した問題で、いじめたとされるクラスメートら3人の親族が「地域の有力者」と報じられた。ネット上で様々な憶測が出ているが、真相はどうなっているのか。
「母がPTA会長」「父が京大医学部卒」
いじめたとされる男子生徒3人の一部親族について、週刊新潮は2012年7月11日発売号でこう報じた。
週刊誌・テレビ報道で憶測広まる
いじめを巡っては、学校が行った全校生徒へのアンケートには、男子生徒を日常的に殴っていたり、死んだハチを食べさせたりするなどの3人の行為が書かれていた。さらに、「自殺の練習」「葬式ごっこ」などの記述もあり、度を超した内容が物議を醸している。
これに対し、大津市教委は、いじめの調査報告書を作成せず、文科省にまで情報が十分に伝わっていなかった。また、「自殺の練習」などの記述について、当時は気づかず事実確認していなかったとし、調べた結果、それが事実であるという判断にはならなかったと説明した。
新潮の記事では、親族にPTA会長らがいたことと、学校や教委の対応との関係にまでは触れていない。一方で、10日夜に放送されたテレ朝系「報道ステーション」では、因果関係をほのめかすような解説がなされた。
被害生徒側からのSOSが市教委に届かず、アンケート結果は隠されていたとして、こう指摘した。
「遺族が口にする不信感 加害者とされる生徒の一部の親族は地域の有力者だった」
ネット上でも、加害生徒の親族について、県警OBがいたといった、真偽の不明な「独自情報」が出回り、様々な憶測がなされている。タレントのデヴィ夫人も、後に削除したものの、こうした情報を元に義憤をぶつけるブログを書いている。
滋賀県警は「親族にOB」を否定
前出の「報道ステーション」では、夜回り先生として知られる水谷修さんがコメンテーターとして出演し、こう市教委を批判した。
「『万引きしろ』というのは、犯罪の教唆でしょう。あるいは、叩く殴る、もう傷害じゃないですか。警察に通報すら怠って、これはもう隠蔽としか取りようがないですね」
加害生徒の親族に地域の有力者がいたかどうかなどについて、大津市教委に取材すると、担当者が協議中として話が聞けなかった。滋賀県教委の学校教育課では、「親族関係などについては、分かりませんし、個人情報に関わることはお答えできないです」と言うのみだった。
滋賀県警の少年課では、取材に対し、親族に県警OBがいることを否定した。
「ネット上には、OBの名前が挙がっていますが、それは加害生徒の祖父などではなく、まったくの事実無根です。いろいろな電話がかかってきて、本人も迷惑しています。親族に警察関係者はおらず、ですから、圧力などはあるわけがありませんよ」
被害届を受理しなかったことについては、こう説明する。
「処罰できるような明確な資料が整っておらず、関係者から事情聴取しないといけませんので、受理に至っていなかったということです。きょう11日から25人の捜査班を作って動いており、受理するかどうかは言えませんが、遺族の方が来られれば対応したいと考えています」
沢村教育長は謝罪すれば許されるとでも思っているのか?そう思っているのなら考え方が古いし、教育長などやめてしまえば良い!
いたずらもあるかもしれないが、名前で特定されては困るから「無記名」にしたとは考えられないのか?考えられなかったのであれば
大津市の教育委員会はレベルがかなり低い。
大津市教育委員会:「『自殺の練習といって首を絞める』『葬式ごっこ』との記載に気づかず、事実確認もその時点では行っていませんでした」
大津市教育委員会、教育委員達よ、こんな言い訳で恥ずかしくないか、こんな言い訳を言って自分は善人と思っているのか、
こんな言い訳で、テレビを見て笑い、心地よく眠れるのか?教育委員をやる人間じゃないよ!気づかないのなら仕方がない。
皆が親になっているかは知らないが、子供に対してどう対応しているのか?俺は大津市教育委員だと自慢に思っているのか?
偽善者であることすら思わないほど神経が麻痺している人間たちなのか?彼らを知っている人達はどうおもっているのか?
類友なのか?
越 直美市長は弁護士として日米の法律事務所勤務及びニューヨーク州司法試験合格(大津市のHP)
の経歴があるのなら、沢村憲次教育長を呼んで事実確認をして公表するべきだろう。アメリカでの経験があるなら、
日本の曖昧な対応について「YES」または「NO」の答えしかない質問ができるはずだ。橋下市長のように
リーダーシップを発揮してもらいたい。テレビが悪いのかもしれないが、弁護士の経験やアメリカでの経験が
ない市長のような印象を受ける。
追加アンケ「葬式ごっこ」見落とした上に非公表 7/11/12(毎日新聞)
大津市立中学2年の男子生徒(当時13歳)がいじめを苦に自殺したとされる問題で、市教委は10日夜、緊急記者会見を開き、昨年10月の全校生徒を対象にしたアンケートとは別に、11月にもアンケートを実施し、「葬式ごっこをした」「『自殺の練習』と言って首を絞めた」など、いじめを示す新たな回答を得ていたことを明らかにした。
1回目のアンケート後、「さらに事実を知りたい」という男子生徒の遺族の要望を受けて追加実施したというが、市教委は十分に事実確認をせず、公表もしなかった。
市教委によると、追加アンケートは昨年11月1日に実施した。最初のアンケートは無記名や伝聞の情報が多く、事実確認が難しかったため遺族の意向に応えて再度行ったとしている。
追加アンケートの回答には、加害者とされる同級生らが「葬式ごっこをしていた」「『自殺の練習』と言って首を絞めた」などの内容も含まれていた。
しかし当時、学校側がこうした記述を見落としたうえ、市教委には「新たな情報は確認できなかった」と報告した。このため、市教委は追跡調査は必要ないと判断し、回答についても非公表にしたという。
アンケートについて、市教委は昨年12月の市議会で2度実施したことを認めていたが、内容は明らかにしていなかった。
記者会見で、沢村憲次教育長は「『葬式ごっこ』などの文言は、最近になってこちらで気づき、学校側に再調査を指示した。事実確認が不十分だった点もあり、批判を受けても仕方がない。深くおわびしたい」と陳謝した。
大津市いじめ自殺 市教委「葬式ごっこ」見落とす 7/11/12(tv-asahi)
滋賀県大津市で中学生が自殺した問題で、大津市の教育委員会が10日深夜に会見を開き、生徒に対して行っていたアンケートの中身を公表しました。そのアンケート用紙、生徒たちが記入したなかには「自殺の練習といって首を絞める」や「葬式ごっこ」などの記述があり、市教委はこれらについて事実確認を行っていませんでした。
大津市教育委員会:「『自殺の練習といって首を絞める』『葬式ごっこ』との記載に気づかず、事実確認もその時点では行っていませんでした」
市教委は、2回目のアンケート結果を初めて公表。「自殺の練習といって首を絞める」などの具体的な記述がありましたが、学校と市教委はこれらを見落とし、以降8カ月間、事実確認を怠りました。
自殺した生徒の祖父:「生徒が先生に言っているのにもっと真剣にやってくれたら…。それが悔しい」
これを受け、大津市の越直美市長は、「学校と市教委の調査はずさんで信用できない」として、遺族が市などを相手取っている訴訟をいったん中断し、和解する意向です。
越直美大津市長:「いじめと自殺の因果関係があるという前提で調査を進めたい。裁判上の責任を取りたい。和解したい」
遺族側弁護士は、「発言は裁判の外で出たもので、意図をはかりかねる。裁判で正式に伝えられてから検討する」と話しています。
大津市長 越直美 高校 まとめ 7/08/12(今の時代)
滋賀県大津市の越直美市長は、滋賀県大津市のマンションで昨年10月、市立中学2年の男子生徒=当時(13)=が飛び降り自殺した問題で、7月6日の定例会見で、事実関係の調査をやり直すことを決定したと明言、「早急に外部の有識者による調査委員会を立ち上げたい」と述べた。
越直美市長は会見で、「これまでは事件の真実について法廷で明らかにされていくのだろうと思っていたが、裁判以前に事実関係の調査をやり直すことを決めた」と発言。「自殺の練習は真実ならいたましい話。市長就任後もっと早く調査に取り組むべきだった」と涙ぐみながら話した。
それにしても、越直美大津市長のプロフィールは凄いように思える。
大津市のホームページに越直美市長のプロフィールが掲載されているが、2000年に北海道大学の法学部を卒業後、その年の11月に司法試験合格、2002年より西村あさひ法律事務所に在籍。2009年にはハーバード大学ロースクールを終了。その年の11月にはニューヨーク州司法試験合格。その後、コロンビア大学客員教授、国連ニューヨーク本部法務部研修などを経て、2012年に大津市長に就任している。
今回、この問題が再燃したのは、学校側が生徒を対象に実施したアンケートに、15人が「死亡した男子生徒が自殺の練習をさせられていた」と答えていたことが7月3日に関係者への取材で判明したからだ。市教育委員会はいじめの存在は認めたが、一貫して「いじめと自殺との因果関係は判断できない」との主張を続けている。
男子生徒の両親は本年2月、自殺の原因はいじめだっだとして、いじめ行為をしたとする男子生徒3人とその保護者、および大津市に約7,720万円の損害賠償を求め提訴。大津地裁で係争中で、市側は「自殺に過失責任はない」と主張している。
越直美市長は2012年3月に、自殺した生徒が通っていた中学校の卒業式に出席し、小学校3年生や高校1年生の頃に自らが受けていたいじめの体験を語ったうえで、いじめや自殺の再発防止を誓った。その後の大津市と加害者と遺族の間で民事裁判における口頭弁論において、自殺した生徒の死といじめの因果関係を否定したこともあり、生徒の遺族は市長の行為は「パフォーマンス」だと非難している。
それにしても、いじめの内容はひどい、かつて東京都足立区で起きた「女子校生コンクリート詰め殺人事件」に匹敵するといっても過言ではない、いやそれ以上であるような気がする。
学校側が全校生徒859人に実施したアンケートには「(同級生が)思い切り肺、おなか、顔を殴ったり、跳び蹴りしていた」という、暴行現場を目撃したとする生徒の証言もあった。さらに、「先生も見て見ぬふり」「一度先生は注意したけれどその後は一緒になって笑っていた」と、教諭がいじめを放置していたことを示す回答も14人からあった。
また男子生徒が死んだハチを食べさせられそうになったり、ズボンをずらされたりしたほか、首を絞められたり、整髪料のスプレーをかけられたりしていたという目撃談もあったようだ。
アンケートには、他に1~3年の15人が伝聞形式で「昼休みに毎日自殺の練習をさせられていた」「(いじめた生徒が)自殺のやり方を練習しておくように言っていた」などと記載との記載もあった。
これらの背景には、いじめの当事者がPTAの会長の息子である、とか、警察OBの孫であるとか、そういった権力がバックにいることが、事件を追及できない原因のようだ。いじめ当事者は実名を公表されているが、それでもこれらの事件が完全に白日のもとに晒されることはないだろう。
警察は自殺と断定しているが、この少年が自殺後、管理人が119番通報し、搬送されたのは、現場から22キロも離れた済生会滋賀県病院へ運んだらしい。この病院は、加害者の祖父(警察OB)が勤務しており、この病院で司法解剖が行われたという話もある。
越直美市長については、日米の弁護士試験に合格という立派な経歴を持ちながら、それを実社会を自ら先導していくために使っていくことがまだできていないようだ。37歳で市長は早いかどうかは別として、次々と起きる事件について、市長として自分ごととして真摯に受け止め、問題の解決を誰よりも先頭に立って陣頭指揮する行動が求められる。
「いじめた側にも人権」これが正当化できるのならいじめられた方よりもいじめた方が有利と考えられる。
大津市教委ではいじめに関しては「いじめた側にも人権」のためにまともな調査はできないので、事を大げさにしても
直ぐに警察を介入させるべきだ。大津市教委の対応には記事を読んでいて腹が立つ。こいつらが給料をもらっていると思うと
さらに腹が立つ。
いじめた側にも人権…「自殺練習」真偽確認せず 7/06/12(読売新聞)
大津市の市立中学2年男子生徒が自殺したことを巡って行われた全校アンケートで「(男子生徒が)自殺の練習をさせられていた」との回答を市教委が公表しなかった問題で、市教委が加害者とされる同級生らに対して直接、真偽を確認していなかったことがわかった。
市教委はこれまで、非公表にした理由を「事実を確認できなかったため」と説明していた。
市教委によると、「自殺の練習」は、生徒16人が回答に記していた。うち実名で回答した4人には聞き取りをしたが、事実は確認できず、それ以上の調査もしなかったという。加害者とされる同級生らにも聞き取りを行う機会はあったが、「練習」については一切尋ねなかったとしている。
その理由について、市教委は読売新聞に対し、「事実確認は可能な範囲でしたつもりだが、いじめた側にも人権があり、教育的配慮が必要と考えた。『自殺の練習』を問いただせば、当事者の生徒や保護者に『いじめを疑っているのか』と不信感を抱かれるかもしれない、との判断もあった」と説明。結局、事実がつかめなかったとして、非公表にしたという。
Kids and Laughing Teachers Bullied Suicide Teen 7/06/12(ABC News)
The suicide of a 13-year-old boy in southern Japan after classmates systematically bullied him — even making him “practice” suicide — while teachers ignored the abuse or laughed has prompted soul-searching among educators across the country.
One of the boy’s last acts was to text his tormentors and leave voice mails for them to say, “I’m going to die.” They texted him back to say, “You should die.”
The middle school student, whose name has not been released, jumped from his 14th floor apartment in the city of Otsu last October after enduring heartrending tales of abuse at the hands of his classmates.
His father filed several reports with the police, but officers never accepted them, saying that they could not prove that bullying led to his suicide, according to Japanese media reports.
Details of the harassment are coming to light eight months later, following a student survey conducted by the city’s board of education. In that anonymous survey, students write the bullying escalated to “punching and kicking” in September last year, about a month before the teen jumped to his death. The victim was pressured into shoplifting, had his legs and arms tied while bullies duck-taped his mouth. Students watched as their peers pressured the teen into eating dead bees, “pantsed” him, and made him “practice” committing suicide.
In the survey, some classmates report alerting teachers to those “practices,” but say nothing was done.
Instead, teachers reportedly laughed as bullies tried to choke the victim.
“He was forced to eat paper, students choked him. Teachers only gave a verbal warning, but then joined in on the bullying by laughing,” comments in the survey read.
Today, the tearful mayor of Otsu, said that she would launch a new investigation into the teen’s suicide to “seek the truth,” calling the board’s survey “inadequate.”
“I feel awful I have to put students through this again,” Naomi Koshi said. “I cannot apologize to the students enough.”
Local media report Otsu has been bombarded with hundreds of calls and emails from angry parents since the bullying came to light on July 4. A bomb threat was called into the board Thursday, forcing students to go home early.
The teen’s family has not commented publicly on the case since the new details surfaced, but in a letter sent to Koshi, the boy’s father called on the mayor to “seek the truth” and come up with a new anti-bullying policy.
“I want bullying to disappear from every school in Japan,” he wrote. “I want schools to become a safe place again.”
「自殺練習」追加調査しない考え…大津市教委 7/05/12(関西発 読売新聞)
大津市で昨年10月、市立中学2年の男子生徒(当時13歳)が飛び降り自殺したことを巡る全校生徒アンケートで、「自殺の練習をさせられていた」との回答を市教委が公表していなかったことについて、4日に記者会見した沢村憲次教育長は「事実と確認できなかったため公表しなかった。隠したわけではない」と述べ、対応に問題はなかったとした。そのうえで、「可能な限り、いじめの事実を調べた」として、現時点では追加調査などはしない考えを示した。
市教委はこの日、男子生徒が亡くなった直後に実施したアンケートで、「自殺の練習をさせられていた」と回答した生徒を16人とした。このうち4人は記名で回答していたため、市教委は聞き取り調査をした。
この生徒らの記載は伝聞によるものだったことから、4人に話したとされる生徒からも事情を聞いた。しかし、自分でその場面を見たとは言わなかったという。
さらに、無記名だった生徒の回答にも、場面を直接見たことをうかがわせるものはなく、名前が不明で追跡調査もできないため、市教委は「自殺の練習をさせられたとの確証は得られなかった」としている。
記者会見で沢村教育長は、生徒の両親が、大津市と、加害者とされる3人とその保護者を相手取って損害賠償を求める訴訟を起こしていることを理由に、追加調査などについては「現時点では何も申し上げられない」と繰り返した。
また、市教委が昨年11月、男子生徒へのいじめについて明らかにした際、アンケートの回答の一部を公表しなかった点を問われると、「公表した内容については、かなり慎重に確認しており、そのほかのことを隠したとは考えていない。自殺の練習については、事実と確認しきれないという結論に至った」と説明した。
男子生徒が通っていた中学では、自殺の1週間前、担任教諭が「(男子生徒が)いじめられているのではないか」と別の生徒から聞いたものの、本人に確かめると、「大丈夫」と答えたという。
このため、学校は当初、「いじめなどの事実はない」としていたが、両親の依頼で全校生徒にアンケートを実施。「トイレで殴られていた」「ハチの死骸を食べさせられそうになっていた」といったいじめがあったことがわかった。校長が両親に調査結果を報告して謝罪したが、両親は継続調査を望んでいた。
この日の市教委の記者会見を受け、男子生徒の父親は「いじめで子どもを亡くすようなことが二度と起こらないようにすることが大切なのに、事実や原因が明らかにされなければ、対策の取りようがない。大津市や加害者側には事実を全て出してほしい」と話した。
長谷川博一・東海学院大教授(臨床心理学)の話「伝聞が含まれていたとはいえ、アンケートでいじめについて回答した生徒の数は多く、内容も多岐にわたっている。市教委は『可能な限り調べた』としているが、問題への深入りを避けているようにも映る。証言内容が真実かどうかを改めて調べたうえで、遺族が納得できるような説明をしなければならない」
静岡市の教育委員会は体質の問題である良い例だろう!
教職員処分件数、文科省に過少報告…静岡市教委 07/13/12(読売新聞)
静岡市教育委員会が、2005~07年度の3年間、文部科学省に報告する教職員の処分件数を過少報告していたことが、市教委への取材でわかった。
最も軽い処分である「厳重注意」を報告していなかった。読売新聞の指摘を受けた市教委は、近く文科省に修正報告する。
調査は各自治体における服務規律の確保などが目的で、毎年、都道府県と政令市の教育委員会に処分件数の報告を求めている。
静岡市教委が過少報告していたのは、懲戒処分より軽く、公表対象ではない内規処分。07年度分では、内規処分13件のうち、最も軽い厳重注意の6件すべてを報告していなかった。6件には、「体罰」の4件や、「わいせつ・セクハラ」の1件が含まれている。
読売新聞の指摘を受け、市教委が調べたところ、05、06年度も同様に厳重注意の件数が報告されていなかった。静岡市は05年に政令市に移行しており、04年度以前の報告は県教委が行っていた。市教委は、05、06年度分について確認作業を進めており、過少報告件数が確定し次第、文科省に修正報告する。
08年度以降は全件数が報告されている。市教委は「当時の担当職員が軽い処分は報告する必要がないと考えたのでは」としている。
文科省は「注目度が高い調査なので、正確な調査結果を、きちんと報告してほしい」としている。
静岡また教員不祥事、「空腹で」女性教諭万引き 05/22/12(読売新聞)
静岡県教委は21日、万引きをした県西部の県立特別支援学校の女性教諭(31)を停職6か月としたほか、不法投棄などで教員2人をいずれも減給10分の1(3か月)の懲戒処分とした。
教職員の懲戒処分は今年度、これで計4件となった。
発表によると、特別支援学校の女性教諭は今年2月14日午後、磐田市内の食料品店で約4500円分の食料品を袋に詰めてレジを通らずに店外に出たところ、警備員に呼び止められて警察に通報された。その後、窃盗容疑で静岡地検浜松支部に書類送検され、不起訴となった。
教諭は当時育児休業中で、精神的に不安定だったといい、「買い物中に空腹になった」と話したという。5月21日付で依願退職した。
県東部の小学校の男性教諭(49)は昨年12月29日夜、小山町上野の山林に、自宅にあったゴルフクラブやコンピューターなど計約125キロのゴミを不法投棄し、廃棄物処理法違反で沼津簡裁から罰金50万円の略式命令を受けた。
教諭は「道徳上問題はあると思ったが、法に触れる認識はなかった。情けない」と話しているという。
県立磐田北高の男性主任技能員(60)は2005年度から今年度にかけて計43回、学校で不要になった古紙などを磐田市内の回収業者に持ち込み、売却費計5万5497円を公金に入れず、私有する軽トラックの維持費に流用した。4月に同僚から同校に指摘があり発覚した。技能員は「軽トラックは学校で仕事に使っていたので、当時は問題ないと思った」と説明しているという。
安倍徹教育長は「不祥事根絶を最重要課題として取り組んでおり、実践的な指導や校内研修などを通じて信頼回復に努めたい」とコメントした。
静岡市の教育委員は考えが甘い。ゆとり教育がどうなったのか?理想と現実のギャップ!
保安院が安全と宣言しても、なぜ国民が信用しないのか?それは信頼できない事実の存在と保安院の目的と現場での実際のパフォーマンスの
ギャップがあるからだろ。
「不祥事はなくならない」からこそどのように不祥事を減らすのかを考えなければならない。否定からはじめてどのような対策が
できるのか?子供への指導ともったいぶった言い方をするが、先生に指導力やカリスマがあれば、「不祥事はなくならない」という
考えでも問題ないはずだ。子供達が先生を尊敬し、信頼すれば問題ない。実際に指導力やカリスマがある先生が何割いるのか?
試験に通り、教員の資格を持っているから先生と思っていたら大間違いだ。指導力やカリスマは必要であると思われるが、
無くても問題ないのが現実だろ!
静岡県で波紋「教員不祥事起きる前提で対策を」 05/16/12(読売新聞)
静岡県と静岡、浜松両政令市の教育委員による初の意見交換会が15日、県庁で開かれた。県内で相次ぐ教員の不祥事について、「不祥事は起きるという前提での対策も検討すべきだ」との意見が出て波紋が広がった。
県と両政令市が教育行政で連携しようと、教育長を含む教育委員計15人が参加し、教職員の資質向上などをテーマに意見交換した。
この中で、県の加藤文夫教育委員が「これほど不祥事が多発すると、一定の確率で不祥事は起きるとの前提で対策を進めないといけない。最低限子どもに迷惑がかからないようにするにはどうすべきかを考える時期なのかなと思う」と発言、「不祥事根絶」という従来の方針を再検討すべきとの考えを示した。浜松市の高木伸三教育長は「私も校長に対し、ゼロにはできないが、少なくしていかなければいけないと指導している」と語った。
この意見に対し、静岡市の教育委員は「『不祥事はなくならない』という考え方だと、先生方が子どもに指導しにくくなる」と懸念の声が上がり、同市の高木雅宏教育長も「繰り返し現場に指導するのが、教育委員会の務め。ゼロにするために、あきらめずにやることが大事だ」と訴えた。
安倍徹・県教育長は取材に、「あくまでも不祥事ゼロを目指し、立ち止まらずに知恵を絞って対応していきたい」と述べた。
PTA費、学校運営に流用 12府県市の監査で改善要求 05/10/12(朝日新聞)
大阪府や名古屋市など12の府県・政令指定市の一部の公立高校が、保護者らから集めた金を公費の代わりに学校経費に充てたとして、2007~11年度の県や市の監査で改善を求められていたことが朝日新聞の調べで分かった。PTA会費や後援会費といった学校徴収金を校舎修繕費や教職員手当などに充てていた。こうした実態を問題視し、文部科学省も9日、全国調査に乗り出した。
学校の経費は、学校教育法で「設置者(府県や市)の負担」とされる。負担の範囲について、文科省の担当者は「給与や施設の建設・修繕など学校本来の役割に必要な経費」と説明する。
朝日新聞は、市立高校のない相模原市を除く全66の都道府県・政令指定市の教育委員会に07~11年度の公立高校の学校徴収金について尋ねた。その結果、12府県・市の監査で、使途を示して「公費負担すべきだ」などと指摘されていた。
日本はアメリカのケースよりはましだと思う。それでも国の経済や企業の力が衰えると採用する人材を選ぶことになる。
第二次世界大戦の勝者となったアメリカは成長する経済の恩恵を受け、多くの人が今までに持てなかった物を買い、
人生を楽しんだ。アメリカの経済が傾きはじめると一戸建ての住宅を買い、車を所有しているミドルクラスが減り、
彼らの子供は大学を卒業しても仕事が見つからなくなる。見つけられても望む職業ではなく、「Dead-end」と呼ばれる
単純作業や保証の無い仕事で彼らの両親のような希望を感じられなくなった。
日本も似たような状態だろう。大学さえ卒業していれば高卒よりも給料や出世で差がつく。その事実だけのために
親は子供を大学に行かせるが、子供は勉強しない。大学も生徒の知識や能力を高めるカリキュラムを提供しない。
日本の経済や企業は傾き始め、必要のない、又は使えそうに無い甘やかされた卒業生を採用しない。学生は
自分の能力や知識に関係なく、イメージや条件で企業を選ぶ。企業にも選ぶ権利があるので、選べれるとは限らない。
ある企業や仕事はA学生にとっては妥協できるかもしれないが、B学生には選択肢ではないかもしれない。
いろいろな学生達がいるのだから、妥協できる点、妥協できない点、評価の仕方も違ってくるはずだ。
きつい仕事でも賃金を優先するのか、土日や祝日に働く仕事だがきつくない仕事、成果で差が出る仕事、安定しているが
給料が安い仕事などいろいろな条件や仕事があるはず。
人生の価値観だって違うはず。日本の学校で仕事や人生について教えてきたか?
中学校において武道・ダンスを必修化(文部科学省)
よりも大事なことがあるだろ!
大卒=エリート「今は昔」…就職戦線に異変 (1/3ページ)
(2/3ページ)
(2/3ページ) 04/15/12 (産経新聞)
大卒がエリートだった昔に比べ、大学数は半世紀で3倍に増え、進学率も50%を超える。しかし、伝統や実績のない大学の学生たちは職にあぶれたり、劣悪な労働環境の企業に就職したりするなど、“ノンエリート”としての職業人生を送らざるをえないケースもある。大学では今、就職支援はもちろん、学生の基礎学力向上や就職後のケアが重要な課題になっている。(横山由紀子)
内定は得られるが…
因数分解、2次方程式、グラフ、図形…。大学1年の授業で、就職試験に出る一般常識問題集に取り組む大学がある。数学、国語、理科、社会、英語は、いずれも中学卒業程度の内容だ。
「基本的な学習に思えるかもしれませんが、1年のスタート時に基礎学力の見直しを図ることで、専門教育に生き、就職試験にも有効。一定ラインの得点を得ていたら就職試験で門前払いされずに済み、就職活動を少しでも有利に進めることができる」。神戸国際大学(神戸市東灘区)経済学部の居神浩教授(社会政策)は話す。
居神教授は『日本労働研究雑誌』(平成22年)に論文「ノンエリート大学生に伝えるべきこと」を発表。「大学の増加で高等教育は大衆化し、学生の質は多様化した」とする。こうしたことから、学生の就職戦線にもちょっとした異変が起きているという。
厳しい就職戦線の中、伝統や実績がない大学の学生は、安易に内定を得られるが劣悪な労働環境の“ブラック企業”に就職してしまう場合があるという。ある卒業生は、商品を売るために社員数人で高齢者を取り囲んで高額ローンを組ませる会社に就職し、数年で退社。何回かの転職の末、しっかりとした会社に就職した。悪徳商法まがいの会社はその後、破産したという。
職業人生把握を
文部科学省の学校基本調査によると、昭和30年度に7.9%だった大学進学率は平成21年、5割を超えた。背景には、1990年代以降の規制緩和で、大学や学部の新増設が進んだことがある。昭和37年度に260校だった大学が、平成2年度は507校、23年度には780校と、50年間で3倍に増えた。
高校からの推薦入試、書類や面接だけで合否を判定するAO入試など、いわゆる“無試験”で入学できるシステムも拡大。受験の選抜機能が失われ、平均以下のレベルにある学生を分厚い層として取り込む形で、進学率は上昇を続けているという。
神戸国際大では先月、2、3年生を対象に、就職後の労働問題を学ぶ講座を開催。求人票や雇用契約書などの確認の仕方、パワハラを受けた際の対応、不利益を被ったときの団体交渉、異議申し立てなどをロールプレーイング形式で学んだ。
居神教授は「仕事のスキルが身に付かず使い捨てにされるブラック企業に、根性論でしがみついていては若者の未来が望めない。大学が大衆化した昨今、大学の知名度にかかわらず、全ての学生たちが“ノンエリート”としての職業を選択してしまう可能性がある」と指摘。そのうえで、「大学は、学生の基礎学力アップなどの就職支援はもとより、就職後の職業人生まで把握しケアすることが必要だ」と話している。
◇
【用語解説】ブラック企業
低賃金での長時間労働やサービス残業、休日や休憩なしの勤務、暴言などのパワーハラスメントが当たり前で、違法性の強い劣悪な労働環境を強いる会社。事前の準備がいらず、1回の面接で即内定がもらえるなど“楽勝就職”できるため、学生が就職先として安易に選んでしまうケースもある。
文部科学省は何を考えているのか?現場が準備できていないのに実行に移す。そこまでする理由があるのか?
文部科学省の回答は理解できません。多くの領域の学習を十分に体験するために絞り込んだのが、武道とダンス。
こんな文部科学省だから子供の将来が暗くなる。文部科学省はあほとしか言えない。クラブ活動などで選択させれば良いだけだろ。
2日の研修で柔道の黒帯を与える都道府県があったり、むちゃくちゃだ。こんな思い付きのような決定で、教師の負担は増えて、
プロを目指す若手ダンサーを講師として使い、更なる税金の無駄遣い。地方自治体や個々の学校が選択で決めることが出来るように
するほうが良いと思う。興味があったり、やってみたければそのような活動に参加するだけで良いと思う。ゆとり教育の失敗から何も
学んでいない文部科学省。
Q: 中学校において武道・ダンスを必修化するのはなぜですか。
A: 生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現する視点から、多くの領域の学習を十分に体験させた上で、
それらをもとに自らが更に探求したい運動を選択できるようにすることが重要です。このため、
中学校1年・2年でこれまで選択必修であった武道とダンスを含めすべての領域を必修とし、3年から領域選択を開始することとします。
また、武道の学習を通じて、我が国固有の伝統と文化に、より一層触れることができるようにします。
(文部科学省)
中学体育:必修ダンスに先生苦悩、プロの卵が助っ人講師に 04/07/12(毎日新聞)
今年度から中学1、2年の体育でダンスが必修になった。仲間と踊る楽しさを感じてもらうのが狙いだが、先生たちの指導力はちょっぴり心もとない。ヒップホップのような現代風ダンスになると、ベテラン教員から「経験がなく教えられない」と悲鳴が上がる。そんな中、プロを目指す若手ダンサーを講師とする試みが福岡県みやこ町で始まっている。プロの「卵」にとってもキャリアアップにつながり、両者のニーズが一致した取り組みとして注目されている。
3月5日、町立勝山中であった授業。軽快なヒップホップのリズムに合わせて踊る女子生徒の動きを見つめる男性がいた。野球帽にあごひげ、だぶだぶのジャージー、耳にピアス。臨時講師の山田健志郎さん(19)だ。
ダンスは昨年度まで選択制で女子だけ実施の学校が多かった。同校もそうだったが、4月からの男女必修化に備え、今年に入り山田さんを講師として試行的に受け入れた。
「福島県教委:『原発の是非に触れるな』と指示」の記事を読んだ後、「福島県 教育レベル」で検索した時に下記のブログを見つけた。
現在も事実かどうか知らない。「原発の是非に触れるな」と指示が出せるような状態であれば、教育レベルが高いとは言えないと思う。
事実を歪めれば、子供や子供の両親は福島県教委のおかしな指示に気付くであろう。気付かないのであれば、やはり教育レベルを指摘されても
仕方のない現実があると言うことだろう。
福島県の会津地方の人たち(会津人)は知能指数が低く、教育レベルが低く! (栃木県)
福島県の会津地方の人たち(福島県の会津地方の人たちを会津人と言っている)は知能指数が低く、教育レベルが低い。福島県立会津高校と福島県立葵高校(この高校は、以前、福島県立会津女子高校だった)と福島県立喜多方高校(この高校は私の出身校)の3校を出た人は会津人でも知能指数が高く、教育レベルも高いが、この3校以外の高校を出た会津人は知能指数が低く、教育レベルが低い。もっとはっきり言えば、知的障害者のレベルの知能指数しかなく、教育レベルも中学校で教わることしかわからない。福島県の会津地方にある高校で、福島県立会津高校と福島県立葵高校と福島県立喜多方高校の3校以外の高校では中学校の教科書のレベルの授業しかやっていないから、高校の教科書を教えておらず、だから、教育レベルが低い。
私は今から23年前の大学時代に就職活動で、福島県の会津地方に工場があった日本モトローラ(この会社はアメリカのモトローラの日本法人)の就職試験を受けた際、私は、この会社の人事部長(この人事部長は中央大学経済学部の出身だったから、私の大学の先輩で、まだ40代前半と若く、日本モトローラはアメリカのモトローラの日本法人だから、若くても能力があれば、40代前半で人事部長をやっていた。日本モトローラは、当時、社員が千人以上いた)に、「福島県の会津地方に工場を建設したのは大失敗だった。福島県の会津地方の人たちは教育レベルが低く、労働者の質が悪い。工場を建設する前に、労働者の質の調査をやったが、こんなに教育レベルが低く、労働者の質が悪いと思わなかった。いずれ、福島県の会津地方の工場は閉鎖し、撤退する。別な地域に工場を建設することが決まっている」と言われた。この言葉の通り、日本モトローラは福島県の会津地方の工場を閉鎖して撤退し、宮城県に工場を建設して移った。
福島県の会津地方の人たちは知能指数が低く、教育レベルが低く、労働者の質が悪いから、福島県の会津地方には一流企業が工場を建設しない。福島県の会津地方の人たちの唯一の魅力は人件費が安いことだ。福島県の会津地方の会社の社員の給料は安い。東京都などの首都圏の会社の社員の給料の半分ぐらいしかもらっていない。だから、下請けや孫請けなどの会社だけが人件費の安さにひかれて、福島県の会津地方に工場を建設する。
福島県の会津地方の人たちは、自分たちが知能指数が低く、教育レベルが低いことを知らない。なぜなら、福島県の会津地方の人たちは福島県の会津地方から出たことがなく、田舎者だからだ。他の地域の人たちを知らないんだ。だから、福島県の会津地方の人たちは、「井の中の蛙、大海を知らず」なんだ。
福島県教委:「原発の是非に触れるな」と指示 現場は混乱 03/22/12(毎日新聞)
東京電力福島第1原発事故を受け、全国に先駆けて放射線教育を実施している福島県教委が、原発事故やそれに伴う被ばくに触れない国の副読本から逸脱しないよう教員を指導していることが分かった。「原発の是非に触れるな」とも指示。学校現場では、指示通りに教えると被ばくに不安を抱く親から批判され、危険性に言及すると違う立場の親から苦情が来るといい、実情に合わない指導で混乱も生じている。放射線教育は4月から全国で始まる見通しで、同様の事態の拡大も懸念される。【井上英介】
福島県内の放射線教育は、小中学校で週1時間の学級活動を使って計2~3時間教える形で、郡山市や会津若松市などの一部の学校で実施されている。
県教委は実施前の昨年11月以降、県内7地域で各校から教員を1人ずつ集めた研修会を開いた。参加した教員によると、指導主事から「副読本に沿って教えよ」「原発には中立的な立場で」などと指導を受けた。会場から「被ばくのリスクや原発事故を子供にどう説明するのか」など質問が出たが、何も答えなかったという。
研修を受けた教員は「副読本は放射線が安全だと言いたげで、不安に苦しむ住民は納得できない。県教委に従えば、県議会が県内の原発の廃炉を求めて決議し、県が廃炉を前提に復興計画を作ったことにも触れられない」と疑問を示す。
小中学校の教員で組織する福島県教組によると、親の間では被ばくの影響について見方が割れ、学校や教委に「放射線の危険性について認識が甘い」「不安をあおり、過保護にするな」など正反対の苦情が寄せられている。放射線量が高い地域の小学校教諭は「親の意向で弁当を持参して給食を食べず、屋外での体育を休む児童がいるが、他の親たちに批判的な空気も生まれるなど厳しい状況にある。副読本や県教委の指導は福島の現実に即していない」と指摘する。
県教委学習指導課は「大半の教員は放射線の素人で、教え方がばらついても困るので副読本に沿うようお願いしている」と話す。
副読本を作成した文部科学省開発企画課は「地域や教員によっては物足りないと感じるかもしれないが、自治体教委の要請もあり、放射線について最低限必要な知識を伝えるために作った。使うも使わないも自治体教委の自由だ。来年度も作ることになれば、意見を踏まえて充実させたい」と説明している。
★放射線教育の副読本 文部科学省が小中高校別に3種類作り、A4判18~22ページ。「100ミリシーベルト以下の被ばくでがんなどになった明確な証拠はない」としつつ「被ばく量はできるだけ少なくすることが大切」とし、中高生には防護や避難の一般的方法も説く。だが、福島第1原発事故への言及は前書きのみで、事故の経過や放射性物質汚染の広がりなどは書かれていない。その一方で放射線が医療や工業、学術研究で役立っていることを強調している。
「教員採用試験に合格し、新年度から高校教諭になることが決まっていた」のならなぜこんな事をしたのだろう。理解できない。
遅かれ早かれ問題を起こしそうだから結果としてはこれで良かったのかもしれない。
橋下大阪市長が全てにおいて正しいとは思わないが、規律が乱れ、組織が腐ると変えるのは難しいので、公務員に対する厳しい処分は仕方がないと思う。
教育長「むなしい」…静岡県先生また性的不祥事 03/15/12(読売新聞)
教職員の不祥事が相次ぎ、静岡県教委が矢継ぎ早の対策を講じる中、また性的不祥事が発覚した。
静岡県警は14日、伊東市吉田、県立伊東商業高校講師和田洋平容疑者(34)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕した。
県教委によると、今年度発覚した性的不祥事は8件目。和田容疑者は今年度の教員採用試験に合格し、新年度から高校教諭になることが決まっていたという。
発表によると、和田容疑者は2月中旬、出会い系サイトで知り合った県内の女子高校生(16)に対し、現金約2万円を支払う約束をして自宅でみだらな行為をした疑い。調べに対し、「18歳未満とは知らなかった」と容疑を一部否認しているという。
和田容疑者は現金を支払わなかったため、2月下旬、女子生徒が「男女のトラブルがある」と110番し、発覚した。和田容疑者は2010年度から同校で理科の授業を担当している。
◆安倍県教育長「残念」◆
相次ぐ教員不祥事を受け、県教委は昨年から再発防止策の強化に取り組んでいる。県庁で14日、報道陣の取材に応じた安倍徹・県教育長は「残念な気持ちでいっぱい」と唇をかんだ。
安倍教育長は「残念さ、むなしさと併せて悔しさもあるが、その裏には、我々がまだ至らない部分があったという反省もある。その至らなさを一つ一つ塗りつぶしていかなければいけない」と語った。
県教委は今後、和田容疑者の懲戒処分を検討するとともに、再発防止策を徹底するため、今月中に臨時校長会を開催する方向で調整しているという。
調子に乗っている英語指導助手がいるのは事実だから良いんじゃないの!
中学英語指導助手が大麻所持容疑 01/23/12(産経新聞)
福岡県警は23日、自宅で乾燥大麻を所持したとして、大麻取締法違反(所持)の疑いで、福岡市立和白中の英語の指導助手で米国人のアンドリュー・シルバーマン容疑者(25)を現行犯逮捕した。
県警によると、シルバーマン容疑者は容疑を否認している。今年に入り、県警にシルバーマン容疑者が「大麻を使っている」との情報提供があり、捜査していた。
逮捕容疑は同日、自宅の机の上に、ポリ袋に入った少量の乾燥大麻を所持した疑い。
文部科学省の英語教育の実施方法に問題があることを示している。別の形の税金の無駄遣い。
英語「役立つ」7割、「生かした仕事」希望は… 01/29/12(読売新聞)
文部科学省・国立教育政策研究所が全国の中学3年生に実施したアンケート調査で、7割の生徒が「英語は将来の就職に役立つ」と答える一方、将来、英語を使う仕事に就きたいと強く希望する生徒は1割にとどまることが分かった。
調査は昨年11月、中学3年生3225人を対象に実施。「英語の学習が大切」と考えた生徒は「どちらかといえば」を含め85%にのぼった。「英語を学習すれば、好きな仕事につくことに役立つと思うか」との問いには、36%が「そう思う」、34%が「どちらかといえばそう思う」と回答。肯定的な意見は計70%と、2003年の前回調査より、23ポイントも増えた。
しかし、「英語は好き」は22%、「どちらかといえば好き」は30%どまり。「将来、英語の勉強を生かした仕事をしたい」と強く願う生徒はわずか11%で、前回より6ポイントも減った。逆に「生かした仕事をしたくない」が43%で、前回(36%)から増えた。
例え正しい方針を実行したとしても、結果が出るまでには3、4年はかかると思う。人はそんなに簡単には変わらない。
メンタルケアだけでは問題の解決にはならないと思う。あるテレビでどのようにキャリアがだめになっていくか、
元キャリアの人達を呼んで議論していた。ほぼ出席した元キャリアが「徐々にだめになっている」との発言に
異論を唱えなかった。つまり静岡でも徐々にだめになっていくケースがあるのではないかと思う。問題を起こした
教員だけでなく、環境、人事そして評価したり方針を立てる全ての要因に問題が隠れていると思う。メンタルケアで
問題が解決すると思っているのであれば組織の思考能力に問題がある。ストレスを教員が感じるのであれば、
何が問題なのか、直接的及び間接的問題を調査し理解する必要がある。組織自体が腐敗していれば直接的及び間接的問題を調査し理解する
ことも出来ないし、現場の問題が上がってきても上層部が適切に対応できないかもしれない。問題が表面化した時点で、
問題が隠せない状態になっていると思って対応するほうが良いと思う。氷山に一角のようなものだ。問題が水面下に存在しているので、
目視できる問題に取り組んでも水面下の問題まで解決しない限り実際に問題は解決できない。
県教育長「万策尽きた」に反響 10/29/11(読売新聞)
「万策尽きた」。相次ぐ教員不祥事を受け、安倍徹県教育長が今月20日、そう発言した後、教職員のメンタルケアに協力を申し出る内容の手紙が2通届いた。県教委は「受け入れるかどうか検討したい」としている。
県教委は個人情報保護を理由に差出人について明らかにしていないが、1通は県内の大学教員からで「相次ぐ不祥事対応には、メンタル面の支援が必要。職員のメンタルサポートで私を使ってください」と、県教委が教職員のメンタルケアを行う場合、協力を申し出る内容。もう1通も「役に立つことがあれば使ってほしい」と、メンタルケアに協力を申し出る内容だった。
県教委は、相次ぐ不祥事に対応するため、県立高校に設置されているセクハラ相談員の増員や、相談員が受け付けた意見を吸い上げて検討し、研修などにつなげるコンプライアンス委員会を設置する方針を明らかにしており、こうした対策の一環として、今後、採用するかを考えるという。
一方、教育長の発言以降、県教委には不祥事を批判するメールや電話が寄せられている。26日現在でメールは20件以上、電話も10件程度寄せられた。
メールの内容は「不祥事が続いているが、専門職に必須と言われている倫理綱領がないからでは。自らが誰のために何を行い、何を守るべきか、再度問い直してほしい」といった意見や、「性的不祥事を起こした教師については、氏名だけでなく、現住所、本籍のある出身地を公表すべきだ」「わいせつし放題だから、俺も静岡で教員になろうかって考えるやつが出てくる」などの厳しい意見が書かれていた。
15歳女子生徒に売春させる 学校教育課長、関与の疑い 愛知・東郷町役場捜索 07/09/11(産経新聞)
当時15歳の専門学校の女子生徒に売春させたとして派遣型風俗店の関係者が愛知県警に逮捕された事件に、同県東郷町教育委員会の学校教育課長(57)が関与していた疑いが強まり、県警は9日までに、児童福祉法違反容疑で町役場や課長宅を家宅捜索した。捜査関係者や同町への取材で分かった。
県警は、女子生徒=同県尾張旭市=を昨年9月に名古屋市東区のホテルで男性客に引き合わせ売春させたとして、同法違反などの疑いで無職、小倉祐介容疑者(34)ら2人を6月下旬に逮捕した。小倉容疑者が働いていた派遣型風俗店の経営者は課長の母親の名義になっており、課長が店に出資していた疑いも浮上。県警は7日の捜索で、役場から課長の携帯電話などを押収し、課長から詳しく事情を聴いている。
町によると、課長は2007年4月から町の子育て支援課長を務め、今年4月から現職。勤務態度は真面目という。
少女99人が毒牙…レイプ教師“クマ”の酷すぎる手口 06/30/11(ZAKZAK)
自己紹介サイトで知り合った女子高生ら99人とわいせつな行為をした中学校の理科教師が、児童福祉法違反の疑いで逮捕された。18歳未満の未成年ばかりを毒牙にかけ、淫らな行為をしてはDVDに記録。普段の授業では「クマ」というあだ名で呼ばれる人気教師だっただけに学校も生徒も衝撃を隠さない。
警視庁少年育成課に逮捕されたのは、東京都小平市立上水中学校の教諭、栗本裕司容疑者(56)。私立高校1年の女子生徒(15)が登録する自己紹介サイトに「32歳のヒロです。8万円で会いませんか」などと書き込み、直接会うよう要求。上半身裸の写真をメール送信させた。
女子生徒は最初、会うのを拒否したが、2日間で約100通のメールが送られ、「写真をばらまかれたくなかったら会え」などと脅迫されたため会った。逮捕容疑は5月6日夜、新宿歌舞伎町のホテルでこの女子生徒とわいせつな行為をした疑い。
ホテルでは、避妊薬と偽って睡眠導入剤を生徒に飲ませ、ビデオカメラ3台で行為を撮影。翌日「もう一度会いたい」と電話で誘い、断られると「会わないなら家に行く。君は妊娠した」などとも脅したという。
容疑者の自宅からは1800人分のアドレスが押収され、DVD150枚には生徒ら計99人との淫行シーンが記録されていた。75人が18歳未満とみられる。
栗本容疑者の勤務先の男子生徒は「ちょっと信じられないです。まさかあの“クマ”が…」と言葉を詰まらせる。
「クマは栗本先生のあだ名ですよ。理科の教師っぽくないのっそりした風貌とガタイの良さから、親しみを込めてこう呼ばれていました。話が面白く、実験を楽しませるのも上手だったので、授業を楽しみにする生徒も多かったと思います。男女問わず、人気がありましたよ」
昨年3月まで5年間在籍した同じ市内の中学校の教職員も「問題行動は一切ありませんでしたし、囲碁将棋部の顧問で、保護者の評判も良く、変なウワサも聞いたことがない。真面目な印象しかなかった」と驚く。
ただ、別の学校関係者は、「栗本先生は、小平市内に赴任した約10年前から市内の賃貸住宅に一人暮らしでした。現在の中学に移った今年4月からは、母親の介護を理由に部活動の顧問の就任を断りましたが、隣接する西東京市の実家に、実は母親と一緒に妹さん夫婦が同居していた。だから、介護の負担があるとは思えなかった」と首をかしげる。
栗本容疑者は、空手の有段者で、大会にも出場する実力者。赴任校では運動部の顧問を度々打診されたが、なぜか断り続けている。
先の関係者は「親をダシにしてまで、放課後に良からぬことをする時間を確保していたのかと思うとゾッとする」と話している。
小学教頭、わいせつ目的誘拐未遂…容疑認める 02/28/11(読売新聞)
中学2年の女子生徒(14)にモデルガンを突きつけ、軽乗用車内に連れ込もうとしたとして、広島県警安佐北署は27日、同県安芸太田町立修道小教頭・吉原一彦容疑者(53)をわいせつ目的誘拐未遂容疑で逮捕した。
「乱暴するつもりだった」と容疑を認めているという。
発表によると、吉原容疑者は同日午後0時45分頃、広島市安佐北区内で、自転車で帰宅中の生徒に、車の中からモデルガンを突きつけ、「殺すぞ、乗れ」と脅し、誘拐しようとした疑い。生徒は車には乗らず、けがはなかった。
吉原容疑者の様子を不審に思った近くの男性(66)が、車で約10分間追跡し、赤信号で止まった吉原容疑者を取り押さえた。同町教委によると、吉原容疑者は教員歴約25年で、2009年4月から現職。
自分が知っているアメリカの教育は日本、韓国や中国の教育とは違う。惨めさや子供には豊かな生活を遅らせたい、
子供の成功により自分達が果たせなかった成功を実現させたい気持ちは多くの一般的なアメリカ人両親は理解できないであろう。
また、アメリカで生まれながらも両親はアメリカ生まれでない場合、両親は教育の格差、人種差別や貧富による格差を
痛いほど体験している。だからこそ、全ての両親ではないが子供に期待し、子供の教育に熱心だ。成功例ばかり注目されるが
中には途中で挫折したり、親に反抗して人生をだめにするケースもある。同じ才能であれば、ハングリー精神も持ち、
労働規則など適用されない環境で仕事をしてきた両親を見てきた子供であれば、苦労していないアメリカ生まれの両親を
持つ子供よりもがんばる傾向がある。結果としてよい成績をとる傾向がある。
遊ぶ時間を犠牲にしたり、恋人を作り人生を謳歌する時間、又は趣味などを犠牲にしても勉強をする、又は、勉強を
させられる環境にいれば、個人の持つポテンシャル以上に良い結果を出せるだろう。
教育方法が良いから、少ない犠牲(勉強時間)で最大の結果が出せるケースもある。しかし、上記の条件を別々にして
データーを収集することは出来ない。日本はゆとり教育(Non Stress Free Education)と呼ばれる教育を行い、失敗した。
いろいろなものを犠牲にしてがむしゃらに上に向かってくる発展途上国の子供達が最低限度の教育チャンスを得た場合、
アメリカのようにはならないが日本の子供の他の発展途上国の子供に劣る(劣っている)時が来る。その時になって、
改革してももう遅い。子供は大人になっている。そして競争能力が備わっていないヤングアダルトを政府は面倒を見続けなければならない。
誰がその負担をするのか???該当者以外の日本国民だ。文部科学省は相撲の八百長を心配する前に、やることがると
気付くべきだ。
「伝統的な中国式スパルタ教育」タイガーママ論争 中国紙「わが国の教育法でない」 (1/2ページ)
(2/3ページ)
(3/3ページ) 01/26/11(産経新聞)
自慢の娘を結果重視の厳しい教育法で育てたとする米国の名門エール大学中国系女性教授の著書「タイガーママ闘いの賛歌」が各国で論争を呼んでいる。厳しい教育法の是非というテーマの普遍性に加え、著者が「伝統的な中国式教育方法」としたことから教育分野でも台頭する中国への脅威論がかきたてられたことが論争の背景にあるようだ。
◇
新京報(中国)
■わが国の教育法ではない
1日付の北京紙「新京報」は「タイガーママは中国式教育の代表ではない」と題する論評記事を掲載し、「タイガーママの子供に対する厳しいしつけは、多くの中国人保護者から見ても受け入れられないものだ」と指摘した。また、タイガーママ式教育が米国社会で大きな反響を呼んだのは、「最近の欧米の人材危機や、速い勢いで世界中に影響力を拡大する中国に対する米国社会の警戒感によるものだ」との見方を示した。
記事は、中国と米国の教育の目的と方法は多くのところで共通しており、「そもそも対立させて考えるべきものではない」と前置きしたうえで、欧米の教育は子供の個性を伸ばし、楽しく学ぶことを重要視しているが、中国でも2000年以上前に孔子が実施した教育方法に「これと通じるものがあった」と主張。中国の教育法が「詰め込み式」と指摘されることに反論した。
また、欧米に移民した中国などのアジア系学生が現地の学生より一流大学への合格率が高いという現実があるのは、「アジア系学生たちが真剣に勉学に励んだ結果だ」とし、教育方法の違いではないとの見方を示した。
このため、欧米社会がアジア系移民の保護者を「子供に社会活動をさせずに勉強を強要している」などと批判するのは筋違いで、「すべての保護者は自分の子供にあった教育方法を選ぶ権利がある」と主張した。
記事は最後に、「タイガーママ式教育は独特の教育方法であり、彼女の子供には効果があるかもしれないが、すべての子供に通用すると思わない」としたうえで、「タイガーママ式教育を『中国式教育』と決めつけるのは大きな誤解を生む」と強調した。(北京 矢板明夫)
■タイム(米国)
■「中国式」実は米国的
米誌タイム(1月31日号)は、「タイガーママ」が米国で激しい論争を巻き起こした背景には、経済や教育分野で米国の脅威となった中国への米国民の強い不安があるとする記事を掲載。著者の「カミソリのようにとぎすまされたペンは、全米の親たちに“われわれは敗北者なのか”との思いを抱かせた」と論評した。
記事は、本がテレビやインターネットで激しく非難されたにもかかわらずベストセラーになったのは、著者である母親が言う「伝統的な中国式教育方法」が米国民の「中国や他の新興国に米国が打ち負かされつつあるという不安」をかき立てたからだと指摘。
A評価以外の成績を許さず、ピアノやバイオリンを徹底的にたたき込む彼女の教育方法を前に、米国の親は「国際経済のなかで自分の子供たちが生き抜くための準備を正しくさせているのか」との強い懸念をもったと述べている。
記事は、最近の米中間の経済指標の格差を見れば、米国民が懸念を持つのは「十分な理由がある」とし、さらに「経済が中国より疲弊しているのであれば、その影響は初等・中等教育システムにも及ぶ」と指摘。最近の国際調査を引き合いに、米国の学生の学力が中国の学生に大きく劣っていると述べた。
一方で、著者の両親は中国人であるものの日本占領下のフィリピンで生活した後、著者が生まれる前に米国に移住しており、本に描かれた内容は「自身や家族に良い生活をさせると決意した移民の物語」だと指摘。その意味で、彼女が称賛する「中国式」の本質は「アメリカ的」なものとの見方を示したうえで、著書は忍耐や勤勉さなど、人生の成功に必要な普遍的な事柄も論じているとした。(黒川信雄)
外国人だのみでしか経営が成り立たない学校は終わりにすべきだ。
アジア・ゲートウェイ戦略会議の35万人計画
や
留学生100万人計画の舞台裏
【中国人留学生への優遇実態】
や
【中国人留学生への優遇実態】
上記を考えると税金の無駄遣いである。テレビでは日本人学生の苦労や景気低迷のために就学を諦めている日本人生徒もいる。
なのに経済成長が著しい中国人学生にこれほどの優遇を与える必要があるのか??もしこのサイトを見る日本人学生がいるのであれば
起こるべきであろう。
あしなが育英会
のために募金協力に参加している学生はもっとこの不公平についてアピールするべきであろう。
偽装留学?青森大が122人除籍…県外就労9割 01/01/11(読売新聞)
青森大学(青森市幸畑)が2008年度から10年度にかけ、通学実態のない計122人の留学生を除籍処分にしていたことが、同大への取材でわかった。
大半が中国人だった。同大から報告を受けた仙台入国管理局が調べたところ、約9割が県外に居住し、就労していたことも判明。仙台入管は就労目的の偽装留学とみており、同大は受け入れ態勢の見直しを進めている。
青森大学によると、通学していない留学生がいるのを08年度に初めて把握し、4人を除籍処分とした。その後の調査で同様の留学生がいるのが分かり、09年度には79人、今年度も10年10月までに39人を除籍した。大学には同年5月現在、計245人の留学生が在籍している。
仙台入管が調査した結果、除籍者の約9割が東京や神奈川、愛知など県外で外国人登録していた。呼び出して面会すると、それぞれの居住地でアルバイトなど仕事に就いていることを認めた。
留学生が大学に通わずにアルバイトに従事した場合、出入国管理法の退去強制事由にあたる可能性がある。仙台入管はすでに除籍者に行政指導で退去を求め、大半の出国を確認した。仙台入管は、「面接などの結果、除籍者は就労目的で来日したと見ざるを得ない。不適正な状況だ」としている。
青森大学は、少子化などで減少している学生確保のため、05年度に中国の日本語学校と提携。中国側が推薦する学生を積極的に受け入れ始め、さらに2校と提携した08年度以降は、留学生の数が以前の約3倍に増えた。除籍者のほとんどが、提携校からの学生だった。
留学生を受け入れる際には、大学の職員が現地に出向き、試験や面接のほか、学費の支払い能力があるかなどを確認していた。しかし、除籍の際に調査すると、成績、年収や預貯金の証明書が偽造されていたケースが次々と見つかった。
こうした事態を受け、同大は10年1月、3校との提携を取りやめ、10年度の留学生受け入れもいったん縮小。11年度の中国人留学生受け入れも予定せず、審査方法を含めた受け入れ態勢の抜本的な見直しを進めている。仙台入管も、審査の甘さが大量の除籍者につながったとみて、改善策を確認するなど指導している。
09年4月に就任した末永洋一学長は取材に対し、「結果的に審査が甘かったと言わざるを得ず、非常に遺憾。大学として焦りがあったのかもしれない。いまは全力で改革に取り組んでいる」と話している。
高1女子生徒にわいせつ行為繰り返す 臨時講師を懲戒免職 12/27/10(産経新聞)
高校1年の女子生徒(16)にわいせつな行為を繰り返したとして、広島県府中市教委は27日、市内の中学校に勤務する非常勤講師の男性(28)を懲戒免職処分にしたと発表した。また、校長を厳重注意、以前の勤務先だった中学校長についても戒告処分とした。近く県青少年健全育成条例違反で刑事告発する。
市教委によると、男性は今年4月以降、女子生徒の自宅や車の中で、生徒にキスしたり抱きしめるなどのわいせつ行為を繰り返したとしている。女子生徒とは採用前に勤務していた学習塾で2年前に知り合ったという。
女子トイレ盗撮小学教諭のあきれた言い訳 11/30/10(読売新聞)
福島県須賀川市教委は29日、市内の小学校に勤務する30歳代の男性教諭が、校内の女子トイレに侵入し、小型ビデオカメラで盗撮しようとしたと発表した。
教諭は現在、自宅待機している。
発表によると、教諭は今月22日午後1時10分頃、1階の児童用女子トイレに入る女性職員を追ってトイレに侵入。個室を仕切る壁下のすき間にカメラを設置し、盗撮しようとした。女性職員が気付いて教頭に報告した。
教諭は「盗撮しようとしたのは初めて。たまたま女性職員がトイレに入るのを見て急に(カメラを)使用したくなった」と話しているという。カメラは、縦5センチ、横3センチ、幅1センチで、昨年12月にインターネットで購入。「初めて校内に持ち込んだ」と話しているという。市教委と同校は、教諭のカメラや公用、私用パソコン内の映像記録を調査し、「盗撮映像や画像はなかった」としている。市教委は「被害者に被害申告の意向がないことなどを尊重した」として、刑事告発はしない方針。
女子児童に目隠し、不可解な行為求めた教諭停職 11/09/10(読売新聞)
埼玉県所沢市の市立小学校の男性教諭(30)が「ご褒美のゲーム」と称し、5~6年の女子児童だけを個別に理科準備室などに呼び出し、アイマスクで目隠しをして触れたものを当てさせたり、様々なポーズを取らせたりする不可解な行為を繰り返したことが分かり、県教委は8日、停職6か月の懲戒処分にした。
県の調査に対し、教諭は「宿題を頑張ったご褒美や、元気がない子を励まそうと楽しいゲームをやった」などと説明。問題発覚後の7月から休んでいるが、辞職の意思は示していないという。
発表によると、判明したのは、〈1〉私物のアイマスクで目隠しし、人体模型の手首部分などを持たせ、名称を答えさせる〈2〉目隠し状態で手を上げたり、後ろに回したりする様々なポーズを取らせた後、ストップウオッチを持たせ、一定時間そのポーズのままでいるよう命じる〈3〉あごにシールを張って、手を使わずに舌や息だけではがさせる――などの行為。
2009年9月から10年7月にかけ、担任クラスの女子児童計6人に対して行い、その様子を眺め、最後に「誰にも言わないでね」と口止めしたという。
別クラスの女子児童が今年7月、廊下の掃除中に、教諭にほうきの柄で尻をつつかれたと担任教諭に訴え、学校が調査して発覚した。県の調査に対し教諭は、口止めした理由について「ほかの児童が『(自分たちにもやってくれないのは)ずるい』と言い出すと思ったから」と釈明したという。
教諭は07年から現小学校に勤務。県教委は「目隠し中にいかがわしい写真を撮るなど、明確なわいせつ行為は発見できなかった」として懲戒免職の処分は見送ったとしている。
小学校教諭、「社会勉強」と女子大生強姦容疑 09/01/10(読売新聞)
知り合いの女子大生(22)に乱暴したとして、広島中央署は1日、広島市安佐北区口田、同市立安(やす)小教諭西本久範容疑者(58)を強姦(ごうかん)容疑で逮捕した。「同意の上だった」と容疑を否認しているという。
発表によると、西本容疑者は8月1日午後1時頃、女子大生に「何もしない。社会勉強だ」などと言って同市西区のホテルへ誘い、乱暴した疑い。
同署によると、女子大生は教員志望で、西本容疑者とは知人を通じて知り合ったといい、教員の仕事の話を聞くために同容疑者と何度か会っていたという。
同校の吉田浩一教頭は「特別支援学級の担任で指導熱心だった。事実関係を確認して対応したい」と話した。
「文部科学省は27日、公立小中学校できめ細かな少人数指導を行うため、『教職員定数改善計画案』を発表した。」
ゆとり教育と同じだ。きめ細やかな少人数指導とはどのような教育なのか理解できない。問題のある教員や
能力の低い教員を何とかしないといけない。
「同省は計画案にさらに、少人数化とは別に4万人の増員計画を盛り込んだ。障害のある児童生徒への対応や、
外国人の子どもに対する日本語指導、栄養教諭、生徒指導など8分野の要員として14年度から5年間で計4万人が必要としている。」
とにかく教職員を増やしたいだけじゃないのか??
教職員を増やす=きめ細かな少人数指導が成り立つのか。「ゆとり教育」の責任を誰も取っていない。教職員を増やす前に、
教職員の質を上げろ、教育委員会の組織の問題を何とかしろ。不祥事を起こす教職員は最低だが、教師として指導者として
不合格でなる教職員はニュースには取り上げられないが多くいると思う。教員免許の更新は問題のある教職員の排除のためだと思っている。
「問題のある教職員の排除」のために問題のない教職員に負担(無駄なお金や時間)を押し付けるな!これが政治かも知れないが
ウンザリする。
盗撮ビデオは学校備品、52歳教諭を懲戒免 09/09/10(読売新聞)
石川県教育委員会は8日、県迷惑防止条例違反(盗撮行為)で金沢簡裁から罰金30万円の略式命令を受けた金沢市立内川小学校の山崎琢司教諭(52)を、地方公務員法に基づき懲戒免職処分とした。
監督責任を問い、同校の小阪秀明校長(54)も戒告処分とした。山崎教諭は8月13日、JR金沢駅西口のコンビニ店で、女子高校生のスカート内を小型ビデオカメラで盗撮したとして逮捕、略式起訴された。
県教委の事情聴取に対し、山崎教諭は「4年前から盗撮をしていた。高校生に興味があり、勤務先の小学校ではやっていない」と話したという。また、盗撮に使ったビデオカメラは学校の備品だったことも判明。靴に仕込んだ特殊レンズが、備品の旧型ビデオカメラと接続しやすかったためという。
小中学校35人学級、来年度から段階実施へ 08/27/10(読売新聞)
文部科学省は27日、公立小中学校できめ細かな少人数指導を行うため、「教職員定数改善計画案」を発表した。
来年度から8年間で教職員を約1万9000人増やし、1学級あたりの上限を小中とも現行の40人から35人に、小学校低学年は30人に引き下げる。学級の上限人数を定める義務標準法の改正案を、来年1月の通常国会に提出する。
学級人数の引き下げは、45人から40人に変えた1980年度以来、30年ぶり。
計画案によると、少人数化は2011年度から8年間で段階的に実施する。まず小学1、2年を35人学級としてスタートさせ、16年度までに小中の全学年を35人とし、17~18年度では小1、小2を30人学級にさらに縮小する。
これに伴い、教職員を増員する。同省は完全実施の場合、現行の教職員(約76万人)より、1万9400人増やせば足りると試算。必要な予算は1200億円(国負担400億円)と見込んでいる。
同省は計画案にさらに、少人数化とは別に4万人の増員計画を盛り込んだ。障害のある児童生徒への対応や、外国人の子どもに対する日本語指導、栄養教諭、生徒指導など8分野の要員として14年度から5年間で計4万人が必要としている。
同僚女性の下着盗んだ高校教諭、懲戒免職 08/27/10(読売新聞)
同僚の女性講師宅に侵入し下着を盗んだなどとして逮捕、起訴された県立大社高の竹崎伸一郎教諭(42)を、島根県教委は26日、同日付で懲戒免職にした。
監督責任を問い、校長を文書訓告、教頭2人を口頭訓告とした。
教員の懲戒処分は今年度になって4件相次いでいる。県教委は27日に全県立校の臨時校長会を開き、不祥事を防ぐための研修などを行う。人事担当者が各校を訪問指導し、具体的な対策を記した「校内研修事例集」を改訂するなどして、再発防止を図る。
県教委高校教育課の発表によると、竹崎教諭は同僚数人との飲み会の帰りに講師宅に侵入。県教委の事情聴取に対し、のぞきをしようと、5月中旬に学校で講師のかばんから鍵を取って合鍵を作ったと答えたという。
少女ら児童買春500人、ネット仲介容疑で逮捕 08/24/10(読売新聞)
神奈川県警は23日、インターネットを通じて児童買春を仲介したとして東京都八王子市堀之内、無職石森大樹容疑者(34)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春周旋)などの容疑で、客の男5人を同法違反(児童買春)容疑で逮捕したと発表した。
発表によると、石森容疑者は昨年9月17日頃、山梨県山梨市の市立山梨北中教諭、大島雅彦容疑者(50)に現金2万6000円を振り込ませて相模原市の高校3年の女子生徒(当時17歳)を紹介、みだらな行為をさせた疑い。
このほかに逮捕されたのは、横浜市栄区、同市障害児福祉保健課職員地下(ちした)満明(40)、兵庫県西宮市、私立報徳学園教諭?野(つるの)敬三(49)ら4容疑者で、それぞれ昨年10月~今年5月、石森容疑者に現金を振り込み、少女にみだらな行為をした疑い。地下容疑者は容疑を否認している。
石森容疑者は、インターネットサイトにメールアドレスを掲載している少女に「バイトしませんか」などとメールを送る一方、サイト掲示板で客を集めていた。約5年間で関東や関西の少女ら約500人に客を引き合わせ、約2000万円の収入があったが、少女らには報酬を支払わなかったという。
児童買春容疑の中学教諭、確認取り次第処分…山梨県教委 08/24/10(読売新聞)
音楽指導に定評、吹奏楽コンクールに出場予定だが…
神奈川県警は23日、インターネットを通じて児童買春をしたとして、山梨市立山梨北中教諭、大島雅彦容疑者(50)(山梨市上神内川)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕したと発表した。
発表によると、大島容疑者は昨年9月17日に現金2万6000円で、神奈川県相模原市南区のホテルで同市の当時高校2年の女子生徒(同17歳)にみだらな行為をした疑い。
大島容疑者は、音楽教諭としての確かな指導には定評があり、顧問を務める同中吹奏楽部は9月に開かれる西関東吹奏楽コンクールに県代表として出場する予定だ。
山梨市教委によると、大島容疑者は1983年に県教委に採用され、09年4月から山梨北中に勤務している。2年生の学年主任で音楽を担当しており、勤務態度はまじめだったという。
逮捕を受け、同市教委は23日、緊急の教育委員会と校長会を実施し、服務規律の徹底を呼びかけ、同中に学校カウンセラーを同日から常駐させる措置を取った。24日に全校集会と保護者会を開いて生徒、保護者に事情を説明する予定。
県教委は、大島容疑者本人と接見し、確認を取り次第、処分する方針。市教委の堀内邦満教育長は「日頃から校長会で服務規律の徹底について話しており信じられない。生徒、保護者の信頼を裏切る行為であってはならないことだ」としている。
渡部前教育長にならい、関係した町教委職員が全員今後受け取る退職金を辞退することを文書で提出し、約
10万円を返済すれば刑事告発はしないことにすれば良いと思う。辞退された退職金の金額で
町
や子供のために使うほうが良いと思うぞ!
寄贈切手で飲み食い、教育長・教委職員も黙認 07/17/10(読売新聞)
北海道月形町教育委員会の職員が寄贈を受けた切手を換金し職場の飲食費に充てていた問題で、飲食に参加した渡部稔・前教育長と町教委職員の多くが、切手を換金した金と認識していたことが16日わかった。
飲食は複数回にわたって行われており、同町の土橋正美副町長は「職場ぐるみの可能性が高い」と指摘。関係職員を処分する方針だ。
町によると、渡部前教育長と町教委職員の計8人が飲食に関与し、2007年春に換金した約10万円は同年12月までに使い切ったという。
町の調査に対し、ほとんどの職員が、切手を売った金を使ったと認識していた。「切手を紛失した管理責任を取る」として今年6月に辞任した渡部前教育長も、今月に入り「(切手を売り飲食に使うことを)黙認した」という内容の文書を町に提出、退職金の受け取りを辞退する意向という。
関係者によると、切手は寄贈されたアルバム3冊ほどに保存されていた。「見返り美人」など収集家に人気の高額なものも含まれていたという。
桜庭誠二町長は取材に、「教育にかかわる職場でこうした事件が起き、誠に残念で遺憾。今後のことは警察に相談したい」と述べ、刑事告発も検討する考えを示した。また、切手を含む図書の寄贈を受けた当時の記録がないことを明かし、「重大な過ちだった」と陳謝した。
「飲酒発覚まずい」信号無視して逃走容疑 中学校長逮捕 07/14/10(朝日新聞)
兵庫県警は13日、同県姫路市立大津中学校の校長、木村勝好容疑者(60)=同市網干区新在家=を道路交通法違反(信号無視)の疑いで現行犯逮捕し、発表した。木村容疑者は「飲酒運転が発覚すると、問題になると思って逃げた」と供述しているという。
網干署によると、木村容疑者は同日午後9時30分ごろ、自宅近くの公園駐車場に止めた車の中にいた際、同署員に職務質問されそうになり車を急発進。バイクで追跡した署員に対し、赤信号を無視しながら約10キロ逃げ、車から降りてさらに100メートル逃走した後に取り押さえられた。呼気1リットル当たり0.05ミリグラムのアルコールが検出され、「車内で缶酎ハイ1本を飲んだ」と供述したという。
小学校教諭、女児ら5人暴行か…DNA一致 07/09/10(読売新聞)
東京・多摩地区で2008年以降、帰宅途中の小学生の女児らが襲われた5件の現場に残されていたDNA型が、今年6月下旬に住居侵入容疑で警視庁に逮捕された東京都稲城市の公立小学校教諭の男(29)の型と一致したことが9日、捜査関係者への取材でわかった。
同庁は近く、男を女児に対する強制わいせつ容疑で再逮捕する方針。
同庁幹部によると、男は6月27日、八王子市内のアパート敷地内に侵入したとして、同庁南大沢署に住居侵入容疑で現行犯逮捕され、拘置中。
一方、多摩地区では08年11月から今年にかけて、小学生女児らが帰宅しようとした際、玄関などの近くに潜んでいた男に家の中に押し込まれ、わいせつ行為をされる事件が5件相次いでいた。いずれの現場にも犯人の体液が残されており、そのすべてがこの男のDNA型と一致したという。
男は、このうち数件について関与をほのめかす供述を始めており、同庁で裏付け捜査を進めている。
教え子の女子高生にみだらな行為、妊娠…教諭逮捕 07/06/10(読売新聞)
教え子の女子高校生(17)にみだらな行為をしたとして、岐阜県警は6日、同県羽島市立羽島中学校教諭・木村岳城(がくじょう)容疑者(42)(愛知県一宮市大和町)を、愛知県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕した。
発表によると、木村容疑者は今年4月17日、一宮市内のホテルで、女子生徒が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑い。女子生徒は妊娠し、翌5月、別の教諭に相談して発覚した。調べに対し、容疑を認めているという。
木村容疑者は昨年度、交流人事の一環で、岐阜県内の高校に数学教諭として赴任。1年生のクラスの担任を務め、女子生徒とは昨年9月から交際していたという。
記者会見した県教委の丹羽章・教職員課長は「教員としてあるまじき行為だ。再発防止に努める」と話した。
小学校教諭、強姦罪で起訴 教え子が被害に 福岡 06/19/10(朝日新聞)
小学生の教え子と性的関係を持ったとして、福岡県内の公立小学校の40代の男性教諭が強姦(ごうかん)の罪で福岡地裁支部に起訴されていたことが19日わかった。18日に同支部で初公判があり、教諭は起訴内容を認めた。この学校を所管する教育委員会は「大変遺憾なことで、弁解のしようがない」としている。
起訴状によると、教諭は県内のホテルで今年3月、女児が13歳未満であることを知りながら性的な関係を持ったとされる。4月に逮捕され、翌月、起訴されていた。
関係者によると、教諭は今春まで女児の担任を数年間にわたり務めた。この間、体を触るなどのわいせつな行為が徐々にエスカレートしていったという。教諭は今年4月、別の小学校に異動。その後、女児の様子がおかしいことに気付いて保護者が事情を聴いたところ、教諭から受けた性被害が判明し、県警に被害届を出したという。
県警と教委は、女児のプライバシーを保護するためとして公表を控えていた。教委はこの教諭について、給与が支払われる起訴休職処分ではなく、給与が出ない欠勤扱いにしている。
関係者によると、教諭は18日の初公判で「『先生、先生』と言われ、徐々に支配欲が芽生えた」などと供述したという。
都立高教諭が児童買春容疑で逮捕 「モデル募集」と誘う 06/15/10(読売新聞)
高校3年の少女(17)にみだらな行為をしたとして、警視庁は東京都八王子市上野町、都立武蔵村山高校教諭の兼次弘俊容疑者(47)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕したと15日、発表した。
少年育成課によると、兼次容疑者は5月16日午後、埼玉県戸田市内のホテルで、高校3年の少女に現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑いがある。容疑を認めているという。
兼次容疑者は昨年7月ごろ、モデルを募るインターネットの掲示板で少女の書き込みを見つけ、「水着などの撮影モデルを募集しています」とメールで誘い、これまでに容疑を含めて都内のホテルなどで計5回会っていた。少女は「撮影モデルから芸能界に入りたかった」と話しているという。
臨時教員が16歳と14歳の姉妹にわいせつ容疑 06/10/10(読売新聞)
神奈川県警は10日、横浜市港南区上大岡東、同市立新田中学校臨時教員の宮内完太容疑者(25)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕した。
発表によると、宮内容疑者は5月3日、同市旭区内の月決め駐車場に止めた乗用車内で、同区内の16歳と14歳の姉妹に現金計6000円を渡し、わいせつな行為をした疑い。調べに対し「彼女と会う時間がなく、遊ぶ相手がほしかった。18歳未満とは知らなかった」と供述。姉妹とは携帯電話のサイトで知り合ったという。
「妹ほしかった」 教え子にわいせつ行為の高校教諭逮捕 05/31/10(産経新聞)
教え子の女子高生にわいせつな行為をしたとして、警視庁八王子署は、児童福祉法違反(淫行)の疑いで、東京都内の私立高校教諭、冨山岳嗣容疑者(28)=神奈川県相模原市南区上鶴間本町=を逮捕した。同署によると、冨山容疑者は容疑を認めており、「昔から妹がほしくて優しく面倒を見てほしかった」と供述しているという。
逮捕容疑は、5月8日午後、私立高校2年の女子生徒(16)=八王子市=を自宅に誘い込み、体を触るなどのわいせつな行為をしたとしている。
同署によると、女子生徒から交際相手について悩みの相談に乗っていた冨山容疑者は事件当日、女子生徒に「かぜを引いたので看病しに来てほしい。一緒に相談にも乗るから」とメールで誘っていたという。わいせつ行為に及んだ後は「ばらしたら生活指導の先生に話す」と迫っていた。
女子生徒は「退学になるのが嫌で我慢した」と話している。
同署によると、冨山容疑者は、日頃から「何でも悩みに乗ってくれる」と同校の女子生徒の間で評判だったという。
安定した公務員の仕事を失うリスクを負うほど「若い子が好きだった」のだろう!
児童買春容疑:35歳中学教諭逮捕…「若い子が好きで」 05/20/10(読売新聞)
神奈川県警少年捜査課と泉署は20日、東京都江戸川区立葛西中学校教諭、上田覚容疑者(35)=台東区東浅草1=を児童ポルノ法違反(児童買春)の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は09年10月、横浜市西区の雑居ビル内で、中学2年だった女子生徒(当時14歳)に1万円を渡してわいせつな行為をしたとしている。さらに09年12月と今年1月にも新宿区のホテルで、高校2年だった女子生徒(同16歳)に計5万円を渡してわいせつな行為をしたとしている。
県警によると、上田容疑者は「若い子が好きだった」と供述し、女子生徒とは携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合ったという。職場では2年生の担任で社会科を担当している。【松倉佑輔】
「人生をかけている」ほど好きだったのかもしれないが、このような事をして交際に結びつくと思ったのだろうか??
日本の教員育成のシステムについて知らないが、大学と文科省及び教育委員会は真剣に改革に取り組む必要があると思う。
55歳中学教諭、同僚女性の盗撮画像で交際迫る 05/19/10(読売新聞)
仙台市教委は18日、同僚の女性教諭を盗撮し、交際を迫ったとして、同市青葉区の男性中学校教諭(55)を懲戒免職処分にしたと発表した。
処分は昨年11月27日付。懲戒処分はすぐに公表するが、「被害者の要望」として半年間公表しなかった。市教委は昨年度の懲戒処分を受けた教職員が計10人(前年度比1人増)とここ5年間で最多とも公表、「教育の信頼を著しく傷つけ、深くおわびする。再発防止に努める」と釈明した。
市教委の発表では、教諭は昨年9月中旬~10月中旬、職員室の女性用トイレにビデオカメラを設置し、同僚の女性教諭を盗撮。同年10月下旬には、勤務後に女性を学校の用事で話があると車に乗せて連れ回し、「人生をかけている」などと盗撮画像を見せて交際を迫った、としている。
市教委は、同カメラ1台、パソコン5台などを教諭から提出させ、仙台北署に相談。同署は同12月、教諭を軽犯罪法違反(のぞき)と建造物侵入の疑いで仙台地検に書類送検。教諭は同月28日に、同法違反などの罪で仙台簡裁に略式起訴された。
このほか、市教委は、かつて担任した児童の母親に昨年7月、性的な電話をかけたとして青葉区の男性小学校教諭(49)を停職6月の懲戒処分。今年2月に、面談時に児童の母親に2回抱きついたとして、太白区の男性小学校教諭(48)も停職6月の懲戒処分にしたと発表した。処分は昨年8月と今年3月だった。
小学校教諭、女性宅侵入し暴行未遂容疑 04/20/10(読売新聞)
小学校教諭による強制わいせつ事件で、愛知県警は20日、同県日進市岩崎台、名古屋市立小学校教諭の大藪享一被告(42)(強制わいせつ致傷罪で起訴)を強姦(ごうかん)未遂と住居侵入の疑いで再逮捕した。
発表によると、大藪被告は2008年12月7日午前2時半頃、同市の女性(33)の自宅玄関付近で女性を脅し、室内に侵入したうえ、両手を縛るなどして暴行しようとした疑い。大藪被告は容疑を認めているという。
同市や同県長久手町、東郷町などでは同年末から、若い女性が自宅前や駐車場で男に襲われる被害が相次いでおり、県警が関連を調べていた。大藪被告は逮捕後、小学校を休職している。
女子生徒に不適切な行為、男性教諭を懲戒免職 04/20/10(読売新聞)
群馬県教委は19日、中部地域の公立中学校の男性教諭(28)が13歳の女子生徒にキスをするなど不適切な行為を繰り返したとして、懲戒免職にしたと発表した。
県教委の発表によると、男性教諭は昨年6月頃~今年3月、女子生徒と携帯電話で私的なメールを交換し、今年1~3月には放課後の校内やカラオケ店、自分の車の中で女子生徒と複数回キスをした。
昨年10月と今年1月に、ほかの生徒や保護者から連絡を受けて学校が調査した際、男性教諭は「メールはもうやめている」と虚偽の説明をしていた。男性教諭は「浅はかな行動で一人の生徒の大切な一生に大きな傷を負わせてしまった」と反省しているという。
福島金夫・県教育長は「誠に遺憾。被害者やその家族、県民の皆様に対し、深くおわび申し上げる」とのコメントを発表した。
小学校教諭、地下鉄で痴漢「好奇心で触った」 11/20/09(読売新聞)
千葉県警浦安署は19日、東京都江東区立豊洲北小学校教諭、中瀬貴之容疑者(23)(千葉県浦安市堀江)を県迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで現行犯逮捕した。
発表によると、中瀬容疑者は同日午後8時45分頃、東京メトロ東西線の東陽町駅―浦安駅間の快速電車内で、千葉県八千代市内の大学2年の女性(19)の下半身を触った疑い。女性が取り押さえ、同署員に引き渡した。中瀬容疑者は「好奇心で触った」と供述しているという。
公務員の採用方法を変える必要がある。
大分県教委の教員採用汚職
では得点が操作された。2次試験は面接だけかもしれないが、今までの経験や体験、
面接も練習されると問題ない回答が帰ってくるのかもしれないが、人間性や自己をコントロール
できる人間を見抜く方法や採用することも必要だろう。
得点が良くても安定だけの理由で公務員や教師を選ぶ人間は教師としてはふさわしくないのかもしれない。
わいせつ、覚せい剤乱用…先生は何やってるんだ 11/05/09(読売新聞)
酒気帯び運転や生徒へのわいせつ行為などで懲戒免職になった教職員が、今年4~10月の7か月で98人に上ることが4日、読売新聞のまとめでわかった。
覚せい剤の乱用もあったほか、神奈川と千葉では10人を数えるなど、各教育委員会は対策に頭を痛めている。
「『先生は何やっているんだ』とみんなに思われる状況。横浜の教育を揺るがしかねない」。政令市で最も多い6人の懲戒免職者を出した横浜市の田村幸久教育長は、今年9月に開いた緊急校長会で、市立小中高など513校の校長に厳しい口調で語りかけた。
同市教委は8月、不祥事を防止するため全教員を対象に半日以上の研修を実施するよう各校に求めていたが、書店で女子中学生の下半身を触ったとして5人目の逮捕者が出た。
10人が懲戒免職になった千葉県。鬼沢佳弘教育長も9月、55の市町村教育長を集めた緊急会議で、「極めて異常な事態。繰り返し粘り強く指導してほしい」と訴えた。10人のうち8人は、懲戒理由が女子高生とみだらな行為をするなどわいせつ事例だった。
教員の薬物使用も出ている。東京都では中学副校長(53)が、熊本県では高校教諭(33)がそれぞれ覚せい剤を使用した疑いで逮捕され懲戒免職に。大阪市でも10月、小学校教諭(34)が友人から覚せい剤を購入し、使用した疑いで逮捕されており、市教委は懲戒免職を含め処分を検討している。
小学生に強制わいせつ容疑 小学校教諭逮捕 愛知・岡崎 10/14/09(朝日新聞)
愛知県警岡崎署は14日、小学生の女児(10)にわいせつな行為をしたとして、同県岡崎市坂左右町堤上、市立六ツ美南部小学校教諭江畑雅導(まさ・みち)容疑者(28)を強制わいせつ容疑で逮捕したと発表した。江畑容疑者は「年少者にわいせつな行為をすることで性的欲求を満たしたかった」と容疑を認めているという。
同署の発表によると、江畑容疑者は8月20日午後4時ごろ、岡崎市の路上で、車に乗って女児を物色し、目をつけた女児に「目をつぶっていて」と言って、わいせつな行為をした疑いがある。女児は江畑容疑者が勤務していた学校の児童ではないという。
同署によると江畑容疑者は、市内の路上で5月下旬、少女3人に車で約300メートルにわたってつきまとった軽犯罪法違反の容疑で取り調べを受けた。その際、自宅の家宅捜索で押収したパソコンに、女児にわいせつ行為をする動画が記録されていたため、犯行が明らかになった。
同署によると、パソコンには公園で遊ぶ女児の写真や動画などが多数保存されているといい、つきまといの軽犯罪法違反容疑でも調べている。
岡崎市教育委員会によると、江畑容疑者は5年生の学級担任をしていたが、9月29日からは「精神的不安定」を理由に休暇をとっている。野田光宏教育監は「教員としてあるまじき行為で逮捕されたことは、誠に残念で、お騒がせしたことを申し訳なく思っている」と陳謝した。
酒量・借金…横浜市教委が全教員の生活実態調査へ 10/06/09(読売新聞)
横浜市教育委員会は、飲酒の量や頻度などを自分で記入する「ライフスタイルチェックシート」を市立校の全教員約1万5600人に配り、細かな生活実態の把握に乗り出す。
問題行動の兆候を早めにつかみ、校長が指導しやすくするのが狙い。
市教委によると、対象は小、中、高校、特別支援学校の全513校。年内に配布し、校長あてに提出してもらう。市立校教員は今年度すでに6人が逮捕され、2007年度の4人、08年度の3人を半年で上回った。飲酒後に書店で女子中学生の尻を触った容疑で現行犯逮捕されるなど、酔って事件を起こすケースが目立つ。
そのため、シートでは飲酒習慣を重点に尋ね、不祥事の芽になりかねない賭け事や借金、悩み事などの項目も設ける方針という。
文部科学省は「全教員の生活把握にまで踏み込んだ不祥事防止対策は聞いたことがない」としている。
市立中の男性校長(53)は「教員の健康管理上の資料としても活用したい。団塊世代の大量退職で現場には若い教員も多く、悩み事などを把握するきっかけになればいい」ととらえる。一方、市立小の男性校長(59)は「教員の多くは『自分は信用されていない』と思うだろう。酒を飲むなとも言えない。現場を知らない人の発想だ」と効果を疑問視する。
横浜市の中学校長を経験した武嶋俊行・上越教育大教授(学校経営)の話「不祥事防止の強い意思表示は理解できるが、疑いのない大部分の教員に網を掛けることになり、現場の管理職と教員の信頼関係が崩れる恐れがある」
高校教諭が女子高生を買春容疑 埼玉 09/17/09(朝日新聞)
女子高校生に現金を払うことを約束してみだらな行為をしたとして、警視庁は、埼玉県立熊谷西高校教諭蛭川浩容疑者(51)=同県深谷市国済寺=を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕した、と17日発表した。蛭川容疑者は容疑を認め、「教え子と同世代の若い女の子がほしかった」と供述しているという。
蔵前署によると、蛭川容疑者は昨年10月19日ごろ、同県桶川市内のホテルで、インターネットの自己紹介サイト「プロフ」で知り合った当時16歳の高校生だった女性に現金1万5千円を払うことを約束し、みだらな行為をした疑いがある。その後、同額を手渡したという。
ある新聞で教員の給料が下がっていると嘆いている元教諭の投稿を読んだ。確かに給料を下げると教員のやる気に影響する可能性も
あるし、能力はあるが教育に対する熱意よりも給料に関心がある人は教員にはならなくなるだろう。しかし、「自分の息子のために」
期末試験を入手する教諭もいる。このような教諭は必要ない。問題のある教諭のための給料、その他の費用及び退職金などを考えるとこれらの
無駄な費用(税金)をカットしなければならない。能力や努力で結果を出せる教諭を維持するためには、やはり問題のある教諭には公務員であっても
公務員を辞めてもらう法改正が必要だ。問題のある教諭達にかかる費用を他の教諭の給料アップに回せばよい。予算や財源に問題がある場合、
教諭達はどのように問題を解決するのか?平等に泣くのか?結果を出すためには鬼になるのか?答えを出せないのであれば、やはり公務員病なのだ!
「息子のために」中学教諭、期末試験を入手し教える 09/16/09(読売新聞)
三重県尾鷲市の尾鷲中学校(出口隆久校長)に勤務する男性教諭(49)が、7月にあった1学期の期末試験の問題を事前に入手し、試験前日に同校に通う長男に教えていたことが16日、わかった。同市教委などによると、男性教諭は現在自宅待機になっていて、「息子のためにやった」と認めているという。
市教委などによると、男性教諭は6月末、職員室内のプリンターに出力されていた作成中の数学の試験問題をノートに書き写した。試験前日、市内の学習塾に通う長男に持たせ、塾に対してこの問題を長男に指導してくれるよう依頼したと話しているという。塾側は長男に個別指導したという。
作成中の試験問題は、実際の期末試験でも問題の順番が入れ替わった程度で、ほぼすべての内容が出題された。塾側が、ノートの内容と試験問題が酷似していたため、不審に思って中学校に通報して発覚した。男性教諭は英語の担当で、この問題の作成にはかかわっていないという。
同校の五味正樹教頭は「教師の信頼を失う、あり得ないことが起こってしまった。生徒や保護者の皆さんに大変申し訳なく思う」と陳謝した。
県教育委員会人材政策室は「懲戒処分の指針」で秘密漏洩(ろうえい)にあたるとして男性教諭の処分を検討している。
経歴詐称の昭和女子大元准教授、学歴もウソ 08/27/09(読売新聞)
教職大学院の認可申請書に記載した昭和女子大(東京都世田谷区)の元准教授(懲戒解雇)の男性(61)の経歴に詐称があった問題で、文部科学省は26日、同大からの学科などの新設を2年間は認めないことを決めた。
同省などによると、元准教授は、職歴の「大学の非常勤講師」も虚偽だったことが判明。岐阜県教委でも男性が高校教諭時代に東大博士課程を修了したとする記録について改めて東大に照会したところ、「事実ではない」と否定されたという。
「文科省は05年に注意喚起の通知を出したが、契約方法は各自治体に一任。業者の実態についても把握しておらず、『質まで判断しようがない』
と説明している。」
文科省はあほか???外国語指導助手(ALT)の手配に関して派遣する民間業者との契約を選択した場合の問題点、問題事例や注意点をまとめて
各自治体に知らせる。入札で安く落札した業者が問題を起こした場合、一定期間の間、入札に参加させない等の問題解決例など選択として知らせるべきであろう。
自治体側が面倒な事に関わりたくないために、問題を知りつつも安易な選択を選んだ場合は、自治体の教育委員会又は判断に関与したもの達を
処分すればよい。留学経験者や帰国子女を除けば、小学校レベルで外国人外国語指導助手(ALT)を使う必要はないと思う。ただ、
これまでの典型的な英語教育や英語指導では問題はあると思うが!「JETプログラム」の外国人外国語指導助手(ALT)は国が費用を出している
から良いが、費用対効果では疑問だ。費用は税金なのだからもっと真剣に取り組んでほしい。教員の対応能力や文科省にも問題があると思う。
小学英語、外国人の指導助手巡る問題山積 07/28/09(読売新聞)
2011年度から必修化される小学5、6年生の英語の授業について、文部科学省が全国の公立小学校約2万1000校などを対象に調査を実施したところ、昨年度に小学校で実施された英語授業のうち7割近くで外国語指導助手(ALT)が活用されていたことがわかった。
生の英語を学ぶ機会が定着してきたことが浮き彫りになった形だが、一方では、簡単に授業を投げ出してしまうALTもいるなど、“質”の問題が浮かび上がっている。
「また辞めるのか」。7月中旬、埼玉県内の市教育委員会の担当者は、業者から米国人ALTが交代するとの電話連絡を受け、頭を抱えた。4月以降、辞めるのは3人目。1人目は「通勤時間が長い」と小学校に現れず、2人目と3人目は「一身上の都合」などを理由に、1学期の授業だけで、学校から消えた。2学期からは4人目が来る。担当者は「継続性が大事なのにこんなに交代するなんて。児童たちにも説明ができない」と困惑する。
「人件費を切りつめるから辞めてしまうんだろう」と、埼玉県内のある学校長はうち明ける。この学校のALT派遣を請け負った業者は、入札で、昨年の業者に比べてALT1人あたり31万円も安く落札した。
文部科学省によると、ALTを活用した小学校の授業のうち、国が仲介する「JETプログラム」によるものが25%で、残りは民間業者への委託など。
この市の場合、40余りの小中学校にALT約20人を派遣する民間業者と契約を結んだが、校長は「風邪で半日休み、給与とボーナスを両方カットされたALTもいた。なりふり構わぬ業者が増えれば、教育の質は保てなくなる」と危機感を募らせた。
関係者によると、業者の新規参入が目立つようになったのは、小学校英語の必修化が打ち出された06年ごろから。かつてはJETプログラムで採用したALTを自治体が直接雇用するのが主流だった。
しかし、自治体側はALTが住むアパートを契約したり、交代要員を確保したりしなければならない。民間業者に委託すれば、こうした手続きは不要になるため、業者を活用する自治体が徐々に増えてきた。
民間ALTを雇用する場合は、学校側が人事管理をする必要がない「業務委託(請負)」にするケースが多い。この場合、教師がALTに直接指示すると、労働局から違法な「偽装請負」だと指導される可能性もあるため、「目の前のALTに指示してもらうため電話してくる先生もいる」(英語教育関連会社)。偽装請負について、文科省は05年に注意喚起の通知を出したが、契約方法は各自治体に一任。業者の実態についても把握しておらず、「質まで判断しようがない」と説明している。
京教大の寺田学長が辞意表明 集団暴行問題 責任痛感と 06/04/09(朝日新聞)
京都教育大(京都市伏見区)の学生6人が集団準女性暴行容疑で逮捕され不起訴処分になった問題で、京教大は7日、寺田光世学長(67)が「学長として責任を痛感した」として辞意を表明した、と発表した。今月下旬をめどに学内に設けた「不祥事に関する特別対策委員会」が中間報告をまとめた後、辞表を出す。
寺田学長は2005年4月に学長に就任。現在2期目で、任期は11年3月まで。任期途中の学長辞任は、国立大学法人として前例がないという。
大学によると、寺田学長は6日の大学の経営協議会で、「学生の不祥事により社会に多大な迷惑をかけた。本学の教育に対する社会的信頼を大きく損ね、関係する方面に多大な混乱と迷惑をかけた」として、辞意を表明したという。
京教大の男子学生6人は、今年2月、中京区の飲食店で、酔って抵抗できない状態の女子大学生を暴行したとして、6月1日に京都府警に集団準女性暴行容疑で逮捕され、その後、女子大生が告訴を取り下げ、不起訴処分になった。大学から3月末に無期停学処分を受けている。
教材納入で水増し請求、59万円詐取容疑で中学教諭ら逮捕 06/07/09(読売新聞)
中学校の教材納入を巡り、水増し請求したとして富山県警捜査2課と富山中央署は7日、富山市蓮町、同市立中教諭正水和久(31)、同市黒崎、教材販売業山崎兵吾(69)の両容疑者を詐欺の疑いで逮捕した。
発表によると、両容疑者は共謀し、2006年6月上旬と10月下旬の2回にわたり、正水容疑者が当時勤務していた同県氷見市の市立中学校で、技術家庭科の教材を購入する際、水増しした請求書を会計担当教諭に渡し、実際の価格との差額計約59万円をだまし取った疑い。
容疑学生の学童保育採用、父が面接 集団準強姦事件 06/04/09(朝日新聞)
女性への集団準強姦(ごうかん)容疑で逮捕された京都教育大の学生6人のうち原田淳平容疑者(21)を、大阪府茨木市教委が逮捕直前まで学童保育の指導員として働かせていた問題で、採用にかかわった父親の原田茂樹青少年課長が4日、八木章治教育長とともに記者会見し、「私の認識が甘かった。被害者の方に謝罪したい」と話した。
市教委によると、原田課長の次男の淳平容疑者は市内の小学校で放課後に児童を預かる学童保育の臨時指導員として、5月1日から5カ月間の任期で採用された。5月30日に「6月1日から別のことがある」として退職。勤務日数は12日間で、約5万円が支払われる予定だった。
学童の臨時指導員の採用は原田課長に決定権があり、原田課長が面接もした。履歴書には京都教育大を「卒業見込み」とあり、3月末に無期停学処分を受けたことは書かれていなかったという。
原田課長は、長続きしない指導員が多く、淳平容疑者に応募を持ちかけたと説明した。八木教育長は「縁故採用と言われればそうかもしれない」と陳謝した。市教委は原田課長の処分を検討し、採用方法を見直すとしている。
中3少女に3万円でみだらな行為…広島の小学校教諭 05/14/09(読売新聞)
女子中学生にみだらな行為をしたとして、広島県警少年対策課などは14日、同県尾道市向東町、同県竹原市立中通小教諭安保(あぼ)貞男容疑者(47)を児童買春・児童ポルノ処罰法違反(児童買春)容疑で逮捕した。
発表によると、安保容疑者は昨年6月7日午後3時頃、広島市中区のホテルで、県内に住む当時中学3年だった14歳の女子生徒に3万円を渡してみだらな行為をした疑い。携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合ったという。
県教委などによると、安保容疑者は1991年に採用され、昨年4月から同小で勤務し、2年生の担任をしている。
榎田好一・県教育長は「事実関係を調査し、厳正に対処したい」とコメントした。
更衣室にビデオカメラ、盗撮の高校教諭を逮捕…沖縄 03/06/09(読売新聞)
勤務先の高校の女性更衣室に忍び込み、盗撮目的でビデオカメラを仕掛けたとして沖縄県教委が停職6か月の懲戒処分にした同県立高校教諭石川修三容疑者(37)(沖縄県豊見城(とみぐすく)市豊見城)を県警那覇署は6日、建造物侵入容疑で逮捕した。
発表によると、石川容疑者は2月10日、勤務する那覇市内の県立高校の女性職員更衣室に正当な理由なく侵入した疑い。石川容疑者は室内の脱衣場とシャワー室に計3台の小型ビデオカメラを隠し、盗撮していた。
カメラの映像に石川容疑者自身が映っていたため犯行が発覚し、県教委は4日付で処分した。那覇署は盗撮行為についても軽犯罪法違反で追及する。
郁文館中・高校の英検不正指南、1995年頃から恒常的に 02/28/09(読売新聞)
私立郁文館中学・高校(東京都文京区)で2002年まで「実用英語技能検定」(英検)の問題を試験前に開封し、生徒に模範解答を指南していた問題で、不正は1995年頃から年3回の試験前に恒常的に行われていたことがわかった。
同校が28日に開いた保護者会で経緯を明らかにした。
同校の説明によると、当時の英語教諭だった堀切一徳前校長らは毎回、「対策講座」を開き、英検を受験する中学3年と高校1年の生徒ら計20~60人を指導していたという。日本英語検定協会(新宿区)は2日に同校から事情を聞く方針。
保護者会には約550人が出席。同校を経営する「郁文館夢学園」の渡辺美樹理事長(49)は保護者会後の記者会見で、「前校長の行為は許されないが、私は不正があったことを知らなかったし、理事長就任前なので責任はないと考えている」と述べた。保護者会に出席した在校生の母親(40)は「今は不正をやってないという説明を聞いて安心した」と話した。
「修学旅行でも淫行」 逮捕の県立高教諭が自供 01/06/09(下野新聞)
学校敷地内にある合宿所で女子生徒が教諭に淫行された事件で、児童福祉法違反の罪で起訴された宇都宮市、県立高校教諭の男(37)が県警の調べに「修学旅行先でも生徒にみだらな行為をした」との供述をしていたことが五日までに分かった。県警は立件するかどうかを含め慎重に捜査する。また、引率した自校の別の生徒に、訪問先の高校で同様の行為をした疑いが強まり、県警は同法違反容疑で六日にも再逮捕する。
昨年十一月に逮捕された男は同十二月十七日、女子生徒が十八歳未満であることを知りながら、教諭などの立場を利用してみだらな行為をしたとして、同法違反の罪で起訴された。
これまでの県警の調べに、男は起訴事実以外にも複数の生徒に同様の行為をしたなどと供述。現場の多くは自校の合宿所だが、修学旅行先での行為も含まれているという。
また、調べによると、男は一昨年八月、自校の生徒とともに訪問した群馬県内の高校敷地内で、連れて行った生徒が十八歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いが持たれている。
これまでに卒業生一人を含め、三人から被害届が出されており、県警は卒業生の事件についても立件する方針。いずれも「繰り返し被害を受けた」と訴えているため、県警は慎重に捜査を進め、事件の全容解明を目指す。 男は被害者に対し「おれとお前の秘密だ」「口外したら死ぬ」などと口止め。このため被害者は、いずれも自分だけが被害に遭っていると思い込んでいたらしい。
「天誅、文科省局長ら殺害」と東大卒の男がブログに、逮捕 11/29/08(読売新聞)
文部科学省局長らの殺害予告をインターネットのブログに書き込んだとして、警視庁は29日、東京都文京区本駒込、無職前田記宏容疑者(25)を脅迫の疑いで逮捕した。
同庁幹部によると、同容疑者は東大を卒業後、定職には就いておらず、「理想を持って勉強してきたが、教科書で勉強したことと社会の現実が違っていたことを思い知り、文科省にだまされたという感情が高まった」などと供述しているという。
発表によると、前田容疑者は今月20日、自分が開設したブログに「1週間以内に次の者を、その自宅において刺殺する」などと書き込み、同省局長や課長クラスの実在する幹部職員10人の名前を列挙して脅迫した疑い。
同庁幹部によると、前田容疑者は「目的は詐欺教育に対する天誅(てんちゅう)。国民主権を回復し、抵抗権を行使して悪を殺害する」などとブログに書き込んでいた。
今月2日ごろ、インターネット上のウェブサイトに、現職の東大教授を名指し、「殺害する」などと書き込んでおり、同庁が通信記録などを照会した結果、文科省幹部の脅迫も判明した。
無職の元東大生「教科書と違う現実が…」 文科省幹部を殺害予告 11/29/08(読売新聞)
文部科学省の局長らの殺害予告をインターネットのブログに書き込んだとして、警視庁捜査1課は29日、脅迫の疑いで、東京都文京区本駒込、無職、前田記宏(ふみひろ)容疑者(25)を逮捕した。
東大を卒業したが就職していないといい、「理想を持って勉強してきたが、教科書の内容と違う現実があることを知り、文科省にだまされたと感じた」などと供述。ほかに東大教授の殺害予告も書き込んでいたが、元厚生次官ら連続殺傷事件と関連はないという。
調べでは、20日午前8時ごろから午後0時50分ごろまでの間、自宅パソコンで自身のブログに「文科省官僚への殺人予告をしているのは私です。1週間以内に次の者を順次、自宅で刺殺する」などと書き込み、文科省初等中等教育局長ら幹部10人の実名を挙げて、脅した疑い。
入札などの取材内容、報道前に市議に提供 和歌山市教委 11/29/08(朝日新聞)
和歌山市教育委員会が今月初め、複数の報道機関から取材を受けた際、記者からの質問や担当課の回答内容、取材者名などをまとめた書類を報道前に市議に提供していたことがわかった。この書類は本来は同市の各部署が市の広報広聴課へ提出するために作成していた。市教委は「不適切だった。今後は口頭も含め情報提供はいっさいしない」としている。
市教委によると、市議に提供した書類は「報道機関取材対応票」(A4判)。4日に3報道機関から取材を受けた、「市教委関連施設での不適切会計」「耐震化工事などの入札」「学校給食民間委託」の3項目について、取材機関名、記者名、電話か直接取材なのか、取材内容、市教委の取材対応者名などをそれぞれ市教委の担当課が記入した。
5、6日に「不適切会計」は全議員に、「入札」は担当委員会の所属議員に、「民間委託」は正副議長や各会派幹部らに、手渡したり電話で内容を伝えたりしたという。
大江嘉幸市教育長は「今月4日の3項目以外で、取材内容を記した文書、メモを市議に渡したことはない。担当課が市議に報告が必要な案件だったと判断したため、と報告を受けている。報道の自由を侵害するつもりはなかったが、教育委員会という組織の独立性を考えれば、不適切と言わざるを得ない」と話している。取材内容の議員への提供は今月7日、岡山県教委でも発覚。県教委は「不適切だった」として、議員への通知をやめることを決めた。
「自生の大麻を採取した」外国語指導助手を逮捕 11/21/08(読売新聞)
北海道警富良野署は20日、中富良野町本町、米国籍の外国語指導助手(ALT)ウィリアム・リングラー容疑者(34)を大麻取締法違反(所持)容疑で現行犯逮捕したと発表した。
発表によると、同容疑者は19日夕、自宅に乾燥大麻数グラムを所持していた疑い。同容疑者は「自分で吸おうと思って、自生していた大麻を採取した」などと供述している。
児童買春:東京・国分寺の小学校長、容疑で逮捕 「出会い系」で知り合い 11/07/08(東京朝刊 毎日新聞)
17歳の少女とわいせつな行為をしたとして、神奈川県警少年捜査課などは6日、東京都八王子市久保山町1、国分寺市立第二小学校校長、長谷川一彦容疑者(54)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)と県青少年保護育成条例違反(わいせつ行為)容疑で逮捕した。「他にも18歳未満と思われる少女5人くらいと同様の行為をした」と供述しているという。
調べでは、長谷川容疑者は5月24日午前1時半ごろ、川崎市幸区の駐車場に止めた乗用車内で、当時市内に住んでいた茨城県の無職少女(17)にわいせつな行為を見せて現金1万円を渡し、6月19日午後8時45分ごろには、川崎区のホテルで同じ少女とわいせつな行為をし、1万2000円を渡した疑い。容疑を認めている。
長谷川容疑者は5月に携帯電話の出会い系サイトを通じて少女と電子メールをやり取りしていた。県青少年保護育成条例違反事件で逮捕された別の男の携帯電話の通信履歴から県警が少女を事情聴取し、発覚したという。
長谷川容疑者は05年4月から同校校長。国分寺市の松井敏夫教育長は6日夕に会見し、「弁解の余地はない。許されることではない」と謝罪した。【山衛守剛、川崎桂吾】
「元校長は『部下をかばう気持ちがあった』と話しているという。」
教育者としての自覚がない。
大分県教育委員会
の教員採用汚職から言えることだが、問題のある教諭には現場から去ってもらうしかない。
修学旅行で飲酒、校長が「事実なし」と虚偽の報告 埼玉 11/06/08(読売新聞)
県立春日部東高校(春日部市)の前教頭(51)と31歳~51歳の男性教諭の計4人が昨年10月、修学旅行先の昼食で飲酒し、当時の校長=定年退職=がこの事実を知りながら、県教委の調査に「飲酒の事実はない」と虚偽の報告をしていたことが5日、分かった。今年7月の再調査で判明した。県教委は近く4人を処分する。
県教委によると、今年2月、教育長あてに修学旅行中の教員の飲酒を知らせる匿名の投書があった。
元校長は2月の調査の際、4人が昨年10月、修学旅行先の大阪市内のお好み焼き店で、昼食にビールをジョッキ1杯ずつ飲んだことを、前教頭から聞いていた。しかし、投書に実名が書かれていなかったため虚偽の報告をし、4人にも口止めしていたという。
元校長は「部下をかばう気持ちがあった」と話しているという。
「学生30万人計画を早期に実現するのが狙い」だけのために「外国人の日本留学試験、中国語と韓国語でも出題」するのか、
文部科学省は???目標達成のために規制を緩めるのか??
外国人の日本留学試験、中国語と韓国語でも出題へ 10/26/08(読売新聞)
文部科学省は25日、日本に留学を希望する外国人の学力を判定するために実施している「日本留学試験」について、新たに「中国語」と「韓国語」で出題する方針を固めた。
受験者数の9割弱を占める中国と韓国に配慮することで、さらに両国から多くの留学生を呼び込み、留学生30万人計画を早期に実現するのが狙いだ。
これまでの試験問題は、「日本語」と「英語」で出題していた。だが、2008年6月の試験では、受験した1万9206人のうち、中国人が74%、韓国人が14%と、両国で9割弱を占めた。文科省は、さらに両国の受験者を増加させると同時に、言葉の壁を超えた基礎学力を測るために両国語の導入を決めた。
夏祭りパトロール中に中3女子をナンパ 小学校教諭逮捕 10/21/08(毎日新聞)
夏祭りのパトロール中にナンパした中学生にわいせつな行為をしたとして、警視庁少年育成課と浅草署は埼玉県青少年健全育成条例違反の疑いで、同県志木市立志木第三小教諭、後藤崇行容疑者(23)=同県和光市新倉=を逮捕した。
調べでは、後藤容疑者は8月9日午後、18歳未満と知りながら、自宅に中学3年の女子生徒(15)を連れ込み、わいせつな行為をした疑い。「彼女がおらず欲望に負けた。後悔している」などと供述しているという。
後藤容疑者は7月中旬に志木市内の神社で開かれた夏祭りのパトロール活動中、女子生徒に「メルアド交換しませんか?」などと声を掛けてナンパ。その後、メールのやりとりを続けていた。女子生徒が9月上旬に東京・池袋で補導された際、「先生とわいせつな行為をした」と話したことから犯行が発覚した。
留学生数水増し、早大が補助金2200万円不正受給 10/15/08(読売新聞)
早稲田大(東京都新宿区)が日本私立学校振興・共済事業団に対し、在籍する留学生の数を実際よりも多い人数で申請し、2003、04年度だけでも2200万円の補助金を過大に受給していたことが、会計検査院の調べでわかった。
水増しした人数は両年度だけで延べ595人に上る。05年度以降も同様の申請をしていたと見られ、不正に受給していた額はさらに増える見通し。検査院は補助金の返還を求める方針。
日本私立学校振興・共済事業団は、国から受ける補助金を財源として、各学校法人に対し、運営費に充てる私立学校等経常費補助金を交付している。07年度の交付額は計3280億5000万円。うち、早大は約93億円を受給している。
この補助金の中では、各大学などが留学生を受け入れている場合は、その数に応じて、特別に増額する制度がある。学生数が数人~30人増えるごとに、100万~数百万円が加算される仕組み。この場合の留学生は、正規の課程に在籍する学生であることが条件だが、早大は正規ではない聴講生や履修生なども含め、申請していた。03年度は申請した留学生数1592人のうち313人、04年度は同1757人のうち282人が、それぞれ対象外だった。このため、早大が過大に受給した特別補助は、03年度1500万円、04年度700万円に上った。
文部科学省によると、海外から来日している留学生の総数は、03年度に初めて10万人を突破し、昨年度は11万8498人だった。大学別の受け入れ数は長年、東京大がトップで早大は2~3位だったが、昨年5月現在、早大が2435人とトップになっていた。
同大では「事務的なミスで、意図的な水増しではない。正式な返還の求めが来た段階で、適切に対処したい」としている。
東大もだめだね!勉強できても、常識を考える能力は低いのか??
1973年に禁止された農薬「酢酸フェニル水銀」を稲の病気に効果があることから使う非常識はどこから来ているのか?
「同大は『地域の皆様に不安を与え、深くおわび申し上げる。実際に生産したお米にまで農薬が残るとは考えにくい』としている。」
自分達が正しいと思えば、規則や法律を守るつもりは東大にはないのだろう!
東大農場で10年前に禁止農薬使い米栽培、住民に販売も 10/02/08(読売新聞)
東京大は2日、東京都西東京市にある付属農場で約10年前、米や果物の栽培に禁止農薬の水銀剤を使用していたと発表した。
当時、米は周辺住民に販売されていたが、健康被害は確認されていないという。
使われたのは、1973年に禁止された農薬「酢酸フェニル水銀」を主成分とした水溶液。97~99年の毎年4月、実習用の水田で栽培する種もみを水銀剤に漬けて消毒していた。リンゴや柿の苗木にも使われたが、果実は食用には使われなかった。
同大によると、農場の技術職員が使用禁止であることを知りながら、稲の病気に効果があることから使用していたという。同大は「地域の皆様に不安を与え、深くおわび申し上げる。実際に生産したお米にまで農薬が残るとは考えにくい」としている。
健康相談などは同大農学系事務部総務課(03・5841・5482)。
法律で大麻を吸引することは違法でない点だけでここまで騒ぐのはおかしい。今後、日本の法律とは関係なしに
大麻を吸っている人達が出入りしている場所への行くことを禁止すればよい。今後は定期的に
世界反ドーピング機関が公認する検査機関の検査を全ての力士に要求すればよい。
塩谷安男弁護士は力士の場合、6日を過ぎても大麻の検査に陽性を示すことがあるとテレビで言っていた。
元若ノ鵬が部屋でも吸っていたのであれば、同じ部屋の力士も大麻の反応が出る可能性もある。
弁護士が一般的な意見を繰り返すのであれば、元若ノ鵬と同じ部屋の力士、全てにドーピング検査を受けさせれば良い。
陽性の反応が出れば、塩谷安男弁護士の言い分も考慮しても良いが、出なければ化学的な根拠がなければ無視すればよい。
【角界大麻汚染】露鵬ら提訴なら「スポーツマンらしくない」 文科相 09/16/08(産経新聞)
尿検査で大麻の陽性反応が出た元力士、露鵬と白露山兄弟が解雇撤回を求めて法廷闘争を辞さない考えを示している問題で、鈴木恒夫文部科学相は16日、閣議後の会見で「国際的に通用する検査機関が『クロ』と認定した。『何をいまさら』というのが国民の率直な感情だろう。スポーツマンらしくない」と述べ、不快感を示した。
鈴木文科相は日本相撲協会の規約が改正され、外部理事登用が可能になった点に言及。「一日も早く相撲道を正常にしてほしい。日本の伝統文化に通じ、相撲道の立て直しに権威ある発言をしてくれる方を据えてほしい。協会の力量が問われる」と述べ、適切な人材を早く登用するよう求めた。既に協会には、登用してほしい外部理事の候補者名を伝えたという。
「課内の男性職員、設置したと名乗り出る 『職員の日常会話に興味』」
大阪府教育委員会、しっかりしろよ!
大分県教委の教員採用汚職
では
大分県教育委員会
が情けない対応しか出来ていない。大阪府の別件だが人材に問題ありでは同じか?
【大阪府教委に盗聴器】課内の男性職員、設置したと名乗り出る 「職員の日常会話に興味」 09/12/08(産経新聞)
大阪府教育委員会の高等学校課内で盗聴器が見つかった問題で、府教委は12日夜、同課の男性職員が設置したと名乗り出たことを明らかにした。男性職員は「特定の職員の日常会話に興味があった」などと動機を説明しているという。
府教委は同日、栗山和之高等学校課長が府警東署を訪れ、発見の経緯を説明、コンセントの小型タップを装った盗聴器を任意提出した。
同署は住居侵入や電波法違反などの犯罪に該当するかどうか慎重に調べる方針。
府教委によると、府庁別館5階の高等学校課は、昼間は誰でも出入り自由で、日常的に高校関係者や保護者が訪れるため、外部の人物が設置したとの見方も出ていた。小型タップは文房具と同様に消耗品扱いで、備品管理の対象外。職員が自宅から持参することもあったという。
姫路港ボート死傷事故:指導主事2人の懲戒免職を答申--三木市賞罰審査会 /兵庫 09/06/08(毎日新聞)
姫路市の姫路港で8月8日、プレジャーボートが防波堤に衝突して三木市立小学校の教頭ら4人が死傷した事故で、三木市職員賞罰審査会は5日、業務上過失致死傷容疑で姫路海上保安部の調べを受けている蓬〓徳三教頭(54)の飲酒操船を容認し同乗した市教委の指導主事2人を懲戒免職処分にするよう、市教委に答申した。近く委員会を開き処分する。教頭については県教委が処分を検討している。
免職処分を求められたのは、学校教育課の穂積正則指導主事(50)▽生涯学習課の藤本貴樹指導主事(54)。
2人は、教頭7人と姫路市沖の男鹿島の民宿で開かれた懇親会に参加。宿泊をしないで帰宅する際、蓬〓教頭の飲酒操船を知りながら制止せずに乗船して教育公務員全体の信用を失墜させたとしている。教育長については指導監督の適正を欠いたとして減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を求めている。【南良靖雄】
〔神戸版〕
放医研の研究費不正プールは6660万円、職員37人処分 08/29/08(読売新聞)
独立行政法人・放射線医学総合研究所(放医研、千葉市)が、取引業者に架空の物品発注を繰り返して国の研究費などを不正に預けていた問題で、放医研は29日、預け金の総額は2001年度から7年間で6660万円にのぼるとの最終調査結果を発表し、関与を認めた43人の職員のうち、現職37人を最高で停職1か月の処分とした。
文部科学省は同日、米倉義晴理事長を厳重注意するとともに、再発防止の徹底を求めた。
調査結果によると、預け金は、研究用試薬や器具類などの購入に使われ、私的流用は確認されなかった。07年度末現在で3160万円の預け金が残っており、放医研は取引業者に残金の返還を求める。
女子中学生にみだらな行為、容疑の中学教諭を免職 愛知 08/23/08(朝日新聞)
愛知県教育委員会は22日、女子中学生にみだらな行為をしたとして逮捕、起訴された同県美浜町立野間中学校の梶谷博教諭(49)を懲戒免職に、交通死亡事故を起こしたとして同県岩倉市内の中学校教諭(25)を減給10分の1、6カ月にしたと発表した。
県教委によると、梶谷教諭は3月9日午前11時半ごろ、同県武豊町内のホテルで女子中学生(当時13)に現金1万5千円を渡す約束をしてみだらな行為をするとともに、行為をビデオカメラで撮影したとされる。
生徒の調査書「改ざん」指示、前県立高校長を静岡県警が聴取 08/07/08(読売新聞)
静岡県立天竜林業高校(浜松市)で、大学推薦入試に提出した調査書の評定のかさ上げが行われ、静岡県警は21日、改ざんを教諭らに指示していたとして前校長(60)(退職)から虚偽公文書作成・同行使容疑で事情聴取した。
県教委が告発していた。
県教委によると、前校長は在職中の2006年度、推薦基準に達していなかった評定平均値3・1の生徒について、教諭に働きかけ、19科目で基準の3・5にかさ上げさせたとされる。また、基準を満たしていた評定平均値4・2の生徒について、合格が確実になるよう教諭に3科目を改ざんさせ、4・3にかさ上げさせたとされる。生徒2人はいずれも、出願先の大学に推薦で入学した。
県教委に4月、内部通報があった。調査の結果、前校長は否定したが、4人の教諭が改ざんを認めた。4教諭を減給の懲戒処分とするとともに、3月末で定年退職していた前校長を7月に告発していた。
前校長は、読売新聞の取材に「希望の進学先に入学するのが困難な生徒の担任に対し、『何とかしよう』『頑張ろう』などとは言ったが、改ざんを指示したことはない」と話していた。
不祥事3大学に罰!「事業・研究資金支給せず」…文科省 07/29/08(読売新聞)
文部科学省は、今年になって学位取得に絡む不祥事などが発覚した横浜市立大と立命館大、瀬戸内短大の計3大学に対し、大学の優れた事業や研究に支給する「競争的資金」計4億2400万円を採択しないことを決めた。
大学の不適切な管理体制を理由に、高等教育を支える競争的資金が不採択になるのは初。同省は資金面でペナルティーを科すことで、綱紀粛正の徹底を求めたいとしている。
横浜市立大は今年3月、医学部の教授らが学位取得に対する謝礼を受け取っていたことが発覚。立命館大は、今年度入試で定員を超えた学部の新入生に他学部への「特別転籍」を促していたことが問題となり、瀬戸内短大は、教職員の退職金を学校の運転資金に充てていたことが表面化した。
大学教育の競争的資金は2002年度、優秀で熱心な研究や教育をしている大学や研究者に資金を手厚く配分するために創設され、公募で交付先を選定する。今年度の予算規模は680億円で、全国の大学から1000件を超える申請が出ている。
このうち横浜市立大が他大学と共同で計画していた「ボーダレス医療維新プログラム」(1億2000万円)など2事業計1億6500万円分と立命館大の2事業計1億9400万円、瀬戸内短大の1事業6500万円が、いずれも採択されない。
「元校長は24日、読売新聞の取材に対し、弁護士を通じて『改ざんを働きかけたことはない。身の潔白が明らかになると期待している』
などとコメントした。」
事実を調査し、もし県立高元校長が改ざんを働きかけた事実があれば厳しい処分をするべきだ。不正を指示し、否定する。校長を経験した
人間としてははずかしことだ。
採用や昇進も金で買えるケースもあるようだからこんな事も起こるのか?
推薦入試用に調査書かさ上げ指示、県立高元校長を刑事告発 07/24/08(読売新聞)
静岡県教委は24日、2007年度の大学推薦入試の際、部下の教諭に働きかけて生徒2人分の調査書の評定平均値をかさ上げさせたとして、県西部の県立高校元校長の男性(60)を虚偽公文書作成・同行使容疑で県警に刑事告発したと発表した。
県警は受理し、関係者に事情を聞くなど捜査する。
県教委によると、この高校で06年度にクラス担任を務めた女性教諭(31)と副担任だった男性教諭(42)が、出願先の大学の推薦基準を満たすよう生徒1人の調査書の評定平均値をかさ上げした。また、別のクラスの担任だった男性教諭(39)と進路担当の男性教諭(43)も別の生徒1人の調査書の評定平均値をかさ上げしていた。
内部告発を受けた県教委が聞き取り調査を実施。4教諭は「当時の校長から働きかけがあり、改ざんした」と証言したが、元校長は否定。県教委は今年6月、4教諭を減給処分とするとともに、2件の改ざんは元校長が4教諭に働きかけて行わせたと判断し、07年度で定年退職した元校長を告発した。元校長は24日、読売新聞の取材に対し、弁護士を通じて「改ざんを働きかけたことはない。身の潔白が明らかになると期待している」などとコメントした。
「漏らしていけない書類か」懲戒処分の文科省幹部、罪悪感薄く 07/11/08(読売新聞)
「相手がどこかの企業の社員だという意識がなくなっていた」「提供した情報は外部に漏らしてはいけない書類ではなかったはず」。
文部科学省の現職幹部ら7人が贈賄側からゴルフ接待などを受けていたことが明らかになった文教施設整備を巡る贈収賄事件。懲戒処分を受けた職員らは同省の調査に対し、罪悪感の薄い弁明を繰り返した。警視庁の捜査対象となった幹部も複数いたが、上司の前文教施設企画部長の大島寛被告(59)に誘われて接待を受け、多額の現金を受け取っていたのも大島被告だけだったため、立件は見送られた。
「懲戒免職は国家公務員の身分を失わせる最も重大な処分。極めて厳粛に受け止めている」。文部科学省にとっては、リクルート事件以来の大規模な不祥事で、省内で開かれた記者会見で、銭谷真美次官は神妙な表情で語った。
警視庁幹部によると、贈賄罪に問われている「五洋建設」子会社顧問の倉重裕一被告(58)は1983年、旧文部省出身の柳川覚治・元参院議員(2004年死去)の私設秘書となったのを機に、大島被告ら同省職員と親交を深め、大島被告から受け取った内部資料をもとに、業界内に情報を流す“仕切り役”としての立場を築き上げていたという。
同庁では内偵捜査の段階から、大島被告のほかにも、複数の現職幹部がゴルフや飲食の接待を受けていたという情報を入手。4月に大島、倉重両被告を逮捕した後、こうした幹部から事情を聞くなどして、度重なる接待やゴルフクラブなどの提供を確認した。
しかし、資料提供などの便宜の大半は、大島被告が一手に引き受けていたことに加え、ゴルフなどの接待は大島被告から誘われて参加するようになるケースがほとんどだった。物品提供も公訴時効(5年)となる時期だったことなどから立件が見送られた。
警視庁幹部は「限りなく黒に近いグレーだったが、刑事責任の追及にはハードルがあった。今回の文科省の懲戒処分は評価したい」と話す。
一方、文教施設企画部以外の部署で働く同省の職員は「こんなに高額なものを平気で受け取っていたとは、同じ省で働く職員として信じられない」と驚く。
同省がまとめた調査報告書では「文教施設企画部は、業務の専門性から人事が限定されていたことも今回の事件を招く一因になった」と分析。同部の人事異動のあり方を見直す方針だ。
教育に関わる人間達がこのようなありさま。人間だから完璧でないのもわかる。
しかし、このようなことをする人間が校長、教頭、教育長及び教育委員会職員
なのだから、教育が良くなるわけが無い。モンスター・チャイルドや
モンスター・ピアレントが存在するのも認めるが、教育に関わる人間が
汚職に関与し、規則を守れとか、りっぱな大人になれとか、社会に貢献しろとか
言っても説得力も無いし、演技が上手くないと伝わらないだろう。
わいろを送り、「平等」とか「公平」とか平気な顔で子供達に言っていたのだろうか??
偽善者だ!こんな教育者がいるから、生徒の親だって不信感を持ったり、
疑問に対しては意見を言ったりするのじゃないか?聞きたくない意見は、
モンスター・ピアレント扱いで無視するのか?それとも隠蔽するのか?
他にも同様のケースが無いか徹底的に調べる必要がある。
県教委元幹部、10人挙げ「合格」指示 教員採用汚職 07/06/08(朝日新聞)
大分県の教員採用をめぐる汚職事件で、逮捕された県教委幹部の間で採用試験の一部受験者の得点水増しを指示するやり取りがあったことが、県警の調べでわかった。県警は教員採用時に組織的な不正をしていた疑いが強いとみて、関係者から事情を聴いている。
指示されたのは、5日に収賄容疑で再逮捕された県教委義務教育課参事の江藤勝由容疑者(52)。07年度の小学校教員の採用試験に絡み、当時の参事兼教育審議監で大分県由布市教育長の二宮政人容疑者(61)=収賄容疑で4日に逮捕=から受験者の名前を示され、合格させるよう指示されたと供述しているという。
挙げた名前は10人前後で、5日に贈賄容疑で再逮捕された義務教育課参事、矢野哲郎(52)、妻で小学校教頭のかおる(50)の両容疑者の長女が含まれていたという。教育審議監は県教委ナンバー2で、二宮元審議監は教員人事の実質的な責任者だった。
調べでは、二宮元審議監、江藤参事は矢野参事夫婦の長女の採用に便宜を図った見返りとして、06年9~10月にそれぞれ100万円相当の金券を夫婦から受け取った疑い。試験は06年7月に筆記などの1次試験、9月に面接などの2次試験があった。1次は489人が受験。うち119人が2次に進み、長女を含め41人が合格した。
江藤参事の供述によると、当時は義務教育課主幹として採用試験の事務を担当し、1次試験の採点終了後に受験者全員の得点を記した表を二宮元審議監に見せた。その際に10人前後の受験者の名前を示され、「合格ラインに入れろ」と指示されたという。矢野参事夫婦の長女も含まれ、江藤参事は「長女の1次、2次試験の点数をかさ上げして合格ラインに届かせた」と供述しているという。
二宮元審議監は中学校、江藤参事は小学校の教諭を経て、県教委や出先事務所で学校運営にあたる指導主事を務めた。00年に県教育センターの副所長と指導主事、03年に小中学校の教員人事を担当する教職員1課の課長と人事係副主幹として、上司と部下の関係だった。
江藤参事は教職員1課が義務教育課に改称した後も小中学校の教員人事の実務を担当し、05年に二宮元審議監が就任後は3回目の上司と部下の関係になった。県警は、江藤参事が二宮元審議監から10人前後の名前を挙げて合格させるよう指示されたことに関心を寄せており、組織的な不正の実態解明を進めている。
大分県教委汚職で5人逮捕、管理職任用試験にも疑惑 07/06/08(読売新聞)
大分県の小学校教員採用試験を巡り、わいろの授受が行われたとして、県教委の元幹部ら5人が県警に逮捕された。供述から管理職任用試験にかかわる疑惑も浮上、不正はさらに広がる可能性が出てきた。
さらに県警は今月4日、県教委ナンバー2の教育審議監だった同県由布市教育長・二宮政人容疑者(61)を別の収賄容疑で逮捕、翌5日には江藤容疑者を収賄容疑で、矢野哲郎、かおる両容疑者を贈賄容疑でそれぞれ再逮捕した。
発表によると、07年度の採用試験で矢野両容疑者が長女の採用に便宜を図り合格させてもらった謝礼として、06年9、10月ごろ、当時教育審議監だった二宮容疑者と二宮容疑者の部下で同課主幹だった江藤容疑者に各100万円分の金券を渡した疑い。
4容疑者は大筋で認めているという。
江藤容疑者の関係者によると、江藤容疑者が、採用試験の全受験者の得点一覧表を示すと、二宮容疑者が長女らの名前を指さし、点数をかさ上げするよう指示したとされる。県警は、二宮容疑者らがほかにも不正に合格させた疑いがあるとみて調べる。
文部科学省によると、07年度の公立学校教員採用試験の平均競争倍率は7・3倍で、大分県はこれを大きく上回る16倍だった。
一方、江藤容疑者は、08年度の校長、教頭の管理職任用試験でも便宜を図った謝礼として受験した4人から金券を受け取ったと供述していることが、複数の関係者の話でわかった。合計額は150万~200万円に上るとみられる。
4人は4月1日付の人事異動で校長、教頭に昇任したという。
関係者によると、江藤容疑者は当時同課課長補佐で、1人十数万~50万円分の金券を受け取ったという。
長女の教員採用で金券百万円贈る、大分県教委の夫婦再逮捕 07/05/08(読売新聞)
大分県警は5日、小学校教員採用試験を巡ってわいろの授受があったとして、県教委義務教育課参事・江藤勝由容疑者(52)を収賄容疑で、同課参事・矢野哲郎(52)と妻の同県佐伯市立重岡小教頭・矢野かおる(50)の両容疑者を贈賄容疑で再逮捕した。
県警は4日夜、同じ収賄容疑で県教委ナンバー2の教育審議監だった同県由布市教育長・二宮政人容疑者(61)を逮捕している。
発表によると、当時小学校教頭だった矢野容疑者とかおる容疑者は、2007年度試験で長女(23)の採用に便宜を図り合格させてもらった謝礼として、06年9、10月ごろに二宮容疑者へ、また同年10月ごろには二宮容疑者の部下で同課主幹だった江藤容疑者へ、それぞれ100万円分の金券を渡した疑い。
矢野両容疑者と江藤容疑者は容疑を認めているという。
二宮容疑者は、07年度の採用試験で合格者の最終案を決裁する立場にあった。
矢野両容疑者は佐伯市立蒲江小校長・浅利幾美容疑者(52)と共謀。08年度の採用試験で浅利容疑者の長男、長女の採用に便宜を図ってもらうため、江藤容疑者に現金300万円と金券100万円分を贈ったとして6月14日に逮捕されていた。
大分地検は5日、浅利容疑者に関する贈収賄事件について、江藤容疑者を収賄罪、矢野哲郎、浅利両容疑者を贈賄罪でそれぞれ大分地裁に起訴し、かおる容疑者は「関与の度合いが低い」として処分保留とした。
「舞鶴の事件みたいになりたいか」 小学校教諭が女子高生に暴行 07/02/08(読売新聞)
女子高生に性的暴行を加えてけがをさせたとして、京都府警捜査1課と宮津署は4日、強姦致傷の疑いで、同府与謝野町立桑飼小学校教諭、細野弘和容疑者(34)を逮捕した。細野容疑者は女子高生に対し、今年5月に同府舞鶴市で高校1年の少女(15)が殺害された事件を持ち出して「東舞鶴の事件みたいになりたいんか」と脅していたという。
調べでは、細野容疑者は今年6月3日夜、府北部の路上で、自転車に乗っていた女子高生を押し倒し、手などに3週間の打撲傷を負わせたうえ、道路脇で性的暴行を加えた疑い。
調べに対し、細野容疑者は「痴漢する目的で押し倒したが、その後は覚えていない」と容疑を一部否認している。
細野容疑者は現場近くで待ち伏せていたといい、女子高生と面識はなかった。現場周辺の地域では昨夏から未成年を狙った痴漢が数件あり、府警は関与を追及している。
細野容疑者は同小で校長、教頭に次ぐポストの教務主任を務めており、学級の担任はなかった。森川智美教頭は「何も事件を知らされていない。何事にも一生懸命頑張る先生だった」と話した。
教育予算を増やすとか、教員を増やす前に、問題のある教員を首にした方がいいぞ。
教員を採用する時に、試験に受かることも大切だが、人格や人間性も参考基準にするべきだ。
たしかに面接だけで人格や人間性を見抜くことは難しい。そして教員になれば、現状では
組合やその他の組織の政治的圧力で簡単に首に出来ない。結局、無駄な更新制度で
ごまかし。人格や人間性や教え方に問題がある教師には辞めてもらうしかないだろ。
文部科学省は問題に対応できないような能力しかないのかもしれないが、国民はもっと文部科学省
を批判するべきだろう!
女子部員10人にわいせつ行為、熊本市立中の教諭を懲戒免職 07/02/08(読売新聞)
熊本県教委は1日、熊本市立中学校の男の教諭(35)が、顧問を務める運動部の女子部員約10人にわいせつ行為を繰り返したとして懲戒免職処分にした。
県教委などによると、教諭は2007年8月から今年5月24日にかけ、「けがの具合を見る」「マッサージをする」と、個別に空き教室や部室に呼び出し、「試合で勝つために度胸をつけてやる」と上着を脱がせたり、服の上から胸を触ったりした。わいせつ行為は計約20回にのぼり、教諭は「親には言うな」と口止めしていたという。
5月24日に被害に遭った生徒が当日、親に相談して発覚した。教諭は「わいせつ行為ととらえられても仕方がない」と認め、同26日から自宅謹慎していた。
県教委は「保護者らが望んでいない」として、刑事告発は見送る方針。
わいせつ行為:女子運動部員十数人触る 中学教諭懲戒免職 07/01/08(毎日新聞)
熊本県教委は1日、熊本市の市立中学校の男性教諭(35)が、顧問を務めていた運動部の女子部員十数人に、わいせつな行為を繰り返していたとして懲戒免職にした。県教委は「保護者の要望」などを受け、学校名も教諭名も明かさなかった。
県教委などによると、教諭は昨年8月~今年5月、部活動中や練習後に「筋力トレーニングの凝りをほぐす」などと言って2~3年生部員を1人ずつ別室に呼び、胸を触ったり、Tシャツを脱がせるなどの行為を計20回した。「人には言うな」などと口止めしていた。1人で4回被害に遭った生徒もいた。
5月24日に2人が被害に遭い、うち1人が保護者に相談して発覚した。この生徒はショックで数日間、登校できなくなったが、スクールカウンセラーと面談し、現在は復帰しているという。
教諭は06年4月に同校着任以来、この運動部の顧問をしていた。「マッサージは部活を強化する手段」などと当初はわいせつ性を否認していたが、現在は認めているという。「担任しているクラスの生徒には何もしていない」と説明している。
校長(54)は5月29日、この運動部の保護者を集めて経緯を説明し謝罪したという。管理責任を問われ、減給(10分の1)1カ月の懲戒処分を受けた校長は取材に「(県・市教委が)記者会見で説明した通りで、それ以上コメントすることはない」と話した。【門田陽介】
【主張】わいせつ教師 教壇に戻さず厳罰で臨め 07/01/08(産経新聞)
教師が教え子や未成年者にわいせつ行為や性的問題を起こす事件が相次いでいる。教育者としてあるまじき行為だ。教育委員会は厳罰で臨み、こうした教師を教壇に立たせてはならない。
文部科学省が年末に公表している調査によれば、わいせつ行為などで懲戒処分や訓告などの処分を受けた教職員は平成18年度で190人にのぼり、前年度に比べて48人も増えている。
調査では自校の児童・生徒へのわいせつ行為が目立つ。教師の立場から教え子の弱みに付け込む卑劣な犯罪に怒りを禁じ得ない。
つい最近も、茨城県行方市の市立中学教諭が11歳の女児に性的暴行を加えたとして、強姦(ごうかん)容疑などで県警に逮捕された。
このケースでは、昨年4月ごろには教師と女児の関係がうわさになっていた。しかし、学校側の確認に対しても教師はこれを否定、その後も教壇に立っていた。学校側の対応は、あまりに身内に甘すぎたと言わざるを得ない。
学校や教委が、教師の不祥事について情報を得ていながら、警察の捜査が始まるまで適切な調査すら行わずに放置する。そんなケースは過去にも起きている。
逮捕や処分されたケースは、氷山の一角にすぎないとの指摘もある。文科省の調査では、過去に処分歴がある再犯者がいることも明らかになっている。
都道府県教委などはそれぞれ懲戒処分の独自基準を設け、処分した場合は原則公表する流れになってきてはいる。だが処分の具体的統一基準はないのが実情だ。
例えば、児童・生徒への性行為やキス、盗撮などをした場合には「免職」とするなど、事例と処分の重さを具体的に明示し、インターネットのホームページなどで公表している教委がある一方、基準が抽象的なままの教委も多い。
処分を受けた教職員の氏名公表も、教委や事案などによって基準が異なり、あいまいだ。
文科省は「懲戒処分基準を作成し、教職員に周知を図ることは厳正な運用や抑止につながる」としている。教委は処分基準を明確にし、厳正に処分すべきだ。
校長までが逮捕され、学校不信は広がるばかりだ。かつて教師は地域の相談役でもあり、尊敬を集める存在だった。高い倫理観が求められるのは当然だ。教壇の信頼回復のためにも、不適格教師には厳罰で臨むほかなかろう。
浜田水産高 着服教員を懲戒免 被害819万円 校長ら5人も処分(島根) 06/30/08(読売新聞)
浜田市の県立浜田水産高(平山明校長)で起こった同窓会費などの着服で、県教委は27日、着服をしたとして同高の村上芳美・実習主任(55)を懲戒免職処分に、管理責任で平山校長や大津義文前校長(隠岐高校長)、村上謙武教頭ら5人を文書や口頭による訓告処分にした。県教委は、被害額を本人の申告額を189万円上回る819万円とした。
県教委は27日、記者会見を開き、河原一朗・高校教育課長が「度重なる不祥事で申し訳ありません」と陳謝。県立学校の会計手順をまとめた「学校徴収金等取扱要綱」を9月までに改定することを明らかにした。
県教委の発表によると、村上実習主任は2008年までに会計をしていた同窓会の会費約684万円を着服。同様に会計を担当した県高校体育連盟ハンドボール専門部でも02~08年に経費135万円を着服。着服金額はそれぞれ84万円、105万円増えた。
村上実習主任は返済の意思を示しており、返済されれば同窓会や県高体連の活動に影響は出ないという。村上実習主任は県教委の調査に対して、「学校や同窓会、子どもたちに申し訳ない」と話している。村上教頭は「二度と起こらないよう、職務規定の順守を徹底したい」と話していた。
【衝撃事件の核心】教師がわいせつ犯に墜ちる「そのとき」 指導上の疑似恋愛が妄想に 06/28/08(産経新聞)
「教育には信頼関係が必要だ」。使い古された感もある言葉だが、それが教育の本質なのだろう。だが、それを逆手に取ったような事件が相次いでいる。5月末にはマクドナルド店内で女子高生にわいせつな行為をした元中学校長が逮捕された。なぜ、教育者によるわいせつ行為はなくならないのか。信頼が欲望に変わってしまう「そのとき」とは-。(加田智之、大矢博之)
■「信頼しているので拒まない」…元校長のあきれた言い分
「もしかして、エンコー(援助交際)じゃないか」
5月30日午後1時ごろ、埼玉県所沢市日吉町のファストフード店「マクドナルド所沢店」2階。店内にいた男子高校生2人は異様な光景を目にした。
カウンター席で、中年の男が女子高生と並んで座っている。親子とはとても思えない証拠に、2人は体を寄せ合い、向き合うように座っているのだ。
男子高校生らが援助交際と錯覚しても不思議ではない光景である。
だが、男子高校生らはこの直後、さらに信じられない光景を目にすることになる。
中年男が、女子高生のスカートの中に手を入れ、その下半身を触り始めたのだ。一方の女子高生は嫌がっているようにしか見えない。
「絶対におかしい」
男子高校生らは店の2軒隣にある交番に直行した。すぐに駆けつけた警察官に中年男は事情を聴かれ、やがて県青少年健全育成条例違反容疑で逮捕された。
男の素性を知った男子高校生らは、さらに信じられない気持ちに駆られただろう。交番の2軒隣にある店でハレンチ行為を行った大胆不敵なこの男は、東京都武蔵村山市教育相談室の前室長、佐藤学容疑者(62)=児童福祉法違反の罪で起訴、再逮捕=だったのだ。
佐藤容疑者は同市立中学校の校長まで務めた“聖職者”だが、所沢署の調べに当初は容疑を否認した。だが、やがて犯意を認め始めた佐藤容疑者は、店内で自分の下半身を触らせていたことまで明らかにするのだ。
「18歳未満の女子高生」「嫌がるのを無理やり」「飲食店内という公衆の面前でのハレンチ行為」…教育者としての良識を疑わざるを得ない言葉が並ぶ今回の事件。
「魔が差してしまった…」
当初はそう供述していた佐藤容疑者はその後、さらに信じられない言葉を口にした。
「(女子生徒は)自分を信頼しているので拒まないと思った」
■自分の欲望を抑えられず…「体形が大人っぽくなったので」
「女子生徒は自分を信頼していた」と供述する佐藤容疑者。そもそも佐藤容疑者が女子高生との間に「信頼関係」が生じていたと錯覚したのはどうしてだろうか。
被害者の女子高生(16)は都内在住の高校2年生。佐藤容疑者が勤務する相談室に中学3年生のころから通うようになり、学校生活の悩みなどを相談していた。
同市教委によると、相談室には7人の相談員がいるが、実際に相談業務を担当するのは臨床心理士の資格を持つ3人の相談員。室長の肩書を持つ佐藤容疑者だが、実際の仕事は相談日程の調整や相談員の取りまとめ役でしかなかった。相談員に対する命令権限すらなかったという。
通常なら接触する機会があるはずもない“事務方”の佐藤容疑者と女子高生。2人はどういう経緯で接触し、関係を深めていったのだろうか。
捜査関係者はこう説明する。
「被害者の女子高生は何人かの相談員に勉強を見てもらっており、佐藤容疑者には社会科を教えてもらっていた。勉強を教えているうちに佐藤容疑者が女子高生に興味を持ったようだ」
教育者としての立場を忘れ、佐藤容疑者は女子高生に性的な興味を抱いていった。その証拠は、佐藤容疑者の次の供述からもうかがえる。
「体形が大人っぽくなっていく女子高生を見て、胸を触りたくなった」
当初は「教育者としての好意」で女子高生の学習を手伝っていた佐藤容疑者。だが、少しずつ大人の体形になっていく女子高生を見ているうちに、性的な妄想を抱くようになったということだろう。
女子高生は、昨年12月ごろからわいせつな行為をさせられていた。拒まない女子高生を見て、佐藤容疑者は自分を「信頼している」と勘違いしたのだが、実際の女子高生の心境は「信頼」にはほど遠かった。
「(わいせつな行為を)断ると、もう(勉強の)相談ができなくなると思い、断れなかった。尊敬している先生だから我慢した」
所沢署の調べに対し、女子高生はそう話しているという。佐藤容疑者は「勉強を教えてもらいたい」という女子高生の思いを逆手に取ったうえ、女子高生にわいせつな行為を続けていたのだ。女子高生が拒めなかった本当の理由を、教育者として長いキャリアがある佐藤容疑者が見抜けなかったはずがない。
捜査幹部はこう吐き捨てた。
「佐藤容疑者は『魔が差したから』と供述しているが、それは本当なのか。信じることはとてもできない」
■勤務時間外の職員室でもわいせつ行為
市教委によると、佐藤容疑者は平成18年3月に校長を最後に退職後、嘱託職員として都に採用された。所沢市に派遣され、週3~4日の勤務に就いていた。
佐藤容疑者は逮捕された日、都内に住んでいる女子高生をわざわざ自分が住んでいる所沢市まで呼び出し、わいせつな行為に及んでいた。
その日は勤務日ではなかったが、そもそも相談室外で職員が相談業務を行うのは「絶対にあってはならないこと」(同市教委)だという。
いわば、他の職員の目を盗んでの犯行だったわけだが、佐藤容疑者が他の職員の目を盗んだのはこの日だけではない。
所沢署は6月23日、児童福祉法違反(児童に淫行させる行為の禁止)の疑いで、佐藤容疑者を再逮捕した。この再逮捕の理由となった犯罪行為に、同市教委は再び唖然とさせられることになる。
「佐藤容疑者は逮捕された前日である5月29日17時20分ごろから、教育相談室に隣接する職員室で、女子生徒に自分の下半身を触らせていた。他の職員は誰もいなかったが、その際も女子高生は勉強を教えてもらうために職員室に行ったようだ」(捜査関係者)
佐藤容疑者の勤務時間は、8時半~17時15分。他の職員は9時~17時。
「職員も片づけなどがあるので、17時20分に職員室に2人しかいなかったとは考えにくいが…」
同市教委幹部は苦々しそうにそう話すが、2人きりになったことが、佐藤容疑者に犯行を決意させたのも事実だ。
実は佐藤容疑者が職場でわいせつな行為に及んだのは、この日が初めてではない。女子高生は所沢署の調べに対し、「職員室や相談室で10数回、同じような行為をさせられた」などと被害を訴えているからだ。
そもそも相談室はその業務の特性上、部屋に入ってしまえば外から中の様子は見えない構造になっている。勤務時間内なら他の職員の目もあるが、勤務後や勤務外なら女子高生と2人きりになる機会は数多くあったのだ。
「勤務態度は問題なかった」(同市教委幹部)という佐藤容疑者。だが、他の職員が帰宅した後など、他の職員の目に触れない所で問題行為を繰り返していたのだ。
■信頼が欲望に…聖職者が「性食者」に墜ちるとき
県青少年健全育成条例違反で逮捕された佐藤容疑者だが、さいたま地検川越支部は児童福祉法違反罪に容疑を切り替えて起訴した。
「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」である県青少年健全育成条例違反に対し、児童福祉法違反は「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」。検察は佐藤容疑者の悪質性をより重視し、児童福祉法違反罪での起訴に踏み切ったとみられる。
佐藤容疑者の悪質性を顕著に物語るのが、「自分を信頼しているので拒まないと思った」という供述だ。
女子高生から信頼されていると勘違いした佐藤容疑者は、わいせつ行為を確信犯的にやっていたといえる。自分の欲望を正当化するための理由として、「自分は女子高生から信頼されている」と考えたとも言えるだろう。
佐藤容疑者が逮捕される2日前の5月29日、同じ埼玉県熊谷市にあるさいたま地裁熊谷支部では、1人の元校長が法廷に立っていた。肉体関係を持った教え子に脅迫メールを送ったとして逮捕・起訴された川口市立川口高校元校長、市川和夫被告(56)だ。
市川被告は法廷で、教え子の女性と肉体関係を持った理由を「彼女を支えるため」などと供述。信頼する自分の影響を受けたおかげで「卒業時はすばらしい生徒になった」などとも得意げに話した。
「男性教師が女子生徒を指導する場合、『疑似恋愛をしろ』と言う人もいる。恋愛と一緒で、好かれた方が信頼を得て指導がスムーズにできるからだが、中には信頼を得たことに甘えて自分を制御できなくなる教師もいる」(教師経験者)
指導のための“恋愛”である現実に目をそむけ、「盲目な恋」にひた走る教師。さらに信頼=支配とでも勘違いし、自分の欲望をぶつけても“安全な”相手と思いこんではいないだろうか。
聖職者が「性食者」に墜ちる背景には、そんな論理が潜んでいるのかもしれない。
【衝撃事件の核心】校内でも“関係” 「自立させるため」教え子脅した校長「法廷での主張」 05/31/08(産経新聞)
「(学校内にある)畳の部屋です…」-。元教え子の20歳代の女性に復縁を迫るメールを送信するなどし、脅迫罪で起訴された埼玉県川口市立川口高校元校長、市川和夫被告(56)。初公判では、学校内で女性と“関係”を持ったことまで暴露された一方、交際はあくまで「女性を支えるため。自立を促すためだった」と繰り返した。殺人すらほのめかすメールまでも「(約束を守る大切さを)教え込むため」と言い切る“元聖職者”の言い分とは…。
「殺すことだって」「因果応報」「男性遍歴」…脅迫メールの文言次々
29日午後1時半、さいたま地裁熊谷支部(永田誠一裁判官)。緑色の上着にジーンズというラフな姿で法廷に現れた市川被告は、検察官が朗読する起訴状を背筋をまっすぐに伸ばして聞いていた。
その起訴状で次々と明らかにされたのは、事件の鍵を握る市川被告が女性に送ったメールなどの内容だ。あまりに常軌を逸したその文面に、事件の概要を把握しているはずの傍聴人らも思わず顔をしかめた。
《…女性の携帯電話に電話をかけ、「僕はA(女性の名前)のためだったら、人を殺すことだって平気だ。約束の日に会わないというのであれば、何をするか分からない。場合によっては、Aの交際相手に、Aの過去の性体験などを暴露したり、その裸体などを撮影した写真を送りつけるかもしれない」…》
《「あなたに最後のチャンスをあげます。着信拒否や相変わらず無視の状態を続けるなら、僕は、あなたの交際相手に会いに行くか、手紙を書きます。僕の知っている全てを話します」などと、Aが(市川被告と会わないことについて)謝罪をしない場合には、Aの交際相手に対してAの過去の性体験などを暴露する旨のメールを送信し…》
《「最後のチャンスを活かしてくれませんでしたね。因果応報となるでしょう。(Aの交際相手に)手紙を送ります」…「あなたの知らないAの男性遍歴について、お知らせしようと思い筆をとりました」などと記載した書面在中の封書をA居宅に郵送し…》
これらはすべて、市川被告が勤務していた高校の校長室から送信されていた。
「起訴状に書かれた内容に間違いありませんか?」と尋ねた裁判官に、市川被告は手を前に組んだまま応えた。
「間違いありません」
「肉体関係目当てか?」に「自立を促すため」
市川被告は県北部の県立高校の教頭を務めていた12、13年ごろ、在校生だったAさんに「放課後に勉強を教えてあげる」などと近づいた。
マンツーマンの指導を通じ、「交際」に発展したのが14年1月ごろ。
Aさんに新しい恋人ができたために19年3月ごろに破局したが、復縁を求める市川被告は徐々に脅し文句を散りばめたメールなどをAさんに送りつけるようになっていった。
今年3月8日、埼玉県警に脅迫容疑で逮捕された市川被告。入試改革を進めるなど高い評価を得ていた教育者の“裏の顔”は、この日の法廷で次々と明るみに出た。
弁護人「Aさんとの交際の着地点はどう考えていたのか?」
市川被告「一緒にいるとAは私を頼るので支えなきゃならない。支えるとしてもそれはいつまでも続くものではない。彼女が自分に依存してしまうと大変なので自立してほしいといつも考えていた」
裁判官「交際を続けた理由は?」
市川被告「色んなことがあった。どうしても(Aさんを)支えなければならなかった」
裁判官「(交際しているときの)気持ちは肉体関係目当てか?」
市川被告「自立してもらいたいという気持ち」
裁判官「肉体関係のある交際と自立の違いは?」
市川被告「今考えると、私は間違っている」
Aさんとの交際は、あくまで「彼女を自立させるため」と供述する市川被告。教師として生徒の自立を手助けするのは当然だが、なぜ肉体関係を結ばなければならないのか。さらに不可解な供述は続く。
校内で関係持ち…離婚を求められていた元校長
裁判官「警察官の供述調書を読むと、学校で“関係”を持った事実があるが?」
市川被告「はい」
裁判官「どこで?」
市川被告「畳の部屋です。畳の部屋があるんです」
傍聴席からは、失笑ともとれるざわめきが起きた。学校内で“関係”を持つことが、どうして生徒の「自立を促す」ことになるのか-。
Aさんは市川被告に愛情を持っていた。妻子ある市川被告に離婚を迫ったこともある。
そこまで自分を愛してくれる教え子に対し、市川被告は正面から向き合っていたのだろうか。
弁護人「Aさんはあなたにどんな感情を持っていたか」
市川被告「当初はあこがれを持っていたと思う。私のところに来て、色んな話をしたり。愛情に飢えていたんだと思う」
裁判官「Aさんはあなたを全面的に信頼して愛情を持っていた」
市川被告「彼女も(愛情が)成長していた。私の方で食い止められなかった」
裁判官「Aさんは『本気で考えてくれない。愛人の立場でむなしく思う』と話している」
市川被告「申し訳ない。そんなことを思っているとは。関係を持ったのがまずかった。支えていると思っていた」
裁判官「あなたの答弁を聞いていると、愛人と付き合っているようにしか聞こえない」
市川被告「私として自立させたかった。その度に(なにかしらの)事件があり、Aが精神的に不安定になる。別れればよかったが…」
教師が生徒と“関係”を持つことが、どうして自立につながるのか。
「Aさんを自立させるために“関係”を持った」ともとれる市川被告の言い分だが、納得している様子の傍聴人はいなかった。
■脅迫メールの理由は「謝罪の大切さを教えるため」…不可解供述繰り返し
「恋人に性体験を暴露する」とまで言われたAさんは、19年12月に市川被告と会うことを了承する。だが、まさにその当日、Aさんは自殺を図った。
指定した場所になかなか現れないAさんにいらだつ市川被告。メールなどの文言はこの後、一気に脅迫傾向をエスカレートさせていった。
「約束を守らなかったことを謝罪させるためにメールを送り続けた」
市川被告の法廷でのこの言い分は、教育者として当然の責務と言わんばかりのものだ。
市川被告「(19年)3月のときの別れ方が悪く、何かあったらAの相談に乗っていた。2度と会わない前提で、12月に、最後にAの自立を祝うという思いで会おうとした」
弁護人「あなたは(2人で会うという)約束を守らなかったAさんに激しい怒りを覚えたことが事件の動機という。2人にとって“約束”とは?」
市川被告「Aは当初は問題があったが、『約束を守る』をベースに人間的に成長した。卒業後も精神的に病んだりしたが“約束”でクリアーしていった。(約束を守るということは)意味があるものだ」
弁護人「約束を守らないAさんにどうした?」
市川被告「怒りというより、教え込む側面がある。Aが約束を軽んずることに、私は(以前から)謝罪しなさいと言っていた。それが治ってきたのに、また出てきた」
検察官「メールを出したことには別の気持ちもあるのではないか?」
市川被告「あくまで謝罪。“関係”を持とうという気持ちはない」
検察官「文言が脅迫的だと自覚しているか?」
市川被告「(Aさんなら)分かってくれるだろうという気持ちがあった。彼女に甘えがあった」
検察官「文章にはAさんの男性遍歴も記載されているが?」
市川被告「彼女が巻き込まれた“事件”の内容。何かあったら提出しようと」
検察官「初体験の内容も事件か?」
市川被告「…一部、事件の内容です」
検察官「卑猥な脅迫メールを『約束を守らせるため』と正当化していないか?」
市川被告「教え込むためだ。謝罪してほしかった。(メールの)内容は恥ずかしいものだった」
Aさんは市川被告が逮捕される直前、市川被告に電話をしたという。メールの文言を「ひどい」というAさんに対し、市川被告はこう話したという。
「ひどいけど、すべて真実だ。(Aさんが)連絡しないで不誠実。謝ってもらいたい」
Aさんは「まだそんなこと言っているの」とだけ話し、電話を切ったという。子供じみた“屁理屈”をこねる市川被告に、Aさんが教育者の姿を見ることができたとはとても思えない。
■「私の影響ですばらしい生徒になった」
市川被告は、メールの文言については反省の言葉を述べている。だが、そのメール送った前提は、あくまで「Aさんに約束の大切さを教えるため」だ。教育者としての自負をのぞかせる法廷供述は他にもあった。
弁護人「Aさんの印象は?」
市川被告「入学当初は問題を抱えていたが、私の影響を受け、卒業するときにはクラスや学年でも上位になった」
市川被告「Aさんは頑張ったので、卒業時はすばらしい生徒になった」
弁護人「(被告は)これまで教育の世界で活躍してきたが?」
市川被告「自分で行った教育にウソはない。自分の仕事はしていたと自信がある」
検察官「Aさんはあなたに自殺にまで追いつめられている」
市川被告「まあ、私は、彼女に自立してもらいたい気持ちがあった」
検察官「Aさんはあなたを想っていた」
市川被告「彼女から別れたくないと言われ、突っぱねるとどうなるか分からないという逡巡がありました」
最終意見陳述で市川被告はこう述べた。
「将来ある彼女は早く立ち直って、幸せになってほしい」
どこか他人事めいたこの言葉にも、教育者として「助言」するかのような気持ちが透けて見える。
教育者としての態度をのぞかせ続ける市川被告の主張に、裁判所はどういう判断を下すのだろうか。
裁判は初公判のこの日に即日結審し、検察側は懲役1年6月を求刑した。
判決は7月15日に言い渡される。
マックで女子高生にわいせつ 元中学校長逮捕 05/31/08(産経新聞)
マクドナルド店内で女子高生にわいせつ行為をしたとして、埼玉県警所沢署は31日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、東京都武蔵村山市教育相談室相談員、佐藤学容疑者(62)=埼玉県所沢市青葉台=を逮捕した。佐藤容疑者は平成18年3月まで、武蔵村山市立第5中学校の校長を務めていた。
調べでは、佐藤容疑者は30日午後1時ごろ、所沢市日吉町のファストフード店「マクドナルド所沢店」2階で、武蔵村山市に住む私立高2年の女子生徒(16)のスカート内に手を入れ、下半身を触るなどした疑い。店内にいた男子高校生2人が犯行を目撃、近くの交番に届け出た。
佐藤容疑者は当初、否認していたが、「女子生徒から相談を受けている間に、魔が差してやってしまった」と供述しているという。
佐藤容疑者は、女子生徒が中学3年のころから、相談室で相談に乗っていたという。女子生徒は「昨年暮れぐらいから、わいせつな行為をされた。尊敬できる先生だから我慢した」と話しており、同署は児童福祉法違反容疑で余罪を追及する。
「林被告は同校野球部出身で、平成12年の選抜高校野球大会に主将として出場、選手宣誓もしている。」
選手宣誓した人間は立派であるべきだが、立派であるとは思わない。しかし、教諭と言う職業を
選ぶべきでないと思う。公務員試験は重要だが、人格も重要だと思う。
墜ちた甲子園球児 教え子にわいせつ行為で有罪判決 05/30/08(産経新聞)
栃木県内のホテルで昨年12月、教え子で高校3年だった女子生徒にわいせつな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反の罪に問われた元作新学院高校教諭、林公則被告(25)の判決公判が30日、宇都宮地裁で開かれた。小林正樹裁判官は「犯行は卑劣で悪質」と断罪し、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。。
林被告は同校野球部出身で、平成12年の選抜高校野球大会に主将として出場、選手宣誓もしている。
検察側は「教師という立場にありながら、教え子にみだらな行為をし、悪質極まりない」と指摘。一方、弁護側は「2人は真剣に交際していた。単に性的欲望を満たすためではなく、処罰対象とされる淫行(いんこう)には当たらない」と無罪を主張していた。
判決によると、林被告は昨年12月15日、同県下野市のホテルで、女子生徒が18歳未満と知りながら、性的欲望を満たすためわいせつな行為をした。
教育予算7兆増なら幼稚園無料・私大生に30万…文科省検討 05/29/08(読売新聞)
「幼稚園、保育所は無償」「私立大学生200万人に30万円支給」――。政府の「教育振興基本計画」で、教育投資の総額が対国内総生産(GDP)比で、現在の3・5%から5%になった場合、文部科学省が検討している増額分1・5%(約7兆円)の使途が29日、明らかになった。
低所得者世帯の大学生の授業料免除や私立の高校・大学生などへの授業料減額などに約2・2兆円をつぎ込むなど大盤振る舞いが目立つ。財務省は反発を強めており、振興計画の閣議決定は6月中旬以降にずれ込みそうだ。
「教育振興基本計画」は、今年度から5年間の教育政策の財政目標を定めるもの。4月の中央教育審議会の答申は、国の財政事情に配慮し、投資額の目標は示さなかった。だが、自民党の文教族議員から「教育にかけるお金をきちんと書き込むべきだ」など“激励”の声があがり、文科省は計画原案で数値目標を織り込んだ。
一方、財務省は「財源や使途が不明」と反発。このため、文科省は増額分約7兆円の使途を急きょまとめた。
年収200万円未満の家庭の大学・短大生の授業料は免除、500万円未満は半額免除する。すべての学校施設の耐震化に約1兆円、3~5歳児までの幼稚園と保育所の無償化費用として計約7700億円を盛り込んだ。また、文科省は同計画に教職員定数の2万5000人増員を盛り込んでおり、この人件費を1750億円と試算している。
今後、このような事を起す学校教育者が出ないようにするためにも、「懲戒免職となるなど、
社会的制裁を受けている」との理由で執行猶予するべきではない。
「校内で“関係”持った」 元教え子脅迫の元校長 05/29/08(産経新聞)
元教え子の20歳代の女性に「過去の性体験を暴露する」とメールを送るなどしたとして、脅迫の罪に問われた埼玉県川口市立川口高校元校長、市川和夫被告(56)=同県上尾市仲町=の初公判が29日、さいたま地裁熊谷支部(永田誠一裁判官)で開かれた。市川被告は起訴事実を認め、即日結審した。
検察側は「文言は卑劣で態度は悪質。メールが届かないことを考えて文書を送りつける行為は、常軌を逸している。校長室からの破廉恥なメールは教育現場の信頼を揺るがした」として懲役1年6月を求刑した。
弁護側は「犯行当時は別れる決意があり、約束を守らない女性に激高したことが動機。懲戒免職となるなど、社会的制裁を受けている」と執行猶予を求めた。
最終陳述で、市川被告は「将来ある彼女は早く立ち直って幸せになってほしい」と述べた。判決は7月15日に言い渡される。
被告人質問で、市川被告は交際を続けた経緯について、「支えてきた。自立してもらいたかった」「離れていこうとすると何かあり、放っておけない気持ちになった」と述べた。また、校内で女性と関係を持ったことも明らかにした。
論告などによると、市川被告は平成14年ごろから、当時教頭として勤務していた高校の生徒だった女性と交際を開始。19年初めに女性に恋人ができ別れを切り出され、会うことを拒否されたため激怒。19年11~12月に4回にわたり、校長室から「会わないと何をするか分からない。人を殺すことは平気だ」「裸の写真を恋人に送る」と女性に電話。また、校長室の公用パソコンから「恋人に過去の性体験を暴露する」などとメールした。
横浜市大が良い大学なのか知らないが、大学の対応や体質は三流なのは間違いない。
横浜市大の学位謝礼問題、告発医師が専門外の診療科に異動 05/11/08(読売新聞)
横浜市立大医学部の学位取得を巡る謝礼授受問題で、同大コンプライアンス(法令順守)推進委員会に内部通報した医師が、神奈川県内にある病院の専門外の診療科に4月1日付で異動していたことがわかった。
同大医学部関係者は、「希望していない専門外の診療科へ異動させないようにしている。今回のようなケースは記憶にない」としている。
読売新聞の取材に対し、医師は昨年11月、嶋田紘教授(64)(3月末で医学部長を退任)の研究室で、「学位を取得した大学院生らとの間で現金の授受が行われている」と推進委に自ら通報したことを明らかにした。
その上で、「1月に異動の内示を受け、『配置転換させられそうだ』と推進委に保護を求めた。研究も途中だった。推進委は訴えに、何も対応してくれなかった」と語った。
推進委は内部通報を受け、嶋田教授や研究室の関係者への聞き取り調査を行い、謝礼の授受を確認したとする報告書を3月にまとめている。
大学の規定は、法令・倫理に反する行為に関して内部通報した者が不利益を受けないよう、保護を義務付けている。推進委メンバーの岡田公夫副学長は「通報者の保護は規定に沿って努力した。結果的に守れたかどうかは明らかにできない」と話している。
内部通報を巡っては、嶋田教授の研究室の准教授ら11人が2月、「医局内の出来事を悪意に歪曲(わいきょく)している」として、通報者の処分を求める申し入れ書を理事長と学長あてに提出していた。
横浜市大は、文部科学省に徹底した調査を求められ、元東京地検特捜部長を委員長とする学位審査対策委員会を設置。嶋田教授ら教授と准教授計16人が総額約570万円を受け取ったとする中間報告を5月2日に公表している。
横浜市大事務局の話「通報者が誰か分からないのに保護できない。人事を止めたら、逆に(通報者が)分かってしまう。人事で望まないところに行くこともある」
教え子と「卒業旅行」 わいせつ行為の中学教諭を逮捕、警視庁 05/10/08(産経新聞)
卒業旅行と称して教え子の女子中学生と2人で旅行に出かけ、わいせつな行為をしたとして、警視庁少年育成課は児童福祉法違反の疑いで、東京都台東区立中学校教諭、鈴木明容疑者(51)=足立区東綾瀬=を逮捕した。「教育者として、人間として恥ずかしい」と容疑を認めている。女子生徒は「先生に嫌われるのが怖かったので断れなかった」と話しているという。
調べでは、鈴木容疑者は昨年3月、当時勤務していた中学校の教え子だった女子生徒=当時(15)=と1泊2日の卒業旅行を計画。2人で栃木県那須町のホテルに自家用車で向かい、わいせつな行為をした疑い。
鈴木容疑者は卒業旅行を保護者に信じ込ませるため、偽の日程表まで作成。ホテルでは「親子のふりをして」と女子生徒に指示し、宿泊者名簿には「鈴木姓」を書かせていた。
台東区教育委員会によると、鈴木容疑者は今年3月から病気休暇中だという。
今年4月、女子生徒が弁護士を通じて上野署に被害を相談したことで発覚。少年育成課は、鈴木容疑者が卒業後約1年間にわたって女子生徒に関係を迫っていたとみて追及する。
前医学部長の嶋田紘教授(64)だけが悪いのか、前嶋田医学部長の前からこのようなことが
起きていたのか調べるべきだろう。また、前嶋田医学部長の力や権力に屈したのか、出世のために
院生らから謝礼を受け取ったのか知らないが、悪しき体質を自己の判断で絶ち切らせるために
謝礼を受け取った教授らに対し厳しい処分をするべきだ。親族などの学位審査にかかわった教授、
奥田研爾・前副学長(62)に対しても処分を行なうべきだ。横浜市立大医学部は常識が無い
教授が多すぎたと言う事だろう。
横浜市大謝礼授受、恐喝まがいの要求も…中間報告公表 05/03/08(読売新聞)
横浜市立大医学部(横浜市金沢区)の学位取得を巡る謝礼授受問題で、同大の学位審査対策委員会は2日、教授と准教授ら16人が大学院生らから総額約570万円を受け取ったとする調査結果(中間報告)を公表した。
院生らへの調査で、指導教授ら17人を名指しして総額約320万円を渡したとしていることが判明。このうち8人は授受を認めた16人とは別の教員で、対策委は「現金授受が広がる可能性が高い」としている。対策委は指導教授が「学位を出さないこともできる」と脅し、謝礼を求めたケースがあったことも指摘した。
対策委によると、院生らの調査は2004~06年度に学位を取得した226人に記名アンケート方式で行い、102人から回答があった。16人が「慣例」などとして指導教授や、学位審査を担当する教授らに現金や商品券を渡したことを認めた。総額計40万円を渡したケースもあった。
2人は指導教授から現金を要求され、うち1人は「学位を出さないこともできると言われた」と証言した。
学位審査にかかわった教授、准教授の調査では、61人全員から2日までに面談などで回答を得た。前医学部長の嶋田紘教授(64)は12人から計300万円で、ほかの15人は60万~4万円だった。
謝礼を渡したと院生らが名指しした17人の中に、受け取りを認めた教授らも含まれているが、少なくとも8人は「受け取っていない」と否定した。
教員と大学院生では、調査対象期間も違っており、対策委は、現金を受け取った教員がさらに増えるとみて、再調査する。
便宜供与は全員が否定しており、対策委は「慣習として受け取っており、金品授受による学位審査への影響はなかった」とした。
さらに、親族などの学位審査にかかわった教授は奥田研爾・前副学長(62)を含め3人で、「極めて不適切」と指摘した。
◇
「学位に対する社会の信頼を揺るがしかねない」――。横浜市立大の学位審査対策委員長を務めた元東京地検特捜部長の宗像紀夫弁護士は2日の記者会見で、医学部の一般常識とかけ離れた慣行を厳しく批判し、「組織全体の問題として厳粛に受け止めるべき」と悪弊に鋭い口調で切り込んだ。
宗像弁護士は、教授らが「医局の教材費などとして使った」と使途を説明しているのに、それを裏付ける領収書が一切、出されていないことについて「裏付けは一つもできない」と言い切った。
現金を渡した側の2人が、指導教授から「学位を出さないこともできる」などと要求されていたことについて、「恐喝に近い悪質なケースだ」「さらに受け取った教員がいる可能性がある。すべて詰める」と語気を強め、再調査を指示したことを明らかにした。
また、「教員に対し、大学として責任ある措置を講じるよう求める」と語った。
宗像弁護士は、経歴を買われて対策委の委員長に就任。教授らへの聞き取りにあたった弁護士5人でつくる調査部会を指揮、統括してきた。
横浜市大教授ら16人、学位取得謝礼で500万受領認める 05/02/08(読売新聞)
横浜市立大医学部(横浜市金沢区)の学位取得を巡る謝礼授受問題で、前医学部長の嶋田紘教授(64)と教授・准教授計16人が、2004年度から07年度までに総額約500万円を大学院生らから受け取っていたことを、同大の学位審査対策委員会の調査に認めていることがわかった。
対策委は2日にも調査の中間結果を公表する。嶋田教授が計300万円と突出しており、同大は5月中にも懲戒処分する方針だ。
対策委は4月4日、元東京地検特捜部長の宗像紀夫弁護士を委員長に10人で発足。文部科学省の指示に基づき04~07年度を対象に、学位審査にかかわった61人のうち、調査に応じた55人から聞き取りをしていた。
大学関係者によると、嶋田教授(今年3月末で医学部長退任)は学位取得の謝礼として、複数の大学院生らから計300万円を受け取っていたことを認めた。
このほか、別の研究室の指導教授3人が23万~15万円を受領。学位論文審査の責任者である主査は、35万~3万円の授受を認めた。主査に次ぐ副査も15万~1万円を受け取っていた。
この問題は昨年11月、内部通報を受けた同大のコンプライアンス(法令順守)推進委員会が調査を開始。嶋田教授の現金授受は確認したが、金額や他の教授らを調べず、文科省から調査の徹底を求められていた。
女子高教諭が女高生にわいせつ行為、出会い系で知り合う 04/24/08(読売新聞)
神奈川県警は24日、日大豊山女子高(東京都板橋区)の教諭で同県鎌倉市御成町、林正樹容疑者(57)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕した。
発表によると、林容疑者は2007年11月6日夕、渋谷区内のカラオケ店客室で、出会い系サイトで知り合った都内の私立高校2年の女子生徒(17)(当時高校1年)に現金1万5000円を渡し、わいせつな行為をした疑い。
林容疑者は、サイトに年齢が35歳だと偽ったうえ、「援助交際未経験や若葉マークの女の子募集。中学生、高校生に教えるのは得意です」などと書き込んでいたという。
県警は、約2年前からこうした書き込みを行っていたとみている。
林容疑者は、同高の1年生の学級担任だった。
経済協力開発機構(OECD)の国際学習到達度調査(PISA)が求める学力を意識している
のだろうが、考える力を身に付けさすことは諸刃の剣だよ。考える能力を身に付けた子供達が
大人になった時、政治家、官僚や公務員のごまかしや嘘まで見抜いてしまうよ。
厚生労働省の問題
や
社会保険庁に責任がある年金問題
と考えると国民を馬鹿にしているのが良くわかる。
新しい日本年金機構
を設立して問題は解決するような事を言っていること自体、ばかにするなと思う!
もっと国民は怒るべきだし、自民党に次回の選挙は勝てないと思わせるようなプレッシャーを
かけるべきだろう。そうすれば、社会保険庁職員の将来よりも、自民の支持率や選挙での勝利を
優先するだろうから、社会保険庁職員に責任を取らせることが出来るだろう。
考える力がつけば、知識と情報から判断するようになる。ごまかしは通じない。
2回目「全国学力テスト」、理由考えさせる出題増える 04/23/08(読売新聞)
全国の小学6年生と中学3年生を対象に22日実施された「全国学力・学習状況調査」(全国学力テスト)。昨年に引き続き2回目となった今年も、約232万人が国語、算数・数学の2科目で「知識」(A)と「活用」(B)のそれぞれ2種類のテストに挑んだ。
昨年と比較すると、思考力や表現力を試すため、子供に理由を考えて書かせる問題が数多く出題され、専門家からは「こうした試験に対応するには、少人数教育などの授業改革がより一層求められている」との声があがっている。
「活用」は、身近な生活に知識を生かす力を試すテスト。解答を選ばせる選択式は小学校の国語Bが12問中2問、算数Bでは13問中5問で、中学校でも国語Bが10問中6問、数学Bは15問中5問にとどまるなど、何らかの解答を考えて書かせる設問が多かった。
「昨年よりも書かせる量が全体的に増えた。時間内に問題を終えられなかった子供も少なくないのでは」
大手進学塾「栄光ゼミナール」もそう分析する。
典型的だったのは、小学校の算数Bで出題された米の生産額を尋ねる問題。2種類のグラフを読ませたうえ、「米の割合が60%から40%に減っているから米の生産額も減っている」という考え方が正しいかどうかと、その理由を尋ねた。
小学5年で学ぶ百分率などの「割合」はイメージがつかみにくく、算数でつまずく一因。米の生産額を導くには60%と40%を単純に比較するのではなく、全体の農業生産額にそれぞれ割合を掛けて計算しなくてはならない。
「活用」では同じように理由を書かせる問題が、小中で計7問出題された。
中学校の国語Bでも「全然」の使い方について「あとに打ち消しの否定表現がくる」という国語辞典の説明と、「『全然明るい』と言うことがある」という若者の回答が多数を占めた世論調査のグラフを見せたうえで、「全然明るい」という表現をしてもいいと思うかどうかを考えさせ、そう思う理由も答えさせた。
これらの問題は経済協力開発機構(OECD)の国際学習到達度調査(PISA)が求める学力とも通じており、大手予備校の河合塾は「国際的に通用する学力をつけさせようとする国の意図がみえる。ただ、こうした学力を身につけさせるには、きめ細かい指導が大切で、教員の定数増や少人数学級などが必要になる」と指摘している。
複数職員がゴルフや会食 文科省汚職、贈賄容疑者と 04/15/08(朝日新聞)
国立大学などの施設整備をめぐる汚職事件に関して、渡海文部科学相は15日の会見で、これまでの省内調査の結果、複数の幹部職員やOBが贈賄容疑で逮捕された建設会社顧問の倉重裕一容疑者(58)とゴルフや会食をしていたことが分かった、と明らかにした。利害関係者とのゴルフは状況によっては国家公務員倫理法に違反する行為で、渡海氏は「残念の一言に尽きる」と述べた。
調査はこれまで、課長以上(担当の文教施設企画部は課長補佐以上)の職員138人、文教施設企画部OBの8人を対象に実施。複数の職員・OBが倉重顧問とゴルフや会食で「一緒になったことがある」と認めたという。ただし、記憶のあいまいな者もいるため、同省は引き続き詳しい調査を実施する方針。詳細な人数や、倉重顧問と知り合った時期、経緯について渡海氏は「捜査がまだ進んでいる」ことを理由に、明らかにしなかった。
国家公務員の接待問題などを受けて00年に施行された国家公務員倫理法と倫理規程は、利害関係者とのゴルフや接待を原則禁じている。文部省(当時)は96年から独自の倫理規定を設け、同様の行為を禁じていたという。
文科省はまた、倉重顧問が顧問を務めるペンタビルダーズや、親会社の五洋建設が国立大学などから受注した工事について、経緯に問題がなかったか調査中で、今週中にも内容をまとめる予定。03年度以降、五洋建設は9件で約30億9千万円、ペンタ社は4件で約3億7千万円の受注があったという。
文部科学省の考え方が甘いんだよ!アメリカだって文系の場合、そう簡単に仕事など見つからない。
日本は教育費が高い。仕事が見つからないのに、無理して博士号を取得する必要なし。
大体、日本は平均的な学力を身に付けさせることには成功しているが、優秀な学生や科学者を
育てることには問題があると思う。工学部卒業者やエンジニアの報酬も低い。日本にこだわりが
ないのなら外国へ行けばよいし、日本では博士号を取得する必要もないだろう。
博士離れ深刻 競争倍率0.9倍割り込む 04/13/08(読売新聞)
世界に伍(ご)していくための高度研究・教育を担う人材を育成する「大学院博士課程」の平均競争倍率が平成19年度、0.9倍を割り込み、過去15年間で最低を記録、関西の有名国立大の中には、定員を充足するために4月に入って追加募集を実施した大学もあるなど、“博士離れ”がより深刻になっていることが12日、分かった。博士課程修了者の就職率が6割を切るなど、博士号を取得しても国内での就職が難しいことが進学を敬遠する大きな理由になっているとみられる。
文部科学省によると、全国の博士課程の入学定員に対する志願者の平均競争倍率は、3年度に開始した「大学院重点化」計画以降、上昇を続け、8年度には1.08倍を記録。15年度まで1倍を超えていたが、その後、漸減を続け、18年度には0.9倍まで低下。そして19年度は計2万3417人の入学総定員に対し、志願者は2万773人で競争倍率は0.89倍に落ち込み、5年度以降初めて0.9倍を割り込んだ。
背景には、重点化計画に伴い、各大学は博士課程の定員を拡充し、在籍者数も増加したが、博士号取得者を希望する職種が増えていないため、取得後も研究職につけないオーバードクターやポストドクターなどいわゆる“余剰博士”の問題が年々深刻化していることがある。文科省のまとめでは、19年度の博士課程修了者の就職率は58.8%、人文社会系に限れば4割を切っている。
このような就職難を反映し、奈良女子大大学院の一部の研究科では今年度、開設後初の3次募集まで実施したが、志願者は1人も現れず、入学者数は定員を大幅に割り込んでいる。
女生徒にわいせつ行為、45歳中学教諭を懲戒免…横浜市教委 04/10/08(読売新聞)
横浜市教育委員会は10日、部活動で指導していた女子生徒の体を触るなどしたとして、市立中学校の男性教諭(45)を懲戒免職処分にした。
発表によると、男性教諭は昨年7月24日から8月13日の4回にわたり、自分が顧問を務める部活動の部員だった生徒を保健相談室に呼び出し、抱きしめたり、キスをしたりしたほか、胸や下腹部を触るなどのわいせつ行為をしたという。
昨年8月、被害を告白する生徒の日記を見た両親が校長に相談したが、教諭は行為を否定。今年3月、女子生徒が、担任に相談したところ、「ウソをつくのは限界」と一転認めた。
学校側は、両親から相談を受けた後、生徒への聞き取りをせず、教諭に対する調査も行為を否定されると、打ち切っていた。市教委は教諭の処分に合わせ、校長を文書訓戒とした。教諭は「ストレスがたまっていた。心の傷を負わせ、申し訳ない」と話しているという。
北海道教員採用試験の面接用資料、事前に流出か 04/07/08(産経新聞)
平成18年9月に実施された北海道の教員採用試験で、札幌市教育委員会が作った面接官用の資料が事前に流出していた疑いのあることがわかった。市教委は事態を重視、面接官を務めた校長らへの調査を始めた。
市教委によると、この資料は「個別面接検査の実施方法について」と題する4枚の文書。評価のポイントなどが示されており、流出が事実なら採用に影響を与えた可能性があるという。
資料は北海道と札幌市の両教委が共同でまとめ、それぞれ個別に印刷した。18年8月23日の説明会で校長128人、指導主事16人に配布。9月2、3日に実施された個別面接で使われた後、回収された。
この年に道、市両教委が行った採用試験では計8094人が受験、計894人が合格している。
奥岡文夫札幌市教育長の話「面接員らを対象に引き続き調査して事実の把握に努め、厳正に対処する」
学位審査に透明性を、横浜市大の問題受け文科省が通知 03/19/08(読売新聞)
横浜市立大医学部(横浜市金沢区)の学位取得を巡る現金授受問題で、文部科学省は19日、すべての国公私立大学に、外部の審査委員を積極的に登用するなど、学位審査の透明性確保を求める通知を出した。
通知は横浜市大の問題に触れ、「学位の信頼性を損なうことにもなりかねず、極めて重大な問題だ」とし、厳正な審査体制の確立を求めた。公開の論文発表会を実施することも促した。
千葉大大学院入試で女子受験生に便宜 セクハラ行為も? 准教授ら懲戒処分 03/17/08(産経新聞)
大学院入試で不適切な出題をしたなどとして、千葉大は17日、同大大学院融合科学研究科の40代の男性准教授を停職12月、不適切な出題を見逃したなどとして同研究科の60代の男性教授を停職15日のそれぞれ懲戒処分にした。
千葉大によると、准教授は平成18年9月と19年2月に行われた大学院入試で、当時受験生だった女子大学院生の英語の出題を担当。2回目の入試に1回目の入試と同じ出題をしたほか、19年6月12日と19日の2回、この大学院生に性的関係を求める発言をした。
大学院生が昨年8月に准教授のセクハラ行為を大学に訴えたため、大学側が調査したところ入試の不適切な出題も発覚した。
教授は入試を監督する立場にありながら2回目の入試で同じ問題が出されたことを見逃し、今年1月には研究室の学生に准教授のセクハラ行為について大学側が事実確認を進めていることを話したという。
横浜市大医学部長、謝礼授受を認める 03/13/08(朝日新聞)
横浜市立大学医学部長が、医学博士の学位を取った医局員らから謝礼金を受け取っていた疑いのある問題で、嶋田紘学部長(64)は12日、大学を通じてコメントを発表し、金銭の授受を認めた。謝礼は研究報告会や懇親会用などとして医局で積み立てたが、すでに返還したとした。複数の関係者によると、返金は、昨年12月に名古屋市立大の博士号取得をめぐる汚職事件が発覚した直後に始まったという。
嶋田学部長はコメントの中で、大学院生や研究生が研究を進め、学位を取得するまでには実験試薬や参考文献の購入など多額の経費が必要だとして、「学位が取得できた時に、謝礼の意味で持ってこられた人もあり、その場合に受け取り、預かった経緯がある」と金銭の授受があったことを明らかにした。
使途については「毎年行っていた研究報告会、それに続く懇親会、学位取得に対する記念品などのために医局で積み立てた。個人として受け取ったものではない」と説明した。そのうえで、「目的がいかなるものにせよ金品の授受については誤解を受けるものと考え、医局長と相談の上、返還している」とした。
一方、複数の関係者は「学部長側が謝礼の返還を始めたのは、名古屋市立大の事件が発覚した後の12月中旬以降」と話す。
嶋田学部長や医局長経験者が複数の医局員宅などを訪れ、返金した。医局員らは、博士号を取得した後に嶋田学部長に渡した謝礼と同額の返金に応じたとされる。ここ3年間で受け取った金銭はほとんど返したという。
返金に応じた際、学部長側から「無かったことにしてくれ」「家族にも口外しないように」と口止めされた医局員もいるという。
名古屋市立大の収賄事件を受けて、横浜市立大では昨年12月、「学位取得をめぐって金品を受け取るのはあってはならないことで、地方公務員法に触れる」という内容の注意喚起を促す文書を、学長と理事長名で教授らに出していた。
嶋田学部長側の返金について、関係者は「名古屋市立大のように収賄罪に問われるのを恐れて返したのではないか」とみている。
横浜市大の論文審査、教授ら十数人にも院生から現金 03/13/08(読売新聞)
横浜市立大医学部(横浜市金沢区)の嶋田紘(ひろし)医学部長(64)の研究室で、学位取得の謝礼として現金の授受が行われていた問題で、嶋田学部長のほかに教授ら十数人が大学院生らから現金を受け取っていたことが12日、関係者の話で分かった。
同大の調査検討委員会も同様の事実を把握し、医学部全教員を対象に調べている。文部科学省は同日、事実関係の調査・報告を速やかに行い、再発防止策を講じるよう同大を指導した。
関係者によると、学位取得を巡る現金の授受は嶋田学部長が消化器病態外科(第2外科)の教授になった1992年ごろから始まったとみられているが、2000年から05年ごろにかけて、少なくとも研究室の大学院生らの論文審査で主査や副査を務めた教授ら十数人が、現金を受け取っていた。額は10万円のケースが多く、一部だけを受け取るケースもあったという。
横浜市大は05年に、理事長名で贈答の授受や饗応(きょうおう)接待を受けることを禁じる通知を教職員に出している。嶋田学部長はその後も謝礼の受け取りを続けていた。嶋田学部長は「謝礼を受け取り、預かったが、研究報告会や学位取得の記念品などのために、医局で積み立てて使い、個人として受け取っていない。しかし、金品の授受は誤解を受けるものと考え、医局長と相談の上、返還している」とのコメントを出した。
一方、文科省はこの日、横浜市大の事務局長を呼んで指導するとともに事態の説明を求めた。同省大学振興課は「現金のやりとりは論外。なぜこのようなことが起き、どう立て直すのか、しっかり対応してほしい」と話している。
横浜市大で博士号取得巡る謝礼授受、医学部長側に340万 03/12/08(読売新聞)
横浜市立大学医学部(横浜市金沢区)の学部長(63)の研究室が、医学博士の学位を取得した大学院生らから「謝礼」として現金を受け取っていたことが11日、わかった。
関係者によると、2003年以降に少なくとも十数人から計340万円を受け取ったことが確認された。現金授受は長年の慣例として続けられ、総額は千数百万円に上るとみられる。横浜市大も現金授受を把握しており、内部調査に着手した。
複数の関係者によると、大学院生ら十数人は03年から07年にかけ、医学博士の学位認定を受けた後、1人当たり10万~30万円を学部長に渡していた。大学院生らは、「30万円の謝礼を払うのが慣例と聞いたため」「謝礼を出さないと人事面で冷遇されると思った」と説明しているという。
学部長は消化器病態外科(第2外科)の教授として、大学院生らに学位論文の作成を指導。学位認定は、別の診療科の教授クラスが主査、複数の准教授クラスが副査を務め、論文審査と面接で行われている。学部長も、副査として審査にかかわるケースが多かった。
関係者によると、学部長は大学側の調査に現金を受け取ったことを認めたうえで、「現金は預かったもので、研究室での新年会や研究会などに使った。私的に使っていない。昨年末から残金は返し始めている」と話しているという。学部長は現金を研究室名義の口座で管理する一方、手元にも数百万円を置いていた。
学部長は1992年、教授に就任。学位取得の謝礼授受は、そのころから行われていたとみられる。
横浜市大は昨年11月、学位取得を巡る現金授受があったことを把握。学内に常設されている「コンプライアンス(法令順守)推進委員会」に、弁護士らの外部有識者を加え、調査を続けている。また、昨年12月には「謝礼名目の金銭授受は社会的に許されない」と理事長名で通知している。
本紙の取材に、学部長は大学事務局を通じて「今の段階ではお話しできない」としている。一方、横浜市大事務局は「今の時点で話すことはない。時期がくれば、大学としてきちんとした態度を取る」と話している。
学位取得を巡る金銭授受については、文部省(現文部科学省)が62年に「個人的な謝礼でも収賄罪が成立する」と通達している。横浜市大のような公立大学法人の教職員は、みなし公務員に当たる。
「彼のこと全部知ってるよ」校長、教え子の交際相手調査 03/10/07(朝日新聞)
教え子だった女性を脅して交際を迫ったなどとして、埼玉県川口市の市立川口高校校長、市川和夫容疑者(56)が逮捕された事件で、市川容疑者が、女性が交際している男性の住所や経歴などを調べあげ、「何があっても知らないよ」などと女性を脅していたことが県警の調べでわかった。県警は、市川容疑者が校長という立場や教育界の人脈を使い、こうした個人情報を入手したとみて調べている。
県警は9日、市立川口高校を家宅捜索し、校長室から市川容疑者が脅迫メールを送ったとされる市所有のパソコン2台などを押収した。
その後の調べで、市川容疑者が女性を脅す際、女性の交際相手の男性の名前をあげ、「(彼の)住所も経歴も全部知ってるよ。人を殺すのは平気だよ」などと電話していたことが新たにわかった。男性の家族構成も把握していたとみられるという。
脅迫メールは校長室の公用パソコンから送っていたとされる。メールは長い時はA4用紙3枚にのぼったという。脅迫文は封書で計十数通、メールは数十回に及んだという。
市川容疑者は、女性が在学中だった02年1月にみだらな行為をして以降、女性が嫌がっているにもかかわらず、計5年間にわたり関係を迫ったとされる。その一方で、06年10月にはJR上尾駅ホームの階段で、女子高校生に痴漢行為をした男を取り押さえたこともある。当時、朝日新聞の取材に「女性が恐怖心を持つような行為は許せない。私の手柄ではない。助けを求めて声をあげた生徒が偉い」などと話していた。
同市教委は9日、会見を開き、校長逮捕の不祥事を謝罪した。同校は8日の卒業式で卒業証書を授与したが、神山則幸教育長は「卒業生から校長名の削除などを要請された場合、真摯(しんし)に対応したい」と述べた。
同校の1、2年生は10日から期末試験の予定で、同日朝の全校集会で事件を説明し、生徒の様子によっては延期も検討するという。
同市教委によると、市川容疑者は77年に県立高校教諭に採用。数学と理科を教える教諭や、県教育委員会の指導主事などを務めた。
英語を知らない生徒に教えるとしても、個人差があると思う。そして英語もそんなに
甘くないぞ!
小学校での英語、先生も「英語力」に不安…英検協会調査 03/07/08(読売新聞)
新しい学習指導要領で小学5年から必修化される英語活動について、教員のうち半数以上が「自分自身の英語力向上」に関する研修が必要と考えていることが、日本英語検定協会の調査でわかった。
英検協会では「すでに総合学習の時間などで英語を扱っていても、必修化された時にきちんと教えられるか不安に思っている教員が多いようだ」としている。
調査は昨年9月、全国の公立小学校から無作為に選んだ1650校にアンケートを送付、教員520人から回答を得た(回答率31・5%)。「小学校で英語活動を教える前にどんな研修が必要か」(複数回答)という問いに対しては、「授業の進め方などの指導法」が76・6%、「自分自身の英語力の向上」が56・9%、「カリキュラムなど指導計画の立て方」が56・3%と多かった。
市区町村教育委員会などが行った研修を受けた経験がある教員は全体の57・3%だったが、このうち研修を「十分」「まあ十分」と感じた教員は計29・7%。英語力向上のために、「すでに自費で英会話学校に通ったり自宅学習したりしている」は28・6%、「今後取り組みたいと考えている」も48・4%に上った。
出会い系書き込みの学校職員、わいせつ写真1000枚所持 01/22/08(読売新聞)
インターネットの出会い系サイトに18歳未満との交際を募る書き込みをしたとして、出会い系サイト規制法違反の疑いで埼玉県警に逮捕された東京都江戸川区立小学校職員の小高茂容疑者(44)(同区南葛西)が、少女らとのわいせつ行為を写した写真1000枚以上を持ち、「この数年間にサイトで知り合った50人の女性と関係を持った」と供述していることが21日、わかった。県警は児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑でも追及する。
調べによると、小高容疑者は昨年8月、「女子小学生と中学生のための援助交際掲示板」という名称のサイトに、携帯端末から「おこづかい欲しい11~15の子いる?」などと書き込んだ疑い。出会い系サイト規制法は、18歳未満の売買春に関する書き込みを禁じている。
県警が小高容疑者の自宅を捜索したところ、少女らとのわいせつ行為の写真1000枚以上と、「今日の相手は高1だよ」などとメモしたノートが見つかった。小高容疑者は複数の出会い系サイトに同様の書き込みをしていたとみられ、県警で裏付けを進めている。
一方、県警が同法違反の非行事実で補導した少女は、埼玉県や茨城県の女子中学生4人(13~15歳)と女子高校生(16)の計5人。少女らは昨年8月、サイトに「Hありでもいいです」などと売春を持ち掛けるような書き込みをしていた疑い。うち3人は、サイトで知り合った男2人(児童買春・児童ポルノ禁止法違反などで逮捕)から1万5000~2万円を受け取り、わいせつな行為をしていた。
「教育者として情けない」 総長逮捕、揺れる東京福祉大 01/20/07(産経新聞)
大学総長が権限を悪用して総長室で女性教員にわいせつ行為を行っていた事件。「教育者として情けない」「就職が心配だ」。“総長逮捕”のニュースが駆け抜けた東京福祉大では21日、職員らが関係者からの電話応対に追われ、学生らは肩を落とした。
JR池袋駅近くの繁華街に本部がある東京福祉大は平成12年4月に創設された。社会福祉学部や教育学部などがある。年々定員を増やしていき、現在は群馬県伊勢崎市のキャンパスなどで約1500人が学んでいる。ほかに全国4カ所に専門学校や通信教育課程などがある。
逮捕された中島恒雄容疑者は総長室のある本部で仕事をすることが多かったとみられる。社会福祉学部3年の女子学生(21)は「すれ違えば向こうからあいさつしてくれるし、寛容な人だと思っていた。信じられないですね」と話す。
だが、寛容さの半面、「職員に厳しく接する姿やプライドの高い側面も垣間見られた」と学生は証言する。同大ホームページによると、中島容疑者は米ハーバード大学大学院での招聘(しょうへい)学者の経歴を持つ。
東京福祉大の教育理念も、中島容疑者がハーバード大大学院在籍時に研究開発し「他大学にない新しい効果的な教えを徹底してきた」とうたう。さらに自らの愛車にもハーバード大のロゴをはるなど、同大との関係を強調していたという。
「入学定員を伸ばすなど、学校経営に熱心な人だっただけに、裏切られた気持ちは強いです」。非常勤の男性講師(30)はいらだちを隠せない様子だった。
東京福祉大総長、強制わいせつ容疑で逮捕 警視庁 01/20/07(朝日新聞)
大学構内で女性教員の体を触ったとして、警視庁は21日、東京福祉大学(東京都豊島区)総長の中島恒雄容疑者(60)=豊島区雑司が谷1丁目=を強制わいせつの疑いで逮捕した。「全く身に覚えがない」と容疑を否認しているという。ほかにも元職員の女性3、4人から同様の被害の相談が寄せられており、同庁は余罪も調べる。
捜査1課などの調べでは、中島容疑者は昨年2月23日午後4時半~5時ごろ、豊島区東池袋4丁目の同大「学習センター」8階の総長室に女性教員(41)を仕事を理由に呼び出し、無理やりキスをしたり服の上から胸を触ったりした疑い。女性は事件直後に大学を辞めた。
ほかの女性も総長室での被害を訴えており、警視庁は中島容疑者が立場を利用してわいせつな行為を繰り返していた疑いがあるとみている。
大学側によると、東京福祉大は00年、社会福祉の単科大として開校。同大は、社会福祉士・精神保健福祉士の国家試験で多数の合格者を出しているとしている。大学のホームページによると、中島容疑者は教育関係などの著書が多数ある。
大学側は「事実を確認中で、現段階では何も答えられない」としている。
朝日新聞(2008年1月26日)より
ニセ学位 国立大医学部教授も
金沢大 三重大 昇進時、経歴に使用
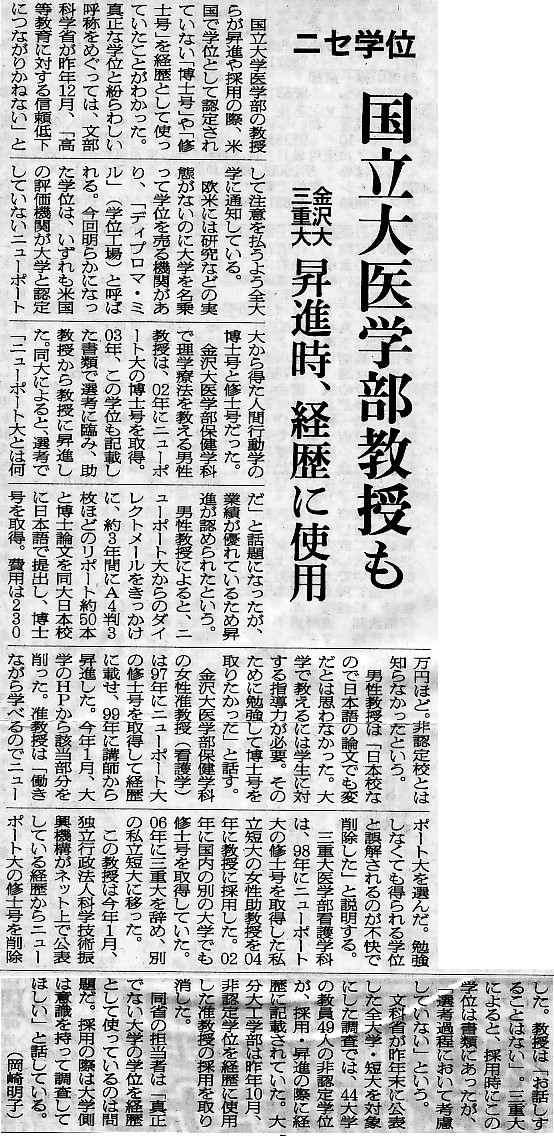
朝日新聞(2008年1月6日)より
ニセモノ社会 5
「学位」金で売ります
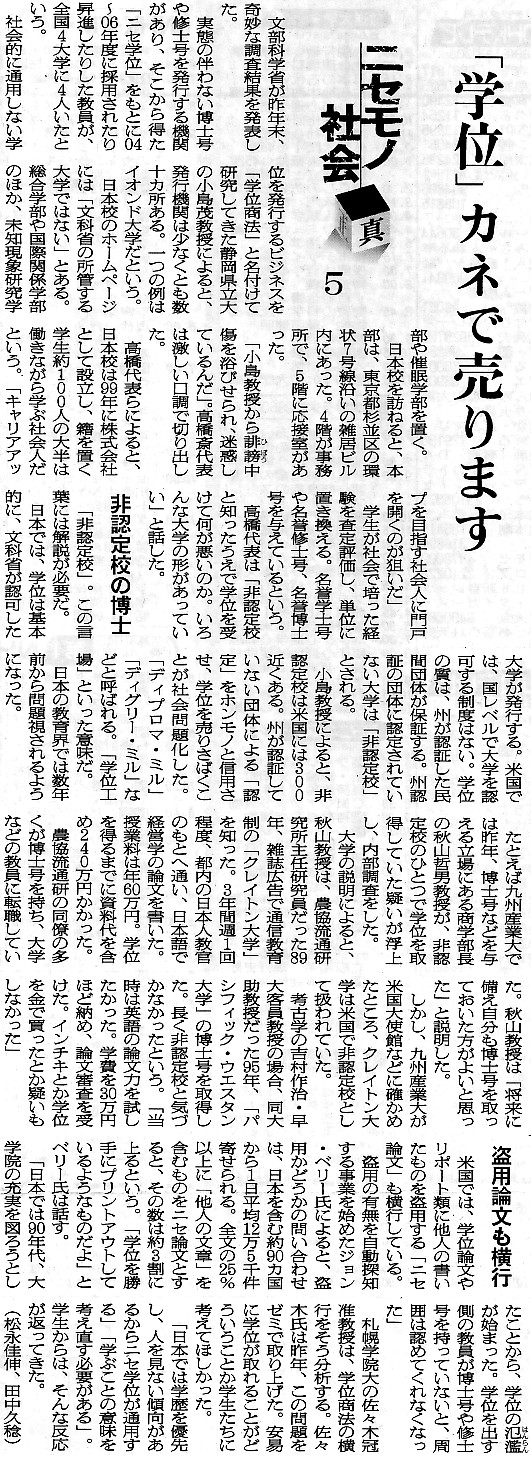
朝日新聞(2008年1月11日)より
架空給料9800万円横領容疑
島根の学校法人 元理事長ら5人逮捕
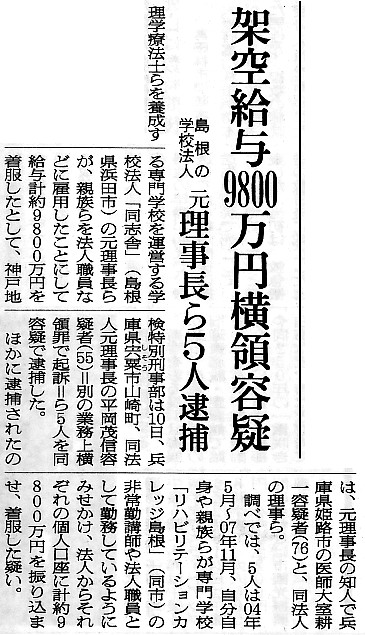
英語教育や国際化と言っても、日本の対応は遅いし、表面的に
言っているように思える。
「帰国子女」の体験も個々により違うであろう。彼女が言っていることは
外国生活をしたことがあるので、経験がない人よりは理解が出来る。
国際化や多様化を受け入れることは簡単ではない。ただ、自己表現が
出来る子供が増えれば、受け入れは簡単になるだろう。会う人に合わせて
自己表現を変える人もいる。出来ない人は悩む。いろいろな経験を
していない人達は新しい環境に対応できない傾向があり、運悪く新しい
環境に放り出された場合、問題を抱えるだろう。何が幸せか、不幸か、
人生が終わりに近づくまでわからない。本人の意見と周りの意見が違う
場合もある。日本の国際化はテレビで言われているほど進んでいないと思う。
文部科学省は学力テストの結果だけでなく、もっと広い視野で教育について
考えてほしい。
朝日新聞(2008年1月11日)より
「帰国子女」を特別視やめて
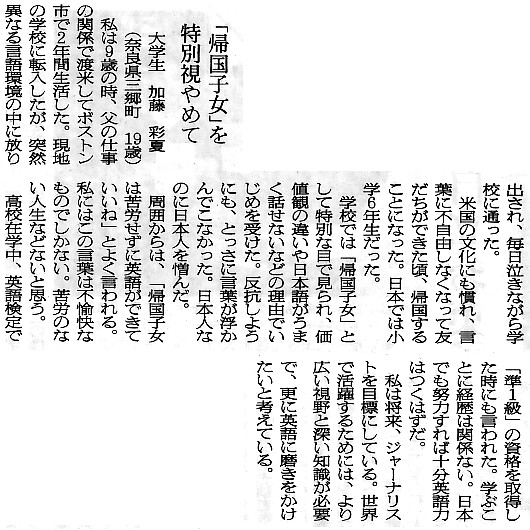
採用・昇進にニセ学位、全国で大学教員48人が利用 12/27/07(読売新聞)
大学を名乗る海外の団体から授与された博士号などのニセの学位を、大学の採用や昇進の際に利用した大学教員が全国で48人に上ることが27日、文部科学省の調査でわかった。
同省では、「大学の信頼低下につながる」として、各大学に厳正な対応を求めた。
調査は、国公私立すべての大学を対象に、今年7~9月に実施。アメリカ、中国、イギリス、オーストラリアに所在地を設定しているが、それぞれの国から大学と認定されていない団体から授与された“学位”の実態について調べた。
その結果、こうしたニセ学位を、採用や昇進の際の審査書類に書いていた大学教員は43校48人(国立は7校8人)。このうち、ニセ学位を持っていることが直接的な判断材料となり採用・昇進につながった教員も4校4人いた。多くは、大学の冊子やホームページにニセ学位を記載していた。
同省などによると、こうした団体は、いずれも教育活動の実態がなく、学位を数十万円程度で売買していることから、「ディグリーミル(学位工場)」と呼ばれている。博士号が取得しにくい文系の教授などが購入するケースも少なくないという。
国内でも、大分大工学部が今年10月、非公認のアメリカの大学の修士号を申請して採用された准教授の雇用契約を取り消したほか、早稲田大の元教授が、今春の定年退職まで同大の教員データベースに、アメリカの実態不明の大学の博士号を経歴として記載していた。
9年制一貫校を制度化だけで目標を見失うな!
ゆとり教育は失敗した。文部科学省の責任だ。反省すべきだ!
だいたい、タウンミーティングでやらせを考える省の体質に問題があった。
キャリアの考え方や方法に問題があったのだろう!
外国人と話す機会があるなら、彼らが子供の時にどのような考え方を学んだのか、
教師の発言や教えることに対して、生徒はどのように受け取っていたのか、
大人になってから海外の教育を見てどのように思うのか、このような点を文部科学省
職員は知るべきである。ただ自問自答する能力を子供達が身に付けた場合、今の日本の
茶番劇(政治)に対して批判的になったり、嘘やごまかしが通用しなくなることになる。
仕方が無いで済ませる日本人でなくなるだろう。
厚生労働省の問題
や
社保庁の問題
を考えても、この程度では済まないだろう。
山陰中央新報(2007年12月13日)より
再生会議の報告書原案
9年制一貫校を制度化 小学校の英語教育実施も
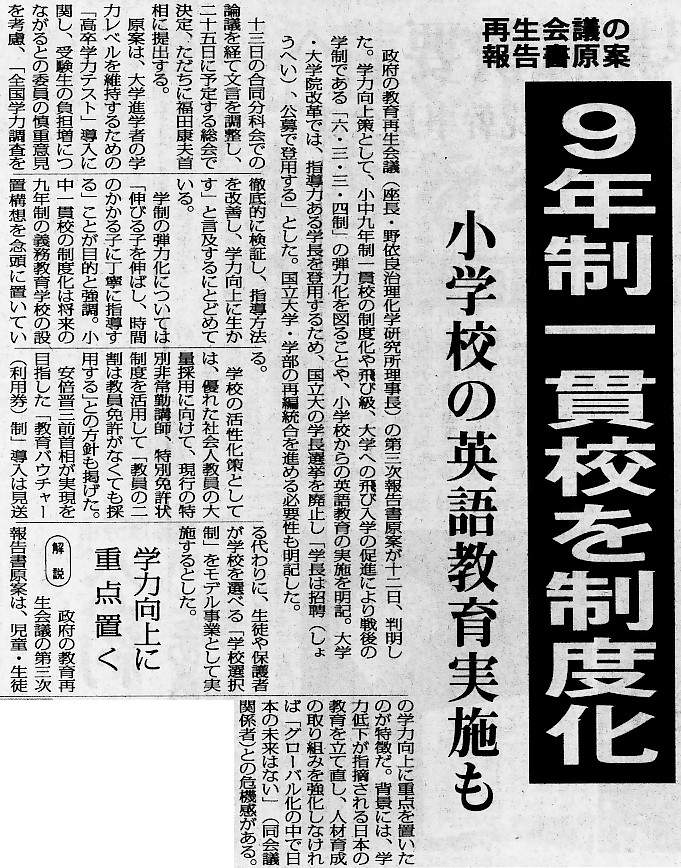
インチキタウンミーティングに教育者が関わっていた
ことでも日本のダメ教育が理解できる。タウンミーティング質問案作成を文科省の広報室長が了承した
ことを考えても、ダメ教育の産物である国民など騙すことなど簡単と考えたのだろう。国がダメ教育を
指導しているのだから、良い結果が出るはずなど無い!
ゆとり教育が原因と考えているようだが、教師の能力も問題であると強く感じる。
日本では教師の問題を取り上げない。組合の圧力や組合が支援している政治家の力が関係しているのだろうか?
教師の不祥事を見ても良くわかる。子供を教育する教師の人格に問題がある。学校は塾ではない。
人格に問題があれば、生徒に教育する立場に残らせるべきではない。
「学力テストの成績に応じた学校予算配分、足立区が廃止へ」
のケースを考えても考え方が間違っていることはわかる。区立小学校校長らが不正を主導した。
競争する環境にさらされると校長自ら、不正に手を染める。自分で考える力がこの校長にあるなら、
不正を主導する前に、やめたはずである。校長になるような人物がこのようなことで、
生徒達や教員に対してリーダーシップを取れるのか???生徒が自分で考える能力があるなら、
このような校長は格下げされるべきだと考えるだろう。自己のコントロールも出来ない、
モラルも守れない人物が校長になる。誰が評価し、責任を取るのか?
なぜ、このような人物が校長になれる文科省の作った制度に疑問を抱くだろう。
昔の日本のように、先生には服従する環境ではない。リーダーシップ、判断力や説明能力が要求される。
しかし、このような能力を持った人物が上に立っているだろうか??違うと思う。
授業時間を増やすことやOECD学力調査対策を単純に考える文科省から変える必要がある。
誰が変えるのか?変われるのか?ここから始める必要があると思う。
中国新聞(2007年12月5日)より
「世界トップ」遠い再浮上 OECD学力調査
文科省言い訳連発 授業増の効果不透明
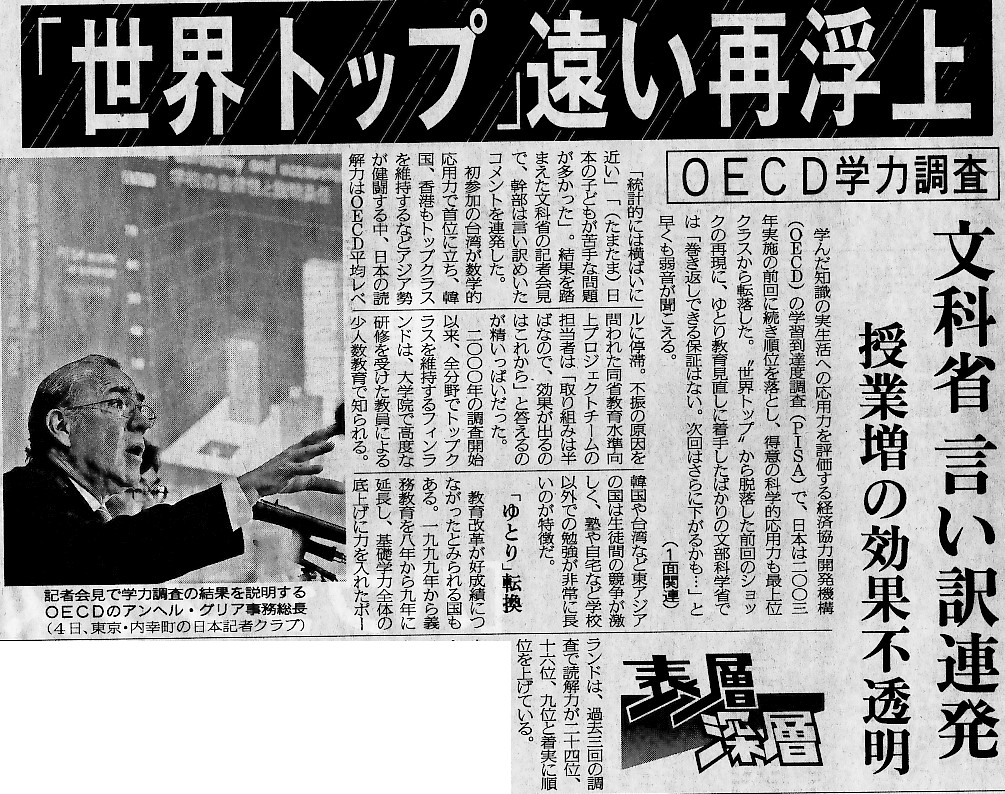
中国新聞(2007年12月5日)より
OECD学力調査
転落の兆候初回から 読解力すでに低迷
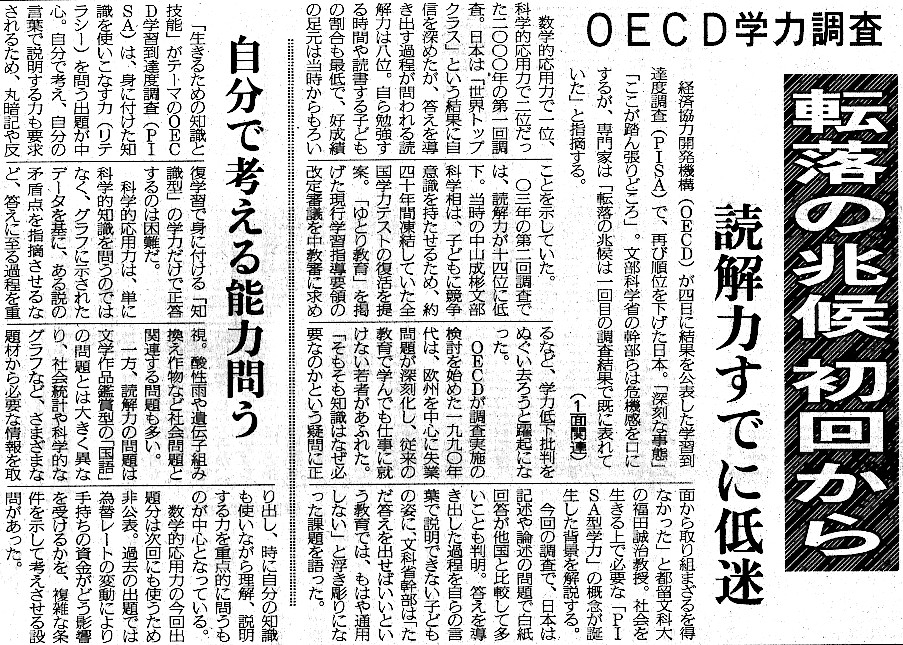
「ウチのしつけに口出すな!」教諭に暴行の父親逮捕 12/04/07(産経新聞)
中学2年の息子の生活態度をめぐり学校側と面談中、激高して教諭につかみかかり、けがをさせたとして、埼玉県警朝霞署は8日、公務執行妨害と傷害の疑いで、同県志木市中宗岡、建築業、富永慎容疑者(36)を逮捕した。
調べでは、富永容疑者は7日午後4時45分ごろ、志木市立宗岡第二中学校の相談室で、サッカー部顧問の男性教諭(48)らと面談中、「うちのしつけに口を出すな」と言って教諭の襟首をつかむなどして、顔に軽傷を負わせた疑い。
富永容疑者の息子(14)はサッカー部に所属。部員間のトラブルなどが原因で休部処分になっていたという。
富永容疑者はテーブルを乗り越えて教諭に詰め寄った。教諭が7日夜、朝霞署に被害届を出した。
「子供が考える時間を」「授業方法の改善を」 OECDテストで求められる対策 12/04/07(産経新聞)
経済協力開発機構(OECD)が4日に結果を公表した生徒の国際学習到達度調査(PISA)で、日本は再び順位を下げた。渡海紀三朗文部科学相も「ゆとり教育」の失敗を挙げた。学習への意欲、関心とも最低レベルで現行学習指導要領で重視されている「生きる力」も育っていないことが浮き彫りに。調査を実施したOECDのアンヘル・グリア事務総長は、日本は応用や活用に必要な能力を育てるよう示唆する。いずれにしても早急な対策が求められている。
■授業時間回復を
なぜ、日本の学力は下げ止まらないのか。
渡海文科相は授業時間、学習内容削減を進めた現行の学習指導要領に課題があったと言及しているが、東京理科大の沢田利夫教授(日本数学教育学会名誉会長)も「調査のたびに落ちていくのは、ゆとり教育で授業時間が減った影響であることが明らかだ。期間が長引くほどさらに低下するだろう」と、指摘する。
現行の指導要領の年間授業時間は小学校6年生で945時間、中学3年生で980時間。最も多かった時期は小6(昭和36~54年度)で1085時間、中3(47~55年度)は1155時間あった。算数は当時週6時間だったが、現在は約4時間、数学も4時間から3時間に減っている。
日本より授業時間が少ないフィンランドが前回に続き、最高位を獲得しているとはいえ、現状では授業時間の回復しか打つ手がないのが現状だ。
■方法、内容も大切
理科教育に詳しい東大の兵藤俊夫教授は「授業時間不足で応用も学んでいなかった。活用力を上げるには、教員が社会や生活上の疑問を提示するなど授業方法を改善しないといけない」とみる。
また、前々回調査(00年)の高1は、小1から理科を学んでいたが、前回の高1から小学1、2年は生活科になったことを指摘。「科学的な思考を習得するには理科を小1から学ぶべきだ」としている。
平成23年度から施行される指導要領では、中学の選択科目が事実上廃止されるほか、数学で2次方程式の解の公式が復活する。小学校では台形の面積の公式が5年に復活、確率の一部が中学から6年へ移るなど、学習内容が増える。
早稲田大の中島博名誉教授は、「大切なのは子供がじっくり答えを導き出す時間的な余裕をつくってあげることだ」として、内容の増加を疑問視する。
■生きる力伸びず
同時に行われたアンケートで、生徒の科学への意欲や関心、興味は参加国中最低レベルで、前回および現行指導要領で大きなテーマだった「生きる力」の具体的指標が高まっていないことが明らかになった。
今回の調査で、日本は記述や論述の問題で白紙回答が他国と比較しても多く、答えを導き出した過程を自らの言葉で説明できない生徒が多かった。
これまでの「丸暗記」型では「生きる力」は得られず、4日に都内で記者会見したグリア事務総長も「単に知識の記憶だけなら、多くの国の労働市場から消えつつある種類の仕事にしか適さない人材育成となっている」と苦言を呈した。
朝日新聞(2007年11月10日)より
少女撮影の元小学教頭
セーラー服常備 連日声かけ
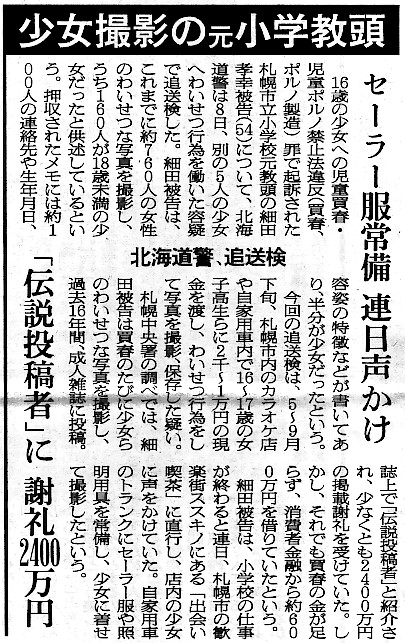
独協医大科研費不正…32人が関与、プール金1億7千万 11/09/07(読売新聞)
栃木県壬生(みぶ)町の独協医大で文部科学省の科学研究費補助金(科研費)などが不正にプールされていた問題で、同大は9日、記者会見し、内部調査結果と関係者の処分を発表した。
不正に関与した教授、准教授ら研究者は計32人に上り、プール金の総額は約1億7200万円。寺野彰学長と副学長2人、事務局長、研究者23人をいずれも減給1か月(10分の1)の懲戒処分としたほか、4人を学長注意とした。寺野学長は給与の自主返納2か月(同)も行う。また、不正に関与した残る5人の研究者のうち4人はすでに退職しており、1人は諭旨退職処分となっている。
プール金は、今年4月に会計検査院の指摘をきっかけに発覚。当初は帳簿や領収書が残る2002年度以降について調査し、約1億円の不正が判明したが、その後、会計検査院の指示などを受けて1998年度までさかのぼって調査した結果、不正額は約1・7倍にふくらんだ。このうち1億980万円は、10月10日付で諭旨退職となった臨床部門の男性准教授によるものだったという。
この准教授を含め、処分された研究者らは、県内の理化学薬品販売業者に架空の発注をし、科研費の余剰金を国に返還せず、プールしていた。
「学校側、自分で考える習慣乏しい」なぜ、今まで学校や文部科学省はそのように考えなかったのか??
考えられない人間になるような教育しかしてこなかった。それを理解せずにゆとり教育(英語では
no-stress free educationと訳しているのを聞いてビックリした。)を推し進めた。
ストレスを感じない教育がゆとり教育であるのなら、文部科学省は大失敗をしたと思う。
考える力とは
守屋元次官の接待問題や「とわだ」の航泊日誌(航海日誌)破棄
について本当に防衛省が信用できる組織であるのか疑問に思い、考える力などである。
ウソとわかるような言い訳しか出来ない防衛省職員自体、ダメ教育の産物だろう。
守屋前次官の問題もダメ教育の産物。大学を卒業する段階でもモラルが身に付かない学校教育に問題がある。
企業の不祥事
を考えると、ゆとり教育の失敗だけでなく、モラルが身に付かない日本のダメ教育を理解することが
重要である。
インチキタウンミーティングに教育者が関わっていた
ことでも日本のダメ教育が理解できる。タウンミーティング質問案作成を文科省の広報室長が了承した
ことを考えても、ダメ教育の産物である国民など騙すことなど簡単と考えたのだろう。国がダメ教育を
指導しているのだから、良い結果が出るはずなど無い!
「学校側、自分で考える習慣乏しい」教育問題で町村長官 10/31/07(産経新聞)
町村官房長官は31日の記者会見で、中央教育審議会の部会が小中学校の授業時間の増加を大筋で了承したことについて「ゆとり教育は間違っていたとは思わない。ゆとり即ゆるみ、即授業時間の減少ということが、結果として学力低下を生んだ。改めてしっかり基礎基本はやるということを徹底しないといけない」と一定の理解を示した。
一方、総合学習の時間が削られる見通しになったことには疑問を呈し、「教科横断的テーマを考えてみようということなのに、学校現場では自分の頭で考える習慣が誠に乏しく、やり方が分からない」「そういう認識が中教審は足りない」など、学校側や中教審を批判。「官房長官というより、元文部大臣の個人的感想を述べた。ちょっと言い過ぎたかもしれない」と語った。
女子生徒にわいせつ行為 高校教師ら11人を懲戒免職 10/31/07(産経新聞)
北海道教育委員会は31日、女子生徒にわいせつ行為をした札幌市の高校教諭(32)と渡島管内の中学教諭(35)を懲戒免職にするなど計11人を懲戒処分にした。
道教委によると、札幌市の高校教諭は7月下旬から9月上旬にかけ3年生の女子生徒と6、7回にわたり教諭の自宅などで性的関係を持った。生徒の様子を不審に思った母親が学校に相談して発覚した。教諭は妻帯者だった。
道教委は生徒らに対するわいせつ行為は生徒が同意していたかどうかにかかわらず、免職にすると定めている。
渡島管内の中学教諭は9月30日夜、顧問をしていた部活動に所属する女子生徒の自宅を、両親が不在であることを知って訪れ、キスをしたり胸を触るなどした。生徒が友人に相談したことで発覚。教諭は「生徒が1人では不安でないかと思った」と話したという。
このほか、女子生徒と自らの性体験などについてメールをやりとりしたり、自宅に3人の女子生徒を呼んでわいせつなDVDのパッケージを見せたりした帯広市の中学教諭(30)を停職6カ月にした。
NOVA余波で講師来ず、小中高で授業打ち切り 10/31/07(読売新聞)
英会話学校最大手の「NOVA」(大阪市)が会社更生法の適用を申請したことで、同社と外国語指導助手(ALT)の派遣契約を結んでいる学校で授業がストップする事態になっている。
同社から講師の派遣を受けていたのは、東京都世田谷区や大阪市など全国11の自治体。各教育委員会はCDで授業をしたり、他の英会話学校に協力を要請したりするなど大わらわで、突然の破綻(はたん)劇に困惑している。
「歌やゲームを通じて、生の英語に触れることができ、児童も授業を楽しみにしていたのに……」。世田谷区立用賀小の内藤信校長は残念そうに話す。
同区教委は、2006年度からNOVAに区立小64校への外国人講師派遣を委託。講師6人が各校を巡回して授業を行い、今年度は年間約2000万円の予算を計上した。
区教委では、同社で講師給与の未払いが表面化したことを受け、今月23日に契約の打ち切りを決定。同社側と条件などを話し合っているさなかの26日、同社が会社更生法の適用を申請した。その直後、担当者から「私では決められないので、保全管理人に聞いてほしい」と連絡があったという。
現在、別の業者に講師の派遣を打診しているが、年度途中とあってメドは立っていない。区教委では、「授業はしばらく中止せざるを得ない。NOVAへの対応は弁護士と相談している」と話す。
区立小中学校計58校で28人の講師が授業を行っていた品川区教委も今月、同社に打ち切りを通告した。
同区教委では、当面はCDの音声を使ったり、地域のボランティアに協力してもらったりして代替授業を行い、来年初めから外国人講師による授業を再開したい考え。担当者は「単価が安く、講師の質も良かったのに、NOVA本体の問題が波及してくるとは」と迷惑顔だ。
都内ではこのほか、目黒区と府中市が同社から派遣を受けていた。米国人男性講師を受け入れていた目黒区立第一中の佐伯英徳校長は、「講師は『給料が出ない』と話していたが、最後まで熱心に授業に取り組んでくれた。これからも同じ講師に来てもらいたい」と話す。
市立小中高校など計335校で講師20人を受け入れていた大阪市教委。今月22日から一部の講師が来なくなり、24日には11人が欠勤した。各校では別の授業に振り替えるなどの対応に追われたといい、「契約解除するしかない」と話す。
同様にNOVAからの講師派遣がストップした栃木県足利市や愛媛県松前町でも対応を検討中だ。
少女わいせつ写真、雑誌に投稿の元教頭起訴 10/19/07(読売新聞)
札幌市立星置東小学校元教頭の細田孝幸容疑者(54)(札幌市手稲区富丘)による児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件で、細田容疑者が、わいせつ画像などの投稿で10年間に約2300万円もの収入を得ていたことが、道警札幌中央署の調べで分かった。札幌地検は19日、細田容疑者を同法違反(児童買春、児童ポルノ製造)の罪で札幌地裁に起訴した。道警は少なくとも約40人の少女が被害にあったとみて、裏付けが取れ次第、追送検する方針。
道警の調べで、細田容疑者には総額約1600万円の借金があったことが判明した。このうち約600万円は多数の女性と交際するために借りていた。押収した手帳から、細田容疑者が約60人の女性と交際していたことが分かったが、うち約40人が18歳未満とみている。
起訴状などによると、細田容疑者は9月21日午後9時ごろ、自分の乗用車の中で、市内の少女(16)に現金6000円を渡し、体を触った。その後、車内で少女にわいせつなポーズをさせてデジタルカメラで撮影した。
札幌市教委は今月10日、細田容疑者を懲戒免職処分にした。
県立高校非常勤講師ら4人を逮捕、恐喝などの容疑 千葉 10/13/07(産経新聞)
千葉県警捜査1課と千葉西署は13日、会社員から現金300万円を脅し取ろうとしたとして、県立大原高校の保健体育の非常勤講師石橋貴裕容疑者(22)=同県九十九里町=を恐喝未遂容疑で逮捕したと発表した。
共犯容疑で逮捕されたのは、とび職内山直記容疑者(23)と無職湯浅隼人容疑者(22)。内山容疑者ら2人と、無職吉井清明容疑者(23)の計3人は恐喝の疑いも持たれている。
調べでは、内山容疑者ら3人は11日午後11時25分ごろ、千葉市緑区のコンビニエンスストアの駐車場で、知り合いの女性(16)と関係を持った同県市原市の男性会社員(36)に「家族にばらすぞ。おまえの家も分かる」と言って現金7万円と携帯電話を脅し取った疑い。その際に謝罪金名目で300万円を要求し、翌12日午後8時20分ごろ、石橋容疑者らが脅し取ろうとした疑い。
研究論文のデータを改ざん 鹿児島大病院の男性助教 10/11/07(産経新聞)
鹿児島大は11日、医学部・歯学部付属病院に勤務する男性助教(38)が、主執筆者として米国の専門誌に発表した論文に実験データの改ざんがあったと発表した。助教は改ざんを認めている。
鹿児島大は調査委員会を設置し、不正の詳しい経緯や、共著者6人の関与、文部科学省などから受けている研究費の使途などを調べる。
問題の論文は突発性肺線維症の発生メカニズムに関するもので「アメリカン・ジャーナル・オブ・パソロジー」(米国病理学会雑誌)の2006年3月号に掲載された。鹿児島大などによると、病理学の分野で世界的な権威がある雑誌だという。
大学への助教の説明によると、血液中のタンパク質量についての実験データのうち、思うような結果が出なかった5人分について、既に取得した2人分のデータを基に、仮説に合うよう改ざんしていた。
論文に同じ図が複数掲載されていたことなどを不審に思った読者から問い合わせを受けて、雑誌編集部が今年9月、大学側に調査を依頼し、不正が発覚した。雑誌側は11月号に助教の名前で、論文取り下げの記事を掲載するという。
「女性教員は以前から校長に悩み事を相談するなどしていた。」
校長が好意を抱かれていると勘違いしたのか、女性教員に興味を持っていたからやさしくしたのか、
女性教員が曖昧なシグナルの出したのか、真実はわからない。しかし、校長が言葉で女性教員が好意を
持っているのか、キスしても良いのか確認すれば、このような結末はなかったであろう。
校長である自覚が足りなかったかもしれない。市教委の基準「セクハラ行為は停職または減給処分」は
改正した方が良い。権限が強い人にはもっと厳しい処分が必要!
女性教員にセクハラで校長を諭旨免職 大阪市教委 10/11/07(産経新聞)
部下の女性教員にセクシュアルハラスメント(性的いやがらせ)行為をしたとして、大阪市教委は10日、鶴見区の市立小学校の男性校長(58)を諭旨免職処分にした。
市教委によると、校長は9月11日午後10時半すぎに阿倍野区で、ビル建物の陰で女性教員を抱き寄せ、キスをするなどした。校長はこの日、メールで部下の女性教員を呼び出し、同区内の居酒屋で飲酒を伴う食事をし、帰宅途中にセクハラ行為に及んだという。
翌日、女性教員の様子がおかしいため、同僚教員が聞いたところ、セクハラ行為が発覚した。
女性教員は以前から校長に悩み事を相談するなどしていた。校長は事実関係を認めたうえで「軽率な行為だった」と話しているという。
市教委の基準では、セクハラ行為は停職または減給処分だが、今回は男性が校長という役職だったことを重くみて諭旨免職処分とした。
女性600人のわいせつ画像投稿で報酬、小学教頭を逮捕 10/01/07(読売新聞)
16歳の少女に報酬を支払ってみだらな行為をしたとして、札幌中央署は1日、札幌市立星置東小学校教頭、細田孝幸容疑者(54)(札幌市手稲区富丘)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕した。
細田容疑者は写真雑誌の投稿の常連として知られ、「知り合った女性約600人のわいせつな写真や映像を撮り、複数の写真雑誌に投稿していた」と供述。同署は、細田容疑者が、投稿で7年間に計約1800万円の報酬を得ていたとみて余罪を追及している。
調べによると、細田容疑者は9月21日午後9時ごろ、札幌市中央区の駐車場に止めた乗用車内で、市内の無職少女(16)に現金6000円を渡し、みだらな行為をした疑い。2人は数日前、市内の出会い系カフェと呼ばれる会員制の飲食店で知り合った。
細田容疑者は少女の裸などもカメラ撮影しており、同署は小学校などを捜索。自宅と車からわいせつなDVD334枚や264人分の写真、セーラー服や手錠、撮影機材などを押収した。画像の中には未成年者のものも含まれているとみられ、同署で分析している。
細田容疑者は、2000年からの7年間、毎日のように市内の繁華街に繰り出しては、知り合った女性のわいせつな写真や映像を撮るなどしていた。そのほとんどを複数の写真雑誌に投稿して報酬を得ていたという。
今年6月ごろに発表された写真雑誌では、投稿者の常連として、雑誌の編集者と誌上対談し、投稿を始めた理由として「投稿料がもらえるのでいいと思った。素人の写真を撮ってみようと思った」などと話していた。逮捕容疑について、細田容疑者は「いかがわしいことについては覚えていない」と供述している。
星置東小の坂本芳明校長は「勤務態度に問題はなく驚いている。子供を指導し、職員も監督する立場にありながら、こうした不祥事は申し訳ない。おわびしたい」とコメントした。
沖縄の人の苦しみは体験した人達でなければわからないだろう!自分は沖縄に行った事もない。
ただ、日本や大人は子供の時に思ったような「善や正義」では決してないと感じる。
沖縄の苦しみや辛い経験は、テレビやドキュメントで見るまで知らなかった。少なくとも
学校教育を通して沖縄の苦しみを知る機会などなかった。
今は、インターネットが普及し、多くの若者や一部の高齢者が安いコストで簡単に情報を
発信できるようになった。高校日本史の教科書検定問題に対して異論のある人達は、もっと
インターネットを通じて沖縄での事実をアピールしていけばよい。日本語だけでなく英語での
アピールは良いだろう。外国人が日本に関して検索した時に、沖縄の人達や過去について知る
良い機会にもなる。継続的な活動が実る場合もある。戦争体験者は少なくなっている。どうしても
沖縄の経験を伝えたいと思うのであれば、何かしらの形(メディア等)で残し、インターネット
等で伝えていくべきだろう。日本政府に高校日本史の教科書に数行の文章を刻ませるのも重要
なのだろうが、もっと多くの情報を発信することも興味も持った人達には助けになるだろう。
集団自決に軍関与、沖縄県民11万人余参加で決議採択 09/30/07(読売新聞)
沖縄戦の集団自決に日本軍の強制があったとする表現を修正させた検定問題を巡り、検定意見撤回を求める超党派の沖縄県民大会が29日、同県宜野湾市の宜野湾海浜公園を主会場に開かれた。
同時開催の石垣、宮古島両市会場合わせて約11万6000人(主催者発表)が参加した。同県では、米兵による少女暴行事件を発端に約8万5000人(同)が集結し、日米地位協定の見直しを求めた1995年の県民総決起大会を上回る規模で、「島ぐるみ」の集会となった。
大会では、「集団自決が日本軍の関与なしに起こり得なかったことを伝えるのは我々の責務」とする決議を採択した。決議文は10月中旬、福田首相、渡海文部科学相、全国会議員に提出する。
大会で、仲井真弘多知事は「記述を削除、修正するため県民を納得させるだけの検証を行ったのか」と遺憾の意を表明した。
渡嘉敷島(渡嘉敷村)で起きた集団自決を生き延びた村教育委員長の吉川嘉勝さん(68)は「米軍の上陸後、雑木林の中で両親や5人の兄弟とともに日本軍から配られた手榴(しゅりゅう)弾で自決しようとしたが、爆発しなかった」として、軍の関与があったとの認識を強調した。
県民大会は、県議会、県遺族連合会など22団体が計画し、県と県内41全市町村が参加した。
検定意見では、近年になり日本軍の強制があったことを否定する学説が出ていることや、当時、沖縄の守備にあたっていた特攻艇部隊の隊長らが「集団自決を命じたと記述された書籍で名誉を傷つけられた」として出版社などに賠償を求める裁判を起こしたことなどから、強制の記述について教科書会社に修正を求めた。
文部科学省教科書課は「規則上、検定意見撤回は難しい。訂正申請はできるが、わかりにくい説明を補足するのが一般的だ」との見解を示している。ただ、1981年度の検定で削除された「沖縄戦での日本軍による住民殺害」の記述は、県議会などによる抗議行動を受けて復活している。
本当に文部科学省などの科学研究費補助金の審査は甘い!私的流用でなく、とにかく
研究費に使えば問題ないのか!そうだとすれば、どのような基準で文部科学省は助成金
を出すのか!ウソでもとにかく理由がまともであれば、助成金を出すのか!どのような
書類を提出させるのか??
総額約1億円の不正に関与した二十数人の教授や准教授らに対してどのような処分を行なうのか?
社会保険庁職員や地方公務員のように
返還すれば問題ないのか?
文部科学省はしっかりしろ!!
独協医大の科研費不正プール、教授ら二十数人関与か 09/21/07(読売新聞)
栃木県壬生町の独協医大(寺野彰学長)で、文部科学省などの科学研究費補助金(科研費)が不正にプールされていた問題で、関与した教員は、教授や准教授ら二十数人に上ることが20日、わかった。
プールするために行った架空発注の相手先は、同県内の理化学薬品販売業者1社で、担当者が余剰金を口座で管理するなどしていた。
プール金は今年4月、臨床医学部門の男性准教授の不正経理について会計検査院から指摘を受けて発覚した。同大は内部調査委員会を設置し、帳簿や領収書が残る2002年以降、約800人の全教員を対象に調査を行ったところ、科研費の助成は約70人が受けており、うち二十数人で総額約1億円の不正が判明した。
同大には、文科省と厚生労働省から毎年度、計2億円程度の科研費が配分されているが、架空発注を受けた業者の担当者は、領収書や伝票を作成し、国に返還すべき余剰金を「預かり金」として口座で管理していた。
現在、口座に残高があるのは、この准教授の約3400万円だけで、ほかの教員は「翌年度の研究費に使った」などと話しているという。同大は5月、この業者との取引を無期限で停止した。担当者はすでに死亡しているという。
記者会見した徳留省悟・副学長は「教員らの話と領収書類がおおむね一致しており、私的流用はない。教員同士や大学の組織ぐるみでの不正ではなかった」と説明している。調査委は10月中に結論を出し、会計検査院や文科省などに報告。補助金を返還し、教員らを処分する。
「学力テストの成績に応じた学校予算配分、足立区が廃止へ」
足立区教育委員会は何を考えているのか理解できない。教諭や教育関係者が
規則を守ることの大切さを率先して示すべきなのに、一部の学校で出来なかった。
だから学力テストの成績に応じた学校予算配分を廃止する。安易な考えだ。このような
対応しか出来ない足立区教育委員会だから、教諭や教育関係者が不正を行ったのであろう。
世の中、競争や実績による評価は存在する。そして公正や秩序を保つために規則や決め事がある。
決め事が守れないから、決め事の原因を排除する。安易な解決策である。社会で出れば、
競争や評価の存在と向き合わなければならない。教諭や学校教育者達が適切に対応できない。
このような人間が人格形成途中の生徒にまともに教育できるのか。自分をコントロールできないのに
生徒にはセルフコントロール(自己抑制)と言って、生徒は納得するのか!
学校崩壊や家庭の教育問題も存在するだろう!しかし、教諭や学校関係者の質の問題も存在する
のではないのか!!!足立区教育委員会は足立区だけの問題と考えず、もっと考えて対応するべきだ!
このような教育委員会や教育者達に何を期待すればよいのか!このような体質だから問題が
悪化するのではないのか!文部科学省にも問題があると思うので、適切な対応が出来るのか
疑問であるが、文部科学省もしっかりしろ!!!!!!!!!!!
学力テストの成績に応じた学校予算配分、足立区が廃止へ 09/20/07(読売新聞)
東京都足立区の区立小学校で起きた学力調査(テスト)の不正問題を受け、区教育委員会は来年度から、学力テストの成績の伸び率に応じて学校予算を配分する制度を廃止する方針を固めた。
成績を予算に反映させることが過度の競争意識をあおり、今回のような不正を招きかねないと判断した。
廃止されるのは、区立小中学校の予算の一部(今年度約2億6000万円)について、前年度の学力テスト結果の伸び率などの基準を反映して配分する制度で、今年度から始まった。
昨秋、区教委は学力テストの結果で学校を4段階にランク分けして予算を配分する方針を表明。その後、批判を浴びて撤回したが、成績の伸び率については配分の際に反映させていた。
学力テストを巡っては、今年7月、区立小学校校長らが区の学力テスト(昨年4月実施)で児童に正解を誘導するなどの不正を行ったことが発覚。都の学力テスト(昨年1月と今年1月実施)でも同様の不正があったことが判明している。
区教委では現在、学力調査委員会で再発防止策を検討中で、成績を予算に反映させる現行制度を「好ましくない」などとする報告書案をまとめ、今月末にも斎藤幸枝教育長に報告する方針。
報告書には、学校別順位の公表をやめ、正答率の分布図を示すなどの方法に変えたり、テスト問題を実施前日に各校に搬入して秘密保持を徹底したりする提言も盛り込まれる。
神戸新聞(2007年9月19日)より
学力テスト不正 成績別の予算廃止へ
東京・足立調査委報告「競争原理」を転換
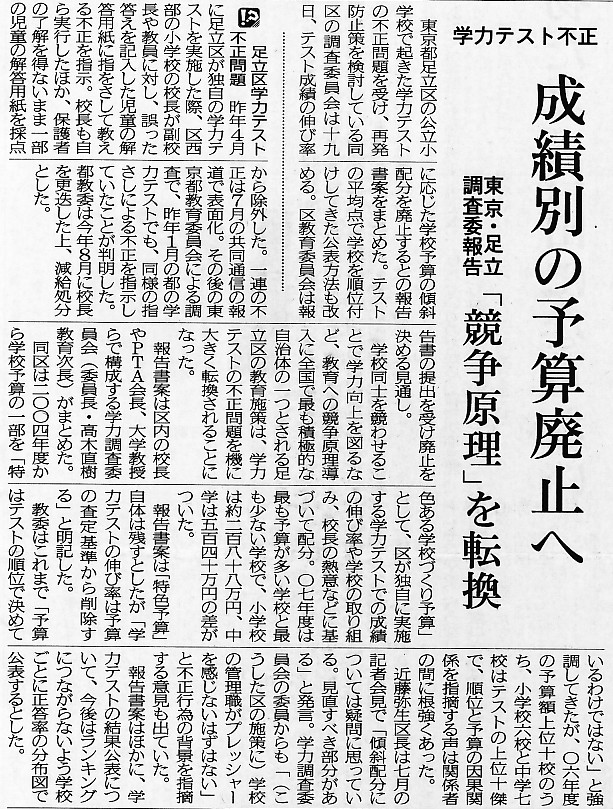
「指導力不足教員:2年連続減少 8割以上はベテラン教師」
何が原因なのか良く知らないが、個人的な意見ではリーダーシップが欠けている結果だと思う。
昔は、先生だからと我慢した子供がいると思うし、先生だから文句を言ってはいけないと
思っていた親もいたと思う。不満を抱いていた子供は大人になり、先生はこうあるべき、
適切な対応と取るべきと言うようになった。アメリカでの経験から言うと、リーダーシップ又は
尊敬されない先生は生徒が言うことを聞かない。先生と言う肩書きだけではついて来ない。
昔の日本のやり方を見てきた、そして新しい変化に対応できないベテラン教師が指導力不足教員
となるのではないか。リーダーシップや尊敬される対応を簡単には身に付けられるとは思えない。
1年ぐらいの研修や大学での勉強は理論であって、生徒を引き付ける能力の取得にはならない。
ゆとり教育(ストレスフリー教育)は間違っていた。いつまで間違った方針を続けるのか!
指導力不足教員:2年連続減少 8割以上はベテラン教師 09/13/07(毎日新聞)
適切な指導ができないなどとして、06年度に「指導力不足」と認定された公立学校の教員は前年度比56人減の450人となり2年連続で減少したことが、文部科学省の調査で分かった。このうち、06年度に新たに認定された教員は同34人減の212人だった。指導力不足教員の減少について、文科省は「00年度から制度が始まり、問題のある教師への対応が進んだ結果」と分析している。
調査は、47都道府県と今年4月政令市になった新潟市と浜松市を除く15政令市の状況をまとめた。
指導力不足教員の内訳は、小学校220人▽中学校119人▽高校72人--などで、40~50代のベテラン教師が8割以上を占めている。自治体からの報告では、「授業中に無駄話が多く、計画通りに教科書の指導ができない」(中学校、40代男性)や「自分から生徒に話しかけようとしない。生徒の引率でも自分から生徒に働きかけない」(特別支援学校、30代男性)などのケースがあったという。
06年度の研修対象者335人のうち、101人が研修後に現場復帰。依願退職104人▽免職4人▽ほかの職種に転任7人--の計115人が教壇を去った。研修継続となったのは99人だった。
自治体別では▽千葉県22人▽三重県19人▽福岡県18人--の順で多かった。
指導力不足教員は、各教委が「学習指導を適切に行うことができない」などと独自に定義・認定している。定義や認定手続きなどにばらつきがあると指摘されており、文科省は8月末に有識者会議を設置して統一的な指針作りを進めている。
また、試用期間(1年間)を経て正式採用にならなかった教員は、前年度比86人増の295人だった。依願退職281人▽不採用4人▽懲戒免職4人--などで、依願退職した教員のうち84人は精神性疾患などによる病気が原因。死亡退職も5人おり、2人は自殺だった。【高山純二】
朝日新聞(2007年9月11日)より
足立区教委 学力テストを事前配布
小中対象 校長ら反発
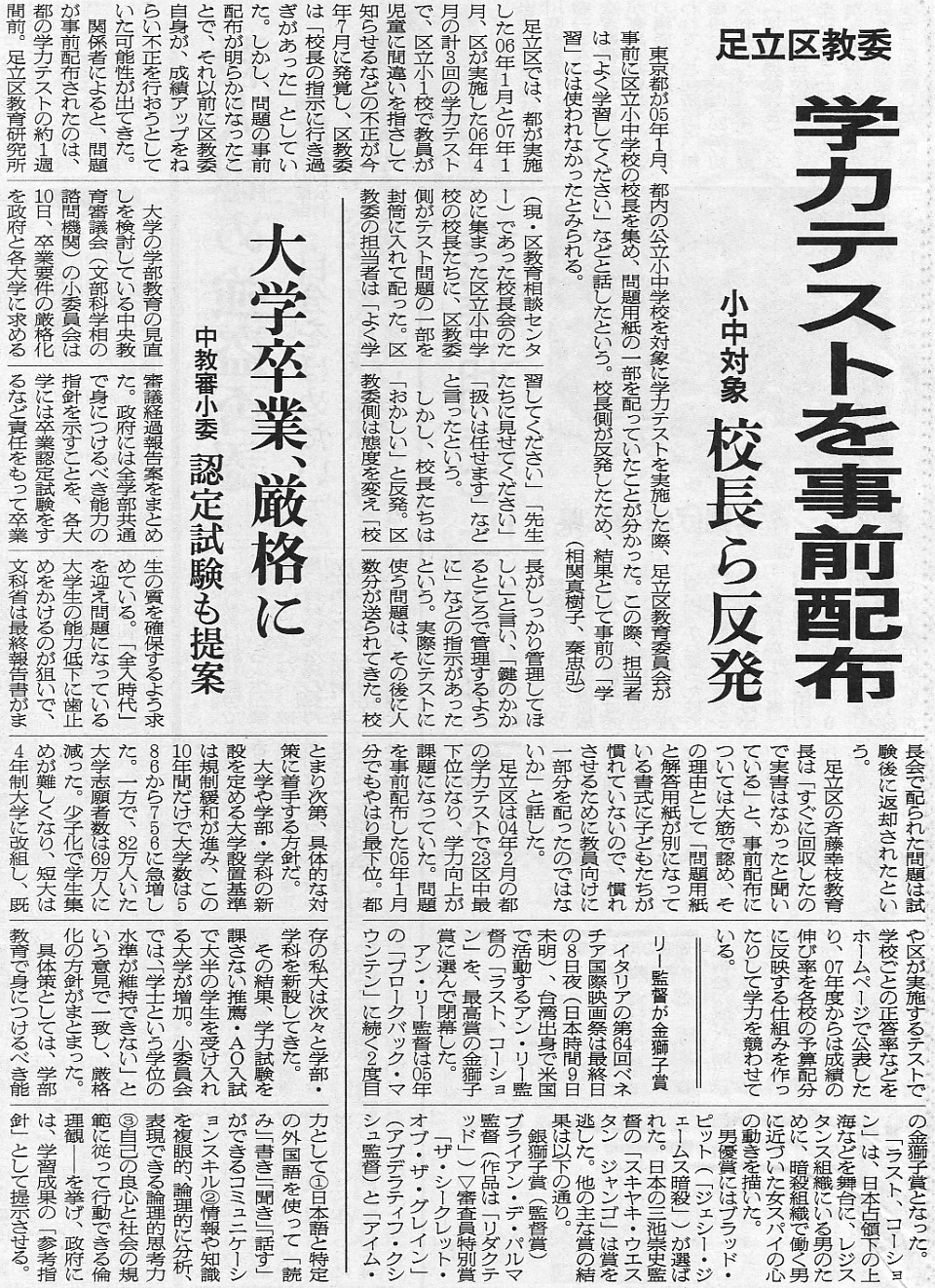
無免許教員:小学校教諭として採用 愛媛県教委 09/11/07(毎日新聞)
愛媛県教委は10日、中学校の教員免許しか持っていない20代の男性を今年4月、小学校教諭として採用していた、と発表した。男性は松山市立小学校で担任を務めていたが、県教委は採用を無効とし、担任を替えた。県教委の平岡長治指導部長は「基本中の基本の確認ミス。あってはならないことで深くおわびする」と陳謝した。
県教委によると、男性は中学校講師をしていたが、小学校の免許を取ろうと大学の通信教育課程に入学。免許に必要な6科目の単位が未認定のまま、昨年の小学校の教員採用試験を受け合格した。男性は出願時に大学発行の免許状取得見込証明書を提出。県教委は免許状そのものは確認せず採用した。男性は今春に単位認定されると思い込んでいたという。
県教委は今年4月以降、男性に免許状の提出を求めたが、男性はそのうち届くと思いながら「紛失した」などと説明。4月6日付で提出した履歴書には架空の教員免許番号を記入していた。県教委が今月6日、大学側に確認し、教員免許を取得していないことが判明した。【古谷秀綱】
「熊本大学教育学部の教授が、公的機関から学位として認められていない米国の非公認大学の「博士号(文学)」を、
自らの最終学歴・学位として公表していたことが分かった。」
文部科学省や日本政府は大学の教育水準を評価・保証する
全米高等教育機関基準認定協議会(CHEA)
が、大学として認定した大学は認めるのか。文部科学省は
「ディプロマ(ディグリー)・ミル」問題について(文部科学省)
認識はしているようである。
参考までに(大学が認められているかチェックできる)
Middle States Commission on Higher Education (MSCHE)
The New England Association of Schools & Colleges (NEASC)
The North Central Association Commission on Accreditation and School Improvement (NCA CASI)
The Northwest Commission on Colleges and Universities (NWCCU)
The Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (COC)
The Western Association of Schools and Colleges (WASC)
独立行政法人 大学評価・学位授与機構
のホームページにも上記の組織は記載されていました。
学位商法:熊大教授が米国の非公認大学「博士号」を公表 08/30/07(毎日新聞)
熊本大学
教育学部の教授が、公的機関から学位として認められていない米国の非公認大学の「博士号(文学)」を、自らの最終学歴・学位として公表していたことが分かった。非公認大学の学位の多くは、数十万~百数十万円を支払うだけで簡単に取得できる「学位商法」として米国などで問題になっている。文部科学省は、海外の非公認大学で取得した学位で採用や昇進を認められた大学教員がいないか、全国1206大学を対象にした実態調査を進めている。
関係者によると、この熊大教授は、大学の教育水準を評価・保証する全米高等教育機関基準認定協議会(CHEA)が、大学として認定していない、米パシフィック・ウエスタン大学(PWU)から学位を取得。独立行政法人・科学技術振興機構の研究者情報サイトには、PWU大学院の博士号を95年に取得と登録し、福祉教育に関する著書(02年)にも経歴欄に博士号を指す「Ph・D」と記載した。教授は佛教大などを経て99年に熊大に移籍したが、現在の同大サイトの研究者情報には「文学修士」のみ記載がある。
取材に対して教授は、同大学広報室を通じ「論文提出などの審査を受けて、学位を受けた。当時は非認定の大学という認識は全くなかった。熊大採用時の履歴には記載していなかった」と回答した。
文科省は国内の大学教員の一部が、国際的に無意味な学位を最終学歴に掲げていることを問題視。国内の全大学に、米国などの公的な認定リストに掲載がない機関が授与した学位名称の有無▽採用・昇進審査の判断材料にしたか--などについて回答を求めている。文科省は、こうしたやり方が横行すれば「大学教育の質の維持が危ぶまれ、国際的な信用低下につながる」として、今秋にも調査結果を公表する。【石田宗久】
児童買春で小学校教諭逮捕 高3女子とわいせつ行為 08/30/07(産経新聞)
宮城県警佐沼署などは30日、当時17歳の女子高生とわいせつな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、仙台市泉区松陵、小学校教諭、星雅実容疑者(47)を逮捕した。「18歳以上だと思っていた」と容疑を一部否認しているという。
調べでは、星容疑者は4月1日、宮城県大崎市のホテルで、ツーショットダイヤルで知り合った同県登米市の公立高校3年の女子生徒に1万5000円を渡し、わいせつな行為をした疑い。別の日にも2万円でこの女子高生と同様の行為をし、「これまで数人と援助交際をしている」と話しているという。
星容疑者は仙台市の小学校で5年生の担任。同市の荒井崇教育長は「事実が明らかになり次第、厳正に処分する」とコメントしている。
バーベキューで飲酒の高校教諭、生徒ら送った後に追突 08/27/07(毎日新聞)
新潟県立巻総合高校の男性教諭(31)が新潟市内で酒気帯び運転をし、追突事故を起こしていたことが27日、わかった。
西蒲署などによると、教諭は25日夕、同市西蒲区の県道で乗用車を運転、信号待ちをしていた軽乗用車に追突した。同署員が調べたところ、呼気からアルコール分が検出された。
教諭は顧問を務める部活動を終えた後、同区内の海岸で生徒らとバーベキューをし、ビールを飲んだという。その後、生徒を車で学校に送り、事故当時は一人で帰宅する途中だった。同校の河内一男校長は「監督責任を痛感している。生徒には事実を説明したい」としている。
徹底的に調べ、ウソを付いた者は懲戒免職にすべきだ。
教育者として恥じるべき行為。
生徒達にも不正をした者は処分される事を示すべきだ。
校長であっても、教員であっても関係ない。
テスト不正:足立区小学教員ら都テストでも 都教委処分へ 08/23/07(毎日新聞)
東京都足立区の区立小学校の教員らが、06年と07年に実施された都の学力テストで誤答した児童の問題個所に指をさして再考を促していたことが分かった。この小学校では06年4月に行われた区学力テストでも同様の不正が明らかになっており、都教育委員会は近く校長を更迭して、処分する方針。
足立区教委によると、不正があったのは、06年1月と07年1月、5年生を対象に実施された計2回の都の学力テスト。教員3人が児童に「指さし」して正解を誘導した。都や区の調査に対し、教員3人は「校長や副校長の指示を受けた」と話しているという。しかし、校長は「はっきり指示した覚えはない」と説明し、副校長は「一切指示していない」と否定しているという。
区は7月下旬、テストの不正発覚後に行った調査結果を都教委に報告。都教委が8月上旬、教員らから事情を聴き、教員1人が「都のテストでも不正を行った」と証言し、発覚した。教員のうち2人は06年4月の区のテストでも同様に指さししていた。【木村健二、吉永磨美】
東北大病院の随意契約、意図的な入札逃れ…内部調査で判明 08/23/07(読売新聞)
東北大学(仙台市)が、一般競争入札が必要な同大病院の手術室工事を随意契約にしていた問題は、病院の契約事務担当の二つの課が工事の早期完成を目指し、特定業者と契約を結ぼうとした意図的な入札逃れだったことが22日、病院の内部調査で明らかになった。
病院側は当初、「意図的な入札逃れではない」としていた。東北大は23日にも、内部調査の結果を文部科学省に報告する。
調査結果によると、契約事務担当の二つの課は、経営管理課と経理課。2課の担当者は、発注前に紹介された特定業者と契約を結び、入札の手間を省くことで、手術室を今年1月までに完成させ、年度内に収入を上げようとしていた。
問題の工事は、昨年10~12月に外来病棟で行われたレーザー視力矯正手術室への改修。契約額は2310万円だったが、工事を〈1〉元の部屋の解体〈2〉空調などの整備〈3〉レーザー機器設置のための内装改修――に3分割し、いずれも一般競争入札が不要な1000万円以下の工事として関東の建設業者に発注していた。
工事は、有名な眼科教授のいる同病院に昨年4月、医療機器販売会社からレーザー視力矯正機器の寄付の申し出があり、計画された。工事の仕様や予算策定について、眼科教授の提案で、販売会社の特約代理店の別の医療機器販売会社に相談し、この会社が建設業者を紹介した。
2課の担当者は建設業者から参考見積もりを取るなどして打ち合わせを重ねた結果、このまま施工に移行したいとして、昨年6月に建設業者に発注の意向を伝えた。同10月に発注し、この前に建設業者らには工事を3分割することを説明していたという。
調査結果は、医療機器販売会社や建設業者と眼科教授との金銭授受や、教授が随意契約を主導した事実は確認されなかったとし、「業者との癒着はなかった」と結論付けている。
検定試験出願怠った専門学校社員、発覚恐れ「偽試験」実施 08/22/07(読売新聞)
資格取得の専門学校ヒューマンアカデミー浜松駅前校(浜松市中区)の男性社員が、受講生11人の医療秘書技能検定試験の出願を怠り、ミス発覚を恐れて偽の検定試験を受けさせていたことが分かった。
ヒューマンアカデミーの親会社で、人材派遣や人材教育などを行うヒューマンホールディングス(東京都新宿区)によると、男性社員は11人の受験申し込みを忘れ、締め切りの5月10日までに手続きを行わなかった。発覚を恐れて受験票を偽造し、試験日の6月10日には他校舎からファクスで試験問題を入手し、偽の検定試験を実施した。
8月初め、受講生から合否の問い合わせを受けた同校が、検定試験を主催する医療秘書教育全国協議会(東京都江戸川区)に確認したところ、受験の事実がないことが分かった。
学校側は、男性社員を8月11日付で解雇。受講生に受験料を返還して謝罪するとともに、次回の試験対策講座を無料で受講できるようにした。同社は「チェック体制の強化と社員教育を徹底し、再発防止に努めます」とコメントしている。
出会い系サイトで知り合う、17歳買春容疑の小学教諭逮捕 08/21/07(読売新聞)
岐阜県警は21日、岐阜市長良福光、同市立三輪南小学校教諭藤垣敬介容疑者(37)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕した。
調べによると、藤垣容疑者は7月8日午後7時ごろ、同県各務原市のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った飲食店従業員の少女(17)に現金2万円を渡し、児童買春した疑い。
調べに対し、藤垣容疑者は「18歳と思い込んでいた」と供述している。
朝日新聞(2007年8月11日)より
東北大、法令違反認める
病院工事入札せず 監査室で再調査へ
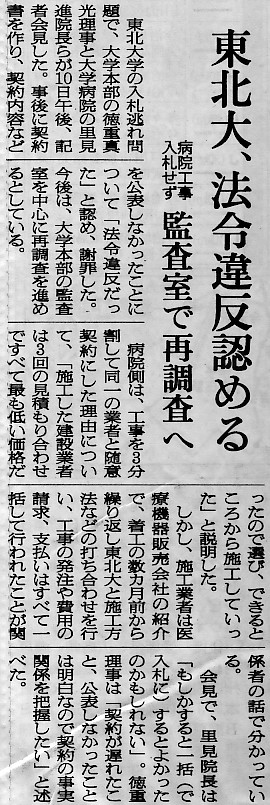
副校長と校長がセクハラ 横浜市教委が懲戒処分 08/09/07(産経新聞)
横浜市教育委員会は9日、それぞれ部下の女性教諭にセクハラ(性的嫌がらせ)をしたとして、横浜市金沢区の市立中学校の副校長(50)を停職3カ月、同市神奈川区の市立中学校の校長(48)を戒告の懲戒処分にした。
副校長は9日付で依願退職した。市教委は10日付で校長を更迭する。
市教委によると、副校長は6月5日夜、懇親会で同じ中学の女性教諭の手を握り続け、タクシーで自宅近くまで送った際に無理やりキスをした。「軽い気持ちでやってしまった」と話しているという。
校長は6月23日夜、市内のスナックで同じ中学の教諭らと飲酒。酒を飲まなかった教諭の1人が運転する車で帰宅する途中、隣に座った女性教諭の手を約1時間にわたり握り続けた。「具合が悪そうだったので励ますつもりだった」と話しているという。
痴漢逮捕:「好みだった」筑波大学准教授 旅行中徳島で 08/05/07(毎日新聞)
徳島県警阿南署などは5日未明、東京都足立区千住寿町、筑波大学准教授、増田哲也容疑者(50)を県迷惑行為防止条例違反(痴漢行為)容疑で逮捕した。
調べでは、増田容疑者は、4日午後4時20分ごろから約50分にわたり、JR牟岐線の列車内で、県内の専門学校生の女性(21)の胸や太ももなどを触った疑い。調べに対し、「夏休み期間に、講演活動を兼ねて旅行していた。好みの女性だったのでムラムラした」と話しているという。
新司法試験で類題指南、慶大処分を法科大学院協が先送り 07/28/07(読売新聞)
新司法試験の「考査委員」として出題を担当した慶応大法科大学院の植村栄治教授(57)が試験の類題を事前に教えた問題を巡り、全74校でつくる法科大学院協会(東京)が、有効な対応策を打ち出せずにいる。
慶応大への処分には踏み切れておらず、他校に対する調査は検討もしていない。9月中旬の合格発表を控え、修了生らの間で「法科大学院制度を信頼していたのに裏切られた」との声が高まり、現場の教員からも批判が出ている。
今月24日、東京都内で開かれた同協会の臨時理事会では、出席した慶応大の理事を途中退席させて対応を検討した。当初は、慶応大を約20人の理事メンバーから外すなどの処分もあり得るとみられていたが、結論は、植村教授の問題に限定した調査委員会の設置にとどまった。
ネット上では、他校でも考査委員が不適切な受験指導をしたという学生からの指摘が相次いでいる。しかし、同協会は「他校については法務省や文部科学省が調査しており、協会としては不確実な情報を基に調べるつもりはない」として、他校の調査については検討すらされなかった。
「協会内では、毎年多くの合格者を出す『上位校』と、その他の大学院の考え方に温度差がある。上位校は、このまま受験競争が続いても生き残れると考えているため、危機感が薄い」。都内の法科大学院の教授は、そう指摘する。別の法科大学院教授も、「ルール違反に対しては早期に厳しい処分を科し、ウミを出し切ることで信頼を取り戻さないといけないのに……」と嘆く。
一方、得点調整などの是正措置を要望していくかどうかについて、同協会では「身内(慶応大)の不祥事が原因だから、協会としては法務省に(是正を)要望しづらい」といった声があり、見送られている。
これに対し、学校レベルでは、要望に踏み切った所も。関西大(大阪府)と関西学院大(兵庫県)の両法科大学院は今月上旬、是正措置などを求める連名の要望書を法務省に提出した。「植村教授から出た情報は関東の他の受験生にも伝わった可能性があり、相対的に関西は不利になった」といった憤りの声が、修了生らから上がっているためだという。
海外の論文盗用の准教授、神戸市外語大が諭旨免職 07/28/07(読売新聞)
神戸市外国語大(神戸市西区)は27日、外国人研究者の論文を盗用したとして、外国語学部の男性准教授(46)を同日付で諭旨免職にしたと発表した。
同大学によると、准教授は2005年10月、4人で労災補償制度に関する著作を共同執筆し、出版したが、担当した46ページ中、約20ページがカナダ人研究者らの2論文の翻訳だったという。
06年4月には労働専門誌が「論文の翻訳」と書評。准教授は同年5月、絶版にしたが、大学には報告せず、大学側は同年12月、外部の研究者からの指摘で把握したという。
大学側の聴取に対し、准教授は「どうしてやったのかわからないが、迷惑をかけて申し訳ない」と認めているという。木村栄一学長は「著作権意識の啓発など再発防止に努める」と謝罪した。
東京都足立区西部の公立小の学力テストで不正に関わった校長は首にすべき。
良い評価を得たいのか、多くの予算をほしいのか、生徒のためであるのか、
理由など関係ない。教育者として不正を選択することに問題がある。
不正に関わった5人の教員が強制の状況で行なっていなければ、5人の教員も首にすべき。
「テスト学力を過度に重視し、学校間で序列をつけて競い合う傾向」の状況で
不正が起こりやすいのは理解できる。しかし、競争があるから不正をするのであれば、
「お金を儲けることが悪いのか。」と言った
村上ファンドの村上世彰氏
と同じである。お金を儲けるために手段を選ばないことはだめなのか?
学力テストで結果を出すために手段を選ばないことはだめなのか?
同じレベルだ。教育に関係する者は見本となるべきだ。
教え方が上手であるなら学習塾や予備校で教えたらよい。
大手企業でもモラルのないことをする。
規則を守ることを教えられない教員は首にすべきだ。
取締まるべきの警察が犯罪を犯す時代。
だめなものはだめと示さないから、おかしなことをするのだ。
身内に甘いのは分かるが、示しをつけろ!
校長、学力テスト中の児童に指で正答教える…東京・足立区 07/17/07(読売新聞)
東京都足立区教育委員会が昨年4月に実施した学力テストで、区内西部にある区立小学校1校の校長と教員計6人が、テスト中に児童の答案用紙を見て回り、誤った解答を指で示すなどして正解を誘導する不正を行っていたことが16日、区教委の調査で分かった。
同校はこの学力テストで、区内での成績が前年の44位から1位に急伸しており、区教委は「管理職からの何らかの指示があった」と判断。今後、第三者委員会を設け、学力テストのあり方などを検討する方針だ。
今月7日、この小学校が障害のある児童らの成績を保護者の了解を得ないまま集計から除外するなどしていた問題が発覚。区教委が同校を含めた区内の全109小中学校を対象に調査し、この日、結果を発表した。
学校ぐるみの不正認める 学力テストで足立区教委公表 07/07/07(河北新報)
昨年4月に実施された東京都足立区の学力テストの際、区西部の公立小で、試験中に校長と教員が児童の答案を指さして誤答に気付かせるなどの不正をしていた問題で、同区教育委員会は16日記者会見し、学校ぐるみで不正行為があったとする調査結果を公表した。
また、テスト後、同校以外にも小学校1校で、保護者の了解なく特定の児童を採点対象から除いていたことも明らかにした。斎藤幸枝教育長は「学校に対する管理不行き届きがあった」などとして謝罪した。
区教委は、テストがあった当時、同小に勤務していた全教員から聞き取り調査。校長と5人の教員が答えを間違っている数人の児童に対し、問題文を指さすなどして誤答に気付かせる不正をしていたことを確認した。
教員はそれぞれ、校長や副校長、主幹の指示があったと説明。校長は自分でコピーや指さしをしたことは認めたが、不正の指示は否定したという。区教委は「校長か副校長かは詰められなかったが、学校幹部の指示がなければ起きなかったこと」と、学校ぐるみだったとの認識を示した。
<学力テスト>校長、教員らが誤答指摘の不正 東京・足立区 07/16/07(毎日新報)
東京都足立区が実施した06年度の区学力テストで不適切な行為が疑われていた問題で、区教委が16日会見し、区立小1校で校長と5人の教員がクラスを見回り、誤答していた児童の問題個所を指さし再考を促していた不正があった、と発表した。区教委は校長の任命権がある東京都教委に処分を求める方針だ。
区教委によると、校長は「普段から指で問題をなぞりながら読むよう指導している」と話し、教員に指さしを命じたことは否定。しかし、テストを受けた2~6年の全クラスの担任は、校長や副校長による指さしの指示があったと証言した。
また、同じ小学校で、テスト前に前年のテストをコピーし、児童に2~3回にわたり練習させていたことも判明。05年と06年はテスト作成業者が同じで、ほぼ同じ問題が出題されたという。同校では、情緒障害児ら3人の答案を採点から除外したことが既に判明。同校は05年に区内全72小学校中44位だったが、翌年1位にはね上がった。
さらに、区が全小中学校を調べたところ、小学校3校、中学校1校で前年のテストをコピーして問題を解かせていた。また、小中学校17校で、やる気がなくテスト用紙に絵を描いた▽外国籍で日本語が未習得――などの小学生16人と中学生5人計21人をテストの調査対象からはずしていた。21人中、1人の親から了解を得ず「不適切だった」という。
足立区は学力テストの各校順位をホームページで発表し、学校ごとに予算を傾斜配分している。区教委は今後、順位の公表を見直す方針。【山本紀子】
学力テスト問題に詳しい藤田英典・国際基督教大教授(教育社会学専攻)の話 起こるべくして起こった問題。45年前に実施されていた全国学力テストでも、誤答を指さして教えるなどの問題行為があった。基礎学力をつけることは大事だが、テスト学力を過度に重視し、学校間で序列をつけて競い合う傾向が強まる中で起こったことで政策のゆがみの表れといえる。
足立区の学力テストで不正 教員「校長の指示」と証言 07/07/07(共同通信)
昨年4月に実施された東京都足立区の学力テストの際、区西部にある公立小で、試験中に教員が児童の答案を指さして誤答に気付かせる不正を行っていたことが7日、分かった。6人の教員が「校長の指示があった」などと証言した。足立区はテストの順位を公表しているほか、学校予算の傾斜配分や学校選択制を取り入れており、教育関係者からは「競争原理の導入が不正の背景にあるのではないか」との指摘も。
「73人合格」実は受験生1人、大阪の私立高が実績水増し 07/20/07(読売新聞)
大阪市住吉区の私立大阪学芸高校(近藤永校長、生徒数約1500人)が2006年度の大学入試で、成績が優秀だった1人の男子生徒に志望と関係のない学部・学科を多数受験させ、合格実績を事実上水増ししていたことがわかった。
関西の有名4私立大(関西大、関西学院大、同志社大、立命館大)の計73学部・学科に出願しすべて合格。受験料計約130万円は同校が全額負担していた。大学入試センター試験の結果だけを利用して合否を判定する入試制度を利用したもので、合格発表後、生徒側に激励金名目で5万円と、数万円相当の腕時計を贈っていた。文部科学省は事実関係を調査する方針。
関係者などによると、同校は5年前、4私大などを受験する生徒の受験料を負担する制度を設けた。規定は非公開で一部生徒だけに告げられる。
73学部・学科に合格した生徒には、センター試験直前の昨年1月、担当者が説明。生徒は国公立大が第一志望だったが、4私大の計5学部・学科の一般入試の受験も希望した。その際、「学校の判断でほかの学部・学科にも出願していいか」と持ちかけ、さらに計68学部・学科に出願手続きをした。生徒は理系志望だったが、出願先には文系の学部・学科も含まれていた。
結果は、すべて合格。生徒は結局、第一志望の国公立大に合格し、進学した。
06年度、同校は4私大の合格者数を延べ144人と公表しているが、半数以上はこの生徒が1人で積み上げたものだった。
読売新聞の取材に対し、同校の中谷清司副校長は「大学合格実績がアピールポイントなのは否定できず、ほかの学校が延べ人数で表示すれば、うちだけ実数というわけにはいかない」と話している。
女子大学院生と性的関係、信州大准教授をセクハラで解雇 06/21/07(読売新聞)
信州大教育学部(長野市)は21日、同学部の30代の男性准教授が、同大の女子大学院生と性的関係を持ったなどとして、20日付で諭旨解雇処分にしたと発表した。
同大によると、大学院生が4月、大学に「セクハラを受けた」と訴え、発覚した。准教授は今年1~2月、学外で大学院生と性的関係を持ったといい、大学側に事実関係を認め、辞職を申し出ていた。大学院生は5月から休学しているという。
危ない外国人が英語教師としてだけでなく、日本に入国できないように処分してほしい。
傷害:女性殴打のNZ人逮捕 署では拳銃強奪図る 名古屋 06/11/07(毎日新聞)
11日午前6時半ごろ、名古屋市東区の愛知県警東署取調室で、傷害容疑で取り調べを受けていたニュージーランド国籍で名古屋市中川区豊成町、英語教師、ミッチェル・ランギ・モヤ容疑者(32)が、監視していた地域課の男性警部補(55)に襲いかかり、右腰に携帯していた拳銃を奪おうとした。警部補は抵抗しながら大声で応援を求め、駆け付けた同僚警察官とともにモヤ容疑者を取り押さえた。
拳銃には実包が入っていたが、警部補らにけがはなかった。同署は強盗未遂と公務執行妨害容疑でも調べる方針。
調べでは、モヤ容疑者は同2時ごろ、同区東桜2の知人女性(28)宅で、女性の顔を殴るなどして10日間のけがを負わせた傷害の疑いで同署員に緊急逮捕された。警部補と別の捜査員の2人が刑事課取調室で調べていたが、警部補が一人になった時に襲いかかったという。東署の佐藤勇治副署長は「今後、被疑者の監視を徹底したい」と話している。【米川直己、松岡洋介】
受験戦争やシンガポールやインドの教育システムが良いかはわからない。
しかし、今の日本の教育で日本は国際競争に生き残れるのだろうか。
格差社会を無くさないといけないと言っているが、日本が国際競争に負けた場合でも
利益を分配するゆとりは日本にあるのか。
過去の日本の教育のような応用力がない詰込みの教育が良いとは思わない。
しかし、他の国が子供の教育に力を注ぎ、子供達も努力した場合、何十年後には
結果として現れるだろう。日本は、差の開きを実感した時にどうするのか。
真剣に考えるべきだ。イッソプ童話のアリとキリギリスのようになってからでは遅い。
朝日新聞(2007年6月5日)より
受験戦争も成長の証し
インド 高まる最高学府への競争 シンガポール 進路の振り分け、小4から

学力テストの結果だけで学校や教師を評価すると、広島県北広島町教委のように
とにかくテストの結果だけを良くしようとする学校や教師が出てくる可能性があることを
裏付けるケースであろう。
学力テストだけでなく、評価は難しいが、生徒の学校での活動やスポーツやその他の活動も
含めて総合的に評価しなければ問題を起すことを示していると思う。点数が全て、偏差値が
全てと考える偏った社会を生み出す結果となるだろう。まあ、タウンミーティングでやらせを
考える職員が存在し、実行されたこと自体、既に偏ったエリートが決定権を持っている社会が
存在することを示している。
広島県北広島町教委の対応は凄く日本的。また、間違った方針を出す政府も日本的。日本だから
仕方が無いか!しかし、間違っている職員や間違っている教育者達が子供達に無駄なことを
させないことを望む。
全国学力テスト前に、町教委が類似問題で解き方指導…広島 05/17/07(毎日新聞)
全国の小学6年と中学3年を対象に文部科学省が4月24日に実施した全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)で、広島県北広島町教委が、テスト前に類似の問題集を作成し、小中学校全21校の児童らに解き方などを指導していたことがわかった。
県教委によると、町教委は2月末、各校に国語と算数(数学)の問題を作るよう指示。できあがった問題を町教委がまとめ、4月初め、小中学校に配布した。各校は授業などで利用したという。
町教委は「問題集は学力テストの平均点を上げるためのものではなく、学力向上のためのもの」としており、県教委も「問題はない」としている。
文部科学省学力調査室の話「事前対策は禁止していないが、町全体での対策は聞いたことがない」
東京国税局職員を強制わいせつで逮捕、地下鉄車内で痴漢 05/15/07(読売新聞)
地下鉄の車内で女性の下腹部を触ったとして、警視庁千住署が、東京国税局資料調査1課連絡調整官、安部義和容疑者(43)を都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕していたことがわかった。
同署は、容疑を強制わいせつに切り替えて調べている。
同署によると、安部容疑者は出勤途中の11日午前8時20分ごろ、東京メトロ千代田線湯島―新御茶ノ水駅間の電車内で、埼玉県越谷市内に住む専門学校生の女性(20)のズボンのチャックを下げて下腹部を触ったところを、同署員に取り押さえられた。
被害者の女性は4月中旬から電車内で痴漢の被害を受けていたため、今月2日、同署に相談し、同署員が一緒に電車に乗り込んで警戒していた。安部容疑者は「度が過ぎたことをしてしまった」と供述しているという。
痴漢逮捕:東大大学院教授、電車内で女性に触る 05/15/07(毎日新聞)
東京大大学院法学政治学研究科の蟻川恒正教授(42)が、JR山手線の電車内で痴漢をしたとして、警視庁新宿署に東京都迷惑防止条例違反容疑で逮捕されていたことが分かった。「犯罪であることは認識している。申し訳ないことをした」と容疑を認め、すでに釈放されている。
調べでは、蟻川教授は11日午後6時ごろ、渋谷-新宿駅間を走行中の山手線内で、スカートの上から乗客の女性会社員(20)の下半身を触った疑い。女性に新宿駅のホームで取り押さえられた。東大の広報担当者は「現在、事実関係を確認中」と話している。【古関俊樹】
教諭が性的暴行1年半、「PTSD」女性が提訴…北海道 05/10/07(読売新聞)
中学校教諭から約1年半にわたり性的暴行を受け、被害を訴えたにもかかわらず、学校側や教委が迅速な対策を取らなかったため、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、北海道東部の10代の女性が、この元教諭と当時の中学校長、地元の町、道を相手取り、慰謝料や治療費など約1億500万円の損害賠償を求める訴えを札幌地裁に起こしたことが10日、わかった。
訴えなどによると、女性は中学生だった2004年6月から、自宅や校内で、30代の教諭から繰り返し性的暴行を受けた。06年に家族に被害を打ち明け、同年2月に警察に被害届を提出。教諭は道青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕され、児童福祉法違反と強制わいせつ罪で実刑判決を受けて服役中。同年4月に懲戒免職処分となっている。
家族は、中学校長に教諭を遠ざけるよう求め、校長は対応を約束したが、教諭の暴行は続いた。家族は昨年2月に町教委に相談したが、「1週間後に再度話を聞きたい」と先延ばしにされたため、警察に通報したという。町側は「迅速な対応を取り、できる範囲で対応した」とし、道教委は「訴状の内容を検討している」と話している。
新潟の小学教諭が東京で昏睡強盗、薬物混ぜた酒飲ませる? 04/26/07(読売新聞)
新潟県上越市の市立美守小教諭、片山宣昭容疑者(45)(同市清里区)が、東京都内の出会い系喫茶で知り合った女性が意識を失ったところで所持品を奪ったとして、今月20日、昏睡(こんすい)強盗容疑で警視庁築地署に逮捕されていたことがわかった。
調べによると、片山容疑者は昨年12月28日、豊島区東池袋の出会い系喫茶から中央区内のアルバイト女性(20)を誘い出し、近くの居酒屋で酒を飲んだ後、意識を失った女性をホテルに連れ込み、約1万円などが入った財布とショルダーバッグ計約6万円相当を奪った疑い。
女性は、居酒屋で飲食を始めてから30分程度で意識がもうろうとなったと説明していることから、同署は片山容疑者が薬物を混ぜた酒を飲ませたとみて調べている。
片山容疑者は冬休みを利用し、家族には「都内の親類に会いに行く」と言って上京。出会い系喫茶に偽名で会員登録していた。
調べに対しては、「現金などは取っていない」と否認しているという。
獣医師試験:問題漏えい関与した2教授を懲戒処分 麻布大 04/26/07(毎日新聞)
昨年度の獣医師国家試験の問題(全300問)のうち5問が麻布大の教授から漏えいした問題で、麻布大は26日、関与した2教授を准教授に降格と出勤停止1週間とする懲戒処分を発表した。政岡俊夫学長も厳重注意処分とした。
この問題は獣医師国家試験の作成委員だった同大獣医学部の西田利穂教授が同学部の鈴木嘉彦教授に問題の提供を依頼し、鈴木教授がその後、提供した問題を学生に口述筆記させた。試験問題は同大の学生を通じて東大、日本獣医生命科学大、東京農工大の受験生にも漏えいした。
いん行逮捕:中学教諭、中2女子とホテルへ 北海道 04/18/07(毎日新聞)
札幌西署は18日、北海道石狩市花畔(ばんなぐろ)2の1、同市立樽川中学校教諭、青山拓也容疑者(29)を道青少年保護育成条例違反(いん行)容疑で逮捕した。
調べでは、青山容疑者は06年10月14日、携帯電話の出会い系サイトで知り合った札幌市内の公立中学2年の女子生徒(14)に、同市手稲区内のラブホテルでいかがわしい行為をした疑い。調べに対し、青山容疑者は「若い女の子と遊びたかった」と容疑を認めている。【久野華代】
神戸大裏金:学生から100万円徴収 実験費名目10年間 04/17/07(毎日新聞)
神戸大工学部応用化学科(神戸市)が05年までの10年間、授業で使う資料を学科の経費で印刷したにもかかわらず、学生から総額約100万円を資料と引き換えに徴収していたことが分かった。同年に信州大教授が同様のケースで処分されたことを受け、同学科は急きょ、この金でロッカーなどの備品を購入し、全額を使い切っていた。
関係者や内部資料によると、同学科はこの資料代を「実験費」の名目で、3年生の実験授業(約100人参加)のガイダンスの際、学生から前後期各500円を徴収していた。総額は10年間で約101万8000円に上ったが、資料の印刷は「学科共通経費」で賄う事務室の印刷機で行っており、学生が負担すべき経費はゼロ。実験用の試料代としては10年間で計約2万円しか支出されていなかった。
残りの約100万円は、学部後援会からの補助金などに紛らせて、研究成果の要旨集作成や研究会参加費などの会計に計上していた。しかし、信州大の教授が05年4月、学内の印刷機でテキストを印刷したのに学生から約21万円の代金を受け取ったとして戒告処分を受けたと報道されたため、同学科はこの金の処理を見直すことにした。5月の教職員会議で、信州大の処分記事のコピーとともに「取扱注意」の資料を配布。「他支出に流用している形に見られる」「会計上説明がつかない」などと指摘している。「実験費」は過去にさかのぼって、すべて実験設備更新のための「学科実験設備積立金」だったとする変更案が審議され、全会一致で承認された。その結果、全額が実験室のロッカーや器具などの購入に支出されたといい、徴収は同年度後期から廃止された。
森本政之・同大工学部長は「ルーズな資金管理を反省している。今後は、同窓会報で卒業生などに経緯を説明したい」と話している。【本多健】
高崎経済大:准教授を懲戒免職 ゼミ女子学生の自殺で 04/10/07(毎日新聞)
高崎経済大学(群馬県高崎市)は9日、指導方法に問題があり、ゼミ生の経済学部2年の女子学生(当時20歳)を自殺に追い込んだとして、同学部の男性准教授(38)を懲戒免職処分とした。学生の自殺を理由に教員が懲戒免職処分を受けるのは異例という。また、管理責任者の木暮至学長を減給10%(2カ月)、石井伸男経済学部長を同(1カ月)とした。
大学によると、准教授は昨年6月、ゼミ生に夏季の宿題として高度な課題を課し、女子学生は一部を提出していなかった。准教授は12月、未提出の3人に「提出しなければ留年」などとメールを送信。期限の1月15日夕、未提出の2人のうち女子学生だけに催促のメールを送った。女子学生は「留年すると分かっています。人生もやめます」と返信。同夜、同県みどり市の渡良瀬川に投身自殺した。
大学の調査委員会はゼミ生や他の教員からの事情聴取で、宿題が2年生としては難解で留年通告が女子学生を自殺に追いやったと結論付けた。また、准教授は他の学生に度を越したセクハラ発言などの暴言があったという。准教授は「間違ったことはしていない」と反論しているという。【伊澤拓也】
コンビニで女子高生盗撮 中学教諭を逮捕 04/07/07(産経新聞)
埼玉県警岩槻署は7日、コンビニで女子高生のスカートの中を隠し撮りしたとして県迷惑防止条例違反の現行犯で、同県鴻巣市立鴻巣北中学校教諭、柿沼真也容疑者(25)を逮捕した。
調べでは、柿沼容疑者は7日午後0時55分ごろ、同県蓮田市本町のファミリーマート蓮田駅東口店で、高校2年の女子生徒(16)に後ろから近づき、バッグの中に隠したデジタルカメラでスカートの中を動画で撮影した疑い。気付いた男性店員(21)が取り押さえた。
容疑を認め「盗撮サイトをよく見ている」と話しているという。
松本元早大教授、研究費3千万不適正使用が新たに判明 03/29/07(読売新聞)
松本和子・元早稲田大教授による研究費不正問題で、文部科学省所管の科学技術振興機構は29日、同機構が松本元教授に交付した研究費のうち総額約3000万円を、元教授が不適正に使用していたとする調査結果を発表した。
同機構は今後、支払先の企業6社に対し返還を求めるとともに、6社との取引を3か月間停止する。松本元教授には5年間、同機構が所管する競争的研究資金の申請資格を停止するなどの措置をとった。
同機構によると、元教授の不適正使用は1997~2006年度、同機構が進める2つの研究プロジェクトに関するもの。遺伝子解析システム開発などの目的で、総額約8億9400万円の研究費を交付された。
しかし、調査の結果、実際はパソコンや実験機材を購入したのに名目を消耗品とするといった付け替え行為が29件(計2065万円)、納品されていない備品の代金を請求した架空請求が19件(計915万円)見つかった。同機構によると、私的流用はなかった。
松本元教授は文科、経済産業両省の研究資金を不正請求し、早大側の返還額は2億1240万円にのぼった。
生徒5人にわいせつ行為 和歌山県立高教諭を懲戒免職 03/29/07(朝日新聞)
和歌山県教委は29日、顧問をしている運動部の女子生徒5人にわいせつな行為を繰り返したとして、県立高校の男性教諭(49)を同日付で懲戒免職処分にした。同高校の校長(57)は戒告処分とした。
県教委によると、教諭は昨年7月中旬から今年1月中旬にかけて、1、2年生の女子部員5人に対し、「足にテーピングをする」「マッサージする」などと言ってロッカールームなどで下半身や胸を触ったほか、遠征先の宿泊施設で自室に呼び出して抱きついたり、キスしたりするなどわいせつ行為を数十回繰り返していた。
被害生徒が今年1月、保護者に打ち明けて発覚した。県教委に対し、教諭は「情が移った。生徒には償いようのないことをしてしまった」と話しているという。
女学生にセクハラ、静岡県立大が助教授を懲戒免職 03/27/07(読売新聞)
静岡県立大学(西垣克学長)は27日、女子学生にセクハラ行為をしたとして、国際関係学部の男性助教授(44)を懲戒免職処分にしたと発表した。
大学によると、助教授は2003年10月~04年8月、女子学生にセクハラ行為をし、女子学生は精神的な苦痛で一時授業を休んだという。男性助教授は「合意の上での行為。セクハラではない」と主張。県人事委員会に不服を申し立てるとした。
大学側は、05年7月に女子学生から相談を受け、緊急対策委員会を設置。双方から事情を聞いていた。
外国語助手雇用で偽装請負の恐れ、大阪6市教委に指導 03/23/07(読売新聞)
英会話学校などとの間で業務委託(請負)契約を交わして送り込まれた公立小中学校の外国語指導助手(ALT)の雇用状況を巡り、大阪府内の6市教委が、大阪労働局から「学校側が指揮命令と受け取られかねない行為をしており、労働者派遣法に違反した偽装請負の恐れがある」として、文書や口頭で指導されていたことがわかった。
文書で指導されたのは高槻市教委、口頭で指導されたのは堺、枚方、東大阪、松原、寝屋川の各市教委。
同労働局などによると、各市教委は英会話学校などとの業務委託契約に基づいてALTの人材供給を受け、学校側は直接指揮命令ができない立場だった。
これらの市では、教諭も同席して授業を進める「チームティーチング(TT)」形式を採用。教諭は授業前に授業の進め方を打ち合わせたり、授業中に説明が不十分と判断するとその場で改善を求めたりするなど、指揮命令と受け取られかねない行為をしていた。
ALTの雇用形態は〈1〉自治体による直接雇用〈2〉業者からの派遣〈3〉業者への業務委託――の3通りがある。直接雇用や派遣では教諭が指揮命令しても問題はないが、ALTが行う指導のカリキュラムを作成したり、人事管理を行ったりする必要が学校側に生じ、負担となるため、業務委託を選択するケースが多いとされる。
業務委託により人材供給を受けたALTをTTに組み入れることについて、大阪労働局は「教諭の補助的存在として指揮命令されるなら不適切。学校側から独立して授業を行えることが重要」としている。
立命館大:研究費2100万円不正使用、教授ら処分へ 03/02/07(毎日新聞)
立命館大(京都市中京区)は2日、理工学部都市システム工学科の江頭進治教授(60)と伊藤隆郭(たかひろ)講師(34)が、01~06年度に「文部科学省21世紀COE(卓越した拠点)プログラム」などの名目で交付された公的研究費のうち、計約2100万円を目的外や不正に使用していたと発表した。立命大はプログラムを辞退し全額を文科省に返還、2人を懲戒処分する方針。【中野彩子】
広島修道大教授でしかも、法学部。知識と行動が一致しない。
大人や企業の倫理の崩壊。子供の行動に問題があっても仕方がない。
モデルとなる大人や企業がこのありさま。
公務員が裏金を作るし、
税金を無駄に使う。そして、退職金は借金して払う。問題がある公務員は懲戒解雇に
して、退職金の総額を減らそう!問題のある公務員以外は、皆、ハッピー!
日本は解決すべき問題が山積みだ!
引っ越しごみ:67キロ投棄容疑で教授を逮捕 広島県警 01/26/07(毎日新聞)
引っ越しの際に不要になったごみを川岸に不法投棄したとして、広島県警広島北署は27日、福岡県志摩町、広島修道大法学部教授、松尾卓憲容疑者(48)を廃棄物処理法違反容疑で逮捕した。容疑を認めているという。
調べでは、松尾容疑者は今年2月19日午後4時~同5時半ごろ、広島市安佐南区沼田町伴の奥畑川の岸に、車や徒歩などで数回にわたり、不要になった鍋や衣類、カーペット、書類などのごみ計67キロを投棄した疑い。
松尾容疑者は民事訴訟法を専攻し、03年4月から同大に勤務。単身赴任で投棄現場近くのアパートに住んでいたが、今年3月末で退職し、自宅のある福岡県に引っ越しをする作業をしていた。松尾容疑者はごみを捨てる姿を近所の住民に目撃されており、同署が事情を聴こうとしたところ、「令状はあるのか」と拒否。そのまま福岡県に転居していたという。【大沢瑞季】
若手キャリア数人を公立中学校などの学校現場に出向させる方針は良いことだ。
ただ、キャリアであることを伏せて事務職員として勤務させるべきだ。
キャリアであることを伏せることにより、本当の現場の実態を見る機会が増えるはずだ。
他の省だが、キャリアが地方に来ても接待やゴマすりだけ。現場に出る時は事前に
誰かが問題ないことを確認した上で現場に行くようでは本当の現状など見えない。
問題があることを報告されれば困る立場の人間が、事前に調整するはずだ。
文部科学省は、キャリアであることがわかるかも知れないが、キャリアであることを
伏せて出向させるべきである。キャリアの肩書きなしで勤務することも、キャリアの
社会勉強になるだろう。
接待やゴマすりを受けていれば、
広島労働局職員が裏金で厚生労働省のキャリアに接待
したような問題が起こるかもしれない。
厚生労働省のキャリアのように接待やゴマすりを当然と思う悪循環が始まる可能性もある。
「教育現場を知れ」文科省が若手官僚を学校教員派遣へ 02/18/07(読売新聞)
文部科学省は来年度から、将来の教育行政を担う若手キャリア官僚を公立中学校などに教員として出向させることを決めた。
「文科省の官僚は教育現場の実態を知らない」との批判を受けたもので、教壇に立ち、児童・生徒と向き合うことで、現場感覚を養うのが狙いだ。手始めに教員免許を持つ入省7年目以下程度の若手数人を1年間出向させる。
文科省では、入省2~4年目のキャリア官僚が約1か月、市町村教育委員会などで研修したり、ベテラン官僚が県教委の課長や県、市の教育長などに出向したりすることはあるが、教員としての出向は初めてとなる。
文科省は、入省7年目以下の若手官僚のうち、教員免許を持つ十数人の中から、本人の希望を勘案して出向者を決める。将来は、教員養成教育を受けていない社会人を学校現場に採用するために設けられた「特別免許状」制度を利用し、教員免許のない若手官僚も出向の対象に含めることを検討するという。
文部科学省:学校に若手キャリア出向 現場実態把握のため 01/26/07(毎日新聞)
文部科学省は、4月から若手キャリア数人を公立中学校などの学校現場に出向させる方針を固めた。これまで、教育委員会などへの出向はあったものの、学校現場への出向は初めて。出向は1年間で、年3人程度を事務職員として勤務させる見通し。
文科省キャリアは教育行政を預かる立場でありながら、「学校現場の実態を知らない」と批判されることがあり、同省内部からも学校現場への出向を求める声が出ていた。このため、同省は若手キャリアに現場の実態を把握させることにした。【高山純二】
教員1人懲戒免、体罰などで6人を懲戒処分 愛知県教委 02/07/07(朝日新聞)
愛知県教育委員会は7日、窃盗容疑で逮捕された男性教諭1人を懲戒免職にするなど、刑事事件、交通事故、生徒への暴力に関する懲戒処分6件を合わせて発表した。
免職になったのは、同県小牧市立小牧小学校の丹羽久男教諭(56)。昨年11月18日、鉢植えを盗む目的で小牧市の生花店に侵入したところ、店主に取り押さえられた。住居侵入と盗みの疑いで逮捕され、起訴猶予処分となった。
また停職になったのは、同県一宮市内の中学校の男性教諭(26)と津島市の中学校の臨時任用講師(23)。一宮市の教諭は昨年11月16~18日、顧問を務めていた野球部に所属する1年生の男子生徒(13)のほおを平手で十数回たたいたり、腹をけったりした。体罰だったとしている。同県津島市の講師は昨年11月、自家用車を運転中、市内で男子高校生(16)をはね、死亡させた。講師は8日付で依願退職する。
このほか同県幡豆郡の中学校の教諭(41)を、授業中1年生の男子生徒2人の耳を引っ張ったり、頭を平手でたたいたりしたとして、減給10分の1(1カ月)。交通死亡事故を起こした同県豊橋市内の中学校男性教諭(28)を減給10分の1(3カ月)、傷害事故を起こした同県豊田市内の小学校教諭(52)を戒告処分とした。
今後の人生を過ごしていくのは辛いかもしれないが、自殺する必要はなかったと思う。
不祥事を起した社会保険庁及び事務所職員やタウンミーティングでやらせを計画した
文部科学省や法務省職員達は自殺することもなく、のうのうと生きている。処分も
軽かった。学校や教育委員会の問題を公表し、今までとは違う人生を選択してほしかった。
教員試験問題漏えいの元校長、自殺遺体で発見…福岡市 02/04/07(読売新聞)
福岡市立小中学校の教員採用試験漏えい問題で、市教委の桑野素行・元理事(60)(1月18日に懲戒免職)から問題案を聞き出したとされる元市立小学校長(65)が4日午前10時50分ごろ、福岡市西区金武の山中で遺体で見つかった。
遺体の状況から福岡県警は自殺と断定した。
調べによると、遺体は元校長を捜していた親族が見つけた。木の枝にひもをかけて首をつったらしく、死後1か月程度経過しているとみられる。
元校長は昨年12月30日、漏えい問題に絡んで市教委の事情聴取を受けた後の1月1日午前、同市早良区の自宅を歩いて外出した。しかし、帰宅しないため、家族が県警早良署に捜索願を提出。「早良区の山の中で歩いている元校長を見かけた」という目撃情報が寄せられ、県警と市消防局、市教委などが付近の山中などを捜索していた。
市教委のこれまでの調査によると、元校長は昨年7月中旬、福岡教育大の後輩で、試験問題検討委員長だった桑野元理事の理事室を訪問。教員採用2次試験の集団討論や模擬指導などの問題案の中身を聞き出し、問題案自体も受け取った。元校長は、これらを基に予想問題を作成。同大同窓会が主催した事前勉強会で受験予定の卒業生約50人に配ったとされる。
指導力不足:中学校長解任 いじめ対応不十分 大阪・八尾 01/26/07(毎日新聞)
大阪府八尾市教委は25日、いじめに遭った市立中学3年の女子生徒(15)が精神疾患を患い不登校になったのは、学校側の対応が不十分だったためだとして、指導力不足を理由に校長(57)を解任し、研修を受けさせる方針を固めた。文部科学省によると、指導力不足で研修を受けた教諭は05年度だけで全国で506人に上るが、管理職が受けるのは極めて異例。いじめが深刻化する中、校長の管理能力を厳しく問う措置といえそうだ。
関係者によると、女子生徒は昨年5月ごろから、「悪口を言った」などと同級生の女子生徒らからいじめられるようになった。さらに、トイレで制服にせっけんをこすりつけられたり、給湯室で蹴られるなどの暴力も振るわれた。
担任の男性教諭(30)は女子生徒がトイレに連れ込まれているのを知りながら「仲の良いグループのいざこざ」としかとらえていなかった。その後、担任は「教室を見回って(いじめた生徒から)守るから」と、女子生徒に約束したものの、休み時間も1人のまま放置したため、その間にいじめられ続けた。
担任への不信感を募らせた女子生徒は同6月、体調を崩して不登校になり、適応障害などと診断された。学校側が必要な書類を生徒に届けないなどの不手際も重なり、保護者との関係は悪化。保護者は担任との接触を拒否したが、校長は担任をそのまま続けさせ、女子生徒は現在も登校できないという。
このため市教委は、校長の初期の認識の甘さや、保護者の対応を担任ら一部教諭に任せ、組織的なサポート態勢をとらなかったことなどが指導力不足にあたるとして、校長職を解くことにした。
校長は「担任が被害者側の気持ちに立って対応できなかった。一連の問題の責任は私にある。申し訳ない思いでいっぱいだ」と釈明。保護者から相談を受けたNPO法人「子どものための民間教育委員会」(大阪市北区)の良井靖昌代表委員は「信じがたいほど無責任な学校の対応が、いじめよりも生徒を傷つけた。いじめによる不登校の多くは、教諭の無関心や対応の問題が大きい」と指摘している。【大場弘行】
▽村山士郎・大東文化大教授(教育学)の話 いじめ対応にかかわった教諭だけの責任が問われる風潮の中で、管理職の責任をはっきりさせるのは理解できる。だが、学校、市教委がどう指導し、何が問題だったのかや、いじめられた子ども、親の思いを全教員が共有し、真の意味で問題が改善されなければ、子どもは安心して学校に戻れない。首をすげ替えるだけでは本末転倒だ。
教員試験漏えい:理事を懲戒免 再試も見送り 福岡市教委 01/18/07(毎日新聞)
福岡市立小中学校などの教員採用試験漏えい問題で、市教委は17日、教育委員会会議を開き、問題案を元小学校長(65)に漏らした試験問題検討委員会トップの市教委理事(60)を懲戒免職にする方針を決めた。18日の人事委員会に諮り正式決定する。また、「受験生への影響は少ない」と判断し、再試験は実施しないことも決めた。
市教委のこれまでの調査によると、理事は昨年7月下旬~8月上旬ごろ、理事室を訪れた元校長に問題案を手渡した疑いが極めて強い。元校長は問題案を基に予想問題を作成し、試験対策セミナーで配った。
委員会は17日の会議で、理事について「教育者としてあるまじき行為。教育行政への信頼を失墜させた責任は重い」として懲戒免職処分とする方針を決定。植木とみ子教育長らの処分は後日検討する。
また、予想問題を見た受験生と見なかった受験生の得点を比較。この結果、論文では差が1点未満で、科目によっては見なかった方が上回ったケースもあった。【安達一成、米岡紘子】
朝日新聞(2007年1月12日)より
理事、原案手渡す
教員採用試験漏洩 「2次」すべて、元校長に
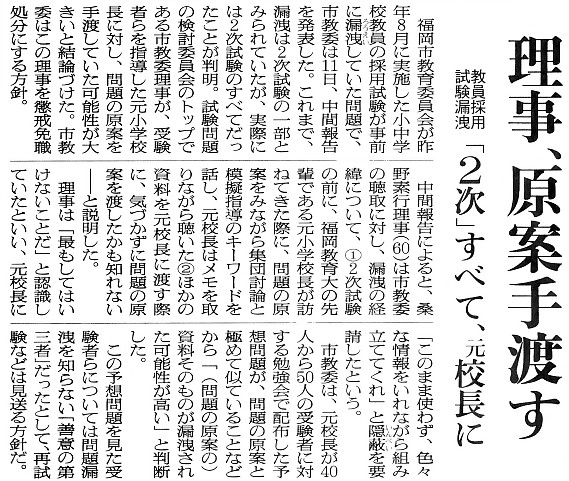
教育者(教諭)の上に立つ者や立った者がこのありさま。子供の問題は、親にも問題は
あるだろう。しかし、モラルの欠如は、教育者のモラルの欠如も原因だろう。
文部科学省や教育委員会の対応の問題
や
必修逃れ
も結果として現れたもの。
タウンミーティングのやらせも低レベルで、国民をばかにした発想。
たしかに日本人は他の国の人達のように、怒らない。諦めはするが批判をしないほうだろう。
だからと言って、やらせを行う職員も情けない。処分も甘い。何とかしろよ!!!
文部科学省職員や教育委員会は、恥ずかしくないのか!恥ずかしくないから、悪いと思わない
人間達だからやっているのかもしれないが、教育の舵取りをする立場の人間としては不適切!
福岡市教委No.3理事、元校長に漏らした疑い 01/06/07(読売新聞)
福岡市立小中学校の教員採用試験2次試験の問題漏えい疑惑で、市教委は6日、市教委ナンバー3の理事(60)が元同市立小学校長(65)に問題案の内容を漏らした疑いが強いと発表した。
2人は福岡教育大(福岡県宗像市)卒業生で先輩、後輩の関係にあり、元校長は、口頭で聞いた内容を基に「予想問題」を作り、同大学の同窓会が卒業生を対象に開いた勉強会で配っていた。
多くの問題が実際の出題とほぼ一致したことから、市教委は、問題案そのものが流出した可能性も否定できないとしている。
漏えいが指摘されているのは、昨年8月22~25日に行われた小中学校教諭の「集団討論」と小学校教諭対象の「模擬指導」の問題案。
市教委が昨年末行った2人への聞き取り調査では、元校長が7月下旬か8月上旬、市教委理事室を訪ねた際、2次試験対策が話題になり、理事は出題テーマとして「障害児学級」など、模擬指導で出題されるキーワードを伝えたという。
調査に対し、元校長は「2次試験に出るとは思わず、聞いた時の記憶と長年の経験を基に予想問題を作成した」と話し、漏えいの認識については否定したという。
しかし、予想問題に記された23テーマのうち、19テーマが実際の出題とほぼ一致。残り4テーマも、理事をトップとして市教委幹部11人で構成する「試験問題検討委員会」で検討後、外されたものだったため、市教委は「記憶だけで問題を再現するのは難しい」として、さらに調査する方針。
また、新たに模擬指導の中学校教諭分にも予想問題があり、大半が実際の出題と同じだったこともわかった。
勉強会は2次試験直前の8月20日、福岡市内の福岡教育大付属小で開かれ、約50人が参加。市教委の調査に対して、うち約20人が予想問題を「見た」と回答した。
元校長は現在、市市民局の非常勤嘱託職員で、今月1日から行方不明。理事は自宅療養中という。
福岡試験問題漏えい:市教委幹部がOBに内容伝達の可能性 01/06/07(毎日新聞)
福岡市立小中学校と養護学校の教員採用試験問題が外部に漏えいしたとされる問題で、試験問題検討委員会の委員を務めている市教委幹部が、市教委のOB職員に問題案の内容を伝えた疑いの強いことが市教委の調査で分かった。このOB職員は市教委から事情を聴かれた直後から行方が分からなくなっている。市教委はこの幹部からさらに事情を聴き、流出経路を含めた問題の全容解明を目指す。
複数の市幹部によると、この幹部は試験問題の作成にかかわっていた。調査委の調べに、事実関係を大筋で認めるような話をしているという。幹部とOB職員は交流が深かった。02年に退職したOB職員は福岡県内の大学出身で、福岡市内の小学校長などを務めた。母校の教職員試験の合格率が最近低下し、懸念していることを周囲に伝えることもあったという。
試験問題検討委員会は市教委幹部ら11人で構成し、毎年行われる教員採用試験2次試験の問題案を作成している。漏えいが指摘された昨年の問題は昨年7月6日に試験問題検討委員会を開いて意見を聞き、同月中旬に問題が決定した。今回、事前に一部学生の間に出回った予想問題と実際の試験問題を照合したところ、7月6日時点の内容が漏えいしたと見られることが分かった。
市教委は昨年末に一部報道機関から試験問題が流出したことを指摘され、植木とみ子教育長ら10人で構成する調査委を設置。これまでに試験問題検討委員会の委員や採用試験にかかわった職員計25人から事情を聴いている。
調査委の調べは昨年末から始まったが、事情を聴かれたOB職員は直後の今月1日から行方が分からなくなった。関係者は自宅近くの駅で顔写真入りのチラシを配るなどして行方を捜し、警察にも捜索願を出している。
朝日新聞(2006年11月6日)より
教員採用問題漏れる 討論・模擬指導のテーマ
福岡市教委
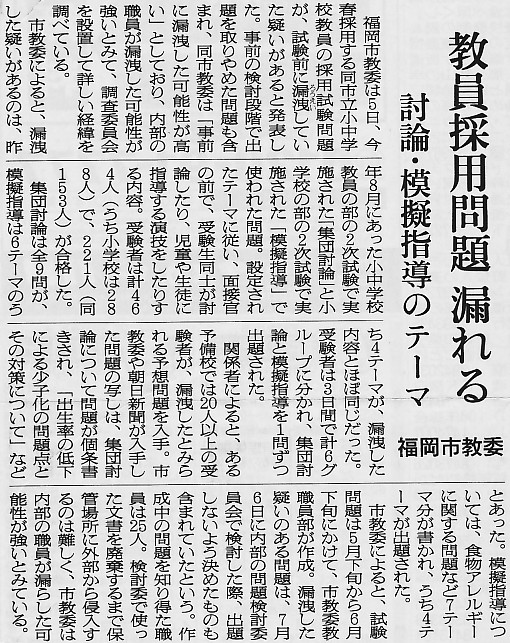
試験問題:小学校と養護学校の教員採用で漏えい 福岡市 01/05/07(毎日新聞)
昨年8月に実施された福岡市立小学校と養護学校の教員採用試験二次試験(実技など)の内容が、事前に漏えいした疑いがあることが5日、分かった。昨年末、一部報道機関から「試験問題と酷似した予想問題が出回っていた」などとする取材を受け、確認した。市教委は調査委員会を設置して漏えいの有無やルートなどを調査中だが、予想問題には作成過程で検討されながら出題されなかった問題も含まれていることなどから、市教委内部から流出した疑いを強めている。
市教委によると、教員採用試験は昨年7~8月に実施。7月21日に1次試験、8月22~24日に小学校教員の2次試験が行われた。漏えいが疑われているのは、2次試験のうち、小学校と養護学校小学部の教員志望者計288人を対象とした「集団討論」と「模擬指導」。その場で示されたテーマに沿って実技を交えるなどして問題解決の技量をみる内容。
昨年8月の2次試験の模擬指導では「早寝早起き朝ごはん運動の指導」「食物アレルギーの子どもが持ってくる弁当に対する級友への対応」「あだ名が発端となったけんかへの対処」--など6テーマが出題され、うち四つが予想問題と一致していた。また、予想問題には出題されなかった予備問や試験作成過程で採用を見送られた問題と同じものが含まれていた。
集団討論では「団塊の世代の一斉退職問題について」など、出題された9テーマのうち七つで本試験と予想問題の内容が重なっていた。【安達一成】
小学教頭、強制わいせつの疑いで逮捕 埼玉・越谷 12/31/06(読売新聞)
埼玉県警越谷署は30日、越谷市七左町7丁目、三郷市立小学校教頭の勝又春夫容疑者(57)を強制わいせつの疑いで逮捕した。
調べでは、勝又容疑者は同日午前1時ごろ、東武伊勢崎線新越谷駅で、タクシー待ちをしていた同市の無職女性(43)に「一緒にホテルに行こう」と声を掛けたが断られたため、女性に後ろから抱きつき、近くの雑居ビルのシャッターに押しつけて胸や下半身を触った疑い。
勝又容疑者は酒に酔っており、「申し訳なかった」と認めているという
試験問題:生徒にファクス 高校教諭懲戒免職処分 奈良 12/27/06(毎日新聞)
奈良県教委は27日、解答例が記入された期末試験問題を生徒宅にファクス送信したとして、県立御所工高の男性教諭(34)を懲戒免職処分(同日付)にした。
同教委によると、この教諭はラグビー部の顧問で、今月7日、電気機器科担当の同僚教諭のロッカーから、翌日の期末試験の問題用紙を勝手に取り出し、コピーして2年生の男子部員宅にファクス送信した。1回で送信できず、ファクス機にエラー報告があったため、他の教諭が不正に気付いた。
教諭は生徒に電気機器の補習を頼まれていたが、用事があったため断り、ファクスを使って質疑応答をするつもりだったという。学校の事情聴取に、「生徒と約束した補習が出来ず責任を感じていた。電気機器の授業は受け持っていないため、同僚の授業用プリントを参考にしてもらうつもりだった」と釈明した。
同校によると、この生徒は受け取ったものが試験の問題用紙と認識せず、同級生1人にも内容を見せていた。このため2人は再試験を受けた。【石田奈津子】
小学校教諭を窃盗容疑で逮捕 山口・岩国 12/27/06(朝日新聞)
山口県警岩国署は26日、広島県呉市の市立小学校教諭加藤潔己(きよみ)容疑者(48)を窃盗容疑で逮捕した。
調べでは、加藤容疑者は25日午前7時ごろ、山口県岩国市麻里布町1丁目の知人男性(26)方に入り込み、現金約2万7000円やキャッシュカードなどを盗んだ疑い。容疑を認めているという。
呉市教委によると、加藤容疑者は4月から病気で休んでいたという。
研究不正関与、2─10年助成せず…厚労省が指針案 12/27/06(読売新聞)
厚生労働省は、研究データのねつ造、改ざん、盗用といった研究不正に関与した研究者に対して、2~10年間、研究助成しないなどの罰則を柱とする不正対策の指針案をまとめた。
文部科学省の対策指針に準じた内容で、来年度の厚生労働科学研究費補助金取扱規定などに盛り込む予定。
罰則は、不正に関与した研究者だけでなく、不正に関与しなくても、不正があった研究論文に責任を負う研究者も対象。その場合、研究資金の申請を1~3年受け付けない。
産業創造研究所、人件費4億6900万円を過大請求 12/26/06(読売新聞)
経済産業省と文部科学省は26日、研究開発事業を委託した財団法人「産業創造研究所」(理事長=田村滋美・東京電力会長)が人件費4億6900万円を過大に請求したとして、全額を返還させると発表した。
同研究所は、放射性廃棄物の地下埋設処分の委託研究など26事業で、人件費を重複して請求していた。経産省は今後1年間、研究の委託を停止する。文科省は検討中。
今年5月、経産省の会計検査で、同研究所の出張記録と勤務状況を示す労務日誌の記載が矛盾する事例が発覚。記録が保存されている過去5年分(2001~05年度)について勤務実態を立ち入り調査したところ、人件費請求の根拠になる労務日誌の管理がずさんで、1日分の勤務で2日分の人件費を請求するなどの不適切な処理が大量に見つかった。労務日誌が委託事業ごとに作成されていたため、国もこうした重複請求に気付かなかった。
国は不正な蓄財や流用はなく、研究の必要経費として使用されていたとして、意図的な重複請求はなかったと判断。処分は、過大請求された経産省所管の3億2900万円と文科省所管の1億4000万円の返還と、委託停止にとどめた。
1959年に設立の同研究所は、電力会社やガス会社などが母体となっており、職員は70人弱。原子力材料研究、カーボンナノチューブ、ディーゼルエンジンの排ガス浄化システムなどの研究に取り組んでいる。
経産省研究開発課は「労務日誌のずさんな管理に弁解の余地はない。ただ、研究者たちに聴取した範囲では、だまし取るという悪意は感じられなかった」と説明している。一方、同研究所は「関係機関に多大なご迷惑をかけ、誠に申し訳ない。過大請求はすみやかに返納する」と話している。
出向していた文科省職員も処分対象に入れるべき。そうでなければ、やはり、文部科学省
も責任がある体質である。見て見ぬふりをした、報告をしなかった文科省職員を許すと
解釈されても仕方が無い。結局、文部科学省も問題体質の組織であることを見てみているような
ものである。
単位不足問題:教育長らに教員の厳正処分求める 文科省 12/22/06(毎日新聞)
高校での単位不足問題で、文部科学省は22日、都道府県、政令指定都市の教育長らに対し、学習指導要領を順守していなかった教員らを法令に照らして厳正に処分するよう求める通知を出した。
通知では「故意に法令に違反した」「過去に同様の処分を受けながら再度不適切な行為をした」場合などに厳正な処分を求めた。公平性を保つため、具体的な処分事例を示すことも検討したが「(文科省は)任命権者ではなく、法的根拠もない」(初等中等教育企画課)として見送った。
都道府県教委に出向していた文科省職員が処分対象になった場合については「通知の趣旨が違う」として触れていない。文科省職員が処分対象になった場合の対応策は決まっておらず、地方だけに処分を要求する形になった。【高山純二】
◇
大阪府の千里国際学園▽清風南海▽大阪国際大和田の私立3校で22日、履修単位不足が判明した。毎日新聞の独自集計では、熊本県を除く678校(公立372校、私立306校)となった。
朝日新聞(2006年12月14日)より
TM調査委 最終報告書(要旨)
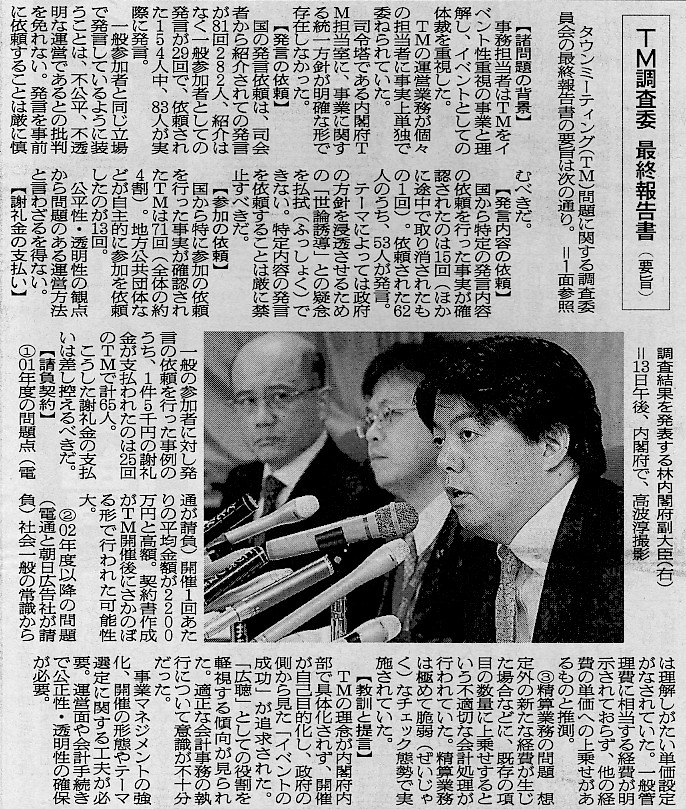
京大の教員でさえも下記のコメントをした主婦のように
考えることが出来なかった。頭が良いだけでは、国の
操り人形になる。良い例であろう。
朝日新聞(2006年12月12日)より
基本法改正で悲鳴が聞こえる
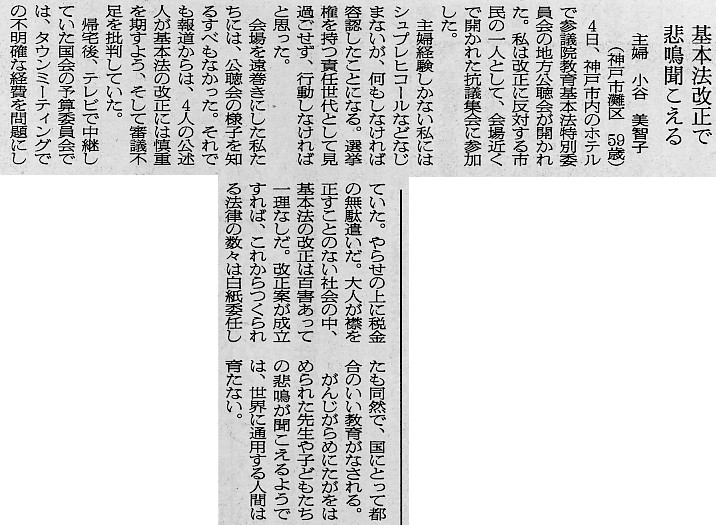
京大の教員の対応に対し、がっかり。頭が良くても
クリティカルな考え方は出来ないようだ。
朝日新聞(2006年12月14日)より
TM京都で応募者排除
京大で教員がやらせ質問
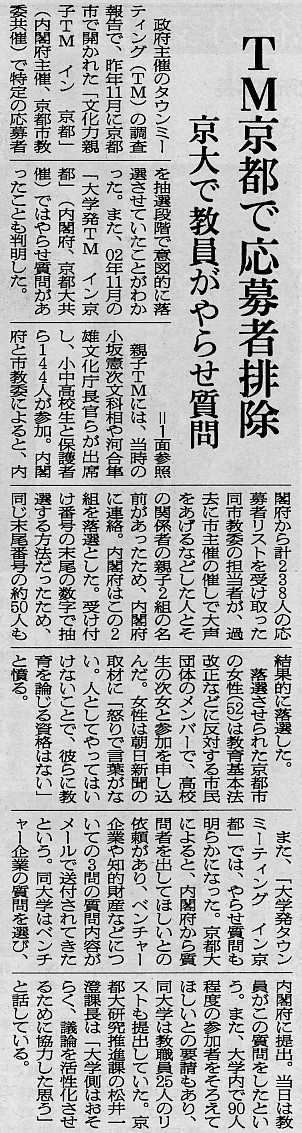
朝日新聞(2006年12月8日)より
いじめ自殺ゼロ「警察統計と違う」
文科省、指摘に対応せず
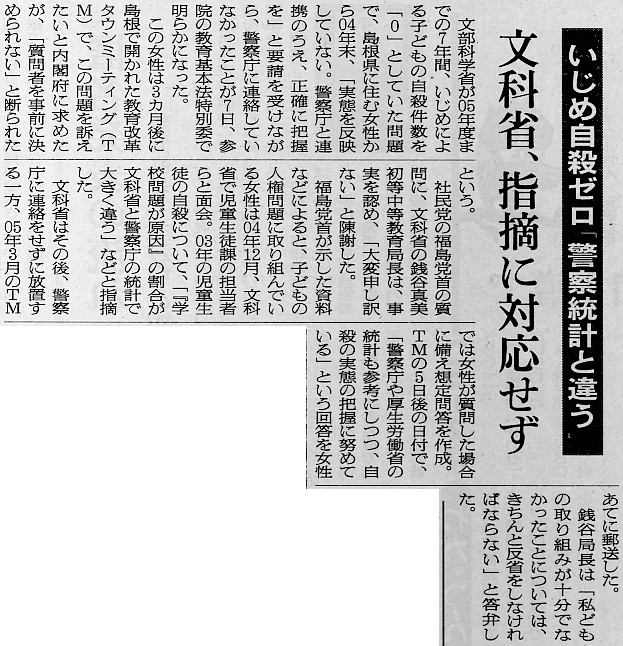
本当に腹が立つし、情けない!
偏差値だけ、テストの点だけ、大学の合否だけに重点を置く学校の姿勢が、
不祥事を起す大人の形成の原因の一つであろう。良い大学を卒業しても
自己の出世などのために、問題を隠蔽したり、タウンミーティングで
やらせを考えるキャリアもいる。良い大学を卒業したかもしれないが、
人間として最低のレベルに属する人間である。しかし、卒業生の進学率や
有名大学の進学率とも関係ない。目先だけにとらわれる。日本社会は
病んでいるのかもしれない。
都立高「必修逃れ」140校以上で出席簿も不正確 11/27/06(読売新聞)
東京都教育委員会が都立高の必修科目の履修漏れを容認していた問題で、都教委の調査の際、全日制と定時制を合わせて延べ140校以上の都立高で、出席簿に不適正な記載が見つかっていたことがわかった。
目立つのは、生徒が複数の教室に分かれて授業を受ける「選択科目」や、必修科目の「総合的な学習の時間」での不備。都教委では出席簿を基に履修漏れにあたるかどうかを判断しているが、「総合学習」の出席状況などについては不透明な部分も残されている。
出席簿は、学校教育法などで正確な記入が義務付けられている。選択科目の授業では、それぞれの担当教員が手持ちの補助簿などに生徒の出欠を控え、授業後すみやかに学級ごとの出席簿に転記することになっている。学校側は、生徒が所定の出席日数を満たしているかどうかを、出席簿で確認する。
都立207校全校に対する都教委の調査では、全日制(191課程)の100校以上、定時・通信制(100課程)の約40校で、補助簿と出席簿とで、出欠が違っていたケースなどが見つかった。
特に、テーマ別の授業や校外学習が多く、1学級に5人以上の教員がかかわることもある「総合学習」では、出欠の実態がわかりにくくなっていたという。
目黒区のある高校では昨年度、3年次の総合学習の時間を最終の6時限目に設定。夏から秋にかけての約2か月間は大学のオープンキャンパスの見学にあてたが、生徒が参加したかどうかを確認しないまま、リポート提出で出席扱いにしていたという。「総合学習の時間に下校させている学校もあったと聞いた」と話す校長もいる。
「総合的な学習の時間」については、進学校を中心に20校前後が、英語の「長文読解」や「ヒアリング」など、受験対策色が濃い授業が組まれるなどしていたことが判明している。
文部科学省の調査でも、総合学習で履修漏れとされた事例はなく、都教委は改善指導にとどめる方針だが、出席簿が不適正なことは履修漏れ隠しにもつながりかねないと判断。各校長に対し、11日付で出席簿の適切な記入を定期的に点検することなどを求める通知を出した。
日本では実際の仕事以上の周りの環境や人間関係からのストレスで疲れると聞くことが多い。
文部科学省や教育委員会が現場を把握せず、いじめ問題や必修逃れを長期の間、放置したように
非効率、体裁のため、そして理論や理想だけで指示したり、辻褄合わせを要求しているから
これらも問題であろう。先生と呼ばれる人達と話すと考え方がサラリーマンの人達と違うと
感じることが多い。教育や環境でこのような考え方になるのかもしれない。
休職教職員:精神性疾患が6割 北海道教委が明らかに 12/12/06(毎日新聞)
札幌市を除く公立の小・中学と北海道立の高校、養護学校などで、05年度に病気で90日以上休職した教職員のうち、精神性疾患によるものが59.7%に上ることが分かった。この割合は95年度27.1%、99年度42.0%、02年度51.8%と年々増加。専門家は「まず多忙さがある。さらに子どもたちが荒れ、保護者、同僚、管理職との関係悪化などがあり、複合的なものが要因」と指摘する。
11日の道議会予算特別委員会で荒島仁道議(公明党)の質問に対し、道教委が明らかにした。
道教委教職員課によると、05年度に病気で休職した教職員は211人。このうち精神性疾患は126人に上った。95年度は42人だった精神性疾患患者は、99年度には84人となり、02年度は120人。02年度以降、休職者数は微減したが、精神性疾患患者は増えている。
同課は「社会の変化や保護者からの期待が高まる一方で、多くの業務を抱えてストレスを感じている」と話す。道教委では昨年度、教職員のメンタルヘルス計画を策定。啓発冊子の配布やセミナー開催のほか、「心の健康相談室」を札幌市内に設置。教職員や家族が気軽に相談できるよう専門スタッフを配置した。
市民団体「教師を支える会」代表の諸富祥彦・明大教授(教育カウンセリング)は「書類作成の雑務など無意味な多忙さをまずやめること。保護者と管理職が現場の教職員を応援する形で環境を改善し、同僚や管理職に弱音が吐ける環境を作る方が急務だ」と指摘している。【内藤陽】
少女買春:容疑の中学教諭を再逮捕 山形 11/28/06(毎日新聞)
出会い系サイトで知り合った高校3年の女子生徒(17)を買春したとして、山形県警米沢署は28日、同県南陽市若狭郷屋、市立宮内中学校教諭、竹田智哉被告(38)=強要未遂罪で起訴=を児童買春禁止法違反容疑で再逮捕した。
調べでは、竹田容疑者は10月下旬、県内の女子生徒に1万円を払い、山形市内のホテルでみだらな行為をした疑い。
竹田容疑者は同時期に、同様に知り合った中学2年の女子生徒(14)から裸の画像を入手、「会わなければ写真をばらまく」などとメールを送ったとして起訴されている。押収した携帯電話の履歴などから今回の事件が発覚した。【大久保渉】
タウンミーティング質問依頼、八戸市教委も5人を処分 11/27/06(読売新聞)
青森県八戸市で9月に開かれた教育改革タウンミーティングで、内閣府などが参加者に質問を依頼した問題で、八戸市教委は27日、「市民の教育行政に対する不信を招いた」として、東森直人・教育政策課長ら職員5人を訓告処分とした。
松山隆豊教育長は「自由な意見交換の場であるタウンミーティングに与える影響を考えるべきで、職務遂行上の注意が足りなかった」と話している。
八戸市教委は、教育基本法改正案賛成の立場で質問者を探すよう内閣府から要請され、2人に質問を依頼。県教委にも1人を探すよう依頼し、計3人のリストを内閣府に送った。
県教委は20日に職員6人を訓告処分としている。
小中学校の先生の残業、平均は2時間8分…文科省調査 11/24/06(読売新聞)
文部科学省は24日、公立小中学校の教員を対象に行った勤務実態調査の結果を、中央教育審議会の作業部会で公表した。
教員一人の平日の勤務時間は平均10時間58分、平均残業時間は2時間8分だった。今回の調査は、政府が昨年に打ち出した公務員の人件費削減方針に伴って実施されたもの。中教審は今後、一般の公務員より高めに設定されている教員の給与水準が妥当かどうかの検討を進める。
教員の基本給は、優れた人材を確保する目的などから、一般の公務員より高めで、残業手当はないものの、基本給の4%にあたる金額が毎月「教職調整額」として一律に支給される。これらを合わせた給与は、大学卒の42歳平均で毎月約41万円で、一般公務員より約2・7%高い。
今回の調査は、全国延べ約5万人の教員の今年7~12月の勤務実態を調べ、この日は7、8月分が暫定結果として公表された。
それによると、小学校では、平均勤務時間は10時間37分、平均残業時間は1時間47分。また、1日に45分設けられている休憩時間のうち、平均9分しか使っていなかった。残業とは別に、テストの採点など自宅での業務時間は53分だった。
中学校では平均勤務時間が11時間16分、平均残業時間は2時間26分、自宅の業務時間は27分だった。夏休み期間の8月は、小中学校とも平日に毎日平均8時間以上勤務していた。
個人別に見ると、平均残業時間が7時間42分(中学校)に及ぶ教員がいる一方で、ゼロの教員も2、3%いるなど、個人差が著しいこともわかった。
このため、この日の作業部会では、「教職調整額を一律に支払うのではなく、残業時間に応じて変えるべき」などの意見が出た。
いじめの背景に親の教育不在あり65%…読売調査 11/19/06(読売新聞)
読売新聞社が11、12日に実施した全国世論調査(面接方式)で、いじめが原因とみられる子供の自殺が相次ぎ、いじめが大きな問題となっている背景を八つの選択肢の中から選んでもらったところ(複数回答)、「親が社会のルールを教えていない」が65%で最も多かった。
次いで、「他人の痛みを思いやることができない」(55%)「親が子どもの悩みを把握できていない」(52%)の順で、家庭での教育の問題が大きいと考えている人が多かった。
4、5位は、「教師の指導力や資質に問題がある」(48%)「学校が責任逃れをして問題を隠す」(45%)だった。
全国の高校で起きた「必修逃れ」の問題で、文部科学省が決めた救済策について、「納得できる」と答えた人は、「どちらかといえば」を合わせて59%に上った。「納得できない」は計36%だった。文科省の救済策では、70時間を上限に本来受けるべき補習授業の時間数を減らすことにしている。
10月に発足した安倍首相の諮問機関「教育再生会議」(野依良治座長)については、「期待している」が計58%で、「期待していない」(計38%)を上回った。
男女別にみると、「期待している」は、女性(62%)が男性(54%)より多かった。年代別では、30、40歳代の「子育て世代」と70歳以上が、いずれも62%と高かった。
「同本部の事務を統括する田中壮一郎生涯学習政策局長らについて『(やらせを)
知らなかったでは免責されない』」
やらせを考え、実行させたのは誰なのか公表するべきである。公表できないような
調査しか出来なのであれば、、田中局長ら同本部の責任者の処分を重くするべきだ。
やらせ質問:基本法改正本部の責任者処分へ 伊吹文科相 11/14/06(毎日新聞)
伊吹文明文部科学相は14日の閣議後の会見で、教育改革タウンミーティングの「やらせ質問」を
文科省広報室長(当時)が作成した問題で、広報室長は省内に設置した「教育基本法改正推進本部」の
事務局メンバーとして質問を作成し、」を主催する内閣府に提出していたとの見解を
示した。同時に、同本部の事務を統括する田中壮一郎生涯学習政策局長らについて「(やらせを)
知らなかったでは免責されない」と述べ、田中局長ら同本部の責任者の処分を検討する考えを示した。
同本部は、基本法改正案の提出を受けて5月に設置。官房総務課や広報室、生涯学習政策局から
約25人の職員を事務局に集め、基本法改正の必要性を訴える広報活動や、国会審議に絡む答弁の
取りまとめなどを行っている。【竹島一登】
「教育改革タウンミーティングの「やらせ質問」問題で、文部科学省広報室長(当時)が
質問案を作成していたことが分かった。同室長は安倍内閣発足後、首相官邸の公募スタッフに
採用され、現在は山谷えり子首相補佐官(教育担当)付の内閣参事官を務めている。」
内閣参事官を辞めさすべきだ!自分がやったことについて理解でいているだろう。
理解できないのであれば、優秀であろうとも大事な仕事を任せるべきでない!!
非常識なことに対して誰も意見を言えない組織(文科省)だからこそ、いじめ、必修逃れ、
学力低下、大学への助成金不正問題、その他の問題を引き起こす舵取りしか出来ないの出だろう。
やらせ質問:文科省広報室長が質問案を作成 処分検討も 11/13/06(毎日新聞)
青森県八戸市で開かれた教育改革タウンミーティングの「やらせ質問」問題で、文部科学省広報室長(当時)が質問案を作成していたことが分かった。同室長は安倍内閣発足後、首相官邸の公募スタッフに採用され、現在は山谷えり子首相補佐官(教育担当)付の内閣参事官を務めている。
塩崎氏は13日の記者会見で「文科省で調査している。調査を見てから判断する」と述べ、処分も検討する考えを示した。伊吹文明文科相は同日、「上司の了解を取らずにやったことではないと思う」と語った。
「一方、札幌市で5月に「再チャレンジ」をテーマに開かれたタウンミーティングで内閣府が
北海道庁に質問者の推薦を依頼していた問題については、「発言者が全くいないのでは困るので、
キックオフ・スピーカーをお願いしたということ。基本的に問題はない」と述べ、議論活性化の
ために質問を依頼するだけなら問題はないとの認識を示した。」
こんな言い訳をするのか????発言者がいなくて困るのであれば、推薦でなく質問者を
募集するべきだろう。質問する人の内容によっては、いろいろな効果も期待できる。
まあ、日本はこんな程度なのだろう。
やらせ質問:民間有識者ら交え調査チーム設置へ 官房長官 11/13/06(毎日新聞)
塩崎恭久官房長官は13日の記者会見で、政府主催のタウンミーティングでの「やらせ質問」問題を調査するため、民間有識者らを交えた調査チームを設置する方針を明らかにした。今週前半にもメンバーを公表する。
塩崎氏は会見で「きっちりうみを出し切る観点で指導いただける方を念頭に人選を進めている」と語った。ただ調査結果をまとめる時期については「大変な分量でよく分からない。国民にはできるだけ早く答えは伝えたい」と述べるにとどめた。
一方、札幌市で5月に「再チャレンジ」をテーマに開かれたタウンミーティングで内閣府が北海道庁に質問者の推薦を依頼していた問題については、「発言者が全くいないのでは困るので、キックオフ・スピーカーをお願いしたということ。基本的に問題はない」と述べ、議論活性化のために質問を依頼するだけなら問題はないとの認識を示した。【西田進一郎】
タウンミーティング質問案を指示した職員及び文科省の広報室長に
タウンミーティングにかかった費用の半分を払わせろ!退職金でも良いし、
月々の給料からの徴収でも良い。出来ない職員は懲戒免職にしろ!!
こんな非常識で国民を馬鹿にしたことを企画し、了承した税金泥棒の公務員は
必要なし!!国の予算が国債(借金)でまかなわれて、国民に負担を負わせている
現状で、非常識すぎる!!こんな職員を残しても問題を引き起こすか、税金の
無駄遣いである!!出来ないのなら文科省職員の3分の1を2年間で減らせ!!
職員を置くだけ税金の無駄である!現状の教育問題の責任の一部は、文科省職員にあり!!
タウンミーティング質問案作成 文科省の広報室長了承 11/11/06(産経新聞)
政府主催の「教育改革タウンミーティング」で政府側が参加者に質問を依頼していた問題で、発覚のきっかけとなった青森県八戸市のケースでは、文部科学省の広報室が質問案を作成し当時の室長が了承していたことが10日、衆院教育基本法特別委員会の質疑で明らかになった。文科省の田中壮一郎生涯学習政策局長が明らかにした。文科省が質問案を作成したのは計3回に上る。
伊吹文明文科相は関係者の処分について「最後まで調べて私が判断する」と述べ、省内での調査を踏まえて処分を検討する考えを示した。
計8回の教育改革タウンミーティングで政府側から質問案の事前依頼があったのは岐阜市、松山市、和歌山市、大分県別府市、八戸市の5回。このうち、岐阜市と松山市のケースでは、教育基本法改正を担当する文科省の教育改革官室が質問案を作成し、同室長が了承した。
内閣府が青森県などを通じてとりまとめた参加実態では、八戸会場の参加者465人のうち、過半数となる279人の教育関係者が動員され、応募による一般参加者は186人に過ぎなかった。同会場でのタウンミーティングは文科省の生涯学習政策局からの要請がきっかけで開催の運びとなり、文科省と連絡を取り合った内閣府の担当者は文科省からの出向者だった。
朝日新聞(2006年11月11日)より
タウンミーティング 参加の半数「関係者」
八戸 県・市が取りまとめ
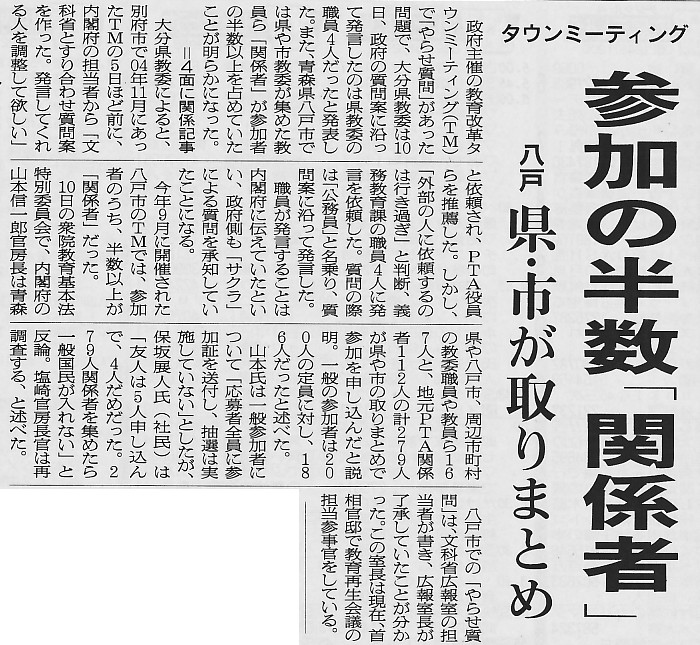
朝日新聞(2006年11月11日)より
文科省、責任逃れに躍起
必修漏れややらせ質問 教育基本法影響を懸念
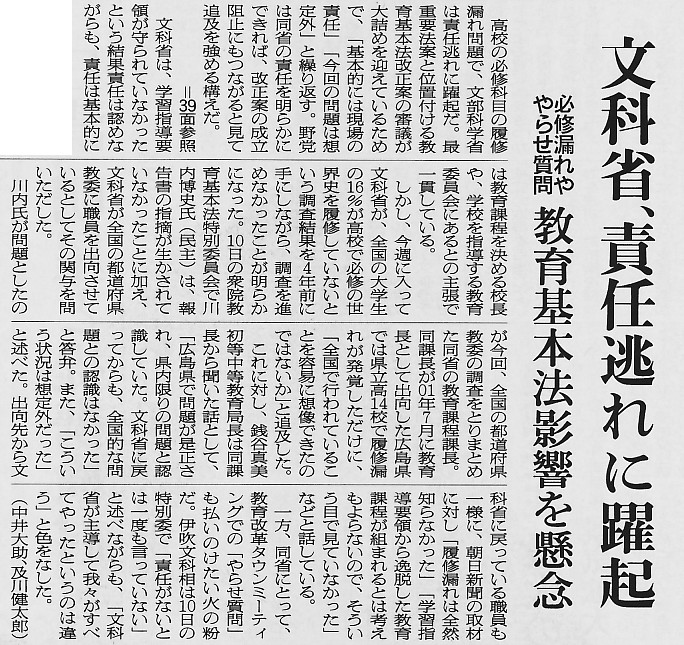
中国新聞(2006年11月11日)より
やらせ質問 関係者まとめて処分
文科相言及 広報室長関与も判明
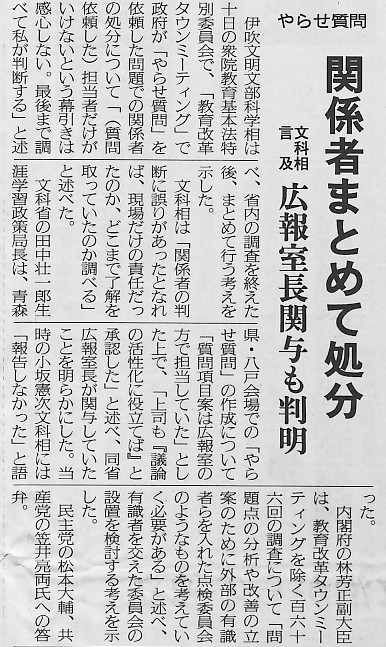
朝日新聞(2006年11月10日)より
教育改革タウンミーティング やらせの裏に文科省
八戸 発言10人→うち依頼6人→うち文案2人

朝日新聞(2006年11月10日)より
教育改革タウンミーティング
やらせ質問 8回中5回 政府、担当者を処分へ
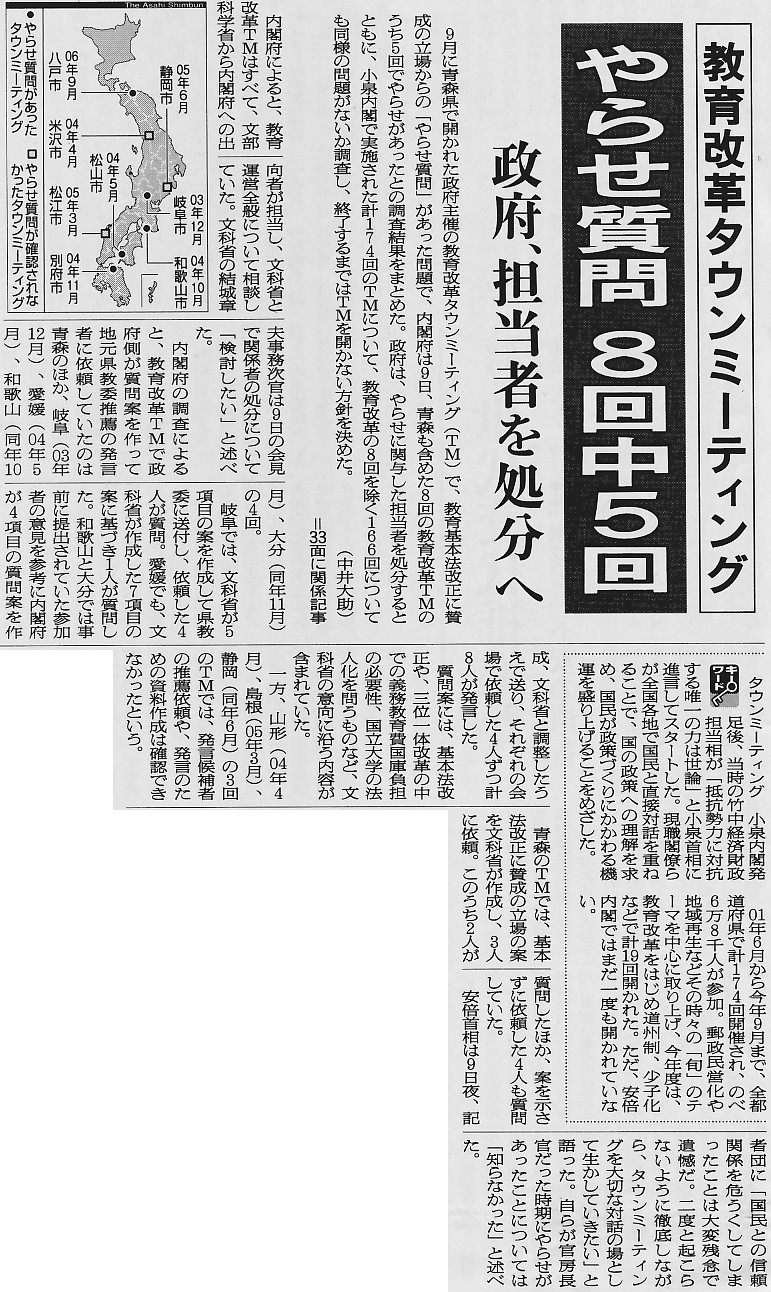
朝日新聞(2006年11月9日)より
やらせ質問
民意をなめるな
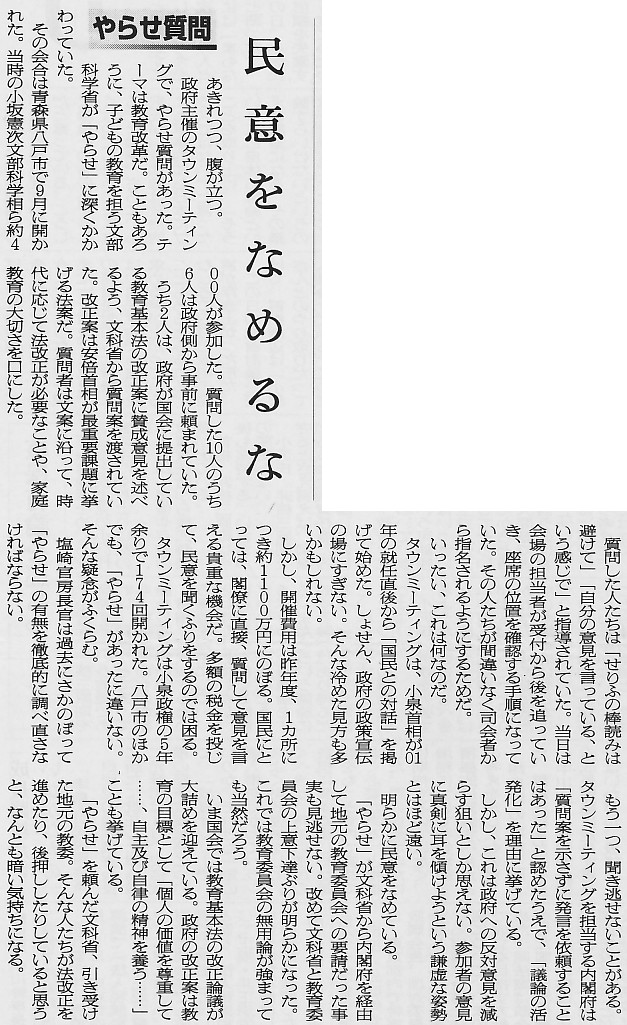
中国新聞(2006年11月9日)より
文科省 報告見過ごす
02年大学生研究会調査 世界史履修漏れ16%
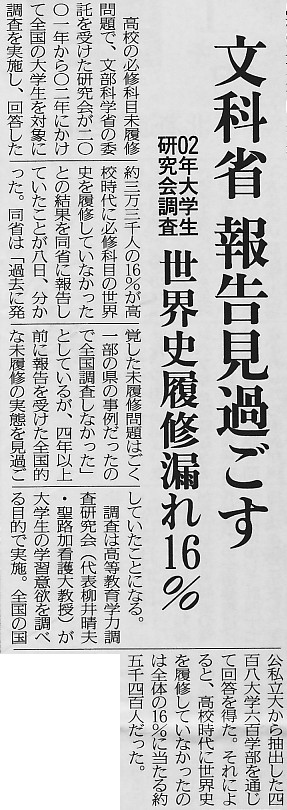
中2女子の裸写メールで交際強要、中学教師逮捕…山形 11/05/06(読売新聞)
山形県警捜査1課と米沢署は5日、同県南陽市立宮内中学校教諭竹田智哉容疑者(38)(南陽市若狭郷屋)を脅迫容疑で逮捕した。
調べによると、竹田容疑者は10月下旬、携帯電話の情報交換サイトで知り合った同県米沢市内の中学2年の女子生徒(14)に自分の裸の写真をメール送信させ、「一度会ってほしい。あの写真をばらまいてもいい。学校にばれたらやばいでしょう」とのメールを返信して脅迫した疑い。
竹田容疑者は10月中旬から女子生徒とメールのやり取りを始め、まず自分の裸を撮影して女子生徒に送りつけたうえで、同様の写真を送るよう要求していた。竹田容疑者は同中で数学を担当、2年生の担任を務めている。
中国新聞(2006年11月4日)より
甘く見られている国民
「やらせ」質問
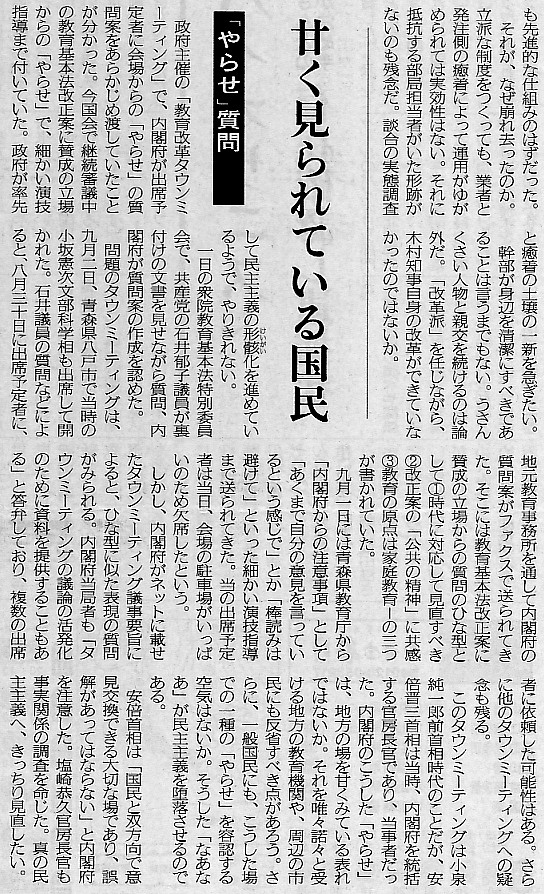
教育委員会を廃止して、一から始めろ!
機能していない!機能していない以上、古いものは捨て、
一から始めるのが良い!
いじめの学校対応に不満増 生徒側から法務省へ申告 10/31/06(産経新聞)
「いじめに対する学校や教師の対応が不十分で人権侵害を受けた」とする生徒側から全国の法務局への申告件数が、平成17年までの4年間で235件増加していたことが31日、分かった。長勢甚遠法相が同日の閣議後記者会見で明らかにした。
いじめが減少傾向にあるとする文部科学省の調査と比較して、長勢法相は「統計の取り方が違うのかもしれないが、悲惨な事件につながることもあり、各省と連携して対応していかなければならない」と述べた。
法務省によると、申告件数は▽13年481件▽14年524件▽15年542件▽16年584件▽17年716件。
「学校に訴えたが『事実はない』と言って取り合わない」「担任教師がその場限りの対応しかしない」などと学校側の対応の悪さを指摘する内容のほか、「先生が自分の嫌いなあだ名で呼び続ける」といった教師がいじめに加担しているケースもあった。
また法務省は同日、緊急に実施した「いじめ問題強化週間」(10月23日~29日)に、「子どもの人権110番」に寄せられた相談件数をまとめた。全国の法務局に寄せられた相談は1369件で、うち「いじめ」に関する相談は647件だった。
具体的には、中学2年の男子が同級生から「死ね」と言われ、担任教諭に相談。教諭は「死ね」と発言した同級生に事実を確認した上で反省文も書かせたが、その親から事実を否定する抗議を受け、学校側が「いじめ」の認定を躊躇(ちゅうちょ)しているケースなどがあった。
岐阜中2自殺の件で校長のコメントをテレビで見たが、ほんと日本の教育関係者は
だめな人間が多いことを実感した。これじゃ、平気で虚偽報告や成績書改ざんをするわけだ。
こいつらは偽善者の代表と言っても良い。偉そうな事を言っているが、尊敬に値しない
人間。常識から外れている。これで一般よりも良い給料を貰い、偉そうにしているのか?
文科省もひどいな!怠慢だ!!校長や教育委員会の処分について何も言わない!
こんな奴らでは何を期待できるのか?結果や実績で評価されると、偽造する、隠蔽する。
これは人間として最低のレベルである。その最低のレベルの人間が教育関係者。
このようなことしかできない人間が子供を教育すること自体、間違っていないか!
圧力があれば、虚偽報告、改ざん、そして隠蔽する教育関係者が多く存在すること自体、
既に日本の教育は間違っていたことを示している。
今回、適切な対応が取れないのであれば、2~3割の教育委員会の人間及び校長の給料を
3年間、2~3割カットしろ。税金泥棒だ!!だめな人間は切る!そうでないと、全てが
腐る!!今回、よくわかっただろ、文科省!文科省だけで改革できるか?出来ないと思う!
岐阜中2自殺:クラブ内で日常的にいじめ 友人が証言 10/31/06(毎日新聞)
岐阜県瑞浪市の市立中学2年の少女(14)が今月23日に自殺した問題で、少女の友人たちが30日、少女がバスケットボールクラブ内でチームメートから日常的に受けていたいじめの実態を明らかにした。近距離からボールをパスして受け取れないと笑ったり、仲間外れにしていたという。30日も2度に及んだ会見でいじめの事実をあいまいにした学校側の対応についても、友人たちは「同じクラスの人たちはいじめがあったと考えている。(少女が)可哀そう」と口をそろえた。
友人たちによると、遺書で名前を挙げられた4人は、練習で少女からのパスをわざととらなかったり、練習後に最後まで後片付けをさせるなど、少女を下級生と同様の扱いにしていた。ある友人は少女について「人一倍まじめで責任感も強いクラスのリーダー的存在だった。良く練習もしていたのに」と唇をかんだ。
また、学校は少女の自殺後、「少女への手紙」という題で生徒らに作文を書かせていた。学校は少女の家族に、生徒らへのアンケートでいじめの事実が確認できなかったと説明していたが、友人の一人は「死んだ人に悪口言う人なんていない。学校は自分を守るようなことばかり言っている。学校が(いじめを)認めないと学校は良くならない」などと批判した。
少女のロッカーの中には図書館で借りたらしい「生きる」というタイトルの詩集があった。ある友人は「自分を慰め、勇気づける内容の詩だった。自殺するほどの苦しみに、私が気づいてあげられればよかった」と声を震わせた。【稲垣衆史】
◇1年生部員が退部…学校側は対策取らず
自殺した少女が在籍していたバスケットボールクラブで、1年生部員が他の部員との人間関係の悩みを訴えて退部していた問題で、学校側が「いじめは見られない」などとして対策を取っていなかったことが30日、分かった。生徒側から“シグナル”が送られていたにもかかわらず、クラブ内にまん延していたいじめを学校側が見過ごしたことが今回の悲劇を招いた格好だ。
学校の説明などによると、1年生は今月19日、「部活動でつらい思いをしている」などと自分の担任に訴えて退部を希望、2日後に退部した。17日には自殺した少女の家族も担任や部活顧問の教諭に「練習後に迎えに行った際、泣き出した」と相談していた。しかし顧問は相次ぐ訴えにも「練習で生徒に接した限り、明確ないじめは見られない」として、他の部員に具体的な指導をしなかった。顧問は30日午後に学校で開いた会見で「いじめを発見できていれば、こういう結果にならなかったかもしれないが、練習の中では兆候が見られなかった」と弁明した。
この1年生の問題については、校長が会見で「6月ごろに担任から聞いた。いじめと考えている」と述べたのに対し、担任は「10月19日に家庭訪問して初めて知った」と食い違いを見せ、校内のいじめに対する情報の共有や共通認識の欠如をさらけ出した。【浜名晋一、安達一正】
会見迷走、いじめの有無で二転三転…岐阜・中2自殺 10/30/06(読売新聞)
岐阜県瑞浪市の市立瑞浪中学校2年の女子生徒(14)が自殺した問題で、学校側は30日、午前と午後の2回にわたって佐々木喜三夫校長(58)らが記者会見したが、いじめがあったかどうかについての見解が、二転三転した。
佐々木校長は、午前の会見で、「言葉によるいじめはあった」としたが、午後には「自殺につながるようないじめはなかった」と話し、迷走を繰り返した。
学校側は女子生徒の自殺後、佐々木校長や学年主任らが再三、女子生徒の自宅を訪問。27日夜に訪れた際には、学年主任がいじめがあったことを認める発言をした。ところが、29日午前の会見で佐々木校長は「いじめは確認できていない」とし、30日午前には「(学年主任は)長時間にわたるやりとりで、意識がもうろうとして事実を確認せずにいじめがあるように表現した」と述べた。
さらに30日午前の会見で佐々木校長は、「『うざい』、『きもい』と、からかういじめはあった」と認める一方、「それが自殺に結びついたかは確認できていない」とした。午後の会見では一転して「自殺につながるようないじめはなかった。(自殺につながらないいじめも)見当たらない」と話すなど混乱した。同席した同市の尾石和正・教育長(64)は「情報が整理されていない。もう少し時間をかけて、事実関係の把握に努める必要がある」と述べた
学校か、教育委員会の人間に責任を取らせろ!!
「伊吹文科相は未履修問題について『管理権、人事権が(文科相に)ないとはいえ、
結果責任の一端はわたしが負う』と述べた。」
文科省に責任が無いのなら、誰の責任なのか、誰が責任を持って管理及び監督する
ようになっていたのか??どのように誰(組織)が責任者を処分するのか?
こんな状態でよく日本の教育はすばらしいと言ってきた人間達がいるものだ?
結果は良くても、モラルなど無い教育関係者がたくさん存在し、学校や教育委員会の
チェックは誰がするのか明確になっていないことになる。
ホリエモン、万歳!!君は学校教育の先を走っていたんだ!結果なんだよ。この国は!
建前と本音は全く違う。人を蹴落とし、人を欺き、人を傷つけても勝者になれば、
誰も文句を言えない。これが学校が教えてきたこと!そして見つかれば俺だけじゃない!!
他にもいる。これが鏡に映った日本の姿!!
公立高、未履修は4万7000人 衆院特別委 10/30/06(産経新聞)
衆院教育基本法特別委員会は30日午前、安倍晋三首相が出席し、政府提出の教育基本法改正案と、民主党の日本国教育基本法案に対する質疑を再開した。質疑では、高校の必修科目の未履修問題や、岐阜県瑞浪市の市立瑞浪中学校(佐々木喜三夫校長)に通う中学2年の女子生徒の自殺などいじめ問題が取り上げられた。
伊吹文明文部科学相は、高校の必修科目の未履修問題について、文科省の実態調査では、33都道府県289校の公立高校で4万7000人の生徒に未履修があったことを明らかにした。国立高校15校には未履修はなかった。全国の公立高校のうち7%で未履修があったことになり、70時間以内の不足が最も多く3万7254人、70-140時間が8722人、140時間超が1118人だった。私立高校分は明日発表の予定で、伊吹文科相は「かなりの数が加わってくると思う」と述べた。
また、伊吹文科相は未履修問題について「管理権、人事権が(文科相に)ないとはいえ、結果責任の一端はわたしが負う」と述べた。さらに、未履修のまま卒業した生徒の高校卒業資格の扱いについて「法制局と詰めている」と述べ、対応の検討に着手したことを明らかにした。
また、伊吹文科相は未履修やいじめ問題への各教育委員会の対応について「率直にいって、誠に責任感がない」と批判し、関連制度を見直して文科省の権限を強める意向を示した。
特にいじめ問題については「校長や学校関係者、教育委員会が(問題を)隠す傾向がある。大変由々しいことだ」と述べた。そのうえで「できるだけ(実態を)隠すことなく、早く子供を救っていくようにという基本方針を伝達している」と、実態を公開し、迅速な対応を取るよう指示していることを説明した。
また、「時代が大きく変わり、家庭の中で訴える相手が少なくなり、学校に重みがかかっている。命をしっかり守る原点を持ちたい」と述べたが、これは、いじめ問題の解決にはまず教育現場での対応改善が先決との考えを示したものだ。
安倍晋三首相は教育基本法改正の目的について「志のある国民を育て、品格ある国家をつくっていくのが改正の目的だ」と述べ、今国会での改正を期す考えを改めて強調した。政府与党は今国会成立を確実にするため11月上旬の衆院通過を目指している。教育基本法の改正が実現すれば昭和22年の制定以来初めてとなる。
「広い意味でいじめ」「原因かは難しい」岐阜・中2自殺 10/30/06(朝日新聞)
岐阜県瑞浪市の市立瑞浪中学2年生の女子生徒(14)が自殺した問題で、同校の佐々木喜三夫校長らが30日午前、同市役所で会見し、「『ウザイ』や『キモイ』といった言葉によるいじめはあった」と明らかにした。一方で、「今の時点では自殺に結びつけるかどうかの判断は難しい」と述べて、学校側は今後も調査を続ける考えを示した。
会見で、佐々木校長は、「27日に遺族宅を訪問した際に撮影されたビデオを見た。その中で『いじめがあった』と表現した」とし、「広い部分でのいじめがあったということ。言葉足らずだったが、悪口も含めると、いじめがあったと思う」と説明した。 「言葉によるいじめやからかいはあったのか」という質問には、「言葉によるいじめやからかいはあった。ただ、自殺に結びつけるかどうかの判断は難しい。推測の域を出ないため確認が難しく、最終的には結びつけられないだろう。ただ、いじめと自殺の関係をうやむやにしようとは思っていない」と述べた。
中2女子生徒が自殺、いじめの可能性 岐阜県瑞浪市 10/30/06(朝日新聞)
岐阜県瑞浪市の市立中学校に通う2年生の女子生徒(14)が23日に自宅で首をつって自殺し、両親が遺書とみられるメモなどから「部活動でいじめを受けていた」と訴えていることが29日、分かった。学校や市教育委員会は、生徒への聞き取りなどから「現時点ではいじめの事実は確認できない」としながらも、いじめが原因の可能性があるとしてさらに調査する。
同日会見した校長らによると、女子生徒は23日午後1時ごろ、学校から帰宅直後に自室で首をつって死んでいるのを母親に発見された。部屋には、所属するバスケットボール部の4人の同級生の名前を挙げ、「本当に迷惑ばかりかけてしまったね。これでお荷物が減るからね」という内容の便箋(びんせん)に書かれたメモを残していた。
女子生徒はまじめな性格で成績も良く、1年では学級委員を務めていた。バスケットで他の部員との技量の差を気にしていたという。
両親によると、17日、母親が学校で担任と顧問に会い、4人の名前を挙げて、練習中に「うざい」などと言われたと訴え、「娘に気を配ってほしい」と頼んだという。パスをする時にわざと遠くに出されることもあったという。こうしたいじめは今夏ごろ、女子生徒がレギュラーになってから始まったとみられるという。
自殺した23日、女子生徒は朝7時半過ぎから部活の練習に普段通り出かけていた。学校によると、練習後、教室で涙ぐむ女子生徒の姿を担任が確認していたという。
学校は24日に生徒らにアンケートを配り、今回の自殺について自由に書かせたところ、「いじめの存在を思わせるような記述はなかった」としている。
25日の葬儀後、両親と校長らは連日、話し合いを持った。いじめの可能性を問いつめる両親に対し、学校側は28日夜、「(名前を挙げられた)4人の親も、子どもが言葉や態度で傷つけ、いじめたと認めている」と発言した。だが、29日の会見では「いじめとは断言できない」と撤回した。
自殺をした日は女子生徒の誕生日だった。両親は「学校側の説明は信用できない。同じように自殺する子が出ないように、事実をはっきりさせてほしい」と話す。
学校側も女子生徒が「うざい」などと言われたことは認めたものの、校長は同日夜、「死に至らしめるいじめだったのかはっきりしない。今後調べる」と説明した。
岐阜中2自殺:学校側の説明二転三転 原因には触れず 10/30/06(毎日新聞)
岐阜県瑞浪市の市立中学2年の少女(14)が今月23日、いじめをほのめかす遺書を残して自殺した問題で、いじめの有無を巡る学校側の説明が二転三転している。同校は少女の家族に対していじめを認めていたが、その後、会見などで「原因は分からない」「広い意味でのいじめはあった」と言い直しを繰り返し、30日には再び「自殺に結びつくいじめの事実はない」と話した。中学校では同日朝、緊急の全校集会が開かれたが、校長は自殺の原因を特定しなかった。
少女の家族によると、校長、学年主任らが28日、自宅を訪ねた際、少女が遺書で名前を挙げたバスケットボールクラブのチームメート4人について、家族が「(4人の)親はいじめがあったと認めているのか」とただすと、学年主任は「無視や強いパスなどで苦しめていたと認めている」と答えていた。家族はこの様子をビデオに収めており、報道陣に公開した。
しかし、校長は29日の会見で「自殺の原因は分からない」と説明。さらに同日夜には「広い意味でのいじめはあったが、自殺の原因となったかは分からない」とやや表現を変え、いじめの存在を一部認める発言をした。
ところが30日朝、全校集会後に、同校の教頭は報道陣に対し「現段階でいじめの事実は確認できていない」。その後、校長も市役所で開いた会見で「『ウザイ』などのからかう発言はいじめに当たると思うが、自殺につながるかは推測の域を出ず、最終的な原因に結びつけられない」と話した。「原因をうやむうやにするつもりか」との質問には「そのつもりはない。原因は知りたい」と答えた。
同校は、いじめの確認について「犯人捜しが先行すると生徒の間に動揺が広がる」として、今後、全校生徒に無記名のアンケートを行い、日ごろの校内でのいじめの有無などを問うという。校長は「学校は警察と違う。踏み込んだ調査はできない」と話した。【浜名晋一、安達一正、稲垣衆史】
◇2回目の緊急全校集会
緊急の全校集会は午前8時半から開かれた。学校の説明によると、集会は自殺翌日の24日に続いて2回目。最初の集会では校長が死因を明かさずに少女の死に触れ、命の大切さを訴えたが、この日の校長は「自殺に結びつくいじめの事実はないが、今後の調査で出てくるかもしれない」と話し、「不安を抱いている子も多いだろうが、より良い学校を目指していこう」とあいさつした。生徒たちは静かに聴き入っていたという。
生徒たちは30日朝、一様に硬い表情で登校。教職員が通学路に立ち、「おはよう」と声をかけた。学校前には多くの報道陣が詰め掛けたが、ほとんどの生徒が記者の問いかけに無言で、足早に校内に入った。1年生の男子生徒は事件について「ショックです」と漏らした。
「必修逃れ」の問題からでもわかるが、文科省に問題があるのは間違いない。
ここまで問題が拡大するまで放置した、又は、問題把握が出来なかった責任がある。
問題を把握しながら対応しなかった教育委員会もあった。
違反をしたものが勝ち。見つかれば皆しているから、泣きつこう。
「赤信号、皆で渡れば怖くない。」が笑いではなく、日本では通用することを
示す事例にもなるだろう。どうする文科省!偉そうにいばり、接待を受け、
現状を把握しない、出来ない情けない組織。公務員の数減らせ!税金泥棒と呼ばれても
しかながないだろう!
これで日本の教育に未来があるのか!理屈や口だけじゃ、だめだよ!
必修逃れ、文科省は扱いに苦慮…要望相次ぎ 10/28/06(読売新聞)
全国各地の高校で必修科目が教えられていない問題で、履修漏れの3年生をどう扱うか、文部科学省が揺れている。
27日にはPTAの団体が配慮を求める要望書を提出したほか、安倍首相も伊吹文部科学相に負担軽減策の策定を指示した。しかし、必修科目を定めた学習指導要領には法的拘束力があり、授業時間短縮には簡単に踏み切れない。“徳政令”を出すのかどうか――。文科省の対応に注目が集まる。
今回履修漏れが見つかった必修科目は、学習指導要領で必ず履修しなければならないと定められている。50分授業を週2回、年間計70回履修するのが原則で、例えば、「世界史」が未履修の生徒は、これから最低70回の補習が必要になる。
当初、伊吹文科相は「指導要領に決めた通りの授業は受けていただく。各都道府県に厳正に通知するつもりだ」と語り、同省内でも、「生徒に履修してもらう」という意見が大勢を占めていた。だが、全国高等学校PTA連合会から生徒への配慮を要望されたり、与党から負担軽減策をまとめるよう求められたりする中、風向きが変わってきた。
文科省によると、学校教育法の施行規則には「カリキュラムは学習指導要領によるものとする」とあるため、学習指導要領には法的拘束力がある。同省が指導要領に従わないという方針を打ち出せば、“超法規的措置”をとることになってしまう。「必ずやるから必修なのに、簡単には曲げられない」と、ある幹部は当惑気味だ。
リポート提出などを条件に、授業時間の短縮も考えられるが、他の幹部は「履修は、授業を受けるという意味。リポートは評価をつけるために使うもので、それで授業時間を減らすのはおかしい」と首をかしげる。
ただ、生徒に責任はないだけに、職員の中からは「災害時や病欠などのように、長期間、授業を受けなくても、単位が認められるケースもある」などの意見も出始めている。
必修逃れ公立高校、286に…文科省調査 10/28/06(読売新聞)
全国の高校で卒業に必要な必修科目が教えられていない問題で、文部科学省は28日、公立の全高校を対象に行った緊急調査の結果を公表した。
兵庫県を除く46都道府県15政令市の3892校のうち、必修逃れの高校は31都道県2政令市286校。このうち284校が、教育委員会に虚偽のカリキュラムを提出していた。
調査結果では、岩手(31校)、北海道(29校)、長野(28校)、静岡(21校)、島根(19校)、愛媛(17校)、福島(15校)などが多かった。島根県は、全公立高校42校のうち半数近い19校、岩手県も79校中31校、福井県も32校中11校で必修逃れを行っていた。
また、富山の公立校では、現在は解消しているものの、11校のうち3校で、卒業生に本来必要な履修単位を取得させないまま卒業させていたケースが判明した。
一方、必修逃れが見つかった高校のうち、2校を除く全校が教育委員会に虚偽のカリキュラムを提出。それ以外の2校も、「県教委に出したカリキュラムで既に必修科目が足りなかったが、県教委が確認出来ず、そのまま授業が行われた」(長野県)、「正しいカリキュラムだったが、生徒が科目を選択する際、学校が指導しなかった」(岡山県)など、教育委員会や学校のミスで生徒が必修科目を受けていなかった。
文科省は今月25日、47都道府県と15政令市の教育委員会に、全公立高校を対象に必修科目をすべて行っていたかどうか27日までに調べ、報告するよう通知していたが、兵庫県は「26、27日の2日間、全県の校長会を開催したため、校長が直接、必修逃れの有無を確認出来なかった」として、回答を31日まで延期した。
一方、読売新聞の全国調査では、必修逃れが判明した高校は、41都道府県で計407校(私立校を含む)に上っている。
文部科学省にも責任がある。学校は生徒に責任は無いと言っているが、
それでは、必修を取らずに受験勉強をして受かった者、必修を取って受からなかった者
が存在する状況ではどうするのか。不公平だ。しかし少し前までは公にならなかった。
生徒には責任がないのであれば、不正を行った学校及び職員の給料のカット5年間等の
重い処分が必要。善人ぶっても責任は取らすべき。結局、学校や教員が結果(合格率&進学率)
の優先するために不正は許されることを多くの学校がやっていたことで証明した。
成績の偽造も許される。関与した職員を免職等を含め処分しない限り、見つからなければ
許されると言う考え方はなくならないだろう。学校での指導者がこのありさまである。
世の中は金、そして、結果と言って、何が悪いのか?多くの学校が行ったことに対して
かわいそうだけで、見逃すのはおかしい。見逃すにしても学校関係者の処分は重くすべきである。
文部科学省の管理能力や指導力のなさにはあきれる。税金泥棒!!
履修不足:「逸脱」の手段さまざま 学校側なりふり構わず 10/27/06(毎日新聞)
全国各地の公私立の高校に広がっている履修単位不足問題。単純に卒業に必要な科目を教えなかっただけではなく、「世界史的に地理を学んでいた」などの理屈で異なる科目を一体化させて履修させたことにしたり、表向きの時間割と実際の授業の内容が異なっていたり、学校によりさまざまな手段で「逸脱」が行われていた。「受験優先」のためには、なりふり構わない学校側の姿勢が浮かび上がった。【佐藤敬一】
履修不足は最初に発覚した地理歴史だけではなく、情報や保健など多くの科目にわたっている。このうち、地理歴史では必修の世界史1科目に加え、日本史、地理から1科目を選択する計2科目履修しなければならないが、1科目しか履修させていなかった。
栃木県の県立宇都宮女子高では「世界史的に地理を学んでいた」として異なる2科目を一体化させて教えることで2科目とも履修とした。県立大田原女子高でも理系の3年生80人が「地理の授業で世界史もまとめて学んだ」として地理Bと世界史Aを履修したことにしていた。
2科目を合わせながらも内容が1科目だけに偏っていた学校もある。
長野県立伊那弥生ケ丘高では、全員が1年時に地理を、2年時には世界史を履修した形になっている。しかし、2年時には(1)世界史だけを学ぶクラス(2)日本史と世界史を学ぶクラスに分かれ、(2)については事実上は日本史の授業が行われていたという。
宮崎県立宮崎大宮高でも、社会科の授業で受験に必要な科目に絞った内容の授業が行われていた。児玉淳郎教頭は「受験を考えた時に絶対的に授業時間が不足しており、偏った内容の授業をしてしまった」と説明した。
掲げた「看板」と内容が違っていたケースも多いとみられる。福岡県立鞍手高では、時間割では必修科目である世界史Aとなっていながらも、実際には地理Bの授業を行っていたという。
静岡県立下田北高では、昨年度初めに教育課程表の「地理歴史」部分に2科目と書いて県教委に提出したが、実際は1科目しか履修させずに卒業させていた。村野好郎教頭は「受験科目を優先して指導したところ、もう一つの科目にいく前に卒業がきてしまった」と説明する。
「必修」逃れ18道県98高校に拡大、成績表改ざんも 10/26/06(読売新聞)
全国の高校で卒業に必要な必修科目が教えられていない問題で、新たに33校で履修漏れがあったことが26日分かった。
履修漏れは18道県98校に拡大した。このうち、青森県立三本木高校では、学習指導要領とつじつまを合わせるため、履修漏れのあった生徒の成績表に、学んでいない科目の成績を記入するという虚偽の記載をしていたことも明らかになった。
新たに判明した高校は、北海道の7校、青森の2校、岩手の5校、山形の1校、栃木の5校、静岡の7校、長野の2校、鳥取の1校、山口の1校、福岡の1校、佐賀の1校。私立も9校含まれている。ほとんどが、地理歴史教科の必修の2科目のうち、1科目しか履修させていなかった。
青森県立三本木高校では、理数科3年生36人について、2年生の時に、必修2科目のうち1科目しか履修していなかったにもかかわらず、成績表では、履修していない科目にも成績をつけていた。
県教委には、2科目を学ばせると報告。生徒には、成績表のつじつま合わせを、2年生に進級する際に説明していた。生徒からは不満や疑問は出なかったという。
また、静岡県立下田北高校では、3年の理数科41人と普通科理系64人の計105人が地理歴史教科で必修科目の世界史を全く履修しないなどの履修漏れがあった。昨年度から続いており、必修科目を未履修のまま107人が今春卒業している。村野好郎教頭は「塾も少なく、大学受験のために必要だった」と話している
教育委員会だけの問題でない。
公務員の事なかれ主義の問題。
責任を明確にし、厳しい処分が必要。
責任を重くするだけでなく、責任の明確化、
重い責任を負う職員の給料を上げるなど、
平等でなく、権限や責任による待遇も考えるべきだ。
同じ給料であれば、誰も責任を取りたがらない、
誰も役職などほしがらない。よく考えて改革が必要。
朝日新聞(2006年10月21日)より
教育委員会を強化へ 担当相指示 権限委譲見直し
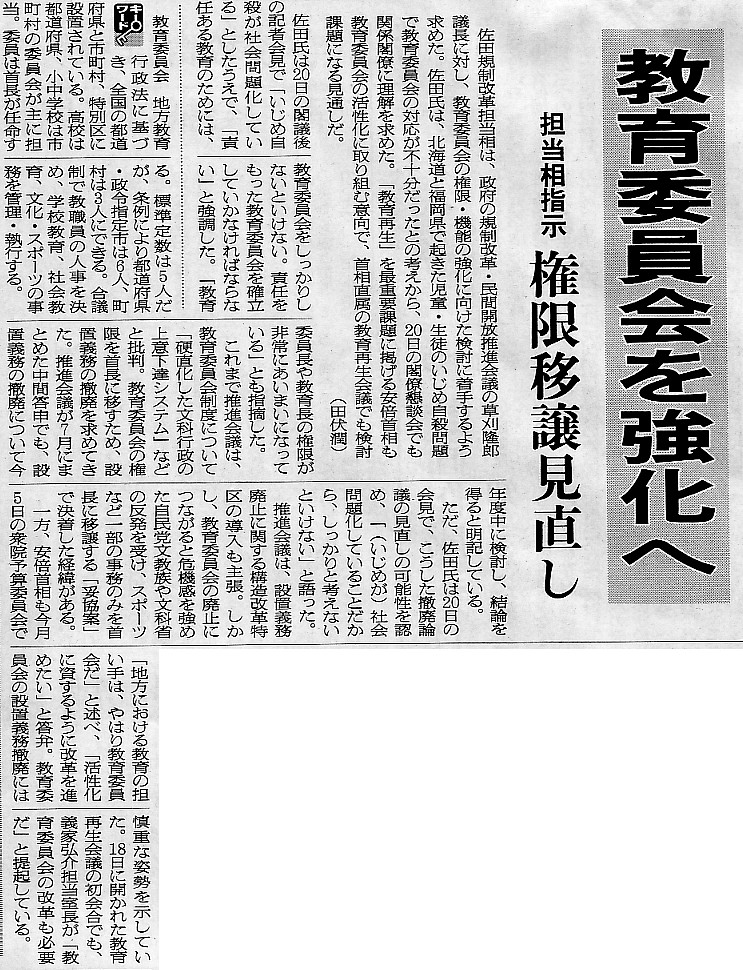
朝日新聞(2006年10月21日)より
道教委も遺書放置 北海道・滝川 小6女児自殺 上司に報告せず、紛失

国立大付属小教諭を逮捕 免停中に運転、一時停止違反 10/20/06(産経新聞)
免許停止中に乗用車を運転し一時停止違反したとして、警視庁田無署が国立東京学芸大付属世田谷小(東京都世田谷区)教諭の男(31)を道交法違反(無免許運転、一時停止違反)の現行犯で逮捕していたことが分かった。教諭は容疑を認め、翌日に釈放された。近く書類送検する。
調べでは、教諭は17日午前1時35分ごろ、自宅近くの東京都東久留米市内で、免停中なのに自家用車を運転し、交差点で一時停止違反したところをパトロール中の同署員に発見された。教諭は多数の交通違反を繰り返したとして、5月2日から180日間の免停処分中だった。
教諭は6年生の担任で、逮捕後は自宅謹慎しているという。
飲酒運転でひき逃げ事故、中学教諭を懲戒免職 岐阜県 10/20/06(産経新聞)
岐阜県教育委員会は20日、今月14日に飲酒運転でひき逃げ事故を起こした同県大垣市立南中学校教諭の小川ナナ容疑者(30)を懲戒免職処分とした。また、監督責任が不十分だったとして、同校の白鳥正忠校長を戒告処分にした。
小川容疑者は、同僚らと酒を飲んだ後の14日午前0時20分ごろ、大垣市内で乗用車を運転中、自転車の女性(52)をはね、そのまま逃げたとして岐阜県警に業務上過失傷害と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕された。
「父親が『最近7年間、全国でいじめによる自殺者ゼロということのようだが、
おかしいのではないか。今回も(筑前)町教委がいろいろと隠すのではないかと懸念している』
と述べると、宮崎視学官は『現在の調査システムに問題があれば、きちんとした事実が
報告されるよう見直すべきところは見直す』と答えた。」
テレビでニュースを見たが、文部科学省の宮崎活志・初等中等教育局視学官らの発言は
形式的に思えた。改善すると発言していたが、「きちんとした事実が報告されるよう
見直すべきところは見直す」とは、厳しい処分を含めているのだろうか。
学校(校長)や教育委員会の幹部の体質に問題があることはわかっているだろう。
もし文部科学省が気付いてもいないのであれば、文部科学省自体にも問題がある。
改善と言っても誰(機関)に指摘してもらい改善するのかも問題になる。
厚生労働省の問題
を見ても組織の問題があることが良くわかる。
福岡いじめ自殺:自殺生徒の父と文科省職員が面談 10/19/06(読売新聞)
福岡県筑前町立三輪中学校2年の男子生徒(13)がいじめを苦に自殺した問題で、福岡県教委に原因調査に訪れた文部科学省の宮崎活志・初等中等教育局視学官らが18日、生徒の父親ら遺族2人と面談し、調査内容を遺族に伝えることを約束した。文科省が遺族との面談に応じ、調査結果の公開を明言することは極めて異例で、専門家は「連鎖的に発生が続く子供たちの自殺問題に対する危機感の表れではないか」と指摘している。
面談は、父親がこの日、県庁に出向いて、文科省幹部に直接要請し、実現した。県庁内で報道陣に公開する形で行われた。
文科省は、今回の調査内容について(1)不適切とされる教員(学年主任)の言動(2)自殺した男子生徒への他生徒のいじめ(3)県、町の教委の対応--と説明。父親が「学校や町教委から報告された内容を遺族にも公開するのか」と尋ねると、宮崎視学官は「はい」と回答した。
父親が「最近7年間、全国でいじめによる自殺者ゼロということのようだが、おかしいのではないか。今回も(筑前)町教委がいろいろと隠すのではないかと懸念している」と述べると、宮崎視学官は「現在の調査システムに問題があれば、きちんとした事実が報告されるよう見直すべきところは見直す」と答えた。【笠井光俊】
みざる きかざる いわざるになりたがる教育委員会や学校が多く存在するから
北海道、福岡県の児童・生徒がいじめを苦に自殺したんだろ!
文部科学省の職員も日本人なんだからわかるだろう。
プールの給水口に吸い込まれて死亡した児童の事故の時、全国で排水口対策の調査が行われたが、
急いでいたから確認せずに報告した学校や地方自治体があった。
同じ事を繰り返すなよ、文部科学省!
確認せずに文部科学省へ報告した教育委員会や学校関係者は免職を覚悟する
ように指導し、忠告すべき。同じ言い訳を受け入れることがあれば、文部科学省の
監督及び指導にも問題がある。
教育委員会の人事評価や抜き打ちチェックも今後、必要。上ばかり見る役人は必要なし!
いじめ自殺緊急調査、文科省が全国の小中高で洗い出し 10/17/06(読売新聞)
北海道、福岡県の児童・生徒がいじめを苦に自殺した問題を受け、文部科学省は16日、全国のすべての小中高校を対象に、自殺の原因となっている「いじめ」について、緊急調査に乗り出す方針を決めた。
今週中にも各都道府県教委や私立、国立の学校に要請する。また、来年度には警察などと連携し、自殺の実態を探る全国調査を実施するほか、教員向けのマニュアルを整備するなど、子供の自殺を食い止めるための体制づくりを早急に進める。
文科省では、これまでも年1回、全国の公立小中高校を対象に、いじめや自殺、不登校の数などを調べてきた。9月に公表した調査結果によると、昨年度の自殺の件数は105件で、ピークだった1979年(380件)と比較すると激減していた。ただ、原因別で見ると、いじめによる自殺の件数は99年度以降ゼロで、調査が実態を反映していないという指摘が出ていた。
例えば、北海道滝川市内の小学校の教室で昨年9月、首をつって自殺した小学6年の女児(当時12歳)は、遺書でいじめを訴えていたが、市教委はいじめに関する記述を隠して発表。当初、遺族にもいじめを認めなかった。
このため、文科省は「教育委員会がすべてを把握していないか、文科省へ報告していないケースもありうる」と判断。今回の全国調査では、現時点で校内で起きているいじめについて、各教委に徹底した洗い出しを要請する。調査対象を国立や私立の学校にも広げ、全体状況の把握を目指す。
どうなっているんだろうね、文部科学省。
公務員の汚い・曖昧の逃げ方で幕引きか??
これで国民にありのように税金を運んでこいと言うのは
虫が良すぎるだろう!!
責任を取らないのが公務員と思える結果が多いが、
これで批判を受けないと思っているのか??
福岡いじめ自殺:教諭発言、一転因果関係認めず 校長会見 10/16/06(毎日新聞)
福岡県筑前町の町立三輪中2年の男子生徒(13)がいじめを苦に自殺した問題で、合谷(ごうや)智校長が16日未明、記者会見し、男子生徒の1年時の担任教諭で、現在2年の学年主任(47)が、男子生徒に対するいじめ発言を繰り返し、それが発端になって生徒たちによるいじめが広がったことを認める一方、教諭の発言と自殺との直接の因果関係については「認められないと思う」と述べた。
合谷校長は15日朝、自殺した男子生徒の家に赴き、遺族に対して「教諭のいじめ発言は自殺に結びついている」と説明していた。だが、16日未明の記者会見で、合谷校長は「遺族への説明時には冷静さを欠いてしまい、『因果関係がある』と説明してしまった。もう一度考え直すと情報が少なく、より多くの情報を集めて分析してみないと因果関係については分からない」と述べた。学年主任は15日、体調を崩したという。【倉岡一樹】
◇全生徒対象にアンケで「調べ直す」…生徒宅訪問の校長
合谷校長は16日午前1時半すぎに教頭とともに自殺した男子生徒宅を訪問、両親と2時間近くにわたって面会した。父親によると、校長は全生徒を対象に教諭らによるいじめについてのアンケートを16日に無記名で実施することを伝え、「もう一度最初から調べ直します」と答えたという。
校長らは面会後、報道陣の質問に一切答えず、無言で車に乗り込んだ。
自宅玄関で取材に応じた父親は「(1年時の)担任が引き金となってその後の(生徒たちによる)いじめが続いたという説明を受けた。でも、私たちが思っているのはそうじゃない。(担任のいじめは生徒が)2年になってからも日常的に続いていた。納得できない」と語気を強めた。
盗撮の下見で教え子宅に侵入、高校非常勤講師を起訴 10/12/06(読売新聞)
盗撮の下見のため、教え子の女子生徒宅に侵入したとして、愛知県立半田商業高の非常勤講師が、住居侵入の疑いで愛知県警半田署に逮捕、名古屋地検半田支部から住居侵入罪で起訴されていたことが、12日わかった。
起訴されたのは、同校非常勤講師福田靖被告(47)(愛知県小坂井町)。
調べでは、福田被告は8月3日午前3時ごろ、半田市内の女子生徒宅庭先で、懐中電灯を持ってうろついていたところを帰宅した家人に見つかり、駆けつけた同署員に現行犯逮捕された。
逮捕の際、福田被告は車内に女子生徒10人分の住所が書かれたメモを持っていた。また、逮捕後の調べで、風呂場を盗撮しようとし、その下見目的で侵入したと供述していた。
福田被告は今年4月、1年間の期限で同校の非常勤講師に採用されていた。同校の教頭は「勤務態度はまじめで、そのようなことをしていたとは信じられない」と話している。県教委は来週中に福田被告を処分する。
窃盗:高校教諭、パチンコ店でゲーム機万引き逮捕 宮崎 10/10/06(毎日新聞)
宮崎南署は9日、宮崎市内のパチンコ店で景品の家庭用ゲーム機を万引きしたとして宮崎市大塚町、県立高城高校教諭、宮元勉容疑者(58)を窃盗容疑で逮捕した。宮元容疑者は「ほしかった」と容疑を認めている。
調べでは、8月13日午後8時半ごろ、パチンコ店内に景品の見本として展示していたゲーム機1台(1万円相当)を盗んだ疑い。
9日午後、同じパチンコ店に宮元容疑者が来店。被害当時の防犯ビデオに映っていた男に似ていたため、店が通報した。
同高によると、宮元容疑者は化学の担当。
【中尾祐児】
わいせつ免職教諭、前任校での被害を県教委公表せず 10/04/06(読売新聞)
栃木県教委が、女子児童10人にわいせつ行為をしたとして懲戒免職とした栃木県の男性小学校教諭(33)について、前任の小学校でも同様な行為をしていたことを把握していたにもかかわらず、被害実態を調査せず、公表もしていなかったことが分かった。
県教委によると、男性教諭は佐野市立小学校で低学年を担任していた今年5~7月、休み時間の教室で女子児童計10人に対し、ひざの上に乗せて尻を繰り返し触り、うち1人にはキスするなどした。
保護者からの訴えから、県教委が9月に調査。男性教諭は同校でのわいせつ行為を認めた上で、臨時教諭をしていた前任の栃木市内の小学校でも「児童の尻を触った」と話したという。
しかし、県教委は前任地での被害の詳細を調べないまま、3日に懲戒処分を決め、同日の会見でも前任地の被害には触れなかった。
児童買春:「彼女がほしかった」高校教諭逮捕 北海道 10/02/06(毎日新聞)
北海道警帯広署は2日、標津町北2西3、道立標津高教諭、平沢淳一容疑者(31)を児童買春禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕したと発表した。平沢容疑者は「17歳とわかっていたが、独身で彼女がほしかった」と容疑を認めている。
調べでは、平沢容疑者は4月30日午後1時ごろ、釧路市内のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った十勝管内の道立高校3年の女子生徒(17)に携帯電話1台(約2万円相当)を渡す約束をしていかがわしい行為をした疑い。平沢容疑者は行為後に、携帯電話と交通費として1万円を渡していた。
女子生徒に渡した携帯電話は平沢容疑者が新規契約し、使用料金も支払っていた。平沢容疑者がその後も女子生徒を誘い続けたため、女子生徒が家族に打ち明け、同署に相談していた。【仲田力行】
テレビで北海道滝川市教委の対応を見ると、問題がある。
暴力が確認できないといじめじゃないのか。もしほんとうに思っているのなら
こいつらに指導能力はない。いじめを理解できていない。言い訳だとしても
市教委の職員。これじゃ、誰に助けを求めれば良いのか子供もわかるまい。
こんな連中が権力を持っているのであれば、良い教育を指導出来るわけが無い。
立派な大人とはこんな逃げ腰の市教委の職員になることだと子供には言えない。
ただこんな連中のような大人になるなと言っても間違ってはいない。
出来るだけ子供の目線で理解し、指導する人間になるように努力する人間になってほしい
と言いたい。偉そうな事を言うような人間じゃないが、少なくとも北海道滝川市教委の職員
のように給料貰っていながら、あんな言葉は言えない。
滝川市の小6自殺、1か月半前に担任に友人関係相談 10/02/06(読売新聞)
北海道滝川市内の小学校で昨年9月、6年生の女児が首をつり、後に死亡した問題で、担任教諭がその1か月半前の7月、友人関係のことで女児から相談を受けていたことが1日、わかった。
自殺を図った後に学校が同級生に行った聞き取り調査でも、「死にたいと漏らしていた」などの証言が多数得られており、学校は昨年10月、女児の家族に「本人のサインを学校、担任として受け止められなかった」との内容の文書を渡していた。
文書は、学校側が事前に把握していた女児の様子について、「席替えのことや友人関係について担任に相談があった」「修学旅行の部屋割りで(女児一人がどのグループにも入れないという)問題が生じた」ことに触れていた。しかし、ともに「担任の指導で解決された」と説明し、いじめは否定していた。
また、文書には6年生への聞き取り調査結果も記載され、「カッターの刃を手首に当てていた」「死にたい、と言っていた」など、自殺の兆候があったことを、多くの児童が証言していた。
同市教委は、「苦しい心の奥をつかめなかったことは残念で、女児や遺族におわびしたい」としながらも、「遺書の文言と、同級生から聞き取った内容を一つずつ照らし合わせて分析したが、自殺の原因に結びつくものは確認できなかった」としている。
自殺の女児、「いじめ」遺書判明 市教委は公表せず 10/01/06(産経新聞)
北海道滝川市の市立小学校の教室で平成17年9月、首つり自殺した6年生の女児=当時(12)=が、学校内でのいじめを示唆する内容の遺書を残していたことが1日、分かった。同市教育委員会は遺書の内容を把握していたが、公表していなかった。
女児は同年9月9日朝、教室で首をつってぐったりしているのを登校した児童に発見された。病院に搬送され意識不明の重体だったが、今年1月6日に死亡した。
市教委によると、教卓上には学校や母親、友人あてに別々の封筒に入れられた7通の遺書があった。このうち学校などにあてた遺書には「キモイと言われてつらかった」などと自殺の理由をほのめかす記述があったという。
校長が家族に遺書を渡す前に急いで目を通したが、いじめを示唆する記述を見落とした。しかし、市教委は17年10月に家族が学校を訪れて遺書を読み上げた際に内容を把握した。
市教委は公表を控えた理由について「遺書の内容に基づき調査したが、女児へのいじめは確認できなかった。原因が特定できないので慎重になって発表しなかった。隠したわけではない」と話している。
無届けで兼業:千葉大大学院教授が報酬5600万円 10/01/06(毎日新聞)
千葉大大学院の杉山和雄元教授(64)が、無許可で兼業し、電気関連企業など12社から技術指導料などとして計約5600万円を得ていたことが分かった。同大の就業規則では、大学外での仕事に関連する活動は許可を得ることが義務付けられている。杉山元教授は「責任を感じた」として9月30日付で辞職した。
同大によると、杉山元教授は99~05年度に計25回、国内外の企業から講演料、技術指導料などとして、1回につき3万~430万円を受け取っていた。
杉山元教授は同大工学部と大学院自然科学研究科に所属していた。東京湾アクアライン、瀬戸大橋の設計に携わるなど景観デザインの専門家として知られている。同大は「兼業手続きを周知してきたので大変遺憾。改めて就業規則を徹底していきたい」と話している。
同大は4月に匿名の投書を受けて調査していた。杉山元教授は同大の調査後、確定申告を修正したという。【中川紗矢子】
科研費:9大学で不適切経理10億円超 会計検査院が指摘 10/01/06(毎日新聞)
文部科学省が交付する科学研究費補助金(科研費)を巡り、東京大など九つの国立大学で、研究用に購入した物品の納品書の日付が、業者側に残った日付と大幅に異なる不適切な経理を行っていたことが、会計検査院の調べで分かった。日付が1カ月以上異なっていた納品書の総額は10億円を超え、文科省は、1年以上ずれていた6大学の計約2000万円分について、補助金適正化法に基づき返還させた。また、私立大学も含めた全大学に対し、納品検査の徹底を通知した。
科研費は独創的・先駆的な研究を発展させる目的で、文系・理系や基礎・応用を問わず、あらゆる学術研究を対象にした政府の研究資金で、06年度の文科省分の規模は総額1895億円。
検査院の調べでは、9大学で注文した物品を業者が大学に納入したものの、事務担当者の確認が遅れたため、業者側と大学側で、それぞれ保管していた帳簿類の納品日付にずれが生じた。うち約2億円分については、大学側の納品が年度末の3月31日を越え、補助対象の翌年度になっており、文科省の補助条件に違反した状態になっていた。さらに約2000万円分は、研究者が1年以上前に納品があったにもかかわらず、大学側に届けていなかった。
ただ、研究費の私的流用やプールなどといった不正行為はなかった。
文科省学術研究助成課は「公務員の定数削減の影響で、事務スタッフの減少が納品を確認する体制の不備につながった。今後、納品検査を徹底させ再発防止したい」と話している。
科研費を巡っては昨年、慶応大医学部教授ら4大学の研究者らが、実験用動物などの架空購入などで、総額約8900万円の不正受給を検査院から指摘された。このほか、別の研究費を巡っても今年、早大理工学部教授の不正受給が発覚している。【斎藤良太】
どのように朝礼で話したのか知らないが「私は昔、お酒を飲んだ後に車を運転したことがある」けれど
後悔している。二度とするつもりは無い。横浜国立大教授でもある高橋和子校長でも
違反した事実は間違っていた。だからこそ、責任を取らせるために処分の厳罰が必要。大人になったら
規則を守ることを心がけてほしいと言ったのであれば、飲酒運転を隠して偉そうなことを
教諭や教育関係者よりもましだ。
横国大付属鎌倉小校長「昔、飲酒運転」朝礼で“告白” 09/22/06(読売新聞)
横浜国立大教授で、同大付属鎌倉小学校(神奈川県鎌倉市雪ノ下、児童718人)の高橋和子校長(53)が今月11日の全校朝礼で、1~6年生の児童を前に、「私は昔、お酒を飲んだ後に車を運転したことがある」と発言していたことがわかった。
高橋校長は21日の臨時保護者会で「不用意だった」と謝罪した。
同小によると、高橋校長は朝礼で、子供3人が死亡した福岡市の飲酒運転事故を取り上げ、「お酒を飲んだら、運転してはいけません。人を死なせるつもりでなくても、こういう事故が起きた」と話し、その後、自分に飲酒運転の経験があるかのような発言をした。その際、一部の児童から「えーっ」と、どよめきが上がった。
「『校長先生が飲酒運転した』と言っていた」と親に伝えた児童もおり、その後、PTA役員と学校幹部の会合で問題になった。
高橋校長は読売新聞の取材に、実際に運転したのは原付きバイクで飲酒から時間がたっていたとしたうえで、「命の大切さを訴えるため、自分の経験を語った方が児童が身近な問題としてとらえやすいと思った。飲酒運転を容認しているととられかねず、不注意だった」と話している。
文部科学省は英語の指導助手の行動や質に注意するべきだ。
中3女子にわいせつ行為 ナイジェリア人を容疑で逮捕 09/20/06(朝日新聞)
中学3年の女子生徒(15)にわいせつな行為をしたとして、三重県警桑名署は20日、愛知県豊田市山之手、語学指導助手、ウヌフェガン・ポール・フェミ容疑者(42)=ナイジェリア国籍=を強制わいせつ容疑で逮捕した。
調べでは、三重県桑名市の中学校に語学指導助手として勤務していたフェミ容疑者が6月27日正午ごろ、体調不良のため、同中学校の職員室前に座っていた女子生徒を両手で抱きしめた疑い。抱きしめたことは認めているが、「介抱するためだった」と供述し、容疑は否認しているという。
桑名署によると、同容疑者は犯行後にいったん帰国しており、先月下旬に再入国。同署が行方を追っていた。
桑名市教委によると、同容疑者は05年4月から英語の指導助手として派遣会社から派遣された。1日平均4時間程度の授業で助手を務めていたという。
ある新聞を読むと、飲酒運転に対して処分を重くしても、飲酒運転が
減る割合が低かった公務員は教育の分野だった。処分を重くしても
飲酒運転はなくならないと反論していた。子供達を指導する立場の人間が
自制心や自己のコントロールが出来ない公務員のトップに入っている事実は
恥だと思わないのか。子供のしつけに対して親の責任はあるが、教師の質
の問題が存在すると思わせる結果だ。これではドラスティクな教育の
改善は期待できない。
酒気帯び蛇行運転、教育長を摘発 山梨・身延町 09/19/06(産経新聞)
山梨県警南部署は19日、道交法違反(酒気帯び運転)容疑で同県身延町相又、千頭和(ちずわ)英樹同町教育長(58)を摘発、交通切符(赤切符)を交付した。近く書類送検する。
調べでは、パトロール中の同署員が同日午前5時20分ごろ、同町の国道52号で、ふらつきながら走行している乗用車を発見し職務質問。酒のにおいがしたため飲酒検査し、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを検出した。
調べに対し千頭和教育長は、同町内の飲食店でビールを数本飲み、自宅に帰る途中だったと供述。「こういう立場にありながら、飲んで運転してしまったことは申し訳ない」などと反省の弁を述べているという。
町教委は「事実を確認していないのでコメントできない」としている。
わいせつビデオ:校内で撮影…進学相談中に映像 大学教授 09/01/06(毎日新聞)
常磐大(水戸市見和1、高木勇夫学長)国際学部長の男性教授(53)が、大学敷地内で知人女性とわいせつ行為をし、自らビデオで撮影していたとして、学部長を免職されていたことが分かった。7月にあった高校生を対象にしたオープンキャンパスで発覚した。教授は来年3月末まで休職するという。
同大総務課によると、7月22日午後1時ごろ、大学内の演習室で、教授は女子高校生2人から進学相談を受けていた。その際、演習室で上映していた国際政治の資料映像に女性の映像が数秒流れた。映像に気が付いた同大の学生がすぐにビデオを停止。後で内容を確認したところ、教授が大学敷地内で女性とわいせつな行為をしている映像が映っていた。
同大は高木学長を中心とする対策室を設け、教授から事情を聴いたところ、教授は「(大学敷地内でわいせつ行為に及んだことについて)申し訳なかった。映像は抹消したものと思っていた」と事実を認めたという。
同大は「社会的信用を失墜させる行為で、職務規定に反する」と判断。8月2日付で学部長職を解き、同21日から7日間の出勤停止にした。その後、教授が来年3月末までの休職を申し出たという。
教授は83年の同大創立当時から勤務しており、今春から同学部長を務めていた。【三木幸治、山本将克】
研究費不正を防止、大学の管理強化で予算倍増…文科省 09/01/06(毎日新聞)
研究費の不正使用を防止するため、文部科学省は大学の管理体制強化にあてる予算を倍増することを決めた。
研究者に配分される科学研究費補助金(科研費)の中で、大学側が経理管理や支援要員の雇用に支出することができる「間接経費」を増やす。今年度予算の2・1倍にあたる311億円を新年度予算の概算要求に盛り込んだ。
契機になったのは松本和子・早稲田大学教授の不正受給で、対策強化には現状の間接経費だけでは不十分と判断した。間接経費の配分対象は現在、年間2000万円以上の研究費を獲得した研究者のいる大学のみだが、年間500万円程度の科研費にも対象を拡大。大型の科研費が集中する国立大以外も、十分な不正対策が取れるようにする。
同省の試算によると、対象を拡大した場合、間接経費が配分される私立大学は現在の111校から約4倍に増える。たとえば現在は間接経費1・9億円の慶応大は4億円に、早稲田大は1・7億円から3・7億円になるという。
痴漢教頭:報告せず自己退職 滋賀県教委は懲戒免職処分に 08/11/06(毎日新聞)
滋賀県教委は、長浜市立中学の男性教頭(54)が痴漢行為をしたとして、11日付で懲戒免職処分とした。教頭は6月に県警の取り調べを受けたが報告せず、7月、自己都合による退職を申し出ていた。県警米原署は、教頭を今月中にも県迷惑防止条例違反容疑で書類送検する方針。
県教委によると、教頭は6月17日、自宅近くの同県米原市の火災を見物した際、後ろにいた女性の下腹部を触るなどして、近くにいた警察官に取り押さえられた。教頭は事件を一切報告せず、7月10日に「転職先が見つかった」などと退職を申し出た。今月3日、県教委に「処分はどうなったのか」と確認する匿名電話があり、発覚。教頭は「魔が差した」などと話しているという。
県教委は、管理職であり、報告を怠ったことから重い処分とした。斎藤俊信教育長は「教育者として極めて恥ずべき許しがたい行為で、誠に申し訳ない」とコメントした。【高橋隆輔】
これからは小樽昭和学園のように経営難に陥いる学校が増えるだろう。
文部科学省は今後の対応を良く考えるべきだ。
不正研究助成金:使用分も返還請求へ 文科省方針 08/07/06(毎日新聞)
データのねつ造や改ざんなど研究不正に対応する指針を作成している文部科学省は、不正をした研究者に対し、原則として使用分の研究費の返還を求める方針を決めた。同省の特別委員会が6月にまとめた指針案では、返還を求める研究費は未使用分が基本とされたが、内閣府から「使用した研究費を返還しなくてよいのはおかしい」との指摘を受けた。8日の特別委に提示し、最終的な指針をまとめる。
指針の対象は、同省の公募による研究費助成を受けた研究の不正行為。研究費を別の目的に使うなど、不正使用については返還規定があったが、研究そのものの不正については規定がなかった。
6月にまとまった案では、研究当初から不正を意図していたなど悪質な場合は研究費の全額返還を求めるが、それ以外は未使用分の返還にとどめるとしていた。
しかし、内閣府の指摘を受け、同省は使用分も含めた返還を原則とすることにした。どの程度返還させるかは、不正内容などを考慮して決める。
指針には、不正行為が認定された研究者に対し、同省への研究費申請を最大で10年間禁止することなども盛り込む。【下桐実雅子】
「数億円、競馬に使った」元学校事務長を横領で逮捕 08/05/06(産経新聞)
大阪府箕面市の学校法人「千里国際学園」の運営資金1500万円を着服したとして、箕面署は5日、業務上横領の疑いで、同学園の元事務長で住所不定、下村啓三容疑者(56)を逮捕した。学園は計約3億5000万円を着服したとして告訴しており、調べに対し下村容疑者は「数億円を引き出した。主に競馬に使った」と容疑を認めているという。
調べでは、下村容疑者は今年4月21日、府内の都銀で同学園の口座から1500万円を引き出し、着服した疑い。
下村容疑者は事務長兼管理マネジャーとして、同学園の運営資金を自由に扱える立場にあったが、4月下旬から欠勤。滋賀県野洲市の自宅を出たまま行方不明になった。
学園が帳簿を調べたところ、4月までの1年間に口座から30回以上、計約3億5000万円が引き出されていたことが判明。
5月末に下村容疑者を懲戒解雇し、6月8日に業務上横領罪で告訴。同署が捜査していた。
下村容疑者が4日夜、同学園に姿を現し、学校関係者に付き添われて同署に出頭した。調べに「経理の立場を利用し、何度も学校の金を引き出した。競馬に通い詰めていた」と供述している。4月以降は、大阪や東京など各地を転々としていたという。
下村容疑者は平成3年から事務職員として勤務し、12年から事務長を務めていた。同学園は中等部、高等部とインターナショナルスクールを運営。海外から帰国した生徒や外国人らも通っている。
小樽昭和学園、学生数減少で民事再生法申請へ 08/02/06(読売新聞)
北海道小樽市で小樽短大などを運営する学校法人「小樽昭和学園」は、同短大が学生数減少で経営難に陥ったとして、札幌地裁に民事再生法の適用を申請する方針を固めた。
負債総額は約3億5000万円。文部科学省によると、大学・短大を運営する学校法人が同法適用を申請するのは、全国で3例目。
四国を中心に予備校を運営している「タカガワ」(本社・徳島市)が経営支援することが決まっており、すでに先月末の理事会で、同社副社長の高川准子氏が学長に就任している。
同社などによると、同短大は1967年に女子短大として設立され、99年からは男女共学となった。
しかし、年々、学生数が減少。今年度は、各学年の定員140人に対し、1年生が33人、2年生が41人と、いずれも大幅に定員割れしていた。
文科省、浅井学園の助成金20億円返還命令へ 08/01/06(読売新聞)
北海道江別市で大学・短大などを経営する学校法人「浅井学園」(札幌市)は1日、前理事長による経費の私的流用事件に関する報告書を文部科学省に提出。
同省は、同学園に2001年度から05年度に交付した私学助成金について、加算金を含め約20億円の返還を命じる方針を明らかにした。
研究費流用:英国籍の男性助教授を懲戒処分 立命館大 07/31/06(毎日新聞)
立命館大は31日、研究費を留学生の生活費などに流用していた理工学部の英国籍の男性助教授(45)を停職20日の懲戒処分にしたと発表した。流用総額は442万円。
立命大によると、助教授は研究室の大学院生6人名義で架空のアルバイト費を請求し、01~04年度に受給した文部科学省からの補助金約299万円と学内研究費約143万円を流用。バングラデシュなどからの留学生8人に渡航費、生活費などとして1人3万~200万円を渡した。助教授自身も別に約80万円を拠出した。既に卒業した留学生2人からは約50万円が助教授に返還されたという。立命大は助教授に流用分の返還を求め、補助金を文科省に返還する。
問題を受け、立命大は研究費適正執行監査委員会を設置する。川村貞夫副学長は会見で「社会からの期待と信頼を踏みにじるもの。大学として十分反省している」と陳謝した。【中野彩子】
“免職教師”実名出さず、「かばい合い」に批判の声 07/29/06(読売新聞)
自治体の教育委員会が、懲戒免職にした教師の氏名を公表しない例が相次いでいる。
「被害者の意向」というウソの理由で匿名発表したのをはじめ、「児童・生徒への教育的配慮」と称して一般の自治体職員より緩い基準で判断したり、処分自体を公表しなかったりするところもあり、識者から批判の声が出ている。
千葉市教委は、同じ民家に10回以上忍び込んで女性の下着を盗んだとして、窃盗容疑などで書類送検された市立小学校の教師(42)を今月19日付で懲戒免職にした。千葉県教委の基準では懲戒免職は実名公表が原則だが、市教委は「被害者側の強い要望」を理由に実名や学校名の発表を拒んだ。
ところが実際には、被害者は実名公表を求めており、翌日の新聞報道を見て、市教委に「事実と違う。教え子たちにも知る権利があるはずだ」と抗議。だが、21日の会見でも、市教育長らは「被害者側から穏便にとの話があった」とウソを重ねた。結局、24日になって虚偽の発表を認め、実名を公表。市教委には抗議が殺到し、教育長らの処分が検討されている。
懲戒免職にした職員の氏名を原則公表する新基準を昨年11月に打ち出した秋田県。ところが、その2週間後、県教委は、酒気帯び運転で懲戒免職にした小学校教師の氏名を伏せて発表。県教委は「報道で氏名が公表されることで、児童・生徒に改めてショックを与える」と、知事部局との“違い”を説明した。
愛知県教委は昨年度、生徒へのわいせつ行為で懲戒免職にした高校教師3人について、「被害者が特定される恐れがある」と処分自体を公表していなかった。
文部科学省は昨年末、都道府県・政令市教委に教職員の懲戒処分の概要を可能な限り詳しく公表するよう通知。同省は「処分自体の非公表は抑止力にもならず、よくない」としている。
千葉市教育委員会の体質はどうなっているのか。このような対応をとった担当者や
幹部は、はずかしくないのか。自己や自分の所属している組織のためにはウソを
ついても良いと言っているようなものだ。
千葉市教育委員会は、どのように教育や教諭達について考えているのか。
古い体質が残っているのか、澱んだ人事があるのか、マスコミは調べて公表してほしい。
上がダメでは、下に問題がなくても悪くなる。
なぜウソにウソを重ねたのか、はっきり回答しろ!!
ウソ認め実名公表 千葉市教委 07/25/06(読売新聞)
女性用下着を盗んだとして懲戒免職処分となった千葉市立小教諭について、被害者の女性が処分された教諭を実名で発表するよう求めたにもかかわらず、同市教育委員会が「被害者が匿名発表を強く要望」と虚偽発表した問題で、市教委は24日、この問題での3度目の会見を開き、虚偽発表を認めて元教諭の実名を公表した。飯森幸弘教育長は、自身や担当者らの処分を検討する考えを示した。
懲戒免職処分(19日付)を受けたのは同市若葉区内の佐藤正一容疑者。市教委は当初43歳と発表していたが、24日になって42歳に訂正した。19日に住居侵入容疑、20日に同容疑と窃盗容疑で千葉地検に書類送検された。犯行当時、市立都賀の台小に勤務していた。
24日の会見で、飯森教育長らは当初、「全体の話し合いの中で匿名発表に被害者が同意してくれたと理解していた。(実名発表を強く主張していた)被害者にきちんと意思を確認すべきだった」などとして虚偽発表を認めなかった。報道陣から再三にわたって問いただされると、「結果としてウソをついたと言われても仕方がない。これまでの発言を撤回する」と虚偽発表を認めた。
飯森教育長らは、被害女性と都賀の台小の校長らが話し合った具体的な内容を把握しておらず、「穏便にしたいと言ったのは被害者側」「被害者の心境も揺れ動いていた」と言い逃れに終始。同席した宮田浩・教職員課主幹は被害女性とのやり取りについて、「覚えていない」と答えた。
また、志村修・学校教育部長は、佐藤容疑者の懲戒免職処分を19日に発表した際、被害女性の主張を把握しており、20日には抗議を受けていた。しかし、市教委は匿名発表について、19日の会見で「被害者の要望」、21日は「被害者側が市教委の判断で結構と言った」とした。24日の会見でも、「あくまでも被害者に配慮して判断した」と述べ、組織的な隠ぺいや佐藤容疑者をかばう考えはなかったことを強調した。
補助金を不正プール、九大教授ら5人処分 07/25/06(読売新聞)
九州大学(福岡市)で2001~05年度の5年間に、日本学術振興会からの科学研究費補助金(科研費)をプールするなどし、3件総額約1530万円の不正経理をしたとして、教授ら5人が処分されていたことがわかった。
同大では、購入物品の現物確認や旅費支出の実態調査など、監査体制の強化に乗り出した。
同大によると、このうち1400万円は、理系学部の教授と助教授が伝票の書き換えや、業者に依頼して作成した物品購入の架空伝票で処理。使ったように見せかけて翌年度に繰り越し、研究費として使い切ったという。
日本学術振興会への投書で発覚したが、同大は「不適切な処理だった」として、02年3月に、教授を訓告処分に、助教授を文書で厳重注意した。
また、文系学部の教授や助教授が、研究の手伝いをした助手や大学院生計11人に科研費から支払った謝礼金計120万円を払い戻しさせ、学生らを学会に連れて行く際の旅費として利用した。03年10月に教授を文書で厳重注意し、助教授を口頭注意した。
医学部で研究費流用、女性職員を懲戒解雇 昭和大 07/14/06(朝日新聞)
昭和大学(東京都品川区)医学部に勤務する研究補助員の女性(46)が、医学部の研究費約1386万円を不正流用していたことが分かった。大学は11日の理事会で、この職員の懲戒解雇を決めた。
女性は99年、医学部第一外科学の研究補助員に採用。同学教室の会計処理を1人で担当してきた。昨年度決算で帳簿と銀行口座の残額が著しくかけ離れていることが判明し、同大が5月から内部調査していた。
調査結果によると、女性は採用当初から約7年間にわたり、企業から拠出された受託研究費や寄付金を無断で引き出し、生活費などに充当。決算期のたびに流用分をクレジットカードの借り入れで口座に入金、発覚を防ぐ工作を繰り返してきた。職員は事実関係を認め、「全額返します」と話しているという。
同大の小口勝司理事長は「二度と起きないよう対応したい。(女性から)返還がない場合は警察への告訴を検討する」とコメントした。
中国新聞(2006年7月13日)より
研究費不正受給
資金還流の疑い 早大調査 松本教授は否定
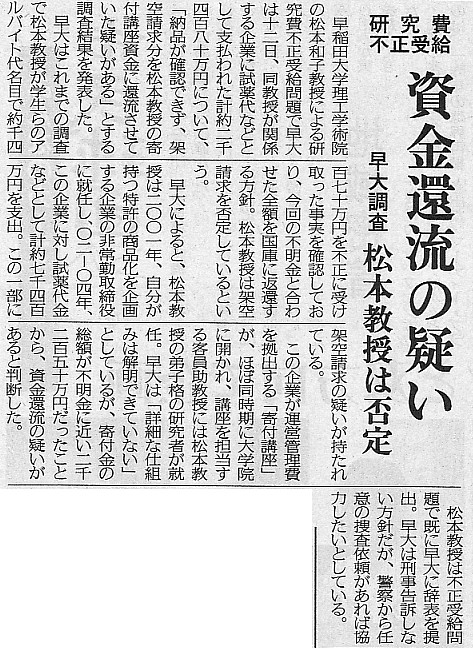
科学技術会議:有識者議員、在任中は国費を受給せず 07/11/06(朝日新聞)
国立天文台の教授(51)が98~01年度に文部科学省から支給された科学研究費補助金のうち185万円を不正に使用していたことが同天文台の調査でわかった。大学院生への謝金として処理したが、実際には旅費や研究の成功祈願のお札代などにあてていた。
不正使用がわかったのは、今秋打ち上げられる太陽観測衛星ソーラーBに搭載する望遠鏡開発のために支給された科研費3440万円の一部。
天文台の調査によると、研究を手伝った大学院生の口座に振り込まれた謝金185万円を自分の銀行口座に返金させ、うち176万円を大学院生の旅費にあてたほか、研究の成功祈願のお札代(8000円)、研究メンバーの結婚式の祝電代(約1000円)など、研究業務とは無関係の支出にもあてていたという。
旅費は科研費からの支出が認められているが、観山正見台長によると、この教授はそれをよく知らず、多忙だったこともあって別の名目で経理処理してしまったと釈明。お札代などの目的外使用を含めて「申し訳ない」と謝罪しているという。文部科学省は「ずさんな経理処理」として詳しい報告を求める一方、一部返還請求なども検討する。
風俗に行かないほうが良いが、教諭が男なら性欲もあるだろう。教え子に手を出すぐらいなら、
見つからないように行っても良いと指導するほうが良い。
しかし、生徒に手を出した場合には、どんな理由があっても絶対に懲戒免職。
シンプルな規則を決めたほうが良い。
みだらな行為:教え子にいん行、中学教諭再逮捕 愛知 07/08/06(朝日新聞)
教え子の女子生徒にみだらな行為をし、その様子をビデオ撮影していたとして、愛知県警少年課と西尾署は7日午後、同県西尾市立中学校教諭、中村庸男容疑者(44)=同市平坂町=を、児童福祉法違反(いん行させる行為)と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)容疑で再逮捕した。中村容疑者は「ほかにも4~5人の少女とみだらな行為をした」と供述しているといい、県警が調べている。
調べでは、中村容疑者は昨年8月ごろ、校舎内で女子生徒に、18歳未満と知りながらみだらな行為をし、隠しカメラで撮影した疑い。
県警は、中村容疑者の自宅や校内から中村容疑者が少女にみだらな行為をする様子が映ったビデオテープ数十本を押収。分析の結果、映像を保存していた記録媒体が児童ポルノに当たり悪質性が高いと判断して再逮捕に踏み切った。【松岡洋介】
はっきり言える事は研究費としてこれまでと同じ予算は必要ない。
予算を減らしても問題はないと言うこと。
立命館大教員が研究費を流用 07/07/06(朝日新聞)
立命館大(京都市北区)は7日、理工学部の教員が文部科学省の科学研究費補助金や学内研究助成金などを留学生の生活費に流用していた、と発表した。調査委員会(委員長・川村貞夫副総長)を設置して調査を始めており、これまでに約370万円の流用が明らかになっているという。月末までに調査をまとめ、文科省に報告する。
同大学によると、教員は02~04年度、研究室の複数の大学院生名義でアルバイト料を研究費の一部として大学に請求し、それぞれの院生名義の口座に振り込ませたうえで、入金された現金を名義の院生とは別の複数の留学生に渡したという。教員は「申し訳ない」と事実を認め、「経済的に困窮している留学生に援助してやりたかった」と話しているという。卒業生からの指摘で発覚した。
同大学は「重く受け止めている。研究費の使用について自己点検し、再発防止策を考えたい」としている。
文科省研究費など370万円、留学生生活費に…立命大 07/07/06(読売新聞)
立命館大学(京都市北区)理工学部の教員が文部科学省の科学研究費補助金などを留学生の生活費に流用していたことがわかった。
同大学が7日、記者会見を開いて明らかにした。不正受給額は約370万円に上り、教員は「留学生らが経済的に困窮しているので援助した」と流用を認めているという。学内の調査委員会は7月末をめどに同省に最終報告する。
同大学によると、教員が不正受給したのは2002~04年度の科学研究補助金など。6月23日に卒業生から情報提供があり、教員の不正がわかったという。
川村貞夫・副学長は「目的外使用という不誠実な事実が起きたことを心からおわびしたい。事実関係をさらに調査するとともに、再発防止に努める」と述べた。
松本教授、流用さらに2300万円 文科省が返還請求へ 07/06/06(読売新聞)
早稲田大学理工学術院の松本和子教授の研究費不正流用問題で、約2300万円の流用があることが新たにわかった。教授が非常勤取締役に名を連ねた企業と、研究室との間の不自然な資金の流れに絡むもので、すでに流用と認定されている1472万円に加え、流用総額は少なくとも計約3800万円に上ることになった。文部科学省は、早大に全額の返還を求める方針だ。
早大の調査によると、松本教授は02年3月から04年4月にかけ、試薬購入などの名目でこの企業に国の研究費から約7400万円を支払った。ところが、うち約2300万円分の納品が確認できず、架空取引の疑いが浮上。早大がさらに調べたところ、ほぼ同額が企業から大学に寄付されていたことがわかった。この企業は同大に寄付講座を開いていた。
この資金の流れの理由は解明されておらず、早大はさらに調査を進める。
産業技術開発機構が独自調査、早大教授の不正問題で 07/02/06(読売新聞)
早稲田大学の松本和子教授が国の研究費を不正受給した問題で、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、松本教授に交付した9年度分、計1億4600万円の経理について、独自に調査することを決めた。
大学の内部調査では不十分と判断した。不正額を確定して資金の返還を求めるとともに、最長6年の研究費応募資格停止を検討する。
調査の対象になるのは、1998~2002年度の医療機器技術研究費4000万円、01~05年度の化学物質評価システム開発費6600万円、05~06年度の高感度画像化システム開発費4000万円。
これまでの早大の調査では、このうち99~2000年度の医療機器技術研究費から、架空のアルバイト名目で約180万円を不正受給したことが明らかになっている。
NEDOは6月中旬から早大の調査について検証していたが、大学の調査委員会まかせでは不正受給額が確定できないと判断した。
◆データねつ造疑惑、化学会が調査委◆
一方、松本教授の論文データねつ造の疑いについて、日本分析化学会(会長・小泉英明・日立製作所フェロー)は1日、調査委員会を設置した。7月中に結論を発表する予定。同学会は昨年度、松本教授の新化合物開発の研究業績に対し、「学会賞」を授与した。
科学技術会議:有識者議員、在任中は国費を受給せず 07/02/06(毎日新聞)
早稲田大理工学部の松本和子教授による公的研究費の不正使用問題で、政府の総合科学技術会議の有識者議員は、在任中は国の科学技術振興調整費を受けないことで合意した。松本教授は今年1月まで有識者議員で、不正使用した研究費には、在任中に受けた振興調整費が含まれていた。
振興調整費は、国の科学技術政策の司令塔とされる同会議が決めた基本方針にのっとって文部科学省が配分する研究費。方針づくりにかかわる有識者議員が、研究費を受け取るのは誤解を招きかねないと判断した。
有識者議員は常勤、非常勤を合わせ現在8人。一線の研究者を含め産学の専門家から首相が任命する。松本教授は02年1月から06年1月まで有識者議員を務めていた。
早大の中間報告で松本教授が不正受給したとされた約1470万円の7割は、99~03年に支給された振興調整費の一部だった。【下桐実雅子】
船の世界の問題
を見ると、やはり管理や監督が甘いから不適切な検査や違法行為が見逃されている。
早大教授の研究費不正使用やその他の不正を考えても、やはり文科省が甘いから
起こったこと考えられる。教授でありながら不正使用した人間も悪い。しかし、
早大教授の研究費不正使用以外にも不正使用がある事実を考えると、
他の教授も不正を行っていても見つからない、処分もされないのなら、
自分もやってみようと行ってきたと思える。横並びの日本的な例である。
多くの税金をどぶに捨ててきた文科省。予算を減らされても仕方がない。
研究費不正対策、指針作成要請へ 総合科学技術会議 06/30/06(朝日新聞)
早稲田大学理工学術院の松本和子教授が国の研究費を不正流用した問題を受けて、総合科学技術会議(議長=小泉首相)は29日、研究予算を所管する文部科学省など8府省に対し、8月までに不正防止策の指針を作るよう求めることを決めた。
不正防止策の対象は、研究者が応募し、国側が審査して支給する「競争的研究費」。8府省で37制度あり、今年度予算は計4701億円。予算額は過去2年間で30%もの伸びを示す一方で、不正防止対策は追いついておらず、流用やプールなどの不正が相次いで発覚。歳出削減を求める財務省からは「不正の背景には金余りがあるのでは」との指摘も出るほどだ。
松本教授の今回の不正では、文科省が省内に対策チームを設け、各研究機関に示す指針案を検討。国の研究費は研究者個人に渡さずに、所属する大学や研究所などの機関が責任を持って管理する「機関管理」を徹底したり、機関が研究者や研究室に対して行う内部監査を強化したりするなどの具体案が挙がっている。総合科学技術会議も、文科省の案に沿った防止対策を各府省に求める方針だ。
早大・松本教授、国際機関にも辞表提出 06/29/06(毎日新聞)
国の研究費を不正に流用した早稲田大の松本和子教授が、国際純正・応用化学連合(IUPAC)に、副会長職の辞表を28日付で出したことがわかった。日本学術会議が明らかにした。松本教授は08年に女性として初めて、IUPAC会長に昇格する予定だった。
IUPACは新しい元素や化学物質の命名法などを決める国際機関。世界65カ国の化学関係の団体が加盟し、日本は化学関係の学会を代表して日本学術会議が加盟している。松本教授は今年1月に副会長に就任、08年1月には日本人で2人目、女性としては1919年の発足以来初の会長就任が決まっていた。
文科省はしっかりしろ。増税なしでは財政が持たない状況なのにこの甘いチェック。
予算を削り、本当に必要な研究だけに絞り込め。金が余っているからチェックが甘いのだろう。
予算の削減が課題の状況。文科省の予算を削れ。増税の前にやることはある。
人の金だと思って、チェックが甘すぎる。
早大教授・研究費不正使用 「聖域」調査甘く 06/29/06(毎日新聞)
早稲田大理工学部の松本和子教授(56)を巡る研究費不正使用問題は、大学経営陣の処分という異例の事態に発展した。松本教授は教授職に加え各公職からも退く意向だが、巨額の研究費の取り扱いを一研究者に委ねてきた大学側の管理責任は大きい。緊縮財政下でも科学研究への投資は着実に増えてきたが、今回の不正をきっかけに、「聖域扱い」への逆風が強まるのは避けられない。【須田桃子、元村有希子、下桐実雅子】
◇「金取れる」とスター視?
不正の発端は04年7月の理工学部による内部調査にさかのぼる。松本教授が非常勤取締役を務めた企業と自身の研究室とが、不明朗な取引をしているという疑惑だった。
理工学部長の足立恒雄教授(28日付で厳重注意処分)を責任者とする内部調査は、総額約7100万円の取引の一部を調べただけで「問題なし」と結論づけた。足立教授は「(本部理事の)村岡さんの了解を得て、国などに伝える必要はないということになった」と当時を振り返る。
村岡洋一理事(理事を辞任)へ報告した逢坂哲弥教授(本部研究推進部長を解任)も「村岡さんには携帯電話で報告し了承を得た。決定権者は村岡さんだ」と主張。ところが、村岡理事は「そんな話は聞いていない」と全面否定している。
研究を巡る大学間競争が激しくなる中、松本教授は現在、遺伝子解析手法の研究など少なくとも三つの公的研究プロジェクトにかかわり、支給総額は約5億1000万円に上る(二つは凍結)。足立学部長は「外部資金(現在は約70億円)を年間100億円にする」と公言しており、多額の研究費を集める「スター研究者」の不正を過小評価した可能性もある。
真相は不明だが、04年の時点で文部科学省に報告していれば、今回の混乱は防げたかもしれない。
一方、研究費を所管する文科省は「研究費が余っていると思われては困る」といら立ちを隠さない。早大が調査結果を発表したのは23日午後。文科省は週明け26日に対策チームを発足させた。異例のスピード対応について責任者の吉川晃・科学技術学術総括官は「ぐずぐずしていては、科学技術振興全体に悪い影響を与える」と話す。
政府は独創的な研究支援のため、研究費を増やし続けてきた。今年度の総額は4701億円で、10年前(1699億円)の3倍になっている。しかしこの間、研究費の不正使用も相次いだ。
今後も拡充方針ではあるが、今回の不正発覚に加え、松本教授自身が総合科学技術会議の議員として、この拡充方針を支えていたこともあり、文科省にとっては「ダブルショック」となった。
◇過熱する総長選--30日に決選投票
今回のゴタゴタの裏で見え隠れするのが今月30日に決選投票となる総長選だ。
11月に任期満了となり再選を目指す白井克彦総長は、渦中の理工学部出身。23日の会見では責任に触れなかったが、28日は一転して自らの減俸処分を発表し「結果責任、監督責任」を認めた。だが、総長選の最中での問題発覚について質問されると、広報室長が「会見趣旨と異なる」と退けた。
一方、学内有志グループは27日夜、早大本部キャンパス内で「公正・適正な真相究明の会」を開催。約200人が集まる中、対立候補の渡辺重範・教育学部教授の選挙対策責任者を務める藁谷友紀・教育学部長が「大学の存立にかかわる大問題」と口火を切った。集会では「調査方法がずさん」など理事会の対応への不満が噴出。白井総長の辞任を求める声も出た。
藁谷学部長らは28日、「白井総長の処分は軽すぎる」などとする質問状を理事会に提出。せめぎあいは過熱している。
◇東大卒マドンナ/サラブレッド学者--松本教授、周囲はこう見る
松本教授(IUPAC提供)=は72年、東京大理学部化学科を卒業。同大大学院在学中の77年に理学部助手に採用された。84年に早大理工学部助教授、89年に教授に昇格した。専門は無機化学・分析化学。最近は、ある種の金属化合物をたんぱく質やDNAなどの生体分子に付けて光らせ、ごく微量でもこれらの物質を分析できる技術の確立に取り組み、研究を生命科学領域に広げた。40件以上の特許を持ち、200本を超える論文を書いている。
02年1月から06年1月まで、国の科学技術政策の司令塔である「総合科学技術会議」の議員を務め、08年には国際純正・応用化学連合(IUPAC)の初の女性会長に就任することが内定していた。自校出身の教員が半数以上を占める早大では東大出身の女性教授は珍しく、「マドンナ的な存在」(理工学部教授)だった。
松本教授を知るある国立大教授は「(父親も著名な研究者で)育ちのいいサラブレッドがなぜ……」と絶句。20年来の知人という化学者は「少なくとも私腹をこやすような人物ではない」と話す。だが早大のある教授は「東大出身という看板や人脈を生かし巨額の研究費をもらうことが当たり前になり、金銭感覚がまひしたのでは」とみる。
==============
◇松本教授の不正の概要
早大調査委の中間報告によると、松本教授は99~03年度にアルバイト代約1470万円を架空請求し、一部を個人名義の銀行口座に還流させた。うち1010万円を02年4月に引き出し、900万円を投資信託で運用。残高は調査時点で約983万円あった。
研究実施期間が過ぎた後も保有しており、調査委は「甚大な不正行為」と判断した。松本教授は架空請求したことを認めたうえで、使用分については、学生の旅費や実験材料の購入に充てたとし、「私的流用はしていない」としている。
また、02~04年にかけ、自分が非常勤取締役を務めていた企業から薬品などを購入したとして約7100万円の研究費を受け取った。うち約2340万円分は納品書がなかったが松本教授は「架空請求はしていない」と弁明しているという。
毎日新聞は松本教授に説明を求めたが、「今は、何も申し上げられない」として取材に応じていない。
==============
◆国の研究費(科学研究費補助金)の不正使用例◆
年度 研究機関 国への返還額
96~02 埼玉医科大 約 4400万円
96~03 慈恵医大 約3億8000万円
98~00 東京大 約 910万円
98~02 芝浦工業大 約 760万円
00~04 慶応大 約 4600万円
02~04 東京工業大 約 680万円
※文部科学省の資料から作成
研究費流用問題、松本・早大教授が辞表 白井総長は減俸 06/28/06(朝日新聞)
早稲田大・理工学術院の松本和子教授による研究費の不正流用問題で早大は28日、不正そのものと、内部調査の不備への責任を負うとして、白井克彦・総長を役職手当3カ月分の減俸処分にすることなどを、記者会見で発表した。また、松本教授が辞表を出したことも明らかにした。
処分は同日付で、村岡洋一・常任理事の研究推進担当業務を解任、理事の辞表を受理した。逢坂哲弥・研究推進部長の同部長職も解任した。また、足立恒雄・理工学術院長ら4人を厳重注意とした。
松本教授について早大は、少なくとも国からの研究費の一部1472万円の流用があったと先週発表し、04年に内部調査をした際には、結果を足立、逢坂両氏が大学本部に報告しなかったなどとしていた。両氏は否定しており、同調する教員らは処分を不当として質問状を出した。
松本教授からの辞表は27日夜、理事会に提出された。流用した研究費の返還も申し出ているという。早大は懲戒処分を検討しており、辞表は受理していない。
早大の研究費13億凍結、不正受給問題で文科省 06/27/06(読売新聞)
早稲田大学の松本和子教授による研究費不正受給問題で、文部科学省は26日、経理体制の整備など不正再発防止に向けた早大の行動計画がまとまるまで、7月から配分される予定の科学技術振興調整費の執行を見合わせることを決め、早大に通知した。
松本教授が科学技術振興調整費3億6200万円の一部を私的に流用した疑いが持たれていることから、「先端科学と健康医療の融合研究拠点の形成」や「科学技術ジャーナリスト養成プログラム」、「研究者養成のための男女平等プラン」など、科学技術振興調整費による8プログラムが見合わせの対象となった。研究費の総額は13億円に上る。
また、文科省は同日、早大が公表した中間報告の内容を確認するため、本部事務所のある大隈会館(東京・新宿)を立ち入り調査した。
文科省の室谷展寛・調整企画室長ら5人が、白井克彦総長らに会い、厳重に注意した。さらに松本教授が大学に提出した謝罪文書や、不正受給した約1500万円から支出した投資信託について、早急に開示するよう求めた。
調査を終えた室谷室長は「大学組織の改善策などを含む行動計画をなるべく早く出すように指示した。詳しい調査は引き続き行う」と話していた。
早大研究費不正使用:2年前の学部内調査は常任理事に報告 06/27/06(毎日新聞)
早稲田大理工学部の松本和子教授による公的研究費不正使用問題で、04年にこの問題の学部内調査にかかわった逢坂哲弥・研究推進部長と足立恒雄・理工学部長が、「本部の村岡洋一常任理事(現副総長)に調査結果を報告し、(学部内で処理してもよいとの)了解を得た」などと主張する文書を大学側に提出したことが26日、分かった。
村岡氏が委員長を務めた早大の調査委員会は23日、調査結果が逢坂教授らの段階でとどまり、本部や文部科学省に伝わらなかったとして、2人などの処分を検討すると発表していた。04年当時に問題を見過ごした責任が大学本部にも及ぶ可能性が出てきた。
村岡氏は調査委員長だったが、26日付で田山輝明常任理事と交代し調査委員も辞めた。大学側は「(村岡氏が担当する)研究推進部が新たな調査対象となる可能性があるため」と説明している。
逢坂教授は23日付で、大学理事会と調査委員会に文書を出した。調査委が同日発表した中間報告の逢坂教授に関する記述について「捏造(ねつぞう)で、名誉棄損の疑いがある」とし、訂正と再調査を求めている。足立教授も26日に「事実関係に誤りがある」とする文書を提出した。
中間報告によると、松本教授と、同教授が非常勤取締役を務めていた企業との不明朗な取引について、理工学部は04年7月14日付で内部調査結果をまとめた。同23日に学部長だった足立教授らが逢坂教授に説明したが、逢坂教授は正式な報告とは認識せず「大学本部、文部科学省などに対する報告はここで途絶えた」(中間報告)という。
しかし、逢坂教授は、同30日に村岡氏に調査結果を報告したと反論。毎日新聞の取材に「不正とは断定できず、理工学部は松本教授にわび状を書かせることで決着したいと考えている、と村岡氏に伝えた」と話した。村岡氏も了承したという。
また、足立教授によると、村岡氏が了承した当日に逢坂教授から連絡を受け、関係者に電子メールを送った記録が残っているという。
これに対し、村岡氏は「(04年7月の段階では)報告を受けていないし、指示もしていない」と話している。【須田桃子、下桐実雅子】
朝日新聞(2006年6月26日)より
研究費不正
国民の信頼を損なった
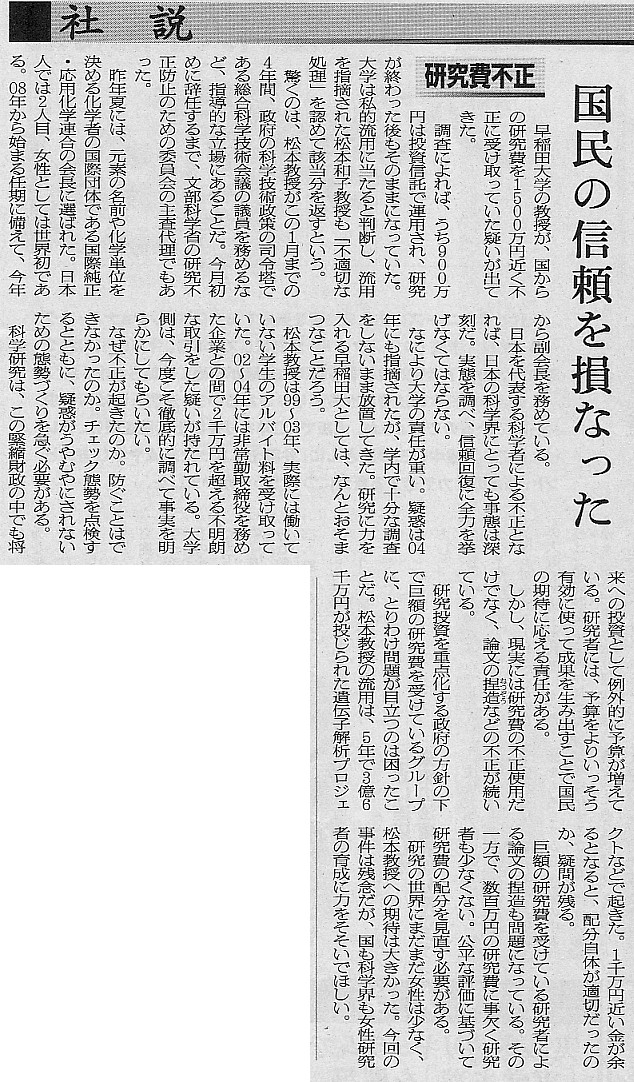
早大研究費不正使用:文科省立ち入り 管理体制で事情聴く 06/26/06(朝日新聞)
文部科学省は26日、早稲田大を立ち入り調査し、研究費管理体制について事情を聴いた。同省は松本和子教授の研究費不正使用の背景に大学当局の管理の甘さがあったとみており、同省が研究費を支給している他の大学なども順次、調査する。
また同省は26日、省内に研究費の不正使用の対策チームを設置した。 調査内容は▽試薬など消耗品購入時の納品書の保管状況▽学生アルバイトの勤務実態▽旅費支出状況▽内部監査マニュアルの整備状況--など。
同省の科学技術振興調整費を受ける約150研究機関のうち、支給額の多い20~30機関を同様に調査する。さらに支給対象機関すべてに、研究費管理の自己点検を指示した。【下桐実雅子】
早大教授の研究費資格停止…文科省、不正分返還要求へ 06/24/06(読売新聞)
松本和子・早稲田大学理工学部教授による研究費の不正受給問題で、文部科学省は24日、松本教授の同省に対する研究費の応募資格を2~5年間、停止することを決めた。
比較的多額の公的な研究費が必要な理工系研究者にとって、研究の継続が極めて困難になる決定だ。
同省は今後、これまでに明らかになった約1500万円以外に不正受給がなかったかを調べ、資格停止の期間を決める方針。不正に受け取った研究費については、年率10・95%の加算金を含めて返還を求める。
また、2年前に同教授とバイオ関連企業との不明朗取引を調査した足立恒雄・理工学術院長(当時の理工学部長)、調査報告を受けながら同省への報告を怠った逢坂哲弥・研究推進部長ら同大の4教授についても、一定期間の研究費の応募資格停止を検討する。
足立院長らは、このバイオ関連企業が01年から同大に資金を提供してきた寄付講座への入金が03年度に止まったため、企業側から事情を聴取。その際、企業が「資金は松本教授との架空取引で作った」と説明したため、約700枚の伝票のうち200枚を抽出して調査した。そのうち3分の2は納品書と請求書が合致したので、その時点で「問題ない」と判断し、調査を打ち切っていた。
流用の早大教授、2年前にも架空取引疑惑 大学報告せず 06/24/06(朝日新聞)
早稲田大の松本和子教授をめぐる疑惑には、研究費の不正流用のほか、企業の寄付金で運営される講座をめぐる不自然な取引もあった。2年前に発覚したにもかかわらず放置された形のこの疑惑。同大は23日の会見で再調査の方針を明らかにしたが、大学側の調査のずさんさや危機管理の甘さが浮き彫りになった。
同大の説明によると、松本教授は、この企業との間で02年3月~04年4月、試薬の購入などで約7400万円の取引をした。しかし、このうち約2300万円分は納品書の存在が確認できなかったほか、02年6月から04年2月まで同社の非常勤取締役に就いていた。
この企業は01年10月から資金を出して同大で寄付講座を開いたが、03年4月に資金の提供をやめ、その理由について松本教授との間の架空取引を示唆する説明をしたため、同大理工学術院(当時は理工学部)側が調査。04年7月に結果を大学の研究推進部長に説明した。
しかし結果が明確でなかったこともあり、部長は単なる相談と受けとめ、文部科学省や総長などに報告しなかった。
ただ、この時の調査は約700枚の伝票から200枚を抽出。その3分の2について納品書と請求書が合致したので、「大丈夫ではないか」と判断したという。
白井克彦総長は「さらに深い調査をすれば、関係省庁に報告すべきことが出てきた疑いがある」と述べ、調査が不十分だったことを認めた。
一方、松本教授は同大に「カラ注文をした覚えはまったくない」と説明しているという。
朝日新聞(2006年6月24日)より
早大教授 流用研究費を投信運用
大学調査 「私的」認定、処分へ

「国の「第3期科学技術基本計画」(06~10年度)では、公募による研究費を引き続き拡充する方針が盛り込まれたが、
後を絶たない不正使用の問題をこのまま放置すれば、予算の削減など研究費全体に影響を与えかねないと判断。
松本教授が今年3月から、同省で不正研究の対応を検討する委員会の主査代理を務め(今月2日付で辞任)
ていたことも事態を深刻にした。」
文科省にも問題があるだろう。不正使用の問題が後を絶たないのは、管理やチェック機能が甘いことを
意味しているのだろう。また、同省で不正研究の対応を検討する委員会の主査代理を務めた教授が
不正使用を行っていたのだから、救いようがない。モラルが欠如し教育者としての自覚もない
教授が不正研究の対応を検討する委員会の主査代理を務め、内部告発がなければ、
そのまま承認し続けていた文科省。
増税や国民の負担を増やす前に不必要な支出を止めるべきだ。
不正使用があること自体、教授達に問題があることを意味している。
問題がある教授に期待するよりも、もっと研究生や助教授が結果を残せる体制にするよう
改革や改善をするべきである。日本は閉鎖的なところがある。
早大研究費流用:監査体制強化で抜本策検討 文科省 06/24/06(毎日新聞)
早稲田大学理工学部の松本和子教授が国などの研究費を私的流用していた問題で、文部科学省は再発防止のため大学の内部監査体制を強化させる抜本策の検討に入った。今回の早大だけでなく、各地で不正受給が発覚していることも背景にあり、当面はガイドライン作りを想定している。
文科省は現在、競争的資金と呼ばれる研究費助成が13種類あるが、松本教授はこのうち科学技術振興調整費などを受給していた。政府は昨年、研究者に公的研究費の不正受給や不正使用があった場合、すべての省庁への研究費応募申請を最大5年間、禁止する方針を決めている。文科省でも不正使用が発覚した時点で個別に対応してきたが、内部監査の強化など抜本的解決策は先送りにしてきた。
また、国の「第3期科学技術基本計画」(06~10年度)では、公募による研究費を引き続き拡充する方針が盛り込まれたが、後を絶たない不正使用の問題をこのまま放置すれば、予算の削減など研究費全体に影響を与えかねないと判断。松本教授が今年3月から、同省で不正研究の対応を検討する委員会の主査代理を務め(今月2日付で辞任)ていたことも事態を深刻にした。
今後の具体的手順は、まず省内に近く検討チームを発足させる。研究費を受給した場合、大学内部でどのような体制で使途をチェックするかなど標準的なモデルなどを検討し、ガイドラインとしてまとめる予定。
不正受給が発覚したケースは、ここ数年では日本医科大老人病研究所が99~04年度に約4億円▽慶応大で00~04年度に約7500万円▽愛知医科大で97~03年度に約4700万円▽東京慈恵医科大で96~03年度に約4億円--などがある。【下桐実雅子】
教諭送検:「キャバクラ行きたかった」勤務先から現金盗む 06/03/06(毎日新聞)
勤務先の学校に忍び込んで現金計約70万円を盗んだとして、大阪府警富田林署は2日、同府河南町の町立中学校の男性教諭(47)=休職中=を窃盗と建造物侵入の両容疑で書類送検した。教諭は「大阪市北区のキャバクラに行く金が欲しかった。お気に入りの子に会いたかった」と容疑を認めている。
調べでは、教諭は昨年12月3日夕、校長室の金庫に保管してあった同校のバザー売上金約48万円を盗み、今年1月4日夕にも、職員室の教頭の机の引き出しに保管してあったクラブ活動費約22万円を盗んだ疑い。
両日とも学校は休みだったが、教諭はセキュリティーシステムを解除して校内に侵入。職員室のかぎ箱から教頭の机のかぎを取り出して、机を開錠した。校長室の金庫のかぎも教頭の机から取り出して、開けていた。
バザー売上金は、生徒らがバングラデシュなどの国に車いすを贈るために集めたものだったという。【隅俊之】
「キャバクラに行きたい…」中学教諭がバザーの金盗む 06/02/06(読売新聞)
勤務している中学校の校長室の金庫などから約70万円を盗んだとして、大阪府警富田林署は2日、大阪府河南町、同町立中学校の男性教諭(47)を窃盗などの疑いで書類送検した。
このうち約48万円は、生徒がバングラデシュに車いすを贈るための輸送費として蓄えていたバザーの収益金だった。男性教諭は「小遣いが少なく、キャバクラに通う金がほしくて盗んだ」と供述している。
調べによると、男性教諭は昨年12月3日夕、職員室の教頭の机の中にあった鍵で、校長室の金庫を開けて約48万円を盗み出し、今年1月4日夕にも教頭の机の手提げ金庫から約22万円を盗んだ疑い。男性教諭は自宅謹慎中で、府教委は近く処分する方針。
同校は、約10年前から中古の車いすを修理してバングラデシュの病院などに贈っている。
「使用された通知票に『平和を願う世界の中の日本人としての自覚』などが併記されていることを挙げ、
『愛する心情を持つことだけを評価しているわけではない』とも語った。」
こんな言い訳を採用して弁解するべきでない。文科省を評価してほしいと言われれば、
良い評価など出来ない。国の機関である文科省を非難するのは愛国心と解釈されるのか。
国の機関であるので批判すると、愛国心がないのか。
子育てにおいても同じことが言える。甘やかすだけが愛ではない。子供が将来、りっぱになれるように
厳しくすることや甘やかさないことが子供のためになるのであれば、子供に怖がられたり、
好かれなくとも行動に移すことが愛なのか。甘やかすことを愛とも言えるが、愛ではなく自分を良く思われたい
と思う自己本位とも言える。
問題のある教員を放置し、現在の状況まで適切な対応を取れなかった文科省に間違いがなかったのか。
子供の学力低下に対する問題点をどう分析してきたのか。ゆとり教育はStress free Educationと
訳されていて驚いた。もしゆとり教育=Stress Free Educationであれば、文科省に間違いであったと
思う。
「愛国心」の評価、行き過ぎ指導へ 文科相 05/27/06(朝日新聞)
小坂文部科学相は26日、愛国心をランク付けする通知票が一部の小学校で使用されていることについて「内心を直接的に評価してはならないと学校長会議や教育長会議で伝達している。通知票に行き過ぎがあれば、学校長の理解を求める努力をしていきたい」と述べ、通知票を通じた強制にならないよう指導する考えを明らかにした。教育基本法改正をめぐる衆院特別委員会で横光克彦氏(民主)に答えた。
小坂氏は「内心の強さをABCで評価するなどとんでもない」とする一方、使用された通知票に「平和を願う世界の中の日本人としての自覚」などが併記されていることを挙げ、「愛する心情を持つことだけを評価しているわけではない」とも語った。小泉首相は24日の同委員会で「こういう項目は持たなくていい」と評価自体を不要としている。
更新制にこだわらなくとも、辞めさせる、教育関係から外させることが出来ればよい。
公務員が問題を起せば、懲戒免職にしても良い。
国の指定する大学などで20~30時間の講習を受ければ更新される仕組みを採用しても
講習の内容が形だけになったり、必要ない講習であれば、意味がない。
時間の無駄で、税金の無駄である。
交通違反した時に処分期間を短縮するための講習も効果があるかと言えば、すごく疑問である。
文科省の指導にも問題があると思う。いろいろ話を聞くと、文科省の指示や対応が
教員の問題にも関連していると思う。もっと、文科省を非難すべきである。
交通違反した時に処分期間を短縮するための講習も効果があるかと言えば、すごく疑問である。
教員免許:更新制、現職にも適用 文科省、中教審に報告へ 05/26/06(毎日新聞)
教員の資質向上のために導入される教員免許更新制について、文部科学省は、現職教員にも適用することが法的に可能だとの結論に達した。26日開かれる中央教育審議会教員養成部会のワーキンググループ(WG)に報告する。WGは以前から全教員を対象とする見解が支配的で、全国約100万人の国公私立現職教員に免許更新制が適用される公算が大きくなった。
現行の教員免許は一度取れば生涯有効だが、更新制が導入されれば免許の有効期間が10年間に限定される。期限が切れる際に、国の指定する大学などで20~30時間の講習を受ければ更新される仕組み。導入自体は昨年12月の中教審中間報告に盛り込まれて決まっているが、WGは現職にも適用できるかどうか慎重に検討していた。
免許を得た時に更新制を前提としていない現職にまでさかのぼって適用することには「法律の一般原則に反する」との意見があり、「教員の負担を増やすだけ」「自発的に学び合う教員同士の研修会も発達している」など現職教員の反発も予想される。
文科省は、免許が失効しても所定の講習を受けて再度申請すれば失効期間の長さに関係なく回復する道を用意することや、現職への適用で資質向上に大きく役立つことなどを踏まえ、法的に問題はないと考えている。
教員の質をめぐっては近年、指導力不足で学級崩壊を招いたり、わいせつ行為や体罰など不祥事を起こす教員への国民の批判が高まっており、中教審は免許更新制の議論を加速させていた。今夏にも小坂憲次文科相に答申する。
中教審は01年12月にまとめた中間報告で、免許更新制を導入するとともに、▽指導力不足教員などに対する人事管理システムを早急に構築する▽教員免許をはく奪する条件を整える▽教職10年の経験がある教員に対しては、個々の勤務成績に応じた研修を実施する--などの資質向上策を提言している。【井上英介】
約7年近くも日本にいて麻薬が違法だと知らないのか?
知り合いの外国人や日本人は麻薬を使っていることを知らなかったのか?
使用後の姿を見られなかったのか、使用しても普通な感じだったのか不思議
である。
関西外大の米国人教員、麻薬密輸容疑で逮捕 05/18/06(朝日新聞)
英国から麻薬を密輸入したとして、大阪水上署と大阪税関が関西外国語大学(大阪府枚方市)の米国人招聘(しょうへい)教員カイル・クーパー容疑者(40)を麻薬取締法違反の疑いで逮捕していたことがわかった。クーパー容疑者は「自分で使うつもりだった。違法とは知らなかった」と供述しているという。
調べでは、クーパー容疑者は4月30日、GHB(4‐ヒドロキシ酪酸)の粉末約121.2グラムを英国から航空貨物で関西空港に密輸入した疑い。
同大国際交流部によると、クーパー容疑者は98年に5年契約で採用。勤務成績は良く、03年に契約を更新していた。
元ホステスに「給料」、前理事長ら逮捕…浅井学園事件 04/13/06(読売新聞)
札幌市の学校法人「浅井学園」の前理事長・浅井幹夫被告(57)らによる乱脈経営事件で、北海道警は13日、学園の出資する人材派遣会社が、浅井被告が親しくしていた女と架空の雇用契約を結び、約600万円を給料名目で支払っていた疑いが強まったとして、業務上横領容疑で浅井被告を再逮捕するとともに、新たに学園幹部と、この女の計2人を同容疑で逮捕した。
新たに逮捕されたのは、学園関連の人材派遣会社「カレッジ・メンテナンス」(3月に解散)の元社長、学園参与、大橋巌(58)(札幌市豊平区)と、高級クラブ元ホステスの無職、渡辺朋子(36)(同市東区)両容疑者。浅井被告は、別の業務上横領容疑で拘置されており、今回が3回目の逮捕になる。
調べによると、浅井被告ら3人は共謀し、2003年4月から04年8月にかけ、「カレッジ」社と渡辺容疑者の間に架空の雇用契約を結ばせ、大橋容疑者が業務上管理していた同社経費から、二十数回にわたり、渡辺容疑者の預金口座に給料名目で計約600万円を振り込ませ、横領した疑い。
調べに対し浅井被告は、「(渡辺容疑者は)実際に働いていた」と容疑を否認している。大橋容疑者は、「働いていた事実はない。浅井被告の指示で振り込んだ」と供述し、渡辺容疑者は「今は話せない」と述べているという。
同社は学園の全額出資で02年に設立。学園への職員派遣などを主業務にしていたが、学園に派遣されたはずの職員に浅井被告宅で家政婦や犬の世話係などもさせていたという。
大橋容疑者は、学園の財務部長を務めており、「金庫番」的存在だった。
分限免職処分:高校教諭、北海道教委「指導力不足」と認定 04/13/06(毎日新聞)
北海道教委から「指導力不足」と認定され、研修を受けた道立美深高(美深町)の清尾栄司教諭(52)について、道教委は12日、分限免職処分とした。指導力不足で免職されたのは道内で初めて。清尾教諭は道人事委員会に不服を申し立てる方針。
道教委は昨年3月、「生徒への指導に問題があり、校長らの指示を無視する」として、清尾教諭を指導力向上制度の研修対象に認定。清尾教諭は同4月から、高校側が示した教師の心構えや生徒の指導方法などの課題について研修日誌を書いた。
この間、清尾教諭は「退職を強要された」と札幌法務局などに人権救済を申し立て。また、校長ら管理職に研修の改善要求書を手渡した際、暴行を受けたとして被害届を出し、美深署は校長ら管理職3人を暴行容疑で旭川地検名寄支部に書類送検していた。
道教委は研修を1年間で解除し、清尾教諭は今年4月から別の研修を受けていた。今回の処分について、道教委は「指導力向上制度の対象となりながら、与えられた課題に取り組まず、研修前から上司の指示に従わないなど、総合的に判断した」(教職員課)と話している。【千々部一好】
<分限処分>
勤務成績が良くなかったり、心身の病気などで職務の遂行に支障がある場合に相当し、免職、休職、降任、降給がある。懲戒処分は、交通違反やわいせつ行為といった個人が犯した法律違反などが対象になる。
教え子にメール9百通「愛しています」 教諭を懲戒免職 03/28/06(朝日新聞)
「愛しています」「何年かたって機会があったら合体しましょうか?」といった内容を含む921通の携帯メールを教え子の女子生徒に送信したとして、神奈川県教育委員会は28日、平塚市内にある県立高校の男性教諭(53)を懲戒免職にした。
県教委によると、理科の授業を担当していた当時2年の生徒に04年6月から半年ほど送信し、うち約100通は勤務時間中だった。
保護者からの連絡で発覚したが、教諭が休職したため、調査が遅れたという。県教委は「2人で食事に行ったことはあるようだが、教諭は恋愛感情は否定している」と説明している。
製鉄所副所長の経歴であれば、目標達成のためにやりかたを問われなかったかもしれない。
重工業は古い体質があると思う。また、民間は目標や利益のためなら許される
行為もある。また、大手と言うこともあるので、権限があればいろいろなことが通っただろう。
全てが平等の公務員、しかも、学校の教諭であれば、理解できない世界と思う。
平等でない世界、違反も不正もまかり通る世界、結果を求められる世界に教諭はなじみが無いだろう。
あまりにも平等や理想の世界に浸りすぎ、世間を知らないかもしれない。
だから、教諭達にも改善すべきことがある。ただ、大手企業の人間を使えば上手くいくと考えた
府教委にも甘さがあったと思う。成功者と考えられる大手企業の人間だから、教育でも成功する
わけではない。校長になる民間人のための研修期間も必要だし、教諭達の意識改革も必要。
民間人校長:大阪府立高校を辞任 教諭らに精神的暴力か 03/25/06(毎日新聞)
大阪府立高校で初の民間人校長に登用された府立高津高校(大阪市天王寺区)の木村智彦校長(59)が24日、府教委に辞職願を提出、受理された。同校の教諭10人が「脅しや人事権を背景に精神的暴力を受けた」として大阪弁護士会に人権救済を申し立てていた。木村校長は任期を1年残して今月末付で辞職する。
申立書によると、木村校長は02年4月の着任後、学校の運営方法に反対意見を述べた教職員を怒鳴ったり、他校への異動を迫るなどし、うつ状態になったり退職に追い込まれたケースもあるという。教諭らは、府教委に解任と再発防止策を講じるよう求めた。
木村校長は会見で、申し立てに対し「信じられない気持ち」と強調。申立書の内容を「(教職員に)ぞんざいな言い方をしたことはあった」としつつ「曲解や誤解、誇張がある。断固反論する」と話した。その上で「学校に混乱を招かないため辞職する」と説明した。
木村校長は住友金属工業で製鉄所副所長などを経て着任。「現役で国公立大学に100人合格」「現役進学決定率60%」などの数値目標を掲げた。さらに、保護者有志の主催で進学塾の講師が土曜日に同校生徒を指導する「自主学習講座」も後押しし、02年春に48人だった同校の国公立大合格者が05年春には119人に増えたという。木村校長は会見で「改革は進んだ」と訴えた。教諭の一人は「改革の目的に反対ではないが、発言を封じる姿勢がおかしい」と話した。【川上克己】
大阪の小学校教諭、授業中にWBC観戦 「気になって」 03/18/06(毎日新聞)
大阪市立小学校の5年生の教室で、担任教諭(47)が授業中に教室内のテレビをつけて、野球の国・地域別対抗戦ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)を観戦していたことがわかった。児童が「勉強に集中できなかった」と保護者に訴えて判明した。市教委は「軽率な行為だ。厳正に対処する」としている。
市教委によると、教諭は16日、算数のプリント学習にあてた4時間目の途中に始まったWBCの日本対韓国の試合を、教室のテレビのスイッチをつけたり消したりして数分にわたって観戦。国語のプリント学習にあてた5時間目も見ていた。
市教委は「テレビは教材として映像を使う際、指導計画を立てて使用するもの」とする。教諭は「試合が気になった。誠に申し訳ない」と話しているという。
セクハラ:女子学生にキス迫る 岐阜大の教授を停職7日 03/17/06(毎日新聞)
岐阜大学(岐阜市)は16日、女子学生に性的嫌がらせ(セクシュアル・ハラスメント)をしたとして、同大の男性教授を停職7日の懲戒処分にしたと発表した。
同大の安田孝志理事によると、教授は昨年11月19日、研究室などで指導している女子学生を合宿先で屋外へ誘い、抱きしめてキスを迫った。女子学生は同大セクシュアル・ハラスメント相談員に相談。同大の調査に対し、教授はこのほかに04年7月から約1年間で計3回、同じ女子学生をスナックに呼び出して抱きつくなどの嫌がらせをしたことを認め、「親ぼくの情だった」と説明しているという。
同大は「女子学生が安心して勉強できる状態の回復を望んでいる」として教授の学部や年齢も非公表とした。停職期間が短いことについては、安田理事は「この教授は教育者としての資質を持った人で、今後は一層の熱心な指導を期待している」と説明した。同大では昨年7月にも同じ学部で女子学生を抱きしめた男性教員が3カ月の減給(10分の1)処分にされた。【中村かさね】
Gifu University tried to protect a professor who kiss a female student
by not announcing the namveo professor and his faculty. Professor's
excuse is "I was trying to show my sense of friendship with her."
"Yasuda (a director at the university) suggested that the period of suspension
was short because the university appreciated the professor as an educator."
This is a problem. Does anyboday agree?
Professor suspended for trying to kiss student 03/17/06(Mainich)
GIFU -- A Gifu University professor has been suspended for seven days for sexual harassment after he hugged a female student and tried to kiss her, school officials said.
Takashi Yasuda, a director at the university, said on Thursday that the professor invited the student outside when they were on a school trip on Nov. 19 last year.
He hugged the woman and tried to kiss her. Later, the student raised the issue with sexual harassment counselors at the university.
The professor reportedly had hugged or harassed her in 2004 as well.
"I was trying to show my sense of friendship with her," Yasuda quoted the professor as saying.
The university didn't announce the name of the professor and his faculty, because officials said the student just wanted to get back to her studies.
Yasuda suggested that the period of suspension was short because the university appreciated the professor as an educator. (Mainichi)
文科省出向で給与補てん、4研究機関計27職員に 04/06/05(読売新聞)
文部科学省所管の4つの研究機関が、同省へ出向させた計27人の給与の一部を補てんしていることが5日わかった。
国家公務員倫理法の倫理規程では、国家公務員が利害関係者から金品の贈与を受けることは原則禁止。今回の補てんは倫理規程に抵触する可能性があり、国家公務員倫理審査会は実態調査に乗り出した。
文科省によると、今年3月1日時点の出向者数の内訳は、特殊法人の核燃料サイクル開発機構9人、日本原子力研究所7人、独立行政法人の宇宙航空研究開発機構(JAXA)7人、科学技術振興機構4人。
科学技術研究を強化する国の方針で、成果主義の導入が進み、有能な人材に高給を支払う傾向が、こうした研究機関でも強まった。研究者を中央官庁へ出向させると、給与が下がることが多い。官庁側に差額を支払う制度がないため、研究機関が「休職給」などの名目で補てんしている。
4法人の中で年間予算が最も大きいJAXAの場合、中央省庁へ出向した職員の給与補てん額は、この5年間で約2億5000万円。2004年度は35人の出向者に、2月までで1人平均150万円を支払った。
同省人事課は「各機関の許認可を握る部署に配置しないなど、人材は適切に活用している」と説明する。しかしJAXAの出向者のうち2人は、JAXAに助言する宇宙開発委員会の担当部署に配属されている。核燃機構の5人も、原子力の安全規制を担当する課へ出向している。同倫理審査会は「禁止行為にあたらないか調査し見解をまとめる」としている。
行政にも専門知識が求められる時代で、官庁と研究機関との人事交流の必要性は高まっている。省内には「国から派遣元に、差額分をまとめて渡す仕組みを作ればいい」との声もある。
教育する機関が、虚偽文書提出。これが事実なら関係者を厳しく処罰すべきだ。
自己の利益のために虚偽文書提出する。モラルを教えられない教育機関は、大きな
問題であろう。企業の不正が公になっている現状を考慮すると、許しがたいことである。
教育機関しかも、国立大がこのようなインチキをおこなう。
このような事がおこらないように厳しい処分が必要であろう。文科省は
このことを考慮して厳しい調査と処分を行うべきである。
信州大、虚偽文書提出の疑い 法科大学院申請で 04/03/05(朝日新聞)
信州大学(小宮山淳学長)が昨年6月、法科大学院の設置を文部科学省に申請する際、予定教員5人の未完成論文を「完成済み」として提出していたことがわかった。設置審査が始まった昨年9月までに論文は完成しており、大学側は「問題ない」と主張している。しかし、文科省は「申請の時点で完成していることが条件。虚偽文書にあたる疑いがある」として調査に乗り出した。
法科大学院は司法制度改革の一環として質の高い法律家を数多く育てることを目的にスタート。少子化時代の生き残り戦略もあって多くの大学が設立を進め、担当分野での業績が豊富な教員の確保に追われた。とくに、地方の国立大学では、大学のブランド力や私学に比べた資金力の差から教員集めが難しい事情があった。
法学部のない信州大は、法律研究教員の在籍する経済学部が主体となって設置を申請。昨年11月に認可され、今月4日に開校する。大学側が確保した教員は21人で、申請の際、それぞれ論文の概要や著書などの実績を記載した個人調書を提出した。
文科省が各大学に示した「大学設置申請書類作成手引」では、発行・発表予定の論文や著書については、出版元の証明書を添付するよう義務づけ、申請以降に投稿予定のものは含めないよう指示している。
関係者や内部文書によると、このうち又坂常人経済学部長ら5人の個人調書の中に、設置を申請した6月30日の時点で完成していなかった論文の概要が含まれていた。大学側は5人の調書に「受領した。経済学部の紀要(論文集)に掲載する」として、論文が完成したことを証明する「発刊予定証明書」を添付した。5人が論文を完成させ、論文集の編集担当者に提出したのは7~8月だった。
編集担当者は「各先生に原稿提出を何度も督促したが、『9月にあがればいい』などと言われた」と話す。
一方、又坂学部長は「申請前は準備のため忙しく、論文ができていなかった」と話している。
法科大学院の設置は、有識者でつくる文科省の大学設置・学校法人審議会が、施設の状況や、個々の教員が担当科目を受け持つ能力があるかどうかなどの点について審査する。教員の審査は、大学側提出の個人調書をもとに判断する。可否の基準は非公表だが、審議会のある委員は「過去5年間の論文の内容が重要。論文数も多い方がいい」と話す。
信州大は21人全員が法科大学院の教員に就任することが認められた。5人の教員の調書に、それぞれ何本の論文の概要が記載されていたかは不明だが、うち1人の教員は、問題の論文を除くと、90年に発表した論文が最後という。
文科省大学振興課大学設置室は「書類提出後に書いた論文は審査の対象として認められない。事実ならば証明書は虚偽を記載した文書にあたる可能性がある。国立大学が虚偽内容を申請したとなれば前代未聞」とし、信州大に対して経緯の調査報告を求めている。
噴き出した暗部/青森公立大不正流用(上) 04/19/04(東奥日報)
(上)疑惑と不信/出張費水増し常態化
おかしい。金の動きが変だ-。青森公立大の事務局幹部に、昨年四月以来、「不明朗な会計が行われている」と、たびたび情報が寄せられていた。「国際交流ハウスのパーティー費用は、どこから出ているの」。有能で、上司から信頼され続けた公立大の前総務課長についてのうわさだった。
内部調査は今年二月から始まった。書類は担当者(同課長)が海外出張している間に調べ上げられ、その結果、予算の出納簿がなくなっていることが分かった。
裏金をつくるため、教員の正規の旅費を水増し、その差額をためていた-。二月から三月まで福士耕司事務局長ら、内部調査チームが行った計四回の聴き取りに対して前総務課長はそう話し、「(流用額は)十年間で約四千三百万円。大学のためだった」と申告した。
年間二千数百万円にも上るパイの大きい教員の研究旅費。それが水増し・架空請求の対象となった。開学時、教員一人当たり年間計百四十万円の出張旅費が認められていたが、限度額を超える旅費が市会計課に請求された。差額は金融機関に作った個人名義の複数のカードローンに入れ、メーンバンクは外された。書類には教員が預けた印鑑が使われた。
出張1件で200万円も
内部調査報告書では、二〇〇二年度だけでも不明朗な海外旅費は十九件、五百九十万円にも上り、出張先は米国、ロシア、ミャンマー、韓国など。出張一件で二百万円を引き出したケースもあった。
大学は、青森市は、なぜこうした動きを見過ごしてきたのか。「慚愧(ざんき)の至り。学長の責任を問われて当然」。問題が報道された四月八日、昨年就任した佐々木恒男学長が記者会見で陳謝した。内部調査報告書は報道機関にも流れ、流用金は大学備品や学長旅費、さらに大学の設置者・佐々木誠造市長が参加した懇談会やゴルフ代に使われことが判明、市長の責任問題まで浮上した。
その市長は十二日の臨時記者会見で「驚天動地。不正流用されたことも、認識もなかった。(適正な)公金から支出されたお金との認識だった」と主張した。
しかし、県民の不信や疑念がくすぶっている。青森市中央四丁目の会社員女性(28)は「市長自らが、ゴルフ代を大学側が(税金から)払ったと認識しているなら、返金した上で、トップとして責任を明確にすべき」と指摘。「あいまいな対応は、何の戒めにもならず問題続発につながる」と言い切った。
膿出し切りたい
今回の不正流用に対し、何時でも発生する大学や教員自身の要求や需要に即座に対応したり、運用資金の必要に迫られたと指摘する関係者も少なくない。細かいものは市の支出決済を受けていられなかったとする。背景に、大学運営にシステムが追い付かない、事務局の未成熟があるというのだ。
問題の実態解明は、十二日発足の大学経理調査委員会に委ねられた。結論は五月末までに出される。焦点は(1)不正流用額の特定と私的流用の有無などを含む使い道(2)さらに重要なのは流用した背景や大学の体質自身-にある。
「大学の膿(うみ)を出し切りたい。学生のために、地域の悲願として誕生した大学の信頼を取り戻すために」。大学関係者はこう指摘した。
噴き出した暗部/青森公立大不正流用(下) 04/20/04(東奥日報)
(下)予算執行の課題/厳格な財務規則が壁
「約束が違う」「君はちょっとな」-。青森公立大学が開学した一九九三年当初、私立大や民間から赴任した教員の多くは、領収書を手にしながら、前総務課長(当時主査)らにこう詰問したという。教員は、東京の格安店や通販で買ったパソコン、書籍の代金の支払いを大学側に求めてきた。
「財務規則上、立て替え払いや指名業者以外の予算執行はできないことになっています」と説明する前総務課長ら大学側。納得できないとする教員は少なくなかった。前総務課長の頭をよぎったのは「市役所でなく、大学を見て仕事をするように」と助言した市長ら幹部の言葉。大きな期待を背に開学した大学運営はスムーズでなければならない。誇りある教員とギスギスした関係であってはいけない。関係者には何としても立派な大学にしなければという雰囲気があった。
人事面の問題指摘
突き上げと感じた前総務課長は「自分の残業代やカードローンから支払い、借金を抱え込んだ」とする。その穴埋めのために海外旅費の水増し請求や架空請求を思いついた-と。数千万円にも上る不正流用の始まり。流用金の使途は、後に教員の研究費のほか、大学関係者の飲食費、接待費と拡大していった。
「(教員や大学関係者から)求められれば、何とかしなければという気持ちになった」と、心の弱さを前課長は認めた。
青森公立大は九三年、東郡六町村と青森市が負担金を拠出して組合形式で開学。負担金の99%を市が出資。実質「市立」の意味合いが強かった。
よちよち歩きの中で、大学運営のノウハウがないまま、市の財務規則を適用し予算執行体制をつくった。そのために、教員と認識のズレも生じた。一方では、有能な教員を招へいするために好待遇の条件を提示した。それでも「教員の要求の高さに、大学の予算体制が付いていかなかった」との声がある。
市による慣れない大学運営。その中で、学長ら大学幹部にとり前総務課長は「できる人材」だったという。教員の要望を上手に調整、突発的な経費支出にも柔軟に対応する“頼れる存在”。ゆえに、大学側が十年以上も手放さなかったとされる。
「彼(前課長)はある意味で、被害者。全部一人で抱え込んでいた。気が付かなかった私たちが悪かった」と山崎五郎副学長。佐々木恒男学長は「一人の人間が、十年以上も金の出し入れを引き受けていた点に問題があった。つらかったろう」と人事面の問題を指摘した。
青森市在住の六十代の男性は「前総務課長だけが悪いとするのはどうか」と言う。娘が青森公立大に通う今別町の五十代の女性は「公立大のずさんな経理、管理体制は残念。大学の体質こそ改善すべき」と話す。公立大二年の女子学生(20)は「大好きな大学だけに、ショック。しっかりしてほしい」と訴えた。
「一番悪いのは自分」
現在、市役所本庁の課長として働く前課長は「お金は大学運営のために使った。必要な金だったと思う。今、働けるのは、大学開設準備から大学をつくりあげてきたという自負があるから」と本紙に語った。
しかし、その自負がおごりとなり、不正につながったのではないか。「大学は常に変化している。それに見合った予算システムが必要だと感じている」と主張した前課長だが、「一番悪いのは自分」と口にした。
大学の最終報告書を踏まえた上で「今回の問題を反省材料として、対策を取りたい」と話す大学設置者・佐々木誠造市長。大学事務局は今回の問題を受け、来年度以降、現状に見合った予算を市側に求めていくことを協議している。同時に教員の自戒も求められよう。財政状況は極めて厳しい環境にあることに変わりはない。
文科省は東大の教授でもこのような人間が存在することを認識し、教員の資質や資格を定期的に
査定し、問題のある教授や教師を排除する対策を行うべきだ。
対応しないのは、放置しているのと同じだ。学力低下の結果を受け止め、改善すべきだ。
東大2教授、セクハラで処分…性行為強要・旅行に誘う 12/24/04(読売新聞)
東京大学は24日、大学院理学系研究科付属原子核科学研究センターの片山武司・元教授(61)が在職中にセクハラ行為をしていたとして、諭旨解雇相当とする処分を決めた。
また、総合文化研究科の50歳代の男性教授もセクハラ行為で停職2か月とした。
東大によると、片山元教授は1995年から2002年にかけ、同大の女子学生と女子職員の計2人に性行為を強要した。
片山元教授は在籍していた理化学研究所で出張旅費を二重取りしていたことが明らかになり、今年6月に自ら同大を退職したが、今回の処分で退職金が3分の1減額される。セクハラ行為については、事実関係を認めたが、強制ではなかったなどと主張しているという。
また、総合文化研究科の男性教授は03年春ごろから、指導する女子学生に対し、私的な海外旅行に同行するよう繰り返し誘った。
東大はこの教授については、被害者への配慮を理由に匿名発表とした。
教育費を削減する提案を出したり、国は何を考えているんだろうね。
「国際調査結果に続き、小中学生の学力低下傾向を示す結果が出た」のは
文科省の責任。
教員の資質や資格などの再チェックなどを甘くしてきた。
問題のある教師に対して、厳しい対応が出来なかった。
ゆとり教育の本来の目標を達成できず、外国の物まねをしただけで、
授業時間を短縮し、学習内容を簡単にした。
塾や外部の講師に頼らなくては学習効果を上げられないほど、現場の質を下げている。
誰が責任を取るのか??公務員は責任を取らなくとも良い状況を変えないと
沈み行く日本を助けることは出来ない。日本は大丈夫と思うなら、国民の負担を
増やすな!!
文科省「ゆとり」転換、授業時間増を検討 12/15/04(読売新聞)
文部科学省は14日、小中学校などの授業時間を増やすため、標準授業時間の見直しの検討に着手した。高校1年の読解力低下を示す今月7日の国際調査結果に続き、小中学生の学力低下傾向を示す結果が出たのを受けての措置。
実現すれば1977年から減り続けていた授業時間が約30年ぶりに増加に転じることになり、文科省が推進してきた「ゆとり教育」の方針を、事実上、転換することになる。省内には異論もあり、慎重に検討を進めている。
検討されているのは、平均的な基準だった標準授業時間を「最低限度」と位置づけを改め、各学校にそれを上回る授業時間を確保してもらうよう促す案や、標準授業時間そのものを引き上げる案など。学校現場に学力向上への意識を高めてもらう一方、近年の学力低下論の噴出で高まる公教育への不信感をぬぐいたいという狙いがある。見直しの方向性がまとまり次第、文科省では年明けにも中央教育審議会に具体的な導入方法や時期などを審議するよう要請する。
標準授業時間は現在、小学校が6年間で計5367時間、中学校が3年間で計2940時間。高校も必要な単位数を取得するための時間数を規定している。標準授業時間が最長だったのは、1968年の学習指導要領改訂後の一定期間。「教育の現代化」に向けて各教科で新しい内容が盛り込まれ、中学校では3360時間から3535時間に拡大。小学校の授業も当時は5821時間という長さだった。
ところが授業についていけない子が問題になり、その反省から77年の改訂で、小中学校とも授業時間を削減。その後も、「ゆとり教育」や学校週5日制の実施で、標準授業時間は削られ続けてきた経緯がある。
小中学校では中3の受験期などを除き、標準を上回る授業時間を確保しているのが実態だが、今後、授業時間を拡大する場合、長期休暇の一部や放課後を授業に充てるケースなども想定され、学校現場にも大きな影響が出そうだ。
2つの国際調査で相次いで学力低下の傾向が示されたことについて、中山文科相は「学校週5日制や学習指導要領の削減が、必ずしも望ましい結果になっていないと思う。その点を率直に認め、対策を講じる必要がある」と述べた。
ゆとり教育の問題や英語教育等が注目されている。本当に英語教育に
関して文部科学省は適切な選択をしているのか。
JETプログラムと呼ばれるものがある。
このプログラムの概要については
ここを見ていただきたい。
プログラムの目的自体は問題ないようである。しかし、ALTと呼ばれる
人達の質、選考基準、又は面接者に問題があるように感じることがある。
本当に適切や面接が行われているのか。面接者の資格や能力に問題が
ないのか。いろいろな省がこのプログラムに係わっている。
一度、真剣に取組まなければならない。
英語教育の強調するのは良いが、あまりにも費用を掛け過ぎたり、
不適切な人材をリクルートするのは、税金の無駄である。
職安の問題や
警察の問題
のように今一度、制度をチェックするべきであろう。
★HOME
リンク先の情報については一切責任を負いかねますことを申し添えます。
リンク先の中には繋がらないものもあると思いますが、ご容赦ください。
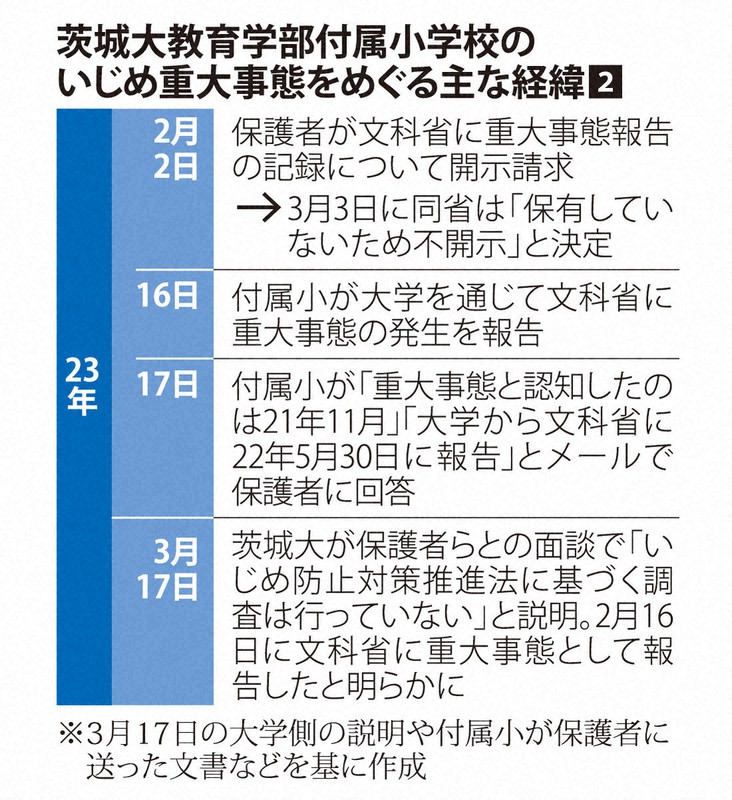
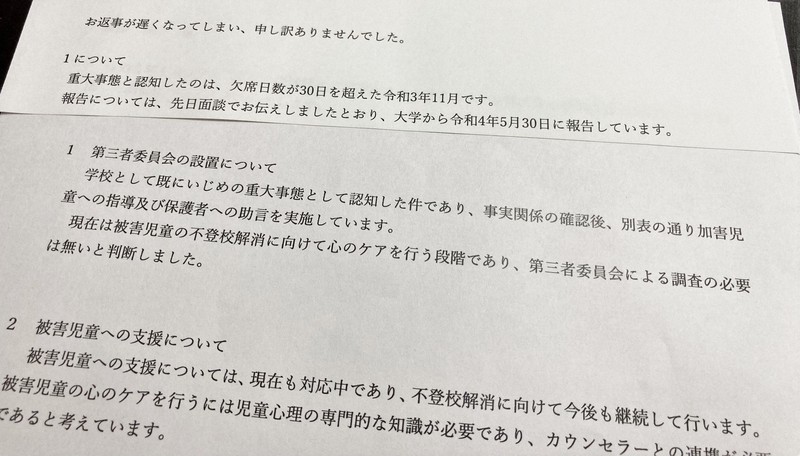
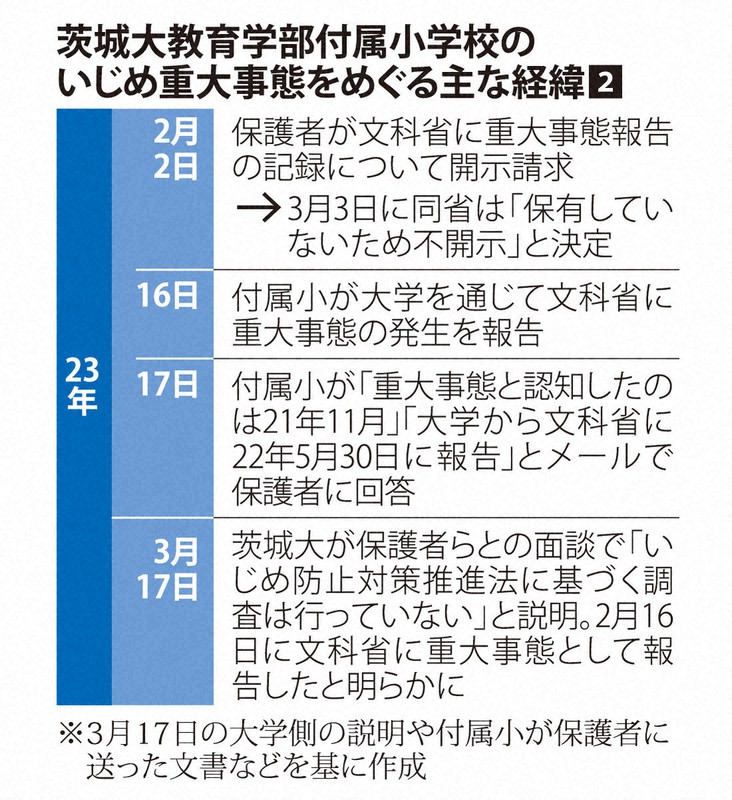
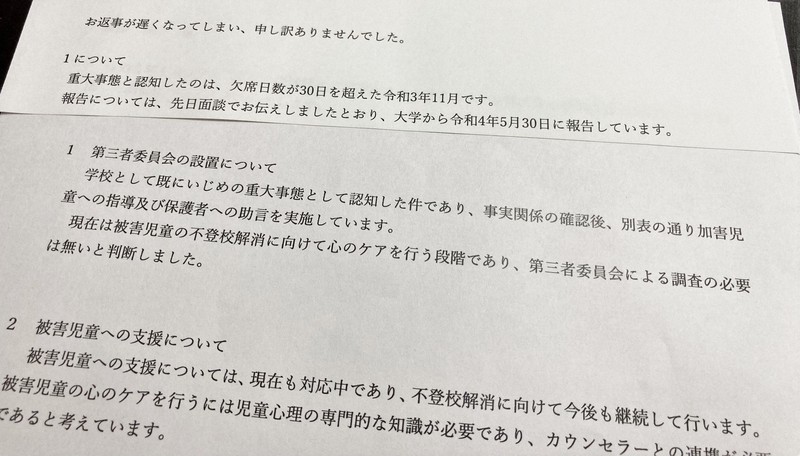


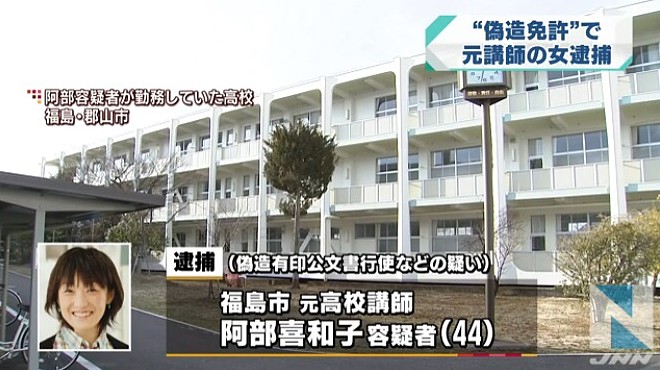

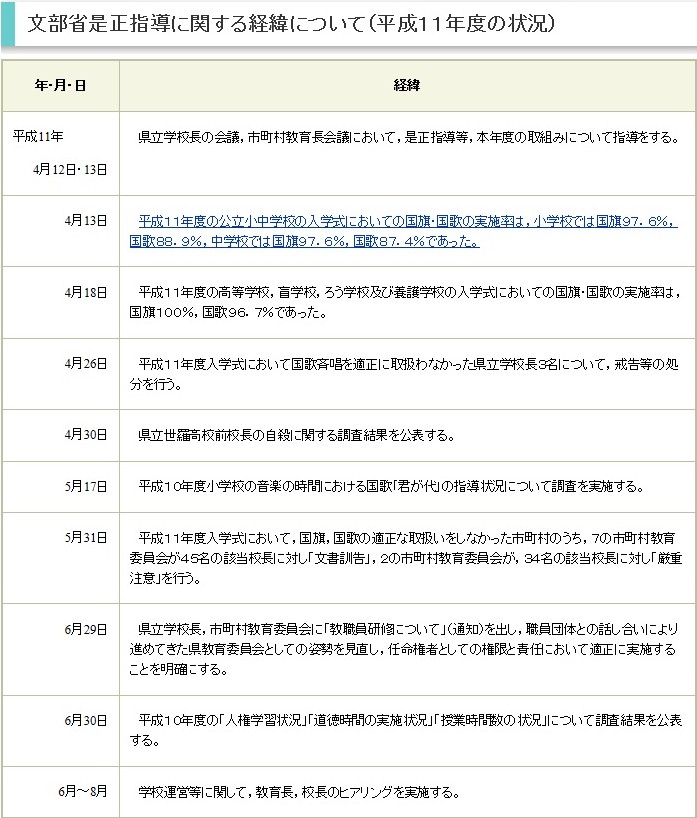
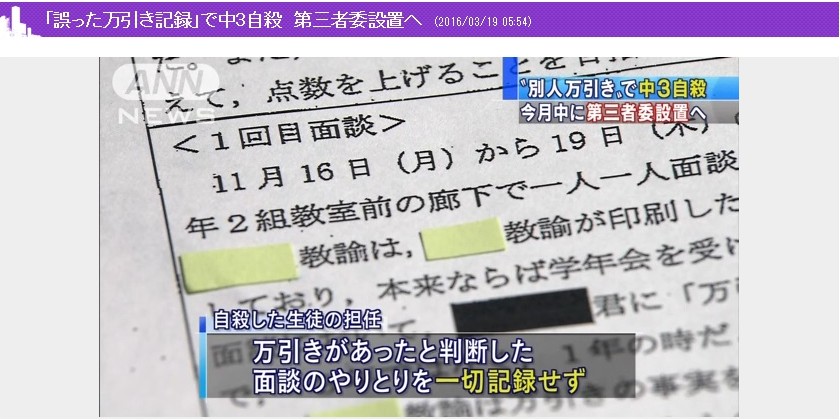



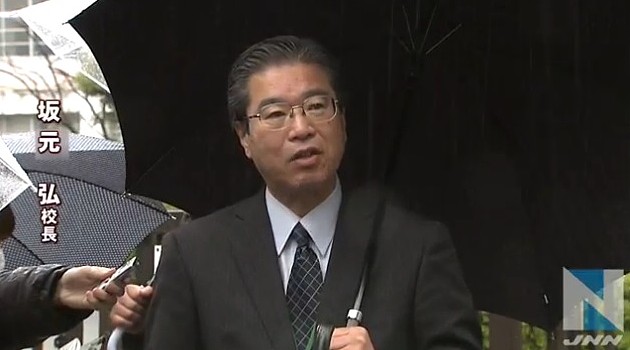 間違った進路指導後に中3生徒自殺、校長が全校集会で謝罪 03/09/16(TBS系(JNN))
間違った進路指導後に中3生徒自殺、校長が全校集会で謝罪 03/09/16(TBS系(JNN))
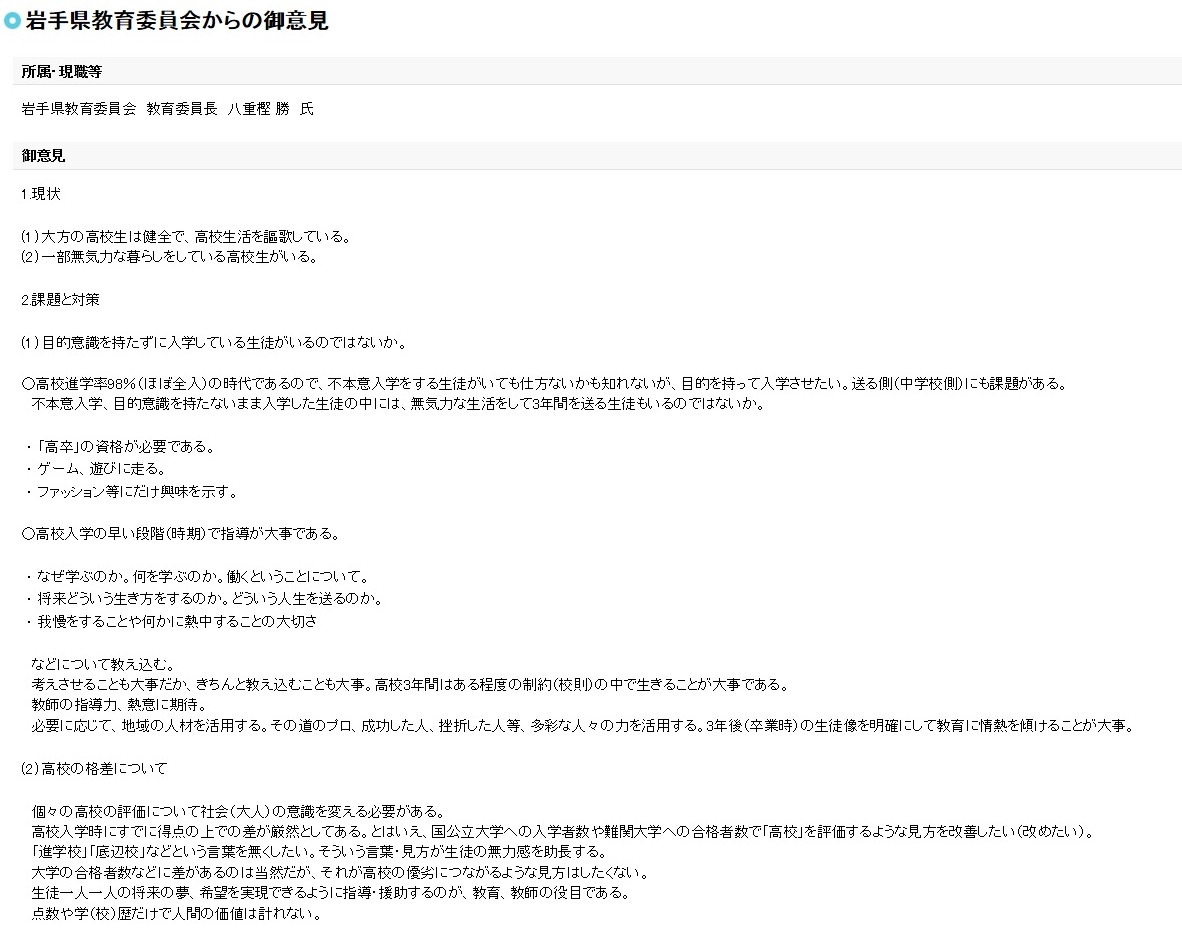
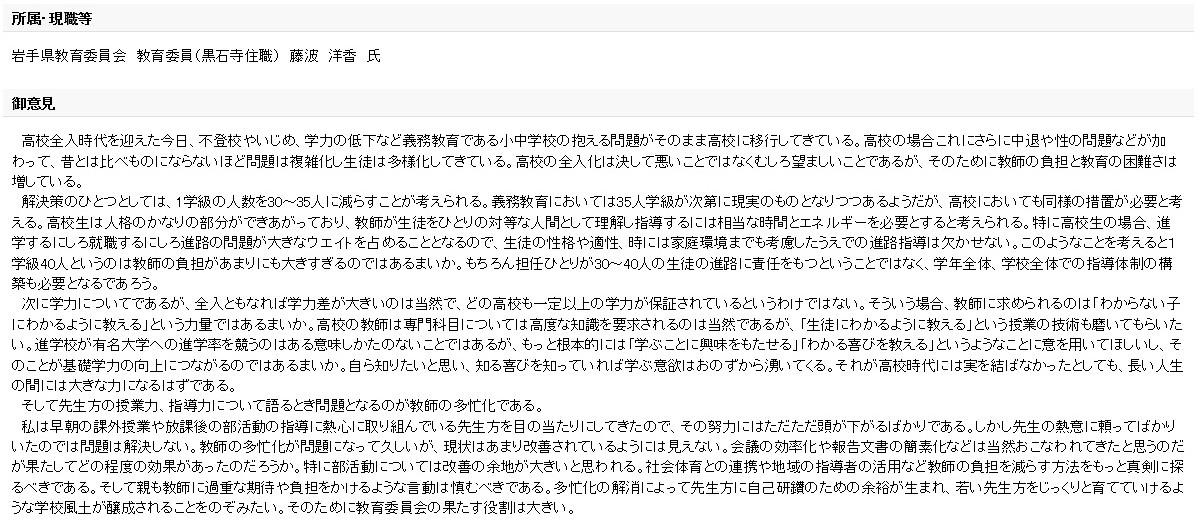
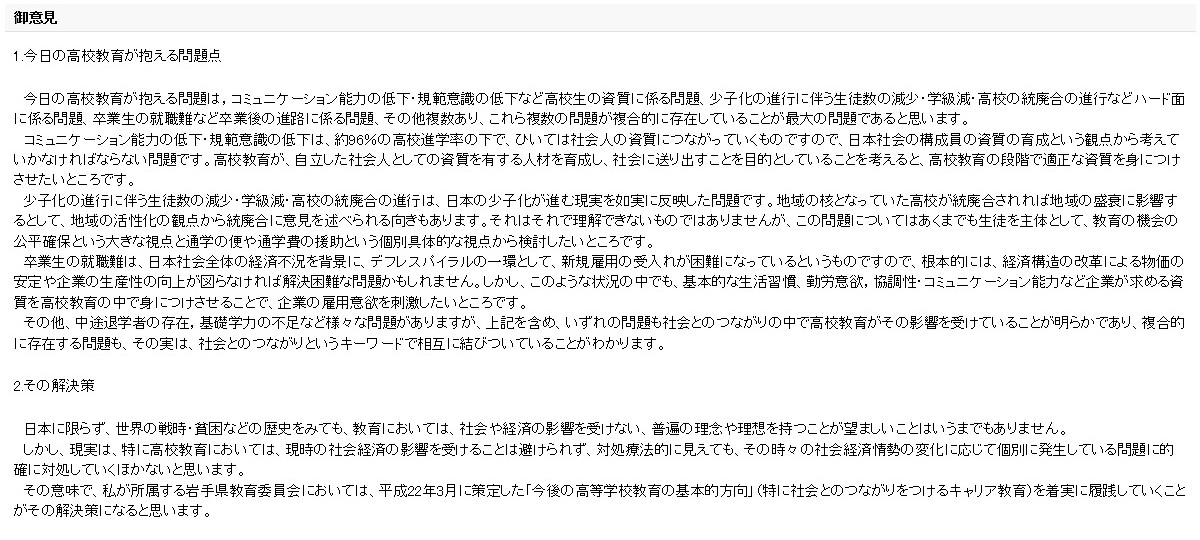
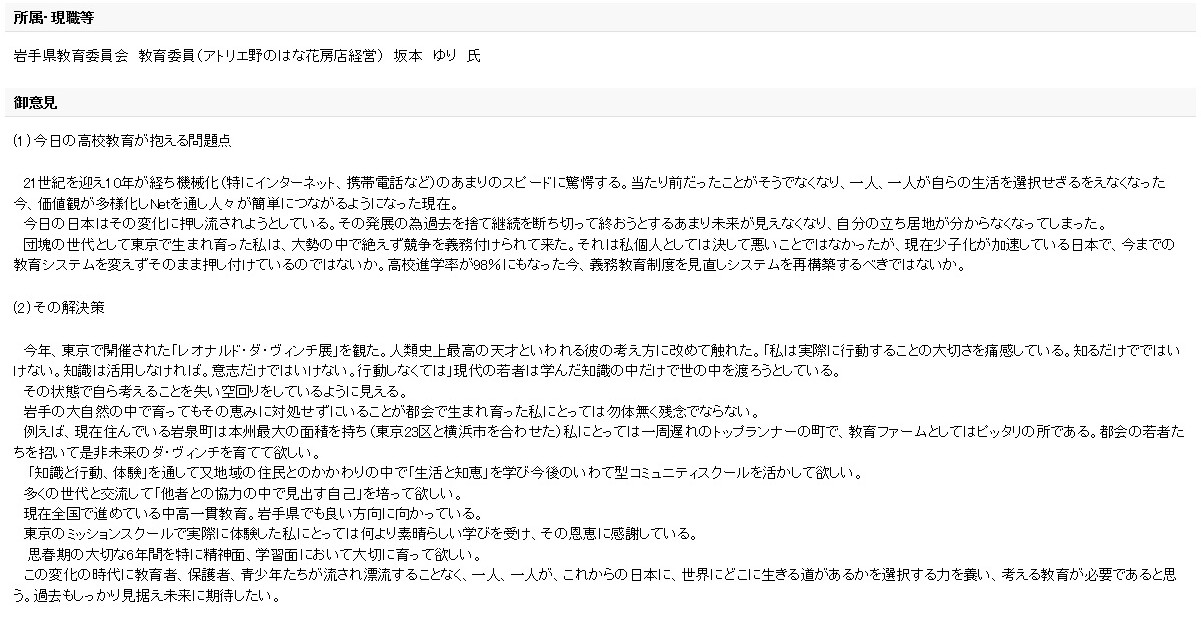
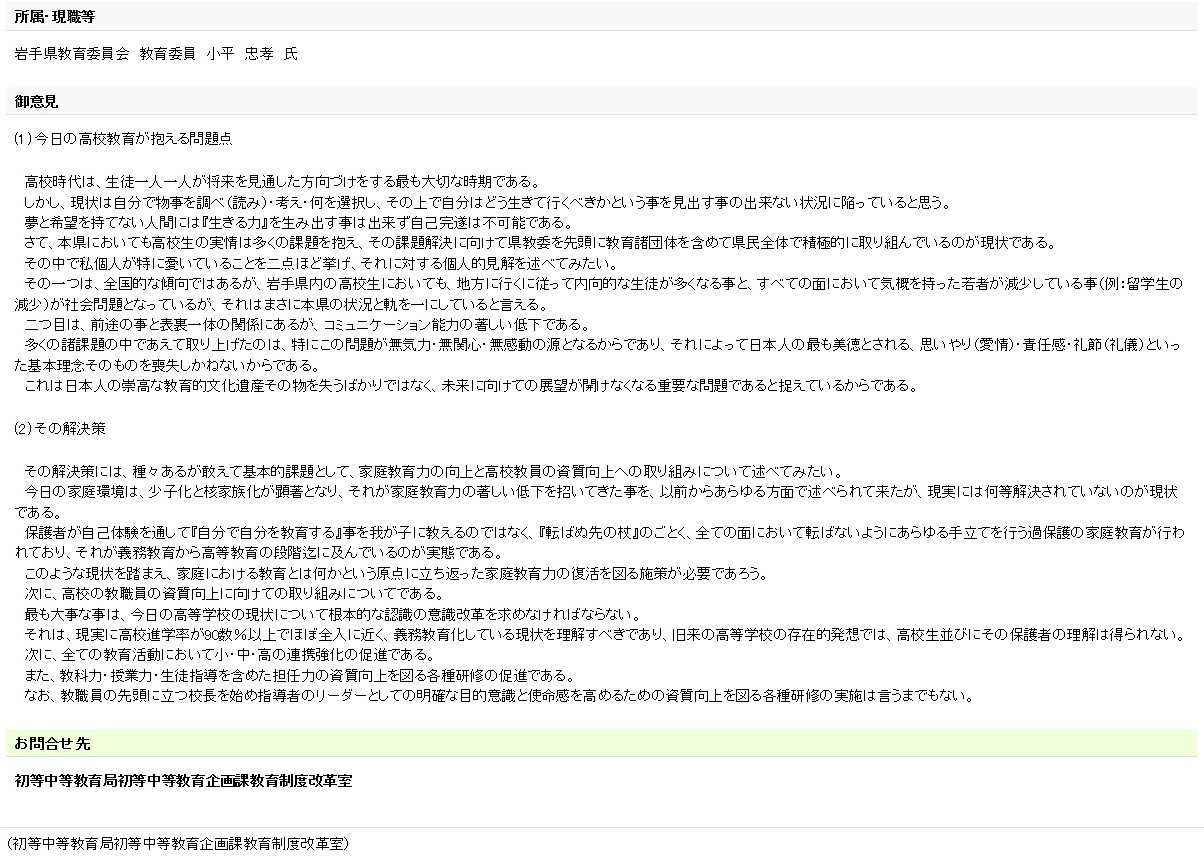


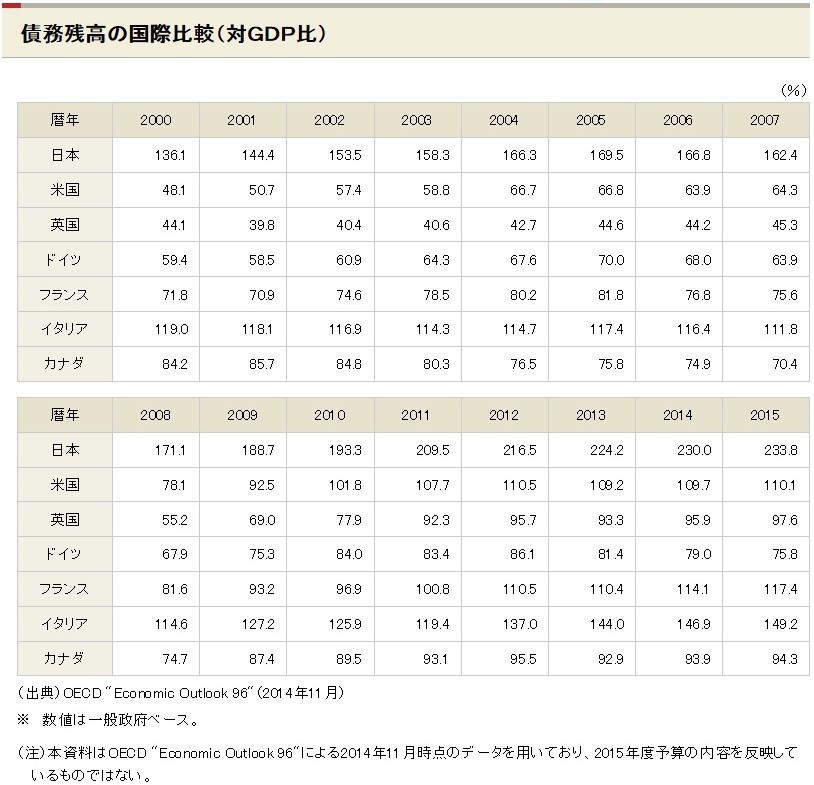

 国立競技場将来構想有識者会議に参加した人々、日本スポーツ振興センター(JSC)及び文部科学省の関係者は理解できないことがあれば建築家の安藤忠雄氏
に質問しなかったのか?また、1300億円は計画の予算だったのか、それとも決まったデザインの見積もりだったのか?この点を明確にするだけで
部分的な責任は誰にあるのか判るのではないのか?
国立競技場将来構想有識者会議に参加した人々、日本スポーツ振興センター(JSC)及び文部科学省の関係者は理解できないことがあれば建築家の安藤忠雄氏
に質問しなかったのか?また、1300億円は計画の予算だったのか、それとも決まったデザインの見積もりだったのか?この点を明確にするだけで
部分的な責任は誰にあるのか判るのではないのか?
 全校に調査を依頼しても正確な報告書が帰って来るとは思わないほうが良い。既に腐った学校が注目を浴びている。しかも、
全校に調査を依頼しても正確な報告書が帰って来るとは思わないほうが良い。既に腐った学校が注目を浴びている。しかも、

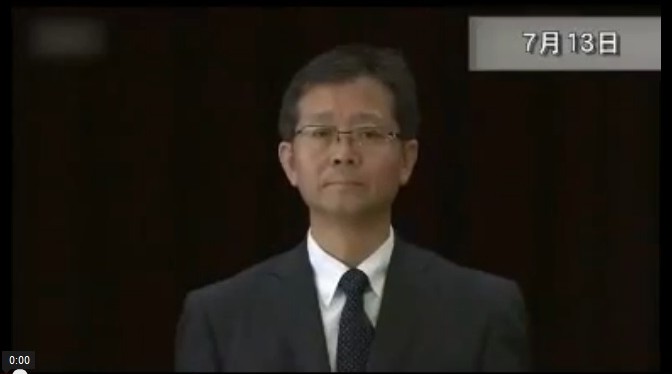
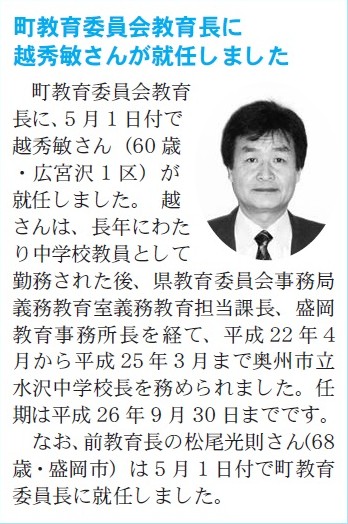 広報2013年7月(矢巾町役場)
広報2013年7月(矢巾町役場)