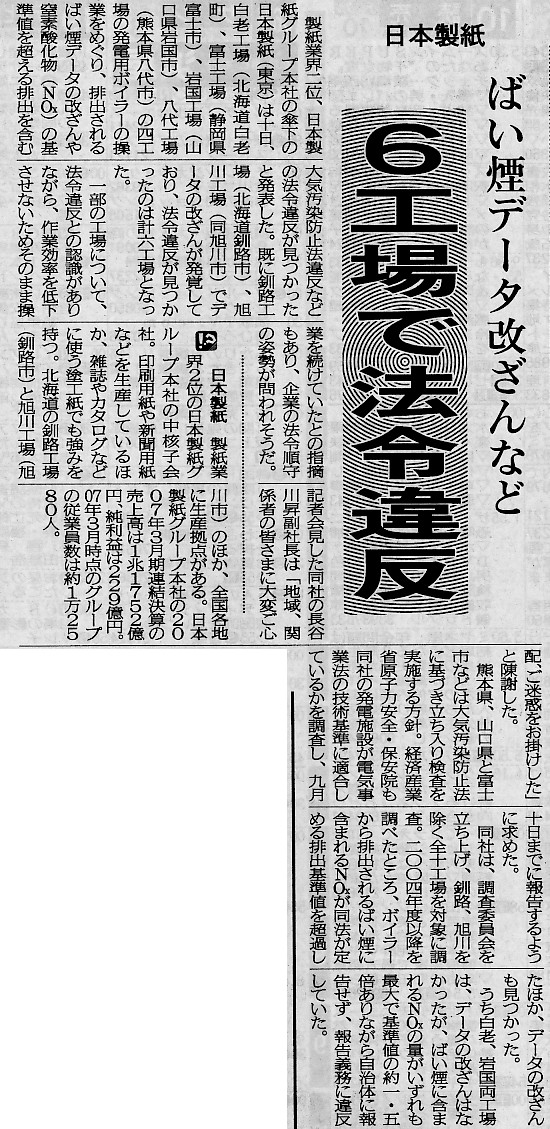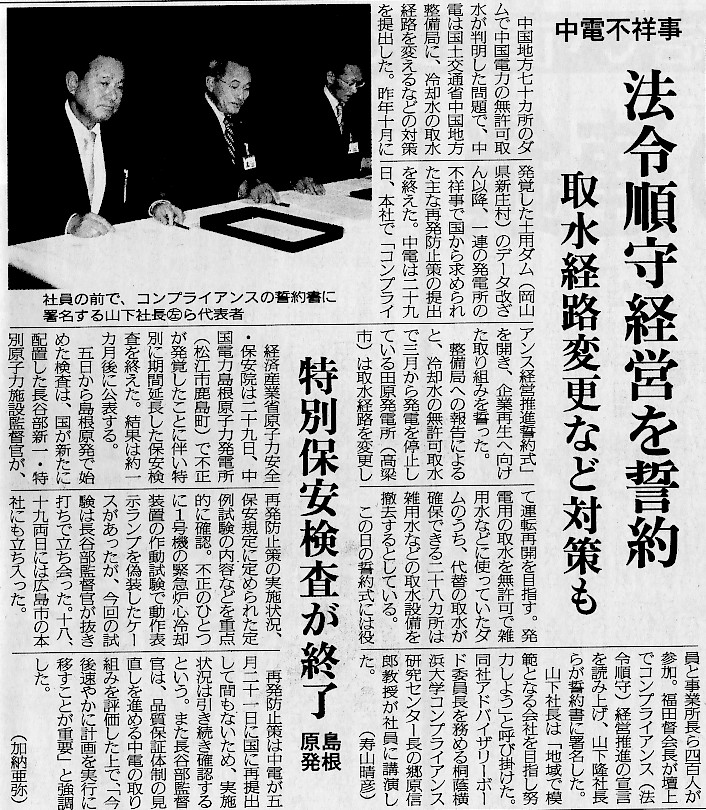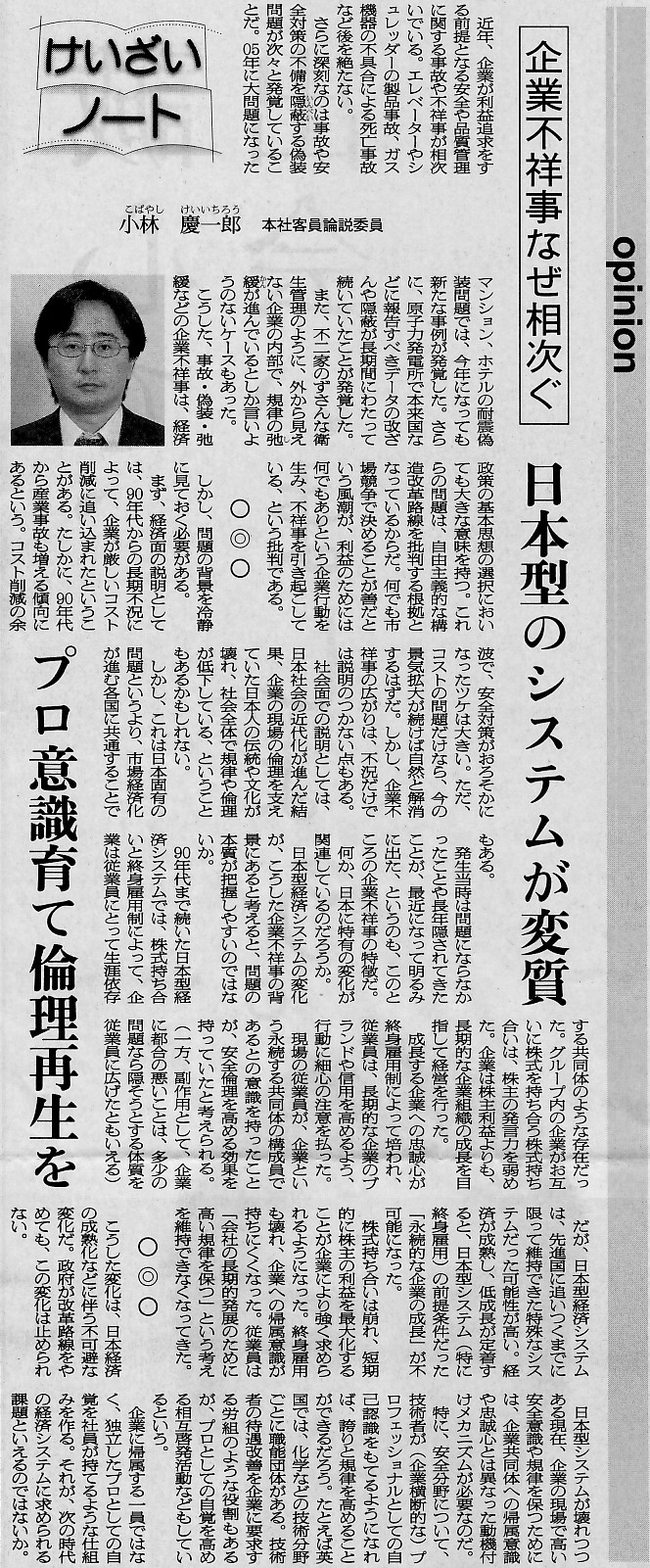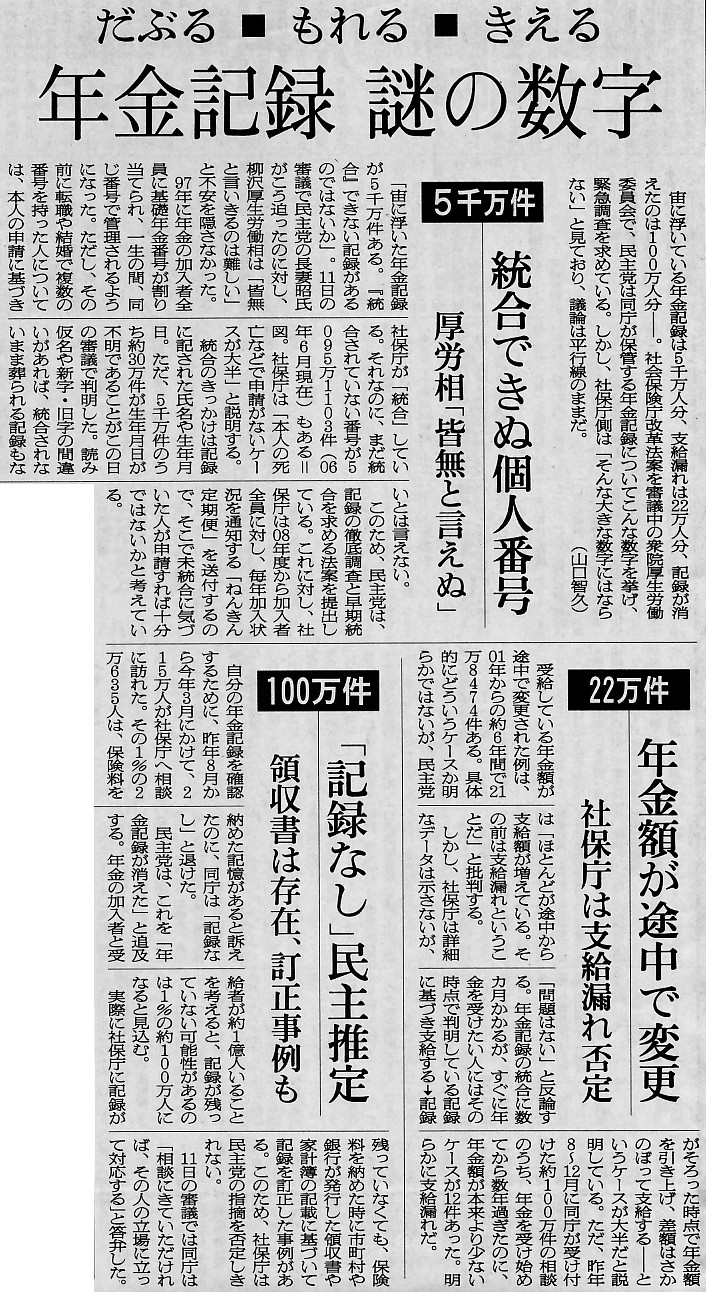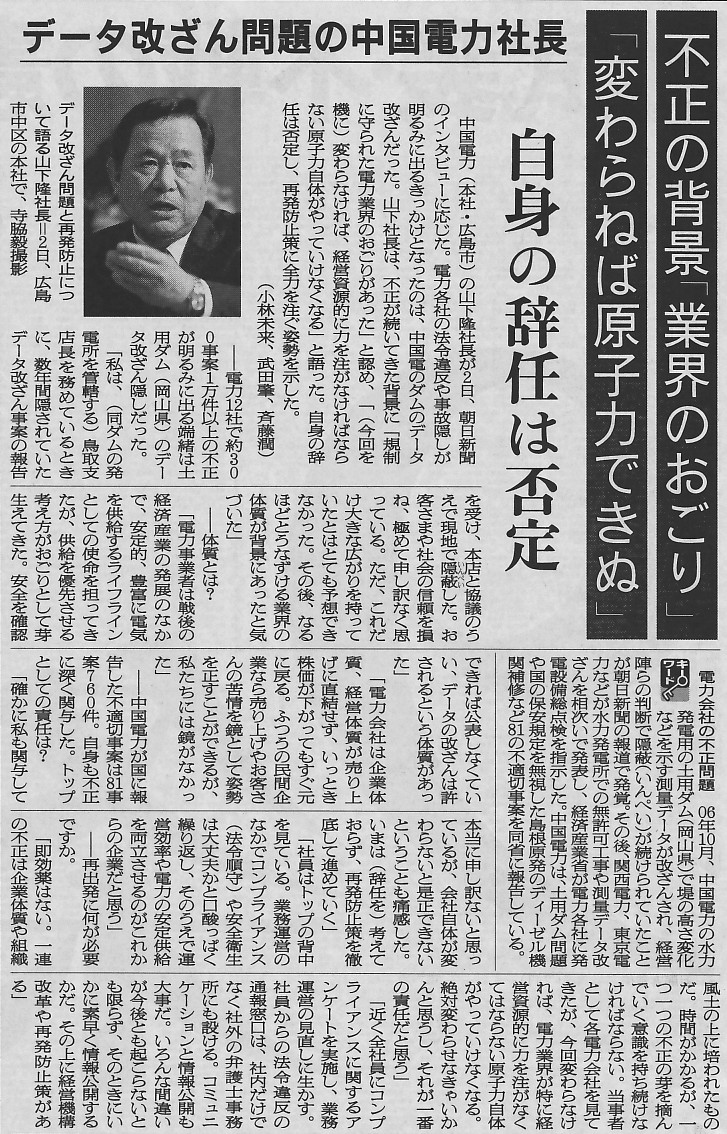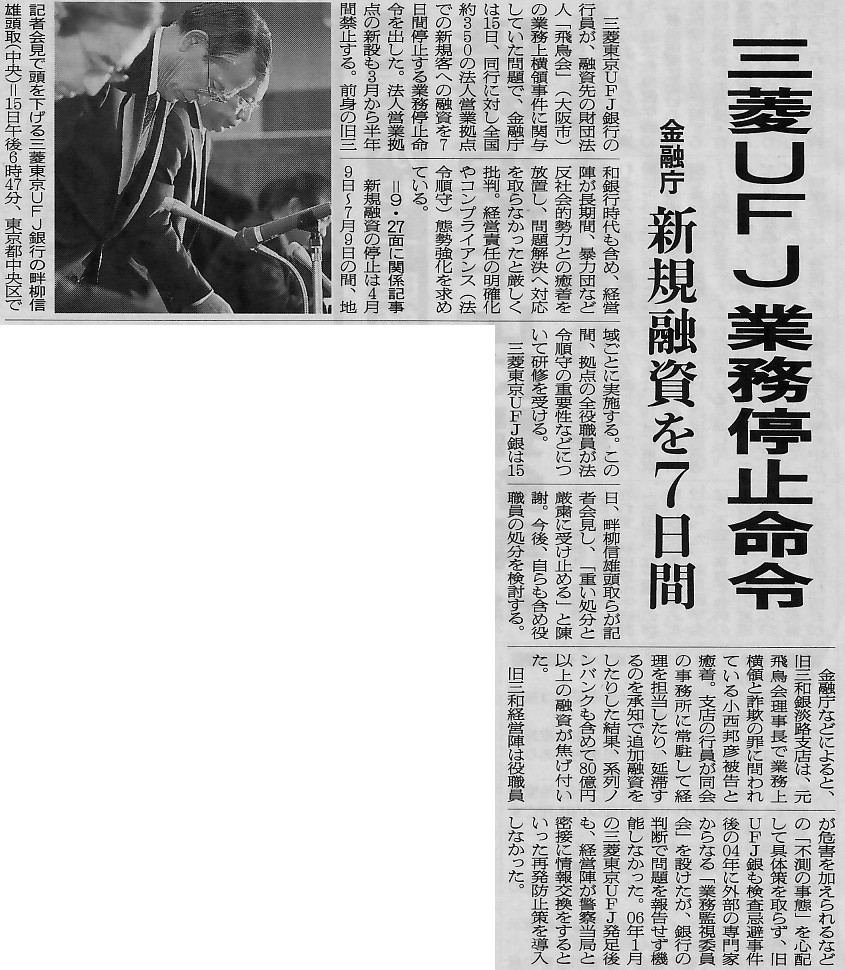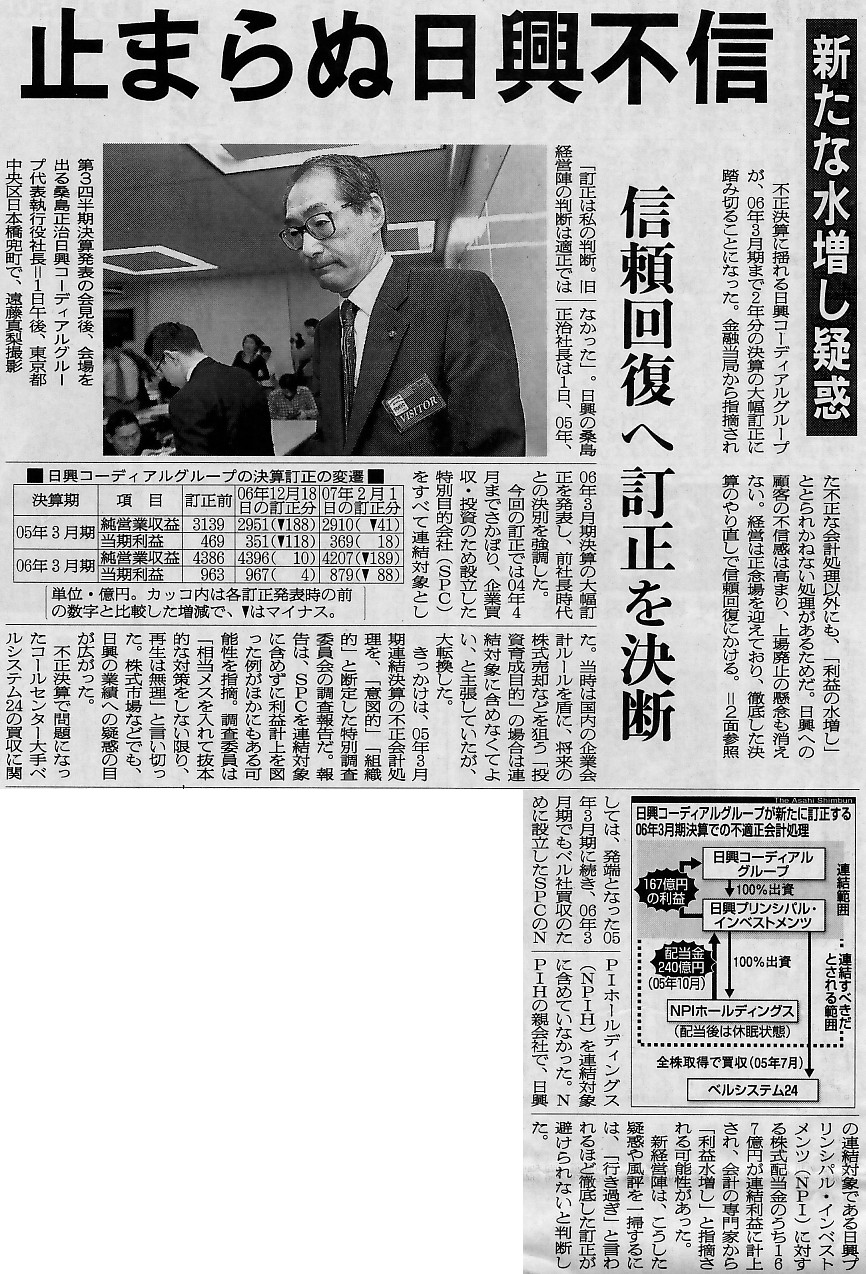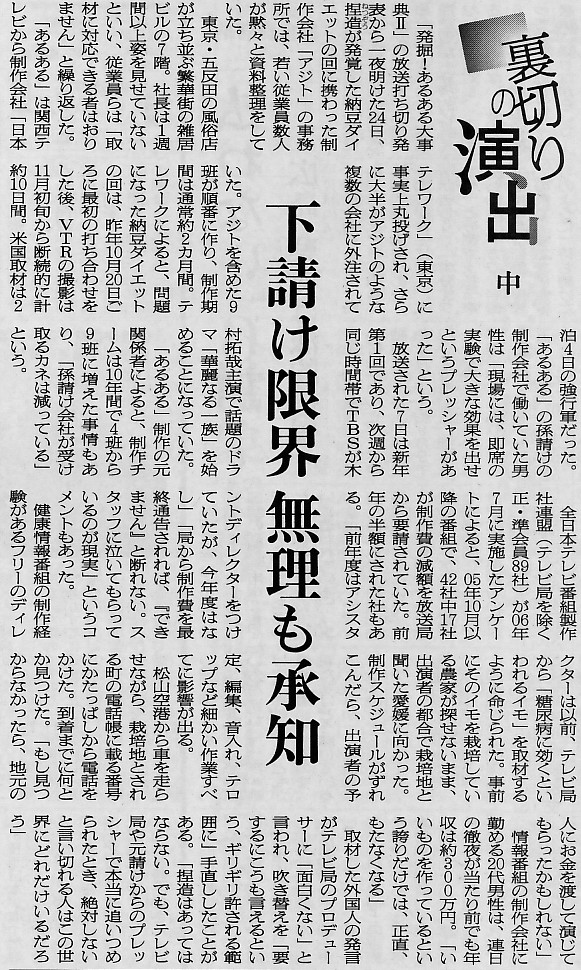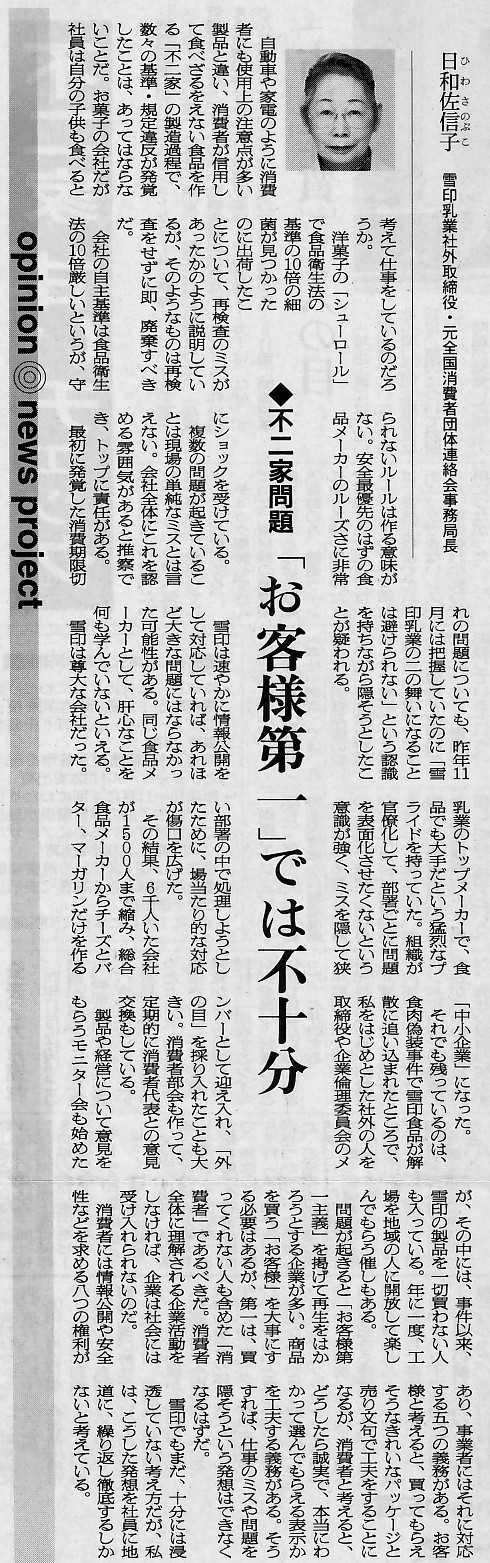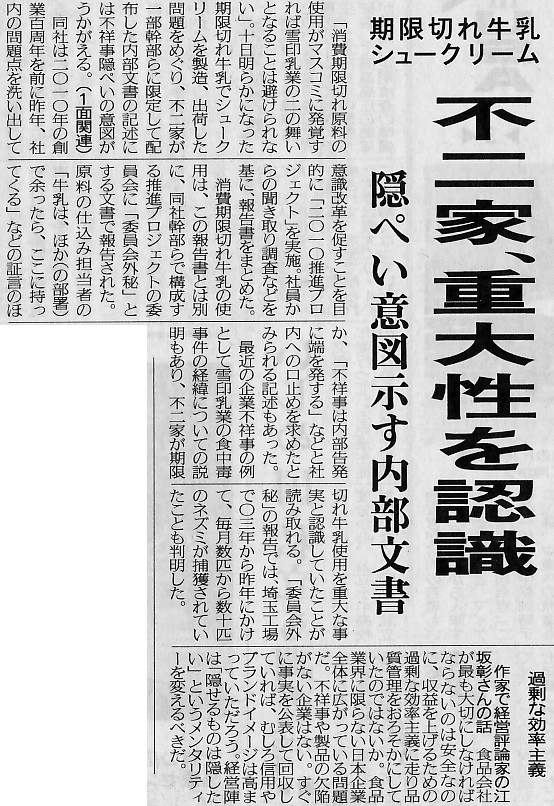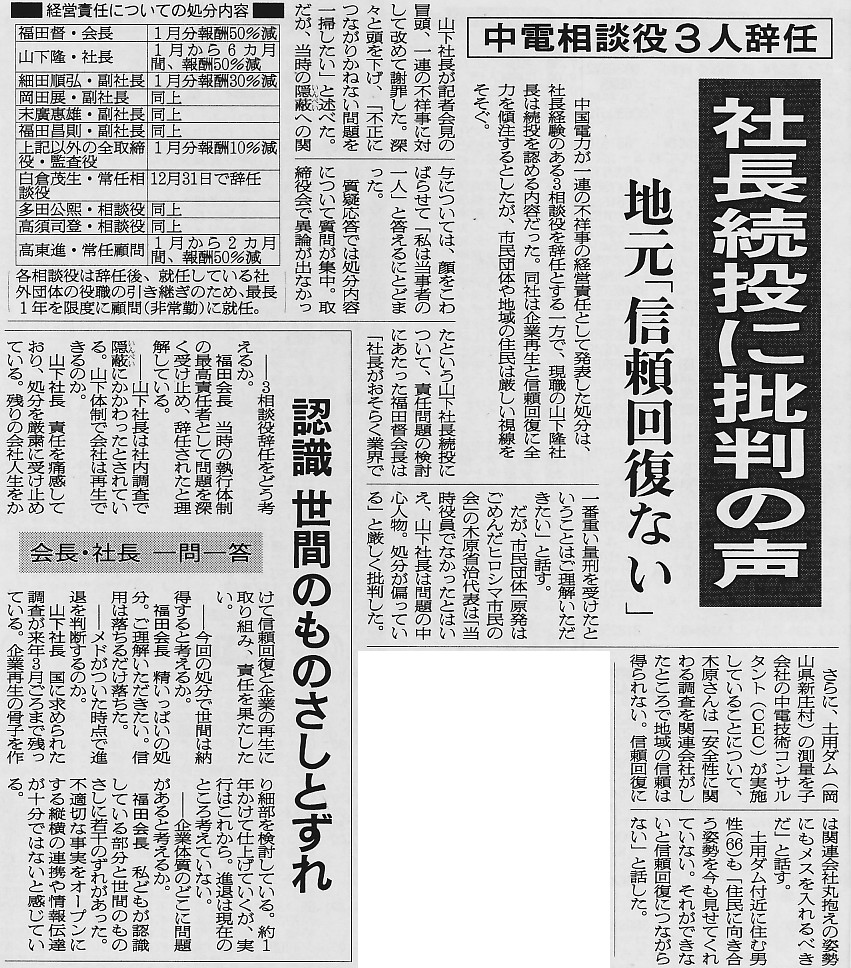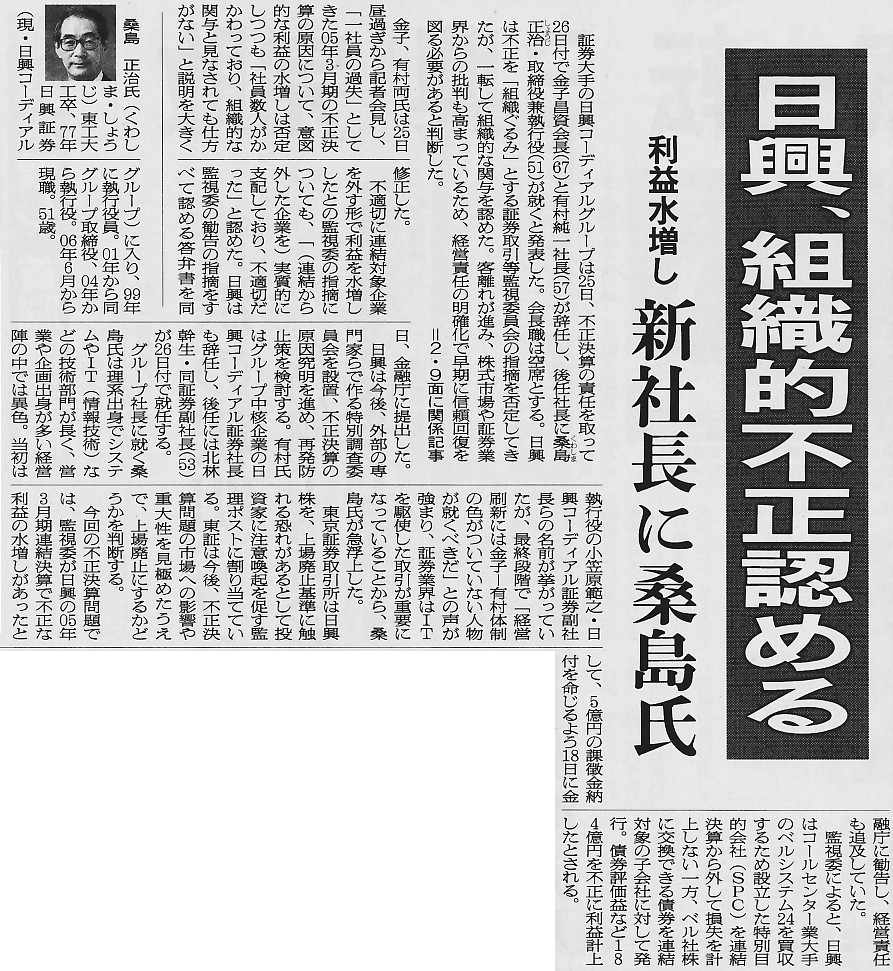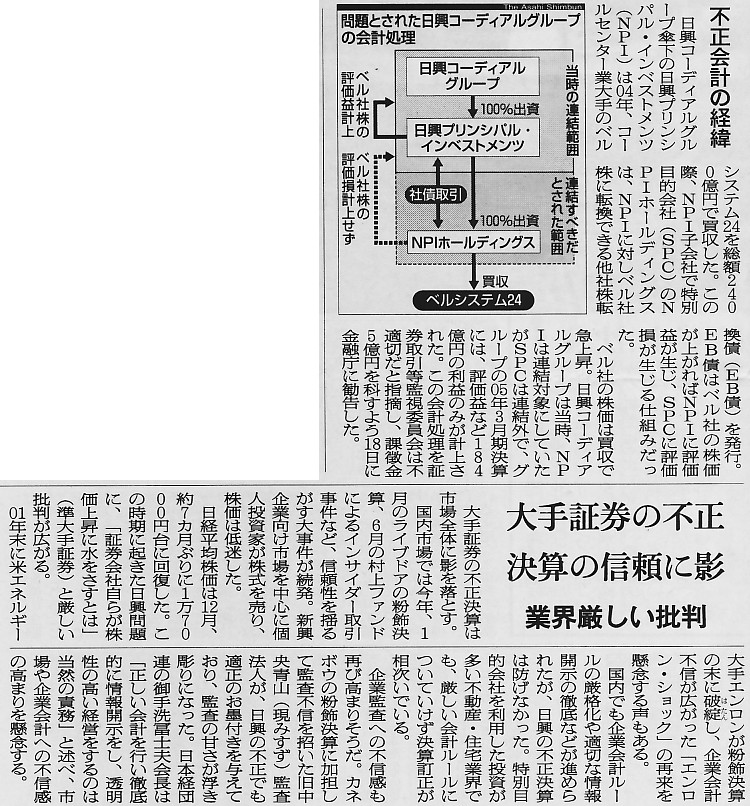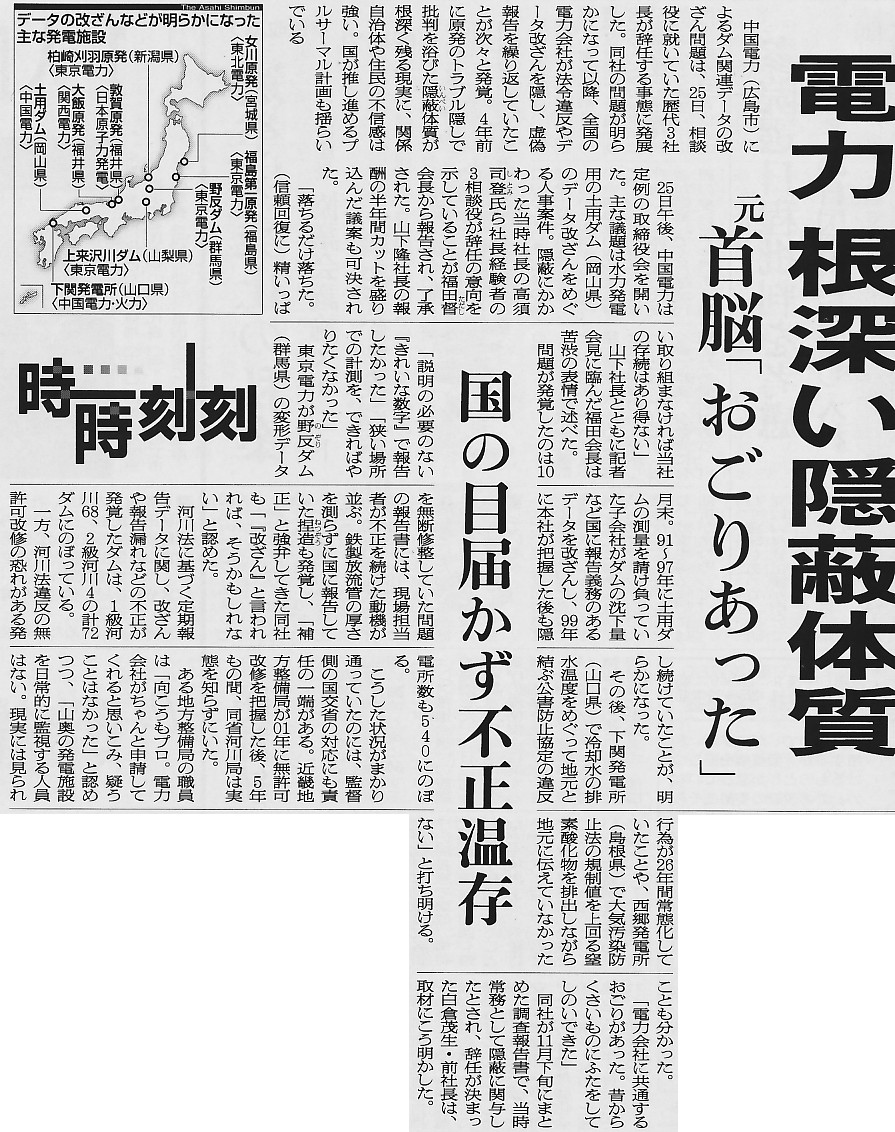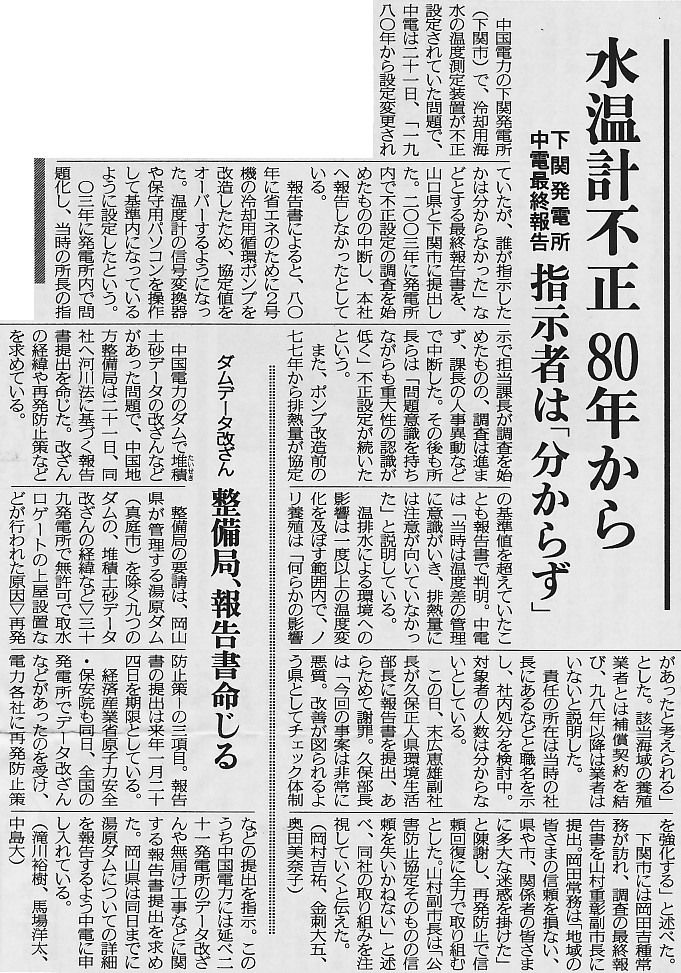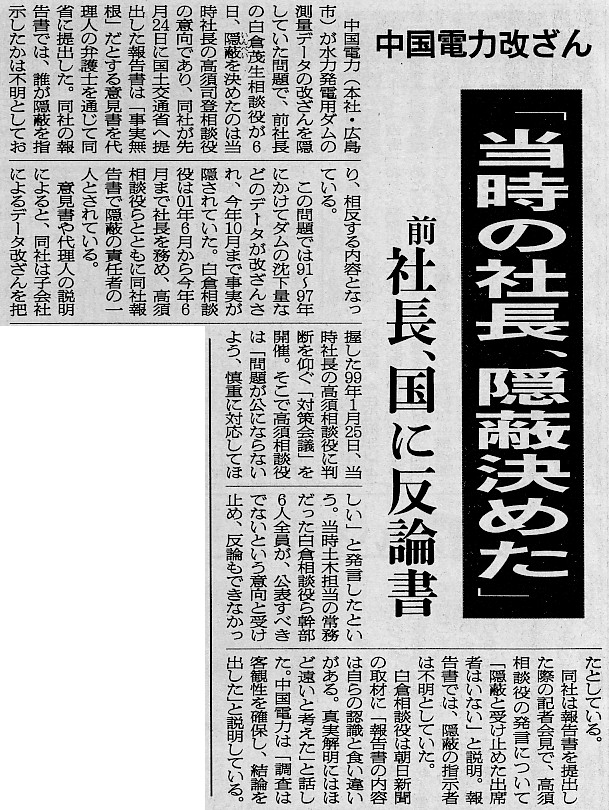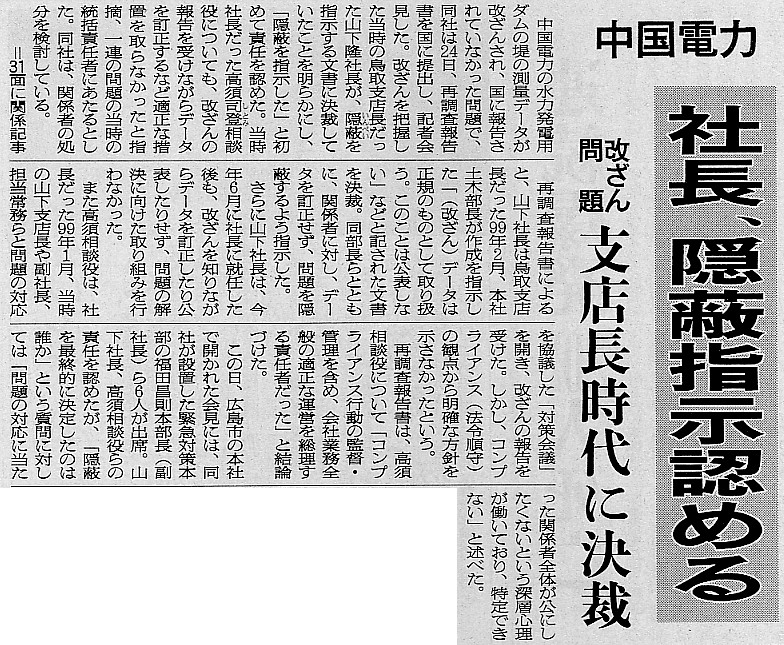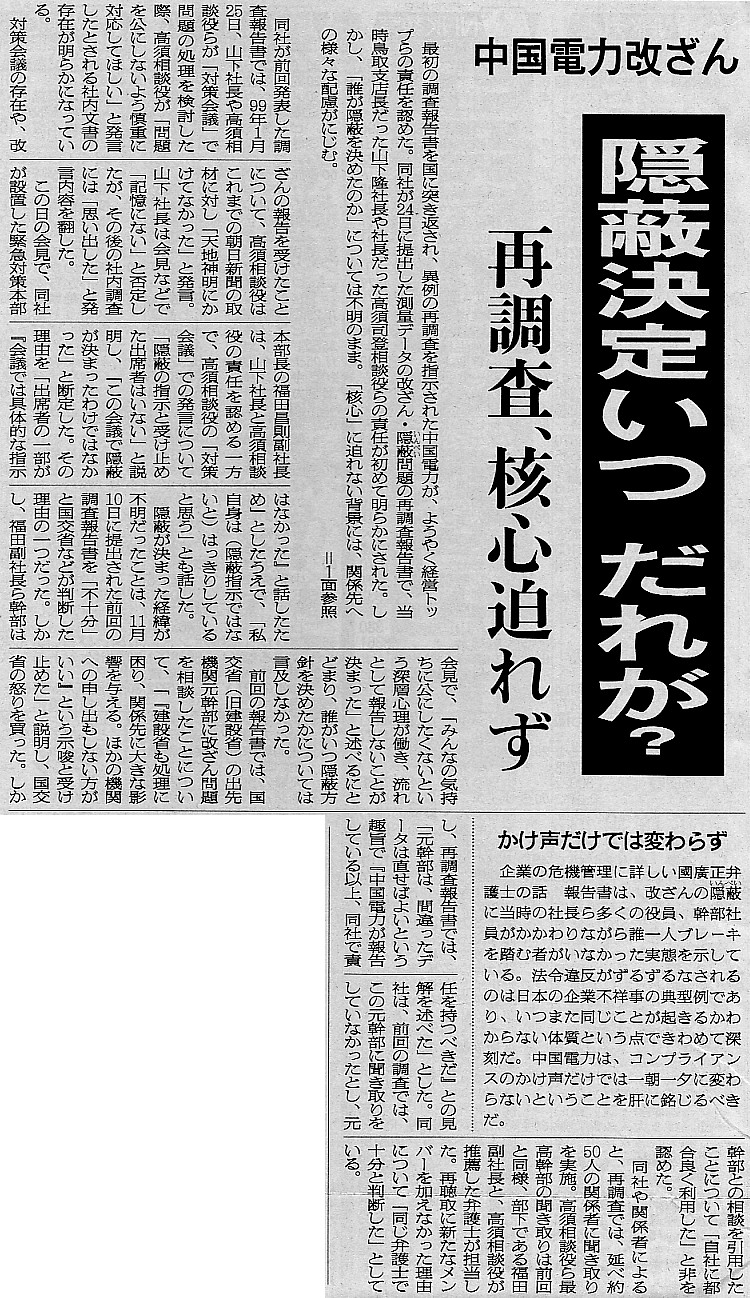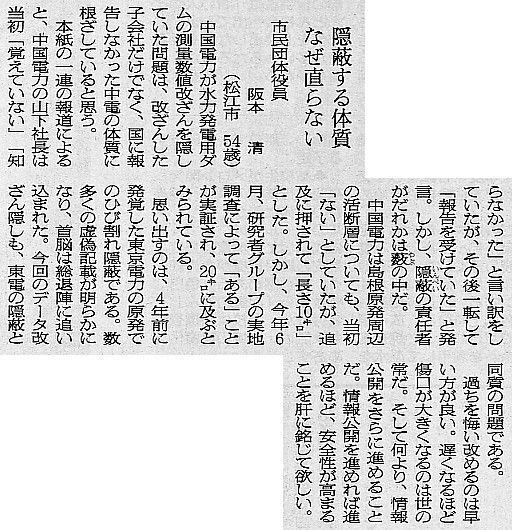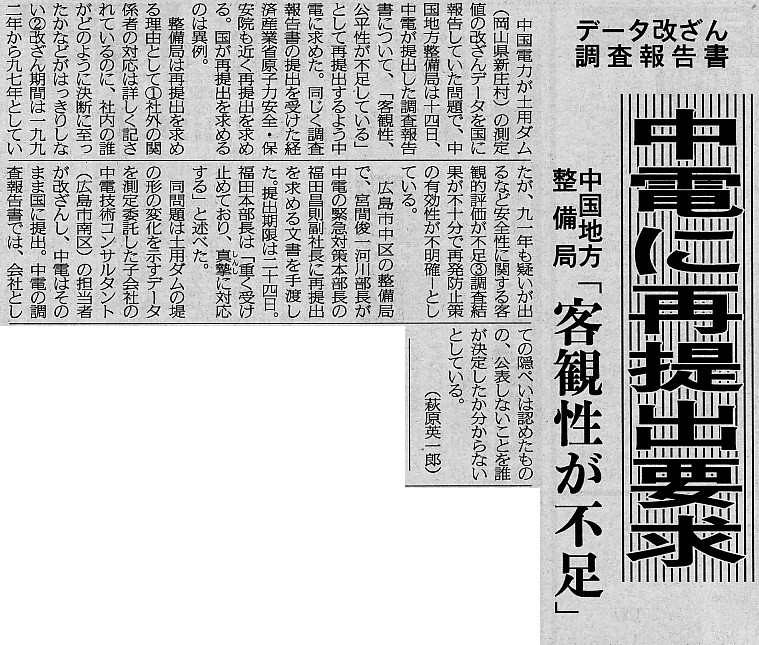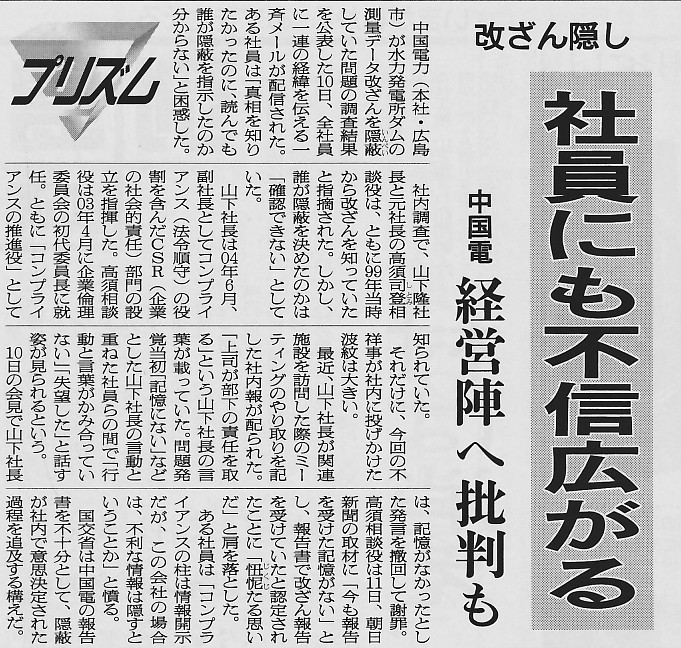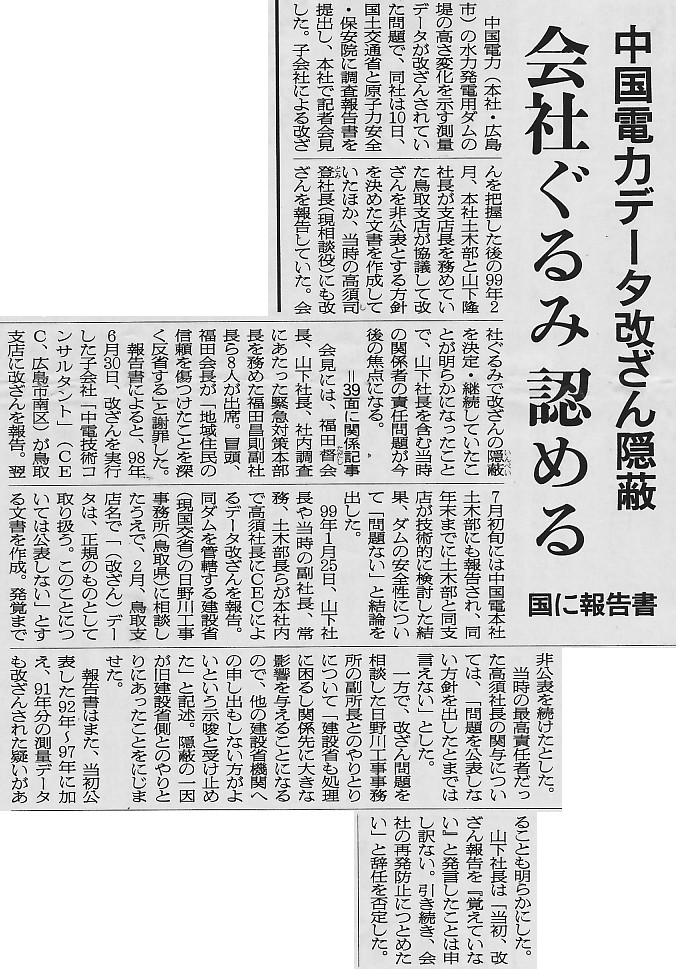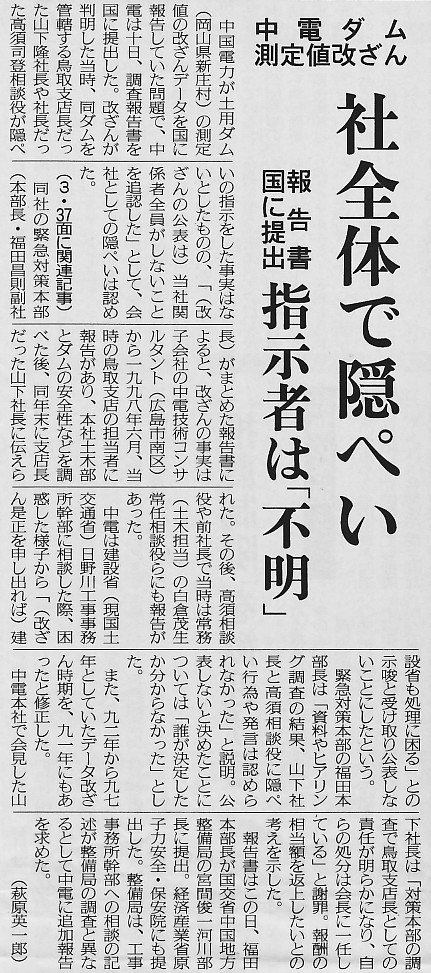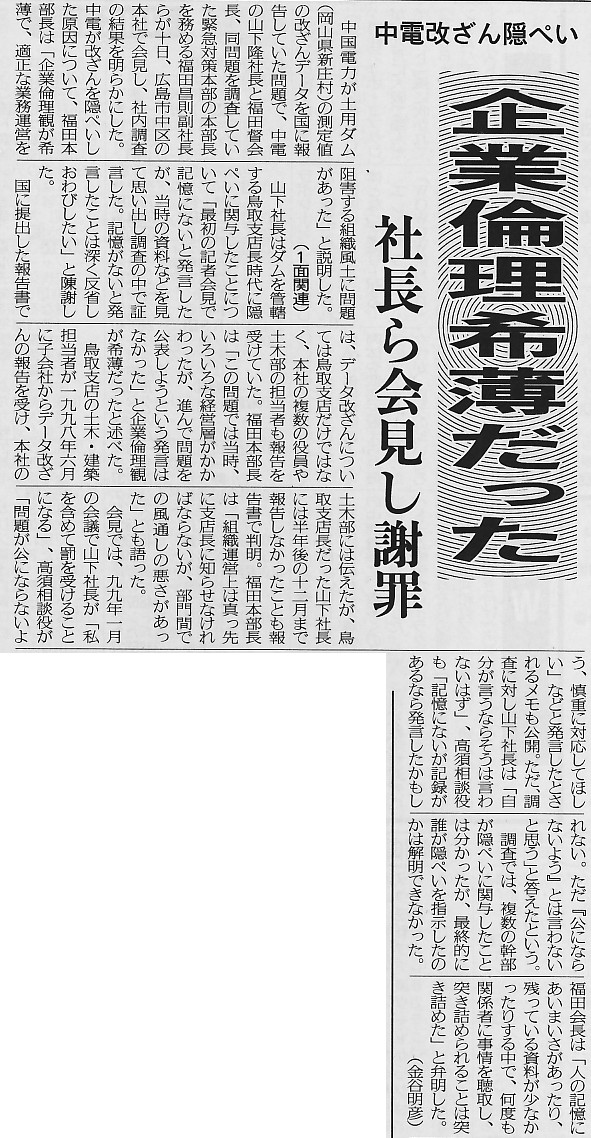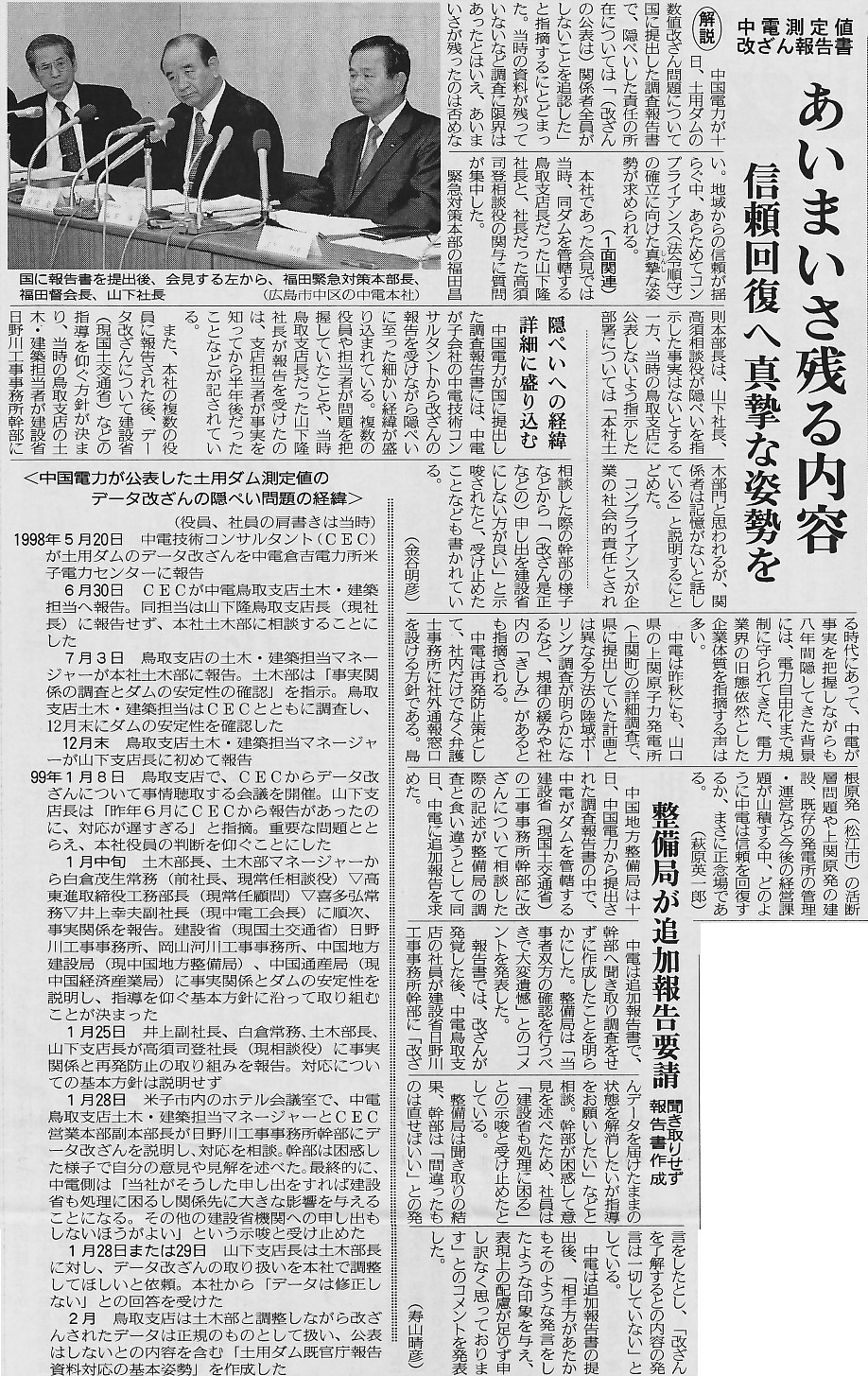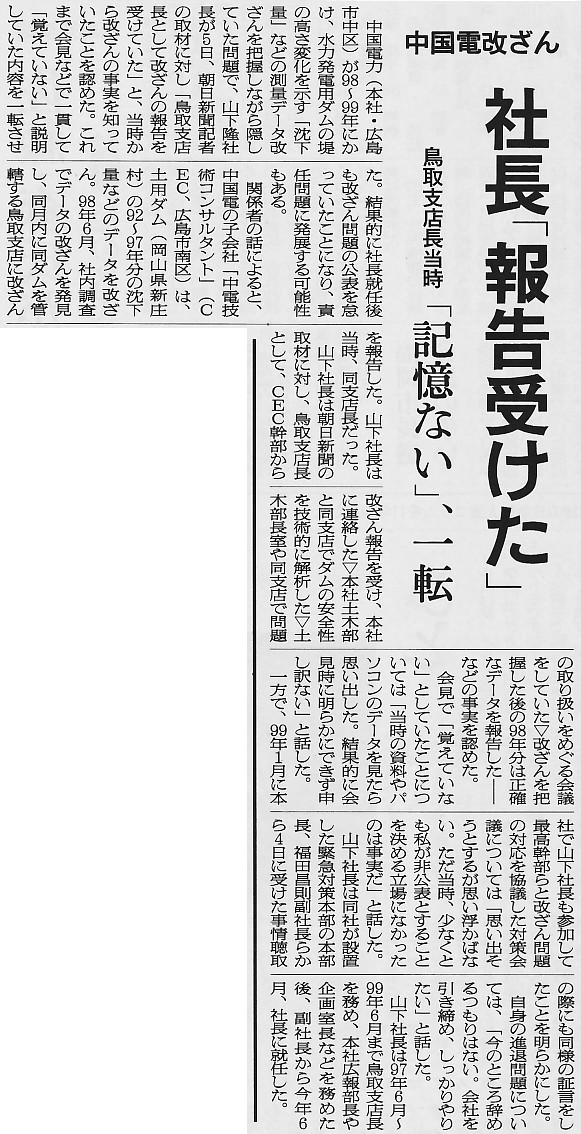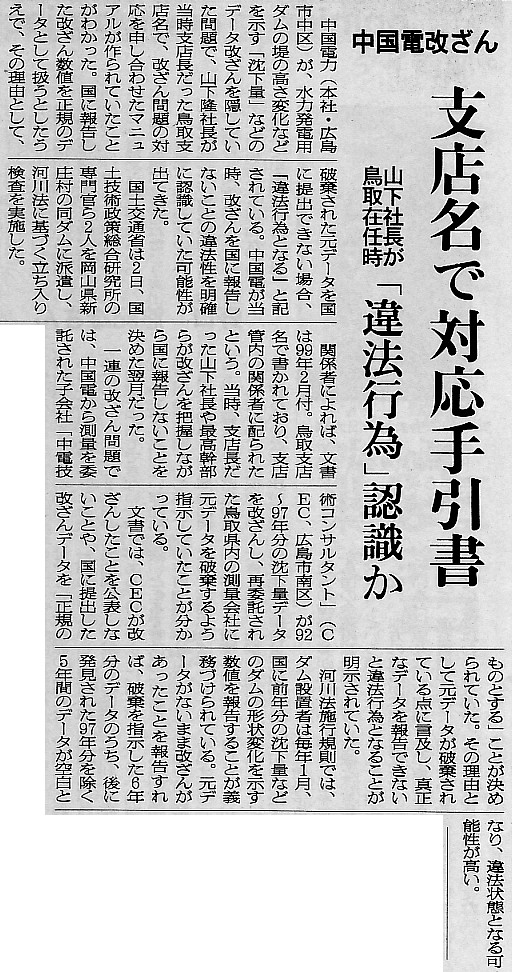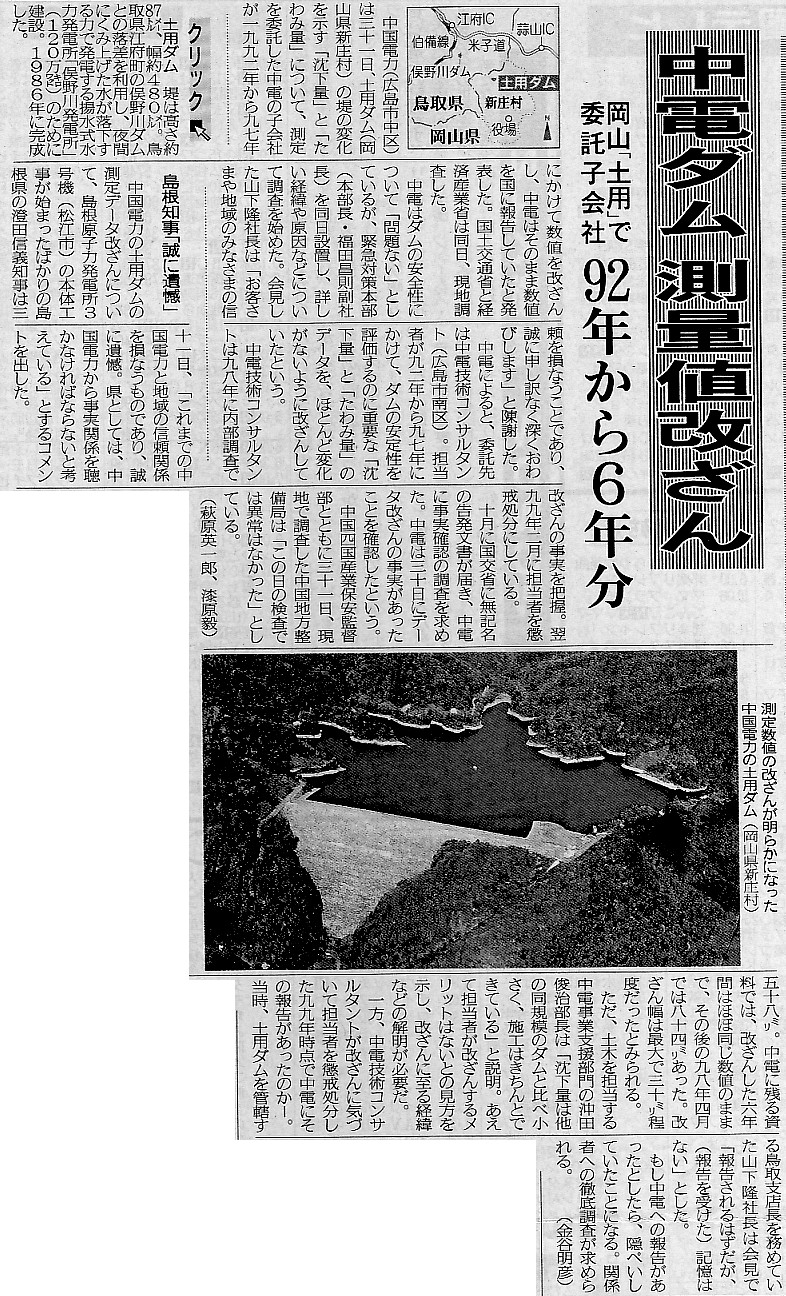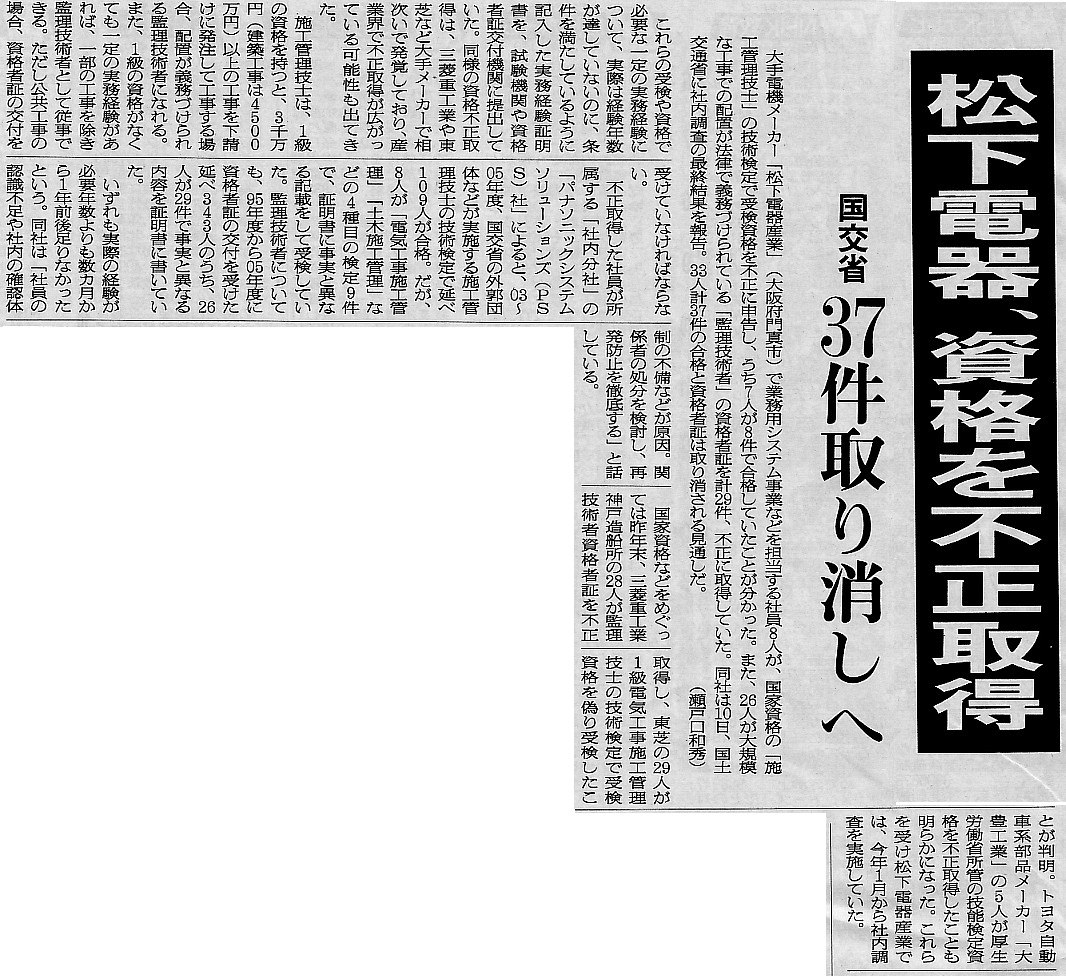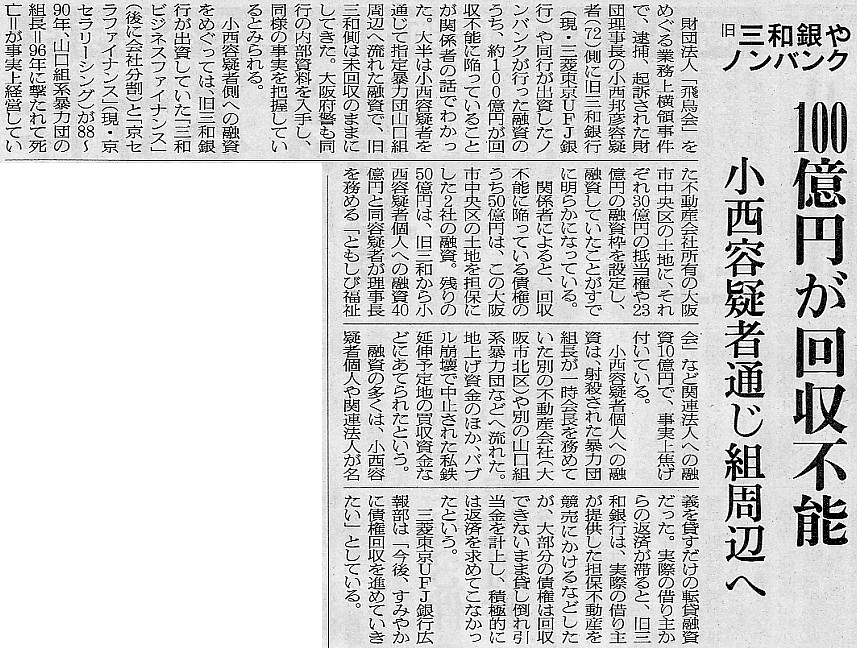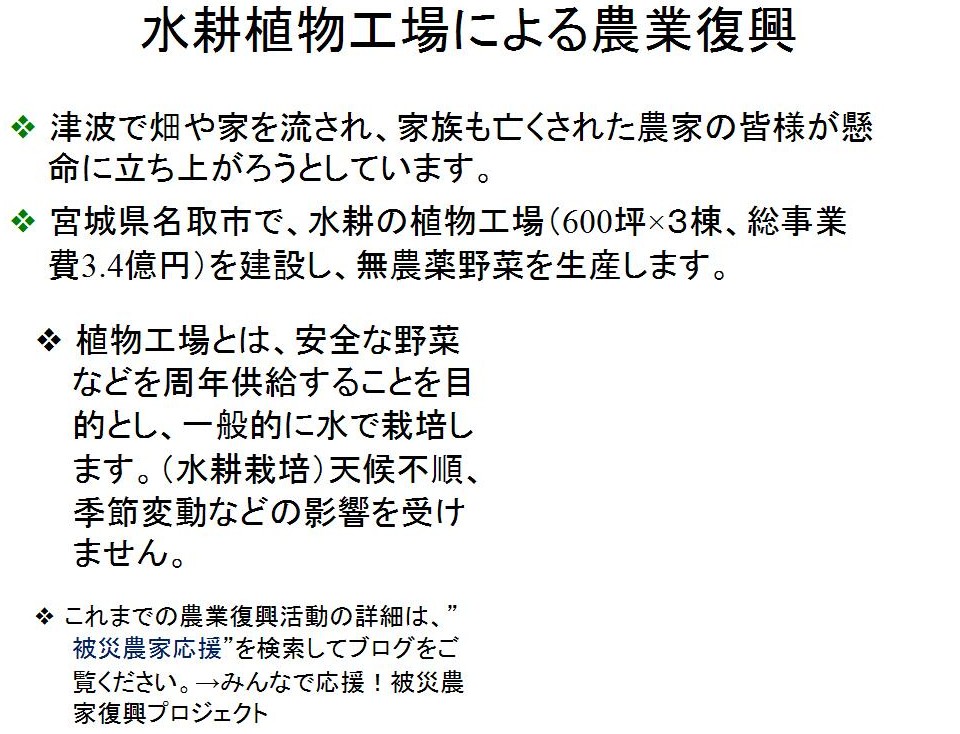
七十七ビジネス情報 2013年夏季号(No.62)(七十七ビジネス振興財団)
開けない人はここをクリック
津波被害水田に野菜工場、生産会社が自己破産へ 12/06/14(朝日新聞)
民間信用調査会社の帝国データバンク仙台支店は4日、野菜生産販売の「さんいちファーム」(宮城県名取市)が事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったと発表した。
負債額は約1億2000万円。
同社は震災後の2011年11月に設立。国や県の補助金などを受けて、津波被害に遭った水田に水耕栽培の野菜工場を建設し、レタスやチンゲンサイなどを生産して販売していた。しかし、生産が安定せず、販売も計画通りに進まなかったため、業績が低迷。債務超過に陥り、資金繰りに行き詰まった。
約105億円の運用益で4億3千万円の課徴金納付命令なら金融商品取引法違反(相場操縦)でも儲けた方がお得だ!
金融関連については全く知らないが外国の投資会社による金融商品取引法違反(相場操縦)は氷山の一角かもしれない。
取引終了前30秒、556億円分注文 株価操縦の疑い 12/06/14(朝日新聞)
伊木緑、長谷文 多田敏男、石山英明
日経平均株価を構成する企業の入れ替えのタイミングを見計らって、株価が不正に操作されていたとされる問題で、証券取引等監視委員会は5日、金融商品取引法違反(相場操縦)の疑いで、香港の資産運用会社「アレイオン・アセットマネジメント」に4億3千万円の課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告し、発表した。アレイオンは一連の取引で、約105億円の運用益を得たとされる。
アレイオンが不正に操作したとされるのは、東証1部上場の日東電工の株価。
監視委が指摘した不正の構図はこうだ。アレイオンは、日東電工が日経平均の構成企業に入ると発表された昨年9月6日以降、日東電工株を徐々に買い付けた。一方で、国内の大手証券会社との間で、実際に構成企業に入る同26日の前日(25日)の終値(引値)で日東電工株を買い取ってもらう「引値保証取引」の契約を締結した。
アレイオンは25日の市場で取引が終了する直前の30秒の間に、新たに約556億円分の日東電工株を購入。株価をつり上げ、その後、引値保証取引を結んだ証券会社に高値で売って多額の利益を得た。監視委は、取引終了間際に大量の株購入を集中させたことが株価操作目的だったと認定した。この30秒間に日東電工株は6690円から7540円に12・7%上昇。ストップ高になっている。翌26日、日東電工株の終値は前日比で約11%下落した。
13年前にこんな準備が可能だったんだ。金銭的に恵まれていた事には間違いないが、すごいと思う。本人や夫の考え方次第だが、やはり養子よりもお互いの遺伝子を受け継ぐ子供の方が可愛いであろう。しかし高校時代のがんは後天性だったのか、先天性だったのか?先天性だったら子供にも遺伝する可能性もある。まあ、子供にがんになっても本人と同じ事が可能なのであるから問題ないと言えば、問題ない。医療の進歩は素晴らしい。
がん発症し高2で卵子を凍結保存、13年後出産 12/06/14(読売新聞)
愛知県の女性(30)が、高校時代にがん治療で生殖機能を失う前に卵子を凍結保存し、12年後、受精卵にして子宮に戻し、今年8月に出産していたことが分かった。
卵子を10年以上凍結保存して出産に至ったケースは珍しいという。
女性の卵子凍結に関わった桑山正成リプロサポートメディカルリサーチセンター(東京都新宿区)所長によると、女性は高校1年時に血液がんの悪性リンパ腫を発症。抗がん剤治療で不妊になる恐れがあった。そのため高校2年になった2001年に不妊治療施設「加藤レディスクリニック」(同区)で卵子を2個採取し、凍結保存した。悪性リンパ腫は抗がん剤治療などで克服した。
女性は昨年結婚し、解凍した卵子2個と夫の精子で体外受精を行った。子宮に戻した受精卵1個で妊娠することができ、今年8月、3295グラムの男児を出産した。
城西大理事長元秘書、1億円架空請求か 領収書偽造疑い 警視庁、書類送検へ (1/2)
(2/2) 12/06/14(産経新聞)
飲食代名目などで経費を架空請求するために領収書を偽造して勤務先の城西大学(埼玉県坂戸市)に提示していたとして、警視庁が有印私文書偽造・同行使容疑で、同大理事長の元秘書の男を近く書類送検する方針を固めたことが5日、捜査関係者への取材で分かった。元秘書は偽造領収書をもとに約1億円の経費を架空請求して受領し、私的に流用していたとみられる。
捜査関係者によると、元秘書は平成22年ごろまでに複数回にわたり仮払い名目で現金計約1億円を引き出し、同額分の物品の購入費や飲食代名目などで領収書を偽造して城西大に提示した疑いが持たれている。偽造領収書で、1回につき10万円程度を請求していた。
偽造領収書は22年ごろ、大学関係者による学内の経理状況の調査の過程で発覚。23年1月に大学関係者が、偽造領収書を城西大側に提示した有印私文書偽造・同行使罪などで容疑者不詳のまま警視庁に刑事告発していた。
警視庁練馬署が業務上横領などの疑いもあるとみて捜査を始めたところ、元秘書が同署に出頭。任意の事情聴取に「架空請求するため、自分が領収書を偽造して大学に提出していた」などと関与を認めたという。
元秘書は数千万円を城西大に弁済。城西大と示談が成立したことなどから、業務上横領などの容疑での立件は見送られる見通し。
犠牲者遺族らには申し訳ないけど、日本から多く学ぶ事はないと思う。JR北海道の改ざんや隠ぺいによる大事故は起こっていないが問題である事に間違いない。
日本よりも韓国の方が不正の隠蔽や腐敗の問題が大きいだけである。仮に日本のシステムを導入したとしても、監査する側が圧力を受けていたり、接待や賄賂を受けていれば本来の効果や機能は期待できるはずが無い。たぶん短時間では無理だろうが、長い目で韓国社会の悪しき部分を変えているように活動するしかないと思う。
韓国旅客船沈没 高校生の遺族「韓国より進んだ日本の安全対策学ぶ」 12/03/14(産経新聞)
韓国の旅客船セウォル号沈没事故で長男を失った夫婦が3日、日本で起きた大事故や災害の犠牲者遺族らの支援に関わる団体などと意見交換するため来日した。今後本格化する事故の真相究明の参考にしたいと話している。
修学旅行でセウォル号に乗り亡くなった高校2年の李昌鉉さん=当時(16)=の父、李南錫さん(49)と母、崔順花さん(49)が、8日まで東京と大阪で、東京電力福島第1原発事故や尼崎JR脱線事故の支援団体や遺族らと交流会などを行う。
李南錫さんは出発前、仁川国際空港で「韓国よりも進んだ安全対策を日本がどう実現させてきたのか、事故の遺族らがどのような活動をしたのか学びたい」と話した。
旧郵政省の元キャリア官僚に判決が出た。
セシウム汚染木くず投棄、コンサル社長に有罪判決 大津地裁 12/02/14(産経新聞 West)
滋賀県高島市の琵琶湖近くの河川敷に、放射性セシウムに汚染された木くずが不法投棄された事件で、廃棄物処理法違反の罪に問われた東京のコンサルタント会社社長、田中良拓被告(42)に大津地裁(赤坂宏一裁判官)は2日、懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年、罰金100万円(求刑懲役2年、罰金100万円)の判決を言い渡した。
田中被告は起訴内容を認めていた。
起訴状などによると、田中被告は平成25年3~4月、東京電力福島第1原発事故で汚染された木くず約310立方メートルを福島県内から持ち込み、高島市安曇川町の河川敷に許可なく捨てたとしている。
11月6日の公判で検察側は、田中被告が24年12月から25年10月、福島県の製材業者から木くず約5千トンを搬出し、東電の損害賠償制度を利用して約1億円の利益を得ていたと指摘。高島市だけでなく、関東や九州にも木くずが運ばれ、現在も放置されているとした。
インスリンの管理は法律で決められているのか?常識の範囲で使用記録を含めた管理体制がずさんであると言う事なのか?
規則で適切な管理が要求されていなければ、同じような事故は防げない。事故後に責任者、又は、担当者が処分されるだけ。行政はどのように考えているのだろうか?
インスリン大量投与、甘い管理…使用記録つけず 12/02/14(読売新聞)
東京都世田谷区の「玉川病院」で今年4月、大量のインスリンを投与された女性患者(91)が意識混濁状態になった事件で、同病院は保管していたインスリンの使用記録をつけていなかったことが病院関係者への取材でわかった。
事件当時、インスリンが入れられていた瓶2本が病院からなくなっており、警視庁は、看護師の高柳愛果容疑者(25)(傷害容疑で逮捕)が病院側の管理態勢の甘さをついてインスリンを持ち出した疑いがあるとみて調べている。
病院によると、インスリンはガラス瓶に入れられ、ナースステーションの薬品棚に保管されていた。棚に鍵はなく、看護師なら誰でも持ち出すことが可能だったという。
棚のインスリンの使用記録はつけておらず、今年4月7日と9日、インスリンが入った瓶2本がなくなっていることが判明したが、最後に持ち出した人物などはわかっていないという。
日本は借金大国である。税金の無駄遣いをやめて、何を優先して、何を諦めるのか、真剣に議論しなければならない。しかし、日本は議論を避ける傾向の国。事実を直視して判断する事を避ける国だと思う。多くの人はぬるま湯に浸かって、最後にはゆであがって死ぬカエルのような選択をするのだろう。だから下記の記事は仕方のない事である。
良い事を言って、良い事を実行する。良い事だが、お金が必要な場合、問題が起こる可能性がある。予算の問題や制限があれば、コスト対効果を考えなければならない。誰でもわかる事である。子供が無く、世話をする親族もいない夫婦は、他の夫婦と同じような生活を送れないと自覚し、準備するべきなのである。準備をしていなければ自己責任で諦めるしかない。国にゆとりがあれば状況は違うかもしれないが、そのような仮定の話をしても無駄。諦めて現状を受け入れるか、他の人に負担を押し付ける、又は、負担を負ってもらう以外の選択肢はない。
「ゆでガエル現象」と言われるものがある。鍋に水を入れ、そこにカエルを入れて徐々に温めていくと、カエルは居心地が良くなって飛び出そうとせずに、最後にはゆであがって死んでしまう。(「紙への道」 )
夫婦で病…離ればなれに 重い医療費、崩れた老後 12/01/14(朝日新聞)
療養の現場では、病気になって生活苦に悩む高齢者も多くいます。
夫婦別々の施設
夫婦はともに病に倒れ、老後の人生設計が狂ってしまった。「人生の終盤にこんな苦痛が待っているとは思いませんでした」。妻(85)はつぶやく。
東京都内に住んでいた夫婦は昨年、夫(71)にがんが見つかった。妻も下血し、腸の病気と診断された。
夫婦には子どもがおらず、世話をする親族もいない。自宅での療養が難しいこともあって、夫は約半年、妻は約50日入院した。
夫は公的医療保険の健康保険組合(健保)に入っていた。70~74歳なら、治療代のうち病院窓口で払う自己負担分は原則2割だ。75歳以上の妻は後期高齢者医療制度により1割で済む。
さらに、大病で治療代がかさむ場合は自己負担を抑える高額療養費制度もある。70歳以上では、収入の区分が「一般」の家庭なら自己負担は1人あたり月に約4万4千円が上限だ。
しかし、これらの保険や制度だけでは、2人の生活は守りきれなかった。
あれだけ騒いだのにひっそり終了?
STAP細胞:「小保方氏の実験終了」理研 12/01/14(毎日新聞)
STAP細胞論文の不正問題で、STAP細胞の有無を実験で検証している理化学研究所は1日、筆頭著者の小保方晴子研究員(31)の実験が予定通り先月末で終了したと明らかにした。実験結果の公表日程は未定という。
理研は今年4月、小保方研究員を入れないチームで検証実験を始め、小保方研究員には単独で7月1日〜先月末に監視カメラの下で実験させた。小保方研究員は先月21日付で、この検証実験チームの一員となっており、今後は自らの実験データの整理をする。チームの実験期限は来年3月末までだが、結果によっては途中での実験打ち切りもあり得るという。【根本毅】
逮捕するかは警察次第。逮捕されても有罪になるかは警察の捜査内容と検察次第。
警察や検察がどこまでやるのか、出来るのかわからない以上、出来るだけだまされないようにするしかない。
航空券未着:「レックス」社長逮捕へ 無登録営業の疑い 12/01/14(毎日新聞)
無登録で旅行業を営んだとして、警視庁保安課は、東京都新宿区の旅行代理店「レックスロード」の社長の男(49)=千葉県浦安市=を旅行業法違反(無登録営業)容疑で逮捕する方針を固めた。レックス社を巡っては今年7月以降、代金を支払ったのに航空券が届かないという苦情が東京都などに相次ぎ、同課が8月、本社を家宅捜索していた。
捜査関係者によると、レックス社は今年4〜7月、観光庁や都に旅行業の登録をしないまま、女性客2人から航空券4枚の注文を受けた疑いが持たれている。
同社は7月、毎日新聞の取材に、代金を受け取ったのに航空券を渡していない客が約500人に上ると説明した。同課は詐欺容疑での立件も視野に捜査したが、代金の詐取が目的だったとまでは言えないと判断した。
都によると、レックス社は1998年に旅行業登録。昨年10月に有効期限が切れ、今年1月に都や観光庁に事業廃止を届け出ていた。【林奈緒美】
お金の力は大きい。
政府の考えや判断次第で、大きなお金が動く。東電の原発事故への税金投入や救済が代表的な例だ。献金する以上の見返りが帰ってくる。今回は原発に関してメディアはあまり取り上げていないけれど、影響や関係がある人にとっては重要な事だと思う。
電力関連会社:自民党へ3228万円献金 5社・3年で 12/01/14(帝国データバンク)
関西、中国、四国、北陸の4電力の関連会社や子会社が福島第1原発事故から昨年までの3年間に、自民党の政治資金団体「国民政治協会」へ、判明しただけで計3228万円を献金していたことがわかった。4電力はいずれも、原発再稼働に向けて安全審査を原子力規制委員会に申請している。電力各社は大幅な電気料金値上げを実施した1974年を機に、公益企業として特定政党への献金は不適切だとして建前上自粛している。
同協会の2011〜13年の政治資金収支報告書によると、原発事故後の献金額は、関連会社では関電の「きんでん」が1300万円で最多。他に中国電の「中電工」、四電の「四電工」、北陸電の「北陸電気工事」が献金を続けていた。子会社では四電の「四電ビジネス」が献金した。
11年は、東京電力の関連会社「関電工」が福島第1原発事故前後の1月と4月に計680万円、中部電力の子会社「トーエネック」も事故前の1月に600万円をそれぞれ献金した。しかし、12年以降は確認されなかった。
全国では、08年から子会社に献金自粛を呼びかけている九州電力の例がある。子会社や関連会社の献金について取材に対し、関電は「各社が適否を判断している。関与すべきでない」▽中国電は「コメントする立場にない。献金自粛は呼びかけていない」▽四電と北陸電は「各社の判断。承知(把握)していない」−−とそれぞれコメントした。
一方、4電力は献金については今回確認されなかったが、政治家のパーティー券購入は続けている。理由について、「情報収集」(関電、四電、北陸電)や「儀礼的なつきあい」(中国電)としている。
政治資金に詳しい上脇博之・神戸学院大大学院教授(憲法学)は「電力会社は表向き献金自粛を言っているだけで、抜け穴があるのが実態だ。自粛を徹底するなら、関連会社の献金やパーティー券購入も自粛しないと意味がない」と指摘している。【関谷俊介】
品質に問題がないのであれば魅力的な企業だ。
「パワービルダーが分譲する物件の最大の特徴は、建売住宅の価格の圧倒的安さにある。建材の共通化や工期の短縮など、徹底したコスト管理により、従来の大手に比べると2~4割は安いと言われる販売価格を実現している。」
土地の制約がなく、オーダーメードにこだわらない人にとっては良い選択かもしれない。建材の共通化によるコスト削減は納得出来る。建材の共通化が可能な仕事を取れば取るほどコストは下がり、利益は出ると思う。仕事の効率は上がるし、それによる工期の短縮も可能だろう。「パワービルダー」がもっと成長すれば、体力のない会社や独自の強みを生かして違う顧客を開拓できない会社は潰れるか、飲み込まれることになるかもしれない。これは仕方のない事。無理な成長をせずに価格破壊に貢献してほしい。
新築戸建て住宅で価格崩壊 首都圏で1千万円台も急増 早まった購入判断に注意 (1/2)
(2/2) 11/30/14 (Business Journal)
千葉県609件、埼玉県645件、神奈川県122件、東京都54件……これが何を表している数字か、おわかりになるだろうか?
リクルートが運営する不動産情報サイト「スーモ」に登録されている、2000万円以下で売り出されている新築一戸建ての件数だ。1都3県を合わせると、ざっと1500件近い数の1000万円台物件が登録されているのである。ちなみに、2004年には100件前後、07年には200件前後であったから、いかに激増しているかがわかる(いずれもスーモの前身「住宅情報ナビ」での同条件検索結果)。
検索結果を詳しく見てみると、4LDK以上の最安物件は千葉県北西部の1430万円。土地41坪、建物30坪の堂々たる外観。最寄り駅から東京駅まで69分で通勤できる閑静な住宅地に建つ新築の土地付き物件が、大手住宅メーカーの建築価格よりも安いのだから、これぞ驚異のコストパフォーマンスだ。
もちろん、新築でそんなに安いのは、間取りがいまいち使いづらかったり、駅からの距離が遠かったり、人気のない私鉄沿線だったりといったデメリットが必ず潜んでいるのだが、それにしてもマイホーム購入希望者からすれば、あっと驚くインパクトは十分あり、一度その価格を知ってしまうと、ほかの物件がすべて高く見えるから不思議だ。
ひとつの物件を複数の不動産仲介業者が登録しているため、実際に購入検討対象になる物件数はこの数分の1になってしまうものの、それでも1000万円台の新築一戸建は首都圏でも、いまや珍しくもない存在になっているのは間違いない。
●価格崩壊の立役者、パワービルダー
新築戸建て市場崩壊の立役者となっているのが「パワービルダー」だ。
パワービルダーとは、1990年代後半から主に関東地方で大量に低価格の戸建てを分譲するようになった住宅建築会社のことで、現在主要各社はどこも全国展開していて、一社だけでも年間数千棟規模の住宅を建てている。ちなみに、13年に関連6社が経営統合して生まれた飯田グループホールディングスは昨年度、傘下企業だけで合計3万6000棟も分譲している。
パワービルダーが分譲する物件の最大の特徴は、建売住宅の価格の圧倒的安さにある。建材の共通化や工期の短縮など、徹底したコスト管理により、従来の大手に比べると2~4割は安いと言われる販売価格を実現している。30坪・標準4LDKの間取りで、大半の物件が2000万円台だ。郊外で地価の安いところになると、1000万円台で新築戸建てを分譲している。
また、一般的なデペロッパーとは異なり、自社内に販売部門を持たず(持っていても、ごく小規模)、販売活動は原則として成功報酬で、地元の不動産仲介会社に委託するのも大きな特徴だ。在庫を抱えることを極端に避ける傾向があるため、売れ残ったら大胆に価格を下げる。一度に200~300万円単位で下げることも珍しくない。例えば、売出価格3180万円の物件が2週間余りの間に4回も価格改定が行われて、1000万円もの大幅プライスダウンが行われたケースすらある(図版参照)。
洋服のバーゲンと同じで、単独でみたら赤字でもプロジェクト全体で黒字であればよいとの姿勢で、完成後一定期間売れなければ、ほとんど捨て値といってもいいくらいの価格にまで下げることもある。
まるで住宅を大量生産の工業製品と同じようなポジションにしてしまったことこそが、パワービルダーの最大の功績といえるだろう。
●郊外では不動産デフレに拍車
パワービルダーの物件を品質面で大手ハウスメーカーと比べると、細部は見劣りしてしまうかもしれないが、かつて「安かろう悪かろう」といわれた建売住宅と違い、基本構造は最新の耐震基準をクリアして10年保証もついており、安全面に問題はない。
たとえるなら、高級車に乗る優越感はないものの、日常的にはまったく不便を感じない大衆車のような快適さをパワービルダーの物件は提供しているのである。
注目すべきなのは、それが不動産相場に与える影響の大きさである。例えば、今まで2000万円で売りに出されていた築25年の中古物件と同じ価格帯で、パワービルダーが新築一戸建て物件を分譲すると、どのような事態が起こるだろうか。「古家付き2000万円の土地」には、もはや誰も目もくれなくなる。何しろ、新築のほうは、同じ広さの土地の上に新しい建物まで付いて2000万円なのだ。
このようなことが続くうちに、郊外の住宅地における不動産価格はどんどん下がっていくのである。アベノミクスの歴史的な金融緩和によって、不動産価格は右肩上がりのようなイメージが先行しているが、それは都心にある一部のマンションや人気沿線に限った話だ。少し郊外の住宅地に目を転じると、いまだにすさまじいまでの不動産デフレの現実を目のあたりにできるのである。
従って、11月4日付当サイト記事『「同額の家賃を払い続けるなら、ローンで購入のほうがオトク」のワナ』でも述べたように、ろくに情報収集もせずに早まった購入決断をすると、後悔する可能性が高いので注意したい。
賃貸住宅の世界で起きている「家賃崩壊」と同じく、分譲の世界でも「価格崩壊」が起きていることをしっかりと頭に入れたうえで、慎重に将来のマイホーム計画を立てたいものである。
日向咲嗣/フリーライター
権限や決定権を持つ人間の不正。システム的には個人の権限や決定権を弱めると本当はもっと良い結果や利益を出せる機会を失う可能性もあるが、籾井(もみい)新一郎容疑者の事件は防止できる、又は、早期に発見出来るメリットがある。結果論で判断するのか、チェック機能を強化するのか、その他の方法を取るかでいろいろな事が言える。チェック機能と言っても、チェックする部署又は最高権限を持つ者が不正に加担したり、怠慢である傾向があれば本来の機能はない。どちらのリスクを優先させるのか、人事や人格の評価をいかに公平に行えるのか、個々の企業の判断次第だ!
海外旅行や愛人との逢瀬…15年間で不正取引94億円 循環取引で会社資産を食い荒らしたベテラン商社マンの素顔 (1/5)
(2/5)
(3/5)
(4/5)
(5/5) 11/28/14 (産経新聞 West)
帳簿の数字を動かすだけで多額の現金が懐に入り、仕事の実績にもつながる循環取引。その〝魔力〟にとらわれた中堅商社元社員の男が、詐欺容疑で大阪府警に逮捕された。架空取引をでっち上げ、工事代金の一部をキックバックさせていた不正を隠蔽するため、循環取引が始まったという。15年間で積み上げた不正取引の総額は約94億6千万円。男はだまし取った金を海外旅行や愛人の生活費など主に遊興費に充てていた。抜群の業績で周囲の信頼を集めたベテラン商社マンの素顔は、肥大した欲望を満たすため会社の資産を食い荒らす「獅子身中の虫」だった。
氷山の一角
東証1部上場の機械商社「椿本興業」の名古屋支店で働いていた元社員、籾井(もみい)新一郎容疑者(56)。工事の発注から工事代金の支払いまで実務を一手に任されていた。与えられた大きな権限を悪用し、椿本興業に架空の工事を下請け企業に発注させ、工事代金をだまし取っていたという。
事件では、籾井容疑者と共謀した詐欺容疑で、椿本興業と長年、取引関係にあった機械メーカー「川端エンジニアリング」社長の川端孝男(47)と、双子の弟で同社元社員の利昭(47)の両容疑者も逮捕されている。
大阪府警によると、下請け企業に架空取引を持ちかけたのは孝男容疑者だったという。
「助けてやってくれないか」。平成19年12月、以前から付き合いのあった電子機械会社に、椿本興業が発注したクレーン設置工事をいったん下請けし、そのまま孫請けに発注するよう頼んだ。見返りとして、電子機械会社には工事代金の5%をマージンとして支払う約束をしたという。
話はじきにまとまり、椿本興業-電子機械会社-孫請け企業の間の架空取引は翌20年5月まで計3回繰り返されたとされる。
孫請け先となったのは、利昭容疑者が個人事業を営んでいた「豊田メディアネットワークス」。
工事代金として椿本興業が振り出した約束手形4通の額面は計787万円。これが10月の最初の逮捕容疑となった。
電子機械会社がマージンを抜き取った後、残りの現金は「豊田メディアネットワークス 川端利昭」名義の銀行口座に振り込まれた。この口座から、利昭容疑者ら3人は約600万円を引き出し、山分けしたとされる。
下請けに入る会社は他にも数社あり、いずれも椿本興業に架空工事を発注させる手口で工事代金をだまし取っていた。
11月、籾井容疑者らは別の架空工事でも代金1400万円を詐取したとする詐欺容疑で再逮捕された。21年8月までのおよそ2年半で行われた架空取引は38件。3人が不正に得た利益は計約6800万円に上るとみられる。
しかし、これは籾井容疑者が川端エンジニアリングと結託して繰り返してきた不正のほんの一部に過ぎなかった。
15年にわたる不正
事実解明と再発防止のために椿本興業が設置した第三者委員会の調査報告書によると、籾井容疑者らの不正は平成10年から15年間、続いていたという。
不正の中心となった籾井容疑者と孝男容疑者は、籾井容疑者が名古屋支店の課長をしていたとき、椿本興業の取引を通じて知り合ったとされる。
その後、籾井容疑者が直接取引を持ちかけ、孝男容疑者は10年、川端エンジニアリングを設立した。
籾井容疑者は自ら川端エンジニアリングを担当した。それと同時に、川端エンジニアリングに水増し発注や架空発注を行い、工事代金の一部をキックバックさせる不正が始まった。当初はいくつもの企業が関わる循環取引ではなく、椿本興業と川端エンジニアリングの2社だけの架空取引だったという。
急速に深まっていった2人の関係は、不景気を背景に川端エンジニアリングの経営が行き詰まったことで危機に陥った。
そのまま倒産すれば、整理手続きで過去の取引が世間に知れ渡り、不正も露見してしまう可能性があった。「倒産を避けるには川端エンジニアリングの資金繰りを維持することが不可欠」と判断した籾井容疑者らは、複数の企業の間で架空取引を繰り返し、資金を環流させる循環取引に手を染めた。
循環取引に加わった会社は椿本興業、川端エンジニアリング以外に7社あったとされる。これらの会社に、籾井容疑者は「川端エンジニアリングの発注枠が決まっているため間に入ってほしい」と循環取引に加わるよう依頼していた。7社には、循環取引を行われるたびに、報酬として取引額の数パーセントのマージンが支払われたという。
循環取引でからくも倒産の危機を免れたことに味を占め、籾井容疑者らは、その後も循環取引を繰り返しながら、工事代金の着服を続けていた。
しかし、自由に金を生み出す〝魔法のシステム〟は23年、取引に加わっていた企業が、帳簿上、架空の在庫を大量に抱えている問題が発覚し、崩壊への道をたどり始めた。
椿本興業の内部調査で籾井容疑者の問題への関与が疑われるようになり、25年2月、籾井容疑者は上司から取引の撤退を指示された。循環取引を続けられなくなった籾井容疑者は翌3月、会社に不正を打ち明けたという。
最後は訴訟合戦
接待費用、スナックでの私的な飲食、海外旅行、愛人の生活費…。1億円以上とみられるだまし取った現金を、籾井容疑者は主に遊興費に充てていた。
椿本興業が設置した第三者委員会の調査報告書によると、籾井容疑者は入社以来、中日本営業本部(現・名古屋支店)で勤務。課長職になって以降は20年間、一貫して、工場やプラントなどの設備を扱う装置営業部門を歩み、常に取引の発注や工事代金の支払いを決裁する権限を持っていた。
管理職となってからは取引の直接の担当者になることはできなかったが、部下の発注番号を使い、架空取引を行っていた。社内報告の際にも、自分で処理したことを隠蔽するために、部下の名前を使っていたという。
社内外での評価は高く、装置営業のキーマンとみられていた。不正発覚後も周囲からは「まさかあの人が」という声が漏れた。
「籾井さんの頼みだったので断ることができなかった。籾井さんの指示は椿本興業の指示なのでだましたことにはならない」。逮捕後の調べに容疑を否認した孝男容疑者の供述には、籾井容疑者の社内での権限の強さがうかがえる。
孝男容疑者は逮捕容疑の共犯ではなく、〝被害者〟の立ち場を貫いている。代表を務める川端エンジニアリングは昨年10月、循環取引に参加させられ、損害を受けたとして、椿本興業と籾井容疑者に約11億円の損害賠償を求め名古屋地裁に提訴した。一方で、椿本興業も川端エンジニアリングを相手取り、今年4月、約18億円の損害賠償請求訴訟を起こしており、訴訟合戦となっている。
昨年5月、椿本興業を懲戒解雇された籾井容疑者は築き上げた地位を失い、同僚たちの信頼も失った。〝不正の盟友〟だった孝男容疑者とは法廷で争う。周囲を裏切り、不正に手を染め続けた籾井容疑者には今、何も残っていない。
高いお金を払って英語を覚える時代ではないと思う。本人がやる気があれば、低額又は無料で英語が学べる。テレビを見たり、インターネットを利用すれば英語のニュースを見たり、聞いたりできる。簡単な英文法が理解出来て、聞き取りが出来れば、英語の上達は早い。英語を学んでいる日本人の多くはこのレベルに到達さえもしていない。
オランダやカナダみたいに、英語のニュースや番組の時はオランダ語やフランス語の字幕、オランダ語やフランス語のニュースや番組の時は、英語の字幕をテレビで流している。日本でも英語と日本で放送すれば英語が出来る人は増えるだろう。文科省が英語教育に多額の税金を投入しようとしているが、税金の無駄遣い。カナダではフランス圏では必要ない人はあまり英語が出来ないし、英語圏では必要のない人はあまりフランス語が出来ない。カナダが良い例だ。使わなければ、使う機会がなければ語学はなかなか身に付かない。
英会話教室「T.I.E.外語学院」が経営破たん 11/27/14(帝国データバンク)
(株)ティ・アイ・イー外語学院(TDB企業コード988334847、資本金1600万円、東京都新宿区百人町1-19-2、代表西崎元信氏)は、11月19日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。
破産管財人は柴田義人弁護士(東京都港区虎ノ門4-3-13、問い合わせ窓口03-6721-3109)。財産状況報告集会期日は2015年2月16日午後1時30分。
当社は、1977年(昭和52年)2月に設立。20 代以上の会社員を主な対象とした英会話教室「T.I.E.外語学院」の運営を手がけ、新宿、銀座、大崎、横浜、大阪梅田など6ヵ所に教室を開設していた。設立当初は、「ティアイイー英語クラブ」の称号で運営を開始。80年1月には、池袋、横浜など5教室を開設し、生徒数が急増。90年9月に、商号を(有)ティアイイー英語クラブから(有)ティ・アイ・イー外語学院に変更。97年7月に株式会社に組織変更を行い、「英語で考える」を教育理念とする独自の指導方法や、割安な料金でのマンツーマン指導が人気を呼び、直近でピークとなる2002年3月期の年収入高は約3億5600万円を計上、生徒数は約1000人を誇っていた。
しかし、2007年10月に英会話学校最大手の(株)ノヴァが会社更生法を申請したことで、利用者が伸び悩み、業界環境が悪化。その後も、小規模ながら他社と一線を画した教育法で差別化を図ったものの、生徒数の減少に歯止めがかからず、2013年3月期の年収入高は約1億7700万円までダウン。今年4月に消費税の増税以降、入会申し込み数が激減し、事業継続のメドが立たず、10月28日に事業を停止していた。
負債は債権者数約500名に対し約2億8000万円。
何度も言っているが、とにかく逮捕する。なぜ早く逮捕する方針を取らなかったのか?そこに問題がある。
「フィリピンの裁判所は5日、昨年4月に違法操業の疑いで逮捕された中国人漁民12人を有罪とし、船長に禁固12年、他の乗組員に禁固6~10年の判決を下した。」 (08/06/14、レコードチャイナ)の対応と
海保の対応の甘さを比べると良く分かると思う。甘い対応の繰り返しは問題の解決にならない。
サンゴ密漁、漁船8隻に減少…摘発強化が奏功か 11/26/14(読売新聞)
希少な「宝石サンゴ」の密漁問題で、海上保安庁は25日、小笠原諸島周辺と伊豆諸島南部の海域で確認された中国漁船とみられる船は、24日時点で8隻になったと発表した。
海保が領海(約22キロ)内での摘発を強化した21日以降、大幅に減少しつつある。
小笠原諸島周辺では、20日に47隻が確認されていたが、海保は、領海内では摘発よりも侵入阻止を優先していた従来の取り締まり方針を転換。巡視船を増強し、21日と23日、領海内で操業していた中国人船長計2人を逮捕した。その後、24日に確認されたのは、小笠原諸島周辺の排他的経済水域(EEZ)に3隻、伊豆諸島南部の領海内に1隻とEEZに4隻にとどまった。
今年10月以降、海保は方針転換の前まで、周辺海域で中国人船長7人を逮捕していたが、領海内での逮捕は1人にとどまっていた。
不祥事を起こす公務員は、民間に比べて安定している事を忘れるから不祥事を起こすのかな?
不倫相手の耳かき店女性を暴行した小学校教師 その理由は… 11/26/14(産経新聞 West)
耳かき専門店で知り合った不倫相手の女性に暴行を加えてけがを負わせたとして、大阪市教委は26日、傷害容疑で逮捕され、略式命令を受けた市立小学校の男性教諭(44)を停職6カ月の懲戒処分とした。
市教委によると、教諭は無料通信アプリ「LINE(ライン)」で女性の返信がこなかったことに怒り、暴行を加えていたという。「大変なことをして猛烈に反省している」と話し、同日付で依願退職した。
元教諭は病気療養で休職中だった昨年秋から今年5月までの間、ひざまくらで耳かきサービスを提供する大阪市北区の専門店に多いときで週に3~4回の頻度で通い、同月ごろから従業員の女性と不倫をしていた。
大阪府警が11月、女性の顔を平手でたたいたり足を蹴ったりして3週間のけがを負わせたとして、傷害容疑で逮捕していた。
元教諭は特別支援学級を担当し勤務態度に問題はなかったという。
悪意のある人達は制度の盲点を突く。大事件や世間の注目を引く事件になってはじめていろいろな事をメディアが調べ、盲点を知る結果となる。その時では遅い場合もあるし、時が経てば忘れる人々もいる。
容疑の妻、戸籍からバツ消す 京都・青酸殺害、再婚歴隠しか 11/25/14(京都新聞)
京都府向日市鶏冠井町の筧勇夫さん=当時(75)=が青酸化合物で殺害されたとされる事件で、京都府警捜査本部(向日町署)に殺人容疑で逮捕された妻の千佐子容疑者(67)が、戸籍簿上、再婚した経歴を消した上で、筧さんと結婚していたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。これまでに死別した夫や交際した男性の名前を女性名に変えて携帯電話に登録していたことも判明。捜査本部は、千佐子容疑者が過去の結婚や交際を隠すために工作していた可能性が高いとみて調べている。
捜査関係者らによると、千佐子容疑者は筧さんとの結婚前に3人の男性と結婚し、いずれも死別していた。通常、妻が夫と死別や離婚をした場合は、妻の戸籍簿には夫の名前に「×」の印が付けられ、死別や離婚の理由が記載される。一方、昨年11月に筧さんと入籍した際、千佐子容疑者の戸籍簿では過去に2回再婚した男性の名前は記載されておらず、最初に結婚した大阪府の男性の姓に戻っていた。3度目の結婚の際にも、同様に戸籍簿には直前に再婚した男性名はなく、大阪府の男性の姓だったという。
行政関係者によると、本籍地を別の場所に移す転籍の手続きなどをすれば、制度上、新たな戸籍簿に再婚した夫の名前などは記載されず、弁護士や司法書士が除籍簿などをたどらない限り再婚の履歴は確認できないという。捜査本部は千佐子容疑者が再婚歴を隠して筧さんに近づいた可能性があるとみている。
捜査関係者の説明では、千佐子容疑者の携帯電話を調べた際、過去に結婚したり交際したりした男性の名前の漢字一字を変えた女性名で登録され、筧さんも女性の偽名で登録されていたという。女性の知人らは実名のままだったといい、捜査本部は男性だけ名前を変えていた目的についても調べる。
携帯700台を不正貸与 詐欺事件で使用、被害総額は数十億 11/20/14(産経新聞 West)
本人確認せず携帯電話を貸し出したとして、岐阜県警高山署は20日、携帯電話不正利用防止法違反の疑いで、レンタル携帯電話会社社長、高橋透友容疑者(31)と、同社アルバイト本間智貴容疑者(22)=いずれも千葉市中央区=を逮捕した。
同署によると、同社は約700台以上の携帯電話を不正に貸し出していた。全国で500件以上の詐欺事件に使われ、被害額は数十億円に上るとみて裏付け捜査を急ぐ。
2人の逮捕容疑は今年3月、身分証明書などで本人確認をせずに客に携帯電話を貸し出した疑い。高橋容疑者は「よく分からない」と容疑を否認、本間容疑者は認めている。
5月に岐阜県高山市の無職女性(71)が証券取引名目で現金100万円をだまし取られる事件があり、使われた携帯電話が高橋容疑者の会社が貸し出したものだったと判明したため同署が調べていた。
「書類だけで車検を通せば金になった」不正車検容疑で5人再逮捕 修理困難なクラシックカー 大阪府警 11/20/14(産経新聞 West)
大阪府警などの合同捜査本部は20日、必要な検査をせずに車検証発行の手続きをしたとして虚偽有印公文書作成・同行使などの疑いで、自動車修理業社長の大喜千寛容疑者(55)=兵庫県芦屋市、沢田拓治容疑者(44)=同西宮市=ら5人を再逮捕した。いずれも部品不足などで修理が難しいクラシックカーを扱っていたという。
逮捕容疑は9~10月、1954年のジャガーなど、外国製の車4台について、保安基準に適合するか検査せず、虚偽の適合証を大阪運輸支局などに申請、車検証を発行させた疑い。
沢田容疑者は「検査によく引っ掛かるため、大喜容疑者にペーパー車検を依頼した」と供述。大喜容疑者は「経営が厳しく、書類だけで車検を通せば金になった」と話している。5人は同容疑で10~11月に逮捕され、大阪地検は20日、いずれも処分保留とした。
日本語訳だからニュアンスが良く分からないが女性の人権団体が西欧諸国で活発に動いているのだろうか?自業自得だし、講演料が20万円以上のようだから既に儲かっているのでは?
英政府、「ナンパ講師」ブランク氏の入国を拒否 11/20/14(AFP=時事)
【AFP=時事】英国政府は19日、「ナンパ講師」として各国で講演を行っている米国人のジュリアン・ブランク(Julien Blanc)氏の入国を認めないことを決めた。英国では、同氏が「身体的・精神的な虐待」を助長しているとして入国拒否を求める請願に16万人近くが署名していた。
リン・フェザーストーン(Lynne Featherstone)内務閣外大臣は、ブランク氏にビザ(査証)を発給すれば、「性暴力や性的嫌がらせの増加を招いていただろう」と述べ、「ブランク氏がわが国に上陸しなくなったことを喜ばしく思う」と付け足した。
リアル・ソーシャル・ダイナミクス(Real Social Dynamics)社の「エグゼクティブコーチ」を務めるスイス系米国人のブランク氏は、女性のひきつけ方を男性たちに教えていると主張しているが、同氏が教授する手法については、虐待的だとの批判が多くの人々から上がっている。英国には、世界各国での講演活動の一環として21日に入国する予定だった。
英当局に対しては、「公共の利益に資さない」との理由でブランク氏へのビザの発給を求める声が上がり、署名募集サイト「change.org」で立ち上げられた請願活動には15万8000人が署名した。
ブランク氏は今年、オーストラリアを訪問した際にも、抗議が殺到したことによりビザが取り消され、滞在の短縮を余儀なくされた。カナダ当局も現在、同様の措置を検討している。
ブランク氏は今週、米CNNテレビとのインタビューで、「僕が気分を害してしまった人たちに謝罪したい」と語っている。一方で、同氏が女性の首を絞める写真や、女性を支配する方法としての暴力を推奨するかのような発言は、「文脈から切り離されて」伝えられており、「ユーモアを狙ったひどい試み」だったと釈明。「人付き合いが苦手な男性たちに、女性とうまく話したり、関係を持ったりできるよう、自信をつける方法を教えている」と主張した。【翻訳編集】 AFPBB News
改正法(サンゴ密漁対策、罰金上限大幅引き上げへ)が成立した事は良い事だ!
福岡地裁・丸田顕裁判官が外国人漁業規制法違反(領海内操業)の罪に問われた中国籍の男性に無罪を言い渡した(10/15/14、産経新聞)ケースもあるので、裁判でどのような判決が出るかが重要。罰金の上限が引き上げられただけで、密漁の罰金がこれまで通りとか、無罪になれば、骨抜き改正法となる。
サンゴ密漁対策、罰金上限大幅引き上げへ 改正法成立 11/19/14(朝日新聞)
小笠原、伊豆両諸島周辺で中国のサンゴ密漁船とみられる漁船が多数出没している問題で、密漁の罰金を大幅に増やす改正法も19日の参院本会議で可決、成立した。27日に公布され、12月7日に施行予定。
改正されたのは、沿岸約370キロの排他的経済水域(EEZ)内で外国人の無許可操業を取り締まる漁業主権法と、沿岸約22キロの領海内で外国人の漁業を禁じる外国人漁業規制法。
現在、漁業主権法は最大1千万円の罰金、外国人漁業規制法は3年以下の懲役または最大400万円の罰金を科すが、罰金額の上限を共に3千万円へ引き上げた。6カ月以下の懲役または最大30万円の罰金を科してきた立ち入り検査忌避は、外国人のみ罰金を最大300万円に増額した。従来の漁業法から、漁業主権法と外国人漁業規制法の対象とした。
水産庁は今後、EEZ内で逮捕された船長が釈放時に支払う担保金の基準額を、無許可操業で最大3千万円、立ち入り検査忌避は最大300万円に増額。加算額も密漁サンゴ1キロあたり600万円に増やす。
世の中は広い!いろいろなストーリーがある。
周辺で6人死亡、遺産8億円=千佐子容疑者、結婚相談所介し 11/19/14(読売新聞)
京都府向日市の筧勇夫さん=当時(75)=殺害容疑で逮捕された妻の千佐子容疑者(67)周辺では、筧さんを含め、結婚相談所を通じて結婚・交際していた男性ら6人が相次ぎ死亡している。捜査関係者らによると、同容疑者は遺産の大半を相続、総額は約8億円に上るという。
他の5人は、兵庫県西宮市の医薬品卸会社社長=同(69)=▽大阪府松原市の農家の男性=同(75)=▽奈良県内の男性▽大阪府貝塚市の本田正徳さん=同(71)=▽兵庫県伊丹市の元内装業経営=同(75)=。
千佐子容疑者は佐賀県出身。北九州市の高校卒業後、市内の都市銀行支店で働いていた1969年、大阪府貝塚市の男性と知り合い結婚した。同市に移り印刷業を営んでいたが、男性は94年に54歳で病死した。
卸会社社長とは2006年に知り合い再婚。社長は同年8月28日、自宅で亡くなり、検視の結果「脳梗塞」とされた。08年2月ごろには農家の男性と3度目の結婚をしたが、男性は同年5月17日、自宅から救急搬送され死亡。「心筋梗塞」だった。
千佐子容疑者はいずれも遺産を相続し、自宅などの不動産を全て売却。億単位の金を得たとみられるが、社長の場合は親族に民事調停を起こされ一部を返還した。
09年ごろには交際相手の奈良の男性が病死。末期がんだったという。
さらに11年9月ごろ、千佐子容疑者は本田さんと「婚約」したが、本田さんは12年3月9日、泉佐野市でミニバイクを運転中に急死。司法解剖で「致死性不整脈」とされた。同容疑者は「内縁の妻」を名乗り、遺言を盾に親族への遺産分与には応じなかった。
13年9月20日には交際中だった元内装業の男性が死亡。がんを患い、千佐子容疑者と近くのファミリーレストランで食事をした直後に容体が急変した。自宅は死後、同容疑者が売却した。この約2カ月後の同年11月1日、同容疑者は筧さんと4度目の結婚をした。
事故報告を怠っていたとなるとやはり問題があったと推測して間違いが無いのでは?
群大病院、事故報告怠る…厚労省が立ち入り検討 11/19/14(読売新聞)
群馬大病院(前橋市)の第二外科で腹腔鏡(ふくくうきょう)を使う肝臓手術を受けた患者8人が死亡した問題で、同病院が、医療法で義務づけられた事故報告を怠っていたことがわかった。
同病院が18日、厚生労働省の聞き取り調査で明らかにした。厚労省は、病院の安全管理体制が不十分だった疑いがあるとして、同法に基づく立ち入り検査を検討している。
同法の施行規則は、医療事故の疑いがある場合、事故発生から原則2週間以内に、公益財団法人「日本医療機能評価機構」(東京)に報告することを義務づけている。
同省によると、聞き取りに応じた同病院の野島美久院長は、事故報告をしなかったことについて、「病院内の対応で手いっぱいだった」と釈明。「少なくとも調査委員会から問題だと指摘された8月には、報告すべきだった」と謝罪したという。
建築確認は思ったよりもずさんな状態なのかもしれない。それとも福井県では建築基準法で定められた遊具の定期検査報告は必要ないと言う事か?
ベルト確認せず…コースター転落事故で書類送検 11/19/14 (読売新聞)
福井県坂井市の遊園地「ワンダーランド」で昨年4月、小学1年の男児(当時6歳)が走行中の2人乗りのジェットコースターから転落し、肋骨(ろっこつ)骨折などの重傷を負った事故で、福井県警捜査1課などは18日、乗客のシートベルトの装着確認などを担当していた元係員の男性(65)と、安全管理を指導する立場だった元支配人の男性(58)を業務上過失傷害容疑で書類送検した。
2人は大筋で容疑を認めているという。
同課の発表では、元係員は男児がシートベルトを確実に装着しているか確認せずにコースターを発進。元支配人は元係員にベルトを引っ張って確認するなど安全確認の具体的手順を指導せずに運転操作業務に従事させ、事故を未然に防ぐ注意義務を怠った疑い。
元係員は「事故以前にもベルトが走行中に外れることがあった」と話しているという。事故後、男児は「怖いので正面のバーをずっと握っていた」と話しており、コースターに乗る姿を父親が撮影していたことから、県警は走行前からベルトが正しく装着されていなかったとの見方を強めた。
同課などは、建築基準法で定められた遊具の定期検査報告を怠っていたとして、同法違反(定期報告)容疑でも捜査していた。だが、1988年のコースター完成時に、同容疑で刑事責任を問うための前提となる建築確認の「検査済証」の交付を県から受けていなかったため、同法違反容疑での立件は見送った。
嘘がばれなければそれで良かったのだろう。かばんを奪われたなら、被害届を出さなければNHKが納得しないと思い、被害届を出したのだろう。防犯カメラがあるのか確認して、嘘を付けば虚偽通報が発覚しなかったであろう。
人間、完璧な人はいないが、人間性が表れたケースであろう。結果として警察に虚偽通報するよりは会社の携帯電話をなくしたことを報告した方がよかったことになる。
「かばん奪われた」と虚偽通報 NHKの警視庁担当女性記者を書類送検へ 11/18/14 (産経新聞)
男にかばんを奪われたと虚偽の110番通報をしたとして、警視庁戸塚署がNHKの警視庁担当の20代女性記者を来月にも軽犯罪法違反容疑で書類送検する方針を固めたことが18日、同署への取材で分かった。記者は「会社の携帯電話をなくしてしまったことを隠したかった」などと容疑を認めているといい、同署が詳しい経緯を調べている。
同署によると、記者は9日午後10時45分ごろ、東京都新宿区上落合の路上で、「20分ほど前に、自転車に乗った男に肩に掛けていたかばんを奪われた」と虚偽の110番通報をした疑いが持たれている。
同署が現場周辺の防犯カメラを調べたところ、記者が当時、かばんを持っていなかったほか、自転車に乗った不審な男の姿も映っていなかったことが分かり、事情を聴いていた。
NHK広報局は「警察から事情を聴かれている段階であり、お答えを控えさせていただきます。NHKとしても本人から話を聴くなどして事実関係を調べています」とコメントした。
個人的な意見だが、政治や財界を巻き込んでの景気浮揚ムードが画策されたと思う。しかし、恩恵を受けたのは株を投資している人々と大手企業だけ。来年にはさらなる増税。増税による景気減速が予想され、日本は世界一位の借金大国。中小企業や自営業者は動かない。しかも、TPPや円安による負担増を体感している企業や人々はテレビや経済評論家が何を言おうが信じないはずだ。
年金運用 GPIFの組織改革議論が本格化 作業班が初会合 11/14/14 (産経新聞) に関して、グリーピアで年金のお金をどぶに捨てた年金積立金管理運用独立行政法人が運用に失敗した時の責任や対応は明確にされていない。こんな状況では多くの国民は動かなかった結果だと思う。
GDP年1.6%減 在庫と設備投資、民間予測と乖離 (1/2)
(2/2) 11/18/14 (SankeiBiz)
7~9月期国内総生産(GDP)速報値は実質年率1.6%減で、事前の民間予測平均の実質年率2.47%増を大幅に下回った。民間予想と政府の統計にこれほど大きな違いが出ることは珍しく、多くのエコノミストが「ネガティブサプライズ」と驚きを隠さない。背景には消費税増税後という特殊な経済状況下で、企業の在庫調整の影響や設備投資の回復を読み切ることの難しさがある。
「在庫の減少が成長率のマイナスに寄与するとは思っていたが、これほどとは思わなかった」。同期の実質GDPが前期比2.2%増と予測していた日本総研の下田裕介副主任研究員は、自身も含む民間予測が大きく外れた理由をこう説明した。在庫の減少はGDPの統計上はマイナスに働くため、7~9月期は結果として成長率を前期比0.6ポイント、年率換算だと2ポイント以上押し下げた。下田氏は前期比0.2ポイント程度の押し下げとみており、GDP速報値との開きが大きくなった形だ。
ただ、在庫の減少は先行きでみれば、プラスとなる可能性が高い。今回の統計が、4~6月期に積み上がった在庫が7~9月期で取り崩されたことを反映したものであれば、「在庫の調整が終わり、生産の増加など景気の持ち直しが期待される」(下田氏)ためだ。今回、もう1つ民間予測と速報値の数値が大きく異なった項目がある。設備投資だ。
民間予測では設備投資について、先行指標とされる機械受注統計や日銀の全国企業短期経済観測調査(短観)の底堅さから、プラスに転じるとの見方が強かった。今回の結果について、農林中金総合研究所の南武志主席研究員は「2四半期連続のマイナスは非整合的な内容」と首をかしげる。こうした民間予測と政府統計の開きについて、明治安田生命保険の小玉祐一チーフエコノミストは「GDP速報値段階は基礎統計がそろっておらず、予測は非常に難しい」と明かす。
内閣府は今回の速報値の数値に加え、設備投資の動向を示す7~9月期の法人企業統計など、より最新の統計データを踏まえ、12月8日に7~9月期GDP改定値を発表する。(永田岳彦)
Amebaプロフィール
早稲田大学大学院を在学中、ファイナンスMBAでインベストメントとグローバル金融をメンイに研究しています。
早稲田大学大学院を卒業して、ルックスも良い。なぜ恐喝未遂容疑で逮捕されるようなことをしたのか?投資で大損でもしたのか?ファンド運用は儲かる時は儲かるけど、無理な運用は人生の破滅なのか?
鈴木雅子を逮捕!岡村泰孝と共に大手外食会社社長を恐喝!(NEWSまとめもりー)
「レイプ疑惑」記事で示談金要求、モデルら逮捕 11/18/14 (読売新聞)
「レイプ疑惑」などと書かれたインターネットサイトの記事を送りつけ、示談金名目で現金を脅し取ろうとしたとして、警視庁新宿署は17日、モデルでファンド運営会社社長の鈴木雅子(31)(横浜市神奈川区西寺尾)、金融会社社長岡村泰孝(66)(東京都練馬区早宮)の両容疑者を恐喝未遂容疑で逮捕したと発表した。
同署幹部によると、2人は今年9月10日頃、首都圏で焼き肉店などを経営する都内の男性(48)に電話し、「(鈴木容疑者が)車の中で強姦(ごうかん)されかけた件ですよ。和解したほうがよろしいんじゃないですか」と言いがかりをつけた上、男性による「レイプ疑惑」を報じた情報サイトの記事をファクスで送りつけ、示談金として現金を脅し取ろうとした疑い。
男性は会社経営者らが集まるクルージングパーティーで鈴木容疑者と知り合い、車に同乗したことがあったという。調べに対し、2人は「金は要求していない」と容疑を否認している。
自業自得!
循環器センター元部長、入札妨害の容疑で逮捕 11/18/14 (読売新聞)
国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)が発注した業務の入札情報を漏えいしたなどとして、大阪地検特捜部は18日、同センター情報統括部の元部長・桑田成規容疑者(47)(現総長付)ら3人を官製談合防止法違反(職員による入札等の妨害)容疑などで逮捕した。
他に逮捕されたのは、業務を受注したコンピューターシステム会社「ダンテック」(兵庫県明石市)の代表取締役・高橋徹容疑者(50)ら。特捜部は同日朝から、桑田容疑者宅(大阪市北区)のほか、ダンテックの本社や大阪支店(大阪市淀川区)などを捜索した。
捜査関係者によると、桑田容疑者は2012年3月と13年1月にあった同センター発注の情報ネットワークシステム運用・保守業務の入札2件で、ダンテックに対し、公告前に入札情報を漏らした疑い。
ダンテックは12年3月分を2億2470万円、13年1月分を6300万円で、それぞれ受注した。
ギリシャ人が日本のレクサスのような外観の中国製の車がすごく安いので買いたいと言っていた。中国製は品質も悪いし、耐久性がないと言ったら、2年しか乗らないから中国製で良いと言い切った。2年間、故障なしで走るとは思わなかったが本人の自由なのでそれ以上何もいわなかった。
ドイツの船主も結構、中国建造船を購入している。価格優先なのか知らないが、コストパフォーマンスで考えると、安いからOKなのか知らないが、個人的には中国建造船は問題があると思う。判断基準も人それぞれなので何とも言えない。想定外の問題を経験した人達は、もう中国製はいらないと言っているケースが多い。
中国製“ニセBMW”を爆破した独人オーナーの怒り…車は赤さび・腐食・欠陥だらけ (1/5)
(2/5)
(3/5)
(4/5)
(5/5) 11/17/14 (産経新聞 West)
独自動車メーカーBMWの意匠を“パクッた”とされる中国製の自動車を手に入れたドイツ人男性が、その余りのポンコツぶりに激怒。車をダイナマイトで爆破するパフォーマンスを行い、その動画をネットで公開したところ、世界中で70万回以上再生される人気となっている。動画では赤さびや腐食だらけで、ブレーキもまともでない同車の“性能”を丁寧に紹介。「こんな車が市場に出回ってはいけない」と破壊が必然であることを強調している。そこまでヤルか…という突っ込みはともかく、こんな車が実際に製造・販売されている事実は空恐ろしくもある。(岡田敏彦)
あまりの低品質…あの“毒ギョーザ”連想
壮絶な“最期”を迎えたのは、中国の自動車メーカー「双環汽車(シュアンファン・オート)」のSUV(スポーツ・ユーティリティー・ビークル)で、「CEO」という名の車だ。CEOといえば最高経営責任者の略だが、そんな“高尚”なネーミングとは裏腹に、この車はBMWの「X5」の意匠権を侵害したとして提訴されたことで有名になった。つまり“パクリ”というわけだ。
約6分間の動画はドイツの自動車専門誌「AutoBild(オートビルド)」が制作し、動画サイトYouTubeで流した(AutoBildのウェブサイトで視聴可能)。主役として登場するのは、ドイツ人の自動車ジャーナリストで同車のオーナーのウォルフガング・ブラウベさんだ。映像では恰幅(かっぷく)のよい中年紳士…といった風情なのだが、表情は非常に怖い。この中国車に怒り心頭なのだ。
動画によると、ブラウベさんは、中国車の品質を確かめるために知人から「CEO」を入手したという。爆破処分を決意した理由は、「例え中古車扱いでも、こんなボロ車を市場に出してはいけない」との結論に至ったため。誰かがこの車に乗ることは危険きわまりないというわけだ。
BMWのほかメルセデスやポルシェ、マイバッハなど著名な自動車メーカーを抱えるドイツ人の目から見れば、この中国車は「許せないもの」に映ったに違いない。
ABS作動せず「戦場から掘り出したような車」
動画に出てくるCEOは一見、新車のように見えるが、近づいてよく見ると、車体各部の塗装がブクブクと膨らみ、塗膜の下がさびだらけなのがわかる。まともな塗装工程を経ない手抜きの証拠だ。メッキ部品さえ赤さびが浮いている。ここで、「この車は製造されて5年、10万キロメートルしか走っていないが、既に分解が始まっている」とナレーションが入る。
ブレーキディスクは表面がさびているだけでなく、冷却穴部分の腐食も始まっているという危険な状態。ブレーキパッドは剥がれ落ち、曇ったヘッドライトの内側にはハエが数匹死んでいるというありさまだ。
ここでAutoBildのテストドライバーが登場し、テストコースでその走行性能を確かめるとして車に乗り込んで一言。「こんな冒険は初めてだ」。
走り出すと、スラローム走行ではステアリングが素直に効かず、サスペンションはふにゃふにゃ。直線走行中に急ブレーキをかけるとスピンし、ABS(安全装置)は正常に作動しない。車をジャッキアップして車体下部を見ると、エンジンもミッションもワイヤ類もさびだらけ。
テストドライバーからは「ノルマンディー上陸作戦(1944年)の際に海岸に埋めた車を、今掘り出してきたようだ」と強烈な皮肉が。「実際のところ、10年落ちの建設機械のようだ」と、もうボロクソだ。
斧で滅多打ち、ダイナマイトで爆破
テスト終了のあと、ブラウベさんが再び登場。「こんな無責任で信用できない車は、誰にも売ってはいけないと思い、中古で売り飛ばさずに持っていた」と告白し、「この車は、破壊されなければならない」と冷徹に宣言。その壊し方は徹底的だった。
まずは二度と走れないようエンジンオイルと冷却水を抜いて走行し、エンジンを焼き付かせるという、映像的には地味ながら致命的な破壊行為を実行。CEOは約2キロで走行不能となったが、ブラウベさんは一言、「まあ、こんなものか」。
さらに消防署と話を付けてポンプ車を用意。電装系を破壊するため、サンルーフから車内に放水するという大がかりな水攻めを実行したが、ここでドアの隙間から水がピューピューと勢いよく漏れてしまい、気密性の欠如も発覚。ブラウベさんはこめかみがビキビキと音をたてそうな怒りようだ。
ついに大木も切り倒せそうな斧を持ち出し、ボディー各部に突き立てて壊しまくった。さらに内装にキックを入れ、ドアの内張パネルを引きちぎり…。最後はダイナマイトを無造作に車内へほうり込み、起爆装置のスイッチをオン。車の上部が吹き飛び、メラメラと炎をあげるCEOをバックに、ブラウベさんは「このガラクタ車が最期を迎えたことをうれしく思う」。ここで初めて笑顔を見せた。
韓国車にも失格の烙印
この全編ドイツ語で語られる爆破パフォーマンスは、YouTubeで70万回以上再生される人気ぶり。背景には、批評のためには自動車を壊すこともいとわない欧米の自動車紹介番組の過激さと辛辣(しんらつ)さがある。最も有名なのが英BBCの人気番組「トップ・ギア」だ。
司会者ジェレミー・クラークソンさんの軽妙なジョークと皮肉たっぷりの批評、同リチャード・ハモンドさんのまじめな走行レビューなどに加え、企画も人気。世界中で特番ロケが行われ、日産の新型GTRに乗ったクラークソンさんと、新幹線やフェリーなど公共交通機関を利用するハモンドさんらが、石川県千里浜から千葉県鋸山まで競争するレース企画も注目を集めた。
こうした企画のなかでも過酷な“試験”は評判で、オフロード車を海に沈めたり、階段で走らせたり、果ては数メートルの高さから落としたりして、まだ走れるかどうかを確かめるなど手加減がない。
生産国や生産メーカーに偏見がないのも特徴で、トヨタ・ハイラックスは褒めまくるもののプリウスは低評価。欧州車も同様に平等な批評を展開するのだが、韓国車だけはほぼ毎回、酷評されている。
特に韓国メーカー、ヒュンダイ・アクセントの回では「ヒュンダイ・アクシデントか?」と名前から気に入らない様子で、走行テストでは何もかも「ダメ」という評価に。
最後はクラークソンさんが「こんな車なら私でも作れる」と言い切り、「では、お見せしよう」と自分で作った“車”をスタジオで紹介。壊れた冷蔵庫など粗大ゴミの家電にタイヤらしきものをつけたガラクタだったが、廃家電のモーターを内蔵しており、スタジオで自走して観客の喝采を浴びた。
こうした歯にきぬ着せぬ批評が当然の欧米で、中国車や韓国車が合格点を得るには、まず安易な“パクリ”と、外見だけを繕う虚飾をやめることが必要なのだが…。戦闘機から自動車までコピーと盗用が当たり前の中国・韓国では、まだまだ時間がかかりそうだ。
博多・ワッフル店集団女性暴行事件 容疑者3人の人物像とは (1/2)
(2/2) 11/17/14 (NEWSポストセブン)
福岡県警中央署は11月8日、勤務先のワッフル店で女性客(25)を暴行したとして、集団強姦などの疑いで新賢佑容疑者(33)と伊牟田祐史容疑者(33)を、犯人隠避容疑で同店経営者の博多屋泰典容疑者(34)を逮捕した。
現場は九州最大の繁華街、福岡・天神のど真ん中。女性に人気の高いファンシーな店構えのスイーツ店だった。仕事帰りのサラリーマンたちが焼き鳥やもつ鍋で一杯やっているすぐ近くで、鬼畜たちは25歳の女性に蛮行を働いていた。
現場近くをよく知る人たちは、以前から「変な店だな」と感じていたという。
「店の前でワッフルを女子高生に配っているのを見たことがあります。いつも客引きしている印象で、親しげというよりも女性を品定めするような感じで話しかけていましたね。事件を聞いた人はみんな『やっぱり』といってます」(飲食店勤務の女性)
「店長はイケメン風ですが、必要以上に話しかけてきてやたら馴れ馴れしいと評判だった」(何度か店を利用した女子学生)
繁華街、飲食店、女性一人客、複数の店員による強姦。これらはいずれも、2007年5月に「ペッパーランチ」心斎橋店(大阪)で起きた監禁強姦事件と共通するキーワードだ。
この大阪の事件を真似たかのような事件を引き起こした容疑者3人はどんな人物なのか。10年近く前から知る地元の企業経営者は、「あの3人は遊び仲間ですよ。同世代ということもあってよくつるんでいました。全員結婚しています」と話す。
博多屋容疑者は福岡の私立大を卒業後、2009年に父親から卵焼き屋の事業を引き継ぎ、そのブランドを利用して「玉子焼き職人がこだわった」(同店ホームページより)というワッフルの製造販売を始めた。
店は天神のほか、博多駅近くと福岡県内のモールにも出していて、ネット販売も行なっている。チョコや抹茶、黒ごまなどいろいろな味のワッフルやアイスクリームをサンドしたワッフルなど豊富に取り揃えていたが、目標の売り上げには届いていなかったようだ。また、7月に結婚したばかりで、今月中に初めての子供が生まれる予定だという。
天神店で接客などを行ない、出資もしていたとされる伊牟田容疑者は身長170センチくらいのがっしりとした体つきで女によくモテたという。ただ、酔うと他人に喧嘩をふっかけたり、近くにあるものを壊したりと酒癖の悪さを露呈することが度々あった。
新容疑者は天神店の店長だった。「数年前に大麻取締法違反で有罪判決を受けた経歴があったことから、今回の事件も薬物絡みの可能性が浮上している」(捜査関係者)という。
「天神の店は、ワッフルを売るというよりも仲間が集まって飲んで遊ぶための店という感じでした。だから、ナンパ感覚で客引きしていたのではないですか。その悪ノリが過ぎたのが今回の事件だと思います」(前出の地元経営者)
面識もない女性客にいきなり襲いかかるという卑劣な行為はとても「悪ノリ」で済まされるものではない。ペッパーランチ事件では、元店員が大阪地裁で懲役10年の実刑判決を受けて服役中。元店長は求刑を上回る判決を不服として大阪高裁でも争ったが、懲役12年の判決は変わらなかった。
捜査は始まったばかりだが、容疑者の所業が明らかにされ、法の裁きを受けることが待たれる。
※週刊ポスト2014年11月28日号
問題に触れない事実は、何か言えない事が隠されていると言う事か?
腹腔鏡、保険手術と偽る…診療報酬を不正請求か 11/16/14 (読売新聞)
群馬大学病院(前橋市)で腹腔鏡(ふくくうきょう)を使う高難度の肝臓手術を受けた患者8人が死亡した問題で、病院側が保険適用外の手術を保険がきく手術として診療報酬を不正請求していた疑いのあることが、遺族らの証言などでわかった。
病院では、8人を含む保険適用外の56人の事例について調査を進めており、不正に受け取っていたと判明すれば健康保険組合などの保険者に返還するとみられる。
腹腔鏡を使う肝臓の切除手術は、比較的実施しやすい「部分切除」などについては2010年4月から保険適用されている。しかし、難易度の高い「区域切除」などの手術の場合は保険適用が認められていない。
14日開かれた記者会見で群馬大病院は、死亡した患者に行った手術がすべて保険適用外の難しい手術であることを認めた。保険適用外の手術は通常、費用は研究として病院持ちで行うか、自費診療として患者側が全額支払う形になる。
昔は、このような問題は指摘されなかったのか?それとも今回が特別なのか?事実を知っている人達しか本当の事はわからない。
東工大の元教授逮捕…研究資金1490万円詐取 11/15/14 (読売新聞)
実験用試薬などを架空発注して大学から研究資金約1490万円をだまし取ったとして、警視庁は15日、東京工業大大学院生命理工学研究科の元教授、岡畑恵雄容疑者(67)(川崎市麻生区)ら4人を詐欺容疑で逮捕した。
ほかに逮捕されたのは、元同大職員・三津川和子(63)(横浜市緑区)、化学製品卸会社「東光化成」(本社東京都)役員・吉田耕司(66)(東京都世田谷区)、同社の元社員・鈴木克行(69)(埼玉県春日部市)の3容疑者。
発表によると、岡畑容疑者らは2009年1月から10年1月の間、実験用の試薬などの名目で架空発注を繰り返し、研究資金約1490万円をだまし取った疑い。大学から東光化成の口座に振り込ませていた。
福岡女子大が公立大学法人である以上、「法の下の平等をうたう憲法14条に反する」との指摘にどのように対応するのだろうか?男女平等とか、民間の会社でさえも女性幹部を登用を推奨している現状で、逆の場合は許されるのか?面白い焦点だ。男女平等を唱える女性団体はどのようなコメントをするのだろうか?福岡女子大の歴史など関係ない。もし歴史を重要視するなら、これまでの歴史を尊重し、男女平等など必要ないと言う事になる。男女平等を唱える女性団体の主張にも矛盾が出てくる。
福岡市の男女平等に対する姿勢も問われる。もしかすると、福岡女子大から男女共学へと変わるきっかけとなるかもしれない。
「県立女子専門学校としての開校以来、91年にわたって女子教育を進めてきた歴史や理念がある。今後も女性リーダーの育成を目指した教育を進める」との理由は私学では通用すると思うが公立では通用しないと思う。男性リーダーの育成を目指した教育は否定されるのに、女性リーダーの育成を目指した教育は許されるのか?男性リーダーの育成を目指した教育を基本とすれば、女性の入学は拒否できるのか?もし、裁判で争われたら、女性の入学拒否の主張は負けるであろう。最近は、特に女性を強調する環境の中で、福岡市はどのように対応するのか興味深い。
「公立女子大行きたい」男性、出願不受理は違憲と提訴へ 11/14/14 (読売新聞)
福岡市の公立大学法人福岡女子大から入学願書を受理されなかった20代の男性(福岡県在住)が大学側を相手取り、受験生としての地位があることの確認を求めて福岡地裁に提訴する。男性は「男性を受験させないのは法の下の平等をうたう憲法14条に反する」と主張。不受理決定の無効の確認と慰謝料40万円の支払いも求めるという。
男性側は「運営に広い裁量が認められる私立ならともかく、国公立の教育施設が受験資格に性別を設けるのは不当」と主張。男性の代理人を務める弁護士によると、国公立の女子大の違憲性を問う初めての訴訟になる見通しという。
訴えによると、男性は今月、栄養士の免許の取得に向けたカリキュラムがある福岡女子大の「食・健康学科」の社会人特別入試に出願したが、不受理とされた。福岡県内の国公立大でこうしたカリキュラムがあるのは福岡女子大だけで、男性は「公立に進めないと経済的な理由で資格取得を断念せざるを得ない」と主張。入学願書の不受理は憲法14条や26条(教育を受ける権利)、教育基本法にも反しているとしている。
福岡女子大の担当者は取材に「県立女子専門学校としての開校以来、91年にわたって女子教育を進めてきた歴史や理念がある。今後も女性リーダーの育成を目指した教育を進める」としたうえで、訴訟については「訴状を見ていない段階でコメントはできないが、きちんと対応したい」と話している。(長谷川健)
日本の対応が甘いし、遅い。それがこの結果だ。
「塚田部会長は、無許可で操業をした場合の罰金の上限について、日本の領海では今の400万円から3000万円に、排他的経済水域では今の1000万円から3000万円に、大幅に引き上げる方向で調整している」(11/13/14, NHK)。
韓国は罰金を重くしているし、「フィリピンの裁判所は5日、昨年4月に違法操業の疑いで逮捕された中国人漁民12人を有罪とし、船長に禁固12年、他の乗組員に禁固6~10年の判決を下した。」 (08/06/14、レコードチャイナ)
今回のようになる前に罰金を上げるべきだった。また、海上保安庁の船は中国漁船が領海内へ入らないような行動を取るよりも逮捕するべきだった。
福岡地裁・丸田顕裁判官が外国人漁業規制法違反(領海内操業)の罪に問われた中国籍の男性に無罪を言い渡した。(10/15/14、産経新聞)日本の司法制度は性善説を基本にしているのか知らないが、外国人に対して甘い。外国人に対して犯罪を犯す事を誘惑している、又は犯罪を犯してもたいした問題でないと勘違いさせると思う。日本が国際的な国であり、外国人を受け入れることが出来ると思っているのなら抜本的な法改正が必要だ。
マグロの違法漁獲に関して言えば、海上で運搬船に移し替えるのである。どこで取れたマグロであるのかなんてわからない。
参考情報:マグロ漁業と便宜置籍船FOC 2007-06-08 (マグロは食卓から消えたか)
需要があり、儲かるのであればマグロを売りさばくことが出来るのなら、珊瑚も同じだと思う。儲かれば裏社会だって動くはず。規制がかなり厳しくなったが原産国の分からないダイヤだって売りさばくことが出来る。サンゴだって同じだと思う。山田吉彦・東海大海洋学部教授の考え方は甘いと思う。本物であり、買う人がいれば売れるのが現実。マネーロンダリングにビットコインが使われている疑いもある。この世の中には日本のような社会だけではない。この事を理解しないと適切な対応は出来ないと思う。
サンゴ密漁:中国船団の謎 日中首脳会談当日に急減 (1/4)
(2/4)
(3/4)
(4/4) 11/14/14 (毎日新聞)
◇17隻(9月15日)→42隻(10月1日)→212隻(10月30日)→141隻(11月10日)
東京都の小笠原諸島周辺などに多数の中国漁船が押し寄せてから2カ月が経過した。突如として現れた大船団に海上保安庁や水産庁はおおわらわだ。「密漁」と呼ぶには大胆すぎる行動の背景に、一体何があるのか。中国サンゴ密漁船団の謎を探った。
10日、日中首脳会談の当日。海上保安庁は、小笠原上空から「ある異変」を確認した。
2日前には200隻を超えていた中国漁船が141隻に減り、しかもうち76隻が小笠原の父島や母島を離れて領海から遠ざかっていたのだ。海保幹部は「積んできた燃料と食料が底を突いたからだろう」としていたが、その後、中国政府が船を割り出し、呼び戻していることが本紙の取材などで明らかになった。
そもそも海保が最初に中国漁船団17隻を上空から確認したのは9月15日だった。その半月後の10月1日には2倍以上の42隻。さらに同30日には伊豆諸島周辺を含めて最多の212隻を確認した。この海域に中国船が数隻で来たことは過去にもあったが、200隻以上の漁船が一度に押し寄せたのは初めてだ。
「中国で赤サンゴは縁起がいいとされ、歴代皇帝の装飾品などに珍重されました。中国では2010年に水産資源を保護するため海島保護法が施行され、サンゴの捕獲やサンゴ礁の破壊が禁止された。その結果、供給が不足し、価格が高騰。一獲千金を夢見る漁民が小笠原諸島まで来るようになった。因果関係は明確です」。中国事情に詳しい遠藤誉・東京福祉大学国際交流センター長がそう解説する。
赤サンゴの価格はここ3、4年で急騰し、日本近海で取れた最高級の深紅のサンゴは1グラム当たり最高1万元(約19万円)と、金の約40倍。昨年、日本近海で赤サンゴを密漁し、2億元(約38億円)分を売り抜けた船長がいるといううわさが中国ではまことしやかに伝えられる。それにしても10月中旬以降の中国密漁船の急増は異常だが……。
遠藤さんは「無罪判決がきっかけになった」とみる。福岡地裁は10月15日、長崎県五島市沖でサンゴを取って外国人漁業規制法違反の罪に問われた中国人船長に対し「日本の領海だと認識していなかった」と無罪を言い渡し、中国国内でも報じられた(判決は確定)。
「中国で捕まれば懲役5年から10年の刑になり、家族の生活が成り立たなくなる。日本では捕まっても無罪、有罪でも罰金刑で釈放される。これでは『泥棒さん日本にいらっしゃい』と言っているようなものです」。だが、小笠原周辺で派手に密漁したサンゴを中国に持ち帰って売りさばけるのだろうか。
遠藤さんが謎解きをする。「福建省、浙江省の信頼できる知人を通して独自に調べたところ、これまで日本近海で取った赤サンゴを漁民たちは海上で密売業者に売り渡していました。携帯電話でサンゴの写真を撮り、それを業者にメールで送り、値段交渉がまとまれば海上で手渡す。サンゴが手元になければ、捕まる可能性は格段に低くなる」
一方、中国などの海洋政策に詳しい山田吉彦・東海大海洋学部教授は「数隻ならともかく200隻以上の密漁船が取ったサンゴ全てを海上で売りさばくことができるのか。どれほどの量、金額か想像もできない」と首をかしげる。
そのうえで船団の目的について大胆な仮説を披露する。「密漁船も数隻は交じっているだろうが、大部分は別の意図を持った船団でしょう。漁民を先兵として使うのは中国の常とう手段です。日本の海保が専従チームを編成して尖閣諸島の守りを固めたため、尖閣以外の海域に密漁船団を送り込み、海保を揺さぶったのではないか。APEC(アジア太平洋経済協力会議)での日中首脳会談を巡る尖閣の交渉で譲歩を引き出す駒にした可能性もある」
政府が尖閣3島を国有化した12年9月以降、尖閣諸島周辺で中国公船による領海侵入が急増し、海保は全国から応援の巡視船を派遣してきた。15年度末までに巡視船12隻、600人体制の尖閣専従チームを編成することが決まり、最初の2隻が10月25日に沖縄県石垣市に就役している。
小笠原では、海保は水産庁の取り締まり船2隻と合わせて5隻程度で密漁船の取り締まりにあたるが、逮捕できた船長は6人。逮捕後も法令に基づき洋上で釈放している。尖閣と小笠原の「二正面作戦」が海保の足を引っ張る。
また、逮捕された中国人船長6人のうち1人は、昨年3月にも沖縄県の宮古島沖でサンゴ密漁中に逮捕され、罰金を払い釈放されている。昨年1年間にサンゴ密漁で海保に逮捕された中国人船長は3人だけだ。山田さんは「偶然にしても不自然でしょう。他にも福建省、浙江省といった広い地域から出てきたはずの漁船が、同じ青色の網を使っているのも不可解です」と中国当局の関与を疑う。
一方、前出の遠藤さんは中国政府の関与説について「何のメリットがあるのか。密漁はどこからみても犯罪行為。おまけに福建省、浙江省は習近平国家主席が治めていた地域です。国際社会の注目を集めるAPECの前に指導者の体面を傷つけるようなことを中国政府がするとは思えない。事実中国は日本に取り締まりの協力を求めている」と反論する。
◇過去の先兵・漁民と違いも
中国政府関与説が一定の説得力を持つのは、中国漁民が「先兵」として使われた前例があるからだ。1978年4月12日未明、中国漁船約200隻が尖閣周辺に集結し、数十隻が領海侵犯を繰り返していると海保から外務省に連絡が入った。当時、外務省中国課で海保からの電話を受けた故杉本信行元上海総領事は著書「大地の咆哮(ほうこう)」で、海保の飛行機や巡視船が中国側の無線を傍受したところ、山東省煙台の人民解放軍基地と福建省アモイの軍港の2カ所から中国漁船に指示が出ていたと明かしている。
だが、今回の小笠原周辺と78年の尖閣の漁船団について宮本アジア研究所代表の宮本雄二・元中国大使は「本質的に異なる」とする。「中国は尖閣で領有権を主張しているが、小笠原では主張していません。これまで中国は、領有権など自らの主張を固めるための行動しか取っていません。今回は現場の漁民の利害関係で動いているとみていいでしょう」と説明する。
78年当時、日中は平和友好条約の締結交渉を続けており、日本側はあえて敏感な尖閣で問題を起こす中国側の真意をはかりかねていた。「あくまで私の仮説だが」と前置きして宮本さんが詳しく解説する。「復権したばかりのトウ小平に不満を持つグループが揺さぶりをかけようとした。中国では指導者に不満を持つグループが、領有権主張など国内的には正しくとも外交的には問題になる行為で揺さぶりをかけるパターンが続いています。今回の小笠原のケースは中国国内でも違法とされる行為。為政者に近い地位にいる人が考える揺さぶりではないでしょう」
中国の政治の透明性はまだ低く、複数の仮説が存在しうる。だが、政府の対中政策は、仮説の検証を待っていられない。89年の天安門事件でも、権力闘争の内幕など真相が明らかになってきたのは最近のことだ。
「当時、私も必死に天安門事件を追いました。現地にスタッフを派遣し、CIA(米中央情報局)やMI6(英秘密情報部)など世界中の情報機関と協力したが、真相は見えてこなかった。だが、政府はその時々の状況判断に基づき政策を立案しなければならない。状況判断を間違えた場合は謙虚に修正していく。対中政策では特に、政策の修正メカニズムを整えていくべきです」
政府関係者によると、外務省と海保は小笠原では中国政府の関与を示す証拠はないと判断し、中国には遺憾を表明し、取り締まり強化を求めるにとどめている。中長期的には罰則強化など国内法改正で対処していく方針だ。中国側も「中国は赤サンゴの違法採取行為を禁止しており、関係部門は法執行を強化していく」(外務省報道官)と歩調を合わせ、福建省、浙江省当局も取り締まりの姿勢を見せる。
だが、台風19号、20号と同時期に北上し、両国の関係改善と合わせるように減少した大漁船団を巡る謎は残されたままだ。13日には再び145隻が確認されている。今後、中国当局が帰港した漁船を摘発するかどうか。小笠原周辺を離れた中国漁船から目が離せなくなってきた。【浦松丈二】
「群馬県庁で行われた会見で、病院側は、この助教が手術に関し、(1)患者への十分な告知と同意(インフォームドコンセント)(2)院内審査組織への申請(3)肝機能チェックなどの術前検査-の3点について、極めて不十分だったことを認めた。申請や検査について助教は『必要ないと思った。認識が甘かった』と話しているという。」
病院のシステムにも問題があるが、執刀した40代の助教は大きな問題がある。このような医者であれば問題を起こしても当然だと思う。ただ、腕が良ければプロセスに問題があっても患者は死亡しなかったであろう。このような事故を防ぐためにプロセスが重要とされているし、プロセスを順守する事が要求される。
調査を徹底的に行えば問題に気付いていた人は見るかるかもしれない。しかし、問題を放置した、又は、見逃したと批判されるかもしれないので見るけるのはかなり難しいと思う。
「認識が甘かった…」 執刀した40代助教が怠った3つの事前準備 (1/3)
(2/3)
(3/3) 09/08/14 (産経新聞)
腹腔鏡(ふくくうきょう)を使った肝臓手術で患者8人が術後4カ月以内に死亡していたことが判明した群馬大病院(前橋市)。いずれも40代の助教(男性)が執刀しており、14日、群馬県庁で行われた会見で、病院側は、この助教が手術に関し、(1)患者への十分な告知と同意(インフォームドコンセント)(2)院内審査組織への申請(3)肝機能チェックなどの術前検査-の3点について、極めて不十分だったことを認めた。申請や検査について助教は「必要ないと思った。認識が甘かった」と話しているという。
この助教が所属する第二外科が平成22年12月から今年6月までに行った腹腔鏡を使った肝臓切除手術は92例。亡くなった8人の執刀も含め、ほとんどを、助教が担当した。92例中、高難度とされる保険適用外の手術は56例あり、死亡した8例も適用外手術だった。
厚生労働省によると、腹腔鏡を使った肝臓の切除手術は比較的実施しやすい「部分切除」などに限り保険適用される。高度な技術が必要な「区域切除」などは有効性や安全性が十分に確認されていないとみなされ保険適用外となっている。
このため保険適用外手術を行うには、厚生労働省への先進医療の届け出や院内審査組織への申請が必要だが(一部内科治療は不要)、他大学と連携して行った7例の手術を除き、助教は申請していなかった。
会見で、野島美久病院長は「(助教は)申請手続きが必要と認識していたが、認識が甘かった。申請したら止められると思い、故意に申請を怠ったわけではない」としたが、ではなぜ必要と認識していた申請を怠ったのか、釈然としない。
また、助教が患者へのインフォームドコンセントを行ったかについて、病院側は「(本人は)患者に保険適用外手術であることや先進医療であることは伝えたと話している」としたが、カルテなどの記録には、助教が患者に説明した旨の記載はなかったという。
厚労省や院内審査組織への申請が必要な高度な手術であることを助教が患者に伝えていたかについても、病院側は「これから確認する」。仮に院内審査組織に助教が申請していた場合、手術を許可していたのかとの問いには「何ともいえない。年齢や疾患のステージなどを厳密に調べる必要がある。まだ、調査は及んでいない」としている。
野島病院長は「問題として(病院側が)認識しているのは術前評価とインフォームドコンセント。診療記録を見た限りインフォームドコンセントは不十分で、肝臓の機能が手術に耐えられるか検査する術前評価も不十分だった」と認めた。
病院側の説明によると、高難度の手術を行う際の術前評価では、肝臓の容量を計算するなどの検査も必要だったが、実施されておらず、外部の専門家からも疑問の声が出ているという。
検査を行わなかったことについて助教は「もう少し簡単な検査で十分という認識で、認識が甘かった。必要ないと思った」などと話しているという。
群馬大病院では、平成17年にも生体肝移植手術で肝臓の一部を提供した女性が手術後に下半身不随となった医療事故が起きており、野島病院長は「同じような事案が起きたことを非常に残念に思う」としている。
8人の中には、術後わずか2週間で死亡した患者もいた。病院側は院内に弁護士や医療事故の専門家など外部から5人を登用した調査委員会を設置、年度内に調査結果をまとめたいとしている。
助教は手術の執刀医から外れたものの今も病院に勤務する。なぜ、ずさんな準備態勢で手術に踏み切ったのか、詳細は調査結果を待つしかない。
◇
腹腔鏡 腹腔鏡は腹部を観察するためのカメラ。腹腔鏡手術では体に数カ所の穴を開け、このカメラとともに手術器具を差し入れ、テレビモニターで内部の映像を見ながら切除や縫合などを行う。開腹手術に比べて患者への負担が少ないため実施が広がっているが、熟練した技術が求められ、ミスによる患者の死亡が後を絶たない。
組織に問題があると常識的な事でも機能しない。問題を把握すると言う事は誰かが責任を取ると言う事。このため把握したくなかったと考えるべきではないのか?
「簡単な手術と言われたのに…」術後悪化の一途 11/14/14 (読売新聞)
高難度の腹腔鏡(ふくくうきょう)を使う肝臓切除手術の後、患者8人が死亡していた前橋市の群馬大病院。
県内外から患者が集まる北関東の医療拠点で、手術の不適切な実施態勢が明らかになった。病院は院長らが記者会見して謝罪した。病院は遺族への説明を始めたが、遺族の中には、手術後から病院側への不信感と疑問を抱き続けた人もいる。
「大変申し訳ありません」。群馬県庁で行われた記者会見の冒頭、野島美久病院長らは深々と頭を下げた。
今回の問題では、安全性や有効性が確認されていない手術が病院の管理部門に申請されないまま多数行われた結果、8件もの死亡例が積み重なった。
報道陣から「ここまで増える前に、病院として食い止められなかったのか」と問われると、「しかるべき手続きが取られておらず、把握が遅れてしまった。(申請など)執刀医らの認識も曖昧だった」と唇をかんだ。
8月末から調査委員会が調べを進める中で、問題点が次々と明らかになっている。カルテや患者に渡した同意書などからは、手術のリスクや、抗がん剤治療など他の選択肢について説明した形跡がみられないという。永井弥生・医療安全管理部長は「もっと丁寧に説明すべきだが、残された文書を見る限り、それがなされていない」と話した。
◇
「簡単な手術と言われ、夫は望みをかけた。それなのに」。群馬大病院第二外科(消化器外科)で、肝臓がんの夫が腹腔鏡手術を受けて死亡した60歳代の女性は、そう打ち明けた。
女性によると、手術前、担当医から「腹腔鏡手術なら2週間で退院できる」と言われ、「早く退院できるなら」と応じた。
しかし、手術の説明は専門用語が多くて理解しづらく、リスクについて説明を受けた記憶はない。「あの時は、わからなくても、夫の病気を治すことで頭の中がいっぱいで、先生を信じて任せるしかなかった」と振り返る。
術後、容体はどんどん悪化。担当医は多忙で、夫の経過について説明を求めても対応してもらえないことが多く、女性は不信感を募らせていった。
中国船主所有の貨物船・ニュースター号(シエラレオネ船籍)はロシアの停船要求を無視して、撃沈された。
2009年2月20日、環球時報によると、ロシア外交部は19日、中国貨物船「新星号」へのロシア国境警備隊による発砲と同船撃沈について声明を発表。同国国境警備隊の発砲は合法的なものであり、「新星号」の沈没と行方不明になった乗組員に対する全責任は同船の船長が負うべきだと主張した。 19日付のロシア「インタファックス通信」によると、ロシア外交部アンドレイ・ネストレンコ報道官は「この事件が引き起こした悲劇について我々は深い遺憾の意を表明する。だがすべての責任は『新星号』船長にある」と発言。「『新星号』はロシア領海を違法に通過しており、我が国の国境警備隊が13日早朝に同船に対し停船を要求したがこれを無視。その後も警備隊のあらゆる呼びかけにも応じなかったため、現地時間午前10時10分に威嚇発砲。だが同船はなおも前進を続けた」
日本はそこまでしなくても良いが、現状は甘すぎる。
中国サンゴ漁船の船長逮捕 6人目 11/13/14 (NHK)
13日午前、小笠原諸島沖の日本の排他的経済水域内を航行していた中国のサンゴ漁船が巡視船の停船命令を無視したとして、33歳の中国人船長が漁業法違反の疑いで逮捕されました。
この周辺の海域で違法に操業していたなどとして中国のサンゴ漁船の船長が逮捕されたのは、先月以降これで6人目です。
横浜海上保安部によりますと、13日午前9時ごろ、小笠原諸島の父島の北西およそ40キロの日本の排他的経済水域内で、中国のサンゴ漁船が航行しているのを巡視船が見つけました。
巡視船が立ち入り検査のため停船命令を出しましたが、漁船が無視したため、海上保安官が乗り移って停船させ、中国人船長の林新財容疑者(33)を漁業法違反の疑いで逮捕しました。
海上保安部によりますと、船内からはサンゴ漁に使う網などの道具が見つかりましたが、サンゴは見つかっていないということです。海上保安部は、ほかの乗組員13人からも事情を聴いて、違法な操業をしていないか調べています。この周辺の日本の領海内や排他的経済水域内では、先月以降、中国のサンゴ漁船が違法に操業したり停船命令を無視したりして船長が逮捕されるケースが相次いでいて、逮捕されたのはこれで6人目です。
領海の外に出るように呼びかけずに、違法操業を発見したら逮捕すればよい。
横浜まで曳航せずに処分できるように小笠原諸島のどこかに臨時の出張所みたいなものを設置出来るように法改正をおこなったほうが安上がりではないのか?
まあ、時が経ち、メディアが報道しなくなるまでの我慢と思っているから現実的な対応をしないのであろう。
サンゴ“密漁船”依然100隻超 11/13/14 (NHK)
小笠原諸島沖でサンゴを密漁しているとみられる中国漁船は、減る傾向にあるものの、依然、100隻以上が確認されています。
海上保安庁は、巡視船が漁船に対し夜を徹して領海の外に出るよう呼びかける映像を公開しました。
小笠原諸島の周辺で中国漁船がサンゴを密漁しているとみられる問題で、一時、200隻を超えていた漁船の数は、今週およそ60隻に減りましたが、海上保安庁が12日に確認したところ、再び増加して117隻に上り、警戒が続いています。
海上保安庁は12日に小笠原諸島沖の日本の領海内で巡視船が警戒を続ける様子を撮影した映像を公開しました。
このうち午前3時ごろの映像では、真っ暗な海に、明かりをつけた10隻ほどの漁船の姿が浮かび上がり、このうち1隻を巡視船がサーチライトで照らし、直ちに領海の外に出るよう中国語で呼びかけています。
また、漁船は午前9時ごろになっても領海内で航行を続け、巡視船が接近し、直ちに領海の外に出るよう中国語で呼びかけています。海上保安庁によりますと、こうした漁船への呼びかけは、この1か月余りの間におよそ4500回に上り、1日平均100回を超えています。
いったん島から遠ざかった漁船の一部が再び島の周辺に戻るケースもあることから、海上保安庁などは警戒を続けることにしています。
職を探している退職した60歳未満の元海上保安官にとっては棚から牡丹餅だな!中国に足を向けて眠れないかも?
入札を予定している造船所も中国に感謝しているだろう。大型巡視船10隻の発注はおいしい。
「すぐにでも巡視船に」海保が150人再雇用へ 11/13/14 (読売新聞)
海上保安庁は要員増強のため、退職した60歳未満の元海上保安官を150人再雇用する方針を決めた。
沖縄・尖閣諸島警備の専従部隊創設などを控え、異例の大量募集となる。12月中に採用試験を行い、来年1月1日付での“スピード採用”となる。
海保は、来年度末までに尖閣諸島警備の専従部隊を創設する計画で10隻の大型巡視船の新造を進めており、すでに3隻を投入した。さらに、小笠原諸島でのサンゴ密漁問題も発生したことなどから、巡視船の乗組員などの要員確保が急務となっている。海保では2010年から退職者の採用を行っているが、これほど大規模の募集は初めて。海保幹部は「即戦力で、すぐにでも巡視船に乗れる。早く態勢を強化したい」と話した。
誰が判断しているのか知らないが、多くの国民が知らないだけで問題を放置しているケースは多い。
サンゴ密漁問題 危機実感、問われる国民と政府対応 11/13/14 (産経新聞)
小笠原諸島周辺海域での中国漁船によるサンゴ密漁問題で、日本政府と国民はようやく、日本が島国であり、「島」とそれを取り巻く「海」が、国防面でいかに重要かということを改めて「実感」したようだ。
対馬、五島列島、佐渡島…など、日本は多くの国境離島を抱えるが、その離島は経済疲弊による過疎化が激化するなど、多くの問題に頭を悩ませている。燃料費の高騰や過疎化による漁業人口の減少もその表れだ。
その隙を突くような中国漁船や韓国漁船による違法操業、密漁は何も今に始まったことではない。対馬や五島列島などでは日常茶飯事に起きている。
中国漁船の避難も同様だ。一昨年には106隻もの漁船が五島列島に避難、地元住民に不安だけでなく、過去には地元漁民の網を壊したり、さまざまな問題を引き起こしている。しかも、損害賠償にまで発展しながら十分な補償を確保できず、結局は地元漁民が泣き寝入りせざるを得なかったという現実もある。
当時、日本国民は、そして日本政府はどういう対策を講じたか。
五島列島の漁民は「五島でもサンゴの密漁はあった。今回は場所が変わっただけ。ただ、規模が違う」という。中国漁船は新たな狩場を求めて“侵略”を続けているのである。
小笠原諸島が直面している危機は、当然、予想された結果だ。島国であるわが国は、言いがかりとしかいいようのないロシア、韓国、中国の対応に一喜一憂させられてきた。北海道・利尻富士町の長岡俊裕町議(57)は利尻、礼文両島の現状を「さまざまな船が航行しているという事実がある。この地域はロシアを相手に潜在的な危機感がある」としながら、「表面上、何も起きていないように見えるから、目が届かない」と警鐘を鳴らす。
今後、国境離島とそれを取りまく海が標的にされる可能性は高い。わが国の国家防衛の最前線基地として大きな役割を担う国境離島とそれを取り巻く環境整備を根本的に講じるべきだ。小笠原周辺海域で起きている“事件”は、これまで、国防を強調しながらも具体的に何ら手を打ってこなかったことの証左である。
今、自衛隊配備の強化、海上保安庁の強化、そして経済活性化による過疎化防止など、主権国家としての日本政府、日本人がどう対応するか、真価が問われている。解散なんかしている余裕はないはずだが…。(編集委員 宮本雅史)
「同当局では、以前も日本から提供を受けた密漁船の写真を元に船主の特定を進めたが、船名が偽装されていることも多かった。登記された本物の漁船が別の場所で発見されたこともある。」
漁船ではないが、中国船の偽装事件が過去に起きている。
「同船のもつ船舶営業運輸証の営業範囲は『国内沿海および長江中下流域の各港間の普通貨物船による運輸』に限られている。同船は、国内関連機関の検査に対応するため、国内港湾監督部門のスタンプと偽造印を使用し、虚偽の航海日誌と運行日誌を作成していた。また、海外からニセの外国船舶証明書を購入したほか、中国の積出港海事局が発行する「国際航行船舶出口岸許可証」も偽造しており、課税対象の輸出貨物を国内から無許可で海外に運び出したあと、外国の港湾ではモンゴル籍の船舶と偽って申請を行い、税関の監督や管理を逃れて密輸を行った。」
「偽造した船員手帳(旅券に相当)を乗組員に持たせた中国からの貨物船が相次いで日本に入港していることが、海上保安庁の調べで分かった。中国国内を航行する「内航船」として中国を出航、沖合で船名や旗を変えて第三国籍の「外航船」に“変身”。国際航海に必要な船員手帳の偽物も用意する手口という。・・・海保によると、中国の内航船の船員は手帳がいらない。輸出の急増で外航船と外航船員が足りなくなったため、内航船が外国船籍を取得して、事実上の「二重船籍」となり、偽造船員手帳を持たせた内航船船員も乗せているという。中国は国内法で外国との二重船籍を禁じている。海保は船籍情報などを中国に送り、中国国内での取り締まり強化を求める方針だ。・・・名古屋港に三月七日に入港した貨物船でも同様の手口が判明、中国人四人が摘発された。これらを含め三月末までに、モンゴルなどに船籍を置き、中国の会社が運航管理する「便宜置籍船」計六隻の中国人船員計二十七人が同様の偽造船員手帳や偽造海技免状を持っていたとして、海保は入管難民法違反容疑などで摘発した。」
船名や船籍の偽装は新しい事でもないし、海上保安庁もこれぐらいの手口は知っているはず???なぜ、問題を最近まで放置していたのか疑問!
問題は簡単には解決しない。いろいろと抜け道があるし、チェックされなければ違法であるのか、偽装船であるのかもわからない。一隻、一隻、地道に逮捕するしかない。漁船の燃料がなくなるまで持久戦とか海保はテレビで言っていたが、海保の船の燃料、食料、その他そして海保職員の給料を考えると、中国漁船以上に日本は税金を消費していることになると思う。はやく法改正で罰金を3倍か5倍に変更し、逮捕するべきだと思う。中国船、中国偽装船、二重国籍船、そして外国船でも関係なく逮捕すればよい。
サンゴ密漁船、中国浙江省が呼び戻し始める 11/13/14 (読売新聞)
【上海=鈴木隆弘】東京・小笠原諸島の周辺海域などで希少な「宝石サンゴ」を中国漁船が密漁している問題で、中国浙江省当局が密漁船を割り出し、日本の海域から呼び戻しを始めたことが12日、当局者への取材で分かった。
同省漁業管理当局などによると、今月上旬以降、密漁船の船主の特定を行い、日本の海域にいる一部の漁船と連絡がとれた。中国に戻るよう指示したが、戻るまで日数がかかり、引き返したかどうかは不明だ。
同当局では、以前も日本から提供を受けた密漁船の写真を元に船主の特定を進めたが、船名が偽装されていることも多かった。登記された本物の漁船が別の場所で発見されたこともある。
一方、福建省のニュースサイト「海峡法治在線」は12日、同省福安市の検察当局が、尖閣諸島(沖縄県)の周辺などで今年2~6月、赤サンゴを密漁した4人を起訴したと報じた。取り締まりを進めていることをアピールする狙いとみられる。
サンゴ密漁 政府与党が一体となり対処 11/13/14 (NHK)
小笠原諸島の周辺で中国漁船がサンゴを密漁しているとみられる問題で、西川農林水産大臣は、自民党の水産部会のメンバーらと会談し、引き続き政府与党が一体となって事態に対処する方針を確認しました。
西川農林水産大臣は12日午後、自民党の秋葉外交部会長や塚田水産部会長らと会談し、議員立法として近く提出される違法な操業に対する罰金を引き上げるための法律の改正案について説明を受けました。
この中で塚田部会長は、無許可で操業をした場合の罰金の上限について、日本の領海では今の400万円から3000万円に、排他的経済水域では今の1000万円から3000万円に、大幅に引き上げる方向で調整していると伝えました。
これに対して西川大臣は、「罰金の引き上げについては全員が賛成だと思うので効果を発揮するようわれわれも期待している。サンゴが取られたあとがどのような状況になっているかということも国民に知らせるべきだと思っているので、そうした調査も含めて対応していきたい」と述べ、引き続き政府与党が一体となって事態に対処する方針を確認しました。
「小笠原諸島の周辺海域などで希少な『宝石サンゴ』を中国漁船が密漁している問題で、浙江省象山県の漁業管理当局の幹部は11日、読売新聞の取材に応じ、同県の漁港からサンゴ漁船数十隻が日本の海域に出ていることを認め、『戻れば厳しく処分し、再発防止のため漁船を破壊する』と明言した。」
地方政府の浙江省象山県の漁業管理当局の幹部の言葉。そして、約束を守るかは疑問。賄賂や汚職がはびこる中国。そして、逃げ道もある。中国へ帰らず、日本で違法操業が確認された漁船をブラックリストに挙がっている国籍に登録する事だ。 典型的な例が、
カンボジア籍船だ。カンボジア船籍に漁船を登録し、違法操業を続ける。このケースはヨーロッパ(EU)で認識され、EUによる制裁措置まで行われている。日本でもブラックリストに挙がっている国籍を利用して国際条約を守らない逃げ道が利用されている。結果として、頻繁に海難を起こしている。
先の先を読んで対応しなければならない。後手に回るのは愚かな行政や政府。日本政府はすみやかに罰金を3倍か5倍に法改正し、逮捕の強化を行うべきだ。カンボジア船籍に漁船を登録し、違法操業を続けるケースによるEUによる制裁措置を考えれば理解できると思うが、問題は簡単には解決しない。相手は規則を守る意思はない事を理解して出来るだけ現状の問題に取り組む必要がある。
「戻れば漁船を破壊」サンゴ密漁に中国当局 11/12/14 (読売新聞)
【象山(中国浙江省)=鈴木隆弘】小笠原諸島の周辺海域などで希少な「宝石サンゴ」を中国漁船が密漁している問題で、浙江省象山県の漁業管理当局の幹部は11日、読売新聞の取材に応じ、同県の漁港からサンゴ漁船数十隻が日本の海域に出ていることを認め、「戻れば厳しく処分し、再発防止のため漁船を破壊する」と明言した。
ただ、サンゴを採取した密漁船は漁港に戻ることは少ないとみられ、幹部は「摘発が極めて難しいのも事実だ」と語った。実際にどこまで厳しく取り締まれるかは不透明だ。
同当局によると、地元漁民の証言から、日本の海域へサンゴ漁に向かった漁船がいることを確認した。今後、戻った漁船からサンゴ採取の網が見つかれば、漁船を押収して破壊する措置を取る。漁民がサンゴを所有していれば、刑事処分を行う方針だ。今月7日、浙江省政府が緊急会議を開き、サンゴ密漁船を厳しく取り締まることを確認している。
民事再生法の適用申請で交付金の不適正使用による返金は免除か、それとも破産へ進むのか?
「DIOジャパン」破綻、民事再生法の適用申請 11/12/14 (読売新聞)
国の緊急雇用対策として東北を中心にコールセンターを開設し、一部で賃金未払いを起こしていた「DIOジャパン」(東京)が12日、10月30日付で民事再生法の適用を東京地裁に申請し、受理されたと発表した。
負債総額は約4億円。
発表によると、宮城県気仙沼市を除く15か所のコールセンターを運営する各子会社も自己破産を申請した。帝国データバンクなどによると、DIOジャパンは東日本大震災後の2011年度から、被災地の失業対策などとして国の交付金で各地にコールセンターを設立したが、受託業務が伸びずに資金繰りが悪化していたという。
厚生労働省は、交付金の不適正使用の疑いがあるとして各自治体に調査を指示している。
元国税局職員であればどのようなケースだと違法であっても摘発されないか、どの程度までだったら見逃されるのか、実際に職員達が放置するケースなどに精通していてもおかしくない。違法であっても摘発されない、又は見逃してもらえる範囲であれば、違法行為を行った方が得、そしてその情報を上手く利用すればお金になると考えても不思議ではない。今回は運が悪かったのか、違反の度が過ぎたのか知らないが、そのようなことではないのだろうか。国税OBらが逮捕されるのは内部情報や国税による行動パターンに精通しているからではないのだろうか?そして「違法に成功=即、お金になる」となる関係が成り立つからではないのか?
開運商法で6400万脱税容疑、国税OBら逮捕 11/12/14 (読売新聞)
開運グッズや祈とうサービスなどで得た所得を隠し、法人税約6400万円を脱税したとして、大阪地検特捜部は11日、大阪市淀川区の通信販売会社「アドライン」(解散)の実質的経営者・河本大介容疑者(34)(大阪市福島区)ら5人を法人税法違反容疑で逮捕し、大阪国税局と合同で関係先を捜索した。
他の4人は、同社担当の税理士だった大阪国税局OBの野上孝行容疑者(47)(大阪府泉佐野市)や同社関係者ら。
発表では、同社は解散した2011年6月期までの1年3か月間に、開運をうたったブレスレットの販売や、高額の祈とうサービスで得た売り上げ約7億6000万円のうち、架空の仕入れを計上するなどして約2億2200万円の所得を隠し、法人税約6400万円を免れた疑い。
「現在検討されているEEZ内での密漁に対する罰金の強化は、一つの対応策であることは確かです。
しかし排他的経済水域におけるサンゴの保護という点では、国際条約との関係もあり、拘留刑を科すことができず、罰金をたとえば現在の上限の3倍に上げたところで、数千万~数十億円もの利益を得るというサンゴ密漁の抜本的な抑止にはならないでしょう。」
上記の考えには賛成できない。サンゴ密漁の抜本的な抑止にならなくとも条件の3倍に上げれば良い。そして出来るだけ逮捕する事。これだけでも効果はあるはずだ。罰金を上げても、法による罰則を重くしても、簡単に逮捕されなければ違法操業を続ける方が良いと判断するだろう。規則が厳しくなり、罰則が重くなろうとも、逮捕されなければ、逮捕されても判決が上限の最高金額の罰金を受けなければ、法改正されてもたいした影響など無い。結局は、結果次第。
中国密漁漁民が恐れているのは中国当局による規制・取締りは同然。中国の制裁は厳しい。日本では覚醒剤で逮捕されても死刑はないが、中国では死刑になる。ただ、中国当局が動く理由がなければ動かない。日本が騒いでも他の国々が興味を示す、又は、協力する理由が無ければ大きな進展はない。韓国警察官と中国漁船の船員が殺し合っている状況に、他の国が介入しているのか?中国と韓国が問題解決に大きく動いているのか?中国当局が動いていれば問題は解決されているはず。なぜ、未だに問題が続くのかを考えれば、簡単には解決できない事は想像できると思う。そうであれば、すみやかに罰金を3倍か5倍に法改正し、逮捕の強化を行うべきである。日中漁業協定を改定などしても、中国当局が本気で規制・取締りをしない限り、リップサービスだけとなると思う。
罰金払って終わり…サンゴ密漁船の罪はなぜ重くできないのか (1/2)
(2/2) 10/29/14 (シェアしたくなる法律相談所)
●なぜサンゴ密漁船は日本に来るのか
小笠原諸島、伊豆諸島などの排他的経済水域(EZZ)を中心として、中国からやってきた漁船が、日本産の赤サンゴなどを密漁している問題はご存じのことでしょう。
背景としては、まずサンゴが貴重で高価であることが挙げられます。小笠原諸島付近で捕れる赤サンゴは、赤色を好む中国では昔から貴重とされており、現在キロ当たり約150万円~200万円するとされています。
更に中国では、自然動物及び植物の乱獲が問題となっており、サンゴの密漁についての取り締まりが厳しくなったことも理由として挙げられます。
中国の刑法では、貴重又は絶滅に瀕している野生動物の捕獲などの罪は、通常5年以上10年以下(悪質だと10年以上)の懲役刑と罰金が科されます。実際、2014年10月22日には浙江省のサンゴ密漁者らに対して、同省の地方裁判所は、中国国内の領海での密漁を理由として、最高懲役6年、罰金最高50万元(約900万円)の実刑判決を下しました。
●懲役などの重い罪を課せばよいのではないか
一方、日本の小笠原諸島沖では、2013年3月に沖縄県宮古島で逮捕されて罰金を払い釈放された船長が10月に再度逮捕されました。この船長も担保金を支払う保証書を記載したため、釈放されています。現在の運用では課されている担保金は、高くて400万円程度と言われており、数千万~数十億円もの利益を得るというサンゴ密漁の抜本的な抑止にならず、上記のような何度も密漁を繰り返しては保証書だけ納めるといった悪質なケースが繰り返される恐れがあります。
この対応について水産省は、罰金及び担保金の金額を増額することで抑止力を上げるとすることを検討しているようです。
しかし、読者の中には、懲役のような自由刑を課して長期間に身柄拘束をして、もって抑止力とするべきだと、考える方も少なくないかもしれません。しかし、結論からいうとこのような対応は国際条約に抵触する恐れがあります。
今回、中国漁船が密漁を行っているのは、主に排他的経済水域(海岸線から12海里を超えて200海里までの水域でEEZと呼ばれます)の範囲となります。
排他的経済水域というのは、国の公権力と、海を自由に航海する権利との調整のために生み出された水域であって、200海里内の沿岸の国の公権力は及びますがその行使できる公権力には制限があります。
このEEZにおける漁業の取締については、日本も批准している国連海洋法条約が方針を定めています。この中では、
1…許可なく漁業をする船を拿捕しても「合理的な保証金の支払又は合理的な他の保証の提供」があった場合速やかに釈放しなければならない、
2…関係国の合意がない限り拘禁、その他のいかなる形態の身体刑も含めてはならない
と規定されています。
したがって、先述の懲役刑などを設定すればいいではないかというアイディアを実現することは、条約の2の規定に抵触することになります。
また、保証金は「合理的な金額」とされているため、極端な話、罰金の金額を何億円などとすることもできないわけです。なお、領海内(12海里内)の外国人の漁業は、外国人漁業規制法というものがあり、懲役刑も規定されています。
●日本側の対策はかなり難しい
現在検討されているEEZ内での密漁に対する罰金の強化は、一つの対応策であることは確かです。
しかし排他的経済水域におけるサンゴの保護という点では、国際条約との関係もあり、拘留刑を科すことができず、罰金をたとえば現在の上限の3倍に上げたところで、数千万~数十億円もの利益を得るというサンゴ密漁の抜本的な抑止にはならないでしょう。
結局、中国密漁漁民が恐れているのは中国当局による規制・取締りであり、中国側の重い腰を動かすように、この問題についての国際的な場においての継続的な非難を続けるとともに、日中漁業協定を改定するなどして中国側の自国民の取締りを徹底させるようにするしかないでしょう。
*著者:弁護士 東城 聡(高井・岡芹法律事務所。得意分野は、渉外取引・労働事件。特に現在はアジア方面の渉外事件と労働事件に注力している。コンサル出身のノウハウを活かし、積極的に支援を実施。)
事実だったら、ひどいな!
女性の遺体遺棄の事件を新聞で時々見るが、テレビでは犯罪は減っていると言っているが、悪質な犯罪は増えているように思える。
同じ事件だが各社の報道表現の違いで感じ方が違う。
「女性が帰ろうとしたところ、新容疑者が「まだ大丈夫ですよ」などと告げた後、突然シャッターを下ろし、電気を暗くした状態で2人で女性に襲いかかったという。その後、新容疑者は女性を近くのラブホテルに無理やり連れて行き、再び暴行。」(スポーツ報知)
「2人は道を歩いていた女性に声をかけて店に招き入れほかの客がいなくなったあとシャッターを閉めてこの女性が出られないようにして犯行に及んでいたということです。さらに新容疑者は店を出た女性を追いかけ、近くのホテルに連れ込んで再び乱暴した疑いが持たれています。」(NHK)
「警察によりますと、2人は6日午前0時ごろ、福岡市天神の飲食店で、25歳の女性客をシャッターを下ろして閉じ込め、 無理やり乱暴をした疑いがもたれています。さらに、新容疑者は泣いて帰宅しようとしたこの女性を追いかけ、 近くのホテルに連れ込み、改めて乱暴をした疑いももたれています。 」(KBC九州朝日放送)
スポーツ報知の表現だとどうやって近くのラブホテルに無理やり連れて行けるのだろうと疑問に思う。しかし、KBC九州朝日放送の表現だと泣いて帰ろうとした女性を追いかけホテルに連れ込んだと、かなりひどい事をしたと感じる。1人が口を塞ぎ、2人で両サイドを固めればラブホテルに連れて行く事は不可能ではないだろう。1人が口を塞いだまま、もう一人が部屋を取ればいいのだからこれも可能。しかし普通の飲食店(ワッフル)でこんな事が起きるのがと驚く。博多は歓楽街もあるから、思った以上に危ないのかもしれない。危険に遭いたくない女性は夜遅くにうろうろしないほうが良いだろう。
他の情報:
【福岡】ワッフル店「tamago.NY」店員ら、女性客を”強かん”か 11/09/14 (気ままに備忘録 and TIPS)
玉子焼き屋さんのベルギーワッフル「博多屋ワッフルズ」
株式会社ハカタヤフーズ 博多屋 泰典 (YouTube)
博多屋ワッフルズ天神店の社長・博多屋泰典が逮捕!従業員の生活は? (ねじ巻きルピン )
新賢佑容疑者は前科があるようですし、そのような人間から何かしらの弱みを握られていて、逆らえない事情などがあったりと、可能性としては低くはなさそうに思えます。
女性客に乱暴容疑 2人逮捕 11/10/14 (NHK)
6日未明、福岡市天神の飲食店で女性客を店から出られないようにして乱暴したなどとして店で働いていた男2人が警察に逮捕されました。
逮捕されたのはいずれも福岡市に住む新賢佑容疑者(33)と伊牟田祐史容疑者(33)の2人です。
警察の調べによりますと2人はおとといの午前0時ごろ自分たちが働いていた福岡市中央区天神のワッフルなどを出す店で、25歳の女性客に乱暴したなどの疑いが持たれています。
2人は道を歩いていた女性に声をかけて店に招き入れほかの客がいなくなったあとシャッターを閉めてこの女性が出られないようにして犯行に及んでいたということです。
さらに新容疑者は店を出た女性を追いかけ、近くのホテルに連れ込んで再び乱暴した疑いが持たれています。
女性から被害届けを受けた警察では新容疑者が乱暴し、伊牟田容疑者もこれに関わっていたとしてきょう逮捕しました。
調べに対し2人は容疑を否認しているということです。
警察では途中まで店にいながら伊牟田容疑者を知らないなどと説明したとしてこの店の経営者の博多屋泰典容疑者(34)も犯人隠避の疑いで逮捕し、3人の関係や犯行の状況について調べています。
ワッフル店店員、シャッター閉め女性暴行 ホテルに連れ込み再び暴行 11/09/14 (スポーツ報知)
福岡県警中央署は8日、勤務先のワッフル店で女性客(25)を暴行したとして集団強姦と強姦の疑いで新賢佑(あらた・けんゆう)容疑者(33)=福岡市東区=を逮捕した。さらに集団強姦容疑の共犯で伊牟田祐史容疑者(33)=同市中央区=を、犯人隠避容疑で同店経営者の博多屋泰典容疑者(34)=同市南区=を逮捕。いずれも容疑を否認している。
中央署によると、新、伊牟田両容疑者は6日午前0時ごろ、福岡市内の繁華街、天神にあるワッフル店「tamago.NY(タマゴ ドット ニューヨーク)」内で女性客に暴行した疑い。
調べに対し、新容疑者は「強姦していません。エッチはしましたが、女性との合意の上です」、伊牟田容疑者は「(容疑は)合ってません」などと供述し、いずれも否認している。
女性は当初、隣のファミリーレストランに入ろうとしたが、ワッフル店の店員が「食事もできますよ」などと呼び込んだため、同店に初めて入った。他に2~3人の女性客がいたが、営業終了の午前0時近くは被害女性だけだった。
女性が帰ろうとしたところ、新容疑者が「まだ大丈夫ですよ」などと告げた後、突然シャッターを下ろし、電気を暗くした状態で2人で女性に襲いかかったという。その後、新容疑者は女性を近くのラブホテルに無理やり連れて行き、再び暴行。女性は被害を受けた後の6日未明、中央署に相談し、事件が発覚した。女性は「抵抗しましたけど、男性の力で…。これ以上抵抗すると何をされるか分からなかったので、ただ涙を流すばかりでした」と訴えたという。
同店の経営者である博多屋容疑者は、事件前の午後10時ごろまで店内にいて伊牟田容疑者が新容疑者と一緒にいたのを知っていたにもかかわらず、事情聴取の際に隠した疑いで逮捕。事件直後に両容疑者から携帯電話に着信を受けたことが捜査で判明しているが、博多屋容疑者は「友人と酒を飲みに行った後で酔っていたので覚えていない」と容疑を否認している。
カフェで女性客を集団暴行 容疑の従業員ら逮捕 11/09/14 (産経新聞)

福岡県警中央署は8日、従業員として勤めるワッフル販売のカフェで女性客を暴行したとして集団強姦と強姦の疑いで新賢佑容疑者(33)=福岡市東区=を逮捕した。また、集団強姦容疑の共犯で伊牟田祐史容疑者(33)=同市中央区=を、犯人隠避容疑で同店経営者の博多屋泰典容疑者(34)=同市南区=を逮捕した。いずれも容疑を否認している。
新、伊牟田両容疑者の逮捕容疑は6日午前0時ごろ、福岡市の繁華街・天神にあるカフェ内に1人でいた20代の女性客を暴行した疑い。新容疑者はその後、同じ女性を近くのラブホテルに無理やり連れて行き、再び暴行した疑い。中央署によると、2人は閉店後、シャッターを閉め、暴行したとしており、2人の関係を含め調べている。
博多屋容疑者の逮捕容疑は、事件直前まで店内にいて、伊牟田容疑者が新容疑者と一緒にいたのを知っていたのに、事情聴取で隠した疑い。
来店した女性客をシャッターを下ろして閉じ込め強姦 社長の男ら3人を逮捕 11/09/14 (KBC九州朝日放送)
6日、福岡市の店舗などで25歳の女性に乱暴したなどとして男2人を、また会社社長1人を、容疑者を 隠していたいたとして、8日逮捕しました。
集団強姦などの疑いで逮捕されたのは、福岡市の職業不詳・新賢佑容疑者(33)と伊牟田祐史容疑者(33)です。 警察によりますと、2人は6日午前0時ごろ、福岡市天神の飲食店で、25歳の女性客をシャッターを下ろして閉じ込め、 無理やり乱暴をした疑いがもたれています。さらに、新容疑者は泣いて帰宅しようとしたこの女性を追いかけ、 近くのホテルに連れ込み、改めて乱暴をした疑いももたれています。
また警察は、犯人隠避の疑いで、ハカタヤフーズ社長・博多屋泰典容疑者(34)も逮捕しています。 3人は容疑を否認しています。
本当にエボラ出血熱感染者が日本に入国したら二次感染は防げないだろう。二次感染が防げないのなら暫定措置でアフリカのリベリア、ギニア及びシエラレオネから出国記録がある全ての人を一所に集めて厳重なチェックをするか、入国拒否にするべきだと思う。デング熱で既に教訓を学んだと思うのだか???
エボラ疑い…その時、厚労省担当者つかまらず 11/09/14 (読売新聞)
関西空港で発熱してエボラ出血熱の可能性が疑われたギニア国籍の20代女性は、8日の検査で、陰性と判明した。
エボラ出血熱の疑い例が出たのは関西で初めてで、厚生労働省は「手順通りに進められた」と評価。ただ、地元の大阪府には情報が入りにくく、府は「陽性だった場合に対応が遅れかねない」として、今後、厚労省に情報提供のあり方の改善を求める。
7日夕に関西空港に到着した女性は、検疫官の呼び掛けに応じ、滞在歴を申告。搬送先のりんくう総合医療センターで採取した血液などの検体を東京の国立感染症研究所に送り、8日午後、厚労省がエボラ出血熱のウイルスが検出されなかったと発表した。
この間、厚労省は女性が乗っていた飛行機の便名の発表や機内の消毒などを実施。同省担当者は「スムーズに対応できた」と話した。
一方、大阪府医療対策課では、女性が空港からセンターに搬送された7日夜、同課職員らが厚労省に繰り返し電話しても担当者がなかなかつかまらず、女性に関する情報を確認できなかった。感染症法では、感染が確定するまで医療機関から自治体への連絡義務はなく、国も「疑い」の段階では自治体への連絡方法を決めていなかったという。
仮に女性が「陽性」だった場合、府は機内で患者の近くに座っていた人への健康調査などを行う必要があり、担当者は「初動態勢を整えるためには、疑いが生じた段階で一刻も早く情報がほしかった」と強調。府は、13日に厚労省で開かれる各都道府県の担当者を集めた会議で、地元自治体との連絡窓口となる職員の配置などを要望する。
最近、横領や着服の記事を良く見るような気がするが、昔は穏便にして来たのだろうか、損を隠すだけのゆとりが企業になくなったのか、それとも、インターネットで情報の伝達が速くなったのだろうか?
常務になるような人材が銀行印を無断で使って預かり証を偽造。モラルと人間性の問題では?
元銀行常務、客の3000万円着服…借金も1億 11/08/14 (読売新聞)
伊予銀行(松山市)は7日、元常務の男性が15年前に、顧客から預かった3000万円を着服していた、と発表した。
元常務は他にも、就業規則に反して別の顧客から1億円を借りていたことも発覚。内部調査を受けた直後に死亡したという。死因は明らかにしていない。
発表では、元常務は人事部課長だった1999年4月、顧客から預入金の名目で受け取った3000万円を着服し、私的に流用したという。また、広島支店長だった2007年3月と08年7月には、別の顧客から計1億円を借り受けた。12年6月から死亡するまで常務だった。
9月2日に、1億円を貸した顧客が同行に「返済がない」などと相談して発覚した。同8日、元常務が内部調査に対して借り入れを認めた。9日以降は無断で欠勤し、12日に家族から元常務が死亡したとの連絡があったという。その後、3000万円を預けた顧客が、新聞に掲載された訃報を見て同行に相談し、着服がわかった。
同行によると、3000万円を預けた顧客には元常務が1700万円を返し、残りは同行が返金した。借り入れた1億円は返済できておらず、同行が対応を検討している。
大塚岩男頭取は7日の記者会見で、「信用を大きく損なうことになり、残念。役職員一同、深く反省し、再発防止に努める」と陳謝した。
伊予銀行元常務、借金後死亡=1億円使途不明、不正認める-愛媛 11/07/14 (時事通信)
伊予銀行(本店松山市)は7日、高岡弘之・元常務取締役(59)が客から借りるなどした1億円が使途不明のまま9月に死亡したと発表した。
同行によると、高岡元常務は広島支店長だった2007~08年、2回に分け、計1億円を客から借り入れ、全額が使途不明になっている。
同行が9月、本人から事情を聞いたところ、不正を認めた。同行は同月12日に死亡を確認。その後、本店人事部課長だった1999年に銀行の印鑑を無断で使うなどし、別の客から3000万円を預かっていたことも発覚した。うち1700万円は本人が客に返還したが、残りは同行が立て替えたままになっている。
新聞で死亡を知った客から、同行に問い合わせがあり、発覚したという。
大塚岩男頭取は記者会見し、「地域の皆さまの信用信頼を損なうことになり、誠に残念。心からおわび申し上げ、信頼回復に全力を尽くします」と話した。死因については「プライバシーに関わる」として明らかにしなかった。
3000万円詐取か 死亡の元伊予銀常務 11/07/14 (愛媛新聞)
伊予銀行(愛媛県松山市)は7日、9月に亡くなった元常務の男性(59)が銀行印を無断で使って預かり証を偽造し、取引先から3000万円を受け取っていたと発表した。詐欺、あるいは業務上横領に該当する疑いがあるとして、調査を進めている。
伊予銀によると、元常務は1999年4月、顧客の1人から3000万円を預かったが、口座などは開設していなかった。
また、2007年3月と08年7月には別の取引先から計1億円を借り入れた。9月2日に1億円を貸した取引先からの連絡で発覚。同行が本人から事情を聴くなど調査していた中、同12日に死亡が確認された。
大塚岩男頭取は「不祥事を発生させ、心からおわびする。厳粛に受け止め、深く反省するとともに内部管理体制の強化に全力を尽くす」と陳謝した。
なぜ、冨田選手は今になって無実を主張するのか?韓国で供述書にサインする前に日本オリンピック委員会(JOC)や日本水泳連盟に相談をしなかったのか?
「冨田選手は会見で、『見知らぬ男にプールサイドで何かをかばんに入れられた』と説明。選手村に帰ってかばんを開け、カメラが入っていることに気づいたが、不用品の処理を頼まれたと思い込んでそのままにしていたという。」
どうして不用品の処理を頼まれたと思うのであろうか?スポーツ選手は練習ばかりして精神的に成長していない、又は、判断能力が低い人もいるかもしれないが、ここまで思考能力が低いとは思わない。まず、かばんに何かを入れられたのであれば、警備員や他の日本人に廃棄をお願いすればよい。かばんに入れられた物が何なのか分らないまま持って帰る行為が理解できない。危険物の可能性もある。
「さらに取り調べの際、『認めれば他の選手と帰国できる』と言われ、容疑を認めたとも主張。」
この件に対して日本オリンピック委員会(JOC)や日本水泳連盟に相談し、確認するべきだったと思う。冨田選手の弁護士がどのような根拠で無罪を主張しているのか今後が楽しみだ。
競泳・冨田選手、会見で無実主張 「カメラ盗んでない」 11/06/14 (朝日新聞)
9月に韓国・仁川で開かれたアジア大会の会場でカメラを盗んだとして、現地の捜査当局から略式起訴処分(罰金100万ウォン)を受けた競泳の元日本代表、冨田尚弥選手(25)が6日、名古屋市内で会見し、「カメラは盗んでいない」と訴えた。一方、日本オリンピック委員会(JOC)は現地で防犯カメラの映像を見せられ、冨田選手の行為を確認したことを明らかにし、「発言に驚いている」とした。
冨田選手の弁護士によると、略式裁判の判決が届いてから7日以内に申し立てれば、韓国で正式な裁判を受けることが可能になり、無罪を主張できる。判決が届き次第、申し立てるかどうか検討するという。
JOCや弁護士などによると、冨田選手は9月25日、プールサイドで韓国報道陣のカメラ(80万円相当)を持ち去った疑いで捜査当局から事情聴取を受けた。冨田選手は現地で窃盗の容疑を認め、供述調書にサインし、略式起訴された。帰国後、日本水泳連盟から選手登録停止処分(2016年3月31日まで)を受けたほか、所属先も解雇された。
冨田選手は会見で、「見知らぬ男にプールサイドで何かをかばんに入れられた」と説明。選手村に帰ってかばんを開け、カメラが入っていることに気づいたが、不用品の処理を頼まれたと思い込んでそのままにしていたという。
さらに取り調べの際、「認めれば他の選手と帰国できる」と言われ、容疑を認めたとも主張。また、この聴取の際、プールの防犯カメラの映像を見せられたが、「カメラを盗む様子をとらえた映像はなかった」などと説明した。
冨田選手会見にJOC困惑 「映像で確認している」 11/06/14 (朝日新聞)
冨田選手の会見を受け、日本オリンピック委員会(JOC)の平真(たいらしん)事務局長は「発言に驚いている。JOCとしては韓国での適正な手続きで下された刑事処分だと判断している」と困惑を隠さなかった。
JOCの説明によると、JOCのスタッフ2人が韓国の警察当局から防犯カメラの映像を見せられ、カメラをカバンに入れている冨田選手の姿を確認した。現地での取り調べには常にスタッフが立ち会い、同席した通訳の日本語の能力にも問題はなかったという。
「緊急入域は、台風など危険な状況の場合、外国船が一時的に領海内に留まることを認める国際的な慣習です。通常は外国船から事前に申請されることになっています」
事前に申請が無ければ、外国船が一時的に領海内に留まることを認めないのか?この点を海上保安庁は明確にしてほしい。申請がなければ留まる事を認めないのなら、移動するように強硬な対応を取るべきだし、申請が無くても法的に留まれるのであれば、無視されても仕方が無い。
中国漁船13隻、小笠原沖領海内にとどまる 11/06/14 (TBS系(JNN))
小笠原沖のサンゴ密漁問題で、台風20号の影響を避けるため、大半の中国漁船が領海外へ出ましたが、13隻の漁船が小笠原沖の領海内にとどまっていることが分かりました。
海上保安庁によりますと、サンゴ密漁目的とみられる200隻以上の中国漁船は、台風20号を避けるため、5日までに大半が領海の外へ退避しました。しかし、6日朝の段階で13隻の漁船が父島や母島周辺の領海内で確認され、海上保安庁はこれらの漁船について、台風の高波のため「人道上、やむを得ない」として、緊急入域を認めています。
緊急入域は、台風など危険な状況の場合、外国船が一時的に領海内に留まることを認める国際的な慣習です。通常は外国船から事前に申請されることになっていますが、今回、中国漁船から申請は出ておらず、海上保安庁の巡視船が申請するよう、繰り返し呼びかけていますが、漁船から応答はないということです。(
中国サンゴ密漁船、台風接近で船員の上陸警戒
海保など監視強化 11/06/14 (日本経済新聞)
小笠原諸島や伊豆諸島の周辺に最大時約210隻が集結した中国サンゴ密漁船とみられる外国漁船の多くは5日、台風20号が接近する周辺海域から離れ始めた。海上保安庁や警視庁は一部の外国船が島に避難し、乗組員が上陸する事態も想定し監視を強化する。
「台風が接近中。南下せよ」。海保の巡視船は5日、小笠原諸島周辺を重点的に警戒。スピーカーを使い、漁船に中国語で警告した。
海保によると、漁船の多くが南東へ移動を始めたが、天候不良で視界が悪く、全船の動きを把握するのは難しい。第3管区海上保安本部(横浜)の幹部は「中国から長時間かけて来ており、採算が取れるまで帰ろうとしない」と指摘する。
台風20号は6日朝にかけて小笠原諸島に最接近する見込みで、最大9メートルの高波が予想される。海保は船体の損傷といった危険が生じた場合、領海内の沖合で停泊を認めるが、乗組員が上陸しないよう監視する方針だ。
父島に住む事務員、坂井公子さん(48)は「避難して入港しようとする漁船がいれば拒否できないのでは。最近は友人との間で、夜は海岸に近づかない方がいいと注意し合っている」と話す。
小笠原村は乗組員が上陸した場合、住民に危険が生じる恐れがあると警視庁に訴えた。警視庁は小笠原署に警察官28人を派遣、警戒を強める。
海保は尖閣諸島(沖縄県)の警備にも多くの巡視船を派遣しており、小笠原との「2方面作戦」を強いられている。漁船団が出没する海域は南北約600キロに及ぶうえ、密漁は原則、現行犯でなければ逮捕できず、摘発のハードルは高い。
海保は10月5日以降、中国人船長5人を逮捕。うち4人は既に担保金(罰金)の支払いを保証する書面を提出し釈放された。密漁の罰金は最高1千万円だが、実際は数百万円程度のケースが多く、多額の利益が見込めるサンゴ密漁には抑止効果が低いとの指摘もある。小笠原の漁業者は罰金引き上げや船体没収など罰則強化を求めている。〔共同〕
脅迫されて飲み込んだのなら、なぜ警察に出頭するのか?見つかっていない以上、逮捕される事もない。飲み込んだものが排出されるのか心配になったのか?
「排泄物」から覚醒剤回収…結晶39個飲み込んで入国したナイジェリア人の男が出頭 11/05/14 (産経新聞)
覚醒剤を体内に隠して密輸したとして、京都府警が覚せい剤取締法違反の疑いで、京都府八幡市八幡三本橋の自称貿易商、ナイジェリア国籍のアニャウー・キング被告(41)=同法違反罪などで起訴=を逮捕していたことが5日、分かった。府警によると「調べてもらって初めて覚醒剤と分かった」と供述している。
逮捕容疑は9月3日、覚醒剤の結晶39個(約370グラム)を体内に隠して中国から関西国際空港に持ち込み、覚醒剤を密輸したとしている。
府警によるとキング被告は、ビニールで包んだ結晶を飲み込んで入国し、翌4日、結晶4個を持って八幡署に「いけないものを国外から持ち込んでしまった」と申告。宇治市内の病院に入院し、残り35個も排泄、科捜研の鑑定で覚醒剤と判明した。
キング被告は「中国で知り合ったマリ人らに親族に危害を加えると脅されて飲み込んだ。サイの角や象の牙だと思っていた」と供述しており、府警が詳しい経緯を調べている。
自業自得!
なぜ、今年になって感染が世界規模になったのか?
アングル:エボラ熱に残る複数の疑問、専門家が警鐘 11/04/14 (ロイター)
[3日 ロイター] - 米政府当局者らは、エボラ出血熱の鍵となる事実を研究者が分かっていると自信を見せている。しかし専門家らは、感染拡大を防ぐのに不可欠な多くの疑問が、依然解決されていないとみている。
ワシントンの米医学研究所で3日に開催されたセミナーで、専門家らは、すべての分からない点には何らかの結果が付随すると強調。弱い科学的根拠に基づく政策は愚かであり、危険だとの見方を示した。
例えば、エボラ熱は発症者の体液に接触し、目や鼻や口から粘膜や血流を通じて感染すると考えられている。しかし、出血熱の専門家であるテキサス大学医学部のトーマス・クスィアゼク博士は、傷のない皮膚からも感染する可能性を排除できないと指摘する。
2つ目の重大な疑問は、発症していない人からも感染するかどうかだ。過去何カ月もの間、米国内外の公衆衛生当局者らは、感染しないとしてきた。
だが、そのような「無症状の感染」が起きる可能性は大いにあると、小児感染症が専門であるユタ大学のアンドリュー・パビア博士は指摘。また、感染量はウイルスの体内への侵入方法によるのかどうかも専門家は分かっていないと述べた。
3つ目の不明な点は、発症までの潜伏期間が、接触した体液の種類によって違いがあるかどうか。もし違いがあるとするなら、血液よりも唾液に接触した人の潜伏期間は、これまで最大だとされてきた21日間よりも長い可能性がある。
テキサス大医学部のウイルス学者であるC・J・ピータース博士は、21日間は1976年にエボラ熱が初めて確認されたときの最大の潜伏期間だったとし、21日間を超えても5%が感染する可能性があるとの見方を示した。
また、体温が38度までならウイルスは人にうつらないと考えられているため、保健当局者は感染の恐れがある人の検温の重要性を強調する。しかし実際に何度の体温で感染し始めるのかは全く不明だと、米連邦労働安全衛生局のマイケル・ホッジソン博士は指摘した。
環境的な問題も残されたままだ。エボラウイルスを除染するのに、泡状、ガス、液体のどれが最も効果的なのか分かっていない。下水道でウイルスが生き残る可能性も不明であり、米環境保護庁国土安全保障研究センターのポール・レミュー氏は、ネズミが「感染する可能性もある」と語った。
(原文:Sharon Begley記者、翻訳:伊藤典子、編集:宮井伸明)
製薬業界は未だに閉ざされた社会と言う事だ!医師や研究機関にこれだけお金が流れているのだから、政界にもお金が流れていると考えても間違っていないかもしれない。
講演医師へ謝礼、昨年度110億円…製薬10社 11/03/14 (読売新聞)
製薬企業の売り上げ上位10社が昨年度、医師らを対象に開いた薬などに関する講演会は計約7万回で、講師の医師らに支払った謝金の総額は約110億円になることが、読売新聞の集計でわかった。
年50回以上講演を行い、1000万円を超える謝金を受け取った医師も10人以上いた。
国内の主要な製薬企業は昨年から、日本製薬工業協会の指針に基づき、医師・医療機関に提供した資金の情報を公開している。個人に支払った講師謝金などは今年初めて対象となった。
各社が謝金を年200万円以上支払った医師はのべ226人。糖尿病や高血圧など生活習慣病分野が約4割と目立った。10社の医薬品売り上げは全体の約半分を占める。10月末までに公開した65社では講演会は16万回超、講師謝金は約236億円。
中国船員は「Chinese Greater Coastal」の免状で日本まで来れる。国際条約上、可能なのかは知らないが、中国船員が過去にも日本に来ていた。
最近の代表的な例では、伊豆大島沖で第18栄福丸と衝突事故を起こたアフリカ・シエラレオネ船籍「JIA HUI(ジィア・フイ)」の海難だ。「JIA HUI(ジィア・フイ)」の船主責任保険(PI保険)会社は船員の免状に問題があるとの理由で支払いを拒否したが、
日本のPSC(外国船舶検査官達)はこの問題を一切指摘してこなかった。
なぜ、急に中国漁船によるサンゴの違法採取が取り上げられるようになったのか知らないが、日本政府が問題を放置するから大きくなったと思う。問題が大きくなるまで問題を解決しようとする姿勢が見られない。
中国「サンゴ、法に基づいた操業を求めている」 11/03/14 (読売新聞)
【北京=竹腰雅彦】中国外務省の華春瑩(フアチュンイン)副報道局長は3日の定例記者会見で、東京・小笠原諸島の周辺海域などで中国漁船がサンゴを違法採取している問題について、「報道に注目している。中国政府は法に基づいた操業を求め、規定違反の赤サンゴの採取を禁じている」と述べた。
その上で「政府の関係部門は、違法行為について法執行を強めていく」と述べた。
菅官房長官は10月31日の記者会見で、この問題で中国に再発防止を求めたことを明らかにしていた。
騙すほうも悪いが、安易にNPOだからと投げ任せた自治体にも責任があると思う。税金が無駄に使われた。回収の方法もない。無駄に使われた額分、本当は恩恵を受けるはずだった町民や地方自治体がなくだけだ。
地方は自由に税金を使わしてほしいと言うが、運営能力や効率的な使用が出来ない自治体が存在する限り、一律な自由な税金は危険だと思う。問題がある地方自治体のために一部の能力とやる気がある自治体が犠牲になるのは残念である。
元幹部に懲役2年4月 NPOの震災事業費横領 11/04/14 (読売新聞)
岩手県山田町から預かった東日本大震災の緊急雇用創出事業費で、事業に無関係な不動産を購入したとして、業務上横領罪に問われた北海道旭川市のNPO法人「大雪りばぁねっと。」(破産手続き中)元幹部の橋川大輔被告(35)=千葉県市川市=に盛岡地裁(岡田健彦裁判長)は4日、懲役2年4月(求刑懲役3年6月)の判決を言い渡した。
起訴状などによると、橋川被告は法人元代表理事岡田栄悟被告(35)=同罪で公判中=と共謀し、平成24年10月9日、事業に関係ないマンションや土地の購入代金として、事業費3千万円を横領したとしている。
これまでの公判で検察側は「不動産の売買契約書に署名するなど、犯行で重要な役割を果たした」と指摘。弁護側は、横領の共謀を否定し、無罪を主張していた。
工事をやり直す費用はかなりの負担だと思う。もしかすると、倒産とか、もう一度別の部分で手抜きを行う可能性もあると思う。
「同局は再発防止のため、現在は工事現場を巡回し、埋め戻し材に磁石を近づけてスラグが混ざっていないか、抜き打ちで確認しているという。」
入札の問題点だ!入札は最低価格で決まるが、過去の業者の仕事の仕上がりは評価されない。過去の仕事や企業の評価は、入札側に賄賂を貰ったり、癒着している人間がいると評価自体が不当に書き換えられるリスクがある。公務員そして業者の問題はなくならないであろう。
文科省職員に脅し…不認可の「幸福の科学大学」 10/31/14 (読売新聞)
来年4月の開設を目指していた「幸福の科学大学」(千葉県長生村)について、下村文部科学相は31日、閣議後の記者会見で、開設を認めない不認可としたことを明らかにした。
文部科学省は同日付で、申請者の学校法人「幸福の科学学園」(栃木県那須町)に文書で通知する。同省は、最長5年間設置を認めない方針。
下村文科相は、「大学設置・学校法人審議会」が「学問の要件を満たしているとは認められない」として開設を認めない答申を出したことや、「文科省職員に対して脅しのような発言がなされるなど、認可の可否の判断にあたって心的圧力をかけるような不正行為があった」と説明した。
同審議会から開設を認める答申があった大学3校と大学院5校については、同日付で認可が通知される。
工事をやり直す費用はかなりの負担だと思う。もしかすると、倒産とか、もう一度別の部分で手抜きを行う可能性もあると思う。
「同局は再発防止のため、現在は工事現場を巡回し、埋め戻し材に磁石を近づけてスラグが混ざっていないか、抜き打ちで確認しているという。」
入札の問題点だ!入札は最低価格で決まるが、過去の業者の仕事の仕上がりは評価されない。過去の仕事や企業の評価は、入札側に賄賂を貰ったり、癒着している人間がいると評価自体が不当に書き換えられるリスクがある。公務員そして業者の問題はなくならないであろう。
水道管工事:220カ所道路盛り上がり…業者が契約違反か 10/31/14 (毎日新聞)
名古屋市上下水道局が2009〜12年度に発注した、老朽化した水道管の取り換え工事で、特定の数社が請け負った約220カ所で道路が盛り上がり、舗装にひびが入るトラブルが生じていたことが、市への取材で分かった。水道管の埋め戻しに使う材料に指定外の物質が混ざっていたのが原因とみられ、市は契約違反があったとして、トラブルがあった全ての箇所で工事をやり直すよう業者側に求めた。
同局によると、トラブルがあったのは名古屋市の千種や南など7区と、同局が管轄する愛知県北名古屋、清須両市での工事。局が昨年秋から、被害の大きかった19カ所を調べたところ、埋め戻し材に、鉄鋼精製時などに生じる「鉄鋼スラグ」が混ざっていた。スラグに含まれる石灰が水を吸って膨らんだため道路が盛り上がったとみられるという。
業者との契約では、埋め戻し材には天然石などを使うことになっており、スラグは指定していなかった。いずれの業者も「資材置き場に積んであったスラグを間違えて使った」「天然石を運び出す際に混入してしまったようだ」などと釈明し、局も意図的な混入があったとは確認できなかった。やり直し工事の費用の一部は市が負担することになる見通し。
同局は再発防止のため、現在は工事現場を巡回し、埋め戻し材に磁石を近づけてスラグが混ざっていないか、抜き打ちで確認しているという。【岡大介】
どこかの組織がケーシー・ヒコックス(Kaci Hickox)を支援していると思われるが、「科学的な根拠もないのに、自分の市民権が侵されるのを傍観しているわけにはいかない」と主張している。しかし、今大丈夫だから今後も発症しないとの科学的な根拠はあるのか?彼女は看護師であり、専門の医者でもなく、医者でさえもない。発症した場合、彼女は責任を取れるはずもない。感染リスクを0に近い確率にしたければ、必要が無ければアメリカには行かない方が良いと思う。
エボラ対策で自宅待機命じられた米看護師、自転車で外出 10/31/14 (AFPBB News)
【AFP=時事】西アフリカでエボラ出血熱患者の治療に携わった後米国に帰国し、地元である北西部のメーン(Maine)州当局から隔離措置として自宅待機を命じられていた女性看護師が30日、自転車で外出した。
CNNテレビによると、取材陣が見守り撮影が続く中、ケーシー・ヒコックス(Kaci Hickox)さんは交際相手の男性と共にヘルメットをかぶって自宅から自転車で出発。2人は記者らと言葉を交わすことなく走り去り、警察車両2台がその後を追った。
ヒコックスさんはシエラレオネから米国へ帰国後、隔離テントに3日間収容された。ニュージャージー(New Jersey)州のクリス・クリスティー(Chris Christie)知事は27日になって隔離措置を解除し、ヒコックスさんは車で自宅のあるメーン州まで送られた。しかしメーン州は、エボラウイルスの潜伏期間21日間のうちまだ12日残っているとして、ヒコックスさんに自宅待機するよう命じていた。
ヒコックスさんはこれに強く反発したが、同州は必要ならば裁判所命令で自宅待機させるという方針を示した。
NBCニュースによると、ヒコックスさんは29日遅く、同州フォートケント(Fort Kent)の自宅で恋人に付き添われて、「体調は万全で症状も一切ないにもかかわらず、州は私が家を出て外部と接触することを許可してくれない」と訴え、もし州が裁判所命令で来月10日までの自宅待機を強制するなら提訴も辞さないと述べた。
ヒコックスさんは、「科学的な根拠もないのに、自分の市民権が侵されるのを傍観しているわけにはいかない」と主張した。
ニュージャージー州やニューヨーク(New York)州、また国防総省といった一部の州や行政機関は、西アフリカでエボラ出血熱患者の治療に当たった後、米国に帰国した医療従事者の隔離を命じており、この措置が大きな議論を巻き起こしている。
その高まる議論の中でバラク・オバマ(Barack Obama)大統領は、国民を安心させようと努めている。29日には帰国した医療従事者との面会後にホワイトハウス(White House)で会見し、自ら志願して治療の最前線に立った人々はその貢献をたたえられるべきだと発言した。【翻訳編集】 AFPBB News
NHKもこの程度なのか?メディアを素直に信じるのは問題がある可能性が思っていたよりも高いかもしれない。
エステサロン「たかの友梨ビューティクリニック」だけが特別ではないと思う。エステサロン「たかの友梨ビューティクリニック」の認知度が高く、規模も大きいが、問題を抱えていたと言う事だと思う。
自爆営業の話は良く聞く。物を売らなければ人件費やその他のコストを回収できない。結果を出せない人は辞めてほしいと思っている企業の意思表示だと思う。これが現実。しかし、公務員の給料や待遇は良くしている。その給料やコストは税金や労働者からの搾取でなりたっている。絶対におかしいと思う。
たかの友梨、提訴の女性社員が告白「お客様に必要のないエステも勧めた」「自爆営業で3重ローン」 (1/2)
(2/2) 10/29/14 (withnews)
エステサロン「たかの友梨ビューティクリニック」で“マタニティ・ハラスメント”があったとして、損害賠償を求めて会社側を提訴した女性社員が29日、弁護団などを通じて『告白文』を公開しました。「客に必要のないパックを勧めた」「忙しくておにぎり1つ食べられない職場だった」「売上達成のため、三重のローンを組んで自社製品やサービスを買わされた」など、切実な実体験が記録されています。
「おにぎり1つ食べられない」
私は髪を触ったり、マッサージをしたりするのが好きで美容に興味を持ち、美容専門学校に入学しました。大手企業に入りたいと思ってましたし、有名なところだったのと、他の企業に比べて(施術の)コースの数が多いため、自分の経験も積めると思って、たかの友梨を選びました。
入社してみて驚いたことは、先輩たちがほとんど休憩を取らずに忙しそうだったことと、研修費と化粧代を最初に給料天引きで引かれていたことでした。(入社前と)入社後では大きなギャップがありました。相当な体力仕事だな、アスリート的な感じだなと思いました。座ることがほとんどなかったので、足がとにかくきつかったのを覚えています。
20歳で入社し、新人の頃から8時から22時くらいまで(朝・夜の練習を含む)長時間労働のうえ、休憩はほとんどありませんでした。母親が作ってくれたお弁当のフタを開けて食べる時間もないため、しかたなくオニギリ1つにしてもらいましたが、それも結局は食べれず、家に持って帰って、母から心配されたりを繰り返していました。
片道1時間半かかる配属先に、定期代4万円のうち、交通費2万円を自己負担しながら通いました(※1)。新人で給与が少ない時はとても経済的に厳しいものでした。お客様にもコースにも慣れていない中、朝早くて夜遅かったので、それについても母親は心配していました。
「自爆営業で3重のローン」
入社後3ヵ月でストレスと不規則な生活から胃腸炎になり1週間入院をしました。医者は、昼休みを取れないため朝と夜にたくさん食べて働くサイクルが、胃酸の分泌に影響を与えていると言っていました。
その後、小さいお店に配属されました。小さいお店だと従業員3人というお店もあります。そこでは売上への負担が大きく、(私も)MAX50万もするローンを何回も組み、最高で同時期に3重のローンを組みました。外へのチラシまきから帰ってきたら店長がローンの用紙を持って待っていました。売上を達成させる為に購入せざるをえない状況でした。自分自身が使わないものもたくさん買いました。自分が使わないコースや美顔器をたくさん買いました。実質的には手取り月10万程度で、給与(二十数万円)の約半分は会社のために使っていました。
「お客様に必要のないエステも勧めた」
働く中での異動も10回ほどと頻繁にあり、とても辛いことでした。新人の時はそのお店の先輩の名前、施術のやり方、お客様について覚えたところ、またすぐに異動、の連続で常に緊張が絶えませんでした。
その中でも長期で働いたお店では業務はもちろん、お客様についても(特徴などを)全部把握して仕事ができました。2年後でも(お客様に)会ったことがあるよねと声をかけてもらえました。時には洋服をいただいたり、昼食を作ってきてくれるお客様もいました。そのお店を異動する際にお客様もショックを受けていましたし、私自身も慣れているお客様と離れるのは辛い思いでした。いつも、会社から、異動は前日に言われました。
トレーナーになってからは大きいお店を転々と異動をし、2日前に大阪への異動を伝えられた際に断っても、「もう決まっていることだから」と強制でした。その時かかった引っ越し費用や交通費も自己負担しました。
お店の技術目標のために、やればやるだけ達成に近づくので長時間労働をし、遅番や早上がり、休みの日でも関係なく、サービス労動でタイムカードを押さずに働くことも多くありました。安いチケットをたくさん売っていたので、目標達成まですごく大変でした。
お客様に合っていないコースへ誘導したりもしました。ペースがゆっくりのコースを受けたい方に、痩身を勧めたりしました(※2)。必要のないパックを勧めたりもしました。効果も半減します。それでも、そうしないと仕事が回りませんでした(※3)。すごく嫌でやりたくない気持ちになりましたし、お客様にも申し訳なかったです。60分のコースで担当が3人変わったこともありました。お客様も落ち着かない状態でした。
入社8年で「『ブラック企業』ではないか?」
これまで私は8年間働いていましたが、産休をとった人は3、4人しか見たことはありませんでした。基本的には妊娠をしたら、みんな退職をしていきました。(会社が)ちゃんとした情報もくれないので、産休を選びようがない中、退職を選ばされた人が多いと思います。
今回私も産休にいたるまで、フロント業務や時短勤務などの軽易業務への転換をもとめましたが拒否されたり、「妊娠5ヶ月で産休に入らないといけない。復職後はフルタイムの正社員で必ず戻ってこないといけない」などと正しい産前・産後休暇を教えて頂けませんでした。また、(高野友梨)院長先生への「お伺い書」(おうかがいしょ)や産休を取得するにあたっての「誓約書」ではそれに加えて、保育園の確保などの条件を約束させられました。最終的には切迫早産で絶対安静を余儀なくされました。
妊娠してから働いている時は、お腹の張りと腰痛がひどかったです。できれば休みたい、休憩も座ってゆっくり取りたいと思いながら、通常の9時から22時までの仕事を出産3か月前くらいまで続けていました。
時短勤務やフロント業務ができていたら、切迫早産になることもなかったですし、(お腹の)命が失われるのではとの心配が、自宅安静後も頭を離れませんでした。
8年間伝えられないほどの精神的苦痛がありました。 でも、お客様の信頼をいただいていたり、後輩スタッフからも離れられないと感じていて、続けていました。
今までこの会社を信じて身を削り頑張ってきましたが、いろいろと矛盾があったことに気付いてからは、『ブラック企業』ではないかと思いはじめました。これから働く人や、いま働いている人、産休をとる人のため、会社が変わってほしいです。若い女性が中心の会社で、従業員みんなが過重労働がなく、産休を取って安心して働き続けられる会社になってほしいです。「100年企業」をめざす会社のためにも現状を理解し改善していただきたく、今回の裁判を行うことに至りました。
■提訴・告白した女性社員を支援する労働組合「エステ・ユニオン」による注釈
※1 「たかの友梨」での交通費負担は最高で月2万円まで
※2 ペースがゆっくりのコースに比べて痩身はお客様の身体的負担が強いですが、単価が高いので、ノルマ達成のためにコースを変更したということ
※3 売上のために予約を詰め込みすぎて多忙になっているため、手が空くパックによって時間を稼いで、そのあいだに他のお客様の施術を行うということ
まあ、建前と本音!踊らされる人はピエロ!
原発汚染水放出後のモニタリング 水産庁も海保も責任逃れ 10/29/14 (NEWSポストセブン)
福島第一原発事故について政府は、772人分あるはずの政府事故調調書を19人分しか公開していない。それは、当時の菅政権=政治家たちの対応の失敗が明らかになるだけではなく官僚機構の不作為まで白日の下に晒されるのを霞が関の役人たちが避けたいからではないか。
国民の安全より保身を優先する役人体質が顕著に現われたのは、2011年4月に海へ汚染水を放出した後のモニタリングだった。
当時、2号機の地下にたまった高濃度汚染水を保管するため、低濃度の汚染水が海に放出された。それに対し国内の漁業関係者や海外から批判が高まり、どれくらい汚染されているのか調査する方針が決まった。
細野豪志・首相補佐官(当時)の調書には各省庁の対応が詳らかにされている。
<ところが、(緊急時の放射線モニタリングを担当する)文部科学省は一切やる気がないと。水産庁に言ったら水産庁は、そんなところの魚は食べないので、食べない魚は測りませんと言ったんです。では海上保安庁に測ってくれと言ったら、海上保安庁には釣り竿がないと、船はあるけれども>
会議に集まった全員が押し付け合いだった。一度解散し、翌日もう1回集まったが、<また同じ状態だった>(細野調書)という。
同氏の調書には見逃せない記述がある。
<厚生労働省も呼んだんです。(厚労省職員が)そんな放射性物質を含んでいる水のところに行ったら健康によくないとかいう話まであって、それで(厚労省は)基準を作れとか何とかと言ったのだけれども、基準を作っている時間はないのでとにかく測ってくれと言って、水だけ取って>
役人たちは、自分たちが水を採取しに行くのも嫌だといいながら、国民には「健康に影響ない」と言い続けていたのである。
※週刊ポスト2014年11月7日号
赤珊瑚密漁急増が注目を受けているだけで、中国人船主による国際条約違反問題は以前から存在している。取締りが甘いとこうなるだけである。日本の対応の甘さが今回の問題を助長させたのか、メディアが騒いでいるだけだと思う。
赤珊瑚密漁急増の背景に2010年の中国海島保護法 10/28/14 (遠藤誉 | 東京福祉大学国際交流センター長、筑波大学名誉教授、理学博士 Yahoo!ニュース)
赤珊瑚密漁急増の背景に2010年の中国海島保護法
中国漁船による小笠原諸島付近における密漁が急増している。その背景には2010年に制定された中国海島保護法の制定がある。それが赤珊瑚価格の急騰と中国漁民の密漁を招いている。それに対する中国政府の対応は?その実態と経緯を追う。
◆中国海島保護法――特に珊瑚捕獲と珊瑚礁破壊を禁止!
2009年12月26日、中国の全人代(全国人民代表大会)常務委員会は「中華人民共和国海島保護法」を制定し、2010年3月1日から施行することを決議した。
海島保護法の目的は「海島とその周辺海域の生態システムを守り、海島の自然資源の合理的な開発利用を保証し、国家海洋権益を保護し、以て、経済社会の持続的発展を促進するものとする」と、第一条にある。
どんなに取り締っても、漁民による乱獲が後を絶たず、遂に保護法制定に到ったわけだ。
それでも、中央の指示が必ずしも末端にまで行き届かない可能性があるので、同法第十一条には、「省、自治区の人民政府(地方政府)は、行政区内の沿海都市、県、鎮などの末端人民政府に海島(資源)保護のための特別専門計画を編成して良い」と規定している。小さな漁村の漁民たちが勝手に振る舞わないように、その末端組織に適合した計画を立て、法を順守させろということだ。
特記すべきは、同法第十六条に「珊瑚および珊瑚礁の採掘と破壊を禁じる」と書いてあることだ。
そこには「自然資源、自然景観と歴史および人文遺跡を保護するために、各地方政府は対応措置を取らなければならない」とさえある。
さあ、これを読みなさいと言いたい文言である。
自国で禁止され、法を破れば重い刑が待っているために、他国に行きましょう、というのが、今回の中国船による密漁の背景にある。
では、漁民はどう動き、それに対して中国の地方政府は、どう対応したのか?
◆中国で赤珊瑚が持つ意味と価値
深海の赤珊瑚は中国の国家第一級の野生動物保護の対象となっている。
なぜなら古来より、赤珊瑚には「瑞祥(ずいしょう)」(めでたいことが起きるという前兆、吉兆)があると言われ、仏典には「七宝」の一つとして列挙されているからだ。そのため古代王朝から皇帝の装飾品には必ず翡翠(ひすい)とともに赤珊瑚がちりばめられている。
中国ではまた、赤珊瑚には貴重な宝石としての存在以外に際立った薬効があるとされている。
たとえば、「血行改善、解熱、てんかん治療、利尿作用、美顔」などの効果である。400年前に出された『本草綱目』にはさらに「そこひ」(白内障、緑内障など)や精神安定にも効果があると書いてある。
いろいろな意味で、赤珊瑚は「霊験あらたかである」と信じられ、中国の宝石市場では和田(ホーテン)翡翠とともに「本物志向」が強烈になっている。
2010年の統計によれば、中国の芸術品販売額は、全世界の33%を占め、アメリカ(30%)、イギリス(19%)、フランス(5%)を凌いで、世界一となっているという。
中国市場における内部予測では、2014年までに中国の億万長者は毎年20%ずつ増えているので、宝石オークションにおける数と価格は急増し、今後さらに記録をつぎつぎと破っていくことだろうとしている。
それに伴い赤珊瑚の密漁は急増するだろう。
◆中国密漁の実態と中国地方政府取締りの現状
中国の南の方にある浙江省寧波市象山県の単という名の男が、つい最近「絶滅野生動物捕獲罪」で逮捕された。象山県の人民検察院は、5年以下の懲役を科すだろうと言われている。
単氏は、エビ漁を生業としていたのだが、収入がどうもイマイチ。そんな折、去年12月のこと、「赤珊瑚漁は、ぼろ儲けするぞ」と仲間から誘いをかけられた。
そこで単氏とその仲間は180万元(日本円は現在のレートで17.6倍なので約3200万円)を投資して赤珊瑚の密漁に着手することになった。投資額が多すぎるので、数名の仲間を募り、投資額に応じて利益の配分を決めることにした。
今年春節のころ、まず82万元を投じて無免許の船舶を購入し、35万元をかけて改装した。作業時に見つからないように船倉(せんそう)(貨物を積んでおく所)にコンクリート塗装をして、甲板の上に珊瑚を獲るための網などを準備した。
さらに中国の漁政関係の法律を執行する当局の目をごまかすために、昇降機などを取り付けた。
今年4月に入り、珊瑚漁の密漁に出かけた。中国の情報には密漁先が書いていないが、日本の小笠原諸島海域だろう。
50日後、単氏らの船は高級な赤珊瑚を満載して帰国。
しかし赤珊瑚と漁政当局に分かれば、すぐに逮捕される。そこで闇市に持って行って加工し密売しようと試みた。
ところが7月17日、象山警察は、庶民からのある通報を受け取った。それは赤珊瑚がある場所に隠されているという通報だった。行ってみると、そこには488万元(約8600万円)に相当する赤珊瑚があるのを発見したのである。すぐさま単氏とその仲間は逮捕されたわけだ。
◆中国当局の苦悩――法治国家を謳ったばかり
浙江省の地方紙「銭江晩報(晩報:夕刊)」によれば、2011年末、浙江省の海洋漁政関係部局は「専案組」(特別捜査本部)を設置し、赤珊瑚の密漁を取り締っているという。
浙江省の海洋と漁政執法総隊の張友松・副隊長は「少数の漁民が高額な利潤を手にしようという誘惑から非合法的な珊瑚漁業に手をつけている。そこには一つの共通点があり、彼らは運輸船を改造して珊瑚捕獲のための用具を船内に隠している」という。
赤珊瑚の密漁船が中国の国旗をわざわざ掲げているのは、なんと、中国当局の目をくらますためだった。
その当局はつぎのような苦悩をもらしている。
「わが国にはまだ、珊瑚密猟船を見分けるための鑑定方法が確立されておらず、それが密漁船であるか否かを見分けるのを非常に困難にしている。ただ単に、船内に珊瑚捕獲のための網が隠されているか否かという事実を突き止めたり、勘に依るしかなく、出航前に隠蔽事実をつかむのは非常に困難。おまけに密漁した珊瑚は、実は海上で闇取引され、密漁者の船には、もう存在していないことが多い」とのこと。
習近平は10月23日に閉幕したばかりの四中全会で「法治国家」「依法治国」(法によって国を治める)を謳った。
おまけに密漁者を数多く出しているのは、福建省や浙江省など、習近平がかつて治めていた地域ばかりだ(詳細は近刊『チャイナ・セブン <紅い皇帝>習近平』)。
さあ、「法治国家」「依法治国」の実行を、まずこの赤珊瑚密漁で実証してもらおうではないか。
さもなければ、11月に北京で開催されるAPECで、中国は面目を失うだろう。
なお、中国共産党機関紙「人民日報」の電子版「人民網」の「強国論壇」という微博(ウェイボー)には「この事件は中国側に落ち度がある。この赤珊瑚は日本に帰属する物だ。犯罪者は厳罰に処すべきである」旨のミニブログが書いてある。
帰国医療者の隔離は非人道的と言うが、感染が拡大した場合、経済的な損失、人命の危険、リスクを負う意思が無かった関係のない人達の隔離及び自由の拘束を引き起こす。エボラ出血熱から回復した人達は存在するが、全ての人達が回復したわけでもない。西アフリカへ行く人達はリスクを承知で行くわけだが、渡航者又は旅行者から感染させられる人達はリスクを承知している訳でもないし、危険性を事前に説明されている訳でもない。
医者、看護師、そしてその他の理由で西アフリカへ渡航する人達はリスクを承知で行く判断を下している。もし、ある一定期間の隔離に不満を抱くのであれば、隔離されている間の補償を得られるように派遣した機関に要求すればよい。病院で重症の患者として入院していると思えば問題はない。経済的な補償が得られるのであれば問題はないと思う。
宇宙に長期間滞在した宇宙飛行士達が地球に帰還後にすぐに普通の生活が出来るのか?普通の生活が出来ない事を不満に思うのであれば、宇宙飛行士などにならなければ良い。宇宙飛行士になる事は強制ではない。宇宙飛行士になりたくても、適応能力、長期の訓練機関、健康の問題、精神的に適応できるの能力などさまざまな制約のために宇宙飛行士になれない。いろいろな条件により宇宙飛行士になる事を諦めさせられる事は非人等出来なのか?夢を否定される事はどう解釈されるのか?
多くの患者を看病したら、関係のない人を感染させて命を奪う事は、意図的でなければ許されるのか?人命を救うために西アフリカへ行ったのであれば、帰国した時に感染させるリスクがないように注意を払う事に協力できないのか?協力できないのであれば、自己満足的な医療行為に従事したかったと批判されても仕方が無いと思う。
帰国医療者の隔離は非人道的…イリノイ州は緩和 10/25/14 (読売新聞)
【ワシントン=中島達雄、ニューヨーク=水野哲也】エボラ出血熱を巡り、西アフリカから米国に帰国した医療従事者について、米イリノイ州は27日、適切な防護服を着用して活動していた場合は外出禁止の対象にしないと発表した。
当初は外出禁止による隔離措置の方針を示していた。米国では帰国者の隔離措置に対して「非人道的だ」といった批判が高まっている。
国際NGO「国境なき医師団」の一員としてシエラレオネで活動後、24日にニュージャージー州の空港に帰国した女性看護師はいきなり隔離され、27日ようやく解放された。女性看護師は同州に「非人道的措置だ」と不満を表明した。
米国では、テキサス州の女性看護師が微熱のある状態で民間機に搭乗したり、ニューヨークで発症した男性医師が発症前に地下鉄に乗ったりしていたことから、国民の間で、発症リスクのある人の隔離を求める声が高まった。
厳しい処分が必要だろう。しかし厳しい処分を下せるような法や規則は存在するのか?
<奈良・診療報酬詐欺>「職員大半が患者」内部証言 10/25/14 (毎日新聞)
奈良市の医療法人「光優会」を巡る診療報酬詐欺事件で、法人グループの職員のほとんどが、奈良県警に逮捕された理事長で精神科医の松山光晴容疑者(54)のクリニックで診察を受けていた患者や元患者だったことが分かった。複数の元職員が毎日新聞の取材に証言した。こうした職員は内部で「患者職員」と呼ばれていたという。調べでは、架空請求の多くは患者職員名義で行われており、松山容疑者が強い立場を悪用していた疑いがある。
光優会グループは、診療所「クリニックやすらぎ八木診療所」(同県橿原市、昨年8月に閉院)の他、奈良、三重両県で自立支援の訓練など福祉サービスを行う事業所6カ所を運営。グループ全体で約60人が勤務していたという。
看護師として診療所で1年半勤務した女性も精神疾患がある患者職員で、働きながら松山容疑者から抗うつ剤など6種類の薬の処方を受けていた。
事業所で行った福祉サービスに支払われる自立支援給付費について、女性は「帳簿に虚偽のサービス内容を記載し、請求を水増しした。松山容疑者の指示通りに動いた」と証言。患者職員にグループの関連店舗の戸締まりをさせたことを「福祉施設での自立訓練などのサービス」と偽って自立支援給付費を請求したこともあったという。
また、10カ月勤務した患者職員ではない看護師女性も「職員らを面接と称してクリニックに呼び出し、受診したことにしていた」と不正の手口を明かす。
患者職員だった男性は「主従関係を利用できる患者職員はうまみがあったのだろう。弱者を食い物にする行為は許せない」と訴えた。
松山容疑者は24日、元職員(健常者)をクリニックで診療したように装い、2011年3月に診療報酬約362万円を東大阪市から詐取した容疑で逮捕された。県警は10年以降、患者職員を含む少なくとも十数人の名義で数千万円をだまし取ったとみて調べている。【伊澤拓也、矢追健介、芝村侑美】
詐欺容疑:医療法人理事長を逮捕…元職員名義で不正受給 10/25/14 (毎日新聞)
架空の診療書類を作って診療報酬を不正受給したとして、奈良県警は24日、医療法人「光優会」理事長で精神科医の松山光晴容疑者(54)=奈良市南登美ケ丘=を詐欺容疑で逮捕した。県警は、松山容疑者が2010年1月以降、光優会グループの元職員や患者ら少なくとも十数人の名義を利用して数千万円をだまし取ったとみて、余罪を追及する。職員として雇った患者の名義も使って、不正な受給を繰り返していた疑いもあるという。
逮捕容疑は、グループの元職員で、当時は東大阪市に住んでいた自営業男性(50)を法人が運営する「クリニックやすらぎ八木診療所」(奈良県橿原市、閉院)で08〜09年に月に6〜26日間診察したように装い、診療報酬明細書(レセプト)を県国民健康保険団体連合会に提出。11年3月に東大阪市から約362万円をだまし取ったとしている。松山容疑者は「(男性を)知っているが診療はしていない。(診療報酬を)請求したことは知らない」と容疑を一部否認しているという。
松山容疑者はクリニックの患者を職員として大量に採用。県警は架空請求の多くが、こうした職員の名義を利用したものだったとみて調べる。
13年10月の家宅捜索で押収した資料などから、年間に数億円の診療報酬を請求していることが判明。県警はクリニックは10年前後から架空請求していたとみている。松山容疑者のパソコンには元職員や元患者など約4000人分の患者データが残っていたという。
法人登記などによると、光優会は1998年3月に設立、クリニックは同年5月に開設された。同名の社団法人とともに、奈良、三重両県で自立支援訓練などの福祉サービスを行う事業所6カ所を運営していた。
内部告発を受けた橿原市が12年11月に刑事告発。報告を受けた奈良県は13年3〜4月、福祉サービスに対して支払われた自立支援給付費約170万円と、通院治療に支払われた自立支援医療費約100万円が不正受給にあたると判断し、それぞれ指定医療機関・事業所の取り消し処分をした。【伊澤拓也、芝村侑美、矢追健介、塩路佳子】
当事者にとってはとてつもなく厳しい対応だが、防御策が無い事を認識した上での判断は素晴らしいと思う。日本ではこのような大胆な判断は出来ないと思う。
◇西アフリカ3カ国から両州の空港 「21日間隔離」 10/25/14 (毎日新聞)
【ニューヨーク草野和彦】米東部ニューヨーク、ニュージャージー両州は24日、西アフリカのリベリア、シエラレオネ、ギニアでエボラ出血熱感染者に接触した医療従事者など旅行者全員に対して、両州の空港から入国した際、21日間の隔離措置を実施することを発表した。ギニアから帰国した男性医師(33)のエボラ出血熱の感染確認を受け、感染拡大防止の「水際対策」強化に乗り出した。
対象は、ニューヨークのJFK国際空港とニュージャージーのニューアーク空港からの入国者。ロイター通信によると、新方針に基づき、西アフリカからニューアーク空港に24日帰国した女性医療従事者がニューアークの大学病院に隔離された。21日間は、エボラ出血熱の最長潜伏期間とされている。AP通信によると、両州の在住者は自宅か病院に隔離され、医療従事者の問診を受ける。州外に住む入国者は医療施設などに隔離される方針。
27日から実施予定の米疾病対策センター(CDC)のガイドラインは、西アフリカ3カ国からの帰国者に対して、体温検査をし、当局に報告することを求める。だが、ニュージャージー州のクリスティー知事は「CDCの基準はあてにならない」と述べ、より強力な措置の必要性を主張。ニューヨーク州のクオモ知事は「公衆衛生があまりにも深刻な状況になっている」と語った。
西アフリカでのエボラ熱流行で感染した米国人は、現地で感染し米国内に移送された医師や報道カメラマンら4人がいずれも完治。米国内では死亡した男性や2人の看護師のほか、別の医師1人が帰国後に発症している。
未だにこの手のビジネスは成り立っているのか?
「温泉」実は温めた水道水…消費者庁が措置命令 10/23/14 (読売新聞)
消費者庁は23日、愛知県南知多町の旅館経営会社「豆千待月(まめせんたいげつ)」(鈴木邦弘社長)が、ホームページや旅行情報ウェブサイトで温めた水道水を温泉のように表示したり、豪州産牛肉や養殖ふぐを使っているのに、和牛や天然ふぐと表示したりしたなどとして、景品表示法(優良誤認)に基づき、消費者への周知と再発防止を求める措置命令を出した。
現在はいずれも改善されているという。
調査をした公正取引委員会中部事務所によると、同社は町内で旅館3軒を経営。旅館「いち豆(ず)」では2012年11月中旬~14年3月17日、三つの貸し切り浴場について、「1300メートルの地下より涌き出る良質な温泉」などとサイトに記載。しかし、調査で水道水を温めたものとわかった。
また、旅館「豆千本館」では12年10月頃~14年1月上旬、料理に「ジューシーな地元和牛の知多牛」を使っているとサイトに表示。旅館「豆千待月」も13年10月頃~14年2月末、料理に天然トラフグを使用していると掲載していた。しかし、それぞれ豪州産の輸入牛肉、養殖トラフグや安価なゴマフグを使っていたという。
天然トラフグの市場価格は1キロ当たり8000円前後が中心だが、養殖トラフグは同3800~4500円ほど、ゴマフグは同1050円ほどだったという。
同社は2008年2月に設立。取材に対し、「担当者が不在で、コメントできない」としている。
今回は有罪となるのか、不起訴となるのか?
ローラの父また逮捕 詐欺の疑い、デング熱療養費だまし取る 10/23/14 (スポニチ)
バングラデシュで診療を受けたと偽り、海外療養費をだまし取ったとして、警視庁組織犯罪対策1課は23日までに、詐欺の疑いで、タレントのローラの父親でバングラデシュ国籍の職業不詳ジュリップ・エイエスエイ・アル容疑者(54)=東京都江東区=を逮捕した。
逮捕容疑は2007年、バングラデシュでデング熱にかかり、病院で約1カ月診療を受けたとする虚偽の申請書を当時住んでいた東京都多摩市に提出し、海外療養費約98万円を同市からだまし取った疑い。
組対1課によると「入院したのは間違いない」と容疑を否認している。一方、バングラデシュ警察は、警視庁の照会に「病院には来ていない」と回答。申請書の医師のサインやゴム印は偽造されたものだったという。
組対1課は、同様の手法で、07年に民間保険会社2社から計約54万円、12年に別の1社から約49万円の保険金を詐取した疑いがあるとみて調べている。
ジュリップ容疑者は、別の詐欺容疑で7月に逮捕されたが、東京地検が8月「現時点では起訴するに足る証拠がない」として処分保留で釈放していた。
ジュリップ容疑者の在留資格は「永住者」。海外療養費は国民健康保険制度の一つで、海外で支払った医療費の一部が還付される。在留資格のある外国人も加入できる。
クリーンなイメージな小渕氏だが今回の経済産業相就任は結果としてマイナスイメージを植え付けてしまったと思える。事実はどうであれ、イメージは簡単に払しょくできないと思う。
小渕氏:売却旧宅に表札 家賃払わず母居住 (1/2)
(2/2) 10/23/14 (毎日新聞)
◇優子氏が理事務めた財団所有
小渕優子前経済産業相が一部相続した東京都内の土地建物を今年3月、小渕氏が9年近く理事を務めた公益財団が寮として使用する目的で購入しながら、現在も小渕氏の母親が住み続け、家賃も支払っていないことが分かった。財団側は事実関係を認めた上で「保守管理をお願いしているとの認識だった」と説明するが、専門家は「政治家側への利益供与に当たる疑いがある」と指摘している。【高橋慶浩】
登記簿や国会議員の資産及び所得等報告書などによると、小渕氏は父恵三元首相の死去に伴い2000年に東京都北区の約891平方メートルの土地と木造2階建て計約250平方メートルの建物を母親や兄弟と共に相続した。土地と建物は昨年12月に群馬県内の建設会社に一括売却された後、その約3カ月後に公益財団法人「本庄国際奨学財団」が計約4億5392万円で購入した。
同財団は恵三元首相の後援者で大手飲料メーカー創業者の故本庄正則氏が設立し、主に途上国からの留学生を支援している。小渕氏は01年4月に財団理事となり、06年9月の文部科学政務官就任に伴っていったん理事を辞任。政務官退任後の08年4月に再び理事となり、同年9月の少子化担当相就任に伴い再び辞任。10年4月にみたび理事に就任し、12年12月の副財務相就任で翌月辞任している。
小渕氏の所得等報告書によると、相続分(土地100分の14、建物6分の1)の売却益は5299万円余。また、恵三元首相の1998年の資産公開によると、妻(小渕氏の母親)はこの飲料メーカーの株を19万5250株(当時の株価で約9億9500万円相当)保有していた。
財団の財産目録や事業報告書によると、土地建物は「学生寮の将来の運営のため購入」したが、開設時期などは具体化していない。事務局長は「現在の建物を生かし、耐震補強をして将来的に留学生を10人ほど受け入れたい。購入元の建設会社の社長とは以前から知り合いで、寮を作りたいと話をしてあったので『どうですか』と持ちかけられた。以前の所有者が小渕家だったのは偶然」と話す。
一方で「建設会社には『家を残したい』と(小渕氏の母親が)希望を言ったと聞いている」と証言。購入から半年以上たった今月も「小渕」の表札が掲げられ、母親が住んでいるという。近くの不動産会社によると、付近の1軒家の家賃相場は専有面積100平方メートル弱で15万円弱といい、約250平方メートルなら単純計算で家賃は三十数万円。固定資産税は坪(3.3平方メートル)当たり2000〜3000円といい、891平方メートルなら五十数万〜八十数万円の計算となる。
事務局長は「我々がしょっちゅう行って窓を開け閉めできない。(母親の)荷物がいっぱいあり、それをかたすというので、それなら自動的に(保守管理を)やってくれるので家賃は必要ないと思った」と説明。「結果として小渕邸と知って購入したが、理事会に諮る際には建設会社から買うとしか言ってない」と明かし、「速やかに出てもらい、管理人を雇う」と述べた。
建設会社は「9月に社長が亡くなり、分からない」と話し、小渕氏の事務所は「質問が多岐にわたるので調査し確認でき次第、説明する」と文書で回答した。
政治資金に詳しい岩井奉信日大教授(政治学)の話 所有者が変われば家賃が発生するのが常識で、誰が見ても納得できる話ではない。公益財団の資格を逸脱した行為で不適切ではないか。買い取ったにもかかわらず居住実態が変わらないなら、そこに何らかのからくりがあるのではと思ってしまう。「家賃はいらない、固定資産税も負担します」では形を変えた利益供与と疑われても仕方がない。
2700万円超自腹補てんが可能なほど局長は報酬を受け取っているのか?それとも後でリターンされる筋書きなのか?運営で成功すれば成功報酬の額が大きいのか?もっと具体的に書いてほしかった。
局長が2700万円超自腹補てん 大阪観光局の音楽祭赤字 10/22/14 (スポニチ)
大阪府・市と地元経済界によって昨年4月に新設された大阪観光局がことし4月下旬に開催した国際音楽イベントが約9400万円の赤字となり、加納国雄局長が2700万円を自腹で補てんすることが22日、分かった。
大阪観光局によると、イベントは大阪国際音楽フェスティバル。大阪城の西の丸庭園でハービー・ハンコックら世界の著名ジャズミュージシャンを集めた国際ジャズ祭を開くなどした。
日本や韓国、台湾の歌手らが出演する「アジアンスターズスーパーライブ」も予定されていたが、韓国で旅客船「セウォル号」の沈没事故が4月16日にあり、「哀悼の意を表す」として中止を決定。これらの影響で当初約1億5000万円と見込んだチケット収入が約3300万円と低迷した。
府と市は、大阪観光局の運営費として年計5億円を支出している。観光局は「税金で補てんはできない」として、今回の赤字のうち約6700万円については他のイベントによる利益などを財源に充て、残りを加納局長が自費で負担する。
加納局長は、香港政府観光局の日本・韓国地区局長を務め、大阪観光局新設にあたり初代局長に起用された。22日会見した加納局長は「監督指導の力不足で多額の損害が出た。このような事態を引き起こし深く反省している」と陳謝した。
表の顔と裏の顔!なぜメディアに取り上げられるようなことをするのだろう。注目を浴びてしまうような気がするが?
フクロウカフェ店長ら逮捕 女性に売春させた疑い 10/21/14 (スポニチ)
福岡県警は21日、出会い系サイトを使い女性に売春させたとして売春防止法違反(管理売春)の疑いで、大阪府羽曳野市、会社役員伊東崇容疑者(39)ら4人を逮捕した。
県警によると、伊東容疑者はフクロウに触れ合えるカフェを福岡市などに展開する会社の取締役で、同市の「フクロウのみせ 博多店」では店長を務め、メディアに取り上げられていた。
逮捕容疑は今年1月~9月、複数の女性に、出会い系サイトで誘った客とホテルで売春させ、収益を得た疑い。「リリアン」の名称で県公安委員会に無店舗型風俗店の届け出があり、伊東容疑者は実質的な経営者だった。
県警によると、売春による収益は年5千万円以上あったといい、暴力団の資金源になっている可能性もあるとみて調べている。
インターネットオークションだけでなく、走行距離メーターの改ざんは困る。インターネットオークションで入札した事はあるが落札できなかった。やはり、かなり安くないと騙された時のリスクを考えれば写真と情報だけでは高い値段で出来ない。あと、運送料も決して安くはないのでリスクを感じる。
話は元に戻るがなぜ改ざんがばれたのだろう。車検証か何かでばれたのだろうか。車検証まで偽造しないと前回の走行距離で改ざんがばれる可能性もある。
走行距離半分以下に改ざん、中古車をネット出品 10/21/14 (読売新聞)
インターネットオークションでの走行距離改ざん車の販売事件で、大阪府警生活経済課などは20日、中古車販売会社社長、谷川光朗(61)(兵庫県芦屋市浜町)と従業員、広島敏幸(28)(堺市西区鳳南町)の両容疑者を詐欺と不正競争防止法違反(誤認惹起(じゃっき))の両容疑で再逮捕した。
発表によると、2人は共謀し、6~8月、約12万~19万キロ走行していた中古の軽乗用車2台の走行距離メーターを、専用機器を使って約5万~7万キロに改ざんしてオークションに出品。三重県と大東市の男性にそれぞれ約24万円で販売した疑い。
谷川容疑者は「詐欺ではない」などと容疑を否認。広島容疑者は認めている。1~8月に390台を販売しており、被害者は36都府県に広がっているという。
大分の教組は活動的で、行動に移す組織なのだろうか?
児童に案内配る 教組主催の懇談会 大分の教員ら200人超厳重注意 10/21/14 (産経新聞)
大分県の日田、竹田両市教育委員会は21日、県教職員組合が主催する懇談会の案内文を勤務時間中に児童らへ配ったのは、地方公務員法の職務専念義務違反に当たるなどとして、教員ら200人超を厳重注意にしたと明らかにした。
懇談会は7~8月に各地で開催。日田市教委によると、案内文を児童に持ち帰らせたり、学級名簿の住所に案内文を送ったりした市立小学校の教員らが165人おり、15日付で厳重注意にした。
一方、竹田市教委は、PTA会合後に案内文を保護者に配るといった行為をしたとして、市立小中学校の教員ら69人を20日付で厳重注意とした。
勤務中の組合活動は地公法で禁止されており、日田市教委は「服務規律の徹底を図る」、竹田市教委は「法令順守の徹底に努める」とそれぞれ話している。
韓国警察のように厳しく取締り、船を没収すればサンゴ密漁は減るであろう。しかし、韓国警察が経験しているような中国船員との衝突が予想される。韓国警察官のように殺害される可能性もあるし、防衛を優先すれば船員が負傷又は死亡するかもしれない。見逃して問題を放置するか、取り締まって違う種類の問題を抱えるのか、決断する必要があると思う。
小笠原:サンゴ密漁 中国船、夜も横行 無灯火で衝突危険 10/21/14 (読売新聞)
小笠原諸島(東京都)近海で中国漁船によるサンゴ密漁が横行している問題で、衝突などを恐れて漁を控える漁船が相次ぎ、地元漁業への影響が深刻化している。海上保安庁が取り締まりを強化しているが、全てを拿捕(だほ)するのは難しく、中国漁船が領海内に入るたびに追い出す「イタチごっこ」が続いている。【佐藤賢二郎】
「鋼鉄製で100トン以上の中国船に対し、こっちは10トン未満のグラスファイバー製。戦車と乳母車ぐらいの差があり、当たったらひとたまりもない」。小笠原村議会議長でサンゴ漁師の佐々木幸美さん(71)は語る。同諸島周辺の水深150〜200メートルの大陸棚は、中国などで珍重されるアカサンゴの他、高級魚のヒメダイやハタが取れ、地元漁師の貴重な漁場となっている。
だが、中国漁船が急増した9月以降、地元漁船の漁網が引っかけられたり、中国船に囲まれたりするトラブルが多発。中国船は夜間、無灯火で操業することも多く、衝突の危険もあるため、地元漁船の多くが操業を控えているという。
佐々木さんによると、小笠原周辺では約15年前まで、台湾漁船による大規模なサンゴ密漁が続き、生態系が破壊された。海底は魚たちの産卵場所でもあり、漁獲高は激減。台湾当局の規制強化で密漁が無くなり、環境が回復したばかりという。
父島の漁師、関伴夫さん(48)は「白昼堂々と操業し、罪の意識も無い。笑顔で手を振る船員もいた」と話す。今月に入って海保が大型巡視船2隻を投入し、態勢を強化した結果、大きな船団は姿を消したが、周辺では今も中国漁船が目撃されており、「監視が手薄になればまた戻ってくる。手遅れになる前に抜本的な対応を取ってほしい」と訴える。
ただ、海保は沖縄県・尖閣諸島周辺で常態化する中国公船による領海侵犯に対応するために全国の巡視船を投入せざるを得ない状況が続く。また、中国漁船を拿捕すれば、巡視船で本土まで4〜5日かけてえい航する必要があり、大幅な戦力ダウンになる。警告を無視して領海内で操業を続けるような悪質なケース以外は拿捕していないのが現状だ。
政府は10月以降、外交ルートを使って複数回、中国側に注意喚起や再発防止を求めているが、効果は出ていない。
契約する前に契約書又はリースする新型機器が要求する機能を満たしているのか確認しなかったのか?千葉県民ではないが、4台分129万7800円X5年もの税金を溝に捨てるのはもったいないし、間抜けだ!11年度に1台を購入しているのなら新型機器のスペックやどのような機能が不足しているのか事前にチェック出来た筈だ。しかしながら、12年12月に4台をリース契約。ばかである例えにも使えるとケースだ。
使用不能機器4台にリース料…県自動車税事務所 10/21/14 (読売新聞)
千葉県自動車税事務所が導入した収納に使う新型機器が、2012年12月から現在まで使えない状態となっているのにリース料が支出されているとして、県監査委員が県税務課と同事務所に対し、改善を求めて注意していたことが20日、わかった。
13年度、全く使われなかった機器4台にリース料129万円が支払われていた。
同課によると、新型機器は自動車税と自動車取得税の納入を受ける際、証紙を貼る代わりに金額を印字することで納入済みの記録とすることができる。11年度に1台を購入、12年12月に4台をリース契約した。
だが、同じく12年12月に使用を始めた自動車税・自動車取得税申告書の光学式文字読み取り装置(OCR)では、新型機器で印字した数字が読み取れなかった。このため、以前使っていた旧型の機器を再び使用し始めた。旧型であれば、OCRで読み取ることができたという。
旧型は10年ほど前に購入して使用していたが、製造中止となったため新型へ切り替えを進めようとしていた。同事務所は現在も旧型を使用する一方、5年間の一括契約としていたため新型4台のリースも受け続けており、昨年度は4台分129万7800円を支払った。監査委員はこのリース代を問題視した。
県税務課は「新型機器の設定の修正を試みたが、できないとわかり、その後、OCRの改修を進めている」と説明している。(田島大志)
虚偽の説明に対する処分は当然。虚偽の説明するほどの状況が存在すること自体、高血圧治療薬「ディオバン」問題が深刻であった事を示していると思う。
ディオバン問題で虚偽説明の千葉大教授を戒告 10/20/14 (読売新聞)
高血圧治療薬「ディオバン」の臨床研究データの改ざん問題で、千葉大は20日、大学の信用を傷つけたとして、同大薬学研究院の高野博之教授を戒告処分とした。
発表によると、教授は研究データの統計解析をノバルティスファーマ社の元社員に依頼するよう大学院生に指示していたにもかかわらず、同大の調査委員会に「研究グループ自らが統計解析した」と虚偽の説明を行い、調査の混乱と長期化を招いた。
調査委は、今年7月にまとめた最終報告で、論文の責任著者の小室一成・東京大教授(当時は千葉大)についても、東大側に処分を求めるように促している。
千葉大は20日、研究不正の再発防止策も発表。学長をトップに、研究に不適切な点があれば、研究の停止を命令できる全学的な統括組織を新設する。大学病院も、臨床研究を目的とした企業からの奨学寄付金の受け入れを禁止する。
弁護士に言われた事がある。法は完全ではない。法は全ての人を守るものではない。悪法であっても法は法である。しかし、多くの人が法について勘違いをしている。法に問題があれば、被害者にならないように注意する事。問題に気付いた時に声を上げる事。状況を変える事が出来なければ、被害者になる前に逃げる又は退避出来る選択肢があるのか考える。問題を解決するために様々な方法を取る。(方法によっては違法のリスクもあるので注意。)
多くの従業員ががんでなくなっても罰金刑としかならない。労働安全衛生法が改正されない限り、今後もこの程度で済ますことが出来ると言う事である。
胆管がん 罰金刑の検察判断に被害者憤り「処分甘すぎる」 (1/2)
(2/2) 10/16/14 (産経新聞)
元従業員ら17人が発症、うち9人が死亡した大阪市の校正印刷会社「サンヨー・シーワィピー」の胆管がん問題は16日、会社と社長の略式起訴で決着した。会社側の責任追及や真相解明を望んできた被害者からは、罰金刑にとどまる検察の刑事処分に「甘すぎる」と憤りの声が漏れた。
同社で胆管がんによる死者が初めて出たのは平成10年。15年と16年にも相次いで従業員が発症したが、事態は変わらなかった。会社側が原因物質と推定される「1、2ジクロロプロパン」が含まれない洗剤に変更したのは、18年になってからだった。
昨年9月、大阪労働局は労働安全衛生法違反の疑いで山村悳唯(とくゆき)社長(68)らを書類送検。山村社長は当時、取材に対し「知識不足で認識していなかった」と話していた。
ある被害者は、13年に従業員が受けた安全講習で産業医を設置することが触れられていたと指摘。「会社側が必要性を認識していながら放置した結果、これだけの被害を招いた証拠だ」とし、大阪労働局などに同社の責任を訴えてきた。
書類送検から1年以上の期間を経て検察が出した処分は略式起訴。ある被害者は「多くの人ががんに苦しみ亡くなったにもかかわらず、罰金刑だけで終わらせていいのか」と話した。
関係者によると、一連の問題の経営責任を明確にするため、山村社長は近く辞任し、後任の社長には次男の健司取締役(37)が就任するという。
大阪胆管がん、全被害者と示談成立へ 印刷会社社長、略式起訴の方向で調整 09/14/14 (産経新聞)
大阪市中央区の校正印刷会社「サンヨー・シーワィピー」で元従業員ら17人が胆管がんを発症し、うち9人が死亡した問題で、同社と全ての被害者との間で示談が成立する見通しとなったことが13日、関係者への取材で分かった。亡くなった元従業員の遺族らに1千万円超を補償するなどの内容とみられる。大阪地検は示談成立後、労働安全衛生法違反罪で同社の山村悳唯(とくゆき)社長(68)を略式起訴する方向で調整している。
同社と補償交渉を進めていたのは、発症した17人のうち、死亡した8人の遺族と生存患者6人で構成する被害者の会。複数の関係者によると、同会側は示談を受け入れる方針をほぼ固めたという。
補償問題をめぐっては昨年9月、死亡した1人の遺族と生存患者2人との間で示談が成立。遺族には1千万円、患者には各400万円(後に亡くなった場合はさらに600万円)を支払うことでまとまった。被害者の会側への補償額は、すでに示談した3人の額を上回る見通しのため、同社は3人についても被害者の会と同じ額まで上積みする方針だという。
同社は平成23年4月~24年4月、従業員が50人以上いるにもかかわらず、法定の産業医や衛生管理者を置かず、衛生委員会も開かなかったとして、24年5月に大阪中央労働基準監督署から是正勧告を受けた。同社は勧告に基づき衛生管理体制を改めたが、大阪労働局は昨年9月、労働安全衛生法違反容疑で同社と山村社長を書類送検した。
大阪地検は業務上過失致死傷罪の適用も検討し、被害者への聞き取りなどを進めたが、同社側が従業員のがん発症を事前に予想するのは困難だったと判断。示談成立後に刑事処分を決定する方針で、最終的には被害者側の処罰感情を考慮した上で決めるとみられる。
【用語解説・胆管がん】肝臓で作られた胆汁を十二指腸に流す胆管にでき、治療が困難ながんの一つとされる。平成24年5月、サンヨー・シーワィピーの元従業員らが相次いで発症し、4人が死亡(後に9人に拡大)していたことが発覚。以降、全国の印刷業従業員らの発症が確認された。厚生労働省の専門家検討会は昨年3月、印刷機の洗浄剤に含まれる化学物質「1、2ジクロロプロパン」などが発症原因と推定する報告書をまとめた。これまでに大阪や愛知、宮城など10都道府県で34人が労災認定されている。
「警戒レベルの導入直後から、新制度を疑問視する声はあった。静岡大防災総合センターの小山真人教授(火山防災学)は情報発信にメリハリがつくようになったことを評価する一方、『言葉の意味が住民感覚とずれている。なぜ噴火の心配の無い状態のゼロから始めないのか』と当時から指摘していた。」
「気象庁も『現状のレベル1は幅が広すぎるかもしれない。活動が静穏な火山もあれば、やや活発化した状態の火山もある』と認める。」
責任は誰なのかになるのかとなると責任逃れのような発言。問題や改善する点があるのならすみやかに対応するべきだろ。本当に申し訳ないとか思っていないと思う。責任をかわすために検討とか、改善とか決まり文句を言うのだろう。交通事故の死亡者数を考えると、今回の犠牲者はたいした数ではない。しかし、関係者にとっては数の問題ではない。犠牲者の関係者ではないので怒りや憎しみは感じないが、キャリアや公務員の体たらくにはいつもウンザリさせられる。少なくとも決定権や発言権のあるキャリアに責任を取らして降格、又は、減給ぐらいはさせるべきだろう。
噴火警戒:最低の「レベル1」実は「安全」ではない 10/15/14 (毎日新聞)
御嶽山(おんたけさん)の噴火を受け、「噴火警戒レベル1」の在り方が問題となっている。「レベル1=噴火の恐れがなく安全」と誤解されるケースがあり、専門家からは「静穏な状態のレベル0を新たに設けるべきだ」との声が上がっている。【飯田和樹】
御嶽山の山頂付近で噴火に遭い、五の池小屋に避難した後、岐阜県側の小坂口に下山した千葉県松戸市の女性(69)は、登山前に火山情報を確認したという。「私がリーダーだったので、いろいろなホームページを見て情報を集めた。御嶽山はレベル1だった。噴火するとはまったく思わなかった」と話す。
噴火警戒レベルは2007年12月、「火山活動度レベル」に代わって火山の活動状況を伝える方法として導入され、1〜5に分類されている。活動度レベルは、火山がどれほど活発かという情報だけで、地元住民や登山者が具体的にどのような対策を取ればよいかには触れていなかった。これを補うため、噴火警戒レベルでは、周辺自治体と協議しレベルごとの防災対応を明確にした。
レベル1は「平常」と位置付けられているが、活動の度合いに幅がある。09年4月から活動がやや活発になり、今年6月にレベル2の「火口周辺規制」に引き上げられた群馬・長野県境の草津白根山について、気象庁火山課は「レベル2に引き上げる前から、実質的にはレベル1.5のような状況だった」と説明する。
警戒レベルの導入直後から、新制度を疑問視する声はあった。静岡大防災総合センターの小山真人教授(火山防災学)は情報発信にメリハリがつくようになったことを評価する一方、「言葉の意味が住民感覚とずれている。なぜ噴火の心配の無い状態のゼロから始めないのか」と当時から指摘していた。
災害時の情報伝達に詳しい同センターの牛山素行教授(災害情報学)は「レベル1であれ、活火山には元々リスクがあるというのだろうが、一般の人に伝わりにくい。1の状態に幅があるなら、静穏な状態をゼロにするのも一つの方法だ。現在、大雨など他の防災気象情報のレベル化を進めており、整合性も取れるかもしれない」と提案した。
気象庁も「現状のレベル1は幅が広すぎるかもしれない。活動が静穏な火山もあれば、やや活発化した状態の火山もある」と認める。登山者に分かりやすく情報を提供する方法を考える検討会の新設を決めている。
人生、いろいろ。母子家庭だったのだろうか?経済的に祖母に頼り切っていたので、別居出来なかったのだろうか?
北海道祖母・母惨殺 娘は祖母に『おしん』的仕打ち受けた 10/14/14 (NEWSポストセブン)
自然が豊富で、のどかな雰囲気が漂う北海道南幌(なんぽろ)町で10月1日に起こった事件は衝撃的なものだった。
1階の寝室に母親(享年47)が、2階の寝室に母方の祖母(享年71)が、寝間着姿のまま絶命していたのだ。母親は喉仏から頸動脈まで切り裂かれ、祖母は頭と胸を中心に7か所刺されており、部屋中が血の海と化していた。
警察に事情聴取を受けているA子(17才)はその家の三女。そのA子を取り巻く環境は地獄そのものだったという。祖母からの仕打ちは相当厳しかったようだ。
「“誰のおかげで飯が食えてるんだ!”って、家のことを全てA子ちゃんに押しつけ始めたんです。小学校の時から家中の掃除やゴミ出しだけでなく、冬になると、彼女は早朝5時から極寒の中、1人で雪かきさせられていました。
このあたりは積雪は1mを超えるんですが、それでも、家の前の雪を全てきれいにしないと、おばあさんは杖でガンガンA子ちゃんを叩き、怒鳴りちらすんです。ある時、私が心配して声をかけたら“ありがとうございます。大丈夫です”って…。
けなげに家の仕事をするA子ちゃんの姿は、かつて大ヒットしたNHK朝ドラ『おしん』そのものでした」(A子の知人)
祖母は、家の仕事を優先させるためA子に友人と遊ぶことさえ許さなかったのだ。
夕方5時までに必ず帰宅させ、庭の草むしりや植木の手入れを毎日やらせ、洗濯や犬の散歩も彼女に強制した。
「ちょっとでも遅れると、おばあさんは怒鳴って叩きますからね。一度、遅刻した罰で叩かれて骨折して、入院したこともありますよ。こういう暴力は、A子ちゃんが高校に入った後もずっと続いていて、最近も、5時直前に慌てて帰宅するのを何度も見ています」(近隣住人)
また、報道では、A子が暮らしていたのは、自宅の“離れ”とされているが、その表現は現実と乖離している。
「A子ちゃんが暮らしていたのは、物置小屋です。4畳ほどの所に、家の荷物が置かれて、わずかなスペースに机だけが置いてあるんですから。彼女は出入りも玄関からではなくて、車庫の裏にある潜り戸を通って裏庭に出て、そこから物置部屋に入っていました」(前出・近隣住人)
“しつけ”と呼ぶにはあまりに過酷なA子の生活の中で、救いとなるべき存在は、母だったはずだ。しかし、母もまた祖母の支配下にあった。
「おばあさんは、母親にもきつく当たっていたんです。“お前の教育が悪いから、この娘はこんなにグズなんだよ!”って。実の娘でさえも、容赦なく杖で叩いていたそうです。子供の学費や生活費など、ほとんどあの人のお金でやりくりしていたので、母親も何も言えなかったそうです。
そのうち母親もノイローゼになって、精神的に不安定になっていきました。いつしか彼女も“あんたのせいでアタシが怒られるんだよ!”って、ことあるごとにA子ちゃんをなじるようになったんです」(前出・近隣住人)
張りつめた心を癒す時間も場所もないまま過ごす毎日は、彼女の心に、負の感情を澱のように蓄積させ、いつしかその感情は心の容量を超えてしまった。
一線を踏み越えたA子に対し、同居していた姉の悲しみは深い。
「姉はこの数年、ずっと仕事で忙しくて、妹の悩みを聞いてあげる時間がなかったそうで、“あの娘が苦しんでいるのを知っていながら、なぜ私が支えになってあげられなかったのか”って、泣き続けているそうです…。彼女は犯人隠避の疑いで警察の事情聴取を受けていますが、“事件を防げなかったのは私の責任です”とまで話しているそうです」(捜査関係者)
※女性セブン2014年10月23・30日号
規則は規則。「低温停止中のため実害はないとみられる」かどうかは問題ない。
事故が起きたが、被害が出なかったらそれで許されるのか?信号無視でも事故にならなかったら、警察に捕まっても罰金や減点は免除されるのか?大量の機器点検漏れから事実上の運転禁止命令が出ている日本原子力研究開発機構の高速増殖炉もんじゅ(福井県)は廃止、解体したほうが良いのでないのか?これまで多額の税金を投入して無駄になってきたと思うし、解体費用も莫大に掛かると思うが、解体した方が良い。
脱税指南の国税OBに有罪 名古屋地裁「巧妙で悪質」 10/14/14 (共同通信)
顧客の中小企業に脱税を指南したとして法人税法違反罪に問われた名古屋国税局OBの元税理士鈴木健彦被告に名古屋地裁(入江猛裁判官)は14日、懲役1年、執行猶予4年、罰金1千万円の判決を言い渡した。
判決理由で、入江裁判官は「税理士として適正な申告をすべきだった。脱税報酬の相当額が女性との交遊費に使われ、方法も巧妙で悪質だった」と指摘。執行猶予を付けた理由として、税理士業を廃業し、反省していることを挙げた。
判決によると、09~11年、税理士として大阪市や三重県四日市市などの8社の税務処理をした際、架空の外注費を計上するなどして計約4200万円を脱税させた。
規則は規則。「低温停止中のため実害はないとみられる」かどうかは問題ではない。
事故が起きたが、被害が出なかったらそれで許されるのか?信号無視でも事故にならなかったら、警察に捕まっても罰金や減点は免除されるのか?大量の機器点検漏れから事実上の運転禁止命令が出ている日本原子力研究開発機構の高速増殖炉もんじゅ(福井県)は廃止、解体したほうが良いのでないのか?これまで多額の税金を投入して無駄になってきたと思うし、解体費用も莫大に掛かると思うが、解体した方が良い。
もんじゅ:監視カメラ3分の1が故障 1年半放置も 10/12/14 (毎日新聞)
大量の機器点検漏れから事実上の運転禁止命令が出ている日本原子力研究開発機構の高速増殖炉もんじゅ(福井県)で、1995年のナトリウム漏えい事故をきっかけに原子炉補助建物に設置された2次系冷却材の監視カメラ計180基のうち、約3分の1が壊れていることが11日、関係者の話で分かった。
原子力規制庁が9月に実施した保安検査で判明。壊れたまま1年半以上放置されていたものもあり、保安規定違反の疑いが持たれている。低温停止中のため実害はないとみられるが、機構の安全管理体制が問われ、命令期間が長期化する可能性が出てきた。(共同)
「『法の下の平等』に反するとの指摘」は大義名分又は屁理屈だと思う。個人的な意見だが、日本人を顧客にしないとカジノは成り立たなくなると思う。カジノが目的なら敢えて日本に来なくても良い。
ラスベガスはカジノだけでは収益が出なくなったから家族で来れるようにアトラクションやテーマパークのようなホテルを提供した。ラスベガスをまねするだけで儲かるのであれば既に儲かっているカジノがあってもおかしくはない。ただ、同じような大規模なカジノエリアは必要とされていないと言う事だ。お金があればラスベガスに行く旅費などたいした金額ではない。カジノが目的でなくとも、今のラスベガスは家族で楽しめる。シンガポールと比べると、ラスベガスの方がスケールがでかい。広範囲で考えると、カリフォルニアのディズニーランド、ユニバーサル・スタジオ、シーワールド、ハリウッドそしてグランドキャニオンなどもついでに行ける。実際に、ユニバーサルスタジオとグランドキャニオン以外はラスベガスに行ったついでに家族と一緒に行った。
「多重債務者の利用は認めない」は当然のことすぎる。住宅ローンや車のローンなど高額のローンがある人達の利用は認めないとするべきだろう。年金問題や将来の蓄えのない人々を考えると結局、見殺しに出来ないので税金が投入される事となる。
カジノ、日本人利用へ方針転換 一定の資格要件設定 10/10/14 (東京新聞)
カジノ合法化を目指す超党派の「国際観光産業振興議員連盟」(会長・細田博之自民党幹事長代行)は10日、幹部会を国会内で開き、カジノを中心とする統合型リゾート施設(IR)整備推進法案に関し、日本人にも一定の資格要件を設けることでカジノの利用を認めることで一致した。法案を修正し、今国会中の成立を目指す。
当初は利用を外国人に限定する方向だったが、「法の下の平等」に反するとの指摘を踏まえ、日本人にも開放することにした。ただ多重債務者の利用は認めないなどの要件を設定し、カジノへの批判に配慮する。
法案は議員立法で昨年12月に提出され、継続審議となっている。
(共同)
事実だったらおもしろい。キャリアで出世を諦めきれずにとんでもない愚かな計画を実行しようとしたことになる。本命の女性を諦めるか、出世を諦めればこのような結末にはならなかったと思う。
内閣府キャリア官僚、不倫で妻殺害のため、韓国からゴムボートで入国図り海上で死亡? 10/09/14 (Business Journal)
前クール(7~9月期)の連続テレビドラマで、上戸彩演じる平凡な主婦が不倫に落ちていくストーリーが話題を呼んだ『昼顔~平日午後3時の恋人たち~』(フジテレビ系)。9月25日放送の最終回は平均視聴率16.5%(関東地区、ビデオリサーチ社調べ)をマークするなど数字的にも健闘したが、そんな『昼顔』も真っ青な“不倫愛憎劇”が現実に起こっていたのだ。
今年1月下旬、北九州市の沖合で、ゴムボート内で男性(30歳)の死体が発見された。男性が内閣府のキャリア官僚であったこと、韓国からゴムボートで対馬海峡を渡る途中に死亡したことから、スパイ疑惑が囁かれるなど発見当時は一部で話題になった事件だ。捜査を担当した海上保安庁は9月2日、「事件性なし」として捜査を打ち切ったが、この男性が帰国しようとした理由については「プライベートな理由のため」として公表を控えた。
しかし、事情を知る公安関係者は、その真相を次のように明らかにする。
「海上保安庁が発表したとおり、彼はスパイではありませんが、映画さながらの激しい愛憎劇であったことは間違いありません」
同関係者によれば、キャリア官僚は東京に妻を残して米国留学していたという。
「彼は結婚前に付き合っていた本命の女性がいたのですが、別の女性といわゆる『できちゃった婚』で結婚をしたのです。それが、日本に残していた現在の奥さんでした」
同関係者によれば、本命の交際相手がいながら別の女性を妊娠させてしまったこのキャリア官僚は、その後逃げるように米国留学し、そしてその本命の女性と復縁するために日本に密入国し、邪魔な存在となった妻を殺害しようと企てたというのだ。それにしても、なぜ真冬の対馬海峡をゴムボートで渡ろうなどと無謀なことを考えたのだろうか。
「公用旅券は通常、赴任・帰任の一次旅券なので、自由に帰国することができない。だから、会議参加を名目に韓国へ渡り、そこから日本への密入国を目指したのです。日本にいないはずの人物が犯人として疑われることはないと考えたのでしょう。事件当初、韓国政府も自国で活動していた日本スパイが秘密裏に脱出したと本当に信じていました。我々は調査して発覚した事件の真相を韓国情報関係者に説明したのですが、なかなか信じてもらえず苦労しましたよ」(同)
本当に「海峡を越えた愛」を実践しようとしたキャリア官僚――。色恋沙汰に学歴や年齢は関係ないが、日本を背負うキャリア官僚がこの事件を起こしたという点が、一番の衝撃だといえよう。
(文=山野一十)
イスラム法学が専門の元同志社大教授は東大及び東大大学院卒。最近、東大卒がネガティブな事件で注目を受けているような気がする。
昔、イスラム教の外国人のお客がモスクに行きたいと行ったので下北沢のモスクに連れて行った事がある。祈り始める前に、男性に対してたぶんアラビア語?、女性に対しては日本語でアナウンスをしていたことに驚いた。イスラム教に改宗した日本女性の多い事。たぶん、イスラム教の男性と結婚した時に改宗したのだろう。連れて行ったお客と離れてはいけないと思い、祈る場所まで行った。スピーカーからお祈りが聞こえてくると、皆、祈り始めた。自分は、イスラム教徒でもないし、イスラム教にも興味もないので座っていた。周りの人が、何で祈らないのか不思議に思っているのか、ちらっとこちらを見るのがとても不快だった。祈りの後になぜここに来たのかと何人かに聞かれたのも不愉快だった。イスラム教のお客を連れて来ただけだからと言っても、なぜアラーを信じないのかとか、いろいろと質問された。良い経験になったがもう行きたいとは思わなかった。
基本的にあまり宗教に熱心になりたいとは思わないので宗教を熱心に信仰する人達と宗教について話すのは好きではない。なぜなら宗教の教え=基本的な思考の基準となっているからだ。宗教を否定する事は彼らを否定する事と思われても困る。
奇麗事でお互いを尊重しあうとか言うけど、直接、関係してくる立場にいると無理だと思う。偽善者か、ドリーマーの言葉だと思う。良いと思っていない事をそれは良いと言うこと自体がそもそも嘘。相手を理解した上で妥協し合う点を見つける事が共存する方法だと思う。
元教授「イスラム国司令官に連絡」 北大生の渡航計画 10/09/14 (朝日新聞)
中東の過激派組織「イスラム国」に北海道大の男子学生(26)=休学中=が戦闘員として加わろうとしたとされる私戦予備・陰謀事件で、古書店関係者から学生を紹介された元大学教授が7日、朝日新聞の取材に応じ、「『イスラム国』の知り合いの司令官と連絡を取り、学生のシリア渡航計画を伝えた」と話した。
警視庁公安部の事情聴取に対して、学生が「元教授から『イスラム国』はあなたを歓迎している、と言われた」と話していることも判明。公安部は元教授が実際に「イスラム国」側に仲介したとみている。
取材に応じたのは、イスラム法学が専門の元同志社大教授、中田考氏(54)。イスラム思想の分野では国内屈指の研究者で、昨年3月以降、調査などで5回、「イスラム国」の支配地域に入り、現地の様子を発表している。
中田氏の説明では、シリア渡航希望者の求人をしていた東京・秋葉原の古書店関係者の紹介で、8月初旬に学生と面会。学生は「早く行きたい」と話し、中田氏の立ち会いでイスラム教に入信した。アラビア語の勉強もしていたという。
早稲田、小保方氏への処分は妥当?甘い? 鎌田総長「大学側にも重大な不備・欠陥」 (1/2)
(2/2) 08/26/14 (産経新聞)
「普遍性を持った原則を定めた中での苦渋の決断」。早稲田大学の鎌田薫総長はこう述べた。
STAP問題の渦中の人、小保方晴子氏が早稲田大学に提出した博士論文については、STAP論文の不正への疑惑が噴出したのと並行して、やはり数多くの疑義が浮上。早稲田大学のブランドを大きく毀損するに至った。
早稲田大学は10月7日に会見を開き、小保方氏の博士号を条件付きで取り消すと発表した。つまり「執行猶予付きの有罪判決」だ。併せて再発防止のためのガイドラインも策定。7月17日の調査委員会報告以降、先進理工研究科運営委員会、研究科長会での審議を経て、10月6日に総長が最終決定し小保方氏の弁護士に文書で伝えたという。
■調査報告書の結論よりも踏み込んだ
7月17日の調査委員会報告書では、数々の不正はあるものの、一度与えた博士号を剥奪することはできない、としていた。報告書は、草稿を誤って提出したという小保方氏の言い分を前提としていた。総長判断では、この言い分は認めたものの、その行為自体が「研究者として果たすべき基本的な注意義務違反であり、重大な過失である」として、学位取り消しに相当する、と一歩踏み込んだ結論を出した。
取り消しを行わない条件は、1年以内に、研究倫理教育や新たに任命される担当教授の指導を受けて論文を完成させ、審査を通ること。審査を通らなければ博士号は取り消しとなるが、通れば小保方氏の博士号はそのまま維持される。
調査報告書で認定された数々のコピー&ペーストは著作権侵害と認定されている。通常なら、一件でも発覚すれば論文は取り下げとなるレベルだ。こういった研究社会の常識に比べ、この早稲田大学の「執行猶予付きの有罪判決」は、玉虫色の決着にも見える。
だが、鎌田薫総長は、「大学側にも指導、審査の過程に重大な不備・欠陥があり、学位を受けた者(小保方氏)だけに一方的に責を負わせることは妥当でない」とした。また、「信頼回復のためにも、大学側の責任を果たすことが大切」と強調した。
大学側の重大な欠陥・不備とは、指導が十分に行き届かなかったこと、草稿を本稿として受理しそのまま博士号審査を通過させてしまったことだ。これにより小保方氏の指導教官であり、博士論文主査を務めた常田聡教授は1カ月の停職、副査は訓戒。また鎌田総長自身と当時の研究科長も管理責任を取り、役職手当20%をそれぞれ5カ月、3カ月自主返上するとした。
■教育の場としての大学側の責任も重視
公表された文書の冒頭には、(1)「学問の府」として不適切な内容を含む学位論文をそのまま公開されている状態を放置しない、(2)「教育の場」として指導と責任を放棄しない、という2点にアンダーラインが引かれて強調されている。
論文不正は認めないという科学界の強い論調に対し、教育機関としての責任を果たすことを強調したもので、単純に甘いだけの決定とも言い切れない。訴訟対策という側面もある。また、今年度から一度不正で取り消されたら二度と提出させないルールに変更されたこともあり、「大学側に不正防止のための施策が十分でなかったのに、無条件で学位を取り消すことは不誠意である」という考え方は揺るがないようだ。
ただ、鎌田総長は「日本のサイエンスの信頼を失墜させたとまでは考えていない」と強い口調で語った。これに対し、国内外の研究者から「早稲田出身のポスドクは危険。あえて採用する気になれない」「日本のPh.Dは採用しない」とまで言われていることに対する危機感が弱いのではないか、と見る向きも少なくない。
今後、小保方氏が学位を維持するためには、担当教授の指導の下に論文を完成させて、2015年10月6日までに審査を通る必要がある。早稲田大学の学位審査は2月と9月の年2回なので、現実的に15年9月の審査に間に合わせなければならないということになる。ただ、数々の不適切な内容が指摘されていることもあり、単純に論文の訂正を提出すれば済むというわけではない。
あらためて研究者倫理教育などを受け、論文の書き方についても厳しい指導が必要とされており、前回のように合否判定の3週間前に提出するというわけにはいかない。数カ月前には提出しなければならないだろう。担当教授は主査、副査ともに今後決定するという。
一方、早稲田の学位論文不正は小保方氏だけではないという指摘も数多く上がっている。これを受けて、論文電子化が本格的に始まった2006年以降について精査を進めている。現時点で700件(全体で2500件)の確認作業を終了、大きな不正はなかったものの不適切な記載が複数見つかっているという。
重大な不正の場合は学位取り消し、そこまでに至らない場合は本人に連絡を取り適切な是正措置を行い、経過は公表する。小保方氏だけ特別扱い、と言われないように気を配っているのが見て取れる。
■スーパーグローバル選定で信頼回復は焦眉の急
再発防止については、不正はもちろん、不適切な論文を出さないよう、厳密な事前チェックを求めるガイドラインを定めている。「事後的な処分は問題があるが、事前であれば修正させるなり不合格とすることができる。不正論文に学位を与えない努力を最優先にする。学位取り消し事由にならないレベルであっても不合格とする」(鎌田総長)。
早稲田大学は9月26日に文部科学省のスーパーグローバル大学創成支援事業対象に選定された。10年間、100億円(うち50億円は補助金)を投じて人材と研究内容の高度化を図り、世界ランキングトップ100を目指す。海外からの留学生獲得も重要のテーマのひとつであり、そのためにも1日も早く信用の回復を図らなければならない。
小保方氏指導の早大教授を停職…総長も手当返上 10/08/14 (読売新聞)
理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダーが2011年に早稲田大に提出した博士論文に、盗用などの不正が見つかった問題で、早大は7日、「指導・審査体制に不備があった」として、小保方氏の指導教員の常田聡教授を停職1か月の懲戒処分にすると発表した。
早大によると、常田教授は、小保方氏の博士論文を審査した責任者だったが、小保方氏の博士論文の最終確認を怠ったため、不備のある論文が受理されたと判断した。このほかに審査に関わった別の早大教授は、補助役だったため懲戒処分ではない訓戒とした。処分はいずれも3日付。
鎌田薫総長は役職手当の20%を5か月分、小保方氏が所属した研究科の当時の研究科長は、役職手当の20%を3か月分、それぞれ自主的に返上する。
北海道大学に合格できる能力があってもこのような結果となる。
イスラム国:北大生ら参加計画 警視庁家宅捜索(1/2)
(2/2) 10/07/14 (毎日新聞)
イスラム過激派組織「イスラム国」に参加するためシリアに渡航しようとしたとして、警視庁公安部は6日、刑法の私戦予備および陰謀の疑いで、北海道大学に在籍し、現在は休学中の学生(26)ら複数の日本人から任意で事情を聴くとともに、大学生の住居とみられる東京都杉並区の一軒家など関係先数カ所を家宅捜索した。
捜査関係者によると、大学生は「シリアに渡航し、イスラム国に加わり戦闘員として働くつもりだった」と話しているという。警視庁によると、国内で同容疑を適用した強制捜査は初めて。
公安部によると、大学生はイスラム国に戦闘員として加わるため、今月7日に日本を出国し、シリアに渡航する計画を立てていた。関係者からの情報提供で内偵を進め、公安部は大学生のパスポートを差し押さえた。
捜査関係者によると、事情聴取されている日本人の中にはシリアへの渡航歴がある人物が含まれている。大学生は、今回聴取を受けたメンバーの一人が東京都千代田区の古書店に掲示したシリアへの渡航を呼びかける張り紙に呼応し、シリアに渡ろうとしたとみられる。
任意聴取を受けた大学生と同居している男性(31)によると、杉並区の一軒家は借り主と大学生を含む20〜30代の男性4人が共同生活をしている。大学生とはツイッターで知り合ったといい、大学生は約2カ月前に北海道から引っ越してきた。6日の捜索で公安部は大学生のパソコンやイスラム関係の書籍などを押収したとみられるが、取材に応じたこの男性を含め大学生以外の3人は聴取を受けておらず、事件とは無関係とみられる。【岸達也、宮崎隆】
◇軍事マニア、本気か疑問…取材の常岡さん
都内の自宅の家宅捜索を受けたフリージャーナリストの常岡浩介さん(45)は毎日新聞の取材に対し、「北大生は以前から取材をしていた人物で、実際にイスラム国へ向かうのなら取材のために同行するつもりだった。任意で事情を聴きたいということだったので拒否した」と話した。
容疑の関係先として捜索を受け、ビデオカメラやパソコンなどの取材機材を押収されたという。
常岡さんによると、男子学生とはイスラム国を取材した際に知り合った友人の紹介で8月に初めて会った。その際、イスラム国に参加するためシリアへの渡航を思い立ったきっかけとして、古書店の張り紙を挙げたという。
ただ、学生は軍事マニアで本気で渡航を希望しているかは疑問に感じたという。
常岡さんは、張り紙を元に同様にイスラム国行きを希望した別のフリーターにも会ったというが「母親の反対で断念したようだ」と話した。【太田誠一】
◇「勤務地シリア」張り紙で募集
張り紙が張られていた古書店はSF小説などを主に扱う書店でJR秋葉原駅近くの雑居ビルの一角にある。
30代の男性従業員によると、張り紙はA4判の紙1枚で、最上部に「求人」と題し、「勤務地」としてシリアと記され、「詳細」として店番まで、とだけ書かれていた。
従業員によると、張り紙を依頼してきたのは「店の関係者の男性」で、4月半ばごろに依頼をしてきて、「シリアに行くときに人手が欲しい。中継をしてくれ」という趣旨の話をしていたという。
張り紙は4月半ばから6日午後3時半ごろに家宅捜索を受けるまで店外や店の入り口付近に張られ、同従業員は8月に取り次いだ1人を含め、少なくとも2〜3人を関係者の男性に仲介したという。
張り紙には、シリアと併せて、「新疆ウイグル自治区」を勤務地とする募集も書かれており、職種として「警備員」と書かれていた。紙はこの日、パソコンとともに押収され、従業員は「イスラム国と紙がつながっているとは思わず、驚いている」と話した。【狩野智彦】
【ことば】私戦予備および陰謀罪
刑法93条で規定されており、外国に対して私的に戦闘行為をする目的で準備や計画をした場合、3カ月以上5年以下の禁錮刑にすると定められている。
大反対だ!増税するから予算が取れると思っているのだろう。
国家公務員給与引き上げ完全実施を閣議決定 10/07/14 (読売新聞)
政府は7日午前の給与関係閣僚会議で、2014年度の国家公務員一般職(行政職)の月給と期末・勤勉手当(ボーナス)を引き上げるよう求めた人事院勧告の完全実施を決めた。
7年ぶりに月給、ボーナスともに引き上げることが柱。続いて行われた閣議で、勧告内容を反映させた給与法改正案を決定した。今国会での成立を目指す。
勧告は、月給を平均1090円(0・27%)増額し、期末・勤勉手当(ボーナス)を0・15か月分引き上げて年間4・10か月分とする内容で、平均年収は約7万9000円(1・2%)増の661万8000円となる。
神戸でもデング熱が広がるのだろうか?
西宮でデング熱、東京訪れず…国内計157人に 10/07/14 (読売新聞)
厚生労働省は7日、兵庫県西宮市の女子学生(19)が、同市内でデング熱に感染したとみられると発表した。
女子学生は最近、東京周辺を訪れていないが、検出したウイルスを解析した結果、代々木公園(東京都渋谷区)周辺の複数の感染者と遺伝子配列が一致。同省などは、同公園周辺で感染した人が西宮市を訪れて蚊に刺され、その蚊が女子学生を刺して感染が広がったとみている。
同省などによると、このほかにも東京で50歳代女性の感染を新たに確認。国内感染者は19都道府県で計157人となった。
世論を考慮して判断を変えたのだろうか?
博士号取り消しも=論文訂正、小保方氏に猶予期間―早大 10/07/14 (時事通信)
理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダーが2011年に早稲田大大学院で博士号を取得した論文について、早大は7日、1年以内をめどに小保方氏が論文を訂正しない場合、博士号を取り消すと発表した。
小保方氏を指導し、博士論文の審査で主査を務めた常田聡教授は停職1カ月の処分とした。鎌田薫総長は管理責任を取り、役職手当の一部を自主的に返上する。
早大が設置した調査委員会(委員長・小林英明弁護士)は7月、小保方氏の論文に文章の流用などの問題があると認めつつ、「博士号の取り消しに該当しない」との報告書をまとめていた。
これに対し早大は今回、「不正の方法により学位の授与を受けた」と判断し、取り消す方針を6日付で決めた。
一方で、小保方氏の指導や論文の審査過程に重大な不備や欠陥があったと説明。おおむね1年以内に小保方氏が論文を訂正したり、指導を受けたりする機会などを与えた上で、適切な博士論文になれば取り消さないとした。
早稲田大:小保方氏の博士号取り消しも 指導教官ら処分 10/07/14 (毎日新聞)
早稲田大の鎌田薫総長は7日、記者会見しSTAP細胞論文(今年7月に撤回)の筆頭筆者である小保方晴子・理化学研究所研究ユニットリーダーが同大に提出した博士論文について、論文の訂正など大学側が提案した条件を満たさない場合は学位(博士号)を取り消す方針を決めた。小保方氏にも6日、伝えたという。
同大は方針について、学位取得の過程で指導・審査に重大な不備・欠陥があったとして、おおむね1年間の猶予期間を設けた上で論文の訂正と再度の論文指導ならびに研究倫理教育を受ける機会を与え、「博士学位論文としてふさわしい」と判断されれば学位を維持するという。期間内に訂正が完了しない場合には、学位は取り消すとしている。
同大はまた、先進理工学研究科の指導・審査体制に不備があったとして、小保方氏の指導教官であった常田聡教授を停職1カ月、副査の教員を訓戒の処分とした。管理責任があったとして、鎌田総長自身が役職手当の20%を5カ月分、当時の研究科長も同じく役職手当の20%を3カ月分、それぞれ自主的に返上するという。
小保方氏の博士論文をめぐって、同大の調査委員会(委員長=小林英明弁護士)が7月、6カ所に不正があったと認定しながらも、それらが博士号を授与した判断に重大な影響を与えていないとして「博士号取り消しに該当しない」とする調査結果を発表していた。これを受け、鎌田総長は学内で検討することを明らかにしていた。【平野美紀/デジタル報道センター】
逮捕はされるし、処分はされるのだろうけど、1億円も使ったのだからある意味お得かもしれない。少額でも窃盗で処罰されるなら大金を使う方が得と言う意味である。出所してから1億円を返済する事は不可能だろうし、自己破産されれば返済する義務もなし。
公益財団法人の元幹部逮捕=電通出資、業務上横領容疑-馬券代、1億円以上着服か 10/05/14 (時事通信)
大手広告代理店電通が出資して設立された公益財団法人「吉田秀雄記念事業財団」(東京都中央区)の口座から現金80万円を引き出し、着服したとして、警視庁捜査2課などは5日、業務上横領容疑で同財団元事務局次長、小口芳和容疑者(63)を逮捕した。同課によると、「競馬につぎ込んだ」と話し、容疑を認めているという。
同課によると、小口容疑者は財団の経理業務を1人で担当する立場を利用し、2006年ごろから計1億円以上を着服していたとみられる。今年7月下旬に財団を懲戒解雇されたという。
逮捕容疑は2月下旬、都内の銀行で、財団の口座から現金80万円を引き出し、着服した疑い。
北大名誉教授の言っている事が正しければ、多くの専門家は気象庁と口裏を合わせる偽善者の集団であると言う事になる。
北大名誉教授が気象庁の対応を批判「明らかな前兆があった」 御嶽山噴火 10/03/14 (夕刊フジ)
死者が47人に達し、戦後最悪の火山災害になった御嶽山(3067メートル)の噴火。小規模な水蒸気噴火だったために予知は困難だったとされるが、何の対策も打てなかった気象庁に批判の声が上がっている。2000年の北海道・有珠山(733メートル)の噴火を的中させた火山学の権威は「初動の遅れが惨事を招いた」と厳しく指弾。「防災体制の見直しが急務だ」と警告を発している。
「すべてが裏目に出てしまった。もっとできることがあったはずだ」
御嶽山の噴火をめぐる気象庁の対応について、こう話すのは、北海道大学名誉教授(火山学)で、「環境防災研究機構北海道」の理事を務める岡田弘(ひろむ)氏(70)だ。
岡田氏は、北大大学院理学研究院附属地震火山研究観測センターの教授だった2000年3月、洞爺湖町と伊達市にまたがる有珠山の噴火を予知。早期に住民を避難させ、被害を最小限に食い止めた実績を持つ。
今回、人的被害が大きくなった背景として、マグマで熱せられた地下水が沸騰し、爆発する「水蒸気噴火」だった点が挙げられている。
噴火には水蒸気噴火のほか、マグマが上昇して吹き出す「マグマ噴火」、高温のマグマが直接、地下水に接して爆発する「マグマ水蒸気噴火」がある。この中で水蒸気噴火は最も予知しにくいとされるが、岡田氏は「それは半世紀以上も前からいわれていることで、今回は明らかな前兆があった。十分対策は打てた」と指摘する。
御嶽山では9月に入り山頂付近で、火山性地震が増加。地下でのマグマの活動を示すとされる低周波地震も発生、噴火の前触れは何度もあった。
「噴火リスクを示す火山性地震の増加は、山側にも自治体にも情報は送られていたが、警戒レベルは平常時と同じ1のままだった。観光シーズンだった地元への影響も考慮したのだろうが、火口周辺への立ち入りが規制される2に上げておけばこれほどの被害は出なかった」(岡田氏)
危険シグナルを見落とした格好の気象庁。同庁の担当者は、会見で「噴火警戒レベルの変更について検討をしたが、地殻変動を伴っていないためしなかった」と言い訳に終始している。この姿勢を岡田氏は「日本全国の火山にはそれぞれ固有のリスクがある。現在の警戒レベルのレベル分けの仕組みでは、火山ごとの実態に即した柔軟な対応ができない。リスクに応じた対策を講じるべきだった」と断じる。
日本には、気象庁が常時観測する47の活火山が点在し、どの山も御嶽山のような噴火を起こす危険がある。悲劇を繰り返さないためにはどうすればいいのか。
岡田氏は「現地に常駐し、火山を定点観測する研究者が必要。いまの日本にはそういう体制が整備されていない。緊急時に、救援体制も含めて全体を統括する人の顔が見えないのも問題だ。火山への対策を抜本的に見直さなくてはならない」と話している。
「この事件以降、業者と職員が1対1で合うことは禁止されているはずだったが、守られていなかった。 水道局関係者は『現実的には、OBが個人的にあいさつに来ただけといわれると拒むことは難しい』と、制度の不備を認める。」
制度の不備があるのなら改善するしかない。時間と人件費の無駄であるが業者と職員が1対1で合うことの禁止を罰則で徹底するしかない。
東京都水道局OBが入手した「究極の秘密」 わずか2万円の上乗せで工事落札 現職が気を使う裏の顔とは… (1/5)
(2/5)
(3/5)
(4/5)
(5/5) 10/01/14 石 平 (中国問題・日中問題評論家)(WEDGE Infinity)
なぜ、6年前に退職したOBが入札情報という「究極の秘密」を手に入れられたのか-。東京都水道局発注の工事で、最低制限価格を不正に入手して落札したとして、元都水道局主任でコンサルタント会社社長、関根敏彦容疑者(66)=埼玉県朝霞市=ら2人が9月18日、公契約関係競売入札妨害容疑で警視庁に逮捕された。わが物顔で古巣に出入りし、金銭の見返りなしに機密情報を聞き出していた関根容疑者。落札価格はわずか2万円を上乗せしただけだった。現役の職員が特別に気を使わざるを得なかったOBの裏の顔とは…。(太田明広、五十嵐一)
コンサル料240万円に成功報酬140万円…現職係長「OBの影響力」
「価格教えてよ」
白いあごひげを蓄え、メガネ姿の関根容疑者は目の前にいる40代の男性係長にこう頼むと、あっさりと必要な情報を手に入れた。平成25年2月、文京区にある都水道局水運用センターでのこと。関根容疑者にとって元の職場に顔を出すことに何の躊躇(ちゅうちょ)もなかった。
手に入れたのは、都水道局が指名競争入札で発注した配水管工事の最低制限価格。予定価格は公表されていたが、公表されていない最低制限価格を下回ると失格になるため、入札を希望する業者にとってはのどから手が出るほどほしい。
その価格は、関根容疑者がコンサルタント契約を結んでいた電気通信工事会社「トキワシステム」(茨城県日立市)社長、緑川克行容疑者(63)=同容疑で逮捕=に電話で伝えられた。緑川容疑者は翌3月、6社が参加した入札で約9600万円で落札。最低制限価格との差は約2万2千円だった。
関根容疑者は緑川容疑者から年間240万円のコンサル料をもらっていたが、今回の成功報酬として、落札価格の1・5%に当たる約140万円を受け取ったという。
入札に不正があったという情報を入手した警視庁捜査2課が捜査に着手し、関根、緑川両容疑者を逮捕した。捜査2課によると、緑川容疑者は「関根容疑者から金額を教えてもらい、落札できた」と容疑を認める一方、関根容疑者は「全て嘘だ」と否認している。
捜査2課は価格を漏らした男性係長からも任意で事情聴取しており、容疑が固まり次第、同容疑で書類送検する方針。男性係長は任意聴取にこう説明しているという。
「関根容疑者はOBとして影響力があり、価格を話さざるを得なかった」
労組支部のナンバー2、同じ部署で長年勤務…「子分がたくさん」
都によると、関根容疑者は昭和41年に入庁後、ほぼ一貫して水運用センターで勤務し、平成20年3月に主任で定年退職した。一見、OBになっても影響力を行使できるほどの地位には思えないが、関根容疑者が約30年以上にわたって労働組合で活動していたことに意味があった。
労組関係者によると、関根容疑者が所属していたのは、水道局員が加盟する「全水道東京水道労働組合」で、セクション別に分けられた40支部の一つの本局給水支部。支部長に次ぐナンバー2の書記長を長く務めていた。
給水支部には担当職員約400人のうち約300人が加盟。労組関係者は「加入率は8割程度とそれほど高くないが、人数では大所帯だ」と話す。
「組合活動に熱心で、労働条件などを争う際には中心となって交渉していた」という関根容疑者。労組関係者は「古株で、下の世代の面倒をよく見ていたから人脈や影響力があった」とした上で、「冗談半分で『俺には子分がたくさんいる』とよく話していた」と打ち明ける。
「労組で力を持ち、今でも職員の人事に一定の影響力を持っているとみられている」。捜査関係者も事件の背景をこう分析する。
別の労組関係者が疑問を投げかけるのは、水運用センター一筋だった関根容疑者の経歴だ。労組関係者は「労組の力があったからこそ希望の部署に居続けられた」と説明する。
これに対し、都水道局は「特定の職場で影響力を持たせないように原則として5年で異動させる」とした上で、「関根容疑者は電気職という専門職採用だったので、結果的に長期間同じ部署に留まったのではないか」と釈明する。
2年前にも贈収賄事件…「なれ合い体質」の組織、OB拒絶できず
捜査関係者によると、関根容疑者は水道局を退職後の22年3月、コンサルタント会社を設立。業界関係者の間では「内部情報に精通している男」との評判が広まっていた。期待に応えるように関根容疑者は、水道局の他の複数の職員からも入札情報を聞き出そうとしていたという。
トキワ社とは会社設立直後にコンサル契約を結び、23年以降に今回の事件分を含む計8件の工事を都から受注。トキワ社の他に4社ともコンサル契約を交わしており、捜査2課は他の工事でも不正な情報漏洩(ろうえい)や入札があった可能性があるとみて全容解明を進めている。
今回の事件は、関根容疑者と男性係長の間で現金などの授受があれば、贈収賄事件に発展する可能性があった。ただ、男性が見返りを受け取った事実は確認されなかったという。
贈収賄事件ならば、カネという欲望に目がくらんだ一職員の犯行で、組織としてはガバナンス(統治)能力が問題となることが多い。だが、捜査幹部は「今回は組織としてOBとのなれ合い体質を続けていた可能性が高く、さらに悪質ではないか」と指摘する。
都水道局をめぐっては、約2年前にも同局発注の工事で入札情報などを教えた見返りに賄賂を受け取った係長が収賄容疑で逮捕される汚職事件が起きている。この事件以降、業者と職員が1対1で合うことは禁止されているはずだったが、守られていなかった。
水道局関係者は「現実的には、OBが個人的にあいさつに来ただけといわれると拒むことは難しい」と、制度の不備を認める。
今回の事件を受け、水道局は「汚職等防止対策本部」を設置し、吉田永局長が「徹底した再発防止の確立に局を挙げて全力で取り組む」とのコメントを出した。ただ、相次ぐ不祥事を前に多くの都民にとってはむなしく聞こえるのでないか。
推測だが結果を良くして出世したい職員が多くいた。それだけだろう。
「8月下旬、新任の総務部長が障害者雇用率について確認したところ、虚偽が発覚。その後、機構は内部調査したが、動機は『はっきり分からない』と説明している。」
間接的には出世とそれに伴う給料やその他の特典のアップであろう。だから「動機は『はっきり分からない』」となるのだろう。直接的な賄賂やメリットではないからそのように結論付けた。目標を発生できなければ組織または責任者の能力不足となり評価が下がる。評価が下がれば出世に響く。推測はあっていると思うのだが?
厚労省所管独法、雇用障害者数水増し・虚偽報告 10/03/14 (読売新聞)
厚生労働省が所管し、全国で労災病院を運営する独立行政法人「労働者健康福祉機構」は2日、雇用する障害者数を水増しするなどして、障害者雇用促進法で定められた雇用率を達成したとする虚偽報告を同省に行っていたと発表した。
虚偽報告は罰金30万円以下の違法行為で、同省は今後、対応を検討する。
機構によると、2010年から14年まで、実際よりも労働者数を少なく、障害者数を多く記載し、法定雇用率(2・1~2・3%)を上回ったと報告していたが、実際には0・76~1・76%だった。
8月下旬、新任の総務部長が障害者雇用率について確認したところ、虚偽が発覚。その後、機構は内部調査したが、動機は「はっきり分からない」と説明している。2010年より前から行っていた可能性もあり、今後、外部の弁護士などを交えた第三者委員会を設置して調査し、関係者の処分を検討するという。
西アフリカから先月、アメリカに入国した男性がエボラ出血熱を発症したニュースを見た。日本も他の国だと笑う前に検疫でのチェックが適切に行われているかダブルチェックするべきである。
米のエボラ出血熱、100人に感染可能性 10/03/14 (読売新聞)
【ワシントン=中島達雄】米南部テキサス州で米国初のエボラ出血熱患者が出た問題で、米疾病対策センター(CDC)は2日、米国内で患者やその親族と接触し、感染した可能性のある人が100人にのぼることを明らかにした。
当初は20人程度とみられていたが、調査が進むにつれて増加。地元の保健当局が同日、80人と見積もったが、さらに20人増えて100人になった。
今のところ、患者以外の発症者は確認されていない。エボラ出血熱の潜伏期間は最長21日間のため、今後も経過観察を続ける。患者の親族4人は、自宅で隔離状態に置かれている。
患者はエボラ出血熱の感染が拡大している西アフリカ・リベリアの男性で、米テキサス州に住む親族に会うため、9月20日にリベリアから米国に入国した。その後、発熱などの症状が出て、26日に病院で診察を受けたが帰宅させられ、28日に救急搬送、30日にエボラ出血熱と診断された。
米 エボラ出血熱患者12~18人と接触 10/02/14 (NHK)
西アフリカから先月、アメリカに入国した男性がエボラ出血熱を発症した問題で、地元の保健当局は、男性が発症してから接触した可能性がある人は少なくとも12人から18人に上ることを明らかにし、今後、体調に変化がないか、監視を続けることにしています。
エボラウイルスの感染が広がっている西アフリカのリベリアから先月20日、アメリカに入国した男性が、入国から4日後に体調を崩し、30日、エボラ出血熱を発症していることが確認されました。アメリカでエボラ出血熱の発症が確認されたのは今回が初めてで、男性は28日から南部テキサス州ダラスの病院で隔離され治療を受けています。
この問題で、州政府や病院の担当者が1日、記者会見し、男性が発症してから入院するまでの4日間に接触した可能性があるのは、男性の親族の子ども5人を含む、少なくとも12人から18人に上ることを明らかにしました。
いずれもこれまでのところ発熱などの症状はなく、自宅にとどまっているということで、保健当局が体調に変化がないか、監視を続けているということです。
一方、この男性は、入院する2日前の先月26日にも病院を受診しましたが、その時点では感染が疑われず、帰宅しています。
会見で病院の担当者は、男性の情報が病院全体で共有できていなかったことを認めており、地元では、対応を疑問視する声が出ています。
9/29 (月)のBSフジLIVE プライムニュースを見ていたら御嶽山噴火について専門家が水蒸気爆発は予測不可能と言っていた。
7分前に膨張は確認できたが連絡するような体制にはなっていなかったとの事。山小屋の管理人の携帯電話又は無線に連絡するようにしていれば犠牲者を防ぐ事は出来なかったとしても犠牲者を減らす事は出来たと思う。頭と機転を利かせれば最小限の費用で出来る事はある。
大学の教授や専門家は研究や調査だけしか考えていないから、このような考えが出て来ない。テレビを見たら、専門家が詐欺師のように予測は不可能、噴火の直前(7分前)で膨張が確認できた、気象庁さえ噴火警戒レベルを噴火するまで1としていたと平気で答えていた。要するに専門家も気象庁も他人の生き死になど関係ないと言っているのと同じだ。活動予算や研究予算が取れれば研究成果やデータをどのように国民のために活用するかなどはどうでも良いと思っているように感じる。本当の事を口にさえ出さなければ心の中まで見透かす事は出来ないので非難されないと思い、他人事のように言い訳ばかり発言しているのだろう。
キャリアや官僚の危機管理意識の欠如や自分達さえ良ければ良いと考えている問題。しかし、高学歴だからしっかりと高給と高待遇を期待する。国民が何も出来ないと諦めるのではなく、一歩でも半歩でもこのようなキャリアや官僚を非難する事を忘れてはならないと思う。
税金泥棒・気象庁-御嶽山噴火後に「噴火警戒レベル3」発表 09/28/14 (カレイドスコープ)
「最初に、こうなって」・・・
そして、多くの登山者が犠牲になった後で・・・
慌てて、「噴火警戒レベル3」に引き上げた税金泥棒省庁・気象庁。
気象庁は、3.11の三陸の大津波の時、「津波の高さは3メートル」と陸前高田市、南三陸町、釜石市、気仙沼市など大勢の死者を出した市町村に警報を出していたのです。
しかし、実際は10メートルから15メートルの津波が襲ったのです。誤差などではなく、安全デマを流したのです。
今回も、噴火後、「噴火警戒レベル3」に引き上げて「予測は難しい」と言い訳に腐心するなど、その姑息な体質は3.11での大失態後もまったく変わっていない。
こんなになっていることを監視カメラでリアルタイムで観察していながら、「死者なし」と報じるバカNHKと、現状を把握できないバカ気象庁の記者会見の動画はこちら。どうして官僚体質は、ここまでの馬鹿を生み出すのか謎だ。
一刻を争う緊急事態に、悠長にも、わざわざ安倍晋三に「自衛隊にヘリコプターの出動を要請した」と言わせるところは、広島の土砂災害でもまったく同じ。そんなことより、お前がまずヘリに乗って現地に行け。オバマだって、そうしているではないの。それとも、天麩羅と寿司が、そんなに恋しいか。
このたぐいまれな愚鈍首相と官僚たちは、「みなさん、だから日本版FEMAの創設が必要なんです!」と最大限、この気象庁の怠慢による人災を利用するでしょう。
その前に自分たちの襟を正すことだ。そうすれば犠牲者は必ず減る。
しかし、山梨の「ありえない」大雪害、広島の「ありえない」大規模な土砂災害、そして、「ありえない」噴火・・・これだけ通常では「ありえない」災害が続いて、多くの国民が命を落とすとなると、安倍晋三と安倍政権は、「呪われた政権」と言う人が大勢、出てくるでしょう。

機関名:独立行政法人産業技術総合研究所 (文部科学省)
全国危ない47火山 箱根山、富士山、那須岳など…専門家が警告! (1/3)
(2/3)
(3/3) 09/08/14 (産経新聞)
長野、岐阜両県にまたがる御嶽山(おんたけさん、3067メートル)が突然、噴火した。晴れた秋の休日。登山者でにぎわう日本百名山の1つは、水蒸気爆発と火砕流にまみれ、多くの犠牲者を出すとともに29日午前現在、山頂付近の登山道などで二十数人が心肺停止状態で取り残されている。活火山は国内各地に点在し、気象庁が常時観測しているものだけで47も存在する。専門家はそのどれもが不意を打って噴火する可能性を指摘する。箱根山、那須岳、吾妻山、もちろん富士山も例外ではない。
御嶽山の噴火で、長野県警は28日、山頂付近の登山道などで31人が心肺停止になっているのを発見し、麓に搬送した男性4人の死亡を確認した。
長野、岐阜両県警と消防、陸上自衛隊は29日、約550人態勢で、残る27人の救助活動を再開。同日午前、陸自のヘリコプターで心肺停止の6人を麓の長野県王滝村に運んだ。27人のほかにも入山届を出したのに連絡が付いていない人や届けを出さずに登った人もおり、長野県警は家族から寄せられた情報などを基に被災状況の把握を急ぐ。
負傷者は少なくとも40人に上り、1991年に43人が犠牲となった長崎県の雲仙・普賢岳噴火以来の惨事となった。
御嶽山は27日午前11時52分ごろ噴火。多くの登山者が取り残されたが、山小屋で一夜を明かすなどして28日夜までに230人以上が自力で下山した。
専門家らでつくる火山噴火予知連絡会は、噴火は地中のマグマによって熱せられた地下水が水蒸気となって地上に噴出する「水蒸気爆発」で、「今後も噴火の可能性がある」との見解をまとめた。噴煙は高さ約7000~1万メートル、火砕流が発生したとした。
気象庁によると、29日朝の噴煙の高さは火口縁上約300メートルで、南東に流れている。5段階の1(平常)から3(入山規制)へ引き上げた噴火警戒レベルを維持している。
行楽シーズン真っ盛りの休日に噴火した御嶽山。実のところ、9月に入ってから1日に50回を超える火山性地震が繰り返し観測されていた。だが、地下のマグマ活動を示す可能性がある火山性微動が検知されず、地殻変動も変化がなかったという。
気象庁は「これだけで前兆とは言えるようなものでない」と説明。記録が残る御嶽山の噴火は2007年、1991年、79年だけで「噴火の数そのものが少ない火山のためデータも少なく、前もって情報を出すだけの材料がなかった」(同庁)と予測について技術的な限界を口にした。
産業技術総合研究所の山元孝広総括研究主幹(地質学)は「予測が容易なのは、地下からマグマがせり上がって起きる大規模な噴火のときだ。今回の噴火は、山頂付近で熱水が噴き出し、水蒸気爆発を起こしたものと考えられ、山頂付近で起きるこうした規模の小さい噴火は予測が非常に困難。噴火の頻度が高い伊豆大島や桜島などとは違い、ほとんどの活火山は山頂付近は観測の対象になっていない。規模が小さければ小さいほど予測は難しくなる」と解説する。
怖いのは日本全国に分布する活火山が、御嶽山と同じような噴火リスクを抱えていることだ。
山元氏は「特に風光明媚(めいび)で温泉もあって、という火山には多くの人が集まるため、噴火すれば大きな被害が出る。関東近辺なら、1977年に噴火した福島の吾妻山、63年に噴火した福島、栃木にまたぐ那須岳が危ない。行楽スポットとして人気の箱根山も同様だ」と警告する。
武蔵野学院大学の島村英紀・特任教授(地球物理学)も「箱根山は昨年5月ごろに群発地震が発生しており、気になる。ケーブルカーも止まるほどの揺れで、大涌谷の近くで噴気が増えて林が枯れているスポットがあり、噴火の兆候らしきものが出ている。それと約300年も噴火が起きていない富士山にも警戒が必要だ。静穏期が終わって火山活動が再び活発化する可能性がある。静穏期はいつ終わりを迎えてもおかしくはない」と警告する。
火山学では噴火の周期性がはっきりしていないのが厄介で、「三宅島のように短いスパンで噴火を繰り返すものもあれば、長い静穏期を経て噴火するものもある」と山元氏。すべての活火山に噴火の恐れが伴うことを再認識しなければならない。
経営コンサルタント会社社長の田中良拓容疑者は旧郵政省の元キャリア官僚。
「捜査関係者らによると、チップは福島県内の製材会社の所有だったが、東京電力福島第一原発事故後、田中容疑者が無償処理を持ちかけ、製材会社から引き取った。田中容疑者はその後、チップの処分費用として東電から約4億円を受け取った。しかし、チップは結局、処分されず、一部が鴨川河川敷に投棄されたという。」
元キャリア官僚だったのだからまあまあの大学は卒業しているのだろう。しかし、やっていることは詐欺師と同じ。まあ、キャリア官僚だから人間的に良いと言うわけではないので不思議に思う事はない。高学歴だから人間的に素晴らしいと勘違いする人は多いと思うのでイメージを変えていく必要がある。
追記:東大に行ったらしい。
毎日新聞「琵琶湖に福島の1万2千ベクレルの汚染物 元京大教授・大阪市立大教授らが刑事告発!」←犯人・田中良拓(元官僚)!【続報】 福島には46万ベクレルの木材樹皮もあり、全国拡散中! 01/30/14 (涼のブログ)
・・・福島県のH製材と、福島原発の東電の現役社員、その東電社員と友達の田中良拓と言う元総務省の官僚が4億7千万円の補償金=我々の税金に群がるためにやった放射能に汚染された木材チップの処理詐欺!
あろう事か、1万2千ベクレル/kgの放射能木材を嫌がらせで、琵琶湖に300トンも放置した事件!
当初は、被害者である滋賀県知事や滋賀県警も捜査に動いていたが、犯人の田中良拓が、東電社員や福島の郡山市長たちと東大時代の友達だと分かると、
原発村の福島県と東電が恐くて、告発をしない!!と言い出したのです。
だから怒った関西の人達が、自分達で「刑事告発」しました。・・・
滋賀汚染チップ事件の整理/西山太吉氏、秘密保護法を批判「民主主義は崩壊」 11/22/13 (細々と彫りつける)
・・・不法投棄にかかわった業者、福島県の汚染チップ排出事業者ともに明らかになっているのです。
おかしいですね。畑先生の言う通りです。なぜ追及しないのでしょうか。
なぜ滋賀県や高島市は手を携えてこれらの業者に撤去、原状回復を要請しないのでしょうか。
先日熊本先生に教わって調べた通り都道府県は不法投棄事業者、そしてその投棄された廃棄物の排出事業者に措置命令をすることができます。
行政処分 | 学ぼう産廃 産廃知識 | 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
滋賀県と高島市は廃棄物処理法を知らないわけがないのですから行政としてできることをしないのはできるのにさぼっているか、できない裏事情があると勘ぐらざるを得ません。
さらに石田紀郎先生が調査した通り、この廃棄物は8000ベクレルを越える恐れがあるのですから、放射能汚染対処特措法の網にかかる可能性がありますから国も放置していいわけではありません。・・・
田中良拓!】琵琶湖に1万2千ベクレルの福島の汚染木材を投棄したまま逃げている犯罪者!! 元郵政総務官僚で池田信夫の盟友 07/03/14 (慌てん坊将軍 弐拾壱)
同一人物?
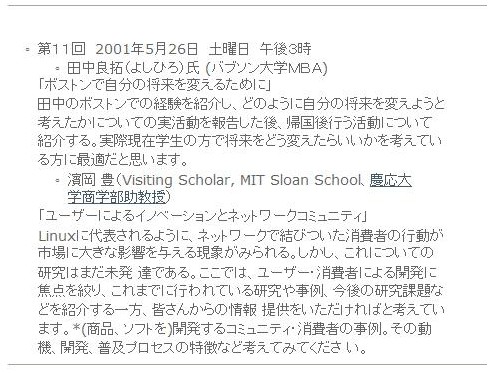
2001年 発表テーマ 第11回 2001年5月26日 土曜日 午後3時 田中良拓(よしひろ)氏 (バブソン大学MBA)「ボストンで自分の将来を変えるために」(ボストン日本人研究者交流会(BJRF))
同一人物?
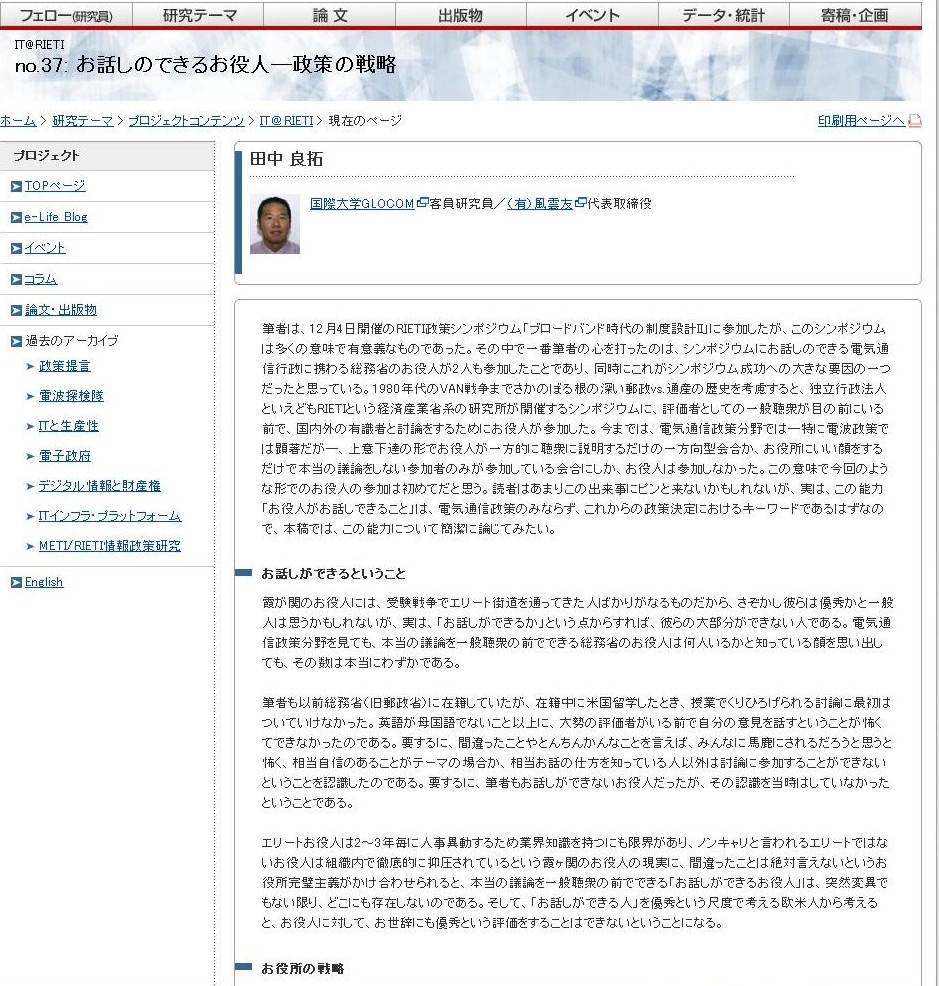
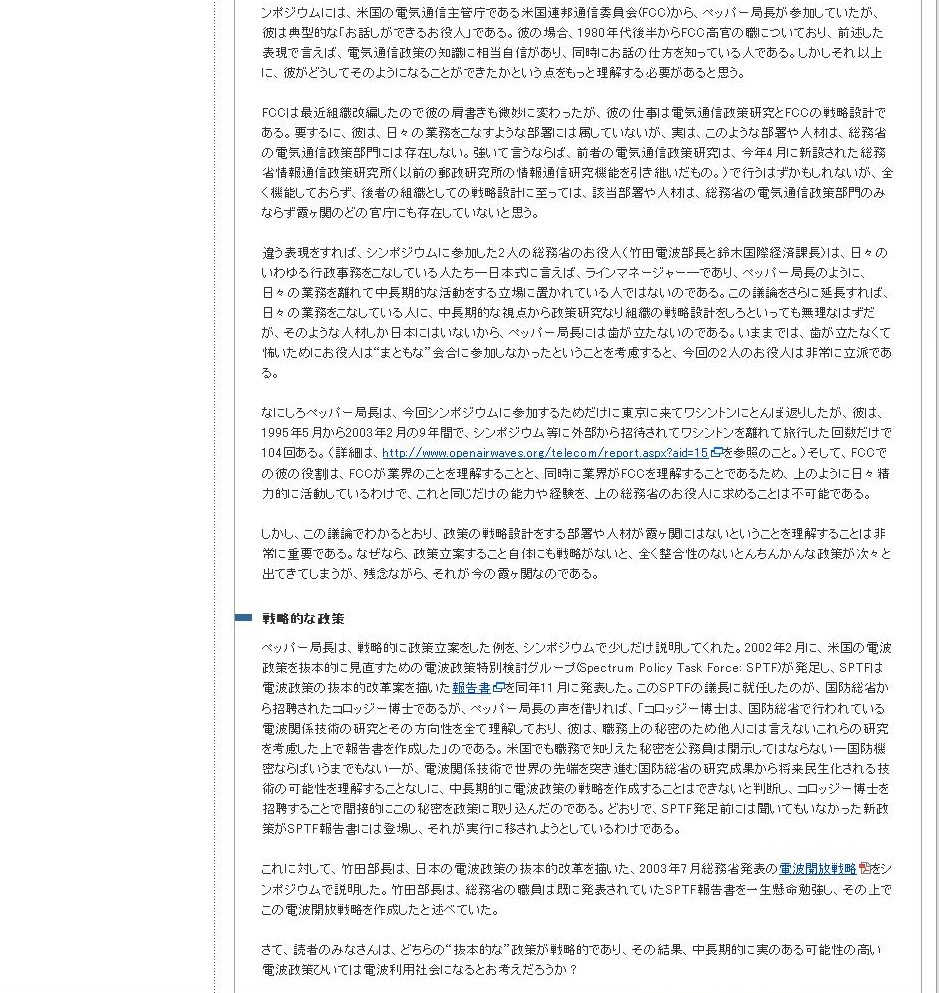
no.37: お話しのできるお役人―政策の戦略 田中 良拓 (独立行政法人 経済産業研究所)
セシウム木材投棄、元キャリア官僚の社長を逮捕 09/26/14 (読売新聞)
滋賀県高島市で昨年、鴨川河川敷に放射性セシウムが付着した樹皮などの木材チップが投棄された問題で、県警は25日、経営コンサルタント会社社長の田中良拓容疑者(42)(東京都中野区)を廃棄物処理法違反と河川法違反の疑いで逮捕した。
容疑を否認している。
発表によると、田中容疑者は神奈川県内の男、滋賀県内の建設会社社長の2人と共謀。昨年3~4月、高島市安曇川町の鴨川河川敷に長さ約570メートル、幅約5メートルにわたり、廃棄物であるチップ約300立方メートルを県の許可なく廃棄、土地の形状を変更した疑い。
県によると、検出された放射性セシウムは1キロ当たり最大3900ベクレルで、国の指定廃棄物の基準(1キロ当たり8000ベクレル超)は下回っていた。今年2月までに撤去され、県などが告発していた。
捜査関係者らによると、チップは福島県内の製材会社の所有だったが、東京電力福島第一原発事故後、田中容疑者が無償処理を持ちかけ、製材会社から引き取った。田中容疑者はその後、チップの処分費用として東電から約4億円を受け取った。しかし、チップは結局、処分されず、一部が鴨川河川敷に投棄されたという。東電は「個別案件については答えられない」とする。
捜査関係者によると、田中容疑者は旧郵政省の元キャリア官僚。神奈川県の男を通じ、滋賀県の建設会社社長にチップの処分を依頼したとされる。これまでの読売新聞の取材に対し、神奈川県の男は「放射性物質に汚染されたものとは知らなかった」と説明。滋賀県の社長は「(神奈川県の男から)河川敷に運んでほしいと言われただけだ」と話していた。県警はこの2人からも事情を聞いている。
滋賀県鴨川河川敷にセシウム木材を不法投棄した元郵政省官僚 10/17/13 (Bran)
滋賀県高島市の鴨川河川敷に放射性セシウムを含む木材チップが不法に放置された問題で、講談社『FRIDAY』が、投棄に関わった会社の社長について報じた。FRIDAYによると、この社長は元郵政省(現総務省)のキャリア官僚だという。
講談社『FRIDAY』10月18日号]
「10tトラックが来たのは、春頃かな。てっきり木材チップで、デコボコ道路を鳴らしているのかと思っていた。近所を散歩している人が県に通報したらしい。」(近隣住民)
滋賀県が調べたところ、投棄作業をしたのは、東京の「ホームサーバー企画」という会社だった。同社社長で元郵政省(現総務省)キャリア官僚の田中良拓氏が、3月15日に河川敷入口の門の扉の鍵を借り受けていることが確認された。
この事態を受けて、県では投棄した運送業者に連日電話したが、不通。仕事を委託したホームサーバー企画の田中社長の電話も不通で、書類で送付した原状回復措置も「受取人不在」だった。
県によると、木材チップは福島県本宮市のHという製材業者からでたものだった。原発周辺の樹木は、表皮に大量の放射性物質が付着している。この業者は、表皮を剥ぎ、線量を下げる作業を東電から受注していた。本来なら、放射性物質が付着した木材は国の許可した最終処分業者によって処分されるはずだが、どういうわけか琵琶湖畔に放置されていた。
「滋賀の県については、田中さんから事情は聞きました。あくまでも田中さんのもとで合法的に処理されていますんで。今朝も電話が来て一切コメントを出さないでくれと言われています。」(H製材社長)
実はH製材は2012年12月、田中社長と事務代行契約を結び、東電との交渉を任せていた。
関係者によると、同社は約9000tの樹木を処理し、1tあたり5万3000円を東電から受け取ることになっていたという。合計4億7700万ものカネが支払われたことになる。
「田中社長は東電内にいる東大時代の同級生からH製材の話を聞き、契約を結んだんです。H製材の社長は田中社長の経歴を聞いて、すっかり信用した。」(東電関係者)
関係者によると、福島から出た木材は鹿児島の堆肥製造会社にも運ばれた。既に堆肥として流通している可能性が高いという。
滋賀県の鴨川河川敷に放置された木材チップ 福島県の製材会社から依頼されたものだった 10/01/13 (Bran)
滋賀県高島市の鴨川河川敷に敷設・放置された木材チップから放射性セシウムが検出された問題で、滋賀県が東京都の会社経営者を河川法違反容疑で、近く県警に刑事告発する方針を固めた。
関係者によると、経営者は今年3~4月ごろ、国有地で県が管理する鴨川左岸の河川敷に幅約3.5メートル、長さ約570メートルに渡って木材チップを敷設し、県に無断で土地の形状を変更した疑いがもたれている。経営者は、東京電力福島第1発の事故で汚染された木材チップの処分を福島県の製材会社から依頼され、滋賀県内に運び込んだとみられる。県はこれまで経営者に対し、書面などで原状回復を求める行政指導を3回行ったが、返答はないという。連絡も取れない状態が続いていることから、告発に踏み切ることにした。
嘉田知事は「やっかいな、持って行き場のない放射性物質が琵琶湖に持ち込まれたのは残念だ」としたうえで、飛散防止などの対策を徹底するとした。
[毎日JP,2013年09月28日]
放置された木材から1キログラムあたり 180~3,000ベクレルの放射性セシウムが検出されている。現場への立ち入り禁止措置、ビニールシートで覆い木材チップの飛散防止措置を実施しているが現在、撤去のめどは立っていない。
組織だけの事を考えればそうなるのかもしれない。結局、身内だけの事しか考えていない。
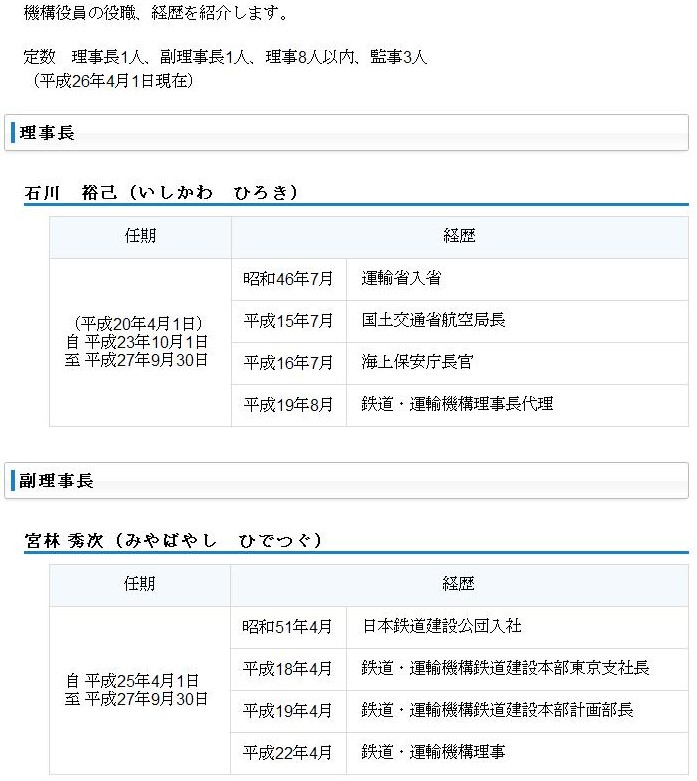
役員一覧 (鉄道・運輸機構)
「OB不在企業を不利に」鉄道・運輸機構副理事長が指示 09/26/14 (朝日新聞)
北陸新幹線の設備工事を巡る官製談合事件に絡み、発注側の独立行政法人「鉄道・運輸機構」の宮林秀次副理事長(62)が、OB不在の企業は入札で不利に扱うよう部下に指示していたことがわかった。機構が26日、第三者委員会(委員長=頃安健司・元大阪高検検事長)の調査報告書を公表した。副理事長は30日付で依願退職する。
報告書によると、宮林氏が不利な扱いを指示していたのは、新幹線や在来線の建設計画担当理事だった間の2010年6月から昨年4月ごろまで。応札額に加え、提案内容も加味する総合評価落札方式による入札が対象だった。機構の支社長らが各地に赴任する前後に、共同企業体(JV)を構成する最大手会社に機構の役職経験者が在籍していない▽2番目の会社に機構OBがいない――などの場合は、最高点を付けないよう指示。「OBが再就職先で肩身の狭い思いをしてはいけないという誤った配慮があった」と結論づけた。
談合事件は公正取引委員会の調査で判明。官製談合防止法違反の罪に問われた機構東京支社の元設備部長=懲戒免職=と部下の同部機械第三課長=停職3カ月=の有罪判決が確定した。
「問題の社員は今年3月、737型機が整備期限を2か月以上も超過していたのに気付いたが、別の定期検査を受ける5月まで放置していた。」
飛行機を運航する会社が一人の社員に全てを任せていたのだろうか?上司はチェックしないのか?
このような管理体制だと運が悪いと大きな事故に繋がるだろう。エクセルでもいつ検査したか日付を記入していれば見逃す事はない。経費削減のためにもし担当の社員にしか技術的な事が理解できないような状態であるなら基本的な問題があると思う。組織的な問題であれば、JR北海道のように簡単には変わらない。
整備期限超過、発覚恐れ記録改ざん…エア・ドゥ 09/26/14 (読売新聞)
北海道を拠点とする航空会社「エア・ドゥ」(札幌市)は26日、羽田―新千歳間で運航したジェット機3機について、最大で4か月間にわたって整備期限を超過していたと発表した。
整備計画担当の社員が期限の時期に気付かず、ミスが発覚するのを恐れて整備記録を改ざんしていたという。運航中の不具合やトラブルなどにはつながらなかったが、事態を重く見た国土交通省は同社を厳重注意した。
国交省によると、期限超過のまま運航していたのは、ボーイング737型機2機と、同767型機1機で、主翼などの整備期限を超過していた。羽田―新千歳、神戸―新千歳などの路線で運航された。
問題の社員は今年3月、737型機が整備期限を2か月以上も超過していたのに気付いたが、別の定期検査を受ける5月まで放置していた。6月には767型機で整備期限を4日超過していたことに気付き、整備計画を管理するコンピューターを操作。3月に整備を受けたように記録を改ざんしていたという。
国交省が8月に行った同社の定期監査で、別の整備記録に不備が見つかり、同社に対して詳細な調査を求めたところ、整備記録の改ざんが発覚したという。国交省は同社に対し、事態が発覚しなかった原因を再調査した上で、再発防止策を10月10日までに報告することを求めた。
面談した教職員に「人を殺してみたかった」と打ち明けていた事実がなぜここまで隠されていたのか?校長にも報告されていたから、校長が会見で悲しみよりも困ったといったような表情を見せたのか?
「人を殺してみたかった」と打ち明けていた事実を教職員と校長で隠蔽していた。「校長も深刻な状況と受け止めず、県教委に報告していなかった。」としか言い訳を重い使いないだろう。事実を隠蔽していましたと言えば責任を取らされる。全てを県教委に報告して県教委に判断をさせれば良かった。しかし全てを報告しない判断は校長が下した。校長の評価や出世にでも影響すると思ったのかもしれない。例え非難されても、疑われても「深刻な状況と受け止めず」としか言えないと思う。後は校長の言い訳を上がどう判断するかだけだ。
佐世保事件、少女の殺人願望を県教委に伝えず 09/25/14 (毎日新聞)
長崎県佐世保市で7月下旬に起きた高1女子生徒殺害事件で、逮捕された同級生の少女(16)(鑑定留置中)が3月に父親を金属バットで殴ったことについて、殴打の6日後、面談した教職員に「人を殺してみたかったので、父親でなくてもよかった。あなたでもいい」などと打ち明けていたことがわかった。
教職員が校長に報告したのは4月下旬で、校長も深刻な状況と受け止めず、県教委に報告していなかった。
県教委が教職員らから事情を聞くなどして判明し、26日の県議会文教厚生委員会で報告する予定だ。
とんでもない事実がはっかくした。建設会社は経営問題に直面する可能性が高い。もし建設会社が倒産すれば、国と「大同特殊鋼」が尻拭いをするのか?国が尻拭いすると言う事は、税金の無駄遣いとなる。どれぐらいの儲けになるのか知らないが、問題が発覚すれば大きな損害になるとは思わなかったのか?思わなかったからやったのだろうけど。
八ッ場ダム:移転先のスラグ 国際基準で「最も危険」 09/19/14 (毎日新聞)
八ッ場ダム(群馬県長野原町)の移転代替地に有害物質を含む建設資材「鉄鋼スラグ」が使われていた問題で、国土交通省八ッ場ダム工事事務所は18日、現地調査を始めた。毎日新聞の報道から1カ月余。このスラグは皮膚や目への有害性が国際基準で最も危険とされ、取り扱う人に保護手袋などの着用が求められているにもかかわらず、現地の住宅建設予定地では庭の砂利としてむき出しのまま置かれている場所もある。専門家は早期撤去が必要と強調している。【杉本修作、沢田勇、角田直哉】
この日の調査には建設資材の専門家も参加し、代替地でスラグの疑いがある砕石を確認。成分を調べる試薬を吹きかけたところ、スラグの特徴であるアルカリ性を示した。今後、専門の鑑定機関で分析する。
スラグは鉄の精製時に排出され、石や砂の形状をしている。そのままでは廃棄物処理法上の産業廃棄物だが、「再生資源」として道路の路盤など一部での使用が国に認められている。しかし、八ッ場ダムでは、大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)の渋川工場(群馬県渋川市)から出たとみられるスラグが渋川市の建設会社に引き渡された後、水没予定地区住民の移転代替住宅地の盛り土などに許可なく使われていた。
スラグなど特定の化学物質を含む製品を取引する際は、有害性の分類や表示の方法を国際的に定めた「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」(GHS=グローバリー・ハーモナイズド・システム)に基づき「安全データシート」と呼ばれる文書を作成する。大同作成の同文書によると、「健康に対する有害性」のうち「皮膚腐食性/刺激性」と「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」は、GHS分類で最も危険とされる「区分1」。「特定標的臓器毒性(反復暴露)」は「区分2(呼吸器系)」と記されていた。
「有害性情報」の欄には「水に接触するとアルカリ性(pH9〜12)を呈し、角膜、鼻の内部組織、皮膚に炎症を起こす可能性があり」「呼吸器感作性・皮膚感作性があるクロム化合物を2〜3%含有する」などと有害の要因や成分を記載。「安全対策」として「適切な保護具(保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面・呼吸用保護具)を着用すること」などを求めていた。
スラグと同じく皮膚や目への影響が「区分1」とされる身近な製品には強力アルカリ洗剤や漂白剤がある。日本中毒情報センターが2008年に受けた家庭用(ネット購入可の業務用含む)洗浄剤等に関する3085件の問い合わせから1454件を厚生労働省が抽出調査したところ、568件(39%)は問い合わせ時点で何らかの症状があった。
スラグは八ッ場ダムのほか、渋川市の遊園地の駐車場や公園の遊歩道などでもむきだしのまま使われている。大同は「除去が必要な場合は県の指導を受けながら使用先と対応を協議して誠意を持って協力させていただく」とコメント。同市の建設会社は「各機関からの問い合わせに苦慮しており、落ち着くまで取材はご勘弁を」と文書で回答した。
◇直ちに撤去が必要だ
日本環境学会顧問の畑明郎・元大阪市立大大学院教授の話 取扱業者が有害性を認識しながら一般の人に知らせないまま生活の場で使っているのは悪質。文書通りのアルカリ強度なら皮膚が溶けることもあり、クロム化合物は発がん性物質の六価クロムに化学変化することもある。本来廃棄処分すべきもので、利用状況を調べ、表層に出ているものは直ちに撤去が必要だ。
◇GHS
化学品の危険性や有害性をわかりやすく分類するために2003年7月の国連の勧告により設けられた世界統一基準。炎やどくろなど9種類の絵表示や注意書きを用いて人体や環境に対する危険性の種類や程度を区分する。国連によると、日本や中国など67カ国が既に導入または導入を検討している。
都水道局:入札妨害 逮捕のOB、庁舎内で価格聞き出す 09/19/14 (毎日新聞)
東京都水道局発注工事を巡る競売入札妨害事件で、業者に最低制限価格に近い価格を漏らしたとして公契約関係競売入札妨害容疑で警視庁捜査2課に逮捕されたコンサルタント会社社長の関根敏彦容疑者(66)が、同局水運用センター(文京区)の庁舎内で現職係長から価格を聞き出していたことが捜査関係者への取材で分かった。
同課は、関根容疑者が都水道局OBの立場を悪用して頻繁に庁舎に出入りし、他の現役職員からも別の入札情報を聞き出した疑いもあるとみて捜査している。同課は18日、都庁舎の水道局など関係先を家宅捜索した。
捜査関係者によると、関根容疑者は電気通信工事会社社長の緑川克行容疑者(63)=同容疑で逮捕=から依頼を受け、2013年2月中旬に同センターを訪問。40代の担当係長に「価格を教えてくれ」と依頼し、その場で情報を聞き出していた。係長との間に金銭の授受は確認されていないという。同課は係長を近く同容疑で書類送検する方針。
関根容疑者の逮捕容疑は同年2〜3月、水道局発注の配水関連工事の指名競争入札で最低制限価格に近い価格を緑川容疑者に教え、約9600万円で落札させたとしている。
同課によると、関根容疑者は08年に都を定年退職し、10年3月にコンサル会社を設立。緑川容疑者と年間240万円でコンサル契約を結んでいた。【福島祥、宮崎隆】
この事件をテレビで見たが、社長は廃油などを再利用したラード(豚脂)の事など知らず、社員が勝手にやっていたと言っていた。
事実かどうかは知らないが、損失177億円(廃油などを再利用したラード(豚脂)を使用した企業からの損害賠償は含まれていないのでは?)と会社の信用を失ったことにより倒産するのではないのか?自業自得だし、不正を行った企業や人が制裁を受けることにより、不正を行う人が減る事を祈る!
<デング熱>熱海で感染者 勤務先で蚊に刺される 09/18/14 (毎日新聞)
厚生労働省と静岡県は18日、熱海保健所管内の20代男性がデング熱に感染したと発表した。男性は今月上旬に東京都内を訪れているほか、発症した今月10日と前日、同県熱海市内の勤務先で蚊に刺されたと話しているという。感染経路は特定できていないが、勤務先周辺の蚊がウイルスを保有している可能性もあり、駆除が実施される。
【背中が紫色に…】デング熱、2度かかると 重症体験者が語る
同県によると、男性は10日に発熱や頭痛などの症状を訴え、15日まで自宅で療養。16日に医療機関を受診し、現在は快方に向かっている。最近の海外渡航歴はなかった。潜伏期間は3~7日程度のため、熱海市内で感染した可能性は低いが、男性を刺した蚊にウイルスがうつった可能性があり、勤務先の会社などが駆除するという。
同県内の感染者は東京都立代々木公園(渋谷区)周辺で感染したとみられる50代男性に次いで2人目。国内の感染者は17都道府県の計132人となった。【西嶋正信、梁川淑広】
特集ワイド:正しく恐れるデング熱 毎日新聞元特派員も重症体験「背中が紫色に…」 尿減少など悪化の兆しに注意 09/08/14 (毎日新聞)
収まる気配のないデング熱騒動だ。ウイルスを媒介するのがごくありふれた蚊(ヒトスジシマカ)だから、それこそ「水鳥の羽音に何とやら」ではないが、蚊の羽音に跳び上がり、目の前をよぎる蚊の影にも身をすくめる人は多いのではないか。耳慣れぬこの病気に、どう向き合うべきか。【吉井理記】
まずは「体験者」の話を聞いてみよう。毎日新聞デジタルメディア局の小松健一局次長(56)。身内の話で恐縮だが、タイ・バンコクのアジア総局に勤務していた2003年、3カ月の間に2回もデング熱に感染し、死を覚悟するほどの重症に陥ったのだ。
「最初は5月にバンコクでウイルスを持った蚊に刺されたのが原因だったようです。朝、出勤する支度をしていたら急に寒くなって。体温は38度5分。そのまま家で休み、翌日も熱が引かなかったから病院に行ったら感染が分かったんです」
この病気、特効薬もワクチンもないから、基本は静養して体の免疫機能がウイルスをやっつけるのを気長に待つしかない。自宅で休み、3日目に熱は下がった。「死者も出る病気と聞いていたのですが、僕は熱で体がしんどい以外は症状が何もない。ふーん、こんなものか、と」
問題は「2度目」だった。当時、中国からラオス、タイを経て亡命する北朝鮮脱出者が相次いでいた。実態を探るためタイ北部とラオスで3日間、取材に駆け回り、バンコクに戻って連載記事を書き始めた直後−−。「連載1回目の原稿を東京に送って自宅に戻り、シャワーを浴びたんです。すごくおなかがペコペコで、晩ご飯を楽しみにしながらタオルで体をぬぐっていた。足をふこうとかがんだ瞬間、ドワッと顔が熱くなり、悪寒が体中を走って……」
風邪やインフルエンザのように「体がだるい」といった前触れもない。「瞬間的」と言っていいほどの突然の発熱だった。測ったら39度。そのまま寝込んだが、翌朝にはまともに歩くこともできなくなり、妻が運転する車で病院に担ぎ込まれた。「医師が僕の腕を指でキュッと押したらすぐに内出血で紫色になった。『ああ、デングフィーバー(デング熱)だね』と。僕の方はもう意識が半分なく、医師の説明も聞き取れないほどでした。熱も40・5度にまで上がり、もちろん即入院」
翌日の昼、ベッドで目覚めると、なんと背中一面が内出血で紫色に変じていた。全身の血管から血液や血漿(けっしょう)成分が漏れる重い「デング出血熱」へと症状が進んでいたのだ。
「入院中、トイレには必ず看護師と一緒に行くよう注意されました。もし転倒したら内臓から出血するから、と……。ベッドに横になりながら『このまま眠ったら、もう目が覚めないんじゃないか』との思いが脳裏をよぎったのを覚えています」
点滴を打ち続けて3日目にようやく快方に向かい、6日目に退院した。熱が下がるまでの記憶はほとんどない。「蚊の多い農村地帯などに入る時は長袖を着て、首筋も布などでガードするのが原則。あの取材ではつい油断して半袖で通してしまって。土地の病気には割と詳しいつもりだったのですが」
普通、デング熱の症状は発熱や頭痛、関節や筋肉の痛み、発疹などで、1〜2週間程度で自然に治る。なぜ2度目は重くなったのか。
伝染病に詳しい内科医でナビタスクリニック立川(東京都立川市)理事長、久住英二さんは「デングウイルスは四つの型があり、ある型に感染した後、別の型に感染したら重症のデング出血熱に至ることがあります。でも、そのメカニズムは完全には分かっていません」と解説する。
厚生労働省によると、感染しても発症するのは10〜50%。このうち重症化するのは1〜5%とされる。デング出血熱になると、血管をつくる細胞がうまく働かず血漿が漏れたり、血を固める作用のある血液凝固因子や血小板が減少し、出血が止まりにくくなったりする。血圧低下で臓器に血液が十分に行き渡らず、最悪死に至る。こうなると集中治療が必要で、輸血・輸液や昇圧剤を使う対症療法を軸に体力を維持し、免疫機能がウイルスを退治するのを待つしかない。
一方、普通のデング熱で軽症なら、感染拡大を防ぐために蚊を室内に入れず、水分補給に注意して安静にしていれば十分だ。熱が高くつらければ市販の解熱剤を使ってもいいが、「その場合は注意すべき点がある」と久住さん。「アスピリンを含む薬は絶対にダメ。血小板の働きを抑える作用があり、出血傾向のある患者の症状を悪化させます。そうした副作用のないアセトアミノフェンを使った薬にすべきです」と警告するのだ。成分は薬の箱やラベルに示されているが、薬局の薬剤師に選んでもらえばより安心だ。
もっとも、素人には自分が重症か軽症か、受診すべきか否かの判断は難しい。久住さんは「軽症なら受診の必要はないが(1)解熱後にだるさが悪化する(2)体のむくみや尿の減少(3)鼻、肛門などからの出血や、女性ならば生理の出血がいつもより多い−−は重症化の兆しで、すぐに受診すべきです」。(2)は、血管からの血漿漏出が疑われるからだ。
重症化し、治療しなかった場合の死亡率は10〜20%と一見高いが「医療レベルが劣悪な国ならともかく、今の日本で死亡するケースはまず考えられません」と断言した。
とはいえ「震源地」となった東京・代々木公園の周辺では施設の閉鎖が相次ぎ、感染者も増える一方だ。感染の恐れはいつまで続くのか。カギを握るのはヒトスジシマカの生態だ。デング熱は人から人への感染はなく、国内ではこの蚊だけがウイルスを人に感染させるのだ。
国立感染症研究所昆虫医科学部の沢辺京子部長によると、この蚊は青森以南に生息し、5月から10月下旬が活動期だ。だから秋が深まれば蚊も姿を消すから感染は収まるはずだが、問題は秋に産みつけられた蚊の卵だ。実はウイルス感染した蚊が産む卵のうち、およそ0・9%が感染し、ふ化した蚊もウイルスを引き継ぐことが確認されている。秋に産み付けられた卵は休眠状態で冬を越し、気温が上がる5月にふ化する。ならば感染した蚊が国内からいなくなることはない?
沢辺さんは「越冬して卵からふ化した蚊がウイルスを持つ可能性はゼロではありませんが、ただでさえ感染した卵が現れる確率は低く、越冬してふ化に至る卵もごくわずか。総合的に考えれば来年、ウイルスを持つ蚊が生まれる確率は限りなく低いので安心してください」と説明する。
久住さんは言う。「海外との交流が活発になればなるほど、日本になかった病気が流入するリスクは大きくなる。いっそデング熱を奇貨として、海外のさまざまな病気に関心を向ける機会と受け取ってはどうでしょう」
敵を知り、己を知れば百戦して危うからず。「正しく恐れる」ことがデング熱克服への近道であるようだ。
この事件をテレビで見たが、社長は廃油などを再利用したラード(豚脂)の事など知らず、社員が勝手にやっていたと言っていた。
事実かどうかは知らないが、損失177億円(廃油などを再利用したラード(豚脂)を使用した企業からの損害賠償は含まれていないのでは?)と会社の信用を失ったことにより倒産するのではないのか?自業自得だし、不正を行った企業や人が制裁を受けることにより、不正を行う人が減る事を祈る!
台湾「廃油ラード」拡大 回収続出、損失177億円 09/18/14 (読売新聞)
【台北=田中靖人】台湾で廃油などを再利用したラード(豚脂)が流通していた問題で、ラードを製造した食用油製造企業の製品を使用した企業や商店が謝罪や商品回収に追い込まれている。馬英九総統は17日、懸念を表明。観光への影響を心配する声も出始めた。
台湾の食品衛生当局によると、問題の会社が廃油だけでなく、香港から輸入した飼料用油を、商品名の違う他のラード24製品に使っていたことが判明した。検察当局は13日、同社会長を拘束。違法油を使用した食品436品目は15日までに回収された。
だが、問題のない同社の製品を使っていても謝罪を強いられたり、無関係の商品まで消費者から返品されたりする商店が続出。経済部(経済産業省に相当)は、経済損失は50億台湾元(約177億円)に上ると推計している。
一部商品の販売を中止した中には、台湾の「モスバーガー」や日本に進出しているカフェ「春水堂」も含まれるが、いずれも日本では問題の油を使用した商品は販売していない。
行政院(内閣)は17日、食品衛生の罰則強化を発表。馬総統は同日、「受けなくていい影響を受けている店がある」と述べ、消費者に冷静な行動を促した。
日本の保安は形だけだから本当に侵入しようと思えば可能だと思う。
原子力科学研に男性が一時侵入、警備員気付かず 09/12/14 (読売新聞)
日本原子力研究開発機構は12日、原子力科学研究所(茨城県)で今年2月、70歳代の男性が運転した乗用車が無許可で敷地内に約1時間にわたって侵入していたと発表した。
乗用車は正門から侵入したが、正門にいた警備員は気付いていなかった。立ち入り制限区域への出入り管理などに問題があるため、原子力規制委員会は同日、原子炉等規制法に基づく核物質防護規定の順守義務違反だとして、同機構を厳重注意した。
同機構によると、男性は迷い込んだだけだったという。
医療機関に229億円を資金提供しても儲かっていると言う事か?
ノバルティス、医療機関に229億円を資金提供 昨年1年間で 09/12/14 (読売新聞)
スイス系の製薬会社ノバルティスファーマ(東京)は12日、2013年に医療関係者に提供した資金を公開した。総額は12年比約7億円減の約229億円だった。
ノ社が提供した資金のうち、指定先の研究室が使い道を特定せずに自由に使える「奨学寄付金」は1058件で計13億1100万円。慶大は計7千万円、東大は計6600万円をそれぞれ受け取っていた。
新薬創出の基礎研究や医薬品の有効性などを調べるための費用である「研究費開発費等」は79億9800万円だった。
情報開示は、日本製薬工業協会が業界の透明性を高めるために定めた指針によるもので、今年が2年目。8月以降、武田薬品工業などが順次公開している。同様の情報公開は先進国では一般的となっている。
立ち入り調査を徹底的にやれば良い。嘘や書類の隠ぺいなど様々な防御を行っていると思うので、クレバーで効率良く調査を行わなければならないと思う。
日銀、韓国国民銀行に立ち入り調査へ 韓国金融界の“闇”は暴かれるか (1/3)
(2/3)
(3/3) 09/08/14 (産経新聞)
韓国最大手銀行の国民銀行東京、大阪支店による不正融資問題で、日銀が両支店への立ち入り調査(日銀考査)を検討していることが10日、分かった。担保水増しなどによる過剰融資が発覚したことで、日銀は国民銀の信用リスク対策が不十分だったとみている。東京を舞台にした韓国系銀行の不正では自殺者も出ている。“闇”は暴かれるか-。
9月初旬の週末、東京・新大久保のコリアタウンは若い女性でにぎわっていた。だが、新宿区を拠点にするタクシー運転手は「韓流ブーム最盛期に比べればだいぶ減ったよ」とこぼす。
コリアタウンの発展には、国民銀など韓国系銀行の力が欠かせなかった。在日韓国人の担保の乏しさに目をつぶって積極支援してきたからだ。
支店ぐるみの過剰融資だったとみられるが、韓国の金融事情に詳しい関係者は「日本の銀行からお金を借りられない在日韓国人を救うためのやむにやまれぬ不正だった」と同情する。
邦銀は「お金を借りたまま韓国に逃げてしまうケースもある」として、在日韓国人への融資に及び腰だったという。
国民銀は韓国系の企業に対しても、支店の限度額を超えて融資できるよう、同じ企業グループの複数法人に分割して貸し出す“裏技”を編み出した。
平成10~20年代初頭の韓流ブームでコリアタウンは巨大化。うるおった在日韓国人や韓国系企業は、国民銀の支店幹部らに謝礼金(リベート)を贈っていた。
ところが、韓流ブームは嫌韓ムードの広がりで一気にしぼんでしまう。在日韓国人や韓国系企業に貸したお金の返済が滞ったことで、国民銀の不正が一気に明るみに出たのだ。日韓の金融当局は、国民銀のほか、ウリ銀行、中小企業銀行など韓国大手銀の在日支店でも同じような不正があったとみており、処分が広がる可能性もある。
大手邦銀の幹部は「同情すべき点はあるが、歴代の支店長や役職員ぐるみの不正であれば、組織のチェック機能が働いていなかったことになる」と批判する。
一方、「コンプライアンス(法令順守)の徹底を求める日本社会に対し、韓国では儒教文化が根強く、上司の不正を告発しにくい」と解説するのは、国内外の金融事情に詳しい西村あさひ法律事務所の松尾直彦弁護士だ。
国民銀の不正をめぐり、金融庁は8月末、東京と大阪の両支店に対し、4カ月間の一部業務停止命令を出した。同行の李建鎬(イ・ゴンホ)銀行長は今月4日に辞任表明した。
韓国の検察当局は昨年末、数百億円に上る不正融資容疑で国民銀の元東京支店幹部らを逮捕。その直後、同支店の与信業務担当の韓国人行員が支店地下の書庫で首をつって死亡しているのが見つかった。
さらに、今年4月に韓国北部にある墓苑の駐車場でウリ銀行の元東京支店長が焼死体で発見された。元支店長は在職中、不正融資の見返りにリベートを受け取っていたとして韓国金融当局の調査を受けており、警察は「自殺」と発表した。
こうした事態を受け、日銀も韓国系銀行の考査に乗り出す方向で調整を始めた。
日銀考査は、日銀と当座預金取引をする金融機関が対象で、行政権限に基づく金融庁検査とは異なる。また、法令順守などに重点を置く金融庁検査に対し、日銀考査は経営の健全性などをチェック。問題点が見つかれば改善を求める。
関係者によると、国内の主要金融機関に対する日銀考査はほぼ2年に1度あるが、外銀への定期考査はなく、必要性が認められれば、考査に入るという。
今回明るみに出た国民銀の過剰融資は、経営の健全性を損なう不正だ。一部の顧客は預金を引き上げ始めたとみられ、日銀は国民銀への考査を本格検討しているようだ。他の韓国系銀行の在日支店に対しても考査の必要性がないかチェックする。
ただ、個別の考査結果は非公表のため、どこまで“闇”を暴けるかは不明だ。
経営の行き詰まり!
「常陽新聞」新社、賃金不払い容疑で書類送検 09/10/14 (読売新聞)
土浦労働基準監督署は10日、茨城県で昨年8月まで日刊紙「常陽新聞」を発行していた常陽新聞新社(本社・茨城県土浦市)と、同社の当時の社長(59)を最低賃金法違反(賃金不払い)の疑いで水戸地検土浦支部に書類送検した。
発表によると、社長は従業員24人に対し、昨年2月~7月分の最低賃金計約987万円を支払わなかった疑い。同社は昨年8月30日に水戸地裁土浦支部に破産を申し立て、事業をやめた。今年2月からは東京都の経営コンサルティング会社が出資した別の新会社が「常陽新聞」を発行している。
新聞の記事は正しいと思って読んだら大間違いの可能性がある教訓となるだろう。
「吉田自身はすでに平成8年の週刊新潮(5月2・9日合併号)のインタビューで『本に真実を書いても何の利益もない』『事実を隠し、自分の主張を混ぜて書くなんていうのは、新聞だってやっている』と捏造(ねつぞう)を認めていた。」
朝日新聞のデタラメさには驚くばかりである。
「強制連行」を広めた吉田清治とは何者なのか 「真実を書いても何の利益もない」 (1/3)
(2/3)
(3/3) 09/08/14 (産経新聞)
そもそも吉田清治とは何者なのか。韓国・済州島で奴隷狩りのように女性を強制連行したというその証言について、現地調査で虚偽だと暴いた現代史家の秦郁彦は、吉田氏を「職業的詐話師」と呼ぶ。実際、証言内容が虚構に満ちているだけでなく、吉田の経歴もまた謎に包まれている。
吉田清治の名はペンネームで、本名は吉田雄兎(ゆうと)。他に別名として東司、栄司を名乗っている。吉田の著書で山口県と記されている本籍地も、実は福岡県だった。門司市立商業学校(当時)の卒業生名簿には「吉田雄兎」の名があるが、卒業生名簿には「死亡」と記されている。
吉田の著書の記述では昭和12年、満州国地籍整理局に務め、14年から中華航空上海支店に勤務したことになっている。しかし、歴史学者の上杉千年の調査では中華航空社員会で吉田を記憶する者はいなかった。
吉田によれば、15年に朝鮮の民族主義者で日本の民間人を殺害した金九を輸送した罪で逮捕され懲役2年の刑を受けたという。ただ、吉田は秦に対し、罪名はアヘン密輸にからむ「軍事物資横領罪」であることを告白している。
17年に山口県労務報国会下関支部動員部長に就いたとする吉田。済州島での慰安婦狩りも、著書で「(強制連行の)実態は私が家内にしゃべったか見せたかしたので、家内の日記の中にありました」と書くが、吉田が実際に妻と結婚したのは「慰安婦狩り」を行ったという時期の1年後のことだとされる。
著書には戦後の吉田の足跡は一切触れられていないが、秦によると22年に下関市議に共産党から出馬し落選。45年ごろには福岡県の日ソ協会役員に就いた。
これら吉田自身の虚構は秦や上杉、戦史研究家の板倉由明らの丹念な研究によって明らかになった。
強制連行の唯一の日本側証言とされてきた済州島での慰安婦狩りに関しては、地元紙「済州新聞」記者、許栄善が取材すると全くのデタラメだと判明した。慰安婦問題で日本政府の責任を追及する立場の中央大教授、吉見義明も「吉田さんの回想は証言として使えない」と判断している。
朝日新聞が自社の吉田証言を取り上げた記事を取り消したのは今年8月のことだが、吉田自身はすでに平成8年の週刊新潮(5月2・9日合併号)のインタビューで「本に真実を書いても何の利益もない」「事実を隠し、自分の主張を混ぜて書くなんていうのは、新聞だってやっている」と捏造(ねつぞう)を認めていた。
吉田は朝日新聞が昭和57年9月2日付朝刊(大阪本社版)で、「済州島で200人の若い朝鮮人女性を『狩り出した』」と大きく報じたことなどを皮切りに、新聞や雑誌、講演に登場するようになった。
サハリン残留韓国・朝鮮人の帰還訴訟を行った弁護士の高木健一の著書によると、吉田は57年9月30日と11月30日の2回、「強制連行の証言者」として出廷。「慰安婦狩りの実態」が法廷で披露されたことに対し、高木は「証言は歴史的にも非常に大きな意義がある」と評価している。
吉田は58年7月に『私の戦争犯罪 朝鮮人強制連行』を著し、58年12月に韓国・天安市の国立墓地に謝罪碑を建てるために訪韓。以降も現地で謝罪を繰り返した。平成12年7月に死去していたことが判明している。
取り締まられて当然!
巻き網漁業者数社が2億円の所得隠し 市場通さず取引、申告せず 国税指摘 09/08/14 (産経新聞)
巻き網漁船を操業する茨城県の漁業者数社が、関東信越国税局の税務調査を受け、市場を通さず魚を取引し所得を申告しなかったとして、2億数千万円の所得隠しを指摘されたことが8日、分かった。関係者によると、追徴税額は約1億円に上るとみられる。
数社は青森県の八戸港に魚を水揚げした際、一部について市場を通さず現地の問屋と直接取引して売り上げを申告しなかったり、架空経費を計上したりしていた。国税局は悪質な仮装隠蔽を伴う所得隠しと判断したもようだ。
個人的に思うが日本の公務員は外国人や外国企業に対して甘い。
機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ…国税指摘 09/07/14 (産経新聞)
日本の航空会社に機長ら外国人パイロットを派遣している海外企業7社が消費税を申告しなかったなどとして、東京国税局から2012年までの6年間で少なくとも計約2億円の申告漏れを指摘されていたことがわかった。
日本で事業を始めた約10年前から納税していない企業もあった。日本でサービスを提供する海外企業が消費税を納めないケースは他にもあるとみられ、国税当局は監視を強めている。
関係者によると、申告漏れを指摘されたのは、米国、ニュージーランド、アイルランドなど5か国・地域のパイロット派遣会社7社。申告漏れの額は多いところで数千万円に上り、それぞれ無申告加算税などを追徴課税され、納付した。
税法の規定により、日本に支店や工場などの拠点を持たない海外企業は、日本で事業を行っても、一部の場合を除き法人税を納める必要はない。だが、消費税は、日本で提供したサービスの売り上げに課税されるため、海外企業も申告して納めなければならない。
7社はそれぞれ、自社に所属する数人から数十人のパイロットや整備士を、国内線を運航するスカイマーク(東京)や、地方空港を拠点とする地域航空会社など数社に派遣。航空会社側から、パイロットへの給与(1人当たり年間約800万~3000万円)を含む派遣料や紹介手数料の支払いを受けていたが、これらにかかる消費税を申告していなかったという。
申告漏れの背景には、海外企業側の消費税に対する認識不足もある。
7社のうち、全日空など日本企業2社も出資したクルー・リソーシズ・ワールドワイド社(米国)は、読売新聞の取材に対し、東京国税局の調査を受けたことを認め、「消費税を納めなければならないという認識がなかった」と文書で回答。
リシュワース・アビエーション社(ニュージーランド)の担当者は、「日本での税金は航空会社側が処理する契約になっており、消費税も対応してくれていると思っていた。悪意はない」と話している。
衛生や食品の生産及び加工に関する問題は中国だけの問題ではないと思うが、故意に行っている点で中国は問題であると思う。
日本に輸入される時に検査されているから安心と思っている人もいるが程度の違いはあるが一部は検査をすり抜けていると感じる。根拠は公務員による検査の質。中国の検査は信じない。賄賂が当然の国。日本の検査にも疑問な点がある。分野は違うが船の検査で明らかな問題が見過ごされている事実。素人でも見れば問題と思うレベル。見逃すほうが難しい。これが現実。国土交通省のサイトの情報などは表向きの情報だ。
【閲覧注意】中国環境汚染食品問題からなる被害とは!? (YouTube)
“超”危険な中国食品、マックやケンタで使用?巨大児や奇形児出産、1歳で胸が異常発達… (1/2)
(2/2) 09/07/14 (ビジネスジャーナル)
今年7月、使用期限切れの鶏肉が混入した食肉が、中国から日本に輸出されていたことが発覚。問題となった製造元は、世界17カ国に50の工場を有し、食肉業界では世界最大規模といわれるアメリカの食肉メーカーOSIグループの子会社で中国現地法人の上海福喜食品。
同社の生産過程として、使用期限切れ鶏肉を使ったり、床に落ちたパティ(ハンバーグのように挽き肉を円盤状にしたもの)やチキンナゲットをそのまま製造ラインに戻すなどの映像が中国・上海のテレビ局・東方衛視にスクープされ、「外資系の食品なら安心」という中国国内に広まっていた考えを覆す、非常にショッキングなニュースとなった。これらの鶏肉は日本にも輸出され、日本マクドナルドの「チキンマックナゲット」やファミリーマートの「ガーリックナゲット」などに使用されていたため、両社がこれらの販売を中止し、購入者に対して返金するなどの騒動となった。
この事件については8月29日、上海の検察が「劣悪な食品を生産、販売した」として同社幹部の6人を逮捕したことが報じられた。これで幕引きが図られるかどうかは不明だが、明らかになったのは中国食品問題の氷山の一角という見方が強く、実態がどうなっているのかに日本でも不安と関心が高まっている。
そこで、中国の食肉問題などに詳しいジャーナリストと共に、中国産食品について取材した。
●恐怖の中国食肉生産事情
「今回の事件は、中国の企業が使用期限切れ鶏肉を使用していたことだけを問題としてニュースが伝わっていますが、中国産食品の恐怖はその程度では収まりません」と、中国産食品問題を長く取材しているジャーナリストは語る。
「まず、ブロイラーを育てている環境に大きな問題があります。通常、ブロイラーを育てる場合は1坪当たり40羽ぐらいが適正な数だといわれています。しかし中国ではコストカットのため、1坪当たり100羽以上育てるというのが常態化してしまっているのです。当然こんな環境では狭すぎて不潔で、すぐにブロイラーは病気で死んでしまいます。そして不潔さゆえに悪臭が広まれば、周辺の住民にも知れ渡り、内部の様子の写真や動画がインターネットで広まるかもしれません。そうすれば社会問題となってしまいます。そこで養鶏業者は、外から見えないように窓も一切ない建物の中でブロイラーを飼育するようになるのです。暗闇に閉じ込められ、さらに健康状態も悪化し、3日で鶏は死滅するといわれるほどひどい環境になるため、劣悪な環境でも死なないように、強い抗生物質を大量に与えるのです。さらに、成長促進剤も大量に与え、わずか40~45日程度という異常ともいえる短い飼育期間で鶏肉が出荷されているのです」
中国でも、中国山東省の鶏肉メーカー・山西粟海集団が、飼料に大量の成長促進剤を加え飼育期間を45日間に短縮させたブロイラーで製造した鶏肉を中国のケンタッキーフライドチキン(KFC)やマクドナルドに卸していた、と地元メディアなどが報じた。この報道の中で、鶏に与えている飼料を食べたハエが即死したと伝えており、中国では「速成鶏」として大きな社会問題となっている。
●人体への影響は?
このような鶏肉を人間が食べても、体に影響はないのだろうか?
実は中国では、薬品を大量に投与して製造された食肉を妊婦が食べた結果、成長促進剤の影響か、4kg以上の巨大児の生まれる率が非常に高くなっているのだ。体重が6~7kgある新生児も珍しくなく、巨大児の出生割合は中国国内の新生児の1割を超えている。これは10年前の5倍以上の数字だというから、割合が多くなっているのは確かだろう。
中国地元メディアによると、1歳の女児の胸が発達する、3歳の女児が初潮を迎える、6歳の男児にヒゲが生えるなど、成長促進剤の影響ではないかといわれる事例が頻発しているという。このような環境でつくられる食品が日本に輸出されているとしたら、これを食べて大丈夫なのだろうか?
「日本は輸入食品の検査を行っていますが、その検査は一部に対してモニタリング検査を実施しているにすぎません。また、日本側がチェックする項目は中国側も知っているため、チェックにひっかからないような細工をしているのではないかとの不安は拭えません」(前出ジャーナリスト)
そもそも中国では、地方に行くと環境汚染はさらに深刻で、住民の過半数ががんを患っている「がん村」と呼ばれる地域が200カ所以上もある。そこでは子供でもがんにかかることがあり、奇形児なども珍しくない。
そんな環境の中では、化学物質に汚染された水を使った畑で野菜がつくられていることも多い。そのように中国産の食品は、鶏肉に限らず、どの食材においても危険をはらんでいる。
「食品は、自分や家族の健康に直結します。だからこそ、可能な限り中国産は避けたほうがいいと思います」(同)
鶏肉の使用期限が切れているというだけではなく、中国産の食品は、ほかにも多くの問題をはらんでいるのかもしれない。その危険性も考えて、私たちは「食の安全」を守ることを考えるべきではないだろうか。
(文=編集部)
危険な中国産食品、なぜ日本で流通?検査率わずか1割、ずさんな食品検疫体制の問題点 (1/3)
(2/3)
(3/3) 09/07/14 (ビジネスジャーナル)
中国食品の安全性については、国民的関心が高い。中国からの食品輸入は、日本の農林水産物・食品の輸入総額995億2427万ドル(2012年)の13.7%を占め、米国の19.4%に次いで第2位の位置を占めている。それだけ、日本は中国食品に依存しているといえる。
まず、12年の日本の主な中国食品の輸入品目は以下の通りである。
・コメ:4万8418トン(輸入シェア7.6%)
・栗:7547トン(同67.0%)
・落花生:7万3331トン(同92.3%)
・リンゴ果汁:6万2241トン(同70.3%)
・ニンニク:1万9568トン(同98.5%)
・ネギ:5万2139トン(同99.9%)
・結球キャベツ:2万9100トン(同85.6%)
・人参・カブ:7万1282トン(同86.0%)
・タマネギ:26万9347トン(同78.6%)
・ごぼう:4万5511トン(同94.4%)
・乾燥野菜:3万9149トン(同85.2%)
・冷凍野菜:38万5878トン(同40.4%)
・野菜缶びん詰類:39万44トン(同51.1%)
・豚肉ソーセージ類:2万4253トン(47.3%)
・鶏肉調製品:22万4618トン(49.7%)
・ウナギ調製品:8818トン(同99.1%)
・ハマグリ:6200トン(同93.5%)
・アサリ:2万4910トン(同69.0%)
以上から、輸入シェアが極めて高い食品が多いことがわかる。特に栗、落花生、リンゴ果汁、ニンニク、ネギ、結球キャベツ、タマネギ、人参・カブ、ごぼう、乾燥野菜、ウナギ調整品、ハマグリなどは、輸入品のほとんどが中国産といえる。
これらの中国食品は、主に加工食品材料として使われる。例えば、タマネギは、日本の品種が中国で栽培され、日本に輸入されるときは、「ムキタマ」と称される皮を剥いた状態で輸入され、ハンバーグなどさまざまな料理材料に使われる。乾燥野菜などは、即席麺の具材に使われ、豚肉ソーセージ類や鶏肉調整品も外食産業などで使われる。このように、中国食品は私たちの食生活に加工食品原材料として入り込んでいる。もちろん、そのままスーパーに並ぶ中国食品もある。
●中国食品の安全性に関する問題点
中国食品の安全性に関して指摘されている問題は、残留農薬汚染、残留抗生物質・合成抗菌剤汚染、残留ホルモン汚染、重金属汚染、アフラトキシン(カビ毒)汚染、ウイルス汚染、違法食品添加物汚染などがある。
残留農薬汚染は、農薬使用方法がずさんで残留値が高いだけでなく、日本では危険な農薬として使用禁止されている農薬が、中国ではヤミ流通などで使われている事例も報告されている。現に、大阪のスーパーで販売されていた中国産ショウガから、日本では禁止されている農薬BHCが高濃度で検出されている。この事案では、中国で依然として危険な農薬が流通し、かつ使用方法も農薬残留値が極めて高くなる収穫後の農薬散布、いわゆるポストハーベストとして使われていたことを証明している。
残留抗生物質・合成抗菌剤使用も深刻な事態となっている。水産物の養殖では、日本では禁止されている発がん性のある合成抗菌剤マカライトグリーンが使用され、現に日本に輸出されている養殖ウナギから検出されている。また、ブロイラーなど家畜にも抗生物質や合成抗菌剤、ホルモン剤が使用され、検出されている。
重金属汚染も問題となっている。中国政府も13年に23省5自治区に「がんの村」があることを認め、鉱山などから排出されるカドミウム、ヒ素、ニッケル、六価クロム、鉛、水銀、亜鉛などの重金属に河川、地下水、農地が汚染されている実態が明らかになった。
アフラトキシンはカビ毒であり、自然界で最強の発がん物質で、人に肝臓がんを引き起こす。熱帯性のカビだが中国でも発生しており、特にコメや落花生が汚染されやすい。
ウイルス汚染は、水産物汚染が主体である。A型肝炎ウイルスやノロウイルスなどによって貝類などが汚染されている。A型肝炎ウイルスは潜伏期間が1カ月もあり、発症しても汚染物質の特定が困難という厄介なウイルスであるが、日本には常在していないウイルスであり、中国産貝類などが汚染されている。
違法食品添加物で世界に衝撃を与えたのが、粉ミルクに有害物質メラミンを意図的に混入していた事件であった。メラミンは、接着剤などに使われる窒素化合物で、人が摂取すると膀胱結石などを引き起こすとされている。それをタンパク質を多く含有しているように偽装するために、牛乳に添加していたのである。粉ミルクによるメラミン被害は、中国国内では30万人ともいわれている。
●中国政府も問題視、増加する自国産食品関連事件
13年7月の人民日報海外版では、中国最高人民法院と中国最高人民検察院が共同で記者会見し、典型的な食品犯罪事例を発表したことが報道されている。それを見ると興味深い事例が列挙されており、以下にいくつか紹介してみる。
「02年、被告人は食用アルコールに水道水、トウモロコシ酒、サイクラミン酸などの原料を混ぜて白酒に配合し、トウモロコシ酒と称して売りさばき暴利をむさぼった」
「10年11月より、被告人陳開梅は、(略)病死豚を買い付け、毎月3万3600円の報酬で被告人張可を雇い、病死豚を(略)養豚場に運搬し、(略)食肉処理させた後、(略)販売し、(略)約202万円の違法所得を得た」
「09年7月より11年7月まで被告人は、済南格林バイオエネルギー有限公司の油脂がレストラン厨房の廃棄油を加工して作られたものであることを知りながら、被告人袁一に販売し、(略)袁一は、(略)不法に加工した油脂を瓶に詰め、周辺の工事現場の食堂・屋台・油条(揚げパン)屋台などの事業主に、(略)販売した」
最高人民法院の孫軍工報道官は、次のように食品犯罪について述べている。
「現在、食品の安全を脅かす刑事事件の数は大幅に上昇しており、時には重大・悪質な食品安全犯罪事件も発生している。例えば、毒粉ミルク・毒もやし・廃棄油・問題のあるカプセル・病死した豚の肉など一連の事件で、一般市民はこれらに対して猛烈に反発している」
中国政府自身が、中国における食品の安全性問題が、深刻な事態になっていることを自認しているのである。
このような中国食品の安全性問題を、私たちはどう受け止めるべきなのであろうか。
冒頭で見たように、日本においては米国産農林水産物・食品に次ぐ輸入金額となっている中国食品は、私たちの食生活に浸透しており、日本国民として、その安全性は、決して軽視できるものではない。しかしながら、中国食品の安全性の確保は、第一義的に中国政府の責任であり、日本国民としては、それを見守るしか手はない。もちろん、日本に輸出される中国食品は、その主要なものは日本の企業による開発輸入であり、輸出企業が日本に輸出する食品の安全性を保障すべきものである。現に、中国食品の安全性を強調する論者は、日本向けの中国食品は、管理された農業で生産されており、問題のないことを指摘している。
しかし、農産物は、いくら管理した農場で生産しても、天候による凶作を避けることができない。需要が一定であれば、凶作による品不足を避けるために、中国国内市場で農産物を確保することは容易に想定できる。それらの農産物の安全性が保障されたものでないことは言うまでもない。
●食品検疫体制の問題点と対策案
日本国民として問題にすべきことは、安全性に問題のある中国食品を水際で排除する日本の食品検疫体制についてである。
日本に輸入される食品は、本来、日本の食品衛生法に適合したものでなければ輸入できない。日本の残留農薬基準や残留抗生物質基準などに違反した食品は、輸入できず、廃棄等されることになる。この食品検疫体制が、100%完全に機能しているのであるならば、いくら中国食品が安全性に問題があったとしても、輸入時にチェックされ、日本の食生活に影響を与えることはないはずである。中国食品の問題は、対岸の火で、中国に旅行するか中国で生活する際に気を付ければいいことになる。
しかし、残念ながら日本の食品検疫における検査率は輸入件数のわずか1割程度で、9割の輸入食品は、無検査で輸入されている。当然その中には、中国食品も含まれているのである。検査の内訳を見てみると、行政検査(国による検査)が2.9%、登録検査機関による検査が7.7%である。この国による検査である行政検査は、モニタリング検査ともいわれ、検査結果が出るまで輸入を認めない本来の食品検疫ではなく、検査対象輸入食品の国内流通を認めるもので、場合によっては、検査結果が出たときは、その輸入食品は食卓に並んでいることもあり得るのである。
では、登録検査機関による検査は、どうなのであろうか。
登録検査機関は民間の検査機関である。この民間の検査機関による検査(7.7%)のうち約4%が自主検査である。それは検疫所による行政指導に基づいて行われる検査であり、サンプリングも輸入業者に任されており、その検査の妥当性には絶えず疑問がつきまとうものである。
民間の検査機関に委託する検査のうち、もうひとつの検査が命令検査である。これは、本来の食品検疫検査であり、検査結果が出るまでは、輸入は認められない。しかし、この検査は輸入件数のわずか3.7%にしかならない。さらに、民間の検査機関は、検査料が一律でないために、輸入業者は、安い検査料の検査機関に検査依頼をするため、一部の民間検査機関(検査料が安いだけに、検査人員も少なく、検査機器も必要最低限のものにとどまる)に検査が殺到している。果たしてまともな検査ができているのか、これも疑問がつきまとう。
本来であれば、国が、検査結果が出るまでは輸入を差し止める食品検疫検査を100%実施すべきである。
なぜそれができないのか。
国が検疫所で行う食品検疫検査に従事している食品衛生監視員は、全国でわずか399人しかいない。食品の検査は、サンプリングから検査機器に検査対象食品を入れるまでの前処理工程まですべて人の手によってなされる。なおかつ、OECDによって定められた検査機関のGLP基準によって、検査従事者は、正職員であることが定められている。要するに食品検査は、それに従事する食品衛生監視員を増やさなければ、検査率が上がらないのである。
筆者は、以前から食品衛生監視員を全国で3000人に増員して、検査率を抜本的に引き上げることを主張している。それに要する予算は、仮に一人年間人件費を1000万円としても、わずか300億円である。
そして、食品衛生法を改正して、国による食品検疫検査を、モニタリング検査から本来の検疫検査に変えれば、中国食品による脅威も問題なくなるはずである。
(文=小倉正行/国会議員政策秘書、ライター)
朝日新聞に対する批判が思っていたよりも大きく、仕方なく対応したとしか思えない。新聞社は公共的な機能を期待されるが民間企業なので好きにすれば良い。しかし記事を読む時にバイアスがある可能性を注意し、信頼性のあるニュートラルな情報源でないと思う人が増えるかもしれない。
朝日新聞、池上氏コラム問題でおわび掲載 「掲載見合わせ判断は間違い」「多様な言論大切にする」 09/06/14 (産経新聞)
朝日新聞が、同紙の従軍慰安婦報道の検証を批判したジャーナリスト、池上彰氏のコラム「新聞ななめ読み」の掲載をいったん見合わせ、その後一転して掲載したことについて、同社は6日付朝刊で「間違った判断」とし、読者に対するおわびを掲載した。
おわびは東京本社報道局長名。8月5、6日付朝刊で慰安婦問題の検証記事を掲載後、「関係者への人権侵害や脅迫的な行為、営業妨害的な行為などが続いていました」と説明。その結果、「こうした動きの激化を懸念するあまり、池上さんの原稿にも過剰に反応してしまいました」と釈明した。
「このままの掲載は難しい」と池上氏に修整を打診したことや、掲載見合わせの発覚後に「不掲載」「論評を封殺」との批判が同社に寄せられたことも報告。「今回の過ちを大きな反省として、原点に立ち返り、多様な言論を大切にしていきます」とした。
同社の広報部はおわびの掲載について「読者のみなさまに対し、改めておわびするとともに、説明が必要と判断し、掲載しました」と説明している。
おもしろいサイトが
楽天Social News (デング熱報道についての真相) にリンクされていた。書いている人は原発反対派の人のようだ。
「ところで、今回のメディアによる「過剰なデング熱問題の報道」ですが、発生当初から『なぜ、こんな軽度の感染症が大騒ぎに?』という疑惑がかけられています。
というのも、今年に限らず例年デング熱の感染症患者は発生しており、それも現在は70名、80名に達していると騒がれていますが、近年に至っては毎年200名以上の感染者が発生しているので、今年の現段階の感染者数も決して異常な数ではないようです。
それでも連日過剰にメディアが騒ぐには、もしかするとデング熱問題とは別のところにメディアの報道目的があり、その目的の1つに『代々木公園に人を近づけないため』という、感染症そのものの危機とは別の裏目的があって、その理由として9月23日に開催される大規模な反原発デモの集会があげられています。」
「数日前にテレビ朝日「報道ステーション」の“岩路真樹”ディレクターが自殺で亡くなったというニュースです。・・・というのも、岩路さんの周囲の人々の間の話では、本人は一切自殺するような素振りもなかったようですし、また知人に「身の危険を感じている。私が死んだら殺されたと思ってください」と漏らしていたという証言も出て来ており、どうも岩路さんは“自殺”ではなく“殺された”という事件性のある絡みの見解の方が強まっています。」
上記の内容を書いているので原発反対派だと判断しました。「近年に至っては毎年200名以上の感染者が発生している」のは海外で感染した日本人の数なのか、海外渡航がないない日本人の数なのか明確に書いていない。ひっかけの個所。今回、問題となっているのは海外渡航歴がない日本人が感染している事実。
「代々木公園で長年裸で野外生活をしている男性が、上記のように『ずっと裸で3年もココに住んでるけど一度も蚊に刺された事ねーよ!』と取材に応じている」と
「代々木公園がデング熱問題の発生源なのかもわからないこと」は関連がない。蚊に刺されないのならデング熱のウイルスを持つ蚊が存在しても感染するわけがない。論理的に書いているようで論理的でない。
基本的に警察が100%信頼できる組織でないと思っているが、殺害の危険性を感じている人間が死亡したケースを自殺と判断して捜査を終了するとは思えない。
「岩路さんの周囲の人々の間の話では、本人は一切自殺するような素振りもなかったようですし、また知人に『身の危険を感じている。私が死んだら殺されたと思ってください』と漏らしていたという証言も出て来ており、どうも岩路さんは“自殺”ではなく“殺された”という事件性のある絡みの見解の方が強まっています。」
もし自分な身の危険を感じているなら知り合いにも話す。証拠を公にするために警察が受け付けなくとも警察まで行き、身の危険を感じている事を説明し説明を受けた警官の名前を聞いて知り合いにも警官の名前を話すし、文章を作成して残しておく。ブログがあればブログにも書き込んでおく。そうすれば例え警察上層部が政治家や政府から圧力をを受けも簡単に自殺と判断出来ないと思う。少なくとも自殺と殺害の両方で捜査しなくてはならないと思う。もしかすると考えが甘いかもしれない。しかし中国ではないのだからそこまで警察組織が腐敗しているとは思えない。
デング熱報道についての真相 09/06/14 (天下泰平)
厚生労働省の幹部は危機管理能力がないと思う。「埼玉県内に住む30歳代の男性が、東京・新宿中央公園内でデング熱に感染した」のが事実であればこれから爆発的に感染者が増えるだろう!感染者が急増してからでは遅いと思う。潜伏期間(感染してから症状が出るまでの期間)は3日から14日とすれば今後感染者が増える可能性は高い。
「広範囲にわたって、ウイルスを持つ蚊が存在していることがはっきりした。」と言う事は想像以上に広がる可能性がある。夕方に車に乗り込もうとドアを開けると一緒に蚊が入ってくる事がある。同じ事が代々木公園でもあったと推測すると蚊の移動範囲はかなり広がっていると考える事が出来る。もう簡単には感染を止められないと思う。「デング熱に感染した人からメスが吸血すると、蚊の腸の内壁細胞にウイルスが感染する。」
デング熱感染源となったあの代々木公園は今、どうなっているのか? 09/03/14 (デイリーポータルZ:@nifty)
いつもと違ってひと気が……
さて、デング熱報道で代々木公園の様子は実際はどうなのか? あれだけニュースで報道されているため、人がいなくなっているのではないか?

あれ? 人は……いるな。
ひっそり静まり返っているというわけではない。ダンスの練習をしているグループもいるし、どこからか太鼓の音も聞こえてきている。
そこそこ人はいる。


デング熱発生を受けて、東京都が殺虫剤を散布したときに使ったフェンスがそのまま置かれている。変わったところといえばそれぐらいだろうか?
人が少ないといえばすくないかもしれない、といった程度だ。思ったほどどうってこと無いふだんの代々木公園が、そこにはあった。
あまりきにしてないひとが多いのでは?
そんななか、持参のビールをのんでくつろいでいるグループを発見。
飲むと蚊が寄ってくるというあのビールを、今この時期のここで飲むのか! と驚いたので話をきいてみた。

取材に行ったつもりが……
蚊にもさされたし、これ以上ここにいてもしょうがないので帰るか……と取材を切り上げ、出口に向かって歩いていたところ、待ち構えていたTV局に取材されてしまった。
腰から蚊取り線香をぶら下げながら公園内をふらふら歩いてるのはよっぽど珍しかったようだ。
翌日、放送された番組を確認すると、インタビュー素材はしっかり使われていた。

デング熱、新宿中央公園でも…代々木以外は初 09/05/14 (読売新聞)
厚生労働省は5日、埼玉県内に住む30歳代の男性が、東京・新宿中央公園内でデング熱に感染したとみられると発表した。
男性は代々木公園やその周辺に立ち寄ったことはなく、直近の海外渡航歴もない。男性の容体は安定しているという。
先月26日に約70年ぶりの国内感染者が確認されて以来、代々木公園やその周辺以外での感染が確認されたのは初めて。
感染止まらず「最終手段」、薬剤散布で蚊駆除へ 09/05/14 (読売新聞)
デング熱の感染拡大問題で、デングウイルスを保有する蚊が園内の広範囲にわたって生息していたことが判明し、東京都は4日、代々木公園(東京都渋谷区)の約8割を占める北側部分の閉鎖に踏み切った。
都は5日以降、薬剤を散布して蚊を駆除する方針だ。公園の閉鎖を受け、周辺施設も対応に追われた。
広範囲
「広範囲にわたって、ウイルスを持つ蚊が存在していることがはっきりした。閉鎖は最終手段だった」
4日、都庁で開かれた記者会見で、都公園課の城田峰生課長はこう語った。
1967年の開園以来、同公園の大部分が閉鎖されるのは初めて。都は感染が確認された直後の8月28日、園内で殺虫剤を噴霧し、ボウフラの発生を抑えるため、噴水池の水を抜く対策もとってきた。しかし、感染者は増え続け、都に寄せられた相談も4日までに812件に上る。デングウイルスを保有する蚊が見つかったことで、閉鎖に踏み切らざるを得なかった。
個人的な意見だが朝日新聞は多くの人の信頼を失ったと思う。信頼や信用を失えば新聞社としては成り立たなくなるのでは?
「訂正、遅きに失した」池上氏のコラム一転掲載 朝日、おわびコメント添付も見合わせ理由なし 09/04/14 (読売新聞)
朝日新聞は4日付朝刊で、同紙の慰安婦報道の検証に関して批判したジャーナリスト、池上彰氏のコラムを掲載した。いったん掲載を見合わせた判断の誤りを認めて池上氏と読者におわびするコメントを付けた。
コラムは「池上彰の新聞ななめ読み」。「訂正、遅きに失したのでは」と題し、「過ちがあったなら、訂正するのは当然。でも、遅きに失したのではないか。過ちを訂正するなら、謝罪もするべきではないか」などと指摘している。
同紙は紙面で「本社はいったん、このコラムの掲載を見合わせましたが、適切ではありませんでした」「社内での検討や池上さんとのやりとりの結果、掲載することが適切だと判断しました」と説明した。
また、池上氏のコメントも「朝日新聞が判断の誤りを認め、あらためて掲載したいとの申し入れを受けました。過ちを認め、謝罪する。このコラムで私が主張したことを、今回に関しては朝日新聞が実行されたと考え、掲載を認めることにしました」と掲載した。
ただ、なぜ見合わせたのかの説明はなかった。
池上彰氏、朝日新聞での連載中止を申し入れ 慰安婦「検証」批判、掲載を拒否され 09/02/14 (読売新聞)
ジャーナリストの池上彰氏(64)が、慰安婦問題に関する記事の一部を取り消した朝日新聞報道を批判した原稿の掲載を拒否されたとして、同紙での連載中止を申し入れていたことが2日、分かった。池上氏は産経新聞の取材に「これまで『朝日の批判でも何でも自由に書いていい』と言われていたが、掲載を拒否され、信頼関係が崩れたと感じた」と説明している。
池上氏によると、連載中止を申し入れたのは、朝日で毎月1回掲載されていた「池上彰の新聞ななめ読み」。池上氏は8月29日掲載分として、朝日の慰安婦報道検証や、それを受けた他紙の反応を論評する予定だった。掲載数日前に原稿を送ったところ、28日に担当者から「掲載できない」と連絡があったという。
池上氏は「原稿の具体的な内容については言えないが、私自身は朝日新聞の検証を不十分だと考えており、そうした内容も含まれていた」と述べた。
まったく東電には責任はないとは言い切れないと思う。
福島第一原発作業員ら、未払い賃金求め東電提訴 09/03/14 (読売新聞)
東京電力福島第一原発の敷地内で、がれき処理や機器の点検作業をしていた協力企業の作業員と元作業員の計4人が3日、東電や元請け企業、勤務先の会社など17社を相手取り、危険手当など未払い賃金計約6200万円の支払いを求めて福島地裁いわき支部に提訴した。
訴状などによると、4人は原発事故後の2011年5月以降、下請けの協力会社の作業員として働いたが、危険手当はほとんど支給されなかったという。東電は元請け企業に危険手当分を支払っていたといい、原告側は元請けや協力会社などが不当な中間搾取をしていると主張。東電には作業員が適正な賃金を受け取れるようにする責任があったとしている。原告の中には、残業代などにも未払い分がある人もいるという。
処分が甘いのでは?
住居に扶養、通勤…医師と看護師が手当不正受給 09/02/14 (読売新聞)
大阪府立病院機構は1日、住居手当や通勤手当などを不正に受給したとして、医師と看護師計9人を減給、戒告の懲戒処分にしたと発表した。
不正受給の総額は915万円で、全額が返還されている。
発表によると、急性期・総合医療センターの部長級医師が自宅を購入し、住居手当の対象外となったにもかかわらず、1989年9月~昨年8月、計762万6000円を不正受給したとして、減給60分の1(1か月)とした。
また、同センターなど4施設の医師、看護師の計8人が、住居手当や扶養手当、通勤手当の変更を届け出ずに計153万円を不正受給したとして、3人を減給60分の1(1か月)、5人を戒告とした。不正は昨年8月、同機構が全職員を対象に実施した諸手当の確認調査で発覚した。
逮捕までに結構時間がかかっている!
預かり金など流用か、「丸大証券」元社長ら逮捕 09/02/14 (読売新聞)
顧客からの預かり金などを適切に信託していなかったとして、警視庁は2日、2012年に破綻した証券会社「丸大証券」(東京都中央区)の元社長、井上雅照容疑者(60)(台東区東浅草)ら3人を金融商品取引法(分別管理義務)違反容疑で逮捕した。
金融機関の関係者が、預かり金と自社資産を分別して保管する義務に違反したとして逮捕されるのは、全国で初めて。
発表によると、ほかに逮捕されたのは、同社の元取締役で韓国籍の鄭真作(チョンチンジャク)(48)(神奈川県鎌倉市植木)と、元経理担当社員、小川晴仁(54)(江戸川区南篠崎町)の両容疑者。
3人は12年2月、顧客保護のため3億7000万円を信託しなければいけなかったのに、7000万円しか信託しなかった疑い。全員、容疑を認めている。同庁は、井上容疑者らが11年1月以降、帳簿を改ざんし、信託すべき金を運転資金に流用していたとみて調べている。
NHKの日曜討論をたまたま見た。
8月31日放送 災害列島ニッポン 命を守るためには (NHK日曜討論)
テーマ
この夏、記録的な大雨による被害が全国各地で相次いでいます。中でも、広島市では、今月20日に大規模な土砂災害が同時多発的に発生、70人を超える方々が犠牲になりました。被害はなぜこれほどまでに拡大したのか?政府や地方自治体の対策の課題は何か?そして私たちの防災意識は?
31日の日曜討論では、「防災の日」を前に、私たちの命を守るためには何が必要か、国土交通大臣と専門家が徹底討論します。
出演者
■国土交通大臣 太田昭宏 さん
■政策研究大学院大学特任教授 池谷浩 さん
■群馬大学大学院教授 片田敏孝 さん
■東京大学大学院准教授 蔵治光一郎 さん
■京都大学大学院教授 藤井聡 さん
全ての人々が納得出来る解決方法などないと思った。財政問題、費用、利害関係者(不動産価値や退去させられる人々)、個々の価値観や人命などで正しく、誰もが賛成出来る選択肢などはない。何を優先させるのかだけの話である。
10年前に30人以上の死亡者を出した広島は10年経っても決断が出来なかった。結果が証明している。誰もが納得出来る選択肢など無い。ただ、自分達が住んでいるエリアそして居住しようとしていた場所が危険であるかどうかについては広島市及び広島県は公表し、不動産会見者には顧客には説明することを義務付けるべきだったと強く感じる。不動産価値は下がるだろうが、広島県や広島市が強引に土砂災害警戒区域・特別警戒区域 (広島県)
に指定するよりも反対者は少ないだろう。
居住する人々は財政的なゆとりがある、ない、又は自分の命を優先する、しないなどについて違った優先順位を持っているだろう。危険が存在しても土地が安く通勤や居住に便利な所に住みたい、必ずしも災害が起きるわけでもないので、災害が起きた時は仕方が無いと思う人もいるだろう。土地が安く通勤や居住に便利な所であっても危険が存在するのであれば、がまんして土地の高い場所又は通勤や居住に不便な所で妥協すると思う人もいるだろう。行政が決めれなければ選択する自由と情報を提供するしかない。京都大学大学院教授 藤井氏のように費用や財政事情を考慮せず、砂防ダムを強調するのはおかしい。太田国土交通大臣のように人命を強調してもお金にゆとりがなければ人々は生きてゆけない。貧困の中での自殺や介護疲れによる殺害や無理心中を考えれば人命と言っても、お金に困ると死を選ぶ状況が存在する。死を選択する状況に追い込まれるのなら、災害に巻き込まれて死亡するのも同じ死である。親に金銭的なゆとりが無く教育費で妥協しなければならない家族も存在する。将来の希望が持てずに自殺するのであれば、災害に巻き込まれて死亡するのも同じ死である。財政問題があるから増税するのか?
日本は先進国での借金の額が一番である。奇麗事は誰でも言える。しかし、現実可能な選択肢しか選べない。そこを考えなければならない。
広島県及び広島市はなぜ土砂災害警戒区域・特別警戒区域 (広島県)
の指定に時間が掛かったのか、本当の理由を公表し、県民に考えさせる機会を与えるべきである。人命優先は奇麗事。人間や企業の利益追及が妨害になったのか?行政と利害関係者との癒着があったのか?全てを公表するべきだ。
広島土砂災害 行政の防災対応を見直せ 08/26/14 (産経新聞)
広島市北部の土砂災害による死者は50人を超えた。断続的な雨で二次災害の危険が伴う中、行方不明者の捜索、救助活動が続いている。
日本列島は大気が不安定な状態が続き、北海道・礼文島でも土砂崩れで2人が亡くなった。被害の拡大を防ぐためにも、非常時における行政の防災対応を見直したい。
今回の土砂災害では、行政の対応が後手に回った。広島市が避難情報を出したのは20日午前4時過ぎで、その1時間前には住民から土砂崩れや生き埋めの通報が寄せられていた。広島市も対応の遅れを認めた。
昨年10月の伊豆大島(東京都大島町)の土砂災害を教訓に、政府は「空振りを恐れず、早めに避難指示や勧告を出すように」と自治体に通達していた。
深夜・未明の災害では避難行動にも危険が伴うため、自治体は難しい判断を迫られる。だが少なくとも住民から通報があった段階では、即座に対応すべきだった。
広島県は地質的に土砂災害が起きやすいとされるが、今回の被災地域の多くは土砂災害防止法に基づく「警戒区域」や「特別警戒区域」に指定されていなかった。
全国でも52万5千にものぼる土砂災害の危険箇所のうち、警戒区域などへの指定は7割にとどまっているという。
こうした問題の背景には、行政の防災対応が平常時の感覚に基づいていることが挙げられる。災害を想定した非常時の防災対応に切り替えなければならない。
一方で、「行政任せでは命は守れない」ということも、改めて肝に銘じたい。特にゲリラ型の局地的豪雨に対しては、住民自身が災害を予測し、命を守る行動を早めに始めることも必要だ。
避難指示を待つのではなく、住民から情報を発信し、自治体は現地の要請に即応する。「自助」「共助」「公助」が一体となった防災の仕組みを構築したい。
大規模災害では、被災状況や被災者数などの情報収集を急ぐ必要もある。その点で、発生から6日目の25日になって広島市が行方不明者の氏名を公表したのは、遅すぎると言わざるを得ない。
捜索活動と人命救助に最善を尽くすためにも、不明者の特定は不可欠だ。プライバシーへの配慮などが氏名公表を遅らせた要因だとしたら、本末転倒も甚だしい。
エステ店「たかの友梨ビューティクリニック」の経営手法はこんな感じなのか?「この業界の実態」、つまりビューティクリニック業界は同じような体質なのか?それとも経営状態が悪くなったのかこのような結果となったのか?
フランスに本部のあるISO認証機関ビューローベリタスにおいて、品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001の認証を取得。日本のエステティックサロンとして初めての認証。 (ウィキペディア) ISOの承認を受けているのであればトレーサビリティーもばっちりなので、調べればぼろが出るかも?
テレビで有名になるのは良いが、悪い事でも注目を受けるのでもろ刃の剣だ!
労働基準監督署はもっと厳しく取り締まるべきだと言う事か?倒産する会社が増える?アベノミクスの失敗?やはり見て見ぬふりをする?
高野友梨社長「会社つぶしてもいいの」威圧か 08/29/14 (読売新聞)
エステ店「たかの友梨ビューティクリニック」を運営する「不二ビューティ」(東京)の高野友梨社長が、仙台店での残業代未払いを仙台労働基準監督署に申告した20歳代の女性従業員に「会社つぶしてもいいの」などと威圧的な発言をしたとして、女性が加入する労働組合が28日、不当労働行為の救済申し立てを宮城県労働委員会に行った。
仙台労基署は女性の申告を受け、今月5日、不二ビューティに労働基準法違反で是正勧告を出した。労組によると、高野社長は21日夜、仙台店の全従業員を集めた食事会で女性を前に座らせ、管理職と共に約2時間半にわたって威圧的な発言を続けたという。女性は翌日からショックで出勤できなくなり、記者会見で「恐怖心しか感じなかった」と話した。
同社は「不当労働行為とされるような行為はしていない」としている。
内部通報者が公益保護申し立て 08/28/14 (NHK)
大手エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」の従業員の女性が、残業代の未払いなどを労働基準監督署に通報したあと、会社の代表から「会社をつぶしてもいいのか」などと全従業員の前で詰問されたとして、28日厚生労働省に公益通報者保護の申し立てを行いました。
「たかの友梨ビューティクリニック」は、仙台市にある店で従業員の女性が残業代の未払いなどがあると内部通報を行い、8月、労働基準監督署から是正勧告を受けました。
労働組合の「エステユニオン」によりますと、是正勧告が出たあと高野友梨代表が仙台店を訪れ、全従業員を集めた場でこの女性に対して「会社をつぶしてもいいのか」とか「職場にいながら会社に矢を向けた」などと、2時間半にわたって問い詰めたということです。
この女性は精神的なショックから、出勤できなくなったということです。
女性は、内部通報をした人への不利益な扱いを禁じた、公益通報者保護法に違反しているとして、28日厚生労働省に公益通報者保護の申し立てを行いました。
「たかの友梨ビューティクリニック」を運営する不二ビューティは「女性の主張を確認していないので、今の段階ではコメントできない」としています。
「たかの友梨社長、組合活動に圧力」 従業員ら申し立て 08/28/14 (朝日新聞)
「たかの友梨ビューティクリニック」を経営する「不二ビューティ」(本社・東京都)の従業員が加入するブラック企業対策ユニオンは28日、同社の高野友梨社長(66)から、組合活動をしていることを理由にパワーハラスメントを受けたとして、宮城県労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てた。
(withnews)弁護団が公開した「高野友梨氏の会話」詳細
同ユニオンや弁護士によると、ユニオン側は今月22日、同社の仙台店に対し、仙台労働基準監督署が残業代の減額などの是正勧告をしたことについて記者会見する予定だった。そのことを知った高野社長は、前日の21日に仙台市を訪れ、仙台店の従業員15人や店長らを飲食店に集め、約2時間半にわたり持論を展開したという。
同ユニオンが公開した当日の高野社長の言葉を録音したデータによると、高野社長は席上、組合に入っている女性を名指しして、「間違っているとはいわないけれども、この業界の実態をわかったときに、どうなんだろうか」と組合活動を非難した。さらに「労働基準法にぴったりそろったら、(会社は)絶対成り立たない」「つぶれるよ、うち。それで困らない?」などと問いただした。
ほかの従業員にも「組合に入られた? 正直に言って」と組合員であるかどうかを確かめようとした。
また、高野社長の名前で全国の店舗に対しファクスした文書を、店長に読み上げさせた。「社員数名が『ユニオン』という団体に加入し、『正義』という名を借りて、会社に待遇改善の団交を要求」「会社を誹謗(ひぼう)することは、自分のこれまで頑張ってきた道を汚すことだと私は思います」といった内容だった。
労働組合法は、労働者が労組を組織する権利を認めており、経営者には労組との団体交渉に応じる義務を課している。高野社長の言動について、28日に会見した組合員の20代の女性は「恐怖でしかなかった。会社には間違えていることを改善して欲しいと言ってきたのに、非難された。ほかの組合員や従業員にも恐怖を与えているので、社長には謝罪してもらいたい」と話す。
不二ビューティの担当者は「申し立ては把握していない。不当労働行為とされるような行為はしていないと認識している」と話す。
不二ビューティは1978年に創業。エステ店「たかの友梨ビューティクリニック」を全国124店舗展開し、従業員は約1千人。2013年9月期の売上高は約160億円。高野社長はテレビのバラエティー番組などに多く出演している。
長時間労働の是正や有休の取得を求め、女性エステティシャン5人が今年5月にユニオンに加入し、会社と団体交渉をしてきた。ユニオンの申告を受けた仙台労働基準監督署が今月5日、同社に対し、違法な残業代の減額や制服代の天引きなどの是正を勧告。不二ビューティの担当者は「減額は計算ミス。すでに是正した」と話している。
「たかの友梨」研修費天引きで仙台労基署勧告 08/23/14 (河北新報)
エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」仙台店(仙台市青葉区)で、従業員の給料から研修費を天引きする際に適切な労使協定が結ばれていなかったなどとして、仙台労基署は22日までに、労働基準法に基づき、運営会社の不二ビューティ(東京)側に協定を結び直すことを勧告した。
従業員を支援するブラック企業被害対策仙台弁護団によると、同社は仙台店の従業員代表と天引きをめぐる協定を適切に結んでいなかった。このほか、有給休暇を取らせなかったり、残業代を減額したりした。
仙台店の従業員4人が6月、「会社が従業員代表の名前を勝手に使って協定書を作った」などとして、同法違反で労基署に申告していた。
同社社長室は「是正勧告があったことは事実だ。労基署の指導に従い、適正な労使関係の確立に取り組む」とする談話を出した。
韓国特集なのだろうが、銀行でも儲けるためには何でもやると言う事なのだろう。
韓国最大手の「国民銀行」支店に業務停止命令 不正融資で金融庁 08/28/14 (読売新聞)
金融庁は28日、韓国最大手の国民銀行(本店・ソウル市)の東京、大阪両支店に対し、一部例外を除く新規取引業務を停止する命令を出した。業務停止期間は9月4日から4カ月間。東京支店(東京都千代田区)が不適切な融資を繰り返していたほか、反社会的勢力との取引防止対策が不十分だったことも判明、厳しい処分に踏み切った。
同庁は韓国の金融監督院と協力し、2度にわたる立ち入り検査などを実施。その結果、複数の歴代東京支店長や役職員が、担保査定の資料を偽造して査定価格を水増し、不適切な融資を行っていたほか、その融資先からリベートとみられる金銭を受け取っていたことなどが分かった。
また、反社会勢力との取引防止の取り組みについても、金融機関に義務づけられている反社会勢力をリストアップしたデータベース構築や、取引に際してのチェックが不十分で、同庁は両支店に対し、経営管理体制などを見直し、9月29日までに業務改善計画を提出し、中立的な第三者による改善計画の検証を行うよう求めた。
同行の東京支店をめぐっては、韓国でも裏金作りが行われていたと報じられ、不正融資の総額は数千億ウォン(数百億円)に達する可能性が指摘されていた。
罰則を重くした方が良い。違反して儲けた金を先行投資しているようなものだ!この先行投資は違反。過去の例からはっきりしていると感じるがノバルティスは公正競争を完全に無視している。
ノバルティス、医師71人に旅費510万円支給 08/27/14 (読売新聞)
大手製薬企業ノバルティスファーマが、4月の日本内科学会に出席した医師71人に旅費計約510万円を支給していたことがわかり、医療用医薬品製造販売業公正取引協議会は27日、同社を業界の公正競争規約に反するとして指導した。
同社は自社製品に関する講演会を東京で開いた際、首都圏以外から出席した糖尿病専門医約160人の旅費を負担したが、うち71人は同時期に東京で開かれた同学会にも出席していた。同協議会は学会旅費の支給は規約で禁じた景品類の提供に当たると判断した。
問題はいろいろな要素が重なって最悪の結果となる。
問題行動を高校に伝えず 中間報告 08/23/14 (産経新聞)
長崎県と県教育委員会は22日、佐世保市の高1女子生徒殺害事件の中間報告書を県議会文教厚生委員会に提出した。殺人容疑で逮捕された少女(16)の問題行動を中学校が高校に引き継いでいなかったことなど、対応の問題点をまとめた。
中間報告によると、少女は小6当時、同級生の給食に洗剤などの異物を混ぜ、中3だったことし3月には父親の頭を金属バットで殴打した。小学校から中学校への進学時、異物混入は問題行動として情報提供されたが、中学校から高校へは異物混入も父親殴打も引き継がれなかった。高校の校長は4月25日に殴打の件を教員の報告で把握したが、警察には通報しなかった。
同級生だった被害者の女子生徒(15)との関係について、学校は「一緒に行動することがあり、仲が良かった」と認識。少女がネコの解剖に興味を持っていたことは「把握していない」と記している。
委員会では県議から「学校の度重なる間違った判断が事件を招いた」と指摘があった。池松誠二教育長は「引き続き学校の対応を検証していく」と述べ、年内に専門家の組織を設け、助言を受ける方針を示した。
佐世保「高1同級生惨殺」事件 すべて私のせいなのか……人生はある日突然、狂い出した 早大卒・弁護士・53歳加害者の父「悔恨と慟哭の日々」 (1/5)
(2/5)
(3/5)
(4/5)
(5/5) 08/22/14(現代ビジネス)
妻を亡くして、3ヵ月で再婚したのはいけないことなのか/
再婚相手に何と説明したらいいのか/予兆はあったが/
これから娘とどう向き合えばいいのか/何もかも失って……
熱心に築き上げてきた地位や名誉は一瞬で消え去った。
同級生をバラバラにするという類を見ない事件が、加害者の父を絶望の淵に追い込んでいる。
親娘はどこで道を誤ってしまったのだろうか—。
「あれほどの事件を起こした娘の親となれば、佐世保で弁護士を続けるのはもう不可能でしょう。
仕事がなくなるんだから、この街にはいられなくなるんじゃないですか。有名人だったのが、かえってアダになってしまった。
いままで外面が良かったぶん、騙されたと失望する人も多いですよ」(加害者の父の知人)
もしかして、自分は子育てに失敗したんじゃないか—。子を持つ親なら、誰でもそう不安になる瞬間があるはずだ。
だが親子のすれ違いが、ここまで取り返しのつかないことになるとは、誰が想像できただろう。
7月26日、長崎県佐世保市内で起きた事件を、簡単に振り返ろう。それは、国道35号線沿いのマンションで起きた。
地元の高校に通う16歳の女子生徒(以下J子)が、中学校からの親友、松尾愛和さん(15歳)を惨殺し、バラバラにしたのだ。
犯行時刻とみられる20時ごろ、2人はJ子がひとり暮らしをするマンションの一室で過ごしていた。
2人きりの空間で、J子は愛和さんの頭部を何度も鈍器で殴ったのち、実家で飼っていた犬のリードで絞殺。
さらに遺体の首と左手首は切断され、事件現場には、腹部を切り裂かれた愛和さんの無惨な姿が残されていた。
事件後、J子は警察の取り調べに対し「中学生の時から殺人欲求があった」「(中学の頃から繰り返し行っていた猫の解剖を)人間でも試してみたかった」
などと淡々と供述。凶器として使われたハンマーやノコギリは事前に購入されたものであることが判明し、殺人が計画的なものだったことが明らかになった。
日本中を驚かせたこの事件の加害者となったJ子の育った家庭は、傍から見れば完全無欠に近い、誰もが羨むエリート一家だった。
冒頭で知人が語っているように、父親のA氏(53歳)は、佐世保市内で「超」がつくほどの売れっ子弁護士だ。
'85年に早稲田大学政治経済学部を卒業後、3年間にわたる猛勉強の末、司法試験に合格。'90年から市内の弁護士事務所で4年間の下積みをした後、
独立し事務所を立ち上げた。現在市内に構える法律事務所は7名の弁護士が所属しており、
「県内で最大、九州でもこんなに大きな弁護士事務所はないという規模」(A氏をよく知る弁護士の友人)だという。
弁護士としてのA氏の腕には定評があり、同市内に本社を置く大手通信販売会社「ジャパネットたかた」や、地元の老舗企業の顧問弁護士も務めていた。
「Aさんはこの街の『顔役』で、知らない人はいないというほどの有名人でした。弁護士として活動をはじめた時期に佐世保市の青年会議所に入り、
最終的にはそこで理事長にまで登りつめ、140人を超える会員を率いていましたよ」(地元住民)
A氏は高校時代にスピードスケートで国体に出場するほどのスポーツマンでもあった。
'01年には39歳の年齢で22年ぶりに国体のリンクに復帰し、それから14年連続で出場している。
「実際には、長崎県でスピードスケートをしている人なんてほとんどいませんから、『予選に参加すれば、即国体出場』のレベル。
とは言え、そういうジャンルを選んで実績を作り上げるというのが、彼のやり手たる所以です。国体出場となれば地元紙などに取り上げられ、
弁護士業のアピールに十分なりますから」(前出の地元住民)
ともあれ、弁護士として評判が高く、さらにスポーツイベントにも積極的に参加するA氏は、紛れもなく地元を代表する名士だった。
「彼は政治家としての道も考えていて、近いうちに佐世保市長選に立候補するという話もでていた」(同前)という。
佐世保で異彩を放つ有名人だったJ子の父だが、昨年10月に急死した母親も、父親に劣らぬ存在感があったという。
J子の母は東京大学文学部出身で、結婚前はテレビ長崎の記者として働いていた。父は地元新聞の幹部、兄も東大出身という名門一家の生まれで、佐世保では指折りの才女だった。
「もともと、J子の両親はともに長崎市出身で、高校の同級生だったんです。高校を卒業してからは会っていなかったそうですが、佐世保で再会したのをきっかけに、結婚したと言っていました。当時父親はすでにこの街で弁護士をしていたんですが、奥さんの実家が仕事の関係で佐世保に引っ越してきて、彼女がたまたま遊びにきたときに再会したと聞いています。2人はすぐに意気投合し、結婚に至ったようです」(2人をよく知る知人)
母は、子育て支援やシングルマザーサポートのためのNPO法人を立ち上げるなど、女性の生き方を支えるボランティアをしてきた。また、'04年からの8年間は、市の教育委員を務めるなど、子ども教育への関心も高かったという。
「彼女がはじめた最初のボランティアは、盲目の方に本を朗読するというものでした。朗読した音声をカセットテープに入れて、目の見えない方々に読み聞かせていたんです。なので、市の福祉施設に出入りしていました。それをきっかけに、だんだんと子育て支援に力を入れるようになっていきました。シングルマザーの方が買い物をしやすいようにと、商店街に『親子広場よんぶらこ』という施設を作り、簡易託児所を設置していました」(同知人)
J子一家と付き合いのあった別の知人は、母親の人柄をこう評価する。
「彼女は東大出身ということをまったくひけらかさない、謙虚な方。恰好も質素で、いつもジーパンにポロシャツというカジュアルな服装で飛び回っていました。ボランティア活動を熱心にされていましたけど、それと同時に旦那さんの仕事も支えていたんですよ。旦那さんの事務所では電話番から雑務まで、裏方の仕事をこなしていました。『私にはこれくらいしかできないですからね』と笑っていたのを覚えています」
そしてJ子の兄も、エリートの両親と遜色のない優等生だった。兄は高校3年生時の模試で全国20位になるほど学業優秀で、母と同じ東大を目指していたという。結局、東大への進学は叶わなかったが、現在都内の有名私立大法学部に在籍している。
幼少期のJ子もまた、周囲を驚かせるほどに聡明な子どもだったという。
「J子ちゃんが4歳のとき、事務所に遊びに来てお父さんと話しているところに居合わせたことがあったんです。その内容が4歳とは思えないほど大人びていてね。私が『J子ちゃんは本当に利発やねぇ』と褒めると、あの子は『利発っておりこうさんって意味?』と返してきたんです。こんなに小さな子なのに、知らない言葉の意味をすぐに理解できるんだ、とびっくりしたのを覚えています。
毎年の年賀状も一家全員の姿が写った写真が使われていて、仲良し家族という印象でした」(同前)
そんな「華麗なる一族」の住まいは、市内を見下ろす高台にある。佐世保で富裕層が家を構えるこの地域のなかでも、その家は群を抜いて目をひく大豪邸だ。敷地は約80坪、建物は地上2階、地下1階という造り。敷地内には丁寧に手入れされた観葉植物が並ぶ。
家に招かれたことのある近隣住民の話では、屋内にはグランドピアノが2台置かれており、リビングでは、しばしば青年会議所のパーティが行われていたという。さらに敷地には通行人が足を休めることのできる庭が造園されており、そこにJ子の父が記した「夢いつまでも 自由に生きて」という言葉が刻まれたプレートが置かれている。
カネ、名誉、賢い妻、優秀で聡明な子どもたち。J子の父は誰もが「こうありたい」「こうなれればいいな」と願うもの、すべてを手にしていたはずだった。
だが、娘のJ子は、親友を絞殺し、遺体をバラバラにする事件を起こした。いったい、それはなぜなのか。実は、外見上眩しいくらいにきらびやかだった家庭は、触れればすぐ粉々に砕け散ってしまうほど大きなヒビが入っていたようだ。
それは父親の言動にも原因があったと語る人物がいる。J子の母と10年以上の付き合いがあった友人だ。
名家だけに、家長の発言力が大きかったのだろうか、この友人によれば、J子の父親は家庭内では妻を押さえつけるような言動を繰り返していたという。友人が明かす。
「ご主人はJ子さんが通う学校のPTA会長をするなど教育熱心で通っていましたが、家庭内では違ったようです。奥さんは、『夫がまったく子育ての手助けをしてくれない』と私に嘆いていました。小学校6年生のとき、J子さんが給食に漂白剤を入れて問題になった際も、ご主人は明らかに自分の体裁を気にした様子で『これ以上騒ぎを大きくしないでくれ』と被害者の両親に口封じを迫ったそうです。奥さんは『いつまでも子どもと向き合おうとしない旦那とはやっていけない。早く別れたい』とまでこぼしていました。
奥さんは外出するときにも、どこへ行くか、何時に帰るかご主人に報告していました。ご主人は、なんでも管理しないと気がすまなかったのでしょう。離婚を持ちかけても、受け入れてくれないとも悩んでいました」
ウチの父親はゴミだから
夫婦揃ってエリートで、少なくとも母親の生前はほころびを外に見せなかったJ子一家だったが、母親はごく親しい人物にだけは、家庭の本当の姿を漏らしていたのだ。もちろん、両親の関係はJ子も知っていた。
またJ子の父A氏には、弁護士としての腕を評価する声がある一方で、その手法に疑問を持つ人々も、少なからずいた。一歩家庭の外に出れば「スーパーマン」だった彼も、かならずしもよい評判ばかりではなかったのだ。
「確かにあの人は弁護士としての能力は高かった。でも、Aさんは弁護士というよりも利益を追求する実業家タイプなんです。依頼人に求める報酬も高額で、訴訟になれば、通常の請求額の倍ほどのおカネをブン取ることもありました。訴訟では、相手を徹底的に潰しにかかる。私の周りでも、彼の情け容赦のないやり方に不満を持つ仲間はいました」(前出の弁護士)
A氏にしてみれば、自分の栄誉と同時に、家族に最高の生活を与え、子ども達に最高の教育を施すという家長としての自負がこうした行動につながったのかもしれない。
ただ少なくとも、娘にその気持ちはうまく伝わっていなかった。父と娘の溝が決定的になるのが、昨年10月の母の急死だった。
「昨年膵臓がんで奥さんが急死されたとき、数百人の参列者が集まったんです。事務所の社葬でしたが、参列者の大半は旦那さんの関係者でした。その葬儀で、旦那さんは1時間にわたって妻がいかにかけがえのない人だったのかを『独演』していました。けれど、私は正直、そのスピーチにも違和感を覚えました。亡くなった奥さんを悼んでいるようでいて、実は『悲しむ夫』の役を演じているような気がしたのです。娘のJ子さんも、そんな父親の姿には失望していたのではないでしょうか」(前出のBさんの友人)
今回の事件を起こすかなり前から、J子が父親を嫌い、憎悪すらしていたのではないかと疑わせる証言が、いくつもある。
「実はJ子さんが中学生の頃、一時的に母親のBさんと家を出ていた時期があったそうなんです。それも、父にJ子さんが暴力をふるうようになり、母親が連れ出したのだと聞いています」(J子の同級生を娘に持つ地元住民)
一部報道では、今年の春にも、J子が金属バットで父に襲いかかり、頭蓋骨を骨折させた、などと報じられている。その引き金となったのが、父の再婚だったことは想像に難くない。
「Aさんは妻が亡くなってから3ヵ月しか経っていないのに、20歳以上年下の女性と再婚しています。若い女性と街を歩いている姿も目撃されている。思春期の娘が父親のそうした行動をどういう目で見ていたのか、言うまでもありません」(地方紙社会部記者)
死んでしまえば、お母さんのことはどうでもいいの?やり場のない怒りをぶつけるように、J子は父に殴りかかった。その頃、J子は父に対しての憤りを、周囲にこう漏らしている。
「中学から高校にあがる前に、ウチの娘がJ子ちゃんと商店街で会ったんです。その時、娘はJ子ちゃんとファーストフード店で世間話をしたのですが、彼女が突然父親のことを『ゴミ』とこき下ろしはじめたそうです。Bさんの死後に開かれた校内の弁論大会でもJ子ちゃんは『マイ・ファーザー・イズ・エイリアン』と言い放ったと聞いています」(前出の同級生母)
父の早すぎる再婚を機に、父娘は別居状態に入った。表向きは「海外留学準備」のため。だが、父と娘の関係は、もはや修復不可能な状態に陥っていた。
ひとり暮らしを始めたJ子の部屋で、やがて惨劇が起こった。母を喪った痛み、別の女を家に迎えた父への憎しみ。鬱積したJ子の怒りが破壊衝動へと変わった時、それが向かった先は、たった一人の彼女の友だち、愛和さんだった。
J子の父は今、深い苦悩と悔恨の底に沈んでいるだろう。自分は、娘を育てることに失敗した。原因は、自分にあるのか。二度と、取り返しのつかない結果を招いてしまった……。
だが、妻が病死した後、53歳の男が若い女性と再婚するのは、それほど悪いことなのか。これから、どれほどの「罰」を受ければ赦してもらえるのか。否、もはや赦されることはないのか。
父親は「稀代の殺人少女の親」という烙印を押され、その十字架を一生背負っていかなければならない。確かに、娘が自分に襲いかかってくるなど、予兆はあったのかもしれない。しかし、発端は、ともすればどこの家庭でも起こり得る家族間の行き違いだった。それなのに、我々一家はまさに「すべて」を失うことになってしまった。
父親への復讐は完了した
これほどの事件が起きてしまった以上、父親が若い新妻、つまりJ子にとっては継母となる女性と築くはずだった家庭の幸せも逃げていくだろう。新妻にとってみれば、血もつながっていない娘が、わずか半年ばかりの結婚生活を送った相手にいたというだけで、殺人事件の加害者家族になってしまったのだ。今後、新妻との生活を続けようとしたとき、父親は何をどう妻に伝えればいいのだろうか。いずれにせよ、2人が夫婦生活を続けることは、現実的には難しい。
父親を憎悪し、呪っていただろうJ子は、絶対にやってはならない殺人という犯罪を行うことで、父親の未来を完全に奪い去り、「復讐」に成功したとも言える。
「J子は未成年だから、何年かしたら社会復帰するでしょう。その時、Aさんはどうするんですかね。自分を殴り殺そうとし、友だちを実際に殺してしまったJ子を引き取って面倒を見ることができるのか。『今度こそ、殺されるかもしれない』。そう脅えながら生きていくのでしょうか……」(別の地元住民)
愛和さんの遺族は、一生J子たちを赦しはしないだろう。赦されることはないと知りながら、それでも遺族に謝罪と補償を続ける日々を送ることになる。
ジャーナリストの青木理氏はこう語る。
「被害者の立場になれば、加害者本人やその親が厳しく責任を問われるのは当然です。しかし、今回の加害者は16歳。立ち直りや更生には、父親の力が必要です。家族が支えてくれなければ、誰もあの子を支えてあげられなくなる。
父親はこれまで通りの暮らしは望めないかもしれない。それでも、少しでもきちんとした形で娘さんを支えて欲しいと思います」
もし同じ立場に立たされたとき、その覚悟ができている父親は、一体どのくらいいるだろうか。J子の父親の姿は、明日のあなたなのかもしれない。
基本的には神は信じない。もし神が存在するなら生後3カ月の子供の何がいけなかったのか?これから経験するだろう苦しみから早く天国に救い上げたのだろうか?運命は多少信じる。しかし単なる偶然で運が悪かっただけなのかも知らない。早い段階で児童施設に保護されなかったら生きていても良い人生など無かったと思う。生後3カ月の子供がどうやって助けを求める事が出来るのか?不可能。こんな虐待を受けていたら生き残っても人間不信になる可能性も高い。キリスト教の考えでは苦しみから救われ神のいる天国へ行ったと言う事になるのだろう。
渋谷・乳児殺害 逮捕18歳少女「苦しむ顔にエクスタシー」 08/22/14 (日刊ゲンダイ)
東京・渋谷区のマンションで、同居していた女性(21)の長女(当時生後3カ月)を殺害したとして、長野市の無職の少女A子(18)が26日、警視庁に逮捕された。A子は「殺意はなかった」と容疑を否認しているという。
「A子は同居していた少女B子(18)とともに昨年11月、長女の口をふさいだ暴行容疑で捕まり、少年院に入っていました。司法解剖の結果、ひものようなもので首を絞めた窒息死と判明し、殺人の容疑に切り替えられた」(捜査事情通)
当時、このマンションに住んでいたのは母親と長女、A子、B子の4人。3人は長野の同郷で、昨年8月ごろから同居していたという。
「3人は風俗関係の仕事をやっていて、知り合ったそうです。同郷つながりから仲良くなり、同居を始めたそうですが、母親はネグレクト気味で、長女の面倒をほとんど見なかった。代わりに面倒を見ていたのがA子とB子でしたが、子どもを押し付けた母親に対する怒りがあったようで、長女を虐待していたそうです」(捜査関係者)
■ミルク代わりに清涼飲料水
A子は長女をいじめていくうちにエクスタシーを感じるようになったという。
「母親は事件の1カ月前に借金から逃げるため、ほとんど帰宅しなくなり、A子らの虐待はひどくなった。水風呂に沈めたり、ミルクの代わりに清涼飲料水を与えたりしていた。口をふさぐ様子をカメラに撮影し、<苦しんでいる写真を見るとテンションが上がる>と話していたといいます」(前出の捜査事情通)
長女を守る人が誰もいなかったとはやるせない。
人間には残酷な部分があり、欲求がある。食べるなどの基本的欲求やその他の欲求は個人により優先レベルが違う。しかし、理性や自分をコントロールすることにより欲求を抑えると本で読んだ事がある。快感や欲求のために人間の殺害は問題だ。
佐世保の少女殺害と同じように精神鑑定を受けるのだろうか?
「苦しがる姿が快感」…生後3カ月の女児を絞殺 同居の少女を逮捕 (1/2)
(2/2) 08/26/14 (産経新聞)
「苦しがる姿が快感」…生後3カ月の女児を絞殺 同居の少女を逮捕 08/22/14 (日刊ゲンダイ)
知人女性(21)から預かっていた生後3カ月の女児の首を絞めて殺害したとして、警視庁少年事件課は殺人容疑で、長野市の無職の少女(18)を逮捕した。同課によると、少女は「殺すようなことはしていない」と容疑を否認している。
逮捕容疑は昨年11月1日午前2時ごろから7時ごろまでの間、東京都渋谷区道玄坂のマンション6階の一室で、女児の首をひものようなもので絞めて窒息させ、殺害したとしている。
少女は同8月ごろから現場のマンションで、女性と女児、別の少女(18)と同居。同日午前2時ごろから2人きりで女児の世話をしており、別の少女が同7時ごろに帰宅し、心肺停止状態の女児を発見し119番通報したが、搬送先の病院で死亡が確認された。
司法解剖の結果、女児の首に絞められたような痕が見つかり、窒息死の疑いがあることが判明。少女は警視庁の事情聴取に「朝起きたら死んでいた」と説明していたが、その後、別の少女らに「女児を殺してしまった」と相談していたことが分かった。
一方、少女と別の少女が女児の搬送前に、現場近くのコンビニ店のごみ箱に同10月中旬に女児の口をふさぐ様子を写した写真を捨てていたことが発覚。2人は同11月15日に暴行容疑で逮捕され、同12月に少年院送致になっていた。少女は当時、「女児が苦しがるのを見るのが快感だった。死んでも構わないと思った」と供述していた。
外国人労働者が増えると言う事は外国籍やハーフの子供が増えると言う事。裕福な外国人であれば子供の教育にお金をかけるが、仕送りや低い賃金で生活にゆとりがなければ子供の教育に時間やお金をかけない傾向が多い。これは日本人貧困層でも同じ事が言える。真剣に考え、厳しく対応しないと大きな問題となる。
「怒羅権などの凶悪な犯罪組織に発展する前に、少年らを更正させていくことが警察の使命だ」
まじめに働いても報われない環境で、しかも働くよりも犯罪を選択するほうが楽にお金が手に入る環境で、どのように更生させるのか?日本国籍で無い外国人は犯罪を犯せば国外退去できないのか?出来ないのなら法改正を行った方が良い。
危険ドラッグ欲しさにひったくり、フィリピン人不良少年グループの実態とは… (1/4)
(2/4)
(3/4)
(4/4) 08/23/14(産経新聞)
危険ドラッグ(脱法ドラッグ)欲しさにひったくりを繰り返していたのは、フィリピン国籍やそのハーフの少年らでつくる不良グループのメンバーだった。少年らは「ピノイ・プライド・チル(PPC)」を名乗り、東京・錦糸町を中心に約200人のメンバーがいると豪語。中国残留孤児の2世、3世を中心とした「怒羅権(ドラゴン)」を連想させるが、果たしてその実態とは…。(荒船清太)
■「危険ドラッグ買った」…酔客狙い、自転車3台で
7月25日午前3時すぎ、東京都台東区浅草橋の路上で、酒を飲んで歩いて帰宅途中だった派遣社員の女性(47)の脇をスピードを出した自転車3台が追い抜くやいなや、女性の左手から現金約1万円入りの財布などが入った手提げバッグを奪っていった。
女性は110番通報したものの、酒に酔っていたことから、追いかけることもかなわず、自転車3台はそのまま夜の闇に吸い込まれていった。ところが、犯人は自分たちから尻尾を出す。間もなく千葉県市川市内のラブホテルで、奪われた女性のクレジットカードが使われたのだ。
警視庁蔵前署員が駆けつけたところ、ホテルにいた3人がカードを使ったことを認めるなどしたため、荒川区に住むフィリピン人と日本人のハーフの少年(19)と、いずれも墨田区に住むフィリピン国籍の16歳と18歳の少年の計3人を窃盗容疑で逮捕した。
少年らは不良グループ「PPC」のメンバーを名乗り、少年事件課の取り調べには素直に容疑を認め、こう供述した。
「奪った財布に入っていたカネで、危険ドラッグを買った」
■「嫌なことを忘れ、いい気分に」…犯行直前に吸引、異常なテンション
ひったくり事件から遡(さかのぼ)ること約3時間半前の25日午後11時半ごろ、千葉県市川市のJR市川駅周辺で、異様なテンションでじゃれあう3人の姿があった。
酒の臭いはしない。代わりに、危険ドラッグ特有の甘ったるい人工的な香料の臭いがうっすらと漂う。3人は市川駅前に危険ドラッグを宅配させて購入。すぐに火を付け、吸引していたのだ。だが、それだけで満足できなかったようだ。
2~3時間後、拠点とする東京・錦糸町に戻ると、ハーフの少年がひったくりを持ちかけた。自転車は2台しかなかったが、2人乗りでは警察官に職務質問される恐れがあるため、1台を盗んで調達。抵抗しなさそうな通行人を物色して犯行に及んだという。
盗んだカネは、また危険ドラッグのために使われた。3人は市川駅前に戻り、さきほど危険ドラッグを頼んだばかりの宅配店に電話。「浦安ならまだ買える」と言われ、浦安駅まで移動して危険ドラッグを購入して吸引した。
「嫌なことを忘れていい気分になりたかった」「テンションが上がるからやった」などと捜査員に説明しているという3人は、1~2年前から危険ドラッグを常用。借金の返済や遊びよりも、危険ドラッグを購入することを何よりも優先するようになっていた。
少年らの自宅からは、危険ドラッグの商品名「スパイラル」の空き袋2つが見つかっており、少年事件課は薬事法上の指定薬物が含まれている可能性があるとみて鑑定を進めている。
■「フィリピン魂」+「かっこいい」 主な活動はコンビニ店での「たむろ」
ピノイ・プライド・チル-。少年らが口にした謎のグループはどんな集団なのか。警視庁幹部は「少年らを逮捕するまで、名前を聞いたこともなかった」といぶかしむ。
外国がからむ不良グループとしては、中国残留孤児の2世、3世を中心とする「怒羅権」が有名だ。強い縄張り意識があり、指定暴力団との抗争も辞さず、振り込め詐欺や強盗などの組織的な犯罪にも手を染める。昨年3月には、警察当局から準暴力団に位置づけられた。
PPCはどうなのか。
「ピノイ・プライド」は直訳すると、「フィリピン人の誇り」で、いわば「大和魂」のフィリピン版。警視庁幹部によると、これに「かっこいい」「クール」などを意味する「チル」を付け加えたのが、組織名の由来とされる。
インターネット上の交流サイト「フェイスクブック」に開設されたPPCのページには、平成21年4月6日に設立されたと明記され、英語で来歴まで書いてある。
「PPC、またの名を極道。都内の有志の若者で構成され、日本警察の要請を受けてメディアは暴力団と呼ぶ。その行動と過激な性質で悪名高く、錦糸町では特に名をはせている」
このページを詳しく見ると、PPCのメンバーの主な活動はコンビニ店前や路上での、しばしば酒を伴った「Tamuro(たむろ)」。「PPCの2012年での定義は『一つの愛』」と意味不明な書き込みもあり、ネット上で公開されたPPCのメンバーがプールで遊ぶ様子を写したビデオを見ても、凶悪性はあまり感じられない。
捜査関係者は「不良に毛が生えたようなグループではないか」と分析。「ひったくりや万引などの犯罪に手を染める程度で、とても暴力団に対抗することはできない組織」とみている。
ただ、逮捕された少年3人は今回の事件を含め、少なくとも3件のひったくりや車上狙いなどに関与していたとみられ、犯罪行為を繰り返していたグループであることに変わりはない。捜査関係者はこう言って気を引き締める。
「怒羅権などの凶悪な犯罪組織に発展する前に、少年らを更正させていくことが警察の使命だ」
委託費の計約43億円は大きな額だ!なぜ厚労省が自ら調査を行わないのか?一部の職員はグルなのか?それともずさんな判断だったので逆にそれを指摘されるのがこわいのか?
謝罪どころか…「DIO」社長が従業員に要求した“誓約書”の呆れた中身 08/22/14 (日刊ゲンダイ)
従業員はカンカンだ。国の緊急雇用創出事業として東日本大震災の被災地などでコールセンターを運営していた「DIOジャパン」。委託費を計約43億円も受け取っておきながら、雇い止めや給料未払いなどが相次ぎ、7月末に突然、本社業務を休止した。厚労省はDIO社に不適正な運営があったとして、関係する11県19市町に、調査の徹底と、必要なら委託費の返還を求めるように通達したというが、それで従業員が納得できるわけもない。
DIO社が宮城県で運営していた「みやぎ美里コールセンター」では今月11日、従業員101人を集めて解雇を通知。一時は「美人社長」と持ち上げられた本門のり子社長もその場に姿を現したが、ある従業員は「謝罪の言葉もなかったし、派手なピアスをじゃらじゃらさせていた」と激怒していた。
■従業員はますます激怒
それだけじゃない。同13日に行われた従業員に対する説明会では、「誓約書」の提出を求められた。その一方的な内容にも、従業員は怒り心頭なのだ。本紙が入手した誓約書には、4項目の“約束”が記されている。
<コールセンター内部のことを他人に話さない><誹謗中傷をしない><内部資料または個人情報を持ち出さない>
と、ここまでは理解できるが、最後の項目には首をかしげたくなる。
<退職後は原則として1年間は、就業していた事業所の所在する県内において、同業他社への就職、役員の就任、ならびに同業の自営をしてはならない>
「給料も払えないような会社に縛られるいわれはないし、納得できない。その場にいた全員が、誓約書にサインしませんでした」(別の従業員)
企業法務に詳しい弁護士によると、こうした競業禁止規定は、たとえば特許が絡むような特殊な技術職などに設けられるのが一般的。税金を使った雇用創出事業であることを考えれば、「違和感を覚える」という。
DIO社の代理人弁護士は「コールセンターでも研修を行っていて、特殊な技術職といえます。法的な問題はない」と説明する。とはいえ、もともと雇用創出事業なのに雇用の機会を奪おうとするなんて、本末転倒だろう。
校長や学校は父親への暴力を知っていたから、殺人事件が起きた時の校長のコメントをテレビで見た時になんて事になったんだと個人的に感じたのかもしれない。加害者がかわいそうとかよりも、何でこんな事が起きてしまったんだと落胆している方か大きく感じた。そう感じたのは自分だけなのだろうか?
高校側、父親への暴力を4月に把握…佐世保殺害 08/19/14 (読売新聞)
長崎県佐世保市の高1女子生徒殺害事件で、逮捕された同級生の少女(16)が今年3月に父親を金属バットで殴ったことについて、高校側が4月下旬に把握していたことがわかった。
児童相談所や警察などには相談していなかった。県教委は、22日に開かれる県議会文教厚生委員会で、こうした経緯を「中間報告」として説明する。
県教委や少女の父親の代理人弁護士によると、少女は3月2日、父親を金属バットで殴り、頭などにけがを負わせた。また、少女は高校入学後、マンションで一人暮らしを始めたが、入学式を入れて3日間しか登校しなかった。
県教委の調査によると、高校側は、職員が1~2週間に1回の頻度で少女の部屋を訪ねたり、食事をしたりしていたほか、メールや電話でも連絡をとっていた。
この職員は4月25日、少女が父親を殴っていたことや一人暮らしをしていることを校長に報告。校長は報告内容を副校長らと共有し、この職員に引き続き少女と会って見守るよう指示した。しかし、関係機関への相談などはせず、保護者との面談も行わなかったという。
思ったほど法は弱者の味方で無い事を理解した方が良い。被害者や被害を受けないと理解する機会が無い。
悪質であれば刑を重くするべきだと思う。警察、検察そして弁護士にとっては結局他人事。基本的に前例に従い対応するだけ。
「兵庫県明石市が今年4月、犯罪被害者支援条例を改正し、全国で初めて賠償金の一部を立て替える制度を開始した。同市市民相談室によると、市内の犯罪被害者の声を受けた条例改正で、一般世帯が最低限1年間暮らせる金額として最大300万円を立て替えられる。市が遺族から加害者に対する300万円分の求償権を譲り受け、加害者の財産を差し押さえて徴収していくという。」
無いよりはましだが、十分ではない。しかし、全て上手くいくわけはないので仕方のない妥協かもしれない。
実行されぬ遺族への「賠償」…息子をリンチで殺された母の慟哭 (1/4)
(2/4)
(3/4)
(4/4) 08/16/14(東洋経済)
神戸市須磨区で平成22年10月、元専門学校生の釜谷圭祐さん=当時(19)=ら2人が暴行され、釜谷さんが死亡、もう1人が重傷を負う事件があった。この事件で、傷害致死傷罪に問われた主犯格の男(26)には25年2月、神戸地裁が懲役14年の実刑判決を言い渡し、上告棄却後の11月に確定した。損害賠償を求めた民事訴訟も含めて一連の裁判は終わったが、この男からの遺族への賠償は今も実行されていないという。釜谷さんの母、美佳さん(48)は「被害者は泣き寝入りするしかないのかもしれない」と悲嘆に暮れる。犯罪被害者や遺族への賠償が進まない現状に、専門家からは「以前から存在するものの解決が難しい問題。国が責任を持って対応しないといけない」との声も上がる。(清作左)
■むなしい「対話」
この事件は、男の仲間らが取り囲む中で起きていたことなどから、当時は「集団リンチ事件」とも呼ばれた。ただ、きっかけは男の勘違いだった。
男は22年10月29日未明、妹と一緒に遊んでいた釜谷さんら2人が妹を“連れ回している”と思い込み、激怒。仲間などを集め、集団で釜谷さんらに暴力をふるって逃げた。男の暴力は神戸地裁判決で「無抵抗の被害者に執拗かつ危険な暴行を加え、死亡させた。遺族の悲しみは察するに余りある」とされたほどで、釜谷さんは顔が判別できないほど殴られ、その日の内に死亡した。
事件を巡っては、男のほかに、同罪に問われた当時少年だった男に懲役3年以上4年6月以下の不定期刑などが確定している。
民事裁判では、神戸地裁から男らにそれぞれ約8千万円の賠償命令が出たが、美佳さんには賠償金は一切支払われていない。そこで美佳さんは実情を把握しようと、兵庫県弁護士会の「犯罪被害者・加害者対話センター」を利用し今年6月、男の母親から直接話を聞いたが、その言葉に愕然(がくぜん)とした。
「私たちは自己破産して払えない。息子には払わせる」
謝罪もなく、ただ、金銭の話を切り出されたのだ。「お金が欲しいわけじゃない。謝罪の気持ちを見せてほしかったのに」。悔しさだけが募った。
■罪の意識の「差」
「圭祐のことを、事件のことを忘れないでほしい」
そんな思いから、美佳さんは事件現場に居合わせ、主犯格の男と知り合いだった男性5人に調停を申し込んだ。5人は釜谷さんの靴や財布を盗むなどしたが、このうち1人は連絡がなく、調停の場にも現れなかった。
調停の際、美佳さんは集まった4人に「本当は現場にいた全員に来て、話し合ってもらいたかった。自分たちで賠償額を決めてほしい」と諭した。今年6月、4人が出した“答え”は、最も賠償額が高いケースでも、2年間毎月1万円を支払うというもの。賠償に加え、釜谷さんの命日に美佳さんに毎年、手紙を出すという内容で調停は終了した。
「あのとき1人でも通報してくれれば、圭祐は助かったかもしれないのに。ばかにしているのだろうか。ことの重大性をわかっているのだろうか」。男性らの認識の低さに悲しさがこみ上げた。
それでも、最初の支払いとなった7月分は4人から入金があったという。美佳さんは「お金を払うことが罪の意識を持ち続けるきっかけになると思う。だからこそ、気持ちとして払ってほしい」と訴える。一方で「もし『支払えない』と言われたら、一般市民が取り立てることもできない。そのときは、泣き寝入りするしかないのかもしれない」と懸念する。
■泣き寝入りを防ぐには
被害者学の第一人者で、常磐大大学院の諸沢英道教授によると、諸沢教授が犯罪被害者の遺族約240人を調査した結果、遺族に一部賠償がなされた例はわずか十数%に止まり、全額支払われた例はなかった。諸沢教授は「被害者の刑事裁判の参加を認めるなど支援制度はできてきたが、被害者への賠償に関する問題は立ち止まったままだ」と指摘。「国や自治体が責任を持って救済措置を作らなくてはならない」と訴える。
ただ、こうした現状に歯止めをかけようと動き出した自治体もある。
兵庫県明石市が今年4月、犯罪被害者支援条例を改正し、全国で初めて賠償金の一部を立て替える制度を開始した。
同市市民相談室によると、市内の犯罪被害者の声を受けた条例改正で、一般世帯が最低限1年間暮らせる金額として最大300万円を立て替えられる。市が遺族から加害者に対する300万円分の求償権を譲り受け、加害者の財産を差し押さえて徴収していくという。
まだ利用者はいないというが、同室の担当者は「使う機会がないことが一番良いが、もし何か起きたときに市民をしっかりと支えてあげたい」と語る。
諸沢教授は、被害者が取り立てる場合、弁護士費用や訴訟費用など金銭面の負担が大きくなると説明し、「もっと、明石市のような制度を他の自治体も制定していく必要がある」と話している。
「現在破産手続き中」なので会社に対する処分は不可能?責任者や社長に対しの処分は規則や法律上、可能なのか?
除染作業員の健診怠る 横浜の業者、診断書を偽造、受診装う? 08/19/14 (産経新聞)
東京電力福島第1原発事故に伴う福島県田村市での除染作業で、作業員を派遣した横浜市鶴見区の業者が必要な健康診断を作業員に受けさせなかったとして、鶴見労働基準監督署が6月、労働安全衛生法違反で是正指導していたことが19日、労基署への取材で分かった。偽造した健康診断書を作り、受診させたように装っていたとみて調べている。
労基署によると、この業者は松栄ワークスで、現在破産手続き中。大手ゼネコンの鹿島(東京)が中心の共同事業体(JV)が環境省から受注した除染作業を請け負っていた。
労基署は、除染作業員には厚生労働省の規則で、被ばく歴の有無の確認や血液、白内障の検査など必要な健診が定められているのに、同社が受診させていなかったとしている。環境省によると、田村市では、住宅の屋根や壁に付着した放射性物質を洗浄したり、農地の表土の線量を下げたりする作業があった。
福島第1原発の解体も予定通りには進まない事は確実だろう。
“氷のフタ”が凍らない! 320億円が溶ける手詰まり「汚染水対策」 08/19/14 (日刊ゲンダイ)
福島第1原発の地下トレンチ(地下道)にたまった高濃度汚染水をせき止めるための「氷のフタ」が、3カ月以上たってもまったく凍らない。7月末からトレンチの汚染水と建屋の接続部分に300トンに上る氷を投入、今月7日はドライアイス1トンも投じたがいまだに凍結していない。
19日の原子力規制委員会では別の工法が議題に上がるという。その工法とは「資材グラウト」の注入が濃厚だ。「資材グラウト」は水中で固まるコンクリートのこと。つまり凍結をあきらめ、コンクリ投入によって固めてしまうつもりだ。
「手詰まりが鮮明になったということです。仮にコンクリ投入で一時的に遮断しても、劣化した隙間やヒビ割れ部分からすぐに汚染水が漏れ出すでしょう。モグラ叩きみたいなもので、根本解決にはなりません」(元大阪市立大学大学院教授の畑明郎氏=環境政策論)
さあ、こうなると同じ方式で進めている「凍土壁」造りもどうなるやら。
「寒冷地の川を見ても分かるように、流れている水を凍結させるのは至難の業です。東電は地下水の流量と速さの想定を見誤ったのでしょう。もともと懸念されていた工法を見切り発車した結果がこれですから、目も当てられません」(畑明郎氏)
凍土壁に投じる国の予算は320億円。「残念」では許されない。
信じる者は救われるではなく、信じる者は騙されるだろう!
着工1週間で暗礁…専門家も危惧する原発「凍土壁」の重大欠陥 (1/2)
(2/2) 08/12/14 (産経新聞)
2日に着工したばかりの福島第1原発の「凍土遮水壁」の工事が、わずか1週間で暗礁に乗り上げようとしている。埋設しようとしている約1500本の凍結管のうち、約170本が地下の埋蔵物とぶつかることが分かり、東京電力と工事を担当する鹿島建設が対応に頭を抱えているのだ。
元大阪市立大学大学院教授(環境政策論)の畑明郎氏がこう言う。
「安倍政権は威勢良く啖呵(たんか)を切って着工したわけですが、もともと、何人もの専門家が凍土壁の工事は不可能だと指摘していました。ただでさえ全長26.4メートルもある凍結管を1メートル間隔で1500本も埋設しなくてはならない難しい工事なのに、地震の影響で建屋の地下の配管が複雑に絡み合い、デコボコになっている。埋蔵物が見つかった場合に避けて凍結管を埋設するのか、貫通させるのかといった方針を固めず、“やってみないと分からない”と見切り発車してしまった。こんな工事に320億円も税金を使うとは信じられない話です」
1500本の凍結管のうち、1割以上の170本が埋設できないとなったら、凍らせて「壁」を造ることは難しいだろう。そもそも凍土壁は2011年6月当時、民主党政権がやろうとして立ち消えになったプランだ。凍土壁はトンネルなどの工事に一時的に使われる技術で、これだけの大規模な工事は前例がない。
「地下の配管を避けたりして、凍結管の“1メートル間隔”が狂えば、当然、凍りにくい場所が出てくるでしょう。工事の終盤になって『壁』がガラガラと崩れたら元のもくあみです」(畑明郎氏)
凍土壁が完成したところで“副作用”が懸念されている。凍土壁の内側の地層に含まれる地下水が減ることで地盤沈下を招き、建屋が傾きかねないという。
今からでも遅くない。取り返しがつかなくなる前にギャンブルをやめて、別の解決策を見いだすべきではないか。
下記のサイトにリンクされている動画を見ていると返事の辻褄があっていない。ウソがばれるのも時間の問題かも?
【画像】 湯川遥菜(日本人)がイスラム過激派組織ISISに捕まり、安江塁が身分を暴露 (NAVER まとめ)
シリアの拘束邦人か…激しく詰問され「日本だ」 08/18/14 (読売新聞)
【カイロ=溝田拓士】内戦中のシリアで日本人が拘束されたとみられる事件で、この日本人とみられる男性が拘束された時の様子が動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿されている。
16日に投稿された約2分ほどの動画によると、男性は地面にあおむけに倒され、複数の男から英語で激しく詰問され、頭から出血している。男たちに「どこから来た」などと問われ、「日本だ」などと答えている。
一方、シリア反体制派の武装組織「自由シリア軍」の関係者(28)は17日、本紙の電話取材に対し、日本人男性がイスラム過激派組織「イスラム国」に拘束された可能性があると語った。
また、拘束された場所はシリア北部アレッポ近くの町マーレアとの情報があると明らかにした。マーレアは激戦地アレッポの約20キロ北にある。付近では、16日に日本人が拘束されたとの情報が入った数日前まで、イスラム国と、シリア反体制派の武装組織「イスラム戦線」が激しい戦闘を行っていたという。
氷山の一角?組織の体質?
ファミマ社員、加盟店への犯罪行為でずさん管理体制露呈 公表しない本部に加盟店が反発 (1/4)
(2/4)
(4/4) 08/18/14(Business Journal)
7月、中国の食品加工会社が期限切れ鶏肉を使用していた問題が発覚。コンビニエンスストアチェーンのファミリーマート(中山勇社長)は、この会社から仕入れた材料を使用していた「ガーリックナゲット」と「ポップコーンチキン」の販売を中止するなど、騒動に揺れた。その同社で、加盟店を指導するスーパーバイザー(SV)による重大な不祥事がわかった。同社はその事実を世間には公表しておらず、企業姿勢も問われそうだ。
今回わかったのは、東京都の多摩地区を担当していたSVが、加盟店からQUOカードを窃取し、伝票操作によって隠していたもの。ファミマ多摩・甲信地区営業統括部の部長印が押された内部文書によると、被害に遭ったのは6店で被害総額は55万9000円とされるが、「もっと多いはずだ」(加盟店主)との見方もある。
●紛糾した店長集会
ファミマがこの不祥事を初めて内部で説明した7月15日の多摩甲信地区店長集会は大荒れとなった。集会の冒頭、多摩・甲信地区営業統括部の村井律夫営業統括部長が、こう切り出した。「今般、当社SVが、自らが担当する商品、現金などを不正に取得するという事案が発生いたしました」。事件そのものにはごく簡単にしかふれず、村井部長はこう続けた。
「加盟者の損害につきましては、調査のうえ責任をもって弁済し補填をさせていただくこととしております。また当社は、当該SVを自宅謹慎処分にし、今後厳正なる処分を下す予定でございます。……深くお詫び申し上げます。今後二度とこのようなことがなきよう、社員の教育体制を見直し、社内に構築し、また、店間伝票等の運用を改善することが急務であると理解しております。ほんとうに申し訳ございませんでした」
何が起きたのか、そのSVは誰なのか。わけがわからないままでは、加盟店は納得できるはずもない。会場から声が上がった。「村井さん、もっと具体的に話してよ」。
質問を予想していなかったのか凍りつく村井部長に代わり、司会役の社員が「質疑応答の時間は設けておりません」と言うが、それでは収まるはずもない。
女性店主も「ちゃんと話してください」。「これ、全加盟店の問題よ」と先ほどの男性店主が続ける。「私(不正を示す)伝票、持ってるんです。コンプライアンスの問題でしょ」。本部側は「ほかの加盟店さんの迷惑になるので、ご退場を」と収拾に躍起となるが、「もみ消すっていうの」と反発され、会場は騒然。見かねた平田満次・営業本部長補佐(常務執行役員)が割って入った。
一部社員が不正を起こしたことは事実です。それによって加盟店さんにご迷惑をかけたことは、私ども株式会社ファミリーマートの、私を含めた幹部社員の管理不行き届きということもわかっておりますし、村井もたいへんな処分を受けるというふうになっております。私(に)もたぶん、処分が降りると思います」
詳しい説明を求める一部加盟店主に、本部側が激高する一幕もあったという。
●QUOカード窃取の手口
いったいSVの不正とは何か。関係者の話を総合すると、SVは自分の担当のファミマ店舗に行き、そこで売っているQUOカードを持ち出す。といっても、万引きではない。「QUOカードを貸して」と言って店員に指示し、レジでは「廃棄処理」する。つまり、QUOカードを会計上「捨てたこと」にするのだ。
「一定額以上のQUOカードの廃棄は、ファミマの会計では『営業雑費』の項目に入ります。SVは、そのマイナスを『来月、販促費として戻すから』と言うのです。廃棄額=販促費なら加盟店に実損はないのですが、きちんと埋めてもらえないことがありました」(加盟店主)
ファミマ本部側の説明では、SVは廃棄処理をせず、自分が持ち出したQUOカードの店間伝票を起票し、ある店舗から別の店舗に移動したことにする操作もしていた。「商品、現金の取得によって、当該店舗には棚不足(あるはずの商品がないこと)が発生します。しかし当該SVは、実地棚卸前に店間伝票を不正に起票する方法を繰り返すなどして、棚不足相当額を別の店舗に移し替え、不正取得の隠蔽工作をし、他の店舗に(も)損害を与えました」(店長集会での村井部長の説明)。いわば損失の付け替えが行われていたことを認めた。
●晴れない疑問
ここまでなら、「1社員(SV)の不祥事」と見えるかもしれない。だが取材を進めると、そうとも言い切れない事情が浮かんできた。
その一つが、このSVがなぜ簡単に「店間伝票を不正に起票」できたか、である。ファミマの店舗が発行する伝票には当然、その店舗の「検収印」がいる。不正をごまかす伝票にも、被害にあった店舗の「印」が押されている。「トラックで商品が入って来た時にすぐ押せるように、検収印はレジの周辺に置いてあり、スタッフなら誰でも押せます。それが悪用されたのでしょう」との見方が有力だが、別の声もある。
「ファミマには、わずかですが直営店もあります。他の店舗で売れないものを直営店に押し付けるため、SVが直営店の検収印を勝手に押すことがあり、そこで崩れたモラルが今回のような不正につながったのではないでしょうか」(業界関係者)
例えば銀行実務では、銀行員が顧客の印鑑を押すのは禁じられている。本部にとって加盟店は「独立事業主」であり「別の会社」。いくら店舗指導にあたる立場だからといって、別会社の判子を勝手に扱うのは許されまい。
筆者の取材に対しファミマは、「社員による不正があったのは事実。当該加盟店に実害を与え、他の加盟店にもご心配をおかけしたことはお詫び申し上げる。当該社員は、社内規定にもとづいて厳重処分した。再発防止については、全社員に事実を伝え社員教育を実施している」(広報グループ)と事実関係を大筋で認めた。
だが、不正の背景とも考えられる検収印の扱いなど管理体制について具体的に質すと、「検収印の扱いなどについては、フランチャイズ本部と加盟店との問題なので、申し訳ないが、第三者にご説明はできない」とのことであった。
別法人である加盟店からQUOカードを窃取する行為は、犯罪にあたる可能性が高い。それを内部問題かのように主張し、公表しないままでよいのか。ファミマの「行動指針」の一つは、「世の中に向かって正直でいよう」。この指針に恥じない取り組みが本部にできるのか。加盟店主たちは、息を呑んで見つめている。
(文=北健一/ジャーナリスト)
「牛肉を仕入れているのは料理長。店舗の最高責任者は店長だが、調理場の責任者として料理長が仕入れをしている。具体的には、仕入れ先の選定や価格の取り決めは本社がやっているが、毎日の発注については料理長が取引先に注文を出している。」
「調理スタッフについては、料理長とその補佐をする「2番」という者がいるが、北新地店については2番も知っていた。取扱量が多いこともあって、当然知っていたと思う。神戸ハーバーランド店と刈谷店については、料理長だけだ。さらに上司に当たるエリアマネージャーやキッチントレーナーは知らなかった。」
価格の取り決めは本社がやっていたのなら経理を確認するとおかしな点に気付くだろう。伝票、原価、そして売上の辻褄が合わない事は明確だろう。エリアマネージャーや本社の誰も気づかないのはおかしい。問題になっていないから見て見ぬふりをしたのではないのか?そうでなければ、木曽路グループは管理がかなりずさんな会社かもしれない。
船の検査でも似たような問題がある。支部が不正を行っているが、本部が見て見ぬふりをしていると思われるケースがある。本部は不正を支持していないが、支部の不正を知りつつも野放しにしていると思われるケースだ。不正が利益に繋がり、問題が発覚しても支部が勝手にやったと言い訳が出来るので放置していると思われる。警察や監査機関の人間でないので強制的な捜査や証拠の押収など出来ないので推測の範囲だ。明らかに問題が存在するが、問題が改善されないのでそのように推測する。
木曽路の偽装も似たようなケースではないのか?まあ、木曽路には行った事が無いので個人的には騙されていないが、行政がこれほどの期間、放置していたのは問題だし、残念だ。
しゃぶしゃぶ木曽路、"松阪牛は偽装でした" (1/4)
(2/4)
(3/4)
(4/4) 08/16/14(東洋経済)
詳報!謝罪会見の一部始終
「店舗をご利用いただきましたお客様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたします」――。会見の冒頭、松原秀樹社長はそう言って、深々と頭を下げた。
“銘柄牛ではない牛肉”を「松阪牛」などと偽って客に提供していた問題で、しゃぶしゃぶチェーン最大手の木曽路は8月15日、会見を開いて謝罪した。
今回不正が発覚したのは、北新地店(大阪市)、神戸ハーバーランド店(神戸市)、刈谷店(愛知県刈谷市)の3店舗、合計7171食に上る。このうち、該当食数が最も多かったのが北新地店の6880食。販売期間は2012年4月から2014年7月まで28カ月に及ぶ。
偽装発覚の発端は、北新地店に大阪市消費者センターが今年7月、2度にわたって立ち入り調査を実施したことだった。これをきっかけに、木曽路も社内調査に乗り出し、上記の3店舗でメニュー偽装を行っていたことが発覚。8月14日に情報を開示した。
すでに、社内に松原社長をトップとする調査委員会を立ち上げており、原因究明を進めている。今後は第三者委員会の設置も検討しているという。また、申し出のあったすべての客に、一定額(松阪牛のメニューと実際に提供した和牛特選霜降肉のメニューとの差額である1000~2000円の範囲内)を補償する方針だ。
会社側と報道陣との会見における主なやり取りは以下のとおり。なお、会社側は複数の幹部が入れ替わりで回答したため、名前を記載していない。
料理長が注文を出していた
――昨年秋、業界全体を巻き込んだ食品の虚偽表示の問題が起きた。今回の問題を当時見抜けなかったのはなぜか。
昨年秋はメニュー表示や食材のトレーサビリティをチェックした。その点については問題なかった。したがって、その時点で出数(販売数)のチェックには及んでいなかった。これは大きなミスだった。仕入れと販売の数字を確認して、再発防止に努めていきたい。
――店長はどのような権限を持っているのか。
牛肉を仕入れているのは料理長。店舗の最高責任者は店長だが、調理場の責任者として料理長が仕入れをしている。具体的には、仕入れ先の選定や価格の取り決めは本社がやっているが、毎日の発注については料理長が取引先に注文を出している。
――料理長は動機についてどう話しているのか。
特に動機としては聞いていないが、「原価の調整のため」という料理長の言葉があった。料理長の職責は、調理場の品質管理、数字面では原価率という予算を守ること。年間で目標の原価率になるように、仕入れ値の高い松阪牛の代わりに和牛特選霜降肉を使っていた。
目標管理はどこもやっている
――本社として各店舗に利益を出すことを強く求めていたのか。
目標管理はどこの会社もやっている。恒常的に悪い店舗であれば、いろいろな指導をしていたが、そうでない店舗も今回の対象に入っている。
――指導とは?
予算というものは、今までの実績から導き出して策定している。その中で、料理長には原価率の目標が課せられており、理論原価と予算原価のすり合わせをしながら、数字の整合性を図っていく。
原価のコントロールについては、従前から料理長が目標を置いてやってきた。ただ、当社においては、何がなんでも利益を出さないといけないというわけではないという認識だ。
会見に臨む松原社長――ほかの115店は不正がなかったのか。
3店舗についてはこういう形になったが、そのほかの店舗についてはないと考えている。
――北新地店は2年以上にわたって偽装が行われていた。料理長以外にも認識していたのではないか。
店長については、3店舗の現職店長は知らなかった。そのうち2店舗の店長は対象期間に勤務していた人間は退職しており、ヒアリングできていない。
調理スタッフについては、料理長とその補佐をする「2番」という者がいるが、北新地店については2番も知っていた。取扱量が多いこともあって、当然知っていたと思う。神戸ハーバーランド店と刈谷店については、料理長だけだ。さらに上司に当たるエリアマネージャーやキッチントレーナーは知らなかった。
――北新地店の料理長は2年間、同じ人物なのか。
途中で料理長が替わっている。2012年2月から前任の料理長が勤務しており、2014年4月から現在の料理長が勤務している。現在の料理長が前任の料理長の下で2番として勤務していた。
調査の中では、現在の料理長が(偽装を)行っていたという申告をした。「いつからやっていたのか」という質問に対しては、「前任の料理長の時からやっている」と答えている。
本社はプレッシャーをかけていない
――本社が過度なプレッシャーをかけてしまったという認識は?
北新地店はそれほど大きく業績が悪い店ではなかった。それほど大きなプレッシャーを彼に与え続けていたという認識はない。
――それでは、料理長が勝手にやった?
私どもも在庫管理などのチェックをしていなかったので、ここまで大きな問題になった。その点は非常に反省している。
3店舗のうち恒常的に悪い店はそんなに多くない。当社の制度が何か環境を作り出してしまうという強い認識はない。ただ、今後の原因究明の中で、何が問題なのか、いろいろな方から意見をいただきながら、考えていきたい。
――どの店舗が売り上げがよくて、どの店舗が悪かったのか。
3店を比較すると、予算への未達度が高かったのは神戸ハーバーランド店。ただ、極端に赤字になっていて、どうしようもないという店舗ではない。
――該当食数が圧倒的に多い北新地店は、社内において、どのような位置づけだったのか。
関西の1号店。第何位かはわからないが、平均以上の売り上げがある店だ。ただ、全国でトップ10というような店ではない。関西でも10番目に入るかどうか。都心型の店舗で、客単価は高い。高単価の商品もほかの店よりたくさん売れる。接待需要も多い。しかし、特別なプレッシャーはない。
――利益を上げたことで料理長にどのようなメリットがあるのか。
賞与制度の項目の中に「利益額の確保」がある。原価率を低く抑えられると、利益が確保できるという評価のつながりになっている。したがって、そういう中で賞与の評価がよくなるという可能性がある。
――外食業界だと料理長に原価管理させるのが一般的だと思うが、原価へのプレッシャーがこういう問題を起こすという指摘もある。料理長に対する評価の見直しを考えているのか。
実態調査をしていく中で見直すことが必要だと考えている。原価管理は大事なことだが、そこに走りすぎてしまうと、商品の品質に問題が出てしまう。数字ばかり追いかけると、料理の質に影響が出ることは承知している。いろいろなあり方を考えていく。
ここ数年は人事考課の中で、顧客満足度行動にスポットを当て、客からのきめの細かい要望について臨機応変に食材の変更など、能動的に対応することを評価してきた。原価管理で行き過ぎがあった実態を踏まえて、考えていきたい。
松阪牛ではないが、上質な肉だった
――告発などの予定は?
当該の料理長は、まだ現在調査中だ。当人からは不正についてやっているという申告を受けているが、全体を把握したうえで、告発などの処分を決めていきたい。まだ方向性は決まっていない。
――管理者、社長の処分については?
これだけの大きな問題となったので、まずは今回の食品偽装の解明をしっかりとやっていきたい。期限はいつまでとは言えない。
――辞任については考えていないのか。
現段階では、そこまで具体的な考えは持っていない。
――和牛特選霜降肉とはどういう肉なのか。
黒毛和牛の5等級のリブロース、サーロイン。当社の中では一番高いグレードの肉だ。その上に位置する商品として、松阪牛がある。決してグレードの低い肉ではない。仕入れ価格は公表を控えるが、世の中では最高グレードとして取り扱われている肉だ。
――味があまり変わらないからごまかせるということか。
問題を引き起こしておいて、こういうことを言うのはどうかとも思うが、木曽路の店舗で提供しているのは、非常に上質な肉。味の面では大きな差はない。とはいえ、「だったらいいだろう」ということはない。
――差額によって、いくらの利益が出たのか。
結論からいうと、算定は済んでいない。社内調査をして約1週間。食数は確定したが、個別のメニューに関しての算定は出来ていない。
――業績について、どのような影響があるか。
影響の度合いは見積もりできない。現在は「未定」ということになる。予想されるのは、信頼を失ったことで売り上げが各店で減少、低迷する可能性がある。それに、ご迷惑をおかけしたお客様に補償をしていくので、コストと言っては失礼だが、そういう費用がかさんだ場合にも業績に影響がある。
この情報はほんと?
タイ代理出産の資産家日本人男性の名前は?大企業創業者は誰? (にらめっこ選抜トピック)
タイ代理出産、「年10人は…」邦人男性聴取へ 08/16/14 (読売新聞)
【バンコク=永田和男】日本人男性(24)がタイでの代理出産で多くの子供をもうけていたとされる問題で、タイ国家警察は15日、この男性が18日にバンコクで事情聴取に応じると連絡してきたことを明らかにした。
記者会見したコーキアット副警視監補は、「なぜ子供を必要としていたのか、真意を聞きたい」と話している。
この問題は、バンコクのコンドミニアムで今月5日、乳幼児9人が保護されて発覚した。副警視監補は会見で、その際に妊娠中の女性1人も保護しており、身ごもっているのが同じ男性の子供かどうかを調べていると説明した。
警察は9人のほか、バンコクの別の病院で2人、カンボジア国内で4人、この男性が父親とみられる子供の存在を把握しており、近くカンボジアにも捜査員を派遣して事情を調べる。
一方、生殖医療サービスを提供する「ニュー・ライフ・グローバル・ネットワーク」(本部・グルジア)の共同創設者マリアム・ククナシビリさんは15日、本紙の電話取材に、この男性の依頼で昨年2人のタイ人代理母を紹介したと説明。男性が「毎年10人は子供を作り続けたい」と話すのを聞いて「異常だ」と判断し、国際刑事警察機構(ICPO)にも通報したが聞き入れられなかった、と話した。
厚生労働省の管理及び監督が甘いからこうなる。
私的流用・高額報酬…社福法人、理事会機能せず 08/13/14 (読売新聞)
社会福祉法人(社福)の役員らが運営費を私的流用したり、理事会に諮らず高額報酬を受け取ったりしたなどとして、41自治体が2009~13年度、計65法人に社会福祉法に基づく改善指導を行っていたことが14日、読売新聞の調査で分かった。
厚生労働省は、「理事会などが機能していない可能性がある」として監査体制の見直しを検討する。
読売新聞は都道府県と政令市、中核市109自治体(13年度末)を対象に、社福への監査実態を尋ねるアンケート調査を実施。各自治体への情報公開請求も行い、監査に関する内部資料を入手した。その結果、09~13年度に、役員が運営費を私的流用したり、理事会の承認を得ずに高額報酬を受け取ったりするなどの「公私混同」が65法人で確認された。うち13年度末までに、29法人は同法に基づく改善命令を受けた。寄付金約1億7000万円が使途不明になり、理事長が一部を私的に流用していた埼玉県内の社福は、改善命令に応じず、12年7月に解散命令を受けている。
65法人のうち約7割が、「理事長が年間2000万円の報酬を理事会の承認を得ずに受け取っていた」(浜松市)など、金銭に絡む不正だった。横浜市の社福の元理事長は06~08年頃、最大で月225万円を受け取り、勤務実態のない妻や長男にも月20万~100万円の給料が支払われていた。元理事長の流用総額は約2億2500万円。同市は社福への通知文書で、「理事会が機能しておらず、不適切な支出を抑止できなかった」と指摘した。
日本だから安全と言う事はない!
航空券届かず…苦情殺到の旅行社、無登録だった 08/13/14 (読売新聞)
夏休みの海外旅行客らから代金を受け取ったのに航空券を渡さないまま、業務を停止している旅行会社「レックスロード」(東京都新宿区)について、警視庁は13日午前、旅行業の登録をせずに航空券を販売していた旅行業法違反(無登録)の疑いで、同社などを捜索した。
都や国には同社に対する苦情などが相次いでおり、同庁は、同社が航空券の発券ができないことを知りながら、営業を続けていたとみて調べている。
捜査関係者によると、同社は観光庁や都に旅行業の登録をしないまま、今年4月14日~7月7日の間、女性客2人にフランスやドイツ行きの航空券を販売した疑い。
同社はホームページ(HP)などで客を募り、欧州路線を中心に海外航空券を取り扱っていた。都によると、同社は1998年に旅行業者の登録をしたが、昨年10月、登録を更新せずに抹消された。同12月に再登録したものの、今年1月に事業廃止届を提出し、再び登録を抹消されていた。
まだ廃業ではないわけだ!他の子会社は大丈夫なのか?
DIO女性社長、子会社101人全員に解雇通知 08/13/14 (読売新聞)
コールセンター運営会社「DIOジャパン」(東京都)は、宮城県美里町の子会社「みやぎ美里コールセンター」の従業員101人全員に対し、解雇を通知した。
町は13日、従業員向けに説明会を開く。
町などによると、DIOの本門のり子社長と弁護士が11日、センターを訪れ、全員の解雇を告げたという。
センターでは、国の緊急雇用創出事業の補助金を活用し、オペレーターの研修事業が今年1月から1年間、行われる予定だった。しかし、DIOが7月末で業務を休止したため、町は継続が困難として、研修事業の業務委託契約を解除した。
一方、登米市の子会社「東北創造ステーション」では、別の企業が業務の一部を引き継ぐ見通しだ。
市などによると、予約業務などをDIOに委託していた東京都内の大手ホテル会社は11日付で契約を破棄し、東京都内のコールセンター会社と12日に委託契約を結んだ。従業員74人のうち、同ホテル関連の業務を担当していた59人には11日、解雇が伝えられたが、希望者はこのコールセンター会社が再雇用する方針だ。
10月まで現在の場所で業務を続け、11月からは仙台市内へ移転する予定だ。このため市はコールセンター会社に対し、市内での事業継続を働きかけるという。
明らかに尋常でない兆候があったわけだ。市内の清掃関係業者に処理を依頼しながら加害者の父親は嫌がらせだと思っていたのか、それとも、娘の仕業とおもっていたのか?嫌がらせなら警察に被害届を出していたに違いない。被害届を出していないのであれば、やはり・・・
「佐世保高1女子惨殺事件」実父も恐れた16歳女子高生の素顔とは?(2)家庭の背景と小動物への虐待 08/13/14 (アサ芸プラス)
今年4月に愛和さんとともに同じ県内でも屈指の進学校である県立高校に進んだA。すでに報じられているように、中学時代までスポーツも勉強も優秀。早大卒で弁護士の父親の影響も受けたと見られ、将来の夢は検事で、母親と同じ東大を目指していた。しかし、Aが高校の1学期に通学したのはわずか3日だった。
そのため彼女は、学校のサポートのもと、カウンセリング治療を受けていた。担当した精神科医は、Aの過去の言動を調査し、小学校6年の時に給食に漂白剤を混入したり、高校入学直前の今年3月に就寝中の父親を金属バットで殴打し、頭蓋骨を陥没させるといったAの異常行動を把握。今回の猟奇殺人の予兆も感じ取っていたというのだ。
地元紙の社会部記者が明かす。
「精神科医は、Aに心理テストを実施し、その結果、彼女が1988年から89年にかけて東京と埼玉で起きた連続幼女殺害事件の宮崎勤元死刑囚や、97年に切断した小1男児の首を自分が通う中学校の校門の近くにさらした、神戸児童連続殺傷事件の『酒鬼薔薇聖斗』少年らと同様の兆候があると診断したようだ。それで、今年6月には、長崎県の児童相談施設に、『このままだと人を殺しかねない』と相談もしていたが、Aの実名は報告せず、結局、有効な対策は取られなかったんです」
さらに、逮捕後の取り調べでの「猫を解剖したことがあり、人間でもやってみたかった」という供述でもクローズアップされた小動物の虐待癖については、実家の“被害”の処理を依頼された市内の清掃関係業者がこう話す。
「今年3月でしたが、Aの実家のガレージに首や手足がバラバラに切断された血だらけの猫が放置されていて、それを職場に出勤しようとしていた父親が見つけて、死骸の処理を依頼されたんです。その後も実家ガレージや庭で複数回、変わり果てた猫の死骸が発見され、そのつど処理を依頼されました。敷地内の壁にできたカエルや金魚などの小動物が叩きつけられたと見られる跡を清掃することを頼まれたこともあります」
Aの異常行動を加速させた要因には、慕っていた実母が昨年10月に亡くなったことで環境が激変したことをあげるムキもある。実母の知人が言う。
「死因は膵臓ガンでした。昨年夏に彼女が入院していた病院にお見舞いに行った時、『お兄ちゃん(Aの5歳年上の兄)は大丈夫だけど、Aが心配。私がまだ面倒を見てあげないと‥‥』と、病床で涙ながらに訴えてきたんです」
大手通販のジャパネットたかたの顧問弁護士などの本業の他、不動産会社も経営し、市内に複数のビルを所有し賃貸ビジネスでも成功した父親は、妻の死からそう日がたたないうちに、「婚活パーティ」に参加した。
「東京都内で開催された弁護士や医師などのセレブ限定のパーティで20歳ほども年の離れた30代の女性と知り合い、今年5月に再婚。しかもその現在の妻、Aにとっての継母は再婚の前に妊娠し、それで結婚を急いでいたとの情報まであるんです」(地元紙記者)
佐世保高1女子惨殺事件」実父も恐れた16歳女子高生の素顔とは?(1)何が彼女を悪魔に変えたのか?- 08/12/14 (アサ芸プラス)
長崎県佐世保市で起きた16歳女子高生による同級生惨殺事件から1週間余り。遺体を解体した動機を「人を殺してみたかった」と供述した逮捕少女の言動は、17年前に神戸で男児の首を屋外にさらした「酒鬼薔薇聖斗」少年と酷似していた。同性愛志向も指摘され、犯行直前には実父も強い恐怖を覚えていたという少女の「悪魔の素顔」とは──。
「友達のAさんと遊びに行くと言って外出した娘の行方がわからなくなった。娘の携帯も通じない」
長崎県佐世保市内の高校1年生・松尾愛和さん(15)の、海上自衛隊に勤める父親から、長崎県警佐世保署に110番通報があったのは、去る7月26日。午後11時過ぎのことだった。
捜査関係者が言う。
「愛和さんの両親は、娘の同級生の少女A(16)が、今年4月から市内の実家を出てワンルームマンションで1人暮らししていることは知っていました。ですが、その住所やAの電話番号などは知らなかったようです。また、2人とも未成年ということもあり、捜査員はまず、市内の高台にあるAの実家を訪ね、Aの両親に、娘に連絡を取るとともに居場所がわかったら、一緒に迎えに行くこともあわせて要請したんです」
そして、捜査員とAの両親がAの住む市内のマンションに到着したのが、4時間後の午前3時頃。佐世保署とAの実家、マンションは、5キロ圏内に収まる距離だが、
「実は、捜査員がAの実家を訪ねるとすぐ、Aの父親は激しく動揺して、顔面蒼白になった。不審に思った捜査員が両親に詳しく事情を聞くと、Aの複雑な家庭環境、これまでの奇怪な行動がわかってきた。そこで最悪の事態を想定し慎重に準備態勢を整えて、マンションに向かったんです」(捜査関係者)
Aの父親が、オートロックのマンションの1階でインターホンを鳴らすと、Aはすぐに降りてきた。
「インターホンのボタンを押す父親の手は震えていましたが、大きめのTシャツとハーフパンツという姿で現れたAは、落ち着き払っていて、愛和さんについて『知りません』と答えた。そこで捜査員が、『念のため部屋の中ば見せてくれんね?』と言うと、Aは無表情のままでうなずいた」(捜査関係者)
午前3時20分頃、Aの部屋に踏み込んだ捜査員が目にしたのは、10畳ほどの部屋に置かれたベッドで、血だらけのシーツの上に横たわった愛和さんの変わり果てた姿だった。
頭部と左手首が切断され、腹部も大きく切り裂かれ、臓器がはみ出ており、ベッドの周辺には、のこぎりやハンマーなどとともに、食べ物や飲み物も散乱していた。
程なくAは、自分が愛和さんを殺害したことを認め、その後の取り調べに「一度人を殺してみたかった」「愛和さんには恨みはない」と供述し、反省や謝罪の言葉は口にしなかったという。
2人は中学校時代からの同級生で、アニメという共通の趣味もあり親しかった。その友人に手をかけ、前述のように父親をも動揺させるほど「恐怖の存在」となっていたA。いったい何が彼女を「悪魔」に変えたのか。
STAP論文共著者バカンティ氏休職へ 08/12/14 (nikkansports.com)
STAP細胞論文の共著者であるチャールズ・バカンティ米ハーバード大教授が、所属する米ブリガム・アンド・ウィメンズ病院の麻酔科長を9月1日付で退任し、1年間休職する意向を示していることが11日分かった。STAP細胞問題との関連は不明。
再生医療研究に詳しい米カリフォルニア大デービス校のポール・ナウフラー准教授が、バカンティ氏が同僚に送ったとされるメールの内容をブログに掲載した。メールはSTAP論文には一切触れていないが、ナウフラー氏は病院の内部調査が進んでいる可能性もあると指摘している。
ブログによると、バカンティ氏はメールで「複雑な気持ちで皆さんに私の決断をお知らせする」と麻酔科長の退任を表明。2002年に着任して以来の自らの業績を振り返り「私の将来の目標を達成し、試みの方向性を変え、最も楽しい事をする時間のために1年間の休暇を取るつもりだ」と述べた。復帰後は「再生医療の研究と、麻酔学の人材育成に力を注ぎたい」としている。
STAP論文を執筆した理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダーはかつてバカンティ氏の研究室に所属していた。バカンティ氏はSTAP細胞に似たアイデアをそれ以前から温めていたとされる。(共同)
過去の理研がどのような組織であったのか知らないが、最近の理研は機能的に対応できない組織と思える。
理研、10日前に異変把握 本人からの辞任申し出も認めず (1/2)
(2/2) 08/12/14 (産経新聞)
理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(神戸市)の笹井芳樹副センター長が5日に自殺した問題をめぐり、理研の対応に批判が高まっている。理研は自殺の約10日前、笹井氏が体調悪化で職務不能な状態に陥ったことを把握しながら、本人が希望していた辞任を認めず、心理面のサポートも十分に行っていなかった。対応の遅れで最悪の事態を防げなかった危機管理の甘さが問われそうだ。
複数の関係者によると、笹井氏の精神状態が極端に悪化したのは7月下旬。主宰する研究室で科学的な議論ができなくなり、研究員が「ディスカッションが成立しない」と25日、竹市雅俊センター長に通報した。
竹市氏はセンターの健康管理室に相談。「医師の受診を勧めてほしい」との回答を受け、笹井氏の家族らと対応を話し合っていた直後に悲劇が起きた。
理研は笹井氏の実質的な後任として、26日付で斎藤茂和神戸事業所長を副センター長に起用。しかし、笹井氏の役職は解かず、斎藤氏の人事も正式に公表しなかった。笹井氏にサポート要員をつけるなどの具体的な支援もしなかった。一連の流れは、事態の緊急性を重く受け止めていなかったようにも受け取れる。
笹井氏はSTAP論文問題発覚後の3月、副センター長の辞任を申し出たが、竹市氏は調査中を理由に認めなかった。外部からの批判も強まり、笹井氏は現職にとどまることに強く責任を感じ、心理的なストレスで体調が悪化していった。
関係者は「ずっと辞めたがっていたが許されず、精神が圧迫された」「7月下旬は精神的負担を軽減する最後のチャンスだったのに、なぜ解放してあげなかったのか」と憤る。
大学院生時代から笹井氏を知る元京都大教授は「研究者として自負心が強く、今後に絶望感を覚えたのかもしれないが、理研のガバナンス(組織統治)の欠如が彼を死に追いやった面は否定できない。懲戒処分の判断も早く下すべきで、決断できないまま、いたずらに苦しめた」と批判する。
同志社大の太田肇教授(組織論)は「理研の対応は極めて不適切で認識が甘い。一刻も早く役職から外すべきだった」と話す。STAP問題の当事者で研究グループの責任者、センターの要職も務めていた笹井氏。「計り知れないプレッシャーに追い詰められたのだろう。研究者が危機管理職を兼ねる体制には無理があり、今後は危機管理の専門職を置く必要がある」と太田教授は指摘した。
理研広報室は「再発防止のため、笹井氏への対応が適切だったか速やかに検証する」としている。
「現行制度では、強制入院には医療保護入院と措置入院の2種類がある。医療保護入院は保護者の同意を必要とする。措置入院の場合も、金属バットで殴られたという父親が警察に被害届を出したり通報したりすることが必要だった。そのうえで「自傷他害のおそれ」があると診断されてはじめて入院ということになる。いずれにせよ、父親が何らかの決断をする必要があった。」
上記が事実であれば、制度上の問題で父親が協力的でなければ何も出来ないと言う事になる。メディアはこれぐらいの事は知っている、又は、知らなくても専門家に聞くなどしてもっと早く情報を記事の中で公開できたはず。なぜ、8月9日付けの産経新聞ではじめて知ったのか。他の新聞社は似たような内容の記事を書いているが、見つけていないだけなのだろうか?
問題がある子供に対し両親が事実を認めない、又は、問題を隠したい場合、現行制度では対応できないことになる。ならば、メディアはテレビ、新聞そしてインターネット等で現行制度の改善について言及するべきではないのか?加害者の父親の判断は弁護士であっても、通常ではないと思う。現行制度では問題を防止する事は出来ない事を多くの視聴者に伝えるべきだ。そうすれば制度改正を認識する人は増えるはずである。視聴率優先になれば、制度の問題などどうでも良いのかもしれない。
片田珠美(99)佐世保高1女子殺害、惨劇の芽は摘めたのか (1/2)
(2/2) 08/09/14 (産経新聞)
長崎県佐世保市で発生した高1女子生徒殺害事件には、大きな衝撃を受けた。こういう事件が起こるたびに人間の持つ攻撃衝動に戦慄し、「人間は人間にとって狼である」という古代ローマの詩人の言葉を思い出す。
精神科医としての長年の経験から痛感するのは、世の中には攻撃衝動がとくに強い人間が存在するという厳然たる事実である。このような攻撃衝動が生まれつきの素質によるのか、生育歴によるのかは精神科医の間でも意見が分かれるが、いずれにせよ、サディズム的傾向の強い人間が存在することは否定しがたい。
だとすれば、われわれにできるのは、フロイトが『文化への不満』で指摘しているように「攻撃的な欲動に制約を加える」ことだけだ。とはいえ、「さまざまな努力にもかかわらず、この文化的な営みはこれまでそれほど大きな成功を収めていない」。
今回も、犯行前に加害者の少女を診察した精神科医が「人を殺しかねない」などと児童相談所に伝えていたにもかかわらず、具体的な対策が取られていなかった。その時点で精神科病院に入院させておくべきだったという意見があるが、実際にはなかなか難しいというのが現場にいる者の正直な気持ちである。
この少女が入院をすんなり受け入れたとは思えないので、強制的に入院させるしかなかっただろう。現行制度では、強制入院には医療保護入院と措置入院の2種類がある。医療保護入院は保護者の同意を必要とする。措置入院の場合も、金属バットで殴られたという父親が警察に被害届を出したり通報したりすることが必要だった。そのうえで「自傷他害のおそれ」があると診断されてはじめて入院ということになる。いずれにせよ、父親が何らかの決断をする必要があった。
このようにして入院させておけば、今回の惨劇は防げたかもしれない。ただ、この少女の場合、父親への怒りと復讐願望が相当強そうなので、退院後に別の形で攻撃衝動を爆発させる可能性が高いと言わざるを得ない。
カミュの『異邦人』で描かれているのは、母の死の直後に人を殺した青年である。愛する者の死という対象喪失を受け入れなければならない「喪」の時期に、生と死の間の境界を破壊する行為である殺人が起こりやすいことは過去の事例を振り返れば明らかである。
この時期に再婚して娘に1人暮らしをさせるという父親の決断は、攻撃衝動の爆発の抑止力になるどころか、真逆に働いたのではないだろうか。
◇
世間を騒がせたニュースや、日常のふとした出来事にも表れる人の心の動きを、精神科医の片田珠美さんが鋭く分析します。片田さんは昭和36(1961)年、広島県生まれ。大阪大医学部卒、京都大大学院人間・環境学研究科博士課程修了。著書に『無差別殺人の精神分析』(新潮選書)、『一億総うつ社会』(ちくま新書)、『なぜ、「怒る」のをやめられないのか』(光文社新書)、『正義という名の凶器』(ベスト新書)、『他人を攻撃せずにはいられない人』(PHP新書)など。
常識で考えれば推測出来る事。今まで野放しになっていたこと自体、行政の怠慢。
ベネッセ流出:名簿業者も不正認識か ダミー部削除し転売 08/11/14 (毎日新聞)
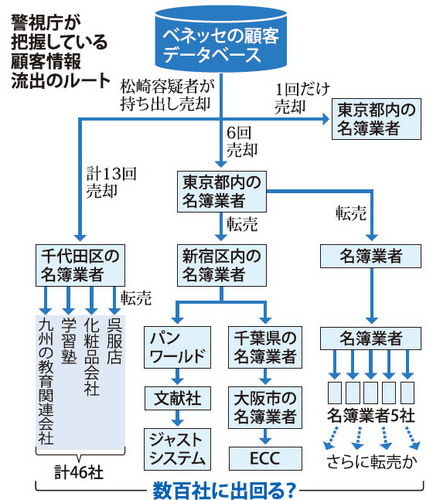
通信教育大手「ベネッセホールディングス」(岡山市)の顧客情報漏えい事件で、元システムエンジニア(SE)、松崎正臣容疑者(39)が持ち出した顧客情報の転売に関わった東京都内の名簿業者の中に、ベネッセから流出した情報と知りながら取引をした疑いがある業者が含まれることが捜査関係者への取材でわかった。不正に入手した情報と認識しながら転売した場合は、不正競争防止法違反(営業秘密の使用・開示)に当たることから、警視庁生活経済課は同法違反容疑での立件も視野に慎重に調べを進める。
捜査関係者によると、松崎容疑者は今年6月までの約1年間に、ベネッセから延べ2億件超の顧客情報を不正に持ち出し、都内の名簿業者3社に売却したとされる。このうち、ベネッセの顧客情報をダイレクトメールの送付に使用した「ジャストシステム」(徳島市)に流出したルートでは、松崎容疑者から直接買い取った業者も含め、名簿業者4社が関与していた。
同課がこれらの名簿業者への事情聴取を進めたところ、松崎容疑者が売却した時点では、流出に備えてベネッセが仕掛けた「進研太郎」名義などの複数のダミー情報が含まれていたが、ジャストシステムが購入した段階では、ダミー情報は削除されていたことがわかった。
現時点での警視庁の聴取に対し、転売に関与した名簿業者はいずれも「不正流出した情報とは知らなかった」と説明しているが、同課はベネッセの顧客情報と認識しながら取引をした業者がいる可能性もあるとみて捜査している。
同課の調べでは、松崎容疑者が売却した顧客情報は少なくとも14の名簿業者に渡り、さらに首都圏や関西、九州など全国の学習塾、化粧品会社など数百社に拡散したとみられている。【林奈緒美】
子供の学費に1400万円も使った。子供は良い就職先で高給取りなのだろうか?そうでなければ厳しい結末になりそうだ。
それはあなたの「小遣い」じゃありません! 医療法人の50代女性職員、患者の預け金1400万円を横領 08/09/14 (産経新聞)
病院や介護老人保健施設を運営する医療法人「鴻池会」(奈良県御所市)は8日、50代の女性職員が入院患者などからの預かり金計約1400万円を横領したと判明したため、懲戒解雇処分にしたと発表した。被害額は法人側が全額弁済しており、今後女性職員の刑事告訴も検討するという。
同法人では、運営する秋津鴻池病院など4施設で入院患者らが日用品購入などのため現金を預ける「小遣いシステム」を設けており、女性職員は平成22年6月~25年1月の間、預かり金を金庫から入金担当者に渡す際、現金計約1400万円を横領していたという。法人の内部調査で女性職員は横領を認め、「子供の学費などに使った」と話したという。
加害者の件もあるが、両親の責任も含めて全容をオープンにするために検察官送致が良いと個人的に思う。いろいろな情報があり、詳細があいまいだ。
佐世保事件に新事実 「養子縁組」と「一人暮らし」への違和感 08/09/14 (日刊ゲンダイ)
長崎・佐世保北高1年の松尾愛和さん(15)殺害事件発生から10日あまり。ちょっと理解しがたい新事実が次々と明らかになっている。
加害少女A子(16)の父親は今年2月、A子を祖母と養子縁組させていた。戸籍上は、A子は父親の妹になったということだ。相続税対策だといわれているが、どうにも違和感を覚えてしまう。父親が翌3月、A子に金属バットで殴られたことと無関係なのか。そして、A子が通院していた精神科医の勧めに従い、4月からA子に一人暮らしをさせ、5月に再婚……。
事件後、父親は「複数の病院の助言に従いながら、できる最大限のことをしてきた」と弁明している。が、愛和さんの遺族関係者から「責任逃れじゃないのか」という批判の声が上がるのも、もっともだろう。
「父親はA子を通院させる一方で、再婚が決まった後、友人知人らに、新妻の写真付きのプロフィルを自慢げに配ったそうです。それに父親がA子の一人暮らしの部屋を訪ねた様子はない。A子の部屋からは猫の首のほかに、現金で100万円も見つかっている。どうも父親は言っていることとやっていることがチグハグな印象です」(捜査事情通)
A子は「生前、実母を殺そうとした」と知人に話していたというし、事件の3日前に「人を殺してみたい」と継母に話していたという。
■本当に医師の勧めだったのか
「A子はかなり危険な状態だった。それなのに事件が起きた先月26日、父親は新妻を連れて顧問先のパーティーに出席し、2次会にも参加していたそうです。その最中に惨劇が起きている」(前出の捜査事情通)
父親は「医師やカウンセラーなどの指導に基づいて対応していた」というが、それすら疑わしく思えてくる。精神科医の町沢静夫氏(町沢メンタルクリニック院長)が言う。
「一般的に『人も殺しかねない』状況で、一人暮らしをさせるというのは考えられません。家庭内暴力などで一時的に距離を置くのは効果的といわれますが、今回のように動物を解剖したり、父親を金属バットで殴るなど明らかに異常なケースでは、一人暮らしはかえって“妄想”が広がる恐れがあります」
実際、そうなった。
父親もA子を放置していたわけじゃないだろうが、もっと違った対応があったのではないのか。
税金の無駄遣い!「失敗を次の糧にしていく。」は言い訳。これで許されるのなら10、100回失敗しても、同じ事が言える。
福島第1、凍らない「氷の壁」断念か 別工法も 19日に規制委が検討 (1/2)
(2/2) 08/12/14 (産経新聞)
東京電力福島第1原発海側のトレンチ(地下道)に滞留する汚染水を遮断するための「氷の壁」が3カ月以上たっても凍らない問題で、7月末から投入している氷やドライアイスに効果が見られないことから、政府が「氷の壁」の断念を検討し、別の工法を探り始めたことが13日、分かった。政府関係者によると、19日に原子力規制委員会による検討会が開かれ、凍結方法の継続の可否について決めるという。
氷の壁は、2号機タービン建屋から海側のトレンチへ流れ込む汚染水をせき止めるため、接合部にセメント袋を並べ、凍結管を通し周囲の水を凍らせる工法。4月末から凍結管に冷媒を流し始めたものの、水温が高くて凍らず、7月30日から氷の投入を始めた。
しかし氷を1日15トン投入しても効果がなく、今月7日からは最大27トンに増やしたが、凍結が見られなかった。
12日までに投じた氷は計約250トンに上る。ドライアイスも7日に1トン投じたものの、小さい配管に詰まってしまい投入を見合わせ、12日に再開した。
氷の壁が凍結しないことは、規制委の検討会でも有識者から指摘されており、「コンクリートを流し込んでトレンチを充(じゅう)填(てん)すべきだ」との意見があった。政府関係者によると、19日に予定されている検討会では、氷投入の効果を評価した上で、効果がないと判断されれば代替工法の作業に着手するという。
規制委は、トレンチにたまっている汚染水が海洋に流れ出す恐れがあることから「最大のリスク」と位置付けており、早期解決を目指している。特に凍結管の中に冷媒を通して水分を凍らせる技術は、1~4号機周囲の土中の水分を凍らせる「凍土遮水壁」と同じで、氷の壁が凍土壁にも影響しないか懸念を示している。
氷やドライアイスの投入について、東電の白井功原子力・立地本部長代理は「十分な検討が不足していたという批判はその通り。失敗を次の糧にしていく。当初予定していたことができないことはあり得る」と話している。(原子力取材班)
なぜ20年以上の長い間、政治的な圧力があったのか、それとも朝日新聞のプライドで吉田清治氏の証言を撤回しなかったのだろうか?
人は間違いを起こす。しかし、間違っていた事がわかれば訂正するべきである。また、吉田清治氏の証言については過去に批判する人達がいた。証言の裏を取っていたのか確認はしなかったのだろうか?確認されていなければ確認するべきではなかったのか?新聞社は週刊誌とは違うのではないのか?それとも週刊誌を見下し過ぎなのか?朝日新聞はプライドを捨てて、どうしてこのように長い間、間違いを認めなかったのか検証し、公表するべきだ!
吉田清治について検索していたら、どの情報が正しいのかわからなくなった。吉田清治のバックグランドは疑問が多くある。なぜ朝日新聞はこの人物の証言を信用したのか?検証する機会はあったのではないのか?新聞社又はテレビ局は吉田清治氏の証言、吉田清治の背景、取材を行った朝日新聞記者について特集をしてほしい。
吉田清治 (ウィキペディア)
吉田清治の息子は朝鮮人…在日成り済まし説を追う (東アジア黙示録)
朝日新聞「慰安婦問題を考える」を検証する 随所に自己正当化と責任転嫁 (1/7)
(2/7)
(3/7)
(4/7)
(5/7)
(6/7)
(7/7) 08/08/14(産経新聞)
■朝日よ、「歴史から目をそらすまい」
朝日新聞が5、6両日に掲載した特集「慰安婦問題を考える」はいくつか視点の欠落があり、「検証」と言うにはあまりに不十分な内容だった。朝鮮人女性を強制連行したと証言した自称・元山口県労務報国会下関支部動員部長、吉田清治氏の証言に関する記事16本を取り消したのはよいが、その他の論点に関しては自己正当化や責任転嫁、他紙の報道をあげつらう姿勢が目立つ。歴史を直視しようとしない朝日新聞の報道姿勢に改めて疑念を抱かざるを得ない。(阿比留瑠比)
◇
5月19日、北九州市内のホテルで、朝日新聞社西部本社の旧友会(OB会)が開かれた。OBで北九州市在住の伊藤伉(つよし)氏は手を挙げて来賓に招かれた木村伊量社長にこう訴えた。
「慰安婦と女子挺身隊の混同、吉田清治氏の嘘の2点については訂正・削除して朝日の名ではっきり示してほしい。それを何としてもやるべきではないか」
木村社長は「貴重なご意見をいただいた。詳しいことはここで言えないが、いずれ検証したい」と応じたという。この出来事は、朝日新聞社内でも、自社の慰安婦報道に問題があることが認識されていたことを物語っている。
にもかかわらず、2日間にわたる特集に謝罪の言葉はなく、言い訳に終始した。
◆ ◆ ◆
5日の特集では、見開きで「慰安婦問題 どう伝えたか 読者の疑問に答えます」と大見出しを打ち、【強制連行】【「済州島で連行」証言】【軍関与示す資料】【「挺身隊」との混同】【元慰安婦 初の証言】-の5つのテーマを検証している。
ところが、「虚偽」と断じて記事を取り消したのは、吉田氏による強制連行に関わる証言だけだった。
挺身隊と慰安婦の混同については「まったく別」で「誤用」と認めながらも当時の「研究の乏しさ」を理由に釈明を重ね、「1993年(平成5年)以降、両者を混同しないよう努めてきた」とむしろ胸を張った。
果たしてそうなのか。朝日新聞の4年3月7日付のコラム「透視鏡」ではこう記している。
「挺身隊と慰安婦の混同に見られるように、歴史の掘り起こしによる事実関係の正確な把握と、それについての(日韓)両国間の情報交換の欠如が今日の事態を招いた一因」
つまり、この時点で挺身隊と慰安婦が全く別の存在だと把握しながら、自らの誤用を認めることも、訂正することも拒んできたことになる。
産経新聞が今年5月、朝日新聞広報部を通じて、慰安婦と挺身隊の混同や強制連行報道について「今もなお正しい報道という認識か」と質問したところ、こんな回答を得た。
「従軍慰安婦問題は最初から明確な全体像が判明したという性格の問題ではありません。(中略)お尋ねの記事は、そのような全体像が明らかになっていく過程のものです。当社はその後の報道の中で、全体像を伝える努力をしています」
初めは全体像が分からなかったから間違いを書いても訂正しなくてもよいと言わんばかりではないか。しかも、今回の特集まで朝日新聞に慰安婦問題の「全体像を伝える努力」はうかがえなかった。
今回取り消した吉田証言についても、5月の段階で「訂正する考えはあるか」と質問したところ、次のように答えている。
「弊社は1997年(平成9年)3月31日付朝刊特集ページで、証言の真偽が確認できないことを詳細に報じ、証言内容を否定する報道を行っています」
実際はどうだったか。9年3月の特集ページでは、吉田氏について「朝日新聞などいくつかのメディアに登場したが、間もなくこの証言を疑問視する声が上がった。済州島の人たちからも、氏の著述を裏付ける証言は出ておらず、真偽は確認できない」と記しただけだ。吉田証言を16本もの記事で取り上げておきながら「真偽は確認できない」の一言で済ませ、「証言内容を否定する報道」を行ったとは言えない。むしろ過去記事の過ちを糊塗(こと)しようという意図が浮き上がる。
今回の特集でも、自社が吉田氏のどの証言をどう取り上げてきたかについてはほとんど触れていない。これでは、何のことだか分からない読者も少なくないだろう。
「強制連行」に関する検証も、朝日は平成3~4年ごろは自明の前提として報じており、4年1月12日付の社説「歴史から目をそむけまい」では「『挺身隊』の名で勧誘または強制連行」と断じている。
その後、強制連行説の雲行きが怪しくなってくると、徐々にトーンを弱め、「強制連行の有無は関係ない」というふうに変えていった経緯があるが、そうした事情も説明していない。
今回の特集では「読者のみなさま」に「軍などが組織的に人さらいのように連行したことを示す資料は見つかっていません」と言いながら、こうも書く。
「インドネシアや中国など日本軍の占領下にあった地域では、兵士が現地の女性を無理やり連行し、慰安婦にしたことを示す供述が、連合軍の戦犯裁判などの資料に記されている。インドネシアでは現地のオランダ人も慰安婦にされた」
兵士の個人犯罪や、冤罪(えんざい)の多い戦犯裁判の記録を持ち出し、なおも「日本の軍・官憲による組織的な強制連行」があったかのように印象操作していると受け取られても仕方あるまい。
「軍関与示す資料」とは、朝日新聞が4年1月11日付朝刊で大きく展開した記事「慰安所 軍関与示す資料」を指す。
政府の河野談話の作成過程検証チームは6月20日、この「主として朝鮮人女性を挺身隊の名で強制連行した。その人数は8万とも20万ともいわれる」と事実ではないことを書いた記事についてこう指摘した。
「朝日新聞が報道したことを契機に、韓国国内における対日批判が過熱した」
ところが、朝日新聞の5日の特集では、自社の報道が日韓関係を悪化させたという認識は欠落している。朝日が繰り返し取り上げたことで吉田証言が韓国でも広く知られるようになり、それが対日感情を悪くしたことへの言及もない。
6日付の特集では、わざわざ1ページを割いて「日韓関係 なぜこじれたか」と題する解説記事を載せたが、ここでも自社の報道が両国関係をこじらせたことへの反省はみられない。
「元慰安婦 初の証言」は、元朝日記者の植村隆氏(今年3月退社)が3年8月11日付朝刊で書いた「元朝鮮人従軍慰安婦 戦後半世紀重い口開く」という記事を指す。
韓国メディアより先に、初めて韓国人元慰安婦の証言を伝えたもので、これも「母に40円でキーセン(朝鮮半島の芸妓(げいぎ))に売られた」と別のインタビューなどで語っている金学順氏について「『女子挺身隊』の名で戦場に連行」と記している。
この誤った記事が慰安婦問題に火が付いた大きなきっかけとなったが、朝日は検証で「意図的な事実のねじ曲げなどはありません」と非を認めなかった。少なくとも事実と異なることを流布させたのだから、せめて謝罪や訂正があってしかるべきだが、それもない。
◆ ◆ ◆
問題点はほかにもある。朝日新聞は「他紙の報道は」という欄を設け、産経、読売、毎日各紙もかつて吉田証言を取り上げたり、慰安婦と挺身隊を混同したりした例もみられたと指摘した。「お互いさまじゃないか」と言わんばかりなので、朝日新聞の9年3月31日付の慰安婦に関する社説「歴史から目をそらすまい」を引用したい。
「ほかの国は謝っていないからと、済まされる問題でもない」
朝日新聞の慰安婦報道により国際社会での日本の評価がどれだけ失墜したか。国民がどれほど不利益を被ったか。今後も検証していかねばならない。
税金が投入されている。また、社会福祉法人のでたらめの取締が甘い。問題があり、対応が悪ければ、認可を取り消すべきだ。
大阪、保育園運営費2億円流用か 法人前理事長ら 08/08/14 (共同通信)
大阪府吹田市の社会福祉法人「紫峯会」の70代の女性の前理事長と、息子で運営する認可保育園の40代の前園長が、公費で賄われている保育園の運営費約2億1千万円を不正に流用していたとして、法人が2人に返還請求したことが8日、吹田市などへの取材で分かった。
市や法人関係者によると、前理事長はまだ就任前だった1979年以降、隣接する自宅の電気・ガスの使用料を保育園に負担させたほか、計約4千万円を不明朗に支出。正規の手続きを経ず、別事業に計約5千万円を支出した。
前園長は、法人が約400万円でリース契約した車を頻繁に個人で使用するなどした。
テレビでコメントしている専門家の意見を聞くと両親との関係が専門家が介入する機会を遅らせたと思えた。猫の解剖は殺害直前に始まったわけではない。加害者の行動や行為について両親は本当に知らなかったのか?
<佐世保高1殺害>重大発言あっても「父親の会見なし」 08/07/14 (東スポWeb)
長崎県佐世保市で同級生を殺害したとして殺人容疑で逮捕された高校1年の女子生徒A(16)が、昨年10月に病死した実母を生前、殺そうと思ったことがあるという趣旨の話を知人女性に伝えていたことが5日、分かった。
Aの母親は昨年夏にがんを患っていることが判明、10月に亡くなった。Aを知る関係者によるとこの春、Aは知人女性に「(生前に)就寝中の母親を殺そうと寝室まで行ったが、思いとどまった」との趣旨の話をしたという。県警はこの発言を把握しており、慎重に捜査を続けている。
また、3月に金属バットで殴打した父親を「殺すつもりだった」と継母に打ち明けていた。関係者らによると、事件3日前の7月23日、少女は継母の運転する車で精神科に向かう途中、父親に対する殺意を継母に打ち明けたという。
父親は4日に精神科とのやりとりをまとめた文書を公表し、事件前日の7月25日に佐世保市の児童相談所に電話したが、宿直担当から「今日はサマータイムで終わってしまった。月曜日に電話してくれ」と言われたとしている。一方、児童相談所の所長は「宿直担当が『ご用件は何ですか』と聞くと、男性は『月曜日にかけます』と電話を切りました」と説明。
小さな違いだが、父親の文書だと児童相談所に失態があったかのよう。父親の代理人は「細かい違いはあるかもしれないが、本質的な問題ではないと思う。(用件を言いにくい)雰囲気はあったと話している」と話す。
同25日は父親と継母、精神科医、カウンセラーの4人でAの入院の話もしたが、精神科医が断ったという。また、父親は文書で「(通院していた病院から)『一人暮らしをさせてはならない』旨の指導を受けたことは皆無である」としている。もっとも精神科医が本当に断ったかどうかを代理人は確認できていない。
まるで保身のための文書にみえる。やはり本人が会見を開くべきではないか。「そのつもりはありません。文書も(先週末の謝罪文公表から)1週間後のつもりでした」(代理人)
Aが事件を起こさなければ、8月2日には父親、継母、Aで実母の施餓鬼供養に行くはずだった。
個人的な意見だが「STAP細胞」に関して自殺するまでの理由はないと思う。それ以外の何かがあったと思う。
6億円研究費に不透明支出 理研・笹井氏自殺「本当の理由」 08/07/14 (朝日新聞)
「死ななくてもいい人を亡くした」――。
国内外の研究者から続々と哀悼の声が寄せられている笹井芳樹・理化学研究所CDB副センター長(52)の自殺。最大のナゾはなぜ、このタイミングで命を絶ったのか、ということだろう。
STAP細胞論文の共著者として、その存在を信じ続け、小保方晴子研究ユニットリーダー(30)に宛てた遺書にも「必ず再現してください」と書き記していたという笹井氏。論文の疑惑が指摘され始めた3月ごろから心理的ストレスを感じ、辞意をほのめかしていたとされる。自殺は、思いつめた末に選んだ「最後の手段」と受け止められているものの、今になってプッツリと生きる意志が絶えてしまった理由はハッキリしない。
「8月中には理研が進めている『STAP細胞』の検証実験の中間報告が公表されます。いまだに再現に成功したという情報はないものの、小保方さん本人が実験に加わることにもなり、わずかだが『希望』は残っている。笹井副センター長が直接、手を出すことはできなくても、間接的に小保方さんをフォローすることはできたはず。このタイミングで自殺を図る意図が分からないのです」(兵庫県警担当記者)
「辞意をほのめかしていた」とされる3月、笹井氏は生命科学分野で優れた研究者に贈られる「上原賞」の贈呈式に出席、副賞として報奨金2000万円を手にしていた。「STAP細胞疑惑」について質問しようと集まった報道陣の前から走り去った姿は、とても「疲労困憊していた」ようには見えなかった。4月に開いた釈明会見でも、難解な専門用語で記者の質問をケムに巻き、したたかな一面を見せている。
■「詐欺」「横領」の指摘
秀才にありがちな「打たれ弱さ」を感じさせなかったし、仮に理研の検証実験で「STAP細胞ナシ」との結論が出たとしても、小保方さんの管理責任を問われただけだ。自ら積み上げてきた研究成果そのものにキズがつくわけではない。
それなのに「最悪の結末」を選んだのはなぜか。理由のひとつとしてささやかれているのが、研究費の“不正流用疑惑”だ。
「笹井氏は年間6億円の研究費が配分されていましたが、なぜか小保方さんの出張旅費やタクシー代まで肩代わりしていた。2人が1年間で55回出張し、約500万円が支出されていたとも報じられています。一緒に出張していたケースもありました。こうした不透明な支出について、理研内部から『詐欺』や『横領』を指摘する声が出ていたのです」(科学ジャーナリスト)
仮に「詐欺」や「横領」で事件化すれば科学界追放は避けられない。ある捜査関係者は「県警が研究費の流れについて調べ始めたと聞いた」と明かす。これが事実なら、笹井氏にとっては屈辱的な展開になっただろう。
危機管理コンサルタントの田中辰巳氏はこう言う。
「人が最終的に死を選ぶには複合的な理由がありますが、笹井氏のように優秀な人の場合、思い描いていた将来像と直面した困難とのギャップに対する失望感、喪失感が大きくなる傾向があります。企業経営者が事件に巻き込まれて逮捕などを予感し、失業や家族を失う恐れを感じるケースと似ています。頭が良過ぎるゆえに先が見えてしまったのかも知れません」
笹井氏にはどんな将来が“見えた”のだろうか。
中国政府(「日本向けは安全」)や日本政府(日中両政府の実務者協議)の言葉など簡単に信じれるわけなどないだろ。
マルハニチロホールディングス(HD)傘下のアクリフーズが製造した一部の冷凍食品から農薬が検出された事件を考えればよくわかる。モニタリングには限界がある。悪意のある従業員や従業員のモラルが低ければ問題は防げない。中国人のモラルの低さは有名だ。
日本と中国政府のパフォーマンスに騙される人達はいるだろうが、また問題は起きる。問題が存在しても公になっていない場合も多い。中国は横に置いて他の国を選択肢に入れて対応するべきだ。2、3年、もしかするとそれ以上、準備に掛かるかもしれないが、国民性や国民のモラルは簡単に変わらない。南米やラテン文化が簡単に変えられるのか?価値観と文化の結びつきは強い。同じ事を繰り返すのは愚かな事だ!
期限切れ肉問題、日中が協議 中国側「日本向けは安全」 08/07/14 (朝日新聞)
中国の食品会社「上海福喜食品」が期限切れの食肉を使っていた問題で、日中両政府の実務者協議が6日、北京で初めて開かれた。中国側は「日本に輸出された食品に問題はない」と説明し、事態の幕引きを急ぐ構えを鮮明にした。日本側はさらに具体的な根拠を示すことを要求。調査の最終結果を待って、今後の対応を判断する方針だ。
中国側は、日本のマクドナルドやファミリーマート向けに出荷された製品に期限切れのものがないとする根拠として、①輸出品には原料から輸出に至るまで登録管理する仕組みがある②輸出品は国内向けとは別の倉庫で保管されるなどの分別がなされている③生産ラインはビデオカメラで録画されており、問題行為は確認できなかった――などを挙げた。ただ、ビデオに映っていない場所で材料の混入がなかったことの証明や、従業員の詳しい証言などの説明はなかった。
現地報道では、国内向けと輸出品は同じ生産ラインで作られ、期限の引き延ばしは様々な手口で日常的に行われていたとされている。日本側は、この日の協議で日本の消費者の不信感は払拭(ふっしょく)できていないと懸念を表明。中国側の担当者は「日本の状況はよく理解している」と応じたという。
今回の協議は、2007~08年の中国製の冷凍ギョーザに農薬が混入された事件を契機につくった「日中食品安全推進イニシアチブ」の枠組みに基づき、日本側が開催を要求。日本側は厚生労働省、中国側は国家質量監督検験検疫総局からそれぞれ課長級が出席した。
期限切れの肉が国内向けに広く流通するなか、中国側が「日本向けは安全」と早々と公表することは、中国国内の世論を刺激するリスクもある。だが、それ以上に、日本の消費者に広がった中国製食品への不信感を早く鎮めたい思惑があるようだ。(北京=斎藤徳彦)
日中、期限切れ食肉問題で緊急実務者協議 中国側は対日輸出食品の安全を強調 08/06/14 (産経新聞)
【北京=川越一】中国の使用期限切れ食肉が日本国内に出回った問題で、日中両政府は6日、北京で「食の安全」に関する緊急実務者協議を行った。中国側は対日輸出食品の安全性を強調したが、輸出用と国内用の食肉が同一の製造ラインで加工されていたことが判明するなど、不安が払拭されたとは言い難い状況だ。
協議には、日本側から厚生労働省輸入食品安全対策室の責任者ら、中国側からは国家品質監督検査検疫総局の担当者らが出席した。
中国側は、問題の食肉を製造・販売した上海の食品加工会社「上海福喜食品」の監視カメラの映像などを調べたと説明。輸出用と国内用の製造時間帯が分けられ、保管庫も別だったなどとして、「輸出食品に問題はない」と主張した。
しかし、どれだけの期間をさかのぼって監視カメラの映像を調査したかなどは明示されなかった。中国側は「日本の状況はよく理解している」としつつも、謝罪はしなかったという。
日中両政府は、2008年に中国製冷凍ギョーザ中毒事件が起きて以降、「食の安全」に関する閣僚級協議を2回、実務者協議を6回開いているが、緊急協議が開かれたのは初めて。
中国産食品問題は解決に長期間 正しい原産地表示の徹底を (1/2)
(2/2) 07/30/14 (ZAKZAK)
中国から使用期限切れの鶏肉が輸入されたことが問題になっている。この影響で、日本マクドナルドやファミリーマートが問題となった製品の販売を中止するなどの対応を迫られた。
輸出していた食品加工会社、上海福喜食品は中国国内に10カ所の工場を有し、トップクラスの会社だという。
これはテレビのワイドショーでも格好の題材だ。というのも、発端となった中国のテレビ番組の映像をそのまま放映できるからだ。廃棄される肉が使われたり、使用期限切れのものが製品になってゆく映像が流された。
国際的な流通を維持しつつ、食品の安全性を守る方法はあるのだろうか。
実態として、中国からの食品は日本に大量に輸入されている。全世界からの輸入食料品に占める中国産シェアは、野菜で5割程度、魚介類や果実で2割程度と多い。
輸入食品の安全性確保がどのようになされているかといえば、輸出国における衛生対策、日本での水際(輸入時)での対策が重要だ。
今回の事件では、「生産報告書は改竄(かいざん)されている」と元従業員は証言しているが、これでは、中国当局でもお手上げだろう。日本での輸入チェックであるが、輸入の1割程度について検査を行っている。
中国産品輸入の事件では、2002年の冷凍ほうれん草事件、07年末の冷凍餃子事件などが思い出される。このような大きな事件があったので中国産品は危険というイメージだが、12年度のデータでは、検査での違反率は0・04%であり、全世界の平均0・06%と比べても高くない。
輸入量が多い分だけ、多くの事件があるが、違反率という比率で見る限り、中国が特に危険とはいえない。もっとも、輸入検査は残留農薬や添加物のチェックが主なので、今回のような使用期限切れ事件を見つけるのは難しいのも実情だ。
今回の事件は、中国のトップクラスの企業での出来事であり、これは氷山の一角だという指摘がある。その背景には、中国がまだ発展途上国で、貧困問題を解決していないという問題がある。つまり、一朝一夕には解決できないということだ。
となると、安全を確保しようとすれば、こうした中国の実情を認識したうえで日本の輸入検査体制を信用し、安価な中国産を購入するか、または自分の目で原産地を確認し中国産を避けるかのいずれかを選択せざるを得ない。
消費者がこうした選択をできるようにするには、原産地表示を徹底させる必要がある。たとえば日本マクドナルドは「鶏肉は、マクドナルドの指定農場で厳しい衛生管理と監視のもとに飼育された中国、タイ産のチキンを使用しています」とあったが、こうした表記について徹底的な検証が必要であろう。
現地の生産全行程を記録しモニタリングすることはコストのかからない具体的方法だ。それくらいしないと日本の消費者の不安は消えない。 (元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)
元SE「名簿業者3社に売った」…ベネッセ流出 08/07/14 (産経新聞)
ベネッセコーポレーションの顧客情報流出事件で、不正競争防止法違反(営業秘密複製)容疑で警視庁に逮捕された元システムエンジニア松崎正臣容疑者(39)が、調べに「持ち出した情報は名簿業者3社に売った」と供述していることが、捜査関係者への取材でわかった。
情報はその後、転売が繰り返され、数百社に流れたとみられる。同庁は、新たに約2000万件の情報を持ち出した疑いが強まったとして、近く松崎容疑者を同容疑で再逮捕する方針。
捜査関係者によると、松崎容疑者は、東京都千代田区の名簿販売会社「セフティー」に今年6月まで計15回、重複分を含めて延べ1億件超の顧客情報を持ち込んだことを認めており、都内の別の2社への売却についても、最近になって供述し始めたという。
このような事件が起きても驚かない人もいるのではないか?
佐世保同級生殺人事件 キムタク髪の父、一周忌前に再婚 08/06/14 (週刊朝日)
長崎県佐世保市で少女A(16歳)が幼なじみのクラスメートを殺害し、遺体を解体した事件の衝撃が広がっている。エリート一家に育ち、東大を目指していた少女はなぜ、むごたらしい“猟奇殺人”を誕生日前日、決行したのか。その“鍵”は、最愛の母の死からわずか数カ月後、再婚した父への愛憎にあった。
少女Aは母親の死を境に、父親との関係が急速に歪み始める。
「寂しさを紛らわすためなのか、父親は若い女性と頻繁に食事するなど夜の街を出歩く機会が増えた。今年初め、お見合いで知り合ったという東京在住の30代前半の女性が佐世保に来るようになりました」(一家の知人)
親子関係は次第に悪化していく。今年1月末に開かれたスケート競技に父子で出場した際、二人は激しくぶつかったという。
「会場でAちゃんとお父さんは大げんかして、周囲の人が『何があったのか』と振り返るほどでした。Aちゃんは『足が痛い』と試合を棄権し、お父さんの言うことをまったく聞かなくなった」(知人男性)
確かに当時の報道を見ると、前日には出場していた少女Aは2日目の種目を足の故障で棄権している。
少女Aは3月、そんな父親を金属バットで殴り、負傷させる事件を起こす。
「2月にAちゃんと父親と食事した時は普通の親子関係に見えた。だが、父親への暴力が激しくなり、家族は身の危険を感じていたようです。『9月からオーストラリアへ留学する』というAちゃんにその準備のためと、一人暮らしをさせたと聞いた」(前出の一家の知人)
今年4月、少女Aは中学と一貫校の県立高に進学したが、1学期はほぼ不登校状態で、3日間しか登校していない。進学を機に、事件の現場となったマンションの一室で、一人暮らしを始めたのだ。
少女Aと入れ替わるようにやってきた、芸能関係の仕事にもかかわっているという華やかな女性と、父親は5月に結婚。地元繁華街を2人が一緒に歩く姿を周囲はとまどいの目で見ていた。
「奥さんの誕生日に合わせて結婚して、新妻のプロフィルを書いた紙を周囲に渡していた。『ピアノが得意』とか、『ソフトバンクのCMの犬の演技指導をしている』とか誇らしげに書いてありましたが、まだ前妻の一周忌も済んでいないのに早すぎではないかと、周りは心配していたんです」(前出の知人男性)
さらに、知人女性はこう語る。
「ピアノや乗馬など共通の趣味があるので交際に至ったと聞きましたが、『自分の子どもが欲しい。だから、年齢が若い子が良かった』とも言っていた。新しい奥さんとの子どもを待望していたようです」
「前妻の一周忌を終えた秋にはハウステンボスの高級ホテルで結婚式を挙げる」と妻は待ち遠しそうに知人に語っていたという。
「新しい奥さんは、家の地下にあるピアノ部屋で、何度か父親と一緒に連弾していたそうです。地下室はAちゃんの実母のリクエストでピアノ部屋にし、夫婦で連弾をしたり、実母がAちゃんにピアノを教えていた思い出の場所。Aちゃんからしたら複雑な思いだったのでは」(前出の知人)
父親はもともと活発な人物だったようで、長男の受験と同時期に10代の受験生が通う佐世保市内の学習塾に通い、11年には九州大学を受験し、入学したという。
「学内に茶髪の中年男性がいて、リアル『ブラック・プレジデント』(ワンマン企業の中年社長が大学に通うテレビドラマ)だと話題になっていた。ピアノ、トライアスロン、ゴルフのサークルに入っていて、ゴルフのスコアは100を切っているから断トツにうまかったと聞いています」(九大の学生)
多忙な弁護士業をこなしながら、サークル活動にいそしむキャンパスライフ。周囲には「若い人と交流して、自分をリフレッシュできた」と語っていたという。前出の知人女性が語る。
「茶髪にロン毛で、片目にかかるように流す髪形はキムタクにそっくり。実際、キムタクがサーファー風の髪形になった時期は本人もそうなったし、『似ていますね』と言うと喜ぶから、意識しているのでは。体も鍛えていて若々しいから、普通の50代とはかなり違いますね」
母の死後、少女Aは英語のスピーチ大会で「マイ・ファザー・イズ・エイリアン」と語り、周囲を驚かせたという。
(本誌・今西憲之、上田耕司、山岡三恵、小泉耕平、牧野めぐみ)
※週刊朝日 2014年8月15日号より抜粋
いろいろな情報の何処までが真実なのか、どこまでが本音なのかは良く分からない。しかし、家庭崩壊、そして仮面家族だったに違いない。少なくとも加害者はそう思っていたのだろう。節税対策協力のご褒美か?たぶん、違うような気がする。こんな節税対策する富裕層はいるのか?幸せってなんだろう?お金に困っていれば、幸せになりにくいが、お金があってもこんな状態じゃ幸せではない。幸せでないからこうなったのか?
女子生徒の部屋から多額の現金 08/05/14 (産経新聞)
長崎県佐世保市で、高校1年生の女子生徒が殺害された事件で、逮捕された同級生の女子生徒の部屋から、現金およそ100万円が押収されていたことが警察への取材でわかりました。警察は、女子生徒が多額の現金を所持していた理由などについて詳しく調べることにしています。
先月27日、佐世保市のマンションの部屋で、15歳の高校1年生の女子生徒が死亡しているのが見つかり、被害者の同級生でこの部屋に1人で住む16歳の女子生徒が、殺人の疑いで警察に逮捕されました。
これまでの調べで、女子生徒は、動機について、「猫を解剖するうちに、人を殺したいと思うようになり、我慢できなくなった」などと供述していることがわかっています。
さらに女子生徒の部屋からは現金およそ100万円が見つかり警察が押収していたことが分かりました。
現金について、女子生徒は「以前、親からもらった」と供述しているということです。
警察は、女子生徒が多額の現金を所持していた理由や生活実態などについて詳しく調べることにしています。
大学生の時、社会学の教授が「豊富な知識や経験を持っていても実際に自分の事になったら上手くいかない事がある、知っている事と実行できる事は違う。しかしいろいろな情報や知識があれば、問題に直面した時に解決に役立つ事は事は多い。」と言っていた。加害者の母親は知識はあったのかもしれない。しかしそれを生かせる人格を持ち合わせていなかったのであろう。
「佐世保市で発生した小6女児の同級生殺害事件では、教育関係者として全国紙に登場し、『教育は1年、2年で結果が出るものではない。改革には10年はかかる』と語っていた。」
10年以上を掛けて、両親の影響を受けて惨殺事件に至ったと言う事になるのだろう。今までの積み重なってきた結果がこうなったのか?
エリート母の過ち 市教育委員の立場で“問題行動”うやむやに 佐世保・同級生殺害 (1/2)
(2/2) 08/04/14 (ZAKZAK)
長崎県佐世保市の県立高校1年、松尾愛和(あいわ)さん(15)が殺害された事件。殺人容疑で逮捕された同級生の少女(16)が凶行に走っていく遠因として父親同様、母親もカギを握っている。少女が小学生時代に給食に洗剤を混入させた際、母親は穏便に済ませようと周囲に働きかけたといい、それが少女が更生する機会を逸したとの指摘もある。超難関国立大卒の才媛で地元の教育委員だった母親。体面がそうさせたのか。
松尾さんを殺害する前にも問題行動を繰り返してきた少女。小学6年だった2010年12月には、クラスメートの給食に水で薄めた漂白剤や洗剤を5回にわたって混入させた。
だが、この問題が当時、佐世保市教育委員会や市議会に報告されることはなかったという。
「騒動が表沙汰にならなかったのは、当時、市教委の教育委員を務めていた母親の尽力によるものが大きい。保護者会で平謝りし、他の父母も大ごとにしたくないということでうやむやのまま、処理されたようだ」(市教委関係者)
捜査関係者によると、少女の母親は、超難関国立大文学部卒で地元放送局で記者として勤務。同級生だった少女の父親と結婚後、育児サークルを立ち上げて書籍も出版するなど教育熱が高い人物だった。
03年10月、同年7月に長崎市で起きた12歳の少年による4歳男児の殺人事件について、サークル代表として地方新聞の取材を受け、「子どもの居場所づくりも大切。(中略)自分をそのまま受け止めてくれるという場があるだけでだいぶ違う」などとコメント。
翌04年6月、佐世保市で発生した小6女児の同級生殺害事件では、教育関係者として全国紙に登場し、「教育は1年、2年で結果が出るものではない。改革には10年はかかる」と語っていた。その年の12月、母親は市教委の教育委員に就任した。
「母親は8年にわたって同職を務め、次の教育委員長の有力候補に挙げられていた。少女が異物混入騒ぎを起こしたのは、教育委員2期目のときだった」(前出の市教委関係者)
同じ県内で起きた2つの悲劇を目の当たりにしながら、なぜ母親は娘の非行をうやむやに済ませてしまったのか、疑問は残る。
昨年10月、すい臓がんで母親が急逝して以降、少女は心のバランスを一段と失っていった。
犯罪心理学に詳しい新潟青陵大大学院の碓井真史教授は「異常な欲望を隠し持つ人が、大切な存在を失って殺人に至ったケースはこれまでもある。少女は、心の中に爆弾を抱えてギリギリのバランスを保って社会生活を送っていた。慕っていた母親の死で抑えていた欲望が暴走した可能性がある」と指摘。
「少女が異物混入騒ぎを起こしたとき、身近にいる人が少女の内面にもう一歩踏み込む選択肢もあった。ただのけんかなどではなく、明らかに異常性を感じさせる行動だ。問題の収束を図るだけでなく、少女の何がそうさせたのかについて根本的な原因を追究するべきだった」と話している。
いろいろな情報の何処までが真実なのか、どこまでが本音なのかは良く分からない。しかし、家庭崩壊、そして仮面家族だったに違いない。少なくとも加害者はそう思っていたのだろう。
「実母を殺そうと思った」 女子生徒が知人に打ち明ける 08/04/14 (産経新聞)
長崎県佐世保市で同級生を殺害したとして殺人容疑で逮捕された高校1年の女子生徒(16)が、昨年10月に病死した実母を生前、殺そうと思ったことがあるという趣旨の話を知人女性に伝えていたことが5日、女子生徒を知る関係者らへの取材で分かった。
関係者らによると、女子生徒は今年春、知人女性に対し、昨年寝ている実母を殺そうと寝室まで行ったが、思いとどまったと打ち明けたという。
母親は当時、がんと診断されて自宅で療養していた。
週刊文集の記事が正しいのならいろいろな人がいろいろなコラムや分析を書いているが殺人を起こさなかったとしても子供に影響を与えると思う。尊敬し、大好きだった父親を金属バットで襲った理由は何なのか?
なぜ父親は祖母(父親の母)の養子にしていたのか?金属バットで襲われる前である。
診察を受けた精神科医に養子の件を含め、全てを話していたのか?事実を話さなければ医師は出来るだけ正確な判断は出来ないと考えている。パズルのようなものだと考えている。いろいろな事例や調査と患者の様子や過去から患者の状態を判断し、助言すると考えているからだ。
メディアはもっと情報を調べて公表してほしい。もしかすると思った以上にいろいろな情報が出てくるかもしれない。家族の在り方、学校の権限と責任の明確化、そして行政の権限を考えさせる機会だと思う。事件は発生しそうな条件を持っている家族の何パーセントかが起こすのかもしれない。条件がそろっていてもその他の環境や人間関係で事件は起きないのだろう。しかし、誰かが事件のきっかけを作り、事件となるのだろう。
【コラム 山口三尊】佐世保高1殺人事件は起きるべくして起きた
佐世保殺人事件で考える「心の障害」とは何か (BLOGOS)
「命の大切さ」を考えるなら
「佐世保高1女子惨殺」金属バット事件の前月 加害少女A子は祖母の養子になっていた! 08/04/14 (週刊文集)
長崎県佐世保市で、県内有数の進学校に通うA子(16)が、高校のクラスメイトの松尾愛和さん(15)を絞殺し、遺体の頭部と左手首を切断した事件で、新たな事実が明らかになった。
今年3月2日、高校進学直前のA子は父親の寝込みを金属バットで襲い、頭部に重傷を負わせているが、その前月、父親はA子を祖母(父親の母)の養子にしていた。父親の代理人を務める弁護士が8月3日、週刊文春の取材に対し事実を認めた。
「財産分与と節税の観点からの措置。父親が娘を切り捨てたわけではない。戸籍上のA子の親は祖母ということになるが、実父が父親である事実は生涯変わりなく、実際に、父親がその後も事実上の父親としてA子と接している」(父親の代理人)
だが、相続税問題に詳しい弁護士はこう指摘する。
「確かにあり得る相続税対策だが、実際には節税に熱心な富裕層でも、そこまで徹底している人は多くはない。仮に相続財産が10億円以上もあるような資産家の場合でも、1000万円程度の控除が増えたからといって納税総額はさして変わらず、それなら戸籍も普通の親子のままでいたいと考える方が多い」
父親は代理人を通じ、書面で「複数の病院の助言に従いながら夫婦で最大限のことをしてきたが、私の力が及ばず、誠に残念」と述べているが、娘が精神的に不安定になっていたこの時期に、なぜ節税のために戸籍の変更をしたのか。父親本人の弁明が俟たれる。
加害者の父親が非難されることを恐れて情報を出しているのだろうか?
「関係者によると、精神科医と両親は入院についても話し合っていたが、7月26日の事件まで少女は1人暮らしのままだった。」
典型的な日本タイプだな。話し合っていても判断できない。それとも言い訳。1人暮らしは判断している。つまり自分の命の危険についてはすみやかに判断を下している。自分に関する危険の排除だけはすみやかに決断している。
「他人を傷つける恐れがある緊急時は、指定医の診察結果に基づき、知事が緊急措置入院を決定できる」について確認していないが、本当に可能であるならば佐世保こども・女性・障害者支援センターはその事を説明したのか。
8月4日の現在、このサイトには繋がらなくなっている。公務員達が得意な逃げか?
高1同級生殺害:少女、3月から精神科に通院 08/04/14 (毎日新聞)
長崎県佐世保市の高1同級生殺害事件で、逮捕された少女(16)が、父親を金属バットで殴った3月から精神科に通院していたことが、父親の代理人弁護士への取材で分かった。精神科医が「同じ屋根の下で寝ていると、命の危険がある」と父親に少女との別居を勧めたという。関係者によると、精神科医と両親は入院についても話し合っていたが、7月26日の事件まで少女は1人暮らしのままだった。
弁護士によると、50代の父親は3月2日に少女に金属バットで頭を殴られた。父親は「死にかけた」と話しているという。そのため、精神科での治療を受けさせることを決意し3月以降、二つの精神科に通院させた。精神科医のアドバイスを受け、少女は4月からマンションで1人暮らしを始めた。
父親は5月に再婚し、少女は時々、佐世保市内の実家を訪れ、父親のために新しい母親と一緒に料理を作るなどしていたという。弁護士は「父親は再婚した妻と共に、医師、カウンセラーなどの指導に基づく対処をしてきた。まったく何もしていなかったというのは誤解だ」と話している。
関係者によると、少女を診察した精神科医は事件前の6月10日、県佐世保こども・女性・障害者支援センター(児童相談所)に「人を殺しかねない」という趣旨の相談をしていた。少女の名前は明かさなかったため、センターは「警察に相談したほうがいい」と助言していた。【大場伸也】
佐川一政で検索した。
佐川一政 (ウィキペディア)「取調べにおける「昔、腹膜炎をやった」という発言を通訳が「脳膜炎」と誤訳したこと」で運良くフランスで不起訴となる。しかし、日本では有罪の判断であったがフランス警察が捜査資料を提出を拒否したために有罪人はならなかったらしい。精神鑑定で心神喪失でなければ、無罪ではないと言う事か?
パリ人肉食事件の佐川一政氏 同級生殺害する犯行心理を分析 08/04/14 (週刊ポスト)
佐世保市内の進学校に通う高校1年生・A子(16)が同級生を殺害するというおぞましい事件が起きた。A子はなぜ大切な親友を殺(あや)め、切り刻むという尋常ならざる凶行に走ったのか。
週刊誌を中心に多くのメディアは、「母親が亡くなって約半年で父親が再婚したのがきっかけ」と、彼女の家庭環境にその動機を求めるが、それは短絡的、非論理的だ。
もちろんA子の人生に少なからぬ影響があったことは間違いないだろうが、同じような事情を抱える家庭はいくらでもある。母の死や父の再婚が犯行の理由というなら、日本に何人もの猟奇的少年犯罪者が生まれることになってしまう。
精神科医や犯罪心理学者たちはメディアで「発達障害」や「性同一性障害」などの病名を挙げてA子の心の闇に迫ろうとするが、どの解説も過去に殺人を犯した少年のいずれにも当てはまりそうなもので、この事件の最大の特徴である「猟奇性」について説明するものではない。
「ある評論家は被害者への恨みが動機だと推測していましたが、全く違います」
こう断言するのは、作家の佐川一政氏(65)。フランスで起きた猟奇的殺人事件「パリ人肉事件」の犯人として日本中を騒がせた人物である。
佐川氏は1981年に留学中のパリで留学生のオランダ人女性を射殺。屍姦のうえ遺体を解体し、一部を食べた。その後、遺体遺棄中に逮捕されるが、心神喪失が認められて不起訴処分になり帰国。これまで刑事責任を問われることはなかった。現在は作家として活動している。
同じ「解体」の経験者として、A子の犯行をどう分析するのか。
「『遺体をバラバラにしてみたかった』という供述に、同性愛的な愛情を強く感じます。『なぜ親友を解体できるのか』ではなく『親友だからこそ解体したかった』と解釈すべきなのです」
佐川氏が女性を解体したのは遺体の運搬が目的で、解体自体が目的ではなかったというが、相手を傷つけることで快感を手に入れる性癖は理解できるという。
「かつての私の中には、まともな人格と、愛する人を食べたいと願う人格の2つがあって、どちらが本当の自分かわかりませんでした。理性のストッパーが弱くなってしまった時、私はあの事件を起こしてしまったのです。
A子さんの犯行時の状況を聞いた時、私と同じ性癖があったのかもしれないと直感しました。A子さんはまだ16歳で人格は形成途上であり不安定です。自分の欲望はあるのに、それについてはっきり説明できる状態ではないのでしょう。こうして事件を起こして、やっと自分のもう一つの姿に気づいたのではないでしょうか」
A子の性癖がどう育まれたのかの解明は、犯罪の抑止と青少年育成に欠かせない課題となる。
※週刊ポスト2014年8月15・22日号
「同じ屋根の下で同じように寝ると、命の危険がある」の助言がなぜが一人暮らしなのか?入院の選択については医師は触れなかったのか?父親を尊敬していても、父親の命を奪うことにためらいはない親子関係だったのか?二つの精神科病院を受診して、同じ助言を受けたのか?加害者と加害者の父親の弁護士だから、不利になる事は一切言わないのだから、バイアス混入情報として判断するほうが良いだろう。
長崎県、県教育委員会、佐世保市教育委員会そして
佐世保こども・女性・障害者支援センター
は本気で改善及び改革を考えているのなら全てを公表するべきだ。隠せば、中途半端な対応しか出て来ない。「命の教育」と子供に危害が加えれられる環境の排除とは矛盾があった。だからこそ、今回の残虐な殺人となったと思う。被害者は生き返らない。被害者家族の不幸も元に戻せない。しかし、同じような事を防ぐ対策は出来る。形だけの対策にするか、本気で取り組むだけかの違い。
加害少女別居、医師から「父親に命の危険」助言 08/04/14 (読売新聞)
長崎県佐世保市の県立高1年の女子生徒(15)が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された少女(16)の父親は、実家で少女から金属バットで殴られ重傷を負ったため、少女をマンションに一人暮らしさせていたことがわかった。
父親はバットで襲われた後、少女に医療機関の精神科を受診させており、医師から「父親に命の危険がある」と助言されていたという。
父親の代理人弁護士が3日、長崎市内で報道陣の取材に応じた。弁護士によると、少女は3月2日、佐世保市の実家で父親の頭部を金属バットで殴った。けがは「命にかかわるもので、死ぬ可能性も十分あった」という。父親は原因がわからず、同月から二つの精神科病院で少女に治療を受けさせた。医師に相談した際、「同じ屋根の下で同じように寝ると、命の危険がある」と助言を受け、事件現場となったマンションに、4月から少女を一人暮らしさせた。一人暮らしは医師も了承していたという。
女子生徒 事件前後の経緯明らかに 父親が公表 08/04/14 (産経新聞)
長崎県佐世保市で同級生を殺害したとして殺人容疑で逮捕された高校1年の女子生徒(16)が通院していた精神科とのやりとりなどを父親がまとめた書面が、4日、弁護士を通じて公表され、事件前後の様子が明らかになった。
金属バットで父を殴打→精神科医「病院で受け入れ困難」…独居に
弁護士によると、女子生徒は3月、父親を金属バットで殴打したため、父親が精神科に通院させていた。父親は医師から「同じ家で寝ていると、命の危険がある」と助言されたため、女子生徒を事件現場となったマンションで4月から1人暮らしをさせていた。
書面によると、事件前日、両親が精神科に行き、入院措置を頼んだが、実現しなかったとしている。医師が「個室はあるが独占することになるので難しい。他の病院でも受け入れは困難」と答えたという。
また、事件の約20日前、医師が両親に児童相談窓口のほか、警察への相談も打診したが、事件前日の話し合いで警察への相談は見送ったという。
弁護士は書面を公表した際、「あくまで父親本人が書いていることだ」とし、病院側に確認していないことを明らかにした。
佐世保こども・女性・障害者支援センターの出来る事及び専門性の詳細をHPに記載した方が良い。
相談しても意味が無いような対応しか出来ないのなら電話する時間の無駄、そして、税金の無駄。県に集約して必要とあれば職員が現地に向かう方法の方が良いのかもしれない。精神科医はお金を取って診察及び助言しているのだから専門性は高いと思う。
最後に父親は弁護士なのだから公務員は一般的に勤務時間外には働かないことを良く知っていると思う。なのに勤務時間外に電話をするのはおかしい。電話をしたくなかったが、医師に電話をするように言われ、仕方がなく形だけの相談だったのだろうか?
生徒の親、窓口に前日電話 県職員退庁で相談できず 08/03/14 (産経新聞)
長崎県佐世保市で高校1年の同級生を殺害したとして逮捕された少女(16)の親が、事件前日の7月25日夕、県の児童相談窓口に相談するため電話していたことが3日、県関係者らへの取材で分かった。電話を受けた宿直担当者は、「職員は勤務時間外で退庁している」と伝えた。親は名乗らず、相談内容も告げなかったという。県関係者は「結果を踏まえると、対処できなかったのは大変残念だ」と話した。
県関係者によると電話は金曜日の7月25日午後6時半ごろ、佐世保こども・女性・障害者支援センターにあった。親は職員の不在を知ると、「月曜にかけ直します」と述べ、電話を切った。少女を診察した精神科医の助言を受け、相談しようとしたとみられる。相談窓口には精神科医も6月10日に電話で相談したことが判明している。少女の氏名は伏せられていたものの、医師は名乗っていた。
行政指導6回!これぐらい無視しないと儲からないのか?そして、違法する方が中国のように得なのかもしれない。
死亡事故のキャンプ場 過去に行政指導6回 08/03/14 (東京新聞)
神奈川県山北町のキャンプ場「ウェルキャンプ西丹沢」で三人が河内川に流され死亡した事故で、無許可で現場の中州に土砂を盛ったり川を掘削したりしたとして、キャンプ場運営会社が二〇〇八年以降、県西土木事務所から六回の行政指導を受けていたことが、県への取材で分かった。
いずれも是正されたが、県は「川の流れを変える危険な行為」と話し、今回も無許可工事がなかったか調査する。神奈川県警は、キャンプ場の安全管理に問題がなかったか調べる。
同事務所によると、現場は民有地で、川の流れを変える工事は県の許可が必要。運営会社は〇八年五月、許可を得ずに事故現場の中州に土砂を持ち込んだとして是正指導を受け、十日後に土砂を撤去した。
同年七月にも中州に土砂を盛っていることが判明し、指導後に是正。その後も一一年八月まで川の形状を変更させるなどして指導を受け、是正していた。
付近の男性住民によると、六、七年前から夏のキャンプシーズン前、川の流れで削られた中州に土砂を積んで補強や拡幅をし、客に利用させていた。男性は「中州は水面からの高さが一メートルほどしかなく、増水したら危険」と話している。
ウェルキャンプ西丹沢の担当者は「社長からの指示がなく、コメントできない」と話している。
亡くなった三人は一日、中州に設けられたキャンプ場にテントを張り、スポーツタイプ多目的車(SUV)で増水した川の対岸に渡ろうとして流された。 (山田祐一郎、小沢慧一)
母子の命奪った1時間の雨「助けて」の声届かず 4人逮捕 08/04/14 (産経新聞)
夏休みの楽しい思い出となるはずだった家族旅行が、悲劇へと暗転した。
神奈川県山北町のキャンプ場内で一家4人が川に流された事故は、母親と小学生の子ども2人が遺体で見つかるという悲しい結末となった。突然降り出した豪雨の中、キャンプ場の利用者は「助けて」と叫ぶ男性の声を聞いていた。雨はわずか1時間ほどでやんだという。
4人は1日午後8時頃、山北町中川のキャンプ場「ウェルキャンプ西丹沢」を流れる河内川で車ごと流された。父親でIT関連会社社長大森慎也さん(43)(藤沢市片瀬山)は自力で岸にたどり着いたが、2日朝までに2~4・5キロ下流で、妻ルミさん(42)と長女の小学3年舞奈(まな)さん(9)、長男の小学2年凱風(がいふう)君(7)の遺体が相次いで発見された。
松田署の発表によると、4人は1日から2泊3日の予定でキャンプ場を訪れ、長さ約100メートル、幅約50メートルの中州にある四輪駆動車専用のキャンプ場に車を止め、テントを張っていた。隣接するキャンプ場に宿泊していた藤沢市の男性(36)は1日夜、「捜して」「助けて」などと叫ぶ男性の声を耳にしたが、豪雨に遮られ、その後の様子は確認できなかったという。
ウェルキャンプ西丹沢は2日、ほぼ通常通りの営業を続けた。事故が起きたキャンプサイトでは、車を川からクレーン車で引き上げる作業が行われたほか、県西土木事務所の職員が現場の地形や状況を確認した。9歳と5歳の娘を連れてきた横浜市青葉区の30歳代の男性は「こんなのどかなところで、痛ましい事故があったことが信じられない。自然の恐ろしさを実感する」と話していた。
最後まで一家の無事を祈り続けた親族や知人らは、突然の悲報を受け、深い悲しみに包まれた。大森さん宅に駆け付けたルミさんの兄(46)は「言葉になりません」と苦しい胸の内を明かした。兄によると、大森さんは夜通しで捜索を手伝い、「責任を感じている」と涙を流し続けていたという。
舞奈さんと凱風君の2人が通っていた藤沢市立片瀬小学校の本橋淳校長は2日朝、取材に応じ、「信じられない」と憔悴(しょうすい)した表情を浮かべた。本橋校長によると、舞奈さんは生き物が大好きで、凱風君はドッジボールに夢中になるなど、2人とも活発な児童だったという。
近所の住民らによると、凱風君は地域のサッカークラブに所属し、コーチを務める大森さんとともに練習に励んでいた。試合には家族で応援に訪れるなど家族仲もよく、自宅のバルコニーに友達を呼んで食事をすることもあったという。
近くに住む主婦(77)は「道ですれ違うと、『こんにちは』と笑顔で声をかけてくれる、礼儀正しいきょうだいだった」と残念そうに話していた。
全くメリットも無いのに名義を貸すだろうか?献金とか、間接的な支援とか、何かあったのではないのか?
久間氏理事長のNPO元幹部らが原発事故賠償金詐取疑い 4人逮捕 08/03/14 (産経新聞)
東京電力福島第1原発事故の風評被害に伴う損害賠償の不正請求事件で、警視庁組織犯罪対策3課は2日、詐欺容疑で、東京都練馬区豊玉南、NPO法人「東日本大震災原子力災害等被災者支援協会」(中野区)自称元理事、進藤一聡容疑者(42)ら4人を逮捕した。同課によると、進藤容疑者は容疑を否認、他の3人は認めている。
NPO法人は平成23年8月に復興支援などを目的に設立され、久間章生元防衛相(73)が理事長を務める。24年2~6月に十数社から計1億数千万円分の賠償請求手続きを代行しており、同課は不正請求を繰り返していた可能性があるとみて調べている。
逮捕容疑は同年4~5月、人材派遣会社が福島県内のホテルなどにコンパニオンを派遣しているように装い、「放射能漏れの影響でキャンセルが相次いだ」とする虚偽書類を東電側に提出し、約1200万円を詐取したとしている。これまでに逮捕された派遣会社関係者らの供述からNPO法人の関与が浮上した。
久間氏は産経新聞の取材に「1年以上前に辞任届を出した。報酬は一度も受け取っておらず、事件のことも知らない」としている。
サインはなぜ見逃されたか 3度はあった惨劇の芽を摘む機会 (1/2)
(2/2) 08/02/14 (産経新聞)
少なくとも3度、惨劇の芽を摘む機会があった。長崎県佐世保市の高1女子生徒(15)殺害事件は、同級生の少女(16)が殺人容疑で逮捕されてから3日で1週間となる。少女は「人を殺しバラバラにしたかった」と供述し、精神鑑定を受ける見通しだ。給食への異物混入、父親への暴力、精神科医の通報-。少女が発したサインはなぜ見逃されたのか。
通報を放置
「小動物の解剖をしている。このまま行けば人を殺しかねない」。少女を診察した精神科医が長崎県の児童相談所へ通報したのは6月10日。相談を放置した長崎県は批判を浴びた。
他人を傷つける恐れがある緊急時は、指定医の診察結果に基づき、知事が緊急措置入院を決定できるからだ。この時点で入院治療を始めていれば、悲劇は避けられた。
別の疑問も浮かぶ。両親はなぜ少女の一人暮らしを続けさせたのか。「今秋からの留学準備のため」とされるが、教育評論家の尾木直樹さんは「準備は実家でできる。孤独を深めれば状況は悪化する」と話す。
相談窓口なく
父親の依頼で少女に接見した弁護士は7月31日、少女は父親の再婚に賛成だったと話した。それまで再婚への反発が原因で中3時に金属バットで父親を殴打したと受け止められていた。実母の一周忌を迎える前に再婚し、少女が「お母さんのこと何とも思っていないのかな」と話していたと多くのメディアが報じたからだ。接見と報道は内容が食い違い、動機の解明は捜査や家庭裁判所の調査に委ねられる。
ただ子への虐待なら児童虐待防止法、夫婦間暴力ならDV防止法があるなかで、思春期の子供の親への暴力に対応する特別法はない。津崎哲郎花園大教授(児童福祉論)は「利用しやすい行政の相談窓口がないことが兆候を社会的に認知できなかった一因」とみる。
意識持てず
「甘さがあったと言われれば真摯(しんし)に受け止めるしかない」。小6時の給食への異物混入事案をめぐり、佐世保市教委の担当者はかみしめるように話した。
少女は“実験”するかのように毎回、薬剤を変え、0・3ミリリットルずつ混入した。初めの4回は級友の女児への「憂さ晴らし」が目的。男児を狙った最後の5回目は動機が分からない。混入を繰り返すうち人体への影響に関心が移った可能性があるが、「当時は問題意識を持てなかった」。
問題の先送り
名士の家で育ったために体面が優先され、問題の解決が先送りされたとの見方もある。
市教委は給食への異物混入を市議会や警察へ報告、通報しなかった。県によると、金属バットで殴られた父親が行政に助けを求めた形跡はない。県教委によると、精神科への通院を学校は知らされていなかった。
捜査や家裁調査で真実を究明し、今度こそ少女の立ち直りにつなげなければ、少女に優しく接していた女子生徒が浮かばれない。
下記の記事が事実ならなおさら長崎県、県教育委員会及び
佐世保こども・女性・障害者支援センターの対応が問題だ。父親は学校の忠告を無視。学校は市教育委員会に父親に対する忠告に関して報告したのか?既に関係者が加害者から逃げようとしている。
父親はなぜ精神科医の忠告を無視し続けたのか?
「精神科医がAを診察できたのは、父親の了解があったからにほかならない。とすれば当然、医師は児童相談所だけでなく父親にも“Aの危険性”を指摘しているはずだ。同時に、一緒に住むとAの殺意が強まるおそれがあるため『しかるべき施設に入れるべき』という話も出たとされる。しかし、父親はAに一人暮らしをさせた。」
記事からの情報だと精神病院に入院しか選択はなさそう。やはり体裁を気にする父親の判断か?
見逃された猟奇少女のサイン、精神科医の通報を無視 08/02/14 (東京スポーツ新聞社)
父親は惨劇を止められたはずだ――。長崎県佐世保市の高校1年生、松尾愛和(あいわ)さん(15)が殺害され、同級生の女子生徒A(16)が逮捕された事件で、Aの父親の知人から「おかしいのは父親」との非難の声が飛び出した。漂白剤混入に、金属バットで父親を殴打…。この時点でAを診察した精神科医から児童相談所に「このままではあの子は人を殺しかねない」と通報があったことが分かった。しかし、児童相談所は動かず、娘の危険な兆候を聞かされたはずの父親は、Aに一人暮らしをさせた。これに対し父親の知人の口から大批判が飛び出した。
精神科医から「佐世保こども・女性・障害者支援センター」(児童相談所)に電話があったのは6月10日。長崎県関係者によると、精神科医は「小学生のときに薬物混入事件を起こし、中学生になって父親を殴打した。小動物の解剖をしている。このままいけば人を殺しかねない」と話したという。
高校1年生で15歳とまでは明かしたものの、医師として守秘義務に抵触するとして名前は言わなかったという。匿名ではどうしようもないと、児童相談所は対応しなかった。しかし、医師は名乗っていたので、医師に直接会って詳細を聞くことはできたはずだ。また、たとえ匿名でも薬物混入事件は市教育委員会が把握していることであり、連携を取れば特定は不可能ではなかったはず。事件は未然に防げたかもしれなかった。
児童相談所所長は「何もお話しできない」を繰り返すのみ。報道陣から「本当は名前を知っていたんじゃないですか」と追及されシドロモドロ。地元の名士の父親に配慮した?との疑惑も出た。
Aの狂気が膨らんだのは家庭だ。一家の大黒柱である父親はどんな人物なのか。
30年来の知人という男性は「あいつが20代のころに、(元農相の)山田正彦さんの法律事務所で働きだしたんだ。山田さんが政治家に転身するときは、あいつも選挙を手伝ってた。その後、独立した。正義感のあるいいやつだった印象しかないよ」と語る。
独立してからめきめきと頭角を現し、事務所は拡大。豪邸も構えた。青年会議所やロータリークラブに顔を出し、人脈を広げた。好人物だったようで、人に好かれたという。将来は政治家を目指していたのだろうか。
しかし、今春に再婚したときは「前の奥さんの一周忌も過ぎてないのに、おかしい」と多くの知人たちから批判的な意見が出たという。父親はある宴会で手の小指を立てながら「この件ではご迷惑かけました」と知人たちに頭を下げていた。
一方、Aの弁護人は31日、「女子生徒が父親の再婚に反対していたとする報道は事実と異なる」などとする見解を、文書で発表した。声明で弁護人は、接見で直接聞いた話として、Aは父親の再婚には賛成しており「実の母親が亡くなって寂しかったので、新しい母親が来てうれしかった。父親のことは尊敬している」と話したとした。
しかし再婚後、Aは金属バットで父親を殴っている。別の知人は「頭蓋骨が陥没し、歯がボロボロになったそうです。手加減が一切なく、娘さんには殺意があったのでしょう。父親は人脈を使って知り合いの病院で治療したみたいで、大ごとにはしないようにしていた。普通の病院ならそうはいきません」と話す。
また、Aが小6のときの漂白剤混入事件について「父親は『学校の管理が悪かったんじゃないか』と言っていました」と前出の知人。
精神科医がAを診察できたのは、父親の了解があったからにほかならない。とすれば当然、医師は児童相談所だけでなく父親にも“Aの危険性”を指摘しているはずだ。同時に、一緒に住むとAの殺意が強まるおそれがあるため「しかるべき施設に入れるべき」という話も出たとされる。しかし、父親はAに一人暮らしをさせた。
「(自分が)バットで殴られたのに、娘を一人暮らしさせるなんておかしい」(同)。精神科医の忠告も無視したのか。
前出の30年来の知人男性は「今度、あいつに会ったら、『一生、娘を支え続けることが償いだぞ』と言ってやりたい」と力なく話した。父親が娘としっかり向き合ってさえいれば凶行を止められたかもしれない。そう考えると愛和さんがあまりにかわいそうだ。
08/01(金) テレビ朝日 【報道ステーション】より 08/03/14 (リンゴジュース まとめ速報)
高1女子殺害の女子生徒・“大人はどう接したのか”
長崎・佐世保の女子生徒殺害事件。
女子生徒に異物を給食に混入された児童の父親は異物混入児に女子生徒から「ごめんなさい」という一言はあった。
事件以来学校にほとんど来ていない。出てきた時は保健室で自習していた。両親からの謝罪もあったと述べた。
佐世保市教育委員会学校教育課・栗林俊明主幹は「学校としてもこちらとしてもカウンセリングの投げかけは行った。該当の保護者が望まれないということもありカウンセリングは2回で終了した」と述べた。
女子生徒が中学生になると異物混入問題は県教育委員会や中学校に引き継がれた。
中学時代は父親を金属バットで襲ったり、猫を複数回解剖したりと問題行動を起こしていた。
しかし校内では問題行動が見受けられず公的なケアは行われなかった。
高校進学後、一人暮らしを始め不登校に。
女子生徒について教育委員会などに報告はなし。
事件のあった部屋の冷蔵庫から猫の首が見つかった。
整然と供述、見えない心=精神鑑定視野に捜査-逮捕から1週間・高1女子殺害 08/02/14 (時事通信)
長崎県佐世保市のマンションで県立高校1年の女子生徒(15)を殺害したとして、同級生の少女(16)が殺人容疑で逮捕されて3日で1週間。少女は殺害行為や遺体の切断を認め、理路整然と事件のことや生活状況などを供述しているという。一方で被害者との間にトラブルは確認されておらず、動機は依然はっきりしない。
◇凄惨な現場
発見時、女子生徒の遺体はベッドの上にあった。県警捜査1課の取り調べに対し、少女は被害者の後頭部を金づちで殴打し、犬をつなぐリード(ひも)で首を絞めたことや、のこぎりで遺体の一部を切断したことを淡々と説明。取り乱す様子はなく、謝罪や反省の言葉もないという。
「ネコを解剖したことがあり、人間でもやってみたかった」という趣旨の供述もあり、マンションの冷蔵庫からはネコの頭蓋骨が見つかった。
凄惨(せいさん)な行為にもかかわらず、少女が冷静に供述していることなどから、県警と長崎地検は家裁送致前に精神鑑定を行う前提で、慎重に捜査を進めている。
◇母の病死、父の再婚
スポーツが得意で、アニメや漫画が好きだったという少女。昨年10月に母親を病気で亡くし、父親はその後再婚した。
少女は今年4月から現場のマンションで1人暮らしをしていた。5月ごろ少女に会ったという幼なじみの女性(17)によると、少女は「(再婚した父親は)お母さんのことなんて、どうでもいいんかな」と漏らしたという。その前の3月ごろには父親を殴打し、入院させるほどのけがをさせていた。
だが、少女は接見した弁護士を通じ、「父親を尊敬しており、再婚に反対した事実は全くない」と説明。継母についても「新しい母が来てくれてうれしかった」と不仲を否定した。
捜査幹部は「未成年者であり、現段階の供述が全てとは限らない」と語り、供述が今後変わる可能性も指摘する。
インターネット上では真偽不明のさまざまな情報が流れた。7月26日夜の事件発生直後には、殺人事件をほのめかすような文章や画像が掲示板に投稿されたが、県警は無関係と断定した。
両親に「事件起こす可能性」=少女診察の医師―1人暮らし継続・高1女子殺害 08/02/14 (時事通信)
長崎県佐世保市の県立高校1年女子生徒(15)が殺害された事件で、逮捕された同級生の少女(16)を診察した医師が、事件前に少女の両親と面談し、「このままでは事件を起こしてしまう可能性がある」と伝えていたことが1日、関係者の話で分かった。少女は医師と両親が面談した後もマンションで1人暮らしを続け、事件を起こした。
医師は6月10日、県の児童相談窓口に電話し、少女が小学6年生の頃に給食に異物を混入させたことや、父親に暴力を振るいけがをさせたことなどを挙げ、「人を殺しかねない」などと相談していた。
関係者によると、医師は県側の助言などを受け、事件前の7月、3回にわたって両親と病院で面談。「事件を起こしてしまう可能性がある」などと告げ、対処を求めたという。
少女は高校に進学した4月から、事件現場のマンションで1人暮らしをしていたが、医師と両親が面談した後も1人暮らしを継続。7月26日に事件を起こした。
一人暮らしやめさせるよう…学校側が父親に忠告 08/02/14 (テレビ朝日系(ANN))
長崎県佐世保市の高校1年生同級生殺害事件で、学校側が、逮捕された女子生徒(16)の一人暮らしをやめさせるよう父親に忠告していたことが分かりました。
女子生徒は先月26日夜、自宅で同級生の女子生徒(15)をハンマーで殴った後、ひもで首を絞めて殺害した疑いが持たれています。遺体はベッドの上で首と左手首が切断され、腹部も割かれていました。逮捕された女子生徒は、高校に入学した今年4月から一人暮らしをしていましたが、学校側は、女子生徒の父親に一人暮らしをやめさせるよう忠告していました。事件は、女性生徒が一人暮らしをしていたマンションの部屋で起きています。
STAPは「ネッシー」…学会、異例の集中批判 08/02/14 (日テレNEWS24)
STAP(スタップ)細胞の論文問題で、理化学研究所による不正調査や検証実験などに対して、約1万5000人の基礎生物学者を抱える日本分子生物学会が、異例の集中批判を展開している。
STAP細胞が存在したかどうかを調べる検証実験の中間報告は、近く公表される見通しだが、「一連の対応は科学を否定するもの」とする強い批判に、理研はどう応えるのか。
同学会が異例の批判を始めたのは先月4日。英科学誌ネイチャーが2本のSTAP論文を撤回する一方、理研が小保方晴子ユニットリーダー自身による検証実験を認め、正式に準備を始めた直後だった。理研チームの検証実験は4月に先行して始まったが、難航している模様だ。
同学会理事長の大隅典子・東北大教授が「理研の対応は、税金で研究を支える国民への背信行為。不正の実態解明が済むまで、検証実験は凍結すべきだ」との声明を出し、口火を切った。理研は6月末に着手した不正の追加調査を何より優先するべきだという指摘だ。
その後、同学会の幹部ら9人も相次いで見解を公表し、学会あげて問題視する姿勢を鮮明にした。「科学的真実そのものの論文が撤回された以上、検証実験は無意味」(町田泰則・名古屋大名誉教授)。「STAP細胞は今や(未確認生物の)ネッシーみたいなもの」(近藤滋・大阪大教授)と、厳しい言葉が並んだ。
強い批判は、理研が外部にほとんど情報を公開せず内向きの対応に終始することへの反発だ。学術界には、研究者が互いに論文の議論や批判を重ねることで、科学の健全な発展を保ってきたとの共通認識がある。
「厚生労働省が15日に発表した調査では、ディオ社が受け取った補助金は42億8600万円、未払い給与は7320万円に上っている。」
補助金は42億8600万円の一部は東日本大震災の被災者の雇用に使われたとしても、かなりの額の税金が無駄に使われた。厚生労働省や地方自治体はコールセンター事業のニーズと将来性をしっかりと検討せずに過去の実績だけでお金をばら撒いたのだろう。8月1日のテレビを見ているとほとんど雇用助成金詐欺に近いと思った。事業の将来性がないと明らかになった時点でなぜ報告しなかったのか?地方自治体は時々はチェックしていたのか?約43億円は少ない金額ではない。回収は出来ないのではないのか?
DIOジャパンの本門のり子代表取締役は会見を開くべきだ。
DIOジャパンが本社業務の休止を発表 08/01/14 (日テレNEWS24)
民間の信用調査会社・東京商工リサーチによると、コールセンターの運営会社・DIOジャパンは先月31日、愛媛・松山市と東京・銀座にある本社業務の休止を発表したという。
DIOジャパンは、全国19の市と町に子会社の形でコールセンターを設置、東日本大震災の被災地などで雇用を増やすための国の助成金を受け取り、それを給与として延べ2100人以上の失業者を雇っていた。しかし、給与の未払いなどが問題になり、厚生労働省が調査している。
東京商工リサーチによると、DIOジャパンは先月31日、松山市と銀座にある本社の業務休止を発表したという。厚生労働省は各地の子会社の状況を確認中で、完全な休業と判明すれば国の助成金の返却を求めるという。
(株)DIOジャパン/業務休止 経営破綻か 08/01/14 (JC-NET)
(株)DIOジャパン(本店:愛媛県松山市三町3-12-13、東京本社:中央区銀座6-2-1、 代表:本門のり子)は7月31日、松山の本社事務所に「本日 お休みです」との掲示を行い、業務を休止した。東京本社も同日から業務を休止した。(東京本 社に電話をかけても話し中が10回以上でつながらず、松山本店に何回電話しても誰も出てこない。こうした事業休止の情報は東京商工リサーチの情報を参照し た)
同社は、インターネット地図やホームページの作成業務が中心で年間売上高は約1億円の規模だったが、平成19年4月に関係会社を吸収合併し、コールセンター業務に参入した。
20 年2月に都城コールセンター、22年9月に小倉コールセンターを開設(小倉は後に閉鎖)し、銀座ビルに東京本社も設置し、インターネットや情報誌などから の宿泊予約代行業務が中心となって、売上高は23年3月期に4億270万円、24年3月期に7億3500万円、さらに25年3月期には10億3200万円 へと急拡大していた。
コールセンターは、東日本大震災で被災した地域などでの雇用のために交付される、国の助成金を使った緊急雇用創出事業を受託して、事業を展開。26年度までに失業者など延べ2143人を雇い、将来にわたる地域の雇用促進が期待されていた。
(実質、当初1年間の雇用者は研修員として研修期間扱い、その間は国の助成金が支払われ、1年後から本採用になるはずだったが、コールセンターの業務がないとして雇い止め、取り扱いの市町村や県は、助成金窓口責任として巨額を支払っており、また、入居建物の設備改修工事なども負担していた。DIOジャパンは雇い止めのほか、給与未払いも発生して、現地では困り果てている)
平成25年に発生したホテルでの食品偽装問題で、コールセンター受託売上が伸び悩んだことなどから業績が急激に悪化したとされ、平成26年4月以降、秋田や山形、三重などで開設していた子会社のコールセンターで従業員の雇い止めや給与遅配が明らかになり、社会問題化している。
なお、厚生労働省の7月15日時点で、DIOジャパンが受け取った委託費は42億8600万円、未払い給与総額は7320万円にのぼっていると発表している。
同社のコールセンターは、石垣島・九州・四国・岐阜県・東北地区の広範囲に及んでおり、緊急雇用創出事業の助成金取得目的ではなかったのかと問題になっている。
なお、同社の株主には、東日本大震災中小企業復興支援投資事業有限責任組合無限責任組合員大和企業投資株式会社がなっており、列記とした公的な復興ファンドを運用する大和企業投資が存在していた。DIOジャパンは市町村を信用させるために十二分活用したことだろう。役員にも社外取締役としてそうそうな人たちを就任させていた(いずれも平成26年6月の同社HP現在、8月1日現在の社外取締役の構成とは異なる可能性がある。)。
|
会社名:株式会社DIOジャパン 平成26年6月の同社のHPより
|
|
東京本店所在地:東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル8F
|
|
TEL.03-5537-3066 FAX.03-5537-3067
|
|
松山本店、都城コールセンター、志摩コンシェルジュセンター
|
|
役員
|
(代表と社外役員のみ掲載)
|
|
代表取締役社長
|
本門 のり子(旧姓 小島)
|
|
元卓球全日本社会人チャンピオン(昭和60年)。
|
|
社外取締役:元東邦レーヨン株式会社 代表取締役副社長
|
泉妻 秀一
|
|
社外取締役:元日清紡ポスタルケミカル株式会社 取締役社長
|
野村 俊郎
|
|
社外取締役:株式会社東京スター銀行 取締役会長
|
佐竹 康峰
|
|
社外取締役:イー・アクセス株式会社 取締役名誉会長・社長
|
千本 倖生
|
|
社外取締役:株式会社セルフリーサイエンス 社外取締役
|
岩崎 俊男
|
|
社外監査役:愛媛エフ・エー・ゼット株式会社 代表取締役社長
|
森本 惇
|
|
資本金
|
462,730千円(平成26年3月末日現在)
|
|
株主
|
本門のり子(旧姓 小島)(DIOジャパン代表取締役)、東日本大震災中小企業復興支援投資事業有限責任組合無限責任組合員大和企業投資株式会社、ほか
|
|
従業員数
|
119名(平成26年4月1日現在)
|
|
※グループ総人員数 756名
|
|
業種
|
情報サービス業
|
|
・コールセンターによるインバウンド事業
|
|
・テレマーケティングによるアウトバウンド事業
|
|
インターネット広告業
|
|
Web制作・コンサルタント業
|
|
事業登録
|
|
|
第二種旅行業(平成20年12月16日登録、愛媛県知事登録旅行業第2-174号)
|
|
特定労働者派遣事業(特38-300308)
|
|
事業支援
|
|
|
松山市/松山市企業立地促進条例にもとづく指定事業者(2007.6.8指定)
|
|
愛媛県/平成19年・20年度チャレンジ企業総合支援事業(2008.1.25採択)
|
|
都城市/都城市企業立地促進条例にもとづく指定事業者(2008.2.4指定)
|
|
宮崎県/宮崎県誘致企業認定事業(2008.2.8認定)
|
ディオジャパン業務休止 東北の立地自治体、困惑 08/01/14 (河北新聞)
東北地方などでコールセンターを運営する情報サービス業の「ディオジャパン」が、業務を休止していることが31日、分かった。会社と連絡が取れない状態となっており、コールセンターが立地する東北の自治体などに動揺が広がった。
東京商工リサーチによると、松山市の本社事務所に「本日 お休みです」との張り紙が貼られ、東京本社も業務を休止している。鶴岡市によると、担当者が同日午後、東京本社を訪れたが入り口に鍵がかかり、社名入り看板が無くなっていたのを確認した。
業務休止の情報は、存続を想定していた自治体に衝撃を与えた。岩手県内で唯一、ディオ社の子会社が運営する奥州コールセンターがある奥州市の担当者は「寝耳に水。子会社の業務がどうなるのか」と困惑した。
鶴岡市と秋田県羽後町のコールセンターは31日が閉鎖日だった。同市では5~7月分の賃金が未払いで、失業給付金の申請に必要な離職証明書も届いていないという。羽後町でも4、5月分の給与計440万円が支払われていない。
いわき市では、ディオ社が7月末でセンターを閉鎖すると市に説明していたが、6月末に事実上閉鎖していたことが31日、分かった。賃金未払いがあるとされ、市が状況を確認しようとしたが、連絡が取れないでいる。
宮城県内には登米、気仙沼両市と美里町に計3カ所が立地している。登米市の藤井敏和副市長は「今後の営業に影響が出る恐れがある」と不安な様子。美里町の担当者は「約110人の従業員の雇用を第一にまずは情報を集めたい」と話した。
ディオ社は、国の緊急雇用対策事業として東日本大震災の被災地などに次々と子会社を設立し、コールセンター事業を拡大。しかし、国の補助事業が終了したセンターの多くで、賃金未払いや解雇通知といった問題が表面化した。
厚生労働省が15日に発表した調査では、ディオ社が受け取った補助金は42億8600万円、未払い給与は7320万円に上っている。
◎岩手国体実行委、寄付100万円返還
情報サービス業「ディオジャパン」の子会社が運営するコールセンターでの賃金遅配などの問題に関連し、2016年岩手国体の実行委員会は31日、同社からの寄付金100万円を全額返還したと発表した。
同社は13年6月、国体の運営資金として準備委員会(当時)に100万円を寄付した。同社の子会社が運営する各地のコールセンターで賃金の遅配などが表面化したことを受けて返還を決めた。
実行委事務局は「厚生労働省の調査で事実関係が確認され、社会的影響を勘案した」と理由を説明した。
やはり処罰される人がいないと、中国のようにやり得になる。
研究論文で不正、東大が4人の関与を認定 08/01/14 (読売新聞)
東京大学分子細胞生物学研究所で、細胞内のたんぱく質の働きなどの論文51本に不適切な画像が多数見つかった問題で、調査を行う東大の科学研究行動規範委員会は1日、加藤茂明元教授(2012年3月辞職)の研究室に所属していた4人が、研究不正に関与したとする報告を公表した。
報告によると、不正に関与したのは加藤元教授のほか、同研究室助教授だった柳沢純・元筑波大教授、同特任講師だった北川浩史(ひろちか)・群馬大教授、同准教授だった武山健一氏。全員が東大を辞職しているが、同委員会は「懲戒事由に相当する可能性がある」と判断した。
加藤元教授については、画像の捏造(ねつぞう)や改ざんを行った事実は確認できなかったが、研究室内で「強圧的な態度で不適切な指示・指導を日常的に行った」とし、不正行為を大きく促したと認定。論文の撤回を回避するために実験ノートなどに手を加えるよう指示し、委員会の調査で、虚偽と考えざるを得ない証言をしたという。
事件が起きたので、非難されても仕方が無いと、時が経って多くの人が忘れるのを待つのだろう。事なかれ主義の対応だから、偽善者を装ってこれからも給料を貰って当たり前の事を言って、行動に関しては一歩引いて生きて行くのだろう。非難はされても、これぐらいでは処分されない。公務員の良いところだ。そして次の被害者が出るまで、防止策は出来ている、体制を一新したとか言い続けるのだろう。
「県教委は『「もっと広い範囲の情報共有のあり方が今後の課題だと強く感じる』と話す。」「命の教育」に陶酔して被害者を出さない、加害者を出さないような対応に何が必要が考えて来なかった証拠だ。「命の教育」が浸透しているからこれまでの体制で問題ないと考え、改善できる点について検討も見直しもしてこなかったのだろう。「県教委は『もっと広い範囲の情報共有のあり方が今後の課題だと強く感じる』」と他人事のコメントに思える。こんな体質だから運が悪いと悲劇が起きる。
精神科医の相談放置、対応に疑問の声…高1殺害 08/01/14 (読売新聞)
長崎県佐世保市の県立高校1年女子生徒(15)が殺害された事件の約1か月半前に、逮捕された同級生の少女(16)の問題行動を相談する電話が県の出先機関に寄せられていた問題で、出先機関の対応に専門家らから疑問の声が上がっている。
内容が具体的で、相談者が少女を診察していた精神科医だったからだ。ただ、対応の難しさを指摘する声も出ている。
県関係者によると、児童相談所などが統合されてできた県佐世保こども・女性・障害者支援センターに6月10日、少女を診察していた精神科医が電話で相談を寄せた。実名を名乗り、少女が猫の解剖をしたり父親を金属バットで殴ったりしていること、小学校時代に同級生の給食に異物を混入したことがあることを伝え、「人を殺しかねない」と相談した。少女の名前は明かさなかった。少女は女子生徒を7月26日夜に殺害した容疑で、翌27日に逮捕された。センター側は「相談者には助言した。できる限りの対応はした」と説明するが、少女を特定したり情報を県や県教育委員会、県警に連絡したりといった具体的な対策を取っていなかった。県教委は「もっと広い範囲の情報共有のあり方が今後の課題だと強く感じる」と話す。
元大阪市中央児童相談所長の津崎哲郎・花園大特任教授(児童福祉論)は「相談内容から、極めて事態が深刻であることは容易に想像できたはずだ。職員が精神科医と面談し、少女への対応を協議するなど積極的に動くべきだった」と指摘。「電話での助言にとどまり、関係機関にも情報を伝えていないのは無責任と言わざるを得ない」と批判した。
尊敬している父を金属バットで殴れるのだろうか?それが尊敬の表現であればそうなのかもしれない。文化が違えば、表現方法も違い。家族だけの価値観や表現方法もあるかもしれない。今後、金属バットで父親を殴った理由も公表されるかもしれない。
佐世保高1殺害 加害少女の狂気を強めた父親の“素行” 08/01/14 (日刊ゲンダイ)
長崎・佐世保北高1年の松尾愛和さん(15)殺害事件で、逮捕された同級生A子(16)は「中学生の頃から人を殺したい欲求があった」などと供述しているという。A子の心の闇は、母親の死、父親の早すぎる再婚でさらに深まったようだ。
「父親が経営する弁護士事務所は県内最大手で、年収は1億円近いなんて噂も。以前から夜の街では有名で、飲み代は月に数百万円という話を聞いたこともあります」(地元タクシー運転手)
何不自由ない暮らしをしていたA子は3年前の父の日に「バカボンのパパ」を模したケーキを父親に贈っている。ところが、昨年10月に母親がすい臓がんで亡くなったのを機に急変。母親の死後に中学で開かれた英語の弁論大会で「マイ・ファーザー・イズ・エイリアン」とスピーチ。四十九日前後から、父親を「アンタ」と呼ぶなど、ぞんざいな物言いが目立つようになったという。今年3月ごろには、父親を金属バットで殴り、入院させた。
■週末には博多方面へ
A子は4月の高校進学と同時に一人暮らしを始め、父親は5月に再婚。親子の溝は、どんどん深まっていったようだ。
「お父さんも、奥さんを亡くした直後は無精ひげを生やすなど憔悴しきった様子でしたが、今年の1月から春先にかけ、ほぼ毎週土曜日、ひとりで電車に乗って博多方面へ出かけていました。本人は<仕事関係で>と言っていましたが、随分とラフな格好でしたね」(地元関係者)
そしてA子の前に現れたのが、新しい母親だった。
「父親が後妻に迎えた女性は30代前半で、A子の母親より20歳年下です。それも胸元が大きく開いたシャツとか、体の線がクッキリと出る服装など派手な印象。佐世保なんて狭い街なのに、誰も彼女の素性を知りません。父親が白いベンツの助手席に乗せて裁判所に現れた時は、さすがに周囲もあっけに取られていた。知人には<東京の有名私大卒><東京の婚活パーティーで知り合った>なんて説明していたようですが、実際のところ、どうなんでしょう」(前出の地元関係者)
お母さん子だったA子がショックを受けたとしても不思議はない。
結局、A子は一人暮らしを始め、そのマンションが凶行の現場に。父親が再婚を急がなければ…とも思えてくる。
「女性がすでに妊娠していたから入籍を早めた、なんてあらぬ噂もあります」(捜査事情通)
いずれにせよ、多感な年頃のA子に暗い影を落としたことだけは確かだろう。
「少女は当時の学校の調査に『そんなに勉強をしているのが分からないと言われ、腹を立てた』と説明。別の男児の給食にも1回混入させた。
関係者によると、少女の母は『しっかり教育します』と謝罪。少女はカウンセリングを受け、学校は市に問題を報告したが、その後、大きな問題にならなかったという。」
学校は市に報告した。つまり、市側になんらかの力が働いたと考えて間違いないのか?だとすれば、その力が今回も影響する可能性は否定できない。
長崎県警、少女の成育歴も捜査 佐世保高1殺害 07/31/14 (日本経済新聞)
長崎県佐世保市の同級生殺害事件で、殺人容疑で逮捕された高校1年の少女(16)が小学校時代、クラスメートの給食に漂白剤などを混入させた経緯について、県警が当時被害に遭った児童の関係者から事情を聴いたことが31日、関係者への取材で分かった。
また、高校によると県警は同級生にも事情を聴いており、事件の背景や動機を解明するため、少女の成育歴を詳しく調べているとみられる。
市教委や関係者によると、少女が小学6年だった2010年12月、ベンジンや漂白剤、洗剤を水で薄めて女児の給食に計4回混入させた。女児は体調を崩し、病院で手当てを受けた。
少女は当時の学校の調査に「そんなに勉強をしているのが分からないと言われ、腹を立てた」と説明。別の男児の給食にも1回混入させた。
関係者によると、少女の母は「しっかり教育します」と謝罪。少女はカウンセリングを受け、学校は市に問題を報告したが、その後、大きな問題にならなかったという。
一方、母は中学3年の昨秋、2カ月間の闘病の末、がんで死亡した。少女は4月に高校に入学し、事件現場となるマンションで一人暮らしを始め、5月に父が再婚した。
この間、少女は父を金属バットで殴り、頭に大けがを負わせていたが、県警に情報は寄せられなかったという。〔共同〕
「弁護人は『女子生徒の父親の依頼で弁護人となり、接見を続けている。』」と言う事なので何が本当かは分からない。友達、又は、知り合いを、恨みが無いのに殺し、自分の欲望のために解剖した人間が、報道内容を気にするのか?仮に本当だとしたら、とてつもなく自己中心的な人間に育てられたと思う。今まで周りを気にしなかったから友達がいなかったような情報が出ている。今さら、何を気にかけるのか?殺害した女生徒には申し訳なく思わなくとも、父親が非難されるような状況を作り出した事に対しては申し訳なく思い、訂正を求めたのか?それとも依頼された弁護士を通しての父親の頼みを聞いたのか?密室なので全く分からない。何が事実なのかもわからない。アメリカでは金持ちの子息が事件を起こすと、本人の本音とは関係なく、凄腕弁護士が軽を軽くするケースが多い。父親が弁護士なら軽を軽くする方法は良く知っているのでは?
「報道は事実と異なる」と弁護人 「父親を尊敬している」とも 女子生徒「被害者は友だち」 07/31/14 (産経新聞)
長崎県佐世保市で高校1年の同級生を殺害したとして逮捕された女子生徒(16)の弁護人は31日、「女子生徒が父親の再婚に反対だったとする報道は事実と異なる」などとする見解を、文書で発表した。その後取材に応じ、被害者について女子生徒が「仲の良い友だちだった。本当に良い子だった」と述べたことを明らかにした。
文書で弁護人は、接見で直接聞いた内容として、(1)父の再婚には賛成だった(2)父を尊敬している(3)母が亡くなって寂しく、新しい母親が来てうれしかった(4)すぐに慣れ、仲良くしていた-と指摘した。
被害者との間にはトラブルや恨みはなかったとした。
弁護人は「女子生徒の父親の依頼で弁護人となり、接見を続けている。会話は普通にできており、徐々に打ち解けている。本も差し入れた」と述べた。接見で報道内容を聞いた女子生徒が驚き、訂正を求めたとしている。
これほどにむちゃくちゃを行って来た製薬会社ノバルティスファーマを野放しにしていただけでなく、大儲けをさせていた厚労省。厚労省の罪は重い!
もっと巧妙にノバルティスファーマが動いていたら、今も野放し状態だったに違いない。
ノバルティス:副作用の報告義務違反 厚労省が改善命令 07/31/14 (毎日新聞)
厚生労働省は31日、白血病治療薬による重い副作用を把握しながら国への報告を怠ったのは薬事法違反にあたるとして、製薬会社ノバルティスファーマ(東京都港区)に業務改善命令を出した。臨床試験やアンケート調査で副作用情報を知った営業部門が、薬の安全性を評価する部署に伝えておらず、安全管理に組織的な問題があるとして1カ月以内に改善計画を提出することも求めた。同省によると、医薬品の副作用の報告義務違反で製薬会社が行政処分を受けるのは初めて。
【ノバルティス強制捜査】疑惑を巡る構図の説明
薬事法は、重い副作用を製薬会社が把握した場合、最長30日以内に国に報告することを義務付けている。ノ社は、白血病治療薬の臨床試験や同社が昨年4月から今年1月に実施したアンケート調査で重い副作用を把握。国に報告したのは臨床試験に社員が関与した問題が明らかになった今年4月以降で、報告義務期間を過ぎていた。
厚労省は、営業部門が医薬品の安全性を評価する社内の部署に連絡していなかったことについても、省令で定める医薬品の安全管理情報の収集義務に違反していると判断した。
ノ社を巡っては、降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の虚偽広告事件で東京地検特捜部が薬事法違反の罪で起訴している。厚労省はこの事件についても業務停止命令を視野に行政処分を検討している。また同社の未報告問題では、ほかに患者の副作用情報約1万件について安全性評価部門に連絡しないまま放置していたことも判明しており、厚労省は調査結果を8月末までに報告することも同社に求めた。【桐野耕一】
通信教育大手「ベネッセコーポレーション」の学習能力とはこの程度なのかもしれない、それとも、反省していない。
ベネッセ、ずさんな「おわび文」に利用者激怒 会員番号が丸見え QRコード露出 07/31/14 (夕刊フジ)
利用者の個人情報を大量に流出させた通信教育大手「ベネッセコーポレーション」(岡山市)の事件対応に批判が集まっている。会員へのおわび文の送付の仕方が「ずさんだ」との指摘が出ているのだ。第三者に会員番号が丸見えで、番号が読み取れるQRコードも露出させるお粗末さ。会員からは「二次被害を招きかねない。個人情報を漏えいさせた責任をどう感じているのか」と怒りの声が出ている。
7月中旬のある日、都内に住む50代の男性のもとに1通の速達が届いた。「ベネッセコーポレーションより重要なお知らせです」と大書された封筒の中には「個人情報漏えいについてのお詫び」と題された謝罪文が入っていた。
男性が気になったのは、男性と、男性の息子の名前とともに外側から見える状態になっていた10桁の番号だった。
「封筒を見て、私と息子の個人情報だと気づきました。10年ほど前、息子が小学生の時に受講していたときの情報を、ベネッセがいまだに保有していることも驚きでしたが、封筒に書かれた番号が何を意味するのかを知って怒りがこみ上げてきました」(男性)
露出していた数字は会員番号で、パスワードとともに入力すると、これまで受講した講座情報などが確認できるという。第三者に見える状態のQRコードも会員番号を確認するもので、カメラ付き携帯電話などのバーコードリーダーをかざすと情報が表示される。
「個人情報を大量に漏えいさせた企業としてはあまりにも不用意な対応だと思いました。謝罪文を郵送するにしても、書留にするなどの配慮ができなかったのか。責任感に欠けるのではないか」(同)
利用者の怒りの声をベネッセコーポレーションはどう聞くか。
同社は「発送業務は外部委託している」(広報担当)とした上で、「現状では会員番号がわかったからといって何かができることはない。お客さまに実害が及ぶ可能性は低いと考えている」(同)と回答した。
そもそも今回の不祥事は、利用者の情報管理を外部委託していたために起きた側面がある。
顧客情報を持ち出したなどとして、警視庁に不正競争防止法違反容疑で逮捕されたシステムエンジニア(SE)の男(39)はベネッセの業務委託先に所属していた。
情報漏えいの被害に遭った利用者の問い合わせに応じる専用の電話窓口も、ベネッセは外部のコールセンターに委託している。
消費者問題に詳しい岡田崇弁護士は「個人情報を流出させたベネッセの当事者意識の低さが、消費者の不信感を募らせている」と指摘し、こう続ける。
「実害がないとはいえ、個人情報の流出を起こした後なのだから、利用者側に不安感を抱かせる対応は極力避けるべきで、会社の対応の悪さを指摘されても仕方がない。そもそもベネッセは問題発覚当初から、委託先の会社や情報を流出させたSEの責任ばかりに言及し、『自分たちも被害者だ』と言わんばかりだった。被害弁償についても、しないと言ったりすると言ったり。対応が場当たり的で、企業の不祥事対応としては最悪の部類に入る」
教育事業に関わる企業としての姿勢が問われている。
「また『テストの点がすべてじゃないやろう』と言った女児に、『テストの点がすべてさ』と言い返したこともあったという。」
難関校や難関大学への合格が目標であれば、「テストの点がすべてさ」との回答は正しい。生き方や目標が違えば、価値観も違う事がある。
ある程度の能力があっても努力を怠れば、勉強しかしていない子供に負けるかもしれない。偏差値や学歴が全てと思っている人間は、そこしか見ない。他の良い部分など評価出来ないかもしれないし、偏った価値観しか持っていないかもしれない。たぶん、加害者の両親の価値観や教えが「テストの点がすべてさ」で表現されていたと思う。
今回の事件後に、加害者の両親の教育方針や育て方が正しかったのかと聞かれたら、多くの人達は「NO」と言うに違いない。「テストの点がすべてさ」はある特定の人達には正しい、しかし、こうなってしまった以上、他の生き方や価値観を教えていればと思うだろう。ある選択がある人には適切であっても、全ての人に適切であるとは限らない。議論で価値観が違う人達が妥協しなければ結論は出ない。人生は判断しない判断を含め、間違っていようが、正しかろうが、判断しなければならないことばかりだ。後にならないと間違っていたのか、正しかったのか分からない事もある。判断による結果には責任が付いてくる。関係者は、今後、この事件と向き合うのか、忘れようとするのかは知らないが、事件の関係者として行きていくしかない。それが人生だから。Life goes on.
「市教委は『少女の進学先に事案の概要を伝え、中学や高校でも見守りは続けられていた』と説明している。」そして見守り続けられ、「命の教育」を10年近く取り組んだ結果がこの惨殺。他の教育委員会と同じく、問題があったとしか思えない。どこの教育委員会も言い訳や嘘だけは上手い。逃げる予行演習だけばっちりなんだよね。
では、中学校での見守りの担当は誰だったのか?担当が変われば引き継ぎは適切に行われていたのか?担当者は報告を誰にしていたのか?市教委は担当者又は学校に報告の提出を要求していたのか?それとも学校に投げ任せてたのか?新聞社の記者様、調べて記事にしてください。このように突っ込まれないと、教育委員会は変わらないと思います。
佐世保・高1女子殺害 ベンジン、洗剤…小6時の給食異物混入「憂さ晴らし」 07/30/14 (産経新聞)
■小6時 少女、人体影響に関心?
長崎県佐世保市の高校1年の少女(16)が同級生を殺害したとして逮捕された事件に絡み、少女が小学6年当時に5回にわたって起こした給食への異物混入騒ぎで、混入物が5回とも異なっていたことが30日、学校関係者への取材で分かった。学校側の調査で、異物混入の動機は4回目まではクラスメートとの口論だったが、最後の5回目は「不明」のままだった。動機の解明が不十分だったことが、少女のその後の成長に影響しなかったのか。佐世保市教委の対応も問われそうだ。
学校関係者によると、少女は小学6年生だった平成22年12月1日から10日ごろにかけて計5回、同じクラスの女児と男児の給食に異物を混入。被害者2人の健康被害はなかったという。1~4回目は女児を狙い、水、ベンジン、液体漂白剤、靴用の粉末洗剤の順に使用していた。
一方、5回目だけは男児を狙い、衣類用の粉末洗剤を使っていた。いずれも薬物など0・3ミリリットルを水道水に混ぜて使用。薬剤は家から持ち出していた。
異物混入の動機について、少女は同年9~10月ごろに、学習態度をめぐり同級生の女児と口げんかになったと説明。「『今から勉強ばかりするのは分からん』といわれ、ばかにされたように感じ、憂さ晴らしをした」と話したという。
また「テストの点がすべてじゃないやろう」と言った女児に、「テストの点がすべてさ」と言い返したこともあったという。
一方、男児への混入については、市教委の調査でも動機は判明せず「不明」のまま。女児の給食への混入を繰り返すうち、薬剤の人体への影響に関心がうつった可能性もある。
学校関係者によると、騒ぎは、5回目の混入直後に表面化。学校側の指導やカウンセリングなどで問題行動がおさまったため、男児を狙った動機については、それ以上、究明されなかった可能性がある。
市教委は「少女の進学先に事案の概要を伝え、中学や高校でも見守りは続けられていた」と説明している。
当時の学校関係者の対応について、教育評論家の尾木直樹さんは「動機が分からないまま見守りを続けても効果は出ない。心の問題を早期に把握できていたら、殺人事件には発展しなかったかもしれない」と指摘する。
中村法道長崎県知事は「兆候らしきものはあったのかもしれない。その時点での対応を含めて検証し、取り組みを協議していく必要がある」と話している。
「県教委はNETIBの取材に対し、少女は高校1年生の1学期に3日間しか出席せず、不登校だったことを明らかにした。」と具体的に「不登校」と書いているのはこの記事だけじゃないのか。他の記事は、留学準備で3日しか登校していない、又は、似たような内容だった。
エリート一家 見逃された前兆 07/30/14 (NETIB-NEWS)
長崎県佐世保市の県立高校1年生の女子生徒を殺害したとして逮捕されている少女(16)は、小さい頃から、ピアノが上手で、父親が得意とする競技と同じスポーツで冬季国体に出場し、成績も優秀だった。両親は、市内の名士で、エリート一家に育った。自宅は、海を見渡す高台ののどかな住宅地にある高級住宅。父親は、県内でも最大規模の法律事務所に所属する弁護士。母親は、県のスポーツ団体の会長を務め、教育委員を務めていた。
殺害の動機、背景について、少女の家庭環境などが影響していることがうかがわれるなか、今回の事件の前兆は、小学6年生時の事件だけではなかった。
捜査関係者によると、「人を殺してみたい」との欲求や「(人間の体の)中を見たい」という動機があったかどうか、今後の捜査で解明していくとしている。「人を殺してみたい」という欲求がいつ頃からあったのかが注目され、中学生の頃からあったという見方も出ている。
動機との関係は今のところ判明していないが、母親が2013年10月に死亡し、半年もしないうちに父親は再婚した。この時期、少女の家庭環境、精神状態が一変したと言える。また、14年に開催された冬季国体で出場した2種目のうち1種目を欠場しているという。
母親の死亡後、少女が金属バットで父親を殴ったことがあるとされており、警察では真偽を含めて事実を解明中だ。
県教委はNETIBの取材に対し、少女は高校1年生の1学期に3日間しか出席せず、不登校だったことを明らかにした。また、小学6年生の時の事件については、小学校から中学校に引き継ぎされていたとしている。
少女一家の自宅周辺の住民で、制服姿の少女を時折見かけたという男性は「10年前の事件(小学生による同級生殺害事件)以来、佐世保市では命の教育に力を入れてきたが、個人の問題、家庭にまではなかなか入っていけない。親が無責任ですよ」と語っていた。
小学6年生時の異物混入事件、母親の死による家庭環境の変化と不登校は、少女の心に起きている異変、事件の前兆とも言える出来事だった。エリート優等生一家の少女に起きていた変化に、父親や学校はなぜ気づかなかったのか。サインを見過ごした代償は、あまりにも大きい。
「外部機関による検査も行っていたが、データが改ざんされていたことなどから不正を確認できず、『(取引先に)だまされた』と語った。」
外部機関が検査をおこなったと書いてあるが、どの検査機関がおこなったのか?詳細を公表するべきである。マクドナルドよりもバーガーキングやウェンディーのハンバーガーが個人的には好きだが、田舎なのでこれらの店はない。話を元に戻すが検査費用はマクドナルドの負担か、それとも中国上海市の食肉加工会社「上海福喜食品」の負担だったのか?マクドナルドの負担でなければ、外部機関と言っても商売、厳しい検査は行うのは難しい。理由は客商売。顧客が簡単に検査を行う検査会社に変更できる。検査を行い、合格する事だけが契約や規則であるなら検査が簡単、又は、便宜を図ってくれる外部機関を選ぶはずだ。利益を優先するなら、当然の選択になる。問題が起きれば検査した外部機関を非難し、損害賠償が要求すればよい。顧客がそれを許すかは顧客次第。今回は結果としてどうなるかだけだ。子供達は「当分マクドナルドでは食べない」と言っている。
マック社長「だまされた」窮地に、経営へ大打撃 07/30/14 (読売新聞)
日本マクドナルドホールディングス(HD)は、チキンナゲットの仕入れ先だった上海の食品会社が品質保持期限を過ぎた商品を出荷していた問題で、経営への打撃が大きくなっている。
問題発覚後、1店舗あたりの平均売上高は想定より15~20%落ち込んでいる。2014年12月期の業績予想を撤回せざるを得なくなり、サラ・カサノバ社長は窮地に陥っている。
カサノバ氏は29日、都内で記者会見し、「ご懸念、ご心配をおかけしたことを深くおわび申し上げます」と陳謝した。外部機関による検査も行っていたが、データが改ざんされていたことなどから不正を確認できず、「(取引先に)だまされた」と語った。
信頼を回復するのは容易ではない。さらに、中国産鶏肉の在庫処分や、安全対策の強化などで「数十億円規模の損失が出てもおかしくない」(財務担当)という状況だ。
起こるべくして起きたと言う事か?一人暮らしの理由はこう言う事だったのか?もし金属バットで父親が殴り殺されていたら、被害者及び被害者家族に不幸は起こらなかった。恥を忍んで父親が病院の精神科に娘を連れて行っていれば今回の事件は回避されたかもしれない。後悔は悲劇が起きないと後悔する状況にならないので、やはり犠牲者は出ていたのかもしれない。
昔、「結婚と家庭」と呼ばれる授業を取った事がある、教授は×3。面白い教授だった。彼曰く、「理論と知識を知っていても実践となると上手くいかない。その結果が、×3」と言っていた。下記のような本が出版されているが思うようには行かないのが人生と言う事なのか?
「元気のたね2」出版 (佐世保北高18回生同期会)
元気のたね2 目次 (佐世保北高18回生同期会)
佐世保女子高生殺害 長崎県「命の教育」実体は非行隠蔽 07/30/14 (世界のニュース Nile_Amen)
独占スクープ!「秋葉原連続通り魔事件」そして犯人(加藤智大被告)の弟は自殺した 兄は人殺し、その家族として生きていくことは苦痛そのものだった……(現代ビジネス) は参考にならないが、事件に至る時点までいろいろな事が蓄積されたと言う点では同じかもしれない。
加害少女、金属バットで父親の頭殴っていた…佐世保高1女子殺害事件 07/30/14 (スポーツ報知)
長崎県佐世保市の同級生殺害事件で、殺人容疑で逮捕された高校1年の少女(16)が、今春に金属バットで父親を殴り、大けがを負わせていたことが29日、関係者への取材で分かった。少女の実母が昨秋に病死し、父親が今春に再婚。県警は、少女が家庭環境の変化に大きな影響を受けた可能性があるとみている。一方、県警は少女が被害者について「個人的な恨みはなかった」と供述していると明らかに。2人の周囲への捜査でも、トラブルは確認できなかったとしている。
佐世保市で同級生の女子生徒(15)を殺害した少女は、家庭内で大きなトラブルを抱えていた。
少女の知人らによると、少女の実母が昨秋に病気で死去し、父親が今春に再婚した。少女は「再婚が早すぎる」こと、また「希望していた海外留学を父親が反対した」ことで父親に反抗。夜中に父親の寝室に入りこみ、金属バットで殴りつけたという。
「頭を殴られ、歯も折れたと聞いている」と話した父親の知人男性によると、「6月ごろに父親に直接会って『再婚して若くなったね』と話しかけると、微妙な笑顔を見せていた」という。
スポーツに打ち込んでいた少女は、昨冬には父親とともに国内の主要大会に出場するなどしていたが、今春からは一人暮らしを始めている。県警は、少女が家庭環境の変化に大きな影響を受けた可能性があるとみて捜査している。
一方、少女が小学6年だった2010年に同級生の給食に異物を混入したことについての詳細も明らかになった。市の教育関係者などによると、同級生の女子児童の給食に計4回にわたって塩素入りの洗剤を混入。この時は女子児童が気付かなかったが、次に今度は男子児童のカレーに洗剤を入れたという。男子児童が気付き、担任に報告。少女の実母と父親は、2人の児童と両親に直接会い、謝罪したという。
少女は逮捕後の県警の取り調べで「小動物を解剖したことがある」とも明かしており、県警は精神鑑定が必要との見方を強めている。
父弁護士、母東大…佐世保・逮捕少女を育てたエリート一家 07/30/14 (日刊ゲンダイ)
長崎県の佐世保北高校1年、松尾愛和さん(15)を殺害した容疑で逮捕された同級生のA子(16)は、誰もがうらやむ“エリート一家”に生まれ育った。
県内でも有数の進学校に通っていたA子。友人からは勉強だけでなくスポーツや芸術にもたけた「文武両道」とみられていたが、それには両親の英才教育があったという。
「A子には弁護士の父親と、教育委員会にも関わっていた母親、それに同じ高校に通っていた兄がいました。父親は早大を卒業後、司法試験に受かり、今では県内でも最大級の事務所を構え、有名企業の顧問弁護士も務めている。母親は東大を出て、地元の放送局に勤めていたそうです。NPO法人の代表を務めたり、出版活動も行っていました」(地元マスコミ関係者)
兄も全国統一高校生テストで上位2ケタに入るほどの秀才。地元でも有名なエリート一家だったという。A子は「お兄ちゃんが総理大臣になるって言っているから、私はNHKのアナウンサーになる」と話していた。
「A子は勉強だけではなくてスポーツも万能で、ウインタースポーツで国体に出た経験もある。他にも県の美術展とかピアノコンクールで入賞するなど、将来を期待されていたんです」(前出の地元マスコミ関係者)
■父親は半年で再婚
そんな優雅な生活も昨秋に母親ががんで亡くなってから一変。父親は半年で再婚し、A子は今年4月から家賃5万円台のマンションで一人暮らしをしていた。「お母さんが亡くなって、すぐにお父さんが別の人を連れてきた。お母さんのこと、どうでもいいのかな」と話すなど落ち込んだ姿を見せていたというA子は、父親を金属バットで殴り、大けがを負わせていたことも分かった。
「実はA子は過去にも小動物を解剖するといった“奇行”を繰り返していた。小学生の時には、学校の給食に塩素系洗剤を投入するという“事件”も起こしている。担任には<バカにされたからやった>と話していたそうですが、A子の母親が<A子は悪くない>と相当抗議したそうです。そのためか、この事件は全く報道されませんでした」(捜査事情通)
高台の高級住宅街で暮らしていた幸せなエリート一家は“バラバラ”になってしまった。
「命の教育」は祭りだった。小6女児殺害事件の対応策を取っているシンボルとして掲げたかっただけなのだろう。
「『今回のような事件は、いくつもの要因が重なって起きる。どこかで防ぐ道はあったはず。専門家などから広く意見を取り入れて背景を検証しないといけない』と訴えた。」
今回の事件に関する記事や情報を見ると既にシグナルは出ている。殺人に至るかが断定できないだけで、明らかなシグナルである。専門家などは必要ない。必要なのはなぜシグナルを故意に見逃したのか、誰が、何が障害だったのかと考えて公表する事だ。しかし、これは実現されない可能性も高い。なぜなら、これまでシグナルを故意に見逃してきた環境が佐世保市にあるからだ。ある少女が残酷に殺されただけで変わるような環境が佐世保市にはないと思う。地方都市規模の町だと、建前と本音、表と裏、これまでの人々の価値観や歴史がある。それは悪い部分があっても仕方なく受け入れなければならない環境があると思う。昔からそこに住んでいないと理解できない暗黙の理解があると思う。日本人であっても、そこにずっと住んでいないと「よそ者」と見られるのは一例だと思う。
「大阪府警、犯罪8万件ごまかし」は大阪府警村の共通認識だったと思う。常識で考えれば間違っている。しかも彼らは警察官。しかし、大阪府警村の共通認識を無視できる状態や環境ではなかったと言う事。ある閉鎖された環境にいなければ理解できない特殊な常識。しがらみがない人にしか改革が出来ないと思われる理由の1つはここにあると思う。しがらみのない人だったら簡単に改革できるのか?特殊は常識を否定された集団が簡単に改革に応じるか?彼らの特殊な常識により繰り返されて行事、特殊な価値観、これまで特殊な常識の従い、費やしてきた時間や努力を簡単には捨てられないだろう。捨てられないから抵抗する。直接、又は、間接的な抵抗。それは妨害かもしれないし、命令拒否かもしれない。
メディアがどこまで情報を公開するのか。反対側の人間達がどのように抵抗するのか。待つしかない。
「命の教育」の十年は何だった?高1殺害で波紋 07/29/14 (読売新聞)
高校1年の同級生を殺害したとして、長崎県佐世保市の少女(16)が逮捕された事件は、2004年に同市で起きた小6女児殺害事件を機に、命の教育を実践したり見守り活動を行ったりしてきた人たちにも、重い課題を突きつけた。「自分たちの取り組みは正しかったのか」と悩みながら、子供たちの命を守るための方法を模索している。
04年に事件が起きた大久保小で、子供たちの見守り活動を続けている民生委員、一山信幸さん(74)は今回の事件に「まさかと思った。市を挙げて子供たちに命の大切さを伝えてきて、少しは心に響いていると思っていたが……」と話す。そして「逮捕された少女が住む地域の住民も、同じような悩みを抱いたのではないか」とため息をついた。
04年の事件を機に、同小の校区では、一山さんら住民が毎朝通学路に立ち、登校してくる児童に「おはよう」と声をかけ続けている。だが今回の事件で「自分たちがやってきたことは十分だったのか」と、自問自答を強いられている。
それでも、「ただ落ち込んでいるだけでは何も進まない。もう一度、子供たちをどう支えていけばいいか、地域住民で話し合わなければ」と、自らに言い聞かせるように語った。
04年の事件後、校長として4年間、大久保小で勤務した三島智彰さん(60)は、今回の事件に「非常に悔しい」と唇をかんだ。
同小赴任後、命の大切さを訴え、児童らが孤立しないよう、家族や学校、地域住民との連携を重視した取り組みに奔走した。来月22、23日にはPTAの大会で、事件後の学校の取り組みについて紹介する予定だった。
「今回の事件は真摯(しんし)に受け止めなければならず、大会でも触れざるを得ない」と表情を曇らせたが、「地域ぐるみで子供の居場所をつくるという狙いは間違いだったとは思わない」。
逮捕された少女が一人暮らしだったことにも触れ、「大人が居場所を作ってやれなかったのかもしれない。学校だけでなく、家庭、地域との連携を進めていくことが不可欠だと改めて思う」と話した。
不登校やひきこもりの児童や生徒の支援をしている佐世保市のNPO法人「フリースペースふきのとう」では、子供や保護者を対象に勉強会を続けてきた。山北真由美理事長(70)は「市教委なども様々な対応を続けてきたが、結果的に、どこかに問題があったということになる」と指摘。
「今回のような事件は、いくつもの要因が重なって起きる。どこかで防ぐ道はあったはず。専門家などから広く意見を取り入れて背景を検証しないといけない」と訴えた。
佐世保高1女子同級生殺害事件の犯罪心理学:人を殺してみたかった・遺体をバラバラにして解剖したかった
碓井 真史 | 社会心理学者/新潟青陵大学大学院教授/スクールカウンセラー 07/29/14 (Yahoo!ニュース)
を読んでいると、加害者の弁護チームが報道を利用して精神障害を強調して医療少年院を狙っているのではないかと思ってしまう。
佐世保高1女子同級生殺害事件の犯罪心理学:人を殺してみたかった・遺体をバラバラにして解剖したかった
碓井 真史 | 社会心理学者/新潟青陵大学大学院教授/スクールカウンセラー 07/29/14 (Yahoo!ニュース)
■長崎佐世保高1女子殺害事件:「人を殺してみたかった」「人を解剖してみたかった」「遺体をバラバラにしてみたかった」
とても勉強ができ、スポーツもでき、立派な家庭で育ち、県内有数の進学校に通う女子生徒(16)。その有能な女生徒が、同級性の女生徒を殺害しました。子どもが子どもを殺す。最悪の悲劇的犯罪です。
長崎県佐世保市で県立高校1年の松尾愛和(あいわ)さん(15)が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された同級生の女子生徒(16)~捜査関係者によると、遺体は首と左手首が切断され、胴体の一部も切られていた。これまでの県警の調べに対し、女子生徒は「すべて私がやりました」などと殺害を認め、動機については「人を殺してみたかった」「遺体をバラバラにしてみたかった」といったことを話しているという。
出典:女子生徒「人を殺してみたかった」 佐世保の同級生殺害 朝日新聞デジタル 7月28日
一般の殺人動機の多くは、人間関係のもつれです。つい、カッとなって殺してしまったというものです。または、金目当ての殺人などもあるでしょう。これらは、もちろん悪いことですが、私たちにも理解できる動機です。
しかし犯行動機として、「人を殺してみたかった」「人を解剖してみたかった」「遺体をバラバラにしたかった」というのは、一般の人の理解を超えています。ここが、彼女の「病理性の高さ」と言えるでしょう。
おそらく、これらの供述はウソではないでしょう。彼女は、ただ殺したかった。そして、遺体を解剖しバラバラにしたかったのでしょう。
(このような供述は、どれほどご遺族の心を苦しめることでしょう。)
■人を殺してみたかった
普通の動機がない殺人の中には、「快楽殺人」があります。人を殺すことが快楽なのです。多くの場合、快楽殺人者は男性で、殺すことに性的快感を得ています。
今回は、性的快感を感じるような狭い意味での「快楽殺人」ではないでしょう。性的快感を得るという目的すらなく、ただ殺したかった「純粋殺人」ではないかと考えられます。
他の動機がなく、殺すこと自体が目的という意味での、「純粋殺人」です。
「人を殺してみたかっか」という供述で思い出すのは、
2000年に発生した、17歳高校3年生男子による愛知県豊川市主婦殺人事件(愛知体験殺人事件)です。
彼の犯行動機が、「人を殺してみたかった」「人を殺す体験がしたかった」でした。
彼も、今回の容疑者女生徒と同様に、成績優秀な高校生でした。彼は、「他人への共感性の欠如、抽象的概念の形成が不全、想像力の欠如、強いこだわり傾向」があり、「高機能広汎(こうはん)性発達障害あるいはアスペルガー症候群」とされ、医療少年院へ送致されました。
(アスペルガー障害だからといって、危険な犯罪を犯すわけでは決してありません。)
■遺体をバラバラにしてみたかった
バラバラ殺人事件は、その衝撃度から、きわめて残虐な犯人像を思い描かれます。しかし多くの場合、遺体を切断する理由は、単純です。遺体を処理したいが、重くて運べないというものです。
しかし、今回の遺体損壊は、身元を隠すためでもなく、遺体を処理するためのものでもありません。
容疑者の女生徒は、小動物の解剖をしていたと伝えられていますが、人間のこともバラバラにしてみたいと思ったのでしょう。首と手首の切断に加えて、胸から腹部にかけてもお大きく切開されていたとも報道されています。
(補足:4/30の報道によれば「ネコを解剖したことがあり、人間でもやってみたかった」と供述)
長崎・佐世保市で、高校1年生の女子生徒が同級生を殺害した事件で、逮捕された少女は「人を解剖してみたかった」と供述しており、遺体の腹部には切られた跡が残されていた。
出典:佐世保同級生殺害 遺体の腹部には切られた跡 フジテレビ系(FNN) 7月29日
この供述から思い出す事件は、2007年に発生した、高校3年生の男子による、会津若松頭部切断母親殺害事件があります。
この少年も優等生でした。
彼は供述しています。
「もっと(母親の遺体を)バラバラにするつもりだったが、ノコギリで切断する音が大きく、(同居の)弟に気づかれると思ってやめた」
「死体を切断して飾ってみたかった」
「グロテスクなものが好きだ」
「母親は好きでも嫌いでもない。恨みはない」
「(殺害するのは)弟でも良かったが、たまたま母親が泊まりに来た」
「遺体を切断してみたかった。だから殺した。だれでもよかった」
「誰でもいいから殺そうと考えていた」
「戦争やテロが起きないかなと思っていた」
この少年は、「比較的軽度な精神障害」があり「障害に対する充分な治療とともに、長時間継続的な教育を施す必要がある。その過程で真の反省を促し、更生させることが望ましい」とされ、医療少年院送致となりました。
家裁は、少年を次のように表現しています。
「少年は障害により、高い知能水準に比して内面の未熟さ、限局された興味へこだわる傾向、情性の希薄さ、他者への共感性が乏しいなどの特質があり、自分の劣等感を刺激されると不満などを蓄積する傾向がある。」
今回の事件の少女も、これまでの事件で「殺してみたかった」「バラバラにしたかった」と語った加害者少年達と、似たような特徴を持っていたのかもしれません。
■小学校時代の給食薬物混入事件
今回の佐世保高1女子殺害事件の容疑者女生徒は、小学校時代にクラスメイト複数の給食に複数回「漂白剤」を入れるという事件を起こしています。
そのときの動機は、報道されていないのでわかりません。
その同級生に対する怒りや恨みがあったのかもしれません。
あるいは、「毒を入れてみたかった」「毒を飲むとどうなるか、観察してみたかった」のかもしれません。
2005年に、静岡で高校1年の女子生徒によるタリウム母親毒殺未遂事件が起きています。
彼女も優等生です。県内でも有数の進学校に通い、化学部に所属していました。
この女生徒は、母親に毒物であるタリウムを与えながら、ネット上のブログで犯行の経緯を日記風に記録していました。内容は、事実と創作が混ざっていたようです。
母親との間に特別な確執はなく、母親のことを、「好きでも嫌いでもない」と語っています。
この事件も、「少女は幼児期から発達上の問題があり、人格のゆがみも認められる」とされ、医療少年院送致となりました。
類似事件で世界的に有名なのが、家族や友人を殺して記録をとっていた「グレアム・ヤング連続毒殺事件」であり、映画化もされています(「グレアムヤング毒殺日記」)。
■なぜ友人を殺害したのか
今回の事件の被害者は、容疑者の友人です。自宅に1人で遊びにくるような関係です。なぜ、この友人を殺害し、遺体を傷つけたのでしょうか。
可能性は、いろいろ考えられます。
・激しい争いがあった。
・激しい争いはなかったが、逆恨みした。
・争いはなかったが、大切な友人だからこそ、何かの理由で裏切られたと感じて絶望して殺害した。
・トラブルは何もなく、嫌いでもなかったが、好きでもなく、身近にいたので、殺してバラバラにした。
上記で紹介した事件も、誰でもいいから殺したかったと語り、そして家族や友人を殺害しています。
■容疑者少女の病理性:事件はなぜ起きたか
事件の背景として、彼女には、何らかの発達上の障害や、パーソナリティーの障害があったのかもしれません。
その彼女の中に、異常な空想が広がっていったのでしょう。人を殺すこと、そして遺体を解剖しバラバラにすることへの欲求が強くなっていったのでしょう。それは、一般の人には理解できない異常な好奇心です。その悪魔のような欲求を、彼女は、小動物の解剖などをしながら何とか抑えていたのかもしれません。
しかし、やさしかったお母さんが亡くなります。家庭環境が大きく変わります。その結果、ぎりぎりのところで保たれていた心のバランスが崩れてしまったのかもしれません。
神戸の酒鬼薔薇事件でも、やさしかったおばあちゃんがなくなった後、彼はネコ殺しを始め、ついに殺人に至いたり、幼児を殺害して遺体を切断する事件を起こしています。
■命を大切にする教育の限界と私たちの課題
佐世保市、長崎市では、10年前にも、子どもが子どもを殺す事件が起きています(2003年:長崎男児誘拐殺人事件・2004年:佐世保小6女児殺害事件)。
佐世保市長崎市で、長崎県全体で、10年前の事件以来、命を大切にする教育が行われてきました。これらの教育は、もちろん意味があったと思います。しかし、10年前の事件も、今回の事件も、酒鬼薔薇事件なども、病理性の高い加害者による事件です。
この病理性は、道徳教育によって改善するようなものではありません。一般の学校教育、家庭教育では、なかなか防止できないものでしょう。とても難しいのですが、給食異物混入事件など子どもの頃にトラブルを起こしたとき、それを一つのサインとしてとらえ、心理的、精神医学的な個別対応がもっとできていたらと思います。
そして、問題を抱えている少年達が犯罪を実行しないですむ、環境づくりでしょう。
今回の事件でも、学校を欠席しがちで一人暮らしの女子生徒の部屋を、先生方が定期的に訪問していました。関係者は努力していました。それでも事件は起きてしまいました。
ただ、もしも大好きなお母さんが生きていて、以前と変わらぬ家庭環境が続いていれば、今回の殺人事件は起きていなかったかもしれません。
彼女も家庭のことで悩んでいたでしょう。自分の心のゆがみのことでも、悩んでいたかもしれません。思春期、青年期の自分探しに失敗したのかもしれません。
犯罪への特効薬はありません。重い刑罰も、今回のように逃亡を考えていない加害者にはあまり効果がないでしょう。
それでも、愛されている環境、愛を実感できる人間関係、やりがいのある学校生活や仕事、楽しい趣味など。これらの「社会的絆」が、どんな場合も犯罪防止につながるでしょう。
今回の女生徒も、医療少年院送致になるかもしれません。犯罪を犯したのですから、制裁を受けるのは当然です。そしていずれ、社会に戻ってきます。心理的、医学的治療を施し、真に反省させるとともに、再犯を防止するためにも、社会的絆が必要です。
事件は起きてしまいました。
私たちが考えるべき事は、被害者の冥福を祈るとともに、被害者側の人々の保護と支援、学校の生徒たちなど傷ついている関係者の保護と支援、そして類似犯罪の防止に努力する事ではないでしょうか。
子どもを犯罪被害から守りましょう(犯罪から子どもを守ろう:岡山誘拐監禁事件から)。
子どもが加害者にならないように努力しましょう。
それは、トラブルが起きたときに、ただ穏便にすますことではありません(「子どもを守る」の本当の意味は?:心理学者が伝える正しい子どもの「傷つけ方」)。
そして、事件の教訓を生かし、少しでも光り輝く社会を作っていきたいと思います。
(加筆:7/29,22:35)
~~~~~~~~~~~~~
犯罪防止
長崎・佐世保高1女子同級生殺害事件の犯罪心理学:教訓はなぜ生かされなかったか(事件の第一報を聞いて)
有能な加害者の心理
有能な人が人生で失敗するとき:犯罪・非行・不適応:大学院出身の岡山倉敷女児誘拐監禁事件容疑者・進学校の殺人者
被害者保護
ネットと世間に流れる「少女はなぜ逃げなかったか」に答える:岡山小5少女誘拐監禁事件被害者保護のために
~~~~~~~~~~~~~
『なぜ少年は犯罪に走ったのか』碓井真史著 ワニのNEW新書
17歳愛知体験殺人・17歳佐賀バスジャック事件・15歳大分一家6人殺傷事件など
『誰でも良いから殺したかった:追いつめられた青少年の心理』碓井真史著 KKベストセラーズ
秋葉原通り魔事件を中心に
「当時の市教委幹部は取材に『できる限りのことをしたつもりだが、これだけの事件が起きてしまった。もっと何かできなかったのかとの思いがあり悔しい。でも、何をすればよかったのかわからない』と話した。」
どのような規制が問題になって、出来る限りの事は何だったのか?何すればよかったのか市教委幹部はわかっていない。何をすればよかったのか分からないのに出来るが気の事をしたとのコメントはおかしくないか?何をすれば良いのか分からなかったのなら、なぜ専門家に相談したり、市教委のレベルでは何をすればよいのかわからないことを認め、県教委や厚労省に報告するべきではなかったのか?つまり、出来る事はあったが出来るだけの事はしたと勝手に決め付けた市教委に問題があった事は明確だ。
4年前、同級生の給食に有害物質 高1殺害容疑の少女 07/29/14 (朝日新聞)
長崎県佐世保市で県立高校1年の女子生徒(15)を殺害したとして殺人容疑で逮捕された同級生の少女(16)が4年前、小学校のクラスメートの給食に、ベンジンなどの有害物質を複数回、混入していたことが佐世保市教育委員会などへの取材でわかった。専門家は「このときの対応次第で、その後の展開が変わった可能性がある」と指摘する。
県警もこの情報を把握しており、今回の殺害事件での、少女の犯行動機などを解明するうえで背景事情として関心を寄せている。
市教委などによると、2010年12月初旬、小学6年生だった少女は、クラスメート2人の給食に5回にわたり、それぞれ水、ベンジン、漂白剤、粉末洗剤2種類の水溶液0・3ミリリットル程度を混ぜた。「一緒にやらない」と、ほかの児童を誘うこともあり、クラスでは公然のことだったという。
同月中旬に、被害を受けた男児が担任に報告して発覚。少女への聞き取りで、男児の給食に1回、女児に4回、異物を混ぜていたことが判明した。少女は当時、「勉強していたことをばかにされたのでやった」と話したという。
市教委は、少女と両親を指導。少女と両親は被害児童の親に謝罪し、最終的に和解したという。その後、市教委はカウンセラーを配置し、少女や、関係した児童や親、教職員らに計15回のカウンセリングをした。
市教委は、事案を報告書にまとめて長崎県教委に報告し、小学校には、少女や被害児童が進学する中学校に報告するよう伝えた。県教委は29日の会見で当時の対応について「具体的な対応は学校や市教委に任せていた」と説明した。
当時の市教委幹部は取材に「できる限りのことをしたつもりだが、これだけの事件が起きてしまった。もっと何かできなかったのかとの思いがあり悔しい。でも、何をすればよかったのかわからない」と話した。
少女は今回の殺害事件の動機について、「人を殺してみたかった」という趣旨の話をしているという。
少年事件の事例研究を長年続けてきた広木克行・神戸大名誉教授(教育学)は、少女が小学6年のときの異物混入の事案を「見逃せない出来事」と指摘。当時の学校や教師らの対応について、「少女に謝罪させるだけで終わったのか、行動の背後にある心理や精神、生活にも目を向けられたのか。いまある情報から言うと、『なぜそういった行動をとったのか』を多面的に見る目が欠けていたのではないか」と話す。
今回の事件は、殺し方や殺した後の対応も映画に出来るほどショッキングだ。切断した部分の写真までアップしている。多くの人が興味を持つだろう。
加害女子高生の写真が佐世保市HPなどから削除 ネット上で疑問の声が相次ぐ (1/2)
(2/2) 07/29/14 ( J-CASTニュース)
長崎県佐世保市の殺人事件で、加害者の女子高生(16)の写真が市のホームページなどから次々削除されたとして、騒ぎになっている。この生徒は、父親と一緒に国体に出場するなど、地元では有名だったというのだ。
県立高校1年の同級生(15)を殺したとして逮捕された生徒は、両親が地元の名士だったこともあって、ネット上で実名などが次々に特定された。
「加害者だけ隠すのはおかしい」との意見も
そんな中で、生徒と父親は、栃木県で2014年1月に開かれた冬季国体のある競技に長崎県代表として出場していたことも分かった。
佐世保市のホームページでは、当時中学3年生だった生徒が親子で出場していたとして、2人のツーショット写真も載せて紹介していた。父親と兄の影響で競技を始め、国体ではトップバッターとして出場するなどと書かれてあった。また、長崎県のホームページでも、国体の壮行会で県の団旗を持った生徒や本番で競技に臨む親子の様子を写真付きで載せていた。
ところが、7月27日に生徒の緊急逮捕が報じられた後、佐世保市や長崎県のホームページから2人の情報が次々に削除されてしまった。
また、父親は、フェイスブックに娘のことを書き込み、11年6月21日の父の日には、ケーキをプレゼントされたことを2人のツーショット写真を載せて報告していた。士業を営んでいる事務所のホームページには、国体に出場した競技のことなどの自己紹介をしていた。しかし、生徒の逮捕後は、フェイスブックが閉鎖され、事務所ホームページも工事中の表記になっている。
こうした動きに対し、ネット上では、いくら未成年だとはいえ、被害生徒の情報はたくさん報じられているのに、加害者だけ隠すのはおかしいと疑問の声が上がった。父親が地元の名士だけに、根拠のない憶測が次々に流されるまでになっている。
「加害生徒に配慮して削除したわけではない」
ホームページから加害生徒らの情報を削除したことについて、佐世保市の国体推進室では、生徒に配慮して削除したわけではないと取材に説明した。
「長崎県で10月に開かれる国体の選手紹介コーナーですので、そこで行う競技でないものは、6か月を過ぎると削除しています。ご指摘の競技についても、1月27日に情報をアップしましたので、7月27日に自動的に削除しました」
生徒逮捕の後に、削除依頼が来たこともないという。6か月が過ぎていない場合については、削除するかは国体佐世保市実行委が判断することだとしている。
また、長崎県教委でも、取材に対し、生徒に配慮して削除したことを否定した。
「ホームページにアクセスが殺到して、サーバーのアラームがずっと鳴る状態でした。ほかのシステムに影響が出る可能性がありましたので、削除しました。影響がなければ、削除する理由がないと考えています」
削除依頼もなかったといい、「圧力がかかったということはありません」と言っている。
加害生徒の父親の事務所では、取材に応対したスタッフが「今回のことについては、何も聞いていません。事務所としても、何もお答えすることはないです」と話した。
もっとも、削除したとしても、ネット上では、すでに生徒や父親の実名や写真などの情報がコピペされるなどして大量に拡散しており、そのことを問題視する声もある。
例えが悪いかもしれないが、身代り試験でも、裏口入学でも本人が卒業出来たら早稲田大学は問題ないと言う事になるのか?だって学位や卒業が取り消しになれば、「生活の基盤、社会的関係を破壊する」するのは間違いない。
小保方氏の博士論文に早稲田大「不正は故意ではない」と判断 07/29/14 (NEWSポストセブン)
理化学研究所の小保方晴子・ユニットリーダーが書いた博士論文に数々の不正が指摘されたことについて、学位を与えた早稲田大学は調査委員会を設置し、このほど報告書の全文を公開した。
改めて、小保方氏のいい加減さが証明された。論文の第一章は80%が剽窃(パクリ)であり、画像、イラストの剽窃も多数見つかった。なんと参考文献のリストすら別の論文からコピーしていた。
その他、画像があるのに説明文がない、意味不明の用語が使われている、論旨不明箇所が多数、実験手続の記載なし、誤字脱字が42か所などと指摘され、さすがに報告書も「合格に値しない論文」と結論づけた。
小保方氏について、「博士学位を授与されるべき人物に値しない」と断じたのは、当然で正しい結論だろう。
ところが、である。同報告書はそれでも学位剥奪はできないとした。小保方氏が調査委に対し、「この論文は草稿段階のものを間違って製本したもので、ちゃんとした本物は別にあった」と主張したことを事実と認定し、「不正はあったが故意ではない」という判断を下したのである。
百歩譲って、小保方氏が「こっちが本物」と提出した論文が当時作られたものだ(今回の騒動後に捏造したものではない)としても、その論文にも剽窃が多数ある。報告書もそれらを著作権法違反と認定している。
違法行為を犯してインチキ論文を提出して学位を取り、「私は工学博士」と名乗って大金を得てきたことが、「不注意なミス」で許されるのか。
報告書では寛大な処分を下す理屈として、学位を剥奪すれば小保方氏の「生活の基盤、社会的関係を破壊する」からだと主張するのだが、不正に対して認識が甘すぎる。
※週刊ポスト2014年8月8日
「NHKスペシャル」の情報が正しいのであればSTAP細胞はほぼ無いと思えるのだが、なぜ理化学研究所は実験を続けるのか?
小保方氏ケガの発端 「NHKスペシャル」識者はこう見た 07/29/14 (日刊ゲンダイ)
NHKの記者らが理研の小保方晴子氏(31)に全治2週間のケガを負わせ、図らずも放送前から世間の注目を集めた「NHKスペシャル」。取材対象者に対して強引な追跡取材をした揚げ句、負傷させてしまうという由々しき事態を引き起こしたが、負傷事故からわずか4日後の27日夜、NHKはNスペの放送に踏み切った。「少し前まで次週放送予定の知床のヒグマの生態に迫った番組を放送する予定だった」(関係者)ところ、放送日を繰り上げたのはテレビ局として話題性を重視した結果であろう。
番組HPの告知では「史上空前と言われる論文の捏造」「執筆者の小保方晴子研究ユニットリーダーは徹底抗戦」といった文言を並べ、最終的に「調査報告 STAP細胞 不正の深層」と強気かつ過激なタイトルを打った。小保方氏には謝罪済みで事故当日のVTRは流さないとしながらも、ハナから不正と決めつけてかかった番組だ。
その中身はSTAP騒動を巡るこれまでの報道を丁寧に総括。そこに今回Nスペが独自に取材をした上で明らかになった「新要素3点」を組み入れた構成だった。その要素とは――小保方氏のSTAP論文で理研の調査委員会が不正画像と認定したのは2つとの指摘だったが、Nスペが依頼した有識者らによると全140の画像のうち7割で疑義が生じたり不自然であったこと。その論文を掲載したネイチャー誌編集長がカメラの前で取材に応じたこと。そして、小保方研究室の冷蔵庫から発見された「ES細胞」を作製した元留学生の存在を突き止め、本人に電話取材したことだ。
「私が直接(小保方氏に)渡したものではない」と話す元留学生の言葉のあと、「私たちは小保方氏にこうした疑問に対し答えて欲しい」というナレーションは、結果的に“暴走取材”に至った言い訳にもとれたが……。上智大教授の碓井広義氏(メディア論)が言う。
「調査報告と題し、番組最後のクレジットもプロデューサーほか制作者個人の名前も記さなかったことからも、あくまで報道番組として手がけたであろう制作陣の意図を感じます。ただし『不正の深層』と加えることで、NHKの旗幟を鮮明にした。笹井芳樹教授の存在にフォーカスした視点で展開することで、当初は複数の科学誌から掲載を却下されていた論文の変貌を視聴者が理解しやすいようにもなっていた。負傷事故はあるまじき失態ですが、速力のある番組がつくれるのは国内ではNHKをおいて他にはない。取材を蓄積し続報を期待したい」
小保方氏が口を開く日は来るのか。
精神鑑定とか言うけど、計画的だし、小動物の解剖を繰り返すなどしていたのなら、解剖を行わない人達に比べるとそれほど精神的におかしくなかったのではないのか?
解剖した小動物が生き返らない事は過去の例から理解していたろうから、他のサイトで書かれていたように生き返ると考えていないだろう。
光市母子殺害事件のような「生き返ってほしいという思いから強姦した」との言い訳はないと思うが、アメリカのようにとにかく精神的異常である事を主張し、無罪を求めるのだろうか?
NHKで2004年に佐世保の小学生が同級生を殺害してから特別な教育を教育委員会主導で行っていたと放送していたのを見たが、効果はあったのだろうか?少なくとも今回のケースでは効果は全くなかったと思う。
「殺すため自室に行った。自分から誘った」周到準備、計画的か 07/29/14 (産経新聞)
長崎県佐世保市の高校1年の女子生徒(15)が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された同級生の少女(16)が「殺すために自分の部屋に2人で行った」と供述していることが29日、捜査関係者への取材で分かった。
県警によると、2人は約1週間前から遊ぶ約束をしていた。少女は「会いたいと自分から誘った」と供述した。遺体のそばからハンマーやのこぎりが押収され、「自分で買った」と供述していることも既に判明。県警は、少女が周到に事前準備の上で自室に招き入れた、計画的な事件の可能性が高いとみて捜査している。
県警によると、殺害された女子生徒は26日午後3時ごろに自宅を出てから5時間後に部屋で殺害されたとみられる。この間の状況について、少女は「一緒に市内で買い物をした」と説明しており、県警は防犯カメラの映像などを調べて詳しい足取りの解明を進めている。
捜査関係者によると、遺体は、首や左手首が切断されていた以外に腹部が大きく切り開かれていた。過去に小動物を解剖したこともあるといい、県警は松尾さんを殺害後に遺体を解剖しようとした可能性があるとみて、少女の精神鑑定を求める方針。
加害者の父親は弁護士だそうだ。ニュースで精神鑑定とか言っていたから何でそんなに対応が早いのかと思っていた。勉強は重要だと思うけど、全てではないと考えさせられる事件。勉強が出来るから人間的にりっぱであるかは別問題。しかし出世した人間やお金を手にした人間が勝者と見られる現実。
松尾愛和さん事件犯行理由は父への復讐か!? 07/29/14 (ニュースニュースニュース!!)
松尾愛和さん殺害の女子高生 小学生から殺人予告 佐世保 07/28/14 (ニュースニュースニュース!!)
加害者の家庭環境
以下の情報はネット上の情報を元にしたもので、真実の可能性が極めて高いものの、
事実誤認や、第三者の創作の可能性はゼロではありません。
新聞やテレビ報道によると、
殺害現場は長崎県佐世保市島瀬町のマンション一室で、2人は同市祇園町の県立高校
(長崎県立佐世保北高等学校)通称北高の1年の同級生だった。
北高は毎年東大など有名校に合格者を出す名門の進学校だった。
捜査関係者によると、女子生徒は過去に小動物の解剖を繰り返すなどの問題行動があった。
殺害されたのは松尾愛和(あいわ)さん(15)で、父の職業は弁護士。
一方加害者の父の職業も弁護士で、愛和さんが帰宅しなかったとき、母親が加害者の
親に電話していることから、親同士が知り合いだったと考えられます。
被害者の父、加害者の父ともに自分の名前を冠した弁護士事務所を、長崎市内の
近所で経営していました。
娘2人は中学から同級生だったので、親子とも数年来の付き合いはあったと思われる。
加害者の母親は長崎県スケート連盟会長で、佐世保市教育委員を務めたが、半年前に
急死しています。
市民運動家として熱心に活動していたらしく、長崎の活動記録や表彰が残っている。
佐世保市の教育を考える市民会議
第2回議事録
「今は、佐世保の中心部に住んでおりまして、3歳の女の子と小学校2年になる
男の子の母親でございます。」
2001年11月に3歳の女の子は、現在15歳の筈で子供の年齢が一致しています。
教育委員だった頃の母親の発言
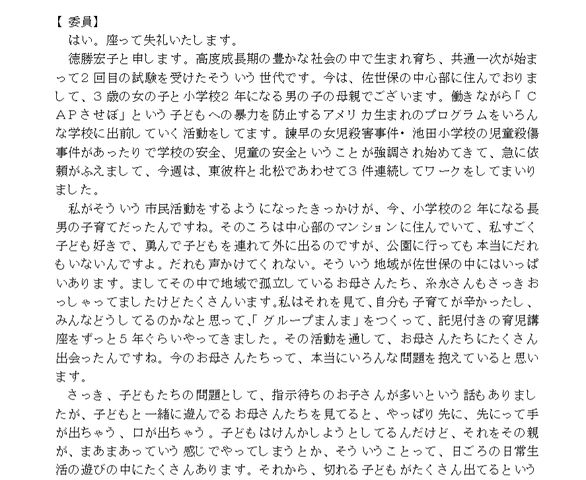
小学生のときに殺害予告
同級生などによると、加害者は小学6年のときに給食に異物を混入する事件を起こしている。
その時、弁護士の父や、教育委員だった母が学校へ乗り込んできて抗議したため、
異物混入事件は報道されることも警察ざたにもならず、外部に漏れないように処理された。
この時だけではなく、加害者の両親のモンスターぶりは地域では有名であり、加害者の兄
の学校に乗り込んでは、学校の経営方針にまで口出ししていたという。
つまり加害者兄妹はどんな問題行動を起こしても、モンスター両親が学校や相手の家に
怒鳴り込んで、むしろ被害者や学校を脅したりするのが日常的になっていたようです。
これらは地元の人や元同級生を名乗るネット上の情報です。
小学校の給食に異物を混ぜたときに、混入するのを男子生徒に見られて発覚した。
加害者の少女は「ぶっ殺してやる!」とか「殺してやりたい」と言っていたという。
それが12歳のときで、3年後に(別な同級生を)本当に殺した事になります。
両親がもみ消さず、学校も弁護士や教育委員の圧力に屈しないで厳しい処分をしていたら、
今度の殺人は起きなかったのではないか?
モンスター親によって問題を起こしても罰を受けずに育った。
罪悪感を感じず、価値観の歪んだ子にした両親の罪は非常に重い。
殺人くらい犯しかねない人格に育ってしまうのは、予見できた気がします。
下記の記事を誰が書いたのか知らないが、「秋葉原連続通り魔事件」を検索したら下記の記事を見つけた。
独占スクープ!「秋葉原連続通り魔事件」そして犯人(加藤智大被告)の弟は自殺した 兄は人殺し、その家族として生きていくことは苦痛そのものだった……(現代ビジネス)
記事を読むと程度の差はあるが、両親にも責任があると思った。弟は被害者であると思うが、村社会である日本社会の悪い部分と良い部分を否定しても何も始まらない。村社会が日本社会の基本であるからだ。原発村が村社会の一例。彼らは田舎に住んでいるわけではない。しかし、原発村の住人である。原発村が存在するからこそ、その中で上手くやれば対価が得られるのである。村社会には、表と裏がある。表から転げ落ちれば裏しかない。それだけである。
長崎佐世保女子高生殺害事件、徳勝 兄 名前 まなみ 動機 丈 (芸能人の離婚話)
ここまで検索した人は、しっているでしょう。
彼の立場を。
佐世保北高校出身
早稲田大学法学部
2011年全国模試20位以内
何があろうと、彼の努力、実力は揺るがない。
彼は世界の宝である。
彼の周辺の人間は全力で彼を支えて下さい。
海外へ出してもいい。
時間を置くべきだ。
兄として、きっと逃げないだろう。
しかし、残忍な事件は、周辺への影響が大きすぎる。
秋葉原の事件の際は、優秀な兄弟まで失ってしまった。
半年だけでもいいので、彼を現実から自由にしてあげてほしい。
父親が最後にできることだと思う。
理路整然・素直…少女の心に何があったのか 07/29/14 (読売新聞)
長崎県佐世保市の県立高校1年の女子生徒(15)を殺害したとして、殺人容疑で逮捕された同級生の少女(16)は、成績が良く、スポーツに熱心な一面もあり、事件の凄惨(せいさん)さとの落差は大きい。
警察の取り調べに「理路整然と素直に答えている」という少女の心に何があったのか。
27日午前3時すぎ、県警の捜査員が少女のマンションを訪れ、女子生徒の居所を尋ねた。少女は「知らんけど」と答えたが、捜査員が部屋に入ると、ベッドの上に女子生徒の遺体があった。少女の服に血痕は付着しておらず、血の付いた服を着替えていたとみられる。
市などによると、少女は成績が良く、複数の習い事もしていた。小学4年の頃から家族の影響でスポーツに励み、大会で活躍したこともあった。
一方で、小学6年だった2010年12月上旬、2人の児童の給食に5回にわたって粉末洗剤やベンジン、漂白剤などをスポイトで入れるトラブルを起こした。担任が調べたところ、少女は「勉強していることを小ばかにされ、不満を持っていた」などと認め、少女と両親が被害者に謝罪した。小学校の関係者によると、少女は突然、大声を出すこともあり、少女と距離を置く同級生も多かったという。
「誰もがうらやむ」名士一家、母の死後、少女の生活激変 「頭よすぎ変わってる」 (1/2)
(2/2) 07/28/14 (産経新聞)
長崎県佐世保市の高校1年、松尾愛和(あいわ)さん(15)が殺害された事件で、遺体の胴体にも激しく傷つけられた痕があったことが28日、長崎県警への取材で分かった。殺人容疑で逮捕された同級生の少女(16)は周囲から「文武両道で多才」と評価される一方、「暗く、変わった子」とも見られていた。昨年秋に母親が亡くなって以降、生活が激変していたといい、県警は事件に至った背景も含め、慎重に調べを進める。
捜査関係者によると、女子生徒の遺体は首などが切断されていただけでなく、胴体にも切断しようとした痕があった。司法解剖の結果、死因は窒息で26日午後8~10時に死亡したとみられる。
学校関係者によると、少女をめぐる環境は最近1年間で激変。仲が良かった母は昨年10月に他界。冬季に父親とともに年代別の全国規模のスポーツ大会に出場した際は「母のためにもがんばる」と話していたという。少女は母の死に際して感情を表に出すことはなかったが、落ち込んでいる様子だった。父親はその後再婚した。
事件現場となったマンションで1人暮らしを始めたのは今年4月。大通りに面し、父親の職場に近く、学校へも徒歩圏。「アニメ好き」が共通点だったという女子生徒の自宅とは徒歩で10分ほどの距離だった。少女は9月から海外留学する予定で、自ら1人暮らしを希望。父親は「留学の練習」ということで許可したという。
一方、幼少期から少女を知る女性は「あまり笑わない。頭が良すぎるのか、少し変わっていた」とも。進学校に通い、父親の影響で始めたスポーツだけでなく、芸術的な才能にも恵まれていた。父親は地元で顔が広く、関係者は「誰もがうらやむような名士の一家」と話す。
ただ、学校関係者によると、少女は小学生時代に同級生の給食に異物を混ぜる問題行動を起こしていた。中学校では小動物の解剖に夢中になっているという噂が広まり、「少し浮いた感じになっていた」という。
県警は28日午後、少女を長崎地検佐世保支部に送検する。14歳以上の未成年者が逮捕されると通常、送検後に勾留され、地検が家裁送致し家裁が処分を判断。故意に人を死亡させた事件では検察官送致(逆送)もある。責任能力が争点となることが想定される事件では、地検は家裁送致前に数カ月間、鑑定留置をするケースが少なくない。
女子高生殺害犯はマンションで1人暮らし 父親は地域の名士で、裕福な環境で育った 07/28/14 (読売新聞)
長崎県佐世保市内の県立高校に通っていた松尾愛和(あいわ)さん(15)が同級生の女子生徒(同)に殺害された事件では、松尾さんも加害者の生徒も同じ中学校・高校に通っており、その学校は地域では有数の進学校だ。
松尾さんも加害者も、父親は国家資格が必要ないわゆる「士業」を市内で営む同業者だ。特に加害者親子はスポーツの分野でも有名で、著名な大会にも親子そろって出場するほど。加害者は裕福で、恵まれた環境に育ったように見えるが、どうして凶行に走ってしまったのか。
高校で1人暮らしをしていたのは加害者だけ
松尾さんが殺害されたのは、加害者が一人暮らしをしている市内の自宅マンション。2人が通っている高校の校長が2014年7月27日に会見して明らかにしたところによると、両親で離れて一人暮らししているのは加害者だけだった。加害者のマンションと実家はあまり離れておらず、加害者の家庭に経済的に余裕があったことをうかがわせる。
さらに、加害者の両親は総じて教育熱心だったようだ。ウェブサイトに公開されていた加害者の父親のプロフィールによると、被害者と加害者が通っていた学校でPTAの役員を務めていた時期もある。
加害者の母親は13年10月にがんで死去している。母親の訃報ではスポーツ団体の長崎県のトップや、佐世保市の教育委員を歴任したことが報じられており、地域への貢献も大きかったようだ。加害者と父親は14年1月に栃木県で開かれた冬季国体にも長崎県代表として出場。長崎新聞には「亡き妻への思い胸に 『集大成の大会』」と題した記事も掲載された。
ただ、加害者の父親はすでに再婚している。そのため、加害者が再婚相手との同居に難色を示した末の一人暮らしだとの見方も出ている。
加害者本人も多才だったようで、14年2月には、美術作品展の版画部門で県知事賞を受賞してもいる。
インターネットや2ちゃんの情報の信頼性は疑問だがいろいろな情報がアップされている。臨床心理士は新聞だけの情報でなく新聞には載らない情報も考慮して判断してほしい。情報のどこまでが事実なのか確認出来る能力はないが、背景にはもっといろいろなものがあり、隠されたものがあるように思える。昔、アメリカで幸せそうに見えるエリート家族は異常であるのが普通である内容の本が出版されたのを思えている。つまり、エリートである両親や祖父母の期待がゆえに、良い子である事を強制され、文武両道の期待に押しつぶされる子供が多いらしい。自殺、薬物依存、自暴自棄や非行などがあるが家族が体裁を保つために公にはならない。問題の無い人間のほうが少ないのに完璧な家族のイメージを保つ努力等が記載されている。記憶が正しければ著者はエリート家族の子供として生まれ育った女性だ。今回の事件でどこまでの情報が出てくるのだろうか?
「母の死から生命の不確かさ意識」「好奇心から遺体切断か」専門家ら分析 07/28/14 (産経新聞)
クラスメートの殺害容疑で逮捕、送検された長崎県佐世保市の高校1年の女子生徒(16)は、「遺体をバラバラにすることに関心があった」という趣旨の供述をするなど、その犯行動機や行動に解明すべき点が多い。心理学の専門家らは、どのような分析をするのか。
東洋大学社会学部の桐生正幸教授(54)=犯罪心理学=は「思春期特有の揺れ動く精神状態の中で、母親の死に接し、人の死や生命の不確かさのようなものを強く意識したのではないか。そこから、興味が生じて調べてみたいという感情が高まり、行動に出てしまった可能性がある」と指摘する。桐生教授は「こういった犯罪では、人間関係が出来上がり自分を信用してくれる人を対象にすることが多い。だから親しい友人をターゲットにしたと考えられる」とも語り、「今後、精神科医の元で父親や友人との関係など成育環境を調べる必要がある」と話す。
一方、臨床心理士の長谷川博一氏(55)は「女子生徒は、母親との死別や父親の再婚で慢性的な孤独感を味わっていた。仲の良い家族のいる同級生への嫉妬が殺害の背景にあったのかもしれない」として、「小動物の解剖をしていた過去を踏まえると人の体の解剖にも興味があって、残虐なことが好きというより、好奇心から遺体を切断したと考えられる」と分析する。また「これまでに謝罪の言葉がないことから、知的レベルは高いが、情緒的に他人に共感する力が未発達で、同級生の苦しみやその家族の悲しみが理解できていない可能性がある」とも話している。
告白する本当の理由はわからないが、実名で顔まで出して証言する勇気はすごい。年齢や関係者が既に死亡している背景も証言出来た理由の一つと考えられる。
この世の中、公にならない話があることは理解できる。まあ、こんな事だから東電は現在も存在できるのだろうと強く思う。
関電、歴代首相7人に年2千万円献金 元副社長が証言 07/28/14 (朝日新聞)

関西電力で政界工作を長年担った内藤千百里(ちもり)・元副社長(91)が朝日新聞の取材に応じ、少なくとも1972年から18年間、在任中の歴代首相7人に「盆暮れに1千万円ずつ献金してきた」と証言した。政界全体に配った資金は年間数億円に上ったという。原発政策の推進や電力会社の発展が目的で、「原資はすべて電気料金だった」と語った。多額の電力マネーを政権中枢に流し込んできた歴史を当事者が実名で明らかにした。
金を渡すと角さんは「頂いたよ」
関電からの2千万円 元首相側「初耳」「わからない」
内藤氏が献金したと証言した7人は、田中角栄、三木武夫、福田赳夫、大平正芳、鈴木善幸、中曽根康弘、竹下登の各元首相(中曽根氏以外は故人)。
内藤氏は47年に京大経済学部を卒業し、関電前身の関西配電に入社。62年に芦原(あしはら)義重社長(故人)の秘書になり、政財界とのパイプ役を約30年間務めた。関電の原発依存度は震災前は5割を超え業界でも高く、原発導入を円滑に進めるには政界工作が重要だったという。
内藤氏は2013年12月から今年7月にかけて69時間取材に応じ、11年3月の東京電力福島第一原発の事故について「政府の対応はけしからん」「長年築いてきた政・官・電力の関係に問題があった」と指摘した上、多額の政治献金を電気料金で賄ってきた関電の歴史を詳細に語った。
海外に逃亡していたのにどうやって入国出来たのか??偽名や偽造パスポートでも使用したのか?なぜ出頭したのか?
ローラさんの父親逮捕 海外治療費詐取の疑い 07/27/14 (産経新聞)
知人がバングラデシュで診療を受けたと偽り、海外治療費約87万円をだまし取ったとして、警視庁は27日までに詐欺の疑いで、タレントのローラさんの父親、ジュリップ・エイエスエイ・アル容疑者(54)を逮捕した。
逮捕容疑は、2008年12月~09年1月、バングラデシュの病院で知人が診療を受けたとする虚偽の診療内容明細書などを、東京都世田谷区役所に提出して、海外療養費を振り込ませた疑い。
警視庁はジュリップ容疑者の逮捕状を取り、国際手配していた。同容疑者が杉並署に出頭したため、26日に逮捕した。
製薬会社ノバルティスファーマが一番悪いが病院側の体質にも問題があったと思う。
降圧剤問題:奨学寄付、企業名公開を…国立大病院側に要請 07/26/14 (毎日新聞)
文部科学省大学病院支援室は25日、企業から奨学寄付金を提供されている国立大の付属病院に対し、提供元の企業名の情報公開を徹底するよう要請した。45病院が加盟する国立大病院長会議の担当者は取材に対し「要請を重く受け止め、前向きに検討する」と話した。
降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験を巡るデータ改ざん事件では、製薬会社ノバルティスファーマが臨床試験をした5大学に計11億円超を提供。ところが論文に寄付金を受領したことや額の記載がなかったり、問題表面化後も大学側が情報をなかなか明らかにしなかったりして、社会の不信感を高めた。
この日の閣議後の記者会見で、下村博文文科相は「大学が奨学寄付金を適切に情報公開することは、社会的信頼を保持するための重要な手段」と指摘。その上で「企業との関係について社会的信頼を損なわないよう、企業名を含めた一層の情報公開が必要だ」と述べた。
国立大病院長会議は6月、企業から研究者に提供された講師謝礼や受託研究費などの資金の公表に関する指針をまとめた。しかし奨学寄付金については、公表するのは診療科ごとの件数と総額にとどめ、寄付元は企業への配慮から控えることにしていた。
奨学寄付金は、企業や個人が大学などを通じて研究者側に提供する寄付金。2012年度は製薬業界だけで計346億円に上る。【河内敏康】
もっと前に声明を出すべきだった。早稲田大調査委員会の報告を含め科学とは何なのかを考えさせるほどの茶番だ。
小保方氏懲戒、実験終了前でも検討を…学術会議 07/25/14 (読売新聞)
日本学術会議は25日、STAP(スタップ)細胞の論文問題について、理化学研究所に対して速やかな不正の解明と関係者の処分を求める声明を発表した。
理研は現在、STAP細胞の有無を確かめるため、小保方晴子ユニットリーダーが参加した検証実験を進めている。大西隆会長は記者会見で、「実験と懲戒処分は切り分けて考えるべきだ」と話し、実験が終わる前でも、小保方氏らの懲戒処分について検討を進めるべきだとの考えを示した。
声明では、STAP細胞論文に次々と疑義が出ている状況から、「研究全体が虚構だったのではという疑念を禁じ得ない段階に達している」と指摘。理研に対し、保存されている細胞などを速やかに調査し、その結果に応じて関係者の処分を行うよう求めた。
三田茂院長が正しいかは白黒付かないにしても政府が言っている事は正しいとは思わない。
「東京は、もはや人が住む場所ではない」東京から岡山に移住した日本人医師の発言が海外で話題に (1/2)
(2/2) 07/25/14 (tocana)
昨年の富士山の世界遺産登録や東京五輪決定のニュースは、2011年の東日本大震災が残したあまりにも大きすぎる課題に苦慮する日本社会の懸念を、一時期完全に拭い去ったかのような明るいムードをもたらした。
しかし現在、この瞬間にも福島第一原子力発電所事故の収束、廃炉に向けた作業が続けられていることも厳然たる事実であり、その終結が遥か先のように思えるのも否めないだろう。また、今年5月には「ビッグコミックスピリッツ」の人気連載漫画『美味しんぼ』の登場人物が劇中で原発事故後の福島県を取材し、その滞在の間に"鼻血"を流す描写(4月28日発売号掲載『美味しんぼ 604話』)が問題になり大きな議論を巻き起こした。
今なお決して無視することができない原発事故の数々の影響が指摘される中、これまで東京で医療に従事していた1人の医師がこの春、岡山県に移り住み医院を再開した。医師の主張は「できれば東日本から移住していただきたい」というショッキングなメッセージである。
【その他の画像はこちらから→http://tocana.jp/2014/07/post_4493.html】
■東京は、もはや住み続ける場所ではない
東京都・小平市で父親の代から50年以上にもわたって地元の人々の医療に貢献してきた「三田医院」の三田茂院長は、今年3月にいったん小平市の医院を閉じ、4月に移住先の岡山県・岡山市で医院を開業して医療活動を再開した。この三田医師の決断は海外でも報じられ、北米を拠点にした情報サイト「VICE」や、エネルギー関連情報サイト「ENENews」などが、三田医師の主張を英語で紹介している。
「ENENews」の記事によれば、三田医師はここ1~2年の間に東京で劇的に放射能汚染が進行していると語っている。東京の各所で滞留した放射性物質が濃縮されて汚染は進行し、「東京は、もはや住み続ける場所ではない」という衝撃の発言が記されているのだ。特に東京の東部地域は深刻であるという。
「残念なことに、東京都民は被災地を哀れむ立場にはありません。なぜなら、都民も同じく事故の犠牲者なのです。対処できる時間は、もうわずかしか残されていません」(三田医師)
■東京の子供たちの白血球が減少している
三田医師は2011年の原発事故以降、子供たちの血液検査結果を分析してきたということだが、昨年の半ば頃から子供たちの血液中の白血球、特に好中球が著しく減少してきていることを示唆している。白血球、好中球は共に人体の免疫機能を司る重要な血液細胞で、その減少は免疫力の低下を招く。当時の小平の病院を訪れた患者の症状は、鼻血、抜け毛、倦怠感、内出血、血尿、皮膚の炎症などがあり、ぜんそくや鼻炎、リウマチ性多発筋痛を患う患者も明らかに増えたという。
これらの症状を完治させることはできないと三田医師は率直に語る一方、移住や転地療養で実際に多くの患者が回復している事実を強く指摘している。「VICE」のインタビュー記事によれば、重症だった乳幼児が家族共々九州に引っ越した後に急激に病状が回復したという例や、他にも大阪、京都、四国などに生活を移した患者の症状も確実に改善しつつあることに触れている。
症状を根本的に治すには、東京を含めた東日本から離れることが一番の治療法なのか? そして三田医師本人が、今回の岡山への移住を決断し身をもって東京を離れる重要性を体現しているのだ。
「東京の人々がより安全な場所に移ってくれることを願っています。少なくとも1年のうち1カ月でも2カ月でもいいので東京を離れることを強くお勧めします」(三田医師)
■海外の反応と東日本の将来
「E News」や「VICE」の記事の読者コメント欄には、三田医師の発言についての外国人からの様々な反応が記されている。
「医学的な検証はどうであれ、子供たちのためを考えれば不安を避けて(東京を離れて)暮らすのは当然だろう」と三田医師を支持する意見もあれば、「ばかげている。他の専門家や医師に彼(三田医師)の主張をどう思うか聞いてみたらいい」と反対する意見もある。
また中には「核戦争後の世界を描いた優れたマンガやアニメが多い日本でこんなことになってしまったのは残念だ」という感想や、輸入された日本の食品に懸念を抱いているという書き込みも見られる。昨年末には日本の「和食」が世界無形文化遺産に登録されたものの、皮肉にも日本産の食品の安全性については海外の目も厳しいようだ。
しかしその一方、ここ数年の訪日外国人数は軒並み過去最高を超え、今年6月には群馬県の富岡製糸場が世界遺産に登録されてますます追い風が吹く中、今後もしばらくは訪日外国人数は上昇を続けると見込まれている。この「日本ブーム」は果たして2020年の東京五輪まで続くのだろうか。旅行先を日本に選んだ理由が「将来行けなくなるかも知れないから......」という動機でないことを切に願いたいものである。
(文=仲田しんじ)
小保方氏以外の関係者の責任も明確に 日本学術会議が声明 07/25/14 (産経新聞)
日本学術会議の大西隆会長は25日、STAP細胞問題に関して、筆頭著者となった理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダーだけでなく、論文を作成した関係者も、関与に応じて責任を明確にするよう理研に求める声明を発表した。
声明は「研究全体が虚構ではないかという疑念を禁じ得ない。国の科学研究全体に負のイメージを与える」として、関係者の責任を明確にするよう求めた。
理研改革委員会(岸輝雄委員長)は6月、不正の再発防止策として、小保方氏が所属する発生・再生科学総合研究センター(神戸市)の解体を提言した。これについて大西会長は「理研は防止する機会が何度もあったが漫然と見過ごした。提言に対する見解を早急に示すことが必要だ」と述べた。
また「理研が健全性を回復するために行う行動を支援する」として、再発防止のための援助を約束した。
厚労省の検疫所職員が船舶衛生検査を行うのを何度か見たが、なぜかなりずさんだと思えるような船(多くの場合、サブスタンダード船)には来ないのだろうか?食料、食料の管理、水の管理、ゴキブリやネズミ対策、医療備品の管理など絶対に適切に出来ていないと推測出来るのに!日本のPSC(外国船舶監督官)のように楽したいから問題の船を避ける傾向は同じなのか。例としては、問題船は英語が通じない事が多い、記録簿などはない、又は、記入されていない、船員が嘘や言い訳ばかりで仕事が良い船のように進まないなどの理由が考えられる。問題が明らかになれば対応や処分を行わなければならない。
他の検査でも同様に楽に検査を行おうと考えれば、検査で発見されるはずの問題が見逃される可能性がある。どのようにターゲットを調べるのか、どのような検査を行うのか、付き添う業者以外は知る事はない。付き添う業者は簡単な検査の方が都合が良いので批判する事はない。こうして問題が見逃されるのかもしれない。7月26日のテレビで中国よりもチェックが甘い国がある、中国は良い方と言っていたが、そんな問題ではないだろ。問題があれば通関させるな!業者も損を何度も被れば教訓を学ばなければ破産か、廃業となるだろう。
検疫に関するガイドライン (厚生労働省) 開けない人はここをクリック |
検疫に関するガイドライン (厚生労働省) 開けない人はここをクリック
【食の安全を脅かすテロ行為】<期限切れ肉>鶏肉問題、厚労省が調査へ 07/23/14 (国家総動員報)
期限切れ肉「組織的」 上海市当局 会社5幹部を拘束 07/24/14 (東京新聞 朝刊)
【上海=加藤直人】米国の大手食品加工会社「OSIグループ」の傘下にある中国上海市の食肉加工会社「上海福喜食品」が使用期限切れの肉類を加工して供給していた問題で、上海市公安当局は二十三日、福喜食品の品質管理担当経理ら幹部五人を刑事拘束した。中国中央テレビ(電子版)が報じた。
上海市食品薬品監督局の副局長は上海紙などの取材に「一連の違法行為は個人の不正ではなく、会社の組織的行為であると分かった」と述べた。使用期限切れの肉類を加工販売していた不正について、公安当局は容疑が固まれば、会社ぐるみの犯罪として幹部らを逮捕するとみられる。
また華僑向けの通信社・中国新聞(電子版)は二十三日、上海市嘉定区にある福喜食品の上海工場の近くの倉庫で、同社従業員が、別会社が加工した鶏肉の入った段ボール箱のラベルをはがし、福喜食品のラベルに貼り替えていたとする上海テレビ記者の新たな潜入取材の内容を報道。福喜食品が、食品の製造加工元の偽装などに及んでいた疑いも出てきた。
◆厚労省 輸入管理体制を調査へ
中国の食肉加工会社の期限切れ肉の問題で、厚生労働省は食品衛生法上の違反などがなかったか情報収集に乗り出した。同省や消費者庁によると、これまで、問題の鶏肉に関する健康被害などの相談は寄せられていないという。
同社が鶏肉を供給していた日本マクドナルドからの連絡を受け、厚労省は輸入された鶏肉に期限切れのものが含まれていたか、衛生管理面で問題がなかったかなどの確認を急いでいる。輸入食品安全対策室は「まずは管理体制など事実関係を調査する」とした。
厚労省は輸入業者に届け出を義務付け、検疫所では輸入食品が食品衛生法に適合するかを確認している。二〇〇八年に中国製冷凍ギョーザに有機リン系殺虫剤「メタミドホス」が混入し、千葉、兵庫両県で中毒患者が出た事件後は、輸入加工食品の新たなガイドラインを策定。業者に対し、製造施設と衛生管理が日本の基準と同等以上であることなどを求めている。食肉の輸入時には残留農薬のほか、サルモネラ菌や大腸菌の付着の有無を検査。製品に使用期限が記載されている場合は問題ないか確認する。
輸入食品の異常発見「難しい」 厚労省「全品検査は不可能」 07/23/14 (産経新聞)
中国の食品会社「上海福喜食品」が使用期限切れの鶏肉を使用していた問題を受け、厚生労働省は輸入された同社商品に食品衛生法上の問題がなかったか調査を行っている。輸入食品の安全性が揺らぐ事件は過去にもあったが、「すべての輸入食品を検査するのは不可能で、異常を発見するのは難しい」(食品安全部)のが現状だ。
同部によると、海外から食品を輸入する際は、品質や衛生状態に問題がないことを輸入業者などが検疫所に書類で届け出る。過去に違反が多かったり輸出国の情報から違反の可能性が高かったりする場合は重点的に検査が行われるが、それ以外のものは約7%(平成24年度実績)が無作為に選ばれ検査されるだけだ。
検査項目は、微生物や残留農薬、添加物が基準値内に収まっているか▽腐敗やカビ付着がないか-など多岐にわたる。違反があった場合は業者に廃棄させる措置が取られるほか、同じ製造業者で違反が繰り返された場合は、その業者の全食品を検査するなど態勢を強化することもある。
上海福喜食品が過去に違反を指摘されたことがあったかは調査中だが、「違反を繰り返し重点検査の対象になったことはない」(同部)。使用期限切れの肉を加工しても、腐敗や微生物の増殖などがなければ発見は難しく、検査の態勢と内容には限界があるという。
嘘が当たり前の体質なのだから、信用するほうがおかしい。
JR北、また虚偽申告…12年の函館線脱線事故 07/25/14 (読売新聞)
北海道八雲町のJR函館線八雲駅で2012年2月に起きた脱線事故を巡り、JR北海道が運輸安全委員会の調査に対し、事故現場付近のレールの計測値を改ざんし、ゆがみなどの異常はなかったと申告していたことがわかった。
安全委は25日、事故は車輪が積雪に乗り上げたことが原因だったとする調査報告書を公表。虚偽申告については、「結果に影響を及ぼす可能性があり、許されることではない」と批判した。
事故は同月29日、駅構内で発生。普通列車(1両)がポイント付近を通過中に脱線した。安全委は、軌道間に積もった雪が固まり、右側車輪が雪に乗り上げたのが事故の原因と判断し、「除雪作業が不十分だった」と指摘した。
JR北海道を巡っては、昨年9月に函館線大沼駅で発生した脱線事故をきっかけに、各路線でレールの計測値を改ざんして、ゆがみなどが放置されていたことが発覚。国土交通省の監査などでも、異常放置が判明しないよう、虚偽申告していたことが判明した。国交省と安全委が鉄道事業法違反などの容疑でJR北海道を刑事告発し、北海道警が捜査を進めている。
あまり、芸能界には興味無いけど、たまたま記事を見たので一言。相手の女性にも全く責任はないとは思わないが、Travis Japanメンバーの森田美勇人に責任を取らしてメンバーから外れてもいいんじゃないのか。ジャニーズから追放でもいいんじゃないの。
ジャニーズJr.森田美勇人、交際相手の妊娠中絶&飲酒発覚! 乱れきった私生活にファン激震 07/24/14 (サイゾーウーマン)
ジャニーズJr.内ユニット・Travis Japanメンバーの森田美勇人が、交際していた女性を妊娠させていたと、7月24日発売の「週刊文春」(文藝春秋)が報じている。現在、18歳の森田は16歳の頃から約1年半にわたり、20代のA子さんと交際。記事では森田の女性に対する非道な対応を告発するとともに、未成年飲酒疑惑にも触れるなど、ショッキングな内容となっている。
記事によると森田とA子さんは2012年春に友人同士の飲み会で知り合い、半年後に交際に発展。彼女の献身的な支えもあって森田は人気Jr.に成長したが、今年3月に彼女の妊娠が発覚したという。
「同誌によれば、森田が避妊具をつけてくれなかったことで妊娠に至ってしまったようですが、A子さんが妊娠を告白すると、森田は『俺の立場も考えてよ』と言い放ち、彼女は泣く泣く堕胎手術を受けたそうです。その後も交際は続いたものの、事務所の関係者に交際がバレてからは、クビになることを恐れて急に態度が冷酷に激変。A子さんは森田の母親からも『私はあんたを許さないよ!』などと罵詈雑言を浴びせられたとか」(ジャニーズに詳しい記者)
そんな森田は6月21日よりスタートしたA.B.C−Z出演の深夜ドラマ『魔法☆男子チェリーズ』(テレビ東京系)や、現在公演中のミュージカル『PLAYZONE 1986・・・・2014 ☆ありがとう!~青山劇場☆』に出演中。報道を知ったファンからは、彼女を妊娠させたにもかかわらず“ポイ捨て”した森田に対し、「終わったな」「避妊しない時点でカス」などと、辛辣なコメントが続出。同誌にはA子さん宛に森田が書いた手紙が掲載されているが、ファンの間では寄せ書き等の文字との検証が行われ、「字体が似てる」という反応が多く上がっている。
「手紙には『俺の為に朝ご飯つくってくれたり』という一文もあり、『手紙の内容が生々しい』と、ファンに衝撃を与えています。『文春』では中絶疑惑に加えて森田が16歳の頃から常習的に飲酒を続けていたという記述や写真もあり、『プロ意識があるならこういう事態にならなかった』という見解が多いようです。しかしジャニーズでは、今年に入ってから同誌にヤラカシへの暴行を報じられたSnow Man・岩本照、未成年飲酒写真を掲載されたジャニーズWEST・藤井流星らも普通に活動をしています。森田もこのまま活動を続けることになりそうですが、ファン離れは避けられないでしょう。今回の一件で、熱心な追っかけのファンに『刺されるのではないか』と心配する人もいるようです」(同)
24日午前5時には、森田とその母親、A子さんと友人による話し合いを録音した“告白”データがネット上で公開された。それを聞いたファンからは「最後の『存在を消そうね』というのが怖すぎる」「ただの18歳のアホなガキだってわかった」など悲痛な声が多く上がっている。
『PLAYZONE』は24日の午後1時30分から東京・青山劇場で公演が予定されているが、彼女の中絶・飲酒疑惑が報じられ、録音データまで公開された今、森田はファンの前にどんな顔を見せるのだろうか? それとも、このままフェードアウトとなるのか――? 今後の森田の活動状況に注目したい。
物流コストやこれまでの投資を考えると中国なのかもしれないが、他の国へシフトも考えたようが良い。文化や国民の価値観に問題がある。インフラが弱い国もあるが調査して別の選択国を探してほしい。
期限切れ肉、偽装常態化「臭いする」牛肉も利用 07/23/14 (読売新聞)
【北京=牧野田亨】上海にある食品加工会社「上海福喜食品」が品質保持期限を過ぎた肉をマクドナルドなどに出荷していた問題について、中国の食品安全担当部門である国家食品薬品監督管理総局は全面的な調査に乗り出した。
古い肉の混入、保証期間の書き換え、検査対策――。中国メディアは日常的に行われていた不正工作を暴露し、取引先のファストフード店などが一部商品を中国国内で販売停止にするなど、影響が広がっている。
日本では、日本マクドナルドとファミリーマートが同社から鶏肉を調達していた。同総局は上海市に対し、上海福喜食品の営業停止、原料と商品の差し押さえを指示した。また、徹底した調査を行い、違法行為は司法機関で刑事責任を追及するよう命じた。中国紙・京華時報によると、上海市公安局が上海福喜食品の責任者を監視下に置いたという。
同社は米食肉大手OSIグループの傘下にあり、同グループ関連の工場は上海以外にも河北、山東、広東など5か所にある。中国国内ではマクドナルドやケンタッキー・フライド・チキン、ピザハットなどが取引先で、上海市当局者によると、上海福喜食品の商品を使用していたのは9社だった。各社は21~22日に関連商品の販売を停止している。
この問題は上海の衛星テレビ局が約2か月に及ぶ潜入取材を経て20日に報道し、発覚。同テレビ局によると、白い衣服にマスク、手袋を着用した作業員らが、18トンの鶏肉を機械に運び込んで加熱・加工し、商品に仕上げていたが、同局の記者が肉の入った袋の表示を見ると、多くが品質保持期限を半月近く過ぎていた。
だが、作業員たちは「関係ない。運べ」と指示したという。中国の品質保持期限は日本の消費期限を示している。
別の作業員は古い商品を混ぜて新しい商品を作る作業について、「混ぜる割合がある。多過ぎると食感が変わる。普通は5%だ」などと語った。また、2013年5月に生産した冷凍の小型ステーキの品質保持期限(通常は半年)を、14年6月に書き換えていたほか、作業員が「(古くて)臭いがする」という牛肉まで利用していた。テレビ報道によると、作業員の一人は「期限切れでも食べても死にはしない」と語っていた。
なぜ験で得た画像の一部を不適切に切り貼りしたのか?プレッシャー、プライド、それとも名声?
論文画像切り貼り、女性元講師を解雇…既に退職 07/23/14 (読売新聞)
筑波大学(つくば市)は22日、米国の科学誌に掲載された論文の画像を改ざんするなどした生命環境系の村山明子元講師(44)を諭旨解雇(処分相当)とし、監督責任のある柳沢純元教授(50)を停職6か月(同)にしたと発表した。
2人は既に退職しており、処分の効力はない。
同大の調査委員会によると、改ざんがあったのは2006~08年に米国の有力科学誌「セル」などに掲載された論文3本。実験で得た画像の一部を不適切に切り貼りしたという。
永田恭介学長は、「不正行為防止について再度徹底し、更なる意識改革を行う」とするコメントを出した。
多くの国民は東電のやり方が理解出来て来たのではないのか。パッキンは新品と言う事だ。このパッキン、どれくらいの耐久性を持っているのか?また、汚染水に含まれる化学物質によりパッキンの寿命が短くならないパッキンが使われているのか?新品だから大丈夫と言う事はない。パッキンが寿命が短い、又は、汚染水に含まれる化学物質によりパッキンの寿命が短くなる場合、水漏れが起きる可能性がある。メディアはパッキンの耐久性や耐化学物質について質問をした事があるのか?質問したが回答されていないのか?質問することを思いつかなかったのか?
残酷な言い方かもしれないが、福島に住んでいなくて運が良かった。政府や東電に期待できないところが追い打ちを掛けている!
汚染水タンクに中古…東電「漏水タンクは新品」 07/23/14 (読売新聞)
東京電力福島第一原子力発電所で汚染水を保管するための組み立て式タンク332基(6月現在)の中に、別の建設現場などで使われた中古タンクが複数含まれていることが23日わかった。
東電は「水漏れを防ぐための止水材(パッキン)などは新品を使っており、強度に問題はない。昨年8月に高濃度汚染水300トンが漏れたタンクは新品だった」と説明している。
東電は、メーカーから納入されたタンクに中古品が含まれていることは把握していたが、「震災直後は急いで設置しなければならず、どれが中古なのかまで確認しなかった」という。
組み立て式タンクは、鋼材をボルトでつなぎ、その継ぎ目にパッキンを挟んで造る。東電は「すべて水漏れ試験などを行い、安全を確認してから使っている」と説明している。
ドラマに出来るような展開だ!畑で腐敗した状態で見つかる。替え玉かもしれない?DNA鑑定も鑑定する人間や関与する人間が買収されていればデータは偽造出来る。例えば、あらかじめ兪容疑者のDNAが鑑定できる部分を渡して、鑑定中にすり替えるとか?既に検察やや警察など多くの人達が情報をリークしたり、不正に関与している状態を考えるとありえるかも?
代金払っても航空券届かず…登録抹消の旅行業者 07/22/14 (読売新聞)
東京都新宿区の旅行会社「レックスロード」に代金を支払ったものの、航空券が届かないという相談が東京都消費生活総合センターに相次ぎ、22日現在、46件に上っている。
100万円以上を支払ったケースもあり、同センターは注意を呼びかけている。
同センターによると、相談は今月2日から寄せられ、同社とは連絡が取れない状態だという。都によると、同社は1998年10月、旅行業者として登録されたが、昨年10月に抹消されている。
一方、今月11日まで同社の広告を掲載していた海外旅行比較サイトを運営する「リクルートライフスタイル」(東京)によると、代金を支払った全国の110人(21日現在)が航空券を受け取っていないという。
同サイトでは、広告掲載時に旅行業登録の有無を確認しているが、登録抹消を把握していなかった。サイトを通じて代金を支払った客には、航空券代を負担するという。
レックスロードはホームページ上で、「この度は急に業務を停止し、心より深くおわび申し上げます」と謝罪文を掲載している。
ドラマに出来るような展開だ!畑で腐敗した状態で見つかる。替え玉かもしれない?DNA鑑定も鑑定する人間や関与する人間が買収されていればデータは偽造出来る。例えば、あらかじめ兪容疑者のDNAが鑑定できる部分を渡して、鑑定中にすり替えるとか?既に検察やや警察など多くの人達が情報をリークしたり、不正に関与している状態を考えるとありえるかも?
経産省と東電の関係がもっと親密になると言う事なのか? 07/22/14 (産経新聞)
東京電力は22日、取締役会を開き、経済産業省出身で経営改革を担当してきた嶋田隆執行役(54)の後任に、経産省経済産業政策局審議官の西山圭太氏(51)が同日付で就任した、と発表した。嶋田氏は取締役専任となる。
西山氏は東大法卒で、昭和60年に通商産業省(当時)入省。福島第1原発事故後の損害賠償金を捻出するため、東電の資産の洗い出すために設立された「東京電力経営・財務調査タスクフォース事務局」の事務局長を務めた経験もある。
今月13日付で、東電の大株主である原子力損害賠償支援機構の連絡調整室次長に就任していた。
ドラマに出来るような展開だ!畑で腐敗した状態で見つかる。替え玉かもしれない?DNA鑑定も鑑定する人間や関与する人間が買収されていればデータは偽造出来る。例えば、あらかじめ兪容疑者のDNAが鑑定できる部分を渡して、鑑定中にすり替えるとか?既に検察やや警察など多くの人達が情報をリークしたり、不正に関与している状態を考えるとありえるかも?
手配の運航会社会長の遺体か 畑で発見、兄のDNAとほぼ一致 07/22/14 (産経新聞)
韓国の旅客船セウォル号沈没事故で、聯合ニュースは22日、南西部の全羅南道順天市内で6月に発見された変死体が運航会社会長、兪炳彦容疑者=背任容疑などで指名手配=である可能性があると報じた。兪容疑者の兄のDNAとほぼ一致したという。警察によると変死体は6月12日、順天市内の畑で腐敗した状態で見つかり、身元確認のためDNA鑑定を依頼していた。
これに先立ち、仁川地検は21日、兪容疑者の逮捕状の有効期限が22日に切れることを受け、有効期限6カ月の逮捕状を再取得した。地検は5億ウォン(約5千万円)の懸賞金をかけて行方を追っていた。最高検幹部は21日記者会見し「追跡に全力を挙げ、必ず逮捕する」と述べた。(共同)
現在の政府がどちらを向いていのかを考えれば公平な対応など期待できるはずが無い。やっと弁護士になっても低収入で困っている弁護士が存在し、違法行為に加担するケースもある。人間性が良いから弁護士になれるわけではない。試験に受かったから弁護士になれるのである。全ての弁護士が正義感をもって仕事をしているわけではない。これが現実。原発の近くに住み、運が悪く事故が起きて被害者になったら公平な対応など期待など出来ない。だからこそ、原発や放射能廃棄物貯蔵施設など受け入れるべきではないと思う。
原発ADR:中立医師を参加させず 5例判明 憤る被災者 (1/2)
(2/2) 07/17/14 (産経新聞)
東京電力福島第1原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR)を担当する国の「原子力損害賠償紛争解決センター」が、避難後に死亡したり後遺障害を負ったりした被災者に対する慰謝料を算定する際、中立的な立場の医師の意見を聞かないまま結論を出していたことが分かった。センター側は迅速に処理するためと説明するが、被災者側の医師の主張を覆し、低額の慰謝料で和解した事案もある。手続きの不透明さが一層鮮明になった。【関谷俊介、神足俊輔】
センターの「業務規程」には「専門的知見を有する者から意見聴取できる」と記載され、独自に中立的な医師から意見聴取できる。しかし、毎日新聞の取材では、死亡事例で3件、後遺障害事例で2件は、この手続きを踏んでいない。このうち、福島県南相馬市の無職女性(66)の場合、被災者側の医師2人の意見が覆された。
女性は高血圧の既往症はあったが他に病気はなく、家事や畑仕事をこなしていた。2011年3月12日の原発事故で避難を開始。10日後の午前5時ごろ、2カ所目の避難先の体育館で、トイレに腰掛けたまま意識を失い、救急搬送され福島市の病院に緊急入院した。
診察結果は脳出血。リハビリで左手足は少しは動くが、感覚は戻らない。つえなしで歩けなくなった。原発事故で自宅への立ち入り制限が続いており、今は次男と孫の3人でアパートを借りて暮らす。「迷惑をかけまい」と台所に立ったこともあったが、まひした左手を包丁で切ったことに気づかず、血が流れていて驚いたこともある。家事ができず「死んだ方がましと思うこともあった」。
原発ADRには女性を診察した医師3人が意見を記載した文書を提出した。救急搬送先の医師は「(原発事故の影響の)程度は分からない」としたが、かかりつけ医とリハビリ担当医がいずれも「ほぼ全面的」に事故の影響とした。東電側は「影響は50%前後」とする、女性を診察したことのない医師の見解を提出。センターは13年8月、中立的な医師に意見を聞かないまま「50%」とし、慰謝料700万円とする和解案を提示。50%と判断した理由は記載されていなかったが「もう年だし、あきらめるしかない」(女性)と、同10月に和解が成立した。
和解後、中立的な医師の意見聴取を実施していないと知った次男は「専門家の意見を聞いてほしかった。これでは申し立てた意味がない」と憤った。センターの事務を担当する「原子力損害賠償紛争和解仲介室」で今年3月まで室長を務めた野山宏氏は取材に対し「専門家への聴取はしていない。一件一件丁寧にやり出したら、今の審理期間(和解まで平均約半年)は維持できない」と話した。
センターを巡っては通常の損害賠償訴訟より低い死亡慰謝料の基準額を設定。「事故の影響はほぼ一律に50%」とするルールも適用し、基準額の半額で和解する事例が相次いでいる実態が明らかになっている。
◇他のADRは幅広い識者が参加
原子力損害賠償紛争解決センターによる裁判外の紛争解決手続き(原発ADR)で、中立的な医師への聴取が行われていない実態に、識者から疑問の声が出ている。他のADRでは意見聴取にとどまらず、幅広い専門家が判断に加わる制度が普及しているからだ。
欠陥建築物などを対象にする国の「建設工事紛争審査会」は、争点が単純な場合は弁護士1人で判断するが、複雑な場合、大学教授や建築士らが加わる。消費者トラブルを取り扱う国民生活センターの「紛争解決委員会」も、事案によって医師、建築士らが加わる。
民間ADRも同様だ。土地の境界や医療過誤、金銭トラブルなど民事全般を取り扱う「総合紛争解決センター」(大阪市)には、弁護士だけでなく、テーマに応じて土地家屋調査士や医師、公認会計士、税理士が参加する。家電製品の事故を巡る「家電製品PLセンター」(東京)も弁護士、学者、技術者らが和解案を決める。
ADRに詳しい植木哲・朝日大教授(民法)は「原発ADRが、法律家だけで判断しているのは問題だ。専門医の意見を聞く機会を設けなければ、被災者の納得できる解決にはならない」と批判した。【高島博之】
お金は力。そう言う事でしょう。
中部電力、政界に裏金2.5億円 元役員が証言 07/18/14 (朝日新聞)
砂押博雄、板橋洋佳 市田隆
中部電力(本店・名古屋市)の元役員が、取引先の建設会社などに工面させた資金を長年簿外で管理して政界対策に充ててきたと朝日新聞に証言した。元役員は政界工作を長年担当し、2004年までの約20年間に少なくとも計2億5千万円を政界対策のために受け取り、多くを知事や国会議員ら政治家側に渡したという。建設会社側への見返りとして「原発関連工事などの発注額に上乗せした」とも証言しており、政界対策資金が利用者が支払う電気料金で賄われた可能性がある。
元役員の証言によれば大手建設会社2社と名古屋市の電子部品製造会社から1985年には資金提供が始まり、建設会社2社からは95年まで、電子部品製造会社からは04年まで続いた。
この間は毎年、建設会社2社から計1千万~1500万円、電子部品製造会社からは100万~200万円を受領。さらにこれら3社とは別に大手建設会社から93年に2回、それぞれ1億円と4千万円を受け取ったという。
安易な外国人労働は将来は問題を引き起こす。国民一人当たりの生産性を増やすことが重要。そして現在の教育システムで高収入のホワイトカラーの量産は無理。一時的な外国人単純労働者は帰国しなかったらどうなるのか?外国人単純労働者に対して医療、福祉、社会保障、子供の教育などを国の財政で負担しなければならなくなる。長期的に見てマイナスである。
日本は問題を直視するするのを嫌うが、学校の教育システムを変える必要がある。勉強をしたくなければ、りっぱな職人や建築や造船などのきつい環境で働く専門的な労働者にある専門的な教育機関で専門知識を持つ労働者になれるような教育システムにするべきである。教養は必要だが勉強が嫌いであれば、読み書きそして礼儀を身に付け労働者として必要なスキルを学べる学校を作るべきである。素人で何も知らないが給料に魅力を感じて入ってくる労働者よりも生産性は高くなると思う。勉強が嫌だからさぼったり、授業で寝るぐらいなら、重機や資格がいる機械の資格を学校で取得するほうが就職に有利だし、企業も喜ぶと思う。高度な教育も受けたいと思った時は、編入できるとか、推薦などの特別枠で勉強できるシステムを作っておけば良い。単に高卒、単に大卒よりも個々の学生の能力はアップすると思う。給料が上がり、周りの評価も良ければ、きつい仕事でも選択する生徒は増えると思う。中途半端な学力重視では、底辺の生徒は何も出来ないし、向上心があり、精神的にタフでなければ単純労働者としての選択しかなくなる。
高卒程度であるが生産性をアップできる学生が増えれば、企業の競争力もアップするし、無駄な政府支援の資格取得費用は減る。一般教養は必要と言えば反論する人は少ないが、中途半端な漢文、古文、音楽、歴史、美術などは無くても良い。全く知らなくても生きていけるし、その他の能力があれば就職できる。精神気にタフであることが要求される仕事がある。文部科学省の机上の空論的な事に無駄に税金を使うのであれば、外国人労働者と外国人労働者に対する政策や法整備を真剣に考え、将来の日本人労働者の事も考えるべきだ。建築でも造船でも、現在は仕事の手順を教える事の出来る日本人達がいるが、10年以上も続ければ、仕事を教える事が出来る日本人が退職、又は、いなくなる。その時になって経験や技術の継承と騒いでも遅い。実際に働かないと身に付かない職人的な技術は存在する。ホワイトカラーとしても魅力が無い、現場で働く労働者としても魅力がない少子化世代の若者が増えたら将来どうするのか?日本は沈没するだけである。
外国人「単純労働」拡大は新たな少子化招く要因に 論説委員・河合雅司 (1/3)
(2/3)
(3/3) 07/20/14 (産経新聞)
◆緩和策を矢継ぎ早に
就職難といわれてきたが、今や職種によっては人手不足である。人繰りがつかず倒産する会社まで出始めた。
少子化に伴い日本の勤労世代は減少している。これまでは景気の悪さに覆い隠され、さほど労働力不足が問題となることはなかったが、今後、景気が本格回復すれば一気に顕在化するだろう。
状況の打開に向け、政府は女性や高齢者の活躍促進、ロボット利用などを掲げるが、急いでいるのが外国人の受け入れ拡大だ。東京五輪などで需要増が見込まれる建設業に続き、造船業でも要件を特例的に緩和することにした。
法務省の有識者会議は外国人技能実習制度に「介護」などを加える案をまとめ、「骨太の方針」や新成長戦略には対象職種拡大や最大3年の在留期間を5年に延長する方針などが盛り込まれた。「女性の活躍推進のため」として、国家戦略特区で家事支援労働を認めることにもなった。
低賃金で単純労働を行う外国人によって手っ取り早く人手不足を解消しようというのだ。だが、技能実習制度は途上国の人々に技能や知識を身につけてもらうためのもので、趣旨を逸脱している。同制度をめぐっては賃金の不払いや過酷な労働を強いる人権侵害も相次いでいる。
◆思惑通り帰国する?
ところで、骨太の方針は「外国人材の活用は移民政策ではない」と強調している。出入国をしっかり管理するから大丈夫と胸を張るが、政府の思惑通りに帰国するかは疑問である。日本に残ろうとする外国人は後を絶たない。
「期間限定」であろうとも、多くの外国人が働き始めれば、人口減少に悩む地方などでは地域経済の支え手として無視できない存在となる。
「当面の人手不足への緊急時限的措置だ」と言って単純労働者をなし崩しに受け入れ、外国人抜きに社会が回らなくなった時点で制度化するのでは本末転倒になる。
政府・与党には外国人の単純労働について「いずれ解禁はやむを得ない」との声も強いが、国策の大転換にもつながる問題だけに国民的な議論が欠かせない。
受け入れには治安の悪化や文化摩擦といった懸念も多いが、最大の問題点は単純労働者の大量受け入れ自体が、日本人の少子化を招く新たな要因になることだ。外国人の受け入れでは人口減少問題は解決せず、むしろ加速する。
理屈は簡単だ。人手不足であれば賃金は上昇し、労働条件もよくなる。人件費が上がる企業は付加価値を高めるべく生産性を上げようとする。ところが、安い賃金で働く外国人労働力が大量に入ってくると、日本人の賃金も総じて抑えられることになる。
若い男性が低収入や不安定な雇用に追いやられれば、求婚はままならなくなる。介護や家事支援といった職種には女性が多いが、仕事を奪われたり、長時間働かなければ生活維持ができなくなったりしたのでは、子供を持つことをためらう人も出てこよう。
◆受け入れずとも成長
受け入れ推進派は、外国人を受け入れなければ日本経済は成長せず、社会が回らなくなるとの見方を示すが、本当だろうか。
人口動態は経済成長を左右する絶対的な条件ではない。その証拠に、高度成長期の労働力人口は年1%程度しか伸びていない。機械化や技術の進歩が寄与したとされる。
労働力人口が激減する日本に求められているのは、高賃金労働者を活用しながら、他国に負けぬ付加価値の高いサービスを生み出すビジネスモデルへの転換だ。低賃金の外国人を大量に受け入れたのでは、構造転換のチャンスをみすみす逃すことにもなる。
もちろん、出生率が劇的に回復しても、生まれた子供が「労働力」として育つには20年程度を要する。それまでは「現在の大人たち」で対応するしかないのも現実だ。
だが逆に考えると、外国人に頼らず約20年間を頑張りさえすれば、展望が開けるということでもある。意思や能力があっても働いていない、働く機会に恵まれない若者も多い。女性や高齢者を含め、意欲のある人が働ける環境の整備を急ぐことである。
人口減少に対し、日本人を増やすことで対応するのか、外国人で穴埋めする道を選ぶのか。いずれにしても、出生率の回復なくしては人口問題の根本解決はありえない。「低賃金の外国人を大量に受け入れた結果、少子化対策が台無しになった」ということがあってはならない。
日本らしい問題だ。留年すれば本当はデメリットだが、日本独特の新規採用のシステムでは有効な選択方法。人材不足とか、人手不足とか言われながら、本来労働者となるはずだった約10万人が学生の身分に留まる。個人にとっては重要な選択だが、マクロ的に見ればばかばかしい。
不本意な内定より留年…「卒業せず」10万人超 07/18/14 (時事通信社)
卒業学年で留年した学生が、今春は10万人を超えて6人に1人に上ることが、読売新聞の「大学の実力」調査でわかった。
10万人を超えたのは2年ぶりで、大学側によると、不本意な内定を断り、あえて留年して「納得できる道」を目指す学生が目立ってきているという。景気が上向いて来たことが背景にあるようだ。
調査には全国の89%の大学が回答した。それによると、2013年5月段階で卒業学年に在籍していた学生のうち、今春卒業しなかったのは10万2810人で全体の16・3%。昨年より3445人増えた。
大学の就職担当者らの分析によると、留年の理由は卒業単位不足のほか、企業の内定を得られなかった就職留年が多いが、今春は、内定を辞退して留年を選ぶ学生が目立つという。
調査委員会の報告書は理解できない。
「博士号の取り消し要件に該当しないと判断した理由について『(博士号を前提とする就職など)生活および社会的関係の多くを基礎から破壊することになる』と指摘。」「生活および社会的関係の多くを基礎から破壊することになる」について考慮する必要はない。問題があれば博士号を取り消せば良い。小保方氏からの訴訟を心配しているだけとしか思えない。
「報告書は、博士論文には文章や実験画像の盗用や、意味不明な記載など多くの問題箇所があると認定。『合格に値せず、小保方氏は博士学位を授与されるべき人物に値しない。早大の博士学位の価値を大きく毀損(きそん)する』と厳しく批判したが、『学位授与に重大な影響を与えたとは言えない』として、早大規則の学位取り消し要件に該当しないと判断した。」
博士号の授与に関して人物評価も判断材料になっているのか知らない。判断材料にならないのなら、「合格に値せず、小保方氏は博士学位を授与されるべき人物に値しない。」と批判する必要はない。また、小保方氏の博士論文に問題があったとしても、論文をチェックして博士号を授与したのは早稲田大大学院。「早大の博士学位の価値を大きく毀損(きそん)する」とはならない。早稲田大大学院が小保方氏のケースから多くを学び、改善する機会を得たのではないのか?
このような報告書を公表する早稲田大が自ら早稲田大の評価を落としているように思える。
博士号剥奪は「生活破壊」=小保方氏論文で回避理由説明―報告書の全文公開・早大 07/18/14 (時事通信社)
理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダーが2011年に早稲田大大学院から博士号を取得した論文に疑義が指摘された問題で、早大は19日、調査委員会の報告書全文をホームページで公開した。博士号の取り消し要件に該当しないと判断した理由について「(博士号を前提とする就職など)生活および社会的関係の多くを基礎から破壊することになる」と指摘。要件に該当するかどうかは、この点に配慮し「厳格に行われなければならない」と説明している。
また報告書は、小保方氏を指導した常田聡教授について、指導教員としても博士論文の主任審査員としても義務違反があると認定。「非常に重い責任がある」と指摘しながら、「一般論として述べれば、解任を伴う懲戒処分をもたらすほどのものではない」と評価していた。
調査委員長の小林英明弁護士は17日に報告書を鎌田薫総長に提出したが、記者会見では概要しか公表していなかった。
報告書は、博士論文には文章や実験画像の盗用や、意味不明な記載など多くの問題箇所があると認定。「合格に値せず、小保方氏は博士学位を授与されるべき人物に値しない。早大の博士学位の価値を大きく毀損(きそん)する」と厳しく批判したが、「学位授与に重大な影響を与えたとは言えない」として、早大規則の学位取り消し要件に該当しないと判断した。
鎌田総長は17日の記者会見で、報告書は大学としての結論ではなく、小保方氏の博士論文の扱いや関係者の処分は今後検討すると説明した。小保方氏以外の博士号取得者の論文も調査しているが、結果の扱いは小保方氏の場合と整合性が取れるよう配慮すると述べた。
元記事では「アメリカの潜水会社(GAVI)がセウォウル号の手伝いに来たが、不合理な要求をし、受け入れられないと一度も潜水せずに帰国した」ということだと思いますが、GAVIに元記事を要約して送ったところ、同社の発表文章を送ってくれました。その内容が記事と全然違うので較べてみます。 (おーるじゃんるさま)
まず朝鮮オンラインの元記事の概要をまとめてみます。
1 GAVIは6時間潜水できる水中人工呼吸器を使用して作業を行うと説明
2 対策本部の一部関係者は潮の流れが速いために水中人工呼吸器は有効ではないと疑念を呈す
3 まずは一度試しに潜ってみることにする
4 GAVIは潜水士の安全のために現場に停泊しているバージ船を動かすように要求してきたが、バージ船を異動することは現在行っている捜索作業を全部中止する必要があり、家族の同意を得られないとして拒否して帰国した
5 対策本部は「GAVIはバージ船が停泊していることを知っていたが、現場に来て突然バージ船の移動を要求してきた。理解に苦しむ」とコメント
6 行方不明者の家族の一人は「わらにもすがる思いで米国の潜水チームの受け入れを求めたが、一度も潜水することなく帰ってしまい、失望した」とコメント
これに対して、GAVIの発表はかなり違います。
1 GIVIが潜水からの撤退を選択した、と韓国政府が報告しているが正しくない
2 必要機材が供給されなかった。事前にリストを渡したが、到着時に情報を求めると「政府が供給する」と言うだけだった。後に対策本部と政府で必要機材リストを分けていると説明され、対策本部分を渡された。要求34品目中の14しかなく、古くて品質も貧弱だった。純度100%の圧縮酸素(Weldig Oxyge)が必要だったが94%しかなく、コンプレッサーは要求サイズの6分の1だけで、かなりの品目を修理せざるを得なかった。使えない物の返却や再送にかなりの時間を浪費した。
3 最初のミーティングでは他の潜水会社が犠牲者家族、政治家、市民、軍の潜水士の同席で行ったが、潜水会社は明らかに怒っており「誰がGAVIを韓国に連れてきた!」と怒鳴っていた。他の潜水会社の疑念を解くために試しに潜水してみることを対策本部から提案された。GAVIは他の潜水会社がきちんとした評価を下さないことを懸念することを明言した。セウォウル号の姉妹船と言われる船に潜ってみたが、全然似ていなかった。この後で油圧系統のデータなどを要求したがもらえなかった。
4 あてがわれた宿舎は、犠牲者家族、マスメディア、街の中心から地理的に離れた場所だった。
5 GAVI本件を担当する李大臣に手紙を書き、責任者のCho氏にリストの受領確認と機材の配達を求めたが、Cho氏はリストの受領確認はしたものの、機材は配達は約束されなかった。最終的に34品目の要求機材のうち、30品目が配達された。この段階で9日間の滞在であった。
6 潜水の日は7月11日にCho氏によって決められた。GAVIの意見は聞かず、ディスカッションも無かった。GAVIは機材が未着であることを理由に反対したが「それらは届く」と繰り返されるのみであり、7月10日にGAVIは船に持っている機材を積み込んだ。
7 当初の合意では到着時に一部支払いであったが実施されなかった。何度も抗議し、無料では潜水できないと繰り返し抗議した結果、潜水の日に到着時支払合意分が送金された。残りはまだ支払われていない。
8 状況確認後、簡単な報告をした。単なる情報共有の為だったが、5~10分程度のつもりが質疑応答で1時間半を費やした。潮の状態が良いのは1時間程度で午後1時から潜水したかったができなかった。次は午前2時だったが夜間にこの規模の潜水は不適切と結論した。
9 安全上の懸念を無数の問題解決手法を使って訴えたが海軍責任者に聞き入れられなかった。彼はライバル会社のバージ船を移動させ、遭難現場にGAVIを連れて行った。GAVIはバージ船を100メートル移動させるという妥協案を出したが受け入れられなかった。さらに家族、軍と政府関係者を退避させるという更なる妥協案もその場で韓国政府関係者に拒絶された。
10 GAVIはソウルに戻り、GAVIの苦境に同情的だった上院議員らに面会して帰国した。
11 コミュニケーションが不足し、現場での援助や協力が無く潜水作業を安全に行うことができなかった。政府担当者は当初のタウンホールミーティングでの合意事項を主製紙、必要な機材を時間どおりに届けることができなかった。GAVIは10万ドル以上の設備を持って家族のために地球を半周して飛んできたのだが。
特に、朝鮮オンラインの元記事は「GAVIはバージ船が停泊していることを知っていたが、現場に来て突然バージ船の移動を要求してきた」と言っていますが、GAVIは当日にバージ船を海軍の責任者が移動させたと言っています。
どちらが本当かはわかりませんが、GAVIの言っていることの半分くらいが本当でも相当とんでもない対応ですね。
「捜査関係者によると、松崎容疑者は、DB管理会社『シンフォーム』から顧客情報を大量にコピーする権限を与えられたごく少数の一人で、秘密管理に関する研修に複数回参加し、誓約書に署名していた。」
権限を与えた少数の一人なら正社員にしなかったベネッセコーポレーショングループ企業『シンフォーム』にも問題はあると思う。派遣の身分に抑えて安く使って来た結果ではないのか?セキュリティーで重要なのは情報漏洩の可能性を低くする事。目先の儲けを優先させた結果かも?
「営業秘密と知っていた」「売却目的」 逮捕のSE、違法性認識か 07/18/14 (産経新聞)
通信教育大手「ベネッセコーポレーション」の顧客情報が不正に持ち出された事件で、データベース(DB)の保守・管理会社に業務委託されていたシステムエンジニアの松崎正臣容疑者(39)=不正競争防止法違反容疑で逮捕=が「売却目的で顧客情報を持ち出した」と供述していることが18日、捜査関係者への取材で分かった。
松崎容疑者は逮捕前の任意の事情聴取に対し「顧客情報が営業秘密であると知っていた」と話しており、警視庁生活経済課は、松崎容疑者が当初から違法性を認識した上で、顧客情報の持ち出しと名簿業者への売却を繰り返していたとみている。
捜査関係者によると、松崎容疑者は、DB管理会社「シンフォーム」から顧客情報を大量にコピーする権限を与えられたごく少数の一人で、秘密管理に関する研修に複数回参加し、誓約書に署名していた。任意聴取には、「顧客情報を売ってはいけないと知っていた」とも話していた。
松崎容疑者が動機について、「パチンコなどで数十万円の借金があった」と説見していたことも判明。松崎容疑者は、名簿業者には「イベントで集めた」と持ちかけて顧客情報を売却しており、生活経済課は、松崎容疑者が発覚を恐れて顧客情報の出所を偽装していたとみている。
ベネッセ漏えい事件に関して法改正の権限を持つ管轄庁にも責任がある。消費者庁が個人情報保護法の見直し及び改正をおこなっていればこのようなざるから落ちるような状態にはなっていなかったはずだ。消費者庁は「出所言わないのが暗黙のルール」について知っていたのか?大きな穴のあいた網のような法では効果が無い。それとも業界との癒着でもあったのか?これでは警察が適切の捜査できたとしても起訴はできない。起訴できなければ不正に入手した情報を扱う名簿業者達を助長させるだけだ。
「出所言わないのが暗黙のルール」…名簿業者 07/17/14 (産経新聞)
ベネッセコーポレーションから流出した顧客情報は、専用のデータベース(DB)から持ち出された後、名簿業者の間で転売されていた。
不正競争防止法など規制する網の外側で「ビジネス」を続ける名簿業者。所管官庁もなく、厳重に管理されるべき個人情報が野放図に広がる一因になっている。
◆不正の認識
「聞かなかったことにしてほしいが、ベネッセの情報だ」。九州の名簿業者の男性は今年1月、同業者からこうささやかれ、約700万件の子供の情報を買い取った。男性は「個人情報の取引は、出所を『言わない』『聞かない』が暗黙のルール。警察に聞かれても『知らなかった』と答えるだけだ」と言い放った。
同法では、厳重に管理された「営業秘密」は、不正持ち出しだけでなく、「不正の利益」を得る目的で買い受け、転売することも禁じている。だが、名簿業者が不正に入手された情報であることを「知らない」と言えば摘発は難しい。
京都府警が2月、詐欺グループに大量の個人情報を提供したとして名簿業者の男を詐欺ほう助容疑で逮捕したが、男は「詐欺に使われると思わなかった」と供述し、不起訴となった。
今回、情報を持ち出したとされるシステムエンジニアが6月まで複数回、買い取りを求めた名簿業者は、警視庁に「ベネッセ社の情報とは知らなかった」と話している。情報が転売された東京都武蔵野市の業者や昭島市の業者も、同様に「知らなかった」と説明している。
ベネッセ流出:ジャスト以外に2ルート 転売で10業者へ (1/2)
(2/2) 07/17/14 (産経新聞)
通信教育大手ベネッセホールディングス(岡山市)の顧客情報漏えい問題で、流出した顧客情報は、三つのルートで名簿業者など少なくとも約10業者に渡っていたことが捜査関係者への取材で分かった。警視庁が17日に不正競争防止法違反(営業秘密の複製)容疑で逮捕状を取った外部業者のシステムエンジニア(SE)の男(39)は、任意の調べに対し「一つの名簿業者にしか売っていない」と供述しているという。しかし、同庁は顧客情報が業者間で転売を繰り返され、さらに広く出回った可能性があるとみて流出ルートの全容解明を進める。
捜査関係者によると、男は昨年12月から問題が発覚する直前の今年6月まで、顧客情報のデータベース(DB)からダウンロードした情報を記憶媒体に移し、特定の名簿業者に複数回売却した疑いが持たれている。
顧客情報の流出先についてはダイレクトメールの送付に利用した通信教育事業を手掛けるソフトウエア会社「ジャストシステム」(徳島市)へのルートが判明していたが、その後の警視庁の調べで、名簿業者以外の企業も含む2ルートの存在が確認され、流出先は少なくとも約10社に上ることが分かった。
男は顧客情報を持ち込んだ名簿業者に身分証明書を提示し、「不正取得した情報ではない」とする誓約書にサインしていた。男から情報を買った名簿業者や他の業者は、いずれも警視庁の任意聴取に「ベネッセの情報とは知らなかった」と説明しているといい、同庁は慎重に裏付けを進めている。
関係者によると、「個人情報取扱事業者」の義務などを定めた2005年の個人情報保護法の全面施行以降、まとまった子供の個人情報を入手するのは難しくなり、名簿業者や子供向けの通信講座事業者にとっては貴重な情報だったとされる。
警視庁は流出した顧客情報とベネッセのDBの照合を進めるとともに、ジャスト社以外の企業にも出回った可能性があるとみて調べている。【林奈緒美】
◇ベネッセの顧客情報漏えいの経緯
2013年12月 顧客データベースを管理する外部業者の男のIDで情報の不正持ち出しが始まる
14年1月ごろ 名簿業者「パンワールド」(東京都武蔵野市)が別の名簿業者から顧客情報を購入
5月中旬 パンワールドが名簿業者「文献社」(福生市)に顧客情報を転売
同21日 文献社が通信教育を手掛ける「ジャストシステム」に顧客情報を転売
6月 ジャストシステムが、購入した顧客情報を利用したダイレクトメール(DM)を送付
同26日〜 DMを受け取ったベネッセの顧客から情報漏えいの問い合わせが相次ぐ
27日 ベネッセが社内調査を開始
30日 ベネッセが警察と経済産業省に報告
7月9日 ベネッセの原田泳幸(えいこう)会長兼社長が記者会見し、「最大約2070万件の情報が漏えいした可能性」と発表
15日 警視庁がベネッセの告訴状を受理
17日 警視庁が男の逮捕状を取得
ベネッセ流出 犯人が背負う「実刑3年」「損害賠償40億円」 07/17/14 (日刊ゲンダイ)
ベネッセの顧客情報流出事件で、警視庁は、データベースにアクセスして顧客情報を流出させた派遣社員の男を、不正競争防止法違反の疑いで週内にも逮捕する。男は、「顧客情報は名簿屋に売った」と供述しているというが、いくらで取引されたのか。
「個人情報の中身によって違いますが、子供の情報の場合、業者に売るときは1件1円が相場。報道されているように流出件数が760万件なら、男の受取額は760万円になりますが、それだけ支払える名簿業者はまずいない。せいぜい200万円くらいではないか」(名簿業者)
今ごろ自分の浅はかさを悔やんでいるかもしれないが、もう遅い。個人情報流出問題に詳しい紀藤正樹弁護士が言う。
「不正競争防止法違反は、『10年以下の懲役または1000万円以下の罰金』で、懲役3年の不正アクセス禁止法違反や同じ3年の業務妨害罪より重い。今回ほど大量の個人情報が流出した事件は前例がなく、警察は被害の大きさを重く見たのです。派遣社員の男性は初犯ですが、執行猶予が付かず、懲役3~5年の実刑判決になるのではないか」
民事で被害者グループに損害賠償訴訟を起こされる可能性も十分だし、すでにベネッセは男を刑事告訴している。
「今のところ、原田会長兼社長は被害者への補償を否定していますが、警察沙汰となった以上、今のように強気のままでいられるか。過去の情報流出事件のように1人当たり500円を補償するとすれば、補償総額は760万人で38億円。このほかに被害者やマスコミ、警察などへの対応による人件費、システム改善費もあるでしょう。一連の騒動に伴うコストを合算すると、40億円前後。男性への損害賠償請求もそれくらいの金額になります」(紀藤正樹氏)
男が巨額の賠償金を負担できるはずはないが、出来心で行ったことの代償はあまりにも大きかった。
天罰が下る人がいないと真面目にやっている人達が浮かばれない。がんばれば報われるとは限らないのが人生。人生は難しい。
厚年基金の元理事に賄賂、ドイツ証券元社員有罪 07/16/14 (産経新聞)
ドイツ証券(東京)による厚生年金基金に対する接待汚職事件で、東京地裁は16日、贈賄罪に問われた元社員越後茂被告(37)に懲役10月、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。
安東章裁判長は「厚生年金基金の業務に対する社会の信頼を害する悪質な犯行だ」と述べた。
判決によると、越後被告は、三井物産連合厚生年金基金が、同証券が運用する10億円分の債券購入を決めた見返りとして2012年4~9月、「みなし公務員」に該当する同基金の元常務理事(61)(収賄罪で有罪確定)に対し、高級クラブやゴルフ場で接待を繰り返し、87万円相当の賄賂を提供した。
判決は「上司も接待を黙認しており、被告を強く非難することはできない」とする一方で、「営業成績を上げて出世したいと考えての犯行で、大きく同情すべきだとは言えない」とした。
ここまでわかっていたら不正に入手した情報とは思わなかったほうがおかしい。名簿業者が弁護士と相談してどのような言い訳をするのだろうか?
提出記録媒体に顧客情報2000万件 派遣社員、業務装い大胆犯行 07/16/14 (産経新聞)
ベネッセコーポレーションから顧客情報が大量に流出した問題で、顧客情報のデータベース(DB)を管理する下請け業者の派遣社員でシステムエンジニア(SE)の男が任意提出した記録媒体に、流出情報と一部が一致する約2千万件の子供の個人情報が見つかっていたことが15日、分かった。SEは発覚直前まで顧客情報のコピーを繰り返して転売。業務を装って大胆な犯行は繰り返されていた。
捜査関係者によると、DBのアクセス記録には、6月下旬に流出が発覚する直前まで約2千万件の顧客情報が繰り返しコピーされた履歴が残り、SEの記録媒体にも約2千万件分の個人情報のファイルが複数あった。一部がベネッセの顧客情報と一致しており、同一のものとみられる。
DBは平成21年に一新され、ベネッセが新しい顧客情報を登録する度に、ほぼリアルタイムで反映される。
顧客が転居した場合も反映されるといい、新鮮で正確な「一級品の情報」(名簿業者)という。
記録媒体には顧客情報のデータが圧縮して保存されており、SEはコピーするたびに自宅で別の記録媒体に移し替え、転売していたとみられる。
名簿業者は過去のデータと照合し、重複分を除いた更新分だけの代金を支払っていたという。
名簿業者も顧客情報を転売しており、警視庁幹部は「どれだけの業者に流れたのか、把握しきれていない」として、流出ルートの全容解明も進めている。
拡散ルートが焦点「素人では門前払い」 流出元から入手業者、刑事罰も 07/15/14 (産経新聞)
名簿業者でさえ収集に苦労するという大量の子供のデータはどんなルートで拡散したのか。東京都内の名簿業者は「素人のSEが業者に持ち込んでも門前払いにされるのが普通で、警察に通報される可能性もある」と首をかしげる。
ベネッセ関係者によると、顧客情報は今年1月ごろには、東京都武蔵野市の名簿業者「パン・ワールド」が入手。福生市の名簿業者「文献社」を通じ、5月にIT大手のジャストシステムに約260万件分が転売された。ベネッセからは少なくとも約760万件分が流出しており、パン社は「他の業者から買った」と説明している。
顧客情報は、このルート以外にも流れていた。別の名簿業者は4月ごろ、800万件分の子供のデータを入手したが、ベネッセからの流出をうかがわせる架空の名前が記載されており、転売を見送った。一方で、「何社にも転売した」とする業者もいるという。
不正流出した顧客情報を売買したパン社や文献社、ジャスト社は法的責任を問われないのか。
経済産業省によると、流出元から直接入手した業者は刑事罰に問うことも可能だが、それ以外の業者が問われるのは基本的に賠償責任のみ。警視庁の事情聴取には、3社とも「別の業者から買った」と供述しており、供述通りなら刑事罰には問えないが、不正入手を指示していたことが発覚すれば、直接入手した業者と一体とみなされて摘発対象となる可能性は残る。
顧客情報の流出先として判明している「パンワールド」(東京都武蔵野市)は「『ベネッセの顧客情報とは知らなかった』と説明したという。」しかし、ベネッセでなくとも大量の顧客データベース(DB)の入手に関して疑問に思わなかったのか?不正に入手した事実を知らなかった言えば罪に問われない事実を最大限に利用した推測される。厳しくすれば名簿業者の多くは廃業か、縮小になるのでは?今後の展開としては業界と行政や政治家との癒着があるのか、行政が適切に対応するか次第だろう?
ベネッセ漏えい:情報持ち出し常習 SE、数百万円で売却 07/16/14 (毎日新聞)
通信教育大手ベネッセホールディングス(岡山市)の顧客情報漏えい問題で、顧客データベース(DB)の保守管理にあたっていた外部業者のシステムエンジニア(SE)の男が警視庁の任意聴取に対し、「昨年末から(発覚直前の)今年6月まで顧客情報の持ち出しを繰り返していた。同じ名簿業者に売却し、合計で数百万円を得た」と供述したことが関係者への取材でわかった。男が警視庁に任意提出した記憶媒体から、DBと一致する大量の個人情報が見つかったことも判明。警視庁は不正競争防止法違反容疑での逮捕に向け、詰めの捜査を進めている。
関係者によると、ベネッセはDBの保守管理をグループ企業の「シンフォーム」(岡山市)に委託し、同社はさらに複数の外部業者に再委託。男はこのうちの一社に派遣社員として勤務し、DBを操作する端末が置かれているシンフォーム東京支社(東京都多摩市)の一室に出入りしていた。
男は警視庁の任意での事情聴取に対し、ベネッセ側から貸与されたパソコンに顧客情報をダウンロードし、記憶媒体にコピーして持ち出しを繰り返したと供述。同じ名簿業者に売却を続けていたが、同庁の調べに売却先の名簿業者は「ベネッセの顧客情報とは知らなかった」と説明したという。
これまでの警視庁の調べで、顧客情報の流出先として判明している「パンワールド」(東京都武蔵野市)、「文献社」(福生市)以外にも2〜3社の名簿業者の存在が確認されたといい、警視庁は情報の拡散ルートの解明を進めている。【林奈緒美】
結構、ずさんなんだ!
北海道大:預け金不正総額5億円超 関与教員59人に 07/16/14 (毎日新聞)
使い残した公的研究費を業者に管理させて翌年度以降に回す「預け金」などの不正経理問題で、北海道大調査委員会(委員長・新田孝彦副学長)は15日、新たに約5100万円の不正経理が判明し、これまでの公表分と合わせた不正総額は約5億3500万円に上るとの最終報告書をまとめた。
北大は、新たに分かった不正に関与した15人のうち、現職の教員13人を停職などの処分にした。関与した教員は退職・転出者も含め計59人になった。山口佳三学長ら理事8人は監督責任があったとして7月分の給与の10分の1を自主返納する。流用分は教員らに返還を求める。
今回の調査は2004〜06年度分と退職・転出者が対象。その結果、教授ら13人が物品購入を装い、実際には購入額に相当する研究費を業者に預けていたり、使用目的以外に使ったりする不適切な経理処理をしていたことが分かった。退職・転出した2人も同様の不正経理をしていた。
研究費を車のタイヤ購入費などに私的流用したとして、元教授(60)が詐欺容疑で道警に刑事告訴されているが、調査委は今回の15人に私的流用はなかったとしている。
処分内容は停職1カ月4人▽出勤停止10日4人▽戒告2人▽訓告3人−−で、退職・転出した2人は処分対象外。記者会見した山口学長は「再発防止に全力で取り組み、信頼回復に尽くしたい」と陳謝した。【千々部一好】
これだけの騒ぎを起こしたし、税金が投入されているのだから失敗又は嘘であれば当然とは思う。
小保方氏 「損害賠償請求」「研究費返還」求められる可能性 07/14/14 (週刊ポスト)
現在、理化学研究所ではSTAP細胞の検証実験準備が行なわれている。小保方晴子・研究ユニットリーダーも理研チームとは別棟の独立した場所で再現実験に参加することになり、当面、懲戒処分審査が中断されることになった。
実験期間は11月末までとなっている。本人は「200回成功した」と会見で発言しているが、「見込みなし」あるいは健康状態が不安定で本格的に取り組めないとなれば途中で打ち切りとされる可能性もある。
理研の調査委員会はすでに「研究不正」を認定する調査結果を出しており、STAP細胞が再現できなければ退職金なしの懲戒解雇も十分あり得る。
年収800万円とも1000万円とも報じられる職を失うだけではない。荘司雅彦・弁護士はこう語る。
「小保方さんに、理研から損害賠償請求訴訟が行なわれる可能性があります。理研の信用を失墜させ、その結果寄付金収入などが減ったとなれば、それを請求することはあり得る。あるいは成功していない実験を成功したとの報告をして予算を出させたとなれば、それも請求の理由になり得ます」
今回は不正を見抜けなかった理研のガバナンスにも問題があることから、損害賠償が実際に行なわれるかは微妙なところではあるが、原資は税金だけにうやむやにすることは許されない。問題はまだある。
早稲田大学大学院時代に受け取っていた、税金で支出された「研究奨励金」などの返還が求められる可能性があるのだ。2008年から3年間、小保方氏は日本学術振興会の特別研究員として、毎月20万円の研究奨励金が支給されていた。また、最大で年間150万円の研究費も大学に補助されていた。3年間で総額1000万円以上になる計算だ。
それを受け取って執筆した博士論文に、米国専門サイトなどからのコピー・アンド・ペーストなど数々の疑義が呈されている(早稲田大学広報室は「小保方氏の論文については調査委員会で調査中」と回答)。
日本学術振興会によれば、「研究奨励金は、不正行為などがあれば返還要求できる規定がある。研究費補助についても捏造や改ざん、盗用などの不正行為があれば返還させることができる」という。
そのような事態となれば、以前と変わらない個人タクシー出勤&ブランド品生活を諦めるどころか、自己破産ということにもなりかねない。
理研に1日でも長くいれば、少なくともその間は給料が出る。それが再現実験参加に意欲的だった理由ではない、と信じたい。
※週刊ポスト2014年7月25日・8月1日号
ベネッセコーポレーションの幹部はグループ会社「シンフォーム」が派遣会社SEを使っている事を知っていたのなら自業自得。メリットとデメリットを考えてコストとは何かを考えるべきであった。
派遣会社SEが「金が欲しかった」と認めたのであるなら、警察はどのように複数の名簿業者に情報が流れたのか徹底的に調べるべきである。仲介者がいたのか、名簿業者の社員と接触したのか、調べる事が出来るはずである。お金を貰っていたのなら誰からなのか、現金なのか、振込なのかは派遣会社SEが知っているだろう。接触者が偽名や嘘の会社名と使っていたとしても、名簿業者に情報を流した人物を特定すればある程度、本人を限定、又は特定できるはずだ。名簿業者が現金で情報の対価を支払っていれば不正な方法による取得を知っていた疑いが強くなる。さらなる調査をすれば他のケースも出てくる可能性は高い。名簿業者が不正な情報だと知らなかったと言っても足跡が付かないように対応していれば疑って捜査するべきだ。
派遣会社SE「金が欲しかった」…ベネッセ流出 07/14/14 (読売新聞)
ベネッセコーポレーションから顧客情報が大量に流出した問題で、顧客情報を持ち出した疑いが持たれているシステムエンジニア(SE)の男性が警視庁の任意の事情聴取に対し、持ち出しへの関与を認めた上で、「金が欲しかった」と話していることが関係者への取材でわかった。
顧客情報は複数の名簿業者に出回っており、不正競争防止法違反(営業秘密領得、開示)容疑で捜査している同庁は、SEが持ち出しの対価として、金銭を受け取っていた可能性があるとみて捜査を進めている。
関係者によると、ベネッセ社は顧客データベース(DB)の管理を、グループ会社「シンフォーム」(岡山市)に委託。DBは、シ社の東京都多摩市の事業所に置かれていた。SEは派遣社員として、この事業所でDBの管理業務に就いていた。
派遣社員にデーターを管理させる行為は、セキュリティーを優先させると間違いだ。ベネッセコーポレーションの幹部が判断したのなら改善するべきである。派遣社員は期限付きの不安定な身分。正社員だから情報漏洩をしないとは言い切れないが、派遣社員であればリスクは高くなると考えるべきだ。
持ちだされたデータがどのように名簿業者に流れたのか徹底的に調べるべき。同じように名簿業者にデータが流れるシステムが出来上がっていると推測出来る。不正取得された情報でない情報はどのような情報なのか?明確に警察は名簿業者に回答させるべきである。「言うな、聞くな」が暗黙の了解になっているのではないのか?
名簿業者、ベネッセから流出「知らなかった」 07/14/14 (読売新聞)
ベネッセコーポレーションから顧客情報が大量に流出した問題で、顧客情報を取引した名簿業者2社が警視庁の任意の事情聴取に「ベネッセから流出した顧客情報だとは知らなかった」と話していることが捜査関係者への取材でわかった。
同庁は不正競争防止法違反で流出ルートの解明を進めているが、名簿業者などが不正取得された情報だとは知らずに入手していれば同法の適用は困難なため、同庁では顧客情報を買い取った経緯について、引き続き業者側から事情を聞く方針。
同庁では、顧客情報約257万件がソフト開発会社「ジャストシステム」(徳島市)に渡った流出ルートを重視。同社では入手した顧客情報をもとに通信教育のダイレクトメール(DM)を小中学生の自宅に発送していた。
捜査関係者によると、事情聴取を受けたのは、ジャスト社に顧客情報を提供した名簿業者と取引があった東京都武蔵野市の業者など2社。いずれも顧客情報を売買していたことは認めたが、情報がベネッセ側から流出していたことは「知らなかった」などと説明しているという。
ベネッセ流出、派遣社員が任意聴取で関与認める 07/14/14 (読売新聞)
ベネッセコーポレーションから顧客情報が大量に流出した問題で、警視庁が、顧客情報の持ち出しに利用されたIDを持つシステムエンジニア(SE)の男性から、任意の事情聴取を始めたことが捜査関係者への取材でわかった。
SEは同庁に対し、情報持ち出しに自身が関与したことを認めているという。同庁は引き続き、SEから事情を聞くと共に、今後、不正競争防止法違反(営業秘密領得、開示)容疑でSEの関係先を捜索する方針。
関係者によると、ベネッセ社の顧客情報は、グループ会社「シンフォーム」(岡山市)の東京都多摩市にある事業所のデータベース(DB)に保管されていた。情報が持ち出されたのは昨年末で、この事業所で派遣社員として働いていたSEのIDで複数回にわたってログインされていたという。
個人的には行政や東電の対応は想定内。だから福島の食べ物は敬遠する。農家が悪いとかそういう問題じゃない。ただ、常識で考えればリスクがあるのは理解できるはず。
コメ汚染が確認されるまで対応しなかった、又は、リスクを考えなかった行政にも問題がある。無知がゆえに対応しなかったのか、天に祈りながら、問題を見て見ぬふりをして来たのだろう。行政が事前の対応をしないのでどちらのケースにしても個々の責任でリスクは回避するべきだと思う。
がれき撤去で飛散、コメ汚染 福島第一の20キロ先水田 07/12/14 (朝日新聞)
東京電力福島第一原発で昨夏に実施した大規模ながれき撤去作業で放射性物質が飛散して、20キロ以上離れた福島県南相馬市の水田を汚染した可能性を農林水産省が指摘し、東電に防止策を要請していたことが分かった。福島県は「他の要因は考えられず、がれき撤去の可能性が限りなく高い」としている。東電は要請を受けて撤去作業を凍結してきたが、広範囲に飛散した可能性を公表しないまま近く再開しようとしている。
原発から20キロ以上離れた南相馬市の避難区域外の水田14カ所と、20キロ圏の避難区域内の5カ所で昨秋に収穫されたコメから基準値(1キロあたり100ベクレル)超のセシウムが検出された。農水省が調べたところ、放射性物質は8月中旬に出始めた穂などに局所的に付着。事故当時に飛散した放射性物質を土壌から吸い上げたのなら均一的に検出されるため、穂が収穫された9月末までの間に新たに飛んできたものと分析した。
この間の8月19日、東電が第一原発3号機の大型がれきをクレーン車で撤去する際、がれきの下敷きになっていた放射性の粉じんが飛散し、別の場所にいた作業員2人が被曝(ひばく)して頭部から最大1平方センチあたり13ベクレルが検出された。この時、風下の北北西方面の5カ所の測定点(原発から2・8~8・3キロ)でも空間線量が上昇し、福島県はがれき撤去による飛散が原因と推定していた。
農水省は(1)コメからセシウムが検出された南相馬市はさらに風下にあたり、8月19日のSPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)の計算では3時間で達する(2)基準超が複数検出されたのは同市だけ(3)前年度は同地域のコメから基準超は検出されていない――などの理由から、8月19日のがれき撤去で飛散した可能性があると判断。今年3月に東電に再発防止を要請した。東電は「どこまで飛散したか把握していないが、防止対策に取り組みながら近く作業を再開する」としている。
東電は3号機のがれき撤去を終えたが、高線量のがれきが残る1号機は手つかずで、建屋を覆ったカバーを近く解体する方針だ。「最も早く作業が進む方法だが、放出量は増える」とし、飛散防止剤の散布を増やして対応するという。それでも天候や風向き次第でどこまで飛散するかは不透明だ。村山武彦東工大教授(リスク管理論)は「飛散の可能性を情報提供するのが大前提だ」と指摘する。(青木美希)
ここまで分かっているのなら犯人もかなり絞れたのか、分かっているのでは?
ベネッセ流出、持ち出し複数回…小分けし複写か 07/12/14 ( 読売新聞)
ベネッセコーポレーションから顧客情報が大量に流出した問題で、顧客情報は社内のデータベース(DB)から複数回に分けて持ち出されていたことが関係者への取材で分かった。
持ち出されてから間もなく名簿業者に出回っており、警視庁は当初から売却目的で情報が持ち出されたとみて、不正競争防止法違反(営業秘密領得、開示)容疑で捜査している。
関係者によると、DBは、管理を請け負っていたベネッセ社のグループ会社「シンフォーム」(岡山市)の東京都多摩市の事業所に設置され、操作する端末がある部屋には、関係者以外は立ち入れないことになっていた。
同社からDBの管理業務の再委託を受けていた会社のシステムエンジニア(SE)のIDで昨年末、複数回のログイン記録があり、顧客情報が持ち出された形跡があった。このDBには約2070万件の顧客情報が保存されていたといい、顧客情報が大量だったことから、USBメモリーなどの記録媒体に小分けして複写したとみられる。
制度自体に問題があると思う。外国人技能実習自体、建前の制度。
外国人技能実習、230団体で不正…昨年 07/12/14 ( 読売新聞)
外国人技能実習制度で来日した外国人に対し、賃金の不払いや人権侵害などの不正を行った受け入れ団体・機関が、昨年は計230団体に上り、2010年に現行制度が始まって以降、3年連続で増加していることが法務省の調べで分かった。
同省は、こうした団体に対し、現在はない罰則を科す仕組みをつくる方針だ。
不正行為の件数も大幅に増え、昨年は前年比126件増の366件となった。内訳は、「賃金等の不払い」が99件で最も多く、受け入れ当初に必要な講習を実施しないといった「研修・技能実習計画との齟齬(そご)」が87件、「講習期間中の業務への従事」が79件の順となった。
具体的なケースでは、ある農業関係の受け入れ機関が、技能実習生が起こしたトラブルを理由にパスポートと在留カードを取り上げ、返却しなかった。水産加工の工場では、水産加工業務が減少していたことから、受け入れ計画と異なる食肉処理の作業に実習生を従事させていた。
たしかに「傘下のベネッセコーポレーションから流出した情報をジャストシステムが全て削除すると発表した」判断は良くない。ジャストシステムがはやく幕引きをしたかったのか、名簿業者からのお願いなのか、両社にとって良いと判断した結果なのか?
ジャストシステムの企業体質や経営陣が問われる判断だと思う。
ベネッセ原田社長、ジャストシステムを批判 「一方的なデータ削除は原因究明を難しくする」 07/12/14 ( ITmedia ニュース)
ベネッセホールディングスの原田泳幸会長兼社長は7月12日、傘下のベネッセコーポレーションから流出した情報をジャストシステムが全て削除すると発表したことに対し、「一方的に情報を削除することは、警察や経済産業省による原因の究明を難しくするだけでなく、情報が漏えいしたお客様の不安感の払しょくには至らない」と批判するコメントを発表した。
ジャストシステムは7月11日、名簿業者を通じて購入した約257万件の個人情報を削除すると発表。「データの出所が明らかになっていない状況で契約に至り、購入していたことが判明」したため、「企業としての道義的責任」と説明している。
原田社長はコメントで、「今回の情報漏えいは教育業界全体への信頼を毀損(きそん)する大変な事件であり、関係する者が自らの利益を守るというレベルで行動すべきではありません」とした。
その上で、再発防止に向け、被疑者の特定だけではなく、データの流通ルートを解明し、流出した個人情報が出回っていないことを検証する必要があるとして、ジャストシステムなど情報を購入した企業や名簿業者に対し、「事実関係をつまびらかにし、お客様の不安を解消するため、積極的に情報を開示し、自主的に警察の捜査へ全面的に協力することを強く要請します」と情報開示を求めた。
一方、「我々は自らの責任を他社に転嫁するものではありません。当社の責任は真摯に受け止め、全力をもって解決にあたって参ります」としている。
名簿業者のたらい回し。今回の事件から学び、法整備を行うべきだ!
ベネッセ漏えい事件「名簿業者」の実態 07/12/14 (読売新聞)
ベネッセコーポレーション(岡山市)が起こした顧客情報漏えい事件では、名簿・データベースを販売する「名簿業者」「データベース販売業者」が問題となっている。漏えいした個人情報が収集・分析・名寄せが行われ、堂々と販売されているのだ。(ITジャーナリスト・三上洋)
「小学6年生のデータ 1件15円~」と堂々と販売されている
ベネッセによる情報漏えい事件は、760万件の顧客情報が漏れたが、それが発覚したのは他社による利用があったからだ。ジャストシステム(徳島市)の関連会社が送ったダイレクトメールが、ベネッセに登録した顧客に届いたことから騒ぎとなり、漏えい事件が発覚した。データをジャストシステムに販売したと報道されている東京多摩エリアの名簿業者のウェブサイトをのぞいてみた。販売しているデータベースのサンプルとして
「小学6年生のデータ 1件15円~ 中学校入試のための塾や進学にあわせたアプローチに活用できます」
と掲載されている。この他にも
「18歳女性のデータ(振り袖専用リスト) 1件25円~」
「投資目的のマンション購入者リスト」
「新築物件情報リスト」
「通信販売購入者リスト」
などを堂々と販売している。
同社のウェブサイトには「日本で唯一全国規模のチャイルド・ローティーンに絞ったデータベースを提供」との宣伝がある。まさに今回のような教育事業者向けに特化した名簿業者と言えるだろう。
同社は、問題のデータを「今年4月下旬~5月ごろ、他社から購入した」とコメントしており、その会社は同じ東京多摩エリアにある会社だと報道されている。その会社のウェブサイトを見ると多岐にわたったデータベースが販売されている。
ゴルフ愛好家=約8万4000人、マンションオーナー=約2万9000人、勤務先付きビジネスマン=約100万人、通販利用者ダイエット=約44万人といったような名簿が、堂々と販売されている。ゲーム利用者から会社経営者まで、あらゆる層のデータが販売されているようだ。
一定の条件を満たせば名簿販売は合法
このように名簿業者は堂々と営業活動をしており、様々な個人情報を集約したデータを販売している。この名簿業者の問題点をまとめておこう。
●現行の法律では、一定条件を満たせば合法
個人情報保護法では、一定の条件を満たせば、名簿・データベースの販売が認められている(本人からの削除の申し出があった場合に提供を中止するなどの条件)。そのため名簿業者の多くはいわゆるオプトアウト(拒否・削除などの手続きのこと)の説明があり、これが合法であることの証明の一つともなっている。しかしながら、「自分で調べて、自分で申し出をしないと、勝手に販売されてしまう」という現状は、掲載されている人にとって不愉快なものだと筆者は考える。
●そもそも、どこから入手したのか? 漏えい・流出がほとんどではないか
名簿の販売自体は法律上問題がないとしても、入手した手段が不正である可能性が高い。たとえば「通信販売利用者 ダイエット」という名簿は、ダイエット関連商品を販売した業者からの流出の可能性が疑われ、正当な方法で入手したものとは考えにくいと思う。このようなデータを販売すること自体に問題があり、法律の改正を考えるべきだろう。
●「名寄せ」「クレンジング」によって名簿の価格を高くしようとする
名簿業者には複数のデータが集まる。ここで行われるのが「名寄せ」「クレンジング」という作業だ。異なるデータから、同一人物・同一家庭のデータを組み合わせて、情報の価値を高める作業だ。たとえば「小学校6年生のデータ」と「年収1000万円以上のビジネスマンリスト」を組み合わせて、「年収1000万円以上で小学校6年生の子供がいる家庭」といったデータが出来上がる。こちらのほうが価値が高くなり、データも高く売れる。そのため名簿業者の多くが名寄せ・クレンジングを行い、抽出したデータを販売している。
●名簿業者同士の売買で流出元が不明になる
名簿業者を利用する企業は、どこから流出したのか知らずに利用する。今回の事件でもダイレクトメールを送ったジャストシステムの関連会社は「ベネッセからの流出だとは認識していなかった」とのコメントを出している。名簿業者が流出元を言わない上に、名簿業者どうしの売買によって、元のデータがどこからのものかが不明確になるからだ。不正な手段で流出したものであっても、グルグルと転売を繰り返し、また上記の「名寄せ・クレンジング」によって、流出元がわからなくなってしまう。
このように名簿業者の問題は、たとえ現時点で合法であったとしても、勝手に掲載されている私たちにとっては、迷惑なことが山積している。ベネッセ漏えい事件は、この問題を大きくクローズアップしたと言えるだろう。
個人情報保護法の見直しと私たちの行動の注意点
偶然ではあるが、この個人情報保護法の見直しが始まっている。官邸のIT総合戦略本部が「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し大綱」を6月25日に出し、7月24日を締め切りとしたパブリックコメントを募集している(「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する意見募集について:内閣官房IT総合戦略室)。この大綱は、ビッグデータ時代のパーソナルデータの扱いに関するものだが、データベースの第三者利用を含んでおり、個人情報保護法の改正も視野に入っている。
ベネッセの事件で明るみになった問題点を基にして、個人情報保護法の改正を望みたい。興味のある方は、パブリックコメントを出していいだろう。
情報漏えいについて、私たちが対策で阻止できる点は非常に小さい。しかし普段から心がけておくべきことがあるので簡単にまとめておこう。
●アンケート・プレゼント応募は「個人情報を売ること」と思う
アンケートに応じたり、プレゼントに応募することを控える。集められたデータは、自社で使うだけでなく第三者に販売されたり、名簿業者に転売される可能性があるからだ。タダでもらえるのではなく「個人情報を売ってもらうもの」と考えて、できるだけ応募しないようにする。
●無料登録のサイト・サービスには、プライベートな情報をできるだけ記入しない
無料サービス・無料サイトでは、できるだけ自分の属性(年収や職業など)を書かないようにする。記入する情報が多過ぎる場合は、回避することを考えよう。
●不審なダイレクトメールは要調査
ダイレクトメールが届いた場合、どこからの情報なのか、公式なデータなのかを考えてみる。場合によっては発送元に問い合わせることも検討。
防衛できることは少ないが、むやみに自分の属性を明らかにしないことは重要だと覚えておきたい。
夢見る高齢者・セレブデータ…名簿売買、野放し 07/10/14 (読売新聞)
ベネッセコーポレーションの顧客情報が大量に流出した問題は、改めて個人情報が「公然」と売買されている実態を浮き彫りにした。
名簿を取り扱う業者を規制する法律はなく、子どもに関する様々な情報が漏れた可能性のある保護者は不安を募らせる。消費者問題の専門家からは「名簿の売買を規制すべきだ」という声も上がっている。
今回の流出では、複数の名簿業者を通じて、通信教育事業を手がけるソフト開発企業「ジャストシステム」(徳島市)にベネッセ社の顧客情報が流れたことがわかっている。
「野放しと言っても過言ではない」。大量の名簿が売り買いされている実態に、警察幹部はそう述べ、危機感を強める。
「セレブデータ」「夢見る高齢者」「大手企業退職者」……。全国の警察は、振り込め詐欺など特殊詐欺事件の捜査で、様々な名簿を押収している。
ベネッセ名簿、ジャストシステムが業者から購入 07/10/14 (読売新聞)
「進研ゼミ」などで知られるベネッセコーポレーションの顧客情報の大量流出問題で、通信教育事業を手がける東証1部上場、ソフト開発会社「ジャストシステム」(徳島市)が、流出した顧客情報を東京都昭島市内の名簿業者から購入し、ダイレクトメールを出していたことが、名簿業者への取材で分かった。
この名簿業者は、都内の別の業者から名簿を購入したという。警視庁ではジャスト社へ名簿が流出した経緯について捜査を進めている。
ジャスト社に販売した名簿業者によると、顧客情報の流出後、ジャスト社と連絡を取ったところ、ジャスト社から「顧客には、名簿の購入先として御社の名前を出した。顧客から電話があった際には、対応してほしい」と言われたという。名簿業者は複数の個人情報を購入した際、この中にベネッセ社の情報も含まれていたという。
名簿業者は「流出が問題となっている個人情報は、不正なものと全く知らずに購入したもので非はない。購入先の名簿業者が情報をどうやって入手したかはわからない」と話した。ジャスト社は「担当者がいないので何もお答えできない」と話している。
ジャスト社は、1979年に創業。ワープロソフトの「一太郎」や日本語入力ソフト「ATOK(エイトック)」で知られる。
多重債務者斡旋 競争激化で困窮の弁護士「報酬50万、飛びついた」 07/09/14 (産経新聞)
東京都内の弁護士数人が、弁護士資格のないNPO法人元代表の紹介を受けて債務整理を行い、報酬の一部をNPO側が受け取っていた問題。“正義の味方”であるはずの弁護士が、なぜ違法な商売に手を貸したのか。弁護士への取材から浮かんだのは「経済的困窮」から違法行為に手を貸す様子だった。
◆「赤字続き…」
「仕事が減って困っていた。月50万円という言葉に飛びついてしまった」
平成22年から約2年間、元代表と提携していた50代の男性弁護士は、産経新聞の取材にこう振り返った。「近年は弁護士が増えて仕事が取れなくなった。事務所は赤字状態が続いていた」とも打ち明けた。
当初、先輩弁護士から「債務整理の仕事をしないか」と誘われた。週3、4件のペースで払い過ぎた利息(過払い金)の返還交渉などを手がけ、多重債務者から手数料などで月300万円を得たこともあったが、実際には事務員が大半を元代表へ送金していたという。
この弁護士は「実務は自分でやっていたので違法性はないと思っていた」と訴えた。
別の40代男性弁護士には「月100万円の報酬」が提示された。当時、弁護士は仕事があまり得られない状況だったという。「事務員に経理を任せていた。帳簿上、全て自分の報酬になるのかと思っていた」と釈明する。
◆懲戒者を標的
23年3月まで元代表と提携していた70代男性弁護士は「経理をNPO側に任せるのは危険だと思った」と振り返る。
同僚弁護士の業務を引き継いだが、元代表との提携が違法だと気付き約1年で提携を打ち切った。「飛びついて抜け出せなくなる弁護士も多いのではないか」と振り返る。
元代表は20年以降、少なくとも7人の弁護士と提携。多くは仕事量が減ったり、懲戒処分を受けたりして経済的に困窮していたという。「そうした弁護士に定期的な報酬を確約することで人員を確保し、債権回収をビジネスとして成立させていた」(検察幹部)
日弁連の調査(22年)によると、平均的な弁護士の年間所得(中央値)は、12年の1300万円から10年間で959万円にダウン。「10年前に比べて弁護士間の競争は厳しくなったか」との質問には、4割以上が「そう思う」と回答した。
別の検察幹部は「弁護士数の急増もあるのかもしれないが、弁護士には高いモラルが求められる。困窮しているといって、法に抵触した行為をするのは言語道断だ」と話している。
ODAリベート、提供の鉄道コンサル社長が辞任 07/08/14 (読売新聞)
政府開発援助(ODA)事業を巡り、ベトナムなど3か国の政府関係者に対し、計約1億6000万円の不正リベートを提供していた鉄道コンサルタント会社「日本交通技術」(JTC、東京)の柿沼民夫社長(65)が、責任を取り6月30日付で代表取締役社長を退いたことがわかった。
JTCでは当面、社長を置かないという。
JTCによると、同日の取締役会で、柿沼氏が引責辞任し、代わって代表取締役に大河原達二・常務取締役(58)が就くことが決まった。柿沼氏は非常勤顧問としてJTCに残るという。柿沼氏は4月28日の記者会見で、「最高責任者として責任を痛感している。しかるべき日に辞任する」と話していた。
JTCに対しては、東京地検特捜部が、不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)容疑で捜査を進めている。
日本ODAのベトナム賄賂問題、両国が迅速に対応 海外紙「ベトナムは日本のODA消極化を懸念」と分析 (1/2)
(2/2) 03/27/14 (NewSphere)
読売新聞は先週3月21日、ベトナム国内における日本の政府開発援助(ODA)によるプロジェクトに関する贈収賄を報じた。これを受けてベトナム政府、運輸省は早急に調査に乗り出した。海外メディアはベトナム側の対応と国内の反応を報じている。
【ODAプロジェクトに関わる賄賂】
読売新聞社によるとJTCの柿沼民夫社長は、ODA資金によるプロジェクトを42億円相当にすることを交換条件に、同社が8,000万円の賄賂を支払ったことを認めた。他にもODA 資金のプロジェクトを請け負うためにベトナム、インドネシア、ウズベキスタンの公務員に賄賂を渡した。2008年2月から今年までの賄賂の総額は、1億3,000万円にも及ぶという。
報道を受けて、ベトナム運輸省は日本交通技術株式会社(JTC)に賄賂を受け取ったベトナム鉄道役員の特定と詳細な情報提供を求める書面を送ったと、ベトナムの新聞『Tuoi Tre』紙は報じている。
すでに4人の鉄道役員が停職処分になり、問題のプロジェクトとJTCに関する責任についてのレポートの提出を言い渡されているという。処分を受けたひとりは『Tuoi Tre』紙に、問題になっているプロジェクトはハノイのYen Vien-Ngoc Hoi鉄道であることを明かした。
【ベトナム政府の対応】
Nguyen Ngoc Dong交通運輸次官は、現地時間火曜日にベトナムを出発、東京の税務当局、東京検察の特別捜査チーム、読売新聞と直接やり取りするために来日した。日本からの収賄者のリストを求め、至急所轄官庁に提出するとした。運輸省の視察責任者Nguyen Van Huyen氏によると、リストが発表されれば調査チームが個別的に対応していく。今後JTCに関わるプロジェクト全ての調査が行われ、関係するプロジェクトの入札が適切な規則に基づいたものかどうかも調べるという。
『Tuoi Tre』紙によると、現地時間の25日火曜日ハノイで、ファン・ミン・ビン、ベトナム副首相兼外相が福田博大使と会談した。副首相は、近年日本のODA資金による建設事業や開発事業への援助に感謝する意向を強調したという。また安倍首相が、ベトナムの持続可能な開発のためにODA政策において同国を重要なパートナーとして位置付けると表明したことを評価した。
その上で、今回の件に関して首相が国内の関係各社に、日本関係者との連携を図るよう指示したことを伝えた。
ベトナム政府が適切な法律に基づいて徹底的に調査する姿勢を示していることを主張し、日本側にも早急に詳しい情報の開示を要請したという。これに対し、福田大使はベトナム側の迅速かつ積極的な応対を評価した。また事件解明に向けてベトナムとの緊密な連携体制を約束した。
【ベトナム国内の反応と今後の両国の対応】
オンライン新聞『VietNam net』は、今回の賄賂事件がソーシャルメディアや国営メディアで、公務員の間で白熱した議論を呼んでいると報じた。経済学者Le Dang Doanh氏は米ニュース番組ボイス・オブ・アメリカ(VOA)に、「非常に遺憾で恥ずべきことだ」と述べた。「今回の件は日本とベトナム間の連携と、日本のODA資金に影響を及ぼすことになった。良好な相互関係が続いてはいるものの、ODA資金が税金から出ていることを考えても、今回のことをきっかけに日本が消極的な対応になる可能性がある」と指摘した。
ダイキン元課長、2億5千万円水増し請求し着服 07/08/14 (読売新聞)
総合空調メーカー「ダイキン工業」(本社・大阪市)の50歳代の元男性課長が、社内システムの外注先に費用を水増し請求させ、キックバックを受ける手口で着服し、今年4月に懲戒解雇されていたことがわかった。
水増し請求は少なくとも昨年3月までの5年間で約2億5000万円に上る。同社は近く、元課長や外注先を大阪府警に刑事告訴する。
同社によると、元課長は長年、同社の情報システムなどを担当。システムの構築や保守を発注した2社に対し、外注費を水増しするように依頼し、水増し分の大半を自分が管理する銀行口座に振り込ませていた。着服した金は遊興費などに充てたという。社内調査に対して事実関係を認めたため、同社は解雇した。
着服は、大阪国税局の税務調査で判明。同国税局は同社が支払った水増し分について、経費と認められないと判断した。ほかの経理ミスと合わせ13年3月期までの5年間で計約8億円の申告漏れを指摘。重加算税や過少申告加算税を含めた約2億4000万円を追徴課税(更正処分)した。
大学生は大人か、子供か。大人として認めるなら大学はそれなりの処分はするべきであろう。
「歌舞伎町“集団昏睡”事件」日本女子大生を陥れる明大野獣サークルの手口(1)パンツ丸出しの露な姿に 07/08/14 (アサ芸プラス)
新宿旧コマ劇場前で、明治大学のサークルに所属する複数の若い女性が昏倒する騒動が発生した。嘔吐、失禁など、ヤジ馬の視線そっちのけで倒れる男女たちは、いずれも「スーパーヤリヤリサワー」なるドリンクを飲んで、異常事態に陥ったという。かつて世間を驚愕させた「スーパーフリー事件」に悪用された“劇薬”を女子大生に飲ませたサークルメンバーの悪質手口とは──。
騒動は、6月20日午後10時過ぎに発生した。新宿・歌舞伎町の旧コマ劇場前は、週末も手伝って、多くの酔客でにぎわっていた。ところが、その通行人をかき分けるように、10人を超える若い男女が、路上で突然、意識を失って倒れたのだ。周囲には、有毒なガスが発生したような形跡もなければ、火災が起きた様子もまったくない。その場に居合わせた目撃者も、あまりにも不可解な光景に、騒然となったという。目撃者の男性が語る。
「若い女性があっちこっちで意識を失ったように倒れていて、地下鉄サリン事件や集団食中毒など、何か大きな事件に巻き込まれたのかと思いました」
すぐに、現場には警察官や救急隊員が駆けつけた。すると、周囲で昏倒している若者を介抱していた男性が顔面を蒼白にして、
「やばい! 通報された。早く起こせ!」
などと、周囲の仲間に呼びかけたという。目撃者が続ける。
「倒れている女性たちは彼らの呼びかけに反応しないどころか、嘔吐を繰り返したり、失禁して道路にシミを作っている女性や、パンツ丸出しで大きい方をしている人もいて、ニオイも臭くて異様な光景だった」
一瞬、警察官の間に「すわっトラブルか」と緊張が走ったが、その後、関係者に聴取を進めると、その場で倒れていたのは、明治大学と日本女子大学の公認のインカレサークル「K」に所属する学生の集団だとわかったのだ。社会部の記者が騒動を振り返る。
「警察に応対した男子学生は、『練習後に約30名のメンバーが旧コマ劇近くの居酒屋で飲み会をして、飲みすぎて倒れてしまっただけ』と説明。警察も薬物の症状などが見られなかったため、事件性はないと判断したようです。複数倒れている中で、急性アルコール中毒で女性(20)と男性(22)が1名ずつ救急車で搬送され、それ以外の学生は介抱していた学生の肩を借りて、その場から移動していきました」
新宿の繁華街で、酔っ払いが急性アルコール中毒で病院に運び込まれるといったケースは少なくない。しかし、10名近くのサークルメンバーが一斉に路上に昏倒する光景は、あまりにも異様だった。
「その場にいたヤジ馬が、写真や動画を次々にネット上にアップ。事件性はなかったものの、すぐに情報が拡散され、最終的には、大学側が謝罪する騒動となった」(前出・社会部記者)
だが、騒動はこれだけでは収まらなかった。このサークル「K」では日常的に、男女メンバーが入り乱れてのコンパが行われており、その場で「スーパーヤリヤリサワー」なるドリンクを飲んでは、乱痴気騒ぎを繰り返していたというのだ。
女子大生「集団昏睡」で明大が謝罪…日本女子大は参加を否定 06/25/14 (日刊ゲンダイ)
6月20日夜11時ごろ、新宿・歌舞伎町の旧コマ劇場前で「女子大生ら10人以上が集団で昏倒している」とネット上で大騒ぎになっていた問題が急展開だ。サークルの学生の関与が疑われていた大学側が24日、釈明する事態に追い込まれた。
この騒動は、旧コマ劇前で異様な光景を目撃した通行人らがツイッター上に写真をアップしたことから始まった。写真には、何人もの若い女性が折り重なるように路上に倒れ、スカートがめくれたり、パンツが丸見えになっている姿が写っていた。ツイートによれば複数の警官が出動し、倒れた女性が「脱糞している」との報告もあって、ネット上ではすぐに“犯人捜し”が始まった。そして、瞬く間に明治大学と日本女子大の公認テニスサークルではないかと、検証する投稿が相次いだ。
サークルの男子メンバーの服装や過去のツイートなどから「一致した」とする書き込みや、<男子メンバーのひとりが、カプセル状のものに何かを仕込んだ画像をツイッターで公開していた>などの情報が錯綜。男女のグループなのに、倒れているのが女性ばかりだったことから、「スーフリの再来か」「酒に何か入れたんじゃないか」と騒ぎは日増しに拡大し、大学側は事実を明らかにすべきだ、という声が高まっていた。
こうした事態を受け、明大は24日、「本学公認サークルに関する報告」と題した記事をホームページに掲載。<新宿旧コマ劇場前で大学生が昏倒していた写真及びその情報が、インターネット上に流れております。この内容について確認したところ、本学公認サークルに所属する部員であることが判明いたしました。本学学生がお騒がせしましたことを心からお詫び申し上げます>と謝罪した。
ただし、一部の疑惑を打ち消すように、<本件については、過度の飲酒から起きた出来事であり、>と強調。<昏倒していた部員の中には未成年者が含まれていることも判明いたしました。なお、これらの部員の体調は回復しております。また、詳細については現在確認中です。結果が判明次第、当該サークルに対し、厳正に対処いたします>と釈明した。
一方、集団昏睡の“被害者”サイドとみられていた日本女子大も同日、ホームページに「本学公認サークルに関する報告」と題したリリースを発表。
<大学でおこなった現時点までの確認では、この会への本学学生の参加は確認されていません。ただし本学の大学公認サークルであることは事実ですので、今後の対応について協議する予定です。この度はお騒がせし、大変申し訳ございませんでした>としている。
世界の科学誌は完ぺきではないし、理研のずさんさがまた1つ明らかになった。
STAP論文、2年前に「ES細胞混入」と指摘 07/07/14 (読売新聞)
理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダーが2012年7月にSTAP(スタップ)細胞の論文を米科学誌サイエンスに投稿した際、審査を担当した研究者から「ES細胞(胚性幹細胞)が混ざっている可能性がある」と指摘されていたことが7日、理研内部の資料でわかった。
サイエンス誌は掲載を見送ったが、英科学誌ネイチャーは14年1月にほぼ同じ趣旨の論文を掲載した。
STAP細胞は、遺伝子データの解析結果などから、実際はES細胞であるとの疑義が上がっている。小保方氏らは2年前にこの指摘を受けていたことになる。
サイエンス誌は3人で論文を審査し、そのうち1人は、STAP細胞ができたとの実験結果は既存の万能細胞のES細胞が混入した場合でも説明でき、その可能性を否定する十分な根拠が示されていないとした。
たとえ「配管の弁に3ミリほどの穴」でもまわりも腐食している可能性が非常に高い。取り替えないと穴は大きくなるし、応急処置と選択しても長く持たないだろう。
配管に穴、海水1・3トン漏れる…福島第一原発 07/07/14 (読売新聞)
東京電力は、福島第一原子力発電所5号機で配管が破損し、燃料の保管プールを冷やすための海水約1・3トンが原子炉建屋内に漏れたと発表した。
海水に放射性物質は含まれていない。東電はプールの冷却を一時中止し、原因を調べている。
東電によると6日午前、原子炉建屋1階で配管の弁に3ミリほどの穴が開き、海水が漏れているのを作業員が見つけた。
5号機は東日本大震災で大きな被災は免れた。1月に廃炉となったが、1~4号機の廃炉作業を進めるための訓練施設になる予定で、今も使用済み燃料や未使用の燃料を保管している。海水は燃料の保管プールを冷やすために使っているという。
プールには994体の燃料があり、7日朝の時点で水温は約25度。東電は「安全管理の上限である65度になるまで8日程度かかり、それまでに復旧させる」と説明している。
専門家ではないが、常識で考えれば失敗する可能性があると思っていた。単純に物を大きくしても成功しないケースはいろいろとあるからだ。凍土遮水壁はどこの企業が担当しているのか?成功しなければ約320億円もの税金をどぶに捨てたのと同じ。
「凍土壁」に暗雲、着工2か月でトンネル未凍結 07/07/14 (読売新聞)
東京電力福島第一原子力発電所の配管用トンネルを凍結止水して汚染水を抜き取る計画に対し、原子力規制委員会は7日、「凍結管の冷凍能力を大幅に強化すべきだ」と指摘、工事方法を抜本的に見直すよう東電に指示した。
着工して2か月が過ぎても凍結に成功していないためで、水を抜き取らないと、土を凍らせて地下水が建屋に流入するのを防ぐ「凍土壁」をトンネル周辺につくることができなくなる。
問題の配管用トンネルは断面が約5メートル四方の大きさ。2、3号機のタービン建屋とつながっており、高濃度の汚染水が約1万1000トンたまっている。東電は4月、2号機建屋と水が行き来しているトンネルの入り口に凍結管を入れ、水を凍らせて流れを止める工事を始めた。そのうえで汚染水を抜き取り、セメントなどで埋める計画だった。
しかし、6月に入っても水が凍っていないことが判明。東電は、凍結管の数を増やしたが、それでも十分に凍らなかった。
東電は7日の規制委の会合で、「1分あたり2ミリの水の流れが凍結の障害」と説明した。しかし、規制委の更田豊志委員らから「その程度の流速で凍らないのはおかしい」と疑問の声が続出。「このままでは、凍土壁も成り立たなくなる。凍結が不十分なら、2倍、3倍と冷凍能力を向上させてほしい」と要求した。
トンネルを横切って凍土壁をつくるためには、トンネル内の汚染水を抜き取っておく必要があり、更田委員は「凍結工事がうまくいかない以上、凍土壁の工事には進めない」と指摘。さらに、凍土壁も同じような仕組みで土を凍らせる工法のため、凍土壁の実現性にも疑問を投げかける形となっている。
福島第1原発:凍土遮水壁ピンチ 汚染水抜き取り難航 07/03/14 (産経新聞)
東京電力福島第1原発で、2、3号機タービン建屋から海側のトレンチ(配管などが通る地下トンネル)に流れ込んだ汚染水を抜き取る作業が難航している。建屋とトレンチの接合部で汚染水を凍らせて流れを止め、水抜きする計画だが、十分に凍結しないためだ。水抜きできなければトレンチ内の汚染水が漏れる恐れがあり、汚染水低減策の柱として1〜4号機を取り囲むように建設する凍土遮水壁の工事ができない。
トレンチは2、3号機にそれぞれあり、高さ、幅とも約5メートルで、地下22メートルに埋まっている。建屋から流れ込んだ汚染水計約1万1000トンがたまっている。
東電は、建屋とトレンチの接合部に、冷却液を流す凍結管計17本を差し込んで付近の水を凍らせる作業を4月から開始した。6月中に氷の壁で接合部を塞いで止水し、7月中旬から汚染水を抜く予定だった。しかし、7月に入っても水は十分に凍っていない。
原因について、東電は「建屋とトレンチの間を汚染水が行き来するため」と推測する。今後、凍結管を2本追加して冷却能力を高めるが、効果は未知数だ。
東電は「海側の凍土遮水壁の着工は10月以降なので、水抜きの時間はある」と楽観するが、更田(ふけた)豊志・原子力規制委員は「トレンチに滞留している汚染水は、今の福島第1原発で最も懸念されるリスクだ。(氷の壁での)止水ができなければ、遮水壁の議論などできない」と指摘する。【斎藤有香】
「将来もらえるか分からない」「手取り増えた方がいいだろう」 年金ネコババ、異例の“口裏合わせ” (1/2)
(2/2) 07/03/14 (産経新聞)
東京電力福島第1原発の汚染水問題で、2号機タービン建屋から海側のトレンチ(地下道)へ流れ込む汚染水をせき止める「氷の壁」が2カ月近くたっても十分に凍結していないことが28日、分かった。事態を重く見た原子力規制委員会は、来月にも開かれる検討会で対応を議論する方針を決定。特に氷の壁は、2日に着工した「凍土遮水壁」と同じ凍結技術を使っており、凍土壁の信頼性にも疑問の声が出ている。
2号機海側の地下には、配管やケーブルを敷設するためのトレンチがあり、高濃度の汚染水が1万トン以上たまっている。トレンチは海側の取水口付近とつながっており、海洋流出の危険があることから、早急に汚染水を取り除く必要があった。
東電はタービン建屋とトレンチの接合部にセメント袋を並べ、そこに凍結管を通し周囲の水を凍らせて「氷の壁」を設ける工事に着手。壁でタービン建屋からの汚染水流入をせき止め、その後、トレンチ内の汚染水を抜き取る計画で、4月には凍結管に冷媒を流し始めた。
しかし東電が今月中旬、内部の温度を測ったところ、十分に凍結していないことが判明。トレンチ内には障害物があり、均等に汚染水が凍らなかったことが原因とみられる。
東電は、新たに凍結管を増やしたり、トンネルにセメントを少しずつ流し込んで壁を造ったりする代替案を検討中という。
凍結管の中に冷媒を通して水分を凍らせる技術は、約1500本の凍結管で1~4号機の周囲の土中の水分を凍らせる「凍土遮水壁」と同じ。凍土壁は、政府が汚染水問題解決の「切り札」と期待して、約320億円の国費を投じ、来年3月の完成を目指している。
原子力規制庁幹部は「海側に滞留している汚染水は濃度が高く、最もリスクが高い。なぜうまくいかないのか原因分析とともに、凍土壁の有効性も議論していく」と話し、次回会合で議題に上げることを明らかにした。(原子力取材班)
間違いは誰にでもあるが、STAP細胞にかんする公表の前に確認をするべきだった。
STAP細胞、若山研究室由来の可能性も 解析に誤りか 07/03/14 (産経新聞)
STAP細胞論文をめぐり、主要著者の若山照彦・山梨大学教授が発表したSTAP細胞にかかわる試料の解析結果が、誤っていた可能性があることが若山教授側への取材でわかった。「改めて詳細な解析結果を公表する」としている。
STAP細胞は、若山教授がマウスを提供し、理化学研究所の小保方(おぼかた)晴子ユニットリーダーがそのマウスから作製したとされていた。若山教授は先月、解析結果をもとに「STAP細胞は自身が提供していないマウスからつくられていた」と説明していたが、若山研究室の関係者は、STAP細胞は若山研究室にあったマウスに由来する可能性を認めた。
若山教授は6月16日に会見を開き、自身が保管していた試料について、第三者機関に依頼していた解析結果を発表した。STAP細胞と同じ遺伝情報を持つはずのSTAP幹細胞には、目印となる遺伝子が15番染色体に組み込まれていたと明らかにした。若山研究室では15番染色体にこの遺伝子のあるマウスは飼育したことがないとし、若山研究室が提供したマウスとは別のマウスで作製された疑いを示唆していた。
厚労省よ、職員の働きに問題が無いと言い切れるのか?自分達に都合が良ければ不定も不適切も許容範囲になっていないのか?年金は100年大丈夫と断言できるのか?
「将来もらえるか分からない」「手取り増えた方がいいだろう」 年金ネコババ、異例の“口裏合わせ” (1/2)
(2/2) 07/03/14 (産経新聞)
NHK受信料を徴収する専門会社が社員らの給与の過少申告を行い、厚生年金や健康保険料の支払いを不正に免れていた疑いがあるとし、日本年金機構が調査していたことが分かった。年金事務所に給与を過少申告する手口は、社員から天引きした保険料の「ネコババ」を図る経営者によって独断で行われることが多く、今回のように社員側と「口裏合わせ」をしていたケースの発覚は異例だ。背景には年金制度への不信感があるとみられ、関係者は「水面下で横行している可能性がある」と指摘する。
厚労省によると、経営者による給与の過少申告は平成19年の「消えた年金問題」をきっかけに相次ぎ発覚。ねんきん特別便で「保険料を払っていたのに記録がない」と気づいた社員からの訴えをもとに、ネコババが判明したのは25年9月末までの約6年間に計6万6886件、被害額は約83億8800万円に及ぶ。
政府は19年12月に記録の修正を認める特例法を策定。経営者を追及し、約55億円分を回収したが、今回のように経営者と社員が結託し、互いに支払いを免れていたケースの発覚は「聞いたことがない」(厚労省幹部)という。
保険料の過少納付は将来受け取れる年金額に影響し「生活が困窮すれば、他の社会保障制度に依存することになりかねない」(同)。また、年金事務所に届ける給与額は全国健康保険協会(協会けんぽ)に納める健康保険料にも影響。より少ない額で「自己負担3割」などの医療費保障を得ていたことになり、厚労省の幹部は「きちんと支払っている人が損をする、制度を骨抜きにする行為だ」と指摘する。
機構では4年に1回、事業所への調査を行っているが、嘘の賃金台帳などで偽装された場合には見破ることは難しい。国土交通省は来月以降、国発注事業の入札に際し、保険加入を裏付ける証明書の提示を義務化し、29年度までに未加入業者をゼロにする方針だが、過少納付まで見破れるかは不透明だ。
厚労省では「保険料納付は事業主に課された責務であり、社内で発覚した場合には積極的に情報提供してほしい」と呼びかけている。
厚労省、ノ社に改善命令へ 白血病治療薬副作用、期限内に報告せず 07/03/14 (産経新聞)
厚生労働省は、白血病治療薬の副作用情報を定められた期限内に国に報告していなかったとして、薬事法に基づき、製薬会社ノバルティスファーマに改善命令を今月下旬にも出す方針を固めた。同省関係者が2日、明らかにした。
副作用報告義務違反で製薬会社が行政処分を受けるのは極めて異例。一連の不祥事でノ社に対する行政処分は初めてとなる。
ノ社の高血圧治療の降圧剤「ディオバン」の臨床研究データ改竄(かいざん)事件では1日、元社員とともに、法人としてのノ社も薬事法違反(誇大広告)の罪で起訴されたが、今回の行政処分には同事件は含まれない。今後、捜査の推移を見ながら厚労省があらためて処分を検討する。
ノ社や関係者によると、ノ社の営業部門が昨年4月から今年1月、白血病治療薬の副作用を軽くする目的で新しい製品への切り替えを提案するため、薬剤師や医師を対象にアンケートを実施した。その中に、国への報告が必要な重い副作用情報が含まれていたが、同社は期限内に報告していなかった。
ノ社は、営業担当社員が副作用情報に接しながら、社内の安全性評価部門に届いていなかったと説明しており、厚労省は安全管理体制に問題があると判断した。
薬事法などは、製薬会社が重い副作用の情報を入手した場合、内容によって15日または30日以内の報告を義務付けている。
ノ社は社内調査で把握した重篤の10例を含む計約30例を期限経過後に報告し、厚労省と医薬品医療機器総合機構(PMDA)が調べていた。
厚労省によると、記録が残る平成10年以降、製薬会社が医薬品の副作用報告義務違反で行政処分を受けた例はない。
バルサルタン:ノバルティス社「論文で宣伝」内部文書化 07/02/14 (読売新聞)
◇元社員、上層部の意向くむ?
降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)臨床試験を巡る虚偽広告事件で、製薬会社ノバルティスファーマが、臨床試験に基づいた学術論文を宣伝に活用するとの営業方針を内部文書化していたことが、関係者への取材で分かった。営業方針は同社上層部にも伝えられていたという。東京地検特捜部は、元社員の白橋伸雄被告(63)が、営業成績を上げたい上層部の意向をくんで、改ざんに及んだ疑いがあるとみて調べを進めている。
関係者によると、ノ社は2000年代以降、自社の医薬品の効能をアピールして販売促進する手段として、大学などが執筆した論文を活用する方針を打ち立てた。同社の経営陣の了承も得た上で、同社の営業戦略について書かれた複数の文書にも盛り込まれた。
バルサルタンについては、東京慈恵会医大の研究チームが臨床試験を終え論文を執筆した06年以降、医療専門誌などに約500種類の広告が出されたことが確認されている。京都府立医大の試験結果も「脳卒中を減らす効果が出た」などと紹介した広告記事が多数掲載された。
白橋被告は大阪市立大非常勤講師の肩書で府立医大の臨床試験に参加。自社の医薬品の臨床試験に関わったことが利益相反に当たると指摘されている。
特捜部は、白橋被告が会社の戦略に沿ってバルサルタンの売り上げを伸ばすため、臨床データの改ざんを行った可能性もあるとみて1日に白橋被告を再逮捕するとともに、法人としてのノ社も起訴した。虚偽の論文を宣伝に使った法人としての責任の重さも考慮したとみられる。
白橋被告は改ざんを否認し、調べに対して黙秘を続けているとされる。【山下俊輔、石山絵歩】
STAP問題の理研も無駄遣い…指摘改善されず 07/01/14 (読売新聞)
財務省は1日、2013年度の予算の無駄遣いを点検した結果を公表した。
対象の58事業には、STAP(スタップ)細胞の論文問題を抱える理化学研究所の研究事業も含まれ、検査キットや実験用動物の購入など、物品調達の契約(予算額531億円)の見直しを求めた。
まとめ買いのほうが安くなるのに、12年度の随意契約11万6000件のうち、13件しか一括購入していなかった。ノートパソコンは年間238回(4673万円)も購入していた。
財務省は08年の調査でも、一定額以上は購入計画を作り、一括購入などをするべきだと理研に指摘したが、改善されていなかったという。
今回の予算執行調査は4~5月に行い、災害対応の専門家を自治体に派遣する総務省の事業など、6事業(予算総額1兆9981億円)で一部廃止や全廃を所管官庁に求めた。残り52事業についても、見直しや単価の引き下げなどを求めた。
W杯サッカー日本中が見てるわけじゃないぞ!丑三つ時の他国試合に放送権料400億円―NHK受信料返せ <2014FIFA ワールドカップC組 日本×コロンビア>(テレビ朝日&各局) 06/30/14 (J-CASTテレビウォッチ)
4時から起きて試合を視聴した。筆者の予想通りの結果だった。ただし、筆者は1対5でコロンビアに負けると予言していたから1点だけ相手のゴール数が少なかった。相変わらず大手メディアは奇跡が起きるようなことを垂れ流していたが、スポーツにおける勝敗や芸術におけるコンクールなどは、『実力があるものが落ちたり負けたりすることはあっても、実力のないものがフロックで勝つことはない』という至言があるように、奇跡なんぞは起きないのである。
これで大騒ぎが静まるので助かる。それよりも問題は他にある。自国の試合を生中継するのはいいとして、今回もNHKは超大金を使って世界中の全試合を中継している。一体どれだけの大金を支払っているかご存知か。今回のテレビ放映権料は400億円である。ジャパンコンソーシアムというNHKと民間放送連盟が共同で分担放送をして、金も分担して支払うのだが、そのうちNHKが70パーセントをもつ。だから、せっせと全部の試合を中継する。受信料を支払っているわれわれは、他国の、丑三つ時の試合まで大金を出して放送してくれなどとは全く頼んでいない。受信料返せ!
全くサッカーに興味のないお年寄りなどはいい迷惑である。近頃のNHKはなりふり構わず視聴率の高いコンテンツに色目を使う。ガキタレントの大騒ぎであるAKB48のイベントにまで擦り寄り、大人の見識あるBBCのような確たる矜持を失っている。アホ。
中国製品検査に不備、コーナンに販売停止処分 06/27/14 (毎日新聞)
ホームセンター大手のコーナン商事(堺市)が、安全検査に不備がある電気製品を販売した問題で、経済産業省は27日、電気用品安全法で義務づけられた検査記録の保存などを怠ったとして、同社に対し、950品目を1~3か月間販売停止とする処分を行った。同省によると、2001年の同法施行以来、販売停止処分は初めて。
経産省は5~6月、同社に立ち入り調査を実施し、01年度以降に主に中国から輸入された約1600品目を調べた。電子レンジや炊飯器など950品目について、海外の製造元から検査記録を取り寄せていなかったり、検査の徹底を指示しなかったりしたことが判明。こうした不備があったのに、検査済みを示す「PSEマーク」を表示していた。
製薬会社ノバルティスファーマの不正行為は底なしだ!厚労省は見ざる、言わざる、聞かざるで裸の王様状態。なんとかしろよ、厚労省!
再発防止や重い処分の検討とか何かやっているのか?
ノバルティス社:元社員、別論文もデータ改ざんか 06/27/14 (毎日新聞)
降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験を巡る薬事法違反事件で、京都府立医大が2011年に発表した論文の臨床データを改ざんしたとして逮捕された製薬会社ノバルティスファーマ元社員、白橋伸雄容疑者(63)が、12年に発表された同大の別の論文のデータ改ざんにも関与した疑いがあることが関係者の話で分かった。東京地検特捜部は同法違反(虚偽広告)での立件を視野に、12年論文の作成過程の解明を進めるとみられる。
府立医大の試験は04年に開始。約3000人の患者を、バルサルタンを投与するグループと、それ以外の降圧剤を投与するグループに分け、降圧作用や脳・心疾患の発症頻度などを比較した。09年に発表した「主論文」は、バルサルタンを服用した患者の方が脳卒中などの発症例が明らかに少なかったなどと結論づけた。
同大はその後もバルサルタンの効果を検証。その結果を「サブ論文」として複数の医学誌に投稿し、いずれもバルサルタンに脳や心臓などの疾患予防効果があるとした。
白橋容疑者は、11年の論文にデータ改ざんした図表を掲載させたなどとして逮捕されたが、12年の複数のサブ論文のデータ解析にも関わり、虚偽の図表などを繰り返し作成していた疑いが浮上しているという。
白橋容疑者は逮捕直後の調べに容疑を否認し、その後は黙秘しているとみられる。
成功しなければ、理研の予算を減額するのであれば理研の好きなようにさせれば良い。
STAP細胞:小保方氏実験なら厳格監視 理研センター長 06/26/14 (毎日新聞)
STAP細胞の検証実験について、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(CDB)の竹市雅俊センター長は25日、小保方(おぼかた)晴子・研究ユニットリーダー自身の手による実験が実現した場合、ビデオでの監視など厳格な管理下で実施するとの計画の概要を、毎日新聞の取材に明らかにした。竹市氏は「疑惑は決定打にはなっていない。STAP細胞があったかどうか、小保方さん自身の実験で見極めたい」と本人参加の意義を述べた。
また、竹市氏は現在CDB内のチームが進めている検証実験に既に小保方氏が立ち会い、実験には直接携わらないで助言していることについて、その頻度は「主治医の許可があるとき」と説明した。
小保方氏の実験参加については、下村博文・文部科学相が支持しているほか、理研の野依良治理事長も「(参加しなければ)決着はつかない」との意向を示している。今後、理研理事会が可否を判断するとみられる。
正式に参加が決定し、小保方氏によってSTAP細胞とみられる細胞ができた場合、(1)竹市氏らの立ち会いや実験全体をビデオで監視、部屋の出入りや細胞培養装置も鍵で管理するなどの条件で再度実験内容を確認(2)小保方氏に習った理研スタッフが独自に再現(3)理研外部の研究グループにも参加を求める--などの手順を明らかにした。一方、小保方氏が1年以内に作製できなければ、プロジェクトを終了するという。現在の検証実験では、STAP細胞は弱酸性の液体にマウスのリンパ球を浸して作り、マウス実験でさまざまな組織になる万能性を確認することを成功の条件としている。
日本分子生物学会理事の篠原彰・大阪大教授は「既に立ち会っているとは驚きだ。未公表での立ち会いは公正さを損なう。まず検証実験の進捗(しんちょく)状況や立ち会う理由を公表すべきだ。小保方氏も、論文の疑義への説明を果たさないまま、実験参加など次のステップに進むべきではない」と話す。【須田桃子】
武田薬品 ARB・ブロプレスの臨床研究CASE-Jで組織的関与 糖尿病の新規発症で有利な結果得る 06/23/14 (ミクス)
ARB・ブロプレス(一般名:カンデサルタン)の臨床研究「CASE-J」の臨床研究不正をめぐり、武田薬品は6月20日記者会見を開き、同剤の付加価値最大化を目的に、研究の企画段階から学会発表、論文作成まで、一貫して組織的かつ継続的な関与があったとの第三者機関の調査結果を公表した。奨学寄附金による総額37億5000万円の資金提供や、複数の社員による労務提供により、京都大学EBMセンターの運営を含めてサポートされており、「医師主導臨床試験である実質的なスポンサーであった」と結論付けた。副次評価項目である糖尿病の新規発症については、当初の解析方法では“有意差なし”だったが、同社が研究者に定義を変更するよう働きかけ、結果としてブロプレスに有利な結果を引き出していたこともわかった。試験結果の公平性、客観性も疑問視されるところだ。一方で、同社の試験データへのアクセス、データの改ざんやねつ造、解析作業への直接的関与は認められなかったとした。
第三者機関であるジョーンズ・デイ法律事務所の調査報告書によると、同社はブロプレスの付加価値最大化、売上最大化を図る、競合品との差別化のツールとして医師主導型臨床試験によるアウトカムスタディの実施を検討。試験の企画段階では、▽試験事務局の選定、▽研究責任医師、運営委員候補への就任依頼、▽試験の大枠の決定、▽奨学寄附金について専門医と相談、決定―していた。「自らの目的をもって試験に必要な人(=専門医の手配)、もの(=事務局の選定)、金(=寄付金)に主体的かつ能動的に決定し、そのお膳立てをしたことも事実」(森雄一郎弁護士)と指摘した。
試験の立ち上げ、症例追跡調査に際しては、京都大学に試験の実施に必要な知識・経験・人材が不足していることから、事務・運営上の課題について定期的に同社と京都大学EBMセンターの担当者が集う会議を開き、協議がなされていた。立ち上げ段階では、プロトコルの作成、データマネジメントシステムの構築、試験実施施設・参加医師の選定などに全面的に関与。京都大学関係者と同社関係者が揃う「京大‐武田ミーティング」を月に1~2回開催し、試験のサポートを行っていた。試験実施施設の選定、参加医師の選定に際しては、同社の営業網を活用して候補医師のリストアップと参加に向けた打診が行われていた。一部のMRでは同社から貸与されたパソコンを用い、調査票の入力作業をサポートしていた。
◎試験のプロセスに武田薬品の意向反映
追跡調査期間終了後には、「試験のプロセスに武田薬品の意向を反映させる働きかけが始まった」(森弁護士)。類似した臨床試験で、ARB・ディオバン(一般名:バルサルタン)とアムロジピンの有効性を比較検討した「VALUE」試験両群間に有意差が認められなかったことから、CASE-J試験結果を懸念。ブロプレスに有利な結果とならなかったことによる売上への悪影響を懸念。「CASE-J対応プロジェクト」を立ち上げ、対策を検討した。“糖尿病の新規発症率”など、ブロプレスに有利な結果が出る可能性が高い追加統計解析項目を統計解析計画書に反映されるよう研究者に働きかけた。
ただ、実際の結果は主要評価項目である累積心血管イベントの発生率、糖尿病の新規発症率ともに、ブロプレスに有利な結果とはならず、対照薬であるCa拮抗薬・アムロジピンと有意差が認められなかった。そこで、同社担当者が定義を変更した解析を行うよう働きかけ、糖尿病の新規発症抑制効果がブロプレスに認められることとなった。慢性腎臓病(CKD)についてのサブ解析でも2群間に有意差が認められず、同社がそれまで行ってきたプロモーションと反することから、研究者に対し、図表の差し替えなどを提案している。
発表に際しても、同社社員が学会発表用のスライドを提供。ブロプレスが有意な見せ方となるよう、メタボリックシンドロームへの有効性や全死亡のカプランマイヤー曲線を盛り込むよう研究者側に修正を提案、最終スライドに盛り込ませていた。
◎武田薬品・長谷川社長「CASE-Jは医師主導臨床研究」
武田薬品の長谷川閑史代表取締役社長は冒頭で、「本来であれば、企業が関与してはいけない医師主導臨床試験に対し、複数の関与や働きかけを行っていたことを深くお詫びする」と謝罪した。「複数の不適切な関与や働きかけが、CASE-J試験の公平性に疑義を生じさせ、ひいては製薬企業全体の信頼性を揺るがしかねない行為だったことを反省している」と述べた。
組織レベルの関与があった点については、社内調査で認められておらず、第三者機関の調査報告で覆った形だが、「調査は不十分であったことは真摯に受け止め、反省している」と述べた。自身や社員の責任問題については、「報告内容を重く受け止め、外部の弁護士に入っていただいているコンプライアンス委員会で可及的速やかに検討していただく。退職した人もいるが、総合的に考えていきたい」とした。
試験の実施施設の選定から当初からマーケティング、売上向上を目的とした“Seeding Trial”ではないか、との指摘については、「(施設選定と販促を)直接結びつけることは飛躍がある。EBMセンターからの依頼に応じて手伝った」とした。また、現在もCASE-J試験は医師主導臨床研究だと考えているか、との質問に対しては「はい、そう思っている」と述べた。
◎記事広告疑念のカプランマイヤー曲線 薬事法違反ではない
同試験のメイン図表である、累積心血管イベントの発生率を示したカプランマイヤー曲線については、商業誌Medical Tribuneに掲載された記事広告「CASE-Jに学ぶ」をはじめ同社販促資材で、ブロプレスに有利なよう図表を改ざん、改変の疑念がもたれている。しかし、第三者機関は同社が京都EBMセンターから紙ベースで図を入手したと説明。数値データは入手していないことから、科学的事実であるデータや解析作業を操作したという事実は確認されていないとした。また、ブロプレスに有利に見えるような意図的な改変を行ったという事実も認められなかったとした。
薬事法の虚偽・誇大広告への抵触も懸念されたが、▽試験結果、試験データについてねつ造、改ざんが認められなかった、▽販促資材全体をみると、医師の誤認を生じさせるとまではいかない、▽カプランマイヤー曲線が完全について同一でなくても誤解は生じない―ことなどから、「薬事法違反とはならない」と結論付けた。また、糖尿病の新規発症抑制効果についても、同様に承認外の効能・効果を記載されているとまでは言えないとした。ただ、ブロプレスの長期的有効性を示す「(曲線の交差部分である)ゴールデンクロスという言葉は、誰が提案し、使われるようになったのか定かではない」(岩﨑真人医薬営業本部長)との発言もあり、全貌解明には至っているとは言い難い。
試験はオープンラベルで行われているため、中間解析以降、患者の脱落や背景因子などに介入が働いていたとの指摘もある。しかし、報告書では中間解析についても「調査していない」としており、調査自体が不十分である可能性もある。
なお、第三者機関として調査に当たったジョーンズ・デイ法律事務所のクライアントとして、武田薬品の米国子会社が含まれており、同事務所ホームページ上にも記載されている。第三者としての中立性が懸念されるところだが、会見で同法律事務所は顧客であることは認めたものの、顧問関係などは否定し、「適切な関係だ」とした。
小保方氏の功績はSTAP細胞ではなく、理研グループの問題を公にさらした事だ。
「遺伝子のチェックが同センターで十分にできていなかった。」どうして十分にチェックが出来ていなかったのか?誰が責任者だったのか?マニュアルは存在したのか?マニュアルにが存在していたのであれば、マニュアルに従ってチェックしていたのか?マウスに問題があれば、実験が無駄になってしまう。研究者その他の人件費などの補償はしないのか?
理研提供のマウス、注文と遺伝子異なっていた 06/23/14 (読売新聞)
研究機関に実験用マウスを提供している理化学研究所バイオリソースセンター(茨城県つくば市)が昨年までの約7年間で、国内外の41機関に対し、注文と違うマウスを178匹提供していたことが22日分かった。
理研によると、2種類の遺伝子組み換えマウスについて、海外の大学からの指摘で、注文された遺伝子とは異なることが昨年判明した。遺伝子のチェックが同センターで十分にできていなかった。
研究機関で実験のデータが論文に使えないなどの支障が出たという。要望があった機関には代替のマウスを送るなどの対応を取った。
同センターは、大学などで作った約6900種類の遺伝子組み換えマウスを預かり、年間数千匹を研究機関に実費で提供している。
理研、誤ったマウスを提供 41機関、研究に支障も 06/22/14 (朝日新聞)
理化学研究所が国内外の研究機関の注文に応じて実験用マウスを提供している事業で、誤ったマウスが繰り返し提供されていたことがわかった。41機関に注文とは異なる計178匹の遺伝子組み換えマウスが提供され、なかには実験データが使えず、研究に支障が出たケースもあった。
正しい遺伝子組み換えマウスの提供は、iPS細胞などの再生医療研究を支える基盤となっており、ミスは研究の信頼性を損なう事態につながりかねない。
誤ったマウスを提供していたのは、理化学研究所バイオリソースセンター(茨城県つくば市)。約6900種類の組み換えマウスを管理・販売する国内最大の実験用マウス提供機関だ。センターは多様な組み換えマウスを開発者から預かって管理。研究機関はセンターが管理するマウスのカタログから実験に適したマウスを選び、繁殖用の種マウスとして数匹購入し、繁殖させて実験に用いる。
マウス誤提供、揺らぐ理研ブランド 「研究時間無駄に」 06/22/14 (朝日新聞)
国内トップの実験用マウスの提供機関である理化学研究所バイオリソースセンター(茨城県つくば市)でマウスの提供ミスが繰り返されていた。注文とは異なるマウスなどを提供されていたのは41機関の46研究室に及ぶ。「理研ブランド」を信じて実験に用いてきた研究者らに戸惑いが広がる。
東京都内の大学の教授に、理化学研究所のバイオリソースセンターからメールが届いたのは昨年12月だった。
標題は「遺伝子組換え情報の訂正とご利用の注意事項」。センターの吉木淳・実験動物開発室長名で送られたメールには、教授の研究室が数年前に購入したマウスに除去したはずの遺伝子が残っていたとあった。
武田薬品、臨床研究に組織的関与 有利な結論引き出す 06/21/14 (日本経済新聞)
武田薬品工業が販売する高血圧治療薬「ブロプレス」の広告で臨床研究の論文と異なるグラフが使われた問題で、調査にあたった第三者機関が20日、報告書を公表した。京都大の臨床研究に同社が企画段階から組織的に関与し、統計解析の項目の定義変更などを働きかけて有利な結果を出させていたと指摘した。
データの捏造(ねつぞう)や改ざんはなかったとした。
報告書によると、同社は臨床研究を行った京都大などに37億5千万円を提供。社員は研究の実施計画書の下書きを作成し、参加医師の選定や統計解析計画書の作成もしていた。統計解析の項目の定義変更を働きかけ、学会発表に用いるグラフの作成も手伝うなどし、ブロプレスに有利な結論が出るようにしていた。
研究に関わった社員は2008年11月時点でブロプレスを服用した患者2人に重篤な副作用が出たことを把握していたが、同社は薬事法に基づく国への報告をしていなかった。
臨床研究は京都大などのチームが01~05年、高血圧の患者約4700人を対象に実施。ブロプレスと別の薬で脳や心臓の病気の発症を抑える効果を比べた。チームは06年の学会でブロプレスに病気の発症を抑える効果があるように見えるグラフを発表。業界のルールでは学会発表時のデータは論文発表後は広告に使えないが、同社は08年の論文発表後も同じグラフを広告に使い続けていた。
記者会見した同社の長谷川閑史社長は、社員らの関与について「研究の公正性に疑義を生じさせるもの」とし、「患者や多くの関係者に迷惑をおかけしたことを深くおわびする」と謝罪。社員らの処分を検討するとした。
武田薬品「研究に組織的関与」で謝罪 06/21/14 (NHK)
大手製薬会社の武田薬品工業は、京都大学などが行った高血圧治療薬の臨床研究に組織的に関わり、研究の公正性に疑義を生じさせかねない関与を続けていたなどとする第三者機関の調査結果を20日、明らかにし、製薬企業全体の信頼を揺るがしかねない行為だったと謝罪しました。
武田薬品工業は、平成18年ごろに高血圧の治療薬「ブロプレス」の宣伝広告を行った際、狭心症や脳卒中をどのくらい抑えられるかを調べた臨床研究の結果と異なる宣伝を行い、誤解を与える内容だったとことし3月に認め謝罪しました。
武田薬品はこの研究について、医師が主導して行ったもので研究自体には関与していないと説明していましたが、第三者機関がまとめた調査報告書によりますと、武田薬品の社員が研究の計画から結果の公表まで一貫して関わっていたことが分かったということです。
具体的には、社員が医師に代わってカルテを閲覧し、条件に合う患者を選んだり、患者データの入力をしたりしていたということです。
さらに、中間解析で狭心症や脳卒中の発症に差がないと分かると、京都大学に働きかけて糖尿病の発症を新たに解析項目に追加させ、計算条件の修正を求めるなどして最終的にはブロプレスの効果が高いという結果を出したとしています。
武田薬品工業は計算条件の修正を求めた点については「働きかけは不適切だったが正しい結果になった」などと主張したうえで、長谷川閑史社長が「結果の公正性に疑念を生じさせかねない関与や働きかけで、製薬企業全体の信頼を揺るがしかねない行為だった。おわび申し上げます」と謝罪しました。
報告書では、研究に参加した患者2人にめまいなど副作用が否定できない重い症状が出ていたものの、国に報告を怠った薬事法違反の疑いについても指摘していて、武田薬品は19日、厚生労働省に報告したということです。
武田薬品、高血圧治療薬「組織的に臨床研究に関与」(14/06/21) - YouTube/A>
業界と大学の体質なのかもしれない。
臨床研究に会社関与=高血圧薬「ブロプレス」—37億円超提供も・武田薬品 06/20/14 (日本経済新聞)
製薬大手の武田薬品工業が販売する高血圧治療薬「ブロプレス」の効果を示す広告のグラフが、基になった臨床研究の論文のグラフと食い違うと指摘された問題をめぐり、同社は20日記者会見し、臨床研究に同社の関与があったとする第三者機関の調査報告書を公表した。
報告書によると、研究を主導した京都大などに約37億5000万円を提供したほか、企画段階から複数の社員が関与。データ管理システムの構築や参加する医師の選定に関わったほか、学会発表資料の作成なども行っていた。
試験データへのアクセスやデータ改ざんなどは確認できなかったという。
広告と論文のグラフの食い違いについては、完全に同一ではないが大きな違いはなく、薬事法で禁じられる誇大広告には当たらないと結論付けた。
さらに、市販後の調査で重い副作用情報2件を認識しながら国に報告していなかったことも明らかにした。
長谷川閑史社長は「組織レベルでの関与があったことは明らかで、大変重く受け止めている。製薬企業全体の信頼を失わせる行為で、真摯(しんし)に反省している」と謝罪した。
ブロプレスの臨床研究をめぐっては、京大病院の医師が2月、広告と論文のグラフが食い違い、同社に有利な内容になっていると米医学誌で指摘。武田薬品は会見し、研究には関与しておらず、広告のグラフは学会で発表されたものを転用しただけと説明していた。
[時事通信社]
このような状態になったら検証実験よりも誰が嘘を付いているのか、白黒つけた方が良い。小保方晴子ユニットリーダーが嘘を付いているのであれば、検証実験をしなくとも「STAP細胞」はないと考えて良いと思う。この二人の言い分が全く違うのだから、どちらかが嘘つきである事は明らかだ!
なぜ科学の世界で、ここまで言い分が違うのか?小保方氏を検証実験に参加させるよりも、どちらが嘘を付いているのか明らかにした方が先だ。税金を無駄にしたくて済む。
小保方氏反論「マウスは若山研究室通じて入手」 06/18/14 (読売新聞)
STAP(スタップ)細胞の論文問題で、理化学研究所の小保方(おぼかた)晴子ユニットリーダーは18日、STAP細胞の作製に用いたとされるマウスはすべて、理研に当時在籍していた若山照彦・山梨大教授の研究室を通じて入手したなどとするコメントを、代理人の三木秀夫弁護士を通じて発表した。
若山氏が16日の記者会見で、作製実験に使われた細胞は自分が提供したマウスではなかったとしたことに対し、反論した。小保方氏は、理研による検証実験に参加したいという意欲も示しているという。
論文では、若山氏が提供したマウスを使って小保方氏がSTAP細胞を作製し、それをもとに若山氏が増殖能力を持たせたSTAP幹細胞を作ったとしていた。反論で、小保方氏は「マウスや細胞は、所属していた研究室(若山研)以外からの入手はない。今後の理研の調査にできる限り協力し、事実関係を明らかにしたい」とした。
若山照彦山梨大教授の会見から判断すると小保方晴子ユニットリーダーがなぜ若山照彦山梨大教授が製作を依頼して渡したマウスとは別の細胞だったのかを説明できなければ小保方氏を検証実験に参加させる必要はない。
理研を含めて、欲や名誉に目がくらんで「STAP細胞」を諦められないのではないのか?もしかしたら「STAP細胞」はあるかもしれない。しかし小保方氏を検証実験に参加させても時間とお金の無駄であると思う。しかし彼女を検証実験に参加させなければ「STAP細胞」が存在しないとの結論にたどり着かないであろう。そうなるとさらなるお金と時間の無駄。
STAP細胞「小保方さんでなければ証明困難」 文科相 06/17/14 (朝日新聞)
理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダーが作ったとされるSTAP細胞が、万能細胞のひとつのES細胞である疑いが強まっている問題で、下村博文文部科学相は17日、「理研は小保方さんの活用を考えながら、一日も早くSTAP細胞を証明する努力をする必要がある」と述べ、検証実験に小保方氏が参加する必要性を改めて示した。
論文の共著者の若山照彦・山梨大教授が16日、STAP細胞が若山研究室に存在しないマウスで作られたと記者会見で明らかにしたことを受け、下村文科相は「二人三脚でやってきた若山教授から出た話なので、小保方さんでなければSTAP細胞を証明するのはより困難」と語った。
また、理研の懲戒委員会が検討している小保方氏の処分について、下村文科相は「今までの経過だけでも十分判断できる材料はそろっている」とした。
若山教授「小保方ノート確認してれば…最悪の結果」 一問一答の詳報 (1/2)
(2/2) 06/17/14 (産経新聞)
製作を依頼して渡したマウスとは別の細胞だった-。新型万能細胞とされる「STAP(スタップ)細胞」を培養して作製した幹細胞について、第三者機関による解析結果を16日発表した若山照彦山梨大教授の会見の主な一問一答は次の通り。
あるという証拠を全て否定する結果
--STAP幹細胞はどんな細胞だったのか
「僕の研究室にいるマウス(由来)ではないということが分かっただけ」
--解析結果の感想は
「予想していた中でも最悪の結果。どうしてこういうことが起きたのか分からない」
--細胞の有無は
「あるという証拠を全て否定する結果となった。しかし、絶対に存在しないと言い切ることはできない」
--3月には細胞の存在を信じたいと言っていたが
「STAP細胞があれば夢の細胞だ。あってほしいと思うが、全ての解析結果がそれを否定している。だが、ないという証明はできない」
まだ結論は出せない
--当時と比べ心境の変化は
「解析結果を見る限り、自分が使ったのは何だったのか、もっと分からないものになってしまった。この4カ月は理化学研究所の調査委員会に協力する仕事がずっと続いている。つらい毎日だ」
--理研の小保方(おぼかた)晴子氏は今回の解析結果と合致するマウスを入手できたか
「そのようなマウスが理研の発生・再生科学総合研究センターにあるかどうかは調査中だが、ポケットに入れて持ち込むことは不可能ではない」
--STAP細胞が胚性幹細胞(ES細胞)である可能性は
「すべての結果をうまく説明できるのは、ES細胞が入っていることだが、まだ結論は出せない」
--小保方氏に対して言いたいことは
「僕はこの問題を解決するため、できる限りのことをした。解決に向け行動してもらいたい」
裏切られたとは考えていない
--今後もSTAP細胞の研究をするのか
「僕自身は再現実験を繰り返しても成功していない。できると言っているのは小保方さんだけで、誰もができるような作製方法を公開してもらえなければ研究をやろうとは思わない」
--理研の改革委員会は若山氏にも責任があると提言した
「小保方さんの実験ノートを確認すべきだったことについてはその通りだ。反省している。だが、優秀だと思っていた研究者に確認はできなかった」
--自身の責任について
「3月に論文撤回を申し出た際、山梨大学長に相談に行った。山梨大では処分しないと言われたが、僕から何らかの処分を大学に申し出る」
--小保方氏に裏切られたと思うか
「考えていません」
行政が本当に適切に対応できなければ不正や違法な活動を行う企業の手助けとなるだろう。一部のNPOに登録されている企業が詐欺行為を行っていたり、違法又は不正行為をおこなっている事実が良い例だ。
外国企業の起業支援へ、手続きの窓口を一元化 06/17/14 (読売新聞)
政府は17日、国家戦略特区諮問会議(議長・安倍首相)を開き、地域を絞って規制緩和を進める国家戦略特区で追加の緩和策を決めた。
起業する際に必要な手続きを一元化する窓口の設置などが含まれ、6月下旬に決める政府の新しい成長戦略に盛り込む。
日本で起業するには現在、登記や税務、年金など煩雑な行政手続きが必要で、外国企業の日本進出への足かせになっているとの指摘が出ている。国家戦略特区に指定された東京圏や関西圏などでは、窓口を集約した「ワンストップセンター」を新設し、外国人が日本で生活する際に必要な手続きの手助けも行う。
起業する外国人の在留資格も緩和する。現在は〈1〉2人以上の常勤職員の雇用〈2〉最低500万円の投資――のいずれかの条件を満たす必要があるが、当初は満たさなくても一定期間内に満たせる見通しがあれば在留を認める。
ドイツ証券汚職、基金幹部接待に会長も同席 06/17/14 (読売新聞)
ドイツ証券(東京)による接待汚職事件で、贈賄罪で公判中の元社員越後茂被告(37)が行った厚生年金基金幹部への接待に、同社の金成(かなり)憲道会長(67)も同席していたことが、関係者への取材でわかった。
金成会長は証券取引等監視委員会の調査に対し、「厚生年金基金の幹部が公務員とみなされることを知らなかった」と説明。監視委は同社に対し、「内部管理体制に問題がある」と指摘していた。
関係者によると、越後被告と金成会長は2011年10月、名古屋市内の高級クラブで、起訴事実の接待先とは別の愛知県内の厚生年金基金の理事長と常務理事を接待。飲食やカラオケなど十数万円の料金は、ドイツ証券が全額負担した。基金に同社との取引を継続してもらうための接待だったという。
京都府立医大はこのような組織であったと言う事。このような組織であっても製薬会社ノバルティスファーマの件が事件になるまで、改革する又は通報により変われる機会はあったと思う。しかし想像以上に組織に問題があったと言う事ではないのか?
「論文を執筆した京都府立医大の医師ら国公立大学の研究者は、みなし公務員。検察幹部は『血圧を下げる以外の効果がないと知りつつ効果を宣伝し、報酬を受け取っていたら収賄に当たる可能性はある』と話す。」
国公立大学でもこのありさまなのか?日本の臨床研究はバイアスがかかっていることを考慮した上で判断しなければならないのか?厚労省、どう思う?
一部症例、外部委に未報告 京都府立医大、ずさんな研究体制 (1/2)
(2/2) 06/12/14 (産経新聞)
製薬会社ノバルティスファーマが販売する降圧剤「ディオバン」の臨床研究データ操作事件で、京都府立医大の研究チームが論文に使用した一部の症例について、医師の診断の是非を検証する外部の判定委員会を通していなかったことが、関係者への取材で分かった。外部のチェック機関を無視していた形だが、一方で判定委の事務局をノ社元社員、白橋伸雄容疑者(63)=薬事法違反容疑で逮捕=が担当するなど判定委の独立性が担保できない状況だった。
東京地検特捜部は事件の背景にこうしたずさんな研究体制があったとみて、研究チームメンバーからも事情を聴いている。
関係者によると、京都府立医大の研究は平成16年1月に始まり、31病院の医師が、ディオバンや既存薬を投与した患者の症例を集めた。判定委は医師の症例判断が正確だったかどうかを判定する機関で、外部の大学教授らで構成される。
関係者によると、病院による患者データの作成は21年1月に終了し、同年3月末まで研究に参加した医師らが患者データを修正。脳卒中や狭心症など高血圧合併症の発生数が数十件変更された。
変更された症例は判定委による検討が必要だったが、研究チームは判定委に報告せず、同年4月以降も研究を継続した。別の関係者によると、研究チームは判定委に対して、自らが行った症例判定についての文書を事後的に送付する形で済ませていたという。
判定委は17年以降、複数回開催されたが、白橋容疑者は事務局として資料を作成するなど事務作業を取り仕切っていた。
制度の不備を悪用して企業と癒着する医師は必要ない。能力があっても、モラルに問題がある医師は必要ない。データ解析や資料作成は自分が行ったように口裏合わせを求めるメールを送った研究チームの中心だった医師は即刻、京都府立医科大学から除外するべきだ。この医師は事件を知りつつ、隠ぺいしてきた人間だ。このような医師が研究チームにいては良いない。問題を起こし、さらに悪質な行為をおこなった医師は処分される事を示すべきだ。
データ改ざん 医師が口裏合わせ求める 06/11/14 (NHK)
大手製薬会社「ノバルティスファーマ」の高血圧治療薬の論文データ改ざん事件で、おととし、逮捕された元社員が大学の臨床研究に関わっていることが学会で問題視された際、研究チームの中心だった医師が、元社員に任せていたデータ解析などを自分が行ったように口裏合わせを求めるメールを元社員らに送っていたことが分かりました。
ノバルティスの元社員、白橋伸雄容疑者(63)は、高血圧治療薬「ディオバン」の臨床研究で、京都府立医科大学の研究チームに虚偽の論文を発表させたとして、薬事法違反の疑いで逮捕されています。
研究チームは、白橋元社員にデータ解析や資料の作成などを任せていましたが、おととし、学会で利害関係のある製薬会社の社員が研究に関わっていることが問題視されました。
関係者によりますと、この際、研究チームの中心だった医師が、データ解析や資料作成は自分が行ったように口裏合わせを求めるメールを白橋元社員と研究の責任者だった元教授に送っていたということです。
しかしそのあと、論文のデータが解析段階で改ざんされた疑いが指摘されるようになると、研究チームは一転してデータ解析を白橋元社員に任せていたことを認めたということです。
今回、明らかになったメールの存在は、研究チームが製薬会社の社員に研究の主要な部分を丸投げしていた実態を隠そうとしていたことをうかがわせるもので、その姿勢が改めて問われることになります。
産学で「偽りの効能」 ノバルティス社元社員逮捕 06/12/14 (東京新聞 朝刊)
降圧剤ディオバン(一般名・バルサルタン)の大学での臨床研究データを改ざんしたとして、販売元の製薬会社ノバルティスファーマ(東京都港区)の元社員白橋伸雄容疑者(63)が薬事法違反(誇大広告)容疑で逮捕された。背景にはノバルティス社と研究者がもたれあい、「偽りの効能」を広めた構図が浮かぶ。これまで四大学がデータ操作の可能性を認め、日本の臨床研究の信頼をおとしめる事態になっている。 (中山岳、加藤益丈)
■発端
「データがそろい過ぎている」。二〇〇七年春、京都大病院循環器内科の由井芳樹医師は、東京慈恵医大のディオバンの臨床研究論文を読んで疑問を抱いた。
血圧を下げる効果は他の降圧剤と同様ながら、狭心症などのリスクを抑える効能をうたっていた。ディオバンを服用した患者グループと他の降圧剤を飲んだグループとの比較研究では、年単位での服用後の血圧の平均値が両グループでまったく同じだった。
その後一二年一月までに、計五大学がディオバンの効能に関する論文を発表。同様の血圧変化の研究結果の数値が、名古屋大を除き、東京慈恵医大と同じく完全に一致。「統計学的にあり得ない」。由井医師は疑念を深めた。すべての研究に白橋容疑者がデータ解析などで関与していた。
由井医師は研究への疑問を投げかける論文を同年四月に発表したが、大きな問題にはならなかった。ノ社は専門誌に反論広告を掲載し、日本高血圧学会幹部らが座談会形式で「疑念は払拭(ふっしょく)された」と論文の正しさを強調したこともあった。
■癒着
風向きが変わったのは同年十二月。日本循環器学会が調査に乗り出し、学会誌に載った京都府立医大の論文を撤回。他大学の論文撤回も相次いだ。ノ社は昨年五月、白橋容疑者の研究への関与を認め「不適切だった」と謝罪した。
ノ社はこれまで五大学の論文を約五百件の広告に利用。ディオバンは十年余りで一兆二千億円を売り上げる看板商品に成長した。この間、ノ社から五大学には総額十一億円余の奨学寄付金が渡った。
三億八千万円を寄付された京都府立医大の研究責任者は昨年、厚生労働省の検討委員会のヒアリングで「年間三千万円あれば研究費をまかなえると、ノ社に伝えた」と説明した。検討委メンバーで、NPO法人「臨床研究適正評価教育機構」の桑島巌理事長は「多額の寄付を得るために研究していたとみられても仕方がない」と批判する。
■捜査
「大学側も改ざんに関わっていた疑いがある」と由井医師。カルテ作成やデータ入力などの段階で、数値が変化しているからだ。
論文を執筆した京都府立医大の医師ら国公立大学の研究者は、みなし公務員。検察幹部は「血圧を下げる以外の効果がないと知りつつ効果を宣伝し、報酬を受け取っていたら収賄に当たる可能性はある」と話す。特捜部は研究に参加した大学や病院の医師からも事情を聴き、全容解明を急ぐ。
とても悪質だ!第三者機関は、17人の弁護士と法律の専門家で構成され、4月中旬にスイス本社の委託を受けた後、7月5日までの約2か月間にわたって調査を実施。第三者機関がまとめた調査報告書を公表した。報告書は、元社員の私物のパソコンの調査ができなかったなど「調査の限界」を主張し、「元社員がデータの意図的な操作、ねつ造、改ざんなどを行ったことを示す事実は認められなかった」としている。 時間の無駄とお金の無駄だったのか、それとも形だけの調査だったのか? 第三者機関による調査の信頼性は高くないと言う事が明らかになった。少なくともこの件に対する調査は結果として信頼性は無いと言う事だ。
厚生労働省の薬事法に基づく調査は調査対象者や対象企業が悪質であれば機能しない事が明確になった。今後、すみやかに制度が機能するように改正するべきだ。
韓国の沈没した旅客船のように事故が起きてから対応していては遅い。
業者に口裏合わせを“依頼” ノバルティス元社員 06/12/14 (東京新聞 朝刊)
ノバルティスファーマの薬を巡る臨床データ改ざん事件で、データを業者から受け取って改ざんしたとみられる元社員の男が国の調査を前に、業者に対して口裏合わせを依頼していたことが分かりました。
ノバルティス社の元社員・白橋伸雄容疑者(63)は、高血圧治療薬「ディオバン」の効果を調べる京都府立医大の臨床研究で、不正に改ざんしたデータを大学側に提供し、虚偽の効果を論文に記載させた疑いが持たれています。関係者によりますと、白橋容疑者は、自分が大学側に紹介したデータの管理業者から直接、データを受け取って改ざんを行ったとみられています。しかし、厚生労働省の調査前に、業者に対して「データは直接、受け取っていないことにしてほしい」などと口裏合わせを依頼するメールを送っていたことが分かりました。東京地検特捜部は、関与を隠そうとしたとみて調べるとともにノバルティス社の立件も検討しています。
ノバルティス元社員 逮捕前 関わりを全面否定 06/11/14 (NHK)
大手製薬会社「ノバルティスファーマ」の高血圧治療薬に関する臨床研究で不正なデータ操作が行われたとされる問題で、東京地検特捜部は、ノバルティスの元社員がデータを改ざんし、京都府立医科大学の研究チームに虚偽の論文を発表させたとして元社員を薬事法違反の疑いで逮捕しました。
元社員は逮捕前の取材に対し不正への関わりを全面的に否定していました。
この問題は、ノバルティスファーマが販売する高血圧の治療薬「ディオバン」について全国5つの大学で行われた臨床研究で不正なデータ操作などが行われたとされるものです。
厚生労働省が刑事告発し、東京地検特捜部がノバルティスや各大学を強制捜査して実態の解明を進めていました。
その結果、5つの大学のうち京都府立医科大学について臨床研究に関わっていたノバルティスの元社員、白橋伸雄容疑者(63)がデータの改ざんを行い、大学側に虚偽の論文を発表させた疑いが強まったとして薬事法違反の疑いで逮捕しました。
医薬品に関する研究論文の内容にうそがあったとして刑事事件に発展したのは初めてです。
特捜部によりますと、白橋元社員はデータの解析を担当し、ディオバンを服用している患者よりも服用していない患者のほうが脳卒中を起こす率が高いように数値を改ざんするなどしていたということです。
大学側は改ざんされたデータやグラフをそのまま論文に引用して発表していたということです。
特捜部は大学やノバルティスが論文に虚偽の内容が含まれていたことを認識していなかったかどうか調べるものとみられます。
白橋元社員は逮捕前の取材に対して不正への関わりを全面的に否定していました。
論文執筆者「気付かなかった」
問題とされた論文を執筆した京都府立医科大学の沢田尚久元講師はNHKの取材に対し、「白橋元社員が解析したデータを受け取り内容を疑うことなくそのまま論文の執筆に使っていた。自分は解析の素人なので解析には関わっていないしデータに不審な点があったことにも気付かなかった」などと話しています。
京都府立医科大「再発防止に努めたい」
問題となった臨床研究を行った京都府立医科大学は「ノバルティスの元社員が逮捕されたことは重く受け止めたい。引き続き特捜部の捜査に協力するとともに再発防止に努めたい」とコメントしています。
厚生労働省「推移見守る」
ノバルティスの元社員が逮捕されたことについて、ことし1月、東京地検特捜部に告発した厚生労働省は「捜査中であり、その推移を見守りたい。ノバルティスについては、この件以外にも副作用の報告漏れなどの問題を抱えていると認識しており、製薬会社として国民の信頼を取り戻せるよう取り組んでもらいたい」というコメントを出しました。
専門家「信頼大きく失った」臨床研究適正評価教育機構の桑島巌理事長は「医学研究の不正を巡って逮捕者が出るというのは極めて異例なことで、今回の事件で医療界は国民の信頼を大きく失った。事件の背景には企業の営利主義や、さらに本来ならきちんとした情報を国民に伝えるべき専門の医師があまりにも企業によりすぎているという癒着の実態があり、企業や医師はこれを機会に襟を正すべきだ。今回の逮捕をきっかけにして、誰がどのような意図を持って不正を行ったか徹底的に真相を解明し、再発防止につなげるべきだ」と話しています。
理研の問題をここまで公に広めた功績がゆえに解体を言う事なのだろう!
小保方氏所属の研究センターは「解体を」 理研改革委、抜本改編求め提言へ (1/2)
(2/2) 06/12/14 (読売新聞)
新型万能細胞とされる「STAP細胞」の論文不正問題で、外部有識者でつくる理化学研究所の改革委員会が、小保方晴子・研究ユニットリーダー(30)が所属する発生・再生科学総合研究センター(神戸市)の解体を求めることが11日、分かった。12日に発表する報告書に盛り込む。研究不正の再発防止へ抜本的な改編が必要と判断した。
関係者によると、報告書で同センターは組織全体を廃止と同じレベルで解体。理研の他の研究施設と、研究内容の重複がないかバランスを考慮した上で、生命科学系の新組織に改編する。名称の変更も求める。
新組織の幹部は理研の外部から登用して刷新。これに伴い、現在の竹市雅俊センター長(70)と、小保方氏の指導役だった笹井芳樹副センター長(52)に事実上、退任を求める。
STAP問題を受け同センターの検証委員会が進めてきた調査では、特例的に英語での面接などを省略した小保方氏の不適切な採用や、研究内容が漏れないよう小保方氏を囲い込み、秘密主義で論文作成を進めたことなどを問題視。センターに自浄能力がなく、ガバナンス(組織統治)が機能していなかったことが不正を生んだ要因と指摘されたことを受け、改革委は解体が不可欠と判断した。
改革委はガバナンスを強化するため、外部を含め計12人で構成する経営会議や、不正抑止本部の設置も報告書に盛り込む。
同センターは平成12年に発足。動物の発生メカニズムや再生医学などの先端研究で世界的に知られ、人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使った世界初の臨床研究も進めている。24年度の予算は約39億円、職員は約500人。22年から翌年に324本の科学論文を発表した。
ばんせい証券、損失2億円を顧客に付け替え 06/11/14 (読売新聞)
商品先物などを扱う「ばんせい証券」(東京)が、自社が運営していたファンドで生じた約2億円の損失を、顧客の厚生年金基金の損失として不正に付け替えていたことが分かった。
基金側は付け替えに気づかず、全額を損金計上していた。証券取引等監視委員会は、同社と傘下の「ばんせい投信投資顧問」に対し、金融商品取引法違反で行政処分するよう、週内にも金融庁に勧告する方針を固めた。
監視委が同証券への処分を勧告するのは4度目。金融庁は、同社に抜本的な経営改善を求める。
関係者によると、ばんせい証券は、顧客の「関東六県電気工事業厚生年金基金」(さいたま市)と契約し、商品先物系のファンドで約17億円を運用していた。
ファンドは2009年4月、船舶関連の債権を約2億6000万円で購入したが、08年のリーマン・ショック以降の世界的不況の影響でほぼ全額が損失となった。契約に基づけば、損失のうち約2億5500万円は本来、ばんせい証券が負担するはずだった。
最近、善より悪の方がはるかに強力であると感じる。製薬大手・ノバルティスファーマ(東京)元社員が逮捕されたことについてこれぐらいの罰はあって良いと思う。
ノバルティス元社員を逮捕=高血圧薬データ不正-薬事法違反容疑・東京地検 06/11/14 (時事通信)
製薬大手ノバルティスファーマの高血圧治療薬ディオバン(一般名バルサルタン)の臨床研究データ操作問題で、東京地検特捜部は11日、薬事法違反(誇大広告)容疑で、同社元社員の白橋伸雄容疑者(63)=神戸市北区=を逮捕した。
医学界と製薬業界を揺るがしたノ社の臨床データ操作問題は刑事事件へと発展した。
逮捕容疑では、白橋容疑者はノ社の部長だった2010年11月~11年9月、京都府立医大が実施した臨床試験のデータを改ざんして虚偽の図表などを作成。研究者に提供して論文に記載させ、ディオバンの効能や効果に関して虚偽の事実をインターネット上に公開し、閲覧可能な状況にした疑い。
厚生労働省は今年1月、ノ社が京都府立医大の論文などに基づき、ディオバンは脳卒中や狭心症を防ぐ効果が他の薬より優れていると誇大に宣伝した疑いがあるとして、同法違反容疑で刑事告発。特捜部は2月、ノ社本社など関係先を家宅捜索していた。
ノ社はこれまで「証拠はない」と疑惑を否定。白橋容疑者も同社の聞き取りなどに対しデータ操作を否定していた。
白橋容疑者の逮捕を受け、ノ社は「事実を厳粛に受け止め、引き続き捜査に全面的に協力していく。ご心配とご迷惑をお掛けし、改めて深くおわびする」とのコメントを出した。
逮捕のノバ社元社員、研究の根幹部分に深く関与 06/11/14 (読売新聞)
製薬業界と医学研究の信頼性を損ねた疑惑に、捜査のメスが入った。高血圧治療薬「ディオバン」の臨床研究データ改ざん問題で、東京地検特捜部が11日、販売元の製薬大手・ノバルティスファーマ(東京)元社員、白橋伸雄容疑者(63)を薬事法違反容疑で逮捕した事件。
今年1月の厚生労働省の刑事告発から半年近くを経ての捜査の急展開に、関係者は一様に驚きの表情を浮かべた。
「重く受け止めたい。引き続き捜査に協力し、再発防止に努めたい」。白橋容疑者がデータを改ざんしたとされる研究が行われた京都府立医科大の担当者は、逮捕の知らせに戸惑いを隠せず、そうコメントするのが精いっぱいだった。
事件の発端は2012年4月、ディオバンに関する論文の血圧データについての不自然さが指摘されたことだった。白橋容疑者はノバルティスファーマの社員のまま、「大阪市立大非常勤講師」の肩書を使って研究に参加し、データ解析を一手に引き受けるなど、研究の根幹部分に深く関与していた。
ノバルティスと東大病院 追加で明らかにされた4臨床研究不正 06/11/14 (日本ビジネスプレス)
5月19日、製薬企業のノバルティス社(以下ノバ社)は「慢性骨髄性白血病治療薬に関する4臨床研究についての社外調査委員会の報告について」と題して、調査報告書を公表した。
この調査報告書は、ノバ社が東京大学医学部附属病院で行われた4つの臨床研究に不正関与した問題について、ノバ社自身が社外調査を依頼し提出を受けた調査結果である。
今回の記事では、この調査報告書が作られることとなった経緯とともに、その内容を検討していきたい。
簡単な経緯
この調査報告書は先述のとおり、ノバ社が東大病院の臨床研究に不正関与した事例について、調査したものである。したがってノバ社が他の病院の臨床研究に不正関与した事例や、東大病院がノバ社以外の製薬企業と研究不正を行っていた事例については、今後の調査が期待される。
ことの発端となったのは今年1月17日から報道された、SIGN研究事件である。東大病院の血液内科と、同科に事務局を置く研究組織TCCが行った、白血病治療薬の医師主導臨床研究に、当該薬の製造元であるノバ社が不正関与していた事件だ。
SIGN研究事件が報道された3日後の1月20日には、ノバ社は社内調査により同社のSIGN研究への不正関与が有ったと公表、2月5日には同事件の社外調査を依頼する。
一方、東大病院はこの間長らく沈黙を保っていたが、3月14日に突如「慢性期慢性骨髄性白血病治療薬の臨床研究「SIGN研究」についての調査中間報告」と題して記者会見を行った。
この記者会見の質疑応答時間中に突然、出席していた門脇病院長が自発的に、東大病院においてノバ社が関わる臨床研究をすべて調査したところ4件で不正関与が認められた、と発表する。
したがって今回の4研究に関する公表は、東大病院の方がノバ社より早かったということになる。もっとも東大病院の内部調査は予備調査の中間報告であるにもかかわらず、その後の情報が途絶えてしまう。
これに対して、ノバ社は4月2日には社外調査委員会の最終調査報告書を受け、翌4月3日には記者会見を実施、この中で同社は今年の夏までに2011年以降に行われた医師主導臨床研究への不正関与をすべて公表すると宣言した。
この流れに従い今回第1弾としてノバ社の社外調査が、東大病院に関わる4件の臨床研究不正関与事件の調査報告書を提出した、ということになる。
内容の前提
この調査報告書は4件の臨床研究に対して、ノバ社のMR(医薬情報担当者)がどのように関与し、その結果として研究内容に影響を与えたのか、についてのみ検討している。
これは既にノバ社が厚生労働省から、降圧剤ディオバン®(バルサルタン)の不正関与事件で薬事法違反の誇大広告で刑事告発を受けており、その際の厚労省のロジックが臨床研究に不正関与しその結果として研究内容が改変され広告に利用されるというスキームで、これに対応したためと思われる。
本来、臨床研究への不正関与と誇大広告は別物であるが、厚労省はこのような法律論で刑事告発まで漕ぎ着けている。
もちろん研究内容に影響を与えていなかったとしても「個人情報の流出」や「患者さんの同意を詐取しての臨床研究実施」は当然問題とされるべきである。
感想の先取りとなってしまうが、この調査報告書は事実の調査は十分だが、法的な分析が物足りないように感じる。
もっともこの点については小粒な事件の調査としてはやむを得ないだろう。ノバ社が関わった膨大な数の臨床研究をすべて丹念に調べていては全体像が把握できなくなる。
そこで読み手の側で、臨床研究に対する不正関与の一般論を綿密に検討したSIGN研究の調査報告書を前提とし、この調査報告書に補填し考えていくことが必要になる。いずれの調査報告書もノバ社が出しており、同社の中では一体として扱われるべきだからだ。
以下の各研究の検討では個別の違反事例の特徴について検討していくが、すべての研究において前提となっている慢性的なMRと病院の関わりは、別途問題とされる可能性があるものだ。もっともこの点については既に別の記事で述べさせていただいているので、今回は指摘するにとどめる。
研究Iについて
研究Iは「初発時慢性期慢性骨髄性白血病に対するイマチニブの至適血中濃度を指標とした早期投与量調整の効果を検討する第II相臨床試験」という名称で、先述の東大病院に事務局を置く研究組織TCCが主導して行った臨床研究である。
内容はノバ社の製品であるグリベックの投与初期段階にある慢性期の慢性骨髄性白血病患者さんを対象に、グリベックの血中トラフ濃度を測定し、至適血中濃度未満の患者さんに対し、グリベックの投与量を増やして血中トラフ濃度が確実に上昇するかどうかなどを調べる臨床研究であった。
この研究Iは登録方法の煩雑さもあって、東大病院を含む10施設が参加したものの、予定登録症例数の100例に対し実際の登録症例数が6例にとどまり、データ解析段階に入らぬまま2011年9月に中止に至った。
不正関与の態様については、ノバ社のMRが臨床研究の実施計画に当たるプロトコールの立案から関わり、医師を交えた検討会議をノバ社の会議室で行い、症例登録についてもMRが管理していたという。SIGN研究と同様の関わり方であるが、注目すべき特徴もある。以下少し長いが引用する。
「症例登録情報については、学術担当ⓟが、症例連絡票に係る症例をまとめた『候補症例登録シート』と題するエクセルファイルを研究事務局から入手すると、その都度、MRやブロックマネージャー等に対して電子メールで報告するなどしてノバ社内で共有していた」(略称等適宜修正、以下同様)
「また、病院#4の担当MRのフォルダに、病院#3が症例登録した特定の患者について、来院予定日と各来院予定日に行われる検査項目を記載した『Tokyo CML Conference イマチニブ臨床試験来院予定表』と題するエクセルファイルが保存されている。このファイルのプロパティ上、前回保存者として学術担当ⓟが記録されていることから、参加施設の担当MRまたは学術担当ⓟが、研究Iの登録患者の来院予定日と検査項目を管理していた可能性がある」(編集部注: 丸数字は機種依存文字であるため#つき数字に変換しました。【例】丸数字3 → #3、以下同様)
以上の記述をまとめると、特定の登録患者の来院予定日や検査項目を製薬企業のMRが管理していた可能性があるということになる。
これは患者さんにとってはかなり不気味なことであり、もし本当ならば情報の取得・共有方法がシステム化されている分、MRがアンケートの運搬機会にコピーし情報を収集していたSIGN研究よりも、個人情報入手の態様が悪いと言える。
研究Iの登録人数が少なかったため特定されたと考えることもできるが、もし登録数が増加していたとしたら同様に情報共有がされていた可能性がある。個人情報保護の観点から研究Iはさらに検討されるべきであり、東大病院側の研究Iへの情報管理体制の調査が待たれる。
研究IIについて
研究IIは「イマチニブ長期服用患者における腎機能への影響実態調査」という名称で、研究Iと同じくTCCが主導して行った臨床研究である。
内容は2001年1月1日から2012年9月30日までの間にグリベックを投与した慢性骨髄性白血病の患者さんの治療データを収集することで、グリベックの長期投与が腎機能に及ぼす影響を明らかにすることを目的としており、新たな検体収集や測定は行わない後方視的研究であった。
もっとも研究IIは類似研究の結果が先に学会で発表されたことなどにより中断し、論文化には至っていない。
不正関与の態様については、SIGN研究や研究Iのようにプロトコールの作成から関わるよりはおとなしく「調査票(書式)の作成および改訂、参加した医療機関への連絡文書案の作成および送信、データ集計表の作成、中間発表のスライド原案の作成等」ということである。
ところで臨床研究の実施に当たっては、参加する医療機関の倫理委員会の承認を得る必要があり、研究IIについては以下のような顛末があったようである。
「研究IIは、研究事務局を務める東大病院においても倫理委員会を通さずにスタートしたが、東大病院だけは倫理委員会を通しておいて欲しいという参加施設からの要望を受け、東大病院の倫理委員会の承認を得ることとなった」
そして調査報告書は以下のように続ける。
「この東大病院の倫理委員会の手続について、MRⓐを始めとするノバ社従業員の関与は認められない」
確かにノバ社の不正関与という視点からすると、プロトコールの作成・倫理委員会への届出に関わっていない以上「関与がない」という結論に至る。
しかし東大病院の側から検討すると、倫理委員会への承認申請に当たってはCOIと呼ばれる利益相反事項を開示する必要があり、そこでは製薬企業の関わりについて開示される必要がある。
そこでTCCが先述のようなノバ社のMRの関わりを説明していないのであれば、倫理委員会に対して虚偽の届出をしたということであり、倫理委員会の承認を詐取したということになる。
研究IIの東大病院における倫理承認手続きの経過と、利益相反事項の説明がどのようになされていたかの調査が必要である。
このように製薬企業の従業員が研究に関わっていることを秘して医師主導臨床研究が行われた場合、「倫理委員会の承認詐取」「患者さんの同意詐取」「個人情報流出の可能性」が常につきまとうことになる。これは他の3研究についても同様である。
研究IIIについて
研究IIIは「イマチニブ治療により分子遺伝学的完全寛解がえられた慢性骨髄性白血病に関する多施設共同後方視的研究」という名称で、主導して行ったのは東京医科大学病院に事務局を置く研究組織TSSGであり、東大病院はこの研究に参加する形で関わっている。
内容はグリベックの投与が継続されている慢性骨髄性白血病の患者さんで、過去24カ月間分子遺伝学的完全寛解を持続している症例と、その継続が困難であった症例の差異を明らかにすることを目的とした後方視的研究である。
2013年9月には100例の目標症例数に対し127例が登録され症例登録が締め切られたが、SIGN研究におけるノバ社の関与等が問題となった影響から、論文発表には至っていないもようである。
不正関与の態様については「参加施設の依頼によるアンケートの研究事務局への運搬、研究事務局の依頼によるアンケートの進捗状況確認のための連絡文書の作成等」ということである。
そして調査報告書には以下のような記述がある。
「MRⓐは、(東大病院の)医師Aから研究事務局に届けるよう依頼されて、記入済みの二次アンケートのアンケート用紙を2回にわたって受領し、これをMRⓔに渡した。また、病院#7の担当MRであるMRⓖは、2013年2月中旬、同病院の医師Jから研究事務局に届けるよう依頼されて、80個の入力済みの二次アンケートのワードファイルが入ったCD-ROMを受領し、これをMRⓔに渡した」(かっこ部分は筆者が補った、以下同様)
「MRⓖは、上記で述べたCD-ROMをMRⓔに渡す前に、CD-ROM内の二次アンケートのワードファイルを自分のネットワークドライブにコピーして保存し、エクセルファイルの形式に整理した。これは、症例データのバックアップだけでなく、グリベックで分子遺伝学的完全寛解を維持できなかった症例について、今後の(ノバ社の新製品である)タシグナへの切替え等を視野に入れた情報収集活動を意図したものであった。なお、ノバ社東京事業所から、記入済みの東大病院の二次アンケート用紙のコピーが発見された。これはMRⓐがMRⓖと同様の意図でコピーしたものである可能性が高い」
このようにアンケートの運搬中にデータをコピーし、患者さんの情報を不正に収集するという手口は、SIGN研究と同様のものである。調査報告書からはアンケートの匿名性の度合いは判然としないが、場合によってはSIGN研究と同様の個人情報流出事案になる可能性がある。
研究IVについて
研究IVは「初発慢性期の慢性骨髄性白血病に対するニロチニブの分子遺伝学的完全寛解達成率を検討する多施設前方視的共同試験」という名称で、主導して行ったのは研究IIIと同じくTSSGであり、東大病院は参加病院である。
内容は初発慢性期における慢性骨髄性白血病の患者さんにタシグナを投与することによって、分子遺伝学的完全寛解の累積達成率を将来にわたって観察することを目的とした、前方視的医師主導臨床研究である。
研究IVは現在も症例登録期間が継続中であるが現状は不明である。
不正関与の態様については「プロトコール案の作成や症例登録票等の各種書式の作成、投与患者の各種情報の集計整理、症例登録を促進する各種連絡文書案の作成と送信等」ということである。
MRの関与形態としてはいわゆるプロトコールからのSIGN研究型である。
この研究IVでは「医師主導臨床研究」の名の下でいったい何が行われていたかが、赤裸々に記述されている。そこで少し詳しく見ていくことにしよう。
▽医師主導って何ですか?
さて研究IVで一番注目すべきは、製薬企業の臨床研究への不正関与という視点からは180度変わって、研究者としての医師がいかに製薬企業とMRを利用しようとしていたかである。以下引用していく。
「研究IVの端緒は、東医病院に所属する医師Eからの提案であった。すなわち、医師Eから、2011年初め頃に、タシグナに関する新しい臨床研究の枠組み案を明らかにした上で、ノバ社の競合相手であるブリストル・マイヤーズ株式会社の活動状況を踏まえるとノバ社においても新たな臨床研究を実施した方が良いのではないかとの提案があり、これを受けて、研究IVの検討が開始された」
「この頃、(ノバ社の)メディカル部門は医師主導臨床研究への関与を限定的なものとする方向に方針転換し、学術担当ⓡを含め、メディカル部門のノバ社従業員は研究IVへの関与を拒否するようになった。そのため、以後は、東医病院を担当するMRⓔが、過去の類似の臨床研究の資料を参照するなどしながら各種関係書類の原案作成等の作業を行うようになった」
この経緯がもし事実であるならば、研究者である医師が製薬企業の競争を利用して、臨床研究を行うよう持ちかけたことになる。そして当の製薬企業の本部からはそっぽを向かれてしまい、結局病院担当のMRが付き合い上、医師のために働くことになったということになる。
このあたりは医薬品の消費者として病院で力を持つ医師と、営業担当としての性格を持つMRの微妙な力関係が透けて見える。また臨床研究への製薬企業の不正関与につき、けして研究者たる医師が被害者ではないことがよく分かる事例である。
「MRⓔは、プロトコール委員の候補の選定や、候補者を委員に選任することについて賛同を求める医師D名義の参加施設宛の連絡文書案の作成等、プロトコール委員の決定手続の補助を行った。研究IVのプロトコール検討会は、2011年9月6日に、ノバ社東京事業所の会議室において開催された。(中略)MRⓔがプロトコール委員の意見をとりまとめて修正案を作成するなどしている」
「研究IVに関する資材としては、慢性骨髄性白血病患者に対する説明文書、慢性骨髄性白血病患者からの同意書、症例登録票、症例登録通知票などがある。これらの資材は、MRⓔが、MRⓕなどの他のノバ社従業員の協力を得ながら、過去の臨床研究における同種資材をベースに原案を作成し、医師Eによる確認を経て内容を確定した」
「少なくとも東医病院に係る倫理委員会申請書類については、MRⓔが作成を代行した」
「MRⓔは、(中略)医師D名義の参加施設宛の連絡文書案を作成した。また、MRⓔおよびMRⓕまたはMRⓗは、TSSGの研究事務局である病院#8血液内科の担当者を差出人とする参加施設宛のメールの文案も作成していた」
「医師Eが当該進捗報告に用いたスライド資料の作成に際しては、MRⓔが過去の他の臨床研究における発表資料を参考に医師Eにおいて報告すべき項目を提案し、医師Eがこれを踏まえて内容を記載していた」
この記載が真実ならば、プロトコールの作成・研究使用書面の作成・倫理委員会への申請書の作成・メールの作成送付・発表資料の作成、すべてをノバ社のMRがやっていたことになり、まさに「至れり尽くせり」である。
いったいどのあたりが「医師主導臨床研究」なのだろうか?
▽組織的な個人情報の収集
個人情報の収集に関しては以下のような事実が記載されている。
「研究IVデータベースは、(中略)MRⓔが研究IVの登録症例について、TSSG症例登録番号、観察研究の登録番号、施設名、担当医師名、性別、身長、体重、Sokal score、合併症、既往歴などを入力したものである。MRⓔは研究IVデータベースを医師Eに提供したほか、ノバ社内部でも少なくとも一部MRと共有していた」
「MRⓔは、折を見て東医病院血液内科の秘書から症例登録票を預かってコピーをとっており、現在に至るまでこれを保管している。MRⓔはこれにより把握した症例登録状況を担当MRにアナウンスするとともに、グラフや一覧表にまとめ、ブロックマネージャーへの研究IVの進捗報告や、各MRに対する次回検査日のリマインド、後記キの参加施設宛のメール文案作成等に用いていた」
「上司のブロックマネージャーは、MRⓔに対し、毎月症例登録状況をチェックするよう指示していたが、実際にはMRⓔが当該秘書の機嫌のよいタイミングを見計らって不定期に症例登録票を借り受けるに止まり、毎月のチェックを実施できていなかった」
文中に出てくるMRが作成していた「研究IVデータベース」が個人情報に該当するのかについてはなお慎重に検討する必要がある。
しかし他の情報と照合することで個人が特定できる可能性が高く、医師主導臨床研究であり製薬企業の関与が予定されていない情報を、ノバ社のブロックマネージャーが収集するように指示をしていたという事実は重く考えるべきであろう。
▽奨学寄附金の実態
奨学寄附金は企業などが大学や教授に寄附を行う制度で、通常は特定の研究目的を定めずに寄附を行う。有名な教授になると複数社から寄附金を集め、それを資金力に研究を進めていくことになる。
研究にかかる費用を奨学寄附金から支出している場合、目的が紐付けられておらず、複数社の寄附が交ざるため、仮に寄附者に研究の目的となる医薬品の製薬企業が入っていたとしても「利益相反はない」というのが、大学の立前である。
東医病院ではないが、東大病院のSIGN研究の中間報告書では、このあたりの大学側の主張が以下のように述べられている。
「(「ノバ社からの血液・腫瘍内科への奨学寄付金」の項目で)本研究が計画されてから今年度までの寄付額は2011年度200万円、2012年度300万円、2013年度300万円であった。本研究に直接関する奨学寄付金はない」
「ノバ社からの血液・腫瘍内科への奨学寄付金については、本研究に対する直接的な寄付金ではなく、通常の寄付金の範囲内と判断された」
もっともノバ社側のSIGN研究外部調査報告書では、同じ奨学寄附金に対する見方はずいぶんと違う。以下引用する。
「支出の制約がなく手続も簡易なことから、営業現場では、奨学寄附金を営業活動の手段または医療機関にMRが出入りするための前提として用いていることがうかがわれる。実際、一部の医療機関等から、露骨な奨学寄附金の要求が行われている事実がうかがわれる記載を含む資料もあった。こうしたことからも、医療機関等が製薬企業に財源的に依存している実態がうかがわれるところである」
「また、ノバ社の医薬品を使用した医師主導臨床研究を実施してもらうこととの見合いで寄附されることが多かった模様である。これは、奨学寄附金の目的に反する点で問題であるのみならず、医師主導で行う医師主導臨床研究の精神にも反するという、二重の問題点を含んでいる」
では研究IVではどうだったのだろうか? 4研究の調査報告書に戻ろう。
「研究IVについては、基本的には観察研究による検査を利用していることから、9か月目に行われるBCR-ABL mRNAモニタリング20を除き、試験費用の負担は生じなかったが、観察研究の症例登録期間終了後に登録された症例については、観察研究による検査を利用することができなくなるため、その試験費用の負担をどうするかが問題になった」
「ノバ社従業員10名は、2013年2月26日に、ノバ社東京事業所でTSSGに関する会議を開き、東医病院に対する奨学寄附金を用いることによって試験費用を東医病院に負担してもらうことが可能であると結論付けた。また、その後の同年3月22日頃に、MRⓘが、試験費用の試算を行い、その支払方法は『東医病院への一括が望ましい』などと記載した資料を作成した」
「これらを受けて、医師Eは、同月30日開催の第22回TSSG定例会議において、MRⓘ作成の上記資料をほぼそのまま一部に取り入れた資料に基づき、毎月3例が症例登録されその半数に対して血中濃度測定等を行った場合の試験費用が1300万9500円になること、およびその支払方法は「一括して東医病院への請求」となることなどを説明し、特段異議は述べられなかった」
「したがって、東医病院に対する奨学寄附金の一部が研究IVの試験費用に充てられた可能性は高いものと思われる」
製薬企業とMRの側の奨学寄附金に関するやり取りが、ここまで公開されることは珍しい。まさしくノバ社のSIGN研究外部調査報告書が述べたとおり、実際にはノバ社の奨学寄附金が、ノバ社の医薬品を対象とした医師主導臨床研究に利用されていたことが如実に分かる。
今後は大学側も、「奨学寄附金を利用しているので利益相反がない」とは言えない実態が克明に表れている。
▽研究IVのまとめ
このように研究IVは、研究者である医師が、ライバル製薬企業の研究が進んでいるという情報をもとにMRをけしかけて、プロトコールから発表資料の作成までやらせたという、かなりひどい「医師主導臨床研究」の事例だ。
むろん研究者であるお医者さんのほとんどは、自らの手でまじめに医師主導臨床研究をしているはずである。だからこそ、このような研究者を放置しておいてはいけないのである。
医療系臨床研究への信頼を維持し、患者さんの臨床研究参加への厚意を裏切らないためにも、医療研究界は自浄作用を働かせていただきたいと思う。
もっともこの調査報告書は、あくまでノバ社の社外調査に、ノバ社のMRが回答した内容である。医師Eにはこの調査報告書の内容が真実なのかを是非、自ら答えていただきたい。
相変わらずの東大病院の対応
5月20日に東大病院は、前日のノバ社の4研究の調査報告書公表を受けて「慢性期慢性骨髄性白血病治療薬の臨床研究について」との記事を公開した。
内容については見ていただければお分かりいただけると思うが、3月14日の「SIGN研究」の「予備調査」の「中間報告書」を再掲しただけである。
経緯でも述べさせていただいたが、今回の4研究はSIGN研究と同じTCCが関わっているものの、SIGN研究とは別の研究である。
そもそもこのSIGN研究の中間報告書では、今回の4研究のことについては全く触れられていない。4研究については中間報告書の質疑応答時間中に門脇病院長が口頭で公表したにすぎないからだ。
さらに言えば東大病院はSIGN研究の予備調査の中間報告を行って以来、今回の内容がほとんどない記事を掲載するまで、全く情報を公開していない。これは東京大学、東大病院、研究責任者、のすべてが一切公の場で発言していないということである。
東大病院の内部調査は先日報道されたアルツハイマー病研究J-ADNIの不正でもそうだが、現在のところ信用に足るだけの実績を示していない。この点は早急に改善が必要である。
おわりに
今回の4研究の調査報告書では、冒頭の調査結果の要旨の部分で早々に「結論」として、「以上のとおり、研究IないしIVの調査の結果、ノバルティスファーマ株式会社従業員の関与によって研究結果が不当に歪められたとは認められない」と記載されている。
確かに「研究結果」への影響はなかったのかもしれないが、そのことは臨床研究不正が引き起こすほんの一面にすぎないことは既に見てきた通りである。
臨床研究と他の研究の最大の違いは、実際の患者さんという人間を対象にしているという点だ。したがって臨床研究の不正は常に患者さんの視点から考えなければならない。
以上のように述べてきたがこのように問題のある事実が明らかになったのは、ノバ社が調査を公表すると決断したからである。ノバ社はこれからも厳しい事例が報告され、社会的批判にさらされるかもしれないが、徹底的な調査と公表を行っている姿勢は高く評価したい。
さて東大病院はどうするのだろうか。
ノバルティス 副作用情報1万件を放置 長年にわたり報告を軽視 06/09/14 (産経新聞)
製薬会社ノバルティスファーマ(東京)が、同社製品を使った患者の副作用情報約1万件を、社内で安全性評価をしないまま放置していたことが9日、分かった。臨床研究をめぐる問題を受けて調査した同社が厚生労働省に届け出た。このうち国に報告義務がある重い副作用がどの程度含まれるかは不明といい、同社で薬事法に違反する行為がなかったか調べている。
同社によると、1万件の中には平成14年当時の副作用情報もあり、同社が長年にわたり報告を軽視してきた実態が浮き彫りになった。調査は4月中旬、全社員約4500人を対象に実施。同社の安全性評価部門に未報告の副作用情報がないか調べたところ、約1万件の報告漏れが見つかった。社員が医療機関で独自に集めたデータや、講演会で医師が発表した資料などで判明したものが多かった。14年の症例もあったが、新薬発売が相次いだ23年以降の分が多いという。
薬事法では、死亡や知られていない重い副作用は15日以内、その他の重い副作用は30日以内の国への報告を製薬会社に義務付けている。同社は社員に有害事象を入手した場合、24時間以内に評価部門に報告することになっていたが、徹底されていなかった。1万件には重複や軽症も多く含まれているとみられる。
同社をめぐっては、白血病治療薬「タシグナ」を使った東大病院などの臨床研究で、重い副作用2件を知りながら放置していた問題が4月上旬に発覚。同社は「社員は営業業活動を重視し、入手した症例を適切に報告することに意識の甘さがあった。再発防止を徹底したい」としている。
副作用など最大1万人分未報告 ノバルティス 06/09/14 (朝日新聞)
製薬大手ノバルティスは9日、同社の薬を使った患者が副作用などの何らかの問題が起こった事実について、把握していたにもかかわらず社内への報告をしていなかった事例が最大で約1万人分あると発表した。中には、薬事法で報告義務がある重い副作用が含まれる可能性もあり、同社が詳しく調べる。
同社は4月、全社員約4500人に問題事案の資料の提出を求めたところ、約1万人分のメモなどの資料が提出された。最も古いのは2002年のものだった。同社はすでに報告されているものなど重複例もあるとみている。同社は「社員の意識の甘さがあった。再発防止策を検討する」としている。
同社には、社員が薬の副作用などを知った場合、社内の安全性評価部門に24時間以内に報告する社内ルールがある。しかし、白血病治療薬をめぐり、国に報告すべき重い副作用の疑いがある事例を知りながら、報告していなかった。
カジノ法案が通れば、初期投資や期待から大きなお金が動き、一時的には儲ける人がいるだろう。しかし、カジノには闇の部分がある。アメリカのラスベガスのようにエンターテイメントに力を入れて、大人、子供、そして家族が楽しめるように変わる方法もある。ネバダ州は地理的に産業には向いていない。雇用を考えると特別な政策がないと期待できない。
シンガポールは独裁ではないが、政府の厳しいコントロールにより成り立っていると思える。シンガポールではシンガポール人がカジノでお金を損失しないように入場料を高く設定している。外国人は無料である。カジノだけでなく、ビジネス、外国人労働者、移民政策等に関して利益優先ですごくリアリスティックだと思う。外国人家政婦に対しては3ヶ月毎に妊娠チェックを行い、妊娠が分かれば国外退去処分にする。これにより外国人家政婦がシンガポールに留まれない。日本ではどのようになっているか。中国人の偽装出生届、フィリピンダンサーとの結婚の問題がある。結果として離婚やシングルマザー問題で貧困にあえぐ子供達がいる。行政コストや税金の負担まで考えて、外国人ダンサーを入国させることにメリットがあったのか?マカオは闇の部分を含めてカジノ優先の政策に思える。
利権、金、政治家への献金や寄付、目先の利益そしてその他のメリット、これらに関与する人達だけのお話だろう。
社会学者滝口直子氏(上)「カジノで成長戦略は絵に描いた餅」 06/09/14 (日刊ゲンダイ)
いよいよカジノ法案が来週、衆院で審議入りする。安倍政権は特区をつくり、外国人観光客を呼び込むことで、成長戦略の目玉にしようとしているが、多くの懸念があるのも事実だ。外資の食い物にされないか。成長戦略になりうるのか。ギャンブル依存性の問題はどうなのか。カジノ研究第一人者の社会学者に聞いてみた。
――安倍晋三首相は先月30日、訪問先のシンガポールでカジノを含む統合型リゾート施設(IR)を視察、「外国人観光客を2020年までに年2000万人へ倍増させたい。IRは(外国人観光客を呼び込む)成長戦略の目玉」と意気込んでいましたね。
カジノ最後発の日本が、トップを走るシンガポールやマカオと競争して世界の富裕層を引っ張ってくることができるのでしょうか。非常に甘い予測といえますし、そもそもヨーロッパやカナダなどではカジノを成長産業とみていません。確かにシンガポールのカジノは成功していますが、そのビジネスモデルが日本でも成り立つのかは疑問です。シンガポールは人口の多いインドやASEAN、中国に近い。お客さんを呼びやすい地理的条件がある。日本がシンガポールに追い付こうとしたら、地理的に近い中国などの富裕層を呼んでくることが不可欠ですが、安倍首相は日中関係や日韓関係を悪化させていますからね。絵に描いたモチとなる可能性は非常に高いと思います。
■日本人の虎の子が海外へ流れる
――最大の顧客となる隣国との関係悪化を招いた“A級戦犯”が、中国の富裕層がカギを握るカジノ推進を口にするのは支離滅裂だと。ブレーキとアクセルを同時に踏んでいるようなものというわけですね。
先月15、16日に都内で開催されたカジノの国際会議「ジャパン・ゲーミング・コングレス」では、安倍首相の発言と正反対のプレゼンテーションがありました。主な顧客は外国人観光客ではなく、日本人の富裕層という内容です。「日本人富裕層の個人金融資産量」を「日本に出来る推定カジノ数(3~10)」で割って、「海外に比べて、日本の1つのカジノ当たりの個人金融資産量は突出しているから日本のカジノは莫大な利益は確実」と投資を呼びかけていました。
――外国人観光客を狙うわけではないんですね。
国際会議には、「スペクトラム・ゲーミング」のフレッド・グシン代表取締役をはじめ海外のカジノ業界の大物が多数参加していましたが、彼らにとって重要なのは、投資が回収できるのかどうかであって、お金を落としてくれるのが外国人であろうが日本人であろうが関係ない。外国人観光客を呼び込むという安倍政権の成長戦略のもくろみは外れ、日本の虎の子の個人資産が外資に流出してしまう事態が考えられます。
また成長産業になるどころか、日本の公営ギャンブルが廃れていったのと同様、衰退産業となる恐れもあります。今の若い世代は小さい頃からオンラインゲームやSNSに慣れ親しんでいますので、わざわざカジノに出かけていくのかは怪しい。今はアジアでカジノがブームだけれども、10年後や20年後は公営ギャンブルと同じ運命をたどっても不思議ではありません。(つづく)
(聞き手=横田一)
▽たきぐち・なおこ 1955年生まれ。カリフォルニア大学民俗・神話学際プログラム、博士号取得。大谷大学短期大学部、文学部助教授を経て、2000年から大谷大学文学部社会学科教授。ギャンブル依存症やアルコール依存症を社会学的に研究している第一人者として知られる。
本当に「まやかし」。公務員が仕事に見合った給料をもらっていないと批判すると、働き過ぎの公務員を引き合いに出す。非効率や出世のための努力に対して税金を使うべきでない。
欧米と逆行 公務員は適用外「残業代ゼロ」のマヤカシ 06/08/14 (日刊ゲンダイ)
アベノミクスの成長戦略に盛り込まれる可能性が高い「ホワイトカラー・エグゼンプション」。サラリーマンの残業代をゼロにしてしまう、とんでもないシロモノだ。「時間」ではなく「成果」に対して、賃金が払われることになる。ノルマを果たすために延々と働くことになり、過労死が急増するのは間違いない。
ところが、公務員には適用しないことが分かった。6日国会で民主党の山井和則議員が「残業代ゼロは公務員も対象なのか」と質問したら、「原則として公務員は対象ではない」と内閣官房が明言したのだ。
安倍政権はホワイトカラー・エグゼンプションを、「残業しても残業代が出ないので労働時間が減る」「生産性が上がる」「成果さえ上げればいいので自由な働き方が可能になる」などと、いいことずくめのように喧伝(けんでん)して導入しようとしている。それほど素晴らしい「労働制度」だと言い張るなら、まず「公務員」に適用すればいい。なのに、身内の公務員は適用外、残業代を払うというのだから、フザケるにも程がある。
■サラリーマンいじめ
「安倍政権が指摘するように、日本人の“生産性”が低いのは事実です。“生産性”だけを比較するとOECD加盟国のなかで19位。長時間働いている。でも、日本人の残業時間が長いのは、残業代があるからではありません。むしろ、欧米に比べて残業代は安い。日本は残業の割増賃金が25%なのに対し、アメリカは50%、ヨーロッパには75%の国もある。
つまり、欧米では長時間働かせると残業代が多額になるので、とにかく時間内に仕事が終わるように企業が工夫せざるを得ない。それが高い“生産性”に結びついているのです。もし、“生産性”を上げたいなら、日本も残業代を75%にすればいい。残業代をゼロにしようなんて、どうかしています」(経済ジャーナリスト・荻原博子氏)
まずは、公務員と国会議員こそ“成果主義”にすべきだ。
科学や研究の分野なので問題と原因を明確に発表してほしい。科学の分野なのに、日本的な曖昧や抽象的な回答はおかしい。
小保方さん、論文取り下げで借金危機 笹井氏らも道連れ 理研総退陣論も 06/05/14 (夕刊フジ)
新型万能細胞「STAP細胞」の論文不正問題が、急展開だ。理化学研究所の小保方晴子・研究ユニットリーダー(30)が補完的な論文に続いて主要論文の撤回にも同意した。「白紙」に戻ったSTAP論文の次に待ち受けるのは、関係者らの処分だ。STAP細胞をぶち上げた理研トップらの退陣を求める声も噴出。小保方氏ら研究者には、研究費の返還も予想されている。
「STAP細胞はあります」と力説した涙の会見から約2カ月。小保方氏が論文撤回に同意した理由について、代理人の三木秀夫弁護士は4日、「理研の検証実験に参加するため、応じざるを得なかった」と説明。「STAP細胞について存在する事実は変わらない」とあらためて主張した。
「仕方がなかったんです。悲しいです」と無念さを吐露したという小保方氏。科学ジャーナリストの大朏(おおつき)博善氏は、「小保方氏の気持ちは研究を続けたいという一心だろう。検証チームに入る代わりに、論文を撤回するといった理研側との取引があったかどうかは不明だが、論文にこだわっている場合ではないと判断したのではないか」と話す。
だが、科学の世界では論文と研究は一心同体だ。主要論文の撤回で科学的信用はなくなり、事実上の「白紙」に戻ったといえる。
東京大の上(かみ)昌広特任教授(医療ガバナンス論)は、「論文の問題はこれで終わったことになる。今後は、研究者と管理者の責任がそれぞれ問われることになるが、管理者としての『経営責任』をうやむやにしてはいけない」と指摘する。
管理責任が浮上しているのは、理研トップの野依(のより)良治理事長、小保方氏が所属する発生・再生科学総合研究センター(CDB)の竹市雅俊センター長、笹井芳樹副センター長らだ。
「どんちゃん騒ぎの記者会見は誰の判断で行われたのか。笹井氏は管理職としてふさわしかったのか。小保方氏はなぜ抜擢されたのか。責任問題は山積している。野依、竹市、笹井氏の辞任は避けられないのではないか」と上氏は続ける。
2012年12月に理研CDBが実施した小保方氏の採用面接では、通常行うはずの英語のヒアリングを省略するなど、“特別扱い”だったことが判明している。
論文撤回により、研究費の返還問題も議論が進む。STAP細胞の研究費は国民の税金であり、今後、理研側が、研究者個人に返還請求する可能性がある。「研究費が不正に使われたのならば、金を返せというのは当然のこと。どの部分を請求するかはケース・バイ・ケースだが、数千万円に及ぶこともある。理研が補完的な論文である『レター』を撤回したため、調査しないというのはおかしい。『レター』については不正が認定されず、研究費の返還も問われなくなる。理研側はこうした民事的問題についてもしっかり議論しなくてはいけない」と上氏。
研究費の返還請求がなされれば、小保方氏は「不正」という不名誉に加え、多大な金銭負担を背負うことになる。国民には見えないところで、さまざまな駆け引きがささやかれるSTAP細胞問題。黒幕は誰なのか。上層部の説明責任が、一層強まっている。
申し訳ないが、もしかすると「STAP細胞」プロジェクトは韓国の貨客船「SEWOL」ではないのか?とんでもない要素が重なりとんでもない結果となったと言う事。
理研がしっかりしていれば、それでも今回の騒動は防げたと思う。
小保方氏、異例の採用…高評価英文に「コピペ」 06/05/14 (読売新聞)
STAP(スタップ)細胞の論文問題で、小保方晴子氏が2012年、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(神戸市)のユニットリーダーに応募した際に提出した「研究計画書」は、留学先の米ハーバード大から提出された特許書類の英文を多数、複製して作成し、画像の説明は誤っていた疑いのあることが、同センターの「自己点検検証委員会」の報告書案で明らかになった。
同センターの選考では、計画書から「小保方氏の英語のレベルは非常に高く、主張が明快で構成力に優れている」と評価していた。
さらに、締め切り日を過ぎて応募した小保方氏の申請書を受理したうえ、一部の審査手続きを省略するなど、採用の経過は異例ずくめだったことも分かった。報告書案は、STAP細胞の研究成果がもたらす利益をセンターが強く意識するあまり、過去の論文などのチェックも不十分なまま、小保方氏を拙速に採用したと断定している。
もうそろそろ終わりでしょうか?しかし、発表前に慎重なチェックは出来なかったのか?
STAP細胞:小保方氏論文 万能性実験 裏付けなし (1/2)
(2/2) 06/02/14 (読売新聞)
◇「実験計画書」「実験ノート」の記載に食い違い
STAP細胞の万能性を示す証拠として理化学研究所の小保方晴子・研究ユニットリーダー側が行ったとする実験を巡り、使われたマウスの種類や実験方法など複数の点について、英科学誌ネイチャーに掲載された論文と理研が許可した動物実験計画書、小保方氏の実験ノートの間で記載内容が著しく異なることが分かった。実験の成功を報告した論文の基本的な部分に裏付けがないことになる。研究の全貌を明らかにしないまま「新たな不正は調べない」として幕引きを急ぐ理研の姿勢が問われそうだ。【浦松丈二】
理研が小保方氏らに許可した実験計画書によると、STAP細胞を「balb/c」という種類の免疫不全マウス5匹の皮下に移植し、7日後、14日後、1カ月後、2カ月後の4回安楽死させ、組織を取り出して、体のさまざまな組織を含むテラトーマ(腫瘍)ができたかどうかを確認する内容だった。
一方、ネイチャーに掲載された2本の論文のうち、小保方氏が撤回に同意していない主要論文には、STAP細胞を「NOD−SCID」という別の種類の免疫不全マウスに移植し、6週間後に組織を取り出して解析したと記載している。「NOD−SCID」は「balb/c」より実験用マウスとして新しく、移植した組織が定着・機能しやすい。
さらに、小保方氏側が理研調査委員会に提出した不服申し立ての理由補充書では、組織を取り出した時期を4週間後としている。論文とも実験計画書とも一致しない。
移植した細胞数も、論文によれば「10の7乗個(1000万個)」だが、理由補充書に示された実験ノートの記載では「10の5乗個(10万個)」。マウスの週齢も食い違う。論文では「4週齢」だが、実験ノートでは「6週齢」だった。
毎日新聞の情報開示請求を受け理研が公開した物品購入記録によると、小保方氏が客員研究員として理研入りした2011年3月から、論文を投稿した13年3月までの間、在籍した研究室は「NOD−SCID」マウスや「4週齢」の免疫不全マウスを購入していない。
ネイチャー誌の投稿規定によると、責任著者は所属機関の動物実験規定を順守していることを確認し、論文に明記する義務がある。STAP論文にも理研の規定通りに実施したとの記載がある。理研の動物実験に関する規定では、事前に実験計画を申請して研究所長の承認を受け、各年度末と終了後に報告しなければならない。計画内容を変更する場合は変更申請をして許可を得る必要があるが、STAP実験については申請は出されていない。理研調査委員会はネイチャー論文に掲載されたテラトーマの画像を「捏造(ねつぞう)」と認定したが、基本的な記載内容も、裏付けとなる重要記録と食い違っていたことになる。理研の調査の不十分さを浮き彫りにしたとも言える。
小保方氏の弁護団は、論文と実験計画書でマウスの種類の記載が異なることについて「小保方氏は病院内で資料もなく、病状からも回答できないため、理研に問い合わせてほしい」、その他の相違点に関しては「質問を読めるような精神状態ではない」とコメント。
理研広報室は「論文のマウスの種類は誤記載。その他の点については担当部署に確認中」としている。
JR北海道の改革は無理ではないのか?JR東日本が嫌がるかもしれないが、JR東日本に吸収合併させるしか改善の道は無いのでは?
国交省、JR北などに立ち入り調査…枕木問題 06/02/14 (読売新聞)
JR北海道の子会社「北海道軌道施設工業」(札幌市)が5月に行った枕木の交換工事で、男性現場責任者(解雇)が工事内容を誤って指示しながら放置し、報告書の数値を捏造(ねつぞう)した問題で、国土交通省は2日午前、同社に立ち入り、問題の経緯などの調査を始めた。
国交省関係者によると、JR北本社には1日に、立ち入りを行ったという。
北海道軌道施設工業には2日午前9時30分頃、国交省職員4人が調査に入った。同省では、過去に同社がJR北から請け負った工事について、工事ミスや検査の放置、データの捏造などがなかったかも調べる方針だ。
国交省は今年1月、JR北に対してJR会社法に基づく監督命令と鉄道事業法の事業改善命令を出し、向こう5年間にわたり安全管理体制などを調べる「常設監査」の実施を盛り込んだ。今回の調査も、常設監査の枠組みで行っているという。
記事の正確さには疑問だが、このような事は現実にあると思う。
ASKAで話題の“接待パーティー” 高級官僚も常連だった 05/31/14 (日刊ゲンダイ)
ASKA事件で注目を集める人材派遣会社「パソナ」グループの迎賓館「仁風林」(東京・港区)を舞台にした接待パーティー。常連客には、国会で追及された田村憲久厚労相や小野寺五典防衛相など現職閣僚を含む与野党の政治家の名前が次々と浮上。政界に激震が走っているが、“接待漬け”されていたのは政界以外にもいる。霞が関のエリート官僚たちだ。
美女が体を密着させながら酒をつぎ、豪華料理に舌鼓を打つ――。「仁風林」の接待パーティーは、さながら高級クラブのサロンのような雰囲気だったという。
接待客の人選や席の配置などを仕切っていたのは、南部靖之代表の“右腕”といわれ、「公共戦略事業・特命担当」の肩書を持つ上斗米明・常務執行役員。財務省出身の天下り官僚だ。
「83年入省で、主税局主税企画官、関税局業務課長などを経て国税庁総務課長に就いたものの、なぜか、たった5カ月で大臣官房付に異動し、そのまま辞職した。2010年に執行役員としてパソナに天下りしました」(事情通)
霞が関で突然の大臣官房付の異動はスキャンダル絡みが多い。南部代表はセクハラなどでミソを付けた有能な人材を利用するのがうまい。ま、いろいろとあったのだろうが、上斗米氏が霞が関とのパイプになったのは間違いない。
「パソナの官僚接待はすごいですよ。局長以上の幹部の多くは、“仁風林パーティー”を知っているはずです。パソナを含む派遣業界は90年代、業界全体で数十億~数百億円規模といわれた派遣社員の社会保険料の未納の扱いについて頭を痛めていました。98年には会計検査院が全国の派遣会社の約400の事業所で、約35億円の社会保険料の徴収漏れがあったことを指摘しています。保険料徴収が厳格化されれば、業界はたちまち火の車。そこで保険料の支払いを緩くするための日雇いや請負といった規制緩和に政界工作を仕掛けた。課長クラスもパーティーに来ていて、南部代表の腰巾着といわれているエリート官僚は大勢います」(元人材派遣会社幹部)
「仁風林」の常連官僚の中には、経産省の局長や中小企業庁の幹部職員がいて、実名が飛び交っている。
文科省の事務方トップ、山中伸一・事務次官の名前も出てきたから文科省に事実確認すると「こんなことを次官に聞けるワケがないし、プライベートなことなので答える必要はない」(事務次官室)ときた。
経済ジャーナリストの荻原博子氏がこう言う。
「労働者あっての国や経済なのに、官僚や派遣業界は、労働者を『出来る限りコキ使って搾取するコマ』としか見ていない。自分たちさえ儲かればいいと思っているから、政官財で“癒着”しようが“談合”しようが、悪いという感覚がないのでしょう」
「仁風林」での政官接待は、98年の銀行と旧大蔵官僚の「ノーパンしゃぶしゃぶ接待」を思い出させる。お車代などの現ナマをもらって、行政をネジ曲げたのだとすれば許されない話だ。
首相が叱責…ASKAの女に異常接近していた小野寺防衛相 (1/2)
(2/2) 05/30/14(日刊ゲンダイ)
こうなると、安倍内閣の閣僚は全員通ってたんじゃないかと思えてくる。パソナグループの迎賓館「仁風林」(東京都港区)。同社の南部靖之代表主催のパーティーに、田村憲久厚労相ら現職閣僚5人が出席したことをこれまでに伝えたが、小野寺五典防衛相(54)も“メンバー”だったことが日刊ゲンダイ本紙の調べで新たに分かった。覚醒剤使用でASKAが逮捕される直前まで通っていたようだ。
「二度と行かないように!」――ASKA事件がはじけた直後、安倍首相は小野寺大臣を呼びつけてこうクギを刺したという。パソナの迎賓館には安倍の“お友達”が何人も通っていた。小野寺が出入りしていたことは、すぐさまレーダーに引っ掛かったようだ。
小野寺は宮城県職員から政治家に転じた。妻の父親が気仙沼市長などを歴任した地元政界の重鎮で、その地盤を引き継ぎ国政進出したが、威を借るわけでもなく、謙虚な真面目キャラに徹している。自民党の重鎮にも評判がよく、ある旧防衛庁長官経験者は「彼は安全保障をよく勉強している。将来の総理候補」と褒めていた。
それがなぜ、政財界の怪しげな面々が集まる場所に顔を出すようになったのか。
「小野寺大臣の目的はASKAの“愛人”栩内香澄美だったそうです。栩内は青森出身で、小野寺大臣は宮城県出身。“同じ東北出身”をアピールして接近しようとしたけど、うまくいかなかったようです」(事情通)
シャブという武器を持っているASKA相手では、小野寺の“スクランブル”失敗も無理はない。
もっとも、妻子を仙台市内に残して単身赴任中の小野寺は独り身が寂しいのか、夜の世界は嫌いじゃないようだ。昨年5月、中国の潜水艦が沖縄・久米島の接続水域内に侵入して日中間に緊張が走った夜、銀座の和風キャバクラでホステスとのひとときを楽しむ様子を「週刊文春」に報じられた。
小野寺の国会事務所は「報道された容疑者と面識はございません」と栩内との関係を否定しつつ、「かなり以前に(仁風林に)伺ったことはありますが、最近はまったく伺っておりません」と回答した。
田村厚労相は就任後も…「パソナ接待館」常連だった5閣僚 (1/3)
(2/3)
(3/3) 05/28/14(日刊ゲンダイ)
「シャブ&ASKA」事件の余波が政界にも広がってきた。ASKA(56=本名・宮崎重明)と一緒に覚醒剤取締法違反容疑で逮捕された栩内香澄美容疑者(37)は大手派遣会社パソナの関連企業に勤め、2人が知り合ったのもパソナの接待施設「仁風林」(東京)だった。この接待施設には政界関係者も入り浸っていた。なんと、複数の現職閣僚も濃厚な接待を受けていたという。
政治ジャーナリストの山田厚俊氏がこう言う。
「閣僚のひとりは田村憲久厚労相です。取材した限り、大臣就任後も『仁風林』に顔を出しています」
今国会の大きなテーマのひとつは派遣法の改正だ。安倍政権は規制を撤廃して派遣労働者を増やす方針。恩恵を受けるのは派遣業界だ。その業界を所管する厚労省のトップが、派遣会社パソナの“接待”を受けていたというのだ。
「議員会館などで開かれる業界の勉強会に顔を出した、というならまだしも、所管の大臣が一企業のパーティーに出席するなんて非常識ですよ」(山田厚俊氏=前出)
■田村事務所は「確認中」
田村と派遣業界はズブズブの関係だ。日本人材派遣協会や日本生産技能労務協会などで構成される「政治連盟新労働研究会」から12年11月、50万円の献金を受け取っている。両協会のトップは昨年8月、派遣法の見直しを審議する労働政策審議会の委員に選ばれ、この後、規制撤廃の方向が決まった。
いったい、パソナと田村大臣との間に何があったのか。「仁風林」の接待による“便宜供与”を疑われても仕方ないのではないか。
田村事務所にあらためて問い合わせると「確認中」と回答した。
驚くのは、田村以外にも常連客として複数の閣僚の名前が挙がっていることだ。
「田村大臣以外に4人の閣僚の名前が浮上しています。いずれも自称『改革派』の閣僚たち。ほかに官僚の名前も複数出ています。官僚は特殊法人への天下りが厳しくなったため、民間企業に天下り枠を求める傾向にある。『仁風林』はその人脈づくりの“窓口”というワケです」(霞が関事情通)
シャブ&ASKA事件は、政界と財界の一大疑獄事件に発展するかもしれない。
運悪く偶然が重なった結果でないのであれば、JALの整備に問題があると言う事だろう。人事の人選ミス、整備コストを削減している、技術の知識が無い人が整備に関する人事権を持っているとか、とにかくコスト削減を強調する人が存在する、整備の事を理解しない人達が強引に整備時間を短縮したとか、いろいろと推測は出来る。結果として、墜落や死亡事故が起きていないから問題ないが、そうなったらどのような言い訳をするのだろう。
JAL整備ミス16件…「異例の頻度」と国交省 05/31/14 (読売新聞)
日本航空が昨年10月から今年5月にかけて、計16件の整備ミスを起こしていたことが30日、国土交通省への取材でわかった。
運航に支障が出たケースはなかったが、国交省は「異例の頻度でミスが起きている」として、日航に原因究明と再発防止を指導した。
国交省や日航によると、3月にボーイング777型機のエンジンを整備した際、着陸時の減速に使う逆噴射装置の部品を取り付け忘れ、約1か月にわたって運航を続けていた。最悪の場合、エンジンの一部が損傷する恐れがあったという。
また、ボーイング767型機の主脚の部品を付け忘れ、制動に影響が出る恐れが出たほか、資格のない整備士が整備作業の最終確認をしていたケースもあった。
東大に任せておけば安心と言う時代ではなくなったのか、それとも、事実や情報のコントロールが出来なくなってきた結果なのか?
主任の東大教授に聞き取り 05/27/14 (佐賀新聞 電子版)
認知症臨床研究で厚労省
アルツハイマー病の大規模な臨床研究(J―ADNI)で不適切なデータ管理が指摘された問題で、田村憲久厚生労働相は27日、東京大の調査中にデータが書き換えられた疑いがあるとして、主任研究者の岩坪威東京大教授に聞き取り調査をする方針を明らかにした。
研究をめぐっては、条件に合わない患者が含まれるなど、データ管理が不適切だと内部研究者が指摘し、東大が1月に調査を始めた。条件に合わない患者14人を例外として認める書類が3月に作成されていたことが、内部研究者の指摘で新たに判明した。
田村氏は閣議後の記者会見で「(東大には)データ保全するようにお願いした。データの書き換えがあったとすれば、仮に改ざんでなくても認められない。厳正に対処していく」と話し、コンピューター上の記録を調べ、どのような種類のデータに変更があったのか確認するとした。
一方、茂木敏充経済産業相は同日の閣議後の記者会見で「データの書き換えの事実を確認した」と明らかにし、データ保全に反する行為かどうか、精査すると説明した。
代表の東大教授が口止めメール J―ADNIデータ操作 05/27/14 (朝日新聞)
アルツハイマー病研究の国内第一人者である岩坪威(たけし)東大教授が、自ら代表研究者を務める国家プロジェクト「J―ADNI(アドニ)」のデータ改ざん疑惑について東大が調査を始めた後に、証拠となるデータをJ―ADNI側が書き換えた事実を知りながら、関係者に口止めをするメールを送っていたことが朝日新聞の調べで分かった。岩坪氏は厚生労働省から調査中のデータ保全を要請されて承諾していたが、実際はデータの書き換えを知りつつ隠そうとしていた。
厚労省は「保全を求めたものに少しでも手を加えるのはおかしい」として27日にも岩坪教授から事情を聴く方針だ。研究トップが調査妨害工作に加担した疑いが浮上し、研究体制が見直される可能性が出てきた。
被験者の症状や検査時間を改ざんした疑惑を朝日新聞が1月に報じた後、厚労省は岩坪教授にデータ保全を要請し、東大に調査を依頼した。ところがその調査中、J―ADNIのデータセンター(データ事務局)に出向する製薬会社エーザイの社員が被験者要件を満たしていない14人に必要な例外申請書を事後的に作成するよう部下の非正規職員に指示し、データを書き換えさせていたことが今月26日の朝日新聞報道で発覚した。
疑惑データを不正更新、隠蔽工作か アルツハイマー研究 05/26/14 (朝日新聞)
アルツハイマー病を研究する国家プロジェクト「J―ADNI(アドニ)」のデータセンターが、臨床研究データの改ざん疑惑の調査中は証拠となる被験者データを触らないよう求めた厚生労働省の要請に反し、少なくとも14人のデータを書き換えたことが朝日新聞の調べで分かった。被験者の要件を満たしていなかったため、研究データとして使うのに必要な例外申請書を事後的に不正に作成していた。このほかにも全データの約2割にあたる613件で一部削除などの更新記録があり、隠蔽(いんぺい)工作が幅広く行われた可能性がある。
改ざん疑惑は1月に朝日新聞報道で発覚。厚労省は代表研究者の岩坪威東大教授にデータ保全を要請して承諾を得た上、東大に調査を依頼した。しかし、調査委員会のメンバーを公表せず、調査も大幅に遅れているため、真相究明に後ろ向きとの批判が出ていた。新たにデータの書き換えが発覚し、東大の調査への信頼が一層揺らぐのは必至だ。
データセンターはJ―ADNIのデータ事務局。認知症治療薬を売るエーザイの出向者が室長格として非正規職員約10人を使い、38病院から軽度認知障害などの高齢者545人の検査結果を登録してきた。関係者によると、書き換えを指示したのもこのエーザイ社員だという。
製薬社員、証拠の書き換え指示 J―ADNI疑惑 05/26/14 (朝日新聞)
国が旗を振るアルツハイマー病研究のデータ改ざん疑惑を東大が調査している最中に、証拠となるデータ自体が調査対象側の手で書き換えられていた。日本の先端医療研究への信頼がどんどん崩れていく。
◇
■職員「データ、次々持ってきた」
関係者によると、データセンターの室長格であるエーザイ社員が、改ざん疑惑が1月に発覚した後に採用された非正規職員2人にデータの書き換えをさせていた。その1人は「エーザイ社員が書き換えるデータを選んで次々に持ってきた。私たちは指示通りにしただけ」と話しているという。
朝日新聞が入手した内部文書には、本来は病院がつくるはずの書類をデータセンターが事後的に不正に作成した記録が残っている。
奈良県立医大で臨床研究の検査を3年間受けた60代男性は、脳卒中を予防する薬を2年目から服用し始めた。この薬はアルツハイマー病の臨床研究の検査に影響を及ぼす可能性があるため、そのまま検査対象にするには奈良県立医大がJ―ADNI研究者でつくる臨床判定委員会に例外申請書を提出して承認を得なければならない。しかし、データセンターが申請は不要と指示したため、申請書は提出されていなかった。
データセンター職員は3月24日、エーザイ社員から指示され、「依頼ミスにより、追加コメントにてご対応を頂きました」として「併用禁止薬服用? 他院治療により1日2錠の抗凝固薬を開始」と記した例外申請書を作成した。関係者によると、検査前に使ってはならない薬を服用した被験者を例外的に認めるよう申請する内容だという。
本来、申請書をつくる立場である奈良県立医大の担当医師は取材に「データセンターから連絡はなく、当方は把握していない」と答えた。(青木美希)
別人がなりすまして問題なくパスポートが取得できる事実は大問題じゃないのか!システムを変える必要があると思う。最近は、整形が流行っているから本人でも疑われる可能性もあるが、今回の件は大問題だ。
何者かが戸籍謄本取得、旅券申請…准看護師不明 05/24/14 (読売新聞)
大阪市西成区の准看護師の岡田里香さん(29)が今年3月下旬から行方不明になっている事件で、失踪後、何者かが岡田さんの戸籍謄本を取得していたことが、捜査関係者への取材でわかった。
幼なじみの日系ブラジル人の女(29)が5月上旬に出国した際に使った岡田さん名義のパスポートは、直前に申請、取得されたものだったことも判明。大阪府警は、女が不正入手した戸籍謄本を悪用し、パスポートの申請時から岡田さんになりすましていたとみている。
捜査関係者によると、岡田さんはパスポートを持っていなかったが、失踪したのと同時期の3月下旬、何者かが岡田さんを名乗って大阪市阿倍野区のパスポートセンター阿倍野分室で申請し、4月上旬に発給を受けていたことがわかった。
この際、本人確認書類として使われた戸籍謄本は、岡田さんとは別人とみられる人物が役所の窓口で発行を受けていたという。
パスポートに使われている顔写真は日系ブラジル人の女のもので、府警は、女が岡田さんを装って一連の手続きをしたと判断。女は不正入手した岡田さん名義のパスポートを使って5月上旬、中国籍の女とともに、羽田空港から中国・上海に渡航していた。
セキュリティーが仇となった!罪がどんどん重くなる。
<韓国旅客船沈没>韓国船級が書類隠し…CCTV映像を確保 05/24/14 (中央日報日本語版)
釜山地検特別捜査本部は23日、「韓国船級の職員が検察の家宅捜索前日に書類を運び出した事実を確認した」と明らかにした。
検察によると、韓国船級釜山本社を家宅捜索する前日の先月23日夜に、役職員が会長室と役員室から書類を運ぶ場面が録画されたCCTV映像を確保したという。
韓国船級は釜山海洋警察のイ警査から家宅捜索が行われるという情報を事前に受けた。捜査情報を流したイ警査は17日に罷免された。
また検察はこの日、海洋水産部の幹部に数回にわたりゴルフ接待をしたり、商品券や法人クレジットカードを渡した容疑(賄賂供与など)で、韓国船級のキム本部長(59)とキム・チーム長(45)に対する拘束令状を請求した。
セウォル号惨事で海洋マフィア問題が注目され、福島原発を含む原発問題では日本版原発マフィアが慣れ合い体質を見せつける。
原子力事業者から3千万円も 研究で規制委審査委員6人 05/22/14 (共同通信)
原子炉や核燃料の安全性について原子力規制委員会に助言する二つの審査会の委員6人が、原発メーカーや電力会社の関連団体からそれぞれ3277万~60万円の研究費などを過去数年間に受け取っていたことが22日、分かった。規制委事務局の原子力規制庁が公表した。
最も多かったのは東京大の関村直人教授で、三菱重工業と電力関係団体の電力中央研究所から研究費計3277万円を受領。審査会長を務める田中知東京大教授は、日立GEニュークリア・エナジーなどから計110万円受領したほか、東京電力の関連団体から50万円以上の報酬も得ていた。
情報がリンクされているサイトのタイトルに疑問を持ったが、情報としては面白いので古い情報ですがリンクします。
極端な情報のような気もするが、日本でもそうだが違法する人達もいる。韓国に行った時だが、おばさんが便器の水で桃を洗っていたのを見た。理解できないほど強烈過ぎて忘れる事が出来ない。
あなたの食卓は大丈夫?韓国食品の“不衛生”な実態(1)キムチでさえ安全性が揺らいでいる (1/2)
(2/2) 04/24/14(アサ芸プラス)
キムチに続き「韓食」文化の世界遺産登録を目指し、国策として世界にアピールする韓国。だが、その実態は、バキュームカーでの調味料運搬、農薬入り生海苔、細菌入りインスタント粥‥‥と、「不衛生」をはるかに超えた、人命を脅かすバイオテロ状態だった。あなたの食卓にも並ぶかもしれない危険な韓国食品の実態を──。
「昨年に比べて売り上げは40%以上も落ちました。韓流ブームの時には平日でも日本人で街はにぎわっていたのに、今は週末でも閑散として、店を閉める飲食店も増えています」
こう嘆くのは、「韓流の総本山」東京・新大久保で働く飲食店店主である。韓国貿易協会の報告書によると、昨年の対日輸出でキムチは前年比約22%下落。ビールは約50%減と、目も当てられない状況だ。
「12年8月に李明博大統領(当時)が竹島に上陸してから、客足が遠のいてきた」(店主)
しかし、原因は政治的背景だけではない。日本では韓国の「食」に対する信頼度がガタ落ちしているのだ。食品問題評論家で食品表示アドバイザーの垣田達哉氏はこう解説する。
「日本でも有名な『辛ラーメン』から発ガン性物質が検出されるなど、韓国では一昨年から食品汚染の問題が相次いで起きています。韓国食品が安全ではないということが意識されるようになり、敬遠する日本人が増えているのです」
ユネスコの無形文化遺産に登録された「キムジャン文化」のキムチでさえ、安全性が揺らいでいる。4月7日には、食品製造・加工メーカー「珍味」の工場で生産されているキムチ製品から食中毒菌が検出され、約1万2000キロが販売中止。回収騒動に発展したのだ。韓国人ジャーナリストの朴龍洙〈パク・ヨンス〉氏はこう語る。
「工場の一件だけではなく、韓国内で作られるキムチは体を害する菌や防腐剤が大量に含まれているとして、韓国人でも食べるのを躊躇〈ちゅうちょ〉することがあります」
信頼と売れ行きの回復に必死なのか、韓国観光公社は「キムチカクテル」を開発し、運営サイトで紹介した。グラスにニンニク、焼酎、キムチジュースを入れて混ぜたあと、キムチ漬けの白菜をコップに添えた衝撃のカクテル。しかし、公開直後から同サイトのコメント欄は大炎上したのだ。
〈観光公社の職員は間違いなくおかしい〉
〈私は韓国人だが、この商品に騙されてはいけない〉
韓国食品の問題はキムチにとどまらない。4月3日には、群山市にある大手調味料製造会社の食品工場で、調味料の原料になる「糖蜜」37トンを、人糞用のバキュームカーで運搬したとして工場関係者が警察に摘発されたのだ。
在韓記者はこう語る。
「会社側は『タンクに沈殿した糖蜜のカスを処分する際、粘着性が強いのでバキュームカーを利用した。食品原料には使用していない』と説明しています。ただ、警察は業者の証言に疑いを持っているようです」
バキュームカーのホースを製造タンクに入れた時点で、食品衛生上問題があるとして、市は行政処分する予定だという。
◆アサヒ芸能4/22発売(5/1号)より
あなたの食卓は大丈夫?韓国食品の“不衛生”な実態(2)養殖海苔に工業用農薬が… 04/30/12 (アサ芸プラス)
垣田氏が指摘する。
「韓国では激しい貧富の格差があり、食品関係者は貧しいのです。規模が小さいため、設備投資にコストをかけられず、手軽で安い方法で生産量を増やします。衛生管理も日本とは比較できないほど不衛生な状況なので、大腸菌などが検出されるのでしょう」
韓国食品の問題は細菌に関連したものだけではない。3月末には海苔の養殖業者17名が、毒性が強い農薬を使用していたことが判明して、書類送検された。在韓記者が語る。
「3年間にわたって、釜山や慶南で海苔の養殖業をする時に、白藻病の予防とシミ除去のために農薬を使用していました。政府は海上汚染を防ぐため、農薬を禁止。代わりに補助金を支給し、『海苔活性処理剤』の使用を勧めていました。しかし、あまり効果がないため、業者は工業用の農薬を使用していたのです」
取締りを行った海洋警察は、消費者に注意を呼びかけた。
「農薬が肌に直接触れた場合、ヤケドや失明のおそれがある。摂取した場合、嘔吐や消化不良、胃腸障害など命に関わる危険性もある」
しかし、3年間で、市場には1900トンもの養殖海苔が流通し、大量に消費されていたのだ。
4月11日にはパン生地メーカーの関係者が警察に捕まった。
「廃棄用の卵3万2000個を養鶏場から相場の3分の1以下の値段で買い取り、パン生地に使用していました。廃棄用の卵は冷蔵保管されていたが割れて中身が見えた状態で、食中毒を起こす危険性があるのです」(在韓記者)
発覚時、毒パンはすでに全国のサービスエリアに納品されていた。
調理現場を見て取れる飲食店での食事さえも安全は保証されていないと、朴氏は語る。
「ソウルなど都市部には道路を挟んで2、3坪規模の飲食店がズラリと並んでいます。衛生面は最悪で、キムチを作る時に道端で作業したり、店によっては水道代をケチって、客に出した皿を洗わずに使うケースもありました」
日本では考えられない環境だが、「人命よりコスト」が優先される韓国では、珍しくないという。
こうした不衛生な実態に、昨年7月から在韓日本大使館はホームページで、「食中毒に注意」の勧告を出している。また、台湾では韓国旅行後に下痢や腹痛、嘔吐の症状を訴える渡航者が多いため、1月に衛生当局が感染予防に努めるよう異例の呼びかけを始めた。
しかし、韓国“毒”食品は自国を飛び出して、日本を含めた海外に輸出され、猛威を振るっていたことが明らかになっている。
韓国産ヒラメで食中毒!寄生虫のクドア・セプテンプンクタータを検出・5人が下痢や嘔吐・昨年9月に日本政府が韓国産ヒラメの精密検査を免除後ヒラメの食中毒が多発・韓国の屎尿処理はそのまま海洋投棄で汚染が深刻化 2012 (正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現)

韓国産ヒラメからクドア・セプテンプンクタータ 07/19/12 (読売新聞)
山形県は18日、新庄市の飲食店で食事した5人が下痢や嘔吐(おうと)などの症状を訴え、同店で提供された韓国産養殖ヒラメの刺し身から寄生虫「クドア・セプテンプンクタータ(クドア)」が検出されたと発表した。
県はクドアを原因とする食中毒と断定。ヒラメの廃棄で、食中毒の拡大や再発を防止できることから、営業停止処分は行わなかった。クドアによる食中毒は県内で初めて。
県食品安全衛生課によると、5人は14日昼に同店でヒラメの刺し身を食べ、約4時間後に症状が出た。4人が医療機関を受診し、うち1人が入院したものの、18日現在、全員が快方に向かっているという。
厚生労働省によると、クドアは養殖ヒラメに寄生することが確認されており、昨年6月、食中毒の原因物質に加えられていた。
日本政府が韓国産ヒラメの精密検査を免除、韓国は輸出拡大に期待 10/04/11 (サーチナ)
韓国農林水産検疫検査本部は4日、日本政府が韓国産ヒラメに実施してきた精密検査を、9月22日から全面的に免除したと明かした。複数の韓国メディアが報じた。
韓国で採れたヒラメは日本に輸出される際、精密検査が行われていたが、通関に時間がかかり検査待機費用が発生していた。パク・ヨンホ本部長は、輸出業界の負担が大きいことから日本政府と話し合いを続け、検査緩和措置の合意に至ったと説明した。
検疫検査本部側は、今回の検査免除で日本にヒラメを輸出する時にかかっていた年間49万7000ドル(約3800万円)の通関遅延料を、削減できるとみている。また価格競争の高まりにより、日本国内で韓国産ヒラメの消費が増え、輸出量が拡大するのではないかと期待感を示した。
パク本部長は、「養殖水産物に対する管理を強化して国内養殖ヒラメの安全性を維持する」とし輸出拡大に向け努力するつもりだと話した。
UPDATE 2-U.S. FDA urges removal of Korean seafood products 06/14/12 (Reuters)
* At least 4 in U.S. sickened after eating seafood
* FDA says U.S. in talks with S.Korean officials
* Problem involves products imported before May 1 (Adds people sickened, background)
WASHINGTON, June 14 (Reuters) - The U.S. Food and Drug Administration urged the removal of South Korean oysters, clams, mussels and scallops from the market, saying the products may have been exposed to human fecal waste and contaminated with norovirus.
At least four people in the United States have become sick after eating South Korean seafood - three in October and one in December, the FDA said on Thursday.
The regulatory warning spans the range of fresh, canned and processed seafood products that contain the seafood types known as molluscan shellfish that entered the United States before May 1, when the FDA first removed them from an interstate list of certified shellfish shippers.
An FDA official said U.S. representatives are in talks with South Korean officials about the problem that involves polluted fishing waters where the seafood was harvested.
An official with the South Korean embassy in Washington had no comment.
Some food companies have already removed the products from their distribution networks. But the agency said not all have complied and it issued the warning in an effort to reach retailers distributors and food service operators.
"These products and any products made with them may have been exposed to human fecal waste and are potentially contaminated with norovirus," the FDA said in a statement.
South Korean shellfish represent only a tiny fraction of the oysters, clams, mussels and scallops sold in the United States.
Norovirus causes gastroenteritis, a disorder characterized by nausea, vomiting, diarrhea, stomach cramps and other symptoms that occur within 12-48 hours of exposure and last up to three days.
The FDA took action after determining that a South Korean program to safeguard shellfish contamination did not meet U.S. standards for sanitary controls.
The agency advised consumers to check seafood labels and contact seafood vendors, if they are concerned about products they have purchased, and throw out any found to be from South Korea. (Reporting By David Morgan, Anna Yukhananov and Salimah Ebrahim; Editing by Bob Burgdorfer and Tim Dobbyn)
昔は着服が穏便に処理されていたのか、それとも最近は従業員のモラルが下がったのか?
元財務担当社員、不正送金し1億1700万着服 05/20/14 (読売新聞)
東証1部上場で半導体材料製造のSUMCOは19日、財務担当だった元男性社員が約1億1700万円を着服していたと発表した。
同社はすでに元社員を警視庁に告訴している。
同社によると、元社員は2009年6月から12年4月の間、5回に分けて、仕入れ先への支払いを装って不正に送金し、会社の資金を着服していた。元社員が希望退職した後、社内の監査で判明した。元社員からは約3000万円を回収しているという。
論文不正で処分教授の別の4本、米誌で取り下げ 05/18/14 (読売新聞)
昨年夏、論文不正で停職処分を受けた大阪薬科大(大阪府高槻市)の男性教授について、関係した別の論文4本が、掲載された米国薬理学会発行の医学誌で取り下げられていたことがわかった。取り下げは4月8日付。
論文は2001年から11年にかけて掲載された。腎不全を発症させたラットを使った実験で、発症の仕組みのほか、予防効果や悪化させる可能性のある物質について調べた内容。
同誌は、調査の結果、データの二重使用が判明したためと説明している。
男性教授には、高血圧に関する論文に不正があるとの情報が08年と09年に寄せられ、同大学が調査委員会を設置。論文で「実験に使った」とされたラットが、実際には別の品種だったことがわかり、調査委が改ざんと認定した。男性教授は昨年6月、20日間の停職処分になった。同大学は、男性教授には処分対象の論文のほかにも研究不正の情報があり、調査を進めているとしている。
日立社員、入札情報を不正取得…保守権限悪用 05/16/14 (読売新聞)
国立国会図書館は15日、職員の業務用ネットワークシステムの管理を委託していた日立製作所(東京)の担当社員が、同図書館が実施予定の複数の入札に関する情報を不正に取得していた、と発表した。
日立によると、情報を入手して応札したケースもあったという。同図書館は日立に対し、指名停止や損害賠償請求などを検討している。
同図書館の発表や日立の説明によると、日立側は2011年6月以降の業務用システムの納入や管理業務を総額約15億7000万円で受注。問題の社員は保守担当で、この間、サーバーにあった図書館職員専用フォルダに複数回、不正にアクセスし、入札を担当する営業担当課長ら少なくとも4人にメールで伝えた。
社員が持ち出した情報には、他社の提案書や参考見積書などが含まれていた。このうち、4月に予定されていた次期システムの納入・管理業務の入札情報を自分のパソコンにコピーしていたが、図書館の職員が3月、社員のパソコン画面に表示された利用ファイルの履歴に入札情報が含まれているのに気づき、不正が発覚。日立はこの入札への参加を辞退し、他社が落札した。
韓国旅客船沈没まではどのような宗教を信仰しようが個人の自由だと思っていたが、これだけの惨事とその原因を知りながら信仰を続けられる事実は恐ろしいと思う。
韓国政府は天下りや癒着について取り組まないといけないが、カルトを取り締まる制度を考えるべきだと思う。
Ferry Owner Cult Members Barricade Compound 05/13/14 (The Chosun Ilbo (English Edition))
Hundreds of members of a cult led by Yoo Byung-eon, who also owns the compromised ferry operator Chonghaejin Marine, are barricading a retreat owned by the sect south of Seoul against investigators.
The cult members gathered at the compound on Tuesday, when prosecutors obtained an arrest warrant for Yoo's eldest son Dae-gyun (44) after he failed to show up for questioning.
They left the compound Tuesday morning but returned in droves on Wednesday, with numbers swelling from around 200 to 800, according to police. As of Wednesday night, around 400 remained in the compound, singing hymns and holding prayer meetings. They packed blankets and instant noodles to prepare for a drawn-out siege, and some were carrying suitcases.
A staffer at the compound said, "The rally will not end soon. More followers will converge."
Banners were posted at the compound protesting against what followers claim is religious persecution. Dozens of followers stood at the entrance with truncheons or walkie-talkies throughout the night.

Followers of cult leader and ferry owner Yoo Byung-eon rally at a compound in Anseong, Gyeonggi Province on Tuesday, holding placards that claim they are victims of religious persecution.
Cult members originally planned a press conference in front of the compound on Wednesday afternoon but canceled the event.
"A representative will announce tomorrow or the day after why we have gathered here and what our complaints are," a spokesman of the cult said. "We did not gather here to protect Yoo but to protect our religious facility after our rights and privacy were invaded."
Another compound staffer claimed he is not sure whether Yoo Byung-eon is hiding in the compound but added he is confident that his eldest son is not there. Prosecutors believe both are hiding in the compound.
An official with the Incheon District Prosecutors’ Office, which is separately investigating the two on charges of embezzlement and breach of trust, said, "Yoo will eventually show up for questioning given his high profile, so we're not immediately going to raid the compound."
englishnews@chosun.com / May 15, 2014
これだから日本で詐欺が儲かるのだろう
ニセ医者の人気講演、つかみは「佐村河内ネタ」…工学博士騙る“余罪”も 05/15/14 (産経新聞)
医師免許を持たない神戸市西区の男性(55)が医学博士や医師と偽り、約10年間にわたって講演活動やラジオ出演をしていた問題は、男性が依頼を受けて講演していた兵庫県三木市に講演料109万円を返還し、「もう講演活動はしない」と反省の弁を述べて一応の終息をみた。だが、男性のことを信じて講演会に足を運び、出演するラジオに耳を傾けていた市民や関係者の間では、怒りと落胆が今も収まらないままだ。一方、この問題の発覚後、男性の過去を知る人物からは、20年以上前に“工学博士”として活動していたという驚きの証言も寄せられた。(井上浩平、中村雅和)
■専門用語駆使、話に説得力
「今、話題になっている佐村河内(さむらごうち)守さん。ご本人は感音性難聴だそうですが、お年寄りの皆さんも他人事ではないですよ」
一連の問題が明らかになる直前の3月中旬、三木市内の公民館で開かれた男性の講演会の一幕だ。くしくも詐称疑惑で騒動を起こした人物をネタに話し始めると、会場の高齢者ら約50人から大きな笑いが起きた。
客席の反応に気をよくしたのか、スーツ姿の男性は眼鏡の奥の目を細めて大きくうなずくと、関西弁に時折、標準語が混じる独特の語り口で、健康や医療をテーマに講演を進めた。
このときは自分が医師であることは明言しなかったが、「病院で血圧の薬を出すやん。今、流行しているのがノルバスクという薬」「久しぶりに風邪薬を買ったが、成分をどうしても見てしまう。硫酸アミドなんて30年前なら劇薬やで」などと、専門用語を交えて医療知識が豊富であることをちらつかせ、話に説得力を持たせていた。
■講演繰り返し地元の“名士”に
男性は平成16年に神戸市西区内の2階建てアパートの1室に「総合医療研究所」と称する事務所兼自宅を置き、“所長”に就任。隣接する三木市を中心に、兵庫県内で自治体や企業が主催するイベントに医学博士として出席し、講演活動を始めた。
講演の主催者に提出した履歴書に記したのは、「灘中学・高校」(神戸市)を経て「東京大学医学部卒業」「米・ニューヨーク州立大学博士課程修了」などの輝かしい学歴。そして、「虎の門病院」(東京)や「国立循環器病センター」(大阪)など、医師として第一線で勤務していたというものだった。
講演会は三木市や地元企業などの主催で、多いときは1カ月に数回、1回につき1万数千円から6万円の謝礼を受け取り、公共施設や学校などで開催された。
男性の活躍の場は、講演会ばかりではなかった。18年からは三木市のコミュニティーFM局で、自ら「ドクター」を名乗り、司会を務める週1回のラジオ番組を持った。企業経営者らも名を連ねる奉仕団体のロータリークラブにも入会し、すっかり地元の名士になりきっていた。
■経歴は「大げさに書いた」
順風満帆に見えた男性の活動は、今年に入り暗転する。実は、約2年前から、番組や講演を聴いた医療関係者らの間で「話の内容が薄く、医学に通じた人とは思えない」などの声が出ていたのだ。
講演の主催者も経歴に疑いを持ち始め、24年から男性を講師に登録していた兵庫県の外郭団体・公益財団法人「兵庫県健康財団」や、19年から49件の講演を依頼していた三木市は、今年3月をもって男性への講演依頼を中止。FM局も番組を打ち切った。
4月中旬、産経新聞の取材に対し、男性は「大げさに書いてしまった」と、経歴がすべて嘘であったことをあっさりと認めた。
その上で、男性は「東京都内の私大医学部に入学したが、2年生の時に中退した。その後、米国カンザス州の大学院で基礎医学を学んだ。論文も執筆したし、申請さえすれば博士号も授与されたはずだが、医学博士の肩書は持っていない」などと釈明した。
さらに「在籍歴や勤務歴は知人のものを流用した」と説明し、「講演会で知人の医師の代役を務めたのがきっかけ。その後も講演の依頼があり、知人の経歴を使い続けた」と弁明した。
■詐称発覚に市民らは怒りと落胆
4月22日の産経新聞夕刊で男性の経歴詐称を報じると、市民をはじめ、卒業生を語られた学校や講演を依頼した行政の関係者から、怒りや落胆の声が上がった。
灘高校の担当者は「OBからの問い合わせもあり、男性の存在は把握していた」と打ち明ける。「そのような人物にかかわるのは、学校の品位を下げてしまうと考えて放っていたが、それにしても腹が立つ話だ」と吐き捨てた。
講演やラジオを聴いたことのあるという三木市の60代の主婦は「先生のファンは多かった。立派な方が近所で話してくれていると信じていたのに…」と肩を落とし、かつて講演を依頼した同市職員は「スーツでビシッと決めた身なりだったし、経歴詐称は夢にも思わなかった。市民に申し訳ない」と反省しきりだった。
取材に対し「もう講演活動はしない」と語った男性。同市から返還を求められた講演料109万円を返還し、刑事告訴も免れた。
「経歴詐称は報道があるまで知らなかった。ただ、本人はひどい人間ではなく、医学論文を発表したいという目標も持っているので、今後も応援したい」と話す妻とともに、男性は再出発を誓っている様子だ。しかし、まだ語られていない事実もあるようで…。
■“工学博士”としても活動?
「カンザス州の大学院と聞いてピンと来ました。詐欺のようなことを、まだやっていたんですね」
平成に入って間もないころの一時期、男性と仕事をしていたという大阪府茨木市のフリーライター(57)は、あきれ顔だ。
この人物によると、男性は当時、「大阪大学工学部教授」を名乗っていた。「東大医学部卒業」や「カンザス州立大客員教授」などの経歴を語り、「自分は医者だが、工学系にも詳しいのでコンピューターのことも分かる」と豪語していたという。
男性が、あるコンピューター関係の企業のセミナーで講師を務めていたことから、フリーライターが当時働いていた業界誌で、コラムを連載してもらった。
その後、同誌主催の講演を依頼したが、華々しすぎる経歴に社内で疑惑の声が上がった。調査したところ虚偽であることが判明し、縁を切ったという。
一連の問題に関する取材は約2カ月間にわたったが、結局、男性については大阪府出身であることと、誕生日くらいしか真実らしいことは確認できなかった。
「人生は単なる寿命の長さでなく、質が問われる時代。結果だよ。元気でシャンシャン、好きなことをした方がいいじゃん」
取材を進めていた3月、三木市で行われた講演会での男性の発言が、どこか、むなしく思いだされた。
ここまでメディアで取り上げられるのは漫画「美味(おい)しんぼ」が影響力を持っている証拠だろう。
放射能の影響やSTAP細胞の件は、特殊で専門家でも意見が分かれている。民主党が政権を取っていた時代、放射能やその他の不都合な情報は公表されなかった。被爆のチェックもかなり遅れた。除染の不適切な作業。除染による効果は、考えられたほど出ていないケースもある。あれは除染に関して大げさな効果を述べたのか、それとも場所によっては除染の効果が出ないケースを想定できなかったのか?除染を計画した時に専門家達はチームにいたのか?なぜ福島出身であることを隠さないといけないのか?広島や長崎で被爆した人達の中には被爆した事を隠したり、他県で暮らした人もいた。なぜなのか?何十年後に、理由がわからない病気になった人達はいなかったのか?そのような事を考えると、単純に不利益を被る人達がいるから、科学的に立証的出来なければ口を塞いでおけと言うのはおかしいのではないのか。
漫画「美味(おい)しんぼ」を読みたくない人は読まなければ良い。個人的には漫画「美味(おい)しんぼ」を読んだ事はない。それだけの話をなぜここまで注目するのか?広島や長崎の被爆者の話をローカルテレビで見るとなぜ全国規模で流れないのだろうかと思う事もある。県外の人には関係のない事だし、事実を知るといろいろな感情を持つ可能性がある。そのような機会を減らしたいと思っている人達がいるのではと思ってしまう。まあ、福島には行った事はないし、行きたいと思わない。行けば、何かを思うだろうし、何かを感じるかもしれない。マンガに関して個人的な意見を言えば、フィクションだし、非現実的なことがいろいろ書かれている。子供のころに読んだマンガの内容は事実と思った子供の時期もある。いちいち言い出したらマンガにならないだろう。ここまで騒ぐ必要はなかったと思う。
准教授「人住めない」に福島大「個人の見解」 05/12/14 (読売新聞)
漫画「美味(おい)しんぼ」で福島県内を取材した主人公が鼻血を出すなどの表現があったことを巡り、県が12日、「(原発事故の)風評を助長するもので断固容認できない」と反論の見解を示すなど、波紋が広がっている。
同日は自民党県連などが発行元に抗議文を送ったほか、漫画に登場する准教授が所属する福島大はコメントを出すなどの対応に追われた。県に寄せられた意見は137件に上った。
12日発売の「ビッグコミックスピリッツ」に掲載された同漫画では、前号に続いて井戸川克隆・前双葉町長が実名で登場し、「福島県内には住むなと言っているんです」「鼻血が出たりひどい疲労感で苦しむ人が大勢いるのは、被曝(ひばく)したからですよ」と発言。福島大の荒木田岳准教授は「福島を広域に除染して人が住めるようにするなんて、できないと思います」と述べている。
これに対し県は、「作中に登場する特定の個人の見解が、あたかも福島の現状であるような印象を読者に与えかねない表現があり、危惧している」として、内容に反論する見解をホームページに掲載した。
佐藤知事は、公務で訪れたさいたま市で報道陣の取材に応じ、「風評を助長する印象で極めて残念」と厳しい表情をみせた。
同漫画を巡っては、12日午後5時までに、県内外から電話やメールで137件の意見が県に寄せられた。多くは「漫画の内容が偏っている」といった批判だが、12日は県の反論を疑問視する意見もあった。
県内政界も反発。自民党県連や、民主、社民、無所属の議員で構成する県議会会派「民主・県民連合」は、「いわれなき風評被害を発信した」などとして、小学館の相賀昌宏社長あてに抗議文を送った。
同日、福島第一原発などを視察した下村文科相は報道陣に、「たとえ漫画でも、よく勉強して描く必要がある」と述べた。
一方、福島大の荒木田准教授は「19日発売の特集記事を待ってから見解を示したい」と、同大を通じて説明。同大は中井勝己学長名で「荒木田氏個人の見解で、福島大の見解ではない」としたうえで、「多方面に迷惑、心配をかけて遺憾。大学人の立場を理解して発言するよう、教職員に注意喚起していく」とした。
小学館は「鼻血などと放射線の因果関係について、断定するものではありません」とする文章をホームページに掲載。「低線量放射線の影響の検証や現地の声を伝える機会が減っている。議論を今一度深める一助となることを願って作者が採用し、編集部もこれを重視して掲載した」とした。
ここまで癒着があると公平な裁きはない。証拠隠滅のほうが、証拠を押さえられて有罪を受けるよりも罪が軽いと判断したのかもしれない。
日本の九州で起きた事件では飲酒運転で逮捕されるよりも、普通の事故で逮捕される事を選び、結局、飲酒運転は立証出来なかった。
法の盲点を付けば罪は軽くなる。どこの国でも同じだ。
【社説】癒着が招いた事故を捜査する人たちも癒着 05/12/14 (朝鮮日報日本語版)
海運汚職について捜査中の釜山地方検察庁特別捜査チームは、船舶の安全検査を行う韓国船級協会に関する捜査情報を海洋警察の担当者に流したとして、同捜査チーム所属の捜査官C氏を在宅で立件し、またC氏から受け取った情報を韓国船級協会の法務チーム長に伝えた海洋警察のL警視の身柄を拘束した。検察は2人の逮捕状を申請したが、裁判所はL氏についてのみ逮捕状を出した。一方、韓国船級協会は家宅捜索が行われる前に、重要資料をパソコンなどから削除したことも分かった。釜山地検は海洋警察に対し、韓国船級協会の前職・現職幹部によるヨットの使用状況に関する資料を提出するよう文書で要請したが、L氏はこの文書を携帯電話で撮影し、韓国船級協会に送っていたという。
韓国船級協会は政府の委託を受けて船舶の検査を行う団体だ。旅客船「セウォル号」が沈没した際、船に設置されていた46隻の救命ボートのうち1隻しか使えなかったことが問題になっているが、今年2月にこの救命ボート全てについて「良好」との判定を下していたのも同協会だった。同協会の会長にはこれまで11人が就任しているが、その中の8人は海洋水産部(省に相当)の元幹部による天下りだった。海洋水産部は退職した官僚を韓国船級協会に再就職させ、同協会は海洋水産部から監督を受ける際、彼らを前面に立てるなどして利用していた。このような実態が知られるようになると「業界とこれを監督する政府部処(省庁)による癒着が、海運業界の安全管理をずさんなものにした」「これが最終的にセウォル号沈没という悲惨な事故を招いた」などと激しい批判が巻き起こった。
しかもこの黒い癒着を解明する捜査の過程で、今度は捜査機関の担当者も被疑者と癒着していたのだ。C氏は海洋警察に勤務する親戚を通じて1年前にL氏と知り合い、それ以来ずっと親しく付き合ってきた。またL氏は海洋警察で情報を取り扱う業務を担当しながら、韓国船級協会の法務チーム長とも顔見知りになったという。その結果、C氏とL氏は個人的な関係を自らの職務よりも優先させて捜査の守秘義務を守らず、C氏はL氏を通じて検察による捜査状況を韓国船級協会にリアルタイムで知らせていたのだ。政府や検察・警察にこのような人間がいる限り、近くまた大惨事が発生するとの心配も現実味を帯びてくる。
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
【捜査情報、検察職員が海上警察に漏洩】 05/09/14 (韓国日報)
韓国船級の押収捜索に参加
機密、何度もやり取りした特別捜査チーム捜査官に令状
セウォル号沈没事件の根本原因と指摘された『黒い癒着』のゴールは、予想以上に深かった。船舶検査機関、韓国船級への検察の家宅捜索計画を密かに漏洩した海洋警察が、検察捜査官から関連情報を入手した事が判明した。韓国船級などの組織的な妨害で、捜査が困難に陥った検察は、捜査官介入の事実が発覚し、波紋を懸念し、戦々恐々としている。
海運業界の不正を捜査中の釜山(プサン)地検特別捜査チーム(チーム長パク・フンジュン特捜部長)は9日、検察の捜査情報を漏洩した疑い(公務上の秘密漏洩)で、特別捜査チーム所属チェ某捜査官(36ㆍ8級)・釜山海警イ某(41)容疑者への拘束令状を請求した事を発表した。
検察によると、イ容疑者は先月24日、釜山地検が韓国船級釜山本社・役職員事務室など9ヵ所を家宅捜査するとの情報をチェ捜査官が、韓国船級の法務チーム長原毛(42)氏に文字メッセージで知らせた容疑を受けている。調査の結果、2人は、海洋警察職員のチェ捜査官の母方の叔父の紹介で会い、1年以上親交を続けて来た事が明らかになった。これらは、家宅捜索の他、検察の捜査機密を数回、電話や文字メッセージでやり取りしたと伝えられた。
これに先立ち検察は、先月29日、韓国船級押収捜索で確保したウォン氏の携帯電話からイ容疑者が1回目の家宅捜索前日の先月23日、関連情報を知らせた文字メッセージを発見。イ容疑者は、ウォン氏の携帯電話が押収された事実を知らず、この2日にも『検察が、海警側に韓国船級のヨット利用資料を要求して来た』と、検察公文を写真に撮り、カカオトークに送っていた。
検察は今月7日、イ容疑者を召喚調査する過程で、チェ捜査官が介入した事実を確認した。釜山地検関係者は「当該捜査官は、先月24日、1回目の家宅捜索に参加したが、これらが交わした情報に重要な捜査状況がある事から、これらの拘束捜査が必要」「情報提供の過程で、金品・接待が行われたのかについても徹底的に調査する」と明かした。
韓国船級の組織的な妨害で、捜査がもたつく中、職員の犯罪容疑が明らかになり検察は困惑を隠せずにいる。最高検察庁が、海運業界の不正捜査を指示したのは先月22日。釜山地検は、これまで韓国船級本社や役職員の自宅など17ヵ所を家宅捜索したが、不正容疑を明確にする決定的な証拠物を確保する事は出来なかった事が分かった。
一方、検察は同日、釜山旅客船運営会社、A社を家宅捜索し、船舶購入に関連する書類・会計帳簿を分析している。検察は、A社が旅客船運航の承認を得る過程に問題が無かったか、運航時貨物・過積載は無かったかなどを調べている。検察は、韓国船級と釜山の某船舶設計業者を捜査する過程で、A社の関連容疑を掴んだ事が分かった。
http://news.hankooki.com/lpage/society/201405/h2014050920565121950.htm
<韓国旅客船沈没>海洋警察、韓国船級に家宅捜索を事前に知らせる 05/08/14 (中央日報日本語版)
海洋警察が韓国船級に検察の家宅捜索情報を事前に知らせたことが明らかになった。
釜山地検と海洋警察によると、先月24日、釜山海経のイ警査は知り合いの韓国船級法務チーム長に携帯電話メッセージを送った。「1時間後に家宅捜索に行く」という内容だった。
釜山地検の関係者は「家宅捜索に行ってみると一部の資料がないなど、事前に備えた印象を受けた」とし「このため捜査に支障が生じている」と述べた。また「家宅捜索1時間前でなく1日前に情報が漏れたという話もある」と付け加えた。
海洋警察は情報を流したイ警査を監察する方針だ。さらに捜査に参加しなかったイ警査が家宅捜索の情報を知ったことに関し、別の情報流出者がいるとみて追跡することにした。
企業の体質は隠せないものだ!底なしに無茶苦茶を行っていたと言う事なのか??
ノバルティス、副作用疑い報告せず 白血病薬の約30例 05/09/14(朝日新聞)
製薬大手ノバルティスはタシグナなどの白血病治療薬による重い副作用の疑いがある約30例を把握しながら、国に報告していなかったことが9日、わかった。厚生労働省は薬事法違反の疑いもあるとみて調べている。
同社は、医師や薬剤師を対象に1月中旬までにアンケートを実施。その調査で、薬事法で15~30日以内に国への報告義務がある重い副作用の疑いが約30例あったにもかかわらず、厚労省に報告したのは4月8日だった。同社は「営業職が行ったアンケートが、国へ報告する社内の担当部署に伝わっていなかった」としている。
タシグナを巡っては、東京大病院を中心とした臨床研究で、同社社員が患者データを入手するなど不適切な関与があった。この臨床研究でも、重い副作用の疑いが2例報告されたが、その後の調査で報告対象外だったと判断された。
医療研究、データ長期保存や監査義務化 不正防止指針案 05/01/14(朝日新聞)
人を対象にした医学研究の倫理指針の見直し作業を進めている厚生労働省と文部科学省の有識者会議は1日、データの長期保存や第三者による監査などを義務づける新指針案をとりまとめた。製薬大手ノバルティスの高血圧治療薬ディオバンの不正論文問題などを受け、研究の透明性や信頼性の確保を強化する。
ディオバン問題では、複数の大学の臨床研究で、ほかの薬より病気の予防効果を高くするためデータの不正操作があった。ノバルティスの社員(当時)が統計解析に加わり、大学が同社から多額の奨学寄付金を受けていた。
新指針案では、利害関係にある企業とのかかわり(利益相反)について、薬と医療機器の有効性や安全性などの研究では、研究責任者が各研究者の状況を把握して研究計画書に記載する。さらに、研究者が被験者らに説明するよう新たに義務づけた。
「小保方氏は『このまま日本にいてもいいのだろうか』と漏らすこともあるという。」
日本に居たければ居れば良い。もう日本になんて居たくないと思うのであれば、海外からオファーがあるのであれば海外に移住すれば良い。
「STAP細胞」が存在するのであれば、時間を掛けて証明すれば良い。ノーベル賞が取れれば、その時に日本は最低な国だと言う事が復讐になるかもしれない。
将来の事は誰もわからない。今回の辛い経験が将来への成功に繋がるかもしれない。成功さえすれば何でも言える。
現時点では訴訟を起こしても勝てないような気がする。研究者として働く選択があるのであれば、そちらの選択の方が賢明と思える。しかし、誰が何と言おうが、
自分がしたいと思う事をするのも自己責任で出来る。それしか言えない。
小保方さんにトドメ刺した「若山資料」と「ポエムノート」 残された道は… 05/09/14(夕刊フジ)
新型万能細胞「STAP細胞」の論文問題で、理化学研究所に不服申し立てを退けられ、研究不正行為が認定された小保方晴子ユニットリーダー(30)。小保方氏にトドメを刺したのは、共著者の一人である若山照彦山梨大教授からの提供資料と、「ポエム」ノートだった。理研による処分審議も始まり、もはや日本で研究活動を続けていくことは困難の状況になっている。
調査委の“隠し玉”は、共著者の一人である若山氏からの資料提供だった。
調査委は、若山氏から、米科学誌サイエンスにSTAP論文と同様のものを投稿した際の審査担当者のレビューを入手。この論文は英科学誌ネイチャーに掲載される前の2012年7月に投稿され、小保方氏、若山氏、ハーバード大のバカンティ教授らが責任著者となっていた。
レビューでは、DNAを分離する「電気泳動」という実験の画像について「異なる実験の結果をまとめて表示するときは白線を入れて区別する必要がある」と指摘。
調査委は、このレビューをもとに、ネイチャーに投稿する13年3月までに、小保方氏は切り貼りが不適切と認識していたはずだと主張した。
STAP細胞の存在を証明するはずの実験ノートも“命取り”となった。
捏造とされた画像について、小保方氏は本来掲載すべき画像があり、不正ではないと主張してきた。だが、該当する実験ノートのページに日付はなく、前後の約8カ月で日付の記載はわずか2回だけ。調査委の真貝洋一委員は、「他の人にはほとんど検証不可能というレベル」と斬り捨てた。
調査委の報告に先立ち、代理人弁護士は7日、小保方氏の実験ノートの一部を公開したが、これも逆効果になったようだ。酸性の刺激で多能性を示す細胞が現れることを確認した際には「陽性かくにん! よかった」などの記述や、思い通りの結果にはハートマークも。
『医者ムラの真実』(ディスカヴァー携書)の著者で近畿大講師の医師、榎木英介氏は「ノートについては絶句した。詳しい数値データや日付もなく、記録になっていない。私的な日記みたいなもので、ポエムだ。弁護士はよくこれを公表したなと思った」と話す。
代理人によれば、小保方氏は「このまま日本にいてもいいのだろうか」と漏らすこともあるという。国内外の研究機関からラブコールを受けているといい、“海外逃亡”する展開もありそうだ。
司法的解釈については知らないが、かなり厳しい言い訳と思える。
STAP論文:小保方さんが追加資料 理研に不服申し立て 05/07/14(毎日新聞)
理化学研究所のSTAP細胞論文問題で、小保方(おぼかた)晴子・研究ユニットリーダー(30)の代理人弁護士は7日、理研に不服申し立ての追加資料を提出したと明らかにした。提出は4日付。小保方氏が画像の取り違えなどのミスをした背景に「論文作成を急がなければならないプレッシャーがあった」などとして再調査を求めている。
不服申し立ての追加資料提出は先月20日に続いて2回目。研究不正を否定する新たな証拠などは含まれていないという。
代理人の三木秀夫弁護士によると、提出した「補充書」はA4判32枚。主な主張は▽複数枚の写真を1枚に組み合わせても「捏造(ねつぞう)や改ざんには当たらない」とした金属材料科学分野での判例がある▽論文執筆時は研究所の移籍手続きで多忙で、「他の研究室に先を越される」などのプレッシャーもあった▽理研によるSTAP細胞の検証実験の結果を待って研究不正かどうかの判断をすべきだ−−の3点。
判例は、昨年8月の仙台地裁判決。論文に不正があると告発された東北大元学長が告発者に損害賠償を求めた訴訟で、捏造や改ざんが否定された。補充書ではこの判例を踏まえて「存在しないデータを故意に作成するなどでなければ、捏造や改ざんに該当しないというのが司法的解釈」と主張した。【畠山哲郎】
旅客船「セウォル号」の事故では多くの犠牲者が出た。多くの問題が重なった結果だと思う。多くの被害者が出た直接的な原因は救命いかだの問題、船員が避難誘導を適切に行わなかった、最後に高校生が従順な優等生だったからだと思う。適切な避難誘導が行われていれば結果は違っていた。犠牲になった以上、あまり書くべきではないのかもしれないが、高校生が常識的に考えて船員によるアナウンスの内容はおかしいと疑問を抱いて脱出をする思考能力と判断力があれば結果は違っていただろう。日本の生徒でもエリート高校であれば同じ対応をしたのではないかと思う。あまりにも良い子で、大事に育てられすぎて、生き残るために何をするべきなのか考える事が出来なかった。こんな事故が無ければ一生懸命勉強して大学に進学し、その後に就職していただろう。
大学合格を目指した教育の落とし穴だと思う。想像もできない状況で生き残るための選択は試験には出ない。想定外の状況は普通、起こらない。想定外の状況で適切な判断を下す事が出来る能力は、これまでの経験や学校の勉強ではない余力の体験があるか、又は、基本的な判断をすることを教えてくれる人達に出会うか次第だと思う。旅客船「セウォル号」と同じ状況で今の自分なら船員の指示など従わないが、高校生の自分であれば、同じように死んでいたかもしれない。運と言えばそれまでだが、いろいろと考えさせられる事がある。
(朝鮮日報日本語版) 【社説】「いつも通り」の虚偽記載 05/06/14 (朝鮮日報日本語版)
先月16日に全羅南道珍島沖合で沈没事故を起こした旅客船「セウォル号」では事故の前日、仁川港を出港する前に乗務員らはいつもと同じように淡々と業務をこなしていたことがわかった。いつもと同じ、とは、要するに乗務員らは出港前に船の安全点検を一切行わず、すべてにおいて「問題なし」と記載された虚偽の報告書を作成し提出していたのだ。検察と警察の合同捜査本部は「セウォル号は船の状態、積載した貨物の量やその船積みされた状態、救命設備など、点検すべき項目はすべて良好という内容の報告書を作成し、仁川港運航管理室に提出していた」と発表した。この報告書は本来なら船長が作成することになっているが、セウォル号は三等航海士のB氏(26)=女性、拘束=が船長に代わって作成し、船長の名前で提出していた。B氏は捜査本部での取り調べで「まともな点検は行わずに記載した」「仕事を学ぶときにも、ただ良好と書けばよいと指導を受けた。いつもと同じようにやっただけだ」と証言した。一等航海士のK氏(42)=拘束=も「安全点検を行う前にまず書類を提出した。これは一種の慣行だった」と証言した。
事故の前日に提出されたセウォル号の安全点検報告書には、貨物657トン、コンテナ0個、自動車150台と記載されていた。ところが実際はコンテナが105個積まれており、これだけで1157トンにも達していた。自動車も180台が積まれていた。しかもコンテナはしっかりと固定されていなかったが、報告書には「船積み状態は良好」と記載されていた。貨物を決められた限度を超えて積載し、船が傾いた時に一方に片寄らないようしっかりと固定しなかったことも、セウォル号が沈没した一つの原因とみられている。救命設備も「良好」と記載されていたが、実際に船に積まれていた46隻の救命ボートのうち、沈没の時に使えたのはわずか1隻のみだった。
「いつも通りやった」と証言したB氏は、航海士としてセウォル号に乗船してからまだ5カ月ほどだという。B氏に対して安全点検をやらずにただ「良好」と記載するよう指導したのは、B氏の前任者か先輩だったはずだ。この前任者あるいは先輩も、その前任者か先輩からそのように指導を受けていたのだろう。このような慣行が定着してしまった影響で、わずか5カ月前に入社したばかりのB氏のような新人も、虚偽の報告書を作成しながら罪悪感など一切感じなかったのだ。このように積み重なった虚偽と惰性は、最終的に船を転覆させ沈めてしまった。
これはセウォル号の乗務員だけの話ではない。問題の報告書を受け取った運航管理者に現場を確認すべき義務は定められていないが、もしこれまでに1回でも現場を確認していれば、その報告書が完全に虚偽だという事実などすぐにわかったはずだ。また報告書を書いたのが船長ではなかったこともその場で摘発していたことだろう。これが行われていればおそらくセウォル号は出港できず、最低限の貨物以外は船から下ろし、これをしっかりと固定するよう指示されていたに違いない。ところが運航管理者はその虚偽の報告書をそのまま受理した。これもおそらく慣行だったのだろう。セウォル号は上から下まで、また前から後ろまですべてが虚偽ばかりで、その虚偽もすべてが慣行という名の下で誰も疑問に感じないまま行われていたのだ。
韓国国内で航行する他の船はどうだろうか。セウォル号だけが特別で、他の船ではすべて安全点検がしっかりと行われているのだろうか。船舶だけではない。韓国国内で多くの人が集まる大型の施設で作成される安全点検関連の報告書は、もしかするとセウォル号と同じく全くの虚偽ではないだろうか。今回の悲惨な事故をきっかけに他の船舶はもちろん、地下鉄、空港、ガス、原子力発電所など、国民の安全と直結したあらゆる施設において改めて安全点検を行うべきだろうが、その前に、これまで提出された安全点検の報告書や内部の慣行をまずはチェックする必要があるのではないか。
「データ引っこ抜きは通常業務」バイドゥ元職員 05/04/14(読売新聞)
「日本語入力の辞書機能向上のため、他社のサーバーからデータを引っこ抜いてくるのは通常の業務だった」。
バイドゥ日本法人で昨年まで働いていた男性はこう打ち明ける。
例えば、上場企業名を入力すれば即座に変換できるようにするため、情報サイトのサーバーに入り、企業名の「読み方」のデータを取得していた。男性は「本などの資料からデータを打ち込むべきだと進言しても、上司に『そんな時間のかかることをやっている暇はない。サーバーからデータを取ってこい』と指示された」と振り返る。
バイドゥの大量アクセスは2007年にも問題になった。同社が、検索エンジンの精度を上げるためのクロールで大量アクセスを行った結果、国内の複数のサイト運営者らが「サイトがつながりにくくなった」などと訴えた。バイドゥは「迷惑をかけた」と謝罪し、アクセスの頻度を下げるなどして対応した。
韓国議会の沈没事故阻止法案が利権団体の圧力で頓挫。与党議員も率先して法案廃棄に協力した 05/01/14(韓国日報)
[単独]『惨事』防ぐ法案3年前失敗に終わった
「海運組合の代わりに安全管理引き受ける専門機関設立」
法案発議されたが政府・与党・ハッピーが反対
船会社の利益団体である海運組合の代わりに海洋安全専門機関を設立して船舶運航安全管理を任せる方案が3年前に推進されたが政府と与党が反対して立法が失敗に終わった事実が確認された。当時専門機関が新設されたとすれば体系的な安全管理でセウォル号沈没惨事を防げたことという指摘が出ている。業界では当時海運業体と『ハッピー(海水部+マフィア)』のロビーのために法案が廃棄された可能性が高いと見ている。
30日、韓国日報の取材の結果、2011年8月チェ・キュソン議員(当時民主党)等は独立機関である海洋安全交通公団を新設して運航管理業務を任せる内容の海事安全法一部改正案を発議した。だが、2011年11月、国土海洋委員会法案審査小委で廃棄されて常任委さえ上程されることができないと発表された。
当時法改正案はセウォル号沈没惨事であらわれた問題をそのまま反映している。貨物過剰積載とバラスト水不足が沈没原因として指定されているが監督を委任された海運組合運航管理者はこれを全く把握できなかったし、海上警察は海運組合を制裁する手段がなかった。すなわち利益団体が運航を管理する矛盾を解決して専門性を高めるために、独立機関である海洋交通安全公団が運航管理者を選任して管理監督を海上警察で一元化しようということが法改正の趣旨であった。
だが、当時国土海洋部が海運組合を積極的に擁護して専門担当機関設置は失敗に終わった。キム・ヒグク当時の国土部2次官は2011年11月、国会国土海洋委に出席して「海運組合で(安全管理業務を)よくしているのにあえて法制サイドに渡す実益がない」と明らかにした。
国土海洋部は法案審査を控えて■船舶安全管理は国土部の固有業務で■海運組合の運航管理体制は検証された制度であり■追加費用が発生して船会社の反発が憂慮されるとして法律改正反対の立場に立った。海上警察と業務管轄の戦いが推察できるだけでなく船会社と癒着の可能性を示唆する大きな課題だ。歴代海運組合理事長12人中10人が海水部(国土部)出身である点を勘案すればハッピーが法案通過を邪魔した可能性が高いというのが政界の観測だ。
法案廃棄には与党議員も積極的に加勢した。当時セヌリ党ヒョン・ギファン議員は法案を「殺さなければならない」として廃棄を主張し、他の議員も概して同調した。
3年前に海運組合を擁護した海水部はセウォル号惨事以後に手遅れになって騒ぐ対策を出して「海運組合を船舶安全管理業務から排除する」と明らかにした。パク・クネ大統領が29日注文した国家安全処設立もやはり安全管理専門担当機関の必要性を示唆している。
政界のある関係者は「国民の生命と直結する安全管理業務が利益団体の影響に左右されて駆け引きの対象に転落したという点で自己恥辱感を感じる」と話した。
韓国日報(韓国語)
http://news.hankooki.com/lpage/society/201405/h2014050103333021950.htm
韓国の保険会社が違法改造船の保険料支払いを拒否。裁判所も支払い義務はないと決定を下した 05/01/14(韓国日報)
裁判所「構造変更で船舶沈没…保険金支給義務ない」
船舶が無理な構造変更の影響で沈没した場合、保険会社が船舶運航社に保険金を支給しなくても良いという裁判所判決が下されてきた。
ソウル中央地方法院民事合議31部(オ・ヨンジュン部長判事)は東部火災が石井建設を相手に出した訴訟で「東部火災に保険金支給義務がないということを確認する」として原告勝訴で判決したと1日明らかにした。
石井建設が保有した船舶『石井36号』という1984年に日本で建造されて2007年に輸入された老後作業船だった。この船は2012年12月、蔚山(ウルサン)新港3工区工事現場で作業途中に片側に傾いて沈没した。
事故原因は無理な構造変更と明らかになった。会社側は工事期間を短縮するために専門家の安全診断なしに任意に作業設備を建て増しした。その結果重さが500t以上伸びた。
船舶安全技術公団釜山(プサン)支部はこれと関連して「増設された設備の重さと位置を勘案すれば顕著に錘の重心が上昇して船舶の復原力が減少したと推定される」という所見書を作成した。
東部火災は船舶保有会社が保険金を請求するとすぐに訴訟を起こした。裁判所は約款上保険金支給義務がないという保険会社の主張を受け入れた。
裁判所は「保険約款に規定された『海上固有の危険(Perils of the seas)』がこの事件沈没事故の支配的で直接的な原因だと断定し難い」として「かえって大々的な構造変更が影響を及ぼした」と指摘した。
裁判所は引き続き「被保険者側が船舶の構造上の欠点や事故発生の可能性に関し非常に注意を欠如したと見られる」として「約款上保険金支給義務を認めることはできない」と判示した。
韓国日報(韓国語)
http://news.hankooki.com/lpage/society/201405/h2014050106102922000.htm
STAP論文調べた側にも疑義 理研委員論文を予備調査 05/01/14(朝日新聞)
STAP(スタップ)細胞の論文問題で、理化学研究所の小保方(おぼかた)晴子ユニットリーダーの不正を認定した調査委員会の複数の委員の論文に、新たに画像加工などを疑う指摘があったことが1日、わかった。委員が所属する理研と東京医科歯科大は、本格調査に入るかどうかを判断する予備調査を始めた。
理研の調査委は委員6人で発足し、石井俊輔上席研究員は別の論文で画像加工の疑いを指摘され調査委員長を辞任している。
理研などによると、今回、新たに疑義が指摘された委員は理研の古関明彦グループディレクター、真貝洋一主任研究員と、田賀哲也・東京医科歯科大教授。
2003年から11年に発表した論文で、遺伝子を解析した画像に切り張りの加工などがあったのではないかとの指摘が所属機関に寄せられたという。
3人は朝日新聞の取材に対し、不正な行為があったとは答えていない。
小保方さん余波 山中教授はコピペ否定 04/29/14(nikkansports.com)
人工多能性幹細胞(iPS細胞)の生みの親でノーベル医学生理学賞を受賞した京大の山中伸弥教授(51)は28日、京大で会見し、海外の学術誌に00年に発表した自身の論文の画像や図表にインターネット上で疑義が指摘されているとした上で「画像の切り貼りはなく、論文の報告内容は正しい」と説明した。STAP細胞論文問題が山中教授にも飛び火したが、同教授は調査に対し段ボール5箱分の実験ノートを提出して否定。一方で生データが発見できなかったことを謝罪した。
黒っぽいスーツに青いネクタイ姿。いつもの穏やかな表情ではなかった。山中教授は、鋭い目つきで論文への疑義について「研究結果は複数の研究者により再現されており、研究者倫理の観点から適切でないことをした記憶もない」と潔白を主張した。
論文は、さまざまな組織や細胞に変化するマウスの胚性幹細胞(ES細胞)研究に関するもの。山中教授が奈良先端科学技術大学院大の助教授だった00年に欧州分子生物学機構の専門誌に発表した。共著者は山中教授を含め8人いた。13年4月にネット上で疑義を指摘されたことを受け山中教授が京大iPS細胞研究所に申し出た。同月から森沢真輔副所長ら3人が同月から調査を始めた。
指摘されたのは2点の図表で、図内の画像が類似している点、データの標準偏差値が不自然である点が挙げられた。山中教授は「画像を切り貼りするような技術はなかった。そうする必要も理由もない」とコピペ疑惑を否定した。疑義は小保方氏のSTAP細胞問題よりも先に指摘されていたが、ノーベル賞受賞者が自らの「潔白」について会見せざるを得ない状況まで追い込まれた。
一方で、実験データ管理については反省した。実験は1998年ごろに山中教授と複数の協力者が実施。しかし、山中教授以外のノートは保管されていなかった。山中教授は調査のため段ボール5箱分の実験ノートを提出したが、図表に関する生データを発見できなかった。「全てのノートを私が保管しておくべきだった。研究者として心より反省し、おわびする。昔の自分に(対して)恥ずかしく思っています」と悔しさをにじませた。
理化学研究所の小保方晴子氏(30)が1月にSTAP細胞論文を発表して以来、関連する研究者が次々とインターネット上で疑惑を告発されている。STAP細胞問題では「研究不正」と認定した理研の調査委員会トップを務めた石井俊輔氏も、08年の論文で画像を編集する不正が指摘され、25日に委員長を辞任した。
山中氏は「今、日本の(科学への)信頼が揺らいでいるのは確かです。1歩1歩、信頼を回復していくしかない」と口元を引き締めた。【鈴木絢子】
◆山中伸弥(やまなか・しんや)1962年(昭37)9月4日、大阪府東大阪市生まれ。神戸大医学部-大阪市立大大学院。奈良先端科学技術大学院大教授などを経て、10年から京大iPS細胞研究所所長。12年10月、ノーベル医学生理学賞受賞が決定。
<STAP細胞問題の経緯>
▼1月28日 小保方氏らが理化学研究所で、STAP細胞発見について会見
▼同30日 英科学誌ネイチャーに2本の論文掲載
▼2月 論文の表現や画像についての不自然さが、ネットで次々指摘される
▼同10日 論文共著者の1人、山梨大の若山教授が会見し「STAP細胞が存在するか確信がなくなった」と発言
▼同11日 理研が問題発覚後、初めて会見。「論文の撤回も視野に入れて検討している」と表明
▼4月1日 理研の調査委員会(石井委員長)が論文不正と認定。論文取り下げを勧告
▼同8日 小保方氏が理研に不服申し立て、再調査を求める
▼同9日 小保方氏が騒動後、初めて会見。謝罪したが「悪意のない間違い」と反論、論文撤回を否定
▼同16日 小保方氏の上司で論文共著者の笹井副センター長が会見。謝罪した上で、「STAP現象は合理性の高い仮説」とした
▼同25日 理研調査委の石井委員長が、自身の論文に不正疑義が出たことを理由に委員長を辞任
りそな行員、1億5500万消失…自殺後に発覚 05/01/14(読売新聞)
りそな銀行の20歳代の男性行員が、担当していた顧客から私的に計約1億5500万円を集めて外国為替証拠金取引(FX取引)などで運用し、大半を消失させていたことがわかった。
同行は、行員が業務外で資金を集めることや、FX取引を行うことは認めていない。国に登録せずに資金を集めて運用することは、金融商品取引法で禁じられており、同行は金融庁に報告した。
同行によると、行員は池袋支店の営業担当で、2013年7~12月、顧客の企業経営者ら3人に対し、「銀行の業務とは別に、出資してくれれば資産を増やす」などと勧誘し、個人や法人名義で出資させたという。行員は今年1月に自殺しており、その後、顧客から「行員と私的な金銭の取引をしていたが、連絡が取れない」と問い合わせを受けて発覚した。行員は自分の証券口座でFX取引や株式のオプション取引で運用したが失敗し、顧客の1人には2000万円を支払った以外は、配当や返金などは行わず、ほぼ消失させたという。行員は顧客のほか、親族や知人からも資金を集めて運用していたが、行員の証券や銀行口座などには、ほとんど資金は残されていなかった。
同行では2008年にも、難波支店(大阪市)の60歳代のパート行員が業務外で、顧客から投資名目で計1億2000万円を預かり、一部しか返還しなかったとして懲戒解雇されている。
りそな銀行の話「行員がこのようなことを起こして誠に遺憾。出資者などには真摯(しんし)に対応していく」
格安航空会社(LCC)はコスト削減が売りだから問題があっても不思議ではない。
機長らの会話記録、消失か…ピーチ機異常降下 05/01/14(読売新聞)
格安航空会社(LCC)のピーチ・アビエーション機が那覇空港の手前で異常降下したトラブルで、同機がトラブル後も運航を継続したため、操縦室内の会話を録音するボイスレコーダーの記録が残っていない可能性があることが国土交通省などへの取材でわかった。
異常降下を巡り、機長と副操縦士のやりとりを解明する客観的証拠が失われていれば、運輸安全委員会の調査に支障が出る恐れもある。
国交省などによると、同機は4月28日午前11時50分頃、新石垣発那覇行き252便として運航中に、那覇空港の手前約7キロの地点で高度が約100メートルに低下。海面などへの異常接近を伝える対地接近警報装置(※GPWS)の警報が鳴った。
このため、機長は着陸をやり直し、同機は約20分後に那覇空港に着陸。同機はその後、関西国際空港に向かうため午後1時前に離陸の準備に入り、午後3時過ぎに同空港に到着した。
ボイスレコーダーは操縦室内の会話を約2時間記録できるが、以前のデータは上書きされ、残らない仕組み。管制官と機長らのやりとりは管制機関側に保存されているが、管制官の指示などを巡って機長と副操縦士が交わした会話は残っていない恐れがあるという。
乗客が知らないだけでこのような事は日常的に起こっているのかもしれない。事故のために行われる調査により理由がわかるのだろう。JR北海道も同じレベル。
【社説】故障知りながら飛行続けたアシアナ航空 04/26/14 (朝鮮日報日本語版)
19日に仁川空港からサイパンに向かっていたアシアナ航空の旅客機でエンジンが故障したが、機長はそれを知りながら目的地まで無理にフライトを続けた。国土交通部(省に相当)は25日にこの事実を摘発したことを発表。問題の航空機は離陸から1時間ほど過ぎたころ、左側エンジンのオイルフィルターに異常が発生したことを知らせる警告メッセージが点灯したが、機長はその後もおよそ4時間にわたり飛行を続け、目的地に到着したという。通常はこの種の警告が点灯した場合、操縦士はまずエンジンの出力を下げて航空機の速度を落とし、それでも警告が消えない場合は周辺の空港に着陸しなければならない。ところが同機はエンジンの出力を下げるなどの対応を取らなかったため警告は点灯し続け、また操縦士はもちろん、アシアナ航空統制室もこのことを把握していたにもかかわらず、サイパンまでの飛行を強行した。
この問題が発生した19日は、韓国で旅客船「セウォル号」沈没事故が発生してから4日目に当たる。国民の誰もが事故を起こした旅客船の船長や船員、さらには船を所有する清海鎮海運の安全意識の低さに怒りをあらわにしていたまさにそのとき、アシアナ航空は極めて危険なフライトを強行していたわけだ。しかも、アシアナ航空はこの問題を隠蔽(いんぺい)するため「規定に従って対応した。すると警告が消えたのでフライトを続けた」と国土交通部に虚偽の報告まで行っていた。
この問題を受け、国土交通部は操縦士に対して資格停止30日、アシアナ航空には運航停止7日あるいは1000万ウォン(約98万円)の罰金を科す予定だという。一歩間違えば240人以上の生命を危険にさらしかねない行動を取った代償としてはあまりにも軽い。今回のように乗客の命を担保とする運航を行った場合、本来なら会社そのものを閉鎖させるほど厳しい処分を下すべきだろう。そうでもしなければ、会社側も問題の重大さを理解できないのではないか。
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
泥沼状態!日本の研究はこのレベルなのか?
「脇甘い、大問題だ」どうなるSTAP論文調査 04/25/14 (読売新聞)
STAP(スタップ)細胞の論文に「改ざんと捏造(ねつぞう)がある」と認定した理化学研究所調査委員会の石井俊輔委員長(62)が、自身の研究論文に問題があったとして25日、突然、辞任した。
調査は今後、どうなるのか。関係者に戸惑いが広がった。
石井氏は理研を通じ、「研究不正ではないが、このような状況で委員長の任務を継続することは、迷惑をおかけすることになる」と辞任理由を文書で発表した。
調査委とは別に、有識者が再発防止策を検討する「改革委員会」の岸輝雄委員長(東京大名誉教授)は、この日、東京都内で開いた会合の後、「脇が甘い。(研究不正と)認定されれば大問題だ」と厳しい口調で話した。
山本科学技術相は閣議後の記者会見で「理研がガバナンス(組織統治)を発揮していることを証明していただきたい」と苦言を呈した。
ドイツ証券接待汚職、元社員「会社ぐるみ」 04/22/14 (読売新聞)
ドイツ証券(東京)による接待汚職事件で、贈賄罪に問われた元社員越後茂被告(37)の初公判が22日、東京地裁(安東章裁判長)であった。
被告は「間違いありません」と起訴事実を認める一方、「上司の指示と了解の下で行った会社ぐるみの犯行だった」と主張した。
検察側の冒頭陳述によると、越後被告が所属した同社営業部では、2012年4月、年金を消失させたAIJ投資顧問による「みなし公務員」の厚生年金基金幹部への接待が社会問題化したため、接待をいったん自粛。しかし、翌5月頃には、「接待はなくせない」との判断から再開したという。
そして、越後被告は自粛期間も含む同年4~9月、10億円分の債券を購入してもらった見返りに、三井物産連合厚生年金基金の元常務理事(61)(収賄罪の有罪確定)を高級クラブやゴルフ場などで繰り返し接待。約87万円相当の賄賂を提供したという。
ドイツ証券汚職、民間取引先を接待と偽装 04/21/14 (読売新聞)
ドイツ証券(東京)による接待汚職事件で、同社営業部がみなし公務員にあたる厚生年金基金幹部への接待を隠すため、民間の取引先を接待したように装って経費処理をしていたことが分かった。
東京地検は22日に東京地裁で開かれる元社員越後茂被告(37)の初公判で、過剰な接待が会社ぐるみで行われていたと主張する見通し。
「飲食、ゴルフ、海外旅行は、接待の『3点セット』だった」。越後被告の直属の上司だった元幹部(44)は、東京地検特捜部の事情聴取にこう供述した。
六本木や銀座の高級クラブをはしごして一晩で数十万円、「視察」と称した欧州旅行に100万円……。元幹部は検事に「契約数に応じてボーナスが決まっていた。営業部内には接待で一件でも多く契約を取ろうとする雰囲気があった」と説明したという。
死亡者はいないが、原因としては重大な事故を引き起こす可能性のある事故だ。
バス逆走、8時間前にも事故…運転手が経営者 04/22/14 (読売新聞)
愛知県一宮市の名神高速道路で観光バスが逆走し、次々に車と衝突した事故で、このバスが長野県内で事故を起こした帰りだったことが分かった。
愛知県警は21日、バスを運行していた「NEK(エヌ・イー・ケイ)交通」(大阪府能勢町)を自動車運転過失傷害の疑いで捜索した。県警によると、同社はバスの男性運転手(63)が経営していたといい、運転手から事情を聞いている。
県警によると、バスは20日午後6時頃、同高速下り線の中央分離帯を乗り越えて上り車線に進入。約110メートル逆走しながら乗用車など9台に次々と衝突し、運転手が頭などに約2週間のけがをしたほか、男女計8人が軽傷を負った。
現場にはブレーキ痕やスリップ痕が見つかっていないことなどから、県警は運転手が居眠り運転をしていた可能性があるとみて調べている。
長野県警の発表によると、バスは事故の約8時間前の20日午前10時15分頃、同県安曇野市内で、信号待ちで止まっていた乗用車に追突し、前に止まっていた乗用車にも玉突き衝突した。バスには運転手のほか乗客と添乗員計30人が乗車していたが、全員けがはなかった。バスは乗客らを降ろし、その後、大阪の会社に戻る途中、再び事故を起こしていた。
虚偽申請1億円超 また慈恵医大で「補助金不正受給」疑惑 04/19/14(日刊ゲンダイ)
慶大医学部、日本医科大と並ぶ私立医大のご三家のひとつ「東京慈恵会医科大」で、国の科学研究費補助金(科研費)の不正受給疑惑が浮上し、大学側が内部調査を進めていることが日刊ゲンダイ本紙の取材で分かった。
科研費は、国が大学研究者らに研究費を助成する制度。研究者が研究目的や計画などを申請し、審査を経て採択されれば助成金が支払われる仕組みだ。文科省によると、2013年度は約2318億円を助成している。
関係者によると、昨年末、肝臓内科の男性医師が科研費の「虚偽申請」などをしていた疑いが発覚。大学側は文科省に報告するとともに内部調査委員会を立ち上げて詳しい調査に乗り出したという。
「問題の医師は、自分のものではない虚偽の論文を提出して科研費を申請していた。その額は1億円を超えているようです。科研費の申請が通れば国に認められた研究とされるため、製薬会社の研究費が付くケースが多い。その額は科研費の3~4倍にもなります。こうした背景もあって虚偽申請が行われた可能性があります」(文科省関係者)
慈恵医大は日刊ゲンダイ本紙に対し「科研費をめぐるプロセス、手続きの一部にルール通りではない部分があった。(不正受給の)金額や詳しい状況は調査中」(広報担当)とコメントした。
■10年前にも同じ不祥事
言うまでもなく、科研費の財源は税金だ。慈恵医大が悪質なのは、科研費の不正受給は今回が初めてではないことだ。04年度にも不正が判明、文科省は、関係した70人の受給資格を一定期間停止し、加算金を含め約5億円の返還命令を出している。慈恵医大は当時、理事長の給与カットなど反省のそぶりを見せていたが不正体質はナ~ンモ変わっていなかったワケだ。
「今回の虚偽申請の手法は、10年前の不正と似ています。問題の医師はあの時関係した70人のひとりです」(前出の文科省関係者)
慈恵医大は、ノバルティスファーマの降圧剤の臨床研究データ操作事件で、東京地検に家宅捜索(薬事法違反の疑い)されてもいる。不正の闇は底なし沼か。
小保方氏が培養し続けた黒い“煩悩細胞”(3)盗作と虚言は一種の「性癖」 04/16/14 (アサ芸プラス)
小保方さんには、一つの謎がある。それは「カネ」だ。愛用する「ヴィヴィアン・ウエストウッド」はTシャツだけでも2万円はする高級ブランドである。文科省関係者が首をかしげる。
「理研の研究職の給与は国立大学の教員の給与を基準にしています。住宅費の補助は出ますが、小保方さんは年収800万円に届くかというところでしょう」
神戸・三宮駅前にマンションを借りている小保方さんだが、理研に来てからの2年間はホテル暮らしをしていた。前出・理研関係者が語る。
「シングルルームのいちばん安い部屋で8000円として、月に約24万円です。また、食事に行く時も、常に高い店に行っていた。給与以外の収入がなければ成立しないでしょう」
日本の先端研究として期待される再生細胞技術には、研究費として文科省や厚労省から億単位の研究費が出る。それだけに、使い込みを疑う声もあるが、理研はその点については一貫して否定しているのだ。前出・理研関係者が語る。
「報道を通じて、彼女の不思議なセレブ生活は知っています。いずれ査察が入ると思いますよ。その時は、コピー用紙1枚の値段や在庫もチェックするので、逃れられない。使い込みがバレれば、数年間、研究費の申請が停止となります。国税レベルの徹底ぶりを知っている研究者が、省庁からの研究費を使い込むのは難しい。しかし、再生細胞系の研究には企業からも研究費が出ます。この管理は本当にユルいのです。懇意にしている業者に本を買ったことにしてもらい、カネを浮かすこともできます」
彼女の上司は大きな裁量権を持つ笹井氏である。ここでも何らかのO・S結合があったのだろうか。
さらに、今回の問題に伴って、ネット公開されている彼女の博士論文についての盗作も指摘された。海外メディアからその点を問われた小保方さんは、
「下書きしたものが残っている」
と答えている。また、「週刊新潮」4月10日号では、博士論文について同誌の直撃にこう答えている。
「早稲田の論文は対外的には未発表」
前出・早稲田大学教員関係者があきれ顔で語る。
「現在、文科省などの指針もあって博士論文はネット公開して、世界で検証することがルールになっています。もちろん下書きしたものは公開しませんから明らかな虚言です。今回のアオリで、彼女が出た研究室の論文がチェックされ、他の卒業生の盗作も露見しました。大学としては権威を失墜させないために、小保方さんには断固とした処分が下されると思います」
伊勢丹で購入したばかりの割烹着を祖母からもらったものと言いのけた小保方さん。博士号が取り消されれば、奨学金、研究費などは返還しなければならない。
「田口ランディその『盗作=万引き』の研究」の著書がある前出・大月教授は、こう分析する。
「虚言癖とか盗作は、万引きや痴漢と同様、性癖としてどうしようもない部分もあるんでしょう。自分をよく見せたい、認められたい、という意識が肥大して自分で制御できないまま暴走した状態で、なかなか治りにくいものです」
小保方さんの「悪意がない」という言葉だけは本当ではないかと、前出・文科省関係者は語る。
「文科省の教育指針が変わり、研究者の業績は『ドクター(博士)の輩出数』が重視されています。ドクターを量産するために、博士論文のチェックは当然甘くなる。最低限の倫理観すら教えていないのですから、彼女にとっては、論文の盗用も画像の加工も当然やっていいものだと思っているのです。今回の事件は起こるべくして起こったと考えるべきです」
STAP細胞は本当に存在するのか。黒いレッテルを貼られた彼女は、どう反論するのか──。
小保方氏が培養し続けた黒い“煩悩細胞”(2)上目遣いに「センセ、センセ」と追いかけ回す 04/15/14 (アサ芸プラス)
大学院の博士課程の1年夏から2年の冬まで、小保方さんは、アメリカのハーバードに留学する。そこで彼女は1人の研究者を夢中にさせるのだ。理研関係者が語る。
「ハーバードでは、ネズミの背中に人間の耳を培養したバカンティ教授の下で万能細胞の研究をしています。帰国する彼女を教授は『アイ・ニード』(僕には必要なんだ)と言って引き留めました。STAP細胞発表後には、『彼女はライジング・スター』とホメちぎっています」
バカンティ教授は、論文撤回騒動で共同執筆者が撤回の意思を示す事態になっても、一貫して小保方さんの味方となっている。
次に彼女が取り入ったのが、当時、理研のチームリーダーだった山梨大学の若山輝彦教授だった。若山教授は、「文藝春秋」4月号「小保方さんがかけてきた涙の電話」で、小保方さんの第一印象をこう語っている。
〈留学先のハーバード大の小島宏司教授から、メールで小保方さんに協力して欲しいと連絡があったのです。(中略)自分の意見もはっきり言うし、プレゼンテーションもうまい。その頃、彼女はまだ博士課程の3年生でしたが、相当レベルの高い学生だなと思いました〉
若山教授の研究室に入った小保方さんは、高校時代同様に、“密着マーク”をするようになった。前出・理研関係者が語る。
「若山先生は、クローンマウスの専門家です。上目遣いで『センセ、センセ』と追いかけ回し、『教えてくださぁい』と鼻にかかった声で呼びかけるのです。若山先生の奥さんも同じ研究室にいましたが、奥さんが先に帰るとすぐにメールで、『先生、ごはん食べにいきましょう☆』と誘いかけていました」
小保方さんが、すり寄っていたのは1人だけではない。この研究室に彼女を推挙した小島教授にも密着しているのだ。この時期、小保方さんは「女性として理系で生きることはつらくないか?」という質問に、こう答えている。
「全然大変じゃないですよ! 女性は珍しいから、みんなちやほやしてくれますし。両手に花です」
前出・理研関係者が失笑する。
「理系が男性社会っていうのはいつの話ですか? 特に生物や化学系への女性の進出は著しいのです。大学での男女比もだいたい半々ですよ。『ちやほや』っていうのは、彼女がそう仕向けていたからでしょう」
12年末、彼女はついにSTAP細胞の作成に成功したと理研に報告した。そして、世界的な科学誌「ネイチャー」に論文を提出するのだが、あえなく却下されてしまう。
「若山先生といても世界レベルの論文は通らないと考えたのか、いつの間にか理研の副センター長である笹井芳樹先生に急接近したのです。笹井先生は、万能細胞である『ES細胞』の第一人者で、ノーベル賞候補にもなった人物です」(前出・理研関係者)
次期センター長の筆頭候補である笹井氏という威光を後ろ盾にした彼女は、30歳の若さでユニットリーダーに昇進する。笹井氏は周囲に「僕のシンデレラ」と漏らしていたほど、小保方さんにご執心だったようだ。
「騒動が発覚したあとも、笹井先生は『僕はケビン・コスナーになる』と語っていました。映画『ボディガード』のように小保方さんを守るという意味のようです。2人の関係は『O・S結合』と言われています。小保方さん、笹井先生の頭文字ですが、酸素(O)と硫黄(S)が結合した『排気ガス』の意味も含まれています」(前出・理研関係者)
最終報告を受けたあと、笹井氏が出したコメントには、いまだSTAP細胞の存在を信じることがつづられている。2人はまだ結合し続けているのだ。
「会見で小保方氏以外の第三者がSTAP細胞作製に成功していると述べた点については、『私の判断だけで名前を公表できないが、成功した人の存在は理研も認識しているはず』と主張した。理研広報室は『再現実験で万能細胞の指標となるたんぱく質が出ていることを確認した人は1人いるが、万能性が証明できたわけではない』としている。」
万能性が証明出来ていない。再現実験で万能細胞の指標となるたんぱく質が出ているだけでは万能性を証明した事にはならないと言う事か?昨日テレビを見ていると、香港の研究所が指標の話をしていた。STAP細胞の存在を証明することは万能性を証明する事であるならば、万能細胞の指標となるたんぱく質が出ているだけでは世界では認められないと権威のある機関や人物が判断すれば、今回の騒動の終わりになるのではないのか?理研広報室は「再現実験で万能細胞の指標となるたんぱく質が出ていることを確認した人は1人いる」とコメントしているので思ったよりもはやく結論が出るかもしれない。
小保方氏が説明文書を配布 「STAP細胞を日々培養」 04/14/14 (朝日新聞)
STAP細胞の論文問題で、理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダーは14日、代理人の三木秀夫弁護士を通じて報道陣に配布した文書で、「STAP細胞は日々培養され、解析されていた」などと主張した。
STAP細胞に関するニュース
この文書はSTAP細胞ができたと改めて主張する内容になっている。ただ科学的なデータや写真などは示していない。
文書では、小保方氏が会見で「STAP細胞は200回以上作製に成功した」と述べた点について、「実験を毎日のように、しかも一日に複数回行うこともあった」と主張。万能細胞の指標となるたんぱく質が出ているかどうかをみて「作製を確認した」と説明している。
また、「2011年4月には、(ネイチャー)論文に書いた方法でSTAP細胞が出来ることを確認し、その後、6月から9月ごろにはいろいろな細胞に、様々なストレス条件(刺激)を用いてSTAP細胞を100回以上作った」などと主張。その後も、遺伝子解析やマウス実験などに必要なSTAP細胞を100回以上作製したとしている。
会見で小保方氏以外の第三者がSTAP細胞作製に成功していると述べた点については、「私の判断だけで名前を公表できないが、成功した人の存在は理研も認識しているはず」と主張した。理研広報室は「再現実験で万能細胞の指標となるたんぱく質が出ていることを確認した人は1人いるが、万能性が証明できたわけではない」としている。
作製の「コツ」については、「所属機関の知的財産であることと、特許等の事情があるため、個人から全てを公表できない」と改めて理解を求めた。「状況が許されるようになれば、言葉で伝えにくいコツが分かるよう映像などを近い将来公開するよう努力したい」としている。
三木弁護士は文書を出した理由について「時間が限られた会見の内容にバッシングが出て、小保方氏が心を痛めている」と話した。
「理化学研究所の『STAP細胞』論文問題で、研究不正をしたとされる小保方(おぼかた)晴子・研究ユニットリーダー(30)は14日、弁護団を通じて文書を発表し、STAP細胞の作製に成功したとする第三者について、『理研も存在は認識しているはず』と主張した。」
おもしろいコメントだ。これで理化学研究所は認識しているのか、いないのか回答しなければならない。「理研も存在は認識しているはず」のコメントもトリッキーだ。「認識している」ではなく「認識しているはず」と言う事は、理研の誰が認識しているのかを含めて理研は明確に回答する必要があると思う。「はず」と言うからには認識している根拠(報告書の提出や口頭での発言等)があるに違いない。「はず」とは推測で、断定ではない。
STAP細胞:小保方氏が文書「成功した人、理研も認識」 04/14/14 (毎日新聞)
理化学研究所の「STAP細胞」論文問題で、研究不正をしたとされる小保方(おぼかた)晴子・研究ユニットリーダー(30)は14日、弁護団を通じて文書を発表し、STAP細胞の作製に成功したとする第三者について、「理研も存在は認識しているはず」と主張した。氏名の公表は「本人に迷惑がかかる」として改めて否定したが、弁護団は氏名を確認したという。
文書は「記者会見に関する補充説明」と題しA4判で3枚。小保方氏が今月9日の記者会見で発言した内容を補充するため弁護団が聞き取ったという。
小保方氏は記者会見で「私自身、STAP細胞の作製に200回以上成功した」としたが、文書では作製の定義について、さまざまな細胞に変化する多能性の指標である「光る細胞」ができた段階だと明らかにした。また、STAP細胞がさまざまな細胞に変化することは複数回確認している、と説明した。
具体的な時期などに関しては、小保方氏が客員研究員として理研で研究を始めた2011年4月には、論文で説明した方法で成功したという。その後、11年6〜9月ごろは、リンパ球や皮膚、筋肉、肺などさまざまな細胞を使い、酸などの刺激で作製を試み、100回以上作ったとしている。
同9月以降も、遺伝子の解析や多能性の確認のために、リンパ球に酸の刺激を与えてSTAP細胞を作製する実験を繰り返し、100回以上は作った、と訴えている。さらに、今回の論文に80点以上の図表を掲載するため、それぞれ複数回の実験が必要で、成功回数は計200回以上に上ると説明した。
STAP細胞は1週間程度で作製できるとし、「毎日のように実験し、1日に複数回行うこともあった」とした。作製法の「コツ」にも言及し、「体調が回復し環境さえ整えば、具体的に教えたい」とした。
小保方氏は記者会見で、自身以外にもSTAP細胞の作製に成功した第三者がいることを明らかにしていた。また、200回以上成功したとの発言を巡っては、「どの段階を成功と言っているのか」「200回以上には最低数年かかる」などの疑問の声が出ていた。【吉田卓矢】
「STAP細胞の詳しい作製手順については『特許等の事情もあり、現時点では私個人からすべてを公表できない』と理解を求めた。」
特許は申請中なのか、申請済みなのか、それぐらいの回答は可能ではないのか?申請済みなのであれば隠す必要はないと思う。また、特許の申請は誰が行っているのか、共同で行っているのか?理研は特許申請に関与しているのか?STAP制作成功者の名前を理研は把握しているのか?理研は出来る範囲で公表するべきだ!
小保方氏、STAP作製成功者「公表できない」 04/12/14 (読売新聞)
STAP(スタップ)細胞の論文問題で、理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダーは14日、STAP細胞を作製した経緯などを改めて説明した文書を、代理人を務める三木秀夫弁護士を通じて発表した。
小保方氏はSTAP細胞の作製について「実験を毎日のように行い、1日に複数回行うこともありました」と説明した。STAP細胞は「日々培養され解析されていました」と強調し、2011年9月までに100回以上、それ以降に100回以上作製したと主張した。作製に成功した第三者については「私の判断だけで、名前を公表することはできません」と説明を拒んだ。
STAP細胞の詳しい作製手順については「特許等の事情もあり、現時点では私個人からすべてを公表できない」と理解を求めた。
持ち込み32キロ 甘い規定 ベトナム航空CA密輸「副機長に誘われた」 04/12/14 (産経新聞)
ベトナム航空の客室乗務員(CA)が万引された衣料品や化粧品を航空機で密輸していた事件で、CAらが機内に32キロ分の荷物の持ち込みを許可されていたことが11日、ベトナム航空への取材で分かった。平成21年に同種事件で副機長が摘発された後も改善されていなかった。警視庁に盗品等運搬容疑で逮捕されたCAのグエン・ビッチ・ゴック容疑者(25)は「副機長に誘われた」と供述。別の万引事件の捜査でもCAらの関与が浮上しており、組織的犯行の疑いが一層強まっている。
■2人一組
一連の密輸は、万引グループが商品を盗み出すことから始まる。
警視庁に窃盗容疑で逮捕されたベトナム人の男4人は関東近県で、ベトナムで人気が高い「資生堂」の化粧品や「ユニクロ」の衣料品を狙って万引を繰り返していた。
ユニクロでは衣料品などに万引防止用のタグを付けており、店外に無断で持ち出せばアラームが鳴る。
万引グループは2人一組で行動。1人が商品を精算せずに持ち出そうとして店員に止められ、騒ぎを起こした隙に、もう1人がスーツケースに大量に商品を詰め込んで逃走する大胆な手口だった。
捜査関係者は「見張り役を置くなど犯行が手慣れている」と指摘する。
盗品はあらかじめ確保された販売ルートに乗ってさばかれる。その中心にいたのが万引グループから盗品を買い取り、グエン容疑者らに郵送していた仲介役の女(30)=盗品等有償譲り受け罪で起訴=だった。
グエン容疑者らは日本からベトナムに盗品を持ち帰り、仲介役の女に紹介された首都ハノイの雑貨店に運び込む。この店は女の妹が経営し、1点250~400円の報酬を払って盗品を受け取り、現地のベトナム人に正規輸入品より安く転売していたとみられる。
盗品はダウンジャケットなど人気が高い特定の商品に偏り、報酬も人気商品ほど高くするなど、細かく定められていた。
■小遣い稼ぎ
「日本から運ぶだけでカネになる仕事がある」。グエン容疑者はベトナム航空の副機長からこう誘われ、昨年6月ごろから盗品密輸に関わるようになった。
グエン容疑者は「多くの同僚が小遣い稼ぎでやっている」とも供述。警視庁はベトナム航空内で副機長やCAら20人超が密輸に関与したとみており、他県警のベトナム人による万引事件の捜査でも、CAらの関与が浮上しているという。
ベトナム航空によると、CAらには手荷物以外に、スーツケースで32キロ分の持ち込みを許可。一方で、ケースの中身の検査は随時行っていたといい、担当者は「税関などが検査を厳格化しないと不正を見抜ききれない」と釈明する。
平成25年に万引容疑で摘発された外国人の4割はベトナム人だった。警視庁幹部は「ベトナム航空ルートを断たなければ、ベトナム人による万引は根絶できない」としている。
どちらが悪いのか、どっちも悪いのか、泥沼状態に思える。ただ、ここまで注目を受けているのだから、事実を公表してほしい。
小保方晴子とSTAP細胞の破綻 - 科学の正論に戻り始めたマスコミ 04/10/14 (世に倦む日日)
小保方晴子さんが悪いのか? ハフポスト・ブロガーはこう見る【STAP細胞】 04/11/14 (ハフポスト)
「国内外の研究者からSTAP細胞の作製成功が報告されていないことに対し、小保方氏は『作製には、ある種のレシピのようなものがある。新たな論文として発表したい』と述べた。 さらに『別の方にやってもらったことがあり、その方は成功している』と説明したが、作製した人物の名前は明かさなかった。」
成功した人物の了解を取って、証人になってもらうべきではないのか?本当にSTAP細胞が存在するなら理研に別れを告げて他の組織で研究を続ける方法もあると思うが、そのような選択を考えていないのか?ある種のレシピを土産に移ることは可能ではないのか?今後の展開が面白そうだ!
理研 10年前にも研究員2人辞職させ上層部は責任逃れた過去 (1/2)
(2/2) 04/11/14(週刊ポスト2014年4月18日号)
理化学研究所(理研)は4月1日に最終調査報告書で、STAP細胞が万能性を持っている証拠の画像を小保方晴子ユニットリーダーが「捏造」し、しかも「不正行為は小保方さんひとりで行った」と明言した。だが、理研の報告には研究者からも疑問の声が上がっている。免疫細胞、血液病理学の権威である難波紘二・広島大名誉教授は疑わしい点のひとつをこう述べた。
「理研は3月14日の会見では『悪意がなかったからシロ』といい、それが4月1日には『悪意があったからクロ』という。悪意があったかどうかなんて証明できないでしょう。それも欠席裁判で、彼女に弁明の機会も与えないのはおかしい」
実はこの点は今後、小保方氏が理研を相手に裁判を起こした場合、理研側に不利に働く可能性がある。
「会見では、『悪意は、刑事事件なら故意というところ』とまで言及している。裁判になれば理研側が『悪意』や『捏造』を立証する責任があるが、本人が否認している場合、証明するのは簡単ではない。小保方さんが精神的苦痛を被ったとして名誉毀損を訴えると、逆に理研のほうが苦しい立場に追い込まれる可能性もある」(弁護士の若狭勝氏)
理研は10年前の2004年にも、血小板の研究で画像データの改ざんが発覚したが、研究員2人の辞職で済ませ上層部は責任を逃れた。このとき後に辞職した研究員に「論文不正に積極的に関わったと受け取られかねない表現」をしたと名誉毀損で訴えられ、HP上の表現を削除するなどして和解に至った過去がある。
トカゲの尻尾切りが、窮鼠猫を噛むに転じる……理研はまたしても暗黒史を繰り返すのか。
研究者の世界はかなり狭く、村社会であることが小保方氏の騒動でメディアで取り上げられた。改善はあるのだろうか?
理化学研究所(理研)は科学の分野でありながら、なぜ明確に出来る事を調査しなかったのか?「2冊のノート」にしても質問および回答について「2冊しかなかった」のと、「提出されたノートは2冊であるが、他にもノートがある」とでは、受け取る側の印象が変わってくる。なぜ確認できるような質問をしなかったのか、質問したが会見では誤解を生むような発言をしたのか?今回の件は、科学の分野であるのに中途半端な事ばかりだ。科学的に事実を明確にする必要が要求される分野で、曖昧で、抽象的な質問と確認なしの勝手な解釈が会見で報告された。おかしい。絶対におかしい。
研究者が見た小保方氏会見 「強引な主張」「証拠示して」「上司に説明責任」 (1/2)
(2/2) 04/10/14(産経新聞)
小保方晴子氏の記者会見での発言について、研究不正問題に詳しい大阪大の中村征樹准教授(科学社会学)は「インパクトのある反論はなかった」と話す。
中村准教授は、「研究成果の信頼性は、そのプロセスが妥当であることに支えられる。『真正な研究結果が存在するので研究不正ではない』と訴えているが、それは科学的には強引な主張だ」と断じる。
信頼性を証明するには「パソコンや実験ノートをどういう形で管理し、どういうデータがあるのかを提示し、説得力のある説明が必要」という中村准教授。一方で「理化学研究所の調査委員会の報告も拙速だったのでは。調査段階で小保方氏の主張を十分に聞き取りし、事実認定すべきだった」と指摘した。
難波紘二・広島大名誉教授(血液病理学)は、「記者会見で謝罪、反省したことは評価するが、もっと早く世間や科学者に説明すべきだった」と語った。
難波名誉教授は、「小保方氏はSTAP細胞の作製に200回以上成功したと話しているが、科学的証拠なしに信じるのは困難。サンプルが保存してあるならそれを示してほしい」と、検証可能なデータの開示が不可欠との認識を示した。
柳田充弘・沖縄科学技術大学院大教授(分子遺伝学)も、「研究不正の嫌疑をかけられた若い人が会見するのはかつて経験がなく感心した」としながらも、「疑義が晴れたとは思っていない」という。
また、「小保方氏の上司に当たる共同研究者がまず出てきて説明しないのはよくない。共同研究者は、より専門的な疑問に答えるべきだ」と、上司の説明責任についても言及した。
小保方氏「STAPある」=論文撤回を否定-「別の人が成功」証拠示さず 04/09/14 (読売新聞)
新しい万能細胞「STAP(スタップ)細胞」の論文問題で、理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダー(30)は9日午後の記者会見で、「STAP細胞はある」と明言した。英科学誌ネイチャーに発表した論文の撤回については「STAP現象が間違いであったと発表することになる」と述べ、同意しない考えを明らかにした。ただ、STAP細胞の存在を証明する明確な証拠は示さなかった。
国内外の研究者からSTAP細胞の作製成功が報告されていないことに対し、小保方氏は「作製には、ある種のレシピのようなものがある。新たな論文として発表したい」と述べた。
さらに「別の方にやってもらったことがあり、その方は成功している」と説明したが、作製した人物の名前は明かさなかった。
小保方氏は、論文の記載に誤りがあったとして「未熟さを情けなく思う」と謝罪した。しかしSTAP細胞の存在については、自分で200回以上作製に成功し、証拠の画像も大量にあると主張。理研の調査委員会が3年間で2冊しかないと指摘したSTAP細胞の実験ノートについても、「少なくとも4、5冊ある」と反論した。
一方で小保方氏は、作製方法の具体的な情報は今後の論文発表に影響するとして明かさず、実験ノートも公開しないと述べた。
調査委の聞き取りについては「弁明する機会が少なく、事実関係を詳細に聞き取るという面では不十分だった」と批判。小保方氏1人が不正を行ったと認定され、上司の関わりが否定されたことに対し、「(不満の気持ちを)持つべきでないと思っている」と悔しさをにじませた。
今回の小保方氏の会見はマスコミを喜ばせるようなものだったと思う。これでしばらくは、ネタに困らないだろう。
「200回以上成功」そんなに簡単に出来るのなら、なぜ理研は1年も必要と言ったのか?
また、200回以上も成功したのに良い画像は撮影できなかったのか?
「小保方氏は『調査委に提出したのは2冊だが、実際にはもっと存在する』と説明した。」理研の調査能力や報告の適切さを疑ってしまう。
小保方氏、理研又は両方に問題があるのではないかと思ってしまう。
「一方、小保方氏側は不服申し立てで画像の加工は認めたものの、『切り貼りしてもしなくても、データから得られる結論が変わらない』と改ざんを否定した。」
論文や実験をばかにしていないか?データーから得られる結論は変わらないが、論文を読むだけでは同じ結果が得られない論文はおかしくないか?秘密のコツを知らなければ実験に成功できないなんてふざけていないか?
会見を見る限り、小保方氏の研究者としての基本的な所に問題があるのか、単なる大嘘つきなのかのどちらかはわからないが、どちらかである事に違いないと思った。また、理研と言う組織に多額の税金をつぎ込むメリットがあるのか疑問に思った。
「STAP細胞、200回以上成功」…小保方氏 04/09/14 (読売新聞)
STAP(スタップ)細胞の論文問題で、理化学研究所発生・再生科学総合研究センターの小保方(おぼかた)晴子ユニットリーダー(30)は9日、大阪市内のホテルで記者会見した。
小保方氏は「STAP細胞は200回以上作製に成功しており、真実です」と訴え、理研に8日、不服申し立てを行った理由を説明した。小保方氏が会見するのは、英科学誌ネイチャーに論文が掲載され、成果発表を行った1月末以来。
小保方氏は会見の冒頭、「私の不勉強、不注意、未熟さゆえに多くの疑念を生みました」と謝罪した。だが、ネイチャーの論文の核心部分に改ざんと捏造があったとした理研調査委員会の最終報告については、「実験は確実に行われており、悪意をもってこの論文を仕上げたわけではない」と反論した。
調査委が「実験ノートが3年で2冊しかなく、どんな実験だったかを追跡できなかった」と指摘した点に関しては、小保方氏は「調査委に提出したのは2冊だが、実際にはもっと存在する」と説明した。
調査委は1日に公表した報告で「STAP細胞をマウスの血液細胞から作製したことを示す遺伝子データの画像は、2枚の画像を切り貼りしたもので、改ざんにあたる」と認定した。一方、小保方氏側は不服申し立てで画像の加工は認めたものの、「切り貼りしてもしなくても、データから得られる結論が変わらない」と改ざんを否定した。
様々な細胞に変化するSTAP細胞の多能性を証明する画像に関しても、「実験条件の全く異なる小保方氏の博士論文と酷似し、捏造だ」とする調査委の判断に対し、小保方氏側は「正しい実験画像が存在し、画像をとり違えただけだ」と主張している。
科学論争かけ離れた場外戦の様相…STAP問題 04/09/14 (読売新聞)
研究不正か否かをめぐり、理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダーと、理研調査委員会が、それぞれ記者会見を開いて主張する異例の展開となったSTAP細胞問題。
小保方氏の会見はテレビやインターネットの動画サイトで中継され、関心の高さを示したが、識者からは「科学とはかけ離れた印象で、違和感がある」との声も出ている。
女性研究者の先輩格に当たる東京大の大島まり教授(生体流体工学)は、「科学論争とは違う場外戦の様相を呈している」と指摘する。写真の取り違えなどのミスは認めつつ、捏造や改ざんは認めない小保方氏の姿勢については、「科学の世界では明白な不正。研究不正に関する理研の規定の文言を争っているのは違和感がある」と語った。
税金950万円でイタリア家具購入も結果を出せるのであれば安い買い物。アメリカのIT企業が日本では受け入れないようなインテリアや物を購入している。結果を出せれば、莫大な利益に繋がるのであれば、少額の投資と考えられているのだろう。結果を出せない者や権力を持つ上司から評価されない人は、会社を去るしかない。ある会社で評価されなくても、他の会社ではそれなりの評価を得たり、成功する人もいる。日本でも結果を出せない研究者には去ってもらうぐらいの対応は必要になると思う。アメリカ式が良いのか、日本式が良いのか、それぞれの研究者が判断すれば良い事。
「1000万円近い高級輸入家具を使わないと『自由な発想』は生まれないのか。」は微妙だ。既に能力があることを証明できた者に対しては多少なりの優遇があっても良いかもしれない。高級家具が誰の要求で、どのように使われているのかは興味あるところだ。
理研は“科学者の楽園” 税金950万円でイタリア家具購入 04/06/14 (日刊ゲンダイ)
「STAP細胞」の「捏造(ねつぞう)」論文問題で大揺れの理化学研究所。週明けにも不服申し立てを行うとされる小保方晴子研究ユニットリーダー(30)の“反撃”に対して神経をとがらせているらしいが、理研が恐れているのは小保方さんだけじゃない。国の補助金削減や事業見直しを求められる「事業仕分け」の議論が蒸し返されることだ。
実は、「科学者の楽園」とも呼ばれる理研は09年、民主党政権下で「事業仕分け」の対象となった。当時は年間予算の3分の2を占める600億~800億円の「運営交付金」が見直しの議題となり、仕分け人の蓮舫参院議員が「2番じゃいけないんですか?」という発言が話題になった。仕分けの結果、事業費縮減が提言されたものの、理研側は猛反発。結局、見直し議論はウヤムヤになった。ところが、今回の「STAP細胞」問題で、再び理研のカネの使い方に注目が集まっているのである。
■小保方さんは年収940万円
「“クロ判定”された小保方さんは年収940万円のほか、5年間で総額1億円の研究予算が与えられていました。そのため、永田町では『若い研究者を厚遇し、好き勝手にさせたことが不正を助長したのではないか』と理研の運営体制を問題視する声が出ているのです」(科学ジャーナリスト)
理研では、研究者の「自由な発想」のために壁の色を変えたり、研究室内を改装したりする。「自由な発想」とは聞こえがいいが、研究とは無関係のカネをジャブジャブ使われたらたまらない。念のため、小保方さんが勤務する理研の発生・再生科学総合研究センターのある神戸事業所の物品調達を確認したら驚いた。ナント、高級家具をバンバン買っているのだ。
「2011年3月にイタリアの高級ブランド『カッシーナ』の家具を2度も購入しています。金額は計約950万円で、いずれも『幹細胞研究開発棟』用です。偶然でしょうが、11年は小保方さんが細胞研究のために理研に入った年と同じです」(文科省担当記者)
1000万円近い高級輸入家具を使わないと「自由な発想」は生まれないのか。揚げ句、その結果がデタラメ論文なんて呆れるばかりだ。
製薬会社:72社 医師や医療機関に年間4827億円提供 04/06/14 (毎日新聞)
◇国の医療分野研究開発関連予算の2.5倍
2013年度に業界団体「日本製薬工業協会」に加盟していた70社と加盟社の子会社2社が、12年度に医師や医療機関に提供した資金の総額が4827億円に上ったことが分かった。国の医療分野の研究開発関連予算1955億円の2.5倍にも上る。降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験疑惑で問題になった奨学寄付金は346億円だった。各社が製薬協の新ルールに従って順次公開した金額を毎日新聞が集計した。製薬業界から医師に流れた資金の全体像が明らかになったのは初めて。
4827億円の内訳は、新薬開発のための臨床試験費用など研究・開発費2471億円▽研究室への奨学寄付金や学会への寄付金など学術研究助成費540億円▽医師個人への講師謝礼や原稿執筆料など270億円▽医師を集めての講演会や説明会の開催費など情報提供関連費1428億円▽接遇費など115億円。
医師が企業から受け取った資金については、国や学会が情報開示を促してきた。製薬業界でも透明化の必要性を認める声が強まり、昨年度から公開が始まった。【河内敏康、八田浩輔】
小保方晴子氏の新型万能細胞「STAP細胞」論文に関する騒動は日本の恥であるが、いろいろな問題が公になったので関係者以外にとっては良い出来事ではないのか。問題が起こらなければ、問題が存在してもリスクを冒してまで多くの人達が注目しないかもしれない事を公表することへのインパクトや影響はないのではないのか?
今回は、小保方晴子氏の新型万能細胞「STAP細胞」がメディアに取り上げられて、世間の人々が小保方晴子氏と「STAP細胞」について程度の違いはあれ知っている。
これらに関して記事にすればかなりの読者を期待できると思う。そこで、「理研が独立行政法人化されたその弊害」、「天下り官僚がおかしな方向に導いている」や
「身内の論理」「学会の権威」に関する情報を簡単に読める。
「理研が独立行政法人化されたその弊害」はどのように組織や人々が新しい環境に対応するか次第だと思う。パーフェクトなシステムなどなかなかない。また、システム自体が比較的に優れていても、システムの中で役割や機能を果たす人材に問題があれば、期待される結果は出ない。人材に問題があれば、体を蝕む癌細胞のようなものだ。癌細胞に蝕まれる体のように、組織(システム)も人材(人々)に蝕まれて機能しなくなる。公務員批判を考えれば所属する組織だけのメリットを優先する問題や民間企業のような効率や改善を行わない問題が存在することは多くの人達が知っている事。民間は自由度はあるが、やり方を間違っていたり、やり方がどうであれ結果を出せなければ、縮小、リストラ、倒産や破産などのリスクがある。外部からの支援なしに簡単に公務員体質からすみやかに変われる人々は少ないと思う。民間でも経営者の放漫経営や不可抗力的な要因でなければ、倒産する会社の従業員達は成長している会社の従業員達とは違う。やはり倒産する会社の従業員達は問題があると思える。
「天下り官僚がおかしな方向に導いている」は半民、半官の問題。財源と予算の決定権を持っている役人の問題。天下りと予算がセットになっている。純粋に効率や改革が出来ない。能力や経験が無い肩書だけの役人を天下りを受け入れないと予算や補助金を貰えない。天下りを期待しているOBや役人が存在する限り、この問題を解決することは出来ない。先輩及び後輩の関係そして将来の天下り先の確保はキャリアの重量課題だと思う。美味しい天下り先がなければキャリアとして公務員になるメリットや魅力はかなり減る。大手をリストラされた人々が簡単に同等の待遇と給料で仕事を簡単に見つける事ができるか?出来ない。能力に関係なく、ある程度の昇進や昇給、終身雇用、そしてこれまでの会社のシステムがあったからこその待遇と給料であれば、一度、組織を離れたら終わりである。キャリアやOBにも同じ事が言える。これまでのシステムに守られてきた結果の待遇と給料であれば、退職すれば高学歴の元キャリアと言うだけでは使えない。癒着や便宜をお願いできるキャリアOBでなければ必要ない。公務員システムのなかにどっぷりと浸かって来たキャリアなど使えない。出世やどうやっから良い天下り先に行けるかだけを考えて働いてきたキャリアなど必要ない。採用するとしても同等の待遇では採用できないだろう。消費税が8%になり、テレビではコメンテーター達が国民は受け入れる覚悟があるとか、仕方がないとか言っているが、誰も税金の使い方については触れていない。無駄に税金を使うようなことを許していては、今後も消費税は仕方がないと言う事で引き上げられるだろう。
論文で仮説と実験を通しての証明。仮説が正しければ、実験結果は仮説と同じ、又は、近い結果となる。こんな単純な関係のチェックを理研は行っていなかった。実験に問題があれば、どこに問題があったか確認や検証できるように、メモや記録などの資料が存在するはずである。それがない。小保方晴子は「悪意のない間違い」と言っているそうだが、悪意とかそれ以前の問題。このような考え方で実験を行い、博士課程を修了できる日本の大学、このような考え方でも採用する理研、そしてこのような問題のチェックを行えなかった理研は問題を抱えていると判断されても仕方がないと思う。理研は性善説の欠陥と言っているようだが、検証出来る資料やメモがない実験は証拠が無いから自白を強要し、自白と辻褄が合うように証拠をでっちあげる警察や検察問題と同レベルだ。改革が必要だ。
小保方晴子氏を「犠牲者」にした独立行政法人・理研の組織的欠陥/井上 久男 04/06/14 (現代ビジネス)
新型万能細胞「STAP細胞」論文で理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダーの研究手法に不正があったとして、同研究所の野依良治理事長は4月1日、記者会見して謝罪、論文の取り下げを正式に勧告するなどと説明した。
*** 「小保方問題」は起こるべくして起きた ***
同時に小保方氏の処分も検討するという。論文の共著者である笹井芳樹氏(理研発生・再生総合研究センター副センター長)と若山照彦氏(山梨大学教授)については、研究不正は認められなかったとした。
理研の対応を見ていると、小保方氏個人の「不正」として片付けようとしているように映る。果たしてこの問題は、有識者らが指摘しているように小保方氏の研究者としての「倫理観の欠如」から発生したのだろうか、あるいは小保方氏の研究手法を早計に「不正」と断じていいのだろうか、といった疑念がわいてくる。
筆者も文系ながら、かつて大学院の博士後期課程で学んで学位論文(ベンチャー論)を書こうと試みていた時期があり、国立大学法人でも2年間特任講師を経験した。期間は短いとはいえ、アカデミックな分野での経験は多少ある。こうした経験も踏まえて、今回の問題を考えてみたい。
そこで筆者は、理研のベテラン研究者に、なぜ、この問題が起きたのかを聞いてみた。匿名を条件に率直に語ってくれたところからは、予想通り、理研という組織や日本の科学技術政策の「欠陥」などが浮かび上がってきた。
その研究者によると、「小保方問題」は起こるべくして起き、小保方氏は理研という組織の「犠牲者」といった側面がある。
*** 独法化で理研は変貌してしまった ***
まず、理研が独立行政法人化されたその弊害も、「小保方問題」の背景にあるようだ。独法化とは、その名の通り、法人=会社になることである。
税金など公的資金で運営されるのではなく、資金調達や組織マネジメントの手法を企業化することで、かつては行政が担っていた分野を民間的に効率重視の運営に変えていくために、「橋本行革」の際に導入された制度だ。そこで働く職員も一部の特定独立行政法人を除いて公務員扱いではなくなる。
税金など公的資金を使ってしかも不効率な運営をする官業から民間的経営に移行していくその発想は肯定的にとらえてもいいだろう。しかし、理研のような組織が独法に向いているのかという点は考えなければならない。
独法化によって理研は、目標を掲げたり、成果を性急に求めたりする組織に変貌した。企業が成果を求めるのと同じ考えである。この結果、「競争的資金」などと呼ばれる補助金が得やすいライフサイエンスなどの限られたテーマに偏る傾向になったという。
理研に限らず、大学や研究機関では研究資金などお金を獲得しやすい研究に傾く風潮が強まっている。分かりやすいジャンルで言うと、バイオ、ナノテク、再生医療、福祉関連などの分野である。大学でも看板だけ変えて、農学部を「バイオ」と付く名称の学部に変更しているのも世間受けを狙ってであろう。
この結果、科学技術バブルと言われほど研究資金が潤沢にあるなかで、研究が特定の分野に偏りつつあるのが実情だ。そもそも優れた研究や革命的な発明は誰もが目を向ける場所からは生まれない。福沢諭吉の言葉にあるように「異端妄説」なのである。
最初は誰もが見向きもしなかったことや、あるいは権威からは否定されていたようことからは新しいものは生まれる。だから、本当のイノベーションも、補助金が得やすいテーマからは生まれにくいだろう。
*** 「天下り官僚がおかしな方向に導いている」 ***
そして理研では成果を出して補助金を求めていこうと、「チームリーダー」「グループリーダー」「準主任研究員」「独立主幹」「上席研究員」など様々な役職ができて組織が複雑になった。
小保方さんの「ユニットリーダー」という役職は大学ならば教授相当に当たるという。そのベテラン研究者は「部下も付き、30歳そこそこの経験のない若い研究者にとっては荷が重い役職ではないか」と指摘する。
独法化と同時に役員に相当する理事に旧科学技術庁(現文部科学省)からの天下りも行なわれるようになった。現在、理事長以下6人の理事のうち2人が旧科学技術庁出身者だ。
「理事長の野依氏にはマネジメント能力がない。2人の天下り官僚に牛耳られて、研究の現場を知らないこうした人たちが早く成果を出せと言って、理研をおかしな方向に導いている。一般論として霞が関のキャリア官僚の中で旧科学技術庁と旧文部省は能力の低い役人が多い」(前出ベテラン研究者)。
成果を性急に求めると同時にその成果を対外的に公表していこうと、広報機能も強化された。公的資金も入った研究成果を世に知らしめることは悪いことではないが、実力もないのに所属する研究者を売り出そうとしたり、研究成果をマスコミ記事に掲載させたりする動きも強まっていたという。
この問題が発覚する前に、小保方氏が割烹着を着てテレビで取り上げられたりしていたが、これも世間受けを狙った「過剰演出」と言えるのではないか。
そして、研究手法の一部に問題があることが指摘され始めると、梯子を外したように組織風土の問題には頬被りして、小保方氏個人の問題として片付けようとしている姿が垣間見える。
企業の不祥事の際にも個人の責任として押し付ける、よくあるパターンだが、理研は民間企業の悪いところだけを真似しているのではないか。
理研の組織について言うと、1917(大正6)年にできた理研は、組織に縛られず、成果にも縛られず、科学者が自由にのびのびと研究できる組織として台頭してきた。組織もシンプルで、基本的には主任研究員と研究員という肩書しかなく、研究者の自由なアイデアと良心に任せた研究がなされていた。
ノーベル賞を獲得した研究者の中には理研出身者も多いが、その一人、物理学賞を取った朝永振一郎氏は「科学者の自由な楽園」というエッセーも書いている(3月21日付日本経済新聞)。
ただ、優れた研究だけでは飯は食えないため、研究成果を商品化するために別会社を設立、食品や部品などを売った。「リケン」という自動車部品メーカーがあるのもその流れだ。
世界的な研究や発明は、目標を定めたり、成果を性急に求めたりして誕生するものではない。
科学者がよく「セレンディピティー(偶然の発見)」という言葉を使うように、試行錯誤をしている中で、ある時突然、発見されるものもある。自由闊達な組織の中で、専門の壁を超えて語り合ったり、仕事をしたりする風土の中から生まれる。
しかし、今の理研からはそうした風土はほとんど消え失せ、成果ばかりを先に求める風潮が強まっている。
*** 未熟な研究者いじめ ***
そもそも小保方氏らの「STAP細胞」についての成果を記者会見して一般社会に知らしめる前に理研は、この研究は大丈夫かと健全に疑い、小保方氏に確認したのだろうか。
小保方氏は「論文の撤回はしない。悪意のない間違いなのに、改ざんや捏造と決めつけられたことにはとても承服できません」(4月2日付朝日新聞)などと反論し、弁護士を立てて理研の決定に不服を申し立てる方針を示している。
ところが理研は当初、小保方氏は論文の撤回に同意したと説明していた。重要な問題なのに、この説明の食い違いは何を意味するのか。理研という組織のマネジメントに何か齟齬をきたしていると見るべきではないだろうか。
また、早稲田大学大学院時代の小保方氏の論文に対する「疑念」までも報じられているが、これも、今回の問題に端を発した「小保方いじめ」ではないかと感じる。
メディア中心に社会全体が最初はあれほど持ち上げておきながら、今になって小保方氏の研究全体や人間性までもこき下ろしている。30歳そこそこの未熟な研究者へのいじめとしか見えないし、人権侵害に当たるのではないか。
そもそも日本では博士号を取得するために、博士後期課程の約3年間に3本程度の「査読論文(指導教官以外の外部の研究者による判定付き論文)」を書かなければならない。そして、その査読論文をまとめる形で学位論文として提出するのが一般的だ。ある著名な大学教授はこう指摘する。
「短期間で実験も重ねて論文を大量に書かないといけない中で、博士論文程度であれば、ある程度コピペしているのは仕方ない。そもそも学位論文は学んだことを書くべきもので、そういう意味からも先達の研究を学んでコピーすることを否定してはいけない。学位論文でコピペを否定していたら、多くの学生は学位が取れない。
新しい発見は研究を重ねていく中で見つかるものであり、学位論文など『研究者の卵』の評価は、着眼点やこれから研究者としてやっていけるかといった資質など人間性の方が大切」
筆者もそう思う。そもそも小保方氏の博士論文や今回の雑誌ネイチャーに掲載された論文を過大評価してはいけなかったのではないか。
筆者であれば、率直に言って、30歳そこそこの大学院出たばかりの研究者がノーベル賞級の研究成果が出せるものかと疑う。これは若さを否定したり、若いということだけで疑ったりしているわけではない。
*** 正確な「STAP細胞」再現はそもそも難しい ***
専門外だが、筆者は小保方氏の研究の着眼点が間違っているとは思わないし、資質がないとも思わない。小保方氏本人が「悪意のない間違い」と言っているように、単純ミスのように見える。
もし博士論文にも問題があるのだとすれば、それは査読した外部の研究者や小保方氏の指導教官にもそれを通した責任があるのではないか。また、ネイチャーの論文は査読ではなく、編集者の判断で載せられるのものだが、載せると判断した編集者の責任もあるのではないか。
さらに、この「STAP細胞」について、理研が1年がかりで再現していくという。これも馬鹿げていると思う。論文の実験段階のデータなどは正確には再現はできないと考えられている。
単純に考えても、材料や機材や環境条件などを100%再現して同じ実験をすることは不可能であり、ネイチャー誌自身が「がん研究に関する論文の実験の89%が再現不可能」などとする記事を掲載しているのだ。
最初の実験で見つかったデータや新しい発見をベースに、様々な条件を加味して研究と実験を重ねて、そのデータや発見に普遍的な理論があるのか否かを追求していくことの方が重要なのではないか。
*** 「身内の論理」「学会の権威」 ***
この「小保方問題」からは少しそれるかもしれないが、最後に査読論文制度の課題にも少し触れておく。
査読論文とは、レフリーと呼ばれる査読者がその中身を判定するものだが、その判定者は覆面ながら、同じ学会の学者であるケースが大半だ。ある意味で「身内」なのである。
たとえば、経済学系の査読論文で査読を通過しようと思えば、「社会学系の論文の引用はするな」といった指導が行われるケースもある。その理由は、経済学者である査読者が社会学系の論文を知らないこともあるからだ。
馬鹿げた指導のようにも見えるが、査読を通そうと思えば、「身内の理論」が優先され、その「身内の理論」の中で処世術にたけた人物が論文に「合格点」が与えられて研究者の職を得て、学会の重鎮となっていくシステムである。
いくら着眼点が優れていようが、ユニークな研究手法であろうが、「身内の論理」にはまってなければ、評価は得にくい。はっきり言ってしまえば、大した研究もしていないのに、学会の権威に気に入られれば、学会にすがって生き延びていけるのである。
だから本当に優れた研究者の中には、査読論文を辞めて、学会に投稿前に論文をホームページなどにさらして、学会以外の外部専門家の評価を得るべきとの声も出始めている。最先端のライフサイエンスでも、バイオやナノテクや様々な研究や学問が融合しているやに聞く。狭い学会内の判断だけで適切かつ正当な判断ができているのだろうかと思う。
この「小保方問題」の根底にある本質的な問題は何か。「科学技術立国」を目指す国だからこそ、政治も学者もメディアも真剣に考える必要がある。
“患者より医師優先”な日本は異質…ノバルティス社、企業文化刷新のため、日本の経営陣更迭 04/04/14 (BLOGOS)/
3日、スイス大手製薬会社の日本法人であるノバルティスファーマは、臨床研究への不適切な関与の責任をとって二之宮義泰社長が辞任すると発表した。後任はスイス本社EGMオンコロジー事業部門責任者のダーク・コッシャ氏となる。
【社長交代の背景と影響】
これは、同社の第三者調査委員会が2日、白血病治療薬「タシグナ」の臨床研究において患者情報を不正入手したり副作用情報を報告しなかったりした行為が、個人情報保護法や薬事法違反に当たる恐れがあると指摘したためである。
同社は第三者調査委員会の調査が終わる夏までの間、医師主導臨床研究への奨学寄付金の拠出を一時中断するとしている。
なお、昨年の夏に問題となった同社の高血圧症治療薬「ディオバン」に関しては、厚生労働省が薬事法の誇大広告にあたるとして、先月ノバルティス社を刑事告発し、東京地検により捜査が行われている。ブルームバーグによれば、ディオバンに関する臨床試験の論文は、データに問題があるとして、欧州心臓病学会により撤回処分になっているという。
【日本は異質?】
「責任を持って法令を順守し、倫理的に事業を遂行」できる、経験豊かな新経営陣によって、新たにノバルティスファーマを立て直す、とスイス本社のデビッド・エプスタイン社長は述べる。日本法人社員の行動は「ノバルティスの倫理基準に反するものです」として、「他国と比べて医師を優先する傾向」を、患者優先の方向に変える必要がある、と語ったという。
さらにエプスタイン社長は、日本は製薬会社と医療・研究機関が密接に協力し合う、世界的にも異質な社会であると述べた、とウォール・ストリート・ジャーナル紙(以下、ウォール紙)は伝えている。
【同社の世界的なイメージ】
ウォール紙によると、同社は日本で起こしたのと同様に、イメージダウンにつながる問題を海外でも起こしているという。
今年初め、ニューヨーク州司法長官は、鉄過剰症治療薬の販売におけるキックバックのスキームに関して、ノバルティスのアメリカ法人を起訴した。中国では、数百の病院で同社の現地スタッフが医師を買収したとの疑惑が持ち上がっている。
ウォール紙によれば、同社の評判にとっての最大の汚点は、昨年2月に退任したダニエル・バセラ元会長に対する退職金問題だった。これは当初、向こう6年で最大7800万ドル(約73億円)を支払うというものだったが、投資家や一般から批判され大幅に削減されたという。
ノバルティス SIGN研究問題で経営陣を刷新 関与のMR上長ら解雇 04/04/14 (ミクスOnline)/
ノバルティス・スイス本社のデビッド・エプスタイン社長は4月3日、都内で記者会見に臨み、医師主導臨床研究「SIGN」にMRらが関与した問題を受け、日本法人のノバルティス ファーマの二之宮義泰代表取締役社長ら経営陣が退任し、ダーク・コッシャ氏が代表取締役社長に就任するなど、経営陣を刷新する人事を発表した。新体制は同日付で、ノバルティス ファーマの代表取締役社長にダーク・コッシャ氏が就任するほか、常務取締役オンコロジー事業本部長にフランシス・ブシャール氏、ノバルティスホールディングジャパン代表取締役社長にマイケル・フェリス氏を就任させる。また、SIGN研究にかかわったMRの上長である現場責任者ら数名については、同社のグローバルの行動・倫理規範に反する行為を行ったとして、4月2日付で解雇したことも明らかにした。
これに伴い、ノバルティス ファーマの二之宮義泰代表取締役社長、淺川一雄常務取締役オンコロジー事業本部長、ノバルティスホールディングジャパンの石川裕子代表取締役社長は4月3日付で辞任した。
会見でエプスタイン氏は、SIGN研究で患者情報保護を侵害した可能性があることや副作用の報告義務を怠ったことを「非常に重く受け止めている」と述べた。同研究では、奨学寄附金の運用の方法やアンケート調査の運搬・収集、事務用品や会議施設の提供、スケジュール調整、研究計画立案・同意書作成、報告書の作成・支援など、同社のグローバルポリシーに反する点が複数あったと説明。「(MRなど同社の社員は)医師主導臨床研究の実施に携わるべきではなかった」と述べた。
問題の根底には、本来臨床研究に携わるメディカル・アフェアーズと営業(コマーシャル)が分離していないことがあると指摘し、早急に分離する必要性を強調した。その上で、「最重要なのは、(日本法人の)企業文化を変化させること」と述べ、新経営陣にはこれまでの日本法人にあったカルチャーをグローバルポリシーに合致したものに変革することに期待をよせた。新社長に就任したコッシャ氏は、「法令を順守し、倫理的な組織作りを行う。信頼回復のために、一丸となって取り組む」と語った。
◎「再発防止研修以降に関与した社員には必要な措置を取る」
エプスタイン氏はまた、ディオバン問題発生後、再発防止に向けて社員、経営陣を対象に、契約型の医師主導臨床研究などをテーマとしたコンプライアンス必須研修を実施してきたと説明。ただ、研修を実施した10月以降も医師主導臨床研究に関する問題があったことを問題視。「再発防止研修以降に、(医師主導臨床研究に)関与した社員については、必要な措置を取っていく」と述べた。特に、データの破棄や証拠の隠蔽にかかわるなど、グローバルの行動規範に従わなかった社員や再発防止研修を受講していない社員については、同社の信頼を損なう可能性があることから、厳しい判断も辞さない構えもみせた。MRなどの処分については、4月2日に「慢性骨髄性白血病治療薬の医師主導臨床研究であるSIGN研究に関する社外調査委員会」(委員長:原田國男氏)がまとめた報告書を踏まえ、決定するという。
◎医師主導臨床研究への支援を一時的に中断
今後の再発防止策として、管理職を含む全社員を対象に3回目となる再発防止の必須研修を実施。臨床研究支援についてのグローバルポリシーを理解してもらうという。ただ、これまで臨床研究をサポートしていた経緯がある社員に対しては、急な行動の変容が必要であることから、「マネジメントの人間が社員と一緒に行って説明する」など管理職のサポートも必要との考えを示した。
同社はまた、2011年以降に実施された過去3年間の医師主導臨床研究について、第三者による調査を実施中であることも明らかにした。調査は2月初旬に開始し、今夏に完了する予定。調査が完了し、全社員がグローバルポリシーを理解するまでの間、日本における医師主導臨床研究に対する支援を一時的に中断することも同日報告した。
新経営陣の略歴は以下の通り。
◆ノバルティスホールディングジャパン株式会社 代表取締役社長
マイケル・フェリス氏(63歳)
国籍:イギリス
2005~10年ノバルティス ファーマ株式会社開発部長、定年後は同社アドバイザー(前職)。
◆ノバルティス ファーマ株式会社 代表取締役社長
ダーク・コッシャ氏(50歳)
国籍:ドイツ
2001年ノバルティス入社。グループ戦略立案担当のほか、ドイツ、スイス、アイルランドの社長を歴任。前職は、ノバルティス ファーマEGM(新興成長市場)オンコロジー事業部門責任者。
◆ノバルティス ファーマ株式会社常務取締役オンコロジー事業本部長
フランシス・ブシャール氏(51歳)
国籍:カナダ
主にコマーシャルやマーケットアクセス並びに臨床開発を統括。前職は、ノバルティス ファーマ アジアパシフィックおよび南アフリカ オンコロジー事業部門責任者。
ノバルティス:社長ら役員3人辞任 スイス本社主導で一新 04/03/14 (毎日新聞)
製薬会社ノバルティスファーマの社員が自社薬の臨床試験に関与していた問題で、スイス本社のデビッド・エプスタイン社長が3日、東京都内で会見し、日本法人の二之宮義泰社長ら役員3人の辞任を発表した。スイス本社主導で経営陣を一新し、再発防止などコンプライアンス(法令順守)の向上を図る。
辞任したのは二之宮社長のほか、浅川一雄常務、持ち株会社ノバルティスホールディングジャパンの石川裕子社長。同日付でノ社の新社長にドイツ法人社長などを歴任したダーク・コッシャ氏、持ち株会社社長にはマイケル・フェリス氏が就任した。記者会見に二之宮氏らは出席しなかった。
昨年、降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験疑惑が発覚。さらに、会社が定めた再発防止策を破って、営業社員らが別の臨床試験に不適切な関与をしていたことが今年1月に発覚していた。
ノ社は2011年以降に同社が関与した全ての臨床試験の第三者調査を始めたことを明らかにし、「別の臨床試験の問題が明らかになる可能性がある」と説明している。調査は今年夏ごろに終える見通しで、調査の間は、国内で医師が企画した臨床試験に対する支援をすべて一時的に中止する。【八田浩輔】
製薬会社丸抱えの研究だ…ノバ社問題調査委 04/02/14 (読売新聞)
東京大病院など22病院が行っていた白血病治療薬の医師主導臨床研究に販売元のノバルティスファーマ社の社員が関与していた問題で、弁護士でつくる同社の社外調査委員会は2日、報告書をまとめ、「薬の販売促進を狙いとする『製薬会社丸抱えの研究』だった」などと批判した。
報告書では、ノバ社が研究に関与した背景として、売り上げに苦戦している白血病の新薬の販売促進につなげたいという思惑があったと指摘。計23項目も問題行為があったと認定し、営業部長ら上司もかなりの部分で状況を把握しており、責任は重いとした。
問題の臨床研究は、従来の薬と新薬の副作用の差を調べるもの。カギとなる副作用の評価を行う調査票は本来、医師が記入すべきだが、一部の社員は代筆していた。データの改ざんは行われていなかったが、調査委の原田国男委員長は「倫理性にかかわり、極めて不適切」との見解を示した。
ノバルティス白血病試験:副作用、国に報告せず (1/2)
(2/2) 04/02/14(毎日新聞)
製薬会社ノバルティスファーマの社員が自社の白血病治療薬の臨床試験に関与していた問題で、ノ社の社員が不正に取得した患者の個人情報の中から、重い副作用があったことを把握しながら国への報告義務を怠っていたことが分かった。昨年末に報道関係者がノ社の試験への関与について取材を始めた後、問題の発覚を恐れた営業担当社員が、証拠になる資料を会社から自宅に持ち帰ったり、電子データを削除したりする隠蔽(いんぺい)工作をしていたことも判明した。【河内敏康、清水健二】
ノ社の社外調査委員会が2日明らかにした。報告書は副作用の報告を怠ったことを「薬事法違反の可能性がある」と指摘した。
調査委は、元裁判官、元検事、元厚生労働事務次官の弁護士3人で構成。2月から会社幹部ら関係者に事情を聴いてきた。臨床試験について、元裁判官の原田国男委員長は「いわば製薬会社丸抱えで、非常に問題だ」と厳しく批判した。
報告書によると、社員は、患者データが記載されたアンケートを医師に代わって回収・保管していた。その過程で、臨床試験で重い副作用が患者2人に出たことを把握したが、国に報告しなかった。薬事法は製薬会社が自社製品で死亡や重篤な副作用事例が出たことを知った場合、15〜30日以内の報告を義務付けており、違反は改善命令の対象になる。ノ社は報告書を受け、2日になってこの副作用情報を国側に報告した。
臨床試験の副作用に関しては、本来は医師が記入すべき重篤度の評価票を、社員が医師の指示で記入していたことも発覚し、調査委は「倫理的に極めて不適切だ」と批判した。
また、患者に無断でアンケートを回収したことについて「個人情報保護法違反の可能性が高い」とした。
隠蔽工作は昨年12月末以降に行われていた。社員が試験関係の資料を会社から自宅に持ち帰り、シュレッダーにかけたり、電子ファイルを削除したりして廃棄。東日本営業部長が資料廃棄を促す発言をした疑いもある。事務局を務めた東大医師も今年1月以降、社員がアンケート回収に携わっていなかったことを装う工作を、試験に参加した医療機関に依頼していた。
◇社員関与の証拠隠蔽も
一連の行為は、降圧剤バルサルタンの臨床試験疑惑発覚に伴い「社員を臨床試験に関与させない」との再発防止策を公表した後も続いていた。報告書は「防止のための社内ルールがなく、今も明文化されていない」と変わらぬ企業体質を批判した。原田委員長は「(バルサルタン問題に)適切に対応していれば今回の事態に至らなかった可能性がある。反省が生かされなかった」と語った。
◇白血病治療薬の臨床試験問題◇
22医療機関の医師が参加した白血病治療薬の副作用を調べる臨床試験が2012年5月に始まった。この試験に、ノバルティスファーマの営業社員らが、降圧剤バルサルタンの臨床試験疑惑の反省から会社が定めた再発防止策を破って関わっていたことが今年に入って発覚。学会発表のデータ解析をするなど試験に全面的に関与し、ノ社は新薬ニロチニブ(商品名タシグナ)の宣伝に利用していた。研究チーム事務局がある東京大病院は3月、医師が集めた患者アンケート255人分のコピーがノ社側に漏えいしたことを公表し、個人情報保護法に反する行為として謝罪した。
復興の名目で国民から税金を徴収し、無駄遣いを行う。デタラメ浪費を止めるためには復興をスローダウンするしかない。復興を望む人達も自分達が利用されている事に気付くべきである。
経費だけで900億円!随意契約で膨らむ原発賠償金の実態 04/01/14 (日刊ゲンダイ)
東京電力が、原子力損害賠償支援機構から福島原発事故の賠償資金として交付された金額が今月下旬の時点で計3兆6870億円に達した。
このうち、被災者に支払われた賠償金は約3兆5700億円余り。残り約1200億円はどこに消えたのか。そこで会計検査院が昨秋に公表した賠償業務の経費を調べてみると、驚いた。ナント、被災者に1円も渡らない経費だけで、計899億円(11~12年度)も支出していたからだ。
なぜ、こんなに浪費しているのか。答えは簡単だ。対応業務を請け負う人材派遣会社との契約が、競争入札で決めるのではなく、“言い値”のまま結ぶ「随意契約」だからだ。契約の内訳を見ると、1億円以上の38件(838億円分)のうち、実に37件(820億円分)は随意契約だった。
■派遣3社で数千人体制
賠償業務を行う現場は、東京・有明のセントラルタワー。ここで、東電と直接、雇用契約を結んでいる東電子会社で派遣会社の「キャリアライズ」と印刷系の「トッパン・フォームズ」のほか、トッパン経由の派遣3社が業務を請け負っている。勤務態勢は数千人規模。これだけ人手があれば、すでに賠償業務を終えていてもおかしくないが、なぜか進まない。業務が長引くほど派遣会社の“ウマミ”は多くなるからだ。
派遣各社の決算を見ると、売上高や利益の対前年比率が、会計検査院が公表した賠償経費の増加率と一致しているのは偶然とは思えない。
13年度分の経費公表は今秋だが、おそらく1000億円は超える。会計検査院も増え続ける賠償業務の経費を把握し、問題視しているようだが、本気で改善を求める姿勢は感じられない。復興予算のデタラメ浪費は続き、被災者はないがしろにされていくばかりだ。
(取材協力=ジャーナリスト・宮田賢浩)
小保方氏のSTAP細胞の発表関連が注目を受けているが、この世界、いろいろあるようだ。
国立環境研究所30代女性研究者らの捏造疑惑について 02/13/14(世界変動展望)
特定領域研究:タンパク質分解による細胞・個体機能の制御
論文3本に不正、筑波大教授退職 画像を改ざん 04/01/14 (朝日新聞)
筑波大は31日、生命環境系の柳澤純教授(50)と村山明子元講師(44)が執筆した論文3本に、画像を改ざんする不正が見つかったと発表した。処分について「厳正に対処する」としている。柳澤教授は一身上の都合を理由に同日付の退職届を出し、受理された。
発表によると、3本の論文は、2人が筑波大にいたときに書いた。分子生物学関連の内容で、2006~08年に米科学誌セルなどに発表された。これらに使われた四つの画像について、切り貼りなどをしていた。本文の盗用は確認されなかったという。
2人は、論文不正の問題が指摘された東京大分子細胞生物学研究所の加藤茂明元教授の研究室に所属した経歴がある。
東大教授を解雇…受験の知人から祝儀受け取る 03/31/14 (読売新聞)
東京大学は31日、同大大学院入試を受験した知人から100万円を受け取ったとして、50歳代の男性教授を諭旨解雇の懲戒処分にしたと発表した。
3月28日付。教授は同大の調査に事実関係を認め、退職届を提出した。
発表によると、教授は2010年夏頃、教授就任の祝儀の名目で、大学院入試の受験を希望していた知人から100万円を受領。その後、教授の所属する研究科を受験する意向を伝えられたにもかかわらず、返還しなかった。さらに、翌11年秋の入試なら優遇できると受け取れる内容のメールを出すなどしたが、同年の入試の出願時期になると、「受け入れるのは難しい」などと態度を翻した。
教授は11年秋、口述試験で試験委員として質問し、採点に関わったが、知人は不合格となり、12年6月、学内のハラスメント防止委員会に訴えた。同大は「教授は入試で便宜を図っていない」などとして刑事告発は検討していないという。
保線費1500万円水増し JR北海道の子会社幹部 03/31/14 (産経新聞)
JR北海道は31日、保線業務を担う子会社「北海道軌道施設工業」(札幌市)の元札幌出張所長が水増しした外注費を下請け業者に還流させ、約1千万円を私的に使っていたと発表した。水増し額は計約1500万円に上り、下請け業者が見返りとして約500万円を受け取っていたという。
JR北海道の保線経費が不正流用されていたことになり、記者会見したJR北海道の小山俊幸常務は「親会社として指導・監督する立場から責任を痛感している。深くおわびしたい」と述べた。
JR北海道によると、平成17年4月~18年3月ごろ、元所長は下請け業者(北海道苫小牧市、倒産)に工事の代金を水増し請求するよう指示。軌道施設工業が余分に支払った代金を下請け業者から還流させていた。
元所長はうち1千万円を私的に使ったり、ビール券を購入してJR北海道の保線担当部署に配ったりしていたという。
日本トップリーグ機構元職員、着服2450万円 03/28/14 (毎日新聞)
球技9競技12団体で組織する日本トップリーグ機構(JTL=会長・森喜朗元首相)の元女性職員による横領問題で、JTLは28日、着服金額が2450万円だったと発表した。
発表によると、着服は2012年5月に発覚。13年3月、失踪した元女性職員の家族が全額弁済した。対応に当たった総務担当理事は、2020年東京五輪・パラリンピック招致成功後の同年9月、会長など他の役員に報告した。31日のJTL社員総会、理事会で責任問題が討議される。
医薬品広告:臨床試験疑惑受け規制見直し検討 厚労省委 03/27/14 (毎日新聞)
降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験疑惑で、厚生労働省の有識者検討委員会は27日、医薬品の広告に関する規制を見直すよう、国に求めることを決めた。製薬会社ノバルティスファーマが、臨床試験を引用した広告で薬の売り上げを伸ばしていたことが、データ操作発覚後の医療現場の混乱を大きくしたため。厚労省は研究チームで対策の検討に入る。
検討委は昨夏以降、疑惑の解明と対策の検討に取り組んできた。昨年9月に公表した厚労相への中間報告に広告を巡る課題を追加し、報告書をまとめた。
薬の広告を巡っては、薬事法で誇大広告が禁じられているものの、広告のために臨床試験が実施されたり、データが操作されたりする事態は想定されていなかった。欧米では広告の事前審査をしている国があり、報告書は「(厳しい規制がある)欧米の事例を参考に広告の適正化策を検討すべきだ」と指摘した。
一方、業界団体「日本製薬工業協会」は、臨床試験をする研究機関に利害関係がある会社が奨学寄付金を渡すことはやめ、会社側が費用負担する場合は、研究機関と委託契約を結んで透明性を高めることを検討委に報告した。【河内敏康、八田浩輔】
ノバルティス臨床データ改ざん問題 厚労省、最終報告書まとめ 03/28/14 (FNNニュース)

製薬会社「ノバルティスファーマ」の高血圧治療薬の臨床研究をめぐるデータ改ざん問題で、厚生労働省は、「会社として関与していたと判断すべき」とする最終報告書をまとめた。
厚労省の検討委員会は、ノバルティスファーマや、大学関係者への聞き取り調査の結果、「研究に関わった元社員一個人というより、実態としては、会社として関与していたと判断すべき」とする最終報告書をまとめた。
また、強制力のない検討委員会の調査では限界があることから、刑事告発し、捜査当局に実態解明を委ねることなどが盛り込まれた。
素人の判断であるが、とんとん みずき橋(木 の 構 造 物)
の写真を見る限り、25年間手入れ不要の建築物には見えない。造りも簡単に見える。コンクリートの地面からの高さも低い。
金の無駄遣い。長くもたせるなら見た目だけ木の橋にすれば良かったと思う。
「25年手入れ不要」の木橋…10年で腐って撤去 千葉 03/27/14(朝日新聞)
25年間手入れ不要と言われた木造橋が10年ほどで腐食し使えなくなった、として、千葉県野田市は26日、橋を同市に無償譲渡した都市再生機構(UR)を相手取り、再建築を求める訴訟をおこすと発表した。橋は現在、主橋梁(きょうりょう)部が撤去され、利用できなくなっている。
木造の「とんとんみずき橋」は、UR(当時は住宅・都市整備公団)が1998年、同市みずき地区に設置した歩行者用の橋で、全長194メートル、幅4~6メートル。市道をまたいで住宅地同士を結び、当時は木造橋としては日本で2番目の長さと言われた。
アフリカ産のボンゴシ材を使い、同市によるとURから「25年間、手入れする必要はない」との説明を受け、2002年に譲り受けたという。しかし同市の点検・調査で、06年には一部腐食が見つかり、10年にはすべての主桁で断面の30%が腐食していることが分かった。そのため、同年には橋が全面通行止めとなり、翌11年7月、主橋梁部64メートルをURが撤去した。
木造橋が地域のシンボルだったため、同市はURに再建築を求めてきたが、URから「法的責任を負うべき根拠がない」との回答が寄せられ、訴訟に踏み切った。訴えでは、再建築のほか、市が支出した維持管理費476万円も請求する。
根本崇市長は、橋の譲渡前の1999年に、愛媛県でボンゴシ材を使った木造橋が腐食、落下した事故があったことに触れ「URは、問題があることは分かっていたはずなのに、25年は手入れ不要との説明のままだった」と批判する。
一方、URは「橋が使用できない状態であることは、遺憾に思っている。市が行う法的措置に適切に対応したい」とコメントしている。
盗品の衣服運んだ疑い、ベトナム航空客室乗務員を逮捕 03/26/14(News i)
ベトナム航空の客室乗務員が、大手衣料品店で盗まれたジャケットを盗品と知りながら運んだとして、警視庁に逮捕されました。警視庁は、ベトナム航空の客室乗務員らが盗まれた品物を頻繁にベトナムに運んでいた疑いがあるとみて、捜査しています。
逮捕されたのは、ベトナム航空の客室乗務員、グエン・ビッチ・ゴック容疑者(25)です。グエン容疑者は去年9月、ユニクロのジャケット21着、12万6千円相当が盗まれたものであることを知りながら、大阪府内から関西国際空港まで運んだ疑いが持たれています。グエン容疑者はジャケットを手荷物としてベトナム航空の飛行機に乗せて、ベトナム本国に運搬していました。
警視庁によりますと、グエン容疑者は、仲介人のグエン・ゴック・ガ被告から盗品を運ぶよう依頼されていましたが、このグエン・ゴック・ガ被告はベトナム人の窃盗グループが盗んだ高級化粧品や医薬品などを仲介していたとみられています。
グエン容疑者は『盗品とは知らなかった』と容疑を否認する一方で、『多くの同僚が小遣い稼ぎでやっている』と供述しているということです。
警視庁は、ベトナム航空の副機長らが関与していた可能性があるとみていて、ベトナム航空の日本支社を家宅捜索して、実態解明を進めています。
昔、外国人の知り合いにベトナムで仕事を取りたかったら贈賄が必要だと言われた事がある。そんなことまでして仕事なんか取らなくても良いと思い、ベトナムは諦めた。今でもそうなんだ!
ODA贈賄疑惑、ベトナム鉄道公社が3人停職 03/24/14(産経新聞)
【バンコク=永田和男】鉄道コンサルタント会社「日本交通技術(JTC)」(東京)による政府開発援助(ODA)事業に絡んだ不正なリベート提供疑惑で、ベトナム鉄道公社は、提供先とされたプロジェクト管理事務所のグエン・バン・ヒエウ所長と、同氏の上司に当たるプロジェクト担当の公社幹部3人を停職処分とした。
ベトナムの国営各メディアが24日報じた。
鉄道公社のチャン・ゴック・タイン総裁は23日、読売新聞が報じたJTCのリベート支出疑惑を受けて緊急会議を招集し、ヒエウ氏の停職と問題の調査に当たるチーム発足を決めた。24日には、タン運輸相の指示で、関係する上司も10日間の停職にして事情を聞くことが決まった。
キヤノン系の「通販工房」が破産 前社長が独断で債務保証や手形処理 03/24/14(産経新聞)
キヤノンは24日、孫会社「通販工房」が先週、東京地裁に破産を申し立てて、手続き開始が決まったと発表した。現時点で同社が把握している負債総額は24億円だが、さらに膨らむ可能性もあるという。
平成19年10月設立で資本金3000万円。キヤノン系列の「キヤノン電子」が54.1%の株式を保有する子会社。自然食品、健康食品などの通販商材の卸販売やコンサルティング業務を行なっていた。23年12月期の売上高は約8億円。
キヤノンの発表によると、通販工房の前社長がキヤノン電子に対し、自らの違法行為を申告。これを受けて社内調査をしたところ、通販工房名義で独断での債務保証や手形の裏書きを行う等を行っていたことが判明した。
キヤノンは資金の使途を含めて事実の全容を把握することができず、負債額が膨らむ可能性が高くなったことを受けて、「破産管財人による事実の確認、負債額の確定、残余財産の公平な分配を図るため、やむなく破産手続の申立てに至った」と説明している。
処方薬横流し、数千万円着服…卸売複数社員 03/23/14(読売新聞)
千葉県の調剤薬局が処方薬を現金問屋に横流ししていた問題に絡み、横流しに社員が関与していた医薬品大手卸売会社「アルフレッサ」(東京都千代田区)の別の複数の社員が、病院などに納入する処方薬の一部を無断で現金問屋に横流しし、代金を着服していたことが関係者の話でわかった。
社員らが不正に得た代金は昨年までの数年間で数千万円に上る。同社側は病院などに被害を弁済しているという。
横流し問題では、調剤薬局「岩波薬局」(千葉県習志野市)が、アルフレッサから処方薬を過大に仕入れ、過大分の薬を現金問屋に横流しして得た売却代金計約1億円を裏金としてプールしていたことが、東京国税局の税務調査で判明。現金問屋への薬の持ち込みは、アルフレッサの社員が引き受けていた。
関係者やアルフレッサ幹部によると、横流しに関与した社員とは別の複数の社員が、病院などに薬を納入する際、薬の一部を無断で東京・神田の現金問屋に売却。総額数千万円の代金を着服していたという。
がんセンター元科長を告発、研究費私的流用疑い 03/22/14(読売新聞)
国立がん研究センター(東京都中央区)は、中央病院の牧本敦・元小児腫瘍科長(46)が国の研究費約549万円を私的流用したとして、業務上横領の疑いで警視庁に刑事告発したことを明らかにした。
センターによると、告発は19日。牧本元科長は2007~08年度、厚生労働省から計約2億2000万円の研究費を受け取り、物品納入業者に架空発注して代金を過大に払い、その分を不正にプールする「預け」の手法で、裏金約2570万円を作ったという。
このうち刑事告発の対象となったのは約549万円分で、09年1月~11年5月に、私物のエアコンやテレビなどの代金に充てた疑いがある。センターは昨年2月、牧本元科長を懲戒解雇したが、その際に、この私的流用分は返還されたという。
何処までが事実なのか知らないけど芸能界って恐ろしいところだ。どの世界も奇麗事だけでは成り立たないのはなんとなく想像できるけど。この恐ろしさが逆に力を持ってしまえば都合か良いシステムなのかもしれない。勝ち組と負け組。学校ではこのような現実を一切教えない。
周防郁雄社長の元・用心棒が街宣再開! バーニングをめぐる暴力団・テレビ局との癒着、枕営業の実態を告発 (1/2)
(2/2) 03/21/14(日刊サイゾー)
芸能取材歴30年以上、タブー知らずのベテランジャーナリストが、縦横無尽に話題の芸能トピックの「裏側」を語り尽くす!
動向を継続的にお伝えしている「大日本新政會」による、バーニングプロダクション糾弾活動だが、久しぶりに動きがあった。
大日本新政會総裁で、二代目松浦組組長の笠岡和雄氏は、かつて“芸能界のドン”バーニングプロの周防郁雄社長の“用心棒”を務め、さまざまな裏仕事をこなしていたが、新規事業をめぐる金銭トラブルが発生し、3年前に両者の関係は破綻。以来、大日本新政會はホームページを通じて、周防氏のスキャンダルを次々と告発してきた。
その内容といえば、用心棒だからこそ知り得た、暴力団やテレビ局との癒着ぶりや枕営業の実態など衝撃的なものばかり。例えば、かつてバーニングに所属していた水野美紀が独立した際、周防氏が彼女を潰そうと画策していた件や、NHKプロデューサーに対する肉欲接待の実態、さらに、みのもんたが社長を務める水道メーター製造販売会社「ニッコク」が談合事件で右翼から街宣車で抗議行動を受けた際、笠岡氏にトラブル処理を依頼し、大物の暴力団幹部が動いた件などだ。
さらに昨年夏には、「週刊文春」(文藝春秋)が、このブログの情報を元に、NHKプロデューサーやみのの件を大々的に報道した。特に、NHKプロデューサーへの肉欲接待報道は、モーニング娘。のメンバーが駆り出されていたという衝撃的なものだったが、バーニングの影響下にある他のマスコミは沈黙。しかし、多くの芸能関係者が、新政會の動向を注視していた。
その後、新政會はバーニングの事務所をはじめ、同プロと関係が深いNHKなどのテレビ局に対して街宣車で繰り出し、糾弾活動を始める。対するバーニング側は、街宣活動の一部を規制する仮処分や、ホームページの掲載差し止めの仮処分を裁判所に申し立て、対抗してきた。
結果、昨年12月頃から、ホームページに関しては、新政會が新しいサーバに移行しては、それに対してバーニング側が仮処分の申し立てをするというイタチごっこの状態が続いていたために、ホームページの公開を一時休止。街宣活動については、特定の暴力団関係者を刺激するのを避けるため、しばらく全面的に停止し、静観することにしたという。
このように糾弾活動が収束したことで、メディア関係者の間では「新政會とバーニングの間で手打ちが行われたのでは?」「手打ちに当たっては、裏社会の実力者と数億円に及ぶ大金が動いたようだ」「大金の原資は、昨年末の日本レコード大賞をEXILEに受賞させるためにエイベックスからバーニングに渡った“プロモーション費”」などなど、具体的だが、にわかに信じがたいウワサが数多く流れた。また、ある右翼団体関係者によると、「実際に、バーニング側には『新政會と話をつけてやる』と仲介を申し出て、金銭を求める勢力もあった」とされる。
だが、新政會の幹部はこう言い切る。
「周防との手打ちなんてありえないよ。そんな話もこちらに来ていないし、金なんて一銭ももらっていない」
実際に新政會は、停止していたホームページを3月から再開。時期を同じくして、街宣活動もスタートしたのだ。
「周防を、とことん追及しますよ。3月中旬から、バーニングや東京や京都のNHKなどへの街宣車による抗議行動を再開しました。新政會に対して街宣禁止の仮処分が出ているエリアについては、友好団体である『闘魂塾』が街宣活動をしています」(新政會幹部)
実際、3月半ば、渋谷のHNK周辺で闘魂塾の街宣車が抗議活動をしていた。街宣の内容は、バーニングが大河ドラマや紅白歌合戦のキャスティングに依然強い決定権を握っているというもの。局内には、暴力団との密接ぶりも明らかな周防氏を切りたがっている幹部は少なくないが、手切れに対する意趣返しとして、文春に報道されたプロデューサーのように、これまで接待を受けてきた自分たちの名前がメディアに出されてしまうのではないかという恐れを抱き、誰も反発する人間はいないというのだ。
「NHKもコンプライアンス重視を打ち出すなら、盆暮れの贈り物や過剰接待を受けることが当たり前になっているバーニングとの関係を清算すべき。籾井勝人会長を筆頭に、国民からの信頼を回復させるためにも、自浄作用が働くことを期待している」(同)
右翼団体の糾弾活動というと、きな臭いものを感じがちだが、今回、批判している内容は至極まっとうである。新政會の今後の動きに注目したい。
(文=本多圭)
丸紅が米当局に罰金90億円 インドネシアでの贈賄で 03/20/14(産経新聞)
【ワシントン=柿内公輔】米司法省は19日、丸紅がインドネシアの電力関連事業の受注をめぐる贈賄への関与を認め、罰金8800万ドル(約90億円)の支払いに同意したと発表した。
司法省によると、丸紅はフランス系企業などとコンソーシアム(企業連合)を組んで、インドネシアで電力関連のサービスを提供できる契約を獲得できるよう、同国の議員や電力会社幹部に要請。米国内のコンサルタント会社を通じ、インドネシアの銀行口座に成功の見返りとして数十万ドルが振り込まれたという。司法省のラマン次官補代行は声明で「丸紅はルールを順守せず、調査への協力も拒んだ」と指摘した。
司法省は外国政府当局者への贈賄を禁じる海外腐敗防止法違反で丸紅を連邦地裁に提訴した。
楽天:元値つり上げ割引装う 社員が指示 03/20/14(毎日新聞)
楽天の複数の社員がインターネット仮想商店街「楽天市場」の出店店舗に、元値をつり上げて割引したように見せかける不当な二重価格表示を指示していたことが19日、出店業者らへの取材で分かった。こうした表示は昨年のプロ野球日本一セールで発覚したが、社員の関与は明らかになっていなかった。
消費者に誤解を与える表示を楽天側が主導していたことになり、楽天は「事実なら看過できない重大な内規違反であり、厳正な処罰を行いたい」としている。
こうした二重価格表示は、景品表示法違反の有利誤認に当たる可能性がある。消費者庁は「事実関係を確認したい」としている。(共同)
「外交官には逮捕や起訴を免れる外交特権があり、同課は外務省を通じ任意の事情聴取に応じるよう要請している。」
日本の外交官が外交特権を使って、ある国の特定の業者と癒着しているとの話を聞いた事がある。同じストーリーだ。その国の役人とも話がついていれば問題になる事もない。おかしな話だが、これが現実。
賭博:「ガーナ大使、店出入り」 部屋入り口に表札も 03/20/14(毎日新聞)
駐日ガーナ大使が借りている東京・渋谷のビルの一室でバカラ賭博が行われた事件で、警視庁保安課に逮捕された胴元の日本人が「大使も店に来たことがある」と供述していることが捜査関係者への取材でわかった。同課は大使が報酬を得て部屋を貸し出すなど違法営業に関与した可能性もあるとみて、賭博開張図利ほう助容疑を視野に捜査している。
保安課によると、この部屋は2012年9月に前ガーナ大使が「個人事務所」として賃貸契約を結び、13年3月に現大使が契約を引き継いだ。前ガーナ大使は契約の際、不動産業者に大使の身分証明書を提示したという。バカラ賭博は12年10月から営業していたとみられ、無職の山野井裕之容疑者(35)=板橋区=ら胴元の日本人男女10人と客2人が賭博開張図利容疑などで逮捕された。
同課の調べに胴元の一部は「現大使も店に来た。大使館の施設なので捕まらないと思った」と供述。入り口には現大使の名前を書いたプレートを掲示していた。店は会員制でその会員規約にも「当施設はガーナ共和国の下でレジャー施設として運営している」との記載があるという。
外交官には逮捕や起訴を免れる外交特権があり、同課は外務省を通じ任意の事情聴取に応じるよう要請している。【林奈緒美】
奇麗事では仕事は取れない。ODAと言えば聞こえが良いが、国内企業の仕事確保のためとも言える。
ODA事業でリベート1億円支出…外国公務員に 03/20/14(読売新聞)
政府開発援助(ODA※)事業を巡り、鉄道コンサルタント会社「日本交通技術(JTC)」(東京)が2008~12年、ベトナムなど3か国で計約60億円の事業を受注した見返りに、約1億円のリベートを不正に支出していたことが関係者の話で分かった。
JTCは読売新聞の取材にリベート支出を認めた。提供先には相手国の公務員らが挙がっており、外国公務員への贈賄を禁じた不正競争防止法違反の疑いが強い。
一連のリベート支出は、東京国税局の税務調査で判明した。JTCは調査に提供先を明かさなかったため「使途秘匿金」と認定され、通常の法人税に加え、支出額の40%にあたる約4000万円の制裁課税を受けた。
結局、自分達だけが良ければ税金が効率良く使われているとか、企業の能力か質などは二の次と言う事だ!「公取委幹部は『機構幹部はOBを受け入れない業者が不利になるように指示しており、公正な競争をゆがめる行為だ』と批判した。」
本当に公平に評価を行えば、機構OBを採用する、又は、好条件で採用する理由がなくなることを意味していると思う。経験者を優遇して採用すると言っても、機構OBの全てが魅力的ではないと思う。また、企業や組織の看板があるから仕事が出来る場合がある。看板が無くなれば、普通、又は、それ以下の場合もある。それと高学歴過ぎる問題もあるだろう。高学歴や過去の役職に見合った給料を払う価値が無いと企業が判断した場合、待遇に妥協しなければ仕事が見つからない。鉄道運輸機構だけの問題ではなく、天下りがある多くの業界で同じ事が言えると思う。
鉄道運輸機構:天下り先優遇 幹部、入札で点数調整 03/19/14(毎日新聞)
独立行政法人「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」(横浜市)の幹部が、「総合評価方式」と呼ばれる入札で機構OBが再就職している建設会社が有利になるよう、部下に評価点の操作を指示していたことが、公正取引委員会の調査で分かった。公取委は19日、法令順守の体制整備が必要だとして機構に改善を申し入れた。
総合評価方式は入札に参加する業者の技術力や実績を点数化して評価し、落札業者を決める入札方法。鉄道・運輸機構では、トンネルや橋など施工に工夫の余地がある工事に導入され、2011〜12年度に計114件が発注された。160点満点の入札が多い。
公取委によると、問題があったのは複数の建設会社が共同企業体(JV)を組んで参加する入札。機構役員らは、JV内で規模が2番目に大きい会社にOBが再就職していない場合、そのJVには最高点をつけないよう部下に指示していた。一番規模の大きい会社にはOBがいることが多く、2番目の企業に着目したとみられる。
北陸新幹線の融雪設備工事の談合事件の調査の過程で、指示を示す資料が押収されたという。さらに、公取委が昨年11月に機構本社を初めて家宅捜索した際、職員がOBの再就職に関する書類を別の場所に隠したり、電子メールを消去したりしていたことも判明した。
また公取委は19日、北陸新幹線の談合事件で起訴された2人を含む機構幹部3人が、業者側に入札の予定価格を教えていたとして、官製談合防止法に基づいて機構に改善措置を要求した。他の工事でも職員が予定価格を業者に教えていたケースが複数確認されたという。
鉄道・運輸機構は「極めて遺憾で深くおわびする。第三者委員会を設置し、事案の背景を分析したい」とのコメントを出した。【古関俊樹】
若い世代が3Kの建設業を避けているのも理由なのでは??勉強を怠り、知識や能力を習得しなければ、3Kと思われる仕事でも働くように教育の場でも教えるべきではないのか。学校で平等とか言っても、社会に出れば平等ではない。景気が悪ければ短期間の職業訓練などで仕事など見つからない。国会の答弁のようには現実は簡単でない。勉強が嫌なら、根性や体力だけでも身に付けさせるべきだろう。そうでなければ3Kの仕事は続けられない。賃金を上げたら景気が良くなるとか言っているが、賃金を上げたら製品価格を上げないと、どこかに歪がでるか、製品が売れなくなる。国際競争にさらされる製品であれば価格を無視する事は出来ない。消費者が購入判断をするからだ。外国人を使えば使うほど、国内のお金が日本から出て行く。企業の経営者は企業の利益が出れば、日本人に給料を払おうと、外国人に給料を払おうと気にしないだろう。しかし良く考えないと仕事がない人々が増え、生活保護受給者が増えると、労働者の負担が大きくなる。国は増税だとか、財政問題との理由で国民へのサービスの質を下げれば良いだけ。政府の行き当たりばったりの対応を放置しておくと絶対にしわ寄せが来る。
外国人実習生制を拡大…政府検討 03/19/14 (読売新聞)
建設業、五輪・復興で人手不足
政府が建設現場の人手不足に対応するため、外国人技能実習制度を活用することを検討している。
2020年の東京五輪・パラリンピック開催までの特例措置として、実習期間(最長3年)を延長することや実習生拡大などを視野に、月内にも対応策をまとめる。ただ、実習生の労働環境の改善などが先決とする慎重論もあり、政府内で綱引きが続いている。
外国人技能実習制度の活用は、今年1月に開かれた関係閣僚会議で、菅官房長官が「東京五輪・パラリンピックに向けて人材がより不足する恐れがある。期間内に確実にやり遂げなければならない」と述べ、本格的な検討が始まった。
政府が危機感を抱くのは、景気回復や東日本大震災の復興加速化により、建設現場ではすでに人手不足が深刻化しているからだ。
08年のリーマン・ショックによる相次ぐ建設会社の倒産や高齢化で、建設業の就業者は、ピーク時の約685万人(97年)から、13年には約499万人と3割近く減少した。とび職や左官など技能労働者の数は震災前の11年1月には、必要な人数とほぼ均衡していたが、今年1月には2%程度の不足に陥っている。政府は景気回復が進めば、事態はさらに深刻化する可能性があるとみている。
こうした中、首相官邸や国土交通省が目を付けたのが、働きながら技術や知識を身につけてもらう外国人技能実習制度だ。現在、国内には建設業だけで実習生が約1万5000人おり、対象者や実習期間を拡大すれば、技能労働者不足の緩和につながると考えている。
ただ、実習生に関しては一部で賃金不払いや不当解雇など劣悪な労働環境が問題として指摘されており、法務省や厚生労働省も実習制度の対象拡大に慎重な姿勢を崩していない。法務省は代わりに、研修を終えた技能労働者の入国や在留を、法相が指定する特定活動として、認めることも検討している。
群馬建協が慎重論提言/外国人材拡大は両刃の剣/「国内若年者確保が本筋」 03/19/14 (建設通信新聞)
「外国人労働者の拡大は両刃の剣。悪影響は最小限に」--。中長期的な建設産業の担い手確保が大きな課題となる中、政府が議論を進める外国人労働者受け入れ拡大について、群馬県建設業協会(青柳剛会長)が実施した会員アンケートでは「大いに賛成」「賛成」合わせて37%が賛意を示す一方、その大半の企業が拡大策に対する意見記述では慎重な姿勢を見せている。こうした結果を踏まえ、同協会では外国人技能実習制度の改正に向けた議論に対し、「改正の影響を多面的に考えて慎重に行うべきだ」と求めている。慎重論が根強いのは、大都市圏以上に担い手確保が難しい地方業界の本音が浮き彫りになった形だ。 =関連2面
外国人技能実習制度改正をめぐる議論に対し、地方建設業界が意見を集約・表出したのは今回が初めて。
青柳会長は、19日に開かれる自民党政務調査会・外国人労働者等特別委員会に出席し、調査結果を踏まえて問題提起する。
同建協は、外国人材活用と若年者の採用・育成をテーマとした会員アンケートを2月に実施。提言・要望も盛り込んだ『外国人材(外国人労働者)活用等に関するアンケート調査報告書』としてまとめた。18日に群馬県庁で会見した青柳会長は「担い手対策がいま一番の課題であり人材確保に正面から向き合う大切な時。外国人材活用について地域やプロジェクトごとにさまざまな考え方があるが、地方の業界の意見、要望を丁寧に説明していきたい」と語った。
さらに、外国人材活用拡大による労務単価の下落などを懸念した上で「いま問われているのは生産性の上がるものづくりの視点」との考えも示し、生産性向上と連動して担い手確保策を具体化する必要性を指摘した。
アンケートを通して担い手対策のあり方を問題提起した背景には、発注者の責務として中長期的な担い手の確保促進を位置付けた「公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)」の改正を含め、国内の若手人材の確保・育成を推進する前向きな流れを確かなものにすべきとの強い思いがある。東京五輪の需要を見込んだ時限的な緊急措置として検討中の外国人技能実習制度の改正が「両刃の剣」となり、こうした前向きな流れを停滞させないか、危機感を示した形だ。
提言では外国人材の活用は、担い手対策の1つとする一方、言葉や習慣の違い、期間雇用による弊害など課題も多く、「目先の労働力の過不足ではなく、人口減少社会に向けたわが国の将来ビジョンと総合的・中長期的な施策展開の中での検討が必要」と結論付けた。
同建協は担い手対策に必要な取り組みとして、人手不足・インフレの時代に適合した入札制度の制定、災害列島とグローバルな経済活動を踏まえた社会インフラの整備、建設投資額の中長期的展望などを挙げ、若者にとって一生を託せる魅力ある産業に再生する必要性を強調している。
[ 2014-03-19 1面]
増える工事、減る若手職人…建設業で人手不足 02/03/14 (読売新聞)
国交省、賃金・社会保険の改善促す
建設現場で人手が足りなくなってきた。
建設業で働く人の数がピーク時の約4分の3に減る一方、景気の持ち直しや2020年の東京五輪・パラリンピックをにらんで、工事の量が増えているからだ。
■現場に70歳
国土交通省の調査によると、建設現場で必要な職人の数に対する足りない人数の割合は、13年平均で1・6%となり、比較可能な1993年以降で最も高くなった。特に、「10年でようやく一人前になる」(建設業関係者)という型枠工やとび工の不足が目立つ。
十分な数の職人を当面、確保できないと見ている企業も、全体の3分の1以上を占めている。70歳以上の職人が働いているケースも少なくないといい、建設業界の労働組合である全国建設労働組合総連合は「足場が悪い現場もあり、無理をしてもらっているのが現実」と指摘する。
ある住宅メーカーは「工事のたびに大工を探している。このまま下請けが疲弊すれば、家の引き渡し時期に影響する」と懸念している。
■復興需要
建設業界で働く人の数は12年の平均で503万人と、ピークだった97年(685万人)より26%減った。仕事のきつさに賃金が見合わない、というイメージが強く、若者の数が減っているからだ。文部科学省の学校基本調査によると、11年に高校や大学を卒業して建設業に就職した人は約3万2000人と、97年の約7万人から半分以下に落ち込んだ。
バブル崩壊後の長引く不況によって工事が減り続けたことで、仕事から離れる人も多くなっている。下請け業者の6割弱が社会保険に加入していないなど、福利厚生が十分でないことも、建設業離れを加速させている。
一方、建設投資額は11年度の約42兆円で底打ちした後、増加基調に転じた。東日本大震災の復興需要に加えて、景気回復に伴うマンション建設などが増えているためだ。
今後も、東京五輪に向けて競技場を造ったり交通網を充実させたりする工事が増えるだけでなく、高度成長期に造られて古くなった道路や橋などを改修する必要もある。働く人が少ないにもかかわらず、工事が増えていけば、不足感はさらに強まりそうだ。
■女性活用も
こうした事態を受けて、国土交通省は、職人の待遇改善に力を入れている。
公共工事に携わる職人の賃金の目安となる「労務単価」を、2月から全国平均で7・1%引き上げて1日当たり1万6190円とした。昨年4月にも15・1%上げており、年度内に2度引き上げるのは異例だ。社会保険に加入していない会社には、国の工事を請け負わせないようにして、職人が集まりやすい環境をつくる。さらに、高校や専門学校での授業や就業体験などを通じて、建設業の魅力を若者に伝えることなども検討する。
中長期的には、これまで遅れていた女性の活用を進めることや、即戦力となる外国人技能実習生の受け入れ拡大なども検討課題となる。ただ、技術力のある職人を育てるには、ある程度の時間がかかるため、これらの対策が当面の人手不足解消につながるかどうかは不透明だ。(山本夕記子)
自由競争で航空券が安くなるのは良い。しかし、LLCで安全面に影響するまでの競争に行ってしまうと思う。事故が起こらなければ安全面対するコスト削減に対して経営陣や現場は慣れているだろう。しかし今回の事件に関する報道は何かがおかしい気がする。
マレーシア航空、旅客機不明事故が財務に追い打ち 03/11/14 (読売新聞)
マレーシア航空の運航するMH370便が消息不明となったことで、既に大幅な赤字に苦しむ同社の財務状況が一段と悪化しそうだ。
アジアで格安航空会社(LCC)の参入が相次ぐ中、マレーシア航空は特に大きな痛手を被ってきた。サービスの質の高さでは定評を得ているものの、クアラルンプール発着便を主力とする東南アジア最大のLCC、エアアジアとの競争に苦戦している。
香港の旅行代理店パッケージ・ツアーズは、一部の顧客からクアラルンプールに向かう便をマレーシア航空から変更するよう要請を受けたことを明らかにした。ただ、パッケージ・ツアーズのコンサルタント、ニン・ユエン氏は「顧客の大半は引き続き理性的で、別の航空会社で座席が確保できなければマレーシア航空で予定通り旅行することに合意している」と述べた。
ナスダックに上場する中国のオンライン旅行代理店Cトリップ・ドット・コム・インターナショナルは、予約のキャンセルや変更を希望する中国人旅行客はあまり多くないと説明。Cトリップの広報担当者は「事故前と後でキャンセル率に大幅な変化はない」と語った。
しかし、ほんの10年前にはアジア市場でほとんど存在しなかった格安航空会社が幅を利かせ始めて以来、マレーシア航空の事業見通しは暗雲が立ちこめたままだ。カリスマ性あふれる米音楽大手ワーナー・ミュージック・グループ元幹部が率いるエアアジアの成功で、今では東南アジアの航空旅客の半分以上をLCCが運ぶ。
マレーシア政府系投資会社カザナ・ナショナルが69.4%出資するマレーシア航空では、最近ビジネスクラス以上の需要が増え、ようやく見通しが上向いてきたところだった。だが過去3年間は連続して赤字。2013年の乗客数は1720万人へと28.5%増加したものの、競争の激化で有償旅客キロ当たりの収入は圧迫されている。
スタンダード&プアーズ・エクイティ・リサーチのアナリスト、シュコール・ユソフ氏は「マレーシア航空は安全性(の実績)が良好で乗務員も素晴らしいが、経営陣がふさわしくない」と述べ、「この業界が何を見据えているか明確な展望がない人々だ。(中略)かなり後れを取っている」と続けた。
ユソフ氏は「財務見通しはMH370便の出来事抜きでも悲惨だ。エアアジアや高い燃料費、不均衡な競争の土台に不満をぶつけても意味はない」と話した。
マレーシア航空は、政府による経営への介入や、コスト削減策への労働組合の反発にも苦しめられている。マレーシア航空を運営するマレーシア航空システムは13年12月期通期で11億7000万リンギット(約370億円)の赤字を計上した。12年の赤字額は4億3200万リンギットで、11年には25億2000万リンギットという過去最大の赤字に沈んでいた。
どのような理由があるのか知らないが、マルナカにはがんばってほしい。いろいろな妨害や嫌がらせを考えると、なかなか手を上げれないのが現実だと思うから。
朝鮮総連、抗告申し立てへ マルナカへの売却に反対 03/18/14(産経新聞)
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)中央本部の土地建物の競売をめぐり、総連の代理人弁護士は18日、東京地裁がマルナカホールディングス(高松市)に売却を許可した場合は、執行抗告を申し立てる方針であることを明らかにした。
地裁は20日に開札をやり直した後、マルナカの書類をあらためて精査し、24日に売却を許可するかどうかの決定を出す。
昨年10月の再入札には、マルナカとモンゴル企業「アバール・リミテッド・ライアビリティー・カンパニー」が入札。アバール社が50億1千万円で落札したが、東京地裁は1月、書類の不備を理由に入札を無効とする決定を出した。
アバール社は執行抗告を申し立てたが、東京高裁が2月、棄却した。東京地裁は3回目の入札実施も検討したが、過去の判例などを踏まえ、今月12日、開札手続きからやり直すことを明らかにした。落札が確実となったマルナカ側は、総連に明け渡しを求める方針を示している。
都会とインターネットの落とし穴。インターネットは便利だ。インターネットを使って安くビジネスを始める事が出来る。
都会には多くの人がいる。都会でインターネットを利用して募集すれば簡単に人を集められるだろう。しかし、多くの人がいるから
履歴書の記載が事実か確認するも簡単ではないし、田舎のように評判を聞く事も難しい。運が悪く、悲劇が起きた。安全や安心を優先すると、コストに影響するのは常識。人材を絞れば、コストアップ。保険に加入すれば、保険料やその他の費用分だけアップ。人材の経験やバックグランドを優先させるとコストアップ。どの分野でも同じことが言える。違いは事件が起きた時に見直しが必要とされるレベルであるかどうか。
「子供2人預けたベビーシッターと連絡取れない」 03/17/14(読売新聞)
16日午後、横浜市磯子区の20歳代の女性が神奈川県警磯子署を訪れ、「子供2人を預けたベビーシッターと連絡が取れない」と通報した。
県警の捜査員が、ベビーシッターの20歳代の男が住む埼玉県富士見市のマンションを訪れたところ、2歳くらいの男児が死んでいるのを発見した。室内には一緒に預けられていた生後8か月の男児もいて、病院に搬送された。県警は男の身柄を確保しており、任意で事情を聞いているが、黙秘している。
県警幹部によると、女性は14日夕方頃、同区のJR根岸線新杉田駅付近で、30歳代の別の男性ベビーシッターに長男と次男を預け、約2時間後にこの男性ベビーシッターが、20歳代のベビーシッターに横浜駅近くで2人を引き渡していた。
女性は、インターネットのベビーシッター紹介サイトを利用して、16日まで預かってもらう予定で申し込んでいた。
架空取引:9億円疑い…商社社員100人以上関与 東京 03/14/14(毎日新聞)
空調機器など各種設備の専門商社「東テク」(東京都中央区、ジャスダック上場)の社員が、7年以上にわたり水増し仕入れ発注や架空の販売手数料の支払いなどの不正取引を繰り返した疑いがあることが分かった。不正取引への関与が疑われる社員は計111人、下請け業者などの外部協力者は約50人に上り、総額は9億円超とみられるという。
同社によると、今年2月上旬に東京国税局から「社員の一部が不適切な外注費の処理をしている可能性がある」と指摘を受け、社内調査をしたところ、水増し発注などの不正取引が判明。同月17日に外部の専門家を含む調査委員会を組織して詳しく調べていた。
調査報告書によると、不正取引への関与が疑われるのは主に営業部門の社員で、会社が設定した接待交際費の予算枠を超えた支出を賄うために始まったとみられる。水増し・架空仕入れ発注(8億2600万円)▽取引事実のない販売手数料などの支払い(3600万円)▽ルームエアコンの無断転売や自己使用(3500万円)−−などが確認された。
これらの不正取引で下請け業者などから営業担当社員に還流した金額は約8億400万円に達し、交際費だけではなく、社員同士の飲食にも充てていたと推測されるという。下請け業者にはOB経営の会社もあった。
東テクは「関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを深くおわびします」としている。【太田誠一】
本当の背景については当事者や関係者しか知らない。しかし、アメリカ留学、しかもハーバード大で何年も過ごして、「遺伝子解析の画像の加工については「『やってはいけないという認識はなかった。申し訳ありません』」は理解できない。論文や科学実験でアメリカでは常識だ。やっている人はいないとは言わない。しかし、見つかれば処分を受ける事を知らない人はほとんどいない。アメリカではモラルや倫理規定が強調される。日本では考えられないほど厳しい。だからこそこんな結末は想像できなかった。
いけないという認識なし…画像加工で小保方さん 03/14/14(読売新聞)
理化学研究所調査委員会の石井俊輔委員長らによると、小保方(おぼかた)晴子ユニットリーダー(30)はこれまで、2月20日、同28日、3月1日の計3回、聞き取り調査に応じた。
遺伝子解析の画像の加工については「やってはいけないという認識はなかった。申し訳ありません」と謝罪したという。
一方、博士論文の画像をSTAP細胞の論文に流用したことについては「昔のデータをそのまま使ってしまった」と釈明するなどしたといい、一連の問題について「単純な間違いだった」と主張しているという。
また、小保方リーダーが所属する理研発生・再生科学総合研究センター(神戸市)の竹市雅俊センター長は、10日に論文の撤回を求めた際の小保方リーダーの様子について「心身ともに消耗した状態だった。『はい』とうなずくという感じだった」と明かした。
今回の問題について、小保方リーダー自身は「自分の気持ちを話したい」と希望したというが、理研は「現段階で調査の当事者だから」として記者会見に同席させなかった。
STAP細胞:疑問点は解消されず 理研幹部、歯切れ悪く 03/14/14(毎日新聞)
「あるべきことでないことが起こった。残念で仕方ない」。「STAP細胞」の作製成功を発表した英科学誌ネイチャーの論文に多くの疑問点が指摘されている問題で14日、東京都内で記者会見した理化学研究所の幹部5人は釈明に追われた。しかし、研究ユニットリーダーの小保方(おぼかた)晴子さん(30)の姿はなく、4時間に及んだ会見でも、データの捏造(ねつぞう)の有無など多くの疑問点は解消されなかった。
「(論文に)重大な過誤があったことは甚だ遺憾です」。野依(のより)良治理事長は会見冒頭、約8秒間頭を下げた後、準備していたメモを読み上げた。
約200人が詰めかけた会見では、データに意図的な操作があったかどうかに質問が集中した。理研幹部は「倫理に反する振る舞いがあった」と認めつつも、「引き続き調査する」として明言を避けた。STAP細胞の存在の有無については「調査の対象範囲を超えている」「第三者の検証を待つしかない」と歯切れの悪い回答に終始した。
一方、改ざんとの認定にいたったDNA画像の切り張りについて、小保方さんは「やってはいけないという認識がなかった」と話していたといい、理研の調査委員会の石井俊輔委員長は「抵抗がなかったのか倫理観を学ぶ機会がなかったのか。コメントするのは適切ではない」と言及した。
ネイチャー誌に掲載した画像について、小保方さんは当初、博士論文で使っていたと説明していなかったといい、石井委員長は「だまそうとしているかどうかはわからない」と応じた。
若さやかっぽう着姿で「リケジョ(理系女子)の星」として注目された小保方さんだが、最近は公の場に出ていない。理研によると、今月上旬に論文撤回を提案されると、うなずきながら小声で「はい」と答えたという。精神的にも疲れ反省しており、理研は調査終了時に小保方さんらに弁明の機会を設ける方針。
「似たようなことが起こっているのであれば、時代のなせる業、カルチャーが変わったなと非常に心配している」。ノーベル賞受賞者として研究の厳しさを知る野依理事長は険しい表情で述べた。【一條優太、斎藤有香、奥山智己】
北陸道事故のバス会社、事故前半月で事故40件 03/14/14(読売新聞)
宮城交通(仙台市泉区)や同社の関連会社が運行するバスの運転が原因で今年2月中旬までに、前年同月の1か月間と比べ3倍に当たる40件の事故を起こしていたことが13日、分かった。
同社の関係者によると、関連会社を含めた宮城交通グループでは2月に、事故が急増。昨年2月は十数件だったが、今年は2月中旬の時点で既に40件に達した。今年は自損事故や、車内の乗客がけがする事故が多かったという。
事態を重くみた同社は2月下旬、運転手に対し、注意喚起していたが、3月3日、富山県小矢部市の北陸道で死傷者28人を出す高速バス事故が起きた。宮城交通は「事故の多くは確認不足や漫然運転が原因」としている。
経営破綻のマウントゴックス、米国で資産保全を申請 ビットコイン取引所 03/11/14(産経新聞)
【ワシントン=柿内公輔】経営破綻した仮想通貨ビットコインの取引所「マウントゴックス」(東京)は11日までに、米テキサス州の連邦破産裁判所に資産保全を申請した。
破産法15条の適用を申請し、同社に対する米国での訴訟を一時凍結するのが目的。日本での再生手続きを優先させたい考えだ。
マウントゴックスは2月28日に日本で民事再生法の適用を申請して破綻。一方、米国でもイリノイ州などで顧客から損害賠償訴訟を起こされている。
破産法15条は比較的、新しい条項で、国境を越えた破産案件を想定している。
偽パスポートはICPOに登録も、照会なし 03/10/14(産経新聞)
【パリ=三井美奈】国際刑事警察機構(ICPO、本部・仏リヨン)は9日、消息不明となったマレーシア航空370便で乗客2人が使用した偽パスポートは、盗難品としてICPOのデータベースに登録されていたと発表した。
オーストリア発行のパスポートは2012年、イタリア発行のパスポートは13年にそれぞれタイで盗まれた。登録から事故発生までに、一度も照会されたことはなかったとしている。
ICPOのロナルド・ノーブル事務総長は「マレーシア航空が照会を行っていれば、我々は370便でテロリストが偽造パスポートを使ったのかと疑わずに済んだはずだ」と発言。英米など一部を除き、多くの国が盗難情報の照会を怠っていると警告した。
セキュリティーから考えると2人も盗難旅券を使用していた事実はショッキングだ!
盗難旅券は被害届が出されていたのか?もし被害届が出されていたとすれば、そのような情報は航空会社で共有されていないのか?
情報が共有されていないのであれば、テロを起こそうと思えば、簡単である事が判明したことになる。もしかしてテロ?
マレーシア機墜落か 北京行き 乗客に盗難旅券使用者? 03/09/14(産経新聞)
【シンガポール=吉村英輝、北京=山本秀也】マレーシアの首都クアラルンプールから北京に向かっていたマレーシア航空370便のボーイング777-200型機(乗客乗員239人)が8日午前2時40分(日本時間同3時40分)ごろ、消息を絶った。マレーシア、ベトナム当局などが墜落した可能性もあるとみて捜索活動を行っている。
マレーシア航空によると、中国南方航空との共同運航便で、乗客は15カ国・地域の227人。うち中国人は153人で最も多かった。日本人はいなかった。
ただ、AP通信は、搭乗名簿に名前があったイタリア人とオーストリア人の2人は以前、タイで旅券を盗まれ、同機に乗っていなかったと伝えており、別人が搭乗した可能性がある。
APは、ベトナム空軍機が同日夕、同国南部の海上で長さ10~15キロの2つの帯状の油を確認したと伝えた。ベトナム当局は、南部沖合のトーチュー島近辺に落ちた可能性があるとみている。マレーシアのナジブ首相は同日夜、航空機の残骸らしきものが見つかっていないため、9日の日の出から航空機での捜索を再開すると述べた。
捜索にはフィリピンやシンガポールのほか、中国や米国も加わった。
マレーシア航空によると、370便はクアラルンプール空港を8日午前0時41分に離陸し、北京には同6時半には到着する予定だった。米NBCテレビ(電子版)は、この機体は2012年、別の航空機と地上で接触事故を起こしていたと伝えた。
バスの運転手をした事はない。長距離運転について個人的な感想を言えば、年を取れば、無理をすると疲労感がなかなか取れないと感じる。
高速バスは安くなければ利用者は増えない。会社の利益、社員の給料、及びその他の要素を考えて判断するしかない。言えることは悪質な業者を見るけるような監査を行い、問題のある業者は市場から追放する事だけは行わなければならない。
死亡したバス事故運転手、13日連続勤務を3回 03/09/14(読売新聞)
富山県小矢部市の北陸道・小矢部川サービスエリア(SA)で高速バスが大型トラックに衝突し26人が死傷した事故で、死亡した宮城交通(仙台市)のバスの小幡和也運転手(37)が、昨年12月から今年1月にかけ、同社の労使協定で限度としている13日連続勤務を、1日の休みを挟んで3回繰り返していたことが、同社への取材でわかった。
小幡運転手は、事故当日まで11日連続で勤務していたことが既に明らかになっており、過酷な勤務が続いていたことがうかがえる。こうした勤務状況について同社社長室は「問題がなかったとは考えていない」としている。
交通産業の安全管理に詳しい安部誠治・関西大教授(公益事業論)は「(2012年の)関越道バス事故後も労働時間については大きな見直しがなく課題となっている。週1日は休むなど、連続勤務の制限が必要」と指摘する。
これは静岡だけの問題ではない。効率や安い人件費を考えると、雇用が減るし、外国人研修生や海外での生産となるだろう。
一部の人達を除けば、必要となくなった人達が必要とされる事はあるのか?同じ賃金ではNOだろう。
採用の募集をしても、3Kの仕事は敬遠されるとテレビやインターネットで関連記事を見る。セーフティーネットと現実の状況を直視出来ない人達の問題は難しいと思う。誰でもきつい仕事などしたくない。簡単に生活保護が得られるのであれば、ずるい人達ほど働かない。ずるい人達のために、本来助けるべき人達への予算も削られる。
簡単な職業訓練でミスマッチなど解消できない。また、正規で雇用すると簡単に解雇できないのでは、体力的に厳しい中小企業は高齢者やお試しで採用する事もない。
このような問題を解決するために、採用に関する基準を緩和すると、ずるい企業が悪用して労働者を使い捨てにする。
少なくともこれからの子供達の教育に対しては真剣に改革に取り組むべきだ。大人になってからでは遅いと思う。職業訓練ぐらいでは簡単に解決できない。また、学力だけでなく、人間性の問題もある。誰もが賛成する解決策はないと思うが、甘く考えていると将来もっと苦しむ人達が増えるだろう。
雇用者5年で9万人減、全国で最悪…静岡 03/07/14(読売新聞)
正規雇用の減少が響く
静岡県内の2012年度の雇用者数が、5年前の07年度と比べて9万人減少し、減少率、減少人数ともに全国の都道府県で最悪だったことが、総務省の「就業構造基本統計調査」でわかった。
県内では、有効求人倍率が全国平均を下回る状況も続いており、静岡労働局は「製造業を中心に生産拠点の海外移転や国内拠点の整理・統合などが影響したとみられ、雇用喪失の規模は大きい」としている。
同調査によると、リーマン・ショック前の07年度、県内の雇用者数は170万3000人だったが、12年度は161万3000人まで減少。減少人数は9万人、減少率は5・2%とともに全国で最も減少した。減少分の9万人のほとんどは正規雇用の減少によるものだった。一方、非正規雇用者はほぼ横ばいだった。
県内で雇用が悪化しているのに対し、全国では、非正規雇用者が大幅に増えたことで、全体の雇用者数は5326万人から5353万人に増加している。
同調査をもとにした静岡労働局による分析では、県内の新規求職者の推移は、リーマン・ショック時に同時に落ち込んだ隣県の愛知県とほぼ同じだったが、雇用者数では同県は07年度の333万人から、12年度は336万人と増えた。
同局は「県内はリーマン・ショック後の回復に他県と大きな違いが出ている。製造業の求人が増加していないことに加え、非製造業でも求人数が伸び悩んでいる」と分析。そのうえで「医療・福祉業、建設業などは伸びしろがあるにもかかわらず、求職者が少ない。自治体や民間などで協力し、ミスマッチ解消に努める必要がある」としている。
取引所トップが死亡 シンガポール警察捜査 03/06/14(産経新聞)
【シンガポール=吉村英輝】シンガポールの英字紙、ストレーツ・タイムズ(電子版)は6日、同国にある仮想通貨ビットコインの取引所「ファースト・メタ」の最高経営責任者(CEO)、オータム・ラドキー氏(28)が2月26日、自宅で死亡して見つかり、警察が死因などを調べていると伝えた。
同紙によると、警察は26日朝、通報を受け、自宅に倒れている米国人女性のラドキー氏を発見。その後、死亡が確認された。
ビットコインをめぐっては、東京に拠点がある世界最大級の取引所「マウントゴックス」が取引を停止して28日に経営破綻するなど、利用者の信用不安が広がっている。
国土交通省はやはりお役人!
「同社の青沼正喜社長は、国土交通省が設置した『バスの運転者の確保及び育成に向けた検討会』で委員を務めており、昨年12月の初会合では、自社の運転手不足について報告していた。」
バスの運転手が職業として魅力が無い、又は、他の選択肢がある場合、志願者は少なくなる。バス料金が高くなれば利用者は減る。本当に必要ない利権を撤廃したり、
違法行為を継続する業者は厳しく処分する、バスの運行だけでなく利用者が利用したくなるアイディアを考えるなど、いろいろな方面から考えないと、簡単には解決できない。簡単にバス運転手の賃金を上げればバス料金に影響する。今回はバスだが、バスだけでなくいろいろな問題を抱えた業界がある。公務員はもっとしっかりと働け!
バス運転手不足で過去運休も、休日出勤常態化か 03/06/14(読売新聞)
富山県小矢部市の北陸自動車道・小矢部川サービスエリアで3日未明に事故が起きた高速バスの仙台―金沢便について、運行する宮城交通(仙台市)は2012年3~7月と13年3~8月の2回にわたり、運転手が足りないため運休していたことが5日、分かった。
同社では、運転手が慢性的に不足し、休日出勤が常態化していたとみられる。亡くなった小幡和也運転手(37)も事故当日まで11日連続での勤務だった。
同社の青沼正喜社長は、国土交通省が設置した「バスの運転者の確保及び育成に向けた検討会」で委員を務めており、昨年12月の初会合では、自社の運転手不足について報告していた。
検討会の資料などによると、宮城交通と北陸鉄道(金沢市)は1992年3月から、共同で仙台―金沢の夜行便の運行を始めた。当初、両社がバス1台と運転手をそれぞれ出し合って、運行していた。しかし、宮城交通は、運転手の不足で2回にわたり運休し、その間は、北陸鉄道が単独で運行していた。
また、宮城交通は原則として「週休2日」になっていたが、13年4~11月に休日出勤した運転手の割合は、平日で平均60%、土日祝日では平均33%に上っていた。宮城交通の担当者は「運転手の採用は苦しいのが現状だが、人手不足と休日出勤の割合が高止まりしている状態は、改善しないといけない」と話した。
ビットコイン、カナダの取引所も業務停止 03/05/14(読売新聞)
【ニューヨーク=越前谷知子】カナダでインターネット上の仮想通貨ビットコインの取引所を運営する「フレックスコイン」が4日、ハッカーによる攻撃で取引業務を停止したと発表した。
発表によると、フレックスコインは今月2日、ハッカーの攻撃を受けて、預かり資産の896ビットコイン(約6000万円相当)が盗まれた。顧客に返済する資産を失ったとして、営業停止を決めたという。フレックスコインは声明で、「司法当局に協力する」と表明した。
一方、別のビットコインの取引所業者の「ポロニエックス」も4日、保管していたビットコインの12・3%が盗まれた、と公表した。
ビットコインをめぐっては、2月末に東京に拠点を置く大手取引所「マウントゴックス」が、外部からの不正アクセスによって保有する約480億円相当のビットコインを失ったとして、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、破綻した。取引業者に対する攻撃が相次ぐ中で、ビットコインに対する投資家の信認が揺らぐのは必至だ。
これが日本のキャリアのDNAではないのか?
菅氏「あぜん」…更迭の日本郵政前社長、顧問に 03/04/14(読売新聞)
日本郵政の坂篤郎前社長が同社の顧問に就任していたことが4日、明らかになった。
これに関連し、菅官房長官は同日の記者会見で「監督官庁(の総務省)も知らないところで復帰し、報酬も支払われていた。あぜんとした」と述べ、同社の対応を厳しく批判した。「(株式)上場に向けて経営効率を高める努力が必要な中、報酬を支払うのは国民から理解されない」とも語り、総務省が何らかの措置を行うことを明らかにした。
坂氏は財務省出身で、第2次安倍内閣発足直前の2012年12月に同社社長に就任したが、菅氏が「財務省によるたらい回しだ」などと問題視し、事実上更迭した経緯がある。後任には西室泰三・元東芝会長が就任している。
預かり金返還応じず…マウント社を米男性が提訴 03/04/14 (読売新聞)
インターネット上の仮想通貨「ビットコイン(BTC=Bitcoin)」の取引サイトを運営し破綻したマウントゴックス社(東京)を巡り、同社が昨夏には、利用者からの預かり金の返還に応じていなかったことが、米国人男性が東京地裁に起こした訴訟でわかった。
男性側は「何度も督促したが、拒否された」と主張しており、同社の資金繰りが行き詰まっていた可能性もある。
関係者によると、同社のサイトを利用していた米国在住の男性は、保有していたBTCをすべて売却。これで得た約93万ドル(当時のレートで約9300万円)を自分の口座に送金するよう求めた。
ところが、同社は「米国で生じた問題により、すぐには返還できない」と送金を拒否。男性が強く返還を求めたところ、数千ドルだけ送金があったという。
男性は仕方なく、預けていたドルの残額で再びBTCを購入。別の取引サイトで売却したが、約10万ドル(同約1000万円)の損失が生じたとして、昨年12月に提訴した。
東京地裁で開かれた第1回口頭弁論で、同社側は請求の棄却を主張。具体的な反論がないまま、今年2月28日に同社が民事再生法の適用を申請して破綻したため、今月5日の期日は取り消された。
同社側は破綻時の記者会見で、預かり金不足が判明したのは今年2月24日だったとしているが、昨夏の時点で資金繰りに何らかの問題が生じていた可能性もある。マウントゴックス社の訴訟代理人の弁護士は「提訴があったのは事実だ」としている。
製薬会社の闇 医師にカネ渡す営業で販売促進を図る慣習あり (1/2)
(2/2) 03/03/14(NEWSポストセブン)
本誌・週刊ポスト2月21日号がスクープした国立大学現役教授による実名証言が大きな反響を呼んでいる。中国地方の名門国立大・岡山大学の森山芳則・薬学部長と榎本秀一・副薬学部長が、これまで厚いベールに覆われていた「製薬会社と大学医学部の癒着の現場」を初めて白日の下に晒したのだ。
製薬会社から金銭的支援を受ける代わりに、大学の医学部教授らが臨床試験のデータを操作し、製薬会社に有利な論文を執筆するなど、不正論文が同大医学部内で横行している実態を生々しい証言で暴いたのである。
「ポストの発売当日、『どういうつもりだ!』と、岡山大のある教授から抗議の電話がかかってきました。長年、隠蔽されてきた不正に光を当てたため、大学内でも私たちを黙らせようとするプレッシャーは大きい。
しかし、それ以上に多くの研究者や職員、学生、薬を服用している患者さんや一般市民の方々から激励をもらった。テレビ局や雑誌メディアなど、マスコミからの接触も相次いでおり、この問題に対する社会の関心の高さに驚いています」(榎本教授)
本誌編集部にも雑誌発売後、「ウチの医学部にも同じような不正論文を疑われるケースがある」といった情報提供が複数寄せられた。医師が製薬会社と結託して、ありもしない薬効などを捏造した論文が全国的に乱発されている──。森山教授らの告発はまさにパンドラの箱を開けたといえる。
患者を欺く不正論文の存在が公になったケースは過去も度々あった。2003年、昭和大藤が丘病院の腎臓内科に所属していた医師(当時)が、英医学誌に腎臓病の投薬治療に関する論文を投稿した。
内容は、臨床研究の結果、慢性腎臓病患者には2種類の薬を併用する方法が有効だとしたものだったが、その後、海外の研究チームが併用投薬した患者で逆に腎機能が低下したケースがあると、論文の内容に疑義を呈した。
その後の調査で、論文に引用されたデータと実際の患者の検査データが一致しなかったことなどが判明。2009年、結局、論文は取り下げられることになった。
その時点では、実際の治療現場で論文が推奨する併用投薬が採用されていなかったことに、胸を撫で下ろすばかりだ。
他にも、2012年には元東邦大学准教授の麻酔科医が国内外の専門誌に発表した193本の論文に疑惑が投げかけられ、論文の撤回に追い込まれるという事件もあった。いずれも「患者不在」の構図は変わらない。東京大学医科学研究所の上昌広・特任教授はこう指摘する。
「製薬会社の社員は裏側では、『奨学寄付金は大学病院勤務の医師に対する営業経費』だとはっきり明言しています。医師に営業する(カネを渡す)ことが、薬の販売促進に繋がるということを、医薬品業界で知らない者はいません。
その背景にあるのは、医薬品は公定価格が決まっていて、他の商品のように値下げなど価格競争ができないこと。そのため製薬会社は売り上げを増やすために、奨学寄付金という営業行為に血眼になる。この歪な癒着構造を変革するには、国による価格統制を緩和するしかありません」
同様に現状に強い危機感を抱くのは、近畿大学医学部講師の榎木英介氏である。
「製薬会社とあまり接点のない私のような病理専門医から見ると、大学医学部と製薬会社の関係は異常に映ります。まだ医学生の時から、製薬会社の営業マンは目星を付けた医者の卵にボールペンやメモ帳を提供したり、お弁当を差し入れしたりといったアプローチで関係を深めていく。
研修医になる頃には、論文を探してきてあげたり、タクシーチケットを配ったりと、さらに密接な関係を作る。その長年の馴れ合いの延長線上に、一部とはいえ、患者の健康や存在を無視したまま医薬品が販売・宣伝される現状があります。これは何としても是正されねばなりません」
薬も医師も信用できないとしたら、患者は何を信じればいいのか。
日本の警察には無理のような気がする。金融庁および財務省と協力してもだめだと思う。
民間の専門家に頼るしかないと思う。しかしプライドがあるからどこまで妥協するのだろう!
被害者は誰?「114億消失」…不自然な説明も 03/01/14 (読売新聞)
サイバー攻撃で巨額の仮想通貨ビットコイン(BTC=Bitcoin)を「盗まれた」として、先月28日に破綻したマウントゴックス社(東京)。
利用者から預かった資金返還のメドは立たず、一方で同社は「自分たちも被害者」と強調する。同社保有の114億円相当のビットコインはどこに消えたのか――。
◆「被害者」は誰?
利用者も捜査機関による真相解明を求める声が上がるが、サイバー空間の前代未聞の問題に対し、警察庁幹部は一様に「情報を収集している段階だ」と口をそろえ、見通しはまったく立っていない。
警察幹部は「誰が被害者なのか、どんな犯罪に該当するのか、見当が付かない」と打ち明ける。サイバー攻撃でビットコインなどが盗まれたなら、ネット犯罪を担当する部署の管轄になるが、マウント社からまだ詳しく事情を聞けておらず、「会社が被害を受けたと断定できる段階ではない」という状況だという。
資金返還のメドが立たない利用者を「被害者」とすることにもハードルがありそうだ。ある警察幹部は「ビットコインは価値が乱高下する上、国の保証がないことも分かっていたはず」と指摘。「リスクを覚悟のうえで購入した人が、被害者になりうるだろうか」と頭を悩ませている。
◆送金先はどこ?
同社は先月28日の記者会見で、85万ビットコイン(破綻前の同社の最終レートで114億円)と顧客からの預かり金最大28億円が「消えた」と説明。原因は「ハッカーによる不正アクセス」と主張する。大量のデータを送りつけるサイバー攻撃を受けたとして同社は2月上旬から取引を停止していたが、楠正憲・国際大学GLOCOM客員研究員は「そんなに巨額を盗み出せば、サイト側は必ず気づくはず。説明は不自然だ」と指摘する。
相手が日本人ばかりであれば逃げる事も簡単だと思うけど、外国人達が行動しはじめているから簡単には逃げられないだろうね。
ビットコイン大手破綻「巨額の損失」…米で提訴 03/01/14 (読売新聞)
【ニューヨーク=広瀬英治】インターネット上の仮想通貨「ビットコイン」取引サイト運営会社「マウントゴックス社」(東京)が経営破綻した問題を巡り、米イリノイ州に住む利用者が「サイト閉鎖で巨額の損失を被った」などとして、同社とマルク・カルプレス社長を相手取って同州連邦地裁に、損害賠償などを求める訴訟を起こしたことが分かった。
この利用者は他の利用者に集団訴訟を呼びかけている。
マウント社の破綻前日にあたる2月27日付の訴状によると、この利用者は2011年から同社サイトでビットコインを取引し、サイト閉鎖時点では現在の価値で約2万5000ドル(約255万円)相当のビットコインを預けていたという。
同社によると、サイトの利用者などは約12万7000人に上る。経営破綻の時点で預かり金が最大約28億円不足しているほか、同社の最終レートで約114億円相当のビットコインが消失しており、返還のめどは立っていない。
規制が無かったから低料金で、いろいろな事が出来たのだろう。もちろん、マネーロンダリングや闇の取引にも使われていたに違いない。
大手取引仲介会社「マウントゴックス」の経営破綻で注目を受けて、問題の部分が大きく取り上げられたと言う事だろう。もう以前とは同じようには行かない。
“ビットコイン” 海外でも波紋広がる 03/01/14 (NHKニュース)
仮想通貨「ビットコイン」の大手取引仲介会社「マウントゴックス」が経営破綻したことを受けて、アメリカの金融監督当局の関係者などからビットコインの取り引きを規制すべきだという声が強まるなど海外でも波紋が広がっています。
ビットコインは、インターネット上で5年ほど前から使われ始めた仮想通貨です。
国や中央銀行の後ろ盾がなく、管理者はいませんが、格安の手数料で代金の決済や外国への送金ができることもあって欧米や中国など世界的に利用が広がりました。
このうち、アメリカではビットコインで支払いができるレストランや店舗などが増えていますが、麻薬の売買など犯罪に悪用されるケースも相次ぎ、取り引きを規制すべきだという声も強まっています。
今回、日本で「マウントゴックス」が経営破綻したことを受けてアメリカ・ニューヨーク州の金融監督当局のトップロースキー監督官は28日、「マウントゴックスで起きたことに関しては事実関係が依然不透明だが、利用者を保護し業者に預けた資金の安全を確保するためにはしっかりした規制が重要な役割を果たすということを浮き彫りにした」という声明を発表しました。
ニューヨーク州は先月、アメリカの州で初めてビットコインなど仮想通貨の規制に乗り出す方針を示し、取り引きを手がける業者を免許制にすることを軸に規制の枠組みを検討しています。
また、アメリカ議会上院、国土安全保障委員会のカーパー委員長は、連邦レベルでも何らかの規制を設ける必要があるという考えを示しています。
さらに、アメリカの中央銀行に当たるFRB=連邦準備制度理事会のイエレン議長も27日、議会の公聴会で仮想通貨を監督する権限はFRBにはないとしたうえで、「これまでの規制が及ばない仮想通貨に対する法的な枠組みは、議会が検討することが適切だ」と述べています。
業界関係者は、今回の問題は、あくまでも犯罪を行った人物やマウントゴックスの経営にあり、ビットコインそのものにはないと主張していますが、マウントゴックスの利用者が損害を受けたとしてマウントゴックスとマルク・カルプレスCEOを相手取ってアメリカの裁判所に集団訴訟を起こす動きも出るなど、海外で波紋が広がっています。
「金庫破り」で盗難 ビットコイン、資金管理ずさん 03/01/14 (日本経済新聞)
仮想通貨の取引所を運営するMTGOXが28日に民事再生手続きを申請した。「未来の通貨」の中心となる取引所だが、ハッキング被害にあったうえ、顧客から預かった現金をきちんと管理せず、客の預かり金28億円も宙に浮いていた。
MTGOXが運営する仮想通貨ビットコインの取引所「マウントゴックス」では、利用者は仮想通貨をやりとりするため、自身の口座にお金やビットコインを預ける。マウントゴックスのビットコインは、ハッカーから「金庫破り」に遭って盗まれていた。
だが、マウントゴックスは客から預かった現金そのものもきちんと管理してこなかった。同社によると2月24日、利用者の現金預かり金と、預金残高が食い違い「預金残高が最大で28億円不足している」ことがわかった。突然取引所を閉鎖した背景には、ずさんな資金管理も背景にあった。
「(客からのお金は)適正に管理されていたと思う」。28日に都内で開いた記者会見で、代理人の弁護士は釈明した。だが同社関係者は「客の預かり金と会社の経費がきちんと区分管理されていなかった」と指摘する。
負債は総額65億円。この中には失われたビットコイン114億円は含まれていない。同社弁護士は会員のビットコイン資産について「再生計画の中で返済の条件を決める」としているが、弁済は同社が事業再建し、再び利益を上げられることが前提だ。問題を抱えたMTGOXを手助けするスポンサーが見あたらなければ、盗まれたとされるビットコインの返済は行き詰まる。
マウントゴックス破綻 ビットコイン114億円消失 02/28/14 (日本経済新聞)
インターネット上の仮想通貨ビットコインの取引所「マウントゴックス」を運営するMTGOX(東京・渋谷)が28日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、同日受理されたと発表した。債務が資産を上回る債務超過に陥っていた。顧客が保有する75万ビットコインのほか、購入用の預かり金も最大28億円程度消失していたことが判明した。
MTGOXのマルク・カルプレス社長は28日夕の記者会見で「ビットコインがなくなってしまい、本当に申し訳ない」と謝罪した。消失したのは顧客分75万ビットコインと自社保有分10万ビットコイン。金額にして「114億円程度」としているが、他の取引所の直近の取引価格(1ビットコイン=550ドル前後)で計算すると、470億円前後になる。
流動負債の総額は65億円で「債務超過の状態にあると判断した」という。同社は25日昼ごろからサービスを停止していた。顧客12万7000人の大半は外国人で、日本人は0.8%、約1000人という。
民事再生法の申請に至った理由は、「ビットコイン」と「預かり金」の消失で負債が急増したため。2月初旬、システムの不具合(バグ)を悪用した不正アクセスが発生し、売買が完了しない取引が急増。「バグの悪用により(ビットコインが)盗まれた可能性が高い」と判断した。
さらに、2月24日、利用者からの預かり金を保管する預金口座の残高が最大で28億円程度不足していることも分かった。「今後膨大な取引を調査する必要がある」。原因はおろか確かな金額も確定できていないという。会社の経費などに使われた可能性もありそうだ。
同社は「被害届の提出と刑事告発を検討している」と説明した。
被害届が出されても形だけの捜査になるのでは?ハッカーの攻撃で85万ビットコイン分もの大量のデータが盗まれたことを分析する能力など警察にあるのか?
ビットコイン「いなくなった」社長深々と頭下げ 02/28/14 (読売新聞)
インターネット上の仮想通貨「ビットコイン」の世界的な取引サイト運営会社「マウントゴックス社」が28日、破綻した。
直前の同社のレートでも114億円に相当する巨額の「カネ」が、ハッカーの攻撃であっという間に「盗み取られた」とするサイバー空間の強盗劇。コインを預けていた投資家は戸惑いを隠せず、法整備の必要性を訴える声も出ている。
◆「ハッカー攻撃」
「システムに弱いところがあってビットコインがなくなって、いなくなって申し訳ない」
薄いグレーのスーツ姿で記者会見場に現れたマウント社のマルク・カルプレス社長は、たどたどしい日本語でこう謝罪すると、深々と頭を下げた。
同社によると、消失したのは85万ビットコインと預かり金最大28億円。これについて同社は「ハッカーによる攻撃が原因」と強調したが、同社の代理人弁護士は「痕跡はある」と述べるだけで、具体的な手口などの説明はさけた。
85万ビットコインの価値は、同社のレートでは破綻前の25日の段階で114億6000万円相当に下がったが、世界の他の交換サイトでは今も480億円相当の価値を保っている。社長は自らは退任する意向を示したが、「ビットコインは将来的にいろいろな使い方が出来る。未来がある」として、新しい「通貨」の形になお未練を残した。
◆どこに消えた?
巨額のビットコインはどこに、どのように消えてしまったのか。
情報セキュリティーに詳しい楠正憲・国際大学GLOCOM客員研究員は「ビットコインの取引記録は公開されているので、詳細に分析すれば不審な取引は見つけ出せる」と指摘する。一方で、「85万ビットコイン分もの大量のデータを気付かれないように盗み取るのは、技術的に非常に難しい。ハッキング被害という同社の主張を検証すべきだ」とも話す。
ビットコインは法規制の対象となっていない仮想通貨で、利用者が返還を求められるか危ぶまれているが、代理人弁護士は「返還の義務がある」との認識を示した。同社は被害届を捜査機関に提出する考えで、警察などの捜査機関が分析することになりそうだ。
JR北「レール異常、放置し脱線」…運輸安全委 02/28/14(読売新聞)
JR函館線大沼駅(北海道七飯町)で昨年9月に貨物列車が脱線した事故で、運輸安全委員会は28日、調査の経過報告書を公表した。
カーブ内側のレールが外側より10ミリ高く、外側に強い圧力がかかる異常な状態で、枕木も老朽化などで損傷していたが、現場付近は過去3年間にわたって補修が行われていなかった。安全委は、JR北海道がこうした異常を放置し続けた結果、脱線事故につながったと指摘した。
安全委によると、事故現場は半径400メートルの左カーブだったが、事故の約3か月前の時点でレールの内外で10ミリの高低差が生じており、レールの幅も規定値より最大で40ミリ広がっていた。さらにレールが外側に最大70ミリゆがんでいたためカーブの曲率がきつくなり、列車走行時に車輪がレールを外側に押し出す力が増大しやすい状態になっていた。
このほか、枕木も老朽化などで損傷が進んでおり、レールを枕木に固定するクギが抜けやすい状態になっていたという。この結果、貨物列車が通過した際にクギが緩んでレールが外側に大きく傾斜、車輪がレールから落ちて脱線したとみられる。
社内規定では、レール幅の広がりやゆがみが19ミリに達した場合、検査翌日から15日以内に補修する必要があるが、管轄の大沼保線管理室は放置。現場付近ではレールや枕木、クギなどについて、少なくとも過去3年間にわたって補修した記録がなかった。
「お弁当屋さんから「シャケ弁」が消えてしまうかもしれない。」なんか極端。今までシャケ弁で何が使われているか気にしなかった人達にも知る機会が出来た。
「シャケ風弁」とか、「シャケ弁」には「サーモントラウト」を使用していますと客がわかるように表示すれば良いだけの話ではないのか。新車みたいな中古車とか、新車でない事がはっきりとわかる表現が使われていれば十分だ。新車みたいに奇麗な中古車とか、あまり使用されていない中古車であるかは、中古車と分かった上で客が状態と値段を考慮して判断する事と同じだと思う。情報を提示した上で客が判断するのであれば問題ない。食べ物に関して本物を使っていても高すぎたり、美味しくなければ、買わない客もいるだろう。情報を提示することの定着を目指すべきだ。
「シャケ弁」が「ニジマス弁」に? 食材偽装の余波 消費者庁ガイドライン案に業界大混乱 (1/3)
(2/3)
(3/3) 02/19/14(産経新聞)
お弁当屋さんから「シャケ弁」が消えてしまうかもしれない。全国のホテルや百貨店で相次いだ食材虚偽表示問題を受け、消費者庁がメニューの食品表示のガイドライン案を作成。その中で、シャケ弁当などで使われる「サーモントラウト」について、「シャケ(サケ)」や「サーモン」と表示するのは問題があると指摘しているためだ。外食業界は「現場は困惑を通り越して混乱している」「このままでは宇治金時や鴨南蛮(かもなんばん)も使えなくなる」と反発している。
弁当店に波及…「唐突な印象」と現場困惑
ホテルのレストランメニューに端を発した虚偽表示問題。その影響が町の食堂や弁当店にも及んでいる。
その一例がサーモントラウトだ。消費者庁が昨年12月に公表したガイドライン案では、不適切な表示例として「サーモントラウト」を挙げ、「サーモン」と表示するのは、景品表示法上、問題になるとした。
持ち帰り弁当チェーン「ほっともっと」の定番メニュー「しゃけ弁当」(390円)にも、ニジマスを海で養殖したサーモントラウトが使われている。
運営するプレナス(福岡市)の担当者は「唐突に出たという印象。協議の行く末を見守りたい」と戸惑い気味。川魚のニジマスは白身だが、海で養殖すると赤身になり、脂も乗っておいしいため、「価格も秋鮭の倍以上する」というサーモントラウトを使用しているという。
元農林水産省食品表示Gメンで「食の安全・安心財団」事務局長の中村啓一氏は「さすがにシャケ弁当を『ニジマス弁当』というのは違和感がある。消費者も混乱する」と指摘する。
消費者庁、指針見直しへ
宅配弁当の業界団体、日本弁当サービス協会の夏目広専務理事は「消費者庁はもうちょっと現場の声を聞いていただきたい」と訴える。案がまとまるまで約1カ月。「あまりに拙速」との批判が業界内に渦巻く。
1月に東京都内で開かれた意見交換会でも業界側から「ニジマスは白身の魚という印象」といった見直しを求める意見が相次いだ。
こうした声を受け、森雅子消費者行政担当相は今月7日、「(表示と実態に)差がなければ違反ではない」と述べ、サーモントラウトを使った弁当に、単に「サケ弁当」と書くだけなら問題ないとの見解を示した。消費者庁は「誤解を招いた」として指針案を見直す方針だ。
「たぬきそば」「きつねうどん」はOK?…広がる波紋
だが、波紋は広がる一方だ。
外食産業の業界団体、日本フードサービス協会の関川和孝常務理事は「案には一部の具体例が示されているのみで、『たぬきそば』や『きつねうどん』がOKかどうなのかも分からない」と困惑する。
かき氷の「宇治金時」は、宇治茶を使っていなければ、「抹茶金時」と表記するのか。カモとアヒルを交配したアイガモを使っている「鴨南蛮」は「アイガモ南蛮」と表記しなければならないのか、といった疑問も出ている。
元農水省食品表示Gメンの中村氏は「定着した食品の名前にまで、規制をかける意味があるのか」と疑問視する。
すでに、店舗でレンジ加熱のみで調理している「豚肉の生姜(しょうが)焼き」を「豚肉の生姜だれ」に変更するレストランも出ているといい、中村氏は「過剰反応しているところもある。消費者庁は料理名に対する景品表示法の考え方をきちんと示すべきだ」と話している。
ノバルティスを捜索 臨床データで薬事法違反の疑い 東京地検特捜部 02/19/14(日本経済新聞)
スイス製薬大手の日本法人ノバルティスファーマ(東京)の高血圧症治療薬を巡る臨床研究データ操作問題で、誤ったデータに基づき薬効を誇大に見せかけて宣伝した疑いが強まったとして、東京地検特捜部は19日、薬事法違反(誇大広告)容疑で同社を家宅捜索した。
厚生労働省は1月、特捜部に同法違反容疑での告発状を提出。特捜部は関係先から資料を押収するなどして、実態解明を進める。
厚労省の調査などによると、ノバルティスの元社員(昨年5月に退職)は高血圧症治療薬ディオバン(一般名バルサルタン)の効果を調べる京都府立医大など5大学の臨床研究に関与。このうち3大学で、血圧値などの統計解析などにデータの操作があった。
同社は操作されたデータに基づく研究論文を引用し、医療専門雑誌などにディオバンの広告記事を掲載。既存の治療薬と比べて脳卒中や狭心症の発症を抑える効果があるなどと宣伝していた。
厚労省はノバルティス社から資料の提出を受けるとともに、関係者から聞き取り調査などを実施。同省の有識者検討委員会は昨年9月の中間報告で、不正なデータに基づく論文を利用した広告について「薬事法が禁じる誇大広告に当たる可能性がある」と指摘。「会社として関与していたと判断すべきだ」と結論付けた。
薬事法は医薬品や医療機器の効果などに関し、虚偽の宣伝や誇大な表現での広告を禁じており、違反した場合、2年以下の懲役か200万円以下の罰金となる。法人自体も併せて処罰する「両罰規定」も置かれている。
ノバルティスを家宅捜索=高血圧薬の誇大広告容疑-東京地検 02/19/14(時事通信)
製薬大手ノバルティスファーマの高血圧治療薬ディオバン(一般名バルサルタン)の臨床研究データ操作問題で、ノ社が改ざんデータに基づく論文を宣伝に利用した疑いがあるとして、東京地検特捜部は19日、薬事法違反(誇大広告)容疑で、同社本社(東京都港区)を家宅捜索した。
ノ社は2011~12年、データが操作された東京慈恵会医大と京都府立医大の臨床試験結果の論文に基づき、ディオバンは脳卒中や狭心症を防ぐ効果が他の薬より優れているなどと誇大に宣伝した疑いが持たれている。厚生労働省が1月、地検に刑事告発していた。
ディオバンをめぐっては、02~10年、5大学が別の治療薬との効果を比較する大規模な臨床研究を実施したが、ノ社元社員の研究への関与と数値の食い違いが判明。慈恵医大や府立医大以外にも、滋賀医大でデータ操作の可能性が指摘された。
ノ社は「証拠はない」と疑惑を否定。元社員も同社の聞き取りなどに対しデータ操作を否定している。
ノ社は臨床研究を始めた02年以降、5大学に対し計11億円余りの奨学寄付金を提供。最多は府立医大への3億8170万円で、慈恵医大は1億8770万円だった。
ノバルティスファーマ広報担当者の話 捜査に関することはコメントできない。引き続き捜査には協力する。
薬事法違反:容疑でノバルティスを家宅捜索 東京地検 02/19/14(毎日新聞)
降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験疑惑で、東京地検特捜部は19日、薬事法違反(誇大広告)容疑で製薬会社ノバルティスファーマ(東京都港区)の家宅捜索に乗り出した。ノ社側はこれまでの厚生労働省の調査に対し、データ操作への関与を否定しているが、特捜部は、医薬研究への信頼を揺るがした問題の実態解明には、強制捜査によって関係資料を押収する必要があると判断したとみられる。
厚労省や民間の「薬害オンブズパースン会議」(代表・鈴木利広弁護士)がノ社を告発していた。厚労省によると、ノ社は2011〜12年、データ操作された東京慈恵会医大と京都府立医大の臨床試験結果を広告記事などに使い、「バルサルタンは脳卒中の予防効果も高い」などとバルサルタンの効果を誇大に広告した疑いがあるとしている。
厚労省は昨年10月〜今年1月、薬事法に基づく調査でノ社に関係書類の提出を求め、社員らの聞き取りを実施したが、データ操作から広告までの過程で不正に関わった個人の特定には至らず、法人としてのノ社以外は「氏名不詳」として東京地検に告発している。薬事法には法人を処罰する「両罰規定」があるが、適用には役員や従業員らの立件が前提となり、特捜部は押収した資料を基にノ社や臨床試験を実施した大学の関係者から事情聴取して不正に関わった個人の特定を目指すとみられる。
バルサルタンを巡っては、慈恵医大と京都府立医大、滋賀医大、名古屋大、千葉大の5大学が臨床試験を実施。いずれもノ社元社員がデータ解析に関わりながら、論文では肩書が伏せられていた。慈恵医大と京都府立医大、滋賀医大はノ社に有利な方向にデータ操作がなされていたと発表。5大学はノ社から総額11億円超の奨学寄付金を受けていた。
レール計測改ざん、JR北を刑事告発…国交省 02/10/14(読売新聞)
JR北海道のレール計測データ改ざん問題で、国土交通省と運輸安全委員会は10日、改ざんで監査が妨害されたなどとして、同社を鉄道事業法違反と運輸安全委員会設置法違反の容疑で北海道警に刑事告発した。
鉄道会社が監査妨害で告発されるのは初めて。告発を受け、道警は同社への捜査を本格化させるとみられる。
国交省によると、昨年9月19日にJR函館線大沼駅構内で貨物列車の脱線事故が発生。その直後に同駅を管轄する大沼保線管理室の社員2人(懲戒解雇)と上部組織の函館保線所の社員(出勤停止30日)らがレール幅の広がりを示すデータを39ミリから25ミリにするなど、複数のデータや保線記録を改ざんした。
改ざんは函館保線管理室でも行われ、両管理室の社員らは動機について、「レールの異常を補修せずに放置していたことを隠したかった」などと説明。国交省などは、関与した社員らが多く、上部組織の指示についても解明する必要があるため、社員ら個人については容疑者を特定せずに「被疑者不詳」として告発した。
JR北を刑事告発へ…レール計測データ改ざん 02/08/14(読売新聞)
JR北海道のレール計測データ改ざん問題で、国土交通省は、改ざんで監査が妨害されたなどとして、週明けにも同社を鉄道事業法違反容疑で北海道警に刑事告発する方針を固めた。
改ざんに多数の社員が関わっており、法人としての同社の刑事責任を問う必要があると判断した。改ざんに関与した社員らについては、上司らの関与を解明する必要があるとして、容疑者を特定せずに告発する方針。
国交省によると、昨年9月19日にJR函館線大沼駅構内で貨物列車の脱線事故が発生。その直後に同駅を管轄する大沼保線管理室の社員2人(懲戒解雇)らがレール幅の広がりを示すデータを39ミリから25ミリにするなど、本社を含め約10人の社員が関与して複数のデータを改ざんした。また、函館保線管理室でも、国交省の特別保安監査が入る前日の同25日、助役(諭旨解雇)を含む計11人が関与してデータの改ざんを行った。
研究データ解析にも社員が深く関与か 02/07/14(NHK)
大手製薬会社「ノバルティスファーマ」の社員が、医師が主導して客観的に調べる白血病の薬の臨床研究に社内のルールなどに違反して関与していた問題で、研究の根幹部分とも言えるデータ解析にも社員が深く関わっていた疑いがあることが関係者への取材で新たに分かりました。
データの管理に責任を負う東京大学病院の医師もこうした関与を了承していた疑いがあることも分かり、医師と製薬会社の関係が改めて問われる事態になっています。
ノバルティスファーマは、高血圧の薬「ディオバン」の効果を調べた臨床研究に、当時の社員が関与したほか、論文のデータが操作された問題を受けて、去年7月、社員は臨床研究に一切、関与しないと公表しました。
しかし、その後も、ノバルティスが販売する白血病の薬「タシグナ」などの副作用を調べる東京大学病院などが行う臨床研究を巡って、ノバルティスの社員が、医療機関から研究データを回収するなどしていたことが分かっています。
さらに研究の根幹部分とも言えるデータ解析にも社員が深く関わっていた疑いがあることが新たに分かりました。
研究に参加していた東京の青梅市立総合病院の医師によりますと、去年4月、研究の事務局を務める東大病院の医師から日本血液学会で研究の中間報告をするよう依頼された直後、ノバルティスの社員が病院を訪れ、研究データの解析結果を渡されたということです。
社員は解釈の方法などを説明し、医師はそれを基に中間報告の資料を作成したということです。
さらに学会で発表する直前の去年9月には、東大病院の医師から、ノバルティスの社員がデータの解析を行うことを了承していたことをうかがわせる内容のメールを受け取ったということです。
この中で東大病院の医師は「昨今の社会事情もあり、臨床試験の結果を製薬会社が解析することは許容されなくなっている」としたうえで、「ノバルティス社の解析でいいと思う点はアイデアを取り入れたいが、医師側で解析した証拠を残しておくことが必要だ」と記しています。
当時、ノバルティスが販売する高血圧の薬「ディオバン」を巡って、社員のデータ解析への関与が問題となっていたことから、対策を講じるよう要請したものとみられ、医師と製薬会社の関係が改めて問われる事態になっています。
青梅市立総合病院の医師は「ノバルティスから解析結果を受けとり、資料を作ったことは軽率な行為で反省している。東大病院の医師とノバルティスが連携していると感じた」と話しています。
これについてノバルティスファーマは、「第三者委員会で調査中なので、コメントを差し控えたい」と話しています。
また東京大学病院は「調査中のため個別の問い合わせには回答を控えたい」と話しています。
厚生労働省は、東大病院とノバルティスの双方から事情を聞くなどしてデータ管理の実態を調べることにしています。
売り上げ確保がねらいか
ノバルティスファーマの元社員は、今回の問題の背景には、競争が激化する白血病の治療薬の市場で、売り上げを確保するねらいがあったと指摘しています。
ノバルティスが販売する白血病の主力薬の「グリベック」は、ことし9月に特許が切れる予定で、特許が切れると、ジェネリック医薬品が発売され、薬の売上げが減ることから、その後のシェアを巡って、すでに競争が激しくなっているということです。
問題の臨床研究は、白血病の治療薬を服用する患者に、ノバルティスが販売する新しい治療薬の「タシグナ」に切り替えてもらい、副作用が軽くなるかどうかなどを調べるものです。
元社員によりますと、ノバルティスの営業部門は、今回の臨床研究の結果を基に「タシグナ」への切り替えを促し、会社の売り上げを確保するねらいがあったと証言しています。
元社員は「臨床研究に積極的に関わっていたのは、他社との競合に勝ちタシグナの売り上げを上げるためだった。社内では、こうした関与について問題だとする声もあったが、評価を気にして従わざるをえない状況だった」と指摘しています。
「医師主導の臨床研究とは言えない」
臨床研究に詳しい臨床研究適正評価教育機構の桑島巖理事長は「公正中立ではなく、医師主導の臨床研究とは言えない。データが企業の手に渡れば、ゆがめられる可能性があり、非常に問題だ」と厳しく批判しています。
また、こうした問題が起きる背景について、桑島理事長は「医師は臨床研究をすれば実績となり、製薬企業は医師が書いた論文を使って薬の販売促進ができるという、長い間の医師と製薬会社のなれ合いが根底にある」と述べ、臨床研究を巡る構造的な問題があると指摘しています。
そのうえで、今後の対策としては、「臨床研究の信頼性を確保するためには、データ解析などの詳細なルールを作り、違反した場合には罰則を設けることも検討すべきだ」と話しています。
東京海上:不払い10万件…自動車保険の一部、公表せず (1/2)
(2/2) 02/06/14(毎日新聞)
東京海上日動火災保険が2003年6月以前に契約した自動車保険で、契約者が本来受け取れるはずの保険金の一部が支払われていない不払いが最大10万件前後あることが6日分かった。生命保険・損害保険業界では05年に大量の保険金不払いが発覚し社会問題化したが、東京海上はこの03年6月以前の契約分の保険金不払いについて、社内調査で把握しながら公表していなかった。
今回、新たに判明したのは、事故で負傷させたり、死亡させたりした相手への損害賠償に充てる自動車保険本体とセットになった「対人臨時費用(臨費)」の不払い。見舞いなどにかかった費用を補償する内容で、契約者は相手が死亡した場合は10万円、入院や通院なら1万〜2万円を受け取ることができた。
東京海上はこの臨費について公表せず、契約者にも通知しなかった理由について「03年6月までは契約者から自動車保険本体と別途、請求があった場合のみ臨費を支払う対応としていたため」と説明。ただ、約款には契約者が別途請求しないと保険金が支払われないとの記載はなく、同社の契約者への対応姿勢が問われそうだ。不払い分については、契約者から請求があれば約款で定めた2年の時効期間が過ぎていても、遅延損害金を上乗せした保険金を支払うとしている。
05年に保険金不払いが社会問題化した際、金融庁は損保各社に02年4月〜05年6月を対象に実態調査をするように指示。東京海上は複数の保険で計約6万3000件の不払いがあったとの調査結果を05〜06年に公表。うち「臨費」は約1万8000件としていた。
しかし、これは本体の自動車事故に関する請求があれば、東京海上から契約者に通知してセットの「臨費」も支払う対応に改めた03年7月以降の分だけだった。03年6月以前の契約分については、「臨費」の支払いに本契約とは別途の請求が必要との対応をしていたことを理由に公表しなかった。東京海上は「運用を変える03年6月以前の契約について(金融庁の調査対象期間となった分だけを03年7月以降と同じ扱いにすれば)契約者に不公平になりかねないと考えた」と説明している。【高橋慶浩】
◇保険金不払い問題◇
保険会社が契約者に本来支払うべき保険金を一部しか支払わなかったり、保険金の支払い請求を不当に拒否したりした問題。2005年に生損保業界で発覚し、金融庁は業務改善命令などを出して改善を求めてきた。最初に発覚した明治安田生命では、社長、会長らの引責辞任に発展した。損保業界では26社で自動車保険などの不払いが約50万件、380億円にのぼっていたことが判明。各社は行政処分を受け、東京海上日動火災は当時の社長が退任した。
ここまでやってこれたのだから佐村氏はかなりの役者だ!どんな気持ちでインタビューを受けていたのだろうか?
曲一部でも…佐村河内氏「イメージだけ」と返事 02/06/14(読売新聞)
両耳の聞こえない作曲家として話題を集めていた 佐村 ( さむら ) 河内 ( ごうち ) 守さん(50)が、別の作曲家に楽曲の制作を依頼していたことが明らかになった5日、コンサートの中止や関連書籍の販売取りやめなどが相次ぎ、波紋が広がった。
ファンから「信じたくない」と驚きの声が上がる一方、ソチ五輪で楽曲を使用する予定のフィギュアスケートの高橋大輔選手(27)側は「プログラムを変更しない」と明らかにした。
◆認めるメール
「ヴァイオリンのためのソナチネ」の楽譜を11日に出版予定だった楽譜出版社「東京ハッスルコピー」の関係者の元には2日、佐村河内さんから自身の作曲ではないことを認めるメールが届いた。
同社関係者は「メロディーの一部でも作っていれば出版は可能」と返信したが、佐村河内さんからは「私はイメージなどをゴーストライターに伝えただけ」という返事だった。これを受け、4作品の出版とレンタルを中止した。
2010年以降、楽曲を演奏してきた東京交響楽団の大野順二楽団長は、「作曲家は通常、リハーサルに姿を見せるが、彼は来たことがなかった」と打ち明けながら、「観客からの反応も極めて良い楽曲だったのでショックだ」と語った。
◆「損害賠償を請求」
「交響曲第1番」の全国ツアーを企画していた音楽事務所「サモンプロモーション」は5日、今後予定していたコンサート計15公演(オーケストラ10公演、ピアノリサイタル5公演)の中止を発表。販売済みチケットは払い戻しに応じるという。
2月と3月にそれぞれ長崎と福岡で同曲を演奏するはずだった九州交響楽団も、突然の中止連絡を受けて対応に追われた。「数百万円規模の収入減になる。主催者には損害賠償を請求する」と事務局は困惑する。
昨年5月、佐村河内さんの著書「交響曲第一番 闇の中の小さな光」を出版した幻冬舎は、絶版を決定。東京・銀座のCD・楽器販売店「ヤマハミュージックリテイリング銀座店」では、午前11時の開店前にCDを店頭から撤去した。
◆市民賞取り消しも
「CDを借りて何度も聞いたのに……」。東京都新宿区の音楽ショップにクラシックレコードを探しに来ていた会社員(51)は言葉を失った。佐村河内さんのドキュメンタリーなどを見て、非常に苦しみながら音楽を作る姿に感動しただけに、「信じたくない」と驚きを隠せない様子だった。
一方、聴覚を失いながらも被爆体験の継承と核兵器廃絶を訴える活動を評価し、2008年に「広島市民賞」を授与した広島市。松井一実市長は5日、「思いも寄らぬことで驚いている」と述べ、作曲が本人でないと確認できれば、賞を取り消す考えを示した。
ピアノ講師の経験もある同市の会社員(61)は「ヒロシマの思いを込めて素晴らしい曲を届けてくれただけに残念。『ベートーベン』とまで称されたことが負担になったのでは」と推測していた。
機構が入札参加依頼、価格も漏洩か…新幹線談合 02/05/14(読売新聞)
北陸新幹線の雪害対策工事を巡る談合事件で、入札に参加した設備工事会社数社の担当者が東京地検特捜部の事情聴取に対し、発注元の「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」東京支社の部長クラスから「入札に参加してほしい」と依頼されたと供述していることが、関係者への取材でわかった。
特捜部などは、談合で形骸化した入札が適切に行われているように装うため、機構側が入札参加業者を募った可能性があるとみている。
特捜部と公正取引委員会は4日、新日本空調など入札参加業者のほか、機構本社(横浜市)と東京支社(東京都港区)も独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で捜索した。問題の入札では、機構支社の課長クラスが予定価格を漏えいしていた疑いも浮上しており、官製談合防止法違反(職員による入札妨害)にあたるかどうか慎重に調べる。
JR北の大量処分 労使なれ合いの闇深く 根本問題手つかずのまま (1/3)
(2/3)
(3/3) 09/26/13(イザ!)
7割を超える保線担当部署でのレール検査データの改竄(かいざん)や270カ所のレール異常放置が明らかになり、75人が処分されたJR北海道。社内調査や国土交通省の特別保安監査の結果では、要員不足に伴う業務効率の低下や現場に対する本社の関心の薄さなどが問題の背景として指摘されたが、国会で度々追及された労使間のなれ合いに関する部分はなく、関係者から不満も漏れる。21日の公表から28日で1週間。組織の根幹に触れないまま出された事業改善命令などに波紋が広がる。
JR北海道は21日、44ある保線担当部署のうち33部署で改竄が行われていたとする社内調査結果を発表。長年のレール異常放置の隠蔽(いんぺい)目的や前任者からの引き継ぎなどが動機とされ、安全軽視の根深い体質があらためて浮き彫りになった。
JR北海道や特別保安監査を行った国交省は、背景の一つとして、合理化によるベテラン社員の減少で技術伝承が不十分になっていた点を指摘。若手が多い現場での作業効率の低下で、補修の遅れや後回しが常態化し、補修の必要がないよう検査データを基準内に改竄する素地が醸成されていったとみられる。
また現場実態に関心が薄い本社の姿勢も問題視した。
増員要求など現場の声が反映されない硬直化した予算編成や業務方針は、現場での意欲低下に作用したとしている。ただ、改竄には「根深いものがある」(国交省)としている。
■影響改めて否定
社内調査結果には、昨秋の国会で問題視された労組に関する検証や記述は見当たらない。
野島誠社長らが参考人招致された集中審議では、4つある労組のうち、約8割を占めるJR北海道労組への遠慮やなれ合いが問題の背景にあるとの疑いが指摘されたが、野島社長はそうした見方を否定。21日の会見でも「一連の事象に対して(労組が)影響しているとは考えていない」と改めて否定した。
一方、データ改竄をめぐっては、一部の労組から平成3年と10年の2度の労使交渉で、改竄が横行しているとの訴えが寄せられた。しかし会社側は「事実確認ができない」と回答し、訴えが生かされることはなかった。
労組関係者は「会社側は人員削減に協力した主要労組には干渉せず良好な関係を保ってきた」と指摘。その上で「労使関係については鉄道利用者の関心も高いだけに、しっかり検証すべきだった」と不満を口にした。
■経営陣の行方は
経営陣の行方も不透明感を増している。太田昭宏国土交通相は21日の会見で「現経営陣の責任は重いが、改善命令や監督命令を全力で推進するのが望ましい」と続投を事実上容認した。後任人材が見つからないほか、経営に影響力がある坂本真一相談役が15日に自殺とみられる遺体で見つかったことも、経営陣の入れ替えに躊躇(ちゅうちょ)する要因になったとみられる。
しかし政府内には「労組とのしがらみのない外部人材を起用すべきだ」との意見は根強い。JR北海道の株式は独立行政法人「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」が全て保有しており、政府による経営への関与は可能。代表権を持つ役員人事は閣議口頭了解を経て決まることになっており、今後は政府主導による経営陣の刷新が行われるとの観測もある。
経営面でも年300億円に上る赤字の解消は手つかずのままで、JR会社法に基づき経営体制を改善させる初の監督命令や経費がかかる事業改善命令などを不安視する向きは少なくない。
国のロボット研究費流用、富士重元部長に逮捕状 01/27/14(朝日新聞)
経済産業省などから委託されたロボットの研究開発費などを不正に流用したとして、栃木県警が、富士重工業(東京)宇都宮製作所の50歳代の元部長について、詐欺容疑で逮捕状を取ったことがわかった。
27日にも逮捕する。
捜査関係者によると、元部長は、取引先への架空発注を繰り返すなどして同省の委託金を不正受給し、約200万円をだまし取った疑いが持たれている。富士重工業は2012年2月、元部長が約1億600万円の不正経理を行い、取引先に一部をプールしたり自身が設立に関与した企業に資金を流したりしていたとして、詐欺容疑で県警に告訴し、懲戒解雇にしていた。
元部長は02年から清掃ロボットを開発するクリーンロボット部長を務め、10年に退職した後も嘱託社員として指揮を執っていた。富士重工業は04~10年度にかけ、同省や科学技術振興機構などからロボット研究開発など8事業で計10億5600万円の委託・補助金を受給している。
甘利経済再生相パーティー券、電力9社覆面購入 01/27/14(朝日新聞)
原発を持つ電力各社が2006年以降、原発再稼働を訴える甘利明経済再生相のパーティー券を水面下で分担して購入してきたことが朝日新聞の調べで分かった。平均的な年間購入額は数百万円とみられるが、各社の1回あたりの購入額を政治資金規正法上の報告義務がない20万円以下に抑えていた。法律の抜け道を利用し、資金源の表面化を防いだものだ。
電力会社役員が自民党に個人献金していることは判明しているが、電力各社が電気料金を原資にパーティー券を分担購入していたことが明らかになるのは初めて。
複数の電力会社幹部によると、甘利氏が電力会社を所管する経済産業相に就いた06年、電力9社は1回あたり約100万円分のパーティー券を分担購入。各社担当者が協議し、事業規模に応じて分担額を決めた。この枠組みは翌年以降も続き、東電などの関連会社が加わることもあった。東電は11年の原発事故後にやめたが、他の8社はほぼ同じ金額で購入を続けてきたという。
「放送局から原発に触れないよう言われたのは事実ですが、命令口調ではなかったのです。」命令調でなくても、仕事に関係していれば全く圧力が無かったとは言えないと思う。ピーター・バラカン氏の受け取り次第だが、仕事に固執していればこのような発言はしなかった。原子力反対派としては反原発運動に関するアピール出来る材料が出来たので必要以上に騒ぐ。最近、新聞紙の広告が目立つ。メディアの収入が落ちて、スポンサーに大きく頼れば、真実であっても言いたい事が言えなくなる。これが現実だろう。
「原発に触れるな」 ピーター・バラカンへの“圧力”の真相 01/24/14(日刊ゲンダイ)
「まだ告示もされていないのに、都知事選が終わるまで原発に触れないよう、他の2つの放送局で言われました」
英国出身のフリーキャスター、ピーター・バラカン氏(62)の発言が波紋を広げている。この発言は同氏のレギュラー番組「バラカン・モーニング」(インターFM)で飛び出したものだ。
圧力を受けたと解釈され、ネットでは原発反対派から「公表してくださったピーターさんとinterFMの英断に敬意を表します」「世論って、こうやって操作されるんだな。怖い」などの書き込みが相次いだ。
ただ、当のバラカン氏は当惑気味で、日刊ゲンダイ本紙の問い合わせにこう回答した。
「放送局から原発に触れないよう言われたのは事実ですが、命令口調ではなかったのです。スタッフから“あまり触れないでくださいね”と言われた程度だったのに、僕の言い方のせいで過大に解釈されてしまいました。みなさんをお騒がせして申し訳なく思っています」
バラカン氏は反原発の姿勢を打ち出していることで有名だ。
07年に反原発集会で、日本のマスメディアはスポンサーに気を使って原発報道を自主規制していると痛烈に批判。原発事故後のインタビューではこう発言している。
<原発のある町の子どもたちは、小学生のうちに社会科見学で原発に行って、お土産なんかもらって、いかに安全かということが刷り込まれてるから、まさかこんなことが起きるとは思っていない。悪く言えば洗脳だと思う。どこの国でもプロパガンダというのはしょうがないですよね。小さいうちに刷り込まれていると、なかなかそれを乗り越えるのは難しいことだと思う>
<そもそもこれだけ地震の多い国に、50基以上もの原発を造ったということに驚きますね>
反原発デモをテレビがあまり報じないことについては、天安門広場のデモをメディアが報じない中国や北朝鮮と「本当に似ていると思う」と切り捨てていた。
それだけに、“やんわり”とはいえ、“バイアス”がかかったのだろう。
「都知事選があり、局としては(原発に)触れられると困るのでしょう。こうしたことは日本の放送の世界では当たり前のように行われてきた。すべての放送局に当てはまります」とバラカン氏。
この国のメディアの底が割れる話である。
ノバルティス社:白血病薬試験 計画書にも社員が関与か 01/24/14(毎日新聞)
◇電子ファイルに社名
製薬会社ノバルティスファーマの社員が自社の白血病治療薬の臨床試験に関与していた問題で、複数の社員が実施計画書や患者の同意書の作成に関わった可能性があることが関係者への取材で分かった。試験開始前から社員が準備に加わっていたとみられる。研究チームは企業の支援を受けない前提で医療機関の倫理委員会から実施の承認を得ており、ノ社と研究の中心となっている東京大病院が調査している。
試験関係者が、試験で使う書類の電子ファイルを調べたところ、試験の目的や進め方を定めて倫理委員会の承認を得る「実施計画書」や、医師が患者に渡す「患者同意書」の作成者情報の中に「Novartis(ノバルティス)」との表記があったという。文書の作成や更新にノ社の関係者が関与した疑いがあるという。
一方、実施計画書には「研究の計画、実施、発表に関して可能性のある利益相反はない」と明記され、研究チームはノ社から資金や人的な支援を受けないことを表明していた。
ノ社は、書類の電子ファイルに社名があったことについて「第三者による調査結果を待ちたい」とコメント。東京大病院は取材に「調査中で回答を控えたい」としている。ノ社が2012年度に、臨床試験の責任者を務める東京大病院の黒川峰夫教授の研究室と参加7医療機関に奨学寄付金計1100万円を出したことについては、ノ社と東京大病院は「試験とは直接関係がない」と説明している。
試験は12年5月に始まった。白血病患者が服用する薬をノ社の新薬に替え、副作用の違いを患者へのアンケートなどから調べている。全国の22医療機関が参加する。
この試験では、営業担当の社員8人が本来は医師間で行うべき患者アンケートの受け渡しを代行。アンケートを多く集めるほどコーヒー店の金券などを受け取れるルールで競い、上司も認識していた。ノ社は降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験疑惑への批判から「研究者が実施すべき業務に社員は関与しない」との再発防止策を昨年7月に示したが、社員によるアンケートの回収は続いていたという。【八田浩輔、河内敏康】
ノバルティス社:研究に社員関与謝罪 再発防止策にも違反 01/23/14(毎日新聞)
製薬会社ノバルティスファーマの社員が自社の白血病治療薬の臨床試験に関与していた問題で、同社が23日東京都内で記者会見を開き、降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の疑惑を巡って自ら定めた再発防止策に違反したことを謝罪した。二之宮義泰社長は「再びこのような事態を招いたことは言い訳のしようがない」と述べ、外部専門家らの調査委員会を設置すると明らかにした。
白血病治療薬の臨床試験は、東大病院の黒川峰夫教授が責任者を務め、22医療機関が参加して2012年5月に始まった。患者が服用する薬をノ社の新薬に替え、副作用の違いを患者へのアンケートなどから調べている。
ノ社によると、営業社員8人が本来は医師間で行うべき患者アンケートの受け渡しを代行。アンケートを多く回収したグループがコーヒー店の金券や会食代など計3万4000円分をもらえるというルールを作って13年6月まで競い、部長級の上司も承知していた。また、試験の研究者の会議場所として営業所の部屋を提供していた。
ただ関与が組織ぐるみだったかなどの詳細については「調査結果を待ちたい」などと繰り返した。
ノ社はバルサルタンの疑惑への批判から「研究者が実施すべき業務に社員は関与しない」との再発防止策を昨年7月に示したが、社員によるアンケートの回収は同12月まで続いていた可能性があるという。
問題の発覚後、東大病院はデータを確認しているが、今のところ改ざんなどは見つかっていない。ノ社は12年度、黒川教授の研究室と参加7医療機関に計1100万円の奨学寄付金を提供していたが、ノ社と東大病院は「寄付は臨床試験とは直接関係しない」と説明している。【八田浩輔、河内敏康】
不正行為が社員教育として叩き込まれてきた証拠。安全軽視も問題はかなり根が深い。
データ改ざん「先輩から教わった」…JR北海道 01/23/14(読売新聞)
JR北海道のレール計測データ改ざん問題で、国土交通省の特別保安監査で改ざんが確認された八雲保線管理室(北海道八雲町)では、補修の基準値を超えた異常箇所のデータを、すべて基準内ギリギリの数値に改ざんしていたことが分かった。
改ざんした社員2人は調査に「前任者の先輩社員から教わったので、悪いことだと思わなかった」などと話しているという。
同社は2人を「先輩社員からの引き継ぎで行われ、悪質性が低い」などとして、社内規定上の懲戒処分(戒告以上)とはせず、口頭または厳重注意処分とした。
同社によると、改ざんしていたのは、列車の進路を変更する「分岐器」(ポイント)部分で、左右のレールの高低差などを測ったデータ。規定では、正規の高さなどからプラス7ミリ~マイナス7ミリを超える異常があった場合、15日以内の補修が義務づけられていた。
しかし、2人は昨年6月と9月、7ミリを超えたデータを全て、補修の必要がない7ミリぴったりに改ざんし、補修も行っていなかった。6月以前の計測データは残っておらず、改ざんがいつから行われたのかは分かっていない。2人は「全てのデータを7ミリに収めるよう、前任者から口頭で引き継ぎを受けていた」などと話したという。
JR北海道、相次ぐ事故…東大卒56歳エリート社長の落とし穴 (1/3)
(2/3)
(3/3) 09/26/13(イザ!)
計267カ所でレール異常の放置が明らかになったJR北海道。経営トップとして事態の収束を図る野島誠社長(56)は同社で17年ぶりとなる技術畑出身の社長として期待されながら、今年6月の就任以降、脱線など相次ぐ事故で頭を下げ続けている。国鉄分割民営化後の早い段階から「将来の社長」と注目されたホープは、この難局をどう乗り切るつもりなのか。
「お客さまにご迷惑をおかけし、おわびしたい」。野島氏は22日の会見で深々と頭を下げた。
国鉄時代から野島氏を知るJR関係者が語る。
「大学で土木工学を学んだ知識を生かし、線路の敷設や保守管理で活躍していた。特に気温などの環境で大きく変化するレールの状態に詳しく、『レールのスペシャリスト』という印象が強い。それだけに、レールの異常を200カ所超で放置してきた問題には非常に驚いた」
野島氏は1956年生まれ、横浜市出身。79年、東京大工学部を卒業後に国鉄へ入社した。東北新幹線など最新技術を導入した大規模工事の進行に影響を受け、国鉄入りへの気持ちを強くしたという。
87年の国鉄分割民営化でJR北海道に配属された。「国鉄時代、北海道赴任中に奥さんと知り合った。そんな縁もあってJR北の配属になったのだろう」(知人)。JR北でも技術畑を歩んだが、働きぶりが評価された90年、投資計画室への異動が転機に。その後は財務課長、経営企画部長、財務部長など会社経営の根幹に関わり、「人の話をよく聞くタイプ。早い段階から将来の社長と目されていた」(同)との証言がある。
常務を経て昨年、専務に。今年6月、満を持して社長に就任した。
前任の小池明夫現会長は、2011年9月に中島尚俊社長(当時)が急逝したのを受けて再登板していたため、リリーフ色が濃かった。期待の本格派トップで、JR北としては17年ぶりに誕生した技術畑出身の社長。野島氏は就任時、事故やトラブルを受けて「現場の技術継承」を課題に挙げ、「若手の採用増や退職者の再雇用を進め、社員を育てやすい環境をつくる」と意気込んでいた。
ところが、就任直後の7月、特急列車の出火トラブルが続発。そして今月、貨物列車の脱線事故をきっかけに、計267カ所でレールの異常を放置していた実態が明らかになった。
企業の危機管理に詳しい広報PR・危機対応コンサルタントの山見博康氏は「超エリートに多い典型的な経営トップ」と分析する。
「現状を否定できず、悪い慣習を破ることをためらうタイプといえる。大企業では摩擦を起こす人材は上から遠ざけられる。超大企業ほど『マニュアル通りにやっています』という困った超エリートが多い。環境は景気や技術革新、業績といった要因で常に変わる。経営トップは変化に対して敏感になり、安全などのマニュアルは柔軟に更新するよう指示しなければならない」
緊急時に必要なのは、能吏よりも現状を打破できるリーダー。人の命を預かる仕事に、ずさんな対応は許されない。
JR北、解雇5人含む75人大量処分 数値改ざん33部署に拡大 01/21/14 (産経新聞)
JR北海道は21日、レール検査数値改ざんにからみ5人の解雇や、野島誠社長ら経営陣の役員報酬減額を含めた計75人の大量処分を発表した。同時に公表した社内調査結果によると、44ある現場の保線部署のうち改ざんが確認されたのは33部署で、判明済みの9部署から大幅に増えた。
保線担当者約800人のうち約16%に当たる社員が「改ざんした経験がある」と認め、約20年前から改ざんがあったと話す担当者もいた。記者会見した野島氏は「安全な鉄道をつくり上げることが使命だ」と述べ、辞任を否定した。
改ざんは昨年9月に函館線大沼駅で起きた貨物列車脱線事故後に発覚。JR北海道は現場を管轄する大沼保線管理室(七飯町)で改ざんに関与した2人を懲戒解雇とし、上部組織に当たる函館保線所の所長ら3人を諭旨解雇とした。役員報酬減額は3カ月で、減額幅は小池明夫会長と野島氏が50%、保線業務を統括する取締役の笠島雅之工務部長と常務3人が30%、その他の取締役が20%。
JR北 大量処分 国交省、異例の5年監査 指導不備反省、抜き打ちで 01/21/14 (産経新聞)
JR会社法に基づく初の監督命令など3つの行政命令を通知した国土交通省は21日、JR北海道に対し今後5年間監査態勢を継続する異例の方針を打ち出した。過去に命令を出しながら指導が行き届かず今回の事態を招いたとの反省からだ。太田昭宏国交相は記者会見で「輸送の安全が阻害され、自助努力による改善が難しい」とJR北海道の組織体質を批判したが、命令の実施状況をチェックする国交省も監督官庁としてのあり方を問われている。
「鉄道事業者としてあってはならない異常な事態が続き、基本的な資質が一から問われている」。国交省での会見の冒頭、太田国交相は相次ぐレール検査データ改竄(かいざん)などを挙げ、JR北海道を取り巻く危機的な状況をこう総括した。
会見では、昨年9月からの特別保安監査の結果に基づいて国交省がまとめた「JR北海道の安全確保のために講ずべき措置」と題する冊子が配布された。冊子では、昨年9月の貨物列車脱線事故直後に行われたデータ改竄について「鉄道事業者としてあるまじき重大な問題。絶対容認できない」と厳しく指弾。
JR北海道が講ずべき措置として、第三者による安全対策監視委員会(仮称)の設置▽安全管理の再構築▽技術部門の業務実施体制の改善-などを指示した。
国交省としても設備投資支援の前倒しや関係法令の厳格な適用を行うと表明。その一環として、太田国交相は「(改竄について)北海道警に刑事告発の相談をしている」と明らかにした。
国交省は過去の反省を踏まえた再発防止策も行う。平成23年5月の石勝線特急脱線火災事故の際、避難誘導に問題があったとして同6月、1度目の事業改善命令を出し、JR北海道も社員教育の強化などを盛り込んだ行動計画をまとめ、国交省に提出した。
しかし、今回の改竄問題では当時の教訓や行動計画は生かされなかった。こうした事態を繰り返さないよう、国交省は今後5年間にわたって抜き打ち式で監査を継続させ、50人態勢でチェックを強化する。
■最後の改革チャンス
日大の綱島均教授(鉄道工学)の話「2回目の事業改善命令は、石勝線の特急脱線火災事故で最初の命令を受けた後、企業体質を改善しなかったからだ。現場担当者は補修を先送りしてもいいといった勝手なルールをつくっていた。そのような状況が常態化し、引き継がれていたのは考えられない。JR北海道は今回の命令が会社を抜本的に改革する最後のチャンスだと思った方がいい。社員に甘い姿勢を改めなければ、鉄道会社としての歴史を終えることになるだろう」
■不退転で安全確立を
交通評論家の佐藤信之さんの話「社内調査によって、個人だけでなく組織全体の安全意識の低さが改めて浮き彫りになった。事業改善命令を受け、JR北海道が利用者である道民の声を反映させた実効性ある改善計画をつくれるかが鍵だ。今回は社会、経済への影響も大きい。計画を立てる段階で第三者機関をつくり、計画を幅広くチェックする仕組みが不可欠だ。第三者機関には自治体関係者も参加し、審議内容を住民に伝えるべきだ。不退転の覚悟で安全確立に取り組んでほしい」
JR北海道に改善命令などの処分方針 01/21/14 (NHK)
太田国土交通大臣は閣議のあとの記者会見で、レールの検査データ改ざんなど一連の問題を巡って、JR北海道に対し鉄道事業法に基づく「事業改善命令」と、JR会社法に基づく「監督命令」などの処分を出す方針を明らかにしました。
この中で太田国土交通大臣は、JR北海道によるレールの検査データ改ざんなど一連の問題について、「JR北海道は鉄道事業者としての基本的な資質を一から問われている状況だ。社を挙げて深く反省する必要があり、企業体質や組織文化を含めて、構造的な改革が必要だ」と述べました。
そのうえで太田大臣はJR北海道に対し、▽鉄道事業法に基づく「事業改善命令」と、▽安全統括管理者の役員を役職から解くよう命じる「解任命令」、▽それに、JR会社法に基づく「監督命令」の処分を出す方針を明らかにしました。
国土交通省はこうした方針を21日会社側に通知し、22日以降、正式に処分することにしています。
JR北海道に「事業改善命令」が出されると、3年前の特急列車の脱線と火災による処分に続いて2度目になりますが、同じ鉄道会社が2度の命令を受けるのは前例がなく、またJR会社法で「監督命令」が出されるとこれが初めてになります。
太田大臣は経営陣について、「経営陣に求められている責任は、一刻も早く利用者の信頼を回復することだ」と述べ、まずは安全の確保を最優先すべきだという考えを示しました。
さらに太田大臣は、データの改ざんを巡って担当者らを刑事告発するかについては、「特別保安監査の結果を踏まえ北海道警察本部と相談している」と述べました。
また、国土交通省はJR北海道に対し、第三者による安全対策監視委員会の設置を求めるとともに、21日、国土交通省に常設の監査チームを設置し、今後、5年ほどの期間にわたり定期的に監査することで、改善が進んでいるか確認していくことにしています。
このほか、ATS=自動列車停止装置をハンマーでたたいて壊した運転士について、免許を取り消す方針を明らかにしました。
同じ会社に2度の命令は異例
安全管理の問題を厳しく問う国の事業改善命令が同じ鉄道会社に2度出されるのは初めてで、深刻な事態と言えます。
事業改善命令は、一連の問題でこれまでに3度出された改善指示と異なり、違反すると懲役や罰金が科される重い処分です。
鉄道事業法が施行された昭和62年以降、6回出され、このうち、▽平成13年には京都府の京福電鉄に、▽平成15年にはJR東日本に、▽平成16年にはJR西日本に、▽平成18年には千葉県の銚子電鉄に、▽平成20年には長崎県の島原鉄道に、▽3年前にはJR北海道に出されていて、過去、同じ会社が2度、命令を受けたことはありません。
また、命令には、国土交通大臣が命じるものと、各地の運輸局長が命じるものの2種類あり、より重大なケースについては大臣が命じています。
過去の命令のうち、大臣によるものは2回で、▽平成15年、JR東日本に命じたケースは、都内の中央線と京浜東北線で行われていた線路工事で配線ミスなどの問題が相次ぎ、ダイヤに大きな影響が出たものです。
▽3年前、JR北海道に出されたケースは、特急列車が脱線しトンネル内で火災を起こした事故に対するもので、乗務員のマニュアルの不備が乗客への誘導や避難の遅れにつながったとして改善を命じました。
今回の命令は国土交通大臣によるもので、しかも前例のない2度目の命令で、深刻な事態と言えます。
監督命令は初 経営陣の意識も問題
国がJR会社法を初めて適用するのは、問題が一部の社員にとどまらず、JR北海道の経営陣の安全に対する意識の問題だと考えたからです。
JR会社法は、昭和62年の国鉄民営化にあわせて作られた法律で、完全民営化したJR東日本、東海、西日本と異なり、国が出資する独立行政法人が株式のすべてを保有しているJR北海道、四国、九州、貨物の4社が対象です。
社長など役員の選任や事業計画の決定には国の認可が必要とされ、国土交通省は各社を監督し、必要な命令を出すことができるとされています。
一連の問題では、安全に関わる予算の確保が不十分だったり、経営陣も出席する「安全推進委員会」が機能していなかったりするなど、経営陣の意識改革も課題として指摘されています。
このため今回、事業改善命令とあわせ監督命令も出すことになりました。
JR会社法に基づく監督命令は、JR発足以来、今回が初めてで異例の対応と言えます。
JR北 改ざん歴代担当者で引き継ぐ 01/21/14 (NHK)
JR北海道を巡る一連の問題で、レールの検査データの改ざんが歴代の担当者の間で引き継がれ、常態化していたことが、国の監査で分かりました。
国土交通省は、抜本的な対策が必要だとして、21日、会社に通知する事業改善命令に併せ、会社の安全部門のトップを解任するよう命じる方針です。
JR北海道では、去年9月に起きた貨物列車の脱線事故をきっかけに、補修が必要なレールを各地で放置していた問題が発覚し、その後、検査データの改ざんも明らかになりました。
国土交通省の特別保安監査で、JR北海道では、問題のあるレールの補修を先送りする方法として、データの改ざんが歴代の担当者の間で引き継がれ、多くの現場で常態化していたことが分かりました。このため国は、抜本的な対策が必要だとして、鉄道事業法に基づいて、21日、会社に通知する事業改善命令に併せ、会社の安全部門のトップの「安全統括管理者」を解任するよう命じる方針です。
「安全統括管理者」は、兵庫県尼崎市で107人が死亡したJR福知山線の脱線事故をきっかけに、安全管理を強化するため新たに導入されたポストで、国が解任するよう命じるのは今回が初めてです。また、会社の経営にも重大な問題があるとして、今回初めて、JR会社法に基づく監督命令も出す方針で、国土交通省は会社から意見を聞いたうえで、正式に処分することにしています。
国交相、JR北へ行政処分…社内体制抜本改善へ 01/21/14 (産経新聞)
JR北海道でレール計測データが改ざんされるなどした問題を巡り、太田国土交通相は21日の閣議後記者会見で、同社に対し、JR会社法に基づく監督命令などの行政処分を行うと公表した。
鉄道事業法に基づいて、豊田誠・鉄道事業本部長を同社の安全業務を統括する「安全統括管理者」から解任するよう命じた上で、安全面などを監視させる外部有識者組織の設置も指示。社内体制を抜本的に改善させ、再発防止を図る。
一方、JR北海道は同日午後、野島誠社長が記者会見し、約800人の保線担当社員を対象に行ったレール計測データの改ざん問題に関する社内調査の結果と、改ざんに関わった社員の処分を発表する。改ざんには数十人が関与したとみられる。
JR北海道の“ドン”坂本真一氏自殺で、どうなる巨大利権「北海道新幹線」計画の未来 01/20/14 (日刊サイゾー)
JR北海道の“ドン”自殺で社内は騒然となっている。関係者間では悲しみをよそに「北海道新幹線の計画が頓挫してしまう」という動揺が広がっている。
15日の朝、北海道余市町の港内で男性の遺体が浮いているのが見つかった。北海道警察は男性を、元JR北海道社長の坂本真一相談役だと特定。目立った外傷がないことから自殺とみている。直前、坂本相談役は関係者間で行方不明が伝えられたばかりだった。
坂本相談役は、社内で“ドン”と呼ばれる超大物だった。1964年に旧国鉄に入社し、JR北海道発足後は96年に社長に就任。03年に会長、07年に相談役となったが、社内を大きく動かす派閥のトップとして大きな力を発揮していた。
「JR北海道は会長派、社長派の二大派閥に分かれていて、長年その対立こそが、ここ最近起こっている諸々の問題の原因でもあったんです。会長派は小池明夫会長の派閥で、社長派は坂本相談役が後ろ盾となり中島尚俊社長が率いていましたが、中島社長は2年前に脱線事故の責任を問われている中で自殺。小池会長が一時、社長を引き継いでいたんですが、坂本相談役の巨大な力が働いて、昨年の夏、野島誠氏が新社長に就いたんです」(JR北海道関係者)
ずさんな安全管理で事故が多発、レール検査データの改ざんも発覚するなど渦中のJR北海道だが、責任者である野島社長は10日に入院、16日に予定だった定例記者会見を延期したばかりだった。
「この会見では、レール検査データ改ざんの調査結果が公表される予定だったのですが、その内容をめぐって水面下では役員たちが紛糾していたんです。急な入院は時間稼ぎだろうという見方がされていた」(同)
その背景に見え隠れする社内の権力闘争に、坂本相談役が悩まされていたという話もある。
「不祥事を機に対立派が実権を握ろうとしていて、そうなると北海道新幹線の誘致をめぐる利権が持っていかれてしまうという構図があった」と関係者。
北海道新幹線はもう40年も前に計画されながら、巨額の資金が投じ続けられてきた利権のバケモノ。来年、青森から函館まで6,000億円近くかけてやっと開通の予定だが、計画では札幌までの延伸で20年後まで工事が続き、その額2兆円は下らないという予測がある。
「JR北海道は何百億も赤字で、新幹線自体が必要とはいえないのですが、自民党の土建族議員の利権としてはこの上なく莫大なもので、複数の大物議員がそれぞれ大手ゼネコンを率いて社内の派閥を引っ張り合っていましたし、坂本相談役がこのまま権力を失えば、あらゆるところに損失が出るという緊迫した状況でした」(同)
社長派の役員たちからは、“完成すれば儲かる”と信ぴょう性のない話が延々と聞かれた北海道新幹線だが、反対意見を封じ込める役目も担っていたとされる坂本相談役の自殺で、状況はさらに混迷してきた。JR北海道の最大の問題である社内の権力闘争は、死者を出しても解消する気配はない。
(文=鈴木雅久)
JR北改竄問題で菅長官、事業改善命令を調整 「法に基づき厳正に対処する」 01/20/14 (産経新聞)
菅義偉官房長官は20日の記者会見で、JR北海道のレール検査数値改ざん問題に関し、国土交通省が鉄道事業法に基づく事業改善命令やJR会社法による監督命令を出す方向で調整していることを明らかにした。「法律に基づき、できるだけ早く厳正に対処する方針だと報告を受けている」と述べた。
同社経営陣や社員に対する刑事告発についても「国民の公共安全輸送機関であり、国交省が厳正に対処する」として検討する考えを重ねて示した。
推計年間1710万円の報酬を捨てても原発に反対するのなら小泉純一郎元首相も悪くはない。長いものには巻かれた方が得な事は多いのかもしれないが、人間としては立派でない。損をすると分かっていてもそのような行動を取るのであれば立派だと思う。何をするのか、どのような行動をとるかは本人の人格とおかれた環境次第!
1700万円の顧問報酬も剥奪 財界が小泉シンクタンクを兵糧攻め (1/3)
(2/3)
(3/3) 01/19/14(日刊ゲンダイ)
「こうなったら、兵糧攻めだ!」――。財界の大物たちの間で物騒なセリフが飛び交っている。攻撃の的は小泉純一郎元首相(72)だ。都知事選で細川元首相とタッグを組んで「原発即時ゼロ」を訴えていることに、財界はカンカン。政界引退後も小泉にヒト・モノ・カネをたっぷりと与えてきただけに「裏切り者は許さん」と、全面戦争の気配だ。
東京・日本橋の三井本館。国の重要文化財に指定されている建物の5階に小泉は現在、個人事務所を構えている。同じフロアに「国際公共政策研究センター」というシンクタンクがあり、その顧問を務める小泉に提供された部屋だ。
「センターの設立は07年3月。小泉氏の首相退任後、経団連会長だったトヨタの奥田碩元会長の呼びかけで誕生したシンクタンクです。小泉氏の労をねぎらうとともに、今後の活動をサポートするのが目的で、奥田氏が中心となって国内の主要企業80社から約18億円の設立資金を集めました」(経団連関係者)
センターの会長には奥田氏が就任。理事はキヤノンの御手洗冨士夫会長兼社長など、毎年の運営費を提供する大企業のトップが務める。問題はそのメンバーで、原子炉プラントのトップメーカーである日立やIHIなど原発関連企業のトップが名を連ねているのだ。
「そもそもセンター設立時にはトヨタ、キヤノンのほか、新日鉄と東京電力が発起人となり、この4社で1億円ずつ捻出した。東電はもちろん、新日鉄の三村明夫元会長は経産省の総合資源エネルギー調査会会長で、原発推進の旗振り役。彼らにすれば、脱原発にシャカリキになっている小泉氏には“恩知らず”という心境でしょう」(前出の経団連関係者)
小泉が「脱原発」を決意したのは昨年8月、フィンランドの核廃棄物最終処分場「オンカロ」を視察したのがきっかけとされる。この視察だって「センターの運営費で賄われた」(財界筋)ともっぱらで、財界の原発推進派は「よくもまあ、俺たちのカネで」と歯がゆい思いのはずだ。
「このままでは、センターの運営費提供をやめる企業が続出しそうです。センターの設立時には『7年間、活動する方針で資金を集めた』ともいわれており、今年が節目の7年目。資金ストップの“大義”は立ちます」(経済ジャーナリスト)
かつて小泉はセンターから推計年間1710万円の報酬を得ていると報じられた。センターの事務局によると、年2回の理事会と年1回の総会への出席のほか、シンポジウムでの講演や、計14人の研究員らと不定期で意見交換しているという。この程度の働きで高額報酬や事務所のほか、専用の送迎車まで用意されているというから、いいご身分である。センターの今後について、事務局は「企業の資金提供が続く限り存続し、その決議は次の理事会で行います。次の理事会の日程? それは教えられません」と答えた。小泉が財界に対してどう反撃に出るのか見モノだ。
ノバルティス関与の臨床研究 いったん中断 01/17/14 (NHK)
大手製薬会社「ノバルティスファーマ」の複数の営業社員が、社内で、営業社員は臨床研究に一切関与しないと決めたあとも、自分の会社が販売する白血病の薬の臨床研究に関与していた問題で、研究の代表を務める東京大学病院の医師は、研究の信頼性が確認されるまで、いったん研究を中断する方針を示しました。
問題になっているのは、ノバルティスなどが販売する白血病の治療薬の副作用について、東京大学病院など22の医療機関が参加して調べている臨床研究です。
この臨床研究では、データの信頼性を保つ目的などで実施計画書が定められていて、患者のアンケートなどのデータは、医療機関が、直接東京大学病院の事務局にファックスすることになっています。
しかし、複数の医師によりますと、ノバルティスの複数の営業社員が、データを回収するなど研究に関与していたということで、専門家は、「データが改ざんされる可能性があり大きな問題だ」と指摘しています。
この臨床研究の代表者で、東京大学病院血液・腫瘍内科の黒川峰夫教授は、「研究を続けるかどうかは医師に事実関係を聞き、研究の信頼性を確認して判断したい」と述べ、調査が終わるまで、いったん研究を中断する考えを示しました。
ノバルティスは、高血圧の治療薬「ディオバン」の効果を調べた臨床研究のデータが操作された問題を受けて、去年11月、営業担当の社員は臨床研究に一切関与しないとする再発防止策を示しました。
しかし、先月まで、営業社員によるデータ回収は続いていたということで、東京大学病院によりますと、これまでに取ったアンケート255例のうち、半数近くの125例について、製薬会社の社員が届けていたということです。
このうち121例については原本などから改ざんがなかったと確認できたとしています。
営業社員からデータを受け取っていた東京大学病院の南谷泰仁特任講師は、NHKの取材に対し、「営業社員がデータを届けることは研究が始まったおととしから続いていた。営業社員がデータの内容を確認したりできる状況になっており、注意するのを怠っていた。データの信頼性に関わる可能性があり、重く受け止めている」と話しています。
これについてノバルティスファーマは、「社内調査をしたところ、複数の営業担当の社員がアンケートを運んでいたことが確認された。再発防止策に違反する行為で不適切だと考えている。それ以外の事実については確認できていないので引き続き調査したい」と話しています。
厚生労働省は「現在、ノバルティスファーマに説明を求めている段階で、事実関係を確認したうえで、適切に対応したい。事実であれば、ノバルティスファーマがみずから示した再発防止策に違反することは明らかで遺憾だ」と話しています。
臨床研究の内容は
今回問題となった「サイントライアル」と呼ばれる臨床研究は、白血病の治療薬を服用する患者に、ノバルティスファーマが販売する新しい薬に切り替えてもらい、副作用が軽くなるかどうか医師が主導して客観的な立場から調べるもので、東京大学病院など22の医療機関が参加しておととしから行われています。
具体的には、ノバルティスファーマの主力薬の「グリベック」と新しい薬「タシグナ」、それに他社の「スプリセル」を1年以上服用する患者に、薬の副作用についてアンケートで20項目以上の質問に答えてもらい副作用を調べます。
そのうえで、「タシグナ」に切り替えてもらいアンケートや血液や心電図などの検査から副作用が少なくなるかどうか調べます。
データの信頼性を保つ目的などで作られるこの臨床研究の実施計画書によりますと、検査結果やアンケートなどのデータは、医療機関が直接、東京大学病院の事務局にファックスすることになっています。
また、一般的に臨床研究では製薬会社から支援を受けた場合、明らかにすることになっていますが、実施計画書ではそうしたことはないと明記されています。
しかし、複数の医師によりますと、研究には関与しないことになっているノバルティスの複数の営業担当の社員が「代わりに届ける」と医師に持ちかけて、アンケートを回収するなど研究に関与していたということです。
この臨床研究を巡っては、去年10月に行われた日本血液学会でグループの代表の医師が副作用の調査結果について中間発表を行っています。
治験と臨床研究の仕組み
臨床研究のうち、製薬会社が開発した薬について国の承認を得るために行われる「治験」は、データ管理など試験の基準が法律で定められていますが、今回のような承認された薬を使って医師がみずから行う臨床研究については、規制する法律はありません。
臨床研究について国は、医療機関や研究機関向けにガイドラインを定めていますが、倫理面や患者の保護などが中心で、研究をどのように行うかは研究者側に任されているのが実情です。
このため医療機関の多くは、研究の信頼性を確保するため、臨床研究の手順やデータの扱いなどを定めた実施計画を作り、病院内の審査機関が事前にチェックする仕組みを導入しています。
今回の臨床試験の実施計画では、アンケートなどのデータを、医療機関が、直接東京大学病院の事務局にファックスするとしていましたが、ノバルティスファーマの複数の営業担当の社員が、「代わりに届ける」と医師に持ちかけて、アンケートを回収するなど研究に関与していました。
ノバルティスファーマの高血圧の薬の効果を調べた臨床研究で、当時の社員が関わったうえデータが操作された問題を受け、厚生労働省は、臨床研究での不正行為を防ぐため法整備が必要かどうか、ことし春にも議論を始める予定です。
患者・家族の会「非常にがっかり」
慢性骨髄性白血病の患者・家族の会の代表、田村英人さんは「今回の臨床研究では、患者一人一人が少しでも生活環境を改善したいと、医師と製薬会社を信頼して協力したもので、少しでも疑いの余地がある軽率な行動があったことは非常にがっかりだ。今後、医師と製薬会社はデータの裏には患者の命があることを忘れずに、正確な扱いをしてほしい」と話しています。
ノバルティス社:白血病治療薬の研究でも不透明な関与 01/17/14(毎日新聞)
製薬会社ノバルティスファーマが販売する白血病治療薬の副作用を調べる臨床試験で、ノ社の社員が医師間の患者データ受け渡しに関与していたことが分かった。ノ社は降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験疑惑への批判から「研究者が実施すべき業務に社員は関与しない」との再発防止策を昨年7月に公表したが、順守していなかった。厚生労働省はノ社から事情聴取する。
東京大病院によると、白血病治療薬の臨床試験は同病院を中心に2012年5月に始まり、継続中。患者データは参加医療機関から事務局の東大病院にファクスするよう手順が定められていたが、ノ社の営業担当社員が東大病院に届けていた。
社員による回収は昨年9月下旬まで続き、255例のうち125例に関与した可能性があるという。東大病院は「データは確認可能で、改ざんは見つかっていない」と説明している。
菅義偉官房長官は17日の記者会見で「自らの再発防止策に違反したのなら極めて遺憾。厳正に対処していきたい」と述べた。ノ社は「不適切だったと反省している」とコメントを出した。【八田浩輔】
JR北海道データ改ざん、上部組織追認か 社員、脱線翌日に相談 01/15/14 (北海道新聞)
JR北海道の函館線大沼駅(渡島管内七飯町)で昨年9月19日に起きた貨物列車脱線事故のレール幅の検査データ改ざん問題で、現場を管轄する大沼保線管理室の上部組織に当たる函館保線所の幹部が改ざんについて現場社員と協議し、追認していた疑いがあることが14日、関係者への取材で分かった。改ざんにかかわった社員が証言した。一方、国土交通省は、JR会社法に基づき、JR北海道に対して組織の問題など幅広い観点から改善を求める「監督命令」を初めて出す方向で検討している。
事故現場での改ざんをめぐり、上部組織の幹部の関与について具体的な証言が出たのは初めて。幹部は関わりを否定しているが、JRはこの幹部が事情を知っているとみて慎重に調査を進めている。
複数の関係者によると、改ざんにかかわった大沼保線管理室と函館保線所の社員計3人のうち同管理室の1人が、同保線所の幹部1人と改ざんについてやりとりがあったことを認めたという。この社員は「事故当日に自分たちの判断で改ざんを行った後、翌日午後に函館保線所の幹部と会って相談した」と証言した。さらに相談後も「現場周辺の数値を改ざんした」などと話しており、幹部が改ざんを追認した疑いもあるという。<北海道新聞1月15日朝刊掲載>
前社長の自殺と関係があるのか知らないが、自殺しなければいけないほどの情報を黙認してきたのか?そうだとすれば今回で膿をださなければ、次の不祥事でまた誰かが自殺するかもしれない。
元JR北海道社長が自殺か? 現相談役、余市港で発見 01/15/14 (産経新聞)
15日午前8時20分ごろ、北海道余市町港町の余市港内で男性の遺体が浮いているのが見つかり、道警は元JR北海道社長の坂本真一相談役(73)の可能性があるとみて確認を急いでいる。遺体に目立った外傷はなく、自殺とみられるという。遺体は防波堤から約100メートル沖合で、航行中の船が見つけた。
JR北海道によると、坂本氏は15日、出社予定だったが会社に姿を見せていなかった。
坂本氏は東京都出身。北海道大工学部を卒業後に昭和39年、旧国鉄に入り、JR北海道の発足後は取締役鉄道事業本部営業部長、専務取締役総合企画本部長などを歴任し、平成8年に第2代社長に就任した。平成15年から会長、同19年から相談役だった。
JR北海道では同23年9月、当時の中島尚俊社長が自殺している。
JR北海道の坂本相談役か、港内に男性の遺体 01/15/14 (読売新聞)
15日午前8時20分頃、北海道余市町港町の余市港内で男性の遺体が浮いているのを、海上自衛隊員が見つけた。
JR北海道の坂本真一相談役(73)が同日朝から行方が分からず、道警が身元を調べている。
坂本相談役は、JR北海道で社長や会長を歴任した。
JR北海道では、2011年9月、中島尚俊社長(当時64歳)の遺体が小樽市沖で発見され、遺書が見つかっている。
JR北海道の社員 脱線の危険性を認識か 01/14/14 (NHK)
JR北海道でレールの検査データが改ざんされていた問題で、このうち脱線事故現場のデータの改ざんに関わった社員が国土交通省に対し、「去年の検査のときから脱線する可能性があると思っていた」と話していることが関係者への取材で分かりました。
国土交通省は社員が脱線の危険性を認識していたとみて調査を進めています。
JR北海道では、一連の問題発覚のきっかけとなった去年9月の脱線事故の直後、「大沼保線管理室」の社員らがレールの検査データを改ざんしていたことが分かっています。
関係者によりますと、国土交通省の特別保安監査に対して、改ざんに関わった社員の1人が、事故前の去年6月の検査で現場付近のレール幅が社内規程の2倍を超えるまで広がっていることに気付いていたということですが、有効な対応を行わず、異常を放置し続けたことを認めているということです。
そのうえで、この社員は「レールを補修しなければ脱線する可能性があると思っていた」と話しているということです。
このため、国土交通省では、社員が脱線の危険性を認識しながら放置していたとみてさらに調べています。
被害者が出る前に「脱線の可能性あると思ったが放置」していた問題が公になったのは良かった。今後、コストの問題、赤字の問題、組織の体質、社員教育、及び記録の管理方法等の問題に取り組み、定期的な確認が必要となるだろう。コストの問題は安全性に影響するし、赤字体質では経営が成り立たない。抜本的な改革が必要だ。
脱線の可能性あると思ったが放置…JR北社員 01/14/14 (読売新聞)
JR北海道の保線担当社員が昨年9月の貨物列車脱線事故直後にレール計測データを改ざんした問題で、改ざんした社員の一人が国土交通省に「レールを補修しなければ脱線する可能性があると思ったが、放置した」などと説明していることが、国交省関係者などへの取材でわかった。
国交省は同社の体制を抜本的に改善させる必要があるとして、近くJR会社法に基づく監督命令と鉄道事業法に基づく事業改善命令を出す方針。監督命令は初めて。
脱線事故は昨年9月19日午後6時過ぎ、JR函館線大沼駅構内で起きた。現場付近のレール幅の広がりは、同年6月の定期検査時に39ミリに達していたが、現場を管轄する大沼保線管理室の社員2人は事故の約2時間後にデータを25ミリと改ざん。その後、上部組織の函館保線所の社員が改ざんの範囲を広げるよう指示した。
社内規定では、レール幅は正規の値より19ミリ以上広がると15日以内に補修しなければならないが、同管理室は約3か月間放置。国交省の特別保安監査で、改ざんした一人が「6月の計測後、同僚と『補修した方がいい』と話した。誰かが『考えておく』と言ったが、放置してしまった」などと経緯を説明したという。
「天下一品」の九条ネギ、中国産ブレンドしていた 01/12/14 (スポーツ報知)
こってりした濃厚スープで人気の中華そばチェーン店「天下一品」を運営する天一食品(大津市)は11日、トッピングメニューに「九条ネギ」と表示しながら、中国産ネギも混ぜ合わせて使っていたことを明らかにした。該当する店舗は東京、愛知、大阪、兵庫など7都道府県18店舗。メニューはすでに「ネギ」と修正した。同社は「認識が甘かった。勉強不足だった」と話している。
同社によると、「九条ネギ」と表示した18店舗は、いずれもフランチャイズ経営。「九条ネギ」の流通が少ない場合は、中国産ネギを混ぜて納品するようグループ内の食材調達会社と合意していた。混在したネギを「九条ネギ」と表示しても問題ないと判断していた。
昨年9月のオーナー店向けに食品表示に関する講習会を開催。その際に、専門家の指導を受けて誤表示に当たることに気付き、同10月に「ネギ」と直した。同時期には、阪神阪急ホテルズなどでメニューの表示が実際に使用した食材と異なるものだったケースが相次いで発覚していた。
同社は1971年に創業者が始めた屋台が母体。現在は全国に232店舗ある。
三菱マテリアル社長、安全規定の不備認める 01/12/14 (スポーツ報知)
5人が死亡した三菱マテリアル四日市工場(三重県四日市市)の爆発事故で、矢尾宏社長が11日、事故後初めて記者会見し、爆発した熱交換器の洗浄作業時の安全規定について「もう少し科学的な方法がなかったものかと考えている」と不備を認め、定量的な基準を含んだマニュアル整備を進める考えを示した。一方、「信頼回復と再発防止策の徹底に努める」と語り、辞任を否定した。
四日市工場で開いた記者会見の冒頭で、矢尾社長は「このような惨事を引き起こしたことを、深く、深く、深くおわび申し上げる」と述べ、頭を下げた。「亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げる」とした上で、遺族や負傷者に誠意ある対応をしていくとした。
事故の責任を問われ「このような悲しみを味わうことのないような仕組みに持っていきたい」と安全管理体制の改善に尽力すると強調。爆発原因は「現時点では分からない」と繰り返した。
熱交換器(長さ約6メートル、直径約1メートル、重さ約5トン)の洗浄に関しては、工場側のマニュアルに「発熱、圧力上昇がなくなることで(分解処理の終了を)判断する」とだけ記され、安全を確保する具体的な手順や客観的指標がなかった。矢尾社長は「規定を守ったのに事故があったのなら(規定自体に)何か問題があったということだ」とし、「マニュアルはものづくりの現場で考えるものだが、専門的な見地で見直し、修正や追加をしていく」と語った。
10日から操業を自粛している四日市工場の再開時期については「安全を総点検する。ハード面のほか安全教育を含め、(地域住民らに)安心だと思っていただけるような改善ができてから判断する」としている。
事故は9日午後2時10分ごろ、半導体部品に使用されるシリコン製造工程にあった熱交換器の洗浄作業中に発生した。
残留農薬、精度100倍下げ検査…アクリフーズ 01/11/14 (読売新聞)
食品大手「マルハニチロホールディングス」の子会社「アクリフーズ」群馬工場(群馬県大泉町)で製造された冷凍食品から農薬マラチオンが検出された問題で、同社が、返品された商品のうち19点を国の残留農薬基準(0・01ppm)より100倍高い1ppmを基準に検査していたことが11日、同社への取材でわかった。
同社は昨年末、「異臭がする」と返品された商品20点のうち9点からマラチオンを検出したと発表したが、残りにもマラチオンが含まれていた可能性がある。このため、同社は8日、群馬県警に提出した1点を除く10点の商品について、外部の検査機関に国の基準値まで検出できる方法で再検査を依頼した。
同社は最初に検査した1点は国基準の精度で測定したが、結果が出るまでに10日以上かかったため、依頼から翌日には結果が分かる1ppm基準での検査に精度を下げたという。広報担当者は「検査期間を早めることを優先したが、検査方法をきちんと説明すべきだった」と釈明している。
レール異常「人手不足で補修放置」…JR北社員 01/10/14 (毎日新聞)
北海道七飯町のJR函館線大沼駅で昨年9月19日に起きた貨物列車の脱線事故直後、現場を管轄するJR北海道の大沼保線管理室などの社員3人がレール計測データを改ざんした問題で、社員が国土交通省の特別保安監査に「人手不足でレールの補修を放置していた」などと話していることがわかった。
社員は以前から改ざんしていたことも認めており、同省は、人手不足を理由に恒常的に改ざんが行われていたとみている。
同管理室では、事故直後に社員2人が現場付近のレール幅の広がりの計測データを39ミリから25ミリに改ざんし、その後、上部組織の函館保線所の社員が改ざんの範囲を広げるよう指示した。元のデータは6月に計測したもの。社内規定では、レール幅は正規の値より19ミリ以上広がると15日以内の補修が義務づけられているが、同管理室は放置していた。
バルサルタン告発:拡大した業界不信 「真相追及を」(1/2)
(2/2) 09/26/13(イザ!)
降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験疑惑は東京地検の捜査にゆだねられることになった。国内有数のヒット薬を後押しした試験データが操作されていたという、日本の医薬研究を揺るがすスキャンダル。試験結果を宣伝に使って利益を得てきた製薬会社ノバルティスファーマはどんな関与をしたのか。そしてだれがデータ操作をしたのか。多くの疑問が残っている。【河内敏康、八田浩輔】
「バルサルタンの注目すべき効果を確かめた」とする京都府立医大の臨床試験論文が、「重大な問題がある」と学術誌から撤回されたのは2013年2月だった。翌月には、試験の統計解析にノ社の社員(昨年5月に退職)が関わり、研究チームに1億円以上の寄付金が渡っていたことが本紙報道で発覚した。
その後、東京慈恵会医大、府立医大などがデータ操作されていた可能性を認めたものの、いずれも「誰がやったのか」を詰め切れず、記者会見では「試験関係者は操作を否定した」「特定できない」と繰り返すばかりだった。厚生労働省の有識者検討委員会で委員を務める桑島巌医師は「我々の聞きとりでも関係者は知らぬ存ぜぬを繰り返し、らちが明かなかった。強制力を持った捜査当局にしっかり追及してもらいたい」と話す。
医療現場も混乱している。土橋内科医院(仙台市)の小田倉弘典院長は「現場の医師は何一つ腑(ふ)に落ちず、もどかしい思いをしている。不安を感じる多くの患者への対応に私も追われてきたし、一部の患者はノバルティスへの憤りから、この薬の服用を拒否した」。すべてのノ社の薬を扱わないようにした開業医もいるという。「患者は医師が出す薬を信用するしかない。真相が明らかにならないうちは安心して薬を飲めない」。血圧が高くて長年、降圧剤を服用してきた愛知県の男性(70)はこう語る。
日本医師会の今村聡副会長は「医療や創薬を成長産業にしようとする日本が、国際社会から信頼を失うような今回の問題を未解明のまま放置することは許されない。大学が自ら解決できなければ、司法の力を借りるしかない」と訴えた。
バルサルタンの売り上げは急激に減った。医療コンサル大手「IMS」によると、データ操作判明後の13年7〜9月の売り上げは前年同期比約16%減。ノ社に勤めた経験がある男性は「疑惑発覚当初の隠蔽(いんぺい)とも受け取れる会社の対応は、製薬業界への不信を拡大させた。退職したからと歴代の社の関係者は表に出ず、逃げ得のようだ。厳格な捜査で対応してもらいたい」と話した。
バルサルタン告発:「誰が」「役割は」立件に課題 01/09/14(毎日新聞)
降圧剤バルサルタンの臨床試験疑惑で、厚生労働省は法人としてのノバルティスファーマを告発したが、不正に関与したとされる人物の特定には至っておらず、刑事責任追及に向けた課題は多い。東京地検は今後、ノ社や臨床試験を実施した大学関係者から事情聴取し、データ操作の経緯などについて実態解明を進める。
薬事法は、虚偽や誇大な表現を使った医薬品広告を禁じており、違反した場合は2年以下の懲役か200万円以下の罰金が科される。法人を罰する「両罰規定」もあるが、適用には役員や従業員らの立件が前提で、個人の犯罪の立証ができなければ会社も罪に問えない。
臨床試験を実施した5大学のうち3大学は試験でデータ操作があったとする調査結果を発表している。検察内には「一社員や現場の研究者だけで何かを決められるわけがない」(幹部)との見方もあり、組織的な不正がなかったか調べを進めるとみられる。
ただ、厚労省が告発対象者を「不詳」としたように、監督官庁による調査が十分ではない中で捜査に着手せざるを得ない。別の検察幹部は「うその効能で暴利を得たとすれば悪質だが、臨床試験から宣伝までの過程で誰がどういう役割を果たしたか確かめるところから始めなければならない。簡単な捜査ではない」と漏らした。【島田信幸】
バルサルタン:ノ社と社員を告発 薬事法違反で厚労省 01/09/14(毎日新聞)
降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験疑惑で、データ操作された試験論文を宣伝に使ったとして、厚生労働省は9日、製薬会社ノバルティスファーマ(東京都港区)と社員を薬事法違反(誇大広告)容疑で東京地検に刑事告発した。社員は個人を特定せず「氏名不詳」とした。厚労省が誇大広告容疑だけで刑事告発するのは初めて。医薬研究への信頼を揺るがした不祥事は、捜査当局による解明が進められる。
厚労省によると、ノ社は2011〜12年、データ操作された東京慈恵会医大と京都府立医大の臨床試験結果を広告記事やPR資料に使い、「バルサルタンは脳卒中の予防効果も高い」などと誇大に広告した疑いがあるとしている。
バルサルタンを巡っては、慈恵医大と府立医大、滋賀医大、名古屋大、千葉大の5大学が臨床試験を実施。いずれもノ社元社員がデータ解析に関わり、論文では肩書を伏せていた。慈恵医大と府立医大、滋賀医大はノ社に有利な方向にデータ操作されていたと発表。名古屋、千葉大はデータ操作を否定している。5大学はノ社から総額11億円超の奨学寄付金を受けていた。
厚労省は昨年10月以降、薬事法に基づく調査でノ社に関係書類の提出を求め、元社員らから聞き取りを進めてきた。ノ社側と大学側の双方が、データ操作への関与を否定している。
厚労省幹部は「完全には実態は解明されていないが、調査でデータ改ざんを知りながら広告に使った疑いが強まる新事実も見つかった」と説明した。
バルサルタンは00年に国内での販売を開始し、累計で1兆2000億円を売り上げてきた大ヒット薬。【桐野耕一】
◇全面的に協力
ノバルティスファーマの話 事態を極めて重く受け止め、今後も当局に全面的に協力する。
オランダ年金基金が東電株売却、原発事故処理への懸念で 01/08/14 (ロイター)
[アムステルダム 7日 ロイター] -オランダの公務員年金基金ABPは7日、東京電力(9501.T: 株価, ニュース, レポート)株式を昨年売却したことを明らかにした。福島第1原発の問題めぐり、ABPが安全性や環境への影響について繰り返し協議を申し入れたものの、東電側が応じなかったため、としている。ABPは、東電を1月1日付けで投資してはならない対象に指定した。
チェルノブイリ以来最悪の原発事故とされる福島第1原発の事故は、発生から3年近くになる今も汚染水の処理などで問題を抱え、昨年末に政府が賠償や除染のための資金支援枠の拡大を決定している。
ABPは、3000億ユーロ(4080億ドル)近い運用資産を持つ世界有数の年金基金。世界的な機関投資家が、東電を投資してはならない対象としたことは、すでに原発事故処理などで厳しい批判にさらされている東電にとってさらなる打撃だ。
ABPの広報担当HarmenGeers氏は7日、保有していた東電株を2013年第4・四半期に売却したことを明らかにした。売却価格は不明。ABPの四半期報告では、第3・四半期末時点で1800万ユーロ相当の東電株を保有していた。
ABPは7日発表した声明で「東電は、福島原発事故発生時、およびその後も、われわれの基準に違反していた。東電は、一般市民の安全についての認識が乏しかったと言える」と指摘した。
Geers氏によると、ABPは自分たちの懸念について繰り返し東電との協議を試みたが、東電からの返答はなかったという。
ABPは、投資禁止対象リストを毎年見直している。禁止対象には、クラスター爆弾製造会社などが含まれている。
東電については、ABPが社会責任投資のガイドラインとしている国連グローバル・コンパクトの10原則の内の「人権」と「環境」の2原則に関する目標を満たしていないと判断したとGeers氏は説明した。
現在のところ東電のコメントは得られていない。
福島汚染水:境界線量、基準の8倍 貯蔵タンク付近 (1/2)
(2/2) 01/10/14 (毎日新聞)
東京電力福島第1原発の汚染水問題で、東電は10日、敷地境界の年間被ばく線量が、周辺への影響を抑えるため廃炉計画で定められた基準「年間1ミリシーベルト未満」の8倍に当たる8ミリシーベルトを超えるとの試算を明らかにした。放射性物質を含む汚染水を入れた貯蔵タンクを敷地境界付近に設置したのが原因という。東電は昨年5月に基準を超えたことを把握したが、増え続ける汚染水の貯蔵場所の確保を優先し対策は後手に回った。原子力規制委員会は10日、今月中に東電に対策と基準まで低減できる時期の提示を求めた。
年間被ばく線量が上昇しているのは敷地南側。そばには、汚染水の入った貯蔵タンクがある。昨年4月に地下貯水槽(7基で計5万8000トン分)での汚染水漏れを受け、急場しのぎでこのタンクに移送した。その後も南側は空き地だったため、増え続ける汚染水を収容するため南側の敷地を中心に増設していた。
この汚染水には、ストロンチウム90などベータ線を出す放射性物質が含まれている。ベータ線は、物体を通り抜ける力は弱いが、タンクの鉄に衝突すると透過力の高いエックス線が発生、放射線量が上昇しているという。この影響で、昨年3月末には基準を下回る年間0.94ミリシーベルトと見積もっていた試算は、同5月には年間7.8ミリシーベルト、同12月には年間8.04ミリシーベルトまで上昇した。
規制委は昨年8月、東電が基準の1ミリシーベルトに戻すことを前提に計画を認可した。規制委の更田豊志(ふけた・とよし)委員は10日の会合で、「1ミリシーベルトに戻ることを前提に計画を認可した。野放図になっていることはよしとしない」と述べた。敷地境界付近の立ち入りは制限されているため、周辺に住民はいないが、有識者からは「将来の住民の帰還に向けて、(線量上昇に)歯止めをかけるべきだ」との意見も出た。一方で、「線量の低減だけにとらわれて、ほかの作業に影響が出ないよう考えるべきだ」などの慎重論も出された。東電の姉川尚史常務は「(原発の建屋から遠い敷地境界近くにタンクを置くことは)原発作業者にとっては、被ばく線量が下がるので有益だが、指示があった敷地境界の線量低減のスケジュールは示したい」と述べた。
汚染水は、壊れた原子炉建屋に地下水1日400トンが流入し、溶けた核燃料に接触して汚染され増加し、タンクに貯蔵されている総量は昨年末で40万トンを超えた。現在、東電は地下水の流入を防ぐために建屋周辺の地中を凍らせる「凍土遮水壁」の設置を計画しているが、前例がない大規模な工事で効果は不透明だ。汚染水を浄化する切り札と位置づけられている多核種除去装置「ALPS(アルプス)」は今月8日に不具合で停止。10日に運転を再開したものの、トラブルが続き安定した運用ができない。稼働してもトリチウム(三重水素)が残るなど課題は山積している。【鳥井真平】
工場爆発:熱交換器は特注品 マニュアル、納入時求めず 01/11/14 (毎日新聞)
作業員5人が死亡する事故の起きた三重県四日市市の「三菱マテリアル」四日市工場で、爆発した熱交換器は同社が子会社に発注した特注品であることが分かった。同社は熱交換器のふたを取り外す際の具体的な作業マニュアルを作っていなかったが、このようなマニュアル作りは同業者や業界団体などでは常識とされていることも判明。マテリアルの安全軽視ぶりが改めて浮き彫りになった。【花岡洋二、和田憲二、黒尾透】
熱交換器を作ったのは、マテリアルの100%子会社「三菱マテリアルテクノ」。同社総務部によると、熱交換器は2004年7月にマテリアルの発注に基づき納品した。毎日新聞の取材に「マニュアルは作成していない」としている。
マテリアルは10日の記者会見で「(爆発した熱交換器は)材質や温度、圧力などの仕様を独自に設計し発注したオーダーメード。テクノでコントロールできる話ではない」とし、テクノ側にマニュアルの作成を求めなかったことを明らかにした。マテリアル自身も具体的なマニュアルを作らず、現場作業員の感触などに委ねていたことを認めている。
会見で猿渡暢也工場長は「今まで感覚に頼っている部分があった。(基準を)定量化できるような仕組みに改めたい」と話し、安全管理体制を強化する考えを示した。
これに対し、同工場と同じ多結晶シリコンを製造している「トクヤマ」(本社・山口県)の広報IRグループは「当社には作業基準書(マニュアル)があり、安全確認作業も載っている。熱交換器のメンテナンスも、作業基準書にのっとっている」と説明した。
日本プラントメンテナンス協会(東京都)の佐藤信義技術委員によると、熱交換器のメンテナンス作業について協会の統一基準はないが、一般的にはユーザー企業が作成する。「引火性の高い流体を使っている熱交換器は、ふたを開ける前に圧力計や温度計を使い、中に圧力が残っていないことを確認する。ふたに付いている小さなバルブを開けてみるなどの確認をするのは常識だ」と話し、具体的マニュアルに基づいた安全確認が重要だと話している。
研修・見学社員巻き込み被害拡大…三重工場爆発 01/11/14 (毎日新聞)
三重県四日市市の「三菱マテリアル」(本社・東京都千代田区)四日市工場で、5人が死亡、12人が負傷した爆発事故で、研修や見学で現場にいた社員も巻き込まれていたことが分かった。
通常の作業の倍の人数が爆発した熱交換器付近にいて、被害が拡大した可能性がある。県警は社員らがどの位置で被害に遭ったのか特定を急いでいる。
同工場は半導体や太陽電池の基板原料となる多結晶シリコンを製造しており、製造過程で発生する化合物が熱交換器内にたまるため、洗浄している。
同社の説明によると、洗浄は約30年前から行っており、通常は約10人程度で作業にあたっているが、爆発事故が起きた今月9日は、約20人が熱交換器近くにいたという。
このうち、死亡した同社社員の豊田裕久さん(48)や、負傷した4人は、2月に別のプラントで同様の作業をすることから、研修のために現場にいたという。また、設備管理部門で現場監督の教育を受けていた社員1人、その上司ら2人も見学に来ていて負傷したという。
ISOなどで要求されるマニュアルは比較的に新しいもの。洗浄が30年前からおこなわれているのならマニュアルの概念など無かったのだろう。それでも人件費を考慮しなくても良い時代には安全を優先していたのかもしれない。コスト(人件費や作業時間)など新たな制限と運が悪かった事などが重なって今回の事故になったのではないのか?マニュアルで詳細まで記載されていない場合、熟練した経験者がいなければ、高学歴の若い作業員や似たような作業を行っている作業員がいても経験を積むまでは行き当たりばったりのはずだ。誰かがやらなければならないのならやるしかない。高学歴で現場を知らない人達が、コストとか資料から得た情報だけで判断していれば、このような事は運が悪ければ起きるだろう。コスト削減とか効率とか言っても、安全率をどこまで妥協するかだけだ。安全率が下がれば、事故率は上がるだろう。しかし正比例で事故率が上がるわけではない。運や確率もあるからだ。マニュアルやチェックリストなどあっても審査や建前だけならば、機能していない場合もある。事故が発生した時に、原因究明の調査でこれらが判明する事もある。調査する人間達が建前だけの調査や経験がなければ、本当の原因や間接的な原因など報告書には含まれないだろう。経験のない又は知識のない調査関係者は、工場から提出された報告書や工場の関係者からの聞き取り以外に何も知らない事があるからだ。それらの資料や情報から調査報告書が作成されるなれば不都合な事実は記載されていないかもしれない。
四日市工場爆発:熱交換器のふた 作業マニュアルなく 01/10/14 (毎日新聞)
作業員5人が死亡、12人が重軽傷を負った三重県四日市市の石油化学製造「三菱マテリアル」四日市工場の爆発事故で、同社が爆発した熱交換器のふたを取り外す際の具体的なマニュアルを作らず、内部が安全な状態かどうかの判断を現場作業員の感触などに委ねていたことが分かった。工場幹部も不備を認め「誰もが分かる基準が必要だったと反省している」と話している。
事故は円筒形の熱交換器(金属製、直径0.9メートル、長さ6メートル、重さ約5トン)のチャンネルカバーと呼ばれるふた部分を取り外す作業の最中に起きた。交換器は内部に約300本のチューブが通され、シリコン製造の過程で主原料の化合物「トリクロロシラン」の残留物が付着する。
トリクロロシランは引火性が高いため、1カ月以上、加湿窒素ガスを器内に注入し、爆発を防ぐ処置をしている。しかし、その後に器内の状態が安定したかどうかを判断する目安として温度計などの機器は使わず、素手で熱交換器に触り、「冷えていれば取り外しても問題ない」と判断するなど、現場作業員の個人の感覚や経験に頼っていたという。
遠藤俊秀副工場長は「器内の温度計測は技術的に限界があり、加湿窒素ガスを入れ続けた時間と、熱が下がっているかの感触で判断した」と説明した。
10日午前に始まった三重県警による現場検証でも、三菱マテリアルの安全対策に問題がなかったかどうかについても調査する見通し。【三上剛輝、千脇康平、石戸諭】
三宅淳巳・横浜国立大学大学院教授(安全工学)の話 今回のような危険を伴う作業の場合、熱交換器の中の温度、圧力、化学物質の状態をモニタリングしたうえで、ふたを外すなどの工程をマニュアル化するのが一般的だ。素手で交換器に触ることのみで温度を確認するというのは、安全管理のあり方としては考えられない。通常とは異なるメンテナンス作業に対する危険度の認識が十分だったかが、今後の検証のポイントとなる。
熱交換器、8年洗浄せず…工場爆発・5人死亡 01/10/14 (毎日新聞)
三重県四日市市の「三菱マテリアル」(本社・東京都千代田区)四日市工場で、同社と下請け業者の作業員計5人が死亡、12人が重軽傷を負った爆発事故で、同社は10日、爆発した水冷熱交換器を7年10か月洗浄していなかったと明らかにした。
同工場では2010年2月、別の交換器の洗浄の際、化学物質の残留物で作業員がやけどをする事故が起きて以降、洗浄の頻度を増やすことを検討していたという。同工場は10日から安全が確認できるまでの間、操業を停止した。
工場には熱交換器を洗浄する際のマニュアルはあるが、どの程度の温度まで下がれば安定状態になるのか、窒素をどれくらいの濃度まで注入すれば良いのかといった数値の基準は書かれておらず、作業員の経験則に従って行われていたという。
四日市工場爆発:死亡の5人即死状態 熱交換器洗浄作業中 01/09/14 (毎日新聞)
9日午後2時5分ごろ、三重県四日市市三田町の石油化学製造「三菱マテリアル」四日市工場で爆発があった。同社社員ら男性作業員5人が死亡。他に男性12人がけがをして、うち1人はやけどなどで重傷。三重県警は業務上過失致死傷容疑で捜査する。同社は10日から、同工場を全面操業停止にする。
同社と市消防本部によると、死亡したのは同社社員の豊田裕久さん(48)=四日市市▽藤田博之さん(34)=同県鈴鹿市▽大畑真徳さん(36)=同県松阪市=と、協力会社「南部組」(四日市市)の社員の古川勇樹さん(25)=四日市市▽南部嘉英さん(42)=鈴鹿市=の計5人。同消防本部によると、いずれも爆風で即死状態という。重傷は、三菱マテリアル社員の山下秀剛さん(39)。
同消防本部によると、爆発したのは、円筒形で金属製の熱交換器(直径0.9メートル、長さ6メートル、重さ4.3トン)。約300本のチューブが通り、中を通った原料を冷やしたり、温めたりする。同工場は水素ガスとトリクロロシランという化合物を混合させ、半導体の材料などにする多結晶シリコンを製造している。
交換器は昨年11月にメンテナンスのためプラントから取り外された。この日水素精製施設から30メートル離れた屋外にクレーンを使って運び出され、つった状態で朝から約20人で洗浄作業中だった。午前中に一方のふた(約250キロ)を取り外し、午後からもう一方を取り外すため、24本のボルトを抜き、ふたを外した数秒後に爆発したという。ふたは約10メートル飛んだ。会社関係者によると、水と窒素ガスをチューブ内に注ぎ込み、爆発を防ぐ処置をしながら作業をしていたという。
交換器は1~2年年ごとに、チューブ内に付着する不要な無機化合物を取り除く作業を行っているという。
消防本部によると、同工場では2012年2月にも装置の洗浄作業中に、排水にたまった内容物とアルカリ水が反応して爆発が起き、洗浄場の排水溝のふたが飛ぶ事故があった。けが人はなかったという。
現場は四日市コンビナート内の臨海部。最も近い民家までは約1キロ。【岡正勝、和田憲二、千脇康平、千葉紀和】
社説:バルサルタン不正 癒着に捜査のメスを 01/09/14 (毎日新聞)
製薬会社ノバルティスファーマの降圧剤「バルサルタン」(商品名ディオバン)を巡る臨床試験疑惑が新たな展開を迎えることになった。
データ操作された試験論文を違法に宣伝に使ったとして、厚生労働省が同社を薬事法違反(誇大広告)容疑で近く東京地検に刑事告発する。不正の再発を防ぎ、日本の臨床研究の信頼性を取り戻すためにも、捜査当局による疑惑解明に期待したい。
臨床試験は、バルサルタンに血圧を下げるだけでなく、脳卒中予防などの効果もあるかを調べるため、国内5大学が実施した。データ解析などでノバルティス社の社員もかかわっており、同社は計11億円余の奨学寄付金を5大学に提供していた。
同社は効果があるとする各論文を宣伝に多用し、バルサルタンは国内で累計1兆2000億円超を売り上げる人気薬となった。
ところが、昨年末までにまとまった各大学の内部調査のうち、京都府立、東京慈恵会、滋賀の3医大で、同社に都合が良い方向にデータ操作されていたことが判明した。
製薬会社は有名医師らに臨床試験を持ちかけ、宣伝に利用する。医師側も、論文が発表できれば自らの業績につながる。
厚労省の行政調査に対して、関係者はいずれもデータ操作への関与を否定している。しかし、複数の大学で操作が発覚した背景には、そんな癒着の構図が透けて見える。
厚労省の患者調査(2011年)によれば、治療を受けている高血圧患者は約900万人に上り、降圧剤の市場は巨大だ。薬代は患者の負担や税金で賄われている。不正な論文に基づく宣伝の被害者は、国民全体といえる。宣伝を信じて薬を処方した医師と患者との信頼関係も破壊してしまった。厚労省の行政調査には限界がある。癒着の構図に捜査のメスを入れてもらいたい。
誰がどのような目的を持ってデータ操作をしたか。ノバルティス社の組織的な関与はなかったのか。関係者は多数に上り、捜査は簡単ではない。しかし、「誇大広告」で得た不当な利益の返還を同社に求めるためにも、真相の究明は欠かせない。各大学に提供された奨学寄付金の使途も明らかにしてほしい。
厚労省の有識者検討委員会や関係学会などから、臨床研究の規制強化や公的研究基金の創設、研究者への倫理教育の強化、不正を取り締まる公的第三者機関の設置などの対策案が提案されている。
不正防止の万能薬はないだろう。それでも、行政や製薬業界、関係学会は当事者として告発を受け止め、患者のための臨床研究の実現に向けた取り組みを進めてもらいたい。
汚染水タンクからX線、対策怠り基準の8倍超 01/09/14 (読売新聞)
福島第一原子力発電所で、汚染水タンクから発生するエックス線の影響を東京電力が軽視し、対策を講じないままタンクを増設し続けていることが9日わかった。
国が昨年8月に認可した廃炉の実施計画では、原発敷地境界の線量を「年1ミリ・シーベルト未満にする」と定めているが、12月には一部で年8ミリ・シーベルトの水準を超えた。
現在、周辺に人は住んでいないが、作業員の被曝(ひばく)量を増やす要因になっている可能性がある。原子力規制委員会は10日に東電を呼び、対策の検討に入る。
タンク内の汚染水から出る放射線は主にベータ線で、物を通り抜ける力が弱い。しかし、ベータ線がタンクの鉄に当たると、通り抜ける力の強いエックス線が発生し、遠方まで達する。
東電によると、様々な種類の放射線を合わせた敷地境界での線量は、昨年3月には最大で年0・94ミリ・シーベルトだったが、5月には同7・8ミリ・シーベルトに急上昇した。汚染水問題の深刻化でタンクが足りなくなり、敷地の端までタンクを増設したため、エックス線が増えたらしい。
旧式の装置と新たな装置の信頼性が違うので比較できないのであれば、それだけだ。比較しようと思う方が間違い。装置を開発したのが東電でなければ、メーカーに計測方法を聞けば良い。特許やノウハウになるのでメーカーが詳細を公表できないのであれば、それだけの話。新たな装置による結果をなぜ公表できないのか疑問だ。たぶん分析結果が公表できないような数値であるのだろう。
地下水の汚染は致命的だと思う。放射線が下がっても、地下水が汚染された時点で居住するのに適しているとは言えないと思う。どのように水脈が繋がっているのか解明する事など時間とお金の無駄。福島に住んでいないから直接関係ないけど、近くの住民はリスクと優先順位を良く考えた方が良いと思う。
東電、ストロンチウム濃度公表せず…測定誤り? 01/09/14 (読売新聞)
東京電力は8日、福島第一原子力発電所の港湾や井戸で海水や地下水を採取して調べている放射性ストロンチウムの濃度について、「測定結果に誤りがある可能性があり、公表できない」と発表した。
海水などは定期的に採取して汚染状況を監視することになっており、放射性セシウムなどは毎週、濃度を分析して公表している。しかし、汚染水に含まれる主要な放射性物質の一つであるストロンチウムは、毎月分析することになっているが、昨年6月に採取した海水などの分析結果を最後に、半年近くも公表していなかった。
東電によると、昨年夏まで使っていた装置の分析結果にばらつきがあり、信頼性に乏しかった。同9月に新たな装置を導入し、信頼性が向上したが、「旧装置と異なる分析結果になった原因を詳しく解明してから、新たな装置による結果を公表したい」と説明している。
データ改ざん、ノバ社を東京地検に告発…厚労省 01/09/14 (読売新聞)
高血圧治療薬「ディオバン」の臨床研究データ改ざん問題で、厚生労働省は9日、不正なデータを広告に用いたことが薬事法違反(虚偽・誇大広告)にあたる疑いがあるとして、販売元のノバルティスファーマ社(東京都港区)と、広告に関わった氏名不詳の同社社員について、同法違反容疑で東京地検に告発状を提出した。
同省は昨秋以降、薬事法に基づき、ノバ社関係者から話を聞いたり、資料提出を命じたりして調査をした結果、「データが改ざんされている事実を知りながら広告に使った疑いが深まった」と判断した。事実関係が明らかになった段階で、行政処分を検討する。
ノバ社は「データ改ざんは知らなかった」と主張している。
同省幹部は告発後の記者会見で、「事実関係をうやむやにすることなく、厳正に対処すべく調査を尽くしてきたが、現時点では完全に実態が解明できていない」と述べ、今後の解明は捜査当局に委ねる考えを示した。
ノバルティスファーマ社告発へ…薬事法違反容疑 01/08/14 (読売新聞)
高血圧治療薬「ディオバン」の臨床研究データ改ざん問題で、厚生労働省は8日、不正なデータを広告に用いたのは薬事法違反(誇大広告)の疑いがあるとして、販売元のノバルティスファーマ社(東京都港区)と、広告に関わった同社の担当責任者を同法違反容疑で東京地検に告発する。
この問題では、同社の元社員(昨年5月退職)がデータ解析に関わった京都府立医大と慈恵医大の臨床研究で、血圧値などのデータが改ざんされたことが両大学の調査で判明。
同社はこのデータに基づき、ディオバンに「脳卒中や狭心症を予防する効果がある」などと宣伝した。改ざんの実行者は特定されていない。
薬事法は、医薬品などで虚偽や誇大な表現を使った広告を出すことを禁じており、違反した場合は、2年以下の懲役か200万円以下の罰金が科せられる。
同省関係者によると、複数の若手社員が調査に対して「先輩から『基準値を超えたデータはパソコンに入力できない。基準値内に数値を変えなさい』と指導された」などと説明。「習った通りにしたので、改ざんが悪いこととは思わなかった」とも話したという。
このような事を言っている若手社員はどこの大学や高校を卒業したのでしょうか?道徳について一切教えなかったのでしょうか?また、これが事実であれば、少なくとも高校は卒業したと推測しますが、小学校、中学校、そして高校で何を学んできたのでしょうか?これは「物を盗んでいも良い、人を騙してでも物を売れ」と習えば、悪い事とは思わないと言っているようなものです。かなりの洗脳教育がJR北海道社員達に行われていたのでしょうか?改ざんが当たり前のように行われていたので感覚が麻痺してたのでしょうか?環境や影響を与える人達はある意味で恐ろしいですね!
アクリフーズの農薬マラチオン混入に関する報道まとめ(継続中) (クミタス~情報ページ)
冷凍食品から農薬 回収を急ぎ、原因明らかに 01/09/14 (福井新聞)
マルハニチロホールディングス子会社のアクリフーズ群馬工場で製造した冷凍食品から農薬「マラチオン」が検出され、県内でも同工場製の食品を食べた小学5年女児ら5人が体調不良を訴えていたことが分かった。食品に農薬を意図的に混入した可能性が高く、警察が捜査を進めている。食の信頼、安全を揺るがす事案だけに、1日も早い原因究明が待たれる。
アクリフーズが製造した冷凍食品から異臭がするという苦情は11月以降、消費者から相次いだ。検査の結果、ピザやコロッケなど一部から基準値を超すマラチオンを検出。アクリフーズは12月29日、同工場で生産した90品目約630万パックを自主回収すると発表した。
農薬混入を発表したのは異臭申し出から1カ月以上たってからだ。公表まで時間がかかった理由として、工場の設備工事で用いた塗料が付着した可能性が高いと判断、詳細な検査が遅れたためとしている。しかし、健康に関わり、しかも600万超という数だけに、自主回収は遅すぎたと言わざるを得ない。
本県をはじめ全国で1400人以上が嘔吐(おうと)や腹痛、頭痛などの体調不良を訴えていることからも、消費者への周知の遅れは否めない。
マラチオンは、ハダニやアブラムシなど多くの種類の害虫を駆除できる有機リン系の農薬。農作物の保護や収穫後の保存など広く使われ、家畜飼料や小麦・トウモロコシの加工品に残留していることが多い。
人の体内では酵素で速やかに分解、排出されるため毒性は低いが、食べると下痢や吐き気などの症状が出ることがある。人が1日に摂取してもよいとされる量は、体重1キロ当たり0・02ミリグラム。アクリフーズは当初「体重20キロの子どもが一度に60個のコロッケを食べないと毒性が発症しないレベル」と説明。その後「8分の1個食べると健康に影響する恐れがあるレベル」と、訂正した。
正確な情報を消費者に提供するのは当然である。農薬のこととはいえ、誤った情報は消費者を惑わすことになった。農薬混入を公表する前、スーパーなどに対象製品を撤去するよう通知していたというから、消費者軽視の姿勢が問われても仕方ない。
製品の回収率は7日現在、約23%にとどまる。冷凍品だけに家庭の冷凍庫に入ったままというケースも考えられる。いま一度、庫内を確認したい。体調不良という人をこれ以上出さないために製品回収を急がねばならない。消費者へのいち早い情報提供は言うまでもない。
コロッケの衣からは残留農薬基準の260万倍に当たる農薬が検出された。材料ではなく加工後に外からかけられた可能性が高いとみられている。
工場内には物品を容易に持ち込めず、ビデオ監視も行われていたという。警察の捜査、マルハ社などによる調査で原因を明らかにしてもらいたい。
冷凍食品農薬検出 アクリフーズ社長、対応の遅れなど謝罪 01/08/14 (FNNニュース)
冷凍食品から農薬が検出された問題で、8日午後、アクリフーズの社長が消費者庁を訪れ、対応の遅れなどについて、謝罪した。
FNNのまとめでは、健康被害の相談件数は、全ての都道府県に及び、1,000件を超えた。
8日、消費者庁に呼ばれたアクリフーズの田辺 裕社長は、これまでの経緯などについて、森大臣に説明を求められた。
アクリフーズの田辺社長は「誠に申し訳ございません」と頭を下げた。
マルハニチロホールディングスの子会社、アクリフーズの群馬工場で製造された冷凍食品から、農薬が検出された問題。
街の人は「何が対象なのかが、一番気になっていたので、早めにこういう対象商品を出してもらいたかった」と話した。
アクリフーズ群馬工場の内部の写真には、たくさんのグラタンが流れる製造ラインが写されていた。
農薬が混入された可能性が高まっている、包装室の写真もあった。
アクリフーズ従業員は「皆さん見ていますし、1人じゃないんですよ、やっているのが。そういうの(農薬混入)は、ちょっと無理があるんじゃないかと思うんです」と話した。
大阪・摂津市では、2013年12月29日の昼、5歳と3歳の子どもと生後9カ月の男の子と、その父親が、当該商品を食べ、嘔吐(おうと)などの症状を訴えた。
生後9カ月の男の子は、6日から入院しているが、回復傾向だという。
消費者への周知に、遅れはなかったのか。
マルハニチロとアクリフーズによると、11月13日、消費者から「石油・機械油のような臭いがする」と申し出があった。
商品を分析した結果、12月13日、「塗料・農薬などの溶媒に使用される物質」が検出された。
しかし会社側は、群馬工場が9月に大がかりな設備工事を行っていたため、ペンキ類が食品に付着するなどした可能性を考えたという。
アクリフーズの田辺社長は「原因追究が、臭気の方に偏ってしまい、その臭気の原因が、石油臭という部分がございましたので、そちらの方に、少し遅れてしまったという、ご説明をさせていただきました」と話した。
会社側は、農薬が付着した可能性を否定する目的で、「残留農薬検査」を実施したが、12月27日、農薬「マラチオン」が検出された。
しかし、会社側が公表したのは、その2日後の29日の夕方。
摂津市の親子が商品を食べたのは、発表される前の29日の昼だった。
この対応に、企業の危機管理の専門家である、コンプライアンス・コミュニケーションズの藤井裕之社長は「お客様の方から、異臭等があるといった報告が上がってから、記者会見を開くまで、1カ月半。これはやっぱり、ちょっと時間がかかりすぎたなと。健康問題ですので、スピーディーな対応が求められる事案ではあるので、途中経過でも構わないので、『こういうことになっているんだ』と、会見等を含めて、広く消費者に、情報提供を早い段階ですればよかったんじゃないかなと」と話した。
消費者庁の阿南 久長官も、「不十分なところがあったのではないかと思います。いったい、何があったのかということを想像して、何があるかわからないということを、常に危機管理体制として、知っておく必要があったのではないか」と苦言を呈した。
JR北データ改ざん「先輩の指導」と一部担当者 01/01/14 (読売新聞)
JR北海道でレール計測データの改ざんが行われた問題で、一部の保線担当社員が国土交通省の特別保安監査に対して「先輩社員から『異常な数値は入力できない』と教わったため、数値を変えた。悪いこととは思わなかった」などと説明していることが同省関係者への取材でわかった。
同省では、改ざんが慣習として引き継がれていた可能性があるとみている。
同社によると、列車の待機などに使われる副本線と、列車の進路を変更する分岐器では、社員がレール幅などを計測した後、保線担当部署のパソコンにデータを入力する仕組みになっている。レール幅などは、社内規定で補修の基準値があり、超えると15日以内に補修しなければならない。
同省関係者によると、複数の若手社員が調査に対して「先輩から『基準値を超えたデータはパソコンに入力できない。基準値内に数値を変えなさい』と指導された」などと説明。「習った通りにしたので、改ざんが悪いこととは思わなかった」とも話したという。
監査では、保線担当部署から改ざんの手法などを明記した文書やマニュアルは見つかっていないといい、同省では、悪習が口頭で引き継がれたとみている。
一方、同省内には「大人がこんな教えを信じて改ざんに手を染めるのか、不自然だ」との見方もあり、事実確認を進めている。
中国のバイドゥ本社が何と発言しようとも情報は流れていると思う。海上自衛隊の飛行機に中国海運艦が照射した問題と同じ。否定しかしない
福島県庁PCデータ、百度サーバーに自動送信 12/28/13(読売新聞)
福島県は27日、県庁内で使用するパソコン10台から、「百度」のサーバーにデータが自動送信されていたと発表した。
データには個人情報が含まれている可能性があるという。
同県が昨年5月以降の通信状況を調べて判明した。自動送信が確認されたパソコンは、商工労働部など六つの部が管理。このうち、総務部の2台、商工労働部、保健福祉部の各1台は、県立技術系短大「テクノアカデミー」の学生名簿や再生可能エネルギー業者情報などの個人情報を取り扱っていた。
いずれも他のソフトをインストールした際、バイドゥIMEが一緒にインストールされたとみられる。27日までに10台とも、このソフトを削除した。
福島県庁PCデータ、百度サーバーに自動送信 12/26/13(読売新聞)
「まるでウイルス」――。
パソコンに入力した文字列を全て外部に送信してしまう中国社製の日本語入力ソフト「バイドゥIME」。国民の大切な情報を扱う役所や大学でも気づかないまま使われていたことに、関係者はショックを受ける。便利なソフトなだけに人気も高く、推定利用者は200万人以上。専門家は「便利なITサービスでも、利用者に仕組みを正しく伝えなければ、悪性のウイルスと同じになってしまう」と指摘する。
「市民の個人情報は漏れていないと信じたいが……」
愛知県豊田市の太田勝彦・情報システム課長はうなだれた。同市では25日午前、バイドゥ側のサーバーとの通信記録を調べ、2時間に数十回の通信が行われていたことを確認。通信記録をたどると、14台のパソコンにバイドゥIMEがインストールされていることが分かった。
14台は、市民福祉部や企画政策部など計8部局で使用しているパソコン。職員から聞き取ったが、いずれも「そんなソフトがインストールされているとは知らない」と驚いていたという。
情報セキュリティーの専門家によると、バイドゥIMEは、無料ソフトの配布サイトなどで、表計算や文書編集のソフトと「抱き合わせ」で配布されていることが多いという。利用者は別のソフトをインストールしているつもりで、バイドゥIMEも入れてしまった可能性がある。
市では、このソフトを削除したうえで、バイドゥのサーバーに接続できないよう対策を講じた。「今後も調査を重ね、仮に市民にかかわる情報漏えいがあればしっかり対応したい」と太田課長は話す。
外部ソフトのインストールが原則禁止となっている中央省庁でも発覚した。公用パソコン5台にインストールされていた外務省では、職員が届け出て、情報通信課が「業務に必要」と認めれば許可される仕組みという。担当者は「バイドゥIMEを許可した記録はない」としており、他のソフトをインストールする際に、入ってしまった可能性もある。
先端技術など知的財産を扱う教育研究機関でもソフトが見つかったが、「自由な気風を大切にする大学では、ソフトの規制は難しい」とある大学関係者は漏らす。職員など事務系の端末計約600台中16台から発覚した東工大のセキュリティー担当者も「事務系端末はまだ把握できるが、研究者や学生の持ち込んだパソコンまで管理できず、全体像はつかめない」と打ち明ける。
バイドゥIMEは、数年前から登場した「クラウド変換」という機能が導入された便利なソフトでもある。変換機能を向上させるため、サーバーに利用者の入力情報を送り、学習させているとみられる。東工大の担当者は、「利用者の便宜を考えた機能だとは理解できる」としながらも、キーボードで入力した内容を監視する「キーロガー」というウイルスと「まるで同じだ」と批判する。
中国の企業らしい問題だ。
百度ソフト、情報外部送信停止…初期設定を変更 12/27/13(読売新聞)
中国の検索大手「百度(バイドゥ)」製の日本語入力ソフト「バイドゥIME」が文字情報を同社のサーバーへ無断で送信していた問題で、同社が設定を改め、情報の外部送信を停止していたことが分かった。
変更についてバイドゥ日本法人は「担当者が不在のため回答できない」としている。
情報セキュリティー会社「ネットエージェント」(東京)の解析によると、設定が変更されたのは、読売新聞がソフトの問題点について取材した後の25日午後10時頃。
同ソフトは「クラウド変換」と呼ばれる仕組みで、多数のパソコンから入力情報をサーバーに送り、変換精度を向上させていた。
これまでの初期設定は、「クラウド入力機能を有効にする」になっていたが、25日夜以降は、「有効」を選択できない状態になっている。
一方、バイドゥは、同様に文字情報を無断で送信していたスマートフォン用の日本語入力ソフト「Simeji(シメジ)」については、27日未明、「情報を送信しないように初期設定を修正した」と発表。同ソフトでは、クラウド変換を利用しない設定に変更しても、入力した文字列が送信されていたが、これについては「プログラムの欠陥だった」と説明している。
【北京=牧野田亨】中国のバイドゥ本社は26日、中国版ツイッター「微博」を通じ、「不法なデータ送信や情報漏えいの問題、危険は存在しない」と主張する声明を出した。
国交省:改ざん究明、異例の告発 JR北悪質さ際だち 12/27/13(毎日新聞)
JR北海道の社員が脱線事故現場のレール検査データを改ざんしていた問題は、国土交通省が関与した数人と法人としての同社を鉄道事業法違反の疑いで北海道警に刑事告発する方針を固めたことで、刑事事件に発展する見込みとなった。今回の改ざんは一連の不祥事とは悪質さの次元が異なる。国土交通省は行政指導レベルではうみを出し切れないと判断、捜査機関の力を借りて責任の明確化を目指す。
JR北海道によると、現場を管轄する大沼保線管理室の社員2人が改ざんしたのは、事故発生からわずか2時間後。当時、現場では復旧作業が行われている最中だった。さらにその2時間後には上部組織の函館保線所の社員が「整合性をもたせろ」と指示し、細かい改ざんが行われた。同社の経営問題に詳しい宮田和保北海道教育大教授は「手口が慣れている」と指摘する。
さらに悪質さを際立たせているのは、事故から2カ月後の12月2日、本社工務部の社員が管理室に事故前の検査データの提出を求めたところ、管理室側が「保管していない」と拒否したことだった。
不審に思った本社社員が管理室のパソコンを調べたところ、「ない」とされた検査記録が保存されていた。精査の結果、国交省運輸安全委員会や北海道警に報告した数値と食い違っていることが発覚。上部組織も絡んだ改ざんだったと明らかになった。
改ざんの動機について同社は「調査中」としているが、脱線事故につながったレール異常の放置を隠蔽(いんぺい)するのが目的だった可能性が高い。この間、国交省は大沼保線管理室に特別保安監査(立ち入り検査)に入っていたが、改ざんの事実は見抜けなかった。菅義偉官房長官は「原因究明を阻害する改ざんほど悪質性の高いものはない」と批判。国交省に厳正な処分を求めていた。
脱線事故について道警は、業務上過失往来危険などの容疑を視野に調べてきた。しかし、検査データの改ざんが組織ぐるみで行われ、しかも虚偽の報告がされていたことに対し、内部では「局面は変わった。遅かれ早かれ刑事事件にせざるをえないだろう」との声もあがる。幹部は「告発があれば捜査を尽くすのは当然」と話した。
「会見には絶対に行くな」国内マスコミ異常反応で、ミスインタのストーカー被害告白は“なかったこと”に!? (1/2)
(2/2) 12/25/13 (日刊サイゾー)
日本人初のミス・インターナショナルグランプリ、吉松育美が大手芸能プロ「ケイダッシュ」幹部の谷口元一氏から脅迫被害を受けたと訴えている件は、刑事と民事の両方で提訴されているにもかかわらず、多くのメディアが無視。一部スポーツ紙がネット上に掲載した記事も、突然削除される事態となっている。
別のスポーツ紙の若い記者からは「夏に彼女について取り上げようとしたら、ストップがかかった」という話も聞かれた。吉松を紙面で特集しようとしたところ、上司のデスクから「それは絶対にダメだ」と、理由も告げずに止められたという。後に分かったのは、今月13日に吉松が東京・霞ヶ関の司法記者クラブで記者会見した脅迫被害だったが、「この会見も、デスクから“絶対に行くな”って言われたんですよ」と記者。
吉松が会見で話したのは谷口氏から受けたさまざまな被害で、大半の媒体がスポーツ紙同様、この芸能プロに気を使い、報じなかった。そのため吉松はさらに16日、外国特派員協会で会見、海外メディアに向かって訴えた。結果、米ワシントンポストやABCニュースなどで取り上げられているにもかかわらず、日本では「なかったこと」になっている異常事態だ。
吉松は本来、昨年の覇者として今年のミス・インターナショナルのイベントに出演する立場だったが、これも主催者の国際文化協会から「体調不良を理由に欠席してほしい」とストップがかかった。関係者によると「ほかにも仕事のオファーが急激に途絶え、決まりかけた仕事でさえ“諸事情でキャンセルに”と連絡があった」という。
吉松が被害を受けた谷口氏は、芸能界では有名な人物だ。「所属のタレントを何かと番組に押し込んでくるし、こっちが必要なタレントをお願いすると、必ずバーターで別のタレントを使わされる」(同)という。
「感情の起伏が激しく、怒ると暴力団かと思うほど怖いが、トラブルがあると涙ながらに謝ってくることもあるので面倒な人物」(同)
吉松は、谷口氏が吉松の海外エージェントとの間に金銭トラブルを抱え、その矛先を吉松に向け、仕事現場に現れたり、実家に脅迫的な電話をかけたりしてきたというが、実のところテレビ関係者は「その手口はおなじみ」という。
「谷口氏は表向き、金の問題を理由に女性タレントにコンタクトを取っているように見えますが、取りたいのは金ではなく女性のほう。弱みを握って意のままに操るのが得意で、タレントとして使いながら私生活でも絡んでくるというウワサ。代表例が自殺した川田亜子さんでしょう。谷口氏とは恋人関係だったなんて話になっていますが、川田さんには内密にしていた恋人が別にいましたし、谷口氏とは恋人というより、仕事と私生活で縛られていた奴隷状態にしか見えなかった」(同)
実際のところはどうか分からないが、確かに吉松も昨年、元K-1プロデューサーの石井和義氏がやってきて、谷口氏の事務所へ入るよう求められた話を明かしている。金銭トラブルの解決を求めるだけなら、そんな要求は出てこないはずだ。
「石井さんはK-1時代、谷口氏の息のかかった女性タレントをイベントに使っていた関係で、谷口氏同様に女性タレントとの関係がいろいろウワサされていた人物。だいたい吉松さんをスカウトする使い走りのようなことだけだったら、喜んでやるわけがなく、なんらかの形で恩恵を受けているはず」(同)
外国特派員協会の会見に訪れたイタリア人記者は「日本のテレビ局や新聞24社に“この話を取り上げないのか”と聞いてまわったが、首を縦に振ったのは週刊誌1社のみだった」と話す。
犯罪が起きても、親しい関係者なら無視する日本のマスコミ。実は筆者もこの取材の渦中で、その幹部の関係者をあたったところ「そんなことやっていると、どこにも出入りできなくなるぞ」と脅かされた。とても健全な世界とは思えない芸能界、吉松の提訴で、その実態が明らかになるのだろうか?
(文=鈴木雅久)
強制わいせつ裁判敗訴の野村総研、被害女性支援者を控訴へ~法曹界から「詭弁」との批判も (1/2)
(2/2) 12/25/13 (日刊サイゾー)
「ブラック企業アナリスト」として、テレビ番組『さんまのホンマでっか!?TV』(フジテレビ系)、「週刊SPA!」(扶桑社)などでもお馴染みの新田龍氏。計100社以上の人事/採用戦略に携わり、数多くの企業の裏側を知り尽くした新田氏が、ほかでは書けない「あの企業の裏側」を暴きます。
株式会社野村総合研究所(東証一部/以下、野村総研)は、同社中国北京社副社長だったY氏による女性への強制わいせつ行為、その通知を受けた同社による被害者女性側への脅迫行為、Y氏によるつきまとい行為が、東京地裁で「真実の通り」として認定されたことを受け、その取り消しを求めて東京高裁に付帯控訴のかたちで控訴したことがわかった。
同事件は、Y氏が取引候補先企業の日本人営業担当女性社員を会社のメールで呼び出し、さかんに酒を飲ませ酔わせた後、女性が乗るタクシーに乗り込んで性的嫌がらせを行い、さらに女性のひとり暮らしの自宅にまでついていき猥褻行為を働いたとされる、いわゆる「野村総研強制わいせつ事件」である(事件内容の詳細はこちら)。
この強制わいせつ行為の通知を受けた野村総研は、弁護士を使って「裁判にするなら友だちを法廷に呼び出してやる」「法的措置をとる」などと被害者女性に脅迫的な対応を繰り返した。そして同社の行為が社会的に悪質すぎるとして、被害者女性を支援する団体の一人(以下、支援者・A氏)が告発したが、ほかにもY氏による行為の被害者女性が多数いることを知った同社は、A氏と被害者女性の一人を「名誉棄損」だとして東京地裁に提訴していたのだ。
まず、被害者女性に対し起こされた裁判においては、当初から野村総研は性犯罪が親告罪であることを悪用して、被害者女性を裁判を使って恫喝し性犯罪の立件をさせないようにする手口を使っているのではないか、という批判が数多くなされていた。そして同社は被害者女性を訴えておきながら、裁判ではなんら名誉棄損の事実を証明することができず、被害者女性と和解もできずに訴えを取り下げて、実質上、同社の全面敗訴が確定した。
そして、支援者・A氏に起こされた裁判では、9月13日に東京地裁民事15部合議A係において判決が言い渡され、三角比呂裁判長は「野村総研の猥褻行為、その上での被害者女性側への脅迫行為、加害者の被害者女性へのつきまとい行為は真実の通りであり、告発に公共性、公益性も認定され名誉棄損、業務妨害にいずれもならない」という主旨の判決を述べて、訴訟費用の負担割合を「野村総研:A氏=9:1」と、告発内容のほとんどについて「真実の通り」と認定した。しかし同時に判決においては、「A氏の告発内容には『野村総研はブラック企業である』と、同社が恒常的に悪質な行為を行っているような心象を受ける表現があったが、その部分については証明が足りないなどとして、告発内容の一部のみ認容をする判決となった。
●野村総研を控訴へ
この判決内容を受けA氏は今回、東京高裁に控訴し、一方の野村総研側は一審で「事実」と認定された一連の悪質行為の認定取り消しを求めて付帯控訴をし、東京高裁で争うこととなった。A氏は控訴に踏み切った理由について、次のように語る。
「内容を考えれば実質的な勝訴である。当方は多くの被害者女性たちに配慮して、被害者情報を加害者の野村総研に明かすような不要な立証は一切しなかったが、それでも大部分は真実の通りと認定いただいている。しかしながらわいせつ、脅迫、つきまといまで認定されている野村総研が、正当な告発について名誉棄損と主張している不当な主張が、たとえごく一部でも認められたままでは、このような恫喝訴訟の行為が助長されて被害者がさらに増えてしまうので、それは防がないといけない」
ちなみに野村総研の代理人弁護士は、一審で東京地裁から「同社と共に脅迫行為を行った」と認定された森・濱田松本法律事務所の高谷知佐子弁護士が変わらず担当している。本裁判は東京高裁民事2部において、12月24日より口頭弁論が開かれる予定である。
この事件について野村総研や、同社が所属する野村ホールディングス、野村総研への訴訟資料支援などをしてきたセブン&アイ・ホールディングスに対し、筆者は取材依頼を申し込んだ。そして、回答期日から遅れて、野村総研から以下のとおり興味深い回答が寄せられた。
「株式会社野村総合研究所
コーポレートコミュニケーション部 広報課
取材のご依頼について
ご質問の判決におきましては、弊社が請求の中で採り上げたブログ記事および送付文書について、被告の弊社に対する名誉・信用棄損、業務妨害が概ね認められ、被告に対し損害賠償の支払いが命じられております。被告がこれに控訴したことにより、現在も同人との間で係争中であるため、関連する取材はお断りをさせていただきます。」
この回答内容から、野村総研は「同社の主張が『概ね」』認められた」と外部に説明している実態が明らかとなった。だが、前出のとおり訴訟費用の負担割合が「野村総研:A氏=9:1」とされたように、認容割合がわずか1割の内容について「概ね」という表現は適切ではない。
ちなみに、判決文を含め今回の全裁判資料を見たある弁護士は、次のように野村総研の姿勢に疑問を呈す。
「この判決は弁護士が見れば、誰がどう見ても野村総研の実質上の大惨敗です。名誉棄損の判決においてはなかなか片方だけが一審から完全勝訴とはならない。認容内容も、判決を見ると損害内容が判決文においても定義されておらず不明なままで、信用棄損の範疇とも考えられるような微額のみを認容しているものです。これは森・濱田松本法律事務所という大手法律事務所を付けた野村総研側への配慮で、裁判所が最後に多少調整を付けたのではないかとも考えられる内容ですから、調整分とも考えられます。
このわずかな内容をもって、野村総研の主張が『概ね』認められたなどとは、誇張を超えて虚偽というべき内容で、典型的な『詭弁』でしょう。名誉棄損罪を構成するかどうかはともかく、弁護士の倫理観としては、こちらのほうが名誉を不当に毀損する詭弁というべきではないでしょうか。まともに倫理観がある会社や経営者、もしくは弁護士であれば反省をするところでしょうが、一審判決を受けても野村総研や代理人弁護士は、なんら反省などしていないことを表していると思います」
弁護士も疑問を抱くような姿勢を取る野村総研と、A氏の争いは、ついに東京高裁にその場が移された。今後も本裁判の動向を注視していく予定である。
(文=新田 龍/株式会社ヴィベアータ代表取締役、ブラック企業アナリスト)
死亡事故がなくてよかったですね。尼崎のような脱線事故で多くの乗客が死んでしまったら、20年前から改ざんが続いていたなんて本当のことなんか言えないだろう。
日本の安全意識は他の国よりは良いかもしれないが、しかしながらこんなものなのであろう!
「データ改ざん、国鉄時代から」JR北の労組側 12/21//13(読売新聞)
JR北海道の経営幹部と4労働組合が、安全運行の確保に向けて一堂に会して議論する合同会議の初会合が20日、札幌市の本社で開かれた。
会議では労組側から「データ改ざんは国鉄時代から行われていた」とする発言も出て、企業体質の改善が容易でないことが浮き彫りにされた。野島誠社長は、今後も3か月に1回程度で合同会議を開くことを提案し、「(労組側の)意見を会社の施策に反映させて安全な鉄道を作っていきたい」と語った。
会社側と4労組が安全問題について、意見を交わすのは同社発足以来初めて。トラブルが収束しない一因には、JR北には労組が複数あることで、社内の意思疎通が十分図れていないとの指摘がある。
4労組は、JR総連系の北海道旅客鉄道労働組合(JR北海道労組、約6000人)、JR連合系のJR北海道労働組合(JR北労組、約550人)、国鉄労働組合北海道本部(国労、約130人)、全日本建設交運一般労働組合北海道鉄道本部(建交労、約10人)。この日はJR北の経営幹部と4労組の委員長ら計16人が出席した。会社側がレールの異常放置や改ざんなど一連の問題の経緯と、特急車両更新の前倒しなど今後の安全対策について紹介。労組側は職場の現状などを説明したという。
会議終了後、4労組が取材に応じた。道労組の鎌田寛司委員長は「複数の保線現場で国鉄時代から改ざんを行っていたと聞いた」と明かした。その上で「データの書き換えを行った社員の問題にとどめず、JR北海道の体質にメスを入れるべきだ」と会議で述べたとしている。国労の工藤義明書記長によると、国労も労使交渉の記録を基に改ざんが20年以上前から問題になっていたとしたが、会社側は聞いたことがないと答えたという。
電力会社は景気の景況を受けないし、安定していると電力会社社員が思って人生設計してきた結果であろう。計画していたような収入が入らなくなった結果だ。
多くの社員が同じような意識を持って人生設計や支出計画を立てていた証拠だ。
安定を感じていない会社員は大きな買い物はしないだろう。し、大きな買い物はしてもリスクを認識しているか、計画的な人生設計が出来ない人達であろう。
電力会社社員にとっては想定外の出来事かもしれないが、多くの人達は個々の判断で対応している。
「これはこの男性だけでなく社員約1万3000人の多くが似たような境遇に追い込まれていて、妻がパートに出ることになったり、車を売った社員もいる。」が事実だとしてもこれからは安定がない会社員のようなライフスタイルをすることにより解決できるはずだ。収入が減ったなら、減ったような生活をすれば良い。子供は私立へ行かさなくとも公立で良い。旅行のタイプを変えたり、総額を減らせば良い。買う衣料品のブランドを変更したり、総額を抑えれば良い。変化に対応できるか、出来ないかで同じ収入でも感じ方は変わってくるはずだ。他の会社へ転職した方が給料が上がるのならば、転職すれば良い。自己責任においての選択だ。
九電社員、年収減で「娘にクリスマスプレゼントも買えない」 ネットでは「高給取りがふざけんな!」と非難の声 (1/2)
(2/2) 12/20/13 (J-CASTニュース)
九州電力の社員の給与が引き下げられ、さらに今年は夏と冬のボーナスが支給されなかったためが困窮し借金するしかなくなった、などといった報道が流れた。ネットでは、「それでも高所得者だろ」「ふざけるな!俺は年収200万で暮らしているんだ」などといった批判の声が挙がった。
九州電力は地元の超優良企業で、もともと年収が高いとされてきた電気・ガスなどエネルギー関連主要25社の中でも上位に位置しているといわれてきた。
■妻がパートに出ることになり自動車も売った
産経新聞の2013年12月15日付けのウエブ版によれば、東京電力福島第1原発事故のあおりを受け、九電が管轄する玄海、川内の原発計6基がすべて停止し九電の経営が急激に悪化した。13年4月から社員の給与が5%カットされ夏に続き冬のボーナスも出ないこととなった。北九州市の新小倉火力発電所に勤務する42歳の男性技師は妻と大学生、高校生の娘との4人家族だが、娘の授業料や家のローンはボーナスで賄うことができなくなり「緊急用」に貯めた預金百数十万円は今冬にも底を尽く。娘にクリスマスプレゼントを買ってやることもできなくなってしまい、もし来年の夏もボーナスがゼロなら借金生活となる。これはこの男性だけでなく社員約1万3000人の多くが似たような境遇に追い込まれていて、妻がパートに出ることになったり、車を売った社員もいる。冬のボーナスが出ない代わりに給与1か月分の退職金の前払い支援策を打ち出した。
「このまま原発が動かないならば、一体どうすればよいのか…」
などと悩む人が増えていると書いている。
この記事に対しネットで「高給取りが貧乏人を装っている」などと怒りの声が挙がっている。一読すると超優良会社社員の転落であり同情を誘う内容なのだが、九電の有価証券報告書を見ると12年度は社員の平均年齢と給与が41歳で782万円と記載されている。また、4月に給与をカットしたりボーナスの支給をやめたのは、電気料金値上げを批判されたための対応だった。つまり、九電の社員は給与を「貰いすぎ」であり、それが経営悪化の一因とされているにもかかわらず電気料金を上げ給与水準を維持するのはけしからん、というもので、経産省の委員会は13年3月に一般社員の平均年収を28%減らすよう求めた。
九電はこのとき、平均年収は826万円だとし、そこから21%減らした650万円を提示し電気料金の原価に算入し申請したが、委員会が示した28%カットという数字は大企業の平均年収と同じ596万円が妥当として出したものだった。
社員一人一人が頑張って現状を乗り越えるしかない
ネットではボーナスが出ないといっても大企業と同等以上の年収のはずなのに、記事に出ている貧しさのアピールは何なんだ、「大企業の社員に失礼だ」、とか、退職金の前払い支援策といっているけれども実質上のボーナスの隠れ蓑なのではないのか、などといった意見も出ていて、
「嫁がパートに出るのがそんなに悲惨なことなのか。世界が違うな」
「もっと大変な暮らししてる奴がごまんといるのに 、なんでこういう奴らは同情してもらえると思ってんだろな?」
「無駄使いし過ぎw 俺、年収200万あれば月5万の奨学金返しても余裕で暮らせるぞ」
「本当に理解できないんだろうな。自分が誰に向かって何を言ってるのか。マイホームも家庭も諦めてる若者が大半な現状を」
などといった意見がネットの掲示板やブログに出ている。九電広報に対し、記事に出ているような社員たちが大変な状況になっているのか問い合わせてみたところ、
「様々な社員がいて一概に話はできないが、給与やボーナスカットということが決まった以上、社員が一人ひとり頑張って現状を乗り切っていかなければなりません」と話していた。
奇麗事だけではスポーツでも勝てない。正々堂々とか、スポーツマンシップは奇麗事なのだろう。
税金で、必要以上にスポーツを振興しなくてもよい。スポーツ庁のような組織も必要ない。日本は財政問題を抱え、増税しないと成り立たない国であると言う事を忘れてはならない。
フェンシング協会、遠征費を不正受給 900万円返却 12/20//13(朝日新聞)
日本フェンシング協会は20日、東京都内で記者会見し、海外遠征に対する日本スポーツ振興センター(JSC)の助成金を不正に受給していたと発表した。協会は既に過大受給した約900万円をJSCに返却し、不正に関わった事務局長を同日付で解雇した。
不正受給が発覚したのは、国の交付金を財源とする「メダルポテンシャルアスリート育成システム構築事業」。協会は今年1~3月に選手、スタッフ延べ約60人を欧州などに派遣し、滞在費として約2800万円を受給。実際には約1900万円しかかかっていなかった。1人平均1泊1万円程度で済んでいたが、2万円分の領収書を選手らに書かせていた。事務局長は「金は協会のために使った」と話しているという。
協会は既に第三者委員会を設けており、他にも同様の事案があるとみて調査を進める方針。山本正秀常務理事は「ショックを受けている。今後は管理を徹底したい」と話した。
フェンシング協会が不正受給=選手育成事業の900万円 12/20//13(時事通信)
日本フェンシング協会は20日、日本スポーツ振興センター(JSC)から支払われた選手育成事業の委託費のうち約900万円を不正受給していたとして、第三者委員会による中間報告を発表した。
同協会は将来、五輪などでメダル獲得が期待される若手選手の育成事業として、約2800万円の委託費を受け取り、今年1~3月の海外遠征などに使った。滞在費などは協会が一括して精算していたが、選手らにそれぞれ架空の領収書を書かせて回収し、総額を水増しした。
JSCには委託費を超える費用がかかったと報告しながら、実際にかかった総額は約1900万円だった。JSCが事実関係を把握した10月になって協会は差額を返還。処理に携わった事務局長を解任した。
第三者委は過去の経理処理などについても調査した上で最終報告書をまとめる。JSCの関係者は「非常に残念なこと。文部科学省とも連携して、今後の対応を決める」と話した。
フェンシング協会、滞在費水増し事業費不正受給 12/20//13(読売新聞)
日本フェンシング協会は20日、都内で記者会見を開き、日本スポーツ振興センター(JSC)から、約870万円を不正に受給したことを明らかにした。
協会が設置した第三者委員会によると、選手の育成事業として、今年の1~3月に海外に若手選手、コーチら延べ約60人を派遣した際、協会事務局長の指示を受けた関係者が、滞在費として1人あたり一律2万円の領収書を書かせた。協会は実際に宿泊施設などに支払った費用との差額を不正に受け取った。協会は今月3日、不正受給分と利息をJSCに返還した。同様の手口で他の事業でも不正をした疑いがあり、文部科学省は過去5年分についても報告を求める。
今回の問題は、今夏にフェンシングの合宿に同行したJSC関係者が、協会側に領収書の記入を求められたことがきっかけで発覚した。協会は弁護士らによる第三者委を組織し、事実関係などを調査していた。
エビチリとか好きだが、安いと何が入っているのかわからないな?高くても安心だとも思えない。
消費者が注目していないだけでいろいろ問題がありそうだ。
輸入届出における代表的な食品衛生法違反事例 (違反事例|厚生労働省)
輸入時における輸入食品違反事例 (違反事例|厚生労働省)
偽装例最多の食材…エビのぷりぷり感は薬品まみれだった! (1/2)
(2/2) 12/20/13 (WEB女性自身)
今回の食品偽装でもっとも数が多かったのが、エビの偽装である。典型的な例が、車エビを「ブラックタイガー」、芝エビを「バナメイエビ」で偽装することだった。そこで、この4種類にオマールエビを加えて食べ比べてみたら……。
「バナメイエビは身がぷりぷりしていますから、エビチリにはちょうどいいんです。でも気になるのは、茹でても身が白変しないことです。それと触感がヌメッとするというか……ちょっとへんな感じがしますね」
そう話すのは、東京・門前仲町にある中華料理店「オリエンタルビストロ・フィールズ」のシェフ五月女(そうとめ)和正さん。五月女さんは週に3回は築地に足を運び、20年間エビを扱ってきた、いわば「エビの目利き」だ。さっそく、五月女さんに5種類のエビをエビチリにしてもらった。味や食感を味わうには、エビチリがいちばんわかりやすいからだ。
芝エビは繊細な味で、エビの甘みが感じられる。ブラックタイガーは体がデカイだけで大味。圧倒的にうまかったのは車エビ。オマールエビももちろんおいしいが、車エビ科とはまったく別物の味わいだ。問題はバナメイエビだ。「プリッ」というよりも「ブヨブヨ」していて水っぽく、圧倒的に味わいが少ないのだ。
じつは、保湿性を高めるため「pH調整剤」や「リン酸塩」などの食品添加物を加える、下処理がされているからだという。ポリリン酸などの酸性の液につけると、エビの筋肉を構成するタンパク質の間に隙間ができて、そこに水が溜まるのだ。
もうひとつ有力と思わる説がある。それは業界でいう「ヤワラエビ」の可能性だ。脱皮直後の殻の柔らかいエビのことを、業界では「ヤワラ」と呼ぶ。一般に甲殻類は、脱皮前後に多量の水分を体内に取り込み、体重が著しく増加する。水分を溜め込んだせいか、タンパク質が凝固しにくい傾向があるらしい。これで、バナメイエビの身のブヨブヨ感と、過熱しても身が白変しない理由が見えてくる。
厚生労働省のHPでは、「輸入食品監視業務」の報告が閲覧できる。そのなかに「輸入食品等の食品衛生法違反事例」という項目があり、酸化防止剤まみれのインド産エビなどの事例が、これでもかというほど列挙されている。
頻出する違反内容は「成分規格不適合(AOZ検出)」というものだ。「AOZ」とは「フラゾリドン」という抗菌剤の代謝物質だという。養殖の段階でエビに投与された「フラゾリドン」が、エビの体内で分解され「AOZ」を生成し、それが検疫で検出されたわけだ。
「フラゾリドン」は日本で禁止されている合成抗菌剤で、発ガン性も否定できないという。だが、輸入エビの食品検査は、厚労省が必要と判断した場合にしか実施されない。ということは、AOZ入りのエビが輸入されている可能性は大いにありうるのではないか。
「たとえばエビチリでも、安いエビをたくさん出すか、高いエビを少し出すか、店ではどちらでも対応できます。どちらを選ぶかはお客さん次第ですが、でも多くの人はエビがたくさん入ってるほうを選ぶのではないでしょうか」(五月女さん)
(FLASH 12月24日号)
実際はこのような訓練は必要なのかを議論し、最終的な判断をするべきではないのか。
「航空法ではこうした行為を禁じており、同委は教官の問題行為が事故につながった可能性があると指摘している。」
しかし、雲の中へ入った経験がないままに資格を取得したら、結局、資格を取得しても雲の中に入ってしまう状況になった時に適切に対応できないのではないのか。
訓練中の死亡事故は減らせるが、資格を取得した後の事故は減らせないのでないのか?
教官指示で雲の中へ、目標失う…航空大機墜落 12/20/13 (読売新聞)
航空大学校帯広分校の訓練機が北海道芽室町の山中に墜落し、指導役の教官と学生ら4人が死傷した事故で、運輸安全委員会は20日、同機は教官の指示で雲の中に入り、周囲の目標を失って墜落したとする調査報告書を公表した。
航空法ではこうした行為を禁じており、同委は教官の問題行為が事故につながった可能性があると指摘している。
大学校は統計の残る1974年以降、死亡事故が4件起きているが、3件は運営が国から独立行政法人に移行した後に発生。同委は「問題点を抽出する必要がある」と指摘し、教官の教育実態を把握して適切に監督する体制を作ることなどを大学校と国に勧告した。
報告書では、同機は2011年7月28日午前9時10分頃に帯広空港を離陸。約10分後、約30キロ離れた剣山の山中に墜落した。同機は墜落直前、教官の指示で雲の中に入り、周囲の目標を失って墜落したという
高血圧薬データ改ざん、ノバ社を刑事告発へ 12/18/13 (読売新聞)
高血圧治療薬「ディオバン」の臨床研究データ改ざん問題で、厚生労働省は、不正なデータを広告に使用したことが薬事法違反(誇大広告)の疑いがあるとして、販売元のノバルティスファーマ社(東京)と問題の広告に関与した同社の担当責任者を、近く同法違反容疑で捜査当局に刑事告発する方針を固めた。
同省の調査に対し、同社は組織としての関与を否定しており、捜査で実態を解明する必要があると判断した。
薬事法は、医薬品などで虚偽や誇大な表現を使った広告を禁じており、違反した場合は2年以下の懲役か200万円以下の罰金。同省によると、記録が残る1975年以降、誇大広告のみで行政処分や刑事罰を科されたケースはない。同省は告発先として、東京地検を軸に最終調整している。
安いのかもしれないが胡散臭そうな宣伝の仕方だ!
「小西会長は『がんの遺伝子検査技術を主にPRしたいとの申し出があり、認めた。懸念があるのは確かだが、反社会的勢力などでない限り、出展は拒否しない}と話している。」
つまり嘘をつくような企業であっても「反社会的勢力など」でなければ問題ない。しかし専門的な知識がない顧客は「反社会的勢力など」でないから信用できるのか判断できないと思う。
癌検査PRのはずが格安出生前検査…中国企業 12/16/13(読売新聞)
妊婦の採血で胎児の染色体の病気を調べる新型出生前検査を手がける中国の遺伝子解析会社「BGI」が、神戸市に関連会社を設立し、検査の受け付けを始めたことがわかった。同社は、京都市で15日まで開かれていた日本婦人科腫瘍学会の学術集会(会長=小西郁生・京都大教授)に出展して、宣伝活動を行った。
新型検査は現在、カウンセリング体制の整備などを条件に日本医学会の認定施設で限定的に実施されている。結果次第では人工妊娠中絶につながりかねないため、十分な説明や相談が必要との配慮からだ。
一方、同社は検査の宣伝資料を認定外の施設に送付。検査を個別に請け負うことを狙っており、今後は認定外施設でも広がる可能性がある。
読売新聞の入手資料によると、関連会社は今年7月設立、ダウン症など3種類の染色体の病気の検査を実施。1件当たり10万円で受注している。
現在、認定施設での検査の患者負担は約20万円。出展した同社担当者は取材に応じなかった。
小西会長は「がんの遺伝子検査技術を主にPRしたいとの申し出があり、認めた。懸念があるのは確かだが、反社会的勢力などでない限り、出展は拒否しない」と話している。
危ないチキンレースになりそうだ!リストラするのは問題ないが、機体の維持管理、維持管理の人材、そしてゆとりのあるシフトにまでリストラの対象が広がっていれば運が悪ければ事故につながる。
豪カンタス、1千人リストラへ…格安競争で苦境 12/15//13(読売新聞)
豪州の航空最大手カンタスグループが業績悪化に苦しんでいる。豪州政府に支援を要請したが、再建できるかどうかは不透明だ。
カンタスは5日、2013年7~12月期の税引き前利益が最大3億豪ドル(約280億円)の赤字になるとの見通しを発表。同時に、従業員を1000人以上減らしたり役員報酬をカットしたりして、3年間で20億豪ドルの経費を削減するリストラ計画も明らかにした。
これを受けて、米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は6日、カンタスの格付けを投資不適格の「BBプラス」に引き下げ、同社の信用不安が高まっている。
カンタスは現在、成田―シドニー線を毎日運航しているほか、子会社の格安航空会社(LCC)ジェットスターも、成田や関西空港と豪州内の空港とを結ぶ路線を運航している。今後の業績によっては、これらの国際線の見直しを迫られる可能性もある。
カンタスの業績が悪化しているのは、航空需要の減少や燃料費の上昇に加え、2000年に参入したLCCのヴァージン・オーストラリアとの競争が要因だ。カンタスも04年、対抗してジェットスターの運航を始めたが、リーマン・ショックで経営はさらに厳しくなった。
安値競争を仕掛けるヴァージン社も、13年6月期決算が赤字となるなど経営は厳しい。現在はシンガポール航空、ニュージーランド航空、アラブ首長国連邦(UAE)のエティハド航空の3社から出資を受け、財務を強化している。
その3社が国営会社であるため、カンタスのアラン・ジョイス最高経営責任者(CEO)は5日の声明で「ヴァージン社は外国政府の資金支援を受けており、競争は公平でない」と批判した上で、豪政府に支援を求めた。ただ、政府内には、公的支援に慎重な意見が根強いとされる。(豪ブリスベーンで、三好益史)
◆カンタスグループ=1920年に設立された豪州の「ナショナル・フラッグ・キャリアー」(国を代表する航空会社)で、成田―シドニー線などを運航している。47年に国営化された後、95年に民営化。日本航空と同じ国際航空連合「ワンワールド」に加盟。
JR北海道の再生遠のく 貨物列車脱線から2時間でデータ書き換え「異次元のガバナンス」 12/14//13(北海道リアルEconomy)
9月に起きたJR函館線大沼駅構内での貨物列車脱線事故から2時間後に、事故現場のレール幅検査データが書き換えられていたことが分かった。書き換えは現場部署を管轄する函館保線所が指示、組織的な隠蔽だったことが初めて発覚した。脱線事故の原因を隠蔽する組織的行為でJR北海道のガバナンス、モラルが一線を超えた異次元にあったことを示すものだ。(写真は桑園駅に直結しているJR北海道の本社)
一連のレール幅異常放置や実際の数値と異なる数値をデータとして入力した行為は鉄道事業者としてあってはならないことだ。しかし、脱線事故からわずか2時間後にデータを書き換えられていたことは、こうした行為が日常的に行われていたことを証明することになった。
現場の混乱をよそにデータ書き換えを指示した上部組織とそれを実行した現場社員にはおそらく抵抗感はなかったのだろう。事故原因究明を妨害しても構わないという現場の感覚を蔓延させた組織はもはや組織とは言えない。
組織のトップである社長の役割は、社員に企業の目的と理念、社会的役割を自覚させることにある。JR北海道は社員約7000人をまとめて行くのに相応しい社長の選び方をしていたのか疑わしい。民営化後、3代目以降の社長は東大卒で昭和44年国鉄同期入社3人が順番に務めるという暗黙知があったというが、そのレールに乗らなかった人物もいる。歯に衣着せず正論を主張するその人物は「社風」に馴染まない空気の中でやがて社長へのレールから外れ、「外」に出されることになった。
「内」に残った2人は社長を「順番」に務めたが、こうしたトップの決め方、決まり方にこそ今日の目を覆いたくなるようなガバナンス欠如の芽があったのではないか。
一般的に事故の原因は設備由来のものもあるが、多くはヒューマンエラー、つまり人間の不安全行動からくる。ところが今回発覚した事故はどちらにも当てはまらない。事故後わずか2時間のデータ書き換えは設備の不良を隠蔽する意図的なヒューマン行動が日常的・組織的に容認されていたからだ。
JR北海道の正式名称は北海道旅客鉄道。国鉄分割で誕生した鉄道会社の多くは「鉄」を使わず「金」偏に「矢」と書いて「てつどう」と無理に読ませている。金を失うことに通じることを嫌い、縁起を担いだからだ。JR北海道は金を失う代わりに信頼を失った。
再生は遠のく一方だ。JR北海道は組織として消滅のカウントダウンを刻み始めた。
組織ぐるみで隠蔽か…JR北、脱線直後にデータ改ざん 12/13//13(ANN NEWS, YouTube)
組織ぐるみで隠蔽か…JR北、脱線直後にデータ改ざん 12/13//13(北海道リアルEconomy)
北海道のJR函館線で起きた貨物列車の脱線事故で、事故直後に事故原因に絡む保線データの改ざんが行われていたことが明らかになりました。
JR北海道は、脱線事故の直後に保線の担当者が現場のレール幅が実際39ミリ広がっていたにもかかわらず、25ミリと改ざんして報告していたことを明らかにしました。さらに、上部組織の函館保線所が、改ざんを隠蔽(いんぺい)しようとほかの9カ所の数値も変更するように指示していたということです。貨物列車が脱線した現場のレール幅は、脱線の危険性が高いレベルに広がった状態だったにもかかわらず、JR北海道は脱線事故が起きるまで3カ月間放置していました。
JR北海道・豊田誠常務:「函館保線所の社員の指示により、整合性を取るためにもう少し細かいデータを(さらに)書き換えた」
脱線事故があった大沼駅構内では、これまでの調査で、改ざんが27カ所に上ることなどから、JR北海道は組織ぐるみでレールの異常を隠蔽しようとしたとみられています。
JR北海道改ざん、3つの謎 11/15//13(読売新聞)
初日の特別保安監査を終え、JR北海道本社から出てきた国土交通省の職員ら(14日午後8時頃、JR北海道本社前で)
JR北海道の函館保線管理室によるレールの計測データ改ざん問題は、国土交通省の3回目の特別保安監査に発展した。
改ざんは最初の監査前日、異常を隠蔽する目的で組織的に行われた可能性が高い。このため、同省は異例の抜き打ち方式で監査に臨むが、本社が改ざん前の計測データを入手しながら同省に報告しなかった理由などが、監査の焦点となりそうだ。
◆国交省幹部、怒り
「鉄道を担当して30年。鉄道会社の改ざんが取りざたされるなんて初めてだ」
14日、ある国交省幹部は怒りをあらわにした。別の幹部も「異常の放置も悪いが、改ざんはそれと一線を画す悪質さだ」と語気を強めた。9月の監査で、同社にだまされた格好の同省は、今回の監査で函館保線管理室以外も徹底的に調査する方針だが、同管理室の改ざん問題では大きく三つの謎が残されている。
◆今も「調査中」
同管理室管内では9月21日、レールの待機などに使われる「副本線」の複数箇所で異常が見つかっていたにもかかわらず、同社本社に「異常はない」と電話で報告した(=表〈1〉)。同管理室の誰が、なぜウソの報告をしたのか分かっていない。同社は今も「調査中」と固く口を閉ざす。
同日の時点では、レールの異常は計9か所で見つかっていた。国交省は他にもないか、緊急の調査を同社に指示。同社はこれを受け、同管理室を含む44の保線担当部署に口頭で報告するよう求めていた。
◆本社はゼロ報告
翌9月22日には、本社が各保線担当部署に、報告の内容を裏付けるためレールの計測データの提出を求めた。同管理室は、レールの補修基準を超える異常が含まれたデータを同社本社に出した(=表〈2〉)。23日には、同社は国交省に全道計97か所で異常の放置が見つかったことを報告したが、同管理室管内は「ゼロ」とされた。
同管理室は21日、「異常はない」と報告しながら、なぜ22日には異常値を改ざんしていないデータを出したのか。本社が23日、同管理室の異常をスッポリ落として国交省に報告した理由と合わせて不明のままで、二つ目の謎となっている。
◆「会社守るため」
最後の謎は、同管理室で改ざんを主導した人物や、その動機だ(=表〈3〉)。
同社などによると、改ざんは、同管理室に特別保安監査が入った前日の25日に行われた疑いが濃い。同社は、同管理室の複数の社員が改ざんに関与したと明らかにしたが、主導した人物や理由などはすべて「調査中」としたままだ。
改ざんの動機について、同社の調査に「会社を守るためだった」などと語る同管理室社員もいたというが、3日前の22日には、本社に異常箇所が記載された改ざん前のデータを提出しており、改ざんしても本社のデータと突き合わせれば判明してしまう。
結果的に改ざんは発覚し、国交省による異例の抜き打ち監査という、JR北海道発足以来最悪の危機を招いた。
「周防氏の威光は通用せず……」現役ミスが暴いた“芸能界のドン”率いるバーニングの闇 (1/2)
(2/2) 12/14/13 (日刊サイゾー)
昨年の「ミス・インターナショナル」で、日本人として初めてグランプリに選ばれた吉松育美が、大手芸能プロ「ケイダッシュ」の幹部で、関連会社「パールダッシュ」社長の谷口元一氏を11日、威力業務妨害で警視庁に刑事告訴、ならびに東京地裁に民事提訴したことを「週刊文春」(文藝春秋)12月19日号と同誌の電子版が報じている。
同誌によると、谷口氏は吉松の海外エージェントであるマット・テイラー氏と以前から金銭トラブルになっており、テイラー氏に1,000万円の借金返済を求めていた。だが、テイラー氏と連絡がつかなかったことが発端で、谷口氏が収録現場に押しかけて吉松を追いかけたり、吉松の実家に電話をかけたり、探偵を使って自宅を撮影させる、仕事関係先に電話をかけるなどの、執拗につきまとうストーカーまがいの行為で業務を妨害。
この谷口氏による関係方面への圧力が原因で、主催者サイドから「マスコミが騒ぐと困るから、世界大会は体調不良を理由に参加を自粛してほしい」と言われ、現役ミスとしての最後の務めを果たすことができなかったという。
吉松は11日に更新した自身のブログで、同誌の取材を受けたことを明かし、「やっと掴んだ大きな夢を一瞬にして、ハンマーでぶち壊された気分でした。この感情というのは、容易に言葉に表すことのできないものです」と告発に踏み切った胸中を暴露した。
「谷口氏とマット氏の因縁は浅からぬものがあった。08年5月に元TBSアナウンサーで当時はフリーだった川田亜子さんが自家用車の中で練炭自殺したが、谷口氏との交際のもつれが死因として浮上。その際、マット氏は川田さんの“最後の恋人”としてメディアに登場し、谷口氏を“糾弾”。その後、マット氏が谷口氏を名誉毀損・脅迫・業務妨害などで東京地裁に提訴していた。生前、川田さんがマット氏に谷口氏を紹介。その際、マット氏に貸した金が返ってこず、金銭トラブルに発展。吉松はマット氏がエージェントでなければ、今回のトラブルに巻き込まれることはなかった」(週刊誌記者)
今後、吉松は録音や写真を証拠として提出する予定だというが、これまで谷口氏が芸能界で振りかざしてきた“威光”は、吉松にはまったく通用しなかったようだ。
「谷口氏といえば、所属は川村龍夫会長率いる『ケイダッシュ』だが、長年“芸能界のドン”ことバーニングプロ・周防郁雄社長の“鉄砲玉”として汚れ仕事をこなし、『所属ケイダッシュ、本籍地バーニング』と言われていた。今までは女性タレントに手を出そうが、ほかの事務所のタレントの仕事を、謀略を巡らせて“強奪”しようが、周防氏の威光をちらつかせて切り抜けてきた。ところが、吉松は今後も芸能界で成り上がろうという未練がなかったので、周防氏の威光がまったく通用しなかった」(芸能プロ幹部)
今後の警察の動きと訴訟の行方が、非常に注目される。
機関銃検査データ改ざん、住友重機が防衛省納入 12/14//13(読売新聞)
住友重機械工業(東京)が防衛省に納入している機関銃について、耐久性などの検査データを改ざんし、同省が要求した性能に満たない製品を納入していた疑いがあることが、同省関係者への取材でわかった。
同社製の機関銃は、自衛隊で広く使用されており、同省で経緯を詳しく調べている。
同省幹部によると、同社では陸自の機関銃や、海空自衛隊の機関砲などを製造。目標への命中率や射程、弾の速度などの性能は、同省が要求した基準通りに製造する取り決めになっている。
ところが、一部の機関銃について、性能確認試験の際、耐久性や発射速度などのデータを改ざんし、基準を満たしたことにしていた疑いがあることが判明。こうした不正は10年以上前から行われたとみられ、問題のある機関銃は1000丁を超える可能性があるという。今年に入って同社から申告があり発覚した。
JR北社員3人、脱線事故対応せずデータ改ざん 12/14//13(読売新聞)
JR北海道の函館線大沼駅(北海道七飯町)で今年9月に起きた貨物列車の脱線事故の直後に、現場を管轄する大沼保線管理室などの社員3人がレール計測データを改ざんした問題で、3人が社内規定に反して、脱線事故の処理業務を怠っていたことが分かった。
保線担当社員として、事故の原因究明などを行う義務があったにもかかわらず、運輸安全委員会の調査妨害につながる改ざんに手を染めていた形だ。
事故は9月19日午後6時5分頃に発生。まず同管理室の社員2人が同日午後8時頃、現場付近の計測データを改ざんした。さらに同10時頃、上部組織の函館保線所の社員1人が同管理室の2人に、改ざんの範囲を広げるよう指示した。
改ざんが行われた午後8~10時頃、事故現場では保線担当社員が原因の調査などを行っていたほか、駅員や車掌が代行バスを手配したり、駅で利用客に列車の運行状況を説明したりしていた。3人も出勤を命じられたが、事故関連の業務には当たらず、大沼保線管理室で過去の計測データを改ざんしていた。
抗がん剤の有料記事「金銭授受なら問題」厚労相 12/13//13(読売新聞)
がん患者向けの月刊誌に掲載された記事が、薬事法が禁じる抗がん剤の広告にあたる可能性があるとして厚生労働省が調査している問題で、田村厚労相は13日の閣議後記者会見で「薬事法違反が認識できれば適切に対応する」と述べ、記事掲載にあたり出版社に金銭を支払っていた製薬会社への行政指導などを行う考えを示した。
田村厚労相は「お金がやりとりされているのであれば問題だ。本当に広告ではないのか」と述べ、広告の要件を明確化する考えも示した。
名大は「データ操作ない」…ディオバン臨床研究 12/14//13(読売新聞)
製薬会社ノバルティスファーマの高血圧治療薬「ディオバン」の臨床研究データが改ざんされていた問題で、名古屋大の調査委員会は13日、同大の臨床研究の論文について「現段階ではデータの捏造(ねつぞう)はない」とする中間報告を発表した。
ノバ社の元社員が、統計解析の専門家として臨床研究に携わったが、調査委は「解析は別の研究員と共同で行っていた」などと指摘。名大に残る141人分のカルテと論文掲載のデータを照合した結果、転記ミスなどがあったものの「恣意(しい)的なデータ操作はなかった」と結論づけた。
石黒直樹・名大医学部付属病院長は「透明性や中立性の面で、臨床研究に元社員が加わっていたことは結果的に不適切」と述べた。
JR北、脱線現場のレール幅改竄、39ミリを25ミリに 3人関与 12/12//13(読売新聞)
北海道七飯町のJR函館線大沼駅で9月に起きた貨物列車の脱線事故で、6月に同じ場所を現場で計測した際、基準値を超えるレール幅の異常な広がりが実際には39ミリだったのに、25ミリと改竄(かいざん)して報告されていたことが12日、分かった。JR北海道が同日の記者会見で明らかにした。
鉄道事業本部長を務める豊田誠常務は「脱線現場でのデータ書き換えで極めて重大な事案だ。大変なご心配とご迷惑をお掛けして申し訳ない」と陳謝した。
JR北海道によると、脱線現場を管轄する大沼保線管理室の保線担当者2人と、上部組織である函館保線所の社員1人の計3人が改竄に関わっていたという。改竄の意図を聞き取っている。
大沼駅の脱線現場は列車同士が行き違う際に片方の列車が待機する「副本線」だった。
トラブル「安全への意識不足」、改竄の背景「人手、技術力不足」 JR北・参考人質疑やり取り (1/3)
(2/3)
(3/3) 10/22/13 (毎日新聞 東京夕刊)
22日に衆院国土交通委員会で行われたJR北海道の野島誠社長らに対する参考人質疑の主なやり取りは次の通り。
【一連の問題への認識】
平沢勝栄議員(自民)「JR北海道はトラブルのデパートだ」
野島誠社長「(乗客79人が負傷した)平成23年5月の石勝線の事故以来、安全性の向上に取り組んできたが、乗客、地域の皆様に多大な心配、迷惑をかけ、心よりおわび申し上げる」
寺島義幸議員(民主)「トップとしてどのような責任を取る考えか」
野島社長「会社発足以来最大の危機と認識している。全社一丸となって安全輸送の確保に取り組まなければならない。社員の先頭に立って不退転の決意でJR北海道の再生を果たしていきたい」
寺島議員「どこに一番の原因があると思うか」
野島社長「すべての業務が乗客の安全のためにあるという共通の認識が社内に十分に醸成されず、安全に対する取り組みが形式的になるなど乗客の安全に対する意識が不足していた」
寺島議員「安全への意識が不足する理由は」
野島社長「厳しい経営環境の中でも、安全に対して必要な資金を確保するよう努めてきたが、各分野で資金が十分に行き渡らなかったという状況が生じ、車両や設備の更新などが十分に進んでいなかった」
平沢議員「特別保安監査では、JR北海道の安全推進委員会はトラブルが頻発しても報告でとどまり、調査、対策がなされていないと指摘された」
野島社長「安全推進委員会は定例的に毎月1回開催のため、トラブルを迅速に議論できなかった」
【データ改竄(かいざん)】
佐藤英道議員(公明)「なぜ、こんなこと(データ改竄)が起きたのか」
野島社長「現在、調査中。背後要因としては人手不足や若手社員が増えたことによる技術力不足などさまざまな問題が絡んでいると推察している」
佐藤議員「調査状況は」
野島社長「現時点でデータ書き換えを認めた現場は、函館保線管理室のほかに新たに8カ所。今後は引き続き、動機や役割分担などの事実関係を徹底的に調査し、全容解明していく」
穀田(こくた)恵二議員(共産)「社長はなぜデータが改竄されたと考えているのか」
野島社長「背後要因については現在、調査中」
穀田議員「現場に対し、上部組織が改竄したという事実はないか。改竄は常態化していたのではないか」
野島社長「上部組織が関与していた事実は判明していない。いつから行われていたのかは現在調査中」
【組合問題】
平沢議員「9月に男性運転士が操作ミスを隠すため、自動列車停止装置(ATS)のスイッチを破壊した問題で、運転士にどういう対応をしたのか」
小山俊幸常務「顧問弁護士とも相談し、過去の懲戒の基準に照らし、15日間の出勤停止とした」
平沢議員「ATSを壊してわずか15日間とは、あきれて物が言えない。器物損壊の被害届を出したのか」
小山常務「計画性がなく、損害額が軽微で、本人も深く反省していることから刑事告訴しなかった」
平沢議員「今、どこの会社でも乗務員にアルコール検査を義務付けているが、JR北海道はどうか」
小山常務「20年11月から導入した。当時は任意。石勝線事故の反省や世の中の状況も踏まえ、24年7月から義務化し、原則全員実施とした」
平沢議員「どこの会社でも義務付けている。『原則』とはどういう意味か」
小山常務「体質的に飲酒できない乗務員については自己管理できるという判断の下、免除した。乗務員は約1600人いるが、免除されているのは11人」
平沢議員「ほかの会社は全員に義務付けている。一昨日(20日)、全員に義務付けたのではないか」
小山常務「一連の事故、不祥事を契機に各方面から批判を受け、遅ればせながら一昨日から全員対象とすることを決めた」
平沢議員「報道では経営幹部が『組合が言うことをきかない』と証言している。JR北海道労組では『ほかの組合員と話をしてはいけない』『結婚式にも出てはいけない』という規律がまかり通っているというが、知っているか」
野島社長「そのような運動方針を掲げ、ごく一部の職場でそうした事象があるということは聞いている。だが、このことにより、業務遂行上問題になるという事象はないと考えている」
抗がん剤記事に製薬会社が金銭…薬事法違反か 12/11//13(読売新聞)
がん患者向けの雑誌に掲載された記事が、薬事法で禁じられた抗がん剤の広告にあたる可能性があるとして、厚生労働省が調査を始めた。
特定の商品をPRする内容の記事が多いことに加え、製薬会社が出版社に金銭を支払っていたことが判明したためで、厚労省は製薬業界に自主ルールの策定と再発防止を求める方針だ。
◆タイアップ
厚労省が問題視しているのは、一般書店で販売されているがん患者向け月刊誌(公称7万部)に掲載された抗がん剤の紹介記事。その多くは、医師らが特定の商品名を挙げて有効性を説明する内容になっている。
発行元の出版社の関係者らによると、記事を掲載する際、抗がん剤を販売する製薬会社から1ページあたり47万~57万円を受け取っていた。関係者の一人は取材に「紹介記事はタイアップ記事と呼ばれていた。部数が伸び悩み、毎号2本程度のタイアップがなければ収支が合わなかった」と明かした。出版社が記事の企画を作り、製薬会社に持ち掛けるのが基本だったという。
読売新聞が製薬会社側に取材したところ、5社が2010~11年の記事に190万~550万円以上を出版社に支払ったことを認めた。5社の支払額は少なくとも計1300万円。うち1社は「医療用医薬品も含む27回の記事で4000万円以上を支払った」と話し、少なくとも9件が抗がん剤に関する記事だという。
一方、出版社の取材に応じた医師や大学教授らは数万円から10万円程度の謝礼を受け取っていたが、多くが「製薬会社から資金が提供されていたとは知らなかった」と話している。
◆温度差
薬事法が抗がん剤の広告を罰則付きで禁じているのは、抗がん剤は副作用が特に強いため、患者が本来必要な薬ではなく、広告の薬を選べば、健康被害を受ける恐れが強いためだ。薬は医師の判断で投与するのが原則だが、がん治療の現場では近年、患者の意思を尊重する傾向が強まり、治療法や薬の選択を患者に委ねるケースが増えている。
厚労省は「金銭の支払いは、記事掲載に宣伝の意図があった可能性が高いことを示している」として調査を開始。自主的に報告してきた製薬会社に詳細な調査と報告を指示し、未報告の会社や出版社からも事情を聞くことを検討している。
一方、製薬会社側の認識には温度差がある。3社は「薬事法に抵触する可能性が高い」「広告と疑われかねない」「倫理的に問題」として、いずれも「今後はやめる」と話した。これに対し、2社は「患者向けの啓発で、違法性はない」「広告ではなく、編集方針に賛同して制作費を負担しただけ」と主張している。
◆「罪深い」
専門家や患者らの中にはタイアップ記事に厳しい視線を注ぐ人もいる。
記事の内容について、複数のがん専門医が「医学的な事実関係に間違いはないが、一部に大げさな表現もある」と指摘。日本医科大武蔵小杉病院の勝俣範之教授(腫瘍内科)は「医師らが薬を客観的に評価しているように見えるが、裏に金のやりとりがあるなら客観性に疑いが生じる」と話す。
患者団体「卵巣がん体験者の会スマイリー」の片木美穂代表は「患者が薬の選択を誤る引き金になりかねず、非常に罪深い。『治った人が何人いる』などの情報に飛びついて、その治療を受けられる病院に駆け込み、亡くなった患者を知っている。宣伝なら、読んだ人がわかるようにすべきだ」と指摘する。
一方、出版社は取材に「商品名を記載したのは患者への情報提供の一環で分かりやすさを追求したに過ぎず、違法性はない」と文書で回答。金銭のやりとりについては回答しなかった。
東電を一度破綻させるしかない。給料を下げたから優秀な人材が流出する。仕方がないことだ。東電だけでなく他の企業も同じような事を経験している。そこで変われない企業は倒産や破産するのである。
東電を破たんさせて、他の企業に売却する方法もあるはずだ。他の電力会社が体力的に問題があるのなら、東電を購入すれば10年は原発を稼働させる事が出来る事を保障するとか極端なオファーで募集すれば良い。他の電力会社も原発を所有し、稼働させてきたのであるのだから問題はないはずだ。人材の流失問題は東電のように起きないはずだ。東電が支援してきた政治家達がいるので簡単には破たんさせないのだろうが、真剣に考えるべきだと思う。
東電、依願退職1400人 止まらない「優秀な人材」流出 (1/2)
(2/2) 12/07/13 (J-CASTニュース)
東京電力で、福島第一原子力発電所の事故後の依願退職者に歯止めがかからない。
当初、東電は2013年度末に11年に比べて約3600人減の3万6000人体制とする削減目標を掲げていた。すでにその目標は達成したが、依願退職者の40%超が本店の経営企画部門や原発技術者などの中核社員で、今後の事業運営に支障をきたす恐れが出てきた。
給与カット、将来の見通し立たず…
東電、「3万6000人体制」はすでに達成。それでも、辞める社員は後を絶たない? 東京電力によると、福島第1原発事故後(2011年4月以降)の依願退職者は、2013年10月末までの累計で1422人に達した。13年度末には1700人に達するとの見方もある。
このうち、本店の経営企画部門や原子力発電の重要課題を担当する、中核社員が依願退職する割合は11年度が34%、12年度には42%を占めた。
東日本大震災前の10年度が依願退職者の24%だったことから、以前に比べて中核社員が離職する割合が上がっていることがわかる。経営不振の企業にありがちな、「優秀な人材ほど、早く辞めていく」状況は、東電も例外ではないということらしい。
そうした中で、福島第一原発の事故後、現場は事態の収束どころか、除染や汚染水、中間貯蔵施設などの問題を抱えて息つく暇もない。11月23日からは4号機原子炉建屋にあるプールから、初めて使用済み核燃料を取り出す作業が始まった。
放射能汚染と背中合わせの状態で、約1500本ある核燃料を建屋から約100メートル離れた保管施設「共用プール」に移すには1年を要するのだから、社員らにかかるプレッシャーは相当だろう。
依願退職者が減らない背景には、原発事故で前人未到の極めて重要な任務にあたっているにもかかわらず、評価は低く、年収の2~3割カットが続いていることがある。また、経営の先行きが見通せないなかで将来への不安が募っているとみられる。
文字どおり必死に働いているのに、「東電」の社員というだけで後ろ指を指される状況に居たたまれないこともある。
国費投入、さらなるリストラで「人がいなくなる」
相次ぐ依願退職者で、東京電力の現場はギリギリの人数になっている。東電によると、2013年度末に3万6000人体制を目指していた人員削減計画は、この12月1日時点で3万5995人になり、すでに目標に到達した。
それにもかかわらず、毎月のように依願退職者は増えている。これから福島の復興事業に相当な人数を投入するのに、さらなる人員削減で現場の業務運営に支障をきたす懸念は高まっている。
さらに、政府・与党内では除染や汚染水対策、中間貯蔵施設の建設などへの国費投入を機に、東電に一段のリストラを求めている。東電が年内に見直す総合事業特別計画(再建計画)では、追加の経営合理化策として、創業以来初の希望退職が盛り込まれるとみられ、その規模は1000人にのぼるとされる。
東電の発電や送配電設備の保守部門では機器の異音を聞き分けられるような、高い技能が求められている。また事務部門でも電気料金の複雑な計算を処理するノウハウが必要とされ、東電はこうした技能やノウハウを遺していかなければ、将来の電力の安定供給に影響が出る懸念があるという。
人材の流出が続くなか、東電は一方で3年ぶりの新卒採用に踏み切り、14年3月卒業予定の大学、高専、高校卒者331人を内定している。
別業務でも利益供与 パンフ作製発注、贈賄業者「丸投げ」で数千万円利益 NTT東日本汚職 12/07//13(産経新聞)
光インターネット回線サービスの委託業務発注をめぐる汚職事件で、NTT法違反の収賄容疑で逮捕されたNTT東日本社員、石川浩一容疑者(48)が、自らの裁量で贈賄業者にパンフレット作製業務も発注していたことが6日、関係者への取材で分かった。贈賄業者は孫請け業者に業務を丸投げしており、数千万円の利益を上げていた。
東京地検特捜部はパンフ作製業務も贈賄の見返りだった可能性があるとみて調べる方針。
調べによると、石川容疑者は、光ネット回線サービス「フレッツ光」の拡張業務委託をめぐり、映像配信会社「ブリッジ・モーション・トゥモロー(BMT)」前社長の浅水博容疑者(52)に便宜を図った見返りに1700万円の賄賂を受け取ったとして特捜部に逮捕された。
石川容疑者は、フレッツ光の拡張とは別にBMTに通信機器販売などに関するパンフ作製業務も発注。だが、BMTは中間マージンを差し引いたうえで、事業をすべて孫請け業者に委託していた。こうした丸投げは複数年にわたっており、BMTは計数千万円の利益を得ていたという。
石川容疑者は事業の発注先を決める権限があったという。NTT東に近い関係者は産経新聞の取材に「丸投げの実態を石川容疑者が知っていたことは確か。NTTの委託業務は発注量が莫(ばく)大(だい)で中小企業には『おいしい仕事』。ある程度の利ざや抜きは横行しているのではないか」と話した。
NTT東汚職、「現金提供3千万円超える」 12/06//13(読売新聞)
NTT東日本の「フレッツ光」事業を巡る汚職事件で、NTT法の収賄容疑で逮捕された同社課長石川浩一(ひろかず)容疑者(48)が、受け取った賄賂の約1700万円を私的な海外旅行や飲食費などに充て、大半を使い切っていたことが関係者の話でわかった。
贈賄側の通信関連会社前社長浅水博容疑者(52)は「現金提供は3000万円を超える」と供述しており、東京地検特捜部が捜査している。
石川容疑者は2011年8月、浅水容疑者から約1700万円が預金されている口座のキャッシュカードを受け取った疑いがあるが、関係者によると、石川容疑者は金を自分の口座に移すなどして、米国ハワイへの家族旅行や私的な飲食費などに充てたという。調べに対し、石川容疑者は現金授受を認め、浅水容疑者は「事業の委託先に選ぶ見返りに現金の提供を持ちかけられた。提供額は3000万円を超えた」と供述。特捜部は、他に賄賂の授受がなかったか調べている。
三井物産の年金基金元理事、過剰接待で収賄容疑 12/05//13(読売新聞)
ドイツ銀行グループで、日本国内で証券業務を行う「ドイツ証券」(東京)の営業担当者が厚生年金基金の幹部に高額接待を繰り返していた問題で、警視庁は5日、長期国債の運用など金融商品契約の謝礼として過剰な接待を行ったとして、同社社員越後茂容疑者(36)(東京都港区)を贈賄の疑いで逮捕した。
顧客だった三井物産連合厚生年金基金の元常務理事で会社役員の釣沢裕容疑者(60)(同三鷹市)を収賄の疑いで逮捕した。
厚生年金基金の役職員は厚生年金保険法で「みなし公務員」に当たる。警視庁は、証券取引等監視委員会から過剰接待の情報提供を受け、贈収賄事件として捜査していた。
同庁の発表では、越後容疑者は2012年4~8月に十数回、金融商品購入の謝礼として、釣沢容疑者を東京・六本木のクラブなど都内の高級飲食店で接待したり、ゴルフのプレー代金や海外旅行代金を負担したりするなど、計約90万円相当の接待をした疑い。釣沢容疑者は金融商品契約の謝礼だと知りながら接待を受けた疑い。
これほどの額を使いそして損失させたのだから、死刑にするべきだろう!法律の問題で不可能。だから法改正も必要だと思う。
元事務長、銀座の高級すし店貸し切り・ハワイも 12/05//13(産経新聞)
長野県建設業厚生年金基金(長野市)の横領事件。
業務上横領罪で起訴、同容疑で再逮捕された元事務長・坂本芳信容疑者(56)は、東京・六本木や銀座の高級クラブに通っていたほか、銀座の高級すし店「久兵衛」も常連客として利用していた。
久兵衛の男性社長によると、坂本容疑者は必ず女性を連れて来店していた。社長は「女性と2人で来店することもあったが、5、6人の女性を連れてきて、店を貸し切りにすることもあった」と振り返る。坂本容疑者の来店時はほとんどの場合、同じ板前が担当することになっていたという。
坂本容疑者は自らが出店費用の支援をした銀座の飲食店の開店記念と開店1周年のパーティーに、それぞれ約50万円を支払い、久兵衛に板前の出張を依頼。来店した客などの目の前ですしを握らせ、振る舞った。
坂本容疑者は、この飲食店で働いていた女性ら十数人を連れて、ハワイへ旅行をしたこともあり、その際にも、久兵衛に板前の現地出張を依頼し、すしパーティーを2回行ったという。
3泊5日の日程で同行した社長によると、板前は2人で、坂本容疑者が現地で借りている別荘ですしを握った。板前の出張料金は100万円以上に上り、社長の旅費なども含め坂本容疑者がすべて負担したという。
社長は坂本容疑者について、「仕事は海外のファンドを運用していると聞いていた。料金が高額になっても、いつも現金で支払っていた」と話している。
この手の事件、証明するのが難しいが、懲戒免職になっているので事実なのかな?
JR西子会社の元支店長を強制わいせつ容疑で逮捕 女性社員に「逆らうと仕事できなくなる」 12/05//13(産経新聞)
部下の女性社員に性的嫌がらせをしたとして、和歌山県警和歌山東署は4日、強制わいせつ容疑でJR西日本の子会社「ジェイアール西日本コミュニケーションズ」の元和歌山支店長、峠憲一郎容疑者(64)=同県田辺市稲成町=を逮捕した。容疑を否認しているという。
逮捕容疑は、9月30日午前8時15分ごろから約10分間にわたって、和歌山市の同支店内で「逆らうと会社で仕事ができなくなる」などと女性社員を脅し、下半身や胸を触るなどしたとしている。
ジェイアール西日本コミュニケーションズなどによると、峠容疑者はJR和歌山駅駅長を務めた後、同社和歌山支店長になったが、「女性へのセクハラ行為があった」として11月下旬に懲戒解雇になった。
同社は「元社員が逮捕されたことは誠に遺憾。警察の捜査に全面的に協力する」としている。
結局はお金が全てなのか?それともホテルや旅館の偽装問題のように横並びの問題なのか?
ドイツ証券を処分勧告へ 監視委、厚年基金幹部に高額接待 12/04//13(産経新聞)
厚生年金基金の資産運用をめぐり、顧客である3つの厚年基金幹部に高額接待を繰り返していたとして、証券取引等監視委員会が金融商品取引法に基づき、ドイツ証券(東京都千代田区)に行政処分を科すよう、金融庁へ勧告する方針を固めたことが4日、関係者への取材で分かった。厚年基金の役職員は厚生年金保険法で「みなし公務員」と規定されている。警視庁も同様の情報を把握しており、贈収賄容疑での立件を視野に捜査を進めている。
関係者によると、同社は平成22~24年、東京都内の厚年基金役員ら3基金の運用担当幹部に対し、1基金あたり数百万円分の飲食や旅行などの接待を繰り返していた疑いが持たれている。基金の運用先の選定で便宜を受ける目的があったとみられ、各基金は接待の見返りとして、ドイツ証券が販売する計数十億円分の金融商品に投資していたという。
金商法に関する内閣府令では、業者が顧客に対し「特別利益の提供」を図ることを禁じている。同社は複数の厚年基金幹部を接待していたが、監視委はこのうち3基金への接待が高額に上るため、同法の「特別な利益」にあたると判断した。ドイツ証券は取材に「監視委による調査中のため、コメントできない」と話している。
厚年基金をめぐっては、昨年11月に福岡県、今年6月には北海道のそれぞれの基金理事長が、運用関係先から金銭を受け取った収賄容疑で逮捕されるなど、両者の癒着が明らかになっている。
お金を稼ぐのは大変だが、使うのは簡単を実現した男。無期懲役には出来ないものだろうか??
10億円の着服認める、元事務長再逮捕へ 年金基金使途不明で 12/01//13(産経新聞)
長野県建設業厚生年金基金で使途不明となっている約24億円の一部を着服したとして、長野県警に逮捕された元事務長坂本芳信容疑者(56)が、少なくとも約10億円の着服を認める供述をしていることが1日、捜査関係者への取材で分かった。
基金の使途不明金は徐々に増え、平成20年度だけで8億円以上に達していたことも判明。県警は週内に、数千万円を着服したとする業務上横領容疑で再逮捕し、巨額使途不明金事件の全容解明を進める。
坂本容疑者は11月、約6400万円の業務上横領容疑で逮捕された。捜査関係者によると「遊興費に使った」と供述。逮捕容疑以外にも横領を認め、総額は現時点で約10億円に上るという。
タイに逃亡する直前の22年6~9月には、毎月1億円以上を口座から引き出し、うち約5千万~7千万円を着服したとみられる。
JR北のデータ改竄、4保線部署は「繰り返していた」 参院国交委、社長ら常習性明らかに 11/28//13(産経新聞)
レール検査データ改竄(かいざん)などJR北海道の一連の問題をめぐり、参院国土交通委員会は28日、野島誠社長ら幹部3人を参考人として招致し集中審議を行った。22日の衆院国交委の集中審議で、JR北海道側は9つの保線部署での改竄を公表したが、この日の審議ではそのうち4部署で過去から改竄が繰り返されてきたと明らかにした。同社での改竄行為の常習性が判明したのは初めて。
JR北海道側は22日の衆院国交委で函館保線管理室以外に新たに滝川、富良野、苫小牧、伊達紋別、室蘭、上川、大沼の各保線管理室と北見管理室の8部署での改竄を公表。
参院国交委で、参考人として出席した笠島雅之工務部長はその後の社内調査の進捗(しんちょく)状況を問われ、「富良野、室蘭、伊達紋別、上川の4部署で過去から改竄が行われていた」と明らかにした。また今後の社内調査のスケジュールについては「12月中旬に調査を終え、年内に取りまとめを行いたい」との意向を示した。
一方、野島社長は運転士が自動列車停止装置(ATS)をハンマーで破壊した問題について、運転士を出勤停止15日間とした処分を見直す考えがないことを明言した。
集中審議には、小山俊幸常務も出席した。
「ガソリンを多く含んだ廃油」が原因のようだ。「ガソリンを多く含んだ油」の説明を受けていれば、「エバークリーン」の責任だろうし、取引先が説明をしていないのであれば過失が割合の話になるのではないのか?
廃油に多量ガソリン、取引先は説明…工場爆発 11/22//13(読売新聞)
千葉県野田市二ツ塚の廃油再生処理工場で2人が死亡した爆発事故で、工場を運営する「エバークリーン」(東京都千代田区)が爆発当日の15日、取引先からガソリンを多く含んだ廃油を回収していたことが、捜査関係者への取材でわかった。
取引先は同社に廃油の中身を説明して引き渡したといい、県警は処理方法に問題があったとみて、22日、業務上過失致死容疑で同社の本社に捜索に入る。
捜査関係者によると、同社は15日、取引先の県内の回収業者から、通常より多い7700リットル近くの廃油を引き受けた。この業者は、タンクローリーで引き取りにきた同社の運転手に「ガソリンを多く含んだ油」と説明した上で引き渡したと県警に説明しているという。廃油は爆発前、爆発元とみられる蒸留施設につながるタンクに入れられた。蒸留施設で重傷を負った2人は県警に、「爆発前にガソリンの臭いがした」と話しており、県警はタンクローリーやタンクに残っていた油を採取して鑑定を進め、同社社員から回収や処理の経緯について話を聞いている。
8保線部署でも改ざん…衆院招致のJR北社長 11/22//13(読売新聞)
レールの計測データの改ざんなどJR北海道でトラブルが相次いでいることを受け、衆院国土交通委員会は22日、同社の野島誠社長ら幹部3人を参考人として招致し、集中審議を行った。
野島社長は改ざんについて、既に判明している函館保線管理室(函館市)とは別に8か所の保線担当部署で行われていたことを明らかにし、「徹底調査した上で、厳格に対応していく」と述べた。
同社は、管内に44か所ある保線担当部署で改ざんの調査を実施。現在までに判明した8か所について具体名は挙げなかったが、野島社長は改ざんが行われた理由について、「人手不足や技術力不足など様々な問題が絡むと推察している」と語った。改ざんで上層部の関与があったかについては「まだつかんでいない」と答えるにとどめた。
レール異常の放置や改ざんなどトラブルが相次いでいることについて、「あってはならないこと。重大な事態を発生させたと認識しており、深刻に受け止めている。多大な迷惑をかけておわびする」と陳謝した。
野島社長は委員の質問にはっきりした声で答え続けた。だが、事前に用意した資料を読み上げる場面も目立ち、委員から「簡潔に答えるように」と求められる一幕もあった。
国交省などによると、JRの社長が安全上の問題で国会に招致されたのは、2005年に乗客106人が死亡したJR福知山線脱線事故を受け、当時のJR西日本社長の垣内剛氏が招致されて以来。
工場などで火事や爆発事故が起きているが、維持管理などに問題があるのではないのか?
火発タンクから濃硫酸、海に流出 11/22//13(読売新聞)
山形県酒田市宮海の発電会社「酒田共同火力発電」は21日、敷地内のタンクから濃硫酸1530リットルが流出し、雨水と共に海に流れ出たと発表した。
発表によると、20日午前11時20分頃、三つあるタンクの一つで計器の接続部分から濃硫酸が漏れているのを職員が発見した。パッキンが劣化していた可能性があるという。18日昼頃から流出していたとみられる。
同社は流出確認後、敷地内で希釈作業を実施。20日に行った水質検査で異常は確認されなかったという。
JR北:「改ざん部署は9カ所」 野島社長らを参考人招致 11/22//13(読売新聞)
JR北海道がレール幅の異常を放置したり検査データを改ざんしたりしていた問題で、衆院国土交通委員会は22日、同社から野島誠社長ら3人を参考人として招致し、集中審議を始めた。野島社長は「安全第一を掲げながら社員に浸透していなかったことを深刻に受け止めている。多くの方にご迷惑をお掛けしたことをおわびする」と改めて謝罪。社内調査の結果、改ざんが確認された保線担当の部署が現時点で、函館保線管理室など9カ所に上ることを明らかにした。審議は同日午後も行われる。
安全問題でJR幹部が国会に招致されるのは、2005年の尼崎脱線事故で当時のJR西日本社長が呼ばれて以来。野島社長のほか、経営部門を統括する小山俊幸常務と、保線部門を総括する笠島雅之工務部長が参考人として出席した。
社長ら幹部で作る安全推進委員会が、重要なトラブルが相次いでいるにもかかわらず、原因や対策の究明していなかったことを問われると、野島社長は「(別の会議である)経営会議では議論していた。再発防止にも一定の効果があった」と釈明した。事故が頻発していることへの認識を確認されると「十分に議論が尽くせていなかった」と一転して謝罪した。
11年に石勝線が脱線炎上し79人が負傷した事故を受けて、同社は昨年、再発防止のための安全基本計画を策定した。野島社長は「成果が出る前に多くの事故が起きてしまった。スピードが足りなかった」と振り返った。今年9月、運転士がミスを隠そうと自動列車停止装置(ATS)を壊したことについて、小山常務は「計画性もなく損害額も軽微だったので刑事告訴しなかった」と説明。平沢勝栄議員(自民)は「組合に遠慮しているのではないか」と指摘した。【森健太郎、安高晋】
仕方ないな!
阿倍野の会社 派遣業許可取り消しへ…厚労省 11/18//13(読売新聞)
事業停止命令に従わず
厚生労働省に営業所を届け出ずに隠し、事業停止命令を受けた期間などにも派遣を続けたのは労働者派遣法に違反し悪質だとして、同省が人材派遣会社「D&H」(大阪市阿倍野区)の派遣事業許可を取り消す方針を固めたことがわかった。現行の許可制度になった2004年以降、同法違反を理由にした許可取り消しは、今年8月、大阪市北区の人材派遣会社への処分に次いで2例目。
関係者によると、同社は10年2月から大阪の本社とは別に、熊本市内に営業所を設け、派遣先が見つかったときだけ働く登録型の「一般労働者派遣事業」の形式で、パチンコ店に約30人を送っていた。しかし、同営業所は、事業所の新設届が出されていなかった。
さらに、本社自体も10年8月から社員を常用雇用している場合に限られる「特定労働者派遣事業」の届け出しかないのに、無許可で一般派遣事業を行ったとして11年4~5月、事業停止命令を受けたが、この間も違法な派遣を続けたという。
同営業所について、同社は厚労省に対し「パチンコ台があり、営業所ではなく、派遣労働者の研修施設」と主張したが、同省は、面接や労務管理が行われ事業所の実態があると判断したとみられる。一般派遣の許可には資産要件があり、事業所数に応じて増額されるため、資産不足を恐れて届け出なかった可能性がある。
これほどまでにデータ改ざんが行われているのであれば、レール幅などの計測データ以外の情報も改ざんされている可能性を疑わなければならないと思う。
JR北、補修基準値内のレールデータも改ざん 11/16//13(読売新聞)
JR北海道がレール幅などの計測データを改ざんしていた問題で、同社函館保線管理室(函館市)が、社内の補修基準値を超過していないレールのデータも改ざんしていたことがわかった。
異常とまでは言えない数値を、正規の数値により近づくように操作しており、国土交通省は改ざんがさらに広範囲にわたる疑いもあるとみて調べている。
函館保線管理室では、9月の国交省による特別保安監査の直前、列車の待機などに使う「副本線」と進路変更に使う「分岐器(ポイント)」の複数の計測データのうち、補修基準値を超えてレールの幅が広がるなどの異常があった計測データを、基準値以下に改ざんしたことが分かっている。監査で異常が発覚することを防ぐためだったが、同社関係者などによると、同管理室は基準値以下のデータについても、正規のレール幅などにより近づけるよう改ざんしていたという。
レール計測原本廃棄し、改ざん検証困難にしてJR北海道はある意味ですごいと思う。国土交通省の保安監査対策を準備し、発覚した時の逃げ道まで準備していた。
過去に起きた多くの事故や問題は氷山の一角として表に出た結果だったのかもしれない。
国土交通省は保安監査の方法について性善説を否定する形で行わなければならないと思う。
JR北、レール計測原本廃棄…改ざん検証困難に 11/15//13(読売新聞)
JR北海道の函館保線管理室(函館市)がレールの計測データを改ざんしていた問題で、複数の保線担当部署で正式なデータの基となる「野帳(やちょう)」と呼ばれる資料が廃棄されていることが、同社への取材でわかった。
野帳の廃棄で、改ざんの検証が困難になる可能性がある。
同社によると、野帳は保線担当部署の社員が列車の進路を変更する「分岐器(ポイント)」のレールの幅などを現場で測る際に使っている。計測担当者が読み上げたデータを、記録担当者が野帳に記録。計測後に現場担当部署に帰って、野帳のデータをパソコンに入力し、正式なデータとして取り扱うという。
しかし、正式なデータは社内規定で次回の計測時まで保管することが義務付けられている一方、野帳は会社の統一様式がないメモとして扱われ、社内規定で保管の義務もないため、直近の野帳のデータが廃棄されていた保線担当部署があるという。
除染費用支払いを拒否し、電気料金値上げで消費者に負担を押し付けた結果だ。今後も同じような事を繰り返すのだろう。
除染費用支払い拒否が認められたので今後も継続できると理解したのかもしれない。
東電に3000億円新規融資へ…経営改善と判断 11/15//13(読売新聞)
東京電力に融資しているメガバンクなどの銀行団は14日、東電が12月の実施を求めていた約3000億円の新規融資に応じる方針を固めた。
国が東電に除染費用などで追加支援を行う方向となったことや、原子力規制委員会による柏崎刈羽原子力発電所6、7号機(新潟県)の安全審査が来週にも始まる見通しとなったことから、経営不安が和らいだと判断した。
今回の新規融資で、昨年の経営再建計画に盛り込まれた1兆700億円の融資計画がすべて実現され、当面の資金繰りにメドが付く。
東電は14日から主力取引行などに2014年3月期で500億円規模の経常利益を確保できるとした収支計画の説明を始めた。発電設備の工事の先送りによる修繕費の圧縮や、人件費の削減により、融資を受けられなくなる恐れがある3年連続の赤字を回避する。
中京学院大に留学生に関する補助金は出ているの?
留学生を不正編入…中京学院大の元准教授ら逮捕 11/13//13(読売新聞)
中国人留学生2人を大学に不正編入させたとして、愛知県警は12日までに、中京学院大学(岐阜県中津川市)の元准教授で、名古屋市天白区、久野輝夫被告(53)(逮捕監禁致傷罪で公判中)と、職業不詳、胡昊(ここう)容疑者(32)、同大4年の女2人(いずれも21歳)の中国人3人を有印私文書偽造・同行使の疑いで逮捕した。
発表によると、4人は共謀し、昨年7月、同大1年生だった女2人が中国の大学で単位を取得したとする成績証明書を偽造して中京学院大に提出し、2人を3年生に編入させた疑い。2人は中国の大学に在籍していなかった。
久野被告は当時、中京学院大の留学生支援部長を務めており、パソコンからは、中国の大学の成績証明書などの偽造書類が数十人分見つかった。久野被告は「学生数を確保するため約3年前から数十人についてやった。自分の実績を認めてもらい、教授になりたかった」と供述する一方、「留学生1人あたり数十万円の報酬を受け取っていた」とも話しており、県警が動機についても調べている。
久野被告は今年3月、名古屋市内の語学学校で中国人男性に暴行を加えるなどしたとして逮捕監禁致傷容疑で逮捕された。その後、「留学生らを不正に入学、編入させていた」と供述し、10月、別の不正入学に関与したとして有印私文書偽造・同行使容疑で逮捕、起訴されていた。同大は「事実確認中でコメントできない」としている。
複数担当者、データ改竄認める「会社守るため…」 JR北海道、職場ぐるみ異常隠蔽の疑い 11/13//13(産経新聞)
レール検査データの改竄が発覚したJR北海道の函館保線管理室(北海道函館市)の複数の担当者が社内調査に改竄を認めたことが13日、同社幹部への取材で分かった。「会社を守るためにやった」と釈明する担当者もいるという。
JR北海道幹部によると、改竄を認めた担当者は「本社に問題ないと虚偽報告し、発覚するのが嫌で国土交通省の特別保安監査の前日に改竄した」と説明。函館保線管理室が職場ぐるみでレール異常を隠蔽した疑いがあるとみて調査を進めている。国交省は13日、12日に続き函館保線管理室を立ち入り調査した。
JR北海道によると、9月19日に函館線大沼駅で起きた貨物列車脱線事故後、現場付近でレール異常が放置されていたことが判明、JR北海道は函館保線管理室を含め44の保線部署に異常を放置したケースがほかになかったか報告を指示。結果、これまでに270カ所でレール異常放置が確認されたが函館保線管理室では確認されていなかった。
JR北、函館保線管理室のデータ改ざん確認 11/13//13(読売新聞)
JR北海道の一部の部署がレール幅などの計測データを改ざんした疑いが浮上した問題で、同社は12日、函館保線管理室(函館市)でデータが改ざんされていたと発表した。
同社は11日深夜、この事実を国土交通省に報告。同省北海道運輸局は11、12日、同社本社に鉄道事業法に基づく立ち入り検査を行った。12日夕には函館保線管理室にも入り、室長から聞き取り調査を行った。
同社の豊田誠・鉄道事業本部長は12日夜、函館保線管理室管内で列車の進路を変更する「分岐器(ポイント)」と、待機などに使われる「副本線」の複数箇所の計測データが改ざんされていたことを明らかにした。このため副本線については、安全が確認できるまでの間、全道で一律時速45キロ以下の速度制限とした。豊田本部長は「世間一般には改ざんと言われてもやむを得ない」と語った。
改ざんは国交省が9月に行った特別保安監査の前後に行われたとみられる。国交省は今後、3回目の特別保安監査も検討する。
JR北「改ざん」確認、保線管理室が関与か 11/12//13(読売新聞)
JR北海道の一部の部署がレールの検査データを改ざんした疑いが浮上した問題について、同社がデータを確認した結果、複数のレールで改ざんが見つかったことが12日、わかった。
同社は11日深夜にデータ改ざんの事実を国土交通省に報告した。改ざんに至った経緯などを調べている。
国交省関係者によると、保線業務を担当する、函館地方にある一部の保線管理室でレールの検査データを改ざんしていたことが同社の調査で判明した。改ざんは国交省が9月に行った特別保安監査の直前に行われたという。
保線管理室では、社員がレールの幅などのデータを測定後、「野帳」と呼ばれる帳簿に記入。パソコンで野帳の数値を入力し、本社とそのデータを共有する仕組みになっている。しかし、同社が調査した結果、野帳のデータと本社のパソコンのデータが一致しないケースが複数で見つかった。改ざんは保線管理室で行われた可能性が高いという。
JR北海道の問題は想像以上に根が深そうだ!
国交省、JR北に立ち入り検査…数値改ざん疑惑 11/12//13(読売新聞)
JR北海道の一部の部署がレールの検査データを改ざんした疑いが浮上した問題について、国土交通省北海道運輸局は、11日深夜から鉄道事業法に基づく立ち入り検査を同社に対し始めた。
太田国土交通相は12日の閣議後記者会見で「事実であれば誠に遺憾で、鉄道事業者としてあってはならないこと。徹底した調査が大事だ」と述べた。検査の進展次第では、国交省による3回目の特別保安監査も検討する。
同社を巡っては、9月19にJR函館線大沼駅構内で起きた貨物列車の脱線事故をきっかけに、レールの幅などの異常を補修せずに放置していたことが発覚。国交省は9月と10月に特別保安監査を実施し、レール管理の実態などを調べてきた。
JR北海道 データを改ざんか 11/11//13(NHK)
異常なレールの放置が相次いだJR北海道で、検査や補修を担う一部の現場の部署が、ことし9月の国の監査の直前に、レールの幅などのデータが基準以内に収まるよう改ざんしていた疑いがあることが関係者への取材で分かりました。
JR北海道は、緊急の調査を始めました。
JR北海道では、ことし9月の脱線事故のあと社内調査をしたところ、合わせて270か所で補修が必要なレールの幅などの異常が放置されていました。
ところが、社内調査に対し「異常はない」と報告した一部の現場の部署が、脱線事故後に行われた国土交通省の特別保安監査の直前、異常が見つかったレールの幅などの検査データを、基準以内に収まるよう数値を改ざんしていた疑いがあることが関係者への取材で分かりました。
NHKが入手したこの部署に関する検査データの内部資料では、今年度、現場で測定したレールの幅などを記録する「野帳(やちょう)」と呼ばれる用紙に記入された数値と、社内のデータベースの数値が明らかに食い違うケースが50以上に上っています。
中には、補修が必要とされる社内の基準の2倍を超えていた数値が基準以内に収まっていたものもありました。
複数の関係者はNHKの取材に対し「脱線事故のあと、国土交通省の特別保安監査が実施されることになったため、その直前に、基準内に収まっているように数値が改ざんされた。さらに問題が発覚しないよう関係する書類を捨てるなどの隠蔽も行われていた」などと証言しています。
JR北海道は、一部のデータに食い違いがあるという情報を把握して、緊急の調査を始めていて、「現在、事実関係について調査確認中です」とコメントしています。
JR北海道の特別保安監査を担当した国土交通省鉄道局は、「どのような事実があるか、会社に確認したい」と話しています。
改ざん箇所は多数
NHKが入手したこの部署に関する内部資料では、同じ日の同じ地点の検査データにもかかわらず2つの異なる数値が存在するなど、改ざんが疑われる箇所が多数みつかりました。
検査地点でのレールの幅の広がりは、プラスは5ミリ、マイナスは3ミリ以内に収めると社内規程で定められています。
ところが、現場で測定した際に記録する「野帳」と呼ばれる用紙に記載されているのは、「ー7ミリ」。
補修が必要な基準を上回った値です。
一方、その野帳を基に入力されるはずの社内のデータベースの数値は「ー3ミリ」。
こちらは基準内に収まっています。
内部資料では、こうした数値の食い違いが確認できただけで50以上に上っていました。
なかには、補修が必要な社内の基準の2倍を超えていた数値が基準以内に収まっていたケースもありました。
メニュー表示に関する問題は深刻だ!業界や組織では罰則がないとか、他社も行っていて問題ないとか等の理由でこれまで続けられてきたのだろう。
一番残念に思うのは問題の理由である。それは「嘘だろう」とか「そのような単純な問題さえ対応できないのであれば会社としてはずさんである組織」と思えるような理由を多くの会社が発言している事。
福島の原発事故や東電の問題に関しても嘘が含まれているのではないかと思っている。個人レベルでは確かめる事は不可能。これが悲しい現実。
メニュー表示問題がここまで広がりながら指摘されてこなかった事実にたいして何を信用して良いのか本当にわからない。自分の判断が間違っている可能性もあるが、自己責任で判断するしかないのかもしれない。
開業から既製品を自家製パン…東京ドームホテル 11/09//13(読売新聞)
東京ドームホテル(東京都文京区)は8日、2000年6月の開業以降、ルームサービスで提供していた既製品のパンを「ホームメイドベーカリー」と表記するなど計16万人にメニュー表示と異なる食品、食材を提供していたと発表した。
ほかにも、近くのビルで直営する中華料理店で今年6月まで、ブラウンエビを「車海老」と表記するなどしていたという。
同ホテルは「表示に対する理解が足りなかった。パンについては、開業直前まで自家製を提供する準備をしており、表記を直すのを忘れた」と話した。
無資格授業「私立はグレー、大丈夫」…前理事長 11/17/13 (読売新聞)
長野県松本市の私立小中一貫校「才教学園」で教員免許法に違反する教員配置が続けられていた問題で、県警は6日、山田昌俊前理事長兼校長(64)と松山治邦元教頭(51)を同法違反容疑で松本区検に書類送検した。
捜査関係者によると、違法配置の理由について、松山元教頭は「校舎移転に伴う借入金の返済のため、人件費を割けなかった」とし、山田前理事長も「経営難でギリギリの人数でやり繰りをするしかなかった」と供述しているという。
発表によると、山田前理事長らは4月8日~7月23日の1学期に、小学校教員の免許など必要な資格を持たないにもかかわらず、11人の教員に対し無資格授業をさせていた疑い。県警によると、教員個人ではなく、雇用した学校法人側が立件されるのは全国初。教員11人について県警は、「雇用主に指示される立場で積極的に違反に関わっていない」として立件を見送った。
学園の資金収支計算書などによると、学園は2007年、一般競争入札で松本市芳川村井町の厚生年金健康福祉施設「サンピア松本」の土地と建物を落札し、翌年、同市内田にあった校舎を移転。金融機関などからの借入金約34億6800万円のうち約32億6400万円を購入資金に充てた。
学園はその後、サンピア松本の一部を売却するなどして、借入金の返済に約17億8000万円を充てたが、巨額の債務が残っており、松山元教頭は「返済のため、免許法違反を繰り返して人繰りをつけていた」と供述している。
松山元教頭は「05年の開校当初から教員数はギリギリだった」としたうえで、教員免許法違反の発覚により取り下げた高校新設申請にも言及し、「学園の進学実績をますます上げなくてはいけないという葛藤の中で違法配置をしてしまった」とも話しているという。
一方、山田前理事長は県警の事情聴取に対し、「私立はグレーだから大丈夫」「私立と公立は違う」などと言って教員に無資格授業を指示していたことを認めたうえで、「有能な教員が集まらず、中学の教員に小学校の授業をさせることでレベルの高い教育を提供しようと思った。教員免許を度外視するのが都合良かった」と説明したという。
三重県が不適切表示の観光ホテルに立ち入り調査 11/04/13 (読売新聞)
近鉄の子会社「近鉄ゴルフアンドリゾート」(大阪市)が、運営する観光ホテル「プライムリゾート賢島」(三重県志摩市)でメニュー表示と異なる種類のエビが使われていたと発表し、三重県は4日、ホテルへの立ち入り調査を行った。
同ホテルによると、ホテル内のレストラン2店舗で、メニューに車海老(えび)と表記しながら、ブラックタイガーやバナメイエビを使っていた。
県は、ホテル側が提供した資料や関係者の話をもとに、景品表示法違反(優良誤認)の有無を調べた。違反が確認されれば再発防止などを指導するという。ホテルの笠谷(かさたに)毅副総支配人は「調査には全面的に協力する」と話した。
別所志津子・県消費生活監は「三重県の食に対する信頼に多大な影響を与えることで残念。ホテルには改善に取り組んでもらいたい」と述べた。
氷山の一角かもしれない問題。まじめにやっている店や人々が馬鹿を見る。
消費者庁は問題に対して真剣に取り組み、規則、罰則そして表示の定義について明確な対応をするべきだ!
3150円お子様ランチの「和牛」は豪産成形肉 11/04/13 (読売新聞)
近鉄系旅館の「奈良万葉若草の宿三笠」(奈良市)は3日、メニューに「和牛」と表示していた料理に豪州産牛の成形肉を用いていたことを明らかにし、利用者らに謝罪した。
この成形肉には、アレルギー症状を引き起こす乳や小麦、大豆が含まれていたがメニューには記していなかった。
運営会社の近鉄旅館システムズ(同市)は10月31日に「三笠」などのメニューに虚偽表示があったと発表。「三笠」では、これまでに料理12品目で虚偽表示があったことが明らかになっていた。
偽装とアレルギー物質の不表示は、同社常務の川越吉晃・三笠総支配人が3日、報道陣に明らかにした。川越総支配人は、調理師らがこの事実を知っていたことも認め、「食材偽装だと言われても仕方ない」と述べた。
同総支配人によると、この成形肉は9月から「和牛」と追記された会席料理(6300円)の一品・朴葉(ほおば)焼きと、10月から提供を始めたお子様ランチ「バンビ御膳」(3150円)の「和牛ステーキ」に使われ、この間、それぞれ64人と32人に提供された。
三笠が仕入れていた成形肉の段ボール箱には、名刺大の商品説明用シールが貼られ、原材料に乳などを含むことが明記されていた。
川越総支配人は、「調理担当の8人のうち(新任の)料理長以外は成形肉だと知っていた」と説明し、「客には『成形肉』とは言わずに予約段階でアレルギーの有無を聞き、該当者には(高価な)伊賀牛に変更したこともあった。アレルギーを発症した人はいない」と釈明した。
東電を分社化する案とか出ているけど反対だ!東電を破たんさせて、株主及び従業員に責任を取ってもらう。
損害賠償を貰えない被害者は国が支払えば良い。あれほどの被害を出して国民負担で、おいしいところだけ残して良い思いをさせるのか?
自民党の族議員は国民の事より、支援してくれる組織や人達しか見ていない。被害者達が動かず、東電の思うようになるのであれば、被害者達にも責任があると思う。大規模な原発事故が起これば、泣き寝入りしかない。そんな原発など必要ない!
原発事故後初の黒字…東電社員が「夜の銀座」に帰ってきた 11/02/13 (ゲンダイネット)
<業者にタカるセコイ輩も>
東京電力は福島原発事故から3年ぶりに中間決算が黒字転換した。
原発事故直後は「世間の目があるから高い店は自粛」なんて“不文律”もあったそうだが、だんだん“夜の宴(うたげ)”も復活しつつあるらしい。ある銀座の小料理屋の女将が耳打ちする。
「本社が銀座の隣にあるでしょ。以前は週に3回通ってくれた東電の常連さんがいたけど、事故後はピタッと来なくなったの。毎回1万~2万円は使う人だから痛かったけど、その人がね、今年の夏ごろから週イチペースで顔を出すようになってきたのよ。『そろそろほとぼりも冷めただろ』なんて笑ってたわ」
座ってウン万円、銀座高級クラブの30代ホステスも口をそろえる。
「東電の客がいなくなって銀座のクラブは大打撃だったのよ。東電だけで持っているような“箱”もあったし。でも、ちらほらだけど見かけるようになってきた。ひと頃の勢いはないし、取引先にたかるセコイ東電さんも増えたけど、来てくれるだけでありがたい」
銀座の40代スナックママもこう話す。
「ウチは1人1万円台。ホント少しずつだけど、東電さんが戻ってきてくれてる。でも『銀座のスナックじゃまずいから、他の店の領収書を用意しといて』なんて頼まれたり。仕方ないわよね」
さすが黒字企業、飲み方が違うが、釈然としない。黒字転換はコスト削減が功を奏したと報じられているが、人件費カットは183億円。一方、庶民に負担を強いた値上げで、電気料金の実入りは1770億円も増えている。自分たちは大して腹を痛めていない。
さすがにまずいと感じたのか、広瀬直己社長は記者会見で「厳しい状況に変わりはない」と神妙な面持ち。下半期は設備工事の増加などで費用がかさむ見通しで、「コスト削減をさらに深掘りしていく」なんて言い訳していた。が、社員には、しおらしいフリは浸透していない。
「今でも悲愴(ひそう)感が漂っているのは原発関連の部署だけで、他は以前の雰囲気に戻りつつある。給料が下がったとはいえ、最近、都心に戸建てを買った同僚もいます。娘の学校のためだとか。『ローンが組めないメガバンクがあった』なんてボヤいていましたが、特に生活が苦しいというわけではありませんね」(本店勤務の30代社員)
せいぜい景気回復に貢献してください。
「麻生太郎財務相は29日、閣議後の記者会見で、東京電力福島第1原発事故に伴う除染費用などをめぐり『(原子力政策は)基本的に国策でやってきた。東電だけにすべて責任があるという話はいかがなものか』と述べ、国費負担に一定の理解を示した。」
額はわからないが税金が使われるのは明らかだ。国費負担=税金で負担=国民の負担。正しければ、東電を破たんさせて、株主及び従業員に責任を取ってもらう。東電の資産を全て売却する。除染費用及び廃炉費用などの不足分は税金で対応する。これで原発事故が発生すればどれほどの費用が必要になるのか明確になるし、原発の安全対策に対する追加投資が妥当であるかも明確になる。コストアップで採算が取れなければ原発新設など断念すべきだ。
除染費用支払い、環境省が改めて請求 東電は「ゼロ回答」 11/01/13 (産経新聞)
東京電力福島第1原発事故の除染費用の支払いを東電が拒んでいる問題で、環境省の井上信治副大臣は1日、東電の石崎芳行副社長を同省に呼び、未払いの約337億円の支払いを改めて求めた。石崎副社長は「事務作業に時間を要している上、経営状況が思わしくない」とする文書を持参し支払えない旨を回答。井上氏は受け取りを拒否し、来週中に具体的な支払金額を回答するよう求めた。
除染費用は国が復興予算で立て替え東電へ請求する仕組み。環境省はこれまで404億円を請求したが東電は67億円しか支払わず、同省は提訴や延滞金を課すことなどを検討してきた。
井上氏は記者会見し「これ以上支払わないなら別の手段を取らざるを得ない」と言明。除染費用をめぐり自民党が国費投入を提言したことには「提言と現行法の義務を果たしてもらうことは全く別物」と語った。
東電福島原発の除染費用 麻生財務相が国費負担に一定の理解 10/29/13 (産経新聞)
麻生太郎財務相は29日、閣議後の記者会見で、東京電力福島第1原発事故に伴う除染費用などをめぐり「(原子力政策は)基本的に国策でやってきた。東電だけにすべて責任があるという話はいかがなものか」と述べ、国費負担に一定の理解を示した。
自民党が東電の除染費用の一部免除を検討していることについては「除染費用の総額が見えていない。いろいろ考えなければいけない」と指摘。党の提言がまとまり次第、協議する考えを示した。
麻生財務相は「前の内閣(民主党政権)では全部、東電に押し付けようとして、結果として長引いている。東電だけでできると思っているところが違う」と述べた。
近鉄系「三笠」:大和肉鶏、当初から偽装 前料理長認める 11/02/13 (読売新聞)
近鉄系のホテルや旅館がメニュー表示と異なる食材を提供していた問題で、奈良市の旅館「奈良万葉若草の宿三笠」が2011年4月からメニューに入れている「大和肉鶏の唐揚げ」の食材について、担当だった前料理長が、京地鶏やブラジル産鶏肉と認識しながら、大和肉鶏とメニューに表記していたことが1日、分かった。三笠の社内調査に対し認めた。一度も大和肉鶏を使っておらず、ミスではなく、意図的な偽装だった疑いが強まった。
三笠のメニューを巡っては、経営する近鉄旅館システムズの北田宣之(のりゆき)社長が10月31日の記者会見で、豪州産の成型肉を「和牛」と表記したことについて、「和牛と信じ込んで新しいメニューを作った」と述べるなど、一連の誤表示は、偽装ではなくミスとの認識を示していた。
しかし、阪急阪神ホテルズの一連の偽装発覚をきっかけに、三笠の支配人が同30日に前料理長に聞いたところ、全く大和肉鶏を使用していなかったことを認め、理由として「大和肉鶏の納入が遅い」との趣旨を説明。メニューと食材を決めた後、支配人らに報告しておらず、社内調査に対し、「『まずい』という認識はなかった」とも話したという。メニューは修学旅行誘致用のパンフレットにも掲載されていた。
前料理長は9月に今の料理長と交代したが、メニュー表示と異なる鶏肉がそのまま使われ続けていた。
大和肉鶏は3品種を掛け合わせた鶏の肉で、奈良県内の養鶏場で飼育されている。赤みを帯びた肉は弾力性があり、うまみ成分を多く含む。県がブランド化を推進しており、生産者でつくる「大和肉鶏農業協同組合」が出願し、07年に特許庁の地域団体商標に登録された。【釣田祐喜、宮本翔平】
苦しい言いわけだ。消費者庁は調理された料理の説明に使われる言葉の定義を定めて公表するべきだ。「鮮魚=十分な鮮度がある解凍した魚」は成り立つのか?だとすれば本当の鮮魚は本当の鮮魚と明記するべきなのか?解凍していない鮮魚と記載するべきなのか?今回の問題から学ぶべき事はあるはずだ。消費者庁はホームページ等を通して表記の定義及び罰則などについて検討し、最終的なものを公表するべきだ。言葉、表記や説明の定義が明確になればお客は注文する時に確認できる。誤りも減る事は間違いない。「料理全体では値段に相応するサービスを行った」等の苦しい言い訳もなくなる。サービスの定義も曖昧だ!料理の材料費だけなのか、土地代、従業員等のコストを含めてのサービスなのだろうか?お客が多いレストランだと、お客の数で固定費用を割るので料理の材料費を除くコストは安くなるはずだ。
やはり消費者庁の適切な対応が必要だ!
近鉄系ホテルは返金せず「値段相応にサービス」 11/01/13 (読売新聞)
近鉄ホテルシステムズ(大阪市)と近鉄旅館システムズ(奈良市)は31日午後、ホテルと旅館計8か所で不適切なメニュー表記があったと発表した。
このうち7ホテルでは加工牛肉の使用を明記せず、37万人以上に提供されたが、返金には応じないとしている。
発表では、「シェラトン都ホテル大阪」(大阪市)や「橿原観光ホテル」(奈良県橿原市)など7ホテルは、牛脂注入肉や成形肉を「ステーキ」などと表記。加工肉使用の明記を求めた消費者庁の指針を把握していなかったという。返金しない理由について、ホテルシステムズの二村(ふたむら)隆社長は記者会見で「料理全体では値段に相応するサービスを行った」と説明した。
一方、「奈良万葉若草の宿三笠」(奈良市)は「和牛」との表記で豪州産成形肉を使用。「大和肉鶏」「大和野菜」で他産地品を使用するなど、計10品目の虚偽表示があった。提供した修学旅行生ら計2万5000人には返金する方針。旅館システムズの北田宣之社長は「料理長が豪州産成形肉を和牛肉と信じ込んでいた。つまらないミスで、偽装ではない」とした。
「シェラトン都ホテル東京」(東京都港区)が冷凍魚を使用していた「鮮魚の天ぷら」は、「魚の天ぷら」に改めたが、「解凍した魚でも十分鮮度はあり、誤りではない」と説明した。
「2人がノ社の社員であることは認識していたが、勤務時間外で研究に参加していたことなどから論文ではノ社所属と明示しなかったとしたうえで、『研究を提案した元社員は素晴らしい統計学者だと今でも思っている』とも述べた。」
滋賀医科大学病院長の柏木厚典副学長のコメントに関して疑問に思う事がある。「勤務時間外」だから論文でノ社所属と明示しなかった。情報は正確に記載されるべきだ。
「研究を提案した元社員は素晴らしい統計学者だと今でも思っている」との個人の能力評価と元社員が倫理的に問題がなかったのか、故意にデーター操作をした可能性の問題について関係がない。統計学者としての評価よりも、元社員が人間的にデーター操作をするような人物には思えなかったと言った方が誤解が少ない。
「警察官はすばらしい=全ての警察官は不正な行為や犯罪行為をしない」が成り立たない事は既に事実から多くの人が知っているのと同じ事だ。
「柏木氏は『意図的にデータを操作したことはない。調査委の結論には疑問があり、意図的な操作だったというのなら、証拠を示してほしい』と強調。『データの誤入力が多かったことは認めるが、科学的論文として不適切だというのは納得できない』と述べた。」
科学的論文の不適正の基準について知らないが、「データの誤入力」が多い論文の信頼性及び重要性については疑問だ。論文が正しければ同じ条件で実験すれば、ほぼ同じ結果が得られるはずである。実験ごとに結果が大きく違えば、そのような論文を支持する科学者は多いのだろうか??
「絶対に不正はない」疑惑の滋賀医大副学長、調査結果を全面否定 ディオバン研究データ操作問題 10/31/13 (産経新聞)
「絶対に不正なことはやっていない」。降圧剤「ディオバン」を使った臨床研究で、論文のデータが意図的に操作されていた疑いを指摘した滋賀医科大側の調査結果に対し、研究責任者だった同大学病院長の柏木厚典副学長(67)は31日、操作の可能性を全面的に否定し、辞任や論文撤回はしない姿勢を示した。一連の問題では初めて、現職の研究責任者が大学側の調査結果に真っ向から反論する事態になった。
柏木氏は「意図的にデータを操作したことはない。調査委の結論には疑問があり、意図的な操作だったというのなら、証拠を示してほしい」と強調。「データの誤入力が多かったことは認めるが、科学的論文として不適切だというのは納得できない」と述べた。
論文の正当性を示すために、カルテが残っていた約100人分の患者のデータを再度、独自に解析した結果を厚生労働省などに提出し、当初の論文と同様の結論が得られると訴えることも検討しているという。
調査委は研究にノバルティス社の元社員(当時現役社員)が関与していた点について「利益相反の観点から問題」と批判したが、柏木氏は「この臨床研究を行った当時、研究者の間で利益相反という考え方は薄かった」と主張。「今回の研究を提案した元社員はデータの解析には関わっていない。元社員の部下は参加したが補助的な作業などをやっただけだ」とした。
2人がノ社の社員であることは認識していたが、勤務時間外で研究に参加していたことなどから論文ではノ社所属と明示しなかったとしたうえで、「研究を提案した元社員は素晴らしい統計学者だと今でも思っている」とも述べた。
ノ社の元社員が関与したディオバンの臨床研究で論文のデータが操作されていたことが判明している京都府立医大や東京慈恵医大では、いずれも研究責任者がすでに退職している。
東京ガスがガス漏れ放置8件 10/31/13 (産経新聞)
東京ガスは31日、下請け会社に委託した東京都内と神奈川県内のガス漏れ修理で、ガス漏れが検知されたにもかかわらず修理せずに放置し、修理したと嘘の報告をしていた不正が計8件あったと発表した。うち1件は、東京ガス社員も関与していた。
同社によると、ガス漏れの放置は、東京都町田市と神奈川県の藤沢、鎌倉、逗子、相模原の各市で、平成21年2月~25年8月の間に計8件確認された。最初に不正が行われたのは藤沢市の現場で、東京ガス社員の指示で行われた。その後、下請け会社の社員が不正を続けたとみられる。漏れたガスは微量で、人体への影響や火災の恐れなどはないという。
修理は工程ごとに写真を撮影して社内へ報告することになっていたが、社員は写真を加工して工事が完了したかのように嘘の報告を行っていた。社員は不正を認めており、同社の聞き取りに「いくら探しても漏(ろう)洩(えい)箇所が見つからないと思った」などと話している。
不正は内部告発で発覚した。同社の荒井英昭常務執行役員は31日に記者会見を開き、「ガス漏れを検知しながら放置するなどとんでもないことで、深くおわび申し上げる。原因究明を踏まえ再発防止に努める」と謝罪した。
「メニュー偽装認める 社長が辞任表明」は顧客の反応を予測できなかったのか、軽視していたのだろうか?
収集された情報や世間の反応から最初の判断を変えたと言う事に思える。
阪急阪神ホテルズ:メニュー偽装認める 社長が辞任表明 10/28/13 (毎日新聞)
阪急阪神ホテルズ(大阪市)が運営するレストランなどでメニュー表示と異なる食材を使用していた問題で、出崎(でさき)弘社長は28日、記者会見を開き、メニューの一部が事実上の偽装だったことを認め、来月1日付で引責辞任すると表明した。出崎社長はこれまで「偽装ではなく誤表示」と主張していたが、「単に表示を誤ったとのレベルを超えており、客にとっては偽装と受け止められても仕方がない」と謝罪。メニュー偽装問題は発覚から1週間でトップ辞任に発展した。
同社は当初、トビウオの魚卵を「レッドキャビア」(マスの魚卵)と表記するなど47品で表示と異なる食材を使っていたと発表。しかし、このうち6品については説明が不十分だったとして再調査した。出崎社長が従業員ら22人に聴取した結果、▽「手作りチョコソース」は、既製の材料を混ぜる手間に着目し、「手作り」と表示▽中国産と日本産をブレンドした「天ざるそば(信州)」は、メニュー採用時のサンプル品に信州にちなむ地名があった−−などの経緯が判明。出崎社長は「欺く意図を持って不当な利益を上げようとはしていないが、客にその理屈は通らない。信頼を裏切る行為にほかならない」と話した。
出崎社長が会見を開くのは問題発覚後2回目。当初は「従業員の知識不足や現場の連携不足があった」として「偽装ではなく誤表示」と主張したが、消費者などから批判が続出していた。出崎社長は「阪急阪神ブランド全体への信頼を失墜させた」として社長とともに、親会社の阪急阪神ホールディングスの取締役も辞任する。後任の社長は29日の臨時取締役会で決める。
同社がグループ傘下のレストランなどを調査した結果、23店で2006年以降、メニューの表記と異なる食材を使った料理が延べ7万8775人に提供されたことが判明。28日午前9時までに1万494人に計2263万円が返金された。【石戸諭、田所柳子、古屋敷尚子】
阪急阪神ホテルズ:後手後手の対応、事態を悪化 10/28/13 (毎日新聞)
阪急阪神ホテルズ(本社・大阪市)がメニューと異なる食材を使っていた問題で28日夜、急きょ記者会見を開いた出崎(でさき)弘社長。事実上の偽装を認め、何度も立ち上がって頭を下げたが、「不当な利益を得るためととらえるなら、偽装ではない」と釈明する場面も。22日に問題が表面化して以来、同社の会見は3回目。従業員に誤表示の認識があったかどうか説明は二転三転し、後手後手の対応が事態をより悪化させた。
会見場の大阪新阪急ホテル(同市北区)には、100人を超す報道陣が詰めかけ、出崎社長が2時間以上にわたり、1人で受け答えした。
冒頭から約25分間は25日からの再調査の結果を報告。出崎社長は24日の会見で従業員が誤表示を認識していなかったと説明したが、この日は一転、一部の従業員が認識しながら放置していたと認めた。青ネギなどを九条ネギと表記した理由については「担当者がメイン料理ではなく、添え野菜なので客に伝えなくても問題ないと思った」と説明。安価なバナメイエビを芝エビとした例では「『小さいエビは芝エビと称する』などとする一般常識と違う業界の習わしがあった」としたが、「どれもお客様には通用しない」と述べ、消費者の意識とのずれを認めた。
誤表示の見解を撤回した理由については、自身が24日に開いた会見の様子をテレビなどで見て「会社の立場だけで説明していた。お客様の視点が足りなかったと感じた」と硬い表情で語った。辞任の意向は26日に親会社の阪急阪神ホールディングス幹部に伝えたが、「まだ再調査が終わっていない」と言われ、28日に受理されたという。「阪急阪神グループ全体の信用問題になり、ここで責任を取るべきだと考えた」と心情を明かした。
ホールディングス社内では、前回の社長会見について「謝罪の意図が伝わっていない」と批判する声が高まっていた。「私の判断が甘かった」。出崎社長は何度も繰り返し、会見場を後にした。【田所柳子、後藤豪、近藤諭】
◇「辞任は仕方ない」
出崎社長の突然の辞任表明に、ホテルの利用者からはさまざまな声が上がった。
大阪新阪急ホテル(大阪市北区)に宿泊にする横浜市保土ケ谷区の男性会社員は「辞めれば騒ぎが収まると思ったのでは。(辞める前に)調理現場だけでなく、どこまでが偽装の事実を把握していたのか、まず明確にしてほしかった」と真相究明を強く求めた。
阪急阪神ホテルズを利用した人達及び利用しようと思う人達が、どう感じどう判断するのか次第だ。利用しない人達は影響を与えられない。
阪急阪神ホテルズの体質や判断基準が今回の件で公になったと思う。現場に問題がある場合もあるが、現場は上には逆らえないと思う。
大手だと「逆らう=/≒辞める/出向」だろう。企業の名前だけで代わりなどすぐ探せると思う!
調理責任者、食い違い認識…阪急阪神ホテルズ 10/28/13 (読売新聞)
阪急阪神ホテルズ(大阪市北区)が運営するレストランなどで発覚した食材偽装問題で、同社の再調査の結果、担当者が食材とメニュー表示の食い違いを認識していたケースがあったことがわかった。
出崎(でさき)弘社長が読売新聞の取材に答えた。中国料理の担当者が、「芝海老(えび)」との表記で安価なバナメイエビを提供していたことを認めたという。出崎社長は29日午前、再調査結果について記者会見を開く。
一連の問題で、出崎社長は24日の会見で「エビの件を含め、食材とメニュー表記の違いについて誰も認識していなかった」との説明を繰り返していた。
出崎社長によると、誤表示があった料理47品目のうち6品目について自ら聞き取りを実施。大阪新阪急ホテル(同)の調理責任者は「業界の慣行では、料理名を中国語から訳す際、小ぶりのエビのことを『芝海老』と表現するという認識だった」と釈明したという。
東電を破たんさせ、はっきりさせるべきだ!先送りやうやむやのままではだめた!こんな状態で原発の新設などあり得ないと思わないのか?
大事故が起これば後始末も出来ない事が明確になったのに何を考えているのだろうか?
東電、除染費用支払い拒否 74億円、国は黙認 10/27/13 (朝日新聞)
【関根慎一、多田敏男】東京電力が除染事業の大半の項目について費用の支払いに応じない考えを2月時点で国に明確に伝えていたことが、朝日新聞が環境省への情報公開請求で得た文書でわかった。国はこれを公表せず、支払い拒否を黙認している。
国が除染費用を立て替えた後、東電に請求するのが「放射性物質汚染対処特別措置法」の規定だ。環境省は現在までに計404億円を請求したが、東電が支払ったのは67億円。国や東電は「内容の確認に時間がかかっている」とし、手続き上の問題と説明してきた。
ところが、東電は2月21日付で環境省に送った文書で、昨年11月の第1回請求分の大半について「支払いが困難であるとの結論に至った」と拒否。環境省が説明を求めると、2月27日付の回答文書で、第2回請求分をあわせた149億円(118項目)のうち、74億円(95項目)について個別に支払わない理由を列挙した。さらに、賠償交渉を仲介する「原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)」に委ねることを検討するよう提案した。
東電 除染費負担を全面拒否 「賠償と二重払い」主張 10/27/13 (朝日新聞)
東京電力が、数兆円に上ると想定される福島第一原発事故による放射能汚染の除染費用を全面的に返済しない方針を政府に伝えていることが分かった。費用は政府が復興予算から立て替え払いし、東電が後に返済することが法律で定められている。しかし、東電は「家や土地に対する損害賠償に加え、除染費用まで払えない」などと主張。このまま返済が滞れば、復興予算に穴があく事態もあり得る。 (桐山純平)
東電は政府が四回にわたって請求した除染費用四百三億円のうち六十七億円しか払っていない。残る支払いが遅れている理由を「書類を精査しているため」と説明してきた。
しかし、複数の政府関係者によると、東電は既に返済が遅れている分だけでなく、数兆円と想定される将来の負担についても返済を拒否する方針を政府側に伝えた。東電取締役は、政府・与党の関係者に対し、土地や建物の価値が減った分の賠償は進めており、ここに除染費用も含まれているため「二重払いになる」などと強調しているという。
これに対する政府・与党内の考え方はばらばらだ。
経済産業省資源エネルギー庁は、東電に理解を示し、除染費用を国が負担するよう財務省などと協議を始めており、与党内でも国費負担論が出ている。
一方、除染を担当する環境省では、東電に延滞金を科すことも検討している。同省幹部は「汚染水対策が大変だから、などの理由も挙げ、東電は全く払おうとしない。ゼロ回答だ」と憤る。
返済拒否の理由について東電に確認を求めたが、担当者は「(除染の)請求内容を個別に確認させていただいて適切に判断したい」とコメントした。
事故後に施行された除染特別措置法では、東電が除染費用を負担することが明記されている。実質的に国有化されている東電が、巨額の除染費用を支払うのは難しいため、電力各社が負担金を出し合い、そこから東電が資金を受け取り、国に返済する仕組みが既にできている。
円請求も支払ったのは67億円のみ 10/27/13 (朝日新聞)
東電、除染費用支払い拒否 74億円、国は黙認
東京電力が除染事業の大半の項目について費用の支払いに応じない考えを2月時点で国に明確に伝えていたことが、朝日新聞が環境省への情報公開請求で得た文書でわかった。国はこれを公表せず、支払い拒否を黙認している。
国が除染費用を立て替えた後、東電に請求するのが「放射性物質汚染対処特別措置法」の規定だ。環境省は現在までに計404億円を請求したが、東電が支払ったのは67億円。国や東電は「内容の確認に時間がかかっている」とし、手続き上の問題と説明してきた。
ところが、東電は2月21日付で環境省に送った文書で、昨年11月の第1回請求分の大半について「支払いが困難であるとの結論に至った」と拒否。環境省が説明を求めると、2月27日付の回答文書で、第2回請求分をあわせた149億円(118項目)のうち、74億円(95項目)について個別に支払わない理由を列挙した。さらに、賠償交渉を仲介する「原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)」に委ねることを検討するよう提案した。
【関根慎一、多田敏男】
ヤマト運輸は安くて便利なのでよく使っているし、インターネット通販でもヤマト運輸を使っているショップを使っている。クール便は基本的に使う事がないのでこのような問題には気付かなかった。商品を送る側としては大問題だろうな!これでは商品の鮮度や品質劣化に繋がる可能性もある。
ヤマトのクール便 ファミマ冷蔵施設 不適切な温度管理 10/26/13 (産経新聞)
宅配便最大手のヤマト運輸(東京都中央区)は25日、鮮魚などを低温で運ぶ「クール宅急便」のサービスについて、全国に約4千ある営業所のうち約5%に相当する約200カ所で不適切な温度管理が行われていたことを明らかにした。
ヤマトの森日出男常務執行役員らは同日、東京都内で開いた記者会見で謝罪。クール宅急便の料金(210~610円)については、返還の可否を今後検討するとした。
同社によると、各地の物流拠点では仕分け用のクールボックスから商品を取り出す際、扉を開けたままの状態で作業する制限時間を5分以内、外気温に直接触れるボックス外での作業を30秒以内と規定していた。
しかし、都内の営業所を撮影したとされる動画を調べた結果、ルールが守られていない実態を確認。約200カ所でルールの逸脱があったという。
一方、コンビニエンスストア大手のファミリーマート(豊島区)では、一部の物流拠点で冷蔵施設内の温度が一時的に規定より上がっていたのに、運営担当の下請け業者が規定内と偽った記録を付けていたことが判明した。
同社によると、冷温保存が必要な商品は冷蔵施設で3~8度に保って仕分け作業などをすると規定。しかし、東京都八王子市にある物流拠点では、商品の仕入れが集中する時間帯に扉の開け閉めが頻繁になり8度を超えることがあったのに、担当者は記録簿に規定内の温度を記したという。
この物流拠点は都内約200店舗に商品を配送。9月に情報が寄せられ、調査して発覚した。
クール宅急便、200カ所で常温仕分け ヤマト運輸 10/25/13 (朝日新聞)
【中村信義】ヤマト運輸の複数の営業所が「クール宅急便」の荷物を常温で仕分けていた問題で、同社は25日に都内で記者会見を開き、全国の営業所の5%に当たる約200カ所で温度管理のルールを守っていなかったことを明らかにした。森日出男常務執行役員は「二度とこのような事態を招かないよう品質向上と信頼回復に努める」と述べ、謝罪した。
朝日新聞の報道を受け、ヤマトが25日に全国の営業所に緊急の聞き取り調査をしてわかったという。
同社は1本の保冷用コンテナの荷物を5分で仕分けるとともに、荷物を取り出す際は外気に触れる時間を30秒以内にするという手順を定めている。聞き取りでは、この時間を超えて荷物を常温の状態にさらすなどの実態がわかったという。
ただ、同社は各営業所で具体的にどんなルールの逸脱があったかなどについては、「詳細を調査中」と述べるにとどめた。
会見では、コンテナを5分以内で仕分けるなどのルール自体に「無理があるので、できないのか」と問う声も出た。森常務は「可能だと思う」としながらも、「改めてルールを見直す必要があることも認識している」と述べた。
今後、さらに精度の高い調査を進め、11月中に抜本的な対策を公表する。
クール宅急便、常温で仕分け ヤマト運輸、荷物27度に 10/25/13 (朝日新聞)
【中村信義】宅配便最大手ヤマト運輸の東京都内にある複数の営業所が、「クール宅急便」で預かった荷物を外気と同じ環境で仕分けていたことが、朝日新聞が入手した動画などからわかった。同社は「食品の安全にも関わり極めて不適切」として、基本ルールを徹底するよう全社員に通知するとともに、実態の調査を始めた。
ヤマトの複数の営業所内で撮られた動画には、保冷用コンテナが開けっ放しになったまま、作業員が仕分けをする様子が収められている。「冷蔵」と書かれたシールが貼られた荷物がコンテナ外に置かれたままになっている場面もある。
現場をよく知る同社関係者が今秋に撮影したこの動画を、朝日新聞に提供した。この関係者は8月に、温度の変化を測定・記録できる機器をクールの荷物の箱に入れ、自ら発送。その記録によると、午前6時台までは11度台だったが、7時40分前後から上昇し、50分ごろには20度を突破。8時10分前後に27度を記録した後に徐々に下がり、8時50分前後には再び11度台に戻った。
みずほ組員融資:現経営陣を温存、甘い対応目立つ (1/2)
(2/2) 10/26/13 (毎日新聞)
みずほ銀行は25日、暴力団員らへの融資を放置した問題を受けて、佐藤康博頭取を半年間無報酬とし、常務執行役員以上の30人超を報酬カットにする社内処分案を固めた。塚本隆史会長は辞任するが、兼務している持ち株会社の会長は留任する方向だ。問題を放置した経営陣を温存させる内容で、みずほの対応は甘さが目立つ。報告を受け、追加処分の是非などを精査する金融庁の対応が焦点となる。【谷川貴史、山口知、竹地広憲】
問題融資を把握した2010年当時の西堀利頭取や、法令順守を担当した役員OBには、報酬の返納を求める。法令順守担当だった小池正兼常務は辞任する。
今回の問題では、歴代トップが抜本的な改善策を講じなかった上、昨年12月からの金融庁検査で問題を指摘されても対応が後手に回った。みずほ銀は金融庁検査で「問題融資の報告は担当役員止まり」と、事実と異なる説明に終始。しかし、9月末の業務改善命令後に行った社内調査で経営トップの関与が判明し、顧客らから「説明責任を果たしていない」との批判が噴出した。
この結果、問題をあぶり出した側の金融庁にも「検査が甘かったのでは」との指摘が相次ぎ、同庁は今月9日、みずほ銀の対応を「誠に遺憾」として異例の追加報告命令に踏み切った。麻生太郎金融担当相も会見などで「検査の質的向上に取り組まなければならない」と釈明せざるを得ない状況だ。
今回の社内処分では、今年7月に持ち株会社傘下の2行を統合し「ワンバンク」を実現した佐藤体制の継続を優先させた側面が強い。塚本氏も銀行の会長職は退くが、親会社のみずほフィナンシャルグループ(FG)会長を続ける方向だ。融資発覚後、約2年間も頭取を務めた塚本氏が、問題を知っていながら放置していたのか、認知しなかったのかの説明も明確でなく、トップの責任はあいまいなまま。自民党内でも「問題の経緯が不明で、なぜこうした処分になったか分からない」との不満が出ている。
みずほ銀は第三者委員会(委員長・中込秀樹弁護士)の調査結果を踏まえ、28日に業務改善計画を金融庁に提出する。みずほに甘い顔を見せれば、金融庁への風当たりも強まりかねない。経営トップの関与の度合いが強まるなどの結果が出れば、金融庁がさらなる経営責任の明確化を迫る事態も予想される。
旧第一勧業銀行による総会屋への利益供与事件時に同行の広報部次長だった作家の江上剛(ごう)さんは「みずほは、今回の問題で統治能力がないことを再び世間に示した。意図的な検査忌避があったかなどの真相を究明し、再発防止に努めてほしい」と話している。
コメロンダリング「何か変だと思いつつ…」 10/25/13 (読売新聞)
三重県四日市市の米穀販売会社「三瀧(みたき)商事」(服部洋子社長)によるコメ偽装問題で、県警は24日、強制捜査に踏み切った。
親族会社や取引先を使い、架空の取引で輸入米や加工用米を主食用米に変える「コメロンダリング」。複雑で巧妙な偽装工作は誰が、どう指示していたのか。解明が始まった。
「加工用米をジャパンゼネラルに売ってほしい」
加工用米の偽装に関わった四日市市の製茶業者「榊原商店」の社長は読売新聞の取材に対し、数年前、三瀧商事からそう持ちかけられたと明かした。玄米茶の販売不振で加工用米の仕入れをやめようと、全国穀類工業協同組合三重県支部長の三瀧商事に電話した時のことだ。
榊原商店の社長は、三瀧商事の親族が経営するジャパンゼネラルという会社を知らなかったが、三瀧商事の説明では、加工用米をあられとして使用するということだった。1俵(60キロ)あたり100円のマージンを渡すと言われ、「何か変だ」と思いつつ、引き受けることにしたという。
稲垣製茶の社長も「おかしいなとは思ったが、国産大麦が不足した時、業者との取引を仲介してもらったので引き受けてしまった。ジャパンゼネラルについては、社名と住所しか知らない」と語った。
三瀧商事は、同族会社と地元の取引先を巻き込み、架空伝票を使って偽装を隠蔽していた。今回、偽装が発覚したのは内部通報があったためだが、農水省の担当者は「それがなければ見抜けなかった」と明かす。
リッツ・カールトン大阪もニセ表示…車海老など 10/25/13 (読売新聞)
阪急阪神ホテルズ(大阪市北区)が運営するレストランなどがメニュー表示と異なる食材を使用していた問題で、グループ会社の阪神ホテルシステムズが運営する「ザ・リッツ・カールトン大阪」(同)は25日、「車海老(えび)」との表記で安価なブラックタイガーを提供するなどしていたことを明らかにした。
同ホテルによると、阪急阪神ホテルズの食材偽装を受けて22日から自主的な調査を実施。エビの虚偽表示があったのは中国料理レストランで、「芝海老」としてバナメイエビを使用していたこともわかった。
このほか、搾りたてを意味する「フレッシュジュース」との表示で昨年10月以降、搾ったうえで冷凍保存し、解凍した後のストレートジュースを使用。ルームサービス用の「自家製パン」9種類のうち3種類が既製品などだった。
企業体質の問題。1つの問題を改善すれば解決できるレベルではない。何年又は何十年で現在の状態になったはずだから、財務や人材の意識改革などを考えると問題は深刻だと思う。JR北海道の似たようなレベルだろう。どこから手をつけたら良いのかわからない。真剣に改革に取り組んでも結果として表れるのは何年後だろう。
阪急阪神ホテルズ:豚肉産地確認せず 業者、書類拒否でも 10/24/13 (毎日新聞)
阪急阪神ホテルズ(本社・大阪市)のメニュー偽装問題で、表示とは産地の異なる豚肉を納品していた業者が4カ月間にわたり、ホテル側から求められた食材の「規格書」の提出を拒んでいたことが分かった。規格書は食材の原産地や原材料などを記すものだったが、ホテル側は提出を受けないまま、この豚肉を使い続けていた。
問題のメニューは「霧島ポークの上海式醤油(しょうゆ)煮込み」。ホテル阪急インターナショナル(大阪市北区)内の中華料理店が2012年9月から約1年間、コース料理(1万円〜1万3500円)の一品として311人に提供した。
同社関係者によると、ホテル側が新しい食材を仕入れる際、原産地や管理状況、アレルギー物質の表示などを記した規格書を納入業者から提出させている。この豚肉も当初は、鹿児島・霧島産と記されていたが、ホテル側が今年5月、アレルギー対策のために規格書の再提出を求めた際、業者側が拒否。その後、再三の催促にも応じなかったが、ホテル側は「古くから取引がある」との理由でこの豚肉を使い続けていた。
他の店舗で偽装が見つかった後の今年9月になって、業者は規格書を提出。他県産との記述があり、偽装が発覚した。ホテルは先月10日、このメニューを廃止したが、少なくとも4カ月間、産地をチェックしないまま表示と異なる料理を提供し続けていた。
同社は取材に対し、「4カ月間も規格書を提出していない業者と取引を続けてきたことは、チェックが甘いと言われても仕方がない」と、管理体制の甘さを認めている。【石戸諭】
阪急阪神ホテルズ:調理担当者、レッドキャビアの偽装認識 10/24/13 (毎日新聞)
阪急阪神ホテルズ(本社・大阪市)のメニュー偽装問題で、ホテルの調理担当者が、食材がトビウオの魚卵であると知りながら、「レッドキャビア」(マスの魚卵)と虚偽表示していたことが関係者への取材で分かった。トビウオの魚卵の価格はマスの3分の1程度だったといい、仕入れ値を安く抑える目的だった疑いもある。
担当者が虚偽表示を認識しながら放置していたケースは「芝エビ」「九条ネギ」に続き3件目で、消費者庁は景品表示法違反(優良誤認)の可能性があるとみて調べる。
同社によると、問題のメニューは大阪新阪急ホテルが会員制サロンで今年6〜7月末に販売した「クラゲのレッドキャビア添え」。7000〜8500円のパーティー料理の一品として計514食を提供した。
一般的にレッドキャビアはマスの魚卵を指す。複数の同社関係者によると、ホテルの担当シェフは当初から、食材がトビウオの魚卵(とびこ)であると知りながら仕入れ、メニューにレッドキャビアと表示。一部の調理担当者は社内調査に「とびこをレッドキャビアとして販売している業者もおり、表示しても問題ないと思っていた」と釈明しているという。
同社によると、トビウオの魚卵は1キロ約5000円で、マスの3分の1程度で取引される。関西地方の食品業者は「トビウオの魚卵は、マスの魚卵と見た目が異なり、間違えようがない。レッドキャビアと表示するなんて聞いたことがない」と驚く。
同社はこれまで、23店舗で47商品のメニューに事実と異なる表示があったと発表。このうち「芝エビ」と「九条ネギ」の2品目は、担当者が誤表示を認識していたと説明していた。芝エビの仕入れ値は1キロ2500円で、実際に使用されたバナメイエビ(1キロ1400円)とは約2倍の開きがあるが、担当者は社内調査に「バナメイエビと芝エビは大きさも同じなので、同じエビだと思っていた」と説明。九条ネギも、実際に使われた一般的なネギと約2・5倍の価格差があることが判明している。【石戸諭】
コメ産地偽装:三瀧商事を家宅捜索 容疑で三重県警 10/24/13 (毎日新聞)
三重県四日市市の米穀販売「三瀧(みたき)商事」(清算手続き中)が主導したコメの産地偽装事件で、県警は24日、日本農林規格(JAS)法違反(虚偽表示)などの疑いで、同市広永町の本社など関係先の家宅捜索を始めた。県警は今後、同社幹部や取引先業者などから任意で事情を聴き、国内で過去最大規模となった偽装米事件の全容解明を目指す。
家宅捜索したのは、同社や服部洋子社長(74)の関係先のほか、関連会社で米穀卸売り「ミタキライス」と両社工場、偽装用米の仕入れ先業者など。
容疑は、少なくとも2010年から今年9月にかけ、加工用米を主食用米と偽装したり、中国や米国産米を国産米と偽って表示するなどして、計4386トンを販売したとされる。農林水産省と三重県は今月4日、同法のほか、食糧法、米トレーサビリティー法違反があったとして、両社と関連4事業者を行政指導していた。
三瀧商事本社では県警の捜査員約40人が午前9時すぎ、段ボール箱などを持って次々と社内に入った。
民間信用調査会社によると、三瀧商事は1877(明治10)年創業。2012年3月期には80億円の売り上げがあったが、同社とミタキライスは今月10日、「信頼を揺るがせる重大な事態を引きおこした」として臨時株主総会で解散決議し、清算手続き中。【岡正勝、大野友嘉子、永野航太】
中国ウナギ、日本語の段ボールに「愛知産」と印 10/24/13 (読売新聞)
中国産ウナギ約19万匹分を国産と偽って流通させたとして、東京都と北海道は23日、いずれも水産販売業の「翔水」(江東区、竹吉勝社長)、「活うなぎの三晃」(札幌市中央区、三馬克彦社長)の2社に対し、日本農林規格(JAS)法に基づき是正措置を講じるよう指示した。
都などによると、両社は2011年3月~13年7月にかけて、中国から輸入したウナギのかば焼き約19万匹(約28トン)を「愛知県産」と記した段ボールに詰め替えて販売した。ウナギは東北地方のスーパーなどで販売されたという。
三晃が10キロ当たり3500円の手数料で翔水から偽装を請け負い、日本語で「うなぎ蒲焼(かばやき)」などと印刷された段ボールを発注。愛知県産の印を押し、翔水が国産ウナギと偽って別の問屋に転売していたという。
ウナギ産地偽装、虚偽証明書も作成した養殖会社 10/23/13 (読売新聞)
静岡県吉田町のウナギ養殖販売会社「大井川うなぎ販売」(藪崎周二社長)が、静岡県産などと産地を偽装したウナギを販売していた問題で、同社が「県産であることを証明します」と記載した虚偽の産地証明書を作成し、販売先に郵送していたことが22日、同社からウナギを仕入れた小売店への取材でわかった。
静岡県警は、同社が産地表示を偽装したうえ、産地証明書で小売店を信用させようとしていたとみて捜査を進めている。
福島県に本社を置くスーパーチェーンが22日、読売新聞の取材に明かした。同チェーンによると、1990年代後半から静岡県産のウナギを販売し、2011年度からは、商品の一部を大井川うなぎ販売から仕入れている。同チェーンは消費者に産地を明示するため、同社に産地証明書の発行を要望。まとまった量を仕入れた後、同社から仕入れ分の産地証明書が郵送されてくるという。
産地証明書には、「長蒲焼80尾 静岡県産」「貴社に出荷致しました品目に関しまして、相違ないことを証明致します」などと記載され、大井川うなぎ販売の押印もあった。同チェーンによると、書面の文言や様式は同社に任せており、同社がパソコンの文書作成ソフトを使って作ったという。
農林水産省によると、産地証明書は公的機関が法律に基づき作成するものでないため、業者のモラルに任されているという。
同チェーンの担当者は「流通ラインを精査した結果、当社の店舗には産地偽装されたウナギは入ってきていない」と説明。そのうえで、「産地証明書は、消費者に対する『産地が見える商品』の担保と考えていた。(取引先の)産地偽装は残念」と話した。
ただ、同チェーンが仕入れた業者は、静岡県産に愛知県産のウナギを混入しており、同チェーンに愛知県産のウナギが出荷された可能性もある。
県警は21日、大井川うなぎ販売のほか、同社が産地偽装を指示した加工4業者を不正競争防止法違反(誤認惹起)容疑で捜索し、押収した伝票データが入ったパソコンを解析するなどしている。
偽装ホテル、一斉にお詫び看板 客「もう信頼できない」 10/23/13 (朝日新聞)
偽装が明らかになったホテルの飲食店にはこの日、「お詫(わ)び」の看板が一斉に掲げられた。
「鮮魚」メニュー実は冷凍
ホテル阪急インターナショナル(大阪市北区)の直営中華料理店は2012年から今年9月まで、九州南部の「霧島ポーク」としていたコース料理の一品で、産地の違う豚肉を使用。仕入れ先が「霧島ポーク」と説明したといい、幹部は「しっかりと産地の証明書を見せてもらうべきだった。ホテルは信頼が第一なのに……」と肩を落とした。
昨年7月から1年間、有機野菜でない食材を「有機野菜」としたホテル阪神(大阪市福島区)の中華料理店は、幹部が取材に「本社でなければ対応できない」と困惑した表情。また、直営レストランなどの21メニューで偽装があった六甲山ホテル(神戸市灘区)は、連絡先の分かる団体客に電話で連絡を始めた。「2年ほど前に利用したが大丈夫か」などと一般客から問い合わせがあったという。
「ホテルだから安心と思っていたのに……。もう信頼できない」。オムライスで虚偽表示をした大阪新阪急ホテルの喫茶店を利用していた70代女性が憤った。牛脂注入肉と明記せずに柔らか牛肉と表示していた「宝塚ホテル」(兵庫県宝塚市)では、金沢市から妻と旅行に来た宿泊客の男性(66)が「一流ホテルで、リッチな気分を味わいたかったのにがっかり。次も来たいという気持ちが失せます」と話した。
「鮮魚」メニュー実は冷凍 阪急阪神ホテルズ異なる表示 10/22/13 (朝日新聞)
阪急阪神ホテルズ(本社・大阪市)は22日、運営する8ホテルなどにある計23店舗で、メニュー表示と異なる食材を使った料理を提供していたと発表した。販売期間は2006年3月から今年9月で、利用客は延べ7万8775人に上る。景品表示法などに抵触する可能性があるとして、同社は消費者庁に報告した。
提供したのは47品目。同社は申し出た客から状況を聞いた上で返金する。返金額は約1億1千万円と見込んでいる。
発表によると、「第一ホテル東京シーフォート」のレストラン「グランカフェ」では12年4月~今年7月、冷凍保存した魚を「鮮魚」として提供。「大阪新阪急ホテル」のバー「シィーファー」では11年6月~今年7月、パーティー料理で「九条ねぎ」と表示しながら一般的な青ネギなどを使用。宴会場のパーティー料理でも11年4月~今年7月、表示食材を芝海老(えび)としながら安価なバナメイエビを使っていた。「手捏(ご)ね煮込みハンバーグ定食」で既製品を提供したり、「自家菜園サラダ」を別ルートの野菜で出した例などもあった。
同社は理由について、メニューの作成担当者と調理担当者、食材を発注する担当者、さらに仕入れ業者などの間で情報伝達と連携に不備があり、誤った表示が継続されたと説明している。ただ、新阪急ホテルの芝海老の例では、表示と食材の違いにシェフが気付きながら「言い出せなかった」として放置されていた。同社は関係するホテル事業の担当役員らを処分する方針。
今年5月に他社のホテルで同様の誤表示があり、記録が残る06年3月以降を自主的に調査して判明した。
記者会見で奥村隆明・総務人事部長は「アピールポイントを強調しようとしてメニューを作り、誤った表示をした。意図的、明確な意思を持っていないが、一線を越えてしまった。本社としてチェックもできていなかった」と謝罪した。
◇
【表示偽装があった施設の連絡先】
■第一ホテル東京シーフォート
03・5460・4424
■吉祥寺第一ホテル
0422・21・9853
■ホテル阪急インターナショナル
06・6377・3606
■大阪新阪急ホテル
レストラン(関西文化サロンなど) 06・6372・3554
宴会 06・6372・9520
■ホテル阪神 06・6344・7985
■宝塚ホテル(宝塚大劇場内フェリエ、関西学院会館内ポプラ、阪神競馬場内フローラ)
0797・85・2608
■六甲山ホテル
レストラン 078・891・0301
宴会 078・891・0473
■京都新阪急ホテル
075・343・5315
■阪急阪神ホテルズレストラン事業部(大阪市立大病院内パティオ)
0797・85・2809
食材偽装:阪急阪神ホテルズ、23店で 計7万8775食−−06年から 10/22/13 (産経新聞)
「阪急阪神ホテルズ」(本社・大阪市)は22日、2006年3月から今年9月にかけて、同社が経営するホテルのレストラン23店舗の47商品で、メニューの表示と異なった食材を使っていたと発表した。冷凍魚を鮮魚と偽ったり、トビウオの魚卵をレッドキャビア(マスの魚卵)などと称したりして料理に使用し、計7万8775食が提供されたという。同社は利用者には料金を返還するとしている。
同社によると、他社のホテルでの食品誤表示を受け、社内調査を実施し、相次いで誤表示が判明したという。計4万食以上が出された「鮮魚のムニエル」と称したメニューでは、冷凍保存した魚を使用。「クラゲのレッドキャビア添え」(514食)では、トビウオの魚卵を使っていた。「手捏(ご)ね煮込みハンバーグ定食」(650食)では、既製品を用いていた。
同社は背景について「食材の仕入れ担当と調理担当者の間でコミュニケーションが取れていなかった」と説明、「意図的な偽装ではない」と釈明している。
誤表示していたレストランがあるホテルは▽第一ホテル東京シーフォート▽吉祥寺第一ホテル▽ホテル阪急インターナショナル▽大阪新阪急ホテル▽ホテル阪神▽宝塚ホテル▽六甲山ホテル▽京都新阪急ホテルの8ホテル。ほかに同社がホテル外で運営している4店舗は▽宝塚大劇場内「フェリエ」▽関西学院会館内「ポプラ」▽阪神競馬場内「フローラ」▽大阪市立大病院内「パティオ」。【石戸諭】
「食品偽装」はヒルトンやプリンスホテルでも 10/22/13 (産経新聞)
ホテルのレストランでの“メニュー偽装”は、これまでにも相次いで発覚。客側に不信を抱かせ、ブランド力を失墜させた。
今年6月には、東京ディズニーリゾート(TDR)のホテルやプリンスホテルで、メニュー表記と異なる食材を使ったことが相次いで判明。この問題が、阪急阪神ホテルズが今回の調査を行うきっかけになった。
TDR内の3ホテルでは「車エビ」と表記しながら「ブラックタイガー」を使うなど、少なくとも計1400食を提供。プリンスホテルが運営する「品川プリンスホテル」など全国の計16施設のレストランでは、メニューでチリ産牛肉を「国産」などと表示していた。同社は「仕入れ部門と調理部門で情報共有されていなかった」とした。
平成20年12月には「ヒルトン東京」内の有名フランス料理店で、料理長の指示で山形牛を前沢牛と表示偽装したとして、公正取引委員会が景品表示法違反(優良誤認)で、ホテルを運営する日本ヒルトンに排除命令を出した。フランス料理店は20年10月に閉店した。
特集ワイド:「内部告発小説」の現役官僚に聞く 「再稼働いいのか」問いたい (1/3)
(2/3)
(3/3) 10/22/13 (毎日新聞 東京夕刊)
■「日本の原発は世界一安全」はウソ
■政界への献金「モンスターシステム」
■電力業界に冷たい職員のチェックリスト
ナゾの覆面作家が現れた。若杉冽(れつ)さん。現役のキャリア官僚である。9月に出版した小説「原発ホワイトアウト」(講談社)で、原発再稼働にひた走る経済産業省と電力業界、政治家を結ぶ闇のトライアングルを描き霞が関からの「内部告発」として波紋を広げている。本人に胸の内を聞いた。【吉井理記】
東京都内の料理屋に現れた若杉さん、もちろん覆面姿ではなく霞が関の住人特有の、特徴に乏しいスーツ姿だ。「尾行対策にね、後ろを気にしながら道をあちこち変えて。時間かかっちゃいました」。ささやきながら腰を落ち着け、ようやく表情を緩めた。
東京大法学部卒、国家公務員1種試験合格、霞が関の省庁勤務−−公にされた素性はこれだけだ。もちろん執筆は役所には秘密。近親者にしか明かしていない。
小説は参院選で政権与党が大勝するところから始まる。電力業界の政治献金で飼い慣らされた与党政治家と業界幹部、両者と軌を一にする経産官僚が原発再稼働に向けて暗躍する姿を縦軸とし、役所のあり方を疑問視する若手官僚の抵抗、原発テロ計画といったエピソードが横軸として交錯していく。「柱の部分は私の知る事実がベース。役所では表立って話題にしませんが、裏ではみんな『詳しすぎる。作者はだれだ』と大騒ぎです」。静かに笑う。
リスクを冒してまでなぜ執筆を? 「現実世界は原発再稼働に向けて着々と動いています。一方で私は、電力業界のずるさや安倍(晋三)首相の言う『日本の原発は世界一安全』がウソなのを知っている。私は公僕です。そうした情報は国民の税金で入手したとも言える。もちろん国家公務員として守秘義務もある。だから小説の体裁を借りて『みなさん、このまま再稼働を認めていいんですか』と問いかけたかった」。声が知らず知らずのうちに高くなり、テーブルに広げた著書を何度かたたいた。
「電力業界のずるさ」の最たるものが、若杉さんが「モンスターシステム」と呼ぶ巨大な集金・献金システムだ。作中で描いた構図とは−−。
電力会社は資材や施設の修繕工事などを、随意契約で相場より割高な価格で業者に発注する。業者は割高分の一部を加盟する電力業界団体に預ける。団体はその預託金を政治献金やパーティー券購入に充て、「大学客員教授」などのポストを買い、浪人中の政治家にあてがう。政治資金収支報告書上は関連企業や取引先企業の名前が使われるため、電力会社は表に出ない。業界団体「日本電力連盟」に“上納”される預託金は年間400億円。これで業界に有利な政治状況をつくり出す、というわけだ。
「これは私が見聞きした事実を基にしています。東京電力福島第1原発事故後、東電の経営状況を調べた国の調査委は、東電が競争入札にした場合より1割強、割高な価格で業務発注していたことを明らかにしました。私は昔は2割だったと聞いていますが」。預託金の原資、元はといえば電気料金だ。割高発注はコストを増やし当然、料金にはね返る。「企業献金がすべて悪いとは言いません。でも国が地域独占を認め、競争環境にない電力会社は別。国民にとって電気料金は税金と同じ重みがあり、税金並みの透明性が欠かせない。業務発注だって競争入札にする規制が必要です」
多額の選挙費用がかかる政治家が電力マネーに弱いのは理屈としては分かる。では公正であるべき官僚は。
「上層部ほど電力業界にねじ曲げられている。退職後の天下りポストが欲しいというのもありますが、一番の理由は出世です。これは本には書きませんでしたが……」と、あるエピソードを語った。
霞が関には省庁の垣根を越えたネットワークがある。かつて、その中で知り合った人物が経産省資源エネルギー庁の電力担当の幹部になった。上司にあたる同省官房長からは「電力と酒飲んで遊んでればいいから」と言われたそうだ。だが電力業界に「従順」と思われたその知人、真面目に電力自由化をやろうとした。「その矢先、ピュッとトバされてしまったんです。もう退職なさった方ですが」
背景にはある「リスト」の存在が絡んでいた。「電力会社が役所の電力・ガス部門に来てほしい職員、そうでない職員を記したものです。『業界に冷たい』職員には印を付け、電力マネーに浸った与党政治家に渡す。政治家は経産省上層部に職員をトバすよう求めるんです」。上層部人事は事実上、政府・与党が握っているから、出世したい幹部は政治家に迎合する。「実は昨年末の衆院選で、まだ野党だった自民党のマニフェスト作成に関わった再稼働推進派の経産省幹部すらいる。今は安倍政権に非常に近い人物です。もはや役人としての一線を越えている……」。覆面作家の顔が紅潮している。
小説では、冬場の「爆弾低気圧」に覆われた北国の原発をテロリストが襲う。非常用発電機や電源車も動かせない暴風雪と酷寒の日、まさに「ホワイトアウト」状態の中、外部電源を支える送電線鉄塔を爆破して「第二の福島」を引き起こす。「今年7月に施行され『世界一厳しい』との触れ込みの新規制基準では、原発敷地内のテロ対策は盛られましたが、敷地外は手つかずのまま。その盲点を描きました」
政府が再稼働や海外輸出の錦の御旗(みはた)にしている新規制基準の「穴」はまだある。「欧州や中国で導入されている最新型原子炉は炉心溶融に備え、溶けた核燃料を冷却する『コアキャッチャー』という仕組みがある。抜本的な安全策ではないが、万が一の際にかなりの時間稼ぎができるのです。これが日本の新規制基準では無視された。電力業界や役所、原子炉メーカーも高額の費用がかかるから国民に知らせない。今や世界的に見ても日本の原発の安全性が劣るのは明らかです」
毎週末、首相官邸や霞が関で行われる脱原発デモ。彼らの声は庁舎の窓越しに若杉さんにも聞こえている。「恥ずかしながら私も福島第1の事故までは、原発があれほどの被害を出す危険な代物だとは思わなかった」。ぽつり漏らした。心情的には脱原発に共鳴する。だが霞が関の中にいるからこそ「デモをいくらやっても原発推進の流れは止められない。電力業界、役所、政治家のモンスターシステムを内部から変えない限りは」との思いが深まる。
「まだまだ驚くべき事実はたくさんあるんです。こうした情報が国民に届けば、きっと世論のうねりが起きる。私が役所に残り続け、素性を明かさないのは、情報をとり続けるためです。さらに第二、第三の『若杉冽』を世に送り出すためにもね」
若杉さんは再び街に溶け込んでいった。次回作の構想は「すでに固まりつつある」と言い残して。
==============
◇「特集ワイド」へご意見、ご感想を
t.yukan@mainichi.co.jp
ファクス03・3212・0279
国産ウナギかば焼き9トン、実は中国・台湾産 10/22/13 (読売新聞)
中国や台湾産のウナギを静岡県産や国産と偽って販売したとして、静岡県は21日、同県吉田町のウナギ養殖販売会社「大井川うなぎ販売」(藪崎周二社長)に対し、日本農林規格(JAS)法と景品表示法に基づき、表示改善を指示した。
産地を偽装したウナギはかば焼きに加工され、昨春以降、少なくとも約9トンが10都道県の卸売業者に販売されたといい、県警は21日、同社などを不正競争防止法違反(誤認惹起(じゃっき))容疑で捜索した。
県の発表によると、同社は2012年4月~13年7月、中国産や台湾産のウナギを、加工5業者(1社は廃業)とともに静岡県産かば焼きなどと偽装し、卸売業者に販売した。県は、加工4業者にもJAS法に基づく改善指示を行った。
みずほ銀行:暴力団排除の念書 融資先には要求 10/22/13 (読売新聞)
グループの信販会社を通じた暴力団員らへの融資を放置した問題を追及されているみずほ銀行が、取引先の一般企業に対しては2009年以降、融資の条件として「暴力団員に便宜供与しない」などと確約させていたことが21日分かった。融資先企業に暴力団排除を厳しく迫りながら、自らのグループによる暴力団融資に甘い対応をしていた矛盾があらわになった形。融資先企業の間ではずさんな対応に批判の声が出ている。
みずほ銀は09年4月、新たに融資を始める際に顧客と締結する「銀行取引約定書」に、反社会的勢力との関係遮断を定めた「暴力団排除条項(暴排条項)」を盛り込んだ。12年6月以降は既存の融資先にも同じ趣旨の覚書を交わすように求めている。
暴排条項は顧客やその保証人が暴力団員や暴力団関係企業、総会屋などに該当しないことを確約させる内容。みずほ銀は11年12月以降、こうした「本人確認」に加え、「暴力団員等に対して資金等を提供し、便宜を供与する」行為をしていないことの誓約も要請。違反した場合は、みずほ銀の請求で顧客らが「直ちに債務を弁済する(借金を返す)」と、融資を打ち切る方針を明記した。
融資先に厳しい誓約を迫る半面、みずほ銀自身は暴排条項を導入した翌年の10年にグループの信販会社オリエントコーポレーション(オリコ)との「提携ローン」に暴力団員向け融資が含まれていることを認識しながら、契約解消など抜本的な対応をせずに放置。問題融資は昨年9月末段階で230件、2億円超に上り、金融庁検査で指摘され、今年9月末に業務改善命令を出されるまで公表もしていなかった。
全国銀行協会は08年と11年に、融資契約に関わる暴排条項の参考例を公表。三菱東京UFJ銀行など他のメガバンクも融資契約で暴力団員らへの便宜供与がないことなど確約を求めている。ただ、その前提は「銀行自らが反社会的勢力との取引排除を徹底すること」(金融当局筋)で、みずほ銀の場合、自らはずさんな対応をしてきたことになる。みずほ銀の取引先である東京都内の人材派遣会社役員は「他人に厳しく、自分には甘くでは話にならない。銀行トップが報告を受けていながら、問題を放置していたのなら、組織ぐるみの(隠蔽(いんぺい))と言われても仕方ない」と批判する。【谷川貴史、工藤昭久】
医師・医療機関に製薬業界から4700億円提供 10/22/13 (読売新聞)
製薬業界から2012年度に国内の医師や医療機関に提供された資金の総額は4700億円を超えることがわかった。
国の医療分野の研究開発予算1700億円の2・7倍に上る。
医学研究の発展のためには産学連携が不可欠だが、高血圧治療薬「ディオバン」の研究データ改ざん問題では、背景に企業との不透明な関係が指摘された。専門家は「資金提供の透明化が必要」と指摘する。
主要な製薬企業70社で作る日本製薬工業協会の指針に基づき、10月上旬までにホームページで初めて金額を自主公表した65社分を読売新聞社が集計した。
公開された金額は、各社が大学などの研究機関や医師に支払った〈1〉共同研究などに使われる研究・開発費〈2〉寄付金などの学術研究助成費〈3〉講師謝礼や原稿料など〈4〉医師向けの講演会、説明会などの情報提供関連費〈5〉飲食や中元歳暮などの接遇費。
項目別で最も多かったのは研究・開発費で計2438億円。その4分の3は、薬の承認を得るために行う治験などの臨床試験費(1840億円)だった。
寄付金などの学術研究助成費は計532億円。うち、指定した研究者が自由に使える奨学寄付金は340億円、研究者を指定せずに大学などに提供する一般寄付金は84億円だった。ディオバン問題では、臨床研究の事実上の見返りとして、販売元のノバルティスファーマから多額の奨学寄付金が支払われていた。
問題がある企業は1つの問題が解決できても、組織の問題が大きすぎて簡単には変えれないと言う事を示しているのだと思う。
運転室の鍵も…JR北の備品、ネットへゾロゾロ 10/14/13 (NHKニュース)
JR北海道のずさんな内部管理が、また明らかになった。
「取扱注意」の内部文書が流出していたが、ほかにも駅員などの制服や腕章、在来線の列車内にある運転室などを開ける鍵などの備品が多数“流通”。鉄道ショップに、線路のポイントを切り替える特殊な鍵が持ち込まれたこともあったという。同社では再三、備品の厳正な取り扱いを社員に指導してきたが、全く行き届いていないのが現状だ。
「新品未使用」「傷みは無くきれいです」――。インターネットのオークションサイトでは、JR北海道の制服がこんなうたい文句で販売されている。他にも同社の腕章や、流出元は不明だが、在来線の列車内にある運転室などを開ける鍵などの備品が多数、出回っている。
同社では2005年、ネット上に制服の流出が確認されたことから、貸与する衣服類に関する規定を改訂。〈1〉衣服類に氏名を記入する〈2〉社員の異動、退職の際は上司が必ず衣服類を返却させる――ことを決めた。しかし、最近も駅員や車掌に貸与される制服や、腕章の出品は続いており「ネット上の写真で見る限り、本物に間違いない」(広報部)という。
文書や備品の流出が止まらない事態に、ある同社幹部は「誰かに、運転士になりすまされたら非常に怖いことだ」と話すが、有効な対策は打てていない。
特急「オホーツク」の非常ブレーキが機能しない状態だった問題では、非常ブレーキの作動に必要なコックのある機器室の鍵が、大量に出回っていたことも判明。同社では今も原因を調べているが、誰がコックを閉じたのか、まだ分かっていない。
「医院では消防の査察や業者による防火設備の点検は行っていましたが、防火扉は、消防法ではなく、建築基準法に基づく設備のため、点検は行われなかったということです。」
防火扉が機能するように物が置かれていないのか査察でチェックするのであれば、防火扉が設置された後は防火扉は消防法に含めて点検対象にするべきであろう。火災発生時には防火扉が機能しているのかが重要であると認識されているのであれば、なぜ誤解を招くような状態を何十年も放置しておいたのだろうか?行政の怠慢であることは間違いない。
今回の火災で多くの犠牲者が出るまでこの問題点を放置していた消防庁及び国土交通省は怠慢であったと強く思う。多くの犠牲者がでなくとも改善出来る点があればすみやかに行うべきであった。過去にも火事で犠牲者は出た。しかし消防署の査察で「防火扉は、消防法ではなく、建築基準法に基づく設備のため、点検は行なわれない」
との事実はテレビや新聞で取り上げられなかったと思う。
消防署は防火扉は消防法ではなく、建築基準法に基づく設備のため、点検を行わない事を査察の時に説明していればよかった。
消防庁及び国土交通省は本当に人命を考えるのであれば、防火扉が設置された後は防火扉は消防法に含めて点検対象にするなどの法律や規則の改正を行うべきだ。
防火設備に係る関係条文等 (国土交通省)
アクセスできない場合はこちらをクリック
消防法施行令 最終改正:平成二五年三月二七日政令第八八号
避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理不適 [消防法第8条第1項]
廊下、階段、避難口などの避難上必要な構造及び設備、あるいは、防火戸などの防火上必要な構造及び設備に関し、これらの構造及び設備がいついかなる時でも果たし得るよう、これらのものの保守につとめて、その機能低下阻止などを図らねばならないことを定めたものであり、その規定に違反する場合に該当します。
(東京消防庁)
防火扉 30年間点検されず 10/14/13 (NHKニュース)
福岡市博多区の整形外科医院が全焼し、入院患者など10人が死亡した火事で、作動しなかった防火扉は、過去30年間、1度も点検されていなかったことが分かりました。
規模が小さいこの医院では、防火扉の点検が義務づけられておらず、制度の問題が指摘されています。
今月11日、福岡市博多区にある「安部整形外科」で入院患者など10人が死亡した火事では、熱や煙を感知して閉まる仕組みの防火扉が作動しなかったため、火元の1階から煙が階段をとおって上の階に広がり被害が拡大したとみられています。
防火扉は定期的に点検を行っていないと正常に作動しないおそれがありますが、この医院の防火扉は、過去30年、点検が行われていなかったことが消防や点検業者への取材で分かりました。
医院では消防の査察や業者による防火設備の点検は行っていましたが、防火扉は、消防法ではなく、建築基準法に基づく設備のため、点検は行われなかったということです。
一方、建築基準法で防火扉などの点検を義務づける対象は、自治体の裁量に任されていて、福岡市では、ベッドの数が20以上の病院だけが対象で、規模の小さい診療所は対象外でした。
今回、火事が起きた整形外科医院は診療所に当たるため、防火扉は、消防法でも建築基準法でも点検が義務づけられず、一度も行われていませんでした。
福岡市のように診療所に防火扉の点検を求めていない自治体は各地にあり、防火対策に詳しい早稲田大学の長谷見雄二教授は「医療機関の防火扉という、患者の命に直結する設備の点検が、制度のはざまで放置されている現状は大きな問題で、国が主導して義務化するなど対策を急ぐべきだ」と指摘しています。
国主体で対策必要
防火対策に詳しい早稲田大学の長谷見雄二教授は「防火扉の点検は建築基準法で定められているため、消防職員が防火扉を動かす感知器まで確認することは難しいのが実態だ。自力で避難する人が難しい人たちの命がかかった問題で、国が主導して点検の質を確保すべきだ」と指摘しています。
実態調べ対策検討
建築基準法を所管する国土交通省では、昭和59年に、診療所に対しても防火扉の点検を義務づけるよう各自治体に助言していますが、実際の判断は自治体の裁量に任されています。
国土交通省は「福岡市がどのような考えで診療所を点検の対象としなかったのか分からないが、今回の火災で防火扉が機能しなかったのは事実なので、点検などの実態を調べて対策を検討していきたい」と話しています。
防火扉点検の動き広がる
制度のはざまで防火扉の点検が義務づけられていなかった診療所では、今回の火事を受けて、防火扉がきちんと作動するか確認する動きが広がっています。
福岡市中央区にある「松本整形外科」は、火事が起きた医院と同じ、入院ができる「有床診療所」で、3階建ての建物の合わせて11か所に防火扉が設置されています。
松本光司院長は、これまで年に2回、消防法に基づいて業者が行う設備点検の中で、防火扉が作動するかについても確認されていると考えていました。
ところが14日、業者から提出された点検結果を改めて確認すると、火災報知機や煙を建物の外に出す排煙設備などは点検されていましたが、建築基準法に基づく設備の防火扉は入っていませんでした。
防火扉はセンサーが煙を感知してロックが解除されても、腐食などがあると壁に収納されたまま動かないおそれがあります。
14日、松本院長がみずからロックを解除してきちんと閉まることを確認しましたが、医院では早急に正式な点検を業者に依頼することにしています。
松本院長は「防火扉も点検されていると思い込んでいたので驚いている。患者の命を守る大切な設備なので、行政は縦割りにならずに漏れなく点検が行われるような制度を作って欲しい」と話していました。
今年6月7日に博多消防署が査察を行った時には防火扉が下りるスペースに障害物が置いてあったのか?査察は抜き打ちだったのか、事前に連絡しての査察だったのか?博多消防署はスプリンクラーの設置義務はなかったから、確認のために防火扉の作動テストは行ったのか?
防火扉が設置されていても維持管理に問題があると疑う時には作動テストを要求はしないのか?「博多消防署は今年6月7日、安部整形外科を査察した。この際、防火管理者が院長の母親で70歳代と高齢者だったことが判明した。」との事実から、維持管理が出来ているのか抜き打ち作動テストが可能であれば、テストすれば良かったのではないのか?作動しなければ維持管理がずさんであることがわかり、もっと踏み込んだ指導が出来たのではないのか?
名前だけの防火管理者が院長の母親であるなら維持管理が行われているのか疑問に思わなかったのか?給料をもらって査察している以上、効率良く問題点を指摘するべきではないのか?2012年に起きた広島県福山のホテル火災では査察自体にも問題があった。
「安部整形外科」の対応に問題があったのは明らかだが、博多消防署の査察はどのように行われ、どのような処分を行って来たのか?
防火扉が設置されていても適切に作動しなければ意味がないのであれば、適切な管理及び作動テストが行われていることを確認するためにどのような事を査察中にしていたのか?新聞社は調べて記事にしてほしい。福山のケースでは死亡者が出るまで、査察の問題は公にならなかった。
博多・病院火災:甘い防火管理体制 責任者は名ばかり 10/11/13 (毎日新聞)
11日未明、10人が死亡した福岡市博多区の医院火災。博多消防署によると、「安部整形外科」には火災予防や被害拡大防止の中心となるべき「防火管理者」が適切に選任されていなかった。火災時に閉じるはずの防火扉が閉じていなかったり、初期消火が行われていなかったり、次々と不備が明らかになっている。
総務省消防庁によると、消防法8条は防火管理者の設置義務がある施設を定めており、患者と職員で定員が計30人以上の安部整形外科も対象に含まれていた。管理者は選任されれば、速やかに建物の状況に応じて避難計画や夜間の配置人数を決めて消防計画を作らなければならないという。
博多消防署は今年6月7日、安部整形外科を査察した。この際、防火管理者が院長の母親で70歳代と高齢者だったことが判明した。同消防署は11日の記者会見で「名前だけになっており変更するよう指導していた」と明らかにしたが、実際には変更届が提出されないまま火災が発生した。
防火管理者は消防主催の講習(2日間)を受けて資格を得た者が選任される仕組みで、避難訓練や夜間当直の計画を立てて推進する。2011年度末時点で、選任義務がある建物は全国で約107万件に上るが、このうち約2割は未選任だった。消防法には未選任の場合、30万円以下の罰金を科す規定がある。
消防関係者は「防火管理者の問題が今回の火災につながったかどうかは分からないが、避難経路の障害物を取り除くといった防火体制の整備や避難訓練が適切に行われていなかった可能性がある」と話す。
一方、今回の火事では防火扉が閉じずに被害が拡大した可能性が指摘されている。消防関係者は「防火扉が下りるスペースに障害物が置いてある場合か、煙や温度を感知するセンサーと防火扉をつなぐ配線に問題があった可能性がある」と指摘している。
防火管理者が不在だった火災としては、浜松市のマージャン店で従業員ら4人が死亡(09年)▽大阪府和泉市の市営住宅で幼い兄妹3人が死亡(06年)−−などがある。いずれも消防当局の立ち入り検査で改善指導を受けていたが火災が起きるまで放置していた。
【金秀蓮、関谷俊介、山本浩資、松谷譲二】
今回は10人もの人がなくなった惨事になった。しかしスプリンクラーの設置義務はなかったのだから10人が死亡したからと言って騒ぐ必要はない。
規則で決まった事さえも守られていないケースはたくさんある。結果として多くの死者が出ていないだけだ。規則を守らせる事を優先させるべきだ。
どこかで線を引いて対応しないと、感情論や結果だけでは混乱や不公平感が残る。
博多・病院火災:スプリンクラーなし 設置義務もなく 10/11/13 (毎日新聞)
高齢者が入院していた整形外科が11日未明、猛火に包まれた。福岡市博多区で患者や医院関係者10人が死亡し、多数のけが人が出た。
総務省消防庁によると、医療施設で5人以上の死者が出た大規模火災は1984年を最後に起こっていない。一方、グループホームなどの福祉施設では火災が相次いでおり、消防法も改正を繰り返して対応してきた経緯がある。
グループホームや特別養護老人ホームのスプリンクラー設置義務は、2006年の長崎県大村市のグループホーム火災を受けて消防法が改正され、延べ床面積が1000平方メートル以上から275平方メートル以上の施設に拡大された。更に10年の札幌市のグループホーム火災を受けて厚生労働省は補助対象を275平方メートル未満の施設にも広げた。
一方、医療施設については夜間の人員が多いという理由から消防法上も19床以下の医院のスプリンクラー設置義務は6000平方メートル以上、20床以上の病院でも3000平方メートル以上と、福祉施設に比べると緩やかになっている。
消防庁によると、ベッド数19床以下の安部整形外科にはスプリンクラーの設置義務はなく、実際にスプリンクラーはなかったという。だが、設置義務のない医療施設にも独自に設置を呼びかけている自治体もある。神戸市は1999年に条例で小規模の医療施設も含めて避難路を2ルート設けるかスプリンクラーを設置するように義務付けた。
防災システム研究所の山村武彦所長は「整形外科は高齢者や歩行困難の患者が多く火災になれば自力での避難が難しい。スプリンクラーは初期消火に有効であり、医療施設での設置義務も従来の面積基準だけでなく、患者の特性に応じて決め体制を強化すべきだ」と指摘している。【関谷俊介、松本光央、青木絵美】
走行中の特急乗務員室に部外者侵入…JR北海道 10/11/13 (読売新聞)
JR北海道で2009年、走行中の列車内で部外者の立ち入りが禁じられている部屋に、部外の男性が侵入する問題が起きていたことが分かった。
男性は同社に「インターネットのオークションで購入した鍵で入った」と話したという。同型の鍵で、特急列車の非常ブレーキが機能しない問題の原因となった、コックのある「機器室」への入室も可能だという。
同社によると、男性は09年7月17日、稚内発札幌行き特急「スーパー宗谷2号」1号車にある、客室乗務員の準備室に侵入した。準備室に入ろうとした客室乗務員が人の気配に気づき、男性を見つけたという。
ドラマ「日曜劇場『半沢直樹』」とダブるのが面白い。
「モラル・・・この銀行に まだモラルなんてものが存在するんですか? 私の言ってることと大和田常務の言ってること、どちらが正しくてどちらが間違ってるか少し考えれば誰にでも分かるはずです。
しかし、皆さんは、これまでずっとこのテーブルの上で黒だと思っているものを詭弁で白にすり替え続けてきた。その結果が、今の、この東京中央銀行です。 (トリ猫家族)
「半沢は京橋支店長・貝瀬を訪ね、伊勢島ホテルからの内部告発をなかったことにした書類が存在している、とコピーを提示した。
その場をなんとか取り繕った貝瀬は大和田常務(香川照之)に指示を仰ごうとするが、逆に大和田から「君が勝手にやったことだろう?」と暗黙の念を押され、観念するしかなかった。
(半沢直樹 第7話 あらすじ ネタバレ 視聴率)
『半沢直樹』のインパクトや影響が大きかっただけに子供達さえ「ドラマじゃないんだ」と言っているところがまた面白い。
金融庁、みずほへ追加の報告命令 追加行政処分の公算大 10/09/13 (SankeiBiz)
金融庁は9日、みずほ銀行が暴力団員など反社会的勢力への融資を放置した問題で、これまでの報告内容が、事実と異なっているとして、追加の報告提出を28日までにみずほ銀と持ち株会社のみずほフィナンシャルグループに求める命令を出した。行内での取引把握状況などを求める。
みずほに対して金融庁は先月27日、業務改善命令を出し、今月28日までに業務改善計画を提出するよう求めた。行政処分の直後に再び報告を求めるのは異例。追加の報告を受け、金融庁がさらに厳しい処分を出す可能性が高い。
これまでの報告では、問題となった取引情報は法令順守担当役員止まりとした。だが、8日の佐藤康博頭取の会見で、当時の頭取である西堀利氏も把握していたほか、佐藤頭取が出席した役員会などにも関係資料が提出されていることがわかった。このため改めて事実関係を確認する必要があると金融庁は判断した。
追加報告での焦点は、社内調査が不十分で、法令順守担当役員止まりと報告したのか、それとも問題が経営トップに波及しないように隠蔽を図ったかだ。組織ぐるみでの検査忌避の可能性は少ないと金融庁ではみているが、「検査に対して不十分な対応」(関係者)という見方は強まっており、追加の行政処分がでる公算が大きくなっている。
みずほに追加報告命令=暴力団融資問題で-経緯説明「事実と異なる」・金融庁 10/09/13 (時事通信)
金融庁は9日、信販会社を介した暴力団組員らへの融資問題をめぐり、みずほ銀行と親会社のみずほフィナンシャルグループ(FG)に対し銀行法に基づく報告徴求命令を出した。役職員が問題を知った時期や経緯、取締役会などへの報告内容について、改めて説明を求めた。従来の説明と異なる事実が新たに発覚したことに伴う措置で、提出期限は28日。みずほ側から報告を受けた上で、追加の行政処分が必要かどうか検討する。
金融庁は9月27日、提携先の信販会社を通じた暴力団組員らへの融資を放置したとして、みずほ銀に業務改善命令を出した。その際、金融庁はみずほ銀の申告に基づき、問題の融資に関する情報は担当役員止まりで、経営陣に伝わっていなかったと判断した。
しかし、その後のみずほ銀の内部調査で、みずほ銀とみずほFGの取締役会や社内のコンプライアンス(法令順守)委員会に11年2月以降、情報が上がっていたことなどが判明。業務改善命令の前提となった報告内容と異なっているため、みずほ銀が今月28日までに提出する業務改善計画とは別に、正確な事実関係を明らかにするよう求めた。
JR北海道の組織体質が簡単には変わらないほど酷いと言う事だろう。「7月12日まで実施した前回の検査では異常はなかったという。」が実際はどうなのだろうか。前回の検査で問題なかったものが、今回は問題がある。
「非常ブレーキに関わる部品のコックを開けておくべきところが、閉めた状態になっていた。」前回の検査で問題がなかったのであれば、誰かがコックを閉めた事になる。故意なのか、故意でないのか知らないが、調査する必要がある。個々の問題を1つ1つ解決していかないと社長や幹部が頭を下げても、改善を言葉にしても実際は変わらないと思う。
非常ブレーキ不能 JR北、特急4万8000キロ走行 人為的ミスか (1/2)
(2/2) 10/08/13 (毎日新聞)
JR北海道は7日、札幌-網走間を走行する特急オホーツクで、自動列車停止装置(ATS)が作動しても非常ブレーキが利かない状態で運行していたと発表した。調査の結果、非常ブレーキを作動させるために開いておくべきコックが閉まっていたことが原因と判明。国土交通省北海道運輸局にも報告し、作動しなかった期間などを調べる。この車両は前回検査から約4万8千キロ走行していた。
◇
JR北は、ATS以外にも、緊急時に列車を停止させる他の2つの装置が作動した場合でも非常ブレーキがかからないようになっていたことも明らかにした。ATSと同様、コックの開閉が原因か調べる。また、同様の構造を持つ他の車両19両の緊急点検を始めた。
JR北はブレーキのコックが閉まっていた理由について、「人がやらないと閉まることはない」と説明し、人為的ミスの可能性を示唆した。
JR北によると、ATSの不具合は7日の検査で発覚した。警報は鳴ったものの、同時に作動するはずの非常ブレーキがかからなかった。手動で停車させることは可能だった。7月12日の前回の検査では異常は見つからなかったという。
ATSは、列車が制限速度を超えたり、停止信号で止まらなかったりした場合、警報音などで運転士に警告を出し、自動でブレーキをかけて列車を停止させるシステム。オホーツクは函館線、石北線のほか、宗谷線の一部を走行する。
鉄道事業本部長の豊田誠常務は8日未明に札幌市の本社で記者会見し、「重大な事象を発生させ、重ねて、重ねておわび申し上げる」と謝罪した。
JR北では9月、ATS操作のミスを隠そうとした男性運転士が2カ所のスイッチをハンマーでたたいたり、蹴ったりして壊すトラブルがあった。
JR北海道:特急、非常ブレーキ利かず走行 最大90日間 10/08/13 (毎日新聞)
JR北海道は7日、札幌−網走間を走る特急「オホーツク」が自動列車停止装置(ATS)の自動非常ブレーキが利かない状態で走行していたと発表した。運転席のある車両のATSを点検したところ、非常ブレーキ関係の部品が不適切な状態になっていた。最大で約90日間、約4万8000キロを非常ブレーキ不作動のまま走っていた可能性があるといい、別の列車に衝突したり、脱線したりする恐れがあった。JR北は、他の車両のATSについても緊急点検に着手した。
ATS以外の非常停止装置二つも作動しない状態だったという。通常のブレーキで手動停車させることは可能だった。
JR北によると、同社の苗穂(なえぼ)運転所(札幌市東区)で7日午後4時半ごろ、前回の検査から90日以内に行う定期検査「交番検査」でオホーツクの車両のATSに問題があることが判明した。非常ブレーキに関わる部品のコックを開けておくべきところが、閉めた状態になっていた。緊急時に警報は鳴るものの、非常ブレーキは作動しない状態だった。7月12日まで実施した前回の検査では異常はなかったという。
JR北のATSをめぐるトラブルは相次いでおり、今年7月には千歳線上野幌−北広島間を走行中の特急「スーパーおおぞら3号」の配電盤から出火し、ATSの部品が焼損した。室蘭線鷲別(わしべつ)駅(登別市)構内では同月、赤信号を見落とした普通列車の運転士が、作動したATSの非常停止装置を解除し、無断で列車を動かしていた。9月には札幌市手稲区の札幌運転所構内で、操作ミスで非常停止した特急列車のATSのスイッチを運転士がハンマーでたたき壊した。【遠藤修平、森健太郎】
【ことば】自動列車停止装置(ATS)
列車の速度を制御し、速度超過や衝突を防ぐ装置。列車の速度や通過時刻を感知し、衝突や制限速度超過の恐れがあれば、警報を鳴らしたりブレーキを自動で作動させたりする。装置は駅やカーブの手前など線路付近と、運転席のある車両に設置され、情報をやりとりして異常を感知する。
本格調査せず、みずほ銀「痛恨、真摯に反省」 10/04/13 (読売新聞)
みずほ銀行が信販会社を通じた暴力団員らへの約2億円の融資を放置した問題で、昨年12月からの金融庁の検査で指摘を受けてからも、みずほ銀が、担当役員だったOBへの聞き取りなど本格的な調査をしていないことが分かった。
担当役員は、みずほ銀が問題を把握した2010年12月以降5人おり、そのうち4人に聞き取りをしていない。
みずほ銀は4日、問題発覚後初めて記者会見を開き、岡部俊胤副頭取が、「対応に甘さがあったのは痛恨の思いだ。真摯に反省している」と謝罪した。
みずほ銀は10年12月に担当役員が問題の融資を認識したが、2年以上にわたり放置し、グループの信販会社、オリエントコーポレーションに対して貸したお金を返すように要求したのは13年春だった。岡部副頭取は、その理由について「提携ローンという特殊性から(暴力団への融資をなくすという)認識が甘かった」と何度も強調した。
岡部副頭取は、問題となった230件、約2億円の融資は、オリコを通じた提携ローンだったことも説明した。融資はオリコが現在、回収しているが、一部は不良債権化していることを認めた。
みずほ銀では、「問題融資」などがあった場合には、頭取が委員長を務める法令順守のための専門委員会へ報告するが、今回の件は報告がなく、議題とならなかった。
岡部副頭取は、問題融資の発覚を受け、みずほ銀との取引を控える取引先企業が出ていることも明らかにした。
みずほ銀は近く、弁護士ら外部の専門家からなる「第三者委員会」を発足させる。金融庁に28日に提出する業務改善計画について、第三者委の意見を反映させる方針だ。
記者会見をしてこなかった理由については、岡部副頭取は「28日に計画を提出し、佐藤康博頭取(みずほフィナンシャルグループ社長)から説明することで責任を果たしたいと思っていた」と釈明した。
レールのデータ、社内で共有ルールなし…JR北 10/04/13 (読売新聞)
JR北海道でずさんなレールの保守管理が横行していた問題で、国土交通省は4日、同社が社内でレールのデータを共有するルールを作成していなかったことを明らかにした。
こうした管理体制の不備がレールの異常の放置を引き起こしたとして、同省は同日、野島誠社長を呼び、改善を指示した。
同省によると、レールの保守管理は、「保線管理室」など同社管内に44部署ある現場の保線部門が担当している。しかし、一部の部署では、検査担当者がレールの検査をしても補修担当者とデータを共有したり、上司が補修状況を確認したりすることを怠っていた。複数の保線管理室などを統括する「保線所」も、保線業務をチェックしておらず、本社は情報共有のあり方などについて、明確なルールを定めていなかったという。
コメ産地偽装、三重の販売会社に是正措置 10/04/13 (読売新聞)
三重県の米穀販売会社「三瀧(みたき)商事」が中国産米が混入したコメを国産米と偽るなどしていた問題で、農林水産省は4日、同社に対し、日本農林規格(JAS)法や食糧法違反などで是正措置を出した。
発覚を免れる偽装工作を行っており、悪質性が高いと判断した。
同省によると、同社では、酒やみそ、菓子などに使われる加工用米も混入していた。産地偽装や加工用米の転用は2010年10月~今年9月で約4386トンに上るとみられ、不正の分量としては過去最大級という。
これらのコメは、産地などを表示する伝票が改ざんされ、製パン大手フジパン(名古屋市)グループ2社に卸されていた。この2社が弁当などを製造し、イオングループの配送センターに納品。中部、関西、中国地方など2府21県の「イオン」「ダイエー」「マックスバリュ」などの店舗で販売されたという。
同省は警察当局と情報交換を進める方針で、不正競争防止法違反にあたる可能性があれば警察が捜査に乗り出すとみられる。林農相は4日、閣議後の記者会見で「組織的に産地や品質表示が偽装されている。悪質で遺憾だ」と述べた。
イオングループの店舗で弁当を結構買っているのですごく残念だ。イオングループは
三重県四日市市の米穀販売会社「三瀧(みたき)商事」とは今後取引をしないのだろうか、それとも時機を見て継続するのだろうか?
おにぎりで産地偽装=農水局立ち入り 10/01/13 (読売新聞)
東海農政局が、米販売の三滝商事(三重県四日市市)が国産米として販売していた米に中国産米が混じっていたとして、同社に対し日本農林規格(JAS)法に基づく立ち入り検査を実施したことが30日、分かった。
問題の米は、フジパングループ傘下のおにぎり、弁当の製造販売業者2社を通じ、東海地域を中心とした2府21県のイオンやダイエーなど、計674店舗で「国産米使用」と表示して販売されていた。
イオンによると、製造元の2社は既に三滝商事との取引を中止しているという。三滝商事の北村文伸管理部長は「ご迷惑をお掛けして申し訳ない」としている。農政局表示・規格課は「調査を行い事実を確認した上で行政処分を検討する」と話している。
イオンの「国産米」弁当、中国産米混入の疑い 10/01/13 (読売新聞)
流通大手イオングループの674店舗で、昨年12月から今年9月にかけて「国産米」として販売された弁当やおにぎりに中国産米が混入していた疑いがあるとして、農林水産省が調べていることが30日、分かった。
同省はコメを納入していた三重県四日市市の米穀販売会社「三瀧(みたき)商事」(服部洋子社長)が産地を偽装していたとみて、日本農林規格(JAS)法に基づき、立ち入り検査している。警察も情報を把握しており、不正競争防止法違反にあたる可能性があれば捜査に乗り出すとみられる。
イオン(本社・千葉市)によると、北陸、中部、関西地方など2府21県にある「イオン」「ダイエー」「マックスバリュ」などの店舗で、昨年12月2日~今年9月4日、原材料を「国産米」と表示して販売した弁当112品目とおにぎり35品目に中国産米が混入していた。イオンによると、混入した中国産米は、農水省により安全性が確認されているという。
三重の業者、中国米を国産と偽装 イオンなど弁当に使用 10/01/13 (読売新聞)
【嶋田圭一郎】流通大手イオン(本社・千葉市)が昨年12月~今年9月上旬、西日本を中心に2府21県のイオンやダイエーなど674店で「国産米使用」と表示して売った弁当やおにぎりに、多量の中国産米が混入していたことがわかった。農林水産省は、コメの販売元の三瀧(みたき)商事(三重県四日市市)が原産地を偽装したとみて、JAS法に基づく立ち入り検査を実施している。
食品の産地偽装に関しては、不正競争防止法違反容疑(誤認惹起〈じゃっき〉行為など)で、警察に摘発されるケースが全国で相次いでいる。
三瀧商事の服部(はっとり)洋子社長は朝日新聞の取材に、「このようなことが起きたことに本当に驚いている。悔やまれる」と話し、産地偽装を認めたうえで、自身の関与は否定した。
問題のコメは、製パン大手・フジパングループ本社(名古屋市)のグループ2社(日本デリカフレッシュ、日本フーズデリカ)に卸され、愛知県内と大阪府内の4工場で弁当やおにぎりに加工され、イオン側に納入された。
フジパン側2社によると、一部の工場に9月12日、農水省東海農政局(名古屋市)の検査が入ったため、三瀧商事に問い合わせた。その際、昨年12月1日~今年9月3日の9カ月間に納めたコメ825トンのうち、約4割が中国産だったと説明があったという。
産地証明書には「愛知産」と記載されていたといい、フジパン側2社は意図的に混入したものとみている。2社は「証明書を信用していた。三瀧商事とは十何年かの付き合いがあったが取引はやめた」としている。
イオンによると、フジパン側から納入された、中国産米が混入した商品は弁当112種類、おにぎり35種類。プライベートブランド「トップバリュ」商品も含まれ、計約1500万個に上るという。昨年12月2日~9月4日、北陸、中部、東海、関西、中国、四国地方の2府21県にあるイオンやダイエー、マックスバリュ、KOHYO、ザ・ビッグなどで売られた。
三瀧商事のフジパン側への説明によると、中国産米は国が主食用で輸入したミニマムアクセス米で「安全性に問題はない」という。
イオンのコーポレート・コミュニケーション部は「三瀧商事に対する法的措置も視野に対応を進める。レシートなどの購買記録があれば返金も検討する」としている。
格安航空会社(LCC)がいつも抱えるジレンマとチキンレース。どこかの格安航空会社(LCC)が大事故を起こすまで赤字覚悟か手を抜くしかないと思われる。
ジェットスター、18便欠航…目視点検実施せず 09/30/13 (読売新聞)
格安航空会社(LCC)のジェットスター・ジャパンは30日、部品の詳細な目視点検を実施していなかったとして、同日に運航予定だった成田発新千歳行きなど、計18便を欠航すると発表した。
今後も欠航が出る見込みで、通常運航のめどは立っていないという。
同社によると、初飛行から10か月以内に必要な目視点検などが行われていなかったという。29日深夜、12機中7機で点検を実施していないことが発覚。機材の不備などは見つかっていない。同社では「1日も早く平常運航できるよう努めたい」と話している。
今までこれほどの被害者が出た事故が過去になかったからどの自治体も対応してこなかったのだろう。はじめての事故(ケース)の被害者達はたいへんだ。
露店爆発事故 行き詰まる補償問題…今も20人が入院、やけど被害の深刻 (1/4)
(2/4)
(3/4)
(4/4) 09/30/13 (産経新聞)
犠牲者3人、55人の負傷者を出した福知山花火大会の露店爆発事故は、数々の目撃者や京都府警などへの取材から、当時の状況が徐々に明らかになってきた。事故を起こした露天商や主催者の責任はどう問われ、負傷者や目撃者の心のケアは−。9月13日時点で、なお3〜85歳の20人が入院を続ける大惨事だが、補償問題は早くも行き詰まりをみせ、被害者への支援が十分行き渡っているとはとても言えない深刻な状況だ。発生から1カ月を過ぎた事故を改めて検証した。
■「何でこんな目に…」
「孫のICUに入るのが嫌なんや。かわいそうで。見たらもう泣いてしまうんや。よう入らんのや…」
祖父は涙を浮かべ、こう語った。
事故当日、男子生徒は、父、母、姉の家族4人で花火大会の見物に訪れ、火元となったベビーカステラ屋台の近くに場所を取っていた。父親と姉が別の屋台へ買い物に行っている間に事故は起きた。
男子生徒は意識はあるものの、全身にやけどを負い、感染症などの危険もあるため、無菌室のICUでの治療が続いている。
母親もやけどを負って入院しており、事故後、父親は連日、病院に泊まり込みで2人に付き添っている。
一方、被害者対策は後手に回り、家族は焦燥感を募らせている。
祖父は「何でこんなにつらい目、苦しい目をみないかんのか。この鬱憤をどこではらしたらいいのか」とつぶやいた。
■一瞬で炎…「水!」
8月15日午前。京都府福知山市の由良川左岸に、場所取りのシートがあちこちに敷かれていた。対岸の右岸で打ち上げられる6千発の花火を見上げる絶好のスポットだからだ。
幅約15メートルの河川敷に露店が2列に並びはじめた。見物客50〜60人が座る10段のコンクリート段を背に、南から飲み物、肉巻き、そしてベビーカステラの露店が立つ。北側は、河川敷と堤防道路を結ぶ階段の分だけスペースがある。
天気は晴。市内の最高気温が36・7度に達した午後4時ごろには、ベビーカステラの露店裏のコンクリート段の上に、照明用の発電機とガソリン燃料の携行缶が置かれていた。
コンクリート段は見物客で埋まった。午後7時25分すぎ。ベビーカステラなど露店3軒の照明が消えた。男性店主(38)が発電機にガソリンを継ぎたそうと携行缶のふたを開ける。その瞬間、「シュー」という音とともに、炭酸飲料が吹き出したかのような勢いでガソリンが噴出した。
店主は携行缶の口を、コンクリート段の壁面や手で押さえつけようとしたが、露店の後ろに座っていた見物客に向かってガソリンは飛び散り続ける。口の向きをカステラ焼き器の方へ向けたとたん、露店が一瞬で巨大な炎に包まれた。
1回目の爆発だ。
「キャー」という悲鳴が上がり、「水!水!」と怒声が飛び交う。みるみるうちに黒煙も上がった。全身火だるまになって河川敷を転げ回る人。髪の毛が焼けて服は溶け、急斜面の土手を駆け上がる人。「痛い、痛い」と泣き叫ぶ子供。体に回った火を、うちわやタオルでたたいて消そうとする人もいる。会場は壮絶な地獄絵図と化した。
「店主とみられる男性が逃げているのを見た」という証言も複数あった。
「道を開けてください」。対岸で待機していた消防車や救急車が続々と駆けつけ、救助活動が始まった。救急車の数が足りず、堤防道路を超えた近くの旅館や薬局には負傷者が続々と運ばれ、やけどした皮膚を氷や水で冷やした。
「ボン」。数分後に消防車が駆けつけた後、発電機付近から火柱が上がった。2回目の爆発。「花火大会は中止になりました」との場内アナウンスが、女性の声で響いた。
■刑事責任どこまで
業務上過失致死傷容疑で捜査を進める京都府警は、やけどを負って入院しているベビーカステラの露店の男性店主からも回復を待って事情を聴く方針だ。店主の刑事責任を問いたい考えだが、主催者側の立件は困難とみられている。
川本哲郎・同志社大法学部教授(刑事法)は「店主が露天商として、普段から露店で火気を扱っていれば、火の危険性を認識しているはずだ」とみる。
府警によると、店主は携行缶の内圧を下げてガソリンの噴出を防ぐ「減圧ネジ」を緩めていなかった可能性が高い。この点についても、川本教授は「消防や主催者側からの指導や講習がなかったとしても、適切な取り扱いが業界内で常識だった場合は過失と認定できる」と指摘する。
また、店主が仮にガソリンの噴出は予測していなかったとしても、「噴出したガソリンをカステラ焼き器の火に向ければ、引火と爆発につながると分かっていたはず。行動自体が過失に当たる」と捜査関係者は指摘する。
ただ、店主は全治3〜6カ月と診断されており、捜査の長期化は避けられない見通しだ。
一方、主催者側や露店の申請などを取りまとめる露店組合側に監督過失があったかどうかは、防火指導や注意喚起をどこまで行っていたかがポイントになる。
ただ、川本教授は「露天商がガソリンや携行缶の危険性を認識しているはずとして、講習などを行わないのは自然」と指摘。「適切に取り扱われると信頼するのが相当と認められる場合、刑事責任を問うのは難しい」とみている。
捜査関係者も、主催者側の刑事責任については「業務上過失致死傷容疑を視野には入れているが、刑事責任を問うのは難しいのではないか」としている。
■安全管理“丸投げ”
では、補償を含め、主催者側の責任はどこまで問われるのか。
花火大会を主管する福知山商工会議所の谷村紘一会頭は事故翌日の会見で「責任はあくまで露天商にあり、第一に露天商がおわびすべきだ」と指摘。主催者側には「包括的、道義的責任がある」と述べるにとどめた。だが、露店の安全管理を露天商側へほぼ「丸投げ」していた実態が明らかになっている。
露天商で組織する京都宮津神農協同組合の代表者は8月6〜8日、河川敷に出店した170店を含む全355店分の申請書を商工会議所に提出。大会2日前の13日、全店に許可が出た。
主催者側が接点をもった露天商は、この組合代表者だけ。火気使用について、主催者側は「十分気をつけるよう口頭で注意した」と強調したが、大会当日に出店していた露天商の男性(50)は「指導は受けていない」と証言する。
出店申請書のチェックもずさんだった。事故を起こしたベビーカステラ店の男性店主は、申請書の販売品目に「たこ」と記入。女性アルバイトがいたのに、営業補助者の氏名や連絡先を空欄にして提出していた。
主催者側は、申請内容と営業実態が異なれば出店を許可しない場合があると決めていたが、現場の確認をしていなかった。
河川法にも抵触していた可能性が高い。主催者側は8月7日、国土交通省から河川敷の占用許可を得る際、露店数を「100店」と申請。実態が70店多いと把握してからも修正せず、12日に許可を受けていた。
主催者側にとって、民事上の「賠償責任」がどこまで問われるかも今後の焦点となるが、現在検討されているのは、保険金を使った被害者への「補償」だ。
加入する賠償責任保険の支払い枠は総額10億円で、1人当たり5千万円。保険会社と協議しているが、業界関係者は「保険が適用されるには、主催者側の落ち度が大きいとみなされる必要がある」と指摘する。
主催者側は「事故対策本部」を設け、8月24日に死亡者と負傷者へ見舞金3万〜5万円の支払いを決めたが、保険会社との協議が長引く中、補償問題は早くも行き詰まりを見せている。
負傷者やその家族からは当面の治療費や生活費に関してさえ、不安の声が上がっている。
暴力団員らへの融資放置、みずほ銀行頭取が謝罪 09/30/13 (読売新聞)
みずほ銀行が、信販会社を通じた暴力団員らへの約2億円の融資を放置し、金融庁から業務改善命令を受けた問題で、同行の佐藤康博頭取は29日夜、記者団に対し、「今回の件は大変遺憾で、心からおわび申し上げたい」と陳謝した。
今回の問題に関する処分について佐藤氏は、「厳正な処置をしていきたい。過去(の法令順守の担当役員)にまでさかのぼって考える。私に責任がないというつもりはまったくない」とした。
問題点を検証し、業務の改善策を検討するため、頭取自身を委員長とする専門の社内委員会を発足させたことも明らかにした。
ただ、230件にのぼる問題の取引に関して、佐藤氏は「暴力団との癒着や特別な関係はない」としただけで、取引の詳細については明らかにしなかった。みずほ銀はこれまで、正式に記者会見を開いて、この問題を具体的に説明していない。
バルサルタン:厚労省、製薬会社調査へ 誇大広告の疑い 09/26/13 (毎日新聞)
降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験疑惑で、厚生労働省はデータが操作された試験論文を宣伝に使ったのは誇大広告を禁じた薬事法に違反する疑いがあるとして、同法に基づき製薬会社ノバルティスファーマ(東京都港区)に対する調査に乗り出す方針を固めた。同社関係者から事情を聴き、必要があれば立ち入り検査も実施する。データ操作の故意性や、ノ社社員らの関与の有無が焦点になる。30日に開かれる同省の検討委員会の中間報告を待って本格的な調査に乗り出す。
薬事法は、医薬品を多くの人に使用させるために、意図的に虚偽や誇大な表現を使った広告を出すことを禁じている。違反した場合は2年以下の懲役か200万円以下の罰金が科せられる。製薬会社には製造販売許可の取り消しや業務停止などの行政処分もある。
バルサルタンについては、東京慈恵会医大や京都府立医大など5大学が臨床試験を実施。慈恵医大と府立医大の論文はバルサルタンに脳卒中などを減らす効果があるという内容で試験規模も大きく、ノ社の宣伝に使われた。両大学は今年7月、「解析データが操作されていた」と発表。ノ社の社員(5月に退職)が肩書を伏せてデータ解析に関与したことを明らかにした。
ノ社は「社員がデータを操作した証拠はない」と関与を否定している。だが、厚労省は誤った論文が宣伝に使われた点を重視。ノ社社員や幹部らが売り上げを伸ばすことを目的にデータ操作に関与していなかったかどうか解明する必要があると判断した。【桐野耕一】
「同社は、今後の給与や賞与などから支給分をカットするなどして年収総額は変わらないようにするとしている。」
事実とすれば受取る月給額が減っていないと嘘になる。
東北電力:「賞与なし」一転、臨時給与 社外口外禁じる 09/25/13 (毎日新聞)
東北電力が電気料金値上げの前提となる経費削減策の一つとして実施した夏の賞与(ボーナス)不支給に関し、社員らに「住宅ローン等支援措置」として「臨時給与」を支給し、社員には「社外へは口外しない」ことを求めていたことが25日、分かった。同社は「年収の一部を前倒しして支給したもので賞与ではない」と説明しているが、「賞与支給と誤解を招く」として公表もしていなかった。
同社は今年2月、経済産業相に電気料金値上げを申請して認可を受け、今月から家庭向けを8.94%値上げ。4月には夏の賞与不支給を公表していた。
同社によると、支給は、今年6月21日と9月20日の2回。住宅などのローンを抱える社員らのためで、支給総額は計約50億円だった。
9月9日付で社内周知用に幹部に配布した文書によると、9月の支給額は社員の場合は基準労働賃金の半分という。
同社は、今後の給与や賞与などから支給分をカットするなどして年収総額は変わらないようにするとしている。
文書では、一般社員には口頭で周知するとし、社外(当社OBも含む)に口外しない▽インターネットへの投稿・書き込みも絶対に行わない▽従業員同士で社外で本措置の会話は慎む▽家族にも、社外で絶対に話題としないよう徹底する−−などと書かれている。
公表しなかったことについて同社は「賞与を支給するという誤解を招く恐れがあった」と説明している。【金森崇之】
明確な基準が必要だ。曖昧だと、問題の解決にならない。
シェアハウス:8割が不適合 「寄宿舎」基準、業界懸念 (1/2)
(2/2) 09/25/13 (毎日新聞)
他人同士が一つの家に集まって住む「シェアハウス」のうち約8割の2000棟以上が、国などの基準で「不適合」とされる可能性が高いことが分かった。狭く危険な「脱法ハウス」の問題に取り組む国土交通省が今月、シェアハウスを含む複数人の居住施設の事実上の規制に乗り出したためで、部分的な改修で対応できない物件も多数に上るとみられる。業界には「安全に配慮した普通のハウスまで排除するのか」「廃業が続出しかねない」と懸念が広がっている。
同省は今月6日、「事業者が入居者を募集し、自ら管理する建物に複数人を住まわせるケース」は「建築基準法上の『寄宿舎』の基準を適用する」と全国の自治体などに通知。学校や会社の寮などが該当する「寄宿舎」の基準を当てはめれば、各室に窓を取り付けることはもちろん、一般住宅や事務所より防火性能の高い間仕切り壁を設けることなどが求められる。
業界団体「日本シェアハウス・ゲストハウス連盟」の今年6〜9月の調べでは、全国に約500のシェアハウス運営業者が存在し、約2500棟(うち8割が東京都内)を運営。このうち2000棟以上が戸建て住宅を再利用したもので、ほとんどが「不適合」となる可能性が高い。残りの一部は寄宿舎扱いだが、大半は事務所やマンションの一室を改修したケースで、多数が法令違反となる可能性がある。
また、都は独自の条例で、寄宿舎もマンションなどと同様、火災時に各室の窓から下りて避難できるよう敷地内に数メートル幅の空き地を設けることを義務付ける。しかし、都心部の住宅は隣家と密接して建っていることが多く、空き地がなければ建て替えが必要になる。
ある業者は「壁を改修するにもいったん退去してもらわなければならず、再開時は賃料も上げざるを得ない。まして、全面建て替えは現実的でない」と話した。連盟幹部は「大規模物件はまだしも、数部屋しかないシェアハウスを寄宿舎に当てはめるのが適当なのか。今後、国交省と話し合っていきたい」としている。
同省建築安全調査室は、「都条例についてコメントする立場にない」とした上で「業界をつぶすつもりはないが、適法な範囲でやっていただくのが望ましい。基準が明示された方が運営しやすいとの声は、業者側からも出ていた」と説明している。【加藤隆寛】
◇ことば【シェアハウス】
親族以外がキッチンやトイレなどを共用して暮らす住居。住人は個々に運営業者と契約し、個室や相部屋内のベッドを専有して住むのが基本。法律上の明確な定義はなく、業者を通さずに一部の部屋を貸したり、友人同士でルームシェアするケースとの線引きは難しい。敷金・礼金など初期費用負担が軽く、連帯保証人が要らない手軽さも受けて、専門ポータルサイト業者によると、2007年末には約400軒7000床だったが、年々増加。新たなライフスタイルとして若者らの人気を集める一方、悪質業者による「脱法ハウス」が社会問題化した。
「豊田本部長は現場の保線担当者らが『基準を知らなかった』『研修をやっていたが、覚えていなかった』と釈明している」
どこまで真実を言っているのか知らないが、そのような事しか言えないのであろう。しかしそのような発言をすると言う事は、
教育や検査の判断基準の徹底を怠っていた事をJR北海道が認めたと言う事だと判断できる。つまり全ての点検マニュアル及び整備マニュアルを見直さないとどこに問題があるのかさえも判断できない状態と言っているようなものである。徹底的なチェックに半年以上かかるのではないかと思う。点検用紙、記録の管理方法、責任者による二重チェックがあるのか、担当者の責任は明確になっているのか、報告を受ける者は誰になっているのか、これらの点だけでも、問題が放置できないシステムになる。こんな単純なシステムさえ機能していないとなると、JR北海道の体質的な問題やマニュアルの信頼性がない事が明らかだと思う。
JR北海道:「教育体制に問題」 訂正、陳謝重ね 09/25/13 (毎日新聞)
JR北海道のレール異常放置問題は、発覚から3日余りで放置箇所が当初の9カ所から267カ所に急増。24日夕に記者会見したばかりの豊田誠・常務鉄道事業本部長は25日朝、再び会見を開き、新たな170カ所の放置を謝罪し、初めて列車の運行に支障が生じる事態にも発展した。【久野華代、山下智恵、遠藤修平】
「データを計算する知識が十分ではなかった。教育体制の問題」。午前8時から緊急記者会見を開いた豊田本部長は、うつむき加減に繰り返した。
報道陣からは、旧国鉄時代の1985年に変わったルールが適用されず、誤った保線作業が続けられていた可能性があることについて質問が集中。豊田本部長は現場の保線担当者らが「基準を知らなかった」「研修をやっていたが、覚えていなかった」と釈明していることを明かし「信頼を損ねる事態。全国で鉄道事業を営む皆さんにもご迷惑をおかけした」と陳謝した。
度重なる調査結果の訂正については「精いっぱい確信を持って出すが『絶対間違いがないか』と言われると、絶対ということはない。会社として万全を期してあげた数字という認識だ」と弱気な表現だった。
JRは24日夜から、170カ所に及ぶ補修作業を夜を徹して進めた。列車の運行見合わせを発表したのは同日午後11時半。広報部が「詳細な情報が入っていない」と繰り返す中、25日未明から続々と札幌市中央区の本社に報道関係者が集まった。2階会議室では工務部の担当者がホワイトボードに数字を書き込みながらレールの異常を見逃した経緯を説明。「技術を担う部門として本当に恥ずかしい初歩的なミス」などと釈明に追われた。
福島原発事故に次ぐほどの問題ではないのか。原発の検査や規則も福島原発事故までスポットライトが当たる事はなかった。
「レール誤検査 28年間継続」疑惑も今回までスポットライトが当たらなかった。しかし運が良かったのか大惨事は起こらなかった。
これからどうするのか?国の役人だと今後基準を必要以上に厳しくする可能性がある。本当は最低限度の基準は絶対に守らせるべきなのだろうけど、コストを考える必要などないお役人は基準を上げることにより安全性確保を宣言するのだろう。今後、どのような情報が出てくるのか見守るしかない。
JR北海道:レール誤検査 28年間継続か 09/25/13 (毎日新聞)
◇新たな異常170カ所を発表
JR北海道が多数の線路異常を補修せず放置していた問題で、新たに7路線170カ所の線路異常が見つかり、同社は25日、民営化以前の旧国鉄時代から28年間、間違った基準で検査を続けていた可能性があることを明らかにした。異常放置はこれまでに97カ所が判明しており、計267カ所に増えた。一方、国土交通省は同日、特別保安監査(立ち入り検査)を20人態勢に増強。野島誠社長らから事情を聴くとともに、監査対象も本社と函館支社にとどめず、旭川と釧路両支社を含む全社に拡大する。
札幌市中央区の本社で記者会見した豊田誠・常務鉄道事業本部長は「度重なる報告変更で信頼を裏切る事態となり、大変申し訳ない」と陳謝した。
JR北海道は24日夜から25日朝にかけ、新たに見つかった線路異常の補修作業を実施。これに伴い特急スーパー宗谷2本を含む計16本が運休し、約660人に影響が出た。一連の異常放置発覚後、補修作業のため実際に列車の運行に支障が出たのは初めて。
同社によると、新たに異常放置が発覚した7路線は宗谷線▽江差線▽札沼線▽函館線▽釧網線▽富良野線▽留萌線。23日夜、国交省鉄道局に線路の異常放置箇所や補修実績を報告したが、24日午後3時ごろ宗谷線の担当者から検査記録に疑問があるとの連絡があり、間違った基準を適用して検査していたことが判明。全路線で記録を再調査したところ、170カ所で同様のミスが見つかった。
170カ所のレールは、いずれも機関車など大型車両の運行に対応するためレール幅の規格が現在より5ミリ広い旧型。旧国鉄時代の1985年から適用されている現在の検査基準では、旧型レールに対しては基準値を新型レールより5ミリ小さく計算しなければならない。しかし、複数の保線部署で旧型のレールに対しても新型レールの基準を適用していたため、現在の基準に比べて最大で3ミリ幅が広がった状態で放置されていた。
豊田本部長は「(85年からの)新基準が保線作業員に理解されず、勘違いが起きた」と説明。部署によっては「そんな考え方があるとは知らなかった」と言う保線担当者もいたという。【遠藤修平、山下智恵】
「JRによると、レールの異常が確認された97か所の緊急点検の報告書を国交省に提出後、あらためて社内でチェックを行ったところ、曲線部のレール基準について、旧国鉄時代の基準を使わなければならないのを忘れ、誤ってJRの基準をそのまま使っていたという。」
JR北海道は今回の件で上手い言い訳が思いつかなくてとうとうこのような理由を報告したのか。これが事実とすると国土交通省はJR北海道の全てのマニュアルに目を通さなくては特別保安監査を終了したとは言い難いだろう。レールの確認基準の徹底も出来ていない、徹底できていないのだからマニュアルも作成されていないはずと言う事になる。このような問題のあるマニュアルやガイドラインでこれまでJR北海道が運行していたとなると、今回に徹底した監査を行わないと今後も問題が発生する可能性を否定できない。別の問題が起こる可能性がある。
例え国土交通省が厳しい処分を出したとしても、新たなマニュアル、上層部の意識改革、現場がマニュアルを理解して実行する事、新たなマニュアルを実行する事によるコストアップなどを考えると簡単にはJR北海道は変わらないだろう。問題を多く抱えた来た組織で改革を行わずに過ごしてきた管理職に何を期待できるのか?国交省から言われた事を実行するのが限界だろう。もしかするとそれさえも出来ないかもしれない。
JR北海道だけの問題だけでなく、コストを抑えて最低限の安全を守れない企業はたくさんあると思う。オリンピックに浮かれ、消費税アップするから防衛費アップしたり、他の無駄遣いを計画しているお役人達は効率的なお金の使い方を考えなければならない。お金をかければ安全率アップは当たり前。東電のようにコストアップ=料金アップ出来ないから多くの企業は知恵を絞ったり、試行錯誤しているのだと思う。
これまで保安監査を行って来た国土交通省、なぜこれまでこのような単純な問題を指摘できなかったのか?監査の意味がない!
JR北海道の一連の事故は「過疎化し衰退する地方」の一里塚 09/25/13 (やまもといちろうBLOG)
レール異常、新たに170か所 JR北海道 09/25/13 (日テレNEWS24)
JR北海道がレールの異常を知りながら放置していたことが明らかになった問題で、社内規定を超えて補修していなかった放置箇所が新たに170か所近くあることがわかった。
JRによると、レールの異常が確認された97か所の緊急点検の報告書を国交省に提出後、あらためて社内でチェックを行ったところ、曲線部のレール基準について、旧国鉄時代の基準を使わなければならないのを忘れ、誤ってJRの基準をそのまま使っていたという。
このため、旧国鉄時代の基準であらためてチェックしたところ、函館線など新たに約170か所で基準値を超え、レールの異常はこれまでの97か所から約270か所へと大幅に増えた。
JRは、新たに見つかった約170か所の緊急補修作業を24日夜から行っているが、その影響で、これまでに特急列車1本を含む5本が運休した他、25日朝もすでに普通列車6本の運休が決まっている。
クローズアップ2013:JR北、異常放置 特異な企業体質、背景 補助金漬け、責任あいまい 採用抑制、中核世代少なく (1/3)
(2/3)
(3/3) 09/25/13 (毎日新聞 東京朝刊)
JR北海道がレール幅の拡大など多数の異常を放置した問題では、その後も次々と検査体制や記録の不備が発覚している。79人が負傷した石勝(せきしょう)線の特急脱線炎上事故(2011年5月)以降トラブルが絶えず、「安全軽視」と言える企業体質がなぜ生じたのか。その背景を探る。【遠藤修平、久野華代、伊藤直孝、松谷譲二】
「道外から訪れる多くの方々の信頼も大きく損なう危機的な事態だ」。北海道の高橋はるみ知事は24日、開会中の道議会本会議で、JR北海道がレール異常を放置していた問題に言及し、再発防止策は「外部の視点」を踏まえるべきだとの認識を示した。菅義偉官房長官は同日午前の記者会見で「事故が頻繁で、(異常が)分かって対処しないのは悪質性がある。組織、体質的な問題もあるのではないか」と批判した。
旧国鉄が旅客6社・貨物1社に分割・民営化されたのは1987年。このうちJR北海道は他社に比べ過疎地域を走る路線が多く、除雪などに膨大な経費がかかり、経営基盤は弱い。このため、国は経営安定基金という「持参金」をもたせ、その運用益で赤字を穴埋めしてきた。
ただ、その基金も近年の金利低下の影響を受け運用益が減少。一時は上場も目指したが果たせず、厳しい経営が続いていた。鉄道事業収入は96年度の800億円をピークに減少している。基金投入という第三セクター的な経営に慣れきって、責任の所在があいまいになっていると指摘する関係者もいる。ほぼ同じ営業キロ数のJR九州は営業黒字(2012年度末現在)を確保しており対照的だ。
赤字経営は人材確保にも影響し、1980年代に採用を大幅に抑制。5月現在で社員約7000人のうち最も多い50代は37・7%。次いで民営化後に入社した20代が27・4%。現場の責任者になるべき40代は9・5%と極端に少ない状況が続いている。国土交通省関係者は「ベテランの職員がどんどん定年退職している。その一方で、採用すべき若手の人員は経営難で抑えているので、技術が伝承されにくい」とJR北海道の人材育成が行き届いていない現状を指摘する。
だが、「いびつな年齢構成は北海道に限った話ではない。事故多発は別に固有の問題があるのではないか」(JR他社の幹部)との声もあり、「なぜ異常が放置されたのか」の答えはまだ見えてこない。JR北海道の豊田誠・鉄道事業本部長は24日の記者会見で、この問いに「いまだにお話しできるところまで状況がつかめていない」と述べることしかできなかった。
2016年春には北海道新幹線・新青森−新函館(仮称)間が開業予定だが、安全管理体制への信頼は完全に失われた。JR北海道はこれまで、高速道路や航空会社との旅客争奪戦に勝ち抜くため高速化も進め、札幌と道内主要都市を結ぶ路線に新型車両を導入。最高時速は国鉄時代の100キロ程度から110〜130キロに伸ばした。
しかし、国交省関係者は「このままではとてもまかせられない。これだけメンテナンスがいいかげんなのだから、開業なんてムリな話だ」と頭を抱える。
◇車両重く、保守にコスト
鉄道のレールは列車の重量や振動、遠心力により横に広がったりするため、各鉄道事業者は整備基準値を定めている。JR北海道の場合、レール幅が規格(1067ミリ)に比べて直線で14ミリ、曲線で19ミリを超えて広がった場合、15日以内に補修するよう内規で定めている。旧国鉄時代の基準を踏襲したもので、JR各社にほぼ共通する内容だ。
大都市圏の在来線の場合、コンクリート製の枕木にレールが固定されている。一方で、特急の走行路線を除くJR北海道の一部の路線には、盛り土に木製の枕木を並べ、クギでレールを固定しているだけの区間もある。JR北は脱線の危険が生まれる基準超過は理論上「43ミリ」としているが、「木製はコンクリート製に比べてゆがみが生じやすく、20ミリ超で脱線のおそれがある」との指摘もある。
また、JR北が使っているディーゼル車の中には、電化された路線を走るJR各社の最新車両に比べ重量が3倍以上のものもあり、レールや枕木が傷みやすいため、大都市部に比べてメンテナンス費用がかかるという。
だが、ある関係者は「JR北海道は民営化後も安全軽視の企業風土の下、レールや枕木の老朽化を長年放置し、メンテナンスに十分な費用を充ててこなかった」といい、「北海道内唯一の鉄道会社であるため、過信、慢心があったことは否定できない」と批判する。そのうえで「問題があるのに見て見ぬふりをし、JR側に全て任せきりにしてきた国の責任も重い」と指摘した。
==============
◇鉄道事業者に対する過去の事業改善命令
01年 7月 福井県内で2回にわたって起きた列車正面衝突事故で、施設保守などの安全管理が適切になされていないとして、京福電鉄(京都市)に自動列車停止装置(ATS)の緊急整備などを命令
03年12月 JR中央線や京浜東北線でトラブルが相次ぎ、「工事や安全上の管理体制がずさん。重大な事故につながる恐れもある」として、JR東日本に改善措置を命令
04年 8月 山陽新幹線などのトンネルや橋の検査記録を改ざんする虚偽記載などが発覚。JR西日本に定期検査の管理体制改善や法令順守の徹底を命令
06年11月 銚子電鉄(千葉県)で、列車が通過中に踏切の遮断機が上がり始めたり、線路の枕木の腐食などが相次いで見つかり、修繕の早期実施などを命令
08年 2月 長崎県南島原市の踏切事故で、故障した踏切の制御装置を約1年間修理していなかった上、装置を遮断する改造などをしていたため、島原鉄道に改善を命令
11年 6月 79人が負傷したJR石勝線の特急脱線炎上事故で、異常時の避難誘導マニュアルが複数あったため、整合性が取れるように見直すことなどをJR北海道に命令
新たに170カ所判明、計267カ所に 国交省、社長ら経営陣聴取へ 09/25/13 (産経新聞)
JR北海道がレール異常を補修せず放置していた問題で、JR北海道は25日、新たに170カ所のレール異常の放置をしていたことを明らかにした。異常放置は97カ所で判明しており、計267カ所に膨らんだ。国土交通省は、野島誠社長ら経営陣への聴取も含めた社内体質の本格調査に乗り出す方針を固めた。特別保安監査の態勢も倍増強化し、対象も全支社に拡大。また問題を見抜けなかった同省内部の指導体制も検証する。
菅義偉官房長官は24日の記者会見で、「(異常を)分かって対処していないのは極めて悪質性がある。組織、体質的な問題もあるのではないかとの観点で監査すべきだ」と述べた。
国交省によると、鉄道の運行部門は、電気、車両、土木、運転の4つに分かれている。
今回の特別保安監査は、JR北が9カ所でレール異常を確認していながら放置していたとして、土木部門に対し、21日から実施された。
本社や札幌保線管理室に入り、保線担当者らへの聴取やパソコン内の管理記録などを確認した。
だが、異常放置が計97カ所に増加。国交省は「土木の他の部門でも法令違反がある恐れがある」とし、電気や車両、運転の分野に範囲を広げ、25日からは監査員を9人から20人に強化して本格調査に乗り出す。
これまで本社と函館支社に限っていた監査対象も25日から、旭川、釧路の両支社を加えた全支社に拡大するという。
またJR北は、レールの補修について運行本数の多い箇所を優先したなどと説明しており、国交省はどの部分に優先的に予算を配分していたのかにも注目。野島社長ら経営陣らへの聴取も検討する。聴取には主任監査員があたる予定。
一方で、JR北をめぐっては、昨年来、整備不良などによる特急列車の発煙・出火が多発。無断発車などのトラブルが絶えない。国交省や北海道運輸局は再三指導しながら、ずさんな管理を見抜けなかった。
国交省幹部は「JR北は坂道を転がる没落ぶりだ。基本さえできていなかったのは予想外だが、われわれも発見の機会はあったはずだ」と話しており、内部の指導体制も検証する。
「あいた口がふさがらない」国交省、根本的改善を指摘 09/24/13 (産経新聞)
貨物列車脱線事故の過程で発覚したJR北海道のずさんな安全管理体制。点検で補修の必要性を認識していながら、長期間放置された結果、事故を招いたとみられる。放置は97カ所にのぼり、国土交通省は23日、事業改善命令を出す方針を固めた。「あり得ない」「裏切られた」。同省幹部は口をそろえる。
国土交通省鉄道局には23日も幹部らが朝から顔をそろえ、対応の協議を続けた。幹部は「常識では考えられない。開いた口がふさがらない」と話す。
異常が見つかったレール幅は、鉄道会社ごとに基準が設けられている。ただ補修の基準よりも厳しい目標を設け、それを超えると即補修する社もある。幹部は「それだけ神経を使うのに長期間放置するという考えが働いたこと自体が理解できない」と話す。
JR北の放置理由にも疑問を投げかける。同社は主に列車のすれ違いなどに使う副本線で放置が目立ち、本線を優先しているうちに後回しになったと弁解。ただ、数日で全ての補修は終了している。別の幹部は「真剣に安全に向き合っていれば補修は可能。社の姿勢に疑問を持たざるを得ない」とする。
国交省は事故の原因分析や安全対策推進のため、JR東日本に協力を求めるようJR北に指導し、両社を仲介した経緯がある。幹部は「これだけJR北の信頼回復に知恵と力を注いできたのに裏切られた気持ち。今回はこれまでとは状況が異なる。根本的な体質に問題があり、小手先だけの改善・改革では済まされない」と語気を強めている。
個人的な推測だが、JR北海道が儲かっていない事と会社の体質も問題であると思う。儲かっていないから安全に関する項目でもお金を掛けたくない。
最低限の費用でなんとかやっていこうとする努力よりも、小手先のごまかしや不都合な事は触れない何とかしようとする体質が上層部にあったのではないのか?
現場は点検やチェックする事が仕事だから一応、仕事はする。報告しても補修の指示がないから現場はそのうちに情報を報告しても無駄だし、報告するだけ時間の無駄だし、仕事が増えるだけなので報告しなくなったのではないのか?管理の上層部は補修を行わなくても問題がないと判断して、補修を延ばす、又は、放置する事が普通になったのではないのか?そして放置する事が異常ではなくなったが、放置による事故が発生しない為に組織の中で放置することに対して危機感がなくなったと思う。
北海道七飯町のJR函館線大沼駅で19日に起きた貨物列車の脱線事故の原因が現場の線路の幅が基準よりも広がっていて補修が必要だったのに、JR北海道が1年前から放置と判明したので組織として適切な説明ができなくなったのではないのか?
人が死んでいないので組織ぐるみで隠す事はないと思うが例え国土交通省から厳しい処分を受けてもそう簡単に組織の体質など変えられないだろう。
レール幅拡大、1年放置...JR北海道 09/22/13 (読売新聞)
北海道七飯町のJR函館線大沼駅で19日に起きた貨物列車(18両編成)の脱線事故で、現場の線路の幅が基準よりも広がっていて補修が必要だったのに、JR北海道が1年前から放置していたことがわかった。国の運輸安全委員会は、線路幅の広がりが事故原因となった可能性があるとみて詳しく調べる。
JR北海道によると、線路幅は本来1067ミリだが、昨年10月の検査では20ミリ上回る1087ミリで、今年6月には25ミリ上回る1092ミリだった。列車が走行すると線路には横に広がろうとする力がかかり、広がり過ぎると脱線などの恐れが生じるため、同社の内規では19ミリ以上拡大した場合、15日以内に補修しなければならない。だが、同社はこれを放置していた。
この問題を受けて、同社が道内の線路の計測データを確認したところ、5~7月の検査で基準値を上回る場所がほかに8か所あった。脱線現場を上回る28ミリの広がりを確認した地点もあったという。いずれも補修は行われていなかったが、同社は問題発覚後の20、21の両日に急きょ実施した。
線路幅に関する情報は、現場の保線所や工務所などにとどまり、本社工務部には報告されていなかったという。同社は、社内報告態勢の見直しを検討するとともに、補修を放置した経緯について調べる。
同社の笠島雅之工務部長は「線路幅の管理不備が脱線につながった可能性は否定できない。放置していた原因は分かっておらず、大変申し訳ない」と謝罪した。
格安航空会社(LCC)の宿命。飛行機はエンジンが止まる事は墜落を意味するから他の乗り物よりも危険だと思う!
上空待機ジェットスター機、燃料不足で緊急着陸 09/13/13 (読売新聞)
18日午後6時39分頃、上空待機していた成田発福岡行きのジェットスター・ジャパン139便(エアバス320型機、乗客乗員174人)が、「燃料不足のため着陸したい」と福岡空港管制塔に連絡し、同56分頃、緊急着陸した。けが人はなかった。
同社は「管制塔から『滑走路に鳥がいる』と連絡があり待機していたところ、燃料が規定の分量を下回る可能性があったため緊急着陸を要請した」と説明。規定では余分に30分間以上飛行できる燃料を積んでおかなければならないという。同機は結局、燃料切れにはならなかった。
同社は日本航空系の格安航空会社(LCC)で、2012年7月に就航した。
フタバ産業:元専務「カネは仲介人に渡した」と虚偽説明 09/13/13 (毎日新聞)
自動車部品メーカー「フタバ産業」(愛知県岡崎市)の中国の子会社を巡る贈賄事件で、不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)容疑で逮捕された同社元専務、寺田武久容疑者(68)が2008年に社内で贈賄疑惑を追及された際、「税関当局に顔が利く仲介人に金を渡したが、公務員には渡しておらず、贈賄にはあたらない」との趣旨の説明をしていたことが、捜査関係者への取材で分かった。愛知県警捜査2課は、社内調査で虚偽の説明をして不正発覚を免れようとしたとみている。【石山絵歩、川崎桂吾】
逮捕容疑は、07年12月、子会社に対する税関の処分を軽くしてもらうため、広東省内の地方政府の幹部に対し、3万香港ドル(約45万円)などを渡したとしている。
同社が関連する民事訴訟の資料によると、同社の監査法人は08年10月ごろ、寺田容疑者がトップを務めていた子会社について、「3700万円に上る不適切な支出がある」と問題視。同社監査役が中国の税関関係者らに対する賄賂だった可能性を指摘していた。
回答を求められた当時の社長は同11月の文書で、中国の税関から違反を指摘され、問題解決のための支出だったと説明。不適切な会計処理を認めたものの、税関幹部ら公務員への賄賂だったことを否定した。社長の説明は、寺田容疑者からの聞き取りを基にしていたという。
寺田容疑者は捜査2課の調べに対し、02年以降、税関や地方政府の幹部に16回にわたって総額で5000万円超の賄賂を渡していたことを認めている。一部については「仲介人に渡したこともあった」と供述している。
同社は社員行動憲章で「国内外を問わず、公務員に対する贈賄は厳しく罰せられる」と定めているが、社内で不正融資問題が発覚したため、贈賄疑惑の調査はされなかった。
当時の社長は12日、毎日新聞の取材に「(贈賄事件は)寺田容疑者が自分で判断したことだと思う」と話した。
◇
県警は13日、寺田容疑者を名古屋地検に送検した。
消費者の多くの女性がカネボウの体質を許すのか、許さないのか、それだけの事だと思う。
組織の体質は簡単には変わらない。組織の中で教育され、人生の50%以上の時間を会社で過ごしてきた幹部や社員達が簡単に変われるのか?
もし幹部や社員達がブレーキとして機能できる企業体質であればここまで問題は放置されてこなかった。
今後は消費者の判断次第だろう!
カネボウ:「白斑」対応遅れ指摘 外部調査報告書 (1/2)
(2/2) 09/04/13 (毎日新聞)
カネボウ化粧品は11日、美白化粧品で肌がまだらに白くなる「白斑」被害が出ている問題について、外部弁護士による第三者調査報告書を公表した。報告書は、2012年9月に医師が白斑と化粧品の因果関係の疑いを指摘した時点で、対策を講じる必要があったと指摘。今年7月の自主回収まで10カ月かかったことを批判した。また、同社が今年5月に問題を把握してから自主回収に踏み切るまで2カ月を要したことも「遅きに過ぎた」と断じた。
報告書によると、同社に顧客から白斑の被害が最初に寄せられたのは11年10月。12年2月には販売部門の販売社員3人にも白斑が発症したが、カネボウは化粧品とは関係ない病気だと思い込み、適切な対応をとらなかった。調査を担当した中込秀樹弁護士は記者会見で「商品ありきで、消費者は後回しだった」と断じた。
カネボウは今年5月、被害者を診察した医師から症例報告を受け、社内調査を開始。美白化粧品に配合した「ロドデノール」という物質が白斑の原因と判断し、商品の自主回収を決めた。これに先立ち、12年9月段階で初めて、大阪府内の大学病院から「化粧品が引き金となった可能性がある」と指摘を受けたが、病気が原因として処理した。報告書はカネボウによる意図的な隠蔽(いんぺい)は否定したものの、「都合が悪いことは無視しようとする態度」と批判した。【西浦久雄】
◇訴訟で賠償額増大も
カネボウ化粧品の夏坂真澄社長は11日、「白斑」被害に関する第三者調査報告書の発表後、記者会見し「被害に遭われた方の笑顔が戻るまで責任を持ち、全力を尽くす」と謝罪した。夏坂社長が役員報酬50%を6カ月間返上するなど役員10人の処分を発表したものの、「問題の対応をすることは私の責任」と、引責辞任は否定した。
カネボウによると、白斑による被害者は1日現在で9959人。夏坂社長は発症者全員の個別訪問を今月中に終え、治療費や慰謝料の支払いに関する協議を進める考えを示した。慰謝料も支払う方針だが、「(賠償が)どれぐらいになるかは分からない」(夏坂社長)状況。顧客が賠償内容に納得せず、製造物責任法(PL法)に基づく訴訟に発展すれば、賠償額や訴訟費用が一層拡大する恐れもある。
自主回収中の8ブランド54製品の売り上げ規模は約50億円で、カネボウ全体の3%弱に過ぎないが、ブランドイメージの失墜で他の主力化粧品の売り上げも急減しており、回収発表後の7〜8月の売り上げは前年同期比で約2割減少した。白斑の原因とみられる美白成分「ロドデノール」を使わない、新たな美白化粧品を年内にも発売する方針だが、顧客離れに歯止めがかかる見通しは立っていない。
親会社の花王にも影響が出ている。花王は2013年12月期の通期業績見通しで、カネボウ製品の売り上げ減により100億円の減収を見込むが、花王社内では「業績の影響以上に、カネボウのブランド力が失墜したダメージが大きい」との声も上がる。
11日の花王の株価は5月の年初来高値に比べ約17%下落した。白斑被害は台湾など海外にも広がっており、花王も戦略の大幅な見直しを迫られそうだ。【松倉佑輔】
◇調査報告書の骨子
・11年10月、顧客から「顔に白抜け」との申し出。12年2月には社員3人に白斑の症状が出たが、病気だとして対応せず
・12年9月、白斑が生じた顧客を診断した医師が「化粧品がトリガー(引き金)になった可能性」を指摘。この時点でカネボウは直ちに対策を講じる必要があった
・13年5月、別の医師からの指摘を受け、担当者が問題を経営陣に報告。商品の自主回収を決定
・同年7月、自主回収を発表したが、より早く対応すべきで、遅きに過ぎた
・花王の消費者相談システムをカネボウに導入していたが、運用が徹底せず、問題認識が遅れた大きな原因になった
福島第1・汚染水:海外メディア辛辣報道 (1/2)
(2/2) 09/04/13 (毎日新聞)
東京電力福島第1原発の汚染水事故で、海外メディアが日本政府や東電に厳しい目を向けている。2020年夏季五輪の開催地決定を前に470億円の国費投入を打ち出したことも「東京の集票目的」とみなされ、反応は極めて辛辣(しんらつ)だ。後手に回った汚染水事故が、五輪招致のみならず、日本政府の信用に影を落としている。【朴鐘珠、ベルリン篠田航一】
猪瀬直樹東京都知事が国際オリンピック委員会(IOC)総会のためブエノスアイレスに乗り込んだ2日、都内の日本外国特派員協会で原子力規制委員会の田中俊一委員長が記者会見に臨んだ。記者席は満席、立ったままの記者もいた。
田中氏が、汚染水の放射性物質の濃度を基準値以下に薄めて海へ放出するのもやむなしと発言すると、仏AFP通信は「福島の(汚染)放水避けられず」と速報。オーストラリアの全国紙は「海を核の捨て場に」の見出しを掲げ「環境保護論者や漁業関係者、近隣諸国の激しい怒りを買うだろう」と伝えた。
会見で田中氏に質問したフランスRTL放送の記者、ジョエル・ルジャンドル氏は3・11以前から日本で取材している。フランスも原発大国。同氏は原発への賛否以前の問題として、東電の企業体質に嫌悪感を抱いていると語る。「情報を公開せず、疑惑が浮上するとまず全否定する。ほとぼりが冷めたころに事実を認めるので非常にずる賢い。日本人や日本メディアの忘れやすい気質を利用している」
マドリードに本社を置くスペイン通信社の東京支局の男性記者、アンドレス・サンチェス・ブラウン氏(33)は、震災後に宮城でボランティアをしながら、福島の被災者を取材してきた。参院選直後に汚染水漏れが発表された背景に意図的なものを感じており「東電をウソつきとまでは呼ばないが、事実を矮小(わいしょう)化させ発表しているのが分かる」と言う。
外国人記者の東電への不信感は、世界各地の報道に反映されている。独紙フランクフルター・アルゲマイネは「東電は外国人記者に『原発は制御下にあり危険は全くない』と説明したが、汚染水は太平洋に流れ込んでいた。こうしたウソと隠蔽(いんぺい)工作で、東電が本当に事故から学んだのかと国民は疑念を深めている」と非難した。
批判の矛先は、原発再稼働と輸出に突き進む安倍晋三政権にも向かう。米紙ニューヨーク・タイムズは「安倍首相が事故処理に積極的な役割を果たすと約束した2週間後に汚染水漏れが発覚した。約束に対する首相の真剣味が問われる」と指摘。政府が3日発表した470億円の汚染水対策費について、米AP通信は「大部分が発表済みのもので、五輪開催地の投票を前に安全性の宣伝との見方が大勢」と伝えた。4日付の韓国有力紙、朝鮮日報は論説委員のコラムで「(IOC総会を意識した対策ということが)事実だとすれば、日本は原発を安全に管理する能力も良心もない国だ」と書いている。
サンチェス・ブラウン氏は、五輪候補地のライバル、スペインでは汚染水という「敵失」を歓迎するような報道は見当たらないとしつつも「五輪には海の競技もある。東京湾が福島から離れているとはいえ、汚染水が選考委員に良くない印象を与えているのは確か」と厳しい見方を示す。
「学内で済む話と。甘かった」…天理大柔道部 09/04/13 (読売新聞)
暴力問題や助成金の不正受給などを受け、解体的出直しに乗り出したばかりの日本柔道界で、新たな不祥事が浮上した。
3日、名門・天理大柔道部で明らかになった暴力問題。
事態を公表しないまま全日本柔道連盟(全柔連)の理事に就任していた同部の藤猪省太(ふじいしょうぞう)部長は、読売新聞の取材に「部内と学校の中の話で終わると思った。甘かった」と語った。「本当に改革しようという気があるのか」。被害にあった1年生の関係者は憤った。
「これほどひどい暴力があった部の部長が、全柔連の理事になるなんて許せない」。被害を受けた部員の関係者は、語気を強めた。
中国高官の子弟採用違法か、JPモルガン大揺れ 09/01/13 (読売新聞)
【ニューヨーク=越前谷知子】米金融大手JPモルガン・チェースが、中国での贈賄疑惑に揺れている。
中国当局幹部の子弟を縁故採用し、中国での事業で便宜供与を受けた可能性があるとして、米証券取引委員会(SEC)が調査を開始した。ブルームバーグ通信など複数のメディアは31日までに、米司法省も調査に乗り出したと報じた。
報道によると、JPモルガンは違法な縁故採用の可能性がある200人を対象に内部調査を進めているという。
SECが情報提供を求めたのは、いずれも中国当局の高官の息子や娘の採用についてだったが、疑惑はさらに広がる可能性がある。この2人はすでにJPモルガンを辞めているが、採用後に親が関係する企業との取引を得ていたという。
ただ内部調査では、違法だったかどうかについての結論は出ていない。
米国では、外国政府の高官の子弟を雇うこと自体は可能。しかし、海外の取引先や顧客などから便宜供与を受けることは、連邦海外腐敗行為防止法で贈賄にあたるとして禁じられている。
有害物質や高濃度汚染水のタンクに組み立て式のタンクを選択する事が問題。高学歴でなくても組み立て式のタンクを選択する時に調べれば今回の問題は理解できたはず。東電の判断はコスト重視の選択としか思えない。
福島汚染水漏れ:高放射線量を検出 敷地内の同型2基から 09/01/13 (毎日新聞)
東京電力福島第1原発でタンクから高濃度汚染水が漏れた問題で、東電は31日、敷地内にある同じ型のタンク2基の底部の外側から最大で毎時1800ミリシーベルトの高い放射線量を検出したと発表した。22日の測定時は最大毎時100ミリシーベルトだった。周辺に水たまりは確認できず、タンク内の水位低下もみられないが、タンクを構成する鋼板の接合部からしみ出ている可能性がある。
2基は約300トンの汚染水が漏れたタンクから約100メートル離れた「H3」区画にある。測定は、タンクから1メートル離れた地面から高さ50センチの場所で実施。前回に比べ線量が高くなった理由について、東電は「原因を調べている」と説明。その上で、「放射線は比較的遮蔽(しゃへい)が容易なベータ線が中心だ。作業員は防護服を着用しており、健康影響は考えにくい。周辺環境への影響も今のところ、みられない」としている。1800ミリシーベルトは、原発作業員の年間被ばく上限に1分あまりで達する線量。
2基とは別に「H4」エリアにあるタンクの底部と、「H5」エリアのタンク同士をつなぐ配管下部で、最大で毎時230ミリシーベルトを検出した。この2基でも水位の変化は見られないが、「配管部に少量の水滴があり、地面に変色が見られる」という。【渡辺諒】
規則で要求される検査に通るだけなら中国の整備会社でも良いと思うが、安全性を重視するなら中国の選択はありえないでしょう。
結局、LCCが注目を受けているが、規則を満足しているから安全とは違う事を理解しなければならないと思う。コストを抑えるプロセスでリスクがあると思う。例えばコストの安い中国の整備会社に委託するリスクの1つが今回のような整備記録の不備。まあ、不備を見つけれらなければ飛行機が事故を起こすまでは問題ないと思われ問題は放置され続けるだろう。
エアバス機整備記録に不備、全日空29便欠航 08/30/13 (読売新聞)
全日本空輸は31日、保有するエアバスA320型機の整備記録に不備が見つかったと発表した。
同社は同型機の点検のため、同日、国内線計29便を欠航させ、約2400人に影響が出た。
全日空や国土交通省によると、不備があったのは、約1年半に1回のペースで機体の詳細を調べる重整備の作業記録。国交省が30日に実施した全日空の監査で、A320型機1機の記録を確認したところ、整備作業後に燃料タンクの一部のパネルを適切に閉めたことを示す項目が記載されていないことが分かった。このため、全日空がほかの同型機の記録を調べ、11機で同様の不記載が見つかった。
全日空は30日夜、12機の点検を開始。31日朝までに6機は終了したが、残り6機は終日かかる見通しとなり、運航を取りやめた。12機の重整備は委託先の中国の整備会社が行っており、全日空は不記載の理由を確認中。国交省は委託作業のチェック体制や再発防止策を全日空に報告させる方針。
規則を守る必要があるから、他の学校も苦労したりコストの問題を抱えていると思う。悪質な行為は良くない。しかも教育機関である。
「学園は一連の問題を公表した20日の記者会見で、延べ64人の教員が必要な免許を持たずに授業をしていたと説明したが、無資格教員は延べ65人となった。」
進学率や有名校への進学実績も重要だ。しかし違反をしても良いと言う事ではない。生徒達が被るかもしれない不利益も検討するべきだが、だからと言ってこのような学校を放置するべきではない。それなりの処分及び定期的なチェックを数年間は行うべきだ。それで学校の経営が成り立たなくなるのであれば仕方がない。
事務員が算数教え、無免許延べ65人…才教学園 08/30/13 (読売新聞)
長野県松本市の私立小中一貫校「才教学園」で、中学校の教員免許しかない教員が小学校の学級担任をするなどしていた問題で、学園は29日、小、中、高校のいずれの教員免許も持たない女性事務員が小学校で算数を教えていたことを明らかにした。
学園は一連の問題を公表した20日の記者会見で、延べ64人の教員が必要な免許を持たずに授業をしていたと説明したが、無資格教員は延べ65人となった。学園によると、山田昌俊校長(64)が28日夜、疲労のため入院したという。
下辻正孝教頭(61)によると、事務員の女性は2006年10月から3か月間に計18回、小学校で算数の授業を教えていた。
下辻教頭は、「当時、学園にいなかったため詳細はわからない」としたうえで、この事務員が同学園が無資格授業問題を公表後、県情報公開・私学課に算数を教えていたことに関して相談し、同課からの指摘で調査したところ、今回の無免許授業が新たに判明したと説明した。
事務員はすでに学園を退職。下辻教頭は「大学卒業程度の学力があれば、小学校の算数を教えることはできるだろう」との認識を示し、「無免許授業の隠蔽を図ったのでは」との記者の質問に「書類をチェックし忘れた」と弁明した。
一方、県は29日、学園に対する3回目の現地調査を実施。県情報公開・私学課の職員が9月2日に始まる2学期の教員の配置態勢を確認し、教員免許法違反の違法性の認識について説明が変遷した経緯を松山治邦前教頭(51)や中野茂保副校長(64)らから聞き取った。学園から派遣要請を受けた県教委教学指導課の職員らも、1学期の授業が学習指導要領に沿って適正に行われたかを確認した。
県は現地調査の際、学園が違法授業を続けていた原因や、2学期以降の是正策を文書で提出するよう、要請した。山田校長の入院も考慮し、締め切り時期は指定しなかったという。
新潟知事「東電うそつく企業」…記者会見で 08/29/13 (読売新聞)
「過去の経験に学べない企業が原発のオペレーションをできるか不安だ」。
28日に東京・有楽町の日本外国特派員協会で記者会見した新潟県の泉田知事は、東京電力や原子力規制委員会への批判を改めて繰り返し、外国メディアに自らの主張の正当性を訴えた。
外国の特派員ら約50人を前に、泉田知事は2011年の福島第一原発事故でメルトダウン(炉心溶融)が約2か月後に判明したことなどを挙げ、東電は「うそをつく企業」と非難した。東電が柏崎刈羽原発で安全審査申請を進めようとしていることについては「広瀬直己社長の頭の9割は福島の賠償と資金調達。安全な原発を運営できるのか疑問を感じている」と述べた。
また、福島第一原発から汚染水が海に流出している問題などにも言及。「5月の段階で放射性物質の濃度が上がっているので、調べればもっと早く発表できた。広瀬社長は3・11の教訓を学べなかった」と対応の遅れを批判した。
新規制基準を作った原子力規制委員会についても「原発の性能基準のみを任務にして自らの役割を狭めようとしているように見える」と対応を疑問視。法律の規制を超える被曝(ひばく)があった場合の対応など、これまで規制委に出した質問に対して回答がなかったことを挙げて「住民の安全を守るという使命感を持たない組織が、安全を守るのは困難ではないか」とした。
批判の矛先は首都圏の住民にも。2002年に発覚した東電のトラブル隠し問題を振り返り、「地域の生活と国家のエネルギー政策について深い考えを都市住民は持っていないのではないか」と原発立地県との意識の差を指摘した。
知事は同日夜、都内の日本記者クラブでも会見し、東電批判を繰り広げた。
バルサルタン疑惑:大阪市大の肩書「都合良かった」 08/23/13 (毎日新聞)
降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験疑惑で、大阪市立大は22日、製薬会社ノバルティスファーマの社員(5月に退職)が同大医学部の非常勤講師として5大学の試験に参加していたことに関する調査結果を公表した。元社員は大学の調査に対し「大阪市大の肩書を使うことはノ社にとって都合が良かったと思う」と証言した。
ノ社はこれまで、元社員について「統計の世界では有名な人物だ」と強調し、大阪市大の非常勤講師を兼務して臨床試験に参加したことの正当性を主張していた。
発表によると、元社員が非常勤講師だったのは2002年4月〜13年3月だが、大学での講義は1回だけで、無給だった。元社員は疑惑の発覚後、大学側の調査に応じ「大阪市大の所属を使うことは、試験をした各大学の研究者やノ社にとって都合が良かったと思う。自分自身も便利だった」と述べたという。講師就任の経緯については「以前から親交のあった大阪市大の教員を通じて大阪市大側から要請された」と説明。この教員には、ノ社から02年度、400万円の奨学寄付金が提供されていた。
元社員は非常勤講師の1年ごとの任期更新時、自社製品を使った試験に非常勤講師の肩書で参加したことを報告しておらず、調査報告は「意図的に不利なことを隠した。極めて悪質だ」と指摘した。また、一部の試験の論文では、元社員の肩書として、実際は大学に存在しない部署名が記されていたことも分かった。
大阪市大は、ノ社について「自社の利益を優先するあまり、元社員の試験への関与を会社ぐるみで支援していたと判断せざるを得ない。ノ社は発覚当初、元社員の関与を否定していた。このような企業姿勢は社会的に許されない」と非難した。ノ社に抗議して謝罪を求める意向を示した。
一方、「大学としては試験に関わっていない。われわれは被害者」としたが、勤務実態を確認せず、元社員を非常勤講師として認め続けてきた自らの責任も認めた。
バルサルタンの臨床試験は、京都府立医、東京慈恵会医、滋賀医、千葉、名古屋の5大学で行われ、血圧を下げる以外の効果を確かめた。元社員は外部に社員であることを伏せ、統計解析などを担当。府立医と慈恵医は、元社員によってデータ操作されたことを疑う調査結果をまとめている。【斎藤広子、河内敏康、八田浩輔】
8月23日の朝の番組で
田崎史郎(ウィキペディア)が福島汚染水漏れについて「想定外」と言っていたが想定外であるわけないだろ!
「組み立て式のタンクは、溶接式に比べて継ぎ目から水が漏れやすい。」と言う事を知らなかったとでも言うのか!知らないのなら知ったかぶりして言うな!
文系で理系やエンジニアリングの知識について知らないのであれば専門外だからわからないと素直に言うべきだ!誤解を招くようなコメントは止めるべきだ。
想定外と簡単にコメントするような信用できない人間をコメンテーターとして使うのは問題!使うとしても専門だけに限定するべきだ!
8月20日のテレビで排水弁をなぜ開けていたかについて東電が説明していた。詐欺師のような説明であった。2つの選択肢の1つしか選べないような説明だった。
問題がはっきりと理解されいれば、トレイを二重にするだけで解決できたはずだ。問題はコスト。ただそれだけ。
「組み立て式のタンクは、溶接式に比べて継ぎ目から水が漏れやすい。」「新規に造るタンクは溶接型に移行している」これもコストの問題。
「東電は会見で『少量の漏れは初期から想定していた』」東電はコストを優先してリスクがあっても組み立て式のタンクを選択した。東電の体質そして判断基準は今後も変わらないと思う。福島の人達は東電の体質や判断基準を理解した上で将来について判断した方が良いと思う。個人的な意見だが待つだけ無駄だと思う。
福島汚染水漏れ:「レベル3」規制委、IAEA照会後結論 08/20/13 (産経新聞)
東京電力福島第1原発の地上タンクから高濃度の放射性物質を含んだ汚染水が漏れた問題で、原子力規制委員会は21日、原発事故の国際評価尺度(INES)でレベル1(逸脱)と暫定評価していた今回のトラブルを「レベル3(重大な異常事象)に該当する」とし、評価が妥当か国際原子力機関(IAEA)に照会することを決めた。評価尺度は原発事故の対応過程で生じたトラブルを想定していないため、IAEAの回答を待って結論を出す。
規制委は、レベル1の発表後、東電が汚染水の漏えい量を約300トンと推計し、水の放射性物質濃度から全体の放出量を約24兆ベクレルとしたことを受け、評価を再検討。この放出量をINESの尺度に照らして換算すると数千テラベクレル(テラは1兆)程度となるため、レベル3に該当すると判断した。
ただ、INESは「健全な施設」で起きた事故を想定しており、この日の規制委定例会では、更田豊志委員から「単純計算に基づいた評価は疑問。レベル7の事故にレベル3が加わることの意味を考える必要がある」と異論が出たが、田中俊一委員長が「一刻の猶予もない状況が起こっている」と述べ、照会することにした。
規制委は、事故対応の応急措置でつくられた施設のトラブルを評価することが適切か▽事故でいったん放出された放射性物質が汚染水として再び流出したとして事故に含むべきか−−をIAEAに照会することを決めた。評価が決まれば、事故そのものの評価がレベル7に引き上げられた2011年4月以降、初めての評価となる。【鳥井真平】
福島第1原発:タンク漏出1カ月前から 保管計画破綻寸前 08/20/13 (産経新聞)
福島第1原発:タンク漏出1カ月前から 保管計画破綻寸前 08/20/13 (産経新聞)
東京電力福島第1原発の地上タンクから約300トンもの高濃度放射性汚染水が漏れた問題は、事故処理の新たな障壁の深刻さを物語る。把握まで1カ月を要するお粗末な点検体制だけでなく、その場しのぎの保管計画の実態も浮き彫りになった。
東電によると19日午前9時50分ごろ、東電社員がタンク周囲にある漏えい防止用のせきの排水弁から流れ出た水計120リットルが外側にたまっているのを見つけた。排水弁は、雨水がせきの内部にたまるとタンクからの漏えいと区別できなくなるため、常時開けられていた。
東電の尾野昌之原子力・立地本部長代理は20日の記者会見で「漏れを迅速に発見するための措置で、さらに外側には土のうの壁もある」と運用の不備を認めなかったが、今後は弁を常時閉じるよう方針転換した。
せきの外への汚染水漏えいを防ぐためのパトロールは、タンク群を取り囲むせきの外周を歩いてタンク外壁やせきの内部を目視するのみで、タンクを個別に巡回することはしていなかった。東電は、周辺の放射線量が毎時100ミリシーベルトと高く「作業時間が限られている」と釈明する。
もともと、今回のような組み立て式のタンクは、溶接式に比べて継ぎ目から水が漏れやすい。東電は会見で「少量の漏れは初期から想定していた」とした上で「新規に造るタンクは溶接型に移行している」と強調したが、今後は老朽化に伴うリスクも加わる。漏えいが見つかったタンクは耐用年数が5年で、すでに2年が経過。東電は会見で「点検や補修方法の検討を現在行っている」と説明、タンクを使い始める時には5年後の対策を考慮していなかったことを明らかにした。【鳥井真平】
架空発注:NK、金型の証明書を偽造 (1/2)
(2/2) 08/19/13 (毎日新聞)
◇販売会社「発注元が指示」
鉄道部品の金型などを架空発注し、裏金を作っていた三重県伊勢市の鉄道部品販売会社「エヌ・ケイカンパニー」(NK)が、実際には製造していない金型の存在を装うため、偽の証明書を作っていたことが関係者の証言で分かった。関係者は、発注元の東証1部上場メーカー「東洋電機製造」(東洋、東京都中央区)の当時の担当者の指示だったと証言している。一方、東洋は19日、毎日新聞の取材に「金型の現物を一切確認していなかった」と認め、実地調査を始めた。第三者による調査も検討する。
複数の関係者によると、NKは東洋からシム(調整板)と呼ばれる部品と、その製造に使う金型などを受注。実際には金型をほとんど作らず、別の工法でシムを納品していた。さらに、2008〜11年ごろ、九州のダミー会社や大阪府内の業者に金型や部品を発注したと装い、裏金として還流させていた。
証言では、証明書が偽造されたのは10〜11年ごろ。NKの社員が愛知県内の鋳造業者の事業所に行き、金属加工品などを撮影。パソコンで写真を加工して東洋から受注した金型のように装い、NK側が金型を預かっていることを示す証明書を偽造したという。
NK関係者は「東洋の担当者から社員が、『何かあった時のために一応作ってくれ』と言われた」と証言。担当者は写真を確認したが、結果的に証明書は提出されていないという。愛知県の鋳造業者は「NKの社員が撮影に来たことがある。何を撮ったかは知らない。NKからシムの金型製造を受注したことはない」と話している。
一方、東洋は19日、自社のホームページで「製品の検査は社内規定通り実施しており、品質に問題はない」と発表した。また、東京証券取引所からは第三者を入れて調査するよう促されたという。
東洋によると、NKとは04年に取引を始め、全てのシムを発注していた。内部調査に対し、当時の担当者は「取引が始まった頃、短い納期でシムが必要になり、金型でのプレス加工より高単価だが短期で製造できるレーザー加工などを依頼した。その際、プレス加工の単価しか払わず不足分を金型代として支払ったが、その後は金型を作る前提で発注していた」と釈明。NK側からの裏金の受領は否定しているという。
東洋は「約3年前から金型の現物を確認するよう社内規定を変えたが、社内管理上の不手際があった」として、シム以外の金型についても調査。納入先のJR東日本も、部品の検査体制などの調査を始めた。【藤田剛、遠藤孝康】
部品架空発注:九州のダミー会社でも…「裏金渡すため」 08/19/13 (毎日新聞)
新幹線などの鉄道部品を大阪府内の業者に架空発注し、裏金を作っていた三重県伊勢市の鉄道部品販売会社「エヌ・ケイカンパニー」(NK)が、実在しない九州のダミー会社にも架空発注を繰り返していたことが、複数の関係者の証言で分かった。東証1部上場のメーカー「東洋電機製造」(東洋)=東京都中央区=の当時の担当者に裏金を渡すための会社だったとの証言もあり、東洋が調査を進めている。
複数の関係者や内部資料によると、NKは2010〜11年、大阪府内の加工業者に鉄道部品の金型などを発注したように装い、振り込んだ発注費約3000万円の大半を裏金として還流させていたことが分かっている。
NKは同様の手法で08〜09年ごろ、「イケダ工業」というダミー会社にシムと呼ばれる部品や金型などの発注を装い、伝票を作成したり、発注費を振り込んだりしたが、実際に納品されることはなかった。
イケダ工業の口座には、月200万〜300万円程度が振り込まれ、裏金になっていたという。所在地は九州になっていたが、実際にはスナックの電話番号だったという。
NK関係者は「東洋の担当者に裏金を渡すためのダミー会社だった」と証言。別の関係者は「『営業に行け』と言われなかったので、『普通の取引先と違うな。おかしいな』と思っていた。後から架空だと分かった」と話す。
NKを実質経営する取締役(46)は取材に対し、イケダ工業について「いろいろな問題があった。実体があるかないかは答えられない」と話し、東洋側への金銭の供与については否定した。【藤田剛、遠藤孝康】
架空発注:新幹線部品の金型作らず裏金に 三重の販売会社 08/19/13 (毎日新聞)
三重県伊勢市の鉄道部品販売会社「エヌ・ケイカンパニー」(NK)が、新幹線部品などを大阪府内の業者に発注したように装い、大半を裏金として還流させていたことが、関係者の証言や内部資料で分かった。東証1部上場のメーカー「東洋電機製造」(東洋)=東京都中央区=から、部品やその製造に使う金型を受注したが、金型は作らず別工法で部品を製造し、金型代を浮かせていたという。裏金は年間約3000万円に上り、関係者は一部が東洋の社員に渡ったと証言する。部品は車両の安定走行に関わる部分にあり、同社は実態調査を始めた。【藤田剛、遠藤孝康】
複数の関係者によると、NKは東洋から「シム」(調整板)と呼ばれる部品を大量に受注。シムは、厚さ0.1〜0.5ミリ、直径20〜40センチのドーナツ状で、銅の合金や鉄などで作られる。モーターの動力を車輪や車軸に伝える「歯車装置」内にあり、車軸と装置内の部品の隙間(すきま)を厳密な規定通りに保つため、重ねて取り付け隙間を埋める。
NKはシムをプレス加工するための金型も東洋から受注したが、ほとんど作っていなかった。金型代は1個200万〜300万円。金型はNKや下請け先が管理する段取りだったため、無くても東洋側に発覚しなかったという。シム自体は、金型を使わない切削加工で別の業者に発注し、東洋に納品していた。
さらに、金型や部品について、NKは大阪府内の業者に架空発注して伝票や金だけを動かし、業者は約1割の手数料を引いてNK側にキックバックしていた。業者は「税金のかからない裏金にするために協力した」と説明し、少なくとも2010〜11年の1年間でNKから約3000万円の入金があったと証言。「裏金の6割は東洋の社員に渡すとNK幹部から聞いた」と話す。
複数のNK関係者も取材に対し、東洋の当時の担当者に社員が裏金の一部を定期的に持参したと証言。数百万円に上る月もあったという。
NKを実質経営する男性取締役(46)は取材に、「金型を作っていなかったのは事実かもしれない。(浮いた金を)接待交際費に回したかもしれないが、全ては答えられない」と、架空発注を事実上認めたが、東洋側への金銭提供は否定した。
部品架空発注:依頼主側に接待攻勢 三重の会社 (1/2)
http://mainichi.jp/select/news/20130819k0000m040136000c2.html" TARGET="_blank">
(2/2) 08/19/13 (毎日新聞)
新幹線などの鉄道車両部品を巡り、多額の不正取引が発覚した。三重県伊勢市の「エヌ・ケイカンパニー」(NK)は、東証1部上場の「東洋電機製造」(東洋)=東京都中央区=から受注した金型を製造せず、協力会社に金型などの名目で架空発注、裏金を作っていた。「ぼろもうけだった」とNK関係者は話す。東洋側への接待は度重なり、「裏金を渡した」との証言もある。不正の背景に根深い癒着が浮かぶ。
裏金作りの要請は、一本の電話だった。「仕事渡すから、B勘(ビーカン)やってくれへんか」。大阪府内の業者は2010年、NKの男性取締役(46)からそう頼まれたと話す。B勘は裏金を意味する隠語。旧知の仲だったので引き受けた。「シム金型費」「シム加工一式」−−。NKから来る発注書には、作ったこともない品目が並ぶ。「『物語』がいっぱい書かれていた」。発注費名目で振り込まれる金は多い月で800万円を超えた。取締役と大阪や三重で待ち合わせ、手数料を引いた残りを現金で手渡した。
裏金作りに使われたのは主に、「シム」と呼ばれる鉄道部品と、その製造のための金型だった。NK関係者は「地下鉄から新幹線まであらゆる車両にシムが使われる。金型は100品番以上あり、頻繁に発注が来た」と証言する。
「おかしいとは思っていたが、取締役の指示には逆らえなかった」。NKの経営は取締役が取り仕切り、社長は名義だけだった。NK関係者は「取締役が白と言えば白。黒と言えば黒になる」とワンマンぶりを指摘する。
NKは2000年に鉄道部品製造「オクノ・テック」(伊勢市)の関連会社として、この取締役が設立。中国での新幹線網の整備やJRの新型車両開発を背景に、東洋に部品を納める商社として成長した。
NK関係者らによると、東洋の担当者が地元に来る際は、社員総出で接待した。「賭けマージャンや賭けゴルフに1回数十万円動くこともあった」という。東洋の担当者が勤務する横浜に行く際には、社員が取締役から「ちょっとこれを持って行け」と頼まれることがあった。A4の封筒に入った数百万円の札束で、横浜の歓楽街などで東洋の担当者に渡したという。
大阪の業者も裏金の分配について「NKの取締役は『自分が4割、東洋の担当者が6割』と話していた」と証言するが、取締役は取材に対し、「現金は渡していない」と否定している。【藤田剛、遠藤孝康】
◇カネ渡していない…取締役一問一答
エヌ・ケイカンパニー(NK)を実質経営する男性取締役(46)は今月11日、三重県伊勢市内の自宅で毎日新聞の取材に応じた。
−−東洋電機製造(東洋)から金型の発注があり、NKはそれを下請けに出したが、架空発注だったのではないか。
金型を作ってなかったのは事実かもしれない。作らなくても、製品さえできたらいいわけやんか。
−−金型代はどうなったのか。
それは(東洋に)返してないと言われるんやったら、他に使っているのかもしれないし、接待交際費に回したのかもしれないし。
−−正しい取引ではないはずだ。
一部問題があったからといって、全てがそういう問題と片付けられたら不満だ。
−−裏金はどこに行ったのか。東洋の担当者への接待とか、本人に渡したとか。
そんなことまで答える? そこまで僕は言うつもりない。そんなことまで言ったら、人間終わりよ。
−−裏金を東洋の担当者に渡したのでは。
渡してないよ、そんなこと。
−−金型を使わずに加工して、品質に問題はない?
何で作ろうが関係ないねん。同じものができる。機械加工した方がきれいや。
薬のデータ捏造、論文捏造など大学医療の問題を東大教授告発 08/17/13 (NEWSポストセブン)
1960年代に発表された山崎豊子の『白い巨塔』は、閉鎖的かつ権威主義的な大学病院の腐敗を描いた作品だった時を経ていま、相次ぐ薬のデータ捏造10+ 件や研究費の不正流用が発覚し、その体質はより腐っていたことが明らかになった。
東京大学医科学研究所先端医療社会コミュニケーションシステム社会連携研究部門で医療ガバナンスを研究している上(かみ)昌広・特任教授(内科医)が、この現状を憂い、膿を出し切るために爆弾告発を決意した。
* * *
いま問題となっている「バルサルタン事件」は、残念ながら氷山の一角に過ぎません。日本の大学病院と製薬会社は、不正や癒着が起きやすい構造になっています。同様の不正はまだまだあるはずです。今後、糖尿病、がん、精神病などの分野でも問題が発覚するでしょう。これらの疾患に関わる医療では巨額のお金が動くからです。
製薬会社に「御用学者」が引っぱり出され、この薬は効くぞというようなことをふれまわる。厚労省は見て見ないふりをする。この構造は、原発事故における“原子力ムラ”と同じです。電力会社が製薬会社、経産省が厚労省に置き換わっただけ。そして、御用学者たちがまんまとそれに使われている。「原発は安全だ」といっていた学者と、いま製薬会社と癒着している医師たちは全く同根です。
〈大手製薬会社ノバルティス10+ 件ファーマの降圧剤ディオバン(一般名・バルサルタン)に関して、脳卒中予防などの効果を調べた複数の大学の臨床データに不正があった問題は、大学側が次々と謝罪する事態となった。医療の信用を大きく損なった「前代未聞の不祥事」として連日のようにマスコミに報じられているが、この深淵には、福島第一原発事故同様、官・民・学の「利権」と「癒着」がある、とバッサリと斬り捨てる医学者がいる。
東京大学医科学研究所先端医療社会コミュニケーションシステム社会連携研究部門で、医療ガバナンスを研究している上昌広・特任教授(内科医)である。〉
バルサルタンは血圧を下げる薬ですが、他の薬と比べて、それほど下がり方は強くない代わりに、心筋梗塞や脳卒中のリスクが半分くらいに減りますよ、と製薬会社は謳っていた。その根拠とされていたのが、京都府立医大や慈恵医大など5つの大学で行なわれた臨床試験論文でした。
ところがその論文に関し、京都大学のドクターがどうも血圧値がおかしいと指摘して調査したところ、血圧値や脳卒中、心筋梗塞の発症数を改竄していたことが判明し、さらに製造元であるノバルティス10+ 件の社員(5月に退職)がデータ解析に関与していたことが分かったのです。
今回の不正はテストの点数でいえば0点を80点に改竄していたようなもの。「心筋梗塞などのリスクが下がる」という論文の“ストーリー”そのものをいじっていたわけです。なぜ不正がこれまで発覚しなかったのかというと、患者を研究対象にしているためです。薬効には個人差があり、環境が異なれば、研究結果は同じになりません。つまり、大学側から見れば、個人差があるなど言い逃れできるのです。臨床研究の“死角”をついた不正です。
〈さらに、ノバルティス10+ 件社は、大学側の“弱み”も巧みについている。臨床研究に詳しいナビタスクリニック立川の谷本哲也医師によると、「日本の大学病院には臨床試験に欠かせない統計解析のプロがいない。人材面でも製薬会社に依存する臨床検査になっていた」という。今回、データ操作した疑いがもたれているノバルティス元社員は、統計解析の専門家として大阪市立大学の講師も務めていた。
一方、慈恵医大の調査報告書によると、臨床検査責任者以下、すべての医師たちが、「自分たちには、データ解析の知識も能力もなく、自分たちがデータ解析を行なったことはない」と証言している。〉
つまり、統計解析という臨床試験のキモの部分を、初めから製薬会社に握られていたわけです。大学が論文を発表するので、製薬会社は“第三者”として、バレない限り不正ができる。実態として、自社の社員がコミットしていても、会社としては関係ないと突っぱねることができる。ノバルティス10+ 件がこの論文について“医師主導臨床研究”と繰り返し言い続けているのは、確信犯です。
論文不正の最大の問題は、数値を操作したことで多くの患者を危機にさらしたことです。脳卒中リスクを減らす薬だという触れ込みですから、それを脳卒中リスクの高い患者に処方しなかったら医師は訴えられかねない。論文を読んだ勉強熱心な医師ほど、バルサルタンを処方した可能性があります。それが嘘なら、バルサルタンで治療を受けていたために、脳卒中や心筋梗塞になったという人がごまんといるはずです。
医療は日進月歩。医師がすべて最先端研究についていくことは不可能です。そこで医師は、論文をわかりやすく解説した医療雑誌に頼ります。ところが、そこには製薬会社の記事広告が満載。有名大学教授を招いた座談会で「バルサルタンは効く」と連呼している。
今回問題になった先生たちも毎週のように講演会や座談会に呼ばれていました。1回15万円ほどの講演料を貰っていたでしょう。小遣い欲しさから、製薬会社にすり寄る教授も生まれます。バルサルタンを宣伝していたある国公立大学教授は、子供を私立の医大に通わせていました。大学の給料だけでは苦しい。こうなると、企業の広告塔を止められなくなります。このような「御用学者」を用いた製薬関係の広告費が、年間1兆円程度といいます。
※週刊ポスト2013年8月30日号
ディオバン問題検討委が初会合 新たに2試験で論文とカルテデータに食い違いも 08/12/13 (ミクスOnline)
降圧薬・ディオバン(一般名:バルサルタン、ノバルティス ファーマ)をめぐる臨床研究でデータの改ざんがあったことを受け、厚労省は「高血圧症治療薬の臨床研究事案に関する検討委員会」(委員長:森嶌昭夫名古屋大学名誉教授)を設置し、8月9日に省内で初会合を開いた。
検討委で、新たに大学の内部調査の中間結果が報告された、「VART Study(研究の中心となった施設:千葉大学)」、「SMART Study(滋賀医科大学)」の2試験でも、新たにカルテデータと論文データの食い違いが発見されたことが分かった。検討委では、9月末をめどに、原因の究明や再発防止策などについて、一定の方向性を出す方針。
田村憲久厚労相は、会の冒頭で、ノバルティスの元社員のデータ統計へのかかわり方について、大学の内部調査と、ノバルティス社の第三者機関の調査結果との間に食い違いがあることを指摘し、事態を重く受け止めているとした。その上で、「論文が違っていたら、医師の処方行動も変わってくる。結果として、患者に不安感をもたらせた大きな問題と言える。閣議決定した成長戦略において、革新的な医療技術の実用化を挙げている。臨床試験に信頼性がないというと大変な問題になってくる」と指摘。「真実がどこにあるかも調べていかないといけない。臨床研究が不振をもたれているということは大変な問題。信頼回復のために力を貸していただきたい」と述べ、検討委に9月末を目途に一定の結論を出すことを求めた。
◎VART 血圧値にカルテデータと食い違いも
この日の検討委では、「KYOTO Heart Study(京都府立医科大学)」、「JIKEI Heart Study(東京慈恵会医科大学)」、「VART Study」、「SMART Study」、「NAGOYA Heart Study(名古屋大学)」の臨床研究で中心となった医療機関と、ノバルティスの元社員が肩書きとしていた大阪市立大学の内部調査の現状と、ノバルティスからのヒアリングが行われた。
VART Studyでは、カルテデータと論文データとの間で血圧値について食い違いがみられたことも分かった。千葉大学では、7月5日に症例データを入手、8日から内部調査を開始した。登録時の症例データ109例のうち、解析対象の108例をカルテから特定し、外部機関の先端医療振興財団臨床研究情報センターが照合を行った。
その結果、イベント数(脳卒中、心不全、血清クレアチニン2倍)には解析に用いられたデータベース情報とカルテデータに相違はみられなかった。一方、血圧の測定全ポイント1512のうち、67ポイント(4.4%)に相違がみられたとした。ただ、「カルテデータでの集計結果とデータベース情報から得られた結果との間に有意差は認められなかった」としている。副次評価項目についても調査中という。
同試験へのノバルティス社の元社員との関与について、臨床研究を開始した際の主任研究者(小室一成氏・現東京大学大学院医学系研究科循環器内科学)は、「ノバルティス社の元社員だということを知っており、プロトコルを作成する委員会などには来ないように言っていた」と説明。同試験では、途中で主任研究者が交代しているが、その後は、「ノバルティスの元社員であることは知らなかった。データについてその方に触れさせることとはなかったと聞いている」(横須賀收氏・千葉大学大学院医学研究院医学研究院長)としている。
◎SMART研究 ずさんなデータで論文と一致しない点も
SMART研究についても、“ずさんなデータ”が含まれており、カルテデータと論文データとの間にかい離がみられる可能性が指摘された。同試験では、2型糖尿病合併高血圧患者における、微量アルブミン尿減少効果をCa拮抗薬とARB群の2群間で比較した。内部調査では、「イベント数ではなく、数値そのものを検討している」(服部隆則氏・滋賀医科大学副学長・教育担当理事)と説明。7月15日に90例のカルテデータを入手し、論文の再現性などについた調査を進めているとした。
現在、カルテデータと論文データとの比較を進めている中にあって、服部氏は「最終的な報告はできない状況」とした上で、「論文の生データを見ると、非常に初歩的なミス、つまりカルテからの入力ミス、計算ミスなどがたくさんでてきている。論文内容と必ずしも一致しない部分もでてきている」と述べた。
Diabetes Careに掲載された主要論文の著者の中に、ノバルティスの元社員の部下が含まれていたことも報告。ノバルティス元社員が主任研究者らと研究立案後に、元社員の部下が研究に参加したと説明した。この元社員の部下は、データ検討委員会や処理にかかわっていたという。
服部氏は、「ノバルティス社の社員2名が関与していたという驚くべき、衝撃的事実が分かってきた。論文の信ぴょう性に関しましては、かなりずさんなデータであるということで、外部委員会にお願いして中立な公表を行いたい」と述べた。今後、研究にかかわった医師、ノバルティスの元社員、元社員の部下らにもヒアリングなどに数週間を要するとし、最終結果については1か月以内に公表する予定とした。
そのほか、ノバルティスの元社員が肩書として用いていた大阪市立大学も内部調査を実施。元社員が所属していた産業医学教室では、「医師主導臨床研究は行っていない。元社員も、産業医学教室で行っていないと主張している。倫理委員会にも当該臨床研究は提出されていない。本学は臨床研究に一切かかわっていない」と述べた。また委嘱についても、“講義”のみを想定したとし、「研究という形でかかわるということは想定していなかった。上司である教授にもそういう相談はしていない。寄附金も産業学教室には一切入っておりません」と、同大学の臨床研究へのかかわりを否定した。同大では元社員は「デスクもメールアドレスも持っていない」とした。なお、委嘱は、2002年4月~13年3月まで(1年更新)。同大では、06年度医学研究セミナーで講義を行ったほか、院生に対してゼミなどで数回指導を行ったとしている。
一方、ノバルティスは奨学寄附金として、2002~12年までの10年間で、東京慈恵会医科大学に1億8770万円、千葉大学に2億4600万円、京都府立医科大学に3億8170万円、滋賀医科大学に6550万円、名古屋大学に2億5200万円の寄付を行ったことも分かった。ただ、同社では2010年以降、契約書で使途を明示した、委託受託契約方式に変更しているとした。また、プロモーション資材として5試験をめぐり、ディオバン関連1384資材のうち、推定495種類を用いていたことも公表。ただし、KYOTO Heart Study関連論文に関する資材は、論文の撤回を受け、13年2月4日以降使用を中止、その他の関連論文についても、5月20日以降は使用を中止しているとした。
◎臨床研究の信頼回復に向けた取り組みが論点に
検討委では、この事案を踏まえた論点案として、▽臨床研究の信頼性及び質を確保する上で具体的な方策と、その場合の課題▽大学研究機関と製薬企業との透明性を確保する具体的な方策▽ノバルティス社が一連の誤ったデータに基づきディオバンに関する広告等の販売促進活動を行ったこと及びそれにより得た売上金額をどう考えるべきか▽臨床研究に対する信頼回復に向けた取り組みとして、大学等研究機関、製薬企業、学界、行政等は何を行うべきか――の4点を挙げている。なお、現在臨床研究では、厚生労働大臣告示として、被験者保護の観点から「臨床研究に関する倫理指針」を定めている。
ノバルティス疑惑、独禁法適用の可能性 厚労省にとって「最悪の事態」も 08/10/13 (郷原信郎が斬る)
今日の毎日新聞朝刊に掲載された【クローズアップ2013:バルサルタン臨床試験疑惑 元検事の郷原信郎弁護士の話】にも書いたように、ノバルティス・ファーマの降圧剤バルサルタンをめぐる臨床試験への同社の社員の関与、論文でのデータ操作等の問題について、「不公正な取引方法」を禁じる独禁法19条の「欺まん的顧客誘引」に該当する可能性がある。
この点については、検事時代の公取委出向の頃からの知り合いの公取委幹部にも感触を聞いてみたところ、「厚労省が薬事法できちんと対応しないようであれば、ウチが独禁法で出ていくこともあり得ますね」とヤル気を見せていた。
公取委には、過去にも厚労省の領域に独禁法で踏み込んだ実績がある。1996年に独禁法3条前段の「私的独占」を適用して排除措置命令を行った「財団法人日本医療食協会及び日清医療食品株式会社に対する件」だ。この件で、厚労省は、貴重な「天下りポスト」をいくつも失った。今回は、医薬品業界という、厚労省が薬価決定を通して支配する、まさに厚労省の「本丸」の問題だ。厚労省にとって、公取委による独禁法の適用は、想像したくもない「悪夢」以外の何物でもないだろう。
独禁法19条で禁止する「不公正な取引方法」の具体的な禁止行為は公取委告示に委ねられており、公正な競争を阻害する行為に対して機動的に適用できる。
「欺まん的顧客誘引」に関しては、「自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること」と定められている(告示8項)。
今回のノバルティスの問題では、降圧剤バルサルタンの心疾患等への効能を、多数の大学の研究者の論文によって根拠づける宣伝広告を行っていたが、データの不正操作等があったことが判明したことによって論文が撤回されたことで、心疾患等に対しての効能の根拠は失われた。降圧剤が高血圧だけでなく心疾患等に対しても顕著な効能があるという広告宣伝は、現状では、明らかに「著しく優良であると誤認」させるものであり、それが、ノバルティスの事業活動の一環として行われたと認められれば、公取委が「欺まん的顧客誘引」に該当するとして、当該宣伝広告を排除する命令を出すことも可能だ。
この排除措置命令は、あくまで、「著しく優良であると誤認」させる広告宣伝が、医薬品事業者間の公正な競争を阻害するということで排除することが目的であり、その点についての故意は要件ではない。ましてや、効能の根拠とされた論文が不正であったことを会社側が認識していたことも不要だ。そういう意味で、独禁法を適用しようと思えばハードルは低い。公取委には、強制手続を含めた「正式審査」を行うことを決断し、立入検査を実施して会社から関係書類を提出させ、会社関係者の事情聴取等を通じて事実解明をしていくこともできる。
もちろん、厚労省の側が薬事法に基づいて十分な対応をするというのであれば、公取委が敢えて踏み込む必要はないであろう。しかし、現在のところ、この問題についての厚労省の対応は「厚労大臣直轄の有識者の検討委員会」による調査・検討に委ねられているようだ。それが、事案の真相解明や薬事法適用による厳正な対応につながらないようであれば、独禁法の出番となる可能性も十分にある。
今朝の毎日新聞朝刊の記事によると、この検討委員会の委員には、以前よりノバルティス社によるプロモーション戦略に参画し、バルサルタンの臨床試験の経過や成果を大きく紹介していきた日経BP社の特命編集委員の宮田満氏が就任しており、他の委員から「委員会の信頼性が疑われかねない」と懸念する声が出ているとのことだ。ネットで調べたところ、日経BP社とノバルティス社という企業間の関係だけではなく、宮田氏個人も、「ノバルティス バイオキャンプ2007国際大会」と題するノバルティス社主催のバイオ研究者の国際交流のための大イベントで審査員代表を務めるなど、同社との接点がある。個人的にも、同社のプロモーションにも深く関わっていた疑いがある。
このような人物が、ノバルティス社の疑惑を含む問題について調査・検討する委員会の委員として加わるのは典型的な「利益相反」である。上記毎日新聞の記事で、日経BP側は「当社としても今回の問題について検証報道を続けており、就任に問題はないと認識している」とコメントしているが、検証報道を行っていても、それによって、日経BP社及び宮田氏個人とノバルティス社との関係から生じる「利益相反」が解消されるものではない。このような委員の人選に何の問題意識も持たなかったとすれば、厚労省には、そもそも、ノバルティス社の問題も含めて、委員会の調査・検討を公正・厳正に行わせる意図がないのではないかと疑わざるを得ない。
厚労省がこうしたことを続けている限り、今回のノバルティスの降圧剤バルサルタンをめぐる疑惑の解明に真剣に取り組むことを期待するのは無理であろう。公取委がこの問題に独禁法で斬り込むという、厚労省にとって「最悪の事態」も起こりえないわけではない。
東大教授詐取:実質経営の会社維持に流用か 08/13/13 (毎日新聞)
東京大学政策ビジョン研究センターを巡る研究費詐取事件で、東京地検特捜部に詐欺容疑で逮捕されたセンター教授、秋山昌範容疑者(55)が実質経営する会社が、山形県への医療情報システム導入計画を2010年に頓挫させていたことが関係者の話で分かった。同社はこれを機に資金繰りが悪化。特捜部は、教授が研究費を会社維持のために流用した疑いがあるとみており、勾留期限の14日にも起訴するとみられる。
山形県は09年7月、県立病院の医療情報システムの入札を実施し、秋山教授が開発中のシステムを提案した大手コンサルタントが約18億円で落札した。患者の投薬情報などを即時に管理するシステムで、教授が実質経営し元妻が代表を務めるARI(エーアールアイ)社が開発に参加していた。しかし、期限までにシステムは納入されず、県は10年9月、契約を解除した。資金不足などで開発に失敗したとみられる。県の担当者は「教授の説明では魅力的なシステムだったが、完成する気配は一向になかった」と話す。
秋山教授は同時期の09〜10年、愛媛県新居浜市でも、在宅患者の食事などの情報をスマートフォンで介護事業者と病院が共有する実証実験を総務省から4725万円で請け負った。この実験を巡っては、他にも厚生労働省などの研究費が教授側に支払われ、うち数百万円がARIに流れたとされる。特捜部は、教授が総務省から実験に必要な費用を得ていたのに厚労省にも研究費を請求し、ARIの資金繰りや私的な使途に流用したとみている模様だ。
一方、教授側は「研究費は正当な研究の対価」と主張している。弁護人は「研究費はARIの人件費に充てられてはいるが、ARIは研究を通じてシステムをバージョンアップしている。架空請求ではない」と反論する。【吉住遊、近松仁太郎】
ノバルティス疑惑、独禁法適用の可能性 厚労省にとって「最悪の事態」も 08/10/13 (郷原信郎が斬る)
今日の毎日新聞朝刊に掲載された【クローズアップ2013:バルサルタン臨床試験疑惑 元検事の郷原信郎弁護士の話】にも書いたように、ノバルティス・ファーマの降圧剤バルサルタンをめぐる臨床試験への同社の社員の関与、論文でのデータ操作等の問題について、「不公正な取引方法」を禁じる独禁法19条の「欺まん的顧客誘引」に該当する可能性がある。
この点については、検事時代の公取委出向の頃からの知り合いの公取委幹部にも感触を聞いてみたところ、「厚労省が薬事法できちんと対応しないようであれば、ウチが独禁法で出ていくこともあり得ますね」とヤル気を見せていた。
公取委には、過去にも厚労省の領域に独禁法で踏み込んだ実績がある。1996年に独禁法3条前段の「私的独占」を適用して排除措置命令を行った「財団法人日本医療食協会及び日清医療食品株式会社に対する件」だ。この件で、厚労省は、貴重な「天下りポスト」をいくつも失った。今回は、医薬品業界という、厚労省が薬価決定を通して支配する、まさに厚労省の「本丸」の問題だ。厚労省にとって、公取委による独禁法の適用は、想像したくもない「悪夢」以外の何物でもないだろう。
独禁法19条で禁止する「不公正な取引方法」の具体的な禁止行為は公取委告示に委ねられており、公正な競争を阻害する行為に対して機動的に適用できる。
「欺まん的顧客誘引」に関しては、「自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること」と定められている(告示8項)。
今回のノバルティスの問題では、降圧剤バルサルタンの心疾患等への効能を、多数の大学の研究者の論文によって根拠づける宣伝広告を行っていたが、データの不正操作等があったことが判明したことによって論文が撤回されたことで、心疾患等に対しての効能の根拠は失われた。降圧剤が高血圧だけでなく心疾患等に対しても顕著な効能があるという広告宣伝は、現状では、明らかに「著しく優良であると誤認」させるものであり、それが、ノバルティスの事業活動の一環として行われたと認められれば、公取委が「欺まん的顧客誘引」に該当するとして、当該宣伝広告を排除する命令を出すことも可能だ。
この排除措置命令は、あくまで、「著しく優良であると誤認」させる広告宣伝が、医薬品事業者間の公正な競争を阻害するということで排除することが目的であり、その点についての故意は要件ではない。ましてや、効能の根拠とされた論文が不正であったことを会社側が認識していたことも不要だ。そういう意味で、独禁法を適用しようと思えばハードルは低い。公取委には、強制手続を含めた「正式審査」を行うことを決断し、立入検査を実施して会社から関係書類を提出させ、会社関係者の事情聴取等を通じて事実解明をしていくこともできる。
もちろん、厚労省の側が薬事法に基づいて十分な対応をするというのであれば、公取委が敢えて踏み込む必要はないであろう。しかし、現在のところ、この問題についての厚労省の対応は「厚労大臣直轄の有識者の検討委員会」による調査・検討に委ねられているようだ。それが、事案の真相解明や薬事法適用による厳正な対応につながらないようであれば、独禁法の出番となる可能性も十分にある。
今朝の毎日新聞朝刊の記事によると、この検討委員会の委員には、以前よりノバルティス社によるプロモーション戦略に参画し、バルサルタンの臨床試験の経過や成果を大きく紹介していきた日経BP社の特命編集委員の宮田満氏が就任しており、他の委員から「委員会の信頼性が疑われかねない」と懸念する声が出ているとのことだ。ネットで調べたところ、日経BP社とノバルティス社という企業間の関係だけではなく、宮田氏個人も、「ノバルティス バイオキャンプ2007国際大会」と題するノバルティス社主催のバイオ研究者の国際交流のための大イベントで審査員代表を務めるなど、同社との接点がある。個人的にも、同社のプロモーションにも深く関わっていた疑いがある。
このような人物が、ノバルティス社の疑惑を含む問題について調査・検討する委員会の委員として加わるのは典型的な「利益相反」である。上記毎日新聞の記事で、日経BP側は「当社としても今回の問題について検証報道を続けており、就任に問題はないと認識している」とコメントしているが、検証報道を行っていても、それによって、日経BP社及び宮田氏個人とノバルティス社との関係から生じる「利益相反」が解消されるものではない。このような委員の人選に何の問題意識も持たなかったとすれば、厚労省には、そもそも、ノバルティス社の問題も含めて、委員会の調査・検討を公正・厳正に行わせる意図がないのではないかと疑わざるを得ない。
厚労省がこうしたことを続けている限り、今回のノバルティスの降圧剤バルサルタンをめぐる疑惑の解明に真剣に取り組むことを期待するのは無理であろう。公取委がこの問題に独禁法で斬り込むという、厚労省にとって「最悪の事態」も起こりえないわけではない。
真相究明、どこまで 高血圧薬ディオバン論文不正 08/08/13 (朝日新聞)
【編集委員・浅井文和、小宮山亮磨、今直也】製薬大手ノバルティスの高血圧治療薬ディオバン。「血圧を下げる効果を超えた作用がある」とした京都府立医科大と東京慈恵会医科大の臨床研究で、論文にデータ操作などの不正が見つかった。いずれもディオバンをのんだ患者と別の薬をのんだ患者それぞれのグループで、脳卒中などの発症率を比べる研究だったが、効果には疑問符がついている。両医大の調査で何が、どこまでわかったのか。
■京都府立医大 脳卒中発症率を改変
京都府立医大の研究では、脳卒中などの発症率のデータがディオバンに有利になるように操作された。
「元社員は市立大の非常勤講師を兼務していたが、参加した5大学の臨床研究の全てで、市立大の許可を得ていないことも判明。市立大側は『重大な虚偽の記載』とみて調べている。」
なぜこのような詐欺の天才のような事が出来たのか?誰も不審に思わなかったのか?それとも暗黙の了解だったのか?
架空の研究グループ名を記載 ディオバン論文不正問題 08/08/13 (朝日新聞)
ノバルティスの高血圧治療薬ディオバンをめぐる臨床研究の論文不正問題で、データの分析をした同社元社員の所属先として記された大阪市立大の研究グループは存在しないことがわかった。元社員は市立大の非常勤講師を兼務していたが、参加した5大学の臨床研究の全てで、市立大の許可を得ていないことも判明。市立大側は「重大な虚偽の記載」とみて調べている。
トピックス「高血圧治療薬の論文不正問題」
元社員はディオバンの効果をほかの高血圧薬と比べた東京慈恵会医科大や京都府立医科大など5大学が実施した臨床研究の統計解析などに関与。当時は現役の社員だったのに論文では社名を出さず、所属先を大阪市立大としていた。
このうち、慈恵医大と千葉大の論文で、所属先として市立大の「臨床疫学」と書かれていた。論文ではこの部門が、臨床研究の実施主体から独立した形で、薬のデータをめぐる統計解析を担っていたとしていた。
「市立大は02年4月、統計解析の専門家だった元社員に無報酬の非常勤講師を委嘱し、今年3月まで続けていた。」
無報酬で講師の仕事を引き受けるメリットは隠れみのと言う事だったのか??
「元社員は東京慈恵医大と千葉大の論文で、所属先を大阪市立大大学院医学研究科の「臨床疫学」講座と記載。」
計画的な犯行を裏付ける1つなのか?
ノ社元社員「所属先」実在せず 降圧剤データ操作問題 08/08/13 (河北新報)
製薬会社ノバルティスファーマ(東京)の降圧剤ディオバン(一般名バルサルタン)を使った臨床研究のデータ操作問題で、大阪市立大非常勤講師として研究に参加していたノ社元社員が所属先として論文に記載していた講座は実在しないことが8日、市立大への取材で分かった。
元社員は東京慈恵医大と千葉大の論文で、所属先を大阪市立大大学院医学研究科の「臨床疫学」講座と記載。市立大が調べたところ、医学研究科にも医学部にもこうした名称の講座はなく、過去にも存在しなかった。
市立大は02年4月、統計解析の専門家だった元社員に無報酬の非常勤講師を委嘱し、今年3月まで続けていた。
ノバルティスファーマ降圧剤に副作用追記-厚労省が指示 08/07/13 (医療介護CBニュース)
降圧剤「ディオバン」(一般名バルサルタン)で皮膚障害の副作用が報告されていることを受け、厚生労働省は7日までに、ディオバンの製造販売元の製薬会社ノバルティスファーマに対し、使用上の注意の「重大な副作用」に、重篤な皮膚症状を伴う中毒性表皮壊死融解症などを追記するよう指示した。
この降圧剤をめぐっては、医師主導臨床研究で同社の社員(当時)がデータ操作に関与した疑いが指摘されている。今回の追記について、同社は「国内症例の集積などに基づくもので、医師主導臨床研究とは関係ない」として、データ操作との関連性を否定している。
厚労省は、使用上の注意の「重大な副作用」の項に、「中毒性表皮壊死融解症、皮膚粘膜眼症候群、多形紅斑があらわれることがある」との記載を加えるとともに、「観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと」などと明記するよう求めた。【新井哉】
まさに企業の社会的責任と企業の体質を示したケースだと思う。
降圧剤:臨床試験 ノバルティスファーマ社ぐるみで支援 (1/2)
(2/2) 08/05/13 (読売新聞)
降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験疑惑で、製薬会社ノバルティスファーマの多くの人間が臨床試験を支援していた実態が浮かび上がっている。厚生労働省は9日に大臣直轄の検討委員会をスタートさせてデータ解析に関わったノ社の社員(5月に退職)から事情を聴く意向だが、真相に切り込むには他の社員たちからの聴取も欠かせない。【八田浩輔、河内敏康】
・社名伏せ データ解析の社員紹介
・大学寄付金「上層部の了承が必要」
◆「統計の専門家」
「大阪市立大の非常勤講師という名刺を渡された。社員と名乗らなかった」。2002年に試験を始めた東京慈恵会医大の望月正武元教授(72)は、元社員との出会いを大学側にこう証言した。
元社員を「統計の専門家」として望月氏に引き合わせたのは、ノ社のマーケティング担当者だ。大阪市大によれば、元社員は02〜12年度に非常勤講師だったが、勤務実態は事実上なかった。慈恵医大によると、4種類の名刺を使い分け、社名が一切書かれていないものもあったという。
◇販売戦略の一環
ノ社の社内資料によれば、00年11月に発売した直後のバルサルタンの年間の売り上げ目標は最大で500億円だったが、他社も含めた同種の降圧剤市場が急拡大するのに伴って上方修正。02年に1000億円を目指す社内プロジェクトがスタートした。関係者は「PRのための予算も増えた」と言う。「降圧を超える効果」が臨床試験で証明されることを期待し、各地の大学に試験が提案されていった。
結局5大学の試験に参加した元社員は、09年に社長賞を受賞している。当時社長だった三谷宏幸最高顧問は「疑義のある論文という認識が無かった。今となっては反省する」と釈明している。
元社員は循環器マーケティング部門に所属していて、当時の上司の多くは既に退社している。ノ社は「調査したが、元社員によるデータ操作や上司が操作を指示したことを示す事実は認められない」と不正への関与を否定するが、退社した当時の上司らからは「強制力がなく難しい」と聞き取りしていない。
◆宣伝記事で援護 慈恵医大の論文は07年に一流医学誌ランセットに掲載された。発表直後から試験の信頼性などを疑問視する意見が国内外の専門家から上がったが、ある関係者は「疑念を打ち消すために、国内外の高血圧分野の権威を招いた座談会形式の宣伝記事を専門誌に掲載した」と明かす。
慈恵医大、京都府立医大のように患者数が3000人を超す大規模臨床試験の経費は数億〜十数億円といわれる。ノ社は使途を限定しない奨学寄付金を府立医大に計1億440万円(09〜12年度)、慈恵医大に計8400万円(05〜07年)提供している。ノ社は「研究の支援に用いられることを意図、期待した」としている。
「数千万円の寄付には役員クラスへの説明と了承が必要だ。上層部が何も知らなかったでは済まされない」(ノ社に在籍した男性)
新法を検討するようだが、当然だ!強制力がないので真相解明も出来ない。元社員のデータ改ざん濃厚…高血圧薬・研究論文 07/31/13 (読売新聞)であるにも関わらず、事実究明が進まない。法的な罰則そして強制力のある調査が必要な事は明白だ!
ディオバン採用中止の報道&ディオバン事件の真相究明を望む
「ノバルティス社はディオバンを累計1兆2000億円売り上げたそうです。
不正論文を元にディオバンを売りまくったノバルティス社は、薬剤費の3割を負担した患者様個人、7割を負担した健保組合、国民健康保険連合会、社会保険診療報酬支払基金に返金すべきだとの意見があるそうです。
こうなると詐欺罪ですから刑事事件に出来ませんか?刑事ならノバルティス社元社員の身柄拘束も可能では。」
07/31/13 (しんどい、痛い、つらい。マスターズⅡのベンチプレス)
臨床研究の不正に罰則…政府が新法を検討 08/05/13 (読売新聞)
政府は、製薬会社ノバルティスファーマの高血圧治療薬「ディオバン」の臨床研究でデータ改ざんが相次いで発覚した問題を受け、臨床研究を規制する新法を制定する方向で検討に入った。
新法は、臨床研究のカルテなどのデータ保存や国への届け出を義務づけ、違反には罰則を設ける内容となる見通しだ。
厚生労働省は、改ざんの実態解明と再発防止策を検討する委員会を設置し、9日から議論を開始する。政府は委員会の結論を踏まえ、新法に関する詰めの検討を行う。
現行制度では、新薬の承認審査に必要な「治験」の場合、薬事法で国への届け出やデータ保存が義務づけられており、不正な行為には承認取り消しや治験の中止、罰金などが科される。だが、臨床研究には倫理指針があるだけで、規制する法律はなく、指針に反しても処罰されない。
東京慈恵会医大の望月正武同大元教授の証言がとてつもなく不自然である事がわかる。このような事態になって黙っているとノバルティス ファーマ社となんらかの関係を疑われると思ったから仕方がなく証言したと思う。法的な罰則が導入されていれば望月正武同大元教授による証言のような不適切な行為の見逃しはなかった、又は、見逃す可能性は低くなっていたと思う。
厚生労働省は臨床研究に関して倫理指針で対応し続ける限り、同じ事が繰り返される可能性を残す。そして強制的な調査が出来ないので嘘を付き通せば、本人及び企業のイメージを悪くをするが、処分や証拠に基づき不正に不正を行ったと断定される事がない。
厚生労働省は臨床研究に関して倫理指針ではなく法的な罰則を新たに導入するべきだ。
法的な罰則がなければ利益が方が大きければ倫理指針に従わない人達はいるはずだ。能力や学歴とは全く関係ない人間性の問題だからだ。
厚生労働省の人間達と有識者達が自分達の業界に有利にするためにしかしながら国民を欺くために法的な罰則でない倫理指針で対応しているように思う。
利益相反(Conflict of Interest:COI)については多くの研究者、科学者そしてエンジニアは理解しているはずだ。しかも英語で論文を書く人達は利益相反(Conflict of Interest:COI)や倫理規定(Code of Ethics)について十分に理解しているはずだ。事実を記載する事でバイアスがあるかもしれないことを想定してデータや数値をチェックできる。自社の製品であれば、自社の社員が関与していれば人間的によほど立派で公平な人間なければデータを自社に有利にする可能性がある。だからこそ利害関係のない人間が行う事により、公平性が保たれる可能性が高くなる。利害関係がある人間が関与していれば情報として明記されるべきである。これぐらいの事はたいした大学など卒業しなくとも理系であれば理解できる事である。
ディオバン採用中止の報道&ディオバン事件の真相究明を望む
「ノバルティス社はディオバンを累計1兆2000億円売り上げたそうです。
不正論文を元にディオバンを売りまくったノバルティス社は、薬剤費の3割を負担した患者様個人、7割を負担した健保組合、国民健康保険連合会、社会保険診療報酬支払基金に返金すべきだとの意見があるそうです。
こうなると詐欺罪ですから刑事事件に出来ませんか?刑事ならノバルティス社元社員の身柄拘束も可能では。」
07/31/13 (しんどい、痛い、つらい。マスターズⅡのベンチプレス)
高血圧薬や研究論文のデータ改ざん濃厚になってきた。しかし強制力のない調査で限界と書いている記事も多い。詐欺罪の刑事事件として警察や検察が介入するべきだ。
イギリスのように法制度化して厳しい制度にすると複雑になり臨床研究に支障が出ると法制度化に反対する意見があるが、それは今までの環境を維持したい、又は、製薬会社との緊密な関係を保ちたい人達側の意見であろう。そしてこの人達は厚生労働省とも関係を持っているのではと推測する。誰がイギリスを全く同じ法制度を導入すると言っているのか?そして同じシステムを導入すると言っているのか?とにかく法的な罰則そして強制力のある調査を導入して詳細はイギリスのシステムよりも緩和したシステムでも良いと思う。法的罰則及び強制力のある調査がなければ、必ずずる賢い人達や企業はそこを十分に理解したうえで対応してくる。いたちごっこだと言う人がいるかもしれないが、それでも倫理指針よりは効果的だと強く思う。もし厚生労働省が倫理指針にこだわるのであれば、調査や背景を無視して結論ありきの対応で、問題を起こした業界よりのスタンスに立っていることを証明している一例と思う。だからこそ、過去の問題に対して厚生労働省の対応や判断が疑問がある説明の1つになると思う。
臨床研究の問題点と基盤整備 東京大学医学部附属病院 臨床試験部 荒川義弘 2006.11.21 (厚生労働省のサイト)を見つけた。開けない人はここをクリック「日本は自主臨床試験にGCPが適用されていないばかりか規制も多く、質・量とも世界にかなりの
遅れをとっている。・・・臨床研究に係わる規制・ガイドライン等の環境整備」が2006年に既に指摘されていた。このような点を考えても厚生労働省の対応に問題があると思える。今回の事件を教訓にして法的な罰則そして強制力のある調査を導入するべきだ。
慈恵医大もノバルティス元社員が解析 望月正武客員教授が丸投げ 07/31/13 (千日ブログ)
産学連携と信頼7(慈恵医大も企業共々責任放棄) 07/31/13 (市原研究室掲示板2)
慈恵医大元教授が証言 高血圧薬ディオバン論文の図表、製薬元社員から 08/02/13 (朝日新聞)
製薬大手ノバルティスの高血圧治療薬ディオバンの効果を調べた東京慈恵会医大の臨床研究の論文不正問題で、研究代表者の望月正武同大元教授(71)が朝日新聞の取材に対し、データを人為的に操作したと疑われる元同社員(今年5月退職)の関わりについて証言した。研究室には統計解析ができるスタッフがおらず、研究結…
東電の対応を見て思うけど、企業の体質の問題じゃなのかな?
千葉・市原のコスモ石油、また流出事故 海には流れず 08/03/13 (朝日新聞)
2日午前6時45分ごろ、千葉県市原市五井海岸のコスモ石油千葉製油所から「原油を移送中に配管から漏れた」と市消防局に通報があった。市消防局によると、タンクと蒸留塔をつなぐ配管に直径5ミリ程度の穴が開いており、計500リットルの原油が流出した。けが人はなく、海への流出もなかった。消防車など11台が出動し、処理した。
同製油所では、東日本大震災で液化石油ガス(LPG)タンク17基が爆発炎上した。昨年6月にもタンクからアスファルトが海上に流出する事故が起きている。
同製油所は、国内4カ所ある同社の製油所のうち最大規模。
同社広報室は朝日新聞の取材に対し、「震災に続き昨年も事故を起こした中で地域の皆さんに申し訳ない。気を引き締めて安全操業に努める」とコメントした。
厚生労働省は臨床研究に関して倫理指針ではなく法的な罰則を新たに導入するべきだ。
法的な罰則がなければ利益が方が大きければ倫理指針に従わない人達はいるはずだ。能力や学歴とは全く関係ない人間性の問題だからだ。
厚生労働省の人間達と有識者達が自分達の業界に有利にするためにしかしながら国民を欺くために法的な罰則でない倫理指針で対応しているように思う。
利益相反(Conflict of Interest:COI)については多くの研究者、科学者そしてエンジニアは理解しているはずだ。しかも英語で論文を書く人達は利益相反(Conflict of Interest:COI)や倫理規定(Code of Ethics)について十分に理解しているはずだ。事実を記載する事でバイアスがあるかもしれないことを想定してデータや数値をチェックできる。自社の製品であれば、自社の社員が関与していれば人間的によほど立派で公平な人間なければデータを自社に有利にする可能性がある。だからこそ利害関係のない人間が行う事により、公平性が保たれる可能性が高くなる。利害関係がある人間が関与していれば情報として明記されるべきである。これぐらいの事はたいした大学など卒業しなくとも理系であれば理解できる事である。だからこそノバルティス ファーマ社の下記のコメントはすごく日本的でふざけたコメントである。「これらの臨床研究が開始された2001年から2004年当時、医師主導臨床研究における利益相反を明確に規定したガイドラインがありませんでした。」との理由で今回のような関わり方が許されると思ったのか?ノバルティス ファーマ社の対応に関する記事を読めば、倫理指針ではなく法的な罰則は必要な事は明らかだ。
利益相反および医師主導臨床研究に対する理解不足:
これらの臨床研究が開始された2001年から2004年当時、医師主導臨床研究における利益相反を明確に規定したガイドラインがありませんでした。このため、元社員およびその上司は、製薬企業の社員の医師主導臨床研究に対するかかわり方について理解が不足しておりました。さらに、当社の教育が不十分であったため、開示の在り方についても正しく理解していませんでした。
06/03/13 (ノバルティス ファーマ株式会社)
ディオバン採用中止の報道&ディオバン事件の真相究明を望む
「ノバルティス社はディオバンを累計1兆2000億円売り上げたそうです。
不正論文を元にディオバンを売りまくったノバルティス社は、薬剤費の3割を負担した患者様個人、7割を負担した健保組合、国民健康保険連合会、社会保険診療報酬支払基金に返金すべきだとの意見があるそうです。
こうなると詐欺罪ですから刑事事件に出来ませんか?刑事ならノバルティス社元社員の身柄拘束も可能では。」
07/31/13 (しんどい、痛い、つらい。マスターズⅡのベンチプレス)
高血圧薬や研究論文のデータ改ざん濃厚になってきた。しかし強制力のない調査で限界と書いている記事も多い。詐欺罪の刑事事件として警察や検察が介入するべきだ。
臨床研究:データ長期保存、倫理指針で盛る方針 厚労省 05/25/13 (毎日新聞)
厚生労働省は25日、臨床研究を実施する研究機関向けの倫理指針で、研究データの長期保存を求める規定を新たに盛り込む方針を決めた。研究成果に対して外部から疑念が出た場合に備え、検証を可能にするための措置。指針は従来、患者の権利保護が主な目的だったが、降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の疑惑などを受け、研究不正を念頭に置いた新たな規定も必要と判断した。
臨床研究と疫学研究の倫理指針の統合作業を進める厚労省10+件の有識者会議で、大筋で了承された。来月下旬に中間報告をまとめる。
この日の会議では、出席者から「資料は研究が批判にさらされた時、科学的に検討するための唯一の材料。保存は研究者の責務だ」などとする意見が相次いだ。厚労省10+件によると、統一した保存期間は定めないが、個別の研究計画を立てる際に期間の設定を求める方針。また、研究の進捗(しんちょく)状況の公開や監査の導入も可能か検討するが、これらについては慎重意見もあり、実現性は不透明だ。
臨床研究の中でも新薬の製造・販売承認のための「治験」では、研究成果の信頼性を確保するために監査やデータの保存義務などの厳格な規制があるが、治験以外の臨床研究では研究者の判断に任されていた。
バルサルタンに血圧を下げる以外の効果もあると結論付けながら、データ操作されていた京都府立医大の論文不正は、臨床研究を巡る制度に不正を許す土壌があることを浮き彫りにし、田村憲久厚労相も指針の早期見直しの必要性に言及していた。府立医大の調査では、研究チームの事務局が保存していた患者データとカルテなどを照合した結果、データ操作が明らかになった。【八田浩輔】
日本医学会利益相反委 ディオバン医師主導臨床研究のCOI申告違反を確認 高久会長「大学・企業双方に責任ある」 05/27/13 (ミクスOnline)
日本医学会利益相反委員会は5月24日、ARBディオバン(一般名:バルサルタン)の医師主導臨床研究をめぐる一連の問題について議論し、利益相反(COI)の開示を定めた日本医学会の指針に違反することを確認した。日本医学会の高久史麿会長は委員会後に記者会見に臨み、「非常に残念なこと。信頼が揺らいだと言われても仕方がないと思っている」と指摘した。
この日の利益相反委員会は、日本循環器学会からディオバンの医師主導臨床研究の問題について報告を受け、今後の対応を議論した。日循学会は、学会機関誌のオンライン版に掲載されたKYOTO HEART Studyのサブ解析に関する2論文について、当時COIに関する指針細則の試行期間であったものの、申告すべき2点の開示がなかった点を指摘。具体的には、ノバルティスファーマの元社員が試験の統計解析に関わり、 かつ同社から京都府立医科大学循環器内科学・腎臓内科学へ200万円以上の奨学寄附金があったのにもかかわらず、それらが開示されなかったことを報告した。委員会後に会見した日循学会の永井良三代表理事は、「試行期間とはいえ2つの論文で利益相反の開示が不十分であったことは大変遺憾」と述べた。
◎ 論文撤回はデータクリーニングの不備
永井代表理事は会見で、KYOTO HEART Studyのサブ解析論文が日循学会の機関紙Circulation Journalから撤回された理由に言及し、「2012年10月に学会会員から試験対象者における血清ナトリウム値やカリウム値の標準偏差(ばらつき)が不自然に大きいと指摘があった」と説明。同誌編集長が京都府立医科大学の筆頭著者に問い合わせたところ「データのクリーニングが不十分なまま解析が行われていた」との回答を得ていたことを明らかにした。永井理事長は、「(ねつ造があったかどうかは)把握していない。カルテに戻って調査しないとわからないだろう」と述べ、現段階でのデータ改ざんの可能性は否定した。
また会見で日本医学会の高久会長は、同問題に関連する大学で第三者機関による調査が行われているとし、「日本医学会としては全国医学部長病院長連絡会議を通じて調査を進めていただきたいと考えている」と述べた。
◎高久会長「COIを守ることが日本の医学研究の進歩のために必要」
COIをめぐっては、日本医学会利益相反委員会が2011年に医学研究の「COIにかかわるガイドライン」を作成し、118の分科会に対してCOI指針の作成を推奨している。ただ、昨年時点で指針を作成した学会は58%に止まる状況だ。この日の会見に同席した利益相反委員会の曽根三郎委員長は、現行の指針でCOIの申告対象期間が「過去1年」となっている点にも触れ、「今回のように長い期間行われる研究もあり、その間、多額の資金が必要となる。1年前から(の開示)では利益相反が正しくわからないのではないか。研究ごとに情報が開示できる仕組みが必要」と指針の見直しも含めて検討していくことを明らかにした。
また高久会長は、日本では医学研究に対する公費助成が不十分であり、産学連携は医学の発展に不可欠との見地から「これからはCOIを守ることが日本の医学研究の進歩のために必要」と理解を求めた。
◎高久会長 京都府立医大によるノバルティスとの取引停止 「やりすぎ」
なお、高久会長は、京都府立医大が5月23日付でノバルティスとの医薬品の取引を停止すると発表したことについて、「今回の件は、京都府立医大とノバルティス双方に責任がある。取引の中止はやり過ぎだと思う。ノバルティスの社員が研究に参加し、統計に関与していたことは府立医大の人は知っていたはず。今になって(論文が)撤回されたから、あるいはメディアに公表されたから当該企業との取引をやめるということは、少しおかしいのでは」との認識を表明した。一方、ノバルティスに対して高久会長は、「現在は当該研究成果を販促に使用していないというが、それまで大いに宣伝してき た。その点については社会的責任がある」と指摘した。日本医学会としての対応については「日本医学会は罰する立場ではない。この件が公になり、社会的に罰を受けているのではないか」と述べた。
企業利益追求…研究ゆがめる 降圧剤「ディオバン」データ 慈恵医大も操作 (1/5ページ)
(2/5ページ)
(3/5ページ)
(4/5ページ)
(5/5ページ) 07/31/13 SankeiBiz(サンケイビズ)
製薬会社「ノバルティスファーマ」(東京)が販売する高血圧治療の降圧剤「ディオバン」(一般名・バルサルタン)を使った臨床研究のデータ操作問題で、東京慈恵医大は7月30日、望月正武客員教授(71)が発表した論文の血圧値のデータにカルテの記載と異なるものがあり、人為的な操作が加えられていたとする調査委員会の中間報告を明らかにした。ディオバンの臨床研究に関する論文でデータ操作が確認されたのは、京都府立医大に続いて2件目。
望月氏は「重大な疑念を生じさせたことにより、患者をはじめ皆様に多大な心配と迷惑をかけたことを深くおわびする」と謝罪し、英医学誌ランセットに掲載した論文の撤回を申し出るとする文書を発表した。
調査委は、操作はデータの解析段階で行われたと分析した上で「解析はノ社の元社員に全面的に委ねられていた」と結論づけており、元社員の不正への関与を強く示唆した。
報告によると、カルテでは、ディオバンを投与していた患者の方が未投与の患者より血圧が低かったが、論文では両者の間に血圧の差がなくなるよう操作されていた。論文はディオバンが他の降圧剤に比べ脳卒中や狭心症などの予防に有効だと結論づけているが、こうした効果が血圧の高低で生じたと思われないようにした可能性があるという。
調査委は元社員に対する聴取も実施。元社員は「データ操作に思い当たることはなく、自分は関係していない」などと説明したが、調査委は元社員の供述は信用できないと判断した。
京都府立医大に続き、東京慈恵医大でも明らかになった降圧剤「ディオバン」の臨床研究をめぐるデータ不正操作。しかし、両大学や、ノバルティスファーマの第三者機関による調査からは、研究者と企業との間で何が起き、なぜ問題が拡大したのかといった真相は依然見えてこない。
警戒される日本人論文
「すでに外国の科学誌などでは『日本人の論文だから注意して読まないといけない』といわれている」。日本学術会議の大西隆会長は相次いで指摘される論文不正が与える影響をこう指摘する。
今回、特に研究者の中で深刻な事態として受け止められているのが、企業の利益追求のために研究結果がゆがめられた疑惑がある、という点だ。臨床研究を行った5大学にはノ社から多額の奨学寄付金が渡され、関与が疑われているノ社の元社員は、データ解析や論文執筆といった幅広い分野で臨床研究に加わっていたにもかかわらず、論文でノ社の所属を隠していた。
外部から金銭提供などを受けることで研究の中立性に疑義が生じることを「利益相反」といい、この状態がデータの不正操作とともに疑惑を増幅させている。
しかし、産学連携が進む現状では、重要な研究になればなるほど、企業との結びつきは強くなり、利益相反は生じやすくなる。
ノ社は昨年236億円提供
日本医学会は2011年、利益相反で研究がゆがめられることがないよう、論文や学会発表を行う際には研究費の提供先を明示するとした利益相反ガイドラインを作成。日本製薬工業協会は会員企業に、来年度から研究者らに支払った金銭を公開するよう求めている。
ノ社も29日、大学などへ支払った研究費や寄付金、謝礼、接待費などを公表。12年は計約236億円だったと明らかにした。
北里大学臨床研究機構の伊藤勝彦部長(54)は「予算がなければ重要な研究はできないし、研究費を出す製薬会社はいい研究結果を出してほしいと思うのも当然。だが、だからといって不正が行われるわけではない。研究者や企業は、利益相反が生じているなら隠すことなく表にした上で研究成果を発表していくべきだ」と指摘している。(SANKEI EXPRESS)
【ディオバンをめぐる問題の経過】
2000年
11月 ノバルティスファーマが国内販売
2002年
1月 東京慈恵医大の望月正武教授(当時)が臨床研究を本格開始
2004年
1月 京都府立大の松原弘明教授(当時)が臨床研究を本格開始
2007年
4月 慈恵医大の研究結果が英ランセット誌に掲載
2009年
1月 日本高血圧学会が「高血圧治療ガイドライン」作成。慈恵医大の論文が参考文献に
2009~12年
府立医大の研究結果が相次いで医学誌に掲載
2012年
4月 ランセット誌が慈恵医大のデータを疑問視する投稿を掲載
12月 府立医大の論文が撤回され始める
2013年
4月 慈恵医大が調査委設置を決定
7月11日 府立医大が「データ操作があった」との調査結果を発表
7月29日 ノ社が「元社員による意図的なデータ操作は確認できなかった」との第三者調査結果を発表
7月30日 慈恵医大が「血圧値のデータが操作されていた」とする中間報告を発表
元社員のデータ改ざん濃厚…高血圧薬・研究論文 07/31/13 (読売新聞)
製薬会社ノバルティスファーマの高血圧治療薬「ディオバン」の大規模臨床研究をめぐる問題で、慈恵医大の調査委員会(委員長=橋本和弘・同大医学科長)は30日、同大の研究論文に関する中間報告書を公表した。
論文の基となった血圧に関するデータが、改ざんされたと結論づけた。
調査委は「データの解析や図表の作製を同社の元社員(今年5月退職)1人に任せきりにしており、大学は関与していない」と説明し、「(データ改ざんに)元社員の関与が強く疑われる」と指摘した。元社員は今月下旬、調査委に、「解析のアドバイスをしただけ」と関与を否定しているという。
調査委は2007年に英医学誌「ランセット」で発表した論文を「撤回することが妥当」と判断した。
ディオバンの臨床研究は、血圧を下げる本来の効果とは別に、脳卒中や狭心症など心血管疾患への効果を検証するために国内5大学で行われた。慈恵医大では02~05年、循環器内科の望月正武教授(当時)が主導した。高血圧患者3081人について、ディオバンを使ったグループとディオバン以外の薬を使ったグループに分け、血圧を下げた。
その後足かけ4年にわたり経過観察し、脳卒中や狭心症など重い心血管疾患が起きた割合を分析したところ、ディオバンを使ったグループが発症する割合は、他のグループに比べ39%少なかったとまとめた。
同大の調査委が、研究に使ったデータと大学に残っていたカルテを照合したところ、大学が保管していた671件分の血圧のデータ中、最高血圧が86件(12・8%)で一致しなかった。二つのグループの血圧のばらつきを小さくし、研究の精度が高く見えるように改ざんした疑いがあるという。
「ノバルティスファーマ(東京)の降圧剤ディオバン(一般名バルサルタン)を使った臨床研究の信頼性を検証していた東京慈恵医大の調査委員会は30日、血圧値のデータが操作されていたとする中間報告をまとめた。」
「橋本委員長は、望月氏や多くの医師が『自分たちにはデータ解析の知識も能力もない』と話したことなどから、統計解析とデータ操作をしたのは元社員との見方を示した。一方、元社員は聴取で『自分は責任ある立場で解析を行ったことはない。操作についても思い当たることはない』と否定したという。」
ほぼ、誰かが完全に嘘を付いている事は間違いない。
外資系の企業であれば徹底した調査が出来るはずだ。出来ないのは明確な報告が出来ない何かがあるのか、報告できない事があり日本の厚労相をなめている証拠。
黙って時間を稼げば何とかなると思っている証拠だろう。ここで厚労省が何も出来ないのであれば、法改正が必要だ!外国企業が違法行為をしても、
徹底的に調査するべきだ!日本は英語アレルギーがあるのか知らないが外国企業に甘すぎる!
慈恵医大でもデータ操作 降圧剤臨床研究 07/31/13 (中国新聞)
ノバルティスファーマ(東京)の降圧剤ディオバン(一般名バルサルタン)を使った臨床研究の信頼性を検証していた東京慈恵医大の調査委員会は30日、血圧値のデータがカルテと一致せず、操作されていたとする中間報告をまとめた。
研究責任者の望月正武もちづき・せいぶ客員教授は英医学誌ランセットに発表した論文の撤回を表明。調査委員長の橋本和弘はしもと・かずひろ医学科長は記者会見で「多くの方々に多大な心配を掛けた」と謝罪するとともに、データ解析を担当したノ社の元社員が操作に関与した可能性を指摘した。
京都府立医大に続き、データ操作と論文撤回という重大事態が起きたことで、日本の臨床研究に対する信頼は大きく損なわれた。
橋本委員長は、望月氏や多くの医師が「自分たちにはデータ解析の知識も能力もない」と話したことなどから、統計解析とデータ操作をしたのは元社員との見方を示した。一方、元社員は聴取で「自分は責任ある立場で解析を行ったことはない。操作についても思い当たることはない」と否定したという。
調査委は学外の3人を含む9人で構成。元社員が、論文では非常勤講師だった大阪市立大の所属を示し、「解析グループはノ社から独立していた」と書いたことを「不実記載」と認定。望月氏の責任は重大とした。血圧データの操作も含め、論文は「すでに価値がない」と断じた。
一方、望月氏の講座にはノ社から、判明した2005~07年だけで計8400万円の寄付があった。ただ、調査委はノ社からの資金提供は論文に記載されており「ルール違反はない」とした。
論文の基になった血圧データには、カルテとは異なるものが相当数あった。研究は、ディオバンが狭心症や脳卒中などの発症を他の薬より減らせるかを調べたもの。操作は他の薬と比較する上で、血圧の下がり方を同じにしようとしたためだと調査委は推測している。ただ、ディオバンの血圧を下げる効果や安全性が否定されたわけではない。
研究は約3千人の患者が参加して02年から行われ、07年、発症を39%減らせるとの結果をランセットに発表していた。
東京慈恵医大でもデータ操作 07/30/13 (NHK)
大手製薬会社「ノバルティスファーマ」の高血圧の薬の効果を調べた複数の大学の臨床研究にこの会社の社員が関与していた問題で、東京慈恵会医科大学の調査委員会は、30日、論文に記載された血圧のデータに人為的な操作が相当数、加えられていたという中間報告を発表しました。
この問題でデータの操作が指摘されたのは京都府立医科大学に続いて2件目です。
この問題は、ノバルティスファーマが販売する高血圧の治療薬「ディオバン」の効果を調べた複数の大学の臨床研究にこの会社の当時の社員が関与していたもので、このうち京都府立医科大学は、論文のデータには人為的な操作があり、ほかの薬より脳卒中や狭心症を減らせるとした臨床研究の結果には誤りがあった可能性が高いとする調査結果を発表しています。
30日、東京慈恵会医科大学の調査委員会が発表した中間報告によりますと大学の研究グループが行った臨床研究の論文には、患者の血圧のデータにカルテの記載と異なるものが相当数あり、人為的なデータの操作があったとしています。
これについて調査委員会は、データの操作は、大学の研究者が行ったものではなくデータの解析の段階で行われたとみられるとしています。
そのうえでデータの解析は、ノバルティスファーマの当時の社員に委ねられていたにもかかわらず、論文にはノバルティスファーマは関与していないと事実に反する記載があり、研究チームの教授の責任は重いとしています。
高血圧薬のディオバンはこうした臨床研究の結果を薬の販売促進などに使っていて、年間1000億円以上を売り上げる商品になっていました。
<降圧剤データ>慈恵医大、元社員に丸投げ「大きな間違い」 07/30/13 (毎日新聞)
累計1兆円を超す売り上げを誇る大ヒット薬を支えた科学的根拠が崩れ去った。降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験で論文不正を認めた東京慈恵会医大の調査結果は、製薬会社ノバルティスファーマの元社員による改ざんの疑いを強く示唆した。一方、医師が製薬企業に過度に依存した試験だったことも浮き彫りとなり、医薬業界への不信感は極まっている。
「遺憾ながら、何者かによってデータが人為的に操作されていると考えられる」。東京都港区の慈恵医大で記者会見した橋本和弘調査委員長は、終始硬い表情を崩さなかった。
調査報告書は「データ操作は統計解析段階でなされた」と推認し、元社員の不正への関与を強く示唆した。一方、今月27日に大学の聞き取りに応じた元社員は、データ操作への関与を否定したばかりか、統計解析を行ったことも否定したという。しかし、責任者の望月正武元教授ら大学側の研究者十数人は「統計解析をしたのは元社員だ」と証言。このため調査委は「元社員の供述は虚偽で信用できない」と判断した。
元社員が試験に参加することになったのは、望月元教授がノ社の営業社員に統計の専門家の紹介を依頼したことがきっかけだった。この時、元社員は当時非常勤講師を務めていた大阪市立大など4種類の名刺を持っていたという。だが「試験の最終段階では、ほとんどの研究者がノ社の社員と分かっていた」(橋本委員長)とした。
今回の調査で、資金提供元の製薬会社元社員に、事務局機能から統計解析という研究の根幹まで丸投げするという研究者側の無責任さも明らかになった。
橋本委員長は「研究者側にとって(元社員は)非常に便利で、信頼して任せてしまった。研究チームの大きな間違いで深くおわびしたい」と陳謝。再発防止策として大学内に「臨床研究センター」を設置する方針などを示した。【八田浩輔、河内敏康、須田桃子】
◇強制力なき調査に限界
バルサルタンの臨床試験論文を巡る東京慈恵会医大、京都府立医大、ノバルティスファーマの調査結果が出そろった。慈恵医大は協力を断られた府立医大と異なり、試験に関与したノ社元社員からも聴取。その結果、不正操作は元社員が行ったと推認したが、「消去法」で導いたものでしかなく、元社員は関与を否定している。強制力をもたない当事者による調査の限界といえる。
府立医大の調査では、データとカルテを突き合わせ、他の薬を服用した患者に起きていない虚偽の脳卒中の記述があるなど、バルサルタンの効果を際立たせる大胆な不正操作があった。一方、慈恵医大ではこうした症例に食い違いは無かったが、結論を導く前提となる血圧値が操作されていた。科学的な再検証で「証拠」は見つかったが、誰がなぜ操作を行ったのか特定できないのは、誰かがうそをついているか、真実を知る人間が調査対象から漏れているからだ。
国は、新薬を承認するための治験と異なり、市販後の臨床試験が適正に行われているかをチェックする有効な手立てを講じてこなかった。このことが今回の疑惑を許した側面がある。厚生労働省は有識者検討会で調査を始める。国民が納得できる結論を導き出す責任がある。【八田浩輔】
慈恵医大でもデータ操作 論文撤回へ、降圧剤臨床問題 07/30/13 (共同通信)
ノバルティスファーマ(東京)の降圧剤ディオバン(一般名バルサルタン)を使った臨床研究の信頼性を検証していた東京慈恵医大の調査委員会は30日、血圧値のデータが操作されていたとする中間報告をまとめた。
研究責任者の望月正武客員教授は「重大な疑念を生じさせた」として英医学誌ランセットに掲載された論文の撤回を申し出るとのコメントを発表した。
京都府立医大の研究に続くデータ操作と論文撤回という重大事態で、日本の臨床研究に対する信頼失墜は深刻さを増した。
元社員関わってない証拠どこにあるのか…厚労相 07/30/13 (読売新聞)
高血圧治療薬「ディオバン」の臨床研究データ改ざん問題で、販売元のノバルティスファーマが発表した「証拠は見つからなかった」とする調査結果に対し、田村厚生労働相は30日の閣議後記者会見で、「納得していない」との見解を示した。
8月上旬に設置する大臣直轄の有識者委員会で、研究に関与した元社員への聞き取りを要請する意向だ。
臨床研究を行った京都府立医大の調査でデータ操作の事実は判明しており、田村厚労相は「元社員が関わっていない証拠はどこにあるのか、同社の報告書だけ読んで素直に納得できる状況にない」と語った。
ドル箱降圧剤の論文撤回「有名教授(京都府立医大)と製薬会社(ノバルティスファーマ)の闇」 (1/3ページ)
(2/3ページ)
(3/3ページ) 04/26/13 (現代ビジネス )
「製薬会社がバックに付いた、ここまで大きな疑獄は記憶にありません。販売元の製薬会社『ノバルティス』は、本社のあるバーゼルから匿名チームを派遣していると聞きました。返り血を浴びるのを恐れてか、他社のMR(医薬情報担当者)もこの件について、口を噤んでいます」(医療誌メディカル担当記者)
医療界が激震している。震源地は京都府立医科大学だ。 '09 ~ '12 年にかけて松原弘明元教授(循環器内科)が発表した降圧剤『バルサルタン』に関する論文が昨年末から相次いで3本撤回され、製薬会社と研究者の「不適切な関係」に光が当てられようとしているのだ。製薬会社『ノバルティスファーマ』(東京・港区)が販売するバルサルタンは、血圧を上げる物質の働きを抑える効果があり、高血圧治療に用いられている薬である。
ことの発端は、医師たちの間で話題をさらった松原氏の大規模な研究だ。 '04 年から約5年間の期間をかけ、松原氏は高血圧患者にバルサルタンを投与する臨床試験を行った。被験者は3000人に上り、日本人に対して行われた初めての巨大臨床試験となった。そしてこの結果が '09 年に論文として発表されると、医学界に再び波紋が拡がった。
「欧州心臓病学会誌の電子版に、バルサルタンは『脳卒中や狭心症などのリスクも下げる効果』があると、降圧以外の薬効があったことを発表したのです。松原氏は立て続けに心臓肥大の症状や糖尿病患者にも同様の効果があると日本循環器学会誌に発表し、時の人になったのです」(循環器学会関係者)
血圧を下げるだけでなく、脳卒中や狭心症のリスクも下げる―薬は飛ぶように売れ、販売元の『ノバルティスファーマ』のNo.1ヒット商品になった。他社のMRが明かす。
「妬みたくなるぐらい売れていました。この業界には『ブロックバスター』という言葉がある。従来の治療方法を変えてしまうほどの効果を持ち、莫大な利益を生み出す新薬のことです。バルサルタンこそ、ブロックバスターでした。日本の医療用医薬品中、3番目に売れているノ社のドル箱商品でここ数年は年間1000億円以上を売り上げていた」
しかし、その〝薬効〟は、急速に失せているようだ。昨年末、日本循環器学会誌が「数多くの解析ミス」が発覚したとして、掲載論文の撤回を発表。今年2月には欧州心臓病学会誌も「致命的な問題がある」と、掲載論文を撤回する異例の事態となった。「NPO法人臨床研究適正評価教育機構」の理事長・桑島巌氏が言う。
「あの論文は、発表当初から大きな問題がありました。『脳卒中や心筋梗塞のリスクが下がった』という研究結果を強調したかったからか、不自然なデータが見られたんです。バルサルタンを投与した高血圧患者1500人と、バルサルタン以外の降圧剤を投与した患者1500人を約5年間調査した結果、双方のグループが到達した血圧値(1500人の平均)がほぼ揃っていました。データが操作され、血圧値が合わされた可能性が高い。なぜか? 実はバルサルタンは、降圧剤としてはそれほど高い効果はない。ほかの降圧剤と効き目で勝負しても優位性で劣るんです。だからこそ、プラスαの薬効を目立たせるため、血圧値を合わせる必要があったのでしょう。 '09 年に開かれたヨーロッパ心臓病学会で、松原氏はこの論文内容をスピーチしたのですが、ヨーロッパの医師たちはデータの信憑性が乏しかったためか、黙殺しました。スイスの高血圧の専門家だけが『本当ならば素晴らしい薬だ』と断ったうえで、『私の母親には投与したくないが、妻の母親になら使う』と皮肉っていました」
松原氏の研究をあらゆる角度からバックアップしていたのが、販売元のノ社だ。大学に記録が残っている '08年以降で、ノ社は京都府立医大に1億440万円の奨学寄付金を提供していた。また松原氏が書いたバルサルタンに関する論文には、生物統計の解析担当者としてSという男が名を連ねていた。このS氏は、紛れもないノ社の社員である。
「Sの肩書は『大阪市立大学』となっていました。Sは非常勤講師として年に数回教壇に立つ程度でしたが、隠れ蓑に使ったのでしょう。専門家が少ない業界とはいえ、製薬会社の社員が表立って統計解析に携わるのは問題がある。第三者による松原論文のカルテと生データの照合を進め、真相を究明する必要があります」(前出・桑島氏)
ノ社はドル箱商品のPRに湯水のようにカネを投資した。医療専門誌にバルサルタンの薬効に関するPR記事を度々掲載し、高名な医師の座談会を行ってその効果を喧伝した。
「物凄い販促でした。日本高血圧学会の理事長や、高血圧のガイドラインを作成する幹部が、松原論文を引き合いに出して褒めちぎるんです。登場した医師には、通常、数万円の謝礼が出て、記事が出る時には原稿料も支払われる。それを見た別の医師が、『こんなにいいものがあるのか』とバルサルタンを処方する。バブルですよ」(前出・医療誌記者)
松原氏は4月上旬にも、 '04年に行った心臓の再生医療の申請のために提出した論文の捏造が指摘され、窮地に立たされている。2月末に責任を取る形で大学を辞めているが、「最後まで泣いて抵抗した」と証言する大学関係者もいる。松原氏は本誌の取材に、「論文不正は絶対にないので辞職の必要はないと考えていました」「(S氏と)個人的な付き合いはまったくありません」と回答した。
ノ社は「一般的に医師主導臨床研究は独立した研究であり、ノバルティスとして関与できる性質のものではない」「(S氏が松原氏と)面会した頻度、個人的な付き合いの有無については、承知しておりません」と回答した。
「実は慈恵医大も、 '07年に松原氏の結果と酷似した内容の、バルサルタンの論文を発表しているんです。この統計解析に携わったのも、S氏です。今後慈恵医大の論文にも不正が見つかれば、さらなる大スキャンダルに繋がる可能性もあります」(前出・桑島氏)
莫大なカネを生んだブロックバスターが、医療界を揺るがす〝劇薬〟になりつつある。
上村全柔連会長、8月中辞任と執行部総退陣表明 07/30/13 (読売新聞)
全日本柔道連盟(全柔連)の上村春樹会長(62)は30日、東京都文京区の講道館で開かれた臨時理事会で、8月中の辞任と執行部の総退陣を表明した。
退陣するのは会長のほか、藤田弘明(75)、佐藤宣践(のぶゆき)(69)の両副会長、小野沢弘史・専務理事(66)、村上清・事務局長(63)の5人。理事ではない村上事務局長を除き、執行部は全員、理事職も退く。
外資系の企業であれば徹底した調査が出来るはずだ。出来ないのは明確な報告が出来ない何かがあるのか、報告できない事があり日本の厚労相をなめている証拠。
黙って時間を稼げば何とかなると思っている証拠だろう。ここで厚労省が何も出来ないのであれば、法改正が必要だ!外国企業が違法行為をしても、
徹底的に調査するべきだ!
降圧剤データ操作問題で厚労相「納得できない」 ノ社調査に不満 07/30/13 (産経新聞)
田村憲久厚生労働相は30日の閣議後会見で、製薬会社「ノバルティスファーマ」(東京)が降圧剤を使った臨床研究のデータ操作問題を受けて第三者機関の調査結果を公表したことについて、「調査結果は十分に納得できるものではなかった」と述べ、ノ社の対応に不満を示した。
田村厚労相はノ社が、元社員による意図的なデータ操作や改竄(かいざん)を行ったことは発見できなかったとしたことについて、「(元)社員が関わっていないという証拠が報告書からは十分に受け止められない」と指摘。今後、厚労省に設置予定の検討会の中で、元社員への聞き取り調査を行いたい意向を示した。
時間の順序が前後するが、
慈恵医大でもデータ操作 降圧剤臨床研究 07/31/13 (中国新聞)から推測すると第三者機関の17人の弁護士と法律の専門家はどのような調査を行ったのだろうか。
弁護士及び法律の専門家だから医療に関しては多少なりの知識があったとしても専門でないと言い訳できる。しかし、残っているデータに改ざんの証拠があれば
データーを操作した証拠があったと報告するべきである。慈恵医大は誰がデーターを改ざんしたのかは断定していないがデーターの改ざんはあったと結論付けてある。
つまり、製薬会社ノバルティスファーマの第三者機関の構成はどのように選ばれたのかは知らないが、17人もいて同じ判断となったのだろうか。映画では自分達の立場で動く人達の人選で形だけの第三者機関による調査がある。今回は徐々に問題が大きくなってきている。調査が適切だったかも後に明らかになると思う。
バルサルタンの医師主導臨床研究に関するノバルティスファーマ社の公表 07/29/13 (研究公正)
バルサルタンの医師主導臨床研究に関して
2013年7月29日
バルサルタン(製品名:ディオバン®)の医師主導臨床研究について、弊社では社内調査に加えて、4月より独立した第三者外部専門家による調査が行われてきました。このたび、外部専門家の調査が終了し、7月29日に記者会見を行いました。つきましては本サイトにおいて、記者会見の冒頭で弊社社長が述べたお詫びと見解、ならびに調査報告書*(「バルサルタンを用いた5つの医師主導臨床研究におけるノバルティスファーマ株式会社の関与に関する報告書」)を公開します。
*この調査報告書には、第三者外部専門家による調査報告(第3章)が含まれています。これは、ノバルティスファーマの本社であるNovartis Pharma AG社から独立した調査を委託された第三者法律事務所により作成されたものです。
【社長記者会見要旨】
このたびは、患者さま、ご家族、医療従事者の皆さま、および国民の皆さまに大変ご心配とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
日本で2001年から2004年の間に開始された、バルサルタンの5つの医師主導臨床研究において、弊社の元社員が関わり、かつ研究論文への開示が適切に行われていなかったことをお詫び申し上げます。これによって、日本の医師主導臨床研究の信頼性を揺るがしかねない事態を生じさせたこと、また、これらの5つの研究の論文を引用して、バルサルタンのプロモーションを行ったことにつきましても、お詫び申し上げます。
弊社では、今回の事態に至ったことを深刻に受け止め、これまで社内調査、第三者による調査が行われてきました。このたび、第三者による、元社員を含めた弊社日本法人を対象とする調査が終了しましたので、結果をお伝えします。
この調査では、残念ながら真相を完全に解明するには至っておりません。弊社としては、この件については決してうやむやにせず、判明したことは誠実に皆さまにお伝えしたいと考えております。
先日の、京都府立医科大学の調査結果の発表によりますと、論文のデータに何らかの操作があったとされています。弊社はこの発表について重く受け止めております。しかし、本研究が医師主導のため、データを持っていない弊社としましては、調査にも限界があります。7月16日、私から京都府立医科大学に対して、協力して真相を解明したいと申し入れる手紙をお送りしました。
また研究に関わっていた弊社の元社員につきましては、本人はこれまで、弊社と第三者機関の10時間以上に及ぶ聞き取り調査に答えているので、改めて大学の調査に応じる必要はないという立場でした。しかし、弊社としては、本人に対し、会社の調査だけではなく、大学の調査に協力する重要性が増していることを伝えてきました。また7月16日には、社長名で本人に調査に協力するよう要請を行いました。その結果、最新の状況では本人がその重要性を理解し、大学による調査に応じることに前向きになっております。
弊社としては、今回の件で患者さまからも多数のお問い合わせをいただいており、誠に申し訳なく思っております。ただし、今回問題となっている医師主導臨床研究は、バルサルタンの承認後に実施されており、降圧剤としてのバルサルタンの有効性、安全性は確認されております。このことは、改めてご理解いただきたいと思います。
今回の医師主導臨床研究で検討された心血管系イベント(脳卒中、心筋梗塞など)の予防効果の研究は、海外では先行して実施されていました。その後、海外では高血圧症の効能に加えて、心筋梗塞後の治療および心不全の治療薬として追加効能が認められました。そのような環境の中で、日本でもバルサルタンが医師主導臨床研究の研究対象に取り上げられたものと理解しています。とはいえ、弊社の元社員がこれらの臨床研究に関与し、未だに真相究明に至っていないことで患者さまが不安に思われていることにつき、大変申し訳なく思っております。
私たちは製薬会社として、高い倫理観を持って社会的責任を果たすことを求められています。今後、あらゆる調査に全面的に協力して真相の解明に当たり、私たちの責務として、二度とこのようなことが起こらないよう、再発防止を徹底してまいります。
患者さま、ご家族、医療従事者の方々、国民の皆さまからの信頼をいただけるよう、全社を挙げて不退転の決意で取り組んでまいります。
改めて、ご迷惑、ご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
元社員の「改ざん認められず」- 「調査の限界」、ノバルティスが調査報告 07/29/13 (キャリアブレイン)
製薬会社ノバルティスファーマの降圧剤「ディオバン」(一般名バルサルタン)の医師主導臨床研究で、同社の社員(当時)がデータ操作に関与した疑いが指摘されている問題で、同社は29日、第三者機関がまとめた調査報告書を公表した。報告書は、元社員の私物のパソコンの調査ができなかったなど「調査の限界」を主張し、「元社員がデータの意図的な操作、ねつ造、改ざんなどを行ったことを示す事実は認められなかった」としている。
第三者機関は、17人の弁護士と法律の専門家で構成され、4月中旬にスイス本社の委託を受けた後、7月5日までの約2か月間にわたって調査を実施。元社員がデータ操作に関与した可能性が指摘されている、東京慈恵会医科大、千葉大、名大、京都府立医科大、滋賀医科大の5つの臨床研究について、元社員や上司らからのヒアリングのほか、研究の関連文書などを調べた。
その結果、すべての研究について、元社員が何らかの形で関与し、それを上司が支援していたことが判明したが、元社員がデータを操作したことを示す証拠は見つからず、上司が改ざんを指示した事実も認められなかったとした。
報告書では、問題のカギを握る社員の多くが退職したため、調査できない元社員がいたことや、入手できない文書があったことなどを指摘し、「研究論文で導かれている結論の整合性を確認するための独立した分析を行うことができなかった」としている。
同社は、元社員の上司に対する懲戒処分を決定し、社員教育の徹底や医師主導臨床研究の手順の強化など、再発防止のための対策を行うとしているが、疑惑がさらに深まる結果となった。社内と第三者機関による調査を終えたことから、同社は調査に一定の区切りを付け、今後は大学の調査に協力するとしている。【敦賀陽平】
運が悪いとしか言いようがない。伊勢湾岸道の事故が起こった辺りは結構、乗用車もトラックもかなりのスピードで飛ばす。
車線変更も頻繁だし、スピードも出している。中央の車線で停止は非常に危険。偶然が重なるとはこのような事かもしれない。
故障し追突された車を見ると日産のティーダみたいだ。18万キロ以上そして20万キロ以上走ったトヨタの車は故障なしだったが、7万キロしか走っていない日産の車が燃料ポンプの故障でエンストした時には困ったし、悲しかった。経験から判断して新車でなければトヨタが1番耐久性があると思っている。まあ、トヨタのディーラーの中にはだめなところもあるのが残念。


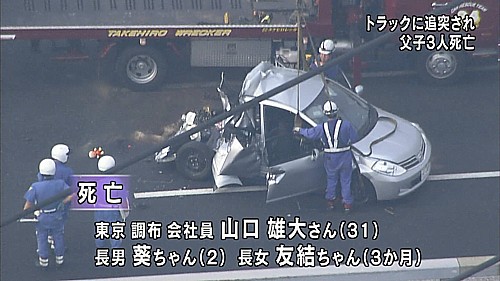
伊勢湾岸道で乗用車にトラック追突、3人死亡1人けが 07/26/13 (News i)
26日朝早く、愛知県の伊勢湾岸自動車道で家族4人の乗った乗用車に大型トラックが追突し、子ども2人を含む3人が死亡、1人がけがをしました。
26日午前4時50分ごろ、愛知県飛島村の伊勢湾岸自動車道下り線で、道路中央で停車していた乗用車に大型トラックが追突しました。乗用車には家族4人が乗っていて、運転席の父親と2歳くらいの男の子、さらに生後3か月くらいの女の赤ちゃんが死亡、助手席の母親が軽いけがをしました。
「お菓子とおもちゃのようなものも散らばっていて、助手席のカバンの中からは衣服とみられるものが見つかっていることから、旅行の最中だったとみられます」(記者)
警察によりますと、けがをした母親は、車を本線上で停車させて運転を交代していたと話しているということです。
また、警察は、トラックを運転していた尾呂富士男容疑者を自動車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕しました。取り調べに尾呂容疑者は、「脇見をしていた」と話しているということです。
伊勢湾岸道:乗用車にトラック追突、3人死亡1人負傷 07/26/13 (毎日新聞)
26日午前4時50分ごろ、愛知県飛島(とびしま)村の伊勢湾岸自動車道下り線で、普通乗用車に大型トラックが追突、乗用車の30代くらいの男性と男児、女の子の乳児の3人が死亡し、30代くらいの女性が首に軽傷を負った。女性は「家族で三重に行く途中で、車が故障して止まった」と話しているという。
県警高速隊は、トラックを運転していた京都市右京区、会社員、尾呂富士男容疑者(54)を自動車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕し、容疑を同致死に切り替えて調べている。「前をよく見ていなかった」などと供述しているという。
高速隊によると、現場は名古屋港の海上に東西に架かる名港西大橋。乗用車は見通しの良い片側3車線の中央の車線で追突された。県警には事故前、「乗用車が中央車線に停車している」との110番通報があったという。事故当時、現場は渋滞していなかった。
乗用車は東京都の八王子ナンバーのレンタカーだった。男性が運転し、男児と女児は後部座席のチャイルドシートに、負傷した女性は助手席に座っていたとみられる。
尾呂容疑者は、東京都江東区から大阪府吹田市に雑貨を運ぶ途中だった。同容疑者が勤務する大阪市鶴見区の運送会社は「担当者が現場に向かっているが、状況はよく分からない」と話している。
事故の影響で、伊勢湾岸道下り線は名港中央インターチェンジ(IC)−飛島IC間が約2時間半にわたって通行止めとなった。【岡大介、井上直樹】
社員が退社したので協力できないで許されるのか?今回の教訓から学び、法的に不正に関与した社員(元社員)の事情聴取への協力又は、
強制的に事情聴取が行えるように法改正を行うべきだ!
厚労相、臨床改ざん問題でノバルティスに元社員の事情聴取への協力要請 07/17/13 (日刊工業新聞)
田村憲久厚生労働相は16日の閣議後会見で、高血圧症治療薬「ディオバン」(一般名バルサルタン)の臨床研究データが改ざんまたは捏造(ねつぞう)された疑いがある問題について、担当していた元社員に対する調査への協力を発売元のノバルティスファーマ(東京都港区)に強く求めた。この問題では元教授が研究に携わった京都府立医科大学の調査で、明らかなデータ操作が認められたものの、同社は担当だった社員がすでに退社したとし、同大学による事情聴取への協力を断った。
田村厚労相は「医療イノベーション(に向けた国の政策)に水を差されては困る。会社も再度努力してほしい」と、事情聴取への協力を要請した。
再発防止策を練るため設置する同相直轄の検討委員会については参院選後、早期に発足させる方針を示した。
療薬データ改ざん、元社員の聴取必要…厚労相 07/16/13 (読売新聞)
高血圧治療薬「ディオバン」の臨床研究のデータ改ざん問題で、販売元のノバルティスファーマの元社員が京都府立医大の調査に応じていないことについて、田村厚生労働相は16日の閣議後記者会見で、「身分を隠してデータ解析に関わった元社員の話が聞けないと実態解明が難しい。会社側にも再度努力いただきたい」と、元社員への聞き取りを強く望む姿勢を示した。
同大は「解析データの作成段階で何らかの操作が行われた」との調査結果を発表したが、元社員の聴取はできず、「意図的(な改ざん)かどうか認定できなかった」とした。同社は「元社員の強い意志で聞き取りが実現しなかった」と説明している。
これに対し、田村厚労相は「データの捏造(ねつぞう)、改ざんが強く示唆される調査結果。意図的に何らかのことが行われた可能性がある。ここに関わった人の話が聞けないと難しい。このままでは終わらない」と語った。
バルサルタン:臨床試験疑惑 元社員、大阪市大調査も拒否 データ解析担当 07/12/13 (毎日新聞 東京夕刊)
降圧剤バルサルタンに血圧を下げる以外の効果もあるとした臨床試験疑惑で、京都府立医大の試験に「大阪市立大」の肩書で加わり、統計解析していた販売元製薬会社ノバルティスファーマの社員(既に退職)が、過去に非常勤講師を務めた大阪市大の調査にも応じていないことが分かった。大阪市大は、疑惑が表面化した5月以降の調査で、元社員に大学での勤務実態がほとんどなかったことや、大学としては試験に一切関わっていなかったことを確認している。元社員は府立医大の調査への協力も拒んでおり、真相究明の大きな障害となっている。
大阪市大によると、元社員には2002年から今年3月まで1年ごとの更新で非常勤講師を委嘱していた。この間、講義は1〜2回程度しかなく、勤務実態も報酬もなかったが、大学側は「統計解析のアドバイスができるので担当してもらっていた」と説明する。
大阪市大は、バルサルタンを巡る5大学の臨床試験に、元社員が関与していたことが明らかになったことを受けて調査を開始。大学によると、ノ社に協力を要請したが、「既に退職している。居場所を把握していない」などの理由で取り次いでもらえなかったという。その後も大学は、元社員と連絡が取れず、聴取のめどは立っていない。
ノ社の調査によると、元社員は一連の臨床試験が行われた02〜07年、循環器マーケティング部門の学術企画グループに所属していた。医師に学術情報を提供して支援する部署だった。研究チームにはノ社の別の社員が「統計の専門家」として紹介していた。
◇元教授、人心掌握狙う?
一方、府立医大の調査では、試験を実施した研究チームとノ社との関係も明らかになった。研究を主導した松原弘明元教授(56)は03年4月に関西医科大から府立医大に赴任。今回の臨床試験はその3カ月後に企画された。11日の会見で伏木信次・府立医大副学長は「松原元教授は外から来たばかりで、(循環器内科)全体をまとめたい意向があった。一方でノバルティス側も大規模臨床研究をする意向があり、(思惑が)一致した」と説明した。
府立医大の調査関係者は「研究者が企業に依存した結果、答案作成者が自分で採点するような構図となった。科学的な臨床試験ではなくビジネス試験。企業の企図と、論文で名誉を得たいという研究者の野心の結合の産物だ」と厳しく批判している。【八田浩輔、河内敏康】
元社員が改ざんに関与? 口つぐむノバルティス 07/12/13 (東洋経済オンライン)
スイス大手製薬会社ノバルティスファーマの社員(当時)が関与した「医師主導臨床試験」をめぐるスキャンダルで、おびただしい数の「データ操作」が行われていたことが、問題となった試験を実施した京都府立医科大学による調査で判明した。このスキャンダルに関しては、すでに『週刊東洋経済』と東洋経済オンラインで掲載(→記事はこちら)していたが、京都府立医科大学の調査で、ノバルティスの関与疑惑が深まった形だ。
京都府立医科大学の調査によると、「データ操作」の結果、医師主導臨床試験に手を貸していた製薬会社の高血圧症治療薬(降圧薬)を用いた場合に、別の薬を用いた場合と比べて「脳卒中や狭心症などのリスクが半減した」との結論が導き出され、国内外の専門誌で「研究成果」として公表されていた。
■ 業界誌を通じ、大々的に宣伝
医療業界誌『日経メディカル』の企画広告では、「日本人高血圧患者を対象とした数々のエビデンス」「日本の医療レベルと試験のクオリティの高さ」などと、医師主導試験の成果が大々的に宣伝され、製薬会社の販促ツールとして用いられていた。今回、それらの内容に根拠がなかったことがわかった。
京都府立医大は7月11日夕に緊急の記者会見を開催。ノバルティスの降圧薬バルサルタン(製品名ディオバン)を用いての、同大学を中心とした「キョートハートスタディ(臨床試験)」の不正にかかわる調査報告を発表した。そこでわかったのは「京都府立医大附属病院で登録され、カルテを調査することのできた223症例について、解析用データでは試験薬群(=ノバルティスの降圧薬)のイベント発生率が低かったのに対して、カルテ調査結果を用いた解析では2群間に有意な差がなかった」というものだ。
これは、平たく言うと、カルテで書かれていた内容と、試験論文に用いられた解析データでは、脳卒中や心筋梗塞などの発生率が大きく食い違っていたということだ。つまり、解析データが作成されるまでの間に、「データ操作」があったことを意味している。
京都府立医大によれば、「ノバルティス社の元社員が統計解析を行っていたと推測される」「元社員が(試験のために設けられた)各種委員会に出席し、事務局的機能を行っていたと推測される」としている。「推測される」との表現にとどめているのは、元社員から調査への協力を得ることができなかったためとしている。
一方、臨床試験データの改ざんや捏造については、元社員の協力が得られなかったことから、「あったかどうかわからない」(調査委員長を務めた伏木信次副学長)との回答に終始。故意があったかがわからないことから、データに数多くの不正がありながらも「操作」という言葉遣いにとどめた。
■ 不問に付されるノバルティスの責任
伏木副学長によれば、「すでに試験に関与した社員が退職したことを理由に、ノバルティスからは元社員へのヒアリングのための協力を得られなかった」という。同社はホームページで「深い反省」「心からのお詫び」を表明しているが、真相究明には消極的な態度をとり続けている。
今回の事件で明らかになったのは、日本の大学で行われている臨床試験の質の低さだ。患者を対象とした試験でありながら、薬事法上の臨床試験(治験)のための省令に基づいていないものが多い。ルールが不明確であるため、データの質や患者の保護で問題が起こりやすいと指摘されてきた。薬事法に基づいていないため、臨床試験の結果を「効能効果」として医薬品の添付文書に記載することも認められていない。当局の目も届きにくい。
その一方で、薬事法に基づかない臨床試験では、製薬会社にとっては自社に有利な結果が出るように医師を支援するインセンティブが働きやすいという見方がされてきた。特に外国の論文に掲載されることを通じて「エビデンス」が逆輸入され、マスメディアの企画広告などのグレーな形で事実上、効能効果をうたう形になっている。まさに法制度のすき間をついたやり方だ。そして、そうしたセールス合戦が最も加熱していると見られていたのが降圧薬などの循環器領域だった。ノバルティスのディオバンはピーク時に年商1000億円以上を売り上げていた。
ノバルティスの降圧薬をめぐっては、東京慈恵医科大学を中心として実施された医師主導臨床試験でも改ざんや捏造の疑惑をめぐる調査が進行中で、近く結果が発表されると見られる。だが、元社員の協力が得られないことを理由に、またもや大学や製薬会社の責任は不問に付される可能性が高そうだ。製薬産業の闇は果てしなく深い。
岡田 広行
ノバルティスファーマ 医学界、製薬業界を震撼させた論文データ「捏造」疑惑 07/01/13 (集中|MEDICAL CONFIDENTIAL)
ノバルティスファーマの降圧剤「ディオバン(一般名=バルサルタン)」の臨床研究不正事件は医学界と製薬業界の信用を揺るがした。既に報道されたように、京都府立医科大学の松原弘明元教授を中心にしたディオバン臨床試験論文が撤回されたことで、同社が論文作成に深く関わっていたことが明るみに出たからだ。松原元教授の広範囲に及ぶ臨床研究には同社から1億円を超える「奨学寄付金」が提供されていた上、同社員(既に退職)が社名を隠し、兼職していた大阪市立大学非常勤講師名で解析を行っていたことで、臨床研究そのものの信用が揺らいだ。しかも同社員は同大だけではなく、慈恵医大、名古屋大、千葉大、滋賀大でもディオバンの臨床研究の解析に関わっていた。慈恵医大の慈恵ハートスタディでは同社員が解析を行い、名古屋大の名古屋ハートスタディでも解析者に名前を連ね、千葉大、滋賀大の臨床研究では助言をしていた。助言といっても、解析を指導し、研究チームの会合に解析者として出席していたという。
寄付金を提供して研究を「主導」
臨床研究は医師主導とはいっても、各大学に奨学寄付金を提供し、社員が加わって解析を行っていたのだから、現実には、同社が〝主導した〟臨床研究に等しい。実際、同社のMR(医薬情報担当者)はこの臨床研究論文を手に医療機関を回り、「この通り当社のディオバンは効果が抜群です」と販促活動をしていたのである。
脳血管疾患や心筋梗塞を引き起こすリスク因子とされる高血圧の人は約4000万人いるとみられ、降圧剤は製薬メーカーにとって大型商品の市場。かつてはACE阻害剤が使われていたが、副作用に空咳が出ることから最近は同等の効果があるARB阻害剤が第一選択肢として使われている。
「その代表格が武田薬品工業の『ブロプレス』だったが、今年、特許切れを迎えることから、配合剤を出す一方、ブロプレスに代わる『アジルバ』を開発、売り込みに力を入れている。もちろん、他社もARBに力を入れ、ノバルティスのディオバンや第一三共の『オルメテック』など、7成分のARBが登場している。そんな競争が激しいARB市場でディオバンがブロックバスター(年商1000億円の医薬品)になったのは捏ねつぞう造した臨床研究を販促に使ったためだった」(ある製薬会社幹部)
ノバルティス社員が関わっていた臨床研究が始まったのは2004年。論文が発表されたのは07年の日本循環器学会で、日本初の大規模臨床研究と注目された。08年には欧州の学術誌にも発表された。だが、そのころから疑問がくすぶっていたという。ある循環器系の教授は次のように話す。
「松原氏の論文では、従来の降圧剤に加えてディオバン服用で血圧の低下とは関係なく、脳卒中や狭心症のリスクが下がった、とある。今までの常識とは異なる結果だ。さらに他社の降圧剤と比較してディオバンの効果だけが突出しているのは、データの取り方が間違っているか解析に誤りがあるのではないか、という疑問が出始めた。だが、松原氏は循環器内科の有名教授。まさかノバルティスがデータ解析をしていたとは思わなかった。これでは臨床研究の信用性に疑問符が付く」
事実が表面化するのは今年2月。ヨーロッパの心臓学会が、詳細は明かさなかったが「複数のデータに重大な問題がある」と、松原教授の論文を撤回。日本循環器学会も「データ解析に誤りがある」として論文を撤回した。この論文撤回が知れ渡り、報道が始まったのである。当初、松原教授は「データ集計の間違いでしかない。結論に影響はない」と主張していたが、データ解析者が同社研究部門の幹部だったことが露見し、利益相反ではないか、わざと社員であることを隠していたのではないか、データも解析結果も捏造があるのではないか、という疑問が噴出。医学、製薬業界を震しんかん撼させる事件に発展、国会でも質問が出る騒ぎに発展したのは周知の通り。
研究者と製薬会社の密接な関係露わに
しかも、松原元教授の研究室には08年以降、民間から253件、4億8000万円の奨学寄付金が提供され、そのうち18件、1億440万円が同社からの奨学寄付金だったことを京都府立医大が明らかにした。さらに、同社は松原元教授に依頼した講演会2件に40万円の謝礼金を支払っていたことも判明。当初、「奨学寄付金は大学を通じて提供したもので、臨床試験目的に提供したものではない。臨床試験もノバルティスが持ち掛けたわけではない」と強弁していた同社も、事ここに至り、内部調査の結果で5大学で行われた臨床試験で社員の関与を認めた。だが、その内容は「京都府立医大の他4大学が行ったバルサルタンの臨床試験で統計、解析を専門にする元社員がデータ解析や助言を行っていた。だが、いずれの試験でも意図的なデータ操作や改ざんを示すものは判明しなかった」と説明。加えて、「元社員は大阪市立大の非常勤講師であったため、大阪市立大の肩書で名前を載せていたが、社員であることを併記すべきであった」と謝罪の弁を語っている。続いて7月1日から5日間、MR2300人の製品プロモーション活動停止と、前社長を含めた9人の取締役の2カ月間の報酬10%カットを発表した。
だが、これで終わりなのだろうか。京都府立医大は同社に対して取引停止のペナルティーを課した。が、第一義的な問題は臨床研究を行った京都府立医大の松原元教授にあるものの、同社にも松原元教授と同等の責任があるはずだ。
スイス・バーゼルに本社を置く同社は、同じバーゼルで起業したチバ社とガイギー社が合併したチバガイギーに、サンド社が加わり、1996年にノバルティスに社名変更。今では世界第2位の売り上げを誇る巨大製薬メーカーだ。傘下にバイオシミラー(バイオ後続品)のサンド社や医療用栄養食品会社、動物薬メーカーを持ち、幅広く優れた医薬品を提供している。OTC医薬品(一般用医薬品)もあり、よく知られているのは禁煙補助薬の「ニコチネルTTS」やアレルギー鼻炎治療薬の「ザジデンAL」、水虫薬の「ラミシールAT」、あるいは鎮痛消炎薬の「ボルタレン」といったものだが、本格的な医薬品も多い。例えば、向精神薬の「リタリン」、中枢神経系領域の「イクセロンパッチ」、2型糖尿病治療薬ではDPP阻害薬の「エクア」、骨髄性白血病治療薬「グリベック」等々、広範囲に及ぶ。最近はオンコロジー(がん領域)にも力を入れ、目下、承認申請中の乳がん治療薬の「アフィニトール」を筆頭に数多くの医薬品を開発している。中でもディオバンとグリベックは世界で40億ドル以上を売り上げる大型商品の仲間入りをしている。
米フォーチュン誌に「世界で最も称賛される製薬企業」に選ばれたほどで、かつての米メルクと同様、経営姿勢も立派なはずだった。その最も称賛される製薬メーカーが、突出した資金を提供して自社医薬品の大規模臨床研究を行ってもらい、しかも社員が重要な解析を担当したのでは〝好結果〟が導き出されるのも当然。営業プロモーション用の臨床研究論文づくりだったとしか見えない。
組織ぐるみ否定してもくすぶる疑問
ノバルティスは報告書で「元社員はノバルティス社員であることを表記するよう、論文の著者に要請する必要があった」としているが、「元社員に臨床試験に関与させるという明確な戦略があったとは特定できなかった」と組織ぐるみではないと記述。その一方、「元社員の部下も一部研究に加わっていた。当時の上司の中には元社員の関与を認識し、支援していた者がいた」と認めながら、元社員や上司、研究者を含めて「当時、臨床研究に関わる活動と会社の業務を隔てる手立てを講ずれば、臨床研究に携わることができると誤った理解があった」と述べる。医師も医学界も製薬業界も透明性ガイドラインに取り組まなかったから、こういうことになったといっているように聞える。かねてから透明性ガイドラインを主張していた製薬メーカーとして、社内の研究部門で臨床研究に携わっている者がいるのを知りながら、口を閉ざしていたのはどういうことか。MRも臨床研究論文を見れば、自社の幹部社員の名前に気付くはずだが、口を閉ざしていたのは、同社の行動規範に反する行為ではなかったか。
同社は渦中の元社員について、定年退職後契約社員になり、(事件発覚後の)5月15日付けで契約期間終了により退職したとしか語らない。だが、論文に「ノブオ シラハシ」と記述された元社員は、3年前に武庫川女子大学薬学部の兼任講師をしていた白橋伸雄氏で、同大学の名簿には「ノバルティスファーマ社サイエンティフィックオペレーション部マネジャー」と記されている。臨床研究論文に同社社員の名を併記しなかったのは、自社医薬品であるため、社名を伏せたとしかいいようがない。同社は報告書でもプレスリリースでも全て「元社員」で済ませているが、かえって組織ぐるみだったことを隠そうとしているように映る。
ディオバンは世界で70 億ドル(11年)を売り、日本ではブロックバスターである、同社のドル箱だ。スイスでは医薬品が金融と並ぶ重要産業で、優秀な学生が製薬企業にシフトする。そのエリートが金融同様に利益追求に走ったのでは「世界に称賛される製薬メーカー」という評価が泣く。
ノバルティス ディオバン(バルサルタン)臨床研究データ捏造疑惑
ノバルティスのディオバン問題の関係者の疑惑について
白橋伸雄(ノバルティスファーマ社の社員:身分を隠し臨床研究の統計解析に関与、大阪市立大学非常勤講師)
松原弘明(京都府立医科大学循環器内科教授:Kyoto Heart Studyの統括責任者、基礎研究でも研究不正)
小室一成(千葉大学、大阪大学、東京大学循環器内科教授:VART関係者、基礎研究論文でも疑惑)
光山勝慶(熊本大学大学院生命科学研究部生体機能薬理学分野教授:Kyoto Heart StudyのEndopint committee member、元 大阪市立大学医学部・医学研究科所属、基礎研究論文でも疑惑)
森下竜一(大阪大学大学院医学系研究科 臨床遺伝子治療学教授:日本高血圧学会理事、小室・光山・堀内氏らとディオバン宣伝のため何度も座談会に参加、基礎研究論文でも疑惑)
萩原俊男(大阪大学大学院医学系研究科 老年・腎臓内科学教授:Jikei Heart Studyに賞賛のコメント、基礎研究論文でも疑惑)
堀内正嗣(日本高血圧学会理事長、 小室・光山・森下氏らとディオバン宣伝のため何度も座談会に参加)
青野吉晃(ノバルティスファーマ社の元営業本部長、現在は日本べーリンガーインゲルハイム社長、白橋伸雄社員が統計解析者として関与したディオバン臨床研究における身分隠蔽(COI違反)を認識していた可能性が高い)
藤井幸子(ディオバンの市販準備からマーケティングの責任者として辣腕を振るい、売上げ年間1000億円を達成するまで担当した。当時の肩書は『ディオバンマーケティング部長』。ノバの企業カラーである『赤』のスーツに身を包み、足しげく大学病院に通っていた。実際に彼女はいろいろな大学にパイプを持っており、日本高血圧学会の幹部にも食い込んでいた。)
原田寿瑞(2002年より、ノバルティスファーマ株式会社にて、高脂血症治療薬、高血圧治療薬のマーケティングマネージャーを担当。2006年4月1日まで、医薬品事業本部 循環器事業部 マーケティング部 ディオバングループ グループマネージャー。その後、医薬品事業本部 マーケティング本部 循環器領域マーケティング部長などを歴任)
フライデーがバルサルタンを年間千億円売った伝説の女部長を報道!その他のノ社元販売責任者 06/14/13 (世界変動展望)
14日発売のフライデーがバルサルタン事件の続報を報じた[1]。内容は概ね次のとおり。
(1)患者や家族に迷惑をかけたとしてノバルティスファーマ社の役員が月額報酬を2ヶ月カットすると発表したが、罪と罰が釣り合っていない。ディオバン(バルサルタン)はこれまで1兆2000億円超売れ、それらの大部分は国民の保険料から出ていること。薬効に疑問符がついた今ノ社はどうやったら社会的責任をとれるのか?一番問題の論文捏造の調査も進展がない。
(2)ノ社、学者、医療専門誌の三位一体でディオバンをブロックバスターに成長させたこと。
※説明 ノ社が大学の学者を厚遇、学者が臨床研究でノ社に有利な成果を発表、それを医療専門誌で宣伝し販促。ディオバンは年間1000億円超売り上げるブロックバスターに成長。
(3)データが捏造・改ざんされた可能性があること。バルサルタンの臨床研究では脳卒中のリスクを下げるなどの薬効が示されたが科学的根拠がなくノ社か大学もしくは双方がデータを作った可能性がある。
(4)バルサルタンの臨床研究(Kyoto Heart Study,VARTなど)ではノ社のS元社員が統計解析者として関与していたこと。
(5)ノ社はアカデミズムを手玉にとり、「日本初の大規模臨床試験になる。話題になりますよ。」と名誉欲をあおって基礎研究の研究者を引っ張り出した。小室一成東大医学系教授もそれ故に引っ張り出された。
(6)ディオバンは年間1000億円超売り上げたが、その成功にはS元社員の上司であるF元ノ社女性社員(以下、F女史)が大きく貢献していた。彼女なくしてディオバンの成功はなかった。
(7)F女史は東京理科大学薬学部卒業、サンド薬品に入社し、合併でノ社に。ノ社初の女性プロダクトマネージャー(※)。論文捏造の可能性のあるS元社員の上司でディオバンマーケティング部長という肩書き。辣腕でディオバンの市販準備からマーケティングまでの責任者でディオバンの年間1000億円の売り上げ達成まで担当。現在はNPO法人の代表を務める。
※ フライデーではノ社初の女性プロダクトマネージャーと記載されてるが、このサイトによるとノ社での出来事ではなくサンド薬品時代の出来事で業界初の女性プロダクトマネージャー[5]。フライデーの記事はこのサイトの記述を参考した可能性があるが、わずかに違っている。
(8)年間100億円売り上げればブロックバスターとよばれるが、F女史はその10倍売った。ノ社のカラーである赤のスーツで大学病院をよく訪れ、いろいろな大学にパイプを持っていた。日本高血圧学会の幹部にも食い込んでいた。医薬業界では最も有名な女性。一方、S元社員はあまり押しは強くなく上からの指示を待っている感じだった。
(9)「コピー機ならゼロックス、検索ならgoogle、降圧剤ならディオバン。」と言い、ディオバンが降圧剤の代名詞になるように熱心に活動していた。医療専門誌の宣伝に目をつけた。ノ社の広告を赤に変更したのもF女史。製薬業界の広告はそれまで白、黒が多かった。
(10)ノ社の内部調査で「Sの上司には臨床研究にSが関与していることを認識し、研究を支援していた者がいた」ことが判明している。F女史はメガスタディにも目を配る立場にいた。仮にノ社がデータを捏造したのならF女史が知らなかったはずはない。きちんと説明する責任がある。
(11)フライデーの記者の直撃取材とF女史の回答
フライデー記者「データ捏造が指摘されていますが?」
F女史「当時のこと?知るわけないでしょ。直接関係ない。(S元社員の)直接の上司でもない。(捏造ではなく)データをインプットする時点で間違っていたのだと思う。私にはわからない。」
フライデー記者「組織ぐるみの不正疑惑がありますが?」
F女史「それは本当に勘違い。あなたたちマスメディアの人たちがものすごい色眼鏡で見ている。」
(12)フライデーの取材に対しF女史はノ社からのヒアリングを受けていることを認めた。残りの質問には「何も知らない。」の一点張りだった。
(13)一番の懸念はディオバンは高い降圧効果がないのに爆発的に売れてしまったことで、他の薬を使っていれば防げたかもしれない脳卒中を起こしてしまった人もいないとは限らないこと。
(14)写真はフライデー記者の直撃取材を受けるF女史。顔にモザイクあり。もう一つは堀内正嗣日本高血圧学会理事長、小室一成東大医学系教授らの顔写真の載ったディオバンの宣伝広告の写真。
以上。数週間後にフライデー関連サイトで記事が掲載されるかもしれないので、詳細を知りたい人はそれまで待つかフライデーを購入していただきたい。
私は今回のフライデーの報道が気になる。(7)のようにF女史の経歴を紹介した。まるでF女史の実名等はネットで調べてくれと言っているようだ。なぜなら、これだけの情報をもとにネットで調べると簡単にF女史の実名と顔写真がわかる。例えばグーグルで「東京理科大学卒業 ノバルティス NPO法人」で検索するとこれらが簡単にわかる。フライデーは事実上F女史の実名と顔写真を暴露したといっていい。フライデーの記事からネットの検索で簡単に実名と顔写真がわかることを情報屋のフライデーが知らなかったはずがないし、多くの読者の中でネット検索を誰もやらないとは思っていないに違いない。事実上の暴露だ。
前に言ったとおり実名、顔写真などプライバシーに関するものはすでに公表されているなら扱っても構わないと考えているので書くが、端的にいってF女史は藤井幸子(Sachiko FUJII)[2][3]。[3]によると、
--
代表理事
藤井 幸子 Sachiko Fujii
東京理科大学薬学部卒業。
国内洗剤メーカー研究所勤務を経て、サンド薬品(スイス製薬会社)で、情報サービス担当5年ほか、マーケティングを20年経験する。
ノバルティスファーマでダイバーシティ推進室を立ち上げ、企業戦略としてのダイバーシティを導入した。
ノバルティスファーマを退職後、2008年より、GEWELの理事として活動し、2011年4月代表理事就任。
興味のある分野はマーケティング的アプローチのD&Iの推進、リーダーシップなど。
--
日経ビジネスの記事による藤井は2006年4月1日以前まで「医薬品事業本部 循環器事業部でマーケティング部長を務めていた[3]」[5]。太字で書いた部分が[1]の記事と合致するので、ここまで合致すればF女史は藤井幸子と断定できる。上で述べたとおり、これらはネットの検索で簡単にわかるので、フライデーの記事は藤井の実名等の事実上の暴露といえる。
フライデーの論調をみると、藤井がバルサルタン事件で大きな役割を果していたように書かれている。
・藤井は統計解析者として臨床研究に関与していたS元社員(白橋伸雄)の上司。白橋が一連の臨床研究の被疑者の一人。
・藤井はかなりの辣腕。白橋は押しは強くなく、上から支持を待っている感じだった。
・藤井は販促に熱心で大学にいろいろパイプを持ち、高血圧学会幹部とも繋がっていた。医療専門誌の宣伝にも目をつけていた。
・ノ社、大学、医療専門誌の三位一体の活動がディオバンの年間1000億円の売り上げに貢献。
・上司が白橋が臨床研究に関与していることを認識し、研究を支援していた。藤井はメガバンクに目を配る立場にいたのだから、仮にノ社がデータ捏造したのなら知らなかったはずがない。
まるで一連の事件の首謀者のような書かれ方だ。赤いスーツに身を包み営業活動に熱心で、ノ社の宣伝広告を赤く変えたが、ディオバンの研究成果等は真っ赤なウソだったかもしれないと皮肉る記事を書かれていた。
私はフライデーの記事が本当かどうかはわからないし、藤井が一連の事件でどう関わっていたのか全くわからないし、ディオバンの販促にどれほど貢献したのかもわからない。ただ、ノ社からのヒアリングを受けていることを藤井が認めたという言及があるので、これが事実なら事件に関与していた可能性はあるだろう。14日のRISFAXの報道で白橋が5つのバルサルタン臨床研究に関与していたことをノ社『は臨床研究を実施した5大学の教授や一部医師が、元社員の所属を「知っていた」と考えている[4]』と報じた。ノ社の調査報告書にその旨の記載があり、ノ社は『元社員が会社のEメールアカウントを用いて、主任教授や医師と連絡を取っていたことを確認しているという[4]』[4]。各臨床研究の研究者たちが白橋のノ社所属を知っていて論文に表記しなかったと示唆するといえる。ノ社と研究者の共謀の疑いはますます強くなった。
二度とこのような事件を起こさないために、バルサルタン事件は徹底的に真相を究明し再発防止策を作らねばらならない。藤井が事件に関与しているならきちんと説明責任を果してほしい。あわせて現在の研究不正調査制度の問題や論文数の水増しなどによる不当な業績評価の問題を改善しなければならない。
参考
[1]"クスリの闇/<疑惑の降圧剤>を1000億円売った「伝説の女部長」
◆ノバルティスファーマ「バルサルタン」、小室一成・東大教授" 記事のタイトルの写し
フライデー 2013.6.28号 (2013.6.14 発売) p86
[2]世界変動展望 著者:"白橋伸雄(Nobuo Shirahashi)・ノバルティスファーマ社社員のバルサルタン不正疑惑への関与について" 世界変動展望 2013.4.30
[3]NPO法人GEWELによる藤井幸子の紹介(顔写真入り)、その写し。日経ビジネス(2007.6.29)の写し。ともに2013.6.14 閲覧。
[4]RISFAX 記事 写し 2013.6.14
[5]ノ社の2006年4月1日付けの人事 写し
藤井 幸子 (ふじい さちこ)
新 ダイバーシティ推進室長
旧 医薬品事業本部 循環器事業部マーケティング部長
原田 寿瑞 (はらだ としみつ)
新 医薬品事業本部 マーケティング本部循環器領域マーケティング部長
旧 医薬品事業本部 循環器事業部マーケティング部 ディオバングループグループマネージャー
とある。2006年4月1日以前まで原田は藤井の部下で藤井の後任が原田。
原田は2011.11.19頃ノ社眼科領域ビジネスフランチャイズ部長(兼)眼科領域営業部長で、
『米国系大手医薬品メーカーにて学術業務を経験後、米国、カナダにてマーケティング研修を経て眼科用剤および循環器用剤の国内プロマネ。その後、米国本社にて米国内市場のための循環器用剤プロマネを担当。その後国内でのプロマネ、営業を経験。 2002年より、ノバルティスファーマ株式会社にて、高脂血症治療薬、高血圧治療薬のマーケティングマネージャーを担当ののち、現職。』(このサイトより、写し、2011.11当時) とある。
また藤井幸子の経歴として
『元 ノバルティスファーマ(株) ディオバン ブランドdirector
サンド薬品時代に業界初の女性プロダクトマネージャーとしてテルネリンを上市、3年で年商100億を達成。カラーブランディングを取り入れた。ノバルティスになってから、営業推進担当として新薬上市における営業部門とのコミュニケーションの課題を認識した。ディオバンのマーケティング責任者として、上市準備から、ブロックバスターとして1000億円の売り上げ達成まで担当した。その後ダイバーシティ推進室を立ち上げ、マーケティング的発想で企業風土改革に取り組んだ。ノバルティスを退職し、NPO GEWEL (ジュエル) で、ダイバーシティ&インクルージョンを広める活動を行っている。』(このサイトより、写し、)
と紹介されている。フライデーの記事と類似する。このサイトを参考にして記事を書いたのかもしれない。
不正研究が発覚した場合の処分を重くするしかない。重い処分を理解したうえで不正を行うのであれば仕方がない。頭が良いかどうかの問題ではなく、人間性やモラルの問題なので未然には防げない。公表された処分者を見て、研究者が不正を思いとどまる事を期待するしかない。
相次ぐ研究不正 性善説前提、虚偽見抜くの難しく 07/25/13 (朝日新聞)
【編集委員・浅井文和】東京大の論文不正では、撤回が妥当とされた論文数が43本と多いほか、加藤茂明元教授は国の重要な研究プロジェクトを担う重鎮だった。論文の発表は、1996年から2011年までの長期間に及んでいる。問題が指摘された論文にかかわり、他大学の教員に就いた弟子もいる。
研究の不正は相次いでいる。昨年6月には、日本麻酔科学会は元東邦大准教授の麻酔科医が発表した論文約170本が捏造(ねつぞう)だったと公表した。ただ、元准教授個人の不正とされた。10月には人工多能性幹細胞(iPS細胞)による世界初の臨床応用をしたと発表した東大特任研究員が虚偽発表だとして懲戒解雇された。
今年4月には京都府立医科大が、元教授の動物実験などの論文14本で改ざんなどがあったと発表。高血圧治療薬の効果を調べた論文も撤回され、同医大は7月、不正なデータ操作があったと判断した。
昨年、科学誌に発表された調査によると、医学生物学分野で過去に撤回された国別不正論文数は、米独に続き日本が第3位だった。
楽天銀行はセキュリティーが甘いのか?楽天銀行で口座を持っていないから関係ないが不正に入手した同行口座のIDとパスワードで預金を盗まれることはとんでもない事だ。
131万円の預金、百数十円に…「頭が真っ白」 07/09/13 (読売新聞)
楽天銀行のインターネットバンキングを巡る不正送金で預金をだまし取られた愛知県の20歳代の女性が、読売新聞の取材に応じた。
◇
3月25日午後、女性の携帯電話が鳴った。楽天銀行の担当者からだった。
「定期預金を解約されましたか?」
身に覚えのない話だった。慌ててスマートフォンで預金残高を確認すると、仕事でコツコツとためた131万円の預金がわずか百数十円になっていた。
キムラ、リ……。取引の履歴には、知らない名前が並んでいた。何が起きたか理解できず、「頭が真っ白になった」という。すぐに近くの警察署に相談に行くと、「これは、サイバー攻撃です」と言われた。
取引履歴を見ると、まず「キムラ」という名義人から女性の口座に、100円の入金があった。次に、100万円と31万円の定期預金が相次いで解約され、さらに「リ」という名義人の口座に、131万円が2度に分けて振り込まれていた。
大きなお金が動く治験ビジネスはやはりいろいろあるようだ!
「治験ビジネス」に群がる企業と監視機関の限界㊤ (集中|MEDICAL CONFIDENTIAL)
「治験ビジネス」に群がる企業と監視機関の限界㊥ (集中|MEDICAL CONFIDENTIAL)
「治験ビジネス」に群がる企業と監視機関の限界㊦ (集中|MEDICAL CONFIDENTIAL)
「東京都や関東甲信越厚生局は偽造書類だらけの申請書を認可していた。役所の肩を持つわけではないが、都は来た書類を受け付けるのが仕事。
チェック機関としての機能は事実上ないに等しい。」
船の世界と同じでお役所のチェック機能はだめ(機能していない)と言う事か??
医師ら報酬2400万円を全額受領 治験データ改ざん 07/01/13 (朝日新聞)
【大高敦】肥満症改善薬の臨床試験(治験)をめぐり、被験者4人の身長が実際より低く記録されたデータ改ざん疑惑で、治験を実施した大阪市の病院が計2460万円を製薬会社側から治験関連費用として受け取り、病院内部の処理でこのほぼ全額が治験を担当した医師2人の収入になっていたことが朝日新聞の調べでわかった。
病院に残されたのは3万円余りで、医師2人は昨年、病院を退職した。病院関係者は「院内の設備や職員を使って治験を実施したのに、通常はあり得ないことだ」と問題視している。
治験は製薬大手「小林製薬」(本社・大阪市)の依頼を受け、医療法人大鵬(たいほう)会「千本(せんぼん)病院」(同市西成区)が2010年4月から実施した。治験責任医師は当時の内科部長(43)で、当時の院長(45)も業務の一部を分担した。治験の契約は病院名で結ばれた。
朝日新聞が入手した内部資料によると、千本病院は10年4月~12年2月、治験業務を補助していた大手の治験施設支援機関「サイトサポート・インスティテュート」(SSI、本社・東京都)から数回にわけて総額2460万円の振り込み入金を受けた。これらは小林製薬がSSIに支払った費用の一部とされる。
入金のうち元内科部長に計2154万円、元院長に計245万円が支払われた。看護師1人にも57万円がわたっていた。病院関係者によると、この看護師は「被験者が足りない」として職員を治験に誘うなど、治験業務の一部に関わっていたという。
「 肥満症改善薬の臨床試験(治験)をめぐるデータ改ざん疑惑について、治験を実施した大阪市の病院の業務を補助していた治験施設支援機関『サイトサポート・インスティテュート』(SSI、本社・東京都)は1日、『社内調査を行ったが、担当医師を契約上支援した治験コーディネーターは2011年9月に退職していることなどにより、データ改ざんの事実は確認できていない。・・・』」
担当したコーディネーターが退職していても、行方不明でない限り業界的に狭い世界なのだから連絡ぐらい出来ると思う。言い訳であれば原因究明などしたいないと言っていると解釈するしかないだろう。
治験支援機関「適切な対応講じる」 肥満薬めぐる疑惑 07/01/13 (朝日新聞)
肥満症改善薬の臨床試験(治験)をめぐるデータ改ざん疑惑について、治験を実施した大阪市の病院の業務を補助していた治験施設支援機関「サイトサポート・インスティテュート」(SSI、本社・東京都)は1日、「社内調査を行ったが、担当医師を契約上支援した治験コーディネーターは2011年9月に退職していることなどにより、データ改ざんの事実は確認できていない。今後、調査結果をふまえ、報道された事項に適切な対応を講じていく」とするコメントを発表した。
治験は製薬大手・小林製薬の依頼を受け、大阪市西成区の医療法人大鵬(たいほう)会「千本(せんぼん)病院」が2010年4月から実施した。朝日新聞の調べでは、被験者72人の中に当時の病院職員6人がふくまれ、うち4人の身長が実際よりも低く記録されていた。小林製薬などによると、身長を測っていたのはSSIのスタッフ。治験責任医師は「スタッフがメモした測定記録をカルテに転記した」と主張している。
肥満度上昇「これ僕じゃない」 治験データ改ざん疑惑 06/30/13 (朝日新聞)
肥満症改善薬の治験で、被験者データの改ざん疑惑が明らかになった。申請は取り下げられたが、国の承認を待つ段階だった。治験には大阪市の病院と大手治験施設支援機関(SMO)が関与していた。事実と異なる記録を書き込んだのはだれなのか――。
肥満薬治験でデータ改ざんか
取材班は5月半ば、被験者になった千本(せんぼん)病院の30代の男性職員と直接会い、治験記録を示した。
「これ僕じゃないですね。絶対ありえへん」
男性は「身長は170センチ」という。ところが、記載された治験登録時の身長は160・3センチ、体重78・0キロ。肥満度を示すBMIの数値も上がっていた。「(肥満体でないのは)みたらわかるでしょう」。男性は戸惑いの表情を浮かべた。
男性は振り返った。「肥満の方だけでなく、細い人も普通の人もおったね」
40代の女性職員の治験記録には、155・2センチ、155・8センチ、155・6センチ……と、治験期間中に行った計8回の測定値が並ぶ。しかし、女性に身長を尋ねると、「160センチです」と答えが返ってきた。
データを改ざんするなんてとんでもない医師達だ。常識、モラル、そして専門家としての「Code of Ethics」が欠如している。病院はこの事実を知っていたのか??
肥満薬の治験でデータ改ざんか 身長偽り肥満度上げる 06/30/13 (朝日新聞)
メタボリック症候群など肥満症に効く市販薬の開発をめぐり、大阪市の病院が実施した臨床試験(治験)のデータの一部が改ざんされた疑いがあることが朝日新聞の調べでわかった。被験者72人の中に治験を実施した病院の職員6人が含まれ、4人の身長が実際より低く記録されていた。治験の条件を満たすため被験者が肥満体となるよう偽装された可能性がある。
治験は、製薬大手「小林製薬」(本社・大阪市)の依頼を受け、医療法人大鵬(たいほう)会「千本(せんぼん)病院」(同市西成区、196床)が2010年4月から実施。小林製薬は11年11月、治験結果をふまえ、市販薬としての製造販売の承認を国に求めたが、朝日新聞の取材後の今年2月、申請を取り下げた。同社は今後、事実確認を進め、病院側に法的手段を検討するとしている。
朝日新聞が入手した内部資料によると、治験の責任医師は当時の内科部長(43)で、当時の院長(45)も業務の一部を分担した。被験者72人の中に当時の職員6人の名前があり、うち4人に直接取材して身長を確かめると、いずれも治験のカルテや症例報告書に記載された身長が実際より約4~10センチ低かった。千本病院も取材に対し、これらの事実を認めた。
「徳島県松茂町の特別養護老人ホーム『和光園』が、2011年10月〜今年1月に亡くなった入居女性3人の預貯金について、相続人の有無を確認せずに引き出し、納骨した同町内の寺に永代供養費として計約850万円を支払っていたことが、県への取材で分かった。うち約200万円は寺から同園に『寄付』として還流していた。」
純粋な寄付じゃない。隠れ蓑的な寄付ともとれる。これって法的には問題ないのか?問題がないのなら仕方がないが、このような問題は今後増えて行くのではないのか?
老人ホーム:死亡入居者の850万円 無断で供養費に 06/20/13 (読売新聞)
徳島県松茂町の特別養護老人ホーム「和光園」が、2011年10月〜今年1月に亡くなった入居女性3人の預貯金について、相続人の有無を確認せずに引き出し、納骨した同町内の寺に永代供養費として計約850万円を支払っていたことが、県への取材で分かった。うち約200万円は寺から同園に「寄付」として還流していた。民法の規定に反する財産処分をしたとして、県は同園を運営する社会福祉法人・成蹊会に改善を勧告した。
県長寿保険課によると、同園は3人と合意の上、入居時に預貯金の通帳を管理。亡くなった後、それぞれの葬儀代などを除いた預貯金全額を永代供養費として寺に渡しており、計約850万円に上るという。民法の規定では、死亡した入居者に相続人がいなければ原則として国に財産を納めなければならないが、同園は市町村を通じた相続人の有無を確認していなかった。同園側は寄付として受け取った200万円を、施設の修繕工事に充てたと説明したという。
今年2月、県に通報があり発覚した。同園は3人以外にこれまでも「慣例」として故人の預貯金を引き出し、供養費として寺に納めていたという。【立野将弘】
安愚楽牧場:社長と弟が「私物化」…元社員が証言 06/20/13 (読売新聞)
「結局、姉と弟の会社に過ぎなかった」。和牛オーナー商法を巡る特定商品預託法違反事件の舞台となった安愚楽牧場(栃木県那須塩原市、2011年8月に経営破綻)で働いていた元社員の男性は語る。同牧場は逮捕された元社長の三ケ尻久美子容疑者(69)と実弟の元役員、増渕進容疑者(59)が1990年代に実権を握って以降、急速に規模を拡大させた。しかし、その実態は姉弟による経営の「私物化」だった。
「黙ってなさい。最終的に私が責任を取るから」。元幹部の男性は、意見を進言するたび三ケ尻容疑者からこう言われたという。
元幹部によると、安愚楽牧場は典型的な縦割りの組織だった。出資者オーナーについて知っているのはオーナー担当の社員だけ。牛の担当社員は牛のことしか分からず、「全てを把握していたのは社長とほんの一部の役員だけだった」。
同牧場はバブル前夜の81年、不動産業も手掛けていた三ケ尻容疑者の夫が創業。夫はその10年ほど前から那須町などの土地を買い回っていたといい、80年ごろ、「ここで牛をやることにした」と地元住民らに話し、驚かせたという。
夫の病死後、三ケ尻容疑者は90年に社長就任。自らはオーナーの勧誘を担当し、増渕容疑者には繁殖牛の面倒を見させた。宇都宮市などで始めたレストラン経営やホテルも好調で、牧場の盆踊り大会に有名演歌歌手を呼ぶほどだったという。
しかし、業績が上がるにつれ専横ぶりが目立つように。別の元幹部によると、牛が病気になった時など、治療法から新たな牛の調達に至るまですべて増渕容疑者の許可が必要だったという。
「牛の知識もないのに一人で全部決めたがった。たまに現場に来ては『何やってるんだ』と怒鳴る。現場は萎縮していた」。三ケ尻容疑者は反対意見を伝える社員を遠ざけるようになったという。
「勧誘が大変」が口癖だったという三ケ尻容疑者。元社員は「親族しか重用せず、組織の体をなしていなかった」と振り返る。【中川聡子、浅野翔太郎】
九州電力:「やらせメール」辞任の前社長、子会社に天下り 06/20/13 (読売新聞)
九州電力前社長で、玄海原子力発電所再稼働をめぐる「やらせメール」問題で辞任した眞部利應(まなべ・としお)顧問(68)が、九電子会社で電気通信事業を手がける九州通信ネットワーク(QTNet、福岡市)の取締役会長に就任することが分かった。九電の社長経験者が、子会社の役員に移るのは異例。
21日にあるQTNetの株主総会と取締役会を経て正式決定する予定。QTNet側から「前社長の経験や人脈を生かしてほしい」と要請があったという。九電顧問も引き続き兼務するが、報酬を受け取らない非常勤となる。
眞部氏は2011年7月に発覚した「やらせメール」問題を受け、12年3月末に社長を事実上引責辞任した。一方で九電は、今春実施した電気料金値上げの際、申請時に原価として算入した顧問・相談役計3人の年間報酬総額8900万円が国から認められず、値上げ幅が圧縮された経緯がある。【寺田剛】
安愚楽牧場元社長ら3人逮捕 虚偽説明で勧誘容疑 出資者7万3千人 06/18/13 (毎日新聞)
和牛オーナー制度が行き詰まり、約4300億円の負債を抱えて経営破綻した畜産会社「安愚楽牧場」(栃木県那須塩原市)をめぐり、事実と異なる説明で出資者を勧誘したとして、警視庁捜査2課は18日、特定商品預託法違反(不実の告知)容疑で、同社元社長、三ケ尻久美子容疑者(69)=同市埼玉=ら3人を逮捕した。
出資者は全国で約7万3千人に上り、同社は平成23年8月に破綻する前の少なくとも数年間、出資金を別のオーナーの配当に充てる「自転車操業」に陥っていた疑いがあり、捜査2課は詐欺容疑での立件も視野に全容解明を進める。
逮捕容疑は、平成23年4~7月、出資者約100人に対し、同社が保有する繁殖牛の頭数が大幅に不足しているにもかかわらず、「牛が実在している」との内容を記載したパンフレットを送付するなど、事実と異なる説明をしたとしている。
同社は昭和56年創業で、全国約40カ所の直営牧場などで繁殖牛を飼育。雑誌広告などで繁殖牛のオーナーを募り、子牛を同社が買い取ることで年3~4%の配当が得られると宣伝し、出資をあおっていた。
東京電力福島第1原発事故の影響で、牛肉価格が下落するなどして経営が悪化。23年8月に民事再生法の適用を申請し、同12月には破産手続きに移った。
その後の消費者庁の立ち入り検査では、繁殖牛が出資者の契約頭数の55~69%しかいないことが判明。景品表示法違反に抵触したとして措置命令が出されていた。
同社をめぐっては被害対策弁護団が栃木県警などに刑事告訴していたほか、警視庁にも被害相談が寄せられていた。
「『800円の水』は良質なミネラルウオーターを提供しているためで『800円から1500円のお値段が通常、レストランが頂戴している値段です』と妥当な料金設定だったことを強調した。」
まあ、良質なミネラルウォーターでも「800円の水」を高いと思う人もいれば、高いとは思わない人もいる。情報としては「水代として800円」と
書かれて反論する必要はなかったと思う。「水代として800円」が高いと思うなら行かなくても良い。自分だったら行かないと思う。年収300万-400万円
の人でも高級店で食べたければ食べれると思う。食べる事が好きとか、価格に対して払う価値のある料理であると思うなら、行くのではないだろうか。
ヨーロッパは日本以上に格差や差別が存在する。しかしここは日本だから、「低所得者は店に来るな」と思わなければ発言するべきではなかったかも?
ブログ炎上の川越シェフ、“年収”発言を謝罪「生意気でした」(1/3ページ)
(2/3ページ)06/18/13(産経新聞)
テレビ番組でも活躍するイケメン人気シェフ、川越達也氏(40)が17日、フジテレビ系情報番組「とくダネ!」やブログなどで、非難の声が殺到した自身の発言について謝罪、釈明した。川越氏は5月にウェブ雑誌のインタビューで、自身が経営する料理店を飲食店評価サイトで批判されたことに、過激な言葉で反論。ブログが炎上する騒ぎに発展していた。(サンケイスポーツ)
川越シェフが神妙な表情で謝罪した。17日の「とくダネ!」で、一連の騒動について「ボクが生意気でした。誤解をまねいてしまったようで本当に申し訳なく思っています」と頭を下げた。
騒ぎの発端は5月19日に公開されたウェブ雑誌でのインタビュー。東京・代官山で経営するイタリア料理店「タツヤ・カワゴエ」が、飲食店評価サイトで「注文していないのに水代として800円取られた」などと批判されたことに反論した。
「くだらない。人を年収で判断してはいけませんが、年収300万-400万円の人が高級店の批判を書き込むこともある」と持論を展開。さらに「そういうお店に行ったことがないから『800円取られた』という感覚になる」と、過激な言葉を並べた。
この発言をめぐって、ネット上では川越氏への批判の声が相次いだ。「低所得者は店に来るなということか」「差別」「上から目線過ぎる」などの内容の書き込みが飲食店評価サイトのブログに数百件寄せられ、炎上する事態に発展した。
騒動を沈静化させようと、川越氏は謝罪、釈明に終始した。年収発言については「一般的なお客さまを表現したかった。ばかにしたわけではありません」と説明。「800円の水」は良質なミネラルウオーターを提供しているためで「800円から1500円のお値段が通常、レストランが頂戴している値段です」と妥当な料金設定だったことを強調した。
川越氏はこの日午前のブログで「ネット社会、情報社会で、活字が独り歩きする怖さを痛感いたしております」と自身の発言が誤解されたとの認識を強調。その後に削除し、会社名で「本人の発言とは違った意味合いで伝わってしまっているということをご理解いただければと思います」とつづった。
言動が発端で炎上した著名人
★高樹沙耶(現・益戸育江=2008年6月) 女優。自身のカフェでのボランティアをブログで募集したところ、「なぜただ働きをさせるのか」などと批判を中心に、約3000件のコメントが寄せられた
★鬼束ちひろ(12年6月) 歌手。ツイッター開始当日、著名人を名指しで「殺してえ」などとつぶやいた。その日のうちにフォロワーが殺到し、ツイッターが炎上。後日、所属事務所が謝罪コメントを発表した
排ガス:京都・衛生組合 清掃工場のデータを0に改ざん 06/18/13 (毎日新聞)
京都府南部の宇治市など3市3町の環境廃棄物行政を担当する城南衛生管理組合(八幡市)は17日、折居清掃工場(宇治市)で、基準値を超える排ガスが発生したものの、工場長の指示でデータを「0」に改ざんしていたことを明らかにした。
同組合によると、工場の排ガス処理設備の配管が腐食し、約3センチの亀裂ができたため、5月2日から3日にかけ、緊急補修をした。補修中、排ガス処理設備を通さずに運転したため、2日深夜から3日未明に、塩化水素と二酸化硫黄の濃度が、組合の管理基準値(1時間平均19ppm)を超える35〜100ppmを記録した。
基準を超える排ガスのデータが記録された工場内の運転日報を、工場長は職員に命じて、3日に6カ所、7日には6カ所の計12カ所を「0」に改ざんした。7日午後になって正しいデータに戻した。
工場の排ガス濃度計は100ppmまでしか測定できない。それ以上が排出されていた可能性があるが実際の数値が分からず、同組合は「人体への影響は不明」と話している。
竹内啓雄・同組合専任副管理者は「工場長は高い数値が出て気が動転し、表面を取り繕ってしまった。廃棄物処理への信頼を損ない、深くおわびします」と陳謝した。【山田英之】
経産省の怠慢なのか?官民の癒着の結果、チェックされていなかったのか?どちらの場合でも、こんな状態では
原発の安全性のチェック、定期点検のチェック、隠ぺいや虚偽報告のチェックなどは出来るわけがない。
重大な原発事故があれば、立地している地方自治体や住民にも責任があると思う。福島の原発事故で原発の危険性及び
放射能漏れによる被害は理解したと思うので、他人事と思わす出来る事から対応した方が良いと思う。
関西電力:社宅空き室維持費 電気料金に 05/26/13 (毎日新聞)
関西電力(大阪市)が昨年、電気料金値上げを国に申請した際、社宅と寮の空き室計約2700室分の維持コスト(年約11億円)を電気料金算定の原価に含めるよう求めていたことが、経済産業省関係者への取材で分かった。しかし、同省は全体の入居率が約6割しかないことに着目し、入居率9割未満の物件のコストは減額して原価に計上(減額査定)した。値上げ申請時、高額な役員報酬などが問題視されたが、有効活用されていない社宅や寮のコストを電気料金を通じて消費者に転嫁する実態が明らかになったのは初めて。
関電は今年5月、33年ぶりに家庭向け電気料金を平均9.75%値上げした。電気料金は、電力会社が払う燃料費や給与など電力供給に必要な費用(原価)に一定の利益を上乗せする「総括原価方式」で決まり、社宅などの維持コストも原価に含めてきたが、これまでチェックされることはなかった。
経産省などによると、関電の社宅と寮は計約7300室あり、入居は約4600室(約6割)にとどまるが、関電は今回の値上げ申請で全室分の維持コストを原価に計上するよう求めた。しかし、社宅の入居率は約5割、単身者向け寮も同約7割にとどまり、同省の有識者会議「電気料金審査専門委員会」は同9割未満の物件のコストは全額を計上せず、入居率に応じて減額して計上することを決めた。電気料金値上げの審査で、電力会社の社宅・寮のコストの減額査定が明らかになったのは初めて。
約7300室の社宅や寮のうち子会社などから賃借している物件が約5000室ある。このうち、変電所に近いなど必要性が特に高いとされる約2000室を除く約3000室分の維持コストを専門委が検証した。その結果、入居率9割未満の物件の賃借料から計約7.95億円▽周辺相場より高い約1000室の賃借料から計約2.9億円−−の計約11億円を減額して原価に計上した。これらとは別に、自社保有の社宅・寮についても、入居率9割未満の物件の修繕費から計約4500万円を減額査定した。
関電によると、社員は約2万2000人で、社員の約3分の1に社宅や寮を用意する厚遇ぶりだ。老朽化などで空き室が大量発生しても賃借や保有を続け、コストを電気料金に転稼していた。関電報道グループは「査定内容を真摯(しんし)に受け止め、経営効率化のさらなる深掘りに向けて方策を検討していきたい」とコメントした。【田中謙吉、向畑泰司】
違法を知った上で大目に見ているのか、違法状態を把握していないのでは大違い。
脱法ハウス:「2割がブラック」 シェアハウス年3割増 05/26/13 (毎日新聞)
新たな居住スタイルとして注目される一方、明確な定義がない「シェアハウス」。どれだけ危険物件が広がっているのかは見えにくい。
「シェアハウス」の名前は2008年の人気テレビドラマで使われたのを機に広まった。一般的には、運営業者が介在し、他人同士がキッチンなどを共有しながら一緒に暮らす住居を指し、物件を紹介するポータルサイト業者によると、07年末には全国に400軒7000床あったが、今年3月末には1700軒1万9000床に達し、年3割のペースで増えている。
一軒家などを共同住宅に用途変更する場合、防災対策や申請が必要になる。だが、ある自治体の建築指導担当者は「気の合う人たちが集まって暮らす住居と、大家族が暮らす住居はどう違うのか。線引きは難しい」と明かす。また「貸事務所だ」と業者が主張した場合、言い分をくつがえす証明が必要なケースもある。この担当者は「どう見ても共同住宅というものや危険なものは是正していく」と強調した上で、「規則が実態に追いついていない」と法令の不備を訴えた。
40業者が加盟する一般社団法人「シェアハウス振興会」の山本久雄代表理事は、「厳密には法令違反でも、可能な限り安全性を保とうとしている『薄いグレー』の業者を除いたとして、私の感覚では4割がグレー、2割がブラックだ」と見る。
70歳を超えても性欲を抑えられない。元気である事は良い事だが場所と相手は考えるべきだと思う。組織の体質に問題があるのは明らかだと思う。
全柔連:理事、辞任へ 「酔ってセクハラ」認める 05/24/13 (毎日新聞)
 東京都柔道連盟 福田二朗会長 (astjt_koikeのジオログ)
東京都柔道連盟 福田二朗会長 (astjt_koikeのジオログ)
全日本柔道連盟(全柔連)理事による女子選手へのセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)問題で、福田二朗理事(76)は24日、毎日新聞の取材に対し自身の行為と認めた上で、週明けの27日にも全柔連理事と東京都柔道連盟会長の職を辞任する意向を示した。
福田理事は、女子選手が同席した1〜2年前の酒席の帰路、抱きついたり、キスしたことを認め、「かなり酔ってしまっていた」と述べた。セクハラ行為はその一度限りで、直後に選手に直接、謝罪したという。
全柔連では、選手15人が告発した全日本女子の暴力問題や、日本スポーツ振興センターからの助成金の不正流用など不祥事が相次ぎ発覚しており、上村春樹会長は改革の道筋をつける来月11日の理事会をめどに辞任の意向を示している。福田理事は「私が辞めないと、全柔連や上村会長の印象がさらに悪くなる。辞表を月曜(27日)に届けたい」と述べた。
女子選手は全国大会出場の経験はあるが、現在は一線を退いており、福田理事とは指導者と選手の関係ではなかったという。福田理事は、選手が謝罪を受け入れたとの認識でいたため、問題が突然、表面化したことに「今になって、なぜだか不思議」とも話した。
この問題は、選手から相談を受けた1992年バルセロナ五輪女子52キロ級銀メダリストの溝口紀子氏(41)が23日に東京都内で開かれた公開の暴力根絶シンポジウムの場で明らかにした。【藤野智成】
今月のことば (公益財団法人 講道館)
2009年 3月
「変」
福田二朗
東京都柔道連盟は、首都東京にあります。東京は、言うまでもなく政治経済の中心であり、官庁を始め、情報の発信基地でもあります。人口1300万人が生活していますが、これに加えて、隣接の埼玉県、千葉県、神奈川県などから通勤する数百万人を飲み込んでいます。しかし、三代続いた江戸っ子はというと、かなり少なくなりつつあります。東京は全国から流入した、新都民によって大都市へと成長してきました。そのような中で柔道界を見ますと、昔の東京の町道場出身者は少なくなりつつあり、大学柔道部出身者も、多くはいろいろな土地からやってきた人たちで、多種多様な考え方を持っており、東京という郷土色を出しづらくなっていますが、その中にあって都柔連は、三十加盟団体がよく融和し統一しております。
また、大企業の本社が多く集中していますが、最近は、米国発の金融危機による世界同時不況の波が予想以上の速さで日本企業を襲い、企業の業績に鮮明に映しだされています。日銀短観によると各大手企業は大幅な減益で、下方修正が行われつつあり、国家財政を圧迫する段階に入っています。それに加え、政治の混迷です。早暁、政治の変化がもたらされる様相を呈しています。テレビで国会審議を見ても、また新聞を読んでも、高齢者を含む弱者に大変困難なしわ寄せが押し寄せています。円高で一ドルは九十円を上下し、株価はダウ平均八千円を上下して、金融機関、保険業を始め、企業の含み益は大変な状態を迎えており、自動車、電気産業の落ち込みに連れて関連企業も急速に悪化し、臨時や派遣の雇用者は想像以上の数字で解雇され、社会問題になっています。現時点での日本経済の状況は、世界的に見た場合、まだ良い方で、海外の比ではないようですが、このまま2009年、2010年と円高が続き、輸出産業の停滞が続けば、長い不況の中を生き抜いていかなければならないことを覚悟せざるを得ません。
このような環境の中で、柔道界はどうでしょうか。不況の長さにもよりますが、都道府県柔道連盟は節約に次ぐ節約を余儀なくされるでしょう。極力、金のかからない大会運営や事業の実施を心がけていかなければならないだろうと覚悟しています。また、国民所得の減少に加え、高齢者の登録離れ、少子化の中で、小学生・中学生・高校生の指導者不足による競技人口の減少、等々の悪条件により登録人口も減少することが心配されます。同時に、昇段者の減少です。これは登録人口と正比例してくると思われます。これらの心配が現実とならないことを祈ってはいますが・・・・・
財政不足を補うため、各都道府県自治体で赤字債権の発行が続く中、体育行政も財政的に過大な期待は持てません。そのような中で我々が最大の関心を持って見守っているのは、政府が学習指導要領の改訂を行い、2012年度から、中学一年、二年生の保険体育で武道が必修となることです。武道団体が待ち望んできたことです。指導者の問題を始め、年間の授業時間が少ない等の条件の中ですが(教育庁の説明では、年間二十〜三十時間。武道指導者も全国的に不足している由)、真剣に取り組まなければなりません。これに関しては、行政および全日本の競技団体が、指導者育成の機関を検討していくことになるでしょうが、我々としても、以前からこのようなことが想定されていたので、十分ではありませんが、「柔道指導者人材バンク」を設け、都柔連独自の登録制を実施して講習会の開催を続けてきています。行政の施策が判然としませんが、上部団体の指導方針が出来上がるときには、それに合わせて、都柔連の人材バンクを再構築していくことになるものと考えています。
話は変わりますが、2013年に東京国体の開催が決定しています。現在、東京都・東京都教育庁・東京都体育協会・開催区市・各競技団体が、開催に向けて検討を重ねています。開催の節は各県柔連のお世話になりますが、よろしくご協力をお願いします。
また、東京都では、2016年のオリンピックの開催地として立候補しています。現時点ではかなり高い評価を受けていますが、国民の大きな支持が起きてこないことに当惑しています。本年十月二日にはIОC総会で決定されるそうですので、柔道関係者の大きな支援と世論の喚起をお願い申し上げます。
最後になりましたが、東京都柔道連盟の冲永荘一会長が2008年9月25日に逝去されました。在任二十一年に及び、都柔連の運営等をきめ細かく指導していただきました。その功績は、我々の手本として輝き続けると思います。財団法人の新法人への移行を含めて大変革の時に、非凡な指導者を失ったことは、大きな損失であったと思わざるを得ません。
(東京都柔道連盟会長)
法的には問題ない。モラルの問題だけ。
国が違えば法律も違う。グローバリゼーションは複雑で、簡単には理解できない。日本の役人もグローバリゼーションを勉強し、理解して規則やガイドラインを
考えなければならない。
米アップル、巨額課税逃れ…「住所ない」手法で 05/22/13 (読売新聞)
米上院の行政監察小委員会は20日、米アップルが海外子会社などを活用して、巨額の課税逃れを行っていたとする調査報告書を公表した。
21日の公聴会にティム・クック最高経営責任者(CEO)を呼び、この問題を追及した。アップルの課税逃れ問題は、米国の税制が抱える欠陥も浮き彫りにしており、税制改革議論が活発化する呼び水になりそうだ。
報告書によると、アップルは、2009年から12年に740億ドル(約7兆5000億円)の利益を米国から海外に移転した。そのうち440億ドル分(約4兆5000億円)について課税を逃れたとし、「アイルランドを実質的なタックスヘイブン(租税回避地)として活用している」と批判した。
アップルの「節税術」は、アイルランドと米国の税制の違いを利用し、高度で複雑な手法を駆使しているという。企業は法人税を、住所が存在する国に支払うのが原則だ。アイルランドでは、法人の実態がある場所が課税上の「住所」となるが、米国では書類上、企業を設立した場所が「住所」になる。
運営の実権を米国に残したまま、アイルランドに会社を設立すると、米国にもアイルランドにも「住所がない」という状態になり、法人税を払わなくて済む。
「背景には、少子化の中、苦しい私立大の経営状況がある。」
出産数のデータを見れば少子化は想定できたこと。少子化傾向が進んでいても大学は増えている。必要とされない大学は淘汰されるべき。
必要とされない大学、必要とされるような大学に変われない大学は淘汰されても仕方がない。高い学費を出して卒業しても就職出来ないのであれば、
就職に有利な学部でないのが分かっていたが好きだから専行したケースを除けば、誰がそのような大学や学部に進学するのか?
お金にゆとりがある人達を除けば少ないと思う。倒産したり、廃業したりする企業が存在する、つまり淘汰されているのである。
教育機関は一般の民間企業と違うが、与えられた期間で変われない、結果を出せない大学や学校は淘汰されるべきだと思う。
大学「やらせ受験」、背景には苦しい私大経営 05/01/13 (読売新聞)
大阪産業大学(大阪府大東市)の2009年度経営学部入試を巡る「やらせ受験」問題は、国の補助金確保を目的に行われた疑いが強まっている。
関係者は「入学意思のない付属高の優秀な生徒で合格枠を埋め、他の志願者を落とそうとした」と証言するが、なぜそんな工作に及んだのか。背景には、少子化の中、苦しい私立大の経営状況がある。
◆ペナルティー
「このままだと『1・37』を超えてしまう。そんな焦りがあった」。同大学関係者によると、当時の入試担当者らが危惧していたのは、私立大学等経常費補助金の減額だった。
同補助金は1970年、私立の大学や短大などを対象に教育環境の向上や学生の負担軽減、経営健全化を目的に設けられた。国費を財源に、日本私立学校振興・共済事業団が交付。額は学生数や教職員数、研究内容などに応じて算出され、同大学は例年、全学部で総額10億円前後を得ていた。
ただ、この補助金は、定員に対する入学者の超過率が基準以上の学部には交付されない。教員の負担が増えると、教育の質低下を招くためで、基準は07年度の1・43倍から、11年度以降は1・3倍に厳格化。09年度当時は経過措置として1・37倍が基準だった。
一方、同学部は例年、推薦入試などで基準を上回る合格者を出していた。併願が多いため、相当数の辞退者を見込んでのことだったが、09年度は辞退者が少なかった。入学者は学部定員(465人)の1・37倍にあたる637人を超えぬようにする必要があったが、推薦段階で600人近くが入学手続きをした。この後の一般入試の定員78人は公表済みで、「大学の都合で合格者数を減らせば問題になる」(同大学関係者)状況だった。
なんとか入学者を減らしたい――。入学意思のない難関大志望の生徒らに謝礼を払って受験させたという付属高の教頭(当時)は、そう大学側から依頼されたと証言。本山美彦学長は4月12日の記者会見で「大学側の関与はなかったと思う」と述べたが、大学内部の議事録にも、依頼を裏付ける記述が残っている。
振り込み詐欺じゃないけれど、地道に働くよりも「AIJ」とか資産運用会社「MRIインターナショナル」のように顧客を騙して
良い思いをした方が楽かもしれない。
金融庁によるチェックや処分はあまいので、モラルや規則を無視して利益優先をさせるのなら
今後もこのような問題は起きるかもしれない。そういう点では日本はまだまだ稼げる市場なのかもしれない。
記事によると顧客は富裕層だし、「麻生太郎金融担当相は26日の記者会見で『監視を強めることと、緩めて(金融業者を)育てるバランスを取ることが難しい』と述べた。」
との事なので金融庁は防止策をしないことを理解して自己判断で投資すれば良い事なので
問題ないと言えば問題ない。ただ、1300億円の予算を取ると国の事業でも簡単ではないと思う。
米MRIインターナショナル:登録抹消 金融庁、定期検査は困難 「第2種業者」1279社と多く 04/27/13(毎日新聞 東京朝刊)
金融庁は26日、米金融業者「MRIインターナショナル」の金融商品取引業の登録を取り消したが、同社のように取引が少ない有価証券を取り扱う「第2種金融商品取引業者」への定期的な検査は困難なのが実情だ。銀行や保険、証券会社に対しては、金融庁や証券取引等監視委員会が定期的に検査を行っている。野村証券など大手の第1種業者に対し、第2種業者は今年3月末現在で1279と数が多く、今の検査体制では間に合わない。
MRIの問題発覚は、昨年12月に投資家から配当の遅れを指摘する情報が寄せられ、監視委が検査を行ったことがきっかけだが、08年6月の登録以降初の検査だった。AIJ投資顧問による年金消失事件を受け、政府は運用会社がうその運用実績を伝えて年金契約を結んだ場合などの刑事罰を引き上げる改正法案を今国会に提出しているが、第2種業者は対象外。業務が有価証券の販売・勧誘のため、資産運用業者とみなされないからだ。麻生太郎金融担当相は26日の記者会見で「監視を強めることと、緩めて(金融業者を)育てるバランスを取ることが難しい」と述べた。【葛西大博】
MRI資産消失疑惑:金融庁が登録抹消 顧客保護を命令 04/27/13(毎日新聞)
米ネバダ州に本社がある資産運用会社「MRIインターナショナル」が日本国内の顧客から預かった資産約1365億円の大半が消失した可能性がある問題で、証券取引等監視委員会は26日、金融商品取引法違反(誇大広告)の疑いで同社と社長(66)の強制調査に乗り出した。金融庁も26日、同社の金融商品取引業の登録を取り消した上で、顧客保護の措置を講じるよう業務改善命令を出した。
監視委によると、昨年12月にMRIのファンドに出資した一部の顧客から「配当の支払いが遅れている」との情報を受け、今年3月に立ち入り検査を実施。その結果、少なくとも2011年以降、同社が出資金の大部分を運用せず、他の顧客への配当金などに流用していたと認定した。「自転車操業」(監視委幹部)の状態だったが、顧客に対しては「出資金は金融商品の購入や回収事業のみに充てられる」などとうその説明をしていたという。
また、ファンドの口座と自社の口座を分別して管理せず、資産合計などについて実態と異なる数値を記載した事業報告書を財務局に提出したとされる。ただ、監視委は預かり金総額や消失額は「資料が全てそろっておらず分かっていない」として明らかにしていない。
監視委は金の流れなどの解明が不可欠と判断。11年2月ごろから13年3月ごろ、利益の見込みなどについて広告で著しく事実と違う表示をしたなどとされる容疑で強制調査に着手した。ファンドは米国の銀行で開設した口座に顧客が直接出資金を振り込み、そこから配当を受け取る仕組みだといい、米本社への調査が不可欠になる。このため米証券取引委員会の協力を得ていくという。
金融庁によると、顧客は富裕層の個人投資家が中心。同社は今年度のファンドのパンフレットも既に作製済みで、多数の顧客を勧誘する計画を進めていたという。同庁は監視委から行政処分の勧告を受けた当日に登録を取り消した。
同社は26日、ホームページ上にコメントを掲載し、「調査に協力してまいります。お客様にご心配をおかけしておりますことを、深くおわび申し上げます」と謝罪した。【牧野宏美】
三菱自が軽自動車でオイル漏れの不具合報告せず 国交省の特別監査で判明 04/23/13(SankeiBiz)
国土交通省は23日、三菱自動車が軽自動車のリコールに消極的だったとして昨年末に特別監査した結果、ユーザーから不具合の情報がありながら「不具合ゼロ」と同省に報告していたことを明らかにした。
国交省によると、三菱自は2006年4月からの約5年半の間に、販売店から軽自動車のエンジンオイル漏れを防ぐゴム製パッキンが外れているとの報告を6件受けた。だが、不具合を自社で確認できないとの理由で11年10月「6件中4件を調査したが不具合はない」と国交省に報告。リコールなどの措置は不要との見解を伝えた。
監査結果では、三菱自はこのほか、不具合の報告を求める販売店への指示が徹底されておらず、不具合の情報も十分に収集できていなかったと指摘された。
ただ特別監査では法令違反は確認されていないといい、国交省は行政処分を科さない方針。
インフル予防接種巡りカルテルか…埼玉の医師会 04/23/13(読売新聞)
インフルエンザ予防接種の料金を巡り、埼玉県内の医師会が最低額を設定していた疑いが強まったとして、公正取引委員会は23日、吉川松伏医師会(同県吉川市、松伏町)に独占禁止法違反(事業者団体による競争制限)容疑で立ち入り検査に入った。
幹部が経営する病院などへの立ち入りも検討する。公取委は、最低額を設けていた医師会がほかにもあるとみて調べている。
予防接種を巡る価格カルテルの疑いで医師会への立ち入り検査が明らかになるのは、2003年の四日市医師会(三重県)以来、2度目。
関係者によると、吉川松伏医師会は数年前から、インフルエンザ予防接種の料金について、13歳以上は「4450円以上」、2回の接種が必要な13歳未満の子どもでは「初回3700円以上」と決めて二十数人の会員に通知し、価格競争を制限した疑いが持たれている。料金は医師会の会合などで決めていたという。
会社から1億3000万円詐取した経理担当 04/23/13(読売新聞)
地下資源開発会社「JX日鉱日石探開」(東京都港区)から約1億3000万円をだまし取ったとして、警視庁は22日、同社経理担当の小島誠容疑者(37)(埼玉県北本市中央)を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕した。
同社は同日、小島容疑者を懲戒解雇とした。
同庁幹部によると、小島容疑者は昨年5~7月に計4回、インターネットバンキングを利用し、同社の資産管理口座から自分の口座に計約1億3000万円を振り込んだ疑い。
小島容疑者の口座には2009年10月~今年1月までに資産管理口座から計11億8000万円の入金があったという。
やり方としては良くないと思うが通常のやり方で東電が逃げているのなら仕方ないかも。
東電は多くの人達に対して被害を出した。その上、多額の税金が既に東電につぎ込まれている。しかしながら本当に
反省しているとは思えない。
新聞記事として取り上げられて多くの人達がこの事実を知ることとなったので、多少なりとも茨城の高萩市はアピール出来たと思う。
東電に風評被害請求断られ電気料金支払わず 茨城の高萩市「現状分かって」 04/17/13(産経新聞)
東京電力福島第1原発事故の損害賠償をめぐり、茨城県高萩市が東電から請求された市庁舎などの電気料金約500万円の支払いを保留していることが17日、同市への取材で分かった。同市観光協会が風評被害対策で制作したテレビCMの費用請求に、東電が応じなかったためとしている。
市によると、観光協会は2月、平成23年12月~24年11月分の海水浴客減少などの損害額として、栃木、群馬両県などで放映した誘客のためのCMの事業費536万円を含む772万円を東電に請求。東電が「減収分以外の支払いは難しい」と回答したため、市は3月25日、東電茨城支店水戸支社に3月請求分(2月使用分)の支払い保留を通知した。
高萩市の草間吉夫市長は「原発事故の被災地が風評被害に苦しんでいる現状を東電に理解してほしい」と主張。東電茨城支店は「個別の案件にはコメントできない」としている。
約5億円が不正支出は大きいな!岩手県山田町はどのような管理をしていたのだろうか??
北海道のNPO、不正支出5億…震災事業交付金 04/02/13(読売新聞)
東日本大震災の緊急雇用創出事業を岩手県山田町から請け負ったNPO法人「大雪(だいせつ)りばぁねっと」(北海道旭川市)に多額の使途不明金があった問題で、県は、同法人が使った2012年度の事業費約7億9000万円のうち約5億円が不正支出だったとする検査通知を町に送った。
通知は3月31日付。厚生労働省によると、国の交付金を活用した雇用創出事業の不正支出としては過去最悪の金額になる。
県や町によると、不正と判断された支出は目的不明の出張費、勤務実態のない人件費など。法人側は、これまでの読売新聞の取材に対し、「不正な支出や私的な流用はない」と説明している。
三菱メリル証券「営業姿勢に問題」…監視委指摘 03/31/13(読売新聞)
リスクの高い金融商品「仕組み債」を、十分な説明がないまま顧客に販売していた疑いがあるとして、「三菱UFJメリルリンチPB証券」(東京都中央区)が証券取引等監視委員会の検査を受け、「会社として営業姿勢に問題がある」と指摘されていたことがわかった。
問題となった契約は約100件に上る。監視委は、同社が収益をあげるために組織的に不適切な営業を繰り返していたとみている。
関係者によると、同社は日経平均株価に連動して償還額や利率が変動する「日経平均リンク債」などの仕組み債を富裕層向けに販売していたが、2010年頃から監視委や証券・金融商品あっせん相談センターに「損失に関する十分な説明がなかった」などの苦情が高齢者らから寄せられるようになった。
東電、電事連へ会費18億円 11年度、料金に上乗せ 03/31/13(朝日新聞)
【大谷聡、野口陽】東京電力が福島第一原発事故後の2011年度、「電気事業連合会」(電事連)に会費として18億円を支払っていたことが朝日新聞の調べでわかった。東電と電事連はその使途を明らかにしていない。東電はこの時期、政府に公的資金の投入を要請し、合理化を打ち出す一方で、不透明な支出を電気料金に上乗せしていた。
電事連は全国の電力10社でつくる、原発推進の業界団体。電気事業に関する啓発や広報、調査研究に加え、業界による意見表明などが事業とされる。法人格を持たない任意団体で、予算・決算額や職員数、具体的な事業の内容などは公表していない。電事連会費の支払い実績額が明らかになるのは初めて。東電は取材に対し18億円の支払いは認めたが、使途や目的については説明しなかった。
11年度は、東電が事故処理や賠償のためとして国に支援を要請し、役員報酬の削減や資産の売却を打ち出していた時期だ。政府は11年5月、東電に公的資金を投入して支援する枠組みを決定した。
翌6月から始まった東電の経営内容を調べる政府の専門家会議は、同年10月の報告書で、電事連への会費について「電気の安定供給に真に必要な費用でない」と指摘。電気料金値上げに関する経産省の有識者会議は12年3月、電気料金への上乗せを「認めるべきではない」と結論づけた。
東電はこれを受け、同年5月に行った値上げ申請では、電事連会費を料金算定のもととなる「原価」に入れなかった。ただ、11年度に支払った18億円は、申請前のため電気料金に上乗せされた。
◇
〈東電広報部の話〉 電事連の活動は大きな意義があると考えており、2011年度の会費18億円を支払った。12年度以降も原価外で会費を支払う予定だ。電事連会費の使途については答える立場にない。
〈電事連広報部の話〉 収入・支出や個別の取引などに関することは、相手もあることから、公表・コメントは差し控える。
職員に対する管理及び監督はしっかりと!
家に落雷とウソ、共済116万請求したJA職員 03/29/13(読売新聞)
JAさが(佐賀市)は28日、共済金の不正請求や積立金の着服などをしたとして、2012年11月に3人の職員(臨時1人を含む)を懲戒解雇処分にしていたことを明らかにした。
JAさがによると、佐賀県小城市の芦刈支所の女性職員(50歳代)は08年9月から約3年間に、自宅に雷が落ちてテレビが壊れたなどと虚偽の理由で、「家財共済」を3回にわたって請求し、計116万円を受け取った。
また、同市の佐城地区中央支所の男性職員(40歳代)は、組合員の積立金管理を担当し、11年8月~12年7月に6回に分けて計77万円を着服。佐賀市の農機センターの女性臨時職員(50歳代)も11年6月~12年10月、外部に支払うための農業機械の修理費など計162万円を着服した。
3人とも全額を弁償しており、刑事告訴は行わない方針。JAさがは12年11月、内部の懲罰委員会を開き、上司ら職員20人を減給などの処分としたほか、役員5人を2、3か月間10%の減俸とした。
3人の懲戒解雇は、今月27日の臨時総代会で報告された。それまで公表しなかった理由について、JAさがは「弁償しており、県やJA佐賀中央会などには報告した。公表の必要はないと判断した」と説明している。
NPO法人=善意・ボランティアではなく、NPO法人=偽善・隠れみの・カモフラージュであることをを証明しているケースだろう。
関電:NPOに年2000万円支援 主婦向けに原発講座 03/25/13(毎日新聞)
大阪市のNPO法人「女性職能集団WARP−LEENET」(ワープ)は、関西電力が年間2000万円に及ぶ支援で活動を支えている。関西の主婦向けに開く原発の講座や施設見学をする「くらし学講座」は活動の柱だが、参加者を募集する新聞広告では「環境を楽しく学ぶ」などとあるだけで、「原発」の記述はない。一方で、05年の原子力政策大綱の公聴会で関係者を動員して原発推進を訴えるなど、関電との「持ちつ持たれつ」の関係が見える。【杉本修作、向畑泰司】
ワープは93年7月、関電が主催した広報イベントに一般モニターとして参加した主婦らを中心に発足し、01年7月にNPO法人格を取得。くらし学講座は発足時から毎年開く中心的事業で、新聞広告や関電が主婦層らに向け開設した会員制情報サイト「e−patio」(今年2月閉鎖)で参加者を募り、毎年約100人が受講した。
新聞広告には「エネルギー資源問題について楽しく学びませんか。6回の講座と3回のバス見学、IH料理教室を開催」とあるが、広告に「原発」の文字はない。受講生のブログによると、1泊2日のバス旅行で福井県の原子力関連施設を見学した際には高級日本料理が振る舞われたとの記載もあった。
1年の受講を終え、意欲がある修了生はOG組織「エレの会」に所属し、さらに詳しい原発や放射能の勉強会が用意されている。ワープの代表、井上チイ子氏によると、年間事業費4500万円のうち2000万円超が関電からの支援という。
井上氏は「仕事として委託を受け委託費をもらうのは広告代理店と同じ。講座は原子力だけではなく、原子力に肩入れしているわけでもない」と説明する。だが、ワープのホームページ(HP)には原子力特別講座など原発関連のイベントが多く、今年1月に取材でその点を指摘すると、直後にHPは閉鎖された。
05年10月に閣議決定された原子力政策大綱の策定会議では、井上氏も策定委員に名を連ねた。同年8月、大綱に市民の声を反映させるため福井市で開かれた公聴会にはワープの幹部数十人が会場に参集し、うち1人が発言して原発推進に向けた広報の拡充を求めた。
偽善と子供への洗脳!中国的だな。これじゃ中国も避難できない日本人達がいると言う事の証明だ。
よく外国人は「日本人は良い人ばかりだ。」と言う。外国人と比べると良い人が多いのかもしれないが、日本人=良い人ではないと
いつも説明している。間違いじゃないと確信できるケースだ。
原発教育:「主婦中心」の人形劇団 団員全員、東電と関連 03/25/13(毎日新聞)
「エネルギーに興味のある主婦を中心に活動を始めた」とホームページ(HP)で自己紹介している人形劇団が、実際には東京電力から広報事業を受注する会社の元女性従業員らにより設立されていた。劇団幹部は毎日新聞の取材に対し、HPの記載に虚偽があると認めた上で、スタッフには1公演当たり各7000円払っていたなどの実態を明かした。
この劇団は「カッパの河太郎一座」。HPなどによると「夏休みに子供に社会体験させようと原発を見学し、親子ともども、エネルギーを作って家庭に届くまでに大変な努力をされていることに気づかされた」として00年、エネルギーに興味のある主婦を中心にインターネット上で「エネルギー倶楽部」を開き、意見交換を主に活動を始めたとしている。
人形劇団を作ったのは「エネルギーの大切さを子供たちにも伝えていきたいと思うようになった」ためで、02年に財団法人・日本立地センターから「エネルギー劇キャラバンNPO支援事業」として人形劇団が認められた、とする。
しかし、劇団の中心メンバーによると、団員5人全員が設立当時、東電から広報事業を受注するリサーチ会社に所属。広報事業は、自宅に数人の主婦を集め、原子力の必要性をパーティー形式で「教育」する内容だったという。
あるメンバーは自宅などで約300回パーティーを開催。そうした中で「子供にもこういう話を聞かせたい」との声があり、日本立地センターの公募事業(発注元は経済産業省資源エネルギー庁で、「次世代層<未就学児・小学生>向けエネルギー劇キャラバン事業」)に応募したところ採用された。公募前にはエネ庁でプレゼンテーションし、その場で支援を約束されたという。エネ庁に自分たちの意思で行ったのか、誰かに勧められたのかは説明しなかった。
人形劇は、シロクマの母親からカッパたちに「SOS」の手紙が届き、現地に向かうと氷が解けて子グマと離れ離れになっていたため助けるものの、地球温暖化の話を知りカッパたちが驚く、といった内容。また、電気がない生活を知るためタイムマシンで江戸時代に行き、電気の便利さや大切さを知るなどの設定になっている。
菅官房長官:秋庭原子力委員、辞任の必要ない 03/25/13(毎日新聞)
菅義偉(よしひで)官房長官は25日午前の記者会見で、内閣府原子力委員会の秋庭悦子委員が設置したNPO法人に電力業界が資金提供していた問題について、「(NPO)顧問として相談に応じることは原子力委員としての活動に支障があるものではない」と述べ、辞任の必要はないとの認識を示した。そのうえで、原子力規制委員会委員には「過去3年間に原子力事業者から年間50万円以上の報酬を受け取っていない」などの基準があることを踏まえ、「原子力委員会をどうするかは当然、議論している」と述べ、同様のルールを設ける可能性を示唆した。政府は今秋の臨時国会にも原子力委員会のあり方を見直す法案を提出する方針。【鈴木美穂】
近藤駿介原子力委員長の電力業界との癒着 05/24/12(院長の独り言)
電力業界:原子力委員NPOに1800万円 震災後 03/25/13(毎日新聞)
原子力委員会委員の秋庭(あきば)悦子氏(64)が設立したNPO法人に、東京電力や電気事業連合会など電力業界側が毎年多額の事業資金を提供していたことが分かった。原子力委員を巡っては東電出身の尾本(おもと)彰氏(64)が福島第1原発事故後も東電から顧問料を受領していたことが判明、安倍晋三首相が「国民の理解を得るのは難しい」と述べ、尾本氏は委員を辞任。秋庭氏が設立したNPO法人は原発事故後、東電や電事連から少なくとも1800万円受領しており、議論を呼ぶのは必至だ。
このNPO法人は「あすかエネルギーフォーラム」(東京都中央区)。消費生活アドバイザーだった秋庭氏が01年に設立し、03年にNPO法人格を取得。10年1月の原子力委員就任に伴って秋庭氏は理事長を退き、顧問となったが、現在もNPO運営の相談にのっているという。
東京都に提出されたあすかの事業報告書によると、09〜11年度に2000万〜4000万円余の事業収入があり、あすか関係者らによると、この多くは東電や、電力10社でつくる業界団体の電事連などからの提供だったという。このうち原発事故後の11年度は2283万円の収入があり、うち600万円余を電事連から受領し、東電から163万円余、日本原子力文化振興財団(原文振)から約250万円受け取っていた。
原文振は原子力の知識普及を目的に、原子力産業界と学会を中心に設立された財団法人で、現在、中部電力出身者が理事長を、関西電力出身者が専務理事を務めている。
あすかは12年度にも電事連から600万円余、原文振から約150万円を受領し、これらを合わせると、原発事故後に電力業界側から少なくとも1800万円を受領していた。非営利のNPOにもかかわらず、11年度末時点で3800万円余の正味財産がある。
これらの資金を元に、あすかは主婦層を対象に原発や放射線などの勉強会開催や機関誌発行などの事業を展開。東電からは消費者アンケート事業を委託され、11年5月まで毎月80万円余受領し、09、10年度は同事業で年間960万円余受け取っていたという。
あすかはこの他、高レベル放射性廃棄物について国民の理解を得るための経済産業相認可法人の事業を下請け受注し、11年度には約1000万円が支払われた。この事業受注についてはある程度公開されているものの、東電と電事連、原文振からの資金受領は公開していない。
全柔連:理事1人が辞任届…助成金不正受給 03/24/13(毎日新聞)
全日本柔道連盟の複数の理事が、実際には選手を指導していないにもかかわらず日本スポーツ振興センターから指導者として強化目的の助成金を受給していた疑いがある問題で、受給していた理事の一人が23日、責任を取って辞任届を全柔連へ送付したことを明らかにした。全柔連では週明けにも第三者委員会を設置し、この理事を含めた関係者へのヒアリング(聞き取り調査)を行う。
この理事は10年から2年間、全柔連から、特に縁のなかった2人の選手を指導対象として割り当てられ、3カ月ごとに30万円を受給した。実際には大会で声をかける程度しかしていなかった。全柔連の強化委員会から3カ月ごとに10万円を徴収される以外は一切使わず残しているというが、「おかしいと声を上げなければいけなかった。できなかった私にも責任がある」と辞任の理由を語った。
また理事は、強化委員会が助成金の一部を各指導者から徴収する際、全柔連事務局の職員から振り込みを指示するメールが送られていたことも明らかにした。この徴収金は懇親会費など選手強化以外の活動に流用されたことがわかっており、第三者委員会が併せて調査することになっている。【石井朗生】
「『内部告発できなかった私に責任がある』と語り、助成金の全額をJSCに返還し、理事を辞任する考えを示した。」
内部告発できなかったではなく、内部告発できない背景や全日本柔道連盟の体質に問題があると思う。
全柔連:理事、不正受給認める 助成金問題 03/23/13(毎日新聞)
全日本柔道連盟(全柔連)の現職理事(55)が22日、指導者を対象とした日本スポーツ振興センター(JSC)の助成金を指導の実体がないにもかかわらず受け取っていたことを認めた。同理事は全柔連の事務局から指南を受けてJSCに虚偽の活動報告書を出していたと明言。「内部告発できなかった私に責任がある」と語り、助成金の全額をJSCに返還し、理事を辞任する考えを示した。
JSCは同日、こうした理事がいるとの疑いについて、全柔連の上村春樹会長に第三者を交えた調査を指示した。上村会長は文部科学省からも第三者委員会の設置を求められたことを明かした。(共同)
内部告発後の懲戒解雇は違法…大王製紙を提訴 03/19/13(読売新聞)
大王製紙の会計処理の問題を内部告発した後、懲戒解雇された同社元課長の男性(50)が19日、「解雇には理由がなく、違法」として、解雇無効と、同社に330万円の損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状によると、男性は、タイの関連会社に不正経理があることを上司に相談したが、適切な対応が期待できなかったため、昨年12月、金融庁などに告発文を送付した。すると、大王側から今年2月、「会社の秘密を漏らした」として課長職を解かれた上、北海道にある関連会社の事業所への出向を命じられた。男性が拒否すると、今月11日付で懲戒解雇されたという。
訴状では、「公益通報者として保護されるべきで、降格から解雇までの一連の処分は人事権を乱用した違法行為だ」と主張している。
大王製紙は「訴状が届いておらず、コメントは差し控えたい」としている。
「大学や高校は事実関係があいまいなまま調査を打ち切っていた。学校法人は『対応が不十分だったと指摘されても仕方ない』としている。」
批判されても反論できない状況と言う事だろう。つまり、「黙認した。」しかし、素直に認められないから「対応が不十分だったと指摘されても仕方ない」
と言う事だろう。
やらせ受験、退職教頭が告白…調査尽くさず 03/18/13(読売新聞)
大阪産業大学(大阪府大東市)が2009年度入試で、入学意思のない付属高校の生徒に受験させていた問題で、当時の付属高の教頭が、退職後の11年秋、学校法人の理事長に「やらせ受験」について文書で告白していたことがわかった。
しかし、大学や高校は事実関係があいまいなまま調査を打ち切っていた。学校法人は「対応が不十分だったと指摘されても仕方ない」としている。
学校法人によると、教頭の名前で理事長宛てに届いた文書には「大学の入試担当部署からの依頼で、成績優秀な生徒に日当を払って受験させた。大変なことをしてしまい、反省している」などという趣旨の内容が記されていた。
同法人は付属高側に説明を求めたというが、事実関係が分からないとして公表していなかった。しかし、今年1月に文部科学省に内部告発があったことを受け、大阪府が高校から聞き取り調査したところ、同高の教諭らは、当時の教頭の指示で生徒に受験させたことを認めたという。
内部告発がなければ発覚しなかった「やらせ受験」。目的は「補助金」。補助金がなければ運営できない学校は残念だか閉鎖するしかないだろう!
始まりがあれば、終わりがある。
大阪産大で「やらせ受験」…付属高生に依頼 03/18/13(読売新聞)
大阪産業大学(大阪府大東市)が2009年度の入試で、入学意思のない付属高校(大阪市城東区)の生徒に、経営学部の一般入試を受験するよう依頼していたことがわかった。
謝礼を支払って受験させたとの内部告発もあり、運営する学校法人が19日に第三者委員会を設置し、事実関係を調査する。依頼された生徒は合格後、全員が入学を辞退。大学側が国からの私立大学等経常費補助金を確保するため、入学者数を調整した可能性もあるという。他の受験生の合否に影響した可能性があり、文部科学省も事実解明を求めている。
学校法人などによると、告発は1月、同省に寄せられた。当時の経営学部の入学定員は465人だったが、一般入試実施前の段階で、推薦入試合格者が600人を超える状況だった。私立大は、入学者が定員の1・37倍(09年当時)を超えた場合、補助金が交付されなくなる規定がある。同学部の一般入試の募集定員は78人で、420人が受験。不交付となる637人を超えないよう、入学意思のない受験生で合格枠を埋め、入学者数を抑えようとした可能性があるという。
コスト削減を優先にしたプロジェクトではこのようなことは良くある事だと思う。結果として死亡者が出ただけの事。
コスト削減や急な変更があるが納期の変更がないケースなどでは良くあることだろ思う。コスト削減や急な変更があっても追加料金がない場合、
自分達には関係ない事は対応しない場合もある。管理責任者が不在、またはプロジェクト責任者が適切に対応していないと問題が発生しても
不思議ではない。結果として問題がある可能性があっても、検査に通る、クレームがないケースだとそのまま問題のリスクは放置されたままだと思う。
事故が起きることで初めて調査や再チェックで問題点が浮き上がるのだと思う。日本の場合、あいまいなままに工事、プロジェクト、建設が進んで
行く場合が多いのではないかと思う。プロジェクトの途中で担当会社や担当者を変えるのも問題だ。責任が曖昧になるし、契約に引き継ぎが発生した場合の
追加費用の支払いとか、引き継ぎに関する打ち合わせの費用はないと思う。また、現場確認の費用がない見積もりの会社を選択したこと自体、コスト削減の
影響だと思う。現場確認の費用はコストアップ。しかし、事故が起きた時はコスト削減が原因になる可能性は高い。今回は死亡者が出たことで調査や原因究明が
行われているだけで、氷山の一角だと思う。そして死亡事故が起きたことでそれぞれの関係者が責任逃れのスタンスを取るので、真実と嘘を見分けて原因究明を
するのは難しいと思う。明確な証拠がなければ個々の証言が真実なのか、
嘘なのか判断するのも難しいだろう。
「捜査関係者は『コ社に道義的責任もある』としながらも『設計変更があってもプロとして建築士の仕事を果たすべきだった』と指摘する。」
捜査関係者は専門的な知識と経験があるのだろうか、「設計変更=技術的に実現可能」とはならないこともある。設計変更により構造計算の結果が十分な
強度がないとなった場合、設計変更は不可能となる。つまり設計変更による構造計算が要求を満足するためには、スロープと本体はつながっていたと仮定して
計算しなければ合格する値が出なかったのではないのか?結果として「スロープと本体はつながっていない」条件で計算すると合格する値が得られていないと思う。
現実にスロープが崩落している。計算で合格する数値が出ているのであれば、スロープの崩壊が想定外であったと結論付けられていると思う。どのような
展開になるのか待つしかないだろう。
コストコ崩落:構造計算担当者、急な設計変更で混乱 03/09/13(毎日新聞)
東日本大震災で東京都町田市の大型スーパー「コストコ多摩境店」のスロープが崩落した死傷事故は、11日で発生から2年になる。警視庁に業務上過失致死傷容疑で書類送検された建築士の社長らへの取材では、コ社側の突然の設計変更で現場が混乱し、構造計算を担当した2人の間で情報が共有されないまま作業が進められた実態も浮かぶ。建築士らは「急な変更が事故の背景にある」と主張する。
関係者によると、最初の建築確認を受けた翌日の02年1月9日、コ社は突然、設計変更を指示。スロープは耐震性を高める筋交(すじか)いのある構造だったが、本体は筋交いを外して柱とはりで支える構造に変わった。構造計算の担当は豊島区の社長(65)から石川県の社長(66)に引き継がれた。
コ社は設計変更の理由として「コストダウン」と「工期短縮」を挙げた。2月の着工を前に、構造計算は「約10日で仕上げるしかなかった」(石川県の社長)。一方、豊島区の社長は「補助役」として石川県の社長を手助けしたが、意思疎通は不十分だった。
致命的だったのはスロープと建物本体の接合部分。石川県の社長は双方を一体として構造計算したが、実際はスロープと本体はつながっていなかった。
豊島区の社長は「石川県の社長にはつながっていないと伝えたが、結果としてそれを前提とした構造計算になっていなかった。必要な情報はコ社から伝わっていると思った」と話す。一方、石川県の社長は「つながっているものだと思っていた」と説明する。接合部分を含め、構造計算に必要な書面が石川県の社長に届いていなかった疑いもある。
コ社は構造計算に直接関わっていないため立件は見送られた。構造計算ミスを見逃したとされる港区の社長(71)は「計算に誤りがあったのは確かだが、混乱を招いたコ社の対応にも問題がある」と話す。捜査関係者は「コ社に道義的責任もある」としながらも「設計変更があってもプロとして建築士の仕事を果たすべきだった」と指摘する。コ社の代理人弁護士は毎日新聞の取材に「コメントできない」としている。【松本惇】
コストコ崩落:建築士4人を書類送検、震災倒壊初の立件 03/09/13(毎日新聞)
東日本大震災で東京都町田市の大型スーパー「コストコ多摩境店」の立体駐車場のスロープが崩落して10人が死傷した事故で、警視庁は8日、構造計算でミスをしたなどとして石川県の設計事務所の社長(66)ら1級建築士4人を業務上過失致死傷容疑で書類送検した。震災による建物倒壊で刑事責任を問うのは初めて。
ほかに書類送検されたのは、最初に構造計算した豊島区の構造設計事務所の社長(65)や、工事監理者だった港区の建築設計事務所の社長(71)と当時の設計部長(60)。
送検容疑は、石川県の社長らは02年1月ごろ、構造計算を誤って耐震性の低い設計をし、工事監理者の社長と設計部長も安全性を確認する義務があったのに見過ごしたとしている。警視庁によると、元設計部長は「私にも責任はあると思う」と供述しているが、3人は否認しているという。
捜査1課などによると、コストコ多摩境店は02年1月に建築確認を受けた直後、建物本体と、外壁に設置されたスロープの設計を変更。当初はいずれも柱とはりの骨組みに筋交(すじか)いを入れた構造だったが、工期短縮などを理由に本体部分だけ筋交いを外した。
設計変更に伴い、構造計算の担当者も豊島区の社長から石川県の社長に代わったが、社長はスロープと建物本体が一体化しているとの誤った前提で計算し、地震でスロープと建物本体の揺れ方に差が生じることを考慮しなかったという。同課は引き継ぎの際、情報共有ができなかったことが原因とみている。
事故では川崎市麻生区の長沢※一さん(当時74歳)と洋子さん(同66歳)夫妻が死亡し、8人が重軽傷を負った。【小泉大士、喜浦遊、松本惇】
※は金へんに英
建築士が悪かったのか、工期短縮と経費削減を求めた施主側が悪かったのか、事実を知らないと何とも言えないな?
仕事がほしくて妥協した建築士が悪いと言えば、そうだし、断れば他の建築士が書類送検されただけかもしれない。
施主側は専門家でないし、安全性に問題があると言われれば設計変更を諦めたと言えば、事実はどうであれ責任は逃れられると思う。
専門家である強みと弱いところであろう。
工期短縮狙い設計変更、スロープ崩落事故で供述 03/08/13(読売新聞)
東日本大震災で東京都町田市の大型スーパー「コストコ多摩境店」のスロープが崩落し、10人が死傷した事故で、設計を担当した複数の建築士が警視庁の調べに「施主側に工期短縮と経費削減を求められ、当初の計画と違う構造になった」と供述していることがわかった。
同庁は安易な設計変更が事故の背景にあるとみており、8日午後、建物の設計を担当した1級建築士4人を業務上過失致死傷容疑で書類送検する。
捜査関係者によると、同店の設計は2001年春頃に始まり、港区の建築事務所の建築士の男(71)ら2人がデザインと工事も含めた監理を担当。同事務所と協議しながら、豊島区の設計事務所の1級建築士の男(65)が構造設計を行い、店舗本体とスロープを、いずれも柱とはりに筋交いを入れるなど地震時の揺れが小さい構造にした。
ところが、同年12月になって、施主側が新たに石川県の1級建築士の男(66)に工期短縮を求めて設計変更を依頼し、店舗本体の設計だけ筋交いのない構造に変更された。当初の設計に関与した3人も、最終的に変更を了承したという。その結果、地震の際の店舗本体とスロープの揺れ方が異なるものになり、接合部分の破断に至ったとみられる。
これが現実で原発事故がなければこのような事実は表に出なかったのであろう!原発が安全とか、適切な管理が行われているとか、
信じないほうがよいだろう。メリットとデメリット、個人が受け入れられる最悪のシナリオを考えて、受け入れられないのであれば
原発から離れた場所で新しい人生をはじめた方が良いだろう。出来ないのであればリスクと共に共存し、何も起こらない事を祈るしかない。
東電、原発作業員の被曝記録を提出せず 2万人分 02/27/13(朝日新聞)
【佐藤純、多田敏男】福島第一原発で事故後に働いた約2万1千人が浴びた放射線量について、東京電力が全国の原発作業員の被曝(ひばく)記録を一元的に管理する公益財団法人「放射線影響協会」(放影協)にまったく提出していないことがわかった。東日本大震災による事故から2年近くたった今も、ずさんな被曝管理は続いている。
【写真】被曝線量一元管理の仕組み
原発作業員は電力会社を頂点に下請けが連なる多重請負構造の中で働いている。会社を転々とする人も多く、一元管理を徹底しなければ被曝限度を超えて働き続ける人が続出しかねない。
被曝線量は一人ひとりが持つ放射線管理手帳に元請けや下請けが記入するとともに、電力各社から放影協の放射線従事者中央登録センターに電子データで送られて一元管理される。各社は新たな作業員が原発に入る際に手帳で被曝線量をチェックし、手帳の中身を確認する場合はセンターに照会する。年間の照会件数は6万~9万件に上る。
酒はほとんど飲まないのでどうでもよいが安い酒でも「味大差ない」のであれば何で高い酒を飲むの?
味よりもステータスなのか?
安酒に高級ラベル!老舗「浪花酒造」でインチキ商法 02/27/13(読売新聞)
大阪府阪南市の酒造会社「浪花酒造10+ 件」が純米酒に醸造アルコールなどを混ぜたり、安価な酒に高級酒のラベルを貼り替えたりしていたことが26日、同社などへの取材で分かった。3つの商品で表示とは違う成分が入っていることが大阪国税局の調査で発覚し、同社は今年1月以前に製造した商品の自主回収を進めている。
日本酒ファンを裏切るような事実が、老舗酒造会社で発覚した。
浪花酒造によると、通常は純米酒や吟醸酒の新酒を製造する際、味を調えるために前年に作った同種の古酒を数%混ぜていたが、前年の商品が完売し古酒の在庫がなくなったため、純米酒1種に醸造アルコールを混ぜたほか、吟醸酒2種に基準以上の醸造アルコールなどを混ぜた。
国税庁の基準では、純米酒は米と米こうじだけで造られ、醸造アルコールを入れることは認められていない。一方、吟醸酒には白米の重量の10%以下の醸造アルコールを入れることが認められている。
国税局が新酒の成分を調べた結果、混ぜられた純米酒や吟醸酒に本来含まれない糖類が含まれていたことが発覚。また、2012年4月までの半年間に製造した純米大吟醸が品切れになった際、安価な吟醸酒に高級な純米大吟醸のラベルを貼って販売していたという。
同社の成子和弘社長(52)は「味がほとんど変わらないので、その場しのぎでやってしまった。反省している」と話している。しかし、微妙な違いを利き分けながら味わうことこそ“通”の楽しみ。「味がほとんど変わらない」という言葉は、行為だけでなく、生産者や日本酒ファンを裏切ることとなった。
浪花酒造10+ 件は江戸時代中期の1716年創業の老舗で、同社の「純米大吟醸 究極の技」は2008年7月の北海道洞爺湖サミットで提供された。現在は1升3万円前後、720ミリリットルが1万5000円前後で販売されている。また、全国新酒鑑評会金賞やモンドセレクションなど数々の受賞歴がある。
阪南市商工会のホームページでも地元の推薦企業とされ、社長の一言として「どんなにITや機械化の時代になろうと手造りに徹し、心のこもった豊かな酒を醸していきます」とメッセージを掲載している。
酒造組合の関係者は「飲む人によって感じ方も違うし、(醸造アルコールを)入れる量にもよるが、先入観もあるし、内容を区別するのは難しいと思う。それぞれに違いがあっていいものなのに、なぜそんなことをしたのか」と残念がった。
◆清酒の製法品質表示基準 国税庁によると、使用する原料、製造方法等の違いにより8種類に分類される。米、米こうじのみを原料とするものには、米の精米歩合が50%以下の「純米大吟醸酒」、同60%以下の「純米吟醸酒」、同60%以下または特別な製造方法(要表示)の「特別純米酒」、精米歩合の規定が定められていない「純米酒」がある。また、米、米こうじに醸造アルコールを添加したものには、米の精米歩合が50%以下の「大吟醸酒」、同60%以下の「吟醸酒」、同60%以下または特別な製造方法(要表示)の「特別本醸造酒」、70%以下の「本醸造酒」がある。醸造アルコールとはでんぷん質物、含糖質物から作られ、適量添加すると香りが高く「スッキリした味」となる。
安い酒に「大吟醸」ラベル…社長「味大差ない」 02/26/13(読売新聞)
大阪府阪南市の酒造会社「浪花酒造」が、製造・販売する日本酒に実際とは異なる銘柄のラベルを貼って販売していたことがわかった。
安い酒に「大吟醸」などの高級品のラベルを貼っていたほか、「高い酒に安い酒のラベルを貼ることもあった。品切れになった時、商品を確保するため場当たり的にやった」と同酒造は説明。1月以前に製造した商品の自主回収を始める。
同酒造によると、不正表示は大阪国税局の調査で発覚した。自主回収の対象は大吟醸、吟醸酒、純米酒など6種類。在庫がない銘柄の注文があった際、瓶に別の銘柄のラベルを貼って出荷しており、5年前から繰り返していた。こうした不正表示は年間1000本に上っていたという。
また新酒を造る際には、味の調節のため同じ銘柄の古い酒を少し混ぜていたが、足りない時は別の銘柄を混ぜていたという。同酒造は江戸中期の1716年創業。年間20万本を生産し、自主回収対象の6種類はうち3割を占める。成子和弘社長(52)は「味に大差はなく、問題ないと思った。認識が甘かった」と話している。
建前は技能実習生のためと言っても、実際は安価な労働者の供給団体が多いはず。たぶん、氷山の一角だと思うが、
逮捕された以上徹底的に調査して公表してもらいたいものである。メリットがなければ技能実習生の受け入れ団体など
やめてしまえばよいのである。
「別のカンボジア人の男(41)は05〜08年に、茨城県で実習を受け、帰国後は「バイクタクシー」の仕事をしていた。」
結局、技能実習制度には問題があると言う事だ。日本でも同じ。失業者の資格取得支援が同じだ。ニーズがない、経験がなければ
資格取得だけでは採用される機会がなくとも資格取得支援講座が存在するのと同じ。技能実習制度は安価な労働者を求める
企業が多いから廃止や改善を求める声が少ないのだと思う。
不正受け入れ:外国人実習生の給料抜き取り (1/2ページ)
(2/2ページ)02/21/13(毎日新聞)
カンボジア人を技能実習生として不正に再入国させたとして茨城県下妻市の受け入れ団体「いなほ協同組合」の元理事長の男が逮捕された事件で、同組合が実習生の給料から本国への送金名目などで毎月1人6万円を不正に抜き取っていたことが21日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁は、03年以降に受け入れた実習生400〜500人から計約4億円を集め、その一部を着服した可能性があるとみて調べる。
逮捕されたのは元理事長の稲富浩一(いなとみ・ひろかず)容疑者(63)=東京都練馬区高野台3。警視庁が21日発表した。「在留資格の変更申請をしたが、不法入国と知らなかった」と否認している。
同組合では給料の「ピンハネ」は常態化していた。
同組合から実習生8人の派遣を受ける富山県の企業によると、給料の振込先となる実習生の個人口座は、同組合が管理。そのうち、本国への送金名目で3万、来日前に無料で学んだ同組合の日本語学校への支援費として3万の計6万円が毎月、差し引かれていたという。同社の担当者は「納得済みの実習生もいたが『払う必要はないのに』と話す人もいた」と明かす。
捜査関係者によると、抜き取った金は一部が実習生の親族へ送金されていたが、ほかは使途不明という。【黒田阿紗子】
◇「遊びに行くな」特別に注意も
不正受け入れの実態についてカンボジア人の男(36)が公判で証言していた。2010年5月ごろ、男は、いなほ協同組合が所有するカンボジアの日本語学校の一室に呼ばれた。男は06年から09年まで外国人技能実習制度を利用して日本で働いていたが、2度目の訪日を目指していた。
部屋にいたのは約10人。姿を現した稲富容疑者は「特別」な注意事項を説明した。「あまり遊びに出るな」「実習生として(日本に)来たのは2回目と絶対に言うな」。外出を避けるのは、知り合いの日本人と会わないようにするためだ。周囲の人が、偽名で再入国するのだと察した。
捜査関係者などによると、同組合はカンボジアに複数の日本語学校を所有。実習生候補のカンボジア人に語学や日本の習慣を教えていた。また、稲富容疑者は現地の送り出し団体「エバーグリーン ファーミング カンボジア」の実質的責任者でもあった。
別のカンボジア人の男(41)は05〜08年に、茨城県で実習を受け、帰国後は「バイクタクシー」の仕事をしていた。「また日本で働きたい」と稲富容疑者に願い出たところ、「名前と生年月日を変えなければ」と指示された。偽名旅券を得るため日本の戸籍にあたる「ファミリーブック」を偽造した。【黒田阿紗子】
検査関係の仕事をしていて学んだ事は検査される側は嘘をつく事があると言う事である。相手をそのまま信じてはいけない。嘘には程度の問題もある。
そして明らかに相手が嘘をついているかの判断をする能力も必要である。まともな検査をすると検査される側から嫌われるし、相手次第であるが
脅される事もある。また、検査される側が検査を甘くしてくれる見返りを提示する事もある。長いものに巻かれる方が楽だとは思うこともある。事実を
知ったら問題が起こった時に責任を問われるので上の人間が事実を知りたがらない事もある。事故や問題が起こらなければ良いが、問題が起きれば
現場が責任を取らされる。原発の世界は知らないが、311後の対応を見ていると安全とか責任とかは問題じゃないように思える。事故の対応中の時から
逃げている。言い訳、嘘、専門家への圧力そして政治家への圧力。よほど多くの国民が強く主張しないと原発問題はうやむやになるだろう。
東電、開口一番に真っ暗で危険と…「妨害」批判 02/07/13(読売新聞)
東京電力が、国会の事故調査委員会に誤った説明をして、福島第一原子力発電所1号機の現地調査を断念させていたことについて、委員だった田中三彦氏が7日午後、記者会見した。
東電は同日朝、「建屋内の明るさについては、委員側からその場で尋ねられたので確認せずに答えた」と釈明していたが、田中氏は「東電から開口一番に、真っ暗で調査は危険だと説明された。虚偽説明は国会を愚弄している」と批判した。
予定していた現地調査は、1号機の冷却装置「非常用復水器」が地震で壊れた可能性を探る目的だった。東電は地震による重要設備の破損はなかったと主張しており、田中氏は「(調査で)変なものを引っ張り出してくると困ったのだろう」と語った。
東電広報部は同日夕、「様々な危険を説明する中で、暗くなるという趣旨の発言が際立って伝わったのではないか」とさらに弁明した。
東電、国会事故調に誤説明…原子炉建屋調査で 02/07/13(読売新聞)
東京電力福島第一原子力発電所事故について、国会の事故調査委員会が昨年3月、1号機原子炉建屋の4階を現地調査しようとしたところ、東電に「真っ暗で危ない」と誤った説明をされたため、調査を断念していたことが7日分かった。
事故調委員だった田中三彦氏は同日、「虚偽説明による重大な調査妨害があった」として、現地調査を要請する文書を衆参両院の議長と経済産業相にファクスなどで提出した。
要請文書によると、事故調は、緊急時の冷却装置「非常用復水器(IC)」が津波でなく地震で壊れたとの疑いをもち、ICがある4階を調査しようとした。その直前の2月28日、同社企画部の玉井俊光部長(当時)らが田中三彦氏らを訪ね、薄明かりが差す4階の映像を見せて「これは(放射性物質の飛散を抑える)カバーの設置前。今は建屋にカバーがかかり照明もない」と説明したという。
しかし、その映像はカバーの設置後に撮影されていた。実際には照明が設置され、真っ暗になることはなかった。事故調はICの損傷の有無を確認できないまま、同年7月に最終報告書をまとめた。
規則と現状のギャップがあっても、時代と共に変化が起きる事もある。規則を守らせるのであればガソリンスタンド2千店超の閉店も仕方ないだろう!
需要と供給そして利益を考えると、不便になる事も仕方のない事かもしれない。
ガソリンスタンド2千店超が閉店…消防法改正で 01/31/13(読売新聞)
2012年度中に閉店するガソリンスタンド(GS)が2000店を突破する見通しであることが、全国石油商業組合連合会(全石連)の試算で明らかになった。
11年度(1034店)の2倍の水準で過去最多となる見込みだ。11年2月に施行された改正消防法で、GSの地下タンクの設置年数に応じ、油漏れ防止装置(1か所あたり500万円程度)などを1月末までに設置することが義務づけられているほか、エコカーの普及で給油が減っていることも閉店する店舗が増えている背景にあるとみられる。
全石連によると、改正消防法で改修の対象となるGSは全国で約7000店舗。経済産業省が2年間の移行期間に必要費用の3分の2を補助する制度を設けているが、制度を利用するのは約5000店にとどまる。過当競争などで廃業する業者も含めれば、閉店は2000店を上回る見通しだ。
儲かっているサムスンでも見えないところではお金をかけない!その上、皮膚を壊死(えし)させ、吸い込んでも死に至る危険があるフッ素漏れを隠ぺいした。
電子機器最大手サムスン電子の企業体質は日本の体質とあまり変わらないのであろう!
サムスン工場 猛毒漏れ ソウル近郊 作業員5人死傷 01/28/13(産経新聞)
【ソウル=共同】韓国メディアによると、ソウル近郊の華城にある同国の半導体・電子機器最大手サムスン電子の半導体工場で27日夜から28日にかけ猛毒のフッ化水素酸(フッ酸)が2度漏れる事故があり、作業員1人が死亡、4人が負傷した。
聯合ニュースによると、同社は事故を消防などに通報せず隠蔽(いんぺい)し、当局の指摘を受け認めた。漏れたフッ酸の量も、当局側が10リットルと推定するがサムスンはもっと少ないなどと主張している。
フッ酸は日本でも毒劇物法で指定される揮発性の液体。皮膚を壊死(えし)させ、吸い込んでも死に至る危険がある。
工場では、貯蔵施設の老朽化で最初の漏洩(ろうえい)が起き、サムスンの関連会社の作業員5人が修理に当たった際にも漏れ出していたとみられる。うち1人が頭痛を訴え病院で死亡した。
ビックリ!! 関電顧問に1億4千万円 値上げ料金一部を給与に 01/28/13(産経新聞)
関西電力は28日、経済産業省が開いた家庭向け電気料金値上げの公聴会で、経営に直接関与しない顧問14人の給与として年間で計約1億4千万円を支払い、一部を電気料金で賄う計画を明らかにした。顧問は関電会長を務めた秋山喜久氏をはじめ同社の有力OBらが就いている。電気料金の一部を使って1人当たり平均1千万円を払うことに利用者の反発が広がった。
関電は昨年11月、家庭の料金を平均11・88%値上げすると政府に申請し、値上げ幅の根拠となる2013~15年度の原価に給与を織り込んだ。金額は、顧問と再雇用した社員を合わせて年平均4億円と公表している。
公聴会で、意見陳述した女性は「給与を(原価に)含めることは適切でない」と指摘した。別の男性も「(水準の高さに)びっくりした」と話した。
新日本に業務改善命令へ 大阪労働局 違法派遣で処分 01/07/13(産経新聞)
人材派遣大手の「新日本」(本社・大阪市北区)が、事業所設立に関する国への届け出を怠り、無許可で派遣業を行ったとして、大阪労働局は17日、労働者派遣法に基づく業務改善命令を出す方針を固めた。厚生労働省によると、違法派遣をめぐり人材派遣会社が国の行政処分を受けるのは異例。
関係者によると、同社は滋賀県内で事業所を設立した際、国への届け出を怠り、無許可で事業を継続。これまでに2回、国の是正指導を受けたが、改善しなかったという。大阪労働局は、再三の指導に従わず、違法状態を放置した同社の体質が悪質と判断し、処分することを決めた。
業務改善命令は、違法行為が発覚した場合、事業主に再発防止を求める行政処分の一つ。期限内に改善がみられなければ、事業停止や登録取り消しの処分を受けることもある。
新日本をめぐっては、従業員への残業代を支払っていなかったとして昨年11月、大阪労働局が本社などを家宅捜索した。
同社は全国7カ所に営業拠点があり、登録社員は約4千人。グループ全体の売上高は約210億円。
研究にかかわっていない論文に執筆者として名を連ねることは結構あるのではないのか?関係者でない人達だけが知らないだけで、このようなことは
昔からあるのではないのか?運悪く、虚偽発表した森口尚史ひさし氏の問題が注目されて研究にかかわっていない論文に執筆者として名を連ねたことが
新聞記事になったと言う事ではないのか??
森口氏論文共同執筆の教授処分…東京医科歯科大 12/28/12(読売新聞)
iPS細胞(人工多能性幹細胞)から作った心筋細胞を患者に移植したと虚偽発表した森口尚史ひさし氏(48)の論文を調査していた東京医科歯科大は28日、共同執筆者の佐藤千史ちふみ・同大大学院保健衛生学研究科教授(63)を、停職2か月の懲戒処分(26日付)にしたと発表した。
研究にかかわっていない論文に執筆者として名を連ね、大学の信用を失墜させたと判断した。また、森口氏が使った海外出張旅費など、不適当とした経費約130万円の返還も佐藤教授に求めた。
同大の調査では、佐藤教授が共同執筆者になった、1996年~今年の論文23本のうち、実際に研究にかかわっていなかった論文は20本あった。
同大によれば、佐藤教授は森口氏の大学院時代の指導教官だが、iPS細胞に関する専門知識がなく、森口氏の論文の内容を検証せずに共同執筆者になった。この点を同大は「研究者としてあるまじき行為」と批判した。大学側は、個々の論文が虚偽かどうかの判断はしていないが、論文のiPS細胞研究は学内では行われず、倫理委員会への申請もなかったとしている。
リコールは費用が発生するし、役人(国土交通省)達は何も知らないから適当に対応しておけと言うことだったのでは??
三菱自動車を立ち入り検査=本社や統括本部など9カ所-リコール消極姿勢で・国交省 12/25/12(時事通信)
三菱自動車がリコール(回収・無償修理)に消極的だったなどとして、国土交通省から厳重注意を受けた問題で、国交省と各運輸局は25日、同社本社(東京都港区)や品質統括本部(愛知県岡崎市)など9カ所に対し、道路運送車両法に基づく立ち入り検査を行った。数日間続く見通しで、法令違反がなかったかどうかを確認する。
他の対象は、販売店に対して技術的なサポートを行う北海道と宮城、埼玉、愛知、大阪、岡山、福岡各府県所在の「テクニカルセンター」。複数の販売店にも検査に入る予定という。
国交省などによると、三菱自動車は2005年2月、軽自動車のエンジンオイル漏れの不具合情報を入手。08年1月の社内会議で事故が発生していないことなどから「リコールは不要」とする判断を下した。
一方、国交省は独自に検証した結果、09年10月と12月にリコールを実施するよう指導。三菱自動車は10年11月に最初のリコールを行ったが、実施前、国交省に対し、「オイルは大量に漏れない」などと実態とは異なった不適切な説明をしたという。
また、明確な根拠がないのに対象車を絞り、同社社員の内部通報や国交省の指摘を受けた。最終的に計4回で10車種計約176万3000台を届け出ており、国内で最多リコールとなった。三菱自動車の外部有識者委員会は19日、調査結果を国交省に報告。同省はリコール検討の姿勢が消極的だったり、同省に不適切な説明をしたりしたなどとして、口頭で厳重注意した。三菱自動車をめぐっては00年と04年にリコール隠しが発覚。これに絡み、同社や同社の元役員らが刑事処分を受けている。
三菱自動車の話 事態を重く受け止め、検査に協力したい。再発防止の改善施策を実行していく。
「同社(中日本高速道路)は『健全性が回復したと判断した。点検は目視が基本で、目視で異常を発見すれば打音も必要という認識だった』と説明している。」
「点検は目視が基本で、目視で異常を発見すれば打音も必要」との判断を下した人は誰なのか?その判断が妥当である根拠は何だったのか?
中日本高速道路でこの判断に異論を唱えたものがいたのか?ほぼ反対意見なしに判断が受け入れられたのか?これらの点をついてマスコミは
取材して公表して欲しい。これぐらいは行わないと同じような事故は防げないと思う!
「打音」の方法は?中日本高速の説明、二転三転 12/06/12(読売新聞)
中日本高速道路(名古屋市)が山梨県の中央道・笹子トンネルで2000年に実施した打音検査で、天井板を支えるつり棒を固定する金具部分に不具合を見つけ、補修していたことがわかった。
こうした経緯がありながら、同社はそれ以降の点検時には打音検査を行っていなかった。同社は「健全性が回復したと判断した。点検は目視が基本で、目視で異常を発見すれば打音も必要という認識だった」と説明している。
つり金具などをたたいた反響音で緩みや腐食の有無を確認する打音検査について、同社は当初、「手の届かないところはやっていなかった」と説明していた。しかし、その後「00年の詳細点検では高所でも実施した」と変更。5日には、この際の打音検査で、つり金具を固定するアンカーボルトのナットの緩みなどが判明し、補修を行った――とさらに説明が変わった。
笹子トンネル、最後のボルト打音検査は12年前 12/05/12(読売新聞)
山梨県の中央自動車道・笹子トンネルの天井板崩落事故で、中日本高速道路が2000年を最後に、天井板をつり下げるアンカーボルトの打音検査を行っていなかったことがわかった。
国土交通省の調査検討委員会が明らかにした。
調査委では、同トンネルで中日本高速が実施した過去3回の「詳細点検」の手法を調査。その結果、00年には、トンネル上部のボルトや付近のコンクリートの劣化を、打音検査で点検していたが、05年と今年9月の点検では、行っていないことがわかった。
調査委では、事故の原因究明と合わせて、点検が適切だったかも調べる方針。
安全対策を一つ一つ積み重ねていれば、こういう結果にならなかった。適切に現地を管理していなかった」
誰かが安全対策を疎かにする判断を下しているはずだ。そこまで調査しないとだめだ。また同じことが繰り返される。
万里の長城遭難:旅行社、現地と定期連絡せず 指導に反し 11/13/12(毎日新聞)
中国・万里の長城で日本人ツアー客3人が死亡した遭難事故で、ツアーを主催した旅行会社「アミューズトラベル」(東京都千代田区)が09年の北海道・トムラウシ山の遭難事故を受け現地と営業所で定期的に連絡を取り合うよう指導を受けながら、実施していなかったことが13日、観光庁の立ち入り検査で分かった。
観光庁は13日、2回目の立ち入り検査を行い、板井克己社長から事故後初めて事情聴取。板井社長は同社で下見をせず現地任せにしていたと認め「管理不足だった」と述べたという。さらに、09年7月に同社の企画で8人が死亡したトムラウシ山の遭難事故を受け、同庁から現地と営業所で気象情報などの連絡を取り合い、悪天候時はツアーを実施するか営業所から判断を受けるよう指導を受けたが、「問題があった場合のみでいいと思った」と実施していなかった。
また、ガイドを委託した中国の旅行会社との契約書について、板井社長は「ないかもしれない」と説明。同庁は実務を把握している添乗員と連絡をとり、契約書や企画書の有無を調べるよう指示した。【桐野耕一、池田知広】
万里の長城遭難、ツアー会社「安全管理が不足」 11/13/12(読売新聞)
中国河北省の万里の長城付近で登山ツアーに参加した日本人旅行客3人が死亡した事故で、ツアーを主催したアミューズトラベル(東京)の板井克己社長(42)が観光庁の聴取に対し、「会社として安全面での管理が不足していた」と話したことが同庁への取材でわかった。
同庁は、旅行の安全確保を求めた旅行業法に違反する疑いもあるとみて、さらに調査を進める。
同庁は13日、事故後2回目の立ち入り検査を実施。板井社長は聴取に対し、ツアーの決行などを自社社員の中国人添乗員や現地ガイドに任せていたことを認め、「安全対策を一つ一つ積み重ねていれば、こういう結果にならなかった。適切に現地を管理していなかった」などと述べ、管理不足を認めたという。
運が悪かった、そしてこのようなずさんな旅行会社は他にも存在するかもしれない。
しかし、2回も死者を出した旅行は旅行会社の体質の問題がある可能性が高い。観光庁を所管する国土交通省はしっかりと調査して
結果の基づいて旅行会社を処分して欲しい。処分が軽い法令しかなければ今回の事件をきっかけに処分を重くするべきだ。
日本の経済は傾き始め、日本政府も財政問題を抱える。贅沢な旅行は一部の富裕層だけで、安い旅行が今まで以上に増えるだろう。
だからこそ最低ラインを明確して、違反した旅行会社は厳しい処分を受けることを認識させるべきだ。
万里の長城遭難:観光庁が旅行会社を立ち入り検査 11/09/12(産経新聞)
中国・万里の長城をツアー中の日本人観光客3人が死亡した遭難事故で、観光庁は9日、不十分な旅行計画と判断ミスが遭難事故につながった疑いがあるとして、旅行業法に基づきツアーを主催した旅行会社「アミューズトラベル」(東京都千代田区)を立ち入り検査した。同社側の説明では、社員が現地の下見をしておらず、悪天候時に決行した判断を現地任せにしていたなどの問題点が浮上しており、業務停止処分などを視野に入れ調査を進める。
一方、観光庁は09年7月に8人が死亡した北海道・トムラウシ山の遭難事故で同社を行政処分した際の指導状況を検証するため、庁内に検証チームを設置。観光庁を所管する羽田雄一郎国土交通相は9日の閣議後の記者会見で「観光庁の対応もしっかり検証したい」と述べた。当時の担当者らから事情を聴き、今月末をめどに中間的な取りまとめをする方針。
アミューズ社によると、事故があったのは「世界遺産 万里の長城 グレートウォール・100キロトレッキング」という10月28日〜11月5日(8泊9日)のツアーで日本人4人が参加。民宿に泊まりながら添乗員と現地ガイドが付き添い、7日間で100キロ余りを歩く計画だった。
同社の説明によると、今月3日に雪が降るとの情報を得ながら現地の判断でツアーを強行。行程途中で大雪に見舞われ、参加者1人が動けなくなった。中国人ガイドが救出を求めるため下山し、救助を待つ間に参加者4人のうち3人が死亡。同社から冬山装備の指示がなく参加者たちは軽装だった。また、今回初めての開催なのに同社の社員が下見をしていなかった上、ガイドの経歴も把握していなかった。
旅行業法に基づく行政処分の基準では、安全確保が不十分な場合の処分を18日間の業務停止と規定。観光庁は、出発の判断や装備の指示、ツアーの下調べが適正に行われたかなどを中心に調査するとみられる。
同社はトムラウシ山の遭難事故について、天候悪化に伴う危険回避の判断基準を設けていないなど安全確保を怠ったとして、観光庁から10年12月に51日間の業務停止処分を受けた。【桐野耕一】
現代と起亜が燃費水増し 米国で販売の90万台 11/03/12(産経新聞)
米環境保護局(EPA)は2日、韓国の現代自動車と傘下の起亜自動車が米国で販売した一部車種の燃費表示が水増しされていたと発表した。現代と起亜はEPAの指摘に従って表示を変えた。対象台数は約90万台に上る。
EPAと現代によると、燃費表示を変えるのは2011~13年型の主力小型車「エラントラ」や2011~12年型の中型車「ソナタ」のハイブリッド車などで、11~13年型の全車種のうち約35%が対象。12年型の対象車の場合、平均で約3%水増しされていた。
米国では乗用車の燃費性能比較を容易にするため、新車販売時に燃費を示すラベルを表示するようメーカーに義務付けている。水増しが明らかになり、表示の信頼性が損なわれる結果となった。
現代は「大変申し訳ない。手続き的な間違いだった」と釈明している。(共同)
中華料理チェーン会長を逮捕、中国人を不法就労 10/31/12(産経新聞)
調理師の在留資格で入国させた中国人を接客係として働かせたとして、大阪府警外事課は30日、全国で中華料理チェーン「●●(ミンミン)」を展開する「●●(ミンミン)本店」(大阪市中央区)代表取締役会長・古田曉生容疑者(63)(京都市伏見区)ら2人を入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕した。(●は王ヘンに「民」)
中国人は調理師経験が全くなかったといい、古田容疑者らは「求人を出しても接客係が集まらないので、ブローカーに依頼して中国から調理師の名目で呼んだ」と容疑を認めている。
発表では、古田容疑者と元専務の粟野徹雄容疑者(63)は2008年1月~今年9月、調理師の技能資格で来日した30歳代の女3人に対し、大阪市内の3店舗で接客業務をさせるなどした疑い。
所属タレントに不正に給付金 芸能活動中も「職業訓練」と偽る 10/04/12(産経新聞)
国の求職者支援制度を悪用し、所属タレントらに不正に給付金を受け取らせたとして、東京労働局は4日、芸能事務所「フェザーインターナショナル」(東京都板橋区)の職業訓練の実施機関認定を取り消したと明らかにした。処分は7月23日付。
東京労働局によると、同事務所は2~9月、同じビルにある訓練校で、パソコンの扱い方などを教える「営業実務」として2コースの認定を受けていた。
受講生計23人のうち19人に不正が確認され、一部は事務所所属のタレント。タレントらが芸能活動などで欠席しても、受講したと偽って1人当たり毎月10万円、総額約510万円の給付金を受けた。
5月、東京労働局に「タレントが休んでも出席扱いになっている」と匿名の通報があり発覚。訓練校は処分を受け閉鎖した。
姫路工場爆発1カ月、いまだ原因説明なし…企業責任問う声強まる 10/29/12(産経新聞)
兵庫県姫路市の化学工場「日本触媒姫路製造所」で37人が死傷したアクリル酸中間貯蔵タンクの爆発事故は、29日で発生から1カ月。兵庫県警の現場検証は約10日の時間を要するほど難航、原因究明には時間がかかりそうだ。一方、放水準備中に犠牲となった消防隊員の遺族に日本触媒から事故原因に関する説明は今もなく、遺族は無念さを拭えないままでいる。
日本触媒は事故発生以降、姫路製造所や大阪本社で会見を実施。タンク内温度の監視態勢について、当初は「管制室で常時監視」と説明したが、のちに「1日数回の巡回で、タンク備え付けの温度計を目視」と訂正するなど、説明は二転三転した。
会見では、「捜査対象なので言えない」「調査中」など歯切れの悪さが目立ち、「当局の捜査に全面的に協力し、原因を究明しだい公表する」と繰り返すように。上智大の田島泰彦教授(メディア法)は「大事故から1カ月たっても原因の情報提供がほとんどないのは異様で、企業責任を果たしていない。捜査にかかわらず、明らかにできるものから随時公表すべきだ」と疑問を呈す。
同製造所では昭和51年3月にも爆発事故が発生。アクリル酸メチルの貯蔵タンクが炎上し、漏れた刺激性ガスの影響は10キロ以上離れた市中心部にも及んだ。日本触媒は再発防止策を講じ、市消防局から即時通報の指導も受けていたが今回、消防への通報はタンクからの白煙を確認してから約45分後だった。
放水準備中に死亡した市消防局の山本永浩消防司令補=当時(28)、2階級特進=の父、雲一さん(61)は「息子と同じ車を見かけると、目で追ってしまう」と、辛い胸の内を明かす。日本触媒からは事故原因に関する説明もなく、雲一さんは「危険物を扱う会社として、対応が幼稚だ。四十九日の後に再度問いただす」と憤りをあらわにした。
同社幹部と社外有識者でつくる事故調査委員会は23日に初会合を開き、今後の日程などを協議した。だが、同社は取材に対し、「(事故調を)年内に数回開くとしか言えない」の一点張り。同社が会見で繰り返し述べた「原因を究明しだい公表」の時期はいつになるのかも、依然不透明な状況が続いている。
三菱電機、40年前から水増し請求 防衛装備品などの受注費 防衛省の調査形骸化 (1/2ページ)
(2/2ページ) 10/25/12 (産経新聞)
防衛・宇宙事業をめぐって三菱電機(東京)が、約40年前から作業費水増しや赤字を付け替える手法で防衛省へ受注費用を過大請求していたことが25日、会計検査院の調べで分かった。担当課長が不正の中心的役割を担っていたことも判明。防衛省の定期調査が形(けい)骸(がい)化(か)しており、検査院が是正を求めた。過大請求の総額算定は継続して行う。
対象となったのは防衛省や総務省などが平成19~23年度、三菱電機側と結んだ防衛装備品や人工衛星に関する契約。三菱電機は防衛省だけで計3124件、6341億円を受注していた。契約額を上限とし、実際の作業員数と労働時間を掛け合わせた「工数」を算出、防衛省に請求する仕組みとなっていた。
検査院が調べた結果、同社の鎌倉製作所(神奈川県鎌倉市)と通信機製作所(兵庫県尼崎市)では、赤字となった別の契約の工数を付け替えたり、デスクワークを作業時間に含めるなどの水増しを行っていた。不正は両製作所の関係課長が主導、アクセス権限を持つ専用端末で工数データを書き換えていた。検査院の聞き取りから、鎌倉製作所では昭和45年ごろから不正が常態化していたことが判明したという。
防衛省による定期調査や監査は、事前に同社と日程などを調整していたため、両製作所は専用端末の存在を明かさず、不用意な発言をしない幹部に応対させて発覚を逃れていた。
一方、防衛省は「代替の調達手段がない」ことを理由に、今年1月から約5カ月間の指名停止期間中、三菱電機と計152件、総額約1118億4千万円の契約を結んでいたことも分かった。防衛省会計監査室は「現在行っている特別調査で実態を調べている」、三菱電機広報部は「防衛省の調査に全面的に協力する」としている。
商社に責任があるが、虚偽説明を行った静岡県内のベンチャー企業も問題だ。
「東レは社内調査などの結果、『詐欺行為の被害に遭ったことは把握している』」詐欺行為を東レが認識しているのなら、
被害届を出せば静岡県内のベンチャー企業も捜査対象になるのかな??
輸出規制の炭素繊維、中国に不正持ち出しか 大阪の商社 軍事転用可 10/24/12(産経新聞)
軍事転用される恐れがある炭素繊維が、大阪府内の商社から中国に不正に持ち出された疑いがあることが捜査関係者などへの取材で分かった。炭素繊維は外為法で輸出が規制されており、外為法違反や詐欺の疑いも浮上。捜査関係者からは「戦闘機に使われれば、燃費など中国の軍事レベル向上につながりかねない」との声も上がっている。
関係者などによると、戦闘機の機体に転用したい中国軍事関係者が最新鋭旅客機「ボーイング787」の機体にも使われる東レの最先端の炭素繊維を入手するよう、大阪府内の商社に依頼。平成21年8月に、この商社が約1キロの炭素繊維を経済産業省の許可を得ないまま、中国に持ち出した疑いがあるという。
この商社は東レと取引実績がなかったため、静岡県内のベンチャー企業に東レの炭素繊維約2トンを2千万円で入手するよう依頼。ベンチャー企業は「工場で生産する水素発生装置のボディーに使う」などと東レ子会社に虚偽説明を行い、サンプル約1キロを確保した。商社はその後、中国側に炭素繊維を手渡したとみられている。静岡県警は捜査を行い、同様の事実を把握している。
東レは社内調査などの結果、「詐欺行為の被害に遭ったことは把握しているが、商社が中国側に対し、低品位の炭素繊維を最先端のものと偽ったのではないか」(首脳)としている。大阪の商社は「特にコメントすることはありません」としている。
この国と原発:第7部・メディアの葛藤/1 続けられた批判記事/石油危機、広告の転機(その1) (1/3ページ)
(2/3ページ)
(3/3ページ) 10/22/12 (東京朝刊 毎日新聞)
「この国と原発」はこれまで6部にわたり、原発推進を巡る政界や地元自治体、中央省庁、業界、学者たちの強固な結びつきの歴史と現状などを報告してきた。多くの読者から評価を頂く一方で、「メディアはどうだったのか」との指摘を受けた。可能な限り過去にもさかのぼり、私たちの足元を見つめたい。第7部はメディアと原発の関係を追う。
「毎日新聞は原発推進の広告と引き換えに原発批判キャンペーンをやめた」。東京電力福島第1原発事故後、こんな話が広まった。共産党機関紙「しんぶん赤旗」や「週刊東洋経済」「別冊宝島」などの雑誌に記事が載り、ブログなどで引用されている。いずれの記事も、鈴木建(たつる)・元電気事業連合会広報部長(故人)の著書「電力産業の新しい挑戦」(日本工業新聞社、1983年)が根拠だ。
74年8月6日、朝日新聞に日本原子力文化振興財団の原発推進広告が掲載された。同書によると、国内初の原発推進の新聞広告で、実質的には電事連が主導した(同書では同年7月と表記)。その後、読売新聞と毎日新聞からも広告出稿を要請され、鈴木氏は読売には応じたが、毎日には「原発反対キャンペーンを張っている」と断る。毎日は編集幹部が「原発の記事は慎重に扱う」などと約束。鈴木氏の指摘したキャンペーン記事は「いつとはなしに消えた」ため、読売に1年遅れて広告を出した−−というのが骨子だ。
文脈から、指摘されたキャンペーンは、国や電力会社の原発推進体制を批判的に報じた「出直せ原子力」(74年10〜11月)と、市民運動や消費者運動をメーンに据えた「キャンペーン’75」(75年1〜12月)の二つの連載とみられる。
当時、鈴木氏と交渉したのは、毎日新聞東京本社広告局産業広告課長だった小林正光氏(72)。小林氏によると、鈴木氏は当初、連載記事のほか、東京社会部の河合武記者の記事が「激しい」と注文をつけたという。
河合氏は、日本で最も早く原発を批判的に報じた記者の一人。49年に入社し、54年の第五福竜丸事件を機に原子力取材にのめり込んだ。社会部の後輩、松尾康二氏(75)によると、湯川秀樹氏ら原発に慎重な物理学者の他、東大の向坊隆(むかいぼうたかし)氏ら推進派の大物とも親しく、「博識でデスクにも臆せず正論をぶっていた」という。
鈴木氏に「反原発キャンペーン」とされた「出直せ原子力」も監修した。74年7月に関西電力美浜原発の放射性物質漏れ事故で、関電の社長が「原子炉のトラブルにはもっと寛大になってほしい」と発言。疑問を持った東京経済部の電力担当、肥塚(こいづか)文博氏(72)が社会部の同僚に呼びかけて企画し、河合氏の指導を仰いだ。
安全審査を形骸化させた原発推進体制の問題点を指摘した河合氏の著書「不思議な国の原子力」(61年、角川新書)はこう結ぶ。「原子力の『関係者』は、常に『国民全体』である。だから原子力は、ガラス張りの中で、公正に進められなければならない」
73年に始まった石油ショックを機に、毎日の社内ではエネルギー問題について議論が交わされ、原発は安全に最大限配慮しながら運転を容認する立場を取った。それを踏まえて社説は、74年9月に原子力船「むつ」が放射線漏れを起こした際に「研究開発を断念すべきではない」との論陣を張った。また、77年4月に高速増殖実験炉「常陽」が日本初の臨界を達成すると「喜ばしい」とした上で「前途多難」と書いた。
毎日新聞が電事連の広告を掲載したのは「キャンペーン’75」が終了した翌月の76年1月30日。紙面を見ると、二つの連載はいずれも中断することなく完結しており、毎日新聞が原発批判キャンペーンをやめた事実はなかった。
規制値超すセシウムを無届けで譲渡容疑 韓国籍の女 10/12/12(朝日新聞)
放射性物質の濃度の規制値を超える放射性セシウムを無届けで売ったとして、警視庁はいずれも韓国籍の黄娟熙(27)、景善美(28)の両容疑者を放射線障害防止法違反(譲り渡し)の疑いで逮捕し、12日発表した。福島第一原発の事故後、譲り渡しについて同法違反での摘発は全国初という。
生活環境課によると、2人は東京都荒川区の放射線測定器専門店「オアシストレード」の従業員。2011年10月から12年4月、規制値の約3.7倍の放射性セシウム137の金属片18個を17人に計約61万円で売った疑いがある。ともに容疑を認め、「セシウムは外国から社長が持ってきた」と供述しているという。セシウムは、放射線測定器が正常に作動するかを検査するためのものという。
同課は11日、客のうち違法性を認識していたと判断した5人を書類送検した。
人為的ミスの可能性も…姫路の爆発事故 10/07/12(朝日新聞)
兵庫県姫路市の日本触媒姫路製造所でアクリル酸の貯蔵タンクが爆発し、37人が死傷した9月29日の事故から6日で1週間となったが、県警は、業務上過失致死傷容疑では2005年のJR福知山線脱線事故以来となる捜査本部を設置し、事故原因の特定を進める。
県警が重視するのはアクリル酸が発熱した経緯。機器の整備不良や作業手順の誤りなど何らかの人為的ミスがあった可能性もあるとみている。
また、消防通報までに50分間かかった経緯にも注目する。石油コンビナート等災害防止法は、「異常現象」を確認し次第、直ちに通報すると定めるが、日本触媒は「従業員は自力で対応できると思ったようだ」としており、見通しの甘さが被害を拡大させた疑いもある。捜査幹部は「捜査は長期化する」との見方を示している。
姫路の工場爆発 以前も通報遅れで指導 10/05/12(NHK ニュース)
先月、爆発事故が起きた兵庫県姫路市の化学工場は、過去に起きた5回の爆発事故や火災のうち、少なくとも3回で通報が遅かったなどとして、消防から指導を受けていたことが分かりました。
兵庫県姫路市にある化学メーカー「日本触媒」の工場で、アクリル酸などを貯蔵するタンクが爆発した事故では、消防隊員1人が死亡するなど37人の死傷者が出ました。
この事故では、工場側がタンクから煙が上がるなどの異常を確認したあと、消防に通報するまでに45分かかったことが分かっています。
消防によりますと、この工場は平成17年までのおよそ30年間に、5回、爆発事故や火災が起きていますが、このうち少なくとも3回で通報が遅かったり通報自体がなかったりしたなどとして、通報時間の短縮を求めるなどの指導を消防から受けていたことが分かりました。
このうち平成17年に起きた火災では、消防への通報までにおよそ1時間かかっていたということです。
今回の事故で、日本触媒の幹部は「結果的に通報が遅かったかも知れない」と話していて、消防は、速やかな通報を定めた石油コンビナート災害防止法に違反する疑いもあるとして調査することにしています。
化学工場爆発 “自社消防隊を優先” 10/03/12(TBS系(JNN))
兵庫県姫路市の化学工場で起きた爆発事故で、工場のマニュアルに「初期対応では自社による消火活動を優先する」という規程があることがわかりました。警察は、消防への通報の遅れにつながった可能性があるとみて調べています。
先月29日、日本触媒姫路製造所でアクリル酸のタンクが爆発。消防隊員1人が死亡し、36人が重軽傷を負いました。
午後1時ごろ、従業員が南側のタンクから白い煙が上がっているのに気がつきましたが、自社の消防隊による消火を優先させた結果、消防へ通報するまでにおよそ50分かかりました。
Q.なるべく自分たちで消火?
「そうですね、初期対応は。自分たちでできる限りのこと、装置の停止などは自分たちで対応」(工場関係者)
午後2時すぎに消防が到着しましたが、およそ20分後、タンクから黄色い物質がこぼれ出し、次々と爆発、炎上しました。工場では、初期対応で自社の消火活動を優先する規程があり、警察は、これが通報の遅れにつながった可能性があるとみて調べています。
一方、2日夜、犠牲になった消防隊員、山本永浩さん(28)の通夜が営まれました。
「仲間思いで、最後の最後まで、あいつだけ諦めないくらい、熱い気持ち持っている」(同期の隊員)
告別式は3日午後、営まれます。
姫路工場爆発、40分通報せず…初動遅れ「自分たちで冷却できると思った」 10/01/12(スポーツ報知 )
兵庫県姫路市の日本触媒姫路製造所で、消防隊員1人が死亡し、多数の負傷者が出た29日の工場爆発で、同社の幹部は30日、初動対応に遅れがあったことを認め、謝罪した。白煙発見から消防などへの通報が40分以上遅れたことについて「自分たちで冷却できると思っていた」と説明。見通しの甘さが浮き彫りになった。また、製造所の停止により、紙おむつ原料の供給に支障が出る可能性もあり、利用者への影響も懸念される。
「ここまでになるとは思えなかった」―。大阪市の日本触媒本社で行われた会見。爆発した姫路製造所で、今春まで所長だった尾方洋介専務執行役員(63)が出席。苦渋の表情で振り返った。
尾方氏は、会見の冒頭で頭を下げ陳謝。その後の質問は通報までの経緯に集中した。説明によると、アクリル酸を貯蔵する製造タンクの近くにいた従業員が、上部に白煙を確認したのは29日午後1時ごろ。だが、防災管理課が網干消防署へ通報したのは同1時40~45分ごろと、40分以上遅れた。その間、自主的に放水をしていたという。
石油コンビナート等災害防止法に基づく規定は、温度が異常で制御不能な場合には、通報を義務付けている。尾方氏は「自分たちで冷却できると思っていた。結果的にはすぐ通報すべきだった」と初動対応のミスを認めた。ただ「規則からの逸脱があったかどうか、判断は難しい」など、細かい点は歯切れの悪い答えに終始した。
火災は30日午後3時半ごろ鎮火。爆発で網干消防署の山本永浩消防副士長(28)が焼死。この日、新たに消防隊員5人が軽いけがをしていたことも判明し、消防隊員の負傷者は23人、全体の負傷者は35人となった。1人が重体。兵庫県警は同日、業務上過失致死傷容疑で、製造所を家宅捜索した。また、姫路市は消防法に基づき、29日付で製造所全体に異例の緊急使用停止命令を出した。
一方、製造所の生産停止で、紙おむつ業界への影響が懸念されている。尾方氏は生産再開について「まず社会に安全対策を示す。いつとは言えない」と生産停止が長期化する恐れを示唆した。同社によると、紙おむつの原料となる高吸水性樹脂は、同社の生産能力が年間47万トンで世界トップ。うち、爆発のあった姫路製造所が32万トンを占める。「姫路製」は、世界で2割程度という大きなシェアを持っている。
国内で高吸水性樹脂を生産するのは姫路だけだが、事故で全プラントが停止。海外工場は「9割以上」の稼働率のため、急激な増産は難しいという。尾方氏によると、樹脂の在庫は1か月分弱。原因究明や安全対策が進まず生産停止が長期化すれば、原料供給もストップし紙おむつメーカーに影響が出る可能性があり、消費者へ波及する恐れも出てきている。
日本触媒姫路製造所に責任があることは明らかだが、消防局もプロなのだから状況の把握及び対応している化学物質のタンクについて
工場に問い合わせることは考えなかったのか?今までこのように惨事を体験しなかったから、状況対応に問題があったが誰も指摘しないし、
誰も改善しようとしなかったのだろう。
状況は全く違うが、福山ホテル火災を防げなかった福山地区消防組合と同じだ。
問題として形として現れるまで問題を放置し対応しない。
素人でも理系のバックグラウンドがあれば化学工場での火事はタンクの中の化学物質の性質を理解することが重要なことくらい考えることができるぞ。
消防局の誰ひとりもそのような事を考えなかったのか?工場側の人間もどのように対処するべきなのか、マニュアルとかを読んだことがないのか?
危機管理のマニュアルとか、火災の時のマニュアルとかは作成されていなかったのか?メディアや新聞社は調べて記事にして欲しい。
タンク内の温度、把握せず冷却活動か 日本触媒爆発事故 10/01/12(朝日新聞)
兵庫県姫路市の日本触媒姫路製造所の爆発事故で、タンクの異常発生後、内部の温度上昇が把握されないまま冷却活動が続いていたことがわかった。消防隊員らは差し迫った危険性を知らずに爆発に巻き込まれた可能性がある。池田全徳(まさのり)社長は1日に記者会見し、「ご迷惑をおかけし、おわび申し上げる」と述べた。
同社によると、タンク内の温度は通常約60度に保たれている。温度計はタンク横に設置され、巡回して目視で確認することになっていたという。事故のあった9月29日も従業員が偶然、タンク上部のベント弁(逃し弁)から白煙が上がっているのを見つけて異常に気付いた、と説明している。
午後1時の白煙確認後、作業員や自衛防災隊がタンクに放水して冷却作業をはじめ、姫路市消防局も放水準備をした。しかし、内部のアクリル酸の温度については、タンクに近づけず、「白いものが出ているということは、かなり上がっていると推察した」(尾方洋介専務)と述べ、把握していなかったことを認めた。
姫路工場爆発:日本触媒、消防通報遅れ認め謝罪 (P-1)
(P-2) 09/30/12(毎日新聞)
兵庫県姫路市の大手化学メーカー「日本触媒」姫路製造所で起きたタンク爆発炎上事故。同社は一夜明けた30日、大阪市中央区の大阪本社で記者会見し、「結果的に事の重大性を読み切れなかった。(異常に気づいた時点で消防に)通報すべきだった」と述べ、事故発生時の初動対応の甘さを認めて謝罪を繰り返した。
【写真で見る】姫路で工場爆発 炎上する消防車など
会見には同社の尾方洋介・代表取締役専務執行役員ら役員3人が出席。尾方専務によると、9月29日午後1時ごろ、爆発が起きたタンク上部の排気ダクトから白煙が出ているのを製造課員が確認。上司に報告し、同20分ごろから消火用ホースでタンクの冷却作業を始めた。同40分ごろ、製造所の自衛消防隊を出動させ、姫路市消防局にも出動を要請。タンクの異常に気づいてから消防に通報するまで、約40分が経過していた。
重大事故時の対応などを定めた同社の「防災規程」では、製造設備の暴走反応など「異常現象」が起きた場合、詳細な手順を定めた自衛防災マニュアルに沿って消防などに通報することになっている。
尾方専務は白煙発見時、タンク内の温度がアクリル酸の沸点の141度近くまで上昇していた可能性を指摘。「製造課員だけで冷却できると判断したのかもしれないが、(発見当初から異常現象と判断し、消防に)通報すべきだった」と述べた。同社は今後、社内に第三者を加えた事故調査委員会を設け、原因究明などに取り組むとした。
◇防災マニュアル内容明かさず
会見では、事故原因や事故時のタンクの安全管理体制などに質問が集中。だが同社は「現地から話が聞けておらず、詳細が分からない」と曖昧な説明に終始した。自衛防災マニュアルの詳しい内容についても「警察の捜査に支障が出る」として明らかにしなかった。
一方、姫路市は29日付で、消防法に基づき製造所に緊急使用停止命令を出し、姫路製造所の工場はストップした。また同市消防局は30日、石油コンビナート等災害防止法の即時通報義務に違反する疑いがあるとして、調査することを明らかにした。
兵庫労働局も同社に職員4人を派遣し、労働安全衛生法に基づく立ち入り調査を始めた。
【遠藤浩二、村松洋、高橋一隆、錦織祐一】
日本触媒 – 爆発 –アクリル酸(1) 09/29/12(生涯現役エンジニア ブログ)
現在(2012年9月29日、21:15)、㈱日本触媒化学姫路工場で火災が続いています。
―― またか。
と、いう思いです。
最初に60kℓの中間タンクの温度が上昇し、避難指示がでたとのことです。これが真実だとすると、「何をやっているのか」と、言いたいです。
アクリル酸は二重結合をもっています。ラジカル重合反応をし易い化学物質です。重合の際に多量の熱を出します。危険です。ですから重合抑制剤を添加しています。
たまたま『重合抑制剤』の添加量が、手違いによって規定よりも少なくなり、その時、たまたま冷却すべきところを、間違って温度を上げる操作をしてしまった。すると『重合抑制剤』の有効温度を超えてしまった。後は「あれよ、あれよ」と見守るだけ。危険を感じて避難指示がでた。
私は、このように見ています。その際に、もっと高温で有効な『重合禁止剤』が準備されており、注入準備がされていたら、その『重合禁止剤』を投入すれば何事もなく済んだでしょう。しかし投入するタイミングが重要であり、遅れるとダメ。しかし投入決断は困難です。なぜなら、投入すると60kℓの中間タンクだけでなく、その下流の製品がすべて不良品になるるので、決断が困難です。躊躇している間に温度がどんどん上昇して前述のように「あれよ、あれよ」という状態になってしまいます。
今、根本原因を推測しました。このような報道は一切ありませんが、この推測が外れていることを祈ります。
日本触媒 – 爆発 –アクリル酸(3) 09/29/12(生涯現役エンジニア ブログ)
兵庫県警は、日本触媒姫路製造所を『業務上過失死傷の容疑で家宅捜索したと報じられました。また、姫路市は消防法によって製造所全体に対して『緊急使用停止命令』を出したとも報じられました。
家宅捜査においては、①安全管理体制に問題がなかったか、②詳しい爆発の原因を調べるとのことです。以上は、10/1付産経新聞でした。
―― 私は、事故当日の報道映像を録画しております。それを改めて再生して視聴しました。すると以下のことが分かりました。
<時系列的状況変化>
1) 60kℓアクリル酸タンクは、通常60℃以下で温度管理している。
2) しかし温度上昇があった。
3) 最初は自分達で冷却努力をした。
4) が、手に負えないので消防へ連絡した。
5) 消防隊が到着した際、このタンクから『白煙』が上っていた。
6) 消防隊は白煙を目標にして放水を始めた。
7) その際爆発が発生した。
<当時の現場状況>
8) 爆発の30分程前に構内一斉『緊急避難』放送があった。
9) 作業員500名が敷地から離脱した。
10) 敷地内にクレーンなどの重機が駐機している。
11) 機械のメンテナンスにあたっていた男性がいた。
12) 消防車のタイヤが燃えている。
13) 遠く離れた場所でも轟音と爆風を感じた。
<以上の状況から判明すること>
14) 当日は、大掛かりな修理作業(定期修理等)の最中だった。
15) 修理中ではあったが、60kℓアクリル酸タンクは充満していた。
16) 減圧蒸留に空気の漏れこみが通常より多く、重合量がいつもより多かった。
17) 冷却追いつかなくて管理温度60℃を超えて上昇した。
18) 添加している重合禁止剤(ハイドロキノン系)の有効温度上限(おそらく80~100℃)を超えた。また、重合によって消費しつくされた。
19) もっと高温で機能する重合禁止剤(硫黄など)は、準備していかなった。
20) 温度がアクリル酸の沸点141℃を超えた。
21) アクリル酸が沸騰し始め、タンクの安全弁が吹いて外気へ勢いよく放出された。
22) 消防隊が到着した際は、このアクリル酸の蒸気が、『煙』のように見えた。
23) だから消防隊は、その『煙』に向かって放水を始めた。
24) その際、爆発が発生した。
25) これは、アクリル酸蒸気(気体)がタンク上空に直径数十メートルの『爆鳴気』の雲のような塊を形成し、これに内部で発生する静電気の放電スパークによって着火し、大爆発したもの。
26) ちなみに、この大爆発のことを『ファイアーボール』という。
―― 消防署への連絡が遅れたから災害が大きくなったというものではありません。アクリル酸タンク温度が管理限界を超えた時点では、どんなに消防隊が努力しても、その温度上昇を止めることはできません。
福島原発に対してヘリコプターや、消防車で放水していた姿を思いだしてください。アクリル酸の重合反応をストップさせる新たな量と質の重合禁止剤が必要なのです。
以上、日本触媒姫路事業所における爆発火災事故に至るまでの概略『シナリオ』を推定して記述しました。化学工場の爆発火災防止を専門とする弊社ならではの推察です。このシナリオが間違っていることを祈ります。
下記の記事が事実であれば危機管理及び管理が適切に行われていなかったと言うことだ。
温度管理が重要で、高温になった場合には近づけないのであれば遠隔カメラで温度を確認できる方法または温度計をデジタルに交換して
管制室でも確認できる方法等の対応策が社内で認識され実行されているまたは対応を実施する計画がなければならないはずだ。
事故からしか学ぶ方法しかないのか?危機管理や管理を理解していない人間達が権限を与えられていたのか、問題を認識してたが
コストのために対応してこなかったのかのどちらかしかないだろう!まあ、適切な管理や対応が欠如していても、運良く事故が起きなければ
結果として問題は問題として認識されないし、誰も責任を問われない。運悪く最悪の結果となったと言えばそれまで。行政が不備を指摘できる
経験と能力を持っていれば事故は防げたかもしれないが、現実的に考えて裸の王様であるケースが多いので期待は出来ない。
タンク温度は未把握 製造所も計器に近づけず? 10/01/12(産経新聞)
兵庫県姫路市の化学工場「日本触媒姫路製造所」で36人が死傷したタンク爆発事故で、爆発したアクリル酸貯蔵タンクの温度を確認するには、貯蔵タンク備え付けの温度計を現場で目視するしか方法がなかったことが1日、同社への取材で分かった。製造所がタンク内の温度上昇を確認したというタンクから白煙が上がったころには、すでにタンクに近づけない状態に陥っていたとみられ、温度計も確認できていないという。
アクリル酸は安定的な物質ではなく、物質同士が重合反応し、高温を発する。高温になりすぎると爆発の危険性があるため、専門家も温度の監視の重要性を指摘している。
事故当日、製造所側は「タンクから離れた管制室で温度を監視していた」と説明していたが、同社が大阪本社(大阪市)で30日に開いた会見によると、タンクの温度を確認する方法について、「タンクに備え付けの温度計を担当者が定期的に回って目視するしかなかった」と一転した。
タンクの通気口から白煙が上がっているのが確認された29日午後1時ごろも、「白煙を見て温度上昇と判断した」だけで、温度計には近づいていないという。
製造所は29日午後1時45分ごろ、消防に対し「異常反応の可能性がある。煙が出ている」と通報したが、タンクの温度は伝えていなかった。
「『爆発の恐れがある』との報告」があったのならアクリル酸貯蔵タンクが爆発するとどのようになるのかわからなかったのか?
工場側も消防署側も専門家なのだから、アクリル酸のデーターシートぐらい目を通して対応したのだろ!なぜこのような惨事になるのか?
まあ、人事なので真剣度が違うが、今後のためには真剣に原因調査はしたほうが良いと思う!
突然の火柱「ナパーム弾のよう」…姫路爆発事故 09/30/12(読売新聞)
突然、大きな爆音と振動が起き、消防車が一瞬にして火炎に包まれた。
兵庫県姫路市網干(あぼし)区の日本触媒姫路製造所で29日に起きた化学薬品タンクの爆発事故。死者1人、重体1人、重軽傷者29人を出した惨事は、消火、警備活動中の消防隊員や警察官らが爆発に巻き込まれる事態となった。現場は怒声や悲鳴が飛び交った。
「アクリル酸のタンクの温度が上がってきている。化学反応が起きるかもしれない」。姫路市消防局の指令センターに、日本触媒姫路製造所からホットラインで緊急事態が告げられたのは午後1時51分だった。
この時、現場のアクリル酸貯蔵タンクからは白煙が上がり、所内の自衛消防隊員十数人が放水を続けていた。市消防局の消防タンク車も約10分後に到着。「爆発の恐れがある」との報告などから、消防局はさらに9台の出動を指令した。県警網干署も、同社からの通報を受けて署員を派遣した。
爆発が起きたのは、タンク冷却のために自衛消防隊が放水していた同2時35分。南北に3基並んだタンクのうち、一番南側のアクリル酸のタンク(容量70トン)が爆発し、北隣のアクリル酸のタンク(同100トン)、トルエンのタンク(同50トン)に延焼したとみられる。
近くにいた男性従業員によると、火のついた液状のアクリル酸が周囲に飛び散り、消防隊員の消防服が燃え、近くの路面も炎に包まれた。消防車にも延焼。付近の従業員や消防隊員、警察官らは一斉に逃げ、現場は大混乱に陥った。
男性従業員は「テレビで見た(焼夷(しょうい)弾の)ナパーム弾の被害を受けたようで、ぞっとした」と振り返った。
「アメリカでは、20年ほど前に、この化学物質の発がん性が懸念」されていた問題を多くの被害者と死亡者が出るまで対応してこなかった厚生労働省
完全な因果関係が判明していないと言うことだが、もし放射能でも科学者達がおなじような事と言っているのであれば恐ろしい。多くの被害者が
出るまで問題は放置され、完全な因果関係が判明されるまで補償や対応は期待できないと言うことである。科学者が正しいのか、正しくないのか、
どちらであっても福島の近くに住んでいないので影響を受ける可能性は低いが、厚生労働省
の対応の悪さには困し、腹が立つ。
胆管がんに関する一斉点検結果の取りまとめ等について (厚生労働省)
大阪の印刷事業場での胆管がんの発生を受けて、全国561の事業場を対象として実施していた一斉点検の結果等を以下の通り取りまとめましたので、お知らせします。
1.一斉点検結果の取りまとめについて
厚生労働省では、印刷事業場での胆管がんの発生を受けて、緊急に全国561の印刷事業場を対象とした一斉点検を実施し、今日、その結果を取りまとめた。
(1)胆管がんの発症
胆管がんを発症した者がいるとするのは3事業場、3人(東京、石川、静岡)であり、大阪、宮城の事業場以外に、複数の胆管がん患者が確認された事業場は無かった。
(2)有機溶剤中毒予防規則の適用状況等
561事業場のうち、有機溶剤中毒予防規則(急性の有機溶剤中毒を予防する観点からの規制)の規制対象物質を使用していた事業場は494ヶ所、こうした事業場のうち何らかの問題が認められた事業場は383ヶ所(77.5%)であった。
(3)作業場所の状況
外気と接していない地下室で作業を行っている事業場は無かった。また、地下室と同視できるような空間で作業を行っている事業場は9ヶ所であった。
(4)使用化学物質
ジクロロメタンを使用している事業場は152ヶ所、1,2-ジクロロプロパンを使用している事業場は10ヶ所であった。
2.今後の対応策について
一斉点検の結果を受け、厚生労働省として以下の4点からなる対応策に取り組むことにした。
(1)現行法令等の遵守の徹底
何らかの問題が認められた事業場の割合が非常に高かったことを受け、全印刷事業場に対し、自主点検を実施させるとともに、未提出事業場を中心に、説明会の実施や監督指導等で、現行法令等の遵守を徹底する。
(2)有機塩素系洗浄剤のばく露低減化の予防的取組
複数の労災請求のあった大阪と宮城の事業場では、労働者が高濃度の有機塩素系洗浄剤にばく露していた可能性が高いことから、脂肪族塩素化合物を用いて通風が不十分な場所で洗浄作業を行う場合には、法令等の規制の対象となっていない場合でも、法令の規制と同様の措置をとるよう指導する。
(3)職業性胆管がん相談窓口の設置
職業性胆管がんに関する各種相談に厚生労働省として対応するため、専用のフリーダイヤルを設ける。時間は月曜から金曜の9:30~12:00と13:00~16:00。
東日本については、7月13日からで、番号は「0120-860-915」、西日本については、7月12日からで、番号は「0120-616-700」。ただし、7月12日については、東日本の相談であっても西日本の番号で受け付ける。
また、産業保健の専門家からの相談体制も整備するため、7月12日から専用のフリーダイヤルを設ける。時間は火、水、木曜の13:00~17:00、番号は「0120-688-224」。
(4)胆管がんの発症に関する疫学的調査の実施
原因の究明のため、産業医学の専門家によるチームを編成し、当該事業場の詳細な調査や胆管がんについての疫学的な調査等を実施する。
なお、既存化学物質対策として、既存化学物質6万種類を対象に、労働者へのばく露の実態等を踏まえて対象物質を的確に絞り込んだ上で、がん原性やリスクの評価を行い、これらの結果に応じて化学物質の規制を強化する取組(既存化学物質評価10カ年計画)を実施する。
「胆管がん」は防げなかったのか? 09/25/12(クローズアップ現代 NHK ONLINE)
あす(26日)のクロ現は「知らされなかった危険 ~胆管がん 相次ぐ死亡報告~」です。
さっそく、プレビューを見てきました。
大阪の印刷会社で複数の従業員が化学物質の影響で胆管がんにかかり、
死亡していた問題が発覚して4カ月。
17年間で14人の発症と、7人の死亡が確認されていいます。
問題となった会社が使っていた洗浄剤に含まれていたのが
「1,2ジクロロプロパン」という化学物質です。
この物質を吸い込むと、肺から血管を通って、肝臓へ集まります。
胆管は、肝臓の中に入り込んでいる管で、その胆管に出来るのが胆管がんです。
胆管がんは50歳未満の人に出来ることは極めて稀とのこと。
しかし、問題の会社では、20代~40代の14人が胆管がんを発症し、
7人が亡くなっています。
VTRの中で、この会社に働いていて6年前に退職した30代の男性が出てきますが、
肝臓の機能が悪化して通院を続けているのだといいます。
これは胆管がんで亡くなった同僚たちと同じ症状なのだといいます。
この映像には衝撃を受けました。
人々が安全な環境で働くという基本的なことが、出来ていないのでしょうか?
これはひとつの会社の問題だけでなく、国の問題でもあります。
なぜ危険な化学物質を、危険だと認定しなかったのでしょうか。
アメリカでは25年前に「1,2ジクロロプロパン」の発がん性について指摘され、
不完全な動物実験のデータでありながらも、発がん性について
製品安全データシートにも記載されるようになったといいます。
日本では、「1,2ジクロロプロパン」が規制されたのは去年になってからだと言います。
ぜひ、ご覧ください。
厚労省が見殺しにした印刷工たち!有毒洗浄剤規制せず次々胆管がん死 09/28/12(GREE ニュース)
大阪のある印刷会社では、勤めていた20~30代の若い従業員ばかり7人が治療の難しい胆管がんで亡くなっていた。いずれもインクを洗浄するための「1,2-ジクロロプロパン」という化学物質を大量に使う校正印刷の作業に従事していた。その後の調べで、亡くなった7人を含め14人の胆管がん発症が確認された。
アメリカでは25年も前に「発がん性の疑いあり」として1,2-ジクロロプロパンは規制されたが、日本ではその情報を得ながら使われ続け、厚生労働省の調査によると、全国の印刷会社で分かっただけでも34人が胆管がんを発症していた。「クローズアップ現代」がその真相に迫ったが、見えてきたのは海外からの有益な情報を拒む厚労省の独善的な判断だった。
アメリカが規制に踏み切ってからも20年放置
大阪の印刷会社はこの化学物質を、印刷機についたインクの洗浄剤として、少なくとも1996年から2006年まで大量に使ってきたことが分かっている。「インクの油がよく落ち、すぐ乾くので使い勝手がよかった」らしい。しかし、1,2-ジクロロプロパンを吸い込むと、肺から血管を通じて肝臓に集まり、肝臓の中に入り込んでいる胆管を刺激してがんを発症させる。
1
8歳からこの印刷会社に勤め始めた本田真吾さん(30)は、入社3年目あたりから職場の周りの人たちに異変が起き始めたのに気づいた。よく食事に誘ってくれ、兄のように慕っていた4歳年上の先輩が胆管がんを発症して2年後になくなった。27歳だった。別の先輩従業員も胆管がんで36歳で亡くなった。その直後の2006年、本田さんも体がだるいなど体調を崩し、病院で調べてもらったところ肝臓機能が悪化していることが分かり会社を辞めた。
「自分にいつがんが発症するか不安な思いもあるし、少しでも早く治したい」と語る本田さんに、最近、医師から辛い事実が告げられた。検査で胆管がんの疑いがある腫瘍が見つかったというのだ。
「まだやり残したことがあるし、生きたいと思う。怖いですね」
30歳の若手からこんな言葉を聞くのは辛い。なぜ長年にわたって異変が発生していたのに、会社は1,2-ジクロロプロパンに気付かなかったのか。実は、アメリカは25年も前にこの化学物質の使用に危険信号を発していた。1970年代にはアメリカでも農薬として広く使われていたが、85年ころからある農村で子どものがん発症が急増、1,2-ジクロロプロパンが原因ではと報道されたのを機に政府が動いた。
翌86年に政府が行っていた動物実験の報告書が公表され、ラット(ドブネズミ)でははっきりした結果は出なかったが、マウス(ハツカネズミ)では発がん性を確認した。これを受けて、米環境保護庁(EPA)はこの化学物質を危険度3番目の「B2」に分類して規制の対象にした。アメリカのシステムについて、化学物質政策シンクタンク代表のギルバート・ロス博士は次のように話す。
「限定的であれ、動物に発がん性が確認されれば、『発がん性が疑われる』として公表するのがアメリカです。政府が公表する有害情報を会社が周知しなければ、巨額の罰金を支払うことになり、実質的な規制になるのです」
厚労省担当課長「EPA(米環境保護庁)がやっても、われわれは独自判断」
日本も製品安全データシートに載せるべきではなかったのか。ところが、厚労省はこの情報を無視した。厚労省労働安全衛生部の半田有通課長は「アメリカの実験結果は完全なものとは言い難かった。EPAがやったから『ハイ、やります』という話ではない。われわれの中で判断します」と開き直る。
アメリカから得た情報をもとに早く動物実験をやっていれば、あるいは胆管がんの発症は防げたかもしれない。厚労省が問題の化学物質の動物実験を実施したのは、アメリカが規制してから十数年後の2000年だ。ラット、マウスで発がん性を確認し、ようやく規制に踏み切ったのは06年だ。アメリカより20年以上も遅れた。
国谷裕子キャスター「遅いですね。有害情報を知ったらどうすればいいのでしょう」
化学物質のリスク評価に詳しい北海道大学の岸玲子教授がこう答えた。「有害物質の情報を得たら情報公開、伝達を早くするというのが原則でしょう。発がん性物質の動物実験は5年かかり、実験施設は1か所しかない。体制を整備するのが望ましいのですが…」
ごく当たり前の安心・安全の原則に思えるのだが、役所のメンツなのか怠慢なのか、それがこの国ではすんなり運ばない。これが日本の厚労省流だ。
モンブラン
*NHKクローズアップ現代(2012年9月26日放送「知らされなかった危険~胆管がん相次ぐ死亡報告~」
クローズアップ現代:大阪市内印刷会社の胆管がん事案 09/26/12(New Horizon)
大阪市内の印刷会社の工場で1年以上勤務していた元従業員約40人のうち、少なくとも男性5人が胆管がんを発症し、4人が死亡した件で、クローズアップ現代で取り上げていた。
胆管がんの原因は、付着したインクを落とすために使用されていた化学物質、「1、2ジクロロプロパン」や「ジクロロメタン」とされている。
アメリカでは、20年ほど前に、この化学物質の発がん性が懸念されるということで、労働衛生の観点から規制が始まり、それに産業界も追随したということである。違法行為は罰金などを課せられるためであり、政府の行動が未然に労災事故・死亡を回避したという紹介であった。
これに対して、日本では、このような規制が入ったのは昨年だということである。また、日本のMSDS(物質等の安全データシート)には”知見なし”というように記述されていたので、日本の事業者も軽く見て、自分たちに都合の良いように解釈して、何らの対策も取らなかったとしている。現在のMSDS(添付URL)には、発がん性の疑いがあると明記されている。
アメリカに遅れること20年、この著しい遅れ、無作為はどこから来ているのだろうか?
番組には、厚生労働省のお役人のインタビューも流された。「アメリカはアメリカだし、日本は、アメリカのデータ・規制などをそのまま取り入れることはしない」という様な話をしていた。何とも傲慢でよく分かっていない人のような印象を持った。
化学物質の世界では、GHS(Global Harmonization System)など、安全性や健康の面で、世界を一つにしようという動きが出ている。その中に在って、アメリカのデータや情報など、利用できるものは利用すべきである。何も対策も取らず、20年以上も放りぱなしでは、何のための厚生労働省であろうか?日本のことだから、こういう分野には専門家の数も少なく、新しいことをやろうと思っても構造上、リソースの面でもできないのだろう。それなら、こういう分野での先進国である欧米のデータや情報を活用すべきだ。予防原理という観点からも、絶対にそうすべきだ。どうも、日本のお役人はおかしい。他人の命は軽いのだろう?
【参考】
1,2 ジクロロプロパン:http://www.st.rim.or.jp/~shw/MSDS/04105252.pdf
ジクロロメタン:http://www.jahcs.org/ghs/methiren.pdf
化学物質というものは本来有害なものです。従って、どのような化学物質(気体、液体、固体に関係なく)であっても、使用する前に必ず性状の確認をし、安全確保のための対策、漏れた場合等に対する緊急時対策、廃棄時の適正処置などを講じる必要があります。経営者側の責務・義務となっています。作業に入る前に、リスクアセスメント(リスク評価)は必ず行わなければなりません。
今回の場合は、十分な換気がなされていなかった、保護具(防護マスクなど)を着用させていなかったということです。当然、そういう職場で働いていた人たちは、化学物質の蒸気に暴露され吸い込んだりするわけです。それが継続すれば、健康上の大きな障害を与えるのは自明なことかと思われます。換気装置があっても、排ガスの除害装置(吸着や燃焼して無害化する装置)がない場合は、蒸気が屋外に流れていくわけですから、周辺にも影響を与えている可能性もありますが、通常、大気で希釈されるので、障害が出ることはないのかも知れません。そこは、調査が必要だと感じますが...
企業のリスクマネジメントが問われています。
胆管がんと化学物質の危険有害性の表示等 07/11/12(人事労務をめぐる日々雑感)
厚労省が印刷会社における胆管がんに関する一斉点検結果を発表しています(こちら)。
現時点で肝胆がんの起因物の可能性があるとされているのが、ジクロロメタンと1,2-ジクロロプロパンです。ジクロロメタンはすでに有機溶剤予防規則において、事業主に対し厳しい法規制が定められていますが、朝日新聞記事(こちら)を見る限り、中には法軽視もはなはだしい事業場があるようです。
印刷所8割、規則違反 局所排気、責任者知らず
8割近い印刷事業所でルール違反――。厚労省の調査で、働く人の健康を守るための「有機溶剤中毒予防規則」(有機則)に違反した事業所が広がっている実態が浮かび上がった。
「局所排気? 聞いたことがない。換気扇で足りると思う」。大阪府内の校正印刷会社に20年勤める現場責任者は話した。有機則は、有機溶剤を吸い込んで屋外へ排出する「局所排気装置」の設置を義務づけているが、この現場責任者は知らなかったという。
問題発覚まで同社は、胆管がん発症との因果関係が疑われている有機溶剤のジクロロメタン80%の洗浄剤を使用。局所排気などの設置が必要だが、「五つある換気扇で十分」と考えていたという。
同じように義務づけられた空気濃度の測定もしたことがなかった。有機溶剤を取り扱う労働者には半年ごとに特別な健康診断を行う必要があるが、一般的な健診を「各自で任意でやっている」という。
校正印刷に携わる別の府内の印刷会社も「今回の問題が発覚して初めて規則を知った」。労働基準監督署の調査を受けたこともなく、規則に関する講習を受けたこともないという。
日本印刷産業連合会(東京)は1980年代から90年代にかけて、手引書「印刷と有機溶剤」を作り、業界内で啓発してきた(略)。
しかし、業界に浸透しなかった。連合会の担当者は「業界の末端まで伝わらなかった面がある。印刷業界は零細企業が多く、健康が後回しになっていたのかもしれない」(以下略)。
この記事だけを見ると、中小零細印刷業者が「ジクロロメタン」等の危険性を認知していなかったとしても、労基署の指導や連合会の周知啓発活動が足りなかったためであり、致し方ないようにも読めますが、果たしてそうでしょうか。以下法規制内容が極めて重要です。
平成4年7月1日から施行されている「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」(安衛法57条の2)において、すでに「ジクロロメタン」を提供した業者等が、ユーザー企業に対して「化学物質等安全データシート」(MSDS)を交付することが義務付けられています。
ジクロロメタンに関するMSDS(こちら)をみると、p8以下に有機則を含めた法規制内容が記載されていますし、人体への影響も明記されています。またMSDSは事業場に掲示することも合わせて求められます。今回、問題となった印刷会社に対しても、購入時に当該文書が交付されている可能性が高く、MSDSが交付されている限り、当該事業主の「法の不知」「危険性の不知」は認められないものと考えます。
「
山口福祉文化大学(ウィキペディア) は『入試段階で学業に対する意欲や経済力を見極めるのは難しく、対策は現状では思い付かない。除籍処分をする段階で、すでに連絡がとれないケースが多く、事実上、指導は難しい』としている。」
他の大学が問題を抱えていないのならなぜ同じことができないのか?入学させたいがために簡単にビザを出すからこのような問題を起こすのだ!
問題を解決できないような大学は終わりにすべきだ!
留学生110人超除籍、不明70人は不法就労か 09/04/12(NHK)
山口福祉文化大(山口県萩市)が東京都墨田区のビルに開設したサテライト教室に在籍していた留学生のうち、2011年以降、授業料の未納や授業への欠席が続いたことを理由に110人以上を除籍処分にしていたことがわかった。
このうち70人以上の行方が確認できていないという。日本で不法就労している可能性もあるとして、法務省東京入国管理局は今年2月、同大に対して留学生を除籍する際は帰国を促すよう異例の指導を行った。
同教室では、5月1日の時点で本校171人の3・5倍にあたる606人が在籍し、うち605人が中国人などの留学生だった。
東京入管によると、同大は11年、授業料未納や3か月以上連続の欠席などを理由に、同教室の留学生約40人を除籍したと入管に報告。除籍処分は今年1~4月に約20人、5月以降も50人以上に上った。5月以降の除籍学生は約3分の1が1年生で、授業にはほとんど出席していなかった。
東京入管は、除籍学生が多いとして入管難民法に基づき、2月に同教室の立ち入り調査を実施した。
同大は08年に同教室を設置。留学生は入学金20万円のほか、日本人の半額の学費(年間授業料38万5000円)で学べるため人気があった。同大では、前身の萩国際大当時の02年と03年にも、中国人留学生ら計76人を除籍処分にしている。
同大は「入試段階で学業に対する意欲や経済力を見極めるのは難しく、対策は現状では思い付かない。除籍処分をする段階で、すでに連絡がとれないケースが多く、事実上、指導は難しい」としている。
この前、恥をかいたから違反を探したんだろうね!
国交省ツアーバス一斉点検、新基準で2台に違反 09/05/12(読売新聞)
国土交通省は5日、関越自動車道で7人が死亡したツアーバス事故を受け、夏休み期間中(7月20日~8月31日)に実施した全国一斉点検の結果を発表した。
運転手1人の夜間走行距離の引き下げなど同省が導入した新基準で、2台(2社)の違反が見つかった。
国交省によると、走行距離表示が395キロとなっていたが実際は400キロを超えていたり、500キロまで走行が認められる特例を申請しながらテレビ電話など必要な機材を積んでいなかったりした。
期間中に計25回実施、計332台を点検した。ほかには道路運送法違反などが71台あった。内訳は点呼の未実施が3台、運行指示書の不携行が8台、バス会社名などの表示を求めたガイドラインの不徹底などが60台に上った。同省は、違反したバス会社に対し、改善報告書の提出を求めている。
文部科学省は不法就労を目的とした留学生の受け皿となる以外で経営が成り立たない
山口福祉文化大学(ウィキペディア)
に税金をつぎ込むべきでない。留学生の失踪や不法就労が相次ぎ、広島入国管理局が中国人留学生127人に対し在留資格認定証明書を交付しないことを決定したことが
過去にもある。終わりにすべきだ!
サテライト教室不備で規制強化へ 09/04/12(NHK)
山口県にある私立大学「山口福祉文化大学」が東京に設置しているサテライト教室について、学生数に合った講義室や図書館が設けられていないなど、法令で定める要件を満たしていないことが分かり、文部科学省は大学に改善を指導するとともに、サテライト教室の規制を強化することになりました。
指導を受けたのは、山口県萩市に本校がある「山口福祉文化大学」です。
文部科学省によりますと、大学が東京・墨田区に設置しているサテライト教室には、萩市にある本校に通う学生171人の3倍を超える600人余りの留学生がいますが、学生数に見合った講義室や図書館、それに医務室といった法令で定める要件を満たしていないことが分かりました。
サテライト教室は、主に地方の大学が、社会人などが学びやすいよう利便性の高い都市部に設けていますが、この大学のサテライト教室の学生は、ほとんどが中国からの留学生だということです。
文部科学省は「サテライト教室が本来の目的に使われておらず、不法就労を目的とした留学生の受け皿になるおそれもある」として、来年にも大学の設置基準を改正し、規制を強化することになりました。
文部科学省は、近く中教審=中央教育審議会の分科会で議論を始めることにしています。
山口福祉文化大学とは
山口福祉文化大学は、地域活性化の切り札として、山口県と萩市から合わせて40億円の補助を受けて平成11年に開校しました。
開校当初から定員割れが続き、学生を確保するため、中国から大量の留学生を受け入れましたが、入学後に行方が分からなくなるケースが相次ぐなど経営状態が悪化し、平成17年に民事再生法の適用を申請しました。
その後、平成19年に名称を山口福祉文化大学に改め再建を目指しましたが、地元では学生が集まらないため、東京にサテライト教室を設けて留学生を受け入れていたということです。
それでも、ことし6月には資金繰りに行き詰まり、2度目の民事再生法の適用を申請し、現在、福島県郡山市の専門学校を運営する学校法人の支援を受けて再建に取り組んでいるということです。
東京サテライトに本校の3・5倍、606人在学 09/04/12(読売新聞)
山口福祉文化大(山口県萩市)が、文部科学省が定める校舎の要件を満たさない東京都内のビルに設置したサテライト教室に、606人の学生を通わせていることがわかった。
このうち605人は中国人など留学生で、文科省は改善を指導した。同省は都心部に開設されたサテライト教室が不法就労の受け皿になる恐れもあるとみて、他の大学が開く同教室の実態調査にも乗り出す方針を固めた。
同大は社会福祉系の4年制単科大。同大によると、5月現在、萩市の本校に171人、東京都墨田区と広島市内のサテライト教室にそれぞれ606人、43人が在籍している。墨田区のサテライト教室の学生数は本校の3・5倍に上り、606人のうち、中国人が536人と大半を占める。ほかはネパール人が27人、ベトナム人が11人など。
線量計紛失、新たに19件 未装着も5件発覚 東電 08/23/12(産経新聞)
東京電力は23日、福島第1原発事故の収束作業中に、社員や下請け企業の作業員による警報付き線量計(APD)の紛失が19件、未装着での作業が5件あったことが、新たに判明したと発表した。
一緒に作業した同僚の線量計などから、被ばく線量は最大で0.72ミリシーベルトと推定され、過大な被ばくはなかったとしている。東電は「管理が十分でなかったことを反省している。再発防止に努める」としている。
作業員が被ばく線量を抑えるために線量計を鉛板カバーで覆っていた問題などを受け、記録が残っている昨年6月以降の装着状況を調べた。東電はこれまで紛失1件、未装着3件を公表していた。
着替えの際に紛失した事例が多かったが、4号機原子炉建屋の解体中、線量を常に確認できるように線量計を防護服の外側にテープで止めていて紛失した作業員もいた。
水質汚濁:大同特殊鋼知多工場を捜索 高アルカリ水排出か 08/20/12(毎日新聞)
大同特殊鋼知多工場(愛知県東海市元浜町)が基準値を超す高アルカリ水を名古屋港に排出した疑いが強まったとして、名古屋海上保安部(名古屋市港区)は20日午前、水質汚濁防止法違反容疑で同工場に家宅捜索に入った。関係者から事情を聴くとともに排出記録などを押収し、裏付けを進めて原因を調べる。県も同日午後に工場を立ち入り調査する。
同海保によると、5月9日、巡視船艇が同工場の排水口から名古屋港に白濁水が排出されているのを発見。水素イオン濃度(pH)の測定で、水質汚濁防止法で定める基準値(pH5〜9)を超すpH9.9〜11.8の高アルカリ水と判明した。現時点では、海洋環境などへの影響は確認されていないという。
大同特殊鋼は「詳細が分からずコメントはできないが、捜査には協力する」と話している。知多工場は自動車部品の素材となる鋼材などを生産している。
名古屋港では10年、新日本製鉄名古屋製鉄所(東海市)が敷地から基準を超す高アルカリ水を漏出させたとして、同海保が同社と担当社員を同法違反容疑で書類送検している。【岡大介】
格安航空(LCC)の発想は悪くない。無駄を省いて価格を下げる。しかし、顧客は安全管理、メンテナンス及びメンテナンススタッフ及び
パイロット達の質まで評価して選ぶことは不可能だろう。事故を起こすか、価格を下げすぎての経営難のどちらかの問題を抱えている
可能性は高い。まあ、格安航空(LCC)以外の航空会社が事故を起こさないかといえば運次第。
伊格安航空が経営難で運航停止、予約30万件残し 08/13/12(AFP=時事)
【AFP=時事】経営難に陥っていたイタリアの格安航空会社ウィンドジェット(Windjet)が12日未明、多くの予約客を残したまま運航を停止し、ローマ(Rome)のフィウミチーノ空港(Fiumicino Airport)では行き場を失った予約客数百人が空港で夜を過ごした。
格安航空では過去にこんな事も 「ジェットスター航空、機内で乗客が突然死」(2011年9月)
同国メディアによれば、イタリア民間航空局(ENAC)は同日、ウィンドジェットの「明らかな能力の欠如」に対するしかるべき措置を取る方針を示した。運航資格の取り消し処分を科す構えとみられている。
ENACによれば、ウィンドジェットには今年10月までに約30万件の予約が入っている。11日夜にローマを出発予定だったイスラエル・テルアビブ(Tel Aviv)行きの便は直前で欠航となり、搭乗を予定していた200人ほどの旅行客は空港で夜を過ごし、12日午後になっても行き場のない状態となっていた。
ENACは11日に緊急対策センターを立ち上げ、ウィンドジェットの予約客が小額の追加料金を払えばアリタリア(Alitalia)航空、メリディアナ(Meridiana)、ブルーパノラマ(Blue Panorama)といった航空会社の便を利用できるよう手配している。アリタリアとメリディアナは、シチリア(Sicily)とローマ、トリノ(Turin)、ミラノ(Milan)、ベローナ(Verona)、ボローニャ(Bologna)などの主要都市を結ぶ臨時便を運行すると発表した。
経営再建中のウィンドジェットはアリタリア航空との買収交渉が決裂した10日以降、予約のキャンセルや発着の遅れが多発していた。
アリタリア航空は数か月前からウィンドジェットと買収交渉を行っていたが、同社が不利な条件を押し付けようとしているとウィンドジェットのステファノ・ラントゥチオ(Stefano Rantuccio)最高経営責任者(CEO)から非難されたことを受け、買収交渉から手を引いていた。
アリタリア航空は、ウィンドジェットを経営難から救うことを目的とした仮契約の内容を尊重する意思が全くなかったとしてウィンドジェット側を非難している。【翻訳編集】 AFPBB News
こうなるとたぶん被爆隠しは常態化していたと考えて間違いないだろう!基準を見直すか、取締りを厳しくして会社に
罰則を課すしかない。最悪の場合、営業停止も仕方がない。隠蔽が巧妙になる可能性もあるが、いままでもずさんだったのだから
結果を考えればさほど問題ではないと思う。
放射能の影響で死なないとか言った電力会社社員もいたが、社員達に対して健康保険による保護を徹底させるとかするべきだろう。
作業員達がリスクを負ってでも高給や高賃金を望むのであれば、綺麗事でなく受け入れる体制を政府は容認するべきだろう。
誰かが後始末をしなければならない。原発の廃棄作業が終了するまで誰かが作業に従事するのは避けられない事実。
数十年来の「常識」悔やむ 「仕方なかった」けれど 08/06/12(朝日新聞)
神奈川県に住む男性(64)は「被曝隠し」報道を読み、「こんなのは前からあります」と家族を通して取材班に連絡してきた。20代後半から約30年間、各地の原発で下請け作業員として働いてきた。被曝隠しは「常識」だったという。
初めて線量計を外したのは、原発で働き始めて5年ほどの頃。周りの作業員の…
被曝隠し「以前から」証言続々 車内に放置や預かり役も 08/06/12(朝日新聞)
東京電力福島第一原発で働く30代男性は今年5月、原発構内の免震重要棟の駐車場に止めたワゴン車の後部座席に約20組の「3点セット」を見つけた。その日の被曝(ひばく)線量を表示する線量計「APD」、長期間の累積線量を測るバッジ型線量計、そして作業員の身分証がひとくくりに束ねられていた。3時間後にのぞいてもそのままだった。被曝線量の限度を超えたら原発で働けなくなるため、線量計を残して現場へ向かったと確信した。その後も同じ光景を5回ほど見たという。
40代男性は3~4月、同じ駐車場で特定の車の中に10組以上置かれているのを10回ほど見た。別の車内で見かけたこともある。
東電は被曝隠しについて「把握したことはない」としてきたが、今月3日に下請け作業員がAPDをつけないで働いたと発表。過去に同様の事例があったと記者会見で認め、調査に乗り出す方針を明らかにした。
警報音鳴るので…被曝隠し偽装、会社側が認める 07/23/12(読売新聞)
東京電力福島第一原発事故の復旧現場で、建設会社「ビルドアップ」(福島県)が作業員の線量計を鉛カバーで覆わせていた問題で、同社は23日、福島県郡山市の事務所で記者会見し、指示したとされる佐柄(さがら)照男取締役(54)が、被曝(ひばく)線量を低く偽装する目的だったことを認めた。
佐柄取締役は「アラーム音が何度も鳴るので、カバーを思いついた。間違った考えだった」と謝罪した。
佐柄取締役と和田孝社長(57)が会見に臨んだ。その説明によると、佐柄取締役は昨年11月28日、作業の準備で同原発に入った。作業場所の一つである1号機の土手で線量計の警報音が短い間隔で鳴ったため、線量が高いと判断。偽装を思いつき、原発構内の廃棄物置き場で鉛板を拾い、同30日に作業員2人と構内で、板を切断して12個の鉛カバー(10センチ四方)を製作した。
30日夜にはいわき市の宿舎で作業員10人に対して、「線量計の前面に鉛のカバーを装着して入りたい」と切り出した。「被曝線量限度が残っていないと、その後作業できなくなる」と説明し、線量を低減させる目的であることも明かした。うち3人は、作業当日の12月1日朝になって装着を拒んだため、作業から外した。
低線量エリアに向かった作業員は鉛カバーは付けず、高線量の土手で作業する佐柄取締役を含めた5人が、線量計を鉛カバーで覆ってポケットに入れた。ただ、線量は低減しなかったといい、偽装はこの1回だけとした。鉛カバーは佐柄取締役が構内に捨てた。
佐柄取締役は終始うつむき加減で、「勝手な判断で皆様に迷惑をかけ誠に申し訳ない」とわびた。
コスト優先に警鐘 岡山・海底トンネル事故で中間報告 07/23/12(朝日新聞)
岡山県倉敷市のJX日鉱日石エネルギー水島製油所で起きた海底トンネル事故で、事故原因を調べている国土交通省の有識者会議は23日、事故防止のための26項目の注意事項をまとめた中間報告を公表した。
中間報告では、現場の設計や施工は現在の技術基準から逸脱していないとしつつも、コスト削減や工期短縮を優先すると、想定していない事故に対応できなくなる可能性があると指摘。トンネル内のコンクリート枠を細かく分割しすぎないことや、電気設備の防水性を高めたり、漏水や出水に対応できる止水対策を講じたりすることを求めた。
事故は2月に起き、掘削作業中にトンネル内に海水が流れ込んで作業員5人が死亡。同省は4月、事故の再発防止を目的に有識者会議を設置し、事故原因の調査などを進めている。
被ばく隠しカバー:原発敷地内の鉛、無断加工 福島 07/23/12(読売新聞)
東京電力福島第1原発事故の収束作業で福島県の建設会社「ビルドアップ」役員が被ばく隠しを指示した問題で、役員は、原発敷地内の倉庫にある放射線遮蔽(しゃへい)用の鉛板を無断で使い、警報付きポケット線量計(APD)を覆うカバーに加工していたことが、ビ社への取材で分かった。不要となった鉛カバーは敷地内に廃棄した。敷地への出入り時は持ち物と身体の検査が義務づけられているため、材料を現地で調達し、廃棄したとみられる。
役員から工作を指示された従業員が、ビ社などの聞き取り調査で証言したという。
ビ社などによると、役員は昨年12月上旬、作業前の準備で原発敷地に入った際、資機材倉庫で従業員数人と厚さ数ミリの板状の鉛を工具を使って加工した。失敗作も出たため、これらも含め敷地内で廃棄したという。
ビ社は、役員が昨年12月上旬〜20日の作業で初めて隠し工作を指示し、鉛カバーを1回だけ使ったとしている。役員は昨年3月と5〜7月にも収束作業に当たり、鉛の保管場所を熟知していた。【栗田慎一】
被曝隠し、9人・約3時間…下請け社長認める 07/22/12(読売新聞)
東京電力福島第一原発事故の復旧現場で、被曝(ひばく)線量を低く装うため、作業員の線量計が細工されていたとされる問題で、作業員を雇っていた下請けの建設会社「ビルドアップ」(福島県浪江町)の和田孝社長(57)が21日、読売新聞の取材に対し、担当役員が、鉛製のカバーで線量計を覆い、作業員9人を約3時間働かせていたと認めたことを明らかにした。
和田社長が21日、現場を指揮する役員と電話で連絡を取り、事情を聞いた。和田社長によると、役員は「事前に現場に行った時、APD(線量計)の警報音の速さに驚き、被曝低減の措置として鉛防御のイメージが頭に浮かんだ」と話し、鉛製のカバーを使用したことを認めた。作業員は「役員の指示を受け、4人ぐらいでカバーを作った」と社長に話しているという。
線量計に鉛カバー強要 被ばく線量偽装図る 厚労省、立ち入り検査 07/21/12(毎日新聞)
東京電力福島第1原発事故の収束作業をめぐり、作業を請け負った福島県内の建設会社の役員が昨年12月、作業員が個別に装着する警報付き線量計(APD)を鉛板のカバーで覆うよう強要していたことが21日、関係者への取材で分かった。これまでにカバーの使用を認めた作業員はいない。
累積被ばく線量が高くなった役員が、遮蔽効果が高いとされる鉛でAPDを覆い、被ばく線量を偽装しようとしたとみられる。厚生労働省は労働安全衛生法違反の疑いもあるとみて調査を開始、福島労働局などが同日、第1原発内の関係先を立ち入り検査した。
関係者によると、装着を強要していたのは、東電グループの東京エネシス(東京)の下請け企業「ビルドアップ」(福島県)の50代の役員。昨年12月1日、作業員宿舎で約10人の作業員に鉛板で作ったカバーを示し、翌日の作業で装着するAPDをカバーで覆うよう求めた。
役員だけが装着した場合、1人だけ極端に被ばく線量が低くなって偽装が発覚するのを恐れたとみられる。
ビルドアップが請け負っていたのは、汚染水を処理する設備の配管が凍結しないようホースに保温材を取り付ける作業。作業現場付近の空間線量は毎時0・3~1・2ミリシーベルトだった。工期は昨年11月下旬から今年3月。
東京エネシス広報室によると、ビルドアップからは「(役員は)カバーを作ったが、作業員は使っていない」と連絡があったという。東京エネシスは「事実だとすれば非常に問題だ」としており、役員が単独で作成したかなどを調べている。
第1原発では、作業員が作業開始時に東電側からAPDを渡され、作業が終わったら返却する。東電はAPDを基に、作業員ごとの1日の作業時間、被ばく線量を管理している
常識で考えればあんなところであのような発言をすれば電力会社の印象を悪くするだけ。そこまでして原発を再稼働させようと
動いている電力会社の姿勢や体質は大いに問題だと思う。
九州電力のやらせ問題はほぼ独占企業である電力会社の共通点であるのかもしれない。
利益のためには手段を選ばない。今回の問題は東電がきっかけを作ったわけだが、電力会社の姿勢や体質を改善する必要があることを
多くの国民にしめしたような気がする。原発自体のリスクだけでなく、原発を管理及び運転する企業の体質も原発事故のリスクに大きな
影響を与えることを多くの国民は知ったと思う。
電力社員の発言認めず 首相、国家戦略相に指示 07/17/12(産経新聞)
野田佳彦首相は17日、将来のエネルギー構成の選択肢に関する意見聴取会で電力会社社員が発言者として参加したことについて、古川元久国家戦略担当相に「意見聴取会にはいささかの疑念も生じさせてはいけないので、電力会社社員の意見表明は遠慮いただくようにしてほしい」と述べ、社員の発言機会を認めないよう指示した。
古川担当相は官邸で首相と協議後、記者団の取材に応じ「もし電力会社の社員であれば、お断りする」と表明。聴取会の「改善策」は電力会社を締め出し、発言者の人選や運営方法をめぐる批判をかわす格好となった。
古川担当相は「参加者は個人の資格で意見表明してもらうよう明確にしたい」と指摘。これまでの運営について「疑念を抱かせる結果になり、申し訳ない」と謝罪した。
22日に札幌市と大阪市で開く次回の意見聴取会から改善策を導入する。
耐震強度偽装問題
の時に1級建築士の免許偽造の問題はなかったのだろうか?それとも調べずに野放しにしていたのだろうか?
1級建築士の免許偽造、新たに神奈川で判明 10件以上の建物を設計 07/13/12(産経新聞)
1級建築士の免許偽造が各地で相次いでいる問題で、60代の2級建築士の男性が1級建築士と偽り、神奈川県内で少なくとも10件以上の建物を設計していたことが13日、県への取材で分かった。県は建築士法違反とみて、処分に向けた手続きを進めている。
昨年12月、大和市に戸建て住宅の建築確認書類を提出した際、1級建築士の免許証のコピーを添付。市が登録番号を確認し、別人の番号と判明した。通報を受けた県が調べたところ、この男性は県に登録された相模原市内の1級建築士事務所の代表者で、1級建築士の登録番号は同じ事務所の1級建築士のものだった。
男性は昭和46年に青森県で2級建築士の資格を取得。神奈川県内では10件以上の住宅の設計監理を行い、うち1件は1級建築士の資格が必要な川崎市内のマンションだった。ただ、いずれも安全上の問題は見つかっていない。男性は今年5月に廃業届を提出しており、県は廃業したかを確認するため近く事務所に立ち入り調査する。県によると、男性は偽造した理由を「1級建築士が病気で働けなかった」と話しているという。
県内では、茅ケ崎市の障害者福祉施設の改修工事で、国に登録されていない1級建築士の名前で書類が偽造されていたことが判明している。
1級建築士の免許証偽造 県内も1件 07/12/12(朝日新聞)
1級建築士の免許証を偽造し、建築士として勤務していたケースが全国で少なくとも3件発覚した問題で、うち1件は新潟で働いていた男性(45)だった。
国土交通省などによると、男性が勤務していたのは住友林業ホームテック新潟営業所(新潟市)。同営業所が4月に県建築士事務所協会に事務所登録の手続きをした際、男性の免許証の写しの登録番号が別人の番号だと分かり、偽造が発覚したという。
男性は数回、建築契約を結ぶときに建築主に設計内容などの説明をしていたが、偽造発覚後、別の建築士が再説明をしたという。男性は5月に解雇されている。
県建築住宅課は、今のところ県内で同様のケースの報告はないとしている。
所属の有名設計事務所で「室長」 1級建築士免許証偽造 07/12/12(朝日新聞)
全国で1級建築士の免許証偽造が明るみに出た問題で、国土交通省が偽造を指摘した大沼一成氏(46)は、大阪市西区の設計会社「IAO竹田設計」でマンションなどの設計に携わっていた。大阪府によると、大沼氏は偽造を認めているという。同社は9日に大沼氏を解雇。免許証の偽造容疑などで府警に刑事告発する方針。
府などによると、大沼氏が関わった建物では、別の1級建築士が設計の統括責任者を務めており、構造設計は別の会社が担当。府は建物の建築確認の手続きは適正で、建物の安全性に問題はないとしている。
IAO竹田設計によると、大沼氏は1986年に入社し、直近まで設計室長に就いていた。建物のデザインを得意とし、これまでマンションを中心に20~30件の設計に関与。担当したマンションが建築雑誌に取り上げられたこともあり、同社幹部は「仕事ぶりはほかの1級建築士のスタッフと遜色がなく、偽造とは思いもしなかった」。
ニセ1級建築士、3府県で確認 免許偽造でなりすまし 全国調査へ 07/11/12(産経新聞)
国土交通省は11日、資格を持たない3人が1級建築士の免許証を偽造し、建築士になりすまし働いていたと発表した。免許偽造の発覚は初めて。国交省はいずれも建築士法に抵触するとみており、同様の事例が見つかる可能性があるとして、都道府県と連携し、全国約11万カ所の建築士事務所を調査に乗り出す。違法行為があれば刑事告発するよう都道府県に要請する。
国交省によると、資格を持たず1級建築士免許証の偽造していたのは、新潟、大阪、三重の3府県の計3人。建築事務所を開設したり、建築事務所に勤務したりしていた。昨年3月から今年5月にかけて、3府県の建築士事務所協会などが、3人の偽造免許証と、建築士の登録情報のデータベースを照合し発覚。ただ、いずれもマンションや住宅などの設計を担当したケースはなかった。
このほか神奈川県でも、国に登録されていない1級建築士の名前で、書類が偽造されていたことが判明した。県によると、NPO法人が運営している茅ケ崎市の障害者向け施設改修工事で、NPO法人が国の補助金を県に申請する際、提出された工事図面に記載された1級建築士の名前が国に登録されていなかった。登録番号も九州の建築士の番号が使われていた。
事故がなければ生き残っていたのか知らないが関越道バス事故で終止符を打った。「焼肉酒家えびす」と同じように思える。
不適切な行いが最悪の事態(事故)となって企業の歴史に終止符を打つ。リスクを認識していたのか、リスクを取らないと
生き残れなかったのか、リスクを考えず安易な選択をおこなったのか、よくわからないが、運が悪かったのは確かであろう。
高速バス事故のツアー主催会社が自己破産申請へ 07/02/12(帝国データバンク)
(株)ハーヴェストホールディングス(TDB企業コード:581914432、資本金5000万円、大阪府豊中市庄内東町3-9-14、代表大屋政士氏、従業員50名)は、7月2日に事業を停止し、事後処理を松田敏明弁護士(大阪府大阪市北区西天満3-1-6、電話06-6361-1722)に一任、自己破産申請の準備に入った。
当社は、1995年(平成7年)12月に設立。当初は、社内旅行や個人向けの旅行斡旋のほか、旅行会社への添乗員派遣業務も行っていた。2005年4月に(株)ハーヴェストツアーに商号変更、2006年8月にはバスを所有し自社運行を開始。2007年8月に現商号となり、バス保有台数を増やし、「ハーヴェストライナー」の名称で運行する夜行バスを中心に手がけていた。また、旅行代理店などへの貸切バス事業でも積極的な受注を行ったことや、ツアーバスの増便により、2011年1月期には年収入高約30億6400万円を計上していた。
しかし、自社運行を開始した2007年1月期が赤字決算となって以降、同業者間の競争激化やデフレの影響により高速バスの運賃や貸切バスの受注価格は下落、辛うじて採算を維持するのが精一杯の状況が続いていた。2012年1月期は、東日本大震災の影響により旅行のキャンセルが相次いだが、ツアー価格を大幅に引き下げるなどして年収入高は約32億6600万円を計上したものの、約2億2800万円の最終赤字となり、財務面でも債務超過に転落していた。2012年1月にはHS観光バス東京営業所で整備管理者に運輸局長の行う研修を受けさせていないとして、行政処分を受けるなど管理体制にも不備を抱えていた。
こうしたなか、今年4月に当社が主催したバスツアーが関越自動車道上り線で運転手の居眠りにより乗客7名が死亡する事故を起こし、以降は高速バスの運行を休止していた。事故を起こしたバスの運行は下請業者が行っていたが、当社自身にも多数の法令違反があったことから業務停止処分を受ける方向となり、先行き見通し難から、今回の措置となった。
負債は2012年1月期末時点で約6億7200万円。
なお、同時に関係会社の(株)HSサポート(東京都新宿区)、(株)ハーヴェストサポート(名古屋市中村区)、(株)HS観光バス(富山県南砺市)、(株)HS観光バス西日本(大阪府豊中市)も事業停止し、自己破産申請の準備に入っている。
社説:東電社内事故調 自己弁護でしかない(1/2ページ)
(2/2ページ)06/22/12(毎日新聞)
まるで、裁判の訴訟対策のようだ。福島第1原発事故は「想定した高さを上回る津波の発生」が原因だと結論づけ、責任逃れと自己弁護に終始している。東京電力の社内事故調査委員会がまとめた最終報告書を読むと、そう言わざるを得ない。
報告書は本体だけでA4判352ページに及び、延べ600人に聞き取り調査したという。しかし、目的に掲げられた「原因を究明し、原発の安全性向上に寄与するため、必要な対策を提案する」姿勢がまったく感じられない。期待されていたのは、事実を積み重ね、事故の真相に迫り、責任の所在を明らかにすることだったはずだが、対応のまずさの指摘に対する釈明ばかりが並ぶ。そのような企業に、これからも原発の運用を託せるのか疑問だ。
例えば、政府の事故調査・検証委員会は昨年12月の中間報告書で、1号機や3号機の冷却装置の操作の習熟不足などを問題点として指摘したが、報告書は「その後の対応に影響を与えたとは考えられない」などと反論する。だが、別の対応を取っていた場合に事態がどう変わっていたかの考察はない。津波の想定も「専門研究機関である国の組織が統一した見解を明示し、審査が行われることが望ましい」と他人任せにする。
菅直人首相(当時)ら官邸の介入については「無用の混乱を助長させた」と断じた。第三者が指摘するなら分かるが、当事者が言うと、責任逃れにしか聞こえない。
一方で、事故をめぐる多くの謎は残されたままだ。
報告書は、福島県飯舘村など原発から北西方向へ広がった放射性物質の主要な排出源は2号機だと結論づけたが、2号機は水素爆発を起こしておらず、損傷箇所や放射能の流出経路ははっきりしない。原子炉の圧力や温度データから、地震による主要機器の損傷はないと評価しているが、高い放射線の影響などで建屋内の機器の現場確認もできていない。
情報公開にも疑問がある。
東電本店と第1原発は回線で結ばれ、事故時のテレビ会議は録画されていた。検証作業には欠かせない資料だが、「プライバシーの問題が生じる」ことなどを理由に公表を拒んでいる。新旧役員の事故責任を問う株主代表訴訟や、被害者による損害賠償訴訟が起きていることが、情報出し渋りの一因だとすれば問題だ。
国際原子力機関の安全原則は1番目に、原発の安全の一義的な責任は事業者が負うと定めている。東電の責任は免れようがなく、徹底的な情報の開示は最低限の責務だ。
近く最終報告をまとめる政府や国会の事故調には、国民が納得できる検証結果の公開を求めたい。
東電事故調査―この体質にはあきれる 06/22/12(朝日新聞)
東京電力による福島原発事故の調査報告書が公表された。
結論を一言でまとめるなら、「原因は想定を超えた津波にある。東電の事後対応に問題はなかった。官邸の介入が混乱を広げた」というものだ。
半ば予想されていた主張とはいえ、これだけの大事故を起こしながら、自己弁護と責任転嫁に終始する姿勢にはあきれるほかない。
こんな会社に、原発の再稼働など許されない。
報告書は、東電社内でも津波が15メートル以上になるケースを試算していながら、対策を講じなかったことについて、「国が統一した見解を示していなかったため」とする。
事故後の対応で、冷却作業などの遅れが指摘されている点には、与えられた条件下で最善を尽くしたと主張する。
東電が官邸に「全面撤退」を申し入れたとされる問題は、官邸側の勘違いとしている。
そもそもの発端は、当時の清水正孝社長からの電話である。電話を受けた一人である枝野官房長官(当時)が会話の内容を詳しく証言しているのに対し、清水氏は「記憶にない」としており、報告書ではこの電話には一切触れていない。
外からの批判に細かく反論する一方、都合の悪いことは避けているとしか思えない。
報告書は、責任を逃れるため東電が情報を都合よく扱っている疑いも残る。
事故後の対応は、東電本社と原発を結ぶテレビ会議システムの情報を公表すればわかる。
しかし、東電は「プライバシー」を理由に公表を拒む。「例えば作業員がどんな姿勢で映っているかわからないから」などの理由をあげる。
東電のもつデータをすべて公開させなければ、福島事故が解明できないことは明白だ。
東電が自らの責任にほとんど言及しないのは、今後の賠償、除染、廃炉費用の負担や株主代表訴訟などを考えて、有利な立場に立ちたいからだろう。
しかし、原因を突き止め、発生後の対応の問題点を洗い出して、今後の教訓を引き出さないのでは、何のための事故調査だろうか。
報告書が示しているのは、事故の真相ではなく、東電という会社の体質である。事故の詳細や責任の所在などを後世に残すという歴史的使命に向き合うよりも、会社を守ることを優先させる企業の実相だ。
原発はこういう会社が運転していたという事実を改めて肝に銘じておこう。
スカイマークの方針を消費者が選ぶと言うことだろう。
スカイマーク:「苦情は当社へ」と改訂…乗客向け機内文書 06/15/12(毎日新聞)
航空会社のスカイマークが乗客向けの機内文書で、苦情があれば公共の「消費生活センター」などに訴えるよう求めていた問題で、同社は15日の運航便から、内容を一部改訂した文書を配備した。改訂版は苦情の連絡先から消費生活センターを削除。自社の「お客様相談センター」だけを掲載し、電話番号も記した。
ただ「丁寧な言葉遣いを当社客室乗務員に義務付けておりません」とする記述を残したほか、乗務員の「接客は補助的なもの」とし、私語に関する苦情を受けない姿勢を維持。髪形やネイルアートを「自由」とする方針も変えず、さらに賛否両論を招きそうだ。(共同)
東電、06年にも大津波想定 福島第一、対策の機会逃す 06/13/12(朝日新聞)
福島第一原発事故が起きる前の2006年、東京電力が巨大津波に襲われた際の被害想定や対策費を見積もっていたことが、朝日新聞が入手した東電の内部資料でわかった。20メートルの津波から施設を守るには「防潮壁建設に80億円」などと試算していた。
津波対策をめぐっては、04年のスマトラ島沖大津波を受けて06年、国が東電に対策の検討を要請したほか、08年には東電が福島第一原発で最大15.7メートルに達すると試算したが、いずれも対策はとられなかった。早期に実施された試算はことごとく生かされず、事故を回避する機会は失われた。
資料は、原子力技術・品質安全部設備設計グループ(当時)で05年12月から06年3月の間に行われた社内研修の一環で作られた。
「現行法では情報提供者はインサイダーに問われない。」
増資インサイダー:野村証券、情報漏えい認める 06/08/12(毎日新聞)
現行法では情報提供者はインサイダーに問われない。このため、監視委は情報を漏えいした企業について「公募増資の主幹事証券会社」と説明するにとどめてきた。しかし、監視委が8日公表したインサイダー事件の舞台になった東電の公募増資の主幹事証券は野村証券1社だけ。自社の関与について明確なコメントを避け続けてきた野村も、認めざるを得ない事態に追い込まれた。
東電の増資を巡るインサイダー取引では、野村証券の男性営業社員は日本に拠点を置くコンサルティング会社を通じ、公募増資情報を漏えい。このコンサル会社と契約を結ぶ米金融機関が増資の公表前に株を空売りし、利益を得る見返りに、その後の株式売買を野村証券を通じて行ってもらう狙いがあったとみられる。
監視委によると、3件のインサイダーで情報漏えいに関与した野村証券の営業員は計4人。個人の資質の問題を超え、営業活動の一環として組織的に情報を漏えいしていた疑いが強まっている。
監視委は、既に野村証券への行政処分を勧告する方針を固めている。野村が公表する調査報告を踏まえ、6月中にも勧告に踏み切る可能性がある。【大久保渉、浜中慎哉】
野村証券の機関投資家営業部長が異動 インサイダー取引問題、証券監視委の調査協力で 06/01/12(産経新聞)
公表前の公募増資情報を入手し、不正な取引で利益を上げていたとする増資インサイダー取引問題で、野村証券は1日、同日付で機関投資家営業部長を異動させる人事を発表した。証券取引等監視委員会による特別検査など、事件の全容を解明するため、調査の協力に専念する。
同社は今回の異動について「営業部長としての職務と特別検査への協力を兼務するのは困難と判断した」と説明している。
金融庁、インサイダー規制強化へ 投資家の日本離れを危惧 05/29/12(産経新聞)
企業の公募増資に絡む内部情報の漏洩(ろうえい)で不正取引が相次いでいることを受け、金融庁は規制強化に乗り出す。日本は情報漏洩に関する規制が甘く、海外から「インサイダー取引の温床」との批判を招いているからだ。このままでは、不信感を募らせた投資家の日本市場離れを招く懸念は強く、汚名返上に向けて不正取引の一掃を急ぐ。
「市場の公正性、公平性の観点から極めて重要な課題だ」。自見庄三郎金融相は29日の閣議後会見で、規制強化など再発防止策を検討する考えを強調した。
公募増資の情報漏洩による不正取引をめぐっては、現行制度では情報の受領者だけが処分対象で、海外投資家を中心に「情報を提供していた側の責任を問えないのはおかしい」との指摘が多い。欧州では不正取引につながりかねない情報を漏らせば、情報を得た側が実際に不正取引を行ったか否かに関係なく罰せられるが、日本では情報を流出させた側は罪に問われない。
このため、金融庁は今後、情報提供者も課徴金処分や刑事罰の対象にするかどうかを検討。不正取引から得た利益を元に決まる課徴金が少額過ぎるとの批判もあることから、課徴金の算出方法も見直す方向だ。
証券取引等監視委員会は3月にも国際石油開発帝石の増資でインサイダー取引を行ったとして、旧中央三井アセット信託銀行(現三井住友信託銀行)に課徴金の納付を命じるよう金融庁に勧告した。だが、勧告された課徴金は運用報酬に基づき、わずか5万円で、課徴金の算出方法見直しは急務だ。
企業が幅広い投資家から資金を集める公募増資は株式市場でも最も重要な情報の一つだ。その情報を公表前に入手したインサイダー取引が横行すれば、市場の信頼性が失墜して流入資金が細り、企業の資金調達にも支障が出かねず、証券会社など市場参加者全体の意識向上も課題になる。(永田岳彦)
違反者に重い罰則が必要と金融庁に電話した時は重い処分は検討していないと言っていなかったがどうしたことだ!公務員など信用や信頼など出来ない人間達と
言うことだろう!そうだ、外務省に苦情の電話した時に、電話を受けた人間は名前さえ言わなかったな!これが公務員達の現状か!
野田総理の原発稼動に関する会見は国民を馬鹿にしているとしか思えなかった。国民のためとか言えば説得できると思ったのか?
安全の話よりも電力事情の影響だけ。「日本、万歳」とでも言ってほしいのか????
インサイダー天国ニッポン 甘い規制で海外ファンド“野放し”(1/4ページ)
(2/4ページ)
(3/4ページ)
(4/4ページ) 05/13/12(産経新聞)
公募増資に絡む内部情報の相次ぐ漏洩(ろうえい)が証券界を揺るがしている。中央三井アセット信託銀行(現三井住友信託銀行)が野村証券の担当者から得た情報を元に株を売買し、不正利益を得たことが3月に発覚。4月にはSMBC日興証券が事前に得た増資情報を元に顧客を勧誘していたことが明らかになった。金融庁は規制強化に乗り出しているが、「インサイダー天国」の汚名をそそぐ“特効薬”は見当たらず、投資家の日本離れはさらに加速しかねない。
情報遮断は不可能
日本の資源開発を牽引(けんいん)する国際石油開発帝石。その増資計画を中央三井アセットのファンドマネジャーが知ったのは、平成22年6月30日のことだった。実際の増資の発表は7月8日。増資の主幹事である野村証券の女性営業担当者から、1週間以上も前に情報を得たのだ。
増資で発行済み株式数が増えれば1株当たりの価値が減るため、株価は下落することが多い。ファンドマネジャーは、7月1、7日に空売りも含めて210株を約1億円で売り抜け、1400万円の運用益を得て顧客に還元していた。
公募増資の場合、証券会社の投資銀行部門に新株発行時期など重要な情報が集まる。このため、部屋の出入り口を部外者と分けたり、電話の録音や防犯カメラで入退室を監視するなど、情報を遮る壁「チャイニーズ・ウオール(万里の長城)」を構築してきた。だが、私的な携帯電話やメールを使えば「遮断はほぼ不可能」(関係者)だ。
野村は3月下旬に社内調査に着手したが、全容解明には至っていない。調査が難航する中、証券取引等監視委員会は先月25日、定期検査が終わったばかりの野村に対し異例の「特別検査」に踏み切った。これを機に一部の機関投資家は野村との取引を見合わせているとされ、業界では一段の「野村離れ」を予想する声も出ている。
氷山の一角
一方、日興はインサイダー情報を使って組織的に営業を展開した。22年1月に三井住友フィナンシャルグループ(FG)の増資情報が65支店に伝わり、うち8支店で実際に顧客に新株の購入を勧めていた。
監視委は、顧客らが三井住友FG株を空売りするなどの「インサイダー取引を行った事実は確認していない」としている。だが、問題発覚後に日興が行った情報管理研修などの対策が「再発防止策になっていない」として、4月13日に金融庁に対し行政処分を行うよう勧告した。
監視委が情報漏洩に厳しい姿勢で臨んでいるのは、東京市場の信頼が地に落ちたためだ。22年の東京電力や日本板硝子などの増資でも株価が増資の公表前から不自然に急落。ヘッジファンドなどの空売りが疑われ、海外から「日本市場はインサイダーの温床だ」との非難の声が上がっていた。発覚した野村、日興の例は「氷山の一角」ともいわれ、市場関係者の間では「監視委の摘発はなお続く」とささやかれている。
課徴金わずか5万円
日本でインサイダー情報の漏洩が続くのは“大甘”ともいえる規制のせいだ。欧州では世間話でも情報を漏らせば、情報を得た側が不正取引を行ったか否かに関係なく罰せられるが、日本では情報を流出させた側は罪に問われない。刑事罰も海外では実刑が珍しくないが、日本では執行猶予がつくケースが大半だ。
課徴金も少なく、勧告を受けた中央三井のケースではわずか5万円。ある外資系証券の運用者は「少なすぎて笑い話になった」と苦笑する。
日本証券業協会は増資を実施する際に、機関投資家に対してどの程度の増資を引き受けるのかを事前に打診する行為を禁じている。だが、空売りを仕掛けたとされる海外の証券会社やファンドは対象外で、事実上“野放し”。監視委が海外ファンドを調査しようとしても、外国語での文書作成や、法務省や外務省、大使館など複数の機関をまたぐ膨大な作業が伴い、「特に重大な事件以外は手が回らない」(関係者)という。
事態を重くみた金融庁は、海外ファンドを不正取引の課徴金制度の適用対象に加える金融商品取引法改正案を今国会に提出するなど規制強化を図るが、「抜本的な対策にはほど遠い」(大手証券)のが現状だ。
東証1部の昨年の売買代金は341兆5875億円と、20年に比べ4割も減少、東京市場の地盤沈下は深刻だ。再浮上を狙い、東証は来年1月に大証と合併するが、規模だけでは投資家の信頼は得られない。早大大学院法務研究科の黒沼悦郎教授は「証券会社が営業姿勢を根本から見直し、規制強化を急がなければ、グローバル化が進む金融市場から見放される」と警鐘を鳴らしている。(小川真由美、永田岳彦)
公務員組織と同じで重大な事故が起きてもずれた認識を変えることが出来ない典型的な例であろう!
「東電の給与高い」批判噴出、圧縮へ圧力 06/08/12(読売新聞)
経済産業省は7日、東京電力による家庭向け電気料金の値上げ申請について、利用者らの意見を聞く公聴会を開いた。
厳しい意見が相次ぎ、東電が7月を目指していた値上げの実施は8月以降にずれ込むのが確実な情勢だ。平均10・28%を申請した値上げ幅もどこまで認められるのか不透明だ。
◆社長釈明
公聴会は午前9時から午後4時まで行われ、会場となった経産省の講堂には約300人が集まった。意見を述べたのは、一般の陳述人10人と、自治体や消費者団体の代表ら10人だ。
陳述人からは、「理解を得られない値上げには断固反対」などと厳しい指摘が続いた。特に東電の人件費を巡っては「民間平均より高い」などの批判が多く出た。
出席した東電の西沢俊夫社長は、「経営合理化を徹底しているが、燃料費の増加を賄うことは非常に難しい」などと釈明に追われた。
ただ、少数ながら、電力の安定供給のために値上げを容認する意見もあった。
インターネットを通じた意見募集では、4日までに約600件が寄せられ、大半が値上げに反対したという。公聴会は9日にも、さいたま市で開かれる。経産省は今後の審査に反映させる方針だ。
◆ハードル
経産省以外にも東電の値上げを検証する動きが出ている。
民主党は7日、東電の値上げなどを検討する小委員会(委員長・海江田万里元経産相)の設置を決めた。値上げ申請内容の透明性や妥当性について検証を進める。
松原消費者相も5日の記者会見で「消費者の観点を踏まえる必要がある」と述べ、消費者団体や有識者らによる値上げ検証チームを設置する方針を示した。
値上げに対する反対が続出していることから、経産省の有識者会議「電気料金審査専門委員会」の議論は今月末~7月上旬までかかるとみられている。このため、東電が申請している7月1日からの値上げはすでに絶望的な状況だ。
東電に対する世論の反発を意識して、民主党や消費者庁の検証が長期化したり、東電が申請している平均10・28%の値上げ幅の大幅圧縮を求める動きが強まり、認可時期が遅れる可能性も出てきた。
問題の氷山の一角だと思うが、結果として大惨事になったのだから当然と言えば当然。他の会社に対して教訓となれば良いほうだろう!
問題のある会社ほど自分達は大丈夫と思うだろうから!
関越道バス事故:「ハーヴェスト」を業務停止処分へ 06/08/12(毎日新聞)
46人が死傷した関越道の高速ツアーバス事故で、観光庁は8日、ツアーを企画した旅行会社「ハーヴェストホールディングス」(大阪府豊中市)に旅行業法に基づく法令違反があったとして、業務停止にする処分案をハ社に通知した。停止期間は1カ月半ほどになる見通し。3回の立ち入り検査で、事故を起こした千葉県のバス会社「陸援隊」にツアーの配車指示書が届いたか確認を怠るなど3項目の法令違反が見つかった。
社員2人を懲戒解雇、役員は減給 旧中央三井系がインサイダー取引で 06/08/12(産経新聞)
旧中央三井アセット信託銀行(現三井住友信託銀行)のインサイダー取引問題で、同行は8日、取引に関わった社員2人を懲戒解雇し、当時の役員らを減給する社内処分を発表した。
証券取引等監視委員会が2度にわたって課徴金納付を勧告したことを重く受け止め、経営陣を含めて責任を明確化する。
社内調査では、解雇した社員の1人が、増資情報を流したとされる野村証券の営業担当者から高額の飲食接待を受けていたことも分かった。
減給の対象は、旧中央三井アセットと当時の親会社に加え、現在の親会社の三井住友トラスト・ホールディングスの取締役ら。それぞれ月例報酬の10~50%を1~5カ月間減給する。
今回は間に合わなかったにしても「法的責任追及は難しい」ことが分かったのだから、法改正をするべきだ。
法改正を行わず、同じ問題が起これば行政の問題であることは間違いない!
ホルムアルデヒド、法的責任追及は「難しい」 06/08/12(読売新聞)
利根川水系の浄水場で、国の基準値を超す化学物質ホルムアルデヒドが検出された問題は、埼玉県が7日、「DOWAハイテック」(本庄市)に行政指導をし、一応の区切りを迎えた。
しかし、浄水処理でホルムアルデヒドを生成する原因物質ヘキサメチレンテトラミン(HMT)は法規制の対象外で、扱いに関心が薄い業者も多い。排出業者と産廃業者に対策の徹底が求められている。
「はっきり言って、現行法では難しい」。原因究明を進めてきた半田順春・県水環境課長は記者会見で、法的責任を問えない悔しさをにじませた。約35万世帯の大規模断水という重大な結果を引き起こしながら、改善命令など行政処分もできなかったためだ。行政指導には強制力がない。
県は早ければ来週中にも、廃棄物処理委託の適正化などをまとめた指導要綱を作る。HMTと同じように塩素と反応してホルムアルデヒドを生成する物質を扱う県内の事業所に示し、順守を求める。
一方、県が追加で行った群馬県高崎市の産廃業者への立ち入り検査では、同社が行った中和処理では、HMTは4割程度の分解、規制対象となる「全窒素」は2割程度の除去しかできない可能性があることが明らかになった。
DOWAハイテックは、「全窒素を排出基準値以下に処理する過程でHMTなどの窒素化合物の濃度も十分に低減される」としていたが、ほかの物質が適正に処理されていたかどうか不透明だ。また、廃液のデータ分析など処理に重要な手続きも収集運搬業者(横浜市)に任せきりにしており、県はこれについても、好ましくなかったとみている。
スカイマークの方針と言うことだろう!安さを優先するのか、安全を優先するのか、中間の航空会社を選ぶのか、消費者が選ぶと言うことだろう。
極限まで価格競争して、安全が保てるのか?運が良ければ何も起らないだろう!戦争に行っても帰ってくる人はいる。運次第!
道端をあるいて車の暴走で命を落とす人もいる。消費者は良く考えて選ぶ時代と言うことだ!
スカイマーク:「機内の苦情は消費生活センターへ」 06/05/12(毎日新聞)
航空会社のスカイマーク(東京都大田区)が乗客に対し、苦情は機内ではなく消費生活センターなどに伝えるよう明記した文書を示しており、東京都消費生活総合センターは4日、同社へ抗議することを決めた。
スカイマークによると、この文書はA4判の「サービスコンセプト」。5月18日から機内全席の前ポケットに入れており、内容は▽客室乗務員は荷物の収納の援助をしない▽客室乗務員に丁寧な言葉遣いを義務づけていない▽客室乗務員は保安要員としての搭乗で接客は補助的なもの−−など8項目。数年前からの方針だが、乗客から客室乗務員の接客について問い合わせが相次いだため作成したという。
文書はさらに「機内での苦情は一切受け付けません。ご理解いただけないお客様には定時運航順守のため退出いただきます。ご不満のあるお客様は『スカイマークお客様相談センター』あるいは『消費生活センター』等に連絡されますようお願いいたします」と明記。都消費生活総合センターに4日、この文書に関する苦情が1件あった。
「議論の経緯を示す内部文書を公表せず、国会事故調査委員会の請求で初めて明らかになったことには『担当者が公開を失念していたためだが、隠(いん)蔽(ぺい)といわれても仕方がない』
と話した。」
いい訳だろうが、「原子力安全委員会の作業部会が平成4年、原発の過酷事故につながる長時間の全電源喪失の対策が不要な理由を電力会社に『作文』するよう指示し、安全設計審査指針の改定を見送った問題」
で誰が出席して、誰が賛成したのか、また、誰が指示したのか公表しろ!
不都合なことはお金と圧力で捻じ曲げる!日本原子力研究開発機構の高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)の安全性を調べるために設置された専門家委員会の委員7人のうち3人へ計1610万円が
寄付されたことも布石の1つであろう。原子力安全委員会が機能していない現状で安全を保障など出来るはずがない!
「不適切」安全委員長が陳謝 電力業界への作文指示で 06/05/12(産経新聞)
原子力安全委員会の作業部会が平成4年、原発の過酷事故につながる長時間の全電源喪失の対策が不要な理由を電力会社に「作文」するよう指示し、安全設計審査指針の改定を見送った問題で、班目(まだらめ)春樹安全委員長は4日、記者会見し「電力会社に文章を作らせるなど明らかに不適切だ。深くおわび申し上げる」と事実関係を認め陳謝した。
部会は非公開で行われ、長時間の全電源喪失対策を不要としている指針の見直しに反発する業界側の意向に沿った報告書を作成した。班目氏は「指針を見直す場があったのに、改定しなくていい理由作りばかりやっていた。非公開だったことも不適切」と述べた。
議論の経緯を示す内部文書を公表せず、国会事故調査委員会の請求で初めて明らかになったことには「担当者が公開を失念していたためだが、隠(いん)蔽(ぺい)といわれても仕方がない」と話した。
国の原子力安全委員会が業界の意向反映し、問題や被害が起これば、国税を投入して、電気料金値上げで更なる負担を押し付ける。
これで電力会社の社員達は本当の意味で責任を取らない。発送電分離は絶対に必要!国が部分的に業界に操作されている!
「原発全電源喪失の対策不要」 安全委、業界の意向反映 06/05/12(朝日新聞)
国の原子力安全委員会の作業部会が1993年に原発の長時間の全電源喪失についての対策は不要と結論づけたのは、電力会社の意向が反映された結果だったことが4日、安全委の公表した資料でわかった。安全委事務局は対策が不要な理由を示す文書を電力会社に作るよう指示。作業部会は電力会社の意向に沿う報告書をまとめたため、指針は改定されなかった。
東京電力福島第一原発は津波に襲われてすべての交流電源が失われ、原子炉の冷却ができなくなり事故を起こした。当時、対策をとっていれば事故を防げた可能性がある。
作業部会は91年につくられ、専門家5人のほか部外協力者として東京電力や関西電力の社員が参加していた。安全委事務局によると、作業部会は当時対策を検討していたが、電力会社が「全交流電源喪失によるリスクは相当低く、設計指針への反映は行き過ぎだ」と反発したという。
原発業界、もんじゅ委員に寄付 3人に計1610万円 06/03/12(朝日新聞)
日本原子力研究開発機構の高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)の安全性を調べるために設置された専門家委員会の委員7人のうち3人が、原子力関連の企業・団体から寄付を受けていたことが、朝日新聞の調べでわかった。寄付は、もんじゅのストレステスト(耐性評価)の業務を受注した原発メーカーなどからで、5年間で計1610万円になる。
委員会は、昨年11月に文部科学相の指示で機構が設置した「もんじゅ安全性総合評価検討委員会」(委員長=片岡勲・大阪大教授)。
朝日新聞が委員の所属大学に情報公開請求し、対象となる過去5年分(2006~10年度)が開示され、委員に直接取材した。寄付を受けていたのは宇根崎博信・京都大教授(計180万円)、片岡教授(計450万円)、竹田敏一・福井大付属国際原子力工学研究所長(計980万円)で、3人は取材に対し受領を認めたうえで、審議への影響を否定している。
一般人には理解できないそして知らない繋がりがあるのだろう!この時期にこのような判断が出来るほど何かがあるのだろう!
東電の清水前社長、富士石油の社外取締役に 05/31/12(読売新聞)
石油開発・元売り大手のAOCホールディングスは31日、傘下の富士石油の社外取締役に、東京電力の清水正孝・前社長を迎える6月25日付の人事を発表した。
清水氏は福島第一原子力発電所事故当時の東電の社長で、昨年6月に責任を取って辞任した。東電はAOCに8・7%を出資する筆頭株主だが、いったん引責した清水氏を起用する人事に批判が出る可能性もある。
東電によると、就任はAOCの要請によるもので、清水氏は月20万円の報酬を受け取る。AOCは「清水氏のエネルギー業界への知見を経営に生かすため」と説明している。清水氏は昨年6月から今年3月まで、無給で東電の顧問を勤めていた。
富士石油は同時に、東電の荒井隆男常務を常勤監査役に迎える。同じAOC傘下のアラビア石油も6月26日付で東電の武井優副社長を社外監査役に起用する。
「日本一の白バス業者」と針生社長 見えない違反広がる (1/2ページ)
(2/2ページ)(産経新聞)
関越道の高速ツアーバス事故で、28日に逮捕された陸援隊社長、針生裕美秀(はりう・ゆみひで)容疑者(55)。道路運送法違反容疑で摘発されたのはこれが初めてではなかった。同社は数々の法令違反を犯しながら、なぜバス事業を続けることができたのか。規制緩和で新規参入が増えバス会社間の競争が激化したことで、「表に見えない違反」が業界に広がっている可能性があると専門家は危惧する。
業界歴25年以上
針生容疑者は白バス営業をしていた10年以上前、周辺に「俺は日本一の白バス業者だ」と豪語していた。
民間調査会社によると、針生容疑者のバス業界歴は25年以上。平成11年当時は東南アジアからの客相手に通常の半値以下で白バス営業をし、「ゆとりのない台湾人らの人助けのため」などと語っていたという。当時の社名は「針生エキスプレス」だった。
転機は12年のバス事業の規制緩和だった。針生容疑者は摘発の責任を取って社長を退任したが、商号を「陸援隊」と改め、14年には事業許可を取得。ほとぼりが冷めた19年には再び社長に返り咲いていた。
過当競争で異常環境
ところが、ほころびはまもなくあらわになる。陸援隊は20年の国交省の監査で、管理記録の不備などが見つかりバスの使用停止処分を受けた。日本バス協会の藤井章治理事長は「規制緩和でバス会社が急増し、過当競争で観光バス業界は異常な環境にある」と訴える。
19年に大阪府吹田市で27人が死傷したツアーバス事故は、運転手の過労運転が原因とされ、会社の安全管理態勢が問われた。
陸援隊は事故後の特別監査で、名義貸しや「日雇い運転手」のほか、シートベルトの不具合など36項目にわたる法令違反を指摘された。厚生労働省の調査でも、労働基準法や最低賃金法に違反している疑いが指摘された。
ただ、これは“氷山の一角”にすぎない可能性も。明治大学の藤井秀登教授(都市交通論)は「法令違反すれすれの零細業者も少なくないだろう」と危惧する。針生社長は法令違反について、27日の説明会の席で「(逮捕は)当然のことだと思う」と語っていた。
チェック態勢の限界
国交省は陸援隊へのチェックの不備は認める一方、「規制緩和後の監査態勢は強化されている」と強調する。バス会社などを監査する自動車監査官と運輸企画専門官は全国306人。確かに、10年前(108人)より約3倍に増えている。
だが、監査対象となるバス、タクシーなどの事業者は計約12万5千社、車両数は計約148万2千台。貸し切りバス事業者だけでも約4500社、4万6千台が対象となり、「事業者を回り切れていない」(国交省の担当者)のが実情だ。
業界団体の高速ツアーバス連絡協議会は、夜間に450キロ以上運行するバスの運転手を2人態勢にするなど自主的な指針を策定した。バス業界に詳しい東京海洋大学の寺田一薫教授(都市交通論)は「安全対策を怠っている事業者がバス業界から退出を余儀なくされるように、監査と処分をさらに強化すべきだ」と訴えている。
ガス対策、作業員に徹底せず 新潟爆発、4人の身元確認 05/28/12(朝日新聞)
情にもろいのか、単なる言い訳なのか、最悪の結果を考えず安易に判断した!陸援隊社長はかなり運が悪いと思うが、
結果を受け入れ責任を取るしかないだろう!
「助けてと言われ、おせっかいを」陸援隊社長 05/28/12(読売新聞)
群馬県の関越自動車道で7人が死亡したツアーバス事故で、県警はバス運行会社「陸援隊」社長の針生裕美秀容疑者(55)を逮捕し、「白バス」営業の強制捜査に乗り出した。
県警は、バス事故を起こした河野化山被告(43)と同社との間で違法な名義貸しが行われるなど、同社のずさんな経営や安全管理が事故の背景にあったとみて、実態解明に努める。
「助けてくれと言われたので、安易におせっかいな気持ちを持った。悔やんでも悔やみきれない」。針生容疑者は27日、金沢市で開いた被害者への説明会後に記者会見。河野被告から名義貸しを頼まれ、面倒をみるようになったと説明した。
事故原因を問われた針生容疑者は「人選ミス」と答え、違法な日雇い状態だった河野被告への管理が行き届いていなかったことを認めた。今月中旬に読売新聞の取材を受けた際も「あの運転手を選んだのが間違いだった」と話していた。
元請が悪いのか、下請けが悪いのか、両者が悪いのか知らないが、運が悪ければ死亡事故!
ガス対策、作業員に徹底せず 新潟爆発、4人の身元確認 05/28/12(朝日新聞)
新潟県南魚沼市のトンネル建設現場で起きた爆発事故で、国から工事を請け負った佐藤工業(本社・東京)が、トンネル内でガスが発生する危険性を伝えられていながら作業員らに徹底していなかったことが、同社への取材で27日、わかった。作業員は事故当日、ガス測定器を持たずにトンネル内で換気設備の点検作業をしていた。
県警は、同社のガス対策が不十分だったことが爆発事故につながった可能性があるとみて、同社北陸支店(富山市)など関連先3カ所を同日、業務上過失傷害容疑で捜索した。トンネル内で作業していた4人の死亡も確認し、死因の特定を進めるとともに、容疑を業務上過失致死傷に切り替えて調べる。
爆発事故は、国道253号の八箇峠(はっかとうげ)トンネルで24日午前10時半ごろ発生。トンネル外部にいた作業員3人が重軽傷を負い、内部で作業中だった4人と連絡が取れなくなった。爆発はトンネル内部に可燃性ガスが充満し、何らかの原因で引火して起きた可能性が指摘されている。
元請けの佐藤工業は27日、朝日新聞の取材に「国からガス発生に留意する必要があると書面で指摘を受けていたことは、事故後に確認した」と説明。一方で、事故発生まで、ガスが発生する危険性の認識は薄かったと認めた。
事故当日の換気設備の点検作業では、同社の作業員がガス測定器を持たずにトンネル内に入っていたという。同社からトンネルの換気設備の下請け工事を依頼された流機エンジニアリング(東京都)は、ガスへの引火を避ける「防爆構造」の換気設備ではなく、通常の換気設備を設置していた。
県警は、27日未明に発見した4人を、トンネル内部で作業していた4人と特定。死亡を確認した。
4人は佐藤工業の小林大輔さん(37)=千葉県市川市北方町、東部電気工業(富山市)の越井幸吉さん(57)=富山市上飯野新町、流機エンジニアリングの大谷雅之さん(39)=川崎市幸区南加瀬=と土田雄史さん(40)=横浜市鶴見区鶴見中央。
東電だけでなく他の電力会社も似たシステムかもしれない。
「東電利益9割は家庭」だから政治家達や専門家達を使いソーラーパネルを普及政策を阻止している可能性もある。
東電利益9割は家庭から…電力販売4割弱なのに 05/23/12(読売新聞)
電気料金の値上げを巡って、東京電力が経済産業省に提示した料金の収益構造の概要が22日分かった。
それによると、2006~10年度の5年間の平均で電気事業の利益の9割強を家庭向けなど「規制部門」から稼いでいる。
家庭向けの料金制度は発電コストを積み上げた原価を元に料金が決まるが、算定方法の見直しを求める声が改めて強まりそうだ。
23日に開かれる「電気料金審査専門委員会」の第2回会合で提示される資料によると、東電が販売した電力量2896億キロ・ワット時のうち家庭向けは38%、大口向けが62%だ。
売上高でみると、電気事業収入4兆9612億円のうち家庭向けは49%、大口向けは51%とほぼ同じ比率だ。
だが、1537億円の利益のうち家庭向けは91%、大口向けは9%になっている。つまり、電力量で4割弱を販売している家庭向けから9割の利益を稼ぎ出している構図だ。
東電管内は、ガス会社や石油元売りなどが特定規模電気事業者(PPS=新電力)として電力小売りを手掛けており、大口向け市場は比較的、競争が激しい。値下げを強いられるため、家庭向けで利益を確保しようとしていたとみられる。
陸援隊幹部の立件を視野 群馬県警、バス名義貸しの疑い 05/15/12(朝日新聞)
群馬県の関越自動車道で46人が死傷した高速ツアーバス事故に関連し、群馬県警がバス運行会社「陸援隊」(千葉県印西市)幹部らについて、道路運送法違反(名義貸し)の疑いでの立件を視野に捜査を進めていることが分かった。捜査幹部が明らかにした。
捜査幹部によると、自動車運転過失致死傷の疑いで逮捕された運転手の河野化山(こうの・かざん)容疑者(43)は自らもバス4台を所有。陸援隊の旅客事業者としての名義を借りて、営業していたという。国土交通省の監査でも、河野容疑者が陸援隊の名義で、中国人観光客らを相手にバスを個人で運行していたことが判明している。
道路運送法では、バスの営業には国土交通大臣の許可が必要で、許可を得た旅客事業者は名義を他人に利用させてはならない、と定められている。名義貸しに適用される罰則は同法では最も重い「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」とされている。
東電のような会社に原発を管理させるのは危険である。専門家達が原発の安全性をアピールしても、管理する会社や社員達の
危機管理能力や判断力に問題があればリスクは常に存在すると言うことだ。
海外の実例知りつつ放置 スマトラ沖地震、インド原発で津波被害 05/15/12(産経新聞)
2004年のスマトラ沖地震でインド南部にあるマドラス原発では、津波でポンプ室が浸水するトラブルが起きていた。冷却用の取水ポンプが津波で使用不能となった東京電力福島第1原発事故の約6年半前。国や東電は海外の実例を知りながら、有効な対策を取らず放置した。
津波に襲われたマドラス原発は22万キロワットの原発2基のうち1基が稼働中だった。警報で海面の異常に気付いた担当者が手動で原子炉を緊急停止した。冷却水用の取水トンネルから海水が押し寄せ、ポンプ室が冠水。敷地は海面から約6メートルの高さ、主要施設はさらに20メートル以上高い位置にあった。
東日本大震災で大津波に襲われた第1原発は、海沿いに置かれたポンプ類や地下の重要機器が浸水。原子炉冷却機能を喪失し、事故を招いた。東電関係者は「社内では津波に弱いとの共通認識だったが、まさか大津波が襲うとは思っていなかった」と話している。
間抜けな保安院!
「保安院は、こうした情報が電力会社の社内で共有されているかは確認していなかったという。」確認すべきことさえ、
確認していない税金泥棒の保安院!国民が信用しない理由を未だに理解できないのか??やはり裸の王様であり、税金泥棒だ!
「津波で電源喪失」認識 18年に保安院と東電 福島第1原発 05/15/12(産経新聞)
経済産業省原子力安全・保安院と東京電力が平成18年、想定外の津波が原発を襲った場合のトラブルに関する勉強会で、東電福島第1原発が津波に襲われれば、電源喪失する恐れがあるとの認識を共有していたことが15日、分かった。
東電は20年、第1原発に高さ10メートルを超える津波が来る可能性があると試算していたが、昨年3月の東日本大震災の直前まで保安院に報告していなかった。
保安院によると、勉強会は16年のスマトラ沖地震で海外の原発に津波被害が出たことを受け、保安院の呼び掛けで電力数社が参加して設置。18年8月に「福島第1原発に14メートルの津波が襲った場合、タービン建屋に海水が入り、電源設備が機能喪失する可能性がある」との文書をまとめていた。
保安院は、こうした情報が電力会社の社内で共有されているかは確認していなかったという。
オリンパス問題の時のように関係者達が事実を言っているのか徹底的な
事実確認が必要であろう。勝俣恒久会長が事実を言っているのであれば、誰が上層部に情報を報告しない判断を下したのか?
東電などとの合同会議の出席者リストを調べて徹底的に調べる必要がある。このような組織が原発を適切に管理できない。
能力や人材の問題よりもモラルや人間性の問題になってくる。問題がある人間達を東電から排除しないといけない。
学歴が良くても、頭が良くても重大な事実を隠蔽する東電幹部及び社員は必要ない。彼らを逮捕しても良いのではないのか??
彼らの行為が大きな被害につながっているのだから!
福島第一の電源喪失リスク、東電に06年指摘 05/15/12(読売新聞)
枝野経済産業相は15日、閣議後の記者会見で、経産省原子力安全・保安院が2006年に、福島第一原子力発電所が津波によって全電源喪失に陥るリスクがあることを東京電力と共有していたことを明らかにした。
14日の国会の原発事故調査委員会で、参考人として招致された勝俣恒久会長はこの事実について、「知らない」と回答。枝野経産相は「共有されなければ、意味がない」として、会議内容の公開も検討するとした。
枝野経産相などによると、04年のインド洋大津波で、インドの原発に被害が発生したことを受け、保安院が、独立行政法人「原子力安全基盤機構(JNES)」、東電などとの合同会議を開催。福島第一原発に高さ14メートルの津波が襲来すると、タービン建屋が浸水し、全電源喪失に陥る可能性が指摘されたという。東電は08年にも国の見解に基づき、15・7メートルの高さの津波を試算していたが、対策には生かさなかった。
車検証に記載された乗車定員以上の座席が設置されたバスは氷山の一角だろう。今回の大惨事がなければ注目されなかったと思う!
陸援隊使用のバス、定員を37席上回る座席設置 05/09/12(読売新聞)
群馬県藤岡市の関越自動車道で7人が死亡したツアーバス事故で、バス運行会社「陸援隊」(千葉県印西市)が使用するバス8台に、車検証に記載された乗車定員を計37席上回る座席が取り付けられ、国土交通省関東運輸局から指導を受けていたことが9日、わかった。
また、同局が同日実施した特別監査で、自動車運転過失致死傷容疑で逮捕された河野化山容疑者(43)が所有するバス1台で、客席5席のシートベルトが未設置だったことが新たに判明。これで河野容疑者が所有する4台のうち、シートベルト未設置が判明したのは計3台となった。
同局は2日と9日の監査で陸援隊が使用する19台のうち、事故車両を除く18台を調査。同局によると、2日に調べた11台のうち8台が、車検証に記載された乗車定員(21~49人)を1~8人上回る座席が取り付けられていた。8台のうち2台は河野容疑者が所有するバスで、定員を1~2人上回る座席が設置されていた。
規制緩和が今回の大惨事に繋がったと批判する人達もいる。規制緩和は悪いことではない。ただ、行政による監査、監督、チェック及び罰則が
甘いと違法行為、違反、そして秩序の混乱等を招く。公務員によるチェックは必要以上の規制によって行政による監査、監督、チェック及び罰則
に問題があっても大手だけに限ることにより問題として注目されなかったと推測する。大手は多少のごまかしや違法行為はあっても
大きな違法行為はおこなってこなかった。しかし規制緩和により多くの参入者に機会が与えられた。その中にはツアー会社「ハーヴェストホールディングス」や
バス運行会社「陸援隊」のような会社が存在した。行政が建前だけで業界と勉強会を行っただけでは問題は出てこない。問題を多少認識しても
専門性や知識を持たない公務員を人事異動で役職を与えても機能するわけが無い。この問題は公務員の組合の問題もあり、なかなか改善されない
だろう。しかし、橋下大阪市長のように踏み込まなければ規制緩和の弊害で起きた事故のために規制強化を行い、実際の問題は解決されていないのに
表面的には幕引きで終わるのであろう。建前だけのバス運行会社の監査は意味が無い。とにかくツアー会社の責任と罰則を強化することを優先する
べきである。その後、バス運行会社の監査を行い問題のある会社には2,3年ほど業務出来ないようにすれば良いのである。2,3年の業務停止は
会社の死活問題かもしれないが、悪質な違法行為を行い会社の消滅は仕方がないと思う。最後に行政による監査、監督、チェック及び罰則が
甘ければ、罰則規定が存在しても状況は改善されない。骨抜き状態では制度やシステムは機能しない。
関越道バス事故:陸援隊「乗務員台帳」作成せず 05/06/12(毎日新聞)
群馬県藤岡市の関越自動車道で46人が死傷した高速ツアーバス事故で、事故を起こした千葉県印西市のバス会社「陸援隊」=針生裕美秀(はりう・ゆみひで)社長(55)=が、「乗務員台帳」を作成していなかったことが国土交通省関東運輸局の特別監査で分かった。さらに河野化山(こうの・かざん)容疑者(43)=自動車運転過失致死傷容疑で逮捕=以外にもアルバイトの運転手を雇っていたことも判明。同運輸局は同社のずさんな労務管理の実態をさらに調べる。
同運輸局によると、08年の同社への監査時には運転手は16人と確認された。しかし、今回の特別監査で、雇用する運転手の氏名や健康状態などを記す乗務員台帳が見つからなかった。台帳作成は道路運送法の規則で義務づけられている。針生社長は「社員運転手は5、6人だけ」と説明。人手が足らない時には、既に日雇いだったことが判明している河野容疑者以外にも、アルバイト運転手を使用していたことを認めたという。
バス運行会社、名義貸しか…関越7人死亡事故 05/05/12(読売新聞)
群馬県藤岡市の関越自動車道で7人が死亡したツアーバス事故で、バス運行会社「陸援隊」(千葉県印西市)が、自動車運転過失致死傷容疑で逮捕された千葉市中央区新宿、運転手河野化山(かざん)容疑者(43)に、道路運送法が禁じた名義貸しを行っていた可能性のあることが、県警と国土交通省関東運輸局への取材で分かった。
県警などが詳しく調べている。
県警などのこれまでの調べで、河野容疑者は4月27日夜から28日朝にかけ、東京ディズニーリゾート(千葉県浦安市)から金沢市に客を乗せて移動した。その後、休憩したホテルで、同社の仕事とは別に、同社のバスを使った中国人向けツアーを手配していた。
関東運輸局の特別監査では、陸援隊は河野容疑者の「乗務員台帳」を作成しておらず、同社の針生裕美秀(ゆみひで)社長も、道路運送法で禁じる「日雇い」状態だったことを認めている。県警と関東運輸局は、この雇用関係が「他人」で、事業者が他人に名義を貸すことを禁じた同法違反にあたらないかを調べている。河野容疑者も、同法の無許可営業にあたる可能性があるとみている。
「同局関係者は『挙げたらきりがないほどの違反が見つかった』と話している。」
ここで行政、監督及び監査するほうにも問題があることが明らかだ。挙げたらきりがないほどの違反をしている会社が野放しになっている。
このような違反する会社が存在するにもかかわらず、元請の旅行会社に対して罰則規定がない。この事実も問題視されていなかった。
国交省はバス業界などとの勉強会を持ちながら違反するバス会社の情報を収集していなかったのか、情報を把握しながら業界に配慮したのか
知らないが、結果として適切な対応を取っていない。
違反している零細バス会社はたくさん存在すると思う。国交省はどのように対応しているのか?バス事業に関しては知らないが、
国交省の他の分野では情報の管理が出来ていない、国際条約と国内法の理解が不十分、検査が不適切などの問題を抱えている。
ざるのような検査が行うのであれば、出来ない職員に検査を行わせずに、自宅待機にして検査を適切に行える職員の給料を増やすべきだ。
問題が存在するのに検査で指摘できないような検査しか出来ない職員は税金の無駄。問題があれば職員の数が限られているとか言うが、
まともに検査が出来ない職員は辞めてもらうしかないのではないか。検査の意味が無い。最初はひやひらする会社もいると思うが、
そのうちに問題は見つけられないと思うようになる。そして違法行為を続ける。これでは人件費と時間つまり税金の無駄である。権限を持っていても、
適切に行使できなければそのような職員など必要ない。まともにやっている職員の士気を下げるだけなので辞めてもらうべきである。
民主党と同じで必要ない。屁理屈はもういい。結果を出してほしい。
関越道バス事故:「陸援隊」に多数の法令違反…運輸局監査 (1/2ページ)
(2/2ページ)(産経新聞)
群馬県藤岡市の関越自動車道で7人が死亡した高速ツアーバス事故で、バス会社「陸援隊」(千葉県印西市、針生裕美秀<はりう・ゆみひで>社長)に多数の法令違反があったことが2日、国土交通省関東運輸局の特別監査で分かった。同省規則で義務づけられている運行指示書を作成せず、乗務前に運転手の健康状態を確認する「点呼」も実施していなかった。針生社長が同局の聴取に対し認めた。
関東運輸局は2日、4月30日に続いて2回目の監査を行い、針生社長からも事情を聴いた。同局は安全管理面で重大な違反が常態化していた疑いもあるとみて、乗務記録などを精査し運行や労務管理の実態を調べる方針。
同局関係者によると、針生社長は運行ルートや休憩場所を記載した運行指示書を作成せず、自動車運転過失致死傷容疑で逮捕された運転手の(河野化山こうのかざん)容疑者(43)に対し、東京ディズニーランド(千葉県浦安市)に着いた後、旅行会社「ハーヴェストホールディングス」(大阪府豊中市)から行程表を受け取るよう指示していたという。また、運転手が遠隔地にいる場合は電話で点呼を実施する義務があるが、それも行わず点呼簿も作成していなかったという。
さらに、事故を起こしたバス以外の運行指示書も一部保存されておらず、乗務時間などを定めた国交省の基準に違反しているケースも認められた。営業所には乗務員の経歴などを記録した乗務員台帳が見つからず、安全教育を怠っていた疑いも浮上。同局関係者は「挙げたらきりがないほどの違反が見つかった」と話している。
一方、成田労働基準監督署は2日、「陸援隊」の勤務実態を調べるため3回目の調査に入った。千葉労働局によると、調査には針生社長が初めて立ち会い、労働基準法が定めた労働時間を超える勤務実態がなかったかなどを聴いた。同署は今後、河野容疑者への聴取も検討する。【一條優太、田中裕之】
まぬけな国交省!高学歴のキャリアがいても質問や説明を求めることも出来なかったと言う事だろう。「バス業界などとの勉強会で『変更の必要がない』との意見が出た」
時に理由を聞いたのか?理由を聞いたのであれば納得できる説明だったのか?適切な理由があれば、事故により7人死亡、そして3人重体であっても
見直しをする必要はない。事故が起きたことにより見直しと言うことは、業界よりの勉強会であったと言うことではないのか??将来の天下り先の
確保のために妥協しているのか?
走行上限670キロ、基準見直し検討 国交省 05/02/12(読売新聞)
関越自動車道の高速ツアーバス事故を受け、国土交通省は1日、670キロとされている運転手1日あたりの走行距離の上限などを定めた指針や、「運転は1日9時間まで」などと定めた国の基準を見直す検討を始めた。今月中にも、バス業界や医療関係者らによる有識者会議を設置する。
国交省によると、現在の上限は大阪府吹田市で平成19年に27人が死傷したスキーバス事故の翌年に施行した指針で示されている。
指針をめぐっては、総務省が21年に貸し切りバス運転手136人を対象に調査を実施。9割近くが運転中に睡魔に襲われた経験があると回答したため、22年9月に「運転者の健康面や生理学的な面を検討して算出されていない」と国交省に改善を勧告した。
しかし、同省はバス業界などとの勉強会で「変更の必要がない」との意見が出たため、見直しを先送りしていた。同省は「上限距離の変更より、事後チェックで指針が守られているかを重視した」と説明している。
事故を起こしたバスは、最短運行距離が約540キロだった。このため、国交省は上限見直しに方針を転換した。
また、同省が運転手の勤務時間や乗務時間に関して告示した「最大拘束時間は1日16時間まで」「連続運転は4時間まで」などの基準の変更も検討する。
同省は「事故原因の調査状況も踏まえた上で、なるべく早く方向性を出したい」と話している。
「河野容疑者は中国残留孤児の子弟とみられ、平成5年に来日、翌6年に日本国籍を取得したと供述。」
中国人が皆悪いと思わないけど文化や仕事に対する考え方が問題だ。日本語が不自由なら運転免許は取れても
日本人と同じように道路標識やその他の指示を理解できたかも疑問。中国残留孤児の問題がこんな形で注目を集めるとは思わなかった。
仕事で名刺には日本人名なのに話し方が外国人としか思えない人に会った事がある。たぶん、中国残留孤児関係で日本国籍を取得したんだろうな!
高速バス衝突 河野容疑者、これまで事故なし 05/01/12(イザ!)
「申し訳ない。事故を起こした。自分は挟まって出られない」
4月29日午前4時40分の事故発生直後、河野化山容疑者(43)は、バス会社「陸援隊」の針生裕美秀社長(55)に携帯電話で報告した。針生社長によると、河野容疑者はバス運転経験の中で、大きな事故は一度もなかったという。
群馬県警によると、河野容疑者は中国残留孤児の子弟とみられ、平成5年に来日、翌6年に日本国籍を取得したと供述。日本語は不自由で、通訳を介して取り調べが行われているという。旅客用の大型2種免許は21年7月に取得していた。河野容疑者を知る人によると、妻も中国人で、娘ら子供にも恵まれていたという。
妻は千葉市内で中華料理店を開いていたが、河野容疑者本人が店に立つことはなく、近隣女性は「(河野容疑者は)『(店とは)別の仕事をしている』と(妻が)話していた」と話す。
河野容疑者は事故で内臓損傷の重傷を負い、前橋赤十字病院に入院していたが、県警によると、病室では自由に歩くことも可能だった。1日午後4時過ぎ、病室で逮捕された。その後、救急患者搬送口から、捜査員に付き添われ、ワゴン車に乗り込んだ。紺色のパーカーに黒いズボン、黒のサンダル姿。フードを目深にかぶり、表情をうかがうことはできなかった。
バス事業のあり方検討会委員名簿
学識経験者竹内健蔵東京女子大学教授(座長)
若林亜理砂駒澤大学教授
加藤博和名古屋大学准教授
有識者秋池玲子ボストンコンサルティンググループ
パートナー&ディレクター
和田由貴夫バスラマ・インターナショナル編集長
業界関係者小田征一(社)日本バス協会理事・高速バス委員長
(京成バス(株)代表取締役会長)
富田浩安(社)日本バス協会理事・貸切委員長
(日の丸自動車興業(株)代表取締役社長)
上杉雅彦(社)日本バス協会理事・地方交通委員長
(神姫バス(株)代表取締役社長)
興津泰則(社)日本旅行業協会国内・訪日旅行業務部長
有野一馬(社)全国旅行業協会専務理事
(島崎有平(社)全国旅行業協会専務理事)
村瀬茂高高速ツアーバス連絡協議会会長
(WILLER TRAVEL(株)代表取締役)
成定竜一高速ツアーバス連絡協議会顧問
(高速バスマーケティング研究所㈱代表取締役)
鎌田佳伸全国交通運輸労働組合総連合
軌道・バス部会事務局長
清水昭男日本私鉄労働組合総連合会交通政策局長
佃栄一日本鉄道労働組合連合会自動車連絡会特別幹事
行政関係者坂明国土交通省大臣官房審議官(自動車局)
(門野秀行国土交通省大臣官房審議官(自動車交通局)
河田守弘国土交通省自動車局総務課長
(加藤隆司国土交通省自動車交通局総務課長)
三上哲史国土交通省自動車局安全政策課長
(渡辺秀樹国土交通省自動車交通局安全政策課長)
鈴木昭久国土交通省自動車局旅客課長
(舩曵義郎国土交通省自動車交通局旅客課長)
(石﨑仁志国土交通省自動車交通局旅客課長)
(新田慎二国土交通省大臣官房参事官(自動車交通局))
廣瀬正順国土交通省自動車局旅客課新輸送サービス対策室長
秋田未樹関東運輸局自動車交通部長
(小林豊関東運輸局自動車交通部長)
鶴田浩久観光庁観光産業課長
(鈴木昭久観光庁観光産業課長)
井上剛志警察庁交通局交通企画課長
(入谷誠警察庁交通局交通企画課長)
この中に天下りのOBがいるのか知らないが、国交省の審議官、部長及び課長が委員となっている。
「1日当たりの運転時間の上限(9時間)に相当する乗務距離の上限は670kmとする」に関して誰も疑問に思わないのか?
「バス事業のあり方検討会」報告書 平成24年3月30日(国交省)
「バス事業のあり方検討会」報告書 平成24年3月30日(国交省)
高学歴の国交省幹部やキャリアは試験に通った事実と高学歴である事実以外には適切な判断をする能力がないと言うことか?
それとも業界からの接待やゴマすりでまともな判断が出来ない状態なのか?
「この指針は、法律に基づく決まりではなくあくまで参考にすべきものとされていて、670キロという数字も『1日当たりの運転時間が9時間を
超えないこと』という法律の決まりを基に、全国のバス業者から提供された実際の運行データから算出されています。」
法律の改正が必要なのか検討さえもしないのか?国交省キャリアが常識を持ち合わせていない事を意味しているのではないか?
運転時間が9時間と言っても、休憩時間を何時間とって9時間の運転になるのか?渋滞が頻繁にある道路では疲労する度合いが違う。
専門家とかドライバーに質問したりアンケートをとる事さえも思いつかなかったのか?こんな状態じゃ、LCCも危ないかもしれない。
厚生労働省は多くの問題を抱えているが、国交省も問題を抱えているのは明らかだ!
貸し切りバス 上限670キロ見直しへ 05/01/12(この国を考える)
670キロの指針 見直し検討へ 05/01/12(NHK)
群馬県の関越自動車道で大型バスが道路脇の壁に衝突して乗客7人が死亡、39人が重軽傷を負った事故で、国土交通省は、長距離を走るバスが交代の運転手を乗せる目安の距離を670キロとした指針などを見直す方向で検討していくことを決めました。
国土交通省は、現在、貸し切りバスの走行距離が670キロを超える場合は交代の運転手を乗せるという指針を定めていますが、今回事故を起こしたバスの走行距離は545キロで、交代の運転手は乗っていませんでした。
この指針は、法律に基づく決まりではなくあくまで参考にすべきものとされていて、670キロという数字も「1日当たりの運転時間が9時間を超えないこと」という法律の決まりを基に、全国のバス業者から提供された実際の運行データから算出されています。
この指針を巡っては、2年前に総務省が「運転手の健康面や生理学的な面での検討を行ったうえで算出されたものではない」などとして、改めるよう勧告しています。
また、今回の事故を受けて「より厳しく見直すべきだ」という意見が出ていることをから、国土交通省は、670キロの指針とその基になっている1日9時間の運転時間などの法律に基づく基準を見直す方向で検討していくことを決めました。
今後、バス業界や労働組合、学識経験者などを集めて検討する方針です。
国土交通省自動車局の谷川仁彦事故防止対策推進官は「重要なのは670キロの見直しだけでなく、法令基準の1日9時間が妥当であったかを含めて考える必要がある。走行距離と運転時間の両方の見直しに向けて検討していきたい」と話しています。
「ツアー会社への取材で、バスが『運行指示書』とは違う遠回りのルートを使っていたことが判明したほか、一部の乗客のシートベルトに
不具合があったことも分かった。(サンケイスポーツ)」
「運行指示書」は厳守だったのか?それとも結果として遠回りのルートを取っていたから疲労が増したとツアー会社は言いたいのか?
個人的な長距離運転から言えば、30~50キロの違いは大したことは無い。それよりも道路の渋滞状況、道路の運転しやすさ(カーブが少ない、
アップダウンがあまりない等)、一車線なのか2車線なのか、通行している高速道路を頻繁に通ったことがある(どちらの車線にいるべきかも
わかるので、気持ち的に楽。カーナビはあくまでも位置確認及び推定到着時刻の確認程度で必要ない)かも重要。
しかも連休は渋滞や道路状況が平日とは比べ物にならないほど酷い。運転が下手なドライバーも多いし、平日以上に前方に注意を払わなければならない。
ツアー会社「ハーヴェストホールディングス」は運行指示書を作成していたのであれば道路状況とか、道路状況により他のルートへの変更、
リアルタイムの道路状況をチェックし、指示するようにしていたのか?運行指示や運行管理とはどこまでなのか?交通事故なので渋滞になった
場合、いつ閉鎖が解除されるのか、他の高速道路に迂回できるのかインターネットでチェックしてもらうように頼むことがある。運転しながら
リアルタイムの状況チェックなど出来ないからだ。頼むことが出来ない場合、感で判断するか、最悪の場合、どの選択が良いかを判断する。
道路閉鎖の解除が思ったよりも早く、待っていたほうが良いと思うこともあった。
厳しい規則や罰則があっても、監督やチェックが甘ければ本来の目的は達成されない。違反するケースが多いからだ。この点では行政 (国土交通省)
の責任は重い。元請が悪質な場合、下請けは仕事を請けるかの選択を迫られる。この点ではある程度の規則と監督及びチェックが必要だ。
元請と下請けの両方の問題があることもある。この場合、行政 (国土交通省)がしっかりしなければ安全は保たれない。なぜなら、元請と下請けの両方が
規則を守らないし、口裏を合わせる可能性もあるからだ。このようなケースでは、監督及びチェックそして罰則が必要だ。
「運行指示書」とは違うルートで遠回り (1/2ページ)
(2/2ページ)(産経新聞)
群馬県藤岡市の関越自動車道で7人が死亡した高速ツアーバス事故で群馬県警は30日までに、自動車運転過失致死傷容疑で河野化山(こうの・かざん)運転手(43)の逮捕状を取った。同日にバス会社などを家宅捜索。ツアー会社への取材で、バスが「運行指示書」とは違う遠回りのルートを使っていたことが判明したほか、一部の乗客のシートベルトに不具合があったことも分かった。(サンケイスポーツ)
楽しいはずの大型連休が暗転し、7人の命が奪われた事故。河野運転手自身も重傷を負って入院しているため、群馬県警は回復を待ち逮捕する。
県警は同日、千葉県印西市のバス会社「陸援隊」と、同じ敷地内にある針生裕美秀(はりう・ゆみひで)社長(55)の自宅を家宅捜索。事故車両も一部復元して実況見分し、座席を並べて衝突時の詳しい状況を調べた。
ツアー会社「ハーヴェストホールディングス」(大阪府豊中市)によると、「運行指示書」には上信越自動車道を通るルートが書かれていたことも判明。県警は押収した運行記録計を分析するとともに、勤務日報や就業規則から管理上の問題がなかったかどうかや、遠回りになる関越道ルートを使った理由を調べる。
同社によると、走行ルートは運行指示書に記載しているが、天候や道路の状況などから運転手の判断による変更を認めており、連絡も必要としていなかった。針生社長はハーヴェスト社に「なぜ関越道を行ったのか分からない」と話している。
国土交通省関東運輸局は30日、陸援隊の特別監査に入り、近畿運輸局もハーヴェスト社を特別監査した。
一方、事故で後頭部を十数針縫うけがを負った乗客の大学4年生、香林聡志さん(22)=金沢市=が、座席のシートベルトが壊れていて装着できなかったと話していることが30日、家族への取材で分かった。
母親の真実さん(47)によると、香林さんは10列目の右窓側の席におり、「(事故発生直後に)気が付くとバスの床に倒れていた。シートベルトを締めていたら飛ばされなかったはず」と話したという。
香林さんは千葉県で友人と会うため、バスに乗り事故に遭遇。29日夜に金沢市に戻った。事故後、ほかの乗客と会話した際に「運転手は休憩中に突っ伏して寝ていた」という話が出ていたという。
バスは28日夜、JR金沢駅を出発し、約400キロ離れた関越道藤岡ジャンクション付近を通過していた29日午前4時40分ごろ、左側の鋼板製の防音壁に正面から衝突。男女7人が死亡し、女性3人が重体、運転手を含む36人が重軽傷を負った。
国土交通省の担当者はなぜ
貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視 結果報告書 平成22年9月(総務省)
を反映した対策を取らなかったのかコメントするべきだ。改善しない理由があるならはっきりと国民に伝えるべきだ。
国土交通省の担当者が間違っているのか、それなりに支持できる理由があるのか公表するべきである。担当者が間違っていれば
間違っていることが公になることでこれから担当者なる職員の真剣度も変わってくるし、なぜ間違った判断が指摘されなかった
経緯も調査できる。業界団体からの献金や圧力があったのか、この点も含めて公表するべきだ。
バス運転中の睡魔9割 総務省の乗務改善勧告生かされず 05/01/12(朝日新聞)
総務省が貸し切りバス運転手を対象に行ったアンケートで、9割が睡魔に襲われたり、事故に繋がりかねない経験をしていたと答えたことが分かった。
総務省は運転手の平均運転距離を短縮する勧告を行なっていたが、改善はされなかった。
参考資料:
貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視 結果報告書 平成22年9月(総務省)
貸切バスの安全確保対策に関する行政評価・監視 結果報告書 平成22年9月(総務省)
貸切バス 安全指導勧告 09/10/10(この国を考える)
形だけの安全対策なのか?
事業用自動車総合安全プラン2009 事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会(国交省)
事業用自動車総合安全プラン2009 事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会(国交省)
法令なんかあっても罰則が軽ければ法令順守などしないほうが徳だ!悪い奴らが得をする制度にしたらだめだ!
罰則は重くするべきだ!国交省の監査が甘くてもだめ、新規参入の際の審査を厳しくしても審査に通ったらマニュアルを
守らない可能性も高い、抜き打ちのチェックも必要だ。審査は厳しくなくても良いが、常識の範囲であれば良いと思う。
しかし抜き打ちのチェックは必ずする事だ。ただ、PSCの検査のような
レベルだったら問題がざるの穴を通るように見逃されて通っていく。世の中の全てを見ることは出来ないが、公務員の検査は
時にたいした事でもないのに規則と言いながら、大きな問題や本当に指摘されなければならない相手を見逃す傾向にあると思う。
ピーチの〝光と影〟浮き彫りに 就航から1カ月、30日も4便欠航 (1/2ページ)
(2/2ページ)(産経新聞)
今回事故を起こした高速バスは定期の路線バスと異なり、旅行会社が観光バスを借り上げて運行する「ツアーバス」だった。格安を売りに人気を集め、年間利用者は600万人。一方で過当競争による過酷勤務などから重大事故も起きており、国土交通省はツアーバスに路線バスと同じ法令を適用するよう方針転換したばかりだった。国交省は29日、日本バス協会などに大型連休中の安全確保を徹底するよう通達した。
業界団体「高速ツアーバス連絡協議会」によると、ツアーバスは、運行を企画・実施する旅行会社が、主にインターネット上の販売会社を通じて乗客を募集し、運行は貸し切りバス会社へ委託する仕組み。定期の路線バス会社の高速バスが道路運送法の適用を受けるのに対し、ツアーバスは旅行業法が適用される。
平成12年からの規制緩和により一気に普及した。17年に21万人だった利用者は22年に600万人と5年で30倍に。閑散期でも全国で1日200台前後が運行され、大型連休など繁忙期はその数倍に増便される。
今回のバス料金は金沢-浦安で3500円と、特急と新幹線を乗り継ぐより1万円近く安い。関西大学の安部誠治教授(公共事業論)は「何より値段が安く、快適なサービスも増えて人気が出た。だが、過当競争で旅行会社はチケットを安売りし、そのしわ寄せでバス会社に無理が行きがちとなる」と話す。
19年2月には大阪府吹田市でスキー客を乗せた長野県のツアーバスが事故を起こし、乗客ら27人が死傷。大阪地裁は運転手が過労状態だったと認定した。事故を受け、国交省はバス会社に対し1日当たりの勤務を9時間、670キロまでとするなど安全策を強化した。
一方で、貸し切りバス会社は11年度の2336社から22年度の4492社へ倍増。行政処分も18年の237件から昨年は過去最高の625件に増えた。バス会社の関係者は「過当競争で旅行会社からの無理な金額設定を断れず、法令順守など安全対策がおろそかになっている零細のバス会社も多い」と打ち明ける。
連絡協議会は吹田市の事故を受け20年に設立され、旅行会社の加入率はハーヴェスト社を含む39社でほぼ100%だが、バス会社の加入はわずか18社で陸援隊も非加入だった。協議会は「バス会社は運行期間も定まらず全体を把握できない」。国交省幹部は「路線や料金設定など届け出の必要がないため、運行実態さえ分からない」と話す。
国交省は今月から、ツアーバスにも路線バスと同じ道路運送法を適用するよう方針転換。旅行会社も乗客への安全義務を負うほか、バス会社の監督も求められ、監査も受ける。バス会社に対しても、新規参入の際の審査や法令順守の事後チェックを強化する。
安部教授は「今回の会社が法令を守っていなかったなら監査体制が不十分だったことになる。ツアーバスという仕組みそのものに問題がなかったかも検証する必要がある」と指摘する。
今回の事故は格安の追求、行政の監督及び管理問題、そしてツアーの選択者の判断問題が最悪の結果となっただけで多くの死者が出たので
残酷な意見と言われるが大した問題ではない。多くの死者や事故が無いだけで同様のリスクは日本の社会にはたくさんある。今人気の
LCCだって行政のチャック体制が甘いと運が悪ければ同様の悲劇はある。国土交通省は業者の免許制や罰則を検討していたそうだが、
遅すぎた。大飯原発の問題だって免震塔やベントフィルターの工事が完了するまで事故が100セント起こらないと誰も保証出来ない。
事故が起きた時に野田首相の政治判断は間違っていたと言われるだけで、強引に押し売りのように進めたほうの勝ちだ!
長距離運転の経験から言えるが、1人だと400キロ以上の運転だと2人の方が良いだろ。眠気が襲ってきたらどうしようもない。
少しぐらいの眠気ならなんとかなるが、目を開けてられないほどの眠気だと対応できない。プロの運転手であれば高速道路の運転、
車線変更やインターチェンジでの車線変更はなれているのであまり疲れないのかもしれない。しかし同じ人間だから、ひどい眠気に
襲われた時は同じだと思う。カーナビで5時間で到着するコースを仮眠を取りながら運転したので9時間かかったことがある。
到着時間が指定されている高速バスであれば必要以上の休憩や仮眠は取れないからひどい眠気を感じた時はとにかく走るのであろう。
今までに高速バスの居眠り運転による事故はあったが、これほどの大事故がなかったので対応が遅れたのだろう。
大事故が起きなければ行政は迅速に対応しない。学歴だけのキャリアは現実を知ろうとしないのであろう。業者の登録制及び罰則の強化は当然だ。
また、バス会社を選択する旅行会社の責任及び罰則も含むべきだ。旅行会社は選択するバス会社の運航状態を確認をする責任はある。
「相手に任せていた」と言い逃れをさしてはならない。もちろん、バス会社が虚偽の情報を報告した場合にはどうしようもない。しかし、
もしかしたら問題があっても、安全や現実を考えずに事故が起きたらバス会社に責任を負わせれた良いと安易に考え、値段だけで選択する会社には
責任とリスクを認識させて責任と罰則を負わせるべきである。このようにしても事故は防げないが、責任とリスクを認識した上で、
リスクを負う会社は少なくなるはずである。死んだ人は帰ってこないが、会社及び責任者達には少なくともそれなりの責任を取らせるべきだ。
「法令上の問題なし」と旅行会社 04/29/12(産経新聞)
群馬県の高速バス事故で、ツアーを手配した旅行会社「ハーヴェストホールディングス」は「バスの運行状況に法令上問題はない」との認識を示した。
事故は29日午前4時40分ごろに発生。群馬県藤岡市岡之郷の関越自動車道藤岡ジャンクション(JCT)付近の上り線で、金沢市から東京に向かっていた高速バスが左の側壁に激突。バスは大破し、乗客乗員46人のうち7人が死亡し、2人が意識不明の重体。11人が重傷、25人が軽傷を負った。
男性運転手(43)=千葉市中央区=もけがをして病院に搬送された。
運転手の休憩取得、把握できず~旅行会社 04/29/12(日テレNEWS24)
29日早朝、群馬・藤岡市の関越自動車道で長距離バスが道路の側壁に衝突して乗客ら46人が死傷した事故で、ツアーを主催した大阪・豊中市の旅行会社「ハーヴェストホールディングス」は「バスの運転手には、2時間ごとに休憩を取るように文書で申し入れていて、法的に問題はない」と主張しているが、実際に運転手が休憩を取っているのかは把握できていないという。
ツアーの企画はハーヴェストが行っているが、参加者の募集は自社のホームページや旅行サイトに委託していた。バスの運行も千葉・印西市のバス会社「針生エクスプレス」に委託していて、いわば、インターネットを介して客に顔を合わせることなく中間的にツアーを行っていたことになる。
このようなことから、ハーヴェストでも、ツアーを申し込んだ代表者の氏名や連絡先がすぐにわかるのは自社のホームページから申し込んだ10組15人分だけということで、残りの30人はサイト運営会社に問い合わせて連絡先を聞くなど、情報把握に苦慮している。
また、針生エクスプレスには去年からバスの運行を依頼しているということで、ハーヴェスト側は「2時間ごとに休憩を取るように文書で申し入れていて、法的に問題はない」と主張しているが、実際に運転手が休憩を取っているのかは把握できていないという。
ハーヴェストは、現在は13組の乗客と連絡がつき、謝罪と今後の対応について話したということで、引き続き情報収集に努めて対応していきたいと話している。
廃材を壁の間に不法投棄、大工ら7人を書類送検 04/13/12(読売新聞)
千葉県のアパートで内壁と外壁の間に廃材が押し込めるようにして捨てられていた事件で、県警は13日、工事を担当した大工の男7人を廃棄物処理法違反(不法投棄)容疑で千葉地検に書類送検した。
県警は昨年7月、大手住宅メーカー「積水ハウス」の県内の支店を同容疑で捜索していたが、「具体的関与を確認できなかった」(捜査幹部)として立件を見送った。
捜査関係者によると、30~70歳代の大工7人は2007年12月~10年6月、東京都内や千葉県内でアパートの建設工事にそれぞれかかわった際、石こうボードや木材などの廃材を、建物の外壁と内壁の隙間に押し込めるなどして捨てた疑い。
「同省によると、同社側は調査に対し『福島などと表示して販売しづらかった』と話しているという。」
福島産だと販売しづらいは言い訳だ。福島産が売れないのであれば、仕入れしなくて良い。安い福島産牛肉を
鹿児島産牛肉と信じて買う消費者をばかにしている。消費者が福島産牛肉を買わないのは消費者の選択する権利だ。
福島の酪農農家が困っているのなら、東電が補償するべきだ。幹部や社員のボーナスをゼロにしても補償するべきだ。
福島と表示、販売しづらい…鹿児島産牛肉と偽装 04/12/12(読売新聞)
福島県産牛肉などの産地表示を偽装して販売したなどとして、農林水産省近畿農政局は13日、食肉販売業「AMMS」(兵庫県伊丹市)に対し、JAS法に基づく表示の改善指示を行った。
同省によると、同社側は調査に対し「福島などと表示して販売しづらかった」と話しているという。福島第一原発事故後、福島県産牛肉で産地偽装が明らかになるのは初めて。
発表では、同社の福田屋此花店(大阪市)は昨年9月~今年2月、福島県産約750キロを含む東北、関東産の牛肉など少なくとも1424キロについて、鹿児島県産などに産地を変えて販売したという。匿名の通報を受けて立ち入り調査を行った結果、明らかになった。
ほぼ全量が消費されていたが、いずれも厚生労働省が昨年、放射性セシウムに汚染された稲わらを食べたとして公表した牛には該当せず、国の規制値を上回る放射性セシウムを含む牛肉も見つかっていないという。
牛肉の個体識別番号偽装、関係先数か所を捜索 04/12/12(読売新聞)
国産牛肉の個体識別番号を長野県産黒毛和牛のものに偽装して出荷したとして、長野県警は12日、協同組合信州ミートパッカー(長野県佐久市)と同組合に食肉処理を委託している信州ハム(同県上田市)など関係先数か所を不正競争防止法違反(誤認惹起(じゃっき)行為)の疑いで捜索した。
脱税:6900万円、容疑で豚肉卸売の京都パッカーを告発--大阪国税局 /京都 03/30/12(毎日新聞)
法人税約6900万円を脱税したとして、大阪国税局が豚肉卸売会社「京都パッカー」(京都市山科区)と同社の野本健一社長(60)を法人税法違反容疑で京都地検に告発していたことが29日、分かった。重加算税を含む追徴税額は約9400万円で、既に修正申告したという。
関係者によると、同社は架空の仕入れ代や商品の運送代を計上するなどの手口で所得を少なく見せかけていた。09年2月までの2年間で、約2億3000万円の所得を隠した疑いが持たれている。【牧野宏美】
ピーチの〝光と影〟浮き彫りに 就航から1カ月、30日も4便欠航 (1/2ページ)
(2/2ページ)(産経新聞)
4月1日で運航開始から丸1カ月を迎える日本初の格安航空会社(LCC)ピーチ・アビエーションは、長崎空港で起きた客室乗務員の操作ミスにより29日に続き30日も4便が欠航する。少ない機材をフルに運行するため、トラブルや整備の遅れが欠航の連鎖につながるLCC特有のリスクが露呈した形だ。ピーチは割安な運賃で平均搭乗率8割程度と好調を維持しているが、初の運行トラブルはLCCの“光と影”を浮き彫りにした。
今回のトラブルでは、28日午前に長崎空港を出発前の機体で、乗務員が誤って緊急時の脱出用スライド(滑り台)を作動させ、機体の修復が必要となった。航空関係者は「頻繁に起こるトラブルではない」としており、発足間もないLCCにおける乗務員の習熟度向上も課題となった。
トラブルが起きた長崎線は25日に就航したばかり。誤操作のあった28日は長崎-関西国際空港線が3便欠航し、29日は同じ機材を使う予定だった関空-長崎線と関空-福岡線の計6便が欠航。30日も同4便の欠航が決まっており、さらに福岡線1往復にも欠航の可能性があるという。
ピーチは現在3機で3路線を運行しており、機体トラブルに備えた予備機を保有していない。このため、欠航本数の増加や長期化につながっている。
格安運賃のため乗客は他社便への振り替え措置も受けられない。ピーチは自社の別便に振り替えるか返金で対応している。現時点では大半の利用者が返金に応じており、大きな混乱はないというが、LCCのデメリットが明確になった。
一方でピーチの搭乗率は運行開始以降、平均で80%前後を維持している。搭乗率が80%を超えると、「予約する側にとっては満席に近い状態に感じられる」(国土交通省関係者)とされており、滑り出しは上々だ。
8月下旬以降の台風シーズンには悪天候による欠航も予想されるだけに、利用客にとっては運賃の安さの“代償”を冷静に見分け、受け止める姿勢が求められそうだ。
組織の体質は簡単には変わらないのであろう。
「会社は『板金工場に専用のクレーンがあり、作業を任せてしまった』と説明しているということです。」
なぜ「専用のクレーン」がラックの分解整備を法律上の資格がない外部板金工場にあるのか?必要がないものが板金工場にあって、
認定工場にはないのか??資格がない工場が分解整備が出来ないのは「常識」ではないのか?認証工場で働いている従業員は
誰一人も気付かなかったのか?人件費を抑制するために大手トラックメーカー「三菱ふそうトラック・バス」の長崎県にある工場では
低学歴の従業員を採用しているのか?常識のある人なら単なる間違いじゃないことぐらい分かると思う。
「これについて、会社は違法行為を全面的に認めたうえで『真摯(しんし)に受け止めて再発防止に努めます』と話しています。」
公務員の言い訳と同じ。口先だけで何とでも言える。重要なのは実行し、結果を出すこと。三菱だけじゃないかもしれないが、
三菱は未だに「安全ではない」と言うことになるのだろう。
違法整備 三菱ふそう工場処分へ 03/22/12(NHKニュース)
大手トラックメーカー「三菱ふそうトラック・バス」の長崎県にある工場が、トラックの分解整備を法律上の資格がない外部の板金工場にさせたうえ、整備記録には自社で整備したとうその記載をしていたことが分かりました。
国土交通省は23日にも道路運送車両法違反で工場を処分するとともに、本社に対して業務の改善を指示する方針です。
違法な整備をしていたのは、神奈川県川崎市に本社がある「三菱ふそうトラック・バス」の長崎県諫早市の工場です。
国土交通省と会社によりますと、この工場は去年10月、部品の強度不足のリコールで持ち込まれたトラックの分解整備を法律で定められた「認証工場」の資格がない近くの板金工場にさせていました。
整備後のトラックはボルトが適切な強さでしめられていなかったうえ、工場は、整備記録に自社で整備したとうその記載をしていました。
これについて、会社は「板金工場に専用のクレーンがあり、作業を任せてしまった」と説明しているということです。
さらに、この工場ではヘッドライトの明るさが基準に達していないバスの整備記録にうそを書いて車検を通すなど、去年12月までの1年間に少なくとも3件違法な車検を行っていました。
国土交通省は、23日にも道路運送車両法に基づいて諫早市の工場に対して、分解整備ができる資格などを一定期間停止にするとともに「三菱ふそうトラック・バス」本社に対しても業務の改善を指示する方針です。
これについて、会社は違法行為を全面的に認めたうえで「真摯(しんし)に受け止めて再発防止に努めます」と話しています。
増資インサイダー:野村証券が社内調査着手 情報管理検証 03/23/12(毎日新聞)
国際石油開発帝石の公募増資を巡るインサイダー取引問題で、営業員による情報漏れを起こした野村証券が内部調査に着手したことが22日、わかった。野村証券は増資を担当した主幹事の1社。インサイダー情報が漏れないために、社内で適切な情報管理体制が構築されていたかが焦点となる。同社は4月にも事実関係を確認した上で、情報管理のあり方を検証する方針だ。【田所柳子、浜中慎哉】
証券取引等監視委員会などによると、中央三井アセット信託銀行のファンドマネジャー(運用担当者)が、野村の営業担当者から増資の情報を得て、国際帝石株を空売りした。情報を漏らした野村側は金融商品取引法違反(インサイダー取引)に問われないが、本来なら、増資の引き受け部門から営業部門に未公開情報が流れない仕組みを整える必要がある。
証券会社の情報管理体制を巡っては、業界団体の日本証券業協会が10年7月、業務で入手した企業情報がむやみに広がらないための自主規則を導入。08~09年に野村やカブドットコム証券でインサイダー取引が発覚したためで、「法人担当部門を他の部門から物理的に隔離」「法人関係情報の電子ファイルを容易に閲覧できなくする」などを求める。守らないと、最大5億円の過怠金などを科す。
もっとも、日証協の規則導入以前から、未公開の企業情報を持つ法人部門と、投資家に株式や投資信託の売買を勧める営業部門は「チャイニーズウオール」と呼ばれる壁を設けるのは世界の常識だ。中国の「万里の長城」を指し、越えがたい壁を意味するもので、ある国内証券会社は、M&A(企業の合併・買収)の案件を話す時は、企業名を符丁で呼ぶルールがある。法人部門と営業部門の社員は入館証を別にし、互いのオフィスに出入りできないようにしている社もある。
とはいえ、現役の証券会社員は「社員同士の個人的なつながりまでは遮断できない。情報のやり取りも、私用の携帯やメールまではチェックされない」と限界を指摘する。
また、増資決定前に主幹事の証券会社が機関投資家の需要を探る「プレヒアリング」による情報漏れを疑う声もある。プレヒアリングも日本証券業協会が07年1月から規則で禁止し、国内証券各社も「やっていない」と口をそろえる。だが、元法人営業担当社員は「2~3年前には『客がどれくらい買うか知らないと仕事にならない』という空気で、プレヒアリングは横行していた」と指摘。国際帝石の増資と前後して、日本板硝子や東電の増資でも株価の不自然な動きがあった。
これらの問題を巡り、22日の参院財政金融委員会では「日本市場の慣行と思われないよう、しっかり対応すべきだ」(大久保勉参院議員)との声が上がった。金融庁の細溝清史監督局長は「証券会社の情報管理体制に問題が認められれば適切に対処する」と説明。金融庁は野村の情報管理体制に問題がないか、聞き取り調査に着手、問題があれば業務改善命令などの行政処分に踏み切る可能性がある。
◇日証協の法人情報管理の主な規則◇
・社内に情報管理部門を設ける
・法人担当部門を他部門から物理的に隔離
・法人関係書類は他部門から隔離して管理
・法人情報が入った電子ファイルは容易に 閲覧できない方法をとる
・法人情報管理が適切か定期的に検査する
野村証券OBがいろいろな事件の裏で動いていたことは既に多くの人が知っている。
悪法でも法は法。監視委と金融庁が「現行法では情報提供者をインサイダー取引で処分できない」
事実を変える必要がないと思うのであれば問題ない。話は変わるが、東北のガレキ引き受け拒否は処分されない。「絆」とか、「自己中心的」と
メディアを通して非難する政治家や人達もいるが、「主幹事の野村証券が情報提供」に関して処分されないのと同じで問題ないのだ。
ガレキ引き受け拒否よりも、「主幹事の野村証券が情報提供」の方が問題であると思うが、監視委と金融庁が
防止策としてどのような対応をするのだろうか。
増資インサイダー:主幹事の野村証券が情報提供 03/22/12(毎日新聞)
東証1部上場の国際石油開発帝石(東京都)が10年に実施した公募増資に絡み、不公正情報に基づく同社株の空売りに関与したとして、証券取引等監視委員会は21日、金融商品取引法違反(インサイダー取引)の疑いで中央三井アセット信託銀行(東京都)に課徴金を科すよう金融庁に勧告した。関係者によると、情報を提供したのは増資の主幹事の1社だった野村証券。現行法では情報提供者をインサイダー取引で処分できないため監視委は社名を伏せたが、会見で「市場の信頼を損なう行為で極めて大きな問題」と批判した。
監視委は会見で、インサイダー情報を提供したのは公募増資の取引事務を担った主幹事の証券会社4社のうちの1社と明かし「証券会社が業務の上で未公表情報を伝達していたのが確認されたのは日本市場初」と述べた。また、中央三井アセット信託銀行はファンドマネジャー(運用担当者)が投資運用業務の一環として不正取引したとみられ、同行の組織的責任は重いと判断、法人対象の勧告に踏み切った。信託銀行がインサイダーで課徴金処分されるのは初。
監視委や関係者によると、同行のファンドマネジャーの男性社員は、国際石油開発帝石の大型公募増資(10年7月8日公表、発行総額5072億円)を巡る情報を公表前の同年6月30日、野村証券の女性営業員から入手。この情報を基に、同行が運用する海外投資家向けの日本株ファンドで、10年7月1日と同7日の2回に分けて国際帝石株1億124万1000円分(現物90株、空売り120株)を増資公表前に売り抜け、増資公表後の株価暴落時点で買い戻し、約1400万円の運用益を上げたという。
国際帝石の株価は公表前日の同7日は終値で46万9000円だったが、公表後の8月17日には37万8500円と暴落。空売りの影響とみられる。
ただし課徴金の額は運用報酬に基づき算定されるため、5万5000円にとどまった。
10年に相次いだ大型公募増資を巡っては、日本板硝子や東京電力の増資でも株価が不自然に急落している。増資に絡む空売りが起因とみられ、主幹事証券会社を通じたインサイダー疑惑があるとして、内外の投資家から指摘が相次いでいた。こうした事情を踏まえ、監視委が主幹事証券会社などの調査を続けていた。
野村証券は21日、インサイダー取引について「誠に遺憾。当局の調査に全面的に協力する」とのコメントを発表した。ただ、情報を中央三井アセット信託銀行の担当者に伝えた人物が野村の社員かどうかについては、毎日新聞の取材に対し、「事実関係を確認中で答えられない」としている。【川名壮志、田所柳子、岩崎誠】
また野村證券OBが!AIJ投資顧問事件の主役たち 03/05/12(NetIB-NEWS|ネットアイビーニュース)
さすが野村證券、人材は多士済々というべきか。企業年金約2,000億円を消失させた投資顧問会社、AIJ投資顧問(東京都中央区)の浅川和彦社長(59)は野村證券出身である。オリンパスの損失化隠し事件で指南役を務めた野村OBの中川昭夫容疑者(61)とは、外資系証券会社で上司と部下の間柄だった。AIJの取締役には野村の元役員が名を連ねており、いずれも「伝説的」と称される面々だ。
<日本版マードフ事件>
「日本版マードフ事件だ」。AIJ投資顧問が2月24日、金融庁から業務停止命令を受けた翌日、米ウォール・ストリート・ジャーナル日本版(25日付)は次のように報じた。
〈AIJ投資顧問について、格付け会社の格付投資情報センター(R&I)が2009年発行したニュースレターの中で米国の巨額金融事件になぞらえて、日本のマードフ事件になりかねないと警告していたことがわかった。(中略)ニュースレターは市場が落ち込んでいるにもかかわらず、AIJの運用利回りは不自然に安定していると警告した〉
ニュースレターは名指しこそしなかったものの、ほとんどの年金専門家にはAIJだとわかるような書き方だったという。
マードフ事件とは08年発覚した米株式市場ナスダックのバーナード・マードフ元会長による「米市場最大」の詐欺事件である。マードフ自ら運営する投資ファンドは、10%を上回る高利回りをうたって投資家から資金を集めたが、実際は市場で運用せず、投資家に配当を回すだけ。被害額は日本円に換算して3.3兆円にのぼった。
リーマン・ショックで大打撃を被った金融界のなかで、4.75%の高利回りを保証して企業年金を集めていたAIJが目を引くのに十分だ。年金専門家のあいだでは、マードフと同じような詐欺事件になると危惧されていたということだ。
<伝説の営業マン>
AIJ社長の浅川和彦氏(59)は横浜市立大学卒業で、75年に野村證券に入社。個人営業部門で実績を積み上げてきた凄腕で、「成績はトップクラスの伝説の営業マンだった」というのが野村OBの評。京都支店営業次席、熊本支店長と出世階段を上っていったが、突然、退社した。バブル崩壊で、個人的な株投資で失敗し借金を抱えたためといわれている。
94年に個人顧客を引き連れて外資系の米ペイン・ウェーバーに転じ、一介の営業マンとして日本株を売る個人向け営業に携わった。この時の上司がオリンパス事件で指南役として逮捕された野村證券OBの中川昭夫容疑者(61)。同じ指南役を務め、所在が不明となっている野村OBの佐川肇・アクシーズ・アメリカ元社長は同僚だった。運命のいたずらというほかはない。
中川氏はペイン社を辞めたあと、佐川氏とともにアクシーズ・ジャパン証券を設立し、オリンパスの損失隠しの指南役を務めることになる。一方、浅川氏は、96年頃に歩合外務員として一吉証券に移った。営業マンとして抜群の成績をあげ、個室と秘書を与えられるという破格の待遇を受けた。当時の女性秘書がAIJの高橋成子取締役である。
その後、独立してAIJの前身の投資顧問会社を買い、2004年ごろから企業年金を扱うようになる。AIJの実質支配下にあり、信託銀行を通じて募集した年金資産をタックス・ヘイブン(租税回避地)のケイマン諸島で運用していたアイティーエム証券(同一ビルに入居)の西村秀昭社長は、山一證券の国際部門の出身。山一が破綻しため98年に同社を設立。浅川氏が外資系証券会社にいた当時からアイティーエムの西村氏とは盟友だったという。営業一筋の浅川氏が企業年金を集め、国際業務に精通した西村氏が運用する役割だ。
また野村證券OBが!AIJ投資顧問事件の主役たち(後) 03/06/12(NetIB-NEWS|ネットアイビーニュース)
<総会屋事件で失脚した元常務>
親分肌の浅川氏はAIJを立ち上げたとき、野村證券OBをビジネスパートナーに招いた。取締役の松木新平氏(67)である。高卒の場立ちからの叩き上げで、株式担当常務まで出世した人物だ。場立ちとは、証券取引所の立会場で、証券会社から派遣されて、身振り手振りで売買処理する取引担当者。コンピュータシステム化にともない立会場が閉鎖されたため、今は存在しない。場立ちとして鍛えられたこともあり、「相場の読める男」というのが野村OBの評だ。
野村に激震が走ったのは97年の総会屋の小池隆一に対する利益供与事件。児玉誉士夫系の大物総会屋、木島力也の影におびえた第一勧業銀行(現・みずほ銀行)は、小池側に460億円の巨額融資をした。そのカネで、小池は野村、山一、日興、大和の4大証券の株式を購入、株価が値下がりしたとして損失補てんを求めた。
野村證券では、酒巻英雄社長(当時)の指示で、株式担当の松木常務は、「花替え」と呼ばれる、自社株取引により作り出した多額の利益を総会屋の口座に付け替えていった。97年5月、松木常務は酒巻社長とともに逮捕され、懲役8月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。総会屋事件がなければ、松木氏は野村本体の副社長もしくはグループ会社のトップになっていただろうと言われている。
浅川氏が顧問に招いたのが経済学者の植草一秀氏(51)。野村総合研究所のエコノミストや早稲田大学大学院教授などを歴任、テレビ番組へレギュラー出演して知名度は高く、広告塔としての役割を担った。だが、痴漢事件(本人は冤罪と主張)で失脚。AIJ事件を受けて、植草氏は自身のブログに「04年から06年まで顧問をしていた」と書いた。
<野村證券のDNA(遺伝子)>
それにしても、オリンパス事件、AIJ事件とも、主役は野村證券のOBたちだ。なぜか?彼らは、野村證券が相場を作り、価格を決めるのが当たり前という、バブルの時代に育った人物たちだ。有名なのは89年の東京急行電鉄株式の株価操作疑惑。稲川会の石井進会長のために、野村は全組織をあげて東急株に買いに向かった。特定の銘柄を推奨することは、この当時、堂々とまかり通っていた。証券界のガリバーと呼ばれる野村が、営業力をフルに使い、集中的に東急株を売買すれば、株価が上がらないほうが不思議である。石井進会長による東急株の仕手戦に、野村が株価釣り上げに協力したのは明々白々だ。
こうした、野村の悪しきDNAを内包しているのが、事件の主役の野村OBたち。利益を出すには、相場をつくればいいという環境のなかで育ってきたので、ヤバイと思われる手法にも躊躇することはない。それが事件につながっている。
東電値上げ:「契約期間は拒否可能」企業に周知せず 03/21/12(毎日新聞)
東京電力が、4月から予定している企業向け電気料金の17%値上げについて、値上げを拒否できることを契約者に知らせていなかったことが21日までに分かった。枝野幸男経済産業相は同日の閣議後記者会見で東電の姿勢を批判し、契約者への説明を徹底するよう指示したことを明らかにした。
今回の値上げは工場や事務所など契約電力50キロワット以上の約24万件が対象。家庭向けと異なり、値上げに国の認可は必要なく、東電と利用者の交渉で料金を決める。
企業向け料金の契約期間は1年で、4月が更新時期ではない企業もある。東電は1月の値上げ発表後、対象者に値上げを知らせる文書を郵送したが、文書には「(値上げに)了承できない場合は3月30日までにご連絡ください」としか記載されておらず、値上げを拒否すれば次の更新まで現行料金が適用される可能性があることは触れていなかった。
東電は、契約者から問い合わせがあり、その後の交渉でも値上げを了承してもらえない場合に料金据え置きを説明していたという。
枝野経産相は閣議後会見で「故意かどうかにかかわらず、開いた口がふさがらない」と東電の経営体質を厳しく批判した。十分な説明を受けずに既に値上げを了承した契約者を含めて、すべての対象者に説明を徹底するよう、16日付で東電に指示したことを明らかにした。
東電は「4月1日からの値上げについて当社の置かれた状況を説明し、理解いただけるように努めていく」と話している。【立山清也、和田憲二】
丸大証券、自己破産を申請 負債総額23億円 03/15/12(朝日新聞)
顧客から預かった資産を流用したとして、金融庁に金融商品取引業の登録を取り消された「丸大証券」(東京都中央区)が14日、自己破産を東京地裁に申請していたことがわかった。信用調査会社の東京商工リサーチによると、負債総額は約23億円。
証券会社が経営破綻(はたん)したときに顧客の損を補償する「日本投資者保護基金」が事実関係を調べている。補償されれば、2000年の南証券(前橋市)以来、2度目となる。
東電:原発事故後も天下り招請 東京都元局長を雇用 03/15/12(読売新聞)
東京電力が、福島第1原発事故後の昨年9月、天下りを受け入れていたことが関係者の話で分かった。東電が3回にわたり要請した末に東京都元環境局長(65)を雇用したもので、元局長は都のエネルギー政策に関する非公式情報を都職員から収集し、東電に提供していた。巨額の公的資金を受けることから社内に慎重論があったが、総務部が推し進め西沢俊夫社長が最終決定しており、電気料金値上げの前提となる合理化に反した経営姿勢に厳しい批判が起こりそうだ。
天下りしたのは環境問題やエネルギー政策などを担当する都環境局長を06年6月に退職した大橋久夫氏。発電所の二酸化炭素(CO2)対策、大型変圧器に含まれる有害物質ポリ塩化ビフェニール(PCB)の処分などを担当する東電環境部の「アドバイザー」として再就職したが、毎日新聞が取材を開始したことを知り2月20日、退職した。
東電関係者らによると、工場などに6~8%のCO2排出削減を義務づける都の制度(10年4月開始)への対応に苦慮していた東電環境部は、震災前から都OBを採用する意向があった。
総務部や東電OBらが人選し、10年夏、元局長に「(11年夏)アドバイザーに迎えたい」と打診すると前向きだったが、昨年3月東日本大震災が発生したため、元局長は「状況が変わった」といったん断った。
東電は同5月にも打診したが拒否された。同8月「がれき処理など震災後の対応で困っている。自治体の考え方を教えてほしい」と要請し、元局長は「経験が生かせるし人のためにもなる」と考え了承した。元局長は「無償でいい」と申し出たが人事部が難色を示し、年収五百数十万円の契約になった。
放射性物質に汚染されたがれき処理について、震災後の特別措置法は東電に国や自治体への協力義務を定めている。
東電環境部には「表面化すれば批判を浴びる」と懸念する声があったが総務部が押し切った。理由について関係者は「がれき処理もあったが(3度も誘った)最大の理由は政策の方向性を知りたかったから」と説明した。
元局長は電力不足対策として都の進める液化天然ガス(LNG)発電所建設計画について、職員から情報収集し会議で報告していた。関係者は「今後(元局長の得意な)環境政策に関する情報も期待していた」と語る。
元局長は都庁退職後、地方自治体などが出資する企業の取締役を経て、昨年7月まで約1年間、都の外郭団体理事長を務めた。【川辺康広、松谷譲二、田中龍士】
西沢俊夫社長の話 会社にプラスになるということで採用した。批判があれば受け止める。
東電天下り:関係改善の切り札 固辞する元局長を説得 03/15/12(読売新聞)
「都の動きに聞き耳を立てていた」。東京電力に天下りした東京都元環境局長、大橋久夫氏(65)は毎日新聞の取材に語った。固辞する元局長を翻意させてまで雇用した東電の真の狙いは、非公式情報の収集と関係改善だったという。「被災者は職さえ失ったのに何をやっているのか」。原発事故による被害に苦しむ福島県からは厳しい批判の声が起こった。【川辺康広、清水憲司、小林直】
「震災対応でぜひ相談に乗ってほしい」。昨年8月末、東電幹部が元局長に切り出した。同5月の要請も断っていた元局長はいったん辞退したが、幹部は「今だからこそお願いしたい」と食い下がった。「あの言葉が殺し文句だった」と元局長は振り返る。
東電には天下りにこだわる強い「動機」があった。
07年10月、都環境局が地球温暖化対策のため開いた産業界との意見交換会。「(企業の)自主的取り組みを前提にした改善策では効果が上がらない」。「二酸化炭素(CO2)の問題は経営に直結する。企業も東京から逃げ出す」。条例改正でCO2の排出削減を義務づけようとする都と、企業努力に委ねるべきだと主張する東電との間で激論が交わされた。結局、10年4月、厳しい排出規制を義務づけた改正条例が施行された。15年以降見直しも予定されている。東電幹部は「丁々発止やり合ったせいか、どうしても都と信頼関係が築けなかった。恋い焦がれる思いで元局長に来ていただいた」と話す。
元局長は入社後、情報収集に奔走した。「依頼はされていないが期待されていることは分かっていた。一を聞けば十を知った」と振り返る。原発事故後の電力不足を受け、都が進める100万キロワット級液化天然ガス発電所の建設計画。単なるアドバルーンか、本気か。猪瀬直樹副知事がリーダーを務める発電所プロジェクトチームの動きを探るため、後輩に電話したり都庁で会ったりした。
元局長は2月20日、「都庁の後輩から毎日新聞が取材していると聞かされ辞めた。都と東電に迷惑をかけたくなかった」と答えた。
福島県いわき市で被災者支援活動を行う渡辺淑彦弁護士は「被災者は職もなく困っている。元局長を雇う五百数十万円で3人は雇用できる」と憤り「行政との癒着体質は事故後も変わっていない」とため息をついた。
NPO法人の中には偽善のNPO法人が存在すると思う。NPO法人=善意の組織と思うのは間違いだと思う。
本当に事実を知りたいのであれば、「同局は13日の市議会常任委員会で『チェックが甘かった』と謝罪。同法人に弁償を求めるとともに、
利益目的で転売された疑いもあるとみて関係者の刑事告発を検討する。」だけでなく刑事告発するべきだ。刑事事件にしないと、
誰も重い口を開かない。「駐日ドミニカ大使館からの依頼」も疑わしい。「右ハンドルの車は輸入できない」のが事実であればバス寄贈の依頼すること
自体が不自然になる。バスが寄贈されるまでに「右ハンドルの車は輸入できない」ことを調べていない、又は、知らないのはおかしい。
それとも「右ハンドルの車は輸入できない」事自体が嘘なのか?大阪市交通局は刑事告発して事実を公表するべきだ。
海外に寄贈のはずが…大阪市のバスなぜか宮城に 03/13/12(読売新聞)
大阪市交通局が4年前、ドミニカ共和国に寄贈するため、同市浪速区のNPO法人に無償譲渡した中古の市バス5台のうち4台が、同国に輸出されずに転売され、仙台空港(宮城県名取市)などで使われていることがわかった。
他の1台は行方不明で、同局は13日の市議会常任委員会で「チェックが甘かった」と謝罪。同法人に弁償を求めるとともに、利益目的で転売された疑いもあるとみて関係者の刑事告発を検討する。
同局によると、NPO法人「食と農の地域開発研究所」が2008年1月、「駐日ドミニカ大使館からの依頼」として市にバス寄贈を打診。同法人は02年にも、別の団体とともに市バス20台を同国に贈った実績があり、市は08年5月に5台を譲った。
ところが昨年8月、中古の市バスが仙台空港で活躍しているとの写真付き記事を、産経新聞が掲載。元の塗装のまま再利用されているのを不審に思った同局職員がバスの車体に書かれた番号を確認し、譲渡したバスだったことがわかった。
同局が5台の行方を調べたところ、同空港内で運送業務に当たる会社が宮城県白石市の中古車販売業者から2台購入し、長野県富士見町も1台買っていた。また、山形市の自動車教習所も別に1台を所有していた。
同局の調査に対し、同法人は「輸出を委託した大阪府内の業者が、通関手続きの際、『右ハンドルの車は輸入できない』と拒まれた。そこでフィリピンの業者に再委託したが、バスを引き渡した後、連絡がつかない」などと説明。中古車販売業者は、「仕入れ先は言えない」と答えたという。
同法人の唐沢清司理事長は、読売新聞の取材に「以前の理事長がしたことで、自分はよくわからない」と話している。
ドミニカ共和国行きバス、なぜか仙台空港着…大阪市バスの怪 03/13/12(産経新聞)
大阪市交通局が平成20年、中米・ドミニカ共和国に無償譲渡したはずの市バス5台が、同国に渡らず、うち2台が仙台空港の旅客輸送バスに転用されていたことが13日、分かった。追跡調査で、長野県富士見町役場や山形県の自動車教習所などへの転売も判明。同局は、仲介した大阪市浪速区のNPO法人に賠償を求める検討をしている。
交通局によると、20年1月、同法人から「ドミニカ共和国支援に市バスを提供してほしい」と依頼があり、廃車バス5台を同年5月に法人側に引き渡した。
ところが昨年8月、仙台空港で稼働する市バスの写真が産経新聞に掲載されたことをきっかけに調べると、同国に譲渡したはずの車体と判明した。
NPO法人側は交通局に対し「なぜ国内にあるのか分からない」と回答。バスは同法人から別の業者に渡り、仙台空港のバスなど3台は宮城県白石市の中古車販売業者を通じて売られたことが分かったが、この業者が「仕入れ先は言えない」と協力を拒否したため、すべての流通経路は解明できていないという。
豚肉輸入脱税マネー、台湾にプール・国内還流か 03/07/12(読売新聞)
輸入豚肉の差額関税制度を悪用して所得税計約9億5000万円を脱税したとされる事件で、所得税法違反容疑で7日逮捕された豚肉輸入販売業柴田謙司(61)、堂谷邦宏(68)両容疑者が、脱税マネーの一部を台湾にいったんプールし、国内に還流させていた疑いのあることがわかった。
東京地検特捜部と東京国税局の調べなどによると、2人は「オリジンフーズ」(東京都港区)など実体のない2社を使い、デンマーク産などの安価な豚を台湾の貿易商社から輸入し、仕入れていた。
輸入の際、基準価格より低い輸入豚肉に課せられる差額関税を免れるため、価格を水増しして貿易商社に支払っていた。これにより、台湾にプールされた脱税マネーを、航空手荷物として国内に持ち帰っていた疑いがあるという。
「早くて安い」 不正車検の見返りに現金、車両整備会社会長ら4人逮捕 03/07/12(産経新聞)
基準に適合しないダンプの車検を通した見返りに現金を受け取ったとして、警視庁交通捜査課は、加重収賄などの疑いで東京都瑞穂町武蔵、自動車整備会社「幸伸車輌」会長、松田幸男(74)と同社長、次男の栄治(46)の両容疑者を、贈賄などの疑いで東京都あきる野市菅生、産廃会社役員、戸嶋淳悦容疑者(76)ら2人をそれぞれ逮捕した。同課によると、4人とも容疑を認めている。
松田容疑者親子は、道路運送車両法で車検検査員が「みなし公務員」に規定される民間業者。同課は受け取った車検代金を賄賂と認定した。
松田容疑者親子の逮捕容疑は、平成22年9~10月、車両後部に設置された「突入防止装置」を法定より高い位置にするなど不正改造された10トンダンプ4台について、検査することなく検査書類を偽造し車検を通したうえ、謝礼として現金計約17万円を受け取るなどしたとしている。
同課によると、松田容疑者親子は戸嶋容疑者ら以外に対しても「土日もOK、安くて早い」などと安価で車検を請け負い、通常6~7時間かかる検査を5~10分で済ませていた。
20~22年にダンプ1125台分の保安基準適合証を不正に発行、少なくとも4千万円を見返りに受け取っていたとみられ、不正車検は乗用車を含めると2千台以上に上るという。
ダンプ改造見過ごし不正車検=見返り4000万円か、業者ら逮捕-警視庁 03/07/12(時事ドットコム)
不正改造された大型ダンプカーを十分に点検せず、保安基準適合証を発行し現金を受け取ったとして、警視庁交通捜査課と八王子署は7日までに、加重収賄容疑などで、民間車検場経営会社の会長松田幸男容疑者(74)=東京都瑞穂町武蔵=ら4人を逮捕した。同課によると、「楽な生活をしたかった」と話し、容疑を認めている。
道路運送車両法で、適合証発行の指定を受けた車検場職員は公務員とみなされる。
松田容疑者らは「土日もOK、安くて早い」とうたい格安で車検を実施。2008年11月からの2年間でダンプ1125台に検査不十分なまま適合証を発行し、4000万円以上を得ていたという。
東電子会社:社員食堂運営を丸投げ 電気料金に上乗せ 03/06/12(毎日新聞)
東京電力が、同社OBの受け皿となっている子会社の利益をかさ上げするため、この子会社に委託した社員専用レストランの運営を、実際は別会社に丸投げし、東電に入るべき利益が入らず、結果的に電気料金上乗せにつながったことが5日、東京都の調査で明らかになった。都は「他の子会社とも、こうした取引が常態化し、電気料金に上乗せされている」(猪瀬直樹副知事)として、近く枝野幸男経済産業相に調査を要請する。
都によると、問題の子会社は東京リビングサービス。東電独身寮の運営や旅行事業など東電の福利厚生や介護、保育園事業にも乗り出している。社員数は1000人で、10年度の売上高は約140億円。「東電OBの受け皿で、取引の7割は東電が相手」(東電関係者)という。
リビング社が、東電から運営を委託されていたのは東京・渋谷の社員専用の高級レストラン「渋谷東友クラブ」。リビング社は実際は、別の会社に高級レストランの運営業務を丸投げし、一部の利益を吸い上げていたという。
都は、東電がOBのいるリビング社に利益が生じるよう、こうした取引をした結果、東電に入るべき利益が大幅に減ったとみている。
レストランは昨年5月末に東電がリビング社との契約を解除したため、現在は外部業者の直営店となっている。東電広報部は子会社を間に挟む取引を認めた上で、「リビング社は売却する方針。今後も取引形態の見直しは進める」としている。
子会社の絡む不明朗な取引については、東電の経営状況を調査した政府の第三者委員会「経営・財務調査委員会」の報告書でも「(子会社を含めた)関係会社は東電向け取引で稼いでいる」と分析。都の調査で不透明な取引の具体的事例が浮かび上がった形だ。【永井大介】
投資顧問会社「AIJ投資顧問」は詐欺の才能がある。旧厚生省(現厚生労働省)OBが経営する年金コンサル会社と一体となり顧客獲得していた。
旧厚生省OBが斡旋 経営会社に役員受け入れ 03/03/12(産経新聞)
投資顧問会社「AIJ投資顧問」(東京都中央区、浅川和彦社長)が年金資産約2千億円を消失させた問題で、旧厚生省(現厚生労働省)OBがAIJとコンサルタント契約を結び、企業年金側に「AIJは年金資産の運用委託先として有望」と仲介していたことが2日、分かった。これを機に複数の企業年金がAIJと契約していた。このOBが経営する年金コンサル会社の役員をAIJ役員が兼務していたこともあり、OBがAIJと一体となり顧客獲得の一翼を担っていた実態が浮上した。
このOBは産経新聞の取材に、複数の企業年金側にAIJを紹介したことを認めたが、「運用実態がこんな状態になっているとは知らなかった。AIJを勧めるときには『最終的に決めるのはそちらです』と念を押していた」と話した。
OBは旧社会保険庁(現・日本年金機構)の年金担当や旧厚生省保険局医療課で課長補佐などを務めた70代の男性。退職後、都内の年金基金常務理事などを歴任した。
関係者やOBによると、OBは平成16年に都内にコンサル会社を設立。AIJとコンサル契約を結び、20年ごろに契約を解除するまで、多くの企業年金担当者に「AIJは運用に安定感があり、大きな損はしない」と紹介。企業年金側からAIJの評判などを尋ねられた際にも「優良委託先」と勧めていた。
このうち、少なくとも関西や中部地方にある4~5の企業年金が、AIJから「高利回りで運用できる」と虚偽の説明を受け、AIJと年金資産の投資一任契約を結んだ。この中にはOBが顧問を務める企業年金もあった。このうち関西の企業年金は現在もAIJと契約を結んだままという。
コンサル会社はAIJから年間500万円前後の報酬を受け取っていた。また、AIJ前社長や現役役員が一時期、コンサル会社の役員を務めていた。
AIJに“お墨付き”を与えた「格付け会社」はどう責任を取るのか 02/28/12(ゲンダイネット)
<札付きを放置した金融庁も大問題>
約2100億円の年金資産をあっという間にパーにした「AIJ投資顧問」(東京)は、顧客の大半が地方の建設業者といった中小企業だった。彼らは一体なぜ、インチキ投資顧問会社を信用したのか。「格付け会社」がタイコ判を押したからだ。
「年金運用先評価、AIJが首位」――。日経新聞朝刊がこう報じたのは、08年11月17日。日経グループの「格付投資情報センター」(R&I)が全国の企業年金基金をアンケート調査した結果、「運用能力」や「提案力」の総合評価ランキングでAIJがトップだったという内容だ。
今となっては、この「運用能力」はウソッパチだったことが明らかになりつつあるが、“天下の日経”が、なぜこんな“ガセ情報”を掲載したのか。「R&I」の担当者はこう言う。
「調査は全国の企業年金基金に対する満足度アンケートで、基金側に5段階評価してもらう内容でした。AIJは、運用体制、情報公開、アドバイス能力などの総合評価で1位でした。大手の投資会社が低迷する中で違和感を覚えましたが、アンケート調査の結果を我々が恣意的に判断するわけにもいかず、そのままランキングを掲載しました」
つまり、ランキングはインチキ投資顧問会社にだまされた基金側の評価であり、掲載はやむを得ない判断――というワケだ。
「我々はその後、独自調査を始め、(ランキング発表3カ月後の)09年2月に情報誌のコラムで、AIJの危うさも指摘しています。名指しこそ避けていますが、読めばAIJと分かる内容で、実際、AIJ側と“戦争状態”になりました」(前出のR&I担当者)
だが、日経といえば、国内の経済報道で圧倒的な影響力を持つ。金融のプロでもない、地方の中小企業のシロウト担当者から見れば、AIJの「信用力」に日経が“お墨付き”を与えたと判断しても不思議じゃない。数カ月後に“うさん臭さ”を疑わせる記事が出ても気付かないだろう。責任逃れは許されない。
「AIJは業界では“ブラック”として有名でした。大手企業は専門担当者を置き、銀行などと頻繁に情報交換しているから、運用成績のおかしさに気付いていました。しかし、中小企業はそうはいかない。インチキ投資話に乗ったのもムリはない。仮に気付いたとしても、カツカツの資金で運用しているから、ハイリターンを信じて任せるしかなかったのでしょう」(経済ジャーナリスト)
しかし、一番悪いのは、コトが大きくなってから慌ててAIJに業務停止命令を出した金融庁である。業界でも“ブラック”で知られたインチキ投資会社を野放しにしてきた責任は重大だ。
「AIJが公表した昨年3月の事業報告書を見ると、『海外私募投信』を買ったことは書いてあるが、詳しい内容や運用はナゾです。プロが見れば誰でも『おかしい』と思うでしょう。少なくとも『R&I』が“不自然さ”をコラムで指摘した09年に調査に乗り出していれば、損失拡大を防げたのではないか」(証券業界関係者)
格付け会社を信じて複雑な商品に手を出し、大損するパターンは米・サブプライムローン問題でも見られた。バカを見るのは常に庶民である。
「NEDOは委託事業費の返還を求めるなどの処分を検討」は当然だろう。
東工大:委託事業で研究者がデータ捏造 燃料電池開発 02/24/12(毎日新聞)
東京工業大(東京都目黒区)は24日、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から委託された燃料電池用触媒の開発研究で、中国籍の男性研究員(35)がデータの改ざんや捏造(ねつぞう)をしていたと発表した。研究者は不正行為を認めており、単独で行ったという。同大は週明けにも研究員と、研究を統括する教授の処分を発表する。
このプロジェクトは、09~12年度に東工大などが委託を受けた、燃料電池開発に関する2事業(事業費総額約14億円)。より安価で発電効率がいい触媒の研究などを行った。
東工大によると、研究員は発電性能を良く見せるためにデータそのものを書き換えるなどした。研究成果を報告した論文は海外の専門誌に掲載され、特許も出願していた。
昨年8月、プロジェクトに参加する企業から指摘を受け、不正が発覚。研究員は大学側に「世界で行われている触媒技術の成果に合わせるような形で捏造をしてしまった」と話しているという。
NEDOは委託事業費の返還を求めるなどの処分を検討している。【神保圭作】
東工大:次期学長就任、辞退届け出 不正経理問題で責任 02/17/12(毎日新聞)
東京工業大の次期学長に選任された岡崎健・前工学部長(62)が学長就任を辞退する届け出を大学側に提出したことが17日、わかった。届け出は16日付。同大は近く学長選考会議を開き、次期学長を選考する方針。
岡崎氏の研究室では、研究費の「預け金」などの不正が行われていたことが明らかになっており、岡崎氏は大学側に対して「研究費の不適切な使用を厳粛に受け止める。混乱を引き起こし、大学に迷惑をかけた」と話しているという。
同大の学長を巡っては昨年7月、当初の次期学長に内定していた大倉一郎・前副学長が不正経理をめぐって学長就任を辞退。岡崎氏は大倉氏の辞退を受けた学長選挙を経て、昨年10月に就任予定だった。不正経理問題が浮上し、文部科学省が経過を見守るとして、就任を留保。同大は特別調査委員会を設置し、岡崎氏の研究室で不正経理があったと認定。岡崎氏の関与は認めないとする一方で「一定の管理責任がある」と指摘した。【神保圭作】
運用失敗、花博記念協会に解散要求…大阪府・市 02/24/12(読売新聞)
大阪府と大阪市が約17億円ずつ出資する財団法人「国際花と緑の博覧会記念協会」(大阪市鶴見区)について、松井一郎知事と橋下徹大阪市長は24日、協会に解散や出資金の返還を求めることを明らかにした。
協会は資産運用の失敗で、14億円(2010年度末)の含み損を抱えている。ただ協会は国所管法人で、法的に府市に解散や返還を求める権限はなく、協会との交渉は難航しそうだ。
府監査によると、協会は02年度以降、元本保証のない金融商品を約47億円で取得したが、10年度末の時価総額は約26億円まで下落。資産全体では14億円の含み損を抱えた。
報道陣に24日、松井知事は「協会はお金の使い方がむちゃくちゃ。大阪府は手を切る」と述べ、橋下市長も「松井知事からは協会は解散の方向でいくと聞いている。いらないものはどんどん解散」と述べた。
もしかしたら氷山の一角で、似たような状況の会社はあるかもね。
AIJ投資顧問が年金資産2千億消失…業務停止 02/24/12(読売新聞)
AIJ投資顧問:年金2千億円の大半消失…123社分運用
AIJ投資顧問の業務停止命令について報道陣の質問に答える自見庄三郎金融担当相(左から2人目)=国会内で2012年2月24日午前9時45分、竹内幹撮影 企業年金を中心に約2000億円の資産を運用する投資顧問会社「AIJ投資顧問」(東京都中央区、浅川和彦社長)が、高利回りで収益を上げているなどと顧客に虚偽の情報を伝えていたとして、金融庁は24日、金融商品取引法違反(投資家の利益に反する事実)の疑いで同社に1カ月の業務停止命令と業務改善命令を出した。証券取引等監視委員会が同社を検査したところ、残高は約200億円しかなく、大半は消失。預託された企業年金は大幅な含み損を抱えるとみられる。
◇金融庁が業務停止命令
同日午前、自見庄三郎金融担当相が記者会見し、「金額は不明だが、顧客資産を毀損(きそん)していたとみられ、投資家保護の観点から命令を出した」と話した。
関係者によると、同社は1989年設立で、資本金2億3000万円。昨年3月末時点で124の企業から預かった2100億円を投資運用していた。そのうちほとんどが企業年金(123社)で、年金1870億円を管理。顧客の大半は建設業、電気工事業などの中小企業による総合型の厚生年金基金だった。
同社は金融派生商品の運用により「市場の変動に左右されずに安定収益が上がる」「リスクを減らし絶対的な収益を目指す」などとうたい、運用実績も好調なように見せかけていたという。
しかし、監視委が今年1月下旬から検査したところ、大半は消失し残高は1割未満にまで落ち込んでいた。業績が不調にもかかわらず、集めた資金を配当に回していた疑いがあるという。監視委の検査で会社側も虚偽の説明があったことを認めているという。
このため金融庁は、残った資金を保全するため早急に業務停止命令を出すことを決定。実態の解明まで資産を引き出すことは不可能になる見込みだ。年金の消失が確定すれば、顧客の厚生年金加入者は深刻な打撃を受ける可能性もある。【川名壮志、田所柳子】
◇企業年金の運用◇
企業年金は、国民年金や厚生年金に上乗せして、企業が任意に設ける年金。大企業なら1社単独、中小企業なら地域・業種が集まって作る年金基金で管理されており、実際の運用は、投資顧問業者などに依頼して行うことが多い。投資顧問業者の事務的なミスなどで損失が出た場合は賠償を求めることができるが、運用の失敗による損失の穴埋めは、金融商品取引法で禁じられている。企業は従業員に、将来年金を支払うことを約束して掛け金を集めているため、損失が出た場合は、企業が不足分を追加拠出することを迫られる場合もある。ただ、企業の財務に余裕がなければ年金基金を解散することもできる。
「地質専門家によると、現場海域の海底は泥と砂が堆積(たいせき)した軟弱な層が広がり、深くくぼんでいる場所もある。10年前に今回と平行する形で行われた隣接トンネルの工事では、水や石が勢いよく噴き出す『噴発』のトラブルが起きていた。」
新聞による情報でしか判断できないが、少なくともリスクは認識した上での判断みたいだから、その判断に問題があったのかが今後の事故防止対策に反映されるだろう。
海底トンネル事故:掘削機前部、沈下か 隙間生じ海水流入 02/14/12(毎日新聞)
岡山県倉敷市のJX日鉱日石エネルギー水島製油所の海底トンネル事故で、海底を掘り進む円筒形掘削機の後部とトンネル壁面との境界部に、隙間(すきま)が生じて落盤を引き起こし、大量の土砂や海水が流入した可能性が高いことが、工事関係者や専門家への取材で分かった。境界部は海底に出現した巨大なくぼみの位置とも一致。掘削機の電源喪失により掘削面と岩盤との圧力バランスの機能が失われるなどし、脆弱(ぜいじゃく)な地盤とも相まって掘削機(重さ141トン)の前部が沈む「ノーズダウン現象」が発生したとみられる。
工事会社の鹿島などによると、今回採用したシールド工法では、横穴を1.4メートル掘り進むごとに壁面ブロック(セグメント)を組み上げていた。
社員が事故直前に現場を見たところ、作業員らは掘削作業を中断していた。その後、壁面ブロックを下から組み上げる作業に入り、天井部は壁面ブロックがまだはめられていないか、ブロックを固定するセメントが注入される前の段階だったとみられる。
トンネル内にいた現場責任者の渕原義信さん(61)は事故直前、地上に「漏電」「ブレーカー」と連絡した。電気系統のトラブルがあったとみられ、壁を支える油圧ジャッキが緊急停止したか、掘削面と地盤との間で圧力バランスが崩れるかした影響で掘削機を突っ張って支える機能が失われ、重量で掘削機が前のめりに沈んで、後部の天井に隙間ができた。このため落盤を引き起こした可能性が高いとみられている。
地質専門家によると、現場海域の海底は泥と砂が堆積(たいせき)した軟弱な層が広がり、深くくぼんでいる場所もある。10年前に今回と平行する形で行われた隣接トンネルの工事では、水や石が勢いよく噴き出す「噴発」のトラブルが起きていた。
シールド工法に詳しいトンネル工学の専門家は「掘削面の土砂の取り込み口は閉じられていたことから、前面からの出水はあり得ない。ノーズダウン現象が大規模に起きたと考えられる」と指摘している。
事故は14日で発生から1週間たつが、残る作業員3人の行方は依然として分かっていない。【井上元宏】
核燃輸送容器:検査基準を企業に配慮 寄付受けた教授主導 02/12/12(毎日新聞)
日本原子力学会が1月に議決した使用済み核燃料などの輸送容器に関する検査基準(学会標準)が、容器設計・製造会社「オー・シー・エル」(東京都)と、同社から多額の寄付を受ける有冨正憲・東京工業大教授が主導する形で審議され、国の規制より緩い内容にまとめられていたことが分かった。原発を巡っては、学会や業界団体が定めた内容が国の基準に採用される例も多いが、「原子力ムラ」内部で自分たちに有利な基準を作り上げていく構図が浮かんだ。【日下部聡】
学会議事録や関係者によると、議決したのは「使用済燃料・混合酸化物新燃料・高レベル放射性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準」。一般からの意見募集の後、今年中にも正式に制定される見込みという。
学会標準は分科会が原案を作成し、専門部会と標準委員会でチェックする仕組みで、10年に輸送容器分科会で検討が始まった。同分科会はオ社の会議室で開かれ、原案の文書化もオ社から参加した委員が行ったという。
有冨氏は同分科会の主査、上部組織の原子燃料サイクル専門部会の部会長で、議決機関・標準委員会の副委員長でもある。東工大の記録によれば、有冨氏は06~10年度、オ社から1485万円の奨学寄付金を受けた。分科会に参加するもう1人の研究者(東工大准教授)も10年度、オ社から100万円の奨学寄付金を受けている。
審議の焦点は、使用済み核燃料などの発する熱が容器にどう伝わるかを調べる「伝熱検査」を、新造容器全てに実施するか否か。原案はメーカーに製造実績があればサンプル検査で可としたが、経済産業省原子力安全・保安院の通達は全数検査を求めている。昨年6月の専門部会では、保安院の安全審査官が反対意見を述べた。
しかし、昨年12月23日~今年1月19日に行われた標準委の投票の結果、研究者や電力会社社員らの賛成多数で可決された。反対は保安院の委員1人。独立行政法人・原子力安全基盤機構の委員が賛否を保留した。
容器メーカー関係者によると、大きな輸送容器なら38本の使用済み核燃料集合体を収納できる。伝熱検査は、集合体と同じ本数の電熱ヒーターを内部にセットしなければならず、負担が大きいという。
有冨氏は「オ社の味方をしているつもりはない。全て検査していたら出荷が滞り、使用済み燃料の処理が進まない。学会としてサンプル検査でいいと判断した」と話す。だが、審査の全段階に関与していることについては「中立性に疑念を持たれても仕方がない。少なくとも分科会主査か標準委副委員長のどちらかは辞めた方がいいと思っている」と話す。
ただ、有冨氏は「容器は原子炉などと違って論文の書ける分野ではなく、研究者が少ない。審議体制に問題があることは分かっていたが、他になり手がいない」とも話した。
オ社の川上数雄常務は「公平、公正、公開の原則にのっとった委員会で活動しており、疑念を招くようなものではない」との見解を示した。
保安院関係者は「輸送容器は市民の近くを通ることもあり、厳しい基準が必要。このまま国の基準にはできない」と話している。
有冨氏は東京電力福島第1原発事故直後、当時の菅直人首相に内閣官房参与に任命されている。
事故は保険と似ている。事故が起こらなければ支払った保険料が無駄に思える。事故が起これば支払った保険料以上に受け取れる。
事故が起こらなければ安全を重視したコストが無駄に思える。事故が起これば多少のコストアップでも安全を重視した対応をしておけばと思う。
「地質調査は、10年前に隣接するトンネルを建設した際のデータを参考にしたため、実施していなかったという。」事故がなければ時間とコストが
削減される。事故が起これば後悔と損失。
「現場には、緊急警報装置は設置されておらず、避難マニュアルもなかった。・・・事故発生の直前に、現場責任者の渕原さんから工場内の事務所にいた鹿島の機械電機担当者に
携帯電話で連絡があったことが分かった。・・・携帯電話の通話内容は、電波事情がよくないためか、よく聞き取れなかった。」
緊急の場合の連絡手段が確立されていなかったことは明らかだ。海底のトンネルからの通信だから、中継器や同等のものがなければ携帯が繋がりにくいことは
常識で考えればわかること。コストを抑えようとしたからためなのか、それとも予算が抑えられたから結果として安全に対するコスト削減になったのか
原因究明を待ちたい。発注責任者及び/又は工場の工事監督責任者はどのように工事が進められるか説明を聞いているはずだ。JX日鉱日石エネルギー水島製油所では
携帯の使用は禁止されているエリアがあるから、どのように緊急連絡を取るのかJX日鉱日石エネルギー水島製油所の責任者は聞いているはずだ。
緊急時の連絡方法が携帯しかないのであればその時に指摘するべきだろう。製油所なのだから緊急時の連絡方法を聞いていないのであれば、責任者にも責任がある。
倉敷トンネル事故:「異常出水だった」 直前、機械不調に 02/08/12(毎日新聞)
なぜ、事故を防げなかったのか--。岡山県倉敷市のJX日鉱日石エネルギー水島製油所で起きた海底トンネル事故で、行方不明となっている作業員5人の役割が、工事を請け負った鹿島やJXなどに対する取材で分かった。鹿島は「シールド工法で考えられないほどの大量の異常出水だった」と説明。岡山県警などは8日午前、事故現場の縦穴で行方不明となった作業員5人の捜索を再開したが、海面は濁ったままで捜索は難航している。【原田悠自】
鹿島水島海底シールド工事事務所によると、トンネル工事は、掘削機で地盤を横に掘り進むシールド工法で進めていた。掘削機は、歯の付いた円盤(直径約4.5メートル)を回転させて土砂を取り込みながら前進する。掘削機先端下部にある直径約60センチの円形口から取り込んだ土砂はベルトコンベヤーで流され、バッテリーカーが引っ張る車両で縦穴の下部まで運搬。さらに、天井クレーンで地上まで持ち上げる。
作業では、宮本光輝さん(39)と真鳥晴次(まとり・はるじ)さん(43)が、約140~160メートルまで掘削が進んだ横穴の先端近くで鉄筋コンクリート製の壁作りを担当。小荒(こあら)勝仁さん(47)は横穴中央にある操縦室から掘削機の操縦に当たった。南坪昭弘さん(57)と角井(かくい)健次さん(61)は土砂や資材を横穴の中ほどから縦穴の底まで運ぶバッテリーカーの運転手だった。渕原義信さん(61)は工事責任者で、通常は掘削作業には入っていなかったという。
現場作業員のうち自力で逃げ出した角井さんが脱出の瞬間、下から「危ない」「逃げろ」という叫び声を聞いており、関係者の話から、渕原さんの声だったとみられる。会社側は「直前に機械の調子がおかしくなった」と説明しており、渕原さんが、何らかのトラブルが起きた現場の状況を確認していた可能性があるとみられる。
現場には、緊急警報装置は設置されておらず、避難マニュアルもなかった。
◇渕原さん携帯で連絡
事故発生の直前に、現場責任者の渕原さんから工場内の事務所にいた鹿島の機械電機担当者に携帯電話で連絡があったことが分かった。鹿島が8日午前、記者会見で明らかにした。
同社によると、携帯電話の受信時刻は7日午後0時17分で、同社の社員が119番通報した約13分前だったという。
携帯電話の通話内容は、電波事情がよくないためか、よく聞き取れなかった。渕原さんの言葉ははっきりしなかったが、担当者は「(機械電機担当の)私に連絡があったのだから、トンネル内で機械トラブルが起きたのだろう」と受け止めて現場に向かった。担当者が自転車で約5分かけて駆けつけたところ、現場の縦穴には既に水が噴出した後だったという。【酒井祥宏】
◇視界ほぼゼロ 縦穴捜索難航
くぼみ周辺の海域では午前9時20分ごろ、徳山海上保安部(山口県)の隊員4人が約50分にわたって潜水調査した。直径約20メートルのくぼみを海底で確認した主任航海士の大黒真司さん(35)は「所持品や手がかりにつながる物はなく、がれきも見当たらなかった。くぼみは垂直に落ち込んでおり、自然にできたとは思えない。今回の事故でできたのではないか」と話していた。
B工場側の縦穴(深さ34メートル)でも午前10時35分ごろ、岡山県警の潜水隊員2人が行方不明者を捜索するため潜水した。水面で待機する他の隊員の足元すら見えない視界不良のため、深さ27.4メートルの地点まで潜ったものの10分程度で引き返した。海水には油やがれきが混入しており、縦穴内の視界はほぼゼロの状態だという。【石井尚、広沢まゆみ】
◇「望み託したい」愛知の請負会社
「望み託したい」愛知の請負会社 従業員3人が行方不明になっている弘新建設(愛知県知多市)の加藤俊裕営業本部長らは8日記者会見し、「(行方不明になっている従業員の)家族への対応に全力で当たっている。8日中には家族の皆さんは、現地へ到着する見込みだ。本人の顔を見るまで望みを託したい」と話した。
【新井敦】
岡山・倉敷市製油所海底トンネル事故 現場近くの海底に直径20メートルのくぼみ 02/08/12(フジテレビ系(FNN) )
岡山・倉敷市で5人が行方不明となった海底トンネルの事故で、現場近くの海底に直径20メートルのくぼみがあったことが海上保安部の調査でわかった。
この事故は、7日午後0時半ごろ、倉敷市のJX日鉱日石エネルギー水島製油所で、掘削作業中の海底トンネルの内部に海水が流れ込み、愛知県の建設会社・弘新建設の渕原義信さん(61)、宮本光輝さん(39)、小荒勝仁さん(47)、東京の建設会社・弘栄建技の真鳥晴次さん(43)、南坪昭弘さん(57)の作業員5人が行方不明になったもの。
現場はがれきが多く、水も濁っているため、捜索はいったん中断され、海上保安部が測量船を使って、海底の状況を調査した。
その結果、トンネルの先端付近の水深およそ12メートルの海底に、直径およそ20メートル、深さが最大で3.5メートルのくぼみがあったことがわかった。
工事を請け負った鹿島建設は、事故の原因について、「掘削中にトンネル内に水が入ってきたか、トンネルが崩落した可能性がある」としているが、特定はできていない。
また、地質調査は、10年前に隣接するトンネルを建設した際のデータを参考にしたため、実施していなかったという。
警察や海上保安部では8日、あらためて現場の状況を確認し、行方不明者の捜索を行うかどうかなど、今後の対応を決めるとともに、くぼみと事故との関連を調べることにしている。
大きな船が上を通ったんじゃないの?どちらかに集約すれば良いんじゃないの?通船を使う必要ないA工場(旧新日本石油)の
存続で良いと思うけど!
石油工場のトンネル崩れ、作業員5人の安否不明 02/07/12(朝日新聞)
7日午後0時35分頃、岡山県倉敷市のJX日鉱日石エネルギー水島製油所工場で、海底にパイプラインを設置するためにトンネルを掘削中、浸水が起きた。
倉敷市消防局によると、トンネル内では同日朝から6人が作業しており、うち1人が自力で脱出。残り5人の行方がわからないという。県警が潜水隊員を派遣するなどし、捜索する。
脱出した作業員によると、海底を通るトンネルの横穴部分で落盤が起き、海水が流れ込んだという。
同社によると、トンネルはA工場(旧新日本石油)と海を挟んで東側にあるB工場(旧ジャパンエナジー)をつなぐ長さ800メートル。2010年から工事に入っていた。
ホームページによると、水島製油所は水島コンビナートの中心部に位置。1961年から操業を開始した。1日あたり約5万8000キロ・リットルの原油を処理できる能力があり、燃料油のほか石油化学製品や潤滑油などを生産している。
本当に公平なら良いけど。下請けで敷地内に入っている会社は、一般的に工場は神様。例え正しくても逆らうことや嫌われる事はしない。
「粟野鉄工所」の社長である井県高浜町の粟野明雄・町議会副議長がどのような理由で提案したのか。真実は言わないだろうから、
何か不正の証拠が出てくるまで推測で終わるだろう。
原発関連工事:高浜町議会副議長の会社が7億円受注 02/07/12(朝日新聞)
関西電力高浜原発が立地する福井県高浜町の粟野明雄・町議会副議長(62)が社長を務める同町の金属加工会社「粟野鉄工所」が10年度までの5年間で、関電発注の原発関連工事を少なくとも133件、計約7億円分受注していたことが分かった。同町議会は昨年9月、原発再稼働などを求める意見書を、東京電力福島第1原発の事故後全国で初めて可決したが、粟野副議長はその提案者だった。多額の原発関連工事を受注する議員が原発事業を推進する構図が浮かび上がった。【古関俊樹、遠藤浩二、柳楽未来】
粟野副議長は03年初当選、現在3期目で、昨年から副議長。原発を推進する「福井県原子力平和利用協議会」の高浜支部事務局長も務める。
県などによると、粟野鉄工所は社員約15人で、10年度の売り上げは約2億円。高浜原発構内に事務所があり、原発関連工事で業績を伸ばしてきた。
工事経歴書などによると、受注したのは「高浜3号機復水ポンプ吊上(つりあ)げ開口部修繕工事」約2163万円(06年度)など。元請けは90年代からで、最近5年間は元請けだけで67件・約5億3600万円分に達している。大半の地元業者が年数件から十数件にとどまる中、元請け67件・下請け66件は突出しているという。
昨年9月に粟野副議長が提案した意見書は「脱原発に大きく振れてしまうことなく……原子力発電を堅持することを求める」などとして定期検査後の原発再稼働などを国に求め、賛成多数で可決された。
再稼働を巡っては、西川一誠・同県知事が「福島第1原発事故の知見を反映した新たな安全基準を国が示さなければ認められない」とするなど慎重姿勢が相次ぎ、原発を抱える同県おおい、美浜両町議会も意見書を見送っている。
粟野副議長は「国内のエネルギー事情を見て原子力が必要だと判断し、意見書を出した。議員活動と会社経営は全く別で、受注の影響はない」と話している。
高浜原発は1・2・4号機が定期検査で停止中で、再稼働に必要な1号機の安全評価(ストレステスト)が1月、関電から経済産業省原子力安全・保安院に提出された。今後、保安院や内閣府原子力安全委員会などの審査を経て、野田佳彦首相らが地元合意を前提に再稼働の是非を判断する。
◇取引先は公平審査
関西電力原子力事業本部の話 個別の契約については回答を差し控える。取引先は公平に審査・登録し、工事内容に最適な取引先を選定して契約を行っている。
「会議では、福島の事故後に政府が打ち出した減原発方針が大綱にどう反映されるかが焦点となっている。原子力委の事務局は3人の選定理由を『安全性などの専門知識を期待した』と説明するが、電力会社や原発メーカーと密接なつながりがあったことになる。
3人は東京大の田中知(さとる=日本原子力学会長)、大阪大の山口彰、京都大の山名元(はじむ)の各教授。3人は寄付を認めたうえで、『会議での発言は寄付に左右されない』などと話している。」
「会議での発言は寄付に左右されない」は信用できない。内閣府原子力委員会の事務局は専門委員を選定する時に業界からの寄付の有無について質問して
いるのか。もし質問していないのなら内閣府原子力委員会を含め、業界よりスタンスの集団と言う事だ。内閣府原子力委員会が公平な対応を取ってきていない
インチキ集団組織と言うことだろう。専門家であろうとなかろうと、既に業界の手が回っている人間が業界が意図しない発言をするはずがない。
寄付を受け取っていること自体、業界と同じ考えか、似た考えである事を意味していると思う。多くの国民が反対し、行動として表さないと内閣府原子力委員会の
体質は簡単には変えられないと思う。そういう点では福島周辺に住んでいないことに感謝する。業界サイドでなければこんな内閣府原子力委員会に期待すること自体、
間違っている。
原子力委3人に業界から寄付 5年間で1800万円 02/06/12(朝日新聞)
東京電力福島第一原発事故後の原子力政策の基本方針(原子力政策大綱)を決めるため内閣府原子力委員会に設けられている会議の専門委員23人のうち、原子力が専門の大学教授3人全員が、2010年度までの5年間に原発関連の企業・団体から計1839万円の寄付を受けていた。朝日新聞の調べでわかった。
会議では、福島の事故後に政府が打ち出した減原発方針が大綱にどう反映されるかが焦点となっている。原子力委の事務局は3人の選定理由を「安全性などの専門知識を期待した」と説明するが、電力会社や原発メーカーと密接なつながりがあったことになる。
3人は東京大の田中知(さとる=日本原子力学会長)、大阪大の山口彰、京都大の山名元(はじむ)の各教授。3人は寄付を認めたうえで、「会議での発言は寄付に左右されない」などと話している。
大企業やその従業員は簡単に変われない。立派なリーダーが存在しても時間がかかる。東電により利益を得た人達もいると思うが、
これだけ利益をほとんど受けていいない人達に迷惑をかけていながらこのような発言をする。
東電を解体して東電と関係がないリーダーシップが発揮できる人達で新たな企業を設立するか、分割して参入したい企業に
売却したほうが良いと思う。
ペーパー車検」容疑で2人逮捕 02/02/12(読売新聞)
必要な点検や整備をせずに車検を通す「ペーパー車検」をしたとして,北海道警札幌白石署は2日,民間車検場の指定を受けている札幌市内の自動車整備会社の検査員の男と,依頼した道内の板金業の男を,虚偽有印公文書作成・同行使と道路運送車両法違反(不正車検)容疑で逮捕した.
道警幹部によると,検査員は昨年8月,依頼した板金業の男と共謀し,乗用車1台について,点検・整備を済ませたとする虚偽の保安基準適合証を作成し,北海道運輸局に提出した疑い.
同局によると,民間車検場として指定された整備業者は,運輸局に車を持ち込まなくても,自社の工場内で検査,保安基準適合証を発行することが出来,同局は保安基準適合証をもとに車検証などの交付を行う.
札幌市“インチキ車検”業者,逮捕
検査や整備をしないで車検に合格させる「ペーパー車検」をしたとして,北海道警は2日,道路運送車両法違反などの疑いで,札幌市の民間車検場「車検センター南郷通」の自動車検査員,長沼一秋容疑者(51)と,自動車修理業,長谷川英二容疑者(62)を逮捕した.
北海道運輸局も2日,2009年8月~11年10月,長沼容疑者が約200台分のペーパー車検をしたとして,車検センター南郷通の自動車整備事業指定を取り消し,検査員の資格も剥奪した.
逮捕容疑は,長沼容疑者は昨年8月,長谷川容疑者が江別市の男性から車検の依頼を受けた軽トラックについて,車両も見ないで虚偽の保安基準適合証を作成,軽自動車検査協会に提出して車検に合格させた疑い.
道警14 件によると,2人は十数年来の知人.長谷川容疑者が不正の見返りに金銭を渡していた可能性もあるとみて調べる.
「東電、値上げを権利と勘違い」…経産相批判 01/31/12(産経新聞)
古川経済財政相は31日、内閣府に東京電力の西沢俊夫社長を呼び、工場やオフィスなどの電気料金の平均17%値上げについて「景気への影響を危惧している」と伝えた。
西沢社長は、政府が検討中の家庭向け料金の算定基準見直しを企業向けにも反映し、値上げ幅を圧縮する意向を示したが、4月からの値上げは予定通り行う考えだ。産業界からも批判の声が出ており、東電の今後の経営を巡る論議にも影響しそうだ。
◆対談
古川経財相は、昨年末に西沢社長が値上げ方針を発表した際、「値上げは(電力会社の)権利」と述べたことについても説明を求めた。西沢社長は「至らないところがあった」と謝罪した上で、「(経営)状況を説明し、顧客に(使用時間帯で単価が変わるなど)いくつかの料金メニューを提示して理解を得たい」と述べた。
今回の値上げ対象は料金が自由化された部門で、政府に指示する権限はない。古川経財相も値上げ幅抑制などの要請はしなかった。
一方、東電は今秋をめどに家庭向けの料金も値上げしたい考えで、これには政府の認可が必要だ。政府は東電のコスト削減を徹底させ、電気料金をなるべく抑えようと、原価を厳しく見積もる新たな算定基準を検討している。西沢社長はこれを企業向けにも適用して値上げ幅を圧縮する方針だが、4月からの17%値上げは「現時点で変えるつもりはない」と強調した。
◆打撃
値上げは企業のコスト増に直結する。ホンダの池史彦・取締役専務執行役員は31日の決算発表記者会見で「我々だって原材料が上がっても、いきなり車を1~2割値上げしない」と不満をあらわにした。富士通の山本正已社長も「グループ全体として10億円弱の影響が出る」と強調した。
SMBC日興証券の試算では、平均17%値上げされると、2012年度の上場企業の経常利益の合計が、値上げしなかった場合に比べ1・5%減る。電気を大量に使う業界は特に危機感が強く、「鉄鋼業界全体のコストが年200億円増える。電炉業界は赤字になる」(日本鉄鋼連盟の林田英治会長)との悲鳴が上がる。
中小企業はさらに深刻で、中小企業が加盟する大田工業連合会(東京都大田区)の舟久保利明会長は「中小は電気代の値上げを製品に転嫁できるかどうかわからない。廃業するところも出るかもしれない」と不安を口にする。
◆影響
枝野経済産業相は31日の記者会見で、「(値上げの)根拠となる情報などの開示、誠実な交渉については必要があれば指示をしたい」と説明した。東電と政府の原子力損害賠償支援機構が3月に共同で策定する総合特別事業計画の認可に際しては、「東電の体質も評価する」と指摘。「『値上げは権利』と勘違いする感覚は電力の安定供給主体として適切ではない」と批判した。
マンション耐震強度不足で14億賠償 検査機関などに地裁命令 01/31/12(産経新聞)
耐震強度不足が判明した横浜市鶴見区のマンションの住民53人が、建築確認をした指定確認検査機関「日本ERI」(東京)と設計事務所、横浜市に建て替え費用など計約14億3千万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁(森義之裁判長)は31日、日本ERIと設計事務所側に計約14億円の支払いを命じる判決を言い渡した。横浜市への請求は棄却した。
マンションは販売会社ヒューザー(破産)が分譲した「セントレジアス鶴見」。下河辺建築設計事務所(東京)が設計して2003年に完成したが、06年に耐震強度が建築基準法の基準の約64%しかないと判明した。建物の構造計算書は下河辺事務所の下請け会社(解散)が作成しており、住民側は「日本ERIは申請時に壁の強度不足に気付き、修正を指示しながら、下請けが手書きで修正しただけの計算書を十分審査しなかった」と強度不足を見過ごした過失を主張した。
この国と原発:第4部・抜け出せない構図/2 議員立法に業・官の壁 01/23/12 (東京朝刊 読売新聞)
◇「電力に落選させられた」
昨年8月、再生可能エネルギー固定価格買い取り法(再生エネ法)が成立した。電力会社に対し、太陽光など自然エネルギーを使って個人や事業者が発電した電力の全量買い取りを義務付ける法律だ。
「感慨無量ですね」と、愛知和男・元環境庁長官は言う。
実は12年前、愛知氏(自民)が会長を務める超党派の「自然エネルギー促進議員連盟」が同様の議員立法を試みた。しかし、愛知氏は直後に落選。議員立法も頓挫した。「電力会社に落とされた」と愛知氏は受け止めている。
発端は、自然エネ普及の市民運動をしていた飯田哲也氏(現・環境エネルギー政策研究所長)が98年、福島瑞穂参院議員(社民、現党首)や愛知氏ら環境問題に関心の深い与野党の国会議員に、議員立法の研究を呼びかけたことだ。「二項対立を超え、政治を巻き込んで政策を練り上げる欧州流の活動を目指した」(飯田氏)。あえて「脱原発」を掲げず、自民党の議員にも積極的に接触した。
その結果、99年11月24日に自然エネ議連が発足した。参加者は257人を数え、梶山静六氏ら自民党の大物も名を連ねた。
飯田氏らと勉強会を重ねた愛知氏らは、00年4月には法案を完成させ、各党に持ち帰っての手続きに入った。ところが、同年6月に衆院が解散。宮城1区の愛知氏は民主党の新人、今野東氏(現参院議員)に1万5000票差で敗れた。予想だにしなかった敗戦だった。
「東北電力が何もしてくれなかった。後で気づいた」と愛知氏は振り返る。それまでの選挙では社員を動員してもらい、日ごろからパーティー券も買ってもらっていた。「選挙の応援は経営側が私、労組は民主党と決まっていた。でも、あの選挙で動いたのは労組だけだった。『ああ、そういうことをするのか』と思ったね」
愛知氏の落選後、自然エネ議連は橋本龍太郎元首相を会長に迎えるが、事務局長の加藤修一参院議員(公明)は「予想に反し、動きは鈍かった」と話す。やがて橋本氏は「法案は政府提案で」と言うようになり、議員立法は立ち消えになった。
愛知氏は「議連には電力業界に近い『監視役』もいた。我々の動きは役所に筒抜けだったと思う」と話す。
一方、通商産業省(当時)は自然エネ議連発足直後から、別の法案作成の動きを活発化させた。紆余(うよ)曲折を経て、買い取り義務のない「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」が02年に成立。飯田氏は「通産官僚と電力の壁に阻まれた。官僚側は政策決定の主導権を奪われることを警戒していた」と話す。
それから10年。成立した再生エネ法は、買い取り価格や期間の決定を第三者機関「調達価格等算定委員会」にゆだねた。官僚の裁量で決められることを防ぐため、国会審議で追加された仕組みだ。
ところが、経済産業省が提示した算定委の人事案は、候補5人のうち3人が再生エネ法に反対または慎重な人物だった。「官僚の反転攻勢だ」(野党議員)との声も上がる。昨年12月5日には与野党5議員らが撤回を求めて記者会見した。
形の上では民主、自民、公明3党の推薦リストに基づき、経産省が決めたことになっている。しかし、柴山昌彦衆院議員(自民)は「党内の担当部会長も(推薦の)経過を聞いていないと言っている。人選のプロセスに問題がある」と訴えた。ある政府関係者も「誰がどんなリストを出したのか、誰も分からない。そんな状態で政策が決まっていくというのは、日中戦争の前のようだ」と話す。
一方で、経産省資源エネルギー庁の担当者は「最終的には大臣が判断した。3党がそれぞれどういうリストを上げてきたか、我々の立場では言えない」と口を閉ざす。
人選の変更はあるのか。不透明感だけが膨らむ中、人事案は24日召集の通常国会に提出される見込みだ。=つづく
関係者は皆無能で役立たずか、大嘘つき。保安院、原子力保安検査官、森山善範原子力災害対策監及び東電の全てがこのありさま。
チェックするほうも、チェックされるほうももたれ合い、馴れ合い、そして同じ仲間の関係だ。ストレステストをチェックする能力も
ない保安院や原子力委員会の判断など信用する根拠がない。自信がないから未公開。
「東電は、ERSSへのデータ送信装置と非常用電源とが未接続だったため、データが送れなかったことは認めた。そのうえで、
会見した松本純一原子力・立地本部長代理は『いつまでに(接続)工事をしなければならないのか、国と約束ができていなかった。
緊急性が高い工事という認識はなかった』と述べた。」
「保安院会見に同席した同機構の担当者は『東電には接続しておくように指示した』と証言し、東電説明とニュアンスが異なる。
接続できなかった原因も東電と保安院の言い分は食い違う。東電は『事前に(ケーブルの長さを)確認して用意したが、情報が違っており、
長さが足りなかった』と説明。保安院は『東電が(非常用電源の)設置場所を間違えたため届かなかった』。」
東電は緊張感もないもない。国も予算だけ取って、計画や工程表のことなど気にもしていなかった事が明白なったと思う。
保安院は安全を口にするが、本当に安全のことなど考えていない。住民を安心させる口実を考え、安全を優先して対応している演技を
組織でやっているのだろう。このような確実に確認するだけで防げる問題を解決できない保安院は安全を判断する能力なし。大きく違う
説明は、書類による記録及び重大と思われる議論については録音を必要とすることを証明している。記録の保存及び議論や会議の録音を
義務付けないのなら保安院はやはり国や政治家の「イエスマン」であり、技術者及び専門家集団ではなく、役者の集団と言うころだろう。
福島第1原発 電源、未接続 責任なすり合い 01/17/12 (読売新聞)
■保安院「東電の設置ミス原因」/東電「震災まで保安院と調整」
福島第1原発の原子炉データを国の原子炉監視システム(ERSS)に送信する装置の非常用電源が外れたまま放置されていた問題で、非常用電源と送信装置をつなぐ接続ケーブルの長さが足りなかったのは、東電が送信装置を誤った場所に設置したのが原因であることが19日、経済産業省原子力安全・保安院の会見で明らかになった。保安院の原子力保安検査官が設置工事に立ち会っていたが、未接続に気付かなかったという。
保安院によると、平成22年11月に行われた設置工事では、データ送信装置と非常用電源ケーブルは、現地の原子力保安検査官が詰める同原発内の部屋に置かれた。その際、工事をした東電側が送信装置を本来置くべき棚ではなく、別の棚に設置したため、非常用電源のケーブルが届かず、接続できなかったという。保安院が未接続を知ったのは、震災後に事故検証を進めていた昨年夏ごろという。
保安院が未接続を把握後も公表しなかったことについて、森山善範原子力災害対策監は「私自身が知らなかったので、機会を逸した」と弁明した。
全国の原発の原子炉データを把握・監視するERSS。そのシステムをないがしろにする“失態”をめぐり、当事者の東京電力と経済産業省原子力安全・保安院が19日、それぞれ会見を開いた。両者の説明はまったくかみ合わず、責任のなすりつけ合いの様相を呈した。(原子力取材班)
東電は、ERSSへのデータ送信装置と非常用電源とが未接続だったため、データが送れなかったことは認めた。そのうえで、会見した松本純一原子力・立地本部長代理は「いつまでに(接続)工事をしなければならないのか、国と約束ができていなかった。緊急性が高い工事という認識はなかった」と述べた。
地震の4カ月前から未接続のまま放置していたことについては、「接続工事をすると通常時のデータ送信が止まるため、ERSSを所管する保安院と調整していた」と説明。「作業をどうするか未調整のまま3月11日を迎えた」とした。
一方、19日午後に緊急会見を開いた保安院の説明は、東電の見解とはまったく違う内容だった。
「保安院としては、接続できていないことは(震災後の昨年)8月か9月ごろまで知らなかった」。保安院の森山善範原子力災害対策監はそう説明した。事実とすると東電が説明した「保安院との調整」はなかったことになる。
森山氏によると、平成22年11月に東電が非常用電源を接続しようとした際、保安院が監視システムの管理を委託した原子力安全基盤機構が立ち会った。原子力保安検査官もいたが、保安院本院への報告はなかったという。
保安院会見に同席した同機構の担当者は「東電には接続しておくように指示した」と証言し、東電説明とニュアンスが異なる。接続できなかった原因も東電と保安院の言い分は食い違う。東電は「事前に(ケーブルの長さを)確認して用意したが、情報が違っており、長さが足りなかった」と説明。保安院は「東電が(非常用電源の)設置場所を間違えたため届かなかった」。
工事実施の経緯についても、東電は「自主的な取り組み」を強調したが、保安院は「機構が全国の原発に指示したもの」という。
安全に関する大問題にもかかわらず、大きく食い違う言い分。どちらが事実なのか。東電は「事実として把握しているのは説明した通り」と主張、保安院の担当者は「東電はなぜそんな説明をするのか…」と話している。
「県教委は『段位を与えるかは連盟の判断』とし、連盟は『受講者は柔道経験がある人ばかり。体育教員としての運動能力も考慮すれば、初段のレベルに十分達している』と説明、見直しの予定はないという。」
県柔道連盟が特例措置として行ってきたこと、「初段のレベルに十分達している」ことを確認できるのであれば問題ないであろう。つまり、大分県柔道連盟による
柔道指導者2日間講習を受ければ体育教員であれば2日後には「初段のレベルに十分達する」根拠や過去のデーターがあると言うことだ。大分県教育委員会
との馴れ合いでなく体育教員であれば誰であっても初段レベルに達することが出来る講習内容を他の県の柔道連盟は勉強するべきだろう。大分県柔道連盟に出来て、
他県の柔道連盟に出来ないはずはない。2日以上の講習は時間の無駄である。他の項目に時間を配分するべきだ。
講習2日で柔道黒帯、20年以上続く「特例」 01/17/12 (読売新聞)
大分県教育委員会が中学、高校の体育教員を対象に開いている柔道指導者講習で、2日間受講した教員が段位(黒帯)認定を申請した場合、県柔道連盟が特例措置として、段位を与えていることがわかった。
県教委によると、講習は毎年、2日間の日程で実施。柔道指導の豊富な講師を外部から招き、受け身や技の掛け方、安全管理などを学ぶ。2011年度は受講者48人のうち14人が認定を申請し、全員が初段に認定された。特例措置は、少なくとも20年以上前から続けられている。初段の認定試験は通常、14歳以上で1年~1年半の経験者が受験できる。
県教委は「段位を与えるかは連盟の判断」とし、連盟は「受講者は柔道経験がある人ばかり。体育教員としての運動能力も考慮すれば、初段のレベルに十分達している」と説明、見直しの予定はないという。
体育教員への柔道の指導者講習を巡っては、愛知県内でも、30年近く受講者全員に段位が授与されていることが判明している。
猛者揃い?わずか2日で柔道黒帯 大分の体育教員研修 01/17/12 (読売新聞)
大分県柔道連盟が県内の中学、高校の体育教員に、2日間の講習を受けるだけで柔道の黒帯(段位)を授与していたことがわかった。講習は、同県教育庁が連盟に委託して開いており、約30年前から毎年1回行っている。
県教育庁体育保健課によると、2011年度は14人が、10年度は5人が受講し、全員、初段になり黒帯をもらった。これまで受講した体育教員のほとんどが合格したという。
剣道も柔道の講習と同じ日に2日間の講習を開き、11、10年度あわせて、受講した4人全員が初段に合格したという。
「原発での偽装請負は慣習」下請け会社会長が証言 01/16/12 (朝日新聞)
関西電力大飯原子力発電所(福井県おおい町)での偽装請負事件で、福岡、福井両県警に社長が逮捕された高田機工(福井県高浜町)の高田稔会長(78)が15日、朝日新聞の取材に応じ、原発での偽装請負は「業界の慣習だった」と語った。原発関連の取引のあった別の建設業者も同様の証言をしており、働き手の確保が難しい原発関連の業界で偽装請負が常態化していた可能性もある。
高田機工社長の富田好容疑者(59)は、元請けの太平電業(東京)、孫請けの総進工業(北九州市若松区)とそれぞれ建設請負契約を結び、実際には総進工業の社員を太平電業に派遣して働かせた職業安定法違反の疑いが持たれている。
高田会長は偽装請負について「原発の下請けに入ったら、この方法が当たり前だと思っていた。福島や九州など、どこの原発でも、やっているのではないか」と述べた。
原発工事の偽装請負「何十年もやってきた」 01/15/12 (読売新聞)
関西電力大飯(おおい)原子力発電所(福井県おおい町)の維持改修工事を巡る偽装請負事件で、職業安定法違反容疑で社長の富田好(よしみ)容疑者(59)が逮捕された高田機工(福井県高浜町)の会長(78)が、読売新聞の取材に応じた。
「我々の業界の商慣習のようなもの」と偽装請負を認めたうえで、指定暴力団・工藤会(本部・北九州市)系組長の妻、池上加奈枝容疑者(36)が社長を務めるドリーム(旧総進工業)から、原発以外の工事も含め延べ約1000人の派遣を受け、1人あたり1万8000円前後の日当を支払ったことを明らかにした。
事件では、太平電業福井地区営業所長(当時・大飯事業所長)の一瀬秀夫容疑者(58)と富田容疑者が職業安定法違反容疑、池上容疑者が同ほう助容疑で逮捕された。2010年3~9月、当時の総進工業が高田機工を通じて太平電業に作業員を派遣していたが、請負契約のように偽装して太平電業の指揮下で働かせていたとされ、福岡、福井両県警は、太平電業が主導したとみて捜査している。
会長は13日に取材に応じ、偽装請負について「間違いなし。あったことだから」と述べた。「何十年もやってきている。他の原発でも行われており、言われてみれば法律違反だが、罪の意識はなかった」と語った。理由について「原発関連工事は不慮のアクシデントが多く、予測がつかない。形だけ請負契約として、かかった費用をまとめて支払ってもらうのが、互いにとって合理的」と説明。太平電業との関係には「長年の付き合いで親と子のようなもの。親に言われれば従う」とした。
総進工業とは数年前、北九州市の大手企業の関連工事を受注した際、知り合いの業者から「いい職人がいる」と紹介され取引を開始。「職人たちは真面目で使いやすかった」といい、日当については「総進工業の取り分がいくらかは分からない」と話した。11年7月頃、福岡県警の捜査員が訪れた際に総進工業と工藤会との関係を知り、同年秋に契約を終了したという。
太平電業社長名の基本契約書を押収 関電偽装請負事件 01/14/12 (朝日新聞)
関西電力大飯原子力発電所(福井県おおい町)での偽装請負事件で、福岡、福井両県警が元請けの太平電業など関係先を家宅捜索し、建設請負契約を偽装した基本契約書を押収していたことが、捜査関係者への取材でわかった。同社の高橋徹社長名の印鑑が押してあったという。両県警は契約書を作った経緯や太平電業の組織的な関与の有無を調べる。
捜査関係者によると、基本契約書は太平電業と下請けの高田機工との間で、大飯原発の保守点検に関して建設請負契約を結ぶ内容で、高橋社長の名と高田機工の富田好容疑者(59)=職業安定法違反容疑で逮捕=の名も書いてあったという。建設請負契約を結ぶには、工事内容や契約額、着手と完成の時期などを記入した書面に、双方の代表者名を記すよう建設業法で定められている。
太平電業の福井地区営業所長、一瀬秀夫容疑者(58)=同=は調べに対し「虚偽の契約書であることは間違いない」と供述しているという。自ら高田機工に人集めを依頼したとも話しているといい、両県警は太平電業が主導して、違法な労働者派遣を請負契約のように偽装したとみている。
富田容疑者も「虚偽の契約書であることは間違いない」と認めているという。
日本が他の国と比べて劣るとは思わない!しかし透明性に関しては疑問を感じる。ウッドフォード氏、悲しいけどこれが日本社会だよ!
日本を理解しているのなら日本の問題点を理解するべきだった!多くの株主は大損をした!多くの株主(銀行や証券会社)は不正よりも損得を重要視していると
思う。多くの国民も正義よりも少し我慢しても安定を求め、争いを避ける傾向がある。こういう国なんだよ。
「日本が好きだから悲しい」 ウッドフォード氏が帰国 01/09/12(朝日新聞)
来日していたオリンパス元社長のマイケル・ウッドフォード氏が8日、成田空港から母国イギリスへの帰路についた。社長復帰を目指したものの、現経営陣との委任状争奪戦(プロキシファイト)を断念せざるをえなくなり、失意の帰国。社長解任は不当だとしてオリンパスに損害賠償を求める訴状を、すでにロンドンの雇用審判所に提出したという。
「悲しい。しかし、やはり銀行の協力がないと、委任状争奪戦で勝利したとしても建設的な結果にならない」。ウッドフォード氏は離日直前、メーンバンク(主取引銀行)を含む国内の主要株主から支持が得られなかったことへの無念を改めて語った。
ウッドフォード氏が告発したオリンパスの不正経理事件。同社はバブル崩壊直後から約20年にわたって巨額の損失をひそかに抱え、投資家らの目を欺き続けていた。その隠蔽(いんぺい)に加担した一部の幹部が社内で優遇されるなど、人事もゆがめられた。告発があって第三者委員会が設けられ、ようやく日本の捜査機関も動き始めた。本来は株主や顧客に還元されるべき利益はどこに行ったのか。不透明な流れの解明が進んでいる。
ウッドフォード氏が不正経理とともに問題視したのは、取締役たちの「イエスマン」ぶりだ。常識で考えても不自然と容易に分かる巨額の支出について、高山修一・現社長は当初「適切だった」と明言。第三者委が「会社を私物視する意識が蔓延(まんえん)」「感覚が鈍磨していた」と、チェックできなかった取締役らを批判したにもかかわらず、取締役の一人だった高山社長は一時、自身の続投に含みを持たせた。ウッドフォード氏は「道化師でも会社を経営できるのか」とその姿勢を酷評した。
また、そうした高山社長らに大株主やメーンバンクから批判の声が上がらなかったことも、不思議でならなかったという。理屈の上では、銀行にも株主がおり、銀行経営者も株主への責任を果たさなければならない。オリンパス株価の下落で巨額の損失を出したのに銀行がそれを黙認しているように見えるのは、なれ合いがあるからではないか。ウッドフォード氏はそう疑っている。
帰国直前の8日朝、ウッドフォード氏は一人で東京・西新宿を歩き、オリンパス本社を眺めた。「解任された10月以降、いい人たちに会えて、私はますます日本を好きになった。だからなおのこと悲しい。この会社を国際的な日本の模範例にできれば素晴らしかったのだが……」。そう語って東京を離れた。(奥山俊宏)
結局、これか!
オリンパス:東証 上場維持の方向で最終調整へ 01/08/12(毎日新聞)
オリンパスの損失隠し問題で、東京証券取引所が有価証券報告書の虚偽記載で上場可否を審査中のオリンパス株について、上場を維持する方向で最終調整に入ったことが8日、わかった。同社が実際に債務超過に陥っていなかったことや、損失隠しが組織ぐるみと言い切れない点、上場廃止となった場合、株主へ多大な影響を与えることなどを考慮した。東証は上場を維持するが、新たに「特設注意市場銘柄」に指定し、「上場契約違約金」(1000万円)の支払いも求める方針だ。
特設注意市場銘柄は内部管理体制などに重大な問題があった企業の株式を東証が指定する制度で、指定から3年たっても改善されない場合は上場廃止となる。上場契約違約金は株式市場に対する投資家の信頼を傷つけたことに対するペナルティーとなる。過去には架空売買による不正な会計処理が問題となったメルシャンなどが、上場廃止を回避したうえで特設注意市場銘柄に指定され、上場契約違約金の支払いを求められたことがある。
東証はオリンパスの第三者委員会が報告書を提出した昨年12月6日、上場廃止基準に抵触する有価証券報告書の虚偽記載が明らかになったとして、投資家に上場廃止の可能性を周知する「監理銘柄」にオリンパス株を指定。東証内で市場監視を担う「自主規制法人」と呼ばれる部門が審査し、関係者へのヒアリングをほぼ終えた。
東証によると、有価証券報告書の虚偽記載による上場の可否判断に数値的なルールはなく、上場廃止となるのは「影響が重大であると認める場合」としか規定に書かれていない。東証は虚偽記載の期間の長短や会社の規模から見た不正経理額の大小、債務超過の有無、不正への組織的なかかわりや株主への影響などを総合的に判断することになっており、今回は上場維持が適切と、月内にも正式に最終判断する方針だ。【浜中慎哉】
高濃度汚染車両、原発外に 東電、適切な管理怠る 12/31/11(朝日新聞)
東京電力福島第一原発の事故当時、原発敷地内に駐車していて高濃度に汚染された東電社員らの車について、東電が適切な管理を怠っていた。なかには、中古車市場に流通したり、近隣住民との間でトラブルを起こしたりしている車も出ている。専門家は「放射線量の高い車は、敷地内で発生したがれきと同様に扱うべきだ」と指摘している。
東電広報部によると、震災から12日後の3月23日からJヴィレッジ(福島県楢葉町、広野町)で放射線検査と除染を始め、一定レベル以上の放射線量の車は外部に出せなくしたが、それ以前は原発敷地内から検査なしで車を持ち出すことが可能だった。震災時、原発内には東電社員755人と協力企業の従業員5660人がいた。社員らが駐車していた車や事故後に持ち出した車の台数は「把握していない」という。
今年6月、東電社員から修理を頼まれたという福島県内の自動車修理業者は、「車のワイパー付近で毎時279マイクロシーベルトを計測したんです。何で、こんな車が原発の外に出るのか」と憤り、測定した際の写真を差し出した。仮に1日12分間浴びた場合、年間被曝(ひばく)量が、国が避難を促す目安の年間20ミリシーベルトを超える値だ。
福島第1原発:1号機非常用電源部屋、91年に浸水事故 12/29/11(毎日新聞)
東京電力は29日、福島第1原発1号機のタービン建屋で91年10月30日に原子炉の冷却用海水が配管から漏れ、地下1階にある非常用電源の部屋が浸水していたことを明らかにした。電源機能は維持されたが、原子炉は同日、停止した。当時から浸水の危険性があったにもかかわらず抜本対策は取られてこなかったことになる。
東電によると、配管は建屋床下の地下にあり、原子炉の熱を海水を通して逃がす役割を担っている。ところが、配管が腐食し中の海水が毎時20立方メートルで漏れた。海水は、扉やケーブルの貫通口などから非常用電源のある部屋にも浸水。2台のうち1台の電源の基礎部分まで冠水したが、駆動機構は無事だったという。
東日本大震災では、津波が地上にある開口部から浸水し非常用電源や配電盤が使えなくなった。原子炉の冷却が困難となり、炉心溶融を招く一因となった。【岡田英】
無実とのこと。面白い展開になった。誰かが大嘘をついているのは確か!これで取引先の男性の聴取はしなければならないだろう。
被害者であると思われる女性の供述の整合性を確かめるためにも必要!無実なら戦うべきだし、無実でないのに無実を主張し、
嘘だとわかったら芸能界人生の終わりかもしれない。週刊誌やメディアも動くだろうから、今後の展開を見守りたい。
大沢伸一が逮捕「100%無実なので、信じてください」 12/29/11(ナタリー )
大沢伸一が12月14日、準強姦の疑いで警視庁野方署に逮捕されていたことが明らかになった。
大沢は部下の女性に対し「取引先の男性の相手をしてほしい。そうしないと会社がつぶれる」と命じ、都内のホテルで男性とわいせつな行為をさせた疑い。これを受けて14日に逮捕されたが本人は「身に覚えがない」と容疑を全面的に否認しており、18日には処分保留で釈放されている。
この逮捕に伴い、12月16日東京・新木場ageHaで開催された「ASOBINITE!!! -冬の陣-」と12月17日新潟・The Planetの「The PLANET Opening Party Vol.35」への出演はキャンセルとなった。
しかし大沢はすでに通常の音楽活動に復帰しており、先日12月23日大阪・心斎橋AVENUE Aのイベントには予定どおり登場。また、本日12月29日東京・代官山AIRで行われる「OFF THE ROCKERと☆Taku TakahashiのBIGな忘年会!!!」、12月31日新木場ageHaの「ageHa COUNTDOWN2012-SUNRISE-」にも予定どおり出演することが決定している。
大沢は今後、自身の潔白を証明するためにも引き続き警察の捜査に全面的に協力していくとのこと。
また、所属会社であるエイベックス・マネジメントもあわせてコメントを発表している。
大沢伸一コメント
逮捕された事は事実です。しかし僕がこの事件に関与してる事は全くありませんし、身に覚えのないことと、完全に否認しています。勿論現在は釈放されていますし、普段どおり音楽活動もしています。その上で警察の捜査には最大限の協力を申し出ており、一刻も早く真相が解明され、自分への嫌疑が晴れる事を望んでおります。
この報道によって関係者各位の方や音楽ファンの皆様には大変心配をおかけしておりますが、僕は100%無実なので、信じてください。
芸能界には詳しくないがそれなりに実績を残しているようだ。
「自らが経営する会社に勤務する女性に『取引先の男性の相手をしてほしい。そうしないと会社が潰れる』などと命令」しなければ
ならないほど芸能界はきびしいのか?それとも同様な事は芸能界では行われているが、誰かに嫌われたために事件にされたのか?
事件になった以上、取引先の男性も事情聴取されるのだろう?(警察の判断次第だけど!)
「取引先の相手を」部下女性にわいせつ行為命令 12/29/11(読売新聞)
部下の女性に取引先とわいせつな行為をさせたとして、警視庁が音楽プロデューサーで会社経営の
「大沢伸一
容疑者(44)を準強姦(ごうかん)容疑で逮捕していたことが捜査関係者への取材でわかった。逮捕は14日。
捜査関係者によると、大沢容疑者は11月、自らが経営する会社に勤務する女性に「取引先の男性の相手をしてほしい。そうしないと会社が潰れる」などと命令し、東京都内のホテルで男性とわいせつな行為をさせた疑い。
同庁は、大沢容疑者が女性に対し、従わなければ解雇されると誤信させたことについて、準強姦罪の要件である抵抗不能な状態に陥らせたと判断した。会社の利益を図ろうとしたとみている。大沢容疑者は歌手の安室奈美恵さんらの作品を手がけていた。
6900億円の追加援助を申請をするのなら社員の給料カット、役員の給料や賞与のカットそしてリストラを先に行うべきだ。
東電:6900億円の追加援助を申請 損害賠償支援機構に 12/27/11(毎日新聞)
東京電力は27日、福島第1原発事故の賠償金を支払うため、原子力損害賠償支援機構に約6900億円の追加の資金援助を申請した。政府が来年3月末をめどに実施する避難区域の再編に伴い、賠償額が従来より膨らむ見通しとなったため。年明けにも枝野幸男経済産業相の認定を受け、機構を通じて支援資金が東電に交付される。
東電は11月に政府認定を受けた緊急特別事業計画で、年度内に必要な賠償額は約1兆100億円と見積もった。このうち、原子力損害賠償法に基づく国の補償金1200億円を除いた約8900億円が年度内に交付される。
しかし、政府の避難区域再編で長期にわたって帰宅困難地域が設定されることになったことによる営業損害や収入補償で4300億円▽精神的被害への賠償額見直しで500億円▽自主避難した住民約150万人が賠償対象に加わることで2100億円--が新たに必要となり、当初見積もっていた支援額では足りなくなった。支援合計額は約1兆6000億円に上る見込み。東電は来年3月末までに自主避難した住民からの賠償受け付けを始める方針。
東電の賠償支払い実績は27日時点で個人、法人向け合計で約2570億円に上る。賠償の実施が遅れているとの指摘もあり、請求書類の審査を簡素化するなどして、できるだけ早期の支払いを目指している。【立山清也】
やらせメールで九電社長、辞任意向…来春にも 12/26/11(読売新聞)
九州電力の真部利応(としお)社長は26日午前、福岡市の九電本社で記者会見し、玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)の再稼働を巡る「やらせメール」問題の責任を取り、早ければ来春にも任期途中で辞任する意向を示した。
真部社長はこれまで定例記者会見などをキャンセルしており、記者会見するのは2か月ぶりだ。
九電は22日、経済産業省に対し、再提出の予定だったメール問題の最終報告書の代わりに、再発防止策の文書を提出した。真部社長は「大臣に受け取ってもらった。一定の区切りと思っている」と述べた。
そのうえで、真部社長は「信頼回復には本来なら新しい体制がいい」とし、業績見通しや電力の需給状況などを見極めた上で「1~2か月後をメドに(進退を)判断したい」と述べ、来春にも後任人事を決める方針を示した。
今のままでは原発事故は防げないと思う。大事故にならないように天に祈るだけ。大事故が起こっても福島県民に対する日本政府の対応を
見ていると人事のような対応。政府や専門家達で福島県民だけでなく日本国民を騙している。その上、東電を破綻させず税金を注ぎ込み、
さらに増税と言う負担を国民に負わせようとしている。踏んだり蹴ったりである。
やらせメール:九電幕引きに佐賀県民から不満 12/23/11(毎日新聞)
九州電力の「やらせメール」問題で、九電は22日、国から求められていた最終報告書の再提出をせず、一連の問題を終わらせたい考えを鮮明にした。九電第三者委員会から「やらせメールの発端」と指摘された佐賀県の古川康知事も前日に減給処分が決まり、収束ムードを漂わせる。知事関与の核心部分をあやふやにしたまま、両者が足並みをそろえるように年内で幕引きをはかろうとしていることに、県民からは不満が噴出した。
「再提出はしない。これで終わりにしたい」。九州電力の深堀慶憲副社長はこの日、国に再発防止策の説明書を提出後、福岡市内に戻って報道陣にこう語り、「再発防止策と信頼回復に取り組むことが(九電が今後)やるべきことだと思う」と述べた。また、枝野幸男経済産業相らとの交渉窓口として、接触を重ねていた九電第三者委委員長を務めた郷原信郎氏に説明書について連絡をするかを問われると「必要ない」と断言。郷原氏に頼らずに解決策を探ったことを示した。25日には九電の全原発が運転を停止することから、今後は再稼働に向け全力を挙げる方針だ。
だが県民には「民意を置き去りにしたままの幕引き」と映っている。やらせメールの舞台となった6月の国主催の説明番組に出演した佐賀市の映画評論家、西村雄一郎さん(60)は「結局何も変わっていない。何のための第三者委員会だったのか。うやむやのうちに終わらせてはならない」と納得がいかない。
また、最終報告書の再提出を強く求めながら、九電のこの日の報告を受け入れた枝野氏に対しても「がっかりした。何か密約があるのではと疑ってしまう。裏切られた思いだ」と憤った。
玄海原発プルサーマル裁判の会の石丸初美代表は「年末になって知事が減給を表明し、慌ただしく国が受け入れようとしているのは、年が明けたら心機一転で原発を再稼働させようとしているからではないか」と指摘。「県民や国民を愚弄(ぐろう)している」と批判した。
郷原氏も「国に提出された説明書には第三者委の指摘に対する受け止めが全く書かれていない。そんな紙切れを出して幕引きにするつもりなら論外だ。常識的には社長が辞任しない限りこの問題は終わらない」と語っている。【中山裕司、竹花周、福永方人】
「配管溶接検査せず記録も改ざん」に対して「厳重注意の処分」保安院はすごく甘い。
財団法人 発電設備技術検査協会 (JAPEIC)
はISO認証
を業務の一部としておこなっている。
「技術が支える安全と信頼」を基本理念
民間の中立的な第三者機関として、コンプライアンスを重視し、誰からも信頼される公正で厳格な検査・審査を実施します
たゆまぬ努力と研鑽によって、高度の専門的知識と技術力を維持し、高品質の検査・審査を実施します
発電設備の溶接・非破壊検査に関する第一人者として、先端的な試験研究機関と研修施設を備え、皆様が直面するさまざまな課題にお応えします
ISO認証業務と
「技術が支える安全と信頼」を基本理念の
組織が「配管溶接検査せず記録も改ざん」は絶対にありえないことでしょう。チェックする組織がずさんな判断と対応をおこなった。
財団法人発電設備技術検査協会役員名簿 (平成23年9月28日現在)
を見てもすごい肩書きばかり。しかし、「配管溶接検査せず記録も改ざん」なぜこのような事が容認されたのか?
財団法人発電設備技術検査協会評議員名簿 (平成23年9月29日現在)
多くの評議員が電力会社役員である事実に問題があるのか?これが安全神話の現実と幻想の良い例だと思います。
玄海原発4号機、配管溶接検査せず記録も改ざん 12/22/11(読売新聞)
経済産業省原子力安全・保安院は22日、九州電力玄海原子力発電所4号機(佐賀県)で使用予定の配管の溶接検査で、九電から作業を受託した「発電設備技術検査協会」(東京)が電気事業法で定められた必要な検査を怠ったうえ、実施したかのように記録を改ざんしていた、と発表した。
今年9月に保安院に情報提供があり、発覚した。保安院は協会と九電に厳重注意の処分を下すとともに、他の電力8社に同様の事例がないか調査を指示した。
保安院によると、協会の検査担当者が今年8月、勘違いから検査の一部を実施しなかった。後日、誤りに気づき、書類を改ざんした。協会は「自主的に実施した検査項目もあり、誤記と判断して修正した」と説明したという。九電は不十分な管理体制を問われた。
「李氏は学位取得後に帰国し北京市で旅行会社を経営」しているのなら学位取り消しはあまり影響ないだろう。
人間性の問題だけ。
筑波大で中国人留学生が論文盗用…学位取り消し 12/17/11(読売新聞)
筑波大は16日、学位論文に盗用があったとして、システム情報工学研究科博士前期課程(経営・政策科学専攻)に在籍していた中国人留学生、李聖浩氏(31)の修士の学位を取り消したと発表した。
同大によると、李氏は2007年1月、同研究科の6人で修士論文にあたる特定課題研究報告書をまとめた際、担当した「法律・規制分析」(計28ページ)の原稿7割弱と六つの図を別の大学の研究論文から盗用していた。執筆者から指摘を受け、同大は昨年6月、調査委員会を設置。李氏は学位取得後に帰国し北京市で旅行会社を経営しており、盗用は認めたが、調査委の聴取には応じなかった。
同大では、処分内容を英語、中国語、韓国語、日本語でホームページで公開する。
清水一彦・教育担当副学長は「論文盗用をチェックするソフトウエアを必要に応じて使うなど、再発防止に努めたい」としている。
シティ銀はイメージ的に良いと思っていたが、日本だけが悪いのか、それとも組織的に問題を抱えているのだろうか?
どちらにしても今回は厳しく対応するべきだ!
シティ銀:一部業務停止へ、元本割れリスク説明怠る 12/16/11(毎日新聞)
米大手金融シティグループの日本法人、シティバンク銀行が投資信託などの金融商品の元本割れリスクを顧客に十分説明せず販売したとして、金融庁は16日、同行に対し1カ月間の一部業務停止命令を出す。同行への業務停止処分は04、09年に次いで3度目で、金融庁は同行内で法令違反防止体制が構築されていなかったことを重く見て、業務改善命令より踏み込んだ対応とした。
同行は金融商品取引法などで販売時に元本割れリスクの説明が義務づけられているのに、十分な説明を怠り販売を繰り返していた。金融庁の立ち入り検査で判明した。投資信託などの購入を勧誘するなど個人金融部門の新規販売業務を1カ月停止させるほか、経営責任の明確化や、業務の見直しを求める。
シティグループの「シティグループ証券」と外資系の「UBSセキュリティーズ・ジャパン・リミテッド」に対しても、両証券に勤務した同じ元社員が、銀行同士が資金を融通する市場で不正に金利を操作しようとしたことが証券取引等監視委員会の検査で判明したため、業務の一部停止命令を出す。シティバンク銀は処分を受け、ダレン・バックリー社長ら幹部が引責辞任する。【田所柳子】
福島県産の米の安全性が保証出来ない現状では風評被害ではないと思う。なぜ、メディアは風評被害と言うのか?
原発事故が原因の可能性についても言うべきだろう。地震だけで福島県産米を消費者が避けると思うのか。国の暫定規制値を超える放射性セシウムが
静岡で生産されたものでも確認されただろう。これは風評被害なのか、事実なのか?
コメ卸業者倒産:風評被害が原因か 東京 12/02/11(毎日新聞)
民間信用調査機関の東京商工リサーチ(TSR)は1日、福島県産米を扱っていた米穀卸「ワタナべ商事」(東京都渋谷区)が11月24日、東京地裁から破産手続きの開始決定を受けたと公表した。TSRの集計で、東京電力福島第1原発事故の風評被害が原因とみられる米穀商の倒産は初めて。破産管財人によると負債総額は2億8000万円。
TSRによると、同社は87年に設立され、日本酒の原料米や主食米を主に扱い、その約6割を福島県産が占めていた。
売り上げは03年5月期に14億円近かったが、日本酒消費の落ち込みなどでここ数年は11億円前後に低迷。さらに、原発事故後に取引先からキャンセルが相次ぎ、8月に事業継続を断念したという。【井上英介】
原子力検査会社の会長ら逮捕…特別背任容疑 12/01/11 (読売新聞)
東京電力福島第一原発の定期点検などを請け負う「非破壊検査」(大阪市)の子会社で、原子力研究施設の検査を行う「瑞豊産業」(東京都台東区)の会長らが不正融資で同社に約1億円の損害を与えたとして、警視庁は1日、元会長・水船隆昌(81)(日野市)、同社会長・山本守也(66)(千葉市)の両容疑者を会社法違反(特別背任)容疑で逮捕した。
発表によると、2人は2006年5月~07年8月、自分たちが代表取締役の電気工事会社(東京都千代田区)に返済能力がないことを知りながら、約10回にわたり総額約1億円を貸し付け、瑞豊産業に同額の損害を与えた疑い。約1億円は電気工事会社の運転資金に充てられたが、同社は昨年3月に破産した。2人とも容疑を認めているという。
コメ:福島産を宮城産と表示 仙台の業者を処分へ 11/29/11 (毎日新聞)
仙台市太白区の米穀卸大手「協同組合ケンベイミヤギ」が実際とは異なるコメの産地や銘柄を表示し小売業者らに販売していたことが分かった。宮城県や同市が日本農林規格(JAS)法などに基づき立ち入り調査しており、行政指導や処分を行う方針。
県などによると、組合は10年産のコメのうち福島県産のコシヒカリとひとめぼれを「宮城県産」と表示したり、未検査米を「青森県産つがるロマン」などと表示し販売した疑いが持たれている。情報提供を受けた県などが10月中旬に立ち入り調査を実施した結果、組合が仕入れや出荷の帳簿類を適正に作成していなかったことも判明。取引記録の作成・保存などを義務付ける米トレーサビリティー法に抵触する疑いもあるとしている。【影山哲也】
中国への不正輸出容疑で都内の会社を捜索 軍事転用可能装置 神奈川県警 11/29/11 (産経新聞)
軍事技術に転用可能な半導体製造プログラムが組み込まれた装置を中国に不正に輸出した疑いが強まったとして、神奈川県警外事課と伊勢佐木署は29日、外為法違反(無許可役務取引)の疑いで、電子機器販売会社「インターテック」(東京都品川区)の本社や支店など関係先の家宅捜索を始めた。
捜査関係者によると、同社は平成22年春ごろから、経済産業相の許可を受けずに、国内電機大手メーカーの半導体を制作するためのプログラムが組み込まれた製造装置を中国側に売却、不正に輸出していた疑いが持たれている。
軍事技術に転用可能な半導体製造装置などは、経産省が定める輸出規制に該当し、輸出の際には許可を受ける必要があると定められている。不正に輸出された装置は軍需工場の生産ラインなどに使われたとみられ、県警は製造された半導体がミサイルの誘導装置などに組み込まれた可能性もあるとみている。
東京都品川区のオフィス街にある同社が入居するビルには同日午前9時前、県警の捜査員が厳しい表情で次々と家宅捜索に入った。物々しい雰囲気に通勤途中のサラリーマンらが足を止めて見入る姿もあった。
大規模な原発事故が発生すれば想像できる以上に被害が出る。多くの国民は直接的又は間接的に理解できたと思う。
そして東京電力の対応が誠意的でないこと明らかだ。賛成又は反対にかかわらず税金が東電救済に使われている。
東電のリストラはまだまだ甘い。この現実を国民はどう判断しているのか??
個人のライフスタイルや愛着もあるのだろうが、橋下氏が勝利し、大阪府知事も橋下派が勝てば、関西に移住する選択が可能な人は
関西以南への移住も良いかもしれない。人や企業が増えれば違った大阪中心の発展もあるかもしれない。東北や関東の放射能問題はすぐには
解決されない。関東は暮らしやすかったかもしれないが関西以南での新しいスタートは良いかもしれない。ただ、原発に対する安全対策は
要求したほうが良い。関西電力の原発が東電と比べて安全とは思えない。原発事故が起これば関東や東北と関西以南のどこに住もうが関係なくなってしまう。
東京電力:温泉施設客激減で原発影響否定 水戸地裁初弁論 11/25/11 (毎日新聞)
東京電力福島第1原発事故の影響で利用客が激減したとして、約130キロ離れた茨城県大洗町の日帰り温泉施設「潮騒の湯」が東電に約4700万円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が24日、水戸地裁(窪木稔裁判長)であった。東電側は「施設の損壊など震災の影響が原因で、事故とは因果関係がない」と請求棄却を求める答弁書を出し、全面的に争う姿勢を示した。
訴状によると事故に伴い、施設前の海や海産物の汚染を人々が懸念したため「施設は最大のセールスポイントを失い、客が激減した」と主張。事故が未収束で放射性物質の拡散が続いている以上「人々が抱く『重大な危惧感』は風評被害とはいえない」と指摘している。
これに対し東電側は「消費者心理や施設の損壊など震災自体の影響だ」として、事故との因果関係や賠償責任を否定した。【酒井雅浩】
不祥事や事故は不正や問題点を浮き彫りにする良い機会だ。都市対抗野球の費用も原価に入っているのであれば、
消費者に納得してもらうべき。多くの消費者が必要ないと思えば、削減するべきだろう!
都市対抗野球の費用も原価に!電力と同じ都市ガス料金の構造 11/18/11 (「週刊ダイヤモンド」)
「料金システムをめぐる議論は、電力業界にとどまらず、ガス業界にも及ぶのではないか」――。
ある都市ガス業界の関係者は、不安の色を隠さない。
都市ガス料金も、電気料金と同じ公共料金システムを採用しているからだ。
それは総括原価方式と呼ばれ、燃料費や人件費、設備修繕費などの原価に、一定の利益(事業報酬)を上乗せして料金を算出するものだ。
巨額な損害賠償を抱える東京電力への政府の第三者委員会「東京電力に関する経営・財務調査委員会」の調査以来、総括原価方式の問題点が注目を集めた。
総括原価方式は、長期的な設備投資は計画を立てやすいという利点はあるものの、その反面、十分なコスト削減努力が反映されないという点や、そもそも不適切な費用項目が料金の原価に含まれているのではないか、という点などが議論されている。
実際、第三者委員会が10月3日、発表した報告書のなかで、直近の10年間で見積もった料金の原価が実績よりも約6000億円多かったことを指摘。総括原価方式による料金の原価のなかに、オール電化関連の広告費や寄付金、社員の福利厚生費などが含まれていたことが明らかになり、批判の対象となった。
枝野幸男経済産業相は9月28日、日本ガス協会の鳥原光憲会長らと懇談後、記者団に対して「優先順位が高いのは電力」としながらも、「同じようなシステムを持っている他の分野も検討を進める」と発言、都市ガス料金も見直し対象にするという認識を示した。
それ以降、都市ガス業界の関係者らは、電気料金と同様に世間の批判がガス料金にも及ぶことを懸念しているのだ。
都市ガス業界の関係者らは「電力会社と同じ土俵で比べられても困る」と強調する。
確かに、わずか全国10社という寡占状態で政治力も強い巨大な地域独占の電力会社に対し、都市ガスの事業者数は200社以上もあり、都市ガスの営業エリア近隣には多数のプロパンガス事業者が営業を行っている。
地域独占の規模という面では、電力会社とは比べようがない。
だが、問題なのは、ガスの普及に関する広告宣伝費や、福祉厚生費など、東京電力で問題視された費用とほぼ同様の原価が、都市ガス料金にも含まれていることだ。
ある関係者は、「大手都市ガス会社を例にみれば、電力会社のオール電化に対抗し、ガスの需要を啓蒙するテレビ宣伝のほか、都市対抗野球の費用も福利厚生費として料金の原価に入っている。電気料金が問題視されるなら、都市ガス料金も例外ではない」と指摘する。
少なくとも総括原価方式という公共料金の制度に対する世間の目が厳しくなることは間違いなさそうだ。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 山本猛嗣)
戸籍不正取得、1万件超か…依頼ルート確立 11/13/11 (読売新聞)
愛知県警捜査員らの戸籍謄本や住民票の写しの不正取得事件で、同県警に偽造有印私文書行使などの容疑で逮捕された東京都中野区、「プライム総合法務事務所」実質経営者の奈須賢二(51)、練馬区、司法書士佐藤隆(50)両容疑者らのグループは、全国各地の探偵事務所や調査会社から依頼を受け、不正取得を繰り返していた疑いのあることが分かった。
プライムが不正取得した戸籍情報は少なくとも1万件に上るとされ、県警は、奈須容疑者らのグループに情報入手を依頼するルートが業界内に確立していたとみている。
捜査関係者によると、依頼は、粟野貞和容疑者(62)が代表を務める横浜市の探偵会社「ガルエージェンシー東名横浜」に集約。粟野容疑者は写し1件につき、約1万円でプライムに取得を依頼していた。
融資した銀行、証券会社や大株主を助けるために
証券取引等監視委員会(ウィキペディア)
が上場廃止回避を検討しているように思える。
証券取引等監視委員会(国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 545(JUN.14.2006) )
は必要ない。このような判断しか出来ない組織は必要なし。
公平な判断をしない国家なのに、偽善者のように平等とか自由とか政治家は言う。騙される日本人達に同情する必要はないと言う事か?
増税も行われる。働けど、働けど、報われない社会!この国はおかしい。
オリンパス、上場廃止回避の可能性も 11/13/11 (読売新聞)
光学機器大手「オリンパス」の損失隠し問題で、証券取引等監視委員会が、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑について行政処分にとどめる方向で検討を始めたことにより、同社の上場廃止が回避される可能性が出てきた。
一方、監視委では、同法違反(偽計)を適用する方針も浮上しているが、検察内部には虚偽記載罪の刑事責任を問うべきだとの意見が強く、今後、東京地検、警視庁との間で協議を行い、最終判断する。
同社は現在、東京証券取引所の監理銘柄に指定され、上場廃止が懸念されている。東証の上場廃止基準によると、投資判断に重大な影響を与える有価証券報告書の虚偽記載があった場合は上場廃止とされる。だが、監視委が同社に課徴金を科すよう金融庁に勧告することで、虚偽記載では刑事責任を問われなければ、基準に抵触せず、廃止が回避される公算が大きくなる。
オリンパス虚偽記載、行政処分へ 上場廃止判断に影響も 11/12/11 (読売新聞)
オリンパスの損失隠し問題で、証券取引等監視委員会は、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑については同社の刑事責任を問わず、行政処分の課徴金にとどめる方向で検討を始めた模様だ。同社が近く、過去の有価証券報告書の訂正を財務局に出すことが条件。東京証券取引所による上場を廃止するかの判断にも影響を及ぼすとみられる。
その一方で監視委は、2006~08年の巨額の買収や投資助言会社への支払いについては、実際には損失を解消する目的があったのに株価の維持をはかるために市場に知らせなかった疑いが強いとみて、同法違反(偽計)容疑での刑事告発を検討していくという。
オリンパスをめぐっては、東証が10日に、上場廃止のおそれがあると投資家に注意をうながす「監理銘柄」に指定した。今年7~9月期の決算報告書が来月14日までに財務局に提出されなかった場合や、過去の有価証券報告書に刑事責任を問われるような重大な虚偽記載があれば、上場廃止となる。
オリンパスの不透明なM&A、金融庁と監視委に調査要請=民主政調副会長 10/25/11 (ロイターニュース)
[東京 25日 ロイター] 民主党の大久保勉政調副会長は25日、M&A(合併・買収)資金の不透明な流れが指摘されている光学機器メーカー、オリンパス(7733.T: 株価, ニュース, レポート)の問題について、異常な取引と述べ、金融庁と証券取引等監視委員会に対して調査するよう要請したことを明らかにした。
日本の企業統治(コーポレートガバナンス)や株式市場の信頼性にかかわる問題に発展する懸念があるとし、経営陣は早期に経緯を明らかにすべきと述べるとともに、国会でも取り上げる可能性を指摘した。ロイターに対して語った。
大久保氏は、25日に金融庁の担当者に対し、オリンパス問題に関する報道について「事実かどうか、少なくとも金融庁はしっかり調べ、証券等監視委員会も関心を持つべき」と伝え、調査するよう要請したことを明らかにした。オリンパス(7733.T: 株価, ニュース, レポート)は、英医療機器メーカーのジャイラス社買収でフィナンシャル・アドバイザー(FA)に6億8700万ドル(当時のレートで約687億円)を支払ったことを公表しているが、資金の実態などが不透明として米連邦捜査局(FBI)も調査に乗り出している。
大久保氏は、買収をめぐる巨額なFA資金と不透明な資金の流れについて「異常」と指摘し、オリンパス経営陣が早期に経緯を明らかにする必要があると述べるとともに、実態の解明を急ぐべきだと強調。「少なくとも投資家が納得するようなかたちで経営陣が説明し、それに対して責任をとらない限り、日本のコーポレートガバナンス(企業統治)や株式市場の信頼性が薄れる」と危機感を表明した。また、「日本企業のコーポレートガバナンスが欠落しているとみなされる恐れが出てくれば、金融庁や東証、もしくは監査役、社外取締役などの制度を再点検する必要が出てくる」と制度の改正・強化の必要性にも言及した。
さらに、こうした日本企業のガバナンスや株式市場の信認に係わる問題は「国会としても看過できない」と指摘。状況によっては、金融担当大臣や東証社長らも含めた議論が必要になるとし、国会の場で問題を取り上げる可能性があると語った。
(ロイターニュース 伊藤純夫)
幹部が組織的にやっただけなんだろ!
証券取引等監視委員会(国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 545(JUN.14.2006) )
は調べなくて良い。
証券取引等監視委員会(ウィキペディア)は必要なし!
オリンパス、ファンドに多額出資で「飛ばし」か 11/12/11 (読売新聞)
光学機器大手「オリンパス」の損失隠し問題で、同社が、2000年に設立した投資ファンドを使って損失隠しを行った疑いがあることが関係者の話でわかった。
出資金300億円には、多額の含み損を抱えた有価証券などが充てられており、同社は出資金名目で“損失飛ばし”を行ったとみられる。同社は、このファンドを通じ、損失の穴埋め工作に使った国内3社を買収しており、証券取引等監視委員会は、このファンドが不正工作解明のカギを握っているとみて調べている。
オリンパスが損失隠しに利用した疑いがあるのは、2000年に設立した投資ファンド「G.C.New Vision Ventures(GCニュービジョンベンチャーズ)」。オリンパスは、00年1月の取締役会で事業投資ファンドへの出資を決議。GCファンドを設立し、翌01年3月までに有価証券などで300億円を出資した。目的は、カメラ、内視鏡など既存の事業とは別に中核事業を育てるためとされた。
社説:オリンパス粉飾 不正の根源の解明を 11/09/11 (毎日新聞)
英国人の元社長が指摘した企業買収をめぐるオリンパスの不明朗な資金の動きは、先送りしてきた損失を穴埋めするための操作であったことが判明した。不正経理は90年代から続いていたという。長期にわたって行われていた粉飾の実態を明らかにし、それにかかわっていた経営者への民事、刑事両面での責任も厳しく問われなければならない。
「買収は適正に行われた」と一貫して説明してきたオリンパスが、一転して自ら不正経理を認めたのは、7日夕になり菊川剛前会長兼社長らが高山修一社長に損失隠しを明らかにしたからだという。
今回のオリンパスをめぐる問題の発端は、マイケル・ウッドフォード元社長の解任だった。英国の医療機器メーカー「ジャイラス」の買収に伴う投資助言会社への高額の支払いに疑問が投げかけられた。
また、国内の電子レンジ容器製造販売会社など3社の買収に伴う損失計上の問題も明らかになり、海外のメディアが大きく報じ、欧米の捜査機関が調査に着手するといった展開をたどった。
菊川氏らが損失隠しの事実を明らかにしたのは、こうした圧力に抗し切れなくなったからだろう。逆に言うと、ウッドフォード氏の社長就任と、半年足らずでの解任がなかったら、粉飾による隠蔽(いんぺい)が続いていたかもしれない。
高山社長は、損失隠し問題の責任者は菊川氏と森久志前副社長、山田秀雄常勤監査役の3人だとして、「必要があれば刑事告発も考える」と述べた。
証券投資で生じた多額の損失が決算書などに記載されず、ごく一部の関係者しか把握しない「含み損」として、長期にわたって扱われていたとみられるが、この粉飾がなぜチェックできなかったのか、他の取締役の責任も含めて徹底的な検証が必要だ。また、決算と経営をチェックしてきた監査法人の責任も重大だ。
オリンパスに対する海外からの疑念は日本の企業社会全体にも向けられている。有価証券報告書への虚偽記載の疑いが濃厚で、上場廃止の可能性もある。
先送りしてきた損失の額や、それを穴埋めするための操作がどのように行われたのか。オリンパスの不正経理の詳細はこれからの調査にかかっているものの、不正防止のために制度整備が続けられてきたにもかかわらず、チェック機能が働いていなかった点を重く受け止めるべきだ。
日本企業のガバナンス(企業統治)が問われており、海外からの疑念を払拭(ふっしょく)する意味からも、証券取引等監視委員会や東京証券取引所などには、厳正な対応を求めたい。
オリンパス:「飛ばし」で数百億円隠蔽か 11/09/11 (毎日新聞)
「会社ぐるみと言われれば、そうかもしれない」。オリンパスの高山修一社長は8日の会見でそう述べ、損失隠しが組織的に行われていた可能性を示唆した。同社が不正経理を認めたことから、証券取引等監視委員会は金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで調査を開始。同社は損失隠しの手口を明らかにしていないが、関係者によると、ペーパー会社などに簿外債務として移す「飛ばし」と呼ばれる手法が取られたとみられる。
会見によると、同社は90年代から有価証券投資などで生じた損失を隠蔽(いんぺい)。08年までのM&A(企業の合併・買収)に伴う投資助言会社への支払いや買収資金を、損失穴埋めに充てていた。隠蔽した損失額は明らかにしなかったが、投資助言会社への支払いに約660億円、買収資金には約734億円が充てられたことから、数百億~1000億円の規模だった可能性がある。こうした損失は毎年提出する有価証券報告書に記載されていない可能性が高い。
隠蔽の手口についても同社は説明を避けたが、過去の同種事件では海外に設立したペーパー会社などに損失を付け替える「飛ばし」という手法が横行している。関係者によると、オリンパスでも同様の処理が行われたとみられる。
監視委幹部は「今どきこんなことをやっている会社なんてない」と驚きを隠さない。監視委は組織性や常習性の有無▽隠蔽など悪質性の認識▽他の容疑での立件の可否--などを総合的に調査し、東京地検特捜部への刑事告発を視野に入れた強制調査に移行するか判断する模様だ。【川名壮志】
株主による訴訟決定だろうね!ああ、これでまた日本人は偽善者で腹黒いと思う外国人が増えるよ!
「Axes(アクシーズ)」も完全に黒だね!知っていても出来る限りとぼける人達がいるんだろうね、オリンパスのように!
不正を大規模に組織的にしてきた事実は重大だ。多くの役員達が会社から追放されるのだろう!これまでの人生とお別れだ!
損失隠しで元会長「黙っていて申し訳なかった」 11/08/11 (読売新聞)
「以前の説明と異なる事実が判明しました」――。
オリンパスの企業買収を巡る巨額支出問題は8日、同社が有価証券の含み損を解消するために損失計上を先送りしていたと発表し、高山修一社長(61)が陳謝。財務担当の森久志副社長(54)が解任される異例の事態に発展した。高山社長は、先月下旬の記者会見で取引の正当性を強調したばかりで、わずか12日後に説明を全面的に翻した。刑事事件に発展する可能性を指摘する識者もおり、世界的精密機器メーカーの屋台骨は大きく揺らいでいる。
高山社長は同日午後0時半から、東京・新宿のホテルで記者会見。海外メディアも含む約130人の報道陣を前に、冒頭、「一連の問題は、過去の損失計上を先送りしたことによるものと判明した。大変申し訳ございません」とうっすらと涙を浮かべながら謝罪した。
高山社長によると、前日の7日夕、森副社長から突然、損失先送りの事実について説明を受けたという。森副社長は、1990年代に有価証券の投資などで損失が出たものの、長年、計上を見送ってきた経緯を説明し、2008年の英医療機器メーカー「ジャイラス」買収と、06~08年の国内3社の買収の際の資金を、この損失解消に利用した、と明かしたという。
会見で高山社長は「(自分は)昨夜まで知らなかった」と関与を否定。「第三者委員会の調査への情報の提供などを通じ、真相究明をすべく最善を尽くしたい」と強調。菊川剛元会長(70)からも「今まで黙っていたことについて、申し訳なかった」と陳謝があったことを明らかにした。
同社が損失隠しなどを公表したことについて、ジャイラス買収でオリンパスが巨額の報酬を支払った投資助言会社「Axes(アクシーズ)」日本法人のグループ企業元幹部は「やっぱりそうだったのか」と話す。
ジャイラス買収を巡る巨額の報酬支払いは、アクシーズと、同社と関係する英ケイマン諸島の投資助言会社「Axam」などを舞台に行われ、この幹部は資金操作の詳しい経緯などは知らなかったという。
元幹部によると、アクシーズのグループ企業は、遅くとも2000年頃には、多額の評価損を抱えたオリンパス保有の有価証券を多数預かっていた。有価証券はその時点で、バブル期の簿価で評価されており、元幹部は「バブル崩壊で抱えた損失を自社で処理できず、アクシーズに買収の助言を頼んできた」と証言した。
また、別の元幹部は、アクシーズ日本法人のオフィスで、オリンパスの財務担当の役員や部長と度々顔を合わせたことを明かす。当時、アクシーズ側とオリンパスは株式を巡る取引があったが、この元幹部は「顧客の幹部が証券会社を何度も訪れるのは不自然。通常の取引とは違うと感じた」と話した。
財団法人「日中経済協会」はたいした組織じゃないかも?
日中経済協会、1500万円を不正受給 11/08/11 (読売新聞)
日本と中国との経済交流などを進める財団法人「日中経済協会」(会長・張富士夫トヨタ自動車会長)が、虚偽の書類を作成するなどして、少なくとも過去5年の間、経済産業省から約1500万円の補助金を不正に受け取っていたことが、会計検査院が7日公表した2010年度決算検査報告書で分かった。
検査院などによると、協会は毎年、経済交流事業として中国に人員を派遣、宿泊費や日当などの経費について半額の補助を受けている。検査院が調べたところ、協会が北京に駐在していた職員1人について、日本から出張派遣したと偽り、虚偽の出張命令書や出金伝票を作成して経産省に提出し、補助金を受給していたことが判明した。不正に受け取った年約300万円の補助金は全額、本来、協会が負担すべき職員の人件費に充てられていた。
『津波想定5メートル』や『全電源喪失は考えなくていい』との条件はおかしいと誰も考えなかったのか?
日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構)の約30人の研究者で誰一人とも考えなかったのであれば、過酷事故対策は必要だが
現在の体質の組織は必要ない。形だけで間違った事を指摘できる人間がいなければ、予算や人数など増やしても意味がない。
万が一、全電源喪失が続けばどのような状態になるのか専門家であれば予想は出来た。ならば全電源喪失を考えなくても良いとの
仮定は間違っているのではないかと誰も言えなかった。原発の安全性の問題以上に問題は深刻だと思う。
この国と原発:第3部・過小評価体質/3 細る過酷事故研究 10/31/11 (東京朝刊 朝日新聞)
◇最悪から目そむけ
「津波対策の目標は5メートルだったが、15メートルの津波が来てしまった。こういう場合、どんな対策をすればよいのでしょうか」
東京電力福島第1原発事故から1カ月余りの4月下旬、東電幹部が宇宙航空研究開発機構(JAXA)を非公式に訪ねた。宇宙開発も原発のような巨大システムを操り、大事故と背中合わせにある。
JAXA側は人の手が届かない宇宙での安全対策について、ロケットや国際宇宙ステーションを題材に説明した。「まず最悪のシナリオを考え、その対策から検討を始める。人命に影響を及ぼさないことを最大の目標に据え、無人ロケットの指令破壊などミッション放棄も選択肢にある」
JAXA関係者は「原発では『津波想定5メートル』や『全電源喪失は考えなくていい』など、国から与えられた条件や規制に従っていれば、あとは考えなくていいという発想だったように感じた。廃炉になってもいいから放射性物質の拡散だけは防ぐ、という目標もありえたかもしれない」と振り返る。
福島第1原発事故のように、打つ手がないまま原子炉内の核燃料を冷やせず重大な損傷に至る過酷事故(シビアアクシデント)は、原発にとってまさに最悪のシナリオだ。原発関係者からは「想定外」との言葉が相次いだが、過酷事故研究が専門の杉本純・京都大教授(原子炉システム安全工学)は「日本には、シビアアクシデントは解決済みという誤った風潮があった」と指摘する。
過酷事故の危険性は米国で75年に提唱された。当時は「現実にはあり得ない」として軽視されていたが、79年の米スリーマイル島原発事故で現実のものとなり、欧米で対策の研究が始まった。日本では、86年の旧ソ連チェルノブイリ原発事故以降、過酷事故研究が本格化した。
杉本教授は日本原子力研究所(現日本原子力研究開発機構)で92年から6年半、過酷事故研究の炉心損傷を担当する室長として、ピーク時には三つの大型プロジェクトを同時に進めた。当時の国からの研究予算は年数億円に上り、約30人の研究者たちを抱えた。だが、03年ごろに電力会社が自主的に取り組む過酷事故対策の整備が終わると、予算は激減。杉本教授が所属していた部署の今年度の予算は2000万円弱に落ち込み、研究者らも3人程度に減った。
杉本教授は「当時の研究は、機器の故障など発電所内のトラブルが原因で起こる事故が中心で、地震や津波など外部の要因によるものは対象でなかった。最新知見に基づき、シビアアクシデントを継続して追いかける動きが、極めて弱かった」と振り返る。
福島第1原発事故を受け、国は電力会社の自主努力としていた過酷事故対策の義務化を決めた。だが、安全研究を専門とする人材は枯渇しかけている。ある専門家は「メーカーも景気が悪化すると、真っ先に安全対策スタッフを解雇してきた」と指摘する。
杉本教授は訴える。「今の日本にはシビアアクシデント研究に携わる研究者も予算も少ない。シビアアクシデント研究者の養成が喫緊の課題だ」=つづく
電力会社・崩れる牙城:東電「ゼロ連結」46社(その1) 実はOBずらり (1/2ページ)
(2/2ページ) 05/30/11(東京朝刊 毎日新聞)
◇「グループ外企業」実はOBずらり 大半が随意契約、電気料金押し上げか
東京電力と緊密な関係にあるが資本関係はないため、表向きは東電のグループ企業と認定されていない、いわゆる「ゼロ連結会社」が、関東圏内に少なくとも46社存在することが29日、毎日新聞の調べで分かった。経営陣に東電OBが並ぶこれらの企業は、取引の大半を随意契約で東電から受注。東電グループの関電工と合わせると、東電発注の電気関連工事の9割超を独占してきた。政府の「東京電力に関する経営・財務調査委員会」(下河辺和彦委員長)は、10月にまとめた報告書でグループ会社との取引が東電の高コスト体質に結びついていることを指摘しており、今回判明したゼロ連結会社も「高い電気料金」の一因になっている可能性が高い。
横浜市西区に本社がある「東電同窓電気」はゼロ連結会社の一つだ。社員360人、10年3月期の売上高は約115億円で、経常利益は3億5800万円。電柱や送電線、変圧器の取り付け、保守点検などの電気関連工事を主な業務としている。売り上げの約7割を東電とそのグループ企業から受注しており、株主には東電OB273人が名を連ねているが、東電との資本関係はない。社名の通り、東電OBが1950年に設立した会社で、創業以来、無借金経営を続ける優良企業だ。
東電との契約はほとんどが随意契約で、競争入札での受注はほとんどない。東電OBの同社幹部は「我々の仕事には特殊技術が必要だ。他社にも門戸は開かれているが、他社に発注すればコストは今よりもっと高くなるだろう」と話す。しかし、経営・財務調査委員会幹部は、ゼロ連結会社の受注価格は「受注する側の言い値に近い」と話す。
東電同窓と同様の会社は、群馬、栃木、埼玉、茨城県など東電管内の各県に複数存在し、それらのほとんどが59年ごろに東電の働きかけで設立された。当時、東電の発注工事をめぐり「関電工がすべての工事を受注している」との批判があったため、「第三者への発注を装う目的で設立したのではないか」(民間調査会社)との見方もある。
46社の内訳は、電気工事関連22社▽機械関連8社▽建築土木4社▽配管工事2社--など。経営・財務委員会は、グループ会社の経営は東電との取引に支えられていると指摘し、報告書では「外部取引の赤字を東電向け取引で補填(ほてん)した形になっているケースも多数見受けられる」と問題視した。同委員会は、東電では電気料金算定の基となる原価の見積もりが、10年間で6000億円以上過大だったと指摘したが、同委員会幹部は「東電の公表資料を見ても、『ゼロ連結会社』の全容把握はできなかった」と話し、「高い電気料金」の闇に迫ることの難しさを吐露した。
==============
■ことば
◇ゼロ連結会社
グループの中核会社との取引や役員受け入れなどを通じて、密接な関係にある企業。資本関係がなく(ゼロ)、グループ(連結)会社を記載する中核会社の有価証券報告書には記載されていないため、こう呼ばれる。中核会社との取引のほとんどは随意契約で、中核会社との関係がなければ存続が難しい会社が多い。このため、高コスト体質や経理操作などによる粉飾の温床になると指摘されている。07年の郵政民営化見直しの際にも、「郵政ファミリー企業」と日本郵政の取引実態を総点検していた「郵政事業の関連法人の整理・見直しに関する委員会」は32社をゼロ連結会社として認定した。日本郵政はこれらを統合し、子会社化した。
政治家を動かす大きな組織に依存するのも良いが、機動性がありグループの結束があるのであれば自分達が思うように動くほうが
良い事もある。大きな船は舵をきるのも遅いし、舵をきっても直ぐにはかわれない。
福井の地域農協、コメ販売を自主展開へ 全中は困惑 10/31/11 (朝日新聞)
福井県越前市の「JA越前たけふ」(冨田隆組合長、組合員数約1万人)は30日、コメの販売や肥料・農薬の購買などの経済事業について、上部団体の「経済連」経由だった従来のやり方を改め、2013年1月から100%出資の子会社「コープ武生(たけふ)」で直接手がける方針を決めた。地域の農協が主力事業で農協全体の流通網を離れて自主展開するのは極めて異例だ。
JAグループを束ねる全国農業協同組合中央会(全中)は「全国初のケースではないか」と話しており、戸惑いを隠さない。
この日の臨時総代会で正式決定した。事業譲渡でJA福井県経済連を通しているコメの流通を簡素化し、JAグループに徴収される中間手数料の削減を見込む。すでに台湾へのコメの輸出も始めており、独自の販路開拓を国内外でさらに進める。
東電の試算よりも実際に必要な額は大きいだろう。「原発が安い」はうそ。原発しかない、だから安全性を優先するべきだったとか言っている
人達がいるが、事故前に原発推進者で誰もそのような事を言わなかった。そこに問題があるのだ。ブレーキが効かない車など必要ない。
福島第1原発:作業員の休憩所は管理区域外…危険手当なく 10/31/11 (毎日新聞)
東京電力福島第1原発事故の収束作業のため東芝と鹿島が設置した作業員用シェルター(休憩所)が、法令による放射線管理区域の設定基準を超える放射線量を計測しているのに同区域に設定されていないことが分かった。このためシェルターで働く作業員は高線量を浴びながら「危険手当」を支払われていない。東芝などは東電が管理主体との見方を示す一方、東電は「シェルター設置者が線量管理を行う」と述べて見解が食い違っており、そのしわ寄せが作業員に及んでいる。
同原発では東日本大震災による事故以降、構内の免震重要棟を主な拠点として収束作業を続けてきたが、作業員が増加して手狭になったため、東芝が5月に西門のすぐ外側に作業員の休憩所としてシェルターを設置。鹿島も8月、東芝の南側に設置した。両シェルターは1~4号機から西に2キロ弱だが、原発の敷地北端よりも近い。
ところが、免震重要棟を含む原発敷地内は全て放射線管理区域と同等の「管理対象区域」とされているのに、両シェルターは対象外。東電によると、免震重要棟の空間線量は毎時1.1~29マイクロシーベルト(4日時点)、東芝シェルターは2~16マイクロシーベルト(7日時点)、鹿島シェルターは2~8.5マイクロシーベルト(同)。労働安全衛生法の電離放射線障害防止規則は3カ月で1.3ミリシーベルトを超える累積線量を管理区域の設定基準とし、毎時換算では2.6マイクロシーベルトで、両シェルターは基準を超える線量を計測している。
高線量にもかかわらず管理区域に設定されていないことについて東芝広報室は「当社は管理区域を設定する立場にない」と説明。鹿島広報室は「管理区域には設定されていないが、東電から示された線量管理、汚染防止の基準に基づき設置、運用管理を行っている」とし、東電が管理主体との認識を示唆した。
東電広報部は「(シェルターを設置した)事業者が作業員の放射線防護の観点から線量管理や汚染防止管理を行っている」とし、管理責任は東芝や鹿島にあるとの見解を示す。
原子炉等規制法の規制と労働安全衛生法の規則は、放射線管理区域を設定するのは「事業者」と定めている。収束作業は東電が事業者だが、シェルター設置は各企業が事業者とも言え、管理主体を押し付け合っている格好だ。このため放射線管理業務などに従事する作業員は、敷地内とシェルターで同じ作業をしながら、危険手当に大きな格差が生じている。【袴田貴行】
九州電力は信じている事を言えばよい。九州電力がいかにお金、影響力、そして政治力を持っていたのかがわかる。
一般の佐賀県民ではどうしようも出来ない問題。多くの佐賀県民が問題を真剣に考えれば何年後少しは変えることが出来るかもしれない。
もし、北九州で原発事故により放射能汚染があった場合、同情はしない。県民は東京電力福島第1原発事故から多くを学んでこなかった結果と
思うからだ。たぶん、福島で苦しんでいる人達や放射能汚染で影響を受けている人達以外は、実際の生活に現実感を持てないと思う。
しかし、現実に苦しんでいる人達がいるのだから、そこから学ばなければならない。広島や長崎県民以外にとっては、原爆も人事と
多くの日本人が考えているのと同じ。
福島の人達は政府に支援を求めるが間違っていると思う。東電に賠償を求めるべきだ。東電が賠償を支払わない、又は十分な額を支払わない場合、
原子力安全保安院が属する政府にどのような対応をするのか求めるべきだ。
国の支援=国民の負担を忘れてはならない。国への支援の要求は他の国民に強制的に負担を負わせる事を要求しているのと同じである。
だから、もし放射能汚染被害があったら九州に支援しなくない。県民は支援を要請する前に、何が出来るのか考え、防御策を実行するべき。
九州電力や佐賀県が多くの県民を意思を無視したのであれば、別の問題になる。
九電会長「どこを直す必要が」 やらせ問題報告再提出で 10/23/11 (朝日新聞)
九州電力の松尾新吾会長は22日夜、月内にも経済産業省に再提出する「やらせメール」問題の報告書について「監督官庁の指導には従うが、どこを直す必要があるのか。取締役会で決めたことを覆す理由を直接聞きたい」と語った。週明けにも経産省側と調整に入りたい考えだ。福岡市内で記者団の質問に答えた。
九電が14日出した報告書は、第三者委員会が指摘した佐賀県や古川康知事のやらせへの関与を認めず、枝野幸男経済産業相が厳しく批判。九電は再提出する報告書では第三者委の指摘を受け入れる方針だが、松尾氏は「見解の相違はいまでもある」として、表現などをめぐって社内で検討を続けていることを認めた。
松尾氏は6月26日の原発説明番組をめぐるやらせ投稿の発端について「九電が過剰反応してつくった知事発言メモが原因だ」との考えを改めて示した。第三者委は古川知事の発言が「やらせに決定的な影響を与えた」としており、関与をめぐる表現などについて、経産省と落としどころを調整したい意向と見られる。
九州電力の「やらせメール」は佐賀県民の問題。県民が問題を真剣に取り組む意思がなければそれで良いのじゃないかと思う。
日本は責任の追及はあまりしない。しかし、もし九州電力の原発で放射能漏れや放射能に関する事故が起きた場合、それは
佐賀県民にも事実の究明の放棄及び企業や自治体の体質問題の放置した責任があると考える。
東京電力福島第1原発事故後、恩恵を受けた地方自治体の被害者達以上に個々の判断責任は思いと思う。「絶対に安全だ」と
説明された。東京電力や国に騙されたとの理由は通用しない。
佐賀知事「辞任避けられぬ」…調査で郷原氏に 10/17/11 読売新聞
九州電力の「やらせメール」問題で、第三者委員会で委員長を務めた郷原信郎弁護士が17日、佐賀県議会原子力安全対策等特別委員会に参考人として出席した。
郷原氏は、第三者委の調査の過程で古川康知事に電話し、6月に知事と面談した九電幹部作成のメモを読み上げたところ、知事は「どんな説明をしても辞任は避けられませんね。公表はいつ頃されるのですか」と発言したことを明らかにした。
また、郷原氏によると、九電側と知事との面談の事実を知り、委員長就任前日の7月26日夜、福岡市内で古川知事と会談し、知事に辞任を促したという。特別委で郷原氏は「色々な事実が出て来て問題にされる前に辞める方がいいのではないかと考え、個人的な立場からアドバイスした」と語った。知事は「どういう理由で辞任したらいいかわからない」と答えたという。
辞任を促すことは、真部利応(としお)社長にも事前に文書などで伝えていたといい、郷原氏は「(辞任が)ベストの選択だという認識を(真部社長と)共有していたと思う」と述べた。
また、九電幹部と面談した際の知事発言がやらせの発端になったと認定した理由について、「知事の発言があったからメモが作られ、それに応じて行動があった。これを、社会的には発言が発端と言う」と述べた。発言ではなく九電幹部が作成したメモが発端になったとする九電側の主張を「論理破綻している」と批判した。
第三者委は2005年の県主催プルサーマル公開討論会での九電による仕込み質問や動員は、県サイドの意向に沿って行われたと認定した。これに関して、郷原氏は「露骨な妨害行為で、県側、知事側は抗議すべきだ」と述べ、県が関与を否定するなら九電に厳しい対応を取るべきとの考えを示した。
特別委に郷原氏が出席するのは初めて。県議3人と郷原氏の質疑が行われる。
国民負担で470億円がJALに注ぎ込まれていたのに、賞与復活を復活させた。これで顧客満足度がアップすると思うのか?
個人的に出来るだけJALを使わないことにしよう。原発問題もJAL以上に国民負担が増えるのだろうな。しかし、東電の対応はかなり悪い!
はやく解体してほしい。
JALへの公的融資、国民負担は470億円に 10/17/11 読売新聞
経営再建中の日本航空に対し、破綻前の2009年6月に行われた政府保証付きの公的融資670億円のうち470億円が国民負担として確定していたことが、会計検査院の検査でわかった。
日航への融資で国民負担額がわかったのは初めて。検査院は11月にまとめる決算検査報告書に盛り込む方針。
融資したのは、国が100%出資している「日本政策投資銀行」。すでに経営が悪化していた日航に対し、民間金融機関とともに総額1000億円を貸し付けた。このうち政投銀分の670億円については、国が「日本政策金融公庫」を通じて最大8割の損失補償(政府保証)をしており、無担保融資だった。
その後の10年1月、日航は東京地裁に会社更生法の適用を申請。負債総額はグループ3社の単純合計で2兆3221億円に上り、金融会社を除く事業会社では過去最大の破綻となった。
検査院の調べによると、政投銀は返済が見込めなくなったとして、10年7月、政府保証分の536億円を公庫に請求し、9月に支払いを受けた。しかし、11月に一律87・5%の無担保債権などを放棄することを盛り込んだ日航の更生計画が裁判所に認可され、同社は残りの債務のうち政投銀にも一部を返済したことから、政投銀はこの分を公庫に返金した。その結果、最終的な国民負担分は470億円となった。
賞与復活を決定=更生手続き完了で―日航 03/30/11 朝日新聞
経営再建中の日本航空が、「生活調整給」として給与の1カ月分前後を3月末までに支給すると決めたことが29日、明らかになった。事実上の賞与復活で、3万人超のグループ社員全員を対象とする。
日航は昨年1月に経営破綻して以来、人員削減や赤字路線撤退など厳しいリストラを推進。今月28日に会社更生手続きを完了し、1年2カ月ぶりに東京地裁の管理から脱した。この間、賞与の支給見送りに加え、給与水準の引き下げや各種手当の削減を実施してきたが、再建へ一定のめどが立ったことから賞与復活に踏み切った。
記者の目:九電「やらせ」と地方の原子力ムラ=関谷俊介 10/05/11 毎日新聞
九州電力のやらせメール問題を調査してきた同社の第三者委員会(委員長・郷原信郎名城大教授)は9月末、九電幹部への古川康・佐賀県知事の発言がやらせの発端として、九電と知事の不透明な関係を断ち切るよう求める最終報告を出した。問題の発覚以降、知事は「私の真意と違うメモが作られ流通した」と責任を否定。九電も自ら設置した第三者委に反論する異例の展開をたどってきた。そのかばい合いを見るにつけ、地方の「原子力ムラ」の強固な結びつきを意識せざるを得ない。
◇知事がシナリオ
第三者委は、玄海原発2、3号機の再稼働に絡んで放映された県民説明番組で九電が再稼働に賛成するメールの投稿を促していたとされる問題を受け、7月に発足した。中間報告で、番組の5日前に知事から「再開容認の立場からも声を」と要請された九電幹部のメモがあると指摘。最終報告は「知事が描くシナリオ通りに再稼働を実現しようとの強い意思に基づいて組織的に行われた」と認定した。
私は玄海原発3号機で09年に始まった全国初のプルサーマルを佐賀支局員として取材した。古川知事は当時、原子力政策に臨む自治体の姿勢について「国の出してきたモノを住民の目線でチェックする」と語っていた。だが、同意に至る経緯は、先に結論ありきで、住民不在という印象をぬぐえなかった。
知事は県主催の討論会などを踏まえプルサーマルに同意したが、最終報告はこれについて「九電が社員らに参加を呼びかけ、県側が容認したうえで『仕込み質問』が行われた」と指摘した。07年に約5万人の署名を受けたプルサーマルの是非を問う県民投票条例案の直接請求については「必要性がない」とする意見を付して議会に提案した。一方で、九電幹部から05年以降、毎年献金を受け、07年の知事選でマニフェストに掲げたがん治療施設誘致についても九電幹部に協力を求め、約40億円の寄付を引き出している。
7月、久しぶりに訪れた佐賀県庁は通用口が閉められ、正面玄関に警備員3人が配置されていた。入ろうとすると行き先を尋ねられる物々しさで、理由を聞くと「原発反対派を入れさせないため」という言葉が返ってきた。知事はこの前月、九電幹部を公舎に招き入れ、やらせメールの“指南”をしていた。
◇県民説得は怠る
東日本大震災以降、佐賀県でも多くの県民が原発の安全性に不安を抱くようになった。だが、知事は県民を説得する努力もせず、専ら九電との意思疎通を重視してきた。私はそこに地方における「原子力ムラ」の構図を見る。
「原子力ムラ」は原子力政策を遂行するため、政官財学が支え合う構図を指すが、地方の「原子力ムラ」の主役は原発立地自治体と電力会社だ。電力会社が原発施設を変更する場合、協定を結ぶ自治体の同意が必要で、首長は強大な権限を持つ。九電は「知事と良好な関係を築きたい」(幹部)。県は財政が厳しい中で資金援助を受けたい。両者の思惑は一致する。その構図は震災後も変わらず、再稼働を巡り慎重な言葉を重ねていた知事は海江田万里経済産業相(当時)と面会した6月29日に「安全性の問題はクリアされた」と発言、九電社長もその日のうちに「大変ありがたい」とコメントを出した。
◇続く献金や寄付
プルサーマルを例に取れば、受け入れで国から自治体に60億円が交付される。原資は私たちの電気料金に上乗せされている。根拠となる電源3法が施行された1974年当時の国会での議論を見ると、原発の立地促進のほか、電力会社の寄付がルーズで恣意(しい)的になることを防ぐ目的があった。電力各社はこの年「公益企業として不適切」と企業献金の自粛も決めたが、個人献金の形での政治献金や自治体への巨額寄付は今も続く。
第三者委は献金禁止など「原発立地自治体の首長との不透明な関係の根絶」を九電に提言した。九電から数十億円の漁業補償を受けてきた地元漁協の元幹部は「これまで説明を受けた『安全』とは何だったのか立ち止まって考えようという空気が出始めている」とメール問題後の変化を認める。そして「家族が原発で働いていたり商売上付き合いがある人も多いが、言うべきことを言えるよう九電とのなれ合いの関係を改めるべきだ」と自戒を込めて語る。
脱原発の道筋を考えるには、まず、電気料金の形で私たちが負担している電力会社の原発マネーのあり方を見直すことだと思う。地域振興の名の下に原発とそこに群がる一部の利害関係者を育んできた寄付や献金を不可能にする仕組みに変えれば、住民不在の元凶である地方の「原子力ムラ」を解体することができると信じている。(西部報道部)
農林水産大臣又は都道府県知事が職員に
告発された安愚楽牧場
獣医師 (ウィキメディア)
に対して
獣医師法 第21 診療簿及び検案簿 (houko.com)
の違反の疑いで調べさせるのであろうか?
でも違反しても
20万円以下の罰金 (houko.com)
であれば違反したほうが得な場合もあると思う。農林水産大臣は獣医師法の罰則を重くするために改正するべきだ。
安愚楽牧場獣医師を告発 宮崎、口蹄疫被害の農家 牛診察せずに医薬品投与の疑い 10/05/11 産経新聞
経営破綻した畜産会社安愚楽牧場(栃木県)の男性獣医師が、宮崎県内の同社の農場で、牛を診察していないのに医薬品の投与を繰り返した疑いがあるとして、口蹄疫被害にあった宮崎県川南町の畜産農家の男性2人が5日、獣医師法違反の疑いで、獣医師の告発状を宮崎県警に提出する。
問題となっているのは、同社の児湯第7牧場(宮崎県川南町)で、昨年の県内7例目の口蹄疫発生農場だった。告発人の農家はいずれも第7牧場の近くで畜産業を経営、口蹄疫では飼育する牛全頭を殺処分した。
告発状によると、獣医師は宮崎県東部の複数の同社農場を担当。昨年3月以降は第7牧場には行かず、牛の診察もしていなかったのに、同3月から4月にかけて、第7牧場の担当者に電話で指示して医薬品を投与させた疑いがあるとしている。
問題の先送り!「東京電力に関する経営・財務調査委員会」は結果に対して責任を持たない。自分を切り刻むことが出来る企業はほとんど
存在しないだろう。利害関係のない組織や人が「なた」を振るわなければならない!
福島第1原発:東電賠償額4.5兆円以上…調査委が報告書 10/03/11 読売新聞
東京電力福島第1原発事故の賠償財源確保に向け、東電の資産査定を行う政府の「東京電力に関する経営・財務調査委員会」(委員長・下河辺和彦弁護士)は3日、野田佳彦首相に報告書を提出した。東電が支払う損害賠償額は13年3月末までで4.5兆円に上ると試算。支払いの原資を確保するため、10年間で2兆5455億円のコストを削減し、3年以内に7074億円の資産売却が必要と結論付けた。東電の電気料金を決める原価計算で、過去10年間で5926億円のコストを過大に見積もっていたとして、料金制度の見直しにも言及した。
報告書を受け、東電は今月下旬をめどに追加リストラ策などを盛り込んだ「特別事業計画」を策定し、原子力損害賠償支援機構に支援を要請する。下河辺委員長は「リストラや資産売却が実現すれば、資金支援に道筋がつく」と述べた。
賠償額について報告書は、農林漁業や観光業などへの風評被害など一過性の損害を2兆6184億円、避難や営業損害など事故収束までかかる損害額を初年度1兆246億円、2年度目8972億円と推計した。これだけで4.5兆円に上るが、営業損害などが長期化したり、除染などの費用負担が上乗せされれば、さらに増える。また、1~4号機の廃炉費用を約1兆1500億円と見積もった。
コスト削減では、東電単体で全社員の約9%に当たる約3600人(グループでは同14%の7400人)を削減し、一般職の給与を10年間にわたり2割削減、企業年金の運用利回りを現行の2.0%から1.5%に引き下げるなどし、人件費を1兆454億円削減するなどとした。
資産売却は、東電の当初計画6000億円に対し、▽不動産2472億円▽有価証券3301億円▽子会社・関連会社1301億円--の売却収入で7074億円を捻出する。
それでも原発が再稼働しないと、火力発電に切り替える燃料費などがかさむ。機構からの資金支援がなく、値上げもしない東電にとって最も厳しいケースでは、12年度に2931億円の債務超過に転落、現預金残高が大幅に不足し、20年度は8兆6427億円の資金不足に陥る。報告書は「再稼働がなければ、著しい料金値上げをしない限り、事業計画の策定は極めて困難」と指摘、再稼働や値上げの必要性をにじませた。一方、11年3月末時点では、廃炉費用の上積みなどを考慮に入れても1兆2922億円の資産超過となるため、金融機関への債権放棄要請は「困難」とした。【和田憲二】
天下りに似たご褒美のような子会社の社長や役員の職を廃止する。これだけでも多くの子会社に適用すればコストカットできる。
被害者に対する損害賠償のためだけに東京電力を生かすのであれば問題ない。不服がある社員で他の会社でもやっていけると思う人は
辞めるだけ。退職金も大幅に減額。社員よりも被害者を優先する気持ちがあれば可能。「補償のために東電を生かす」と政府(民主党)が
言っていることが本当であれば、出来るはず。
東電の資金不足、今後10年で最大8兆6千億円 10/03/11 読売新聞
東京電力の経営を調査していた政府の第三者委員会「経営・財務調査委員会」(下河辺和彦委員長)は3日、委員会報告書を野田首相に提出した。
それによると、福島第一原子力発電所事故の賠償額が今後2年間で約4兆5000億円、廃炉費用は1兆1500億円に上る。このため、東電は人件費削減と保有不動産などの売却で総額3兆2500億円を捻出し、国の原子力損害賠償支援機構も増資で東電を公的管理下に置いて支援する方向だ。
報告書は、電気料金の値上げと原発の再稼働がともに今後10年間できない最悪のケースで、東電が8兆6000億円の資金不足となり、2018年度に1兆9800億円の債務超過になる可能性があると指摘した。電気料金を10%値上げし、原発が再稼働した場合も、18年度に約7900億円の資金が不足するという。このため、支援機構からの増資、資金貸し付けなどの資金援助が必要としている。
電気料金の値上げを極力抑えるため、東電自身によるリストラも強く求めている。10年間で、東電の試算額の約2倍にあたる2兆5455億円のコスト削減が可能とした。非効率な関連会社との取引の見直しや代理店の排除、発電所などの設計見直しを求めている。さらに、保有株や関連会社、不動産の売却で7074億円を確保する。
反省乏しい東電報告案…「やむを得ぬ」多用 10/02/11 朝日新聞
福島第一原子力発電所の事故原因などを調査している東京電力の福島原子力事故調査委員会がまとめた中間報告案は、「やむを得なかった」との表現が多用され、事故の拡大を防げなかったことへの厳しい分析や反省の視点に乏しい。
政府の事故調査・検証委員会の調査で明らかになった機材の誤配など、自社に不都合な内容や指摘は見あたらず、社内調査の限界を浮き彫りにしている。
東電が2008年春に出した津波の試算は、遡上高を今回の津波とほぼ同じ、最大15・7メートルとし、同年12月に行った貞観津波(869年)をモデルとした試算は最大9・2メートルとしていた。しかし中間報告案は、これらの試算を「仮想的な『波源』を立てた試行的なもので、津波対策のベースになるものではない」と一蹴した。
その一方で、土木学会が02年に出した「津波評価技術」に基づく、従来の想定である津波の高さ5・7メートルについて、「確立された最新の知見に基づく想定」と強調し、「今回のような大津波は想定できなかった」と結論付けた。
初期対応の遅れについては、とりわけ「自己弁護」と受け取れる見解が目立つ。
東電は、1号機の炉心損傷開始を「地震発生後約4時間」と解析するが、消防車による1号機への注水が始まったのは3月12日午前5時46分。格納容器内の圧力を下げるベントの成功は、同日午後2時頃だった。2、3号機では、緊急炉心冷却装置などがしばらく動いていたが、この停止後、消防ポンプによる注水再開までは6~7時間を要した。
政府事故調の調査では、東電は手動でのベントを想定しておらず、本店が手配した機材が別の場所に誤配されたり、現場がベントや注水に必要なバッテリーや空気圧縮機の備蓄状況を把握していなかったりしたことも明らかになっている。
だが、中間報告案は、津波によるがれきの散乱や放射線量の上昇など過酷な作業環境を強調し、注水について「厳しい環境の中、できる限り迅速な対応を行った」とした。さらに、「アクシデントマネジメント(過酷事故対策)を含むリスク低減の取り組みが効果を発揮した」とし、その根拠に自動車のバッテリーを使った弁の操作などを挙げて、「臨機かつ直接的に安全設備を操作する応用動作により、炉心の冷却を行った」と評価した。
独占企業の強み。政治家や学者をお金で抱えるほうが誠実な仕事よりも儲かると言う事だろう。
自由とか言われながらも、やはり日本はこんな国。民主党が行う増税には反対。
公務員の給料の削減額が小さすぎる。日本がギリシャみたいになったらどうするのか。
増税するからそんなことはならないと言うのか??東京電力の原発事故による除染作業にかかる費用は
東電が支払うべきだ。原発による発電で儲けてきたのだから、当然。リスクを低く評価しコストを抑えたのだから、
責任は取るべきだ。政治家達も情けない!
東電、年5千万円パーティー券 献金自粛の一方で購入 10/02/11 朝日新聞
東京電力が2009年までの数年間にわたり、自民党を中心とした50人以上の国会議員のパーティー券などを少なくとも年間計5千万円以上購入していたことが分かった。原子力政策における各議員の重要度や、電力施策への協力度を査定して購入額を決定。1回あたりの購入額を政治資金収支報告書に記載義務がない20万円以下に抑え、表面化しないようにしていた。
東電は1974年以降、「電力供給の地域独占が認められた公益企業にそぐわない」として企業献金を自粛している。その一方で、組織的に議員をランク付けし、パーティー券を購入する形で資金提供していた実態が初めて明らかになった。
複数の東電幹部らによると、東電本社には毎年、国会議員本人や秘書から政治資金集めのためのパーティー券購入の依頼が、窓口役の総務部に多数寄せられていた。東電はパーティー券の購入予算枠を確保しており、毎年50人以上の議員に配分したという。
議員ごとに原子力政策における重要度、東電の業務への協力度などを査定。東電の原発が立地・建設中の青森、福島、新潟の3県から選出された議員や、電力会社を所管する経済産業省の大臣、副大臣、政務官の経験者などは、購入額が高い議員にランク付けされた。
議員の政治団体や資金管理団体が開いたパーティーや勉強会に対する1回あたりの購入額は、政治資金規正法に違反せずに企業名を出さないようにするため、収支報告書に記載義務がない20万円以下と決められていた。査定が高い議員は上限の20万円を複数回購入。東電との関係が浅い議員は券2枚を計4万円で購入したり、依頼を断ったりしたという。
パーティー券の購入は長年続いていたとみられ、09年までの数年間は、毎年5千万円以上を購入。約1億円にのぼった年もあった。
また、09年の政権交代までは、自民党議員と民主党議員の購入金額の割合は約10対1と、自民党側が中心だった。交代後の10年も券購入を続けたが、民主党議員の購入額を増やしたという。
パーティー券購入について、東電元役員は「東電の施設がある県の選出議員かどうかや、電力施策や電力業界にどのくらい理解があるかを考慮した。関連企業に割り当て分を購入してもらうこともあった」と証言。収支報告書に社名が記載されないように金額を抑えた点については、「政治家と公的な企業につながりがあるというだけで、良からぬ見方をされる。表にならないに越したことはない」と話している。
東電広報部はパーティー券購入について、「社会通念上のお付き合い程度で行っているが、具体的な購入内容は公表を控える。飲食への支払いで、対価を伴っているので、政治献金ではない。(企業献金の自粛とは)矛盾していない」としている。(市田隆、藤森かもめ)
九電やらせ第三者委、佐賀知事への献金中止提言へ 09/30/11 朝日新聞
九州電力の「やらせメール」問題などを調査している第三者委員会(郷原信郎委員長)は30日午後に公表する最終報告で、一連の問題は九電と佐賀県の不透明な関係が原因と認定し、古川康知事らへの政治献金などをやめるよう求める。ほかの電力各社の対応にも影響を与えそうだ。
九電幹部ら7人は、知事の政治団体に対して2006~09年、計42万円を個人献金の形で寄付。昨年10月の政治資金パーティーでは、九電がパーティー券を買ったり関係会社にあっせんしたりしていた。ほかに、木原奉文県議(前県議会原子力安全対策等特別委員長)も09年、九電幹部ら9人から計6万5千円の献金を受けている。
こうした事実を踏まえ、第三者委は、電力会社と原発立地自治体との間で透明性が疑われるような行為をしないよう求める。パーティー券の購入や関係会社へのあっせん、事実上の企業献金との批判がある幹部らの寄付もやめるよう促す。
一方、玄海原発(佐賀県玄海町)のプルサーマル計画に関する県主催の公開討論会(05年12月)で、九電が仕込んだ「やらせ質問」は、九電の当時の経営トップだった松尾新吾会長が、知事の意向を忖度(そんたく)した結果だったと認定する。
九電は、公開討論会前に知事が「プルサーマルの賛成派もいないと議論が深まらない」などと話していたことから、やらせ質問や動員を計画。県と事前協議を繰り返し、やらせ質問の台本も作っていたという。
第三者委は「九電トップと知事の間に何らかの意思疎通があったと見るのが合理的」と判断。「(やらせ質問などを)九電トップが知らなかったというのは考えられない」などと指摘する。真部利応社長についても知事の関与を隠そうとしたとして、「不透明な企業行動を先導したと言うべきで、九電の信頼を失墜させた」と厳しく批判する見通しだ。(斎藤徹、多田敏男)
「佐賀県関与を九電隠蔽」 やらせ問題第三者委最終報告 09/30/11 朝日新聞
九州電力の委託で「やらせメール」問題などを調査している第三者委員会(郷原信郎委員長)は30日、最終報告書を出した。やらせに佐賀県が関与していたのに、九電の経営トップが隠そうとしたと指摘。関与を否定してきた古川康知事や続投に意欲を示す真部利応(まなべ・としお)社長の責任が問われる。
都内で記者会見した郷原委員長は「問題発覚後の経営トップの対応に非常に問題があった」と述べた。この日も真部社長は委員会の会見要請を拒み、コメントを出した。九電は報告書を受けて10月中旬にも社内処分を決め、国に報告する。
報告書によると、2005年12月の玄海原発(佐賀県玄海町)のプルサーマル計画を巡る県主催の公開討論会で、九電は県の要請を受けて進行台本を用意し、社員ら7人に仕込み質問をさせていた。賛成の立場から発言した質問者の大半を九電関係者が占め「露骨なやらせ行為で県民を欺いた」と批判。当時社長の松尾新吾会長ら経営トップと知事の間に「何らかの意思疎通があったと見るのが合理的」だとした。
今年6月の玄海原発再開に向けた国のテレビ番組でも、九電社員らがメールやファクスで賛成意見を投稿していた。報告書は、知事が九電幹部と事前に面談した際に「再開容認の立場からもネットを通じて意見や質問を出して欲しい」などと発言したことが、やらせ投稿につながったと認定。「知事の要請に応え、知事が描くシナリオ通りに再稼働を実現するため、組織的に行われた」とした。
5月にインターネットで中継された国から県への説明会でも、県側の要請に応じて九電が10件程度の書き込みをしていたと認めた。
真部社長ら現在の経営トップについても、問題発覚後、原子力部門内で関係資料の廃棄といった調査妨害が行われたのに適切に対応しなかったと批判。「知事と九電の関係を隠蔽(いんぺい)しようという姿勢をとった」として、企業の信頼を失墜した責任は重いと指摘した。
国主催シンポ等7件で「やらせ」…経産省報告書 09/30/11 読売新聞
経済産業省原子力安全・保安院が原子力関連のシンポジウムで電力会社に「やらせ質問」などを要請していた問題で、同省の第三者調査委員会は30日、新たに判明した計4件を含め、国主催のシンポジウムなど計7件で、国によるやらせ質問や動員の要請があったとする最終報告書を公表した。
一方、九州電力の「やらせメール問題」を受けて設置された第三者委員会も同日、最終報告書を公表。古川康・佐賀県知事の責任にも言及した。
これまでの調査では九州電力玄海、四国電力伊方、中部電力浜岡の3原発のシンポジウムで、保安院側が電力会社に賛成意見の表明を求めるなどしていたことが明らかになっている。
最終報告書によると、2006年10月28~29日に3回開かれた女川原発の住民説明会では、保安院の原子力安全広報課長が、開催前に打ち合わせに訪れた東北電力の担当者に対し、「東北電力の関係者もどんどん参加して、意見を言いなさい」と発言。説明会は会場を複数のブロックに分け、順に質問する形式で、この課長は東北電力関係者を各ブロックに一定数配置することも要求していた。
臨床検査部の主任技師だった黒沼俊光氏が正しいとすれば、
厚生労働省の幹部達(厚生労働省)
は何をやっているのか?? 天下りのために業界との癒着があるのか?? それとも単なる給料泥棒(役立たず)なのか??
がんセンター、告発職員に嫌がらせの数々「隠蔽、組織ぐるみ」/11.09.29/産経新聞
「がんの専門家集団」を称する国立がん研究センター東病院(千葉県柏市)で行われていたずさんな検査。28日に会見した同病院の職員で、臨床検査部の主任技師だった黒沼俊光氏(49)は検査の実態について証言、公益通報を行ったことを明らかにした。黒沼氏の家族はがんを患っているといい、「がんセンターは患者の最終的なよりどころ。その臨床検査部が医療不祥事をおかし、組織ぐるみで隠すことは許されない」と訴えた。
黒沼氏は、これまで同病院の臨床検査部で主任臨床検査技師として勤務。黒沼氏によると、平成17年に始まった基準値の設定ミスや、がんの発生を確認する「腫瘍マーカー」での試薬の誤使用のほかにも、臨床検査部では不祥事が繰り返されていたが、部外に報告されることはなかったとする。
黒沼氏が再三、上司や病院長らに対し、不祥事を指摘、公益通報を行うと発言したところ、上司からは「おとなしくしていろ」などと言われたという。
乳がん患者である黒沼氏の妻(48)が18年に同病院で検査を受けた際には、黒沼氏がずさんな検査を指摘していた同僚によって検体を破棄され、データを改竄(かいざん)されるなどの嫌がらせも受けたとしている。
黒沼氏が今年5月以降、その他の不祥事告発とあわせて、病院に内容証明郵便を送ったところ、「内容証明書の送付を禁止する」などとする業務命令も出された。
8月には、「臨床検査部を混乱させている」として、東病院長付に配置換えが行われた。
度重なるストレスで、黒沼氏は左目がほとんど失明状態になり、自律神経失調症も患い、現在は病気休職中という。黒沼氏は「正しいことを正しいと言ってきた。それを妨害する行為は許せない」と話した。
独占企業の強み。政治家や学者をお金で抱えるほうが誠実な仕事よりも儲かると言う事だろう。
電気料金原価、6千億円高く見積もり 東電、10年間で 09/29/11(朝日新聞)
東京電力の電気料金算定のもとになる見積もり(燃料費などを除く)が、実際にかかった費用よりも、過去10年間で計約6千億円高いことが、政府の「東京電力に関する経営・財務調査委員会」の調査でわかった。電気代が必要以上に高く設定されていた可能性があり、調査委は近くまとめる報告書に盛り込む。
自由化されていない家庭用の電気料金は、電力会社が今後1年間にかかる人件費や燃料費、修繕費などの原価を見積もり、一定の利益を上乗せして決める。
報告書案によると、過去10年で計6186億円分、見積もりが実績を上回っていた。大きな原因として修繕費を挙げ、1割ほど過大とした。報告書案は「経営効率化によるものというよりも、そもそも届け出時の原価が適正ではなかったと推察される」と指摘した。
注目を浴びているLCC。しかし、下記のような危険が存在する事を理解したほうが良い。
全日空、異常な傾きを翌日把握…隠蔽は否定 09/29/11(読売新聞)
全日空140便(エアーニッポン運航)が異常に傾き失速寸前になったことについて、全日空側がトラブル翌日には把握していたにもかかわらず、公表していなかったことが分かった。
全日空の長瀬真副社長とエアーニッポンの内薗幸一社長らが28日夜、東京・霞が関の国土交通省で記者会見を行い明らかにした。飛行データなどでトラブル翌日の7日には、機体の異常な姿勢を確認したが、同日夜の報道発表の際には、「傾きの詳細はわからない」として説明をしなかった。
これについて、長瀬副社長らは「お客様に隠蔽しようとしたわけではなく、運輸安全委の調査中の事案のため説明できなかった」と釈明を繰り返した。
また長瀬副社長は今回のトラブルについて「かなり危機的な状態だったと認識している」と頭を下げた。さらにトラブル発生が深夜だったことから、社内連絡や国交省への報告なども遅れたことを明かした。
番組中、やらせ「告発」メールも来ていたのに… 09/28/11(読売新聞)
九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)の再稼働を巡る「やらせメール」問題で、6月に経済産業省が主催した佐賀県民向け説明番組に、やらせを告発するメールが番組中に投稿されたことが28日、わかった。
経産省資源エネルギー庁は当時、このメールを九電側に照会していなかった。同庁は、「当時は内容を精査しておらず、気づかなかった」と弁明している。
同庁によると告発メールには、「九電社員が、運転再開を容認するメールを送るよう命じられている。第三者による徹底した調査を」などと書かれていたという。
一方、同庁は番組終了後に589件と公表していた投稿総数が、実際は706件(賛成302件、反対241件、その他163件)だったことを明らかにした。当初は、番組後の記者会見に間に合わせるため、途中集計を公表したという。
報酬を貰っていたら強いことは言えない。当然のこと。政府の「原子力損害賠償紛争審査会」が形だけの組織だからこうなるのだろう。
まあ、被害者を助けるよりは、東京電力を助けるほうが信念でなく利益を考えるなら大きなメリットになる。中立性を考えたら
あまり名前が知られている人達よりも、公正や中立的な判断が出来る人を選ぶべきだ。政府や文部科学省が実際に中立性の立場でなく、
東電や電力業界よりであれば人選にも反映されてくるだろう。
紛争審2委員、電力系研究所から報酬 原発事故賠償 09/23/11(毎日新聞)
東京電力の原発事故に伴う損害賠償の目安をつくる政府の「原子力損害賠償紛争審査会」の一部委員が、電力業界とつながりの深い研究機関から、毎月20万円ほどの報酬を得ていることが分かった。審査会は、円滑に賠償を進めるため、東電と被害者の間に立って紛争を解決する役割を担っているが、中立性に疑問が生じる恐れがある。
審査会は4月11日、文部科学省に設置された。現在の委員は9人で、学習院大教授の野村豊弘氏(68)と早大大学院教授の大塚直氏(52)が、「日本エネルギー法研究所」(東京都港区)から報酬を得ていた。
野村氏は4月にエネ法研の理事・所長に就任して以来、毎月20万円程度の固定給を受け取っている。大塚氏は委員就任前から研究部長の職にあり、毎月20万円の固定給を得ていた。ただ、周囲からの助言で、6月末に研究部長を辞め、4~6月の報酬を返納した。
エネ法研は、年間1億数千万円の運営費のほとんどを、財団法人「電力中央研究所」(東京都千代田区)からの研究委託に頼る。電中研の今年度の事業規模は339億円。300億円近くは電力業界が拠出し、そのうちの90億円ほどを東京電力が負担している。
人的にも、電力業界とのつながりは深い。エネ法研の役職員は約20人。理事長を含む6人の理事はすべて法学者だが、研究員は沖縄を除く電力9社からの出向や派遣。事務部長と事務課長は歴代、東電出身者だ。
東電とつながる研究機関から、委員が固定給を得ていることについて、文科省原子力損害賠償対策室は「委員の選考過程での目配りに瑕疵(かし)があり、エネ法研についての認識が甘かったという批判は受けるかもしれない」と認める。ただ、今後の委員の扱いについては「疑義が生じれば、そのときに対応を考えたい」と説明している。
エネ法研との関係では、別の委員も研究班の「主査」を務めていたが、中立性を考え、主査を辞めて委員に就いた。6月には、福島県立医科大副学長への就任が内定した委員が「利害関係者になる恐れがある」として委員を辞めている。(木村裕明、大津智義)
まだまだリストラ策は甘いと思う。「現役の削減に踏み切る。ただ、今後数年は事故対応で人員が必要で、早期実現は難しそうだ。」
人員削減が不可能なら、給料の削減や賞与の削減、社員に対する手当ての削減など他の方法はある。給料の削減や賞与の削減による
退職者が出ても仕方がないこと。強制的なリストラと個人判断による退職。結果を見て、さらなる強制的なリストラを検討すればよい。
福島原発の現場で作業している社員以外に対してはさらなる給料の削減や賞与の削減を実施するべき。
東京電力:年金支給額引き下げや人員削減 リストラ策概要 09/21/11(毎日新聞)
東京電力のリストラ策の概要が20日、分かった。企業年金の支給額引き下げや、同社初の希望退職募集による数千人規模の人員削減を検討。本店を含む不動産売却の積み増しも進め、福島第1原発事故の損害賠償支払いや、火力発電への切り替えに伴う燃料費負担の増加に対応する。ただ、政府は東電に対し一段のリストラを求めており、東電はリストラ内容に理解を得られるまで、料金の値上げ申請を先送りする可能性もある。
東電の資産査定を行う政府の「経営・財務調査委員会」が同日開かれ、東電の西沢俊夫社長が初めて出席。西沢社長は会合後、年金見直しについて「聖域を設けず検討する」と述べ、OBも含む減額に初めて言及した。東電の企業年金の予定利率は現役社員で年2・0%、OBで最高年5・5%。予定利率引き下げには社員やOBの同意が必要で、調整は難航しそうだ。
一方、本体社員約3万6000人のうち、希望退職で数千人規模を削減する考え。東電は新卒採用見送りによる人員削減を打ち出していたが、「政府支援で世論の理解を得るには、一段の合理化が不可欠」として、現役の削減に踏み切る。ただ、今後数年は事故対応で人員が必要で、早期実現は難しそうだ。
また、従来のリストラ策で1000億円程度としていた不動産売却も「深掘りをしたい」(西沢社長)と大幅に積み増す。東京都千代田区の本店を売却し、そのまま賃借することも検討するが、「長期的に収益改善につながらない」との見方もあり、慎重に判断する。
ただ、調査委の下河辺和彦委員長は「まだ緩い」と述べ、再考を求める方針だ。調査委の委員5人は、東電の賠償支払いを支援する「原子力損害賠償支援機構」の運営委員に就任。東電の経営を監視する方針で、十分なリストラを実施しない限り料金値上げにも慎重な構え。西沢社長も「まずは経営の合理化をする」と述べ、経済産業相への認可申請先送りを示唆した。
東電は5月、不動産やKDDI株など保有資産売却で6000億円以上の資金を捻出し、人件費削減や人員削減などで11年度に5000億円以上のコストを削減するリストラ策を公表していた。【立山清也、宮島寛】
ここまで来たら、佐賀県や知事の責任と事実の公表が必要だろうな!もし玄海原発で放射能が放出される事故が起こったら、
佐賀県民だけでなく周囲の人達にも被害が及ぶ可能性もある。佐賀県民が事故が起きた時は仕方がないと思っても、利害関係で
被害を受ける可能性がある人達に対しても説明責任と調査・公表責任があると思う。
九電やらせ:佐賀県「仕込み質問」関与か 05年討論会 09/20/11(朝日新聞)
九州電力の「やらせメール」問題で、玄海原発(佐賀県玄海町)へのプルサーマル導入に関する佐賀県主催の討論会(05年12月)を巡り、九電が賛成意見を表明させるために質問者を仕込むことについて、事前に県側と協議していたことが関係者への取材で分かった。九電第三者委員会(郷原信郎委員長)は、県側の仕込み質問への関与の度合いについて調査している。
第三者委が8日にまとめた中間報告では、九電が社員ら約40人に対し、討論会で推進や中立的な質問をするよう依頼。さらに1カ所に固まらないよう会場内に散らばって座るよう要請していたことが明らかになっている。
関係者によると、九電は開催前、県との打ち合わせで賛成派の質問者を準備していることを説明。会場の座席表も示し、質問者がどこに座るかも伝えた。やらせ問題発覚後、九電が廃棄しようとした資料の中に、座席表など県との協議を示す資料が含まれていたという。
討論会には717人が参加し、県が質問者を選ぶ形で18人が質問し、うち7、8人が九電側が用意した質問者だったという。
ある九電関係者は「県との打ち合わせの場で、(05年10月に開かれた)国主催のシンポジウムで反対派の質問が相次ぎ収拾がつかなくなり、二の舞いは避けたいという話が出た」と述べた。
玄海原発へのプルサーマル導入について、古川康・佐賀県知事は討論会までは賛否を明らかにしていなかったが、討論会終了後、初めて「安全性への理解はある程度深まったのではないか」と理解を示し、翌06年3月に九電に同意書を提出。09年11月、全国初のプルサーマル発電が開始された。【福永方人】
良い時には良い思いをしてきた。悪い時には覚悟をすべき。政治的な圧力があったのだろうか??
しかし、まだ東電の社員やOBの企業年金の支給額を削減する方針は甘い。なんで東電の尻拭いを税金で払わされるの??
東電の努力は不十分!
東電、企業年金を減額へ 数千人の人員削減も 09/17/11(朝日新聞)
東京電力が、社員やOBの企業年金の支給額を削減する方針を固めた。人員も数千人規模で削減する。原発事故の賠償問題で政府支援を受けたり、料金を値上げしたりするには、5月に公表した合理化策を積み増して、世論の理解を得ることが必要と判断した。
企業年金は、給付額に影響する利回りを引き下げる方針だ。現在は現役社員が年2.0%、OBが最高で年5.5%。下げ幅は調整中だ。引き下げには社員やOBの同意が必要となる。
約3万7千人いる社員(今年3月末時点)も、今後減らす。ただ、当面は賠償支払いの業務に約3千人をあてるため、人員削減には数年かかる見通しだ。1100人を予定していた来春入社の新卒採用は中止を決めている。今後、希望退職を募ることも検討する。
なんで園庭除染に関して東電に損害賠償を請求せずに保護者が負担するの?自分には関係ないけど、もし保護者として請求されたら
東電に請求して東電が請求を拒否したら考えると言う。東電が被害を起こしたのだから東電が補償すべきだ。
園庭除染、保護者も負担?千葉・柏の一部幼稚園が請求 09/17/11(読売新聞)
東京電力福島第一原発事故の後に高い放射線量が測定され、「ホットスポット」との指摘が出ている千葉県柏市の私立幼稚園協会が、園庭などの除染費用について幼稚園が保護者に請求することを認める方針を決め、加盟する園に通知していたことが分かった。協会によると、一部の園で実際に請求を始めるところも出てきているという。
協会の説明によると、7月の臨時役員会で保護者への請求を認め、加盟する33園に通知した。周辺より放射線の線量の高い所を中心に、園庭の表土の除去や、側溝の清掃、砂場の入れ替えなど放射線の除染を実施した場合、「低減作業協力金」として園児1人あたり1万円を請求できるとした。協会は「保護者の強い要望を受けた」と説明。通知では「幼児をお預かりする幼稚園では小中学校よりも除染を徹底することが必要なことは明らか」としている。
保護者への要請文のひな型も協会が作成。かかった費用の内容について、保護者の求めがあった場合に示すことができるようにすることを園に求めている。請求するかしないかは各園の判断とされ、9月に入り、一部の園でこの文書を保護者に配り始めており、保護者から協会に問い合わせが寄せられているという。
九電やらせ質問者の席配置、佐賀県と事前調整 09/17/11(読売新聞)
九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)でのプルサーマル発電計画を巡り、導入前の2005年12月に開かれた佐賀県主催の公開討論会で、九電が質問を指示した社員らの座席の配置について、佐賀県の担当者と事前に打ち合わせをしていたことが16日、分かった。
関係者によると、九電と佐賀県の担当者が質問者の座席配置などを話し合った内容の資料が九電社内に残っていた。九電の第三者委員会も事実関係を慎重に調べている。
討論会は、県民が計画の是非を判断する最後の議論の場として、唐津市のホテルで開かれた。第三者委の中間報告書によると、会場が原発慎重論に染まることを懸念した九電側は、佐賀支店と玄海原発でそれぞれ約20人の「質問者」を仕立て、推進する質問を割り当てた上で、会場内にまんべんなく配置した。その結果、18人中7~8人の「仕込み質問」が行われた。
多くの人が東京電力が福島第1原発事故による被害で苦しんでいるのに「東電の賞与回復」だと!原発事故の収束や電力供給にあたる社員の士気を保つため
なら東京電力福島第1原発の現場で働いている社員に限って行えばよい。それなら多くの人が納得すると思う?? 安全な所にいる社員達の賞与を
回復させる必要なし。テレビを通して多くの人達が苦しんでいるのを知らないのだろうか??自業自得の人達もいるけれど、東電は十分な補償を
するのか??「東電を破綻させるべきだ。」とテレビで言われなくなったのでもう反省した態度を見せなくても良いと思ったのだろうか??
東電の賞与回復「認められない」 調査委 09/15/11(毎日新聞)
東京電力が来年度から3年間の電気料金の値上げ終了後に、半減中の一般社員の賞与水準を元に戻そうとしている問題で、政府の第三者機関「東電に関する経営・財務調査委員会」は14日の非公式会合で、「15年度に賞与水準を回復することは認められない」との考えで一致した。
15%という電気料金の値上げ幅についても、委員から批判的な声があった。ただ、値上げの理由としている火力発電所の燃料費の増加が、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働の行方に左右されるなど見通しが不透明なため、是非の判断は先送りした。
東電は賠償や事故対応の費用を捻出するリストラの一環として、7月から一般社員の賃金の5%、賞与の5割を削減中。賃金カットは賠償が終わるまで続ける方針だ。ただ、原発事故の収束や電力供給にあたる社員の士気を保つため、さらなる給与水準のリストラについては否定的な声もある。(福田直之)
もう原発のリスクの問題じゃない。原発事故調査も適切に出来ない国は原発を増やすべきでない。保安院は法的権限を行使して原発事故調査に協力してこない。
お金ほしさに原発を受け入れた地域で事故が起こっても必要以上に助ける必要はないと思えてきた。原発の被害者のコメントをテレビで聞いても
「原発や放射能について今でも勉強していないだろう。」と思える発言をする。救いようがない人達だと思う。原発や放射能について知りたくなければ
個人の判断だから仕方がない。個人の責任と判断において決めること。ただ、日本の経済力は衰退し続けている。現状維持か、かなり緩やかな
衰退が可能なのかもわからない。そんな状態なのに、今までと同じように考えていてはだめだと思う。こんな事を言っても無駄かもね。
福島第1原発:東電、過酷事故発生時の手順書も黒塗り 09/12/11(毎日新聞)
東京電力が福島第1原発の「事故時運転操作手順書」の大半を黒塗りして開示した問題で、再開示を要求していた衆議院科学技術・イノベーション推進特別委員会(川内博史委員長)は12日、同社が別の「シビアアクシデント(過酷事故)発生時の手順書」でもほとんどすべてを塗りつぶして開示したことを明らかにした。
一方、経済産業省原子力安全・保安院がこの日の同委員会理事会で、原子炉等規制法などによって手順書の開示命令ができるという初めての説明をした。このため、同委員会は経済産業相に対し、初めて同法に基づいて開示命令を出すように請求した。開示請求は通算4回目。
理事会では、保安院と東電幹部がシビアアクシデント手順書を持参して説明した。資料は表紙と目次のA4判3枚で、目次50行のうち開示されたのは「消火系」と「不活性ガス」と書かれた2行のみ。両者から内容についての説明はなく、東電は会議後に資料を回収し、「核物質防護と知的財産上の問題」と説明したという。
川内委員長は「これだけの事故を起こしておいてまったく資料開示に応じないのは遺憾。保安院も法的権限があるのを知りながら、これまで何もしていなかったということで理事からも怒りの声が上がった」と話した。
一方、この日の会見で東電は「あくまで運転操作にかかわる手順書は社内文書。一般的に公開するものではないと考えている」としている。【関東晋慈】
東京電力福島第1原発事故は住民達が踊らされた可能性がある事を調べる機会を与えた。福島の被害者達の人生を事故前に戻すことはできないが、
原発の近くに住んでいる人々に考えさせる機会を与えたと思う。佐賀の原発近くに住む農家のインタビューをテレビで見たが、
目先の利益だけで判断する人達がいることも理解できた。プロセスが正しかろうが、間違っていようが結果でしか判断できないケースもある。
東京電力福島第1原発事故は結果として大きな被害を起こし、多くの役人や専門家が発言した原発安全論は嘘であったことも明らかになった。
そこで今度は日本の経済発展には原発が必要と世論の指示を得ようとしている。
安定性はなくても国の政策として安価な太陽光発電の普及を
進めるべきである。量産化、規格化、そして大量購入による価格交渉で太陽光発電はもっと安く出来るはずである。
北電また「やらせ」…ご意見聴く会へ賛成要請 09/10/11(読売新聞)
北海道電力が泊原子力発電所(北海道泊村)に3号機(出力91・2万キロ・ワット)を建設する計画を進めていた2000年3月、複数の周辺住民に対し、道主催の会合に出席して計画に賛成する意見を表明するよう要請していたことが9日、わかった。
複数の出席者が証言した。北電を巡っては、道などが08年10月に催した3号機へのプルサーマル計画導入に関するシンポジウムで、社員に計画推進の意見を出すようメールで依頼していたことが判明しており、「やらせ」工作が常態化していた疑いが強まった。
問題の会合は、3月30日に泊村公民館で開かれた「道民のご意見を聴く会」。295人が出席し、26人が意見を述べた。テーマは道内のエネルギー施策だったが、意見は泊3号機の建設計画に集中し、賛否は13人ずつだった。
LCCが注目されているが、LCCには下記のような問題が隠れている可能性がある。機長や副機長は資格だけ持っていれば良い。
コスト削減のためチェック体制が甘くなる傾向がある。どこまでがコスト削減出来るのか、どこまでコスト削減すれば安全性が
低下するのか判断が難しい。的確な判断できる人達がチェックし判断しているのかも重要な点になる。まあ、重大な事故が起こるまでは
LCCの人気は続くだろう。
副操縦士が内規に違反、酸素マスクつけず ANA機の急降下トラブル 操作ミスとの因果関係調査 09/10/11(産経新聞)
浜松市沖の太平洋上空を飛行していた全日空機が約1900メートル急降下したトラブルで、全日空は9日、急降下につながる操作ミスをした副操縦士が、一定以上の高度を飛行中にコックピットで1人になった場合に社内規定で着用を義務づけている酸素マスクをしていなかったと明らかにした。
当時、機内では気圧の急激な低下などの異常事態はなかったというが、運輸安全委員会はトラブルとの因果関係を調べる。
全日空では、高度約7500メートル以上を飛行中に機長と副操縦士のいずれかが席を外した場合、残った1人は非常時に対応が遅れないよう、酸素マスクをつけなくてはならないと規定。
だが、機長が席を外している間、副操縦士は酸素マスクをつけておらず、機長が戻った際にコックピットのドアを解錠しようとして間違って機体の向きを調整するスイッチを操作。機体が不安定になり、約30秒間急降下した。
「担当者らは『監査は捜査とは違う』と限界も口にした。社会福祉事業は『性善説』によりかかった側面が強い。」
だったら監査の方法を改善すればよい。簡単に限界と言うのはおかしい。現在の監査システムには限界があるので報告したが、広島、大竹両市は
改善を放置したのであれば担当者の責任ではない。「性善説」によりかかった監査制度に限界や問題があると感じたのであれば報告すればよい。
報告書を放置や無視する判断を上司や市幹部が下せは、それは上司や市幹部達の責任。新聞の記事がどこまで詳細に情報を提供できるのか知らないが
記事を読む限り、広島、大竹両市の担当者にも責任はある。
広島・社福法人不正運用:ずさんな経営、疑惑噴出 10年も不正見抜けず /広島 08/27/11(毎日新聞 地方版)
なぜ不正を見抜けなかったのか--。保育所4カ所を運営する県内有数の社会福祉法人・ひまわり福祉会(安佐南区)で発覚した巨額の不正経理問題。公金を含む保育所運営費を前理事長(25日付で解任)の親族が私的に流用したり、税理士も絡んだ不透明な資金運用などの疑惑が噴出した。ずさんな法人経営だけでなく、不正を約10年も見逃していた自治体監査のあり方が問われるのは必至だ。【寺岡俊、中里顕、星大樹、北浦静香】
■県、市
同法人を所管する県、保育所がある広島、大竹両市の担当者らは26日、県庁で記者会見した。01年度以降、約2億8000万円にも上る不正経理が見過ごされ、保育の充実のために支給される公金が不正に流用された事態だが、担当者らは「出勤簿や休暇簿、支出に関係する書類などは整理され、つじつまもあっていた」と釈明。「顧問税理士の関与が深くなるほど、不正を見抜くのは難しくなる」とも述べた。
05年度以降、県は2年に1回、社会福祉法に基づく法人監査を実施し、広島市は児童福祉法に基づく施設監査を毎年行ってきた。県は09年の監査で、外部との業務契約に不審点があるのに気付き、改善するよう指摘したが、親族経営の“独走”は止まらなかった。
県が求めた書類を法人が提出しないなど、不誠実な対応が続いた。県は法人に対し、第三者委員会を設置して内部調査を進め、運営適正化を図るよう指示。追調査の過程で、解任された理事らが保育所運営費を生活費に流用したり、保育と関係ない資金捻出に充てていたなどの実態をあぶり出したという。
しかし、担当者らは「監査は捜査とは違う」と限界も口にした。社会福祉事業は「性善説」によりかかった側面が強い。解任された沖キヌエ前理事長(75)の次男は、勤務実態がないのに給与が支払われていたが、職員会議録などから事実は明白だった。広島市は今年2月の調査で事務長らに聞き取りをしただけで、本人に確認していない。同市の担当課長は「説明を鵜呑みにした」と弁明した。
◇私的流用認める
■法人
沖前理事長と共に理事を解任された長男(51)は26日、報道陣の取材に応じ、「借金の返済や飲食費など私的に使っていた。不正という認識はあった」などと答えた。同法人が運営する4保育所の一つ「ひまわりやすにし保育園」(安佐南区)の園長でもあった長男は「保護者の方々には申し訳ない」と語る一方、「監査で見抜けなかった方が悪い」などと責任転嫁した。
同法人は25日夜、各保育所ごとに保護者説明会を開き、保育サービスには影響がないことを伝えた。「ひまわりやまもと保育園」(同区)では、沖前理事長が集まった保護者約30人に謝罪したという。長男を預けている30代の主婦は「保育士さんまでピリピリした雰囲気になってしまったら困る」と話した。
■税理士
不正経理に関与したとして県が懲戒請求し、刑事告発も検討している税理士は取材に対し、「道義的責任はあるが納得できない。法的責任ということになれば争う」と語った。
この税理士は20年以上前から法人の顧問税理士を務め、今月に入って辞任。県の発表によると、法人は税理士が関係する会社と架空の業務契約を結び、経費を支出していた。
税理士の説明によると、寄付金2400万円の返還を法人に求めてきた男性に対し、税理士が代表を務める会社など2社に経費を支払うよう装い、法人は返却金を捻出。税理士は08年に会社の使用中止を求め、以降は実態のない団体に入金される形になったが、税理士はこの団体の通帳を管理していたという。
大企業の官僚化。建前だけの調査がその証。まともに調査などしていないのに「調査の結果、事実確認が出来なかった。」と言う。
多くの人が信じていないが、何も出来ないし、大きな力に刃向かえば報復の危険があることにうすうす気付いている。事実から
顔を背け、日本は平和であると信じ込もうとする。いま、福島で何が起っているのか??知的で情報入手出来る人以外、真実の
半分も知らないと思う。悩んでいても何も変わらないが、事実から顔を背けていると絶対に大きな改善はない。
北電で新たなやらせ=当初「問題なし」と発表-泊原発 08/31/11(時事通信)
北海道電力は31日、泊原発3号機(北海道泊村)のプルサーマル計画をめぐり道主催のシンポジウムで「やらせ」が発覚したことに関連し、国主催のシンポジウムでも社員に出席を促すメールを送っていたことが判明したと発表した。
問題のシンポジウムは2008年8月31日に泊村で開催され、325人が参加。北電は今年7月末、いったんは「社員に参加を要請した事実はない」と発表していた。その後、道主催の場でやらせが発覚したことを受け、さらに調査した結果、新たに問題が判明したという。
それによると、メールを送ったのは地元調整に当たる泊事務所渉外課で、当初、同課などが発信したメールを調べたほか、社員から聞き取りもしたが、問題は確認できなかったという。その後、調査対象を広げたところ、メールを受信した社員のパソコンから見つかった。
31日記者会見した高橋賢友常務は「(当初の)調査で事実確認ができなかった。おわび申し上げたい」と陳謝した。
「やらせ」と「隠蔽」は原発業界では国民が知らないだけで常識だったのかもしれない??
しかし、なぜ、九州電力や北海道電力のやらせは共産党発なのか??他の党には電力会社からの献金や支持があるから非難できないのか??
利害関係がない共産党だから情報を公開できるのか??もしそうなら、原発の安全性を考えるよりも、人的な面で既に安全を軽視する
構造や体質が日本で確立されていると考えて間違いないだろう。だとすれば安全とか安全重視など茶番のための道具。その道具で
ごまかされる原発近隣住民と日本国民。騙すほうも悪いが、騙されるほうにも問題があることは理解したほうが良いだろう。
泊原発プルサーマル計画、一時凍結 やらせメールで北電 08/29/11(朝日新聞)
北海道電力泊原発(北海道泊村)3号機をめぐる「やらせメール」問題を受け、北電は29日、3号機で導入を目指しているプルサーマル計画を一時凍結する方針を明らかにした。近く有識者らによる「やらせ」問題の調査委員会を設置。9月末までに組織的関与の有無などを調べる方針で、少なくとも結果が出るまでプルサーマル用燃料を加工しないという。
北電は、通常の原子炉でウランとプルトニウムの混合酸化物燃料を燃やすプルサーマル計画を2012年春に導入する方針で、近くフランスの工場で燃料の加工を始める予定だった。
ただ、2008年10月に開催された計画導入の是非を問う北海道など主催のシンポジウムをめぐり、北電の現地事務所が社員に出席と賛成意見を述べるよう促すメールを送っていたことが判明した。
「仮定の計算」と釈明 10メートル超の津波で東電「対策必要な想定津波ではない」 08/25/11(産経新聞)
福島県沖でマグニチュード(M)8以上の大地震が起きた際、東京電力福島第1原発に高さ10メートル以上の津波が到達する可能性があると試算していたことが明らかになった問題で、東電は25日、「公表しなかったのは、一定の仮定に基づくあくまで試算だったため」と弁明。「設計上、運用上対策を取らなければならない想定津波ではない」との認識を改めて示した。
経済産業省原子力安全・保安院によると、東電が東日本大震災4日前の3月7日、経済産業省原子力安全・保安院に試算結果を報告した際、保安院の担当者は「設備面での対応が必要ではないか」と口頭で指導したとされる。
しかし、東電の松本純一原子力・立地本部長代理は「私どもはそういう指示を口頭で受けたことはない」と否定。「(保安院から)お話があった内容が違うという認識だ」と強調した。
試算では、明治29(1896)年の明治三陸地震が福島県沖で発生したと仮定し、福島第1原発周辺では最大で高さ10・2メートルの津波が発生、15・7メートルの高さまで水が押し寄せると算出された。
セカンドチャンスは必要だと思う。しかし、変わらない人間もいる。医者、弁護士、そして会計士も同じことが言える。
被害者が出ないようにするべきなのか、それとも加害者の公正を優先させるのか?少なくとも3度目のチャンスは与えるべきでない。
入院患者の足の爪剥がし、看護助手の女また逮捕 08/25/11(読売新聞)
勤務先の病院で入院患者の足の爪を剥がしたとして、京都府警五条署は25日、京都市西京区川島六ノ坪町、看護助手・佐藤あけみ容疑者(37)を傷害容疑で逮捕した。
容疑を認め、「仕事のストレスがたまり、イライラしてやった」と供述。佐藤容疑者は7年前にも、仕事上のストレスなどから同市内の別の病院で同様の事件を起こして逮捕され、傷害罪で懲役3年8月の実刑判決を受けていた。
発表によると、佐藤容疑者は24日午前10時30分頃、京都市中京区の毛利病院で、手首の骨折などで入院していた女性(80)の左足親指の爪を手で剥がした疑い。
この女性以外にも患者数人が爪を剥がされた形跡があり、同署が詳しく調べている。
同日正午過ぎ、巡回中の看護師が、女性の爪が剥がれ出血していることに気付き、病院側がこの女性のシーツ交換などを担当した佐藤容疑者に事情を聞いたところ、「自分がやった」と認めたため、同署に通報した。
日本看護協会などによると、看護助手は看護師を補助する職種で、国家資格など公的資格は必要ないという。同署によると、佐藤容疑者は、看護助手を募集していた同病院の面接を受け、「経験があり、夜勤もします」などと説明。今月6日に採用され、同日から勤務していた。
佐藤容疑者は、別の病院で看護助手として勤務していた2004年9~10月、女性患者6人の爪計49枚を剥がし、06年1月に実刑判決を受けたが、同署によると、毛利病院側はこのことを知らなかったという。
人件費はカットが必要。そして官僚の天下りと同様、ポスト確保のために不必要な職や会社が存在する。
そのような職や会社は廃止すべきだ。しかし、使用する製品の質はあまり下げないほうが良い。
ただ、納入業者との癒着やキックバック、請求書に含まれる接待費用などはチェックして馴れ合いをやめなければならない。
東電人件費、他の業界より高い…政府第三者委 08/24/11(読売新聞)
東京電力の資産や経営状況を調べる政府の第三者委員会「経営・財務調査委員会」(委員長・下河辺和彦弁護士)は24日、第5回会合を開いた。
下河辺委員長は会合後の記者会見で、東電の人件費は「他業界と比べて高い感は否めない」と述べ、退職金や企業年金、福利厚生を含めて見直しの対象にすべきだとの考えを示した。
この日の会合では、企業年金などを含めた東電の人件費を電力他社や他業界の実態と比較した。また、設備投資や資材などの調達コストについて、下河辺委員長は「東電が(安全性の確保という名目で)もろもろの資材に高い品質を要求することで、割高なコスト構造が安易に受け継がれていないか。チェックが必要だ」と述べ、妥当性を検証する必要性を強調した。
原発問題、運悪く九州電力だけが注目されているが、実際は、原発問題は闇で隠された部分が多く、根が深いと思う。
大事故さえ起こらなければ、専門家達を金で飼いならしておけば、誰も反論できない。裁判でも専門家達を味方につけておけば、
負けることはない。
九電側から献金…佐賀県議、特別委委員長辞任へ 08/23/11(読売新聞)
九州電力の「やらせメール」問題を審議している佐賀県議会原子力安全対策等特別委員会の木原奉文委員長(58)(自民)の政治団体が2009年に九電幹部ら6人から計5万円の個人献金を受けていたことが23日、わかった。
木原氏の政治団体「きはら奉文後援会」の09年の政治資金収支報告書によると、2月に当時の原子力管理部長が2万円、佐賀支店長が1万円、副支店長ら4人が各5000円の計5万円を個人名で寄付した。
当時の原子力管理部長は、現・原子力発電本部副本部長の中村明・上席執行役員。やらせ問題を調査している九電第三者委員会から提出を求められた資料について、社内で廃棄を指示した。
原子力安全対策等特別委は23日、「やらせメール」問題を巡り、県民説明番組前に古川康知事と面談した九電の段上(だんがみ)守・副社長(当時)ら3人が参考人として出席する予定だったが、献金問題の発覚を受けて議員の一部が木原氏の辞任を求めるなど紛糾。木原氏は謝罪し、委員長を辞任することになった。
補助金不正受給、オペラ団体なぜ相次ぐのか 08/16/11(読売新聞)
名門オペラ団体・東京室内歌劇場(太刀川悦代・運営委員長)が2007~10年度に17事業で文化庁などから受けた支援金約2億1390万円を不正に受給していたとして、文化庁は来月にも同歌劇場に不正受給額の返還請求をする。
オペラ界では、昨年の日本オペラ連盟に続く、支援金を巡る不正発覚だ。同歌劇場は、上演機会の少ないオペラを日本初演することに定評がある。しかし、海外の歌劇場が毎年のように来日公演を行っている現状で、今回のケースでは最大1事業約4800万円という多額の支援金を出してまで、国内でオペラを制作する意義があるのか、疑問視する声もあがりかねない。
音楽・演劇両要素を持つオペラは「総合芸術」と呼ばれる。クラシック音楽の演奏会と芝居の公演、いわば2公演分行っているようなもので、当然、費用もかさむ。オーケストラ・歌手の出演料、ホールの賃貸料、舞台セット費、衣装代など、多岐にわたり、1事業約2000万~3000万円、大きい公演では1億円を超える。
東京室内歌劇場事務局は、不正受給分も「すべてオペラ制作にかかわることに使った。事務所運営費もかかるが、その費用は支援の対象外。その分、ほかの費目を多く請求した」と釈明。不正受給時の運営委員長・竹澤嘉明氏は「半ば慣習的に行っていた。変えようと思っていたが、そのまま今に至った」と話している。
長引く不況もあり、オペラ団体の運営は軒並み苦しい。今回の問題は、制作にお金がかかるから、というよりも、それに伴う支援金が巨額であるがゆえ、運営の苦境を不正な会計処理により、安易に解決したものと言えよう。基本的に当事者のモラルの問題だが、公的支援を受ける団体に、経理の公開を義務づけるなどの対策が求められる。
文化庁の山崎秀保・芸術文化課長は「規則通りに会計を処理している団体がほとんど」と指摘する。同庁は防止策とし、帳簿・領収書の提出を義務化したことに加え、近く庁内に検討委員会を設ける。
16世紀末にイタリアで始まったオペラは、当初から封建君主らに保護され、パトロンの存在と切り離しては語りえない。現代でも欧州では、額は減る傾向にあるものの手厚い公的支援を受けている。しかし日本のこの厳しい財政事情ではなおのこと、制作者は公的支援を当然視せず、襟を正す必要がある。(文化部 鷲見一郎)
福島原発が地方自治体にも似たような問題があったのではないかと推測する。被害者になったかもしれないが、責任は責任として
同じような問題があったから調べるべきだと思う。
九電やらせ:地元側が「見返り」要求 資料に記録 08/10/11(毎日新聞)
九州電力の「やらせメール」問題に絡み、原子力発電本部ナンバー2の副本部長が廃棄を指示していたプルサーマル関連資料には、佐賀県内の議員や自治体関係者らによる九電への要求や要望などの記録も含まれていたことが、関係者の話で分かった。
同社は05年から06年にかけて、玄海原発(同県玄海町)で予定していたプルサーマル発電(09年12月運転開始)の地元了解を得るため、県議や自治体関係者らへの働きかけを強めていた。廃棄を指示した資料の中には、プルサーマルを円滑に推進する見返りとして、九電側が地域振興などの要求、要望を突き付けられていたことが分かる内容の記録が含まれていたとみられる。
06年3月に県と玄海町がプルサーマルを事前了解した後に地元で反対運動が起きた際には、自民党県議が反対に加勢しない見返りに、がん治療施設への誘致協力を九電に求めるなど、実際に九電は当時、地元からさまざまな要望を受けていたことが分かっている。
九電第三者委員会などによると、副本部長は7月下旬と8月5日、同本部の課長級社員と佐賀支社の原発担当課長に資料の廃棄を指示。佐賀支社分は廃棄前に回収したが、同本部の資料は実際に廃棄された。【斎藤良太、石戸久代】
九州電力は組織的に「黒」であることは明白だ。裏で組織的に動いていたことも明らかになった。関与した全ての幹部達を退職させないと
組織として変わることはできないだろう。九州電力も東電の原発事故の被害者ではある。なぜなら、福島原発事故がなければ
組織的に裏で動いていたことは公にならなかったであろうから。しかし、原発賛成者の一部を除く九州の人達にとっては今回の問題が
公になって良かったと思う。このような組織で原発事故が起こったらどうなるのか??九州を見捨てる可能性もないことはない。
福島に対してもかなり酷い対応を国は取っていると思う。だから福島に住んでいないことに感謝している。事故が起こってからは
遅いと思う。
九州電力:廃棄資料に佐賀議員らとの記録も 08/10/11(毎日新聞)
九州電力の「やらせメール」問題に絡み、中村明・原子力発電本部副本部長が廃棄を指示していた資料の中に、佐賀県内の議員らとのやり取りを記録した文書が含まれていることが関係者の話で分かった。九電はプルサーマル発電の実現に向けて地域住民を戸別訪問したり、議員や県関係者に説明したりする「理解活動」をしており、このうち個人が特定される発言の記録などを「抜き取る」よう指示していたという。
九電第三者委員会(郷原信郎委員長)によると、副本部長が廃棄するよう指示していたのは、09年12月に玄海原発(佐賀県玄海町)で始まった全国初のプルサーマル発電に関する資料の一部。記録にはプルサーマル発電への賛否なども記されていたとみられる。
廃棄を命じた理由について、中村副本部長は毎日新聞などの取材に「役所関係など色々な地元の方がいるので、個人的に影響を受けるような情報は外に出さない方がいいと思った」と述べた。【綿貫洋、小原擁】
九州電力:プルサーマル資料廃棄 副本部長指示で 08/10/11(毎日新聞)
九州電力の「やらせメール問題」に絡み、同社原子力発電本部の中村明・副本部長が、同本部と佐賀支社に保管されていたプルサーマル発電関連の書類を廃棄するよう指示していたことが9日、九電第三者委員会の調査で分かった。実際に廃棄された書類の中には、国への報告対象となっていた説明会の資料も含まれており、第三者委は悪質な隠蔽(いんぺい)工作があったとみて、詳しく調べる。
第三者委の郷原信郎委員長が同日、福岡市内で会見を開き、明らかにした。それによると、中村副本部長は社内調査で7月21日に求められた、05年10月の玄海原発(佐賀県玄海町)におけるプルサーマルに関する説明会の書類について、「個人に迷惑がかかる資料は抜いておけ」と部下に指示。廃棄された書類の分量などは不明という。郷原委員長は、副本部長の言う「個人」について、「政治家や県、国の関係などが考えられる」と述べた。
九電のやらせメール発覚を機に、経済産業省は全国の電力会社に過去の国主催の説明会での動員実態などを明らかにするよう求めていた。05年10月の説明会も対象で、九電は7月29日に調査結果を報告していた。しかし、調査段階で隠蔽があったことになるため、報告の信ぴょう性も疑われることになる。
また、副本部長は8月5日、第三者委から提出を求められた、佐賀支社のプルサーマル関連資料の廃棄も指示。だが内部通報で第三者委が廃棄場所に残っていたファイル15冊を回収、廃棄を防いだ。
中村副本部長はやらせメール発覚前の7月4日、鹿児島県議会で「そうした事実はない」とメール問題について虚偽答弁。6月28日の株主総会前に同本部が用意していたやらせメール問題に関する想定問答の作成にもかかわっていたとされる。
中村副本部長は9日夜、毎日新聞などの取材に対し、「個人に迷惑をかけるわけにはいかなかった。(上司などから)指示は受けていない」と述べて、隠蔽が自身の指示だったことを認めた。対象については「過去何年分かにわたるプルサーマル関連資料のうち、個人情報が分かるもの」と述べた。【中園敦二、小原擁、阿部周一】
指示した幹部が九州電力関連会社に天下っている場合、退職金なしで即刻、辞めさせるべきだ。
やらせ調査に九電が証拠隠し…郷原委員長が会見 08/09/11(読売新聞)
九州電力の「やらせメール」問題を調査している第三者委員会の郷原信郎委員長は9日、福岡市で記者会見し、九電の原子力発電本部が、玄海原発3号機のプルサーマル計画について、2005年に行われた説明会やシンポジウムに関する資料などを廃棄する証拠隠しを、先月から今月にかけて行っていたことを明らかにした。
郷原委員長によると、同本部が保管していたプルサーマルに関する2、3冊のファイルから一部を廃棄していた。プルサーマルに理解を得るための活動に関する資料で、個人名なども含まれているという。佐賀支社でも15冊のファイルを廃棄しようとしていたが、社内からの情報提供があり、廃棄前に第三者委事務局の経営管理本部が回収した。
九電やらせメール:課長級職員 知事メモ送信後に削除要請 08/08/11(毎日新聞)
佐賀県の古川康知事が九州電力の「やらせメール」を誘発する発言をした問題で、九電佐賀支社長が作成した知事発言のメモが同社の約100人にメール配信された後、社内の指摘で受信した社員に削除するよう指示が流れていたが分かった。同社幹部は「知事に迷惑がかかったらまずいと判断したようだ」と述べ、古川知事への配慮があったことを認めた。
一方、知事発言メモは、眞部利應(まなべ・としお)社長の秘書にも送信されていたことが新たに分かった。眞部社長が問題発覚前からメモの存在を認識していた可能性が浮上した。
また、九電が6月28日にあった株主総会に向け、やらせメールを認める内容の想定問答を用意していたことも明らかになった。原子力部門の管理職が作成したが、実際の総会ではやらせメールに関する質問は出なかった。九電関係者によると、この内容は担当役員が答えるレベルで、社長は目にしていなかったという。
九電、やらせ問題で国に虚偽報告 国会追及前に総会対策 08/09/11(朝日新聞)
九州電力の「やらせメール」問題で、原子力発電部門が6月28日の株主総会向けに、この問題の想定問答をまとめていたことがわかった。九電は「7月6日に国会で追及されて初めて問題を把握した」と説明、7月14日に経済産業省に出した調査報告書でもそうしているが、原発部門は早い段階で知っていたのに公表を避けてきたとみられる。
九電は想定問答に加えて幹部と佐賀県の古川康知事との会談の事実も報告書に記しておらず、国に虚偽報告をしていたことになる。
九電の原発部門の課長級社員は、国主催のテレビ番組(6月26日放送)に玄海原発(佐賀県)2、3号機の運転再開に賛成意見を送るよう、6月22日にメールで社員らに指示を出した。
九電の複数の幹部によると、番組放送前後から「やらせ疑惑」の指摘がインターネット上に相次ぎ、共産党も追及する姿勢を見せていた。
このため原発部門内で対応を協議し、総会で質問があったときに担当役員が答えられるよう事実関係を整理した回答案を作ったという。回答案は経営陣が目を通す可能性が高く、少なくとも原発部門の幹部はやらせ問題を把握していたことになる。
だが、やらせ指示があった当時の原発部門幹部の一人(現上席執行役員)は、7月4日の鹿児島県議会で「番組があると社内などに連絡はしたが、どうこうしろとは言ってない」とやらせを否定していた。
真部利応(まなべ・としお)社長は問題が発覚した7月6日の会見から一貫して「国会で追及されるまで知らなかった」としている。
また九電は国への報告で、テレビ番組後、複数の報道機関から「やらせ」について問い合わせがあったが、「事実関係を十分な調査をせず、見過ごしていた」と説明していた。
佐賀知事、九電メモ「ニュアンス違う」 県議会で主張 08/09/11(朝日新聞)
九州電力の「やらせメール」問題で、佐賀県の古川康知事は9日、県議会の特別委員会で、九電幹部が知事発言として記録したメモについて「こうした項目に話が及んだことは確かで、全面否定はしない」と述べた。一方で「内容やニュアンスが違う」とし、九電側に発言が誤解されたと主張。「責任をとる考えはない」とした。
古川知事は6月21日朝、九電幹部と会談し、玄海原発(同県玄海町)の運転再開に向け、国が県民向けに企画したテレビ番組(6月26日放送)について、再開容認の立場から番組に意見を送るよう発言。九電幹部のメモによると、知事は自民党系県議が容認するよう支持者に働きかけることも九電に求めるなどした。
この点について知事は特別委で「自民党の県議には原発への不安の声が支持者から寄せられており、安全性を認識してもらう必要があると述べた」と釈明。再開容認の声を出すよう発言した点については「経済界には再開を容認する声があると聞く。この機会に、そうした声を寄せてほしいので発言した。九電に要請したものではない」との説明を繰り返した。
九電:副社長が知事の意向くむ 佐賀支社長「配信に驚愕」 08/07/11(毎日新聞)
九州電力の「やらせメール」を誘発した佐賀県の古川康知事の発言メモが社内に添付メールとして回ったのは、原子力担当の段上守副社長(当時)の指示だったことが、九電関係者への取材で分かった。メモを作成した佐賀支社長は知事との会談の備忘録として作り、副社長側に渡したと証言しているといい、副社長が社員らのやらせを後押しするため知事の意向を受ける形で知事の発言を利用したとみられる。
関係者によると、副社長は佐賀支社長ら幹部3人で6月21日に知事と会談した後、内容をメモにするよう支社長に指示。支社長は同日中にA4判2枚にまとめ、副社長の秘書にメールで送った。その後、副社長が部下の担当部長にメモを回し、課長級社員がメールに添付して原子力部門の約100人に配信された。
一方、佐賀支社長は「副社長から『メモを作ってね』と言われ、副社長の個人的な備忘録として作ったので、原子力部門で共有化されたと聞いた時は驚愕(きょうがく)した」と話しているという。
また佐賀支社長は、知事から「原発の再稼働を容認する意見を出していくことも必要だ」との趣旨の発言について、会談の前にも「何回か聞いていた」と説明。一方で、知事の発言の意図については「九電が自ら意見を出せとか、社員を使って賛成意見を出せというようには受け取っていない。メモは発言内容を簡潔にしてしまい、不正確で誤解を生じさせるような文言になっている」と釈明しているという。【竹花周、小原擁】
政治家は黒い部分も持ち合わせていないと選挙には勝てないのかもしれない。今回は運悪く表に出ないはずの情報が公になった。
佐賀県の古川康知事は事実を話すべきであろう。
佐賀県民はどのように見ているのだろうか??最近思うことは、間違った判断であっても責任を持って政治家を評価し、投票することが
重要。佐賀県で原発事故が起これば部分的には県民の責任。福島のように大規模な原発被害は起らないと思っていたとの言い訳はもう使えない。
九電やらせメール:佐賀知事 自民系県議に働きかけ求める 08/06/11(毎日新聞)
佐賀県の古川康知事が九州電力の「やらせメール」を誘発する発言をした問題で、九電幹部が作成した古川知事の発言メモの概要が九電関係者への取材で分かった。九電玄海原発(同県玄海町)2、3号機の運転再開に向け、九電に対し、支持者などを通じて自民党系県議に働きかけるように求め、国主催の県民向け説明番組には賛成意見の投稿を要請する内容になっている。
メモの概要によると、古川知事は「自民党系県議に選挙を通じて不安の声が寄せられていることから、支持者にいろいろなルートで働きかけるようにする」「運転再開容認の立場から番組にネットを通じ意見や質問を出す」の2点を求めた。
また▽運転再開に向けた動きを一つ一つ丁寧にやっていくことが肝要▽番組出演者のうち1人は商工会議所専務理事を予定し、反対派は代表者選抜が難しいので普通の参加者を選ぶことになる▽危惧される国側のリスクは菅総理の言動--など具体的な内容が記されていた。
古川知事と九電の前副社長ら幹部3人は番組放映5日前の6月21日、佐賀市の知事公舎で面談。その際、知事は「経済界からも賛成意見を出してほしい」と伝えた。九電側は前副社長が同席した佐賀支社長にメモ作成を指示。メモは原子力本部に渡り、社員約100人に送ったメールに添付する形で広がった。
古川知事は面談での発言について「やらせメールを要請した事実はない」と否定し、九電の眞部利應(まなべとしお)社長も「やらせは知事の発言が引き金ではなく、不正確な文書の作成が誤解を与えた」と擁護している。ただ、今回判明したメモは県議への働きかけや番組参加者の選定など、具体的で詳細なことから、古川知事の原発再稼働への積極姿勢を浮き彫りにする形となった。【石戸久代、福永方人】
◇古川知事は「根拠は何?」
佐賀県の古川康知事は6日午前、同県唐津市で開かれた講演後、報道陣に対し、発言の事実関係について「何を根拠におっしゃっているのかわからない」とのみ答えて車に乗り込んだ。知事は2日の会見で、九電で作成された発言メモについて「見ていない」と話していた。
佐賀知事と九電副社長面会、社長は番組前に把握 08/04/11(読売新聞)
九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)の再稼働を巡る「やらせメール」問題で、九電の真部利応(としお)社長は4日の佐賀県議会原子力安全対策等特別委員会で、玄海原発の国主催の説明番組前に、段上(だんがみ)守・副社長(当時)から、古川康知事と面談した事実を聞いていたことを明らかにした。しかし、具体的な内容について「第三者委員会の調査結果を待ちたい」と繰り返したため、議員から不満の声が上がり、審議が約2時間中断するなど紛糾した。
真部社長によると、段上氏から報告を受けたのは番組2日前の6月24日夕。「当時の最大の関心事は再稼働の問題。それ以外の話はあったとしても印象にない」と述べ、知事発言の内容は記憶がないとした。
真部社長は、面談に同席した大坪潔晴・佐賀支店長(当時)が作成した知事発言メモについて、「社内調査が始まった後の7月6日か7日に初めて知った」と説明。知事が賛成投稿を要請しているように読める文章だったため、大坪氏にやり取りを思い出して作り直すよう指示したという。
「『今回のメール投稿要請は知事との面談とは関わりなく、当社の責任で生じたもの』とした上で、『知事に責任を転嫁しようとしているように受け止められることが本意ではなかった。事実を隠蔽しようとする意図は全くなかった』と説明した。」
「メモの記載内容と当事者の供述内容の間に食い違いがあり、知事の発言内容について正確に事実を把握できなかったことや、知事の政治生命にも重大な影響を及ぼす可能性があることなどを理由に挙げた。」
かなり「ダーク」。同社幹部(元副社長ら3人)はまともにメモが取れないし、面談の内容を正確に伝えられないほどの問題があったのか?なぜそのように
能力的に問題がある人間が幹部になれるのか?疑問だらけだ!何かを隠していると思われても仕方がない言い訳しか出来ないのは実際に何かあったことを示しているのか??
九電HPでおわび「投稿要請、知事と関係ない」 08/01/11(毎日新聞)
九州電力玄海原子力発電所の再稼働を巡る「やらせメール」問題で、九電は31日、佐賀県の古川康知事と同社幹部が国主催の説明会前に面談した事実を公表しなかったことについて、「心より深くおわび申し上げる」とホームページで謝罪した。
メモの記載内容と当事者の供述内容の間に食い違いがあり、知事の発言内容について正確に事実を把握できなかったことや、知事の政治生命にも重大な影響を及ぼす可能性があることなどを理由に挙げた。
さらに、「今回のメール投稿要請は知事との面談とは関わりなく、当社の責任で生じたもの」とした上で、「知事に責任を転嫁しようとしているように受け止められることが本意ではなかった。事実を隠蔽しようとする意図は全くなかった」と説明した。
「軽率だった」…佐賀県知事、九電への発言で 07/31/11(毎日新聞)
きっかけは、知事の言葉だったのか。
九州電力玄海原発(佐賀県玄海町)の再稼働を巡る「やらせメール」問題で、九電が設置した第三者委員会の調査などから、「再稼働容認の声を」とする古川康・佐賀県知事の発言を九電側が重視し、最終的にやらせメールを指示していた疑いが30日、浮かび上がった。「今思えば、軽率のそしりを免れない」。古川知事は釈明に追われた。
第三者委の郷原信郎委員長と知事の説明によると、九電の段上守・副社長(当時)ら3人が県庁に到着したのは6月21日午前8時40分頃。そのまま知事公舎に招かれた。
段上氏と諸岡雅俊・原子力発電本部長(同)が退任のあいさつをすると、話題は玄海原発の再稼働の情勢、そして5日後に予定されていた国主催の説明会番組へと移った。「賛成意見は表に出ていない」「再稼働を容認する声を出していくことも必要」といった知事の言葉に、3人は耳を傾けたという。
偽善者集団の保安院!
保安院:四国電にも「動員」要請 07/29/11(毎日新聞)
四国電力は29日、伊方原発3号機のプルサーマル発電に関して国が06年に開いたシンポジウムへの参加者の「動員」を、経済産業省原子力安全・保安院が四電に要請していたとの調査結果を発表した。
四電によると、シンポは06年6月、国が同3号機のプルサーマル発電計画を許可した後、計画について地元の理解を深めるため愛媛県伊方町で開かれた。その約1カ月前、保安院から四電にメールなどでシンポジウムへの参加者を集めるよう要請があった。
四電は社員や関連会社などに呼びかけて少なくとも313人が事前に参加を登録。シンポ当日の出席者は587人だったが、四電の要請による出席者が何人いたかは不明という。
シンポでは参加者対象のアンケートがあり、プルサーマルの必要性と安全性について「理解できたか」という質問に、回答者の過半数が「理解できた」「だいたい理解できた」と答えたという。【岡田英】
保安院:中部電に「やらせ質問」要請 プルサーマルシンポ 07/29/11(毎日新聞)
中部電力は29日、07年8月に静岡県御前崎市で開かれた浜岡原発のプルサーマル計画をめぐる国主催シンポジウムで、経済産業省原子力安全・保安院から同社に対し、シンポジウム参加者を集めたうえで、参加者がプルサーマル反対派だけにならないよう質問を作成し、地元参加者に質問してもらうよう口頭依頼があったと発表した。中部電は社員らに出席要請はしたが、「やらせ質問」は拒否した。九州電力の「やらせメール」問題を受けた調査で判明した。電力会社側だけでなく、保安院も「意見操作」に加担していたことが明らかになった。
同社によると、保安院からの依頼を受け、中部電本店原子力部グループ長が、地元参加者の質問想定文を作成した。しかし、同社の関係部署で検討した結果、「特定意見を表明するよう依頼することはコンプライアンス(法令順守)上問題がある」として、保安院の依頼には応じられないと決定した。
やらせ質問の想定文は保存され、自然エネルギーとプルサーマルのコストを聞いたり、化石燃料があと何年もつのかという内容だった。文案が使用されなかったことは確認したという。
一方、中部電側はシンポジウム参加者を集めるようにとの保安院からの依頼や、会場に空席が目立つのは適切ではないという判断から、社員や関連会社などに参加を呼び掛けた。参加の強制はしていないとしている。
中部電は「直ちにコンプライアンスに反しないが、議論を誘導する意思があったとの誤解があったことを深く反省している」としている。
シンポジウムには524人が出席し、周辺住民ら12人が質問したが、計画推進や耐震性を懸念する内容が中心だった。中部電は、同社の要請による出席者数は不明としたうえで「発言者に関係者はいなかったことを確認した」としている。
参加者アンケートには357人が回答し、うち、プルサーマルの必要性を「理解できた」「だいたい理解できた」との回答は59%に達した。中部電は「アンケートをよく見せる意図はなかったが誤解を招いた」と述べた。【丸山進】
◇保安院自身の総点検を
経済産業省が主催したプルサーマルについてのシンポジウムで、原子力安全・保安院が質問が反対派に偏らないよう中部電力に「やらせ質問」の作成を依頼していたことが事実とすれば、原発の安全性を規制するはずの官庁が、推進に「加担」していたと言われても仕方ない極めて深刻な事態だ。規制官庁としては自殺行為に等しく、早急に事実関係を明らかにし、責任を明確化することが求められる。
推進側の資源エネルギー庁と規制側の保安院が経産省内に同居していることについては以前から批判が出ていた。中部電のシンポジウムでは07年の中越沖地震を受け、プルサーマルの安全性や耐震性について懸念する質問が上がっていたという。住民の安全性の懸念にきちんと答えるための説明会になっていたのか改めて詳細な調査が必要だ。
東日本大震災後、保安院内部からも「原発の稼働率を上げるための安全規制になっていたのではないか」と反省する声が出ている。九電の「やらせメール事件」で、同省は電力会社の体質の見直しを指示した。細野豪志原発事故担当相は保安院の分離独立など組織再編の試案を8月上旬にも示すことにしているが、その前に保安院自身の総点検が求められる。【足立旬子】
保安院は信頼できる組織ではないと思っていたが、やはりと言うことか!保安院が他の電力会社に「やらせ」を要請したかは知らないが、
要請に応じた電力会社は絶対に事実を言わないだろうな。経産省はまさか事実を報告されると思わなかったのか、形だけの調査をしたつもり
が墓穴を掘ったのか???たぶん、「No more supprise!」だろうね!経産省は誰が「やらせ」を依頼したのか調べて公表するべきだ!
保安院が「やらせ」依頼 浜岡原発シンポで中部電に 国の関与発覚は初 07/29/11 (読売新聞)
中部電力は29日、2007年8月に開かれた浜岡原発(静岡県御前崎市)のプルサーマルに関するシンポジウムで、経済産業省原子力安全・保安院から質問を作成して地元住民に発言させる「やらせ」の依頼があったと明らかにした。
中部電は質問案を作成したが、コンプライアンス上問題があると判断し、最終的に断っていた。九州電力の「やらせメール」問題など一連の問題で、国の関与が明らかになったのは初めて。中部電はシンポジウムで、浜岡原発の事務所の社員や地元の関連企業に任意で参加を呼び掛けた。プルサーマルへの賛成など特定の意見の表明を要請したことはなかったという。
経産省は九電のやらせメール問題を受けて、過去のシンポジウムで同様の問題がなかったかどうか全国の電力会社に調査を指示。これを受けた中部電の社内調査で発覚した。
保安院、中電にやらせ質問要請…中電は実行せず 07/29/11 (読売新聞)
中部電力は29日、2007年8月に国主催で地元・静岡県御前崎市で開催された浜岡原子力発電所のプルサーマル計画に関するシンポジウムで、同社社員や関連企業などに参加を要請していたとの内部調査結果をまとめ、経済産業省に報告した。
報告書では原子力安全・保安院から、質問がプルサーマル反対派だけにならないように質問を作成し、地元住民に質問を依頼するよう要請があったことも明らかにした。ただ、同社の判断で、特定の意見表明の依頼はしなかったという。同社は「参加の呼びかけが議論を誘導する意思があったという誤解を招く恐れがあったと深く反省している」と謝罪した。
中部電力の発表によると、説明会の参加者は524人で、このうち同社社員は150人前後だった。関連企業の参加者は把握していないという。
推測だが、このようにして力やお金を持つ大企業が一般市民、メディア、中小企業そして政治家などを直接的、又は間接的に
操作してきた例が過去にもあるのだろう。九州電力のやり方が異常であるとは思えない。もし、異常であるのなら役員のほとんどを
辞任させるべきだろう。異常な行動を制御できない役員達など必要ない!
プルサーマル公開討論、参加者の半数が九電動員 07/29/11 (読売新聞)
九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)3号機のプルサーマル発電計画について、佐賀県が2005年12月に公開討論会を主催した際、九電が動員した社員や関連会社員らは、参加者全体(782人)の半数近い三百数十人に上っていたことが28日、九電関係者の証言でわかった。
さらに、会場での参加者アンケートに積極的に回答するよう指示していたことも判明した。
アンケート結果は原発の安全性に肯定的な意見が約65%を占め、同県の古川康知事はこの結果などを参考に、06年3月に計画への同意を表明した。九電は29日、この討論会を含め、過去、組織的な動員が常態化していたことを経済産業省に報告する。
討論会は、県民が同計画の是非を判断する最後の議論の場として、唐津市のホテルで開かれた。玄海町など地元3市町住民が優先され、他の地域の住民は抽選となった。
中国だから下記の記事のようなことはありなのだろう。昔、中国の列車事故で日本からの修学旅行生が死亡した。補償額は400万円ぐらいだったと思う。
中国を旅行し、列車事故で死亡しても損害賠償金が400万円前後では利用しないほうが良い。死んでしまったら生き返ることは出来ない。
「遺族の1人は26日、鉄道事故の補償限度額の3倍に当たる50万元(約600万円)の賠償金で合意した。」400万円よりはアップだが
やはり日本人の感覚としては50万元(約600万円)は安すぎるだろう!
列車事故で中国が高額賠償金、早期幕引き図る? 07/26/11 (読売新聞)
【温州(中国浙江省)=比嘉清太】当地で23日に起きた高速鉄道の追突、脱線事故で、中国当局は26日、犠牲者の遺族に高額の賠償金を提示した。
迅速な賠償金提示には遺族の不満を封じ込め、早期の幕引きを図る狙いがあるとみられる。
新華社電によると、遺族の1人は26日、鉄道事故の補償限度額の3倍に当たる50万元(約600万円)の賠償金で合意した。ほかの遺族に対する交渉も早急に進めるとみられ、中国紙記者は「カネで口封じをしている」と指摘した。
事故で亡くなった乗客の遺族の間では、「復旧が優先され救助活動が拙速に打ち切られた」との憤まんが渦巻いており、遺族の一部は25日夜、温州の地元当局庁舎前で道路を封鎖する抗議活動を行った。当局は、抗議拡大を防ごうと神経をとがらせており、26日は火葬場に警官30人を配置し、遺族の動向を監視した。
九電やらせメール:前副社長らに関連会社社長の辞任勧告 07/25/11 (毎日新聞)
玄海原発2、3号機再稼働に関する「やらせメール」問題で九州電力は、発端となる指示をした前原子力担当副社長の段上(だんがみ)守氏と前取締役原子力発電本部長の諸岡雅俊氏(いずれも6月末で退任し、関連会社社長に就任)の2人に対し、関連会社の社長職辞任を促す方針を固めた。
事実上の引責辞任勧告となる。27日の取締役会で決定する。
「有印私文書偽造・同行使の疑いで経営者宅と同社を家宅捜索したことが捜査関係者への取材でわかった。 」
昔、広島県警は「有印私文書偽造・同行使」は犯罪にならないと言っていた。まあ、あのころは警察の言う事を素直に
信じていた。今は、教訓から学び、警察官だからと言って簡単に信用することはない。普通の警官はそんなに法律の事を
知らないこともわかった。まあ、法律に精通していたら弁護士になった方が良いから、これが現実なんだろうけど。
ところで虚偽申請容疑の経営者は人間的にどのような人だったのだろうか?虚偽申請する人など世の中にたくさんいる。
処分されるべき人だったから捜査されたのだろうか?
特養開設で虚偽申請容疑、介護サービス会社を捜索 愛知 07/25/11 (産経新聞)
愛知県豊明市で無届けの有料老人ホームを運営する介護サービス会社「中日看護センター」の女性経営者(70)が、特別養護老人ホーム(特養)の開設をめぐり名古屋市に虚偽の書類を提出したとして、愛知県警が有印私文書偽造・同行使の疑いで経営者宅と同社を家宅捜索したことが捜査関係者への取材でわかった。
捜査関係者や名古屋市によると、経営者は昨年9月28日、同市緑区内に特養を設置することを申請する際、資産状況を証明するための銀行口座の預金残高証明書が他人名義なのに、自分名義に偽造して同市に提出した疑いが持たれている。実際の名義人は同社が運営する老人ホームの入所者で、預金残高は約7200万円だったという。
同市は証明書の原本を出すよう求めたが、経営者はコピーを提出した。同市が銀行に照会したところ、他人名義の口座と判明したという。同市は今年6月に愛知署に告訴。県警が今月13日に家宅捜索した。
中国だから下記の記事のようなことはありなのだろう。昔、中国の列車事故で日本からの修学旅行生が死亡した。補償額は400万円ぐらいだったと思う。
中国を旅行し、列車事故で死亡しても損害賠償金が400万円前後では利用しないほうが良い。死んでしまったら生き返ることは出来ない。
話は変わるが、福島原発で日本に住んでいる中国人が「中国の原発は日本よりも危ないと思う。」と言っていた。中国政府からの人間は
「中国の原発は安全だし、今後も原発を推進する。」と日本のテレビで発言していた。高速鉄道と同じレベルであれば、運が悪ければ
原発事故は起こるのであろう。その時、日本にも被害は来るのであろう。
鉄道省と新華社が死者数“食い違い” 事故原因より撤去作業優先 (1/2ページ)
(2/2ページ) 07/25/11 (産経新聞)
【温州(中国浙江省)=河崎真澄】中国浙江省の温州で23日夜に起きた高速鉄道追突事故の死傷者数をめぐり、国営新華社通信の報道と鉄道省の見解が食い違う異例の事態となり“情報の錯綜(さくそう)”が続いている。
新華社通信は24日午前に死者数35人、うち外国人2人と伝えたが、中国中央テレビは同日夕方に34人に修正した。一方、新華社は同日夜、「新たに8人の遺体がみつかった」と速報。死者数を43人に増やした。
ところが同日深夜、鉄道省の王勇平報道官が温州で行った記者会見で、「私が把握している死者数は35人という数字だけ」と述べて新華社の報道を否定。死者に外国人2人が含まれているとの新華社の報道内容については「知らなかった」と発言。地元記者が反発する場面もあった。
負傷者数をめぐっても同報道官は192人と発表。新華社が伝えていた210人以上という数字を否定した。だが2本の列車に合わせて1400人前後が乗っていた中での大惨事であり、浙江衛星テレビは25日未明、「(発表された死傷者以外に)行方不明者が、まだ多数いるもようだ」と、疑念を呈した。
大破した車両は24日、事故原因の調査も進まぬうちに、重機で切断するなど撤去作業が優先された。現場で陣頭指揮に当たっていた盛光祖鉄道相は記者団に対し「(24日)夕方までに運転を再開させる」と話しており、大破した車両の撤去を急がせた可能性もある。
一方、王報道官は同日深夜の会見で、事故車両の一部を付近の農地に重機で穴を掘って埋めたことを認めた。救助作業を円滑に進めるためだった、としているが、ずさんな対応を疑問視する声もある。
中国に新幹線の技術を提供したら真似された。常識で考えても中国だったらやることは想像できたはずだ。川崎重工の対応が甘すぎたのは明らか。
受注担当者達が受注だけしか考えていなかったのか、その後の対応を考えられる人材がトップにいなかったのか?
今回の事故は今後の受注活動に影響を与えるのは間違いないだろう。コストがかなり安くても命のリスクを軽視する先進国はないだろうから
発展途上国又は後進国しか相手に出来ないだろう。結果として川重を助けるような出来ことだが、今後、日本はもっと真剣に対応するべきだろう。
死者32人、190人超負傷 制御装置に重大な問題か 07/24/11 (産経新聞)
中国浙江省温州市で23日夜、高速鉄道の列車が別の高速列車に追突して双方の車両が脱線、一部車両が高架橋から転落した事故で、中国国営通信の新華社は24日早朝(日本時間同)、死者は32人、負傷者は191人と伝えた。現場では、地元の救助隊のほか中国軍兵士も出動し徹夜態勢で乗客の救出活動を続けた。
高速鉄道の列車が追突する異例の事故により、列車衝突回避に欠かせない制御装置に重大な問題があった可能性が浮上。救援と原因調査のため専門チームを現場に派遣した鉄道省当局は、事故原因の徹底究明に乗り出す構えだ。
上海の日本総領事館によると、24日未明時点で死傷者に日本人がいるとの情報はないが、同総領事館が引き続き情報収集を進めている。
中国中央テレビは24日未明、懸命の救出活動が続く現場の様子などを伝えた。献血の呼び掛けに多数の地元住民が応じているとし、負傷者の治療で病院が血液不足に陥っている実態を伝えた。(共同)
China high-speed train crash kills 35 07/23/11 (CBC)
 China high-speed train crash kills 35
China high-speed train crash kills 35
A Chinese bullet train lost power after being struck by lightning and was hit from behind by another train, sending four carriages off a bridge, killing at least 35 people and injuring 191, state media reported.
The official Xinhua News Agency said four cars on the second train plunged about 20 to 30 metres off the bridge.
Emergency workers carry out rescue operations while a crowd gathers among the wreckage of two carriages after a bullet train derailed and fell off a bridge following a collision with a second train. (China Daily/Reuters)The first train was travelling from the Zhejiang provincial capital of Hangzhou when the accident occurred in Wenzhou city at about 8:30 p.m. local time, Xinhua said.
Pictures on the Internet showed one badly damaged car lying on its side by the bridge and the second car leaning against the bridge after landing on its end.
 China high-speed train crash kills 35
China high-speed train crash kills 35
Xinhua quoted an unidentified witness as saying "rescuers have dragged many passengers out of the coach that fell on the ground."
The trains involved are "D" trains, the first generation bullet train with an average speed of about 150 kilometres per hour and not as fast as the new Beijing-Shanghai line.
Xinhua said the train hit by lightning was "D3115." It said the Ministry of Railways confirmed that it was hit from behind by train "D301."
China has spent billions of dollars and plans more massive spending to link the country with a high-speed rail network.
Recently, power outages and other malfunctions have plagued the showcase high-speed line between Beijing and Shanghai since it opened on June 30.
Official plans call for China's bullet train network to expand to 13,000 kilometres of track this year and 16,000 kilometres by 2020.
The huge spending connected with the rail expansion also has been blamed for corruption, and Railways Minister Liu Zhijun was dismissed this spring amid an investigation into unspecified corruption allegations.
No details have been released about the allegations against him, but news reports say they include kickbacks, bribes, illegal contracts and sexual liaisons.
「本当の原発発電原価」を公表しない経産省・電力業界の「詐術」 (Foresightコンテンツ-新潮社ニュースマガジン)
塩谷喜雄 Shioya Yoshio
科学ジャーナリスト
爆発後の福島第1原発3号機原子炉建屋[東京電力提供]=2011年3月21日【時事通信社】 この国では、「安定した復興」とは元の黙阿弥のことを指すらしい。政治家たちの錯乱ぶりに隠れて、原発と電力の地域独占は何の検証も経ずに、今まで通りそっくり継続される気配が濃厚である。福島の事故が打ち砕いた原発安全神話に代わって、経済産業省と電力会社が流布するのはもっぱら原発「安価」神話だ。
火力や水力に比べ原発の発電原価が断然安いという、架空の、妄想に近い数字が幅を利かせている。評価も監視も放棄した新聞・テレビは、今度も懲りずに虚構の安価神話をただ丸呑みして、確かな事実であるかのように伝え、社会を欺き続けている。日本経済が沈没するとすれば、その原因は原発停止による電力不足や料金高騰などではなく、行政と業界が一体となった利権と強欲体質の温存が主因であろう。
汚染疑い牛、新潟県知事が東電に賠償を要求 07/23/11 (朝日新聞)
東京電力の西沢俊夫社長が22日、就任後初めて新潟県を訪れ、泉田知事や、柏崎刈羽原子力発電所が立地する柏崎市、刈羽村の首長と会談した。
泉田知事は、放射性セシウムに汚染された稲わらを食べた疑いのある肉牛が出荷されている問題で、肉牛の価格低下部分などの損害賠償を求めた。西沢社長は「国とも相談しながら対応したい」とするにとどまり、具体的な言及を避けた。
泉田知事は会談の冒頭、損害賠償に関する申し入れ書を西沢社長に手渡した。申し入れ書では、〈1〉肉牛の出荷自粛に伴う収入の減少部分〈2〉汚染された稲わらの代替を購入する経費〈3〉風評被害による牛肉の価格低下部分――などを損害の対象とし、「仮渡し金の速やかな支払いを含め、補償を速やかに行う」ことを求めた。
政府は、国の暫定規制値を超えた牛肉を国が買い上げる方針を示している。新潟県から出荷された牛肉では規制値を超えるものは見つかっていないが、知事は「国のフレームワーク(枠組み)とは関係なくやってほしい」と要望した。
非公開の会談後、西沢社長は記者団に「国もいろいろ検討しているし、(原子力損害賠償紛争)審査会でも、指針がこれから出てくる。それを踏まえて対応したい」と述べたが、踏み込んだ発言はしなかった。
中越沖地震で停止したままの号機が残る柏崎刈羽原発については、「(地震後の点検など)やることをきちっとやるということに尽きる。(運転再開への)見通しなどは予断をもって云々(うんぬん)ということはない」と述べた。
西沢社長は知事との会談に先立ち、会田洋・柏崎市長、品田宏夫・刈羽村長と、それぞれ面会。いずれも柏崎刈羽原発の運転再開についてのやりとりは無かったという。西沢社長は福島第一原発の事故について謝罪し、「福島の教訓などを踏まえて柏崎刈羽原発の安全対策を徹底したい」と述べた。
メール例文、部長が作り営業所長らが配布 九電佐賀支社 07/20/11 (朝日新聞)
九州電力玄海原発(佐賀県玄海町)2、3号機の運転再開を巡る「やらせメール」問題で、再開に賛成するメールの例文は九電佐賀支社の玄海原子力担当部長が作り、総務部長の指示で営業所長らが取引先に配っていたことが分かった。大坪潔晴(きよはる)支社長(57)が19日、明らかにした。
国が6月26日に主催したテレビ番組は、原発の安全性を県民に説明する趣旨で、運転再開への賛否をインターネットで県民らから番組に投稿してもらう手法を採用。このため「運転再開に反対か慎重な意見が増えると危惧していた」と大坪支社長は認めた。
大坪支社長によると、対策を練るよう当時の支社の総務、企画管理、玄海原子力担当の3部長に指示。3部長が話し合い、見本となる例文を作って取引先に配り、賛成意見を投稿するよう頼むことを決めた。支社の玄海原子力担当部長が新聞の投書欄などを参考に作文。総務部長の指示で営業所長らが26社を訪問した。
住宅ローン汚職:別の住宅支援機構職員が142万円受領 07/19/11 (毎日新聞)
住宅ローン「フラット35」を巡る汚職事件で元営業推進室長が起訴された独立行政法人住宅金融支援機構(東京都文京区)は19日、別の50代男性職員が贈賄側の金融業者「住宅金融モーゲージ」(同港区)から計142万円を受け取っていたなどとして、懲戒免職処分にしたと発表した。同機構の宍戸信哉理事長は同日、大畠章宏国土交通相から厳重注意を受けた。
同機構によると、本店の金融機関営業担当部長だった男性職員は07年6月~08年2月ごろ、モ社から計142万円を受け取り、飲食接待を数十回受けた。別の部署にいた05年11~12月ごろにも、フラット取扱金融機関から飲食接待を10回程度受けたという。
事件では東京地検が今年6月、元営業推進室長、久世悟被告(52)を収賄罪で、モ社元会長の堀川嘉次被告(66)を贈賄罪で起訴。起訴状によると、久世被告は07年11月~08年9月、フラット35の取扱業者になることを目指していた堀川被告に、他の取扱業者の財務状況などの情報を教えた見返りとして計200万円を受け取ったとしている。
男性職員の問題は、久世被告の逮捕後、同機構が首都圏のフラット営業担当を中心に264人に聞き取り調査をして発覚した。男性職員は事件当時、久世被告と同じ部署にいたが、仕事上の接点は特になかったという。
また、久世被告の管理監督責任として本店部長クラスの職員を訓告、別の50代の男性職員もモ社の負担で2回会食をしたとして訓告処分とした。【樋岡徹也】
中国政府がだまらしたら終わり。そんなところだから問題ないでしょう。
ドラム缶千本分超の原油が流出 中国山東省沖の渤海 賠償額は24億円超 07/15/11 (産経新聞)
15日付の中国紙、京華時報によると、中国山東省沖の渤海で起きた海上油田原油流出事故で、生産作業を担当する米石油大手コノコフィリップスは14日、流出した原油などの総量は約1500バレルに上ることを明らかにした。約200リットル入りのドラム缶約1193本分に当たる。
同社は第三者の専門家とともに流出量の確定を急いでおり、中国側専門家は事故賠償額が2億元(約24億5千万円)を超える可能性を指摘した。(共同)
一度原発を許したら被害者になり苦労するかは運次第。将来、九州電力の原発は運良く事故を起こさないかもしれない。
しかし、事故を起こしたら福島第一原発事故と同じ運命を背負う。ただそれだけ。
独占企業であることのメリットと驕り。福島第一原発事故に関して政府は国民負担とか言っているけど、
福島の人達が不満と怒りを感じるが我慢できるのならそれで良いのではないか。多くの福島の被害者達が立ち上がらないのなら、
今後、他の原発で事故が起ころうとも日本人は立ち上がらないと思う。政治家や政党を選んだのは日本国民。「仕方がない」で我慢できるのなら
地域問題として扱えばよい。東京電力の株主優遇を見ても不公平な扱いが許されていることがわかる。この件に関してテレビからあまり批判を聞かない。
原爆が落とされた国と言っても、広島や長崎の人々と他の都道府県の人々との温度差は大きい。この温度差は他人事は他人事と言っているようなもの。九州の原発も
九州の人達が判断すればよい。何かあれば福島の被害者達のようにその時に考えればよい。九州の人達が九州電力の体質や考え方に我慢できるのなら
それでも良いのかも???
メールの文面まずかっただけ…問題意識低い九電 07/12/11 (読売新聞)
「やらせメール」問題で、九電の内部調査が行われている最中も、同社幹部やOBからは「文面がまずかっただけ」「『やらせ』と言われるほどのものなのか」といった発言が聞かれる。
信頼回復に努める立場にもかかわらず、問題意識の低さが浮き彫りとなった形だ。
真部利応(としお)社長は6日の記者会見で、「やらせメール」が誰の指示だったのか報道陣に質問され、「それが誰かというのは、大きな問題ですか」と、逆に聞き返した。
九電内には、メール問題を悪質だと認識していない空気がある。役員の一人は、「やらせメールが小さな問題とは言わないが、電力会社としては夏場の安定した電力供給の方が比べものにならないくらい大問題」と言い切る。
10日、賛成メールの2割が「やらせ」だったと報じられると、執行役員は「過半数だったら大問題だけど、2割というのは多いのかなぁ」と話した。
11日の鹿児島県議会に出席した幹部は「部下の課長が安易に呼びかけた」と責任逃れとも受け取れる発言をした。
「男性社員は『こんなコンプライアンスに反する行為は、自分の会社のためにはならない』と考え、知人に相談した」
多くの社員達は知らないだけで大企業だから不正やおかしな事をしていないとは限らない。だから隠蔽が存在するし、
政治家や闇の人間達との関係があるケースもある。福島原発事故については悪い意味では東電はがんばっている。
普通なら東電は解体だろ!
やらせメール、子会社社員が説明会前日に告発 07/08/11 (読売新聞)
九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)2、3号機の再稼働を巡る「やらせメール」問題が表面化したのは、九電子会社の男性社員による内部告発がきっかけだったことがわかった。
共産党福岡県委員会によると、説明会前日の6月25日、この男性社員が県内の党事務所を訪れ、「やらせメール」の指示があったことを情報提供した。会社が社員向けに通知した文書も同党に提供した。
メールは同22日、九電本社原子力発電本部の課長級社員から、子会社4社と九電の3事業所の社員各1人に送信された。男性社員の会社では、再稼働への賛成意見をメールで説明会に送るよう社員に通知された。男性社員は「こんなコンプライアンスに反する行為は、自分の会社のためにはならない」と考え、知人に相談したところ、共産党の事務所を紹介されたという。
「当時の原子力発電担当の副社長と、再稼働の地元交渉役を担っていた原子力発電本部の担当役員(いずれも6月末に退職)の2人が関与していた」
要するに九州電力は自己の利益のためなら、モラルもないし、手段も選ばない体質であることを証明しているようなものだ。退職しているから
退職金も貰えるし、処分もされないのだろう。やらせメール後、すぐに退職しているのだから不正な行為であることも認識していたのだろう。
悪質であること間違いなし。こんな体質の企業だと、何か不都合なことがあれば隠蔽することを躊躇しないかもしれない。
やらせメール、九電元副社長ら関与…社長陳謝 07/08/11 (読売新聞)
九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)2、3号機の再稼働を巡る「やらせメール」問題に、当時の原子力発電担当の副社長と、再稼働の地元交渉役を担っていた原子力発電本部の担当役員(いずれも6月末に退職)の2人が関与していたことが8日、九電の内部調査でわかった。
週明けに調査結果を発表する。今後、第三者委員会を発足させて幹部らの処分を決める方針。経営陣の関与が明らかになったことで、真部利応(としお)社長の経営責任が問われるのは必至だ。真部社長は同日、経済産業省の松下忠洋副大臣と会談し、メール問題について、陳謝した。
九電幹部らによると、2人は、県民向けの説明会が開かれる数日前の6月下旬、説明会の日程などを社員や子会社に周知するなどし、説明会を再稼働に理解を得る機会にすべきだとの意向を伝えたとみられる。
九電社内では、説明会の2日後の同28日に株主総会を控えていたため、説明会で再稼働への反対意見が相次げば、紛糾が予想された株主総会にさらに影響が出ることが懸念されていたという。九電幹部の一人は、「2人は『よろしく頼む』という気持ちを、部下に伝えたようだ」と話している。
その意向は、原子力発電本部の部長級社員を通じて課長級社員に伝わり、子会社4社と3事業所にメールで指示された。指示を受けた子会社の4人はいずれも九電本社の出身者だった。
「体質変わっていない」ことなど常識があり、企業の裏を知っている人であれば良くわかっていること。
しかし、政府は悪徳商売詐欺師のように問題はないとか、問題は解決したと奇麗事を言う。ここに問題がある。
なぜ東電の株主は救済されるのか?東電の株主に責任はないのか?大株主である東京都は責任がないのか?
利益しか考えなかった金融機関には責任がないのか?
日本政府が真剣に原発の完全管理や検査組織の改善に取り組んでいないことは明らかなこと。住民は納得しないが、
電力問題があるから稼動させてほしい。その代わり何年後には安全対策を行うとか、順番に安全対策をおこなうとか
真剣に取り組まないから不信が生まれるのだ。保安院が信用できる組織なのか?「NO」だろう!なのに保安院を
信用してほしいと言う事自体ばかげている。いつまでこの茶番劇プラスアルファーを続けるのか??
「体質変わっていない」やらせメールで経産相 07/08/11 (読売新聞)
海江田経済産業相は8日、閣議後の記者会見で、九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)2、3号機の再稼働を巡る「やらせメール」問題について、「今度の(福島第一原子力発電所の)事故を受けても、電力会社の体質や思考は何も変わっていないのではないか。これでは国民の信頼は得られない。本当に大きな失望を感じた」と述べた。
そのうえで「失望感にとどまっているわけにはいかない。二度とそういうことのないよう、しっかりとチェックしていかないといけない」として、九電に再発防止を強く求める考えを強調した。
九州電力が東京電力のように原発事故を起こしても、株主は守られるのだろう!
株主の責任とは何なのか??
原子力発電所がどの程度安全なのか、また、リスク管理について議論し、改善すべきだと思う。
しかし、東電だけでなく九州電力を見ても分かるが、組織に問題がある。原子力発電の危険性だけでなく、
電力会社(人災の可能性を含む組織)の体質の問題を解決しない限り現状は良くならないと思う。
九州には住んでいないので九州に旅行に行っている間に原発事故を起こさなければそれで良い。
東電を解体しない政府を見ていると問題の解決を望んでいないと思える。九州の人達が福島県の被害者達の
状況について把握していると思えないが、福島のようになった時点で考えればよい。九州の人達の問題。
九州の人達が今回の問題を穏便にしたいのならそれで良いのでは考えてしまう。
役員もメール作成に関与 九電、組織ぐるみか 原発番組の周知狙い 07/08/11 (産経新聞)
佐賀・玄海原発の安全性を説明する番組宛てに、九州電力社員が子会社に「やらせメール」を投稿するよう依頼していた問題で、九電の課長級男性社員が問題のメールを作成する際、当時の原子力担当役員が関与していたことが8日、分かった。同社関係者が明らかにした。番組放送の周知を呼び掛けるのが狙いだったとみられる。
メール発信源の男性社員は九電原子力発電本部に所属。メール作成は上司の部長が指示していたことが分かっていたが、さらに役員レベルの関与が判明したことで、九電が組織ぐるみで原発の再開に向けて番組に関わった可能性が高まった。
九電社長、社員を聴取 20分間、内容明かさず 07/07/11 (産経新聞)
九州電力社員が玄海原発(佐賀県玄海町)の安全性を説明する番組あてに原発再開を支持する「やらせメール」を送信するよう子会社に依頼していた問題で、九電の真部利応社長は7日、発信元とされる同社原子力発電本部の課長級男性社員を約20分間、事情聴取した。
聴取は7日午前10時20分に始まり、同40分ごろ終了。子会社にメールを送った動機や送信先などの事実確認をしたという。社員の答えについて九電は、7日夕までに開示していない。
九電によると、男性社員は6月22日に「西日本プラント工業」「九電産業」(ともに福岡市)など子会社4社と九電3事業所の担当者計7人に依頼メールを送信した。
依頼メールは、子会社社員らに自宅のパソコンを使って原発再開を容認する立場から意見や質問を番組あてに出すよう要請。一部子会社は社内ネットの掲示板に依頼文を掲載し、全社員が閲覧できる状態だった。
メール作成に九電役員も関与 当時の原子力担当 07/08/11 (西日本新聞)
九州電力「やらせメール」問題で、九電社員が子会社宛てのメールを作成する際、当時の原子力担当役員が関与していたことが8日、同社関係者への取材で分かった。番組の周知が目的だったという。
「玄海」覆う不信 原発再開・同意撤回 07/08/11 (西日本新聞朝刊)
「これまでの議論は何だったのか」「すべて信用できない」-。九州電力玄海原発(玄海町)2、3号機の運転再開をめぐり同町の岸本英雄町長が「再開同意」を撤回した7日、住民には不満と不信が渦巻いた。県民の理解を深めようと国がインターネットなどで放送した「説明番組」では九電による「やらせメール」も発覚。「議論はスタート地点ではなく、さらに後ろに下がった」。県関係者から嘆きに似た声が漏れた。
「今までの議論が水の泡になった」と憤るのは、6月26日の「説明番組」に出演した玄海町の農業平田義信さん(49)。国が全原発を対象に安全性を評価するストレステストの実施を表明したことに触れ、「国が番組で『安全だ』と断言したのは何だったのか。地方を振り回さないでほしい」と語気を強めた。
同町の主婦新雅子さん(77)は「これまでの説明はうそだったのか。何も信用できない」。同町の造園業山口孝司さん(55)も「後手後手で対策をひねり出す国のやり方にはあきれてしまう」と語り、地元同意の撤回を強いられた岸本町長に同情した。
九電による「やらせメール」でも、あらためて厳しい意見が相次いだ。これまで「再開容認派」だったという同町区長の山口正広さん(60)は「これまで長年かけて積み上げてきた九電との信頼は一気に失墜してしまった」と、町長の撤回判断を支持。一方、町内で民宿を営む男性(46)は「原発で町が潤っているのは確か。町長が撤回しても、一日も早く再稼働してほしいという気持ちは変わらない」と語った。
再稼働をめぐり、古川康知事は「立地町の意向」を判断条件の一つに据えていた。古川知事はこの日、菅直人首相に来県要請するため上京。県幹部の一人は「岸本町長は国に不信感を抱いたのだろう」。別の幹部は「安全の議論はやり直し。政府への信頼という意味では議論が後退した感が否めない」と語った。
九電に抗議数百件 「原発をやる資格ない」 07/07/11 (西日本新聞夕刊)
玄海原発(佐賀県玄海町)の県民説明番組をめぐる九州電力の「やらせメール」問題発覚から一夜明けた7日、同社本店(福岡市中央区)には、「原子力発電をやる資格はない」など、市民からの抗議電話やメールが午前中だけで数百件殺到、社員たちは対応に追われた。
九電によると、この日は朝から電話が鳴りやまない状態が続いた。「メールは誰の指示で送信されたのか」「事実関係を明らかにしろ」など、抗議や苦情がほとんどだったという。
本店では午前8時50分の業務開始を前に、社員が硬い表情で出社。報道陣から質問されても、「すいません」の一言だけで足早に立ち去った。男性社員の一人は「ちょっと状況がよく分からない」と話し、店内に急いだ。
本店前では、脱原発を求めて座り込みを続ける市民グループ「原発とめよう! 九電本店前ひろば」の青柳行信代表(64)が「やらせは組織ぐるみとも言える。市民の声に耳を傾け、取りあえず原発は停止して」と訴え。メンバーの大学院生の女性(25)=福岡市城南区=は「やっぱりかという感じ。『原発は安全』というのも真っ赤なうそだと分かった」と憤った。
近く責任判断 「やらせ」で九電社長 07/07/11 (西日本新聞夕刊)
玄海原発(佐賀県玄海町)の再稼働をめぐる九州電力の「やらせメール」問題で、九電の真部利応(まなべとしお)社長は7日朝、西日本新聞の取材に対し「早急に調査結果をまとめて今週中にも上京し、国に説明する」との考えを明らかにした。スケジュールを調整した上で8日にも海江田万里経済産業相や経産省幹部と面会し、説明、陳謝したい意向。
責任の取り方については、海外出張中の松尾新吾九電会長や国の意向も踏まえ、自らの進退も含め近く判断するとみられる。真部社長は取材に対し「まずは調査をしっかりやることが重要」とする一方、「すぐに投げ出していいのか、ということがある。責任の取り方にもいろいろある」と述べ、報酬カットを含め検討する意向を示した。
九電によると、玄海原発再稼働に地元の理解を得るため、国が6月末に放送した「説明番組」の前に、九電の本店課長級社員が、再稼働に賛同する意見を一般市民を装ってメールで同番組に投稿するよう社内や関連会社にメールで依頼していた。
ちぐはぐ対応・やらせメール…町長「怒り100%」 07/08/11 (読売新聞)
九州電力玄海原発2、3号機の再稼働問題で、7日、九電の真部利応(としお)社長に電話をかけて再稼働了承の撤回を伝えた佐賀県玄海町の岸本英雄町長。
この日行われた町議会原子力対策特別委員会で、政府のちぐはぐな対応や「やらせメール」で信頼を損ねた九電に激しく怒った。
玄海町で7日行われた町議会原子力対策特別委員会での岸本町長と議員の主なやり取り。
――海江田経産相が、ストレステスト(耐性検査)は安心を高める措置と言った一方、菅首相は再稼働や継続運転に必要な措置と明言したが
「閣内不一致という印象。再稼働を次に確認する場合は、菅首相ではない総理をつくっていただき、国が姿勢を示すことが大事」
――稼働中の1、4号機も止めてテストしてから、動かしてほしいと九電に申し入れてはどうか
「1、4号機はどう扱うか議論されるべきだ。その旨を町議会の意見として九電には伝えていくつもり。経産相は6日、安全は確保されているが、住民の安心を増すためにテストすると言った。多少は理解できるつもりで聞いた。その後に菅首相が再稼働はテストが前提だという発言があったことで怒り100%になってしまった」
――やらせメールの件で九電の体質や組織的な問題をどう考える
「信頼関係に少しひびが入った。人事管理の面で怠っていたように思える」
「やらせメール」2300人閲覧…九電子会社 07/08/11 (読売新聞)
九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)2、3号機の再稼働を巡る「やらせメール」問題で、九電から県民向け説明会に、再稼働に賛成するメールを送るよう指示された子会社4社(いずれも福岡市)の社員計約4400人のうち、少なくとも約2300人が指示メールの内容を閲覧していたことが7日、九電の社内調査でわかった。
九電は、3事業所(玄海原発、川内原発、川内原子力総合事務所)の社員を含めて、実際に何人が説明会に投稿したのか、調査を進めている。
九電によると、原子力発電本部の課長級社員が6月22日と同24日、子会社4社の原子力部門担当者に対し再稼働への賛成メールを送るよう指示。担当者は自社の社員に呼びかけ計2300人がメールを閲覧したという。子会社の一つ、西日本プラント工業によると、説明会3日前の6月23日、社内イントラ掲示板で再稼働を容認する意見を説明会にメールで送るよう呼びかけ全社員の6割に当たる1404人が閲覧したという。
九州電力、メール問題でおわび行脚 07/07/11 (読売新聞)
九州電力玄海原子力発電所(佐賀県玄海町)の再稼働をめぐる「やらせメール」問題で、九電の幹部社員らが7日、謝罪のため、玄海、川内(せんだい)の両原発が立地する一帯の自治体を訪れた。
鹿児島県議会には、山元春義副社長らが訪れ、「一番大事なときにご迷惑をかけ、信頼を失うようなことをしてしまい誠に申し訳ない」と金子万寿夫議長らに謝罪。社内で調査を進め、11日の原子力安全対策等特別委員会で結果を報告することを約束した。
今月4日の特別委で問題が取り上げられた際、参考人として出席した中村明・原子力発電本部副本部長は「そのような事実はない」と完全否定していた。
山元副社長の謝罪を受け、金子議長は「議会としても不愉快だし、県民にも申し訳ない」と苦言を呈した。
川内原発を抱える鹿児島県薩摩川内市役所には、九電川内原子力総合事務所の古城悟所長代理ら2人が訪問して岩切秀雄市長らに謝罪。古城所長代理らはその後、隣接するいちき串木野、阿久根の両市を訪問した。30キロ圏内の出水(いずみ)市やさつま町にも九電社員がおわびに訪れたという。
嘘でも見つからなければそれで良い。「大臣認定を受けるには、民間評価機関に提出したサンプルが防火性能を満たしていればよく、
製品そのものをチェックする仕組みはない。」正直者がばかを見るのが日本の制度だ。
大臣認定の不燃木材、9社が防火性能満たさず 06/29/11 (読売新聞)
国土交通省は29日、杉やヒノキなどにホウ酸などの薬液を加えて燃えにくくした建材「不燃木材」として、国土交通大臣の認定を受けていたメーカー10社の製品を抜き打ちで調査したところ、うち9社の製品が建築基準法で定める防火性能を満たしていなかったと発表した。
同省は9社に対し、原因究明と再発防止を求める。
9社は、「ヨコタニ」(奈良県)、「チャネルオリジナル」(横浜市)、「アドコスミック」(京都市)など。いずれも2004~07年に大臣認定を受けていた。
同省の加熱試験などの結果、9社の製品は、基準以上の熱を外部に発したり、亀裂が入ったりした。薬液の注入量が少なかったり、成分が薄かった可能性が強いという。大臣認定を受けるには、民間評価機関に提出したサンプルが防火性能を満たしていればよく、製品そのものをチェックする仕組みはない。
株を紙切れにして東電は1からはじめれば良い。他の企業であれば当然そうなる。
大口の株主だけを救済するために税金が使われる。東電を企業として認識しているのであれば、政府の救済がなるとも
当然だと考えるべきだろう。一番責任が問われる大株主は救済される。これでは失敗から何も学ばない。学ぶ必要もない
前例を作るだけだ。増税しか待っていない将来。責任を取るべき企業や官僚は責任を取らない。民主党よ、こんな国に子供を
住ませたいと思うか??
「リストラ、独自判断で」東電・西沢新社長に聞く 06/29/11 (読売新聞)
企業年金削減も視野
インタビューに答える西沢俊夫・東京電力新社長(東京・千代田区の東電本店で)=源幸正倫撮影 東京電力は28日の株主総会後の取締役会で、退任する清水正孝社長の後任社長に、西沢俊夫常務を選任した。(聞き手・井上忠明)
新社長に就任した西沢氏は、読売新聞のインタビューに応じ、予定する6000億円以上の資産売却について、「独自の判断で行う」と述べ、東電の新経営陣主導でリストラを行う姿勢を強調した。企業年金の削減や、希望退職についても検討する考えを示した。主なやりとりは以下の通り。
――福島第一原発事故の賠償支援を行う原子力損害賠償支援機構法案の行方が不透明だ。
「成立しなければ資金繰りは非常に厳しくなる。成立が遅れれば、賠償の支払いは国と相談する」
――被害者への仮払いは、国の負担金1200億円を超えて支払えないのか。
「国の負担を超えて支払えば、債務と認識しないといけない。早く補償はしたいが、無尽蔵に出せば企業として成り立たない」
――資産売却では政府が設けた第三者委員会の意見を参考にするか。
「売却はあくまでも我々が行うもので、(委員会に直接の)権限はない。ただ、貴重なご意見としては承りたい。我々も電気事業に関係のない資産の売却と徹底したコストカットをやる」
――発電所の売却も聖域ではないとの考えがある。
「そこは議論の必要がある。我々の考え方を示す」
――希望退職や企業年金の削減は。
「視野には入っている。今は事故処理や賠償などで人手が必要で、見極めながら検討する。ただ、企業年金は法律で守られており、一方的に決められない」
――電気料金の値上げは検討するか。
「今はまだ念頭にない。まず徹底した合理化を行い、社会の理解を得ることに専念する」
――今夏の電力需給は。
「(企業や家庭の節電で)大丈夫と思うが、安心はしていない。昨夏のような猛暑が続けば、(計画停電はせずに)節電をお願いして電力をやり繰りする」
クローズアップ2011:内部被ばく 東電、甘い計算法主張 06/15/11 (毎日新聞 東京朝刊)
◇厚労相「内部被ばく100ミリシーベルト限度」
東京電力福島第1原発で、限度を超えた被ばくをする作業員が相次いでいる。特に放射性物質を体内に取り込む内部被ばくが深刻だ。細川律夫厚生労働相は14日、内部被ばくが100ミリシーベルトを超えた人を作業から外すよう東電に指示したが、被ばく量の算定を巡って東電と厚労省が対立、作業員の安全を優先した対策が遅れた。作業の長期化が避けられない中、被ばくの実態把握さえおぼつかない現状は、東電が工程表で公約した復旧作業にも影響しかねない。
◇根拠薄い「政治判断」
「東電は当初、内部被ばく線量を甘い方法で計算していた」。厚労省の幹部は憤る。
福島第1原発の作業員から緊急時の上限の250ミリシーベルトを超える被ばくをしたとみられる2人の存在が発覚した5月30日には、内部被ばくの線量は不明だった。線量計算を巡り厚労省は、同原発で最初に水素爆発があった3月12日を起算点にするよう東電に求めた。しかし、東電側は「いつ内部被ばくしたかは不明。3月末まで作業したなら震災当日と月末の中間の3月21日前後を起算点にすべきだ」などと主張した。
内部被ばくは「ホールボディーカウンター」という機器を使い、ある時点の線量を測った上で過去にさかのぼって総量を積算する。さかのぼる期間が長いほど積算線量は高くなるため、東電側の計算では厚労省より積算線量が低くなる。厚労省労働基準局の職員は「厳しく計算するよう説得したが向こうも譲らず、にらみ合いが続いた」と証言する。
ただ、東電の測定値は「暫定値」で、最終的な線量は放射線医学総合研究所(放医研)が精密に検査し算出する。放医研は厚労省と同じ起算点を用いて6月10日、2人の内部被ばくを590~540ミリシーベルト、外部被ばくと合わせて678~643ミリシーベルトで確定させた。
東電も最終的には放医研に合わせて計算し直して13日に同省へ報告、新たに6人の上限超えが判明した。
一方、細川厚労相が「内部被ばくの限度は100ミリシーベルト」と指示したのは根拠の薄い「政治判断」だった。
最初の上限超え発覚後、厚労省は同様の作業をしていた約130人の内部被ばく線量を測るよう東電に指示し、6月3日に報告させた。この時点では新たな上限超えはいなかったが、100ミリシーベルト超が3人いた。当時は線量計算を巡り東電と争っていた時期で、厚労省は「100ミリシーベルト超の3人も最終的に上限超えの可能性が高い」と判断、作業から外すよう指示していた。
その後、東電が計算し直した13日の報告を同省は「実態に近い」と評価。この報告では新たな上限超え6人のほか、200ミリシーベルト超の作業員が6人いたため、この6人も念のため作業から外すよう事務レベルで指示した。
しかし、細川厚労相は「100ミリシーベルト超」で作業から外した3日の指示にこだわり、事務レベルの指示を変更した。基準が後退したと受け取られるのを恐れたとも見えるが、労基局の高崎真一・計画課長は「東電の対応が遅れがちな点も踏まえた政治判断」と説明した。【井上英介】
◇基準高すぎる
元原発作業員が東電に損害賠償を求めた訴訟で原告代理人を務めた鈴木篤弁護士は「原告は年間70ミリシーベルトの外部被ばくで多発性骨髄腫が労災認定されたが、5ミリシーベルトで白血病が労災認定されたケースもある。今回の内部被ばくには絶句するしかない」と話す。その上で「100ミリシーベルトという基準は高すぎる。そもそも、内部被ばくの基準がなかったのは大問題だ」と指摘している。
◇3月の作業員、2割未検査
被ばく線量が250ミリシーベルトを超えた作業員8人は、事故発生直後に構内で作業していた。東電の松本純一原子力・立地本部長代理は「発生から1週間はマスク着用の徹底や空気中の放射線測定ができていなかった」と説明する。
最初に250ミリシーベルトを超えたことが判明した2人は、3、4号機の中央制御室の運転員で、3月11日はマスクを着けていなかった。新たに判明した6人について東電は「マスク着用の指示は出した」としているが、現場でどの程度徹底されていたかは不明だ。
現状把握も追いついていない。放射性物質がピークだった3月に同原発で作業していた3726人のうち、内部被ばく量が判明しているのは約6割の2367人。残る1359人の半分は検査すら受けていない。
測定器(ホールボディーカウンター)はわずか4台しかない。東電は「よそから運ぶにも専門業者に依頼したり設置場所の補強工事が必要で時間がかかっている」と釈明する。
現場から約20キロ離れた前線基地の「Jヴィレッジ」(福島県楢葉町)で車両の除染作業に携わる下請け会社の男性(28)は「内部被ばくの基準を設けるのは当然だが、それ以前に検査の環境を整えるべきだ」と訴える。ホールボディーカウンターが足りないためなかなか検査を受けられず、作業員の不満がくすぶっているという。
東電は5月に見直した工程表に「作業環境の改善」を盛り込んだ。休憩所の増設など一部は着手しているが、「上限超え」が増える中、作業に支障が出る恐れもある。
松本本部長代理は会見で「作業員が足りなくなる事態にはならない」と強調した。経済産業省原子力安全・保安院の西山英彦審議官は「作業員が足りなくなれば、他の電力会社などの協力で人材を確保しながら、工程に支障がないよう努めたい」と話す。小林圭二・元京都大原子炉実験所講師(原子核工学)は、「東電や政府はメンツをかけて工程表通りに復旧を進めようとしているが、作業員の人命や健康を軽視している」と憤る。【岡田英、久野華代、袴田貴行、河内敏康】
==============
■福島第1原発での限度を超えた被ばくを巡る動き■
4月27日 50代女性社員が法定の限度(女性は3カ月で5ミリシーベルト)を超える17.55ミリシーベルトの被ばくと東電が発表
5月 1日 40代女性社員が7.49ミリシーベルトの被ばくと東電が発表
30日 30代と40代の男性社員が、緊急時被ばく限度の250ミリシーベルトを超える被ばくの可能性があると東電が発表
6月 7日 厚生労働省が労働安全衛生法に基づき福島第1原発に立ち入り調査
10日 放射線医学総合研究所の評価で30代社員の被ばく量は678ミリシーベルト、40代社員は643ミリシーベルトと判明。経済産業省原子力安全・保安院が東電を厳重注意。厚労省が是正勧告
13日 新たに6人が250ミリシーベルトを超えた可能性があると厚労省が発表
14日 細川律夫厚労相が、内部被ばくが100ミリシーベルトを超えた作業員は作業から外すよう東電に指示
東証社長、東電の法的整理を主張 「日航と同様に」 06/04/11 (朝日新聞)
東京証券取引所グループの斉藤惇社長は、原発事故で経営危機にある東京電力について、法的整理による再建が望ましいという見解を明らかにした。朝日新聞のウェブマガジン「法と経済のジャーナル Asahi Judiciary」のインタビューに答えた。
斉藤社長は産業再生機構(現在は解散)の元社長。ダイエーやカネボウの再生を手がけた経験から「東電でも(会社更生法で再建中の)日本航空と同様の処理が望ましい」と語った。
1990年代の金融システム危機を参考にした処理案も提示。特別法をつくり、東電の資産内容を厳しく調査。債務超過ならば一時国有化し、銀行には債権放棄を求める。その場合、東電は上場廃止になるが、数年後に発電会社として再上場する案を示した。送電設備の売却や原発の国有化の可能性も指摘した。
いすゞが検査逃れ? ディーゼルトラックが高濃度のNOx排出 同社「意図的ではない」と否定 06/03/11 (産経新聞)
いすゞ自動車のディーゼル4トントラック「フォワード」が、平成22年の排出ガス規制(ポスト新長期規制)に試験段階では適合しているとしていたにも関わらず、実際の走行状態ではNO●(=x)(窒素酸化物)が基準の3倍以上排出されていたことが3日、東京都環境科学研究所の調査で分かった。同社は同日、国土交通省にフォワード計886台のリコールを届け出た。
都は「排出ガス低減性能を無効化させる機能を搭載していた」と判断した。こうした事例がみつかるのは初めてという。都は国交省に道路運送車両法違反の疑いで通報している。
都環境局によると、トラックは時速60キロで200秒程度走行すると、車載コンピューターが自動的に作動し、基準を約3倍上回る360ppmの濃度のNO●(=x)を排出するという。これを「無効化機能」と指摘した。
都は国に対し、排出ガス規制では明文化されていない「無効化機能」の禁止について規定を設けるように求めるとともに、都の環境確保条例の規定も見直していくという。
これに対し、同社は「エンジン制御プログラムの影響で、低速状態での継続走行や急激な加速の際に、NO●(=x)の排出値が悪化する恐れがある」と説明。「検査逃れなど、意図的なものではないが、誠意を持って対応する」と話している。
同社は都の指摘を受け、社内調査を実施した上で、5月25日以降、出荷を停止。販売済みの全車両について、プログラムを書き換え、エンジン本体の対策も検討するという。
都によると、アメリカでは1998年、燃費向上のために無効化機能を搭載したとして、フォード社が大気浄化法違反などで総額780万ドルの賠償金などを支払った事例があるという。
マニュアルは形式的なものでなく、実際に使われていなければ意味がない。マニュアルや規則があるから問題ないと思っていたら
大間違い。マニュアルはあくまでも補足的なものであって判断する人間が重要である。危険を伴う結果又は危険を伴う現場では
マニュアルの重要度が高いのでマニュアル作成や改正にコストや時間がかかることを理解するべきだと思う。保険と同じで
事故が起きるまでは必要とされないし、内容も注目されることはない。死亡者がいないので運が良かった。
山本太郎、オフィシャルツイッターアカウント
占冠村の特急事故:乗員対応、手順書通り 出火気付かず避難誘導なし/北海道 05/27/11 (毎日新聞)
JR石勝線のトンネル内で起きた特急列車の脱線・火災事故で、運転士や車掌の行動はほぼJR北海道のマニュアルや規則通りだったにもかかわらず、出火に気付かなかったことなどで結果的に事態に対応しきれなかったことが、同社への取材で分かった。乗客への避難誘導ができなかった点はJRも対応の誤りを認めており、今後マニュアルの見直しも求められそうだ。
JRによると、列車のトラブル時のマニュアルには「異常時運転取扱手順書」「トンネル内における列車火災時の処置手順」などがある。
事故直後に取材に応じた「スーパーおおぞら14号」の男性車掌(60)によると、車掌は占冠村の「第1ニニウトンネル」に入る直前に異音を耳にし、男性運転士(26)に車内電話で緊急停止を要請した。異常時手順書の「異常を感じたら、ただちに列車を停止すること」との指示に沿った対応だった。
止まったのは、トンネルから約200メートル入った地点。トンネル内の処置手順は、火災発生時はトンネル内にとどまらず外に出るよう求めている。運転士は火災は把握していなかったが、煙があったため前進を試みた。だがギアが切り替わらず、車両は動かなかった。
車掌は周囲の乗客に「私が先に降りて、出口までどのくらいかかるか見てくる」と話し、列車を降りた。JRの乗務員規則では、運転指令の許可がなければ乗客を車外に出してはいけないことになっている。だが乗客は煙の充満に耐えきれず、車掌が戻る前に非常用コックを開けて自主避難を始めた。
運転手と車掌、客室乗務員の計4人は乗客が全員下車してから避難を始めたが、乗客の誘導には誰も当たらなかった。4人には最後まで、火災が起きている認識はなかったとみられる。
運転士は運転歴10カ月の若手、車掌は勤続30年超。JR北海道の一條昌幸鉄道事業本部長は「状況判断をもう少し早くすべきだった」と話している。【伊藤直孝、吉井理記、小川祐希】
==============
◇JR特急火災事故の経過
《27日午後》
9時 56分 特急スーパーおおぞら14号が占冠村のトンネル内で急停止。後列1~3号車両に煙が充満
57分 運転士が運転指令センター(札幌市)に「1、2号車で機関停止」と連絡
10時 8分 運転士が1~3号車の乗客を前列4~6号車に誘導開始
11分 運転士が運転指令に「全部止まっている」と連絡。その後、車掌がいったん下車し脱出経路のトンネル出口を確認
21分 運転指令が事故発生の110番
30分 いったん車両を降りて車体を確認した運転士が運転指令に「全車、煙が発生している。火災は発生していない」と連絡。乗客が自発的に降車して避難を始める
34分 車掌が運転指令に「乗客が車両から降り始めた」と連絡
43分 運転指令が「列車から煙が出ている」と119番
11時27分 乗客全員が降りた後、運転士と車掌、客室乗務員の計4人が最後に下車
《28日午前》
0時ごろ 乗員・乗客全員がトンネルの外に出る
2分 JRが道警からの連絡で火災を認識
3時10分 乗客207人が占冠村の施設に避難。その後、バスで札幌や千歳へ移動
18分 道警が車両からの全員避難を確認
7時36分 火災が鎮火
※JR北海道、道警の発表などによる
下記の2つの記事を考えると仕事は厳しいね。お金のためには二つの顔が必要なのか?電力会社は民間企業と言ったり、公的な役割をになっていると民主党は言っている。
公的な役割を担っている企業が不利益な発言をしたから後ろから圧力をかけてもよいのか?民間企業だから許されるのなら、
東電を救済しなくてもよいとも考えられる。東京電力福島第一原子力発電所の事故は現実に起きた。被害も将来における被害を考えると
想像もつかないほど酷い。常識で考えると原発についておかしな点はあった。しかし金や政治的な圧力で押さえ込んできた。
投資家も金融機関も隠れたリスクを見逃してきた。何かあれば政治家に頼る、又は電気料金に上乗せすれば問題なので安定した
投資先を考えていたのだろう。事故が起こった以上、官僚や政治家の屁理屈では日本の批判はメディアをコントロールすることにより
可能かもしれないが、世界からの批判は抑えることは出来ない。インタネットや急速に成長している通信手段により昔のように
力で押さえ込むことも難しくなった。原発の危険性と管理問題による危険性を真剣に考えるべきだろう。日本の問題は問題点とリスクが
全て公開されることはない。
山本太郎、オフィシャルツイッターアカウント
津波被害の文献知りながら「記録なし」と説明 関西電力 05/27/11 (毎日新聞)
関西電力の原発がある福井県若狭地方での過去の津波被害をめぐり、関電が被害を記述する文献の存在を把握しながら、「文献記録はない」と地元などに説明してきたことが26日、分かった。
文献に記述があったのは1586年に発生した「天正大地震」。敦賀短大の外岡慎一郎(とのおか・しんいちろう)教授(日本中世史)によると、京都の神社に伝わる「兼見卿記(かねみきょうき)」と、ポルトガル人宣教師ルイス・フロイスの「日本史」の二つの文献に、若狭地方が地震にともなう大津波に襲われ、多数の人が死亡したとする記述があった。
一方、これまで関電は地元への広報誌などで、「文献などからも周辺で津波による大きな被害記録はありません」と説明してきた。
関電によると、1975年発行の「日本被害地震総覧」(東京大学出版会)が天正大地震は岐阜県付近を震源とする内陸地震だったとしていることから、同社は「津波は起こらなかったと判断した」(広報)という。兼見卿記など二つの文献の内容は81年に把握していたが、「総覧は過去の被害を網羅したもので、より信用性が高いと判断した」という。
ただ、都合の良い記述だけをもとにした説明との批判が起こる可能性もあり、今後、関電の説明責任が問われそうだ。夏の電力供給のカギを握る福井県内の原発の運転再開を認めるかどうか、地元の判断にも影響する可能性がある。(清井聡、溝呂木佐季)
山本太郎、出演予定のドラマ降板に 反原発発言が原因か ツイッターで大反響 05/27/11 (毎日新聞)
原発問題に関する発言を問題視され、決まっていたドラマを降板させられたことを自身のツイッターで告白した山本太郎に、心配の声が寄せられている。
25日夜、山本は自身のツイッターに、「今日、マネージャーからmailがあった。『7月8月に予定されていたドラマですが、原発発言が問題になっており、なくなりました。』だって。マネージャーには申し訳ない事をした。僕をブッキングする為に追い続けた企画だったろうに。ごめんね」とツイート。山本は23日に、福島から来た子を持つ親たち100人を含む多くの人たちと共に文部科学省前に集結し、文科省が定めた学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安「放射線量年間20ミリシーベルト」の撤回を訴えたばかり。わずか2日後のことだった。
山本はこれまでも脱原発のデモに参加したり、福島の子どもたちを疎開させるために立ち上げられたプロジェクト「オペレーションコドモタチ」を通して、通常の1ミリシーベルトの20倍となる基準値に異を唱え、「チェルノブイリでは、年間5ミリシーベルトで住民は強制退去。なのに福島の子どもたちは、文部科学省によると20ミリシーベルトでも大丈夫らしいです。殺人行為です。避難させれば、賠償などとんでもないお金がかかる。だから、国は見殺しにしようとしている。それが答えです」という7分以上にわたるメッセージを伝えていた。
23日、われわれの取材に応えた山本は、「電力会社はメディアの最大のスポンサーですし、さまざまな事情はあります」と言っていたが、言葉どおりの現実が彼を待ち構えていた。たったひとりで立ち上がり、デモにも堂々と参加を続けてきた山本に、ネット上では、「やっぱり干されてしまった!」「ひどすぎる!」「これが現実かよ……」と、同情の声が次々に上がっている。心配するフォロワーたちに向け、山本は「抗議するからTV局、プロデューサー教えて、などなど励まし有難う! 外されたドラマでも、現場には迷惑掛けられないから言えない。一俳優の終わりの始まりなんて大した事じゃない。そんな事より皆さんの正義感溢れるエネルギー、20mSV撤回、子供達の疎開、脱原発へ! 皆で日本の崩壊食い止めよう!」と、今後も変わらず、声を上げ続けていく覚悟を伝えている。(編集部:森田真帆)
東電株を保有しているのだから仕方がない。年約25億円の配当なしで黒字になるように努力してほしい。
「都の3月末の保有株数は4267万株で、第5位の大株主。」東電を解体したら株が紙切れになるかもしれない。
東京都には他の都道府県に比べると稼げる企業がある。目先の利益だけを考えずに東電を解体することに賛成してほしい。
都バス事業、赤字転落も 年間25億…東電配当見送り 05/26/11 11時20分 (読売新聞)
東京電力福島第1原発事故に伴い、東電株の配当が見送られる影響で、年約25億円の配当を受けていた都交通局の平成23年度のバス事業が赤字に転落するおそれがあることが25日、分かった。
都は、都交通局の前身である東京市電気局が行っていた電気事業を、戦後に東電が吸収した経緯から、東電株を大量に所有。交通事業会計に組み入れられ、都電の廃止路線を引き継いだ都営バス事業が年約25億円の配当を予算化している。
都の3月末の保有株数は4267万株で、第5位の大株主。都営バス事業は黒字続きだが、21年度決算ベースで計算すると、約8億円の黒字は、東電の配当がなくなると17億円以上の赤字になる。
都は300億円以上ある累積資金残を取り崩すなどして対応し、当面、バス運賃の値上げはしない方針。
東電決算に監査法人「継続企業の前提に疑義」 保安院 05/26/11 11時20分 (読売新聞)
東京電力は26日、今月20日に発表した2011年3月期の連結決算について、監査法人から、福島第一原子力発電所の事故に伴う賠償額が不透明で、賠償の枠組みも今後の検討を要することなどから、今後の経営にリスクがあるとの指摘を受けていたことを明らかにした。
監査法人は、決算自体は適正という意見を表明したが、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在している」と指摘した。
東電は20日の決算で、金融機関を除く日本企業としては最大となる1兆2473億円の税引き後利益の赤字を計上した。
東京電力はISOをほとんどの発電所で取得していない。
柏崎刈羽原子力発電所が「ISO9001」認証取得 (東京電力)しただけだ。
東京電力株式会社(100%出資)の子会社 東電工業 (東電工業)
は原子力部門でも ISO 9001 認証取得している。
組織のフローチャートには福島第一原子力事業所(東電工業)
も入っている。東電工業がかかわっていればマニュアルに下請け作業員や教育及び訓練も記載されていると思う。
詳細は知らないが、東電工業がかかわっていればISO認証のキャンセルや明らかな法令違反があることは
間違いない。5月25日のNHKのニュースで見たが何も教育を受けていない作業員が福島原発で働かされていた。
信じられないことだ。まあ、これが現実なのであろう。
内部被ばく基準超え 作業員の不安(NHKニュースウォッチ9)
復旧作業が続く東京電力福島第一原子力発電所。NHKの取材で、内部被ばくが基準値を超えている作業員が相次ぎ、中には基準値の50倍に達している作業員もいることがわかりました。
福島原発:東電に厳重注意…被ばく管理ずさん 保安院 05/26/11 0時02分 (毎日新聞)
東京電力福島第1、第2原発の労働者の被ばく管理について複数の法令違反があったとして、経済産業省原子力安全・保安院は25日、東電に文書で厳重注意した。保安院によると、第1原発で復旧作業の拠点となる免震重要棟は、空気中の放射性物質濃度が法定の値を超えていたが、マスクなどの適切な防護をしていなかった。
放射線量が上昇した構内で、放射線業務従事者に指定されていない女性従業員が5人働き、うち2人の被ばく量は一般人の被ばく限度(年間1ミリシーベルト)を超えた。同従事者の指定を受けている女性従業員2人も、被ばく量が限度(3カ月で5ミリシーベルト)を超えていた。第2原発では3月14日~4月21日、大気中の放射線量が国の基準値を上回ったが、作業員に線量計を携帯させるなどの適切な管理を怠った。【足立旬子、関雄輔】
ほんと日本人は悲しい人生を歩まされるのが好きだ!こんな政府そしてこんな政治家達に利用され働かされる。
一部の金持ちや大企業は安泰で中小企業や下請企業だけしわ寄せで苦しむ。もちろん中小企業や下請企業の従業員も苦しむ。
これじゃ幸せになれないな!
独自入手の極秘資料が暴く 国民欺く東電賠償スキーム
(1/3ページ)
大前提は「絶対に東電を破綻させない」(2/3ページ)
利害関係者すべてが責任を逃れるスキーム (2/3ページ) 05/20/11(ダイヤモンド)
東京電力の福島第1原子力発電所の事故の損害賠償をめぐり、本誌は政府が賠償スキームの根拠とした極秘資料を入手した。詳細を分析すると、国民だけに負担を強いる賠償スキームのいびつな構造が浮かび上がった。与党内からも批判が噴出し、その法案成立には暗雲が垂れ込めてきた。
政府は東電の賠償スキーム決定を1日先送り、5月13日に正式発表した。Photo:REUTERS/AFLO 「せっかく救済案をまとめたというのに、このままでは東電が倒産してしまう」
5月中旬、金融政策に詳しい民主党の中堅議員は、こんなことを口にした。東京電力の経営破綻が現実のものとなりつつあると感じていたからだ。そんな事態になれば、金融市場は大混乱に陥りかねず、危機感を強めていたのだ。
政府は、東電の福島第1原子力発電所事故をめぐる損害賠償が巨額になることを受け、賠償を支援するスキームの策定を急いでいた。5月に入ってからは閣僚間で詰めの作業を進め、13日に正式な政府案として発表する。
その中身は、一義的には東電が賠償責任を負うものの、賠償額が大き過ぎて支払えなくなった場合には、官民で新設する賠償機構に投入した資金を使って支援するというものだ。
ところが、政府内の了承も取り付け、あとは開会中の通常国会に法案を提出するのを待つだけだというのに、民主党内は大混乱に陥っていた。
「賠償は国が責任を負うべき」
「もっと東電のリストラを進めるべきだ」
政府案の発表後も、国や東電の責任をめぐって異論が噴出。民主党内の意見は大きく分かれ、今もなお党内には不満が燻り続けているのだ。
それもそのはず。民主党内での議論は、政府案発表の直前にしか行われておらず、党内調整は皆無に等しかった。そればかりか、「政府案への賛成が大前提で、まさに結論ありきの出来レース」(党幹部)だったため、多くの議員が納得しないまま公表されてしまったからだ。
「破綻させない」を前提に?
都合のいい数字積み上げ
確かに、与党内から異論が出るのも無理のない話。政府案の中身を詳細に分析すれば、じつに多くの火種を内包したものであるかが明らかだからだ。その足がかりは、本誌が独自に入手した内部資料にある。
これは、政府案を作成する際、東電の将来の財務状況について政府内部で独自に試算したシミュレーション。ペーパーの右上には、「会議後回収」の判が押されており、政府高官しか目にしていないものだ。
その中身を理解するために、まずは賠償スキームの詳細について触れておく。まず、被害者への賠償金の支払いを官民で支援する「賠償機構」を設立、この機構に銀行が融資を行い、その融資には政府保証を付ける。
拡大画像表示はこちらをクリック 機構には、東電を含む原発を保有する電力会社も負担金を拠出、政府も現金と同義の「交付国債」を発行して機構に注入する。こうして資金が集まった機構が、東電の優先株を引き受けるなどして、東電に資金援助するかたちだ(右図参照)。
そのうえで、今度は下の表に目を転じていただきたい。これはシミュレーションのポイントをまとめたもの。試算の前提条件として、被害者への賠償金を10兆円と仮定し、2011年度から5年にわたって年間2兆円ずつ支払うことにしている。その資金は機構から援助されるが、東電は機構に対し、負担金というかたちで25年かけて返済する設定だ。
拡大画像表示はこちらをクリック ここで押さえておいてほしいのは、このシミュレーションが、「絶対に東電を破綻させない」という大前提で作成されている点だ。理由は二つ。電力の安定供給を維持しつつ、確実な賠償の支払い義務も負わせる必要があるためだ。
そのため出発点として、この資料には、「社債でのリファイナンスがメインストーリー」とある。つまり社債を発行し、自ら資金調達できる状態にまで自立することがゴールとされているのだ。
それゆえ、東電が15年度から社債を7000億円発行すると想定(①)。そのためには、前年度には黒字化しなければならないし(②)、社債発行には格付けでA格が必要。そこで、自己資本比率が最低でも10%を維持していなければならないと考えている(③)。
11年度に10兆円の賠償金が負債に乗ると、東電は即、債務超過に陥る。そのため、「機構宛請求権」なるものを資産側に同じ額だけ計上して相殺している。
資産と負債に等しい額を乗せても、維持しなければならない自己資本比率は引き下がるから、11年度に機構が優先株を引き受けるかたちで1兆8000億円、資本注入することにしている(④)。
それでもなお、原子力発電の代わりとなる火力発電の燃料費がコストを押し上げるため、12年度末には自己資本比率が10%を下回る危険性がある。それを回避するためには約1兆円の電気料収入の増加が必要で、その多くを電気料金としていとも簡単に転嫁するとしている(⑤)。こうした“荒業”を使わなければ、社債の発行やリファイナンスもままならず、東電は破綻の憂き目に遭う。そうならないように、さまざまな数字を“創作”したものといえるのだ。
ましてや前提条件が甘い。格付けが維持されていても社債を発行できるとは限らないし、自己資本比率が10%以上であればA格かといえば、「それだけで決まるわけではない」と格付け機関関係者は口を揃える。原発の廃炉費用も、10兆円という見通しもあるなかで、わずか1.5兆円にすぎない。
そしてなにより、賠償金を10兆円と仮定しているが、バランスシート上で資産と負債に同額を計上しているため、賠償額がいくらであろうと東電自身はなにも傷まず支払うことができるという奇策が講じられているのだ。
すべては電気料金に転嫁?
25年間で30万円上乗せ
しかし、東電がこうしたスキームを使わねばならないほど追い込まれているかといえば、そうでもない。
東電が取り組むとしているコストカットは、5兆5000億円の営業費用のうち、人件費の1割カットなどでわずか3100億円にとどまる。少なくとも6000億円は持っているとされる不動産や株式といった資産の処分額は、3000億円にすぎず、これとは別に1000億円の海外資産も保有したままだ。
東電だけではない。株主責任という意味でいえば減資するのが普通だが、株主の負担は検討されていない。それどころか、18年度からは既存株主への配当を再開させるとしている始末だ。
金融機関や社債権者に至っては、毎年1545億円の利息が据え置かれており、まったく傷まない。銀行側は「3月に行った超低金利での東電への緊急融資2兆円で、十分な責任を果たしている」と反論するが、こうした状況で利息が保証されるというのも、なんとも都合のいい話ではある。
つまり、東電はもちろん、本来責任を負うべき利害関係者すべてが責任を逃れるスキームといえるのだが、唯一、負担を押し付けられている主体がいる。国民だ。
内部資料を基に電気料金を試算してみると、一般世帯の月額負担を6142円とすれば、東電管内の一般家庭の負担は25年間で約30万円上乗せされる。全国で見ても1万0800円(中国電力)~3万8700円(関西電力)だ。
なにも電気料金への転嫁だけではない。賠償機構に入る資金を見れば、その出どころはすべて税金だ。いみじくも、財務省幹部が「国が支援に乗り出せば、電気料金の値上げか増税は避けられない」と明かすように、結局負担を強いられるのは国民だけなのだ。
菅政権は、こうした欺瞞に満ちた賠償スキームについて、今国会で法案を提出、可決する構えを見せていた。だが、現時点では法案提出すらされておらず、6月22日に期末を迎える会期の延長さえ態度を決めかねている。
さらには、身内からの思わぬ反発に怖じ気づいたとの見方もあり、永田町では、とりあえず法案提出を見送り、8月にも召集する臨時国会に審議を先送りするのではないかとの観測までも浮上する。しかし、たとえ会期を延長し、党内をまとめ上げたとしても、今度は自民党など野党との攻防が待っており、波乱要因には事欠かない。
ただ、法案が提出されなければ、東電が破綻の危機に瀕する。それはすなわち、賠償主体が不在になることを意味する。となれば、救済されるべき被害者が賠償を受けられないことになりかねないという、最悪の事態になる可能性をはらんでいるといえる。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 池田光史、小島健志、山口圭介)
東電は、破産こそが、対立の激しい問題を解決するための、時の試練を経た唯一の方法なのだ。 05/22/11 (株式日記と経済展望)
絶対に起こしてはならない原発事故を起こした東電は、破産こそが、
対立の激しい問題を解決するための、時の試練を経た唯一の方法なのだ。
2011年5月22日 日曜日
◆東電救済策-日本の社会主義的解決方法 5月18日 ウォールストリートジャーナル
政府によるみせかけの東京電力救済計画のような大失策が、「進歩」にみえるのは、日本においてだけだろう。政治家は、矛盾に満ちたシグナルを市場や企業、納税者に送り続けている。銀行の経営陣は抵抗し、東電はその間に挟まれた状態だ。自民党が紫煙たちのぼる舞台裏でこういった決断を下してきた戦後60年間とは対照的に、日本は今、より「正直な」社会主義という形につまずきながらも向かっていることを示しているのかもしれない。
東電についての政府の計画は、多かれ少なかれ、日本から出てくると予想されていたものだ。日本政府は、福島第1原子力発電所事故の被害者への賠償を行うための機構を納税者負担により設立する見込みで、東電とその他の電力会社が返済していくとみられている。賠償総額には上限がないものの、過度の金融混乱を避けるため、東電の年間返済額には「穏やかな上限」が設けられる。
この問題をめぐっては、ここ数日、さまざまな意見、批判が相次いでいる。枝野幸男官房長官は13日、東電債権者である大手銀行がまず、震災以前に貸した債権を放棄しなければ、政府の賠償スキームに納税者の理解は得られないと発言。一方、野田佳彦財務相と自見庄三郎金融相は、債務再編は東電と債権者の間の問題だとし、政府の介入に否定的な見方を示した。
一方、銀行側もこれまでにない反応を示している。三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の永易克典社長は16日、枝野長官の発言について、「非常に唐突で違和感がある」と語った。おそらく永易社長はこう言いたかったのだろう――政府の支援計画、とりわけ東電債権者に現段階で損失を強いるやり方は、東電が破産手続きを選んだ場合に予想される枠組みから大きく外れている、と。
当然のことだが、より市場主導型の国では、破産が、まさに東電の取るべき手段である。福島第1原発事故の結果、東電が抱えることになる負債の額はまだ確定されていないものの、政府が賠償に上限を設けない限り、巨額になることは確かだ。また、他の多くの電力会社と同様、東電は多額の負債を抱える。東電は、日本で最大級の社債発行体であり、3月11日以前の銀行の東電向け債権は約2兆円ともいわれる。企業の資産がこのような状態にある以上、破産こそが、対立の激しい問題を解決するための、時の試練を経た唯一の方法なのだ。
とはいえ、本当に破産という事態を望む者は誰もいない。東電が破産すれば、(法的義務はなくても)政治的な理由から、政府が賠償のための支出を余儀なくされる、と政治家は理解している。永易社長は「唐突で違和感がある」と述べたものの、銀行側は、枝野長官の債権放棄発言は震災前の融資に関するもの、と受け止めた。東電の破産となれば、銀行は、震災後2カ月間に融資した2兆円近くの債権についても大幅償却の必要に迫られる。銀行は、おそらく震災前の融資の損失を乗り越えられるだろうが、震災後の融資分の減損処理もあわせると経営に対する影響は大きい。
しかし、こういったこと自体、日本では特に珍しくはない。日本は常に大企業の破産を回避してきた。事業会社の破産としては戦後最大となった日本航空の破たん処理でさえ、政府主導で注意深く行われた。
新しいことは、東電のような企業リスクを社会がどのような形で扱うべきかについて、国民の議論がついに始まったことである。この議論はほとんど偶然によるものだ。菅直人首相は、こうした場合の長年の政治手法だった「舞台裏取引」が苦手だとお見受けする。民主党は、何をしたいのかについて本当に混乱しているようだ。彼らは、緊迫した記者会見やインタビューのカメラを前にして、「党内」議論をやっている。これでは、銀行など、他の関係者に議論に口を差し挟む余地を与えるだけだ。
日本政府が東電を破産させるという正論を行わないとしたら、政府は、国民の前で十分な議論のもとに合意をまとめるという方法としては正しいが、間違ったことをすることになる。納税者は、この問題から無傷で逃れられると期待するべきではない。しかし、少なくとも、誰が責めを負うべきかについて国民は知っている。
(私のコメント)
今日も朝からテレビでは原発の事故の問題のオンパレードです。原発の事故は絶対に起こしてはならないというのが日本のエネルギー政策の基本原則なのですが、実際に原発の事故は起きてしまった。起きてはならない事故が起きると、福島県のみならず東京にも放射能が飛んできた。おかげで風評被害で野菜や牛乳は売れなくなり、コンビニから乾電池からミネラルウォーターまで無くなってしまった。
原子炉は圧力容器や格納容器がしっかりしているから放射能は漏れないと言う話でしたが、いまだに放射能は撒き散らかされている。メルトダウンで圧力容器の底が抜けて核燃料がこぼれ出ているらしい。こうなると核燃料を回収する作業は数十年間はかかることになるだろう。使用済み燃料棒はなんとか回収できるかもしれませんが、量がとても多い。
東京電力は盛んに「想定外」を連発して責任を逃れようとしていますが、安全対策を怠った責任は東京電力にある。地震や津波も沿岸地域では定期的に起きており、後からでも地震や津波対策は出来たはずだ。政府の原子力政策も原子力安全委員会も経済産業省の原子力安全保安院も監視機関として機能しない仕組みにも問題があった。
つまり政府と東京電力双方に事故が起きる原因が内在していたのですが、一民間会社では原子力発電は、事故の事を考えれば荷が重過ぎるのであり、実際に事故を起こしてしまった東電は倒産は免れないところだ。常識的経営感覚がある経営者なら原子力発電はリスクがあってやりたくなかったことだろう。しかし九電力会社は原発を保有している。
日本の経営の特質は、横並び経営であり、みんな一斉に同じ事をやる。銀行の金融危機でも銀行は金融自由化で一斉に土地を担保に貸し出し競争を始めた。その土地が暴落すると全部の銀行が経営危機が起きてしまった。原子力発電でも我も我もと原子力発電を始めましたが、大消費地を抱える東京電力や関西電力は仕方がないにしても、沖縄を除く全部が原子力発電を始めてしまった。
ウォールストリートジャーナルは社会主義的と書いていますが、最終的に連帯責任で負うべきであり例外を許そうとはしない社会だ。それは学校教育から連帯責任を負わせることで相互監視させるような仕組みにしている。だから日本人にとっては村八分が一番きつい制裁であり、教室でも村八分が「いじめ」の手段になる。
原子力村でも、原子力発電が危険だと言うと原子力村から村八分にされる世界であり、自己主張することは難しい。みんな同じ事をして連帯責任だから一致団結はしやすいが、例外を認めない非寛容な世界になる。原子力発電でも賛成か反対かのどちらかであり、多様性がない。今回の事故の賠償責任にしても連帯責任で国民全部にしわ寄せが行くのだろう。
銀行の貸し手責任も有って無きがごとくであり、倒産する可能性の高い東電に事故後に2兆円近くも貸した銀行は貸し手責任を問われるだろう。実質的に東電は債務超過の状態であり、会社更生法などで出直すべきだろう。計画停電はそれに対する牽制の意味で行なったものであり、東電が倒産すれば停電しますよと言う脅しだった。
最終的には新東京電力が業務を引き継げばいいのであり、債務を清算して年金などもカットしてゼロからやり直せば良い。与謝野大臣は債権放棄など常識的にありえないといっていますが、東京電力は普通の株式会社だ。だからウォールストリートジャーナルは破産を主張していますが、他の電力会社への見せしめのためにも破産させるべきだろう。そうすれば他の電力会社は原発経営に慎重になるだろう。今まで電力会社は事故を起こしても国が面倒見てくれると思っているから原発事故が起きたのだ。
日本は多様な意見を認めようとはしないで、一致団結ばかりを尊重している。異論を言う者がいれば村八分にして冷や飯を食わせる。しかしそのような方法では、今回のような大事故が起きてしまうと責任の追求が曖昧になり、新しい仕組みづくりが出来なくなってしまう。曖昧なままに事故が処理されて東電は救済されて元のままなら、再び同じような事故は起きるだろう。柏崎の原発事故にしても中越地震で周辺設備が破損したのに、福島第一原発には防災対策が検討されなかった。
公務員制度も、年功賃金制度や解雇の規制や天下りなど霞ヶ関村の掟に背くものは村八分にされますが、公務員も正規公務員と派遣とでは天と地ほどの差がある。東京電力も本社で正規社員として働いている社員と、下請けで危険な業務をしている社員とでは天と地ほどの差がある。問題を起こしているのは規制に守られた正規社員であり、彼らは楽な仕事をして危険な仕事は下請けに回す。
東電を潰すリスクを理解しました。それでも東電を潰せと言います。「誰が責任を追うのか。それはまず私たち国民です。」
国民が東電を潰すことによるリスクを理解し判断すれば東電は潰すことができると解釈できます。どの選択をしても国民の
負担になる。
「東電を潰せば主要株主の金融に打撃を受ける。もしこれが経営基盤が揺らぐレベルの場合、金融業界が
バブルがはじけたときのように貸し渋りや貸しはがしを始める可能性があります。」東電の救済のために金を注ぎ込むのであれば、
東電を潰して救済のために使われる予定のお金を銀行救済や国が低金利でお金を貸せばよいだけのことです。
「電力会社は、知れば知るほど日本経済の支柱であると見えます。」何があっても、責任を取るべきであっても電力会社を
破綻させることが出来ないのであれば国有化にすればよいと思います。
「『東電が』『政治家が』『役人が』と言う前に、自分の過失をまず認める。」このようなふざけた結論は受け入れられません。
まるで国民が全て悪いと言っているようです。東電の件ではありませんが、公務員や政治家に問題点の改善を言い続けていますが、
改善がほとんど見られません。10年間は「政治家」や「役人」にとって十分な時間ではないのでしょうか。自分がやっていることを
東大卒のキャリアが出来ない事実は理解できません。能力ではたぶんあちらが上。しかしやる気がない。改善する気がない。
現場を理解する気がない。屁理屈と言い訳の世界に住んでいる。移動の時期が来るのを待つだけ。このような社会には飽き飽きしています。
東電を潰せ!東電を潰せ!下記のサイトを読んでも考えは変わりません。痛みを伴うから痛みを先送りにする。痛みを伴うから
正面から問題に取り組まない。それも選択肢の一つでしょう。しかし、東電を潰さないことで利益を得る企業や人間は大企業や金持ちだけです。
中小企業も影響を受けるでしょう。消滅する企業もあれば、生き残る企業もある。日本の将来は明るくないので、今回、消滅しなくても
そのうちに消滅する企業はあります。金融業界のバブルがはじけても何とかやっています。だから、東電を潰しても問題はありません。
東電を潰すリスクを把握してでも、東電潰せと言えますか? 05/14/11 (pc4beginnerの日記)
本日のサブタイトルは「日本はどんな主義国家だったでしょうか」です。
東電賠償スキーム、事実上株主・社債権者などを免責
この記事は、以下の情報と併せてみると味わい深く読むことができます。
東京電力 主要株主構成(平成22年3月31日現在)
今回の東電救済で責任を免責された主要株主、金融系ばっかり(除 東京都)。もちろん最初の記事内で批判をしている方が勤める外資系証券は入っていない。日本の経済システムが破綻を認めさせない一番の弊害の可能性があります。
つまり、東電を潰せば主要株主の金融に打撃を受ける。もしこれが経営基盤が揺らぐレベルの場合、金融業界がバブルがはじけたときのように貸し渋りや貸しはがしを始める可能性があります。ただでさえ冷え込みが危惧される経済に大きな悪影響を与える可能性があります。
鉄板の経営基盤を持つ電力会社は、知れば知るほど日本経済の支柱であると見えます。まるでバブル期の土地のようです。国際競争力という視点で見れば、これが生み出す「カネ」が巡り巡って日本の会社に力を与えていることになる。潰れない電力会社の存在日本経済が力の源の大きな一つだった場合、簡単に「潰せ」と言えるのでしょうか。
政府はこのような潰さない意図を徹底的に説明すべきではないでしょうか。そして何が問題で、なんのために潰さ(せ)ないのかはっきりさせる。その上で潰す事が出来る電力会社にしなければ、先々でまずい気がします。
で、ですね。
誰が責任を追うのか。それはまず私たち国民です。現在の政治家や国家システムを容認してきたのは私たち。それについてはきちんと責任を負った上で、この先どうするか考えないと、何も決められません。
「東電が」「政治家が」「役人が」と言う前に、自分の過失をまず認める。きれい事ではありますが、相手に難しい問題を押し付けるなら、まず自分がしないといけないと思いますが、おかしな話でしょうか。
民主主義は、本来は王政や社会主義と比べ国民が政治に参加しやすいシステムです。それはつまり、国家の運営について国民の責任はより重くなるということではないでしょうか。
それを忘れて「東電が」「政治家が」「役人が」とヒステリックに叫ばれるとすごく違和感があるのです。
ね、「国民の代表」を標榜するマスコミの皆様方(にっこり)。
懲りない東電、被災者の人生より社員の老後を優先 05/14/11 (ZAKZAK(夕刊フジ))
★企業年金の削減しない
福島第1原発の事故をめぐり、数兆円に及ぶ巨額の補償を迫られる東京電力の清水正孝社長(66)は13日、参考人として出席した参院予算委員会で、企業年金についての削減は考えていないことを明らかにした。日本航空破たんの際には、企業年金が減額されただけに、増税や電力使用料の値上げが避けられない国民からの反発は必至だ。
同委員会で質問したみんなの党の中西健治氏に対し、清水社長は「(社員の)老後の生活にも直結し、現時点で検討していない」と明言。この発言に、菅直人首相は「国民の納得が得られるかどうか判断してほしい」と、改めて減額を促した。
同社の企業年金は1人月額40万円以上とされ、賠償金の原資捻出に伴うリストラの有力候補だが、減額には同社OBと現役社員の3分の2の賛同が必要。トップ自らが早くも予防線を張った格好だが、老後どころか現在の生活のすべてを奪われた原発避難者からは怒りの声があがりそうだ。
東電の賠償金をめぐっては、13日の会見で枝野幸男官房長官が、「電気料金であれ税金であれ国民に転嫁せずにやっていくことに最大限努力する」と国民負担の極小化を強調。先ごろ明らかになった賠償の枠組みでも、官民で設立する機構を通じ、政府は交付国債の付与や公的資金の注入を実施するほか、原発を持つ電力会社10社も負担金を拠出し、金融機関も事実上無条件で融資するなど、国民が直接的な負担を感じない配慮がされている。
ただ、経済産業省は、電力各社が負担金を電気料金に転嫁することを容認する姿勢を示しており、全国的な電気代の値上げにつながる可能性は高い。それに、公的資金も元はといえば国民の税金だ。
同じく公的資金を受けた日航では、高額批判の強かった年金の削減が大きな焦点となり、現役が約5割、退職者が約3割をカットされた。東電でも今後、料金値上げなどで国民に負担を求める際に焦点となる可能性がある。
スバル不具合車被害者の会 FRONT PAGE
スバル不具合車被害者の会 その後
興味深いサイトを見た。それぞれの販売会社と車を製造している会社(メーカー)は同じグループではない場合が多い。これは自分のトラブルから学んだこと。
「本社の連絡先(電話番号)は知らない」と言った店長も存在した。こんな発言は人を馬鹿にしていると相手は感じていないと思うのだろう。
世界的な不景気で自動車メーカーも苦しんでいる。個々の社員達は自分達の生活を考えるのだろうが、問題のある会社は倒産するか、どこかの会社に
吸収されるほうが良い。体質を改善できない会社が消費者の選択によって沈んでいくのであれば自然の法則である。だが、誠意を持ってがんばれば
生き残れるのか?不正や悪い事をしている会社が生き残ることもある。これが現実だと個人的な経験から思う。騙す人間も騙される人間もたくさんいる。
同じ確率でも運が良い人、運が悪い人が存在する。車だけに限らず、いろいろな状況で判断する状況がある。その時に良い選択を出来るように情報収集や提供
ができるサイトが増える事を期待する。
JR福知山線脱線事故 (ウィキペディア)
尼崎・脱線事故 (読売新聞)
JR福知山線脱線事故 被害者が自殺 (Birth of Blues)
JR福知山線脱線事故 (ヒートの情報倉庫)
JR福知山線脱線事故の教訓 (防災システム研究所)
東電の体質及び東電が起こした人災を考えれば東電救済はありえません。被害者達の多くは気付いていないと思われるが
ここまで被害を出したのだから大きな改革で締めくくるしかない。
肥田舜太郎/鎌仲ひとみ、『内部被曝の脅威――原爆から劣化ウラン弾まで』(じゃくの音楽日記帳)
日本SF作家クラブ公認ネットマガジン「SF Prologue Wave」。福島第一原発事故後のSFの役割。取り返しのつかないことを認めること。(ねこねこブログ)
「世界中の資金を集めても(一度放射能に汚染された地域の再浄化は)不可能」とボブ(コロンビア川の放射能汚染浄化作業を担当したワシントン州環境監督官ボブ・ウィルソン)は断言した。飲料水として摂取しているコロンビア川の上流では既にN原子炉がある場所から放射能漏洩が起きている。ほとんど永遠に消滅することがない、様々な発癌性の放射性物質が地下水を汚染してしまった。この浄化作業に費やされているのは年間2000億ドルという巨額な国家予算だ。放射能を浄化する技術を開発し、世界にそれを売ろうという計画だった。
しかし、それから14年が経っても、いったん汚染された大地と水を浄化する技術はいまだに開発されていない。コロンビア川流域の600万人の住民が影響を受けることになる汚染の進行を止める方法は何もないのだ。
(肥田舜太郎、鎌仲ひとみ「内部被曝の脅威」)
原発事故「最も憂慮すべきは遺伝子変異」レナート・キュンツィ 03/23/11 (swissinfo.ch)
東電の送電分離案、政府内で急浮上 電力各社は反発も 05/15/11 (日経web版)
東京電力の発電部門と送電部門を分離する案が、政府内で急浮上してきた。東電福島第1原子力発電所事故をきっかけに長年の地域独占を見直し、新規参入を促すしくみを取り入れる内容だ。ただ、供給体制の抜本的な見直しとなるだけに、電力各社の反発も避けられそうにない。実現に向け課題は山積している。
日本の電力は電力会社による発電と送電、小売りまでの一貫体制になっている。電力自由化の流れで電力ビジネスへの新規参入組も生まれたが、東電などの送電網を自由に使えるわけではない。
3月の計画停電の際も電力の小売業者にあたる特定事業者は販売網を断たれた。東電が送電インフラを握るためだ。加えて、電力会社に払う送電線の賃借料は顧客に販売する電気料金の約2割を占めるとされる。送電網を握る大手電力が差別的な取り扱いをして新規参入を阻んでいるとの指摘もあり、電力販売に占める新規参入組のシェアは3%に満たない。
枝野幸男官房長官は16日の記者会見で東電の送電部門分離について「選択肢としては十分あり得る」と発言。週末には玄葉光一郎国家戦略相(民主党政調会長)も「発電と送電の分離など電力事業の形態の議論を妨げることはない」と述べており、政府・与党で電力会社の地域独占体制の見直し機運が高まっている。
政府は13日に決めた東電の賠償支援スキームに「電力事業形態のあり方などの見直しの検討を進め、所要の改革を行う」と明記。中長期の課題と位置付けた。ただスキームには野党から「東電救済策だ」との批判がつきまとう。国会論戦を乗り切るためにも、電力事業のあり方への切り込みを迫られている。
電力会社の送電分離は、1990年代から議論が続く課題。既存の電力会社による一貫体制を見直し、新規参入事業者が送電設備を使いやすくすることが狙いだ。欧州では英国やドイツ、フランスなどが90年代に入ってから相次いで発電と送電を分離した。送電ネットワークが整備済みの先進国では、利点の方が大きいとされる。
ただ電力会社からの反発は根強い。電圧など電気の品質を安定させにくくなるほか、電力の完全自由化につながるとの理由だ。経済産業省は約10年前に送電分離を目指したが、東電などが押し返した経緯がある。
新規参入組にあたる全国の独立系発電事業者の発電能力は約740万キロワットで、このうち3割超の260万キロワット程度が東電管内。東電は賠償スキームの中で政府の管理下に置かれるため、比較的分離を実現しやすい。
もっとも株式上場した民間企業の分割を政府が決められるのかという課題もある。東電の発電と送電の分離が実現に向けて動き出せば、他電力にも分離論は波及する。電力業界全体の反発へと広がれば、賠償のために設立する機構への各電力の負担金などにまで波乱が及ぶ展開も考えられる。
東電存続を前提にしないなら可能です 05/15/11 (酔っ払いのうわごと )
私は、児玉論説副委員長が東電の存続を前提にしているから『枠組みにはやはり無理がある』と考えてしまうのだと思います。存続という前提を外せば児玉副委員長にも違った風景が見えてくるのではないのでしょうか。
例えば、東電の会社更生法による処理という考えがあります。会社更生法ですと、東電の株主責任も問えますし、債券に投資していた金融機関にも債権を放棄させる事が出来るのです。不動産などの売却も徹底した物になると思いますし、従業員の給与も削減できます。会社更生法の適用を受けた日本航空の飛行機が、きちんと運航している事を考えると会社更生法下の東電の電力供給能力に問題が生じるとも思えません。
一つ問題があるとすれば、それは原発の被災者に対する賠償金が保護される優先度が低い一般債権となってしまう事でしょう。枝野官房長官も、この事を言って現在の枠組みの正しさを主張していたと思います。しかし、それは特別法を作って賠償金の優先度を上げれば済む話でしかありません。または政府が賠償基金を作って東電に請求しても良いのです。そうすれば税金と同じで優先度が一番になりますから。私は、このコラムを東電を潰さない「ため」にする話に過ぎないと思います。
それに東電の場合は、児玉副委員長が言うように『資産と負債を清算し、会社を整理すれば終わり』ではありません。普通の会社なら資産を売り払えば、それまでですけれど東電の資産である発電所と送電線は日銭を稼ぐ事が出来るからです。その日銭を当てにすれば新東京電力でも、東京発電と東京送電への分社化だって考えられます。何なら東電の国有化もです。
何れにしても、最初から無理だという事を前提にして話を進めるのは頭が固すると思います。多くの民間有識者からすると『東電の解散』(会社更生法適用)は少しも『想定外』では無いのですから。
原発賠償案 これは東電救済策だ 05/12/11 (東京新聞 社説)
東京電力・福島第一原発事故の被災者に対する賠償案が固まりつつある。はっきり言って、これは国民負担による東電救済策だ。菅直人政権は霞が関と金融機関の利益を代弁するつもりなのか。
賠償案は政府が設立する機構に交付国債を発行し、機構は必要に応じて東電に資本も注入する。賠償は東電が上限なく負担するが、資金が不足すれば交付国債を現金化して支払い、後で東電が長期で分割返済する。
一見すると、東電が賠償責任を負っているように見える。ところが、東電の純資産は約二・五兆円にとどまり、リストラに保険金を加えても、十兆円ともいわれる賠償費用を賄い切れない。
実際、勝俣恒久会長は会見で「東電が全額補償するとなったら、まったく足りない」と認めている。つまり、東電はすでに破綻状態なのだ。“実質破綻”している東電を存続させた場合、賠償負担は結局、電力料金の値上げによって国民に転嫁されてしまう。
東電だけではない。機構に負担金を払う他の電力会社も同じだ。事故に関係ない地域の利用者も料金値上げで負担する結果になる。被災者にすれば、賠償金を自分が負担するような話であり、とうてい納得できないだろう。
一方で、被災者には十分な補償が必要だ。したがって政府の支援は避けられないだろうが、その前にまず東電と株主、社員、取引金融機関ら利害関係者が最大限の負担をする。それが株式会社と資本市場の原理原則である。
ところが今回の枠組みでは、リストラが不十分なうえ、株式の100%減資や社債、借入金債務のカットも盛り込まれていない。
東電をつぶせば電力供給が止まるわけでもない。燃料代など事業継続に必要な運転資金を政府が保証しつつ、一時国有化する。政府の監督下でリストラを進め賠償資金を確保しつつ、発電と送電を分離する。発電分野は新規事業者に門戸を開く一方、旧東電の発電事業は民間に売却する。
銀行再建でも使われた一時国有化の手法は、東電再建でも十分に参考になるはずだ。
菅首相は原発事故を受けてエネルギー基本計画を白紙に戻し、太陽光など再生可能エネルギーの活用を推進すると表明した。そのためにも新規参入による技術革新を促す枠組みが不可欠である。賠償案は東電と癒着した霞が関と金融機関の利益を優先してつくられた産物だ。根本から再考を求める。
誰がウソをつかせたのか 05/13/11 (BLOGOS)
東京にある外資系企業の経営者の集まる会で、講演した。
その後の質疑応答で、現在、新聞、テレビが報道しているような荒唐無稽な東電救済案を
政府が間違って提出するようなことは起きないだろうね、と質問が飛んだ。
いや、政府はまじめにそうした案を考えているようだ、と答えると、
日本は資本主義なのか、いやその前に法治国家なのかと反発された。
東電株を持っている高齢者がかわいそうではないのかなどという質問が大手メディアから来るぐらいだから、
我が国の資本主義のルールはどこへ行ってしまったのか。
年金で東電株を買った高齢者は、東電は安全だ、東電株は国債みたいなものだと思って買っていたんだ、
株式のリスクのことなんか知るはずがないではないか、
知っていたらこんな株買っていなかったんだから、減資しろというのは乱暴ではないか、
という質問すらするメディアがある。
高利回りのジャンクボンドを国債みたいなものだと思って買ってみたらどうなんだろう。
政府は、国民負担を小さくする等という文言を東電救済プランに入れてお茶を濁すみたいだが、
国民負担を小さくするためには、
一、賠償金をせっせと値切る
二、株主の責任を追及する
三、金融機関の責任を追及する
四、広告宣伝費等不要なコストを削減し利益を出して賠償に回す
五、東電の資産を丸ごと売却する
しかないではないか。依然として東電はテレビでお詫びCMを流している。
二、三、四、五をやらないなら、賠償金を値切るのだろうか。
いやいや、他の電力会社にも負担させるのですというかもしれないが、
それは東電以外の値上げにつながり、やっぱり国民負担になる。
この事態になって、まだ役員の責任すら追及しないのだろうか。
東電が原子力損害賠償紛争審査会に賠償限度への配慮や算定基準の明確化などを求める要望書を提出した件で、
記者から要望書の公開を求められた東電は、紛争審査会事務局との合意で、要望書は公開しないことになって
いると答えた。しかし、そのような合意は存在しなかったと文科省は明確に否定している。
東電はウソをついたのだ。
東電の誰がそうしたウソをつかせたのか、メディアは追及していない。
震災直後のCNNのインタビューで、東電は官僚的な体質で情報公開が遅いが、彼らはウソはついていない
と思うと、僕は答えた。今や、それは間違いだったことがはっきりした。東電は、ウソをつく体質なのだ。
そして、日本の大手メディアはそれを知っている。
日本の大手メディアは、東電の誰が指揮をして、ウソをつかせたのかをきちんと追及する責任がある。
いや、中央のキー局はいいんですけどね、地方のネット局にとっては電力会社はまだ大手のスポンサーなんですよ。
だから、ネット局のことを考えると、つい、二の足を踏んじゃうんですよね、
などと言っている場合ではない!!
住宅金融機構元室長、贈賄企業の資金集めに同行 05/18/11 (読売新聞)
独立行政法人「住宅金融支援機構」(東京)の住宅ローン事業を巡る贈収賄事件で、同機構の元営業推進室長・久世悟容疑者(52)が、住宅ローン会社「住宅金融モーゲージ」(同)への出資者を探すため、同社元会長・堀川嘉次容疑者(65)と一緒に企業回りをしていたことが、捜査関係者への取材でわかった。
同機構の住宅ローン「フラット35」の取扱金融機関に新規参入するには、5億円以上の資本金が必要で、警視庁では、堀川容疑者が久世容疑者の信用力を利用して、出資を募ろうとしたとみている。
同庁は18日午前、東京都文京区の同機構本店などを捜索し、事件の実態解明を進めている。
捜査関係者によると、久世容疑者は、堀川容疑者と知り合った2007年夏以降、東京都内や千葉、埼玉両県などで堀川容疑者が企業回りした際、勤務を抜け出して同行。京都府内の企業を訪ねた時は、休暇を取って一緒に回り、堀川容疑者から10万円の謝礼を受け取っていたという。
田中森一元特捜検事の関連会社に便宜 「住宅金融支援機構」職員に収賄疑惑 05/17/11 (産経新聞)
長期固定金利型住宅ローン「フラット35」をめぐり、住宅ローン会社に便宜を図る見返りにわいろを受け取った疑いが強まったとして、警視庁捜査2課は17日、収賄の疑いで国土交通省などが所管する独立行政法人「住宅金融支援機構」(旧住宅金融公庫、東京都文京区)の元業務推進部営業推進室長(52)の取り調べを始めた。贈賄側も含めて容疑が固まり次第、逮捕する。
住宅ローン会社は元特捜検事で元弁護士の田中森一受刑者(67)=詐欺罪で有罪確定=が経営にかかわった「住宅金融モーゲージ」(東京都港区)。同社は、住宅ローン債権ビジネスへの参入を目指し、平成18年6月に設立された。田中受刑者が設立に深くかかわっており、資金集めに奔走していたとされるが、田中受刑者の収監後、経営実態がなくなっていた。
捜査関係者によると、元室長は、同社がフラット35をめぐる住宅ローン債権ビジネスに参入するのにあたって便宜を図った見返りに、同社側から数百万円のわいろを受け取った疑いが持たれている。
フラット35は、同機構が民間金融機関と連携して提供する住宅ローン。最長35年間金利変動がなく、保証料や繰り上げ返済手数料が0円とうたっている。取扱機関になるには、資本金が5億円以上などの条件を満たし、同機構の審査で認定される必要がある。
同機構は、住宅の建築や購入のための個人への融資事業などを行う。昭和25年に設立された住宅金融公庫の業務を引き継ぐ形で、平成19年4月に設立。今年4月現在で約900人の職員がいる。
民主党の事業仕分けでは賃貸住宅融資などいくつかの事業が廃止対象となったが、東日本大震災の被災者向け融資の金利優遇策を拡大するなど、存在感が高まっている。
「東電の清水正孝社長は、『資金調達が極めて厳しく、資金がショートして公正、迅速な補償ができなくなる可能性もある』と述べ、
公的資金を投入するための賠償支援関連法案の今国会での成立を求めた。」
被害者の事なんか心配していないだろう??企業年金の削減は考えていないと発言。自分達の支援のことだけしか考えてない。
こんな企業を存続させる必要ない。
「1号機は安定状態」原子力安全委 「展望変えず」工程表で首相 05/16/11 11:20 (産経新聞)
原子力安全委員会の班目春樹委員長は16日午前の衆院予算委員会で、メルトダウン(炉心溶融)が判明した東電福島第1原発の現状について「温度はどんどん下がっており、原子炉圧力容器底部の温度は現在100度程度で、一定の安定状態にある」との認識を示した。
また菅直人首相は、事故収束までの期間を6~9カ月とした東電の工程表について「(収束作業の)手だてに多少の変化はあるかもしれないが、なんとか時間的な展望は変えずに進めることができるのではないか」と述べた。
さらに、17日にも東電が工程表の改定を発表することに関連し、「政府としても対応し、どのようなことを進めていくかをまとめて発表したい」と述べた。
東電の清水正孝社長は、「資金調達が極めて厳しく、資金がショートして公正、迅速な補償ができなくなる可能性もある」と述べ、公的資金を投入するための賠償支援関連法案の今国会での成立を求めた。
株主達が東電社員の大幅な年金削減を要求しないのであれば、株を紙切れにするべきだ。東電も株主も国民負担により
救済する必要なし。
被害者のことより加害者を庇う東電社長 (唯我独尊男の独り言)
東電解体へのプロセス (Go with the Flow)
“公的資金入れない可能性も” 05/13/11 (NHK)
枝野官房長官は、記者会見で、記者団が「金融機関などが、東京電力に行った融資について、一切債権放棄をしない場合でも、東京電力に公的資金を注入することに国民の理解が得られると考えているか」と質問したのに対し、「震災発生後に福島第一原子力発電所の事故への対応などのために行われた融資については、別に考えないといけない。しかし、震災発生以前の融資について『国民の理解を得られるか』と問われれば、到底、得られることはないと私は思っている」と述べました。そのうえで、枝野官房長官は、金融機関などが一切債権放棄を行わない場合、公的資金の注入を行わない可能性もあるという考えを示しました。
「老後の生活に直結」東電社長、年金削減を拒否 首相が再考求める 05/13/11 23:58 (産経新聞)
東京電力の清水正孝社長は13日の参院予算委員会で、福島第1原子力発電所事故の損害賠償資金を確保するためのリストラ策として、企業年金や退職金の削減を求める声が出ていることに対し、「老後の生活に直結する問題で現時点では考えていない」と述べ、検討対象とはしない考えを示した。中西健治氏(みんな)の質問に答えた。
これに対し、菅直人首相はその後の同委員会で、年金削減について、「国民の納得が得られるか、東電自身できちっと判断していただきたい」と語り、減額を再考するよう促した。
年金削減は、賠償問題で国の支援を受けるにあたっての条件である追加リストラの検討項目に挙がっていた。ただ、削減には現役社員約3万6千人と、給付対象の退職者約1万人の3分の2以上の同意を得る必要がある。
公的資金の投入を受けた日本航空では、高額批判の強かった年金の削減が大きな焦点となり、現役が約5割、退職者が約3割をカットされた。東電でも今後、料金値上げなどで国民に負担を求める際に焦点となる可能性がある。
東電トップ報酬半減でも3600万だったなんて 05/13/11(読売新聞)
海江田経済産業相は14日、テレビ朝日の番組に出演し、東京電力の役員報酬について、「驚いたが(一部の首脳は)50%カットで3600万円くらい。ちょっとおかしいので、もっと努力してほしいと言った」と述べ、東電に対し、一段のリストラを求めた経緯を説明した。
役員報酬はもともと7200万円前後だった計算になり、役員を厚遇してきた企業体質に改めて批判も出そうだ。
東電は当初のリストラ策では、常務以上の役員報酬は50%カットだった。しかし、政府・与党内でリストラの大幅な上積みを求める声があり、東電は、勝俣恒久会長、清水正孝社長ら代表取締役8人の役員報酬を5月から当面の間、全額返上することを決めた。
参院予算委:「退職金、年金減額検討していない」東電社長 05/13/11 19時10分(毎日新聞)
東京電力の清水正孝社長は13日の参院予算委員会に参考人として出席し、社員の退職金や企業年金について「老後の生活資金に直結する問題で、現時点では(減額を)検討していない」と述べ、リストラの対象としていないことを明らかにした。福島第1原発事故の賠償に向け、政府の決めた賠償の枠組みは、電気代の値上がりや国民負担につながる可能性があるだけに、「年金温存」の方針は反発を招きそうだ。
一方、菅直人首相は同委で「東電自身に(賠償へ)大きな努力をしてもらうのは当然。それがなければ最終的に国民の納得を得られるか、きちんと判断してほしい」と、東電に減額の検討を促した。中西健治氏(みんなの党)の質問に答えた。【松尾良】
東電社長、賠償支援を政府に要請 05/10/11 (J-CASTニュース)
東京電力の清水正孝社長は2011年5月10日、首相官邸を訪れ、福島第1原発事故に伴う賠償問題に対して政府に支援を要請した。海江田万里・経済産業相らが対応した。清水社長は要請後、「大臣からは、『後ほど回答する』ということだった」と記者団に話した。また、役員報酬の「当分の間」の返上や資産売却などの経営合理化を検討しているとして、近く公表することを明かした。
北朝鮮から衣類密輸、中国製に偽装…5人逮捕へ 05/11/11 (読売新聞)
全面的に輸入が禁じられている北朝鮮から衣類を密輸入したとして、兵庫県警は、アパレル会社(名古屋市)東京店の40歳代の男性社員や大阪市内の貿易会社元会長(65)ら5人を11日にも外為法違反(無承認輸入)容疑で逮捕する方針を固めた。
社員らは北朝鮮の工場に衣類の縫製を委託し、中国製に偽装して日本で販売していたという。
他の3人は貿易会社の元社長(47)と元従業員(42)、大阪市内の繊維業者。捜査関係者によると、社員らは共謀し、2009年4月、北朝鮮製の女性用ショートパンツ約300着を中国・大連経由で大阪南港に輸入した疑いが持たれている。
貿易会社側が北朝鮮とのパイプ役で、アパレル会社側がデザインを考案。繊維業者らが北朝鮮に生地を送って工場で縫製し、大連で中国製のタグをつけ生産地を偽っていたという。北朝鮮は人件費が安いとされ、コスト抑制が狙いだったとみられる。
不適切で危険な行為を続けてきても、これまでは死亡事故が起きなかった。つまり、不適切な行為を継続していても、運が良ければ
大きな事故にはならない。ただ運が悪ければ事故が起きる要素は存在するから死亡事故が起きた。一人ぐらいの死亡事故であれば
なんとか穏便に済ますことが出来たのかもしれないが、多くの被害者が出たために世間の注目を集めた。
同じ包丁で内臓も処理 卸業者が使い分けせず 05/10/11 22:15 (産経新聞)
4人が死亡した焼き肉チェーン店「焼肉酒家えびす」の集団食中毒事件で、ユッケに使われた牛もも肉を納入した食肉卸業者「大和屋商店」(東京都板橋区)が、大腸菌などが付着した恐れのある牛の内臓処理に使ったのと同じ包丁やまな板で、他の部位も加工していたことが10日、板橋区保健所への取材で分かった。
神奈川、富山、福井の3県警と警視庁の合同捜査本部は10日までに、大和屋商店の社長らを任意で事情聴取した。
O111やO157などの腸管出血性大腸菌は牛の腸内に生息しているとされる。同区保健所によると、大和屋商店はフーズ社のほかにも複数の焼き肉店にレバーなど牛の内臓を納入しているが、加工時に部位の違いに応じて担当の作業員や調理器具を分けていなかった。
フォークリフト:技能講習で答案に手を加える 不正合格か 05/10/11(毎日新聞)
フォークリフトの運転技能講習を巡り、厚生労働省所管の特別民間法人「陸上貨物運送事業労働災害防止協会」(陸災防)大阪府支部(大阪市城東区)の職員が、合格点に達していない受講者の答案用紙に手を加え、少なくとも6人を合格させた疑いのあることが10日、毎日新聞の取材で分かった。大阪労働局は労働安全衛生法違反の疑いがあるとみて調査しており、近く講習業務停止などの処分をする方針。
同法によると、最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転するためには、所持している運転免許証の種類などに応じ、労働局が登録する「教習機関」の技能講習を受け、修了試験に合格する必要がある。陸災防大阪府支部は73年に教習機関に指定され、運送業者らに講習と試験を実施している。
同支部によると、昨年11月に85人が技能講習を受講し、全員が試験に合格。これを不審に思った支部からの申告で労働局が調査したところ、支部職員が採点中にマークシート式の答案の一部を消しゴムで消すなど疑わしい行為が発覚。少なくとも6人が不合格だったと判断した。修了試験の合格率は通常、全国平均で約98%だが、同支部は89~90%程度という。
6人は合格を取り消され、再受講して修了試験に合格した。
藤田清・同支部専務理事は取材に「採点のため答案用紙をパソコンで読み込む際、マークの消し損じがあるとエラーが出るので(職員が)消しゴムで消すことがあったようだ。故意があったかどうか分からない」と釈明。「なぜ全員が合格になっていたのかは不思議としか言いようがない」と困惑している。
陸災防は労働災害防止団体法に基づき、運送業界を対象に労働災害防止に関する指導を行う公的団体。全国で約4万7000業者が加盟し、09年度は国から約2億3000万円の補助金を受けた。大阪府支部には約3590業者が加盟し、年間800~1200人が技能講習を受けている。【藤田剛、牧野宏美】
「清水社長は海江田経産相あての支援要請の文書で『(東電が)資金面で近く立ちゆかなくなり、迅速な補償だけでなく、電気の安定供給にも支障をきたすおそれがある』とした。
そのうえで、東電の賠償を政府が支援する枠組みの策定を求めた。」
優しい言葉で「助けてくれなければ、あなたが困るでしょ。」と言っているのと同じだ。資金面で近く立ちゆかなくなるなのであれば、
東電全社員のボーナスをカットするべきでないのか。ボーナスなしでやっている中小企業の従業員はたくさんいる。彼らから徴収された税金の
一部も東電救済に使われるのだ。もっと真剣にリストラを考えるべきだろう。東電を解体したほうが良いのではないか!
東電会長ら役員報酬返上へ 原発賠償、政府に支援要請 05/10/11(朝日新聞)
東京電力の清水正孝社長は10日午前、首相官邸に枝野幸男官房長官、海江田万里経済産業相らを訪ね、福島第一原子力発電所の事故に伴う損害賠償について政府の支援を要請した。要請を受け、海江田経産相は13日を目標に政府支援の枠組みを決める意向を示した。
清水社長は支援要請にあたって、枝野官房長官らに「我々の最大の合理化が前提」などと話し、追加のリストラ策を示した。代表権を持つ会長、社長、副社長の8人が役員報酬を全額返上する。東電の役員報酬の平均は2009年度で年約3700万円にのぼる。
保有株式や不動産、事業の整理など資産売却も当初の3千億円程度から積み増す。5千億円前後にするとみられ、「できる限りの資金を捻出し、賠償に充てる」としている。
一方、清水社長は海江田経産相あての支援要請の文書で「(東電が)資金面で近く立ちゆかなくなり、迅速な補償だけでなく、電気の安定供給にも支障をきたすおそれがある」とした。そのうえで、東電の賠償を政府が支援する枠組みの策定を求めた。
要請を受けた後に記者会見した海江田経産相は、役員報酬返上を「評価する」と述べた。これを踏まえ、政府の支援枠組み策定は「13日を目標としたい」と語った。また、10日夜にも、賠償に伴う電気料金値上げを抑えることなど、政府からの要望を伝えるとした。
東電は賠償金を捻出するため、これまでに役員報酬の半減や一般社員の年収2割削減、新卒採用見送りなどのリストラ策をまとめていた。しかし、閣僚の一部などから、東電のリストラが不十分なままでは政府支援に踏み切ることが難しいとの意見が出ていた。
菅政権は原発事故の被害者への賠償を進めるため、東電の賠償を支援する方針。この枠組みについて関係閣僚らが最終調整を続けている。
東電の賠償額は数兆円規模とみられる。政府支援がまとまらないと、5月中旬に予定している11年3月期の決算発表が遅れる恐れもある。
「東電、代表取締役の報酬を全額返上」はいつまで続けるのか?期間が明確にされていない。「常務取締役については半減から60%に削減幅を5月から拡大する。」
も期間が明確でない。例えば、政府から借りるお金を全額返済するまでリストラを続けるとかもっと明確な提示が必要だろ。
「社員の給与も課長級以上の管理職が年俸を約25%、一般社員は年収の約20%を減額するとしていた。」については
どうなるのか?東電がなくなればボーナスや退職金もなくなる。それを考えればリストラが甘い。これぐらいで政府に支援要請だなんて考えが
甘い。ボーナスも出せない会社で倒産や破産する会社もたくさんある。このような企業に税金による救済があったのか??税金を使う救済を
求めるにしてはリストラが甘すぎるだろ。
東電、代表取締役の報酬を全額返上 原発賠償で政府に支援要請 05/10/11(産経新聞)
東京電力の清水正孝社長は10日午前、福島第1原子力発電所事故による周辺地域への賠償をめぐり、枝野幸男官房長官や海江田万里経済産業相らと首相官邸で会談し、政府の支援を求めた。併せて、役員報酬削減などのリストラ策を拡大することを明らかにした。
会談で、清水社長は「当社として最大限の経営合理化に取り組んでいくが、被害者への公正かつ迅速な補償を確実に実施するため、国による支援をよろしくお願いします」と述べ、要望書を提出した。
会談終了後、清水社長は記者団に対し、自身や勝俣恒久会長を含む代表取締役の報酬を全額返上することを明らかにした。これまでは半減するとしていた。また、常務取締役については半減から60%に削減幅を5月から拡大する。
政府は賠償総額は数兆円にのぼり、電気料金の引き上げも必要になるとみており、賠償のための新機構設立を柱とする支援策を検討している。関係閣僚会議では、電気料金引き上げや政府が支援を行う前提として東電にリストラの徹底を求める声が強かった。
東電は4月25日、社長ら常務以上の取締役の報酬を半減するほか、執行役員の報酬も40%減額するなどのリストラ策を発表。社員の給与も課長級以上の管理職が年俸を約25%、一般社員は年収の約20%を減額するとしていた。さらに東電は資産売却も進める考えだ。
政府は、新機構を特別立法で設立する案を検討。将来の原子力事故の発生に備える保険機能も持たせることにし、電力各社に負担を求める。原資捻出のため、東電以外の電力会社でも電気料金の値上げにつながる可能性もある。
ユッケ食中毒、発覚直後に廃棄指示 運営会社、各店舗に 05/10/11(朝日新聞)
焼き肉チェーン店「焼肉酒家(さかや)えびす」の集団食中毒事件で、運営会社「フーズ・フォーラス」(金沢市)が、最初の食中毒発生の連絡を富山県から受けた直後に、開封済みのユッケ用生肉の廃棄を各店舗に指示していたことがわかった。同社が9日明らかにした。
開封済みの肉はすでに処分されて検査が不可能になっており、富山・福井両県警などの合同捜査本部は、フーズ社が廃棄を決めた経緯を詳しく調べる。
富山県によると、同県高岡市の6歳の男児(後に死亡)らが4月22日、砺波店で食事した後に食中毒になったとして、県は27日午前、フーズ社本社に連絡、砺波店を立ち入り検査した。同社によると、直後の同日午後3時ごろ、本社が砺波店以外の全店舗にユッケの販売中止を命じ、真空パックから開封したユッケ用の生肉について「賞味期限が切れて腐るので捨てるように指示した」という。未開封分は保管され、一部は捜査本部が押収した。
フーズ社は「証拠隠滅をする意図はなかった」としている。幹部の一人は朝日新聞の取材に対し、「(食中毒で)いずれ営業停止は避けられないと判断し、売れない肉を取っておく必要がないと思って廃棄させた」と話している。
食中毒症状を訴えた患者は4月17~26日に店舗で食事しており、捜査本部などはこの間に販売されたユッケが腸管出血性大腸菌O(オー)111に汚染されていた可能性が高いとみている。
ウソ求人で原発派遣の労働者、3日間線量計なしで活動 05/10/11(スポーツ報知)
大阪市西成区のあいりん地区で、宮城県女川町での運転手の仕事に応募した大阪市の60代男性が福島第1原発で働かされていた問題で、西成労働福祉センターは9日、男性と業者に聞き取り調査し、男性が原発敷地内で約2週間、防護服を着用して給水作業に従事していたと明らかにした。男性は「4日目にやっと線量計が配られた」などと話している。一方、募集した業者は、混乱の中で誤った仕事内容を伝えたと釈明している。
「宮城県女川町、10トンダンプ運転手、日当1万2000円、30日間」―。この求人情報に応募した男性は、防護服と防じんマスクを着用させられ、福島第1原発の敷地内へと放り込まれていた。
同センターによると、男性は3月19日に大阪を出発。岐阜県で元請け業者と合流後、特に説明がないまま原発事故の対応拠点「Jヴィレッジ」(福島県広野町など)に到着。この時点で初めて、原発敷地内で作業することに気付いたという。
同20日からの作業は1日約6時間。原発5、6号機冷却のため、給水タンクにホースやポンプを設けて給水車に水を移し替える内容だった。男性によると「4日目にやっと線量計が配られた」。放射線の情報や健康被害に関する説明は乏しく「精神的ストレスで心臓がパクパクする感じ。長生きなどいろんなことを諦めた」と振り返った。その後計測した被ばく線量は基準値以下だった。
男性を雇った業者「北陸工機」(岐阜県大垣市)は東京電力の3次下請け。当初、「元請けの建設業者から『現場は女川』と言われ、大阪で募集した」と主張したが、9日になって「(元請けから依頼があったのは福島第1原発での作業だったが)混乱の中で(誤って)女川町の現場を伝えてしまった」と釈明した。一方、愛知県の元請け業者は「“福島第1原発付近で散水車の運転手”と業務内容を伝えたが、原発敷地内の作業とは言っていなかった」と話している。うその労働条件を提示して労働者を集めたり契約を結んだりするのは職業安定法や労働基準法に抵触する恐れがあり、大阪労働局が調査している。
原発の現場では4月中旬ごろから「原発建屋内なら(募集時の賃金の)3倍」「退避区域なら1・5倍」など、“危険手当”ともいえる作業員の賃金体系を業者ごとに設定。男性も最大で募集時の条件の倍に当たる日当約2万4000円を受け取ったが「おかしいと思ったが物を言える雰囲気ではなかった。賃金も仕事に見合っていない」と話した。
あのユッケのお肉は板橋区の(株)大和屋商店が卸販売 (underground JARO's)
ユッケに「生肉向けでない」廃用牛の肉 05/09/11(読売新聞)
焼き肉チェーン「焼肉酒家えびす」の集団食中毒事件で、客が食べた生肉のユッケに業界で生食向けでないとされる出産を繰り返した「廃用牛」が含まれていたことが9日、読売新聞の調べでわかった。
卸元の食肉加工卸業者「大和屋商店」(東京・板橋区)が先月11~16日に加工し、死亡した客4人を含む患者が食べたとみられる14頭の牛に含まれていた。大和屋は、えびす側に「ユッケ用のサンプルができました」「和牛の血統で味があります」と品質を保証するメールを送っていた。富山県警などの合同捜査本部は、死亡した客から検出した腸管出血性大腸菌O(オー)111の汚染源を捜査するとともに、肉の流通ルートの特定を進めている。
畜産農家らによると、「廃用牛」とは、出産を繰り返し、子牛が産めなくなった雌の経産牛など。肉質が悪く、ハンバーグなどの加工食品の原料などに使われることが多いという。
ジャーナリストの東谷暁氏についてあまり知らないが、彼の説明には納得できない。「事故の原因となった非常用ディーゼル発電機不起動の確率は1000分の1だった」
と書いているが確立は確立だ。また、確立の求め方によっても確立が変わってくる。また、非常用ディーゼル発電機が起動しない、または、
十分な電力が供給できない場合、どのような事態になるかを考えれば確立の話で議論するのはおかしい。重要な部分については
2重、3重の安全対策が取られるべきである。ここで、東谷暁氏の説明の信用性を疑う。「非常用ディーゼル発電機は頑丈で津波にも拘(かか)わらず一旦は
起動したが、この非常用ディーゼル発電機のサブ冷却系が津波にやられていたためオーバーヒートして途中で停(と)まったとの説は有力である。」
非常用ディーゼル発電機は機能を果たさなければ意味がない。発電機が回れば熱が発生する。原発と同じで冷却しなければならない。
「非常用ディーゼル発電機のサブ冷却系」であろうが「メイン冷却系」であろうが冷却できなければ「オーバーヒート」するのは常識である。
東大を卒業しなくとも、エンジン関係の仕事をしているものであれば高卒でも理解できる。エンジンが水冷なり空冷なり冷却できなければ
オーバーヒートすることを理解することは難しくない。ここでも、東谷暁氏が書いている事を理解した上で書いているのか、それとも、
理解できない人達を対象に知ったかぶりで書いているのか知らないが、疑問を感じる。
「国鉄解体では組織内の技術が守られたかに見えたが、JR西日本では制御技術と技術者集団の継承性が損なわれて、福知山線事故という悲劇を生み出した。」
と「JALについてはいま給与体系や親方日の丸体質ばかりが論じられるが、最終的に利用者の信用を失ったのは多発した事故だった。この場合も、半官半民から完全な民間企業への変身が強調されるあまり、
整備という航空業のコアを外注してしまうことで、組織内に蓄積された安全技術が流出したからである。」を例に「東電を解体」のリスクを
説明しようとしている。
厚生労働省
は十分に機能しているか。機能しているとは思えない。政府機関は採算性を考えない。予算が取れればそれでよい。
民間は競争にされされる。コスト削減重視で利益を出しても、運悪く事故や重大な死亡事故を起こせば会社の存続も危なくなる。
コスト削減、顧客のニーズに対応する、新しい技術や新しいシステム、会社経営の改革そして運などのさまざまな点で結果を
出したものだけが生き残る。良い物を作ったり、良いサービスを提供しても顧客に認めれらなかったり、マーケティングをおろそかに
したため、又は運が悪い(時代の流れ)だけで存続できない会社もある。コストをかけても安全性を維持できない会社はあるが、
コストをかければ安全性は維持または向上できる。それが出来ない組織であれば消滅も仕方がない。組織が半官半民から完全な民間企業
に変身しても問題はない。問題は半官半民の体質のままでは厳しい競争で生き残ってきた企業と戦えない。従業員の意識が変わらなければ
存続や再生は簡単ではない。倒産した会社の従業員達を見ると、やはり倒産した会社の従業員なのである。これだから会社が倒産したんだと
思うことがある。成長している会社の従業員や問題を抱えていない会社の従業員とは違う。長い間に倒産する会社の体質に馴染んでいると
感じる。何かあると前の会社とかうちの会社(倒産した会社)と比べるが、比べても意味がない。しかし、終身雇用で倒産するまで
同じ会社で働いている人達は他の会社を知らない。どっぶりと倒産した会社の人間になっているのである。そして会社が倒産して
困っていてもメンタル的にも技術的にも他の会社に対応できない。だから再就職に困るのである。他の会社が魅力的に思う
社員であれば採用すると思う。
話を戻すが「整備という航空業のコアを外注してしまうことで、組織内に蓄積された安全技術が流出したからである。」と全てを理解しているように
書いているが、どの部分を外注すべきか、どの技術はコストがかかっても継承すべきであるか検討されるべきであった。しかし、
そこが軽視された、または、現場の意見を聞き、理解しようとしなかった幹部達がいた。そう言う事だと思う。外注を簡単に考えるが
外注を選定する人材そして外注先の仕事を評価できる人間が組織内にいなければどこかで安全性を損なう問題がいつか起こる。もしコストの
問題で適切な評価を出来る人材確保が出来ない、他の部分とのバランスを取りながら会社経営が成り立たないのであれば会社が
存続できなくとも仕方がないのである。個人的な意見としては、自分は素人であるが、お金を貰ってこのような事しか書けないのであれば
他の人が批判しているように東電に擦り寄って生きていくしかない。
ジャーナリスト・東谷暁 東電叩きによる「人災」 (1/2ページ)
(2/2ページ) 04/29/11 03:04 (産経新聞)
もういいかげんに「東電叩(たた)き」をやめてはどうか。たしかに、今回の福島第1原発事故については東京電力にも責任があるだろう。しかし、そのことといま蔓延(まんえん)している陰湿な東電叩きとはほとんど関係がない。
まず、東電の「想定外」発言を批判して何から何まで「人災」だと言うのは、恐怖に煽(あお)られた短絡にすぎない。この世の危険には確率計算できるリスクと、計算できない不確実性があって、リスクについて東電はかなりの程度まで想定していた。
最終的に今回の事故の原因となった非常用ディーゼル発電機不起動の確率は1000分の1だったが、東電はこれを2台並列に設置して100万分の1の確率にまで低下させていた。しかも、非常用ディーゼル発電機は頑丈で津波にも拘(かか)わらず一旦は起動したが、この非常用ディーゼル発電機のサブ冷却系が津波にやられていたためオーバーヒートして途中で停(と)まったとの説は有力である。
なかには、巨大な津波が来ることは分かっていたのに、低い防潮堤しかなかったため事故が起こったのだから、東電が対策を怠ったことになるという人もいる。しかし、これまで14メートルを超えるような津波は三陸海岸のものであって、福島浜通りに来たという記録はない。また、最近おずおずと発言を始めた地震予知学者たちも、口を揃(そろ)えてマグニチュード9は想定していなかったという。それでどうして東電がマグニチュード9によって起こる巨大津波を想定できるのだろうか。
そもそも、たとえ東電が巨大津波を想定していたとしても、できる対策とできない対策がある。もし想定できることはすべて予防策の対象とすべきなら、岩手、宮城、福島3県の海岸に、巨大防潮堤を建設しなかった県および政府は、あれほど多くの被災者を、最初から見捨てていたことになるのではないのか。
私が東電叩きをやめろというのは、それが私たちにとって損だからでもある。東電叩きには、東電に責任があるから政府は援助をするなとか、東電を解体しろという主張すらある。しかし、これこそ、私たちに新たなリスクを負わせることになるだろう。
これまでも高度な技術をもった事業体を解体したさいには、巨大なリスクが生まれた。国鉄解体では組織内の技術が守られたかに見えたが、JR西日本では制御技術と技術者集団の継承性が損なわれて、福知山線事故という悲劇を生み出した。
また、JALについてはいま給与体系や親方日の丸体質ばかりが論じられるが、最終的に利用者の信用を失ったのは多発した事故だった。この場合も、半官半民から完全な民間企業への変身が強調されるあまり、整備という航空業のコアを外注してしまうことで、組織内に蓄積された安全技術が流出したからである。
原発という技術は、現代における最先端の技術の塊のようなものであり、ことに安全を確保するための制御技術は、設計者と使用者との間の連携が失われれば機能が低下してしまう。しかも、制御技術は組織そのものによって維持されている。これを東電叩きに乗じた怪しげな扇動によって解体してしまえば、新たな事故を招来しないともかぎらない。そうなってしまえば、今度こそ、東電叩きによる「人災」ということになるだろう。(ひがしたに さとし)
東電の賠償、電気料値上げで…政府・民主容認へ 05/04/11 (読売新聞)
福島第一原子力発電所の事故の賠償策を巡り、政府・民主党が3日、東京電力が負担する賠償金に充てるため、電気料金の値上げを容認する新たな仕組みを設ける方向で調整に入った。
数兆円と想定される賠償金を支払う枠組みは、東電のリストラと毎年の利益から捻出するのが原則だが、それだけでは資金が足りないためだ。今回の枠組みで資金拠出を求められる他の電力会社についても、一定の電気料金の値上げを認める方向だ。
電気料金の値上げは国民の負担増となるため、東電だけでなく、他の電力会社も含めて徹底したリストラを求めたうえで、賠償総額が見通せるようになってから値上げ幅を検討する。
安易な値上げにならないよう政府が厳しくチェックするが、標準的な世帯の場合、月数百円程度の大幅な値上げとなる可能性がある。
東電、役員報酬5割減でも平均2000万円超 「無給が筋」続々 05/04/11 (産経新聞)
福島第1原子力発電所の事故に伴う対応の一環として東京電力が発表した「役員報酬50%削減」に「まだ高い」との批判がくすぶっている。半減しても平均で2千万円超で、「会長、社長は無給が筋」といった声や、政府の連帯責任を訴える指摘がやまない。
東電は平成19年11月、新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原発の事故で、常務以上の年間報酬を20%削減した。今回は削減幅を大幅に拡大。影響の大きさを踏まえると同時に、約540億円を捻出し、被災者への補償に充てる狙いがある。
だが、海江田万里経産相は、勝俣恒久会長や清水正孝社長を念頭に「まだカットが足りない」と述べた。東京商工リサーチの友田信男・情報本部副本部長も「けた外れの被害規模や日本の信用を失墜させた影響を考えれば、役員全員が報酬ゼロでいい」と厳しい。
米系コンサルタント会社タワーズワトソンによると、多くの企業は不祥事の際の報酬について、内規で1~5割削減を1カ月から半年間、または無期限と定めているという。
同社の阿部直彦・経営者報酬部門統括は「東電の『年収50%削減、期限なし』はめったにない規模」としながら、東電が不祥事のたびに報酬削減を繰り返した経緯から、「経営改善の点で効果がなかった」と指摘。業績連動型の導入が解決策の一つとみる。
一方、政府にも責任があるとする声もある。独協大学の森永卓郎教授は「経済産業省幹部や内閣の政務三役以上も報酬を半減した後で、東電は原子力担当の副社長以上を無給にする措置が適当」と話している。
東電副社長へ住民「戦争よりひどい」記事を印刷する 05/01/11 8時37分(日刊スポーツ)
東京電力の鼓紀男副社長らは4月30日、福島県飯舘村と川俣町を訪れ、福島第1原発事故の計画的避難区域に入ったことを謝罪した。同22日の指定以来、幹部の現地入りは初めて。鼓副社長は頭を下げ、正座したまま住民の質疑に応じたが、住民からは「住む所さえない。戦争よりひどいと言うお年寄りもいる」「子供が産めない体になるか不安」などの声が相次いだ。一部避難の川俣町では女性が「あなた方は事故後も高額な給料や報酬をもらっているのか」と問い詰めると、副社長は「具体的な金額はご容赦いただきたい」と口ごもりながら答えた。
東電の本音が現れた例だ。将来、東電が所有する原発が事故を起こした場合、同じような対応を取ると考えられる。
東電のエリアに住んでいないので、原発の影響を受ける地域の判断次第。しかし賠償額を負担できなければ国民負担を
要求するので東電が所有する全ての原発を5年以内に停止する事を望む。「原発が安全かどうか」の議論が必要だが、東電の
対応に問題あり。自民党はどのように考えているのか国会で示してほしい。自民党が変わっていなければ、業界擁護に
回ると思われるが知りたい。
東電、賠償免責の認識 「巨大な天変地異に該当」 04/28/11 (朝日新聞)
福島第一原発の事故に絡み、福島県双葉町の会社社長の男性(34)が東京電力に損害賠償金の仮払いを求めた仮処分申し立てで、東電側が今回の大震災は原子力損害賠償法(原賠法)上の「異常に巨大な天災地変」に当たり、「(東電が)免責されると解する余地がある」との見解を示したことがわかった。
原賠法では、「異常に巨大な天災地変」は事業者の免責事由になっており、この点に対する東電側の考え方が明らかになるのは初めて。東電側は一貫して申し立ての却下を求めているが、免責を主張するかについては「諸般の事情」を理由に留保している。
東電側が見解を示したのは、東京地裁あての26日付準備書面。今回の大震災では免責規定が適用されないとする男性側に対して、「免責が実際にはほとんどありえないような解釈は、事業の健全な発達という法の目的を軽視しており、狭すぎる」と主張。「異常に巨大な天災地変」は、想像を超えるような非常に大きな規模やエネルギーの地震・津波をいい、今回の大震災が該当するとした。
一方、男性側は「免責規定は、立法経緯から、限りなく限定的に解釈されなければならない」と主張。規定は、天災地変自体の規模だけから判断できるものではなく、その異常な大きさゆえに損害に対処できないような事態が生じた場合に限って適用されるとして、今回は賠償を想定できない事態に至っていないと言っている。
菅政権は東電に第一義的な賠償責任があるとの立場で、枝野幸男官房長官は東電の免責を否定しているが、男性側代理人の松井勝弁護士(東京弁護士会)は「責任主体の東電自身がこうした見解を持っている以上、国主導の枠組みによる賠償手続きも、東電と国の負担割合をめぐって長期化する恐れがある」と指摘。本訴訟も視野に、引き続き司法手続きを進めるという。これに対して、東電広報部は「係争中であり、当社からのコメントは差し控えたい」と言っている。(隅田佳孝)
いろいろな東電解体反対派の力が存在するし、どうなるのかわからない。とにかく東電解体へ進んでほしい。東電の体質は問題だ!
経産省幹部が公表をストップさせた「東京電力解体」案 この霞ヶ関とのもたれあいこそが問題だ
(2/4ページ)
(3/4ページ)
(4/4ページ) 04/15/11 (現代ビジネス)
福島第一原子力発電所の放射能漏れ事故が長期化する中、東京電力のあり方が焦点になってきた。
兆円単位に及ぶとみられる被災者への補償負担を考えれば、東京電力が自力で苦境を乗り越えられる可能性はほとんどない。いずれにせよ、政府の関与は避けられない。では、東京電力をどうすべきなのだろうか。問題点を整理しておきたい。
東電処理政策の目標として、とりあえず次の4点を考える。事故の再発防止、納得感がある補償、国民負担の最小化、電力の安定供給確保である。ほかにもあるだろうが、ひとまず措く。
まず、事故はなぜ起きたか。巨大な地震と津波という自然災害が直接の原因だが、そもそも原発の安全確保体制にも問題があった。
政府は原子力安全・保安院と原子力安全委員会という二本立てで原発の安全性を監視していた。前者は経済産業省の外局であり、後者は内閣府の審議会(+事務局)という位置づけである。
東電が天下り先の経産省に監視できるわけがない
経産省は外局に資源エネルギー庁も抱え、省を挙げて原発推進の旗を振ってきた。同じ役所が右手で原発を応援し、左手でチェックする体制になっていたのだ。現場で働く役人は同じ経産官僚である。東電は経産省からOB官僚の天下りを受け入れてきた。
規制する側が規制される側の世話になってきたわけで、これで十分に監視できるわけがない。
原子力安全委員会は学者が委員を務めている。実態は政府と東電の「御用学者」ばかりと言っていい。たとえば、松浦祥次郎元委員長は安全確保には「費用がかかる」と発言していた(テレビ朝日『サンデーフロントライン』4月10日)。番組でも指摘したが、東電のカネの心配をするのは、税金で報酬を得ている原子力安全委員の仕事ではない。これでは東電の代弁者ではないか。
保安院も安全委員会も「監視役」という本来の役割を果たしていなかった。保安院の経産省からの切り離しを含めて、抜本的な体制見直しは当然である。
東電を十分チェックできなかったのは、単に政府側の体制の問題というだけでなく、実は東電が地域独占だったという点を無視できない。
ほかに代替できる企業がないから、東電の力は必然的に強大になる。問題が生じたときに政府がペナルティを課したところで「絶対につぶせない」ので、時が経てば元に戻ってしまう。
政府とのなれ合いは、他に競争相手がいない地域独占が招いた必然の結果である。なれ合いが不十分な監視の温床となって、それが事故につながった。そう考えれば、地域独占をやめることがもっとも根本的な再発防止策であり、東電処理の必要条件になる。
電力事業をめぐっては、かねて発電事業と送電事業の切り分け(発送分離)が課題になっていた。発送分離して東電の送電線を自由に使えるようにすれば、発電事業に企業が新規参入しやすくなる。風力や太陽光など新しい再生可能エネルギーの活用も進むだろう。
ここは東電の発送分離に加えて、地域独占の廃止も組み合わせるべきだ。
「絶対につぶれない」という前提を見直す
納得感のある補償をするには、政府の支援が不可欠になる。一方、政府は国民負担を最小化する必要もある。そのためには、独占にあぐらをかいて大甘になっていたはずの東電の経営に徹底的なメスを入れなければならない。
役員報酬・退職金の返上はもちろん社員待遇の見直し、不用資産の売却、子会社の整理など大リストラが必要だ。
以上を前提に、電力供給の確保と新しい経営形態を考える。ここに「東京電力の処理策」と題された6枚紙がある。作成したのは経産省のベテラン官僚である。これをみると、いくつか斬新なアイデアがある。
先に東電処理の出口(EXIT)をみよう。
東電を発送分離して「東京発電会社」と「東京発電会社」に分けた後、第2段階として発電部門の東京発電会社を「事業所単位で分割し、持ち株会社の下に子会社として直接配置する」とある。その後で子会社の売却を提案している。
つまり東京発電A社、東京発電B社、東京発電C社というように発電所単位で子会社にして、それぞれ売却してしまうという案だ。これだと、発送分離に加えて1社による地域独占もなくなる。Aに致命的な事故や不祥事があった場合には、AをつぶしてBやC、あるいは新規に参入した会社が経営を引き継ぐことが可能になる。
これまでのように「絶対につぶれない」という前提がなくなる点が重要だ。もしものときは「会社がつぶれる」という状態に置くことで、それぞれの経営に緊張感が生まれる。経営母体が異なるのでAとB、Cの間で競争が生じて、ひいては電力料金の抑制にもつながるだろう。
この出口に至る途中のプロセスはどうするのか。
処理策は東電の経営を監視する「東電経営監視委員会」を弁護士や企業再生専門家らでつくり、経営を事実上、監視委員会の下に置くように提案している。一方で資金不足に陥って電力を供給できないような事態に陥らないよう、政府が必要に応じて東電の借入資金に政府保証をつける。
当面は事業をそのまま継続する。ただし役員報酬の返上など大リストラは、この段階で直ちに着手する。そうでなければ、企業価値を算定するときに東電の値段が無駄に高くなってしまう。ひいては国民負担につながる。
その後、放射能漏れの被災者に対する補償額、国と東電の負担割合が決まってから、東電の企業価値を算定し、経営監視委員会が再生プランを作成する。プランが出来れば、現在の株式は100%減資して、新たに株式を発行する。100%減資は既存株主にも責任を負担してもらうためだ。
誰が新会社の株主になるのか
問題は、だれが新株式を買うのか。この点について、ペーパーは何も触れていない。
考えられるのは、まず政府だ。政府が東電の新株式を買えば、国有化になる。
政府でなくても、たとえば企業再生支援機構のような組織を使う手もあるかもしれない。支援機構は政府と金融機関が預金保険機構を通じて出資し、2009年に設立された。本来は中堅、中小企業の再生のために存続期間5年限定でつくられた国の認可法人だが、大幅に資本金を拡充して東電再生に使う。
あるいは、東電再生を目的にした政府と民間による専用ファンドを新設する手もあるだろう。
ただし国有化にせよ、支援機構あるいは専用ファンドの保有にせよ、それが最終決着ではない。あくまで発送電を分離し、地域独占もやめて会社を複数に分割、それぞれ民間に売却するところが出口である。売却先として、電力供給義務を課したうえで、外資に門戸を開いてもいいだろう。
巷では、東電に対する怒りも手伝って「東電国有化」論が飛び交っているが、単に政府が東電を国有化するだけでは、これまでの政府との癒着関係が致命的にひどくなるだけだ。原発事故の反省もうやむやにされ、官僚と御用学者が再び大手をふって歩くようになるだろう。
政府と御用学者、東電は事実上、一体だった。それが事故の遠因になった。政府と東電を切り離し、複数の民間企業が競争して発電事業を担うようにする。そこがポイントである。国有化は途中経過で一時的にありうるが、それが問題の解ではない。
考えてみれば、電力供給も1社による地域独占状態より、複数の会社が発電事業に取り組んだほうが安定する。それは当たり前ではないか。1社に問題が生じても、別の社がセーフティネットになるからだ。
東電が宣伝していた「地域独占で供給が安定する」という話は、今回の事故で完璧に崩壊した。それは神話だったのだ。
経産省体質にこそメスを
最後に前回のコラムで試したように、思考実験として「政府が東電の資金難を支援するだけにとどめ、東電の経営形態は現状のまま」とした場合にどうなるか、考えてみよう。つまり抜本的な東電処理政策を実行しないケースだ。
政府は形だけ監視体制を手直しする。たとえば原子力安全・保安院と原子力安全委員会を合体して、独立の「原子力規制委員会」を新設したとする。
そこが東電を監視するが、東電自体は相変わらず「絶対につぶれない」状態に置かれているので、たとえ官僚に厳しく指導されたところで「どうせ、おれたちはつぶせないでしょ。だれが電力を供給するの。なんなら、あなたを天下りで受け入れてあげるよ」となめられるのが関の山だ。
東電1社だけでは、だめだ。電力供給体制の複数化が東電見直し論の鍵である。
ちなみに、この6枚紙の「処理策」はすでに経産省幹部も目を通している。ところが、執筆した官僚が公表しようとすると「絶対にだめだ」とストップをかけたという。天下りを通じて東電となれ合ってきた経産省の既得権益を侵す恐れがあるからだ。
そういう経産省の体質こそ、国会で真っ先に追及されるべきである。海江田万里経産相も、ここは勝負どころだ。しっかりと指導してほしい。そうでなければ、これから苦しい暮らしが待っている何万人もの被災者たちが浮かばれない。
NHKの国会中継で東電社長の答弁は全く責任を感じていない様子と完全に政府に一任するようなまるで人事のような対応と感じた。
こんな東電を国民負担で存続させる必要があるのか????
東京電力の清水正孝社長は13日午後の記者会見で、「国との協議をさせていただきながら、原子力損害賠償制度によって誠意をもって対応したい。
現在準備している」と述べた。
東電がこんな対応しかやってこないから「生活困る」との理由で出荷制限無視するしか選択肢がなかったのだろう。東電の資産を全て
売却して補償に当てる。東電の発電所や送電線は近隣の電力会社に売却すればよい。他の電力会社には魅力的な投資と思う。!普通はこんなチャンスなど
絶対、ありえない。足りない部分は国民負担を検討で良いのではないか。
東京電力をつぶす男 04/24/11 (AREA-net.jp)
東電清水社長が仮払い補償金について会見 プレスクラブ (2011年04月15日)(USTREAM)
基準値超の香取市産ホウレンソウ出荷は1万束超す 千葉 04/28/11 19:34 (産経新聞)
国の暫定基準値を超す放射性物質が検出されたとして、国が出荷停止を要請した千葉県香取市産のホウレンソウ7885束が匝瑳(そうさ)市の八日市場青果地方卸売市場に出荷されていた問題で、県は28日、出荷自粛と出荷停止期間だった1日~22日の間に、香取市内の農家15戸から、計1万1379束が出荷されていたと発表した。
県によると、販売先は印旛地域や山武地域、匝瑳市などの青果店や小売店の27業者で、県内が中心だが、このうち都内に1700束、横浜市に423束がそれぞれ含まれていた。事態を重視した県は同日、同市場に対して卸売り業務に対する改善勧告を行った。
県によると、問題のホウレンソウの出荷内訳は、出荷自粛を要請した1日~4日に計1512束、出荷停止となった5日~22日に計9867束が同市場に出荷された。香取市の農家15戸のうち、最も多いのが2207束で、2日連続で275束出荷したケースもあった。他の農家も期間中、1671束~10束を出荷していた。
出荷制限無視は「生活困る」から…大半高齢者 04/28/11 11時14分 (読売新聞)
千葉県香取市の農家10戸が出荷制限に従わず、ホウレンソウを匝瑳市の八日市場青果地方卸売市場に出荷していたことを受け、香取市の宇井成一市長と同市場の泊元明社長は27日、県庁で記者会見し、出荷していた生産者は70~80歳代が大半で、うち1人が「生活が困るのでやった」と話していることを明らかにした。
また、ホウレンソウの主な流通先は匝瑳、旭市や多古、横芝光町の青果店で、東京都内の青果店にも流通した可能性があることが判明、同市場などはさらに追跡調査を進める。
県と市のこれまでの調査によると、農家の1戸がホウレンソウを同市場に持ち込んだうわさが広まり、別の農家も追随して出荷したとみられている。10戸が共同で出荷を画策したり、特定の農家がほかの農家に出荷を持ちかけたりした形跡はなかったという。生産者には複数の農協組合員も含まれ、全員が「ホウレンソウが出荷制限の対象とされていたことは承知していた」と、改めて認めたという。
一方、県は26日、同市場が、ホウレンソウが香取市産だと知りながら受け入れていたと発表していたが、泊社長は、受け入れの際に生産地を確認していなかったことが今回の問題を引き起こしたと強調した。入荷伝票には生産者の屋号の記載欄しかないため、入荷の際、ホウレンソウの産地を確認する仕組みが存在していなかったといい、泊社長は「手落ちだった。監督不行き届きで、深く反省している」として謝罪した。
会見に先立ち、宇井市長と泊社長は森田知事を訪ねて謝罪した。会談は約8分間で終了し、森田知事は「残念なこと。法に基づいて決まったことは皆が守らないといけない」と語っただけで、宇井市長と泊社長に問題について深く質問することはなかった。
また、香取市農政課は取材に対し、今回の経過を説明。市は、旧佐原市を除く市内産のホウレンソウが出荷自粛の対象となった3月31日には対象地域の生産者団体に出荷自粛を要請、市全域でホウレンソウが出荷制限となった4月4日には、畑作農家の約4100戸に対し、農業者団体を通じて文書を配布したという。
同課は「出荷制限が守られているかどうかは確認していなかったが、現実問題として、そこまでは確認できない」と話し、今後、再び出荷制限となった場合には従うよう、改めて生産者に徹底する方針という。
東電賠償求め仮処分申請 双葉の社長「避難で事業休止」 04/15/11 (朝日新聞)
福島第一原発の事故で避難指示を受け、事業の休止に追い込まれたなどとして、福島県双葉町の会社社長の男性(34)が東京電力に対して損害賠償金計4440万円の仮払いを求める仮処分を東京地裁に申し立てたことがわかった。東電側は14日、申し立ての却下を求める答弁書を出した。
事故後、司法の場で損害賠償金の支払いを東電側に求める動きが明るみに出たのは初めて。
申し立ては7日付。申立書などによると、男性は同原発から約2キロの工業団地で年商約4億円、従業員18人の鋼構造物工事会社を経営。大震災当日に同原発から半径3キロ圏内の住民に避難指示が出て、会社に立ち入れなくなった。
男性側は、事故と事業休止には因果関係があり、避難指示が解除されても事業再開までには最低6カ月かかるとして、この間の従業員給与を含む事業経費(月700万円)と男性自身の役員報酬(月40万円)の仮払いを求めている。
国は11日、原子力損害賠償法に基づき、損害賠償の指針をつくる第三者機関、原子力損害賠償紛争審査会を設けた。男性の代理人弁護士は「どのような内容の指針が、どの程度の時間で出るのかが見えない。迅速な司法手続きによる判断を求めたい」と言う。
一方、東電側は答弁書で「審査会の指針に基づく任意交渉と、和解の仲介で解決を図るのが基本方針で、個々の案件ごとに司法判断を受けて解決していく方法では補償実務に混乱をもたらし、公正・迅速な補償ができない」と主張した。
男性は今、埼玉県内の親族宅に、家族と身を寄せている。会社が振り出した400万円の支払手形は10日に不渡りになった。男性は「従業員も仕事に就けておらず、一日でも早く再建への道筋をつけたい」と話している。(隅田佳孝)
「事故対策の拠点建物、個人の被曝線量記録せず 東電、ずさん管理」厚労省幹部の問題じゃない。作業者達が
将来、放射線による被曝によって健康を害しても、死亡しても良いと間接的に言っているようなもの。裁判になっても
記録がないんだから勝てる確率も低い。厚労省幹部がそんなことも理解できないはずがない。全て承知の上だろ。「フクシマ50」
は「神風50」として教科書に載るかも知れない。偽善の仮面をかぶった厚労省幹部がこれまでいろいろな問題で適切な
対応をしてこなかった理由の1つは自分達のことしか考えていない、自分達の今後の出世のためにはどのように立ち回る
べきかしか考えていないと思う。
産業界の圧力があれば上限規定を撤廃する検討する。ある基準は国際基準に変更し、ある基準は国内方法を続ける。
ある利益者達(企業又は業界)のためだけに判断され、国民や作業者達の安全性や健康は無視される。しかし
訴える者達が弱者であれば無視したり、裁判で引っ張る。厚労省だけではないかもしれないが、汚すぎる!
まあ、これが日本の政府機関の真の顔なのだろう。震災復興とか原発とか奇麗事を言いながら国民負担を選択の余地なしに
強要する。この点では自民党であっても同じかもしれないが、直ぐには変えられないが国民は真剣に政治について
考える必要があると思う。
事故対策の拠点建物、個人の被曝線量記録せず 東電、ずさん管理 04/28/11 10:56 (産経新聞)
福島第1原発事故の対策拠点で作業員が寝泊まりする「免震重要棟」内で浴びた放射線量について、東京電力は個人の線量を毎日は記録せず、後から行動を聞き取って推計していたことが28日、分かった。東電のずさんな被曝管理に批判が強まりそうだ。
東電によると、屋外の現場作業などをする場合は線量計を持参するが、免震重要棟内では時間当たりの放射線量を記録していただけ。緊急的作業が一段落した3月23日以降、棟内に滞在していた時間を聞き取り、滞在中の被曝線量を推計したという。
棟内では事故後、高い線量が続き、水素爆発などが起きた直後には、毎時100マイクロシーベルト(0・1ミリシーベルト)を超えたこともあった。主に免震重要棟で作業する放射線業務従事者ではない人であっても、一般人の限度である年間1ミリシーベルトを超える被曝をした恐れが強い。
被ばく線量:年50ミリシーベルト 上限撤廃検討…厚労省 04/28/11(毎日新聞)
厚生労働省は27日、原発作業員の被ばく線量について、通常時は年間50ミリシーベルトとする上限規定を撤廃する検討を始めた。5年間で100ミリシーベルトの上限は維持する。福島第1原発の事故では、全国各地から作業員が応援派遣されているため、現行の上限規定のままでは、他の原発の点検業務に当たる作業員が確保できなくなるという懸念が産業界などから出ていた。
一方、通常時とは別に、緊急時の被ばく線量について厚労省は先月、福島第1原発の復旧作業に限り、100ミリシーベルトの上限を250ミリシーベルトに引き上げる特例措置を設けている。
副学長2人辞めても理由を説明しない新潟大 04/28/11 (読売新聞)
新潟大学の永山庸男(つねお)教授が、副学長職を任期途中の3月末で外れていたことが27日、わかった。
また、理事・副学長だった山下威士氏も、3月末で辞職していた。2人の任期はいずれも来年1月末まであった。新大では50歳代の男性教授が、数十億円の医療装置を購入する契約を業者と不正に結んでいた問題が発覚しているが、新大総務課は「(不正契約問題との)関連についてはコメントしない。人事の理由は公表していない」としている。
新大によると、永山教授は2008年2月、評価・広報担当の副学長に就任、学長室長も兼ねた。大学側は、学長による解任か、自発的な辞任かは、明らかにしていない。永山教授の代理人の弁護士は、取材に対し「大学から『誰に対しても一切何事もしゃべってはならない』旨の業務命令が出されているので、誠に遺憾ながら説明できない」などと答えた。
一方、山下氏は08年4月、総務担当の理事と副学長に就任。取材に対し、「一身上の理由で辞めた。(不正契約問題のことを)知っているべき立場だったのに知らなかった責任を取った、というのも一因」などと述べた。
理事と副学長の任免については、国立大学法人法などに準じた学内規定で、学長が単独で行うことができるという。
男性教授による不正契約問題を巡り、新大は「捜査への影響を避けるため」として、教授の氏名や所属先、医療装置の種類、不正の方法など、具体的な内容を明らかにしていない。
原発は絶対反対とは思わない。しかし東電の不適切な対応により結果として人災による損害拡大となった。東電が損害賠償を
支払うべきだろ。絶対安全とは言えない魚を知らないうちに国にするリスクに30年近くの曝されて、国民負担として尻拭いまでさせられる。
金融機関、株主そして東電社員達を守るために国民負担が増えるのか??東電も原発も一切要らない。首都も東京電力のエリア以外に移せば良い。
金融機関を守る必要があるなら電力会社だけでなく、日本の全ての金融機関にも損害賠償の一部を負担させろ!会社の倒産や損失は
金融機関が考慮すべきリスクだろ!
「許し難い行為だ」全漁連の抗議に首相が陳謝 補償は「責任持ち対処」 04/27/11 (産経新聞)
菅直人首相は27日、官邸で全国漁業協同組合連合会(全漁連)の服部郁弘会長らと会い、東京電力福島第1原発事故で放射性物質を含む汚染水が海に流出したことに関し「ご迷惑を掛けていることをおわびします」と陳謝した。被害補償については「政府として責任を持って対処したい」と明言した。
服部氏は「相談や連絡なく汚染水を流出させたのは許し難い行為だ」と強く抗議。風評被害の解消や補償に万全を期すよう要請するとともに、漁村復興に向けた予算措置を求めた。首相は、事態の収束に全力を挙げる考えを示した。
原発事故をめぐっては、福島、茨城両県沖で取れたコウナゴから食品衛生法の暫定基準値を超える放射性物質が検出され、地元漁協が出漁自粛を強いられるなどの被害が出ている。
金沢大、捏造・セクハラ等処分者名を徹底非公表 04/27/11 (読売新聞)
国立大で教員の不祥事が相次ぐ中、金沢大の情報隠しの体質が目立っている。
研究界のモラルの根幹を揺るがす不正でも、プライバシーなどを盾に実名や研究内容を伏せるなど、身内の保護を優先。有識者からは、大学側の見識を問う声も出ている。
金沢大では昨年8月末、教授や准教授3人をアカハラやセクハラ、暴行で、けん責や減給処分にしたと発表した。処分から発表までに2か月以上かかった上、いずれのケースも「被害者が特定される」として具体的な内容を明かさなかった。
今年3月25日には、40歳代の男性講師が、研究データを捏造(ねつぞう)し、文部科学省の補助金を10年間にわたり不正に取得していたとして、懲戒解雇したと発表。この時は氏名や年齢はおろか、研究内容すらも明らかにしなかった。
同じ日に会見した香川大は、男性准教授(45)が電車内で乗客に暴行したと発表。年齢や担当科目などを明らかにしている。
多くの国立大では、データ捏造や論文盗用を巡る処分では実名を公表しており、金沢大とは“透明度”に大きな開きがある。
金沢大の情報隠しの姿勢が際立ったのは、男性講師による補助金不正受給についての記者会見だった。
実名公表を求める報道陣に対し、桜井勝(しょう)副学長は「本学の公表基準やプライバシーの問題を考えると、氏名までは出せない」とし、研究内容についても「公表すると、データベースから氏名が検索できる」と拒否した。
国立大の公表基準は各大学が独自に定め、金沢大では「懲戒処分の概要は、個人が識別されないものを基本として公表する」とし、「社会的影響や被処分者の職責を考え、別途の取り扱い(公表)をすることもある」との例外を設けている。
データ捏造による公金の不正受給という案件にもかかわらず、桜井副学長は「研究者コミュニティーへの影響はあるが、一般社会への影響は低い」と述べ、例外を適用しないと明言。
講師は、捏造データを複数の学会で発表していたが、「学会の発表が直ちに(一般に)広がることはあり得ない」「学会では、前回の発表に間違いがあっても、次の回に否定しない」とし、研究内容を広く公開して情報を修正する必要はないとの認識を示した。
一部メディアが、講師の研究内容について、血栓を起こしやすい「抗リン脂質抗体症候群」に関するものと突き止めたが、「抗リン脂質というものはない」として最後まで認めなかった。
文科省によると、各国立大が公表基準の根拠としているのは、独立行政法人等情報公開法だ。同法では、個人が識別できても、慣行として公にされている情報や、職員の職務遂行の内容にかかわる部分は、開示することになっている。
情報公開の問題に詳しい杉浦英樹弁護士(日弁連の元情報問題対策委員長)は、「今回のケースでは、研究内容の公表を拒否する理由はなく、実名も公表するのが健全な感覚」とし、「金沢大は、情報公開による不正の是正や再発防止よりも、大学の利益を優先させている」と指摘している。(小寺以作)
抗議に対してどのような対応するのかで真の東電の顔が分かるかもしれない!民主党が国民負担と平気な顔で言いながら
東電の存続を当然と思っていること自体許せない。東電の社員のボーナスを50%カットだと!東電がなくなればボーナスや退職金は
なくなる。今後、ボーナスはゼロでも良いだろう。嫌な社員は他の会社に行けばよい!東電は本当に反省などしていないと思う。
国民負担で東電存続の手厚い民主党のろくでもない案を当然と思っているのだろうか??
東電本店前、福島の牛伴い抗議「早く賠償を」 04/26/11 (読売新聞)
東京電力福島第一原子力発電所の事故で、周辺の農産物から食品衛生法の暫定規制値を超える放射性物質が検出されたことなどを受け、農民運動全国連合会などが26日、東京・内幸町の東電本店前に福島県の肉牛や乳牛を伴って抗議に訪れ、早期の賠償を求めた。
福島県の約160人を中心に、宮城、岩手や群馬などの農家や酪農家ら約250人が集まった。「協力要員」として、福島県田村市の肉牛、千葉県睦沢町の乳牛を連れ、出荷停止となった茨城県稲敷市産のほうれん草約100キロも持参した。
同連合会常任委員の斎藤敏之さん(61)は「農家はもはや精神的にも経済的にも限界。すみやかな賠償を強く求めたい」と話した。
なぜ適切な判断が出来ない企業を存続させるのか??東電の資産を売却すべきだ!電力関係は近隣の電力会社。
民主党は自滅への行進をしていると思える!
細野補佐官「東電は大きな判断やりにくい会社」 04/25/11 (読売新聞)
政府と東京電力、文部科学省、経済産業省原子力安全・保安院、原子力安全委員会などでつくる福島第一原子力発電所事故対策統合本部(本部長=菅首相)は25日、これまで東電や保安院で別々に行っていた会見を一本化し、初の共同記者会見を開いた。
午後5時20分過ぎから始まった会見は、事故当初の政府や東電の対応を巡る質問が相次ぎ、4時間近く続いた。
統合本部事務局長の細野豪志首相補佐官は、同原発1号機で3月12日に行われた放射性物質を含む蒸気を放出する「ベント」操作を巡り、「政府としては11日夜にはベント実施の腹を決めたが、(東電が)なかなか実施しなかったので、午前6時50分に命令に切り替えた」と説明。東電について「電力供給という(日々あまり変化がない)ルーチンワークに慣れた会社なので、何か大きな判断が若干、やりにくい会社なのかなと感じていた」と述べ、東電の動きが鈍かったことを批判した。
「最終的には国民負担になるが、東電、政府が責任をもって説明するべきだ」
東電が適切な判断と対応を行わなかったから損害賠償額が増えた。4月25日の国会中継をNHKで見た。
俺には関係ないが、福島の被害者達は東電社長の回答に納得したのか??あんな回答しか出来ない会社に原発なんかを動かしてほしくない。
あんな会社を救う必要があるのか??東京に電力会社は必要だが、東電でなくても良い。あんな社長と会社なんか消滅したほうが良いだろう。
東電がなくなったら誰も補償しない??国と日本国民の負担で補償するのだから東電なんか必要ない!東電の資産をとにかく売却して
補償に当てろ。足りない分は国民負担でも仕方ないだろう。民主党よ、日本を思う心があるならメインステージから降りろ!
危機管理能力なし!的確な判断が出来ていない!言い訳ばかりで見苦しい!
四国電力社長、賠償負担に難色「東電救済なら筋違い」 04/25/11 (朝日新聞)
東京電力福島第一原発の事故に伴う賠償問題で、四国電力の千葉昭社長は25日、松山市内での記者会見で「国には認可責任があるのだから、国の責任を明確にし、株主やお客様にきちんと説明できるような論拠がないと難しい」との考えを示した。
賠償の枠組みの政府原案では、東電の賠償を支援する機構を、ほかの電力各社も負担して新設する方針が示されている。
千葉社長は「将来の原発事故のリスクに対する保険なら額次第で株主の理解も得られるだろうが、福島の事故があって東電を救済するというスキームであれば、筋からしておかしい」と述べ、国による救済が優先されるべきだとした。
また、賠償が電気料金の値上げにつながる可能性について「最終的には国民負担になるが、東電、政府が責任をもって説明するべきだ」と述べた。
農水省職員による検査も原発の検査と同様に甘い!これで放射能汚染された農作物、魚介類、そして酪農品が市場に出回っても
見つけ出すことなど出来ないだろう!メディアは風評被害と繰り返す前に、どれだけ不正や産地偽装が見逃されてきたか調べるべきだろう。
「『健康被害が報告されていない』などの理由で不起訴処分(起訴猶予)となった。」放射能汚染されたものを食べても直ちに
健康被害が出ないから産地偽装しても不起訴になるのかな?まあ、魚介類をあまり食べない食生活なので他の人達よりは安全であろう。
加工食品に使われていたら調べようがない。使用されたものの産地まで書くようになっていないし、外食のメニューにもそのような
情報はない。公務員による検査は書類とか形式にはこだわるが、それ以外のチェックは非常に甘い。また、ごまかしていても
見抜けるような公務員は少ない。権限を持っているだけで経験や知識不足の場合が多い。公務員の仕事を知っている人達は、
事実を知っているだろうが、事実を指摘したら自分達に跳ね返ってくるから何も言わないのだろう。だから公務員の言葉を信用できない。
少なくとも自分達が見たことについては事実だから。たぶん、他の分野や業種も同じかもと思うと敬遠するのだろう。
全ての省庁で消費される食料品は3年間に限定して福島県及び近隣の県産に限定する宣言をするべきだろう。菅首相のパフォーマンスだけでは
不十分だ。
事故米52トン、主食用として消費 農水省、8社を処分 04/22/11 (朝日新聞)
2003~08年に米国やベトナムなどから輸入された事故米や麦が食用として不正転売されていた事件で、事故米52トンが主食用として消費されていたことが農林水産省の調査でわかった。農水省は22日、輸入・流通にかかわった伊藤忠商事など計8社を処分した。
事故米や事故麦は、輸入米に高い関税をかける代わりに一定量の輸入が義務づけられたミニマムアクセス米などとして輸入されたが、検疫でカビが確認され、飼料用など食用でないとされたもの。
農水省は、流通先が不明だった事故米3277トン分、カナダ産デュラム小麦622トン分の流れを調べた。事故米のうち942トンは酒やみそ、酢、しょうゆの加工原材料。52トン分は主食用だったが、小売店など一般の流通ルートでは販売されていなかったという。事故米の残りと事故麦は流通先が特定できなかった。
農水省は「残留農薬やカビ毒は検出されておらず、健康への影響は報告されていない」としている。
農水省は、輸入していた伊藤忠商事、兼松、双日、丸紅、ヴォークス・トレーディングの5社を、「最終的に飼料用として適切に使用されたか確認しなかった」として、輸入米麦の政府買い入れ入札の指名停止3カ月とした。5社の10年の輸入量実績は米で全体の48%、麦で30%という。
また事故米の偽装や流通にかかわった倉科商店(神奈川県藤沢市)、濱田物産(神戸市)、伊東精麦所(長崎県諫早市)は販売停止などの処分とした。(大谷聡)
事故麦622トンも流通 農水省の事故米事件調査で判明 04/22/11 (朝日新聞)
2008年までに米国から輸入された事故米3155トンが食用として不正転売されていた事件で、食用でない麦622トンも食用に偽装されて流通していたことが農林水産省の調査でわかった。農水省は22日午後、これらの米麦を輸入した大手商社を指名停止にする。
この事件では、神奈川県伊勢原市の加工業者「協和精麦(せいばく)」が、カビの発生などで非食用とされた事故米を家畜の飼料用に加工したと偽り、食用として転売していたことを昨年春に認めた。農水省の追加の調査で、同社は同時期に輸入された非食用の事故麦についても、飼料用の加工をせず、食用として流通させたことを認めたという。
農水省は流通先も調査。事故米の一部は焼酎の原料などになっていたことが確認されたが、麦については書類が残っておらず、解明できなかった。事故米や麦は残留農薬やカビ毒は検出されておらず、健康への影響はなかったとみられる。
偽装された3155トンを含む事故米5251トンは、03~08年に伊藤忠商事、双日、丸紅など大手商社計6社が輸入していた。農水省はこのうち5社程度について「最終的に適切に使用されたか確認しなかった」として処分を行う。農水省は08年、この5251トンについて「飼料用に使われたと確認した」という誤った発表をしていた。
この事件では、時効にかからない事故米82トン分について、神奈川県警が昨年8月、協和精麦など転売にかかわった業者2社と元社長ら4人を食品衛生法違反などの疑いで書類送検。「健康被害が報告されていない」などの理由で不起訴処分(起訴猶予)となった。(大谷聡)
元警察署長、教習所指導員に不正証明書発行か 03/23/11 (読売新聞)
京都府井手町の山城自動車教習所のトップにあたる管理者の元京都府警南署長(63)が2009年、観光バスなどの運転に必要な「大型2種免許」の取得を目指していた同教習所の指導員に対し、必要な講習を受けたとする虚偽の終了証明書を発行、同免許を取得させた疑いが浮上し、府警が公印不正使用、道交法違反(運転免許不正取得)容疑などで捜査していることがわかった。
元署長は任意の調べに、この1件について「責任は私にある」などと供述したという。府警は、他の不正発行や関与者の有無を詳しく調べる。
捜査関係者によると、元署長は09年12月、運転免許試験場で同免許の技能試験に合格した指導員が、同免許の取得に必要な「応急救護処置講習」(6時限)などを受講していないのに受けたとする府公安委員会の公印を押した終了証明書を発行、この際、指示もしくは黙認して、同免許を不正取得させた疑いが持たれている。今月上旬、府警への匿名の情報提供で発覚した。
福島第1原発爆発:世界各国に衝撃 日本技術の信頼低下も 03/14/11 (毎日新聞)
東京電力福島第1原発の相次ぐ水素爆発や燃料棒の露出は、世界各国に衝撃を与え、技術大国日本の「安全神話」を揺るがす事態になっている。
米CNNや英BBCはじめ欧米メディアは「(旧ソ連で86年に起きた)チェルノブイリ原発事故の再発を防げるのか」などと日本政府の対応に批判的な論調を強めている。スイス紙NZZ・アム・ゾンタークは、ビルディ・ジュネーブ大教授の話として「日本政府は事故の重要性を低く見積もっている。被ばくの危険性を低レベルに公表しているが、半径20キロ圏外に住民を避難させた事実は原発を制御できていない証拠」と伝えた。
インドでは日印原子力協定交渉への影響を懸念する声が広がっている。ニューデリーのシンクタンク「エネルギー資源研究所」のダディッチ上席研究員は「世論が(日本の原発技術に)厳しい目を向ける可能性が高い」と指摘。シン首相は14日、国内20カ所の原発で安全対策の再点検を命じたことを明らかにした。
韓国の青瓦台(大統領府)は任太熙(イム・テヒ)大統領室長が緊急会議を開催し、放射性物質の周辺国への影響などが論議された。聯合ニュースによると、2月に放射能漏れ事故を起こした大田市の研究用原子炉の再稼働が14日、「安全に万全を期す」という当局の判断で、15日に延期された。
クリーンエネルギーの一つとして原発促進政策に転換した米国では、複数の議員から原発見直しを求める声が上がっている。民主党のマーキー下院議員は、連邦政府が緊急事態への対応策を強化するまで、新規建設計画の一時停止を求める手紙をオバマ大統領に送った。米国では31州65カ所の発電所で104基の原子炉が稼働し、総電力の2割をまかなっている。オバマ大統領が提案した360億ドル(2兆9520億円)の原発建設融資策を巡り、議会で議論を呼ぶのは必至だ。
ドイツのウェスターウェレ副首相兼外相は14日、連立与党が昨年、法制化した原発利用延長の凍結も含めた原発政策見直しを記者団に表明。連立与党は09年の発足から一貫して原発利用延長に積極的だったが、ドイツが原発政策で再び転機を迎える可能性がある。
英国も、中断していた原発建設を再開し、25年までに原発10基を新設、電力供給量の4割を原発がまかなう政策を推進しているが、政府は今回の事故を機に、安全面を中心に原発懐疑論が高まることを警戒している。
日本の事故を受け、オーストラリアのギラード首相やイスラエルのネタニヤフ首相は自国での原発建設に反対する姿勢を表明。フィリピンの大統領府副報道官も凍結中の原発の再稼働を否定した。20年に初の原発の操業開始を目指していたタイのアピシット首相も、「(原発に消極的な)私の意見は皆知っている。日本の出来事がわが国の意思決定にどう影響を与えるか、検討している」と述べた。
一方、中国では原発の冷却装置が機能しなかった点に注目が集まっているが、「第一財経日報」は「中国の新型原発では冷却をめぐる問題は生じない」と報道。原発専門家の話として、中国の新型原発は原子炉の上部に数千トンの水をためるようになっており、非常時には動力なしでも重力で水が落下して冷却する仕組みのため問題は起きないとしている。
ロシア国営原子力企業ロスアトムの当局者は、旧ソ連で86年に起きたチェルノブイリ原発事故では炉心溶融から爆発につながった点を取り上げ、現時点では福島第1原発の原子炉が爆発する可能性は小さいと指摘する。ただロシアは1月に日本との原子力協定を批准したばかりで、日本企業の技術に着目してきたが、事故を受けて、日本製技術の安全性について再考する可能性もありそうだ。
中東初となるブシェール原発を近く稼働予定のイランは計画を続行する方針。国営通信によると、原子力庁のラストハ副長官は福島第1原発のケースについて「(原子炉が入る)金属製の構造物自体は破壊されておらず、放出された放射性物質は少ない」とし、似た構造のブシェール原発の安全性を強調した。
福島第一2号機、燃料棒すべて露出…冷却水消失 03/15/11 02時38分 (読売新聞)
東京電力福島第一原子力発電所2号機で14日午後6時過ぎ、原子炉内の冷却水が、ほぼ完全に失われ、燃料棒がすべて露出して冷却できない状態になった。
東電が同日発表した。水位はいったん回復したが、再び低下し、同日午後11時ごろ、燃料棒が全部露出した。空だき状態が続くと燃料棒が溶けだす炉心溶融の懸念がある。同日夜に記者会見した枝野官房長官は、1~3号機どれでも燃料棒の溶融が起きている「可能性は高い」との見方を示した。
同日午後9時37分、同原発の正門での放射線量は毎時3130マイクロ・?と、地震後に公表された値では最高を示した。
東電によると、2号機はこれまで原子炉の圧力や温度などは比較的安定していたが、同日午後1時38分、冷却水の循環ポンプが止まり、炉内の圧力が上昇、水位が低下し始めた。同5時17分に約3・7メートルの燃料棒上端から露出が始まり、同6時22分に全体が露出した。
東電は冷却水の循環停止後、別のポンプで海水を原子炉に直接入れる準備を進め、同6時24分、注入を開始した。しかし、炉内の圧力が高かった上に、作業員が1、3号機のポンプの見回りで目を離した間に、海水注入ポンプは燃料が切れて停止。燃料を補給して注入を再開したが、約3時間、完全に燃料が露出した状態が続いた。
その後、水位は回復したが、同日午後11時ごろ、原子炉の冷却水が再びなくなり、燃料棒が完全に露出した状態になった。原子炉から格納容器に蒸気を逃がす二つの弁が完全に閉まり、原子炉内の蒸気圧力が上昇し、海水の注入ができなくなった。
東電は、15日午前0時2分から格納容器内の蒸気を外部に放出する新たな弁を開けた。この弁から外部に放出する蒸気には、原子炉内から直接出た蒸気が含まれており、これまでに放出された蒸気より放射能が高い。
冷却水が消失し、燃料棒の露出が続くと、高温の燃料が冷やされず、炉内の温度が2000度超まで上昇して、燃料が溶けだす恐れがある。
建屋が吹き飛んだ1、3号機の水素爆発より深刻な事態で、炉心溶融によって大量の放射性物質が大気中に漏れる可能性もある。
冷却水喪失(LOCA)によって炉心溶融を起こした事故は、1979年の米スリーマイル島原発事故などがある。
ポンプの燃料も確認せず、燃料切れ。非常用発電機は作動しない。ポンプの切り替えが出来るように2台ぐらい用意しておけよ!
東日本大震災:2号機一時空だき状態 燃料棒破損の恐れも 03/14/11 20時09分 (毎日新聞)
東京電力は14日、東日本大震災で被災した福島第1原発2号機で原子炉の水位が急速に低下し、長さが約4メートルある燃料棒が一時水面から完全に露出する「空だき状態」になったと発表した。その後、燃料棒は半分まで水中に入ったが、破損した可能性がある。経済産業省原子力安全・保安院によると、冷却機能が喪失した上、注水に使う消防車5台のポンプが同日午前に3号機で発生した水素爆発などで故障、2台しか稼働していないことが響いた恐れがある。
東電によると、水位が測定不能となった空だき状態になったのは午後6時22分。午後8時ごろに注水が始まった。燃料棒が長時間、完全に露出すると、燃料が損傷し炉内で固まって再臨界し圧力容器を破損。放射性物質が外部に漏れる。
保安院によると、同日午後1時25分、同発電所2号機で原子炉内の圧力を利用して水を循環させて炉内の温度を下げる機能がすべて失われた。東電は、原子力災害対策特別措置法に基づき国に原子力緊急事態宣言を求めた。原子炉隔離時冷却系(RCIC)と呼ばれる機能が停止、原子炉内に注水できなくなったのが原因という。
東電は同日午後4時34分、海水の注入準備に入った。注水には消防車のポンプを使うが、数不足に加え、職員が目を離したすきに燃料が切れて停止したという。その後、注水を再開し、午後9時34分に半分まで回復した。枝野幸男官房長官は午後9時過ぎの会見で「水位の上昇は確認された」と語った。
1、3号機のように建屋内にたまった水素が爆発する可能性がある。東電は、建屋の壁面に穴を開けることを検討している。
3号機の水素爆発で発生した負傷者は11人でうち6人が被ばくした。政府は「燃料棒のある圧力容器と格納容器は健全」とし、保安院は20キロ圏内の付近住民に対し、爆発直後に屋内退避を求めたが、同日午後2時過ぎ、20キロ圏外に退避するよう要請した。警察庁によると、14日午後1時現在、半径10キロ圏内には約60人がとどまり、自衛隊のヘリが搬送する予定だ。10~20キロ圏内には約360人が残り、警察の誘導でバス搬送を始めている。
一方、炉内が高温のために緊急事態宣言が出されていた福島第2原発の1、2、4号機のうち、1、2号機が14日午後、核燃料の分裂が止まる「冷温停止」の状態になった。
燃料棒露出、水注入ポンプ燃料切れ見逃しか 03/14/11 20:06 (読売新聞)
福島第一原発2号機で原子炉の燃料棒が完全露出し、一時的にせよ「空だき」状態となった原因について、14日午後9時すぎに記者会見した枝野官房長官は、「水を注入して冷却する作業に入っていたが、一時、(注入用の)ポンプの燃料不足で、想定より時間がかかった」と説明。
初歩的な作業ミスによって重大な事態を引き起こした可能性を示唆した。
東電などによると、2号機では当時、港から直接、海水を取水し、ポンプで原子炉内へ送り込んでいた。1、3号機でも同様の注水作業を行っており、作業員が1、3号機用のポンプの見回り後に、2号機用のポンプを確認した際、燃料切れで停止しているのを見つけたという。
ある東電幹部は「想定外の大地震による作業員の不足と、深刻な事故が重なったことで、(原発の『命綱』である)注水ポンプから目を離す事態が生じた」と漏らした。
2号機、燃料棒すべて露出=炉心溶融否定できず-東電福島第1原発 03/14/11 20:06 (時事通信)
東京電力は14日午後7時45分、福島第1原発2号機の冷却水が大幅に減少し、約4メートルある燃料棒がすべて露出したと福島県に通報した。核燃料の一部が溶ける炉心溶融も否定できないとしている。
仮に、冷却水がすべて失われたとすると、極めて深刻な状態。
東電によると、炉内に海水を入れるためのポンプの燃料が切れていたといい、燃料を入れた上で作業を再開する。
灰褐色の煙300メートル上昇…爆発の3号機 03/14/11 14時30分 (読売新聞)
今回の福島第一原発3号機の爆発には、12日の1号機の爆発といくつかの違いがある。
まず、1号機の時には水素爆発で発生した水蒸気を示す白煙がたちこめたが、今回は、白煙以外に、赤い炎を伴う灰褐色の煙が上空高く上った。また、爆発をとらえたニュース画像では、煙の中に、厚みのある大きな塊がいくつも飛び散っていた。詳細は不明だが、この爆発の後にも、爆発があったという。
今のところ、炎や灰褐色の煙、塊が何であるかは不明。3号機にたまった水蒸気の量が1号機よりも多かったので爆発の規模が大きくなったとも考えられるが、かなりの高温で燃焼を伴う別の破壊的な異変が起きていた可能性もある。
また、建屋内の上部にたまった水素が爆発したなら、一度の爆発で済むはずだ。1回目の爆発の影響で、高圧状態の配管などが破損し、爆発音がしたか、建屋上部以外のどこかにたまっていた水素が爆発した可能性がある。最悪の事態を想定すると、1回目の爆発によって、高圧の格納容器が損傷し、新たな爆発を生じたということも考えられる。その場合、原子炉を覆う最後の壁が破れたことになり、放射能を帯びた水、水蒸気などが外部へ放出されることになる。
あわやメルトダウン、福島第一原発2号機電源喪失水位低下 06/19/10 (「風のたより」より)
今日19日から、東京電力は福島第一原発3号機の定期検査に入り、9月23日までの間に、安全審査の想定外のMOX燃料を装荷しプルサーマルをはじめようとしています。
しかし、17日午後、第一原発2号機であわやメルトダウンの事故が発生しました。発電機の故障で自動停止したものの、外部電源遮断の上に非常用ディーゼル発電機がすぐ作動せず、電源喪失となり給水ポンプが停止、原子炉内の水位が約2m低下、約15分後に非常ディーゼル発電機が起動し隔離時冷却系ポンプによる注水で水位回復するという、深刻な事態でした。東京電力は事実経過を明らかにしておらず、真相はまだ闇の中ですが、この事故は誠に重大です。
福島第1原発 放射線量が再上昇し、東電「緊急事態」通報 03/13/11 11:14 (産経新聞)
東京電力は福島第1原発の敷地境界で13日午前、放射線量の値が再び上昇して制限値を超えたため、原子力災害対策特別措置法に基づく「緊急事態」の通報を国に行った。
原発の敷地の境界では12日午後に一時、1時間に1015マイクロシーベルトの放射線量を計測。その後、いったん数値は減少したが、今朝8時20分に882マイクロシーベルトを計測した。法令が定める一般人の年間被曝線量の限度は千マイクロシーベルト。
原発3号機では13日朝から、原子炉格納容器内の微量の放射性物質を含む蒸気を外部に放出する弁を開ける作業を行っていて、東京電力は数値上昇との関連を調べている。
住宅金融支援機構職員、融資書類を捏造…停職に 03/09/11(読売新聞)
国土交通省所管の独立行政法人「住宅金融支援機構」(東京)は9日、まちづくり推進部の男性職員(42)が今年2月、顧客に渡す「融資予約通知書」を捏造(ねつぞう)していたと発表した。
同機構は同日付で、この職員を停職2か月としたほか、上司にあたる40歳代の女性管理職について監督責任を問い、戒告とする懲戒処分を行った。
同機構によると、職員は昨年9月、顧客から融資審査の申し込みを受けたが、関係書類が不足して審査が出来ないにもかかわらず、顧客に告げずに放置。顧客から融資の可否について頻繁に問い合わせを受けるのに困り、上司の決裁を受けずに勝手に通知書を作成し、渡したという。融資保証会社が同機構に照会し、発覚した。
5社サッシ防火基準外、全国で3万棟使用 03/09/11(読売新聞)
国土交通省は9日、「YKK AP」(東京)、「新日軽」(同)、「不二サッシ」(神奈川)の3社が販売し、計約1万3000棟で使用されているアルミサッシが、建築基準法で定める防火基準を満たしていなかったと発表した。
この問題では、大手サッシメーカーの「トステム」(東京)、「三協立山アルミ」(富山)のサッシも基準外だったことがすでに判明。同省によると、5社が販売したサッシを使用した住宅は全国で計約3万棟に上るという。
このサッシは、火災時の延焼を防ぐために家屋の内外から高熱を受けても20分間、窓ガラスが脱落しないという基準が設定されているが、3社のサッシは7~12分間で脱落してしまったという。
薬販売試験:全柔協組合員らが不正出願 実務経験水増し 03/09/11(朝日新聞)
改正薬事法で新設された一般用医薬品の登録販売者試験で「全国柔整鍼灸(しんきゅう)協同組合」(全柔協、大阪市)の組合員や家族が10年5~9月、受験資格として必要な実務従事時間を水増しした書類を提出していたことが分かった。調査した大阪府と奈良県が把握しただけで15人が13都府県に提出した計40通が虚偽の内容と判明、合格者を含む全員の受験資格を無効とした。厚生労働省は業務記録が組織的に偽造された疑いがあるとみて、出願した他の組合員ら270人についても関係42都道府県に調査を指示した。【坂本智尚、蓬田正志】
登録販売者の受験資格は、厚労省医薬食品局長通知で定められている。高卒者の場合、薬剤師や登録販売者の指導・管理の下で1年以上(毎月80時間以上)医薬品販売に従事した実務経験が必要で、出願時に医薬品販売業者などが発行した実務経験証明書を提出しなければならない。
関係者によると、組合員らは全柔協の仲介で家庭置き薬の販売業者「日本配薬」(東京都杉並区)と請負契約を締結。自分で置き薬販売などの実務に当たった時間を業務記録に書き、全柔協に送付した。
日本配薬は全柔協から受け取った業務記録を基に実務経験時間を把握し、組合員ら285人に計650通の証明書を発行した。
全柔協は業務記録の記載内容をチェックしていたといい、組合員の一人は「従事時間が不足した場合は『棚整理や薬の陳列の仕事をしたことにして時間を増やせばよい』とアドバイスされた」と話す。
こうした不正の情報提供を受けた大阪府と奈良県が一部組合員の業務記録を日本配薬に提出させ調べたところ、顧客を午前0時に訪問していたり、毎月同じ日時に訪問しているなどの不審点が発覚。「訪問先」と記載された顧客に確認した結果、実際には訪問していないなどの不正を確認した。
このため、奈良県は合格者4人を含む7人、大阪府は13人(うち5人は奈良県も併願)の願書を各受験者に取り下げさせた。
全柔協は厚労省の認可団体で組合員数約3000人。主に近畿地区で開業する柔道整復師や鍼灸師が加入している。
岸野雅方理事長は毎日新聞の取材に「コメントは一切拒否する」と話した。日本配薬の社長(64)は「全柔協幹部から09年3月に提携話が持ち込まれた。組合員の実務を管理すべき立場でありながらチェックせず証明書を発行したことは弁解の余地がない。責任を感じている」と話している。
【ことば】一般用医薬品の登録販売者 09年6月施行の改正薬事法で創設された資格。副作用のリスクで分類した1~3類の薬のうち、種類数で9割以上を占める2、3類を販売できる。試験は国のガイドラインに基づき、都道府県が08年度から実施。10年12月までの3年間で17万1689人が受験し、6割近い9万7033人が合格した。
◇法施行経過措置を悪用
「(全柔協組合員らの不正出願は)氷山の一角。特に置き薬の販売は外回りなのでチェックが難しく、実務経験の虚偽申告は薬事法改正前から必ず起こると声を上げていた。制度を作った厚生労働省にも責任がある」。全日本医薬品登録販売者協会の岩元龍治会長はそう指摘する。
厚労省は改正薬事法の施行後3年間の「経過措置」として、置き薬の販売業者に雇われた人は登録販売者の資格がなくても1人で販売業務ができるようにしたうえ、この時間を受験資格の実務経験とみなすことにした。今回の不正はこの経過措置が悪用された形だ。
内部資料によると、全柔協の岸野理事長は09年7月に大阪市で開いた講習会で「チャンスはこの2、3年だ」とアピール。12年5月末の経過措置期限までに受験資格を得るよう組合員に呼びかけていた。複数の組合員によると、全柔協は09年4月~昨年8月ごろ、組合報などでも「登録販売者の資格を取れば、薬を扱えるようになり、患者への総合診療が可能」「鎮痛剤や漢方薬も使える」と、登録販売者にも許されていない薬の処方行為が可能かのように宣伝。組合員約400人が受験を希望し、置き薬が入った薬箱50組の購入費用や試験対策セミナーの受講料などとして、1人20万~40万円を全柔協に納めたという。
海砂採取組合に罰金命令、1.3億円脱税認定 佐賀地裁 03/07/11(朝日新聞)
佐賀、福岡両県の沖合で海砂を採取、販売する唐津湾海区砂採取協同組合(佐賀県唐津市、三浦重徳代表理事)と同組合の三浦光則・元総務兼経理担当部長(53)が法人税法違反の罪に問われた脱税事件の判決公判が7日、佐賀地裁であった。若宮利信裁判長は組合に罰金3200万円(求刑罰金4千万円)、三浦元部長に懲役1年6カ月執行猶予4年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
判決によると、組合は砂の販売代金などの売り上げから一部を除外して所得を過少申告。2008年3月期までの3年間に約5億8千万円の所得を隠し、法人税約1億3千万円を脱税した。若宮裁判長は「脱税額は多額で申告納税制度を揺るがしかねない」と述べた。
判決は脱税の手口として、採取した海砂を別の業者に販売する際、砂に含まれる水分や貝殻などの重量分として代金から差し引く商慣習や、他県の業者のチャーター船を使った取引を悪用したと認定。「犯行は計画的で巧妙、悪質。組合の経営、監査体制に不備があった」と指摘した。
組合の脱税事件をめぐっては、昨年3月に福岡国税局が佐賀地検に告発。県の認可量を超えた違法採取の有無について注目が集まったが、公判では明らかにならなかった。
雇用創出事業めぐり不適正経理か NPOに立ち入り検査 (1/2ページ)
(2/2ページ)03/06/10(朝日新聞)
総務省の雇用創出事業をめぐり、交付金の支給決定先で不適正経理の疑いが浮上し、同省が立ち入り検査をしていたことが分かった。同省は近く、外部の弁護士らによる調査チームを立ち上げ、これ以外にも事業37件、計約27億円の交付決定先を調べる異例の対応をとることを決めた。
立ち入り検査を受けたのは、東京都内の特定非営利活動法人(NPO法人)。交付金の支給が決まったこのNPO法人で不適正な経理が行われている疑いがあるとの情報を得たため、総務省は今月、補助金適正化法にもとづく初の立ち入り検査を実施した。
この事業は、情報通信技術(ICT)を使って地域の公共サービス向上や雇用創出を図る狙いの「ICTふるさと元気事業」。同省は昨年5月、企業、NPO法人などが提案した事業59件に対し、計約47億円を交付することを決定した。このうち立ち入り検査を受けたNPO法人への交付金は7900万円。同省は今年1月、法人側から事業の実績報告書や経費精算の書類の提出を受け、今月末までに交付金を支払う予定だった。
同省は立ち入り検査などの結果から、このNPO法人の請求経費は実際より高い疑いがあり、システム開発などでNPO法人が法人役員の経営企業に再委託していることも問題だとみている。
これとは別に、同省は、地方自治体の事業を除く約27億円の交付決定先37件についても、不適正な経理処理がないか調べる方針を決定。弁護士や公認会計士、コンピューターシステム専門家らのチームに調査してもらう。
同省の立ち入り検査を受けたNPO法人理事は「総務省からは『金額が適正ではないのでは』と言われている。立ち上げたばかりのNPO法人のため、事務員もいないので足りないところはあるが、やっている内容に問題はないと思っている」と話している。
元会計検査院局長の有川博・日大教授は「交付決定先が提出する経費の領収書などのチェックは、国側の時間も人手も制限されるため、十分に手が回らない可能性がある。今回、全体的に調査するのは、不正防止のシステム作りが拙速だった疑いもある」と指摘している。
野球賭博の捜査終結 書類送検力士らは36人に 警視庁 03/04/11(朝日新聞)
大相撲の野球賭博事件をめぐり、警視庁は3日、力士ら26人を賭博容疑で、胴元の執行(しぎょう)稔スポーツトレーナー(43)を賭博開帳図利(とり)容疑で書類送検した。胴元側として逮捕、起訴された元幕下力士・山本俊作被告(35)ら3人も賭博開帳図利容疑で追送検した。
ただ、いずれも賭け金の動きなどを裏付ける証拠に乏しいとして警視庁は東京地検に処罰を求める意見を付けておらず、不起訴になる見通しだ。元大関琴光喜関への恐喝を契機に昨年5月に表面化した野球賭博をめぐる捜査はこれで終結。一連の捜査による逮捕者は元幕下力士・古市満朝被告(38)ら8人に上り、書類送検された親方や力士らは36人となった。
2009~10年に力士らが賭けの対象にした試合は1542試合にのぼったという。
今回書類送検された力士ら26人は、山本被告、元十両力士・古市貞秀被告(35)、執行トレーナーをそれぞれ胴元とする3ルートの賭博客。08~10年に開催されたプロ野球や高校野球の試合を対象に賭け金を払った疑いがある。
山本被告の追送検容疑は08年5~11月、元琴光喜ら6人から賭け金を集めたというもの。古市被告と母親の古市米子被告(64)は08年3月~09年9月、豪栄道関ら7人から、トレーナーは09年3月~10年5月、豊ノ島関ら13人から賭け金を集めた疑いがある。
山本被告は山口組弘道会系組長側との間で数千万円のやりとりがあったことが確認されたが、組長が死亡していることなどから暴力団側の立件には至らなかった。
捜査過程で、力士らの携帯電話のメールから、相撲賭博疑惑や八百長問題が発覚。警視庁は、相撲賭博は証拠が少ないため立件を見送った。八百長については犯罪に当たらないとして、捜査対象にならなかった。
看護記録虚偽記載…コピペで5000件水増し? 02/27/11(読売新聞)
大阪府東大阪市の医療法人「聖和錦秀会」が運営する訪問看護事業所「すみれ草」で、訪問先の患者の容体を記載することを義務付けた看護記録がなかったり、虚偽の内容が記載されていたりするケースが5000件以上あることが読売新聞の取材でわかった。
通常、レセプト(診療報酬明細書)は看護記録を基に作成されなければならず、大阪府は「療養費」の不正請求の疑いがあるとして近く監査を行う方針。
聖和錦秀会によると、虚偽記載をしていたのは事業所の責任者を務める看護師ら。同法人は読売新聞の取材に対し、実際に訪問していないのに行ったように装って療養費を請求したケースがあったことを認め、「調査委員会を設置し、療養費の返還も検討する」としている。厚生労働省によると、訪問看護の療養費を巡る不正請求が発覚するのは初めてという。
同法人によると、患者宅を訪問した看護師たちは、体温や血圧などを測ったり、質問したりして、体調を確認。看護記録として事業所内のパソコンで入力、保存することになっている。
ところが、読売新聞が入手した記録によると、訪問したはずの日の記録が白紙のものや、毎回、患者の体温や会話内容が全く同じだったものが大量にあった。
本紙の取材に、法人側は「看護師のうち3人が『パソコンでコピー&ペーストした』と認めた」としている。
“クロ”親方に退職金、力士には給料 ズレてる相撲協会 02/26/11(読売新聞)
ここまでくると、あきれてものも言えない。日本相撲協会が、自ら八百長への関与を認めている竹縄親方(35)=元幕内春日錦=へ、1500万円もの養老金(退職金)を支給していたというのだ。同親方は今年1月の初場所限りで力士を引退。額は明らかになっていないが、相撲協会の寄付行為の規定で計算すると1571万円にも上るという。(夕刊フジ)
放駒理事長(63)は「力士を辞めた時点で支払った。その後にこの(八百長)問題が出た」とし、問題なしを強調する。しかし、竹縄親方は現役時代の昨年の春、夏場所での八百長関与を認めており、八百長含みのキャリアに対して退職金が支払われた格好だ。
規定では除名(解雇)処分を受けた者に対しては退職金は支払われない。同じく関与を認めている十両千代白鵬(27)らが今後、除名となった場合には支払われず、竹縄親方のみが“辞め得”となる。
また25日は、八百長問題発覚後、最初の給与支給日。特別調査委員会が八百長関与を認定した十両千代白鵬(27)と清瀬海(26)、竹縄親方の3人からは相撲協会に対し、受け取りを辞退する連絡はなかったという。
十両力士の月給は103万6000円で、年寄は80万8000円。八百長力士に多額の退職金・月給を支払う協会、クロと認定されながらそれを受け取る力士。相撲界に世間の常識は通用しないようだ。
さらに特別調査委員会による疑惑の14人の携帯電話の調査で、未提出組の4人のうち2人は八百長問題が発覚した今月2日に紛失や機種変更をしたと証言したという。
1人は日本相撲協会から事情聴取を受けた2日に紛失。1人は2日に機種を変更し、古い電話機を「ゴミとして処分した」という。未提出組の他の1人も1月下旬か2月上旬に変えたと説明。誰の目にも“証拠隠滅”としか映らない。
それに対し、特別調査委員会は変更した新しい電話機の提出を促すというが、意味がないのは明白だ。
相撲界には“存亡の危機”は感じられない。
氷見ブリ偽装:「氷山の一角」の指摘も 関係者の話を検証 02/21/11(読売新聞)
富山県警による捜査が続くブリ産地偽装事件。関係者を取材していると、意外なことに「石川県産のブリは以前から『氷見ブリ』と扱われてきた」などという話をよく耳にする。なぜそのような声が上がるのか。関係者の話を検証した。【大森治幸、小林祥晃】
◇七尾産も氷見ブリ
富山県の氷見漁協は「どこで取れたブリを『氷見ブリ』と呼ぶかを定めた明確な規定は、これまでなかった」としている。しかし、氷見市で仲買人らに取材すると、石川県七尾市沖の定置網でとれたブリのうち、氷見市との境界線に極めて近い場所で取れたものは『氷見産』として取り扱われているという。これは仲買人の間では共通認識のようだ。
関係者によると、トラック輸送が盛んでなかった数十年前、境界線のすぐ北側の定置網でとれるブリは、船で直接氷見港に運んでいた歴史がある。それが仲買人の「共通認識」につながっているとみられる。
◇「沖締め」も特徴
仲買人や漁業関係者が「氷見産」と認めるには、もう一つ条件を満たす必要があるという。それは「沖締め」と呼ばれる水揚げ方法だ。
氷見沖の定置網でブリを取る漁師は、船倉に氷を積んで海に出る。沖に着くと海水を加えてシャーベット状にし、引き揚げたブリをその中に放り込む。そうすることでブリは新鮮なまま港に運ばれる。これが沖締めだ。
ブリは水温8度以下では気絶して仮死状態になる。この状態では意識はないが細胞は生きているので、身の劣化を遅らせることができる。また魚が移動によるストレスを感じないので、体内に疲労物質の乳酸がたまらない。これらを両立する沖締めは、鮮度を保つには最適なのだ。
氷見では伝統的にこの漁法でブリを取ってきた。これが「他県産に比べ品質が良い」という評価につながっている。
◇チェックの仕組み不可欠
しかし、これらの共通認識や定義は明文化されたり、広く世間に公表されたりしてはいない。仲間内でしか通用しない暗黙のルールは、守られているうちは良いが、崩れ始めると歯止めが利かなくなる。実際、近年はこれらのルールは形骸化し、浅吉は氷山の一角だったとの指摘も多い。
ある仲買人は取材に対し「多かれ少なかれ、みんな(浅吉と)同じようなことをやっている」と答えた。「浅吉は度を超していた」と話す関係者もいる。能登半島の宇出津港(石川県能登町)では、漁業関係者が「数年前まで、宇出津港に揚がったブリも氷見に運ばれ氷見産として出荷された」と証言。毎日新聞に寄せられた読者のメールには「山陰地方に住んでいた時『ブリを富山に運べば高値がつく』と聞いた」と書かれていた。
事件を受け、氷見漁協などは来季までに「氷見産」の定義を明確にし、商標登録する方針だ。消費者に分かりやすい基準を作り、公表することは再発防止の第一歩だが、違反がないか、業界内部でチェックする仕組みづくりも不可欠だろう。
==============
■メモ
◇ブリ産地偽装事件
富山県氷見市の水産物仲卸業者「浅吉」が昨年12月、福井県産ブリを「氷見産」などと偽って東京・築地市場などに出荷。富山県がJAS(日本農林規格)法に基づき改善を指示し、その後、富山県警も不正競争防止法違反容疑で家宅捜索した。同社は「認識が甘かった」などと事実と異なる表示で出荷したことを認めている。
JX日鉱日石、30年間ばいじんデータねつ造 02/17/11(読売新聞)
石油元売り大手「JX日鉱日石エネルギー」(本社・東京)の水島製油所(岡山県倉敷市)が、少なくとも30年にわたって、大気汚染防止法などに定められた排ガス中のばいじん濃度測定をしていないにもかかわらず、実測したように装った虚偽のデータを、岡山県などに提出していたことがわかった。
17日、同社が県に経緯を報告した。内部調査で今月初旬、偽装報告が発覚。同社が実測したところ、同法の基準値未満だったが、過去については不明という。
同社の発表によると、偽装報告があったのは、同製油所内にある2工場のうちのA工場。液化石油ガス(LPG)を燃料として使用していた49施設で、目視によるばいじんの有無の確認しかしていないのに、試料を取ってばいじん濃度を実測したかのように基準内の数値を記入して、県などに報告していた。重油を燃料とする他の施設では実測していたという。
「『大相撲つぶれる』竹本議員が徹底調査疑問視」相撲ファンなのか相撲関係者から依頼されたのか知らないが、どのような調査を
しようがどのような結果になろうが、相撲を助けることを前提で話している人達が多くいる。下記のような記事を見ると相撲は甘やかされてきた
ことが良く理解できる。大相撲がつぶれる??今まで通りでなくとも、規模が小さくなっても相撲を存続させたい人達が少ない収入でも、
ボランティアでもがんばれば相撲は残る。それを存続できなくなるとか、つぶれるとか大げさに騒ぐのはおかしい。相撲を残したいと思う人や
相撲ファンがいれば、相撲は残る。今まで通りでないだけだ。改革を「相撲がつぶれる」と騒ぎ立て避けような方向に持っていく人達の常識を疑う!
八百長問題:「大相撲つぶれる」竹本議員が徹底調査疑問視 02/15/11(朝日新聞)
自民党の竹本直一(なおかず)衆院議員(比例近畿)が15日、自民党本部で開かれた党のスポーツ立国調査会の会合で、大相撲の八百長問題について「今の措置は非常にまずい。本当に調査すると長期化し、大相撲がつぶれてしまう」と、徹底調査に疑問を呈した。
竹本議員は八百長問題の調査について「(昨年の)尖閣諸島と同じで、先を見通した対応ができていない。自民政権の時は中国船を追い返すだけだったが、逮捕したために中国のメンツが立たなくなってしまった。八百長も『過去を問わない』としてやらないと、始末がつかない」との持論を展開した。さらに「大相撲の世界は裁判所や学校の職員と違うのだから無色透明を求めても仕方ない。『明日以降、八百長をしたら厳格な処分を求める』などとしないと、大相撲が危機にひんしてしまう」と述べた。
竹本議員は大阪府出身で、自民のシャドウ・キャビネット(影の内閣)で国家公安委員長などを務める。調査会で、スポーツ基本法案の流れや来年度のスポーツ予算の説明を受けた後に、挙手して意見を述べた。【百留康隆】
「割れた強化ガラスは一般的なガラスの数倍の強度があるといい、民間検査機関の強度試験をパスしていた。」
ジャパネットたかた(長崎県佐世保市)は民間検査機関の名前を公表するべきだ。中国では検査に問題があってもお金次第で合格証明書を出す。
世界中で騙された人達は事実を知っている。
ジャパネット販売TV台、ガラス破損66件 経産省調査 02/16/11(朝日新聞)
通信販売大手のジャパネットたかた(長崎県佐世保市)が2005年12月~09年2月に販売したテレビ台の天板や棚板の強化ガラスが突然割れる事故が、全国で66件起きていることがわかった。この期間に販売されたテレビ台は約47万台という。経済産業省は15日、同社の高田明社長から事情を聴くなど調査を始めた。
同社と大阪市内の輸入業者は先月、66件の事故について経産省所管の独立行政法人・製品評価技術基盤機構(NITE〈ナイト〉)にまとめて報告した。報告などによると、事故は発売2カ月後の06年2月から起こり、09年に急増して計40件に。同年2月に販売を終えてからも続き、10年には26件発生した。その一方で、同社は事故の発生をテレビ台の購入者に伝えていなかったという。
同社によると、問題のテレビ台は台湾製と中国製の2種類で、テレビとセットで販売された。割れた強化ガラスは一般的なガラスの数倍の強度があるといい、民間検査機関の強度試験をパスしていた。だが突然、粒状に割れる事故が台湾製で41件、中国製で25件発生。けが人はいないが、テレビが台から落ちて「テレビやDVDプレーヤー、床に傷が付いた」などの苦情が寄せられていたという。
NITEによると、強化ガラスが突然割れる事故はこの10年間にテーブルや鍋ぶたなどでも計約100件報告されており、「ガラスに残った不純物が膨張して割れるケースが多い」という。経産省は今回のテレビ台について、事故件数が多いことから調査に踏み切った。同社は今後、購入者に注意を呼びかけるとともに、リコール(回収・交換など)についても検討する、としている。
同社は86年設立で、従業員はパートらを含み約500人。09年12月期の売上高は1491億円。テレビの生放送で高田社長が実演販売するなどして業績を伸ばしている。(茂木克信)
「同委員長は『八百長は認定するのが難しい。昔は人情相撲などはあったと思うよ』と私見を述べ
『私の推測では国民の約3割は相撲を楽しみにしている。大相撲を存続させるためにも夏場所は絶対開催しなくてはいけない』と強い口調で話した。」
約3割の国民のために税金が使われているのか??杉山邦博氏は相撲ファンだけを考慮して発言しているが、相撲ファン以外の人達を無視するのか??
だったら国民の税金を使う必要はない??宗教的な事も重要であるなら信者や関係者だけでやればよい。歴史があるについても同じだ。
相撲ファンだけが決める問題じゃないと思う。
大相撲:横審・鶴田委員長「夏場所は絶対開催しなくては…」 02/14/11 (読売新聞)
横綱審議委員会の鶴田卓彦委員長が、3月にも臨時の会合を招集することを明かした。「2、3日前に協会から(八百長問題の)報告を受けた。現状では静観するしかないが、委員の間でも心配している人がいる。ひと段落ついたら集まることになる」と明言。横審は横綱に関する答申を行う機関だが、会合では協会へのアドバイスや意見などを話し合うもよう。
同委員長は「八百長は認定するのが難しい。昔は人情相撲などはあったと思うよ」と私見を述べ「私の推測では国民の約3割は相撲を楽しみにしている。大相撲を存続させるためにも夏場所は絶対開催しなくてはいけない」と強い口調で話した。(スポニチ)
ビール製造鍋・避妊具… 阪大教授、謎の研究費不正使用 (1/2ページ)
(2/2ページ) 02/11/11(朝日新聞)
ビール製造用の大型鍋、遊興用の避妊具……。4千万円を超す研究費の不正使用が判明した大阪大の研究室の支出のなかには、適正な購入と認められたものの、不可解な物品も数々ある。この研究室の教授だった森本兼曩(かねひさ)特任教授(64)は大阪大の調査委員会に対し、研究や教育目的だったと説明。調査委は「自由な発想のもとでの研究には必要」としている。
研究室の倉庫として使われている冷温室。新品の大型鍋三つ、ビールの原料の麦、瓶詰用のふたなどが入った段ボールが置かれている。
鍋はいずれも2008年2月、森本特任教授が文科省の科研費で栃木県の業者から計19万9500円で購入した。業者によると、ビール製造用の特注品。研究室が提出した書類には「研究で必要なため購入」と記されていた。
しかし、当時の研究室関係者は「ビールの製造を指示された。森本先生の趣味で、研究とは無関係だった」と証言する。その前年、森本特任教授の指示で研究員らが実験室で別の鍋を使ってビールを醸造し、森本特任教授と研究員が学内で飲んだと語る。瓶につめ、世話になった人たちに贈ったという。国税庁によると、酒造には免許が必要で酒税法違反の疑いもある。
その後、研究室で本格的にビールを製造するため鍋を購入したが、ビールづくりを担当していた人が研究室を辞めたこともあり、鍋は使われないまま放置されているという。森本特任教授は調査委に、「森林から出る化学物質を調べ、健康飲料をつくるため」と説明したという。
04年8月には、研究室の運営費交付金を使い、「パロディーコンドーム」「キングバナナ」などの遊興用避妊具96個を計4万2151円で購入していた。若者の性感染症予防策を学ぶため、実習で学生らが神戸市内の店舗で購入したという。これらの避妊具は行方不明という。
環境医学を専門とする森本特任教授の研究とは直接関係ないとみられる書籍も多数購入。「オサマ・ビン・ラディン発言」「近代ヤクザ肯定論」など。森本特任教授が定年になる直前、定年退職を控えた官僚を主人公にした浅田次郎氏の小説「ハッピー・リタイアメント」を買った。
研究費は大学の経理部局で管理。研究室からの届け出を、経理部局が書面の不備がないことを確認して支出する。大学の経理責任者は「研究費執行の権限は教授にある。教授が研究に必要だといえば支払わざるを得ない」。森本特任教授は「研究費の支出は研究室の会計責任者にまかせている」と話す。(坪谷英紀、木村俊介)
研究費流用4176万円、阪大元教授刑事告訴へ 02/11/11 (読売新聞)
大阪大学の調査委員会は、同大大学院の医学系研究科研究室で、国などの研究費4176万円が不正に使用されたとする最終調査結果を公表した。
うち約452万円が、この研究室にいた森本兼曩元教授の家族の米国旅行費などに私的流用されたと認定した。森本元教授は3900万円を返還しているが、阪大は詐欺容疑で刑事告訴する方針。
報告書によると、この研究室では2004~10年に総額約1690万円に上る国内のカラ出張や大学への申告内容と違う出張があった。パソコンなどの物品購入名目で約1593万円の架空伝票も作成された。
さらに、同時期に所属していた研究員や秘書、技術補佐員5人全員の給与のうち378万円を研究室に納めさせていた。
下記のような学校は専門学校は氷山の一角だろう。「同校は生徒数160人で生徒全員が中国やバングラデシュなど外国人。日本人の学生はいなかったという。」
これだけ大規模にやって見つからなかったという事は、偽装留学に関与している学校がたくさんいても取締りされていない可能性があると言うこと。
今回の摘発をきっかけに全国的に取締ってほしい。相撲の八百長と同じ。大規模に厳しく処分されないと続いていくだけ。
「偽装留学」で学校法人幹部らを書類送検 授業2回出席を千円で売る摘発は全国初 02/09/11 (産経新聞)
留学目的で入学した留学生の不法就労を手助けしたとして、警視庁組織犯罪対策1課は9日、入管難民法違反(資格外活動)幇(ほう)助(じょ)の疑いで、さいたま市の学校法人「村上学園大宮文化デザイン専門学校」の理事長(64)ら4人を書類送検した。偽装留学に絡み、学校法人幹部を摘発するのは全国初という。
同課によると、理事長らは学校を休みがちな留学生に対し、授業2回分の出席を1000円で売るなどして出席日数を水増し。在留許可の更新で必要な出席状況証明書を偽装して交付していた。平成20年以降、約30人の留学生から計約90万円を得たとみている。
逮捕容疑は昨年、同校に通う中国籍とバングラデシュ国籍の2人が留学目的で入国したと知りながら、授業の出席日数を水増しした出席状況証明書を交付、不法就労を手助けしたとしている。
同課によると、バングラデシュ人の留学生は同校について、「留学生の間で学校に行っていなくても出席扱いにしてもらえる学校として知られていた」と話しているという。
同校は生徒数160人で生徒全員が中国やバングラデシュなど外国人。日本人の学生はいなかったという。
氷見産ブリ偽装、詰め替え工作映像?漁協が確認 02/09/11 (読売新聞)
氷見産ブリの産地偽装問題で、氷見漁協が昨年12月中旬、水産卸会社「浅吉」(富山県氷見市)が氷見魚市場内の「活魚センター」で、福井県産ブリを氷見産ブリ用の青箱に詰め替える偽装工作をしていたとみられる同11日の防犯カメラ映像を確認していたことが8日、複数の漁協幹部らへの取材でわかった。
この映像は現在、保存期間が過ぎて消えており、その内容を巡って、富山県警が漁協幹部から事情を聞いている。漁協が早い段階で、偽装を知っていた可能性があり、同16日に東京・築地市場側から偽装疑惑を指摘された後も事実解明に消極的だった漁協の姿勢が今後、さらに問われそうだ。
複数の漁協幹部によると、昨年12月中旬、浅吉が魚市場内で他産地のブリを氷見産の箱に詰め替えているとの情報を聞き、幹部3人が防犯カメラの映像を点検した。この中には、同社が福井県内で偽装用の同県産(美浜産)を仕入れたとされた同11日の夜、従業員らが氷見魚市場内の活魚センターにトラックで入り、フォークリフトに乗るなどしている作業の様子が映っていた。同日の箱の詰め替え作業を巡っては、県警が強制捜査に入った先月27日、同センター周辺で同社の森谷貞夫代表取締役の立ち会いのもと、現場を調べていた。
漁協幹部は、この内容を森本太郎組合長に報告。昨年12月16日には、築地市場の都水産物卸売業者協会などから、氷見産ブリに産地偽装の疑いがあるとして漁協へ調査要請があり、森本組合長らは森谷代表取締役を漁協に呼び、防犯カメラの映像の話をしながら事情を聞いたが、森谷代表は否定も肯定もしなかったという。
このあと、同25日に漁協の広瀬達之参事らが築地市場の同協会を訪ね、「偽装について調べたが、分からなかった」と報告。同協会の小山利夫専務理事は、読売新聞の取材に、「漁協から防犯カメラの話は一切聞いていない」と話している。
漁協幹部の一人は、「防犯カメラの映像は見たが、浅吉が偽装をしているという確信までは持てなかった。偽装を知っていて隠していたということはない」としている。森本組合長は、読売新聞の取材に、「捜査中の件なので、お答えできない」としている。
浅吉を巡っては、福井県で水揚げされたブリ900本以上を、氷見産などと産地を偽って1都7県で販売したとして、富山県が先月25日、日本農林規格(JAS)法に基づいて改善を指示し、名前を公表。県警も同27日、不正競争防止法違反(虚偽表示)の疑いで、同社の事務所など関係先を家宅捜索し、森谷代表から任意で事情を聞くなどしている。
協会は調査能力及び監督能力がない。力士達は協力しない。相撲を選んだことは自己責任。相撲だけが特別じゃない。
力士が自分達の首を絞めるのであればそれも自己責任。八百長を行っていない力士に迷惑をかけるのも個々の判断。
相撲を選んだ。運悪く今回の事件が発覚し、困っている。テレビでは相撲ファンだけにアピールしているが、相撲ファンのためだけに
税金が使われていると思っているのか??考え方自体が間違っているだろう!存続したいなら、協会も力士達も真剣に取り組むべきだ。
大相撲:八百長問題 春場所中止 「部屋経費」どうなる 力士・師匠、広がる戸惑い 02/08/11 (毎日新聞 東京朝刊)
大相撲春場所の開催中止決定から一夜明けた7日、各相撲部屋では、けいこが通常通り行われた。横綱・白鵬が所属する宮城野部屋では朝げいこがあったが、「見学お断り」の張り紙が掲示された。宮城野親方(元前頭・竹葉山)によると、白鵬は朝げいこを休んだという。【大矢伸一、飯山太郎、町田徳丈】
また、東京・両国国技館には、定期健康診断を受ける一部の部屋の力士たちが訪れた。先の初場所で10年九州場所に続き、2場所連続で白鵬を破った関脇・稀勢の里(鳴戸部屋)は取り囲む報道陣の問い掛けに、一言「残念です」と話して口を結んだ。
土俵生活19年のベテラン、モンゴル出身の幕内・旭天鵬(大島部屋)は「本場所があるのが当たり前だった。何に向けてけいこすればいいのか」と戸惑いを隠せない様子。十両・佐田の富士(境川部屋)は「昨日(6日)、師匠から説明があった。けいこするのが仕事ですから、頑張ってけいこするしかない」と悲壮感を漂わせた。
一方、「本場所無期限中止」の衝撃は、力士だけでなく相撲部屋で弟子を預かる師匠(部屋持ち親方)も直撃した。師匠には、部屋の維持経費や力士らを養うための経費が、日本相撲協会から支給されている。本場所ごとに支給される規定になっているため、開催中止は波紋を広げそうだ。
協会から支給される主な経費には、相撲部屋維持費、けいこ場経費、けいこ場補助費があり、力士10人の部屋で計算すると、地方場所の場合、この三つの経費だけで220万円になる。師匠は支給された経費を弟子の食費や部屋・地方宿舎の光熱費や賃貸料などに充てている。
湊部屋の師匠、湊親方(元前頭・湊富士)は「本場所がないとどうなるのかというのが一番の心配だが、(経費は)出てもらわないと。毎日生活しているものですから、出ないと困る」と話していた。
==============
◇1場所に支給される主な経費◇
相撲部屋維持費 ※11万5000円
けいこ場経費 ※ 5万5000円
けいこ場補助費(東京) 30万円
けいこ場補助費(地方) 50万円
※力士1人当たり
協会は調査能力及び監督能力がないという事で、公益法人
に認めないと言う事で終わりにすればよい。力士ら協会の調査に非協力的であること自体、彼らが所属する協会に税金を注ぎ込む必要がない理由だ。
相撲ファンがいれば規模は小さくなっても続けていける。相撲を続けたい人達次第だ。力士や協会は相撲ファンだけにアピールだけすればよい。
景気低迷で解散する実業団チームもある。存続出来るかはファン次第。それで良いのではないか!
「携帯電話壊した」「機種変更した」 力士ら協会の調査に非協力的 02/07/11 (産経新聞)
大相撲の力士らの携帯電話に、八百長相撲への関与が疑われるメールの記録があった問題で、力士らが日本相撲協会の調査に協力せず、携帯電話の提出も「壊した」などと応じていないことが、分かった。7日、協会の放駒理事長から報告を受けた文部科学省が明らかにした。
一連の八百長問題は、警視庁が押収した力士ら2人の携帯電話メール記録が、文科省に提供されて表面化。これまでに計14人が関与した疑惑が明らかになっており、協会の特別調査委員会は、事情聴取や2人以外の携帯電話提出を要求するなどして調査を続けている。
協会の報告を受けた文科省によると、力士らは調査に協力的な姿勢を見せない上、中には当時使っていた携帯電話提出にも応じず、「壊してしまっている」「機種を変更してしまった」と弁解した者もいた。
こうした姿勢が、調査が遅れる原因となっているという。
前副学長の言いなりで経理処理…富山大不正受給 02/06/11 (読売新聞)
富山大の小林正・前副学長兼付属病院長が厚生労働省の研究費補助金を不正受給していた問題で、受給条件を満たしているかを調べる大学の経理事務が小林氏の言いなりに処理され、チェック機能を果たしていなかったことが、同大への取材でわかった。
補助金対象となっていた糖尿病患者に関するデータベース用ソフトは、まったく動かない代物だったのに大学側が小林氏に任せきりで、調べずに完成品として受け取っていたことも判明。大学側のずさんな管理体制も浮き彫りになっている。
4日に開かれた記者会見では、西頭徳三学長は、国からの補助金など外部資金の経理事務では担当職員を置いているとしていた。しかし、大学関係者によると、実際は研究の中身を十分に理解できないため、研究責任者である小林氏の指示通りに、書類作りなどの対応をしていたという。
また、問題となったデータベース用ソフトについて、小林氏は、動かないことを知りながら完成品として、補助金を受け取るためのうその書類を提出し、大学側も通していた。西頭学長は同日の記者会見でも、「専門的になると、どんなソフトか、(他人は)ほとんど口出しできない状態」とし、事務担当者のチェックの難しさを認めていた。
小林氏は2006年度、全国の病院から糖尿病の症例を1万件集めてデータベース化するため、厚労省の厚生労働科学研究費補助金を活用して、2つの研究ソフトの開発などを、都内にあるそれぞれ別の業者に発注した。
07年度には、この補助金で研究を病院にPRするガイド本を3000冊制作する予定だったが、市販の糖尿病に関する本の表紙を取り換えただけのダミー本を1冊作り、補助金を不正に受け取っていた。研究ソフトは08~09年度に完成し、ガイド本も09年度には作成されたが、補助金の不正受給は06~08年度の計約4700万円に上った。
この問題は、09年5月に同省生活習慣病対策室から「補助金の不正経理に関する告発があり、調査してほしい」と指摘されて発覚。小林氏は今月4日付で諭旨解雇となった。
発覚から処分・公表までに1年9か月も経過していることについて、西頭学長は学内に設けた調査委員会を19回開き、小林氏や関係者らから事情を聞いていたほか、厚労省でも調査を進めていたことなどを理由に挙げた。小林氏がソフトを開発した業者などから、あっせんを受けた事実や私的流用はなかったとして、刑事告訴は見送っている。
「触って安全バー確認」仕様書に明記 コースター事故 02/07/11 (朝日新聞)
東京都文京区の遊園地「東京ドームシティアトラクションズ」のコースターから東京都羽村市の会社員倉野内史明さん(34)が転落、死亡した事故で、安全バーがきちんとかかっているか手で触って確認するよう、コースターの輸入元の仕様書に明記されていたことが警視庁への取材でわかった。
施設側は2000年3月の納入時に仕様書を受け取ったが、マニュアル類に明文化していなかったとみられ、従業員への指導も徹底していなかったとされる。6日で事故から1週間。警視庁は、施設側の安全管理に問題があったとの見方を強めている。
捜査1課によると、倉野内さんは「スピニングコースター舞姫」が発車してまもなく、体が安全バーとともに前後に揺れていたといい、初めから安全バーはロックされていなかったとみられる。
当時担当していたアルバイトの大学生は警視庁の事情聴取に「必ず手で押すように、との指導は受けていない」と説明。同様の説明をしているほかの従業員もいるという。
捜査権がないことを理由にまともな調査が出来ないのなら法人認可取り消して、自由させるべきだ。
政府には財政問題を抱えている。消費税を上げると言っている。問題を解決できない組織になぜ税金を注ぎ込むのか???
理解できない。いろいろなしがらみがあるから高木義明文部科学相は協会の法人認可取り消しは言及避けたのだろうが、
はっきり物を言えない文部科学相は日本相撲協会と同じ体質の組織トップとも思える。民主党は長く続きそうもないし、
長く続けてもらっても困る。相撲協会と同じだ。ピリオドを打たないといけない。
文科相、総理大臣杯の辞退を示唆 協会の法人認可取り消しは言及避ける 02/04/11 (産経新聞)
大相撲の力士らの携帯電話に八百長に関与したとみられるメールの記録が残っていた問題で、高木義明文部科学相は4日の定例会見で、本場所で行われている内閣総理大臣杯の授与に触れ、「(昨年の)名古屋場所で辞退したという経緯もある」と述べ、日本相撲協会の辞退に言及した。
ただ、実際に辞退を求めるかについては、「(協会の)調査結果を見てから」と明言を避けた。
協会の公益法人認可取り消しについては、「一般論では組織的な不祥事があり、解決が困難である場合」という条件をあげたが、「まずは(協会の)報告を聞いてから」とし、今後の方針については言及を避けた。
また、同日朝の閣僚懇談会で、公益法人改革を担当する蓮舫行政刷新担当相が「『認可取り消し』という言葉が出ているが、とらざるを得ない手続きがあり、すぐにでも取り消されるという誤解が生じてはいけない」と発言したことも明かした。
総理大臣杯については、菅直人首相が授与見送りを検討している。
クローズアップ2011:相撲協会、八百長立証難しく 迫る春場所、幕引き急ぐ 02/04/11 (毎日新聞 東京朝刊)
◇4人解雇で「けじめ」か
大相撲の八百長疑惑で3日、日本相撲協会の特別調査委員会による調査が始まった。放駒理事長(元大関・魁傑)は「徹底解明する」と約束し、28日に番付発表を控えた春場所(3月13日初日、大阪府立体育会館)へ向け調査を急ぐ。だが、調査の結果次第では、NHKの中継中止や、場所開催の是非そのものに議論が及ぶ可能性がある。
相撲協会はこれまで、八百長の存在を認めたことはない。だが、今回は野球賭博事件に絡んで押収された携帯電話のメールから、竹縄親方(元前頭・春日錦)らがやり取りした八百長を疑わせる文言が明らかになった。協会内部でも徐々に、メールのやりとりが確認された4人の解雇処分は避けられないとの声が大きくなってきた。
ある古参親方は「問題は長期化できない。あれだけのやり取りが表に出て、言い逃れはできないだろう。6日には4人の解雇処分が決まるのではないか」とみる。
協会が6日に開く臨時理事会で特別調査委員会の報告を受け、直ちに竹縄親方、十両の千代白鵬関(九重部屋)と清瀬海関(北の湖部屋)、三段目の恵那司力士(入間川部屋)の解雇処分を決め、けじめとする見方だ。
裏返せば、4人以外の八百長疑惑の立証は難しく、協会と力士間で争えば問題が長期化する、ということを意味する。4人のメールには、力士や元力士9人の名前も記載されているが、否定されれば特別調査委が覆すだけの証拠をそろえるのは簡単ではない。
実際、特別調査委の伊藤滋座長(早大特命教授)は2日の会見で今回の調査について、「大変難しいと思う。メール以外に物証がないですから」と説明した。
慎重な姿勢の背景には、昨年の野球賭博事件の経験がある。協会は特別調査委を設置して調査を進めた。しかし、週刊誌に野球賭博や裏カジノへの関与を報じられた佐ノ山親方(元大関・千代大海)については結論を導き出せず、放駒理事長も「シロでもなく、クロでもないグレー」として、厳しく指導することで幕引きせざるをえなかった。
協会の生活指導部特別委員会の外部委員として、角界の規律を保つための助言をしてきた木暮浩明・伊藤忠商事理事も「特別調査委には捜査権がない。力士が勇気と覚悟を持って正直に告白することは考えにくいので、調査は難航するのではないか」と話す。
角界内では、4人の解雇が現実的な幕引きラインと見る向きがある。だが、世論は角界に厳しい視線を向けており、玉虫色の結論では理解を得られない状況になりつつある。【大矢伸一、藤野智成】
◇開催へ高いハードル NHK放送中止も/副文科相「全容解明を」
3日開かれたNHKの定例会見。記者の質問は春場所の中継に集中した。松本正之会長は「(相撲協会の対応を)重大な関心を持って見守りたい」と話す一方で、「放送するかしないかという以前の問題」と強調。「従来(の不祥事)とは別次元の事象だ」として放送中止もありうることを示唆した。
2日から3日正午までにNHKに寄せられた大相撲に関する視聴者の声は約430件に上る。半分は「相撲が好きで見ていたが、もう許せない。しっかり追及してほしい」「相撲協会が場所開催をやめるべき問題だ。相撲界の根深い体質にがっかりした」などと、中継に否定的な意見だったという。
NHKの福地茂雄前会長は昨年7月、賭博問題に絡んで名古屋場所の中継中止を決断した。松本会長は福地前会長の判断を前提に対応を検討することを明らかにした。
そもそも春場所は開催できるのか。
「全容解明されなければ、国民の支持も得られない。どれだけ速やかに厳正公正に調査できるか、それが大前提」。鈴木寛副文部科学相は3日の会見で、開催の条件を示した。「メールは警察の捜査で発見された極めて信ぴょう性が高い証拠」として、八百長があったことを前提に調査することを求めた。協会に高いハードルを設定した形だ。
スポーツジャーナリストの二宮清純さんはさらに厳しく、「協会は過去にさかのぼって八百長の実態を調査すべきだ」と強調する。そのためには、協会が設置した特別調査委員会ではなく、所管官庁である文科省が責任を持って調査に当たるべきだと指摘。プロ野球界の「黒い霧事件」を例に、「八百長に手を出したら角界から永久追放される」という前例を作ることで、今後の抑止力にすることを求めた。
放駒理事長は、八百長疑惑が表面化した2日夕、「今は調査する段階なので、春場所うんぬんということは考えてない」とした。ただ、「やはり、すぐ大阪場所が来るので、その前には片付けたいなと思っている」と、開催へ向けて問題解決を急ぎたいという姿勢を示した。
これに対し二宮さんは「3月場所開催ありきのような話になっているが、早いと思う。今回は土俵内の問題で、相撲界の屋台骨が揺らぐ話。これまでの不祥事と同様の処分の仕方をしようとしているが、信頼を取り戻すなら時間をかけても徹底解明する必要がある。ここで真相究明を徹底しないと、角界改革と言っても誰も聞く耳持たず、それこそ『大相撲の千秋楽』になる」と警鐘を鳴らす。【内藤陽、袴田貴行】
==============
◇八百長疑惑を巡る今後の動き
5日 特別調査委員会の第2回会合でメールで名前の挙がった力士ら14人への調査結果をまとめる
6日 理事会で調査結果を報告
大相撲春場所のチケット販売開始
フジテレビ日本大相撲トーナメント(中止)
11日 NHK福祉大相撲(中止)
28日 春場所番付発表
3月13日 春場所初日
下記のような記事まで出てきた。事実を確認するべきだ。もうこうなったら
日本相撲協会
に対して
公益法人
の許可を出すのは難しいだろう。このような組織に税の優遇措置を与える必要はない。
「力士はカネでどうにでもなる」暴力団関係者の「常識」 02/03/11 (朝日新聞)
「相撲で八百長が行われているのは私らの世界では常識だ」。大相撲の取組を賭けの対象にする賭博にかかわっているという複数の暴力団関係者は、そう証言する。接近を試みた力士に普段から酒食でもてなして関係をつくり、仕掛けたい一番の前に不正を依頼する、というやり方だ。今回明らかになった疑惑の構図や動機はまだ明らかではないが、暴力団関係者らは「力士はカネでどうにでもなるというのも私らの常識」と言う。
相撲賭博は、多くの暴力団組織が「手軽な資金集め」として重宝しているという。サイコロ二つの目の合計が奇数か偶数かを賭ける「丁半ばくち」と同じように単純に力士の勝ち負けを予想するだけで、客には人気がある。
多くの場合、客からの注文取りは取組一番ごとに行い、締め切りは取組の直前までとしている。力士が四股を踏んでいるときに携帯電話で「どっちにする?」と聞く。賭けの対象は、番付最下位の序ノ口から最高位の横綱まですべての力士の取組だ。
賭け金は、1万円の客もいれば10万円張る客もいる。賭博を仕切る胴元は勝った客、負けた客の双方から賭け金の1割を取る。精算は末端の組員に担わせる。負けた客のところには回収に出向き、勝った客は組員のアパートなどに呼んで支払う。1日の取組で約300万円が動くが、胴元が損をすることはない。精算役の組員には「逮捕されても胴元の名や組織のことは絶対に明かすな」と言い含めているという。
のめり込んだ末に数百万円負ける客もいる。「何とかならないか」と胴元側に泣きついてくる。ここから八百長の仕掛けが始まる。暴力団関係者が、日頃から手なずけている力士に、客を居酒屋などで引き合わせる。客が力士に「あすは勝ってくれよ」「必ず負けろよ」と頼む。聞き入れてくれたら数十万円出す、と約束する。「簡単に応じる力士は少なくない」と暴力団関係者は話す。
一方で、別の暴力団関係者は「現役の力士からは『賭博と関係なく八百長を行うこともある』と聞いた」という。負け越しの危機に直面した力士が、地位陥落を免れるため対戦相手に負けるよう頼む。そんなことが珍しくない、と懇意の力士は明かしたという。(編集委員・緒方健二)
法人税の脱税指南容疑、名古屋国税局OBを逮捕 02/03/11 (朝日新聞)
代表取締役を務めている運送会社「刈谷配送」(愛知県知立市)の脱税を指南した疑いが強まったとして、名古屋地検特捜部は3日、名古屋国税局OBで名古屋税理士会所属の税理士・高木成典容疑者(50)(名古屋市天白区)を法人税法違反の疑いで逮捕した。高木容疑者の関係者が明らかにした。
関係者によると、高木容疑者は同社の法人税を免れるため、同社幹部らに対して架空の経費を計上するよう指示するなどし、数年間で所得約2億円を隠し、法人税を脱税した疑いが持たれている。また、同様の手口で、同社の役員らが代表を務める介護サービス会社「日本介護サービス」(同県豊田市)でも脱税を指示したという。隠した所得の一部は、高木容疑者側に渡っていたという。
高木容疑者は同国税局管内の豊田税務署を2006年に退職。その後、税理士登録していた。
税金を日本相撲協会に注ぎ込む必要なし!相撲が好きな人達は八百長でも何でも見ればよい。税金を注ぎ込むことには反対だ!
「すぐにはたかず途中で投げます」力士八百長メール発見 02/02/11 (朝日新聞)
大相撲の野球賭博事件の捜査で警視庁が力士らの携帯電話のメールを調べる中で、相撲の取組で八百長が行われていたことをうかがわせる内容のメールが見つかっていたことがわかった。昨年の3月場所と5月場所の取組で八百長が行われたとみられる内容で、勝ち星を数十万円で売買していたととれるメールも含まれているという。
警察当局は、日本相撲協会の監督官庁の文部科学省に連絡。文科省は2日、協会に対し外部の有識者でつくる協会内の委員会で調査し、結果を報告するよう求めた。協会は同日午後、東京・両国の国技館で緊急理事会を開き、対応の協議を始めた。
大相撲の八百長疑惑はこれまで週刊誌報道などでたびたび指摘されてきたが、協会側は民事裁判などで八百長の存在を一貫して否定してきた。
関係者や文科省幹部によると、メールは「今度はこちらをよろしく」「今回の取組はスムーズだったね」などといった趣旨の記述。取組相手同士で「ぶつかってその後、流れでいきましょう」「すぐにはたかないで途中で投げます」など土俵での具体的な動きを記したものもあるという。
また、「二つ貸したから一つ返してもらうよ」「○○には貸し、○○には借り」など、星の貸し借りや、星を一番数十万円で売買していたとみられる20、30、50などの数字もあった。振込先とみられる銀行口座の番号もあった。
警視庁が昨年7月、賭博事件の捜査で押収した携帯電話を解析。その結果、当時の十両春日錦(現在は春日野部屋付親方)と十両千代白鵬の携帯に八百長とうかがえるメールがあった。さらに、この2人が、十両清瀬海と三段目の恵那司とメールをやりとりしていることが判明。4人のメールの中には、八百長に関与した可能性がある力士9人(うち幕内4人)の名前があったという。メールは昨年3~6月に送受信されたという。
警察当局が文科省に説明したところでは、メールのやりとりに沿った取組結果になっていたという。
八百長自体は犯罪に当たらず、刑事事件として立件される可能性は低いとみられる。
日本相撲協会や文部科学省にまともな内部調査は期待出来ない。もう税金を日本相撲協会に注ぎ込む必要なし!
八百長相撲疑いメール、十両ら数人関与か 02/02/11 (読売新聞)
大相撲の野球賭博事件で、警視庁が昨年7月に相撲部屋の一斉捜索で押収した力士の携帯電話から、八百長相撲が行われていたことをうかがわせるメールが見つかっていたことが、捜査関係者への取材でわかった。
メールの送受信には、現役の十両力士ら数人が関与しており、金銭をやり取りしているような記述もあった。メールの内容は、警察庁を通じて日本相撲協会を所管する文部科学省に伝えられ、同省は2日、同協会に調査を指示した。同協会は、内部調査などに乗り出すとみられる。
経営状態がどのようなレベルなのか知らない。儲かっていればコスト追求と契約社員に頼るために副作用が出たのであろう。
もし儲かっていなければ閉鎖か、継続しても改善は期待できないであろう。コスト削減の結果が不運と重なって事故となって現れた。
転落死した人が標準の体格であれば、これまでと同じ事をしていても事故は起きなかっただろう。しかし、運が悪く適切なマニュアルと指示、
それを徹底させる人及び実行する人がいなかったのだろう。
コースター転落死、運行業務をバイト任せ 02/01/11 (読売新聞)
東京都文京区の遊園地「東京ドームシティアトラクションズ」で先月30日、会社員倉野内史明さん(34)が小型コースターから転落死した事故で、安全バーの固定状況を確認し、発車ボタンを押すなどの運行業務はアルバイトの女子大生に一任され、現場責任者の契約社員は監督していなかったことが、捜査関係者への取材でわかった。
警視庁は1日午前、遊園地を運営する東京ドーム社(文京区)やコースターを輸入した杉並区の遊具機器販売会社など3か所を業務上過失致死容疑で捜索、安全管理体制についても調べを進めている。
捜査関係者らによると、事故当時、コースターには現場責任者の女性契約社員と女子大生のほか、アルバイトの男女の計4人の係員がいた。アルバイトの男女は乗降口での客の誘導だけを担当。運行前のアナウンスをした後、バーの固定状況を点検し、出発ボタンを押すなどの運行業務は女子大生が一人で行っていた。
田辺三菱製薬(本社・大阪市)に管理能力がないのなら、国が処分を下すしかないだろう。まあ、行政がどこまでできるのか疑問ではあるが??
田辺三菱子会社、別の試験も未実施 注射薬めぐり担当者 (1/2ページ)
(2/2ページ) 01/26/11(朝日新聞)
田辺三菱製薬(大阪市)の子会社が品質試験をしていない医療機関向けの注射薬を出荷していた問題で、試験を怠った担当社員が2009年、注射薬の変質の有無をチェックする別の試験も実施していなかったことが分かった。田辺三菱側はこの際、未実施を把握したが、品質試験の担当を続けさせていた。
子会社「田辺三菱製薬工場」の足利工場(栃木県足利市)で新たに判明した未実施の試験は、薬の有効期間中の品質保持を確認する「安定性試験」。閉塞(へいそく)性動脈硬化症などの治療に使われる注射薬「リプル注」「パルクス注」が対象で、この試験担当社員が07~10年、この二つを含む4注射薬について品質試験の一部を実施せず、虚偽の試験結果を記録していたことが既に分かっている。パルクスは同工場が製造、大正製薬が販売している。田辺三菱と大正製薬は、法的な義務はない安定性試験を自主的に行うことを取り決めていた。
田辺三菱によると、この社員は08年3月~09年9月に安定性試験を担当。3カ月後の09年12月、一部を実施していなかったことを上司に報告した。リプル、パルクスの有効期限は14カ月で、担当社員は15カ月間の状況を調べる試験を行っていたが、12カ月後、13カ月後、14カ月後にそれぞれ実施すべき試験の一部をしていなかったという。社員は「他の仕事が多忙で、失念していた」と説明。未実施分の試験記録は白紙の状態だった。
この報告を受けた親会社の田辺三菱などは10年1月、大正製薬に連絡し、謝罪。再試験を行うことで合意した。
だが、田辺三菱側は、この社員を安定性試験の担当から外したが、処分などは行わず、今月になって未実施が発覚した注射薬の品質試験を10年3月まで担当させていた。
また、田辺三菱の土屋裕弘社長らが品質試験の未実施などを謝罪した26日の記者会見では、田辺三菱側は記者から他にも未実施の試験がなかったか問われたが、安定性試験の未実施を公表しなかった。
危機管理コンサルタントの田中辰巳さん(57)は「薬の安定性試験の未実施が発覚した時、他の試験や過去の試験を徹底的に調査し、担当社員を厳しく処分していれば、品質試験の未実施の問題もその時点で解決できたはずだ。会社の体質、マネジメントの弱さが最大の問題だ」と指摘している。
田辺三菱は「担当社員が安定性試験の一部をしていなかったのは事実」としている。(矢崎慶一、上沢博之)
氷見ブリ産地偽装、卸の「浅吉」捜索 01/27/11 (読売新聞)
福井県産ブリを富山県氷見産などと偽って販売したとして、富山県警は27日、不正競争防止法違反(虚偽表示)の疑いで、同県氷見市の水産卸会社「浅吉」と関係先を捜索した。
同社を巡っては、福井県産のブリ900本以上を、氷見産などと産地を偽って1都7県で販売したとして、富山県が25日、日本農林規格(JAS)法に基づいて改善を指示していた。
氷見漁協では、北海道沖から冬場に南下し、「天然のいけす」と呼ばれる富山湾氷見沖などの定置網で捕獲され、氷見漁港に水揚げされたものを「氷見ブリ」と呼んでおり、高値で取引されている。しかし昨年12月、東京都水産物卸売業者協会と築地市場の水産卸会社5社が、入荷量などから氷見産ブリの表示に疑問があるとして、氷見漁協などに調査を求めていた。
氷見ブリ産地偽装、卸会社認める…販路1都7県 01/26/11 (読売新聞)
氷見産ブリなどと産地偽装して東京・築地市場などで福井県産を販売していた水産卸会社「浅吉」(氷見市)に対し、富山県は25日、「悪質な行為」と県内で初めて日本農林規格(JAS)法違反での指示・公表に踏み切った。
販路は裏付けが取れただけで1都7県に及び、浅吉は「日本海産で肥えて脂身があるのを氷見ブリにした」などと偽装を認めた。全国的に知名度があり、高値がついてきた氷見ブリの信頼性が揺らぐのは必至。「地に落ちたブランドを立て直さないといけない」。同業者らは強い危機感を募らせた。
発表によると、浅吉は昨年12月13~18日、東京、栃木など1都7県の水産卸売業者計14社に対し、少なくとも900本の福井県産ブリを、氷見産や石川県産ブリとして販売。築地市場で2社に824本を氷見産として販売し、うち少なくとも445本は福井県産だった。また、同17、18日には、1都7県の12社に、石川県産と偽って少なくとも140本を販売したことも判明した。
仕入れた福井県産ブリは敦賀漁港で競り落とされたもので、通常、白い箱に入っているが、浅吉は県の調べに「氷見市の作業現場で氷見産ブリと表示のある青い箱に入れ替えて築地市場に送った」と話しているという。県農林水産部の太田清参事は25日の記者会見で、「値段も含め、氷見産なら売れるとの意識が働いたのでは」と分析し、高値で売るために偽装したとの見方を示した。
今回の指示を受け、浅吉はすべての食品の表示を点検し、社内チェック態勢を強化するなどの対策を講じ、2月25日までに書面で提出することが義務づけられた。
石井知事は25日、「偽装事件が起こったことは残念。せっかくブランド化して評価の高い氷見ブリだから、これを機に、襟を正し、氷見ブリの信用力が高まるようにしてほしい」と強調した。
田辺三菱製薬(本社・大阪市)は問題が多すぎる。組織ぐるみの隠蔽のようだ。政府は子会社を無期限の操業停止にするべきだ。
田辺三菱、また不適切試験 子会社社員が一部の薬で怠る (1/2ページ)
(2/2ページ) 01/26/11(朝日新聞)
田辺三菱製薬(本社・大阪市)の子会社が品質試験をしていない医療機関向けの注射薬を出荷していた、と社外の弁護士らによる調査チームが指摘し、田辺三菱が厚生労働省にこの調査結果を報告していたことが分かった。2007~10年3月の約3年間に試験担当社員が一部の試験を行わず、出荷の基準に合格したように虚偽の試験結果を記録した行為があったとしている。田辺三菱は、これらの指摘を「受け入れざるをえない重大な状況と認識している」と答えている。
田辺三菱と別の子会社は昨年4月、薬の承認申請で試験データを改ざんしたなどとして業務停止処分を受けた。
今回の問題で、田辺三菱側の社内調査は「試験は行われていた」としていた。だが、その後の社外の調査チームの調べに対し、試験担当社員は、試験の一部を実施しなかったことを認め、その理由を「手間がかかる」などと話した。残りの大部分の試験項目については「試験をした」などと否定したという。厚労省は、薬事法違反にあたるかどうかを判断する見通しだ。田辺三菱によると、健康被害は報告されていないという。
問題となった子会社は「田辺三菱製薬工場」(大阪市)。同社の足利工場(栃木県足利市)が製造や試験をしている医療機関向けの注射剤「リプル注」「パルクス注」「リメタゾン静注」「パズクロス点滴静注液」の4製品で、不適切試験の疑いが持たれている。
田辺三菱と同工場は昨年9月、品質管理部で4製品の試験の大半を1人で担当する社員が試験をしていない疑いがあるとの報告を受け、社内調査を実施。「本人もやったと言っているし、記録でも裏付けられた」として「試験は行われていた」と結論づけた。だが、朝日新聞が同工場社員らにこの疑いに関する取材をした後の昨年12月末から、田辺三菱は改めて、社外の赤松幸夫弁護士らによる調査チームでの再調査を開始した。
調査チームは、4製品にそれぞれ行う十数項目の試験のうち、担当社員が試験をしていない疑いが持たれた4項目の試験について調べた。
一つの試験項目は、使うべき備品の数に比べ購入量が少なかったことなどから、「全体の77%は実施していない」と判断。記録では必要な試験は行われたことになっているため、虚偽の試験結果が記入されたとみている。もう一つの項目では、機器の使用記録が3年間で1回しかなかったことなどから「試験を実施したとは思えない」とした。
調査チームは、その他の2項目についても、試験をしたとする社員の説明が「不合理で不自然」などとして、「実施しているとは思えない」との見解を示した。昨年の社内調査の結果も「肯定できない」と結論づけた。
リプル、パルクスを開発したLTTバイオファーマ(東京都)によると、リプル、パルクスは閉塞(へいそく)性動脈硬化症などの手術や治療に使われる代表的な薬。二つの薬は1988年に販売が開始され、二つとも田辺三菱製薬が製造しているが、パルクスは大正製薬が販売している。田辺三菱製薬によると、リプルの年間の売上高は約80億円。後発医薬品の影響で単価も下がってきたが、「過去のピーク時には二つの薬で約500億円の市場規模。そのころよりは落ちているが、依然として注射薬の定番」(LTT社)という。
田辺三菱は「問題なしとした社内調査は、調査のノウハウなどが不十分だった。隠蔽(いんぺい)する趣旨はなかった。今後は原因究明などの調査を続ける」としている。(矢崎慶一、上沢博之)
年金掛け金22億円不明、担当者に逮捕状 01/25/11 (読売新聞)
長野県建設業厚生年金基金で、年金の掛け金約21億9000万円が不明になっている問題で、長野県警が前事務長の男(53)(懲戒解雇)について業務上横領容疑で逮捕状を取ったことが25日、県警への取材でわかった。
県警は、長野市にある同年金基金事務所の捜索を始めた。
同年金基金によると、年金の掛け金を預ける口座から2006年6月~10年9月、30回以上にわたり約21億9000万円が無断で引き出されていた。口座を1人で管理していた前事務長は不明金疑惑が浮上すると、行方をくらましている。
捜査関係者によると、前事務長は昨年9月頃、年金基金の口座から数千万円を引き出し、着服した疑い。
同年金基金は昨年8月、運用委託先の生命保険会社から「入金額が少ない」と指摘を受け、調査を始めた。関東信越厚生局が同9月、特別監査に乗り出した。前事務長は基金の内部調査に「一部の掛け金を支部に返還していた」と説明した。
ウナギ偽装:ヨーカ堂元社員らに有罪判決 横浜地裁 01/11/11 (毎日新聞)
イトーヨーカ堂が輸入した中国産ウナギの偽装事件で、食品衛生法違反罪に問われた同社元食品事業部マネジャー、石原荘太郎被告(59)と海産物輸入販売業「高山シーフード」元社員、小池信行被告(47)に対し、横浜地裁は11日、いずれも懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡した。成川洋司裁判官は「消費者の信頼をないがしろにした計画的かつ組織的犯行」と批判した。
判決によると、両被告らはヨーカ堂が輸入したウナギ約15トンを高山シーフードの輸入と表示した箱に詰め替え、09年6~10月、計約634万円で2業者に販売した。
「偽装を直接指示していない」と主張していた石原被告に対し、成川裁判官は「ヨーカ堂の名を隠すよう依頼し、事件の発端をつくった」と指摘した。
ほかに起訴されていた高山シーフード社長の高山智広(54)、食品商社「日洋」元社員の津田裕史(56)の両被告は起訴内容を否認、公判が続いている。【高橋直純】
贈賄側7億7900万円所得隠し…眼科監査汚職 01/05/11 (読売新聞)
コンタクトレンズ(CL)診療所への監査を巡る汚職事件で、贈賄側のCL関連会社「シンワメディカル」(堺市)などグループ3社が大阪国税局の税務調査を受け、昨年2月期までの7年間に約7億7900万円の所得を隠していたことが5日、わかった。
コンサルタント料名目で診療所から毎月受け取っていた診療報酬の一部を売り上げから除外したり、架空の広告宣伝費を計上したりして所得を圧縮。同国税局は全額を重加算税の対象として追徴課税するとみられる。
隠した所得の一部が、厚生労働省の特別医療指導監査官だった住友克敏被告(50)(懲戒免職、収賄罪で公判中)への賄賂計1175万円の原資になったとされる。
関係者によると、大阪府警からの課税通報を受け、同国税局がシンワ社のほか、「アイケアステーション」(大阪市中央区)、「四国シンワメディカル」(徳島市)を調査した。
どのような判決になるのだろうか?山崎正夫被告は負ければ上告すると思われるから長期戦になると思う。
もし山崎正夫被告が勝てば、大企業であれば政治的な圧力やコネを使い、不都合な証拠は隠蔽、捜査関係者にはあめで対応することが
許される世の中である事を示すだろう。最近、検察の不祥事が注目を集めたが、裁判制度や裁判官の対応についても疑問に思うことがある。
被害者達はこのような点についても世の中の注目を得るような行動を取るべきだと思う。どの裁判官が担当するかも影響するから結果を待つしかない。
宝塚線脱線 前社長「どれほど考えても危険に気付けず」 12/21/10 (朝日新聞)
JR宝塚線脱線事故の初公判で、山崎正夫被告(67)の意見陳述の要旨は以下の通り。
JR西の経営を担っていた者として、ご遺族の皆様、おけがをされた方々にどのように謝罪させていただけばよいのか、そのすべさえ分からず、ただただ深くおわび申し上げるほかございません。
「本件曲線で脱線転覆事故が発生する危険性を認識していたにもかかわらず、経費増大を危惧して、あえてATSを設置しなかった」との検察官の指摘につきましては、事実とはまったく異なるそのような決めつけをされたことに対し、非常なるショックを覚えております。この点は、裁判で何としても潔白を明らかにしたいと存じます。
また、「部下に対し、ATSを整備するよう指示すべきであった」とのご指摘ですが、過去を真剣に振り返り、自分に落ち度はなかったのか、曲線の危険性やATS設置の必要性に気付くことができる場面は本当にどこにもなかったのかと自問自答を重ねましたが、どれほど考えをめぐらしても、それに気付くことはできなかったと申し上げざるを得ません。
この裁判において、私は、承知している事実と自らの認識を包み隠さず、すべて明らかにしてまいる所存です。また、ご指摘いただいたことやご質問に対しましても、真摯(しんし)にお答えしてまいります。裁判所におかれましては、どうか事実を明らかにしていただきますよう心からお願い申し上げます。そして、そのことが、多くのご被害者やご遺族の皆様の願いでもあると信じております。
JR福知山線脱線:山崎前社長が無罪主張 神戸地裁初公判 12/21/10 (毎日新聞)
乗客106人と運転士が死亡した兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故(05年4月)で、業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本前社長、山崎正夫被告(67)に対する初公判が21日午前、神戸地裁(岡田信裁判長)で始まった。山崎被告は起訴内容について、「危険性を認識などの指摘は事実と全く異なる。潔白を明らかにしたい」と全面否認し、無罪を主張。一方で、「106人の尊い命を奪い、多くの人にけがをさせた。おわび申し上げる」と謝罪した。鉄道事故で経営幹部の刑事責任が問われるのは異例。
負傷者は、兵庫県警の調べで562人とされたが、検察は因果関係を立証できた493人と認定。起訴状朗読で運転士を除く死亡者と合わせ599人の氏名を読み上げた。
起訴内容の認否で弁護側は「鉄道業界では当時、カーブの安全対策は、余裕のある制限速度を設け、速度順守は運転士に委ねるのが常識で、カーブに自動列車停止装置(ATS)を急整備すべきとの規範意識はなかった」と主張。被告には、危険性の認識も事故の予見可能性もなく、過失はなかったと述べた。
これに対し、検察側は冒頭陳述で、▽被告が安全対策室長だった93年5月、東海道・山陽線のATS設置を巡り、経費削減のために重要度の低いものを減らす検討を指示▽その際、カーブでの速度超過による事故の危険性について報告を受けていた--と指摘。当時は運転士の人為的ミスが多発し、設備面で補うのが業界の常識だったうえ、JR函館線事故などの報告も受けており、予見可能性があったのは明らかと断じた。午後は弁護側の冒頭陳述も行われる。
必要に応じ列車を減速させる新型ATSを現場カーブに設置していれば事故を防げたという点は弁護側も認めている。JR西は90年以降、新型ATSを半径450メートル未満のカーブに路線ごとに設置。03年9月の経営会議で、事故現場にも05年5月までに設置することを決めていたが、設置直前に事故が起きた。
業務上過失致死傷罪は裁判員裁判の対象外。公判では計30人の証人が採され、来年9月まで計29回の期日が決まっている。現場の線形変更にかかわった関係者や被告の元部下、鉄道の専門家らが証言する。
山崎被告は東大工学部卒。旧国鉄を経てJR西では安全対策室長や鉄道本部長などを歴任し、事故直後に副社長に、06年2月に技術畑出身者で初の社長になった。09年7月に在宅起訴され辞任した。【重石岳史】
【ことば】JR福知山線脱線事故 兵庫県尼崎市のJR福知山線塚口-尼崎間で05年4月25日、宝塚発同志社前行き快速(7両)が制限速度70キロの右カーブに時速約115キロで進入し、1~5両目が脱線。一部は線路脇のマンションに激突し、大破。兵庫県警は死亡した運転士(当時23歳)ら10人を書類送検し、神戸地検が09年7月、山崎前社長だけを起訴した。一方、遺族らが告訴した井手正敬被告(75)ら歴代3社長は、検察審査会での議決を経て指定弁護士により業務上過失致死傷罪で強制起訴された。
■起訴内容 山崎被告は鉄道本部長として、JR西日本の取締役会決議に基づき安全対策を一任されており、(1)福知山線から(新規開業の)東西線への乗り入れを円滑にするため、96年12月21日に事故現場カーブを半径600メートルから304メートルの急カーブに付け替えた(2)97年3月8日の東西線開業に伴うダイヤ改正に伴い、現場カーブ直前で最高時速120キロになる快速電車が1日34本から94本に増えた(3)96年12月4日にJR函館線の急カーブで起きた貨物列車脱線事故はATSがあれば防げた--の3点すべてを知り、事故を予見できた。
だが、経費増大を危惧するなどして、ATSを現場カーブに優先的に設置するよう指示すべき業務上の注意義務を怠り、脱線事故を起こした。
名義貸しに強度不足関与…1級建築士4人の免許取り消し 12/13/10 (朝日新聞)
国土交通省は13日、耐震強度不足の建築や名義貸しに関与したとして、建築士法に基づき、1級建築士4人の免許を取り消したと発表した。
静岡県の立川秀樹・元建築士は1996年から、1級建築士事務所の開設に必要な管理建築士として、自分の名義を使うことを承諾。2年前からは、自らは何もしていないのに、住宅や店舗計28棟で設計や工事監理を担当したように名義を貸していた。
いずれも兵庫県の畑中浩之元建築士と水川典明元建築士は、計561棟の戸建て住宅の耐震強度不足が発覚したファースト住建(同県尼崎市)の物件で設計を担当。茨城県の大和田光彦元建築士は、栃木県内の戸建て住宅の新築で、建築確認の書類を偽造し、正規の手続きを踏んだように装っていたが、実際は無届けだった。大和田元建築士は2004年にも同様の書類の偽造で業務停止8カ月の処分を受けていた。
偽造:建築士、
長期優良住宅
認定書を 国交省が処分 12/14/10(毎日新聞 東京朝刊)
長期優良住宅の認定書を偽造したなどとして、国土交通省は13日、住宅メーカー「タマホーム」(東京都港区)宮崎支店(宮崎市)の郡司和徳1級建築士を11カ月の業務停止とする懲戒処分を発表した。国交省によると、長期優良住宅を巡る処分は初めて。
国交省によると、郡司1級建築士は宮崎県内で、建築主から宮崎市などへの長期優良住宅の認定申請を代理で行っているが、戸建て住宅16件で代理申請せずに認定通知書を偽造した。認定通知書は代理人に交付され、建築主には代理人がコピーを渡す仕組みであることを悪用し、公印のある正式の認定書の名義を変えてコピーを作成したという。【石原聖】
強度に影響の傷も 広島高速 12/14/10 (中国新聞)
関西エックス線(広島市西区)が担当した広島高速2号、3号延伸部の橋桁溶接部の傷を調べる検査が不適切だった問題で、広島高速道路公社は13日、3号出島―吉島間の元安川を渡る高架橋に長期的にみた場合、橋の強度に影響する傷があったことを公表した。
再検査で広島高速2号に10カ所、3号に166カ所の傷が見つかった。このうち元安川を渡る高架橋で、本格的な補修が必要な傷や溶接の不具合が判明した。溶接工事の担当業者が13日に工事を始め、来年9月までに終える。公社は「当面の通行の安全性に問題はない」としている。
また、公社は一連の不適切検査の原因について、同社の検査能力が不十分だったことが主な原因とする調査結果をまとめた。今回の検査手法での実績がほとんどないことに加え、過密工程で検査精度が低下し、誤判定が相次いだとした。無資格の職員も加わっていたほか、一部データを改ざんしていた。
公社は13日、関西エックス線を下請等の制限6カ月の処分とした。検査を委託した三菱重工鉄構エンジニアリング(中区)を6カ月、広成建設(東区)と川田工業(東京)を各1カ月の指名停止とした。
市川 海老蔵さんが妻・麻央さんに贈った婚約指輪輸入の際、消費税の申告なされず 12/10/10 フジテレビ系(FNN)
市川 海老蔵さん(33)が妻・小林麻央さん(28)に贈った婚約指輪について、日本に輸入する際に、消費税の申告が確認されておらず、東京税関が調査していることがわかった。
2009年12月24日に、市川 団十郎さんは「本人の話によると『モナコの公演の時に発注した』と」と話していた。
関係者によると、海老蔵さんは、妻・麻央さんに贈ったダイヤモンドの婚約指輪を、知人を介して、アメリカからおよそ1,000万円で購入したという。
アメリカからダイヤモンドを日本に輸入する場合、空港で申告し、消費税を支払うことになっているが、このダイヤモンドについては、持ち込んだ人が特定できておらず、税関への申告が確認できないという。
消費税額は、およそ50万円で、東京税関は今後、海老蔵さん本人から話を聞くなど、調査を行う方針。
初の制度、監査人甘いチェック…政治資金報告書 12/02/10(読売新聞)
30日公表された2009年の国会議員関係団体の政治資金収支報告書。
今回から政治資金の使途の透明性を確保する目的で政治資金監査制度が適用されたが、資料不足にもかかわらず、監査人が議員側の言い分を認めてしまっているケースが相次いで判明した。親族が監査したり、少なくとも10人の監査人が監査対象の団体に献金したりしており、識者からは早くも「法改正も含めて見直しが必要だ」との指摘も出ている。
小沢鋭仁前環境相(民主)の資金管理団体は、コピー機のリース代など少なくとも15件、計約55万円分の支出について、領収書を添付せずに収支報告書を提出。小沢事務所は「頼んでも支出先が領収書の発行に応じてくれなかった」と説明し、監査人も事務所側の言い分を受け入れた。しかし、読売新聞の取材に対し、支出先のリース会社は「依頼があれば領収書を発行している」と反論。その後、同事務所は最初の説明を撤回し、「事務所も監査人も知識不足だった。リース会社に領収書の発行を依頼する」と釈明した。
監査人本人への報酬15万円について、領収書を発行してもらうことができなかったことを意味する「徴難」などと収支報告書に記載したのは、大島九州男参院議員(同)の政党支部。大島事務所は「領収書が手元にないものを自動的に『徴難』としてしまったかもしれない。監査人からも指摘されなかった」と明かした。
水落敏栄参院議員(自民)の政党支部は、支部の収支報告書を監査した兄から30万円の寄付を受け取っていた。水落事務所は「監査報酬を節約したいと思って兄に依頼したが、今後は寄付を控えてもらうことも検討する」とコメントした。
また、監査人から政党支部が10万円の寄付を受けていた村田吉隆衆院議員(同)事務所は「監査では1円から全てをチェックされるので、見ず知らずの第三者に監査を頼みたくない」と本音を漏らした。
添付すべき領収書がないと監査人が指摘した「亡失」のケースは、23議員の24団体で407件、計約760万円に上った。
小里泰弘衆院議員(同)の資金管理団体はパーティー会場費約300万円の領収書を紛失。小里事務所は「再発行の依頼を試みたが、会場に使ったホテルがすでに閉鎖しており、やむを得なかった」と釈明した。
独法汚職、業者との癒着調査せず 09年に内部から指摘 (1/2ページ)
(2/2ページ)11/27/10(朝日新聞)
経済産業省所管の独立行政法人「石油天然ガス・金属鉱物資源機構」の海底資源探査事業をめぐる汚職事件で、同機構側が昨年1月ごろ、元職員の平山裕章容疑者(41)=収賄容疑で逮捕=と贈賄側の癒着を疑う指摘があったにもかかわらず、十分な調査をせずに問題を事実上放置していたことが、関係者の話で分かった。
指摘は同事業の関係者が会議の席で行った。岩松一夫容疑者(62)=贈賄容疑で逮捕=が2008年10月に設立した人材派遣会社の本店が、平山容疑者の住所に置かれているとし、両者の関係についての詳しい調査を求めていた。当時の同機構幹部は「本格的に調査していれば、平山容疑者を担当から外すなど汚職防止がはかれたはずだ」と話しており、同機構の管理体制が問題となりそうだ。
機構や内部資料などによると、探査船「資源」の運航計画などを打ち合わせるため、同機構で08年10月ごろに開かれた会議で、平山容疑者は、岩松容疑者が新たに同月設立した人材派遣会社「N.O.D.」から探査船事業の調査員を採用する案を明らかにした。その後、翌年1月ごろの会議で、平山容疑者が出した年賀状の記載から、N社の本店が、平山容疑者が所有するマンションの部屋と同じ場所であることを出席者が指摘。両者の関係を問題視し、調査を求めたという。
一連の会議には、同機構の理事(当時)や平山容疑者の直属の上司などが出席していた。だが、09年4月にはN社の社員3人を探査船事業の調査員などに採用した。同機構側は「規定に沿って採用しているので問題ない」とし、1月に会議で出た指摘に関する調査も行わなかったという。
同機構の河野博文理事長は、平山容疑者らが逮捕された16日の記者会見で、「昨年秋、外部から癒着を指摘する情報が寄せられたが、(平山容疑者が同年11月に)退職したため調査ができなかった」と説明していた。
この説明とは矛盾し、同年1月ごろには会議に出席していた当時の同機構理事らは癒着を疑う指摘を受けていた。同機構は朝日新聞の取材に対し、「理事長には(癒着の指摘に関する)報告はなかった。捜査中なので、対象者からのヒアリングができていない。捜査が終わり次第、調査していきたい」としている。
平山容疑者は、探査船「資源」の調査員や船員の採用で有利な取り計らいをした謝礼などとして、岩松容疑者から08年5月~09年10月に16回にわたり現金計約2900万円を受け取ったとされる。(沢伸也)
CNN東京支局のコメントはおかしい。CNNの本部と連絡を取ったのかは知らない。しかし、「SDカードがウイルスに感染している可能性があるなどと判断し、
内容を確認しないまま廃棄したという。」と言う事はCNN東京支局はウイルスには対応できないと言っている事と同じだ。もし事実だとすると、
ウイルスに感染してない保証がないメディアはCNN東京支局では開けない、ウイルス対策に無防備な状態である通信社と言うことになる。
CNN東京支局はたいした役割を持っていないのだろう。CNN東京支局を相手にしても仕方がない。今度は、英語を勉強して直接本部に投稿するべきだろう。
【海保職員「流出」】映像をCNN東京支局に郵送 「放送されず動画サイト投稿」海上保安官が説明 11/20/10(朝日新聞)
沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突ビデオをめぐる映像流出事件で、関与を認めた神戸海上保安部(神戸市)の海上保安官(43)が、東京地検の事情聴取に対し、「映像を米CNNテレビの東京支局に郵送した」と説明をしていることが25日、捜査関係者への取材で分かった。
保安官は「CNNが映像を放映しなかったので、動画サイトへの投稿を決意した」と話しており、捜査当局は保安官が投稿を決めた時期の裏付けになるとみて調べている。
捜査関係者によると、保安官は聴取に対し、動画サイトに投稿する数日前、映像を記録した外部記憶媒体のSDカードを封筒に入れ、東京都港区の同支局に郵送。封筒に差出人名などは書かず、SDカードに保存した映像データの内容についても説明文などは同封しなかったと話している。
同支局側は、SDカードがウイルスに感染している可能性があるなどと判断し、内容を確認しないまま廃棄したという。
保安官は10月中旬、乗務していた巡視艇内の共用パソコンからUSBメモリー(外部記憶媒体)に映像を保存。一時的に、個人に支給された公用パソコンに移し替えた後、自宅のパソコンの編集ソフトなどで映像を分割し、11月4日午後に神戸市内のインターネットカフェから投稿したとされる。
独法元職員、人件費2千万円水増し 贈賄側に利益供与か 11/20/10(朝日新聞)
経済産業省所管の独立行政法人「石油天然ガス・金属鉱物資源機構」の海底資源探査事業をめぐる汚職事件で、収賄容疑で逮捕された元職員平山裕章容疑者(41)が、贈賄側の人材派遣会社から派遣された探査船「資源」の調査員らの人件費を割高に設定し、約2千万円を水増しして支払っていたことが同機構への取材でわかった。
警視庁は、平山容疑者が贈賄側に利益が出るように、採用者の日給をかさ上げしたとみて調べている。機構は昨年12月、派遣会社からこの約2千万円を返還させたという。
機構は、国が定めた労務単価を適用し、人件費を算定。測量技師などの資格の有無や語学力、経験などから技術レベルを決め、それに応じて日給を決めたという。「主任」から「助手」まで数段階あり、約5万~2万円の日給が支払われたという。
捜査関係者や機構によると、贈賄容疑で逮捕された岩松一夫容疑者(62)の経営する派遣会社「アイエルイー」は、探査船事業に2008年3月に1人、その後も2人を派遣した。岩松容疑者らは、より多くの人材を派遣するため同年10月ごろに派遣会社「N.O.D.」を新たに設立し、さらに15人を派遣したという。
この2社から派遣された計18人のなかには、大学を卒業したばかりで最低の「助手」レベルの技術しかないにもかかわらず、より高いレベルに設定された人が数人いた。機構によると、この数人の水増し分約2千万円が過剰に支払われていた。09年に機構の内部調査で発覚したという。
機構によると、調査員らの採用にあたっては、探査船チームのサブリーダー(課長代理)の平山容疑者を中心に応募者を面接し、技術レベルを判断していたという。採用の最終決裁者は担当理事で、書類上は理事が決裁した形になっているが、機構は「理事のチェックは働かず、平山容疑者の面接が通れば、それでよしとなっていた」と説明している。
元職員「年間700万円ぐらい必要」 石油ガス機構汚職 11/18/10(朝日新聞)
経済産業省所管の独立行政法人「石油天然ガス・金属鉱物資源機構」(JOGMEC)の海底資源探査事業を巡る汚職事件で、収賄容疑で逮捕された元職員平山裕章容疑者(41)に、ペーパー会社を介して現金を提供する仕組みを贈賄側業者が提案していたことが捜査関係者への取材でわかった。平山容疑者は当初、必要な金額を具体的に贈賄側に提示したといい、警視庁は、両者が相談して取引を装ったわいろの授受を始めたとみて調べている。
捜査関係者によると、贈賄容疑で逮捕された岩松一夫容疑者(62)が社長を務める人材派遣会社「アイエルイー」は2008年3月、同機構に調査員などの派遣を始めた。同月、平山容疑者らはわいろの受け皿となるペーパー会社を設立。岩松容疑者は「ペーパー会社に発注したように装うので、論文などを出してくれ。そうすれば金を出せる」と提案したという。現金提供を受けるにあたり、平山容疑者は「年間700万円ぐらい必要だ」と岩松容疑者に伝えたという。
同年5月、アイ社からペーパー会社に、調査費名目で現金の振り込みが始まった。同年9月ごろにかけ計約800万円が渡ったという。取引があるように装うため、平山容疑者の論文などがペーパー会社からアイ社に送られたという。
08年10月には、岩松容疑者らは同機構や資源探査船「資源」の運航・管理を委託している共同企業体に、より多くの調査員らを派遣するため、平山容疑者の親族を代表者に新たな人材派遣会社「N.O.D.」を設立。同時に別のペーパー会社もつくった。
N社からは、二つのペーパー会社の銀行口座に現金が振り込まれた。まず09年5月に約600万円、その後、6~10月に毎月約300万円が振り込まれた。捜査関係者によると、金額は両容疑者が話し合って決めたという。
この二つのペーパー会社を通じた、岩松容疑者から平山容疑者へのわいろの提供は計約2900万円にのぼった。
元職員側へほかにも2千万円 資源探査めぐる独法汚職 11/18/10(朝日新聞)
国の資源探査船「資源」の調査員らの派遣契約をめぐる汚職事件で、人材派遣会社から約2900万円を受け取ったとして収賄容疑で逮捕された経済産業省所管の独立行政法人「石油天然ガス・金属鉱物資源機構」(JOGMEC)元職員平山裕章容疑者(41)側に、同社からほかにも、現金などで約2千万円が渡っていたことが捜査関係者への取材でわかった。
平山容疑者側には計約5千万円が流れていたことになる。ただ、警視庁は、この約2千万円分についてはわいろ性が薄いとして立件を見送る方針だ。同庁は17日、川崎市の同機構本部などを家宅捜索した。
捜査2課によると、平山容疑者の逮捕容疑は、「資源」の調査員や船員の派遣業務で有利な取り計らいをした謝礼などとして、人材派遣会社社長岩松一夫容疑者(62)=贈賄容疑で逮捕=から2008年5月~09年10月に16回にわたり現金計約2900万円を受け取ったというもの。この金は、平山容疑者が自分の親族を役員にして設立したペーパー会社2社の銀行口座に、岩松容疑者の会社との取引を装って振り込まれていた。
捜査関係者によると、このほか、平山容疑者は同機構を退職した後の09年12月~今年10月にも、別のペーパー会社を受け皿に、岩松容疑者側から10回にわたり現金計約1千万円を受け取っていたという。
また、岩松容疑者が実質的に経営していたとされる別の人材派遣会社(今年3月に解散)は平山容疑者が所有するマンションの部屋に本店が置かれ、平山容疑者の親族が代表取締役になっている。この親族に報酬名目で12回にわたり計約400万円が支払われていたという。
さらに、岩松容疑者は人材派遣会社の経費として、平山容疑者のマンションや駐車場の賃料、光熱費など数百万円分を平山容疑者側に払っていたという。
岩松容疑者は、同機構が「資源」の運航・管理を委託している共同企業体の事務所で、07年12月~09年10月に所長を務めた。関係者によると、その縁で平山容疑者と知り合った。平山容疑者は機構の待遇に不満を漏らし、「金もうけがしたい」などと相談していたという。
独法元職員を逮捕 資源探査めぐり3千万円収賄容疑 11/16/10(朝日新聞)
日本周辺海域の資源を調査している国の探査船「資源」の調査員らの派遣契約をめぐり、業者に便宜を図って現金約3千万円を受け取ったとして、警視庁は16日、経済産業省所管の独立行政法人「石油天然ガス・金属鉱物資源機構」(JOGMEC、本部・川崎市)の元職員平山裕章容疑者(41)=東京都中央区=を収賄の疑いで逮捕し、発表した。船舶関係会社社長の岩松一夫容疑者(62)=横浜市=も贈賄容疑で逮捕した。
「資源」は尖閣諸島のガス田開発問題などを契機に2008年2月に導入された。捜査2課などによると、平山容疑者は「資源」の運航・管理などを担当。調査員らの派遣業務で有利な取り計らいをした見返りなどとして、08年5月~09年10月ごろ、岩松容疑者から十数回にわたり現金計約3千万円を受け取った疑いがある。
同船の事業は資源エネルギー庁が同機構に委託し、機構は運航・管理を民間の共同企業体に再委託。調査員らの採用は主に機構が、船員などは共同企業体が行っている。平山容疑者には調査員の選定などで実質的権限があったという。
平山容疑者らは現金の受け皿として、平山容疑者の親族を代表者とするペーパー会社を作り、岩松容疑者の会社との取引を装ってペーパー会社の銀行口座に金を振り込ませていたとされる。
同機構は旧石油公団などの統合で04年に発足。元職員も石油公団の出身で、昨年11月ごろ退職している。同機構の10年度予算は約1兆5647億円。09年度は国から約880億円の交付・出資金を受け、昨年の事業仕分けでは交付金の剰余分の返還を求められた。理事長は河野博文・元資源エネルギー庁長官。
NHK捜査情報漏えい:記者倫理を逸脱…内部からも批判 10/09/10(毎日新聞)
「記者倫理の原則を踏みにじった」--。8日に発覚したNHK報道局スポーツ部記者が捜査情報を漏らした問題は、NHK内部からも批判の声が上がった。04年夏の受信料着服問題をきっかけに相次いで明るみに出た不祥事。NHKは数々の改革を打ち出してきたが、今回の問題は成果が上がっていない実態を浮き彫りにした。
「インサイダー事件以降、コンプライアンス順守に取り組んできたのに、残念に思っている」。8日、東京・渋谷のNHKで会見した冷水(しみず)仁彦報道局長と坂本忠宣報道局編集主幹は淡々と話した。
NHKの内部調査に対し、この記者は「他社から聞いた情報の真偽を確認したかった。メールをきっかけに相手との関係性を保ちたかった」と説明しているという。なぜメールだったのかとの問いには「携帯電話がつながらず、メールで返事をもらいたかったようだ」と話した。
NHKは捜査情報の入手先の確認をしておらず、会見に出席した報道陣約40人からは「NHKが得た情報の提供ではないのか」との質問が相次いだ。
これに対し冷水報道局長らは「この記者が、事件捜査を取材する部門の記者と接触した形跡はない」「情報管理は徹底している」と説明したが、その根拠は十分に示されず「今後も事実関係を調べていく」と話すにとどまった。
また「捜査対象に情報の確認を求めるのは不自然」との指摘には「他社の情報なので、上司らに伝えることができなかったらしい」と答えた。
送信相手の相撲部屋の親方は捜査対象で、関係先には情報通りその日の午前、家宅捜索が入った。男性記者に返信はなかったというが、このメールが事件捜査に与えた影響については「相手が捜索に対して対応を取ったのかは分からない」と述べた。【棚部秀行】
◇地方局「なぜ実名非公表」
NHKの地方放送局の職員は「取材活動の中心となる報道局でこのようなことが起き、地方機関に与える影響は大きい。おそらく士気も下がるだろう。われわれはまじめに働いているのに……。これでは改革が進んでいないと思われても仕方ない」と憤った口調で話した。
別の職員は「取材倫理上の問題という点では、インサイダー事件と同じ。あの時は氏名を公表したのに、なぜ今回は非公表なのか」と、メールを送った記者の実名を公表しなかったことに疑問を呈した。
また報道局の記者は「いわば容疑者にしゃべってしまったようなもので、記者のモラルの根幹が問われる問題だ。NHKということで信頼度が落ちたり、信頼関係を築くのに支障をきたさないか心配している」と今後の影響を懸念している。【高橋咲子】
年金入札情報漏えい:「会社の上司に報告」山本容疑者供述 10/16/10(毎日新聞)
日本年金機構の年金記録照合業務を巡る入札情報漏えい事件で、警視庁に競売入札妨害容疑で逮捕された「NTTソルコ」の営業担当部長、山本一郎容疑者(43)が、年金機構職員の高沢信一容疑者(46)=官製談合防止法違反容疑で逮捕=から未公表の入札情報を聞く度に「会社の上司に報告した」と供述していることが捜査関係者への取材で分かった。ソルコ社が入札情報が漏れていることを知りながら、黙認していた可能性が浮かんだ。
警視庁捜査2課によると、山本容疑者は2~5月、旧社会保険庁時代の同僚だった高沢容疑者から、入札の仕様書案や他社の「技術点評価一覧表」などを入手。他社の応札状況を類推し、入札を優位に進めたとされる。
捜査関係者によると、山本容疑者は上司に入手した情報を報告したが、止めるような指示は受けなかったという。一方、ソルコ社は5月の入札に備えたプロジェクトチームを4月に結成し、山本容疑者を中心に据えた。山本容疑者は「上司も(未公表の情報を取ることも)営業の範囲内と考えていたと思う」と供述しているという。
ソルコ社は毎日新聞の取材に対し、「不適切な行為を助長するような行為はなかったと認識している」とコメントしている。【川崎桂吾、前谷宏】
年金機構職員を逮捕 入札情報漏らした疑い 10/15/10(朝日新聞)
宙に浮いた年金記録問題の対策として、日本年金機構(本部・東京都杉並区)が外部委託する業務の入札に関する情報が業者側に漏れた問題で、警視庁は14日、同機構人事管理部参事役高沢信一容疑者(46)を官製談合防止法違反の疑いで逮捕し、発表した。また、情報を受け取っていた情報処理会社「NTTソルコ」(同港区)の社員で旧社会保険庁OBの山本一郎容疑者(43)を競売入札妨害の疑いで逮捕した。
委託業務は、約7億2千万件の紙台帳記録とコンピューター記録を照合する作業に関するもので、作業を行う場所や人員、照合に使う端末の確保などが含まれる。今年度から4年間の事業で、照合作業全体の費用は約2千億円の見込み。作業は全国29拠点で行われ、機構は拠点ごとに業者を入札で選定する。
入札は4月5日に公示。参加各社の提案内容を評価した技術点と、応札金額を合わせて落札業者を決める総合評価方式で、5月25~27日に実施された。
捜査2課によると、記録問題対策部にいた高沢容疑者は2~5月、旧社保庁で同僚だった山本容疑者に、内部資料である入札に関する情報を提供し、入札の公正を害した疑いが持たれている。高沢容疑者は、未公表の予定価格を類推できる予算関係資料をメールで送信したり、各社の技術点をまとめた資料を手渡したりしていた。
高沢、山本両容疑者は「不正な行為をして入札の公正を害したことに間違いない」と容疑を認めているという。
高沢容疑者は当時、同部で照合作業のマニュアル作成などを担当。部内のパソコンで入札情報などにアクセスできる立場だった。6月に問題が発覚し、人事管理部付に異動した。
ソルコ社は17拠点の入札に参加し、うち2拠点で落札。落札額は計約12億5千万円だった。機構はソルコ社が落札した2拠点の入札やり直しを決定。今回の問題の影響で、業務全体に遅れが出ている。
日本年金機構は、宙に浮いた年金問題など、相次ぐ不祥事を受け廃止された社会保険庁の後継組織として、今年1月に発足した特殊法人。
2・5億円前理事長「経営に口出さない」念書 08/21/10(読売新聞)
大阪府民共済生活協同組合(大阪市)から違法な退職金約2億5000万円を受け取っていた松本一鶯(いちおう)・前理事長(75)が2008年4月頃、就任直前の山田信治・副理事長(64)に対し、「経営には口出ししない」という趣旨の「念書」を書かせていたことがわかった。
山田副理事長は元府幹部で、監督官庁出身者を役員に迎えるにあたり、内部事情を知られるのを嫌ったとみられる。山田副理事長は「外部の人間へのアレルギーがあったのだろう」としている。
山田副理事長によると、30年来の知り合いだった松本前理事長から「役員に迎えたい」と声がかかり、就任したという。その一方、▽常勤役員会の意向を尊重する▽任期は4年――などと記した念書への署名を求められ、応じた。
就任時、府民共済の理事は12人で、常勤は松本前理事長を含む5人、山田副理事長ら7人は非常勤だった。常勤理事らは、全理事がメンバーの「理事会」とは別に、「常勤役員会」を組織し、重要案件の前さばきなどをしていたという。
府民共済のある関係者は「常勤理事は、松本前理事長に近い人物で固められていた」と指摘。念書を得て山田副理事長を迎えた理由について、「府とのパイプ役に期待する反面、警戒したのではないか」とみる。
山田副理事長は、府では商工労働部長や企画調整部長などを歴任。最後は太田房江・前知事の特別秘書を務め、08年2月に太田前知事が引退した際に辞職した。読売新聞の取材に、念書について、「再就職にあたり、拒否できる立場になかった」と釈明。一方で、「理事会で注文を付けることは頻繁にあり、事実上、反古(ほご)になっていた」と語った。実際、松本前理事長が退職金に30%の特別功労加算金上乗せを要求した際、山田副理事長は強硬に反対して翻意させた理事の一人とされる。
「ヨーカ堂の名伏せる」業者間で打ち合わせ ウナギ偽装 08/19/10(朝日新聞)
大手スーパー「イトーヨーカ堂」元社員らによる中国産ウナギの輸入業者偽装事件で、海産物販売業者「高山シーフード」が、ヨーカ堂輸入のウナギを買い取る際、仲介食品商社との間でヨーカ堂の名前を伏せるよう事前に打ち合わせていたことが捜査関係者への取材でわかった。神奈川県警はヨーカ堂側の関与についても調べる。
県警の調べによると、ヨーカ堂は2005~06年、食品商社「日洋」を経由して高山シーフードに中国産の冷凍ウナギ78トンを販売。その後、輸入がヨーカ堂であることを隠すため、高山シーフード元社員の小池信行容疑者(47)=東京都文京区=が別の業者に指示し、「輸入者 イトーヨーカ堂」と書かれた箱から「高山シーフード」と表示した箱にウナギを詰め替える作業をさせ、09年にほかの業者に転売した疑いがある。
捜査関係者によると、05年にヨーカ堂から日洋を介して高山シーフードにウナギを払い下げる一連の取引が始まる前の段階で、日洋と高山シーフードの間で話し合いがあったという。両社が協議した結果、「ヨーカ堂の名前が外部に出ないように」という結論になったとみられる。
高山シーフード社長の高山智広容疑者(54)=東京都三鷹市=は逮捕前、取材に「日洋からウナギを買った時に、ウナギ取引担当だった小池容疑者から『(転売先に)ヨーカ堂の名前は出さないでくれ』と言われた」と明かしている。また、ヨーカ堂が売った理由について小池容疑者は「商品の規格が変わり、ヨーカ堂では売れなくなった」と説明したという。
ウナギ偽装、仲介者存在か 転売に倉庫借りて詰め替え(1/2ページ)
(2/2ページ)08/19/10(朝日新聞)
大手スーパー「イトーヨーカ堂」の元社員らがかかわったとされる中国産ウナギの輸入者偽装で、「ヨーカ堂」の名前を隠すための箱の詰め替え作業現場の一つになったのは、宮城県の水産加工会社の倉庫だった。同社社長の証言から、偽装を仲介したブローカー的な業者の存在も浮かぶ。
関係者の話を総合すると、2006年5月下旬、宮城県北部の市にあった冷蔵倉庫の一角に、トラックが大量の段ボール箱を運び込んだ。約1600個の箱の中身は中国産冷凍ウナギのかば焼き。作業員がパックを取り出し、別の箱に詰め替える。約16トンのウナギの入れ替えは、数日に及んだという。
「高校の同級生に頼まれて場所と人手を貸しただけ。作業内容は何も知らされていなかった」。倉庫を所有する水産加工会社の男性社長(46)は語る。「同級生」とは同じ市の出身の男(47)。かつてこの土地で水産業を営み、当時は千葉県の水産関連会社の実質的経営者だったという。
だが、この会社の登記上の所在地には民家があるだけで、実態がはっきりしない。男は地元を離れた後、「高山シーフード」社員だった小池信行容疑者(47)と接点ができたらしい。神奈川県警は、男が偽装に深くかかわった疑いがあるとみている。
06年当時、男から社長に数年ぶりに電話があった。「場所と人手を貸してほしい」と依頼され、男はすぐに千葉県からウナギと段ボールを運んできた。男はパートや外国人研修生ら約10人に作業を指示し、自らも加わったという。「当時はイトーヨーカ堂が輸入したウナギとは知らなかった」と社長は話す。
作業後、新しい段ボールは男が用意したトラックに積まれ、関東方面に運ばれて行ったらしい。水産加工会社には「加工賃」名目で84万5千円が支払われたという。
それから3年余の09年11月、神奈川県警の捜査員が水産加工会社を訪ねた。当時の作業が、ヨーカ堂が輸入したウナギの詰め替えだったと知った。
仲介した男はこの時、水産加工会社の社員として中国にいた。男は一時帰国し県警に説明のため出向いたが、社長には「そちらの会社には迷惑をかけていない。悪いことはしていない」と言い残し、中国へ戻った。その後、連絡が取れなくなったという。(毛利光輝)
ウナギ偽装、ヨーカ堂元社員ら逮捕 輸入者偽り転売容疑 08/18/10(朝日新聞)
大手スーパー「イトーヨーカ堂」(本社・東京)の元社員らが中国産ウナギの輸入業者を偽装して転売した疑いが強まり、神奈川県警は18日、ヨーカ堂の元社員、石原荘太郎(58)=千葉市若葉区=や海産物販売業者「高山シーフード」社長の高山智広(54)=東京都三鷹市=ら6容疑者を食品衛生法(表示の基準)違反の疑いで逮捕し、発表した。
ほかに逮捕されたのは、ヨーカ堂社員の大嶋由紀容疑者(34)=東京都足立区=や、高山シーフードの元社員小池信行容疑者(47)=東京都文京区=ら。小池容疑者を除く5人は容疑を否認しているという。
県警生活経済課によると、石原容疑者は大嶋容疑者らと共謀。2009年6~10月、中国産冷凍ウナギのかば焼き約15トンを、「輸入者 イトーヨーカ堂」と表示された箱から「輸入者 高山シーフード」などと表示された箱に入れ替え、東京都西東京市の業者など2社に計634万円で転売した疑いがある。
石原容疑者は当時、ヨーカ堂の食品事業部海外担当マネジャーで、大嶋容疑者が部下だったという。
ヨーカ堂の各店を展開する「セブン&アイ・ホールディングス」の説明や同課の調べによると、ヨーカ堂は03~05年、約千トンのウナギを自社商品に使う目的で中国から輸入したが、05~06年5月に78トンを食品商社「日洋」(東京都新宿区)を通じ高山シーフードに販売したという。これらのウナギの箱を取りかえたうえで、さらに転売したとみられる。
高山容疑者は逮捕前、朝日新聞の取材に「元社員(の小池容疑者)から『ヨーカ堂の名前は出さないでくれ』と言われたが、ヨーカ堂自体が輸入していたとは思わなかった」と話していた。
セブン社によると、05年に国内外で中国産ウナギから禁止薬品が検出される問題などが起きて需要が落ちたため、自社で使い切れない分を高山シーフードに売却したという。ただ、箱の取りかえについては「会社として指示したことはない」と組織ぐるみの関与を否定している。
一連の偽装は09年10月、横浜市の卸売市場で、賞味期限が切れた中国産ウナギの空き箱が見つかったことがきっかけで発覚した。同市が調査したところ、箱を捨てた横浜市の業者が賞味期限の改ざんを認めた。
県警が不正競争防止法違反容疑で捜査を進めたところ、実際に輸入したのはヨーカ堂だったことが判明。ヨーカ堂本社などを家宅捜索し、偽装の疑いが浮かんだ。
ウナギ偽装、転売先に禁止薬剤の説明なし 08/18/10(毎日新聞)
イトーヨーカ堂(東京・千代田区)が中国から輸入したウナギかば焼きの輸入元改ざん問題は、神奈川県警が18日、関係者6人を食品衛生法違反容疑(虚偽表示)で逮捕して刑事事件に発展した。
転売されたかば焼きからは結果的に、使用が禁止されている合成抗菌剤「マラカイトグリーン」が検出された。しかし、関係者は、同社で輸入を担当した石原荘太郎容疑者(58)から、転売先の高山シーフード(東京・三鷹市)側に抗菌剤に関する説明はなかったと証言しており、食の安全がないがしろにされた可能性も出ている。
「ヨーカ堂さんが仕入れた商品をよそに売らないといけないのは、ただ事ではないと思った。でも、マラカイトグリーンの危険性は全く触れられなかった」。同容疑で逮捕された高山シーフード元社員、小池信行容疑者(47)は17日、読売新聞の取材に、転売交渉のやり取りをこう証言した。
イトーヨーカ堂によると、ウナギかば焼きは、中国から2003~05年に同社が輸入。店頭販売を予定していた。当時は中国産ウナギから健康被害が疑われるマラカイトグリーンが相次いで検出され、消費者の買い控えが起きていた。
小池容疑者によると、食品業者の知人を通じ、石原容疑者らを紹介された。知人からは、「(イトーヨーカ堂で)商品がだいぶ残って困っている。協力してくれないか。商品に問題はないから」と説明を受けた。
イトーヨーカ堂によると、輸入したかば焼きは、中国での養殖池ごとに分けて自主検査を行った。一部でマラカイトグリーンが検出されたが、同社は検出が確認されなかった78トンを、取引関係のある日洋(東京都新宿区)を介して05~06年、高山シーフードに転売したという。しかし、その後の横浜市の調査で、マラカイトグリーンが含まれる商品があった。
小池容疑者はイトーヨーカ堂側の対応について、「問題があったのなら(中国に)返品すればよかった。それをしなかったのはなぜなのか」と疑問を示した。
県警は、店頭販売にそぐわない商品を転売することで、石原容疑者らが仕入れの損失を回避する狙いもあったとみて捜査している。
◇
イトーヨーカ堂の持ち株会社「セブン&アイ・ホールディングス」は18日、「イトーヨーカ堂社員が逮捕されたことは大変残念で、遺憾です。弊社では違法性はないものと信じておりますが、神奈川県警による捜査の行方を慎重に見守りたいと思います」とのコメントを出した。
船の検査で横浜地方検察庁に告発したら立件は難しいと返してきた。承認されていない検査を行ったかどうかは不明だが、検査を行った証拠として書類を
発行した。企業からの支払いが確認できた時点で不正行為の証拠になると思ったが横浜地方検察庁の判断は違った。違法行為をやったほうが得だと思う。
正直者がばかを見る日本の社会。検事は忙しいと言われ、新聞を読むと呉の検事は都会と比べると忙しくないと書いていた。ほんと、人を馬鹿にしている。
おまけに「違法行為を犯したすべてのものを取締るわけじゃない。社会に影響を与えるような犯罪者を取締る。」と言われた。ほんとなら、
中学や高校の社会の授業で教えるべきだ。一般的に小さな犯罪は取締らない。これが事実なら苦情を言う国民もいるだろう。まあ、ドラマと現実の違いを
知らない人間が馬鹿だということだろう。
「ペーパー車検」摘発、民間の検査員2人…否認 08/17/10(読売新聞)
必要な点検や整備なしで車検を通過させる「ペーパー車検」をしたとして、埼玉県警は17日、民間車検場の指定を受けている埼玉県三郷市の自動車整備会社の検査員2人を、虚偽有印公文書作成・同行使、道路運送車両法違反(不正車検)容疑で逮捕した。
逮捕されたのは、同社整備工の下島康弘(47)(三郷市半田)、河野正博(41)(東京都葛飾区東水元)両容疑者。発表によると、2人は今年4月、同県草加市の運送会社から依頼を受けたトラック3台について、点検・整備を済ませたとする虚偽の保安基準適合証を作成し、関東運輸局春日部自動車検査登録事務所などに提出した疑い。2人は「やっていません」と容疑を否認しているという。
民間車検場として国から指定された整備業者は、運輸局に車を持ち込まずに自社の工場内で検査し、保安基準適合証など書類上の審査だけで車検を更新できる。事業者や検査員らは、国に代わって業務を行う「みなし公務員」として、金品などを受け取って便宜を図れば収賄罪が適用される。不正行為の報酬として金銭を受け取っていた場合、収賄容疑で立件される可能性がある。
同社の工場は昨年、「同規模工場の3倍から10倍」(捜査関係者)にあたる約5000台分の車検を処理したといい、県警は、会社ぐるみの不正が繰り返されていないかどうか、実態調査を進める。
取材に対し、同社役員(65)は「組織的な不正も、謝礼金の受領も一切ない。従業員にも『ペーパー車検はするな』と日頃から言っている」と話している。
ヨーカ堂:元社員ら捜査へ 輸入業者偽装し中国ウナギ転売 08/17/10(毎日新聞)
大手スーパー「イトーヨーカ堂」(本社・東京都千代田区)が輸入し売れ残った中国産冷凍ウナギを、別の業者が輸入したように装って転売したとして、神奈川県警生活経済課は近く、関与したヨーカ堂の元社員ら6人について食品衛生法違反(虚偽表示)容疑で強制捜査に乗り出す方針を固めた。
捜査関係者などによると、ヨーカ堂は05年ごろにウナギを輸入した。同社店舗やグループのセブン-イレブンで販売したが、中国産ウナギへの不信が高まったため大量の売れ残りが発生。グループの弁当食材を扱う食品商社「日洋」(新宿区)を通じ、水産物販売業「高山シーフード」(東京都三鷹市)に転売されたとみられる。
ヨーカ堂側は自社名が表示された商品の流通に難色を示し、元社員らは06年5月ごろ、食品衛生法で明記が義務づけられている「輸入者」欄に「イトーヨーカ堂」と記された箱から、高山シーフードを輸入者とした箱に詰め替えたとされる。
さらに転売された魚介類販売業「ヤマト・フーズ」(横浜市金沢区)は賞味期限が07年5月26日だったのに「09年11月23日」と改ざんし09年7月、横浜市中央卸売市場南部市場の3店舗に売ったという。
場内のゴミ集積所で賞味期限が偽装された空き箱が見つかり、市保健所がヤマト社の仕入れたウナギを調べたところ、使用が禁止されている合成抗菌剤「マラカイトグリーン」を検出した。県警は09年11月にヤマト社などを不正競争防止法違反容疑で捜索。輸入元としてヨーカ堂が浮上し今年7月、ヨーカ堂本社を食品衛生法違反容疑の関連先として家宅捜索した。
ヨーカ堂を展開するセブン&アイ・ホールディングスは「当社としては改ざんを依頼したわけではなく、転売後についてはコメントしようがない。きちんと自主検査し、問題ないということで売った」としている。【高橋直純、吉住遊】
ヨーカ堂、中国ウナギ輸入元改ざん・転売の疑い 08/17/10(読売新聞)
イトーヨーカ堂(東京・千代田区)が2005年に中国から輸入したウナギかば焼きが輸入元を改ざんして転売された疑いがあることが16日、神奈川県警への取材で分かった。
県警は、イトーヨーカ堂海外部マネジャーだった元社員ら数人を食品衛生法違反容疑(虚偽表示)で立件する方針を固めた。
05年に中国産ウナギから使用が禁止されている合成抗菌剤「マラカイトグリーン」が相次いで検出され、消費者の買い控えが起きている。
ヨーカ堂は店頭販売のために輸入したが、仲介業者を通じて数社に転売。このうち「ヤマト・フーズ」(横浜市金沢区)が賞味期限を2年半延ばして販売したとして、県警は不正競争防止法違反の疑いで捜索している。
捜査関係者によると、海外部マネジャーだった50歳代の元社員らは06年頃、中国福建省の「福清斉翔食品有限公司」からの輸入元はイトーヨーカ堂なのに、「高山シーフード」(東京・三鷹市)の元社員に指示し、かば焼きの箱の輸入者欄に「高山」とうそを記入。09年7月、仲介業者を介し、数社に売った疑い。
イトーヨーカ堂の持ち株会社セブン&アイ・ホールディングスなどによると、中国産ウナギの買い控えが進んだため、輸入したうち数十トンを日洋(東京・新宿区)を通じて高山に転売した。「転売したものは、自主検査でマラカイトグリーンが検出されなかった」としている。
横浜市が、ヤマト・フーズが仕入れたものを検査したところ、マラカイトグリーンが検出された。
海外部マネジャーだった元社員は取材に対し、「『イトーヨーカ堂に迷惑がかからないように取り扱いは慎重に』とお願いしたが、輸入者欄の改ざんは指示していない」と話している。
一方、高山シーフード元社員は「改ざんは事実。お互いの意思を確認した上でやった」と話した。
Feds: Utah bus company wasn't properly licensed Aug 12, 2010(AP News)
By PAUL FOY (AP)
SALT LAKE CITY — The bus operator involved in a deadly Utah crash that killed three members of a Japanese tour group and injured 11 other passengers is under investigation for operating across state lines without a license, a federal official said Thursday.
Canyon Transportation Inc., of the Salt Lake suburb of Sandy, faces fines that could be significant if the company didn't have enough liability insurance for interstate operators, said Bob Kelleher, administrator for the Utah office of the Federal Motor Carrier Safety Administration. He couldn't immediately provide any figures.
"We're conducting a full investigation, following up to determine whether the company met all the regulations," Kelleher said.
Canyon Transportation apparently fell between the regulatory cracks. Kelleher said the Utah Department of Transportation was supposed to regulate the company, but the state agency couldn't cite any inspections or enforcement activity.
"Up until a couple of days ago, I didn't know anything about this company," Kelleher told The Associated Press. The company mostly picks up people from Salt Lake City's airport for short rides to ski areas and wasn't supposed to operate outside of Utah, he said.
Canyon Transportation provided the 2006 Ford E350 shuttle bus that picked up a group of 14 Japanese tourists in Las Vegas for a four-day tour of Utah's national parks and Arizona's Grand Canyon, according to the Utah Highway Patrol and tour organizers. The group set out Monday and the bus rolled that evening on Interstate 15 near Cedar City, about 250 miles south of Salt Lake City.
Hiroki Hayase, a 20-year-old man from Osaka, was killed in the crash, and authorities Thursday identified the two others who died as Junji Hoshino, 38, and his wife Junko Hoshino, 40, from Shinjuku.
A database managed by the Federal Motor Carrier Safety Administration shows that Utah recently issued logbook violations against Canyon Transportation's drivers. The federal database indicated no other state enforcement activity or violations against the company.
Kelleher said the lack of any other activity in the federal database means the Utah Department of Transportation wasn't regularly inspecting the small operator or enforcing any rules.
State transportation officials said they had no enforcement records on Canyon Transportation and that it wasn't clear if their inspectors issued the logbook violation. It could have been entered by Utah troopers or port of entry officials.
"If we do have any records, we would have already given them to the feds," said UDOT spokesman Adan Carrillo, who acknowledged his agency was responsible for regulating the company.
A Canyon Transportation dispatcher said no executives were available for comment, but another company involved in the tour says the bus operator has been operating across state lines for years without a fatal accident.
"My understanding is they've done plenty of interstate work. They've been in business for 30 years," said Keith Griffall, CEO and co-owner of tour organizer Western Leisure Inc.
Griffall said he has worked with Canyon Transportation for years but Thursday was the first time he heard it lacked a federal license to operate across state lines.
"As far as the regulations go, they get so technical — I don't know anything about that," he said.
Kelleher said other bus operators obtain interstate licenses and there was no question that Canyon Transportation lacked authority to run buses outside of Utah.
The driver, Yasushi Mikuni, 26, is under investigation by Utah troopers who say he was distracted or drowsy when he rolled the bus. Troopers said they found no mechanical problem that would have caused the crash.
Mikuni, a Japanese national living in Las Vegas on a work and education visa, escaped the accident with minor injuries.
It wasn't clear if the driver, a part-time student at the College of Southern Nevada, had a commercial driver's license. Kelleher said a commercial license isn't necessary for a bus with fewer than 16 seats.
Mikuni was ticketed June 1 for speeding on a Utah highway in a Nissan sedan, according to court records. He paid a $115 fine for driving 86 mph in a 75 mph zone in Millard County, records show.
Utah Highway Patrol records show Mikuni also was ticketed May 20 for a tinted-window violation in Juab County, The Salt Lake Tribune reported.
The Ford E350 shuttle bus that rolled over had seat belts, Trooper Todd Johnson said, but it wasn't clear how many of the passengers were wearing them. Kristi Christensen, 31, a nurse who arrived at the wreckage five minutes after the accident, said she found all but three of the 14 passengers thrown from the bus.
Griffall said his company and Nippon Travel Agency in Tokyo were among several companies that helped organize or provided customers for the tour. Those companies hired Canyon Transportation to provide the shuttle bus and its driver, and Griffall said his company was paying the driver separately to double as a tour guide.
Many of the tour companies are helping to pay for lodging and food for accident victims and family members, he said.
"Our thoughts and prayers are with the victims of this tragic accident and their families," Griffall said. "We've been in business for 30 years and never had a fatal accident. We're a small company, and everybody here is feeling the grief and sorrow."
個人的に思うのが、「学生が運転」と言う事実よりも「学生ビザ」だけで働いていたのか、運転手とガイドを一人で兼ねていたのかの2点が問題と思う。
アメリカでは日本人留学生が小遣いや生活費の足しにするために就労ビザがないにもかかわらずバイトをするケースがある。違法であるが、
多くの日本人留学生がバイトをしていると思う。LAS VEGAS SUNの記事によれば、運転手の日本人留学生はコミュニティーカレッジの生徒だ。
コミュニティーカレッジの日本人留学生は、州立大やある程度のレベルの私立大学の日本人留学生に比べるとバイトをしている割合が高い。
これは一般的にコミュニティーカレッジのレベルが低い、そして授業の内容もそれほど難しくないことが多いからだ。
まあ、違法なバイトは日本人留学生だけの問題ではない。アメリカに頻繁に行ったことがある日本人添乗員や少なくともアメリカ留学経験がある
旅行代理店会社員であればこのような事実は知っているはずである。
アメリカ人だったら、学生でなかったら安全に運転するかとの点については何も影響しないと思う。単なる運転手でプロ意識を持っている人は少ないと思う。
首になると困るとか、家族がいるから等の理由で性格的に安全運転を心がける人はいるかもしれない。ただ、本当に自己管理が出来、人生計画を
立てることができるアメリカ人であれば、何かよほどの理由がなければ運転手になることはない。運転手になる人はなるだけの理由がある。
日本人14人を案内して、そして運転もこなす。運転、ツアールート、及びツアーの案内にかなり慣れている人であれば問題ないかもしれないが、
1人で2役をこなすのは難しかったと思う。疲れると運転に支障が出る。今回の事件で、学生ビザだけの留学生を働かせる会社を厳しく取締ることもないだろうし、
学生ビザだけの日本人留学生がバイトをしなくなることもない。日本の旅行会社が委託や選択する時に情報の提供とチェックを厳しくすることしかできない
だろう。今回のツアーが安かったのかは知らない。しかし、安いツアーにリスクはつきもの。また、高いツアーにも関わらず、サービスが悪ければ
次回からはその旅行会社を使わない選択をするぐらいしか出来ないだろう。
米バス事故「学生が運転」、安全徹底に疑問の声 08/12/10(読売新聞)
【シーダーシティー(米ユタ州)=飯田達人】米ユタ州の高速道路で観光バスが横転し、日本人15人が死傷した事故で、大学生がアルバイトで長距離の観光バスを運転していたことに、現地のツアー事情に詳しい関係者からは「安全を徹底できるとは思えない」などの疑問の声が上がっている。
ユタ州警察では、運転手の日本人留学生(26)の居眠りの疑いもあるとみて事情聴取を続けている。
ユタ州警察の発表などによると、留学生はアルバイトでバスを運転し、事故当日は14人のツアー客を案内していた。
ツアーを主催した同州の旅行会社「ウエスタンレジャー」は、運転を同州の送迎サービス会社「キャニオントランスポーテーション」に委託。留学生は同社の所属だった。同社では「現在警察による捜査中」との理由で取材を拒んでいる。
ウ社は社員10人以下で1980年代に創業。社長は、「運転手がどういう人物だったのかは詳しく把握していない」と話している。
同警察によると、米国では21歳以上なら商用運転免許証を取得できるため、夏休みなどに学生がアルバイトで観光バスの運転手をすることは珍しくないというが、ラスベガス周辺でツアーを多く主催する米旅行会社の日本支店スタッフは「学生はビザの関係で就労時間が制限され、安全教育も徹底できない。乗客の命を預かる長距離運転をさせていたとは信じられない」と指摘する。
日本でも、学生アルバイトをバスやタクシーの運転手にすることを明確には禁止していないが、ジェイアールバス関東(東京都渋谷区)では、「学生が商用バスの運転手をすることは聞いたことがない」と話している。
◇
ユタ州警察は11日、バスの運転手の名前を「ミクニ・ヤスシ」さん(漢字表記不明)と発表した。ネバダ州ラスベガスの大学で観光学を専攻していたという。同警察によると、ミクニさんは「(事故時のことは)よく覚えていない」などと供述している。
Nurse recalls carnage after Utah tour bus crash BY PAUL FOY The Associated Press Wednesday, Aug. 11, 2010 | 4:29 p.m.(LAS VEGAS SUN)
A nurse who stopped at a deadly tourist bus crash in Utah described the scene as eerily quiet, with Japanese tourists _ dead, dying or badly injured _ scattered across a highway median.
Kristi Christensen, 31, and her husband arrived within minutes of Monday's rollover on Interstate 15 near Cedar City. It killed three of the tourists and left 11 with broken bones, head or internal injuries. Authorities who blame driver error said Wednesday they found no mechanical problems that would have caused the accident.
"There were cameras, luggage and broken glass everywhere," said Christensen, speaking at Intermountain Medical Center in the Salt Lake City suburb of Murray, where four of the injured passengers are clinging to life.
The Utah Highway Patrol said Wednesday that investigators who inspected the Ford E-350 shuttle bus ruled out mechanical problems as a possible cause. The group was on its way to Bryce Canyon National Park when it crashed about 250 miles southwest of Salt Lake City.
Christensen, who is eight months' pregnant, tended to a half-dozen passengers for nearly an hour before the last of 13 ambulances had taken the injured away.
She arrived five minutes before the first paramedics and firefighters. At first, she tried unsuccessfully to revive a dying woman with a weak pulse who was thrown 30 or 40 feet from the bus.
Christensen found three other passengers trapped inside the bus, a mangled heap laying on its top, wheels up.
"It was like, where do I start? Who do I go to? I wanted to quickly see who was alive or not," she said.
Japan dispatched a diplomatic official to Salt Lake City hospitals, but the man told AP he wasn't authorized to speak, and the patients told hospital officials they don't want any information released to the media.
Two men and two women, part of the group of Japanese tourists, remained in critical condition Wednesday with head, neck and back injuries at Intermountain Medical Center, where they have been able to utter a few words with medically trained interpreters.
"They are severely injured and have potentially life-threatening injuries," said Jess Gomez, a spokesman for the hospital.
Family members of those tourists were due to arrive Wednesday night from Japan.
Christensen said the bus driver was the only occupant she found standing or walking.
"He was in shock," she said. "He was kind of in panic mode." The driver didn't offer a reason for the crash, she said.
Utah authorities identified the driver Wednesday as Yasushi Mikuni, 26, who lives in Las Vegas on a U.S. visa.
Troopers said Mikuni was distracted or drowsy when the bus veered off the road, and that when he tried to correct the vehicle, it rolled one and a half times, landing on its top. Prosecutors will review the investigation and decide whether charges are warranted. Efforts to reach Mikuni on Wednesday were unsuccessful and Iron County Attorney Scott Garrett was not available for comment.
Mikuni is a community college student studying for an associate's degree in travel and tourism, said College of Southern Nevada spokeswoman K.C. Brekken. Mikuni had been a student at the Las Vegas school since spring 2007 and took one class this summer, she said. He was registered for two more this fall, Brekken said.
UHP was still not releasing the names of two of the victims on Wednesday, waiting on approval from Japanese consulate officials who were trying to reach relatives.
The group was on a tour that started in Las Vegas, made a stop at Utah's Zion National Park and crashed at 6:40 p.m. Monday 90 miles short of Bryce Canyon, a popular stop for international tourists.
「情報は「流通監視チーム」に伝えられた。 このチームは、2008年秋に事故米問題が発覚した後に農水省内に設置された非公式な組織だ。
福岡農政事務所が96回も偽装業者の工場を立ち入り検査しながら見逃していたことを受けて発足した。」
下ががんばってもトップが無能か、やる気なしでは結果は出ない。トップにやる気があっても、下が無能またはやる気なしでは結果が出ない。
「流通監視チーム」は少なくとも96回も偽装業者の工場を立ち入り検査しながら見逃していた福岡農政事務所の職員達とは違うことを示せた
ことについては評価する。「石破茂農水相が期限を区切って迅速に調査すると会見で表明した後だったため、拙速でずさんな調査になった」こと
を考えると、政治家や省の調査結果を信用する価値はないと改めて思う。誰を信じるのか、何を信じるのか???あくまでも個人の責任で
信用するのか、調査できないのでリスクを出来るだけ回避する行動を取るのか、または被害者になる可能性があるが運を天に任せるしかないのだろう。
農水省、大手商社も事故米調査へ 用途未確認なら処分 07/27/10(朝日新聞)
事故米を食用に偽装して転売したとして神奈川県警が4社を家宅捜索した食品衛生法違反事件で、農林水産省は、捜査対象となった82トン以外を輸入した大手商社数社についても、適切な使用を確認していたか調査する方針を決めた。確認を怠っていたと認定した場合、82トンを輸入した豊田通商(名古屋市)と同様に行政処分を出す。
農水省は2008年11月、商社が輸入した事故米の流通を調査し、計5251トンについて「飼料用として使用されたことを確認」と発表。しかし今年に入り、このうち3155トン分について協和精麦(神奈川県伊勢原市)が偽装を認めた。神奈川県警の捜査は時効にかからない82トンが対象になっている。
県警の捜索対象は協和精麦など4社だが、農水省は輸入元の豊田通商についても「最終的に飼料用として適切に使用されたか確認しなかった」として、輸入米などの入札への指名停止3カ月の処分を出した。
約5千トンの事故米は豊田通商以外に双日、伊藤忠商事、丸紅など計6社が輸入していた。農水省はこれらの大手商社のうち、協和精麦が偽装を認めた約3千トンの輸入元となった会社から順次事情を聴く。豊田通商と同様、確認を怠ったと判明した場合、処分する方針。
豊田通商は「販売先から加工台帳を入手し、飼料用として処理されたものと認識していた。実際には食用として販売されたのは誠に遺憾」とコメントしている。
伝票にMA米…「もしや」 農水省職員、事故米見破る(1/2ページ)
(2/2ページ)07/26/10(朝日新聞)
2年前に終わっていたかにみえた事件が、再び動き出した。事故米の不正転売問題で、神奈川県警が26日、偽装・転売にかかわったとされる4社の捜索に踏み切った。約3千トンもの事故米が食用に化けていたことを浮かび上がらせたのは、1人の農林水産省職員の目だった。
「なんだ、これは」。昨年9月、ある酒造業者の事務所で、農水省地方農政事務所の職員が1枚の伝票に目をとめた。「米国産 ミニマムアクセス(MA)米」。仕入れ元は米穀業者の名前が記されていた。
国産の加工用米が決められた用途以外に使われていないかを調べる、通常の立ち入り調査の最中だった。輸入米に高関税をかける代わりに一定量の輸入が義務づけられたのが、MA米。これが酒に使われることはあり得ないわけではないが、その場合も地域の酒造組合などを通して供給されることが多く、米穀業者経由のことはほとんどない。この職員は不自然に感じた。
「もしかしたら」。職員の頭に、MA米の事故米が食用に不正転用されていた2年前の事故米問題がよぎった。「念のため調べてみたい」。情報は「流通監視チーム」に伝えられた。
このチームは、2008年秋に事故米問題が発覚した後に農水省内に設置された非公式な組織だ。福岡農政事務所が96回も偽装業者の工場を立ち入り検査しながら見逃していたことを受けて発足した。米の流通を担当する総合食料局の職員が、JAS法を管轄する消費・安全局の「食品Gメン」に同行して研修を受けた。検査マニュアルをつくり、検査は抜き打ちに改められ、モノの流れだけでなく通帳も含めカネの実際の流れも調べるようになった。
流通監視チームが伝票を調べ、業者を一つ一つたどった。取引の流れは複雑で解明に時間がかかったが、今年春になり、焼酎の原料になったのは事故米だった可能性が高まった。今年4月から6月にかけ、食用への偽装に関与したとみられる4社に立ち入り検査を実施。聞き取り調査に対し、協和精麦の幹部は「米を飼料用に加工したことは一度もない」と認めた。台帳をたぐると、偽装は計3155トンにのぼっていた。
この3155トンを含む5251トンについて農水省は08年11月、「飼料用に使われたことを確認した」と発表していた。それだけに、偽装の発覚について協議する農水省の幹部会議は重苦しい雰囲気に包まれたが、公表と告発に反対する意見は出なかったという。「結果的には2年前の自分たちの失敗を掘り起こすことになったが、偽装を今になって見抜くことができたと前向きにとらえ、今後に生かしたい」。農水省幹部の一人は言った。
振興銀、昨秋も132億円損失隠しか 金融庁の検査中 07/25/10(朝日新聞)
日本振興銀行(本店・東京都千代田区)が不良債権の損失を隠したとされる問題で、判明していた不良債権約211億円分に加え、振興銀が昨年9月、新たに約132億円分も取引先に融資した資金を使って高値で買い取らせ、損失を隠していた疑いがあることが分かった。
朝日新聞が入手した取引先企業のメールなどで、企業への融資を少額に分割したり、企業同士で融資金をまわしたりするなど複雑な仕組みにしていたことも明らかになった。振興銀関係者は「昨年9月は金融庁の検査中だったので、不良債権隠しを把握されないようにしていたのではないか」と指摘している。
振興銀関係者の話や内部資料によると、振興銀が「飛ばし」と呼ばれる手口で新たに隠していた疑いのある不良債権は、商工ローン大手「SFCG」(破産手続き中)から買い取った額面で1千億円超の貸し出し債権の一部の約132億円分。判明していた約211億円分と合わせて総額約343億円分になった。
取引の流れは、(1)振興銀が昨年9月、取引先の「中小企業振興ネットワーク」加盟企業約40社に1億~3億円ずつ融資(2)この融資金が別の加盟4社にそれぞれ30億円超ずつ集められた後、4社が計約132億円を匿名組合に出資(3)匿名組合は、振興銀の不良債権約132億円分を引き取っていた保証会社から債権を買い取り(4)保証会社は振興銀に約132億円を弁済――というものだ。振興銀の融資は同月中にこの仕組みで銀行に戻ってきた。これにより、不良債権を実際より高値で売却できたとみられ、振興銀は自行の決算から不良債権を切り離し、損失を隠した疑いが持たれている。
一方、この取引に加わった岡山市内の電子機器販売会社に対し、ネットワークの中核企業から送られたメールを朝日新聞が入手。振興銀から融資を受け、それを別のネットワーク加盟企業に貸し付けることを要請する内容が記載されていた。契約書類では、融資目的は会社の「運転資金」となっていたが、実際は別目的に使うことを企業側が承知していたことが裏付けられた。
振興銀経営管理室は「中小企業振興ネットワーク参加企業との取引状況については社内で精査を行っております」としている。(沢伸也)
「無報酬」天下り法人会長に年1300万円 謝金名目で(1/2ページ)
(2/2ページ)07/23/10(朝日新聞)
経済産業省所管の財団法人「石油開発情報センター」(東京都)が、非常勤の会長について無報酬と公表しながら、実際には役員報酬以外の「謝金」として年間約1300万円を支払っていたことが分かった。歴代の会長ポストには旧通商産業省OBが就いていた。有識者らは「実質的な役員報酬。報酬隠しとみられても仕方ない」と指摘している。
謝金は、会合に招いた専門家などに支払う謝礼のお金として1回につき1万~2万円などと支出規定が明文化されている。だが会長への謝金には明文化した規定を設けず、内部決裁だけで済ませ、不透明な支出となっていた。同センター会員の石油会社などにも、朝日新聞の今年5月の取材後、この支出について初めて報告があったという。
独立行政法人を対象とした総務省の調査では、17法人が中央官庁の天下りOB73人に人件費以外の名目で高給を支払っていたことが判明。同省は昨年度、各省庁に原則廃止を要請した。財団法人など公益法人は調査対象外だった。
同センターは、財団法人の根本規則で、会長を含む非常勤の理事10人は無報酬と定め、ホームページなどで公表している。会長の職務はセンターの総理や外国の要人への対応などで週3日勤務。
複数の関係者によると、センターは会長に月々100万円余、年間約1300万円を支払い、役員報酬ではない謝金として計上していた。この支払い理由について、関係者は「20人規模の組織で有給の常勤理事長もいるのに、天下り官僚にまで多額の報酬を出していることがわかれば批判を受けると考えたのではないか」と話している。
センターは「歴代会長には役務の正当な対価を謝金として支払っている。だが額は公表の対象外なので回答は差し控える。(根本規則で)無報酬となっていると、わかりづらいので改めたい。設立以来、この支出がなされてきた理由は今となってはわからない」としている。
監督する経産省資源エネルギー庁石油・天然ガス課は「会長への謝金については把握しているが、役員報酬ではなく、謝金なので不適切とは考えていない」とする。
これに対し、元会計検査院局長の有川博日大教授(公共政策)は「謝金は1日2万円程度が常識的な上限で365日働いても1千万円は超えない。会長への謝金は実質的な役員報酬で規則と整合性がとれていないことは明らかだ」と批判。千葉大法経学部の新藤宗幸教授(行政学)は「謝金にしては多額過ぎ、裏報酬に等しい。公金を回して天下り官僚を生活させるシステムは根底から見直すべきで、監督官庁の責任も重い。他の公益法人でも同様の仕組みがないか政府は調査すべきだ」と指摘した。(上沢博之)
「しかし今回、このうち約6割が虚偽と判明、調査が『ザル状態』だったことになる。 山田正彦農水相は22日、取材に対し
『なぜ2年前の調査で見落としたのかしっかり調べる。食の安全のことなので、今までになく厳正に対処したい』と話した。」
「なぜ?」理由は簡単だ。やる気がないからだ。全ての公務員とは言わないが、やる気のない公務員達をたくさん見てきた。理由や言い訳を考える
時間があったら真実を探す時間に費やすべきだ。正直者が馬鹿を見る。これが日本の実態だ。
事故米転用さらに3千トン、業者認める 農水省見抜けず(1/2ページ)
(2/2ページ)07/23/10(朝日新聞)
2007年に米国から輸入された事故米82トンが不正に食用に転売されていた問題で、関与していた加工業者が農林水産省の調査に対し、さらに約3千トンについて偽装を認めていることがわかった。農水省は08年、この約3千トンを含む約5千トンについて追跡調査し「飼料用に使われたと確認」と発表していた。大半が偽装だったのに、それを全く見抜けないほど、当時の調査がずさんだったことになる。
08年の調査は聞き取りが中心で、農水省幹部は「加工台帳を偽装され、関係業者で口裏をあわされると、強制調査権もなく偽装を見抜くことは困難だった」と説明している。当時の石破茂農水相が期限を区切って迅速に調査すると会見で表明した後だったため、拙速でずさんな調査になった、と振り返る幹部もいる。
加工業者は神奈川県伊勢原市の協和精麦(せいばく)。大麦の加工を主な事業にしている。事故米を粉砕して麦のぬかを混ぜ、家畜の飼料にする加工をしていたと台帳などで記していたが、加工は一切行っていないと調査に認めた。台帳を調べたところ、偽装された事故米は計約3千トンに達した。
約3千トンの取引の大半は、協和精麦のほか、今回ともに刑事告発の対象とされる甘糟損害貨物(同県)、石田物産(同)、共伸商事(愛知県)と実施していたという。書類上で所有権を移動させるだけの取引だった。農水省によると、当時事故米を扱う業者は全国的には多くなかった。
この約3千トンの大半は03~06年に輸入されており、食品衛生法の公訴時効(3年)が成立しているため、農水省は82トンの取引に絞って刑事告発の準備を進める一方、約3千トンについても取引の流れを調べている。
事故米には国が輸入販売したものと、商社がしたものの2種類があった。三笠フーズ(大阪市)や浅井(名古屋市)は国販売の事故米を不正転売し、問題が発覚した。
輸入米に高関税をかける代わりに一定量の輸入が義務づけられたミニマムアクセス米の年間輸入量は、七十数万トン。農水省は問題発覚を受け、03~08年度の国販売分の事故米6700トン余の流通先を08年に調べ、約4600トンの不正転売を確認していた。
また08年10、11月には、厚生労働省と協力して、商社が輸入した事故米についても、適正に処理されたか調査を実施した。その結果、販売先が捜査対象となったなどの理由で確認が困難だった一部を除き、5251トンについて「飼料用として使用されたことを確認」し、問題はなかったと発表。しかし今回、このうち約6割が虚偽と判明、調査が「ザル状態」だったことになる。
山田正彦農水相は22日、取材に対し「なぜ2年前の調査で見落としたのかしっかり調べる。食の安全のことなので、今までになく厳正に対処したい」と話した。
「これらを的確に行える体制と規模を備える必要があるとしているが、協会の担当職員は、
本部に11人、名古屋に2人、仙台、神戸、福岡に各1人にとどまっていた。」
楽して儲けていたのだから、結果に対しては責任を持つべきだ。元東京入管局長や元仙台入管局次長を経験したOBが
このような怠慢を見逃したのだから仕方がない結果だ。
厚労省所管法人の不正残業見逃し、03年から 07/22/10(読売新聞)
外国人研修・技能実習制度を巡り、厚生労働省所管の社団法人「経営労働協会」(東京都千代田区)が研修先企業の所定時間外労働を見逃していた問題で、行政処分の対象となった不正は、2003年から常態化していたことが分かった。協会は定期監査を実施していたが、名古屋入国管理局から指摘を受けた昨年11月まで是正指導などは行っていなかった。協会側は読売新聞の取材に、「要員が少なく、適正な監査ができなかった」とし、外国人約1000人を受け入れながら、組織の体制が不十分だったことを認めた。
協会とともに研修生の3年間受け入れ停止処分を受けたのは、名古屋市北区の婦人服製造会社。関係者によると、同社の縫製工場は03年から、第1次受け入れ機関の協会の仲介で、不正が発覚した昨年までに中国人研修生計9人を受け入れたが、当初から所定時間外労働をさせていたという。
協会職員は、国の指針に従って、監査のため3か月に1回程度、縫製工場を訪問していた。しかし、労働時間については、年間総時間数の目安を示しただけで、休日の土日出勤などに対する是正指導は一度もしていなかったという。
不正発覚時、協会が受け入れた研修生約1000人は全国約120社で働いていた。指針では、第1次受け入れ機関は3か月に1度の監査で、研修内容を十分把握するため、通訳を同行させて研修生から聴取し、研修日誌の内容を確認するよう求めている。そのうえで、これらを的確に行える体制と規模を備える必要があるとしているが、協会の担当職員は、本部に11人、名古屋に2人、仙台、神戸、福岡に各1人にとどまっていた。
元東京入管局長の柴田博一理事長は取材に対し、要員不足を認め、「他の研修先企業でも、監査は不十分だった可能性がある。入管OBがいながら不正を見逃してしまい、申し訳ない」と話した。婦人服製造会社の経営者の男性(61)は「協会を信用していたので、処分を受けるとは夢にも思っていなかった」と語った。
一方、協会の川北貞雄理事は「3年間受け入れ停止の処分は重く、研修生受け入れ事業はやめざるを得ないだろう」としている。
「〈事故米の不正転売問題〉「三笠フーズ」や「浅井」(ともに破産手続き中)などが、カビの発生などで工業用途に限って販売が認められた事故米を、
より高値で売れる食用として売っていた。」
上記を考えると、事故米の不正転売に関して告発される4社が同じ運命になっても仕方がない。前の社長と連絡が取れない、直接の担当者が死亡した等の理由は言い訳だ。
事故米の不正転売、新たに82トン 農水省、4社告発へ (1/2ページ)
(2/2ページ)07/22/10(朝日新聞)
カビの発生で食用に適さなくなった事故米82トンが、不正に食用米として転売されていたことが判明し、農林水産省が業者4社を告発することがわかった。不正転売が2008年に発覚したのを受け同省は当時、転売の有無について追跡調査し、今回新たに判明した82トンを含む商社輸入分5千トン余を「飼料用に使われたことを確認した」と公表したが、今年になって業者による加工台帳の偽装が判明した。当時の調査のずさんさが今になって露呈した形だ。
農水省によると、問題の米は07年4月、輸入米に高関税をかける代わりに一定量の輸入が義務づけられたミニマムアクセス(MA)米として豊田通商(名古屋市)が米国から輸入、同年6月、検疫でカビが確認された。そこで、同社は飼料用として甘糟損害貨物(神奈川県)に販売。協和精麦(同)で飼料用に処理されるはずだったが、米は実際には石田物産(同)、共伸商事(愛知県)へと流通し、最終的には事故米ということを隠して、複数の食品加工業者に食用として販売された疑いが強い。台帳類は、協和精麦で飼料処理されたように偽装されていた。
三笠フーズ(大阪市)や浅井(名古屋市)が、国販売の事故米を不正に転売していたため、農水省は厚生労働省と連携し、商社の輸入販売分も追跡調査。08年11月、今回の82トンを含む5251トンについて、飼料用での使用を確認できたとして問題はないと公表していた。
だが、実際の調査では、取引先の保護や企業秘密を盾に、売却先の情報提供を拒む業者が続出。強制捜査権がなく、台帳や書類に矛盾がないかの確認が中心で業者の申告をうのみにせざるをえず、結果的に協和精麦による加工台帳の偽装を見抜けなかったと見られる。
今年4月、農水省がこの82トンとは別に、せんべいなどへの加工用のMA米に不正転売がないか調査する中で、流通経路不明の米を発見。調べる過程で、今回の問題が見つかった。82トンは既に消費された可能性が強いが、残留農薬やカビ毒は検疫で検出されておらず、食べたとしても健康への影響はないとみられる。
農水省は豊田通商以外の4社を、食品衛生法違反や不正競争防止法違反、偽計業務妨害などの疑いで刑事告発する。4社には未登記の業者もあり、活動実態や相互の関係を調べている。豊田通商については、飼料処理されたかの確認を怠っただけだとして告発対象にはせず、輸入米麦の政府買い入れ入札などについて、3カ月指名停止にする。
朝日新聞の取材に対し、甘糟損害貨物は「前の社長がやったことだが、いまは連絡がつかない」、協和精麦は「石田物産に頼まれ、米を細かく粉砕する加工をしただけ。直接の担当者は死亡したため、細かい経緯は分からない」などと説明している。
◇
〈事故米の不正転売問題〉「三笠フーズ」や「浅井」(ともに破産手続き中)などが、カビの発生などで工業用途に限って販売が認められた事故米を、より高値で売れる食用として売っていた。事故米を売り渡していた農林水産省が2008年9月に公表した。その後、福岡農政事務所が三笠フーズの工場を96回立ち入り調査しながら不正を見逃すなど、農水省の失態が発覚。太田誠一農水相と白須敏朗事務次官は同月、失言の責任をとって辞任した。また、農水省が流通ルートの一部にあたる375カ所を実名公表したことで風評被害も発生。総額約160億円の経営支援策が実施された。
【風(5)揺れる大相撲】カネ不透明でも低い税率の公益法人 07/21/10(産経新聞)
異例ずくめの今回の名古屋場所で、初めて「満員御礼」の垂れ幕がかかったのは先週末の17日。日本相撲協会・名古屋場所担当部長の二所ノ関理事(元関脇金剛)は「胸が熱くなった」と感想を漏らした。
だが、昨今の角界をめぐっては、野球賭博問題だけでなくさまざまな不祥事が噴出し、そのたびに協会が繰り返した「反省」と「出直し」の言葉がむなしく響いた。明確な再生の道筋を示せない角界の体たらくの根幹には、協会の甘えがあるように思えてならない。
年6回の本場所を運営する協会は、文部科学省が所管する財団法人だ。税制上の優遇措置があり、本場所などの収益事業に適用される法人税率は、一般法人の30%より低い22%。国の補助金などの受け入れはないが、昨年の事業収入は100億円を超えており、運営資金は潤沢といえる。
《力士、親方、関係者の下の下までカネが回っていて不透明。個人企業ならいいが、公益法人ではそんなムチャは許されない》とは、東京都在住の70歳代男性の指摘。《民営の興業団体にして、勝手にやって自浄できなければ倒産すればいい》と手厳しい。
協会のあり方については、運営方針を決める12人の理事に問題があるとの声も多い。別の男性(62)は《力士出身の理事は2~3人にして、その他は一般人にすべき。世間のことを知らない人間ばかりでは、組織の自浄能力があるはずがない》と断じる。協会運営が角界関係者だけで完結する「閉鎖性」を断ち切るべきとの指摘だ。
「同協会は厚生労働省所管の社団法人。理事長は柴田博一・元東京入管局長で、元仙台入管局次長も理事に名を連ねており、
いわゆる『天下り先』の公益法人だ。」
OBを受け入れOBの人脈や経歴などを利用して甘いチェックを期待したのだろう。最低の社団法人だ。まあ、社団法人や民間を含む他の組織でも
同じようなメリットを期待してOBを受け入れているところがある。元東京入管局長や元仙台入管局次長が理事になっても不正残業見逃しは
防げない。つまり、キャリアの人間が使い物になるか、本気で仕事をするかは別の次元の話ということだろう。
外国人研修生の不正残業見逃し 名古屋入管が処分 07/21/10(朝日新聞)
外国人研修・技能実習生を受け入れた愛知県内の縫製工場で所定時間外に研修生が働かされていたのに見逃したとして、名古屋入国管理局が第1次受け入れ機関の社団法人「経営労働協会」(東京都千代田区)を3年間の受け入れ停止処分としていたことがわかった。処分は4月19日付。
同協会は厚生労働省所管の社団法人。理事長は柴田博一・元東京入管局長で、元仙台入管局次長も理事に名を連ねており、いわゆる「天下り先」の公益法人だ。
同協会によると、県内の縫製工場で昨年、協会を通じて受け入れた中国人研修生3人が、研修計画に記載されていない休日の土曜日などに残業をさせられていた。研修生を支援する団体の指摘を受け、法務省が調査に乗り出した結果、不正を確認したという。
第1次受け入れ機関は、研修先企業が適正に実習するよう指導・監督する義務がある。同協会も入管OBらが、3カ月に1回の割合で全国各地の企業を回って、経営者や実習生らと面談する定期監査をしていた。
ただ、同協会は2008年にも、三重県内の研修先企業が、正規の実習生以外に不法残留の中国人も雇っていたのを見逃したとして名古屋入管から「監督体制が不十分だ」と行政指導を受けていた。協会幹部は今回の処分を受け、「企業側には国の法令を順守するよう再三指導してきたが目配りが足りなかった。処分は重く、事業から撤退せざるを得ない」と話した。
同協会によると、設立は1969年。91年以降、同協会を通じて、のべ約4千人の外国人研修生が来日し、水産加工や繊維業など全国約120社で研修してきた。
協会を所管する厚労省労働基準局は「協会が処分を受けたことは極めて遺憾。技能実習生が引き続き実習を受けられるよう、別の受け入れ機関への移籍を含めて指導していきたい」としている。
外国人研修・技能実習制度をめぐっては、低賃金や残業代の未払いといった問題が多発している。今月から施行された改正入管難民法には、第1次受け入れ機関に対し、中小企業など労働現場への監督を強化するよう求める内容が盛り込まれた。
大規模農場で症状見過ごし 口蹄疫、感染調査の鍵 07/19/10(中日新聞)
宮崎県の口蹄疫問題で、4月下旬に疑い例が確認された川南町の大規模農場で、獣医師が県の家畜保健衛生所に異常を通報した6日前から、牛数頭によだれの症状が出ていたことが18日、経営会社への取材で分かった。当時は、国内10年ぶりとなる都農町の1例目の公表前。別の関係者によると、国が実施した抗体検査の結果から、大規模農場の感染時期は遅くとも4月上旬とみられる。
口蹄疫問題では数十軒の農場で症状が見過ごされた可能性が指摘されているが、農林水産省の疫学調査チームは牛700頭以上を飼育する大規模農場の状況が、感染拡大ルート究明の鍵の一つとみて調査を進めている。
大規模農場では都農町の1例目公表後、牛の舌にただれなどの異常も発見したが経過観察とし、すぐ届けていなかった。
経営会社側は「よだれはやや多い程度で風邪を疑った。1例目の公表前に口蹄疫を予見するのは著しく困難で、舌のただれなどがある牛が増えた時点で届けた」とする。
同社の弁護士によると、大規模農場では4月18日、よだれの症状がある牛数頭を把握。獣医師が風邪を疑い、ほかの牛も含め抗生物質を投与した。県が都農町での1例目を公表したのは同20日。翌21日には、大規模農場のすぐ近くにある農場2カ所でも疑い例が出た。
(共同)
【振興銀事件】側近の部署が債権審査 融資実績上げる目的に (1/2ページ)
(2/2ページ) 07/17/10(朝日新聞)
日本振興銀行(東京都千代田区)の銀行法違反(検査忌避)事件で、元会長の木村剛容疑者(48)が経営破綻した商工ローン大手「SFCG」などから買い取る際の債権の審査を、専門部署の「審査部」ではなく、側近の元執行役、関本信洋容疑者(38)がいた「企画部」に担当させていたことが16日、振興銀関係者への取材で分かった。木村容疑者が審査を形骸(けいがい)化させ、買い取り件数を増やすことで融資実績を上げる目的があったとみられる。
振興銀関係者によると、同行は平成18年、大阪市の商工ローン業者から債権買い取りを始めたのを契機に、債権取引業務を拡大。19年にはSFCGからも同様の買い取りを行うようになった。債権買い取りは、振興銀にとって手数料収入が得られるほか、債務者に対する融資実績としてカウントされるという。売却側は当座の現金を受け取れるメリットがあった。
債権買い取りの際、通常は融資審査を担当する審査部が債権が回収可能かなど信用性をチェックする。審査部が不適格と判断すると、買い取り契約が成立しない場合もある。
しかし、振興銀では審査部を通さず、関本容疑者が所属していた企画部が審査を実施。その際、関本容疑者が作った独自のマニュアルを使用していたという。同行関係者は「企画部による審査は法に抵触するわけではないが、債権買い取りを思うままに拡大させるため、(木村容疑者は)審査部を外したのではないか」とみている。
振興銀は中小企業への融資から債権買い取りに主業務をシフトしたことで、19年3月期に黒字化を実現。しかし、20年前後にSFCGから買い取った債権の多くが回収不能となった上、同社が21年2月に破綻した際、債権約3万5千件(総額約2千億円)の中にほかの金融機関にも譲渡した債権が含まれていた二重譲渡問題が発覚。経営悪化の一因となった。
検査忌避事件で削除されたメールには、SFCGとの債権取引に関するものが含まれていたとされる。同行の審査体制の甘さが結果としてSFCG側につけ込まれる形となり、経営悪化や検査忌避につながったとみられる。
削除の振興銀メール、偶然見つけたフォルダーにぞろぞろ 07/16/10(朝日新聞)
日本振興銀行(本店・東京都千代田区)の検査妨害事件で、業務用の電子メールの削除が発覚したのは、振興銀が提出しなかった行員の業務メールを、金融庁の検査官が偶然コンピューター内で見つけたことがきっかけだったことが関係者への取材でわかった。警視庁は、大量のメール削除は前会長木村剛(たけし)容疑者(48)が主導したとみて経緯をさらに調べている。
振興銀の検査は昨年6月に始まった。関係者によると、開始から約3カ月がたったころ、検査官が業務メールの検査とは別の作業をしていたところ、コンピューター内に行員のフォルダーがあるのを見つけた。このフォルダーを開けたところ、多数の業務メールを偶然見つけたという。
これらのメールは、振興銀が検査用に設けたサーバーからは削除されており、検査官の要請で振興銀が提出した分に含まれていなかった。削除前にサーバーから複写され、行員のフォルダーに保存されていたとみられるが、経緯は不明だ。
メールの発見を受け、検査官は振興銀の担当者に「メールを削除したのではないか」と指摘。担当者は「調べる」と答え、9月中旬に「必要なメールを抽出する作業中に過って消してしまった。人為的ミスで故意ではない」と虚偽の説明をしたという。
こうした説明内容は、検査開始を控えた時期に木村前会長と幹部らが検査への対応を検討した会議の場で話し合われ、検査で発覚した場合はそのように釈明すると申し合わせていたという。
このメール削除発覚後、金融庁はバックアップのデータからも復元し、削除されていた業務メールすべてを入手。その結果、計七百数十本が削除されていたことが判明した。サーバーへの接続記録から、元執行役関本信洋容疑者(38)らが削除を実行していたこともわかったという。
大相撲:福岡の山口組系組員が交渉同席 琴光喜関恐喝 07/16/10(読売新聞)
大相撲の元大関・琴光喜関(34)が350万円を恐喝された事件で、元力士の古市満朝容疑者(38)が3月、大阪市内でさらに1億3000万円を要求した交渉の場に同席したのは、福岡に拠点を置く山口組系暴力団の組員だったことが分かった。古市容疑者は以前、福岡市で風俗店経営にかかわっていたことが判明している。警視庁組織犯罪対策3課は、組員の関与について慎重に捜査している。
捜査関係者によると、古市容疑者は当初、調べに容疑を否認していたが、その後「うそをついていた」と認めた。脅し取った金については「阿武松(おうのまつ)部屋への差し入れや後輩力士におごったりした」と供述しているという。同部屋には、古市容疑者の父親が大阪府内で開く相撲道場の出身者や弟が所属している。
一方、東京地検は15日、古市容疑者を恐喝罪で起訴した。起訴状によると、古市被告は1月25日、賭博の仲介役だった同部屋の床山(29)に電話で「賭博に関与していることをマスコミや警察に知らせる」と伝言。翌26日に千葉県内で、床山を介し元琴光喜関から現金を脅し取ったとされる。【酒井祥宏】
赤字取引先に融資続行…削除メールに記述 07/16/10(読売新聞)
日本振興銀行(東京都千代田区)の検査妨害事件で、同行が昨年夏以降、毎月赤字を出すなど破綻(はたん)の恐れがあった融資先企業に、銀行法で禁じられた「回収困難な融資」を約半年間継続していた疑いが強いことが15日、関係者への取材でわかった。
警視庁が同法違反(検査忌避)容疑で逮捕した同行前会長の木村剛(たけし)容疑者(48)の指示で削除された電子メールには、こうした融資内容を記したものもあり、同庁は木村容疑者が不透明な営業実態を隠そうとしたとみている。
この融資先は、岡山市の電子機器販売会社。同社は、同行の融資先企業で作る任意団体で木村容疑者が理事長を務めていた「中小企業振興ネットワーク」に加盟。同社元役員によると、2007年秋頃から業績不振に陥り、09年夏以降、毎月約2000万円の赤字を出していた。同年8月時点で同行からの融資残高は約2億円だったが、同社の返済は滞り、不良債権化。元本返済の見込みもなかった。
しかし、同行は同月以降も同社に毎月2000万円前後の融資を継続。同年12月までに計7000万円以上の追加融資を行った。
同社は追加融資の一部で利息を返済したが、同12月、別の加盟会社と合併して解散した。元役員は「振興銀は湯水のように融資を続けていた。不良債権を隠したかったのだろう」と話す。
金融庁によると、回収見込みのない融資は銀行法で禁じられており、業務停止命令などの対象。警視庁幹部によると、同行が金融庁検査を妨害する目的で削除した700通以上の電子メールの中には、こうした不良債権隠しとみられる融資案件についての記述もあった。警視庁は、削除されたメールの内容を分析、経営実態についても調べている。
◇
東京地裁は15日、木村容疑者や同行前社長の西野達也容疑者(54)ら5人について、10日間の拘置を認める決定をした。
木村前会長、検査中に振興銀株手放す 高値で大量売却か 07/15/10(朝日新聞)
銀行法違反(検査忌避)容疑で逮捕された日本振興銀行前会長の木村剛(たけし)容疑者(48)が、金融庁の検査期間中に、自ら保有していた大量の振興銀株を手放していたことが分かった。このうち今年3月には、950株、約3億円分を、同行から融資を受けている取引先に売却していた。検査後、同行は赤字に転落しており、前会長は高値の状態で売却したとみられる。
振興銀の開示資料などによると、木村前会長は金融庁の検査が続いている2009年10月から今年3月末までの間に、3249株以上を手放していた。木村前会長は09年9月末時点で、発行済み株式の6.2%に当たる1万1千株を保有する筆頭株主だったが、今年3月末時点では開示対象となる10位以内から外れており、10位の保有株数から算定すると、半年で保有株式の3割以上を手放したことになる。
同行の内部資料などによると、木村前会長は今年3月、同行の融資先で大株主でもある信用保証会社「中小企業保証機構」(本社・大阪市)に、同行株950株を売却した。関係者によると、1株あたりの価格は33万5千円だったといい、総額は約3億円になる。この株価は、同じ時期に実施した第三者割当増資のために決められた金額と同額で、中間決算では黒字だった09年9月末時点の純資産額などから割り出された。
しかし、同行は金融庁検査で貸し倒れ引当金不足を指摘され、積み増ししたために10年3月期には純損益が51億円の赤字に転落した。純資産から割り出す方法で株価を算定すると、純資産の目減り分だけ安くなり、前会長は高値で売り抜けたことになる。だが、同行は非上場で、インサイダー取引を禁止する金融商品取引法には抵触しない。
振興銀の株式を売買するには取締役会の議決が必要だが、木村前会長の取引について日本振興銀行は「個人情報保護の観点から、株式の取引の詳細については答えられない」(経営管理室)とし、売却額や売却先を公表していない。中小企業保証機構は「取材対応はできない」としている。(大津智義、大平要)
振興銀:全支店に「証拠隠滅」指示 中小企業ネットの書類 07/15/10(毎日新聞)
日本振興銀行(東京都千代田区)による検査妨害事件で、同行が5月下旬に金融庁から一部業務停止命令を受けた後、同行の融資先企業などで構成する任意団体「中小企業振興ネットワーク」との取引に関する書類やメールを破棄するよう全支店に指示していたことが同行関係者への取材でわかった。同行が金融庁から銀行法違反(検査忌避)容疑で告発される見通しが強まっていた時期の指示だったことから、支店関係者は「捜査当局の家宅捜索に備えた証拠隠滅の可能性を感じた」と話している。【伊澤拓也、酒井祥宏、川崎桂吾】
支店関係者によると、指示があったのは5月27日の一部業務停止命令から数日後の6月初めだった。同行本店の営業幹部がテレビ電話を使った朝礼で「処分を受けたので、自粛ムードにするため銀行内のポスターやのぼりを外すように」と伝えた後、「中小企業振興ネットワークに関係する資料、メールを破棄すること」と指示した。破棄する理由についての説明はなかったという。警視庁による一斉捜索は6月11日だった。
捜査関係者によると、同行前会長の木村剛容疑者(48)らは検査対象の約280件のメールを意図的に削除したとして逮捕されたが、削除されたメールのほとんどは同ネットワークとの取引に関するものだった。警視庁は、同ネットワークとの不透明な取引を隠すために検査妨害が行われた疑いが強いとみている。
金融庁は09年6月~今年3月、同行のリスク管理状況などを調査するために実施した立ち入り検査で、検査対象のメールを破棄するなどの法令違反が確認されたとして、同行に対し、新規の大口融資や営業活動などの業務を4カ月間停止する一部業務停止命令を出した。
◆ ◆
警視庁は15日、木村前会長ら5人を銀行法違反(検査忌避)容疑で東京地検に送検した。
ウナギ偽装:セイワ、大福本社など捜索 警視庁と大阪府警 07/15/10(毎日新聞)
台湾や中国産のウナギかば焼きを「愛知県産」と偽装して販売していた問題で、食品加工会社「大福」(大阪府茨木市)がウナギ卸売り大手「セイワフード」(東京都港区)の指示を受け、販売先に渡す「ウナギ加工証明書」を偽造していたことが分かった。警視庁と大阪府警の合同捜査本部は15日、セイワと大福の本社など約10カ所を不正競争防止法違反(虚偽表示)容疑で家宅捜索し、偽装工作の全容解明を進める。
農林水産省近畿農政局によると、大福が作成した証明書には商品名や原産国、製造者などが記載されていたが、原産国は「愛知県三河産」と虚偽の記載をしていた。大福はセイワからの指示を受け、証明書を偽造していた。販売先に証明書を送付する法的義務はないが、小売店などが販売元に要請する場合があり、近畿農政局は偽装を隠ぺいするために証明書を偽造したとみている。
捜索容疑は、セイワや元常務(解任)、大福が09年12月~今年5月、大福の加工工場(茨木市)で台湾産ウナギ加工品約1トンを段ボール箱に詰め直して「愛知県産」のシールを添付。愛知県産ウナギかば焼きと偽装して京都市内の卸業者に販売したとしている。【町田徳丈】
日本振興銀:前会長ら逮捕 実態は「木村銀行」 07/14/10(毎日新聞)
「債務者の気持ちが分かる金融が必要」と中小企業救済を目指して日本振興銀行の設立を宣言して7年。小泉政権時代に金融庁顧問も務めた同行前会長、木村剛容疑者(48)が銀行法違反(検査忌避)容疑で警視庁に逮捕された。自他ともに認める「金融のプロ」がすべてを支配していた「木村銀行」。逮捕容疑は、かつて自らも作成に携わった金融検査マニュアルに基づいた検査への妨害だった。【酒井祥宏、川崎桂吾、袴田貴行】
木村前会長は98年に35歳で日銀を退職後、金融監督庁(現・金融庁)の金融検査マニュアルの検討委員を99年まで務めた。その後、金融と企業財務の総合コンサルティング会社を設立すると、不良債権問題の論客として、頭角を現した。日銀時代からの著作や共著はビジネス分野の月別ベストセラートップ10の常連で、経営不振企業を実名で列挙した「大手30社リスト」の作成者とされ、一躍注目を集めた。
大きな転機は竹中平蔵金融担当相(当時)に抜てきされ金融庁顧問に就任した02年だった。任務は大手銀行が抱える不良債権の抜本処理を目指す「金融再生プログラム」の策定だった。その発言力は大きく、木村前会長が不良債権処理のプロジェクトチームのメンバーに起用されたとの情報が流れると、銀行株を中心に株価がバブル経済崩壊後の最安値を更新するほどだった。
「債務者の気持ちが分かる金融が必要。中小企業に必要な資金を供給する」。03年8月に日本振興銀行の設立を発表し、05年には社長に就任した。同年6月に会長になるとブログで「12年には1兆円の金融グループになる」と豪語したが、09年3月には商工ローン大手「SFCG」(破産手続き中)から買い取った債権の二重譲渡問題が発覚。今年3月期決算の純損益が51億円の赤字となり、引責辞任に追い込まれた。
金融庁顧問に就任前、毎日新聞の取材に「(不良債権問題は)個別銀行に任せておいては片づかない。金融当局が強権を振るう形で一斉査定するなどのプロセスが必要」と述べていた木村前会長。強く主張した金融検査に自らつまずいた形となった。
ある捜査幹部は「振興銀行は木村前会長の個人商店。木村銀行だった。検査忌避は木村前会長の了解なしにはあり得ない」とみる。経済ジャーナリストの須田慎一郎さんは「素人でもやらないような検査忌避をしたとするならば、金融のプロという自負と金融庁顧問をしたおごりがあったのでは」と指摘する。
◇日本振興銀行と検査妨害を巡る経過◇
04年4月 木村剛容疑者が東京青年会議所有志と開業
05年1月 社外取締役の木村容疑者が社長就任
6月 木村容疑者が社長を退任し会長に就任
08年4月 3月期決算で初の経常黒字と発表
09年2月 SFCG破綻(はたん)
3月 SFCGから買い取った債権の二重譲渡問題が発覚
6月 金融庁の立ち入り検査開始
10年3月 立ち入り検査終了
5月 木村容疑者が赤字決算の責任を取り退任
〃 金融庁が4カ月の一部業務停止命令
6月 金融庁が検査妨害で刑事告発。警視庁が家宅捜索
7月 警視庁が木村容疑者らを検査妨害容疑で逮捕
やばいメール消しておけ「木村前会長が指示」 07/14/10(読売新聞)
日本振興銀行の検査妨害事件で、同行の元執行役(38)が警視庁の任意の事情聴取に対し、金融庁の立ち入り検査前に開いた対策会議で、同行役員らとともに出席していた木村剛(たけし)・前会長(48)から、メールの削除を指示されたなどと供述していたことが13日、関係者への取材でわかった。
対策会議では、違法性の強い取引内容を記した電子メールを検査前に削除する方針が決められたとされ、警視庁は木村前会長がメールの削除に深く関与していたとみて調べている。
関係者によると、対策会議は、金融庁が同行に立ち入り検査の通知を出した3日後の昨年5月29日に同行内で開かれた。警視庁はこの会議がメール削除などの検査妨害を行うための謀議の場だったとみて、複数の関係者から任意で事情を聞いてきた。その結果、元執行役が、会議には自分を含む同行役員ら3人のほか、木村前会長も出席していたことを認め、「会議の場で木村前会長から、『やばいメールは消しておけ』と指示された」などと供述。会議の後も、木村前会長から複数回、メール削除が確実に完了したかどうかの問い合わせを受けたとする趣旨の供述をしたという。
同行は、商工ローン大手「SFCG」(破産手続き中)から債権を買い取り、その後、出資法の上限金利(29・2%)を上回る45・7%の手数料を上乗せしてSFCGに買い戻させる取引を行っていたことが明らかになっており、削除されたメールの中には、こうした取引内容も含まれていた。
金融庁は同行に検査の通知を行った際、社内の業務用メールの保存を要請していたが、削除されたメールにはこうした業務用メールが多数含まれていた。
元執行役は、警視庁の調べに、昨年6月16日から始まった金融庁の立ち入り検査で、検査対象メールが削除されていたことが発覚した際のことについて、「木村前会長から、『ヒューマンエラー(人為ミス)ということで対応しろ』と指示を受けた」とも話したという。
捜査関係者によると、木村前会長は警視庁の任意聴取に検査妨害への関与を否定。同行が銀行法違反(検査忌避)容疑で捜索を受けた翌日の今年6月12日には、西野達也社長が記者会見で、対策会議への自身の出席を否定した上で、木村前会長の関与については「コメントしない」としている。警視庁は、ほかの同行幹部などからも詳しく事情を聞き、対策会議の詳しいやり取りについて調べている。
振興銀の木村前会長ら立件へ 金融庁の検査妨害容疑 07/13/10(朝日新聞)
中小企業向け融資を専門にする日本振興銀行(本店・東京都千代田区)が金融庁の立ち入り検査の際、業務にかかわる電子メールを削除し検査妨害したとされる事件で、警視庁は、木村剛前会長(48)と元幹部ら数人について、銀行法違反(検査忌避)容疑で近く立件する方針を固めた。
振興銀をめぐっては、貸金業者への事実上の融資が出資法違反にあたる疑いがあるほか、不透明な融資も指摘されており、警視庁は不正の全容解明を目指す。
金融庁は2009年5月に、振興銀に立ち入り検査の実施を通知した。関係者によると、この後、振興銀の当時の執行役らは同行のサーバーに接続し、業務に関する電子メール数百通を削除。6月16日から始まった検査で、検査官に業務メールの「すべて」と偽って、提出した疑いが持たれている。メールの削除は、木村前会長の指示の下に行われた疑いがあると警視庁はみている。
削除されたメールには、経営破綻(はたん)した商工ローン大手SFCGとの違法な取引に関するものが含まれていた。振興銀はSFCGから債権を買い取る際、一定期間経過後に買い戻させる約束で、事実上の融資をしていた。金利にあたる手数料は年45.7%にのぼり、出資法が定める上限金利の29.2%を上回っていたという。
また、振興銀の融資先企業など百数十社で構成する「中小企業振興ネットワーク」の加盟企業との間で交わされたメールも削除されたという。
捜査2課は、金融庁の告発を受け、今年6月11日、検査忌避の疑いで振興銀の家宅捜索に着手。ネットワーク加盟企業などを含め、幅広く関係資料を押収してきた。また、木村前会長や幹部らから任意の事情聴取を重ねてきた。
力士ら報道後に賭博メール削除、証拠隠ぺい? 07/08/10(読売新聞)
大相撲の野球賭博問題で、賭博に関与したとして警視庁が事情を聞いた複数の力士が、元大関琴光喜(34)が野球賭博に絡んで口止め料を脅し取られたと週刊誌が報じた5月下旬以降、携帯電話のメールを削除したり、機種変更したりしていたことが8日、わかった。
同庁は、携帯電話を使って野球賭博の仲介役と連絡を取っていた力士らが、賭博の証拠を隠す目的で行ったとみている。
同庁は8日も引き続き、八角部屋(東京都墨田区)や北の湖部屋(江東区)など関係先数か所を賭博開張図利容疑で捜索するとともに、琴光喜や前大嶽親方(42)からも再び、事情を聞いている。
警察当局や相撲関係者によると、警視庁は、琴光喜の問題が報じられた後の5月下旬以降に行った力士たちへの事情聴取で、携帯電話の通話履歴やメールを見せるよう求めた。ところが、複数の力士は、野球賭博にかかわるメールについて、「週刊誌報道の後に削除した」などと話し、携帯が壊れたとの理由で機種変更した力士もいた。
野球賭博への関与を打ち明けた阿武(おうの)松(まつ)部屋の元力士によると、同部屋では、プロ野球の試合が始まる約2時間前、胴元から仲介役の幕下力士(34)や床山(29)の携帯に対戦カード別のハンデなどがメールで送られ、これを参考に力士らは、試合開始30分前までに携帯やメールで賭け金の額などを仲介役に伝えていたという。
規則は規則。大相撲野球賭博が事件として報道されなくとも違法行為。今までは見つからなかった。
もし違法と思わないのだったら、なぜ携帯の情報を消去するのか??確信犯達の悪質行為だ!
日本相撲協会は暴力団との関わりはないと言ったが信用できないね!一般法人でやっていくべきだ。
名古屋場所 案内所建物を許可前に着工、急きょ撤去 07/08/10(朝日新聞)
大相撲名古屋場所に来た観客に弁当販売などのサービスをする「相撲案内所」のプレハブ建物が、名古屋市の許可が下りる前に着工するという不適切な手続きをしていたことがわかった。建物の基礎がなかったことも判明。日本相撲協会の担当・錦島親方(元幕内蔵玉錦)は「間に合わないから、(プレハブを壊して)応急措置でテントでやる」と説明している。
名古屋市建築指導部によると、建物はプレハブで軽量鉄骨2階建て。着工に必要な建築確認申請の「確認済証」を、市が今月6日に交付したが、それより前に着工していたことが発覚した。市が現地を確認したところ、建物の基礎が無かったこともわかり、市は確認済証の交付前に着工したことを注意。基礎を新たに造るか、同等の補強工事をするよう指導した。
8日朝、建築主の協会側が「改修する時間的余裕が無いので、建物を撤去し、テントで対応する」と市に連絡した。
案内所の女性は度重なる不測の事態に困惑した様子。「弁当を扱っているのに空調が不十分だと、衛生上困る」と話した。
中日新聞社スポーツ事業部の加藤宏幸部長は「費用の補償問題などは、場所後に話し合うことになる」と話した。
相撲案内所は、「相撲茶屋」とも呼ばれ、独立経営している。自分の店でチケットを買ってくれた観客に、席まで飲食物を届けるなどのサービスをしている。
会場内の設備を担当する錦島親方は「申し訳ない気持ちです」と話した上で、市から指摘を受けたことに、「今まで何十年もやってもらって、何も問題なかったのに」と戸惑っていた。
日本相撲協会を「公益財団法人」として認定する必要はない。一般法人でよい。今までの不祥事に対する対応、そして
今回の事件に対する対応は問題がありすぎ。伝統と言って悪しき古い体質まで継承している。
仙谷官房長官:暴力団との関係断て 相撲協会の処遇に言及 07/06/10(毎日新聞)
仙谷由人官房長官は7日、日本相撲協会の処遇について「黒い世界との関係が完全に払拭(ふっしょく)されないと、公益法人という形で興行を行うのは許されない」と述べた。同協会は文部科学省所管の財団法人で、税制上の優遇措置を受けているが、暴力団との関係を断たない限り、公益法人として存続させるのは難しいとの認識を示したものだ。
政府は公益法人制度改革に取り組んでおり、現在の公益法人は第三者委員会「公益認定等委員会」に公益性を認定されない限り、一般法人となる。
日本相撲協会は「公益財団法人」への移行を目指しているが、仙谷氏は7日の記者会見で「そこ(暴力団)との関係があっては通用しない。『公益』と言うわけにはいかないというのは、市民的な感覚として当然ではないか」と強調した。【横田愛】
角界にまた衝撃 村山理事長代行「捜査に全面協力指示」 07/06/10(朝日新聞)
名古屋場所の初日を4日後に控えた角界に、また衝撃が走った。
一斉捜索の知らせを受けた日本相撲協会の村山弘義・理事長代行は、疲れた表情で口を開いた。「捜査には全面的に協力するよう、すでに関係者には指示している」
代行への就任が決まった後、自宅には脅迫電話がかかってきたという。6日には文部科学省やNHKをまわって、賭博に関係した力士らの処分や、不祥事が続く協会の改革などについて説明した。テレビ・ラジオでの生中継の中止は、重く受け止めざるをえなかった。
元東京高検検事長。捜査を指揮する側から、捜査を受ける組織のトップへ立場が変わった。「警察の捜査によって全容が解明され、出される結果に対し、協会として対応していきたい」と話した。
一方、愛知県尾張旭市の阿武松(おうのまつ)部屋の宿舎では、約1時間半にわたる家宅捜索が終わると、師匠(元関脇益荒雄)が「お騒がせしてすみません。ただいま捜索を受けましたが、詳しいことはお許し下さい」と頭を下げた。部屋の半数近い力士が野球賭博をしていたとして、協会から降格の懲戒処分を受けている。
この日の朝げいこでは、名古屋場所を謹慎休場する幕内の若荒雄関や十両の大道関が、若手に交じって汗を流した。しかし、けいこ場の周りには「関係者以外立入禁止」の張り紙とロープが張られ、力士たちは落ち着かない様子だった。
愛知県扶桑町の境川部屋の宿舎でも、謹慎中の幕内豪栄道関や豊響関らが早朝から通常通りけいこをした。境川親方(元小結両国)は、家宅捜索について「テレビで見て知ったが、東京の部屋からはまだ連絡がない。なかなか土俵外のことが落ち着かなくて、ファンに申し訳ない。力士たちも動揺している」と複雑な表情。その後、宿舎にも捜査員が入った。
愛知県愛西市に宿舎がある大嶽部屋にも、困惑が広がった。前師匠(元関脇貴闘力)が、野球賭博へのかかわりが悪質だったとして協会を解雇された。前日に手続きが完了し、正式に部屋を継承した大嶽親方(元十両大竜)は、けいこを終えると「(家宅捜索は)うちにも来るでしょうね。何も心配することはないし、捜査があるなら協力したい」と淡々と話した。
テレビでコメンテーターが大相撲野球賭博の事件は警察が解明すると無責任な事を言っていた。
警察は警察が捜査したい範囲以外は捜査しないし、関係者から調書も取らない。
警察が事件の全容を捜査すると発表していない限り、警察が全容を解明するために捜査するとは思わないほうが良い。
村山理事長代行の任期は3週間。短すぎる。村山理事長代行が適任かどうかはわからないが、外部の目でおかしなところが
あれば改革が必要だろう。今回はやくざが絡んでいるとすると、中井国家公安委員長は警察に徹底的に捜査することを
指示するべきだ。
【大相撲野球賭博】「捜査に協力しない者いる」 中井国家公安委員長が異例の苦言 07/06/10(産経新聞)
力士らの野球賭博問題で中井洽(ひろし)国家公安委員長は6日、閣議後の定例会見で、日本相撲協会の村山弘義理事長代行らに対し、「十分捜査に協力していない者がいる」と警視庁の捜査に協力するよう協会として関係者に通達を出すよう要請したことを明らかにした。
村山理事長代行ら協会幹部は5日、警察庁を訪問、中井氏や安藤隆春・警察庁長官に処分内容などを報告していた。この際、中井氏は「捜査にはさらに時間がかかる」と捜査の長期化に言及。「大半(の力士や親方)は協力していただいているが、協力していない者もいる」と苦言を呈し、通達を要請したという。
中井氏は6日の会見で「テレビで釈明するのは熱心だが、捜査では言を左右する者がいる。自分の身を守る意識があるんだろうが、きちっと話をし、捜査が早く済むようにしてほしい」と求めた上で「協会全体の体質改善というのはまだまだこれから。長い道のりだろう」と述べた
大阪市の団体、手抜き監査…決算書点検せず「健全」 07/06/10(読売新聞)
大阪市の外郭団体「市消防振興協会」の経営状況について、2008年度に包括外部監査を行った公認会計士(66)が、決算書などの財務諸表を点検していないのに報告書に「決算書を確認した」と記載し、「財政状態は健全」と評価していたことがわかった。
市の独自監査で今年5月、同協会のずさんな会計処理が発覚し、市監査委員は「外部監査人の主張や説明とは大きな乖離(かいり)がある」と異例の指摘をしていた。外部監査の信頼性が損なわれかねない事態に、専門家からは「前代未聞の手抜き監査で、到底市民の理解は得られない」と批判の声が上がっている。
同協会は、市民の防災意識向上などを目的に1992年に設立。市が100%出資し、応急手当ての知識を広める講習会の開催や月刊誌「大阪消防」の発行を市から随意契約で請け負うなどしている。市によると、問題の外部監査は、同協会など計13外郭団体の財務処理や経営の効率性などを検証する目的で行われ、市は会計士と06~08年度に契約を結び、各年2000万円の報酬を支払っていた。
この会計士は報告書で「03~07年度の決算書を関係書類と適宜照合した」などと明記。同協会については、発行書籍の在庫が多すぎる点などを指摘したが、「財政状態は健全と言える」と結論づけた。
一方、市監査委員が同協会を個別調査したところ、08年度の帳簿の収支が12か月すべてで一致していなかったり、会計年度区分を勝手に変更するなど、数々のずさんな会計処理が明らかになった。07年度も同様だったが、外部監査では一切触れられていなかった。
不審に思った市監査委員が今年3月、会計士から事情聴取。会計士側は「監査日数が短く、財務諸表のチェックはできなかった。出納事務よりも委託契約の中身に焦点を絞った」などと説明し、「『健全』と記載したのはよくなかった」と話したという。
市監査委員の一人は「多額の税金を使っており、市民は当然、財務諸表を監査していると思っている」と批判し、報告書では「外部監査は市民の納得を得るものとなるよう取り組むべきだ」と言及した。
会計士は読売新聞の取材に「包括外部監査は財務諸表に何らかの保証を与えるものではない。団体ごとの監査方法を逐一記載すれば(見なかったことの)誤解は生まれなかったが、そのような断り書きは煩雑で、市民の関心事でもない。監査人としての責務は十分に果たした」としている。
自治体の包括外部監査の評価付けを行っている「全国市民オンブズマン連絡会議」幹事の井上善雄弁護士の話「監査の視点が違うと言っても、財務諸表さえ見ていないのは契約不履行だ。市は外部監査の対象になった他団体についても調査し、結果次第では報酬返金を求めるべきだ」
◆包括外部監査=自治体が弁護士や公認会計士ら外部の有識者と契約し、その自治体の予算執行や組織運営が適正に行われているかをチェックする制度。カラ出張などが社会問題化し、1997年の地方自治法の改正で中核市以上に義務付けられた。監査のテーマは監査人が設定する。
破綻前、納税も困難に SFCG、預金10億円割り込む 06/18/10(朝日新聞)
商工ローン大手「SFCG」(旧商工ファンド)が破綻(はたん)直前に資産を流出させたとされる事件で、同社は2008年8月には預金残高が10億円を割り込み、税の納付も困難な状況に陥っていたことが関係者の話でわかった。同社は同年10月ごろ債権譲渡を開始し、逮捕容疑の譲渡はその約2カ月後だった。
警視庁は、同社の財務状態が悪化する中、元社長大島健伸(けんしん)容疑者(62)=民事再生法違反容疑などで逮捕=らが破綻への認識を強めていったとみて調べている。
関係者によると、SFCGは08年2月ごろから資金繰りが厳しくなり、同年8月には預金残高が10億円弱にまで減少。10月末に約28億円の国税や地方税の納付期限を控えていたが、払えない状態に陥っていた。こうした中、大島容疑者は10月ごろから、債権を親族会社に移すよう指示するようになったという。
同年10月下旬に約129億円の債権を親族会社へ譲渡したと登記したのを手始めに、譲渡額は増加。逮捕容疑を含む、12月の登記分だけで少なくとも親族会社3社に計約714億円の債権を流出させた。
大島容疑者は、親族会社に債権を無償譲渡する方法についても部下から報告を受け、頻繁に指示していたという。
SFCG元幹部によると、同年12月には、部下から大島容疑者に、金融機関などへ債権の二重譲渡が多く行われていることが報告されていたという。
日本相撲協会は大相撲を運営している文部科学省公認の財団法人だ。しかし、文部科学省はもう面倒を見る必要はないと思う。
不祥事や暴力団。税金を使っていても対応が遅い。多分、意識改革が出来ないことを示している。他のスポーツのように自助努力で運営させればよい。
角界と暴力団、根深い関係 用心棒・祝儀・後援会… 06/16/10(朝日新聞)
「手間のかからない金づる」――。大相撲の大関琴光喜関らが手を染めていた野球賭博は、暴力団の資金源の一つとされる。以前は興行に直接かかわるなど、暴力団は相撲界と縁が深かったが、今はほとんど表に出ない。正体を隠したまま、力士と親密な関係を築く場合もあるという。
■商談や遊びの場
野球賭博は「大した手間もかけず1シーズンで数億円稼げる金づる」と関東の暴力団関係者はいう。野球の盛んな広島が発祥地といい、その後全国に広がった。「角界にも顧客はいる」とこの関係者は明かす。
そもそも大相撲は、かつて暴力団の有力な資金源のひとつだった。山口組は昭和初期から、浪曲や歌謡曲などの芸能とともに大相撲の興行に力を入れていた、と警察の内部資料にある。
警察の取り締まりで、暴力団が直接興行を取り仕切るケースは激減したが、地方巡業などには間接的にかかわっているという。興行の期間中にトラブルが起きないよう「用心棒」役を担うなどして「力士との接点ができた」と関東の暴力団関係者は話す。
ひいきの力士を接待して飲み食いさせ「祝儀」名目で多額の現金を渡す。力士を応援する会社経営者が居合わせることも多く「興行がカネにならなくても、接待で知り合う社長らに話を持ち掛け、カネを引っ張る算段をする」と、この関係者は明かす。
別の暴力団関係者は「本場所は組幹部の社交場だった」と言う。ある場所の特別席は、特定暴力団幹部の「指定席」として知られていた。「維持員席」とみられるが、この関係者は「入手の経緯は知らない」と言葉を濁す。
テレビ中継に映ることで、刑務所に服役中の仲間の組員を励ます狙いもある一方、同席する別組織の組幹部との商談や遊びの場でもある。土俵上の取組を賭けの対象にすることもあり、1回の取組で数百万円が飛び交うという。
検査直前にパスワード漏れか 振興銀役員ら接続権限なし 06/14/10(読売新聞)
日本振興銀行が金融庁の立ち入り検査の際、業務の電子メールを削除して検査を妨害したとされる事件で、削除を実行したとされる当時の執行役やその部下は、サーバーに接続する権限を本来持っていなかったことが関係当局への取材でわかった。検査の直前に行内でパスワードなどが漏れた疑いがあるという。
警視庁は、違法な債権譲渡取引を隠すためにメールを削除するとの判断が、行内でどのように決定されたか、解明を進めている。
立ち入り検査は昨年5月26日に金融庁から振興銀に通知され、6月16日に始まった。通知の際、業務のメールを用意しておくよう求められ、この直後に数百本のメールが削除されたという。当時の融資企画担当の執行役やその部下らが削除したとみられる。
関係当局者によると、立ち入り検査にあたり、検査官は金融機関から、メールが保存されているサーバーに接続するための新しいパスワードなどの提供を受け、それ以降、金融機関が勝手に接続できないようにする。
パスワードはシステム担当者から検査官に付与され、知るのは行内で数人に限られる。しかし、執行役らはこのパスワードで接続してメールを削除したとされ、パスワードが漏れていたとみられる。
削除されたメールは、経営破綻(はたん)した商工ローン大手SFCGとの間の債権譲渡など、違法性が疑われる取引にかかわるもの。執行役が自らSFCG側とやりとりしたものが多く含まれるという。
一方、振興銀は、立ち入り検査の際、検査官の聞き取りに応対する担当者を執行役ら数人に限定。聞き取りに応じる時間も制限していた。ほかの金融機関の検査ではすぐに提出される融資先の資料も振興銀は「存在しない」としてすぐに出さないなど、検査に非協力的だったという。
振興銀検査妨害、疑惑の会議に社長「参加せず」 06/12/10(読売新聞)
中小企業向け融資を専門とする日本振興銀行(本店・東京都千代田区)が金融庁の検査資料となる電子メールを意図的に削除したとされる検査妨害事件で、同行の西野達也社長は12日、都内で記者会見し、「預金者や取引先の皆様に大変な心配と迷惑をかけた」と謝罪した。
同事件を巡っては、同行の役員らが金融庁の立ち入り検査前に対策会議を開き、出資法違反の疑いが強い取引内容を示した電子メールについて、削除する方針を決めた疑惑が浮上しているが、西野社長は「会議には参加していない」と述べる一方、対策会議が開かれたことを知っていたかどうかについては「捜査中」を理由に回答を避けた。
西野社長はメールの削除を「昨年9月に金融庁の指摘を受けて知った」と説明。木村剛・前会長(48)の関与については「捜査の進展を待ちたい」と述べるにとどまった。
昨日、ニュースで口蹄疫のかかった牛を見落とした獣医の言い訳を聞いた。しかし、「口蹄疫」の事をまったく考えていないわけではない。
ならば、もし感染していた時のリスクを考えれば再チェックをするべきだったのではないのか??風評を恐れた??インターネットで
検索すると10年前にも宮崎は口蹄疫を経験しているではないか。結局、初歩的な対応を怠ったために被害の規模を縮小できた可能性も
あるのに税金が無駄に投入される。全被害を保障すると赤松農水大臣の発言に税金が使われると国民は思わないのだろうか??
まあ、どこが夏の選挙で議席を伸ばすのかしらないけど、民主党は終わりだと思うよ!期待は期待でしかなかった。日本の将来は明るくない。
だからこそ、真剣に将来の事を考え将来のために効率よく税金を使わないといけないのに、日本の政治は茶番劇。最近、愛国心とか聞かなくなった
けど、将来、日本を見捨てる人達は日本を見捨てるんだろうな!日本を立て直すよりも、自分達だけ脱出するほうが簡単。本当は
日本から脱出できない国民が真剣に将来を考えなければいけないのだろうけど、そんな事を思っていないから政治家の茶番劇は続くのだろうね!
10年前の口蹄疫のこと。 05/19/10(アセラブログ)
宮崎で発生した口蹄疫
霊長類フォーラム:人獣共通感染症(第96回)4/19/00
宮崎で発生した口蹄疫
口蹄疫が宮崎県で発生し大きな問題になっています。92年ぶりだそうです。病原 体の口蹄疫ウイルスは最初に発 見されたウイルスで、1898年にドイツでレフラーとフロッシュにより、その存在 が証明されたものです。その経 緯については私の著書「エマージングウイルスの世紀」p. 18と本講座(第58回) で触れています。
口蹄疫ウイルスは古い論文ではヒトに感染したことが報告されていますが、私は人 獣共通感染症とみなす必要はな いと考えています。そのため、今回の口蹄疫の発生を本講座で取り上げるつもりはあ りませんでした。しかし、よく 考えてみるとこれはエマージングウイルス感染の典型的なものです。マレーシアでの ニパウイルス感染では100万 頭近いブタが、1997年に台湾で発生した口蹄疫では385万頭のブタが殺処分さ れましたが、前者がヒトの健康 被害、後者は畜産への被害という観点で異なるだけです。エマージング感染症での危 機管理という面から眺めると本 質的には同じと考えられます。そこで本講座でも危機管理の観点から宮崎県での口蹄 疫を取り上げることにした次第 です。
1.口蹄疫対策の国際的枠組み
ヒトの感染症予防・制圧のための国際機関は世界保健機関WHOです。家畜伝染病の 分野でWHOの役割を果たしてい るのは国際獣疫事務局OIE (Office International des Epizooties)です。別名 Animal WHOとも呼ばれています。これには世界155カ国が加盟しており、日本代表は農水 省畜産局衛生課長です。私は1 0年間ほど、OIEで学術顧問と動物バイオテクノロジー作業部会の委員をつとめてい ます。OIEは国際的な家畜の貿 易の際に監視が必要な家畜伝染病をリストA, Bとふたつに列記しています。リストAは危険性の高いもので、その中でも口蹄疫と牛 疫がトップクラスです。リスト Bには日本脳炎などが含まれています。
口蹄疫の診断はOIEが作成している診断法とワクチンのための基準マニュアル Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccinesに準じて行われます。国際的に共通の基準で診断が行われるわけです。OIE が指定した世界口蹄疫レファ レンス・センターは英国家畜衛生研究所Institute for Animal Health(IAH)パーブラ イト支所の中に設置 されています。ここはロンドンのヒースロー空港から車で40分くらいの所にあり、 近くにはアスコット競馬場もあ るロンドン郊外の最高級住宅地のはずれです。センター長はポール・キッチンPaul Kitchingがつとめています。ついでですが、私は10年あまりパーブライト支所で牛 疫ウイルスについて共同研究 を行っており、ポール・キッチンは動物実験のライセンス保持者として協力してくれ ています。(英国は動物福祉の 観点から動物実験を行うにはライセンスが必要ですので)。
口蹄疫は全世界に存在しています。OIEが清浄国と認めているのは日本や欧米など 39カ国に過ぎません。とくに 現在大きな問題になっているのはアセアン諸国で、OIE、国連食糧農業機関FAOと国際 原子力機関が共同で南アジア 口蹄疫キャンペーンを開始しています。(国際原子力機関が加わっているのは意外か もしれませんが、ここは口蹄疫 や牛疫の診断のためのELISAキット作製の面でFAOに協力しています)。これにはOIE のアジア・太平洋地域を担当 する東京事務所の代表である小沢義博先生が中心的役割を果たしておられます。
2.宮崎での発生の経緯
農水省のプレスレリーズが家畜衛生試験場(家衛試)ホームページ http://ss.niah.affrc.go.jp/に転載 されており、リアルタイムに情報が提供されています。また、その英文のまとめに相 当するものを家衛試の佐藤国雄 研究技術情報官がProMedに投稿されています。それらのニュースにもとづいて整理し てみます。
最初の発生例:3月8日に飼育中の肉用牛10頭のうち、2頭に発熱が見つかって います。これが発症時期と推測 されます。12日に獣医師に診察してもらい抗生物質などが投与されましたが、ほか のウシでも発症するものが出て きたために21日に獣医師が家畜衛生保健所に届け出ました。
血液と皮膚の病変部のサンプルが22日に家衛試に送られ、25日にELISAで口蹄 疫抗体陽性、またもっとも遅く 19日に発症したウシの皮膚のサンプルでPCR陽性の結果が得られました。そこで、 疑似患畜として10頭すべてが 殺処分されました。 第2の例:家衛試での血清サーベイランスで見いだされたものです。4月1日に肉 用牛9頭を飼育している農場の 牛1頭が抗体陽性と判明し、あらためて血清検査を行ったところ9頭中6頭に抗体が 検出されました。これも疑似患 畜として4月4日にすべて殺処分されています。なお、3月28日の立ち入り検査の 際、これらの牛では臨床症状は 見られていません。
第3の例:同じく血清サーベイランスで見いだされたものです。肉用牛16頭を飼 育している農場で3月29日に 採取した2頭の血清が抗体陽性と判明したため、あらためて10頭の血清について検 査を行った結果、4月9日に1 0頭すべてが抗体陽性と診断されました。その結果、疑似患畜として16頭すべてが 殺処分されました。
4月14日に家衛試の海外病研究部の特殊実験棟で、このウシの喉の粘膜サンプル から初代ウシ腎細胞培養でウイ ルスが分離され、ELISAとPCRで口蹄疫ウイルスと同定されました。
ところで、抗体陽性のウシは疑似患畜となっていますが、清浄国で、信頼しうる ELISAで抗体が見つかれば疑似で はなく真性とみなせるものと思います。OIEの基準マニュアルでは口蹄疫の診断はウ イルス抗原の検出で行うとなっ ていますが、清浄地域でワクチンを用いていない場所では抗体の検出でも診断可能と いう趣旨が述べられています。
3.原因ウイルス
口蹄疫ウイルスはエンベロープを持たない小型のRNAウイルスです。エンベロープ の代わりにウイルス粒子の外側 にはカプシドと呼ばれる殻があり、その主要な蛋白はVP-1です。これは非常に変異を 起こしやすい性質のもので、I AHではVP-1の配列にもとずいて口蹄疫ウイルスの系統樹を作っています。第1例の口 蹄疫ウイルスVP-1のPCR産物 の配列は家衛試で解析され、さらにIAHで調べられた結果、アジアで流行しているO型 ウイルスではあるが、新しいサ ブタイプのものとして、O/Miyazaki/JAP/2000株という仮称が提案されました。
1997年の台湾での発生はブタに親和性のある口蹄疫ウイルスとみなされていま す。症状が見られたのはブタと 水牛です。一方、1999年6月に台湾の金門島では乳牛で症状がみられており、1 997年のウイルスとは別のウ シ親和性のものと推測されています。ただし、同じウシでも在来種の黄牛では症状は みられません。韓国で現在発生 しているものは乳牛で症状が見られています。
宮崎の発生では肉用牛である和牛が感染したわけですが、病変は軽度であって教科 書に出ている口蹄疫に特徴的と される水疱はほとんど見つかっていません。
4.ワクチン
口蹄疫の予防には不活化ワクチンが用いられています。中国は生ワクチンを開発し ていますが安全性に疑問があり ます。OIEでは生ワクチンは認めていません。ヨーロッパではフランスのリヨンにあ るメリューと英国のウエルカム が不活化ワクチンを製造しています。ウエルカムの製造施設はIAHの建物を間借りし たものです。すなわち同じ敷地 内に民間の口蹄疫ワクチン製造施設とOIE世界口蹄疫レファレンス・センターが存在 していることになります。日本 は非常用にヨーロッパからワクチンを輸入して備蓄しています。
ウイルス感染の場合、有効なワクチンがあれば流行を阻止するためにはそれを使用 するのが常識ですが、口蹄疫の 場合には簡単にはあてはまりません。OIEが口蹄疫清浄国とみなす条件としてワクチ ンを使用していない国で病気が 発生していないこととなっています。口蹄疫の監視は抗体調査に依存しています。も しもワクチン接種したウシがい ると、感染による抗体か、ワクチンによる抗体か、区別ができなくなります。発生が 疑われる場合でも、これはワク チンによる抗体だと言い逃れされることにもなります。
今回のような限局した発生であればワクチンを使用せずに、発生のあった農場の動 物をすべて殺処分することが清 浄国の立場を保つのに必要なわけです。もしも発生地域の周辺でワクチン接種を行っ たとすると、ワクチンを接種さ れたウシがすべていなくなったのち、3ヶ月間病気の発生がないことという条件にな ります。一度ワクチンを使用す ると、清浄国にもどるには大変な手間と期間が必要となります。有効なワクチンが あっても、畜産の保護という観点 からワクチンの使用は簡単には実施できません。
しかし、流行が広がればワクチンを使用しなければならない事態になります。宮崎 とほぼ同じ頃に韓国でも口蹄疫 が66年ぶりに発生し、かなり広がっているようです。4月14日付けのAP電によれ ば、韓国ではこれまでに900 頭のウシとブタを殺処分し、20万頭にワクチン接種を行ったとのことです。さらに 国中の偶蹄類1100万頭すべ てにワクチン接種を行う計画と伝えられています。
5.診断体制
口蹄疫の最大の発生地域に日本は囲まれています。そして、口蹄疫ウイルスは物理 的処置に非常に抵抗性が強いウ イルスです。藁に付着した口蹄疫ウイルスは夏では4週間、冬では9週間生存すると いわれています。家畜の飼料や 敷き藁として輸入される稲藁や麦藁に付着して入ってくる可能性もあるわけです。台 湾や中国との人や物の往来を考 えれば、これまで日本に口蹄疫が入ってこなかったのは、むしろ幸運だったのかもし れません。今回と同様のことは これからも起こりうるものと考えるべきです。
今回は家衛試での抗体検査とPCRで迅速診断ができました。抗体検査も順調に進ん でいるようで、すでに3万以上 のサンプルで抗体陰性が確かめられています。しかし、背景を見ると充分な検査体制 ができていたとは思えません。
口蹄疫ウイルスはもっとも危険な家畜伝染病病原体として最高度の隔離のもとで取 り扱わなければなりません。そ のために特殊実験棟が海外病研究部に建築され、その使用のための安全管理規定は1 988年に作られました。私も その検討委員として参加しました。しかし、肝心の口蹄疫ウイルスの輸入は農水省か ら許可されず、現在にいたって います。
ウイルスがだめでもウイルスの遺伝子を用いた診断の方法もあります。現実に感染 症研究所ではレベル4実験室が 使用できないためにマールブルグウイルス、エボラウイルス、ラッサウイルス、Bウ イルスなどは遺伝子の面での診断 と、不活化抗原を用いたELISAなどの検査体制を作ってきています。
ところが、口蹄疫ウイルスについては、遺伝子の輸入も認められませんでした。わ ずかに認められたのは、輸入後 に期限が切れた不活化ワクチンを診断用抗原として使用することと、ウイルス遺伝子 の一部配列の合成核酸を作るこ とだけでした。建物ができても研究はまったく行えなかったわけです。
実は、私も口蹄疫ウイルスの遺伝子の一部を輸入しようとして10年ほど前に農水 省に申請したことがあります。 この経緯は私の著書「エマージングウイルスの世紀」p. 282にも書きましたが、ウイルス全体の遺伝子の20分の1くらいのサイズに過ぎな い430塩基対の遺伝子断片で 、感染性にはまったく関係のない部分です。具体的にはIRES (internal ribosome entry site)といって、蛋白を合成する際に必要な部分です。しかし、これも許可されませ んでした。米国ではプラムアイ ランドに農務省の海外病研究所があります。(この研究所のことは本講座(第60 回)でご紹介しました)。そこで 抽出した口蹄疫ウイルスのVP-1遺伝子はジェネンテックなどのベンチャーに提供さ れ、レベル1実験室で遺伝子工学 によるワクチン開発に利用されていました。そのことを明記したFederal Register(日本の官報に相当します)のコピーも添付したのですが、米国の科学的論 理は日本の行政当局では通用 しませんでした。
宮崎の発生での診断に役にたったのは、IAHから提供されていたELISAキットと、数 年前にやっと農水省から許可 してもらって作ってあった合成核酸でした。両手をしばられた状態だと、かって家衛 試海外病部の担当者が私に嘆い ていましたが、そのような状態でよく頑張っていただけたものと思います。
6.口蹄疫のヒトへの感染性
今回の発生でマスコミからの問い合わせでまず問題にされたのはヒトに感染しない かという点でした。Pro Medには人獣共通感染症とするドイツの雑誌が引用されています。これは Foot-and-mouth disease as zoonosis. Archives of Virology, Supplement13, 95, 1997です。そのほかに、人獣共通感染症ハンドブックHandbook of zoonoses, CRC Press, 1994の中にも口蹄疫の章があります。厳密な意味では人獣共通感染症という視点で取 り上げられているわけです。
ヒトでの感染の報告で有名なものは1834年に3人の獣医が4日間、発病したウ シのミルクを250mlずつ飲ん だところ臨床症状が出たという内容です。当時からヒトへの感染は問題だったことが わかります。ただし、これは口 蹄疫ウイルスが分離される前の時代の話しで科学的には信頼性はありません。
1950-60年代にはヨーロッパで口蹄疫が流行していました。口蹄疫ウイルス のヒトへの感染の可能性につい ての報告はこの時期に集中しています。たとえば、不活化口蹄疫ワクチンを製造して いる研究所の作業員は高濃度の 口蹄疫ウイルスに接触する機会があり、彼らの中で軽度の発熱や水疱の症状を示した ものがいたという報告がありま す。一方、感染・発病が起こりにくいことを示す状況証拠も示されています。種痘ワ クチンはウシのお腹の皮膚で作 られていましたが、1960年代にこれが口蹄疫ウイルスに汚染していて、それが米 国、ノルウェイ、ルーマニアで 多数の子供に接種されたことがあります。しかし、発病例は皆無でした。稀には軽い 感染があったとみなされるもの の、ヒトの健康に被害をあたえるものではないというのが、これらの報告の結論で す。
Kazuya Yamanouchi (山内一也)
口蹄疫猛威4.5万頭を殺処分 「なぜ宮崎が」と悲鳴 05/07/10(J-CASTニュース)
宮崎県で牛や豚に感染する家畜病・口蹄疫が猛威を奮っている。10年前に県内で発生した際は35頭の殺処分で済んだが、今回は感染が確認されて数週間で約4万5000頭の殺処分が決定した。東国原英夫知事も「非常事態を宣言してもいい」と述べるほどで、早急な収束が望まれている。
口蹄疫は牛や豚、羊など蹄が2つに割れている偶蹄類(ぐうているい)に伝染するウイルス性の家畜病。感染すると口や蹄に水疱ができ、衰弱して死ぬこともある。
東国原知事「非常事態宣言してもよいほど」
極めて伝染力が強いということだけでなく、ウイルス抗原が変異を起こしやすいことから、根絶は困難とされている。人には感染せず、感染した肉を食べても影響はないものの、1997年に台湾で発生した際には、豚18万頭が死亡。385万頭が殺処分された。
2010年4月20日、宮崎県の都農町で、牛数頭に感染した可能性があると発表された。当初は牛だけだったが、やがて拡大。27日には、同県川南町の県畜産試験場で、牛よりもウイルスが増殖しやすい豚で確認され、検査結果を待たずに試験場の豚計486頭の殺処分が決定された。県は家畜の移動制限や畜舎の消毒などで封じ込めを図っているが、5月7日までに35例の感染の疑いが確認され、約4万5000頭の殺処分が決定している。
今後も拡大が懸念されており、東国原県知事も5日にあった県の口蹄疫防疫対策本部会議で、「非常事態を宣言してもよいと思うほど深刻な事態。農家は心理的な疲弊が予想される」と話している。
10年前は封じ込めに成功
宮崎県は10年前、00年にも口蹄疫を経験している。そのときは日本国内の感染確認は実に92年ぶりだったものの35頭の殺処分で収束。米国の農務省からも「日本の一部地域で口蹄疫が発生したが、流行は迅速に封じ込められ、根絶された」とお墨付きを貰った。
今回の流行は過去最大規模のものとなってしまったが、一体何が違っていたのか。県の口蹄疫防疫対策本部の担当者は、
「前回は小さい農家で散発的に確認されただけでしたが、今回感染が確認された川南町には、大規模の養豚場が集中しています」
と話す。初動防疫についても、10年前の経験を踏まえた上で、国よりも細かいマニュアルに則って行ったといい「危機管理はしっかりしています」。宮崎県は豚の飼養頭数が鹿児島県に次いで全国2位。口蹄疫によって豚・牛の移動・搬出が制限されているほか、競りも中止しており、今後の拡大によっては県の経済にとっても大きな打撃となる。
「発生農場を見ても、閉鎖型の最新施設で、防疫対策はかなりのものです。韓国や香港で感染が確認されて、心配してはいたのですが、もう『なぜ宮崎が』という思いです。現在こちらでは不休で防疫活動に当たっています。いち早く収束させないといけません」
と話している。
流産1週間前に女性搬送 容疑医師が渡した錠剤服用後 05/20/10(朝日新聞)
交際相手の女性看護師に子宮収縮剤を投与し流産させたとして医師小林達之助容疑者(36)が不同意堕胎容疑で逮捕された事件で、女性は小林容疑者から渡された錠剤を服用して異常が生じ、病院に救急搬送されていたことが捜査関係者への取材でわかった。この時は流産とは診断されなかったが、小林容疑者はその約1週間後、女性に点滴を打ち、流産させたとされる。
警視庁は、女性に小林容疑者が執拗(しつよう)に薬剤を与えたとみて、使用した薬剤の入手先などを調べている。
捜査1課や捜査関係者によると、女性は2008年12月末に妊娠がわかり、小林容疑者に伝えた。小林容疑者は09年1月初め、女性に子宮収縮剤の錠剤6錠を「ビタミン剤」と偽って手渡した。女性がその数日後に自宅で錠剤をのんだところ、出血などの異常が起き、救急車で近くの病院に搬送。治療を受け、帰宅した。この際、小林容疑者も病院に駆けつけたという。
女性はその後も吐き気などを訴えていた。小林容疑者は約1週間後、今度は子宮収縮剤の点滴を女性宅に持参し、投与。女性はその直後に流産したという。
小林容疑者は女性に「妊娠した体には栄養が必要だ。ビタミン不足を補える。君のためだから」などと言って薬剤を与えていたという。
小林容疑者は当時、既婚者であることを女性に隠して結婚について話をし、女性の流産後も交際を続けていたという。
血液内科医、小林達之助容疑者は証拠を残しすぎ。「性の自宅に残されていた点滴パックを調べたところ、小林容疑者の指紋は検出されなかった。
捜査1課は小林容疑者が指紋が付かないよう手袋をするなどの細工をした可能性があるとみている。」は考えすぎかも??
職業柄、手袋をしただけかもしれない??
不同意堕胎:逮捕の医師「ビタミン剤」と交際女性にメール 05/20/10(読売新聞)
妊娠していた交際相手の女性に子宮収縮剤を投与して流産させたとして、不同意堕胎容疑で逮捕された東京慈恵会医科大学付属病院の腫瘍(しゅよう)・血液内科医、小林達之助容疑者(36)が昨年1月に女性に錠剤を手渡した後、女性の携帯電話に「錠剤はビタミン剤です」とのメールを送っていたことが分かった。警視庁捜査1課は、小林容疑者が女性をだましたことを示す有力な物証とみている。同課は20日、小林容疑者を東京地検に送検した。小林容疑者は容疑を否認しているという。
捜査関係者によると、小林容疑者は09年1月上旬、東京都墨田区に住む看護師の女性宅を訪れ、子宮収縮剤3日分計6錠を手渡した。その際、同病院産婦人科に勤務する同僚の実名を挙げ「彼も体に良いと言っていた」などと説明した。自らパソコンで作成したとみられる効能などを記したうその説明書も渡していたという。
さらに、小林容疑者は女性宅から帰宅した後、女性の携帯に「錠剤はビタミン剤です。安心して飲んでください」という趣旨のメールを送っていたという。女性は1月中旬に小林容疑者が持参した点滴パックに入った子宮収縮剤を点滴するよう勧められ、点滴後、自宅トイレで流産した。捜査1課は、錠剤が効かなかったため、小林容疑者がより効果のある点滴を使ったとみている。
また、女性の自宅に残されていた点滴パックを調べたところ、小林容疑者の指紋は検出されなかった。捜査1課は小林容疑者が指紋が付かないよう手袋をするなどの細工をした可能性があるとみている。【神澤龍二、山本太一、内橋寿明】
「酸っぱい」カツ重…売れ残りトンカツ肉転用 05/07/10(読売新聞)
神奈川を拠点とする生活協同組合「コープかながわ」のハーモス荏田店(横浜市青葉区)が、本来なら処分する生のトンカツの売れ残りを冷凍保存した上で、カツ重に調理し、原材料名なども表示しないまま販売していたことが分かった。
同店は購入者から「味がおかしい」と苦情を受けた後、保健所にカツ重に転用して再販売したことを隠して報告しており、保健所は食品衛生法に違反する疑いがあるとして調査を始めた。
コープかながわは、静岡や山梨県も含め計152店舗を支える「ユーコープ事業連合」(同市港北区)の会員組織。ユーコープによると、同店は今年3月28日、全店共通のセールの目玉として国産豚を使ったロースカツ約1100枚を仕入れ、1枚198円で販売。カツはパン粉をまぶした冷蔵の生肉で、消費期限は当日限りとされていた。
内規では、売れ残りは品質が保てない恐れがあることから、すべて廃棄する決まりだったが、同店は売れ残った約330枚の生肉をすべて冷凍保存し、4月24日までにカツ重に調理して1個498円で販売。この日、2個を購入した同市内の夫婦から「酸っぱい味がして、吐き出した」と店に苦情があった。
同店には約330枚のうち約80枚しか残っておらず、約250枚がカツ重として販売されたとみられる。店の担当者は「大量に売れ残り、もったいないと思った」と説明したという。また、販売の際、食品衛生法で義務づけられた原材料名なども、パックに表示していなかった。
ユーコープによると、苦情のあった商品を検査したところ、健康に被害が出るような問題は見つからなかったが、肉質が劣化していたという。同店は4月26日、保健所に苦情内容を報告。その際、カツ重への転用や消費期限には触れなかった上、納入時は冷蔵の生肉だったにもかかわらず、「冷凍の状態で店に納入されたカツを調理した」と虚偽の説明をしていた。
ユーコープ広報課は「まだ調査中なので、きちんと報告しなかっただけ」と説明している。一方で、保健所は「店側の報告内容は事実の隠蔽(いんぺい)にあたる。当事者から事情を聞いて、事実関係を明らかにする」としている。
今回は、裸の大様の現代版だろう。東大の博士号、助教という肩書で誰も疑いもなくちやほやする。
東大は確認を怠った。「7年に助教とした東大は、昨年秋頃にインターネット上で元助教の経歴詐称などが話題になり、
外部から指摘を受けるまで問題に気づかなかった。」まあ、東大の判断や東大を必要以上に信頼する必要はない良い例と
なったと思う。東大がどう判断しようが、東大の教授が何と言おうとも、信用出来る根拠がなければ信頼する必要はない。
日本人は、自分で納得する前に誰が言ったとか、肩書きで判断する傾向がある。そのような傾向を改善する必要がある
ことを示した良い機会だと思う。
トルコ人元助教「宇宙飛行士候補」ウソ証明書も 04/27/10(読売新聞)
「博士号剥奪(はくだつ)」という前代未聞の不祥事はなぜ起こったのか。
東京大大学院工学系研究科助教だったトルコ人研究者、アニリール・セルカン氏(37)の博士論文盗用や経歴詐称問題で、同大の浜田純一学長は26日、強い危機感をにじませながら再発防止策を語った。
だが東大の博士号、助教という肩書は、結果的に元助教が異色の研究者として持てはやされるお墨付きとなり、東大のみならず、日本の大学や研究機関が翻弄(ほんろう)されることになった。
2003年に学位を認め、07年に助教とした東大は、昨年秋頃にインターネット上で元助教の経歴詐称などが話題になり、外部から指摘を受けるまで問題に気づかなかった。元助教はこの間、研究機関やほかの大学の非常勤講師などに採用され、マスコミにも大きく取り上げられるようになった。
元助教に関しては、米航空宇宙局(NASA)などが、宇宙飛行士候補だった事実はないことを確認したが、トルコ人初の宇宙飛行士候補である、との「証明書」まで存在していた。
在日トルコ大使館が確認した「証明書」はA4判1枚で、公用語のトルコ語ではなく英語で記されており、発行元は「トルコ運輸省」。実在する同省高官の署名まであったが、大使館が本国にファクスで確認したところ、偽造と判明したという。
元助教は、著書などで、「東大の工学博士でトルコ人初の宇宙飛行士候補、スキー競技の金メダリスト」などとつづっていたが、トルコ側では、「冬季長野五輪の際にスキーのコーチとして来日した」といった事実もない、としている。
東大の浜田学長は、経歴チェックについて「以前は確認作業をしていたが、審査論文も増え、人手も不足したことから簡素化していた」と語った。現在事前の丁寧な経歴チェックは困難で、研究者の「良心」に頼らざるを得ない状況という。
元助教の博士論文は、工学系研究科の教官5人が審査し、元助教が所属していた研究室の指導教官がとりまとめていた。浜田学長は、「指導教官が論文審査をまとめることにはメリットもある」と述べる一方、指導教官が責任者だったことや審査に第三者が入っていなかったことの是非を検討し、審査に問題があった場合は関係者を処分することも検討している、とした。
東大、論文盗用厳罰化…トルコ人元助教不正で 04/27/10(読売新聞)
東京大大学院工学系研究科助教だったトルコ人研究者、アニリール・セルカン氏(37)に、経歴詐称や、工学博士の学位論文での悪質な盗用があったとして同大が学位を取り消し、懲戒解雇相当とした問題で、浜田純一東大学長は26日、今後審査体制を総点検して問題点を見直すほか、論文盗用などの不祥事に対する処分の「厳罰化」を徹底することを明らかにした。
東大によると、同大が博士号を取り消す不祥事は初めてで、浜田学長は読売新聞の取材に対し、経歴のチェック等が簡素化されていたことを明らかにした上で、「信じられない事態。どこに問題があったか見直し公表する」と述べた。東大は調査委員会を設置、論文の審査に関与した教官らに経歴確認や論文審査の状況について事情を聞いている。
元助教に関しては、博士論文の4割にデータなどの盗用があり、「米国のイリノイ工科大、トルコのイスタンブール工科大卒業」といった経歴も詐称だったと東大が認定した。
東大によると、元助教は、今年2月に事情を聞いた際盗用の事実を認めたという。マネジャーだった女性は読売新聞の取材に対し、「本人はすでにトルコに帰国した。ほかはノーコメント」としている。
適切な調査を行うことが信頼。不正調査の上、虚偽報告。やはり頭だけで、道徳や倫理に関しては欠如しているのだろう。
「4人は研究員の経歴に傷が付いてはいけないと、故意の架空請求ではなく、重複発注によるミスだったとする報告書を作成」に関して
事務職員4人が同意した。まあ、頭だけの東大なのだろう。
「経歴傷付いては」東大の不正調査で虚偽報告 04/23/10(読売新聞)
東京大学は23日、国から補助された科学研究費の不正使用の調査を行っていた事務職員4人(課長3人、副課長1人)が、手心を加えるため虚偽の報告を行ったとして、戒告処分にしたと発表した。
処分は21日付。
同大広報部によると、4人が調査したのは、大学院農学生命科学研究科の50歳代の教授が2008年5月、実験器具会社に架空の請求書を作らせ、科研費約44万円を不正にプールし、事務用品の購入に流用した問題。
まず、学内の全教職員の取引を対象にした調査で疑惑が浮かび、同年9月、4人が調査を始めた。この科研費は教授が指導する若手研究員に出されたものだった。4人は研究員の経歴に傷が付いてはいけないと、故意の架空請求ではなく、重複発注によるミスだったとする報告書を作成、同年12月に大学側に提出した。
ところが、その後、処分を行うための委員会が、教授らから聞き取りをしたところ、架空発注の事実が発覚。報告書の虚偽が判明した。教授は今年1月、15日の停職処分を受けた。
福島原発、耐震安全性数値に誤り…半年以上報告せず 04/20/10(読売新聞)
東京電力は19日、国に提出済みの福島第1、第2原発の耐震安全性評価の中間報告について、一部の解析用数値に誤りがあり、修正後の報告書を経済産業省原子力安全・保安院に提出したと発表した。
誤りは昨年9月に発覚したが、今月になって県や国に報告した。
発表によると、誤りが見つかったのは、第1原発1~3、6号機と第2原発1~3号機の原子炉建屋についての評価部分で、屋根部分の鉄骨の断面積など一部の数値が誤ったまま計算されていた。この結果、計4機の中のボルトなどの部品にかかる力が、本来よりも大きくされたり、小さくされたりしていた。
安全性にかかわる評価に影響はなかった。
計算は、外部の業者4社に委託して行われたもので、東電は今回の中間報告書作成の際に妥当性を確認しなかった。最終報告に向けた作業をしていた昨年9月に誤りが発覚。今月8日に原子力安全・保安院へ、9日に県に対して報告した。発表や報告が遅れた理由について、同社は「評価自体に影響はなく、再計算して確実に発表できるまで時間がかかった」と説明している。
県原子力安全対策課は、「品質の信頼性という県民の安全安心にかかわる重大な問題であり、判明した段階で情報公開すべきだった。二度とないようにしてもらいたい」としている。
児童買春で警視庁嘱託の少年補導員逮捕 04/16/10(日テレNEWS24)
警視庁に嘱託された少年補導員の男が、女子中学生に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、警視庁に逮捕された。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・武蔵村山市の会社経営・峯岸一郎容疑者(51)。警視庁によると、峯岸容疑者は去年12月、中学2年の女子生徒2人(当時14)が18歳未満であることを知りながら、現金10万円を渡し、ホテルでわいせつな行為をした疑いが持たれている。調べに対し、峯岸容疑者は「若い女性に興味があった」と容疑を認めているという。
峯岸容疑者は、警視庁から嘱託を受けて街頭で少年を補導する活動を行っていた。
「 不正には全社員の約4分の1にあたる計約20人がかかわっており、このうち同製剤の開発の責任者である幹部3人は
旧ミドリ十字出身者だったという。」
白と黒を混ぜたら白にはならない。子会社の製造会社「バイファ」(北海道千歳市)を解散すればよい。
薬害エイズ事件の被害者の苦しみに比べれば失業の苦しみは軽いだろう。
一度、苦しみを経験するのも今後の人生のためには良いことになるかもしれない。
田辺三菱製薬:業務停止命令 「反省の姿勢ない」 C型肝炎原告、強く批判 04/14/10(毎日新聞)
「薬害再発防止の誓いは何だったのか」。厚生労働省から業務停止命令を受けた田辺三菱製薬は薬害C型肝炎訴訟の被告企業で、原告患者らへの謝罪と再発防止を盛り込んで和解していた。にもかかわらず今回の不祥事に至ったことで、同訴訟原告らからは強い批判の声があがった。【佐々木洋、石川淳一、松本惇】
同社製の血液製剤フィブリノゲンでC型肝炎に感染したとして訴訟を起こし、08年9月に和解合意し謝罪を受けた全国原告団代表の山口美智子さん(53)は「驚きと怒りを覚える。企業として反省する姿勢が抜けている」と指摘。「1年半前の謝罪の際にも疑わしかったが、再発防止の約束も信用できない」と述べた。
一方、田辺三菱製薬の土屋裕弘(みちひろ)社長は13日夜、藤井武彦バイファ社長とともに会見し「あってはならないことで深くおわび申し上げる。グループ各社の規制順守の徹底を図り、再発防止に努める」と陳謝した。
両社の社外調査委員会(委員長・郷原信郎弁護士)の報告書は旧ミドリ十字時代の薬害エイズ事件(96年)に触れ「メドウェイの開発は経営不振を脱却する起死回生の策として立案されたが、動物実験などで思うような結果が出ずに製造承認が大幅に遅れ、現場の開発担当者に大きなプレッシャーがかかっていた」と分析した。
社長に先立ち会見した郷原弁護士は「(改ざんに関与した)旧ミドリ十字社員の倫理意識の欠如が大きな要因の一つ」と指摘しつつ「自ら厚労省に通報しており『製薬会社大手で初の業務停止』という処分が適当かというと、ちょっと違うと思う」と述べた。
厚生労働省によると医薬品承認申請に関する薬事法違反での製薬会社への業務停止命令は75年以降で約80件。94年には抗ウイルス剤のソリブジンの副作用問題で発売後に死者15人を出した日本商事が105日間の製造業務停止処分を受けたが、田辺三菱のような大手の業務停止は異例という。
田辺三菱を業務停止…子会社データ改ざんで 04/14/10(読売新聞)
田辺三菱製薬(大阪市)の子会社が新薬の試験データを改ざんした問題を調査していた厚生労働省は13日、薬事法に基づき、田辺三菱を今月17日から25日間の一部業務停止とする行政処分を発表した。
大手製薬会社の業務停止は異例。データを改ざんした子会社は、薬害エイズ事件などの血液製剤を作った旧ミドリ十字が設立しているが、同省によると、旧ミドリ十字出身者ら約20人が組織的に不正にかかわっていたという。
田辺三菱は、子会社に対する監督責任が問われた。同社のほか、子会社の製造会社「バイファ」(北海道千歳市)が、今月14日から30日間の業務停止処分を受けた。
発表によると、同社は1999年から2008年にかけて、世界初の遺伝子組み換え技術による人血清アルブミン製剤「メドウェイ注」の試験データなどを改ざん。不純物の濃度を実際より低く見せかけたり、アレルギーの陽性反応を陰性のデータに差し替えたり、16件の不正を行っていた。
不正には全社員の約4分の1にあたる計約20人がかかわっており、このうち同製剤の開発の責任者である幹部3人は旧ミドリ十字出身者だったという。
厚労省は「遺伝子組み換えという新しい技術による新薬の開発で不正があったことは、医薬品の承認申請を棄損する重大な違反だ」と指摘した。田辺三菱については「不正を漫然と見逃した」と判断した。
同製剤は、重いやけどや出血性ショックの患者に使われる。07年10月に承認を受け、08年5月に販売を開始したが、田辺三菱は昨年3月に不正を公表し、すでに自主回収している。現在、製造・販売はストップしており、健康被害は報告されていない。
田辺三菱の業務停止処分は、処方せんが必要な医療用医薬品の製造・販売が対象。代替がない医薬品や供給が止まると医療現場が混乱する医薬品7品目は除かれた。
旧ミドリ十字は合併の末、現在は田辺三菱に吸収されている。バイファは同製剤を開発するため、旧ミドリ十字が96年に設立した。薬害エイズ事件で旧ミドリ十字では、エイズウイルスが混入した非加熱血液製剤の販売を続け、患者が死亡したとして、歴代社長2人について業務上過失致死罪での実刑判決が確定している。
◆田辺三菱社長が謝罪◆
田辺三菱製薬の土屋裕弘社長は13日夜、都内でバイファの藤井武彦社長らと記者会見し、「人の生命にかかわる製薬企業として、あってはならないこと。深くおわびしたい」と述べ、深々と頭を下げた。
薬害エイズ事件などの問題を引き起こした旧ミドリ十字。その体質を払拭(ふっしょく)できなかったことについて、土屋社長は「もう少し、人事交流を行っていれば、違った展開があったかも知れない」と苦渋の表情を見せた。
同社に先立ち会見に臨んだ社外調査委員会委員長の郷原信郎弁護士は、「バイファは旧ミドリ十字の経営が厳しい時に設立された会社で、同社の利益重視、安全性軽視の企業姿勢が表れている」と問題点を指摘した。
会社の名前が変わったからそこで働いていた人間も名前がわかったように変われるのかというと「NO」だろう。
今回の「
田辺三菱製薬
子会社、社長が試験データ不正の指摘を放置」が良い例だ。
「調査委は、ミドリ十字時代からメドウェイの開発、製造を担ったバ社の初代社長について、
『不正の可能性を認識しながら事実確認をしなかった』とみている。 」
田辺三菱製薬、血液製剤を自主回収 試験データ改ざんで [2009年03月24日(火)] (「医療・福祉・介護・環境の得々かわら版」)
田辺三菱製薬子会社、社長が試験データ不正の指摘を放置(1/2ページ)
(2/2ページ) 03/09/10(朝日新聞)
田辺三菱製薬(大阪市)の子会社バイファ(北海道千歳市)で、やけどや大量出血のショック時に使われるアルブミン製剤の承認申請に必要な試験データの差し替えなどが行われ、バ社の社長(当時)がそうした不正をうかがわせる社内の調査結果を知りながら、詳しい調査や改善を指示していなかったことが社外調査委員会(委員長=郷原信郎弁護士)の調べでわかった。
田辺三菱は昨年3月に不正を公表、調査委に調査を依頼していた。厚生労働省は「データ差し替えは医薬品の承認制度の根幹を揺るがす行為」として両社に数回、立ち入り検査をし、担当者から事情を聴いた。薬事法違反での行政処分を検討している。
調査委の報告書や厚労省によると、問題の製剤は両社が共同開発した遺伝子組み換え人血清アルブミン製剤「メドウェイ注5%」。世界初の遺伝子組み換えのアルブミンとして、田辺三菱が2007年10月に厚労相の承認を得て、08年5月に発売した。
製造を担当したバ社は05年10月~07年3月、ラットで行ったアレルギー反応を調べる試験で、品質不適合となったサンプルを別のものと差し替えて再試験をしたり、都合の良い試験成績を流用して記録を作ったりしたほか、界面活性剤の含量を調べる試験では、意図的に試料を薄めていた。
さらに調査委の調べで、「メドウェイ注25%」についても、承認申請をめぐる試験で、試料を薄めたり、規定外の試薬を加えたりしていたことがわかった。
調査委の調べでは、05年に就任したバ社の2代目の社長は、社内の意識調査で不正をうかがわせる内容の回答があったのに、取り合わなかった。調べに対し、「(親会社からの)出向者との待遇面での格差などに不満をもつ現地採用者が、過激な表現や針小棒大な回答をしていると考えた」と話したという。
田辺三菱は、旧ミドリ十字などが合併を重ねて今の姿になった。調査委は、ミドリ十字時代からメドウェイの開発、製造を担ったバ社の初代社長について、「不正の可能性を認識しながら事実確認をしなかった」とみている。
不正はバ社のグループマネジャー(GM)の指示で、歴代の検査担当者ら数人が組織的に関与していたという。承認を得る手続きが遅れていたため、「経営への影響を懸念した」と調査委は指摘する。GMはミドリ十字出身で、「人事権を背景に高圧的、強権的態度をとっていたために、(部下らは)不正行為の指示に逆らえなかった」という。
田辺三菱広報部は「当局の調査が続いており、コメントできない」としている。
法務省所管法人、元最高裁判事に破格条件で融資 04/13/10(読売新聞)
法務省所管の社団法人「民事法情報センター」(東京都新宿区)が昨年3月、理事長を務める元最高裁判事の香川保一氏(88)に対し、無利子・無担保で1500万円を貸し付けていたことがわかった。
貸し付けは理事会の審議を経ずに行われ、返済の期限も設けていなかった。同時期、センターの役員報酬も改定され、香川氏の報酬は月50万円から同100万円に倍増していた。好条件の融資や報酬の増額に“お手盛り”との批判が上がるのは必至で、センターへの公費支出が23日に始まる政府の「事業仕分け」の対象になる可能性もある。
センターによると、昨年3月、香川氏に1500万円を無担保で貸し付けた際、借用書を作成したものの、利息や返済期限は明記していなかった。貸し付けにあたって、理事長と常務理事各1人、さらに無報酬の非常勤理事10人で構成する理事会で事前に審議したこともなく、同年6月に「理事長に貸し付けた」と報告されただけだった。センターの2008年度決算報告書には「長期貸付金」として記載されている。
センターでは同じ昨年3月、理事長の報酬を月50万円から100万円に、常務理事の報酬も50万円から70万円にする報酬の改定も実施したが、これも6月の理事会まで報告していなかった。
1500万円をどんな目的で貸し付けたのかについて、センターの岩佐勝博常務理事は「当時、使用目的ははっきりとは聞いていなかった」としている。
センターは1986年3月設立。08年度の収入1億7600万円のうち、公証人や司法書士ら個人会員約180人からの会費収入は約750万円ほどで、「月刊民事法情報」(年間購読料1万5536円)と「月刊登記インターネット」(同9450円)や、住宅地図に公図番号を記した「ブルーマップ」の売り上げが収入の大半を占めている。
これらの出版物は地方法務局や裁判所など国の機関でも購入しており、法務省によると、07年度の国と同センターとの契約額は1800万円だった。
香川氏は裁判官出身で、法務省民事局長などを経て、86年から最高裁判事を務め、91年に退官。同年にセンター理事になり、05年から理事長を務めている。
法務省民事局商事課の話「昨年の検査で長期貸付金があることは把握していたが、詳細までは調べていなかった。貸付金の目的が法人の設立目的と合致しているかどうかが問題で、問題があるなら調査したい」
トルコ人研究者、アニリール・セルカン氏の
学歴詐称(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より)
について東京大学さえもチェックできなかった?チェックしていなかった?
日本は学歴や資格についてチェックできるような制度やチェックする義務について迅速に検討するべきだ。
東京大学が学歴詐称問題について長期の間見落としてきた事実は、学歴や資格詐称問題について日本のチェック体制は
甘すぎる事を示した良いケースになると思う。
論文盗用のトルコ人、東大が「懲戒解雇相当」 04/02/10(読売新聞)
他人の論文を盗用したとして先月、東京大学が工学博士の学位を取り消したトルコ人研究者、アニリール・セルカン氏(37)について、東大は2日、大学院工学系研究科の「助教」の身分を「懲戒解雇相当」にしたと発表した。
3月31日付。セルカン氏は先月2日に学位を取り消された後、同15日に辞職願を提出。辞職は承認されなかったが、雇用関係についての民法の規定で同月29日に辞職が成立していた。懲戒解雇相当の決定で退職手当は支給されない。
東大によると、セルカン氏は2005年度、東大が助手の採用選考を実施した際、米国のイリノイ工科大学を卒業していないのに、履歴書には、同大を卒業し、学士の学位を授与されたなどと虚偽の記載をした。
また、06年度の科学研究費補助金の研究実績報告書に報告した三つの論文のうち、一つの論文に盗用が9か所、盗用の疑いが7か所あった。残り2つの論文については存在そのものが確認できなかった。
東大の田中明彦副学長は「極めて遺憾。社会的責任を痛感している」とするコメントを発表した。
島根原発:123カ所で点検漏れ 1号機の運転停止 03/31/10(毎日新聞 東京朝刊)
中国電力(本社・広島市)は30日、島根原発1、2号機(いずれも松江市)で計123カ所の点検漏れがあったと発表した。機器が点検計画通りに交換されていないのに、点検していたことにされていた。同社は1号機の運転を31日から停止、定期検査のために運転停止中の2号機と共に点検する。経済産業省原子力安全・保安院によると、点検漏れを原因とした原発の運転停止は初めて。【細谷拓海、岡崎英遠】
中国電力は「放射能漏れなど安全面での問題はない」というが、ずさんな安全管理の実態が明らかとなった。
同社は30日、保安院に報告。保安院は「保守管理が適切にされていないことは遺憾」として、4月30日までに、原因と再発防止策について報告するように指示した。
報告書によると、点検漏れがあったのは、1号機が、異常時に原子炉内に水を送る高圧注水系のタービンを回すための「蒸気外側隔離弁」など14系統74カ所、2号機が8系統49カ所。うち、法律で定められた検査対象は、38カ所と23カ所あった。
09年6月の定期検査で、蒸気外側隔離弁のモーターが、06年9月からの定期検査で取り換えるはずだったのに実施されていなかったことが発覚。ポンプのパッキンやボルトなど計123カ所の点検漏れが分かった。機器の中には、1989年以降、点検されていなかったものもあるという。
中国電力によると、機器のサイズが合わず交換できなかった場合などに、点検部署が点検管理部署にその事実を伝えていないことがあった。管理部署は確認しないまま、点検したものとして処理していたという。
◇中国電力「検査したか、分からないものも」
中国電力は30日午後、島根県庁で記者会見した。清水希茂・島根原子力本部長らが「心配をおかけしたことについて、誠に申し訳なく、深くおわび申し上げます」と謝罪した。点検記録の保存自体がずさんで「検査したかどうか分からないものもある」と説明するなど、無責任な安全管理体制が浮き彫りになった。
会見では、「安全管理意識が決定的に欠如していないか」といった質問が矢継ぎ早に飛んだが、幹部たちは答えに詰まりながら「全力で安全管理に努めたい」と繰り返すだけだった。「いつからこんな事態になったのか」との質問に対し「点検記録が残っている中で最も古いのは89年の1号機。記録が残っていないものもあり、検査したのか、していないのか、分からないものもある」といった回答まで飛び出した。【岡崎英遠、目野創】
◇形骸化する「自主検査」
原発1基の点検項目は数万件と膨大で、国が逐一検査できないため、電力会社が自ら安全運転に必要な「保安規定」を決めて定期検査し、国が不備を抜き打ち審査する仕組みになっている。09年には、この自主検査体制への信頼性に基づき、国の定期検査を現行の13カ月間隔から最大2年間隔に延ばせる「新検査制度」が導入された。
今回判明した問題は、こうした自主検査体制の信頼性を損なう恐れがある。中国電力は点検作業とその確認を別の部署で行う体制に改めた。しかし点検部署が発電所内の検討抜きで部品交換を見送った上に、確認部署も連絡がなかったため「交換済み」と記録するという形骸(けいがい)化した体制の一端が明らかになった。【山田大輔】
下記の記事が本当であれば、スカイマークはひどいな。前田隆平航空局長はどのような対応をするのだろうか。
船についてだがよく船長から安全管理マニュアル(SMS)に書かれている「Master's Responsibility」と「Overriding Authority」は建前だけだと
不満を聞く。ただ会社がマニュアルに記載している以上、裁判や訴訟になった場合、船長の独断と会社が主張しても記載していないよりは
会社の責任について触れられる機会があるだろう。「Master's Responsibility」と「Overriding Authority」は内部審査や外部審査でもチェックされる
項目である。知らなかったとは言えないのである。船長が「Master's Responsibility」と「Overriding Authority」について知らないと回答すれば、
内部審査や外部審査でのインタビューでどのように回答していたのかと言うことになる。
飛行機は多くの人命を乗せて飛ぶ。安全に関しては一般商船以上であると推測する。しかし、現実は下記の記事のようなことが起こっている。
整備、部品の交換サイクル、点検の期間、建前の整備記録でなく、事実の記載などはどのようになっているのかを考えると恐ろしいことだ。
事故などはいろいろな要素が重なって悪い結果となるのだ。問題があったが影響が出ない時にどのような対策を取るかが重要であって、
事故調査が必要とされる事故が起こってからでは遅いと思う。
体調不良のスカイマークCA、社長一声「交代ならぬ」」(1/2ページ)
(2/2ページ) 03/09/10(朝日新聞)
スカイマークの機長が、体調不良で声が十分に出ない客室乗務員(CA)を交代させようとしたところ、西久保慎一社長と井手隆司会長が認めず、逆に機長を交代させて運航を強行していたことがわかった。
航空法は機長に乗員への指揮権を与えており、個々の運航では機長の判断が最優先される。同社の運航規定でも、安全に対する最終決定権は機長にあると定められている。また、CAは保安要員で、非常時に大声で乗客を避難誘導する役割がある。
機長の判断を経営者が覆したことについて、国土交通省は「前代未聞。安全にとってゆゆしき事態」として文書で厳重注意した。
同省によると、問題が起きたのは2月5日の羽田―福岡便。チーフ格のCAは風邪の治りかけで大きな声が出せない状態だった。出発前に気づいた外国人機長が「避難誘導などに支障をきたす」と交代を指示した。
ところが、事態を聞きつけた西久保社長は「健康上、問題はない」として認めず、安全統括管理者の井手会長も「会社の命令」として交代なしに運航するよう指示したという。機長は「安全が確保できない以上飛べない」と拒否したため、社長らは機長を交代。別の機長がCAの交代なしの運航を受け入れ、約1時間遅れで出発させたという。
この問題で機長と社長らが口論になったといい、機長は、この際に社長らが「手をあげた」などとして警視庁東京空港署に被害届を提出。同署が経緯を調べているという。同社は機長との雇用契約を即日解除した。
体調不良のスカイマークCA、社長一声「交代ならぬ」 03/09/10(朝日新聞)
一方、国交省に呼ばれた社長と会長は9日、前田隆平航空局長に「申し訳ありませんでした」と謝罪したものの、記者団から「なぜCAの交代を認めなかったのか」と問われても一切答えなかった。スカイマークの広報担当は「CAの体調を確かめたうえで乗務させた。機長を交代させ、欠航を避けた判断は当時としては正しかったと思っているが、国交省の指摘を厳粛に受け止める」としている。
元機長で航空評論家の前根明さんは「CAはサービス要員であると同時に保安要員。万が一を考えて交代を指示した機長の判断は妥当だ。経営者が権威をもって、安全を封じ込めるような体質は改められるべきだ」と話している。
契約解除となった機長がこの件だけでこのような処遇を受けたのか知らない。しかし、この件だけで即日解除となったのであれば
スカイマークは安全軽視の体質があると推測しても間違いではないであろう。
サブスタンダード船
を考えると、やはり問題がある管理会社や船主は、他の船でも同じような基準で運航し、管理する。
船が古いから問題があると言い訳するが、適切な管理と保守点検が行われている船は、船齢が古くても状態が良い。
5年ぐらいの船齢の差などは建造造船所や管理状態次第では関係ないし、船齢が若くても見劣りする場合もある。
大事故が起こるかは運次第。運が良ければ、何も起きない。戦争に行っても帰ってくる人はいるし、車を運転しなくても
事故に巻き込まれ死亡する人もいる。確立だけを考えれば推測できるが、未来については誰も知りえない。国交省が
どのように判断し、対応するだけの話だろう。まあ、個人的にはスカイマークを利用したことがないので関係ないと言えばそれまでだ。
飛行の安全重視の機長、交代させ即日契約解除 03/09/10(読売新聞)
国土交通省は9日、スカイマークの西久保慎一社長(54)と井手隆司会長(56)が先月、安全のため客室乗務員の交代を求めた機長にそのまま運航するよう命じた上、拒否した機長を交代させていた、と発表した。
同社はこの機長との雇用契約を即日解除していたという。同省は「機長の安全上の判断を否定して運航を命じることは不適切」だとして、同社に文書で厳重注意した。
国交省によると、先月5日、羽田発福岡行きのスカイマーク17便(乗客乗員183人)の外国人機長が、客室乗務員を取りまとめる先任客室乗務員がのどの調子を崩し十分に声が出せないことに気付いた。
機長は非常脱出などの際に支障が出ると判断、乗務員の交代を同社に求めた。ところが、西久保社長と井手会長は、そのまま運航するよう命令。
機長が拒否すると別の機長と交代させ、同便は約1時間遅れで出発した。運航を拒否した機長との契約期間は約2年間残っていたが、同社は即日解除とした。
郵便不正事件で誰が嘘を付いているのか??嘘を付いていることが判明したら、執行猶予を付けてイやる必要はない。
また、検察の取調べも疑問だらけ!これまでの冤罪は警察や検察の体質の問題なのか??調書を作成し、辻褄が合うように
容疑者に認めさせるのか??これが日本の現実なのか??こんな日本に愛国心を抱かないと非国民なのか??
石井議員、厚労省への口添え否定…郵便不正公判 03/04/10(読売新聞)
郵便不正事件に絡み、自称障害者団体「凛(りん)の会」に偽の障害者団体証明書を発行したとして、虚偽有印公文書作成などの罪に問われた厚生労働省元局長・村木厚子被告(54)の公判が4日、大阪地裁で行われ、民主党の石井一参院議員(75)が弁護側証人として出廷した。
石井議員は同会側から依頼を受け、厚労省に口添えの電話をかけたとされる点について「全くありません」と否定。同会関係者と面会したとされる日も「千葉県成田市のゴルフ場で同僚議員らとプレーしており、会うことはできない」と証言した。
検察側主張によると、石井議員は衆院議員だった2004年2月、元秘書だった同会の元会長・倉沢邦夫被告(74)や元会員(67)と議員会館で面会し、証明書発行への協力を要請され、村木被告の上司だった塩田幸雄・元障害保健福祉部長(58)に電話をかけ、便宜を図るよう求めた。その後、塩田元部長から指示を受けた当時課長の村木被告が、元係長・上村勉被告(40)に証明書作成を指示したとされる。
これまでの公判で、倉沢被告は「04年2月25日に議員会館の石井議員の事務所を訪ねた」と証言したが、石井議員は「(倉沢被告と会ったことは)ない。記憶にないのではなく、絶対にない」と説明。弁護側は、石井議員の手帳をモニター画面に映し、ゴルフ場名やスタート時間などが記されたその日の記述を示した。
サブスタンダード船
と似た状況だ。違法な行為(不適切な検査)を行うから検査依頼が来る。
依頼する人間は不適切な検査を行う検査会社や検査官を探している。問題なので
厳しい外国船舶監督官
が検査を行えば、出港前に出港停止命令を受ける。不備の是正を受ければ出港も
出来ないし、是正に費用が発生する。まあ、不適切な検査を行ったからと言って、
逮捕されたケースを聞いたことがないので何年経っても問題は改善されない。
サブスタンダード船
の撲滅は夢物語だ。国交省にやる気があれば本当は改善していると思うけど、
一部の人達以外、事実を知る人はいない。
行政書士:警視庁が監視強化 外国人の不法就労助長 03/02/10(毎日新聞)
警視庁が東京都や東京入国管理局と連絡会議を作り、入国管理局に虚偽の申請をして外国人の不法就労や偽装結婚に加担する行政書士の監視を強化している。事件への関与が疑われながら、出入国管理法違反容疑などで立件できなかった行政書士は少なくない。このため帳簿の不備について行政書士法違反容疑で摘発し、懲戒処分権限を持つ都に違法情報を通報して、業務停止に追い込む方針だ。【町田徳丈】
警視庁は06年以降、不法就労を手助けしたとして、少なくとも5人の行政書士を入管法違反容疑などで逮捕している。だが捜査幹部によると「虚偽申請の疑いが強い行政書士は他にもいたが、本人が『虚偽とは知らなかった』と容疑を否認したため、立件を見送らざるを得なかった事案もかなりある」という。
そこで警視庁が力を入れているのは行政書士法違反での摘発だ。同法は依頼者の住所や氏名、報酬額などを帳簿に残すよう定めているが、虚偽申請への関与が疑われる行政書士は帳簿を保存していないケースが多いことに着目。罰金100万円以下の罰則がある同法を積極的に適用したうえで、違反情報を都に通報し、業務停止(2年以内)などの懲戒処分につなげ「社会的制裁を与えたい」(捜査幹部)考えだ。
警視庁は2月、都内の行政書士(59)を行政書士法違反容疑で書類送検した。この行政書士は08年1月~09年9月、複数のブローカーから計百数十万円の報酬を受け取り、日本人男性と偽装結婚した韓国人女性の在留資格の変更手続きを約20件代行していた。警視庁は入管法違反のほう助容疑での立件を検討したが、行政書士は「偽装結婚とは知らなかった」と主張した。このため帳簿が不備だったことに注目し、行政書士法違反で摘発した。
警視庁は09年11月にも別の行政書士を行政書士法違反で書類送検し、同法違反での摘発を強化している。
一方、日本行政書士会連合会によると、会員からは「行政書士法違反容疑での立件はやり過ぎ」という意見も出ているという。連合会は「指導を徹底したい」と話している。
◇「塀の上歩いてる」
東京・池袋や新宿歌舞伎町で売られる中国人や台湾人向けの新聞には行政書士の広告が目立つ。「黒転白(特別在留許可)」「不法滞在的結婚手続」など、違法行為をにおわせる言葉が並んでいる。
「黒転白」は日本に滞在する中国人の間で3~4年前に使われ始めた俗語で「違法状態のものを合法にする」という意味。不法残留の中国人が偽装結婚で在留資格を得る意味も持つという。「黒転白」と掲載していた東京都内の行政書士は「文面は中国人スタッフが書いた。広告としてインパクトがあるらしい。すべてが違法ではない」と説明した。
都内の別の行政書士は、中国人の会社経営者から「仕事があるからうちの傘下に入れ」と誘われた。「こちらは金になるし、そちらも仕事が増えるからいいじゃないか」。行政書士は違法な手続きを代行させられる予感がして断ったという。
取材に応じた複数の行政書士は「中国人に雇われている行政書士がいると聞く」と証言する。過当競争や不況で仕事量がここ数年で3割減った事務所もあり、安定した収入を求めるあまり虚偽申請に加担するのだという。
日本語が分かる外国人なら入国管理局への申請手続きは本人でも可能だ。ある行政書士は「本人が申請せず行政書士に頼む外国人は後ろめたい理由があるか、ブラックな案件」と話し「いつ悪徳ブローカーに取り込まれるか分からない。仲間とは『我々は塀の上を歩いているんだ』とよく話している」と明かした。【前谷宏】
ブレーキ分解せず車検通した疑い いすゞ子会社書類送検 02/10/10(朝日新聞)
書類にうその記載をし不正に車検を通したとして、神奈川県警は10日、いすゞ自動車子会社の販売店「神奈川いすゞ自動車」(横浜市)と、県内7カ所の同社サービス工場の自動車検査員計11人を道路運送車両法違反の疑いで書類送検し、発表した。
交通捜査課などによると、11人は2007年4月下旬~12月中旬の車検で、実際は作業していないのに、トラックのドラムブレーキを分解して整備・点検したとして、書類にうそを書いた疑いがある。虚偽記載はいすゞ製トラック22台で見つかった。
分解しないと整備が不十分になることがあり、ブレーキがききにくくなるおそれもある。整備不良が原因とみられる事故は確認されていないという。検査員は「車検の時間短縮、効率確保が目的。会社の指示はなく自分の判断でやった」と話しているという。
山口大で研究費不正1億3千万円、教授解雇へ 02/10/10(読売新聞)
山口大で公的研究費を巡り、不正経理が繰り返されていた疑いがあることがわかり、同大は9日、教員の懲戒処分について審査する臨時の教育研究評議会を開き、不正の疑いが持たれている大学院理工学研究科の男性教授(60歳代)と医学部長(同)から事情を聞いた。
2人は不正への関与を認め、評議会は男性教授を懲戒解雇、医学部長を停職1か月とする方針を決め、2人に通告した。2人が弁明できる期間を経て月内にも処分が決定する見通し。
このうち男性教授は、広島国税局や大学の調査で、パソコンやデジタルカメラ約1億3000万円分を偽装購入していたことが判明。デジカメ約20台の私的流用も明らかになった。
男性教授は最初、偽装購入を認めたが、私的流用については否定。しかし、広島国税局などの調査に基づき、購入したデジカメ約20台が市場に出回っていることを指摘されると、私的流用も認めたという。
医学部長については、大学の調査で2004年度までに物品の架空発注などで計約160万円を業者の元にプールしていたことがわかった。医学部長は評議会で、研究用消耗品の購入に充てていたことを認めた。
不正経理問題は昨年10月に広島国税局が行った税務調査で発覚、これまでに二十数人の関与が浮上した。今回の2人が3月末で定年退職を迎えるため、大学は先行して調査を進めた。男性教授については詐欺容疑で告訴する準備をしている。
また、評議員で大学院理工学研究科の男性教授(50歳代)も不正経理に関与した疑いが出ており、この教授は大学側に評議員辞任の意向を伝えた。同大は近く辞任を認める。
全建国保の脱退相次ぐ 徳島支部、大半無資格者か 01/26/10(朝日新聞)
「全国建設工事業国民健康保険組合」(本部・東京)に無資格者が多数加入していた問題で、同組合の徳島県支部(徳島市)の加入者が問題発覚後、地元市町村の国民健康保険に移るケースが相次いでいることがわかった。多くは建設関連の仕事を廃業したとして同組合発行の資格喪失証明書を提出しているが、自治体担当者は「ほとんどが問題となっている無資格者である可能性が高い」とみている。
徳島市保険年金課によると、徳島県支部から市の国保に移る手続きをした人は問題発覚後の昨年12月末から1月21日までに35世帯65人。いずれも世帯主が「建設関連の仕事を廃業した」と組合発行の資格喪失証明書を提出した。
しかし、市の担当者は「同じ期間に建設関連の別の組合から移ってくる例はほとんどない。一つの組合だけ、短期間でこれだけ廃業が出るのは不自然」と話している。
同県小松島、鳴門、阿南の3市の国保へも、1月だけでそれぞれ9人、8人、2人が同組合から移った。鳴門市では、組合の脱退理由のほとんどが「廃業」。件数を数えていない美馬、阿波両市にも組合からの切り替えや、市の国保保険料について問い合わせが相次いでいるという。
組合が徳島県支部の組合員1888人(家族を除く)を調査した結果、16日現在で回答した1542人のうち、「建設関連の仕事に従事していない」と答えたのは655人。「従事している」と答えた人の中にも証明書を添付していない人が123人いた。
朝日新聞の取材で、県支部の組合員には、建設関連の仕事に従事していない銀行や電力会社、自治体の退職者がいることが分かった。「市町村国保より保険料が安い、と知人から教えられた」と説明しており、加入する際の資格審査で、県支部から資格の有無を問われなかったと答えた人も相当数いた。
全建国保:徳島県支部立ち入り検査 無資格加入者「問題あるが偽装はない」 /徳島 01/26/10(毎日新聞)
◇県支部長が認識
東京都と厚生労働省関東信越厚生局による立ち入り検査が入った「全国建設工事業国民健康保険組合」の徳島県支部(徳島市富田橋1)。調査が始まった25日、多くの報道陣で緊迫感が漂った。
県支部の事務所では、検査開始前に支部長が取材に応じた。無資格の加入者の存在が指摘されている点には「問題はあるが、書類の偽装はなかったと考えている」との認識を示した。県支部では、加入時に各建設関連業の母体組織による雇用や就労の証明書の提出を求めるほか、保険証交付時に年1回、就労状況を確認するという。約35人が脱退を申し出ていることも明らかにしたが、「大半は仕事ができなくなった廃業が理由」と説明した。
一方、組合を脱退しようと訪れる男性(70)の姿も。鳴門市在住の男性は約1年半前に身内の勧めで加入し、建設関係会社に勤める息子を手伝うことがあったという。「市町村国保では毎月2万2千円で、今は月1万5500円。少しでも安く、負担を減らそうと加入した。脱退せないかんと思う」と話した。
約4時間の検査終了後、都の担当者らは「調査中で答えられる段階にない」と言葉少なに事務所を後にした。検査は28日までの予定。【井上卓也】
儲からなければ贅沢は出来ない。安くなければ一般庶民は利用する可能性が低い。これが現実。
効率的にお金が使われないと分かっていながら一時的なお金(税金)のばら撒き。交際外交で
見え張った血税のばら撒き。いろいろと考えないといけない時代になった。JALと同じ運命を
日本は突き進むのか???温泉旅館「延楽」が不法就労中国人を使わないと生き残れないのであれば、
時代の流れとして受け入れるしかない。人間と同じである。生まれて来る人もいれば、老いて死んでいく人もいる。
入管法違反容疑:中国人不法就労 老舗旅館社長を書類送検 01/25/10(毎日新聞)
就労資格のない中国人を仲居として働かせたとして、警視庁組織犯罪対策1課は25日、富山県黒部市の温泉旅館「延楽」の男性社長(59)を入管法違反(不法就労助長)容疑で書類送検した。同課によると、延楽は08年2月以降、中国人約15人を雇っており、社長は「不法就労とわかっていたが、人手不足で見て見ぬふりをした」と供述しているという。
送検容疑は、08年2月~09年11月、東京都内の人材派遣会社から紹介された中国人女性2人に就労資格がないと知りながら、仲居をさせたとしている。
同課は昨年11月、中国人の職業を在留期間が長くなる通訳などに偽装させ、延楽などに派遣したとして、職業紹介業の中国人ら5人を同法違反(不法就労助長など)容疑で逮捕し、社長らの関与を捜査していた。
また、同課は25日、この中国人らと共謀して東京入管に虚偽の書類を提出したとして、行政書士の男性(70)=東京都墨田区=についても同法違反(資格外活動ほう助)容疑で書類送検した。
延楽は天皇、皇后両陛下が宿泊したこともある老舗旅館。【村上尊一】
従業員の感覚を変えるのは難しい。倒産した会社の従業員達を何度か見たが、頭ではわかっているのかも知れないけど、
倒産した会社の価値観や経験を基準として判断したり、話をする。存在しない会社のことをなかなか切り離せない。
JALは存在しているが、短い時間で従業員の価値観や経験をリセットするのは難しいこと。現実に向き合うことが出来なければ、
全日本空輸(ANA)と統合する案も悪くないかもしれない。退職金カット及びボーナスカットの現状で誰が嫌われながら、
改革の大なたを現場で振るうのか???プライドと良き時代を懐かしむことしか出来ない高給取り従業員に対して、何を期待できる
のか??能力があれば、郷愁と折り合いをつけ、他の会社で生きていくほうが楽かもしれない。
参考までに興味があれば下記のサイトを
「派閥抗争いつまで」40代の危機感、背景に 日航内紛 02/26/06(短い一日、空にっき)
「派閥抗争いつまで」40代の危機感、背景に 日航内紛 02/27/06(何かをすれば何かが変わる)
元客室乗務員の私が思う「日本航空の問題点」 あなたは公的資金導入に賛成ですか、反対ですか? 11/25/09(ニュース畑)
ゴルフコンペ、クルージング……懲りないJALは再生するか 01/25/10(ダイヤモンド・オンライン)
「旧正月前の1月28日、ゴルフをしながら懇親会をやりましょう」。日本航空(JAL)の法的整理方針が決まったのは1月8日。その翌週、JAL台湾支店の王富民営業マネジャー名で取引先に出されたこのメールは、月1回開催しているJALと現地の旅行代理店などが参加するゴルフコンペの案内状だ。
費用は割り勘だが、プレー後の懇親会費用はJAL持ち。さすがに取引先からは「正気なのか?」との声が上がっており、中止の可能性もあるという。
台湾だけではない。フランス・パリ支店では1月15日、支店従業員や空港スタッフなど約100人を集め、新年会としてセーヌ川クルージングパーティが会社経費で開催された。
同じ頃、日本では1月19日の会社更生法適用申請を控え、政府や霞が関を巻き込んで、信用不安の火消しや、今後の安全運航を担保するための施策検討が急ピッチで行われていた。
会社が倒産するにもかかわらず、危機感ゼロでゴルフやクルージングに興じている海外支店と国際線事業は、今後のJAL再生計画でいちばん頭の痛い部分だ。
未曾有の航空不況で世界中のエアラインが赤字決算を余儀なくされるなか、機材年齢が古く、大量の燃油を食う大型機を中心に飛ばしているJALは他社以上の苦戦を強いられている。
また、これまでフラッグシップ・エアラインとして「大使館に準じる存在」を目指した海外支店の経費も重くのしかかっている。「JALのプライドの源泉」ともいえる国際線と海外ネットワークは、赤字の元凶でもあるのだ。
今回、企業再生支援機構による3000億円の増資や、日本政策投資銀行などによる6000億円の融資枠が用意されているものの、今年度の営業赤字は約2600億円にも上る予定。法的整理によってさらなる顧客減も懸念されている。潤沢な資金が用意されているとは言いがたい。
資金が足りなくなる前に再生の道筋をつけなければ、再度公費をつぎ込むか、もしくは清算の道を歩むよりほかはなくなる。
ロクに再生計画を議論しないまま法的整理に踏み切ったため、詳細なリストラ計画は今後の大きな課題。国際線を大リストラしたうえで、全日本空輸(ANA)に統合させる案も検討の俎上に載せられている。
国土交通省は「JALとANAの国内2社体制による競争環境の維持」が持論だが、ここにきて前原誠司・国土交通大臣の口から「JAL・ANAの2社体制が成り立つかどうか、見極めるべき」との発言も出ている。
倒産の憂き目に遭ってなお、お公家体質が横行しているJALだが、公的資金でV字回復というような明るい未来はなさそうだ。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 津本朋子)
財団法人交通安全協会の会費徴収について(島根県)
を参考にしてほしい。財団法人交通安全協会の会費も着服した女性職員の退職金に使われているんだろ??
もしそうだとしたら、会費が不適切に使用されているんじゃないか??
でも、
財団法人福岡県交通安全協会
に会費など払ったことのない福岡県以外の県に住んでいる人間としては抗議する権利もないか!
福岡県に在住で会費を払った人は抗議すべきかもね。
島根県のホームページには「警察本部としましては、交通安全協会等の公益法人を指導・監督する立場にあることから、
定期的に立入検査等を実施し、会計経理等に問題がないかなどチェックするほか会費の徴収方法等について、
更新手数料の徴収等と明確に区分するよう今後とも指導していきます。」と書いてある。福岡県警本部は、
島根県のようにチェックはしていなかったことは間違いない。
警察署で売上金千数百万円着服 証紙販売の安全協会職員 01/11/10(朝日新聞)
福岡県警OBが所属する財団法人「県警友会」の委嘱を受け、筑紫野署内で県領収証紙を販売していた女性が売上金千数百万円を着服していたことが、関係者への取材でわかった。女性は筑紫交通安全協会の職員で、協会が県警友会に被害を全額弁済。県警友会は「被害が回復したので、刑事告訴は見送った」と説明し、告訴や公表はしていなかった。
県警友会や協会によると、女性職員が販売していたのは道路使用許可や運転免許更新の申請時に必要な証紙。県警友会が県の指定を受けて運転免許試験場や各警察署内で販売し、大半の署では地元の交通安全協会の職員に委嘱しているという。職員が売上金を県警友会に送金し、県警友会は協力金を協会に払う。
この女性職員も委嘱を受けて筑紫野署内で販売。売上金の送金が長期間滞っていたことから、2008年春に着服が発覚した。着服した金は自身が所有する貸しビルの維持費などに充てていたという。発覚後に依願退職した。
被害については筑紫交通安全協会が全額、県警友会に弁済した。協会の今村省吾会長は「証紙の販売に協会は直接かかわっていないが、女性職員が後日協会に返済すると約束したので、立て替える形で弁済した。依願退職にしたのは、退職金を返済に充てるためだった」と話している。女性は毎月一定の金額を協会に支払っているという。
県警友会の吉川貴久会長は「着服は非常に残念。今後同様の事案が起きないように、売上金の管理を徹底したい」と話す。問題発覚後、筑紫野署内では県警友会の会員が直接、証紙を販売している。
警察署内での証紙販売を巡っては、佐賀県警小城署内でも交通安全協会の職員が売上金約195万円を着服していたことが発覚。県警が業務上横領の疑いで書類送検し、09年11月に佐賀地検が不起訴処分にしている。
「給与減と偽文書」を提出して厳しい罰則はあるの??無いんじゃ、やり得かもね!
社労士が年金保険料で不正、給与減と偽文書 0/04/09(読売新聞)
大阪府南部の社会保険労務士(69)が、府内の建設会社の厚生年金保険料と健康保険料負担を減らすため、社員らを降給したとする虚偽文書を作成し、社会保険事務所に提出していたことが、旧大阪社会保険事務局(現・日本年金機構近畿ブロック本部)の調査でわかった。
免れた保険料は労使合わせて1000万円以上に上るとみられる。同機構は社労士法違反にあたるとして厚生労働省に報告する。
同機構の調査などによると、社労士は2005年3月、厚生年金保険料などを滞納していた建設会社社長から相談を受け、保険料算定の基礎になる給与月額を減らすよう助言。社長の給与を50万円から30万円に、役員・社員10人も26万~32万円から15万~20万円に降給したとする虚偽の変更届を作成し、同4月、地元の社保事務所に提出した。
これに伴い、同社と役員・社員らが折半する保険料の総額は月約80万円から約50万円に減った。社員らは不正に減額された事実を知らされず、正規の保険料を天引きされていた。
08年9月、社保事務所による定期調査で発覚した。
このほか、社労士は、府内の自動販売機販売・管理会社の社長から頼まれ、政府管掌健康保険(現・全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料納付手続きを代行。その際も、給与を低く偽って申告し、少なくとも08年9月までの約4年にわたり、月額保険料約2万5000~4万5000円を免れさせていた。
旧大阪社会保険事務局の調べに対し、社労士は一連の不正事実をおおむね認め、「手続き業務の契約を継続してもらうためだった」と説明しているという。
勤務実体ないのに給与支払い 原子力機構OBに受注3社(1/2ページ)
(2/2ページ) 12/04/09(朝日新聞)
独立行政法人「日本原子力研究開発機構」(茨城県東海村)の関連施設の保守・点検などを請け負う企業グループ3社が、勤務の実体が無いのに同機構OB3人らに報酬や給与を支払い、利益供与していたなどとして、関東信越国税局から計約1億円の所得隠しを指摘されていたことが分かった。
同機構の年間予算額は約2千億円で、うち9割以上は国の交付金など。グループ各社の売り上げは、同機構からの請負業務がほぼ全額を占めており、公金を還元する形で同機構OBへの実質的な利益供与を行った構図だ。
機構OB3人は顧問や嘱託扱いで報酬・給与を得ていた模様で、同機構はその実態を把握していないため、再就職者の公表対象でもなかった。
2007年までの7年間に計約1億円の所得隠しを指摘されたのは、グループ中核の「常陽産業」と「原子力技術」、「ナスカ」の3社(いずれも東海村)。3社を含むグループ6社が税務調査を受けており、他の経理ミスを含む申告漏れ総額は二十数億円。重加算税を含む追徴税額は8億円前後で、既に修正申告しているという。
グループ関係者によると、常陽産業など3社は、元理事1人を含む同機構のOB3人らの役員報酬や給与について、勤務の実体が無いのに負担していた。同国税局は、利益供与を経費に仮装した悪質な所得隠しと判断した模様だ。また、これとは別に約1億円の所得隠しの中には、子会社を吸収合併した際、子会社に支払ったコンサルタント料には実体がなく、経費とは認められないとされた分も一部あるという。
この元理事(68)は取材に「週1回とか月何回とか会社に行ったり、受注の相談に乗ったりした。(報酬額は)他社と合わせて月20万円くらい」と答えた。
常陽産業と原子力技術は「勤務していないのに給与を支払うなど、あり得ない」などとコメントしている。
常陽産業は1972年設立。同機構の前身組織「動力炉・核燃料開発事業団(動燃)」の時代に作業衣のクリーニングを一手に引き受けた後、各種業務を請け負うことになった。グループ各社は、同機構の東海村などにある原子力施設に計1千数百人の社員を派遣している。
民間信用調査会社によると、売上高は常陽産業が07年6月期に約39億円、原子力技術が同7月期に約36億円。(舟橋宏太、中村信義)
◇
〈日本原子力研究開発機構〉 核燃料サイクル開発機構と、日本原子力研究所が05年に統合された、文部科学省所管の独立行政法人。原子力に関する基礎研究や、核燃料サイクルの確立に必要な高速増殖炉の開発などを行っている。年間予算額は約2千億円で、収入の9割以上は国の運営費交付金などが占めている。会計検査院によると、随意契約を結んだ主な民間企業や公益法人への再就職者は122人(07年4月現在)。
郵政3社:横領14億円 金融庁、初の業務改善命令 12/05/09(毎日新聞)
金融庁と総務省は4日、日本郵政傘下のゆうちょ銀行など3社に対し、顧客から預かった貯金など計14億8000万円の横領があったとして、業務改善命令を出した。金融庁が日本郵政グループに行政処分を行うのは、07年10月の民営化後初めて。来年1月6日までに、内部管理体制強化などを盛り込んだ改善計画の提出を求めた。
金融庁などによると、横領が発覚したのは、郵便局とゆうちょ銀直営店の計4店。03~09年にゆうちょ銀行千種店(名古屋市)の元主任が、顧客8人から国債購入名目で預かった計約1億2000万円を着服しており、逮捕、起訴されている。
このほか、郵便局会社の元局長が預金など計約7億2000万円▽元主任が約16年間で計2億6000万円以上▽元簡易郵便局長が7年間で計3億6000万円以上--をそれぞれ着服していた。金融庁はこの3人について、捜査中のため店名などは明らかにできないとしている。金融庁によると、社内規則に反して預かり証を発行せずに通帳を預かり、着服したケースや他の保険に入ると偽り途中解約したまま着服した事例などが見られた。
今年4~6月、顧客からの指摘を受け、ゆうちょ銀行などが社内調査をした結果、発覚。金融庁が8月にゆうちょ銀行などに対し、報告を求めた。ゆうちょ銀などは、被害にあった顧客計103人に対し弁済を進めている。
この日、日本郵政の株式売却凍結法が成立し、本格化している郵政民営化の見直し作業では、利用者の利便性向上や職員の業務負担の軽減のため、貯金の本人確認といった手続きを簡便化することも検討されている。【井出晋平、中井正裕】
郵便局長らが横領・詐欺15億円 郵政3社に改善命令 12/04/09(朝日新聞)
金融庁と総務省は4日、日本郵政グループのゆうちょ銀行とかんぽ生命保険、郵便局会社の3社に、業務改善命令を出した。職員ら4人が高額の詐欺・横領事案を起こし、法令順守体制に問題があったと判断した。貯金や保険を勝手に払い戻す手口で、被害額は4件で計約14億8千万円、被害者数は103人。旧特定郵便局長の横領事案の被害額は約7億2千万円で、貯金や保険に絡む1件あたりの被害額としては過去最悪という。
金融庁や日本郵政グループ3社によると、4月以降、郵便局長らが顧客の貯金通帳や保険証書を預かって勝手に引き出すといった詐欺・横領事案が4件発覚した。いずれも顧客の指摘があるまで気づかず、最長16年以上わからない事例もあったという。
日本郵政グループ3社は、郵便局長ら職員3人を懲戒解雇し、簡易郵便局長は契約解除の処分にした。このうち約1億2千万円をだまし取ったとされる、ゆうちょ銀行千種店(名古屋市)の元主任は詐欺罪で起訴され、4日に懲役4年の判決があった。このほか3件の横領事案(旧特定郵便局長の約7億2千万円、郵便局主任の約2億6千万円、簡易郵便局長の約3億6千万円)は捜査中として、郵便局名などを公表していない。
金融庁は被害が高額で集中して発覚したため、銀行法や保険業法に基づき8月上旬に調査を命令。管理者が防犯点検をしているかのように装うなど、法令順守体制に大きな問題があったため、処分に踏み切った。
総務省も「内部監視体制が不十分で研修や検査が形骸(けいがい)化している」と指摘。今後も横領が続けば経営にも大きな影響があるとして、郵便局会社に改善命令を出した。金融庁と総務省は再発防止や経営責任の明確化を含む改善計画を、来年1月6日までに提出するよう命じている。
郵政3社で横領14億、金融庁が業務改善命令 12/04/09(読売新聞)
日本郵政グループは4日、国内の3郵便局とゆうちょ銀行千種店(名古屋市)で、顧客の貯金を横領するなどの不祥事が相次ぎ、被害者計103人、被害総額は14億6000万円に上ったと発表した。
金融庁は同日、これに先立ち、グループ内のゆうちょ銀行、かんぽ生命保険、郵便局会社の3社に対し、内部管理体制の強化や再発防止策の策定などを求め、業務改善命令を出した。同庁による日本郵政グループへの行政処分は2007年の民営化後、初めて。
発表によると、被害額が最も大きかったのは、郵便局長が07年7月頃から1年半にわたり、31人の顧客から貯金の払戻金や保険の還付金を着服し、計7億2000万円を横領していたケース。
別の郵便局では、局員が1992年ごろから約16年間にわたり、33人の顧客から、生命保険の貸付金など計2億6000万円を着服していた。また、簡易郵便局長は02年頃から約7年間にわたり、顧客31人の貯金の払戻金など約3億6000万円を横領した。郵政3社は捜査中を理由に、局名などを明らかにしなかった。
同銀行千種店では、男性行員(55)が03年から5年以上にわたり、国債の購入代金として、顧客8人から預かった1億2000万円をだまし取った。詐欺罪に問われた行員は4日、名古屋地裁で懲役4年の実刑判決を受けた。郵便局の局長らは、顧客に「金利が良くなったので預け替えをしませんか」などと持ち掛け、預かった通帳から無断で貯金を引き出すなどしていた。
いずれも、今年4月以降の顧客の問い合わせなどで発覚。簡易郵便局長が委託契約を解除され、ほかの3人はいずれも懲戒解雇されている。一方、金融庁は、被害額の端数も加えると被害総額は約14億8000万円になると指摘している。
記者会見した郵政3社は「深くおわび申し上げます」などと謝罪した。
「垣内剛元社長と会食していたことが判明した楠木委員は、20日に記者会見し、『(接触の)時期をずらせば良かったと反省している』
と話す一方、『絶対に内容を漏らさないということであれば、(調査期間中に)プライベートで会うことがなぜ問題なのか』などと持論を述べた。」
専門的知識があるのかどうかは別として、状況と自分の立場を理解できない人間は運輸安全委員に任命するべきでない。
国土交通省は人選に問題があった事を反省し、改善に努めるべきだ。「絶対に内容を漏らさないということであれば、(調査期間中に)プライベートで会うことがなぜ問題なのか」
の点では、JRの人間から接触や関連のある質問や情報を聞かれたかどうか、接触した委員は問題として公表される前に公表したのか???
自分の立場を理解して少なくともどうしても会わなければならない理由がなければ会うべきでない。それが理解できない人間など委員に選ばれる
べきでなかった。今回の問題で委員の人選に問題があったことを国交省は認識し、反省すべきだ。
運輸安全委、JR西が接触の2委員は再任せず 11/20/09(読売新聞)
JR福知山線脱線事故の最終報告書案の漏えい問題にからみ、前原国土交通相は20日の会見で、JR西日本が接触していた運輸安全委員会の委員のうち、現職の宮本昌幸、楠木行雄の両氏について、現在の任期終了後、再任しないことを明らかにした。
委員の任期は1期3年と定められており、最大3期までが通例。楠木委員は来年2月に2期目を、宮本委員は来年9月に3期目の任期を終える。前原国交相は2人を再任しないことについて「遺族、被害者の心情を察した」と述べた。
また、垣内剛元社長と会食していたことが判明した楠木委員は、20日に記者会見し、「(接触の)時期をずらせば良かったと反省している」と話す一方、「絶対に内容を漏らさないということであれば、(調査期間中に)プライベートで会うことがなぜ問題なのか」などと持論を述べた。
一方、事故の最終報告書の信頼性について、遺族らや有識者が検証するチームの初会合は、12月7日に開かれることが決まった。
JR西、前社長が直接指示…事故報告書案漏えい 11/10/09(読売新聞)
JR福知山線脱線事故の最終報告書案漏えい問題で、JR西日本の山崎正夫・前社長(現・嘱託)が、国土交通省航空・鉄道事故調査委員会(現・運輸安全委員会)の窓口となる同社の担当部門の社員(55)に対し、漏えい工作を直接指示していたことがわかった。
社員を通して事前に入手した報告書案を公述人への応募を働きかけた国鉄OBに送付。そのうえで、山崎前社長が、述べてほしい意見をOBらに伝えていた。刑事責任追及をかわす狙いがあったとみられ、山崎前社長が工作を主導していた可能性が強まった。
JR関係者らによると、事実調査報告書が公表される前の2006年12月頃、山崎前社長は社員に対し、「報告書案の内容を把握したいので、その資料をできるだけ早く入手してほしい」と指示。これを受け、社員は事故調の佐藤泰生・元鉄道部会長(70)らから報告書案を入手した。
山崎前社長は社員から入手したとの報告を受けた際、07年2月予定の意見聴取会で意見を述べてもらう公述人候補に、国鉄OBだった伊多波美智夫、小野純朗両氏の名前を挙げ、「あらかじめ報告書案を送っておいてくれ」と要請した。
その際、山崎前社長は社員に、「伊多波さんは運転保安設備の専門家。新型の自動列車停止装置(ATS)をカーブに整備することは一般的ではなかったという当社の意見を理解してもらいたい」、「小野さんはダイヤに詳しい。福知山線のダイヤは過密ではないという話をしてもらいたい」と話していたという。
この頃、兵庫県警は、現場カーブへのATS未設置を業務上過失致死傷容疑で立件する最大の焦点に絞り込み、幹部らの聴取を進めていた。また事故を起こした運転士が異常な速度で運転した背景に、余裕のないダイヤがあったとみていた。
山崎前社長の発言は、こうした捜査をかわす狙いがあったとみられる。
事故調委員接待の東京副本部長を更迭…JR西 10/29/09(読売新聞)
JR福知山線脱線事故の最終報告書案漏えい問題で、JR西日本は28日、国土交通省航空・鉄道事故調査委員会(現・運輸安全委員会)の委員に飲食接待を繰り返していたとして、鈴木喜也・東京本部副本部長を同日付で解任し、新設の鉄道本部技術部(地球環境)担当に異動させる更迭人事を発表した。
真鍋精志副社長は「職を解くということで事実上の処分だ。関係者の全体的な処分は(社内調査の)最終報告書が出た時に対応する」とした。
JR西によると、鈴木氏は2006年9月~07年12月、土屋隆一郎副社長(辞任)の指示で、国鉄時代の上司だった元委員と都内の中華料理店などで10回程度、会食していた。
JR西の対応はひどすぎる!知り合いや家族に被害にあった人間がいないから、JR西は信用できないと思うだけだ。
JR西の対応から判断して他の件でも汚い対応や行為をする可能性があることは考えられる。JR西は日本企業の隠蔽体質を
強く引き継いでいる企業の一つかもしれない。
福知山線事故聴取で口裏合わせ…JR西、対策勉強会 10/18/09(読売新聞)
JR福知山線脱線事故で、JR西日本が、兵庫県警に事情聴取される予定の幹部を対象に、「聴取対策勉強会」を開いていたことがわかった。
県警の聴取に対するJR西幹部らの供述内容が一貫していたことから、幹部を追及したところ、この事実が判明。県警は当時から組織的な口裏合わせとみていたという。
JR西を巡っては、県警や神戸地検の聴取を受けた内容をメモにまとめ、聴取を控えた幹部らに資料とともに配布していた問題が明らかになっている。
捜査関係者によると、聴取対策勉強会が開かれていたのは本社の会議室。聴取を控えた幹部をここに呼び、想定問答を検討していた。
実際に、幹部らの当時の供述は〈1〉遺族や負傷者へのおわびの言葉〈2〉安全対策はちゃんと取っていた〈3〉現場カーブの危険性は予測できなかった――などほぼ同じ文言が同じ順番で述べられ、判で押したような構成になっていたという。
JR西側は「自分の認識や経験の範囲内で回答するよう指導しており、供述の内容に統一感はなかった」としている。
「山崎前社長は背景に『国鉄一家の絆』があったと明かした上で、『皆さまのお気持ちを裏切り、深く傷つけることになってしまった』と沈痛な表情で語り、
取締役としての自らの進退を、佐々木社長に一任していることを明らかにした。」
「国鉄一家の絆」と言う体質が問題であると山崎前社長が発言しているなら、やはり今回の件に関与した人間は役人から外すべきであろう。
相談や取締役に残ることは許すべきでない。土屋隆一郎・副社長も役員として残る限り、真の改革や改善はありえない。見せ掛けだけの改革や
改善となるだろう。例え、関与したJRの人間を相談役や役員から外しても本当に体質が変わるのかさえも疑わしい。
「まだあったのか」口裏合わせに怒る遺族ら 10/17/09(読売新聞)
「『国鉄一家』の絆(きずな)に頼り、思慮に欠けた愚かな行動をした」。
JR福知山線脱線事故を巡る国土交通省航空・鉄道事故調査委員会(現・運輸安全委員会)の情報漏えい問題で、JR西日本の「おわびの会」が17日、兵庫県伊丹市のホテルで開かれた。次から次へと新事実が明らかになる事態に、遺族らは「もう信じられない」と不信感を募らせた。JR西幹部は一連の問題について、ひたすら謝罪と釈明を繰り返し、社長直属の社内チームを発足させて、事実調査を進めていることを明らかにした。
非公開で開かれた会には、遺族や負傷者ら約170人が詰め掛けた。冒頭、佐々木隆之社長(63)や山崎正夫・前社長(66)ら役員11人が並んで頭を下げ、佐々木社長や山崎前社長らがおわびの文章を読み上げた。
佐々木社長は、山崎前社長や土屋隆一郎・副社長(59)らが事故調側に情報漏えいを働きかけたことや、有識者に意見聴取会の公述人になるよう求め、謝礼を支払ったことなどについて経緯を説明。
「まさにコンプライアンス違反で、会社としてあるまじき行為」「組織的な行為と言われれば、返す言葉もない」などと組織ぐるみを認め、謝罪を重ねた。
また、佐々木社長が捜査機関の事情聴取を受けた幹部や社員の供述内容などをメモにまとめ、聴取を控えた幹部らに資料とともに配布するなどしていたことを明かし、「強い不信感を招く行為だった」と述べた。静まりかえった会場からは、「まだあったのか」「口裏合わせではないか」というささやきや、あきれたようなため息が漏れた。
山崎前社長は背景に「国鉄一家の絆」があったと明かした上で、「皆さまのお気持ちを裏切り、深く傷つけることになってしまった」と沈痛な表情で語り、取締役としての自らの進退を、佐々木社長に一任していることを明らかにした。
その後の質疑応答では、遺族からJR西の姿勢に対し、批判が集中。男性が一連の問題について、「当時、社内でおかしいとの声が上がらなかったのか」と尋ねると、山崎前社長は「ありませんでした」と声を絞り出すのがやっと。
午後の会に出席する、次男の昌毅さん(当時18歳)を亡くした上田弘志さん(55)(神戸市北区)は「2年前に山崎前社長に会い、『大きな組織だけに事故調などと裏取引しているのではないか』と聞くと、『事故調は中立。絶対にあり得ない』と言い張っていた。大きな裏切りだ。今回、全面的に謝罪したぐらいでは到底納得できない」と憤りをあらわにしていた。
JR西が口裏合わせ、地検聴取前に幹部にメモ 10/17/09(読売新聞)
JR福知山線脱線事故で、JR西日本が、兵庫県警と神戸地検から事情聴取を受けた幹部らに供述内容をまとめたメモを提出させ、聴取を控えた幹部らに見せていたことがわかった。
幹部らに自動列車停止装置(ATS)などに関するJR西側の主張を盛り込んだ資料をあらかじめ読ませていたことも判明。口裏合わせとも取れる行為で、神戸地検は「供述内容を指導している」として、捜査妨害に当たるとみなし、JR西側に注意した。JR西は「聴取を受ける社員の不安感を和らげ、想定される質問に対応したかった」と釈明している。
事故を巡る国土交通省航空・鉄道事故調査委員会(現・運輸安全委員会)の情報漏えい問題を受け、JR西が17日、遺族らを対象に兵庫県伊丹市で開いたおわびの会で佐々木隆之社長(63)が明らかにした。佐々木社長は「強い不信感を招く行為だった」と謝罪した。
JR西などによると、同社の安全推進部が、事情聴取を受けた幹部や社員に捜査員とのやりとりなどをまとめるように指示し、そのメモを部内で管理、他の幹部らが事情聴取を受ける際、配布していた。
また、2007年2月、事故調の意見聴取会で、JR西側が現場カーブへのATS設置が遅れた点について、「カーブでの大幅な速度超過は考えておらず、必ずしも対策が必要とは考えていなかった」とする公述書も資料として配布していたとみられる。
08年10月、神戸地検はJR西本社を捜索し、これらの事実を把握。「会社として統一的な発言を行わせようとしている」などと注意し、同社はその後、こうした行為をやめたという。
おわびの会には佐々木社長や山崎正夫・前社長(66)らが出席。今回の問題のほか、情報漏えいや資料未提出、公述人への依頼と次々と発覚した事実も取り上げて陳謝した。
JR西前社長が自ら要請 事故調・公述人問題 10/16/09(朝日新聞)
JR宝塚線(福知山線)脱線事故の調査をめぐり、JR西日本が、国土交通省航空・鉄道事故調査委員会(現・運輸安全委員会)が開いた意見聴取会の公述人になるよう有識者や旧国鉄OBら4人に要請した問題で、このうち3人には同社の山崎正夫前社長が直接要請していたことが、JR西への取材でわかった。
当時社長だった山崎氏が直接要請したのは、交通システムが専門の井口雅一・東京大名誉教授と旧国鉄OBの伊多波(いたば)美智夫・秋田内陸縦貫鉄道元専務、同じくOBの小野純朗・日本鉄道運転協会会長の3人。井口氏は事故調からも公述人の依頼を受けており、山崎氏の要請はその後だったという。
伊多波氏は、07年2月に開かれた意見聴取会の約1カ月前に、山崎氏から電話か面会で直接、公述人になるよう持ちかけられたという。承諾した伊多波氏は、事故調がまとめた事実調査報告書案を読み込み、JR西側に手書きで公述書の原案を送った。後日、ワープロで清書された公述書がファクスで送られてきたという。
伊多波氏と小野氏は公述人の選考からは漏れ、JR西は意見聴取会後に、申請資料づくりの手間賃として2人にそれぞれ現金10万円の謝礼を支払ったという。
要請した4人については山崎氏と当時の副社長が選んだという。山崎氏は朝日新聞の取材に対して、「公述の中身に注文は出していない」と話している。
「木村元副大臣に120万円」 逮捕の全精社協元次長 10/16/09(読売新聞)
全国の障害者施設などでつくる社会福祉法人「全国精神障害者社会復帰施設協会」(全精社協、東京)の不正経理事件で、逮捕された元事務局次長、五月女(そうとめ)定雄容疑者(58)が大阪地検特捜部の調べに対し、元厚生労働副大臣で当時自民党衆院議員(香川2区)の木村義雄氏(61)に07年、協会の金約120万円を提供した、と供述していることがわかった。当時の派閥トップ議員のパーティー券代として求められたと説明しているという。
木村氏をめぐっては、全精社協が厚労省から08年度の補助金を受ける際、同省幹部らに交付を促す電話をしたことが明らかになっている。
特捜部は15日、元次長を協会の金835万円を個人で着服したとする業務上横領罪で起訴した。逮捕容疑は964万円だったが、差額の約120万円は協会のこうした政界向けの活動に使われた疑いがあるとみて差し引いた。
五月女元次長の供述によると、会計担当だった元次長は全精社協が精神障害者支援施設「ハートピアきつれ川」(栃木県さくら市)の事業譲渡を受けた後の07年5月、元特別顧問(死亡)らとともに木村氏と東京都内で面会。木村氏から、派閥トップ議員のパーティー券を買う金を融通してほしいなどと頼まれたとされる。元特別顧問の指示で約120万円を協会口座から引き出し、提供したという。
特捜部は、協会の会計資料から同額の支出があったことも確認したとみられる。
木村氏の事務所は15日現在、朝日新聞の取材の申し入れに応じていない。当時の派閥トップ議員の事務所は取材に「木村氏に売りさばきを依頼したことはない。全精社協に購入してもらったこともない」と否定している。
全精社協の資料には、協会が木村氏本人のパーティー券を07、08年度に二百数十万円分購入したとする記録があることも特捜部の調べでわかっている。
全精社協の不正経理、元事務局次長を起訴 10/15/09(読売新聞)
社会福祉法人「全国精神障害者社会復帰施設協会」(全精社協、東京)の不正経理事件で、大阪地検特捜部は15日、元事務局次長・五月女(そうとめ)定雄容疑者(58)を約840万円の業務上横領罪で起訴した。
調べに対し、五月女容疑者は起訴事実を認め、「経理チェックがずさんで、幹部が不明朗な会計処理をしているのを見て、少しぐらい横領しても大丈夫だろうと思った」と供述しているという。
起訴状などによると、五月女容疑者は事務用品の架空・水増し発注やカラ出張で多額の裏金を捻出(ねんしゅつ)。2005年9月~08年4月、約960万円を無断で引き出し、約840万円を競馬や借金返済に充てたとされる。差額約120万円については「今年7月に死亡した元上司に渡した。元上司が政治家や官僚への工作資金に使ったと思う」などと説明しているという。
消費期限改ざん:イオン傘下のスーパーが 派遣社員が告発 10/06/09(毎日新聞)
流通業界大手イオングループ傘下の「マックスバリュ東海」(静岡県長泉町)が運営するスーパー「ヤオハン立野店」(浜松市南区)で08年10月~09年1月、消費期限切れになった鮮魚の期限を改ざんして販売していたことが6日、明らかになった。マックスバリュ東海は役員3人や販売にかかわった社員ら計11人を降格や減給の社内処分にした。
同社広報室によると、派遣社員の60代男性が、鮮魚売り場チーフ(責任者)の40代男性から指示を受け消費期限を改ざんした。派遣社員が退職後の6月、改ざんを記録したノートのコピーを同社へ郵送して発覚。同社が調査したところ、ブリの消費期限が11回にわたり改ざんされていたことを確認。10回は切り身で、1回はしゃぶしゃぶ用として販売したという。同社は浜松市保健所に改ざんを報告し、文書などで指導を受けた。
チーフだった男性は「売り上げ目標のプレッシャーに負けて社内ルールに違反してしまった」と改ざんを認めたといい、同社は降格させるとともに県内の別店舗へ異動させた。
派遣社員のノートにはブリ以外にメヒカリ、ニギスなど計6品目を改ざんしたとの記述があったが、同社は「確証を得られたのはブリだけだった」と説明している。【田口雅士】
◇「やってはいけないことをやった」
マックスバリュ東海の内山一美社長は6日午前、記者会見し「やってはいけないことをやってしまった。大変反省している。再発防止に努めたい」と話した。
郵便割引、不備把握後も280万通発送 10/05/09(朝日新聞)
障害者団体向けの郵便割引制度の不正利用問題を受けた会計検査院の検査で、郵便事業会社(日本郵便)の審査で低料第3種郵便物の承認取り消しなどの必要があったにもかかわらず、約280万通の刊行物が1年以上低料金のまま引き受けられていたことが分かった。検査院は、社内の相互チェック体制の不備とみて、日本郵便に体制見直しを求める方針だ。
関係者によると、日本郵便などは、旧郵政省時代の1980年と91年にも第3種郵便物に関する問題を指摘されたことを受けて、不正防止のために「第3種郵便物調査事務センター」を設置。低料第3種を利用している定期刊行物の発行者から発行のたびに窓口に見本が提出されているかの調査や、承認条件を満たしているかを確認する年1回の定期調査を実施し、結果を日本郵便の支社に毎月報告し、支社は承認取り消しなどの通知をすることになっている。
しかし、検査院が昨年10月の問題発覚直前までの3カ月分を調べた結果、発行者から見本が提出されていなかったり、発行状況に関する報告書などに不備があったりした問題がセンターから報告されていたにもかかわらず、30以上の同社支店や郵便局が、低料金のまま1年以上も刊行物を引き受けていたという。発送されていた刊行物は280万通以上で収納金額は約1億円にのぼった。
いずれも、本来は発行者に承認の取り消しなどを通知する必要があった。センターが承認取り消しなどを決めてから1年以上経過しても、発行者が是正したかどうかすら確認できない刊行物は300種超あったという。社内のどの部署も追跡調査を行っていなかった。
福知山線事故のATS資料、県警にも提出せず…JR西 09/29/09(読売新聞)
JR福知山線脱線事故で、JR西日本が航空・鉄道事故調査委員会に自動列車停止装置(ATS)に関する社内会議資料の一部を提出しなかった問題で、同社は兵庫県警にも同じ部分を提出していなかったことがわかった。
JR西は、「県警からは、事故調に出したのと同じ資料の任意提出を求められた。意図的に隠したのではない」と説明している。
JR西によると、提出していなかったのは、1996年に起きたJR函館線の脱線事故の後に開かれた同社鉄道本部内の会議用資料9枚のうち最後の2枚。この中には、ATSを設置していれば防げた事例として、函館線の事故が記載されていたとされる。
山崎正夫・前社長(66)は当時、鉄道本部長だった。
JR福知山線脱線事故の捜査では、現場の状況が似ていた函館線の事故を受け、JR西幹部らがカーブの危険性やATS設置の必要性を認識していたかが焦点の一つだった。
「会食の食事代は、『ウーロン茶と焼きそばくらいしか食べていないので、先に帰る時に同行者に2000円程度を渡していた』と述べた。」は
接触が発覚したときの為にあえて低額になるように配慮したとも思える。内偵のつもりであれば、後で言った、言っていない等の信憑性が問題に
なるので会話を録音するべきだろう。証明できないような行為や立証できない事を調査報告書に書いても意味が無い。JR西日本が組織ぐるみでない
と言うのであれば、組織の指示がなくともJR西日本の利益に繋がれば何でもやるべきだと言う考え方が幹部達に浸透していたと考えてもおかしくない。
そのような偏った考え方がJR西日本の常識であれば、隠蔽や会社に不利になる事実を公表するわけが無い。また、国鉄時代の職員がこのような対応を
取った事実は、公務員も同じような価値観で生きている可能性がある。自分達(身内)の不祥事は隠蔽し、公平には調査できない体質があることも
疑われる。今回の事故調査の問題を教訓に、公務員(身内)の不祥事の事故調査は適切には出来ない事を前提に改革や改善を行うべきだ。
「内偵のつもりだった」福知山線漏えいで元委員 09/28/09(読売新聞)
JR福知山線脱線事故の最終調査報告書案の漏えい問題に絡み、JR西日本の幹部と接触していた国土交通省航空・鉄道事故調査委員会(現・運輸安全委員会)の鉄道部会長だった佐藤泰生・元委員(70)が28日午前、記者会見し、「(JR西の内情を)内偵するつもりで会っていた。誤解を招く行動で、大変反省している」と述べた。
佐藤元委員は、2006年8月から報告書が公表された07年6月にかけ、国鉄時代の後輩だったJR西の鈴木喜也・執行役員東京本部副本部長(55)と都内の中華料理屋などで10回前後、会食していた。
佐藤元委員は、鈴木副本部長との接触を繰り返した動機について、「日勤教育が事故の最大の問題だと思っていたが、JR西日本は認めようとせず、内情がよく分からなかった。内偵のつもりで話を聞いていた」と説明。鈴木副本部長との関係については、「古い知り合いで、東京で昔の友達と会うという場に行って、1時間ほど話を聞いて帰るということをしていた」と述べ、あくまで独自調査の一環という認識を示した。
一方で、「情報漏えいは絶対にしないようにと気を使い、共通の知人の1人を横に置いていた」と釈明し、報告書の内容の漏えいについては否定した。
ただ、鈴木副本部長が聞きたい内容をメモにした紙を持参して質問し、「これはマルだね」「バツだね」と、審議の状況について答えたことがあった。また、「日勤教育のことは報告書に載りますか」と質問されて、「当たり前だろう」と答えたこともあり、「探りが入っているな」と感じたという。
会食の食事代は、「ウーロン茶と焼きそばくらいしか食べていないので、先に帰る時に同行者に2000円程度を渡していた」と述べた。
事故調漏えい:JR西前社長、中間報告書素案も入手 09/29/09(毎日新聞)
JR福知山線脱線事故の最終調査報告書案が事前に漏えいしていた問題で、JR西日本の山崎正夫社長(当時)が航空・鉄道事故調査委員会(現・運輸安全委員会)の山口浩一委員(当時)から、事実調査報告書案も入手していたことが、JR西への取材で分かった。06年12月の公表直前に提供を受けたとみられ、最終報告書案入手の約半年前にあたる。事実調査報告書は一連の調査の中間報告で、乗客106人が死亡した事故の全容や企業責任に言及していた。
JR西によると、山崎前社長は事実調査報告書案を入手後、事故調との窓口となる同社の事故対策審議室に渡し、社内で共有していたという。同社は直後の07年2月、事故調が開いた意見聴取会に臨むが、その事前準備に活用したとみられる。報告書案の修正要求はしなかったという。
事実調査報告書は、運転ミスの無線連絡に気を取られた運転士のブレーキ操作が遅れ、脱線した可能性を示唆。余裕のないダイヤ設定や安全投資の遅れなど、JR西の安全軽視の姿勢にも触れていた。事故調はこの事実調査報告書を基にさらに調査を進め、07年6月に最終調査報告書を公表した。
山崎前社長によると、一連の問題を巡っては06年夏~秋ごろ、山崎前社長側から旧知の山口元委員に面会を打診。以降、東京の飲食店などで、3、4回、昼食や夕食を共にした。二つの報告書案はこの際に入手したとみられる。【鳴海崇】
国交相、報告書案漏えいでJR西社長に調査命令へ 09/28/09(読売新聞)
JR福知山線脱線事故の最終調査報告書案の漏えい問題で、前原国土交通相は28日、JR西日本の佐々木隆之社長を国交省に呼び、全容調査と改善策の報告を求める命令書を手渡した。
鉄道事業法に基づく調査報告命令は初めて。
前原国交相は佐々木社長に対し、「情報漏えいや報告書の変更を求める働きかけは国民への背信行為。早急に事実の解明を」と求めた。佐々木社長は「信頼回復の取り組みを進めるべき幹部が軽率なことをした。重大な問題だと考えている。申し訳ない」と謝罪した。
JR西日本は今後、事故調委員などに接触した社員や接触の日時、場所などの実態調査を行い、同省に改善措置を報告する。佐々木社長は「外部の方の力を借り、真剣に調査を進めたい。できるだけ早くまとめたい」と述べた。また、今回の問題について役員が個別に遺族宅などを訪問し、説明と謝罪を行う意向を示した。
一方、運輸安全委員会も遺族らへの説明会を来週にも開く方針を決めた。
鉄道事故調査、人選見直しへ 旧国鉄出身に偏りがち 09/28/09(朝日新聞)
JR宝塚線(福知山線)脱線事故の調査情報漏洩(ろうえい)問題で、運輸安全委員会は、旧国鉄関係者に偏りがちな委員の構成の見直しを検討する。委員は両議院の同意を得て国土交通大臣が任命する規定になっており、今後、前原誠司国土交通相に進言するなどして判断を促すことになる。
JR西日本の幹部が同委の前身の航空・鉄道事故調査委員会に接触を図っていた07年当時、鉄道部会の委員(法制担当を除く)は4人で、うち3人が旧国鉄の出身者だった。JR西日本はこの点に着目。山崎正夫前社長(66)は、同じ技術職の先輩である山口浩一元委員(71)に報告書案の改変を依頼。鈴木喜也東京本部副本部長(55)は、土屋隆一郎副社長(59)の指示を受け、やはり旧国鉄時代の先輩の佐藤泰生元鉄道部会長(70)から情報を引き出そうとした。
山口元委員と佐藤元部会長はすでに退任しているが、現在の鉄道部会も、4人中2人が旧国鉄系の研究者だ。
今回の問題で、旧国鉄の先輩後輩関係を悪用した、事故調査をする側とされる側との「なれ合い」の構図が明らかになり、安全委では、委員の人選・構成の見直しを求める意見が強まった。
だが、大学などで研究が進む航空分野と違い、鉄道では旧国鉄・JRの研究機関以外に専門家育成の場は乏しく、同委幹部の一人は「人選は難しい課題。当面は、旧国鉄・JR出身の調査メンバーはJRの事故では調査への関与を控えるなど、運用面で対応せざるを得ない」とも話している。(佐々木学)
社説:JR報告書漏えい 何を信じろというのか 09/27/09(毎日新聞)
国土交通省航空・鉄道事故調査委員会(現・運輸安全委員会)の元委員が、在任中に担当したJR福知山線事故の最終報告書案をJR西日本の山崎正夫前社長に漏らし、山崎前社長が内容の修正を働きかけていたことが明らかになった。
事故調は刑事責任追及とは別に、当事者からあらゆる情報を集めて事故原因を究明し、再発防止や安全性向上に役立てるのが本来の目的だ。その公正さや中立性を損ない、国民からの信頼を著しく失墜させる行為である。不正を主導した山崎前社長の責任は極めて重い。
07年6月に公表された事故調の最終報告書は、現場が急カーブに改造された際にATS(自動列車停止装置)を優先的に設置すべきだった、などと指摘した。
山崎前社長は元委員を接待して報告書の内容を公表前に知った。さらに、自分が鉄道本部長時代にかかわったATS設置問題と事故の因果関係の記述を削ることも依頼した。元委員は事故調で修正を提案したが、通らなかったという。
山崎前社長は神戸地検の捜査で、ATS設置を怠った責任者として業務上過失致死傷罪で起訴され、社長を退任したが、取締役に残った。
「早く情報を手に入れ、対応するためだった」と山崎前社長は釈明している。だが、JRや自分の責任を回避する工作と見られてもやむを得ない振る舞いだ。「不適切」で済む問題ではない。
元委員は旧国鉄OBで、山崎前社長の先輩だった。「国鉄一家」気分が抜けていないから、筋違いの依頼に気軽に応じたのではないか。山崎前社長にも、身内への甘えがあったことは否定できまい。
事故後経営トップに就任した山崎前社長は、JR西日本の企業風土改善や職員の意識改革を呼びかけてきた。だが、音頭を取るトップみずからが古い体質にどっぷりひたっていたのでは実効が上がるはずもない。他の幹部にも猛省を求める。
報告書漏えいの事実は前原誠司国土交通相や運輸安全委が記者会見して公表した。政権交代の波及効果だろう。委員人選や調査方法改善について、納得のいく情報開示を進めてほしい。
裏切られた思いがもっとも強いのは事故被害者や遺族である。事故調の報告書を真摯(しんし)に受け止めて再発防止に生かす、というJR西日本の説明を信じたくても、これでは受け入れる余地はなくなる。
一連の工作がすべて山崎前社長の個人行動だったのか、など解明すべき疑問点は多い。JR西日本はきちんと検証し、けじめをつけることが不可欠だ。信頼関係の立て直しは、それからの話である。
JR西幹部「社内対策室から事故調へ接触要請」 09/26/09(読売新聞)
事故調の鉄道部会長だった佐藤元委員と接触していたJR西日本幹部の鈴木喜也・執行役員東京本部副本部長(55)が26日夜、記者会見し、当時所属していた社内の「事故対策審議室」のメンバーから「(佐藤元委員と)知り合いなら、聞けることがあったら聞いてきてくれ」と接触を要請されたことを明らかにした。
鈴木副本部長によると、佐藤元委員とは2006年8月~07年6月、都内の中華料理店などで10回ほど面会。国鉄時代の知人と3人で会い、代金は鈴木副本部長らが負担したという。会合で鈴木副本部長が「どんな議論をされていますか」と尋ねると、佐藤元委員は「日勤教育のことが出ているよ」などと答えたという。
一方で、鈴木副本部長は「接触は会社ぐるみではなかった」と強調した。
「ATSの必要性」議事録、JR西提出せず 09/26/09(読売新聞)
乗客106人が死亡した2005年4月のJR福知山線脱線事故(兵庫県)で、JR西日本が国土交通省航空・鉄道事故調査委員会(当時、事故調)に対し、1996年に起きたJR函館線の脱線事故後に開かれた社内会議の議事録の一部を提出していなかったことがわかった。
函館線の事故は福知山線と状況が似ており、未提出分には「(函館線の事故は)自動列車停止装置(ATS)を設置していれば防げた」という趣旨の記載があった。神戸地検は、JR西側が福知山線の現場にATS設置の必要性を認識していた重要な証拠とみている。
関係者によると、事故調に提出された議事録は7枚だったとされる。だが、地検が今年5月、本社などを捜索した際に、実際には9枚あり、2枚が未提出だったことを確認したという。当時、鉄道本部長だった山崎正夫・前社長(66)(業務上過失致死傷罪で在宅起訴)も会議に出席していたという。
函館線の事故は96年12月、半径300メートルのカーブで、速度超過のJR貨物のコンテナ列車が脱線した。福知山線の現場カーブが半径600メートルから同304メートルに付け替えられたのは、事故の直後。地検は山崎前社長に対する起訴状で、現場カーブの付け替え当時に危険性を認識できたのにATSを設置しなかった、としている。
一方、JR西はこれまで「社内会議で函館線の事故は報告されたが、ATS設置の議論には至らなかった」と説明していた。議事録の一部が提出されなかったことについて、JR西側は、単なるコピー漏れとしているという。
福知山線脱線事故の調査を巡っては、事故調の山口浩一元委員(71)が、07年6月に最終報告書が公表される前に、山崎前社長に報告書案を漏らし、山崎前社長から「ATSがあれば事故が防げた」などとする文言を報告書案から削除するよう求められていたことが、明らかになっている。
「軽率、不適切な行為」…JR西・前社長が謝罪 09/25/09(読売新聞)
JR福知山線脱線事故(兵庫県)の事故調査報告書案漏えい問題で、JR西日本の山崎正夫前社長は25日、JR西で記者会見。
「(相手に守秘義務違反をさせたという点で)悪いという認識はあった。極めて軽率、不適切な行為で申し訳なく思っている」と述べ、「遺族やけがをされた方々に深くおわびしたい」と頭を下げた。
山崎前社長によると、山口・元委員とは事故翌年の06年夏か秋頃に自分から電話をかけ、2人きりで3、4回会ったという。「事故調の議論の内容を早く知り、対応したい一念だった」と理由を述べた。
「ATSがあれば事故が防げた」という文言を報告書案から削除するように求めたことについては、「会社から公式に要望していた内容で問題はないが、個人的なやりとりは不適切だった」と釈明。報告書の写しは、自分で読んだ後に担当社員に渡したという。
飲食接待は昼夜各1回ずつで、飲食代は山崎前社長が支払った。会うときには、菓子折りや(市販されていない)鉄道模型を持って行ったが、「食事をしたのは赤ちょうちんのような店で、接待や供応というイメージではない」と説明し、金銭の授受も否定した。
遺族らに対しては、「私に期待を寄せていただいた方々には、申し訳ないと言うしかない」と陳謝した。
会見中、終始表情をこわばらせ、謝罪や反省の言葉を30回近く繰り返したが、取締役にとどまり、被害者対応に当たる意向を示した。
尼崎脱線:事故調報告案漏らす 元委員がJR西の前社長に 09/25/09(毎日新聞)
兵庫県尼崎市で05年4月に発生したJR福知山線脱線事故で、運輸安全委員会は25日、事故原因を調査した当時の航空・鉄道事故調査委員会(08年10月に運輸安全委に改組)の山口浩一・元委員(71)が、JR西日本の山崎正夫前社長に働きかけられ、調査状況の情報や報告書案を伝えていたと発表した。山口元委員は事故調で報告書案の修正を求める発言をしたが、報告書への影響はなかったという。事故調査委員会設置法では、委員の秘密保持義務があるが、罰則規定がなく、処分対象にはならない。
安全委などによると、山口元委員は06年5月以降、山崎前社長に面会するなどして、委員会の進ちょく状況を教えた。さらに、報告書が07年6月に公表される直前の07年4~5月ごろ、報告書案のコピーを1、2回、山崎前社長に渡した。
また、山崎前社長が報告書について「後出しじゃんけんであり、表現を柔らかくするか削除してほしい」と要求。山口元委員はそれに応じ、委員会で「現場カーブにATS(自動列車停止装置)があれば事故は回避できた」などとの記述を「後出しじゃんけんなのでいかがなものか」と発言していた。関係者によると、山崎前社長は山口元委員への飲食接待もしていたという。今回の漏えいは、事故に関する捜査で発覚。捜査当局が安全委に連絡したという。
前原誠司国土交通相は25日の閣議後会見で「亡くなった方々やご遺族に心からおわびを申し上げる」と謝罪。運輸安全委の後藤昇弘委員長は「国民のみなさま、被害に遭われた方々に不快の念を与え、残念で申し訳ない。おわび申し上げる」と陳謝した。
事故では乗客106人と運転士が死亡。事故調は07年6月、運転士がブレーキ操作を誤り、制限速度を約46キロ超過して現場カーブに進入したことが原因とする最終報告書を国交相に提出した。現場カーブにATSが設置されていれば、事故は回避できたと結論付け、「優先的に整備すべきだった」と指摘。運転士への懲罰的な日勤教育など、JR西の企業体質が事故に影響した可能性が高いとも指摘していた。
山崎前社長は事故現場を現在の急カーブに付け替えた当時、安全対策全般を統括する常務鉄道本部長だったとして神戸地検が今年7月、業務上過失致死傷罪で神戸地裁に在宅起訴している。山崎前社長は06年2月、社長に就任し、起訴を受けて今年8月、社長を辞任した。一方、山口元委員は1961年、国鉄に入社。主に運転畑を歩み、01年に非常勤の事故調委員に任命され、07年まで務めた。
安全委は情報漏えいを受け、委員などが原因に関係する恐れのある人とかかわりがある場合、委員会の会議へ参加停止できるなどの申し合わせをした。【平井桂月、長谷川豊、石原聖】
▽山崎正夫前社長の話 航空・鉄道事故調査委員会の調査に全面的に協力する中で、調査状況を把握し、迅速に対応するとの思いから報告書案などを事前にもらった。軽率で不適切な行為であったと反省しており、申し訳なく思っている。
国交省:福山通運の福岡センター、6日間の停止処分に 09/04/09(毎日新聞)
国土交通省は4日、福山通運(広島県福山市)が事業計画にない北九州-東京間で貨物を航空運送として受託したのは貨物利用運送事業法違反に当たるとして5日から、同社福岡流通センター(福岡市東区)の貨物利用運送事業(国内航空)を6日間の停止処分とした。全国規模の運送業者が同法違反で事業停止処分となるのは初めて。
国交省によると、福山通運は昨年8月から北九州-東京間で航空運送の受託を始めた際、国交省に事業計画の変更届を出していなかった。今年2月、国交省の定期監査で発覚し、5月に文書で警告されたが、そのまま違反を続けた。6月に変更を申請したが、認可が下りないまま、運送を継続していた。
福山通運の向井秀也専務は「受託運送をやめなければいけないという自覚がなかった。再発防止に取り組みたい」と話している。
福山通運は、空輸に必要な爆発物検査をしていないのに、検査済みと偽って航空会社に荷物を預けていたとして1日、荷物検査業務の停止処分を受けており、4日に国交省から事業改善命令も受けた。【平井桂月】
会計士に退職金20億、法人税37億滞納も 07/29/09(読売新聞)
総合人材サービス会社旧グッドウィル・グループ(GWG)による人材派遣会社買収を仲介した投資事業会社を巡る脱税事件で、法人税法違反容疑で逮捕状が出ているオーナー兼元社長の公認会計士(51)が社長退任時、退職金として20億円を受け取っていたことが関係者の話でわかった。
同社はその2か月後、法人税など約39億円の申告をしたが、今も大半を滞納したまま。自ら多額の退職金を得る一方、税金を滞納するなど、ずさんな経理実態を浮き彫りにしている。
関係者によると、会計士は2006年5月、投資事業会社「コリンシアンパートナーズ」を設立し、社長に就任。同社の運営するファンド「コリンシアン投資事業有限責任組合弐号」を使って同年10月、GWGによる人材派遣会社「クリスタル」の買収を仲介し、約383億円とクリスタル株1万3635株(取得価格約131億円)を得た。
コリンシアン社は、これらをファンドの組合員(出資者)だった格闘技団体代表と別の投資事業会社元代表と分配した結果、手元に約180億円とクリスタル株の一部が残った。
会計士は買収の仲介から1年半後の08年4月下旬、社長職を役員に譲って辞任した際、退職金として20億円を受け取っていた。会計士は同社から数億円の借金をしており、退職金の一部を返済に充てていたという。会計士の知人は「退職後も会社に出勤し、役員に指示して会社の資金を動かしていた」などと証言しており、会計士は、コリンシアン社の発行済み株式1080株すべてを握るオーナーとして、経営の実権を握り続けた。
コリンシアン社は、買収仲介の現金収入だけで約180億円を得たが、多額の経費がかかったなどとして、08年6月に申告した法人所得は89億円。この法人所得に対する法人税などの税額は約39億円だが、現在まで約2億円しか納めていない。
会計士は東京地検特捜部の事情聴取を受けた直後の今月10日、中部国際空港から香港に出国した。
「シートベルトなし」経緯不明 大分・バス横転事故 07/15/09(毎日新聞)
大分県日出(ひじ)町の大分自動車道で、柳ケ浦高校(同県宇佐市)の大型バス(定員47人)が横転して野球部員が死傷した事故で、バスの座席にシートベルトが設置されていなかったのは道路運送車両法に基づく保安基準に違反する可能性があることが14日、九州運輸局大分運輸支局などへの取材でわかった。ただ、これまでの車検でシートベルトの不備は指摘されておらず、シートベルトがなぜないのかの経緯も不明。運輸支局は県警と連絡を取りながら事実関係を調べている。
運輸支局の説明によると、同法に基づく保安基準では、87年9月以降に製造された車は路線バスなどを除き、前向きの全座席(折りたたみ式の補助席を除く)にシートベルトを設置することが義務づけられている。製造元の三菱ふそうトラック・バス(川崎市)によると、事故のあったバスは91年12月製で、全席にシートベルトをつけて出荷した記録があるという。
一方、同校はこのバスを91年12月に新車で購入。職員の話などから、遅くとも93年ごろにはシートベルトはなかったことを確認したという。
このバスは年1回の車検が義務づけられている。同校が約10年前から車検を依頼していた宇佐市内の整備業者は「営業用の車両ではないので、シートベルトのチェックは必要ないと考えていた」と話している。
新車として新規登録する場合、運輸支局での検査が必要。大分運輸支局は「シートベルトがついていない状態で新規検査を通るとは考えにくいが、書類が残っていないので91年当時の状況は分からない。新規検査時にベルトがあったかどうかを含め、調査している」としている。
この事故で、大分地検は13日、自動車運転過失致死傷の疑いで送検された同校野球部の不破大樹・副部長(26)を処分保留で釈放した。県警と地検は任意の捜査を続ける方針。
汚染米:有印私文書偽造で浅井被告を追起訴 捜査終結 07/15/09(毎日新聞)
接着剤製造会社「浅井」(名古屋市瑞穂区、破産手続き中)による汚染米転売事件で、名古屋地検は14日、同社長の浅井利憲容疑者(57)=食品衛生法違反(規格外食品の販売)罪で起訴=を有印私文書偽造・同行使罪で名古屋地裁に追起訴した。これにより汚染米転売事件の捜査は終結した。
起訴状によると、浅井被告は07年2~9月、実在する合板会社の受領書を偽造、同3~9月まで計6回、農林水産省東海農政局に提出したとされる。
愛知、三重両県警合同捜査本部によると、浅井被告は合板会社のゴム印を使って受領書を偽造。農薬メタミドホスに汚染された中国産もち精米を工業用目的で出荷したように装っていた。
捜査本部によると、浅井被告は06年12月~07年5月、政府から汚染米約570トンを1キロ5~6円で購入し、全量を米穀仲介業「ノノガキ穀販」(三重県四日市市)に転売。元社長の野々垣勝被告(46)=食品衛生法違反罪で起訴=は全量を同50円で食用として転売した。【中村かさね】
郵便局員が貯金無断引き出し、関係者殺害図る 07/08/09(読売新聞)
定額貯金を無断で引き出したことが発覚するのを恐れ、貯金の名義人の妻の北海道帯広市の女性(61)を殺害しようとしたとして、北海道警帯広署は8日、同市西8北7、郵便局会社の幕別郵便局社員、渋田一博容疑者(35)を殺人未遂容疑で逮捕した。
発表によると、渋田容疑者は7日午後3時50分頃、女性宅で、女性の背後から首を両手で絞め、殺害しようとしたほか、目撃した女性の長女(32)の首も絞め、2人にけがを負わせた疑い。
農村システム不正:委託団体が虚偽説明 業者の見積もりを 06/26/09(毎日新聞)
社団法人「日本農村情報システム協会」(自己破産)による6億円余の不正支出問題で、協会に事業費を水増し請求した理由について、業務委託先の任意団体「情報システム技術会議」は「再委託先の東京都内の業者の事業費がかさんだため必要になった」と説明していたが、業者からの実際の請求額は見積もりの範囲内だったことが分かった。説明は虚偽の可能性が高く、不正支出の大半は同会議内で使途不明になった疑いが強まった。
協会を所管する農林水産省などによると、協会は市町村から防災無線の設計などを請け負い、94年から大半を情報システム技術会議に委託。同会議は都内と京都市内の業者に再委託していた。協会の副会長は89年6月~今年3月、同会議理事長を兼任し、月100万円の報酬を得ている。
同会議は03年ごろから協会に対し、事業費が市町村との契約額を上回っているとして、水増しを要求。協会は求められるままに支出し、不正支出は少なくとも6億4600万円に上った。
水増し請求について協会理事を兼任していた同会議理事(60)は「都内の業者による事業の日数が予定より延びたり、範囲が広くなったりして経費が余計にかかったため」と説明。京都市内の業者については「ほとんど見積もりの範囲内だった」としていた。
だが、都内の業者や業者の内部資料によると、業者の請求額の大半は少なくとも過去4年間、見積額の範囲内だった。請求額が見積額を超えるのは年1~2回、天候の影響などで事業をやり直したケースだけだった。【奥山智己】
公務員の不正に対しても厳しい態度で行ってほしい。農水省の問題や
郵便不正事件
などは隠蔽が明らかだ。しかし、内部調査は甘い。まともな調査も行われず、
そのような事は確認できないと幕引き。食品の産地偽装は農水省職員の対応にも問題が
あったが、うやむやにしてしまった。
証拠隠し許さん!…警察と行政、偽装や悪質商法に連携対処 06/25/09(読売新聞)
全国各地で食品の産地偽装や住宅のリフォーム詐欺が後を絶たないことから、政府は被害拡大を防ぐため、監督官庁の農水、経産両省に寄せられた相談や内部告発を、速やかに行政処分や警察による摘発に結びつける体制を整備する。
行政の立ち入り調査をきっかけに証拠を隠滅する業者が目立つため、悪質な場合は、行政と警察が各都道府県ごとに設置した協議会に情報を提供し、事前通告なしで立ち入り調査を実施したうえで迅速に警察に告発する。
26日の犯罪対策閣僚会議に報告し、7月にも実施する。
「比内地鶏」や「飛騨牛」など、昨年1年間に警察が摘発した食品偽装事件は、過去最多の計16件で前年の4倍。悪質な住宅リフォームや点検商法などの特定商取引法違反事件も30件増の142件で、被害額は107億円を超えている。
こうした消費者関連事件は、監督権限を持つ両省などが立ち入り調査を実施し、営業停止などの行政処分をしたうえで警察に告発するのが一般的だった。
しかし、立ち入りを事前通告すると証拠が発見できないケースも多く、愛媛県の業者によるウナギの産地偽装事件では、農政事務所と県が昨年6月、立ち入り調査を事前通告したことで帳簿などが改ざんされ、県警が9月に捜索に入った時には必要な書類が焼却されていた。
このため両省や自治体などが調査に入る前から警察と協議する場が必要と判断した。消費者庁が新設されれば、同庁が集約した苦情や相談をもとに、監督権限を持つ両省などに調査を要請するという流れを作る。警察庁も両省などに告発状のひな型を配布し、摘発強化に乗り出す。
九州乳業 赤字166億円、新体制を承認 06/25/09(大分合同新聞)
私的整理により抜本的経営再建を目指す九州乳業(九乳)=大分市=の定時株主総会が25日、同市の本社で開かれ、第46期(2008年4月~09年3月)の決算を承認。旧株主による資本の減資と新株主による出資、新役員の選任などによって経営体制を固め、新たなスタートを切った。決算は保有資産の再評価による減損処理などを行った結果、最終損益は166億4200万円の赤字となった。
急激な景気悪化に伴う消費者の買い控えなど経営環境が悪化する中、牛乳の消費拡大に努めたものの、売上高は180億9000万円で、前期比13・3%減。収益面では上期が原油高による製造経費の増加、下期は売り上げの急激な低下により利益が確保できず、経常損益は19億7300万円の赤字(前期比20億3400万円減)となった。
また「過年度に不適切な会計処理があった」として、工場や敷地など資産の再評価により前期損益修正損を82億4700万円、目減りした分を減損損失として63億7500万円計上。その結果、129億8000万円の債務超過に陥った。
早期の経営改善・健全化と債務超過の解消を図るため、金融機関に金融債務(九州乳業本体で145億5000万円)の一部放棄を求める調整を、整理回収機構(RCC)に依頼。株主責任を明確にするため、筆頭株主の大分県酪農業協同組合は現在の出資を100%減資後、2億円を再増資。農畜産業振興機構(国)や大分県などは90%を減資。減資分は債務弁済に充てる。新たにフンドーキン醤油や大分ガス、フォレストホールディングスグループ、三和酒類に出資を仰ぐ。
役員人事は経営責任を明確にするため、従来の常勤の取締役、監査役は部門の責任者2人を除いて全員退任。新社長に県OBの江川清一氏が就いたほか、メーンバンクの農林中央金庫や、大分銀行、フンドーキン醤油から役員を迎えた。
不適切な会計処理については、外部専門家で構成する第三者委員会で調査を進めている。責任があると指摘された役員や会計監査人に対しては、「法的手続きを含めた厳正な対応を検討中」としている。
同社が掲げた再建計画は(1)生産拠点の統廃合や人件費の大幅な削減(2)コスト管理の徹底(3)利益率の高い製品の販売拡大(4)子会社・関連会社18社の整理―が柱。
既に4月から従業員の賃金を40%削減。取締役を15人から8人に減らし、従業員も約100人削減し211人とした。
奈良病院詐欺:生活保護費を管理…不当な天引きの有無捜査 06/22/09(毎日新聞)
奈良県大和郡山市の医療法人雄山会「山本病院」が、生活保護受給者に対し、手術や検査をしたように装って診療報酬を不正請求していたとされる詐欺事件で、同病院が受給者の保護費を一括管理していたことが、県や関係者への取材で分かった。生活保護受給者は、医療費以外に日用品費などが公費で支払われる。県警は、同病院が受給者の了解を得ていたかや不当な天引きをしていなかったかなど慎重に調べる。
県によると、同病院は生活保護法に基づく指定医療機関。21日に実施した立ち入り検査では、入院患者は79人で、このうち約6割が生活保護受給者だった。受給者には、医療費の他に日用品費など月額約2万3000円が支給される。
県によると、病院は受給者の約半数の保護費を管理。テレビなどのリース代をそこから差し引いていたという。以前勤務していた元職員は「患者が事務室で『金を下ろしてくれ』と言っていた。市への生活保護の申請手続きなども病院がやっていた。こんなことまでするのかとびっくりした」と話す。本人の同意があれば、保護費の管理は違法ではない。
これまでの県の調査では、不当な天引きなどは確認されていないが、関係者によると、保護費の管理を病院側に任せきってチェックしていなかったり、気づかない受給者もいるとみられる。【上野宏人、高瀬浩平】
診療報酬不正請求:病院など奈良県警が捜索、理事長ら聴取 06/21/09(毎日新聞)
奈良県大和郡山市の医療法人雄山会「山本病院」が、生活保護受給者に対し、手術や検査をしたように装って診療報酬を不正請求したとして、奈良県警は21日、詐欺容疑で同病院と理事長(51)、事務長(57)の自宅を家宅捜索。2人から任意で事情を聴いた。引き続き不正の実態を詳しく調べる。
生活保護受給者は、医療費が全額公費で賄われる。高額な治療を受けさせても確実に医療費を回収できるため、悪用されやすい。
捜査関係者によると、理事長らは05~06年、大阪や京都の生活保護受給者を入院させ、実際にはしていない心臓カテーテル手術や検査をしたように装い、100万円を超える診療報酬を不正受給した疑いがある。
県は、同病院が受給者に必要のない検査をしているとの内部告発を受けて、昨年3月と今年3月の2回、立ち入り検査し、指導していた。【上野宏人】
◇「カテーテルはようもうかる」
「カテーテルはようもうかる。救急車の中でやったこともある」。過去に病院に勤務していた関係者によると、理事長はこう話していたという。
病院によると、心臓カテーテル手術は週6、7件、年間300件を超えるペースで行われていた。さらに、入院が長期化するなど、他の病院が敬遠する生活保護受給者を積極的に受け入れた。県によると、今年1月末時点で、入院患者76人のうち受給者は約6割。前年同期に比べて、約1割増加していた。【高瀬浩平】
なんでこんな事が今まで見逃されていたのだろうか???ラブホテルを経営する宗教法人ておかしくないか?
骨髄財団「セクハラは事実」 東京地裁、疑惑指摘職員の解雇無効 06/12/09(産経新聞)
常務理事のセクハラ疑惑を指摘したため懲戒解雇されたとして、骨髄バンクを運営する「骨髄移植推進財団」の山崎裕一元総務部長が、解雇の無効と職員としての地位の確認などを求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。白石哲裁判官は、セクハラ疑惑を事実と認定、山崎氏の解雇無効を言い渡した。
白石裁判官は、セクハラ疑惑について「細部では事実と一致しない部分もあるが、基本的には事実」と指摘。「財団がセクハラ疑惑の調査をきちんと行わないため、山崎氏は外部に情報を漏らした。情報漏洩により財団が名誉を傷付けられたとしても、解雇は重すぎる」と判断した。
判決などによると、山崎氏は平成17年4月の総務部長就任直後、常務理事からセクハラを受けている職員から相談された。山崎氏は職員から聞き取りを行い、理事長に報告書を提出した。
これに対し、財団は「セクハラを指摘した報告書には虚偽があり、個人の誹謗中傷文書だ。財団の社会的信用を低下させた」として、平成18年9月に解雇していた。
農村システム協の不正支出…天下りの幹部、お手盛り給与 06/06/09 (読売新聞)
農林水産、経済産業、総務の3省が所管する社団法人「日本農村情報システム協会」(東京都豊島区)の不正支出問題。
自己破産の方針を決めた協会は今後、通産省(現・経産省)OBの副会長(79)が代表を兼務する任意団体に不透明な業務委託を続けていたとして、6億円以上の委託費返還を求める方針だが、実はこの任意団体の恩恵を被っていたのは副会長一人ではない。破綻(はたん)の背景には、中央省庁OBらが巨額の補助金という「甘い汁」を吸う構図が見え隠れする。
◆二つの財布◆
農水省などの指摘によると、協会は、同じビル内にある任意団体「情報システム技術会議」にコンサルタント業務などを委託、うち6億4600万円は水増しなど不正支出だったという。
副会長は2005年に非常勤になるまで年1000万円の給与を受け取る一方、約20年前から今年3月まで技術会議の理事長職に就き、同会議からも年1200万円を受け取っていた。
“二つの財布”を持っていたのは副会長ばかりではない。
農水省を退職後、複数の公益法人を「渡り」、06年に協会に入った常務理事(64)も、就任初年度は協会から800万円の年収を得ながら、技術会議からも顧問名目で250万円を受領していた。長男と次男がそれぞれ協会に勤務していた時期もある。
経産省出身で07年7月に就任した理事(59)も、協会からの900万円の年収のほか、技術会議からも年400万円の顧問料を受け取っていた。
協会は04年には基本財産4億4000万円を使い果たし、監査の度に赤字隠しの工作を続ける状態だったが、「協会は毎月数百万、時には1000万円単位でぽんぽんと振り込んでくれた」と技術会議関係者は話す。だが、協会側は「出張費などがかさんだ」との釈明を繰り返すばかりで、役員報酬を含め、詳細な使途についてはいまだに正式に明らかにしていない。
◆暗黙の条件◆
協会の主力業務は、農漁村へのケーブルテレビや防災無線の普及事業。国の補助金を利用して敷設したい市町村を顧客に、コンサルタント業務などを行ってきた。農水省幹部は「ある時期まで、補助事業の採択を希望する場合、協会にコンサルを依頼するのが暗黙の条件だった」と明かす。
きっかけは、1991年3月の構造改善局長(当時)名の通達だ。農業構造改善事業の計画策定を巡り、同協会などの名前を挙げ、「適当と認められる者には委託することができる」という一節が入っていた。
農水省は「協会に計画策定を委託することも可能ということを示しただけ」と釈明するが、「市町村側にすれば『補助金が欲しければ協会を使え』と受け止めたようだ」と認める。
こうした「ひも付きの補助事業」の実態が国会などで批判され、農水省が97年4月にこの通達を廃止するまでに、多い年で2億円近い補助金が協会に“還流”していたという。
◆甘い指導◆
00年4月、農水省は協会などに対し、業務外注の際には入札を行うよう指導。ところが、協会はその後も、技術会議に随意契約で発注していたが、農水省は「技術会議のことは把握できなかった」と話す。
農水省では毎年、協会に職員を派遣し、決算などを精査していた。農水省は「不正を見抜けなかったのは経理が操作されていたため」と釈明する。だが、05年度決算では、4億6000万円近い基本財産がありながら、その運用益がわずか「2264円」。「通常ならあり得ない不自然な数字」(構造改善課)でありながら、矛盾を見過ごしていた。(十時武士、池亀創、畑武尊)
ラブホ休憩料を「お布施」に 宗教法人14億円所得隠し 06/09/09 (朝日新聞)
長野県など中部地方を中心にラブホテルを経営する宗教法人が関東信越国税局から約14億円の所得隠しを指摘されていたことが分かった。ホテルの休憩料などの収入は本来、課税対象だが、国税局はこの宗教法人が休憩料の一部を非課税のお布施と偽っていたなどと認定した模様だ。
公益法人の一種の宗教法人は実質的な税率が低いため、同法人への追徴税額は重加算税を含めて約3億円。同法人は指摘を不服として異議申し立てをしている。これらのホテルは同県千曲市のキノコ・野菜類加工販売会社の前社長(71)が実質的経営者とみられ、同社の現社長(46)は「実際に国内の恵まれない子にお金を送っている。国税当局とは争う」と話している。
この宗教法人は「宇宙真理学会」。香川県多度津町の10階建てマンションの一室が主な事務所となっているが、朝日新聞が調べたところ、宗教施設は見当たらず、信者などの存在も確認できなかった。ドアノブには四国電力からの「電気の契約を廃止」という通知が下がっていた。近所の人によると、20年ほど前から人の出入りはないという。
同じ系列のホテルは長野をはじめ静岡、岐阜、群馬、新潟の計5県に少なくとも23軒ある。このうち長野市内のホテルには玄関に観音像と「宇宙真理学会」の看板が掲げられ、部屋には「世界の恵まれない子どもたちに喜捨をお願いします」「少しでも多くの幼い命を救うために」などと書かれた張り紙があった。
ホテルは、客から得た休憩料や宿泊料の6割ほどを課税対象の売り上げとして計上し、残りは客からのお布施(喜捨)扱いにしていた模様だ。フロントに問い合わせると、宿泊料の5500円のうち「2千円を喜捨に充てる」と説明した。
違法建築はたぶん、たくさんあると思う。どんどんチェックして指摘してほしい。
田中義剛さんの「花畑牧場」違反建築3棟、北海道が是正指導 06/06/09 (読売新聞)
タレントの田中義剛さん(51)が経営する「花畑牧場」(本社・北海道中札内村)で、生キャラメルを製造する工場など建物3棟が建築基準法に違反していることがわかり、北海道は3日付で文書で是正を指導した。
関係者によると、違反が明らかになったのは生キャラメルやチーズ、アイスクリームなどを製造している中札内村の同社第1工房と第2工房、飲食店「ホエー豚亭」の3棟。
同社は道の建築確認を受けないまま、建物の大部分を建設していた。道のこれまでの調査では、〈1〉防火壁や非常用照明装置の未設置〈2〉排煙設備の不足〈3〉廊下幅や天井の高さの不足--などの違反があったことがわかっている。
道は同社に対し、7月1日までに是正計画書を提出するよう求めている。
田中義剛さんの話「この件に関しては、専門家に依頼し、その判断として問題はないとのことだったが、指導を真摯(しんし)に受け止め、設計変更などの対応を始めている」
農水系法人、幹部関係会社に別の問題支出6億円 06/05/09 (読売新聞)
農林水産省などが所管する社団法人「日本農村情報システム協会」(東京都豊島区)を巡る不正支出問題で、市町村に気象情報を提供するサービスでも、同協会が、幹部職員の親族が社長を務める会社などと委託契約を結び、昨年度までの12年間で約6億円を支出していたことがわかった。
問題の会社は、社員は元協会職員が1人いるだけで、実体はないとみられる。衛星回線の使用料や気象情報の購入代金など必要経費を除く約1億円が使途不明になっており、農水省は業務委託の経緯や詳細を調査するよう、協会に求めている。
協会や農水省によると、問題となっているのは農業や漁業の被害予測などに関する気象情報を提供する事業。市町村に観測装置を設置してデータを集め、気象庁の過去の観測データと照らし合わせて分析し、農業被害予測などを市町村に伝える内容だった。
協会は、市町村とつながれた衛星回線の使用手続きや気象データ購入などの業務を、システム開発会社に年間約5500万円で委託していたが、このシステム開発会社は協会内に登記上の本社を置き、社長には、気象情報サービスの担当責任者である協会幹部の親族が就任。この社長は長野県に在住し勤務実態はなかった。社員は協会から転籍した社員が1人いるだけで、実際には別の協会職員が業務を担当していた。
昨夏、外部からの指摘で協会が調査に乗り出したところ、これらの不透明な業務委託が判明。問題のシステム会社の前にも、協会副会長が社長を務める協会の関連会社など2社と同様の業務委託を繰り返していたことがわかった。
協会は、経緯について、業務の責任者に説明を求めてきたが、聴取に応じないまま欠勤を続け、昨年11月に退職。協会では今年3月末でシステム開発会社との契約を打ち切ったという。
事業は1998年度までは農水省補助対象で、データ送受信機などの周辺機器類を設置した市町村には、観測設備1台につき平均約1000万円が補助されていた。ピーク時で約100市町村、現時点でも約40市町村が利用しているという。同協会にもコンピューター設備やソフト開発費などに計2億1000万円が補助されていた。
同協会幹部は「不要な業務委託を見過ごし、協会の財政を圧迫してきた責任があり、申し訳ないが、事情のわかる職員がいないため、詳細を検証できていない」としている。
農村システム:不正支出を前事務局長が決裁 組織ぐるみか 06/05/09 (毎日新聞)
農林水産、経済産業、総務の3省が所管する社団法人「日本農村情報システム協会」が6億円余りを水増しして不正に支出していた問題で、支出の際に協会の前事務局長が経理部長の作成した文書を決裁していたことが分かった。文書には総務部長ら複数の決裁印も押されているといい、不正支出が組織的に行われていた疑いが強まった。
3省などによると、同協会は市町村から防災無線の設計などを請け負い、大半を任意団体「情報システム技術会議」に委託。同会議は03年ごろから、事業費が市町村との契約額を上回っているとして、超過分を含めた費用を請求し、協会は求められるままに定款に反して基本財産(4億3900万円)を取り崩すなどして支出していた。04年度に基本財産を使い切った後は金融機関から借り入れ、今年3月末までに6億5600万円の債務超過に陥り、先月29日に3省から民法に基づく業務改善命令を受けた。
同協会が同会議に支出する際は以前から、経理部長が文書を作成し、総務部長が決裁。07年7月からは前事務局長も決裁印を押していた。3省はこうした経緯を把握しており、前事務局長や総務部長など複数の決裁印が押されていた文書も確認しているという。
同協会の前事務局長は「技術会議からの請求は一度に複数の事業で数千万から数億円になった。請求があれば支出することが慣例となっていたので、増額して請求されているとは分からなかった」と話している。【奥山智己】
こんな事がありえるから、公務員は口頭だけで文書で回答したがらないのかな??????
職業能力協の事務所、天下り2法人にまた貸し…4千万不正請求 05/28/09 (読売新聞)
常勤役員をすべて厚生労働省のOBが占める同省所管法人「中央職業能力開発協会」(東京都文京区)が1999年以降、同省OBが再就職している2法人に事務所を“また貸し”し、2法人が払うべき賃料や諸経費まで同省からの補助金などで賄っていたことが分かった。
会計検査院が調べた2002~06年度の5年間で不正額は約4000万円に上った。協会を巡っては既に、職員らによる飲食費などの不正使用が明らかになっており、検査院は同省に審査の徹底を求めた。
協会は99年1月から東京都文京区のビル約2000平方メートルを借りて入居。約1億円にのぼる事務所の賃料のほか、電気や電話、清掃代など諸経費を国の補助金などから支出し、毎年その使途を報告している。
ところが、同協会では、入居当初から、2000平方メートルのうち、約50平方メートルを同省所管の社団法人「全国技能士会連合会(全技連)」に、別の約50平方メートルを保険代理店に、それぞれ賃貸借契約も結ばないまま“また貸し”。厚労省には2法人の使用したスペースや電気、電話、清掃費なども、協会で使用したように偽って請求していた。
協会がビルオーナーに支払っている賃料は50平方メートル当たり年間約260万円で、電話代や清掃費なども含めると、検査院では全技連の事務所経費は年間約370万円、代理店分は同約430万円に相当すると算出。これらは厚労省への請求分に含めるべきではなかったとして、02~06年度で計3972万円が不正請求だったと指摘した。
指摘を受けて協会は不正請求分を返還し、2法人も既に同ビルから退去した。
不正請求する一方、協会は全技連から年間160万円、保険代理店から同60万円を家賃や電気代、電話代、清掃代などを含めた定額で受け取っていた。
協会の理事長や常務理事ら計4人の常勤役員は全員、厚労省のOB。また、全技連も会長と常務理事の2ポストを厚労省から天下った2人のOBが務めている。保険代理店は、同協会の関連施設で職業訓練を受ける人の保険契約を担当するなど、仕事の7割は協会からの業務で、社長によると「過去3~4代の社長は厚労省OBだった」という。
協会では「過大請求は経理処理上のミス」とし、2法人に便宜をはかったことについては「誤解を招く結果になったのは大変申し訳ない」と話している。厚労省では「身内だからといって審査を甘くしたわけではない」としている。
同協会の年間収入は06年度で総額約36億円。このうち、協会が実施している技能検定などの収入は3割程度で、7割近くは国からの補助金や委託費となっている。今年度補正予算案では、同協会に職業訓練者の生活支援給付などとして7000億円が計上されている。
協会を巡っては06年度までの5年間で、傘下の8県の協会と合わせて計3500万円が職員らによる飲食費などに使われていたことが検査院の調査で分かっている。
郵便不正で厚労省係長ら逮捕、ニセの稟議書など作った疑い 05/26/09 (読売新聞)
障害者団体向けの郵便料金割引制度が悪用された郵便法違反事件に絡み、自称障害者団体「白山会」(東京都文京区)の前身「凛(りん)の会」(解散)に対し、制度を受けやすくするため偽の「稟議書」などを作っていたとして、大阪地検特捜部は26日、厚生労働省の障害保健福祉部企画課・施設管理室予算係長、上村勉容疑者(39)と、凛の会の元メンバー・河野克史(ただし)容疑者(68)を虚偽公文書作成、同行使容疑で逮捕した。
2人は容疑を認めているという。
特捜部の調べによると、上村容疑者は同課社会参加係長として障害者団体証明書の申請窓口を担当していた2004年4月下旬、凛の会元会員らと共謀し、証明書を発行するための決裁手続きが進んでいるように装う稟議書や、証明書が間もなく交付されるという趣旨の文書を作成した疑い。
凛の会は稟議書などの交付を受け、小規模団体でも制度を利用して定期刊行物を発行できるよう協力しているNPO法人「障害者団体定期刊行物協会」(東京都世田谷区)に提出した疑い。
郵便不正「稟議書出したことない」…厚労省係長の一問一答 05/26/09 (読売新聞)
郵便法違反事件は26日、大阪地検特捜部が厚生労働省障害保健福祉部の係長(39)らを虚偽公文書作成などの容疑で取り調べを始めたが、係長は今月、数回にわたって読売新聞の取材に応じ、「心当たりがない」と容疑を全面的に否定していた。
主な一問一答は次の通り。
――凛(りん)の会から障害者団体証明書の申請を受け付けていないか。
「私の在任時は1件も申請がなく、身に覚えがない。書類も何も残っていないんでしょ」
――稟議(りんぎ)書なども作っていないか。
「そんな文書を出したことはないですよ」
――凛の会の元会員と会ったことはないか。
「全くありません。問い合わせを受けたこともない」
――証明書が偽造と疑われていることについて、どう思うか。
「私は起案した記憶がない。これ以上、何を聞かれてもどうしようもない。心外としか言いようがない」
郵便料金不正でニセ稟議書、厚労省係長らを逮捕へ 05/26/09 (読売新聞)
障害者団体向けの料金割引制度が悪用された郵便法違反事件に絡み、厚生労働省の障害保健福祉部係長(39)が、自称障害者団体「白山会」(東京都文京区)の前身「凛(りん)の会」(解散)に対し、制度の適用を受けやすくするため偽の「稟議(りんぎ)書」などを作っていた疑いが強まり、大阪地検特捜部は26日、虚偽公文書作成、同行使の両容疑で、係長の取り調べを始めた。
凛の会元会員(68)についても両容疑の身分なき共犯として聴取しており、容疑が固まり次第、2人を逮捕する方針。係長は容疑を認めているという。
凛の会は、郵便事業会社(日本郵便)に対し、厚労省発行とされる偽の障害者団体証明書を提出しており、特捜部は、この偽証明書についても係長らの関与を追及する。日本郵便がかかわった郵便不正は、厚労省も巻き込んだ事件に発展する可能性が出てきた。
関係者によると、係長は厚労省障害保健福祉部企画課で障害者団体証明書の申請窓口を担当していた2004年4月下旬、凛の会元会員らと共謀し、証明書を発行するための決裁手続きが進んでいるように装う稟議書や、証明書が間もなく交付されるという趣旨の文書を作成した疑いが持たれている。偽の稟議書の起案者欄には、係長の署名があったとされる。
凛の会は稟議書などの交付を受け、小規模団体でも制度を利用して定期刊行物を発行できるよう協力しているNPO法人「障害者団体定期刊行物協会」(東京都世田谷区)に提出した疑いが持たれている。
凛の会は04年2月頃、厚労省側に証明書の発行を持ちかけたところ、同協会に相談するよう言われた。しかし、同協会から営利目的の団体ではないかと疑われ、念書を要求されたため、元会員が係長に稟議書などの交付を依頼したとみられる。
郵便法違反:「会社を団体に」DM発送時、日本郵便が指導 05/21/09 (毎日新聞)
障害者団体向け割引制度を悪用した郵便法違反事件で、障害者団体「健康フォーラム」(東京都港区)が06年、違法ダイレクトメール(DM)を発送する際、郵便事業会社(日本郵便)側が、同団体に対し、有限会社から任意団体に組織改編するよう指導していたことが分かった。本来、福祉目的の制度を有限会社が利用できないことを知っていた日本郵便側が、商業目的の団体と認識しながら体裁だけ整えさせ、不正を助長させていた疑いが強まった。
東京都港区などによると、当時、任意団体だった健康フォーラムは05年6月、制度利用のための証明書を区から取得した。その後、有限会社に組織を変え、同年11月に証明書を再取得。しかし06年4月ごろ、「任意団体に戻す」と申告。6月に3度目の証明書が発行された。
その際、代表の菊田利雄容疑者(61)が「有限会社では本来、制度を利用できず、発送が止められるかもしれないので、任意団体に戻すよう郵便側に言われた」と説明。区は指導の趣旨や法律上の問題がないかを日本郵便側に問い合わせた上で証明書を出したという。しかし、障害者団体としての活動実態はなかったとされる。
日本郵便渉外広報部は、「理由は分からないが、もともとが障害者団体だったので、福祉の実態があると判断したのかもしれない」としている。【林田七恵、久保聡】
不正DMに特割適用 逮捕の日本郵便2支店 05/21/09 (朝日新聞)
障害者団体向けの郵便割引制度を悪用したダイレクトメール(DM)広告の発送が郵便事業会社(JP日本郵便)で大量に見逃されていた郵便法違反事件で、支店長らが逮捕された大阪と東京の2支店が、さらに特別な割引を不正DMに適用していたことがわかった。大阪地検特捜部は、支店長らが不正DMと知りながら、こうした特別割引を適用したとみて調べる。
不正DMを持ち込んだ広告会社側も特捜部の調べに、安さを理由に2支店を選んだことを認めているという。
障害者団体の定期刊行物を送るための「低料第3種郵便物制度」では、通常1通120円の郵送料が8円になる。日本郵便によると、発送数が2千通以上~20万通以上になる場合や、配達が3~7日かかってもかまわない場合にはさらに料金が割り引かれ、1通7.76円~6.96円になる。これに加え、全国73の大規模支店では、個別の割引制度があり、最大で1通6.16円まで割り引かれるという。
支店長が逮捕された新大阪支店(大阪市此花区)と、総務主任が逮捕された新東京支店(東京都江東区)は、大規模支店のなかでも有数の拠点だった。健康飲料販売会社「キューサイ」(福岡市)と家電量販大手「ベスト電器」(同)などのDM計約270万通の発送を見逃したとして2人が逮捕されたケースでは、1通あたりの料金は新大阪が1通6.72円、新東京が6.80円だったという。
この2支店から企業のDMを複数の障害者団体名義で発送した大阪市の広告会社「新生企業」(現・伸正)=社長らが再逮捕=側は特捜部の調べに対し、特別割引の適用によって料金を抑えられることから、2支店に持ち込んだことを認めているという。
郵便法違反:日本郵便支店長逮捕 法令順守意識の低さ示す 05/21/09 (毎日新聞)
障害者団体向け割引制度を悪用した郵便法違反事件で19日、職員2人の逮捕者を出した日本郵政グループの郵便事業会社(日本郵便)は、制度の趣旨に見合わない大量の刊行物の持ち込みをチェックすることなく長年にわたって放置し続けていた。事件は担当者だけでなく、組織としての法令順守の意識の低さを示している。【望月麻紀、中井正裕】
障害者団体向け割引郵便の発送数は07年度1億2226万通に達し、98年度比で5倍に増えていた。同郵便を含む第3種郵便事業は元々コスト高で、営業損失は近年減少傾向とはいえ、07年度で156億円に達している。民営化後も「福祉事業で必要だ」として残ったが、基幹サービス維持のため合理化を進める同社にとって、この赤字負担は重い。
今回の悪用では一度に29万5000通もの郵便物が持ち込まれたケースもあり、大阪地検の調べでは、逮捕された支店長らも悪用の事実に気づいていたという。それにもかかわらず長年にわたり、悪用が放置されてきた。
同社内規では、一度に3000通以上の差し出しがあった場合支社に報告し、不審な点があれば特別調査が行われる。しかし同日会見した塚田為康常務は「報告はほとんどなかった」と話し、支店でのずさんな引き受けの実態を明らかにした。
さらに、年1回の定期調査で行うはずの「発行部数の8割以上が有料購読されているか」のチェックも甘く、郵便物が大量に送付される結果となったと説明した。
監督官庁の鳩山邦夫総務相はこの日、記者団に「国民の信頼を著しく失った。監督官庁として申し訳ない」と謝罪。その上で「善意の制度を悪用することは絶対に許し難い大犯罪」と語気を強め、再発防止のため昨年12月の業務改善命令に続き、改めて命令を出す考えを明らかにした。
持ち株会社日本郵政の西川善文社長には続投の是非を巡る問題が浮上している。会見に同席した北村憲雄・日本郵便会長は「西川氏に責任があるなしの問題ではない」と述べたが、鳩山総務相は「これから精査していく」と話しており、影響も予想される。
郵便法違反:「自分の腹痛まない」…現場に無責任体質 05/19/09 (読売新聞)
福祉制度を悪用した郵便法違反事件は19日、制度を運営する郵便事業会社(日本郵便)の支店長が逮捕される事態に発展した。ある元郵便局長は毎日新聞の取材に「損しても自分の腹が痛むわけじゃない。まあいいか、と不正な発送を許していた」と証言。違法ダイレクトメール(DM)を黙認したとされる背景に、現場の無責任体質があったことを明らかにした。さらに民営化の影響で、ノルマ優先となっていたとも指摘し、構造的な原因が浮かび上がった。
近畿地方の元郵便局長によると、事業所や団体による大量発送は、割引料金が適用されたものでも、一度に多額の郵便収入が期待できるため、「郵便局ごとに(大量発送の)ノルマが課せられていた」という。特に、07年10月の民営化後は局同士の競争も激しくなり、一度に1000単位以上で発送する事業所や団体は「おいしい客だった」と告白する。
また、多忙な時期には次の客を待たせるわけにいかず、「自分が損するわけじゃないし、どうでもいいわと(審査が)ルーズになる。手早く処理しないと上司に怒られるし」と不正を黙認することがあったと暴露した。
一方、関係者によると、障害者団体「白山会」会長、守田義国容疑者(69)は07年1月に、埼玉県内の2支店で、違法DMの発送を試みたが拒否され、翌月、新東京支店で発送が許可された。
守田容疑者は毎日新聞の取材に「郵便側は何年も前から(不正を)見過ごしていたのに、たまたま何百回に1回か知らんけど、これはダメですよと言われた。慣習でずっと発送していたのに、急にダメと言われたら困る」と郵便側の不正の認識を指摘していた。
違法DMに名義を貸したとされる障害者団体関係者は取材に対し、06年、日本郵便近畿支社の幹部に制度の不正利用があることをいったんは告発したが、「分かりました」というだけで、取り合ってもらえなかったと話した。
日本郵便支店長ら逮捕状、DM発送で3億円不正割引の疑い 05/19/09 (読売新聞)
障害者団体向けの料金割引制度が悪用された郵便法違反事件で、郵便事業会社(日本郵便)社員が違法なダイレクトメール(DM)と知りながら発送を承認し、郵便料金計約3億円の支払いを免れさせていた疑いが強まり、大阪地検特捜部は、同法違反容疑で、新大阪支店(大阪市此花区)の支店長(59)と新東京支店(東京都江東区)の主任(39)の逮捕状を取った。
19日にも取り調べ、容疑が固まり次第、逮捕するとともに、日本郵便本社(千代田区)なども捜索する。特捜部の調べでは、新大阪支店長は2008年秋、健康飲料販売会社「キューサイ」(福岡市)などのDM約140万通、新東京支店主任は07年2月、家電量販大手「ベスト電器」(同)のDM約130万通について、制度の要件を満たさないことを認識しながら発送を認め、正規料金との差額約1億6000万円、約1億4000万円をそれぞれ免れさせた疑いが持たれている。
制度の適用には、定期刊行物の発行部数の8割以上が有償購読者とする要件があるが、両支店から発送されたDMは、いずれも顧客に無償で送られており、制度の対象外だった。
2人は特捜部の任意聴取に対し、「要件を満たさないだろうと思っていた」と供述したという。
郵便法は、郵便料金を不正に免れた者に対する罰則の上限を罰金刑(30万円以下)にしているが、郵便職員の場合は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」とより厳しく規定している。
漢検、背任立件へ詰め…架空委託2億3000万円 05/14/09 (読売新聞)
不明朗な運営が問題になっている財団法人「日本漢字能力検定協会」の大久保昇・前理事長(73)と長男の浩・前副理事長(45)が、自分たちで行った協会の広報業務を前理事長が代表を務める広告会社「メディアボックス」に業務委託したとして、協会から少なくとも計2億3000万円を支出させていたことが、協会関係者の証言で明らかになった。
本来、委託は不要で、メディア社の利益を上げるための「架空委託」だった疑いが強い。
前理事長らは、メディア社から計1億円以上の役員報酬や株式配当を得ており、京都地検もこうした取引実態について、前理事長らの背任容疑立件に向けて詰めの捜査に入った。
協会関係者によると「架空委託」の疑いがあるのは、メディア社に委託された13業務のうち、広報、PRを年間を通じてどのように実施するかを企画、管理する「年間プロモーション企画」「進行管理」の2業務。実際には前理事長と前副理事長の2人で行っていたが、前理事長がメディア社代表として委託費を請求、協会理事長として支出を承認していた。
メディア社の内部資料によると、2006~08年度の3年間の売上高計7億6000万円のほぼすべてが協会からの委託費。このうち、「架空委託」の疑いがある2業務の委託費2億3000万円全額がメディア社の利益になった。残る5億3000万円で委託された広報誌の編集・印刷など11業務は別の20社に4億8000万円で再委託され、差額の5000万円が利益となった。
「若林被告は『違法性はないと思っていた』、松谷被告は『郵便局が受け入れているので許可されていると思っていた』と供述しているという。」
上記が事実なのか何とも言えないが、証拠がなければ罪が軽くなるのでそう言うしかないだろう。1年に1度はチェックを郵政職員及び日本郵便職員が
適切に行っていればこのようなことは起こらなかっただろう。違法であるのかよりも、違法行為をチェックしているのか、見つけられる可能性が
あるのか等の要素が重要だと思う。規則があっても指摘されなければ、規則を守らないことが普通となってしまう。これは郵便料金不正事件だけに
言える事ではない。多くの不正に関して言えることだ。
担当であった郵政職員及び日本郵便職員の責任や処分についても総務省は厳しくチェックし、再発防止策についても公表するべきだ。
郵便料金不正:ベスト電器元部長ら10人を起訴 大阪地検 05/06/09 (毎日新聞)
大阪地検特捜部は6日、障害者団体「白山会」(東京都文京区)会長、守田義国容疑者(69)ら10人を郵便法違反で起訴した。免れた郵便料金は、逮捕容疑では計約2億4000万円だったが、起訴分では、さらに約4億円増額された。
起訴状によると、守田被告ら10人は共謀して07年2月~08年2月、家電量販会社「ベスト電器」(福岡市)のダイレクトメール(DM)計約570万通を白山会などの定期刊行物を装って発送、郵便料金計約6億4580万円を不法に免れたとされる。
特捜部によると、ベスト電器は05年8月から計約1190万通を発注し、総額約13億3600万円を免れたという。また、発注を仲介した広告会社「博報堂エルグ」(福岡市)と通販会社「ウイルコ」(石川県白山市)は1通当たり12~16円、広告会社「新生企業」(現・伸正、大阪市)は平均約2・5円の手数料を得たとされる。
他に起訴されたのは、ベスト電器元部長、久保俊晴(51)▽博報堂エルグ執行役員、板垣信行(47)▽ウイルコ前会長、若林和芳(57)▽同社執行役員、松谷昭(64)--の各容疑者ら。特捜部によると、いずれも事実関係は認めているが、若林被告は「違法性はないと思っていた」、松谷被告は「郵便局が受け入れているので許可されていると思っていた」と供述しているという。【林田七恵、久保聡】
郵便法違反:違法DM、10年以上前から 広告主50社超 05/04/09 (毎日新聞)
障害者団体向けの郵便割引制度の悪用が広告・通販業界で10年以上前から横行し、大手企業など50社以上が広告主としてその手口に便乗していたことが毎日新聞の調べで分かった。制度を悪用した郵便法違反事件は、大阪地検特捜部が6日、逮捕した障害者団体会長ら10人を郵便法違反罪で起訴する方針。捜査は違法ダイレクトメール(DM)の発送を黙認した郵便事業会社(日本郵便)側に移る見通しだ。
特捜部によると、社長らが逮捕された広告会社「新生企業」(現・伸正、大阪市)が07年2月、通販会社「ウイルコ」(石川県白山市)前会長らと共謀し、家電量販会社「ベスト電器」(福岡市)の違法DM約210万通を障害者団体の刊行物と偽装して割引郵送したとされる。
関係者によると、新生企業はウイルコのほか、福岡市の印刷会社と大阪市の通販会社(民事再生手続き中)も得意先だった。印刷会社は06年秋から2年間で約1350万通を新生側に発注。通販会社は06年半ばから半年間で発注数は不明だが、約3億円相当を依頼していたという。
一方、埼玉県上尾市の通販会社は取材に「05年7月~08年9月、新生企業のほか広告会社2社に(違法DM)計約1360万通を発注した」と証言。制度悪用の広告会社は新生企業だけではないと明かした。
また、静岡市の健康食品販売会社の幹部は「割引制度の利用は12~13年前からある。北陸から九州まで10社以上の広告会社から利用を勧誘された」と話す。勧誘したとされる広告会社の顧客への取材で、違法DMを使った広告主は50社以上に上ることも分かった。
広告業界関係者によると、十数年前から、消費者のターゲットを絞れるDMが健康食品会社などで重宝され、低料金で大量発送できる制度悪用の手口が口コミで広がったという。毎日新聞の取材に応じた広告主の企業はいずれも「福祉のためと言われたし、郵便局の許可があるなら合法と思った」と、郵便側の「お墨付き」を悪用の言い訳に挙げた。【林田七恵、久保聡】
郵便不正6.5億円 ベスト電器元部長、容疑認める供述 05/02/09 (朝日新聞)
家電量販大手「ベスト電器」(福岡市)のダイレクトメール(DM)広告をめぐる郵便法違反事件で、大阪地検特捜部は、逮捕した同社の元販売促進部長、久保俊晴容疑者(51)ら10人全員について、勾留(こうりゅう)期限の6日にも、郵便料金約6億5千万円を不正に免れたとして起訴する方針を固めた。逮捕容疑のほかにも、約4億円の支払いを免れていたことを裏付けた。久保元部長は逮捕当初から一転、容疑を認める趣旨の供述をしているという。
ほかに起訴されるのは、不正DMの作成にかかわったとされる広告会社「博報堂エルグ」(福岡市)執行役員の板垣信行容疑者(47)や、DMの印刷を請け負ったとされる大手通販・印刷会社「ウイルコ」(石川県白山市)前会長の若林和芳容疑者(57)ら。
久保元部長らは07年2月、障害者団体向けの郵便料金割引制度の要件を満たしていないのに、ベスト電器のDM広告約214万通を、自称・障害者団体「白山会」(東京)などの定期刊行物として同社の顧客らに発送。正規料金との差額約2億4千万円を免れたとして逮捕された。
ベスト電器は05年8月以降、不正DM約1190万通を発送し、約13億円の支払いを免れていた。このうち特捜部が新たに起訴事実に追加するのは、逮捕容疑となった時期の後も10人が関与したとされる07年8月~昨年2月の発送分で、約350万通にかかわる約4億円の差額分とみられる。
特捜部は、社長らが逮捕された広告会社「新生企業」(現・伸正、大阪市西区)側が大手のウイルコに取引を持ちかけたのをきっかけに、制度の悪用が広がったと判断。大手企業までもが福祉目的の制度を不正に利用したことを重視し、全員を起訴することに決めたとみられる。
無断でJASマーク、注意後も継続…そば製粉会社を捜索 05/01/09 (読売新聞)
東京都三鷹市のそば製粉会社「島田製粉」(島田信隆社長)が、同社の「深大寺そば」などの商品に無断でJAS(日本農林規格)マークをつけて販売していたとして、警視庁は30日、同社や製造工場など数か所をJAS法違反の疑いで捜索した。
同庁幹部によると、同社は2007年12月~今年2月、JASの認定業者ではないのに、委託先が製造した乾めんのパッケージにJASマークをつけて販売した疑いが持たれている。
JASマークは国が製品の品質を保証する印。農林水産省は今年2~3月、同社に口頭で注意を行い、この際、島田社長は「制度のことを知らなかった」と話していたが、その後も販売を続けたため、4月28日、同庁に刑事告発していた。
日本郵便側も立件へ…割引悪用を故意に見逃した疑い 05/01/09 (読売新聞)
障害者団体向けの料金割引制度が悪用された郵便法違反事件で、大阪地検特捜部は、郵便事業会社(日本郵便)社員が故意に不正を見逃していた疑いを強め、家電量販大手「ベスト電器」(福岡市)などのダイレクトメール(DM)を大量に受け付けた支店担当者数人について、5月中にも同法違反容疑で立件する方針を固めた。
担当者らは特捜部の任意聴取に、「制度の要件を満たさないかもしれないと思った」と供述しているという。事件は、制度を管轄する日本郵便側が刑事責任を問われる異例の事態に進展する見通しとなった。
制度の適用を受けるには、定期刊行物の発行部数のうち有償購読者が8割以上とする要件がある。ところが、DMの大半は広告主のベスト電器や印刷・通販会社「ウイルコ」(石川県白山市)の顧客に無償で送られており、要件を満たしていなかった。
特捜部の調べによると、ベスト電器のDMは、自称障害者団体が発行する定期刊行物を同封した約214万通が2007年2月に新東京支店(東京都)などから、ウイルコのDMについては、約690万通が06年4月~08年10月、新大阪支店(大阪市)からそれぞれ発送。1回の持ち込みは1万~30万通だった。
漢検:関連4社、委託97%丸投げ 中抜き3年で34億円 04/30/09 (毎日新聞)
財団法人「日本漢字能力検定協会」(京都市)の大久保昇前理事長らが代表を務める関連会社4社が08年度、協会の委託業務の約97%(金額ベース)を半額以下で別の会社へ再委託し、約12億1000万円を“中抜き”していたことが分かった。06~08年度の3年間で約33億8000万円に上る。再委託しなかった残り約3%の業務も協会の外部調査委員会から見直しを求められており、実質的には関連会社の介在がすべて不必要だったことになる。
協会は30日に開く理事会で、いったんは取引継続を決めていた不動産・出版会社「オーク」と情報処理会社「日本統計事務センター」への業務委託の解消を盛り込んだ改革案を諮る方針。
内部資料によると、再委託の率が特に高かったのは、取引額の大きいオークと日本統計事務センターだった。オークは08年度、8億7000万円で協会から受注した書籍製作・販売業務すべてを3億6000万円で計21社に外注。日本統計事務センターもシステム開発や採点など11億9000万円の99%に当たる業務を4億8000万円で計24社へ再委託していた。
一方、広告会社「メディアボックス」は08年度、協会から受注した2億6000万円のうち広報業務7000万円を外注に出さなかったものの、調査委は「本来は前理事長と前副理事長が行う業務で、同社を介在させる必要性はない」と指摘。文章工学研究所との600万円の取引も、再委託先である研究者個人との取引だった。
これらから、4社は08年度、協会から23億2000万円で受けた業務のうち22億5000万円分を10億4000万円で外注し、“中抜き”した利益は54%に上っていた計算になる。また、06~08年度の3年間で、68億8000万円の受託業務のうち66億5000万円分を32億7000万円で再委託していた。【木下武、広瀬登】
清水寺:「今年の漢字」の舞台使用中止も 漢検改革が前提 04/23/09 (毎日新聞)
財団法人「日本漢字能力検定協会」(京都市)が毎年12月に実施している「今年の漢字」発表の舞台、清水寺(同市東山区)が23日、記者会見を開き、大久保昇前理事長らが代表を務める関連会社との不適切な取引解消など協会の改革が進まなければ、発表会場としての使用を断る方針を示した。また、協会理事で、毎年「今年の漢字」を揮毫(きごう)している森清範貫主が5月1日付で理事を辞任することも明らかにした。
協会は95年から、一年の世相を表す漢字一字を公募し、最も多かった文字を「今年の漢字」と認定。「漢字の日」の12月12日、森貫主が境内で大きな色紙に揮毫する発表イベントは年末の風物詩となっている。
会見した大西真興執事長によると、寺側は当初「京都の魅力の底上げにつながるので、いろんな寺院の持ち回りにしては」と提案。しかし、協会から「うまくいったので今後もお願いしたい」と頼まれ、清水寺での開催が定着したという。
大西執事長は「協会の経理や運営に問題があった。透明性が高まり、『漢検も変わった』と評価できれば前向きに考える。だが、今のままではできない」と述べた。一方、森貫主が07年4月の就任以降、一度も理事会に出席していないことについては「貫主は責任を重く受け止めている。名誉職的な意味で理事を受け、認識の甘さがあった」と釈明した。
また、今年1月下旬に協会の問題が持ち上がって以降「協会とグルになって金もうけをしているのか」という電話や手紙が相次いでいることに言及。イベントでは会場使用料としてお供え名目で50万円、貫主への謝礼20万円を受け取っていることを明らかにした。
協会理事では、新たに坂井利之・京大名誉教授も辞任。森貫主と合わせ、これで旧体制の理事8人中6人が辞任もしくは辞任表明した。【木下武、広瀬登】
漢検協会:関連会社、再委託で利益率50% 04/20/09 (毎日新聞)
財団法人「日本漢字能力検定協会」(京都市)の大久保浩前副理事長を代表とする情報処理会社「日本統計事務センター」が、協会から業務委託された日本漢字能力検定(漢検)の事務を他社へ再委託した際の利益率が50%に上っていたことが分かった。業務を右から左へ「丸投げ」しただけで、受注額の半分を手にしていたことになる。
協会の外部調査委員会の調べなどによると、同社は08年度、協会から約11億9000万円の業務を受注。このうち▽漢検の受け付け業務▽採点業務▽決済業務--で計10億円近くに上り、採点業務のごく一部を除いて他社に再委託していた。
協会から受け取る手数料は、受検者1人当たりの採点作業料が180円などと単価が決められており、それに受検者数を掛けた金額を協会に請求。別の会社に低い価格で再委託することで、おおむね50%の利益率を保っていたという。
漢検業務そのもの以外のシステム開発でも、協会から9000万円で受注した業務を2000万円で再委託したケースもあったことが既に判明している。
調査委は受け付けや採点業務の外部委託自体は合理性があるとしているが「日本統計事務センターが別の会社に再委託している事実をみると、同社に委託する必然性はない」としている。【木下武、広瀬登】
防耐火材性能偽装:サッシメーカー前社長らを告訴 04/22/09 (毎日新聞)
国土交通相認定の防耐火材の性能偽装問題で、性能評価を請け負った財団法人日本建築総合試験所(本部・大阪府吹田市)は22日、詐欺の疑いでサッシメーカー、エクセルシャノン(東京都港区、中村辰美社長)の前社長と元開発技術部長を警視庁に告訴したと発表した。
同試験所によると、2人は07年10月、実際の製品より防火性能を高めた試験体を偽装して試験を受け、建築基準法で規定された性能評価書を08年2月にだまし取ったとされる。
国交省の調べでは、性能不足の防火樹脂製窓は5社が販売し、約5500棟で使用されており、交換の準備を進めている。同省の07年11月の調査に対し、エクセルシャノンは「(不正など)問題はない」と回答しており、同省と試験所は「主導的立場で、計画的で悪質性が高い」と判断した。【平井桂月】
漢検前理事長ら背任の疑い、関連4社と不適切取引…地検捜査 04/17/09 (読売新聞)
財団法人「日本漢字能力検定協会」(京都市下京区)が大久保昇前理事長(73)らの関連企業4社に多額の業務委託をしている問題で、大久保前理事長や長男の浩前副理事長(45)とその家族計5人が、4社から昨年度までの3年間に5億3000万円の報酬を得ていたことが関係者の話で分かった。
4社との取引については、協会の調査委員会も合理性や価格の妥当性の面から「法律上許されない取引」と指摘。京都地検は、一連の取引が協会に損害を与え、4社を通じて前理事長側に利益が流れた疑いがあるとみて、背任容疑での立件を視野に捜査を進めている。
大久保前理事長は15日の記者会見で「協会からは報酬を得ていない」と話していたが、関係者によると、大久保前理事長は、代表を務める出版会社「オーク」と広告会社「メディアボックス」から年間約7000万円の収入を得ていた。
浩前副理事長は、オークとメディアボックスなど3社から年間約5000万円以上の報酬を得ていたほか、役員などを務める家族3人も4社から年間3980万~7110万円の報酬を得ており、2008年度までの3年間に大久保一族が4社から得ていた総額は5億2985万円にのぼるという。
4社の売上高は、8割以上が協会との取引によるもので、協会が設置した調査委員会はこれら4社との取引について、「合理性がない」とした上で、「重大な任務違背で責任は重い」と指摘。文部科学省も、メディアボックス(委託料36億円)と文章工学研究所(同6300万円)の2社については「取引を解消すべき」と指導し、大久保前理事長らは、こうした指摘を受け入れる形で、2社との取引を解消する方針を明らかにしていた。
調査報告書は、協会から4社に流れていた総額250億円にのぼる資金について、「協会に保存されるべき資産が外部に流出していた」とも指摘しており、地検は、このうちの一部が刑法の背任にあたる可能性もあるとみて捜査している。
NHKのニュースを見ていたら郵政職員及び日本郵便職員が1年に1度はチェックするようになっていたが、実際はチェックしていないから
不正が15年近くも見逃された来たと言っていた。日本の役人によるチェックの甘さはどの省庁でも同じなのかもしれない。
性善説と言いつつも実際は公務員達はチェックをしたくない、又はチェックが出来るだけの能力や経験が持つ職員がいないのが
事実ではないのか??
1年に1度はチェックを郵政職員及び日本郵便職員が行っていたのなら、癒着や何らかの形で見返りがあったと思ってしまう。
不正を見逃す理由がない限り、郵政職員及び日本郵便職員が不正を指摘しない理由が考えられない。
郵便不正容疑、日本郵便も捜索 ベスト電器元部長逮捕 04/16/09 (朝日新聞)
ダイレクトメール(DM)広告の発送をめぐる郵便不正事件で、大阪地検特捜部は16日、家電量販大手「ベスト電器」(福岡市博多区)のDM広告の発送をめぐり約2億4千万円の料金を免れたとして、同社の元販売促進部長、久保俊晴容疑者(51)を郵便法違反容疑で逮捕した。大手広告会社「博報堂」の子会社「博報堂エルグ」(同)の執行役員ら逮捕状を取った残る9人も取り調べており、容疑が固まれば逮捕する。郵便事業会社(JP日本郵便)の新東京支店(東京都江東区)も関連先として家宅捜索した。
特捜部は、事件にかかわったとされる障害者団体に郵便料金割引制度の適用を認めていたJP側に不正への関与がなかったか本格的に調べる。また、特捜部は同日午前、ベスト電器本社や、DM印刷を請け負った東証2部上場で大手通販・印刷会社「ウイルコ」の東京営業部(東京都中央区)の捜索を始めた。
ベスト電器、博報堂エルグの幹部以外で逮捕されるのは、ウイルコの若林和芳会長(57)と執行役員▽障害者団体「白山会」(東京都文京区)の守田義国会長(69)▽同「健康フォーラム」(同港区)の菊田利雄代表らのほか、すでに別の郵便法違反の罪で起訴された広告会社「新生企業」(現・伸正、大阪市西区)社長の宇田敏代被告(53)と、元取締役の阿部徹被告(55)。
ベスト電器は、通常なら1通120円が最低8円で送れる「心身障害者用低料第3種郵便物制度」を使い、05年8月~昨年2月にDM広告約1100万通を発送していた。
特捜部の調べによると、10人はこのうち約200万通を、07年2月、「発行部数の8割以上が購読されている」などの制度の要件を満たしていないと知りながら、9回前後にわたってベスト電器の顧客らに不正に発送。正規料金との差額約2億4千万円の支払いを免れた疑いがある。
特捜部は、新生企業の宇田社長らを2月に逮捕し、ウイルコが広告主となったDM発送で9億円余りの料金を免れたとする郵便法違反の罪で起訴した。この捜査で今回の不正を把握したとみられる。
1通8円格安郵便、うまみに群がるベスト電器や博報堂子会社 04/16/09 (読売新聞)
取引に関与した企業・団体が「うまみ」を分け合っていた――。
16日、大阪地検特捜部が、広告主だった大手家電量販店「ベスト電器」(福岡市)などの強制捜査に乗り出した郵便法違反事件。約1190万通発送されたダイレクトメール(DM)で同社などが不正に免れた郵便料金は約13億円に上ったという。印刷・通販会社「ウイルコ」(石川県白山市)が広告会社「新生企業」(現・伸正)との間で問題の取引を始めたのは、創業者の若林和芳会長(57)の意向だったとされる。不正全体の構図が暴かれようとしている。
「格安で郵送できるDMがある。上場企業が何社も利用し、障害者にも役立つ」
2005年5月、大手広告会社「博報堂」の九州支社(福岡市)にウイルコの担当者が営業に訪れた。ウイルコはすでに新生企業と組んで自社商品のDMを大量発送しており、障害者団体のための割引制度による差益の大きさを知り尽くしていた。
“格安”の取引話は博報堂の子会社「博報堂エルグ」が翌月、博報堂側が「超お得意様」とするベスト電器に提案した。2か月後には、ベスト電器の広告付きDMに障害者団体発行の定期刊行物が同封されて、顧客に届けられた。
広告業界の関係者によると、ベスト電器は、顧客一人ひとりにアピールできるよう、テレビや新聞よりDMによる販促を重視していた。広告関係者は「業界内で勝ち残るため、広告経費の圧縮も魅力だったはず」と指摘する。
障害者団体に適用される郵便料金の割引制度を利用すると、通常1通120円のところを8円前後で発送でき、差益が出る。ベスト電器のDMは08年2月頃までに計約1190万通が発送された。正規料金との差額は約13億円に上った。ウイルコと新生企業がそれぞれ1通4~5円の手数料、障害者団体が1通3円の報酬を得るなどしていたが、ベスト電器にとっても大きな経費削減になったとみられる。
新生企業との取引で自社商品のDM約210万通を送っていた大手通販会社は「広告主の節減割合が最も多く、経費はかなり低く抑えられたはず」と証言する。
郵便事業会社から差額分の返還を請求されている障害者団体の幹部は「もうかるから、みんなが食いついた。でも、一番得していた広告主の責任を追及しなければ、事件の本質は見えない」と話した。
有名であっても本来のチェック機能を果たしていなかった理事・評議員会は役割を果たせないのなら、いないに等しい。名義を借りているだけだ。
文科省は問題があれば「漢検協会」の解散を要求すればよい。
「私物化ない」「取引は正当」漢検理事長、3時間の抗弁 04/16/09 (読売新聞)
漢字検定を国内最大の受検者数280万人というブランドに育て上げた財団法人「日本漢字能力検定協会」(京都市下京区)の大久保昇理事長(73)らは、これまで残留するとしていた理事職も、一転して辞任することになった。
「私物化はしていない」「取引は正当だった」。初めての記者会見は約3時間にも及び、関連企業への総額250億円に上る業務委託や高額な不動産購入について反論し、最後まで、不明朗な取引などについて責任を否定し続けた。
大久保理事長と長男の浩副理事長(45)は15日、文部科学省に報告書を提出後の午後5時過ぎ、報道陣のフラッシュを浴びながら、弁護士2人とともに省内の記者会見室に現れた。大久保理事長は冒頭、「数多くの受検生にご心配をかけて申し訳ありませんでした」と述べ、親子そろって何度も頭を下げた。
しかし、理事長らが代表取締役を務める関連企業4社との取引や、京都市内の土地・建物購入などの妥当性を指摘されると、「取引に問題はない」と述べ、浩副理事長が「疑義を持たれたことについて真摯(しんし)に受け止めなくてはならない」としつつも、一貫して「問題はない」と繰り返した。
取引が背任行為に当たるのではないかとの指摘にも、浩副理事長は「取引の知識が欠落していた。手続き上の問題で真摯に対応しなければならない」と述べるにとどまった。理事長への質問は、ほとんど副理事長が回答。大久保理事長がぶぜんとし、顔を紅潮させる場面も見られた。
ただ大久保理事長は、漢検への思いを語る際には多弁になり、「協会を私物化しているとは思わない。日本の文化を向上させるためにやってきた」「受検生の支持は今をもっても高い」と持論を展開。ただ、その信念を汚したとの認識はないのかとの質問には言葉を詰まらせ、「組織運営には問題があったが、文化を守りたいということは間違いなかった」と語った。
◆文科省「検証に疑問」◆
漢検側の報告を受け、文科省生涯学習推進課の上月正博課長は、「一定の改善は図られたが、検証が十分行われたか疑問が残る」との見解を示した。
大久保理事長らが今月10日の理事会・評議員会で、関連企業4社との取引を承認させ、正当化したことについて、「過去の取引を追認させており疑問」とし、私的流用の有無や背任行為についても、「報告書を見てさらに検討したい」と語った。
漢検の大久保親子、理事職も辞任へ…「取引解消」は2社だけ 04/16/09 (読売新聞)
財団法人「日本漢字能力検定協会」(京都市下京区)が公益事業では認められない多額の利益を上げて文部科学省から指導された問題で、同協会の大久保昇理事長(73)が15日、同省に業務改善の報告書を提出した。
大久保理事長は一連の問題発覚後、長男の浩副理事長(45)と初めて記者会見して謝罪、協会の理事をそろって辞任する考えを示したが、同省は、報告書の内容が不十分とみており、新体制のもとで再検証を求める。
報告書では、〈1〉理事会や評議員会のチェック機能の強化〈2〉現在の検定料1500~5000円を、6月から100~500円引き下げ〈3〉京都・南禅寺近くの土地・建物(購入費用約6億7000万円)の売却――などの方針を示した。
大久保理事長らが代表取締役を務め、2008年度までの16年間で委託額が総額250億円に上っていた関連企業については、4社のうち2社との取引を解消するとした。しかし、取引解消は、委託額の少なかった「メディアボックス」と「文章工学研究所」の2社(委託額計36億9400万円)で、「オーク」と「日本統計事務センター」(同計213億円)との取引は継続し、理事長らは今後も協会運営のアドバイスを行うという。
大久保理事長は、今月10日の理事会・評議員会では理事長を辞任するものの、理事として協会にとどまることが決まっていたが、「道義的責任を明確にしたい」として、理事の職も辞することにした。
◆改善報告書、随所で表現後退◆
漢検側の報告書は、協会が一連の問題発覚後に設けた弁護士らによる調査委員会の報告書に基づいたものだが、随所で表現が後退していた。
「(大久保理事長らが)法律上許容されない取引を行ってきた。重大な任務違背で、責任は重い」。調査委が今月上旬にまとめた報告書では、刑法の背任罪に該当する可能性も示唆していたが、この日の報告書からは踏み込んだ指摘は消えた。理事長らの関連企業4社のうちメディアボックスなど3社との取引については、調査委の「合理性がない」との指摘に対し、漢検の報告書は、4社とも「合理性はあった」と変更。委託額が最も多いオークとの取引については、「契約継続を見直すべきだ」「速やかに解消」から、「見直しを協議」「解消は慎重に検討」と変わった。
チェック機能を果たしていなかった理事・評議員会の運営に関しても、調査委は「委任状出席はすべて禁止」としていたが、この日の報告書では「原則禁止」に。文科省は「内容をよく精査したい」としている。
積水ハウス建築士が文書偽造 国交省が3人処分 04/14/09 (朝日新聞)
国土交通省と静岡県は14日、戸建て住宅最大手の積水ハウス(大阪市)の浜松支店が、着工前に建築計画を事前審査する建築確認の手続きが済んだように書類を偽造したなどとして、建築士3人に対し、免許取り消しや業務停止の懲戒処分をしたと発表した。同社は、昨年12月にも建築確認を受けずにアパートを建て、建築士2人が処分を受けている。
一連の偽造について、静岡県警は9日に元社員の五十住肇容疑者(50)=懲戒解雇=を有印公文書偽造・同行使容疑で逮捕した。五十住容疑者は戸建てやアパート計10棟について17通の書類を偽造し、このうち3棟は建築確認を受けずに着工していた。県は五十住容疑者の2級建築士の免許を取り消した。
国交省は、五十住容疑者の上司だった浜松支店の1級建築士2人を業務停止7カ月と同3カ月とした。積水ハウスは「社として監督責任を痛感し、二度と起こらないよう徹底する」(広報部)としている。
漢検、身内企業との取引隠匿…理事長ら決算報告から削除指示 04/11/09 (読売新聞)
日本漢字能力検定協会(京都市)が、大久保昇理事長(73)らの関連4社に多額の業務を委託していた問題で、協会の監査を担当した公認会計士が、2006年度決算報告書に4社との個別の取引を明記したにもかかわらず、大久保理事長らの指示で、協会がその記載をすべて削除したうえで、理事・評議員会と文部科学省に提出していたことが、明らかになった。
協会が10日の理事・評議員会に提出した内部資料によると、一連の問題発覚後に設置された弁護士、公認会計士らによる調査委員会が指摘。協会は「法令順守に対する認識不足だった」としている。
同年度から導入された新公益会計基準で、関連法人との取引などの場合、相手の代表者名、所在地、資産総額、取引内容を決算報告書に「注記」として記載するよう規定された。
内部資料などによると、協会と同年度決算の監査契約を結んだ公認会計士は、新基準に従って、大久保理事長が代表を務める出版会社など3社、長男の浩副理事長(45)が代表の情報処理会社との取引をそれぞれ決算報告書に記載した。
協会から4社に計24億円が支払われていたが、07年6月に開かれた理事会と評議員会には、そうした取引の記載が削除された決算報告書案を提案。両会で決議、承認され、文科省にも提出された。
公認会計士は監査途中で退任したが、協会関係者は「公認会計士は理事長や副理事長の指示に従わなかったようだ」と証言している。
文科省は協会に対し、公認会計士の監査を受け、新基準に従った決算報告書を作成するよう文書で指導したが、協会が文科省や理事・評議員会に取引の全容を報告したのは、一連の問題発覚後の今年2月だった。
内部資料によると、調査委は、4社との取引で不必要な支出が生じたとして、「協会に保存されるべき資産が流出した」と指摘した。
集団密航:手引きの元議員秘書らを逮捕 助長容疑で 04/03/09 (毎日新聞)
食品加工会社で働かせることを目的にミャンマー国籍の女性を集団密航させたとして、警視庁組織犯罪対策1課は3日、東京都杉並区成田東5、衆院議員の元秘書で会社員の舘沢恵一(58)と千葉県浦安市当代島3、会社役員、前田一美(57)の両容疑者を入管法違反(集団密航助長)容疑で逮捕したと発表した。
逮捕容疑は、08年4月21日、ミャンマー人女性2人を茨城県土浦市の食品加工会社で弁当作りなどの単純労働に就労させるため、「通訳として迎え入れる」と東京入国管理局に虚偽申請して入国させたとしている。
組対1課によると、両容疑者は集団密航のブローカーで、これまでに中国人、バングラデシュ人など約30人を集団密航させ、密航者から1人あたり10万円の手数料を受け取っていた。密航者の受け入れ先の企業や入管当局とのやりとりの中で、衆院議員の元秘書の経歴を名乗っていたという。【町田徳丈】
「美少年」裏金問題、農政局が社長から事情聴取 04/02/09 (読売新聞)
熊本県城南町の酒造会社「美少年酒造」が、事故米を不正転売した米穀加工販売会社「三笠フーズ」(大阪市)側から裏金を受け取っていた問題で、農林水産省九州農政局(熊本市)は2日、裏金の捻出(ねんしゅつ)方法などについて、美少年酒造の緒方直明社長らから事情を聞いた。
今後、行政処分の必要性や法令違反の有無などを判断する。
農政局によると、聞き取りは約1時間半にわたって行われ、緒方社長ら幹部3人から裏金作りの手口や受け取った裏金の金額、三笠フーズ側との原料米の取引方法などについて説明を受けた。
国は事故米の転売先として風評被害などを受けた業者の支援に取り組んでいるが、米の買い入れなどで法令違反のないことが前提。聞き取りは、美少年酒造が支援を申請した場合に備えて行われた。緒方社長は説明後、報道陣に「経営支援の申請については未定」と話した。
美少年酒造:米の不正取引で裏金、社長「経営難から」 04/01/09(毎日新聞)
三笠フーズ(大阪市)による事故米不正転売事件で被害企業となった熊本県城南町の美少年酒造(緒方直明社長)は3月31日、記者会見し、不透明な米取引をして裏金作りをしていたことを明らかにした。仕入れた1等米の一部を三笠フーズの関連会社、辰之巳(東京都中央区)に精米に出し、同社からは精米した3等米を受け取っていた。差額分は、辰之巳の社長だった三笠フーズ社長、冬木三男被告が美少年酒造を訪れ直接手渡していたという。
会見によると、緒方社長が就任した87年から07年まで、冬木被告から年間約150万円提供を受けていた。ただ、こうした差額分の提供は82年以前からもあったという。裏金は200万円を超えた年もあった。これらの金は帳簿には付けていなかったという。
美少年酒造は、飲食店への貸付金が焦げ付くなどして不良債権ができた。不良債権は90年ごろには約3000万円に上ったという。緒方社長は「良くないことだからやめないといけないと思いながら、経営の苦しさからやってしまった」という。
事故米転売事件で、美少年酒造は、辰之巳が殺虫剤に汚染された非食用のベトナム産うるち米を販売した酒造会社の一つとなっていた。その後、風評被害で売り上げが一時10分の1に落ち込むなど低迷。熊本県の提案で、県庁内で販売会を開くなどの支援を受けた。石破茂農相は「国が食用転用を見抜けなかった」と同社を訪れて謝罪もした。
緒方社長は「事故米騒動とは関係ない」としながら「応援をしてくれた人たちに大きな裏切りをした。本当に申し訳ない」と語った。進退については「対策を取った上で、責任を明らかにして時期が来ればけじめをつけたい」と語った。【遠山和宏】
旧ミドリ十字は薬害エイズ事件の会社だろ。やはり会社の体質なのだろう。
「バイファ社は、田辺三菱製薬の前身の旧ミドリ十字が、同製剤を開発するため1996年に設立された。
データ改ざんにかかわっていたのは、旧ミドリ十字出身の品質管理責任者(すでに退職)やその部下ら計5人で、
承認が下りないことを恐れて改ざんしたとみられるという。」
会社や自分たちの利益のためには何でもありでは困る。旧ミドリ十字出身の社員の考え方は簡単には変わらないだろう。
問題を起こせば、厳しく処分するべきだ。改ざんに関与した社員は、今も田辺三菱製薬にいるのか????
田辺三菱製薬、試験データ改ざんで製剤承認取り下げ 03/24/09 (読売新聞)
田辺三菱製薬(大阪市)は24日、子会社「バイファ」(北海道千歳市)と共同開発して薬事法の製造販売承認を受けた人血清アルブミン製剤について、承認の際に提出した試験データに改ざんなどの不正行為が見つかったとして、同製剤の製造販売承認を取り下げるとともに自主回収すると発表した。
製薬企業が試験データの改ざんが原因で承認を取り下げるのは異例。
問題の製剤は、重度熱傷の治療などに使われる「メドウェイ注」。実際に出荷された同製剤の安全性は確認されており、これまでに使用した患者807人(2月末時点)から健康被害は報告されてないという。
田辺三菱製薬は、酵母を使ったバイオ技術で、世界初の遺伝子組み換えによる同製剤を開発。2007年10月に承認を受け、昨年5月から販売していた。
データ改ざんを行っていたのはバイファ社の社員で、製品にアレルギーが生じる酵母成分が混入しないことを調べるラット試験で、一部のラットにアレルギーの陽性反応が出ていたのに、陰性反応のデータと差し替えるなどしていたという。昨年末、同製剤の有効期間延長を求める申請手続き中に、不正が発覚した。
バイファ社は、田辺三菱製薬の前身の旧ミドリ十字が、同製剤を開発するため1996年に設立された。データ改ざんにかかわっていたのは、旧ミドリ十字出身の品質管理責任者(すでに退職)やその部下ら計5人で、承認が下りないことを恐れて改ざんしたとみられるという。
厚労省内で記者会見した田辺三菱製薬の小峰健嗣副社長は、「社会からの信頼を損なう行為で心よりおわびする。グループ全体で再発防止に努めたい」と陳謝した。
「OBは関係者に『4回目の運搬途中、かばんを開けて金と分かった。(大賀容疑者を)とがめたが、給料をもらう立場だったのでその後も断れなかった』と話しているという。」
退職するまで警官として働いても、給料をもらう立場になったらおかしなことでもやる。警官も人間だ。だったら、もっと謙虚に行動してほしい。
そして、警官は間違っていない、自分達は正しいと考えることを改めてほしい。警官も間違いをするし、全ての警官が正しいとは限らない。
大分コンサル脱税:大賀容疑者、県警OBに裏金運搬指示 03/23/09(毎日新聞)
キヤノンの施設建設工事を巡る脱税事件で、大分市のコンサルタント会社「大光」社長、大賀規久容疑者(65)が、「資料が入っている」と偽り、裏金入りのかばんをグループ会社社員の大分県警OB(65)=逮捕後処分保留で釈放=に運ぶよう指示していたことが捜査関係者の話で分かった。運搬は7回に及び、県警OBは大阪市でコンサルタント会社社長、難波英雄容疑者(61)から受け取り、新幹線で東京などに移動して大賀容疑者側に渡したという。
大賀、難波両容疑者間の裏金授受の詳細が判明したのは初めて。東京地検特捜部は大手ゼネコン「鹿島」や電気設備工事大手「九電工」などがキヤノン工事受注の見返りとして難波容疑者に渡した裏金が、大賀容疑者に渡ったことを裏付ける事実とみている。特捜部は拘置期限の23日午後にも、両容疑者を法人税法違反で追起訴し、総額約10億円に及ぶ脱税事件の捜査を終えるとみられる。
捜査関係者によると、大賀容疑者は05年、県警OBに「大阪の難波(容疑者)のところから資料を運んでほしい」と依頼。OBは大阪市のJR新大阪駅で難波容疑者から旅行用の大型かばんを受け取って、新幹線で東京に向かい、大賀容疑者の部下に渡した。重かったため後日、OBが「何が入っていたのか」と尋ねたところ、大賀容疑者は「中身は資料ではなく(政治家の)パーティー券」などと説明した。しかし、実際は裏金だったという。
裏金の運搬はその後も続き、OBは大阪市の難波容疑者の会社事務所などで紙袋やかばんを受け取り、東京・赤坂の大賀容疑者の事務所や大賀容疑者の定宿とされる虎ノ門のホテルなどに運んだ。大賀容疑者は、難波容疑者を裏金の集金役に、事情を知らないOBを運び屋にそれぞれ使うことで、巧妙に資金移動を隠そうとしたとみられる。
OBは関係者に「4回目の運搬途中、かばんを開けて金と分かった。(大賀容疑者を)とがめたが、給料をもらう立場だったのでその後も断れなかった」と話しているという。
「ホップ被告は『少なくとも5、6人の同僚が同じことをしていた』と明かし、『金が欲しかった』と動機を述べた。」
「日本支社の担当者は『捜査には全面的に協力する。ほかに関与があれば、うみを出しきりたい。しかし、本国では公務員の副業禁止規定すらなく、
倫理意識も日本とは違う。社員に日本の法令や常識を教育していくには時間がかかるだろう』と話す。」
日本支社の担当者はポップ被告の同僚5、6人の捜査についても全面的に協力するの?日本の警察や検察も捜査を続けるの??
ベトナム航空盗品密輸、初公判で副機長「5、6人の同僚も」 12/08/08(朝日新聞)
ベトナム航空乗務員らによる盗品密輸出事件で、盗品有償譲り受けと同運搬の罪に問われたベトナム国籍の同航空副機長ダン・スアン・ホップ被告(33)の初公判が19日、さいたま地裁(中谷雄二郎裁判官)であり、ホップ被告は起訴事実を認めた。
検察側は懲役2年6月と罰金50万円を求刑、弁護側は寛大な判決を求め、即日結審した。
起訴状によると、ホップ被告はホーチミン市在住の女(34)(盗品有償譲り受け容疑で逮捕状)と共謀し、2008年1月30日、大阪府泉佐野市のホテルで、宅配便で送られてきたデジタルビデオカメラ用テープ27本(販売価格約1万500円)を盗品と知りながら約3400円で買ったなどとされる。
ホップ被告は「少なくとも5、6人の同僚が同じことをしていた」と明かし、「金が欲しかった」と動機を述べた。
「日本支社の担当者は『捜査には全面的に協力する。ほかに関与があれば、うみを出しきりたい。しかし、本国では公務員の副業禁止規定すらなく、
倫理意識も日本とは違う。社員に日本の法令や常識を教育していくには時間がかかるだろう』と話す。」
他の機長が犯罪に関与していれば、日本の警察は逮捕すればよい。何人か逮捕されれば理解できるだろう。日本支社の担当者が法令や常識を教育する
のに時間がかかると言うのなら仕方のないこと。違法行為=逮捕を説明するだけのこと。そんなに難しいことなのか???
ベトナム航空密輸、全国で万引き組織化 逮捕者80人超 12/08/08(朝日新聞)
国営「ベトナム航空」の副機長が日本から盗品を密輸しようとして逮捕された事件で、これまでにベトナム人ら80人以上が逮捕された。埼玉、山口など14府県警による捜査で、日本各地での万引きが組織化され、ベトナムではビジネスになっている実態が浮かび上がった。同社は近く、再発防止策を国土交通省に提出する方針だ。
起訴状によると、副機長のダン・スアン・ホップ被告(33)は08年7月11日、盗品である化粧品10点(約1万7千円相当)を大阪府泉佐野市のホテルからスーツケースに入れて関西空港まで運んだほか、同年1月30日、盗品であると知りながらビデオテープ27本(1万456円相当)を3420円で買い受けた、とされる。19日に初公判が開かれる。
副機長は昨年12月、成田空港のホテルで逮捕された。その直後、同乗する予定だった客室乗務員らは合同捜査本部の事情聴取に、「(盗品運びは)知っていましたよ」と淡々と話したという。
捜査の端緒は、10年ほど前から全国各地で増えたドラッグストアの万引きだった。逮捕した複数のベトナム人から「盗品はベトナム航空のクルーが本国に持ち帰っている」などという供述が出た。
被害は徐々に増え始め、とりわけ05年以降、中部地方で目立ち、08年ごろから関西や関東にも広がった。ベトナム航空が05年、中部―ホーチミン便を就航させ、07年末に運休するのと軌を一にした動きで、税関関係者からは「同航空クルーの手荷物が目立って多い」という証言もあった。
そこで、捜査当局は同社をにらんだ捜査を本格化させた。だが、犯行の裏付けとなる盗品は国外に持ち出されたと見られた。さらに、機長や客室乗務員は国家公務員で、「本国では高収入・高学歴の『セレブ』に属する。うかつに事情聴取できる状況ではなかった」という。
突破口を開いたのが山口県警だ。昨年7月、盗品買い受け容疑で兵庫県姫路市のベトナム人の女(33)を逮捕。関西空港へのフライト時、副機長の宿泊先のホテルに盗品を郵送するよう指示した文書が家宅捜索で見つかった。
その後、埼玉、愛知、兵庫、広島、山口の各県警が、大阪府八尾市や東京都三鷹市、群馬県伊勢崎市に住むベトナム人の買い取り役を次々に逮捕。伊勢崎市の家宅捜索でも、副機長の宿泊先への宅配伝票などが見つかった。
一連の事件での逮捕者は窃盗の実行役七十数人、買い取り役が十数人にのぼり、ホップ副機長以外の複数のベトナム航空関係者あての「ゆうパック」や宅配便の伝票も押収された。送付先は関西や成田空港近くのホテルだったという。
主犯格とみて、埼玉県警が盗品等有償譲り受け容疑で指名手配したのは、ホーチミン市に住む女(34)だ。買い取り役に「欲しい品」の銘柄や個数を発注。口紅やファンデーションなどの化粧品、携帯用おしり洗浄器やシャワーヘッド、使い捨てカメラや栄養ドリンクが多かったという。
副機長は女の指示で、日本の宿泊先に届いた盗品を「手荷物」として本国へ運び込み、1回約100ドルの報酬を受け取っていた、という。
捜査関係者は「(副機長の事件は)数ある中で、たまたま逮捕にこぎ着けたに過ぎない。社内で、小遣い稼ぎ感覚で密輸が横行していたのではないか」と話す。
ベトナム航空が国交省に提出する再発防止策は、法令順守の徹底を掲げた上で、(1)乗務員らの自主的な手荷物検査(2)スーツケース以外の手荷物の機内持ち込み禁止(3)法令順守のマニュアルづくり――などを盛り込む方針だ。
日本支社の担当者は「捜査には全面的に協力する。ほかに関与があれば、うみを出しきりたい。しかし、本国では公務員の副業禁止規定すらなく、倫理意識も日本とは違う。社員に日本の法令や常識を教育していくには時間がかかるだろう」と話す。(奥田薫子、小暮純治)
有名であっても本来の役割を果たせないのなら、いないに等しい。名義を借りているだけだ。
いかにも日本的であるが、文部科学省は指導する義務がある。
農水省によるヤミ専従調査の事実隠ぺい
のように悪質なことはしないでほしい。問題があれば「漢検協会」を解散を要求すればよい。
「漢検協会」理事・評議員名ばかり、会議出席ゼロも 03/16/09 (読売新聞)
財団法人「日本漢字能力検定協会」(京都市)が多額の利益を上げていた問題で、協会の理事や評議員が、文部科学省から「役割を適切、十分に果たしていたとは言い難い」との指導を受けたことに対し、理事・評議員からは自らの辞任の申し出がある一方、大久保昇理事長の辞任を求める声も上がっている。
理事、評議員のうち、大久保理事長と息子の浩副理事長を除く19人は、著名な文化人や国語学者らで構成されている。しかし、会議に一度も出席したことがないメンバーもいるという。
同省などによると、理事、評議員の会議などの出席率は低く、特に理事会は、問題発覚後開かれた2回のうち1回は、大久保理事長と浩副理事長だけが出席。もう1回も、代理人を除けば、理事本人はほかに1人しか出席しなかった。
2回とも欠席した元国立国語研究所長の水谷修・名古屋外大学長は「仕事があった。もっと詳しく知ろうとするべきだったかもしれない」と話す。
評議員会(13人)でも、約10年前に就任したが、出席したことがない哲学者の梅原猛さんは大久保理事長に依頼されて加わった。梅原さんは「信用したことを後悔している。関連会社への委託などとんでもないことで、評議員の機能を果たせなかった自分への怒りも感じる」と評議員を続けるかどうかは検討中という。評議員の中には、野間佐和子講談社社長のように、すでに辞表を提出した人もおり、複数の理事、評議員も辞任を検討しているという。
一方、評議員で、同協会の内部調査委員会委員でもある大森厚・中央工学校理事長は、「理事長が責任を取って辞任し、新体制で再出発するべきだ」と自発的な辞任を求めている。
信濃川から不正取水、JR東日本の水利権取り消し…国交省 03/10/09 (読売新聞)
JR東日本が新潟県の信濃川水力発電所で、信濃川から不正に取水を繰り返していた問題で、国土交通省北陸地方整備局は10日、JR東の水利権を取り消した。
信濃川発電所は、JR東で使う全電力の23%をまかなっていた。記者会見したJR東の清野智社長は、首都圏などでの電車運行への影響について、「(電力需要が増える)夏の時期に若干の不安はあるが、対策を考える」と述べた。
不足する電力は、川崎市にある火力発電所をフル稼働させ、購入先の東京電力に供給を増やすよう要請する。コスト増に伴う運賃値上げについて清野社長は、「影響はない」と否定した。
北陸地方整備局によると、JR東は信濃川発電所で2008年までの7年間に、新潟県十日町市の宮中ダムから決められた量より3・1億トン多く取水した。
発電所には、取水が決められた量を超えても許容範囲になるよう細工した観測機器を設置していた。
輸出申請の簡略化制度を悪用…外為法違反の「ホーコス」 03/05/09 (読売新聞)
工作機械製造大手「ホーコス」(広島県福山市)の不正輸出事件で、警視庁などに外為法違反容疑で逮捕された元同社課長代理の青山正彦容疑者(51)らが、不正輸出した「マシニングセンタ」(MC)の約500台のうち約200台について、手続きを簡略化できる輸出申請制度を悪用していたことがわかった。
同制度を利用した2004年以降、同社の不正輸出は急増しており、同庁は同社が組織的に不正をしていた疑いがあるとみて調べる。
同庁幹部によると、核開発に転用可能な工作機械を輸出する場合、通常、作動時の誤差などの性能を台数分検査して、そのデータを書類に添付し経済産業相の許可を得る。
経産省は00年に同一機種なら5台の平均値を一度申告すれば、その後の輸出時はこの手続きが簡略化される制度を導入した。同庁幹部によると、1回の改ざんで不正輸出を繰り返すことが可能なため、同社はこの制度を悪用。03年12月、一部機種について、輸出許可の不要な低い性能に改ざんしたデータを申告し、その後不正輸出を繰り返していたという。
この機種の作動時の誤差は、経産相の許可が必要な2マイクロ・メートル程度だったが、同容疑者らは、書類に6マイクロ・メートル以上の数値を記載した偽の申告書類を提出していたという。
02年以降の輸出、大半で虚偽申告か 広島の工作機業者 03/05/09 (朝日新聞)
広島県福山市の工作機械メーカー、ホーコスによる不正輸出事件で、同社が02年以降に輸出した工作機械の大半で性能を低く偽って経済産業省や税関に申告していたことが警視庁公安部と広島県警の合同捜査本部への取材でわかった。少なくとも約500台以上が不正に輸出された可能性があるという。
捜査本部によると、同社は90年ごろから、工作機械「マシニングセンター」(MC)の輸出を始め、現在までに計約900台を米国や中国、韓国、インドネシアなど計16カ国に輸出。02年以降、輸出量が急増しており、約700台以上がこの時期に輸出されていた。
捜査本部が、押収した同年以降の資料を分析したところ、このうちの約600台は輸出の際に経済産業相の許可を必要とする輸出制限基準に該当した高性能機種だったことが判明。しかし同社は、このうち約9割について加工精度を低く偽り、「非該当」として経産省や税関に申告していたという。
残り約1割については国内の商社などを介した輸出で、これらは商社などが「該当」と申請して許可を取得していた。このため捜査本部は、同社が直接手続きをしたケースはほとんどが不正輸出だったとみている。
一方、同社幹部は捜査本部の任意の事情聴取に対し、「輸出関連の法律をよく知らなかった」「輸出管理は部下に任せていた」などと話しているという。だが、捜査本部は、同社の社員が出席した輸出管理の法律や実務を学ぶ講習会の内容を幹部に報告していることや、性能データの改ざんについて懸念を示す社員がメールを幹部に送っていることなどを把握しているといい、同社幹部が不正を承知していたか調べる方針だ。
旧郵政ずさん入札…実態ない会社・不参加業者に「売却」 03/03/09 (読売新聞)
旧日本郵政公社が一括売却した施設が相次ぎ転売されていた問題を巡り、入札で他社と争った企業の代表者が入札に参加したことさえ知らなかったり、活動実態のない会社が落札グループに含まれたりしていたことがわかった。
落札業者は「不動産の一括売却ではよくあること」というが、公的資産の売却としては不透明さがつきまとう。日本郵政の売却リストに、実際の売却先とは異なる企業が記入されるなど、少なくとも39か所に誤りがあることも判明。資産管理の在り方そのものが問われている。
「名義貸しだけなので、入札についてはわからない」
不動産投資を目的とする有限会社「駿河ホールディングス」(東京都港区)の取締役だった男性は、読売新聞の取材にそう答えた。
同社は2007年2月、旧公社の178施設が一括売却された一般競争入札に参加。入札調書によると、マンション販売会社「コスモスイニシア」(千代田区)が率いる企業グループとの争いとなったが、2回目の入札で辞退している。
登記簿や関係者によると、駿河社は04年10月に設立され、昨年5月に解散。入札当時の代表だった男性は、都内の投資会社に依頼されて取締役に就任しただけで、郵政物件の入札には一切かかわっていないという。投資会社は、駿河社の不動産管理を行っていることは認めたが、出資関係など詳細は「答えられない」という。
鳥取県岩美町と鹿児島県指宿市の「かんぽの宿」をそれぞれ評価額1万円で購入し、転売していた不動産会社「レッドスロープ」(中央区)も、不動産投資を目的にする会社だ。
登記簿などによると、同社は、06年2月に186件の一括売却が行われた入札の半月前に設立。現在の所在地となっている東京・銀座のビル入り口には表札が掲げられているが、会社は無人で鍵がかかったまま。同じビルに入居するIT関連会社の会社員(34)は、「出入りする社員も見たことがないし、明かりがついている様子もなかった」と話す。
レッド社の社長は、親会社の不動産会社「リーテック」(千代田区)の役員も兼ねる。同社も、05年と07年の一括売却で計36件の郵政物件を購入しているが、担当者は「実態がないと言われるが、不動産業界ではよくあること。なぜ子会社を設立し、入札に参加したかは答えられない」としている。
一方、04年から昨年にかけて売却した計634物件の売却先や売却額(評価額)などが記載された日本郵政の売却リストは、民主党の要求に基づき作成された。
06年2月の一括売却のうち37件の売却先は、いずれもリーテックと記されているが、同社はそもそもこの時の入札に参加していない。実際は、リー社が出資した二つの子会社(いずれも中央区)が単独や、別の企業と共同で購入していた。日本郵政の担当者が登記簿を確認しなかった初歩的なミスが原因とみられる。別の2施設の売却金額にも誤りが見つかった。
旧富士銀行出身で明大の高木勝教授の話「入札に実態がない会社を参加させた時点で、公的財産の処分に欠かせない透明性が失われた。一覧表の間違いも、資産管理がでたらめと批判されて当然。ずさんな印象を国民に与えてしまった」(谷合俊史、阿部真司)
精密機器メーカー「オリンパス」のコンプライアンス(法令順守)は体裁だけのものだったのだろう。
結局、日本の社会は建前だけ、口だけのケースが多いと思う。
大分県教委の教員採用汚職事件
を考えても、原因の究明よりも幕引きを優先した。社会人となる子供に手本を見せるはず先生が
自己(子供)の利益のために不正に手を染めた。また、先生達が不正な昇進があると言ううわさ(事実?)
に対して何も出来なかった。そして
大分県教委汚職事件(大分合同新聞社)
で教育委員会が適切な対応を怠ってきた事実は日本の社会の腐敗の結果だ。ただ、発展途上国の腐敗や賄賂問題はもっとひどい。
これらの国と比べて日本は良いと言っていてはかなしいと思う。
制裁を受けた浜田さんに同情はする。誰も見ないかもしれないがこの記事をリンクする。多くの人達が精密機器メーカー「オリンパス」の
対応に疑問を抱くことを祈る。
社内告発で制裁「納得できない」…オリンパス社員が会見 03/03/09 (読売新聞)
精密機器メーカー「オリンパス」のコンプライアンス(法令順守)通報窓口に上司らを告発したところ、配置転換などの制裁を受けたとして、同社社員の浜田正晴さん(48)が2日、東京弁護士会に人権救済を申し立てた。
申し立て後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見した浜田さんは「誇りを持って働いてきたのに、様々な嫌がらせを受け、精神的に追いつめられている」と心情を訴えた。
申立書によると、浜田さんは通報から2か月後の2007年8月、「部長付」という特殊な肩書で閑職への異動を言い渡された上、約1年半にわたって〈1〉業務命令で、部署外との連絡を原則禁止されている〈2〉長期病欠者らに下される最低水準の人事評価になった〈3〉毎月、自分だけに実施される密室での特別面談で、暴言を浴びせられた――などのパワーハラスメントを受けていると主張している。
記者会見で、浜田さんは「今の状況はまるでろう獄。会社の信頼を守るための行動が、こんな仕打ちとなって返ってきたことに、どうしても納得ができない」と話した。
浜田さんは取引先から機密情報を知る社員を引き抜こうとしていた上司の行為が、不正競争防止法違反(営業秘密の侵害)に当たる可能性があると判断し、07年6月、コンプライアンス窓口に通報。窓口の責任者は、通報者名が分かるメールを浜田さんの上司らに送信している。
オリンパス広報IR室は「正式な連絡を受けていないのでコメントできない」としている。
粉飾決算:循環取引で100億円か 新潟・機械メーカー 02/26/09(毎日新聞)
新潟県長岡市の機械メーカー「プロデュース」=ジャスダック上場廃止、民事再生手続き中=による粉飾決算事件で、さいたま地検特別刑事部と証券取引等監視委員会は来週後半にも、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載など)の疑いで強制捜査に乗り出す方針を固めた模様だ。佐藤英児前社長(40)や監査担当の公認会計士(39)らが07年6月期までの2事業年度で、協力企業との間で帳簿上だけで商品の売買を繰り返す「循環取引」を実行し、売上額を約100億円水増しした疑いがあるという。
法人としての同社も立件する方針。佐藤前社長は業績好調を装った07年6月期決算公表後の07年11月、保有する自社株2000株を約6億5000万円で売却した。翌月、プロデュースも増資で約40億円の資金を調達しており悪質性が高いと判断した。佐藤前社長は証券監視委の任意の聴取に容疑を認めている模様だ。
関係者によると、プロデュースは06年6月期決算の売上高が実際は約30億円だったのに約58億円に、07年6月期も約30億円を約97億円に水増し。虚偽の有価証券報告書を作成し関東財務局(さいたま市)に提出した疑い。
水増しは十数社が関与した循環取引によるもので、経営実体のないダミー会社も含まれていた。証券監視委などはジャスダック上場(05年12月)を狙った佐藤前社長が、06年6月期の数年前から計画的に粉飾決算を実行したと見ている。
一方、会計士は東京都内の監査法人の元理事長。不正な決算処理に積極的に関与した疑いがあるという。会計監査の担当者が不正の見返りに報酬を受領すると、会社法上の収賄罪が成立するため、同地検は会計士が同社から受領した報酬の趣旨についても関心を寄せている模様だ。
証券監視委は昨年9月18日、プロデュースを強制調査するなど調べを進めてきた。同社は昨年10月、ジャスダック上場廃止となり、既に事業の一部を埼玉県内の機械メーカーに譲渡することが決まっている。【堀文彦】
【ことば】循環取引
自らが販売した商品を、複数の協力企業間で転売させた後、再度買い取る手口。実際には商品自体が実在しないケースがほとんどで、何度も循環取引を繰り返し、その都度売り上げを計上する。協力企業も売上高が増えるほか、手数料を利益計上できるメリットがある。
自民国政協:収支書に西松本社住所 OB団体献金隠れみの 02/25/09 (毎日新聞)
準大手ゼネコン「西松建設」(東京都港区)がOBの政治団体「新政治問題研究会」(新政研、解散)を隠れみのに違法な企業献金をしたとされる疑惑で、自民党の政治資金団体・国民政治協会が新政研から献金を受けた際、政治資金収支報告書に新政研の住所として西松建設の住所を記していたことが分かった。また、宮下創平元厚相の政治団体は同様に記した上、新政研の代表者欄に西松の現職役員名を記入。献金を受け取った側も新政研が西松建設のダミーと認識していた可能性が浮上した。【杉本修作】
政治資金規正法では違法な企業献金と認識していた場合、受領した政治家側も罰せられる。ただし、政治資金団体への企業献金自体は認められている。
政治資金収支報告書によると、国民政治協会は03年12月、新政研から約500万円の献金を受けた。新政研の所在地は千代田区のマンションだったが、協会は西松本社所在地の港区虎ノ門と記していた。その後、協会は記載を修正したが、「誤った原因は担当者が代わり分からない」と述べるにとどまり、新政研と西松との関係については「知らなかった」と釈明した。
また、02年に計200万円を受けた宮下元厚相の政治団体「創風会」は、新政研の所在地を同様に港区虎ノ門と記入。代表者の欄には西松OBの本来の代表者ではなく、当時の西松現職役員名を記していた。創風会の代理として対応した元厚相の長男の宮下一郎衆院議員(長野5区)事務所は「なぜ間違えたか分からない」としている。
新政研と「未来産業研究会」の二つの政治団体は、西松前社長の国沢幹雄被告(70)=外為法違反で起訴=の指示で95年と98年に同社OBが設立。06年の解散までに、小沢一郎民主党代表や森喜朗元首相らの政治団体に計約4億7800万円を献金していた。
新政研などでは、西松の一部社員から会費を集めた後、会社側が賞与に上乗せして補てんしていたとされ、献金は事実上、違法な企業献金だった疑いが持たれている。
大光:大分県警OB、裏金?運び役に 02/21/09 (毎日新聞)
キヤノンの施設建設を巡るコンサルタント会社「大光」(大分市)の脱税事件で逮捕されたグループの警備会社「デューク」(大分市)元社員、川端智幸容疑者(65)=元大分県警警部補=が、大阪市のコンサルタント会社社長、難波英雄容疑者(61)を大光社長、大賀規久容疑者(65)に紹介していたことが分かった。大賀容疑者の指示で裏金とみられる現金の運び役も務めており、東京地検特捜部は脱税工作への関与について追及している。
大光関係者によると、川端容疑者は難波容疑者と4、5年前に知り合い、大賀容疑者から「工事屋を紹介してくれ」と言われ、難波容疑者を紹介した。その後、難波容疑者は大光グループに架空領収書を提供するなど大賀容疑者の脱税工作に協力したとされる。
また、川端容疑者は、大賀容疑者の指示で現金入りのカバンを業者や関連会社など関係先に届けていたという。川端容疑者は調べに対し「大賀社長から『パーティー券を届けて』と言われ、(カバンを)運んでいた。最近まで、中身が現金とは知らなかった」と供述しているという。特捜部は、大賀容疑者らが隠した所得の一部だったとみて調べている模様だ。
一方、特捜部は20日、法人税法違反容疑で逮捕した計13人のうち、元大分県議会議長で元大光取締役、長田助勝容疑者(80)ら3人を処分保留で釈放した。脱税工作への関与は従属的とみられ、起訴猶予になる見通し。
かんぽの宿売却前に多額設備費 TVや冷凍庫3.5億円 02/18/09 (読売新聞)
宿泊・保養施設「かんぽの宿」の売却契約が進んでいた08年10月末から12月下旬にかけて、日本郵政が地上デジタル放送に対応した液晶テレビや超低温冷凍庫など計3億5千万円分を購入していたことが分かった。売却が最終局面を迎えた最中に多額の設備費を投じる必要があったのか、議論を呼びそうだ。
18日の衆院予算委員会で、公明党の大口善徳衆院議員が質問し、日本郵政の高木祥吉副社長が事実関係を認めた。
日本郵政によると、08年10月31日に液晶テレビ(20~46インチ)3447台などを約3億3838万円で購入。12月19日に超低温冷凍庫35台を約1047万円で買った。いずれも一般競争入札だった。
液晶テレビは11年7月に予定される地デジへの完全移行に向けた購入で、施設63カ所に納品。超低温冷凍庫は飲食部門の直営化を進める過程で食材を保存する必要があり、35カ所に納品した。
日本郵政は当時、選考過程に残っていたオリックス不動産とホテルマネージメントインターナショナル、住友不動産(後に辞退)の3社に備品購入を伝え、「売却価格に反映された」としている。ただ、鳩山総務相は「国民も懸念するだろう。すべての点が不透明なので解明しなければならない」と答弁。高木副社長も「専門家による第三者委員会で検討したい」と述べた。
防耐火材偽装:ミサワ子会社、住宅ドア2種で耐火性能を偽装 02/18/09 (毎日新聞)
防耐火材の性能偽装問題で、国土交通省は17日、大手住宅メーカー「ミサワホーム」(東京都新宿区)の子会社「ミサワテクノ」(長野県松本市)が、認定製品より性能の劣る住宅用ドア2種を製造・販売していたと発表した。東京や大阪などの94棟に使用されており、両社が安全性を確認している。問題のドアは01年3月に国交相に認定された。工場生産の際、当時の開発担当者が表面材の厚さ5ミリを0・8ミリ薄くするなどした。
サッシ耐火偽装、新たに3社7製品も…国交省が改修指示 02/17/09 (読売新聞)
サッシメーカーなどによる耐火性能の偽装問題で、国土交通省は17日、新たにミサワテクノ(長野県)、三協立山アルミ(富山県)、トクヤマ(山口県)の防耐火用建材7製品が、国交相認定とは異なる仕様で製造されていたと発表した。
これらの製品は戸建て住宅やホテルなど計108棟で使用されているが、防耐火性能が認定基準を満たしていない可能性が高いという。同省は「火災時の逃げ遅れなど重大な結果を招きかねない」として各社に改修などを指示した。
発表などによると、ミサワテクノの2製品は住宅用防火ドア。親会社のミサワホーム(東京都)が2001年8月~今年1月、東京、神奈川などの計94棟で358個を使用したが、製造過程で燃焼を抑える表面材を薄くするなどしていた。
三協立山アルミの防火用樹脂サッシ4製品は02年6月~06年8月、ホテルやマンションなど計14棟に595個を販売。火災時に窓枠などのすき間をふさぐ加熱膨張剤の量を減らしたり窓枠を補強する鋼板を薄くしたりしていた。
トクヤマの1製品は内壁などに使う不燃板で、表面材の材質を一部変えていた。しかし、不燃材としての使用実績は現在確認されていないという。各社は意図的な偽装を否定し、「商品開発担当者が軽微な変更は問題ないと安易に考えた」(三協立山アルミ)などとしている。
相談は、住宅リフォーム・紛争処理支援センター(03・3556・5147)などで受ける。
漢検協の委託広告会社「従業員ほとんどいない」と理事長 02/16/09 (読売新聞)
巨額の利益を上げていることが問題となっている財団法人「日本漢字能力検定協会」(京都市下京区)が広報業務などを委託していた広告会社「メディアボックス」(同市西京区)について、同社の代表も務める大久保昇・協会理事長が「従業員はほとんどいない」と、協会の評議員に説明していたことがわかった。
複数の関係者は、同社の業務は協会の職員が行っていたと証言。
委託費は3年間で7億6000万円にのぼり、文部科学省は、同社が会社としての実体がないのに、委託費の一部を利益として得るシステムになっていた可能性があるとみて解明を進める。
協会は問題発覚後に開かれた今月6日の理事・評議員会で、同社の存在を初めて明らかにし、2006年4月~08年12月までに計約7億6000万円で同社に広報・広告業務を委託していたと説明。同社の実態に関する質問に、大久保理事長は「従業員はかつてはいたが、今はほとんどいない」と回答したという。
協会関係者によると、広告制作などの実務は、メディアボックスが広告会社などに下請けに出す形になっていた。しかし、関係者は、協会が委託したとする広報に関する企画や、広告会社などとの交渉などの業務は、実際は協会職員が行っていたと証言。協会は、同社が広告会社などに支払う金額に数十%上乗せして、同社に支払っていたといい、その差額が同社の利益になっていたという。
広告会社の関係者らによると、打ち合わせは協会職員と行い、協会の担当者から「見積書や請求書は、メディアボックスあてに」と頼まれたこともあるという。
政界・国税・警察…大賀容疑者、口利きビジネスに人脈作り 02/14/09 (読売新聞)
キヤノンの工場建設を巡る法人税法違反(脱税)事件で、逮捕された大分市のコンサルタント会社「大光」社長・大賀規久容疑者(65)は、口利きビジネスを展開するために、地方政界や国税、警察にも交友を広げていた。
事件では、キヤノンの御手洗冨士夫会長(73)との親密な間柄をテコに大手ゼネコン鹿島などからリベートを受け取っていたとみられるが、虚実ない交ぜになった人脈を相手によって使い分け、誇示していたという。
「キヤノンの工場建設に絡む事業を請け負う会社を作りたい」。2002年に徳島県知事に対する贈賄容疑などで逮捕され、有罪が確定したコンサルタント会社「業際都市開発研究所」の尾崎光郎元代表(63)は1990年の「大光」設立時、大賀容疑者にこう誘われて出資に応じた。2人はこの数年前からの知り合いだった。公共工事の口利きビジネスでは手を組む関係にあった。
大賀容疑者の地元関係者によると、同容疑者の公共工事への口利きは「30年以上前から知られていた」といい、政治家とのパイプ作りにもいそしんでいた。大分県の広瀬勝貞知事は記者会見などで、大賀容疑者について「選挙でお世話になったり、キヤノンのことを教えてもらったりした」と話している。
大光の設立後数年で、尾崎元代表は大賀容疑者とたもとを分かつ。元代表の説明によると、大賀容疑者が元代表の名前を勝手に使って業者から数百万円の口利き料を集めたことがわかったためだという。
大賀容疑者が、政治家とともに人脈作りに力を注いだのは国税と警察だった。
大光グループの建設関連会社「ライトブラック」(大分市)と内装工事会社「匠(たくみ)」(東京都千代田区)の監査役には、大分県を管轄する熊本国税局長を92年まで務めた税理士が就任していた。退職後も「ノンキャリアのドン」と呼ばれた大物。大賀容疑者は知り合いの業者に「税務署が入った時のために、おれの名刺を金庫に張っておけばいい」と吹聴することもあったという。
元国税局長は「現役時代も含め何度か食事をしたことはある。匠には出資して監査役にも入ったが、ライトブラックは勝手に名前を使われた」と話した。
警察人脈のキーマンは、80年代に大分県警本部長を務めたキャリア官僚。元本部長が退職後に東京・永田町に警備会社を設立するとフロアの一部を間借りし、匠などの事務所を置いた。元本部長は約10年前に死去したが、現在も賃貸関係は続いている。
大賀容疑者は周囲に、元本部長以外にも複数の警察OBの名前を挙げ、「親しくしている」と言うことがあったという。しかし、名指しされたOBらは「御手洗さんとゴルフをした時に、顔を見たことがあるぐらい」「1回会っただけ。どんな人だったのか覚えていない」と一様に親密ぶりを否定している。
文部科学省によるチェック体制が甘かったと言える。文科省にチェックするだけの能力と
人材がいるのかも疑問だ?天下り問題が注目を浴びているが、天下りする公務員の多くが名誉職だけで
漢字検定協会のように問題をあっても、仕事をしていない場合、問題が解決されないし、知識や経験がない
ために効率よく税金が使われてない場合も多いと思う。
「協会は大久保昇理事長と長男の大久保浩副理事長のほか6人の理事が運営。評議員はそれをチェックする立場だったが、
ほとんどは学者や教育者で、年2回の評議員会では、理事長らの説明を追認するだけだったという。」
知名度や何かで有名と言うだけではチェック機能は働かない。そしてこれは多くの組織でも言えると思う。
今回は、文部科学省と漢字検定協会との間に癒着や親密な関係がなく、単に文部科学省の指導力不足だけのようだが、
文部科学省OBなどが入れば調査自体を甘くしたり、形だけの調査で結論に至る可能性もある。
財団法人「日本漢字能力検定協会」は解散して、必要とあれば新しい組織で立ち上げるべきだろう。
漢字検定協会:評議員ノーチェック、経営は理事長親子任せ 02/12/09 (読売新聞)
財団法人「日本漢字能力検定協会」(京都市下京区)の公益事業としては過大な利益が問題になっているが、複数の評議員が毎日新聞の取材に「名前も知らない関連会社に多額の宣伝費を払っていたとは知らなかった」「経営が分かるのは理事長親子だけ」などと語った。評議員13人のうち11人は漢字・国語・文章の専門家で「漢字は分かるが数字はさっぱり」と言う人も。トップに任せきりの運営状況が明らかになった。
協会関係者によると、協会は大久保昇理事長と長男の大久保浩副理事長のほか6人の理事が運営。評議員はそれをチェックする立場だったが、ほとんどは学者や教育者で、年2回の評議員会では、理事長らの説明を追認するだけだったという。
評議員の一人は「理事長は有名人好きで、理事や評議員は名誉職も多い。定例会では理事長と副理事長の説明を黙って聞いていることが多かった」と話す。別の評議員は、協会が03年に約6億7000万円で邸宅を購入したと報告された際に「もっと他のことに使えばいいのに」と思ったが、意見は控えたという。
問題発覚後の今月6日、定例会に出た評議員は、協会が3年間で約7億6000万円の業務委託費を払っていたとされる理事長が代表の広告会社「メディアボックス」について「金額どころか、名前を聞いたのも初めて」と証言。「評議会も理事会も経営のことは分からない人ばかり。このメンバーにチェック機能を求めるのは元々無理」と言い切った。
文部科学省は、協会がチェック機能不全に陥っていた可能性があるとみている。【木下武、広瀬登、藤田文亮】
漢検協会、計43億円の巨額積立 02/10/09 (大分合同新聞)
公益法人では認められない多額の利益を上げていたとして、文部科学省の立ち入り検査を受けた「財団法人日本漢字能力検定協会」が、新事業開発資金や建設資金など将来の支出に備える引当金名目で、2007年度に約5億4000万円を繰り入れていたことが10日、同省の調査で分かった。
これら引き当て資産の積立額は06年度の約38億円から5億円増えて約43億円に膨らみ、文科省は「公益事業への還元など具体的な目的が明確でない」とし、協会に説明を求めている。
文科省などによると、協会は07年度に約72億円の収入があったが、新事業開発資金に3億6000万円、建設資金に1億2000万円など引き当て資産4項目に計約5億4000万円を繰り入れていた。
また協会が「資料館にする」として03年7月に購入した京都市内の土地建物が、事前に協会理事会で購入の承認を得た物件とは異なることも判明。協会は「(金額などが)同程度の物件なら、変更も含め事務局に一任することになっていた」と文科省に報告しているという。
個人的には出来るだけキャノン製品を購入してきたが、キャノンに批判的な記事を書いた新聞社に対する報復や
今回の事件を考えると、今後はいろいろな点で考えるべきだと思う。企業体質に問題があれば将来に問題として
現れる可能性もある。キャノン製品を選んで購入してきただけに残念だ。
「鹿島に発注を」造成工事でキヤノン、大分県に要請文送る 02/12/09 (読売新聞)
キヤノンの工場建設を巡る法人税法違反事件で、脱税の舞台となった大分市の2事業所の用地造成工事について、キヤノンが事業主体の大分県土地開発公社に対し、鹿島への発注を求める「要請文」を送っていたことがわかった。
工事は要請通り、計約80億円の随意契約で鹿島が請け負っていた。鹿島はこの工事でも、東京地検特捜部に逮捕された大分市のコンサルタント会社「大光」社長・大賀規久容疑者(65)側にリベートを提供したとみられ、大賀容疑者の口利きを背景に「鹿島ありき」で業者選定が進んだことがうかがえる。
同公社はデジタルカメラ工場の用地造成を2003年12月に約31億6700万円で、プリンターカートリッジ工場の用地造成を05年7月に約48億1300万円で、鹿島に発注したが、キヤノンは契約のそれぞれ約10~20日前に総務本部長の常務名の要請文を公社理事長あてに送付していた。
いずれの文書でも、造成から建物建設までの期間が短いとしたうえで、「安全性や価格競争の面で群を抜き、必ずや弊社の期待する迅速な事業が実施される」などと鹿島を称賛。「鹿島を選定していただくよう、特段のご配慮をお願い申し上げます」と推薦していた。
公社の内規では250万円を超える工事は原則的に入札を行うことになっていたが、公社も「緊急性を要する」として要請を受け入れ、ほかの大手ゼネコンから見積もりをとることもなく、鹿島との随意契約に踏み切っていた。
緊急性を理由とした随意契約は台風などの災害時以外には適用例がなく、契約当事者以外の企業の意向に沿って発注先を決定するのも極めて異例。同公社の久保隆専務理事は「キヤノン誘致が前提の工事なので、意向を打診したが、あくまでも公社が主体となって鹿島を選定した」と話しているが、選定経緯を示す記録は残っていないという。
同公社は、キヤノンが07年11月に進出を表明した同県日田市のプリンター関連工場の用地造成工事についても、当初、鹿島に随意契約で発注する意向を示していた。しかし同年12月、鹿島が2事業所に絡んで東京国税局から約6億円の所得隠しを指摘されたことが発覚し、指名競争入札に切り替えられた。
キヤノン広報部は「公社側から鹿島と随意契約して構わないか意向確認したいと言われ、書面を出した」と説明している。
◆逮捕元県議長、公社理事時代に鹿島から50万円◆
大分市のキヤノン関連2事業所進出を巡っては、脱税事件で逮捕された元大分県議会議長の長田助勝容疑者(80)が、鹿島に用地造成工事を発注した県土地開発公社理事時代の2005~06年頃、鹿島側から計50万円を受け取っていたことがわかった。
長田容疑者は「大光」グループのコンサルタント会社「ライトブラック」(大分市)の監査役に就く一方、07年4月まで7期県議を務めたが、50万円は政治資金収支報告書にも記載していなかった。
長田容疑者が公社理事をしていたのは00~07年。取材に対し、長田容疑者は鹿島の支店幹部から2回にわたって現金を受け取ったことを認め、「年末だったのでお歳暮のつもりだった。多忙で収支報告書への記載を忘れた」と釈明、「鹿島に受注の便宜は図っておらず、謝礼ではない」と話した。
一方、2事業所のうちプリンターカートリッジ工場については、大分県が実際にかかった費用よりも安い価格でキヤノンに用地を売却したとして、市民オンブズマンが広瀬勝貞知事を相手取って、差額18億円の返還を求める訴訟を大分地裁に起こしている。
同県などによると、県は当初、工場用地(37・1ヘクタール)の取得・造成費を61億円と見積もりながら、キヤノンとは50億円で譲渡する契約を締結。実際には市道移設が必要だったことなどから約68億円かかったが、差額の約18億円をキヤノンに求めず、補助金を公社に支出して穴埋めした。
広瀬知事は「誘致競争が激しくなるなか、リスクを負うことも必要。工場稼働後の税収増などで取り戻せると判断した」と説明するが、オンブズマン側は「キヤノンと価格交渉を行わなかったのは、知事の裁量権を逸脱している」と主張している。
「指点字」研究費2億超詐取か…人件費水増し、独立法人から 02/10/09 (読売新聞)
両手の指を点字に見立てて言葉を伝える「指点字」の変換装置の研究を、総務省所管の独立行政法人「情報通信研究機構」(東京都小金井市)から受託した千葉県内の情報関連会社の男性社長(50)が、架空の研究員の人件費を申請して委託研究費1億4000万円を不正受給したとして、警視庁は10日、この社長を詐欺容疑で逮捕する。
社長は、同じ手口で同機構から総額2億8000万円を詐取した疑いがあり、同庁で裏付けを進める。
捜査関係者によると、社長は2006年度、指点字の変換装置の研究を同機構から受託した際、研究員約20人を雇って給与を支払ったと偽り、委託研究費1億4000万円をだまし取った疑いが持たれている。同様の名目で翌年度も同額を受け取っていた。
指点字は、重ねた指の動きで視覚障害者らが意思を伝え合う手段。社長は指の動きを文字に変換する装置の開発名目で研究費を申請し、開発研究を行っていたが、研究員はほとんど雇っていなかったという。架空給与の偽装は、同機構のチェックで08年2月に発覚。同機構は全額返還を求めたが、社長は応じていないという。同機構は、情報通信分野で優れた民間の研究に委託研究費を助成している。
大分キヤノン工事脱税疑惑:鹿島社員、裏金提供認める 02/09/09 (毎日新聞)
キヤノンの工事を巡るコンサルタント会社「大光」(大分市)の大賀規久社長(65)らによる脱税疑惑で、工事を受注した大手ゼネコン「鹿島」の担当社員が東京地検特捜部の調べに「大賀社長から裏金を要求され断り切れず渡した」と供述していることが鹿島関係者への取材で分かった。金融ブローカーが大賀社長側に架空の領収書を渡し脱税工作に協力していたことも判明。特捜部は近く大賀社長ら10人前後を法人税法違反容疑で取り調べる方針を固めた模様だ。
鹿島関係者によると、裏金の提供を認めているのは、大分市のデジタルカメラ生産子会社「大分キヤノン」造成・建設工事(受注額約220億円)や隣接するプリンター関連生産子会社「大分キヤノンマテリアル」造成・建設工事(同約278億円)を担当した現地の工事担当者ら。
担当者らは1月20日ごろから始まった任意の事情聴取に対し、「領収書のいらない金(裏金)を大賀社長に要求され断れなかった。工事を受注できたので成功報酬として事後的に渡した」などと総額約5億円に上る資金提供を認めているという。
捜査関係者によると、新たに関与が判明したのは金融ブローカーら。金融ブローカーらは、大賀社長や大賀社長の腹心とされる大阪市のコンサルタント会社社長(61)の要求に応じ、金額を水増ししたり、架空の領収書を発行。大賀社長らはこの領収書を基に架空経費を計上、所得を大幅に圧縮して税務申告した疑いがあるという。
大賀社長には、川崎市幸区のキヤノン矢向(やこう)事業所の電気関連工事を鹿島の下請けとして受注した電気設備工事大手「九電工」も約2億円の裏金を提供していた実態が既に判明。大光や建設関連会社「匠(たくみ)」(東京都千代田区)、同「ライトブラック」(大分市)の大光グループ計3社は、7億円超の裏金については税務申告しておらず、総額約30億円の申告漏れが分かっている。
文科省は財団法人「日本漢字能力検定協会」に対して
A HREF="http://100.yahoo.co.jp/detail/%E8%B2%A1%E5%9B%A3%E6%B3%95%E4%BA%BA/" target="_blank">財団法人 (Yahoo!百科事典)
の許可を取り消して解散にすればよい。公益事業では認められない多額の利益を上げていた問題と
「1999~2007年度、指導監督基準に違反しているとして、文部科学省から延べ13件の指導を受けていた」事実は許される
べきでない。
文科省が漢検協に指導、9年で13件…検定料値下げなど 02/08/09 (読売新聞)
財団法人「日本漢字能力検定協会」(京都市下京区)が公益事業では認められない多額の利益を上げていた問題で、同協会は1999~2007年度、指導監督基準に違反しているとして、文部科学省から延べ13件の指導を受けていたことがわかった。
基準に違反したままの点もあり、同省は9日の立ち入り検査で改善状況を詳しく調べる。
同協会が6日の理事・評議員会で提出した報告書や、同省の検査結果などによると、検定料の値下げについての指導は99~07年度で4回あった。同協会は07年度から1級を6000円から5000円に値下げするなどした。
また、同省は04、05年度、大久保昇理事長が代表取締役の出版会社「オーク」(京都市西京区)との取引についても「適正でない」と2回にわたって指導。05年度には、同協会が本部ビルを同社から年間1億8000万円で借り受けていることは、指導基準に反する恐れがあるとして改善を求めたが、同協会は「事業運営の質的向上に貢献している」などと説明したという。
一方、公益法人は、基本財産や固定資産などの台帳を作成し、公認会計士による監査を受けることなどが定められているが、07年度の検査で、同協会が行っていなかったことがわかり、同省は改善指導していた。
「漢検協会」立ち入り検査へ、カネの流れなど調査…文科省 02/06/09(読売新聞)
財団法人「日本漢字能力検定協会」(京都市下京区、大久保昇理事長)が公益事業では認められない多額の利益を上げるなどしていた問題で、文部科学省は9日午後から同協会に立ち入り検査に入る方針を決めた。
同協会は、利益を上げることが認められていない検定事業などで過去5年間に約20億円の利益を得ていたほか、南禅寺(同市左京区)近くの住宅地に土地と建物を約6億7000万円で購入していた。
また、大久保理事長が代表を務める広告会社「メディアボックス」(同市西京区)に、広報費など年2億~3億円の業務委託費を払い、文科省に報告しなかった。同省は、多額の利益や不動産取引が公益法人としての事業内容に抵触する可能性があるとみており、協会の財務状況や不透明なカネの流れについて調べる。
旧東京三菱銀の元副頭取、地上げ資金融資に介在か 01/28/09(読売新聞)
東京・渋谷の再開発をめぐる不動産会社「カーロ・ファクトリー」(東京都港区、現テールトゥシエル)の脱税事件で、2003年ごろ、東京三菱銀行(現三菱東京UFJ銀行)の当時の副頭取がカーロ社の元社長(48)からの依頼を受け、共同開発にあたった住宅販売会社(武蔵野市)への融資を担当支社に働きかけていたことがわかった。
元社長は複数の民事訴訟で「暴力団幹部と近い」と認定されており、同銀行は融資の経緯に問題がなかったかどうか調査している。
東京地検特捜部と東京国税局は27日、元社長らの法人税法違反容疑でカーロ社の関係先を捜索した。
脱税疑惑の舞台になった渋谷区南平台町の土地は登記簿上は、住宅販売会社が03年~06年に取得し、大手不動産会社に転売した形になっている。
しかし、複数の関係者によると、住宅販売会社は銀行からの融資の受け皿として元社長に共同開発を持ちかけられたもので、実際の地上げや転売の交渉はカーロ社が担当していた。土地の転売益百数十億円の分配が問題になった際にも、元社長は住宅販売会社に「そちらは名義だけだ」と言い張って、6割近くを自分の取り分にしていたという。
東京三菱銀行はこの開発への融資に中心的に関与。住宅販売会社への総額約216億円の融資は、3銀行とノンバンク2社がシンジケート団を組んで実行、うち同銀行グループが九十数億円を占めている。融資は住宅販売会社からカーロ社に流れて地上げ用資金に使われたが、元社長と組んで地上げにあたった不動産業者は「驚くほど資金が潤沢だった。東京三菱の融資がなければ、地上げは成功しなかった」と話している。
同銀行の融資は、カーロ社元社長が当時の副頭取に依頼した。元副頭取が担当支社に融資話をつないだほか、同銀行では、地上げの対象だったビルを持つ外資系システム開発会社の幹部も、カーロ社に紹介していた。元社長は共通の知人だった相撲部屋の親方から元副頭取に引き合わされたといい、「頻繁に食事をする仲だ」などと吹聴していた。
元社長は過去の地上げで暴力団関係者と協力したこともあったほか、関与した取引を巡る複数の民事訴訟の判決で、「暴力団幹部と近い」と認定されている。このため、三菱東京UFJ銀行では住宅販売会社への融資が、反社会的勢力への便宜供与にあたらないかどうか調べている。
現在は系列証券会社会長に就いている元副頭取は読売新聞の取材に、「担当支社に『(元社長の)話を聞いてやれ』とは言った」として働きかけを認めたものの、「どういう素性か調べるように指示したが、関係機関から反社会的勢力との指摘はなかった」としている。
税理士ら59億円提供 生保不正契約の代理店に 01/18/09(朝日新聞)
企業向け保険で大規模に不正契約を結んでいたアクサ生命保険などの販売代理店グループ側に、少なくとも13人の税理士や公認会計士が計59億円を貸し付けたり出資したりしていたことが分かった。このうち10人は、医療機関向けにコンサルティング活動をする税理士らが作った任意団体の会員だった。複数の税理士らが利殖目当ての資金提供だったと認めたが、不正契約については「知らなかった」としている。
この問題では、日本税理士会連合会の前会長(78)が妻ら親族とともに販売代理店の一社の役員に就任。代理店を率いて不正契約を主導した金融会社「信和総合リース」(東京都千代田区、08年12月に破産)側に、金利12%で5億5千万円を貸し付けていたことが判明している。前会長を含む13人から提供された資金は、同社の傘下にあった代理店グループが、中小企業などの名義を借りて結んだ不正契約の保険料立て替えなどに使われたとされ、結果的に資金面で信和側を支えていたことになる。
朝日新聞が入手した信和総合リースの破産手続きの関係資料によると、同社には13人の税理士や会計士が5千万~23億4千万円を提供していた。同社の資産を査定した事業再生コンサルタント会社によれば、貸し付けのほか、税理士らの顧問先企業などからの「運用委託」名目だった。4.5~15.5%の利息や分配金を受け取る契約だったとみられるが、創業者だった元社長の死亡(昨年10月)や破産で回収は難しいという。
1人で23億4千万円を提供したとされる首都圏の公認会計士は「元社長から手数料を上乗せして返すと言われた。『別の会計士にも助けてもらっている』と言われたので信用した」と話す。この会計士に元社長を紹介されたという通信販売会社の創業者も、関係会社名義などで計54億円を貸し付けていたとされるが、「すべて会計士に任せていた」と言っている。
一方、信和側に資金提供をしていた税理士や会計士ら13人のうち10人は、医療機関向けのコンサルティング活動を目的に作られた任意団体の会員だったことも分かった。
この団体は、信和との間で02年4月~08年8月に保険にかかわる業務委託契約を結ぶなどしていたが、代表をしている税理士は「団体として会員と元社長を仲介したことはない。元社長は、団体の会合などで知り合った税理士らに個別に資金提供を頼んでいたようだ」と話している。(富田祥広)
企業向け生保不正1万件 アクサ代理店、100億円利益 01/16/09(朝日新聞)
仏保険大手アクサグループのアクサ生命保険や三井住友海上火災保険グループの生保を相手に、企業向けの不正な保険契約が大規模に結ばれていたことがわかった。生保から払われる多額の販売手数料を目当てに、代理店が企業の名義を借りて契約を結び、一時的に保険料を立て替えたうえで早期に解約していた。不正契約数は1万件超、代理店側が得た手数料は100億円規模になる。
保険料の立て替えといった特別の利益を契約者に与えることは、契約の公平性や不正防止の観点から保険業法で禁止されている。1万件を超す不正契約は過去最大規模で、金融庁も調査を始めた。
アクサ生命や三井住友海上きらめき生命などによると、不正契約をしていたのは08年12月に倒産した金融会社「信和総合リース」(東京都千代田区)の複数のグループ代理店。関係者によると、代理店は中小企業経営者らに「保険料を立て替える」などと持ちかけて高額な保険契約を結び、販売手数料を得ていた。契約が増えるほど手数料は上乗せして支払われる仕組みだった。中小企業に代わって契約を管理し、3年前後で早期解約、解約返戻金も手にしていた。こうして得た資金を別の契約の保険料に回し、契約数を急速に伸ばしていった。
名義を貸した中小企業の中には、「謝礼」として信和側から数十万円程度を受け取っていたケースがある。保険料を立て替えてもらっているのに自社の資金で払ったことにして損金処理し、税金を不正に少なくする手法も採られていたという。
信和側は全国の複数の税理士と提携。顧問先の中小企業を紹介してもらい、契約が成立すると税理士に紹介料を払っていた。関係者は「税理士も不正契約を知りうる立場だった」と指摘している。
信和関連の契約は02年ごろから結ばれ始めた。契約数はきらめき生命が人数ベースで2千件、払った手数料は19億円。アクサ生命は「調査中」としているが1万件、100億円近くに達する模様だ。アクサ生命は一般企業の売上高に相当する保険料等収入が、08年3月期で6645億円ある準大手。「不正契約による手数料などの損害は小さくないが、経営への直接的な影響はない」としている。
きらめき生命は、信和グループを通じた契約の99%が早期解約されたことから、07年に不正に気づいた。信和側に渡った販売手数料と解約返戻金の合計から保険料を差し引いた、約3億6千万円の返還を要求。信和側が半額を返金することで08年3月に和解した。アクサ生命は、信和グループの綱渡りのような資金繰りが08年夏に行き詰まり、保険料の支払いが滞り始めてから、不正に気づいたという。
アクサ生命は「不正に積極的に関与していた」として部長級社員1人を08年11月に懲戒解雇、上司の執行役員2人も責任をとって12月に退任したとしている。解雇された元社員は取材に対し「信和関連の契約数を増やすことは、所属部署の営業成績を伸ばすために役員ら上司の指示で行った」と証言している。
ほかにもアクサグループのアクサフィナンシャル生命や日本生命など10社以上の保険会社が、信和側と販売契約を結んでいた。金融庁の指示で、各社は不正契約がなかったかどうか調べている。(多田敏男、鯨岡仁)
「癌研」13億4000万円の粉飾決算 01/16/09(読売新聞)
国内屈指のがん専門病院を運営する財団法人「癌(がん)研究会」(東京都江東区)の安西邦夫理事長(東京ガス相談役)は16日、記者会見を開き、財団が2007年度の決算報告書で、収入を水増しするなどして約13億4000万円の粉飾決算を行っていたと発表した。
財団は医師や職員の賞与を支払うため、半年ごとに銀行から約10億円のつなぎ融資を受けていたが、前事務局長(65)が「赤字が大きいと貸してくれない」と虚偽の決算を作成したという。
安西理事長らによると、決算の粉飾は前事務局長が前常務理事(69)の承認を得た上で、財務部などの職員に指示して行われた。財団が経営する「癌研有明病院」(同)の07年度の財務について、架空の医療費の収入伝票などを作成して約8億9000万円を水増しする一方、業者に支払った薬代のうち、約4億5000万円分を帳簿から除外した。その結果、実際は約15億円の赤字だったのに、1億数千万円程度の赤字に見せかけていた。
財団は16日、07年度決算を修正する報告書を文部科学、厚生労働両省に提出した。
同病院は05年3月、東京・西巣鴨から江東区有明に移転した際、用地購入費などとして金融機関から約317億円を借り入れた。しかし、西巣鴨の土地が計画より22億円安い値段で売却せざるをえなくなったほか、薬剤費の高騰などが重なり、資金繰りの厳しい状況が続いていた。
そうした中、年2回の賞与の際には各約10億円を銀行から一時的に借り入れ、半年ごとに返済してきたという。前事務局長は財団の調査に対し、「計画通りに収支が改善しないと、銀行との関係が悪化し、貸してくれないと思った」と説明した。
粉飾を承認していた前常務理事は昨年6月に退任。後任の常務理事が気づき、両省に報告していた。財団は今後、公認会計士らを入れた調査委員会を設け、再発防止策を作る。安西理事長は会見で「全く予期していなかった。(前事務局長と前常務理事は)責任感が強いタイプだったが、やってはいけないことをしてしまった。責任を感じている」と謝罪した。
両省は財団が自発的に調査・報告した経緯を酌み、処分は行わない方針。文科省の担当者は「あまりにもお粗末。調査委員会の調査を見守りたい」としている。
サッシ耐火偽装、前社長が隠ぺい黙認…国交省「極めて悪質」 01/09/09(読売新聞)
サッシメーカー「エクセルシャノン」(東京都)などが戸建て住宅やマンションに使われる防火用樹脂サッシの耐火性能を偽装していた問題で、同社では2007年12月の時点で当時の社長が開発部門から偽装の報告を受けながら、隠ぺいを黙認していたことが、同社の内部調査でわかった。
08年4月に交代した現在の社長も同様の報告を受けたまま放置し、組織ぐるみの隠ぺいが続いていた。国土交通省では「法令順守の意識が欠け、極めて悪質」と批判している。
内部調査によると、同社の開発部門は、大手建材メーカー「ニチアス」(同)の耐火性能偽装問題が07年10月に発覚した後、国交省から不正の有無の報告を求められると、「偽装を報告すれば、サッシの窓枠全体の取り換えなど大規模な改修を迫られる」などと判断。当時の社長に対し、これまでの偽装の事実を打ち明け、調査をしないまま国交省に「偽装なし」と虚偽報告することの了承を得ていた。現在の中村辰美社長も08年4月の就任の際、偽装や虚偽報告の事実を告げられたが、改修用のサッシの開発を優先し、隠ぺいの継続を容認していたという。
しかし、同年9月の同社の取締役会で、社外取締役として出席した親会社の「トクヤマ」(山口県)専務が、サッシの製造過程に不審点を指摘したことをきっかけにトクヤマ側にも偽装の事実が伝わり、同12月26日、エクセルシャノンはようやく国交省に偽装を報告していた。同社は今回、大臣認定の不正取得が判明したサッシ27種すべての開発に関与している。
同社とともに大臣認定を不正取得していた「新日軽」(東京都)や「三協立山アルミ」(富山県)も、ニチアスの問題発覚後、国交省に同様に虚偽報告をしていた。両社は、開発部門の判断で経営陣の関与はないとしているが、同省はさらに経緯を調べるよう指示した。
国家試験で集団替え玉 建築施工管理技士 斡旋のスクール代表ら逮捕 12/02/08(産経新聞)
国土交通省が所管する国家資格「建築施工管理技士」を取得するための「1・2級建築施工管理技術検定試験」の大阪会場で、申請者とは別の人物が不正に試験を受ける“替え玉”受験が集団で行われていたことが6日、わかった。
替え玉は過去3年間で10人前後が発覚し、大阪市内の資格スクールがブローカーとして関与していたことも判明。国交省からの刑事告発を受けた大阪府警捜査2課は、スクールの代表ら数人を有印私文書偽造・同行使などの疑いで逮捕し、替え玉受験の実態解明を進めている。
今年は1級試験が全国10会場、2級試験が13会場で実施されており、国交省は大阪以外でも不正が行われていた可能性もあるとみて調査を始めた。
逮捕されたのは、資格スクール「建設業技術協会」(大阪市中央区)代表、足立憲治容疑者(52)ら数人。
調べや関係者によると、足立容疑者は今年の1・2級試験で、同スクールの受講生数人の受検申請書に、別の男の証明写真を張るなどして偽造し、別の男に受験させた疑いが持たれている。足立容疑者らは1件につき数十万円の報酬を得ていたという。
替え玉受験が最初に見つかったのは、6~7月に申し込みのあった2級試験。国交省の指定試験機関「建設業振興基金」(東京)が7~8月、大阪府内の建設会社の従業員の申込書を審査した際、書類には30歳すぎと記載されていたが、添付写真の人物が60歳前後にしか見えなかったことから疑惑が浮上した。
同基金が同じ会社の別の従業員の申請書も調べた結果、1級試験と2級試験で氏名が異なるにもかかわらず、顔写真が同じケースも見つかった。この会社は同基金からの問い合わせに、「写真を張り間違えた」などとあいまいな説明に終始したため、国交省が11月、刑事告発に踏み切った。
同基金のその後の調査で、大阪会場で受験した建設会社4~5社の計10人前後が替え玉受験をしていたことも判明。さらに府警の捜査で、こうした受験者の大半が足立容疑者の経営するスクールに通っており、足立容疑者がブローカーとして替え玉受験を斡旋(あっせん)していたことがわかったという。
同基金によると、今年の1級試験は6月に学科、10月に実地が行われ、それぞれ2万5684人、1万9502人が受験。2級試験は学科、実地とも11月でそれぞれ2万2920人、1万9778人が参加した。合格者はいずれも来年2月に発表される。
1・2級建築施工管理技士
建築工事の施工計画を作成し、現場の工程や品質を管理する人材を認定する国交省認定の国家資格。試験は昭和58年度に始まり、平成19年度までに1級21万6708人、2級35万6843人が合格している。19年度の合格率は1級が34・1%、2級は35・5%。公共工事発注時の評価基準となる経営事項審査でも、資格者がいると評価点がプラスになる。一定規模の建設現場に置くことが義務づけられている監理技術者は、1級が資格要件。小規模な工事で必要な主任技術者も2級を取得しなければならない。
世界中でサブプライムローンの影響は深刻のようだ。日本だけでなく、韓国も中小企業支援では
有効な手段は実施できていない。これじゃ、今回の不況はそう簡単に乗り切れそうにない。
少なくとも日本政府は若い世代に負担を負わせる無駄遣いは止めてほしい。
穴だらけの中小企業支援、巨額が無駄に 12/03/08(朝鮮日報)
自動車部品メーカーのP社は昨年の売上高が1100億ウォン(約70億円)で従業員数は400人を超える。誰が見ても堂々とした中堅企業だが、法的には「中小企業」に分類される。昨年には中小企業施設改善資金として10億ウォン(約6400万円)も受け取った。帳簿上の資本金は50億ウォン(約3億2000万円)で、資本金80億ウォン(約5億1000万円)以下という中小企業の基準を満たすためだ。
中小企業庁は2日、P社のように中小企業の基準を無理に満たしている言わば「偽装中小企業」に支払われるさまざまな政府支援金、技術保証・信用保証基金の規模が1兆1300億ウォン(約700億円)に達するとの試算を明らかにした。
イオン水機メーカーの経営者は最近、「中小企業技術革新開発事業資金」として2億ウォンの支援を受けた。しかし、1億ウォンを息子の留学費用に流用していたことが発覚し、検察当局に逮捕された。この経営者は既に商用化に失敗した技術にもかかわらず、「異物除去性能を革新的に向上させるフィルターを開発する」と書類をでっち上げ、支援を受けていた。
中小企業支援資金が不正に支出されている。一部の不道徳な中小企業は偽の書類で政府から支援金を受け取り、個人の負債返済、交際費、子供の留学費用などに充てている。本当に技術開発、施設拡充で競争力を高めなければならない中小企業はじだんだを踏む思いをしている。
現在政府が中小企業を対象に実施している支援規模は約100項目で30兆ウォン(約1兆9000億円、直接支援と融資の合計)に達するとみられる。政府機関のうち、中小企業庁が今年、中小企業に支援する金額は3兆ウォン(約1900億円)前後で、来年は4兆ウォン(約2600億円)に増額される。しかし、複雑で非効率的な審査、評価方式、いい加減な事後管理、一部企業のモラルハザードなどが重なり、中小企業支援資金がとんでもないところに使われているとの専門家の指摘が相次いでいる。
特別取材チーム
方聖秀(パン・ソンス)記者=チーム長
金承範(キム・スンボム)記者
李性勲(イ・ソンフン)記者
三菱UFJ銀の元室長、未公開株譲渡受けて利益2千万円 12/02/08(読売新聞)
三菱東京UFJ銀行の元渋谷法人新規室長が融資先から関係企業の未公開株譲渡を受け、2000万円以上の利益を上げていたことがわかった。
元室長は、不動産会社「コシ・トラスト」(東京都渋谷区)グループが偽造書類を使って同銀行から不正に融資を引き出し、約70億円が焦げ付いた問題にもかかわっている。同銀行は、審査体制の甘さに加え、融資先との行き過ぎた関係も焦げ付きにつながったとみて、元室長の処分を検討している。
同銀行などによると、元室長は旧東京三菱銀行支店に勤務していた1999年12月、かつて融資を担当していた旧オリコンと関係のある音楽情報のデータベース会社「おりこんダイレクトデジタル」(東京都港区)の未公開株10株を旧オリコンの創業者から額面価格の計50万円で取得した。
同社株が2000年11月、大証ナスダック・ジャパン(現ヘラクレス)に上場して株価が値上がりした後、一部の株を売却して2000万円以上の利益を上げていたという。
同銀行では、部署の異動から1年以内に融資を担当した企業や関係企業の株を売買する行為を禁止している。元室長の異動は株を取得する1年以上前だったが、同銀行では「銀行員の立場を利用して不当に利益を上げることを禁じる規定に基づいて、判断したい」としている。
おりこんダイレクトデジタルは01年に旧オリコンを子会社化し、02年にオリコンに社名変更した。
元室長は、渋谷法人新規室に異動後の02~05年にコシ・トラストや同社から紹介された企業など約80社を恵比寿支社や渋谷支社などに取り次いだ。約300億円の融資のうち約70億円が焦げ付いている。
前任の理事にも裏金80万円 埼玉の年金基金背任 11/20/08(朝日新聞)
埼玉県国民年金基金のパンフレット製作費の水増しによる背任事件で、逮捕された常務理事黒沢博史容疑者(62)の前任者に、業者からキックバックされた裏金のうち約80万円が渡っていたことが警視庁への取材でわかった。この前常務理事(68)は別の不正でも業者からキックバックを受けた疑いがあるといい、同庁は解明を進めている。
前常務理事は朝日新聞の取材に「現金を受け取ったかどうか覚えていない。思い出せない」と話した。
捜査2課によると、同基金は出版会社「社会保険研究所」(東京都千代田区)に00年度から発注を開始。黒沢容疑者は07年度までの8年間に計約560万円を水増し請求させ、うち約500万円をキックバックさせていた。
このうち、前常務理事時代の00~04年度の5年間には、計約290万円のキックバックがあった。この中から約80万円が前常務理事に渡っていたという。03、04年度は前常務理事の口座に業者から直接振り込まれていた。
00~04年度分の残り約210万円と、05年以降分をあわせた約420万円は黒沢容疑者が受け取っていた、と同課はみている。
前常務理事は、同基金が設立された91年5月に常務理事に就任し、05年春に黒沢容疑者に引き継ぐまでの約14年間、同基金の実質的なトップの立場にいた。
こうした不正の仕組みについて、黒沢容疑者は調べに、「前常務理事の見よう見まねだった」と供述しているという。
同課は、前常務理事がほかにも、別の業者に印刷物を発注する際に水増し請求させ、キックバックを受けていた疑いがあるとみている。
チャリティーコンサートやNPO法人を隠れ蓑にしたら駄目だよな!
NPO法人に対しても抜き打ちでチェックする必要があるだろう!まともに運営しているNPO法人は
迷惑な話だろうが、嘘や偽りはあることを想定する必要はあるだろう。
慈善事業、宗教的に熱心、損をしてまで人に尽くしたい、商売の才能、人徳、人脈又はリーダーシップなどの
さまざまな点を持ち合わせていないと、存続や拡大は難しいと思う。良いことをしても世間から求められる
ことはないかもしれないし、知名度がないと、詐欺まがいの団体と間違われる。
絶え間ない努力が要求されるのだろうね。
社会保険庁職員は公務員だけど、まともな事をしているのか疑問!
税金を無題使っている点では、詐欺に近い。これで給料を貰っているのだから、詐欺に近いけれど、処分されない行為。
何とか出来ない事実に腹が立つ。
話は元に戻るが、NPO法人のチェックを厳しくする必要あり。
比女性の不法就労関与、倉田議員の元秘書を強制捜査へ 10/18/08(読売新聞)
自民党の倉田雅年衆院議員(比例東海)の元公設秘書(59)が、災害復興支援を目的としたチャリティー名目で、短期滞在ビザで入国したフィリピン人女性を不法就労させていた疑いが強まり、静岡県警は週明けにも入管法違反(不法就労助長)容疑で強制捜査に乗り出す方針を固めた。
捜査関係者によると、元公設秘書は、チャリティーコンサートへの出演名目で来日したフィリピン人女性を会場に派遣する団体「未来チャリティー実行委員会」の事務局を務め、今年5月にNPO法人「MIRAI」(静岡市葵区)に衣替えした際にもかかわった。
実行委員会は2005年頃から、チャリティー活動と称し、フィリピン人女性を興行ビザではなく短期滞在ビザで入国させ、身元保証人となったうえ、運営にかかわる飲食店に派遣。ダンスや歌を披露させたり接客させたりして、女性に報酬を支払っていた疑いがもたれている。
県警は9月末、NPO法人が運営にかかわる浜松市南区の飲食店経営者を風営法違反(無許可営業)容疑で逮捕。経営者は入管法違反容疑で再逮捕された。飲食店の売上金の一部は謝礼金などとして元公設秘書が受け取ったとみられる。
倉田議員自身は読売新聞の取材に、不法就労事件への関与を否定している。
最近、程度の差はあれ、不正を行い、運や実力そしてその時の経済や社会のニーズがないと企業として
大きく成長するのは難しいのかもしれないと思うことがある。一生懸命にがんばった結果として、
取引先、消費者又はユーザーに認められる企業もあるが、マイナーであるかもしれないと思い始めた。
20年間も検査対象のホースをメーカーがすり替え続けても、問題が指摘されてこなかったのか、
ある程度の品質を保っていたのか、問題を上手くもみ消したのか、不正は今まで公にならなかった。
これで良いのなら、消防法の規定を緩和するべきだ。他の企業も同様にすり替えをおこなったのか、
まともに検査を受けてきたのか知らないが、まともにやっている企業が存在すれば不公平だ。
中国製の消防ホースは新品でも水漏れするケースがある。それほどひどくなければOKするべきなのかな?
消防ホース検査不正、大阪のメーカーがすり替え20年 10/09/08(読売新聞)
東証1部上場の消防用ホースメーカー「芦森工業」(大阪市西区)が約20年間にわたり、消防法に基づいて製品強度を調べる出荷前検定で、検査対象のホースを強度の十分なものにすり替えて合格させていたことがわかった。
全国約1000自治体の消防局・本部などに納入されたホースに強度の劣る製品が含まれているかどうかは不明という。総務省消防庁は消防法違反の疑いが強いとして、同社から事情を聞く。
消防法の規定で、消防用ホースを販売するには、出荷前に特殊法人「日本消防検定協会」(東京)が実施する検定に合格しなければならない。
同社によると、毎週3000~4000本が検定を受けており、工場を訪れた協会職員の前で、同社の担当者が数百本のホースから数本ずつ抜き取り、一部を切り取って強度などを検査している。
その際、品質にばらつきのあるゴム製ホースについては、同社の担当者が、事前に強度を確認して切り取っておいた別のホース片にすり替えて検査をパスしていた。同社の内部調査に対し、担当者は「約20年前から一部製品についてすり替えをしていた」と説明しているという。
同社総務部は「全製品が規定の水圧に耐えられることを確認しており、安全性に問題はない」としている。
日本消防検定協会は、8日に予定していた同社製品の検定を中止した。
同社は1878年創業で資本金は約80億円。消防用ホースではシェア約4割の最大手で、年間十数万本を販売している。
消防用ホース「芦森工業」立ち入り、出荷前検定ですり替え 10/09/08(読売新聞)
消防用ホースメーカー「芦森工業」(大阪市西区)が出荷前検定で検査対象のホースをすり替えていた問題で、日本消防検定協会(東京)は9日午前、同社大阪工場(大阪府摂津市)に立ち入り調査に入った。
同協会は、ホースをすり替えた手口や経緯について詳しく事情を聞く。
また、総務省消防庁は同協会に、すり替えを可能にした原因を調べた上で、検査体制や方法を見直すよう指示した。
総務省で記者会見した三好勝則・同協会理事によると、検定は通常、協会職員2人で行う。三好理事は、「職員がほかの検査をしていたため、目が届かなかった可能性がある。その間にホースをすり替えられたのではないか」と述べた。
また、東京消防庁に6日夕、「芦森工業で検査対象品のすり替えが行われている」と匿名の情報提供があったことを明らかにした。
茨城県国保連の横領事件、元会計課主任が起訴事実認める 09/30/08(読売新聞)
茨城県国民健康保険団体連合会の保険料横領事件で、業務上横領罪に問われた元会計課主任、森知勇(ともお)被告(34)(水戸市河和田)の初公判が30日、水戸地裁(鈴嶋晋一裁判官)であり、森被告は「間違いありません」と起訴事実を認めた。
事件を巡っては、同連合会が口座の管理を森被告一人に任せるなど、ずさんな事務処理体制が明らかになった。
検察側の冒頭陳述などによると、森被告は会計課出納係の主任だった2005年5月下旬から08年3月下旬までの間、計327回にわたり11億385万円を連合会の口座から引き出し、消費者金融への返済や競艇に使ったとされる。検察側は、消費者金融の借金返済に充てるために横領を始めたと指摘した。
県警の発表などによると、森被告は「(友人に連れられて初めて行った競艇で当たり)賭け金を大きくすればもっともうかると思った」と供述。上司の不在時に公印を持ち出し、あらかじめ銀行の窓口などから持ち帰っていた大量の払戻請求書に押印して公金を引き出していたが、「上司は新聞を読んでいるだけだったので、絶対に発覚しないと思った」としていた。
同連合会は茨城県内の市町村などで構成し、国民健康保険や介護保険の保険料を保管。病院などからの診療報酬請求を審査して支払っている。
フルキャスト、処分中も労働者派遣…再び事業停止へ 09/29/08(読売新聞)
厚生労働省は、日雇い派遣大手「フルキャスト」(東京都渋谷区)に対し、2度目の事業停止命令を出す方針を固めた。
同社が昨年、違法派遣で事業停止となった期間中も派遣を続けるなどしたためで、同社の全支店で来月上旬から1か月の処分となる見通し。日雇い派遣業界では、最大手だった「グッドウィル」が度重なる違反で廃業に追い込まれており、フルキャストへの再度の事業停止が、規制強化の流れをさらに加速させる可能性もある。
フルキャストは昨年3月、労働者派遣法が禁じた建設、警備業に労働者を派遣したとして厚労省から事業改善命令を受けながら、同5月には、違法な港湾作業に労働者を派遣。これを受け、厚労省は同8月、同社に改めて事業改善命令を出した上で、違反があった3支店に8月10日から2か月、残る313支店に同1か月の事業停止を命じた。
しかし、同社はこの期間中にも、命令に違反して労働者派遣を続け、違反件数は900件を超えていたとされ、厚労省は、改善のための努力が不十分で悪質と判断したとみられる。
厚労省は同社の弁明を聞いたうえで、来月初めにも、東京労働局から1か月の事業停止命令を出す方針。命令が出れば、同社は新たに派遣契約を結んで労働者を派遣することができなくなる。同時に、違反の原因究明と再発防止の措置を求める事業改善命令も出される見通しだ。
フルキャストによると、同社の支店は現在、全国に156店あり、稼働する派遣労働者は1日8000人前後。日雇い派遣を原則禁止する厚労省の方針などを受け、中長期派遣への切り替えを進めているものの、現在も派遣労働者の4割程度を日雇いが占める。
フルキャスト広報室は、読売新聞の取材に「現時点で事実を確認できていない。弊社は事業改善命令に対する改善結果報告をすべて終了しており、信頼回復に努めている」などとコメントした。
入札・営業、社長が全国奔走 汚染米転売の三笠フーズ 09/25/08(朝日新聞)
有害成分を含む大量の米が全国で広く消費され、「食の安全」を脅かした事故米問題は、刑事事件に発展した。三笠フーズはなぜ、不正転売に手を染めたのか。社長の目的は、安い事故米を高い食用米と偽って利ざやを稼ぐことだったと3府県警はみている。
◇
農林水産省が転用を公表した前日の9月4日午後。三笠フーズの冬木三男社長(73)は大阪市内の本社にいた。
「名前が出ることはかなわん。やめてくれへんか」
同社関係者によると、農水省大阪農政事務所の職員から転用の公表を告げられ、顔色が変わったという。押し問答の末、職員が帰ると冬木社長は「(告発したのは)うちの人間や」と社員の実名をあげて犯人捜しを始めた。翌5日、公表を知った社長は「おれは消える。取材が来たらノーコメントで通せ」と言い残し、会社を出たという。
問題が大きく報道された翌6日、冬木社長は記者会見で頭を下げた。それ以降は公の場に姿を見せていない。
同社関係者や民間信用調査会社によると、大阪府出身の冬木社長は、20歳前後で府内の米穀販売会社で働き始めた。当時を知る業界関係者は「流通経路などを勉強して熟知していた」と話す。
1960年代末から商社に移り、米の売買を担う。76年、知人が経営していた米卸売会社「辰之巳」を買収し、翌77年に三笠フーズを設立。自ら営業に回って人脈を広げた。90年前後からは天丼やカレーのチェーン店の外食産業に進出するなど、事業を拡大していった。社内ではワンマンで、「米一粒も落とすな」が口癖だった。
転用のきっかけは97年。事故米の購入資格を持つ取引先の米穀飼料製造販売会社「宮崎商店」(福岡県)を買収し、経営者の宮崎一雄氏(76)を顧問として雇い入れたことだった。
事故米の購入資格を得た冬木社長は自ら全国の農政事務所を回り、事故米の営業も自身が担った。九州の酒造会社関係者は「突然やってきて、いい米がある、と売り込まれた」と話す。会社は近年、年10億円規模を売り上げ、安定した経営を続けていた。しかし、転用の発覚で一変した。
「政治に巻き込まれた。国策捜査だ」。冬木社長は最近、社内でこう漏らしているという。
チャリティー掲げビザ…実はフィリピンパブ NPO摘発 09/25/08(朝日新聞)
フィリピン人女性が災害の復興支援などの名目でチャリティーコンサートに出演するとして短期滞在ビザで入国し、実際はフィリピンパブに酷似した店で働くケースが相次いでいる。外務省や警察庁が警戒を強めるなか、静岡県警が25日、同種の店で働く女性たちのビザ発給で身元保証などをしていたNPO法人などの強制捜査に着手した。
海外から「人身売買の温床」との指摘を受けてフィリピンパブで働く女性への入国管理の厳格化が進むなか、警察当局は「抜け穴的な手法」とみて実態解明を進める方針だ。
県警が同日、風俗営業法違反(無許可営業)容疑の関係先として家宅捜索をしたのは、女性たちの身元保証をしている静岡市葵区本通1丁目の「未来チャリティー実行委員会静岡事務局」「NPO法人MIRAI」(同じ住所に存在)。24日には、拠点のひとつとみられる同県浜松市南区新橋町の飲食店「クラスメッツ」を同法違反容疑で家宅捜索し、経営者(47)らを逮捕。フィリピン人女性2人も入国管理法違反(資格外活動)容疑で逮捕した。
調べでは、経営者らは元々、同じ場所でフィリピンパブを経営していたが、いったん閉店して営業許可を返上。その後、チャリティーショーをするとして「クラスメッツ」を開店した。県警は、同店は本来は風営法の許可が必要であるのに許可を得ずに営業していた、としている。
同店の客は1時間4千円などの料金を払って入店。06年に土砂災害で被害を受けたフィリピン・レイテ島への復興支援のチャリティーショーをするとして、短期滞在ビザで入国したフィリピン人女性らが、席について接客。女性たちは指名料などのチップも受け取り、合間にダンスなども披露していた。客に出す領収書の発行名義は「未来チャリティー」だった。
外務省によると、04年版の米国の人身取引報告書が、フィリピンパブの実態などを問題視して日本を人身売買の「要監視国」としたため、日本はフィリピン人女性に対する興行ビザの発給を厳格化した。フィリピン側の証明書類があれば基本的に発給していたのを改め、興行の実績などを審査するようにした。これにより、興行ビザで入国したフィリピン人は04年には約8万人いたが、07年には5700人程度まで急減した。
その一方で、警察や入管当局によると、07年春ごろから、チャリティーコンサートに出演するという名目でフィリピン人女性が短期滞在のビザ申請をするケースが増加した。「就労はしない」として興行ビザを取らずに入国するケースだ。
静岡県警の捜索を受けた未来チャリティーは、この手法で女性を入国させ、フィリピン大使館主催のコンサートなどに出演する一方で、「クラスメッツ」の他にも同様の形態の店を東京都新宿区や愛知県豊橋市など4カ所に相次いで出店。店で働く女性の身元保証もしていた。
外務省は、興行ビザにかわる手段としてチャリティーコンサートが悪用されていると警戒を強め、今年5月には警視庁が東京都新宿区にある未来チャリティーの系列店を立ち入り調査していた。
汚染米に380社が関係、新潟でも不正転用判明…農水省 09/16/08(読売新聞)
米穀加工販売会社「三笠フーズ」(大阪市)などが工業用の「事故米」を食用に転用していた問題で、新たに澱粉(でんぷん)製造会社「島田化学工業」(新潟県長岡市)も事故米の不正転用を行っていたことが16日、農林水産省の調査でわかった。
これで不正転用が判明した業者は4社になった。三笠フーズが転売した事故米の仲介・販売などにかかわった業者は現時点で24都府県の約380社にのぼることも判明し、内閣府が全社の社名を公表した。
それによると、三笠フーズが転売した事故米の流通に関係した中間流通業者は50社で、製造・販売にかかわった業者は約320社。このうち給食会社大手「日清医療食品」(東京都)などが卸したモチ米を使っていた給食施設が110か所以上を占めた。このほか外食業者や米穀販売店などもあった。
農水省は、事故米の転売先企業名は同意を得てから公表してきたが、公表の遅れが消費者の不安を増幅させたとの批判を受け、今回、全社名を明らかにした。
一方、島田化学工業は、2003~07年度に、カビがはえた事故米など236トンを工業用のりの原料として国から購入。このうち3トンは工業用のりとして使ったが、それ以外は用途を特定せずに販売したという。
農水省では、不正競争防止法違反容疑で熊本県警に告発している三笠フーズに加え、他の3社についても刑事告発を視野に対応を検討している。同時に、同省の責任を検証するため、消費者団体の代表などによる第三者委員会が近く野田消費者相の下に設置される。検討結果を踏まえて関係職員が処分される見通し。
また、今後は事故米が国内流通しないよう、残留農薬やカビなどの問題が判明した場合は輸出国への返送や焼却処分などを行う。
三笠フーズによる事故米転売問題で、大阪、福岡、熊本3府県警は今週中にも合同捜査本部を設置する。
農林水産省
は自分達の勝手な判断で検査を甘くする。本当は今回のようなことが
起こらないように検査をするべきなのだが、誰もチェックしないし批判されても
無視も出来る。
食肉製造加工会社「ミートホープ」のミンチ偽装問題
でも無能とやる気の無さを示してくれた。通報や告発があっても不適切なチェックで問題なし判定。
昔、海上保安職員に嘘の報告を業者が行っている
と言ったら、業者に電話で問い合わせして嘘の報告はないと言っているとして処理した。仕方が無いので、
脅迫された時にテープに録音した。
そして保安職員にテープを聞かせた。
日本の公務員は甘いね!そして業者は事故の利益やメリットがあれば公務員を物や金で良い思いをさせる。
これが現実だろう!弱いものいじめの公務員。悪い奴らには何もしない。悪い奴らが儲ける。
おかしい日本、批判し続けるしかないだろう!
事故米、国検査時に「倉庫移動」隠ぺい工作…従業員が証言 09/10/08(読売新聞)
米穀加工販売会社「三笠フーズ」(大阪市)グループが事故米を食用に転用していた問題で、同社九州工場(福岡県筑前町)の男性従業員が9日、読売新聞の取材に応じ、「国の定期検査のたびに、事故米を別の倉庫に移し替えていた。事故米を食用米に混ぜる役割の従業員もいた」と隠ぺい工作の手口を生々しく証言した。
男性によると、工場の敷地内には、焼酎など加工用の食用米を保管する第1倉庫、飲食店に卸す飯用米を保管する第2倉庫、事故米を保管する第3倉庫が隣接。三つの倉庫にはそれぞれ、通常30キロ入りの米袋が約1100~1400袋ずつ保管されていた。
事故米のうち、帳簿上、工業用のり製造業者に出荷した形にしている分が第3倉庫に残っていると矛盾することから、毎月1回、農林水産省福岡農政事務所(福岡市)の立ち入り検査が行われる際には、この事故米を第1倉庫に移し、検査官の目につかないよう倉庫の最も奥の床に置き、その上に食用米を積んで隠していたという。
男性は昨年末、工場所長だった宮崎雄三・営業課長(49)から、「第1倉庫に移した事故米が農政事務所に見つかるとまずい。分からないようにしてほしい」と直接指示されたと言い、「事故米の隠し場所は従業員全員が知っていた」と証言している。農政事務所からは立ち入り検査の約1週間前に事前連絡が来るため、「隠ぺい工作の準備は簡単にできた」と話している。
事故米を出荷する際、食用米に混ぜる作業は特定の従業員1人だけに任されていたという。「いつの間にか第1倉庫から事故米が消えているので、おかしいと思った」と打ち明けた。
不正転売が表面化して以降、会社幹部らが責任をなすり合う姿を見て、「酒造会社や関係者に迷惑をかけて申し訳ないと思った。真実を語り、すべてを明らかにすることが私の責任の取り方と考え、取材に応じた」と話した。
「韓流」配給会社、1.6億円脱税の疑い 東京国税告発 09/05/08(朝日新聞)
「韓流ブーム」を背景に、韓国ドラマの配給で売り上げを伸ばした「コリア・エンターテインメント」(東京都渋谷区)と成七龍・前社長(38)が、東京国税局から法人税法違反(脱税)の疑いで東京地検に告発されていたことが分かった。隠した所得は07年3月期までの3年間で計約4億5千万円に上り、法人税計約1億6千万円の支払いを免れていた。
同社は「指摘に従って修正申告した。1日に社長が交代しており、再発防止に努めたい」とコメントした。
同社広報部によると、同社は04年から3年ほどの間、「散策」「ドクターK」など8本の韓国映画配給権を韓国の代理店から買い付けた際、代金を水増しして支払ったという。同社は「1千万円の映画を、契約上は1億円で購入したことにして同額を支払うなどした。水増し分は次回の買い付けに使うつもりだった」と説明している。
国税局は「経費の水増しであり、申告所得を圧縮した」と認定した模様だ。購入したドラマの仕入れ時期を前倒しして計上し、所得を圧縮していた点も所得隠しと認定されたほか、「韓流タレント」の写真集など商品の売り上げの一部も除外していたという。
隠した所得の大半は韓国の銀行口座に預金されていたとみられるが、同社は「韓国の代理店が『すべて正規の代金だ』として、(水増し分の)返還請求に応じてくれない。今年に入って代理店を提訴したが、敗訴した」などとしている。
民間信用調査会社によると、同社は00年に設立。韓国ドラマや映画の配給権を買い取り、日本国内の放送会社に販売してきた。「冬のソナタ」などドラマのDVD販売も手がけてきた。同社は韓流ブームの前から実績があり、知名度は高く急成長しているという。08年3月期の売上高は約20億円に上り、最近ではドラマ「商道」、「幸せな女」などがヒットした。(中村信義、舟橋宏太)
「厚労省は、近く同協会の各検査所を立ち入り検査し、法令上の検査でも問題が確認されれば、登録検査機関の取り消しも含め、処分を検討する方針だ。」
サブスタンダード船
の多くは適切に検査を行わずに証書を発給する
検査会社の問題
と
検査が簡単又は故意に検査を見逃してくれることを知って依頼又は選択する
海運関連業界
の問題です。登録検査機関の取り消しの処分をしないと検査の問題は解決しないでしょう。
日本では食品の問題が注目を浴びている。やはり同じことが言えるでしょう。
冷凍食品検査協が安全証明書を偽造、輸入食器など19件で 09/05/08(読売新聞)
厚生労働省の登録検査機関である財団法人「日本冷凍食品検査協会」(本部・東京都港区)は5日、東京検査所が昨年7月~今年3月、輸入業者が自主検査のため依頼した食器やおもちゃなど19件の検査で、安全性を保証する証明書を偽造していたと発表した。
このうち、中国製プラスチックカップは、その後の検査で、水や食品を入れた際、容器の成分の溶け出す量が食品衛生法に違反していることも判明。厚労省は、輸入された212個のうち、すでに販売された49個の回収を指示した。
同協会によると、19件の証明書は、担当課の男性課長が、業務の遅れをごまかすために偽造。6件は試験をせず、13件は試験途中だった。偽造証明書は、輸入届け出の際、検疫所に提出されていた。課長は今年5月末に依願退職している。
このほか、同協会では、店舗の衛生検査などで、試験項目の一部を実施していないのに、実施したと虚偽報告していたケースも2例見つかった。
同協会によると、2004年~今年にかけ、スーパーの調理室の衛生検査で、サルモネラ菌の検査を度々怠りながら、スーパー側には実施したことにしていた。
昨年4月~今年3月には、複数の業者から依頼された香港向けの輸出冷凍マグロの検査で、放射能検査をしていなかったという。
同協会は、食品衛生法に基づく厚労省の登録検査機関として、輸入食品の検査などを手がけている。今回、問題が判明した検査は法令に基づくものではなく業者による自主検査で、罰則の対象外。
厚労省は、近く同協会の各検査所を立ち入り検査し、法令上の検査でも問題が確認されれば、登録検査機関の取り消しも含め、処分を検討する方針だ。
「同省によると、同社では二重帳簿の作成や記録の偽造が行われており、会社ぐるみで不正の発覚を防ごうとしていた可能性もあるという。」
農林水産省
は刑事告発する準備しているのなら、早く告発してくれ。これはひどいだろ!
基準5倍のメタミドホスも検出、「工業米」を食用転売 09/05/08(読売新聞)
大阪市北区の米穀加工販売会社「三笠フーズ」が、基準値を超える残留農薬が検出されたり、カビが生えたりしているため、工業用の使用に限定された「事故米」を、食用と偽って転売していたことが分かった。5日、農林水産省が発表した。
現時点では健康被害は確認されていないが、同社の九州工場がある福岡県は同日、食品衛生法(有害食品などの販売)に基づき、転売したコメやその加工品の回収を命じた。同省では同法違反容疑で大阪府警、福岡県警に同社を告発する方針。
同省によると、同社は2003~08年度、工業用の糊(のり)の製造などに使うとして政府から事故米計約1779トンを購入。このうち、発がん性のあるカビ毒「アフラトキシン」が検出されていた9トンのうち計約3トンを鹿児島、熊本両県の焼酎会社4社に転売していた。また、有機リン系殺虫剤「メタミドホス」が暫定基準値(0・01ppm)の5倍(0・05ppm)検出された中国産のモチ米計約800トンのうち、約295トン分が転売され、菓子の原料などの米粉などとして利用された疑いがあるという。
同省によると、同社では二重帳簿の作成や記録の偽造が行われており、会社ぐるみで不正の発覚を防ごうとしていた可能性もあるという。
カビ、農薬含有米を転売 輸入米で三笠フーズ 09/05/08(西日本新聞)
農林水産省は5日、カビ毒アフラトキシンや殺虫剤メタミドホスが基準値を超えて残留し「非食用」としていた中国などからのミニマムアクセス(最低輸入量)米を、中堅の米粉加工業「三笠フーズ」(大阪市)が「食用」として焼酎などの原料に不正転売していた、と発表した。米菓についても使われていた恐れがあり流通経路を調査している。現時点では、健康被害の報告はないという。
同省は食品衛生法違反容疑で大阪府警と福岡県警に刑事告発する準備を進めている。三笠フーズの福岡県内の倉庫から出荷。農水省と福岡県は三笠フーズや関係団体に対し、自主回収を指示、食品衛生法に基づき本格的な調査に乗り出した。同社の冬木三男社長は農水省に「違反行為に当たることは認識していた」と述べている。
問題のコメは、鹿児島と熊本の焼酎メーカー4社や、大阪、京都などの米穀店や仲介業者など計20社が購入。さらに増え、西日本一帯で流通している可能性もある。農水省はこのうち、鹿児島の焼酎メーカー3社が購入したアフラトキシンが残留していたコメを焼酎原料として使用していたことを確認している。
NHKの処分職員再雇用、また発覚…子会社に定年退職後 08/22/08(読売新聞)
不祥事で懲戒処分を受けたNHK職員がNHK本体や関連会社に相次いで再雇用されている問題で、カラ出張を繰り返したとして2004年に出勤停止7日の処分を受けた元エグゼクティブ・プロデューサー(57)も、今年6月の定年退職後、翌7月から子会社「NHK情報ネットワーク」に再雇用されていたことが21日、わかった。
国立病院汚職:落札、複数で97~100% ヤマト社、別の医師とも癒着か 08/19/08(毎日新聞)
国立身体障害者リハビリテーションセンター病院(埼玉県所沢市)への医療機器納入を巡る汚職事件で、贈賄側の眼科医療機器販売会社「ヤマト樹脂光学」(東京都千代田区、破産手続き中)が、同病院など複数の国立病院の一般競争入札で、予定価格に極めて近い97~100%で落札を続けていたことが分かった。警視庁捜査2課は、リハビリ病院元部長、簗島(やなしま)謙次容疑者(63)=収賄容疑で逮捕=以外にも癒着を深めていた眼科医がいるとみて追及する。
調べでは、ヤマト社はリハビリ病院が07年10月発注した「散瞳・無散瞳一体型眼底カメラ」を予定価格と同額(750万円)で落札したほか、04年12月には「マルチカラーレーザー光凝固装置」を予定価格の99・9%で、05年11月には「超音波白内障硝子体手術装置用ハンドピース」を97・6%で落札した。
眼科への現金の寄付や高額機器の寄贈が問題化した東北大病院では、06年度に受注した7件の医療機器入札のうち、3件を予定価格と同額で落札した。【杉本修作、町田徳丈】
ヤマト樹脂関係者「20年前から現金渡していた」 08/19/08(朝日新聞)
国立身体障害者リハビリテーションセンター(埼玉県所沢市)発注の医療機器納入に絡む汚職事件で、収賄容疑で逮捕された同センター病院元部長の簗島(やなしま)謙次容疑者(63)が、贈賄側のヤマト樹脂光学から長年にわたり現金を受け取っていた疑いがあることがわかった。同社関係者は「現金授受は約20年前から続いていた」と証言。警視庁は両者の癒着は以前から常態化していたとみて調べている。
捜査2課によると、簗島元部長は同センターが発注した医療機器の納入に便宜を図った見返りなどとして、07年1~4月、ヤマト社社長の久保村広子容疑者(74)から毎月約15万円ずつ4回にわたり計約60万円を受け取った疑いがあるという。
ヤマト社の関係者の証言では、簗島元部長は05年1月以降、ほぼ毎月1度の割合でヤマト社を訪れ、そのたびに久保村社長らから直接現金を受け取っていたという。04年以前は、ヤマト社の担当社員が同センターを訪れて現金を渡していたといい、現金授受は約20年前から続いていたという。簗島元部長は89年に同病院の第3機能回復訓練部長になっており、授受開始が指摘される時期はこのころに当たる。
この同社関係者は「渡していた金額は、ずっと以前から1回15万円程度。『顧問料』という名目だったが、渡す側はわいろという認識だった」と言う。
別の同社関係者は「現金の提供によって、病院が機器を発注する際は仕様がヤマトのものにほぼ限定される内容になるなど、便宜を得られるようになった」と証言する。
捜査2課によると、簗島元部長は調べに対し、現金の受け取りは認めているが、わいろ性は否認しているという。
NHKとしては良くない対応だろう!多くの人達はどのように感じているのか?
NHKは不祥事を起こしても依願退職して社会的制裁を受ければ仕事はNHKからもらえるという事か。
NHK、停職処分の元解説主幹も再雇用 08/19/08(読売新聞)
不祥事で懲戒処分を受けたNHK職員がNHK本体や関連団体に相次いで再雇用されている問題で、新たに、シンガポール特派員時代に経費の水増し請求をしたとして2005年に停職3か月の処分を受けた元解説主幹(59)も、06年6月に定年退職した後、翌7月からNHKの解説委員として再雇用されていることが18日、わかった。
懲戒処分を受けた職員がNHKや関連団体に再就職しているケースは、これで4人目。
NHK:万引きの元富山放送局長と委嘱契約 08/16/08(毎日新聞)
NHKが、万引き事件を起こして依願退職した元富山放送局長と、番組を視聴、批評する「専門モニター」を委嘱する契約を結んでいたことがわかった。NHKでは、セクハラ行為で熊本放送局長を更迭された元職員が定年退職後に子会社に再雇用されたことが判明したばかり。今度はNHK本体で、しかも依願退職した職員と雇用契約を交わしていたことは、不祥事に対するNHKの問題意識の希薄さを鮮明にした。
元富山放送局長は06年10月に停職3カ月の懲戒処分を受け、同月依願退職した。だが昨年11月、番組に問題がないか審査する考査室が、報道番組を中心に月20本程度を視聴して意見を提出する「専門モニター」として1年間の委嘱契約を結んだ。
さらに、出張旅費の精算で不適切な経理処理をしたため、06年6月に停職1カ月の処分を受け、依願退職した元山口放送局長が、昨年10月に視聴者対応などを受け持つ関連団体「NHKサービスセンター」(東京都渋谷区)に1年間の契約職員として再雇用されていたこともわかった。主に視聴者から寄せられた電子メールの対応をしているという。
サービスセンターもNHKも「依願退職で責任を取り、社会的制裁も受けている。制作現場での経験を生かしてもらうためお願いした」と口をそろえ、何の問題もないことを強調している。
服部孝章・立教大教授(メディア法)は「税金に準ずる受信料で成り立つ事業体は、社会保険庁を解体してできる組織が懲戒歴のある職員を雇用しないのと同様に考えないといけないことを自覚すべきだ。制裁を受けたからといって、懲戒処分を受けた職員を受け入れる感覚には首を傾げざるを得ない」と非難している。【丸山進】
NHK:セクハラで解任の元放送局長、子会社に再就職 08/15/08(毎日新聞)
送別会で複数の女性にセクハラ行為をしたとして熊本放送局長を解任、減給処分を受けたNHK元職員が7月に子会社の制作会社「NHK情報ネットワーク」(JN、東京都渋谷区)に再就職していたことが分かった。社会保険庁を廃止して発足する「日本年金機構」では懲戒処分歴のある職員の一律不採用が閣議決定されたのに比べ、国家公務員より身内に甘いNHKの体質が浮き彫りになった。
元職員は社会部出身。07年4月に熊本放送局長を解任。放送総局付となった後、6月にライツアーカイブセンターに異動し、08年6月に定年退職した。7月から報道系の子会社であるJNに幹部クラスのエグゼクティブ・プロデューサーとして雇用され、主にニュース原稿のデータベース化を担当している。JNは「これまでの経験や仕事ぶりから必要な人材だと判断した。懲戒処分を受けて制裁は済んだと考えている」と説明。NHK広報局は「個別の人事には答えられない」とコメントしているが、NHK内部からは「目立たない部署で救済したのではないか」と疑問の声も出ている。
JNはNHKが株式の約7割を保有し、社長や常勤取締役6人はすべてNHKのOB。【丸山進】
船の場合、手入れの悪い船は
サブスタンダード船
になる可能性が高い。問題のある船は、全体的に船が腐食している場合が多いので、
厳しくチェックしないとあちこちが腐食しているケースが多い。配管も例外ではない。
たぶん、製造プラントも同じ事が言えるのだろう。
石原産業:四日市工場で塩酸ガス漏れ 管に穴、3分間 08/14/08(毎日新聞)
大手化学メーカー、石原産業(本社・大阪市)は13日、三重県四日市市の四日市工場で、酸化チタン製造プラント内の塩化炉排気管に穴が開き、塩酸酸性ガスを含むガスが約3分間漏れたと発表した。周辺に影響は出ていないという。
ガス漏れは、同日午後6時45分、従業員が気づき、塩化炉の運転を止めた。排気管は鉄製で内側に耐火材が塗られている。穴は直径1~2ミリ程度といい、管内を通るガスにより管が摩耗したと見ている。
石原産業は、猛毒ホスゲンの無届け製造などの不正発表後、火災など事故が多発したことを受け、6月27日~7月24日の間、順次施設運転を停止して総点検をした。110件の修理をしたが、排気管の摩耗は気づかなかったという。【清藤天】
「わいろは受注額の10%」PCI元幹部供述 相場の倍払う 08/05/08(産経新聞)
ベトナムの政府開発援助(ODA)事業をめぐる贈賄事件で、前社長らが逮捕された大手建設コンサルタント会社「パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)」(東京)の元幹部が、東京地検特捜部の調べに対し「ベトナム当局側から受注額10%のわいろを要求された」と供述していることが5日、分かった。同国でのわいろの相場は5%程度とされ、倍額の要求だった。PCI側はこれをほぼ受け入れ、総額約2億7000万円のわいろを提供、事業の受注に成功したという。
贈賄工作の対象となったのは、ホーチミン市を横断する「サイゴン東西ハイウエー」建設事業のコンサル業務。PCIは2001(平成13)年、日本や現地のコンサル会社と共同企業体(JV)を組み、第1期事業について、約11億円で受注。03(同15)年には、第2期事業を約20億円の随意契約で受注した。
設計を中心としたコンサル業務は通常、設計に入る前に「サプロフ」という事業が可能かどうかの調査を実施する。サプロフを行ったコンサル会社が設計業務も受注するケースが多い。
関係者によると、同事業については、PCIと、日本の別の大手コンサル会社のJVがサプロフを受注。ところが、01年の設計業務の入札では、ベトナム当局側からの要請で、このJVを解消して別々のJVで入札を争うことになった。
この際、このコンサル会社のベトナム現地事務所に、ベトナム当局側からわいろの要求があり、要求額は受注額の10%にあたる約1億円だった。ベトナムでのわいろの相場は5%とされ、コンサル会社は倍額の要求だったため拒否。同じころ、PCIのベトナム事務所にもベトナム当局側から同額の要求があり、PCIは要求額をほぼ受け入れ、事業の受注に成功したという。
第2期事業を受注した03年にも、10%の要求があったといい、PCI側は約2億円の提供を約束。最終的に、01年から06年にかけ、総受注額の10%程度にあたる約2億7000万円が分割で提供されたという。
書類偽造は「納期早めるため」…不正輸出メーカー 08/01/08(読売新聞)
広島県福山市の工作機械メーカー「ホーコス」が、核兵器開発に利用される恐れのある工作機械を不正輸出していた外為法違反事件で、同社の複数の輸出担当者が、機械の性能を低く見せかけた偽造書類を税関に提出した理由について、「輸出規制リストの対象機器は、許可が下りるまでに時間がかかる。納期を少しでも早めて販売実績を上げるためだった」と供述していることがわかった。
警視庁では、同社が軍事転用のリスクを認識しながら、利益優先で不正を繰り返していたとみて調べている。
同庁幹部によると、不正輸出された「マシニングセンタ」をはじめ、軍事転用の恐れがある高性能の機器を輸出する場合、経産省に性能や輸出先企業などを詳細に申告し、審査を受けなければならない。輸出先が核兵器開発に利用される可能性が低い国でも、許可が下りるまでには最低でも1か月ほどかかるという。
中国フグ130トンを「国産」、下関・水産会社が偽装認める 07/23/08(読売新聞)
山口県下関市の水産物加工卸売会社「エツヒロ」(森敏一社長)が、中国からの輸入養殖トラフグなどを国産として販売していた疑いで農林水産省の立ち入り調査を受けた問題で、エ社が中国産養殖トラフグを2005年に60トン、06年に77トン購入し、その大部分を国産として出荷していたことが関係者の話でわかった。
農水省は23日、森社長を山口農政事務所(山口市)に呼び、日本農林規格(JAS)法に基づき、産地を適正に表示するよう改善を指示した。
森社長は23日午後、下関市で記者会見し、「消費者と関係者の信用と信頼を裏切ってしまった」と産地偽装を認め、謝罪した。
関係者によると、エ社は05年と06年、水産商社を介して中国河北省、遼寧省産の養殖トラフグを1回につき十数トン~三十数トン輸入。現地で内臓などを取り除いた後、冷凍したものを入荷していた。購入価格は加工賃込みで1キロ当たり約1700円で、同様の加工をした国産品のほぼ半値だったという。
エ社はこれらをさらに刺し身、鍋物用の切り身などに加工して、大手スーパーなどに出荷。刺し身用に骨を取り除くなどするため、総出荷重量は輸入時の4割程度という。
この関係者は「両年とも中国産として出荷されていなかったとエ社関係者から聞いている」と証言した。
アンコウも国産に偽装…山口・下関の加工業者「エツヒロ」 07/22/08(読売新聞)
山口県下関市の水産物加工卸売会社「エツヒロ」が、中国からの輸入養殖トラフグを国産として販売していた疑いで農林水産省の立ち入り調査を受けた問題で、エツヒロはアンコウやシロサバフグも国産に偽装して販売していたことがわかった。
農水省は23日、エツヒロに対し、日本農林規格(JAS)法に基づき改善を指示する。
農水省の調査によると、エツヒロは少なくとも、今年3月から6月にかけて、刺し身や切り身などに加工した中国産養殖トラフグやシロサバフグ、アンコウ計約5トンを「熊本県産」や「山口県産」として出荷。首都圏や近畿圏、中国、四国地方のスーパーなどに納入していた。
この際、トラフグは養殖フグの産地である熊本県産を、シロサバフグはフグの水揚げ地として有名な山口県産を名乗るなど、魚種によって偽装する県を変えていた。
また、農水省では出荷記録などからエツヒロが2005年度以降、同様の産地偽装をしていた可能性があるとみて調べている。
下関市によると、05年度の養殖トラフグの市場卸売価格(1キロ当たり)は中国産の平均約1300円に対し、国産は約1900円でほぼ1・5倍の開きがあるという。
中国産トラフグ、「熊本産」と表示し出荷か…下関の業者 07/22/08(読売新聞)
山口県下関市の水産物加工卸売会社「エツヒロ」が、中国からの輸入養殖トラフグを国産として販売していた疑いで、農林水産省の立ち入り調査を数回にわたって受けていたことがわかった。
首都圏以西の大手スーパーなどに出荷されており、同省は日本農林規格(JAS)法違反の疑いがあるとみて調査を進めている。
関係者によると、エツヒロは今年4月、東京都内の水産商社から中国産養殖トラフグ約2トンを購入。刺し身に加工し、6月にかけて首都圏や近畿圏、中国、四国地方のスーパーなどに「熊本県産」と表示して出荷した疑いが持たれている。
同省は今月7日以降、数回にわたって山口県長門市の工場などを立ち入り調査。複数の幹部は同省の事情聴取に対し、事実関係を認めているという。民間信用調査機関によると、2007年度の売上高は約6億円で、下関市内では中堅のフグ取扱業者。
森敏一社長は「出荷までの全工程を把握していないので詳細はわからないが、産地偽装はなかったと思っている」と話している。
事実だったら
日本司法支援センター(法テラス)
はひどい組織だな。センター長を首にしろ!確かにいろいろな人間がいる。しかし、
日本司法支援センター(法テラス)
でこの対応はひどいな!「悩みを抱えている方々にくつろいでいただけるような、さんさんと陽が差し、気持ちの良いテラスのような場所」は
偽善用のアピールなのか??
セクハラ提訴:申告で雇用切り 法テラス女性オペレーター 07/14/08(毎日新聞)
セクハラ被害を申告したら雇用契約を打ち切られたとして、
日本司法支援センター(法テラス)
のコールセンターに勤めていた東京都内の30代女性が14日、法テラスから業務を受託している経営コンサルタント業「アクセンチュア」(東京都港区)と上司を相手取り、約800万円の賠償などを求めて東京地裁に提訴した。
訴えによると、同社の契約社員に採用された女性は06年10月から、法テラスのコールセンターでオペレーターを務めていた。上司のセンター長は07年10月、時給増額の話をする名目で飲酒に誘い、帰宅途中のタクシー車内で無理やり胸をなで回したり、キスしたという。直後に1400円だった時給が500円増額された。
女性は精神的に不安定になり「急性ストレス障害」などと診断された。会社に被害を訴えたところ、同社は一方的に時給を減額し、今年6月末に雇用契約を更新しなかった。女性は「会社はセクハラ防止義務を怠り、告発したら首という仕打ちで2次被害を発生させた」と訴えている。【銭場裕司】
生コンに違法原料、横浜のマンションなど工事停止に 07/08/08(読売新聞)
神奈川県藤沢市のコンクリート製造会社「六会(むつあい)コンクリート」が、生コンクリートに日本工業規格(JIS)で認められていない一般ごみの焼却灰から作った材料を混ぜていたことが、国土交通省などの調査でわかった。
建設中の横浜市のマンション3棟と藤沢市の工場事務棟1棟でコンクリート表面がはがれるなどし、工事停止となっている。同社は8日付でJIS認証を取り消された。
発表によると、同社は2007年7月~08年6月、一般ごみの焼却灰を加熱した後、冷却して出来たガラス状の粒「溶融スラグ」を混ぜて生コンクリートを製造していた。
工事前に建設業者が立ち会うサンプル試験で、混入していないものを使用。納入先は神奈川県内で300件を超え、国交省は耐久性に問題ないか自治体に調査を指示した。
溶融スラグを混ぜると内部が膨張し、表面が2~3ミリはがれる「ポップアウト」という現象が起きることがある。建築基準法は、梁(はり)や柱に使用するコンクリートはJISに基づき砂利やセメントなどを原料とするよう規定しており、柱などに使うと同法違反となる。
横浜市内のマンション建設を請け負ったゼネコンから同省に通報があり、発覚。いずれも分譲会社が、購入者と解約手続きを進める。
また、神奈川県によると、工事中の県道藤沢鎌倉線の「大仏隧道(ずいどう)(大仏トンネル)歩道」で大量に使われ、強度が確保できない恐れがあるとして強度試験を行う。
同社は「入手した砂の品質がよくなかったため、溶融スラグを代替品として使った」と釈明しているという。
「タイ高官に4億超賄賂」 西松建設元幹部が東京地検聴取に 07/05/08(産経新聞)
元社員が海外で作った裏金約1億円を無届けで持ち込んだとして、外為法違反容疑で東京地検特捜部の家宅捜索を受けた東証1部上場の中堅ゼネコン「西松建設」(東京都港区)の元幹部が、特捜部の事情聴取に「タイのトンネル工事受注で便宜を図ってもらう見返りに、タイ政府当局者に4億円以上の賄賂を渡した」と話していることが5日、関係者の話で分かった。
関係者によると、西松建設は平成15年9月、現地の大手ゼネコンと共同企業体(JV)を組み、バンコク都庁発注の洪水防止トンネル工事を受注。その際、西松建設の現地社員が、受注の便宜を図ってもらう見返りとして、タイ政府当局者や、入札担当者らに賄賂を渡したという。賄賂の提供は、現地大手ゼネコン幹部と相談して決め、総額4億円以上に上るという。
特捜部は6月4日、税関への届け出をせず、海外から約1億円を持ち込んだとして、西松建設を家宅捜索している。1億円は海外で請け負った工事費を実際より高く見せかけるなどの手口で捻出したとされ、特捜部が、同社関係者らから事情聴取するなど、使途の解明を進めている。
外国公務員への賄賂の提供は不正競争防止法で禁じられている。諸外国では多くの摘発例があるが、日本では平成10年の制定以来、大手電気工事会社社員がフィリピン政府高官にゴルフセットを提供し、昨年3月に略式起訴された1件だけにとどまっている。
最近では、大手コンサルタント会社「PCI」(東京)が、ODA事業受注をめぐり、ベトナム政府高官に数千万円の賄賂を提供していた疑いが浮上している。
ヤマダ電機には結構行くんだけどね!安いのは認めるがクリーンなイメージを持っていない。
大きくなれば、メーカーだって顔色を見るようになる。力が全てなのかね???
ヤマダ電機、独禁法違反で排除措置命令…業者から従業員派遣 06/30/08(読売新聞)
家電量販店最大手・ヤマダ電機(前橋市)が納入業者から不当に従業員の派遣を受けていたとされる問題で、公正取引委員会は30日、同社の優越的地位の乱用を認定、独占禁止法違反(不公正な取引方法)で排除措置命令を出した。
同社は、昨年5月に公取委の立ち入り検査を受けるまで派遣費用を負担していなかった。検査後、日当などを負担するようになったが、公取委は「額が不十分で違反状態が続いている」とした。優越的地位の乱用で、家電量販店が行政処分を受けるのは初めて。
公取委によると、ヤマダ電機は2005年11月から昨年5月まで、延べ361店舗の開店や改装のため、計約250社から延べ約16万6000人の従業員を派遣させ、人件費などを支払わないまま商品の陳列や補充、接客などをさせた。
また、05年11月から昨年11月ごろまで、店内で展示したり、返品されたりした商品を処分するセールでも、人件費など負担せずに、パソコンやデジカメの納入業者にソフトウエアの初期化や商品のクリーニングなどをさせた。
同社は立ち入り検査後、派遣された従業員1人につき5000円の日当や700円の弁当代を負担するようになったが、公取委は、交通費や宿泊費なども負担すべきだと指摘した。
優越的地位の乱用の規制対象は05年11月の告示施行までは百貨店やスーパーなどに限られていたが、施行後は、家電量販店などに拡大。ヤマダ電機の売上高は、業界で初めて1兆円を突破、昨年度は約1兆7300億円に上り、トップの摘発を通じて競争が激しい家電量販業界の取引の適正化を促した形だ。
ヤマダ電機の話「排除命令を真摯(しんし)に受け止め、コンプライアンス(法令順守)体制の強化に努める」
東大と言うブランドだけで判断したらよくない。良い例だね!
東大が不正経理で消費税隠し 7500万円追徴課税 07/01/08(産経新聞)
東京大学が東京国税局の税務調査を受け、平成16年の1年間の消費税約6000万円について、意図的に納税を免れたと指摘されていたことが分かった。消耗品を購入するために支出した約30億円について、経費計上する時期を前倒しするなど不適切な経理処理が原因で、消費税分を不正に控除されるよう申告していたという。追徴税額は重加算税などを含め約7500万円で、東大はすでに修正申告している。
東大や関係者によると、問題となったのは、国などから受けた研究費や交付金の扱いについて。余った研究費を使い切ったことにするため、試料など消耗品や備品を購入したことにし、取引業者側に日付などを偽った請求書を作成させていたという。実際の納品は、請求書に記載のある日付の翌年度だった。同国税局はこうした約30億円分の経理処理について、意図的に計上時期をずらしたと認定したもようだ。
国立大学法人が受け取った研究費などの収入には消費税がかかるが、こうした収入で消耗品などを購入したときに支払った消費税分は控除される。東大は、消費税法で保管が義務づけられている領収書も紛失していたという。
ウナギ偽装で魚秀の利益3億円、週内にも一斉捜索へ 06/30/08(読売新聞)
ウナギ販売業「魚秀」(大阪市)と「マルハニチロホールディングス」の子会社「神港魚類」(神戸市)が、中国産ウナギのかば焼きを国産の「一色産ウナギ」と偽って販売していた問題で、一連の偽装取引による魚秀側の利益が約3億円にのぼるとみられることが分かった。
また、徳島県警の任意聴取に対し、魚秀の役員を兼務する高知県南国市の水産加工会社役員が、魚秀側から相談を受け、高松市内のブローカーに偽装工作を請け負わせていたことを認めたという。兵庫、徳島両県警は30日午後、合同捜査本部を設置したうえで、今週中にも関係先を不正競争防止法違反(虚偽表示)容疑で一斉捜索する。
農水省の調査や関係者によると、中国産かば焼きの価格は国産の半分程度で、魚秀から神港魚類の課長へ渡った1000万円について、魚秀の中谷彰宏社長は「(ウナギ偽装の)取引のもうけから払った」と説明しているという。
社説:偽装ウナギ 不安につけ込むあくどい手口 06/30/08(読売新聞)
退廃の連鎖とも呼びたくなる。驚くべき食品偽装事件がまた起きた。
大阪市のウナギ輸入販売会社「魚秀」と神戸市の卸売会社「神港魚類」が中国産ウナギのかば焼きを「愛知県三河一色産」と偽装して売っていた。農林水産省はJAS(日本農林規格)法違反で業務改善指示をし、警察も不正競争防止法違反の疑いがあるとして捜査している。
昨年来、偽装問題が相次いで表面化しているのに、当事者は「ひとごと」と看過し「ばれなきゃいい」と高をくくっていたとしか思えない。これでは消費者も、誠実な生産や取引をしている業者もたまったものではない。なぜこうも平然と横行するのかを追及し、効果的な抑止策を真剣に考えるべきだ。ブランドを信じて高い買い物をさせられた消費者の感覚に照らせば、これは計画的な詐欺といっても過言ではない。
国産と中国産のウナギとでは値に大きな開きがある。農水省によると、1キロ当たり中国産1800~1900円、国産は4000~5000円といい、偽装すればたちまちこの「差益」が入る。魚秀側は偽装が表面化した当初、毒物混入ギョーザ事件で中国産食品の売れ行きが落ち込み、在庫を大量にさばかなければならなくなったのでと釈明したが、実際にはそんな急場しのぎではなく、入念な偽装工作をしていたのではないかと思われる。
例えば、手の込んだ架空の流通ルートの設定だ。
ウナギが魚秀から神港魚類に渡る間に、架空の会社と東京に実在する二つの商社を経たように装い、実際には取引がないのに実在2社には計約4000万円が「仕入れ代金」として振り込まれていた。
現物を伴わない帳簿上の取引である「帳合い」とみられるが、これによって外観上の流通を複雑にし、偽装が発覚しにくくしようとしたらしい。
また、魚秀から神港魚類の課長に1000万円が渡され、趣旨について「口止め料」「謝礼」と両社が対立する。さらに魚秀から「1億円出すから責任を全部かぶってくれ」ともちかけられたという証言も出るなど、不正の規模の大きさや広がりもうかがわせる。
食品安全への関心は高い。不安から、割高でも国産のブランド品を選びたい消費者心理につけこんだ偽装不正は、購買者だけでなく、優良ブランド品全体の信用も深く傷つけ、創意工夫の競争をおとしめる。
昨年来、食品から工業製品まで、産地・内容偽装、耐性偽装などが次々に明るみに出、当事者が法的、社会的制裁を受けながら、こうしてまた新たな偽装不正が表面化する。この現実をどうとらえたらよいのか。
その視点で今回の事件をとらえて全容解明し、「偽装横行社会」の歯止めとなる手がかりを得たい。
ウナギ産地偽装:魚秀、偽装計画後仕入れ350トン 「在庫処分」と矛盾 06/29/08(毎日新聞)
中国産ウナギの偽装問題で、徳島市に拠点のあるウナギ輸入販売会社「魚秀」(中谷彰宏社長)が今年1~6月、中国産ウナギ約350トンを仕入れていたことが分かった。中谷社長は「偽装は在庫処分が目的」と説明しているが、偽装を計画した1月下旬以降に大量のウナギを買い付けており、利ざや目的だった可能性が出てきた。
新たなウナギの購入は、問題発覚後の徳島市の立ち入り検査で判明。350トンすべてを同市にある親会社「徳島魚市場」(吉本隆一社長)から計5億3600万円で仕入れていた。
中谷社長の話などによると、魚秀と神戸市の卸売業者「神港魚類」の担当課長が1月下旬、偽装による中国産ウナギの売り抜けを計画。3~4月、愛知県一色産と偽装した256トンを約7億7000万円で神港魚類に出荷した。動機について、中谷社長は「(農薬混入の)ギョーザ問題などで中国産ウナギが販売不振になり、どうにかして在庫を売りさばきたいと思った」と説明している。
一方、昨年12月~今年1月ごろに開かれた徳島魚市場の定例会議では、徳島魚市場が仕入れた中国産ウナギが大量に在庫になっていることが話題になった。中谷社長は当時、同社の社員も兼ねており、この会議に出席。吉本社長が「損をしてでも売れ。半値なら売れるだろう」などと指示したのに対し、「売ります」と発言したという。
◇魚秀社長解任へ
ウナギの偽装問題で、「魚秀」の中谷社長が「偽装は高松市内の工場でしたが、作業は知人に頼んだので詳しい内容は知らない」と関係者に話していることが分かった。一方、魚秀の親会社「徳島魚市場」の吉本隆一社長は28日、週明けにも魚秀の臨時株主総会を開き、偽装にかかわった中谷社長ら複数の役員を解任する方針を明らかにした。
ベトナムODA、贈賄先はホーチミン市道路責任者 06/28/08(読売新聞)
ベトナムでの政府開発援助(ODA)事業を巡る大手コンサルタント会社「パシフィックコンサルタンツインターナショナル」(PCI)の贈賄疑惑で、資金を受け取ったのは、ホーチミン市の横断幹線道路プロジェクト組織の責任者だったことが、PCI関係者の証言で分かった。
資金提供は少なくとも、2003年と06年の2回行われていたことも判明。PCI元幹部は東京地検特捜部に対し、「本社から受注の見返りとして金を渡すよう指示された」などと供述しており、特捜部は不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)容疑で捜査を進めている。
PCIは2001年度、ホーチミン市を東西に横断する幹線道路建設工事のコンサルタント業務を約11億円で受注。03年度には、同社を含む共同企業体が随意契約で、約20億円のコンサル業務を受注した。いずれも円借款によるODA事業だった。
PCI関係者によると、資金を渡した相手は、この横断幹線道路プロジェクト組織「PMU」の責任者。PMUは、日本の市役所に当たる行政組織「ホーチミン市人民委員会」に設けられた管理組織で、道路工事や下水道工事などの社会資本整備を担っている。横断幹線道路は、同市を流れるサイゴン川両岸を地下トンネルで結ぶもので、総事業費約800億円の巨大プロジェクトだった。
資金提供は、PCIを含む共同企業体がコンサル業務を受注した直後の03年春のほか、06年にも行われていた。いずれも米ドルで支払い、提供額は総額数千万円にのぼるという。
これまでに提供の事実を特捜部に認めているPCI元常務は、「資金提供はいずれも本社の指示だった」と供述しているほか、03年の資金提供については、「受注させてもらった見返りだった」などとも話しているという。この元常務はその後、PCIが脱税工作に使った香港の関係会社の代表に就任。PCIは東南アジアのODA事業の受注工作費をこの会社に送金していた。
特捜部は今後、ベトナム司法当局と協力して、不透明な資金提供の解明を目指す方針だ。
偽装隠蔽?ウナギの産地証明書送付状、卸売業者が廃棄 06/27/08(読売新聞)
ウナギ販売業「魚秀」(大阪市)と水産物卸売業「神港魚類」(神戸市)が中国産ウナギのかば焼きを国産の「一色産ウナギ」と偽って販売していた問題で、魚秀の中谷彰宏社長から1000万円を受け取っていた神港魚類の担当課長(40)が、産地証明書の送り主などがわかる送付状を廃棄していたことが、わかった。
農林水産省は偽装を隠蔽(いんぺい)するために破棄した疑いもあるとみている。
「東京の人物やったことに」…魚秀社長が神港魚類と口裏合わせ 06/26/08(読売新聞)
農水省が魚秀と神港魚類を立ち入り調査する直前の6月10日、魚秀の中谷彰宏社長と神港魚類の担当課長(40)らが徳島市内で、偽装隠ぺいについて話し合っていたことがわかった。
神港魚類幹部によると、5月27日、中谷社長から1000万円の現金を受け取った担当課長は、6月10日に再び魚秀側関係者からJR徳島駅前の居酒屋に呼び出された。中谷社長のほか、複数の魚秀側関係者がおり、近く実施される農水省の調査をどうやって乗り切るかが話し合われた。
この際、魚秀側からは「(偽装は)東京の人物が全部やったことにしよう」などとの話が出たという。課長はこの場では発言せず、翌日以降も偽装について神港魚類に報告していなかったという。
飛騨牛偽装:「丸明」社長、偽装認める 辞任を表明 06/27/08(毎日新聞)
「丸明」の吉田明一社長は26日、本社で記者会見を開き、低い等級の和牛を「飛騨牛」として直営店で売った等級偽装を公の場で初めて認めた。消費期限改ざん、ミンチに期限切れ肉を混ぜたことも合わせ、自身が指示して偽装などを主導したと認めた。その上で「会社を取り締まる私に責任がある。今後は役職には就かない」と社長を辞任する考えを示した。
同社は今後、外部監査を導入するとともに外部から経営陣を招く方針を明らかにした。しかし、オーナーである吉田社長は「社内に残り、従業員を教育したい」と述べ、引き続き社内に影響力を行使する意向も示した。【山田尚弘】
ウナギ国産偽装、200万匹…「魚秀」などに改善指示 06/25/08(読売新聞)
中国産ウナギを原料とするかば焼きを国産の地域ブランド「一色産ウナギ」の製品と偽装して販売していたとして、農林水産省は25日、ウナギ販売業「魚秀」(大阪市)と、水産業界最大手「マルハニチロホールディングス」の100%子会社の水産物卸売業「神港魚類」(神戸市)に対し、日本農林規格(JAS)法に基づき改善を指示した。
魚秀は偽装を認めた。同社は年間1200~1300トン(約960万~1040万匹)のウナギを中国から輸入している。
魚秀は不正の発覚を逃れるため、神港魚類との取引の間に、架空会社を介在させるなどの隠ぺい行為を行っていたことも判明。同省は「悪質性は相当高い」と判断した。
農水省によると、徳島市に事業拠点がある魚秀は今年3月~4月、原料原産地が中国産のウナギのかば焼きに「愛知県三河一色産」と虚偽の表示をし、同県岡崎市に所在地があるとする「一色フード」を製造会社と称して、少なくとも256トン(約205万匹)を東京都内の商社2社を経由して神港魚類に販売。このうち、約49トンは西日本一円の卸売業者に売却された。一色フードは住所も架空で、製造・販売の実態もなかった。
魚秀は、神港魚類からの代金を受け取る際、口座を通さずに現金で決済したり、現物を送る物流会社の伝票に自社の名前が残らないような工作をしたりしていたという。
魚秀の中谷彰宏社長らは徳島市内で記者会見し、偽装は今年2月から始まったことなどを明らかにした。中谷社長は、中国産ウナギの在庫を大量に抱え、消費者の間で中国産食品への不安が高まったことが偽装のきっかけとし、「悪いのはわかっていたが、なるべく早く(在庫を)はけさせたいという思いから始めた。一色産なら有名なので売れると思った。食への不信感を募らせることになり申し訳ない」と謝罪した。
神港魚類の大堀隆社長らも神戸市の本社で記者会見し、「消費者に迷惑をかけ申し訳ない」と述べたが、偽装の認識については「魚秀から紹介された東京の会社から商品を購入していただけ」と語るにとどまった。
農水省によると、神港魚類も魚秀から事実を知らされ、偽装を認識していた。
鋼材不祥事、計10社に JIS認証品に値上がり懸念 06/19/08(読売新聞)
経済産業省は18日、鋼材の品質データ偽造や規格との不整合などの問題が、特殊鋼メーカーの不二越など新たに4社で見つかったと発表した。一連の不祥事は最終的に国内の鉄鋼メーカー90社のうち大手4社を含む計10社に拡大した。行き過ぎたコスト削減が一因とみられ、取引中止や当該品種の値上がり懸念も出始めた。
不二越以外で問題が発覚したのは三菱製鋼室蘭特殊鋼、大同特殊鋼、淀川製鋼所。不二越は工具用の鋼材について契約上必要な硬さ試験を実施したかのように装い、データを偽造していた。三菱は、不純物の有無を見る顕微鏡検査を実施していたが、その頻度が日本工業規格(JIS)が求める基準に満たなかった。
大同と淀川は、鋼材の品質は確保されており、データの偽造もなかったとされるが、契約やJIS認証を満たす上で手続きミスがあった。JIS認証が取り消される可能性は4社ともないという。
ただ、JFEスチールのデータ偽造が発端となった一連の不祥事は、大手から中小メーカーまで業界ぐるみの様相が強まった。日本鉄鋼連盟は18日、宗岡正二会長(新日本製鉄社長)名の陳謝コメントを発表。加盟社の副社長らが話し合って品質管理のガイドラインを設ける、とした。
子会社のJIS認証が取り消される可能性がある国内4位、神戸製鋼所の犬伏泰夫社長は同日の取材に「言い訳しようもない」と前置きした上で、「7年ほど前に多くの鉄鋼メーカーが生きるか死ぬかという状況に追い込まれ、コスト意識が強くなり過ぎた。それが(一連の不祥事の)きっかけかもしれない」。
現場は混乱している。ある配管工事会社は、新日鉄子会社でJIS認証が取り消されたニッタイからステンレス鋼管を仕入れ、工場の空調向けに加工していたが、「うそをついていたニッタイからは、もう仕入れない」(幹部)。
ステンレス鋼管(継ぎ目無しを除く)は、国内シェアの約1割を占めるニッタイだけではなく、約2割の日新製鋼と約1割のナストーア(日本冶金工業子会社)もJIS認証を取り消された。認証のあるステンレス鋼管が品薄になるとみられ、値上がりは避けられそうにない。この幹部は「調達費が増える分は、加工品の納入先に負担してもらえるだろうか」と心配する。プラントメーカーなども、鋼材の調達先や品質について調査を進めている模様だ。
株式市場も反応している。新日鉄の株価は、子会社ニッタイの不祥事を発表した5月29日以降、日経平均の上昇に逆行し約6%下落した。(江渕崇、堀内京子、山本精作)
鋼管の試験データねつ造、神鋼・新日鉄などの子会社でも 06/11/08(読売新聞)
鉄鋼大手で相次いで発覚している鋼管の試験データ捏造(ねつぞう)問題で、神戸製鋼所(本社・神戸市)などの子会社3社で、新たに強度・耐圧試験を省略し、データを捏造して製品を出荷していたことが11日、わかった。
無試験の製品は鋼材・鋼棒が1288トン、鋼管が98万本余に上る。
データ捏造が判明したのは、神戸製鋼所の子会社「日本高周波鋼業」富山製造所(富山県射水市)、新日本製鉄の子会社「ニッタイ」野田工場(千葉県野田市)、日本冶金工業の子会社「ナストーア」茅ヶ崎製造所(神奈川県茅ヶ崎市)。
各社の発表などによると、日本高周波鋼業富山製造所では、ドリルの歯に使用される高速度工具鋼材206トンについて、日本工業規格(JIS)で義務づけられている強度試験を実施せず、過去のデータを基に試験データを捏造して出荷。配管同士をつなぐためのステンレス鋼棒1082トンも出荷先の条件を満たしていなかった。
ナストーア茅ヶ崎製造所では、ステンレス鋼管の一部についてJISで義務づけられた水圧試験を行わずに、データを捏造して出荷。無試験の鋼管は計97万6000本に上る。
経済産業省はナストーアについて、工業標準化法違反の疑いがあるとして、認証機関による立ち入り検査を11日に実施。日本高周波鋼業については12日に実施する。
このほか、ニッタイ野田工場では化学プラントの配管で使用するチタン溶接管など約5300本の水圧試験を実施しないまま、取引先が要求する数字をそのまま記入して出荷していた。
一方、日本金属工業(本社・東京都新宿区)の子会社「日金工鋼管」(愛知県碧南市)では、マンション空調用配管などの鋼管約4万6000本で検査証明書の記載に不備があった。実際に行った試験とは別の試験名が記載されていた。
一連の問題を巡っては、経産省が13日までに鉄鋼各社に総点検を行うよう求めている。
下水道談合復活の重電各社、公取委が立ち入り検査 06/10/08(読売新聞)
下水道施設に使われる電気設備工事を巡り、独占禁止法違反容疑(不当な取引制限)で刑事告発された重電各社が談合を復活させた疑惑で、公正取引委員会は10日午前、日立製作所や東芝、三菱電機など1995年に告発した8社を含む計9社の本社や北海道支社などと札幌市役所を同法違反容疑(同)で立ち入り検査した。
同市が発注する工事を巡る容疑。受注予定者について市側から「意向」が出ていたとの情報もあり、公取委は官製談合防止法の適用も視野に、調べを進める。
ほかに立ち入り検査を受けたのは富士電機システムズ、明電舎、安川電機、日新電機、神鋼電機、東洋電機製造。関係者によると、9社は2003~05年度ごろ、同市建設局(05年3月までは下水道局)が発注した電気設備工事を巡って、市側から伝わった意向に従い、受注予定業者を決めるなどした疑いが持たれている。
同市発注工事の年間市場規模は数十億円に上る。95年に告発された9社のうち、高岳製作所は札幌市を巡る容疑では、検査対象から外れた。東洋電機製造は前回は告発されていない。
95年に告発された談合でも、自治体からの意向の存在が明らかになったが、当時は発注機関の関与を規制する法律がなく、自治体の責任は問われなかった。
官製談合防止法は、北海道庁発注の農業土木を巡る談合(2000年5月排除勧告)で発注機関の関与が明らかになり、官の責任追及を求める声が強まったことから03年1月に施行された。同月末に北海道岩見沢市が同法による摘発第1号になった。
民営化高速道路会社、所得隠し1億8千万…経費前倒し 06/09/08(読売新聞)
日本道路公団民営化でできた「東日本高速道路会社」(東京都千代田区)が、コンサルタント会社に発注した調査費の計上時期を意図的に前倒ししたとして、東京国税局から2007年3月期までの2年間で約1億8000万円の所得隠しを指摘されたことがわかった。
単純な経理ミスを含めた申告漏れは計約38億5000万円に上り、追徴税額は重加算税を含めて約13億円。同社は今月5日、修正申告して納付も済ませた。
同社の発表によると、複数のコンサルタント会社に外注した道路設計などの調査について、外注先からの調査報告書の受け取りが翌年度にずれ込んだのに、納品書の日付を改ざんして年度内に受け取ったように装った点について、同国税局から不正だと認定された。
このほか、工事の積算システムなどの改修費を経費として計上していたが、同国税局から「会社の機能が向上しており、資産として計上すべきだ」と申告漏れを指摘された。
裏金「役員の指示で運んだ」…西松建設の元社員が供述 06/08/08(読売新聞)
東証1部上場の中堅ゼネコン「西松建設」(東京都港区)が、海外から裏金約1億円を無断で国内に持ち込んだとされる事件で、同社元社員が東京地検特捜部の調べに、「役員から指示され、東南アジアの事業で捻出(ねんしゅつ)した裏金を持ち込んだ」と供述していることが分かった。
元社員は裏金を航空機の手荷物に入れて運んでいたことも判明。特捜部は役員ら同社上層部が関与していた可能性が高いとみて、外国為替及び外国貿易法(外為法)違反容疑で慎重に調べを進めるとともに、裏金の使途にも関心を持っている。
同社関係者などによると、同社は東南アジアで請け負った工事に絡んで不正な経理操作を行い、裏金を捻出。2005年ごろ、当時の同社社員が裏金のうち約1億円を、航空機で帰国する際に複数回に分けて手荷物に入れ、日本円で国内に持ち込んだが、税関には届け出なかったという。
この社員はすでに同社を退社しており、特捜部の調べに対し、こうした経緯を認めた上で、「会社の役員から、海外で作った裏金を国内に運ぶよう指示された」などと供述している。
外為法では、国外から100万円を超える現金を持ち込む際、税関に届け出るよう義務付けており、違反した場合は6月以下の懲役か20万円以下の罰金が科せられる。特捜部は今月4日、同法違反容疑で同社本社や関係先数か所を捜索した。
同社は1937年設立。主に大型土木工事を手がける中堅ゼネコンで、香港や東南アジアで受注実績がある。特捜部の捜査を受けていることについて、西松建設総務部は「捜査の目的が分からないのでコメントは控えたい」としている。
工場の規則だとか、会社の規則だとか、うるさいことを言う割には、自分達に
都合の良い事は偽装したり、守らなかったりするんだよね!製造所長はそんな
人間かもしれない。そしてそんな製造所長に何もいえない「YES」マンの部下。
ISOを取得しているのか知らないが、取得していたらISOはもう必要ないだろう。
ISOの意味はない。今回は新日鉄子会社のニッタイ(千葉県野田市)の不正で
怖くなった人達が今なら許されると思って公表したのだろう。
ステンレス鋼管データ、日新製鋼も偽造 06/04/08(読売新聞)
日新製鋼は4日、工場配管などに使うステンレス鋼管計55万本で、日本工業規格(JIS)に必要な水圧試験などをせずに、試験済みを装って出荷していたと発表した。工業標準化法違反の疑いがあり、当該品種のJIS認証が取り消される可能性が高い。
日新製鋼は国内の鉄鋼5位。鋼管の品質に関するデータ偽造は、2位のJFEスチール、首位の新日本製鉄に続き3社目で、業界内で偽造が横行していた実態が明らかになった。
日新で必要な試験をしていなかったのは同社尼崎製造所(兵庫県尼崎市)。JFEなどの不祥事を受けて、記録の残る過去5年間分を調べたところ、2品種の約55万2400本で水圧試験などをした記録がなかった。これらの鋼管は、出荷時の証明書に「GOOD」と記載して試験をパスしたように装い、国内の鉄鋼問屋やゼネコンなど300社以上に出荷していた。2日に経済産業省に報告し、当該品種の生産と出荷を止めた。
4日に会見した松永成章副社長は「試験には時間がかかるので生産性が落ちると製造所長が判断したようだ。組織ぐるみと言われてもやむを得ない」と陳謝した。
尼崎製造所には同日、民間のJIS認証機関が立ち入り検査をした。同様の不祥事が発覚した新日鉄子会社のニッタイ(千葉県野田市)は既に認証を取り消されており、生産停止が長期に及ぶ見通しになっている。(堀内京子)
「松永成章副社長は記者会見で『不正はいまの製造所長も承知していた。少なくとも5年前に
始まっていたと認識している』と話した。」
製造所長がどのような人間なのか知らない。製造所長よりも上の幹部は不正を知らなかったのか、
このような不正が上に伝わる制度が日新製鋼に存在しないのか、経済産業省は調べて公表するべきだ。
結局、ばれなければ不正は日本では受け入れられているのだろう。品質的には問題ないのだろうが、
品質まで犠牲にする企業が増え、試験を偽装すれば、秩序が保てなくなる。製造所長が誰かの
圧力で動いたのか、個人の判断であるなら、人間的には尊敬出来ない人物なのであろう。
耐圧試験行わずに鋼管出荷、日新製鋼も55万本 06/04/08(読売新聞)
鉄鋼大手の日新製鋼(本社・東京都千代田区)は4日、マンションの給水給湯配管などに使用される円筒状鋼管を、日本工業規格(JIS)が義務づける耐圧試験を行わないまま合格したように偽装し、出荷していたと発表した。
過去5年間で計約55万本に上るという。同社が東京都内で開いた記者会見で明らかにした。経済産業省は、工業標準化法違反の疑いがあるとして厳重注意し、調査に乗り出した。
同社によると、尼崎製造所(兵庫県尼崎市)で、過去5年間の試験記録を調べたところ、一般配管用の鋼管約248万5000本のうち約7万2000本で、穴の有無などを調べる「耐漏れ試験」が、工場配管用の鋼管約431万1000本のうち約48万本で、水圧試験が、それぞれ行われていなかった。
無試験の鋼管は直径約9~22センチ、長さ約3~4メートルで、製造所内にある品質保証部門が検査証明書に「GOOD」と記していた。国内メーカー延べ483社に出荷された分に含まれているという。
同社は「検査には10~20分程度の時間がかかるため、他の鋼管の生産量が減少してしまうことが懸念された。クレームもなかった」と説明している。
JFEスチール、新日本製鉄で相次いで鋼管の強度試験を巡るデータ捏造(ねつぞう)問題が発覚したのを受け、社内調査した結果、判明した。登録認証機関が4日、立ち入り検査を実施。不正が確認されれば、JIS認証が取り消される可能性も出ている。日新製鋼は不正が見つかった2種類の鋼管の製造・出荷を停止した。
松永成章副社長は記者会見で「不正はいまの製造所長も承知していた。少なくとも5年前に始まっていたと認識している」と話した。
大きければ潰されない。大きければ政治家の力で何とか成る。
そう言う時代は終わらせなければならない。日雇い派遣大手グッドウィルは
変われないだろう。後は行政とマーケットが決めることだ。
「支店長名ばかり、本社が実権」グッドウィル経験者証言 06/04/08(朝日新聞)
日雇い派遣大手グッドウィルの派遣労働者を港湾関連会社が二重派遣したとされる事件では、グッドウィルの当時の支店長やその統括役が職業安定法違反の幇助(ほうじょ)容疑で逮捕された。ただ、支店長経験者は「大口契約では実質的権限を本社が握っている」と証言する。警視庁は歴代役員を含む同社幹部らから事情を聴くなどして、かかわりを調べている。
「どこの支店でも社員は2~3人で、支店長とは名ばかり。契約企業については本社が権限を握って指示しており、責任は重い」。関東地方でグッドウィルの支店長を3年近く務めた20代の男性は内情を話す。
男性は05年に入社。直後に、支店で支店長に次ぐサブマネージャーになった。「入社から5日間研修を受けたが営業の話ばかり。守らなければならない法律についてはほとんど説明を受けなかった。採用翌日から支店長の人もいた」。半年足らずで支店長に昇任し近くの支店に異動。別の支店でも支店長を務めた。
関係者によると、支店の社員は支店長とサブマネージャーの2人しかいないことも多い。あとはアルバイトが、数十人から数百人の派遣労働者と派遣先企業との連絡など実務に当たる。
男性は「派遣先との細かい交渉はブロック長やエリアマネージャー、統括部長など支店を統括する立場の人がする。大手からは多額の現金が払われるため役員が直接交渉することもあった」と明かす。本社には、労働災害や行政指導などトラブルに対処するためのリスクマネジメント課という組織図に載っていない部署もあったという。
支店の仕事は営業が主で、繁忙期には泊まり込んだ。ブロック長からだけでなく役員からも契約企業を増やすよう指示するメールや電話がよく届いた。「支店にもランクがあり、競わされた。退職率が高く、その度に入社間もない社員が支店長になっていた」
本社幹部に華やかな場所に連れて行ってもらうことも多く「感覚がまひしていった人もいた」と話す。必要な資格を持つ支店長らが名義を貸して、無資格の社員が実質的に支店長を務めている支店もあったという。
グッドウィルには派遣先の業種により、運転手ならEX(エクスプレス)、パチンコ店ならAM(アミューズメント)、飲食店ならFC(フードキャスティング)など様々な支店の区分があった。だが形式だけで、人が足りないと貸し借りしていたという。
「派遣は日本の雇用に不可欠で、派遣業はなくてはならない業態。グッドウィルの反省を生かし、労働者中心の業界にしないといけない」。男性はグッドウィルが家宅捜索を受けたあと、小さな派遣会社に移った。派遣業の健全化を願い、捜査を見詰める。(小林誠一、伊藤和也)
グッドウイル:二重派遣、常態化か 改善命令後も継続 06/04/08(毎日新聞)
日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京都港区、GW)による労働者の違法派遣事件で、GWが05年6月に厚生労働省から「偽装請負」などで事業改善命令を受けた後も、職業安定法で認められていない「二重派遣」を繰り返していたことが分かった。警視庁保安課は、違法派遣が常態化していたとみて、GW上層部の関与についても追及する。
調べでは、05年の行政処分は、この年の4月に東京都渋谷区のビル改修工事現場で発生した作業員7人の一酸化炭素中毒事故がきっかけだった。負傷した作業員はGW池袋支店から建設業者へ派遣され、労働者派遣法で禁じられている建設業務に従事していたことが判明。さらにGW池袋支店と建設業者が請負契約を結んでいたにもかかわらず、実際は建設業者が作業員を指揮する「偽装請負」だったことが分かった。厚生労働省は同年6月、GWに事業改善命令を出した。
今回、職業安定法(労働者供給事業の禁止)違反ほう助容疑で逮捕されたGW事業戦略課長、上村泰輔容疑者(37)らは、港湾運送会社「東和リース」(港区)が別の派遣先に二重派遣することを知りながら、労働者を派遣した疑いが持たれているが、この二重派遣は04年10月から07年6月まで、新宿など5事業所で行われていた。また、静岡や千葉県内などの62事業所も07年8月まで、建設業務への派遣や二重派遣を繰り返していた。
厚労省の事業改善命令を受けた後も、全国各地で違法な二重派遣を繰り返していたことになる。
このことについて、GWは「(行政処分を受け)違法派遣を防止するためのチェックシートの導入を進めていたが、契約内容などの確認が不十分だった」と釈明している。【武内亮、町田徳丈】
PCI事件、ODA裏金を立件へ…1億数千万円プール 05/31/08(読売新聞)
中国での遺棄化学兵器処理事業を巡る詐欺事件などで摘発された大手コンサルタント会社「パシフィックコンサルタンツインターナショナル」(PCI、東京都多摩市)が、東南アジアの政府開発援助(ODA)事業に絡み、香港の関係会社を使い、過去数年間に1億数千万円の裏金をプールしていたことが分かった。東京地検特捜部は悪質な所得隠しにあたるとみて、PCI元幹部らを法人税法違反(脱税)容疑で立件する方針を固めた。遺棄兵器ビジネスを巡る事件は、ODAを舞台にした不正経理事件に発展する見通しになった。
PCI関係者によると、香港の会社は2003年ごろ、同社を退社していた元常務が設立した。PCIは、東南アジア諸国のODA事業を受注するための情報収集などをこの香港の会社に委託し、調査費として毎年計約1億円を送金。香港の会社はこの資金を、各国の政府関係者などから情報収集する民間ブローカーに支払っていた。
ところが、特捜部が調べたところ、香港の会社に送金された金の一部は裏金としてプールされ、その額は過去数年間で計1億数千万円に上ることが判明。裏金作りは当時のPCI幹部も把握しており、特捜部では、裏金がどのように使われたか解明を急いでいる。
PCI元幹部によると、少なくとも1990年代までは、ODAの受注を有利に進めるため、PCI側は東南アジアの政府高官にリベートを支払っていた。PCI関係者は「香港の会社に支払われた金の中には、政府高官に渡ったものもあるはずだ」と指摘する。
PCIは02~06年度に総額543億円のODA事業を受注している。同社は「捜査中なのでコメントできない」としている。
データねつ造の新日鉄子会社、JIS表示認定を取り消し 05/30/08(読売新聞)
鉄鋼最大手の新日本製鉄(本社・東京都千代田区)が出荷した円筒状鋼管の水圧試験データ捏造(ねつぞう)問題で、品質保証の民間認定機関「日本品質保証機構」は30日、データを捏造した同社子会社「ニッタイ」野田工場(千葉県野田市)に対し、工業標準化法に基づき、日本工業規格(JIS)の表示認定を取り消した。
経済産業省が同日発表した。
経産省によると、認証取り消しは、認証業務を国から同機構に委ねた2005年10月のJIS法改正以来初めて。6か月間は再取得できないという。
JISマークがなくても、製品の製造は可能だが、取引先の信用を得にくく、ニッタイは「事実上、ほとんどの製品の出荷ができなくなる」とみている。
ニッタイは昨年1月30日に同機構から認証を受け、この5年間で約12万6000本を生産・出荷。大半がJISマークを付けていたという。
新日鉄広報センターは「今回の決定を厳粛に受け止める。当社グループの品質監査のあり方について、見直し改善を図り、信頼回復と再発防止に全力を尽くす」としている。
グッドウィル高級老人ホーム、柱など800か所に不整合 05/30/08(読売新聞)
介護事業を手がけていたグッドウィル・グループ(GWG、東京)が東京都世田谷区内に開設した高級有料老人ホームで、建築確認を受けた設計に比べ、実際の鉄筋本数が少ないなどの不整合が多数あることが、30日、東京都の調査でわかった。
食い違いのある柱や梁(はり)などの部材は、約800か所確認された。事態を重視した都は、建築基準法上の耐震強度を満たしているかどうかの検証を始めた。GWGなどは同日午後、説明会を開き、入居者にこうした経緯を説明する。
この有料老人ホームは、2006年5月に開設された「バーリントンハウス馬事公苑」(7階建て、139室)。構造計画研究所(東京)が構造設計を担当。指定確認検査機関の日本建築設備・昇降機センター(同)が建築確認を行い、東急建設(同)が建設した。入居一時金は1室5000万円台から3億円。入居者約70人の平均年齢は75歳で、うち2割が要介護・要支援の状態にある。
関係者によると、不動産コンサルティング会社「ゼクス」(同)が昨年12月に、約200億円で、同施設と都内の別の施設計2か所をGWGから取得する予定だった。ところが、ゼクス側が「馬事公苑」の建築関係書類をチェックしたところ、建築確認時の設計と実際の建物の間で、柱や梁の鉄筋本数が少ないなどの食い違いが見つかった。このため、同施設の運営だけは予定通りゼクスに引き継がれたが、譲渡はこれまで延期されている。
相談を受けた都が同センターや東急建設から提出された資料などをもとに詳細に点検した結果、地下1階から7階の柱や梁など計約3000か所のうち、3割弱の計約800か所で不整合が確認された。このうち、柱と床ではそれぞれ100か所以上あったという。
一部は鉄筋本数が増えていたケースもあったが、本数が減ったり鉄筋の間隔が広がったりしていた例が多かった。都は最終的な不整合の確定作業を急ぐとともに、GWG側に対し、建築基準法に基づく構造計算の再検証と報告を求めている。
構造計画研究所は読売新聞の取材に、「都からこれまで指摘を受けた不整合の大半は、計画変更の手続きの中で修正され、解消されていると考えている。さらに指摘事項の精査を続けているが、一部に不整合があったことは事実で、これを真摯(しんし)に受け止め、社内で再発防止に全力で取り組んでいる。ただし自社検証の結果、建物の安全性に問題はないと認識している」と説明。同センターは、「不整合は本来あってはならないことで、内容を精査したい」と話している。東急建設とGWGは、「入居者説明会が終わるまで取材には応じられない」としている。
一方、国土交通省住宅局では、「不整合が都の調査通りとすれば、建築基準法上、問題だ。安全性を早急に確認すべきだ」として、都を通じて報告を求めている。
「GPが15日の記者会見で送り主の了承を得ずに入手したと発表。『(乗組員の)横領行為の
証拠として提出するためで、違法性はない』と主張している。」
本当とは思えないけど、「データ捏造は工場長の判断」が事実と言うのであれば、
退職金無しで解雇だな!新日鉄の名前を汚し、工場長の権限を乱用したことになる。
工場長だから何をしても良い、何を命令しても良いとは思わない。この工場長を任命した
人間達にも責任があるだろう。
「データ捏造は工場長の判断」新日鉄などが会見 05/29/08(読売新聞)
鉄鋼最大手の新日本製鉄(本社・東京都千代田区)が出荷した円筒状鋼管の水圧試験データが捏造(ねつぞう)されていた問題で、同社などは29日、千葉県庁で記者会見し、捏造は、同社から子会社「ニッタイ」(本社・千葉県野田市)野田工場に出向後、転籍した工場長(56)の判断で行われていたことを明らかにした。
ニッタイは工場長に対する処分を検討している。両社によると、工場長は、現場作業者に対し「水圧試験はやらなくていい」と指示。作業日誌に、架空の数値を記入させていた。
新日鉄、データねつ造…鋼管12万本を試験せずに出荷 05/29/08(読売新聞)
鉄鋼最大手の新日本製鉄(本社・東京都千代田区)が、天然ガスプラントなどに使用される円筒状鋼管を日本工業規格(JIS)が義務づける水圧試験が行われていないのに捏造(ねつぞう)されたデータのまま出荷していたことがわかった。
報告を受けた経済産業省は、工業標準化法違反にあたる疑いがあるとして調査に乗り出す。
関係者によると、千葉県野田市の新日鉄子会社「ニッタイ」野田工場で、過去5年間の作業日誌を調べたところ、鋼管約12万6000本のうち約12万本で水圧試験が行われていなかった。
試験結果の数値をでっちあげ、試験に適合したように装って鋼管を「新日鉄ブランド」として国内約100社に出荷していた。鋼管は直径約1メートル~20センチ、長さ11~4メートル。ステンレス製で、工場の配管などとして使われている。
不正は工場長が指示していたとみられる。野田工場は27日付ですべての出荷を停止した。
ニッタイは「これまで安全性で問題になってはいない。調査を進めており、結果が判明ししだい公表したい」としており、新日鉄は、納入先などへ事情説明する。経産省の第三者機関は29日にも、ニッタイに立ち入り検査する方針。
鋼管の強度試験を巡るデータ捏造は、鉄鋼大手のJFEスチール(本社・東京都千代田区)の東日本製鉄所千葉溶接管工場でも明らかになり、経産省が厳重注意している。
スカイネットアジア航空の病歴隠し、新たに3人 05/23/08(読売新聞)
スカイネットアジア航空(宮崎市)が自社の操縦士に対し、国の身体検査で病歴を隠すよう指示していた問題で、同社は23日、新たに3人で同様の不正が確認されたと国土交通省に報告した。
同社によると、3人は2007~08年の検査時に腹部や目の治療歴を申告しなかった。
いずれも本人や上司が「軽い治療で申告の必要はない」と勝手に判断していたという。
JFE、十数年前から手書きでグラフ捏造…専用の定規なぞる 05/22/08(読売新聞)
鉄鋼大手のJFEスチール(本社・東京都千代田区)が、石油パイプラインなどに使われる鋼管の強度試験のデータを捏造(ねつぞう)していた問題で、東日本製鉄所千葉溶接管工場の作業員らが水圧試験のグラフを手製の定規を使って試験紙に手書きするなどの単純な方法ででっち上げていたことが、関係者の証言でわかった。関係者は「十数年にわたって捏造していた」とも話しており、同社は捏造が始まった経緯や社内のチェック体制などを詳しく調査している。
関係者らによると、鋼管を水圧試験の検査機にかけると、データは専用の試験紙にグラフの体裁で印字される仕組みになっている。グラフの横軸が圧力、縦軸が時間を表している。
捏造は、薄いプラスチックを切って作った定規を未使用の試験紙に当て、定規をなぞって線を引く方法が一般的だった。グラフの形状は鋼管の種類によって異なるため、定規も十数種を作製。検査機と同じインクを使うペンも作製していたという。
作業は、工場内の試験機近くにある作業小屋で行われ、机の引き出しに定規やペンとともに未使用の試験紙が常備されていた。時間に余裕があるときにデータをまとめて捏造して、保管しておくこともあった。このほか、1本の鋼管の水圧試験を何度も繰り返して試験紙を作りため、他の鋼管に流用したこともあったという。
捏造された試験紙は現場で保存して品質保証室には結果のみを報告。同室が米国や日本国内などの納入先に検査証明書を提出した。同社の調査では、品質保証室はデータ捏造には関与していなかったとみられる。
また、関係者は「作業責任者が捏造を指示していた」としているが、同社はどのレベルまで捏造を承知していたかなどについて調査することにしている。
同製鉄所総務部は「偽のデータは過去のものをパターン化して書いていたと(社内調査で)聞いている。捏造用の道具があったかどうかについては、よく調べてみないとわからない」としている。
【衝撃事件の核心】美人姉妹殺害の現場も…階数水増しのマンション 05/16/08(産経新聞)
「サ~ビスサッサ 賃貸住宅サ~ビス~」
関西人にはテレビCMでおなじみの不動産賃貸会社「賃貸住宅サービス」。同社を含む関連会社数社を束ね、大阪市内を中心に約1200棟(約2万5000室)の管理物件を持つ不動産管理会社「ユービー」(大阪市淀川区)のマンションで、建築確認申請時よりも階数を水増ししたマンションの存在が発覚した。
その中には2年前、大阪市浪速区で27歳と19歳の美人姉妹が殺害された事件の現場マンションも含まれていた。
■12階建てだけど13階建て?
ユービーによるマンションの階数水増し問題は、フリーライターによるインターネットサイトの記事が発端。
大阪市淀川区宮原のマンションが不動産登記では12階だが、本当は13階になっているという内容だった。
実際に登記上は12階だが、ユービーのサイトでこの物件を確認すると13階、現地で階数を確認してももちろん13階だ。
マンション内のエレベーターのボタンは13階部分だけが白いプラスチック板で覆われ、押せない仕組みになっていた。
ほかにも同様の階数水増しが7棟も見つかった。
■「信用と信頼」の看板
これらのマンションは、申請内容より1階高い物件もあれば、2階高い物件もあった。なかでも注目されたのが浪速区塩草の10階建てマンションだ。
申請では地上8階地下1階となっていたが、注目の理由は水増しではない。
取材で現地に足を運べば、大阪社会部の記者ならほとんどが気付く。
「あれ、ここって数年前に姉妹が殺されたマンションですよ」
平成17年11月、当時27歳と19歳の姉妹が、24歳の男=死刑確定=に殺害された事件の現場マンションだった。
凄惨な事件だっただけに、人々の記憶にも残っているマンションだが、屋上広告には「信用と信頼…」の文字が。
■鈍感と取材無視と
話はマンションの階数水増しに戻る。
一連の問題をめぐっては、大阪市建築指導部の対応にも疑問が残る。
当初は反応も鈍く、「申請と違うからといって、すぐに建築基準法違反とはいえない。最終的に容積率がオーバーしていたら違法にはなるが…。建築計画の変更手続きがなかったという問題はある」といったものだった。
一方、ユービーは不正が発覚した13日以降、マスコミを無視し続けた。
報道各社が本社に集まっているにもかかわらず、「担当幹部がいない」の一点張りで逃げ切ろうとした。
3日後の16日になってようやく社長名の謝罪文をファクスで送ってきたが、「時すでに遅し」の感が。信用も信頼も大きく揺らいだ。
「GPが15日の記者会見で送り主の了承を得ずに入手したと発表。『(乗組員の)横領行為の
証拠として提出するためで、違法性はない』と主張している。」
環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(GP)の主張は間違っている。
たしかに、証拠を抑えない限り共同船舶は調査すると言うだけで、適切な調査などしない
可能性も高い。しかし、「送り主の了承を得ずに入手」はおかしだろ。もちろん、逮捕されてでも
(乗組員の)横領行為を公にしたいのであれば「グリーンピース・ジャパン」(GP)の選択だが!
宅配鯨肉紛失はグリーンピースの窃盗? 西濃運輸が青森県警に被害届 05/16/08(産経新聞)
日本の調査捕鯨船「日新丸」の乗組員が鯨肉を横領したとして、環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(GP)が東京地検に告発状を提出した問題で、乗組員の荷物を扱った「西濃運輸」(岐阜県大垣市)が16日、鯨肉の入った荷物1個をGPに盗まれた疑いがあるとして、青森県警に被害届を提出した。
西濃運輸によると、被害に遭ったのは、乗組員が15日に東京港から北海道函館市の自宅に送った段ボール箱4箱のうち1箱。中には鯨肉などが入っていた。16日午前8時半過ぎ、青森に到着、函館行きのトラックに積み込む際、紛失に気づいた。
同社は配送ミスの可能性もあるとみて調べていたが、GPが15日の記者会見で送り主の了承を得ずに入手したと発表。「(乗組員の)横領行為の証拠として提出するためで、違法性はない」と主張している。
また、調査捕鯨を担当した共同船舶は「明らかな窃盗行為で、法的手段を含め対応をする」としており、週明けにも今後の対応を協議する。
調査捕鯨肉持ち出し疑惑で保護団体が告発状、水産庁は調査指示 05/16/08(読売新聞)
調査捕鯨で捕獲されたクジラ肉の一部が、乗組員によって大量に持ち出されているという情報が寄せられた問題で、水産庁は15日午後、調査捕鯨の実施主体の財団法人「日本鯨類研究所」(鯨研)と、捕鯨に使用する船や乗組員が所属する船会社「共同船舶」の関係者を同庁に呼び、乗組員の聞き取りなど詳細な調査を行うよう指示した。
この問題を独自に調査した環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」は同日午後、調査捕鯨船の乗組員12人について、業務上横領容疑での告発状を東京地検に提出した。
共同船舶は、読売新聞の取材に対し、自社で買い付けたクジラ肉の一部を捕鯨船団の全乗組員に1人約10キロずつ現物給与として無料で渡しているほか、それ以上の量のクジラ肉を希望する乗組員に対して、1人あたり約3キロを上限に売却していたと説明した。
◇
グリーンピース・ジャパンが、クジラ肉の入った段ボール箱を青森市内の宅配便の施設から無断で持ち出したと明らかにしたことを受け、宅配便会社の「西濃運輸」(岐阜県大垣市)は同日午後、青森県警青森署に遺失物として届け出をした。
乗組員が調査捕鯨のクジラ肉を横流し?水産庁が調査へ 05/15/08(読売新聞)
南極海で行われている日本の調査捕鯨で捕獲されたクジラ肉の一部が、乗組員によって大量に持ち出されているという情報が寄せられ、水産庁は実態調査に乗り出すことを決めた。
不正な持ち出しが確認されれば行政指導するとしている。
この問題を独自に調査した環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(東京・新宿区)の星川淳事務局長らは15日、記者会見し、調査捕鯨船の乗組員12人を業務上横領容疑で東京地検に告発すると発表した。
星川事務局長らは、先月に日本に戻った調査母船「日新丸」の乗組員12人が、クジラ肉を入れた段ボール箱計47箱を自宅などに宅配便で送っていたと指摘。メンバーが先月15日に都内の宅配便の配送所に立ち入り、伝票を目撃したため、翌16日に青森市内の宅配便の施設から無断で1箱を持ち出し、中から23・5キロのクジラ肉を見つけたことを明らかにした。同席した弁護士は「横領を告発するための行為で違法性はない」と主張している。
調査捕鯨は水産庁の許可を受け、財団法人「日本鯨類研究所」(鯨研)が実施。クジラ肉は売却され、調査費用に充てられている。
鯨研は捕鯨船団の全乗組員約220人に下船の際、クジラ肉を1人数キロずつ無料で配っていたことは認めたが、石川創・捕鯨調査部次長は「船室の狭さなどから大量に持ち出せるとは考えにくい。無料配布は慣例で問題ない」としている。
このような事が見逃されてきた事実が、
耐震偽装
の形となったのだろう。「工事後に必要な市の完了検査を受け」なくとも
問題にもならないし、指摘もされない。多くの人が知らないだけで建築基準法違反は
結構、あると思われる。
「9階建て」で申請のマンション 完成したら11階 05/14/08(朝日新聞)
大阪市の不動産会社「ユービー」(同市淀川区)と関連会社の「賃貸住宅サービス」(同)の所有する市内のマンション5棟が、建築時に市に申請した内容よりも階数を1~2階水増ししていたことが明らかになった。市は13日、建築基準法違反の疑いがあるとして調査に乗り出した。
市によると、同市淀川区宮原1丁目の賃貸マンションは現在13階建てだが、94年の建築申請時は12階としていた。同区の別のマンションも申請時の11階が現在は12階に、福島区のマンションも9階が11階に増築されていた。このほか北区の二つのマンションでも階数が一つ増えていた。
5棟については、工事後に必要な市の完了検査を受けておらず、いずれも書類上は「工事中」の扱いだった。市は階数の水増しが耐震性に影響している可能性もあると見て、詳しく調査をする。
ユービーの関連会社は、テレビコマーシャルなどで知られる「週刊賃貸住宅サービス」を発行している。
機長に「病歴」口止め、スカイネットアジア航空が身体検査で不正 05/13/08(読売新聞)
羽田―宮崎便などを運航するスカイネットアジア航空(宮崎市)の機長が航空機操縦に必要な身体検査を受けた際、同社の指示で申告すべき病歴を隠していたことが、国土交通省の調査でわかった。
身体検査を巡る会社ぐるみの不正は異例で、同省は13日、同社に業務改善勧告を行った。
同省によると、不正な身体検査が行われたのは、2人の外国人機長。このうち米国人機長(59)は2005年3月に採用後、がんの治療歴を申告したが、運航本部副本部長(当時)は、航空法が定めた身体検査で不合格になることを恐れて口止めを指示。機長は同年7月の検査に合格し、今年4月まで約2000時間の飛行を続けた。
検査は半年ごとに行われ、昨年の検査で機長が医師に病歴を告白して不合格になると、副本部長は再び口止めし、社内規定で認められていない別の医師の検査を受けさせていた。
スイス人機長(49)が06年の検査で脳波の異常が確認された際も、同じく社内規定で認められていない医師の診察を受けさせていた。
不正は同省に寄せられた投書で発覚。現在は2人とも乗務停止になっている。
国交省で記者会見した藤原民雄社長は「安全を脅かすような事態で責任を感じている」と陳謝した。同社は藤原社長に役員報酬の返上(50%、1か月)、不正に関与した幹部3人を降格などの処分を行った。
外国人研修「不正行為」 過去最高の449団体・企業 05/09/08(朝日新聞)
低賃金労働などが問題になっている外国人研修・技能実習制度で、不正行為をしていた受け入れ団体・企業が、07年は過去最高の449にのぼり、06年の2倍になっていることが分かった。9日、法務省が発表した。時給300円で時間外労働をさせたり、預金通帳を取り上げたりと、悪質な例が目立つ。
昨年の立ち入り調査で発覚した主な不正は、賃金の不払いなどの「労働関係法規違反」が178件▽多数を雇うために入国管理局に届けた企業以外で働かせた「名義貸し」が115件▽休日労働や残業をさせた「所定時間外作業」が98件などだった。
例えば、神奈川県の製菓会社では、「菓子製造の研修」として研修生を受け入れながら、実際には、出来上がった菓子を包む作業しかさせていなかった。福岡県の縫製業者は、研修・実習生が屋内用の靴のまま屋外に出ただけで、千円の罰金を賃金から差し引いていた。また、山梨県の機械製造業者は実習生から旅券と預金通帳を取り上げ、返却を求められても拒否していたという。
この制度を利用しているのは約1600企業と約1900団体。通報や告発に基づいて、法務省が全国の団体・企業を立ち入り調査し、不正行為が認められた場合には、入管法に基づき、最低3年間は研修生を受け入れられなくなる。(市川美亜子)
船場吉兆:アユは二度揚げ、刺身のツマは洗う……使いまわし手口明らかに 05/09/08(毎日新聞)
老舗料亭・船場吉兆(大阪市)の博多店(福岡市博多区)と天神店(同市中央区、現在は閉店)が客の食べ残しの食材(延べ9品目)を使い回していた問題で、具体的な手口が8日明らかになった。「アユ揚げ」は湯木正徳・前社長の指示で二度揚げされたほか、刺し身のツマはパート従業員が洗い、造り場(調理場)に持参していたという。博多店の河合元子店長は「鮮度が良いのは原則的に使い回していた。刺し身のツマについては店の多くの従業員が知っていた」と述べ、使い回しが常態化していた様子が浮かび上がった。
河合店長が8日、博多区保健福祉センターに提出した報告書によると、博多店の使い回しは99年3月のオープン直後から、閉店した天神店も同じく04年3月から行っていた。使い回した品目は、博多店が▽金時ニンジン▽ウド▽ボウフウ▽オオバ▽わさび▽刺し身▽アユのおどり場げの7品。天神店は金時ニンジンとボウフウの2品だったという。
報告書作成のため、博多店は辞めた店員も含めて聞き取り調査したという。河合店長は「実際に刺し身のツマを洗ったり、前社長の指示でアユを揚げ直すなどした人がいた」と話す一方、「私自身は見ていません」と関与していないことを強調した。今後の経営については「本社からの回答を待つのみです」と話した。【鈴木実穂】
野村証券のコメントをテレビで見たが、お粗末だった。京都大のブランドと日本語が堪能である
理由だけで採用したのか、採用する時の面接ではモラルや性格を軽視したのか??
勤務態度に問題ないと言っていたが、モラルが欠如した社員が入社した場合、野村証券の体制では
このようなインサイダー取引事件は防げないと言うことが明らかになった。組織的でなく、
個人的な犯罪とコメントしていた。しかし、組織としての防止対策はお粗末であることには変わりない。
個人の能力は結果を出すためには必要な要素だ。しかし、モラルや人間性に問題がある場合、
個人的な能力よりもモラルや人間性を重視するべきだろう!野村証券は少なくともブランド重視で
モラルや人間性などの内面を重要視しないのであろう。しかし、モラルも必要であることを
認識させる良い教訓になってほしい。野村証券だけでなく、個人の能力だけでなくモラルや性格も
採用には考慮することを大手企業は認識するべきだろう。企業の不祥事を見ればわかることであろう。
野村証券社員インサイダー:容疑で社員ら逮捕 5000万円利益か--東京地検特捜部 04/23/08(毎日新聞 東京朝刊)
証券最大手の野村証券を舞台にしたインサイダー取引事件で、東京地検特捜部は22日、同社社員ら中国人3人を証券取引法(現・金融商品取引法)違反容疑で逮捕した。3人は東証2部上場の富士通子会社の内部情報をもとにインサイダー取引をした疑い。逮捕容疑以外にも、企業の合併・買収(M&A)情報を利用した取引をしていた疑いがあり、特捜部は証券取引等監視委員会と連携して全容解明を目指す。
逮捕されたのは▽野村の企業情報部に在籍し、現在は香港の現地法人に勤務している〓瑜(れいゆ)(30)=同日付で懲戒解雇▽留学先の京都大に同時期に在学していた知人の蘇春光(37)▽弟の蘇春成(25)の3容疑者。〓容疑者は容疑を大筋で認めているとみられる。
調べによると、企業にM&Aを提案する企業情報部に所属していた〓容疑者は昨年4月、野村が東証2部上場の電子部品製造会社「富士通デバイス」とアドバイザリー契約を結んだ際に契約担当を務め、同社が株式交換によって富士通の完全子会社になる内部情報を入手。公表前の昨年5月8~24日、計7000株を1169万円で購入した疑い。
〓容疑者から内部情報を聞いた蘇春光容疑者が、弟の蘇春成容疑者らの名義の口座を使って株の売買をしていたという。富士通デバイスは同月24日に完全子会社化を発表し、同日に1655円だった株価が2100~2500円台に急騰。〓容疑者らは公表後の6月15日に全株を売り抜け、約490万円の利益を得たとされる。
野村がM&Aの企画・提案をして、〓容疑者らが買い付けた銘柄は、富士通デバイス株を含めて計21銘柄に上り、約5000万円の利益を得ていたことも判明。監視委の強制調査容疑の一つとなった筒中プラスチック工業株は、06年10月に購入して売り抜け、約100万円の利益が出たという。また、06年7月に王子製紙が発表した北越製紙に対する敵対的TOB(株式の公開買い付け)でも、公表前に北越製紙株を買い付けたとされる。
◇「チェック限界あった」--渡部社長が謝罪会見
社員のインサイダー事件を受けて22日夜に記者会見した野村証券の渡部賢一社長は、「証券市場を汚す重大な問題であり、本当に申し訳ない」と謝罪し、同日付で社員を解雇したことを明らかにした。ただ、かかわった取引案件などの具体的事実関係については「調査中」として歯切れの悪い説明に終始。自らを含む経営陣の責任についても「事実関係の確認を待ってから考えたい」と明言を避けた。
渡部社長は「社員に対して株式取引を野村証券の口座のみで行うよう義務づけており、インサイダー取引のチェック体制はできていると思っていた」と説明。知人の口座を使って取引を行っていたことについては、「他の口座まではチェックできず限界があった」と述べた。【坂井隆之】
◇経営陣の責任重大--中枢で「八百長」見抜けず
「3回目を起こせば、社会的な信頼を二度と取り戻せない」。総会屋への利益供与事件で経営陣が総退陣したのを受け、野村証券社長に就いた氏家純一氏(現野村ホールディングス会長)は97年9月、全国の幹部にこう訴えた。しかし、1回目の証券不祥事(91年)、2回目の利益供与に続き、3度目が起きた。
企業の内部情報を公表前に知った上での株の売買を「インサイダー取引」という。いわば「レース結果が分かっている馬券」を買う八百長だ。証券会社は取引企業のあらゆる財務情報を握っている。その社員がインサイダー取引に手を染める市場をだれが信頼するだろうか。
野村証券の親会社、野村ホールディングスは22日、「会社としても誠に遺憾」とするコメントを発表、関与した社員を解雇した。同時に、「個人的な行為」と強調し、経営陣の進退問題には波及させないことも示唆した。
しかし、M&A(企業の合併・買収)を扱う「企業情報部」で1年以上にわたりインサイダー取引が続いていた疑惑が発覚したことについて、証券界では「野村の社内体制の不備が原因で、個人の問題では済まされない」との見方が大勢となっている。内部管理体制強化の公約は、果たされていなかった。
証券最大手によるインサイダー取引は「株は悪いもの」との印象を個人投資家に植え付け、「貯蓄から投資へ」という流れにも悪影響を及ぼしそうだ。【瀬尾忠義、野原大輔
入社4カ月後から不正か 野村元社員 他社で開設の5口座利用 04/23/08(毎日新聞)
野村証券元社員による株のインサイダー取引事件で、東京地検特捜部に逮捕された●(=がんだれに萬)瑜容疑者(30)=22日付で解雇=が、野村証券に入社した4カ月後からインサイダーと疑われる株取引を始めていたことが23日、証券取引等監視委員会の調べで分かった。
「新人の育成期」ともいえる時期から不正が行われていたとみられ、モラル欠如が疑われる。野村証券も事態を重視し、平成19年12月から勤務していた香港現地法人でも同様の不正をしていなかったかどうか、独自に確認調査する。
監視委や野村証券によると、●(=がんだれに萬)容疑者は18年2月に野村証券に入社。企業の合併・買収(M&A)などを担当する企業情報部に配属された。
同年6月ごろから、知人の蘇春光容疑者(37)らの名義で不審な取引が始まった。監視委が不正とみている取引は昨年12月に●(=がんだれに萬)容疑者が香港に転勤するまで続き、21銘柄に及んだ。
野村証券の中国人社員ら3人逮捕、担当外の株でも不正 04/23/08(読売新聞)
証券最大手「野村証券」(東京都中央区)の中国人社員らによるインサイダー取引事件で、東京地検特捜部は22日夜、企業情報部に勤務していたレイ瑜(れいゆ)容疑者(30)(同日付で解雇)ら3人を金融商品取引法違反の疑いで逮捕した。(レイはガンダレに「萬」)
レイ容疑者は、証券取引等監視委員会などの調べに不正を認めている。監視委の調べで、不正に売買されたとみられるM&A(企業の合併・買収)絡みの21銘柄のうち11銘柄以上は、レイ容疑者の担当外の企業だったことが判明。同社の情報管理に不備があった可能性が浮上した。
レイ容疑者のほかに逮捕されたのは、機械部品メーカー社員の蘇春光(そしゅんこう)(37)と、弟の蘇春成(しゅんせい)(25)の2容疑者。
特捜部の発表などによると、3人は2007年5月8日~24日、野村証券がアドバイザリー契約を結んだソフトウエア開発会社「富士通デバイス」が株式交換で富士通の完全子会社になるとのM&A絡みの内部情報を悪用し、公表前に同社株計7000株を1169万円で買い付けた疑い。
レイ容疑者は同年4月20日ごろ、企業情報部内で情報を入手し蘇容疑者兄弟に伝えていた。兄弟は公表で株価が上昇した後に株を売却し、約490万円の利益を得たという。
特捜部と監視委の調べによると、3人は06年6月~07年12月、容疑事実のほかに内部情報で20銘柄の株を売買し約4000万円の利益を得ていたとみられる。
野村証券の渡部賢一社長は22日夜、記者会見して「証券市場を預かる者がこのような不祥事を起こし、申し訳ありません」と謝罪した。
企業情報部には六つの課があり、株売買に利用された内部情報のうち、デバイス社の案件などはレイ容疑者が所属していた3課が担当、レイ容疑者も打ち合わせなどに出席していた。しかし、半数以上は企業情報部内の別の課で担当した企業の情報だったという。
株式公開買い付け(TOB)や株式交換によるM&Aが発表されれば、対象の企業の株価はほぼ確実に値上がりするなど、企業情報部にはインサイダー取引に結びつく情報が集中する。こうした部署では特に情報管理が徹底されており、自分が関与していない案件については同じ部内であっても情報が遮断される仕組みになっているという。
監視委ではレイ容疑者がどのようにして直接携わっていない企業の情報を入手できたのか、社内の漏えいルートや情報管理体制についても調査を進めている。
インサイダー:容疑の野村証券社員ら逮捕へ 東京地検 04/22/08(毎日新聞)
野村証券の社員が、東証2部上場の富士通子会社など2社の内部情報をもとにインサイダー取引を行っていた疑いが強まり、証券取引等監視委員会は22日、社員ら3人に対し、証券取引法(現金融商品取引法)違反の疑いで、強制調査に乗り出し、事情聴取を始めた。監視委と連携して捜査していた東京地検特捜部は、3人を逮捕する方針を固めた模様だ。
監視委は同日、関係先十数カ所を捜索し、併せて東京都中央区の野村証券本社などを任意で調査した。
関係者によると、3人は野村証券の企業情報部に在籍していた中国人の男性社員(30)や、京都大に同時期に在学していた知人の中国人と口座を貸したとみられるその親族。
社員は現在香港の現地法人に勤務している。社員は企業の合併・買収(M&A)を提案する同部の業務を通じて、東証2部上場の電子部品製造会社「富士通デバイス」が株式交換によって富士通の完全子会社になるという情報を入手。公表前の昨年5月、知人の中国人と計7000株を約1200万円で購入した。
株式交換では、完全子会社化される会社の株が、付加価値を上乗せした親会社の新株と交換されるため、公表後は子会社の株価が上昇する傾向にあり、インサイダー情報の一つとされる。富士通デバイスは同月24日に完全子会社化を発表し、1655円だった株価が2100~2500円台に急騰。社員らは公表後に売り抜け、約500万円の利益を得た疑いが持たれている。
さらに社員は、合成樹脂製品製造会社「住友ベークライト」が、東証・大証1部上場だったプラスチックシート製造会社「筒中(つつなか)プラスチック工業」の株を公開買い付け(TOB)し、吸収合併することに合意したという情報を入手。公表前の06年10月に筒中株計1万2000株を約500万円で購入した。
TOBによる合併合意が発表されたのは同月31日で、436円だった株価は発表後には最高535円まで急騰した。社員らは公表後に売り抜け、約100万円の利益を得たとみられる。
社員らが買い付けたのは、この2銘柄を含め野村がM&Aの企画・提案をするなどした計21銘柄に上り、約4000万円の利益を得ていたという。
野村証券は1925年創業。資本金100億円。国内161本支店を持ち、大和証券、日興コーディアル証券と並ぶ3大証券会社の一つ。
インサイダー:野村証券社員事件…複数口座使い隠ぺい 04/22/08(毎日新聞)
野村証券の中国人社員(30)によるインサイダー取引事件で、この社員が知人の中国人名義など複数の証券口座を使って株取引をしていたことが、関係者の話で分かった。証券取引等監視委員会と東京地検特捜部は、多数回にわたった株の発注をいくつかの口座に分散させて、不正取引の発覚を防ぐ狙いがあったとみて調べている模様だ。
関係者によると、社員らは証券取引法違反容疑が持たれる「富士通デバイス」株など2銘柄を含め計21銘柄を買い付け、約4000万円の利益を得ていた。これらの銘柄では、野村がM&A(企業の合併・買収)の企画・提案をしていたことから、社員が業務を通じて知った未公表のM&A情報を悪用してインサイダー取引を繰り返した疑いも浮上している。
社員は、M&Aを希望する会社に具体的手法や手続きの助言を行う企業情報部に所属。06年春ごろから株取引を始め、1年余の間に四十数銘柄を買い付けていた。このうち約20銘柄の上場企業については、野村からの企画・提案を受けて、株式の公開買い付け(TOB)や株式交換などの手法でM&Aが実施されていた。
社員と知人の中国人は同時期に京都大に在学し、そこで知り合ったとみられる。社員はM&Aの企画・提案を通じて知った株式交換などの情報を知人に伝え、知人名義の口座で取引をさせた疑いがある。この知人はさらに親族から証券口座を借りて取引していたとみられる。
社員と同様、知人らも頻繁に売買を繰り返し利益を得ていることから、監視委と特捜部は不正と知りながら取引をしていた疑いが強いとみている模様だ。
長崎の高校生64人、賞味期限11か月過ぎた揚げめんで食中毒 04/21/08(読売新聞)
長崎県佐世保市は21日、同市世知原(せちばる)町の宿泊研修施設「県立世知原少年自然の家」で皿うどんを食べた同県立高校の1年生ら118人のうち64人が、吐き気や腹痛など食中毒症状を訴えたと発表した。
賞味期限を11か月過ぎた揚げめんを使用していたのが原因で、市は同施設の食堂を3日間の営業停止処分とし、納入した同市の卸業者「古賀食産」に対し、期限切れのめんの廃棄を命じた。
市などによると、14日から2泊3日の日程で新入生研修合宿をしていた男子生徒29人と女子生徒32人、引率教師3人で、うち11人が病院で診察を受けたが、いずれも軽症だった。
食堂は同施設が委託した市内の業者が営業し、16日の昼食に皿うどんを出した。生徒らは食べ始めてすぐにめんの異臭に気づき、直後から次々に発症。調理師らはめんの変質に気付かなかったとしている。
三井住友銀融資焦げ付き、コシ社が行員親族に会社設立費300万 04/18/08(読売新聞)
三井住友銀行で巨額の融資が焦げ付いている問題で、融資先の不動産会社「コシ・トラスト」(東京都渋谷区)側が300万円を出資し、担当の男性行員(43)の親族のためにコンサルタント会社を設立していたことがわかった。
会社はコ社と関係の深い業者の事務所に間借りし、親族はコ社から計300万円のコンサルタント料も受け取っていた。
行員にはコ社側にマンション家賃計410万円を負担してもらった疑いが浮上しており、コ社との親密ぶりをうかがわせる事実がまた明らかになった。
行員の説明などによると、行員は2003年秋ごろ、コ社の事務所で親族とコ社社長(39)を引き合わせた。親族は飲食業経営に関心があり、社長から「焼き肉店の出店計画を考えてほしい」と依頼されたという。同年12月に資本金300万円をコ社側が出資して、渋谷区内に有限会社を設立。親族が社長に就任し、法人名義の口座の通帳と実印が手渡された。
この会社が本格的にコンサルティング業務を始めたのは05年4月から。「東京にデスクがないと仕事ができない」と親族から相談を受けたコ社側が、行員のマンション家賃を振り込んでいたグループの自動車販売会社「ケイファインダー」(渋谷区)の事務所の机を提供。親族は同年5月~06年2月の10か月間、飲食店の企画立案のコンサルタント料としてコ社から毎月30万円を受け取っていた。
親族はこの間にバーや九州料理店の出店計画など3件を提案したが採用されたものはなく、行員絡みの融資が減ると同時に報酬支払いも打ち切られた。親族は現在も神奈川県の自宅でコンサルティング業務を続けているという。親族は読売新聞の取材に「飲食店の企画提案の仕事はしていた」と説明。行員は「(取引があったのは)親族の仕事が評価されたから。出資を受けたのは不適切だとは思っていない」としている。
航空貨物運送でカルテル容疑 公取委、13社へ立ち入り 04/16/08(朝日新聞)
日本発の国際航空貨物便の運送代金の一部をめぐり、大手運送会社が価格カルテルを結んでいた疑いがあるとして、公正取引委員会は16日、日本通運と近鉄エクスプレス、日本郵船系列の郵船航空サービス(いずれも東京)の大手3社を含む計13社に対し、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで立ち入り検査に入った。
他に立ち入りを受けているのは▽西日本鉄道(福岡)▽阪急エクスプレス(大阪)▽日新(神奈川)などと、業界団体の「航空貨物運送協会」。検査対象は本社や支店など計約20カ所。国際宅配便と合わせた年間の市場規模は約6400億円で、上位3社で5割近いシェアがあるという。国際航空による貨物輸送は輸出・輸入ともに年間約160万トン。電子部品などの機械機器を中心に貿易総額の約3割を占める。
問題となっているのは、各運送会社が自動車メーカーや大手電機メーカーなど、複数の荷主から電子機器などの小口貨物を引き受け、送り先ごとに荷物をコンテナへ詰め直して航空会社に渡す業務。業界では「混載業者」「フォワーダー」などと呼ばれている。
各社は、航空会社から機内の貨物スペースを買い取ってコンテナを積み込む。運賃には、原油価格上昇分を吸収するために航空会社が設定した「燃油サーチャージ」という付加運賃も含まれており、あわせた金額を航空会社に支払っている。
関係者によると、運送各社は04年以降、荷主との価格交渉の際に、燃油サーチャージの上昇分を「燃油サーチャージ加算」などと称して一定割合を乗じ、その金額を荷主側に転嫁させることなどで合意した疑いがもたれている。
日本では、航空会社同士が決める国際航空貨物運賃も燃油サーチャージも独占禁止法の適用除外とされているが、公取委は、利用者である運送会社がこの適用除外に便乗し、横並びで転嫁していたとみている。
米司法省や欧州委員会も昨年10月、大手国際運送会社が貨物運賃や貨物の燃油サーチャージをめぐって価格カルテルを結んでいた疑いがあるとして調査している。
大手3社は「公取委の調べには協力していく」などと話している。
〈燃油サーチャージ=燃油特別付加運賃〉 航空機や船の燃料のもとになる原油価格の高騰で、営業努力が及ばないほどの燃料の値上がりに対し、運賃本体とは別建てで燃料費の一部を徴収する付加運賃。日本の国際航空便は、貨物が01年、旅客が05年から導入した。シンガポール市場のジェット燃料(ケロシン)価格を指標として3カ月ごとに見直され、航空会社が国土交通大臣の認可を受けて改定する。
大手・栗本鉄工所も虚偽報告 高速道資材の試験 04/05/08(朝日新聞)
高速道路の橋の部分の強度維持に必要な資材「ポリエチレン製シース(保護管)」の試験報告書が一部企業によって捏造(ねつぞう)されていた問題に関連し、鋳鉄管製造大手の「栗本鉄工所」(大阪市)も実際には行われていない試験の報告書を西日本高速道路会社に提出していたことが分かった。同鉄工所は「仕入れ先の試験データを転用したが、意図的な捏造ではない」と主張している。
問題の報告書は、シースの搬入先である滋賀県内の「新名神高速・池田高架橋」工事向けに作成された。試験者の欄に社名と社印があり、大阪府交野市にある同社交野工場で、すべての試験に「合格」したことになっている。
しかし、実際には、昨年の秋に橋の施工業者から報告書の提出を求められた同社は、シースの製造元(廃業)の事業を引き継いだ資材会社から二つの「報告書」を入手。自社では試験をしていないのに、入手した「報告書」の試験日や温度、湿度を変えて独自の報告書を作成、提出した。試験日は、納入1、2週間前に検査証明書を出す業界の慣習に合わせたという。
これに対し、二つの「報告書」を栗本側に渡した資材会社の担当者は、一つは「調査の結果、試験をやっていないと判断せざるを得ない」とし、もう一つは「別の製品の報告書で、そのように栗本にも伝えた」と言っている。(野上祐、西川圭介)
結局、元警察官であってもこの程度のレベルだ。
「今年3月に山口県で同様の問題があり、協会が各職員を調べたところ発覚したという。」
最近の若者だけでなく、年寄りもモラルが無い。協会が調べなければ黙っているつもりだったのか。
情けない県警OBだ。「一昨年年6月以降、速度超過や物損事故などで違反点数が累積し、
昨年6月から7月にかけて30日間の免停となった」
この恥知らずの県警OBには指導する資格なし!名前を公表するべきだと思うほどのケースだ。
交通安全協会は企業ではないが、現状のような活動の継続のために本当に必要なのか。
少なくとも再編が必要ではないのか!
県警OB、免停後も運転免許試験場の指導員続ける 福岡 04/03/08(毎日新聞)
福岡県警OBで、運転免許試験場の講習指導員を務める県交通安全協会の男性職員(68)が、スピード違反などで免許停止となった期間中も指導員として勤務を続けていたことが3日、分かった。職員は「交通安全を呼び掛ける指導員にあるまじき行為」として3月末に訓戒処分を受け、自主退職した。
福岡県交通安全協会の大場正文総務課長は「再発防止策を徹底する」と話している。
協会によると、職員は県警退職後の平成11年から安全協会に勤務し、福岡市南区の運転免許試験場で、免許更新者や行政処分対象者への実技や座学の指導を担当。一昨年年6月以降、速度超過や物損事故などで違反点数が累積し、昨年6月から7月にかけて30日間の免停となったが、協会には報告せず、勤務を続けていた。
今年3月に山口県で同様の問題があり、協会が各職員を調べたところ発覚したという。
外国人研修・実習制度なんて名ばかりだろう。割り切って単純作業を認めたらどうか?
その代わり、不法滞在者を使用した経営者や会社には、懲役1年とか、罰金、500万円とか、
それなりの重い処分を行なえばよい。
「菓子店は助言に従い組合を通じてビザを申請し、入管などは書類審査だけで発給。」
入管も甘いな、まともに仕事をしているのか????時には抜き打ちが必要じゃないのか?
チェックが甘い税関
や
チェックが甘い外国船舶監督官
給料泥棒の社会保険庁職員
も同じレベル。
ところで業種偽装を提案した「えひめ中小企業ネットワーク協同組合」はどんな組織だ?
まともな協同組合なのか、それとも、何でもありの協同組合なのか?
外国人研修:洋菓子店「かまぼこ製造」…業種偽り受け入れ 03/29/08(毎日新聞)
愛媛県内の洋菓子チェーン店が、水産物を扱っていないにもかかわらず「水産練り製品(かまぼこ類)」を製造していると偽って中国人研修生を受け入れ、「研修」とは名ばかりの単純作業に従事させていたことが分かった。人手不足解消のため、こうした「業種偽装」で外国人研修生を受け入れている企業は少なくないとみられ、関係者は「氷山の一角だ」と指摘している。
外国人研修・実習制度は単純作業を認めておらず、食品関連ではかつお節やかまぼこ類、ハム・ソーセージ類の製造など6業種のみが対象。菓子づくりはできない。このため同菓子店が加盟している研修生の受け入れ組合「えひめ中小企業ネットワーク協同組合」が業種偽装を提案した。
菓子店の経営幹部が昨年4月ごろ、受け入れを組合に相談。組合は「会社登記に『練り製品』の記述がある。水産物を海外委託生産していることにすれば大丈夫」などと助言したという。
菓子店は助言に従い組合を通じてビザを申請し、入管などは書類審査だけで発給。中国人研修生の女性4人が同12月に入国し、同社工場で菓子類のこん包、検品などの単純作業に従事していた。菓子店は生活費等の名目で1人当たり月約6万円を支払った。菓子店幹部は「人手不足解消になると思い、深く考えずにやった」と謝罪。組合は4人を帰国させるとしている。
研修生の実情に詳しい市民団体「外国人研修生ネットワーク福井」の高原一郎さんは「水産物加工という名目で受け入れながら、冷凍食品や総菜の検品など、実作業と違う形で研修生を受け入れている企業は多いはず」と話している。【後藤直義】
インドネシア大使館職員にリベート、ビザ代理申請の国内2社 03/31/08(読売新聞)
インドネシアに商用などで入国する際に必要な査証(ビザ)の代理申請をしている国内の企業2社が、在日インドネシア大使館(東京・品川区)の日本人男性職員(50)の口座に、多額の資金を振り込んでいたことが読売新聞の調査でわかった。
総額は2006年までの5年間で約2000万円に上り、うち1社は資金提供がビザ発給のリベートだったことを認めている。不正競争防止法(外国公務員への贈賄)に抵触する可能性があり、捜査当局も情報収集している。
問題の企業は旅行会社「ナショナルビジネスサポート(NBS)」(中央区)と、インドネシアの大手石油会社の関連会社「ファーイースト興産」(港区)。
読売新聞の調べによると、問題の日本人職員は10年以上前から同大使館のビザ発給業務を担当し、大手銀行に開設した個人口座には、この2社から月10~30万円が振り込まれていた。確認できた06年までの5年間ではNBSから約1400万円が、ファーイースト興産からは約600万円が入金されていた。
同大使館にビザを申請する際の正規の手数料は2500~1万1500円で、ファーイースト興産によると、この日本人職員から手数料とは別に申請者1人当たり4000円を要求されて口座に振り込んでいた。
通常、どの国でもビザの申請から発給まで数日から数週間が必要とされるが、同社は「職員の権限は絶大でビザを即日で取得できることもあった」として、ビザ発給の便宜を図ってもらう見返りに資金提供していたことを認めている。
NBSの社長(59)は資金提供の事実は認めたが、「顧問料みたいなもの」と話している。業界関係者によると、同国のビザの代理申請をしている企業は国内に約30社。NBSの申請数は年間5000件前後で、全体の半数を占めるという。
不正競争防止法は、贈賄相手を「外国公務員」としているため、大使館採用の問題の職員は対象にならないとみられるが、資金がインドネシア政府関係者に渡った場合などは抵触する。
この職員は「誰かに便宜を図ったことはない」と語り、同大使館は「取材には応じられない」としている。
◆捜査当局、可能な限り解明を◆
外国公務員への贈賄禁止条項は経済協力開発機構(OECD)加盟国が「外国公務員への贈賄防止条約」を締結したのを契機に、1998年、不正競争防止法に盛り込まれた。
国際的な商取引の公正性を確保する狙いがあるが、日本で立件されたのは昨年3月、電設大手「九電工」の子会社がフィリピン捜査当局幹部2人にゴルフクラブセットを渡したとして罰金などの略式命令を受けた事件だけ。背景には、わいろの提供先の事情聴取が困難で趣旨などが解明できないという事情がある。
今回は、提供先が大使館採用のスタッフで「外国公務員」にあたらないとみられる一方、日本人であるため、外国公務員と比べ容易に事情聴取できるという面もある。捜査当局には可能な限りの解明を期待したい。(社会部 佐藤直信)
西日本高速道路は品質試験報告書を捏造(ねつぞう)する会社や捏造された書類が
添付された製品で問題ないなら、品質試験報告書を要求するな。
「 西日本高速道路の小川篤生管理事業本部長は30日、記者会見し『シースは橋の強度に
直接影響しない。施工時に破損がなく、将来劣化する可能性は低い』と強調した。」
ならば小川篤生管理事業本部長を含む安全性をチェックした職員は、将来、問題が発生した
場合、資産の没収を含め、責任を取ることを書面で書け。出来ないのなら言い訳のような発言を
するな。「シースは内部に鋼線を通してコンクリートの強度を高めるのに使われる管」の品質に
関して責任を持て!いい加減なことを言うなよ!
「捏造は3社」高速架橋 無試験で強度確保資材 03/31/08(産経新聞)
大阪府八尾市の建材販売会社「エスティーエンジニアリング」が、高速道路の架橋工事でコンクリートの強度を確保するための資材「ポリエチレン製シース(保護管)」の品質試験報告書を捏造(ねつぞう)し、第二東名高速道路など計22カ所、33の橋の工事で納入していたことが30日、西日本高速道路会社などの調査で分かった。
また「ウエックスジャパン」(東京都)も、シースの品質試験を実施せず他社の試験データを引用して報告書を作成。1カ所の工事で納入していた。このほか、「東拓工業」(大阪市)も試験の一部を行っておらず、納入した5種類のシースについて、報告書の一部の欄が空白だったことも判明し、高速道路会社側のチェック体制の甘さも浮き彫りになった。
エス社は「試験の費用負担が大きかった。品質は試験導入前と変わりなく、安全性に問題はない」と説明している。
シースは内部に鋼線を通してコンクリートの強度を高めるのに使われる管。エス社は直径45~80ミリの製品を設計に応じた長さにして納入していた。
旧日本道路公団は平成16年、シースの規格基準を作成。10項目ある試験基準に適合しなければならないと定め、民営化後の高速道路会社もこれを引き継いだ。
エス社は、すべて「合格」したと偽った報告書を17年4月と5月に作成。同年8月から今年3月にかけ、大分県の東九州自動車道など、旧公団と東日本、中日本、西日本の各高速道路会社が発注した高速道の33の橋工事に納入した。
外部の指摘を受け、3月に初めて試験を実施。9項目を終えた段階で、基準はいずれも満たしているという。
ウエックス社によると、ほかのメーカーの試験データを基に報告書を作り、18年11月ごろ、山口県内の山陽自動車道の橋工事で納入した。
西日本高速道路の小川篤生管理事業本部長は30日、記者会見し「シースは橋の強度に直接影響しない。施工時に破損がなく、将来劣化する可能性は低い」と強調した。
昔は会社の名誉のために不正を大目に見てきたのか、それとも、最近の日本人はモラルが無くなったのか?
着服:「日本旅行」の子会社 部長が1億1700万円 03/29/08(毎日新聞)
業界3位の大手旅行会社「日本旅行」(東京都港区)の子会社で、経理担当責任者の業務部長(50)が、旅行契約代金など1億1700万円を着服していたことが分かった。業務部長は着服を認め、会社側の調べに「個人的な消費に充てた」と話しているという。日本旅行は子会社がある沖縄県警への刑事告訴を検討している。
この子会社は「日本旅行沖縄」(那覇市)。日本旅行によると17日、取引先の同県内のホテルから日本旅行沖縄に代金支払いを督促する連絡があった。社内調査したところ、帳簿と現金残高に1億1700万円の差額が判明した。業務部長が経理用パソコンで預金簿や預金残高証明などの数字を改ざんしていた。業務部長は90年に入社。当時から経理を担当しており、日本旅行は正確な着服額や開始時期などを調べている。【高橋昌紀】
法定点検せずLPG新規供給、千葉の会社を行政処分 03/27/08(読売新聞)
経産省関東東北産業保安監督部は27日、家庭用プロパンガスに使われる液化石油ガス(LPG)の供給に際し、燃焼設備の法定点検を実施していなかったなどして、LPG販売会社「昭和瓦斯実業」(本社・千葉県市川市、牛尾健社長)に対し、6か月間の新規顧客契約停止などを命じる行政処分をした。
同監督部によると、同社は2007年12月までの約4年間、茨城、埼玉、千葉、栃木の4県で、新規契約者にガス供給を始める際、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」で義務づけられた配管やガス栓などの安全点検を実施していなかった。未実施の件数は計4346件で、全点検の25・9%に上った。
既存の顧客に対する安全点検の未実施も1万3212件確認され、うち1万169件は点検したように記録を捏造(ねつぞう)していたという。
不法就労助長:茨城の食品加工会社社長を逮捕 警視庁 03/25/08(毎日新聞)
不法滞在の外国人従業員を雇っていたとして、警視庁組織犯罪対策1課と愛宕署が、茨城県坂東市の食品加工会社「マナカ商事」社長、間中和雄容疑者(53)を出入国管理法違反(不法就労助長)容疑で逮捕していたことが分かった。同社は大手牛丼チェーンやスーパー向けに紅しょうがを販売している。
調べでは、間中容疑者は05年12月~今年2月、不法滞在のタイ人男性(32)ら3人を従業員として雇っていた疑い。容疑を認め「当初は外国人研修生を雇っていたが、労働時間に制限がある。本人たちも働きたがっているので、不法就労に目をつぶっていたら人数が増えてしまった」と供述しているという。
昨年6月、愛宕署員が東京都港区内で、同社従業員だったタイ人男性(38)=既に強制退去処分=に職務質問し、偽造旅券での密入国が判明。警視庁と東京入国管理局が今年2月に同社を合同で摘発し、同様の手口で密入国したり、不法残留したタイ人従業員の男女8人を確認した。
間中容疑者はタイ人の面接を自ら行い、雇った従業員は工場敷地内の寮に住まわせ、日当約8000円で雇っていた。38歳の男性が逮捕された際、別の従業員に「君たちも警察に捕まるので外出しないように」と指示したという。
民間信用調査機関によると、マナカ商事は73年の設立で年商は約29億7000万円。【曽田拓】
国産ウナギ偽装、静岡の商社捜索 03/21/08(読売新聞)
静岡市の食品総合商社「東海澱粉(でんぷん)」が台湾、中国産ウナギを国産と偽って販売していた問題で、鹿児島県警は21日、同社の本社と鹿児島県東串良町の大隅営業所など5か所を不正競争防止法違反(産地誤認惹起(じゃっき))容疑で捜索した。
調べによると、同営業所は2006年12月ごろから07年1月ごろにかけて、台湾、中国から輸入したウナギ計約14・1トンを国産に偽装し、鹿児島県内の加工業者に販売した疑い。捜索は21日朝から行われ、本社と営業所のほか、鹿児島県鹿屋市の大隅営業所元所長宅などを捜索した。
同社によるウナギの産地偽装では、農水省が2月20日、同社に対し厳重注意処分を行った。同社総務課は「捜索には驚いているが、警察には全面的に協力していきたい」と話していた。
同じウナギでも国産と台湾産だと値段が違う!詐欺とも言えるね!
「東海澱粉」偽装ウナギ幹部も把握 会長引責辞任へ 03/03/08(産経新聞)
食品総合商社「東海澱粉」(静岡市)が中国、台湾産のウナギを「国産」と偽って販売していた問題で、農林水産省は3日、同社が平成14年から偽装を始め、19年までに産地を偽装したウナギ計約1300トンを販売、本社の幹部も営業所の偽装を認識していたことを確認したと発表した。
東海澱粉は3日、神野一成会長が引責辞任する方針を発表。神野建二社長は同日記者会見し、本社の担当部長が5年ほど前に偽装を把握していたことを認めた上で「指示などはしていない。会社ぐるみとの指摘については、今後の調査で明らかにする」と述べた。
農水省によると、産地を偽装したウナギの販売は鹿児島県の大隅営業所で14年から始まり、すでに明らかになっている約340トンに加え、同営業所と愛知県の三河営業所で新たに約970トンの偽装が行われたことが判明した。
中国製の冷凍食品のように農薬が入っていなければ、問題ないだろう。
しかしね、JR東海の子会社でも利益優先の姿勢は問題。これが極端になれば、
安全の軽視になり、運が悪ければ事故に繋がるのだろう!
新幹線駅弁の期限偽装、4工場長が「認識」 02/23/08(読売新聞)
東海道新幹線の駅弁などの消費期限表示が偽装されていた問題で、製造したJR東海の子会社「ジェイアール東海パッセンジャーズ」(東京)の4工場の工場長が、社内調査に「偽装を認識していた」と話していることがわかった。
4工場とも、少なくとも1年前には表示偽装を行っており、同社は組織的関与についてさらに調査を進める。
同社によると、21日午前に内部告発があったのを受けて調査したところ、取締役を務める東京工場長のほか、淀川(大阪市淀川区)、摂津(大阪府摂津市)、名古屋の3工場長が認めたという。
同社が23日に開設したフリーダイヤル(0120・919・212)には朝から、「いい加減なことをするな」「弁当を買って食べたので不安」などの苦情や相談が相次ぎ、社員10人が対応に追われた。
グッドウィルが労災隠し 宮崎、派遣労働者が指骨折 02/21/07(産経新聞)
日雇い派遣大手グッドウィル(東京)が、昨年12月に宮崎県都城市で起きた派遣労働者の男性(29)の労災事故を、今年2月まで労働基準監督署に報告していなかったことが21日、分かった。同社は「対応は不適切だったと認識し、反省している」としている。
この男性によると、事故は昨年12月17日夕方に発生。都城市の運送会社の倉庫で、積み降ろし作業でコンテナを閉める際、左手薬指にけがをし、病院で骨折と診断された。
翌日に労災の適用を求めたが、グッドウィルの従業員から「仕事が来なくなる。労災を使ってくれるな。働けるだろう」と拒まれたという。2月につめがはがれるなど、症状が悪化したため、自ら労災を申請した。
グッドウィルの都城支店長らが今月13日、男性の自宅を訪れ謝罪。事故を知っていながら労基署に報告しなかったことを認めたという。同社は18日、都城労基署に報告書を提出した。
男性は「明らかな労災隠しだ。うやむやにしたら、また同じようなことが起き、派遣労働者が泣くことになる」と話している。
ブリヂストン、中南米や東南アジアで「わいろ」 02/13/08(読売新聞)
石油をタンカーから貯蔵施設に移すために使われるマリンホースの販売をめぐる国際カルテルを結んでいたブリヂストン(東京都中央区)が、外国政府などにマリンホースを購入してもらう見返りなどの趣旨で、外国公務員への不正な支出を繰り返していた疑いがあることが、同社の内部調査でわかった。
不正支出額は2003年以降の取引約20件で計約1億5000万円に上る疑いがある。同社は12日、不正競争防止法違反(外国公務員への利益供与)の可能性があるとして、東京地検に調査内容を報告した。
同社が公表した内部調査の概要によると、不正な支出の舞台になったのは、中南米や東南アジアでの海外公共調達事業。海外子会社を通じて現地のエージェントに支払う手数料に売上額の数%を加算して支払い、上乗せ分はエージェントから外国政府や公的機関の幹部に渡されていた疑いがあるという。
対象となった製品は、マリンホースのほか、船の接岸時にクッションになる「防舷材」や、空気で膨らませて河川をせき止める「ラバーダム」など。いずれも同社化工品海外部が扱っており、3品目の年間売り上げは計約90億円に上る。
不正支出には同部の10人前後がかかわったとみられ、部長や課長の決裁を経て「追加の手数料請求」などの名目で経費として処理していた。同社は個別の支出先を明らかにしなかったが、受注の見返りのほか、自社に有利な仕様で発注するよう働きかける趣旨で支払われたケースもあった。不正支出は15年以上前から続いていた疑いもあるという。
マリンホースをめぐる国際カルテルでは、日米欧の当局が昨年5月に一斉調査に着手。米司法省が事件当時のブリヂストン化工品海外部部長を逮捕し、公正取引委員会も同社を含む日英仏伊のメーカー5社を処分する方針を固めている。
不正支出は、国際カルテル発覚を受け、ブリヂストンが日米の弁護士に調査を委託して明らかになった。
同社は12日午前、東京地検に調査内容を報告。同日午後に都内のホテルで記者会見を開き、荒川詔四(しょうし)社長が「重大なコンプライアンス(法令順守)違反。当社に対する信頼を裏切るもので心よりおわびする」と謝罪し、マリンホース事業からの撤退と化工品海外部の廃止を明らかにした。
内部調査を3か月をめどに終え、検察当局の判断も考慮したうえで、経営陣の処分を検討するという。
朝日新聞(2008年2月9日)より
IHI,特設注意市場に
東証・大証 三洋、監理銘柄外れる
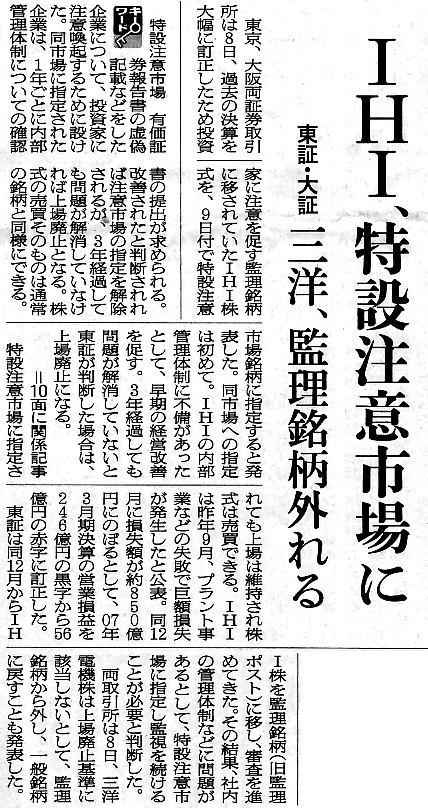
鉄くず輸出で中国に24億円不正送金、7業者を捜索 01/29/08(読売新聞)
不法滞在の中国人らを相手に地下銀行を営んでいたとして、警視庁に摘発された中国人グループが、預かった現金で鉄くずを購入し、中国に輸出する形で送金していたことがわかった。
北京五輪を控え、中国では金属価格が高騰していることから、利ざやを稼ぐ狙いもあったとみられる。
警視庁は、輸出に関係した日本側の業者が、地下銀行の不正資金と知りながら取引していた疑いがあるとして、28日朝から、東京や大阪などの金属輸出入業者7社を銀行法違反(無許可営業)容疑で捜索、全容解明を進めている。
同庁組織犯罪対策1課によると、銀行法違反や本人確認法違反の疑いで逮捕されたのは、神奈川、千葉県内に拠点を置く二つの中国人グループの男女12人と、グループに銀行口座を提供していた日本人の男3人。
供述や押収資料などから、両グループが、2002年7月~昨年9月、口コミで連絡してきた各地の不法滞在の中国人ら約4000人から、約24億円の送金を依頼されていたことがわかった。
さらに、預かった現金は、逮捕された中国人名義の銀行口座に移された後、全国の金属輸出入業者94社に振り込まれていたことが判明。一部の業者に事情を聞いたところ、「日本から鉄くずを輸出した代金として、中国側の企業から振り込まれた」と説明した。
中国人向け地下銀行では、これまで、預かった現金を「運び屋」と呼ばれる人物が、中国に直接運び、“送金先”である不法滞在者の現地の家族らに渡していた。今回摘発された中国人グループは、高騰している鉄くずを現地で売却することで、地下銀行用の資金だけでなく、多額の利益も得ていたとみられる。
同課は、輸出先の中国・福建省にある複数の企業も、グループの一味の可能性が高いとみている。日本側の業者の中には、総額約16億円の入金を受けていたところもあり、同庁は、入金額が多い7社について、地下銀行の関与を知った上で取引していた可能性があるとみて、捜索に踏み切った。
消費者や購入者にとっては安くて、品質が良い物はありがたい。しかし、安くするためや、利益を
増やすために偽装や労働者に極度の負担を負わせるのは良くない。子供がマクドナルドのハンバーガー
が好きなので仕方がないから行っているが、今後、行く回数を減らそうと思う。
訴訟を起したマック店長。働きすぎて
社会保険庁
や
厚生労働省
がお金を無駄遣いしていることや、
日本の無駄使い
について考えたこともないんだろうね。屁理屈ばかりの公務員。ほんと、嫌になる。
訴訟を起したマック店長、健闘を祈る!
マック店長の管理職扱いは違法、残業代など支払い命令 01/28/08(読売新聞)
日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店の店長を管理職と見なして残業代を支払わないのは違法として、埼玉県熊谷市の店舗の男性店長が、同社を相手取り、2年分の未払い残業代や慰謝料など約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
斎藤巌裁判官は「店長の権限は店舗内に限られており、経営者と一体的な立場で事業を行う管理職とは言えない」と述べ、未払い残業代など約755万円の支払いを命じた。
従業員の地位が管理職に当たるかどうかが争われた訴訟は多いが、今回のように全国で約1700人とされる直営店長の身分に影響が及ぶようなケースは過去に例がない。全国展開している金融業者や書店の店長についても同種訴訟が起こされているほか、労使協議や労働審判で問題となっており、影響を与えそうだ。
訴えていたのは、「125熊谷店」の店長、高野広志さん(46)。判決によると、高野さんは1987年に同社に入社し、99年に店長に昇格した。店長になった後も一般社員やアルバイトと同じように早朝から深夜まで調理や接客を行い、残業時間が月100時間以上に及ぶこともあったが、店長は管理職だとの理由で残業代は支払われなくなった。
労働基準法は、規定の労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働や休日出勤には残業代を支払うよう義務づけているが、管理職にあたる「管理監督者」には、この規定が適用されない。訴訟では、同社の直営店長が管理監督者に当たるかどうかが最大の争点となった。
判決はまず、管理監督者について、「企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場にあるような重要な職務と権限を与えられ、賃金などで一般労働者より優遇されている者」と指摘。
その上で、日本マクドナルドの直営店長の権限について、<1>アルバイトの採用や勤務シフトの決定など店舗内に限られ、本社の打ち出した営業時間に従うことを余儀なくされている<2>独自のメニューを開発したり、商品価格を設定したりできない――などの理由から、「管理職といえるような重要な職務と権限を与えられているとは認められない」と判断。さらに、自ら勤務シフトに入って残業を余儀なくされるなど労働時間の自由裁量がないという勤務実態や、賃金の面でも十分な待遇を受けているといえないことを踏まえ、「店長は管理職ではない」と結論づけた。慰謝料については「残業代などの支払いで十分」として認めなかった。
朝日新聞(2008年1月26日)より
耐火偽装 5社21件でも
日軽金・YKK APなど
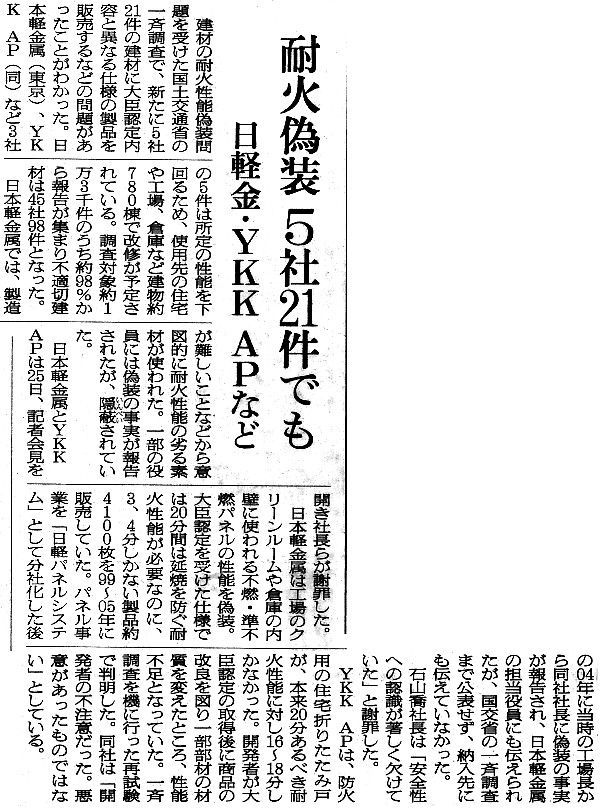
朝日新聞(2008年1月26日)より
加盟7割 古紙率偽装
製紙連、17社確認
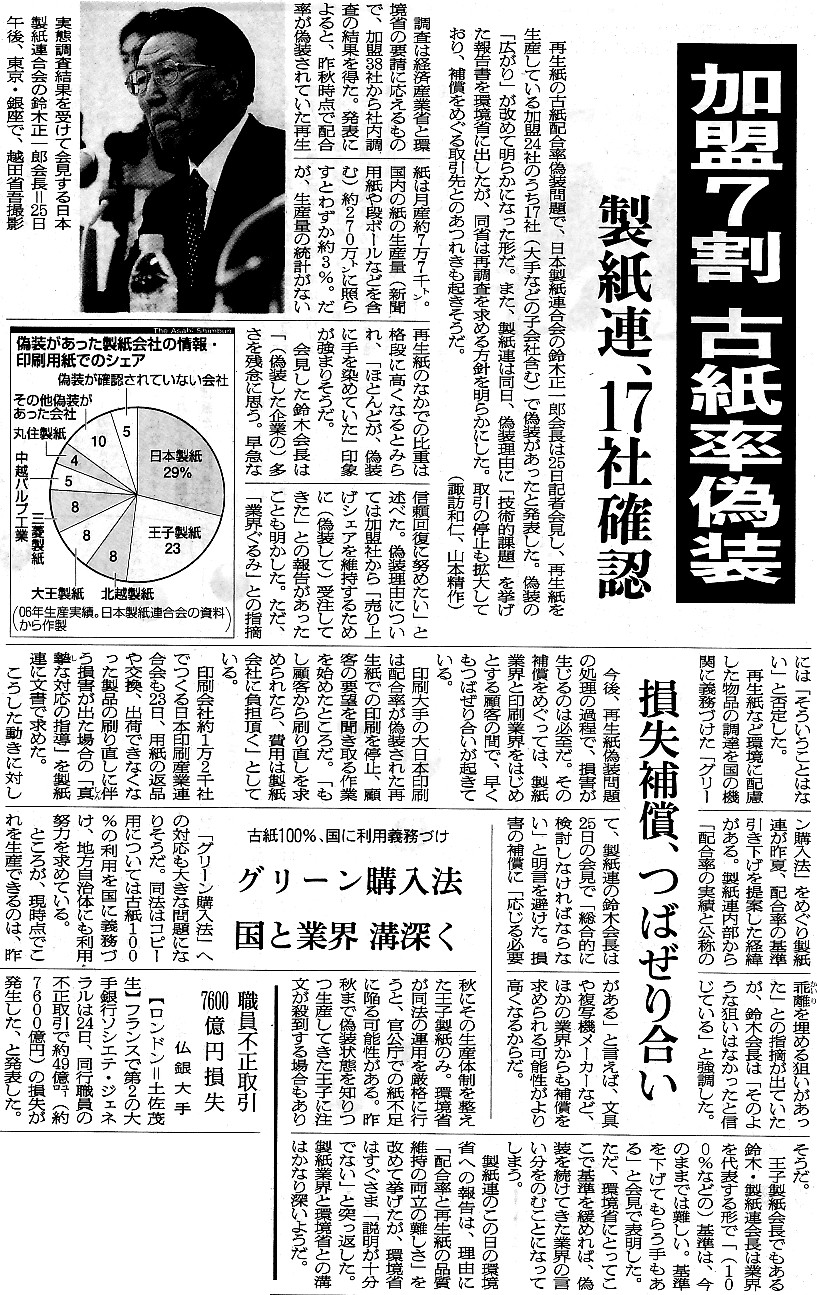
古紙配合率、洋紙生産24社中の17社で偽装 01/25/08(読売新聞)
再生紙に含まれる古紙配合率を製紙会社が偽装していた問題で、日本製紙連合会(東京都中央区)は25日、コピー用紙や印刷用紙など「洋紙」を生産している会員企業24社のうち、7割にあたる17社で配合率の偽装があったとする調査結果を発表した。
連合会は同日、調査結果を環境省に報告したが、同省では、偽装が始まった時期が不明であるなど「全容解明には程遠い」としており、偽装を認めた製紙会社に対して再調査を求める方針だ。
調査は、環境省と経済産業省の指示を受け、連合会が会員企業38社を対象に実施した。洋紙に関しては、扱っている24社のうち、大手5社を含む14社がすでに記者会見などで偽装を認めていたが、新たに巴川製紙所(同区)、三善製紙(金沢市)、大興製紙(静岡県富士市)の3社の偽装が判明した。板紙と呼ばれる段ボールやパルプのみを生産し、洋紙を扱っていない14社はいずれも偽装はないと回答した。
偽装をした理由については、「高い品質が求められ、良質な古紙の入手が難しくなる中で、技術的な対応ができなかった」とする回答が多かったという。
記者会見した連合会の鈴木正一郎会長(王子製紙会長)は、偽装について業界内で「談合」や「暗黙の了解」があったのではないかという質問に対し、「全くそうしたことはない」と強く否定した。
これに対し環境省幹部は「再発防止を考える上で不可欠な原因究明がなされないなど、不十分としかいいようのない調査結果」と不快感をあらわにしていた。
メッキ鋼板でカルテル、公取委が大手4社を強制調査 01/24/08(読売新聞)
防さびや防腐の処理をした鋼板の販売をめぐり、メッキ鋼板メーカーが価格カルテルを結んだ疑いが強まり、公正取引委員会は24日午前、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで、日新製鋼(東京都千代田区)など大手4社の本社など計5か所への強制調査に着手した。
カルテルの対象製品は屋根や外壁などの屋外用建材として広く使われており、市場規模は年間3000億円を超えるという。公取委は、国民生活への影響が大きく悪質な事案とみて、刑事告発を視野に調査を進めている。
ほかに強制調査を受けているのは、日鉄住金鋼板(中央区)、JFE鋼板(同)、淀川製鋼所(大阪市)の3社。関係者によると、4社は溶かした亜鉛に鋼板を浸した「溶融亜鉛メッキ処理」を施した製品について、2006年度、数回にわたって値上げを実施したが、事前に連絡を取り合い、値上げ幅や時期などを決めていた疑いが持たれている。
販売先の建材メーカーなどには、「鋼材など原材料の高騰を受けた値上げ」と説明していたが、カルテルで決められた値上げ幅はコストアップ分を上回っているとみられ、便乗した形で収益改善も狙った疑いもあるという。
4社のシェア(市場占有率)は約80%に上り、06年度以前も、年に数回値上げを実施している。日新製鋼は03年12月、ステンレス鋼板の販売をめぐる価格カルテルでも、同法違反で排除勧告を受けている。
4社は、公取委の強制調査を受けたことを認めているが、容疑などについては「コメントできない」としている。
紀州製紙も古紙配合率偽装、社長が会見で明らかに 01/23/08(読売新聞)
再生紙に含まれる古紙の配合率を製紙会社が偽装していた問題で、「紀州製紙」(東京)は22日、都内で記者会見を開き、自社製品がグリーン購入法で定められた基準に達していないと認識した後も、官公庁向けに出荷を続けていたことを認めた。
このほか、丸住製紙(愛媛)、日本大昭和板紙(東京)、王子特殊紙(同)、三島製紙(同)の4社も同日、配合率を偽装していたと発表した。偽装を正式に認めた製紙会社はこれで計13社となった。
会見した紀州製紙の小林功社長によると、昨年4月に同業他社で再生紙の古紙配合率を見直す動きが出てきたため、自社製品の古紙の配合率を調べたところ、古紙100%と表示したコピー用紙で実際は40%程度しか含まれていないことなどがわかったという。
その後、表示通りの製品が作れないか検討したが、同社の技術力では品質基準を満たした古紙100%のコピー用紙は製造できないことが同9月に判明した。しかし、販売量の低下を防ぐために出荷を継続し、基準を満たさない製品は卸売会社を通じ、防衛省や厚生労働省にも納入された。
同法は、国や独立行政法人に環境に配慮した製品の購入を義務づけ、コピー用紙は古紙の配合率100%などの納入基準を定めている。小林社長は「(基準を)努力目標的にとらえていた。認識が甘かった」などと釈明した。
昨年10~12月に同社が生産した再生紙のうち、同法の対象となるコピー用紙など3品目の古紙配合率は70~100%の表示だったが、実際は14~38%で、すべて表示を下回っていた。
再生紙問題、グリーン購入法提案時に偽装認識…業界役員 01/21/07(読売新聞)
製紙会社が再生紙に含まれる古紙の配合率を偽っていた問題で、「中越パルプ工業」(東京都中央区)の長岡剣太郎社長は21日、記者会見を開き、1年前から偽装に気付いていたことを明らかにした上で、業界団体が昨夏、国にグリーン購入法の基準となっている古紙配合率の引き下げを提案したのは、「業界全体で(偽装が)あって、実態との差を埋めるためだと思った」と話した。
長岡社長は業界団体の常任理事を務めている。業界団体の役員が偽装を知りつつ、国に基準緩和を求めたことを認めたことで、製紙業界の倫理感の欠如が浮き彫りになった。
同法は、国や独立行政法人に環境に配慮した製品の購入を義務付け、コピー用紙の古紙配合率を100%とすることなど、商品ごとの購入基準を定めている。この基準について環境省では毎年、見直しに関する提案を受け付け、検討会で論議した上で、年度ごとに見直している。
製紙会社38社が加盟する「日本製紙連合会」は昨年7月、「間伐材などから作ったパルプを使い、製造過程も工夫すれば、温室効果ガスの二酸化炭素(CO2)の排出量は抑えられる」などとして、コピー用紙の古紙配合率を100%から70%に引き下げることなどを環境省に提案した。
今回の偽装発覚で、新年度の基準見直しは見送られたが、製紙会社がこうした基準をそもそも満たしていなかったことが次々と明らかになっている。これについて同連合会の常任理事を務める長岡社長は会見で、「約1年前、部下との雑談で配合率の乖離(かいり)があると薄々感じていた」と明かし、「提案は業界全般にある(偽装された)配合率との差を埋めるためにされると思った」と話した。
一方、同連合会の鈴木正一郎会長は21日の記者会見で、「(昨年7月の提案当時は)偽装が行われていたことは知らなかった。あくまで環境への配慮を考えてのこと」と述べ、配合率の偽装を知りながら基準緩和を求めたことは否定した。
中越パルプ工業によると、昨年10~12月に生産された同社の再生紙製品を調べたところ、同法対象の全製品7品目と、他の再生紙製品のほぼすべてで古紙の配合率が表示よりも低かった。再生紙は1990年から販売されているが、96年ごろには偽装が始まっていたという。
また、「特種東海ホールディングス」(同)も21日、記者会見を開き、封筒用紙などの再生紙7品目で古紙の配合率が偽装されていたと発表した。大手5社はすでに再生紙での偽装を認めており、これで配合率を偽っていた製紙会社は計7社となった。
皆で偽装すれば、選択の余地がない。日本の紙を買うのか、買わないのかの選択になる。
「赤信号、皆で渡れば怖くない!」の良い例だろう!
日本の政府が省エネとかCO2削減とか言っているが、国民は嫌だと思えば無理して付き合う
必要ないことが今回の例でも良くわかる。
大王・三菱・北越も再生紙偽装、業界ぐるみ不正の様相 01/18/07(読売新聞)
「日本製紙」と「王子製紙」が再生紙に含まれる古紙の割合を偽装していた問題で、「大王製紙」、「三菱製紙」、「北越製紙」の3社が18日午後、記者会見を開き、コピー用紙などの再生紙で、古紙の割合が表示を大幅に下回る偽装があったと発表した。
製紙業界大手5社がいずれも再生紙の古紙配合率を偽装していたことで、業界ぐるみの不正の構造が浮かび上がった形だが、談合などの行為は各社とも否定している。
この大手5社は、再生紙はがきでの偽装がすでに判明している。この日の会見では、コピー用紙などの再生紙についても、大王が7品目、三菱は11品目、北越紙が5品目で、それぞれ配合率を偽装していたことを明らかにした。大王については再生紙をうたいながら、古紙を全く含んでいない製品もあった。
官公庁が購入する際、環境に配慮して古紙の割合を定めているグリーン購入法の適用商品を巡っては、大王が「官報用紙など販売総数の68%が偽装だった」としたほか、三菱も「対象となる6品目のすべてで基準に満たなかった」などとした。大王が今年度、コピー機メーカーなどを通じて内閣府や経済産業省など少なくとも7府省に納入した「古紙100%」のコピー用紙には実際は41%しか古紙が含まれていないなど、グリーン購入制度がないがしろにされていた。
最初に配合率の偽装が明らかになった日本製紙の中村雅知社長は16日に引責辞任する意向を表明したが、他の4社長はいずれも辞任の考えはないとしている。
法令違反を行なう会社を使うのがメリットであれば、使いつづける。
これが日本の現状。表と裏があるのが日本。
再生紙の偽装や製紙業界の全てが偽装に関わった事実を考えても
否定できない事実。多くの人が疑問や疑いを持ちながら、口に出来ない、
口に出したら抹殺されると思いながら、自分勝手を「俺だけじゃない。」
と思いながら加速させているのだろう。
グッドウィル全708支店事業停止、派遣労働者に不安の声 01/18/07(読売新聞)
違法派遣を繰り返したとして、厚生労働省から事業停止命令を受けた日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京都港区)は18日、全708支店で4~2か月の事業停止に入った。
停止対象は新規の派遣のみだが、同社の場合、日雇いを中心に派遣者数が1日約3万4000人にも上るだけに影響は大きい。引っ越しシーズンを控えた物流業界や、派遣労働者本人からも不安の声が聞こえてくる。
物流業界は日によって業務量の差が大きいため、人手を調整しやすい日雇い派遣に頼るケースが多い。
「処分が明けたらまたグッドウィルにお願いしたい」。熊本市の運送会社の人事担当者はこう話す。事業停止命令の見通しが明らかになった昨年末以降、求人誌に広告を掲載したりして人手の確保に努めてきたが、応募があったのは60歳以上が中心で、若者は少ない。「運送業は仕事がきついので敬遠される」とこぼす。
山形市の運送会社の人事担当者も「数年前から企業の採用意欲が旺盛になり、都会に人材が吸い込まれているため、(グッドウィルからの派遣の)代わりを探すのが難しい」と嘆く。大阪市内の運輸会社は「あれだけの法令違反を犯した会社を使い続けるのは難しい」との見方を示した。
派遣労働者は失業への不安を口にする。危険業務として労働者派遣法で禁じられた建設現場で働かされたこともあったという大阪市内の男性(29)は「僕はまだ若いので、次の派遣会社を探せるが、一部の人は仕事にあぶれるかもしれない」と話した。
派遣労働者でつくる労働組合「グッドウィルユニオン」(東京)にも、「どうやって生活すればいいのか」「家賃が払えない」などといった相談が相次いでいる。日雇い派遣の労働者は収入が不安定なため、同社の事業停止で仕事がなくなれば、生活不安に直結する。同ユニオンの関根秀一郎書記長は「日雇い派遣を認めてきた国にも責任がある。労働者のフォローにも目を向けてほしい」と指摘する。
王子製紙の再生紙9品で偽装、古紙配合率「ゼロ」も 01/18/07(読売新聞)
再生紙はがきの古紙の割合が偽装されていた問題で、業界最大手「王子製紙」(東京都中央区)は18日記者会見して、はがき以外のコピー用紙などの再生紙計9品目で古紙の割合が表示を大幅に下回っていたと発表した。
再生紙とうたいながら古紙が全く含まれていない製品もあった。はがき以外の再生紙で、日本製紙(千代田区)に続き、業界トップでも古紙の割合を偽っていたことが明らかになったことで、環境偽装が製紙業界ぐるみで行われていた可能性も出てきた。
王子製紙によると、昨年4~12月に生産した再生紙製品を調査したところ、古紙100%と表示しているコピー用紙が実際には40%、40%と表示している厚紙では0%など、計9品目で古紙の割合を実際より高く表示していたことがわかった。
古紙を40%の割合で使用することになっている2008年用年賀はがきのうち、208トンを納入したインクジェット紙には古紙が全く含まれていなかった。
同社は、その理由を「古紙が足りないときに、木材パルプで間に合わせ、それを惰性で続けてしまった」などと説明している。
偽装が始まった時期は不明だが、コピー用紙については少なくとも10年前から行われていた。
偽装があったのは昨年12月までの生産分という。昨年10~12月の生産分では、官公庁が購入する際に古紙の割合を定めたグリーン購入法が適用される製品での偽装は見つかっていないとしている。
記者会見した篠田和久社長は「過去に社会の信頼を裏切る行為があったことは誠に遺憾。深く反省するとともに深くおわびします」と謝罪したが、「現時点では私中心の指導体制で頑張っていきたい」と述べた。
「同法では、紙類や文具類など約220品目を「特定調達品目」として指定、官公庁などが
購入する際の基準を示しているが、違反した場合の罰則などはない。」
罰則がなければ、ウソでも何でも仕事を取った物の勝ち。悲しいけど、これが現実!
日本製紙、官公庁にも偽装再生紙 01/18/07(読売新聞)
製紙大手の「日本製紙」(東京都千代田区)が再生紙の古紙の割合を偽っていた問題で、2001年施行の「グリーン購入法」が、官公庁や独立行政法人に環境に配慮した製品の購入を義務付けた後も、同社は、同法の基準に満たないコピー用紙を基準に達しているよう偽って出荷していたことがわかった。
環境省は17日、古紙の配合率基準に満たない製品の官公庁への納入が常態化していた可能性があるとみて、同法の見直しに向けた検討会を月内に設置することを決めた。
同社の調査によると、昨年10~12月にかけて生産した官公庁向けのコピーやノート、封筒の用紙など、同法の対象商品の生産量は月平均約1万6000トン。
このうち、100%古紙を使うことが求められているコピー用紙など約1万トン分で、実際の古紙の配合率が同法の基準を下回っていた。
同社では1990年代から、古紙の配合率が表示より低い再生紙の出荷を始めており、2001年のグリーン購入法施行後も、配合率を偽装した再生紙の出荷を続けていた。印刷会社など納入先の求めに応じて発行する品質保証書には虚偽の配合率を記載していた。
同社は「グリーン購入法の趣旨に関する理解が不足していた」(総務・人事本部)などと釈明している。
同法では、紙類や文具類など約220品目を「特定調達品目」として指定、官公庁などが購入する際の基準を示しているが、違反した場合の罰則などはない。
安さを求めれば何でもありだろう!事故や死亡事故が起きるまで、問題があっても
改善しない。事故や死亡事故で、制裁措置や入札禁止などの処分がなければ、
同じ事は繰り返される。会社が悪いのか、問題のある会社で働くしかない人間の
運の悪さなのか、事故に遭った人とその家族の感じ方だ。行政のチェックの甘さは
言うまでもない!発注元の市水道局は時々、抜き打ちのチェックはするべきだ。
問題のある会社には警告し、改善のないところは、入札に参加させないとか、
問題を見つけた時には何%か、支払い金額から差し引くとか、厳しい対応が必要だろう!
「発電機の使用知らず」北九州CO中毒死、現場監督が説明 01/13/07(読売新聞)
北九州市の送水管工事現場で7日、作業員3人が一酸化炭素(CO)中毒で死亡した事故で、元請け業者の「平林組」(北九州市)の現場代理人(現場監督)が、発注元の市水道局などの事情聴取に対し、一酸化炭素の排出源になったとみられる発電機について、「事故が起きた横穴に持ち込まれるとは知らなかった。知っていたら止めていた」と話していることがわかった。
福岡県警は、現場の指揮系統や発電機が使用された経緯を詳しく調べる。
一方、事故現場では、横穴に空気を送るため、送風機ではなく、工具などの動力となるコンプレッサー(空気圧縮機)で代用していたことも判明した。
コンプレッサーを取り扱っている業者は「圧縮した空気に不純物が混じる可能性があり、地下工事で作業員の呼吸用空気を確保するために使う機械ではない」としている。
「宝印刷」でインサイダー取引、証券監視委が刑事告発へ 01/13/07(読売新聞)
決算書類などの作成を請け負う東証1部上場の印刷会社「宝印刷」(東京都豊島区)の複数の社員が、印刷物の注文で知った情報をもとに、株のインサイダー取引をしていたことが証券取引等監視委員会の調べでわかった。
不正な取引は数年前から10以上の銘柄で繰り返され、数千万円単位で売買をしていた社員もいた。監視委は社員ら数人を近く証券取引法違反の疑いで札幌地検に刑事告発し、残りの社員については課徴金納付命令を出すよう金融庁に勧告する。
宝印刷は有価証券報告書や株主総会の招集通知の作成・印刷などで2000社近い上場企業の内部情報を扱っている。不正取引をしたとみられる社員は複数の部署にまたがり、管理体制の甘さが問われている。
関係者によると、不正取引には少なくとも退職者を含む3人が関与した。監視委では、ほかにもかかわった社員がいないかどうか調べを進めている。
社員らは数年前から、株式公開買い付け(TOB)に関する印刷物の注文を社内の端末で閲覧、TOBの対象企業の株を公表前に買い付け、値上がり後に売却するなどした疑いが持たれている。TOBは、企業の経営権取得などのため、不特定の株主から株を買い取る手法で、通常は買い取り価格が時価よりも高く設定されるため、対象企業の株価は上昇が見込まれる。
監視委は昨年夏に強制調査に着手。不正取引で札幌営業所に勤務していた元社員が数百万円、ほかの社員らも売却益を得ていたことを突き止めた。同社では約2年前まで担当部署以外でもTOBなどに関する情報を閲覧できたほか、強制調査の直前まで社員の株取引も禁止していなかった。
宝印刷は企業の情報開示のコンサルティング業務も行っており、07年5月期の連結売上高は117億円。
宝印刷は「調査には協力している。処分が決まるまで、コメントは控えたい」と話している。
朝日新聞(2008年1月12日)より
違法放置思いツケ グッドウィル事業停止
虚偽報告際だつ悪質性

違法行為を繰り返す企業は処分されなければならない。たとえ、大企業であっても!
他の企業や同業者に示しがつかない。
労働者が必要であれば、他の派遣会社に仕事のオファーが行くはずである。
泣く人、笑う人がいると思うが、とにかく他の派遣会社へ登録に行くべきだろう。
東京労働局に相談相次ぐ グッドウィル事業停止 01/12/08(朝日新聞)
違法派遣を繰り返していた日雇い派遣大手グッドウィルが事業停止命令を受けた問題で、東京労働局は12日、臨時の電話相談窓口をおいた。雇用不安が広がるなか、58件の相談があった。15日からは全国の労働局でも一斉に相談を受け付ける。
窓口には「処分が始まる今月18日以降、仕事があるかどうか不安だ」といった相談が相次いだ。労働局の担当者は「会社側に契約内容を確認してほしい」などと助言していた。
グッドウィルは、708事業所のうち違法行為を直接行った67事業所が18日から4カ月間、残る全事業所に2カ月間の事業停止となる。多い時で1日あたり約3万4000人を派遣していたが、過去最長となる停止処分で、かなりの仕事がなくなる見込みだ。
やはり、中国は信用できない!中国の工場で生産されたから、中国の要求に従わないと
輸出できない。おかしいだろ。また、中国の要求に従う企業もなさけない。
中国でなく、他のアジアに工場を分散させる企業もあるようだが、個人的には正しいと
思う。
「昨年8月から販売を開始し、初回生産分の1万個は完売した。同社は『中国政府の指示により』
表現を変更したとする断り書きを商品に同封。」
買っていないけど、「地球儀上の台湾を『台湾島』と表記」した点に気付いて子供は凄いと
思う。
中国指示で「台湾島」表記の地球儀、2社が販売中止 12/10/07(読売新聞)
学習教材大手「学研」の子会社「学研トイズ」(東京都大田区)は10日、中国で生産した音声ガイド機能付き地球儀「スマートグローブ」の販売中止を発表した。
地球儀上の台湾を「台湾島」と表記し、音声では「中華人民共和国」と紹介していることや、樺太の南半分と千島列島をロシア連邦に区分したことに、顧客から苦情が相次いだため。
同社によると、この商品は、付属のペン型部品で地球儀の表面に触れると、国名や首都などが読み上げられる。昨年8月から販売を開始し、初回生産分の1万個は完売した。同社は「中国政府の指示により」表現を変更したとする断り書きを商品に同封。しかし、同社は販売中止の公表にあたって「直接の指示は受けていなかった」と説明した。
また「タカラトミー」(東京都葛飾区)も同日、同じ機能を持った地球儀「トーキンググローブ」の販売中止を発表した。「中国の工場で生産していたため、『台湾島』と表記していたが、日本国内向けとしては配慮を欠いた」と説明している。
耐火材偽装:不適切建材、認定後に材料変更も 目立つ業界のずさんさ 01/09/08(毎日新聞)
耐火・防火建材の性能偽装問題で、新たに40社に不正の疑いが見つかったことは、大臣認定制度の形骸(けいがい)化と業界のずさんさを浮き彫りにした。国土交通省は市販品の抜き打ち調査など大臣認定制度の改善、業界各社は管理体制の見直しをようやく打ち出すが、消費者保護の潮流に乗れない体質は否めない。
問題となった40社はニチアスや東洋ゴムのような意図的な不正を否定し、国交省も「悪意はない」とみている。ただ、名の知られた企業も多く、「カイゼン」など高い品質管理を誇るトヨタ自動車も含まれる。トヨタは「書類への初歩的な記載ミス」と平謝りで、認定機関の再試験を受ける方針だ。他の企業も再試験で改めて認定を受けるほか、法令順守体制の徹底で再発防止を図る。
ただ、一連の性能偽装の背景には、大臣認定制度自体の問題も大きい。現在は試験を通れば、その後は誰もチェックしない仕組みだ。今回問題のあったイトーキは、認定後に材料を変更するのがまかり通ってきた。認定機関の試験の監視も甘く、業者の不正を防げなかった。認定機関も業者も大臣認定の「お墨付き」だけを重視し、肝心の性能に背を向けた形だ。【後藤逸郎】
朝日新聞(2008年1月9日)より
耐火偽装 東洋ゴム役員ら減給
社内調査報告書 「無理な事業化原因」

朝日新聞(2008年1月9日)より
耐火性能40社77件問題
国交省 4社7件認定取消し
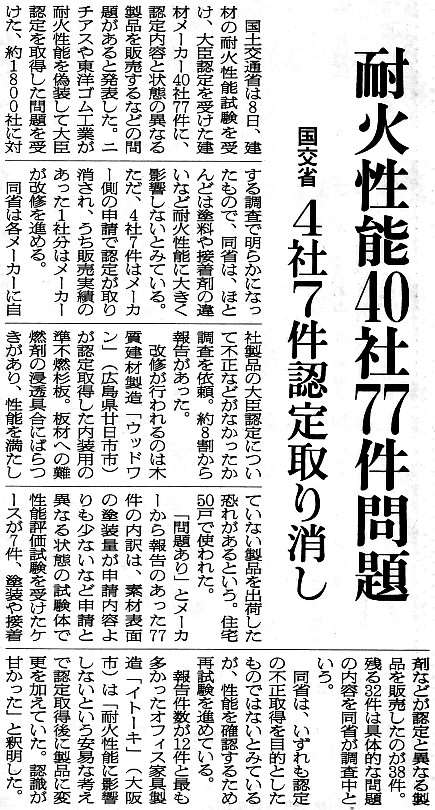
耐火材偽装:不適切建材、「認識不足」と故意否定 会見は1社、文書で謝罪だけも 01/09/08(東京朝刊 毎日新聞)
国土交通省が8日発表した耐火・防火建材の緊急調査で、建材メーカーなど40社が大臣認定制度をないがしろにしていたことが分かった。各社は会見や広報文で謝罪の言葉を連ねたが「制度について認識不足だったため」と故意であることを否定した。国交省は「あってはならない事態だ」と危機感を強めた。
「多大なるご迷惑をかけた。おわび申し上げる」。東京・霞が関の国交省。謝罪会見でイトーキ(大阪府)の金子清孝社長は頭を下げた。一方で「(仕様変更のための)改良は耐火性能に関係のない塗料などに限っていた。性能は落ちていない」と強調した。
この日、謝罪会見を開いたのはイトーキだけだった。一部企業は「今まで以上に法令順守の精神で、このような事態を引き起こさないように徹底してまいります」(松下電工)「事業から撤退します。誠に申し訳ありません」(ウッドワン)などとする広報文にとどまった。
ニチアスなどの問題発覚直後、国交省は「建築現場で実物をチェックするなどの防止方法はある。だが、まじめな業者に負担をかけることは避けたい」と制度の厳格化に慎重だった。しかし次第に「性善説に頼る制度には限界がある」と方針を変えつつある。
大臣認定を委託されている指定性能評価機関は8日、試験を受ける建材を製作段階からチェックする不正防止策を国交省に示した。【高橋昌紀】
耐火材偽装:耐火建材、40社不適切 仕様変更後、再試験せず--国交省調査 01/09/08(東京朝刊 毎日新聞)
耐火・防火建材の性能偽装問題を受けて国土交通省が建材メーカーに行った緊急調査で、40社の製品77件(73~07年認定)に大臣認定を受けた際とは異なる仕様の建材を販売するなど不適切なケースがあることが分かった。材質など変更をしたものは、再試験を受けなければならないが、怠った。国交省は「認定制度の信頼性を揺るがす行為で、許し難い」と批判している。
各社は国交省に対し、「再試験が必要だと知らなかった」と回答したという。
大臣認定を受けた耐火・防火建材については昨年10月以降、ニチアスと東洋ゴム工業の2社の性能偽装が発覚したため、国交省は大臣認定を受けた1788社(認定約1万4000件)に緊急調査を指示していた。
4日現在のまとめによると、40社の77件が素材などの仕様変更をしていたのに、試験を受けていなかった。これらはマンションなど少なくとも約300棟の壁や扉などに使われていた。国交省はこの40社にヒアリングを実施中で、確認できた18社名を公表した。
「ウッドワン」(広島県)の準不燃性の杉板は、薬剤の注入が不均一で製品によってばらつきがあった。同社製品は、住宅など50棟に使われているが、今後大臣認定が取り消され、改修が進められる。また、現段階で使用実績のない3社の製品についても大臣認定が取り消される。
燃えやすい恐れがある「サファリウッド協同組合」(宮崎県)の杉板は、認定時にはなかった塗装が施されていた。間仕切り壁の塗装など認定時とは違う素材を使用し、不適切な建材が12件と最も多かった「イトーキ」(大阪府)。問題の建材は240棟以上の銀行などで使用されている。
国交省は大臣認定の約160件を対象に、新たに抜き打ちの調査もする。同省建築指導課は「問題の建材が使用された物件の特定を急ぎ、建築基準法に適合するかどうかを確認する」としている。【高橋昌紀】
==============
<問題のあった企業>
グレイスコーポレーション▽コニシ▽トヨタ自動車▽ウッドワン=以上、製品の大臣認定取り消し予定▽セブン工業▽日本リフェクス▽日本防災化学研究所▽松下電工▽ユニチカグラスファイバー▽サファリウッド協同組合▽福田金属箔粉工業▽日建板▽クリオン▽アルポリック▽大泰化工▽リケンテクノス▽オーツカ▽イトーキ(国交省公表分)
==============
■ことば
◇建材の大臣認定制度
国土交通相は、一定基準の耐火性や不燃性があると認めた建材に「大臣認定」というお墨付きを与えている。大臣指定の6性能評価機関が試験を行う。建築基準法は「防火地域・準防火地域」では「特別な材料を使う場合は大臣認定が必要」と規定。住宅地ではほとんどが対象になる。住宅メーカーは大臣認定を受けた建材しか購入せず、認定製品を使っていれば建築確認手続きも簡略化できる。
朝日新聞(2007年12月28日)より
「改ざん、上層部関与なし」
栗本鉄工所 最終報告書
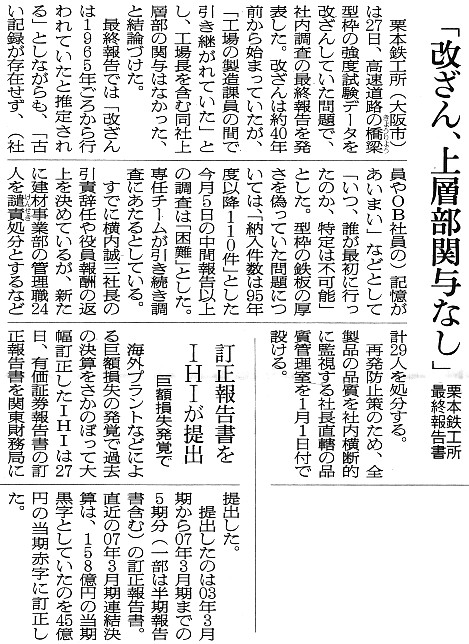
こんどは無免許で梅酒を製造販売 船場吉兆 12/25/07(産経新聞)
船場吉兆(大阪市中央区)による偽装表示事件で、同社が無免許で梅酒を製造し、本店や福岡市内の博多店で販売していたことが25日、わかった。酒税法に抵触する疑いがある。船場吉兆側は「国税当局から指摘があり、現在調査を受けている。詳しいことはまだわからない」と話している。
関係者によると、船場吉兆は酒類販売の免許はあるが、製造免許は取得していない。しかし、調理スタッフが梅を漬け込んで梅酒を自家製造し、食前酒などとして客に提供していたという。
博多店では平成11年ごろからメニューに載せ、グラス1杯700~800円で販売。本店ではそれ以前から梅酒を提供していた。博多店の関係者は「本店ではずっと梅酒を出していたので、博多店もその流れをくんでメニューに加えた。酒税法は特に意識していなかったのではないか」と話している。
無免許で梅酒を製造、販売していたことは、船場吉兆が農林水産省に提出した「改善報告書」の中でも触れられておらず、経営陣に違法性の認識がなかった可能性もあるとみられる。
グッドウィル折口会長代表権返上へ、違法派遣1か月百件超 12/10/07(読売新聞)
厚生労働省が事業停止命令を出す方針を固めたグッドウィル・グループの日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京都港区)による違法派遣は今年8月の1か月間だけで、83支店で計109件に上ったことが、同社の社内調査結果をまとめた内部資料や関係者の話でわかった。
違法派遣による売上高はこの1か月だけで約1900万円と算出されている。厚労省は同社の全国737支店のうち89支店で法令違反を確認。この89支店は4か月、その他の支店は2か月の事業停止(新規の派遣禁止)とする方針。
グッドウィル・グループは23日、厚労省から事業停止命令の通知を受けたことの責任を取って、12月末日でグループの代表取締役を務める折口雅博会長が代表権を返上すると発表した。
関係者によると、グッドウィルは、7月に関東地方の支店で「二重派遣」などの違法行為が表面化したため、翌8月、全国の支店を対象に内部調査を実施した。
判明した違法派遣109件のうち最も多かったのは、同社から派遣労働者を受け入れた企業が、さらに別の企業に労働者を送り込む「二重派遣」で51件に上った。二重派遣は事故が起きた際の責任の所在があいまいになりやすく、中間マージンが増えて賃金が低く抑えられる恐れがあり、職業安定法で禁じられている。
安全面などを考慮し、労働者派遣法が禁止している業務への派遣も目立ち、港湾での運送作業が33件、建設現場への派遣が16件、警備業務も1件あった。
こうした禁止業務への派遣は、受け入れ側が現場で勝手に禁止業務に就かせていたとの釈明がされることもある。だが、派遣元は派遣労働者がどんな仕事に就いているかを把握する必要がある上、グッドウィル関係者は「営業ノルマが厳しいため、禁止業務に就くとわかっていながら派遣したことも多かった」と語る。
グッドウィル・グループも、こうした違法派遣についての処分を受け入れることを表明したうえで、折口会長の代表権返上に加え、グッドウィルの神野彰史社長が役員報酬の月額50%を6か月分返上するなど、役員と執行役員計11人の報酬や給与を返上、または減額する。
マルシェ:馬肉「とろ」不当表示、社長が謝罪会見 大阪 12/15/07(毎日新聞)
脂を人工注入した赤身の馬肉を「とろ」などとしたのは不当表示で景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、公正取引委員会の排除命令を受けた「マルシェ」(大阪市阿倍野区)の谷垣雅之社長が15日、大阪市内で会見し、「メニュー表示に対する認識の甘さ、不注意から起きた。深く反省している」と謝罪した。
同社によると、運営する居心伝▽酔虎伝▽八剣伝の計265店舗で、05年5月~今年5月までの間、メニューやチラシに「とろ馬刺し」「極トロ馬刺し」と記載し、約27万食を販売した。
会見で同社側は、「業者の商品名にある表示がトロの質を示すと説明された。意図的に虚偽の表示をしたつもりは一切ない」と強調。役員の処分について谷垣社長は「監査役などの意見を聞きながら、今後検討していきたい」と述べるにとどめた。
山陰中央新報(2007年12月13日)より
フジモリ産業も偽装
橋の型枠、71年ごろから 高速道3社調査
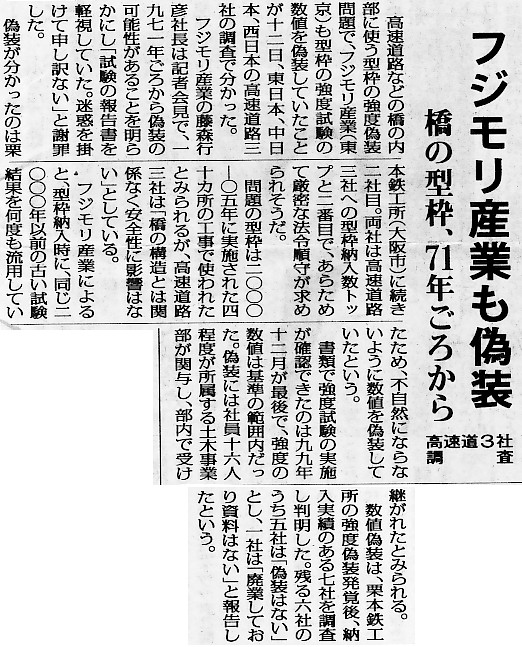
鹿島建設、6億円の所得隠し…キヤノン工場受注で裏金 12/10/07(読売新聞)
キヤノンが大分市に新設した事業所などをめぐり、用地造成と建設工事を受注した大手ゼネコン「鹿島建設」(東京都港区)が、下請けに工事を発注したように装って裏金を捻出(ねんしゅつ)したとして、東京国税局から2006年3月期までの2年間で約6億円の所得隠しを指摘されたことがわかった。
鹿島は裏金の使途を明らかにしなかったため、同国税局から「使途秘匿金」と認定された。関係者によると、裏金の一部は受注工作の謝礼として、地元の建設会社に渡った可能性があるという。
単純な経理ミスも含めた鹿島の申告漏れは約30億円に上り、鹿島は重加算税も含めて数億円を追徴課税(更正処分)されたとみられる。
問題になったのは、キヤノンが05年~07年、総額約1800億円を投じて大分市に新設したデジタルカメラ生産工場とプリンターのカートリッジ製造工場を擁する事業所。鹿島は大分県から用地造成の工事を請け負い、キヤノンから2工場の建設を受注した。
関係者によると、同国税局の調査で、鹿島が下請けに発注した工事のうち約5億円分は架空だったことが判明。鹿島は架空発注で捻出した裏金の使途を明らかにしなかったため、使途秘匿金として法人税率と合わせて70%の重い税率が課せられたという。
ただ、裏金の一部は、鹿島が受注できるようキヤノン側への口利きを依頼した建設会社に渡った可能性が高い。この建設会社の社長はキヤノンの御手洗冨士夫会長(72)と同郷で、会長とも懇意にしているという。
建設会社は大分県由布市にあるキヤノンの保養施設の土地売買にも関与していたほか、この社長が経営する警備会社はキヤノン大分事業所の警備業務を請け負うなど、キヤノン関連の仕事を多く受注しているという。
御手洗会長は10日朝、報道陣に対し「(私は)関係ない。迷惑している」と話し、キヤノンは「鹿島は社内の正規の審査過程を経て施工業者に採用した。建設会社の関与は承知していない」とコメント。一方、鹿島広報室は「個別案件には答えられない」としている。
船場吉兆:心斎橋店パート従業員に解雇提案…反発され撤回 12/06/07(毎日新聞)
牛肉の産地偽装による不正競争防止法違反容疑で大阪府警の家宅捜索を受けた高級料亭「船場吉兆」(大阪市)が、心斎橋店(同)のパート従業員に解雇方針を示したことが分かった。非正規労働者で作る「アルバイト・派遣・パート関西労働組合」(同)が明らかにした。船場吉兆は団体交渉で解雇を提案。反発されて撤回したが、今後の見通しを明らかにしておらず、パート従業員らは「早く営業再開できるよう、幹部は辞任してほしい」と訴えている。
船場吉兆は先月16日の家宅捜索後、全店で営業を停止。パート従業員は接客で雇用しており、大阪の本店、心斎橋店のほか、福岡の2店舗を合わせ、数十人のパート従業員がいるとみられる。心斎橋店では、約20人のパート従業員のうち約10人が「会社から何の説明もなく不安」と同労組に加入した。「しばらく営業できないので帰っていい」と言われただけで、給与支払いや営業再開の説明はなかったという。
同労組は先月29日と今月1日、会社と団体交渉を実施。労組によると、1回目の交渉に出席した湯木喜久郎取締役が「パート従業員全員を12月29日で解雇したい」と提案したという。労組は6日にも団体交渉する。仲村実・同労組事務長は「経営責任を明確にするよう求める」と話している。
船場吉兆は「責任者がいないので分からない」としている。【小林祥晃】
型枠鉄板の偽装、10年で110件…栗本鉄工所が中間報告 12/06/07(読売新聞)
鋼材メーカー「栗本鉄工所」(本社・大阪市)が、高速道路の橋に使う鉄製円筒型枠の強度試験データを改ざんした問題で、高速道路の橋げたなどに使われる型枠の鉄板の厚さがカタログ値を下回るものを納入したのが、2005年までの10年間に少なくとも110件あったことが、わかった。
同社が5日、社内調査の中間報告で明らかにした。同社は「担当者の判断」と組織的な不正関与を否定したが、調査を続けて最終報告をまとめる。
中間報告によるとカタログで鉄板の厚さ1・6~0・6ミリと記載した型枠の注文を受け、10年間に旧日本道路公団や自治体などの工事に3679件を納入した。このうち、110件で実際の鉄板の厚さがカタログ値より0・4~0・1ミリ薄かった。カタログ値通りは1549件、残り2020件は確認できなかった。
同社は、同タイプの型枠を1961年から旧公団の工事に納入していたが、65年ごろから、強度試験に合格しなかった場合は、型枠の内側に補強材を入れるなどして再試験を通過させていた。
しかし、型枠のサイズによっては補強材を使うことができず、強度試験のデータそのものを改ざんするようになった。
こうした偽装に関与した社員らは社内調査に「安全上問題ないと思った」「コストを削減したかった」と話しているという。
名古屋の「丸八証券」、証取監視委が相場固定の疑いで捜索 12/05/07(読売新聞)
中堅の地場証券会社「丸八証券」(名古屋市)が新規上場の主幹事を引き受けた企業の株価を不当に高値で維持していた問題で、証券取引等監視委員会は5日、証券取引法違反(相場固定)の疑いで同証券を捜索した。
金融庁は、株価維持行為が同法違反に当たるとして10月に業務停止命令を出しているが、監視委は悪質性が高いと判断、刑事責任追及のため、捜索に踏み切った。
監視委の調べによると、2006年3月に上場した大阪府の食品会社「ケイエス冷凍食品」(名古屋証券取引所2部)の株価が下落したことから、丸八証券の元取締役ら2人は、顧客にケイエス冷凍食品の株購入を勧めるよう営業員らに指示。同年4月中旬~5月下旬、顧客103人から203件、3万3200株の買い注文を受けて市場で買い付け、株価を固定した疑いが持たれている。
同証券が、新規上場の主幹事を引き受けたのはケイエス冷凍食品が初めてで、元取締役らは監視委に対し「(上場を目指すほかの会社から)新たに主幹事業務を引き受けるため、上場後も面倒を見る証券会社だということを示したかった」などと話しているという。
比内地鶏「放し飼い」せずにかごで飼育、秋田の5業者 12/04/07(読売新聞)
秋田県は4日、同県特産の比内地鶏を生産している県内147業者のうち5業者が、地鶏の飼育法としてJAS(日本農林規格)法で認められていない「ケージ(かご)飼い」をしていたと発表した。
この5業者と、県の調査に応じなかった3業者について、県は、本物の比内地鶏であると証明する「確認書」の発行を取り消す方針。8業者の年間出荷数は約12万5000羽で、県内全体の17%余りにあたる。
JAS法では、比内地鶏など地鶏の飼育法について、孵化(ふか)後28日以降、<1>鶏舎内または屋外で鶏が床面や地面を自由に運動できる「平(ひら)飼い」<2>日中に屋外で飼育する「放し飼い」――をすることと規定している。ところが、1業者はすべての鶏をかごの中で飼育。3業者は部分的に、残る1業者は出荷前の一定期間、かごで飼育していた。
県は、放し飼いなどを確認できない限り、8業者に確認書を発行しないが、ケージ飼いを認めた5業者のうち4業者は放し飼いにする方向で検討するという。
秋田県では10月、大館市の食肉加工・製造会社「比内鶏」による製品の偽装が発覚。生産業者の団体が11月24日、「ケージ飼いしている業者がいる」と明らかにしたことを受けて、県が緊急調査を進めていた。
荏原製作所が裏金補てん3億円、代理店の受注工作費 12/03/07(読売新聞)
大手プラントメーカー「荏原製作所」(東京都大田区)が2004~06年、同社の代理店が東京国税局から追徴課税された法人税などを補てんするために、代理店側に計3億2000万円を支払っていたことがわかった。
代理店は自治体が発注するごみ焼却施設などの受注工作を担当していた。荏原は3億2000万円を帳簿上、経費の「販売手数料」としていたが、税務当局に対しては課税対象の「交際費」として処理しており、正規の手数料でないことを自ら認めた形だ。関係者は「不正な受注工作の口止め料の意味もあった」と証言している。
関係者によると、追徴課税され、滞納していた税金の穴埋めを、荏原にしてもらっていたのは、同社の代理店だったコンサルティング会社「オーエム(OM)プラント」(港区)。自治体のごみ焼却施設や汚泥・し尿処理施設を受注するため、予定価格などの入札に関する情報を入手したり、荏原が受注することへの賛成を取り付けたりする工作を担っていたという。
詳細な情報を得るために、地元議員ら自治体に影響力のある有力者を接待したり、謝礼を渡したりすることもあり、そのための費用に、架空外注費を計上して捻出(ねんしゅつ)した裏金を充てていた。不正な活動や工作費に裏金を使っていることは、荏原側も黙認していたという。
OM社は03年、税務調査を受け、01年12月期までの3年間で約9億円の所得隠しを指摘された。うち4億円は使途を明らかにしなかったため「使途秘匿金」と認定され、重加算税を含め約6億円を追徴された。
OM社の社長(67)は04年、荏原の旧経営陣に対し、「裏金は荏原の受注工作に使った」と主張。これを受け、荏原はOM社に6億円の支払いを約束し、06年まで5回に分けて計3億2000万円を支払った。OM社はこれを納税に充てたとみられるが、荏原は内部告発を機に、その後の支払いを中止した。
荏原は今年4月に経営陣を刷新した際、OM社への販売手数料は不正支出だったと認めた。OM社への支払いは元副社長(69)が独断で部下に指示したもので、元副社長には数千万円を着服した疑いもあるとして、損害賠償請求訴訟も検討するという。
これに対し、元副社長は社内調査に「当時の経営トップも了承していた」と説明。OM社への支払いは元副社長が退任した04年6月以降も続いていることから、不正支出は会社ぐるみで行われていた可能性が高い。
読売新聞の取材に対し、OM社社長は「荏原に裏切られたが、何も話したくない」とし、荏原製作所広報室は「詳細は調査中で、年内には発表したい」と話している。
船場吉兆、社長自ら偽装用牛肉を注文…業者証言 11/18/07(読売新聞)
高級料亭「吉兆」のグループ会社「船場吉兆」(大阪市中央区)による牛肉の産地偽装表示事件で、同社に牛肉を納入していた福岡県久留米市の食肉販売業者が17日、読売新聞の取材に応じ、船場吉兆の湯木正徳社長(74)が業者に直接、注文の電話をかけてくることがあった、と証言した。
大阪府警生活環境課の調べで、長男の喜久郎取締役(44)が牛肉や鶏肉の仕入れを担当していたことも判明し、府警は、同社経営陣が偽装を把握していた疑いが強いとみている。
久留米市の業者によると、同社とは3年前から定期的な取引が始まった。納入していたのは、鹿児島産黒牛や佐賀産伊万里牛で、月に1~2回ずつ、注文に応じて肉を送っていた。発注は仕入れ担当者からが多かったが、湯木社長自身が肉を求める電話をかけてくることもあったという。
一方、府警の調べでは、喜久郎取締役が、本店で提供する料理で取り扱う食材の買い付けや、同社が販売している贈答用商品の原材料の仕入れを担当していた。関係者によると、普段から、商品納入の時期や数量などについて、業者に電話で指示していたという。
府警は、偽装が会社ぐるみで行われていた可能性が高いとみて、上層部の指示がなかったかなど、関係者から事情聴取を進める。
吉兆ブランド変質 「昔ならあり得ぬ」と元従業員 11/16/07(朝日新聞)
「吉兆ブランド」に捜査のメスが入った。高級料亭「船場吉兆」(大阪市)をめぐる食品の表示偽装発覚から2週間余り。大阪府警は16日、異例の早さで強制捜査に乗り出した。偽装は現場の独断か、それとも会社ぐるみだったのか――。「吉兆さんだけは信じていたのに」。信頼を寄せてきた消費者らは、オフィス街の本店に次々と入る捜査員を落胆や怒りの表情で見守った。
「主人がすべてを仕切っていた店なのに。従業員や業者のせいなど、昔ならありえない話」。吉兆で板前修業していた男性(63)は古巣の「変質」に首をかしげた。
吉兆は、文化功労者となった故・湯木貞一氏が1930年に創業した。大阪・高麗橋の本店から船場、京都、東京などに店を増やしていった。
本店には長男、ほかの店は4人の娘に料理人の夫を迎え、多店舗展開を支えた。「船場吉兆」の前身にあたる船場の店は「ビル吉兆」と呼ばれ、三女と、婿で九州出身の正徳氏が切り盛りを任されていた。
「魚は明石、牛肉は近江牛、鶏は名古屋コーチン。仕入れは貞一さんが認めたところだけ」。魚は毎朝、高麗橋店から受け取っていた。20歳で船場の店に入った男性にも、貞一氏のカリスマ性が心に残った。
「うちの店は料理の世界の東大みたいなもん。誇りを持ちなさい」。貞一氏は若い板前に足をもませながら、料理人の心得を語り聞かせた。入り婿を意味する「新宅(しんたく)さん」と呼ばれていた正徳氏も、同席して静かにうなずいていた。
正徳氏は夜明け前から板前たちと青果市場に出かけ、仕事後は、売り上げ日報を自らの手で高麗橋店まで届けた。「とにかくよく働き、貞一さんに絶対服従していた」
90年代、各店は五つの会社組織になり、独自性を強めていった。
男性は、船場吉兆本店でも牛肉と鶏肉の産地、原材料偽装が発覚した9日の記者会見を見た。「福岡出店も、地元九州を思う正徳さんの意向が強く働いたのではないか。あの貞一さんから学んだ正徳さんが『従業員まかせ』『業者まかせ』ですませていたとは考えにくい。悲しいとしかいいようがない」
大阪市中央区の船場吉兆本店ビルには午前10時過ぎ、府警の捜査員約20人が従業員用の入り口から家宅捜索に入った。現場は繊維会社などの事務所が立ち並ぶオフィス街の一角。多くの報道陣で騒然とする中、近隣のビジネスマンらも仕事の手を止めて捜索を見守った。
会社員徳安文雄さん(63)は「高い料金をとるわ、偽装やわと、あんまりな話。どこまで偽装が広がっているのか、だれがうそをついているのか、府警は徹底的に解明してほしい」。近くに勤めていながら一度も利用したことがないという高級料亭に捜査員が入っていくのを複雑な思いで見つめた。
近くの繊維会社社長(65)も「大阪を代表する老舗(しにせ)料亭として信頼してきたのに、『まさか吉兆が』と裏切られた思いだ」と驚いた。別の繊維会社に勤める大阪市淀川区のパート藤本和子さん(72)は「『どうせ消費者には分からへん』と、たかをくくっていたのだろう。強制捜査は自業自得です」。
中央区の商業ビルにある心斎橋店では、この日昼過ぎに「誠に勝手ながら臨時休業させていただきます」との張り紙が入り口ドアに張られた。同店の川浦訓好マネジャーは「本店とは一切連絡がつかない。私の判断で休業を決めた。今後、どうすればいいのか」と困惑しながら話した。
福岡市の船場吉兆博多店(博多区)もこの日、通常営業を急きょ取りやめ、予約客限定の営業に変更。同市中央区の天神店は10日から休業している。
昼になっても開店せず 船場吉兆本店 11/15/07(読売新聞)
高級料亭「吉兆」グループの船場吉兆(大阪市)による食品表示偽装問題で、パート女性らが湯木尚治取締役から指示があったと証言した会見から一夜明けた15日、大阪市中央区の本店は開店時間の午前11時を過ぎても入り口が閉まったままだった。
向かいのオフィスビル内の会社に勤める男性(61)によると、普段は従業員の女性が朝から店の前で掃除をしているが、この日はその姿も見られなかった。
男性は「まさか船場吉兆でも組織ぐるみだったのか…。たまに昼食を食べに行ったりもしていたので気になりますね」と話していた。
一方、心斎橋店(同市中央区)は通常通り午前11時から営業を開始。同店の従業員などによると、本店の15日の営業予定は聞いていないという。
得意客用「つゆ」賞味期限も偽装、船場吉兆本店で張り替え 11/15/07(読売新聞)
高級料亭「吉兆」を展開するグループ会社の一つ「船場吉兆」(大阪市)の消費・賞味期限改ざん問題で、同社が本店でも、得意客向けの贈答用商品について、期限表示を最長3か月延ばしてラベルを張り替えていたことが、大阪市への報告でわかった。
本店での期限ラベル張り替えが明らかになったのは初めて。張り替え後の表示は賞味期限内だったが、同社のずさんさが改めて浮き彫りになった。
報告によると、同社は5~7月に製造した「めん・だしセット」のつゆに3か月間の賞味期限を表示し、6月下旬~7月末ごろ、得意客への中元に配布。その後、残った20~30セットを8月に進物として配った際、その時点から3か月先を期限とする表示にラベルを張り替えたという。
市保健所に対し、同社は「本来の賞味期限は1年半」とし、「最も古い5月製造分を張り替えても期限は超えることはないと考えた」と弁明したという。
市保健所は「1年半の賞味期限自体には妥当性があり食品衛生法違反とまでは言えないが、認識が甘い」と指摘。今後は途中で変更することがないよう行政指導する。読売新聞の取材に対し、船場吉兆は「担当者と連絡がつかない」としている。
つゆの賞味期限は容器や濃度によって異なるが、日本農林規格(JAS)法に基づき検査・格付けを行う財団法人「日本醤油技術センター」(東京)は1~2年とする指針を示している。
朝日新聞(2007年11月15日)より
船場吉兆パート会見 偽装指示生々しく
「1カ月くらい延ばせ」「がんばって売れ」「何度も賞味期限聞くな」
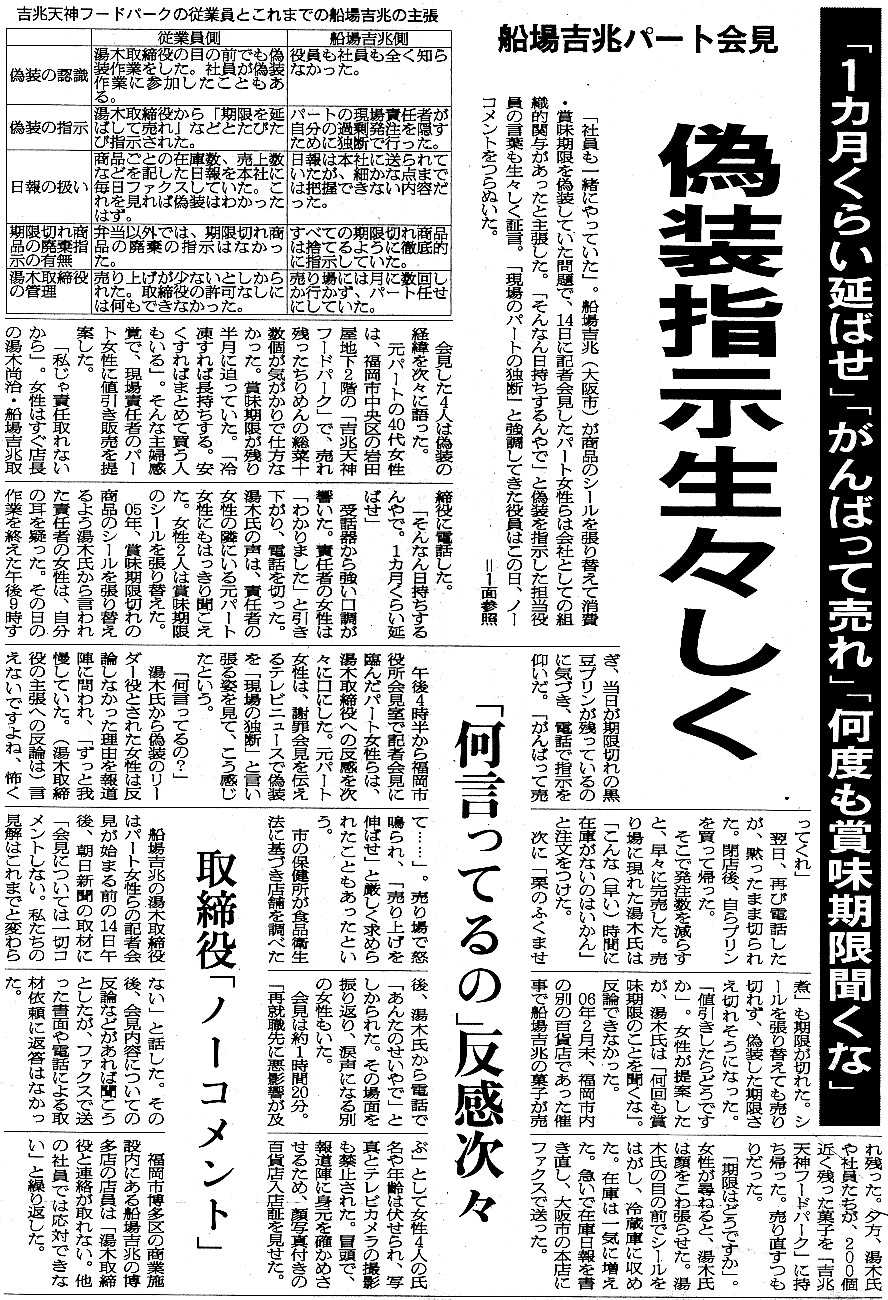
船場吉兆「取締役が改ざん指示」…パート販売員ら証言 11/14/07(読売新聞)
高級料亭「吉兆」のグループ会社・船場吉兆(大阪市)が福岡市の店舗で菓子や総菜の期限表示を改ざんしていた問題で、売り場責任者のパート女性従業員らが14日、福岡市内で記者会見し、九州地区を統括する湯木尚治取締役(38)が、この責任者に対し、消費・賞味期限が近づいた菓子や総菜類について、表示の改ざんによって期限を延ばして販売するよう指示していた、と証言。
表示ラベルの張り替えによる改ざんを日常的に行っていたことを明らかにした。同社経営陣はこれまで「現場のパートに任せきりだった」と説明していた。
記者会見したのは、福岡市の百貨店の店舗に勤務していた40歳代のパートの販売責任者とアルバイト3人。説明によると、販売責任者は店舗オープン3か月後の2004年5月に働き始め、その時はすでに店舗内でラベルの張り替えが行われていた。
期限表示の改ざんを指示されたのは、少なくとも3品目。このうち、賞味期限が近づいた栗(くり)の総菜について販売責任者が対応を仰いだところ、湯木取締役から「延ばして売って」と指示された。賞味期限まで1か月を切ったちりめんを使った総菜なども、「頑張って売って」「それは日持ちがする。1か月くらい延ばして」などと命じられたという。
湯木取締役は、弁当とすしの売れ残りは廃棄するよう指示したが、それ以外は4人とも廃棄の指示を受けたことはなかった。
06年2月には、市内の別の百貨店で開かれた催事で売れ残った「栗入り黒豆プリン」約200個を、湯木取締役や船場吉兆の社員らがこの店舗に持ち込み、アルバイトらが湯木取締役らの目の前でラベルをはがし、店舗内の冷蔵庫に入れたという。
この店舗では毎日、商品ごとの前日在庫、納入、販売などの数を記した日報を大阪市の本社にファクスで送っていた。アルバイトの女性は「日報を見れば本社でも期限切れ商品の販売は分かると思う」と話した。
また、パートの販売責任者は、福岡市が9月に立ち入り調査を始めた後、部屋で事実上の軟禁状態にされ、すべて販売責任者の判断で改ざんを行ったとする文書を湯木取締役から示されて、「会社の役員にしか見せないから、名前を書いてくれ」と要求され、拒否したことを明らかにした。
船場吉兆、期限切れ偽装把握か…日報の在庫数にズレ 11/14/07(読売新聞)
高級料亭「吉兆」のグループ会社・船場吉兆(大阪市)が福岡市の店舗で菓子や総菜の期限表示のラベルを張り替えていた問題で、船場吉兆の日報に記載された納入数や在庫数のズレなどから、会社側も偽装の実態を把握していた可能性があることが農林水産省の調査でわかった。
同社経営陣はこれまで「現場のパートに任せきりだった」と会社側の関与を否定しており、農水省は引き続き事実関係を調べる。
農水省によると、大阪の本店への調査で、昨年1月以降の日報を確認した。日報は福岡の店から毎日ファクスで送られており、農水省では「数字を突き合わせると、期限切れの商品の販売は容易にわかる」としている。一方、同社の湯木尚治取締役は読売新聞の取材に対し、「日報では、期限切れ商品の販売も把握はできない」と話している。
コミニカ:社長と元顧問弁護士を脱税容疑で逮捕 11/12/07(毎日新聞)
東京地検特捜部は12日、精密フィギュアメーカー「コミニカ」(東京都新宿区)の社長、大久保恭子(52)と元顧問弁護士、竹原隆信(49)の両容疑者を法人税法違反(脱税)容疑で逮捕した。調べでは、両容疑者は商品仕入れ額を水増し計上するなどの方法で、05年2月期まで3年間の所得約1億9800万円を隠し、法人税約5700万円を免れた疑い。
コミニカはアニメキャラクターを立体像化する精密フィギュアの草分け的な存在。スタジオジブリ作品「千と千尋の神隠し」「もののけ姫」「となりのトトロ」などのフィギュアやアクセサリー販売で知られる。信用調査会社によると、同社は85年に設立され、過去数年間は毎年2億5000万~4億7000万円程度の売り上げがあった。
竹原容疑者は元検事で、87年の退官まで横浜地検などで勤務した。その後は弁護士登録し、東京都内の大手法律事務所に所属していたが、今年8月に登録を抹消した。竹原容疑者は大久保容疑者と事実婚関係にあり、隠した所得を自分の口座などに入金して管理していたという。【田村彰子】
船場吉兆:表示偽装、取締役も知っていた…現場責任者証言 11/11/07(毎日新聞)
高級料亭や加工食品販売を営む「船場吉兆」(本店・大阪市中央区)が、賞味・消費期限切れの菓子や総菜を「吉兆天神フードパーク」(福岡市)で販売していた問題で、同フードパークの現場責任者だったパート従業員が農林水産省の聞き取り調査に対し「期限ラベルの張り替えは取締役も知っていた」と説明していることが10日分かった。同社経営陣はこれまで「パート従業員にすべて任せていた」と説明しているが、双方の主張が対立しており、農水省は引き続き調査を進める。
同フードパークでは責任者のパート従業員の下でアルバイト5人が働いていた。農水省の調査で、賞味・消費期限のラベルを張り替え、売れ残った菓子と総菜計12品目、計3439個を販売したことが判明している。
パート従業員は約3年前から同フードパークで勤務。関係者によると、パート従業員は表示偽装について、農水省に「ラベル張り替えは前任者からの引き継ぎ事項だった。売り上げや在庫は商品ごとに毎日、大阪の本社にファクスで報告していた」と説明したという。
ラベルの張り替えはほぼ毎日していたといい、九州統括責任者の湯木尚治取締役に、消費期限の近づいた菓子の取り扱いについて尋ねた時は「頑張って売るように」と言われた。また、百貨店のイベントで売れ残った商品がフードパークに持ち込まれ、当日が消費期限の菓子のラベルを湯木取締役の前ではがしたこともあったという。
パート従業員は「湯木取締役の了解がなければ、売れ残った商品の廃棄はできなかった。店では期限切れという言葉を使えない雰囲気があった」と農水省に証言した。
船場吉兆は9日、湯木正徳社長ら3役員が記者会見したが、フードパークから売り上げや在庫の報告は一切なく、売れ残りを表示偽装して販売する指示はしていないと説明。「現場に任せ切りで、偽装は(福岡市や農水省の調査まで)まったく知らなかった」と会社側の関与を否定している。
同社ではフードパークでの賞味・消費期限の偽装に続き、大阪の本店で牛肉や鶏肉の加工品の偽装表示が明らかになり、農水省が改善を指示している。【食品偽装取材班】
「船場吉兆に一度も『地鶏』と言っていない」 鶏肉店主証言 11/10/07(読売新聞)
高級料亭吉兆グループの船場吉兆(大阪市)が産地や原材料を偽装していた問題で、同社に鶏肉を出荷していた京都市の老舗鶏肉専門店「とり安」の男性店主(63)が10日、産経新聞の取材に対し、「(同社との)取引は約15年間に及び、書類にも『地鶏』と書いたことは一度もない」と証言した。偽装が発覚した際、同社は「裏切られた」として店主側に非があるとの立場を強調していた。
店主によると、船場吉兆と取引を始めたのは約15年前。夕方、店じまいをするために掃除をしていたところ、1人の男性が突然、「鶏は残っていますか」と姿をみせ、店内に残っていた鶏肉を買って帰った。翌日、男性から電話で「父親も『これはおいしい』と喜んでいる」と謝意を伝えられ、付き合いが始まったという。
半年後、発送先となっていた店に電話したことがきっかけで、この男性が船場吉兆の湯木正徳社長で、鶏肉をほめてくれたのが国内の料理界で初めて文化功労者に選ばれた料理人、湯木貞一さん(故人)だと知った。
「腰を抜かした。父親といったら、先代の社長さんでしょう。料理の神様みたいな人ですから」
それ以来、店主は同社に卸す肉は家族のだれにも触らせず、1人でさばき続けた。ただ、取引の際に渡す請求書や領収書に『地鶏』と記したことは一度もなかったという。
しかし、同社が商品の「地鶏こがねみそ漬け」「地鶏すき焼き」にブロイラーを使用していた偽装が発覚した9日、同社側から「だましたのか」「地鶏と思っていたのに」などと責められた。湯木社長らが会見で「業者には地鶏と注文し、1キロ5500円の高値で購入していた。裏切られた」などと話したことに衝撃を受けた。
「うちは一言も地鶏と言っていないし、店にも若鶏専門店と書いている。若鶏といえばブロイラーだし、15年にわたって誠心誠意、最高級のブロイラーを卸してきたのに…。一体これまでの信頼関係は何だったのか」
店主は今、怒りよりもむなしさの方が強いという。
「国交省建築指導課は『試験方法にも問題があると認識しており、何らかの対応を考えたい』としている。」
今まで試験方法を再評価してこなかった国交省にも責任がある。
「各機関はサンプルだけで簡易な成分検査を行うのが通例で、両社はこれを悪用し、
偽装した試験体と申請通りのサンプルを使い分けるなどして検査をすり抜けていたとみられる。」
「ニチアスは、試験体に水を多く含ませるなどして耐火性を高め、サンプルは申請書通りのものを提出していた。
東洋ゴム工業では、試験体の断熱パネルに水酸化アルミニウムの粉末を混入して偽装していた。」
パナマビューローの検査見逃しに匹敵する。
PSC(外国船舶監督官:国交省職員)
の多くが経験不足なのか、やる気が無いのか、真実は不明であるが問題を指摘出来ない。
これも同じようなことだろう。
悪質な企業に対して厳しい処分及び制裁を法的に行なえるように国交省は対応するべきだ!!
耐火偽装、実物大の建材の成分検査せず 11/10/07(読売新聞)
建材メーカー「ニチアス」(東京都)と「東洋ゴム工業」(大阪市)による耐火性能の偽装問題で、6か所ある性能評価機関が、耐火性試験を行う際、メーカーから提出された庇(ひさし)や壁など実物大の建材(試験体)と建材の一部(サンプル)のうち、試験体の成分検査をしていないことがわかった。
各機関はサンプルだけで簡易な成分検査を行うのが通例で、両社はこれを悪用し、偽装した試験体と申請通りのサンプルを使い分けるなどして検査をすり抜けていたとみられる。国土交通省は試験方法の見直しを検討している。
国交省建築指導課によると、耐火などの性能評価は、建築基準法に基づき6か所の性能評価機関で実施することになっている。各機関は加熱試験や成分検査を行い、パスしたメーカーに性能評価書を発行し、国が認定する仕組み。
各機関によると、性能評価を行う際には、メーカーから試験体、サンプルの提供を受ける。サンプルは解体するなどして、含水率や比重などを調べ、目視で申請書通りの材料が使われているかを確認するが、試験体はサンプルと同一との前提があるため、加熱試験のみで、成分検査は行わないという。
ニチアスは、試験体に水を多く含ませるなどして耐火性を高め、サンプルは申請書通りのものを提出していた。東洋ゴム工業では、試験体の断熱パネルに水酸化アルミニウムの粉末を混入して偽装していた。
国交省建築指導課は「試験方法にも問題があると認識しており、何らかの対応を考えたい」としている。
加ト吉「循環取引」、私文書偽造容疑で週明けにも一斉捜索 11/10/07(読売新聞)
冷凍食品大手「加ト吉」(本社・香川県観音寺市)グループが、実際には商品を動かさず伝票上だけで売買する「循環取引」を繰り返し、約1000億円の売り上げを水増ししていた問題で、香川県警は、取引の一部に加ト吉子会社「加ト吉水産」(同)の偽造印が使われていたとして、週明けにも容疑者不詳のまま有印私文書偽造・同行使容疑で関係先を一斉捜索する方針を固めた。
捜索対象は、取引を主導したとされる加ト吉の高須稔・元常務(68)、同県の貿易会社社長(58)の自宅や取引先企業など二十数か所。県警は関係資料を押収、循環取引の全容解明を進める。
昔は不祥事を起すたびに社長や責任者が辞めて幕引きだった。辞めるのではなく、
再発防止や原因究明が重要だと思ってきた。しかし、最近は責任者が責任逃れをするし、
都合が悪くなると、ウソだと思うが「記憶に無い」と言う。このような経営者や責任者は
人間的に失格だと思うが、このような経営者の会社への処分が甘い。
薬害肝炎
で舛添厚労相が対応したいと発言したら、財務省と相談してからと町村官房長官が言った。
国にも責任があるだろ!舛添厚労相は国民一人一人が200円を負担してくれたら
患者を救済できると言ったが、まず第一に
厚生労働省
職員の退職金の一部を救済に当てるべきだろう。特に、責任があった職員には
退職金の一部又は50%の返納、関係があった職員の2割の退職金の返納。
関係が無い職員は5%の返納が必要。関係がある省の職員が責任を取らずに、
国民に一律に負担を押し付けるのはおかしい。
防衛省
は無駄使いが多いのだから、防衛省の予算を減らして薬害肝炎の被害者救済に回すべきだ。
防衛省の予算を減らして被害者が救済されるなら防衛省も不服はないだろう。
日本国民の安全と命を守るために防衛省が必要であるなら、命を救うことには変わりない。
厚生労働省
は日本国民を見殺しにしてきた。ミサイルなどの予算を減らしても良い。
役人が責任逃れをする。だから、民間の取締まりや処分が甘いのだろう。
民間の取締りを適切に行なえば、役人の不祥事や不正を見逃すのかと国民は怒る。
国のけじめのつけ方、責任の取り方は醜いほどに汚い!
上記の事を考えると、ニチアス川島社長ら幹部3人が引責辞任は潔いと思える。
耐火性能偽装、ニチアス川島社長ら幹部3人が引責辞任 11/08/07(読売新聞)
耐火性能を偽った住宅建材を販売していた建材大手ニチアスは8日、川島吉一社長(58)、田中勇会長(70)、奥本久治専務執行役員(63)の3人の代表取締役が偽装問題の責任をとって辞任する人事を発表した。
3人は、昨年10月の社内調査で防火建材の国土交通相認定を不正取得していたことを把握したが、公表していなかった。
田中氏と奥本氏は8日付で辞任。川島氏は社内の原因究明対策委員会の報告を受けたうえで、11月30日に退任し、それまでに後任社長を決める。3人とも退職金を辞退する。
8日に記者会見した川島社長は「大臣認定を不正に取得し、事実を一年間隠蔽して被害を拡大した責任をとりたい。大変申し訳ない」と謝罪。「強い非難やしっ責を受け止め、再発防止のために社内体制を作り替えていきたい」と述べた。
偽装が発覚した先月30日以降、住宅メーカーが取引の中止を検討していることや、建材の改修費用が少なくとも300億円に上ることなどが明らかになり、同社の株価も急落していた。同社によると、同社の電話相談窓口には7日夕までに約1800件の問い合わせがあり、このうち約500件は「うちの家の安全性は大丈夫か?」といった不安の声だという。
国交相認定を不正取得した建材が使われている住宅は計約10万棟で、耐火性が基準以下と確認されたものは約4万棟を数える。同社では新たに認定を取得した建材を使って改修工事を急ぎたいとしている。
弁護士も加わった同社の原因究明対策委員会では、偽装が判明している建材以外についても過去の試験データを基に調査しており、認定を受けている131件のうち53件で偽装がないことを確認した。
本当に日本は横並び!良いことも悪いことも!今回も推測は正しいことが明らかになった。
強度不足鋼材
のケースでもフジテックの問題だけではなかった。
大手建材メーカー「ニチアス」による耐火性能の偽装問題は東洋ゴム工業にも広がった。
国土交通相認定を不正に取得した防火用断熱板はどこの機関で試験を受けたのか??
どのような不正だったのか??国交省は公表してほしい!
東洋ゴム工業、偽装の断熱板使用は176件…半数強が店舗 11/08/07(読売新聞)
東洋ゴム工業(大阪市)による建材の不燃性能偽装問題で、国土交通相認定を不正に取得した防火用断熱板が使用されている建物176件の半数強が、ドラッグストアなどの店舗であることがわかった。
所在地は首都圏を中心に16都県にわたり、同社は建物の所有者への連絡を急いでいる。
同社が作成した建物のリストによると、問題の断熱板の設置場所は、埼玉(64件)、千葉(15件)、東京(13件)、神奈川(8件)など。92件が店舗で、うち71件をドラッグストアが占めている。同社は1か月以内に改修方法を決めたいとしている。
問い合わせは、同社の相談窓口(0800・3001456)へ。
「疑問感じながら慣習で」 営業所員、赤福偽装に罪悪感 11/04/07(朝日新聞)
「おかしいと思いながら、慣習としてやっていた」。和菓子メーカー赤福(三重県伊勢市)の偽装問題で、名古屋市から食品衛生法違反にあたるとして営業禁止処分を受けた同社名古屋営業所(名古屋市中川区)の従業員は、朝日新聞の取材にこう語った。組織の一員としての義務感と罪悪感に苦しみながら、消費者を欺き続けた。しかし、次々と明らかになる本社主導の偽装の悪質さは現場の想像をはるかに超えていた。
同営業所は赤福にとって伊勢、大阪に並ぶ重要な市場である名古屋方面向けの出荷拠点として、04年に完成した。名古屋駅周辺など主に愛知県内に、20人ほどの社員が7ルートで赤福餅を送り出す。3個入りパックの商品も作った。
裏の役割があった。いったん完成して製造日を表示した未出荷の商品が持ち込まれると、35平方メートルほどの包装室で包装し直し、表示上の製造日を次の出荷日にずらす「まき直し」をした。
市は食品衛生法に基づく営業禁止の直接の理由として、(1)本社からの6000箱を冷凍せずに「まき直し」をした(2)3個パックの消費期限を本当の日付から1日後にずらす「先付け」をした、という2点を挙げた。
市や関係者によると、同営業所での偽装の段取りはこうだ。
本社から夕方に連絡を受け、東名阪自動車道などの売店を結ぶ「名阪ルート」の配送車から店頭に出されなかった商品を受け入れ、すぐに零下40度の冷凍室へ。翌朝7時ごろの本社の指示で「まき直し」。2~4人が約80度のスチームが出る解凍機で解凍後、包装紙がうまくはがれるように大きな扇風機で乾かす。
包装紙に解凍当日を製造日とした印を機械で押す。年、月、日それぞれの数字の後に「・」(ピリオド)。「まき直し」の行程に再び回ることを防ぐ目印だ。製造者欄の「N」は名古屋で「まき直し」をしたことを示す。だがそれらの意味を知る所員はいなかった。
各地の売れ行きを把握し、商品の移動を細かく判断する本社側の指示と、指示に従い冷解凍や再包装、日付の表示、出荷や再出荷をする現場の作業が相まって偽装は完結する。
名古屋での偽装は9月まで続いた。明白な偽りである「先付け」について従業員は「おかしいと思いながら、慣習としてやっていた。本社の指示があり、しないといけなかった」とうなだれた。
10月中旬以降、次々に赤福の不正が明るみに出た。売れ残った商品を、冷凍せずに「まき直し」を施して再出荷したり、消費期限の切れた商品を餅とあんに分けて再び赤福餅の材料にしたり。
市によると、同営業所にも売れ残りが戻されていた。そうとは知らない営業所は未出荷品と同様に「まき直し」をし、再出荷してしまっていた。
「店頭に出た商品を再冷凍しないのは食品会社として当然」と信じてきた従業員は、常軌を逸した不正に加担していたと知り、言葉を失った。
10月末、浜田益嗣(ますたね)前会長が引責辞任した。
従業員は「辞任は妥当。責任のなすり合いをしても仕方がない。顧客の信頼を取り戻す努力を続けるしかない」と言葉少なに語った。
名古屋市は本社と現場一体で偽装を続けた赤福の商品管理体制全体の改善を見極める必要があるとみて、本社を管轄する三重県と連携を強める。
「へんば餅」に原材料記載漏れ、県が立ち入り検査 11/04/07(読売新聞)
三重県伊勢市の和菓子メーカー「へんばや商店」(奥野宗一社長)が、主力商品「へんば餅(もち)」で、不適切な表示をしていた疑いがあることが4日、わかった。
同県は10月31日、同社から「原材料の記載に漏れがあった」との報告を受け、1日、日本農林規格(JAS)法違反の疑いで同社を立ち入り調査した。
県農水産物安全室などで事実確認を進めているが、へんば餅はこしあん入りの餅で、原材料表記に「水あめ」と「食塩」が抜け落ちていたという。また、「上新粉・砂糖・小豆・酵素(大豆)・トレハロース」の表示が重量順でなかった疑いもある。
同社は1775年創業。江戸時代、伊勢神宮近くを流れる宮川のほとりに茶店を設けたのが始まりで、参拝客がここで馬を返したことから、「へんば餅」と名付けたという。
クレジット会社:悪質商法を助長 「審査どんどん通す」 11/03/07(毎日新聞)
高額商品を大量に売りつける「次々販売」が問題となる中、元訪問販売業者が毎日新聞の取材に、大手クレジット会社に「加盟店になれば、どんどん審査を通す」と勧誘され、独居老人に多数の羽毛布団を売りつけていたことを証言した。この元業者は「複数の個人業者がセールスを断りきれない顧客の『カモリスト』を共有し、売り上げを分け合っている」と話す。クレジット会社が悪質商法を助長している実態が明らかになった。
証言したのは大手訪問販売会社から15年前に独立し、今年1月まで自営で布団を訪問販売していた50代の男性。「羽毛は原価の20~30倍以上、1枚数十万円の値で売れる。必要のない人にも売った」という。
男性によると、「カモリスト」と呼ばれる名簿は大手訪問販売業者の営業マンらが退職する際に持ち出した顧客情報を寄せ集めてそれぞれ作成する。顧客は大半が独居老人で、リストには訪問時に聞き出した年齢や家族構成、預金残高までも克明に記している。「元教諭で知識はあるが、『湿気』という言葉に弱い」「町内会長で体裁を気にするので、家に入りやすい」--など、顧客ごとの落とし方もある。
リストは業者間で交換され、ある業者のリストで別の業者が販売に成功すれば、売り上げの一部をリストの所有業者に分配する。顧客の預金が底をつくとクレジット契約による購入を持ちかけ、「ご飯が食べられなくなるところまでむしり取る」。食費もなくなり公営住宅で野菜作りを始めた高齢者もいたという。
男性は事務所を構えた直後、複数のクレジット会社に勧誘された。ある大手に「うちだけの加盟店になってくれれば、無理が利く。多くの審査を通す」と持ちかけられ、話に乗った。この大手は1人の高齢者に1カ月で3枚の羽毛布団を売りつけても審査をパスさせてくれたという。
被害者救済に取り組む弁護士に説得され、男性は廃業した。「悪いこととは思ったが、簡単に年何千万円も稼げるのでやめられなかった。クレジット会社は悪質業者と知りながら、いくらでも審査を通してくれた。規制を強めなければ次々販売はなくならない」と話す。
◇ ◇
経済産業省は05年7月、クレジット会社に対し、加盟店の管理強化に努めるよう求める7回目の通達を出した。だが次々販売の被害相談は依然として多く、国民生活センターによると06年度は1万6106件に上る。
同省は訪問販売を規制する特定商取引法を改正し、必要以上の販売を取り消せるよう定める方針だが、業者名や商品名を変えればすり抜けられるとの指摘がある。割賦販売法改正を論議する産業構造審議会小委員会では、クレジット会社に加盟店調査を法的に義務付けるべきだとの意見が出ている。【クレジット問題取材班】
◇情報をお寄せ下さい。
〒100-8051(住所不要)毎日新聞「クレジット問題取材班」。メールは表題を「クレジット」としてkurashi@mbx.mainichi.co.jpへ。
会社が大変なのも事実。損失を抑えたいと思うことも理解できる。しかし、このような対応。
会社組織に問題があるのは明らかのように思える。簡単に解決できる問題じゃないようだ。
不正合格めざし何度も実験した大手建材メーカー「ニチアス」の体質の問題は、外部からの
改革者なしでは実現できないかもしれない。表向きは改善や改革のふりは出来る。しかし、
真の体質改善や改革は難しいであろう。
耐火材偽装:「準耐火性能確認」でニチアスが訂正、謝罪 11/02/07(毎日新聞)
耐火材の性能を偽装していた大手建材メーカー「ニチアス」(東京都港区)は1日、国土交通省の指示で行っていた偽装耐火材の再評価試験で「準耐火性能が確認された」と発表していたが、実際は性能評価をまだ受けていなかったことが分かった。同社は、「不適切な記載があった」として謝罪、訂正した。
同社は1日夜、偽装に伴う住宅の改修などによる特別損失見込みを約4万棟分など約300億円と発表。再評価試験の対象となっている4種類の耐火材が使用された約6万棟分は含めず、発表文で「準耐火性能が確認されました。取替、改修の必要性が低くなりますので、費用見込み額には含めておりません」としていた。文書は東京証券取引所のHPに「投資判断上重要な会社情報」として掲載された。
ところが、実際は4種類のうち1種類について、試験項目の一部が終了しただけだった。1日の再評価試験に立ち会った社員が、本社に試験の途中経過を報告した際、本社の担当者がよく確認しないで事実と異なる発表文を作成したという。川島吉一社長の了解を得て、公表していた。
同社は2日午前、「不適切な記載があった」として、HPなどに「最終の耐火性能は公式な評価を経て後日確認される」などの文言を追加し、修正した。佐藤照夫同社技術本部長は「社内に再試験を急がねばとの気持ちがあった。社会にさらに混乱を招くことになり、批判は甘んじて受けたい」と話している。【高橋昌紀】
「浜田前会長は、不正行為について『(売れ残りをなくすため)じわじわと現場からの知恵が入っていった』
と社員の判断で始まったとの見解を示した。」浜田前会長が正しいと仮定すると、処分を受ける社員が存在
すると言うことなのか?利益を上げるため、多くの従業員が偽善者を装いながら、生きてきたと言う事か?
モラルの欠如、これは既に1970年ごろから崩壊していた。隠れた影響が子供達の犯罪や冷酷な事件と
して現れたのか??法改正や責任の追求が必要なのか?
社会保険庁問題
や
厚生労働省の体質問題(血液製剤の投与によりC型肝炎問題)
も責任が曖昧のままだ。この曖昧が不正や隠ぺいもOK?役人だって汚い?ウソや言い訳ばかり。
俺達だって大丈夫との間違ったイメージを発信してきたのかもしれない!日本は沈没するのか!
永遠の繁栄などありえない。もう傾き始めていると思うが、いつ気が付くのか??
赤福:消費期限偽装 会長が引責辞任 不正行為は「現場からの知恵」 11/02/07(毎日新聞)
老舗和菓子メーカー「赤福」(三重県伊勢市)の消費期限偽装問題で、赤福の偽装が始まった当時の社長である浜田益嗣会長(70)が1日、問題発覚後初めて会見し、10月31日付で同社会長を引責辞任し、関連会社の役員や公職についても辞任すると発表した。浜田前会長は、不正行為について「(売れ残りをなくすため)じわじわと現場からの知恵が入っていった」と社員の判断で始まったとの見解を示した。【飯田和樹】
船場吉兆、行政処分へ 農水省、偽装に「常習性」の見方 11/02/07(朝日新聞)
高級料亭「吉兆」を展開するグループ会社の一つ「船場(せんば)吉兆」(大阪市)が福岡市の百貨店で消費・賞味期限切れの菓子を偽装販売していた問題で、実態調査を続けていた農水省は近く、日本農林規格(JAS)法に基づく行政処分を出す方針を固めた。処分内容は、消費・賞味期限を正しく表示するよう求め、事業者名を違反内容とともに実名で公表する「指示・公表」になる公算が大きくなっている。
同省は、船場吉兆が偽装販売していた「黒豆プリン」などについて、JAS法で定めた「飲食料品等の品質表示基準」に違反するとの見解を固めた。
この問題では、同省福岡農政事務所が福岡市から提供された情報を元に偽装ラベルの実態を調査。軽微な違反の場合は公表されない「指導」が適用されるが、偽装表示の期間が長く常習性があるとの見方を強め、さらに重い「指示・公表」処分とする構えだ。
船場吉兆は先月29日、06年1月から07年9月にかけて販売した5種類の菓子計約8000個のうち計2971個について消費・賞味期限を偽装していたことを発表。ほかにも今月1日、百貨店側が総菜類にも偽装表示があったと発表している。
不正合格めざし何度も実験した大手建材メーカー「ニチアス」は確信犯であることは間違いない。
厳しい処分(刑事告発を含む)が不可能であれば、国交省は法改正を含めて検討する必要がある。
このような不正を考え、実行することが許されるのであれば、社会の秩序など守れない。
規則や法律など守る必要が無い。利益のために不正を行い、大きな力で他を圧倒する。
これで良いのか??
「美しい日本」は広まらなかった。多分、不正、隠ぺいやごまかしが存在しながら、
何も悪いことなどしていない顔をする人達から冗談の言葉と思われていたに違いない。
偽装建材の無償改修広がる、国交相「刑事告発可能か検討」 11/01/07(読売新聞)
大手建材メーカー「ニチアス」(東京・港区)による耐火性能の偽装問題で、同社から問題の防火建材を購入した住宅メーカーの間で、無償改修に乗り出す動きが広がっている。
9社のうち、最大の取引先だった旭化成ホームズ(東京)が約3万8000棟について改修を表明しているほか、住友林業(同)、トヨタホーム(名古屋市)、アキュラホーム(東京)の3社が、国の認定基準を満たしていなかった防火用天井板(不燃板)を使用した計56棟分について、無償で改修することを決めた。
一方、ニチアスの調査で、認定基準を満たしているとされたタイプの建材を使用しているのは、ミサワホーム(東京)の約5万棟、エースホーム(同)約290棟、トヨタホーム165棟、アキュラホーム1051棟、古河林業(同)約30棟、エス・バイ・エル(大阪市)約1700棟、大和ハウス工業(同)約350棟――となっている。
各社では、指定性能評価機関が改めて実施する耐火性試験の結果を見て、改修するかどうか判断する考えだ。
◇
冬柴国土交通相は2日の閣議後の記者会見で、ニチアスの耐火偽装問題について、「犯罪事実を認知すれば(公務員として)告発する手続きがあるので、関係部署と相談していきたい」と述べ、法務省や警察庁と協議して刑事告発が可能かどうか検討する考えを示した。
また、同社が防火建材の大臣認定を不正に取得していたことについては、「認定制度の信頼性を傷つけ、誠に遺憾」と批判。「大臣認定の条件を満たした製品として買った人(住宅メーカー)に対し、詐欺罪が成立すると思う。告訴するかどうかは被害者が判断すること」と語った。
「ベターリビングでは、『想定外の事態で、落ち度はなかったと考えている。
巧妙な手口で見抜けなかった』としている。」「この試験を担当した評価機関は、目視のチェックしか行っていなかったことも判明。」
耐火性試験で水分量をチェックするのは当たり前。実際に使われる防火建材よりも
多くの水分を含んでいれば、温度上昇に影響する。温度上昇するまで発火することはない。
チェックする担当者が経験も無い素人だったのか、
ずさんな試験(検査)が日常的に行われてきたのいずれかしか考えられない。
国交省は耐火性試験以外の試験方法についても調査すべきだ!
耐震強度偽装事件
と同様にチェック(試験)体制に問題があると言える。国土交通省は問題が大きくなるまで
問題を把握出来ていない。しっかりしてほしい。
PSCによる検査の現状
からも国交省の対応が推測できるが、素直に問題を指摘されたら対応することを心がけてほしい。
防衛省よりもマシかもしれないが、ダメ組織と
比べて安心しないでほしい。PSCならわかると思うが、航海日誌を間違って破棄する
船に訪船したことはありますか?不正を隠すために故意に破棄したり、書き換える船は存在する。
うっかりして破棄するのは海上自衛隊の艦艇だけだろう。こんなダメ自衛官と
比べる事自体、ありえない。
ニチアス、不正合格めざし何度も実験…水分量など設定 11/01/07(読売新聞)
大手建材メーカー「ニチアス」(東京・港区)による耐火性能の偽装問題で、同社は、2000年に耐火性試験が始まった直後から、不正に合格するため、社内の研究所で実験を繰り返し、サンプルに含ませる水分量など詳細な条件を設定していたことが、同社の内部調査でわかった。
この試験を担当した評価機関は、目視のチェックしか行っていなかったことも判明。国土交通省では、試験の不備もあるとみて、試験方法の見直しの検討を始めた。
防火建材の耐火性試験は、00年6月の改正建築基準法施行を受け、始まった。
内部調査によると、ニチアスの技術開発チームは、耐火性の高い商品開発が思うように進まず、不正を考案した。試験開始直後から、浜松市内にある同社研究所の実験炉で、サンプルとして提出する不燃板の材質や含ませる水分量、さらに燃えにくい塗料の種類など、何度も変えて実験を繰り返し、試験で合格しやすい条件を設定した。
特に、水分量については、認定基準は5%未満だが、水がしたたったりにじんだりして外観から分からないようにするため、「基準の6倍以内」が最も効果的だと特定していた。
耐火用の間仕切り壁は01年2月、軒裏に使用する防火用天井板(不燃板)は同年10月に、それぞれ最初の国交相認定を取得。いずれの試験でも、サンプルに基準を超える水を含ませる不正な手法だったことがすでに判明している。
同社関係者は「試験の合格を急ぐ余り、誤った方向に進んでしまった」と打ち明けた。
一方、同社の防火建材の耐火性試験を担当したのは、指定性能評価機関の財団法人「ベターリビング」(東京都千代田区)。
同機関では加熱試験に先立ち、同社が提出したサンプルを目視でチェックしただけだった。外観上、見えない部分や、材質や含まれる水分量などは、基準に適合しているかどうか詳細に確認していなかった。
ベターリビングでは、「想定外の事態で、落ち度はなかったと考えている。巧妙な手口で見抜けなかった」としている。
このため、国交省では今後、サンプルの作成過程に評価機関の検査員が立ち会ったり、複数のサンプルの提出を求め、材質をチェックしたりするなどの対策を検討することにしている。
「ニチアスによると、民間性能評価機関で1日に再試験した結果、一定の耐火性が認められ、
改修の可能性が低いと判断した。ニチアスは4~6年前、この評価機関の試験を不正な
手口でくぐり抜けたが『今回は不正はしていない』(佐藤照夫技術本部長)という。」
疑問な点は不正なしで一定の耐火性が認められる可能性がある耐火材も不正に検査に通す
必要があったのか??本来の説明以下の性能であるが、ある一定の耐火性があるのか、
再試験に使われたサンプルが改良型なのかと疑ってしまう!「『今回は不正はしていない』
(佐藤照夫技術本部長)という。」とのコメントだが、今回以外は不正を繰り返してきた
ようにも聞こえる。国交省は民間性能評価機関の試験方法や他のケースでも不正な試験が
なかったのか調査するべきだ。
一定の耐火性の定義及び説明されていた性能と試験性能の比較を具体的に住宅購入者に伝える
必要があると思う!国交省もホームページで詳細を公表するべきだ!
耐火材偽装:ニチアス、改修・交換費用300億円 11/01/07(毎日新聞)
耐火材の性能を偽装していた大手建材メーカー「ニチアス」(東京都港区)は1日、問題となった建材の取り換えや改修にかかる費用を、約300億円と見込んでいることを明らかにした。07年9月中間決算に特別損失として計上する。
改修対象は、耐火性45分と同60分の軒裏天井が約4万棟、耐火構造の間仕切り壁2種類が計約750件。自社の改修方法で試算した。4万棟のうち大半は、無償改修を打ち出した住宅メーカー「旭化成ホームズ」分が占める。旭化成ホームズなど納入先からの費用請求に備え、300億円を引き当てることにした。
他に性能を偽装していた6万棟分の耐火性については改修対象に含めず、費用として計上しない。ニチアスによると、民間性能評価機関で1日に再試験した結果、一定の耐火性が認められ、改修の可能性が低いと判断した。ニチアスは4~6年前、この評価機関の試験を不正な手口でくぐり抜けたが「今回は不正はしていない」(佐藤照夫技術本部長)という。
ただ、納入先の住宅メーカーが改修を求めた場合は応じる方針で、費用はさらに増える可能性もある。【辻本貴洋】
ある会社が検査したケースで国土交通省職員に問題を指摘したら、「私が判断します。」
と言って問題を指摘しなかった。国土交通省職員が時間をかけて判断する必要は無かった。
規則を基準にして、満足しているかどうかの簡単な判断であった。探せばこれからも
問題は出てくるのだろう!厳しくすれば、業者や業界からの反発や嫌がらせはあるだろう。
問題が発覚しなければ、
守屋元次官のように業者に身を任せる
のが最善だろう。接待を受けて悪い気持ちにはならないだろう。特にモラルの低いキャリアや
職員達は何も感じないであろう。だからこそ、
問題のある公務員には厳しい処分が必要!
そして、
不正を行った企業に対しても厳しい処分が必要!
日本は技術大国を目指す割には、技術者のモラルが低く、技術者が大切にされていない。
黙認した社長や役員でもあった建材事業本部長(同)の罪は重い!国土交通省は技術者のモラルそして
社長を含む役員の責任や処分についても再度、考えるべきだ。
中国電力の山下隆社長のような考えを
持つ責任者を処分する法整備が必要だ!
「覚えていない」とか「聞いていない」を口にする経営者達を逃がしてはだめだ!責任を取らせるべきだ!
ニチアス役員が偽装黙認、耐火認定を他社に先行され焦り 10/31/07(読売新聞)
大手建材メーカー「ニチアス」(東京都港区)が防火建材の国土交通相認定を不正に取得していた問題で、同社は、2000年から始まった耐火性の性能試験で、他社に先行されたことがきっかけで不正を始めていたことが、同社の内部調査でわかった。
また、同社では当初から担当役員が黙認しており、組織ぐるみで行われていた。同社関係者は「焦りがあった」としている。
防火建材の耐火性試験は、00年6月の改正建築基準法施行を受け、1000度前後の高熱を遮断するといった性能を客観的に評価する目的で始まった。
同社によると、耐火性試験での不正は、開発部長(当時)をトップにした技術開発チームの5人前後が関与し、役員でもあった建材事業本部長(同)にも報告、了承を得ていたという。
最初の不正は01年2月、技術開発チームの発案でオフィスビルなどの耐火用間仕切り壁で行われ、指定性能評価機関が行う試験に持ち込むサンプルの不燃板に基準を超える水を含ませるなどの手法が取られた。
その後、一戸建て住宅の軒裏などに使われる防火用天井板(不燃板)にも拡大、05年8月までに計20回の試験で不正を繰り返していた。国交相はこのうち16件の認定を取り消した。
同社関係者によると、間仕切り壁については他社が01年2月ごろに、不燃板についても複数の同業者が同年5月から9月にかけて、それぞれ国交相認定を取得していたが、同社では開発が進んでいなかった。この関係者は、「事業を拡大し、商品を売る対抗上、どうしても大臣認定を取得したいという焦りがあった」としている。
長年思っていたが、思っていたとおりだ!偽装、隠ぺい、そしてウソ!
国は適切なチェックを行なってきたのか?多分、「ノー」だろう。
そして、偽装、隠ぺい、そしてウソを想定した処分を考えていないだろう。
防衛省もあのような不祥事に対応できていない。
守屋前次官の退職金返納も彼の判断次第で、国民の手前、「返して」と国は泣きつくしかない状態である。
公務員の退職金、返納制強化を検討
を検討しているようだが、どこまでやるのか、いつ決まるのか、未だにわからない。
国はしっかりとしなければならない。裸の王様から脱皮とずる賢い狐との離別が必要!
「宅用の防火建材を製造する際、虚偽のサンプルで耐火性試験を受け、国交相の認定を不正に取得していたと発表した。」
国交省はまた騙された!どう対応するのか?たぶん、他の会社も似たような事をしていることも
考えられる。ただ言える事は、虚偽のサンプルで耐火性試験をパスする行為は、非常に重大なことだ。
「何を信用するのか」と言う点に行き着く。大手建材メーカー「ニチアス」の社長も問題の隠蔽に
関わっている。秩序を守る点からも厳しい対応と処分が必要だ!それとも、国交省は業界から
泣きつかれたら簡単に許すのか??今後の対応を見守りたい。
住宅4万棟で耐火性劣る天井板?「ニチアス」が認定で不正 10/31/07(読売新聞)
国土交通省は30日、大手建材メーカー「ニチアス」(東京都港区)が、住宅用の防火建材を製造する際、虚偽のサンプルで耐火性試験を受け、国交相の認定を不正に取得していたと発表した。
この建材は全国で計約10万棟の住宅に使用され、同社の調査では、うち約4万棟は認定基準より耐火性が劣っていたという。同社の社長らは昨年10月に問題を把握しながら公表せず、今月29日まで出荷を続けていた。国交省は同社に対し、すべての住宅について改めて耐火性があるかどうか調査を指示した。
国交省などによると、問題の建材は、軒裏に使用する防火用天井板(不燃板)。同社は2001年10月~05年8月、指定性能評価機関の耐火性試験を受け、3タイプの不燃板について、30~60分の耐火性を認められ、国交相認定を取得した。
ところが、同社は試験を受ける際、耐火性が高まるように、屋根の垂木の上に敷く不燃板に基準の2~6倍の水を含ませていたほか、軒下側の不燃板の材質を断熱性の高いものに取り換えていた。
実際の商品は、耐火性60分タイプは45分、45分タイプは30分しか耐火性がなかった。オフィスビルなどの耐火用間仕切り壁も、不燃板に水を含ませる方法で認定を不正に取得し、約750棟に使用していた。
同社は昨年10月の社内調査で、川島吉一社長ら役員3人が問題を把握した。しかし、納入先の旭化成ホームズ(東京都新宿区)やミサワホーム(同)などの住宅メーカーには知らせず、その後も約1万7000棟分を出荷していた。国交省への報告は、今月17日だった。
川島社長は国交省内で記者会見し、「顧客より住宅メーカーとの関係を優先させ、代わりの資材開発を急いでいるうちに時間がかかってしまった」と釈明した。
一方、ニチアス最大の取引先だった旭化成ホームズは30日、問題の建材を使用している住宅は、首都圏を中心に約3万8000棟に上ることを明らかにした。大半は1時間の準耐火構造をセールスポイントにした「ヘーベルハウス」ブランドの一戸建て住宅で、01年7月以降の契約者が対象。同社は、すべての住宅を無償で改修することにしている。
親会社の旭化成の蛭田史郎社長も記者会見し、「不正は非常に残念。改修にかかった費用の請求も含め法的手段を検討する」と話した。
国交省は、住宅リフォーム・紛争処理支援センターに電話相談窓口(03・3556・5147、土日を除く午前10時~正午、午後1~5時)を設置した。
ペットフードも偽装…使ってないのに「ササミ」「ビーフ」 10/31/07(読売新聞)
ドッグフード製造・販売会社「サンライズ」(大阪市中央区)が、看板商品の原材料名について、実際には使っていないのに「ササミ」「ビーフ」と表示するなどして販売していたことがわかった。
ペットフードを巡っては直接規制する法令がなく、農林水産省と環境省が法規制を視野に検討を進めている。今回の問題は、今後の検討に影響を与えそうだ。
問題の商品は、「ほねっこ」「ゴン太のふっくらソフト」。1か月あたりの出荷量はそれぞれ約80トンと約770トン。読売新聞が24日、不正表示について文書で質問したところ、サンライズは30日に事実関係を認めた。「ほねっこ」の一部は今年2月から10月にかけ、ササミを使っていないのに原材料名に表示し、混入した白身魚は表記していなかった。「ふっくらソフト」は昨年10月から今年7月にかけ、牛肉を使用していないのに「ビーフ」と表示していた。
同社は「ササミを調達できない時、栄養価を落としてはいけないと考え、代わりに魚を入れた」などと説明。中田立治社長もこれらの事実を把握しており、「認識が甘かった」と話しているという。
「船場吉兆」偽装で福岡市が菓子店検査 10/31/07(産経新聞)
船場吉兆(大阪市中央区)が福岡市の百貨店の自社店舗で消費期限のラベルを張り替えた菓子を販売していた問題を受け、福岡市は31日、市内の菓子販売店や製造業者に対し、偽装表示など食品衛生法に違反する事例がないか立ち入り検査を始めた。
市内の百貨店や大手スーパー内に出店する菓子店を中心に、11月末までの1カ月間で検査する予定。消費期限などの日付の記載に問題がないか、消費期限のラベルの張り替えが行われていないかなどを調べる。
同市食品安全推進課によると、31日中に職員約30人で約300店を検査する予定。
英語学校の倒産が聞かれるようになった。英語学校の流行も補助金削減と共に終わりを
迎えているのだろう。だとすれば、安易な救済は慎むべきだ!
国がやっているJETプログラム。コスト対効果はどうなっているのか?
「国際化」と奇麗事だけでは、多額の費用を注ぎ込む事には反対だ!
日本の財政問題が国民の負担を増やしている状況で、
未だに無駄使いが行なわれている。
国は効率やコスト対効果を考えて英語教育を考えてほしい。ただ、ネイティブの先生達を
呼べば英語が出来るようになると安易に考えるのは間違いだ。勉強方法や学習効率を考える
べきだ。
環境を整えるのも大事だ。しかし、子供の勉強しようとする姿勢や積極的な姿勢も重要なことを
理解するべきだ。これは英語学習だけでない。文部科学省が間違っていることは結果が示している!
NOVA、取引装い前社長関連財団に1億円 10/29/07(読売新聞)
会社更生法適用を申請した英会話学校最大手の「NOVA」(大阪市)が今年3月までの7年間、猿橋(さはし)望・前社長(10月25日付で解任)が理事長を務める財団法人に対し、教材の取引を装って計約1億円の利益を提供していたことがわかった。
業務はすべてNOVA側で行っており、財団側もNOVAからの事実上の寄付だったことを認めている。財団の理事には猿橋前社長と親しい元衆院議員も名を連ねており、NOVAの関係者は「財団は社長個人の活動。会社には何のメリットもなかった」としている。
財団法人は、外務省所管の「異文化コミュニケーション財団」(東京都千代田区)。建設相などを歴任した中山正暉・元衆院議員も非常勤の理事を務めている。
外務省に提出された報告などによると、同財団は児童向け英会話教材を開発し、学校や教育団体に有償で配布しているほか、外国語の会話力を測定する検定試験などを実施している。
財団は2000~06年度に、NOVAに対して教材の出版印刷費や開発費などの名目で約5億2440万円を支払う一方、NOVAから完成した教材の売却代金の図書・資料頒布代、検定事業代など約6億2540万円を受け取り、その差額として約1億円の利益を得ていた。
実際には財団に常勤しているのは理事1人だけで、教材の開発・販売や検定はNOVAで行っていた。取引はNOVAが赤字になった05~06年度も継続され、財団はこの2年間に計約3900万円の利益を上げた。
財団はこの利益を年1回開いていた食文化などに関するフォーラムの開催費用に充てていたほか、事務所の家賃や理事らの交際費も支出。外務省から事務処理などに関する規則が未整備だとして、改善を指導されたこともあった。こうした実態について、財団関係者は「取引を装った寄付だ。取引価格などは猿橋社長からすべて指示を受けていた」と証言。NOVAの元幹部は「猿橋さんは自分の権威付けや、政治家と関係を作るために財団を使っていたようだ」としている。
同財団は、犬養毅や秋山真之(さねゆき)、新渡戸稲造らを発起人に1915年、南洋諸島の調査研究を目的に創立された南洋協会が前身。長く活動が停滞していたが、猿橋前社長が知人の紹介で運営に乗り出し、99年に名称を異文化コミュニケーション財団に変更、理事長に就任した。
PCI不正流用9千万円、弁護士口座へ 委託費名目で 10/28/07(朝日新聞)
国発注の中国の遺棄化学兵器処理事業をめぐり、「パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)」(東京都多摩市)のグループ会社が不正に流用した疑いがある約9000万円は、再開発事業の委託費などの名目で、委託先の弁護士名義の口座に振り込まれていたことが関係者の話でわかった。約9000万円がPCI元社長(71)の要求で支出され、架空経費を計上する手口で処理されていたことも判明した。東京地検特捜部は特別背任などの疑いで調べている。
PCIは、海外の建設コンサルタント業務大手。グループ会社「パシフィックプログラムマネージメント(PPM)」(千代田区)は、同じくグループ会社の「遺棄化学兵器処理機構」(港区)が04年度に国から受注した処理事業の一部について、PCIなどの共同企業体を通じて約2億7000万円で再委託を受けた。使途不明になったのはそのうちの約9000万円。同機構は04年3月に処理事業の専門会社として設立され、国からの受注が一本化された。
関係者によると、当時、PPM社長になっていたPCI元社長は、後任のPCI社長(当時)らに対し、同機構の設立は自分の功績だと主張。約9000万円の報酬を支払うよう要求したという。
PCI側はこれに応じ、処理事業を発注者の内閣府に無断でPPMに再委託。その際、架空経費を計上する手口で約9000万円を上乗せして支払った。後任の社長は周囲に「元社長に言われてやむなく支払った」と話しているという。
PPMは04年4月、この約9000万円のうち約5000万円を都内の弁護士名義の口座に振り込み、残る約4000万円も同年6月に同じ口座に振り込んだ。この入金は、都内で計画されていた再開発事業の業務委託費などをPPMから弁護士に渡す名目だったとされる。
一連の取引では、処理事業を約2億7000万円で再委託されたPPMが、さらに都内の建設設計会社4社に計約1億6000万円で発注。PPMは約1億1000万円の利ざやを得た形となっていた。
特捜部はすでにPCI本社や元社長宅などを捜索。同社幹部らから事情聴取を進め、資金の流れの解明を進めている。
「『入校しようかどうか迷っている客がいたら、とにかく粘れ』。本部のノルマは、
教室数が急増した2004~05年を境に厳しさを増した。」
どこの会社でもノルマはあるだろう!結局、このような状況になった以上、
責任者には責任を取らせるべきだ!
NOVA社員「返金説明は意味ないと分かっていた」 10/27/07(読売新聞)
「生活に不安はあるが、『これで楽になれる』というのが実感」――。500億円規模の負債を抱えて会社更生法の適用を申請した英会話学校大手のNOVA(大阪市)で、最後まで教室を守り続けたのは、20歳代の社員やスタッフたちだった。
中途解約に伴う返金や給料の遅配で講師らが次々と退職する中、殺到する苦情対応に追われた。破たんで行き場を失いながらも、肩の荷が下りた様子だった。
首都圏のオフィス街にある教室でマネジャー(店長)をしていた20歳代の女性社員。大学卒業後、「英語が好きなので、英語を学びたい人の手助けができれば」と入社したが、希望はほどなく失望に変わった。
「入校しようかどうか迷っている客がいたら、とにかく粘れ」。本部のノルマは、教室数が急増した2004~05年を境に厳しさを増した。上司に反論し、1時間にわたってどなられた同僚もいた。
特に大変だったのは、契約や解約をめぐるトラブルから経済産業省の処分を受け、受講生の解約が殺到した今年6月以降の4か月半。受講生が暴れて警察ざたになった教室もあったが、本部の担当には電話もつながらない。
「それでも給与をもらっている以上、踏みとどまろうと自分に言い聞かせてきた」
外国人講師の給料が遅れ始めた9月中旬ごろからは、講師の欠勤でレッスンができなくなるケースが増加。毎日数十件もクレームが殺到し、若い女性社員が受付をする教室はどこも混迷を極めた。一人暮らしをしていたスタッフは「あした食べるお米も買えない」と訴え、一日中泣いていた女子社員は倒れた後、そのまま来なくなった。
東京都内の大規模校で働いていたスタッフの女性(21)は6月以降、本来の仕事ではない中途解約の返金の遅れについての苦情電話の応対に駆り出された。
統括本部のマニュアルでは、「申し入れがあった順に返金しています」と答えるよう指示されていたが、「そんな順番に意味がないことは、自分でよく分かっていました」。受講生から詰め寄られることもしょっちゅうで、「社員、講師が何の情報もないまま矢面に立たされた。会社の姿勢は許せない」と話す。
26日夜、東京・新宿の同社東京本部。社員や講師を対象にした保全管理人の説明会に出席した女性マネジャーは、「もらっていない2か月分の給料とボーナスについては、何も分からないまま。あしたから再就職先を探します」と吹っ切れた表情で話した。
NOVA 取締役と監査役計4人が辞任 10/25/07(産経新聞)
資金繰りの悪化で経営が不安視されている英会話学校大手のNOVA(大阪市、猿橋望社長)は25日、取締役1人と監査役3人の計4人が、この日までに同社に辞任届を提出したと発表した。同社は海外ファンドへの新株予約権発行で運営資金を調達したばかり。同社は26日、緊急役員会を開催し、今後の対応を協議するが、主要な役員の辞意表明で、さらに厳しい局面を迎えそうだ。
辞任届は、常勤監査役1人、非常勤監査役2人に加え、経営陣で最古参のアンデルス・ルンドクヴィスト取締役からも提出されている。これで、社長を除く6人の役員のうち、4人が辞意を表明したことになる。
同社では、相次ぐ給与遅配などにより、経理などの管理部門でも社員が流出しており、監査業務に支障が生じていることが背景にあるとみられる。
取締役のルンドクヴィスト氏は、猿橋社長とともに同社を創立したメンバーの1人。大阪・心斎橋で開いた同社初の英会話スクールの講師も務めた。現在は外国人講師のマネジメント部門のトップで、講師らからの信望が厚かったという。
経済産業省から処分を受けた後、社内外への説明責任を十分果たさず、一方で、海外ファンドからの資金調達などを進めた猿橋社長の姿勢に、ルンドクヴィスト氏は反発を強めたとみられる。
同社は24日、外国のファンド2社に新株予約権を発行、7000万円の資金を調達した。しかし、ファンドに対して新株を発行、資金調達をさらに進めるには株価が35円以上との条件があり、今回の役員の辞意表明は市場に影を落としかねない。また、監査役が全員辞任の方向ということで、11月に予定される中間決算発表への影響も懸念される。
会社も、社長も、従業員も地獄へおちないと目が覚めないと言う事だろう!
テレビで「比内鶏」の藤原社長の会見を見たが酷い!反省の態度なし!
利益、会社の存続、自己満足のためなら、全て許されると思っているのか!
まじめにやっても生き残れない会社や努力しても生き残れない会社もある。
食肉加工・製造会社「比内鶏」は存続できないと思うが、残す必要なし!
同情する必要も感じない!
「比内鶏」社長が初めて記者会見、自らの指示で偽装認める 10/25/07(読売新聞)
秋田県大館市の食肉加工・製造会社「比内鶏」が地元特産の比内地鶏を偽装した加工品を製造、販売していた問題で、行方不明になっていた同社の藤原誠一社長(76)が24日、問題発覚後初めて、同社で記者会見した。
藤原社長は、同社が偽装した15種類の製品のうち10種類以上について、自らの指示で偽装したことを認め、陳謝した。
そのうえで、偽装の動機について「比内地鶏の全国ブームに便乗し、商売を手広くしていきたいという事業欲から行った」と話した。社長職を辞任する意思はあるとしたが、時期についての明言は避けた。
藤原社長によると、自身が偽装に関与し始めたのは、社長就任(1996年)の約1年後から。偽装はこれ以前から行われ、「前社長とその前の社長が中心となって行い、自分は黙認していた」と説明。「(社長就任後に)その流れを引き継いでしまった」と語った。
藤原社長は、偽装した製品に自らの指示で「比内地鶏」の名称を使うことを決定。つみれやおでんについては、「(卵を産まなくなった安価な雌鶏=めんどり=の)廃鶏(はいけい)肉でやりなさい」と指示したという。
賞味期限の改ざんは加工製品については認めたが、生肉については否定した。
偽装に対し、社内で異論はほとんどなかったといい、「反対を唱えられない雰囲気があったのかもしれない」と話した。
一方で、偽装の背景には会社の経営の苦しさがあったとし、「消費者をだましたという感覚ではなかった」とも発言した。
「赤福」に無期限営業禁止命令、農水省が立ち入り検査 10/19/07(読売新聞)
老舗和菓子メーカー「赤福」(三重県伊勢市)が店頭で売れ残った主力商品「赤福餅(もち)」の製造日を替えて再出荷していた問題で、三重県伊勢保健所は19日、食品衛生法違反があったとして、同社を同日から無期限の営業禁止処分とした。
また、あんと餅を分けてそれぞれ再利用した実態などを調べるため、農林水産省は同日、日本農林規格(JAS)法に基づき、改めて同社本社などの立ち入り検査に入った。
同日午前8時半、同保健所で命令書を手渡された浜田典保社長は「大変迷惑をかけて申し訳ない。今後も指導をお願いします」と陳謝した。
一方、農水省の検査対象は、同社本社と、本社、名古屋、大阪の3工場。検査は同日午前10時から行われ、偽装表示を始めた時期や数量などを幹部らに確認している。農水省が本社に立ち入るのは今回で4回目となる。
1億円不正流用のPCI、系列会社と架空契約結び資金捻出 10/18/07(読売新聞)
国が中国で進めている遺棄化学兵器処理事業を巡る約1億円の不正流用事件で、大手コンサルタント会社「パシフィックコンサルタンツインターナショナル」(PCI、東京都多摩市)が、受注した事業の費用を流用するため、グループ会社と架空の業務委託契約を結び、資金を捻出(ねんしゅつ)していた疑いの強いことがわかった。
このグループ会社について、PCI関係者は「不正経理を行うためのトンネル会社」としている。東京地検特捜部は、こうした不正経理にPCIの荒木民生元社長(71)も関与していた可能性があるとみている。
17日に特別背任容疑で捜索を受けたPCIのグループ企業「遺棄化学兵器処理機構」(港区)は、2004年度、内閣府から遺棄化学兵器処理事業の総合管理業務などを約79億円で随意契約で受注、その一部をPCIなどの共同企業体に委託した。
関係者によると、PCIはこの業務の一部について、04~05年にグループ会社「パシフィックプログラムマネージメント」(PPM、千代田区、現パシフィック事業開発)に約2億円で再委託、PPMが複数の下請け会社に約1億円で発注したことにしていた。
ところが、このPCIとPPMとの約2億円の再委託契約は書類上だけで実態がなく、実際は、PCIが直接、下請け会社に発注していた疑いが強いという。
PPMから業務を下請け受注したとされる都内の建築設計会社は、取材に、「業務はPCIから直接、受注していた。PPMからは受けていない」と話している。
特捜部は17日、下請け会社数社も捜索し、今後、下請け業務の実態についても調べを進める。
PPMは、都内の土地開発計画を巡り、荒木元社長が警視庁に告発された特別背任疑惑でも、約1億5000万円を捻出する不正経理にかかわったとされている。PCIの関係者は「PPMは、荒木元社長が不正経理を行うためのトンネル会社だった」としている。
特捜部の捜索を受け、PCIとPPMは17日、連名で、「鋭意、事実関係を調査中で、現段階では本件に関してのコメントは控えたい。特捜部の捜査には全面的に協力していく」との書面を出した。
留学中からマリファナ、コカイン…トンボ鉛筆元会長初公判 10/16/07(読売新聞)
覚せい剤取締法違反などの罪に問われたトンボ鉛筆元会長、小川洋平被告(60)の16日の東京地裁での初公判で、検察側が読み上げた冒頭陳述の要旨は次の通り。
◇
第1 被告人の身上、経歴
被告人は、父親が社長を務めていた株式会社トンボ鉛筆に入社し、昭和54年から同61年まではドイツおよびアメリカに勤務した。帰国後、同社の取締役、副社長を経て、平成3年3月から社長、同15年3月から会長を務め、犯行時に至った。
第2 犯行に至る経緯、犯行状況等
1 被告人は、アメリカ留学中、知人女性から勧められて乾燥大麻(マリフアナ)を吸煙したのをはじめとして、大麻樹脂、コカインの摂取も経験した。その後、日本において、外国人女性から勧められるなどして、平成14年ごろから、MDMAの経口摂取を、15年3月ごろからは覚醒(かくせい)剤の加熱吸引を繰り返していた。
2 被告人は19年8月13日午前0時すぎごろ、本件ホテルに1人でチェックインし、同ホテル客室において、その1週間前に外国人から20万円で購入したと称する覚醒剤の一部を使用し、犯行におよんだ。
3 同日、令状により同ホテルの被告人使用客室の捜索が行われ、被告人がズボンポケット内に入れるなどして所持していた覚醒剤および大麻が発見押収された。大麻について、被告人は、以前覚醒剤を購入した際におまけでもらったと供述している。
4 翌8月14日、被告人方の捜索が行われた際、被告人が以前それぞれ別機会に外国人から購入したり、もらったりして自宅に保管していた、N-エチルMDA、MDMAおよび覚醒剤の混合粉末(ピンク色)並びにコカイン粉末(黄色)が発見され、押収された。
大手コンサル元社長ら、国の海外事業費1億不正流用 10/16/07(読売新聞)
政府開発援助(ODA)事業を多数手掛ける大手コンサルタント会社「パシフィックコンサルタンツインターナショナル」(PCI、東京都多摩市)の元社長(71)らが、受注した国発注の海外事業を巡り、事業費の一部約1億円を不正に流用していた疑いがあることが、関係者の話で分かった。
東京地検特捜部も同様の事実を把握しており、特別背任容疑で近く本格捜査に乗り出す。
PCIは、国内外の約40社で構成する建設コンサルタントグループの中核会社で、主に国際協力機構(JICA)などが発注するODA事業を数多く受注している。
関係者によると、問題の事業は、国が発注した海外事業で、同グループの関連会社が受注した後、PCIなどに業務を委託した。PCIは2004~05年、この事業の一部をグループの土木建築会社「パシフィックプログラムマネージメント」(PPM、現パシフィック事業開発)に、約2億円で再委託した。
その後、PPMは、この事業を、さらに複数の会社に下請け発注したが、その額は約1億円にとどまっており、差額分の約1億円の使途が不明になっているという。当時、PPMの社長は、PCIの元社長が務めていた。
このため、特捜部では、PCI元社長らが、本来1億円で済む再委託事業を2億円でPPMに委託し、PCIに差額の1億円分の損害を与えた疑いがあるとみて調べている。
PCIを巡っては、会計検査院の調べなどで、2006年までにコスタリカなど16か国のODA事業で不正経理が相次いで発覚。JICAから06年3月まで計3回、18か月間に及ぶ異例の長期の指名停止処分を受けた。
「1973年ごろ、解凍して包装し直した日を製造日とする偽装を始めた。」
何十年も製造日の偽装表示を続け、大きな問題もなく、問題を指摘されてこなかった。
雪印も不二家の不祥事も、企業の体質と深い関係があるのだろう。
「同社の冷解凍設備は、赤福餅を氷点下35度で急速冷凍し、80度のスチームを当て、
45~50分で解凍処理する。」本当に問題がないのなら、表示すればよい。
日本人の傾向としては当日製造の赤福餅を買うと思うので、正直に書けば結局、
売れ残り、または、値段を下げるしかないだろう。
赤福の冷解凍、1月に社内でも疑問の声 10/14/07(読売新聞)
和菓子の老舗「赤福」による製造日の偽装表示問題で、大手菓子メーカー「不二家」の期限切れ原料使用が問題化した今年1月、赤福社内でも問題視する声が広がったにもかかわらず、大規模設備で34年間続けてきた製造工程を急に変更できないとして「赤福餅(もち)」の冷解凍を継続していたことがわかった。
配送車に積んだ商品を工場内に持ち帰って冷凍保存する行為は中止されたが、一部の製品を工場内で冷凍保存し、解凍して包装した日を製造日にする行為は継続されたという。
同社の冷解凍設備は、赤福餅を氷点下35度で急速冷凍し、80度のスチームを当て、45~50分で解凍処理する。1973年ごろ、解凍して包装し直した日を製造日とする偽装を始めた。
大阪営業所でも同時期に三重県伊勢市の本社工場と同タイプの設備を整え、同様の偽装表示もしていたという。
同社は「ラインが出来ていた以上、引くに引けない状態だった」としている。
また、日本農林規格(JAS)法で「砂糖、小豆、もち米」と重量順にすべき原材料の表記を「小豆、もち米、砂糖」としたことについて、同社は「十勝産の小豆が、赤福餅の最も重要な部分であり、前面に出したいという事情があった」と説明した。
にせ名古屋コーチン問題 愛知県、加工品も調査へ 10/12/07(朝日新聞)
にせの名古屋コーチンが出回っている問題で、愛知県は12日、加工品についても調査対象に加えると発表した。発端となった独立行政法人「農業・食品産業技術総合研究機構」の調査で「名古屋コーチンではない」と判別された商品の約7割が加工品だったにもかかわらず、調査対象から加工品を外したことへの批判を受けて方針転換した。
ただ、同機構の調査で「名古屋コーチンではない」とされた、名古屋コーチン普及協会の杉本勇会長が理事長を務める名古屋市南部食鶏加工協同組合(名古屋市熱田区)の加工品を対象に含んでいるかどうかについては「どこの業者の品物を調べるかは答えられない」としている。
新たにDNA検査をするのは、薫製19点、みそ漬け4点、しぐれ3点、弁当・手羽煮・佃煮(つくだに)各2点、昆布巻き・そぼろ・焼き鳥・混ぜご飯の素(もと)・コロッケ・レトルトカレー各1点の計38点。11~12日に名古屋市と豊橋市のデパートや小売店で購入した。生肉は県農業総合試験場(長久手町)で検査しているが、加工品については「農業総合試験場の検査だと検証に半年かかる」として同機構に依頼する。
「赤福」30年前から冷凍・再包装 10/12/07(読売新聞)
創業300年の和菓子の老舗「赤福」(本社・三重県伊勢市)による製造日の偽装表示問題で、農林水産省は12日、同社に対し、日本農林規格(JAS)法に基づき、不適正表示の改善や再発防止策の提出などを指示した。
同社は、製造日に出荷しなかった商品を冷凍保存し、解凍して包装し直した日を製造日として出荷していた。不適正表示で販売された商品は2004年9月からの3年間で約605万箱に上り、総出荷量の18%にあたるという。
農水省によると、同社は看板商品の「赤福餅(もち)」について、包装済みの商品を直接、本社工場内の冷凍庫に運んだり、配送車で東海地方の販売店舗を回った後に残った商品を持ち帰ったりして冷凍保存。その後、「まき直し」と称して注文数などに応じて解凍し、再包装した日を製造年月日と表示する行為を繰り返していた。
赤福餅の消費期限は、夏場が製造日を含め2日、冬場が3日となっている。同社はホームページで「製造したその日限りでの販売としています」などと紹介していた。しかし、実際には最大で2週間冷凍した後に解凍し、再包装したケースもあった。農水省の調査に対し同社は、「まき直し」と呼ばれる行為は1973年から行っていたと説明しているという。
配送車に積んだ商品を工場内に持ち帰り、冷凍保存する行為は、今年1月下旬にやめていたという。農水省は、大手菓子メーカー「不二家」の期限切れ原料使用が問題化した時期と一致しているため、赤福側が悪質性を認識していた可能性があるとみて調べている。
また、JAS法は原材料名について使用した重量順に表示するよう定めており、本来は「砂糖、小豆、もち米」としなければならないのに、少なくとも2000年3月以降、「小豆、もち米、砂糖」と表示し続けていた。
若林農相は12日の閣議後記者会見で、「信用度の高い老舗のメーカーでこのようなことがあったのは、大変重大なことだと受け止めている」と述べた。
赤福は読売新聞の取材に対し、「農水省の判断の内容をみて、今後の対応を検討し、会見などできちんと説明をしていきたい」としている。
群馬・東和銀、経営悪化把握しながら追加融資 10/12/07(読売新聞)
東証1部上場の第二地銀「東和銀行」(前橋市、吉永國光頭取)が、複数の取引先企業の経営悪化を把握しながら追加融資を続けるなどして損失を拡大させていたことがわかった。
金融庁は銀行内の審査体制に問題があったとして、近く同銀行に業務改善命令を出す。取引先の中には旧大蔵省OBの増田煕男(ひろお)前頭取(70)らと関係の深い企業も含まれていたことも判明。これを受けて、同銀行は前頭取らの意向で不適切な融資が行われたとみて調査委員会を設置し、商法の特別背任罪などでの刑事告訴を検討する。
関係者によると、問題の融資が実行されたのは、地元の建材販売会社や不動産会社、福祉関連会社など10社前後で、この多くが経営不振に陥っていた。一部は、同銀行が実施した増資の引受先になっていたほか、経営者と増田前頭取らが個人的に親密だった企業も含まれている。
こうした企業については、本店の審査・融資部門や担当支店から「業績回復の見込みは低く、回収不能額が増える恐れがある」と追加融資に慎重な意見が出ていたが、最終的に常務会などでは融資が認められていた。融資先の経営実態に合わせて査定基準が変更された可能性もあるという。
建材販売会社の場合、実質的な債務超過状態のままで融資が繰り返されており、同社が今年2月に経営破たんしたことで約17億円が回収不能になった。
同銀行は今年3月期連結決算で過去最悪となる274億円の赤字(税引き後)に転落し、1994年6月から頭取を務めていた増田氏は今年5月に退任した。
金融庁は今春、同銀行に対する検査に着手。追加融資は支店などから稟議(りんぎ)書が上申され、審査部門を経て常務会で承認する正規の手続きを踏んで実行されているが、ずさんな審査体制が焦げ付きを膨らませたと判断したとみられる。
同銀行が設ける調査委員会では、特定の融資案件について増田前頭取の具体的な指示がなかったかどうかを検証する。
増田前頭取は、読売新聞の取材に「取引先と飲食程度の付き合いはあった」としつつ、「現場の意見を無視して融資を指示したことは一度もない」と話している。
東和銀行は1917年創業。相互銀行時代に東京の深川信用組合などと合併し、91年に東証1部に上場した。今年3月末時点の預金残高は1兆6600億円で、群馬県や埼玉県などに91店舗がある。
「赤福」が消費期限を偽装 農水省、改善を指示 10/10/07(読売新聞)
創業300年の餅菓子の老舗(しにせ)「赤福」(三重県伊勢市)が商品の「赤福餅」の消費期限を偽って表示、販売していたとして、農林水産省は12日、日本農林規格(JAS)法に基づき、改善を指示した。赤福は出荷しなかった商品の包装をはがして冷凍保存し、解凍した日を改めて製造日と偽り、再包装して消費期限を改ざんしていた。同様の手法で長期にわたって消費期限の偽装は続けられていたという。
JAS法は原材料名を質量の多い順に記載するよう義務づけている。同省は、赤福が原材料名を「小豆、もち米、砂糖」の順に記載していたが、実際は砂糖の質量が最も多かった。同省はこの点でも改善を指示した。
同省によると、赤福は、いったん包装した商品を冷凍保存させて、再包装する手法を「まき直し」と呼び、日常的に消費期限を改ざんしていたという。改ざんは少なくとも04年9月からの3年間で総出荷量の18%にあたる605万4459箱に上るという。
赤福は「農水省の指摘は、間違いございません」とコメントを出した。同社は同日、「赤福餅」の販売を伊勢、鳥羽市内の直営6店舗に制限し、高速道路のサービスエリアのほか、JRや近鉄などの駅などで販売していた分の回収を始めた。
赤福は1707年に創業し、伊勢土産の代表格として全国の駅やスーパーなどで販売されている。
「ホンダベルノ」会社名義で車庫飛ばし、28人を書類送検 10/10/07(読売新聞)
横浜市港北区の自動車販売会社「ホンダベルノ神奈川東」が社員の私有車を会社名義と偽って車庫登録していたとして、神奈川県警交通捜査課は10日、社長(51)と支店長、社員の計28人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで横浜地検に書類送検した。
県警は、同社は1995年ごろから、社員の私有車の自動車保険料を大口契約して安く抑えるため、会社名義と偽り、車の保管場所を登録する「車庫飛ばし」をしていたとみている。保険料は個人契約より約8割割り引かれていたとみられる。
調べによると、社長らは2003年12月~06年8月、社員18人の私有車を横浜、川崎市にある7営業所が車庫になっているように装って、会社名義で車庫証明を取得し、関東運輸局神奈川運輸支局などにうその車検登録をした疑い。
社長は「社員の福利厚生のためにやった」と話している。
ガス点検記録1万件ねつ造、LP販売大手に契約停止処分 10/09/07(読売新聞)
LPガス販売大手「グロリアガス」(東京都千代田区)がガス設備の点検を実施したように約1万件の記録を捏造(ねつぞう)するなどしていたことがわかり、経済産業省原子力安全・保安院は9日、同社の関東、東北、九州の各支社に6~3か月間、新規契約締結の停止を命じる行政処分を出した。
液化石油ガス法では、契約時と4年に1度以上、ガス漏れの有無や風呂釜などの燃焼機器に正常な圧力でガスが供給されているかなどの点検を義務付けているが、同社は2004年4月~今年6月、計約6300戸でLPガスの契約時の点検を怠っていた。
法定点検を実施していなかった戸数は、この約6300戸を含む計約1万5400戸に上り、同社ではこのうち計約1万戸分について点検記録を捏造。さらに計約4300戸には、緊急時に保安業務を行う業者の連絡先などを記した書面も交付していなかった。
同社は、三井液化ガスの100%子会社で、全国約13万5000戸にLPガスを供給している。同社は、保安院が指摘した違反事実をすべて認めた上で、「処分を真摯(しんし)に受け止めるとともに、お客様にご迷惑をおかけしたことを深く心からおわび申し上げます」とするコメントを出した。
丸全昭和運輸が下請け代を不当減額、公取委が勧告 10/02/07(読売新聞)
東証一部上場の運送会社「丸全昭和運輸」(横浜市)が、「値引き」などと称して下請け代金計約5300万円を不当に減額していたとして、公正取引委員会は2日、下請法違反(下請け代金の減額の禁止)に基づき同社に勧告した。
公取委によると、同社は2005年11月~昨年10月、荷主から値引き要請があると、利益を確保するため、関連する下請け業者に「値引き」を依頼。計101業者に支払うべき代金から0・2~10%分を負担させる形で、計5303万4888円を不当に減額した。
こうした減額は1996年ごろから続いていたという。同社は公取委の調査を受け、今年6月、認定された不当な減額分を下請け業者に全額返還している。
日本人社員や講師らの給与遅配や給与から天引きの家賃を滞納。
NOVAはそんなに困っているのだろうか?本当に困っているのなら
救世主が出てこない限り、先は長くないかもしれない!
NOVAが講師給与から天引きの家賃を滞納 10/01/07(産経新聞)
日本人社員や講師らの給与遅配が続いている英会話大手、NOVAで、同社が大阪市内などで借り上げたアパートに住む外国人講師十数人が、家賃の滞納を理由に家主からの退去を求められていることが1日、わかった。借り上げ住宅に住む講師らの家賃は給料から天引きされているが、NOVAから家主への支払いが滞っているとみられる。NOVA側は「個別の案件についてはコメントできない」としているが、今後、家主が同社の経営を不安視して退去をもとめるケースが相次ぐ可能性がある。
大阪市内に住む女性講師2人は先月末、家主から「家賃が支払われていない。出ていってほしい」と促された。2人は来日当初の契約時に、約25万円の給与から数万円を家賃として天引きすることに同意する契約書に署名し、同社が借り上げたアパートに入居。家賃はこれまでNOVAが支払っていたという。
2人は「会社が家賃を払っていなかったことは、家主に対してとても申し訳なく思う。住む場所を失うのは困るので会社は早くなんとかしてほしい」と不安をもらした。
住宅からの退去を求められた講師からの相談は、NOVAの外国人講師らの相談窓口となっている労働組合「ゼネラルユニオン」(大阪市、山原克二委員長)にも寄せられている。先月末、大阪市内の数カ所のほか静岡県、新潟県などの講師からも相談があった。ユニオンによると、NOVAの担当者はどの住宅で家賃が未払いなのか把握できていなかったといい、「相談があれば、別の住居を速やかに提供するなどすぐに対応したい」と返答したという。
兵庫・姫路公共工事で虚偽書類を市に提出しても10日間の業務停止で済むのだから
無許可業者に仕事をさせる方が安上がり。もし問題があったら誰が責任を取るのか?
市の担当者なのか?
朝日新聞(2007年9月29日)より
神鋼子会社 孫受けに無許可業者
兵庫・姫路公共工事 虚偽書類を市に提出
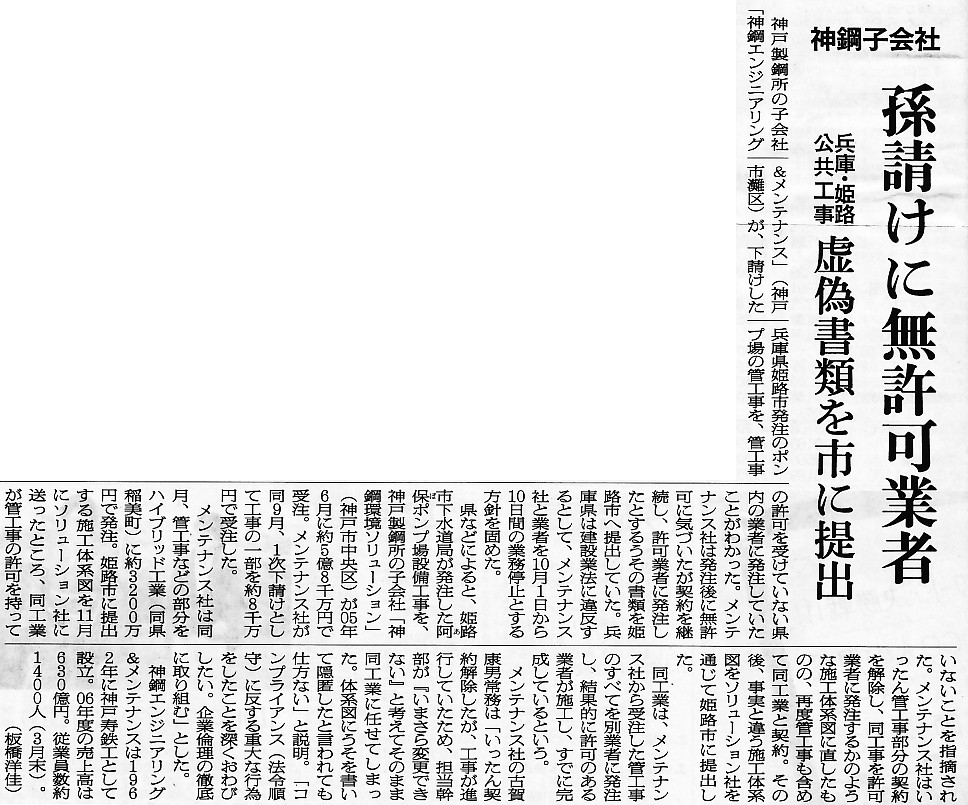
朝日新聞(2007年9月28日)より
変わる顧客サービス 10.1郵政民営化
「お役所」意識改革へ

2007年に伊藤ハムは関税法違反罪で起訴された。
やはり企業体質があるのか?
「伊藤ハムは『伝票用のゴム印を流用して鹿児島県産と表示すれば納入条件をクリアできると
安易に考えた。深くお詫び申し上げ、再発防止に努めたい』としている」
たぶん、豚肉産地を偽装が簡単に見つからないと安易に考えたのだろう。簡単に見つかると思った
のであれば、伊藤ハムが産地を偽装と公表される方が長い目で見て損と考えるから、リスクが大きすぎる。
再発防止を考えるのであれば、社員の意識改革及び幹部社員の意識改革が重要であろう!
豚肉産地を偽装 伊藤ハム子会社 09/28/07(産経新聞)
伊藤ハムの関連会社「伊藤ハムミート販売西」(兵庫県西宮市)が、他の国産豚肉に鹿児島県産と表示して大手スーパーに販売していたことがわかり、農水省は28日、JAS(日本農林規格)法に基づき、業者名の公表と表示是正を指示する行政処分を行った。
産地偽装の情報をもとに、農水省が8月から9月の間、同社奈良営業所に対し調査した。
その結果、同社は近畿地方の大手食品総合スーパーから鹿児島県産を納入することを条件に豚肉を販売。鹿児島県産が不足すると、他の豚肉を同県産に偽装し、平成17年12月~今年6月まで1年7カ月の間、同スーパーに約13トンを販売していたことが確認された。
同社は伊藤ハムの食肉や加工品の中間流通・販売を行っており、入荷時に空白になっているラベルの産地欄に「鹿児島県」とゴム印を押していた。
伊藤ハムは「伝票用のゴム印を流用して鹿児島県産と表示すれば納入条件をクリアできると安易に考えた。深くお詫び申し上げ、再発防止に努めたい」としている
企業の名前だけじゃ、信用できない時代なのか!
積水ハウス・みずほ銀に賠償命令 大阪高裁差し戻し控訴審 09/27/07(産経新聞)
積水ハウス(大阪市)とみずほ銀行(東京都)から、違法建築になるマンションの建築プランを提案され、返済できない借金を抱えて損害を受けたとして、京都市内の自営業の男性が、両社に計約3億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が27日大阪高裁であり、渡辺等裁判長は「違法建築になることを説明する義務があった」として、男性の訴えを棄却した2審判決を変更し、4500万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は平成2~3年、両社の提案で約4億6000万円の融資を受け、京都市内にマンションを建設。その際、返済にあてるため、敷地の一部を売却する予定だったが、売却すると容積率の制限を超え、違法建築になることが判明した。男性は「売却できず返済不能になった」と提訴した。
渡辺裁判長は判決理由で「担当者は土地を売却すれば違法になることを認識していた」と認定。そのうえで「計画を提案しながら原告側に説明しておらず、説明義務に違反することは明らか」と判断した。
1審・大阪地裁判決は両社の賠償責任を認め、3000万円の支払いを命じたが、2審判決で男性の訴えが棄却されたため上告。最高裁第1小法廷は昨年6月、「説明義務があったのに怠った」として2審判決を破棄、大阪高裁に差し戻していた。
積水ハウスの話「一貫して融資の返済問題であると主張してきた。判決文を詳細に検討した上で判断したい」
みずほ銀行の話「判決内容を確認の上、今後の対応を検討する」
ヤマト運輸に労働時間改ざんの疑い、関西支社に是正勧告 09/23/07(読売新聞)
宅配便最大手「ヤマト運輸」(本社・東京都中央区)が、大阪市内の集配センターなど2か所で宅配ドライバーらにサービス残業(賃金未払い残業)をさせていたとして、大阪南労働基準監督署が労働基準法違反で是正勧告をしていたことがわかった。
同社は、ドライバーにコンピューター端末「ポータブルポス(PP)」を携帯させ、出勤・退勤時刻を記録、管理しているが、給与計算の基となる勤怠記録が実際の端末記録と異なり、労働時間が短くなっていたケースが判明。記録改ざんの疑いもあり、同労基署は関西支社(大阪市)に対し、大阪市内のセンターなどを管轄する大阪主管支店管内の従業員に過去2年間の未払い賃金を支払い、10月末までに改善報告書を提出するよう命じた。また、関西支社管内の全従業員約2万2000人の過去2年間の労働実態を調査のうえ、サービス残業があれば未払い賃金を支払うよう是正指導した。
ヤマト運輸広報課の話「従業員がタイムスケジュール通りに業務を行わなかったためで、サービス残業を行わせたわけではない。2か所以外のセンターでは問題はないと考えている。勤怠記録とPPの記録に差異があったかどうかは、労使協議にかかわるので詳しくお答えする必要はない」
豚肉の差額関税を悪用、14億円脱税で輸入会社社長を逮捕 09/20/07(読売新聞)
国産豚肉の保護を目的とする「差額関税制度」を悪用し、昨年の約10か月間で輸入豚肉にかかる関税約14億円を脱税したとして、大阪地検特捜部は20日、滋賀県長浜市の食肉輸入販売会社「大豊」社長、冨義明容疑者(60)を関税法違反の疑いで逮捕した。
また大阪税関と合同で同社などを捜索した。特捜部などは、冨容疑者が1999年ごろから同社や別会社名義で同様の不正を繰り返し、脱税総額は100億円規模の可能性があるとみている。
調べによると、冨容疑者は昨年1月24日~11月1日までの計97回にわたり、カナダから計約816万キロの冷凍豚肉を輸入した際、1キロ当たりの輸入価格を実際より170円前後、高く偽って大阪税関に申告し、差額関税約14億3000万円を免れた疑い。
うち43回分は大豊名義で申告していたが、18回分は大阪市の食品輸入会社、36回分は埼玉県越谷市の食品輸入会社の名義を借り、冨容疑者は両社に1キロ当たり10円を謝礼として支払うことを約束。特捜部は両社の幹部らについても任意で事情を聴いている。
大阪税関の昨年の調査で不正が発覚。同社は昨秋の輸入分について修正申告し、約2億2000万円の関税を追加納付したが、大阪税関がそれ以前の取引についても調査していた。近く特捜部に告発する。
冨容疑者は食肉卸加工団体の専務理事をしていた1992年にも、同様の手口で名古屋地検に関税法違反罪で起訴されている。
逮捕前、冨容疑者は読売新聞の取材に、「大阪税関の指摘を受け、修正申告した。脱税を繰り返していたわけではない。逃げも隠れもしない」と話していた。
差額関税制度を悪用した不正は後を絶たず、これまでに愛媛県四国中央市の食肉卸会社「協畜」(脱税総額約119億円)などが摘発された。また、食肉加工メーカーとしては初めて、兵庫県西宮市の「伊藤ハム」が関税法違反罪で起訴された。
民間信用調査機関によると、大豊は、冨容疑者が社長を務める別の食肉卸会社の輸入卸部門として99年5月に設立。昨年4月期の売上高は約90億円。
整理回収機構の常務、巨額債務者と海外旅行…倫理抵触も 09/16/07(読売新聞)
整理回収機構(東京都千代田区)の常務執行役員(57)が2004~05年、債務者の不動産会社前社長(55)と2度にわたり、海外へのグループ旅行に同行していたことがわかった。
前社長は旅行直後に同機構から111億円の連帯保証債務の支払いを免除されたが、常務は前社長側に知人を介して、この交渉にあたった弁護士を推薦していた。常務の行為は、利害関係者との親密な交際を禁じた倫理規程に抵触する可能性があり、同機構は調査を始めた。
この常務は弁護士資格を持ち、企業再生本部を担当している。1999~04年に同機構の顧問弁護士を務めた後、役員に就任した。
関係者によると、常務と旅行していたのは、静岡県内にあった不動産会社の前社長。2人は、共通の知人である経営コンサルタントの会社が主催した04年9月の中国旅行と、05年9月のモロッコ旅行に、ほかの5、6人と参加した。
いずれも旅費は約50万円で、常務は自分で負担していた。2人はほかにもゴルフや飲食で2、3回、顔を合わせていたという。
この前社長は94年に親族から不動産会社の経営を引き継いだ際、横浜市内の不動産開発などで、旧住宅金融専門会社(旧住専)から受けた数百億円の融資を個人で連帯保証した。債権は同機構に引き継がれ、05年時点で不動産会社の債務は120億円、前社長の連帯保証分はこのうち111億3900万円に上っていた。
常務は最初の旅行の後、経営コンサルタントから同機構側との交渉の進め方を相談され、知人の弁護士を推薦。前社長は05年春から、この弁護士を代理人に立てて、同機構と連帯保証債務の減額を交渉していた。
同機構は、モロッコ旅行の翌月の同年10月、前社長には主だった資産や収入がないとして、4000万円を支払わせることで111億円の連帯保証債務の支払いを免除する合意書を交わした。不動産会社に対する債権120億円は、1000万円以下で大手金融会社に売却された。
常務は前社長と海外旅行したことを同機構に伝えていなかったが、同機構は、旅行の事実をつかんでいれば資産状況を再調査した可能性もあったとしている。
常務は、同機構に対し、前社長から債務について相談を受けたことを認め、「整理回収機構と真正面から話し合った方がいいと話しただけ」と述べたという。これについて、同機構は「債務免除を決めたのは、常務の担当とは違う部署だが、常務の行為に問題がなかったかどうか調査している」と話している。
常務は、読売新聞の取材に対し「整理回収機構にすべて話してある」、前社長は「常務とは特に親密な間柄ではない」と回答した。
中国人実習生を不正派遣、窓口団体関係企業が仲介 08/29/07(読売新聞)
外国人研修・技能実習制度で来日した中国人実習生を、2003~06年に明治乳業の子会社など少なくとも5社が雇用した際、静岡県内の人材派遣会社が不正に介在していたことが読売新聞の調べでわかった。
この人材派遣会社は、実習生の受け入れ窓口となった同県内の中小企業協同組合の役員が設立し、管理費名目などで収入を得ていた。日本では外国人の単純労働が認められておらず、労働力不足の現場では同制度が受け皿になっているが、中間搾取のリスクを排除するため、私企業が介在しないことを前提にしており、法務省は調査に乗り出す方針だ。
実習生と受け入れ企業の間に介在していたのは、静岡県函南町に本部を置く「協同組合SEITO」の専務理事(39)が経営する人材派遣会社「マル産」(現ネクシオ)と同「レイバーデザイン」(現くみあいサポート)。
実習生は受け入れ企業に直接雇用されるため、本来、給与の支払いや社会保険の手続きは受け入れ企業が行わなければならない。ところが、同組合から中国人を受け入れた明治乳業の子会社「明治ケンコーハム」(東京)などは、実習生への給与支払いなどの業務をマル産とレイバーデザインに委託。明治ケンコーハムの場合、03年11月~06年11月に両社に実習生の給与として計約1億7000万円を払ったが、うち約1700万円が管理費として派遣2社に入ったという。
同組合は01年4月に専務理事の親族らが発起人となって設立された。これまでにアジアの研修・実習生計約700人を受け入れ、同県内外の加盟企業156社に送り込んできた。マル産の所在地は組合と同じ事務所にあり、組合理事長が同社役員を兼ねていた。レイバーデザインも同じ所在地で専務理事と親族が役員だった。
専務理事は読売新聞の取材に対し、派遣会社が実習生の給与を支払うなどしていたことを認めた上で、「ルールに従い、昨年中に改めた。今は問題ない」としている。明治ケンコーハムは「制度への理解が不十分だった。派遣という認識はなかったが、そう見られても仕方がない面があると思う」としている。
同制度の問題に詳しい桑原靖夫・独協大前学長は「悪質なケースだが、この制度には多くの欠陥があり、悪用されやすい。表に出ないだけで、実際には同様なことがかなり行われている可能性もある。外国人労働者の受け入れのあり方という視点から、制度の改廃を含めて根本的に考え直す必要がある」と指摘している。
独立行政法人で残業代未払い 労基署が是正勧告 08/25/07(朝日新聞)
車検業務を国から委託されている自動車検査独立行政法人の中部検査部(名古屋市中川区)が、40代の男性職員の昨年の残業手当の一部を支払わなかったなどとして、名古屋南労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが分かった。男性は7月、過重勤務により抑うつ状態になったなどとして、同法人を相手取り、慰謝料など約555万円の支払いを求め名古屋地裁に提訴した。
同法人によると、2月に同労基署から、男性の06年4~12月分の残業手当の一部が未払いなうえ、超過勤務を1年360時間までなどと定めた労使協定にも違反しているとして是正勧告を受けた。
男性は国土交通省中部運輸局から出向し、06年度は同検査部の管理課係長だった。同検査部は、同期間の男性の超過勤務は385時間で、うち139時間が未払いだったとして約39万円を支払った。
また、訴状によると、男性は事務見直しや部下が休暇を取ったことなどから残業が増加。昨年12月に医師から抑うつ状態との診断を受け、今春、出向元の中部運輸局に戻ったが、自宅療養が続いているという。
同法人は「超過勤務の適正な管理・縮減に取り組むなかで勧告を受けたことは残念。提訴については現段階ではコメントできない」としている。
「白い恋人」賞味期限改ざん、北海道が石屋製菓を行政処分 08/23/07(読売新聞)
チョコレート菓子「白い恋人」などの賞味期限改ざん問題で、北海道は23日、メーカーの「石屋製菓」(札幌市)に対し、日本農林規格(JAS)法に基づき再発防止を指示する行政処分を行った。
9月25日までに点検体制の整備など具体的な改善措置を報告するよう求めた。
道庁で山本邦彦副知事から指示書を交付された同社の石水勲社長は「処分を重く受け止め、1日も早い信頼回復に努める」と答えた。
道は指示書で、<1>1度表示した賞味期限を過ぎた商品に、新たな期限を再表示しての販売中止<2>原因究明と再発防止<3>経営陣、全従業員の食品表示に関する知識習得とJAS法順守<4>品質表示に関する点検体制の整備――を求めている。
また、JAS法違反には当たらないものの、「白い恋人」やミルフィーユ菓子「美冬」などで発覚した賞味期限の二重設定についても、道は農水省ガイドラインに沿って適切な期限設定を求めた。
石屋製菓:「白い恋人」のほか5商品でも賞味期限延長 08/22/07(毎日新聞)
「石屋製菓」(札幌市西区)が主力商品「白い恋人」の賞味期限を改ざんするなどしていた問題で、石水勲社長は22日、札幌市内で記者会見し、「白い恋人」のほかにも新たに5商品で社内基準で決めた賞味期限を延長していたことを明らかにした。同社は17日から賞味期限の延長が他の商品にもなかったか、内部調査していた。石水社長は「残念な結果になった」と話し、同席した次期社長の島田俊平顧問とともに謝罪した。
新たな賞味期限延長が分かったのはミルフィーユ菓子「美冬(みふゆ)」▽「マイスタークッキー」▽「コーティングチョコレート」▽「オレンジコンフィ」▽「鳴子パイ」
「美冬」は昨年5月ごろ、本来は45日間の賞味期限を約10日延長し、約250箱を出荷した。「マイスタークッキー」は過去2年で数回、賞味期限が3カ月だった時は4カ月に、4カ月に変更した後は5カ月にそれぞれ1カ月延長。延長した製品は1回につき約10~300枚だった。
「コーティングチョコレート」は今年4月、3カ月の賞味期限を2カ月延長して40個を出荷。「オレンジコンフィ」は今年2月、1カ月の賞味期限を数日延長し約260個を出荷。「鳴子パイ」は今年4~6月、45日の賞味期限を半月~1カ月延長し約250個を出荷していた。
恒常的な賞味期限の延長が明らかになっている「白い恋人」については今年5~6月、4カ月の賞味期限を1カ月延長し、約9000個を出荷していた。
「美冬」「マイスタークッキー」「白い恋人」は在庫品、「コーティングチョコレート」「オレンジコンフィ」は返品分、「鳴子パイ」は在庫、返品の商品をそれぞれ延長していた。商品は包装紙を外し、新たな賞味期限で包装し直していたという。
賞味期限の延長は同社の総合管理課長が伊藤道行統括部長と相談し、判断。石水社長は知らなかったという。
同社は23日に臨時株主総会と取締役会を開く。その後、外部の有識者らを招いた「コンプライアンス確立委員会」を設置する。委員会では(1)原因の徹底究明(2)再発防止策(3)社員のコンプライアンスなどを第三者の目でチェック--などに取り組む。【三沢邦彦】
中華航空:事故機の英語社名と花マーク塗りつぶす 08/22/07(毎日新聞)
 那覇空港で中華航空機が爆発、炎上した事故で、中華航空は21日、事故機の胴体左側面にある「CHINA AIRLINES」という英語の社名ロゴと垂直尾翼にある紅梅の花のマークを白いペンキで塗りつぶした。事故機の映像や写真が連日報道されるため、企業イメージの低下を避けるのが狙いとみられる。
那覇空港で中華航空機が爆発、炎上した事故で、中華航空は21日、事故機の胴体左側面にある「CHINA AIRLINES」という英語の社名ロゴと垂直尾翼にある紅梅の花のマークを白いペンキで塗りつぶした。事故機の映像や写真が連日報道されるため、企業イメージの低下を避けるのが狙いとみられる。
同社は事前に国土交通省航空・鉄道事故調査委員会(事故調)に了解を求め、事故調も調査には支障がないと判断して要求を受け入れた。同社はこの日の事故調などによる実況見分後に塗りつぶした。
ロゴやマークを塗りつぶしたことについて、中華航空の広報担当は「国際慣例に従った。詳細はよくわからない」とだけ話した。【木下武】
札幌商工会議所の副会頭や、自らが設立に尽力したサッカーJ2・コンサドーレ札幌を運営する
北海道フットボールクラブ(HFC)の非常勤取締役も辞任する必要もないと思うが、
責任を取らない首相や電力会社のトップと比べると良い決断だ。
社長は黙認していただけで社長の指示でなく、担当課長や伊藤道行・取締役統括部長が
判断していたのであれば、改ざんの判断に関与した社員達の処分も公表すべきだ。
社長だけが辞任して許される問題ではない。ただ、社長が改ざんを指示していて、
公表していないだけで事実が公になるよりも責任を取る形での辞任であれば、違う話に
なる。事実を公表してほしい。
石屋製菓:石水社長、週明けに引責辞任 賞味期限改ざんで 08/17/07(毎日新聞)
「石屋製菓」(札幌市西区)が主力商品「白い恋人」の一部で賞味期限を改ざんするなどしていた問題で、石水勲社長は17日会見し、週明けに引責辞任すると発表した。後任には北洋銀行の島田俊平常務が就く。石水社長は当初、「事件が落ち着いた時点で、社長を含めた人事で新体制として立て直したい」(16日会見)と話し、責任の先送りを示唆していたが、消費者や取引先などからの批判に抗しきれず、辞任に追い込まれた。
この日の会見で石水社長は「まだ新事実が出る可能性を否定できず、私一人の力量では処理できない」と、辞任の理由を述べた。さらに、「今後、会社に戻ることはない」と言明し、経営の一線から退く意向も示した。札幌商工会議所の副会頭や、自らが設立に尽力したサッカーJ2・コンサドーレ札幌を運営する北海道フットボールクラブ(HFC)の非常勤取締役も辞任する見通し。
石水社長は創業家2代目のオーナー社長。「白い恋人」を自ら開発し、北海道を代表するブランド商品に育て上げた。【三沢邦彦】
パナマビューロー
や
神○造船(広島)
は食品関係で無いから得だよな!
不正を行っても処分されないのだから!
国土交通省が第1回船内居住環境改善モデル設計研究会
を開くようだが、見栄を張らないで守らせることが出来る項目だけを決めるべきだ。ごまかしを
見逃すようなら改善項目など研究会で話し合うだけ時間の無駄。
不二家、ミートホープ、そして「白い恋人」を製造・販売する石屋製菓。
他の会社の不祥事がニュースで取り上げられているのを見ても改善できないのだろうな、
行き着くとこまで行かないと!改善していたら、消滅を待つだけなのか?
これで日本の景気は良いと考えられるのか?
「白い恋人」 賞味期限、甘い設定 繁盛期は6カ月 08/17/07(朝日新聞)
北海道の観光土産「白い恋人」に賞味期限の改ざんが見つかった問題で、製造・販売する石屋製菓(札幌市)が社内で「4カ月」と決めていた賞味期限を、自己都合で最大「6カ月」まで延長していた実態が明らかになった。賞味期限の延長は、いったん消費者に示した期限を書き換える改ざんとは異なり、直ちに違法行為ではないが、立ち入り検査をした札幌市保健所は「6カ月の根拠は科学的に不十分だ」と指摘する。
通常は4カ月。繁盛期や在庫が膨らんだ場合は5~6カ月――。製造元の石屋製菓ではこの10年間、「白い恋人」の包装に印字する賞味期限が、都合によって延長されてきた。こうした作業が、石水勲社長の了承のもとで日常的に行われていたことが、社長自らの会見で明らかになった。
会見によると、賞味期限の延長は、96年に包装パッケージを一新してからずっと続けていたという。石水社長は16日の記者会見で、「消費者は新しいものを求めるから」と話した。
これに対し、札幌市保健所は「賞味期限は、消費者に(食物を)安全に提供できる根拠」とし、期限が統一されていないことは消費者にとって「わかりにくい」と指摘。最大6カ月に延長していることについては「科学的根拠として不十分だ」との見解を示した。
問題となった改ざんや菌検出の背景には、こうした期限延長などに見られる消費者軽視の姿勢があった。社長や統括部長(57)の会見によると、改ざんなどの経緯は次のようになる――。
4月24日、発売30周年の記念包装で売れ残った「白い恋人」4476箱を前に、統括部長は「大丈夫だろう」と決意した。包装紙を張り替え、1カ月先の賞味期限を打って再出荷するやり方だった。しかし、社長には報告されなかった。
6月27日、自社の定期検査でアイスキャンディーから大腸菌群が出た。その後の保健所の調査では破棄した商品4トンのうち8割以上から検出される深刻な事態だった。7月28日にはバウムクーヘンからも黄色ブドウ球菌を検出した。
6月下旬、同社のホームページあてに、賞味期限の改ざんを告発する匿名のメールが届いた。7月には大腸菌群の検出を告発するメールも届いた。いずれも社内からと見られるが、報告を受けた統括部長は自分の胸にしまい込んだ。
8月9日、匿名の告発が、札幌市保健所にもたらされた。翌日から立ち入り検査が入り、機材の不備を指摘された。同社は新聞広告で公表したが、賞味期限改ざんや食中毒菌のことは隠し続けた。
「他にも不正があるんじゃないか。小出しにしていたら、大変なことになりますよ」。13日昼、顧問弁護士が社長に進言した。統括部長がすべてを打ち明けたのは同日夕。緊急の記者会見は、翌14日午後9時に開かれた。
石水社長は創業家の2代目で、会社を現在の形にまで引っ張った。商工会議所の副会頭を務め、今春の札幌市長選では保守系候補の後援会幹部を務めた。社外の活動が忙しく、ここ数年は統括部長が実質的に経営を担っていた。
「順風満帆で、会社が増長していたのかも知れない」。石水社長は会見で、こう話した。
単独の判断なのか、氷山の一角なのか?
訪問介護大手のコムスン
の問題は組織内に広がっていた。
医療器具の滅菌有効期限、ニチイ学館契約社員が改ざん 08/17/07(読売新聞)
千葉県循環器病センター(市原市鶴舞)で、医療器具の滅菌作業を委託されている医療事務大手「ニチイ学館」(東京都千代田区)の契約社員9人が、一部物品の滅菌の有効期限を日常的に改ざんしていたことが16日、わかった。
同センターは、ニチイ学館に再発防止策について報告を求める。
期限が改ざんされていたのは、メスなどの医療器具を載せるトレー、ガーゼの容器など。
内部のマニュアルでは、有効期限を滅菌後1週間と定め、期限が来たら返却して滅菌処理を施して保管する。
契約社員は少なくとも昨年末ごろから、物品の請求があった時点で、有効期限を記入するテープに1週間後の日付を書き入れて物品に張り、各部署に供給していた。業務の負担を減らそうと独断で改ざんを始めたとみられる。
「白い恋人」賞味期限、11年前から改ざん指示…社長会見 08/17/07(読売新聞)
チョコレート菓子「白い恋人」の賞味期限改ざんなどが発覚した札幌市の菓子メーカー「石屋製菓」の石水勲社長は16日に行った記者会見で、同社が4か月と定めていた「白い恋人」の賞味期限表示を、同社の在庫の状況によっては5~6か月に延ばしていたことを明らかにした。
この不適切な表示は、11年前から石水社長の了承の下で行っていた。北海道庁と札幌市は同日それぞれ記者会見し、石屋製菓に対して改善指示や行政処分を行う方針を示した。
同社によると、「白い恋人」は原則として、製造日から4か月後の月末に賞味期限を設定していた。しかし、保存能力の高い個別包装フィルムを使うようになった1996年から、在庫状況に応じて、5~6か月後の月末に設定して出荷していたという。
一方、札幌市保健所の柏原守・食品指導課長は会見で、こうした期限延長を15日の立ち入り調査で把握したことを明らかにし、「客観的に説明できる根拠ではない」と批判した。衛生管理面についても、製造機具の消毒に使う塩素の希釈を目分量で行うなど、「ずさんさを感じるものだった」と指摘。同社の6~7月の自主検査では、アイスクリームなどのサンプル173個のうち、66個から大腸菌群が検出されていたことも明らかにした。
柏原課長は「白い恋人」など、全商品の消費、賞味期限の再検討や、アイス類とバウムクーヘンの細菌汚染の原因究明と改善などを口頭で指示したとした。
また、道くらし安全課は、売れ残ったキャンペーン限定商品の賞味期限を1か月延長して再表示し、販売していたことは日本農林規格(JAS)法の品質表示違反に当たるとの見解を発表した。
「賞味期限は社内の基準で4カ月と設定している・・・『白い恋人』の賞味期限は、
包装フィルムが新しくなった96年に決められた。社内のテストで4~6カ月経過しても
重さや味に変化がないことから、4カ月に設定したという。」
安全サイドを取って4ヶ月としたことは理解できる。重さや味に関して1~2ヶ月のばらつきに対しては
クレームがないから継続したと言うことか??
これでは正当化出来ないな!6カ月経過しても重さや味に全く変化が無かったと言うのであれば、
1から2ヶ月の延長も問題ない。しかし、問題があるが数値的に小さいから無視したのであれば
会社の体質と言うしかないな!
石屋製菓:「白い恋人」賞味期限延長、11年前から 08/16/07(毎日新聞)
「石屋製菓」(札幌市西区)が主力商品「白い恋人」の一部で賞味期限を改ざんしていた問題で、石水勲社長は16日記者会見し、賞味期限は社内の基準で4カ月と設定しているが、商品の在庫が膨らんだ場合は賞味期限を最大2カ月延ばして出荷していたことを明らかにした。賞味期限を延長して出荷する行為は11年前から行われ、石水社長も了解していた。
石水社長はキャンペーン限定品の賞味期限改ざんについては、今月13日に事実を知ったと説明しているが、今回の賞味期限延長については「在庫の状況を見ながら日付を延ばしていたのは知っていた。品質には問題ない」と話している。
「白い恋人」の賞味期限は、包装フィルムが新しくなった96年に決められた。社内のテストで4~6カ月経過しても重さや味に変化がないことから、4カ月に設定したという。7~8割の商品は4カ月の賞味期限で出荷されるが、夏の観光シーズンの前などは、在庫に余裕を持たせるため、賞味期限を5~6カ月に設定していた。
社内でも「6カ月は大丈夫」との認識は広まっており、石水社長も14日の会見で「『白い恋人』は本来、賞味期限を記載しなくてもいい商品だ」と発言していた。
また同社は16日、「白い恋人」を含む全商品を回収し、商品が安全に出荷できるまでは本社工場の製造ラインを再開しないことを明らかにした。同社は製造ラインの停止を当初、16日から4日間としていた。再開時期は現段階では未定という。【三沢邦彦】
「白い恋人」賞味期限、改ざん10年 社長も事実把握 08/16/07(朝日新聞)
北海道の代表的な土産「白い恋人」の賞味期限を製造元の石屋製菓(札幌市)が改竄(かいざん)し、アイスクリームなどから食中毒の原因となる菌を検出しながら隠蔽(いんぺい)した問題で、石屋製菓の石水勲社長は16日記者会見し、「白い恋人」の賞味期限を過去10年にわたり日常的に改竄していたと発表した。改竄の事実は石水社長も把握していた。
石水社長は白い恋人以外のすべての商品も店頭などから回収し、当初16日から4日間としていた自主休業を延長する意向を明らかにした。
石水社長らによると、「白い恋人」の包装袋を品質保持性能に優れたものに切り替えた平成8年以降、同社の社内規定で4カ月と決めていた賞味期限を、出荷する商品の2、3割程度を、5カ月か6カ月に改竄していた。改竄は在庫が多く残った場合に行っていたという。
問題が14日に発覚して以降、札幌市内の百貨店や新千歳空港の土産物店から、白い恋人などすべての石屋製菓商品を撤去する動きが広がっている。
白い恋人は段ボール箱3万-4万箱が出荷されており、返品された分は在庫の2万5000箱とともに廃棄処分にする。
「白い恋人」10年前から賞味期限延長 社長も承知 08/16/07(朝日新聞)
北海道の観光土産として知られるチョコレート菓子「白い恋人」に賞味期限改ざんなどが見つかった問題で、製造・販売する石屋製菓(本社・札幌市)の石水勲社長は16日、記者会見し、10年ほど前から賞味期限を社内規定より延長する行為があったことを認めた。また、衛生管理態勢が整うまで、期限を設けずに工場の操業を停止するとし、「白い恋人」を含む同社のすべての商品を回収する意向も公表した。
石水社長は、「白い恋人」の賞味期限について、96年ごろから繁忙期や在庫が膨らんだ際には規定の「4カ月」ではなく、5~6カ月に延ばすこともあった、と明かした。石水社長もこれを知っていたという。
同社は16日から本社工場の操業を自主的に休止し、生産ラインの点検を始めていた。休止期間は当初は4日間としていたが、安全が確認されるまで当面続けることにした。
同社の製品は「白い恋人」が主力商品で約8割を占め、首都圏などで人気があるのはもっぱら「白い恋人」。土産品店や百貨店での商品撤去の動きが加速したが、これまでは希望する小売店を対象に「白い恋人」だけを回収していた。
同社の従業員はパートを含め約480人。工場の生産ラインが止まってもパートを含む従業員の雇用は確保する、とした。
同社には16日、返品の品々が本社に次々に送られてきた。また、この日から本社工場に隣接する同社のテーマパーク「白い恋人パーク」を臨時休業とした。
「白い恋人」石屋製菓、出荷済み全商品回収へ 08/16/07(読売新聞)
チョコレート菓子「白い恋人」の賞味期限偽装などが発覚した北海道の大手菓子メーカー「石屋製菓」の石水勲社長は16日、札幌市内で記者会見し、19日までとしていた自主休業期間を延長するとともに、出荷したすべての商品を回収することを明らかにした。
休業については、「(生産過程を)すべて調査し、行政の指導を受けながら万全の体制が整うまで」で、具体的な再開時期は未定としている。休業期間中の雇用は維持する。
商品の回収についてはこれまで、問題のあった「白い恋人」や黄色ブドウ球菌が検出されたバウムクーヘンなどを回収し、それ以外の商品は、販売店の求めに応じて引き取っていた。
また「白い恋人」の賞味期限は原則的には4か月だが、偽装のあった「30周年キャンペーン限定商品」以外にも5か月や6か月に設定していた商品があり、15日夜に札幌市保健所から不適切と指摘されたことも明らかにした。
この点について、石水社長は「6か月でも品質劣化がなく、例外的に5か月、6か月のものがあった」などと説明した。
「石屋製菓」返品処理で期限改ざん…課長提案、部長が容認 08/16/07(読売新聞)
チョコレート菓子「白い恋人」の賞味期限偽装などが発覚した北海道の大手菓子メーカー「石屋製菓」(本社・札幌市)の石水勲社長(63)は15日、札幌市内で記者会見し、偽装の詳しい経緯を明らかにした。
それによると、偽装が話し合われたのは4月24日。担当課長から、伊藤道行・取締役統括部長(57)に「30周年記念の『白い恋人』に予想以上の返品が出そうだ」と報告があり、「賞味期限をずらしましょうか」と提案されたという。
伊藤部長は「日付を替えるのは良くない。工場併設のテーマパークの入館者に配ったり、3個詰めの小売りにしたりするなど、ほかの手法はないのか」と難色を示したが、返品数が多く、結局、偽装を認めた。
偽装作業が行われたのは5月5、6の両日。担当課長が立ち会い、普段「白い恋人」の製造ラインを担当している従業員やパート職員約20人が、1か月延長した賞味期限が記載された包装用紙に包み直した。
伊藤部長は会見中、「人としてやってはいけないことをしてしまった。重苦しい、つらい気持ちだった」と、終始うつむいていた。
◇
石屋製菓は会見で16日から4日間、自主休業し、全商品の生産を停止すると発表した。停止期間中、生産工程のチェックや機器の清掃などを行う。返品された商品は、廃棄処分にする。また、大腸菌群が検出されたアイスクリーム製品について、2005年以降の検査記録がなかったことも明らかにした。札幌市保健所と道庁は15日、食品衛生法や日本農林規格(JAS)法に違反している疑いがあるとして、本社工場への合同立ち入り調査を行った。
同社は年に1、2回アイスクリームの商品検査をしてきたが、04年分までしか記録がないという。05年以降は検査が実施されていたかどうかも確認できていないという。さらに、7月にはアイスクリームで大腸菌群が検出されたことを告発するメールが会社あてに届いていたが、黙殺していたという。
石水社長は原因として、「社外の活動が増えた結果(部下に)仕事をかぶせてしまった」と話した。
「消費期限」と「賞味期限」はどう違う?(よくわかる時事問題)
「品質保持期限」と「賞味期限」(三重県のHPより)
上記の情報を参考にすると、石屋製菓の石水社長は包装技術の進歩で約半年は味も変わらないと説明。安全面も問題がない
と言っている。それではこれまでの賞味期限に6ヶ月を足して記載すればよい。ウソか本当なのか疑問が
持たれる説明は必要ない。ゆとりや安全サイドを見て、賞味期限を企業が設定するのであれば、
ホームページなどで他社との違いを説明するのも良い。また、安全を重視していることを
消費者にアピールするのも良いだろう。
商品の賞味期限の改竄(かいざん)は良くない。石屋製菓は包装技術の進歩で約半年は味も変わらない
ことを説明し、今後、延長された賞味期間を記載すればよい。しかし、次回も賞味期限の改竄(かいざん)
があれば、
「ミートホープ」と同様に
石屋製菓はその程度の会社と社員であってと言うことになる。
石屋製菓を立ち入り検査 「白い恋人」期限改ざんで 08/15/07(毎日新聞)
札幌市の石屋製菓が北海道土産として知られる「白い恋人」の賞味期限を改竄(かいざん)し、アイスクリームなどから食中毒の原因となる菌を検出しながら隠蔽(いんぺい)していた問題で、札幌市と北海道は15日午後、問題の商品を製造していた同社本社工場(西区宮の沢)を食品衛生法などに基づき合同で立ち入り検査した。違反が裏付けられれば、営業停止などの行政処分を検討する。
食品衛生法を所管する札幌市は、大腸菌群が検出されたアイスクリーム「ミルキーロッキー」や、黄色ブドウ球菌が検出されたバウムクーヘンの製造ラインを点検し、衛生管理に問題がなかったか調査。いずれも食中毒の原因となる恐れがあり、食品衛生法で商品に含まれてはいけないことになっている。
石屋製菓によると、ミルキーロッキーから菌を検出した後、製造機械を煮沸消毒して以降は新たな菌は検出していない。バウムクーヘンは梱包(こんぽう)過程で作業員の手から菌が付着した可能性があるという。
日本農林規格(JAS)法を所管する北海道は賞味期限が改竄されていた白い恋人の出荷記録などを点検する。
道と札幌市が工場を検査 「白い恋人」改ざん 08/15/07(朝日新聞)
北海道土産として知られる菓子「白い恋人」の賞味期限が改ざんされるなどした問題で、道と札幌市は15日、製造元の石屋製菓(札幌市)の工場を立ち入り検査した。同社の他の菓子からは黄色ブドウ球菌や大腸菌群が検出されており、道と市は、賞味期限の表示を義務づけている日本農林規格(JAS)法と食品衛生法に違反する恐れがあるとして、衛生管理体制を調べた上で処分を決める方針だ。
また、同社は16~19日の4日間、工場を自主休業し、製造ラインを点検することを決めた。同社によると、改ざんは5月に担当役員の指示で行われたが、社長には報告しなかった。6月には改ざんを指摘する匿名のメールが同社に届いたが、担当役員は社長に伝えず発覚が遅れたという。
「白い恋人」は段ボール3万~4万個分が出荷されているが、同社は出荷先から返却希望のあった商品の回収を進めており、在庫の2万5000個分とともに廃棄処分にする。
石屋製菓:大きく傷ついたブランド 不祥事は幹部が主導 08/15/07(毎日新聞)
「白い恋人」のブランドが大きく傷ついた--。14日明らかになった石屋製菓(札幌市西区)の賞味期限改ざんなどの不祥事は同社幹部が主導していた。石水勲社長は「改ざんなど一番嫌いなこと。規範意識が欠如していた」と語気を強めたが、失われた信頼回復の道は遠い。
改ざんなどを主導したのは取締役の伊藤道行統括部長。同夜の会見で伊藤統括部長は「申し訳ないとしかいえない。(当時の記憶は)薄れている」と言葉少な。バウムクーヘンから黄色ブドウ球菌が検出されたのに出荷したことや、アイスクリーム商品「ミルキーロッキー」から自主検査の時点で大腸菌群が見つかったのにもかかわらず出荷を止めなかった理由について具体的な言及はなかった。
発売から30年たつ「白い恋人」は同社の売り上げのうち、約8割を占める全国的に有名な商品。夏休みの観光シーズンを迎えた今が最も売り上げを望める時期という。
「白い恋人」の賞味期限は4カ月だが、石水社長は「包装技術の進歩で約半年は味も変わらない」と説明。安全面も問題がなく、このことは社内で常識になっていたといい、返品商品の賞味期限改ざん・再出荷の遠因になったとしている。
石水社長は「これまで挫折がなく、損をしていなかったことが原因。あまりにも残念だ」と述べ、大きな体をすぼめながら肩を落とした。【三沢邦彦】
◇業過致死傷罪で雪印乳業有罪に
大手食品会社では過去、ずさんな品質管理が原因で健康被害を実際に出したり、出しかねない事案が相次いでいる。
00年6月の雪印乳業食中毒事件では、劣悪な衛生管理のもと黄色ブドウ球菌の毒素が混入した脱脂粉乳から低脂肪乳が製造・出荷され、下痢など食中毒発症者が約1万5000人に上った。
同社大樹工場の元工場長らは製品への苦情が出ると機器の洗浄を命じたり日報を改ざんするなどの隠ぺい工作に走り、業務上過失致死傷罪などで有罪判決を受けた。同社は乳飲料部門を売却するなど解体的な出直しを迫られた。
また、菓子メーカー大手の不二家で今年1月、消費期限切れ牛乳でシュークリームを作っていたことが判明。社内調査結果の公表を2カ月間も遅らせ、隠ぺい体質が批判された。また、国のガイドラインを上回る細菌が検出された洋菓子の出荷や、工場で大量のネズミが捕獲されていた衛生上の問題も発覚。同社は洋菓子販売を一時全面休止。社長は退任し、業績も大きく落ち込んだ。
食品販売大手ニチレイの関連会社の工場では今年2月、出荷前の検査で基準の最高18倍の大腸菌群が検出されているにもかかわらず、スモークサーモンや紅サケを出荷したことが明らかになった。
きれい事だけじゃ、仕事は取れない。うちがやらなくても、他の派遣会社がやるだろう。
だったら、うちで仕事を取ればよい。
国の機関の検査なんて簡単だ。見つかるわけなど無い。
こんな考え方があったのでは??
でも、誰かがチェックや取締りをしないと、まともにやっている企業や人材派遣会社がばか(損をする)
を見る。もしかすると、偽装は人材派遣業界では当然なのかもしれない。業界や業界と取引がない
人達だけが現状を知らないのかもしれない。そして、偽装は氷山の一角であるのかもしれない。
氷山の一角であるのか、行政の対応次第でわかるであろう。
スタッフグループ傘下、派遣契約書を偽造し長期に同一作業 08/06/07(読売新聞)
人材派遣最大手「スタッフサービスグループ」(東京)傘下の人材派遣会社「テクノサービス九州」(熊本市)が、熊本県内の電子部品製造工場で働く派遣労働者30~40人の派遣契約書を偽造し、違法に契約期間の制限を超えて同じ業務に就かせていたことがわかった。
熊本労働局は6日、労働者派遣法に基づき工場を立ち入り調査した。
グループの持ち株会社「スタッフサービス・ホールディングス」広報宣伝部によると、テクノ社は製造業への人材派遣を行っており、2005年12月から06年3月にかけ、中央電子工業(東京)との間で携帯電話に用いる半導体の検査業務に1年間就業するとの契約を結び、同社熊本工場(熊本県宇城市)に労働者を派遣した。
製造業務への派遣労働者の受け入れ期間について、労働者派遣法は最長1年(今年3月以降は最長3年)と制限し、期間終了後は3か月超の猶予期間がなければ、同じ会社(工場)での同一業務への受け入れはできない。ただ、同じ会社でも業務内容が異なれば猶予期間は不要で、テクノ社と中央電子工業は、別の業務に就くとの契約書を偽造し、実際は同じ業務に就かせていた。
同広報宣伝部は、動機について「3か月超の猶予期間が発生すると、業務継続に支障が生じると思ったためではないか」としたうえで、「コンプライアンス(法令順守)を徹底してきたが不適切な対応があった。真摯(しんし)に受け止め、関連会社で同様の違法行為がないか精査する」と陳謝した。
中央電子工業は「現時点ではコメントできない」としている。
食肉製造加工会社「ミートホープ」
と基本的な考え方は同じじゃないか
処分マグロ半値で仕入れ、マルハ子会社が系列内の会社から 08/04/07(読売新聞)
水産大手「マルハグループ本社」の子会社「北州食品」(東京都中央区)が、業務用として販売したマグロの加工食品に混ぜていた賞味期限切れのマグロたたきは、グループ内の別会社から在庫処分品として相場の半値で仕入れられていたことがわかった。
別会社も賞味期限の迫ったマグロたたきを大量にさばくことができ、グループ内で「持ちつ持たれつ」の関係になっていた。
読売新聞が入手した資料によると、北州食品は少なくとも昨年6月と7月の計2回、別のグループ会社が輸入したタイ産の冷凍マグロたたき(1パック300グラム入り)計11トン余を購入。北州食品の「仕入報告書」には、当時の仙台工場長らの印鑑が押され、「在庫処分品です。格安スキミ原料として」などと明記されていた。
同様の商品の仕入れ価格は1キロあたり1300~1400円が目安だが、この時は、賞味期限が1か月~3か月後に迫っていたため、半値の同650円だった。業界関係者によると、通常は賞味期限が切れたマグロたたきは養殖魚のエサ用などとして同3円前後で販売しているため、グループ会社側にも、この取引で売り上げ増のメリットがあった。
仙台工場では、ほとんどの賞味期限が切れた9月以降も検査で色やにおいを確かめて、「品質には問題ない」と判断し、マグロ加工食品への混入を続けていたという。今年1月に当時の品質管理部長が不正を見つけるまで、仕入れた11トン余のうち約2・8トンが使用された。
1月に使用が中止された時点で、同工場内や倉庫には、約8・6トンが在庫として残っていたといい、部長の指摘がなければ、さらに混入が続けられた可能性が高い。
同じグループ会社からの大量仕入れの経緯について、北州食品は「マグロ価格が高騰し、安いものを探していたら、たまたまグループ会社にあった。グループ内という理由で買ったわけではない」と説明。「相手は賞味期限内に販売している。うちの責任だ」とも話し、仕入れを指示した当時の仙台工場長らの処分を検討している。
ある水産会社幹部は「半値で取引されたのなら、売る方も買う方も、品物が悪いとの認識はあったはずだ。グループ内に『利益第一』という風潮があるのではないか」と指摘している。
エレベーター:強度不足問題で鋼材納入会社社長が辞職へ 08/04/07(毎日新聞)
エレベーター大手の「フジテック」(滋賀県彦根市)が製造したエレベーター560台で鋼材の強度が不足していた問題で、国土交通省は3日、同社と鋼材の納入元から受けた報告内容を公表した。02年9月からとされていた強度不足の鋼材が使われていた時期は、93年1月からだったことが判明した。新たにエレベーター481台とエスカレーター556台の構造上大事な部分に使われていたことが分かったが、強度不足の恐れはないという。同省は詳細な強度計算の結果を報告するようフジテックに指示した。
鋼材を納入していたJFE商事建材販売(大阪市)の岩瀬光治社長は、「社会的、道義的責任がある」として、再発防止策のめどがついた段階で辞職する意向を表明した。
報告書によると、両社の主張は平行線のまま。フジテックは「注文と異なる鋼材を納入する合意は決してしていない」「鋼材の検査証明書が事実と異なっていた」と納入元の責任を指摘した。自社の管理体制にも問題があったとして、社外の検査機関による鋼材の抜き取り検査などの再発防止策を発表した。
一方、JFE商事建材販売は「両社の担当者間で、注文書とは異なる鋼材を納入する合意があった」と強く反論。内容の違う検査証明書の提出は「フジテックの強い要望で担当者が独断で行った特異な事例」と説明し、社内体制の見直しを表明した。
相次いで国交省内で記者会見した両社の社長は自社の責任にも言及した。フジテックの内山高一社長は「組織として発見できず、深く反省している」と述べ、JFE商事建材販売の岩瀬社長は「担当者が無断で書類を提出することを防止する仕組みがなかった」と話した。
原因が判明しないままの状態について、国交省建築指導課の水流(つる)潤太郎課長は「非常に遺憾。国の調査に強制力はないが、しっかりした説明を求めたい」と話している。【長谷川豊、高橋昌紀】
◇ ◇
フジテックによると、強度不足の560台のうち330台は補強を終えた。9月中に全台の補強が完了する予定という。
フルキャスト:兵庫の3支店は2カ月の停止処分 厚労省 08/04/07(毎日新聞)
人材派遣大手「フルキャスト」(本社・東京都渋谷区)の兵庫県内の支店が労働者派遣法で禁じられている港湾荷役業務に労働者を派遣していた問題で、厚生労働省・東京労働局は3日、フ社に対し、同法に基づく事業停止命令と事業改善命令を行った。事業停止は兵庫県内の3支店が2カ月、その他の支店を1カ月とする内容。フ社は3月に事業改善命令を受けており、悪質性が高いことから、異例の重い処分となった。
この命令を受け、フは平野岳史会長と漆崎博之社長の役員報酬50%返上(3カ月)など幹部計7人の報酬を50~10%(同)を返上するなどの社内処分を発表。また今期限りで平野会長の代表権を返上することも合わせて発表した。
同局によると、兵庫県内のフ社の三宮支店、元町支店、三宮北口支店の3支店は5月1日と2日、計6人の労働者に対し神戸市の新港第2突堤にある荷さばき場のコンテナ内でペットボトルの荷さばき作業を行わせた。
このため同局は、違法のあった3支店で8月10日から2カ月間、その他の支店では1カ月間、派遣先企業との新たな派遣契約の締結や、過去に契約した派遣先企業への新規の労働者派遣を禁止する。
フ社は、06年8月に神奈川県内の支店が建設現場に労働者を派遣していたため、神奈川労働局が是正指導。また07年3月27日には、東京労働局がフ社の53支店が建設や警備業への派遣を繰り返していたとして事業改善命令を出した。同社は4月末に改善報告書を提出したが、内容に不備があったことから同局が5月2日に再提出を指示していた。同局は「業務の改善に専念すべき処分期間内に違法な派遣を繰り返すなどの点を重く見た」としている。
フ社は今回の処分による労働者の影響については、8月9日現在で派遣している労働者は派遣は停止しないが、新しい仕事の紹介はできないなどと説明。「原因となった問題点すべてに対し全力を挙げて再発防止に取り組む」としている。
一方、今回の処分についてフ社の労組の関根秀一郎書記長は「業界で港湾や建設への派遣は後を絶たない。突発需要に対応する日雇い派遣では起こるべくして起こる問題で、このスタイルの派遣を認めてきた政府の責任は大きい。事業停止は当然だが、その間の労働者の生活保障にも目をむけるべきだ」と話した。また、日本労働弁護団の棗一郎弁護士は「労働の規制緩和で派遣業種を拡大してきた結果、労働者の安全が脅かされる今回の事態を招いた。厚労省は労働者派遣法の見直しとともに、法の厳格な適用をすべきだ」と話している。【東海林智、市川明代】
フルキャスト:法令順守の不備が急成長にブレーキ 08/04/07(毎日新聞)
3日、厚生労働省から事業停止処分を受けた人材派遣大手のフルキャストは、日雇いの軽作業請負・派遣業務でグッドウィル・グループ(GWG)と肩を並べるように急成長を遂げてきた。介護事業をめぐって子会社のコムスンが同省から処分を受けたGWGと同様、法令順守の不備が企業の成長に大きなブレーキをかける結果となった。
フルキャストは、89年に設立した家庭教師センター「神奈川進学研究会」が前身で、当初の創業メンバーは平野岳史会長ら3人だった。92年に現在のフルキャストを設立し、軽作業請負業を始めた。アルバイトらを登録し、企業からの要請を受けて工場や建設現場などに派遣し、給料は日払い制とする手法で、会社を成長軌道に乗せた。
日雇いの軽作業から、工場ライン業務に人材を派遣する業務や、技術系の派遣業務などに事業を拡大。不況下で大企業が雇用を削減する代わりに派遣労働者の採用を増やす動きが成長を後押しし、04年9月には東証1部上場を果たした。平野会長は、会員数300社を超える日本ベンチャー協議会の会長を務めるなど、ベンチャー企業家の代表的存在だ。
だが、このところ建設や警備など禁止業務への派遣が次々と発覚。「業務管理費」として日雇い派遣の労働者の給与から天引きしていたことも問題となり、全額の返還を表明するなど、強い逆風が吹いている。同社は法令順守体制の強化を優先させるため、10月に予定していた持ち株会社体制への移行を延期するなど企業の拡大路線を一時ストップさせる方針を示しているが、今回の問題で今後の経営が更に厳しくなりそうだ。【平地修】
人や会社の体質など簡単に変わるものではない。
社会保険庁職員の3分の2は
新しい組織で使うなと言っている
が、それを支持するような出来事だ。
「厚生労働省は3日、人材派遣会社大手の『フルキャスト』(本社・東京都渋谷区)に対し、
労働者派遣法に基づき一定期間の事業を禁じる事業停止命令を出すことを決めた。」
大手であっても処分は必要。大手の不正が容認されれば、業界は無秩序になり、
何でもありになってしまう。
フルキャストに事業停止命令へ、違法派遣改善せず…厚労省 08/03/07(読売新聞)
厚生労働省は2日、大手人材派遣会社「フルキャスト」(東京都渋谷区)に対し、労働者派遣法に基づく事業停止命令を出す方向で検討を始めた。
同社は、今年3月に同法が禁じる建設、警備業に労働者を派遣したことを理由に事業改善命令を受けているが、同省では、その後も同様の違法派遣が行われていた疑いがあるとして、さらに重い処分が必要と判断したとみられる。
東京労働局が今年3月に同社に出した事業改善命令は、昨年1~12月に全国329支店のうちの53支店で、労働者派遣法が禁じる建設業や警備業への労働者派遣を繰り返していた疑いが浮上したことを受けたもの。横浜市旭区の二俣川支店では昨年8月、建設業などへの派遣を行わないよう神奈川労働局から是正指導を受けながらも改めなかったほか、その後も、甲府支店(甲府市)で昨年10~12月の9日間に延べ66人を警備業に派遣するなど、各地で同様の違法派遣が行われたことが確認されていた。
関係者によると、同社はその後、東京労働局に改善報告書を提出したが、別の支店などで違法派遣が依然として行われていることが確認されたという。同社は1992年創業。昨年末現在の登録労働者数は約163万人、昨年9月期決算の連結売上高は901億円。
フルキャスト:事業停止命令へ 違法派遣で厚労省 08/03/07(毎日新聞)
厚生労働省は3日、人材派遣会社大手の「フルキャスト」(本社・東京都渋谷区)に対し、労働者派遣法に基づき一定期間の事業を禁じる事業停止命令を出すことを決めた。同社は同法違反で業務改善命令を受けているが、その後、同法で禁じられている港湾荷役業務に労働者を派遣していたため処分する。同日午後に同社の担当者を呼んで命令書を渡す。
フルキャスト関係者らによると、今年5月に関西の事業所が兵庫県内の港湾エリアで複数の労働者を派遣し、ペットボトルの仕分けなどの荷役作業をしたという。労働者派遣法では、危険を伴い専門的な知識や技術を必要とする港湾運送業務や警備、建設業への派遣を禁じている。
同社は昨年8月に神奈川県内の支店が建設現場に労働者を派遣していたことが発覚、神奈川労働局から是正指導を受けた。その後も甲府支店で警備業への労働者派遣が発覚、仙台市内の警備会社でも同様の派遣があったとして宮城県警の捜索を受けている。今年3月には、同社の全国の53事業所が建設や警備業への派遣を繰り返していたとして東京労働局が業務改善命令を出している。
こうした中、今回新たな違反が発覚したため、厚労省は、より重い処分である事業停止命令が必要と判断した。悪質性が高いとみて、全事業所が対象になる可能性が高く、一定期間新たな派遣ができなくなる事態も予想される。同法に基づく業務停止命令は、昨年10月に大阪労働局が人材派遣会社の「コラボレート」に出している。
フルキャストは日雇い派遣で最大手のグッドウィルに次ぐ大手で、1日に1万人を超える労働者を派遣しているという。【東海林智】
食肉加工卸会社「ミートホープ」
の社長の考えかた(DNA)は大手企業の子会社社長にも広がっていた。
偽装や違反は食肉加工卸会社「ミートホープ」で終わらないことを示している。
一酸 化炭素(Carbon Monoxide)
が生鮮品(マグロも含む)に使われた事の表示義務に関して、アメリカで議論されている。
水産大手「マルハグループ本社」の子会社社長でも賞味期限切れマグロ使用、出荷黙認
するようでは日本ではかなり厳しい罰則がなければ一酸 化炭素(Carbon Monoxide)
の使用許可を出すべきではないだろう。
賞味期限切れマグロ使用、マルハ子会社社長が出荷黙認 08/03/07(読売新聞)
水産大手「マルハグループ本社」の子会社「北州食品」(東京都中央区)が、業務用として販売したマグロの加工食品に、賞味期限切れのマグロたたきを混ぜて出荷していた問題で、筒井明彦社長が今年1月、社員から混入の事実について報告を受けながら、出荷を黙認していたことがわかった。
問題の商品は3月まで出荷され、同社が6月に自主回収を始めた時には、すでに大半が消費されていた。事態を重く見た水産庁では、品質管理の徹底を求める通知を業界団体に出した。
北州食品によると、今年1月中旬、同社の品質管理部長(当時)が宮城県の仙台工場を点検中、従業員が、昨年7月に賞味期限の切れたタイ産冷凍品「鮪(まぐろ)タタキ」を、原料の一部として使っているのを見つけた。品質管理部長は、この事実をすぐに本社に報告し、筒井社長にも伝えられた。
筒井社長は混入をやめるよう指示したものの、「製品検査に合格しており、(消費者に)健康被害が発生するわけではない」との判断から、在庫として保管されていた商品の出荷停止や、取引先への説明などの対応はとらなかった。このため、賞味期限切れの原料が混ざった商品の出荷は3月まで続き、すし店やスーパーなどでネギトロ巻きや総菜として販売された。
同社が自主回収の方針を決めて、同県に報告したのは6月中旬。31社に販売したマグロ8トン余が回収対象になったが、ほとんどが販売された後で、回収できたのは約5キロだけだった。
同社の対応の遅さについては、取引業者からも批判が出ている。問題発覚後、北州食品からの仕入れを打ち切った業者の幹部は、「北州側から説明を受けるより前に、期限切れマグロの混入のうわさを聞いた」と明かし、「混入以上に、隠ぺいするような企業姿勢に疑問を感じた」と説明する。
一方、北州食品はホームページ上に「事態を認識してからの対応に時間がかかった点について、社長として大いに反省しております」という社長の見解を掲載。6月になって回収を始めた理由については、「4月にマルハ品質保証グループから出向した品質責任者の意見を入れた」などと釈明している。
新日鉄など4社、鋼材で価格カルテル…公取が立ち入りへ 07/31/07(読売新聞)
公共工事などを請け負ったゼネコンに納入する鋼材をめぐり、鉄鋼大手の新日本製鉄(東京都千代田区)、JFEスチール(同)、住友金属工業(大阪市)と機械大手のクボタ(同)の計4社が、談合や価格カルテルを繰り返していた疑いが強まり、公正取引委員会は31日、4社の本社や支店、業界団体の鋼管杭(こうかんぐい)協会(東京都中央区)など計約30か所を、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで立ち入り検査した。
談合などが疑われる鋼材は、基礎工事用のくい打ちや護岸工事などに使われるもので、市場規模は年間約1000億円に達する。鉄鋼業界では、新日鉄と住金が2007年3月期まで3期連続で経常利益を更新するなど、好調な業績が続いているが、社会基盤の整備にも使われる鋼材の取引で、不当な利益を得ていた疑いが浮上した。
関係者によると、談合とカルテルの対象になったとされる鋼材は、軟弱な地盤で建造物を支えるために、地中に深く打ち込んで使うパイプ状の「鋼管杭」と、つなぎ合わせて土砂や地下水などをせき止めるために使う鋼板の「鋼矢板(こうやいた)」の2品目。
4社は、ゼネコンから引き合いがあった官需用の鋼管杭について、事前に話し合いを持ち、納入業者を決めていた疑い。クボタを除く3社は、鋼矢板でも談合した疑いが持たれている。
4社は、鋼材の販売価格やシェア(市場占有率)について、取り決めをしていたという。
談合は2005年ごろまで、価格カルテルは04年~05年ごろ、それぞれ続けられていたという。4社の鋼管杭のシェアは100%、鋼矢板はクボタを除く3社で80%を超える。
新日本製鉄やJFEスチールなど4社は、いずれも公取委の立ち入り検査を受けていることを認め、「検査には全面的に協力している。詳細についてはコメントできない」などと説明している。
子会社が補助金を不正受給、エネ庁が大ガス立ち入り調査へ 07/31/07(読売新聞)
新エネルギーの導入促進を図る国の補助金事業をめぐり、大阪ガス(大阪市)の子会社などが、補助金交付条件に反して大阪ガスに工事を優先発注しながら、所管する経済産業省資源エネルギー庁に虚偽の説明をして約5000万円の交付を受けていたことがわかった。
大阪ガスは「補助金の不適正な受給にあたる」と判断。大阪ガスグループは昨年度までの8年間に、同様の補助金事業で35件の交付を受けており、報告を受けた同庁は31日、大阪ガス本社を立ち入り調査する。
同社も社内調査委員会を設置し、不正の有無を調べる。
交付を受けていたのは、天然ガスを使った省エネ電源システムの設置・維持管理事業。2004年10月、子会社「コージェネテクノサービス」(大阪市)と大阪市のリース会社が同庁に補助金を申請、認められた。
発注にあたり同庁は原則、入札か、複数の見積書を取った上での随意契約を補助金交付条件とし、1社からしか見積もりを取らない特命随意契約の場合には、選定理由を求めている。
しかし、コ社などは04年12月、システムを大阪ガスに特命随意契約で優先発注したのに、大阪ガスの担当者を通じ、取引先の設備会社2社に見積書の作成を依頼し、複数社から見積もりを取って工事価格を比較したように偽装。同庁の検査の際、3社の見積書を同庁の担当者に示し、最も安かった大阪ガスに発注したようにしていたという。検査後、コ社とリース会社には、補助金計5124万円が交付された。
大阪ガスの担当者らは社内調査に対し、「見積もり合わせに時間をかけると工事の完成が遅れると思った。特命随意契約は、きちんとした理由がなければ認められないので複数の見積書をそろえた」と説明。大阪ガスの担当者がコ社から受注するため主導したとみられる。
JFE側は岩瀬光治社長らが12日会見で「フジテックから『市中の鋼材でいいから』と要請されたといい、
検査証明書も偽造したという。」ことが事実であるならたいへんなことだ。
食肉製造加工会社「ミートホープ」のミンチ偽装問題
と同様にひどい。
鋼材の納入元:JFE商事建材販売
は、顧客の要望があれば、検査証明書を偽造することを意味している。そして、フジテック(滋賀県彦根市)
のために検査証明書を偽造したのがはじめてなのか、それても、過去にも同様に検査証明書を偽造を依頼が
あれば行っていたのか、行政は調査する必要がある。また、他の企業も検査証明書を偽造を行ったことが
あるのか調べる必要もある。
経産省、JFE側を厳重注意 エレベーター強度偽装 07/14/07(毎日新聞)
フジテック(滋賀県彦根市)製のエレベーターに設計よりも強度の低い鋼材が使われていた問題で、経済産業省が、鋼材を納入していた商社、JFE商事建材販売(大阪市)から事情聴取し、厳重注意していたことがわかった。建築物の安全を所管する国土交通省は、偽装は1万2000基のエレベーターだけにとどまらない可能性があるとして、経産省と連携して原因究明と再発防止策を進める考えだ。
関係者によると、経産省は、親会社のJFE商事(東京都)と、グループ中核の大手鉄鋼メーカー、JFEスチール(同)からもすでに事情聴取。フジテックからも報告を受けたという。
経産省が問題視しているのは、JFE商事建材販売が強度の低い鋼材をフジテックに納めた際、高強度の鋼材だと保証する虚偽の検査証明書を提出していた点。JFE側は「フジテック社員も(虚偽を)了解していた」と主張しているが、同省は「明らかに不適切だ」として厳重注意し、あわせて再発防止策の報告も求めた。
鋼材取引をめぐっては、JFE側が検査証明書の偽造を認め、「フジテック社員と合意のうえだった」としているのに対し、フジテックは「すり替えは知らなかった」と反論するなど真っ向から対立。国交省は今月末にフジテックから報告を受けた後、JFE側にも再聴取する意向だ。
エレベーターの安全は建築基準法で規定されているが、強度不足の機械を設置したメーカーは、故意でなければ処罰されない。鋼材の強度を偽る行為に、どの法律を適用すべきかも、国交省の見解は定まっていない。
ただ、鋼材は、さまざまな工業製品や建築物に用いられていることから、大手鉄鋼メーカー系商社による今回の偽装について、両省は「日本の工業や建築の信頼を損ないかねない。社会の安全にもかかわる深刻な事態」と受け止める。国交省が事実の究明を進めるとともに、経産省と連携して再発防止策を検討する方針だ。
強度不足エレベーター:鋼材の納入元と主張に食い違い 07/13/07(毎日新聞)
フジテック(滋賀県彦根市)が製造したエレベーター560台が鋼材の強度不足で建築基準法に違反していた問題で、フジテック側は「強度不足の鋼材使用の認識はなかった」としているのに対し、鋼材の納入元は「フジテックも承知していたはず」と主張している。強度が弱い鋼材が使用された理由の真相を解明するため、フジテックは弁護士や元検事らによる第三者委員会を設置し、調査することを決めた。
フジテックによると、かご枠などには「SS400」と呼ばれる鋼材を使うはずだったが、実際には強度が3分の2程度で値段も5~6%安い「SPHC」が、JFE商事建材販売(大阪市)から納入されていた。検査証明書はSS400と偽装されていた。このためフジテックは、SPHCをSS400と思い込んで使ったという。
この取引が始まった02年9月から今年6月までに、納入量は毎月40トンに上り、エレベーター1万2727台、エスカレーター634台に弱い鋼材が使われた。このうちエレベーター560台が強度不足に陥った。
JFE側は岩瀬光治社長らが12日会見したが、その説明はまったく異なる。同社はSPHCの納入を意図的と認めたが、その理由は「フジテックの資材部の要望」。SS400は市場流通量が少ないため、納期を急いだフジテックから「市中の鋼材でいいから」と要請されたといい、検査証明書も偽造したという。
一方、業界関係者によると、鋼材の納入は、市場に左右されずに安定供給を図るため年間取引量を事前に決める例が多い。この関係者は「高品質が必要なエレベーターの部材確保には、年間取引が必須だ」と言い、両社の取引のずさんさが問題の背景にあると指摘した。【長谷川豊、高橋昌紀】
◇緊急点検などで対応に追われ
フジテック社のエレベーターが設置されている鉄道や病院、観光施設などは13日、緊急点検するなど対応に追われた。
JR大崎駅(品川区)では、改札口と山手線ホームをつなぐエレベーター2台が利用できなくなり、電動車椅子の乗客を駅員数人が階段を使って運んだ。JR東日本によると、首都圏の7駅で14台の運行を停止。14日朝からは、うち13台について減速して運転を再開する。
東京・六本木ヒルズにある「けやき坂コンプレックス」(地上7階、地下3階)では1台が強度不足と判明。管理する森ビル広報室は「メーカーは早急に改修工事をして」と困惑気味だ。格安家賃で批判を浴びた港区の衆議院赤坂議員宿舎では、7台のうちの1台を停止させた。メーカーの安全確認後に運転再開する。
和歌山県は、県庁南別館の1台を止めた。南別館は大規模災害時、防災センターとなるだけに、県は「一日も早く対応して」と話す。滋賀県彦根市の彦根城で開催中の「国宝・彦根城築城400年祭」では、会場に仮設のフジテック寄贈のエレベーターがあり、午後から運転をやめた。奈良県立医大病院(橿原市)では、病棟の一般用3台に職員が乗り込んで、運転を続けた。
牛肉偽装の告発情報、農水省と道庁の検証は“灰色決着”
で幕引きをしたから、強度不足エレベーターにも伝染したか??????
フジテック株式会社は
ISO9001を取得している。
JQAが発行した証書の写真まで公開している。
また、「フジテックは品質保証の国際規格「ISO9000」シリーズの認証を日本、フジテックホンコン、フジテックシンガポール、
フジテックUK、フジテックコリア、フジテックタイワン、華昇フジテック(中国)、上海華昇フジテック(中国)、
フジテックエジプトが取得し、グローバルな品質体制の下、世界の人々に信頼される商品づくりを目指しています。」
とホームページで書かれています。
「会見したJFE商事建材販売の岩瀬光治社長は、両社の担当者レベルで口頭の合意があったと
明かした上で、『強度の強い鋼材は市場では手に入りにくく、納入まで時間がかかることを
説明していたが、短期の納入を依頼された』などと説明した。」
「フジテックは、注文通りの割高な金額を支払ったと主張しているが、JFE商事建材販売では、
『納入する際には、強度が弱い鋼材の価格(割安の価格)の金額を受け取った』としている。」
たぶん、JFE商事建材販売の岩瀬光治社長の発言の方が信頼できるだろう。
フジテックは
ISO9001を取得している
のだから、全てのプロセスにおいて、検証出来るように記録が残っているはずである。
JFE商事建材販売への発注も記録又は書類による発注になっていると思う。
また、エレベーターの製造工程で書類の間違いがあっても、現場の人間は納入された鋼材が
違うことに気付いていたに違いない。もし、気付かなかったのであれば、鋼材の違いも分からない
人間しか現場にいないことになる。いずれにしても、ISOの不備である。
両社の担当者レベルで口頭の合意があったことはISOでは記録する必要がある。
もし、問題があれば「強度の強い鋼材は市場では手に入りにくく、納入まで時間がかかることを
説明していたが、短期の納入を依頼された」等のメモなり理由が記載される。
今回のように問題が発覚すれば、担当者の責任もしくは、担当者の上司が知っていれば、
担当者及び上司の責任であるとことが明確に、簡単に分かる。
牛肉偽装の告発情報に関する農水省と道庁の検証
のような納得できない説明のみの幕引きはありえない。社会保険庁の問題の理由の1つに「日の丸親方」と
あったが、懲戒免職にならない、適当な理由(屁理屈)をつけてうやむやに出来るメリットが「日の丸親方」
と解釈している。
農林水産省
と
北海道庁
が悪い模範になるから、おかしなことが起こる。役人よ、見逃してやるのか?
農林水産省
職員が簡単な処分で終わるから??
強度不足エレベーター、36都道府県で…第三者委を設置へ 07/13/07(読売新聞)
エレベーターの安全上の問題がまた発覚した。強度不足が判明した「フジテック」(滋賀県彦根市)製の560基は、36都道府県の集合住宅や商業ビル、JRの駅などに設置されていた。
「注文とは異なる弱い鋼材を納入された」。フジテック側は12日の記者会見で、納入元の「JFE商事建材販売」(大阪市)の責任を強調したが、同社は「フジテックと合意の上だった」と反論。両者の見解が食い違っているため、フジテックは、元検事らで作る第三者委員会を近く設置し、7月末までに調査結果を公表するとしている。
同日夜、東京・霞が関の国土交通省で、まず、フジテックの内山高一社長らが記者会見。JFE商事建材販売が、注文していた鋼材よりも強度が弱く、1キロあたり3~4円値段の安いものを納入していたことを明らかにした。「問い合わせたところ、どういう形で鋼材を納入したのか、記録がないとの回答で、すべてが注文とは別の鋼材だったと考えざるをえない」と指摘。「わが社の関係する担当者のヒアリングもしたが、合意した事実は確認できなかった」と話した。
これに対し、続いて会見したJFE商事建材販売の岩瀬光治社長は、両社の担当者レベルで口頭の合意があったと明かした上で、「強度の強い鋼材は市場では手に入りにくく、納入まで時間がかかることを説明していたが、短期の納入を依頼された」などと説明した。
また、強度が弱く割安の鋼材を、実際にいくらで納入していたかについても、見解が異なっている。フジテックは、注文通りの割高な金額を支払ったと主張しているが、JFE商事建材販売では、「納入する際には、強度が弱い鋼材の価格(割安の価格)の金額を受け取った」としている。
フジテックは、「まだ所有者に知らせていない」との理由から、強度不足のエレベーターが設置されている具体的な施設名を公表していない。しかし、JR東日本は12日、560基のうち、14基がJR大崎、荻窪、横浜など7駅にあり、安全が確認されるまで使用中止にすると発表した。
エレベーター:フジテック製の強度不足判明、改修を指示 07/12/07(毎日新聞)
国土交通省は12日、フジテック(滋賀県彦根市)が製造したエレベーター560台のかご枠などに使っている鋼材の強度が基準の3分の2しかなく、建築基準法に違反していたと発表した。大地震などの際にかごがゆがみ、通常の走行ができなくなる可能性がある。同省は、自治体を通じてエレベーターの所有者に補強工事の実施を求めるとともに、工事完了までは利用人数を制限するよう指導する。
同省やフジテックなどによると、弱い鋼材が使用されたとみられるのは、02年9月~今年6月にフジテックが製造したエレベーター560台。設計上の強度よりも3分の1程度弱い別の鋼材を使っていた。
使用されているのは、36都道府県のマンションや事務所、病院など多岐にわたり、JR西日本の各駅では約150台に達する。建築基準法は、エレベーターの強度を通常運行時の3倍の安全率を見込んでいるため、同省は「今回の強度不足で直ちにかご枠が破壊されたり、ゆがんだりすることはない」とみている。
この日記者会見したフジテックの内山高一社長によると、鋼材の購入先のJFE商事建材販売(大阪市)との取引では、書類上は設計通りの鋼材が納入されていることになっていた。しかし、J社が6月28日、「別の商品を納入していた」と報告してきたという。【長谷川豊、高橋昌紀】
王子製紙も基準値超えるばい煙排出、釧路など3工場で 07/13/07(毎日新聞)
王子製紙の釧路(北海道)、苫小牧(同)、富士(静岡県)の3工場で2004年7月から今年6月にかけて、窒素酸化物(NOx)の基準値を超えたばい煙を排出していたことが13日分かった。
日本製紙の工場で基準値を超えるばい煙を排出したり、データ改ざんを行ったりしていたことが判明したことから、釧路支庁が12日、王子製紙釧路工場を抜き打ち検査、苫小牧工場は胆振支庁が13日、立ち入り検査した。両工場のばい煙に含まれるNOxが大気汚染防止法で定める基準値を超えていたことが分かった。
静岡県富士市によると、富士工場のばい煙は同市と取り決めたNOx排出基準値を超えていたが、同工場はデータを改ざんし、基準値を下回っているとして同市に報告していた。
神戸新聞(2007年7月11日)より
日本製紙 ばい煙データ改ざんなど
6工場で法令違反
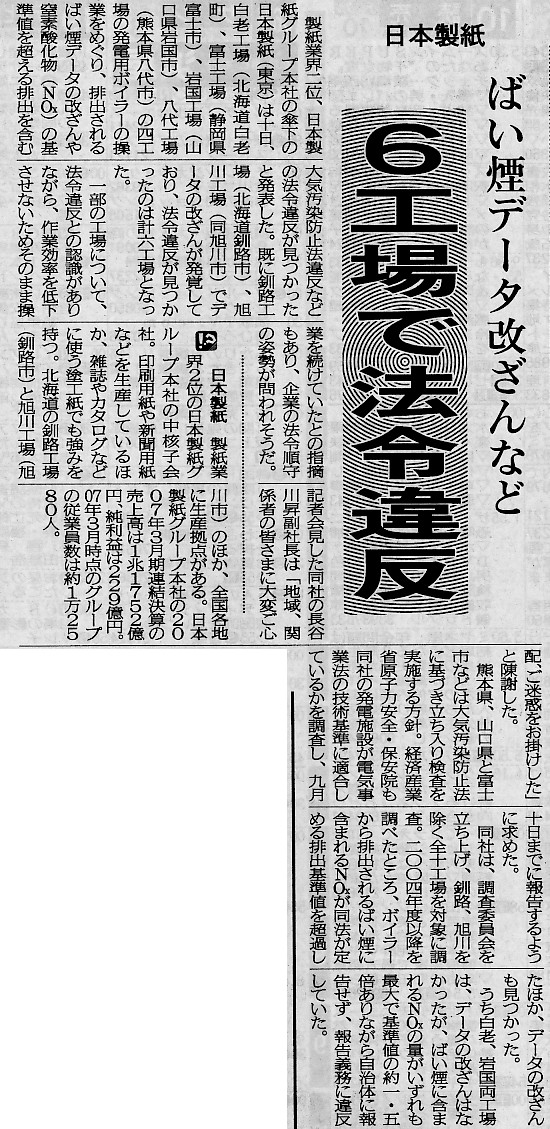
排出データ改ざん:日本製紙、新たに4工場で違反 07/10/07(毎日新聞)
日本製紙(東京都千代田区)の北海道にある2工場(旭川、釧路)で発電用ボイラーのばい煙データを改ざんしていた問題で、同社は10日、他の全国10工場を調査した結果、新たに白老(北海道)、富士(静岡県)、岩国(山口県)、八代(熊本県)の4工場でも大気汚染防止法に違反する行為が判明したと発表した。全12工場の半数が違反していたことになり、記者会見した長谷川昇副社長は「地域住民にご心配、迷惑をかけ深くおわびする」と陳謝した。
同社によると、白老、岩国、八代の3工場では、排出基準値を超える窒素酸化物(NOx)を排出しながら、地元自治体に報告していなかった。また、富士と八代では、記録紙にデータが残らないように改ざんしていた。「ボイラーを一度止めると再起動に1日かかる。現場が作業効率を優先したのかもしれない」と話している。
同社は、現場の判断だけで改ざんが行われたのかなど原因究明を続け、判明し次第、関係者を処分するとしている。また、再発防止策として、記録紙の厳格な管理や法令順守教育を徹底する。【小島昇】
加ト吉社長、コロッケ無断販売で管理不行き届き認める 06/27/07(読売新聞)
食品大手「加ト吉」(香川県観音寺市)の金森哲治社長は26日、東京都内で2007年3月期決算の訂正について記者会見した。
この席上、子会社である北海道加ト吉の前工場長(24日解任)が、製造過程で余った冷凍コロッケを、食肉製造加工会社「ミートホープ」(北海道苫小牧市)に無断で販売していたことについて、「管理の不行き届きと認めざるを得ない」と述べ、既に設置した外部調査委員会が26日から調査に乗り出したことを明らかにした。
また、07年3月期までの6年間に、不明朗な循環取引で売上高が水増しされた金額が、当初見込みの984億円から1061億円に増えたと発表した。
朝日新聞(2007年6月30日)より
中電不祥事 法令順守経営を誓約
取水経路変更など対策も
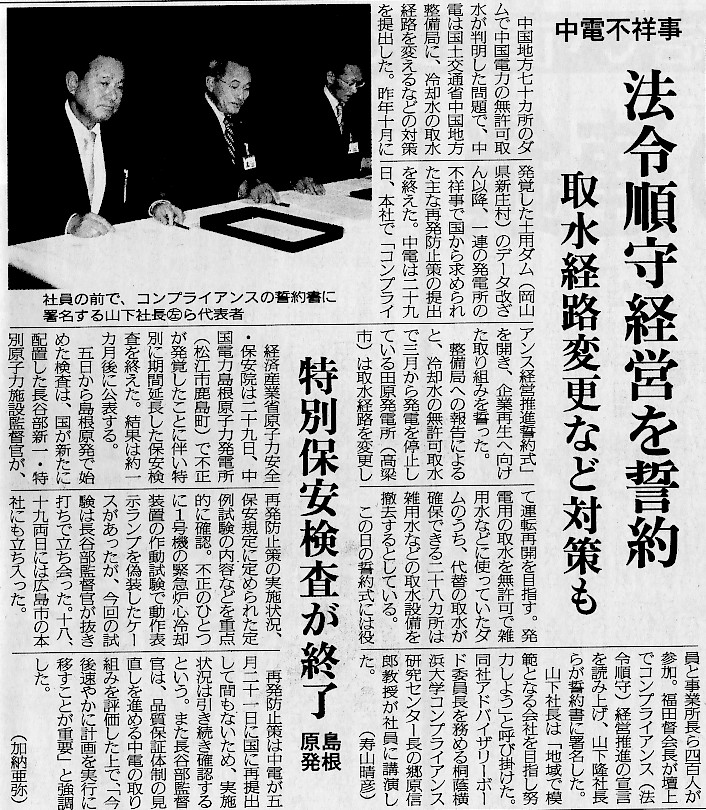
「豚肉混入は日常的」「社長の指示」パート従業員が証言 06/21/07(読売新聞)
牛肉ミンチに豚肉などを混入させていた北海道苫小牧市の食肉製造加工会社「ミートホープ」(田中稔社長)の現役パート従業員の女性が21日、読売新聞の取材に「牛ひき肉の中に豚の心臓や血液などを混ぜた肉を作っていた。偽装行為は、社長の指示で数年前から最近まで日常的に行っていた」と証言した。
「社長の方針に従わない場合、その場で『明日からこなくていい』と言われた社員もいたようだ」とも話している。
女性は数年前から同社製造部門に勤務している。女性によると、混入は、女性が勤務を始めた当初から行われていた。混入の指示は社長から工場の班長を通じて受け、「社長が工場の冷蔵庫にある材料を見て班長に指示し、その日のあり合わせの材料で作ることもあった」という。
農水省がミート社などに立ち入り検査 ミンチ偽装問題 06/22/07(朝日新聞)
ミートホープによる牛ミンチ偽装問題で、農林水産省は22日午前、同社と関連の販売会社「バルスミート」(北海道苫小牧市)、豚肉混入の「牛ミンチ」で冷凍の「牛コロッケ」を製造したとされる北海道加ト吉(北海道赤平市)の3社の本社や工場に、日本農林規格(JAS)法違反の疑いで立ち入り検査に入った。北海道職員も、ミート社と北海道加ト吉の両社へ検査に入った。
同省などは、ミート社がミンチ肉を作る際に記録した「投入原料日報」などの提出を求める一方、北海道加ト吉の原材料の点検体制に不備がなかったか調べを進める。
ミート社では、田中稔社長の長男の取締役が「このような事態を招き、消費者や関係機関にご迷惑をおかけして申し訳ありません」とする社長コメントを読み上げた。
豚肉混入ミンチ:国産鶏肉をブラジル産と偽る 06/21/07(毎日新聞)
北海道苫小牧市の食品加工卸会社「ミートホープ」が「牛ミンチ」に豚肉を混ぜていた問題で、同社の田中稔社長らが21日午前、記者会見し、国産鶏肉をブラジル産と偽って出荷していたことも明らかにした。苫小牧保健所が5年前と昨年に内部告発を受け食品衛生法に基づく立ち入り検査をしていたことも判明。道農政事務所も今年3月と5月に立ち入り検査をしているが、偽装は確認できず、豚肉混入などの偽装は巧妙に行われていたとみられる。苫小牧署も田中社長らから不正競争防止法違反の疑いで任意で事情を聴いている。
鶏肉産地の偽装は田中社長と一緒に記者会見した長男の均取締役が記者の質問を受け、過去に出荷したことがあると認めた。豚肉の混入についても「事故的なものではなく故意的なものだ」と認め、昨年7月以降、出荷した牛ミンチを回収することを表明した。
苫小牧保健所によると5年前に同社が外国産肉を国産肉と偽って表示しているとの匿名の通報があった。昨年にも牛肉に他の肉を混入したり、基準値を超える食品添加物を使用しているとの情報が寄せられ、立ち入り検査を実施。添加物が基準値を上回っていることは確認し該当商品の出荷停止処分を行ったが、偽装は見つけられなかった。書類や工場内の在庫などを調べたが、製品のDNA検査などは費用がかかるため行わなかったという。同保健所の幹部は「立ち入りの技術が不十分だったかもしれない」と話す。【金子淳、鈴木勝一】
ごまかしは、ミート社だけでないと思う。会社の規模の差はあっても、
やっている会社は存在するだろう。
まあ、不正が見つかる可能性は低いと見る。だからこそ、日本企業の不祥事での
対応は悪い。認めれば終わり。グレーゾーンで幕引き出来れば、イメージダウンだけで
済む。日本は熱しやすく、冷めやすい国。
ミート社と6社が取引停止 事前に悪いうわさも 06/21/07(朝日新聞)
食品加工卸会社ミートホープ(北海道苫小牧市)の牛ミンチ偽装問題で、食品関連業界に波紋が広がっている。コンビニエンスストアや食品会社など、ミート社の肉を扱っていた各地の企業は20日、事実確認や商品回収など対応に追われた。少なくとも6社が取引を停止した。
●コンビニも
コンビニ大手のローソン(東京都品川区)は20日、全国の店頭で販売していた「ビーフコロッケ」の販売を中止した。レジわきのケースで保温したものを持ち帰り販売していた若者に人気の商品だが、ミート社のひき肉などで北海道加ト吉が製造していた。
商品に具体的な問題を確認したわけではないが、社会問題化しているため、販売を見合わせたという。商品に含まれる「牛ミンチ」について社内の品質管理部門で鑑定する方針だ。
練り製品で知られる紀文食品(中央区)は、ミート社から豚肉と鶏肉を仕入れ、ギョーザの材料にしていた。今回の問題で「即刻取引を中止した」。北海道の工場には、東京工場の材料を空輸するほか、道内の別会社からの入荷を始めた。
明治乳業(江東区)は、業務用冷凍食品「パーティーラザニア」の出荷停止を決めた。ミート社の牛ひき肉と豚ひき肉を使用していた。卸問屋にも同商品の使用停止を伝えた。在庫は廃棄処分にする。
味の素(中央区)は、子会社が製造する業務用「ニュー牛肉コロッケ」でミート社の「牛ミンチ」を使っていた。「万全を期すため出荷を停止した」という。
●怒り
ピラフなどの材料として鶏肉と豚肉を仕入れていたアスカフーズ(秋田県横手市)は同日午前に対策会議を開いて取引停止を決めた。営業部長は「どの社も品質保持をぎりぎりのコストでやっている。肉をごまかすという安易な手段に強い怒りを感じる」。
ケイエス冷凍食品(大阪府泉佐野市)も取引停止。幹部は「一業者の不祥事により業界全体の信用を失いかねない」と危機感を募らせた。
やはり関西の食品加工会社の社長は、ミート社に電話し、応対した専務に「おたくの肉は、シロなんですか、クロなんですか」と迫った。専務は何を尋ねても「調査中。コメントできない」と繰り返すばかりだった。社長は「ひどい対応で、強い不信感を持った」と取引停止を決断した。
●うわさ
日本水産(東京都千代田区)は、グループ会社がミート社と取引していた。「業界内でよくないうわさがあったので昨年末に取引をやめていた」(広報課長)という。
ミート社から牛ミンチを仕入れていた北海道の食品メーカーのある社員も「昨年、まがい物のミンチを作っているといううわさを聞いた」と打ち明ける。以前にも、異物が混入していたため一時的に取引停止だったこともあったという。
加ト吉製コロッケ材料「豚肉混入を容認」…納入会社社長 06/21/07(読売新聞)
食品大手「加ト吉」(本社・香川県)の連結子会社「北海道加ト吉」(北海道赤平市)製の冷凍コロッケの材料に使う牛肉のミンチに、表示にはない豚肉のミンチが混入されていたとされる問題で、ミンチを納入していた北海道苫小牧市の食肉製造加工会社「ミートホープ」の田中稔社長が20日夜、記者会見して意図的な混入を認めた。
同社の元従業員は「社長の指示を受けて、豚肉を混ぜていた」と証言しており、組織的に安価な豚肉の混入が行われていた疑いが強い。北海道警は、詐欺や不正競争防止法違反容疑などで捜査を始めた。
北海道は同日、ミート社に対し立ち入り調査を実施。道警もミート社や加ト吉の関係者から事情を聞き、関係書類の提出を受けた。
苫小牧市内の本社で記者会見したミート社の田中社長は「昨年、肉が足りない時、(牛肉に)豚肉を混ぜることを容認した。偽装と言われても仕方がない」と話した。ただ、混入の指示については、「自分から言ったかどうか思い出せない」と明言を避けた。
しかし、ミート社の元従業員は同日、読売新聞の取材に対し、「工場では田中社長の指示を受けて、牛肉に豚などの安価な肉を混ぜるなどしていた」と証言。「いいのかなと思ったが、(自分が会社に)いる以上仕方ないと思った」とも話した。
読売新聞が入手した「投入原料日報」と題する2006年7月のミート社の内部文書には、商品名と投入した原料名などが記されている。加ト吉に納入する「オースト(ラリア)産ビーフ」(1100キロ・グラム)には、原料名に「豚心(心臓)480キロ・グラム」「ラムクズ70キロ・グラム」などの記載があった。
一方、加ト吉の金森哲治社長は同日夕、東京都内で記者会見し、仕入れ先のミート社で、牛肉に豚肉が意図的に混入されていたとする調査結果を明らかにした。加ト吉側の関与については否定した。
加ト吉によると、北海道加ト吉とミート社との取引は2000年6月から。ミート社が納めた肉を使ったコロッケは32品目(月間販売数約437万個)で、原材料には牛肉以外の肉の表示はなかった。同社は、これらの出荷をすべて停止し、うち自社で販売している9品目を自主回収することを決めた。32品目のうち家庭用は日本生活協同組合連合会(東京都渋谷区)が各地の店舗で売っていた「CO・OP牛肉コロッケ」など3品目で、残りは業務用という。
豚混入の「牛ミンチ」出荷か 農水省と北海道が調査へ 06/20/07(産経新聞)
北海道苫小牧市の食肉加工販売会社「ミートホープ」(田中稔社長)が豚肉を混ぜたひき肉を「牛ミンチ」として出荷していた疑いがあることが20日、分かった。冷凍食品大手「加ト吉」(香川県観音寺市)の連結子会社「北海道加ト吉」など複数の食品会社に卸しており、牛肉コロッケなどの商品として全国に流通していたとみられる。田中社長は「誤って混ざってしまった可能性があり、調査中」と話している。
農水省と北海道は、原材料名を明記するよう定めた日本農林規格(JAS)法に違反する疑いがあるとして、ミート社や北海道加ト吉を調査する方針を固めた。
加ト吉は小林一夫専務を本部長とする危機管理本部を設置。北海道加ト吉はミート社から仕入れ豚肉が混入していた疑いがある商品の製造を中止した。問題の商品は、日本生活協同組合連合会が販売する冷凍の「CO・OP 牛肉コロッケ」(1パック8個入り)。連合会によると、平成15年3月からこれまでに計500万パックを販売したという。
ミート社の田中社長によると、ひき肉を作る機械が一つで、牛肉や豚肉、鶏肉を次々にひくので機械の中に残って混ざったり、牛肉が足りない場合に豚肉を混ぜたりした可能性があるという。
ミート社のホームページなどによると、昭和51年に設立。系列会社を含めて社員は約500人。平成18年3月期の売上高は約16億5000万円。
豚肉混入:コープなど、商品撤去の対応に追われる 北海道 06/20/07(毎日新聞)
食品会社のモラルが疑われる問題が20日、またもや発覚した。苫小牧市の食肉加工会社「ミートホープ」が牛ミンチに豚肉を混入していた問題で、同社の肉をコロッケに加工して販売していた「北海道加ト吉」や「生活協同組合コープさっぽろ」は朝から対応に追われた。食卓の身近なおかずだけに関係者の衝撃は大きい。
コープさっぽろは20日、道内98店舗中84店で扱っていた「CO・OP牛肉コロッケ」を撤去するよう各店に指示した。本部によると、同商品は03年に日本生活協同組合連合会から仕入れて販売するようになり、昨年までに年間約5万個を販売。これまでに味や品質について客から苦情などはなかったという。
同組合は商品の原産地や加工履歴の管理体制(トレーサビリティー)の一環として、納入商品の原材料や添加物を詳細に記した「商品カルテ」を仕入先に提出させている。同組合の石坂裕幸理事長補佐は「トレーサビリティーの根幹を揺るがす重大事件」と話している。商品仕入れ担当者は「表示偽装は食品を扱うメーカーとしてあってはならないことだ」と怒りをあらわにした。
赤平市の北海道加ト吉本社・工場も慌ただしい雰囲気に包まれた。報道関係者に対応した沖田哲夫・管理部長兼総務課長は「肉の偽装は寝耳に水。まったく把握していない」と困惑した様子。同工場にミートホープから納入される材料肉には証明書が添付され、製品化されたコロッケは味見しても牛肉と豚肉の違いは分からないという。
「ミートホープ」の工場で十数年前まで働いていた50代の男性は「あの会社は社長がワンマン。注文が来るたび、何をどのように混ぜるか手書きの指示書が来た。従業員はその通りに動いていた」と話す。何を混ぜたか詳細に記録した日報も見たという。「7、8年前から冷凍食品の販路を拡大し、コスト削減のため極端な混入を始めたようだ」と推測する。
北海道消費者協会の本田均事務局長は「消費者は表示を信頼して商品を購入するので、大元で不正を働かれたら見抜く方法がない。事実とすればひどい事件で、道産品のイメージも傷つけるだろう」と話した。【西端栄一郎、鈴木勝一】
豚肉混入ミンチ:加ト吉、32品目出荷停止 金森社長会見 06/20/07(毎日新聞)
加ト吉の金森哲治社長は20日、東京都内で会見し、ミートホープの肉を使用している32品目の商品の出荷を停止したことを明らかにした。このうち9品目は自社ブランドで販売しており、店頭からの撤去と回収を始めた。金森社長は「お客様にご迷惑をおかけして申し訳ない」と陳謝した。
加ト吉は同日、北海道苫小牧市のミートホープ工場の立ち入り調査を実施。工場長は「05年8月から1年間に3回、牛肉が不足した際に豚肉を混ぜた」と証言したという。事実確認のため原料のサンプルをDNA鑑定に出しており、22日夜に結果が出る予定。
加ト吉が製造する32品目のうち自社ブランドの9品目以外は、他社から委託を受けて生産している。自社の9品目は家庭用が1品目で月間約21万パックを販売。その他は業務用で同約52万食が売れている。【工藤昭久】
豚肉混入ミンチ:田中社長が指示 会社ぐるみ関与か 06/20/07(毎日新聞)
北海道苫小牧市の食品加工卸会社「ミートホープ」(田中稔社長)が、生産した「牛ミンチ」に豚肉を混ぜていた問題で、田中社長は20日夜、「(豚肉を)入れたことがあったかもしれない。偽装と言われてもしかたない。工場長と話したが、『(豚肉などを牛肉に)入れると言ったはずだ』と言われた。そういうことがあったかもしれない」と自らの関与を示唆した。同社の元幹部の男性は20日、毎日新聞の取材に応じ、「社長の指示で会社ぐるみで豚肉を混入していた」と会社側の積極的関与を証言した。
田中社長は「消費者に不安を与えたことは申し訳ない」と謝罪。混入時期は、市内に第2工場を設立した05年11月ごろから06年7月までだったと述べた。動機は「良い牛肉が足りないことがあった」と説明したが、自らの指示については「よく分からない。自分から言ったのか相談されたのか覚えてない」と明言を避けた。
一方、毎日新聞の取材に応じた元幹部によると、田中社長は毎日のように担当者と打ち合わせ、原料に何を使うか細かく指示。田中社長が数年前に入院した時も、社員が指示を受けるため病室に通ったという。元幹部は「新規の注文を取るときは顧客と打ち合わせて原料を決めるが、契約書通りに作ることはほとんどなかった」と振り返る。
また、毎日新聞が入手した「投入原料日報」では「牛ダイヤ」と呼ばれるひき肉にカモ肉を混入したことが記されていた。投入原料日報について田中社長は「会社としての公式の書類ではない。工場の人間が私的に作ったのでは」としている。【金子淳、大谷津統一、田中裕之】
NOVAに数社が提携打診、猿橋社長「資産売却を検討」 06/16/07(読売新聞)
英会話学校最大手、NOVAの猿橋(さはし)望社長は15日、読売新聞の単独インタビューに応じ、流通業など同業以外の複数企業から資本・業務提携の打診を受けていることを明らかにし、「信用補完は必要で、検討している」と提携に前向きな姿勢を示した。
同社は契約時に虚偽説明があったなどとして、経済産業省から特定商取引法に基づく一部業務停止命令を受けている。猿橋社長は2007年3月期連結決算で2期連続の税引き後赤字に陥った財務を立て直すため、大阪市内にある自社所有の土地、建物(時価数十億円相当)の売却を検討していることも明らかにした。
NOVAは13日の一部業務停止命令で長期の新規契約を禁じられたうえ、15日には厚生労働省から、働く人に受講料を補助する「教育訓練給付金制度」の指定を20日付で取り消すと通知された。5年間、新たな指定を受けられない。
現在は受講料の4割(上限20万円)が受講者に支給されている。対象は指定を受けている32講座で、20日以降に受講し始めると給付金を受け取れなくなる。同社ではこれまで約7万1000人の受講生が約160億9000万円を受給した。同制度は受講生勧誘の際の大きな武器となっていただけに、今後の事業運営に影響しそうだ。財務の立て直しに向けた提携について、猿橋社長は「自分たちだけで一生懸命やって(信用回復が)できるのか。提携先があれば早く(信用補完が)できるかもしれない。流通業界などから話をいただいている」と複数の企業から打診を受けていることを明らかにした。
一方、新規契約の減少や解約の増加に伴い懸念される当面の資金繰りについては、「問題はなく、金融機関の支援も必要ない」と述べた。しかし、「これから(新規契約の)夏枯れに入るので、資金の余力を考えて不動産を売却することも検討している」と、大阪市中心部に保有する不動産の売却を検討していることを明らかにした。
NOVAを巡っては、今年2月に経産省と東京都が特定商取引法に基づく立ち入り検査を実施した前後から、流通業界などから提携の打診が相次いでいた。
関係者によると、ファンドを通じて交渉したものの、条件面で折り合わず断念した流通大手がある一方、依然として意欲的な別の流通大手もあるという。900か所以上の教室網や40万人を超える受講生に着目し、大型商業施設への集客効果を期待しているとみられる。
NOVA受講生への教育給付金制度、20日から取り消し 06/15/07(朝日新聞)
英会話学校最大手「NOVA」(統括本部・大阪市)が、経済産業省から一部業務の停止を命令されたことを受け、厚生労働省は15日、働く人に受講料を補助する「教育訓練給付金制度」の指定を20日付で取り消すことを通知した。
対象となるのは指定を受けている32講座で、20日以降に受講し始めると、給付金を受け取れなくなる。同社は取り消しから5年間、新たな指定を受けられない。
この制度は、労働者の能力開発や再就職支援のため、厚労相の指定する講座の受講料を補助する制度。雇用保険料で賄われ、現在は受講料の4割(上限20万円)が受講者に支給されている。NOVAについては、経産省の処分内容が、「教育訓練を実施する者として著しく不適当」という、指定除外基準に当てはまると判断された。
同社は、1999年10月に最初の指定を受け、今年4月までに、約7万1000人の受講生が約160億9000万円を受給した。この指定は受講生を勧誘する際の大きな武器となっており、今後の同社の事業運営に影響を与えそうだ。
同社広報担当は「生徒に迷惑のかからない対応を考える。再度指定を受けられるような環境作りに努めたい」としている。
NOVAとコムスンの講座、教育訓練給付の指定取り消し 06/15/07(朝日新聞)
厚生労働省は15日、英会話学校最大手「NOVA」の外国語講座32講座と、訪問介護最大手「コムスン」によるホームヘルパー養成講座2講座について、受講者の入学金や受講料の一部を助成する教育訓練給付制度の対象から除外すると発表した。両社は今月、厚労省や経済産業省から違法行為に対する処分を相次いで受けており「教育訓練を実施する者として著しく不適当」と判断した。
除外されたのは、NOVAが英会話やフランス語、ドイツ語などの講座、コムスンはホームヘルパー2級講座と同1級講座。NOVAは20日以降、コムスンは18日以降にそれぞれ受講を開始した人が給付金の対象外となる。現在、受講している人には支給される。また、両社の講座は今後5年間、制度の対象外とされる。
教育訓練給付制度は、自己啓発のため、厚労省指定の民間講座を受けた労働者に対し、雇用保険から費用の最大4割(上限20万円)を助成する制度。06年度には、コムスンの2講座で76人が給付金を受けており、支給総額は約260万円。NOVAの32講座では約4700人が給付金を受け、支給総額は約5億6000万円に上る。
コムスンは今月6日、介護報酬の不正請求問題で厚労省から事業所の新規指定や更新を認めない処分を受け、NOVAも13日、経産省から特定商取引法違反で業務の一部停止命令を受けている。
訓練給付金打ち切り検討 NOVA問題で厚労省 06/15/07(産経新聞)
英会話学校最大手のNOVA(統括本部・大阪市)が経済産業省から新規受講契約の業務停止命令を受けたのを踏まえ、厚生労働省は、NOVAの一部利用者を対象にした教育訓練給付金制度による経費補助を打ち切るかどうか検討を始めた。
同制度は失業者らの職業能力を高めて再就職を促すのを目的に、厚労省が指定した教育訓練を修了した人に経費を補助する制度。雇用保険に一定期間加入している人が申請できる。NOVAでは32のレッスンが対象で、昨年度は約4700人の利用者が計5億6000万円の給付を受けた。
厚労省はNOVAが受講契約時に虚偽の説明をするなど特定商取引法に違反する行為を繰り返していたことを受け「取り消しを含め、慎重に検討する」としている。
NOVA:一部業務停止、6カ月間 経産省が命令 06/14/07(毎日新聞)
英会話学校の最大手「NOVA」(統括本部・大阪市)が中途解約時に高い精算金を要求していた問題で経済産業省は13日、特定商取引法に基づき1年を超えるコースおよび授業時間が70時間を超えるコースの新規契約を6カ月間禁止する業務停止命令を出した。解約手続きなどに関する違反は18件に上り、本社がマニュアルを作り指導した組織的なものだった。経産省の許可を得ているとうそを言ってだましたり、中途解約を申し出た際、返金はなく数万円を請求される悪質な例もあった。
また、東京都も同日、都条例に基づき改善勧告をした。
同省によると、有効期間3年間の600ポイント(1ポイントで1コマ40分間のレッスンを受講)を購入した女性の場合、全額(約92万円)の一部を現金で、残りをクレジットで払う契約をした。週3回ほど通おうとしたが、2、3日前でも予約がとれず週1回しか受講できない状況が続いた。中途解約を申し出て返金を求めたところ逆に「今、辞めると7万円ほど請求させていただくことになる。続けたほうがいい」と言われたという。
また、契約日を実際より前倒ししていた例では「もうクーリングオフできません。この考え方で経産省の許可を得ている」などとうそを重ねていた。
入学金についても、年間を通じて免除していたにもかかわらず、キャンペーン期間中に入学すれば全額免除すると広告で表示し、その時点で入学すれば有利であるかのように装っていた。
同省と都は今年2月、NOVAに対して同法に基づく立ち入り検査を実施。4月には最高裁が「精算規定は受講者の解約権行使を制約するもので、特商法に反して無効」と初判断。NOVAの敗訴が確定していた。【北川仁士】
▽NOVA統括本部の話 経済産業省による一部業務停止と東京都による勧告を受け、このような事態を招いたことを深く反省し心よりおわび申し上げます。指示のあった点はおおむね改善が済んでおりますが、関係者の皆様のご不安をいち早く取り除けるよう努めて参ります。
グッドウィル・グループ(GWG)については良く知らないが、
一般的には悪質な事をする会社の体質は潰されるまで変わらない。
「『役員の中にコムスンの役員が含まれていないかなど通常の申請時より厳しく審査したい』
としながら『これだけ大きな問題を起こしたのだから、会社側もきちんとした対応をしてくるのではないか』という見方も示した。」
考えが甘い。今度は、もっと巧妙にしてくると考えた方が良い。騙されれてから相手が悪いと
嘆くのは愚か者である。
コムスン:別会社に事業譲渡…都道府県に戸惑い 06/07/07(毎日新聞)
コムスンが関連会社「日本シルバーサービス」への事業譲渡方針を突然発表したことに、事業者指定の権限を持つ都道府県には、戸惑いが広がっている。厚生労働省は現段階で譲渡が適法かどうかの判断を保留しており、自治体担当者は「どうすれば利用者を守れるのか」と悩む。
独自監査でコムスンの不正請求を最初に指摘した東京都。担当者は「不正体質はグループ全体の問題の可能性がある。現場は『申請されたから認めます』で済まない」と語る。都は4月、コムスンの3事業所の指定取消処分をしようとした矢先、廃業届を出された苦い経験がある。コムスン側の手法に強い疑問を示しつつ、国に対しても「相手の出方を予想していなかったなら、判断が甘すぎる」と指摘する。
埼玉県の担当者は「受益者を保護することが第一義」とし、譲渡を「事業所がなくなるよりはいい」と受け止める。ただし不正が発覚した事業所を廃止したことは「組織的な印象を受けた」と話す。神奈川県高齢福祉課は「申請を受けた時点で慎重に見極め、特に有料老人ホーム、グループホームなど入所施設は配慮する」との姿勢だ。
今回の通知の直接の理由に原因になった事業所があった青森県は「法令上問題がなければ、色めがねで見るわけにもいかない」としつつ「日本シルバーサービスは県内に事業所がないので、どういう会社かも分からない」と戸惑う。急展開の連続に「朝から新聞の切り抜きを集めて勉強中」と苦笑する。
厚生労働省は「まず今のサービス利用者保護の計画を出させ、内部で譲渡するのであれば厳しく審査する」としている。幹部からは「今の時点では譲渡計画の実効性に何の担保もない。株主向けのアピールでは」と疑問も漏れている。
コムスン:別会社に事業譲渡…東海3県、容認に歯がゆさ 06/07/07(毎日新聞)
訪問介護最大手「コムスン」の親会社、グッドウィル・グループ(GWG)が関連事業をグループ内の別会社「日本シルバーサービス」に譲渡する方針を打ち出したことに批判が集まる中、譲渡先会社からの新規事業所の申請を審査することになる都道府県の担当者は、利用者のサービスを確保する必要もあり、審査を含めた対応に苦慮している。
県内に110のコムスンの事業所がある愛知。県高齢福祉課の担当者は「脱法的なことを認めてしまうことには、行政として『これで良いのか』という歯がゆい思いがある」と打ち明ける。その一方で、「一番重要なのは、利用者に適切なサービスが安定供給されるかどうか。(コムスン後の)受け皿が確保されるのであれば、やむを得ない面もないわけじゃない」と複雑な心境をのぞかせた。
三重県の長寿社会室は「県内に日本シルバーサービスの事業所はないはずで、詳しい情報がない」と戸惑いを隠さない。その上で「同社から新規申請が出た場合は、役員の中にコムスンの役員が含まれていないかなど通常の申請時より厳しく審査したい」としながら「これだけ大きな問題を起こしたのだから、会社側もきちんとした対応をしてくるのではないか」という見方も示した。
岐阜県にはコムスンの事業所が36あり、今回の処分で更新が認められなくなる13事業所について、経営を譲渡するか利用者の受け入れ先を探さなくてはならなくなる。県高齢福祉課の担当者は「法的に問題がなければ、事業譲渡を認めない理由はないが、(介護請求の不正請求など)背景が背景なので、国や他の自治体の方針を見極めたい」としている。
【武本光政、田中功一、中村かさね】
「コムスン」介護集金を業者が代行、トラブル続発 06/07/07(読売新聞)
介護事業所の新規指定などが認められなくなったグッドウィル・グループ(GWG)の訪問介護大手「コムスン」(東京都港区)が介護サービスを利用した高齢者らの集金業務の一部を債権回収業者に代行させ、「支払い済み」と主張する利用者との間でトラブルが頻発していたことが7日、わかった。
回収業者への委託は違法な取り立てにはあたらないものの、ほかの業務に比べて苦情が頻発。「債権管理がずさん」として、回収業者側から3か月で契約を打ち切られる事態になった。
関係者によると、同社は昨年11月、都内の債権回収業者と契約。支払いが滞っている介護サービスの利用者負担分について「集金代行」の形で業務を発注した。
実際の請負では、同社が提供した利用者の個人データに従って、業者が「弊社は債権の調査・管理等を行っている。支払いをされる場合は右記口座へ早急に送金下さるようご案内申し上げます。至急ご連絡ください」という文面のはがきを郵送していた。
ところが、業者に対して、はがきを受け取った利用者から「支払いが済んでいる」「架空請求ではないか」といった苦情が約100件も相次いだ。このため、業者はトラブルの多さから収益が見込めないと判断、今年1月末で請負を打ち切ったという。同様の苦情は、都や国民生活センターなどにも寄せられている。
元職員らによると、コムスンでは利用者負担分(1割)が現金払いされた場合、職員が入金処理を怠ったり、本社の手続きミスで滞納扱いのままになっているケースが頻発していた。「利用した覚えがないのに請求のはがきが届いた」という苦情は各事業所にもよく来ていたといい、同社が十分な確認をしないまま、回収業者に集金代行を委託していた実態がうかがえる。
回収業者については、読売新聞の取材に対し、コムスン以外の複数の大手介護事業者が「契約していない」と回答しているほか、コムスンの元社員らは「利用者から入金があっても、滞納者リストから名前が削除されないことがあった」と証言している。
同社をめぐっては、都内の9割近い事業所で、介護保険外の散歩への付き添いを「身体介助」としたり、サービス時間を実際よりも長くしたりするなどして請求額を水増ししていたことが判明しているが、利益優先主義が浮かび上がった形だ。
◇
この問題で、都福祉保健局は、コムスンに対し、利用者向けの総合的な相談窓口のほか、事業所ごとに相談窓口や専用電話を直ちに設置することを6日付の文書で指導した。
また、指定更新が認められなくなる事業所については、早急に引き継ぎに関する全体計画を策定し、遅くとも今月中に文書で報告することも求めた。
このほか、都は、利用者サービスの低下防止や、廃止する事業所の利用者に対して、代わりの事業者を確実に紹介することなども指導した。
日商会頭:「社保庁を解体」「グッドウィルの責任大きい」 06/07/07(毎日新聞)
日本商工会議所の山口信夫会頭は7日の定例会見で、年金支給漏れ問題について「民間では考えられないようなずさんで無責任な体制だ。早急に社会保険庁を解体して改編を急いでやるべきだ」と社保庁の体質を批判。政権を担ってきた自民党の責任を指摘したが、「政争の具にはせず、与野党が一致して国民が安心できる対案を示すことを最優先すべきだ」と語った。
また、事業所の新規指定・更新禁止処分を受けた訪問介護大手「コムスン」が介護サービス事業のグループ会社への譲渡を決めたことについて、山口会頭は「脱法行為であり、社会的には許されないのではないか」との認識を示した。そのうえで、「親会社のグッドウィルの社会的責任は大きい」と厳しく指弾した。【内山勢】
コムスン事業所の新規・更新、2011年末まで認めず 06/06/07(読売新聞)
厚生労働省は6日、グッドウィル・グループ(GWG)の訪問介護大手「コムスン」(東京都港区)の全国の事業所の新規指定と更新を、2011年12月まで行わないよう都道府県に通知した。
2006年4月施行の改正介護保険法により、不正な行為があった事業者による指定・更新を5年にわたり認めないとする規定を適用した。コムスンは、全国8か所の事業所で、雇用していない訪問介護員を勤務しているなどと偽り、介護事業所指定を不正に取得したことが問題とされた。この規定を全国規模で適用するのは初めて。
同省によると、5月末現在、同社の介護事業所は2081事業所(介護予防サービス事業所除く)あるが、同法では不正がなかった事業所も含めて更新が5年間禁じられるため、来年度には1424事業所に減少、最終的には、2011年度に426事業所にまで減る。2081事業所には、訪問介護だけでなく、デイサービスやグループホームなどの事業所も含まれる。サービス利用者は、更新時期まではサービスを受けることができるが、事業所の更新が認められないと、事業所を変えなければならなくなる。
同省によると、不正があったのは、東京都内の4か所と青森、群馬、岡山、兵庫県の各事業所。都内では別の事業所のヘルパーを常勤扱いするなどして、介護保険法の基準を満たしたように装って申請していた。
このうち、不正があった兵庫県の事業所の指定申請が昨年12月だったため、この時点から起算して5年間、更新や新規指定を行わないこととした。改正法ではまた、事業所の指定更新制を新たに設け、事業所は、不正がなくても6年ごとに指定を更新しなければならないとしている。
厚生労働省介護保険指導室は、「来年4月の最初の更新時期まで時間があるので、コムスンはその間に、利用者に影響が及ばないよう、適切に対応してほしい」と話している。
コムスンは、1988年設立。97年にGWGが資本参加し、現在はGWGの100%子会社。訪問介護事業者最大手で、利用者は約6万5000人。訪問介護のほか、居宅介護支援などの事業所を全国に展開している。
コムスン:解説 制度揺るがす不正、厚労省強い姿勢 06/06/07(毎日新聞)
全国に約2万カ所ある訪問介護事業所の約1割を占める最大手のコムスンが撤退を余儀なくされることは、介護サービス全体への影響も大きい。それでも厚生労働省が厳しい処分に踏み込んだのは、コムスンの不正が組織的に行われていた疑いが濃く、放置すれば、介護保険制度への信用性低下にもつながるとの懸念があるとみられる。
コムスンを運営するグッドウィル・グループは、総合人材サービスの大手。介護保険事業への参入を早々と表明し、00年4月の制度開始時には業界最大規模の体制を整えた。しかし、わずか3カ月後には利用の低迷から社員4400人のうち1600人のリストラ方針を表明し、事業所数も増減を繰り返すなど、不安定な経営が続いていた。
今回の処分理由は、青森県と兵庫県での職員数の虚偽申請だが、コムスンは東京都、岡山、群馬県などでも不正な申請が発覚している。介護報酬を請求できない掃除の時間を加算するなどの不正請求も明らかになっており、本社が各事業所に手口を指示していた疑いも持たれている。
介護報酬の不正請求を巡っては、コムスン以外の事業者への処分も全国で相次いでいる。処分が続けば全国にサービスが行き届かなくなる懸念もあるが、厚労省老健局は「新規参入を促してカバーしていきたい」と不正の監視と排除を最優先する姿勢だ。【清水健二】
コムスン:不許可…「現場に影響大きい」利用者ら不安 06/06/07(毎日新聞)
訪問介護の最大手の「コムスン」が、介護保険事業から撤退する公算が大きくなった。厚生労働省は6日、コムスンに介護施設の新規開設や更新を今後認めないことを決定。勤務実態の虚偽申請が、2万4000人に及ぶ従業員を抱える業界トップの「崩壊」につながった。介護関係者や全国利用者に衝撃と不安が広がった。
「利用者が多いので、影響は少なくないでしょう」。認知症のお年寄り家族を支える活動を20年以上続ける群馬県前橋市の竹田千恵子さん(82)は、不安の声を上げる。さらに「本来介護は、企業が利潤を追求する対象になじまない。人手が足りないので民間が担うのはやむを得ないが『それぞれの家庭に密着して地道に支えるのが本質』という警鐘を鳴らしている気もします」と、厚生労働省の出した厳しい「決定」を解説してみせた。
介護保険法が施行され、社会福祉協議会が行ってきたヘルパーの仕事の民間化が一気に進められた。コムスンは、地元の人を採用し、急成長してきた経緯がある。「介護保険法に基づき、利益を追求できる枠は一定なのに、収益を無理に増やそうと、介護員の水増し請求を続けてきたのではないでしょうか」と竹田さんは推測する。
「コムスンが行った不正は絶対に許されないが、このままコムスンが介護事業から撤退することになれば、介護の現場に与える影響が大きすぎる」と心配するのは、大谷強・関西学院大教授(社会保障)。「最も被害を受けるのは介護を受ける利用者。慣れたヘルパーの介護を受けられなくなる不安は大きい。コムスンが抱えるケアマネージャーやヘルパーなども失業してしまう」と話した。
介護保険利用者への情報提供を行っている「介護情報ネットワーク協会」(神戸市)の糟谷有彦代表理事は「(コムスンの対応は)悪質だったのである程度は予想できた結果だ」と話す。そのうえで、「コムスン以外の事業所が充実している地域でなく、コムスンに頼ってきた地方への影響は計り知れない。地方を中心に新たな『介護難民』が発生する可能性がある」と指摘した。
コムスン:厚労省、介護不許可 撤退は不可避か 06/06/07(毎日新聞)
グッドウィル・グループ(GWG)の訪問介護最大手「コムスン」(東京都港区)が青森、兵庫県で運営していた事業所で雇用していない訪問介護員を勤務しているなどと偽って申請し、事業所指定を受けていた問題で、厚生労働省は6日、コムスンの介護事業所の新規開設や更新を認めないよう都道府県に通知した。介護事業所についてこうした処分が下されたのは全国初めて。コムスンは介護サービス事業から撤退する可能性が強まった。
同省老健局によると、コムスンは06年7月に青森県、今年1月に兵庫県内の事業所の新規指定を受けたが、その際、勤務実体のない職員数を水増しするなどの虚偽の申請をした。
コムスンは、04年4月~今年1月、東京都、岡山県、青森県、群馬県、兵庫県の計8事業所の新規指定の際に虚偽の申請をしたことが各都県の監査で発覚。各都県は各事業所を廃止処分にした。
介護保険法では、事業所が廃止されると、より厳しい「指定取り消し」処分ができなかったが、昨春の同法改正で「居宅サービス等に関し不正または著しく不当な行為をした」申請者に対し、指定取り消し処分ができるようになった。このため同省は、昨春以降に指定された青森、兵庫県のケースについて規定を適用し、申請者であるコムスンが全国展開する事業所の新規指定・更新を認めないようにした。
今回の処分により、申請者のコムスンの役員が、別会社で介護サービス事業を行うこともできなくなる。利用者は、更新期限を迎えるまでは各事業所でサービスを受けられる。
コムスンは全国に約2081事業所を展開しているが、今後、更新期限(6年間)を迎える事業所が順次廃止されていくことになる。その結果、コムスンの事業所は2011年度には426カ所になり、事業継続は困難になる。【柴田朗、清水健二】
NEC不正22億円、架空発注で裏金 国税指摘 05/29/07(朝日新聞)
大手電機メーカー「NEC」(東京都港区)の営業系幹部社員らが架空や水増しの発注を繰り返し、下請け会社などから現金を還流させて裏金をつくっていたことが東京国税局の税務調査で分かった。06年3月期まで7年間の不正支出は総額約22億円にのぼり、大半を裏金として還流。取引先の接待に充てていたなどとして、交際費と認定されたとみられる。
不正支出を含む所得隠しの総額は23億円。ほかに研究開発費用をめぐる経理ミスなども指摘され、7年間の申告漏れ総額は約40億円にのぼった。同社は過去に多額の赤字を抱えており、増えた所得は相殺されるため、重加算税を含めて追徴税は発生しなかった。
不正経理に関与したのは計五つの事業部の営業部門。事業部長から主任クラスまで、50~30歳代の計10人がかかわり、上司と部下が一緒になって不正を働いたケースもあったという。
同社は社内調査でこのうち8人の関与が明白になったとして、死亡した1人を除く7人を懲戒解雇処分とした。今後、損害賠償や刑事告訴を検討する方針。
関係者によると、NECはグループで請け負った業務を、保守サービスの「NECフィールディング」(港区)のほか、ソフト開発やシステム工事関連の子会社にそれぞれ発注し、子会社はさらに下請け会社に外注するなどしていた。
国税局が調べたところ、このうち営業部門からの発注の一部に実態がなく、架空や水増しだったことが判明。渡した金の大半が、発注した事業部の担当者に還流され、裏金として管理されていたことも分かった。子会社を通さず、直接協力会社に支出して還流させる手口もあった。
裏金は、取引先を銀座の高級クラブなどで接待する費用に充てられ、多いときは百万円単位の支払いもあったとされる。ほかにクレームをつける顧客への対策費用にも充てていた。また、一部は社員らが飲食に使っていたという。
国税局は、接待費用などは交際費にあたり、組織ぐるみで経費に見せかけて所得を減らしたとして、悪質な所得隠しと認定した模様だ。
◇
NECコーポレートコミュニケーション部の話 不正取引が発生したことは誠に遺憾で、ご迷惑をかけたことを深くおわびする。再発防止を徹底したい。
朝日新聞(2007年5月12日)より
企業不祥事なぜ相次ぐ 日本型のシステムが変質
プロ意識育て倫理再生を
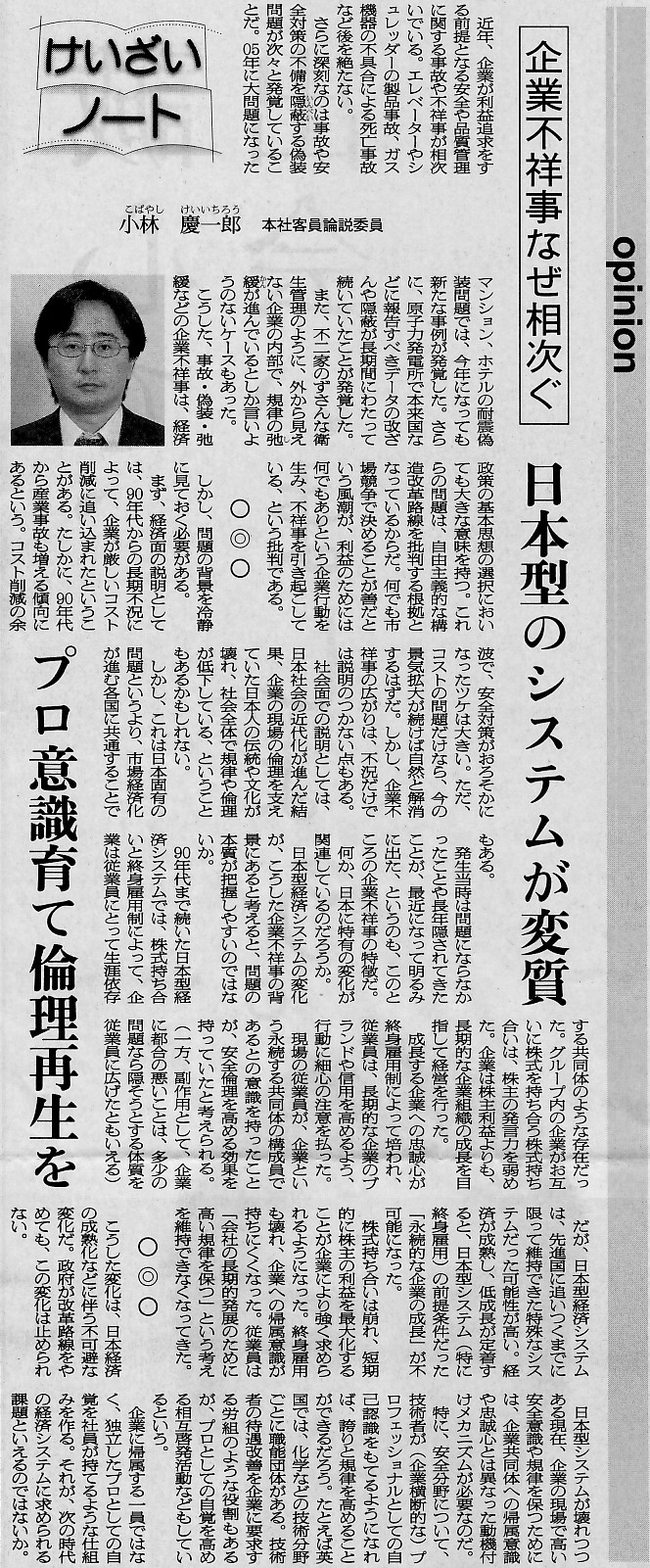
三菱重工 234人が監理技術資格を不正取得 05/17/07(朝日新聞)
三菱重工業(東京)の横浜や広島、長崎など計11事業所で、大規模工事で配置が義務づけられている国土交通相認定の監理技術者の資格者証を計234人が、要件を満たしていない実務経験を記載するなどして、不正に取得していたことが同社の社内調査で分かった。同社では05年、神戸造船所の社員28人の同資格者証不正取得が明らかになっており、実務経験に基づく社内の資格者の約4割が不正取得だった。同省は、無資格の社員が有資格者として工事に従事していた可能性があるとみて、建設業法違反の疑いで処分を検討している。
同省が神戸造船所での不正取得を受け、昨年7月、全事業所対象の調査を同社に指示していた。
同社は、実務経験を基に同資格者証を取得した社員が所属する計14事業所の計624人について調べた結果、横浜製作所(横浜市)72人▽高砂製作所(兵庫県高砂市)66人▽広島製作所(広島市)25人▽長崎造船所(長崎市)21人、など計11事業所の計234人の同資格者証取得を「不適切」と判断した。神戸造船所でも新たに15人の不正が判明した。
234人のうち5人は神戸造船所での問題発覚後に同資格者証を取得していた。同社は昨年9月、234人分の資格者証を返還し、登録は抹消された。
同社によると、この234人は、05年に発覚した不正取得と同様に、規定の実務経験に算入されない経歴を記載するなどしていた。同資格者証取得のためには「実務経験証明書」を財団法人「建設業技術者センター」に提出しなくてはならないが、同社では、主に本人が記憶に基づいて経験を記載し、上司が社内記録とほとんど照合せず、同社代表者名の職印を押して同センターに提出していたという。一部は証明書に記載していない工事を勘案すると、結果的には要件を満たしているという。建設業法で資格者証の携帯を義務づけられた公共工事には、同資格者証を不正取得した9人が従事していたという。
国交省の処分基準では、同法で義務づけられた監理技術者を配置しなかった場合、原則として15日以上の営業停止処分にするとされている。同社から調査の報告を受けた国交省関東地方整備局は、今回のケースが処分対象になるか検討を進めている。
三菱重工業社長室広報グループの話 会社としてきちんとチェックや管理ができていなかったことが原因で、反省している。再発防止の取り組みを引き続き進め、法令順守に努めたい。
〈キーワード〉監理技術者 建設工事の施工計画の作成や工程管理、品質管理などに指導監督的な立場であたる技術者。建設業法は、元請け業者が3000万円以上の工事を下請け発注するような大規模工事の施工時に配置を義務づけている。財団法人「建設業技術者センター」が資格者証を交付している。発注者が国や自治体などの場合、資格者証の携帯が必要。
内閣府のホームページに内閣府本府等所管公益法人(法人の概要)
として紹介されている社団法人 全国はちみつ公正取引協議会の主な目的は
「景品表示法第10条第1項の規定に基づいて認定を受けたはちみつ類の公正競争規約を円滑、かつ、効果的に運用することにより、公正な取引の推進を図り、もって国民生活の向上に寄与することを目的とする。」
主な事業は
5.規約の規定に違反する疑いのある事実の調査に関すること
6.規約の規定に違反する者に対する措置に関すること
7.関係官庁との連絡及び一施策の協力に関すること
内閣府のホームページ
は間違った情報を記載している。
「会見に同席した岡本光治事務局長は『規約は知っていたが、定期検査は品質管理の一環でやっており、自発的に改善してもらうという前提があったので……』などと弁明を繰り返したが、2000年度以降の検査で3回にわたり注意を受けた業者もいたという。
報道陣から“身内への甘さ”を指摘されると、藤井副会長は『そう思われても仕方がない。意識的に偽物を作ったのかどうか、調査をやれば区別できたかもしれない』と語った。」
内閣府
はホームページの情報を迅速に訂正するべきだ。岡本光治事務局長と藤井副会長の発言は内閣府は
間違っていると言っていると思える。それとも、内閣府が正しくて、社団法人 全国はちみつ公正取引協議会が
岡本光治事務局長と藤井副会長が答弁に困り、そのような発言をしたのか??内閣府は適切な対応をするべきだ。
純粋はちみつ甘味料混入疑惑、農水省が表示を重点調査へ 05/15/07(読売新聞)
社団法人「全国はちみつ公正取引協議会」(東京都中央区)
の会員業者の商品に、人工甘味料などが混入していた疑惑が発覚したことを受け、農林水産省は15日、はちみつの表示に関する重点調査を実施すると発表した。
食品の表示について定めた日本農林規格(JAS)法に違反するケースがあれば、改善指示や業者名の公表に踏み切る。
同省によると、重点調査は16日から約3か月かけて実施。全国の店頭で売られている「純粋はちみつ」約300点について、はちみつ以外の糖分などの含有の有無を検査する。調査結果は、同協議会を所管する公正取引委員会や都道府県に提供し、連携して適正表示を徹底させる方針だ。
松岡農相は15日の閣議後の記者会見で、「純粋といいながら、そういうものが入っていたことが事実だとすれば、まさに『看板に偽りあり』で、大変遺憾なことだ」と述べた。
疑惑あるのに調査せず、はちみつ公正取引協が事実認め謝罪 05/14/07(読売新聞)
社団法人「全国はちみつ公正取引協議会」(東京都中央区)
の会員業者の商品に人工甘味料などの混入疑惑が発覚した問題で、同協議会の幹部は14日、都内で記者会見し、1982年以降25年間、混入の疑いを把握してもその都度、十分な調査を行ってこなかったことを明らかにした。
同協議会は、昨年度の検査で陽性となった業者に対する調査を始めており、故意による混入が確認されれば、処分や業者名の公表を行う考えだが、消費者団体からは、対応の甘さを厳しく指摘する声もあがっている。
経済産業省内で会見した藤井新三副会長は「お騒がせしたことを申し訳ないと思っています」と切り出し、「混入が疑われる会員に、警告・注意などの措置を講じてきたが、公正取引委員会への報告を怠り、十分な調査を尽くしていなかった。反省している」と謝罪し、対応の甘さを認めた。
同協議会によると、異性化糖(でんぷんなどを原料とする人工甘味料)の含有をチェックする定期検査は82年から始まった。陽性反応が出た場合、文書で「注意」や「警告」を出すだけで、規約で定める事情聴取など詳しい調査は行っていないという。
同協議会の事務局長は代々、公正取引協議会制度を熟知する公取委OB。会見に同席した岡本光治事務局長は「規約は知っていたが、定期検査は品質管理の一環でやっており、自発的に改善してもらうという前提があったので……」などと弁明を繰り返したが、2000年度以降の検査で3回にわたり注意を受けた業者もいたという。
報道陣から“身内への甘さ”を指摘されると、藤井副会長は「そう思われても仕方がない。意識的に偽物を作ったのかどうか、調査をやれば区別できたかもしれない」と語った。
今回の調査対象は、06年度に異性化糖などを調べる検査で陽性となった商品を販売した会員業者14社のうち、すでに退会した1社を除く13社。各社に対し、事実関係を報告する文書の提出を求めており、その内容を精査したうえで現地調査を行う。
藤井副会長は「故意による混入などが確認できれば、厳正に対処する」と述べ、会員業者の処分や業者名の公表を検討する考えを示したが、05年度以前の検査で陽性だった商品については調査は行わないという。
混入はちみつに「公正」印、公取委が会長から事情聴取 05/14/07(読売新聞)
社団法人「全国はちみつ公正取引協議会」(東京都中央区)の会員業者の商品に人工甘味料などの混入疑惑が発覚した問題で、検査で陽性となった商品を販売する業者の中に、同協議会の役員が経営する会社が含まれていたことがわかった。
さらに、消費者に品質のお墨付きを与えた「公正マーク」を付けた商品もあった。公正取引委員会は消費者の信頼を損ないかねない問題とみて、同協議会会長から事情聴取を行うなど指導を始めた。
不当表示を防止するため公取委の認可を得て設立された同協議会は、公正競争規約に基づき、年1回の定期検査で会員業者の商品の成分が適正かどうかチェックしている。異性化糖(でんぷんなどを原料とする人工甘味料)や水あめ類の含有の有無を調べる検査では、過去7年間で全体の2割、延べ120点が陽性と判定されている。
同協議会は読売新聞の取材に対し、この中に理事(計20人)を務める業者が販売する商品が含まれていることを認めたが、業者名や数は明らかにしていない。
同協議会は規約などで、役員が経営する会社に疑義が生じた場合の対処を定めておらず、こうしたチェック体制の不備が、協議会としての対応の甘さにつながったとみられる。
また、同協議会は、規約に定めた成分基準などを守り、個別の検査結果に基づいて適正な表示をしていると認めた業者に対しては、商品に「公正取引」のマークの使用を認めている。消費者に商品の信頼性を示す指標とされるもので、現在、会員106業者のうち約80業者が使用している。
ところがその後の定期検査で、このマークが付いた商品でも陽性反応が出て、「『注意』を出したケースがある」(同協議会事務局)という。これについても、同協議会では業者への事情聴取を行わず、使用許可を取り消すこともしなかった。
このマークは、商品にシールをはる場合は1枚4円で販売されている。使用料収入は年間約2000万円で、同協議会の総収入の半分を占める。
公取委はすでに、同協議会の野々垣孝会長らから事情を聞くなど調査を始めた。陽性反応が出た業者に、必要な調査をせず規約が順守されていなかったことを問題視した上で、疑いのある商品について調査の徹底を求めた。
朝日新聞(2007年5月12日)より
企業不祥事なぜ相次ぐ 日本型のシステムが変質
プロ意識育て倫理再生を
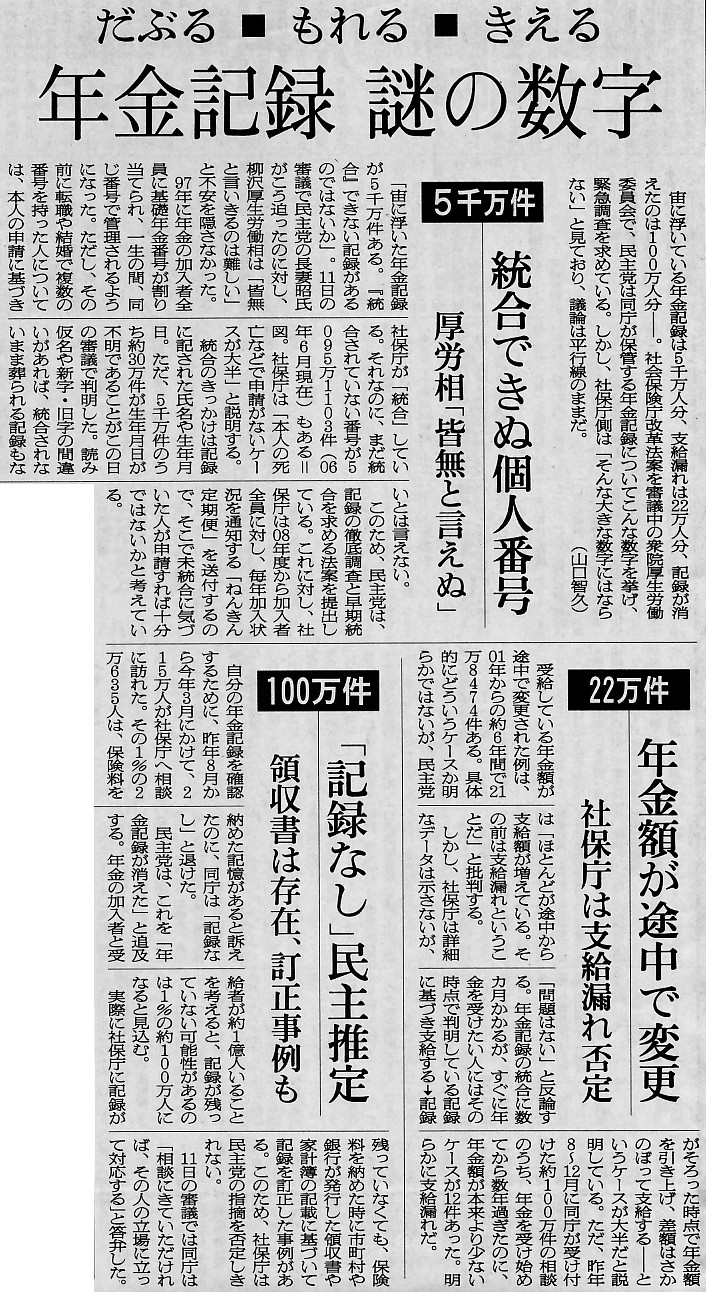
エキスポランドは信用が全く出来ない組織だ。「全日本遊園施設協会」の会長を兼務するエキスポランド(大阪府吹田市)の山田三郎社長
も恥を知れ。最近は、演技力がある人間が責任者に向いているのかも知れない。嘘を付きながら
何も知らない、本当に申し訳ないと演技できるリーダーや指導者が国民を騙せる可能性が高い。
北陸電力の臨界事故隠し
でも現場だけが知っていたと最初は報告した。
中国電社長はデータ改ざん把握について「記憶なかった」
と発言した。
「同社の建部淳施設営業部長はこれまで、車軸の探傷試験については規則で定められておらず、
自主的に行うものと説明。しかし、その後の調査で誤りを認め、虚偽報告していたと謝罪した。
また、探傷試験について、山田社長から実施するよう指示はなかったとしている。」
このような対応をする人間が、国土交通省所管の財団法人「日本建築設備・昇降機センター」が
開いた講習の講師を2年もしていた。日本建築設備・昇降機センターは詳細について説明する
必要がある。こんな不適切な人間を起用した責任は重い。事故後の対応も最低と思わないか。
独立行政法人 日本万国博覧会記念機構
の理事達も説明責任があるだろ。肩書きを持って公務員をしていたのだから、公の場で
説明と今後の対応を示せ。
エキスポ社長、全国に探傷試験を通達 遊園施設協会長名で 05/11/07(読売新聞)
「風神雷神II」の事故を起こしたエキスポランド(大阪府吹田市)の山田三郎社長が会長を兼務する「全日本遊園施設協会」が平成8年、山田会長名で、全国の都道府県や市などの特定行政庁あてに「遊戯施設 安全管理マニュアル」を送付していたことが11日、分かった。この中には「コースターの車軸は年に1回以上の探傷試験を実施し、周期を延ばしてはならない」などと記されていた。山田社長が検査内容を熟知していたにもかかわらず、社内に指示していなかったとされる問題が裏付けられた格好だ。
マニュアルは全122ページで平成8年10月7日に発行され、コースターなどの遊戯施設の管理方法などを規定。保守点検は、日本工業規格(JIS)の検査標準に従って行うことなどを詳細に定めており、吹田市もこのマニュアルを保管しているという。
エキスポランドは例年1~2月に実施する探傷試験を今年は先送りし、昨年1月末以降実施していなかったが、マニュアルは年次検査に関して「コースターの車軸は年に1回以上の探傷試験を実施し、周期を延ばしてはならない」などと記していた。
同社の建部淳施設営業部長はこれまで、車軸の探傷試験については規則で定められておらず、自主的に行うものと説明。しかし、その後の調査で誤りを認め、虚偽報告していたと謝罪した。また、探傷試験について、山田社長から実施するよう指示はなかったとしている。吹田署捜査本部は、社内でマニュアルが周知されず、安全管理を怠っていた可能性があるとみて調べを進める。
マニュアルの作成には、風神雷神IIを製造した「トーゴ」や、エキスポ社の関連会社の社員らも含まれていた。
◇
菅義偉総務相は11日午前の閣議後の記者会見で、大阪府吹田市の遊園地「エキスポランド」のジェットコースター事故に関し、「遊戯施設の安全確保対策に関する緊急実態調査」を実施すると発表した。総務省の行政評価局が緊急に行うもので、対象は全国の遊戯施設事業者のほか、国土交通省などの行政機関。事業者に対しては、整備や定期点検が適正に行われているか聞き取り調査を実施する。
独立行政法人 日本万国博覧会記念機構
と
エキスポランド
の関係は公にされるべきだ。
「日本万国博覧会記念機構の理事のうちそのうちの3人が、財務省や警察庁からの天下り。」
理事たちの経歴はすばらしい。
藤原啓司氏は、東大、大蔵省、東京税関長の経歴を持つ。
田中正広氏は、鳥取県警本部、近畿管区警察学校長、警視庁刑事局指紋鑑識官の経歴を持つ。
今川日出男氏は、前職が大阪府知事公室長。
中井昭夫氏は、元NTT。
幹事の村上仁志氏は、元銀行員。
きっこのブログより
日本工業規格(JIS)規定に反し車軸の「探傷検査」を延期したエキスポランド社の建部淳・施設営業部長に
説明を求めるべきであろう。理事の1人である田中正広氏は、鳥取県警本部、近畿管区警察学校長、警視庁刑事局指紋鑑識官の経歴を持つ。
警察での経験から対応に期待ができる。適切な対応ができなければ、必要なし。
一番適任者である人物が役に立たなければ、やはり、天下り軍団。やる気なしと思われても仕方が無いかも!
「『講師の資格要件に沿って選任した。今後は適当な人物かどうか、確認する必要性を感じている』と
話した」適切な人物かどうかは確認するとは、実際にどのような管理を行っているのか、不正を行って
いないか、現場まで出向いて確認するのか。具体的な方法を考えていないのだろう。これでは、
建部淳・施設営業部長と同じレベルかも??
日本工業規格(JIS)規定を知らなくとも、講習で使用されるテキストの内容を理解しなくとも、
講師が出来る。しかも、国土交通省所管の財団法人「日本建築設備・昇降機センター」にはクレーム
も来ない。すばらしい組織であり、「天下りばんざい」のシステムになっている。機能不能でもチェックも
されないし、評価もされない。
コースター事故:JIS違反指示の部長が検査資格の講師 05/10/07(毎日新聞)
大阪府吹田市の「エキスポランド」のジェットコースター事故で、日本工業規格(JIS)規定に反し車軸の「探傷検査」を延期したエキスポランド社の建部淳・施設営業部長が、「昇降機検査資格者」の資格取得講習で講師を務めていたことが分かった。担当は遊戯施設の定期検査に関する授業。
JISでは「(遊戯施設の乗り物の)車輪軸は年1回以上の探傷試験を行うこと」と定められている。「風神雷神2」は今年1月に前回の探傷検査から丸1年が経過したが、新アトラクション導入に伴い、探傷検査に必要なコースター解体の場所が確保できなかったため、同社の技術部門トップの建部部長が今月中旬まで検査延期を決定。結局検査前の今月5日に車軸が折れ、死亡事故が起きた。事故後、建部部長は「それまで異常がなく延期しても大丈夫と思った。JISで探傷検査が義務付けられているのは知らなかった」と説明した。
遊戯施設の定期検査は、国家資格の「昇降機検査資格者」だけが行える。資格取得は一定年数以上の実務経験を積み、計4日間の講習を受け、試験に合格する必要がある。講習と試験は年4回、東京か大阪で実施。建部部長は04~06年に大阪会場で「遊戯施設の検査標準」の授業を担当した。テキストには検査資格者の職務として「管理者や所有者に定期検査の主旨を徹底させる」と明記されていた。
講習と試験を実施する「財団法人日本建築設備・昇降機センター」によると、全日本遊園施設協会から建部部長の推薦を受けたという。同センターの橋本滋・昇降機部長は「講師の資格要件に沿って選任した。今後は適当な人物かどうか、確認する必要性を感じている」と話した。
独立行政法人 日本万国博覧会記念機構
と
エキスポランド
の関係は公にされるべきだ。
「日本万国博覧会記念機構の理事のうちそのうちの3人が、財務省や警察庁からの天下り。」
理事たちの経歴はすばらしい。
藤原啓司氏は、東大、大蔵省、東京税関長の経歴を持つ。
田中正広氏は、鳥取県警本部、近畿管区警察学校長、警視庁刑事局指紋鑑識官の経歴を持つ。
今川日出男氏は、前職が大阪府知事公室長。
中井昭夫氏は、元NTT。
幹事の村上仁志氏は、元銀行員。
きっこのブログより
理事達の経験がすばらしいので、もちろん、管理やいろいろな資料にも
目を通しているだろうし、渡された資料を理解するのに問題がない証明となる高学歴と
能力を持っていると判断出来る。しかし、なぜ、このような惨事が起こったのか。
天下りは能力の高い官僚や公務員が民間でも能力を発揮できると、
政府や政府組織は言っているが、実際は仕事をしていない、または、
仕事が出来ない、高学歴と過去の経歴は何の役にも立たないことを証明して
いると思う。もし、彼らが理事として、管理職を経験した官僚や公務員と
して仕事をやっているのであれば、彼らの責任を警察は問うべきである。
なぜ、車の車検があるのか。なぜ、メーカーが部品の取り替え時期をマニュアルに
書いてあるのか、理解できないほどの能力しかないのであれば、責任は問えないであろう。
さっさと、天下りの給料と退職金目当てで、仕事などしていなかったと言った方がよい
かもしれない。もし、彼らの責任を問わないのであれば、
警察もそれだけの組織なのであろう。
「国土交通省は、『不適切と言わざるを得ない』と指摘。」しているが、
国交省にも問題がある。検査方法があいまい。遊具と言っても、いろいろなものがある。
危険度の高い遊具の検査方法。検査する者の資格の明確化がないのも問題。
建築士が、機械工学や金属や化学の知識があるとは思えない。
あるメーカーが点検をして、問題がなければ使いつづけるとコメントしていたが、
安全性のため、問題が無くともある一定の期間が過ぎれば、交換をメンテナンス マニュアルに
書いてある車、船、飛行機のケースがある。
金属もいろいろな特性がある。だからこそ、材料試験があるし、試験結果によるデータも重要。
多くの技術者や大学や専門学校で工学部である学生は金属疲労について聞いたことがあるだろう。
新しい言葉ではない。遊具が特別であるとは思えない。
このようなコメントをすること自体、国交省の規則が曖昧で、甘いことの証明となるだろう。
「建部部長によると、山田三郎社長はJISで年1回の探傷検査が義務付けられていることを
知っていたが、検査延期は社長決裁が必要でなく、事故前に問題が表面化することはなかった。
他の検査資格者からもJISの規定に反しているとの指摘はなかったという。」
JISもだめ、
ISO
もだめ。結局、問題や不備を防ぐことは出来ない。法や規則による、罰則もなし!
サブスタンダード船
を生み出す
検査会社
と同じだ。罰則が無ければ、改善や問題の解決無し。不祥事を起す企業。
罰則がないと秩序は保てないと言う事だろう。安倍総理。美しい日本は、存在しない??
美しい日本語よりもモラルや法令順守が優先だ。
コースター事故:エキスポランド、部長判断で検査せず 05/09/07(毎日新聞)
大阪府吹田市の遊園地「エキスポランド」で、ジェットコースター「風神雷神2」の車軸が折れて脱線し、乗客の女性(19)が死亡した事故で、株式会社「エキスポランド」が今年1月、日本工業規格(JIS)に反して車軸の亀裂を調べる「探傷検査」を行わなかったのは、技術部門トップの建部淳・施設営業部長の判断だったことが分かった。建部部長は同社の安全検査の最終責任者で、国家資格の昇降機検査資格者。8日会見した建部部長は「探傷検査がJISで定められていることは、事故後に初めて確認した。社内の24人の資格者はみな熟知していなかった」と、ずさんな検査体制を認めた。
同社は毎年1~2月ごろ、ジェットコースターを解体し、金属の微細な亀裂を調べる探傷検査をしてきた。しかし、今年の解体検査は延期され、今月中旬の予定だった。延期の理由について建部部長は当初、「新アトラクションの開設で、解体検査をする車庫がふさがっていた」と説明。しかし3月に検査用スペースができていたことを指摘されると「これまで一度も探傷検査で傷が確認されなかったので、3カ月遅らせても大丈夫と考えた」と答えていた。この日の会見で建部部長は「探傷検査は屋外でもできる。延期せず、安全を優先すべきだった。検査のやり方は先輩から引き継いだが、間違った意識で取り組んでいた。私のミスだ」と謝罪した。
建部部長によると、山田三郎社長はJISで年1回の探傷検査が義務付けられていることを知っていたが、検査延期は社長決裁が必要でなく、事故前に問題が表面化することはなかった。他の検査資格者からもJISの規定に反しているとの指摘はなかったという。
ジェットコースターの定期検査は、建築基準法で規定。具体的な検査項目はJISなどで定められており、「車輪軸は年1回以上の探傷試験を行うこと」とされている。検査は、検査資格者が責任を持つことになっているという。
エキスポランド、探傷試験せずに市へ「不適合なし」報告 05/07/07(読売新聞)
エキスポランドが、今年1月に実施した建築基準法に基づく定期検査で、折損した車軸について、日本工業規格(JIS)の検査基準に反して、亀裂の有無を調べる「探傷試験」を行わずに、「A(不適合の指摘なし)」と判定し、吹田市に報告していたことがわかった。
同基準の順守を指導している国土交通省は、「不適切と言わざるを得ない」と指摘。同園のずさんな安全管理態勢を改めて浮き彫りにしている。同園によると、年1回の定期検査では車体を解体し、超音波による探傷試験を実施しているが、今年1月の検査では探傷試験は実施せず、大型連休後に先送りしていたという。
◇
吹田市は7日、エキスポランドに対し、風神雷神2について安全が確認されるまでの間、使用を禁止するよう通告した。
エキスポ、車軸を15年交換せず…他園は5年交換例も 05/07/07(読売新聞)
大阪府吹田市の遊園地「エキスポランド」の立ち乗り型ジェットコースター「風神雷神2」が脱線し、乗客20人が死傷した事故で、事故車と同じメーカー製の立ち乗り型コースターを設置する全国5か所の遊園地のうち、一度も車軸を交換していなかったのはエキスポランドだけだったことがわかった。
他は5~14年で交換していたが、エキスポランドは1992年の運行開始以来、未交換で、車軸の耐用年数も把握していなかった。
車軸の折損は、切断面の形状から金属疲労が原因となった可能性が高く、府警吹田署の捜査本部は、ずさんな検査で異常が見過ごされた疑いがあるとみて詳しく調べる。
府警によると、車軸は軸の方向に対して垂直に切れており、こうした切断面は、金属疲労による破断で生じることが多いという。
府警は6日、同園事務所などを捜索し、7日には現場検証を実施している。吹田市も近く、建築基準法に基づき、立ち入り検査する。
エキスポランドは6日の記者会見で、車軸の交換時期について、メーカー側から説明などはなく、耐用年数も知らなかったと説明している。
エキスポランド以外に、遊具メーカー「トーゴ」(東京)製の立ち乗り型コースターがあるのは、よみうりランド(同)、ルスツリゾート(北海道)、鷲羽山ハイランド(岡山県)、三井グリーンランド(熊本県)。
82年に導入したよみうりランドは、最近では2000年に車軸交換、すべての部品を7年ごとに交換しているという。
87年に設置した鷲羽山ハイランドは、交換頻度は「5、6年に1度」(担当者)と説明。85年から営業するルスツリゾートも、これまでに2回交換した。三井グリーンランドは、運行3万回ごとに解体検査を実施。一昨年6月、車軸に摩耗が見つかり、初めて取り換えた。
海運業界では、大阪府吹田市の遊園地「エキスポランド」のジェットコースター「風神雷神2」のように管理及び検査や
状態に問題がある船を
サブスタンダード船
と呼ぶ。
検査会社の問題
と
旗国(行政)
のどちらか、又は、両方に問題があるために、
「エキスポランド」のジェットコースター「風神雷神2」のように問題がある
サブスタンダード船
が野放しになっている現状がある。国土交通省はこの件については、
国際会議で「建築基準法は設置者に検査を義務付けているが、
検査結果の確認を行政側に求めておらず、同市の担当者も『(遊園地側から出される)検査表を信用するしかなかった』と話している。」
ような問題が起きないように旗国(行政)の管理・監督体制を監査することを提案した
のでこの後は、遊具の管理・監督を含めて適切に対応出来ると思う。行わなかったら、怠慢だろう。
絶叫マシン、安全点検に“法の穴”…行政に確認求めず 05/07/07(読売新聞)
大阪府吹田市の遊園地「エキスポランド」で起きたジェットコースター「風神雷神2」の脱線事故で、こうした「絶叫マシン」などの安全点検は遊園地にゆだねられている現状がある。
建築基準法は設置者に検査を義務付けているが、検査結果の確認を行政側に求めておらず、同市の担当者も「(遊園地側から出される)検査表を信用するしかなかった」と話している。
絶叫マシンの安全検査について国は、建築基準法で、設置者が半年から1年おきに行うことなどを定めているだけだ。
定期検査で設置者は「軌条・走路」や「台車・車輪装置」などの各項目について、検査資格者に3段階で評価させる。検査資格者は1、2級建築士や、日本建築設備・昇降機センターの講習の修了者で、結果を示した「検査表」は、管轄する都道府県や区市町に報告される。しかし、同法は、日々の点検について、具体的な方法を定めておらず、定期検査の結果が正しいかどうかの確認を行政側に求めていない。
「風神雷神2」も、今年2月、吹田市がエキスポランドから受理した検査表の47項目は、すべて安全上問題がないA評価だった。同園では、定期検査では、約10人のスタッフが2班に分かれて4、5日でチェックしていたという。
同市の平田健司・建築指導課長は「遊具の専門知識を持つ職員を抱えることは不可能で、検査表を信用するしかない」とし、検査のあり方について「市だけで改善できず、国も含めた議論が必要」と訴える。
国土交通省建築指導課の担当者は、「遊戯施設の安全管理については、所有者が一義的に責任を持つ。ただ仮に検査の報告内容に問題があったとすれば、報告が適切に行われていたのか、検証が必要になるのではないか」としている。
こうした現状について青木義男・日本大教授(安全設計工学)は「人気が高い遊園地は、安全性確保のために十分な経費をかけられるが、苦境に立つところは削減してしまう可能性がある。異常を見極めるのは人間であり、その技術を引き継いでいくことが大切だ」と指摘する。
「風神雷神2」と同種のジェットコースターがある岡山県倉敷市の「鷲羽山ハイランド」では事故後、6日から専属技術者2人が遊具を金づちでたたくなどして点検を実施している。今後、メーカーの検査技師を呼び、さらに詳しい検査を行う予定だ。
朝日新聞(2007年5月3日)より
データ改ざん問題の中国電力社長 自身の辞任は否定
不正の背景「業界のおごり」「変わらねば原子力できぬ」
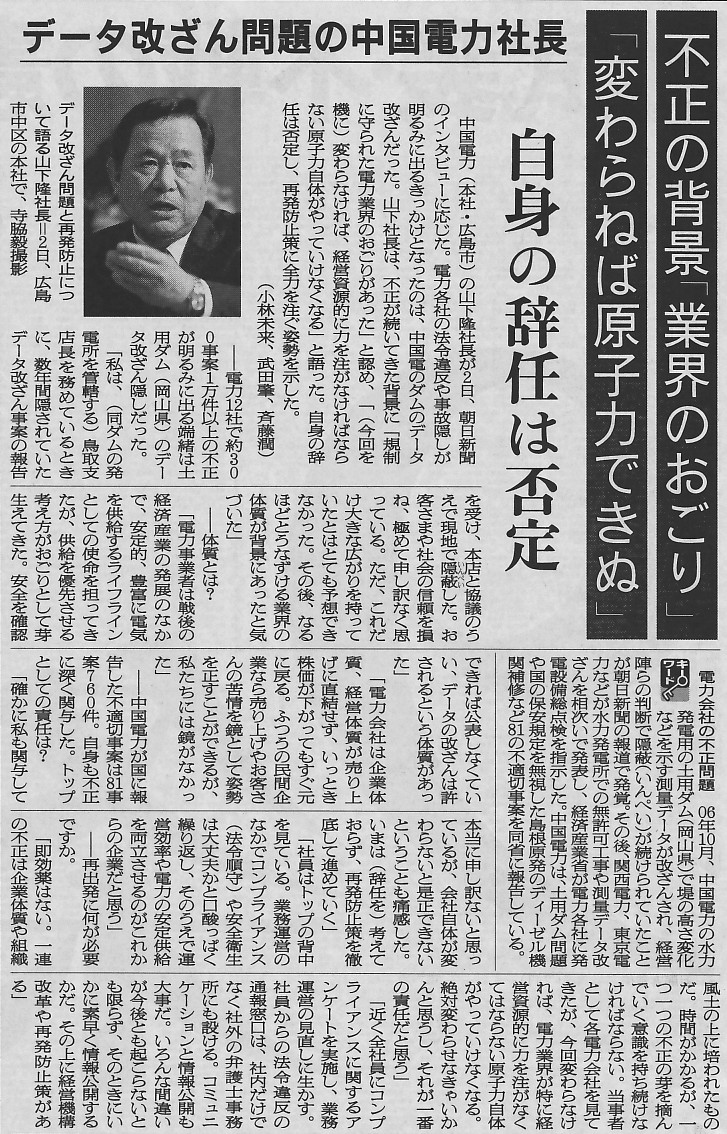
法的に問題ない。
「同園では、建築基準法で定められた年1回の定期検査の際、独自に解体検査も実施。」
耐震偽装問題でも、法の不備があると感じたが、またもや法の不備か!
問題がなければ、見直さない国や省の対応にも問題がある。
常識で事故が起こる前に見直さなければならない法、規則、通達が多くあるはず。
死亡事故が起きたことにより「たぶん??」定期検査や検査基準についても改正や見直しが
あると思うが、なぜ、改正や見直しが放置されてきたのか?お金にゆとりがある時は、自主的
な解体検査等の管理や維持などで問題が発生しないだろう。しかし、不祥事を起す企業や建前
だけの法令順守を掲げる会社が多い中、法や規則で最低限の基準を定めないと、問題は
防げないだろう。
大阪の遊園地でコースター車輪脱落、1人死亡19人重軽傷 05/02/07(読売新聞)
5日午後0時50分ごろ、大阪府吹田市千里万博公園の遊園地「エキスポランド」で、走行中の立ち乗り式のジェットコースター「風神雷神2」(6両編成、乗客20人)の2両目の車軸が折れて車輪が落下、車体が大きく傾き、乗客の滋賀県東近江市、会社員小河原(こがわら)良乃さん(19)がレール沿いの鉄柵に頭部を打ちつけて即死、友人の同県豊郷町、古川小百合さん(20)が重傷、11~45歳の18人が軽傷を負った。
事故を目撃した15人が気分の悪さを訴え、病院で手当てを受けた。国土交通省は、事故を起こした遊具メーカー「トーゴ」(東京、倒産)製の立ち乗り式ジェットコースターを使う全国の遊園地などに6日、緊急点検を要請する。
同園は、1~2月に予定していた超音波や磁気で車軸の傷などを確認する解体検査を延期していた。車軸は1992年の運転開始以来、一度も交換していなかったという。府警捜査1課は安全管理の不備が事故につながった可能性があるとみて吹田署に捜査本部を設置、業務上過失致死傷容疑で6日に同園事務所などを捜索する。
調べなどでは、コースターは、全長970メートルのコースを、1両あたり左右各五つの車輪でレールをはさみ込んで走行する。定員24人で、1両に4人が前後に2人ずつ立ったまま乗り込み、最高時速75キロで1周約2分20秒で走破する。
事故では、2両目左側の車輪を支える合金製車軸(長さ約40センチ、直径約5センチ)が乗降場所から約440メートル地点で折れ、そのまま約240メートル走行後、車輪がレールから外れて落下。車体が左側に約45度傾き、2両目左前列に立っていた小河原さんが鉄柵(高さ約1メートル)に激突した。古川さんは、小河原さんのすぐ後ろにおり、別に女性客2人が乗っていた。同園によると、事故時の速度は約30キロと推定され、コースターは乗降場所の約50メートル手前の地上約6メートル地点で止まったという。乗客らは最大1時間半、コースター上で救助を待った。
同園では、建築基準法で定められた年1回の定期検査の際、独自に解体検査も実施。しかし、今年1~2月の定期検査では、解体に使う車庫に空きがなかったため解体検査を今月15日に行う予定だった。
コースターは、90年に大阪市で開かれた「国際花と緑の博覧会」会場で人気を呼んだ「風神雷神」をモデルに開発された。同園は事故から約1時間後、遊具の運転を取りやめて臨時閉園した。6日も休園する。
エキスポランドの建部淳・施設営業部長は記者会見で、「金属疲労か、車軸の加工に問題があったと思われる」とした上で、「解体検査は義務づけられているわけではなく、法令違反はなかった。検査を行っていても今回の事故が防げたかどうか分からない」と釈明した。
コースター事故:エキスポランド社長が謝罪会見 05/05/07(毎日新聞)
ジェットコースター事故で、大阪府吹田市の株式会社エキスポランドは敷地内の従業員施設で午後4時から、緊急会見をした。以後、深夜まで取材の対応に追われた。山田三郎社長は「楽しみの施設を悲しみの施設にしてしまい申し訳ない。最高責任者としておわびのしようがない」と謝罪。しかし会社側はその後の説明で、点検方法などについて「ぬかりはなかった」と強調した。
会見では建部淳・施設営業部長が事故状況を説明し、年1回車体を解体して実施する検査を今月15日に予定していたことや、92年の製造以来、車軸の交換をしていなかった事実などを明らかにした。
解体する検査は直近では昨年1月に実施したが、同社は「解体検査は必ず行う必要はなく、自主的にやっているので、時期をずらしても法的には違反ではない」と説明。車輪部分の点検は「機械全体を分解しなくてもジャッキで持ち上げるなどして目視でも検査が可能。今回、車軸が折れた部分も目視で調べられる」と話し、この日の始業前の点検でも異常はなかったと話した。
車軸の破損については、「金属疲労か」「製造上の問題なのか」との質問に対し「(大阪府警)科学捜査研究所が出す結果と違うといけないので」と言及を避けた。
山田社長は遊園地や娯楽場の開発、経営などを手がける「泉陽興業」(大阪市浪速区)の会長を兼務。会見で「35年で8000万人を迎え、大きな事故もなくやってきた。社会に迷惑をかけてしまい、ひたすらおわびする。被害者の方には誠意の限りを尽くします」と頭を下げた。
コースター事故:脱線で女性死亡、乗客ら34人搬送 大阪 05/05/07(毎日新聞)
5日午後0時48分ごろ、大阪府吹田市の万博記念公園内にある遊園地「エキスポランド」で、ジェットコースター「風神雷神2」(6両編成、全長1050メートル、最高時速75キロ)の2両目が脱線し、同車両の前列左側に乗っていた滋賀県東近江市、会社員、小河原良乃(こがわら・よしの)さん(19)が鉄製の手すりと衝突し死亡した。2両目前部の車軸部分が折れており、走行中に車体がレールから外れて、最大で45度傾いて走行したという。小河原さん以外の乗客19人と、事故を見て気分が悪くなった人を含む計34人が病院に搬送された。大阪府警は業務上過失致死傷容疑で同日、吹田署に捜査本部を設置した。
捜査本部の調べや、株式会社エキスポランドの説明によると、事故を起こしたコースターは1両4人乗りの6両編成。最大24人乗りだったが、事故時は20人が乗車。小河原さんは手すりに衝突した際、頭部を強打し即死。後列左側に乗っていた滋賀県豊郷町の女性(20)も、手すりなどに前頭部を打って重傷。この2人以外の11~45歳の乗客計18人が軽傷を負った。
小河原さんと重傷を負った女性は友人同士。この日は計6人で遊びに来ていたという。
風神雷神2は座席に座らず、立った状態で体を背もたれに固定する立ち乗りコースター。車両の車底部には、レールと車両を固定する車輪が左右に設置されている。左右それぞれ五つの車輪でレールをはさみ込んで固定する構造で、五つの車輪は直径5~7.5センチの車軸で車体とつながっている。脱輪した2両目は、進行方向左側の車軸が左から10センチの部分で折損していた。車軸が折れたことで、車輪が脱落。レールと車体が離れ、左側に傾いたとみられる。手すりに衝突時には時速30キロ程度だったとみられる。
コースターは毎日、車両本体や安全装置を点検し、空の状態で3回運行させている。この日の朝の点検で、異常は発見されなかった。午後1時半から30分の中間点検が予定されていたが、その直前に事故が発生した。
同社によると、年1回は分解して超音波や磁石を使った解体点検も行っていたが、直近は昨年1月で、「(今年は)3カ月半遅らせても大丈夫」と判断し、今月15日に実施する予定だったという。法的には問題ないが、遅らせた理由について同社は「新アトラクションを建設する影響で、車体を解体するスペースが確保できなかった」と説明した。折れた車軸については、92年の製造以来、交換したことがなかった。
◇
エキスポランドは事故を受け、6日の休園を決定。7日以降の営業については未定という。
【ことば】風神雷神2 大阪市で90年に開催された「国際花と緑の博覧会」(大阪花博)で運行したコースター「風神雷神」をモデルに、92年にエキスポランドの新たな目玉アトラクションとして設置された。乗客は座席に座らず、立ったまま滑降する。1両4人乗りの6両編成で定員は24人。安全のため、身長140センチ未満の人は利用できない。全長は1050メートルで、最高時速は75キロに達し、所要時間は約2分20秒。地上から最高40メートルの高さがあり、コースはアップダウンが激しく、後半には旋回もある。
【ことば】エキスポランド 1970年開催の「日本万国博覧会」の成功を記念して、跡地に整備された万博公園内にある大規模遊園地。近くには博覧会のシンボルとなった「太陽の塔」(岡本太郎作)がある。
最近は、社長や幹部の無能さをアピールし、責任は無いと報告するのがはやりなのか。
「重大な品質悪化が会社上層部に報告されず、社内体制に大きな問題があった」
北陸電力の臨界事故隠し
でも現場だけが知っていたと最初は報告した。
中国電社長はデータ改ざん把握について「記憶なかった」
と発言した。
上が知らなければ、許されるのか??故意でなければ、能力不足で済ますのか??
国土交通省は、建築基準法による年1回の定期検査に関して、検査会社に対して処罰的な項目を
追加する必要があると思う。処罰がなければ、
船舶に対してでたらめな検査を平気で行う検査会社
のように問題は解決しないだろう。「ロープの状況を『良好』とする虚偽の報告書を作成」程度
の行為なんか、通常のレベルだ。もっと酷いケースがある。しかし、めったに見つからない。
全く、見つからないケースもあるのだ。
日本オーチスの破断ワイヤ、赤さび1年10か月放置 05/02/07(読売新聞)
六本木ヒルズ「森タワー」(東京都港区)のエレベーターのワイヤロープが破断し、火事が発生した問題で、事故機を管理する「日本オーチス・エレベータ」(中央区)が、2005年1月にロープの赤さびなどを確認しながら、1年10か月も清掃を行わず放置していたことが1日、同社の社内調査でわかった。
今年3月の定期検査ではロープの太さを調べただけで、ロープの状況を「良好」とする虚偽の報告書を作成していた。
同社の江崎英二社長らが同日、国土交通省で記者会見して明らかにした。それによると、同社は05年1月、事故機を含む計11基のエレベーターの保守点検を行った際、ロープがこすれて生じる金属粉や潤滑油、ホコリなどがロープの表面に付着し、赤さびなどが発生していることを確認。赤さびを取り除く清掃や給油を実施することを当時の社長が出席していた本社の品質責任者会議で決めた。
しかし、事故機の清掃は06年11月、同年12月、07年3月の計4回行われたものの、赤さびや汚れを部分的に除去するにとどまった。
建築基準法では年1回の定期検査が義務付けられ、赤さびを確認して以降の05年~07年の毎年3月に同社の検査員が検査を実施していた。しかし、少なくとも07年の時点では汚れで破断の有無が確認できない状態だったのに、専用の検査機器も使用せず、ロープの太さだけを調べて、ロープの状態を「良好」とする報告書を作成。所有者の「森ビル」を通じて東京都に提出する手続きを進めていた。この報告は、日本オーチス社本社の担当者も把握していた。
赤さびについては、2005年の時点で、別の場所の同社製92基でも見つかっていた。同じ現象は同業他社の製品でも起きており、一部の社はロープごと交換することを決めていた。
また、六本木ヒルズの11基については、定期検査とは別の保守点検で昨秋、「汚れが激しく、除去するのは困難」との報告が日本オーチス社にあがったが、同社が交換を決定したのは今年2月。昨秋の段階で交換を決めていれば、火事を防ぐことができた可能性も指摘されている。江崎社長は、「2005年1月に赤さびが確認できた段階で、ロープの交換の検討を始めるべきだった」と判断の遅れを認めた上で、「重大な品質悪化が会社上層部に報告されず、社内体制に大きな問題があった」と陳謝した。
重油パイプラインの不正改造を隠ぺい…北海道電力が発表 04/10/07(読売新聞)
北海道電力は10日、伊達火力発電所(北海道伊達市)で重油パイプラインに関する不正行為を隠ぺいしていたと発表した。
現在の発電所長と本店の保守担当リーダーら9人は不正を知りながら、社内調査に申告していなかった。一方、中国電力は島根原子力発電所の冷却水流量のデータ改ざんなど3件の不正が見つかったと発表した。
国の指示で行った電力各社の一斉調査のとりまとめから10日余りで新たな不正が相次ぎ発覚したことで、調査の信頼性も揺らぐことになった。
北海道電力は、伊達発電所と約26キロ離れた送油所(室蘭市)を結ぶパイプラインで、漏えい検知装置と送油の緊急遮断機能の一部が働かないよう不正改造していた。漏えいがなくても、たびたび検知装置が作動したためで、不正は1978年の運転開始直後から続いていた可能性がある。
消防署が年一回行う保安検査では、遮断機能が一時的に働くように戻す偽装工作を繰り返しており、消防法違反の可能性が高い。
隠ぺい発覚のきっかけは今月4日、消費者向けの苦情窓口に送られてきた匿名の書面。不正を隠ぺいしていた発電所長とリーダーの2人は、先月までの社内調査では、社員から事情を聞き取る側だった。発電所長は「発電所が運転停止になることを恐れ、言い出せなかった」と話している。
一方、中国電力は島根原発2号機(松江市)で、91年7月から現在まで、冷却水流量が実測より0・4%程度小さく表示されるように計測装置を操作し、国の検査時などに原子炉出力の微調整をごまかしていた。
北海道電が不正隠し 重油漏れ警報、機能しないまま放置 04/10/07(朝日新聞)
北海道電力伊達火力発電所(北海道伊達市)で、パイプラインの重油漏れの検知装置を不正に動かないようにしていたことが10日、わかった。同社は電力会社の不正に関する国への報告期限の3月30日以前に知っていたが、隠していた。同社は10日、消防法違反の疑いがあるとして、経済産業省原子力安全・保安院に報告する。
関係者によると、パイプラインは室蘭市から火力発電所まで約26キロ、燃料用の重油を運んでいる。以前に重油漏れの検知装置が誤作動して警報が鳴り、弁が自動的に閉まるトラブルがあった。このため、検知装置の異常を修理せず、装置が働かずに弁が常に開いている状態に改造した。
同社では、社員らから不正の報告を受けていたが、調査担当者はこの報告について十分調べずに、国への報告をしていなかった。
4月になって再度社内の窓口に調査を求める情報があり、不正の事実が発覚した。
また、中国電力の島根原発2号機(松江市)でも91年に原子炉に冷却水を戻す復水器の流量が実際よりも0.4%ほど低く出るよう値を改ざんしていた。同社は3月末の報告書提出時に事実を把握していたが詳細がつかめなかったため、10日、保安院に報告することにした。
日興、上場廃止へ 不正決算問題で3証取 03/02/07(朝日新聞)
東京、大阪、名古屋の3証券取引所は2日、不正な利益水増しで過去の決算を訂正した国内3大証券のひとつ日興コーディアルグループの株式を、上場廃止する方向で最終調整に入った。前経営陣が利益水増しに関与し、水増し額も多額なため「悪質性が高く上場廃止基準に触れる」と判断している模様だ。東証は3月中旬に正式決定し、4月中旬に廃止する見通し。日興は廃止も視野に米金融大手シティグループの傘下入りなどを検討しており、近く提携戦略を固めるとみられる。
審査を担当する東証上場部は、来週末にも不正決算に関する調査と事実関係の分析を終え、3月中旬までに西室泰三社長が上場廃止を最終決定する方向だ。大阪、名古屋も月内にも廃止を正式決定する見通し。廃止されても証券業務は継続でき、顧客が預けている資産にも影響はない。
東証は昨年12月に不正決算が発覚して以降、日興への聞き取り調査を進め、日興が2月末に04年9月中間~06年9月中間期決算の訂正報告書を関東財務局に提出後、報告書の分析を進めてきた。
日興はコールセンター大手のベルシステム24の買収に絡み、連結に加えるべき損失を連結外に外したり、債券の発行日を偽ったりして不正に利益を計上した。
上場廃止の判断で焦点になるのが、一連の行為が、廃止基準の「有価証券報告書の虚偽記載を行い、その影響が重大である」に該当するかどうかだ。
東証は、日興の特別調査委員会が、山本元・前グループ財務部門執行役常務らが一連の不正に関与し、有村純一前社長の関与も疑われる、と指摘したことなどを重視。最終的に利益の水増しが2年間で約420億円にのぼったこともあり、「組織ぐるみの不正は悪質で、市場や投資家に与えた影響は大きい」との見方を強めている。
廃止決定の場合、東証は1カ月間、日興株を売買可能な「整理ポスト」に置く。日興の個人株主は06年末で約9万5000人。廃止後も証券会社を通じて売却できるが、常に買い手がつくかわからず、価格も不安定になる可能性がある。
日興の現経営陣は、有村氏ら前経営陣に総額31億円の損害賠償請求訴訟を起こす方針を表明するなど、過去との決別姿勢を示すことで上場維持へ期待をつなぐ一方、廃止を前提に提携戦略も検討してきた。信用補完のためにシティグループとの協議を中心に、他の金融大手との提携強化などの対応を急ぐ考えだ。
シティは、日興を日本での事業拠点と位置づけており、上場廃止の場合は、日興の完全子会社化も視野に入れている。
不二家:小売などの在庫 全量引き取り廃棄へ 02/23/07(毎日新聞)
不二家は22日、チョコレートなど一般菓子の3月上旬の販売再開に向けて、小売り各社や卸売業者などが倉庫や店舗で保管したままになっている一般菓子の在庫を全量引き取って廃棄する方向で検討に入った。問題発覚前に製造された商品をすべて廃棄し、同社を支援している山崎製パンの指導下で3月以降に製造した商品だけを販売することを明確にして消費者や流通各社の不安を払しょくする狙い。在庫全量廃棄を安全性確保の決め手と位置づけ、失った信頼回復につなげたい考えだ。
一般菓子の販売について、不二家は(1)米国の衛生管理手法「AIB」での点検完了(2)品質管理の国際規格(ISO)の再認証取得(3)保健所が指摘した問題点の改善--で工場の安全性をアピールし、再開にこぎ着ける戦略だった。
しかし、再建を助言する有識者会議「『外部から不二家を変える』改革委員会」(委員長・田中一昭拓殖大教授)は「不二家が生まれ変わったと納得できる具体策が足りない」と注文。これを受けて、不二家を支援している山崎との間で、安全性確保のための新たな対策を詰めていた。
在庫の全量廃棄については山崎と最終調整中で、不二家が小売り各社や卸売業者から在庫をすべて引き取る代わりに、新しく製造した商品を提供する計画。現在も不二家の一般菓子の販売を続けている一部小売りに対しては、「在庫廃棄は、新生・不二家をアピールするために不可欠」と理解を求め、商品の入れ替えに応じてもらう方針だ。山崎から打診を受けた流通各社は、在庫の全量廃棄に対し前向きに協力する姿勢を示しているという。
全量廃棄には多額の資金が必要なため、銀座本社売却など不二家の資産整理の検討が加速する可能性が高い。
多くの不祥事を起した結果として、仕方のないことだろう。
さまざまな問題を起して解体が決まった社会保険庁
は、未だに職員の保護に懸命である。こんな組織の人間達に過去の実績があるだけで、信用しない国民が
多いにもかかわらず、採用や雇用しようとする国を国民はどう思うのか??
社会保険庁と比べると、良い幕引きだと思う。
みすず監査法人、大手3法人への業務移管検討を発表 02/17/07(毎日新聞)
大手監査法人「みすず監査法人」(旧中央青山監査法人)は20日、同法人の監査業務と公認会計士らを2007年7月末をめどに新日本、トーマツ、あずさの大手3監査法人に移管する方向で検討していると発表した。
3法人と協議入りで合意した。具体的な業務移管の方法や約2500人の会計士らのうちどの程度を移管するかなど、詳細は今後の協議で検討する。全面的な移管に発展すれば、4大監査法人の一角であるみすずが、事実上解体されることになる。監査手法の違いなどが障害となり、業務や会計士の移管が円滑に進まない場合は、みすずと監査契約を結んでいる約600社の上場企業の会計監査に影響が出る懸念もある。
みすずでは、前身の旧中央青山監査法人が手がけたカネボウの粉飾決算事件や、昨年末に発覚した日興コーディアルグループの不正会計問題など、不祥事が相次いでいる。
同日記者会見した片山英木理事長は他法人への業務移管を決めた理由について、「監査法人に一番必要な信用を損なった。みすずのままで監査業務を行うと、先行きが不透明だ」と述べた。
みすずは一部の監査対象企業に対して、今回の業務移管の方針について説明を始めた。監査対象企業の混乱を避けるため、2007年3月期決算の監査は従来通り実施し、業務移管は今夏以降に行う。
みすずは、日興コーディアルグループの不正会計を見逃したことで、金融庁から行政処分される可能性が浮上している。片山理事長は「行政処分の有無にかかわらず移管を進める」と説明した。
朝日新聞(2007年2月16日)より
三菱UFJ業務停止命令 金融庁新規融資を7日間
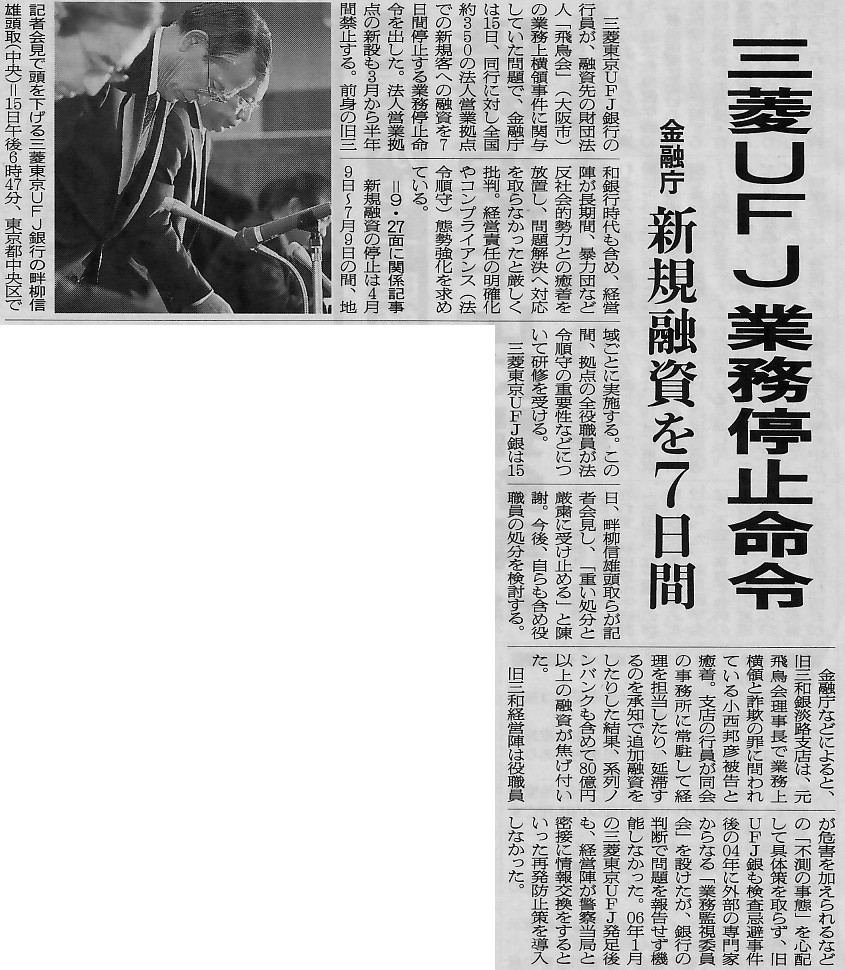
朝日新聞(2007年2月16日)より
三菱UFJ、相次ぐ処分 「構造的問題」指摘の声

リンナイCO中毒:事故記録引き継がず 危機管理に甘さ 02/17/07(毎日新聞)
ガス機器メーカー「リンナイ」(名古屋市)製の小型ガス湯沸かし器で95年7月に東京都内で一家6人が一酸化炭素(CO)中毒となり、ガス事業者から報告を受けた同社は、ユーザーへの注意喚起を含めて対策を講じていなかったことが分かった。同社は、昨年1月、事故情報を一元管理する部署を新設したが、同事故や92年の弁護士一家5人の死亡事故などの引き継ぎはなく、危機管理の甘さが改めて浮き彫りになった。【川辺康広】
事故は95年7月12日夜、東京都多摩市東寺方のアパートで発生。一家6人がめまいや吐き気を訴えて病院に搬送された。いずれも症状は軽かったが、警視庁は、換気せず湯沸かし器を使用したことによるCO中毒と断定した。
使われていたのは不完全燃焼防止装置が付いていない「RU-5E」(83年1月~87年2月製造)。ほぼ同タイプの「RU-5EX」と合わせ約55万6000台が販売された。同社は、事故5日後、プロパンガス事業者を通じ事故概要を把握したが、社員を現地に派遣して原因を究明したり、ユーザーに注意喚起するなどしなかった。事故は製品管理に当たる品質保証部に報告しなければならないが、商品開発部で止まっていたという。
同社は、社長の交代に伴う組織改革で、昨年1月に事故情報を集約するため「QI(品質情報)センター」を設置した。しかし、同事故や東京都中野区で92年12月に弁護士一家5人が死亡した事故などの記録は引き継がれていなかった。
同社総務部は「情報管理がずさんだった。QIセンターの社員を増やし再発防止を徹底したい」と話している。
番組ねつ造:担当ディレクターに責任押しつけ…関テレ 02/15/07(毎日新聞)
ねつ造行為の多くは担当ディレクターによる独断で、単独で行われた--。関西テレビ(大阪市北区)のねつ造問題で、14日に全容が明らかになった総務省への報告書からは「ねつ造の実行行為者」とされる孫請け制作会社「アジト」の担当ディレクターに責任を押しつける関テレの姿勢が浮かび上がる。
報告書によると、担当ディレクターは05年にはチーフディレクターとして番組制作の指導的な役割を担うようになった。
ねつ造した今年1月7日放送の「納豆ダイエット」で、06年12月6日の海外ロケで予定していた米学者のインタビューが取れなかった。
「どうしようかな、やばいな」と思った一方で、「ボイスオーバー(元音声と別に音声を入れ、元音声は聞こえにくくなる)でかけてしまえばいいやとどこかで思っていた」と振り返る。最終的には「これでいくしかない」という開き直りともとれる心境を述べている。架空のコメントを入れたことには「戻るに戻れないという気持ち」と説明した。また、やせたことを示すのに別人の写真を使用したことも「仮のつもりでインターネット上のものを使った。さすがにまずいと思って、過去の取材の写真に差し替えた」と明かした。
海外ロケから帰国4日後の12月12日にオフラインチェックと呼ばれる編集されたVTRを関テレのプロデューサーらが確認する予定など、放送に向けて番組制作の日程が目白押しだったことが背景にはあった。
また、1月7日の放送を関テレは「1月の第1回で、当社にとって戦略的に重要視されていた枠」と説明。競合する他局の番組とのし烈な視聴率競争の中で、周囲の期待を集めた企画だったことをうかがわせ、担当ディレクターもそれを強く意識していたとした。
一方、「リサーチ及び企画の立案に時間をかけることができるように8~9班の制作チームを組んで、内容の真実性の保証についての一次的責任は各制作チームが負っていた」と関テレがねつ造の責任を下請け、孫請けに押しつけるかのような記述もある。番組編集の最初の工程である「オフライン編集」を「極めて重要な工程」と位置づけながらも「制作プロダクションの多くはディレクターの単独作業で、今回の問題の多くもこの段階で発生した」と、傍観者のような記載もあった。
番組ねつ造:知りつつも通報せず 関西テレビの孫請け会社 02/14/07(毎日新聞)
関西テレビ(大阪市北区)が「発掘!あるある大事典2」のねつ造問題で総務省に提出した報告書で、最初に問題が発覚した「納豆ダイエット」(1月7日放送)について、孫請けの制作会社「アジト」(東京都品川区)の社長には事前に同社のディレクターからねつ造の報告があったのに、社長が関西テレビや元請けの「日本テレワーク」(同品川区)に通報していなかったと記載していることが新たに分かった。また、日本テレワークにはコンプライアンス(法令順守)担当がいたが、形式的な対策だけで、番組内容のチェックをしていなかったとしている。
報告書によると、ねつ造はアジトのディレクターが行い、同社長は報告を受けながら制止・通報しなかったと記載している。関西テレビや日本テレワークのプロデューサーは「ねつ造はあり得ない」と信頼し、ビデオ上の演出や字幕、発言が的確かどうかだけをチェックしていたという。
日本テレワークでは2年前、テレビ東京の「教えて!ウルトラ実験隊」でもねつ造問題を起こし、コンプライアンス担当を置いたが、その役割は放送後のトラブル対応が主で、番組内容のチェックまでは行っていなかったとしている。
今後の再発防止策としては、ロケ収録に社員立ち会いを義務づけたり、外部の専門家を置くなどの番組監修者の充実・強化も記している。
報告書の内容について、隅井孝雄・元京都学園大教授(国際メディア論)は「関西テレビが番組の点検も監督もせず、責任を放棄していたことを意味する内容だ。本社は大阪なのに、東京で制作したため、管理監督の体制が不十分だったのではないか」と話している。
関西テレビは報告書の内容を報道機関に一切明らかにしていない。総務省は「事実をねじ曲げたかどうかの検証が十分でなく、再発防止も具体的なものがなかった」として今月末までの再報告を求めている。
データ改ざん:東電と関電がプログラム導入 02/14/07(毎日新聞)
東京電力と関西電力は14日、両社のほぼすべての水力発電所300カ所以上で、発電出力が国に届け出た最大出力を上回っても、常に最大出力以下となるようデータを改ざんするコンピュータープログラムを導入していたと発表した。東電ではほぼすべて、関電では8割の発電所で、プログラムに基づいて改ざんされていたとみられる。両社とも安全性に問題はないとしているが、報告を受けた国土交通省は「あってはならないこと」として、15日にも電力各社に同様の事例がないか調査・報告を求める。
水力発電は、大雨や水面の波立ち、測定誤差などで一時的に最大出力を1%ほど超えることがある。運転は水力発電所を数カ所まとめた「制御所」で管理され、両社はここのコンピュータープログラムを、超過分を切り捨て、ちょうど最大出力と記録するよう設定していた。水力発電所は、発電出力から取水量を計算することが多く、結果として大半で、国交省に取水量を虚偽報告していた。
東電は1981年度以降順次、全19制御所にこのプログラムを組み込んでいたが、04年度までにすべて削除した。取水量の虚偽報告は、東電の全161水力発電所のうち131カ所に達した。
関電は、本社の定めた「標準仕様」として、全30カ所の制御所に1973年度から順次プログラムを組み込み、昨年11月までに削除した。取水量の虚偽報告は、別の方式での改ざんも合わせて、遅くとも65年から続き、全148水力発電所中125カ所あった。
改ざん理由について、東電は「超過が発電所の運転日誌に残るのを嫌ったようだがはっきりしない」。関電は「誤差程度の超過だと安易に扱い、問題意識を持たずに続けてきた」としている。【高木昭午】
朝日新聞(2007年2月14日)より
上場維持へ改革姿勢 日興、内部管理を強化 米国流監視、機能せず

激務でうつ病に…整備士、ANA子会社に賠償求め提訴 02/09/07(読売新聞)
ANA子会社の「エアーニッポン」(東京都港区)の整備士配置が不十分で、激務のためにうつ病になったとして、神奈川県の男性整備士(42)が9日、同社を相手取り、治療費や慰謝料など約2330万円の損害賠償を求める訴訟を横浜地裁に起こした。
原告代理人によると、整備士が航空会社の安全管理体制を指摘する訴訟を起こすのは異例という。
訴えによると、男性は2000年に鹿児島空港の同社事務所に配属されたが、離陸前の航空機整備で、1機に整備士1人しか配置されず、機体の到着が遅れた際は3機同時に整備させられることがあった。冬場の除霜作業の時間が取られておらず、整備時間を削って充てることもあった。
会社は定時運行を要求するだけで、不具合が見つかった際の支援要員の配置もなく、激務と精神的重圧から、男性は01年以降うつ病を発症して計3回休職した。
男性は「会社は目先の利益を追求し、乗客の安全をないがしろにしている。いつ重大事故が起きてもおかしくない」と話している。
エアーニッポンは「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
朝日新聞(2007年2月2日)より
止まらぬ日興不信 新たな水増し疑惑
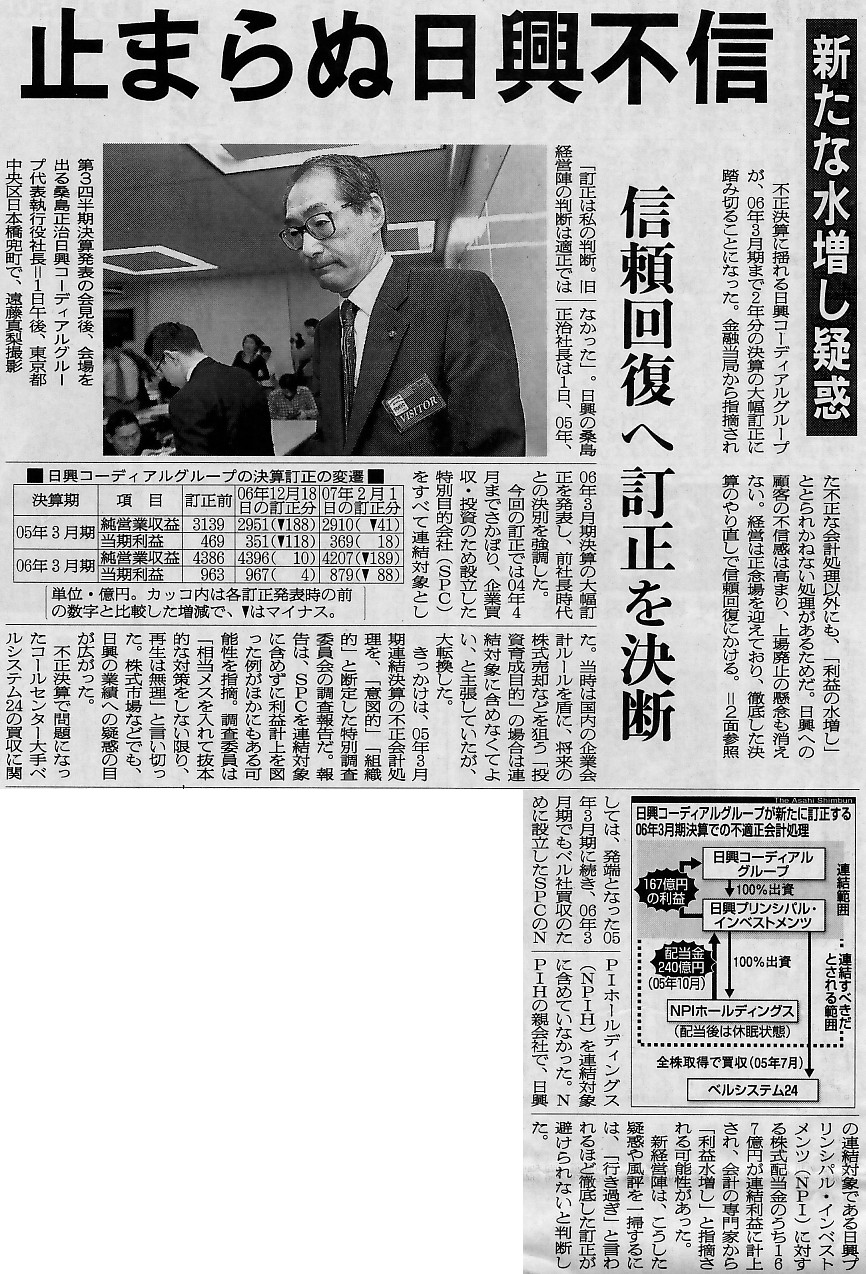
不二家:品質管理の国際規格、3工場で基準満たせず 01/31/07(毎日新聞)
消費期限切れ原料の使用などで揺れる大手菓子メーカーの不二家は31日、小売り向けの一般菓子の3工場が既に取得している品質管理の国際規格「ISO9001」について、検査機関のSGSジャパンの再審査を受けた結果、基準を満たせなかったことを明らかにした。不二家は再審査を「お墨付き」にして、店舗から不二家商品を撤去している大手スーパーなどに早期の販売再開を働きかける方針だったが、基準を満たしていないことが改めて分かったことで、再開時期が遅れるのは必至となった。
再審査を受けたのは、「ルック」チョコレートなどを作る平塚工場(神奈川県平塚市)▽「カントリーマアム」などを作る秦野工場(同県秦野市)▽「ミルキー」などを作る富士裾野工場(静岡県裾野市)。民間の検査機関に臨時審査を依頼し、立ち入りの審査などを受けた。しかし、30日、一部の審査項目について「さらに再審査の必要がある」との報告があったという。不二家は指摘を受けた項目の改善内容を1カ月以内に報告し、再度審査を受ける。
不二家広報室は「ISO9001の認証がはく奪されたわけではなく、指摘された部分の改善を急ぐ」と話している。【宮島寛】
不二家:消費期限延長は食品衛生法違反 厚労省が見解 01/29/07(毎日新聞)
不二家泉佐野工場(大阪府泉佐野市)がシュークリームの消費期限を社内基準より1日長く表示していた問題について、厚生労働省は「基準に合う表示を義務付けた食品衛生法に違反する」との見解を大阪府と埼玉県に伝えた。両府県は今後、この見解も参考にして行政処分の是非などを判断する見通し。
この問題で大阪府が厚労省に対し、法令解釈の照会をしていた。厚労省は「科学的な根拠などがなく、期限を延長した場合、食品衛生法に違反する」としている。不二家は埼玉工場でも消費期限を長く表示したケースが発覚している。【玉木達也】
朝日新聞(2007年1月28日)より
三菱UFJ銀、行政処分 金融庁方針「飛鳥会」不正に関与

不二家:泉佐野工場が細菌検査を省略 01/26/07(毎日新聞)
不二家泉佐野工場(大阪府泉佐野市)が必要な細菌検査を省略し、細菌数が不明のままケーキなど洋菓子約2万5000個を販売していたことが26日、同工場が大阪府に提出した報告書で明らかになった。大腸菌群や黄色ブドウ球菌についても、厚生労働省は検出されれば販売しないと定めているが、同工場はマニュアルで「1グラム当たり大腸菌群10万個以上、黄色ブドウ球菌1000個以上を回収」と、極めて甘く定めていた。ずさんな衛生管理の実態がさらに判明したことを受けて、府は、29日に異例の再度の立ち入り検査を行う。
02年に作成された社内マニュアルによると、同社は主に一般生菌、大腸菌群、黄色ブドウ球菌の数について出荷後に検査を実施。菌の多さによって(1)現場注意・改善(2)工場長に報告(3)回収--の3段階の対応を規定している。
しかし、同工場では、2~4通りある検査のうち、最も低いレベルの検査しか行わないケースが多かった。昨年5~9月に実施した9回の生菌検査では、さらにレベルの高い検査が必要とされる基準値を上回ったイチゴパフェなど計約2万5000個について、再検査せずに販売していた。
いずれの検査票も工場長印があり、工場の担当者は「大半が一番低いレベルだけで基準をクリアしていたので、手を抜くようになった」と説明したという。
一方、大腸菌群について、府の指導指針は1グラム当たり1万個未満。不二家本社も同じだが、泉佐野工場はその10倍を許容するマニュアルで運用していた。工場関係者は「なぜか分からない」と答えたという。【大場弘行】
三菱UFJ銀:「飛鳥会」不正関与で行政処分検討 金融庁 01/27/07(毎日新聞)
財団法人「飛鳥会」の元理事長が大阪市から管理を受託した駐車場の収入を横領していた事件にからみ、金融庁は、三菱東京UFJ銀行が長期にわたって元理事長の不正にかかわったとして、行政処分を出す方向で検討に入った。同行は理事会に行員を常駐させていたほか、横領した元理事長側に数十億円の融資を行っており、一部業務の停止も含めた厳しい処分が出る可能性もある。
関係者などによると、三菱東京UFJの前身の三和銀行淡路支店が84年ごろから、歴代の法人営業課長を同会に経理担当として常駐させ、同会が管理する駐車場の収入を理事長だった小西邦彦被告の口座に振り込むなどした。また、同行と関連ノンバンクから、小西被告側に数十億円の融資をしていた。同行などは、これらの融資が未回収になっているとして返還を求める訴訟を起こしている。小西被告は24日に業務上横領と詐欺の罪で懲役6年の実刑判決を大阪地裁から受けた。
金融庁は、大手銀行が犯罪行為を行った元理事長と長期にわたって不透明な関係を続け、行員が不正にかかわったことなどについて、重大な法令順守体制の欠陥があったとみて、厳しい行政処分を検討している。【坂井隆之】
不二家:埼玉工場 ネズミ、実は485匹捕獲 内部文書 01/26/07(毎日新聞)
消費期限切れ原料使用が問題になった大手菓子メーカー、不二家の埼玉工場(埼玉県新座市)で、03年1月~昨年8月の約3年半に485匹のネズミが捕獲されていたことが、同社の内部文書で分かった。文書には「ネズミ捕獲がマスコミに漏れた時点で、経営危機、破たんは免れない」と記されていた。同社は消費期限切れ問題で「発覚すれば雪印の二の舞い」などと隠ぺいを図ったとも受け取れる文書が明らかになっており、同社の体質が改めて問われそうだ。
関係者によると、内部文書は社内の構造改革チームの会議に「委員会外秘」として提出された。ネズミのイラストを配して捕獲数を棒グラフで月ごとに示し、03年に109匹、04年に221匹、05年に145匹、06年に10匹が捕獲され、長期にわたり大量のネズミが発生していた。とくに04年は3月から7月まで毎月20匹以上が捕獲され、4月は最高の50匹だった。
同社は問題発覚直後に「埼玉工場で04年に最も多い月で50匹のネズミを捕獲した」ことを明らかにしていたが、この資料をもとにしたとみられる。文書には「至急対策すべき重大事項」とも記載されていた。
同社は現在、外部の有識者による改革委員会を設置するなどして衛生管理体制の改善を図っている。ただ、こうした内部文書で指摘された事実がその後どう取り扱われたかは明確になっていない。【三沢耕平】
朝日新聞(2007年1月25日)より
裏切りの演出 中 下請け限界 無理も承知 (発掘!あるある大辞典II)
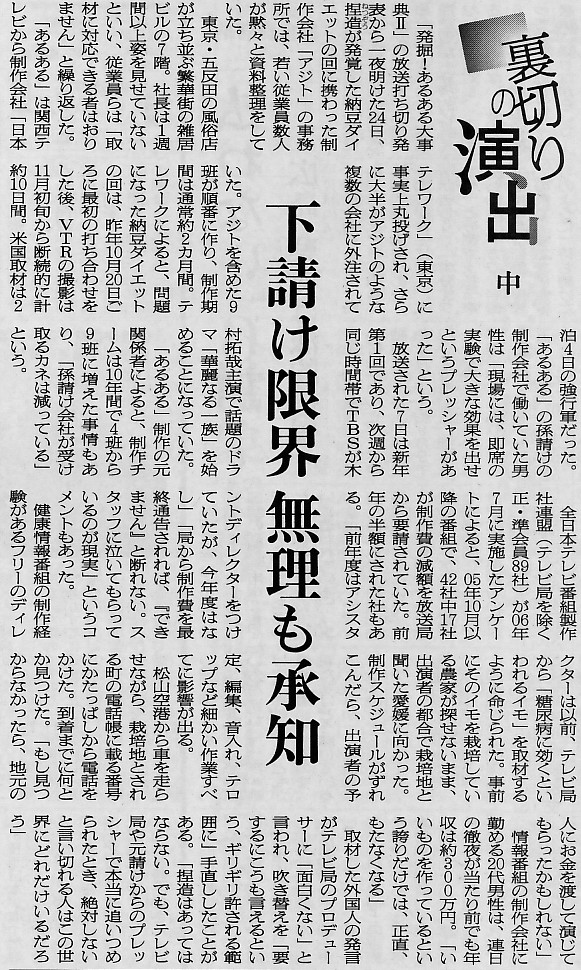
「経済産業省の北畑隆生次官は・・・企業などにISOを付与する民間の認証機関を認定する団体で
ある「日本適合性認定協会(JAB)」に対し、どこに問題があるのか調べるよう要請したことを
正式に明らかにした。」
ISOについて知っている人は問題に気付いている。しかし、「日本適合性認定協会(JAB)」
は現状の問題を正直に報告するのだろうか??
建築確認のイーホームズ、日本ERIを含む民間確認会社や
自治体のチェックの甘さの問題と似たところがある。「うちだけじゃない!!!」のレベルにまで
発展しなければ、経済産業省の北畑隆生次官の調査要請は意味をなさない。
経済産業省の北畑隆生次官は、船舶検査でISOを取得した国土交通省にも連絡を取り、
ISO9000の取得が義務付けられている船舶検査会社が検査した船舶の中で、特定の検査会社
が検査した船の多くが
サブスタンダード船
の呼ばれる船である確率が高い理由を聞くと良い。ISOのマニュアル通りに行えば、このような
結果にはならないはずだが、現実は違う。そして、このような船舶検査会社のISO認定も
取り消されていない。特定の国籍の船舶の検査取消しを旗国から受けても、ISO認定の取消しは
聞いたことが無い。なぜなのか??? 理由を知りたい。しかし、どこも何も言わない。
経済産業省の北畑隆生次官は、問題と原因を公にする必要があると思う。(同じ考えを
持つ人もいます)
不二家のISO認証「非常に問題」と経産次官 01/15/07(読売新聞)
経済産業省の北畑隆生次官は15日の記者会見で、不二家が、品質・環境管理の国際規格「ISO」の認証を受けていたことについて、「非常に問題がある」と述べた。
さらに、企業などにISOを付与する民間の認証機関を認定する団体である「日本適合性認定協会(JAB)」に対し、どこに問題があるのか調べるよう要請したことを正式に明らかにした。
朝日新聞(2007年1月13日)より
不二家問題 「お客様第一」では不十分 日和佐信子 雪印乳業社外取締役
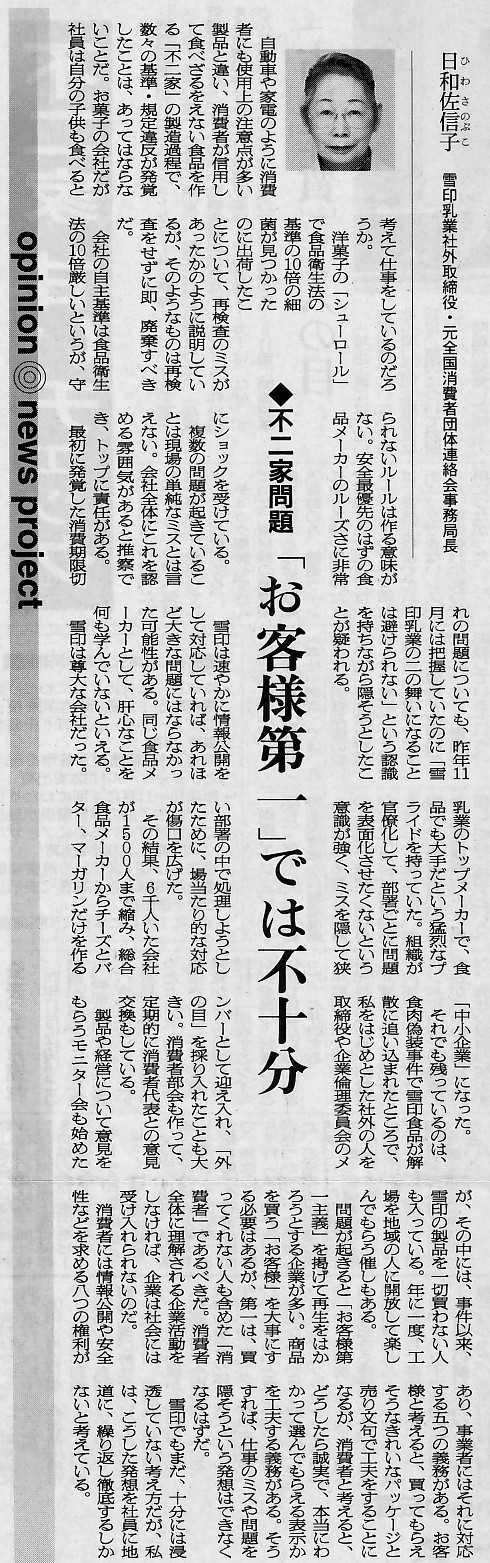
中国新聞(2007年1月11日)より
期限切れ牛乳シュークリーム 不二家、重大性を認識
隠ぺい意図示す内部文書
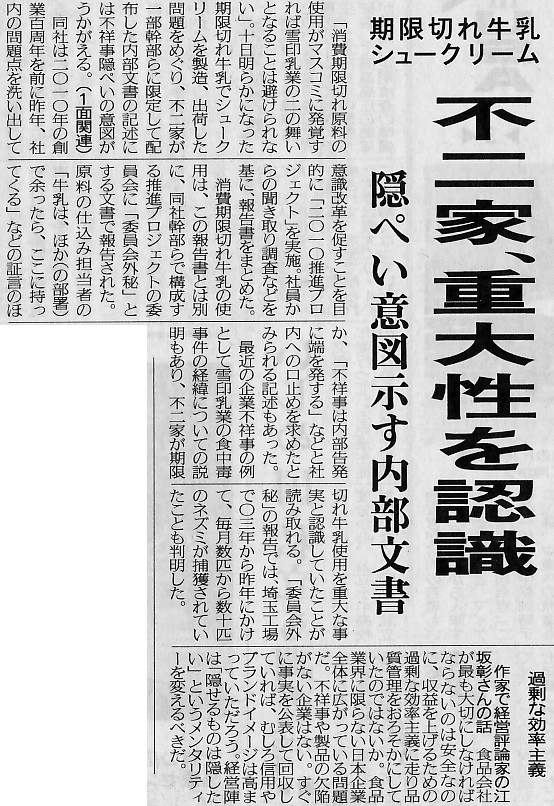
朝日新聞(2006年12月26日)より
中国電相談役3人辞任
社長続投に批判の声 地元「信頼回復ない」
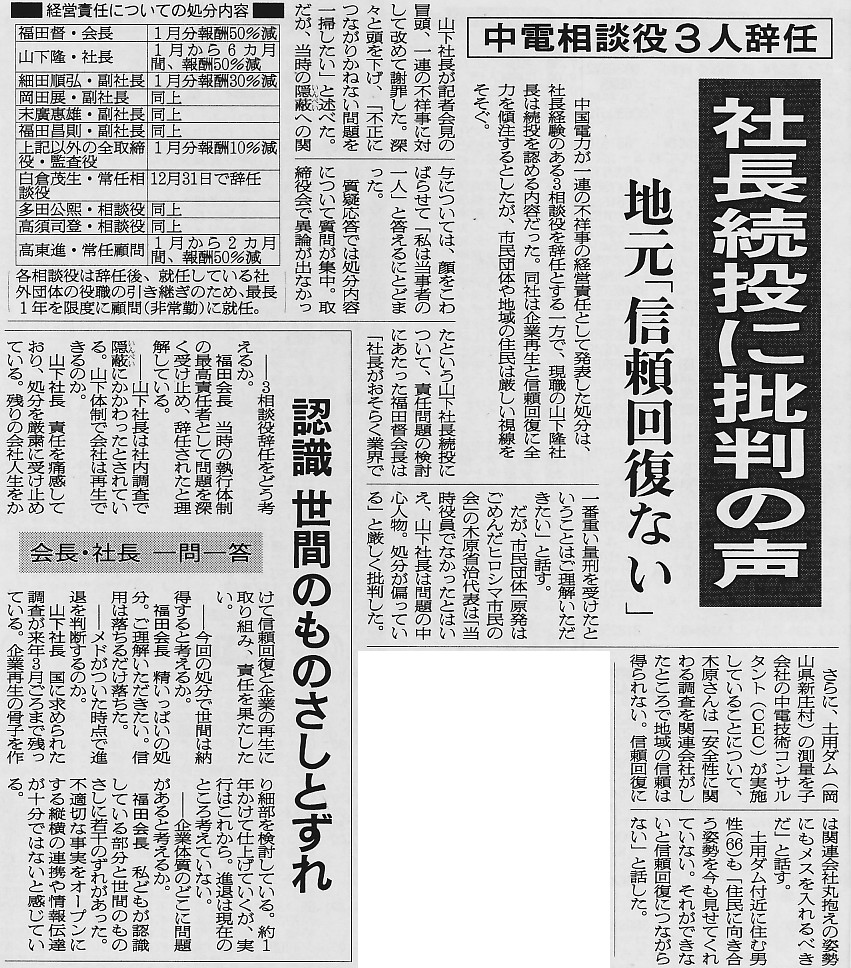
朝日新聞(2006年12月26日)より
日興、組織的不正認める
利益水増し 新社長に桑島氏
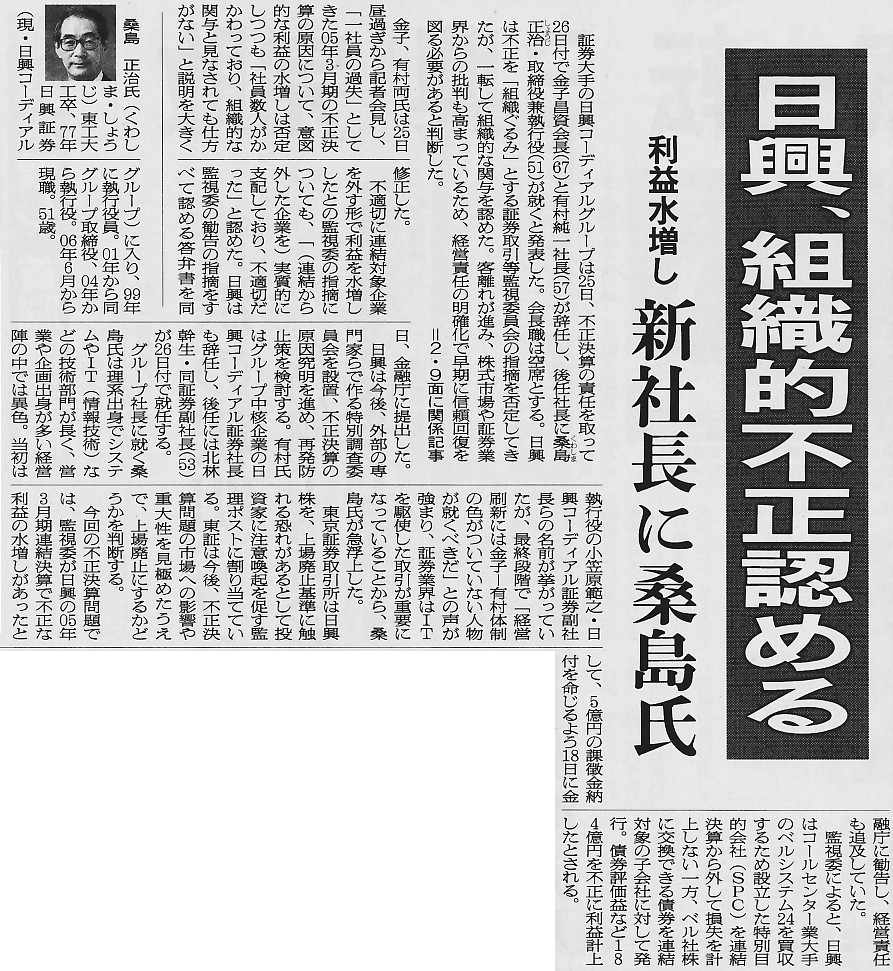
朝日新聞(2006年12月26日)より
大手証券の不正決算の信頼に影
業界厳しい批判
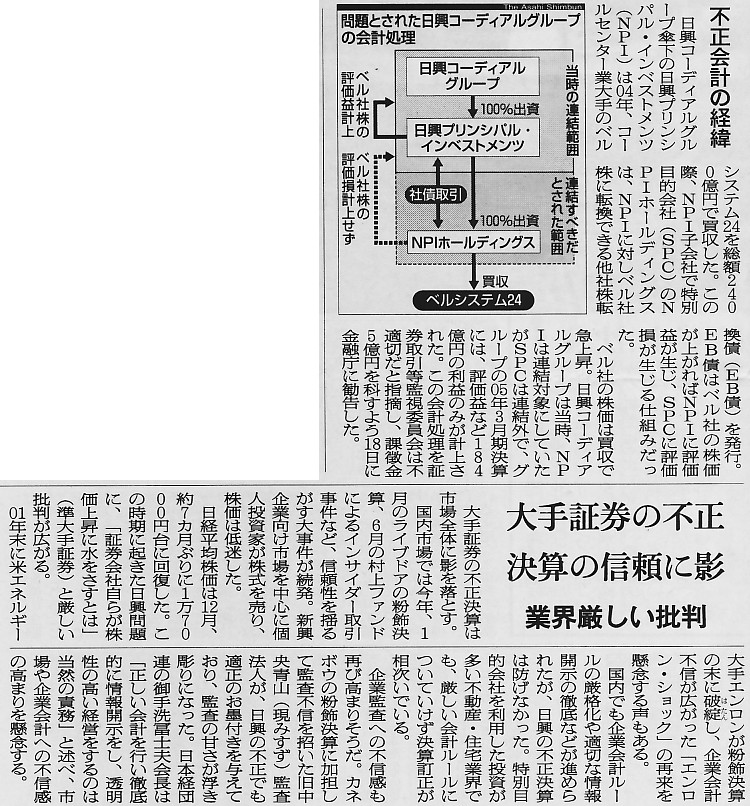
日興コーディアルグループは徹底的にさらなる調査を行い、責任のある幹部には責任を取らせるべき。
尻尾きりを行う企業は潰せ!!
旧中央青山監査法人(みすず監査法人)の体質は変わらないのかもしれない。
長年、粉飾決算を見逃す暗黙の了解が会社に充満しているのかもしれない!
やはり、長年、不正を行う会社や不祥事を見逃す会社の役員や社員は、このような
体質に漬かりすぎてやり直しが出来ないのかもしれない。
日興人事:新社長に桑島氏 有村社長と金子会長は引責辞任 11/25/06(毎日新聞)
日興コーディアルグループは25日、臨時取締役会を開き、有価証券報告書に虚偽記載をした問題で有村純一社長(57)と金子昌資会長(67)が引責辞任し、後任の社長に桑島正治取締役(51)を起用する人事を決めた。就任は26日付。同グループは当初、不正な会計処理は「担当社員が1人で行った」と説明し、担当役員の辞任や社長の報酬減額などの処分を発表したが、投資家や証券業界の信頼を得られなかった。このため、不正に組織的に関与したことを認め、人事刷新でトップの責任を明確にした。会長職は当面、空席とする。
また、外部の専門家らで構成する特別調査委員会を設置し、虚偽記載問題の事実解明を進めることも明らかにした。
桑島氏はシステム分野の経験が長く、今回の不正な会計処理にかかわっていないことに加え、経営トップの若返りを図ることで、不正の再発防止を含む経営体制の刷新をアピールするのに適任と判断したと見られる。
同グループは、虚偽記載を公表した18日の会見で「子会社の投資会社、日興プリンシパル・インベストメンツ(NPI)が04年8月に社債を発行した際、担当社員が正規の手続きを経ないまま翌9月になってミスに気付き、8月に手続きを完了していたように書類を改ざんした」と説明した。
これに対し、山本有二金融担当相が22日の閣議後会見で、不正が組織的だったとの報告を証券取引等監視委員会から受けており「(経営トップの)辞任、解任はありうる」と発言。同グループの対応が注目されていた。【瀬尾忠義】
25日正午過ぎに開いた記者会見で、金子会長は「18日に発表した通り、有価証券報告書を訂正する。すべて認める答弁書を先ほど金融庁に提出した。グループ内の隅々まで内部管理体制が行き届いていなかった。資本市場の担い手として誠に遺憾であり、おわび申し上げます」と陳謝。また、有村社長は虚偽記載について「一個人のミスではない。組織としての管理不徹底が原因」と述べた。
【略歴】桑島 正治氏(くわしま・しょうじ 東京工業大卒。77年日興証券(現日興コーディアルグループ)。グループIT部長などを経て01年10月から取締役。51歳。富山県出身。
朝日新聞(2006年12月26日)より
企業監査また不信
日興首脳陣退陣 旧中央青山責任問題も

日興の会長・社長が引責辞任、新社長に桑島氏が昇格 12/25/06(読売新聞)
日興コーディアルグループは25日午前の臨時取締役会で、不正会計処理問題に会社の組織的な関与があったことを認め、金子昌資会長(67)と有村純一社長(57)が26日付で引責辞任することを決めた。
後任の社長には桑島正治取締役(51)が昇格し、会長は当面空席とする。両首脳の退任で経営トップの管理責任を明確にして、事態の収拾を図る方針だ。
有村社長は同日の記者会見で、不正処理が起きた原因について「一個人のミスではなく、組織としての管理が不徹底だった。数人が一連の行為にかかわっていた」と述べ、会社としての対応に問題があったことを認めた。ただ、「会社として利益を膨らませる意図はなかった」と釈明した。金子会長は「資本市場の担い手の当社がこうした事態を引き起こしたのは遺憾で、申し訳ない」と陳謝した。
桑島氏は理科系の出身でシステム分野の経験が長い。グループの情報システム会社である日興システムソリューションズの会長も兼務している。証券業務の情報技術(IT)化が進んでいるため、システムに精通していることが、後任社長に選ばれた理由という。
後任には、グループ執行役で、傘下の日興コーディアル証券の小笠原範之副社長らも浮上したが、グループ取締役からの選任が適切と判断した。
有村社長は、兼務している日興コーディアル証券の社長も退任する。後任には同証券の北林幹生副社長(53)が昇格する。持ち株会社と証券会社の社長を分けて相互監視体制を強め、不正経理などの再発を防ぐ狙いがある。
不正会計の舞台となった子会社の日興プリンシパル・インベストメンツの城戸一幸社長と、平野博文会長も退任する予定だ。経営体制を刷新し、投資家や顧客の「日興離れ」に歯止めをかけたい考えだ。日興は、外部の専門家を中心とした特別調査委員会を設置し、社内調査とは別に、不正会計処理の原因を究明して、再発防止策を策定する。
日興は来年1月16日までに、東京証券取引所に訂正有価証券報告書を提出する。東証は報告を受け、日興の虚偽記載が上場廃止にあたるかどうか結論を出す。
日興が組織的な関与を認めたことで、決算を適正だとした旧中央青山監査法人(みすず監査法人)の責任問題も焦点となる。
朝日新聞(2006年12月26日)より
電力根深い隠蔽体質 元首脳「おごりあった」
国の目届かず不正温存
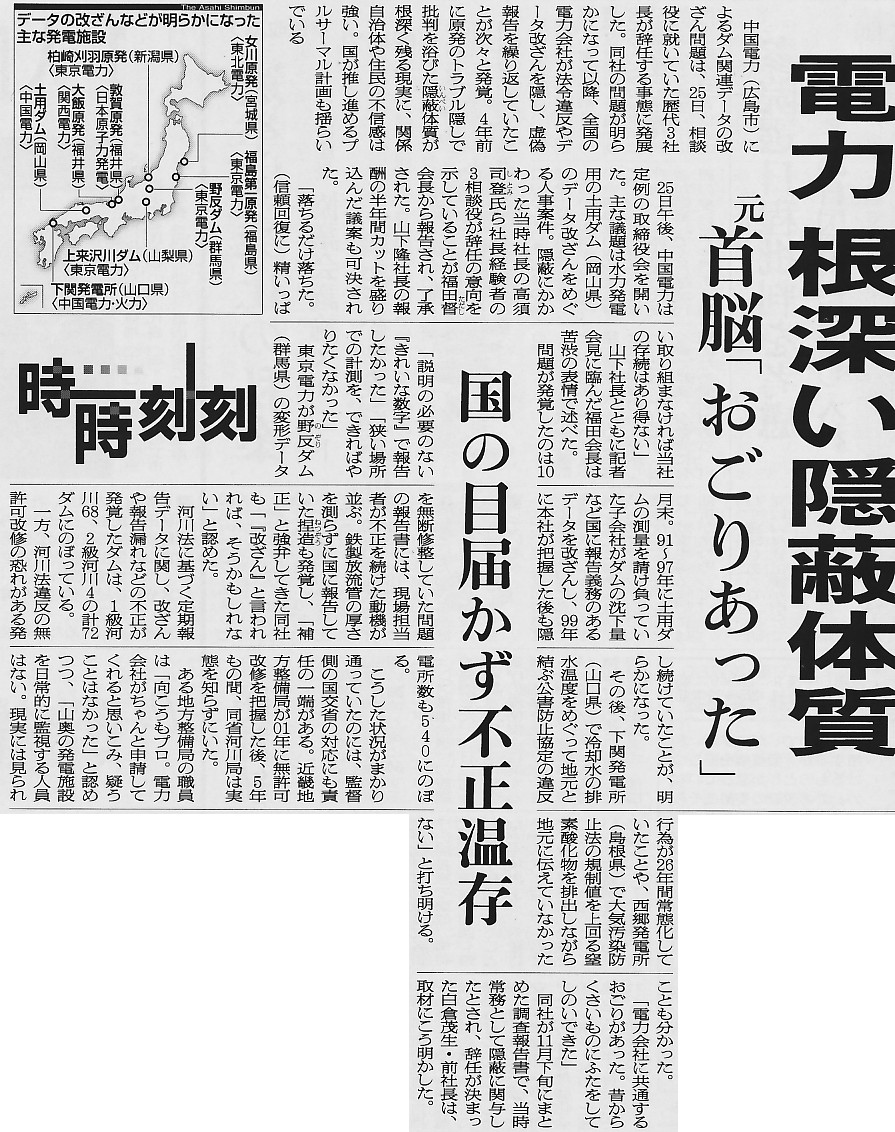
今回の中国電力データ改ざんで多くの企業が似たような体質を引き継いでいる可能性が
高いと実感させられた。また、問題に対する対応も遅く、誠実さに欠けた。
今後も中国電力データ改ざん事件から何も学んでいない企業が似たような問題の発覚で
注目を集めるのだろう。
中国電力データ改ざん、社長経験者3人が引責辞任へ 12/23/06(読売新聞)
中国電力(本社・広島市)が子会社によるダム測量数値の改ざんを知りながら隠ぺいしていた問題で、隠ぺいが社内で決定された1999年当時、社長だった高須司登(しとみ)相談役(74)、会長だった多田公熙(こうき)相談役(83)、土木担当常務だった白倉茂生相談役(70)の社長経験者3人が辞任する意向を固めた。25日の取締役会で報告する。
また、ダムを管轄する鳥取支店長だった山下隆社長(63)ら現経営陣の報酬カットなどの処分も行う。
この問題を巡っては、中国電力の子会社が91~97年、水力発電用の「土用ダム」(岡山県新庄村)で沈下量などの測量データを改ざんしていた。中国電力は11月、高須相談役ら当時の経営陣が知りながら放置していたとする調査報告書を国に提出した。
中国電力3相談役が引責辞任へ ダム測定データ改竄 12/23/06(読売新聞)
中国電力が土用ダム(岡山県)の測定データを改竄(かいざん)、隠ぺいしていた問題で、同社が隠蔽(いんぺい)を決めた平成11年当時社長だった高須司登前会長(74)と、土木担当常務だった白倉茂生前社長(70)、会長だった多田公熙氏(83)の3人が23日までに、責任を取り相談役を辞任する意向を固めた。
ダムを管轄する鳥取支店長だった山下隆社長(63)は続投する見通し。
問題は、子会社「中電技術コンサルタント」が平成4-9年ごろにかけて、土用ダムの堤の高さの変化を測った「沈下量」などのデータを、数値にほとんど変化がないように改竄、中国電力がそのまま国に報告していたことが10月、内部告発で発覚した。
国の指示を受け、同社は社内調査を実施。11月にまとめた報告書は、高須前会長や白倉前社長、山下社長ら幹部が改竄を把握したうえで、社として隠蔽を決めていたと結論づけた。誰が隠蔽を指示したかは不明としながら「問題の解決に向け、取り組みを行わなかった責任」などがあったと指摘した。
「指示者は『分からず』」でも良いけれど、問題があっても上に上げられない
体質が中電にはあると言っているのと同じである。国はそれで良いなら
原発に問題があれば、誰に責任を取らせるのか、規則や法を作るべき。
中国新聞(2006年12月22日)より
水温計不正80年から
下関発電所 中電最終報告 指示者は「分からず」
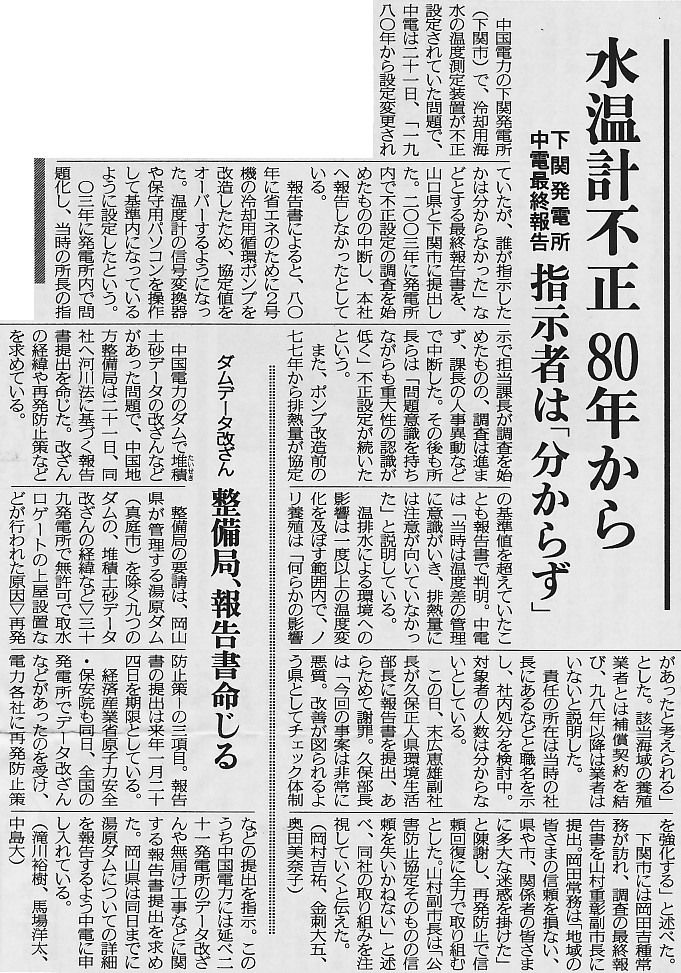
中国新聞(2006年12月15日)より
追跡2006 中電不祥事
巨大企業のきしみ噴出

朝日新聞(2006年12月7日)より
中国電力改ざん 「当時の社長、隠蔽決めた」
前社長、国に反論書
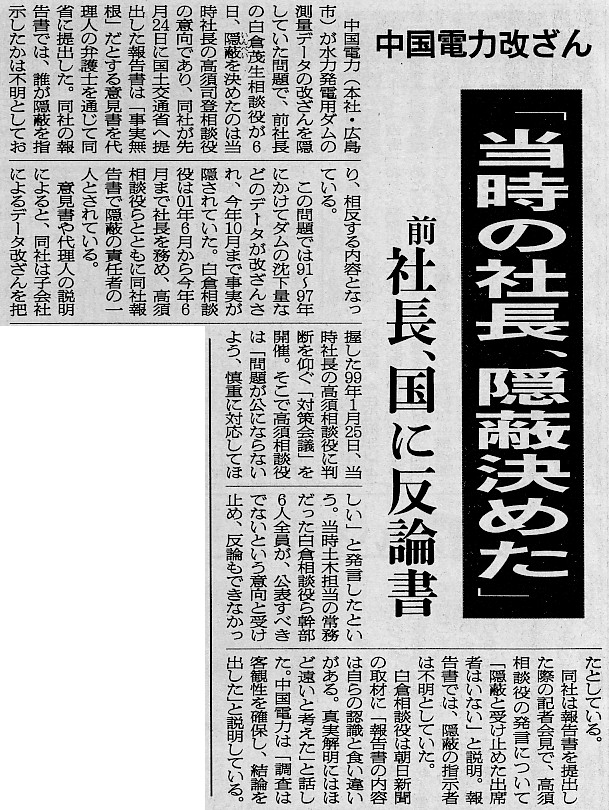
東電、福島第一原発でもデータ改ざん 20年前からか 12/05/06(朝日新聞)
東京電力は5日、福島第一原発1号機(福島県大熊町)の定期検査などで、温排水の温度を実際より1度低く記録して国に報告していた、と発表した。データ改ざんは約20年前から続いていた可能性がある。東電では11月末、柏崎刈羽原発1、4号機(新潟県柏崎市)で同様の排水温の改ざんが発覚したばかり。「ほかでは不正はない」としていたが、その後の調査で覆った。安全上の問題はないが、同社の体質が問われそうだ。
経済産業省原子力安全・保安院は「検査の判定には影響しないが、あってはならないこと」として、ほかの原発でも改ざんがなかったか、来年1月末までに調査結果を報告するよう電気事業法(報告徴収)などに基づいて東電に指示した。
東電によると、タービンの安全状態を示す指標として、冷却用海水の取水口側と放水口側で水温を測定し、その平均値を国に報告している。今月末の定検を前に、計測装置を管理する東芝の技術者がプログラムを分析したところ、発電所の仕様書と異なり、排水側の水温の平均値を1度低くするデータ操作が見つかった。東芝の記録では、不正な処理は88年に東電の指示で行われ、「93年に東電に報告済み」との記載もあったという。
1号機は設計上、海水温の温度差を9度以内と想定しているが、定期検査など安全上の点検項目には含まれておらず、改ざんした理由は現段階で分かっていない。
周辺の漁場や生態系への影響を評価するため、福島県に報告している排水温のデータは別に測定しており、そちらには改ざんはなかったという。
逃げ切れると思ったのか、山下隆社長は!それともこれまで、過去の社長達は
不都合なことを隠蔽したのか?いろいろな憶測が出来る展開だ。
緊急対策本部長の福田昌則副社長は真実を確認できなかったのか、それとも、
組織的に行われたことへの本当の調査は出来ないことを知りつつ対応したのか?
全ては今後の調査結果と国土交通省の対応次第だろう。
多くの人は中国電力が情けない対応をとったと思っているだろう。
朝日新聞(2006年11月25日)より
中国電力 社長、隠蔽支持認める
改ざん問題 支店長時代に決済
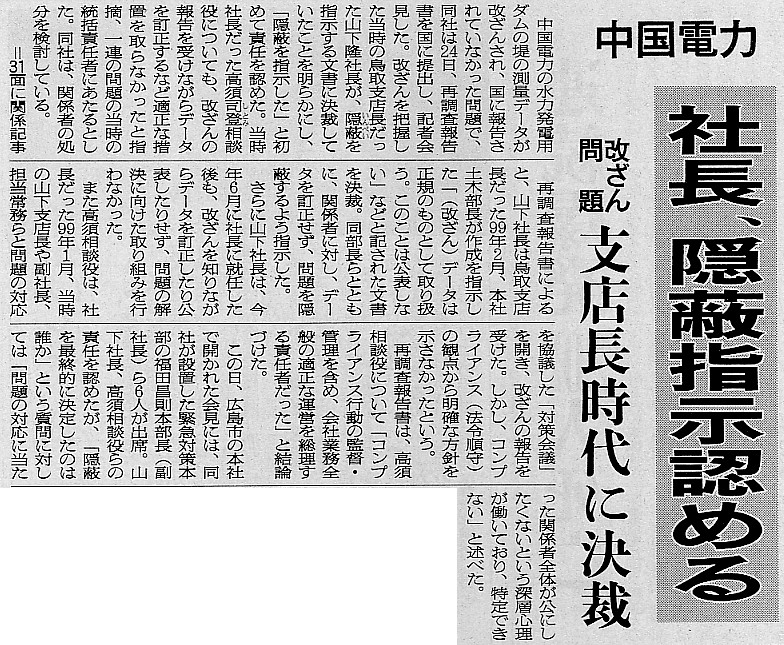
朝日新聞(2006年11月25日)より
中国電力改ざん 隠蔽決定いつだれが?
再調査、核心迫れず
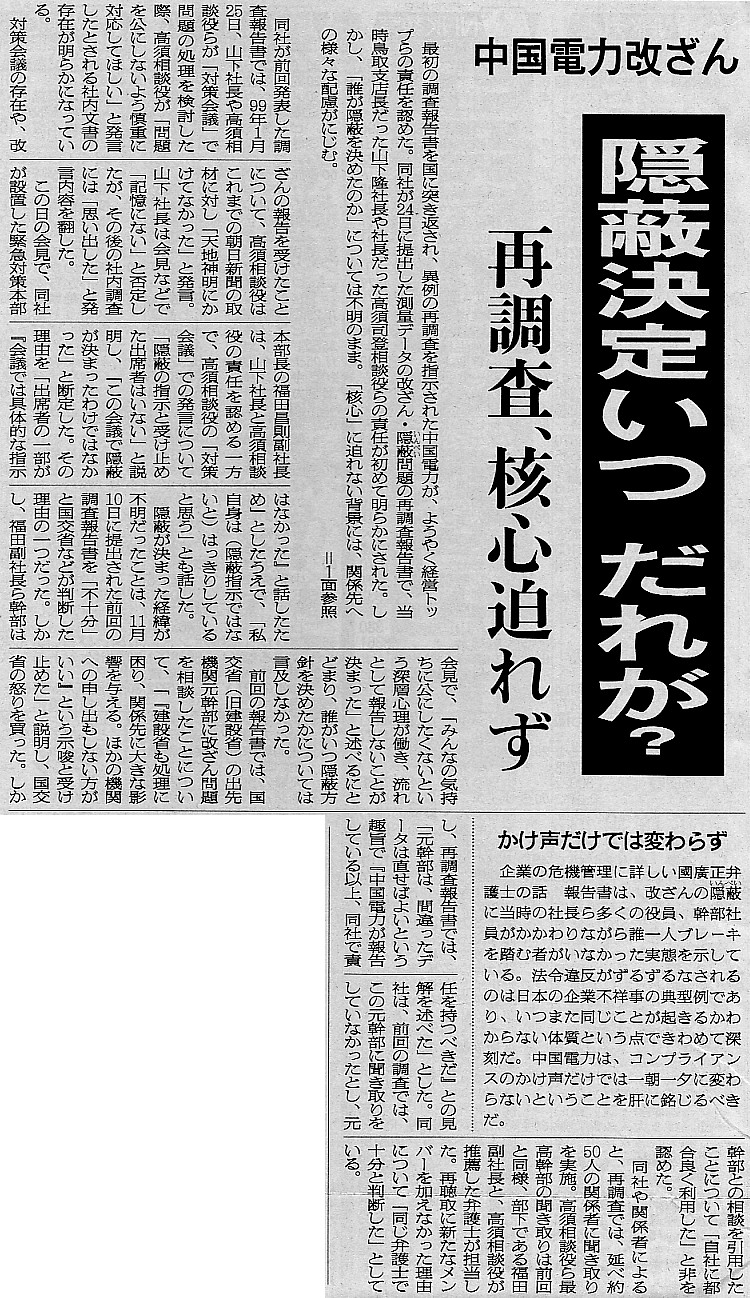
ダム:東電に使用停止命令 国交省「安全確認できない」 11/24/06(毎日新聞)
電力会社が国に無許可で水力発電所の改修工事をしていた問題で、国土交通省は24日、東京電力に対して「小武川(こむかわ)第3発電所 上来沢川(かみくりざわがわ)ダム」の使用停止を命じた。「安全性が確認できない」との理由で、河川法に基づく措置。一連の問題で使用停止になったのは初めて。
問題の工事は97年3月、堤(高さ約19メートル、幅約50メートル)を貫通させた土砂排出用トンネル(直径約1.5メートル)が、土砂で詰まり機能しなくなったため、コンクリートで埋めたうえ、別のトンネルを設置していた。同省は「大規模改修なのに安全性が未確認だ」と判断。今後、設計図や資料と照合して安全性を見極める。
発電所は出力2000キロワット。山梨県北部の700世帯に電力供給しているが、使用停止後はほかの発電所から供給するため影響はない。同社は「国の措置を重く受け止めて、適切な管理に努めたい」とコメントしている。【種市房子】
朝日新聞(2006年11月19日)より
隠蔽する体質なぜ直らない
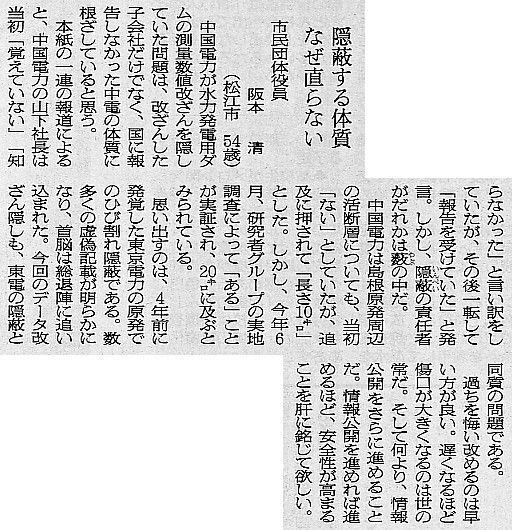
中国新聞(2006年11月15日)より
データ改ざん 調査報告書 中電に再提出要求
中国地方整備局 「客観性が不足」
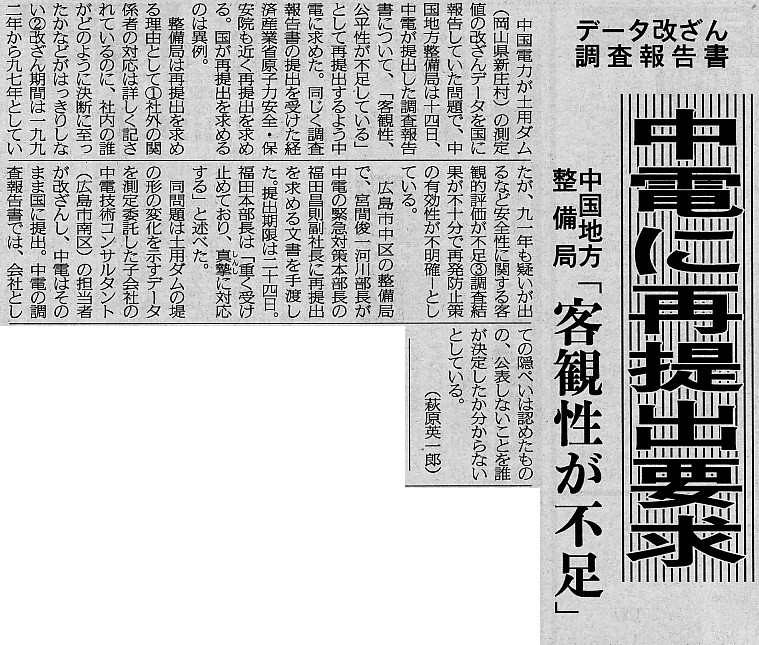
朝日新聞(2006年11月12日)より
改ざん隠し 社員にも不信広がる
中国電 経営陣へ批判も
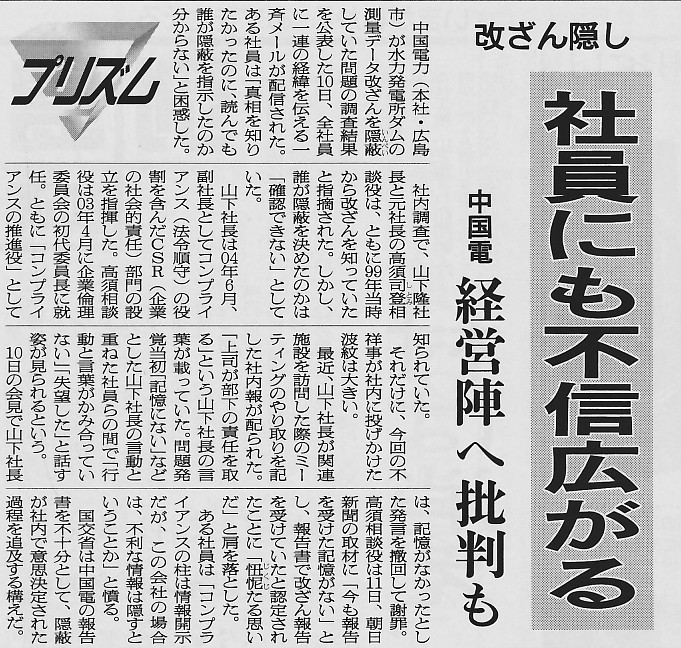
朝日新聞(2006年11月11日)より
中国電力データ改ざん隠蔽 会社ぐるみ認める
国へ報告書
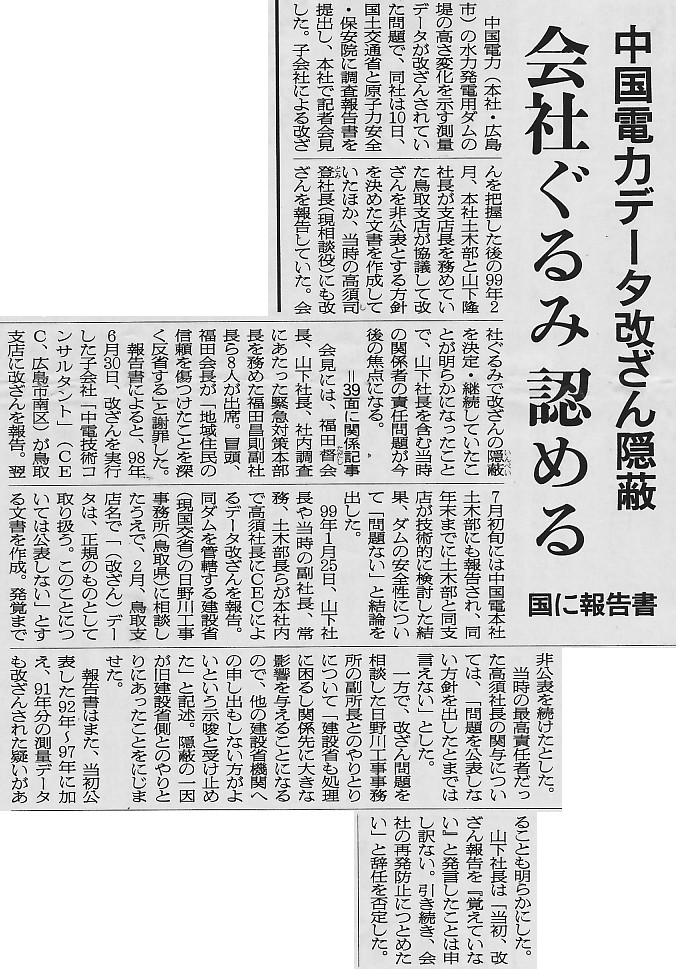
中国新聞(2006年11月11日)より
中電ダム測定値改ざん
社全体で隠ぺい 報告書国に提出 指示者は「不明」
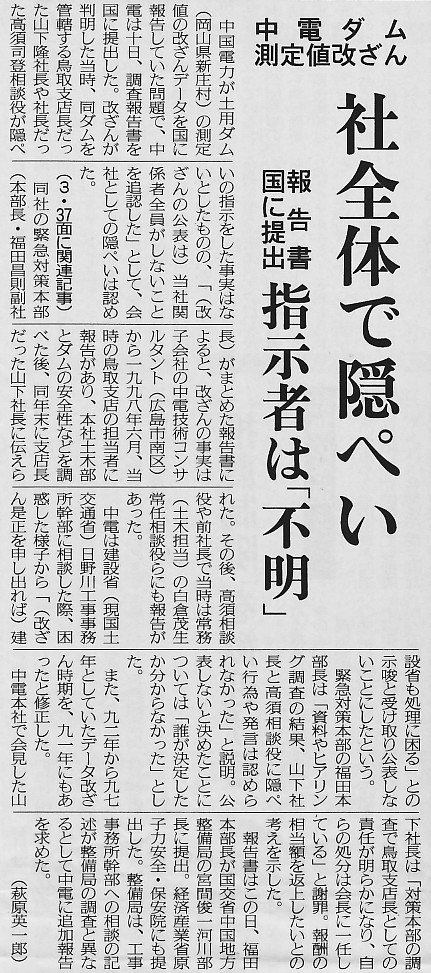
中国新聞(2006年11月11日)より
中電改ざん隠ぺい
企業倫理希薄だった 社長ら会見し謝罪
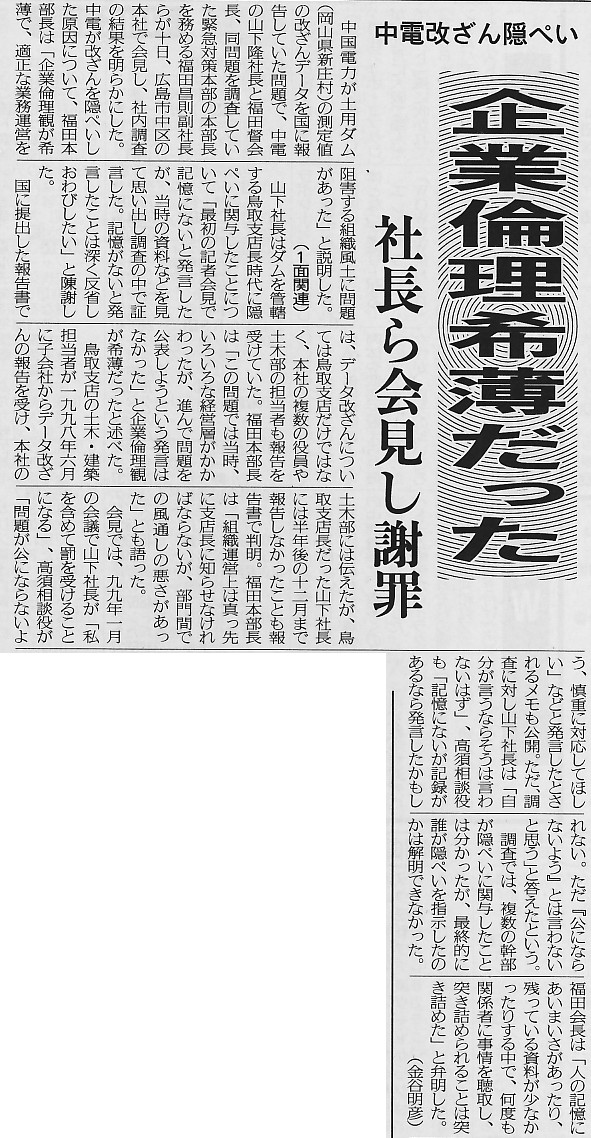
中国新聞(2006年11月11日)より
中電測定値改ざん報告書
あいまいさ残る内容 信頼回復へ真摯な姿勢を
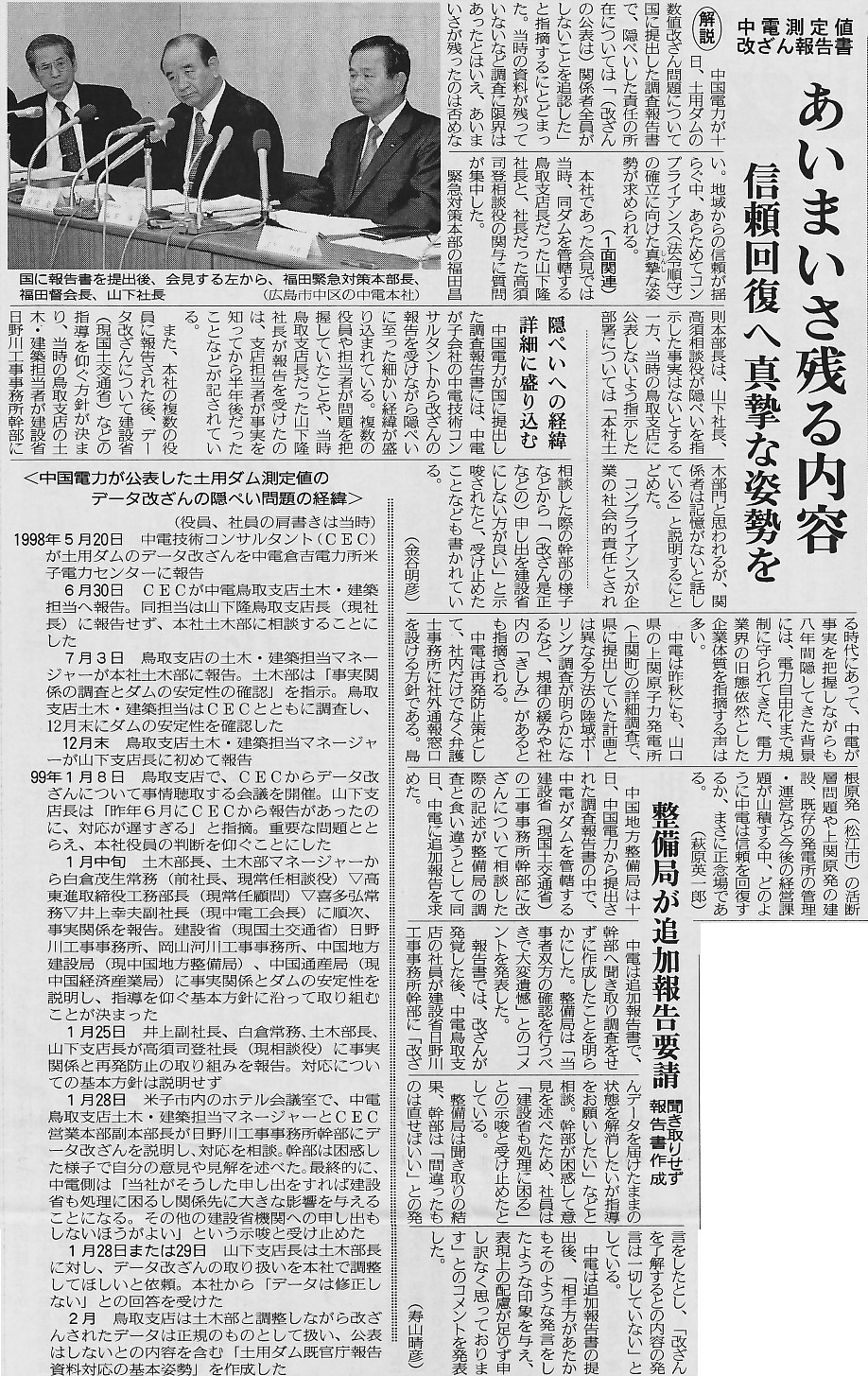
朝日新聞(2006年11月11日)より
中国電改ざん隠し 「確認できず」連発
元社長の責任否定 信頼一層失う調査結果

恥の上塗りはやめた方が良い! 中国電力が組織的に隠蔽するような重大な事を
覚えていないような社長に的確で正しい判断が出来るのか??
経験や知識の蓄えが出来ない社長はふさわしいのか??
言い訳が思いつかないから、思い出せないが言い訳!これで国土交通省も納得するのでしょうか??
このような体質の会社が原発で問題を起したらどのような対応をするのでしょうか?
隠せるところまで隠蔽し、時が経てば記憶に無い!会社の体質が変わる保証はないが、
やはり隠蔽が発覚した以上、社長は交代するべきだ!
中国電社長もデータ改ざん把握 「記憶なかった」と謝罪 11/10/06(読売新聞)
中国電力(広島市)が土用ダム(岡山県新庄村)の改竄(かいざん)データを国に報告していた問題で、同社の緊急対策本部は10日、当時ダムを管轄する鳥取支店の支店長だった山下隆社長や、当時社長だった高須司登相談役ら幹部が改竄を把握しながら、社として隠蔽を決めていたとする社内調査結果を公表した。
山下社長は問題が発覚した10月31日の会見で「当時のことは記憶にない」と話していたが、「資料を見て思い出した。深く反省している。社長として再発防止策の策定が責務と考えており、けじめとして報酬を相当額返上したい」と述べ、辞任の考えはないことを明らかにした。
緊急対策本部長の福田昌則副社長は「関係者の記憶があいまいで(隠蔽を)決めた詳しい経緯は分からない」と説明。山下社長や高須相談役が会議で「タイミングが悪い」「罰を受けることになる」などと発言したとされるメモを公表したが、いずれも隠蔽指示はなかったとしている。
同社は、関係者の処分を早急に決める方針。「ダムの安全性に問題はない」という。
朝日新聞(2006年11月9日)より
中国電改ざん 「隠蔽会議」に議事録
同社の対策本部入手

中電、事実把握も「公表せず」 ダムのデータ改ざん問題 11/08/06(読売新聞)
中国電力(広島市)が土用ダム(岡山県新庄村)の改竄(かいざん)データを国に報告していた問題で、同社が改竄の事実を把握した上で公表しないと決めていたことが8日、同社緊急対策本部の社内調査で分かった。
同社は測量を委託した子会社「中電技術コンサルタント」からの報告を受け対応を協議したが、元の測量データが確認できないことなどから、公表しないと決めたという。
ダムを管轄する鳥取支店の支店長だった山下隆社長は、問題が発覚した10月31日の記者会見で「当時のことは記憶にない」と説明していた。対策本部は引き続き山下社長の関与を調べている。
問題は、平成4-9年のダムの沈下量などの測量値が改竄されていたことが10年、コンサル社の内部調査で発覚した。
中国電力は10日にも国土交通省や経済産業省に社内調査の結果を報告する。
朝日新聞(2006年11月6日)より
中国電改ざん 社長「報告受けた」
鳥取支店長当時「記憶ない」、一転
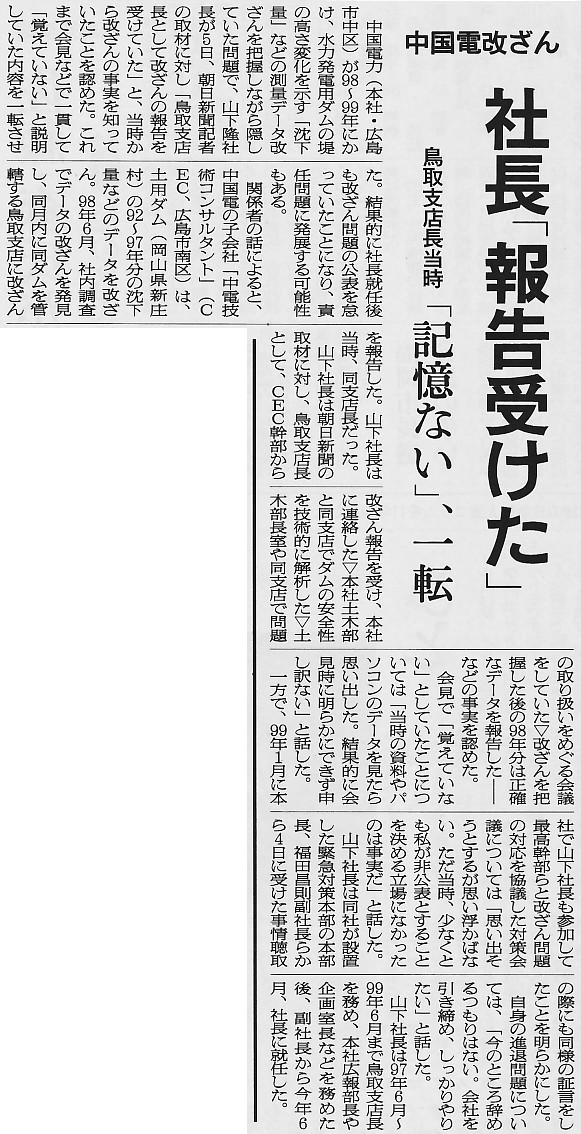
山下隆社長は「自身の進退問題については、『今のところ辞めるつもりはない。会社を引き締め、
しっかりやりたい』と話した。」
山下隆社長は、辞めるしかないだろう。人間的な常識が欠けるトップでやるのか。
まともな判断や決断は出来るのか??責任逃れの言い訳に聞こえる!
「99年1月に本社で山下社長も参加して最高幹部らと改ざん問題の対応を協議した対策会議については
『思い出そうとするが思い浮かばない。ただ当時、少なくとも私が非公表とすることを決める立場に
なかったのは事実だ』と話した。」
副社長でも非公表とすることを決める立場でもなく、今年6月に社長になっても公表を決める立場で
ないのなら、誰が決める立場なのか?これ以上、恥をかく前に辞任したほうが良いだろう!
それとも、上が決めたら自分の判断、価値観、良心を無視しないと、社長になれないのが、中国電力
と呼ばれる組織なのか??
運が悪いのか、足を引っ張った人間が組織内にいるのか、神が知ることだが、
辞めるしかない!!子供でもだましているのか?言い訳が見苦しい!
中国電ダムデータ改ざん、社長「報告受けた」 11/05/06(読売新聞)
中国電力(本社・広島市中区)が98~99年にかけ、水力発電用ダムの堤の高さ変化を示す「沈下量」などの測量データ改ざんを把握しながら隠していた問題で、山下隆社長が5日、朝日新聞記者の取材に対し「鳥取支店長として改ざんの報告を受けていた」と、当時から改ざんの事実を知っていたことを認めた。これまで会見などで一貫して「覚えていない」と説明していた内容を一転させた。結果的に社長就任後も改ざん問題の公表を怠っていたことになり、責任問題に発展する可能性もある。
関係者の話によると、中国電の子会社「中電技術コンサルタント」(CEC、広島市南区)は、土用ダム(岡山県新庄村)の92~97年分の沈下量などのデータを改ざん。98年6月、社内調査でデータの改ざんを発見し、同月内に同ダムを管轄する鳥取支店に改ざんを報告した。山下社長は当時、同支店長だった。
山下社長は朝日新聞の取材に対し、鳥取支店長として、CEC幹部から改ざん報告を受け、本社に連絡した▽本社土木部と同支店でダムの安全性を技術的に解析した▽土木部長室や同支店で問題の取り扱いをめぐる会議をしていた▽改ざんを把握した後の98年分は正確なデータを報告した――などの事実を認めた。
会見で「覚えていない」としていたことについては「当時の資料やパソコンのデータを見たら思い出した。結果的に会見時に明らかにできず申し訳ない」と話した。
一方で、99年1月に本社で山下社長も参加して最高幹部らと改ざん問題の対応を協議した対策会議については「思い出そうとするが思い浮かばない。ただ当時、少なくとも私が非公表とすることを決める立場になかったのは事実だ」と話した。
山下社長は同社が設置した緊急対策本部の本部長、福田昌則副社長らから4日に受けた事情聴取の際にも同様の証言をしたことを明らかにした。
自身の進退問題については、「今のところ辞めるつもりはない。会社を引き締め、しっかりやりたい」と話した。
山下社長は97年6月~99年6月まで鳥取支店長を務め、本社広報部長や企画室長などを務めた後、副社長から今年6月、社長に就任した。
朝日新聞(2006年11月4日)より
中国電改ざん 支店名で対応手引書
山下社長が鳥取在任時 「違法行為」認識か
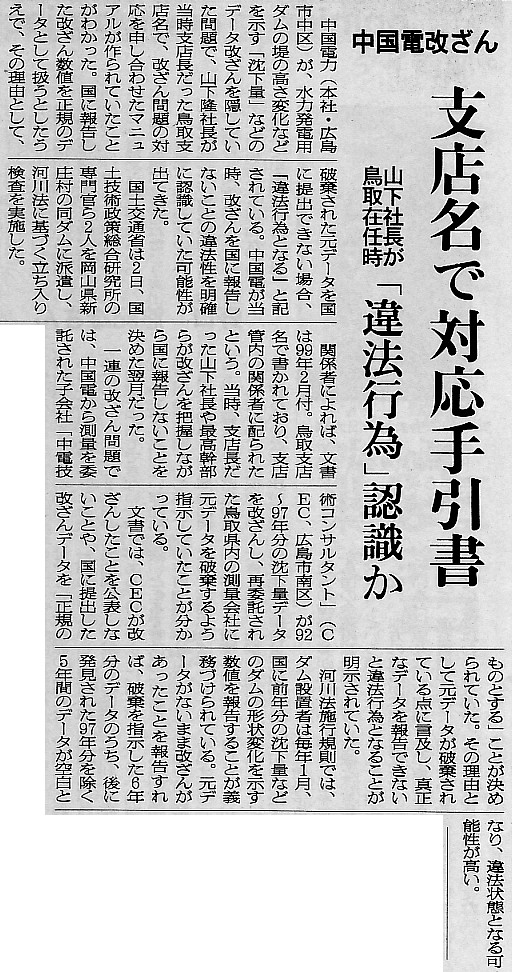
中国新聞(2006年11月2日)より
中電ダム測量値改ざん
岡山「土用」で委託子会社 92年から6年分
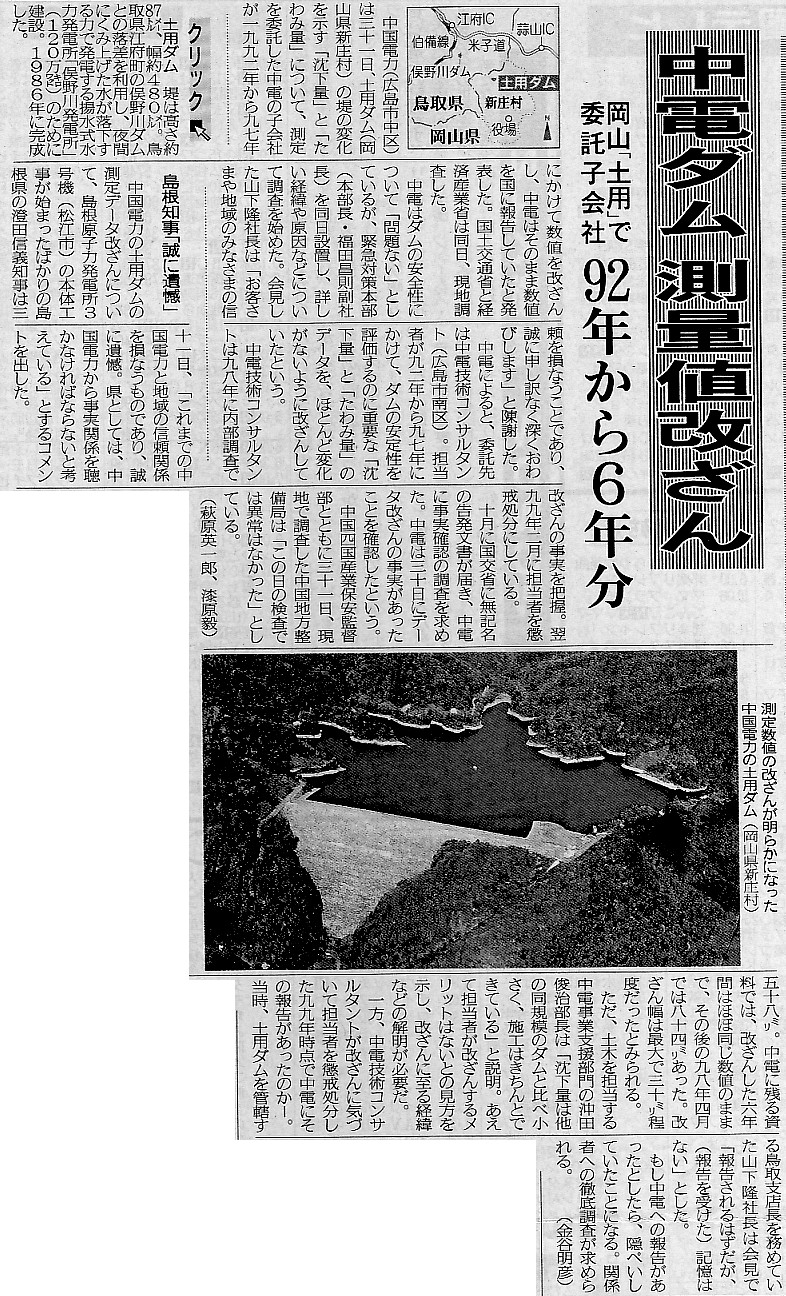
朝日新聞(10/12/06)より
松下電器、資格を不正取得 国交省37件取消しへ
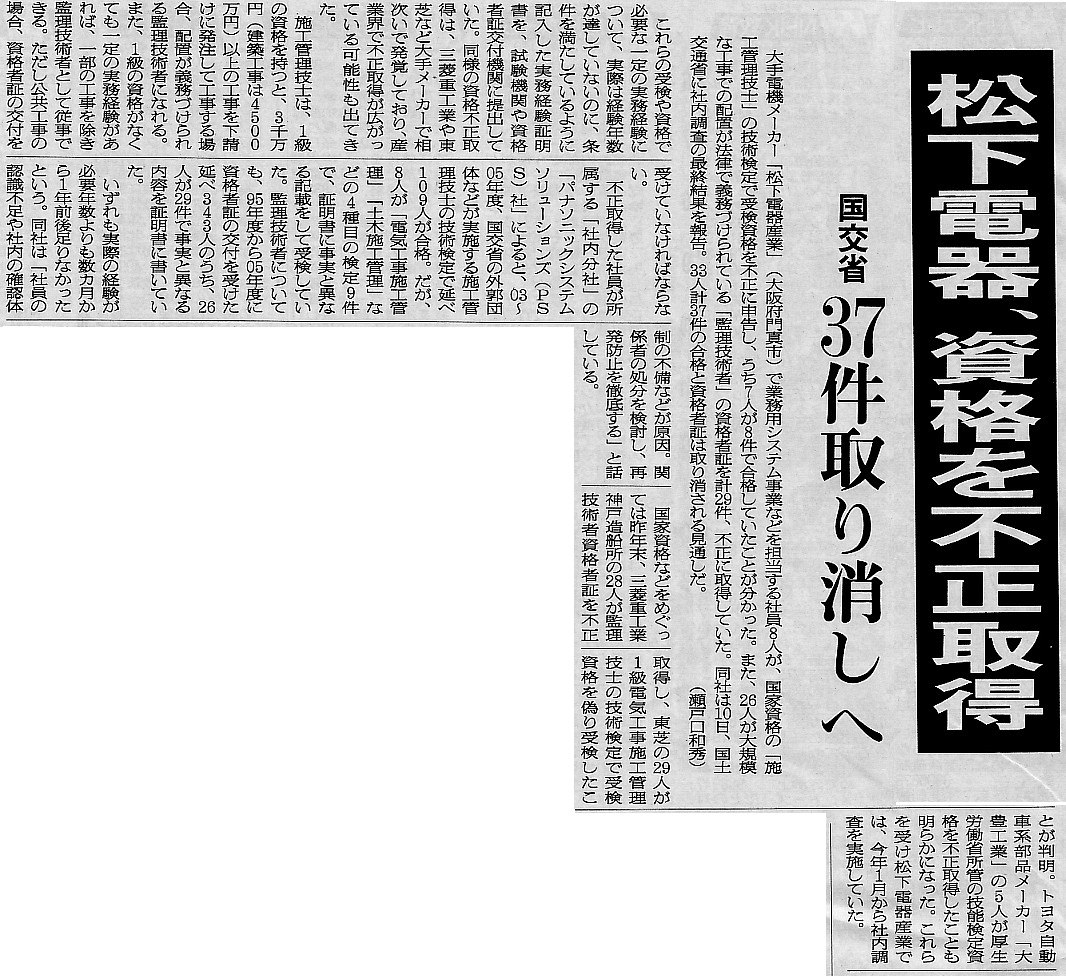
ミツトヨ“悪質” 兵器開発に転用・転売「認識あった」 08/28/06(産経新聞)
精密機器大手「ミツトヨ」の不正輸出事件で、警視庁公安部に逮捕された容疑者の一部が、核兵器開発にも転用可能な3次元測定器の輸出について、「大量破壊兵器(WMD)の開発のために転用や転売される恐れの認識はあった」との趣旨の供述をしていることが27日、分かった。公安部は、ミツトヨがWMD開発懸念国に転売されることも念頭に、組織的に不正輸出を企てたとみている。しかし、エンドユーザー(使用者)の解明は難しく、警視庁幹部は「日本の脅威につながる北朝鮮に流れた可能性も十分にある」と指摘している。
ミツトヨ社長の手塚和作容疑者(67)ら5人は平成13年、3次元測定器2台を無許可で、核関連部品などの国際的密売ネットワーク「核の闇市場」と関連の深い会社「スコミ・プレシジョン・エンジニアリング(SCOPE)」があるマレーシアに輸出したとして逮捕された。1台はSCOPE社から転売され、ドバイ経由でWMD開発懸念国のリビアに渡ったとされる。
こうした転売や、測定器の核兵器開発への転用の可能性について、逮捕された容疑者の一部は「(転売、転用される)認識はあった」と話している。
SCOPE社に輸出された2台のうち残る1台は未開封で、マレーシアに残されていたことも確認され、公安部はこの1台も同様に、WMD開発懸念国に転売される予定だったとみている。
WMDの開発に使われる可能性の高い機器は、経済産業省の指導で、転売しないよう取引先から誓約書を取ることを求められているが、ミツトヨはこうした手続きをせず、誓約書も取っていなかった。さらに、参考人聴取に複数の社員が「製品が売れれば、転売先はどうでもよかった」と説明。公安部は、逮捕された役員が転売や転用の可能性を認識しながら不正輸出を主導したとみている。
これまでの調べで、ミツトヨは測定器を輸出する際、規制水準以下の「低性能」と偽装するための数値改竄(かいざん)ソフトを独自開発し、7年以降、1万台以上の測定器を不正輸出していたとされる。捜査幹部は「これだけ膨大な数のエンドユーザーを突き止めることは困難。核兵器開発以外にミサイル技術の開発にも使われた疑いや、『核の闇市場』を通じ、北朝鮮へ流れた可能性もある。会社の利益を優先し、脅威を拡散させたといえるミツトヨは非常に悪質」と話している。
「偽装請負」?大阪労働局が松下子会社の実態調査 08/09/06(読売新聞)
松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ」(大阪府茨木市)が、茨木工場で勤務する社員を請負業者側に出向させ、請負労働者に直接、業務の指揮をしているのは、労働者派遣法に抵触する恐れがあるとして、大阪労働局は9日、実態調査に乗り出した。
関係者によると、松下側は茨木工場で、契約上は業者側が業務全体を受託する「請負」なのに、松下側社員が請負労働者を指揮する「偽装請負」を行っているとして、昨年7月、大阪労働局から是正命令を受けた。これを受け、松下側は請負労働者全員を、松下側が直接指揮できる派遣社員に切り替えた。
しかし、松下側は今年5月、再び請負契約に戻し、自社社員を「技術指導」の名目で業者側に出向させ、請負労働者を直接指揮する形に変更した。派遣社員には、労働者の労務、安全管理などの責任を松下側が負う必要があり、労働者側から「請負契約に戻したのは、責任回避のための脱法行為ではないか」との指摘が出ていた。
一方、松下側は今月、茨木工場と兵庫県尼崎市の尼崎工場に勤務する請負労働者計1800人のうち約2割を、正社員などとして採用する方針を明らかにしている。
朝日新聞(06/18/06)より
旧三和銀やノンバンク 100億円が回収不能 小西容疑者通じ組周辺へ
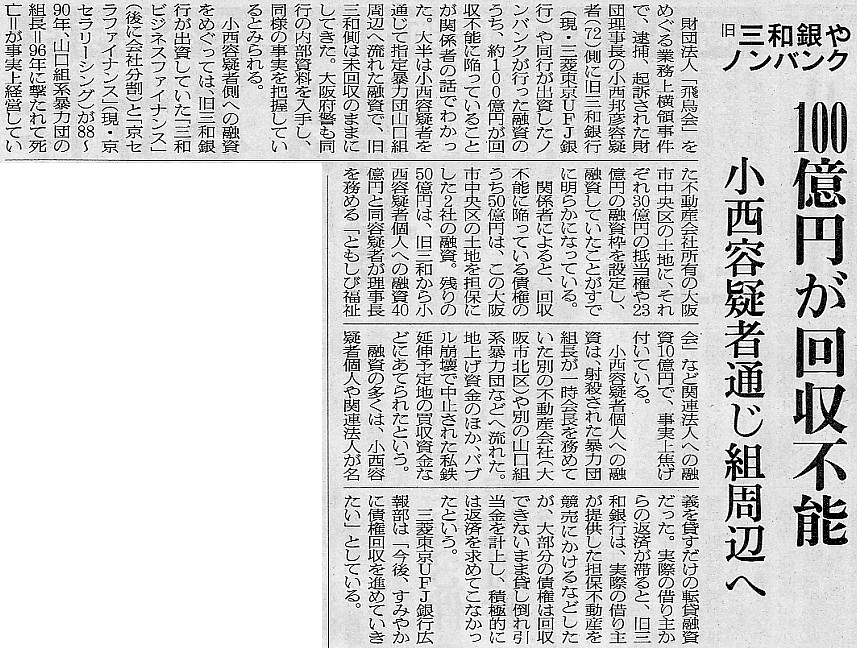
飛鳥会横領事件:旧三和銀が暴力団系企業に融資 05/21/06(毎日新聞)
財団法人「飛鳥会」理事長の小西邦彦容疑者(72)による業務上横領事件で、バブル経済期に旧三和銀行(現・三菱東京UFJ銀行)が、小西容疑者を通じて暴力団系企業に「地上げ資金」を融資していたことが分かった。関連ノンバンクなどを通じての暴力団系企業への融資のため、小西容疑者や関連法人が表向きの債務者になったという。大阪府警は、バブル期のこうしたいきさつも同行が小西容疑者との関係を切れなかった一因とみている。地上げ資金の融資残高は約50億円に上り、不良債権化していた。
同行淡路支店は長年、飛鳥会に経理担当の行員を派遣しており、今回の事件で同支店次長、釘本実紀也容疑者(42)が業務上横領のほう助容疑で逮捕された。
登記などによると、大阪市中央区の繁華街にある約550平方メートルの土地には88年、ノンバンク「京セラファイナンス」(現・京セラリーシング)が極度額23億円の根抵当権を設定。当時は山口組系暴力団組長の関連企業が所有する土地で、債務者は小西容疑者が理事長を務める社会福祉法人「ともしび福祉会」だった。また、旧三和銀行の関連ノンバンク「三和ビジネスファイナンス」(現・三菱UFJファクター)も90年、同じ土地を担保に小西容疑者に30億円を融資した。
関係者によると、こうした形で抵当が付けられた暴力団関係の不動産は複数あり、ともしび福祉会や小西容疑者が債務者になっているが、「実際には暴力団系企業に地上げ資金を提供する融資だった」としている。
バブル期の地上げへの融資は、短期で回収できるため効率が良く、各金融機関はさまざまな形で資金提供したという。銀行から暴力団系企業への融資はできないため、小西容疑者が債務者として“名義貸し”して、行内の審査を通るようにしたとみられる。こうした融資はバブル崩壊とともに不良債権化。融資元は担保物件を売却するなどして一部を回収し、98年以降は小西容疑者への融資は行っていない。
三菱東京UFJ銀行広報部は「具体的なことは答えられない」としている。京セラリーシングは「融資枠の設定は事実のようだが、詳細は分からない」と話している。
飛鳥会・小西容疑者への50億円、旧三和銀本店が決定 05/20/06(朝日新聞)
大阪市の外郭団体「市開発公社」から直営駐車場の管理を委託されていた財団法人「飛鳥会」(大阪市東淀川区)を巡る業務上横領事件で、飛鳥会理事長の小西邦彦容疑者(72)(逮捕)側から山口組系暴力団組長側に資金提供が行われ、これに三菱東京UFJ銀行淡路支社課長・釘本実紀也容疑者(42)(同)が関与していたことが、大阪府警の調べでわかった。
資金調達や口座振り込みの手続きを一手に引き受けていたという。別の山口組系暴力団側に流れた小西容疑者への巨額融資が、同銀行の前身の旧三和銀行本店の取引案件だったことも判明。経済界が暴力団排除に取り組むなか、金融機関としてのモラルが問われそうだ。
調べによると、小西容疑者は2005年ごろ、飛鳥会事務所で現金を山口組系暴力団組長に手渡していた。この現金は、釘本容疑者が小西容疑者の複数口座から引き出して現金化していた。釘本容疑者は平日、同事務所に常駐しており、現金受け渡しの場にも同席していた。同組長については、暴力団関係者であることを以前から知っていたという。
小西容疑者が取締役になっているペーパー会社「あすか管理」の口座から、同組長の知人女性名義口座に、今年2月までの2年間で計約500万円が振り込まれたが、いずれの口座も同支社で開設されていた。
釘本容疑者は小西容疑者の指示通り振り込んだと供述し、他の複数の人物にも定期的に現金を振り込んでいたことを、新たに認めた。府警はこうした資金の中に、着服された駐車料金収入が含まれていた可能性があるとみている。
関係者によると、旧三和銀行グループがバブル期に、別の山口組系暴力団の関係企業が所有する不動産を担保に、小西容疑者に貸し付けた計80億円の「転貸融資」のうち、1988年の30億円、91年の20億円の計50億円は、同銀行本店で審査のうえ融資決定された。
融資金はそのまま小西容疑者から暴力団の関係企業に貸し付けられたが、同銀行は、かなりの額を回収できないまま2002年に不良債権として処理した。府警は、暴力団の地上げ資金に使われたとみている。
警察庁は91年、金融・証券業界に暴力団排除の徹底を要請。97年、全国銀行協会連合会(現全国銀行協会)は、暴力団などとの絶縁を宣言する倫理憲章を採択している。
三菱東京UFJ銀行広報部の話「個別の融資案件へのコメントは控えたい」
社会的責任のISO新規格協議 「日本色」前面に 02/21/06(朝日新聞)
企業の不祥事が相次ぐ中で、工業規格や企業行動の国際ルールを定める国際標準化機構(ISO、本部・ジュネーブ)が企業や組織の社会的責任の規格「ISO26000」の策定作業を進めている。国際規格に適合した企業は、社会的責任を果たす組織として国際的な商取引や人材確保に有利になるとみられている。とくに今回は本格的なISO規格で初めて日本勢が議論をリードしていることもあり、二〇〇八年に予定される発効に向けて産業界の注目が高まっている。(村山繁)
ISO26000は、昨年から具体的な検討作業が始まった。昨年二回行われた総会では五十四カ国、二十四国際機関の約三百五十人が参加。ISO会議としてはISO9000を上回り、過去最大規模の国際会議となっている。
ISO26000が目指すのは、企業などの組織が地域や活動の性格などにかかわらず、それぞれの利害関係者との間に生まれる社会的責任を果たす行動を促すことを目指している。法律順守や人権への配慮、知的財産の管理、個人情報保護のほか、組織内の不正防止に向けた内部統制も含まれる見通しだ。
策定議論に参加する経済産業省の矢野友三郎標準企画室課長補佐も「海外進出の成否は、進出先に認められるかどうかがカギを握る。社会的責任の証明を迫られる可能性も高く、新しいISOの枠組みはその手助けになる」と話す。
これまでの議論で目次にあたる「設計仕様書」が決まり、第三者審査で規格に適合しているかどうかのお墨付きを与える「第三者認証」を目的としないことが明記された。過熱気味の認証ビジネスにさらされることは「社会的責任にはふさわしくない」との判断があったためだ。
この合意形成には日本の意見が大きく作用した。仕様書の内容も日本案にほぼ沿った形でまとまっている。参加国で唯一、対案を提示した日本が二回にわたってプレゼンテーションを実施し、実効性ある規格づくりの必要性を強調したことが奏功した。
今回の日本側の対応には、環境管理システムの規格であるISO14000シリーズの策定時に出遅れた苦い経験が生きている。一九八〇年代末から議論は始まっていたが、日本が参加したのは九〇年代初め。日本が参加した段階には、すでに方向性が決まっており、本文の肉付け作業が残されていただけだった。
その基準では日本が得意とする排出ガス有害物質低減などを直接的には求めず、事業所の環境管理の段取りなどが規格通りかどうかを問う枠組みだった。多くの日本企業は、世界一厳しい日本の環境管理基準をクリアする技術を持ちながら、ISOを取得するため、新たな対応を迫られた。
今回の議論に参加している日本経団連の田中秀明社会本部長は「議論への参加にかかわらず、すべての組織にわかりやすく使い勝手のいい枠組みにしたい」と高い目標を掲げおり、「日本色」を打ち出したISO規格誕生に期待が高まっている。
◇
【用語解説】ISO(国際標準化機構)
1947年設立の民間国際機関。電機・電子分野以外の工業規格の国際標準を制定する。現在は約150カ国が加盟し、日本からは日本工業標準調査会が参加している。製品規格が主体だったが、最近では品質管理のような制度の標準化が進められている。
サブスタンダード船問題
もこの企業の社会的責任に関連があります。「法律順守」
「環境対策」「社会貢献」の点から、サブスタンダード船を使っている、又は
サブスタンダード船と関連がある企業や下請けに対して大企業は助長するような
ことをすべきでない。つまり、サブスタンダード船をコスト削減だけのために
使用する企業を使わない。
サブスタンダード船を物流の手段として使わない
事が大企業の社会的責任(CRR)であると思われる。しかしながら、
現状を見ていると大企業の中には指摘されないからサブスタンダード船を直接的、
又は、間接的に利用しているところがある。
サブスタンダード船の使用は、「環境対策」の無視や軽視である。
日本海で座礁した「ナオトカ」、スペインで座礁した「プレスティージ」
パキスタンで座礁したタンカーは、現実に環境問題を引き起こしている。
サブスタンダード船問題は世界規模で取組まれている。日本でも座礁した
船主責任保険に未加入のブスタンダード船に多くの自治体が困っている。
一般的に、多くの船はP&I(Protection & Indemnity)保険に入っています。これは
船主責任保険と日本では呼ばれています。リンクしているサイトを参考に見てください。
通常の船舶保険でカバーされない賠償責任をカバーします。カバーする範囲は、保険会社に
よって違いますが、船主責任保険が重要であるがわかります。
宮崎市の一ツ葉海岸沖でホンジュラス船籍のタグボートが
座礁した事故が座礁した事故で、県、市などが困っている。船主が責任を取らないからである。
船主責任保険に入っていないので、補償が払えないのであろう。日本にはたくさんの外国の放置船
がある。これらの船舶は、船主責任保険に加入していないので、放置されたのであろう。
また、保険にかからない状態の
(問題のある)船舶(問題のある)船舶であるから、加入できなかったのであろう。
(他で、検査は通るが、保険に掛からない事情については、後で説明する。)
このような問題を知りながらサブスタンダード船を物流の手段としている企業は
企業の社会的責任を果たしているとは言えない。不祥事を起した企業は運悪く
公になっただけで、やはり企業の社会的責任を果たしていなかったと思う。
物流の大手企業は船を使う前に船舶が船主責任保険に加入しているか、
また、下記のことをチェックするべきであろう。
船舶を接岸をさせる前にチェックすることが船舶が座礁した
時に自治体や環境に対して将来的に貢献することを理解するべきであろう。
ISO9001とかISO14001を取得して自慢しているだけでは思慮が
なさすぎるだろう。
物流ではトラックの運行問題で犠牲者が出た時に、注目を集めた。この時は、
高知日通であった。この時の日通の対応は非常に非難を浴びた。副社長の
責任感がなかった事を世間に曝す形になったからだ。
国土交通省は、船主責任保険に加入していない船舶を利用、又は、接岸させて
いる現状を大手、そして、出来れば全ての企業に対して調査するべきであろう。
協力が得られない所は、PSCによる船舶検査により状況を把握すれば良い。
また、問題のある企業の情報を地方自治体に伝えることも良いであろう。
公にするのも良いであろう。これにより企業の社会的責任をより意識する
企業も増えるであろう。そうすれば、工場の虚偽報告の発覚が明らかになったが
、このような問題も減るであろう。
-
1.船舶名
-
2.船主名
-
3.保険者名及び住所
-
4.保険開始日
-
5.保険てん補額(1976年責任制限条約の責任限度額以下でないこと)
次の更新まで続く。
★警察不祥事:警察の裏金作り
★成田官製談合
★★耐震データ偽造!
★耐震データ偽造(Part2)
★三菱自動車(ふそう)
耐震強度偽装問題
で日本はたいへんである。
広島県警はたいしたことは出来なかったが、耐震強度偽装では500人も動員されている。
「国連機関、欠陥船根絶へ出張監査 日本提唱」はりっぱである。
足元を見ていないところが残念である。
国連機関、欠陥船根絶へ出張監査 日本提唱で攻め姿勢へ 01/19/04 (朝日新聞)
海難事故などの原因となる欠陥船をなくすため、国連の国際海事機関(IMO)が、今年から加盟国に出向いて、各国の検査制度を監査する取り組みを始める。外国船の検査は寄港国で実施していたが、日本近海で北朝鮮やロシア船の原油流出事故などが相次いだことから、日本の提唱で「攻めの姿勢」に転換。各国の検査体制をチェックすることで、欠陥船を放置させない体制づくりを整えたい考えだ。
新制度は、日本が中心となって昨年11月にロンドンで開かれたIMO総会に共同提案され、実施が決議された。
7月から始まる試験監査には、日本と共同提案した欧米諸国や韓国など約30カ国が参加予定。北朝鮮やロシアはIMOに加盟しているが、今回の試験監査への参加の意向は示していない。将来的には加盟国すべてを強制的に監査したい意向だ。
船舶の安全基準は、IMOが定めた海上人命安全条約(SOLAS条約)で定められており、基準を守らせるのは母国の責任だ。
日本の場合、この条約に沿って船舶安全法や国土交通省令で詳細な基準を明示し、自国船を定期検査している。一方、国内に寄港した外国船については、国土交通省が船舶安全検査(PSC)を実施、基準を満たさない場合は改善を命じる仕組みになっている。
しかし、老朽船や欠陥船は一向に減らない。97年に日本海で重油流出事故を起こしたロシアタンカーのナホトカ号は建造後26年たち、老朽化が著しかった。02年に茨城県沖で起きた北朝鮮貨物船の重油流出事故を契機に国交省が北朝鮮船へのPSCを強化した結果、貨客船の万景峰(マンギョンボン)号などで欠陥が相次いで見つかった。
上記に関係なく大手企業は利用している又は接岸させている船舶が船主責任保険に加入
していることを確認し、進んで環境及び社会に貢献するべきであろう。
関連記事のリンク集
造船大国日本の船の解体責任と常石セブ造船問題環境問題を考える
法律家のページより
オーストラリアにおける新しい保険証書所持義務 UK P&I CLUBのHPより
ロシア極東の石油・船舶事情
経済協力開発機構
外国座礁船 県が撤去 数千万円かけ行政代執行へ 宮崎
<入港禁止>繰り返しPSC指摘受けた船舶 国交省検討
船主保険未加入は入港拒否 放置船対策で法案提出へ
北朝鮮船の加入は2・8% 船主保険で国交省が調査
稚内港に入港するロシア船の8割が船主責任保険未加入
国交省、船舶保険義務化提案へ
牛肉偽装告発の西宮冷蔵、消費者のカンパで営業再開へ 02/07/04 (読売新聞)
雪印食品による牛肉偽装事件の舞台となり、2002年11月から休業している兵庫県西宮市の倉庫会社「西宮冷蔵」の水谷洋一社長は6日、今春にも営業を再開する意向を明らかにした。全国から寄せられた再建支援のカンパが800万円を超え、運転資金のめどが立ったためという。
水谷社長が雪印食品の偽装を告発した後、他の取引先が同社を敬遠、休業に追い込まれた。だが、「勇気を持って告発した会社を廃業させてはいけない」と消費者団体のメンバーらがカンパを寄せていた。
不正はいろいろな組織で存在する!
★HOME
リンク先の情報については一切責任を負いかねますことを申し添えます。
リンク先の中には繋がらないものもあると思いますが、ご容赦ください。
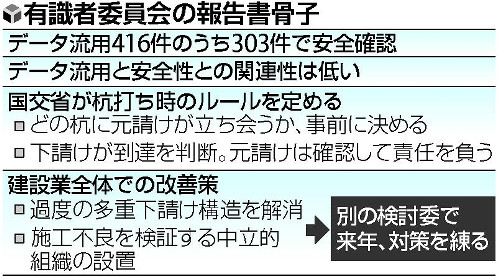

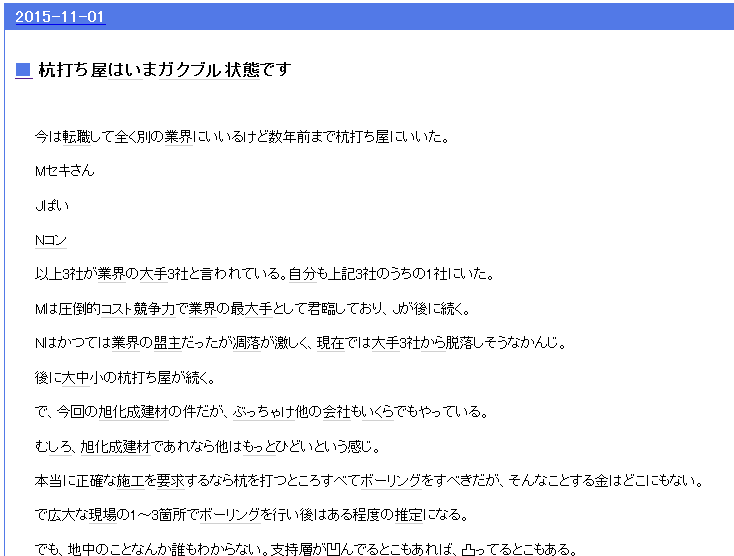
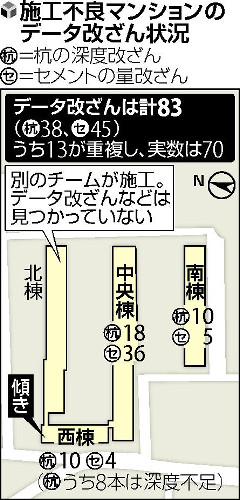

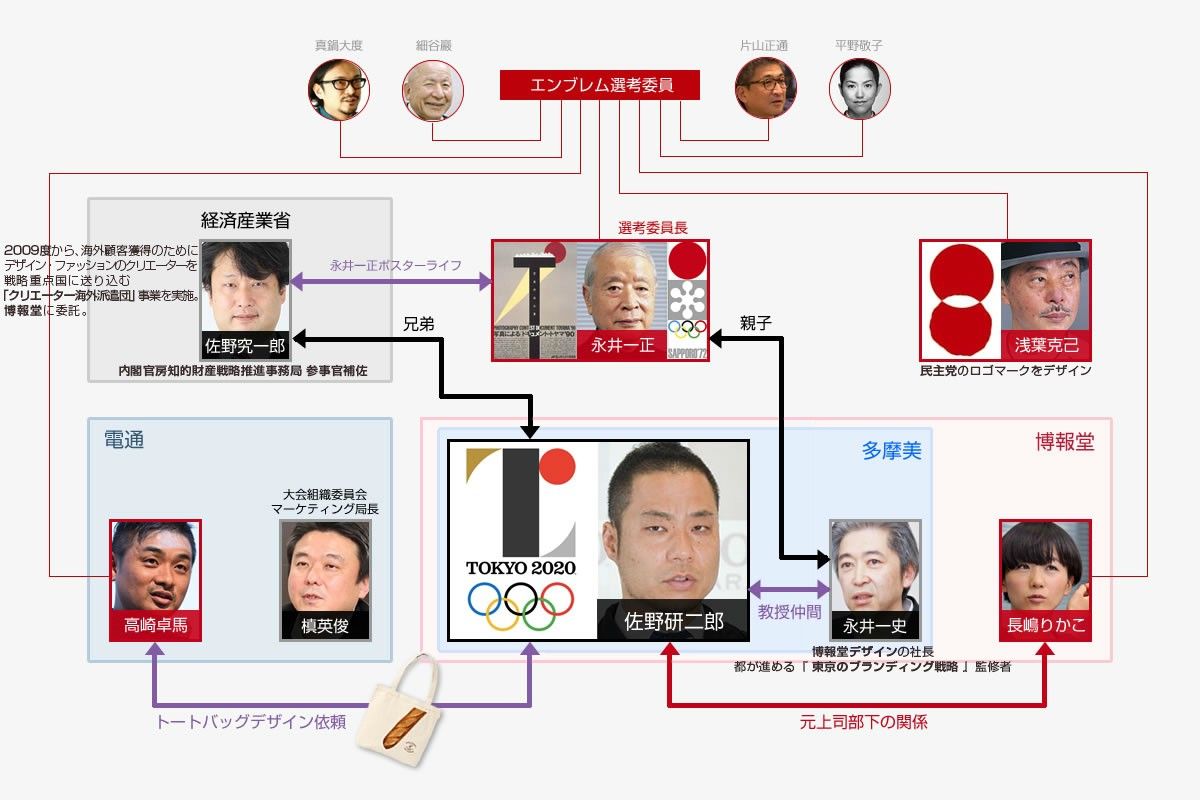
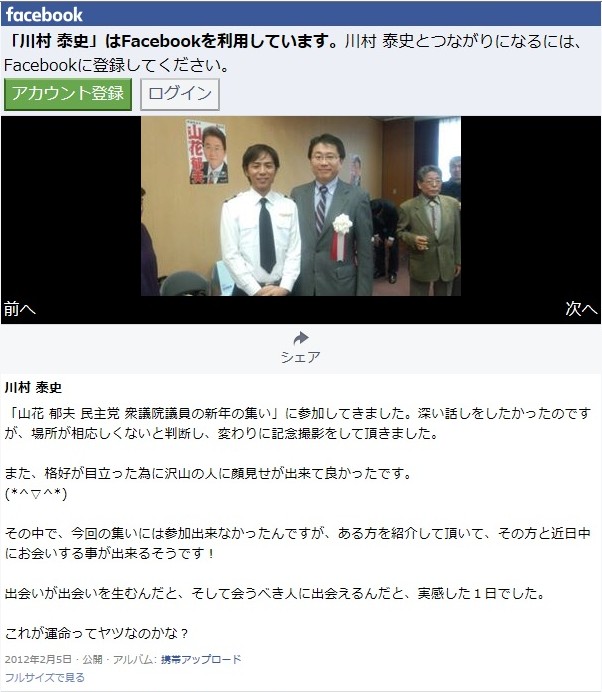

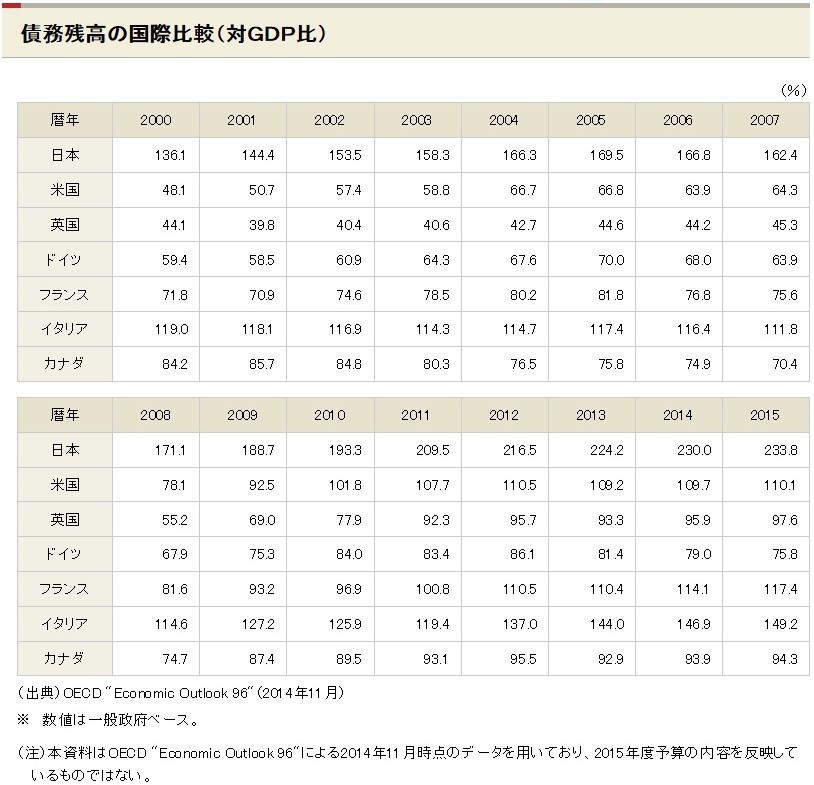

 国立競技場将来構想有識者会議に参加した人々、日本スポーツ振興センター(JSC)及び文部科学省の関係者は理解できないことがあれば建築家の安藤忠雄氏
に質問しなかったのか?また、1300億円は計画の予算だったのか、それとも決まったデザインの見積もりだったのか?この点を明確にするだけで
部分的な責任は誰にあるのか判るのではないのか?
国立競技場将来構想有識者会議に参加した人々、日本スポーツ振興センター(JSC)及び文部科学省の関係者は理解できないことがあれば建築家の安藤忠雄氏
に質問しなかったのか?また、1300億円は計画の予算だったのか、それとも決まったデザインの見積もりだったのか?この点を明確にするだけで
部分的な責任は誰にあるのか判るのではないのか?
 「文科省は安価な外国産への変更などを求めている」けど文科省の人間は品質や耐久性などを理解しての判断したのか?
デメリットを理解した上での判断であれば良いが、材質をケチると耐久性や維持管理が莫大な金額になることがある。
よく役人は自分達がその部署にいなくなれば関係ない、責任を問われないのだから目先だけの判断でよいと考えているような対応を取ることが
あるが、実際はどうなのか?
「文科省は安価な外国産への変更などを求めている」けど文科省の人間は品質や耐久性などを理解しての判断したのか?
デメリットを理解した上での判断であれば良いが、材質をケチると耐久性や維持管理が莫大な金額になることがある。
よく役人は自分達がその部署にいなくなれば関係ない、責任を問われないのだから目先だけの判断でよいと考えているような対応を取ることが
あるが、実際はどうなのか?







 男性によると、着陸の5分ほど前、高度を下げる機体が大きく揺れた。着陸と同時に「バーン」という大きな音がして上下に揺れ、乗客の女性らの「キャー」という悲鳴が機内に響いた。両側の窓の外に火柱が見え、床から出る焦げ臭い煙で視界が悪くなり、機内は一気にパニック状態になった。
男性によると、着陸の5分ほど前、高度を下げる機体が大きく揺れた。着陸と同時に「バーン」という大きな音がして上下に揺れ、乗客の女性らの「キャー」という悲鳴が機内に響いた。両側の窓の外に火柱が見え、床から出る焦げ臭い煙で視界が悪くなり、機内は一気にパニック状態になった。

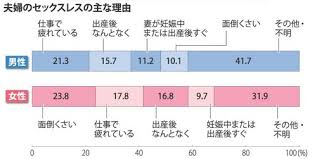





















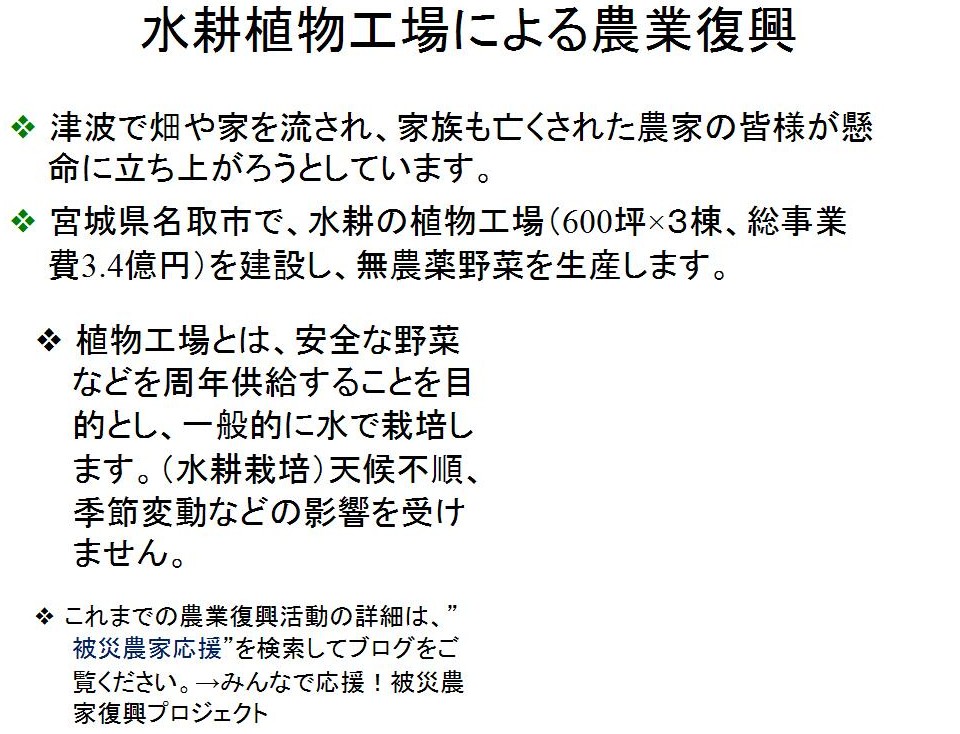

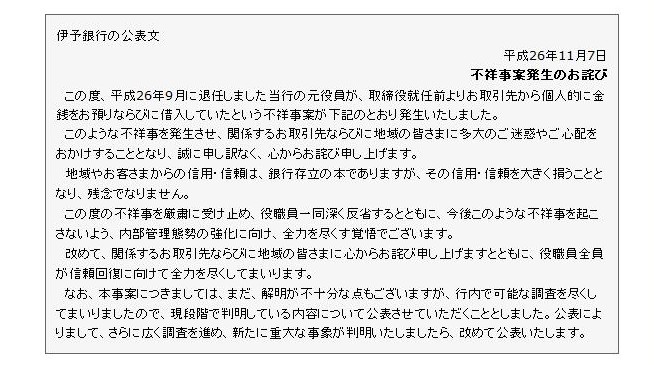

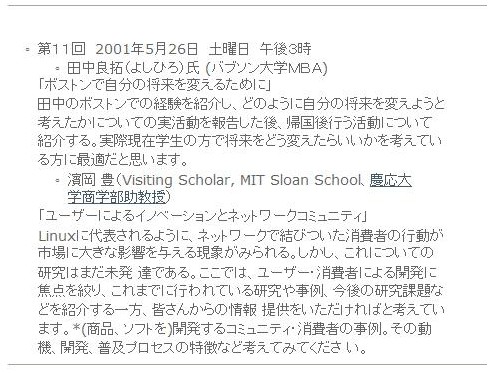
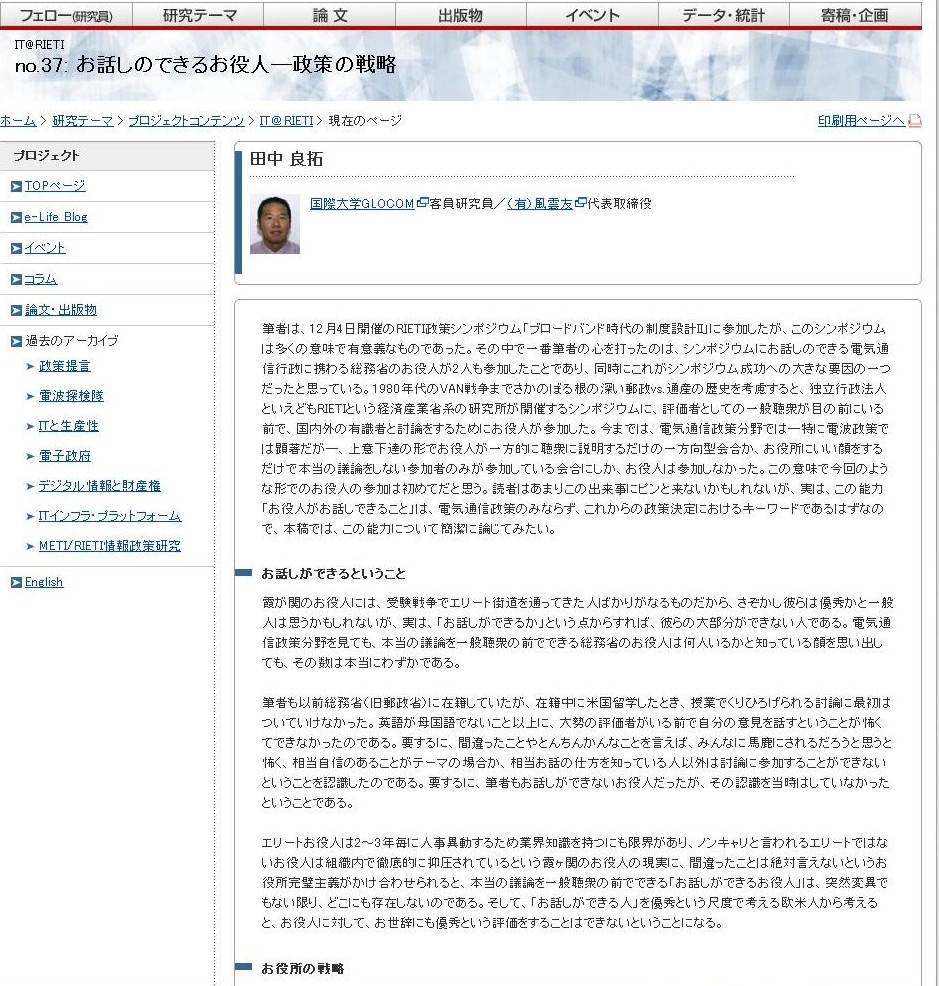
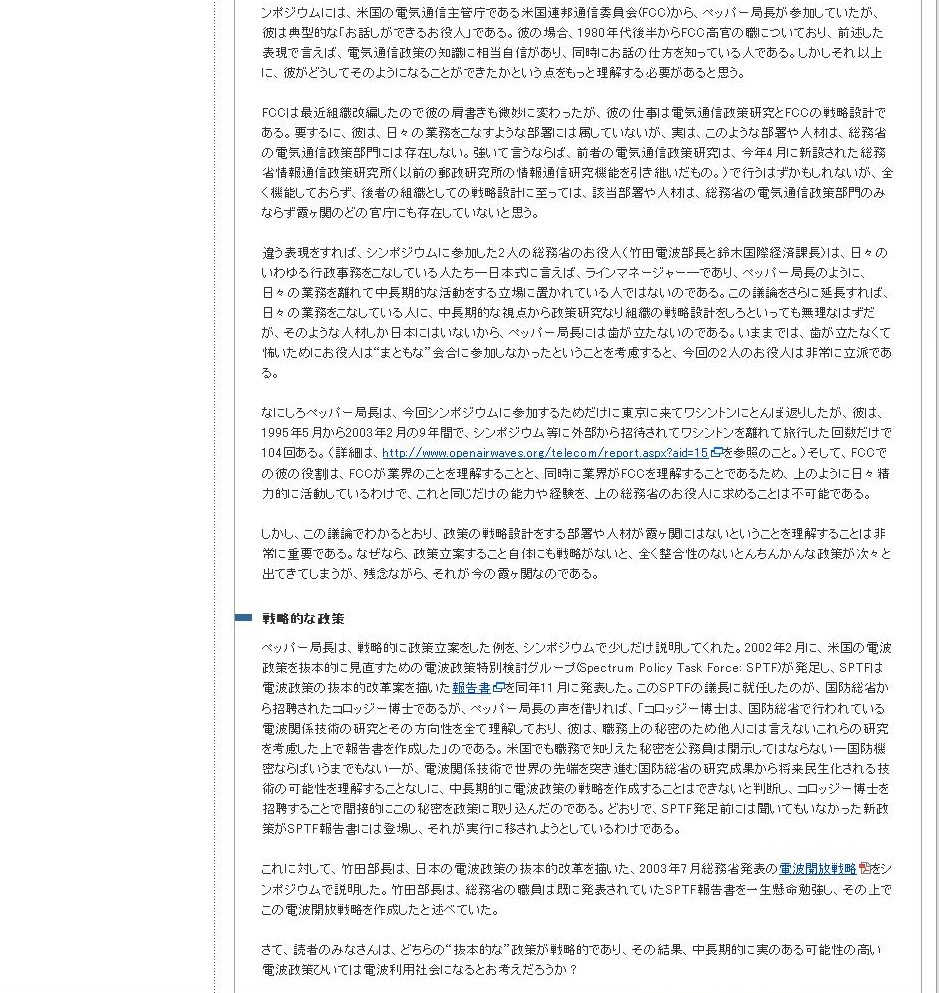
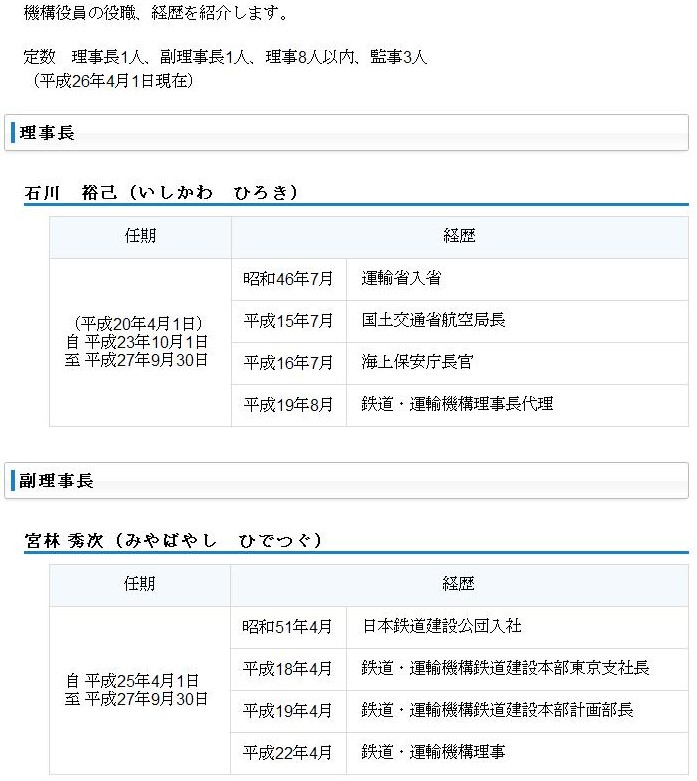





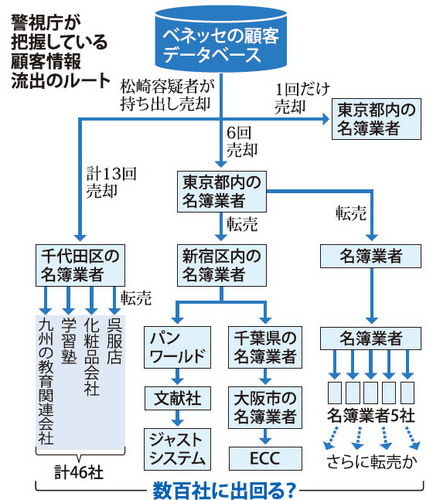
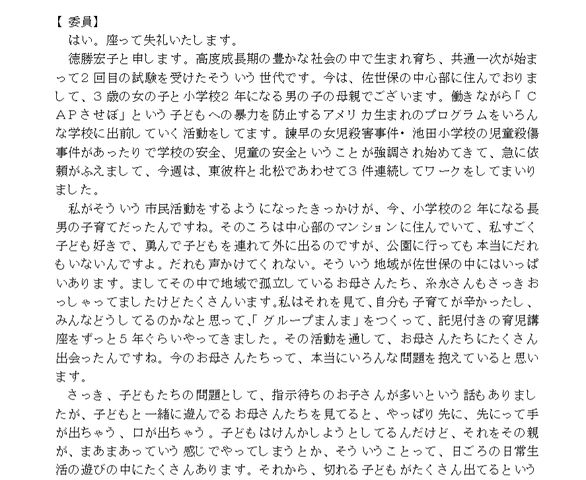






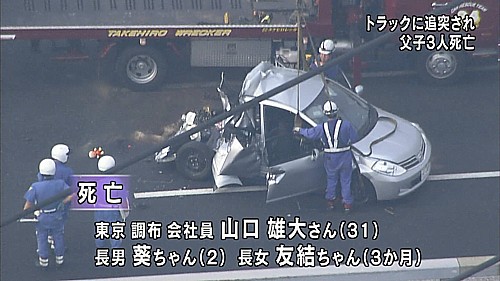
 東京都柔道連盟 福田二朗会長 (astjt_koikeのジオログ)
東京都柔道連盟 福田二朗会長 (astjt_koikeのジオログ) China high-speed train crash kills 35
China high-speed train crash kills 35
 China high-speed train crash kills 35
China high-speed train crash kills 35
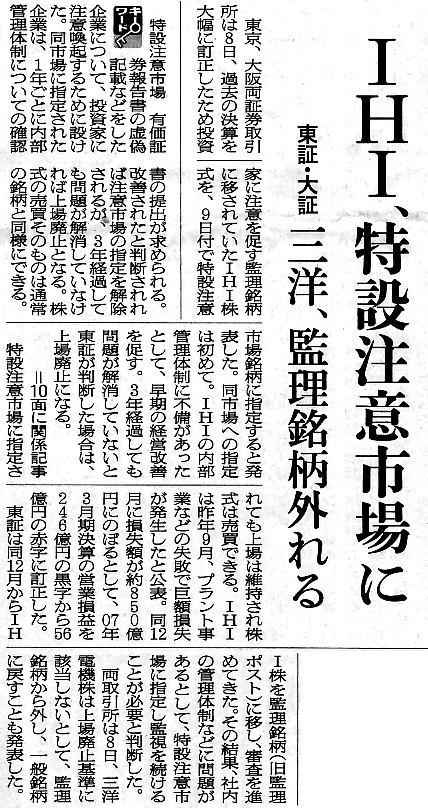
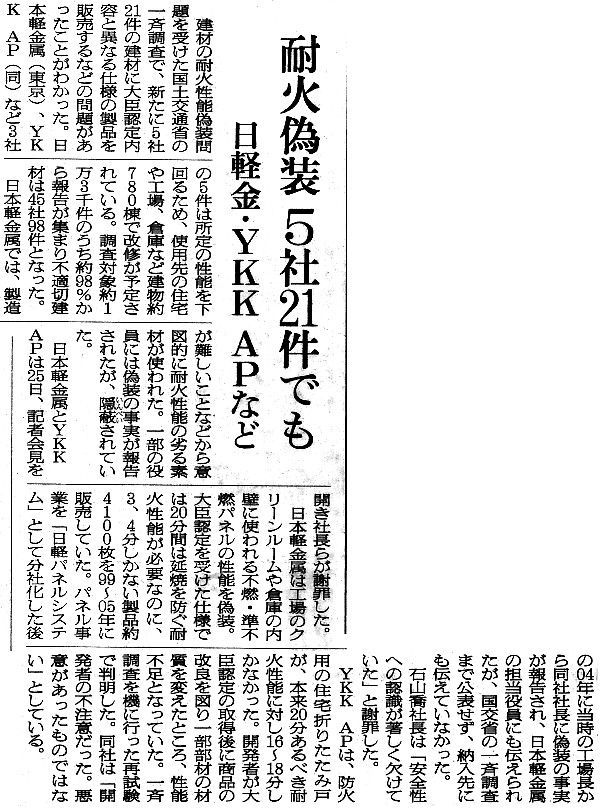
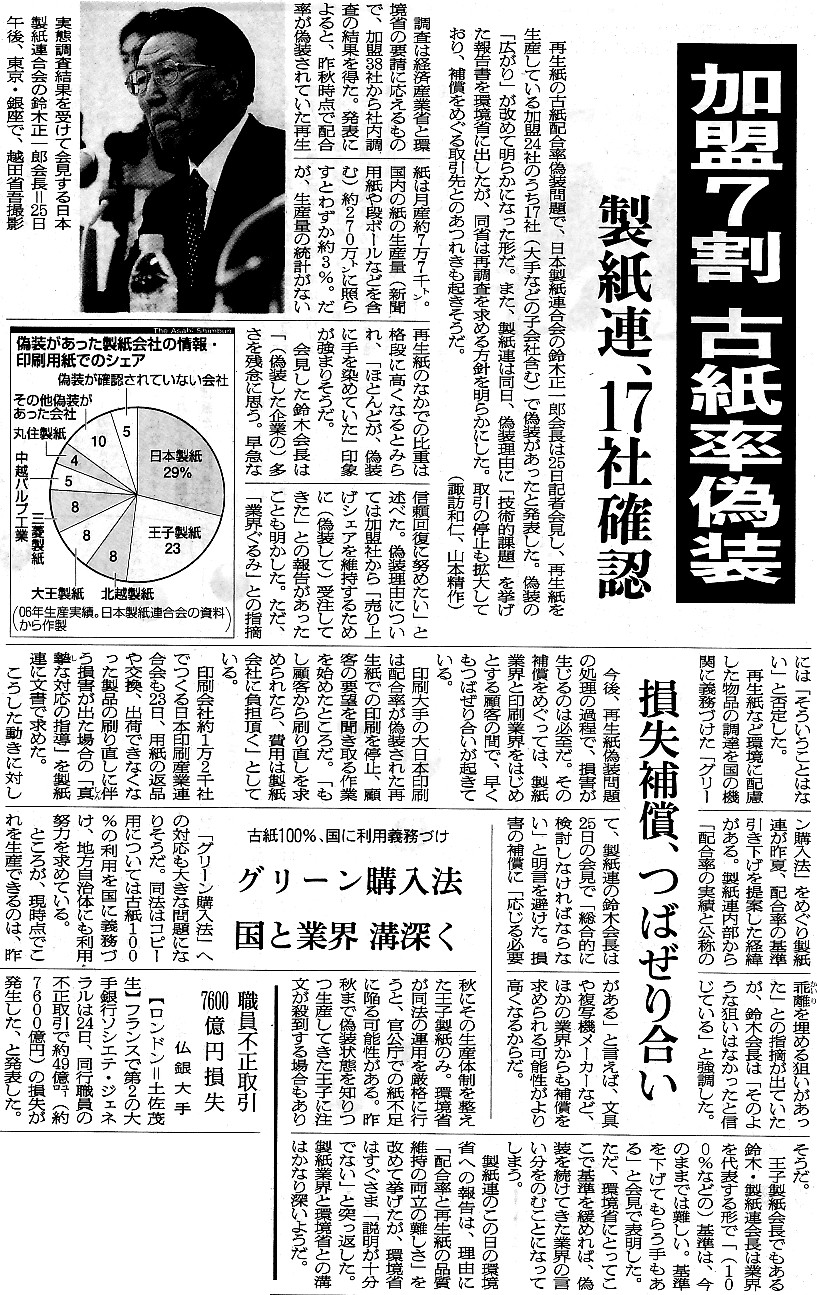


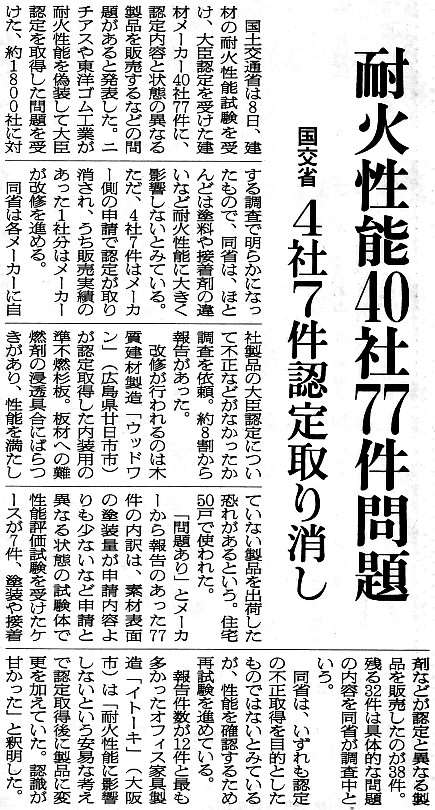
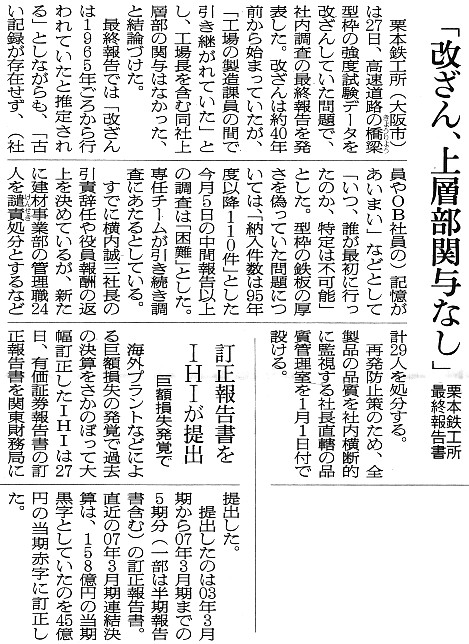
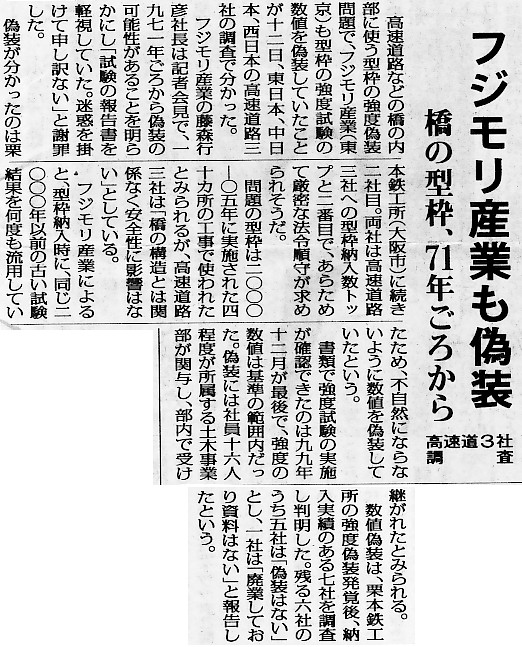
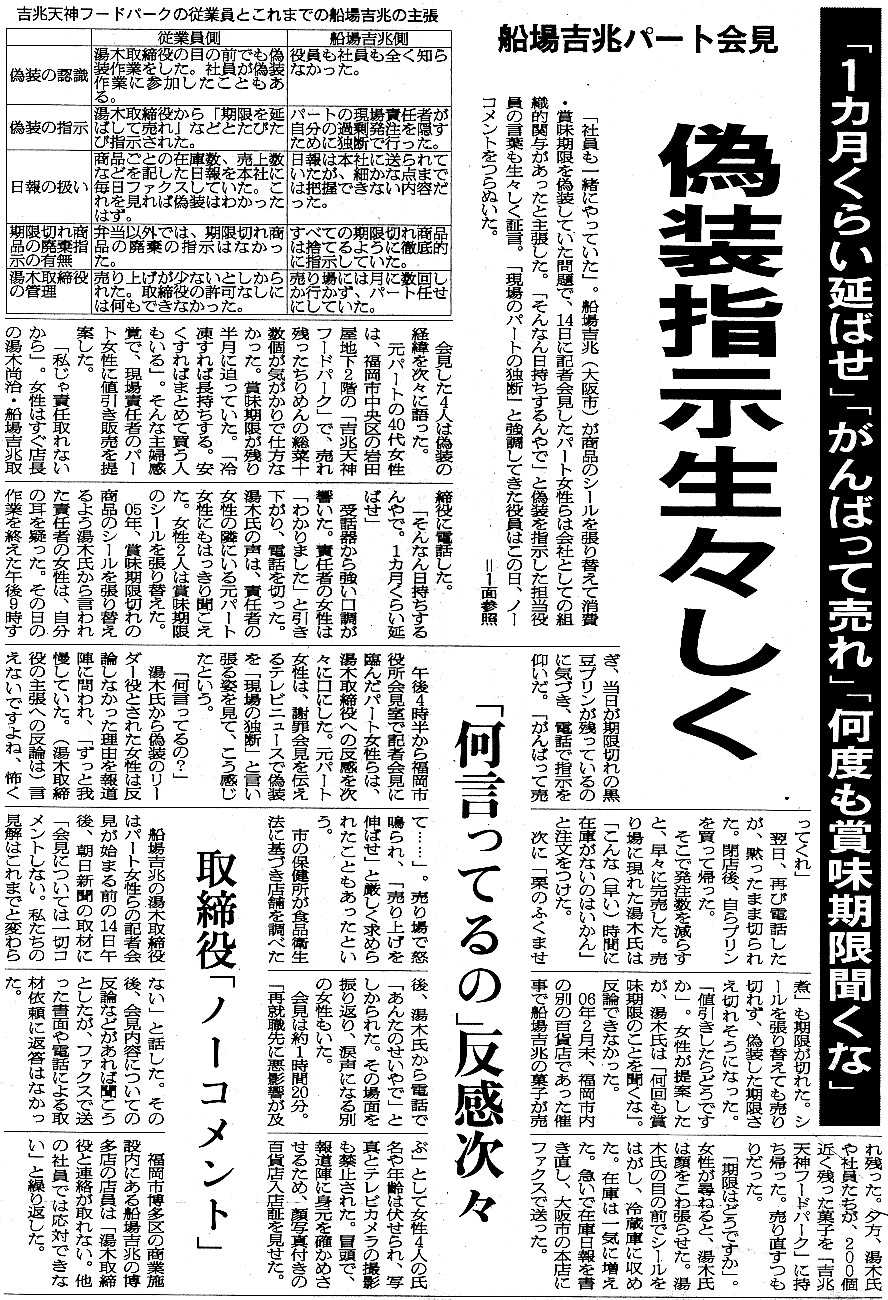
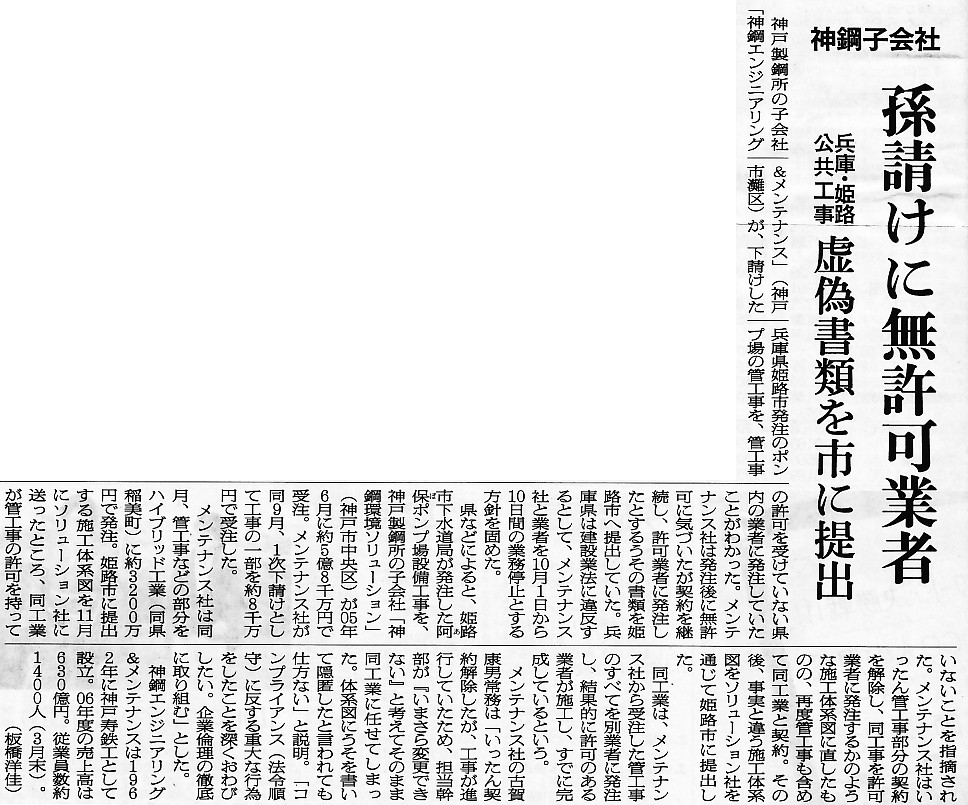

 那覇空港で中華航空機が爆発、炎上した事故で、中華航空は21日、事故機の胴体左側面にある「CHINA AIRLINES」という英語の社名ロゴと垂直尾翼にある紅梅の花のマークを白いペンキで塗りつぶした。事故機の映像や写真が連日報道されるため、企業イメージの低下を避けるのが狙いとみられる。
那覇空港で中華航空機が爆発、炎上した事故で、中華航空は21日、事故機の胴体左側面にある「CHINA AIRLINES」という英語の社名ロゴと垂直尾翼にある紅梅の花のマークを白いペンキで塗りつぶした。事故機の映像や写真が連日報道されるため、企業イメージの低下を避けるのが狙いとみられる。