最近、企業の社会的責任と言う言葉を聞くようになった。企業の社会的責任とは どのような意味があるのか。英語ではCorporate Social Responsibility(CSR)と 表現されています。企業の社会的責任(CSR)は「社会」「環境」「経済」 「法律順守」「地域貢献」等を含みます。
ただ、儲ければ良いと良いとか、コストのために安全や環境を無視する企業は 企業の社会的責任を果たしていると言えないでしょう。
これだけ飛行機や船で飲酒に関係する問題が起きているのに飲酒に関して自己管理できないのは問題だと思う。
能力があっても、自己管理できない人材は必要以上に上にあげない方が良いと思う。
全日空は22日、30代の男性操縦士が乗務前の呼気検査でアルコールが検出され、19日早朝の運航便が遅延したと明らかにした。全日空グループでは昨年10月以降、パイロットの飲酒による運航便の遅延が相次いでいる。
同社によると、副操縦士は19日午前1時ごろ、宿泊先の神戸市のホテルで、いずれも350ミリリットルの缶ビール1本と酎ハイ半分程度を飲んだ。同6時過ぎに神戸空港に出勤した際、呼気1リットル中0.05ミリグラムのアルコールが検出された。副操縦士が乗務予定だった神戸発羽田便はパイロットを交代し、約1時間40分遅れて同8時44分に出発した。
同社は規定で、宿泊先での乗務24時間前以降の飲酒を禁じている。【花牟礼紀仁】
賃貸アパート大手「レオパレス21」(東京都中野区)の違法建築問題で、同社が2012年12月に建築基準法に違反する物件について検討していたことを示す社内文書の存在が21日、明らかになった。一連の違法建築問題について同社はこれまで「昨年、物件オーナーからの指摘で判明した」と説明していたが、6年前に問題を認識していた可能性がある。
この文書は、同社側から入手した共産党の宮本岳志議員が21日の衆院予算委員会で明らかにした。文書の内容は国土交通省も把握している。
文書は12年12月26日付で、賃貸借契約や物件の瑕疵(かし)を巡って物件オーナーから損害賠償を請求された訴訟の経緯などをまとめたもの。「一番の懸念は、現時点で『レオパレスが建築基準法違反』という記録が残ること」とし、「本裁判における当社の選択肢」という項目では「本裁判において、建築基準法違反という文言は記載されない」「本裁判にかかわった弁護士らにオーナーが相談した場合、高い確率で建物検査をアドバイスされる懸念あり」などと書かれている。
同社は昨年4月、自社ブランド「ゴールドネイル(GN)」シリーズなどで屋根裏などに延焼防止の仕切り壁が未設置だった問題を公表した。今回明らかになった文書の中で顧問弁護士の助言として「本裁判以降、GNの瑕疵について完全に蓋(ふた)をすることは不可能である」「1部上場企業でコンプライアンス順守を表明している以上、GNの修繕については今後プロジェクトを組んで対応すべきだ」といった記載もあった。
同社は取材に「この時点では担当者は物件の工法上、仕切り壁は必要ないと認識していた。昨年、別の物件の未設置を指摘され、再検討した結果、建築基準法に違反すると分かった」と説明している。【花牟礼紀仁】
独立行政法人(総務省)のサイトには次のように書かれている。
独立行政法人日本学生支援機構には「独立行政法人」がついている。貸した奨学金の返済問題がある事はニュースやメディアで知っているが、回収の方法が適切とは思えない。もし回収の問題を改善、又は、解決したければ、奨学金の承認プロセスを改善や変更する、進学した学校別の卒業生の収入や返済状況のデータを分析して、専攻や学校次第で借りれる限度額を設定するなど対応すれば良いと思う。この事により一部の可能性やこれまでは奨学金を得られた学生が切捨てれるとは思うが、独立行政法人日本学生支援機構が不誠実な回収をやらなければ存続が難しい、又は、「(回収できなくなった)分は税金で補塡(ほてん)せざるを得なくなるため」と言うのであれば、仕方がない選択だと思う。
独立行政法人の業務運営は、主務大臣が与える目標に基づき各法人の自主性・自律性の下に行われるとともに、事後に主務大臣がその業務実績について評価を行い、業務・組織の見直しを図ることとされています。
総務省では、独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行っているほか、主務大臣による目標策定、業績評価が客観的かつ厳正に行われるよう、政府統一的な指針を定めています。また、総務省には政府唯一の第三者機関として独立行政法人評価制度委員会が設置されており、主務大臣による目標策定、評価や業務・組織の見直しをチェックし、必要に応じて意見を述べることとされています。
独立行政法人通則法(平成11年法律103号)(抄)
第2条
この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
日本学生支援機構はこのような判断を行う前に奨学金を承認する基準やプロセスを変更するべきだったと思う。
奨学金の返還をめぐり、日本学生支援機構が保証人に半額の支払い義務しかないことを伝えずに全額を求めてきた問題で、機構は新年度から保証人になる人に伝える一方で、すでに返還中の保証人には伝えない方針を決めた。機構から知らされないまま返還を続ける保証人は延べ1200人を超える見通しだ。専門家は不公平だ、などと指摘している。
奨学金の場合、保証人(4親等以内の親族)は連帯保証人(親)と異なり、民法の「分別の利益」によって支払い義務が半分になる。朝日新聞は昨年11月、機構がその旨を説明しないまま保証人に全額請求し、応じなければ法的措置をとると伝えていたと報じた。これを受けて機構は、返還を終えた人や裁判で返還計画が確定した人を除いて、機構と協議して返還中の人などが分別の利益を主張した場合には減額に応じる方針を示した。
機構によると、減額される可能性があるのは、全額請求を受けた保証人のうち機構と協議して返還中の人と、督促に応じて返還中の人を合わせた延べ1353人。このうち分別の利益を主張して減額を認められたのは延べ75人で、残る9割超の延べ1278人は機構から知らされないまま全額分の返還を続けている。返還中に分別の利益を主張すれば、機構は減額に応じるとしている。
機構は公式ウェブサイトの「保証人について」の項目に分別の利益に関する説明を入れたほか、新年度から契約する保証人に契約時の書類などで説明することにした。返還中の保証人に直接伝えない理由について、遠藤勝裕理事長は「伝えれば事実上、半額を回収できなくなり、その分は税金で補塡(ほてん)せざるを得なくなるため」と話している。
内閣府消費者委員会で委員長を務めた河上正二・青山学院大法科大学院教授は「保証人に法知識がないことを利用して回収するのは不公正ではないか。また、一部の保証人にしか情報を提供しないことになり、不公平だ。公的な機関として適切とは言えない」と指摘する。(諸永裕司、大津智義)
車検を不正に通す見返りに現金を受け取ったとして、大阪府警が大阪府泉大津市の自動車整備会社「川上自動車鈑金塗装」の自動車検査員、本京春樹容疑者(33)を、加重収賄や虚偽有印公文書作成などの容疑で逮捕・送検していたことが、捜査関係者への取材で分かった。府警は、不正車検を依頼した側の自動車販売業者ら7人も同作成容疑などで逮捕。過去2年間で計約180台分の車検が、不正だったとみられる。
本京容疑者の勤務先は、同社が経営する国指定の民間車検場。検査員は道路運送車両法で「みなし公務員」となり、収賄罪の適用対象となる。
捜査関係者によると、本京容疑者は昨年、同府和泉市の自動車販売業「ピアレス」社長、石本和成容疑者(35)から依頼された乗用車2台について、保安基準に適合しているように装った虚偽の書類を近畿運輸局に提出。車検を通した見返りに、石本容疑者から計約8万円の賄賂を受け取った疑いが持たれている。
この2台は基準に合わない改造車だが、本京容疑者は整備や点検をせず、書類だけで車検を通す「ペーパー車検」で済ませていた。
他にも、販売業者ら6人が不正車検を依頼したとして、同作成などの容疑で逮捕され、改造車の一部の所有者も書類送検された。
昨年、大阪府内で開かれた自動車展示会で、車高を低くしたり、車幅を広げたりした改造車が集まっているのを捜査員が発見。内偵を進め、本京容疑者が車検に関わっていることを突き止めた。
一方、府警は21日にも、法人としての同社を道路運送車両法違反の疑いで書類送検する方針。【宮川佐知子】
◇整備費高額 不正、後絶たず
不正車検を依頼したとして逮捕された自動車販売業の石本容疑者は、客の要望に応じて改造する「カスタムカー」を売りにしていた。改造車は愛好家らに根強い人気があるが、車検を通すのは難しく、不正は後を絶たない。
大阪府内の中古車販売店によると、改造車でも基準に適合するように整備し直せば、車検を通すのは可能だ。ただ「通常より時間がかかるうえ、費用も高額になるため、大手の車検場では敬遠される」という。
石本容疑者もペーパー車検を引き受けてくれる業者を探す中で、自動車検査員の本京容疑者と知り合った。
国土交通省によると、2017年度、民間車検場約3万カ所のうち、ペーパー車検などで指定取り消しなどの処分を受けた車検場は56カ所。警視庁は17年、違法に改造したダンプカーの車検を通す見返りに報酬を受け取ったとして、東京都内の自動車整備会社社長らを加重収賄などの容疑で逮捕している。【宮川佐知子】
制度改正はパイロット不足の解消のためだと思うが、計器飛行証明が取得できない、又は、計器飛行証明の不正取得の原因とならないか?
訓練費を払い、訓練を受ければ簡単に計器飛行証明が取得できるのか?実技(飛行訓練)は問題ないとしても地上座学でトラブル人はいるのではないのか?
定年退職した自衛隊のパイロットが航空会社に再就職しやすくするため、国土交通省は19日、高額な資格取得費用を自己負担せずにすむ制度改正を4月に実施すると発表した。外国人観光客増加などで見込まれるパイロット需要の拡大に対応するのが狙い。
国交省によると、外国人観光客増や格安航空会社(LCC)の増加に伴い、パイロットは不足傾向にある。同省は、航空大学校での養成数を増やすなどして対応しているが、同省の年間新規需要予測(2020年に380人)には現状、約40人不足している。30年にはさらに不足感が増すと見込まれている。
航空会社に再就職を希望する退職自衛官は現在、訓練費350万~450万円を自己負担して民間機用の計器飛行証明を取得しなければならない。防衛省によると、自衛隊のパイロットは50代半ばで定年を迎えるが、訓練費の自己負担が障壁となり、航空会社に再就職する人は年間1、2人という。
制度改正後は、計器飛行証明を取得するための訓練を、入社後に実施する別の訓練と併せて実施する。【花牟礼紀仁】
JA阿蘇の臨時職員が、顧客の葬儀代およそ2200万円を着服していたことが分かり、JA阿蘇はこの職員を解雇し、警察に刑事告訴しました。
「こういう不祥事が起きたことに対して組合員、そして社会の皆さんにご心配をおかけしていることを心よりお詫び申し上げます、大変申し訳ございませんでした」(JA阿蘇原山寅雄組合長)
JA阿蘇によりますと、顧客の葬儀代2199万円を着服していたのは、葬儀場を運営、管理する部署に勤務していた45歳の男性臨時職員です。男性は、2015年の5月から葬儀代の1件あたり70万円~100万円を少なくとも22回にわたって着服したもので「生活費や遊ぶ金に使った」と話しているということです。
JA阿蘇は、この臨時職員を先月29日に懲戒解雇し18日、業務上横領の疑いで警察に刑事告訴しました。
JA阿蘇では、2012年にも同様の不祥事があり、更なる再発防止に務めたい」と話しています。
レオパレス21を検索していたら下記の記事を見つけた。
レオパレス21の法令違反の疑いとISO9001認証の信頼性 06/11/2018((有)ロジカル・コミュニケーションの“気づき”ブログ)
レオパレス21はISO(国際標準化機構)9001の認定を受けていたらしい。ISO9001認証を受け継続的に認定を維持するためには会社による内部監査と認定機関の外部監査を満足しなければ維持は不可能になる。下記の記事に書かれている問題が存在すればISO9001認証の維持は常識で考えれば無理である。なぜ認証の維持が可能であったのかは故意に問題を隠蔽し、監査に通るためだけの資料、記録、そして内部監査を作成した、又は、問題が存在したが認定機関の外部監査員が見過ごした、又は見逃したと推測する。現実に
英大手ISO認証機関ロイド・レジスター・クオリティ・アシュアランス(LRQA)が認証で不正。無資格者による審査、手続き省略等(各紙) 07/23/18(一般社団法人環境金融研究機構)がニュースになっている。
ISO(国際標準化機構)の認定機関が増えれば顧客の利便性が向上し、競争によりより良いサービスが提供される可能性はある。ただ、仕事を受注するためにインチキや不正見逃しのチキンレースを加熱させる可能性がある事を理解しておかなければならない。管理及び監督する機関や組織はメリットとデメリットを理解した上で対応しないと公平な競争や本来の意図や目的が達成されない事が発生する。
ISOの認定を受けている会社や組織だから疑う事もなく信用出来るとは考えると間違いであると経験から思う。
JUGEMテーマ:ビジネス
2018年5月29日付の時事通信が
「レオパレス21法令違反の疑い 3万棟調査」
という見出し記事を報じていました。
記事によると(以下要約)
◆レオパレス21は5月29日に、賃貸アパートで建築基準法違反の疑いがある施工不良が見つかったと発表した
(※1996年から2009年にかけて施工されたアパートで、既に埼玉や大阪など12都府県の38棟で問題が確認されており、速やかに補修を行う予定)
◆これまで12都府県で屋根裏に延焼や音漏れを防ぐ壁が設置されていないことが確認された
◆2019年6月までに国内全3万7853棟を対象に調査を進める
◆施工不良が判明した場合は補修を行う
◆レオパレス21によると、建築図面や施工マニュアルの一部に問題の壁が記載されていなかった
◆これらの不備は、社内検査体制が不十分だったことが原因
◆田尻和人専務は施工管理責任を認めて陳謝した
◆田尻専務は、「コスト削減や工期短縮を狙った意図的な手抜きではない」と説明した
そうです。
レオパレス21は、確か1989年に上場しましたが、このころから急激に、レオパレス21の賃貸アパートが日本中に増えていった気がします。
仕事柄、建設会社に訪問する機会も多いですが、一般論として、
・急激に業績が伸びたときに問題は発生する
・利益至上主義になると、施工不良が増える
・建物の見えない部分は手抜き工事になりやすい
といった問題点がでてきます。
その原因の一つは「工期短縮主義」でしょう。
本来、建築物は、構造物の品質で勝負するべきものですが、発注者の受注量が急激に増えると、どうしても「工期」が優先事項となります。
そのため、施工業者に負担はのしかかり、暗黙のうちに、手抜き工事が横行していくわけです。
また、仕事が増えると、技術力のない職人も多く使わざるを得なくなり、意図的でなくとも、施工品質は下がっていきます。
レオパレス21のウェブサイトをチェックすると、
平成30年5月29日付のニュースリリースとして
「当社施工物件における界壁工事の不備について」
と題したお詫び文が公表されていました。
http://www.leopalace21.co.jp/news/2018/0529_2507.html
謝罪文の必須事項と言われる「社長限界でしょ」で内容をチェックすると、「処分、賠償」に関する記述が弱いです。ただ、個別に連絡するとあるので、賠償に関しては、程度に応じて、お見舞金などが設定され、対象者に通知されるのかもしれないので、「処分」についての記載はないものの合格点をつけられる謝罪文といえるでしょう。
謝罪文の中で興味深かったのが、「原因」と「再発防止」です。
以下に一部、引用してみます。
(以下、引用)
(前文略)
2.発生原因
・図面と施工マニュアルの整合性の不備
当時、物件のバージョンアップが頻繁に行われており、建物の仕様が分かりにくくなっていたことや、施工業者に渡している図面と施工マニュアルの整合性に不備があったことが確認されております。
・社内検査体制の不備
検査は行ってはいたものの、規格商品であることから図面等と現場との照合確認が不十分であったことと、検査内容も自主検査に留まっており、社内検査体制も不十分であったと認識しております。
引き続き調査を行い、発生原因の究明に努めてまいります。
3. 現在の検査体制と更なる再発防止策
組織及び現場人員体制の見直しを行い、2008年にはISO 9001の認証を取得致しました。
以降、順次体制強化を図り、本部によるチェック体制を整えております。
現在では9回の社内検査に加え、第三者による検査を4回行い、品質管理に努めております。
発生原因について十分に究明を行ったうえで、更なる再発防止策を講じる所存です。
(後略)
(引用ここまで)
感想としては
「発生原因の究明が現時点では“現象”にとどまっている」
と感じました。
なぜ、
・図面度施工マニュアルに不備が生じたのか
・図面と現場との照合確認が不十分になったのか
・社内検査体制が不十分になったのか
といった点を深く究明しなければ、真の意味での「再発防止策」とはなりません。
また、謝罪文にもあるように、レオパレス21(注)は、2008年11月27日に品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001の認証を受け、現在は2015年版の取得を世界的に著名な認証機関のひとつである「ビューローベリタスジャパン株式会社 システム認証事業本部」(BVサーティフィケーション)で認証を継続しています。
注:レオパレス21の認証登録範囲
「株式会社レオパレス21 建築請負事業部 建築統括部 ・ コーポレート業務推進本部 商品技術統括部」
2017年の日産自動車や神戸製鋼の検査不正問題以降、認証機関にお墨付きを与えている認定機関のJAB(公益財団法人日本適合性認定協会)は、社会的な問題となった不祥事が発生した場合、当該組織を認証している認証機関にその経緯説明と認証に関する対応策を報告させることをより徹底しています。
基本的には、認証機関が、自らの認証の信頼性と妥当性を社会に対して証明することが求められます。
ただ、社会システムとして、ISOマネジメントシステム認証の信頼性向上のためにも、認証機関はもちろん、認定機関も中途半端にこの問題の「終結」をして欲しくないと思います。
今後のBVやJABの調査報告を注視したいと思います。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ596号より)
品質データ改ざんなどの不適切行為報道に関連する認証について 12/113/18(公益財団法人 日本適合性認定協会)


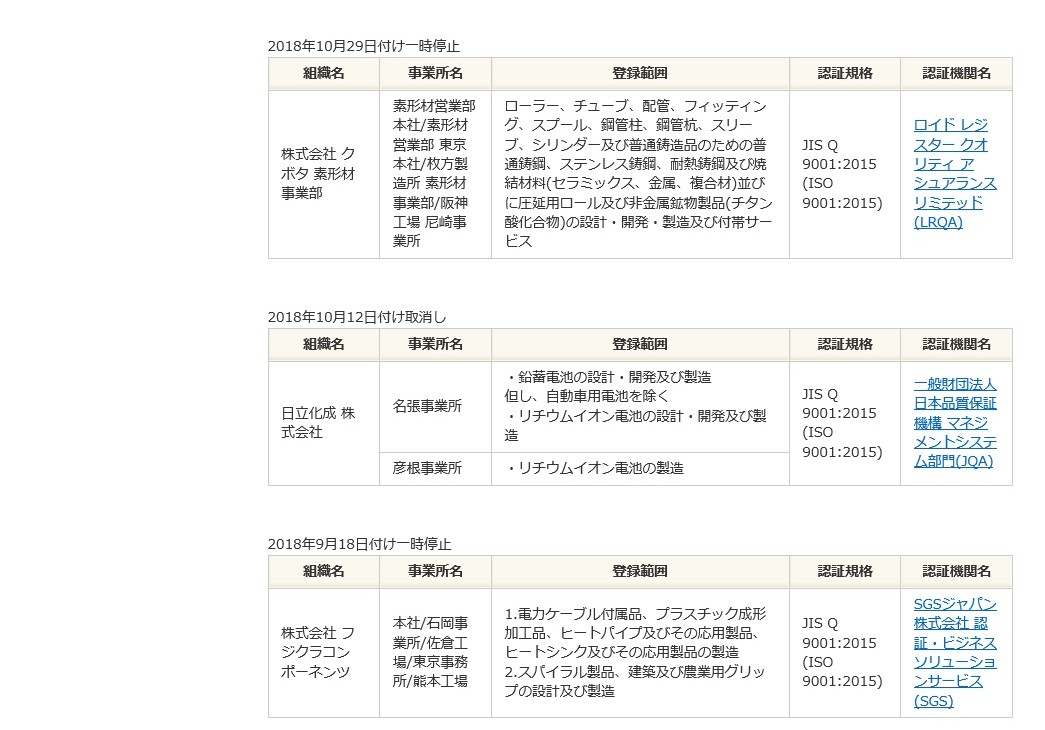
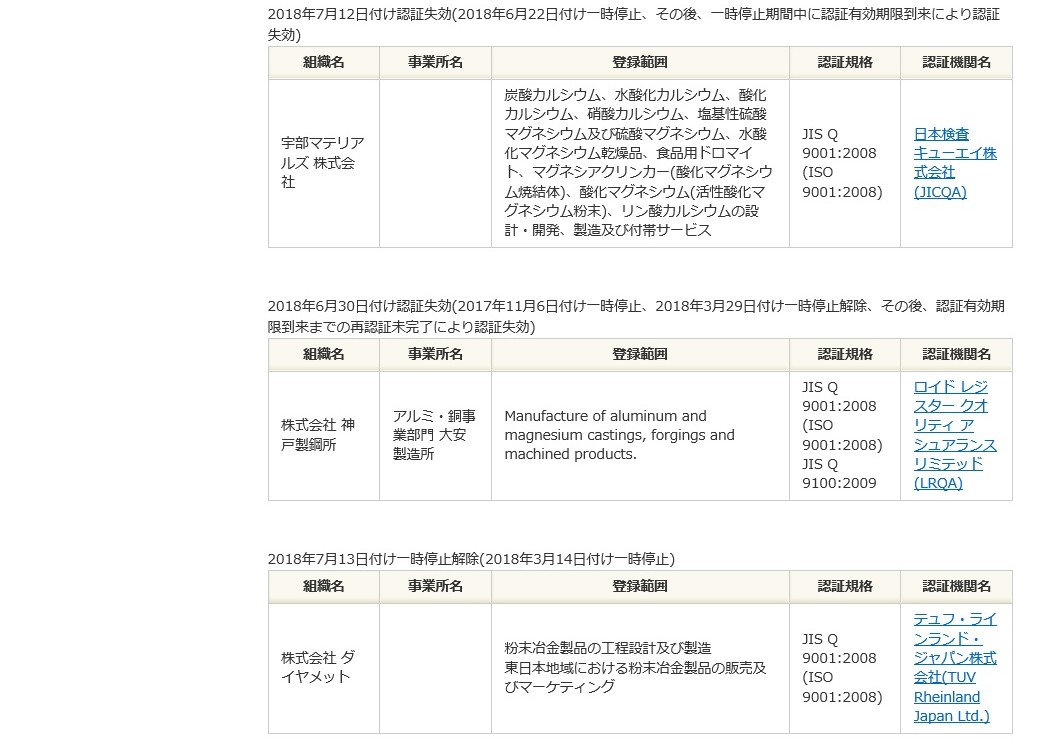
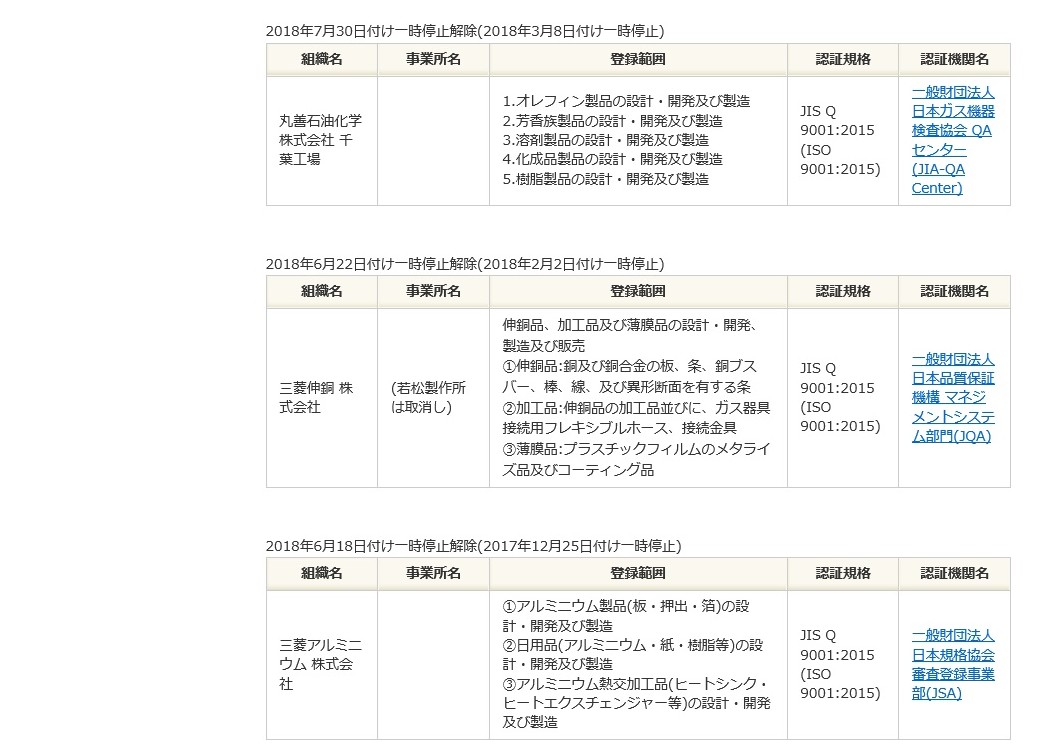

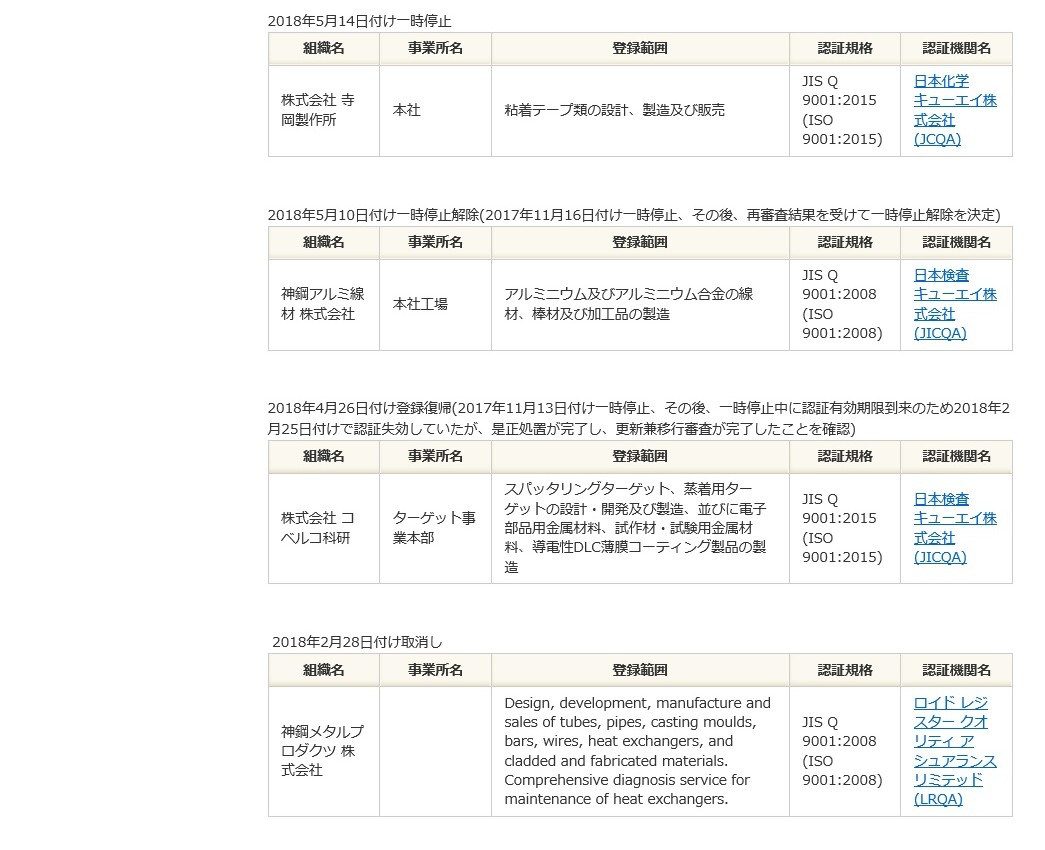

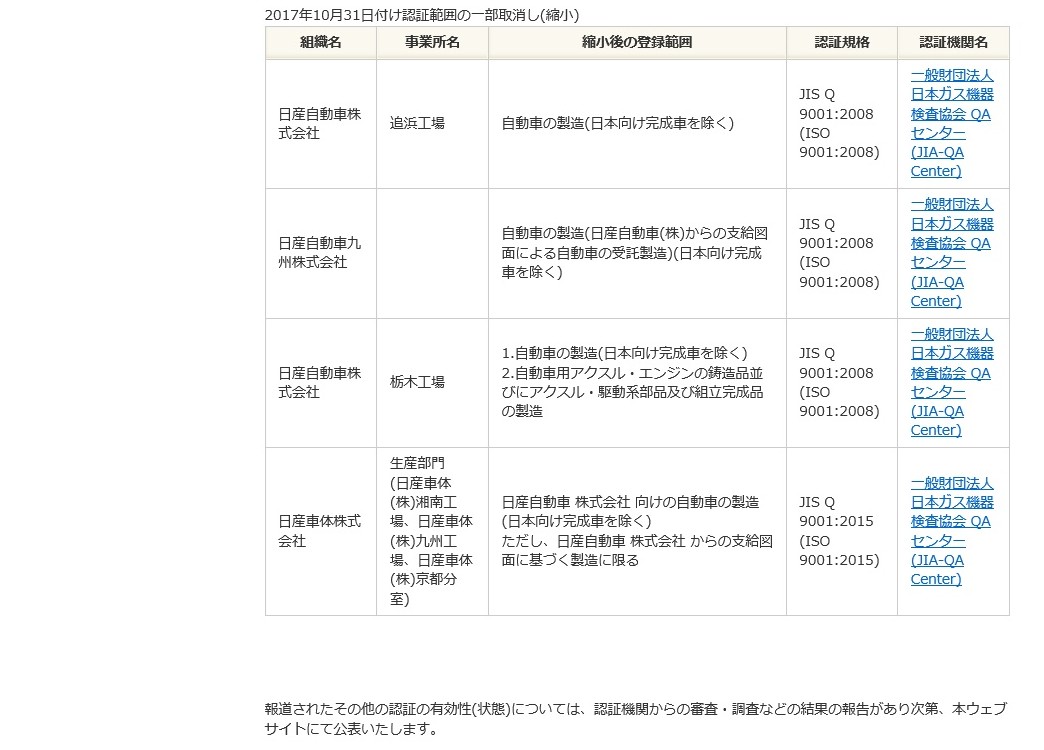
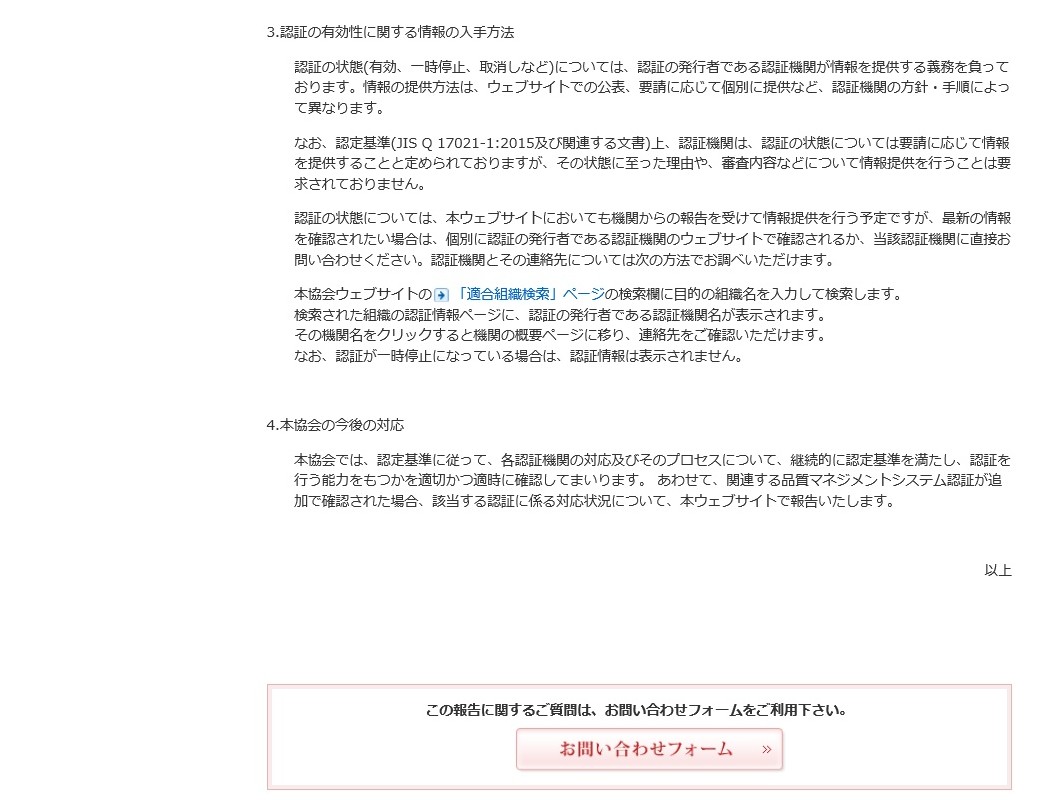
認証取得組織からのISO9001自主返上について 12/26/18(ISO認証機関 ビューローベリタス)

下記の記事のケースが去年の6月に施工不備が発覚で、適切な対応が行われていない。レオパレス21が悪質な会社なのか、去年の6月の時点で会社が財務的にゆとりがないのかよくわからないが、この記事の内容が普通であるのなら、レオパレス21は長く持たないと思う。オーナー達を泣かせる事により長く生き延びる可能性もある。
オーナー達や記事で国の検査体制を批判しているが、国の検査能力は高くないと思う。人材がいない。例え、検査能力が適切であったとしても、今度は違法や不正でお金を儲けたい業者が政治家や政府に儲けが出るようにお願いして結局、おかしくなると思う。
お金の力や影響力は凄い。バランスを保つことは難しい。レオパレス21とオーナー達が苦しむ事により他の人達が自己防衛策として多少、良い方向に自己修正するであろう。違法や不正がいけないと思っての自己修正ではなく、レオパレス21とオーナー達のようになりたくないとの生存本能から自己修正だと思う。
被害や影響が大きければ大きいほど、国交省は検査体制や基準を厳しくするであろう。だからと言って問題がなくなるわけではない。まあ、問題の影響を受けない人達は小さな幸せを感じるのだろうね!
インチキを売りにして商売している会社や人達が存在する。少なくとも知っている件が公になっているかと言えば「NO」である。だからインチキに乗っかる人達もいるし、騙される人達もいる。形が違えど、食うものと食われるものは存在する。自己責任で自衛するしかないと思う。自己防衛出来ない人、又は、運が悪い人は消えて行くしかないのかもしれない。
最大約1万4000人に退去が求められる可能性に発展したレオパレス21の施工不備問題。耐火性や遮音性に不備があるアパートも多く、入居者やオーナーから不安の声が上がっています。
入居男性「有名会社だから信頼できると…」
兵庫県伊丹市にあるレオパレス21のアパートで8年間、ひとり暮らしをしている伊藤信行さん(42)。2月初旬、住んでいる建物が防火基準を満たしていないことがわかりました。
「結構辛いですよね。不安もありますし怒りというか。レオパレスっていう有名会社だったので信頼できると思っていました」(伊藤信行さん)
去年、建設した建物のうち200棟余りのアパートなどで施工不備が見つかったレオパレス21。今月7日、新たに33都府県の1324棟の建物で耐火構造や遮音性が国の準を満たしていないなどの不備があったことを明らかにしました。
3階建ての共同住宅では延焼しにくくするため、天井の石膏ボードを2枚張りにすることなどが定められていますが、1枚だけになっていました。また、外壁の断熱材や部屋を区切る壁には綿状のガラス繊維素材などを使うことが定められていますが、実際はコストを低く抑えることができる発砲ウレタンが使用されていたのです。
「一番大きな問題は出火したときに燃えやすいことですから、寝ている間に隣から出火したときに十分に避難する時間がないとか、(避難する)時間がないままに燃えてしまうとか、そういうリスクが高くなると思います」(タウ・プロジェクトマネジメンツ 高塚哲治・一級建築士)
紙1枚だけで「3月末までに退去してください」
伊藤さんのもとには2月はじめ、レオパレスから一通の手紙が届きました。
「『何やろうな』って最初思って、『何かの請求かな』と思っていたら、『3月末までに退去してください』って内容の封書だったので。(Q.この紙1枚?)そうですね、これだけです。(Q.説明に回ってくることもなく?)全くありません。8年間ここに住んでいて、何不自由なく暮らしていたので、それがいきなり引っ越しってなって、辛いというか腹立たしい」(伊藤さん)
施行の不備が見つかった1300余りの建物に住む入居者の数は1万4400人あまり。レオパレス21はこのうち、耐火構造に特に問題がある641棟の約7700人に対し、3月末までに転居するよう求めています。伊藤さんは現在急いで引っ越し先を探していますが、思うように物件が見つからないといいます。
「引っ越し先がまだ決まっていない状態で仕事をしているので、それが一番不安です」(伊藤さん)
オーナー「2枚張りのはずが1枚だけ」アパートに施工不備
困っているのは入居者だけではありません。両親がレオパレスオーナーである男性は去年6月、大阪市内にあるアパートに施工不備があることがわかりました。
「『やっぱりか』という感じでは思いますね」(レオパレスオーナーの50代息子)
設計図では部屋を区切る壁が2枚張りとなっているにもかかわらず、1枚だけになっていたり、壁の板が途中で切断され隙間ができているのが見つかったのです。
そもそも、レオパレスは一般から募ったオーナーに建築費用などを支払わせてアパートを建設し、オーナーはそのアパートの部屋を貸して家賃収入を得ています。今回の施工不備は建築費を支払ったオーナーにとっても寝耳に水でした。問題が発覚してからもう8か月も経っていますが、未だに改修計画すら示されていないといいます。
「計画ぐらいは出してもらう。それに対して進捗を報告してもらったらわかるんですけど。今の時点でまだ何も連絡というか、(見通しが)立っていないという話なのでそこが一番心配ですね」(レオパレスオーナーの50代息子)
オーナー説明会 不安や怒りの声「何も解決していない」
2月17日、レオパレス21は関西で初めてとなるオーナー向けの説明会を開きました。
【説明会のレオパレス役員の音声】
「私どもがご心配ご迷惑をおかけして、誠に申し訳ございません」
説明会では、レオパレス21の役員が今回の問題が発覚した経緯や施工不備が見つかった建物に関する報告を行いました。
【レオパレス役員】
「何よりも会社のその時の体質、売り上げを急ぐ、工期を可能な限り短縮させる。3月末が入居の一番のシーズンなので出来る限りそこにあわせたいと」
今回の問題の原因について、少しでも売り上げを伸ばすため、3月の決算に間に合うよう工事を急いだなどと話しましたが、出席したオーナーからは…
【オーナーの音声】
「会社として隠蔽体質でしょ、どこが現場の責任なんですか。組織上の問題でしょ。予めわかっているわけでしょ。そういう反省もなしにどうして我々オーナーは納得できるんですか」
これに対し会社側は…
【レオパレス役員】
「おっしゃるとおりでございます。緊張感を持ってやれることを全て数か月の中で大至急やっていくと」
【オーナー】
「数か月じゃないですよ、数か月じゃ持たないですよ」
【レオパレス役員】
「肝に銘じて対応したいと思います。よろしくお願いします」
説明会は約1時間半に及びましたが、修繕を行う具体的な時期などは示されず、出席したオーナーたちの不安を取り除くことはできませんでした。参加したオーナーは…
「謝罪はありました。ありましたけど、そう簡単なものではないし、謝罪があったからと言って、まだ何も解決はしていませんし。実際に(改修が)履行されてからじゃないと不安は払拭されませんので」(レオパレスオーナーの50代息子)
このほか説明会に参加したオーナーからは「改修費の負担や家賃保証をするというが、レオパレスにつぶれられても困る」、「改修が終わってもイメージダウンで新たな入居者を探すのが難しいのでは…」といった声もありました。全国に広がったレオパレス21の施工不備問題。入居者とオーナーの不安は増す一方で先行きは不透明です。
これが氷山の一角で他の農家も同じような対応していたら豚コレラ感染は当分収束しないだろう。
外国はもっとひどいと聞く。中国やインドでは死んだ豚などをミンチにしたり、他の豚とまぜて売っているらしい。普通な事なのでおどろくことではないらしい。海外生活が長くなると信用できないルートの食物を食べれなくなると言っていた。
19日未明、愛知県愛西市で、死んだ豚を燃やしたとして警察と県が養豚場の管理者の男性から事情を聴いています。豚コレラの感染が広がっていますが、男性は豚の異常を愛知県に報告していませんでした。
19日午前1時過ぎ、愛西市内の養豚場の近くを通りがかった女性から「何かを燃やしていて臭いがひどい」との通報があり、警察が駆けつけたところ、男性が数頭の豚を燃やしていました。
男性に事情を聞いたところ「養豚場で死んだ豚を5頭、燃やして処分しようとしました」と話しているということです。
豚コレラの発生以降、県は養豚業者に対し、飼育する豚に異常が見られる場合は速やかに報告するよう求めていますが、男性は報告せず死んだ豚を燃やしていました。
現在、愛知県の担当者が現場に入り、この養豚場で飼育されているほかの豚に異常がないか、検査しています。
「レオパレス21」が生き残れるのか見当が付かないし、生き残れようが生き残れなくても個人的には関係ない。
不正や違法に直接的、又は、間接的に関与して問題が発覚し、大きく取り上げられた時のリスクを負いたくないので、仕事が取れなかったり、利益が少なくても仕方がないと思いながら選択する。「レオパレス21」の問題は存在していたが問題として注目を集めてこなかった。これまでの人生経験から言えば不正や違法を行っても、痛い思いをする人達や会社は実際にやっている人や会社に比べればはるかに小さい数字だと思う。
だから痛い思いをしている人達や会社のニュースが報道されても、極端に不正や違法行為を止める事はないのだと思う。止める人達や会社は存在すると思うがやはり数字で考えれば少ないと思う。
関係者達からすればドライな意見は受け入れられないだろうが、レオパレス21に関しては自業自得だし、騙された人達はもっと慎重に判断するか、不正や違法を知る事が出来なかった場合は運が悪かったと諦めるしかないと思う。
例えば、自分で適切な判断が出来なくても、情報通の知り合いがいるとか、いろいろな噂から最悪のケースや確率を考えて判断してくれる知り合いがいれば被害者にならないかったかもしれない。安全な選択ばかりを取ると大きな儲けは得られないと思うので、自分の判断や信用できる人の判断を信用してリスクを負う事は必要だと思う。投資はギャンブル的な面があると思う。不確実な部分が存在する中で判断するしかない。本当に安全であれば
皆同じ選択するので配当(利益)は少なくなる。大穴があるから、確率は非常に少ないが高額のお金を受け取る事が出来るのだと思う。
人生自体が判断の連続である。判断しなくても、判断しない選択、行動を起こさなくても行動を起こさない選択を選んでいる事になると思う。
最後に「金融庁は・・・融資の審査が適切だったかどうかも調べる。」と書かれているが、会社が不正を行う体質であれば、その他の部分でも不正を行った可能性は高いと思う。個人的な不正であれば、個人の活動や権限がある部分に限定されると思うが、組織として不正を容認していれば、組織の人間が不正は容認されると判断して他の部分でも不正を行う可能性は高いと思う。
賃貸アパート大手「レオパレス21」(東京都中野区)の物件で施工不良が見つかった問題で、金融庁は物件所有者(オーナー)向けの融資が焦げ付く可能性がどの程度あるのかを把握するため、各金融機関を一斉調査する方針を固めた。レオパレスは補修工事費用や募集保留期間中の空室賃料を補償するとしているが、募集を再開しても、信用失墜で入居者が集まらず、返済が滞りかねないと判断。国土交通省と連携し、施工不良物件の範囲が固まり次第、着手する。融資の審査が適切だったかどうかも調べる。
【新たに判明した建築基準法の規定違反】

レオパレスの物件を巡っては、設計図と異なる天井部分の工事を行い、耐火性能が不足するなどの施工不良が、33都府県の1324棟で今月、新たに発覚。改修のため、入居者計1万4443人に転居を促す事態になっている。これらの物件を含め、全3万9085棟の調査を実施中だ。1月28日現在、調査した約1万4000棟のうち、8割以上で何らかの不備が見つかっている。補修工事が終わるまで入居者を募集しないため、今後、空室率が急増する見通しだ。
レオパレスは、オーナーから賃貸アパートの建築を受注し、完成後に一括で借り上げて転貸する「サブリース」を展開している。オーナーに対しては、空室でも一定の家賃収入を保証しており、毎月支払う家賃の総額は約250億円に上るという。
金融庁は、入居者の住み替え費用の全額負担や、補修工事費の計上に加え、信用の失墜で経営がさらに悪化する恐れがあると判断。同社と取引するオーナー数や物件数が多いことから、国交省の協力を得ながら、金融機関を通じて返済への影響を早期に見極めることにした。【鳴海崇】
結果として賠償金10億円は想定外の展開だったと思う。まあ、基礎学力不足と会社の強欲が最悪の結果となって表れたと言う事だと思う。
不動産会社APAMANは13日、傘下の賃貸仲介会社が運営する札幌市豊平区のアパマンショップ平岸駅前店で引き起こした爆発火災事故の賠償金などで、2019年9月期に特別損失10億円を計上すると発表した。これに伴い、同期の連結純損益予想を従来の6億円の黒字から1億円の赤字に下方修正した。
また、爆発事故に関する経営責任を明確にするため、大村浩次社長が月額報酬の30%を3カ月間返上するなどの社内処分を決めた。
「不正融資が金融庁から業務停止処分を受けたシェアハウスなど投資用不動産以外でもまん延していた可能性があり、信頼回復がさらに遠のきかねない。」
銀行の体質に問題があれば、どこかに吸収合併されるなどしてまともな銀行があるのか知らないが、かなり良いと思われる銀行のやり方に染められる以外、改善は難しいと思う。
体質に問題があれば今までの問題を最小に偽装したり、隠そうとする行員がいるから膿を出しきれない。信頼を失った状態で厳しい環境で回復するのはかなり難しいと思う。苦しくなってまたおかしな事をやると思う。
油圧機器大手のKYBは13日、全国で千件を超える建物に設置した免震・制振装置に検査データの改ざんがあった問題で調査結果を公表した。不正の原因として納期順守や「受注ありきの工場運営」を挙げた。2019年3月期の連結純損失の予想は従来の42億円から100億円に下方修正した。不正があった装置の交換費用などを織り込み、赤字が拡大する。
KYBは昨年10月、装置の性能検査で、国や顧客の基準の範囲内に収まるよう数値を書き換えていたと発表した。外部の弁護士らでつくる調査委員会が不正の詳細や背景を調べていた。
「不正融資が金融庁から業務停止処分を受けたシェアハウスなど投資用不動産以外でもまん延していた可能性があり、信頼回復がさらに遠のきかねない。」
銀行の体質に問題があれば、どこかに吸収合併されるなどしてまともな銀行があるのか知らないが、かなり良いと思われる銀行のやり方に染められる以外、改善は難しいと思う。
体質に問題があれば今までの問題を最小に偽装したり、隠そうとする行員がいるから膿を出しきれない。信頼を失った状態で厳しい環境で回復するのはかなり難しいと思う。苦しくなってまたおかしな事をやると思う。
スルガ銀行の行員がデート商法詐欺まがいの行為に関与し、個人向けの無担保ローンを融資していた疑いがあることが13日、関係者の話で分かった。借入金使途や年収が改ざんされた書類に基づいて契約するなど、ずさんな手続きだったもようだ。スルガ銀広報室は共同通信の取材に、弁護士を交えた調査に着手したことを明らかにした。
不正融資が金融庁から業務停止処分を受けたシェアハウスなど投資用不動産以外でもまん延していた可能性があり、信頼回復がさらに遠のきかねない。このローンを巡る事実関係について広報室は個別の取引であることを理由に説明を控えた。
チェックや確認作業は経験、知識又は/そして資格があれば出来ると思う人は多いだろう。個人的な経験から言えば、悪質な会社や人達が存在するのでそのようなケースの対応を想定して報酬なり、権限や対応を想定しないと現実的には検査体制の適正化の現実化は無理だと思う。
悪質でもレベルが違ってくると思う。嘘、偽造書類や偽装データ、嫌がらせから脅迫までいろいろなレベルがある。コスト削減のため、納期短縮のためなどいろいろあるが、結局はお金である。つまり、納期短縮により人件費、レンタルしていれば日数の短縮、人材であれば、短縮により人件費だけでなく他の現場に人材が移動できるので効率がアップするなどで利益がアップする。
悪質な対応やインチキするメリットがあるのである。問題を見抜く人達は敵であり、利益を下げる人達になるのである。そんな仕事を安い料金や給料で受ける人達がいるのか?そんな仕事をするよりは検査を簡単にしたり、問題を黙認するほうが、仕事の依頼はアップするし、仕事は楽だし、儲けもアップする。
大阪市の上水道工事の不正では「実際に水道工事を担当したことがある元市職員も、『業者は改良土を使わず、砕石や堀った土を埋めていた』と、不正に気付いていたことを取材に認めた。『職員はみんな見て見ぬふりをしていた』と悔やむ。」との証言する元市職員がいる。公務員達であってもこのような問題が起きるのである。
レオパレス21のオーナーの中にはコストアップには嫌な顔をする人達はいると思う。ただ、今回のように問題が公になり被害をうけるようになって動いた人達はいるのではないのか?
少子化の流れは変わらないし、人口は減っているのだから最悪、レオパレス21が倒産しても短期的に問題が起きると思うが、中長期的には問題はないと思う。オーナーにとっては最重要事項となるが、関係ない人達にとっては時間が経てば忘れられるであろう。
レオパレス21の施工不良の問題で、複数のオーナーが12日、国土交通省などに監視体制を強化するよう求めた。オーナーなどによると、行政とオーナーに出す図面とは別に、建築現場には施工マニュアルという形で、建て方の指示と材料が届き、それに従い、下請け業者は物件を建てていくという。マニュアルには、組み立て方はあるものの材料までは記されていなかったという。図面通りに建てられるかどうかを確認するのは現場に立ち会う建築士で、各自治体は建てる前と建てた後にチェックする必要がある。施工不良の物件が見つかった東京都立川市の担当者は「部材とか製品という部分については工事監理者の報告の内容をもとに適合、不適合と判断している」として、「見抜くことは困難だったと考えられる」と話す。レオパレスの物件に関する書類を見ると、設計者と工事監理者は同じで、身内がチェックしていたことになる。現在の法律では問題はないが、物件のオーナーらは「検査体制の適正化の実現に向けた、法整備の改正を提言していきたい」と訴えた。
「レオパレスの物件オーナー会の代表者らが午後に国会を訪れ、国交省にはレオパレスに対する監視体制の厳格化を求めるということです。オーナー側は『検査体制の不備は国に責任がある』と話しています。また、金融庁には不動産融資の在り方について見直しを求め、レオパレスに低金利で大規模な融資を金融機関に促してほしいと要望する予定です。」
ヒューザーの違法建築マンションなどの問題では国の検査体制の不備は問われていない。監視体制の厳格化と言っても、規則を厳しくするのか、制度を改善するのか、検査する機関や検査員に対する罰則を重くするのか、具体的に言わないと無理だと思う。規則を厳しくしても、検査する機関や検査員が手を抜けば、規則を厳しくしても問題は見過ごされる可能性がある。規則を厳しくし、検査する機関や検査員に対する不適切な検査の罰則を重くしても、不適切な検査である証明が簡単に出来なければ、処分されない可能性がある。また、検査する機関や検査員が厳しくチェックするようになれば納期やコストに影響を与えると思う。たぶん、コストアップになると思う。
総合的に見て多くのアパートのオーナーと借り手の多くが規則を満足しているアパートを求めるデメリットを理解して望むのであればこのような問題が簡単に起こせないように改善すれば良いと思う。
しかし、残念ながら今回の賃貸アパート大手「レオパレス21」の問題には適用されないので将来の改善しか期待できない。いつもの事だが大きな問題が起きないと問題が改善されない。
賃貸アパート大手「レオパレス21」の物件に耐火性が基準に満たない素材が使われた問題で、12日午後、オーナーの代表者らが国土交通省と金融庁に検査の厳格化などを求めます。
レオパレス21は全国の1万棟以上のアパートで施工不良が発覚し、8000人近くが来月中の退去を求められています。こうしたなか、レオパレスの物件オーナー会の代表者らが午後に国会を訪れ、国交省にはレオパレスに対する監視体制の厳格化を求めるということです。オーナー側は「検査体制の不備は国に責任がある」と話しています。また、金融庁には不動産融資の在り方について見直しを求め、レオパレスに低金利で大規模な融資を金融機関に促してほしいと要望する予定です。
「一連の問題を巡っては、不正に関する情報を一部の市職員が放置していたことも既に明らかになっている。市は今後も、弁護士らによる監察チームで調査を続ける。」
弁護士らによる監察チームしっかり調査するのかな?厚生労働省による「毎月勤労統計」の不正調査を検証した第三者委員会「特別監察委員会」には弁護士達が含まれているけど、適切な調査を行ったとは思えない。
大阪市発注の上水道工事を巡り、関わったほぼ全ての業者が不正な利益を得ていたことが、市関係者への取材で明らかになった。工事で道路を掘削した後、安全性の高い資材を埋め戻したと伝票上で偽り、実際には安価な砕石を戻す不正が横行していたことが毎日新聞の報道で発覚。これを受け、市水道局が2012年度以降に完成した約1100件の工事を調査したところ、全体の95%以上で不正が確認された。
ほぼ全ての業者が不正を認めており、市は近く調査結果を公表し、計約400社を一斉に3カ月の指名停止処分にする方針。市の工事に参加する業者の大半を占めている。これほど大量の指名停止は過去に例がない。市内の水道管の老朽化率は全国的にみても高く、今後の更新工事などが滞る恐れが出てきた。
市は03年度以降、水道工事で地面を掘った際の埋め戻し材に、「改良土」を使うよう設計書に明記している。改良土は、建設工事で出た土に石灰を混ぜて水分を除去し、有害物質が含まれていないかを確認した再生資材。掘削土の状態を調べた上で、安全性が高い改良土を使う決まりになっている。市指定の土壌メーカーが製造している。
毎日新聞は昨年2月、改良土の代わりに、業者がコンクリートなどを砕いた安価な再生砕石を埋める不正が横行していると報道。高価な改良土と再生砕石との差額は、公金で業者に支払われていることから、市は記録が残る12年度以降の工事について調べた。
複数の関係者によると、これまで調査した完了済みの水道管敷設工事652件と、細い給水管の約500件の工事を調査。その結果、改良土が適正に使われていたのは、30件程度しか確認できなかった。関与した業者のほぼ全てが市の調査に「実際には改良土を使っていなかった」と認めたという。
適切な資材を使わないと契約違反となり、安全性の問題も懸念されるが、道路陥没などの実害は確認されていない。改良土を使ったとする工事費が支出された形だが、市は「改良土と砕石の差額が算出しにくい」などとし、業者への損害賠償請求は見送るという。
調査開始時に施工が始まっていた工事約270件については、大半が適切だったと判断されたが、一連の問題発覚後に改良土に切り替えた疑いがある。
一連の問題を巡っては、不正に関する情報を一部の市職員が放置していたことも既に明らかになっている。市は今後も、弁護士らによる監察チームで調査を続ける。【遠藤浩二】
「実際に水道工事を担当したことがある元市職員も、「業者は改良土を使わず、砕石や堀った土を埋めていた」と、不正に気付いていたことを取材に認めた。「職員はみんな見て見ぬふりをしていた」と悔やむ。・・・ある業界関係者は「市がきちんと調べれば、もっと早く不正は分かったはず。あまりにもずさんだ。業者だけでなく、市職員も処分されるべき」と憤る。」
公務員は処分されない制度が「職員はみんな見て見ぬふりをしていた」との結果になったと思う。父親に殺害された千葉県野田市の小学4年の女児と基本的には同じ。「責任を取らされる事はない。」との考えがベースに存在していると思う。公務員の給料が大手企業を基本にするのであれば、責任の取らせ方に関しても民間並みにするべきではないのか?給料は同じ、ノルマはない、そして責任は問われないでは総合的に判断して同じとは考えられないと思う。
職員の処分方法について今回の事件には適用されないにしても今後の問題に対しては処分方法を改善し、厳しく処分するべきである。
民間会社の全ての工事を監督できないと公務員は言うかもしれない。公平ではないが、効率とコストを考えれば抜き無知チェックを行い、問題が発覚した場合、厳しい処分を下すしかない。そして、チェックを行う職員は警察との連携が可能になる制度を事前に準備しておくべきである。不正による利益はお金である。お金のためにはいろいろな人間に見返りを約束したり、お金を払って妨害や恐喝を考える人間達は存在すると思う。そこまで考えて対応しなければこのような問題は簡単には減らないと思う。
大阪市が適切な対応を取らなければいろいろな圧力、利権、お金、利害関係、そして政治家との関係などいろいろな問題が市役所内にも存在すると疑うべきだと思う。
ほぼ全ての工事で業者による不正が発覚した大阪市発注の上水道工事は、受注業者の大半が3カ月の指名停止処分を受けるという、前代未聞の事態に発展する。長年にわたる不正は、これまで何度も市に指摘された経緯もあり、市のチェック態勢のずさんさが改めて浮き彫りになった。関係職員の処分を求める声も出始めており、今後の市の対応が注目される。【遠藤浩二】
「うちだけでなく、どの業者もみんなやっていた」。市内のある水道工事業者が取材に打ち明けた。この業者は工事後、市指定の改良土を使わず、安価な砕石などを埋め戻していた。
安全性の高い改良土は1トン200~400円で取引されるが、市内では砕石が1トン50円程度と、かなり安価で手に入る。改良土を指定メーカーから運ぶ手間と費用もかからず、長年不正を続けていたという。「ここまで広がっていたとは思わなかった。確かに悪いことをしたが、市役所が知らないわけがない」とも強調する。
実際に水道工事を担当したことがある元市職員も、「業者は改良土を使わず、砕石や堀った土を埋めていた」と、不正に気付いていたことを取材に認めた。「職員はみんな見て見ぬふりをしていた」と悔やむ。
これまでに、改良土メーカー2社が市に不正を指摘。うち1社は2015年と16年、「自社の伝票が偽造され、改良土が使われたことにされている疑いがある」と市に直接伝えたが、市は偽造について確認せず、不正は野放しにされた。
ある業界関係者は「市がきちんと調べれば、もっと早く不正は分かったはず。あまりにもずさんだ。業者だけでなく、市職員も処分されるべき」と憤る。
掘削時の産廃、管理票を大量偽造も
大阪市の上下水道工事を巡っては、他にも多くの不正が明らかになっている。
水道工事では、道路を掘る際に出るアスファルトと、その下地となる砕石や鉄鋼スラグが産業廃棄物となる。毎日新聞は昨年4月、産廃を適切に処理したことを示す管理票「マニフェスト」が大量に偽造された疑いがあると市に指摘。市は調査したマニフェストのうち、半数に当たる約2万3500枚に偽造の疑いがあると発表し、現在も調査を進めている。
複数の業者は、産廃処分場の印鑑を偽造して処分場で適切に処理したように装い、大阪・関西万博の開催地に決まった人工島・夢洲(大阪市此花区)に産廃を大量に不法投棄したと証言している。
一方、下水道工事でも、市が指定した資材を使わない不正が横行している。市はこれまでに、2012年度からの対象工事269件のうち、171件で不正を確認。110社を指名停止処分にし、計約1億6400万円を業者に賠償請求している。
黒字が出ない企業は黒字を出すような選択を取るか、銀行などの債権者が引導を渡すまでの時間の問題であれ、吸収合併、倒産、破産、そして事業譲渡などネガティブな選択しか残されていない。
カリスマのある経営者に交代、外部から有能な立て直しのプロ、又はその他の選択で立て直しを試みる事は出来るが痛み、優先順位が低い項目の断念、従業員の削減、無駄ではないが断念する、又は、中止する項目などいろいろな物を受け入れなければならない。士気は下がるし、忠誠心や愛着を失う可能性はあるし、会社を見捨てる従業員が出てくる可能性がある。
景気の上向きや時代の流れが良い方向に向くなど運の部分はあると思うが、傾く会社を戻すのは難しと思う。下記のケースは会社が存続する事を前提とした話であるが、将来、存在しない可能性のある会社に対してはどのような対応が出来るのだろうか?倒産する前に貰えるものは貰っておく方法なのだろうか?
スバルで2015年~2017年に7億円以上の残業代未払いがあり、対象社員は3421人だったことが今年1月にわかり、大きな波紋を呼んだ。2016年12月にあった群馬製作所の男性(当時46)の自殺が労災認定され、そのことを遺族代理人が発表したことに伴い、発覚した問題だ。
亡くなった男性の場合、記録上の残業時間はゼロとなっていた。午後5時の時点でいったん入出ゲートで退出処理をしたうえで自席に戻り、改めて仕事を再開するというのが「当たり前」になっていたとされる。
男性は長時間労働と上司からの厳しい叱責のため、うつ病となり、飛び降り自殺した。帰宅前に家族に送ったメールの時間などから推定すると、うつ病の発症前1カ月は残業が「124時間31分」、2カ月が「100時間39分」だったとみられるという。
今回はスバルで深刻な問題があることがわかったが、他社の残業代未払い事例も度々報じられている。未払いは「論外」だが、それ以前に、退社したことにして残業するのも大きな問題だ。労働問題に詳しい河村健夫弁護士に聞いた。
●立証責任は労働者側に
ーー表向き「退出」としておきながら、残業をさせることが当たり前になっている職場の問題点を教えてください
「サービス残業をさせた上に、証拠の隠滅工作をするとはとんでもない会社ですが、このような会社は時々目にします。常套手段はタイムカードを退勤で押させた後に残業させる方法です。
こんな行為は、もちろん違法です。労働基準法は使用者に労働日数や労働時間等を適正に記入した賃金台帳等を作成し、3年間保存する義務を課します(労働基準法108条等)。使用者の労働時間把握義務は、労働安全衛生法66条8の3でも明示されています。
表面上『退勤』扱いとしつつ仕事をさせる行為は、労働時間を故意に少なく見せかける違反行為です。このような違法行為は、上司にも本人にも不利益を生じます」
ーーどういうことでしょうか
「残業をした本人には、実際の労働時間に基づく残業代請求を行おうとしても証拠がなく、満額の残業代をもらえないリスクが生じます。
残業代を請求する裁判では原告に立証責任がありますので、会社側が嘘の時刻を記載したタイムカードを定時退社の証拠であるとして提出したときには、労働者が実際の労働時間を裏付ける証拠を提出しなければなりません。
また、過労により健康を害しても、虚偽のタイムカードが証拠とされて労働時間が少なく算定され、労災が認められないリスクも生じます」
ーー上司についてはどうでしょうか
「サービス残業を隠蔽しようとした上司には、損害賠償責任が生じます。
上司は時間管理義務についての『履行補助者』と呼ばれますが、故意に履行補助者としての任務(部下の労働時間等を把握する義務)を放棄したのですから、不法行為の加害者として賠償責任を負います。
会社が遅延利息を含む多額の残業代の支払いをした際は、会社の損害の分担を求められることもあります」
●サービス残業は給与額を「低く偽装する行為」
ーー未払いの残業代を会社は簡単に払ってくれるでしょうか
「サービス残業が横行する職場というのは、労働者の基本的権利である給与についてすら我慢を強いられる職場ですから、在職時に残業代を払ってくれとは言い難いでしょう。どうしても退職時の請求が多くなります」
ーー請求しにくい雰囲気もあるのかもしれませんね。ただ時効の問題がありますよね
「はい。残業代請求には2年の時効があります。つまり、10年間サービス残業を我慢しても、退職時に残業代請求をした場合は2年分しか回収できないということです。
この点については、民法の時効に関する規定の改定に合わせて残業代の時効も5年にしようとする動きもありますが、企業側の抵抗でなかなか前に進んでいない状況です」
ーーサービス残業の蔓延は、企業にとってもマイナスイメージになりますよね
「サービス残業の横行は企業の側にも損失をもたらします。違法行為が職場で横行することによる勤労意欲の減退や生産性の低下、発覚による企業イメージの低下、発覚により一時に多額の残業代を払わなければならなくなる経営リスクなど、そのマイナス面は多大です。
労働者が自らの働きぶりに関する評価要素として重視するのは、何と言っても『給与』です。サービス残業はその給与の額を『低く偽装する行為』ですから、労働者からすれば使用者による最大の裏切りです。働く側の視点を使用者も忘れないでほしいと思います」
【取材協力弁護士】
河村 健夫(かわむら・たけお)弁護士
東京大学卒。弁護士経験17年。鉄建公団訴訟(JR採用差別事件)といった大型勝訴案件から個人の解雇案件まで労働事件を広く手がける。社会福祉士と共同で事務所を運営し「カウンセリングできる法律事務所」を目指す。大正大学講師(福祉法学)。
事務所名:むさん社会福祉法律事務所
「同社は発泡ウレタンを使った理由について「価格は安くないが、作業効率が高い。法令違反の認識はなく、現場の施工管理体制が不十分だった」と説明する。しかし、現場監督経験のある建築関係者は「ありえない話だ。現場は設計図と部材が異なることに気付いていたはず。施工不良は長期にわたり件数も多く、うっかりミスなどではない。組織的に行われていた可能性が高い」とみる。」
図面、施工指示、発注資料、 納入資料、そして現場の全てを見なくても専門家、業者、又は知識がある人達は問題に気付くと思う。
このような現状で建築確認が通るシステムでは、国交省はヒューザーの違法建築マンションから何を変えたのだろうか?
賃貸アパート大手「レオパレス21」(東京都中野区)の物件で施工不良が新たに見つかった問題で、同社が施工不良の物件で使用した外壁などの部材が、建築基準法で認められていないものだったことが国土交通省などへの取材で判明した。コスト削減のため耐火性に劣る違法な部材を使っていた可能性があり、業界では「組織的な不正」を指摘する声も出ている。
同社はアパートの外壁の内部に使う部材について、自治体などにはガラスを溶かして繊維状にした「グラスウール」などを用いると申請していたが、実際には「発泡ウレタン」を用いていた。グラスウールは断熱性・耐火性が高く、建築基準法で使用が認められているが、発泡ウレタンは耐火性が劣り、外壁への使用は認められていない。
同社は発泡ウレタンを使った理由について「価格は安くないが、作業効率が高い。法令違反の認識はなく、現場の施工管理体制が不十分だった」と説明する。しかし、現場監督経験のある建築関係者は「ありえない話だ。現場は設計図と部材が異なることに気付いていたはず。施工不良は長期にわたり件数も多く、うっかりミスなどではない。組織的に行われていた可能性が高い」とみる。
不動産コンサルタント会社「さくら事務所」の長嶋修会長は「発泡ウレタンの方がグラスウールより価格が安い。コスト削減のため意図的に安い部材を使っていたのではないか。そうでなければ、わざわざ部材を変える必要はない」と指摘している。【川口雅浩】
「レオパレスはこれまでの記者会見で『社内の設計部門と(部材の)発注部門の情報共有が図れていなかった』『図面の表記の不統一で現場の誤解を招いた』などと説明してきた。」
統計不正の厚労省と同じような言い訳だ。
不正調査問題の外部有識者による特別監察委員の会荒井史男委員長代理(元名古屋高裁長官)は弁護士なので何とかしてくれるかもしれない。
地獄の沙汰も金次第はケースバイケースだけど現実的に成り立つことはある。
レオパレス21が国の基準を満たさないアパートを建てた問題で、同社が地方自治体に出した建築確認用の設計図面には基準に合った部材を記しながら、実際の現場には基準外の違う部材を運び込んだ疑いのある事例が複数見つかった。関係者が8日明らかにした。
アパートなどを建てるレオパレスのような業者は、その図面を地元の地方自治体に事前に出して、建築基準法の法令を満たしているかどうかの確認を受ける。「建築確認」と呼ばれる仕組みだ。
関係者によると、今回不備が明らかになった物件の中から、レオパレスが図面に記した部材と、同社が建築現場に実際に運び込んだ部材が違う物件が見つかった。その中に、図面の部材が基準を満たす一方、運んだ部材は基準を満たしていない例が複数あった。
レオパレスはこれまでの記者会見で「社内の設計部門と(部材の)発注部門の情報共有が図れていなかった」「図面の表記の不統一で現場の誤解を招いた」などと説明してきた。
「東京都日野市のアパートに住む女子大学生(20)は昨夏に同社の施工点検を受けたが、調査結果の連絡はない。『ニュースを見て不安を感じる。私たちの安全より、ばれなければそれでいいと思っていたのでは』と憤った。」
大変だけど良い人生勉強になったのではないのか?「安全より、ばれなければそれでいい」と思う人達や会社は存在するし、数でも言ってもかなりあると思う。この事を忘れずに、就職活動、住宅やマンションの購入、その他の高価な買い物の時に生かせれば、これぐらいの苦労は逆にプラスになると思う。世の中、学校では教えてもらえい、問題が大きくなるまでニュースにならない事はたくさんあると思う。少なくとも個人的にはそう思う。
レオパレス21のアパートで暮らす住民やオーナーには動揺が広がっている。川崎市のアパートに暮らす大学3年の男性(21)は「大手だから安心と思って選んだのに。不安と不満しかない」と語る。
【新たに判明した建築基準法の規定違反】
学業と部活の両立のため、2017年春に引っ越した。「当社施工物件における界壁(各戸を区切る壁)工事の不備について」という文書が届いたのは昨年6月。施工に不備があった場合、転居や一時的な住み替えの希望に応じると書かれていたものの、その後会社から連絡はない。
現在は就職活動の真っただ中で「仮に引っ越しとなっても時間がない」とため息をつく。会社の窓口に電話をかけ続けたがつながらない状態が続いた。
東京都日野市のアパートに住む女子大学生(20)は昨夏に同社の施工点検を受けたが、調査結果の連絡はない。「ニュースを見て不安を感じる。私たちの安全より、ばれなければそれでいいと思っていたのでは」と憤った。
福岡県宗像市の男性(69)は09年に同社でアパートを建ててオーナーになった直後から土台や廊下でひび割れが相次いだ。同社の対応にも疑問を感じ、昨年に運営や管理などの契約を解除した直後に不具合を調べる連絡が届いた。
しかし、同社に連絡すると「件数が多すぎていつ調査できるか分からない」。10月になってようやく社員が説明に来たが、調査への立ち会いを求めると拒否され、いまだに調査できていない。
20戸の入居者には安心してもらうため男性が独自に調査すると説明して回った。「一切迷惑をかけないという触れ込みだったのでオーナーになったのに。もはや詐欺的だ」と語気を強めた。【千脇康平、山本有紀、堀智行】
下記が立証されればゴーン被告は終わりだね!
日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告(64)が、レバノンで日産販売代理店を経営する友人側に、日産から計約33億円を融資させていたことが7日、現地関係者への取材で分かった。融資金の大半は返済されておらず、本来の目的以外に使用された可能性もあるという。東京地検特捜部も把握しており、不正融資の疑いもあるとみて資金の流れを慎重に調べている。
この代理店には平成24年以降、当時日産の最高経営責任者(CEO)だったゴーン被告が直轄する「CEOリザーブ」という予備費から、日産子会社「中東日産」を通じ、インセンティブ(報奨金)を装って約17億円が支出されている。
関係者によると、融資されたのは計3千万ドル(現在のレートで約33億円)で、CEOリザーブからではなく、通常の事業費から支出されていた。24年に1千万ドルが融資された後、25年に500万ドル、28年に1500万ドルがそれぞれ追加された。これらは全てゴーン被告の指示で行われ、金利の一部を除き、ほぼ返済されていないという。
融資先は、代理店を経営する会社のオーナーが代表となっている別の会社。融資を受けるために設立された実体のないペーパーカンパニーとみられる。
目的について、ゴーン被告は「オーナーから『会社(代理店)の株を買い増しして過半数を取得し、意思決定を迅速にするので貸してほしい』と頼まれた」と説明したが、実際には株は買い増しされていない可能性があるという。
28年の融資では、ゴーン被告から「2日後までに用意してほしい」と切迫した様子で要請があったとされる。
融資が日産の業務と関係なく、オーナーの利益を図る目的だった場合、会社法違反(特別背任)に該当する可能性もあり、特捜部は資金の流れや融資目的などを詳しく調べている。
中東の日産販売代理店をめぐっては、オマーンの店にもCEOリザーブから約35億円が報奨金に偽装されて支出されていたことが明らかになっている。(ドバイ 山本浩輔)
レオパレスが故意に違法アパート建てたのなら自業自得!
レオパレスは違法を知らず、下請けが勝手に違法アパートを建てたのなら下請け業者の自業自得!
事実は知らないが不正が発覚する確率の方が低いと思うので、不正が発覚した場合は自業自得だと思う。
アパート建設大手、レオパレス21が建てたアパートに建築基準法違反の疑いが出ていた問題で、同社は7日、国の基準を満たしていない物件が新たに見つかり、法令違反の疑いがある建物が延べ1324棟にのぼると発表した。これまでに施工したアパート計3万8千棟余りを調査したところ、外壁や天井の耐火性や遮音性などについて国が認定する仕様と異なる物件が見つかったという。
補修工事などの費用として360億円の特別損失を2018年4~12月期決算で計上し、19年3月期通期の純損益は380億~400億円の赤字になる見通し。18年10月時点では、50億~70億円の純損失を見込んでいたが、赤字幅が大きく膨らむ。(田中美保)
行政の怠慢と業者の利益優先主義が状況を悪化させたと思う。行政は統計不正の厚労省のように言い訳を考えるのに(税金が財源の給料を貰いながら)必死になるのだろう。業者の利益優先に原因があるが、良心的にまじめに頑張っている業者が一番の被害者のように思える。
小4女児が父親に殺害された事件のように行政は自分達の事が最優先で業者は二の次だろうし、仕方のない事なのかもしれない。どの世界にも問題はある。嫌で撤退できるのなら撤退すれば良いと思う。業界が縮小すれば、今度は税金を使って新規参入や規模拡大の支援をするだけ。税金と呼ばれる血を吸う行政は寄生虫のように生きる事が出来る。行政次第では人々はもっと幸せに楽に暮らせることが出来ると思う。行政は人々によって動かされる。行政は独り歩きしない。
日本や日本人達にも責任がある。子供達の人格形成や教育に権限や責任がある文科省に部分的に責任があると思う。まあ、文科省事態、組織として問題を抱えているようだし、身内に甘く自浄能力に欠落しているのだから大した期待は出来ないのかもしれない。
科学や技術が進歩する。しかし、人は成長してもやがて死ぬ。悪い奴らもやがて死ぬ。そして悪い奴らは新たに生まれる。似たようなサイクルが繰り返される。同じ事を繰り返すのか、良い方向に変えるのかは人々次第である。苦しんだり、痛い思いをしなければ、学ばない人達はいるし、それでも学ばない人達はいる。最終的には運次第である。
岐阜市で昨年9月に国内で26年ぶりに発生した家畜伝染病「豚(とん)コレラ」は6日、一挙に5府県へ拡大した。農林水産省と岐阜県は飼養衛生管理基準の順守による封じ込めを進めてきたが、有効な対策を打ち出せておらず、さらなる拡大も懸念される。農水省は同日、岐阜市内に現地対策本部を設け対策に本腰を入れるが、発生から5カ月たった今も収束の兆しは見えない。県内の養豚業者からは「拡大を防ぐため、ワクチン投与などの抜本的な対策が必要だ」との声も上がっている。
恵那市内の養豚場で豚コレラの感染が確認されたことなどを受けて、古田肇知事は6日の対策会議で「収束が見えない中、さらに拡散する事態で大変重く受け止めている」と述べた。
岐阜市内で現地対策本部の発足式に臨んだ小里泰弘農水副大臣は同日、県庁で古田知事と面談し「想定外の事態」と言い表した。県庁内からは「当然、想定しておくべき事態だ」と国の対応の遅さを皮肉る声も漏れた。
農水省はこれまで、農場の防疫の手引きともいうべき飼養衛生管理基準を盾に「しっかり守れば発生しない」と繰り返した。県が手探りで進める野生イノシシ対策にも具体策は示さなかった。
今月5日に農水省は、国による県内全養豚農場の現地指導、現地対策本部の設置、対策事業の緊急拡充の三つを発表した。県が行ってきた農場の指導に国や第三者機関が加わる現地指導は、飼養衛生管理基準の順守徹底を掲げるが、農場指導に当たる県担当者は「農場の規模によって柔軟な対応が必要」と対応の難しさを語る。農家にとって有益な防疫改善につながるかは不透明だ。さらに、野生イノシシの拡散を防ぐ防護柵への補助制度も、県は既に70キロ以上の防護柵を完成させており、連携のぎこちなさが透けて見える。
農水省はワクチン投与に消極的だが、5府県に感染が広がった今、県内の養豚業者には「ここまでの感染拡大は予想できなかった」と不安と懸念が広がり、ワクチンが必要との声が出ている。
韓国の文在寅政権は北朝鮮の金正恩に融和的だと日本国内では批判されている。だが、対北制裁については、日本のほうがよっぽど消極的なのだ。国連安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネル元委員の古川勝久氏が、日本が国連の対北制裁をきちんと実行できていない実態について解説する。
* * *
日朝貿易は全面禁止のはずだが、今も平壌では日本製品が溢れかえっている。それは日本の対北制裁の法制が時代遅れだからだ。
北朝鮮や外国の協力者はグローバル・ネットワークを通じて制裁を回避するため、国連制裁は非合法ネットワーク全体の機能停止を目的に、北朝鮮国外で制裁違反に加担する企業や個人との取引も禁止している。
しかし、日本の外為法が禁じるのは、あくまでも日朝間の経済取引だ。「仕出し地」または「仕向け地」を北朝鮮とする貨物と資金の移動であり、第三国にいる北朝鮮の協力者との取引自体は必ずしも違法ではない。北朝鮮はグローバルに活動するが、日本の制裁法制の目的はいまだに二国間貿易の取り締まりだ。
金融制裁の遅れも致命的だ。世界36か国が加盟し、マネーロンダリング対策や国際テロ資金対策を行う政府間機関である「FATF」(金融活動作業部会)は2014年6月に日本を名指しで、遅々として進まないマネロン・テロ資金対策を批判する異例の声明を発表した。 国連安保理決議は、対北朝鮮金融制裁としてFATFの勧告の履行を義務づけている。日本は金融制裁もちゃんと履行できていない。
事実、2017年5~6月に北朝鮮関連の資金洗浄容疑事案が発生した。会社経営者の男性が松山市にある地方銀行に5度にわたり多額の現金を持ち込み、計5億5千万円を香港の企業に送金した。その後、2018年になって送金先と北朝鮮とのつながりが発覚した次第だ。
北朝鮮関係の送金は他にも複数件、確認されている。日本国内には多数の北朝鮮関係者がおり、中にはシンガポールにある北朝鮮のフロント企業に多額の送金をしていた人物も複数名いる。
金融機関を監督する金融庁には、刑事訴訟法に基づく捜査権がなく、北朝鮮関連の懸念企業・個人の情報も限定的だ。各都道府県警が資金洗浄事件を捜査するが、多くの場合、国際捜査の能力は限定的である。
2019年にFATFは日本の取り組みを再審査する。仮に日本の取り組みが不十分とみなされると、日本の金融機関の国際金融取引市場での取引が制限される可能性も否定できない。米政府が日本の金融機関に莫大な課徴金を科す懸念もある。
だが、政府高官によると、官邸は「国内法改正の話はするな」と圧力をかけていたという(2018年11月時点)。日朝会談に向けた水面下交渉が図られる折、制裁法制の整備のタイミングを逸したのかもしれない。
ただ、忘れてはならない。北朝鮮制裁の措置は、長期にわたり他の様々な分野でも必要とされるものだ。
国連安保理では、北朝鮮の他にもイスラム国やスーダンなど、14の制裁対象がある。北朝鮮制裁と同様、いずれでも資産凍結、取引禁止、物資・技術の移転阻止等の制裁措置が義務だ。日本政府はこれらの制裁も不十分だ。
資金洗浄対策等の金融制裁は組織犯罪や国際テロ対策としても必須だ。機微技術(*大量破壊兵器などに転用できる技術、製品)の移転阻止は、核・ミサイル等の不拡散のために未来永劫、必要となる。日本の取り組みの遅れは、国際社会の取り組みに冷水を浴びせかねない。
私たちには、国際社会のためにも責任ある対応が求められているはずだ。
●ふるかわ・かつひさ/1966年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。1998年ハーバード大学ケネディ政治行政大学院にて修士号取得。99年読売論壇新人賞優秀賞受賞。2011年から4年半、国連の「専門家パネル」委員を務める。その経験をまとめた『北朝鮮 核の資金源「国連捜査」秘録』で新潮ドキュメント賞を受賞。
※SAPIO2019年1・2月号
「統括会社を巡っては、ルノー幹部に不透明な報酬が支払われたほか、フランスのダチ元法相にも支払いがあったとされている。」
上記が事実なら前会長カルロス・ゴーン被告は表と裏の顔を持ち、不正や違法を含めて素晴らしい業績をたたき出した可能性があると思う。
そして不透明な支払いのわかっている部分は氷山の一角かもしれない。
日産自動車が会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された前会長カルロス・ゴーン被告の不正行為について、企業連合を組むフランス自動車大手ルノーとの共同調査に着手したことが6日、関係者への取材で分かった。オランダにある両社の統括会社が対象。会計監査会社に依頼し、報酬や経費の使途も調べる。
統括会社を巡っては、ルノー幹部に不透明な報酬が支払われたほか、フランスのダチ元法相にも支払いがあったとされている。関係者は「不正の温床となった恐れがある」との見方を示した。
準大手ゼネコンが滋賀県東近江市で進めていた倉庫建設工事をめぐり、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(関生支部)の幹部らが、提携する協同組合の加盟企業と供給契約を結ぶようゼネコン側を脅したとされる事件で、滋賀県警組織犯罪対策課は5日、恐喝未遂の疑いで同支部の幹部や組合員計15人を逮捕した。県警はいずれの認否も明らかにしていない。
逮捕されたのは、別の威力業務妨害事件で起訴されている同支部執行委員の萱原成樹被告(53)=京都市右京区=ら3被告と、組合員12人の計15人。
県警によると、15人は嫌がらせ行為を行う「実行部隊」とみられる。県警はさらに同容疑で別の組合員1人の逮捕状も取っており、近く逮捕する方針。
逮捕容疑は平成29年3月10日から同7月3日までの間、他の幹部らと共謀し、協同組合の加盟企業と生コンクリートの供給契約を結ばせようと、ゼネコン側に対し、滋賀県や京都府内の建設現場などで、「ダンプの車検証のステッカーが見えない」「建設業の許可証もないですよ」と因縁をつけたり、中傷する内容のビラを配ったりするなどの嫌がらせを繰り返したとしている。
静岡県磐田市立図書館の設備改修工事を巡り、前副市長鈴木裕容疑者(63)ら3人が公競売入札妨害容疑で逮捕された事件で、県警は2日、市役所や落札業者の菱和設備浜松支店(浜松市東区)などを家宅捜索した。関係資料を押収し、金品授受の有無を含め、予定価格が菱和側に伝わった経緯を調べる。
他に逮捕されたのは、磐田市都市整備課長の村松俊文容疑者(57)と、菱和設備浜松支店長の西田昌也容疑者(54)。
捜査関係者によると、3人は容疑を認めているという。
求刑が重いのか、軽いのはよくわからない。
アルミ・銅製品などの品質データ改ざん事件で、不正競争防止法違反(虚偽表示)罪に問われた法人としての神戸製鋼所の公判が31日、立川簡裁(八木正一裁判官)で開かれ、検察側が罰金1億円を求刑し結審した。
判決は3月13日に言い渡される。
公判には同社の山口貢社長(61)も出廷。顧客などに対し「ご迷惑とご心配をお掛けし、深くおわび申し上げる」と謝罪した。また、再発防止について「企業風土の改革は容易ではないが、それ相応の覚悟をもって取り組んでいく」と述べた。
特別監察委員会委員長の荒井史男委員長代理(元名古屋高裁長官)は「正しい方向に戻さなかったということだけで、組織として隠そうとしたと認めることはできない」との結論に至るまでの経緯は下記の通りと言う事なのか?
外部有識者による特別監察委員会は聞き取りに関して厚労省から制限時間り、指示を受けていたのか?それとも、特別監察委員会の知識と経験から
十分な聞き取りを行ったと判断したのだろうか?
「毎月勤労統計」の不正調査問題で、厚生労働省は28日午前、外部有識者による特別監察委員会が聞き取り対象とした厚労省職員・元職員計37人への聞き取り状況を公表した。1人あたりの聞き取り時間は、最長が課長級職員に対する5時間55分で、最短は部局長級や課長級ら3人に15分。部局長級の1人には、対面での聞き取りをせずにメールだけで済ませていた。
厚労省は野党側の求めに応じ、関連資料を提出した。資料によると、監察委の前身となる監察チームは昨年12月27日~今年1月14日、延べ29人に1回あたり15~165分の聞き取りをした。監察委は設置日の1月16日から21日に、延べ40人に1回あたり10~100分聞き取りを実施。10分の人には複数回の聞き取りをしていた。
実人数では、統計情報部長や局長級の政策統括官(統計・情報政策、政策評価担当)ら部局長級が11人、雇用統計課長や雇用・賃金福祉統計課長ら課長級が9人、課長補佐・係長級が17人だった。
個人的な経験から協力できる相手や妥協してでもメリットの方が大きい場合には、共同経営は良いと思うが、そうでなければ、共同経営は避けるべきだと思う。自由度が制限されるし、伝達系統、命令系統、責任系統、外国人や外国企業であれば、文化、価値観や使用言語の違いによるネガティブな影響などで良い事はないと思う。対立が解決できないまま、分裂すると、男女の仲ではないが、感情的な問題が残り、知らない方が良かったと思うケースがあると思う。
オリックスとフランスの空港運営大手バンシの子会社「バンシ・エアポート」が内心はどう思っているかは本人や会社で働いている従業員しか知らない事である。

【写真】台風21号の被害で孤立し、混乱する空港内の様子
「関空が民営化されて、責任の所在がわからなくなった。だから、有事の時に対応できない。文書は関空の経営を憂う人が書いたと言われているが、フランス人幹部と対立した人たちの合作とも言われている」(KAP関係者)
文書に記されている驚きの内容を紹介しよう。
* * * 「怪文書」と聞けば、何を思い浮かべるだろうか。政治の世界でライバルを追い落とすために作成された出所不明の文書。政界だけではない。官僚機構や会社組織の内部でも、権力闘争が激化するとどこからともなく生まれ、人知れず右から左へ流れていく。その情報の多くは出所不明で真偽もわからない。だが、すべてがニセモノとは限らない。ごくまれに“良質な”怪文書が出回ることもある。
ここにA4用紙14枚にまとめられた文書がある。冒頭には、こう書かれている。
<台風発生、その後の報告ミス、情報提供不足による混乱の1日、12時~15時台風通過。3000人孤立の情報、大規模浸水、停電、ネットワーク断絶、ビル損壊など>
単語の羅列は、昨年9月4日に台風21号の直撃を受けて大混乱に陥った関空の“機能不全”をあらわしている。当時、巨大台風の影響で約7800人の旅客らが空港内で孤立した。一刻も早い脱出と空港機能の回復が急務だったその時、対策にあたるはずの空港運営会社「関空エアポート」(KAP)で起きていたのは、主導権争いをめぐる会社幹部たちの子供じみた言い争いだった。文書には、その様子が日誌の時系列形式で克明に記録されている。
一例をあげてみよう。
* * * <9月7日(金) KAP内部分裂が露呈。トップ同士で口喧嘩>
エマヌエル・ムノント副社長「国交省の発表を事前に聞いていない。意図的にバンシへ知らさなかったのではないか」
山谷佳之副社長「直接報告した」
ムノント氏「翻訳が稚拙だった。翻訳チームの不手際だ」
この発言に山谷氏は、机を叩いて激昂してこう言い放った。
山谷氏「それほど不信感を持つなら君が日本語を学べばいい」
熱くなる2人に職員の一人が仲裁に入る。
「現場は緊迫している状況だから、冷静に議論をして適切な経営判断を」
* * *
KAPは、国内初となる関西国際空港と大阪空港(兵庫県伊丹市)の民営化で運営権を獲得し、2016年4月に事業を開始した。オリックスとフランスの空港運営大手バンシの子会社「バンシ・エアポート」が40%ずつ資して経営されている。ムノント副社長はバンシ、山谷社長はオリックス出身の幹部だ。
ただ、KAPは表向きは一つの会社ではあっても、空港事業を始めるまでは歴史も文化も異なるまったく別の組織。訪日外国人の増加の追い風もあり黒字化を達成した一方、「利益優先のKAPのやり方が嫌になったベテラン社員が次々に辞めて、現場の力が落ちた」(関係者)との声もある。それを白日の下にさらしたのが、台風21号だった。平時はうまくやっているように見せていても、いざ有事になると本性が出る。災害発生時点から両社では対応方針の違いで意見が何度も食い違い、そのたびに現場は大混乱に陥った。
文書でも、その内実の描写に力点が置かれている。
災害が発生した9月4日には、KAPの社内会議で国への情報共有やプレス発表をすべきとの提案があがるも、ムノント副社長が「民間企業であり国のことは気にする必要はない。プレス発表のタイミングや内容は当社独自の判断で行うべき」と主張。KAPから国に何の報告もなされなかった。同日17時にプレス発表するも、被害状況の要点を淡々と説明するのみでお詫びや今後の見通しもなし。これに旅客や航空会社を含む空港関係者が激しく反発した。
混乱に拍車をかけたのは、翌5日の動きだ。
空港内に取り残された旅客に対して何の情報提供もなく、クレームが増加。空港外への脱出計画がどうなっているのか、いつ実施されるのか、そもそもKAPがそれを検討しているかどうかもすらわからない状況だった。現場スタッフは会社から説明がないので問い合わせを受けても対応できず、疲労困憊に。<(職員は>明確な方針や情報の伝達や指示がないことからひたすら謝りたおすのみ>だったと書かれている。情報不足からデマも流れた。
また、KAPが空港内で孤立していた7800人の旅客を「3000人」と見積もったことがさらなる混乱を招く。バスによる脱出作戦は台数が圧倒的に足りず、数時間待ちになった。
次第に空港内で働く従業員の統率も乱れていく。旅客にまぎれてバスに乗ったり、通勤用のマイカーの移動を規制しなかったりしたことから連絡橋で大渋滞が発生。旅客の中には、従業員が先に脱出していく姿を見て怒りの声が渦巻く。そうなるのも当然で、KAPは<当時数千人と言われた従業員の島内孤立にはまったく配慮せず>といった状態だったからだ。
後でわかったことだと、3000人の見積もりは、空港スタッフがざっと見回して推定した人数がそのまま正式な人数になっていたという。文書には、外部有識者のコメントとして「3000という数字は、別件でもKAPがよく使う数字」と説明されている。
現場の混乱をよそに、KAPの幹部は主導権争いを続けていた。
<当初、(KAPと航空会社の)事務方同士連絡していた事は順調に物事の調整が進んでいたのが、フランス人が表に出てくるようになり、急に何も進まなくなった。これにはエアライン担当者もあきれていた>(4日)
<KAPから国にまったく情報を上げていないからか、国はエアラインやその他事業者から直接情報収集をするようになる>(5日)
<バンシが「情報統制、情報統制」と唱えて一切の情報を外に出さず。この頃から、オリックス陣営とバンシ陣営との意見相違や対立がだんだん増えてくる>(5日)
国内線は被災3日後の7日に再開されたが、KAPの混乱は続く。
<完全なモラルハザード状態。経営は情報管理を叫ぶだけで有効な対策とられず。社員もオリックスとバンシの仕切れなさや、内部もめを見て相当やる気を失せる状態>(11日)
場外では意外な人物も登場する。
<官房長官補佐官の福田が、「オリックスは民間運営の代表企業として国と連携して復興を頑張っている」と言い始める。オリックスからの根回しか? そんな暇あったら復旧対応に力注げ>(14日)
福田氏とは、昨年11月に官房長官補佐官を辞任した福田隆之氏のこと。福田氏は空港や水道事業などのPFI(民間資金を活用した社会資本整備)に精通している民間人として菅義偉官房長官に登用されたが、昨年の臨時国会開幕前にフランスの水道事業者から接待を受けていた疑惑が持ち上がり、その直後に辞任が発表された。「国会の答弁に耐えられないので、解任された」(官邸関係者)と言われている。
福田氏は、オリックスの社外取締役である竹中平蔵氏にもかわいがられていて、空港や水道のコンセッション方式(運営権の条件付き長期売却)導入の旗振り役だった。現在進められている千歳空港など北海道内の7空港の一括民営化では、KPAの山谷社長や竹中氏と一緒に北海道内で宣伝活動をしていたこともある。
実は、オリックスとバンシの企業連合は北海道内の空港運営にも意欲を見せていた。両社のプランはすでに入札の一次審査を通過していて、関空での実績もあったことから有力候補にあがっていた。余談になるが、竹中氏は過去には阪神タイガースファンを自称していたが、北海道の空港民営化が話題になりはじめたころから、メディアに対して北海道日本ハムファイターズのファンを宣言するようになった。ところが、昨年12月下旬、オリックスとバンシは突如として審査からの撤退を表明。表向きの理由は「災害対応に集中するため」とされているが、関係者の間では「高潮被害の対応の失態が広く知られてしまい、両社の亀裂が修復できていない。北海道どころではなくなったのでは」とささやかれている。
KAPの企業統治の問題は災害の前から指摘されていた。「上司に意見を言う人物を人事で冷遇され、コストカットで利用者の利便性向上につながる投資はされなかった。航空会社からの批判も多い」(政府関係者)という。
文書には、こんなことも書かれていた。
<経営の苦しい時期の関空を支えてきた事業パートナーとなる空港利用者を離反させ、ノウハウを持つ社員をないがしろにして離反させ、むしろ民営化前より経営基盤が悪化している>
文書に書かれている内容についてKAPにたずねると、こう回答した。
<被災・復旧対策におきましては、外国人幹部・日本人幹部を含む弊社の役職員が早期の避難及び復旧という共通の目的の下、一丸となり対策に当たっておりました。対立や対応方針の混乱があったという認識はございません。一刻も早い復旧に向けて、弊社幹部役職員において議論が白熱する場面はございましたが、ご指摘の「口論」とは認識しておりません>
民間の能力を活かして経営を効率化させるとして導入された空港民営化は、現在、福岡空港や高松空港などでも準備が進んでいる。だが、民営化された関空の災害対応は、とてもではないが「プロの仕事」とは思えなかった。だからこそ、関係者たちは怒りの気持ちで記録を残したのではないか。この文章には、悲憤の涙が満ちている。
* * * ※質問状に対するKAPの回答は以下の通り。
──被災時に社内で口論があったのは事実でしょうか。
9月4日に台風21号によって関西国際空港は被災し、その後の被災・復旧対策におきましては、外国人幹部・日本人幹部を含む弊社の役職員が早期の避難及び復旧という共通の目的の下、一丸となり対策に当たっておりました。対立や対応方針の混乱があったという認識はございません。
一刻も早い復旧に向けて、弊社幹部役職員において議論が白熱する場面はございましたが、ご指摘の「口論」とは認識しておりません。すべての関係者がそれぞれの意見を出し、最善を尽くすという意識の中のものであります。
弊社といたしましては、今後も全社一丸となって、この度の被災による教訓を活かし、より安心・安全な空港運営の実現に向けて取り組んで参る所存です。
──人数の推定の間違いが、渋滞を引き起こした原因になったと指摘されています。
9月4日にお示した約3000人という人数につきましては、21時現在に空港内に滞留されていた「旅客」についての数ですが、一方、5日に実際に島外に出た約7800人という人数は、9月4日21時現在に滞留されていた上記の約3000人の旅客数に加え、従業員数千名も含む数です。従いまして、人数の推測を誤ったというものではなく、そもそもの数値の性質が異なるものとご理解いただければと存じます。
「もうレース感覚ですね。その日その日の運動会で、1位を取ろうと必死でした」
また、島外に出る方々の輸送につきましては、バス25台(1台あたり定員52名)と船3隻(1隻あたり定員、2隻は定員110名、1隻は定員115名)を5日早朝6時からピストン輸送で運航開始できるよう準備が完了しており、その時点で島外に出ることを希望されていた8000人規模の輸送ができる能力に問題はございませんでした。
しかしながら、当時連絡橋が一車線のみの相互片側通行であったこと、また、対岸となる泉佐野も被害を受け、泉佐野市側の高速道路出口における交通規制に加え、市内における停電による信号停止や倒木による道路の不通など、様々な要因が重なり、激しい渋滞が対岸~連絡橋~空港島内に断続的発生したことが輸送に大きな影響を与えたものです。
弊社といたしましては、当時の状況の中で、連絡橋の交通を管轄する警察及びNEXCO西日本様にもご協力をいただき、最善を尽くしていただいたものと認識しております。
また、従業員の帰宅につきまして、空港内の事業者数は355者、1万7363人の従業員が勤務しておりますが、日頃から「お客様優先」の意識をもって業務にあたっており、被災翌日以降も泊まり込みで職務に当たった者が多数でした。ただ一方、体調の問題等から帰宅を必要とする従業員も多数残留しておりましたのも事実です。このような状況において、弊社といたしましては、お客様を優先しつつ、これら帰宅を必要とする従業員についても安全に空港外に輸送いたしました。渋滞の原因については、帰宅人数の多寡にかかわるものではなく、上記のとおり、両岸及び連絡橋が被災したことによる様々な要因が重なったことで起きたものであり、ご指摘の原因については当たらないものと認識しております。
──被災当時、情報公開のあり方をめぐって社内で対立があったことは事実でしょうか。
関西国際空港をご利用のお客様への情報開示の重要性についての認識は出身母体の違いに関わらず、弊社全役職員の共通した理解です。インフラとしての空港運営企業として、未復旧の施設への立ち入りによる危険回避、テロなどの未然防止など安全保障の観点から、一部の施設などの被災状況等についてメディアの方々に開示できない状況や撮影をお断りせざるを得ない状況もございましたが、ご利用のお客様に対して必要となる情報を早期に公表するという点において役職員間において姿勢・認識の相違はございません。
──災害対応でフランス人の幹部が途中から外されたことは事実でしょうか。
ご指摘いただいている事実は一切ございません。最高運用責任者であるバンシからの出向者(米国人)は被災初日から対策本部に常駐しており、また、発生当日は諸事情により空港に居合わせなかったフランス人幹部も漸次参集し、以降、被災・復旧対策に全力で当たっております。
──オリックス社とバンシ・エアポート社は北海道7空港の民営化に参入する意向を示していたが、昨年12月に第二次審査を辞退したのはなぜでしょうか。
ご質問は弊社株主であるオリックスとバンシに関するものですので、申し訳ございませんが、弊社としてお答えすることはできません。
(AERA dot.編集部/西岡千史)
[パリ 27日 ロイター] - フランスのルメール経済・財務相は27日、ルノーの会長兼最高経営責任者(CEO)を辞任したカルロス・ゴーン氏について、退職手当を「法外な」金額にすべきではないと述べるとともに、政府として問題を注視していく考えを示した。
24日にゴーン氏の後任を指名したルノーは、同氏への手当について最終決定していない。一方、フランスでは低賃金や不平等を不満とする反政府デモが起きており、ゴーン氏の報酬問題は火種になりかねない。
ルメール氏は国内ラジオのフランス・アンテルで「カルロス・ゴーン氏への手当が法外なものになった場合、誰も納得しないだろう」と述べ、「われわれは極めて慎重に注視するつもりだ」と表明した。
仏政府はルノーの筆頭株主で、持ち分は15%。取締会には2人の代表を送っている。
国内労組の労働総同盟(CGT)は、ゴーン氏の手当が2500万―2800万ユーロ(2800万―3200万ドル)となり、加えて年金として年間80万ユーロが支払われることになると試算した。
ルメール氏は、どのような手当であれば容認できるかとの問いには答えなかったが、ゴーン氏が政府から再任の承認を得るため、2018年の報酬を前の年の740万ユーロから30%カットすることに合意したことを指摘した。
さらに、フランスに拠点を置く大手企業の幹部らに税制上の居住地をフランスにすることを求める法案を、数カ月以内に提出するとした。
「技能実習生の問題に詳しい指宿昭一弁護士は『事実なら偽装請負であり、技能実習計画にも反する行為だ。実習制度も労働法も理解していない企業に受け入れる資格はない。(受け入れ企業を指導する)監理団体の責任も問われるし、このような受け入れを認めた法務省入国管理局の責任も重大だ』と話した。」
実習制度と労働法を理解している企業の方が少ないと思う。技能実習制度自体が安価な労働力を得る隠れ蓑になっていると思うし、ある自治体は外国人労働力確保のために日本語学校を開設した記事を読むと、安価な外国人労働力が本音だと思う。日本は事実を率直に言わない社会だし、率直に言われてもロジカルに考えられないので詐欺のように騙してほしい文化だと思う。
愛知県の青果卸会社と関連会社の農業生産法人に雇用され、北海道の農家などで農作業に従事しているベトナム人技能実習生21人が解雇を通知された問題で、全員が25日付で解雇された。青果卸会社の担当役員は取材に「そもそも農作業ができる社員はいなかった」と明かし、事実上、派遣先農家に実習を丸投げしていたと証言。識者は、職業安定法違反(偽装請負)に当たる疑いがあると指摘している。
【解説動画】入管収容施設の問題点と『難民』の実態
担当役員によると、青果卸会社は自社農場でカボチャや大根の栽培を手がけたことがあるが、収穫に至らず、「実習生に教えるような人間(社員)はいなかった」という。そのため、農業指導は北海道の請負契約農家に委ねていた。役員は「実習生を連れて行けば教えてもらえるので、社員は農家への送迎だけを行っていた」と話した。一方、実習生を受け入れていたある農家も「うちで雇っている(日本人の)女性が実習生に教え、作業内容も指示していた」と、不適切な運営実態を証言した。
技能実習制度上、請負契約を結ぶこと自体は禁止されていない。だが、請負契約先の農家側が実習生の指揮命令を行うことは、雇用責任が不透明になることから職業安定法44条で禁止されている。また、実習の丸投げは、実習生を受け入れる際に作成する義務がある技能実習計画にも違反している可能性がある。担当役員は「(偽装請負や実習計画違反になるという)認識はなかった」としている。
技能実習生の問題に詳しい指宿昭一弁護士は「事実なら偽装請負であり、技能実習計画にも反する行為だ。実習制度も労働法も理解していない企業に受け入れる資格はない。(受け入れ企業を指導する)監理団体の責任も問われるし、このような受け入れを認めた法務省入国管理局の責任も重大だ」と話した。
解雇された実習生のうち7人は労組に加入し、賃金や補償金の支払いなどを訴えている。【片平知宏】
「同社はこの事案を今月11日まで国土交通省へ報告しておらず、『飲酒事案と捉えていなかったため、報告していなかった』としている。」
全日空の定義ではどのようなケースが飲酒事案となるのか?飲酒した操縦士による乗務未遂は飲酒案件でないのなら定義を変更しない限り、同じ問題は起きる可能性は高い。個人的には言い訳だと思う。
全日空の40歳代の男性副操縦士(当時)が、乗務前のアルコール検査で同社の基準値を超えたため、後輩に検査を身代わりさせていたことがわかった。同社はこの副操縦士を出勤停止1か月の処分としたという。
同社によると、副操縦士は2014年5月、羽田発上海行きの便に乗務する前の呼気検査で、基準値を超えるアルコール分が検出されたため、後輩の操縦士に2回目の検査を身代わりさせたという。その後の再検査で副操縦士は基準値を下回ったが、地上スタッフが身代わりに気付き、副操縦士には乗務させなかった。
同社はこの事案を今月11日まで国土交通省へ報告しておらず、「飲酒事案と捉えていなかったため、報告していなかった」としている。
日本では飲酒が原因による重大事故が発生していないので、認識、チェックそして処分が甘い事が明らかになったと思う。
全日空の男性副操縦士(当時40代)が2014年5月、羽田空港で乗務前の呼気アルコール検査を、別の男性パイロット(当時30代)に受けさせていたことが25日、北海道新聞の取材で分かった。日航が今月7日に同様のケースを国土交通省に報告したことを受け、全日空は11日に報告した。
管理担当者が不正に気付く
昨年10月に日航の副操縦士が大量飲酒を理由に英国で逮捕され、パイロットの飲酒が問題視される中、同社はこの問題を公表していない。
全日空などによると、副操縦士は14年5月10日、羽田発上海行きの便に乗務する前、検知器による呼気検査で同社の基準値(呼気1リットル当たり0・1ミリグラム)を超えるアルコールが検知された。
副操縦士は、同便に乗務しない別の男性パイロットに依頼して再検査を受けさせ、通過したように装ったが、パイロットの管理担当者が不正に気付いた。
日航の報道を受け報告
不正に関わった2人はこの便に乗務せず、別のパイロットによって予定時刻の約30分遅れで出発した。同社は同年、副操縦士を出勤停止1カ月の懲戒処分、代わりに検査を受けたパイロットを訓戒処分とした。
日航では、17年12月に男性機長が検査を別の機長に受けさせていたことが一部メディアの取材で発覚し、今月7日に国交省に報告、9日に発表した。国交省によると、こうした事例の報告義務はないが、全日空は「日航の報道を受けて国交省に報告した」と説明している。
日航は9日、成田発米シカゴ行きの男性機長(59)が2017年12月、乗務前の呼気アルコール検査を、同乗するもう1人の機長(53)に代わりに受けさせた不正があったと発表した。2人は予定通り乗務し、帰国後、替え玉になった機長からの報告で不正が発覚。日航は18年2月、2人を懲戒処分にした。当時は公表せず、一部メディアの取材があったことから今月7日に国土交通省に報告した。
日航によると、不正があったのは17年12月2日の日航10便ボーイング777で、検査を受けなかった機長は便の統括役だった。
問題は氷山の一角だと思う。三菱自動車(東京都)とパナソニック(大阪府)でこの有り様では、中小や零細企業だともっとずさんだと思う。 メスがはいっていない、又は、メスを入れないから問題が発覚しないだけかもしれない。
法務省と厚生労働省は25日、三菱自動車(東京都)とパナソニック(大阪府)など4社について、国に提出していた技能実習計画の認定を取り消したと発表した。三菱自は実習計画と異なる作業をさせたこと、パナソニックは社員をめぐる労働基準法違反が確定したことが問題とされた。4社は5年間、新たな実習生の受け入れができなくなり、新在留資格「特定技能」の外国人も同じ期間、受け入れられない可能性が高い。
技能実習生の労働環境などを保障するため、2017年に施行された技能実習適正化法に基づいて実習計画を取り消された企業は過去に4社あるが、主要企業は初めて。三菱自、パナソニックは処分について「真摯(しんし)に受け止めている」などとそれぞれコメントした。
法務省によると、三菱自は岡崎製作所(愛知県岡崎市)で溶接作業を学んでもらうために受け入れたフィリピン人の実習生28人に、実習計画にはなかった車の部品の組み立てなどの作業をさせていた。同省は27人の認定を取り消し、1人は計画通りの作業に従事させるよう、改善命令を出した。27人のうち24人はすでに帰国し、残りの3人は別の企業に転籍したという。
同製作所での同様の不正は実習生の受け入れを始めた08年から始まり、国の調査が入った昨年5月まで続いていたという。今回の処分によって、三菱自で働いている残りの実習生は計画で示された期限が切れると、別の企業への転籍や帰国を余儀なくされる。同省は三菱自に実習生を派遣していた監理団体「協同組合フレンドニッポン(FN)」(広島市)などについても調査をしている。
高額補償金がアメリカで言う「ゴールデンパラシュート」なら驚く事ではない。有能な人材をヘッドハンティングする時の条件に
「ゴールデンパラシュート」が含まれることは普通。
「仏メディアが報じた。株主総会での承認が必要なため、実際に支給されるかは不明だが、労働組合は『信じられない』と反発している。」
フランスの状況は知らないが、フランスにも同じようなシステムがあるのなら驚く事ではない。労働組合が驚いているのならフランスでは同じシステムがないのであろう。日本ではそのような条件はあると思うが、ポピュラーではない。
【パリ時事】フランスの自動車大手ルノーの会長兼最高経営責任者(CEO)を辞任したカルロス・ゴーン被告に対し、競合他社に転職しないことを条件に最大400万ユーロ(約4億9700万円)の補償金を支払う規定があることが明らかになった。
仏メディアが報じた。株主総会での承認が必要なため、実際に支給されるかは不明だが、労働組合は「信じられない」と反発している。
補償金は、ゴーン被告が転職して企業秘密を漏らすのを防ぐことが目的だという。
ルノーによると、ゴーン被告の2018年分の固定報酬は100万ユーロ。成果に応じた変動分の報酬は後払いで、仏メディアによると21年までに総額500万ユーロ支払われる予定だった。ただ、受取時にルノーに在籍している必要があるため、全額支払われる可能性は低いとみられている。
「樋口委員長は、東京都内の従業員500人以上の事業所における抽出調査を容認するマニュアルが作成されていたことを挙げ、『隠そうとしていれば(マニュアルに)書かないと思う』と説明。荒井史男委員長代理(元名古屋高裁長官)も『正しい方向に戻さなかったということだけで、組織として隠そうとしたと認めることはできない』と話した。」
「警察が押収した会社のマニュアルには、『汚水は処理せず雨の日に流せ』という内容の指示があったほか、行政の立ち入り検査の際はきれいな工業用水を流していたということで、警察は会社ぐるみの犯行とみて追及しています。」
特別監察委員会樋口委員長の判断が正しければマニュアルに指示していあると言う事は違法で隠そうと思えばマニュアルに書かないと考えられないだろうか?違法の認識がなかったのではとも考えられる。
特別監察委員会樋口委員長や荒井史男委員長代理(元名古屋高裁長官)の判断が常識なのか、それとも非常識であるのか?
メディアの方々、わかりやすいように下記の事件と比較しながら説明してください。
名古屋にある国内最大級の食品リサイクル工場で汚水垂れ流しの疑いです。
この会社の社長ら2人が、リサイクルで出た汚水を海にそのまま流していた容疑で逮捕されました。
逮捕されたのは、食品廃棄物のリサイクル事業などを行う「熊本清掃社」の社長 村平光士郎容疑者(46)と、名古屋市港区にある食品リサイクル工場「バイオプラザなごや」の工場長代理 都築勇太容疑者(34)です。
警察によりますと、2人は、去年9月から11月まで5回にわたり、生ごみから肥料を作る際に出た排水基準を超えた汚水を処理せず、海に流した水質汚濁防止法違反の疑いが持たれています。
この工場では、名古屋市で1年間に出る事業系生ごみの3分の1以上を処理し、「名古屋から生ごみをなくす」などとアピールしていました。
「結論から言うととてもいいです」
(生ごみからのたい肥をアピールする村平光士郎容疑者 2009年取材・当時常務取締役)
村平容疑者は、「違法な排水は指示していない」と容疑を否認していますが、都築容疑者は、「村平容疑者から指示を受け夜中に汚水を流していた」と容疑を認めていると言うことです。
警察が押収した会社のマニュアルには、「汚水は処理せず雨の日に流せ」という内容の指示があったほか、行政の立ち入り検査の際はきれいな工業用水を流していたということで、警察は会社ぐるみの犯行とみて追及しています。
「スバルは『(調査結果を)隠すような意図はなく、公表すべきだとは認識していなかった』(広報)としている。」
特別監察委員会委員長の荒井史男委員長代理(元名古屋高裁長官)は「正しい方向に戻さなかったということだけで、組織として隠そうとしたと認めることはできない」が厚労省の勤労統計不正問題に適応できるのなら、スバルの広報の説明も受け入れられると言う事?
自動車大手スバルが2015年から17年にかけて、社員3421人に計7億7千万円の残業代を払っていなかったことが、24日わかった。16年に男性社員が過労自殺し、その後の社内調査で昨年1月までに判明した。スバルはこれまで1年間にわたり問題を公表しておらず、企業姿勢が問われる事態だ。
24日に男性の遺族の代理人が会見し、男性に残業代の未払いがあったと説明。さらにスバルは朝日新聞の取材に対し、未払いが多数の社員に広がっていたと明らかにした。
代理人によると、16年12月、車両工場の群馬製作所(群馬県太田市)の総務部に勤務する男性社員(当時46)が、長時間労働や上司の激しい叱責(しっせき)が原因で過労自殺した。スバルによると、同製作所の社員数人に残業代未払いがあったとして、太田労働基準監督署から17年7月に同製作所が労働基準法違反で是正勧告を受けたという。
こうした中で、同製作所では社員の残業時間を把握できていないことが判明した。そのためスバルは17年末、社内全部門の非正規を含めた社員1万7359人について、15年7月から2年間の未払い残業代の有無を調査。その結果、残業時間の記録は社員の自己申告だけで、パソコンの使用や出退勤の履歴などとは照合されず、過少申告が常態化していたことがわかった。
過少申告の理由について、社員の約6割が「(部署で決めた残業時間の)上限を超えないようにした」と回答。「上司から残業の指示を受けていなかった」との回答も約2割あったという。上司による過少申告の指示は確認できなかったとしている。スバルは「(調査結果を)隠すような意図はなく、公表すべきだとは認識していなかった」(広報)としている。
東京地裁がゴーン被告の有罪を望んでいるのなら保釈を認めない、又は、外国人のずる賢さを警戒しているのなら保釈を認めないだろう。
海外の承認や外国語で記載された書類の正当性を確認するのはとても大変で困難な作業。日本側だけの証拠で判断できる事が望ましいであろう。
外国では賄賂や腐敗が常識の国々が多くあり、政府系機関職員や公務員による公文書の偽造、事実でないないようの文書が公文書として作成される、
証人の偽証などいろいろな問題がある。
公務員の底辺のレベルでは信用できない書類を信用するか、信用に値しない文書を信じるとか、愚かな現実を見た経験からの推測。まあ、権力を公務員達が我々が判断する立場なので我々が判断したと言えばそれで終わり。面白い案件でなければメディはスルー。
ここまで世界中で注目を集めているのだからゴーン被告が無罪となれば東京地検や東京地裁の面目や信用度は地に落ちると思う。
まあ、「最初の請求では保釈後の制限住居を東京のフランス大使公邸かパリにする」であれば日本の法律は適用されないので法は法であると主張すれば何も出来ないと個人的に思う。日本人であれば国外脱出できなければ逃げようがないが、ゴーン被告であれば、フランスでも、ブラジルでも、レバノンでもどこでも隠れる事は出来るし、資金的にも十分な貯えや隠し資産は可能だと思う。ブラジルやレバノンであれば、お金のためには法を犯してもいろいろな事をしてくれる人々はいるであろう。お金で出来る事は日本以上にたくさんあると推測する。
東京地裁は22日、私的投資の損失を日産自動車に付け替えたなどとして会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された前会長、カルロス・ゴーン被告(64)の保釈を認めない決定をした。弁護人が18日に2回目となる保釈請求を出していた。地裁は東京地検特捜部や弁護人から改めて意見を聞くなどした結果、口裏合わせなど証拠隠滅の恐れが高いと判断したとみられる。弁護人は決定を不服として準抗告するかどうか検討するが、ゴーン被告の勾留はさらに続く見通しとなった。
ゴーン被告は昨年11月19日に金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑で逮捕されて以来、東京拘置所(東京都葛飾区)で2カ月以上勾留されている。
弁護側は、ゴーン被告が会社法違反などの罪で起訴された今月11日に保釈請求を出したが、15日に却下され、準抗告も17日に棄却された。証拠隠滅や海外逃亡の恐れがあることなどが理由とみられる。
最初の請求では保釈後の制限住居を東京のフランス大使公邸かパリにすると地裁に伝えていたが、2回目は、日本国内に変更して請求していた。さらに代理人を通じ「裁判所が正当と考える全ての保釈の条件を尊重する」との声明を出し、旅券の提出や毎日の出頭、高額の保釈保証金などを受け入れるとしていた。
ゴーン被告は地裁で8日に開かれた勾留理由開示手続きで、いずれの起訴内容も否認した上で「根拠もなく嫌疑をかけられ、不当に勾留されている」と無罪を訴えていた。
ゴーン被告は昨年12月10日に平成22~26年度の報酬を過少に記載したとして起訴され、27~29年度分の容疑で再逮捕された。その後、同月20日に地裁が特捜部の勾留延長請求を却下し、保釈される可能性が高まったが、翌21日に会社法違反容疑で再逮捕された。
ゴーン被告をめぐっては、「長期勾留」などと海外メディアを中心に日本の刑事司法制度を批判する報道が続いていた。
ジェネリック(後発)医薬品で効果や品質で問題がなければ、いかに効率よく医薬品を生産出来るか次第だと思う。
チキンレースの逆ヴァージョン。
厚労省の流通価格調査はどこまで機能しているのか?
カルテルが確定すれば重い処分を出せば良い。
ジェネリック(後発)医薬品の卸価格でカルテルを結んだ疑いがあるとして、公正取引委員会は22日午前、独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で医薬品メーカーの日本ケミファ(東京都千代田区)、コーアイセイ(山形市)の2社に立ち入り検査を始めた。ジェネリック医薬品の取引のみを対象にした立ち入り検査は初めて。
関係者によると、2社は2018年ごろ、腎臓病患者向けのジェネリック医薬品「炭酸ランタンOD錠」について、卸売業者に納入する卸価格を不当に申し合わせていた疑いがある。価格競争が起きないようにして値崩れを防ぐ目的だった可能性があるという。炭酸ランタンOD錠は2社を含む計5社が18年2月に製造承認を受けたが、同年6月時点で日本ケミファとコーアイセイだけが販売に向けた準備を進めていた。
メーカーからの卸価格は、患者に処方される際の薬価の改定にも影響する。卸価格が高ければ、将来的には患者の医療費負担が増えていた可能性もある。
問題が発覚した以上処分するのは当然だし、処分される事に対して自業自得だと思う。
話は変わるが毎月勤労統計の不適切調査問題に関して関与した職員は全て処分するべきだと思う。
上司の命令だったと証言し、証拠や証明できた職員達は処分を軽減するべきだと思う。命令した事が証明された職員は処分を重くするべきだ。
柴山文部科学相は22日、文部科学省の私大支援事業を巡る汚職事件や入試での不正な得点操作が昨年発覚した東京医科大(東京)に対して、2018年度の私学助成金を全額交付せず、ゼロにすると正式に発表した。同大は前年度、約23億円を受給していた。私大の助成金が不交付となるのは極めて異例だ。
アメリカンフットボール部の危険なタックル問題の後、大学としての対応に問題があった日本大(同)への助成金についても、35%の減額を決めた。
また、医学部入試問題で不適切な入試が行われたと認定された岩手医科大(岩手)、昭和大(東京)、順天堂大(同)、北里大(同)、金沢医科大(石川)、福岡大(福岡)も、25%の減額とされた。
テレビ局社員は注目を受けると思うので注意しなければならないと思う。
福井県警は21日、福井県鯖江市神明町3丁目、福井テレビ制作部副部長の畑祐一郎容疑者(42)を県青少年愛護条例違反の疑いで逮捕し、発表した。
あわら署によると、畑容疑者は2017年12月21日、同県内のホテルで18歳未満と知りながら、当時高校生だった少女にわいせつな行為をした疑い。福井テレビは「弊社の社員が逮捕されたことを重く受け止め、事実関係を確認し、厳重に処分する」としている。
航空会社アイベックスエアラインズ(東京)は18日、男性機長が社内で義務付けられたアルコール検査を受けずに国内線の便に乗務したと発表した。検査のことを忘れていたという。
同社によると、男性機長は今月9日、検知器による呼気検査を受けずに仙台空港発大阪(伊丹)行きの便に乗務。同じ機体で伊丹から新潟に飛行中、失念に気付いたという。新潟到着後の検査ではアルコール分は検出されなかった。
ある意味、それぞれにメリットがある関係だった。あえていうのなら切り捨てられた下請けや社員達。
この世の中、大義名分は必要。特に日本では大義名分が必要。三菱にしても燃費不正問題を早期に対応せずに日産・ルノーグループに救ってもらった。
「3社連合は29年に販売台数が約1060万台と世界2位のグループとなった」。これからは転落しかないと思う。どれほど転落するかは
今後の展開そして個々の企業がどのような選択を取り、社員達がどのように頑張るか次第だと思う。
毛利元就の三本の矢ではないが、3人が協力すれば1+1+1よりももっと良い結果を出せるが、足を引っ張り合えば、個々が独立して経営するよりも
悪い結果が出る事がある。いろいろな選択や方法にはメリットとデメリットがあり、メリットとデメリットの割合や差がそれぞれのケースで違うと思う。
短期、中期、そして長期のどの時点で評価するかによっても違ってくると思う。
このような状況になった以上、徹底的に調査して膿を出さないと、中途半端なままでは違う形で問題は出てくると思う。また、ゴーン容疑者なしで
日産と三菱が協力できるのか凄く疑問。日本人は外国人には従うが、日本人同士ではプライドや派閥などで妥協できない悲しい部分がある。ルノーとは
無理でも日産と三菱が協力すればデメリットを軽減できそうに思えるが、それが出来ないのが日本人だと思う。
この騒動の影響は数年から5年以上経たないと判断出来ないと思うし、日本や世界的な経済の状況によっても影響されるので、単純には評価できないと思う。ただ、日本の検察がどこまで出来るか、有罪なのか、無罪なのかについてはもっと早い段階で結論が出ると思う。
日産自動車と三菱自動車の会長を兼務していたカルロス・ゴーン被告(64)に、10億円の非開示報酬に関する新たな不正疑惑が浮上した。ゴーン被告は両社の資本提携をまとめ、仏ルノーを含め販売台数世界2位の3社連合を形成したが、今回発覚した不正はその功績を汚し、連携にも影を落としそうだ。(高橋寛次)
【図解】2つの特別背任容疑をめぐる主張
関係者にとって衝撃的だったのは、日産と三菱自の協業の象徴ともいうべき統括会社「日産三菱BV」をゴーン被告が設立した目的が、巨額の非開示報酬を得るためだったという調査結果だ。
調査を担当した西村あさひ法律事務所の梅林啓弁護士によると、ゴーン被告と元日産代表取締役のグレゴリー・ケリー被告(62)は平成28年6月頃、「日本で開示対象外となる報酬をゴーン被告に支払えないか」という目的で、日産と三菱自が折半出資する統括会社設立の検討を始めたという。記者団の取材に応じた三菱自の益子修会長兼最高経営責任者(69)は、「われわれも日産も、純粋なシナジー(相乗効果)が目的と聞いていた」と驚きを隠さなかった。
ゴーン被告は日産の社長だった28年5月、燃費不正問題が発覚して窮地に陥った三菱自と電撃的な資本提携で合意。株式の34%を取得して事実上傘下に収め、3社連合を形成した。当時の会見では「相乗効果が見込める。日産が弱い東南アジアの事業でメリットがある」と提携の意義を強調していた。その後、三菱自の業績はV字回復し、3社連合は29年に販売台数が約1060万台と世界2位のグループとなった。
日産の再建に成功した後は、必達目標を掲げてもクリアできないケースが目立つなど精彩を欠いていたゴーン被告だったが、三菱自への出資決断の速さは高く評価されている。しかし今回、「(28年10月に)資本提携が発足する前から、今回の支払いの仕組みが計画されていたことが明らかになった」(梅林氏)。
益子氏は記者団から「(日産との)提携そのものに不信感を抱かないか」と聞かれると色をなして反論。「現在の自動車産業が抱える問題を考えると、1社で対処することは難しい。アライアンス(企業連合)の力は不可欠で、今回の問題とは峻別(しゅんべつ)して考えるべきだ」と話した。だが、調査結果をみると、相乗効果を出そうと努力してきた従業員への背信行為が、現場の士気に影響する懸念は否めない。
前会長カルロス・ゴーン被告の経営者としての能力は素晴らしいと思うが、これまでのニュースをしっていれば人間的に問題があり、強欲である事に同意する人は多いと思う。
三菱自動車は18日、臨時の取締役会を開いた。前会長カルロス・ゴーン被告が役員報酬を不正に受け取っていなかったかどうかを内部で調べた結果を報告。調査では、筆頭株主の日産自動車とオランダに設立した統括会社「日産三菱BV」から、ゴーン被告に約10億円の報酬が支払われていたことが判明した。三菱自は、不透明な資金の流れだとして問題視している。
統括会社は、日産と三菱自が折半出資で2017年6月に設立。両社の提携効果を高める戦略の立案が狙いとされ、ゴーン被告が会長兼最高経営責任者(CEO)に就いた。両社の連結対象ではないため、報酬は開示していない。
こんなひどい会社がまだ存在しているし、情報提供(通報)がなければ処分されない現実があるとはひどい。
「中部運輸局は17日付で、高速バス会社『WILLER EXPRESS名古屋営業所』に対し、バス3台を30日間の使用停止とする処分を下しました。」
バス3台に対する処分だけなら3か月から半年の使用停止にするべきだと思う。もし事故が起きたら保険は下りないだろう。
運転手一人さえもどうにも出来ないほど経営が苦しいのならそれ以外にも問題があるかもしれない。
高速バスをここ数年使っていないけどスキーバス事故の教訓や規制強化でもこんな有様である事に驚く。
運転免許が失効していた職員に15回にわたってバスを運転させていたとして、中部運輸局は17日付で、高速バス会社「WILLER EXPRESS名古屋営業所」に対し、バス3台を30日間の使用停止とする処分を下しました。
中部運輸局によると同営業所は、運転免許が失効した40代の男性運転手に、去年6月から7月にかけ高速バスを15回にわたり運転させていたということです。去年11月に情報提供を受けた中部運輸局が、営業所を調べたところ発覚しました。
「WILLER EXPRESS」は中京テレビの取材に対し、「今回の件を真摯(しんし)に受け止め、お客様に安心安全なサービスを提供できるよう努力していきたい」とコメントしています。
中京テレビNEWS
東京オリンピック招致委員会は実際にコンサルティング業務が行われたのか確認やチェックをしていたのか?
JOC(日本オリンピック委員会)・竹田会長の捜査にも影響を及ぼすのか。
シンガポールの裁判所は16日、東京オリンピック招致委員会が契約していたコンサルタント会社の元代表に対し、虚偽の報告をしていた罪で、禁錮1週間の有罪判決を言い渡した。
・必見「“五輪コンサル”に禁錮刑 東京の招致委が契約」の動画
有罪判決を受けたのは、シンガポールのコンサルタント会社、ブラックタイディングス社の元代表、タン・トンハン被告(36)。
タン被告は、2014年に得た55万シンガポールドル、およそ4,400万円について、実際はコンサルティング業務をしていないのにもかかわらず、「コンサルタント料金だった」と、汚職捜査当局に虚偽の報告をしたという。
ブラックタイディングス社は、2013年に東京オリンピック招致委員会と2億円を超える契約を結んでいて、フランス司法当局は「贈賄」にあたるとして捜査を進めている。
タン被告は、2月20日から収監される予定。
良い生活や生活水準を経験してしまうとコントロールや現実を受け入れる事に失敗すると自己抑制が効かないのだろうか?
輪廻転生がないのならお金持ち、貧乏人、その他の人の人生は一回限り。自己責任で思うようにすれば良いのかもしれない。自己責任は
忘れずに!
野村証券の社員の女が、男性客から野村カードをだまし取り、現金あわせて620万円余りを盗んだ疑いで逮捕された。
複数の顧客がだまされていて、被害総額は5300万円にのぼる。
逮捕されたのは、野村証券でフィナンシャルアドバイザーとして勤務していた嶋直美容疑者(46)。
嶋容疑者は2017年、神奈川・横浜市の80代男性から野村カードなどをだまし取り、620万円余りを盗んだ疑いが持たれている。
野村証券によると、同様の手口であわせて6人の客がだまされ、被害はおよそ5300万円にのぼる。
嶋容疑者はすでに解雇され、「生活費や遊興費に使った」と話しているという。
FNN
業界が以前と全く同じとは思わないが下記の記事は事実の一部だと思う。
軽井沢のバス事故で、バスを運行していた「イーエスピー」(東京都羽村市)は、国の基準額の下限を下回る安値で仕事を請け負っていた。事故を受け、国は不当な安値防止へ規制を強化したが、取材すると、変わらない業界の実態も見えてきた。
「下限未満でないと仕事はもらえない。それが今も業界の暗黙のルールです」。関東地方のバス会社で安全管理を統括する男性社員(27)はこう話す。
この会社が昨年引き受けた中国人観光客向けの3泊4日のツアー。運賃は下限額ギリギリの52万円。しかし旅行会社と話し合い、「手数料」の名目で29万円を差し引いた。請求した額は23万円。こうした契約は珍しくなく、現在の相場は「下限額の5~6割ほど」という。「もはやたたき売り状態ですよ」
事故後、国土交通省は安全管理や監査体制の強化など85項目の対策を打ち出した。安値対策では、契約上認められる運賃の範囲を、旅行会社と交わす「運送引受書」に書くよう義務づけた。この書面は国などが行う監査時の点検対象で、下限額を明示させることで、安全コストの削減につながる不当な安値での受発注を防ぐ狙いがあった。
だが、関東の別のバス会社の運行担当は、旅行会社とバス会社との間には一部で国の狙いを裏切る「共犯関係」が働く、と話す。
バス業界には閑散期と繁忙期があり、閑散期に受注するには繁忙期に安値で引き受け、旅行会社に恩を売ることが重要という。「バス代を抑えたい旅行会社と、安くても定期的に仕事が欲しいバス会社。利害が一致すると、法を守る意識など飛んでしまう。バス会社は旅行会社に嫌われたくないんです」(田中奏子)
「この事故は、貸切バス事業者のなかに、バス運行に関する様々な規制を守る気がまったくない者がいた、という事実をあらわにしました。規制の「実効性」が不十分、つまり規制があるにもかかわらず、一部の会社で守られていなかったのです。・・・貸切バス事業においては、運転手の運転時間や拘束時間、車両の整備管理など細かい規制が以前から決まっていましたし、過去の事故を受けさらに強化されていたにも関わらず、このバス事業者には、それらを守る意識がまったく欠けていたわけです。2000(平成14)年に貸切バス事業への新規参入が自由化された結果、中小事業者が増加し、そのなかには同社のように『どうせバレないだろう』として法令を守る気が足りない事業者もいたということです。」
飛行機のパイロットのアルコール検査の不正、不適切な計測、替え玉や記録しないなどバス業界だけに問題があるとは思えない。国交省は現実を把握して規則や管理監督の方法を考えるべきだ。規則があっても守らなけれ問題ないし、ばれなければ不正を行った方が楽だとか、得だと思わせる環境を
放置した結果、大惨事が運悪く起きたと言う事だと思う。
「バス事業者どうしが、安全対策を含めた自らの品質を競い合う市場環境を作り上げていくことが必要だと言えます。」
理想的ではあるが、現実的に絶対に無理だと思う。監督官庁は性悪説を基本に対応していくしかないと思う。日本企業のデータ改ざん、隠蔽、偽装、
不正検査のニュースからも推測できるが、日本社会が大きく変わらないと無理だと思う。これらのニュースはいかに理想的な事が日本だけでないとと確信するが無理であると思う。努力としては問題ないが、実現は無理であるので、少しでも向上するように努力や改善するしかないと思う。
事故を起こした事業者は法令順守の意識があまりに低かった
2016年1月15日未明、長野県軽井沢町の国道18号「碓氷バイパス」で、東京から長野県のスキー場へ向かっていた貸切バスが対向車線を越えて道路外に転落、15人が亡くなり、残る26人も重軽傷を負うという大事故が発生しました。当該バス事業者の運行管理体制があまりにずさんだったことから社会の大きな関心を集め、国土交通省やバス業界、バス車両メーカーらでは再発防止策の策定に追われました。
【写真】「安全なバス事業者」の証、車両のココに注目
この事故は、貸切バス事業者のなかに、バス運行に関する様々な規制を守る気がまったくない者がいた、という事実をあらわにしました。規制の「実効性」が不十分、つまり規制があるにもかかわらず、一部の会社で守られていなかったのです。
事故後の捜査と報道により、事故を起こしたバス事業者「イーエスピー」では、運転手の健康状態確認などのため義務とされている運行前の「点呼」が実施されていない、「運行指示書」に具体的なルートが記載されていないといった、最も初歩的なルールさえ守られていなかったことが明らかになっています。
さらに、貸切バス事業者が旅行会社から受け取る運賃額について新しい制度が導入されていたにも関わらず、それを下回る額で旅行会社から受注していました。この「新運賃・料金制度」は、「旅行会社から受け取る運賃額が低額で、安全への取り組みを十分に行えない」というバス業界の声を受け導入されたものです。バス事業者が受け取る金額を上げるように制度を変えたのに、その制度さえ守っていなかったのは不可解です。大型バス運転経験の乏しい運転手を、十分な研修を経ずに乗客を乗せた「実車」乗務へ送り出した点も、常識的なバス事業者と比べ安全意識が驚くほど欠如していたと言わざるを得ません。
貸切バス事業においては、運転手の運転時間や拘束時間、車両の整備管理など細かい規制が以前から決まっていましたし、過去の事故を受けさらに強化されていたにも関わらず、このバス事業者には、それらを守る意識がまったく欠けていたわけです。2000(平成14)年に貸切バス事業への新規参入が自由化された結果、中小事業者が増加し、そのなかには同社のように「どうせバレないだろう」として法令を守る気が足りない事業者もいたということです。
悪質な事業者は「排除」 強化された規制の数々
この軽井沢での事故を受け、国土交通省では法令を改正し、バス事業者らの費用負担も得て「貸切バス事業適正化実施機関」を指定。同機関が各事業者を巡回し指導を行う一方で、問題が多い事業者があれば通報し、国による監査が優先的に行われる体制が作られました。また、貸切バスの事業許可を更新制とし、各事業者は原則として5年おきに国による審査を受けなければ事業を継続できない仕組みとなりました。
後者は、2017年度に初めて適用されましたが、対象となった事業者のうち1割以上が更新を辞退し貸切バス事業から撤退するなど、中小事業者を指導し品質を底上げしつつ、悪質な事業者を退出させる仕組みが回り始めています。
また、この事故によって、万一の事故の際に被害を最小限に留めるための「車両側の対策」が不十分だったことも露呈したと言えます。バス業界では従来、運転時間や拘束時間に上限を設け運転手の過労を防止するなど、事故をいかに未然に防ぐか、という点に重点を置いて対策がなされてきました。しかし、どれほど厳格に運行管理を行い、運転手の技術向上を図っても、事故を「ゼロ」にすることはできません。
そこで、2014年以降、新造される貸切バスや高速バス車両について、衝突の危険があるときに自動で減速または停止する「衝突被害軽減ブレーキ」(いわゆる「自動ブレーキ」)を搭載することが順次義務化されました。さらに、2018年からは、日野自動車といすゞ自動車が販売する大型貸切バス、高速バスには「ドライバー異常時対応システム(EDSS)」(運転手が運転中に意識を失った場合など、バスガイドや乗客がボタンを押すことでバスが自動停止するシステム)の標準搭載が始まり、今後は他車種への展開やさらなる技術の高度化が予定されています。事故防止や事故の原因究明に使われる「ドライブレコーダー」も、2017年以降、貸切バス全車に装着することが順次義務化されています。
貸切バスの利用者側も変化 安全性の「認定」重要に
軽井沢での事故を受け、紹介したもの以外でも多くの制度改正が行われました。こうした制度を着実に実行していくことこそ、業界の底上げを図るという意味で最も重要な対策です。一方、もうひとつ重要なことが、安全への取り組みをただの「コスト」だと受け取るのではなく、努力したぶん、自らの会社を選んでもらえるようになる「投資」だと思える市場環境を作ることです。
事故後、貸切バスを利用する側である旅行業界も変化しています。旅行会社がバスツアーを企画し集客する際、実際に利用するバス事業者の名前をパンフレットなどに明記することとなりました。
それまで、航空会社やホテルについてはパンフレットに固有名詞で記載され、仮に変更になれば利用者から差額返金などが求められていたのに対し、貸切バスは会社名の記載がなく、どの事業者も同じという扱いだったのです。たしかに従前のルールであれば、ツアーを企画する旅行会社にとっては、ツアーの集客状況(参加人数)や行程に応じて直前に別の契約バス事業者に振り替えることも容易です。これは、バス事業者にとっても状況に応じて車両を提供できるので、運用が楽であることは間違いありません。
しかし、それでは、すべての貸切バスは、使いまわしのきく「汎用パーツ」になってしまいます。前述の通り2000(平成14)年以降、貸切バス事業者のレベルの差は拡大しているので、その差を「可視化」し、品質の高い事業者に予約が集まったり、その対価として高い運賃を受け取ることができたりするような市場環境を作る必要があります。
そのための対策が、日本バス協会による「貸切バス事業者安全性評価認定制度」(通称:セーフティバス)です。同協会の担当者がバス事業者に出向き取り組みを評価するとともに、事故歴を反映して安全性の高い事業者を認定するもので、全国約4500社のうち、2018年12月現在で1718社が認定済み、そのうち318社が最難関の「三ツ星」を取得しています。
大手旅行会社を中心に、発注(利用)先を、同制度認定のバス事業者に限定する動きも生まれています。その結果、中小規模の事業者でも同制度の認定を目指す事業者が増えています。認定を受けるには、運行管理の体制などを充実させる努力が必要で、中小事業者のレベルアップにつながります。
「ルールだから仕方なく」から、「選んでもらうため」の安全対策へ
これまでバス業界には、「安全対策は見えないところで地道に行うもの」「お客様に不安感を与えないよう、安全対策をあえて説明しない」という雰囲気がありました。いまでは、安全への取り組みを可視化し、積極的に説明することで乗客に安心感を与える動きが始まっています。
前述の「衝突被害軽減ブレーキ」や「ドライバー異常時対応システム」など先進的技術を用いた安全対策についても、バス車両の外側にステッカーなどで表示するためのガイドラインも国によって作られました。今後は、バス事業者どうしが、安全対策を含めた自らの品質を競い合う市場環境を作り上げていくことが必要だと言えます。
一方、ほかの業界同様、バス業界でも人手不足が深刻化しています。運行管理体制や車両の安全装置が不十分なバス事業者は運転手からも選ばれなくなり、「人手不足倒産」のリスクさえ生まれています。「規制で決まっているから仕方なくルールを守る」安全対策から、「お客様や従業員から選んでもらうため」積極的な意識で行う安全対策へと、業界全体で舵を切ることこそ、貸切バス業界変革のゴールだと言えるでしょう。
最後に、この事故で亡くなった方をはじめ被害者、そのご家族の気持ちを思うと、バス業界の関係者として沈痛な気持ちになります。バス業界に関わるすべての人が、真摯に、このような事故の再発防止に努め続けることを願っています。
成定竜一(高速バスマーケティング研究所代表)
個人的に日本の司法制度には疑問を感じる事はある。しかし、良くも悪くもこれが日本である。
日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告だけが不当な扱いをされたと日本の司法制度がヨーロッパやその他の海外の国々と違うのでは大きな違いだと思う。
最後に本当にキャロル・ゴーンさんは日本の司法制度の改革を求めているのか?それとも夫の件が終われば見向きもしないのだろうか?
今回の件で日本の司法制度に関して少しは改善されるかもしれないが、改善や改善の適応までにはカルロス・ゴーン被告のケースは間に合わないと思う。
カルロス・ゴーン被告の記事がどこまで事実なのか知らない。そして、有罪か無罪かは法制度、検察、裁判所そして証拠や証人次第で変わる。ただ、無茶苦茶にやっていると思う。日産がゴーン被告と対立しなければ絶対に公表されない事ばかりであるが、公になった以上、なるようにしかないと思う。
日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン被告の妻が13日、夫が不当な扱いを受けているなどとする文書を国際人権団体に送ったことがわかった。
文書はゴーン被告の妻、キャロル・ゴーンさんから国際人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」の日本支部に宛てて送られたもので、「夫に対する不当な扱いと不平等な日本の司法制度に光を当ててもらいたい」などと要請している。
また、拘置所の部屋は暖房もなく風呂は週に2~3度しか許されず、体重は2週間で7キロ減ったなどと訴えている。
その上で、捜査当局は弁護士が立ち会わない中で夜や休日も取り調べを行っていると非難していて、日本政府に対して司法制度改革をするよう求めている。
日本テレビ系(NNN)
「同社によると、販売担当者がメキシコ産クロマグロを仕入れる際、伝票に『国内産』と記した上、計約3.2トンを52回にわたりスーパーに納入していた。昨年3月にスーパーから産地証明書の提出を求められ発覚した。」
「スーパーから産地証明書の提出」を求められまでの52回も「国内産」として納入したのは悪質だと思う。数回であれば、間違えた可能性はあるが、
52回は確信犯だと思う。
水産物卸会社「横手水産物地方卸売市場」の歴史は浅いの?
秋田県横手市の水産物卸会社「横手水産物地方卸売市場」が2017年8月~18年3月、外国産マグロを国産と偽り、県内のスーパー1店に納入していたことが13日、同社への取材で分かった。和泉健一社長は「産地偽装はとんでもないことで管理が行き届かなかった。消費者に対しても申し訳ない」と話している。
同社によると、販売担当者がメキシコ産クロマグロを仕入れる際、伝票に「国内産」と記した上、計約3.2トンを52回にわたりスーパーに納入していた。昨年3月にスーパーから産地証明書の提出を求められ発覚した。
「日産関係者によると、ジュファリ氏の会社『ハリド・ジュファリカンパニー』は、自動車関係の仕事をしていなかったという。」
日産関係者は証拠をもっているのだろうか、それとも、東京地検特捜部は証言できる人間の協力を得ているのだろうか?
日本でもそうだが、中東の方が上や周りからの圧力はありそうだから、何のメリットもなく日産や東京地検特捜部に協力するとは思えない。
日産自動車の元会長、カルロス・ゴーン被告(64)が、日産の子会社からサウジアラビアの知人の会社に13億円を支出した事件で、この会社が自動車関連の仕事をしていなかったことがわかった。
ゴーン被告は、サウジアラビア人の知人、ハリド・ジュファリ氏の会社に、日産の子会社「中東日産」からおよそ13億円を支出させるなどした罪で、追起訴された。
ゴーン被告は、ジュファリ氏について、「日産のために働いた正当な報酬」だとして容疑を否認している。
しかし、日産関係者によると、ジュファリ氏の会社「ハリド・ジュファリカンパニー」は、自動車関係の仕事をしていなかったという。
東京地検特捜部は、ゴーン被告からジュファリ氏への支払われた金は、謝礼だった可能性があるとみて調べている。
FNN
「ゴーン事件でフランスが報復」が事実であろうがなかろうが、関係のある人達には困った事であろうが、関係のない人達にはどうでも良い事。
問題は、東京地検特捜部がゴーン容疑者を有罪に出来るのか、そして、日本オリンピック委員会(JOC)の竹田恒和会長を有罪の出来るのかだと思う。
捜査しても有罪に出来なければ当事者、関係者そして利害関係者達は不愉快な思いをするであろうが、ただそれだけである。
国によって法律や似たような法律であっても解釈が違ってくる。常識やモラルと法的に違法であるか、有罪になるのかは全く次元が違う。
日本で違法でも外国では違法でないケースはたくさんある。アメリカなどは州が違えば、違法であるかの基準が全く違ってくる。
納得出来ても、出来なくても、法や規則が違う国やエリアに行くのであれば受け入れるしかない。
日本であっても同じように法や規則が適用されているとは思えない。または、法や規則を解釈する人が違えば、結果も違ってくる。外国の
法や規則であればなおさら違うが大きくなると思う。
東京地検特捜部がフランス政府からの報復なり、ネガティブな対応を想定していないとは思えない。判断する人がどう思ったかは知らないが、
相手の気に入らない事をすれば、相手がかなり出来た人でなければ、それなりの報復は想定するべきだと思う。
個人的には東京オリンピックを指示していなかったので、事実はどうだったのか知らないが、有罪にされるような手段を選択したのなら仕方のない事だと思う。この世の中、綺麗ごとばかりではない事は理解している。特に結果をコントロールしたければ不正やごまかしは選択のひとつになると思う。
だから、不正、データ改ざん、不正や違法検査、虚偽報告などいろいろな選択をするのである。ばれなければ不適切な選択を選んで勝者となった者達が得をする。不正が見つかれば、不正を行った者は不正をしなかった以上に損が発生する可能性が高い。
ゴーン容疑者が無罪となっても、彼が行った事を知った人達は彼に対する印象や考え方を変える人がいるだろう。もし、今回の騒動が公にならなければ
多くの人達はゴーン容疑者がどんな事をしてきたのか、どんな人間なのか、知る事はなかった。事実とは関係なく、多くの日本人のゴーン容疑者に対するイメージは良いままであったであろう。
東京地検特捜部と日産はここまで来たのだから引き下がったら面目を失うだけで総合的にマイナスで終わるであろう。行き付く所まで行けば良いと思う。衝突しないと見えてこない事はある。個人的にプラスマイナスでプラスか、0(ゼロ)であれば良いと思う。外国人は日本人をお金を持っている事は否定しないが見下している事が多い。日本のガッツを見せた方が良いと思う。真似はしなくて良いが、韓国の理解できない対応を少しは参考にすれば良いと思う。
2020年の東京五輪・パラリンピックの招致を巡る贈収賄疑惑で、フランス司法当局は11日、日本の招致委員会の委員長で日本オリンピック委員会(JOC)の竹田恒和会長を訴追する手続きを開始した。フランスのル・モンド紙(電子版)が報じた。
同日午後には、東京地検特捜部が日産自動車のカルロス・ゴーン前会長を会社法違反(特別背任)で追起訴したばかり。絶妙なタイミングでの捜査開始報道に、ネット上では「ゴーン逮捕の報復か」といった見方が広まっている。
竹田氏の疑惑は、少なくとも2016年5月の時点でイギリス紙「ガーディアン」の報道などで、捜査が行われていたことが明らかになっている。日本の招致委員会は、国際陸上競技連盟(IAAF)前会長のラミン・ディアク氏の息子、パパマッサタ・ディアク氏と関係が深いシンガポールのコンサルタント会社、ブラック・タイディングズ社に13年7月と10月、合計約2億3000万円を振り込んでいた。東京五輪の招致が決定したのは13年9月7日。その前後の多額の入金に、贈賄があったのではと疑われていた。
ただ、報道は断続的に続いたものの訴追の動きは見えなかった。それがこのタイミングで捜査の再開が表面化した。竹田氏は、昨年12月10日にすでにフランス当局から事情聴取を受けたという。ちなみに、ゴーン氏が特捜部に逮捕されたのは昨年11月19日で、12月10日は金融商品取引法違反の容疑で再逮捕された日だった。
ジャーナリストの田中良紹氏は、こう話す。
「国際政治の世界では『自国民が不当な理由で他国に拘束された』と考えたら、報復するのが鉄則。沈静化していた捜査がこのタイミングで訴追手続きに入ったことは、日本政府に強烈なパンチを与えたことになる。日本政府は表向き否定するでしょうが、政治家なら誰もが『フランス政府からのメッセージ』と捉えたはずです」
逮捕や身体拘束の応酬は、国際政治の世界では日常茶飯事だ。最近では、中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)の最高財務責任者が米国の要請によりカナダで逮捕されたことを受け、中国は同国内にいるカナダ人のビジネスマンや元外交官を拘束した。米国では、昨年12月にロシア人女性がスパイ容疑により同国で有罪になると、ロシアは同月に米国人男性を同じくスパイ容疑で拘束した。ちなみに、同じ程度の容疑を理由に相手国の国民を拘束することは、事態をさらに悪化させないための知恵でもある。竹田氏も、前述のとおりゴーン氏と同じく他国の関係者への資金提供が不正だったと疑われている。
身体拘束の応酬は、日本も経験している。10年に起きた尖閣諸島(沖縄県石垣市)での中国漁船衝突事件では、海上保安庁が中国人船長を逮捕。中国は報復として同国本土にいた日本人会社員4人を拘束したうえで、日本政府に船長の釈放を要請した。結果として、中国人船長は処分保留で釈放された(日本人会社員も後日解放)。中国人船長の処分保留について日本政府は、「那覇地検独自の判断」と説明したが、当時の官房長官だった仙谷由人氏は後に、検察当局に船長釈放を働きかけたことを産経新聞のインタビューで明らかにしている。
前出の田中氏は言う。
「特捜部は、現在でもゴーン氏を逮捕した容疑についてほとんど説明していない。一方で、マスコミを利用してゴーン氏を悪者にする情報を次々とリークして、印象操作をしている。日産をめぐっては日仏の自動車産業戦争の側面もあることから、フランス政府は、この動きは日本政府が特捜部を使ってゴーン氏を追放しようとしていると認識しているのでしょう。もちろん、表向きは両国政府とも司法当局への介入は否定します。しかし、これほどの事態になれば政府間で水面下の交渉をせざるをえません」
実は、フランスはすでに警告を発していた。フランス大統領府は、ゴーン氏の逮捕直後から広まっていた日産の日本人経営陣によるクーデター説に「陰謀なら外交的にかなり深刻な危機を引き起こす」とコメントしていた。元駐日フランス大使のフィリップ・フォール氏は、一連の捜査について毎日新聞の取材に「民主主義の国はこういうやり方をしない。今、日本で起きていることはサウジアラビアで起きていることのようだ」(昨年12月10日付)と、厳しく日本を批判していた。
一方、特捜部はフランスほか国際社会で巻き起こった批判を無視。ゴーン氏の勾留を続け、東京地裁が勾留延長申請を却下したにもかかわらず、昨年12月21日に3度目となる逮捕を実行した。それだけではない。ゴーン氏がやせ細った姿で今月8日に東京地裁に出廷したことは、フランスのみならず世界中に衝撃を与えた。米国のウォール・ストリート・ジャーナル紙は社説(9日付)で、少女が奇妙な世界に迷い込んで不可思議な体験をする児童小説「不思議の国のアリス」になぞらえて、「不思議の国のゴーン」と日本を批判した。
「人質司法」と批判されてきた日本の司法制度、そして特捜部の強引な捜査手法は、法の支配や善悪の規範など通用しない、“力”が支配する国際社会のパワーポリティクスの介入を招いた。ゴーン氏が11日に追起訴されたことを受け、弁護人は同日に東京地裁に保釈請求を出した。判断は15日以降になると思われる。それまでに安倍晋三首相とマクロン仏大統領は水面下でどう動くのか。ゴーン事件は、新たな展開を迎えた。(AERA dot.編集部/西岡千史)
全てを公表するのか、それともリスクを負ってもうやむやにするのか?結果が出るまでどの選択が良いのかわからないかもしれない。
AKBのファンではないので、ここから流れが変わっても個人的には困らない。逆にAKBだけでいろいろな都道府県にクローンは要らないと思う。
NGT48メンバーの山口真帆さん暴行事件をめぐり、インターネット上で関与を疑う声が上がっていたNGT48メンバーの2名は、事件とは無関係だったことが「週刊文春デジタル」の取材でわかった。1月12日、インターネット生放送番組「直撃! 週刊文春ライブ」が報じた。
【写真】山口さんが配信していたSHOWROOMより
事件後、山口さんはSNSに「あるメンバーは私の家に行けと犯人をそそのかしていました」と書き込んでいたが、新潟県警が名前の挙がった2名の携帯電話の通信履歴などを調べた結果、関与を示すような内容は出てこなかったという。
山口さんへの暴行容疑で逮捕(不起訴)されたのは、A氏(25歳・無職)とB氏(25歳・無職)。この他に20代前半のC氏も事情聴取を受けている。加害者グループは、NGT48メンバー・中井りかとの交際が昨年6月に報じられたZ氏率いる“アイドルハンター軍団”の一員だった。周囲から「Z会」と呼ばれていたグループは、1年以上前から、事件現場となったマンション内に部屋を借りていたことも判明。その目的は、NGT48メンバーとの「接触活動」だという。
「直撃! 週刊文春ライブ」は、事件当日のドキュメントやA、B両氏が不起訴と判断された真相、事件後にNGT48の今村悦朗支配人がメンバーに送ったメール文面などについても詳しく報じている。
「週刊文春」編集部/週刊文春
疑いのある客室乗務員だけにアルコール検査を実施すれば良いと思うけど、差別とか不平等な扱いだと言われるリスクがあれば、全ての
客室乗務員にアルコール検査を実施するしかない。勤務中に飲酒を繰り返す客室乗務員が存在し、問題を解決できなかったのだから仕方がない。
やる以上、アルコール検査の実施が建前だけで不正がないようにしっかりとやるべきだとお思う。パイロットの中には不正やインチキが存在していたので同じ事を繰り返さないようにするべきだと思う。
日航によると、11日に国土交通省に報告した再発防止策では、全ての客室乗務員を対象に、目的地到着後のアルコール検査を実施するとしている。昨年12月には乗務前の検査を始めている。
規則は規則かもしれないが、世の中、検査を通すのための検査が存在するので問題があっても検査を通すのだから実際に資格は建前だけと
思える事がある。
現実の問題は別として、規則では適正に資格を取得しなければならないので処分は仕方がない。
LIXIL子会社の「LIXIL鈴木シャッター」(東京都豊島区)は11日、防火シャッターなどの定期検査を行う防火設備検査員の資格を社員13人が不正に取得していたと発表した。
国土交通省は今後、資格の返納命令を出す方針。
同社や国交省によると、13人は2015~17年度に、資格取得の前提となる防火設備講習を受ける際、上司の指示で実務経験期間が実際は1カ月~2年1カ月だったのに「(受講資格がある)3年以上」と偽っていた。資格取得後、東京都と千葉、長野両県の学校や病院など計68棟で定期検査を行っていたという。
「日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者が、フランスの富裕税課税を逃れるためオランダに税務上の居住地を移していたとされる問題」は
フランスに落ちる税金が少ないだけで何ら問題はないと思う。
「税務上の居住者となるには、オランダではフランスと同様、原則年間183日以上の滞在が必要。仏紙リベラシオンは、主にパリと日本を行き来するゴーン容疑者がこの要件を満たす可能性は低いと指摘した。」
上記の件では、「原則年間183日以上の滞在」を満たしていなければ大問題だと思う。
【パリ時事】日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者が、フランスの富裕税課税を逃れるためオランダに税務上の居住地を移していたとされる問題で、仏ラジオ・ヨーロッパ1は10日、「公共心に欠け、違法性が無くても大問題だ」と指摘した。
同容疑者が会長兼最高経営責任者(CEO)を務める仏自動車大手ルノーの労組幹部は仏テレビに対し「我慢できない」と反発した。
ヨーロッパ1は、ゴーン容疑者の逮捕直後の昨年11月、ルメール仏経済・財務相が同容疑者の仏国内での納税状況に関し「報告すべき特別な点はない」と説明したことについて「うそだったのではないか」と批判した。
税務上の居住者となるには、オランダではフランスと同様、原則年間183日以上の滞在が必要。仏紙リベラシオンは、主にパリと日本を行き来するゴーン容疑者がこの要件を満たす可能性は低いと指摘した。
事実であれば本当にひどい!
「カメラを取り付けたことで私が罪に問われたとしても仕方がありません。責任は引き受ける覚悟です。ただ、このまま“盗撮”状態が続くことだけは耐えられなかった……」。沈痛な面持ちで語るのは、「串カツ田中」の更衣室に隠しカメラを設置した業者である。彼の告発がなければこの不祥事が露見することはなかった。「居酒屋業界の革命児」が全面謝罪に追い込まれた、盗撮問題の真相とは――。
【動画】女性社長による“証拠隠滅”場面
串カツ田中のホームページに〈フランチャイズ加盟店による盗撮問題発生について〉とのリリースが掲載されたのは12月21日の晩のこと。概説すれば、串カツ田中のフランチャイズ加盟店・H社が運営する、神奈川県内の4店舗で盗撮が発覚したというのだ。
2008年、東京・三軒茶屋に1号店をオープンした串カツ田中は快進撃を続け、すでに200店舗を突破。16年には東証マザーズへのスピード上場も果たした。そんな同社は、〈スタッフが笑顔で安心して働け、かつ、やりがいのある会社〉を企業理念に掲げている。
にもかかわらず、なぜ従業員の着替えを「盗撮」していたのか。
「私に隠しカメラの設置を依頼してきたのはH社のAさんという取締役でした」
そう明かすのは冒頭の業者である。
「Aさんとは知人を介して5年ほど前に知り合いました。私が通信設備の仕事をしていたことで、2016年からH社が運営する串カツ田中の店舗への防犯カメラの設置を請け負ってきた」
そして、1店舗目を手掛けた際、業者はこんなことを言われたという。
「店を訪れたAさんは、“ここにカメラをつけてくれ。ただし、撮ってることがバレないように”と更衣室の天井を指さしました。“他の店で盗難があってね。防犯用なんだ”と。たとえ防犯用と言われても、更衣室に隠しカメラを設置すること自体、私には抵抗がありました。ただ、Aさんに仕事を干されては困るので口を噤んでしまった。そのことがいまも悔やまれます」
「防犯目的」は詭弁
A氏の依頼を断れなかった業者は、串カツ田中の3店舗の更衣室に「煙感知器型」の隠しカメラを取り付ける。ちなみに、盗撮が発覚したもう1店舗は別の業者が担当している。
この「盗撮」行為についてはH社の女性社長も把握しており、実際に映像が見られたのは管理者である業者の他にはA氏と社長だけ。つまり、H社の社長と取締役は、自分の店で働くスタッフの着替えを常時、のぞき見できたことになる。
その後、設置業者はA氏とトラブルになり、暴力まで振るわれたことから今回の告発に踏み切ったのだ。
さて、すでに串カツ田中はこの業者が明かした「盗撮」の事実を全面的に認め、
〈被害に遭われた当該店舗の従業員の皆様には多大なる精神的苦痛とご迷惑をお掛けしたことに深くお詫び申し上げます〉
と、謝罪するに至った。
だが、本誌(「週刊新潮」)が取材に乗り出した当初、関係者の対応はとても潔いとは言えないものだった。カメラには写らなかった内幕を明かすと―。
12月20日、まず本誌はA氏に隠しカメラの設置を依頼した理由を質したが、
「全然意味が分からないです。全く身に覚えがないんですけど。取材と言われても今日は忙しいし、明日はゴルフが入ってるんで」
と疑惑を全否定した上で逃げの一手。続いて女性社長に尋ねると、
「盗撮? はぁ? ちゃんと取材してから記事を載せてください。うちの店舗に更衣室なんてないですよ。ロッカールームもありません。従業員の着替えは、えっと、お手洗い……」
その場しのぎの言い訳にしても、飲食店のスタッフが「トイレで着替える」というのは感心しない。
ちなみに、掲載の写真は、業者の告発の動きを察知した女性社長が、更衣室の隠しカメラの電源を切る様子。本誌が取材を申し込む5日前に撮影されたもので、「証拠隠滅」を図った彼女が「盗撮」の事実を知らなかったワケがない。
このようにH社側の対応があまりにも要領を得ないため、今度は串カツ田中の本社に取材を申し込んだ。
すると、更衣室の隠しカメラについてあっさり認めるのである。ただし、
「カメラはあくまで防犯を目的に設置したということです。設置業者による情報流出について警察に被害届を申請中なので、これ以上はお答えできかねます」
という木で鼻を括ったようなご対応。この説明に、セクハラ問題に詳しい上谷さくら弁護士は首を傾げる。
「防犯目的であれば、むしろカメラの存在を従業員に周知すべきでしょう。今回のようなケースで防犯目的と弁明するのは詭弁に過ぎません。また、更衣室に隠しカメラを設置した時点で“のぞき見”に当たるため、軽犯罪法に触れる可能性もあると思います」
やはり「盗撮」を正当化するのは難しい。串カツ田中もこれ以上の言い逃れはできないと悟ったのだろう。21日の晩に、改めて業者による告発内容を認める回答が届いた。そして、すぐさま事実の公表となった次第。
ソースの二度づけは禁止でも、回答が2度に亘るのは構わないようだ。
「週刊新潮」2019年1月3・10日号 掲載
日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告(64)を巡る特別背任事件に絡み、ゴーン被告が2009~17年、中東5か国の販売代理店などに対し、日産の「機密費」から総額約1億ドル(現在のレートで約110億円)を支出していたことが関係者の話でわかった。サウジアラビアの知人側に送金された計1470万ドル(同約16億円)も含まれており、東京地検特捜部は、各国に捜査共助を要請し、支出の経緯などを調べている。
関係者によると、「機密費」は「CEO reserves(積立金)」と呼ばれる資金。日産の最高経営責任者(CEO)だったゴーン被告が08年12月頃、部下らに指示して創設させたとされ、CEOの判断で支出できる。
徹底的にやれば良い。
日産自動車前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)の側近で仏ルノー副社長のムナ・セペリ氏に、3社連合を組む日産、ルノー、三菱自動車の統括会社「ルノー・日産B・V」から不透明な報酬が支払われていたことが10日わかった。セペリ氏はオランダ・アムステルダムにある統括会社の取締役を兼ねるが、2012~16年の5年間に役員報酬とは異なる非公表の報酬として計約50万ユーロ(約6200万円)を受け取っていた。
【写真】隠し報酬の構図
統括会社内に設けられた「ガバナンス(企業統治)・人事・報酬委員会」の委員でもあるセペリ氏に対し、委員の報酬として年10万ユーロが支払われており、統括会社のトップを務めるゴーン容疑者が支給を承認していた。3社連合の関係者が、支給を認めたゴーン容疑者らの直筆のサインが入った書簡や、セペリ氏に約50万ユーロが支払われたことを示す証明書を入手し、その内容を明らかにした。
ゴーン容疑者が日産における自身の報酬を隠しただけでなく、ルノー幹部への「隠し報酬」に関与した疑いも明るみに出たことで、ゴーン容疑者の会長兼CEO(最高経営責任者)職の解任を見送っているルノーの判断に影響を及ぼす可能性もある。
書簡は13年3月26日付。役員報酬の虚偽記載の疑いで逮捕されたゴーン容疑者と日産前代表取締役のグレッグ・ケリー被告の署名が末尾に直筆で記されていた。報酬の支払いを示す証明書には、ゴーン容疑者の役員報酬の過少記載などに加担したとされる日産の秘書室幹部の直筆サインがあった。
統括会社の取締役には日産の西川(さいかわ)広人社長兼CEOらも名を連ねるが、統括会社から役員報酬を受け取っている取締役はいないとされる。同委員会はゴーン容疑者、ケリー被告とセペリ氏の3人のみで構成され、セペリ氏だけが委員報酬を受け取っていたとみられる。
日本航空の46歳の女性客室乗務員(CA)が昨年12月、乗務中に飲酒した問題で、国土交通省は11日、日航に行政指導としては最も重い業務改善勧告を出す。日航は昨年12月、パイロットの飲酒不祥事で同省から行政処分である事業改善命令を受けたばかり。日航は10日、これまで飲酒を否定していたCAが機内で飲んだことを認めたと明らかにした。
日航によると、CAは昨年12月17日の成田発ホノルル行きと、2017年11月17日のホノルル発成田行きの機内で飲酒した。昨年12月の乗務中、同僚が酒の臭いに気付いて発覚。乗客に提供していないのにシャンパンの空き瓶(170ミリリットル)が機内で見つかったことから、日航は機内での飲酒があったと判断した。
CAは当初、飲酒を認めていなかったが、昨年12月26日、上司に飲酒を申告。同社が今月8日まで聞き取りを重ねた結果、12月の乗務では「シャンパンを半分飲み、残りは捨てた」と説明し、17年11月にも飲酒したことを認めた。「(飲酒の調査結果を発表した)12月25日の会社幹部の記者会見をニュースで見て、迷惑をかけて申し訳ないと思った」と話しているという。
飲酒不祥事が相次いだことから国交省は、国内の航空会社のパイロットについて、わずかでもアルコールが検出されると乗務させない方針を決定。今後は、CAや整備担当者らの飲酒ルールについても議論する。【花牟礼紀仁】
日本航空はパイロットが頭でわかっていても飲酒をやめられないほどパイロットが多いのか?国交省は飲酒やアルコール検査の不正行為に関して厳しい罰則を設けないとざるの規則になるかもしれない。
日本航空の機長が、自分の代わりに別のパイロットに乗務前のアルコール検査を受けさせていたことがわかった。
日本航空によると、2017年12月、成田発シカゴ行きの便に乗務予定の50代の機長が、予備の検査でアルコールが検知されたため、自分の代わりに、別のパイロットに本番のアルコール検査を受けさせ、そのまま乗務していたという。
身代わりのパイロットが「替え玉」になったことを打ち明けたため、不正が発覚した。
当時、検査は1人で行われていて、この機長は、アルコールの基準値を下回っていたと説明している。
日本航空は9日、同社の男性統括機長(59)が2017年12月、成田空港で乗務前のアルコール検査を行わず、同僚の男性機長(53)に代行させた不正行為があったと発表した。統括機長は前日に飲酒しており、検査をした場合にアルコールの値が社内基準に抵触する恐れがあったが、このまま乗務した。
日航によると、17年12月2日、成田発シカゴ行きの旅客便(乗客乗員152人)に乗務予定だった統括機長が予備のアルコール感知器を使って検査したところ、呼気1リットル当たり0.09ミリグラムの反応があった。社内基準値は同0.1ミリグラムで、不安を感じた統括機長は同乗する予定の機長に検査の代行を依頼。機長は再検査を勧めたが、最終的に代行した。
統括機長は前日夕に350ミリリットル入り酎ハイを3本飲んでおり、飲酒量も社内で設定した目安を超えていたという。
その後、代行した機長が所属長に報告して不正が発覚。日航は統括機長と機長を懲戒処分とした。
また、10年11月に豪シドニーで、別の既に退職した男性機長が当局のアルコール抜き打ち検査を受け、結果が同国の基準値に抵触したとして、乗務を禁じられたケースもあったという。
勤務中にお酒を飲まないとやっていられないとはかなり危険な状態なのか、働き方に対する姿勢がその程度だったのか?
本当に疲れているだけなら栄養ドリンクとか、栄養サプリメントでお酒ではないはず。
本当の理由なのか知らないが、教育とか陸上勤務の方が良いのでは??
日本航空の客室乗務員が乗務中にシャンパンを飲んでいた問題で、同じ客室乗務員が、過去にも乗務中にシャンパンを飲んでいたことが新たにわかった。
日本航空によると、46歳の女性客室乗務員が、2017年11月のホノルル発成田着の機内で、乗務中に客に振る舞うシャンパンを隠れて飲んでいたという。
この客室乗務員は2018年12月、乗務中にシャンパンを飲み、同僚からアルコールのにおいがするとの報告で、飲酒が発覚している。
発覚当時、飲酒を否定していたが、現在は認めており、女性乗務員は「疲れがたまっていたので飲んでしまった」と話しているという。
パイロットによる飲酒問題が相次ぐ中、国土交通省は、乗務前の飲酒検査を新たに義務づけ、アルコール基準を呼気1リットルあたり0.09mgとする方針を固めた。
日本では現在、パイロットのアルコール基準や検査の義務はなく、対策は航空会社にゆだねられているが、11月、日本航空のパイロットがイギリスで実刑判決を受けるなど、パイロットの飲酒問題が相次いで発覚している。
このため、国交省は、乗務前にアルコール検知器での飲酒検査を義務づけ、基準値を呼気1リットルあたり0.09mgとする案を19日に開かれる検討会で示す予定。
車や、鉄道、船舶での基準値は0.15mgで、それらより厳しい基準となる。
オマーンの知人やレバノンの知人は捜査に協力するだろうか?東京地検に協力するメリットはないと思える。事実とは別にカルロス・ゴーン容疑者が 無罪となればほとぼりが冷めてからお礼だって期待できる。カルロス・ゴーン容疑者がどんな人物なのか知らないし、彼とオマーンの知人やレバノンの知人との関係がどのようなレベルなのかも知らないので勝手な個人的な推測だ。人間は感情的な動物でもあるが、打算で動く動物でもある。メリット、デメリットとリスクの可能性を考えて判断すると考える事は出来ると思う。
日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者が、逮捕容疑となったサウジアラビアの知人側に日産側から支出したおよそ16億円とは別に、オマーンとレバノンの知人側にも、あわせておよそ50億円を支出していたことがわかった。
・映像でわかる「約50億円をオマーンとレバノンの知人会社に ゴーン容疑者」
ゴーン容疑者は、私的な損失の信用保証に協力した、サウジアラビアのハリド・ジュファリ氏の会社に、およそ16億円を子会社の中東日産を通じて支出させるなどした疑いが持たれている。
関係者によると、ゴーン容疑者は、中東日産から、ジュファリ氏側だけではなく、オマーンの知人の会社におよそ35億円、レバノンの知人の会社におよそ17億円を支出していたという。
これらの支出の原資は、いずれも、CEO(最高経営責任者)だったゴーン容疑者が使途を決められる、「CEOリザーブ」から支出されたとみられ、ジュファリ氏への支出については、中東日産の幹部が、「明らかに不自然な支出で、現場からも要請していない」と話していることもわかった。
東京地検特捜部は、不透明な資金の実態解明を進めている。
日産前会長ゴーン容疑者が有罪になればとんでもない大嘘付きとのイメージが定着するだろう。もし、ゴーン容疑者が無罪となれば、日産、日本の検察そして日本の司法制度は世界中でイメージを悪化させるであろう。
日産前会長ゴーン容疑者が、中東オマーンの会社で幹部を務める知人から約16億円を受け取った疑いのあることが9日、関係者への取材で分かった。知人の会社には日産側から約35億円が支出されており、東京地検が資金の流れを調べている。
格安航空会社(LCC)の「インドネシア・エアアジアX」(IDX)の財務が悪化しているのかもしれない。明確な理由がない限りインドネシア・エアアジアX(IDX)の飛行機は避けれるのなら避けた方が良いかもしれない。整備部品、整備費用、整備スケジュールや整備に関する支払いなど にも影響していれば、運が悪いと事故に繋がる可能性が高い。飛行機が墜落してからでは遅い。
格安航空会社(LCC)の「インドネシア・エアアジアX」(IDX)が、成田空港の空港使用料を滞納していることがわかった。滞納額は数億円に上るとみられる。成田国際空港会社が督促しているが、IDXは来週で日本路線の運休を決めており、支払いを受けられるかは不透明な状況だ。定期便を運航する航空会社が多額の使用料を滞納するのは異例。
IDXはマレーシアのLCC「エアアジア」の関連会社で、ビーチリゾートとして人気のバリ(インドネシア)を拠点に長距離路線を運航。日本では2017年以降、成田とバリ、ジャカルタそれぞれを結ぶ便を飛ばしており、現在は成田―バリ間を原則1日1往復している。
関係者によると、IDXは数か月前から成田国際空港会社への月数千万円の使用料の支払いが滞るようになった。空港会社は再三納付を求めてきたが、IDXは今月14日の便を最後に休航を決めており、回収が困難になる恐れがある。
ジャカルタにあるIDX本社は読売新聞の取材に「滞納の件は成田空港と協議している」とコメントしたが、金額や滞納理由などは答えなかった。エアアジアの広報担当者は「IDXはなるべく早く支払う意向だ」と説明。運休については「エアアジアグループ全体の中で決まったこと。休航する便の搭乗率は低くなく、未納が(運休の)理由ではない」としている。
不正入試に関する記事を見るたびに東京医大の裏口入学に絡み、文科省佐野太前局長(59歳)の受託収賄罪事件の影響は凄かったと思う。
本音は知らないが、文科省の一部職員は幕引きしたいが、批判を受けたくないのでしぶしぶやっているのかもしれない。体質や人間の考え方は簡単には変わらないと思うので、文科省の体質は簡単には変わらないと思う。
東京医科大は8日、医学部の不正入試問題を巡り、特定の受験生の優遇と大学への寄付に関連があった可能性や、国会議員の口利き疑惑が指摘されたことを受け、第三者委員会に依頼して追加調査を実施すると明らかにした。過去の入試での問題漏えい疑惑についても事実関係を確認する。
東京医大の不正入試に関する調査は、弁護士をメンバーとして昨年8月に設置された第三者委が実施。昨年末に「最終報告書」をまとめ、国会議員や同窓会関係者らの依頼で、特定の受験生を優遇するなど数々の不正が長年続いた疑いを指摘した。ただ議員らへのヒアリングなどが不十分で詳細は確認できなかったとも記していた。
全日本空輸は機長に対して厳しい処分を行わないと信頼を失うのではないのか?
英国の空港で乗務前に基準値を超えるアルコールが検出されたとして、日本航空の男性副操縦士に有罪判決で注意しなければならない時期に飲酒の上、虚偽申告、しかも副操縦士に口裏合わせまで依頼している。
全日本空輸次第であるが、このような機長は安全なフライトを考えれば必要ないと思う。
事故がないだけで日本の航空会社は安全でない事を疑わせる事が短期間に起きていると思う。
全日本空輸は8日、グループ会社のANAウイングスの機長から乗務前にアルコールが検出された問題で、機長が社内調査に対し、飲酒量を過少申告したり、飲酒時間を偽ったりしていたと発表した。
同僚の副操縦士は口裏合わせを依頼され、虚偽の説明をしたという。
全日空によると、40代の男性機長は3日、大阪・伊丹空港で行った乗務前の検査で、アルコール反応が複数回出た。乗務を交代したため伊丹発宮崎行きなど5便に遅れが生じ、乗客計677人に影響した。
機長は当初、前日に大阪市内のホテルで350ミリリットル入りハイボールを2缶飲んだと説明。飲酒時間は2日午後7時までで、いずれも全日空グループの規定に抵触しない内容だった。
しかし、機長の説明につじつまが合わない点があり、追及されると飲食店でビールやハイボールなどを計4杯飲んだと告白。規定に違反して2日午後10時ごろまで飲んでいたとし、虚偽申告も認めた。
一緒に飲んでいた30代の男性副操縦士は機長から依頼され、虚偽申告に沿う説明をしていた。機長は処分が重くなることを恐れ、虚偽申告や口裏合わせを行ったという。
全日空グループの機長から、乗務前にアルコールが検出された問題で、機長が規定の時間を過ぎても飲酒していたことが新たにわかった。
機長は、時間内に飲酒をやめたと、会社にうその報告をしていた。
この問題は1月3日、ANAウイングスの機長が、乗務前の検査でアルコールが検出され、5つの便に遅れが出たもの。
当初、機長は「飲酒はしたが、規定時間内に酒を飲むのはやめた」と話していた。
しかし、実際は決められた乗務の12時間前を過ぎても、副操縦士と一緒に、焼き肉店でビールなど4杯を飲酒していたことが発覚し、機長がうその報告をしていたことがわかった。
「同社は『無免許の事実を把握していなかったが、業務での運転はなかった』と説明している。」
山口のような都会でない地域に住んで業務で運転せずに新聞記者の仕事をこなせたのだろうか?いつもタクシーか、運転する人と
行動していたと言う事か?
運転免許証の有効期限が切れているのを認識しながら車を運転したなどとして、山口県警が朝日新聞山口総局の男性記者(30歳代)を道路交通法違反(無免許運転、速度超過)容疑で書類送検していたことがわかった。山口区検は男性記者を同法違反で略式起訴し、山口簡裁が4日付で罰金31万2000円の略式命令を出した。
朝日新聞西部本社によると、男性記者は昨年9月下旬、同県宇部市内で私有車を運転中、制限速度を19キロ超過したとして県警に検挙された。その際、免許証の提示を求められ、無免許が発覚した。男性記者は同社の調査に対し、「2年前に免許の有効期限が切れているのに気付いた」と話したという。同社は「無免許の事実を把握していなかったが、業務での運転はなかった」と説明している。
「取材に対し、複数の警察官が『小遣い稼ぎだった』『上司から頼まれて断れなかった』と認めた。同社側もいったんは事実関係を認めたが、その後は『個人のプライバシーに関わるので、これ以上は答えられない』と取材を拒否した。」
副業禁止抵触のリスクを知っていたのか、知らなかったのかは知らないが、現時点で、「EDUーCOM」は十分に理解していると思う。今後は、隠れてもっと姑息に同様の事を継続するか、止めるのかのどちらかだと思う。
警察庁と県警が今回の件について問題や解答を執筆して現金を受け取る事を禁止するのかは組織の本音次第であろう。建前と本音は違う。建前と本音が違えば行動に反映されると思う。今後、同様な事に警察官が関与するとしても、禁止されていた事をするのと、知らなかった、又は、副業禁止抵触の認識がなかったと言い訳が出来るのでは、処分の重さに影響すると思う。
「同社(EDUーCOM)のホームページには『法律のスペシャリスト』が問題集を作成しているとあるが、関係者は『警察内部の通達や規定は公表されないことが多い。捜査など実務に関する設問を自前で作るのは難しく、警察官に頼んでいた』と証言した。」
昇任試験の勉強で受験者が同じ条件で勉強するのであれば捜査など実務に関する設問が実際と違っていても問題はない。要するに昇任試験の対策問題集「KOSUZO」(コスゾー)を購入すれば有利になる事で売り上げを伸ばそうとしたと言う事ではないのか?
警察庁と17道府県警の警察官が、昇任試験の対策問題集を出版する民間企業の依頼を受け、問題や解答を執筆して現金を受け取っていたことが西日本新聞の取材で分かった。企業の内部資料によると、過去7年間で467人に1億円超が支払われていた。最も高額だった大阪府警の現職警視正には1500万円超が支払われた記録があった。取材に対し複数の警察官が現金授受を認め、一部は飲食接待を受けたことも認めた。識者は「公務員が特定業者の営利活動に協力するのは明らかにおかしい。業者との癒着が疑われる」と指摘する。
【一覧】最高額は1500万円超 執筆額内訳
この企業は「EDUーCOM」(東京)。関係者によると、内部資料は同社が作成した2010年1月~17年3月の支払いリスト。警察官467人の氏名や執筆料、支払日が記され、ほとんどが警部以上の幹部だった。執筆料は、階級に応じた単価にページ数を掛けて算出していた。
最高額の大阪府警の現職警視正は7年間で1万8778ページ分執筆していた。このほか、宮城県警の警視正と京都府警の警視がそれぞれ約500万円、千葉県警の警部が約317万円など。福岡県警の最高額は本部所属の警視で2年間に約80万円、熊本県警は警視級の署長で4年間に約250万円だった。
複数年にわたって執筆し、50万円以上を受け取った警察官は41人で合計額は約8150万円に上った。執筆料が多額に上るケースでは、リストに載る警察官が窓口役で、複数で執筆を分担した可能性がある。
地方公務員法などに抵触する恐れ
一方、巻頭言や設問を1回だけ執筆した警察官が半数を占め、大半の執筆料が数千~2万数千円だった。
公務員の副業は原則禁止されている。警察庁と各警察本部に情報公開請求したところ、いずれも副業許可は出ていなかった。地方公務員法(兼業の禁止)などに抵触する恐れがあるが、警察庁などは「個別の事柄についてはコメントを差し控える」と回答した。
「小遣い稼ぎだった」「断れなかった」
取材に対し、複数の警察官が「小遣い稼ぎだった」「上司から頼まれて断れなかった」と認めた。同社側もいったんは事実関係を認めたが、その後は「個人のプライバシーに関わるので、これ以上は答えられない」と取材を拒否した。
同社のホームページには「法律のスペシャリスト」が問題集を作成しているとあるが、関係者は「警察内部の通達や規定は公表されないことが多い。捜査など実務に関する設問を自前で作るのは難しく、警察官に頼んでいた」と証言した。
同社は09年設立。昇任試験の対策問題集「KOSUZO」(コスゾー)を毎月発行し、全国向け「全国版」と、大阪や福岡など10道府県警に特化した「県版」がある。市販はしていない。民間調査会社によると、社員数は20人程度。販売部数は不明だが、年商は数億円とみられる。
小遣い稼ぎ、悪質だ 田中孝男・九州大大学院教授(行政法)の話
公務員が特定業者の営利活動に協力するのは不公正だ。金銭が伴うと業者に取り込まれる恐れがあるし、癒着の温床にもなりうる。組織として昇任試験対策の問題集を必要としているのなら、公的な手続きを経て無報酬で執筆すればいい。
公務員には職務専念義務があり、公務に支障を来しかねない副業は制限されている。勤務時間外でも無許可で反復・継続的に執筆していれば、国家公務員法や地方公務員法に抵触する恐れがある。反復・継続的の判断は各行政機関の裁量に委ねられているが、同じ年に2回執筆していれば該当しうる。今回のケースは頻度や報酬額からみて小遣い稼ぎの要素が強く悪質だ。
執筆料が年間20万円を超えていれば確定申告が必要で、仮にしていなければ脱税だ。法律を取り扱う警察官は特に襟を正さなければならない。
SNSで調査報道の依頼を受付中!
西日本新聞「あなたの特命取材班」は、暮らしの疑問から地域の困り事、行政や企業の不正告発まで、SNSで寄せられた読者の情報提供や要望に応え、調査報道で課題解決を目指します。ツイッターやフェイスブックの文中に「#あなたの特命取材班 」を入れて発信してください。
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)が私的な損失を日産に付け替えたなどとして逮捕された特別背任事件で、前会長が日産子会社からサウジアラビアの実業家ハリド・ジュファリ氏に送金した約16億円について、子会社の担当者(当時)が東京地検特捜部に「明らかに不自然な支出で、現場から要請もしていない」と証言していることが、関係者への取材でわかった。特捜部は約16億円が使途不明の支出であり、実態は前会長らの私的な利益を図るものだったとみて調べている。
ゴーン前会長はジュファリ氏への約16億円について「現地の販売店のトラブル処理や、投資を呼び込むための王族へのロビー活動、王族や政府との面会の仲介を担ってもらっていた」として、「仕事への正当な対価だった」と主張。弁護人も「王族との面会の適正価格を評価するのは難しい。無報酬でやることはありえない」と主張している。
これに対し、ドバイの子会社「中東日産」の担当者は、ロビー活動などのためであれば、現場から「緊急で数億円が必要」などと本社に支出を求めるのが普通だと説明。現場ではジュファリ氏によるロビー活動の必要性は感じておらず、「約16億円は上司の命令でそのまま送金した」と証言しているという。
また、中東日産の年度ごとの事業目標について達成できたかどうかを計算する際、約16億円の送金は支出に含まれていなかったことも判明。特捜部は証言や資料から、ゴーン前会長がCEO(最高経営責任者)直轄の「CEOリザーブ(予備費)」を使って、トップダウンで送金を指示していたとみている。
ゴーン前会長は、約18億5千万円の評価損を生んだ私的な取引をめぐって、ジュファリ氏から約30億円分の信用保証の協力を得た見返りに、中東日産から計1470万ドル(現在のレートで約16億円)を不正に送金した疑いが持たれている。2009年6月~12年3月の間の4回にわたり、「販売促進費」などの名目で送金したとされる。
注目を受けている中でこのような事が起き、アルコールの分解は人によって差がある事が科学的にわかっている以上、航空会社は
健康診断時、又は、一度、パイロットのアルコールの分解の傾向を全パイロットに行い、アルコールの分解が遅いパイロットには
医師のアドバイスを参考に乗務前12時間よりも前に飲酒を控えるように指導するべきだと思う。
国交省はアルコールの分解には個人差がある事を考慮した上でアルコール検査に関する具体的な基準を罰則とともに設けるべきだと思う。
3日朝、全日空グループのANAウイングスが運航する大阪発宮崎行きの全日空501便ボーイング737で、40代男性機長から乗務前の呼気検査でアルコールが検出され、乗務を交代した。全日空の運航便を含む計5便(乗客計677人)に影響し、那覇発大阪行きに最大104分の遅れが出た。
全日空によると、機長は前日、滞在中のホテル自室で、同乗予定だった副操縦士と一緒に飲酒。聞き取りに対し、社内規定が定める乗務前12時間より前の2日午後7時までに、缶ハイボール(350ミリリットル)2本を飲んだと説明しており、ANAウイングスが詳しい事実関係を調べる。
下記の記事だと、パイロットに無理をさせる航空会社が悪いとか、パイロット不足が問題だと言っているように感じる。
パイロット不足はどこも同じ条件。それでも会社によって対応は違うと思う。また、顧客はサービスなのか、価格なのか、それともコンビネーションなのか判断する必要はあると思う。後は、無茶苦茶にやっている航空会社が事故を起こすまでのチキンレースだと思う。
グローバリゼーションと規制緩和は効率と価格に関して良い影響を与えたが、競争の激化と価格競争を加熱をもたらしたと思う。
国内の航空会社でパイロットによる飲酒の不祥事が相次いでいる。10月には基準値を大幅に上回るアルコールが検出されたなどとして、ロンドン発羽田行きの便に搭乗予定だった日本航空の男性副操縦士が英警察当局に逮捕され、禁錮10月の実刑判決を言い渡された。国内でも機長の搭乗前日の深酒で、多くの便の発着が遅れる事態も起きている。一般よりも厳しい規律の下にあるはずの航空業界でいま、何が起きているのか。現役やOBのパイロットに話を聞いた。【和田浩幸/統合デジタル取材センター】
徹夜でフライト/「疲れたね」
「時差がある中で長時間勤務する国際線は特に疲れがたまりやすい。路線や運航回数の増加に伴い、最近は1人当たりの勤務がタイトになっているのが実情です」
大手航空会社の国際線で操縦かんを握る40代の男性機長は打ち明ける。今月のある日には午前11時過ぎにインドのムンバイに向け成田空港を出発。日本との時差は3時間半で、現地時間午後6時半(日本時間午後10時)ごろに着陸した。同僚と食事を済ませ、ホテルで床に就いたのは午後10時半(同翌日午前2時)ごろだった。
この日は幸い7時間ほど眠れ、疲れを取ることができた。だが、日本では子どもを保育園に送るため午前5時ごろに起床するリズムが体に定着しており、海外にいてもその時間になると、はっと目が覚めてしまうことがあるという。
さらに過酷なのは帰りの便だ。ムンバイ発成田行きは午後8時(同午後11時半)に出発し、到着は翌日午前7時過ぎだ。交代の操縦士はおらず、副操縦士との2人体制のため徹夜でコックピットに座り、8時間近いフライトでトイレ以外の休憩は取れなかった。「眠い」「疲れたね」。副操縦士との間でそう声を掛け合うこともあるという。
国際線の月間搭乗回数は以前の倍に
男性機長は日本と世界の各都市を月4~5往復する。乗務時間は最大90時間に上り、フライトの間に1~3日の休日を挟むサイクルを繰り返している。
この会社では、月に20日間出勤して10日間休むという勤務自体は以前と変わっていない。しかし8年前に同社を退職した元機長の男性によると、現役時代の長距離国際線の搭乗回数は月に2往復から2往復半程度。それ以外は体力的に負担の少ない国内線に搭乗したり、交代要員として空港で待機したりしていたという。「昔は乗務時間が月80時間を超えるようなことはなかった。不規則な勤務は国際線パイロットの宿命だが、だからこそ体調管理は重要で、勤務に余裕がないのは問題だ」
パイロット不足、男性機長「限界ぎりぎり」
羽田空港では2010年に4番目の滑走路がオープンし、長期的な航空需要の増大に対応するため24時間運用も本格化した。これに伴い、地方空港も羽田とのネットワークで柔軟なダイヤ編成を行って外国人観光客を誘致しようと、次々と運用時間を延長している。パイロットの勤務がタイトになったのはそんな事情が背景にあるとみられる。
国土交通省によると、17年の旅客輸送人数は国際線が約2214万人で09年(約1539万人)より44%、国内線は約1億185万人で同年(約8398万人)より21%増えた。国内主要航空会社のパイロット数も、11年1月時点の5522人から今年1月時点は6538人に増加したが、国交省の関係者は「不足感がある」と言う。
別の航空会社に勤める50代の男性機長は「運航回数が増えただけでなく、羽田の24時間化などで深夜や早朝の勤務も増えた。パイロット不足の影響で一人一人が限界ぎりぎりまで働いているのが現状だ」と訴える。
「昼と夜の勤務で疲労が違う」
国内の航空会社にある13の労働組合で組織する「日本乗員組合連絡会議」が16年に実施したパイロット対象のアンケートによると、回答者222人のうち98%の217人が「昼間と夜間・深夜の勤務では疲労が違う」と答えた。その理由として「勤務前に眠れず疲労を持ち越したまま乗務せざるを得ない」「乗務環境が日中と違うため緊張を強いられる」などが挙げられた。
同会議は「需要増に合わせて利用者の利便性を高めることはいいことだが、ストレスの要因は疲労以外にもさまざまな背景がある。パイロットの置かれた環境をきちんと分析し、対策を講じる必要がある」と指摘する。
ロンドンで逮捕の副操縦士「酒で解決しようとした」
国交省によると、乗務前のパイロットに飲酒の影響が残っていることが発覚したケースは13年1月から今年11月末までに計41件に上り、1件が欠航、22件に遅れが生じた。全てにおいて勤務との因果関係があるわけではないが、ロンドンで逮捕された日航副操縦士の弁護人は現地の裁判で、「仕事で家族と長期間離れる寂しさに加え、不規則な勤務時間などによって不眠症に陥り、酒を飲んで解決しようとした」などと主張した。
こうした事態を受け、国交省は11月、飲酒基準を巡る有識者検討会を設置。国内の航空会社に乗務前のアルコール呼気検査を義務付け、反応が出た場合は数値にかかわらず乗務禁止とするルールを導入する方針だ。
専門家「疲労、ストレス、睡眠を含む総合的な対策を」
元日航機長で航空評論家の小林宏之さんは「乗務前に飲酒の影響を残すのは自己管理ができていない証拠。安全を考えれば基準の導入は必要だ」と語る。
ただ、パイロットは着陸時に強い緊張を強いられ、乗務後も神経が高ぶって眠れなくなることがよくあるという。「基準に抵触しない時間と量であれば、お酒はリラックスのために有効な側面もある。睡眠不足になってしまっては次のフライトで判断力が低下しかねない」と語る。そのうえで「飲酒問題の背景には、パイロットに過酷な勤務を求めている構造的な課題がある。飲酒の管理にとどまらず、疲労やストレス、睡眠などの管理も含めた総合的な安全対策が求められる」と指摘した。
会社に勤めているから違法労働と言えるのだろう。自営業や独立して会社を立ち上げたばかりの人などは自己判断なので何時間働こうが、移動中の
信号待ちの時におにぎりやパンをかじっていても問題にはならない。
会社とは違って規則だとか、綺麗ごとを言っていると会社や事業が軌道に乗る前に終わってしまうかもしれない。
今までの働かせ方に問題があったとは思うが、日本人の人件費が上がり、経済が順調に成長していない時にこのような問題を起こしても問題は順調に解決しないと思う。時期的には遅すぎるし、状況を悪くすると思う。
それでも問題を解決しようと思うのなら現状の維持を止めて、無駄である事の継続を止めるべきである。個人的な考えなので間違っているかもしれないが飲料自販機の売り上げは過去と比べて減っているのではないのか?コンビニは増えるし、カーナビの普及でどこにお店があるのか、簡単に検索できる。
以前に比べれば飲料自販機で買おうと思う人は減ったのではないのか?
会社として消費動向が変わってもすぐに他の事業を立ち上げて利益を出すことは簡単でないし、慣れている事を繰り返す方が効率は良いと思うので
他の事業に変わる会社は少ないであろう。自販機ベンダー業界の業者の数が横ばいなのか、減っているのか知らないが、減っているのであれば
違法労働が改善に向かえば、さらに業者は減って行くであろう。業者が減れば、問題自体が減ったり、なくなったりするかもしれない。
本当は、低賃金で長時間働く業界が減り、高賃金で短時間の業界が成長するのが理想的だ。残念な事は、労働者の能力が理想的な成長に
追いつかないのと思うので、結局は能力が低い労働者はさらに厳しい仕事を探すか、無職の状態が続くと思う。
国の財政にゆとりがあれば再分配は可能であろうが、財政にゆとりがなく、無駄に簡単にメスを入れる事が出来ず、公務員の待遇や給料に切り込むことが出来ない現状では将来に希望はない。
森友事件の本質やNHK報道の舞台裏を記した『 安倍官邸vs.NHK 森友事件をスクープした私が辞めた理由 』(文藝春秋)。その著者で元NHK記者の相澤冬樹氏が今回、直撃取材を試みたのが、森友事件を巡って虚偽答弁を重ねてきた佐川宣寿理財局長(当時=61)だ。財務省のごく一部のOBとは顔を合わせているという佐川氏だが――。
【写真】書き換え前と、大幅に文言が削られた書き換え後の文書
◆ ◆ ◆
本はNHK内にある書店でも完売し、さらに追加分が平積みされているというから、NHK内でも関心が高いのだろう。かつての同僚からは「よく書いてくれた」との評価や、「もっと核心に迫るものを期待していた。さらに踏み込んでほしい」というお叱りと励ましの声が伝わってくる。
私が本で「特ダネに激怒した」と書いた小池英夫報道局長。発売日に行われた報道局の編集会議では「私の意向で報道内容が恣意的に歪められたことはない」と述べていた。だが、その言葉を額面通りに受け止める記者は少なかろう。彼らは「Kアラート」と呼ばれる“圧力”に直面してきたのだから。
事件の一方の主役、森友学園の籠池泰典前理事長もすでにこの本を読んでくれている。「森友事件は森友学園の事件ではなく、国と大阪府の事件」との指摘について「的を射ている」とした上でこう語った。
「小学校設立は、安倍(晋三)首相と昭恵夫人、それに大阪府の松井(一郎)知事のスクラムによって始まった。ところが17年2月に問題が明らかになると、私がトカゲのしっぽ切りにされた。真犯人の責任は問われていない。相澤さんにはそこを追及してほしい」
その厳しい指摘に応えることこそ、記者の務めだ。
しっぽとして切られた最大の被害者は、自ら命を絶つところに追い込まれた近畿財務局の職員だろう。仮にBさんとする。Bさんについての元同僚たちの評判は極めていい。誠実に仕事をこなす有能な役人――そのBさんが公文書改ざんという常識外れの不正行為を押しつけられたのだ。
その無念の思いをBさんはメモのような形で書き残している。完全な形では明らかになっていないが、改ざんについて「もとはすべて佐川理財局長(当時)の指示だ」とはっきり記しているという。財務省の中枢にいる人物の指示で、自分はこんな不正をやらされたのだという思いを文書に残していたのである。
その無念の思いについて、当の佐川氏はどう受け止めているのか。NHK在職中も知人を通じて取材を依頼していたが、直接話すことは結局叶わなかった。
私は佐川氏の自宅を訪ねた
12月のとある朝。私は都内の閑静な住宅地にある佐川氏の自宅を訪ねた。しばらく姿を見せるのを待ったが、ゴミ収集日なのにゴミを出す動きすらない。近所の人の話では、最近は誰もこの家には住んでいないようだ。だが、玄関の花は生き生きしているし、誰かが定期的に訪れて手入れをしているようだ。本に手紙を添えて郵便受けの中に入れた。佐川氏が受け取り読んでくれることを願って。
翌朝、私は再び佐川氏の自宅を訪ねた。昨日は玄関前に止まっていた車が、今朝はない。誰かが来た証拠だ。再び手紙を書いて、郵便受けに投函した。
考えてみれば、佐川氏が関与したのは国会答弁と公文書改ざんだ。もちろんそれらは許されることではないが、肝心の国有地売却には関与していない。首相答弁との整合性を取ろうとした結果、役人人生を棒に振ってしまったことを思えば、彼もしっぽとして切られた一人なのかもしれない。
森友事件は多くの人の人生を変えた。私の人生も変えた。亡くなった近畿財務局職員の無念の思いを晴らすまで、真相追及の手を緩めるわけにはいかない。
相澤 冬樹/週刊文春 2019年1月3・10日号
下記の記事、推測の形で書かれているが、実際に、どこまで証拠や証人をおさえているのだろうか?
日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告(64)を巡る特別背任事件で、ゴーン被告がサウジアラビアの知人側に提供した「機密費」は、ゴーン被告の指示で2008年12月頃に創設されたことが関係者の話でわかった。機密費がサウジ以外の中東各国の関係先に流れていたことも判明。東京地検特捜部は、私的損失で多額の評価損を抱えたゴーン被告が、その穴埋めなどに利用するため、自身の判断で使える資金を用意させたとみている。
関係者によると、ゴーン被告は日産の役員報酬を日本円からドル建てにするため、06年頃から新生銀行(東京)との間でスワップ取引を行っていたが、08年秋のリーマン・ショックに伴う円高で約18億5000万円の評価損が発生した。同行から追加担保を求められたゴーン被告は、同年10月に評価損を含む全ての権利を自分の資産管理会社から日産に付け替え、追加担保を回避したとされる。
外国人労働者や外国人留学生の提出した書類や資料が本物であるのか、事実であるのか確認がこんな状態で、解決方法を見つけられないまま、 人材不足とか、他国に外国人労働者が逃げると言う理由だけで中途半端なシステムのまま、多くの外国人労働者を受け入れるようになる。
外国人はめっぽう弱い日本。情けない国である。
下記の記事の内容が事実であれば日産自動車の幹部の裏切りがなければ、多くの日産社員や下請けは、ゴーン容疑者のために馬鹿をこれからも 見続けていたのであろう。
まあ、前会長カルロス・ゴーン容疑者に好き勝手にさせる切っ掛けを作った日産の経営者や幹部にも責任がある。ルノーに下るきっかけを作った 事が原因のスタート。
日産自動車の資金が、海外のペーパーカンパニーを通じ、前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)や、同容疑者の親族側に流出していた疑いがあることが31日、関係者への取材で分かった。
流出した資金は億単位に上るという。疑惑は日産側の調査で判明。東京地検特捜部も把握しており、日産から提供を受けた資料などを分析し、不明朗な資金の流れの解明を進めているもようだ。
関係者によると、日産から億単位の資金が送金されたのは、海外にある複数の会社で、いずれも経営実体のないペーパーカンパニーだったとみられている。同容疑者の生まれ故郷ブラジルや、少年期を過ごしたレバノンなどに設立されていた。
ペーパーカンパニーに流れた億単位の資金は本来、日産が支出する必要がなく、最終的にゴーン容疑者本人のほか、同容疑者の親族や親しい知人に渡っていた疑いがあるという。
特捜部がゴーン容疑者を再逮捕した特別背任事件では、サウジアラビア人の知人側に渡った日産資金1470万ドル(現在のレートで約16億円)は、実態が伴わない「販売促進費」などの名目で送金されたとみられている。
新たに浮上した日産資金の流出疑惑も、実態のない名目で送金されていた可能性があるが、送金先のペーパーカンパニーがあるレバノンなどでは、十分な捜査協力が得られる見込みは低い。このため、特捜部は慎重に裏付け捜査を進めているもようだ。
ゴーン容疑者の日産「私物化」疑惑をめぐっては、これまで、オランダの子会社「ジーア」を通じた投資資金での海外不動産購入や、同容疑者の姉と実態のないアドバイザリー業務契約を結び、年約10万ドル(約1100万円)の日産経費が不正支出された疑いが指摘されている。
東京地裁は31日、ゴーン容疑者の勾留期限を1月11日まで延長することを認める決定をした。特捜部は日産に私的損失を付け替え、サウジアラビア人の知人側に約16億円を流出させたなどとされる特別背任容疑の捜査を急ぐ。
急成長する会社は、扱う物やサービスが良い、やり方が斬新である、これまでの常識を無視して無駄を省く、総合的な視点で物事を考える、表の顔とは違って汚いやり方をする、又は、これらのコンビネーションだと思う。
我慢して現場や現状を理解する事は重要だと思うが、自分の判断で引き時である、他の選択肢や妥協できる事を探す、根拠のない感であるが
将来がないなど、辞めるべきだと思えば辞めたら良いと思う。辞める事が間違っていれば、その事から学んで次に生かせればそれで良いと思う。
人との付き合い方が上手い、詐欺的な能力がある、相手を騙しても心が痛まない、又は、これらのコンビネーションがあれば営業として結果を
出せる可能性は高いと個人的には思う。このような事が出来ないと思う人は、他の会社や他の業種を給料が安くても妥協して選ぶ方が良いと思う。
個人的な意見であるが保険代理店だけに問題があるのではなく、良い会社や良い業種は存在すると思うが、悪い会社や一般的に悪い業種はあると思う。
入社するまで、周りが見えてくるまで、問題に気付かない事はあると思う。悪い会社ほど自分達に問題があるのを知っているから、表向きは
良いイメージを与えようとする。騙す相手が悪いのか、気付かない方も悪いのか、個々のケースを判断するのはお互いの言い分が違ったり、正反対
だったりするので難しいが、騙されないように個々が努力するしかないと思う。
わたしが保険営業を辞めた理由 10/19/15(マネー研究所|NIKKEI STYLE)
労働者に多額の経費を負担させる保険代理店の働かせ方を巡り、元外交員が相次ぎ会社側を訴えていることが判明した。広島地裁に労働審判を申し立てた元外交員の60代男性は「会社が社員から金を吸い上げる搾取は許せない」と訴える。
男性や弁護士によると、男性は2014年夏から3年3カ月、広島市の保険代理店に勤務。働き始めてから数カ月が過ぎると、入社時に約束されていた月12万円の「基本給」がなくなり、事実上の完全歩合給になった。保険契約が成立すれば手数料が給料として得られるシステムだったが、給料からはさまざまな名目で多額の経費が差し引かれた。
最も負担が大きかったのは、会社側から一方的に配信される「契約の見込みがある顧客」の情報料で月数十万円、総額で約600万円に上った。ただ見込み客は「外交員と面談するだけで商品券がもらえる」といったインターネット広告などで集められており、実際には数時間かけて会いに行っても契約に結びつかないことも多かった。自分で見込み客を選ぶこともできなかった。
他にも「事務所維持管理費」名目で年30万~60万円、「PCリース代・システム利用料」名目で月5000~1万円などが天引きされた。保険契約が成立すれば得られる手数料と経費との収支が赤字になった月には会社から赤字の穴埋めを求められ、貯金などを取り崩して払い続けた。
男性は退職後の今年6月、支払われなかった基本給や天引きされた経費など約1170万円を会社に請求する労働審判を広島地裁に申し立て、地裁からは10月、会社が約120万円の解決金を支払う内容の審判を受けた。
請求額の一部しか認められず、弁護士からは「本格的に訴訟で争った方がいい」と言われた。だが、がんの手術を受けたばかりで「数年かかる訴訟に体が耐えられない」と思い、やむなく審判を受け入れた。各地で提訴した原告には「泣き寝入りせず、納得できるまで闘ってほしい」とエールを送る。
全国被害者弁護団の結成前でも長崎訴訟の中川拓弁護士が通常の労働相談ホットライン(0120・41・6105)で相談を受け付ける。【樋口岳大】
「乗り合い」代理店が急成長
被告3社を含む乗り合い代理店は、店頭や訪問販売などで複数の保険会社の保険を販売し、積極的にテレビでCMを流すなどして近年急成長した業態だ。大手生保系から独立系まで大小の代理店が乱立し競争も激しい。
3社のうち最大の1社は、東京都に本社を置く、業界でも比較的大規模な代理店で全国に支店がある。東京商工リサーチによると、従業員数約1200人、年間売上高約85億円。1社はほぼ全国に支店網がある千葉県の代理店で従業員約300人、残る1社は東京都の小規模代理店。
実態は個人事業主
元外交員からの訴えが相次ぐ背景には、金融庁が2014年に「保険会社向けの総合的な監督指針」を改正し、保険代理店と外交員が雇用関係を結ぶよう、ルールを厳格化したことがある。
改正前は外交員を個人事業主と位置付け、業務委託契約を結ぶケースが業界の慣行として広がっていた。この場合、代理店は外交員の社会保険料負担など雇用主の責任を負わずに済むが、管理が行き届かず不適切な販売が行われる恐れがあった。このため、金融庁は保険業法で禁止される「再委託」に当たると指針に明記し、代理店側に外交員を正社員や契約社員など何らかの形で雇用するよう求めた。
東京都内に本社を置くある大規模代理店は指針改正後、委託契約だった外交員を正社員に切り替えた。外交員の数は約1600人から約900人に減ったが、65歳以上の嘱託を除き全て正社員化した。歩合制だが社会保険料はもちろん、電話代やコピー代などの経費も会社が負担しているという。
だが、原告らは被告の代理店では「事務所維持管理費」やパソコンのリース料まで徴収されていたと主張しており、東京の代理店幹部は「他の代理店ではいろいろ問題が起きていると聞く。業界全体としてはまだ過渡期にある」と話す。外交員を雇用しながら実態は個人事業主のような働かせ方を続ける代理店が一部に残っていることが問題の根幹にある。【畠山哲郎】
「脇田滋・龍谷大名誉教授(労働法)の話 最低賃金を下回る賃金や多額の天引きといった、労働法を逸脱する働かせ方が保険代理店業界に広がっている可能性があり、厚生労働省はきちんと調査して指導すべきだ。無理な働かせ方が不正な保険契約につながる恐れもあり、金融庁も監督する必要がある。」
厚生労働省の体質に対しては疑問があるし、以前、金融庁にクレームの電話をした時は、担当者がかなり上から目線の態度で改善する検討は一切しないと言い切った。まあ、直接的ではないと思うがこれだからスルガ銀行の問題が起きたと思う。まあ、適当な言い訳や説明をして幕引きすれば良いと金融庁が思っていれば今後もいろいろな問題は改善されないであろう。
保険代理店に雇用された元外交員(保険募集人)が、給料から多額の経費が天引きされるなどして不当に低賃金で働かされたと主張し、会社側を訴えるケースが相次いでいる。毎日新聞の取材では、全国の少なくとも6地裁・支部に11人が提訴し、1人が労働審判を申し立てた。12人は3社に対し未払い賃金など計約6300万円の支払いを求め、他に複数の提訴予定がある。労働問題に取り組む弁護士らは「業界の一部で搾取的な働かせ方が横行している」と警鐘を鳴らし、近く「全国被害者弁護団」を結成して救済に乗り出す。
【元外交員「搾取許せぬ」顧客情報600万円自腹も】
訴訟や労働審判は、札幌▽東京▽大阪▽広島▽長崎――の各地裁と福岡地裁小倉支部に起こされた。12人は契約社員などとして9カ月から3年3カ月働き、約70万~2000万円を請求。他に札幌、東京、広島の各地裁などで新たな提訴予定があり、同種の訴えは今後も増えそうだ。
訴状などによると、原告らは毎月十数万円の「基本給」があるとの条件で入社したが、実際は一部しか支払われなかった。また、契約を検討している顧客を会社側が紹介した際の情報料として、契約が取れたかどうかに関係なく1件当たり数万円、1カ月では数十万円を徴収されるなど、多額の経費負担を強いられた。
原告らの月給は、契約成立時に保険会社から代理店に支払われる手数料などから経費を差し引く形で計算される。月給がほとんどない月があるだけでなく、経費が手数料収入を上回った場合は個人で赤字分を補填(ほてん)しなければならなかった。社会保険料の会社負担分を徴収されていた人もいた。
長崎訴訟の原告代理人で、全国弁護団にも参加予定の中川拓弁護士は「会社として負担すべき経費や赤字のリスクを労働者に押し付けている」と批判する。
被告3社は、いずれも複数の生保などを販売する乗り合い代理店で、うち1社は1000人規模の外交員を抱えて全国展開する。取材に3社は「コメントは差し控えたい」などと回答した。業界を所管する金融庁は「労働問題なので我々は判断できない。しかし顧客との保険契約に問題が生じれば対応する」とし、厚生労働省は「労働基準監督署に相談があれば適切に対応したい」としている。【樋口岳大、畠山哲郎、杉本修作】
◇国は指導・監督を
脇田滋・龍谷大名誉教授(労働法)の話 最低賃金を下回る賃金や多額の天引きといった、労働法を逸脱する働かせ方が保険代理店業界に広がっている可能性があり、厚生労働省はきちんと調査して指導すべきだ。無理な働かせ方が不正な保険契約につながる恐れもあり、金融庁も監督する必要がある。
保険コンサルタント 後田亨
「お客様の一生涯のパートナー」「あんしんのアフターフォロー」。保険会社がよく使う言葉です。これらの言葉から、保険加入の相談・コンサルティング、保険の見直し、そして保険金支払いの手続きまで、長い期間にわたってすべて同じ担当者が、責任を持ってアドバイスしてくれるのではないかという印象を持つ人も多いのではないでしょうか。
しかし、かつて大手生命保険会社で営業の仕事をしていた私に言わせると、そういうことほとんどないと言っていいでしょう。私がなぜ保険営業の仕事を辞めたのか、一般化できる部分もあると思いますので、個人史を振り返ってみたいと思います。
「保険営業の仕事って、すごく稼ぐ人もいるらしいですね。なぜ辞めたんですか?」。あるお客様に聞かれました。私は「稼げない人のほうが断然多いですよ。自分の場合は、ほかにも理由がありましたけど」と回答しました。
歩合制の営業担当者や代理店の収入については、スポーツ選手のように高額所得者はごく一部だけ、という認識が広がったほうがいいと思います。
例えば、2010年度から14年度までの5年間に大手生命保険会社4社は合計で15万人を優に超える営業職員を採用していますが、在籍者数は逆に1万人近く減っています。
退社の理由は、収入面の問題だけに限らないはずとはいえ、新規契約を継続的に獲得することが容易でないこと、外回りの仕事にかかる経費(自己負担です)が大きいことなどを理由に見切りをつける人も多いのだと推察します。
私が大手生保を退社したのは、他社にもっと良い商品があったからです。入院保障を一生涯持つタイプの商品を試算したところ、外資系保険会社の商品に比べて100万円くらい保険料が高くなることがわかり、「これはまずいだろう」と考えるようになったのです。
保険会社の破綻が続いていた2000年前後は、大手の財務体力を重視していましたが、「自分だったら外資系の保険に入るのでは?」と自問すると、答えに詰まってしまったのです。顧客本位で退社を決めたというより、「他人から突っ込まれるのは避けたい」と決断したわけです。
複数の保険会社の商品を扱う代理店に勤務してからは、「自分でも入りたい保険」をお客様に薦めることができるようになりました。
しかし、新たな問題が生じました。そもそも加入に値する保険は少ないことに気づいたのです。保険の利用が向いているのは、現役世代の急死などまれに起こりうる事態に限られていて、老後の入院など「誰にでも起こりうる事態」の備えには向かないとわかってしまうと、明快な論理だけに後戻りできなくなりました。
代理店在籍中に出版の機会に恵まれ、その後も著述関連の仕事依頼が途切れなかったため、代理店を離れ今日に至っています。
「より望ましい情報提供のあり方を模索してきた」とまとめるとウソになります。営業の仕事に飽きていた面も強かったからです。
実際、対面販売の場数を踏むと、お客様の悩みや質問などにはパターンがあることがわかり、解決策の提案はさほど難しくなくなります。また、本当に顧客本位で考えた提案をすることより、相手の予見や期待を大きく裏切らない対応に徹するほうが成約につながりやすい面もあるのです。
最近、こんな想像をします。死亡・医療・介護・貯蓄などの目的別に多様な保険を薦めていた過去の私と、必要最小限の保険活用を説く最近の私が2人いて、両方から交互に話を聞くことになったお客さんがいるとしたら、どちらの主張を受け入れられるだろうかということです。
親しい人に不幸が起こったばかりの人は前者の私を、大量に供給される保険会社のテレビCMなどに疑問を持っている人は今の私を好ましく思うかもしれません。
以上、個人史を振り返りましたが、一般論としては、契約時の担当者は退社する可能性が高いこと、保険会社により商品の優劣が存在することを知っていただきたいと思います。
さらに、保険の相談相手と接する際は、相手と自分には商品知識に大きな差があることと、相手の真意を見抜くのは難しいということを前提にしてください。そして、「そもそも、保険会社の営業担当者に求める答えはすでに自分の中で決まっているのではないだろうか」と自分自身を疑ってみることが大切だと思います。
自民党前衆院議員の赤枝恒雄氏で検索してみるとそんなに悪い事をしているように思えない。まあ、情報が偏っているのかわからないが、 不正入試問題で関与したのなら事実を認め謝罪して、知っている事を全て話せば良いのではないのか?
東京医科大(東京)の不正入試問題で、医学部看護学科の一般入試で特定の受験生を合格させるよう前理事長に依頼した国会議員について、同大職員が、同大出身の産婦人科医で自民党前衆院議員の赤枝恒雄氏(74)だと説明していることが大学関係者の話でわかった。第三者委員会(委員長・那須弘平弁護士)も赤枝氏だったと把握しているが、赤枝氏は取材に対し、関与を否定している。
同大が29日に公表した最終報告書によると、臼井正彦前理事長(77)は2013年の看護学科の一般入試で、特定の受験生の受験番号を当時の看護学科設立準備室の副室長に伝え、合否判定で「どうにかしてもらいたい」と指示。その際、国会議員(当時)から依頼されたと告げたという。
システム的に電源が切る事が容易に出来たのだろうか、また、清掃中に電源が入らないような装置やシステムがあったのだろうか?
システムに問題があったのか、操作に問題があったのか、情報が少ないので判断できない。
今後、外国人労働者が増えればこのような事故は増えるかもしれない。コミュニケーションが取れないと指示が上手く理解されないし、
操作手順やマニュアルが日本語で書いてあれば理解できる可能性は低い。日本語で書いてあっても経験や知識がないと理解できない日本人は
存在する。
まあ、死んでも当事者の問題なので関係者は自分の身は自分で守る事を考えるべきだと思う。
三重県鈴鹿市の工場で30日、清掃作業をしていた男性が、スクリューコンベヤに巻き込まれ死亡する事故がありました。
警察によりますと、30日午後3時15分ごろ、三重県鈴鹿市にある総合コーンインダストリー「敷島スターチ」の鈴鹿工場で、コーンスターチを貯蔵するタンクを清掃していた鈴鹿市に住むメンテナンス会社社員・高村将夫さん(29)が、タンク底に設置されていたスクリューコンベヤに巻き込まれ、現場で死亡が確認されました。
当時、清掃作業は高村さんを含む3人で行われていたということです。警察は、清掃作業中にスクリューコンベヤが動いた経緯など、事故の原因を詳しく調べています。
東京医大の裏口入学に絡み、文科省佐野太前局長(59歳)の受託収賄罪事件では
本人の意図とは全く関係ないが、医学部受験のシステムに関して改革や膿が表に出るきっかけを作った意味では佐野太前局長の貢献は素晴らしいと思う。
佐野太前局長の逮捕なしではここまで問題が深く切り込まれる事はなかったであろう。彼の事件で人生が悪い方向に変わった人間達がいるし、良い方向に変わった人間がいる。
一般的に、何かが大きく変わる時、笑うものと泣くもの、上昇する人間と下降する人間が割合はそれぞれのケースで違うがあると思う。
今回の事件は多くの人達が良い方向へ向かったと思うだけで、嫌な思いをしている人達は存在する。不正検査やデータ改ざんも同じ。
やっている関係者にとっては良い事である。不正検査やデータ改ざんが発覚すれば、関与した人間や影響を受けた人間達には不幸な事になる。
それ以上でもないし、それ以下でもない。ただ、個人的には悪い事をした人間達が裁かれる、又は、処分される事は良い事に思える。
東京医科大が29日に公表した不正入試をめぐる第三者委員会の最終報告では、同大の推薦入試で、小論文の問題が特定の受験生に漏洩(ろうえい)していた疑いがあることも明らかになった。平成25~28年度の入試で合格ラインに達していた計127人が不合格となっていたことも判明。すでに判明している今年と昨年の分も含め、不正により不合格となった受験生は計228人に上ることとなった。
【図解】文科省汚職事件で行われた「裏口入学」
最終報告によると、第三者委が東京医科大の平成25~30年度入試を調査していたところ、推薦入試を受けた受験生が試験前、通っていた予備校の講師や友人に「試験問題が手に入った」などと話していたことが分かり、その受験生の成績を確認したところ、小論文で1位の成績だったという。
東京医科大の担当者らは第三者委のヒアリングに対し、漏洩の事実を否定したが、第三者委では「問題漏洩が行われたのではないかとの合理的な疑いの余地を残す」と指摘。ただし、確認するには長時間を要するため、最終報告で疑いの事実を示すだけにとどめたとしている。
このほか報告書では、25~28年度入試で、女子や浪人生を不利にする得点調整などが行われ、一般入試とセンター利用入試で109人、推薦入試で18人が当時の合格ラインを上回りながら不合格になったことも明らかにした。今年と昨年の入試でも計101人が不正で不合格となっており、東京医科大ではこれらの受験生への補償について、個別の事情を聴いた上で判断するという。
医学部入試の不正問題をめぐり、東京医科大は29日、国会議員を含む複数の政治家から受験生に関する依頼があったとみられると指摘する第三者委員会の最終報告書を公表した。特定の受験者について、「寄付は3千万円は用意する」などと配慮を求める手紙などが、前理事長や前学長が保管していた資料から見つかったことも明らかにした。
報告書によると、文部科学省の汚職事件に絡み辞任した臼井正彦前理事長と鈴木衛(まもる)前学長=いずれも贈賄罪で在宅起訴=がそれぞれ保管していた資料には、(1)受験生の名前と受験番号を伝えた上で配慮を求める内容の手紙など(2)2人がそれぞれ受験生の名前と受験番号などを列記して作成したメモ-があった。
こうした資料の中には、寄付金を求めていたことをうかがわせる資料も含まれていた。臼井氏に対し、特定の受験生について配慮を求める内容の書面で、「もし入学を許されましたら育てて頂く大学のためには寄付は3千万円は用意するつもりでおります」などと記載されていた。
また、臼井氏が作成したメモには、受験生の名前の横に「1000」「2000」「2500」などと記載されたものもあったという。第三者委は、特定の受験生を有利に扱う調整について「東京医大への寄付金との間には何らかの関連性があった可能性がある」と指摘した。
不正に関わった関係者の中には、国会議員を介して依頼したケースもあり、国会議員に対し、受験生の名前と受験番号などを記載したファクスを送っていた。ほかにも政治家と思われる記載が関係資料にみられ、第三者委は「政治家から受験生に関する依頼がなされることがあった」と指摘した。
テレビで言っていたが法的に補償する義務はないらしいので、「アパマンショップリーシング北海道」から別の名前で仕事をするつもりならいつでも逃げれると思う。「アパマンショップ」に対するイメージの悪化や低い評価を受け入れる覚悟が出来たらいつでも逃げれると思う。
「どこかではしごを外されるのでは」
札幌市豊平区平岸の建物で16日夜に起きた爆発と火災で、被害を受けた住宅の住人や店舗の経営者らが、補償の先行きが見通せない状況に不安を募らせている。爆発元とみられる不動産仲介業「アパマンショップ平岸駅前店」の運営会社は「法的範囲内で全額を補償する」との姿勢だが、対象や時期は不明確なまま。周辺の被害は広範囲に及び、専門家は「補償の手続きは長期化する可能性がある。運営会社は早期に行程を示すべきだ」と指摘する。
【動画】札幌市豊平区で爆発 建物倒壊
「何がいつごろ補償されるか分からず、心が晴れない」。現場から約40メートルの飲食店を経営する女性は肩を落とす。
店は正面の大型窓ガラスが割れ、食器や外壁も壊れた。実費でガラスの取り換えや清掃をし、25日に営業を再開したが、客足は遠のいたままだ。平岸駅前店を運営する「アパマンショップリーシング北海道」(札幌)の担当者から休業による損失も補償するとの説明を受けたが「具体性がなく、心配だ」と漏らす。
現場近くのマンションに住む60代男性は、割れた窓ガラスをプラスチック板でふさいだままの状態で年末を迎える。同社が22日に開いた説明会に出席したが、「どこかではしごを外されるのでは」と感じ、修繕に踏み切れない。
早くても数か月先か
札幌市消防局によると、28日までに現場から半径約250メートルのマンションや店舗など39棟と、車両25台で被害が判明。爆風や飛散したがれきで窓ガラスが割れた被害が多く、外壁の照明など設備の破損もあった。市消防局は引き続き被害を調査中で、今後さらに増える可能性もあるという。
同社は被害の大きいマンション2棟の住人を対象に説明会を開いたほか、戸別訪問などで補償する方針を示しているが、時期などの説明はない。北海道新聞の28日の取材にも「事情が一人一人異なり、個別に交渉を進める」と答えるにとどめた。
損害賠償を巡る問題に詳しい高森健弁護士(札幌)は建物や設備の修理費、自宅に住めない期間の宿泊費など「爆発と火災が原因と認められる財産上の損害や出費は補償の対象」と説明。一方で「慰謝料などを含め、補償額は当事者間の交渉か裁判で決まる。実際に受けられるのは早くても数カ月先だろう」と話す。
日本損害保険協会北海道支部は「アパマンショップ側の対応を待てず自ら住宅の修繕などをする場合、後日請求できるよう契約書や記録を残してほしい」。高森弁護士は「最低限の金額の仮払いや、早期に賠償の時期を示すなど、アパマン側には被害者の不安に応える対応が必要だ」と話す。(樋口雄大、佐藤圭史、角田悠馬)
下記の記事が事実であれば本当に情けない話である。
泣く子も黙る天下のNHK。その中核子会社に赤字付け替え疑惑が浮上した。しかし、当のNHKはこの問題を放置。「親」としての責任を投げ捨てたかのようである。そんなデタラメな態度は、子どもたちだって許しはしまい。そう……。チコちゃんに叱られる!
***
新聞69・6点、民放テレビ62・9点、ラジオ57・2点。
公益財団法人新聞通信調査会の調査によると、18歳以上の男女5千人を対象に各メディアの信頼度を100点満点で尋ねたところ、このような結果になったという。そして――。
70・8点。
信頼度トップに輝いたのはNHKだった。皆様のNHK、天下のNHK、信頼のNHK。
しかし、信頼とは目に見えないものゆえに、強固であると同時に脆(もろ)い。それは、コストカッターとして辣腕を振るってきたカリスマが、私腹を肥やしていた疑いで一夜にして強欲男に転落した、どこぞの経営者の一件が雄弁に物語っている。つまり信頼とは、「ごまかし」が明るみに出た時点で崩壊するものと言えよう……。
「『SSS事業』(後述)が、直接的にはNHKの子会社であるNHKグローバルメディアサービス(以下GMS)の仕事であることはもちろん承知していましたが、私はNHKさん本体が主体の仕事だと認識していました。NHKという冠が付いた企業の仕事であれば、子会社のものだろうが何だろうが、普通は『NHKの仕事』だと思いますよね」
こう戸惑いつつ証言するのは、ヤクルトで活躍した元プロ野球選手でスポーツライターの青島健太氏だ。
「つまりNHKさんのためだからということで、編集長の私を含め、50名以上の寄稿者がSSS事業に協力したと思うのですが、それがある日、陽の目を見ないまま突然中止になった。すっきりした説明を聞かせていただかないと、寄稿してくださった方々に申し訳が立ちません」
こうして「不信感」を生じさせ、突如、終了したSSSなる事業だが、
「さらに問題なのは、このSSSの経費を他の事業、例えば『みずほオリンピックプロジェクト』なるものの経費に付け替えた粉飾決算が疑われることです」
こう告発するのは、SSS事業を委託された「下請け」で、青島氏を編集長に起用した制作会社の社長だ。メガバンクの名前も登場する衝撃の告発。その詳細に入る前に、まずはSSSについての説明が必要であろう。
SSS事業
制作会社の社長が振り返る。
「GMSから、2020年の東京五輪に向けて何か良い企画はないかとの相談があり、私はネット版のスポーツ百科事典とでも言うべきものを提案しました。これが後に『Sports Social Studies(SSS)』と名付けられるわけですが、障害者スポーツも含め、ありとあらゆる競技に関するルールや技などを、その道の専門家に解説してもらうというウェブサイトです。この企画が採用され、14年の9月頃から正式にSSSプロジェクトは始動しました」
ここで、青島氏が「NHKの仕事」との印象を受けたSSS事業を、制作会社に下請けに回したGMSについて触れておくと、〈日本放送協会の委託等により、ニュース、スポーツ、および情報にかかわる番組等の開発、企画、制作、購入、頒布〉(同社ホームページより)などを事業とするNHKの子会社で、現社長はNHK本体の政治部長や報道局テレビニュース部長、専務理事などを歴任した後(のち)、15年6月に現職に就任している。彼以外にも、
「取締役には『元NHK』とNHKからの出向者が居並んでいて、400人弱の社員も、その少なからぬ割合をNHKの出向者が占めている。NHKにとっての重要な『天下り先』であり、子会社の中でNHKからの出資額が3番目に多い中核子会社と言えます」(NHK職員)
信用調査会社の関係者曰く、
「決算もNHK本体と連結ですから、NHKと一心同体の会社と言っていいでしょう」
そのGMSによって動き出したSSS事業だったが、
「どうやらGMSの内部では不協和音が生じていたようです。具体的には、SSSは同社の企画事業部門が主導したものの、NHK本体との結び付きがとりわけ強いスポーツ部門がいい顔をしなかったらしく、次第にGMSの担当者から『SSS名目では経費が払いにくい』などと言われるようになり、別事業名目で経費を請求してほしい旨を指示された。実際、それに従って、別事業を『急ごしらえ』したりもしました。私どもは下請けですから、どんな形であれ、もらうものをもらわないと話になりません。従わざるを得ないわけです」(制作会社社長)
約1300万円の「実態なき報酬」
下請けの悲哀を味わわされたこの社長氏が「例えば」として続ける。
「15年10月頃のことでした。GMSの担当者から、『みずほ銀行は20年の東京五輪のスポンサーだから、彼らに事業を提案するためのプレゼン資料を作ってほしい』と依頼され、やはり下請けとして私どもが資料を作成しました」
そのプレゼン資料を見てみると、
〈企画A案 障がい者スポーツセミナー支援展開「パラリンピアン・サポートキャラバン」〉
〈企画B案 5年間密着ドキュメンタリームービー「オリンピックが育む子供たちの記録」〉
などと記されている。お世辞にも「エッジ」が利いた企画とは到底思えない上に、そもそも企画書は10枚程度のもので、誰がどう見ても練られたプレゼン資料とは言い難い。それもそのはずで、
「一夜漬けとまでは言いませんが、徹底的にデータを調べあげた上で作ったわけでもなく、アイディアの羅列といったようなものでしたからね。SSSが正式に公開された暁に、みずほに広告主になってもらえたら好都合。またSSSにみずほが付いているとの印象を与えられれば、GMSの社内でもSSSへの理解が深まるので、平たく言えば、あくまでみずほとの関係を強化するための『入口』としてのプレゼン資料だと聞かされて作ったものです。SSSが上手くいくならばと、サービスのような気持ちでやった仕事でした。プレゼン内容はSSSとは関係ありません。これを持って、1度だけみずほとの打ち合わせに参加しましたが、この程度の仕事だったにも拘(かかわ)らず、GMSから計864万円が振り込まれました。自分で作っておいて何ですが、みずほに持っていったプレゼン資料は、どう吹っかけても50万円がいいところです」(同)
差し引き800万円超が「実態なき報酬」というわけだが、
「GMSの担当者から、『この支払いにはSSSの経費も含まれていますから』との説明を受け、納得しました。さらに追加で翌16年、『何か形にしないとSSSの経費が払えないから』と、みずほオリンピックプロジェクト用の新たなプレゼン資料を作るよう言われ、また作成しました。これも50万円もらえれば儲けものというものでしたが、432万円もGMSから振り込まれてきました」(同)
とどのつまりこういうことだ。GMS内で「問題視」され始めていたSSS事業の経費を、その名目のままでは下請けの制作会社に払うのは難しい。そこで、みずほオリンピックプロジェクト名目に付け替え、実質最高でも計100万円の仕事に対して、864万プラス432万円、計1296万円も制作会社側に支払った――。そんな疑惑を抱えながら、結局、SSS事業は16年12月に、採算が取れないとして頓挫した。
「GMS内部の人から、SSSの赤字は約1億円に達したと聞いています。GMSはこの赤字を糊塗するために、他の事業名目に付け替え、紛れ込ませたんだと思います。GMSと話しても埒が明かないと考え、今年の10月末、一連の事態をNHK本体に文書で問い合わせましたが、今に至るもNHK本体からの連絡はありません」(同)
(2)へつづく
NHKの子会社、NHKグローバルメディアサービス(以下GMS)に噴出した赤字付け替え疑惑。2014年にスタートするも2年後に頓挫した東京五輪向け事業「Sports Social Studies(SSS)」をめぐるもので、その経費処理にあたり、本来の事業名目ではなく「みずほオリンピックプロジェクト」なる別の名目に付け替えた可能性が取り沙汰されるのだ。
SSS事業を委託された「下請け」制作会社社長は、“GMSの担当者から、SSSとは関係のない「みずほ」のプレゼン資料を作るよう依頼された”“実質計100万円のその仕事に対し、計1296万円が支払われた”“支払いにあたっては、GMSの担当者から「SSSの経費も含まれている」と説明された”と証言する(前回参照)。
「GMS内部の人から、SSSの赤字は約1億円に達したと聞いています。GMSはこの赤字を糊塗するために、他の事業名目に付け替え、紛れ込ませたんだと思います」(制作会社社長)
NHK本体に問い合わせるも、連絡はないという。
***
公認会計士で日大大学院准教授の丸森一寛氏はこう指摘する。
「SSS事業は全く利益を上げることなく頓挫したのですから、本来、通常の損失ではなく特別な事情で発生した『特別損失』として決算書に計上すべきものと言えます。しかし、特別損失という項目は決算書の中で非常に目立ち、株主などからきちんとした説明が求められることになるケースが多い。社内の派閥争いなど、外部に説明しにくい事情で事業計画が頓挫したために、他の事業に付け替え、特別損失になることを避けた可能性が考えられます」
さらには、
「制作会社に支払われた約1300万円は経費、すなわち損金として計上されるべきものです。しかし、その実態がどんなに多く見積もっても100万円程度の仕事だったのであれば、差し引き約1200万円は損金ではなく制作会社への寄附金ということになる。本来は寄附金であるものを損金計上していた場合、所得の過少申告、粉飾決算にあたります」(同)
なお16年度および17年度のGMSの決算書を見ても、特別損失は計上されていない……。
さて、実際にタックルをした学生は、日大指導者から悪質なタックルをするように指示されたと告白しています。一方で、指導者たちは自分たちの責任ではあると言いながらも、それは意気込みの話であって、悪質なタックルをしろという意味ではないと主張しています。
GMS、NHKの回答は
さて、GMSはどう答えるか。週刊新潮が、みずほオリンピックプロジェクトなるものにおける当該制作会社による「急ごしらえプレゼン資料」以外の成果物があるのか、つまり制作会社が1296万円相当の仕事をした根拠を示してほしいと質問すると、
〈SSSに伴う経費の処理は当社において適正に終了しています。(中略)当社が、SSSの赤字額を少なく見せるためにSSSの経費を他の業務の経費に付け替えたり、SSSに係る見積書を改ざんする必要性は皆無であり、かかる費用の付け替えや見積書の改ざんを行った事実は一切認識していません〉
こう回答。1296万円相当の成果物を具体的に一切示すことなく、適正に経理処理したのだから付け替え等はない、要は「正しいのだから正しいのだ」という、説明にならない説明に終始したのだった。
元NHK局員でメディアアナリストの鈴木祐司氏が解説する。
「海老沢勝二元会長も子会社のNHKエンタープライズからの返り咲き組でしたが、子会社や関連会社で頑張ると本体の要職に復帰できる目がある。ゆえに、NHKでは子会社の幹部が実績を残そうとして暴走する可能性が否定できません」
また、GMSと連結決算であり、子会社の指導監督責任を負うNHK本体は、
〈グローバルメディアサービスが責任をもって対応すると聞いています〉(広報局)
と、まるで他人事。
放送ジャーナリストの小田桐誠氏が斬る。
「20年10月からの受信料値下げをようやく受け入れましたが、NHKの受信料収入は増えていますし、ネットでの同時配信計画など肥大化を続けていて、民業圧迫との声が上がっています。そうした環境下にあるからこそ、NHKには公共放送として一層襟を正した姿勢と透明性が求められる。もちろん、NHKは連結子会社の監督責任を負っているわけですから、厳正に調査し対処すべきです」
GMSによるSSS疑惑。問われるNHKの信頼。こんな「親子」のために受信料を払っているのかと思うと……。受信料の負担義務を誰かに「付け替え」したくなる。
「週刊新潮」2018年12月20日号 掲載
新潮社
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』で探した塩路一郎の内容を見ると、地獄があるかは疑問だが、地獄が存在すれば
地獄で苦しむべき人間に思える。しかし、塩路一郎が権力を持つようにした日産にも責任があると思える。
カルロス・ゴーン氏の逮捕で、日産の歴史や塩路一郎と呼ばれる人物を知ったが、この世の中、知らないだけ、又は、注目を受けないだけで
いろいろな問題が存在する事を教えられた気がする。最近の企業の不祥事やデータ改ざんは過去から受け継がれてきた負の遺産が表に
出てきた結果であると推測出来る。
これが多くの日本人が知らない日本の真実の姿の一部である事が想像できる。事実を知ったところで何かが出来るわけでもないし、会社が大きければ
戦うよりは比較的に良心的な会社に出来るだけ早く転職する方が幸せな人生を過ごせるかもしれない。
日産の車を持っていた事があるがトヨタの車に品質や耐久性で個人的な経験で比べると日産の車を選ぶ理由はない。まあ、人の判断基準や評価基準は
違うので個々が判断すればよい。個々の評価や印象が違うのは当然なので個々のリスクで判断すれば良い。
日産の「絶対的権力者」がその座を追われたのはカルロス・ゴーン氏が初めてではない。かつて自動車労連の会長として日産の経営を牛耳った塩路一郎氏という人物がいた。塩路氏のもとで、名もなき多くのミドルの人生が犠牲になった。元豪州日産社長の古川幸氏もその1人だ。古川氏が過ごした“地獄の日々”を『日産自動車極秘ファイル2300枚』(プレジデント社)から紹介する――。
※本稿は、川勝宣昭『日産自動車極秘ファイル2300枚』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
■元子会社社長が過ごした地獄の日々
日産圏の労組である自動車労連の会長として23万人の頂点に君臨しながら、生産現場の人事権、管理権を握り、日産の経営を壟断(ろうだん)。生産性の低下を招き、コスト競争力でトヨタに大きく水を空けられるに至った元凶である絶対的権力者・塩路一郎を倒し、日産のゆがんだ労使関係を正常化させる――。
日産の広報室の一課長であった私が、同じ30~40代の同志の課長たちと打倒塩路独裁体制に向け、極秘で地下活動を開始したのは1979年のことだった。塩路一郎に関する情報を収集するなかで、私は1つ上の世代のある人物のことを知った。
元豪州日産社長の古川幸さん。塩路一郎の異常なまでの復讐心の的となったことで、日産での人生を奪われ、奈落の底へと突き落とされた経験の持ち主だった。
古川さんの息子さんも日産に勤めていた。地下活動を開始した翌年の1980年4月、私は息子さんを介して連絡をとり、面会を申し込んだ。そして、その地獄のような日々の話を聞き、塩路一郎という人間の恐ろしさに身を震わせることになる。
■「今すぐここへ奥さんを呼びなさい」
横浜に住む古川さんから、落ち合う場所として指定されたのは、港の見える丘公園のふもとにあるホテルのティールームだった。席について待っていると、1人の年配の男性が少し離れた席から私のほうをしきりに見ていた。そして、ふと立ち上がり、近づいてきて、「古川です」と名乗った。
私を観察していたのは、実は塩路側の回し者ではないか、確認したようだった。それほどの警戒ぶりに驚かされた。
私は古川さんに思いのたけを語った。今の塩路体制が続く限り、日産に明日はない。これをなんとしても倒したい。それにはどう戦えばいいのか、塩路一郎をよく知る立場からアドバイスをしていただきたい。
まわりの耳もあるので、外では話せないことなのだろう。古川さんは私をご自宅へといざなった。
「君、今すぐここへ奥さんを呼びなさい。君は今、どんなに危険なことをやろうとしているか、わかっているのか。絶対やっちゃいかん。すぐ奥さんを呼ぶから電話番号を教えなさい。君にやめるよう、奥さんから説得してもらうから」
ご自宅に上がるなり、古川さんは目の色を変えて忠告し始めた。「いえ、やめるわけにはいきません」。私が決意を語ると、古川さんの奥さんまで出てきて、「絶対やってはいけません。主人がどれだけ大変な思いをしたか、ご存じですか」と、これまでの出来事をとつとつと語り始めたのだ。
■1年間続いた“座敷牢”での日々
以前、豪州日産の社長を務めていたとき、取材のため訪ねてきた新聞記者との間で自動車労連会長の話題になった。塩路一郎について若いころから知っていた古川さんは、何気なく、「あれはたいした人物ではありませんよ」と漏らした。ここから予想外の事態が始まる。
まもなく、豪州日産社長の職を解かれ、帰国命令が下った。
日本で待っていたのは、「人事部付」の辞令と人事部の部屋に置かれた机1つだった。仕事はいっさい与えられない。朝出社しても、誰からも声もかけられない。「ひと言も口を利くな」と部内で指示が出されていた。
何をするともなく時間だけが経過し、夕方になると退社する。やがて、精神状態が不安定になったのか、帰宅後、テーブルの角に額をガンガンと繰り返しぶつけ、血が流れてもぶつけ続けた。それはまるで自らの命を絶とうとしているかのようだった。
「そういう主人の姿を私は見ているんです。組合に刃向かうなど、お願いですからやめてください」
「いえ、もうやると決めました」
夫妻から必死の説得を受けても応じるわけにはいかなかった。夜も更けて終電もなくなり、その晩は泊めていただいた。
翌朝のことだ。
「これをあとで読んでください。誰にも見せたことがないけれど、あなたには渡しておきたい」
ご自宅を辞するとき、古川さんから、当時書いたという手記を託された。そこには、1年間も続いた“座敷牢”のような日々の壮絶な記録が、400字詰め原稿用紙16枚に手書き文字でぎっしりとつづられていた。
■部下もなく、仕事もなく、書類もなく
手記は、机1つだけを与えられた早春のころの回想から始まる。
----------
部下もなく、仕事もなく回される書類も一枚も無い。
晴れた日には太陽の日射しがまぶしく私の沈む気持を鋭く奥底まで射し通した。明るい他人の笑顔が何故かうつろに遠くこだまし、人生に喜びも笑いも何処にも見当たらぬような目まいで、ボーッとした。
雨の日は、泣くに泣けない気持が往きも帰りも会社通いの重い足を、更に重くした。坐った会社の席での雨の一日は殊に長く、近くのビルの屋上に叩きつけられる雨足を飽きずに物悲しく眺めていた。
----------
エリートコースの豪州日産社長から、一転、座敷牢の日々を強いられ、魂の抜け殻になった。それが、オーストラリアで古川さんが発したひと言を知った塩路一郎による報復だったことは、手記のなかで人事担当役員から聞いた話として示されている。精神的ストレスから胃潰瘍になり、足もしびれるなど、身体的にも異変が生じるようになり、通院しているうちに夏も終わった。
手記の記述は秋へと移る。古川さんは、人事担当役員から、日産を離れ、群馬県の小さな町にある、従業員40人のプラスチックメーカーの役員として出る案を提示された。
古川さんは長く従事した営業販売関係の仕事を希望したが、塩路一郎の意向により、自動車労連傘下の労組がある企業、すなわち、日産圏の販売会社などへ転じることはできないこと、そのプラスチックメーカーであれば、日産圏外なので、了解が得られたことが伝えられた。
それでも一縷の望みを抱いて面会を申し込んだ川又会長(当時)からも、こう言い渡されるのだ。
■息子を“人質”に取るかのような発言
----------
「波紋を大きくする事は会社にとっても君個人にとっても得策ぢゃない。まして息子(長男)も日産にいるわけだから……。君一人が犠牲になったようで可哀相だが、だからといって(波紋を大きくすれば)鉄板の上で一人でやけどをして焼死ぬ丈だよ」
----------
経営トップが部下に対し、その息子を“人質”にとるかのような発言をしたり、「鉄板の上で焼け死ぬのみ」と脅したりしてまで、承諾を求める。人間としての良心の判断よりも、塩路一郎との関係を優先させ、「早く出ろ」といわんばかりに、1人の人間を扱う言葉だった。
手記は、日産で自分の身に何が起きたかを書き残しておこうと思ったのだろう。最後は、不本意ながらも、与えられた次の仕事に向かおうとする思いをつづって終わる。
----------
自分はいま揚げるべき凧を持っていない。しかし何かを揚げなければならぬ。
――そんな思いがやってくる。
凧に似たものを、
高く揚がるものを、
烈風に舞い狂うものを、
高く揚げなければならぬと思ふ。
曼珠沙華 ゆく雲遠く人遠く
----------
■常軌を逸した塩路一郎の復讐心
「あれはたいした人物ではありませんよ」のひと言を耳にして、相手から日産での人生のすべてを奪おうとする、常軌を逸した塩路一郎の復讐心。
その異常な要求を丸のみし、海外法人社長の座から窓際の座敷牢へと追いやったばかりか、労使関係を維持するため、古川さん1人をいけにえに差し出し、日産から追い出した経営陣の情けないほどの及び腰。
日産は病んでいるどころか、腐っている。古川さんの手記は私の胸に芽生えた義憤に火をつけた。人としての正義と尊厳をかけて、絶対に塩路一郎を倒す。
塩路一郎は異常な男だ。ならば、自分もこの男以上に異常にならなければ倒せない。これからはこのことを片時も忘れずにいよう。私は心に誓った。(文中敬称略)
----------
川勝宣昭(かわかつ・のぶあき)
経営コンサルタント
日産自動車にて、生産、広報、全社経営企画、更には技術開発企画から海外営業、現地法人経営者という幅広いキャリアを積んだ後、急成長企業の日本電産にスカウト移籍。同社取締役(M&A担当)を経て、カリスマ経営者・永守重信氏の直接指導のもと、日本電産グループ会社の再建に従事。「スピードと徹底」経営の実践導入で破綻寸前企業の1年以内の急速浮上(売上倍増)と黒字化を達成。著書にベストセラーとなった『日本電産永守重信社長からのファクス42枚』(小社刊)。『日本電産流V字回復経営の教科書』(東洋経済新報社)がある。
----------
経営コンサルタント 川勝 宣昭
透明性を高める事が優先順位であれば、今回の日産前会長カルロス・ゴーン事件の混乱は良かった事になる。
【パリ共同】フランスの公共ラジオ、フランス・アンフォは27日、自動車大手ルノーと日産自動車、三菱自動車のオランダにある3社連合の統括会社が、ルノーの経営陣に不透明な形で報酬を支払っているとして、ルノーの一部労組が筆頭株主のフランス政府に対し、透明化を図るよう求めたと報じた。
統括会社を巡っては、日産前会長カルロス・ゴーン容疑者側が日本の有価証券報告書に高額の報酬を記載しなくてすむよう、同社を通じた報酬の受領をルノー側と相談したと報じられた。実行はされなかったとされる。
ルノーのある幹部は最大13万ユーロ(1600万円)の追加報酬を数年間受け取ったという。
法律的にはどうなるの?違法や処分について朝日新聞は説明を入れてほしい。
地方銀行の西京銀行(山口県周南市)のアパート投資向け融資の資料が改ざんされていた問題で、東証1部上場の不動産会社「TATERU」(タテル、東京、古木大咲代表)は27日、従業員31人が改ざんに関与し、不正の件数は350件にのぼると公表した。
同社の特別調査委員会(委員長=浜邦久弁護士)の調査報告書によると、不正に関与した31人は顧客のネットバンキング画面を偽造するなどして貯蓄額を水増しし、金融機関に提出していた。報告書は金融機関名を明らかにしていないが、多くは西京銀行が融資した模様だ。350件の改ざんは調査期間のアパート成約棟数の約15%。2015年末のマザーズ上場前から改ざんが常態化し、上場後も続いていた。
改ざんが多発した背景には、営業現場に前年より150~200棟多い販売を毎年求めるノルマや、営業本部長らが営業成績の良くない営業部長を強く叱るといったパワーハラスメント(パワハラ)の横行、歩合給のため無理をして成約する動機、があったという。
時代が変わったと言う事を『DAYS JAPAN』の社長解任される事で実感したのでは?
検索すると早稲田大学教育学部卒のようだ!このころから日本の教育はダブルスタンダードだったのかもしれない。
フォトジャーナリストの広河隆一氏は12月26日、報道写真誌「DAYS JAPAN」(2019年2月に廃刊予定)を発行するデイズジャパンの代表取締役を解任された。(浜田理央 / ハフポスト日本版)
広河氏が職場に出入りしていた女性7人に性行為やヌード写真の撮影などを要求していたことを、週刊文春が報じたことを受けて、同誌の公式サイト上で発表した。
広河氏のコメントとして、「その当時、(文春の)取材に応じられた方々の気持ちに気がつくことができず、傷つけたという認識に欠けていました」と説明。「私の向き合い方が不実であったため、このように傷つけることになった方々に対して、心からお詫びいたします」と謝意を示した。
デイズジャパンだけでなく、認定NPO法人沖縄・球美の里の名誉理事長を解任されたことも報告した。
文春の報道は?
週刊文春は、2007年~17年ごろにかけて、編集部にアルバイトなどで出入りしていた女性7人が、広河氏から性暴力やセクハラの被害を受けたという証言を掲載。
記事によると、写真の指導名目でホテルの部屋に呼び出されたというある女性は、「あっという間にベッドに移動させられ、抗えないままセックスが終わった」と証言。行為後、裸の写真を撮影されたこともあったという。
そのほかにも、広河氏が女性を傷つける行為を繰り返していたと報じている。
広河氏は週刊文春の取材に対して、事実の一部を認める一方、“強要“は否定した。
これに対して、「メディアにおけるセクハラを考える会」代表を務める大阪国際大の谷口真由美准教授は、Facebookで「人権派のフォトジャーナリストを標榜していた人が、身近にいる女性の存在、そして人権をあまりに軽んじてきた」と広河氏を批判した。
浜田理央 / ハフポスト日本版
下記が事実であれば、やってはいけないとわかっていても止められない可能性が高いから重症だと思う。
勤務中でもアルコールの摂取をコントロール出来なのであれば、日常の生活でも何らかの影響が出ているかもしれない。
もしかすると、アルコール中毒ではなく、ばれないだろうと思ってやっていたのかもしれない。本人が事実を話さない限り、事実は
わからないであろう。
乗務中の女性客室乗務員(46)から社内基準を超えるアルコールが検出されたことで、日本航空(JAL/JL、9201)は12月25日、この客室乗務員が機内で飲酒していたと発表した。機内に搭載したシャンパンの小ビン(約170ml)40本のうち、乗客に提供していないにもかかわらず、1本が空きビンとなって機内のゴミ箱から見つかった。また、2017年11月にも、飲酒の疑いがあったことがわかった。いずれも本人は飲酒を否定しているという。
客室乗務員が乗務していたのは、17日の成田発ホノルル行きJL786便(ボーイング787-9型機、登録記号JA874J)。成田を午後7時58分に乗客123人(幼児1人含む)と乗員12人(パイロット2人、客室乗務員10人)を乗せて出発し、ホノルルには現地時間同日午前7時27分に到着した。機内で飲酒した客室乗務員は、乗務2時間前に成田で飲酒検査を受けたが、この時点でアルコールは検出されなかった。
しかし、同僚の客室乗務員3人がアルコール臭を感じ、別の1人を加えた4人が普段と様子が異なると感じていた。報告を受けた客室責任者である先任客室乗務員が日本時間午後11時50分ごろ、手持ちのアルコール感知機を使って検査したところ、呼気から社内基準の1リットル当たり0.1mgに対し、0.15mgのアルコール値が2回検出された。その後、30分ほどあけて3回目の検査したところ、基準値を再度超えた。ホノルル到着後に検査した際は、アルコールは検出されなかったという。
飲酒した客室乗務員は、機内サービス時はビジネスクラスの進行方向右側の列を担当。アルコール値検出後、すべての業務から外された。緊急脱出時にドアを扱うポジションは左前方2番目の「L2」ドアで、離着陸時に客室乗務員が座るL2ドア付近の座席は、この客室乗務員しか使用していなかった。また、ラバトリー(化粧室)を何度も出入りしているとの同僚からの目撃証言があったという。
JL789便の機材は、787-9のうち「E91」仕様と呼ばれる3クラス203席の座席配置で、各クラスの座席数はビジネスクラス52席、プレミアムエコノミー35席、エコノミー116席。客室乗務員が飲んだとみられるシャンパンは、ビジネスとプレエコの間にある「MIDギャレー」と呼ばれるギャレー(厨房設備)から持ち出されていた。JALによると、ビジネスクラス担当もこのギャレーを使用するため、立ち入ることは同僚から不自然に見えなかったという。
シャンパンの空きビンは、MIDギャレーのゴミ箱から見つかった。JALでは客室乗務員がラバトリーを頻繁に出入りしていたことから、ラバトリー内で飲酒したとの見方を示している。
飲酒した客室乗務員の様子がおかしいと感じた同僚4人は、ビジネスとプレエコ担当が1人ずつ、エコノミー担当が2人。社内調査では「ぽわーんとした雰囲気だった」などの証言があったという。また、JALが社員に対して実施している飲酒に関する講習を、この客室乗務員は10日に受講したばかりだった。このため、JALでは講習内容の見直しを検討する。
再発防止策として、JALでは業務中の客室乗務員が実施する相互確認で、アルコール飲料や薬品の影響が疑われる場合、会社に報告することを義務化。管理職1人がマネジメントする客室乗務員の人数を見直す。JALの安部映里客室本部長は、「これまで1人あたり40人から45人を管理してきたが、2割から3割減らす」と説明し、客室乗務員の様子を従来より細かく把握できるように改める。
今回の飲酒発覚を受け、赤坂祐二社長が月額報酬の20%を、安部客室本部長が同10%をそれぞれ1カ月分自主返納。飲酒した客室乗務員についても、処分を検討する。JALによると、5月に飲酒が発覚した客室乗務員の場合、会社側が処分後、自主的に退職したという。
監督する国土交通省航空局(JCAB)は、21日にJALに対し、事業改善命令を出している。JALは2019年1月18日までに、再発防止策を報告する。
Tadayuki YOSHIKAWA
日本政策金融公庫は25日、業務システム開発の入札を巡り、富士通社員に他の入札企業の情報を漏らしたなどとして、システム部門の男性職員2人を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。また、入札のスケジュールを漏らした別の男性職員を戒告処分、倫理規定上認められていない会食をした男性職員を減給処分にした。田中一穂総裁は役員報酬10分の1(2カ月)を自主返納する。
田中総裁は東京都内で記者会見し「政府系金融機関で入札情報漏えいを招き、申し訳ない。国民におわび申し上げる」と陳謝した。
公庫によると、漏えいが起きたのは今年2月以降に開かれた3件の一般競争入札。男性職員はシステム拡充の入札前に、他の入札企業に対する技術評価などを富士通側に伝えた。別の男性職員は他の2件の入札に関し予定価格算定の基礎となる情報などを漏らした。
公庫のシステム開発に関わった業務委託先の男性も富士通の提案書作成を援助し、情報を漏らしていた。入札の1件は富士通が約40億円で落札。残り2件も応札したが、6月に漏えいが発覚し、富士通が辞退した。
公庫は富士通からの連絡を受け、内部で調査していた。伊藤健二副総裁は漏えいの目的について「システム開発を円滑にするため信頼できる業者に落札させたかった」と説明。金銭の授受はなかったという。問題を受け、同公庫は富士通の入札資格を3カ月間停止した。【深津誠】
事実であれば大問題だと思う。事実確認、又は、事実を認めていないからフランチャイズ会社「H社」なのだろうか?
12月21日夜に「串カツ田中ホールディングス」が突如として発表した更衣室へのカメラ設置問題。神奈川県内の4店舗を経営するフランチャイズ会社が盗難防止のために行ったとの説明で、発覚のきっかけは〈お客様相談室〉への“通報”だった、と発表文にはある。
【動画】女性社長による“証拠隠滅”場面
実を言うとこの公表は、“盗撮カメラ”の情報をキャッチした週刊新潮からの取材を受けた直後のことだった。カメラ設置を把握してから、それを公にするまでに、少なくとも1週間の“空白”があるのだ。
***
「カメラを取り付けたことで私が罪に問われたとしても仕方がありません。責任は引き受ける覚悟です。ただ、このまま“盗撮”状態が続くことだけは耐えられなかった……」
沈痛な面持ちで告発するのは、店舗に隠しカメラを設置した業者当人である。この業者は、問題のフランチャイズ会社「H社」の役員に指示され、2016年から更衣室の天井にカメラを設置してきた。その理由を“仕事を干されるのが恐かった”と語る。
串カツ田中の発表文には、経緯説明として、12月15日にカメラを撤去したとある。が、H社の女性社長は発表2日前にあたる20日時点で、本誌の取材に「盗撮? はぁ?」と全面否定していた。
今回、本誌は、この社長がカメラを撤去する映像も入手している。更衣室を訪れた社長がカメラの位置を確認し、かがみこんで電源を落とす一部始終を捉えた、15日付の映像である。
発表から1週間を要したことについて〈事実確認に時間を要した〉と串カツ田中の発表文書にはあるが、その対応には疑問が残る。盗撮被害にあった従業員は納得するだろうか。
12月26日発売の「週刊新潮」では、設置業者が明かした串カツ田中の「盗撮問題」の真相について、さらに詳しく報じる。また現在「デイリー新潮」にて、女性社長による“証拠隠滅”場面の動画を公開している。
「週刊新潮」2019年1月3・10日号 掲載
下記が事実であれば新たな展開になるのか?
日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告(64)が日産の資金を私的に流用したなどとして会社法違反(特別背任)容疑で再逮捕された事件で、ゴーン被告が私的な投資で抱えた巨額の損失を巡り、中東の知人が30億円前後の「保証料」を負担した疑いのあることが関係者の話でわかった。東京地検特捜部は、日産側の「機密費」から知人側に提供された約16億円は、この保証料の返済に充てられた可能性があるとみている。
日産の代表取締役兼最高経営責任者(CEO)だったゴーン被告は2008年10月、新生銀行(東京)との間で契約したスワップ取引で約18億5000万円の評価損が発生し、契約者を自分の資産管理会社から日産に付け替えた上、09~12年、日産の連結子会社「中東日産会社」(アラブ首長国連邦)から知人側に計1470万ドル(現在のレートで約16億円)を振り込ませ、日産に損害を与えた疑いで再逮捕された。
消臭スプレー缶120本の処分方法となぜ消臭スプレーを大量に保持していたのかが運営会社「アパマンショップリーシング北海道」と業務と
関係していたからこのような対応を取る羽目になったと思う。
想像も付かないような結果になったが、不適切な事を行い、運が悪いとこのような損失が起きる事もある例だと思う。
札幌市豊平区の爆発事故で、出火元とみられる不動産仲介店の運営会社「アパマンショップリーシング北海道」(同市)は22日夜、初めての住民説明会を同区で開いた。終了後、佐藤大生社長らが報道陣の取材に応じ、被害補償について原状回復に必要な費用の全額を同社が負担する方向で検討していることを明らかにした。
【写真】説明会終了後、弁護士とともに報道陣の取材に応じる佐藤大生社長(右)=2018年12月22日午後9時57分、札幌市豊平区
説明会は現場のすぐそばにある15階建てマンション「ファミール平岸」の住民が対象で約80人が参加。報道陣には非公開だった。佐藤社長や同社代理人の中村隆弁護士の説明では、全42世帯のほぼ全てで窓ガラスの破損やサッシのゆがみなど、何らかの被害が生じている。
説明会では、佐藤社長が謝罪し、補償の手続きや補修工事のスケジュールを説明。同社は復旧費用を全額負担する方向で検討し、休業補償など法的に認められる補償範囲は全てカバーする考えだ。
しかし、具体的な補償金額やその回答期限を住民に示すことができず、質疑は約2時間に及んだ。「窓に板をはっても部屋が寒い」、「小さな子どもがいる家庭では、ガラスの破片が飛散しいると危なくて住めない」といった声が上がった。事故原因や経緯の説明もしていないという。
佐藤社長は「まだ納得いただけない内容だった。再度、説明会を開いて検討させていただきたい」と述べた。現場周辺の店舗に対しては説明会は開かず、個別に訪問して対応するという。(布田一樹、遠藤美波)
日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者(64)が私的な投資の損失を日産に付け替えるなどしたとされる特別背任事件で、日産側からゴーン容疑者の知人側に流出させたとされる約16億円が、「販売促進費」などの架空の名目で支出されていたことが23日、関係者への取材で分かった。東京地検特捜部は不正な支出を隠蔽する意図があったとみて経緯を調べている。ゴーン容疑者は調べに対し「ロビー活動などに対する正当な報酬だ」と容疑を否認している。
【図解】ゴーン容疑者をめぐる逮捕後の刑事手続き
この約16億円が「CEO(最高経営責任者)リザーブ(積立金)」と呼ばれる予算に計上されない予備費から支出されていたことも判明。本来は災害見舞金などに使われ、当時CEOだったゴーン容疑者の裁量で支出できたという。
ゴーン容疑者の逮捕容疑は平成20年10月、自身の資産管理会社と新生銀行(東京)との間で契約した通貨のデリバティブ(金融派生商品)取引で生じた約18億5千万円の評価損を日産に付け替えたとしている。さらに、その契約を資産管理会社に戻す際、信用保証に協力したサウジアラビア人の知人が経営する会社に21年6月~24年3月、日産子会社から1470万ドル(現在のレートで約16億円)を入金させた疑いがある。
関係者によると、ゴーン容疑者は、子会社の「中東日産会社」(アラブ首長国連邦)に指示し、予備費の中から「販売促進費」などの名目で4回に分け、計約1470万ドルを知人の会社に送金させていた。しかし、送金先の会社には、日産に関する販売促進などの活動実態は確認されていないという。
このサウジアラビア人の知人はゴーン容疑者と30年来の付き合いがあり、現地で投資活動などを行っている実業家だという。
ゴーン容疑者は調べに対し、この資金提供について「投資に関する王族へのロビー活動や、現地の有力販売店との長期にわたるトラブル解決などで全般的に日産のために尽力してくれたことへの報酬だった」と供述しているという。
一方、私的な投資の損失を日産に付け替えたとされる容疑については「(損失拡大で必要性が生じた)追加の担保が見つかるまでの間、日産の信用力を借りるため一時的に契約者を変更しただけだ。最初から戻すつもりで、日産に実損を与えていない」として容疑を否認しているという。
札幌市豊平区平岸の爆発事故から5日。UHBが取材したアパマンショップ元従業員の証言からは過剰ノルマ、消臭作業を行えない労働環境の実態が明らかになってきました。問題の本質はどこにあるのでしょうか?
この事故は16日午後8時30分ごろ、札幌市豊平区平岸の不動産仲介会社でスプレー缶120本のガス抜きをしていたところ爆発し、52人が負傷したものです。
運営会社では相談窓口を設置し、爆発でのケガの治療費やガラスや車の修理代などの補償をする相談対応を始めました。
アパマンショップリーシング北海道 佐藤大生社長:「きょうは20組以上訪問予定です」
被害者:「まだアパマンから連絡は来ていない。誠心誠意対応してほしい」
被害に遭った居酒屋:「予約をお断りしている状態で、いつごろ再開できるのか不安な毎日です」
相談窓口は午前10時から午後7時、今月28日までです。
捜査関係者によりますとスプレー120本を一度に処理した理由について店長らは「白い煙が出て火事と勘違いされると思い閉めきっていた」と話していることがわかりました。
また処分した120本の中に使用期限が近いスプレー缶もあったということです。重傷を負った30代店長の母親は…。
店長の母親:「(息子と)話もできない。全部シャットアウト。(Q申し訳ないと?)その気持ちでそうなっていると思う」
火傷の治療をしながら責任を感じている様子だということです。
警察は店長の刑事責任を追及する方針ですが、責任を問われるのは果たして現場だけなのでしょうか?
120本もの消臭スプレー缶の在庫を抱えた背景には、過剰なノルマはなかったのでしょうか?運営会社の社長は会見で…。
アパマンショップリーシング北海道 佐藤大生社長:「ノルマを社員に持たせていることはない。当社で商品を売ったことでの表彰はない」「こういう商材に対してのペナルティはありません」
しかし、アパマンショップの元従業員によると…。
アパマンショップ元従業員:「店舗の売り上げのノルマはありますからね、悪いと降格しますしね。いくらやらないと給料に歩合がつかないと設定されている金額がある。(Q.運営会社はノルマやインセンティブはないというが?)そんなことはない。数字をあげてなんぼの会社なので」
ノルマの存在があったと証言しています。また、契約をしていながら消臭作業を行わなかったことが大量在庫の背景にありそうですが、労働環境について社長は…。
アパマンショップリーシング北海道 佐藤大生社長:「(人手は)足りている認識ではあります。特別長く働いている認識はございません」
これについても元従業員は反論しています。
アパマンショップ元従業員:「スプレー缶なんですが物理的に考えて、噴射しに行くことが無理なんですよ。夜中の1時までとかまでやればまけないこともないんでしょうけど。会社はまけと言うが、売り上げを上げろと言うがまけない。そもそも上の人間(スプレー缶が)たまっていくのが分かっていてやらせているので、調査しているとか言っているけど調査する前から分かっている」
今回の爆発事故、果たして責任を問われるべきは?労働問題に詳しい専門家に聞きました。
ユナイテッド・コモンズ法律事務所 淺野高宏弁護士:「元従業員の方が大きなノルマを課されて、過密なスケジュールのもとで追い込まれていたという話も出ている。仮に事実だと前提に考えると店長一人の責任で終わらせる問題ではないと。企業全体としてこの問題の本質的な原因についてしっかり究明して対策を立てなければいけない、そういう問題」
運営会社の社長はノルマはなかったと否定しましたが…。
ユナイテッド・コモンズ法律事務所 淺野高宏弁護士:「会社が明示的にこの目標を必ず達成せよと、達成しなければペナルティーがあると言わなくても一定の目標を定めてそれに向かって営業マンに対して叱咤激励して目標達成するように指導していれば、それは必ず達成しなさいと言われてなくてもノルマと捉えていい」
契約していながら消臭作業を行っていなかった点についても、運営会社の管理のあり方に疑問があると言います。
ユナイテッド・コモンズ法律事務所 淺野高宏弁護士:「会社としては業績管理するとともに、労働時間の管理もやっている。配置されている人員からして、この労働時間で報告されている業績に見合った仕事ができているだろうかというのは、当然数字を見れば予測がつく。明確に今回のようにオプションなりで契約した消臭スプレーを、現に使用していたかしていないかまで、チェックしてないにしても、果たしてそういう契約に見合った実際の営業活動が本当に出来ているかどうか疑問をもつ契機はあったんだろうと思う」
問題の本質を解決するのに必要なこととは。
ユナイテッド・コモンズ法律事務所 淺野高宏弁護士:「まだ事故が起きて原因がどこまではっきりしているかわからないような段階で、一店舗の従業員がやったことですと簡単に結論付けてしまうというのは、本当にこの問題の持つ重大さを正しく認識しているのか疑問を持たれると思う。本当の内部的な問題の真相を適正に解明してもらう努力をしてほしい。他の従業員も見てますからね、会社の対応を。ここで頑張って働いていくっていうモチベーションを持てるかどうかは、こういう不祥事が起きた時の担当者に対する会社の対応はとっても大事だと思う」
当機構は、2018年11月14日、15日、製造業者であるセントラル硝子プラントサービス株式会社 加工事業本部 西日本加工部 大阪工場に対し審査を実施しました。
その結果、セントラル硝子プラントサービス株式会社が事業買収した旧富士ハードウェアー株式会社が、過去に製造したJISマーク表示製品において、社内規格で定めたヒートソーク工程を実施していないにも拘わらずその記録を作成していたこと、また、JISで定められた試験方法で寸法検査を行わずにJISマークを付して継続的に出荷していた事実が確認されたことから、品質管理体制が日本工業規格への適合性の認証に関する省令に定める基準を満足しておらず、その内容が重大であると認められたため、2018年12月21日付けで同製造業者の認証を取り消しました。
認証取消しとなる製造業者
(1)製造業者名及び所在地 セントラル硝子プラントサービス株式会社
三重県松坂市大口町字新地1624番地3
<工場名及び所在地>
セントラル硝子プラントサービス株式会社 加工事業本部 西日本加工部 大阪工場
大阪府大阪市淀川区三津屋南3丁目8番45号
(2)認証年月日、認証番号、取消しの対象となるJIS番号 認証の年月日:2008年6月27日
なお、2018年7月までは富士ハードウェアー株式会社が認証取得者
認証番号:JQ0507111
JIS番号:JIS R 3206(強化ガラス)
 広島県の呉市役所本庁舎に使われた、1000枚以上の強化ガラスの一部に、不良品が交じっていたことがわかった。
広島県の呉市役所本庁舎に使われた、1000枚以上の強化ガラスの一部に、不良品が交じっていたことがわかった。
3年前の2015年に完成した呉市の本庁舎では、これまでに3度も、突然、ガラスが割れる事案が起きた。調査が行われ、12日に、呉市に施工業者の五洋建設とセントラル硝子から報告があった。
内容は、「ガラスが割れる原因になる不純物を取り除いていない製品が一部納品されていた」というもの。
本庁舎に使われた「セントラル硝子」社製の強化ガラスは、1170枚にのぼる。
呉市総務課・小山成則課長「残念な気持ちです。誠実に対応してもらいたいのと、管理体制をしっかりしてほしい」
呉市によると、セントラル硝子の強化ガラスのうち997枚は、業者負担で交換されるという。
禁錮10カ月の処分を受けたJAL副操縦士の記事に関してアルコール検査の不正が日航で常態化していると思ったがやはり氷山の一角であったのだろう。そして、このパイロットも氷山の一角の一部であろう。
日本航空で昨年8月~先月上旬、パイロットが出発前のアルコール検査を意図的に行わなかったケースが163件あったことがわかった。このうち110件は男性機長(52)1人によるもので、「酒を飲まなかった日は不要だと思った」と話しているという。日航は機長の処分を検討している。
日航の発表では、この期間に検査が実施されなかった事例は計224件あり、意図的なものを除く61件は失念などが理由だった。163件のうち、49件はこの機長と同乗した副操縦士ら26人によるもので、機長に同調して検査を受けなかったという。
国土交通省は事業改善命令の中で、この点も「安全管理体制が十分機能していない」と批判した。
パイロットの乗務前アルコール検査データが欠落していた問題で、日本航空は20日、パイロットが意図的に検査をすり抜けたために記録が残らなかったケースが163件に上ると公表した。うち110件は、男性機長(52)によるもので、社内調査に「(感知)機器による検査は(航空法に基づく)運航規程に定められていないから」と話したという。日航は機長を注意・指導し、今後はすり抜けに対して厳罰で臨むため、運航規程に機器による検査を明記する。
日航によると、内部に息を吹き込む新型アルコール感知器を導入した昨年8月~今年11月、乗務のために出勤したパイロットは延べ約22万人で、うち4175件のデータが残っていなかった。
意図的なすり抜けのうち、49件は問題の機長と同乗予定だった副操縦士26人によるもので、機長に同調して検査を受けなかった。別の機長(56)も同様の理由で4回、検査をすり抜けていた。110件をすり抜けていた問題の機長は「出発前、副操縦士と相互に飲酒の影響がないことは確認した」と話しているという。
また、日航は20日、今月17日の成田発ホノルル行きの便に乗務中の女性客室乗務員(CA、46歳)の呼気から社内基準(呼気1リットル中0・1ミリグラム)を超える同0・15ミリグラムのアルコールが検出されたことを明らかにした。乗務前検査では反応はなかったが、出発から約4時間後に同僚2人が酒臭いことに気づき、機内で検査して発覚した。
CAは「14日以降飲酒していない」と話しており、日航は今後、詳しく事情を聴いて事実関係を特定する。日航では5月、国際線の機内トイレで、休憩中の男性CA(退職)が缶ビールを飲んだことが発覚している。【花牟礼紀仁】
パイロットの飲酒による不祥事が相次いだ問題を受け、国土交通省は19日、国内の航空会社に対し、乗務前のアルコール呼気検査を義務付け、反応が出た場合は数値にかかわらず乗務禁止とする方針を決めた。自家用を含む全パイロットのアルコール濃度基準は、呼気1リットル中0.09ミリグラム未満とした上で、旅客や貨物輸送にたずさわるパイロットには、より厳しい基準を課した。
国交省の有識者検討会は19日、同省が示した基準案を了承。同省は年度内にも航空各社に新方針を通達する。血中濃度の測定は時間がかかり、費用負担も大きいため、検査の義務化は見送った。
同省の担当者は「世界で最も厳しい部類の基準だ。旅客輸送に関わるパイロットについては、アルコール反応が出れば乗務できないトラックやバス乗務員の基準を参考にした」と説明している。
日本航空の男性副操縦士(懲戒解雇)が10月末、乗務前検査を不正にすり抜け、酒気帯び状態でロンドン発羽田行きの便に乗務しようとして逮捕され、英国・刑事法院で実刑判決を受けた。このため、機器内部にストローなどで息を吹き込む新型のアルコール感知器の使用を義務付ける。また、検査データを一定期間保管することや、検査すり抜け対策としてパイロットの所属部署以外の社員の立ち会いを求める。
現行法令では、乗務の8時間前以降の飲酒を禁じているが、呼気中濃度の数値基準や呼気検査の義務はなかった。日航や全日空は現在、道路交通法の酒気帯び運転の基準(呼気1リットル中0.15ミリグラム)より厳しい同0.1ミリグラムを社内基準にしている。【花牟礼紀仁】
カルロス・ゴーン容疑者が実際に不正に手を染めていたとしても、ルノーやフランス政府のとってゴーン容疑者を処分するよりも
恩を売った方がルノーと日産の関係がルノー優位になればゴーン容疑者を処分しない可能性がある事を西川社長は考えたのだろうか?
また、日本の検察が有罪に出来ると思ったので、有罪になったゴーン容疑者をルノーは切り捨てなければならないと思ったのだろうか?
何が真実なのかは重要だが、どのような結果になるかが事実よりも重要な事がある。結果を待つしかないであろう。日本人は日本人は強いが
外国人に弱いケースが多いと思う。外国人コンプレックスなのか、思考や判断プロセスが日本の常識で考えるので間違っているのかよくわからないが
この点は日本人として情けないと思う。
ゴーン容疑者、近く保釈
日産自動車前会長のカルロス・ゴーン容疑者の役員報酬の過少記載事件で東京地方裁判所は20日、ゴーン容疑者と、不正に協力したとされる同社前代表取締役のグレッグ・ケリー容疑者について、検察が求めた21日以降の勾留延長を認めない決定をした。21日以降に保釈される可能性が出てきた。そして仏ルノー支配からの脱却を目指す日産のシナリオも揺らいでいる。ゴーン容疑者の処遇をめぐり両社の溝は埋まらず、ルノーのけん制で日産は17日に予定していたゴーン容疑者の後任となる暫定会長の選任を見送った。日産はゴーン容疑者の不正を契機にコーポレートガバナンス(企業統治)改革や、ルノー優位の資本関係の見直しを進めたい考えだが、ルノーが「ゴーン不正」を認めなければ主導権を握れない。
<主導権握れず、狂ったシナリオ>
日産はゴーン容疑者の後任について、現在の日本人取締役の中から選び、17日の取締役会で決める計画だった。日産の会長は取締役会を招集し、議長を務める権限がある。日産は、ゴーン容疑者が君臨していたこのトップの椅子を逮捕から1カ月足らずで奪取し、日産主導で「ポスト・ゴーン」の新体制を築くための布石とするつもりだったとみられる。
日産は内部調査の結果、ゴーン容疑者による報酬の過少記載、投資資金・経費の私的利用という不正を確認した。西川広人日産社長兼最高経営責任者(CEO)は不正の原因について、「長期にわたる(ゴーン容疑者への)権力の一極集中」と説明していた。
ルノーが日産に43・4%出資するのに対し、日産のルノーへの出資は15%に留まり、議決権もない。こうしたアンバランスな資本関係がゴーン不正の遠因になったとの見方が日産社内では根強い。西川社長は、「日産が極端に個人に依存した形から脱却するにはいい機会になる」と経営立て直しに向けた決意を語っていた。
不正を契機にゴーン体制を完全否定して一気にガバナンス改革を進め、最終的にルノー優位の資本関係を見直し、“独立”を勝ち取る―。日産のこれまでの言動からはこんなシナリオが透ける。
ではなぜ日産は当初のシナリオを翻し、新会長選任を見送ったのか。「(17日設置した)ガバナンス改善特別委員会での議論を踏まえて決めるべきだ」(西川社長)と考えたことが一点。もう一つ見逃せないのは、ルノーの動きだ。
「(ルノーにはゴーン容疑者の)虚偽記載について十分に説明したが、分かってもらえていないようだ」。日産経営幹部は唇をかむ。
<ルノーはゴーン会長残留>
ルノーは13日の取締役会でゴーン容疑者の会長兼CEOの解任を11月に続き再び見送った。ルノーはゴーン容疑者の不正に関する日産の内部調査情報を確認したが、ゴーン容疑者の反論を聞いていないことや、ルノー社内での不正は確認できなかったとして見送りを決めた。
もともと両社の間には、ルノーが日産に最高執行責任者(COO)以上の役員を送り込めるとの協定があり、ルノーは今回の会長人事に介入する姿勢を隠さなかった。
日産は11月22日の取締役会で、ゴーン容疑者の会長職と代表取締役の解任を全会一致で決めた。ルノー出身の取締役2人を説得し、全会一致で決議できるかが焦点だった。
日産はこの第一関門を突破し、いったんは賭けに勝った。このため「(解任しなければ)コントラスト(対比)になるので、ルノーも同じ結論を出す」(関係者)と期待していた。
日産がルノーとの資本関係見直しをゴールとする一連の改革を主導するには、ルノーがゴーン容疑者の不正を認めることが出発点だ。そうでなければ、日産のガバナンス改善やルノーとの資本関係見直しが必要という理屈が成り立ちはしない。
関係者は「『日産がゴーン容疑者を解任したことの意味』をルノーが理解すれば、特殊な状況の中で、今後どうしていくかを(ルノーでなく)日産に任せるだろう」と日産側の期待を述べていた。しかし両社の溝は埋まらず、日産主導のシナリオは狂い始めた。
日産が下支え…譲れないルノー
ルノーとしては、両社の資本関係見直しまで含めた改革を日産主導で進めることを簡単には容認できない事情がある。99年の資本提携当時はルノーが日産を救済したが、現在の状況は様変わりした。
日産は米中という自動車の二大市場で足場を着実に築き、17年の世界販売台数は581万台。それに対しルノーは376万台にとどまる。17年は当期利益の約4割を日産からの持ち分法利益や配当収入が占めており、日産がルノーの経営を下支えしている。
日産は技術面でも電気自動車(EV)分野などでリードしており、「実力としては上」と自負する。「連合が瓦解したら両社にマイナスだが、そのショック度はルノーの方が上回る」(SBI証券の遠藤功治企業調査部長)。仮に日産が独立性を高めれば、ルノーは経営が立ちゆかなくなるリスクも生じる。
ルノーに15%を出資する大株主の仏政府は最低でも連合の現体制の維持を狙う。フランスでは失業率が10%前後で高止まりのうえ、マクロン政権は大規模デモの頻発で求心力が一段と落ちている。
さらに足元では米フォード・モーターの仏国内工場の閉鎖計画に対し、ルメール経済・財務相が非難し、計画変更を求めている。雇用吸収力の高い自動車は政府の産業政策の要なだけに、日産の独立性を高めるような大胆な決断は期待しにくい。
<嫌な予兆>
ルノーがゴーン容疑者の解任を見送る結論を出した13日の取締役会。その2日前から日産にとって嫌な予兆はあった。日産は不正の内部調査結果をルノー取締役に直接説明する方針だったが、ルノー側の意向で同社弁護士を通じての提供となった。
「不正の生々しい部分はルノーの取締役の一人ひとりに届いていない。日産と同じレベルで理解してもらえるよう、説明の機会をもらえるよう継続して努力する。ルノーにも聞く姿勢を持ってもらいたい」と西川社長は17日の会見で話した。
ただ、ルノーが経営体制の見直しで主導権を握るため、日産に対して臨時株主総会の早期招集を要求しているとの情報もあり、駆け引きは激しさを増している。
日産は「経営トップ人事」「ガバナンス改革」「資本関係見直し」のいずれのテーマでも大株主であるルノーの意向を無視できない。三菱自動車を含む3社連合の発展という共通ゴールを見据え、まず「ゴーン不正」という基本認識で一致し、ルノーと出発点をそろえられるか。日産経営陣の交渉力、説得力が試される局面が続く。
資本面では「不均衡な関係」にある日産、ルノーの連合は、ゴーン容疑者の強力なリーダーシップにより「対等の精神」を付与され、バランスをとってきた。そのカリスマ退場で連合は将棋倒しのように危うい状態で均衡を保っている。どちらが強引な一手を打てば瓦解しかねない。しばらくにらみ合いが続きそうだ。
日刊工業新聞・後藤信之、渡辺光太
「同学園は「今年3月の年度末が解体期限と誤解していた」「中学開校に向け思わぬ出費が相次ぎ、解体資金を確保できなかった」などと説明。高校、中学とも定員割れの状態などで余力がないとしており、約5千万円の支払いも19年度までできないという。」
どのような契約書を交わしたのか知らないが、契約書次第では契約を無効に出来るのではないのか?
定員割れの学校を存続させる意味があるのだろうか?
本庄第一高を経営する学校法人塩原学園(埼玉県本庄市、相川浩一理事長)が、廃校した旧県立本庄北高の土地建物を格安で県から購入したが、格安の条件だった建物の取り壊しをせず一部を使い続けていることがわかった。市民オンブズマンが県に情報公開請求をした直後、契約が変更され、県の対応も疑問視されている。
旧本庄北高は、1977年開校で、2013年に廃校となった。敷地は約4万3千平方メートルで、校舎などは計約1万3千平方メートル。同学園の本庄第一高は隣にあり、新たに本庄第一中を開校する用地として敷地と建物の購入を県に申し入れた。
13年末から2回あった入札は成立せず、県が予定価格を大幅に引き下げた14年5月の3回目の入札で、評価額約4億2千万円のところ同学園は7千万円で落札。敷地内の18ある建物のうち校舎2棟と体育館の計3棟だけ残し、残り15は同学園が3年のうちに解体することが「格安」の条件だった。本庄第一中は16年4月に開校した。
だが、期限の昨年8月までには解体されず、外部の指摘を受けた県が今年2月に調査。解体するとしていた建物の浄化槽を使い続けていることもわかった。
これに対し、県管財課は3月、解体期限を20年8月まで延長を認める案を作ったが、庁内で理解を得られなかった。同学園は、解体すべき建物15のうち七つを解体せず利用することに方針転換。これにより、同学園が新たに約5542万円を県に支払うよう、当初の契約を変更する方針案を県は8月28日にまとめた。
同学園は「今年3月の年度末が解体期限と誤解していた」「中学開校に向け思わぬ出費が相次ぎ、解体資金を確保できなかった」などと説明。高校、中学とも定員割れの状態などで余力がないとしており、約5千万円の支払いも19年度までできないという。
一方で、この契約変更の知事決裁は10月18日。狭山市民オンブズマンの田中寿夫さんが同10日に情報公開請求をした8日後で、田中さんは「2カ月近くも決裁が放置され不自然」と指摘。県管財課は「議会などがあって遅くなった。オンブズマンの動きとは関係ない」と説明している。(松浦新)
「日本航空は20日、成田発ホノルル行きの日航786便(乗客乗員135人)に乗務していた女性客室乗務員(CA)=(46)=から、同社の基準値を超えるアルコールが検出されたと明らかにした。
CAは「飲酒は一切していない」と否定しているといい、日航は事実関係を調査している。
日航によると、17日夜に成田空港を出発した同便に乗務していたCAについて、同僚から「アルコール臭がする」との報告が2度にわたり、責任者である先任客室乗務員に上がった。」
本当に「飲酒は一切していない」が事実であれば問題ないが、もし飲酒したことがばれれば時期が時期だけに重い処分を受けそうだ。
また、飲酒していないにもかかわらず、基準値を超えるアルコールが検出されたとすれば、計測機器の定期的なチェック、又は、計測器を
他のメーカーの変更しなくてはならないと思う。
日本航空は20日、成田発ホノルル行きの日航786便(乗客乗員135人)に乗務していた女性客室乗務員(CA)=(46)=から、同社の基準値を超えるアルコールが検出されたと明らかにした。
CAは「飲酒は一切していない」と否定しているといい、日航は事実関係を調査している。
日航によると、17日夜に成田空港を出発した同便に乗務していたCAについて、同僚から「アルコール臭がする」との報告が2度にわたり、責任者である先任客室乗務員に上がった。
呼気検査を2度実施したところ、いずれも同社の基準値を超える1リットル当たり0.15ミリグラムのアルコールが検出された。さらに30分ほど間隔を空けて再検査をしたところ、基準に抵触する同0.1ミリグラムのアルコールが確認された。
日航はCAを業務から外し、ホノルル到着後に再び検査をしたが、その際はアルコールは検出されなかった。乗務前の検査でも問題なかったという。
CAはマウスウォッシュを頻繁に使っていたと説明しているが、うがいなどをしてもアルコール値が出ているため、日航はマウスウォッシュ以外の影響があるとみている。
「もう耐えられない」。マレー系英国人で英国弁護士資格を持つ専務執行役員は今年5月、日本人幹部にそう打ち明けた。幹部が「全部話してくれ」と問い返すと、「……会長の資金操作があまりにもひどい」。一旦重い口を開くと、そこからは日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者(64)の巨額な報酬隠しや私的流用、自らの関与を告白し始めた。この告白が、半年後、ゴーン前会長の逮捕につながることになった。
横浜市の日産グローバル本社21階には「ゴーンズルーム」と呼ばれるゴーン前会長の執務室があり、隣接するのが前会長の職務をサポートする中枢組織の最高経営責任者(CEO)オフィスだ。執行役員は2014年4月、そこのトップに就任。社内から「こんなに出世するとは思いもしなかった」と陰口をたたかれるほど重用されたのも、前会長の右腕として報酬隠しを主導したとされる前代表取締役のグレッグ・ケリー容疑者(62)とともに不正に関与してきたからだとみられる。それがなぜ翻意したのか。
この執行役員の告白より前、監査役らは10年にオランダに設立された子会社「ジーア」に不審を抱いていた。この会社を通じて前会長用にレバノン・ベイルートなど海外の複数の高級住宅が購入されており、その不明朗な金の流れを追う極秘の調査チームが動き始めていた。日産関係者は「執行役員は元来がまじめな性格で、極秘の調査チームの接触を受けて洗いざらい話し始めた」と明かす。
調査チームは長年前会長に仕えていた日本人の秘書室幹部の説得にも成功。執行役員と秘書室幹部の調査協力によって調査は加速、逮捕容疑となった50億円超の報酬隠しを含む前会長らの不正の証拠が積み上げられていった。
前会長はなぜ報酬を隠す必要があったのか。伏線として、CEOを務める仏自動車大手ルノーでの高額報酬批判がある。別の執行役員は「フランス国内での批判を避けようとする意味があったのだろう」と語る。
前会長のルノーCEO再任がパリの株主総会で決まった6月。調査は山場を迎えていた。内部調査に関わった関係者は「内容が内容だけに会長の耳に入ればクビになる。ごく限られた人間が閉ざされた空間で事を進めた」と振り返る。前会長が月に数日しか出社しないことが秘密保持には好都合だった。
◇
世界に衝撃を与えたゴーン前会長の逮捕から1カ月が経過した。逮捕の背景に何があったのかを検証する。
半年の潜行捜査
「日産自動車の弁護士を呼んでくれ」。11月19日夕、レバノン発のビジネスジェット機が羽田空港に着陸すると、待ち構えていた東京地検特捜部の係官らに任意同行を求められた前会長、カルロス・ゴーン容疑者(64)はそう応じた。自ら20年近く率いた組織に見放されたことを知らずに発した言葉だった。
一方、前代表取締役のグレッグ・ケリー容疑者(62)は同日、ゴーン前会長より数十分早くジェット機で羽田空港に到着し社用車で宿泊先の東京都内のホテルに向かっていた。高速道路を走行中、運転手に「近くのパーキングエリア(PA)で止まってください」と電話が入った。車がPAに入って駐車場に止まると前代表取締役もまた、近づいてきた特捜部の係官らに任意同行を求められた。2人は同日夜、東京・霞が関の東京地検内で逮捕された。
「着手は2人が同時来日するこの日しかなかった。2人とも海外にいることが多い。片方を先に逮捕すれば、もう一方が日本に来なくなるかもしれない。この日を逃し、さらに時間を費やせば、捜査情報が漏れて事件が潰れるリスクもあった」。ある検察幹部はこう振り返る。
特捜部は日産から情報提供を得て内偵捜査を開始。7月には、文部科学省の局長級幹部2人の逮捕につながった汚職事件に着手していたが、水面下でごく少数の検事が“日産案件”の潜行捜査を続けていた。
秋に入り捜査は大きな進展を見せる。特捜部は前会長の「報酬隠し」に関わっていた外国人の専務執行役員と、日本人秘書室幹部との間で「司法取引」の合意に至った。執行役員らには6月に導入されたばかりの同制度に詳しい元検事の弁護士2人がついていた。執行役員らは、前会長が巨額な報酬の一部を退任後に受け取ることを記した文書にサインするなど重要な役割を果たしていたとされる。
特捜部は、2人から文書などの証拠の提供を受ける代わりに、刑事処分を軽減することを約束したとみられる。「これで仮にゴーン氏らが否認しても、有罪に持ち込める」。“Xデー”に向けて、特捜部外からも英語に堪能な応援検事を集めた。
最後の「関門」は2人の同時来日のタイミングだった。前会長は、11月21日に東京都の小池百合子知事との対談イベントに臨むため、同19日に来日することが決まっていた。一方、ケリー前代表取締役が日本に来るのは「年に数回」(日産幹部)の頻度。今回は特捜部の捜査に協力していた日産が、前代表取締役に社内会議への出席を持ちかけたという。
首に持病を抱えるケリー前代表取締役は、米国の病院で12月7日に手術を受ける予定が入っており、当初は「テレビ会議でお願いしたい」と、来日に難色を示していた。だが、日産側が「ゴーン前会長の報酬に関する話し合いがしたいので来てもらいたい」と説得したという。日産内でもほとんどの社員らは前会長の疑惑を知らなかった。逮捕の数日前。ある日産幹部は、前会長の疑惑について外国人執行役員から説明を受け、「近く逮捕される」と知らされた。幹部は衝撃を受けた。そして運命の日が訪れた。
自分たちに捜査が及んでいることに全く気付かないまま逮捕された2人。ゴーン前会長の弁護人には元東京地検特捜部長の大鶴基成弁護士がつき、ケリー前代表取締役には海外ロースクール卒で「ロス疑惑事件」で無罪判決を勝ち取った喜田村洋一弁護士がついた。2人の「大物弁護士」を味方につけた前会長らは、特捜部と全面対決の構えを見せている。
大鶴弁護士は特捜部長時代、「ライブドア事件」や「村上ファンド事件」などを指揮し、剛腕として知られた。一方、前会長らへの捜査を指揮する森本宏・現東京地検特捜部長は、「大鶴特捜部」時代の“若手のエース”だった。昨秋に就任後、「リニア談合事件」や「文科省汚職事件」を手がけ、威勢を見せている。今回の事件は、特捜部師弟対決の様相も呈している。
ルノー寄り 求心力急落
逮捕されたゴーン前会長に重用され、“ゴーンチルドレン”としてトップに上り詰めた西川(さいかわ)広人社長。「極端に特定の個人に依存した形から抜け出すよい見直しの機会になる」。11月19日の逮捕時の記者会見で、前会長との決別を強調した。社内記録上、西川社長が捜査協力していた監査役から不正を知らされたのは10月だとされ、日産は「クーデター」を否定する。しかし日産側には、連合を組む仏自動車大手ルノーとの統合を進めようとする前会長への不信感が極限まで高まっていた。
前会長は2月ごろからルノーとの統合をそれまでのように明確に否定しなくなった。兼務するルノー最高経営責任者(CEO)の任期満了が6月に迫り、続投のためには筆頭株主である仏政府の意向を無視できなくなったからとみられる。「マクロン仏政権が前会長に突きつけたCEO続投の条件が、2022年までに日産とルノーの関係を不可逆的にすること」(日産幹部)。不可逆的とは経営統合を意味する。
前会長もかつては「日産側に立ってルノーや仏政府に対する防波堤役」(元幹部)となり、15年には仏政府から日産の経営の独立を尊重する合意を取り付けた。合意が破られれば日産はルノー株を追加取得して「ルノー支配」に対抗できるため、日産幹部の間では統合を抑止できるという意味を込めて「核のボタン」と呼ばれていた。
それだけに、3月に三菱自動車を含めた3社連合の部品共通化や共同開発などの統合強化策が発表されると日産に動揺が走った。従来より経営統合に一歩踏み込む内容だったからだ。社内には「会長はルノーとの統合に本気だ。開発も資金も日産任せのルノーにのみ込まれるなんて」(男性社員)といった不満や不安が広がった。
同時に日産内部で前会長の求心力は急速に低下。昨秋以降の一連の完成車検査の不正でも矢面に立つことはなく、西川社長に責任を押し付けるような発言が目立つようにもなっていた。
「カリスマ経営者」の逮捕から1カ月。日産は前会長の解任、ルノーとの後任人事を巡る攻防などめまぐるしい動きに直面し、前会長逮捕は日仏首脳をも巻き込んだ水面下での交渉にまで発展した。
西川社長は今月17日の記者会見で記者から「ここまでの展開に誤算はないか」と問われ、「重大な不正はここで絶対に止めなければいけなかったし、その決断は間違っていなかった」と強調した。ルノーや仏政府との関係がどうなるか、そして不正を見逃し続けた社内のガバナンス体制を強化できるのか。直面する課題は多く、今後の展開は見通せない。
今回の検証は、巽賢司、遠山和宏、金寿英、松本尚也、藤渕志保、柳沢亮、ロンドン・三沢耕平が担当しました。
下記の記事が事実であれば少なくとも前代表取締役のグレッグ・ケリー容疑者の人間性がろくでもない事が推測できる。
今回、前代表取締役のグレッグ・ケリー容疑者が有罪となるかは、日本の法律、検察の能力そして日産が決定的な証拠を提出出来るか次第であろう。
フランスの経済紙レゼコー電子版は19日、日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者(64)を巡る不明朗な会計処理の計画を示す日産の内部文書を入手したと報じた。前会長とともに逮捕された前代表取締役のグレッグ・ケリー容疑者(62)と仏自動車大手ルノーの幹部が前会長の高額報酬開示を回避するため、オランダにある両社の統括会社経由で前会長に追加報酬を支払う方法を模索。仏国内法で開示義務が生じる可能性があり最終的に断念したが、両社幹部が協力し報酬隠しを計画していたことが明らかになった。
【写真特集】カルロス・ゴーン会長 写真で振り返る
同紙によると、ケリー前代表取締役とルノーの女性幹部ら両社の少数の幹部は2010年以降、定期的にメールなどで情報交換し、統括会社「ルノー・日産BV(RNBV)」を経由して前会長に追加報酬の一部を支払う方策を検討した。日本で同年、内閣府令が改正されて年間1億円以上の報酬を受けた取締役らの公表が義務付けられたことへの対応で、前会長の意向だったという。
同年4月22日付の前代表取締役から女性幹部へのメールには「公にならない形で合法的に支払える方法を考えていただき感謝する」などのやり取りがあった。こうしたやり取りは、前会長退任後に役員報酬を受け取る方法を考案する直前だったとみられる。【松本尚也、パリ賀有勇】
過料の適用はやめて、死亡事故が起きた時には十年以上、関与した従業員、責任者そして経営者を禁固刑にすれば良い。
日産やスバルの車を買いたい人達がいるのであれば自己責任で購入すればよい。外国メーカーの車よりも品質が高ければそれで良いと思う。
ただ、問題のあった日本のメーカーの問題は少なくとも10年間、ホームページなどで問題が改善されたも公表し続ければ良いと思う。
欠陥ではないが下記のサイトのコメントで日産リーフに関していろいろとネガティブな事が書かれている。個人的には以前、低走行車なのに日産の車で
トラブったので日産の車は買わない。
バッテリーの劣化は? 買い取り額は? 中古のEVを買っても大丈夫??? 12/20/18(Yahoo!ニュース)
出荷前の自動車検査が不正に行われていた問題で、国土交通省は19日、道路運送車両法に基づき、日産自動車とSUBARU(スバル)両社に過料を適用するよう、横浜、東京両地裁に通知した。
過料適用を求めた自動車は日産が454台、スバルが278台。過料の1台当たりの上限額は30万円で、日産が最大で1億3620万円、スバルは同8340万円に上る可能性がある。この金額が実際に科された場合、同法に基づく過料としては、日産が過去最大になるという。
検査不正問題をめぐって、国交省は今年3月にも、必要な検査が行われていなかったとして、日産に過料適用を求める通知を出していた。度重なる検査不正問題による行政処分は、同社のブランドイメージをさらに傷つけることになりそうだ。
また、同省は19日、日産に対して再発防止策の実施状況を四半期ごとに報告するよう指導した。
同省によると、過料適用を求めた自動車台数のうち、排ガスの抜き取り検査で試験条件を満たさなかったのに、測定値を書き換えたものが日産は393台、スバルは278台に上った。日産は行っていなかった騒音などの抜き取り検査を実施したように装っていたとして、さらに61台も適用するよう通知した。
日産は「関係者の皆さまの信頼回復に努める」とコメント。スバルは「このような事態に至ったことを厳粛に受け止める」としている。
行政が事実確認を行わないと事実は出てこないであろう。
「札幌市豊平区の雑居ビルで42人が重軽傷を負った爆発事故で、不動産仲介会社の社長が「消臭作業獲得のノルマは無かった」との発言に現役の複数の関係者から反論の声が上がっています。」
事実だとしても名乗り出る事は難しいし、元従業員が名乗り出ても今回は違うと言われれば、終わりのような気がする。
当事者や関係者達しか知らない事実はあると思う。
札幌市豊平区の雑居ビルで42人が重軽傷を負った爆発事故で、不動産仲介会社の社長が「消臭作業獲得のノルマは無かった」との発言に現役の複数の関係者から反論の声が上がっています。
この事故は16日午後8時30分ごろ、札幌市豊平区平岸の雑居ビルで大きな爆発があり、不動産仲介会社の30代の店長が重傷、飲食店などにいた男女計42人がけがをしたものです。
18日の会見で社長は爆発の原因とされる新品の120本のスプレー缶のガス抜きを一気に行ったことの背景として「消臭作業獲得のノルマはなかった」と発言しましたが、現役の複数の関係者からは「直営店ではノルマがあったのではないか」と反論の声が上がっていることがわかりました。
現場では、19日も現場検証が行われています。
不正やデータ改ざんは多くの国民が知らないだけどもっと多くの会社や企業が関与しているのではないかと思う。
外国と比べると日本は良いだけで、日本人が思うほど、又は、知らないだけで不正やデータ改ざんは頻繁に起こっていると考えた方が正しいのか?
油圧機器大手「KYB」(東京)による免震・制振用オイルダンパーの検査データ改ざん問題で、同社は19日、不適切な改ざん行為が新たに確認されたと発表した。これまで判明している手口とは別の方法。今回の不正発覚で、国などの基準に適合しない物件は、疑いを含めると、1102件に上った。
KYBは10月、国の基準や顧客が求める性能基準に収める目的で係数を不正に入力し、検査データを改ざんしていたと発表。顧客への説明や取り換え工事に向けて動いていたが、11月15日に新たな不正の疑いが浮上したため、改めて調査を始めるとしていた。
発覚 1300万円着服 女性職員「服や旅行に…」
森林組合の女性職員が架空請求などを繰り返し、1300万円あまりを着服していました。
徳島県三好市の三好西部森林組合によりますと、集金を担当していた52歳の女性職員は原木の購入費を架空に請求したり、集金した代金を入金しなかったりする手口で着服を繰り返していました。着服した金額は、2015年から4年間で1300万円あまりになり、女性職員は「洋服の購入費や、大阪への旅行代金などに使った」と話しているということです。組合の幹部は「信頼して任せていた」「残念だ」と話していて、詐欺と横領の疑いで刑事告訴する方針です。
責任とか、賠償とか、法的にどうなるのかまだニュースでは触れていないが、個人になるのか、それとも、「アパマンショップリーシング北海道」に なるかで実際に被害者達にお金が支払われるのか決まると思う。
札幌市で16日夜に起きた爆発事故で、倒壊建物に入居していた不動産仲介店を運営する「アパマンショップリーシング北海道」(同市北区)の佐藤大生(たいき)社長が18日に会見した。店長が室内で在庫の消臭スプレーを処分するため、120本を並べて立て続けに噴射し、約20分後に給湯器を使おうとして爆発が起きたと説明。「心よりおわび申し上げたい」と謝罪した。
店内には当時、店長と従業員の2人がいた。佐藤社長が2人から聞き取ったところ、スプレーを噴射したのは事故当日の2日後に店の改装を控え、在庫を処分するためだったという。
午後8時ごろから、店長が1人で店内のテーブル4カ所に120本を並べて中身を噴射させた。店内が煙ったため、2人はいったん外へ出た。15~20分後に戻り、店長が手を洗おうと給湯器をつけたところ、爆発が起きたという。店長は「匂いは残っていた」と話しているという。
佐藤社長によると、スプレーは、入居直前に部屋の消臭などのために使う。入居予定者に希望を尋ねたうえで、施工代金も含めて1本1万~2万円で販売。ボタンを押すと噴射が続き、3~4分で全量が出る。原価は約1千円という。
佐藤社長は、スプレーの処分について「通常やる業務にはなっていない」と話し、120本ものスプレーを処分したことについて、「理由の一つに未施工があったと聞いている」とした。入居者から消臭代を受け取っていながらスプレーを使わなかったもので、佐藤社長は「全部が全部そう(未施工)ではないと思っていますが、件数を精査したい」と話した。
当時、店内には160本の新品の消臭スプレーがあった。通常の在庫は50~60本といい、これだけたくさんあったことについて、店長は「店舗を引き継いだ時にもともとの在庫が多かった」と説明したという。
スプレーの販売業者によると、この消臭スプレーには可燃性の物質が含まれている。だが、佐藤社長は「店長は可燃性を認識していなかった」とした。
北海道警は爆発現場で約100本のスプレー缶を回収しており、爆発との関連を調べている。
NPO法人ピースウィンズ・ジャパン(PWJ)の大西健丞代表理事は一時はテレビで取り上げられていたので覚えている。
下記の記事が事実ならひどいと思う。そして、NPO法人ピースウィンズ・ジャパン(PWJ)と大西健丞代表理事は信頼を失うだろう。
殺処分。嫌な響きである。ゼロになるに越したことはないが、そう謳って救った犬たちが、実は殺処分以上の虐待にさらされ――。ピースワンコ・ジャパンのそんな実態を、本誌(「週刊新潮」)は2度にわたりレポートしてきたが、ついにこの“偽善組織”が書類送検され、同時に愛護団体から告発されたのだ。
ピースワンコ問題の理解には、先月26日、広島県警福山北署に送られた告発状を読むのが早そうだ。動物愛護管理法に違反しているとして、ピースワンコ・ジャパンの事業を司るNPO法人ピースウィンズ・ジャパン(PWJ)の大西健丞代表理事と、ピースワンコの責任者、大西純子氏を告発したものだ。以下、概要をザッと示そう。
広島県神石高原町に本部を置くピースワンコが行うのは、行政が収容した犬を引き取って里親に渡す事業で、2016年からは広島県内で殺処分対象となった犬はすべて引き取り、その資金に、神石高原町のふるさと納税を使ってきた。
ところが、四つのシェルターのなかで最大で非公開のスコラ高原シェルターは、今年1月時点で1400頭収容の過密状態。ところがスタッフは数人だけで、餌も1日1回。劣悪な環境で極度のストレス状態にある犬たちは、弱い犬を集団で攻撃し、月に30頭が死亡していた。また、ピースワンコは不妊・去勢手術を基本的に行わない方針なので、子犬もよく生まれるが、感染症などで死亡したり、夜中に生まれるとほかの犬に食べられたりしていた。なのに少なくとも今年1月まで、このシェルターには外科の器具すらなく、犬の数が多すぎるため、子犬を蹴りあげるなど、職員の乱暴な扱いが目立った――。
「我々は状況証拠や内部告発者の証言を集め、ピースワンコが行っていることは動物愛護管理法違反だから捜査してほしい、という趣旨で告発しました。〈愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者〉への罰則を定めた動物愛護管理法第44条1項への違反。加えて〈健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること〉〈疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと〉を禁じた、同じ条の2項への違反です」
と語るのは、告発した日本の保護犬猫の未来を考えるネットワーク代表の多田和恵さん。現在、ネットワークに76団体が賛同、浅田美代子、杉本彩ら芸能人も名を連ねている。
ところで、告発状に書かれた内容は、ピースワンコの内部で働いた竹中玲子獣医師の証言として、去る9月に本誌が報じたものとほぼ一致する。この記事に対してピースワンコは、
〈きわめて一方的で事実と異なる記述が多く、(中略)十分な裏付けのない誹謗中傷に強く抗議する〉
などとHPに書いたが、くだんの竹中獣医師は、
「自分が見聞きしたものを正直に伝えたのに、“裏付けのない誹謗中傷”だと中傷されて、非常に残念」
と憤る。また公開のシェルターであっても、今年勤務した元職員によれば、
「頭数が多すぎるため、みな犬への接し方が雑になり、犬が人嫌いにならないかと心配でした。毎日外に出て運動できる犬など、ほとんどいないんです。子犬の感染症はワクチンで防げる場合もあるのに、まともにワクチンも打っていない。こうした内部事情については、外に漏らさないように箝口令が敷かれています」
3億円以上が使途不明
ところで、竹中獣医師がスコラ高原シェルターで働いたのは、「狂犬病予防注射を打つのが追いつかないので手伝ってほしい」と言われてのことだった。
その旨も先の記事で触れていたが、先月20日、ついに広島県警はPWJを書類送検したのだ。大西代表理事ら3人が狂犬病予防法違反の、PWJ自体とほかの職員2人は、犬舎から12頭が逃げ出した件で、県動物愛護管理条例違反の疑いがあるという。県警に近い関係者によれば、
「職員や元職員から幅広く事情聴取していて、もちろん目標はもっと先にあります。怠慢な広島県が主犯でピースワンコが共犯、ふるさと納税の納税者が被害者、という構図です」
犬を際限なく引き取れば過密状態になり、予防注射は行き届かず、脱走犬も現れる、というのは当然の帰結だろう。そのうえ、自身も元NPO法人代表の土谷和之氏によれば、PWJは認定NPOにしては、異例の“不透明さ”だそうだ。
「一部公開されているピースワンコ事業の会計報告を見ると、17年度は経常収益11億円のうち、ふるさと納税に当たる受取助成金等が5・3億円。一方、総額8億円の経常費用のうち3・4億円は、“その他の経費”内の“その他の経費”とされている。つまり使途不明金で、監査を受けたとして堂々と出してます。ふるさと納税を使いながら年に3億円以上が使途不明とは、認定NPOとして常識的にあり得ない規模です」
これでは、ふるさと納税をほかの目的に使うために、犬を引き取り続けていると思われても仕方あるまい。
それにしても、行政はなぜ、こんな団体に犬を渡し続けるのか。広島県動物愛護センターは、
「計画的な立ち入り検査により、問題があれば適宜指導を行っています」
と返答するが、
「県の食品生活衛生課にピースワンコの現状を訴えたのですが、“今までなんの問題もございませんでした”という回答でした」
と、先の元職員。なにも見てはいないのだ。再び多田代表が言う。
「広島県からピースワンコへの犬の譲渡を止めさせなければなりません。県の現場職員たちはもう譲渡をやめたくても、県は“殺処分ゼロ”を維持したくて、ピースワンコは全部引き取ってくれるから、という流れがあるようです。でも、13年改正の動物愛護管理法について、環境省を含めた話し合いの場では、殺処分ゼロの弊害としての現場の混乱が指摘されています。繁殖を抑制しながら飼わないとネグレクトと判断する、という趣旨が、法改正の際に盛り込まれる可能性もある、と見る賛同者もいます」
引き取られた犬は虐待され、非業の死を遂げ、そのために、ふるさと納税が使われるが、多くが使途不明。捨ておけることではない。
「週刊新潮」2018年12月13日号 掲載
「素案には、外国人労働者が在留資格を申請する際、ブローカーの存在の有無を報告させることも盛り込んだ。」
申請者の名前と印又はサインを必修とし、ブローカーの存在の有無に虚偽記載が多い場合には罰則が出来るようにするべきである。
虚偽記載のチェックが難しいかもしれないが、抜き打ちでチェックする方法を取れば良いと思う。
政府は17日、来年4月に始める外国人労働者の受け入れ拡大で、新たな在留資格「特定技能」の取得に必要な日本語能力試験を当面9か国で実施する方針を固めた。関係省庁は外国人との共生のための費用として、2019年度予算案に総額約140億円を計上する方向で調整している。
日本語能力試験の実施国数は、外国人との共生のための「総合的対応策」の素案に明記し、法務省が17日に開いた有識者検討会で示した。
具体的な国名は明記されていないが、ベトナムやフィリピン、カンボジアなど東南アジアが中心となる見通しだ。9か国との間では、悪質なブローカーによる外国人労働者からの金銭の搾取を防ぐため、政府間文書を作る。素案には、外国人労働者が在留資格を申請する際、ブローカーの存在の有無を報告させることも盛り込んだ。
アパマンショップ平岸駅前店の従業員の学歴は知らないが、文科省、義務教育のレベルではたくさんのスプレー缶のガスを放出して
使用すると火が付く湯沸かし器を使うとどうなるのか考えたり出来ないようだ。学校の質に問題があったのだろうか?
従業員の学歴が大卒であれば、私大に行ってたくさんの借金を抱える学生がいるとたくさんの記事やニュースで取り上げられているが、
このような簡単な事を考えられないカリキュラムしか提供できないのであれば、そのような大学は必要ないし、「大卒」と書けるがために
大金を支払うのであれば文科省は大学の定義や能力に関してしっかりと検討するべきだ。
不動産仲介「アパマンショップ」を経営するAPAMAN株式会社は18日、札幌市豊平区で16日夜に起きた爆発事故で、現場の建物に入居する「アパマンショップ平岸駅前店」の従業員が消臭剤のスプレー缶100本以上のガス抜き作業後、湯沸かし器をつけた際に爆発が起きたことについて公式サイトに謝罪文を掲載した。
公式サイトに「平成30年12月16日20時半頃、当社連結子会社株式会社アパマンショップリーシング北海道の運営するアパマンショップ平岸駅前店にて爆発事故が発生致しました。爆発事故による被害に遭われた方々、周辺住民の方々、及び関係する全ての皆様に心よりお詫び申し上げます」と謝罪文を掲載。
事故の原因について「事故当時、店舗内にいた従業員から聞き取り調査を行いましたところ、消臭スプレー缶約120本の廃棄処理後、湯沸かし器を点けたところ爆発が起きたとの報告を受けました。その他詳細につきましては当局にて調査中です」と説明し、「お怪我をされました方々の一日も早いご回復をお祈り申し上げるとともに、被害を受けられました皆さま方には心からお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。
今後の見通しについては「本件に伴う連結業績見通しに与える影響は現時点では不明です。今後の見通しに関して業績予想の修正等が必要であることが判明した場合には、速やかにお知らせいたします」としている。
「キナ臭いof the year」
報道プライムサンデーのご意見番、落合陽一氏(ピクシーダストテクノロジーCEO)がこう表現するのは、中国の通信機器大手、ファーウェイ(華為技術/HUAWEI)の孟晩舟副会長逮捕を巡る問題だ。
【画像】携帯から見つかった“余計なもの”の正体!さらに40年前の深センはこんなにも違った…
ファーウェイは現在、スマホの販売台数シェアでアップル社を抜き世界第2位のグローバル企業。1987年、中国人民解放軍出身の任正非氏が創業した。今回逮捕された容疑者は、任氏の娘で次期CEOの有力候補とみられる人物だ。落合氏は次のように語る。
「これは国際的な貿易の対立なのか、経済的な対立なのか、もしくは安全保障上のものなのか、三つ巴の関係になっていて、どうしようもない」
今回の事件の背景にいったい何があるのか?16日放送の報道プライムサンデーでは、ファーウェイの成長の軌跡から、問題の真相と今後に迫った。
ファーウェイ製品から見つかった「余計なもの」の正体
与党関係者は「政府がファーウェイの製品を分解したところハードウェアに“余計なもの”が見つかった」と語る。
「余計なもの」とは何なのか?防衛省サイバー防衛隊初代隊長で、現在はラック・ナショナルセキュリティ研究所の所長を務める佐藤雅俊氏は次のように話した。
「我々が入手している情報によると、日本のある法人向けファーウェイ携帯電話が、通信状況をモニターしていると、スパイウェアに似たような挙動をする。しかも通信先が中国らしいという情報。例えば、携帯での閲覧履歴、実際マイクがオフにしていたのがオンになって、あるところに流したりとか。スパイが携帯に入り込んでるような感じ」
佐藤氏が入手した情報によれば、日本のある法人向けのファーウェイ製スマホを分析したところ、スパイウェアが発見されたという。これはユーザーが知らない間に、遠隔操作でネットの閲覧履歴情報などを盗んだり、マイクのスイッチを入れてユーザーの会話を盗み聞きしたりすることができるソフトで、スパイの様な動きをする“悪質”なものだという。
佐藤氏は「ファーウェイが(情報を)取っているのではなく、中国政府が取っていると思われる。防衛関係の技術や日本の最先端の技術を搾取して中国の繁栄にいかそうと」と続ける。
一方、ファーウェイ側は14日、HP上でこの“余計なもの”に関して「まったくの事実無根です。日本に導入されているファーウェイの製品はファーウェイならびに日本のお客様の厳格な導入試験に合格しております」としている。
ファーウェイ生んだ中国のシリコンバレー
アメリカでは、安全保障上の脅威とみなされ、政府機関での使用が禁止されているファーウェイ。そして、日本の総務省も次世代通信システム5Gから、ファーウェイなどを事実上排除する方針を決めた。
ファーウェイを生んだのは、中国のシリコンバレーと呼ばれる広東省・深セン。40年前は何もない田舎町だったが、改革開放路線を機に経済特区となると一気に世界有数のITタウンへと急成長。ファーウェイは深センと共に急成長し、世界的大企業に変貌を遂げた。
本社を訪れたことのある早稲田大学ビジネススクール准教授の入山章栄氏は、「凄い会社だなと感じました。物凄く大きな大学のキャンパスのような敷地に、ありとあらゆる本社機能が入っている。そこに世界中から優秀な人材を集めて、若い人は寮に住まわせている」と、現地を取材して驚いたという。
研究開発をふさわしい環境で進めようと、本社を郊外に建設。最近は研究開発に売り上げの15%を投入するなどの力の入れようだ。ファーウェイ本社のエンジニアの初任給は月額約83万円と超高給で、世界中から優秀な人材を集めているという。中国ビジネスに詳しい現代ビジネスのコラムニスト・近藤氏は、「日本企業が中国企業を部品メーカーと考えていたが、今は逆転しつつある。最先端のものに限っていうと、日本企業が中国企業の下請けになっている」と、今やファーウェイは、日本企業を凌駕する存在になっていると分析する。
そして、習近平氏の野望である『中国製造2025』を実現するためのキーとなる技術が、ファーウェイがリードしている次世代通信システム5Gだ。
現在の4Gから5Gになると、通信容量は一気に100倍になり、2時間の映画も2~3秒でダウンロードできるようになり、車の自動運転や遠隔医療が可能になるなど、我々の生活が大きく変わるという。近藤氏は、そこにこそ、ファーウェイ副会長逮捕の背景があると指摘する。
「5G戦争の覇権争いがあると思う。何が何でもファーウェイを叩いておかないと、21世紀のアメリカの覇権がおぼつかないと判断したのだと思う」
『中国製造2025』のきっかけは尖閣国有化!?
中国とアメリカはハイテク製品をめぐる覇権争い。
中国の習近平国家主席は、『中国製造2025』という計画を進めている。その目標の一つが、2025年までに半導体など、ハイテク製品のキーパーツの70%を中国製にすることだ。実はこの計画が生まれたきっかけが、2012年9月、日本が行った尖閣諸島国有化だと中国事情に詳しい東京福祉大学国際交流センター長の遠藤誉氏は解説する。
「とても意外な因果関係ですが、尖閣諸島を日本が国有化して、中国では非常に激しい反日暴動が起きました。その時に日本製品の不買運動をやった。しかし『日本製品を買わない』と、呼びかけているスマホが、『外側はメイドインチャイナだけど、中は全部日本の半導体じゃないか』と。このスマホを使うのか、使わないのか。捨てるのか否か、という論争になり、『半導体も作れない中国政府とは何事か』と反日デモが反政府運動に向かっていった」
そのため、キーパーツもメイドインチャイナにしようとして『中国製造2025』が生まれたというのだ。そして、この計画を推し進めるにあたって必要不可欠なのがファーウェイの技術だ。ファーウェイは今、スマホのシェアが世界2位、通信基地局のシェアでは世界1位。さらに5G技術では世界トップクラスを走っているという。
アメリカ側は、そんなファーウェイの製品を使っていると、スパイ行為に使われるおそれがあるなどとして、安全保障上の脅威だと指摘して排除に乗り出した。日本の与党関係者からは「ファーウェイの製品を分解したら“余計なもの”が見つかった」というコメントが出ている。確かにこの“余計なもの”が中国側に利用されて、スマホの通信が傍受されたりしたら心配ということになる。
落合氏は「通信系(の怪しい動き)は一旦ネットワークを遮断して、パケットを観察すれば大体わかると思います。ただ外側から『もしもの時に止まってください』という信号が送られたときに、それでチップが止まらないかどうかを証明するのは難しいので、基地局にあるハードウェアにどんなソフトが入っているのかをチェックするのは本当に難しい」と危険性を指摘した。
もし、ファーウェイが中国政府のいいなりとなり、安全保障上の脅威になるとしたら…。そこで、ファーウェイは中国政府の手下なのかどうか、を詳しく解説する。
ファーウェイは中国政府の手下なのか?
ファーウェイを立ち上げたのが任正非総裁。中国人民解放軍の出身ということで、政府側の人間ではないかと疑われている。しかし任総裁の経歴を見てみると、1983年に人民解放軍をリストラされている。
遠藤氏:
実は1983年前後に100万人の中国人民解放軍のリストラがありまして、その中の一人だった任氏は、路頭に迷うような状況の中で、1987年に仲間と一人5万円くらい、全部で30万円くらいのお金をようやく集めて、民間の零細企業を立ち上げた。当初は電話交換機の代理販売などをしていて、今のハイテクとは全然違います。元々任氏も、土木建築が専門で、通信に関する知識がないので、代理販売しかできませんでした。
こうして民間企業として誕生したファーウェイが急成長するきっかけになった出来事があった。インドの通信会社との取引で、入札の際にファーウェイと競合していた企業が「ファーウェイには技術力がない!」とインドの通信会社に告げ口をしたため、ファーウェイは入札すらできずに終わってしまったという苦い経験があったという。この告げ口をしたというライバル企業が国有企業のZTEだった。
遠藤氏:
国有企業というのは、政府の子供のようなものですから、政府が直接資金を投入して、じゃぶじゃぶとお金をもらっている。中国政府と関連を持っていますから、政府に『情報をくれ』と言えば、すぐに情報をもらえますから、『ファーウェイには技術がないよ』という情報をインドの会社に訴えた。
ファーウェイはこれが悔しくて、技術力を高めようと考えた。2004年、半導体を作る子会社「ハイシリコン」を設立し、研究開発に力を注いた。ハイシリコンが作る半導体はファーウェイだけにしか提供されず、この子会社が作る半導体は今や世界トップクラスになった。
一方、ライバル企業のZTEは国有企業なので、中国政府から豊富な資金援助をされながらも、半導体は輸入に頼っていたため、アメリカから取引禁止の制裁措置を受け、事業が停止するという大打撃をくらってしまった。
『2017年中国半導体関係企業の収益ランキング』をみると、ハイシリコンは国有企業を抑えてダントツ。「国有企業は全然利益をあげず、民間企業がトップに立っているという現実がある」と遠藤氏は指摘した。
ファーウェイ急成長を支えた2つの方針
なぜ政府から豊富な資金援助を受けている国有企業ではなく、民間企業がトップに立てたのか?その背景にはファーウェイの2つの方針があった。
その1つめは、『従業員を大切に』という方針だ。
その具体的な表れが、従業員の持ち株制にある。持ち株の98.7%を従業員が持ち、残りの1.3%しか役員などは持たないのだ。そのため従業員は会社が儲かれば、自身も儲かるため、従業員のモチベーションが非常に高いという。
さらにCEO(最高経営責任者)は3人の輪番制で、半年に1回交代する仕組みになっている。遠藤氏は「一人がやっていると、不正がはびこってしまうかもしれない。不平等になる。従って半年に1回の輪番制で不正が起きないように、腐敗が起きないようにする。あくまでも従業員が主人公だ」とするのが狙いだと解説した。
パトリック・ハーラン:
これはアメリカでも聞かない、先進的な体制だと思う。
落合氏:
珍しいと思いますね。急成長を遂げる会社は経営者が持っている持ち株比率が高いので、それが従業員に反映されているのは非常に面白いと思う。給与でも、アメリカのシリコンバレーを超えるような待遇で採っているから、非常に強いと思いますね。
パトリック・ハーラン:
これ、製造手段を労働者が持っているということは、まさに共産主義の体制ですね?
遠藤氏:
まさに純粋な共産主義ではないかと。
従って習近平国家主席としては、なかなか潰しにくいというところもありますでしょうね。国有企業のZTEと喧嘩をしているという状況ですから、習近平さんは、民間企業と国有企業の間に挟まれて、窮地に追い込まれていると思いますよ。
もう一つのファーウェイの方針が『家族経営をしない』。これは任総裁が決めたという。
その一方で、副会長なのは任総裁の娘だ。これはどういうことなのか?
遠藤氏:
2010年10月の取締役会で、長男を役員にしようとしたんですね。ところが、選挙で落とされた。そのために2011年に『家族経営はしない』と宣言してしまったんです。そのあとに孟さんが娘であることが明らかになってきた。相続させないというのが分かったので、表に出したんです。その意味では、フェアな経営をしている。
総裁にはなれない!?孟容疑者の意外な素顔
ここで、副会長である孟晩舟容疑者の経歴を見ていく。
孟氏は1993年に創業者の娘であることを明かさずに一般入社で、受付や事務作業をしていた。5年後の1998年に一度会社を離れ、大学院に行き会計学の修士を取得。その後復職して、コスト削減や経営改革で手腕を発揮。その実力が認められて、2011年にCFO(最高財務責任者)に就任した。親の力ではなく、実力で地位を勝ち取ったという。
しかし遠藤氏は、「家族経営をしない」という方針があるので「彼女が総裁になることはあり得ない」と断言した。
さらに孟氏には、もう一つエピソードがある。
2011年3月11日、東日本大震災が起きた1週間後に香港にいた孟氏は、日本へと向かった。同じ飛行機には猛氏を含め、2人しか乗客がいなかったという。そして東京のオフィスで余震にあいながら陣頭指揮を振るった。部下たちに防護服を着せ、東北地方での通信設備の修理に力を尽くしたそうだ。
そんなファーウェイは中国の若者たちに絶大な人気を誇っている。その秘密は、ファーウェイが従業員を大切にする民間企業であったためだと遠藤氏は言う。若者たちの多くが遠藤氏にこんなことを話したという。
「国有企業なんて誰が応援するものですか!私たちは何を買うかによって、一党支配体制への無言の抵抗を表現しているんです」
遠藤氏は、「表立って一党支配体制に抵抗を示すと逮捕されてしまいますから、物を購入する。消費者はリッチになったので、購入することによって『自分たちは共産党は大嫌いなんだ』と、『国有企業のものなんか誰が買うか』という意思表示をしている。『新しいカタチの選挙だ』と若者が言っていました」と解説した。
“新しいカタチの選挙”。中国には普通の選挙はない。買うことが選挙と同じような意味を持つというのだ。
落合氏は「ファーウェイはこれまでの国有企業とは違って、クールな中国を標榜しているような気がする。深センで新しい技術が出てくる土壌を作ってきたのは、ファーウェイなど最近伸びてきている民間企業のパワーだと思っている。例えばSNS上に自分の信用情報が出るなど、新しいITによる管理や、それによって便利になっていく社会づくりとか、スマホによって成り立っている」と付け加えた。
中国の若者たちの支持により成長してきたファーウェイの姿が浮かび上がってきた。「ファーウェイは中国政府の手下なのか?」という問いへの遠藤氏の答えはー。
パトリック・ハーラン:
話を聞いていると案外応援したくなりましたけど、でも僕心配しているのは一党独裁の国ですね。中国政府と民間企業の間では、民間企業が協力しなければならないという義務が法律上あるらしいですね。手下じゃなくても、『何かくれよ』と言われたら断れないんじゃないか。
遠藤氏:
だから脅威は脅威です。政府と協力関係にないと、つまり反政府であっては伸びないですよね。中国政府とファーウェイが協力関係にある、というのはあり得るだろうと思います。しかし、もしも中国政府の言いなりになっている、あるいはスパイ行動をして中国政府に情報を与えている、というようなことがあれば、中国の若者が完全にファーウェイから離れていくと思います。『誰がそんなところを応援するか』と。
そんな中、日本政府はファーウェイ製品を“排除”へ、という動きを見せている。
遠藤氏:
もし本当にスパイウェアが入っているということなどがあれば、政府関係者とか自衛隊とかだけではなく、一般の民間会社も、我々個人もプライバシーがあるから、そういう中国製の通信機器は徹底して排除すべきです。
生半可な、玉虫色の日中友好とかを考えて、ファーウェイとかZTEとかの名前を使わない、こういう配慮をしていると、中国はもっと増長して、中国の若者たちがどんどんファーウェイを応援するということになります。なので、私はどんなことがあっても、ハードウェアに余計なものがくっついているんだったら、『こんなものがついていたよ』ということを示すべきだし、証拠を示す、エビデンスを出すべきだと思います。
エビデンスを出したら、中国の若者はみんな離れます。すると結果的に『中国製造2025』が失敗します。そうすると中国が『制覇しよう』『アメリカを乗り越えよう』という野望は挫けてしまいます。達成することができなくなる。
日本政府は、どういう決意でいるのかを明確に示すべきで、本当に『中国製造2025』をつぶそう、中国のような言論統制をやるような一党支配の独裁国家ですから、そういう国が世界を制覇するようになったら、どれだけ恐ろしいことが起きるかということを考えれば、私は徹底してエビデンスを出すべきだと思います。アメリカのトランプ政権も、是非とも本当のエビデンスを示して、本当に排除しなければいけないんだなという判断をする材料を私たち国民に欲しいです。
中途半端な圧力はかえって中国を強くしてしまう。日本は圧力をかけるしか方法がない状況にある。そして5G技術にプレイヤーとして参加できていない現実もある。
落合氏は「冷戦と同じような構造だ。中国側につくのはどれくらいいるのか、アメリカ側につくのはどれくらいいるのか、という冷戦です。国と企業との結びつきがどれくらい強いのか。個人の情報は一人一人の問題だと思うので、それに対応していくのは一人一人の課題だと思います。僕らはアメリカと中国の間に挟まって本当にいいのかと思う」と結んだ。
ハイテク製品をめぐる米中の対立は始まったばかりだ。
(報道プライムサンデー 12月16日放送分より)
「指導の都度、4者とも改善の意向を文書などで示したものの、結局実行されないまま、爆発炎上となってしまったという。」
指導は指導された側が改善する意思があれば機能するが、相手が時間稼ぎや実行する意思がない場合、機能しない事が証明されたと思う。
爆発・倒壊した木造モルタル2階建ての建物がいつ建築されたのか知らないが、古いのではないかと推測する。
まあ、今回の爆発で所有者が得をしたのか、損をしたのか、わからないが、損をしたのであれば自業自得、そして得をしたのなら
行政は指導に関する改善、罰則強化又は規則改正がなければ、このようなケースは運が悪ければ今後も起こるであろう。
札幌市消防局は17日、不動産仲介会社や飲食店が入る建物に防火管理者が選任されていなかったり、消防計画が作成されていなかったりなどの多くの不備があったことを明らかにした。
【現場見取り図】吹き飛んだ建物と当時いた人数
消防局によると、爆発・倒壊した木造モルタル2階建ての建物の所有者と三つのテナントにはそれぞれ、防火管理者を置く義務があったが、いずれも選任されておらず、消防計画も作成されていなかった。漏電火災報知機や避難器具も設置されていなかった。
これらは消防法などで建物所有者やテナントに義務づけられているもので、消防局は2016年6月から今年10月まで、立ち入り検査や文書で計12回にわたり指導をしてきた。指導の都度、4者とも改善の意向を文書などで示したものの、結局実行されないまま、爆発炎上となってしまったという。
「ゴーン容疑者の家族は中にある私物を持ち出したいと訴えていたが、ロイター通信によると裁判所がこれを認め、14日、ゴーン容疑者の娘が現金や書類などを持ち出した。」
日産は大手なのだからブラジルの法律や事情に詳しい人に相談できるはず。ブラジルの法律に問題があると思うのならブラジル人を雇うのは極力避けた方が良いと思う。悪法であろうとも法は法である。
日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者の娘が日産側から提供されたブラジルのマンションに立ち入り、現金や書類などを持ち出した。日産側はこれに反発している。
ブラジル・リオデジャネイロには日産側がゴーン容疑者に提供していた高級マンションがある。ゴーン容疑者の逮捕後、日産側は不正に関する証拠が残されている可能性があるとして、保全のため、マンションの鍵を交換していた。
ゴーン容疑者の家族は中にある私物を持ち出したいと訴えていたが、ロイター通信によると裁判所がこれを認め、14日、ゴーン容疑者の娘が現金や書類などを持ち出した。
これに対し、日産側は書類の確認を求めたものの、認められなかったとした上で、「書類が私物とは考えられない」と反発している。
国税庁は14日、源泉徴収票などのデータ入力を委託した会社が、国内の別の業者に無断で再委託していたと発表した。
再委託されたのは約69万件分で、うち少なくとも約55万人分のマイナンバー(社会保障と税の共通番号)が記載されていた可能性がある。現段階では、再委託先からの漏えいは確認されていないという。
同庁によると、問題があったのはシステム開発会社「システムズ・デザイン」(東京都杉並区)。2017年度から源泉徴収票など約138万件のデータ入力を受注していたが、業務量が増えたことから、東京、大阪両国税局の発注分を国内の3業者に再委託したという。また、作業見本として源泉徴収票など134件の画像を各社のパソコンで保管していた。
国税局が11月に行った定期監査で発覚。既に契約を解除しており、入札参加資格も停止する。
東京医科大(東京)の不正入試問題で、同大を運営する学校法人の理事会の理事16人のうち、問題発覚後に就任した理事長や学長ら5人を除く11人が21日付で一斉辞任することがわかった。理事会の選出母体である評議員会を構成する評議員50人のうち46人(理事との兼務を含む)も辞任する。一連の問題の責任を取る形で、問題発覚時の体制は一新される。
同大では7月、文部科学省の私大支援事業を巡る汚職事件で、同省前局長の息子を医学部医学科に裏口入学させていたことが発覚。当時の臼井正彦理事長(77)(贈賄罪で起訴)と鈴木衛(まもる)学長(69)(同)が同月、引責辞任した。
翌8月には、医学科の入試で女子や浪人回数を重ねた受験生を一律に減点したり、裏口入学の対象者とみられる受験生計19人に加点したりしていたことが明らかになった。
「日産自動車は13日までに、同社から『理由のない利益』を得ていたとして、元会長ゴーン容疑者の姉をブラジル・リオデジャネイロ州の裁判所に提訴した。」
上記が事実でゴーン容疑者又は側近の前代表取締役グレッグ・ケリー容疑者がだまって決めた事でないのであれば、日産に実際に責任がある人達がいるのでは?
【サンパウロ時事】日産自動車は13日までに、同社から「理由のない利益」を得ていたとして、元会長ゴーン容疑者の姉をブラジル・リオデジャネイロ州の裁判所に提訴した。
ゴーン容疑者はリオでコンサルタント会社を経営する姉と実体のない業務契約を結び、年約10万ドル(約1100万円)を日産経費から支出した疑惑がある。
日産のブラジル法人は「司法手続きの問題に関しては、日産はコメントしない」として、具体的な提訴内容を明らかにしていない。
本当に多くの会社が悪質であるのなら、サービス残業を行い、利益を出しても外国から日本は儲けすぎと批判されるのであればスローダウンして
無理をせずに利益を出す方法を考えた方が良いのではないか?
会社の事ばかり考えず、大学での学んだ事を仕事で生かせるように企業、大学や学生達が変わるべきでないのか?大学生がどれほど大学でべんきょうしているのか現状を把握していないが、4年間も学んだ事が生かせない事は時間とお金の無駄であると思える。これまでは良い企業や大手企業で就職出来れば良い生活が得られる可能性が高いから多くの学生や社会人は疑問に感じなかったのかもしれない。日本社会がそうなのだから現状を受け入れるしかないと思われてきたと思う。
本当に変えたいのならリスクを取る事や行動する事が必要だと思う。ただ、一番手は努力の割には損する可能性が高いと思う。この障害を越えてでも
変えたいと思う日本人が増えない限りは大きな変化はないと思う。
今野晴貴 | NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
ネット上で「ブラック企業マップ」というwebサイトが話題だ。
「ブラック企業マップ」はTwitterの@blackcorpmapというアカウントが運営しているもので、厚生労働省が公表している「労働基準関係法令違反に係る公表事案」を元に、労基署から労働基準法等違反で書類送検された全国の企業名を1000社以上掲載している。
企業名の他、地域や地図から検索ができ、次のような情報が掲載されている。
公表日 H30.3.9
違反法条 労働安全衛生法第59条,労働安全衛生規則第36条
事案概要 クレーンの運転の業務に、特別教育を実施していない労働者を就かせたもの
その他参考事項 H30.3.9送検
人を大量に使い潰す労務管理を戦略的に行うブラック企業は、社会にあってはならない存在だ。悪質なケースについて、公表も含むペナルティは当然だろう。違法行為を行った企業名を示し、アーカイブ化することは必要だといえる。
しかし、企業にとってはいつまでも違法行為の記録がアーカイブとして残ってしまうことで大きな影響を受けることになる。すでに問題を改善している企業からすれば、継続的な掲載は不当に感じる部分もあるだろう。
そこで今回は、なぜこのようなサイトが必要とされるのか、継続掲載の問題はどう解決すれば良いのかについて、考えていきたい。
違法企業公表の流れと限界
これまで、違法企業の情報はほとんど世の中に出てこなかった。そのため、求職者が違法行為を行っていたり、悪質な労働環境の会社を見分けることは、絶望的に困難だったと言って良い。
その象徴が、過労死企業名の非公表という状況である。最高裁は遺族からの過労死企業名の公表要求に対し、これを否決しているのである。
そのため、どの企業で過労死が起こったのかは、現在でも基本的に公にならない。遺族が記者会見を行うなどしてメディアに伝えてはじめて、ニュースになり私たちが知ることができるのだ。
参考:「「過労死」はどのように明るみにでるのか? 遺族が裁判を起こすまで」
したがって、もっとも重大な労働問題である過労死すら、私たちが知ることができるのは「氷山の一角」に過ぎないと言うことになる。それも、遺族が労災を申請し行政に認められたケースの内、さらに少数しかわからないのだ。
最近、労基署が取り締まりを行った違法企業のうち、悪質なケースは企業名を公表するという措置が設けられた。これに基づき発表されているのが、冒頭の「ブラック企業マップ」が参照している「労働基準関係法令違反に係る公表事案」である。
国がブラック企業に関する情報を公開する政策を積極的にとったことをまずは評価したい。だが、この仕組みはブラック企業対策としては残念ながらほとんど機能していないのが現状だ。
多くのブラック企業に共通する問題である残業代未払や長時間労働では、ほとんど送検されておらず、労働安全衛生法に関する違反や長時間労働での労災について違反が確認された場合にばかり書類送検されているからだ。
公表されている事例の内、例えば、次のような違反行為のケースが多いのだ。
「高さ6.8mの屋根の端に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの」
「ゴンドラを使用するに当たり作業開始前の点検を労働者に行わせなかったもの」
残業代の不払いや長時間労働が摘発されにくいのは、「証拠」が集めにくいからだ。また、経営者が「タイムカードはあるけど、その通りに本当に働いていたとは思えない」などなかなか「故意」を認めず、残業させていたことじたいを否定する場合も多い。
こうなると監督官の捜査は行き詰まってしまい、送検を諦めてしまうケースが多い。ある現役監督官は「上手に言い訳する企業ほど、書類送検しにくいんです」と苦言を呈するほどだ。
以上のように、労基署が書類送検した企業リストはブラック企業を特定するものとして不完全なのが現状だ。そのため、同資料にもとづいて作成された「ブラック企業マップ」の企業一覧もまた、あくまで「氷山の一角」にすぎないのである。
それでも、その「数少ない公開情報」を見やすく届けるということは極めて重要だと思われる。
参考:「ブラック企業名公表、その効果は?」
参考:「労基署の送検リストは「ブラック企業リスト」じゃなかった?」
労働者が諦めてしまったら「事件化」されない
「氷山の一角に過ぎない」という点をさらに詳しく説明していこう。
私たちに寄せられている労働相談においても、明らかに「ブラック」であるにもかかわらず、相談者が諦めてしまったために、事件化できなかったものは珍しくない。
労働者が相談や申告をしようと労基署に行ったものの、窓口の職員に「在職だと会社にばれるので申告しない方がいいのでは」などと「助言」をされ、申告を諦めてしまうパターンもよく見かける。
労基に申告をしたことを理由に会社が労働者に嫌がらせをすれば、それ自体が労働基準法違法となる。しかし、労働者を守る実質的な担保があるわけではない。仮に労基署が動いたとしても、適当な調査で終わったり、会社の中で犯人探しが始まったりすることもある。
こうした事情で、ブラック企業に勤め明らかに違法行為に直面しながらも、申告を諦めてしまう人が非常に多いのだ。
例えば次のような相談事例がある。
ある私立学校では、教員は週6日の授業の勤務に加え、休日出勤も多く、振替休日もほとんど取れなかった。就業規則上は17時が定時だが、20時までの業務、受験生向けの学校説明会、部活動、入試の準備など時間外勤務の残業代が一切払われていなかった。人によっては過労死ラインである月80時間の残業時間近くまで働いている人もいた。
この違法状態に直面した相談者は、労働基準監督署への申告ではなく、「情報提供」を行った。申告すれば、学校にそれがわかるが、情報提供であればそうした危険性が少ないと考えたからだ。
ところが、労基署が調査に入ると学校はタイムカードの書き換えを全社的に命じた。その結果、会社は改ざんした書類を労基署に提出し、残業代未払いも結局何も解決しなかった。
申告とは違い情報提供だけだったので、労基から相談者本人にはどのような調査がなされたのか、何らかの是正勧告や指導が出たのか出ていないのかも一切教えてもらえなかった。
その結果として残業代も何も支払われず、それ以降はタイムカードを改ざんしてつけるように職場の慣行が改悪されただけだった。もちろん、このようなケースは公開されることもない。
取り締まりの後も違法行為を継続するケースが多い
次に、継続的な掲載による企業の不利益の問題を考えていこう。
違法行為を過去に行った企業の名前がネットにアーカイブ化することによって、会社が労働環境を改善をしてもネット上に悪評が残る可能性がある。
しかし、こうした問題が生じるのは、企業名の公表後もその会社が労働環境を改善したかどうか、会社の外にいる人間からは判断できないことが理由である。
アーカイブを消すためには「改善したことの確証」が必要だろう。確証もないうちに企業からの苦情でアーカイブを消せば、ブラック企業の「火消し」を手伝うことにもなりかねない。
だから、私は過去の事例を載せている「ブラック企業マップ」のやり方は、現状ではやむを得ない手法だと思う。
事実、労基署の取り締まりの後も会社が違法行為を継続するケースは多い。以前にブラック企業の代表格として大きく批判を浴びた「すき家」は、過去、わずか1年余りの間に20回以上も労基署から指導されていた。
また、2008年6月に入社二か月目の社員が過労自死したワタミでは、2008年4月から13年2月の間に労基署から是正勧告を24件、指導票17件を受けていたことが分かっている。
二社とも、いくら行政が指導しても改善されなかったのだ。
さらに、私たちに寄せられた相談事例でも、労基署が動いたにも関わらず違法行為が継続した事例があった。
この企業では残業代がほとんど払われておらず、月によっては100時間ほど残業している月もあった。そのため、労基署が是正勧告を出し、それをきっかけに、会社は働き方改革をやると宣伝するようになった。
ところが、現場はまったく変わらなかったという。会社は支店長に対し職場で長時間労働があると査定を下げると指示を出していたのだが、これによって残業時間が減るのではなくたんに残業していることを隠すようになった。
22時には消灯され、社員は職場から出なくてはならなくなったが、社員は会社の外で会議や仕事をするようになっただけだった。その後私たちが紹介したユニオン(労働組合)がそうした実態を明らかにし、改善させ残業代を取り返すことができたが、労基署の是正勧告だけでは改善しなかったことは明らかだろう。
このように、一度企業名を公表された事案だからといって、労働環境が改善されるとは限らない。結局企業名が分かったところで、現在改善されたか、されていないかは入社してみないと分からないということに変わりがないのである。
職場の改善を「モニタリング」する労組の役割
ブラック企業が改善したのかどうかを社会的に可視化し、また改善した状況が継続するように社会的に監視するにはどうすればいいのだろうか。
実は、これには労働組合(ユニオン)が有効だ。職場に労働組合が結成されれば、職場の状況が会社の外から「モニタリング」可能な状況となる。具体的には、会社は改善した労働条件の内容を労働協約として労組と結ぶことができる。
そして労働協約を広くメディアやネットなどを通じて発信すれば、改善を実際にしたという確証を得ることができるだろう。また、会社が労働協約の内容を破れば、労組がそれを問題にし、新たな違法行為ともなるため、改善状況を継続するプレッシャーにもなる。
このようなプランは、何も机上の空論ではない。近年、過去に「ブラック企業」と批判されていた企業が労組と労働協約を結ぶことで労働条件の改善を社会に広くアピールする事例が実際にいくつか出てき始めている。
参考:「たかの友梨が「究極のホワイト企業」に変貌」
有期雇用の「5年ルール」の実態と解決策 TBC社とユニオンの画期的取り組み
このように、「改善した」ことが、会社のアピールではなく、労働組合によって確認された企業の名前は「ブラック企業マップ」から消去するという手続きを取っても良いはずだ。また、逆に「改善した企業」として紹介しても良いだろう。
そうすれば、企業にはますます改善の機運が生まれる。
「ブラック企業マップ」は、行政が労働基準法等違反で書類送検した企業の公表データをネット上にアーカイブとして見やすく可視化したという点で、とても有意義な試みである。
こうした取り組みがさらに発展するためには、労組によって労使関係をつくることが重要な鍵となってくると考えられる。
「NHKは『報道局長の意向で報道内容を恣意的に歪めた事実はありません。なお、取材や制作の過程に関することにはお答えしていません』と回答した。」
上記のコメントが本当に事実なのか利害関係がなく公平な組織や人間が検証しなければ、鵜呑みには出来ない。ただ、安倍政権への忖度があったのであれば安倍政権を敵に回しても構わない大きな組織は存在しないと思うので、大きな組織が検証する事はないし、独立しているジャーナリストが任命される事はないので検証や証明は不可能だし、現実的ではないと思う。
NHKだから全てを信頼又は信用できると考えるのは間違いで、ケースバイケースで判断するべきだと思う。
安倍昭恵首相夫人が名誉校長を務める小学校に対し、国有地が格安で払い下げられた森友事件。メディアが取材合戦を繰り広げる中、NHKは報道姿勢が消極的で、安倍政権への忖度が取り沙汰されてきた。
このほど、NHKで森友事件を取材していた記者が、「週刊文春」に手記を寄せ、上層部の意向で、報道が縮小した経緯を明らかにした。
今回、手記を寄せたのは元NHK記者の相澤冬樹氏(56=現大阪日日新聞論説委員)だ。相澤氏はNHKの大阪報道部記者として、森友学園への国有地売却に近畿財務局の背任の疑いがあること、財務省が森友学園側に「口裏合わせ」を求めていたことなどをいち早く報じてきた。だが今年5月中旬、記者から考査部への異動を告げられ、8月末にNHKを退職した。
〈NHK大阪報道部の司法担当記者だった私は、発覚時から森友事件を追いかけ続けてきた。その間、感じてきたのは、事実をあるがままに報じようとしないNHKの姿勢だ〉(手記より)
手記では、安倍官邸中枢との太いパイプで知られる小池英夫報道局長からの圧力について言及している。
〈「私は聞いてない。なぜ出したんだ」
電話の向こうで激怒する声が響く。声の主は、全国のNHKの報道部門を束ねる小池英夫報道局長。電話を受けているのはNHK大阪放送局のA報道部長だ。
私はたまたまA部長のそばにいたため、電話の内容を知ることになった。「なぜ出したのか」と問われているのは、私が報じた森友事件の特ダネ。近畿財務局が森友学園に国有地を売却する前に、学園が支払える上限額を事前に聞き出していたというニュースだ〉
昨年7月26日夜に報じたこの特ダネは、小池氏の怒りを受け、意味合いが弱められ、翌7月27日朝の「おはよう日本」ではオーダー(放送順)も後ろに下げられたという。
NHKは「報道局長の意向で報道内容を恣意的に歪めた事実はありません。なお、取材や制作の過程に関することにはお答えしていません」と回答した。
12月13日(木)発売の「週刊文春」で、相澤氏は、小池氏らから受けた圧力の実態や、口裏合わせ報道などスクープの裏側のほか、退職後の取材で判明した森友事件の新事実についても綴っている。さらに、相澤氏は初の著書『安倍官邸vs.NHK 森友事件をスクープした私が辞めた理由』(文藝春秋)で、スクープの発端からNHK退職までの一連の経緯を詳細に明かしている。国民の知る権利に奉仕することが求められる公共放送・NHKで、報道を巡り、政権への忖度が働いているとの当事者の実名証言は、今後波紋を広げそうだ。
「ローンの返済に充てた」。客から預かった定期積み立ての掛け金を着服するなどした銀行員が懲戒解雇です。
第三銀行によりますと、三重県内で勤務していた25歳の男性は、2017年10月から2018年9月までの間に、
13人の顧客から預かった定期積み立ての掛け金の一部を抜き取るなどして、あわせて132万6000円を着服していたということです。
今年9月、顧客から「満期の連絡を受けたが金額が合わない」と連絡を受け、調べていたところ着服が発覚しました。
第三銀行は今年10月に男性を懲戒解雇しました。
男性は「ローンやクレジットの返済にあてた」と話し着服した全額を返済したということです。
第三銀行は、「お客様に多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。再発防止・信頼回復に向け、全行をあげて取り組んでまいります」とコメントしています。
パイロットの安全意識への批判が高まっている。
乗務前の飲酒により、JALの副操縦士はロンドンのヒースロー空港で逮捕され、ANAウイングスの機長は沖縄県内の計5便に乗務できない事態となった。スカイマークでも機長から規定値を超えるアルコールが検出され遅延を起こした。
【関連画像】“危なそうな人”を作り出しているのは誰か?
「パイロットのアルコール問題は古くて新しい問題。10年くらい前から日本だけでなく、欧米でも度々トラブルが起きていたんです。ただ、各社ともスタンバイ要員がいたから、表立った問題にならなかっただけです」
こう話してくれたのは、現在海外のエアラインで乗務する50代のパイロットである。
彼が指摘する通り、2002年には、米国のウエスト航空のパイロットから大量のアルコールが検出され、その場で逮捕。09年には、ユナイテッド航空の副操縦士が酒に酔ったまま操縦しようとした疑いで逮捕。最近では、今年6月に英ブリティッシュ・エアウェイズのパイロットが酒気帯びのまま乗務に就こうとして禁固刑に、11月にはインドのエア・インディアのパイロットからアルコールが検出され3年間の免許停止処分となっている。
いったいなぜ、こんなにも問題が顕在化しているのか。単なる個人のモラルの問題なのか? あるいはパイロットの「2030年問題」が関係しているのか?(2030年問題は後ほど説明します)。
知人など数人の関係者に話が聞けたので、今回は「パイロット問題の裏にあるもの」というテーマであれこれ考えてみようと思う。
事件後のJAL社長会見への違和感
まずは11月29日(日本時間30日)に、禁固10カ月の実刑判決が言い渡され、懲戒解雇処分を受けたJAL副操縦士の事件のおさらいから(出所:JALの報告書)。
事件が起きたのは、10月28日のロンドン発羽田行きのJL44便。
副操縦士は、ホテルを出てから機内で身柄を拘束されるまで、機長ら同乗クルー計13人と行動を共にしていたが、アルコール臭に気づいたのは、バスを運転していた運転手のみだった(運転手の通報がきっかけで逮捕)。
副操縦士はバスの運転手のすぐ後ろに座り、その距離は約60センチ。機長は、さらにその1.8メートルほど後ろに座っていた。機長2人は、JALの聞き取りに対して「今になって思えば、(副操縦士は)自分たちから距離を置くようなそぶりがあった」と答えたという。
そして、乗務前の検査をすり抜けた機長らが機内に乗り込んだところに、バス運転手から通報を受けた保安官が副操縦士を呼び出しにきた。
ところが、副操縦士は、「アルコールは飲んでいない。マウスウォッシュによるものだ。うがいをさせてほしい」と大声で叫び、トイレに入る。その過程で保安官がアルコール臭を確認したため、警察官に連絡し身柄が拘束された。
副操縦士の飲酒は、「乗務開始12時間前から運航終了までの飲酒を禁じる」とした運航規程に沿っていたものの、結果的に英国の法令に定められた血中アルコール濃度が基準値の200mg/Lの9倍以上の1890mg/Lだった。
JL44便は、本来は機長2人と副操縦士1人の計3人で運航予定だったが、副操縦士の拘束を受けて2人だけで予定より1時間9分遅れで出発した。
一方、29日の裁判で副操縦士の担当弁護士は、
「仕事で家族と長期間離れる寂しさに加え、不規則な勤務時間などによって被告は不眠症に陥っていた。酒を飲んで解決しようとしてしまい、本人も(飲酒を)問題として認識していた」
と主張している。
この事件を知った時、私が真っ先に思い出したのが、1977年にJALの貨物便が離陸直後に起こした墜落事故だ。乗員と添乗員の5人全員が死亡し、アメリカ人機長の遺体から大量のアルコールが検出されたのだ。飛行機が炎上する映像は、当時私が住んでいた米国アラバマでも大々的に報じられ、子供ながらにショックで、めちゃくちゃ怖かったのを鮮明に記憶している。
事件後に会見を行ったJALの赤坂祐二社長は、「世代間のコミュニケーション手段として、(飲みニケーション)を是としているところはあった。公共交通機関を担う一員として、これについても考え直さなくてはならない」と言及していたけれど、今回の一件って、コミュニケーション手法だとか、その手の問題なのだろうか……。
航空会社任せの「性善説」ルール
そもそも日本では現在、航空法に基づき、乗務前8時間以内の飲酒を禁じているものの、アルコール検知器の使用は義務ではなく、検査基準なども会社任せ。それはある意味、「会社側のモラルを信頼した」運用になっていたと捉えることができる。
欧米でアルコール乗務が問題化していた10年ほど前、ANAでは国内のメインとなる空港にストローに息を吹き込むタイプの「精密型」アルコール検知器を設置し、乗員への啓蒙活動を行なった。その結果、基準値をオーバーする例は激減したため、現在設置されているのは羽田空港のみとなった。
JALは国内ではストロータイプ「精密型」の検知器を採用しているが、海外で使っているのは「簡易型」だ。さらに、朝日新聞が国内の航空会社25社を調査したところ、8社が検査を義務付けておらず、検査を実施している17社のうち12社は精度の低い「簡易型」を主に使用していることがわかっている(参照記事はこちら)。
しかも、私が関係者に確認したところ、
「精密型の検知器のある空港では、意外と、散発的にひっかかる人がいて。交代とかで対応できていたけど、今回は検査ではなく、バスの運転手の通報によるものだったので、たまたまクローズアップされた感がある」
とのこと。
乗客の人命を第一に考えるなら、会社側はこんなに大きな事件になる前に何らかの手立てを講じられたはずだ。
JALは報告書で副操縦士について、
・普段から飲酒量が多いという情報があった。
・体調面(腰痛)の問題も抱えており、出社後に乗務をキャンセルしたことがあった。
・過度なストレス環境下にあった可能性があり、組織が個人に何らかの対応を実施していれば、過度の飲酒を抑制できた可能性がある。
との要因分析を行っている。
とどのつまり、事件は起こるべくして起きたもので、「個人のモラル」の問題ではあるものの、「個人のモラルだけ」の問題ではない――と言えるのだ。
“危なそうな人”を作り出しているのは誰か?
あまり知られていないとは思うが、17年10月から日本でも、パイロットの「疲労リスク管理(FRM)」がスタートしている。
FRMは09年に起きた米国コルガン空港の航空機事故をきっかけに、事故遺族の運動により欧米でスタートした制度で、そこには「乗員、乗客、住民のすべての命を大切にしてほしい」というメッセージが込められている。
この事故は米国の短距離国内線で起きたもので、機体が炎上し、住宅地に墜落。乗客乗員49人が全員死亡したほか、墜落現場となった民家で住民1人が死亡、2人が負傷した。その原因は、「機長の過労」が引き金となった単純な操縦ミスだったのである。
機長・副操縦士は、低賃金(機長の年収は約6万ドル、副操縦士は同1.6万ドル)のためホテルに泊まらず、操縦士用の待合室で仮眠を繰り返していたそうだ。会社のソファで一夜を過ごすのは規則違反だったが、黙認されており、機長たちは事件当日もソファで睡眠を取っていたことがわかっている。
さらに、ボイスレコーダーや関係者への聞き取りから、操縦士が日常的に疲労に悩まされていたことが判明し、CVR(コックピットボイスレコーダー)には何度もあくびをするのが記録されていたという。
こうやって書いているだけで怖くなってしまうのだが、1993~2009年に起きた航空機事故で、パイロットの「疲労」に起因した事故は11件だったとの米国国家運輸安全委員会の報告もある。疲れ切ったパイロットの操縦ミスにより、310人もの人たちが犠牲になっているというのだ。
日本に先立ち、2010年以降、米国や欧州ではFRMが義務化・施行されている。
FRMを導入すると、事業者は運航乗務員の疲労を考慮するとともに、支障がある場合には乗務させない、運航乗務員は自らが疲労状態を管理する、疲労により乗務に支障がある場合には乗務しない――といったルールを規定に明記しなくてはならない。
航空会社が「人の命の重さ」をもっと真剣に考え、FRMをしっかりと実施していれば、未然に防げる事件だったのである。
「再発防止に向けた取り組みを徹底し、信頼回復に努めてまいります」などとお決まりの文句はもう聞き飽きた。“自分”の任務を忘れた“危なそうな人”を作り出しているのは、いったい誰なのかを今一度考えてほしい。
働いているのは人であり、その働く人に「人の命」がかかっていることを本気でわかってほしい。もっと言ってしまえば、それを考えない航空会社に飛行機など飛ばしてほしくない、というか、飛ばす資格はない、と思えてならないのである。
もちろん、疲労とアルコール問題との直接的な関係性は、単純に論じるべきものではないのかもしれない。しかしながら、疲れ切った体の癒しや、睡眠問題の解決のためにアルコールに頼ってしまうケースは現実に存在する。海外のエアラインの中には、アルコール検査で引っかかった乗務員には、会社の責任で専門治療を行う会社もあると聞いた。「ただし、それも2回までで、3回目は問答無用で解職」とのこと。
会社側がまず、然るべき責任を負って就業環境を整備し、従業員のケアを施す。従業員は、その環境下で自らの責務をしっかりと果す。そうした形で、安全のための仕組み作りに努めているのである。
パイロット不足の中で問題が深刻化する恐れ
言うまでもなく、世界中でパイロット不足は深刻である。
いわゆる「2030年問題」。最近では、「そんな悠長なことは言ってられん!」と、10年前倒しした「2020年問題」という呼び名も一部で使われ始めた。
国際民間航空機関(ICAO)によれば、2010年段階でのパイロット数は全世界で46万人だったにもかかわらず、30年にはおよそ2倍の98万人が必要になると予測されている。とりわけアジア太平洋地域は深刻で、パイロット需要は10年比で4.5 倍増と試算されている。LCCの台頭、経済発展に伴う航空需要の伸び、飛行機の小型化・多頻度化などがその背景だ。
思い起こせば、昨年11月にはAIRDO(エア・ドゥ)が、新千歳─羽田間と新千歳─仙台間で計34便(17往復)を運休。ピーチ・アビエーション、バニラエアが「パイロットが足りない」「パイロットが病欠」等の理由で、運航を取りやめていたこともわかった。欧州ではLCC最大手のライアンエアが11月から来年3月までで、計1万8000便を運休することを決めるなど、世界中の航空会社、とりわけLCCでパイロットが確保できていない現状が明るみに出た。
「まったく足りてないのに会社は次々と飛行機買うんだもん。ほんと、どうしろって言うんだろうね。パイロットの争奪戦のおかげで、LCCでも賃金はだいぶ上がっているけど……」
と話してくれた関係者もいた。
路線の拡大と生産性の向上を目的に、燃費効率のいい航空機を大量に購入し、便数を増やす。月間乗務時間を延長し、渡航先の宿泊数を削減。ミニマムクルー(最少乗員数)の基準も変え、インターバル(休憩)をなくし、夏休みを廃止するetc etc……。「国内線を飛ぶ、エアバスや737の乗務員は、便の多さ、長時間勤務、運航宿泊の多さが問題。一方、国際線が中心の787や777は、乗務時間の長さ、時差、徹夜勤務が問題です」(関係者談)。
16年に日本乗員組合と大原記念労働科学研究所が行なった調査では、次のような興味深い結果が得られている。
・機長の98.3%、副操縦士の97.1%が、「昼間と夜間・深夜の時間帯で、勤務による疲労が違う」と感じている。
・勤務時間帯による疲労の違いの原因としては、「乗務前に眠れず、疲労を持ち越したまま乗務せざるをえないこと」「夜間は乗務環境が日中と違うため緊張を強いられる」といった声が挙がっている。
・機長と副操縦士で別々に分析すると、副操縦士は「乗務前から疲労」している傾向が見られる。年齢が若く、身体的体力の回復も早い副操縦士が乗務前から疲労する理由としては、副操縦士は機長より年齢が若いため、家族がいる場合、子供の年齢が低いことが影響している可能性が考えられる。
・「深夜時刻帯のフライトがスケジュールに含まれている場合、事前に分かっていれば、昼間のフライトと同じように体調の管理ができるか」という問いに対しては、機長の82.9%、副操縦士の69.5%が「できない」と回答。フライトの多さ、時差調整、早朝・深夜勤務、年齢的なものなどが阻害要因として考えられると指摘されている。
10kg以上ある重い「パイロットケース」を持つ理由
個人的な話だし、何度かこのコラムでも書いたが、新人CAのときフライトエンジニアが10kg以上ある重い「パイロットケース」を持つ理由をこう話してくれたことがあった。
「重たいだろ? これがね、僕たちが人命を預かっているという、仕事の重さ、なんだ」
コックピットの計器の数値は絶対に暗記してはいけない。覚えた途端にミスは起こる。絶対に覚えないことが、ミスを防ぐ最大の方法。“人間ならでは”のミスを防ぐために、“自分”の仕事の重さを忘れないために、たくさんのマニュアルの入った大きな重たいカバンを持って歩くと教えてくれたのだ。
私がCAだった頃、海外のステイ先では乗務前日は20時までにホテルに帰り、パーサーに帰宅したことを伝えるように教育されていた。あの頃は、「学生でもないのに……」と思っていたけれど、アレも“自分の仕事の重さ“教育の一環だった。
「JAL純利益◯%増、ANA同●%増」といったカネのことより、「JAL乗員、客室乗務員、整備士の健康度◯%増、ANA同●%増」などと、働く人たちの心身充実度も併せて会社が評価される社会になってほしい……。
河合 薫
時々思うが、日本は学校のようだ。立派な大人に対して禁〇厳命はおかしいと思う。個々が判断し、問題を起こせば処分、懲戒処分又は懲戒免職で
良いと思う。大人なのだから個々が判断して飲むのか、飲まないのかを判断すればよい。勘違いしている上司が部下の立場、部下の意思、又は部下の
勤務予定を無視してお酒を飲ませれば上司を含めて処分すればよい。上司が無理に飲ませた事を周りが報告出来ないような会社であれば、禁酒厳命は仕方のない選択かもしれない。
JALだけでなく記憶が正しいとすれば福岡県が似たような事をしていたと思う。飲酒運転で事故を起こせば懲戒免職のリスクがある。公務員として
仕事を失うリスクを考えて飲酒した後の対応を考えるように説明すれば、子供ではないのだから、個人の選択の自由だと思う。
英国警察にJALの副操縦士が逮捕された事件は、JALの体質の問題が公になり、国交省の管理及び監督にまで疑問に思われる事になった。ALの副操縦士の逮捕がなければ、事実や現状の問題が注目される事はなかったので、他の問題が注目を浴びないように禁酒厳命となったと推測する。
大手でこのような状態なのだから、多くの日本人達が知らないいろいろな業界の問題はたくさん存在するのかもしれない。
「入社してから初めて、お酒なしの忘年会をやる羽目になりました……」
こうぼやくのは、副操縦士の“酩酊事件”で揺れる日本航空(JAL)の本社社員だ。会社から社員に「年内は禁酒」の通達メールが届いたという。くしくも本格的な忘年会シーズンを迎えたタイミングでの禁酒令発動。社員の間には、戸惑いが広がっている。
酩酊事件は、まず10月28日、ロンドン・ヒースロー空港で発生した。ロンドン-羽田便に乗務予定だった副操縦士から現地基準の約10倍のアルコールが検出。副操縦士は英国警察に逮捕された。11月29日、英アイズルワース刑事法院は、副操縦士に禁錮10カ月の実刑判決を言い渡した。これを受けてJALは30日、同副操縦士の懲戒解雇を発表。代表取締役社長は月額報酬20%減(3カ月)、取締役専務執行役員運航本部長も同10%を減額(同)とした。
さらに、11月28日、国内でJALグループの日本エアコミューターでもアルコール問題が発生。鹿児島-屋久島便に乗務予定だった機長から、基準値を超えるアルコールが検出され、便の遅延が発生した。
「ロンドンの事案の後にも全社員に注意喚起のメールが出されたのですが、鹿児島の事案を受け、対応強化として禁酒の通達メールが出されたんです」(前出のJAL社員)
JALグループの連結従業員数は約3万3千人(3月時点)。メールは「年内は、社内組織単位の飲酒を伴う懇親会・忘年会を自粛すること」「公の場でのJALグループ関連の会話自粛」「JALグループが分かる社章等の取り外し」を徹底するように、といった趣旨の内容だったという。
前出のJAL社員は飲み放題付きプランで都内の店を前々から予約していたが、急きょ飲み放題をキャンセルする羽目に。
「忘年会は例年、若手が盛り上げ役として余興をするのですが、今年はアルコールなしで会場はどこか白けたムード。見てるほうもやるほうも地獄でした。一生懸命練習をしてきた若手がかわいそう……」(同)
JAL広報に禁酒通達の真偽を確認した。
「社長から全グループ社員に対する事例周知と注意喚起をし、社員一人一人の意識改革を徹底する方針で動いていますが、その詳細については公開しておりません」(JAL広報部)
危機管理に詳しく、国内外で2千件を超えるリスクマネジメントを担当してきた白井邦芳さん(ACEコンサルティング)は、今回の禁酒通達について指摘する。
「緊急措置なのでしょうが、会社側に“ダメと言ったところで、またやるだろう”という考えがある。不祥事を防ぐために何かを全面禁止にすれば、結局は“隠れてやればいい”となります。コンプライアンスは、なぜそれがダメなのかを具体的に説明し理解させることが大事なのです。それを飛び越えた過剰なルール設定は、本末転倒です」
形式主義に陥らず、信頼の翼を取り戻してほしい。(本誌・松岡かすみ)
※週刊朝日 2018年12月21日号
「点検で補強の『控え壁』の有無、古さ、傾き、ひび割れなどを確認すれば危険性が判断できる、とした。」
お金を払って業者が点検を行っていたが問題や危険性は指摘されなかった。もし、危険性が判断できるのであればなぜ、業者が
問題や危険性を指摘しなかったのかが問題になる。また、ずさんな点検の可能性もある。
誰が悪いのか、誰が事実を言っているのか根拠のある資料や証拠がないとブロック塀の撤去の考え方は変わらないと思う。
ブロック塀の耐用年数は「おおよそ30年」が事実としても、基礎や鉄筋がどれぐらいはいっているかも重要だと思う。ただ、
資料や施工要領の図面などを作成し残すなど規則がなければ、簡単に危険性は判断できない。新しくブロック塀を作る場合には
規則を改正して要求する事は可能であるが、既存のブロック塀に関しては判断が難しいと思う。
結局、「塀内部の不良箇所を見つけるのは困難」と考えて撤去やブロック塀をさせる方針を決めても仕方がないと思う。
何でも単純に風評被害と言うのはおかしい。適切な施工を行えば安全と言うのであれば間違っていないと思うが、点検を行った
業者の例を丁寧に説明しないと多くの人達は納得しないと思う。業者が問題や危険性を見つける事は可能だったのかを全国建築コンクリートブロック工業会は科学的に検証するべきだと思う。そして点検に関して、経験、資格、資料や図面は必要なのか、点検コストや点検時間など説明に
入れるべきだと思う。
大阪北部地震で大阪府高槻市立寿栄(じゅえい)小学校のブロック塀が倒壊し、登校中の4年生の女児が死亡した事故で、全国建築コンクリートブロック工業会(東京)など業界4団体が10日、高槻市に陳情書を提出した。ブロック塀の危険性が強調され、風評被害があるとして、公共施設のブロックを全撤去するとした市の方針を撤回するよう求めた。
工業会は、ブロック塀の耐用年数は「おおよそ30年」とし、倒壊したブロック塀は築40年以上と古く、「通常なら建て替えないといけなかった」と指摘。点検で補強の「控え壁」の有無、古さ、傾き、ひび割れなどを確認すれば危険性が判断できる、とした。
その上で、「ブロック塀そのものが危険かのような一方的な声明を発表した」と同市の浜田剛史市長らを批判。「今後、風評被害がボディーブローのようにきいてくる」と主張した。工業会によると、全国で153事業所(従業員4人以上)がブロックを製造。6月の大阪北部地震後、出荷が減っているという。柳沢佳雄会長は「事故は手抜き工事が主な原因。ブロック塀全てが悪いとするのは問題のすり替え」と話した。
市の事故調査委員会は10月末、「設計・施工不良と腐食が倒壊の主因」と結論づけた。「塀内部の不良箇所を見つけるのは困難」とも指摘し、学校からブロックの構造物をすべて撤去し、今後設置しないのが望ましいとした。これを踏まえ、市は市内の小中学校からブロック塀をすべて撤去する方針を決めている。(室矢英樹)
順天堂大(東京都)は10日、医学部入試をめぐって設置した第三者委員会から「合理的な理由なく、女子や浪人回数の多い受験生を不利に扱っていた」と指摘されたと公表した。特に面接などが行われる2次試験では「女子はコミュニケーション能力が高いため、補正する必要がある」として点数を一律に下げていた。大学によるとこの結果、2017、18年春の入試では本来合格していた計165人が不合格となった。大学はこのうち、2次試験で不合格となった48人(うち女子47人)を追加合格にする方針という。
【写真】会見する順天堂大の新井一学長と代田浩之医学部長(右端)=2018年12月10日午後5時22分、東京都文京区、西畑志朗撮影
第三者委の報告書によると、女子を不利に扱っていた理由を順大の教職員らに聞き取り調査をしたところ、(1)女子が男子よりも精神的な成熟が早く、受験時はコミュニケーション能力も高い傾向にあるが、入学後はその差が解消されるため補正を行う必要があった(2)医学部1年生全員が入る千葉県印西市のキャンパスの女子寮の収容人数が少ない――と説明があったという。
第三者委は、(1)について「性別より受験生個人の資質や特性を重視すべきである」と指摘し、「合理性がない」と判断。(2)についても、女子寮の収容定員が大幅に増えても医学部の女子学生が増えておらず、合格者選考会議などで収容人数が特に審議されていなかったとして、「制限する合理的な理由はない」と結論づけた。(増谷文生)
疑惑のレベルで問題が公にならないように強い口裏合わせがある医学部不適切入試のような問題は日本にたくさん存在すると思う。
証拠や証言者が出てこないから白黒判断できない。例え、事実だとしても証明されるまでは事実とは認められない。
多くの受験生や浪人生が起こっているが、「文科省汚職事件」で東京医大前理事長の臼井正彦被告(77歳)を贈賄側、佐野、谷口の両被告を収賄側とする裏口入学事件が公になったから、長年の秘密を隠せなくなっただけのこと。
普通の裏口入学事件ではここまでメスは入らなかったし、逮捕者が出てもここまで影響を与える事はなかったと思う。例え、医学部に入って医者になったとしてもある問題に直面するまで、親や親せきが医者でない限り、医者の問題で公になっていない問題を知る事はないであろう。
問題に直面した時、多額の学費と長年の努力を台無しにしてまで問題を表の世界に出そうとするのか?問題を表に出そうとする事が成功するかはわからないし、握りつぶされるかもしれない。見て見ぬふりをすれば、見逃していけば、他の人達と似たような平穏な生活が継続できる可能性は高い。
医師の世界だけでなく、平穏や安定した生活が継続するために見て見ぬふりをしている人達は多くの人達が思う以上にたぶん多いと思う。
単純に医学部の問題と捉えず、個々が少しの努力でも良いから良い方向に向かうように実行すれば少しの努力X何万人で多少は良くなると思う。
「受験する前から20点も差がついていたなんて…」。福岡県内の薬学部に通う女子大学生は絶句した。
【一覧】現役生に加点も…発覚した医学部入試の主な問題
浪人生活を重ねたいわゆる「多浪生」。2浪以降、福岡大医学部を2回受験した。「絶対に医師になりたかった。朝から晩まで勉強詰めだった」。1点が合否を分ける-。ミスがないよう、少しでも得点できるよう気を張っていた。それだけに「受験生の努力を踏みにじる行為だ」と憤る。
福大は今回の措置を「不正ではない」と繰り返した。これには「受験生から見れば不正そのもの。募集要項に書けないようなことはやめて透明性の高い入試にしてほしい」と注文した。
福岡市内の男子予備校生(19)は1浪だった昨年、2次試験で不合格に。「学科試験で10点上でも、不当な調査書評価でひっくり返るなんて不公平」と憤る。
一方、福大医学部に通う学生の受け止めは「どの大学でもやっているでしょ。ようやく表に出たのか、という程度で驚きはありません」と語る2年男子(22)と同様の言葉が相次いだ。2浪で一般入試を合格した同学生。「浪人冷遇を前提で突破する力を付けるだけ」と浪人時を振り返ったが、もしも自分が不合格だったらどう思うかと質問すると「怒りで許せないと思います」。
卒業生で福大病院に勤める30代医師は「医学界の常識は世間の非常識。これを機に正常化してくれれば」と述べた。
日産に乗りたい人達は日産の車に乗れば良い。個々が自己責任で選べばよい事。
日本製品は中国製品よりは比べ物にならないほど良いが、安さに負けて中国製品だと知っていて買う事がある。
思った以上にひどい製品を買った時はお金をもう少し払って日本製品を買えばよかったと思う事は何度も経験した。
ただ、日本の会社が中国で生産し販売しているから信頼していいのかと言えば、必ずしもそうでない。
予算、期待度、過去の経験などいろいろなコンビネーションで購入判断を決める。日産の車に関しても、個々の基準が違うから
個々の価値観次第だと思う。
日産自動車で、昨秋以降4度目となる検査関連の不正が発覚した。今後は西川広人社長ら経営陣の責任問題が焦点となりそうだ。同社は7日夕に記者会見を開いたが、西川社長は今年7月と9月に続いて出席しなかった。経営トップが自ら説明責任を果たそうとする姿勢は見られず、企業統治は深刻な不全状態に陥っている。
西川社長は昨年10月と11月の会見には出席した。「信頼を回復して事業を正常化させることが使命だ」などと述べ、報酬の一部を自主返納する方針を示した。今年6月の株主総会では「法令順守の体制を強化していくのが私の責務だ」と強調した。
一方、今年7月と9月は、生産部門トップの山内康裕チーフ・コンペティティブ・オフィサー(CCO)が会見。7日の会見には国内生産と品質保証の各担当役員が出席し、説明者が「格落ち」した。本田聖二常務執行役員は、西川社長が出席しない理由を問われ、「私が日本の生産事業の責任者だ」などと説明した。
今回の不正が見つかったのは、SUBARU(スバル)でブレーキ検査の不適切行為が発覚したのがきっかけ。同社の件がなければ、表面化しなかった可能性があり、日産の自浄作用の乏しさは否めない。本田氏は「うみは出し切ったと思っている」と主張したが、9月にも山内氏が不正の終結を宣言したばかりで、信頼性には疑問符が付く。
ケミカルタンカーの貨物の対応と似ている。貨物のデータシートに従い、対応手順を掲示しておく。
救助に向かう時、呼吸器や対化学薬品スースなどを着用して救助に向かう。可燃、又は、爆発の危険性や
毒性の貨物であれば、計測機器を携帯する。
現実的には、いろいろな教育や知識があれば小さな製紙工場に勤めていないので仕方のないことかもしれない。
会社の体質に問題があるかもしれないが、基本的にはコストの問題であろう。お金にゆとりがあれば検知装置や従業員を
教育するゆとりはあったと思う。事故後には「毒ガスを検知する機器を設置するなど安全対策」が取れれているようであるが
毒ガス検知機器は定期的にメンテナンスが必要で安くはないと思う。何か所、検知機器を設置しているのか知らないが、
数が多くなればメンテナンスのコストはアップする。
今年6月、石川県白山市の製紙工場で作業員3人が死亡した事故で、県警は安全管理を怠ったとして安全管理の責任者1人を書類送検しました。
この事故は今年6月、石川県白山市相川新町の「中川製紙」で男性作業員3人が再生紙の原料をためるタンクの中で相次いで倒れ死亡したものです。
この事故が起きる直前、タンクの内部では原料が詰まるトラブルが起きていました。異変に気付いた作業員1人がタンクの中に入って倒れ、その後、助けに入った他の2人も相次いで倒れました。
タンク内には高濃度の硫化水素が発生していて、3人の死因は硫化水素を吸ったことによる急性中毒でした。
労働安全衛生法では、硫化水素などの有毒ガスが発生する現場には資格を持つ責任者を配置しなければなりませんが、事故当時、中川製紙には不在でした。
また硫化水素が発生する場所には国の規制で毒ガスの吸引を防ぐ呼吸器の設置などが義務付けられていますが、中川製紙には設置されていませんでした。
県警はこうした状況や関係者の聴取などから、安全管理義務を怠ったとして、安全管理の責任者で技術顧問の男性1人を業務上過失致死の疑いで書類送検しました。
また金沢労働基準監督署も労働安全衛生法違反の疑いで会社と同じ技術顧問の男性1人を書類送検しました。
中川製紙では事故後工場内に毒ガスを検知する機器を設置するなど安全対策を進め、現在は操業を再開しています。
業者が示し合わせた検査記録を改ざんしたのか、それとも、検査記録を改ざんしている業者が処分されてないので、同じように真似て
記録改ざんしたのか、調べた方が良いと思う。
結果次第では、日本で行われている検査の現状を推測するのに役に立つと思う。
関西電気保安協会など関西で電気設備の定期点検をする4事業者が7日、大阪府や兵庫県などの集合住宅計1862棟で、調査記録を改ざんする電気事業法違反があったと発表した。エレベーターや水道ポンプの電気設備の調査数値が基準を上回り、軽微な漏電の疑いがある場合などに基準内になるように書き換えていたという。
改ざんがあったのは同協会で707棟、関電サービスで711棟、きんでんサービスで378棟、兵庫県電気工事工業組合で66棟。計118人の調査員が不正に関わった。基準値を超えると精密点検が必要で、エレベーターなどを止める必要がある。同協会の川辺辰也理事長は「お客様にご苦労をかけると考えてしまった。非常に反省し、再発防止を徹底したい」と陳謝した。
住宅の電気設備の点検は電気事業法上の義務で、関西電力が9業者に委託している。今年10月に中部電力管内で同様の事案があり、経済産業省が調査を求めていたなかで発覚した。各事業者は漏電による火災の危険性はないとしているが、再点検して通知するという。(西尾邦明)
いろいろな情報が事実なら、後は検察の能力次第であろう。
日産自動車で、新車の出荷前に実施する完成検査で新たな不正が見つかったことが6日、分かった。国土交通省と協議しており、対象車種のリコール(回収・無償修理)も検討している。同社は詳細について明らかにしていない。
今年9月、日産は検査不正の再発防止策を盛り込んだ報告書を同省に提出。その際に同社幹部は「うみは出し切った」と述べていた。
日産は昨年9月、国内工場で実施する完成検査を無資格の従業員が実施していたと公表した。その後も不正を継続していたことが判明し、100万台以上の大規模リコールに発展した。今年7月には完成検査の中で実施する燃費・排ガスに関する抜き取り検査でも不正が見つかった。
英国の空港で乗務前に基準値を超えるアルコールが検出されたとして、日本航空の男性副操縦士に有罪判決で日本でずさんに扱われていた
アルコール検査の現状と言うパンドラの箱が開かれてしまったと言う事だろう。
「国内の航空各社でパイロットの飲酒による不祥事が相次いでいる問題で、日本航空が昨年8月に導入した新型のアルコール感知器の検査記録約22万件のうち、約3800件のデータが残っていないことが日航への取材で明らかになった。日航は「意図的に検査をすり抜けた事例は確認されていない」としているが、国土交通省はずさんな検査実態について調査を進めており、行政処分も検討している。・・・
感知器はオンライン化され、測定データは記録される仕組みだったが、立ち入り検査で一部データの欠落が判明したという。
データが欠落していたことについて、日航がパイロットに聞き取りをしたところ、社員番号の誤入力や、システムの不具合で検査用アプリが起動しなかったことが主な原因だったことが判明した。」
個人的には言い訳だと思う。数件から数十件であれば間違いとか、個人の問題だと思うが、「約3800件のデータが残っていない」事が記録として残っていない、又は、問題として報告されていない事はおかしい。オンライン化されていなくても、記録簿を作成して記載し、システムの不具合であれば、システムの不具合の時だけ記録簿に記載するなどを対応し、システム不具合の発生又はシステム不具合の修正を報告すれば良いだけの事である。
JALに採用されるような人達がそのような事を考えられないとは思えない。コネとか、能力的には問題ないが応用が出来ない数パーセントの問題社員が
存在する可能性はあるが、それでもこのようなずさんな状態にならない。
問題は大手のJALでこの有り様。そして国土交通省がこの問題を見逃していたのか、見ようとしなかったのか、事実は知らないが、英国の空港で乗務前に基準値を超えるアルコールが検出されたとして、日本航空の男性副操縦士に有罪判決で形だけかも知らないが対応せざるを得ない状態になったと思う。
日本は基本的に横並びの構造なので、JALでこの体たらくであれば他の航空会社も同様か、それ以下である可能性は高いと思う。
アルコール検査が厳しくなってもお酒好きのパイロット達の生活が変わるのと、ホテルやホテル周辺でのアルコール消費に影響が出るだけで、
それ以外の人達には関係ないか、事故の確率が低下するので良い事ばかりである。
そう言う意味では、なぜ国土交通省がアルコール検査の問題を把握しなかったのか、又は、航空法の改正を考えなかったのかは理解できない。想像以上にパイロット達がホテルやホテル周辺でのアルコール消費に使うお金の額が大きく、政治家達に改正しない事を働き掛けてきたのだろうか?
「日航は、アルコール濃度の社内基準を航空法に基づく運航規定に明記し、基準値を上回った場合、停職以上の懲戒処分とする再発防止策を示している。」
日航だけの問題ではないと思うので国土交通省は航空法を改正して曖昧でないようにするべきだ。
国内の航空各社でパイロットの飲酒による不祥事が相次いでいる問題で、日本航空が昨年8月に導入した新型のアルコール感知器の検査記録約22万件のうち、約3800件のデータが残っていないことが日航への取材で明らかになった。日航は「意図的に検査をすり抜けた事例は確認されていない」としているが、国土交通省はずさんな検査実態について調査を進めており、行政処分も検討している。
日航によると、パイロットは乗務前、感知器に息を吹き込み、呼気中のアルコール濃度が社内基準(1リットル中0・1ミリグラム)未満であることを確認する。ロンドンで10月下旬、酒気帯び状態で羽田便に乗務しようとしたとして、副操縦士(42)=懲戒解雇=が逮捕されたことを受け、国交省は11月27日から3日間、羽田空港の日航事務所などを立ち入り検査。感知器はオンライン化され、測定データは記録される仕組みだったが、立ち入り検査で一部データの欠落が判明したという。
データが欠落していたことについて、日航がパイロットに聞き取りをしたところ、社員番号の誤入力や、システムの不具合で検査用アプリが起動しなかったことが主な原因だったことが判明した。3800件には、新型感知器の導入当初、関西空港や伊丹空港でオンライン化の整備が間に合わず、記録が残らなかったケースも含まれている。
また、乗務前の打ち合わせが忙しく、アルコール検査を実施していなかったケースもあったという。日航は「詳しい件数は未確認だが、ごく少数」と説明している。
副操縦士は逮捕当日、アルコール検査を意図的にすり抜けていたが、航空機に移動するバスの中で、運転手が酒臭いことに気付いて発覚した。副操縦士は11月末、英国の刑事法院で禁錮10月の実刑判決を言い渡された。
日航は、アルコール濃度の社内基準を航空法に基づく運航規定に明記し、基準値を上回った場合、停職以上の懲戒処分とする再発防止策を示している。【花牟礼紀仁】
九州工業大(北九州市戸畑区)は5日、鉄製の棒(長さ約50~60センチ)で男子学生(20歳代)を殴るなどしたとして、工学研究院の男性助教(30歳代)を同日付で懲戒解雇処分にしたと発表した。助教は「実験に失敗されて腹が立った」と話しているという。
同大によると、助教は6月頃に学生の右腕を、8月上旬には頭を鉄棒で殴り、2針縫うけがを負わせた。病院では「頭にものが落ちてきた」と医師に説明するよう要求。学生の母親からの連絡で発覚した。
尾家祐二学長は記者会見で「教職員にあるまじき行為で再発防止に取り組む」と陳謝した。
いろいろな情報が事実なら、後は検察の能力次第であろう。
別文書には西川社長の署名も
日産自動車の会長だったカルロス・ゴーン容疑者(64)が年約10億円の報酬を退任後の支払いにして隠したとされる事件で、ゴーン前会長と日産側が交わした合意に関する文書に、ゴーン前会長と秘書室幹部の署名があったことが、関係者への取材でわかった。この秘書室幹部が東京地検特捜部と司法取引し、捜査に協力したとみられる。
関係者によると、合意に関する文書には、ゴーン前会長が日産に入った1999年に結んだ報酬契約に基づくとして、年間報酬は総額約20億円、実際に受け取った額は約10億円、差額は約10億円といった具合に記載されていた。2009、10年度の報酬は11年の作成日が入った文書に、11、12年度の報酬は13年作成の文書に2年分ずつまとめて記載され、ゴーン前会長と秘書室幹部の署名があったという。
また特捜部は、差額は退任後にコンサルタント料などの別名目で支払うことにし、側近の前代表取締役グレッグ・ケリー容疑者(62)がその計画を主導していたとみている。関係者によると、特捜部は支払い名目に関する書面も入手。この書面には、ケリー前代表取締役と西川(さいかわ)広人社長兼CEO(最高経営責任者)の署名があったという。
一方、ケリー前代表取締役は支…
いろいろな情報が事実なら、後は検察の能力次第であろう。
報酬の過少記載事件で逮捕された日産自動車の元会長、カルロス・ゴーン容疑者(64)が、実際の報酬額などの一覧表に自ら修正を加えるなどし、主体的に関わっていた疑いがあることがわかった。
ゴーン容疑者が、有価証券報告書に記載しなかった報酬は、8年間でおよそ90億円にのぼり、これらを退任後に受け取るための覚書を日産側と毎年交わしていたとみられている。
この覚書のほかにも、毎年の実際の報酬額と後払いの累積額などが書かれた一覧表が作成され、ゴーン容疑者が自ら手書きで修正を入れた箇所があることがわかった。
東京地検特捜部は、ゴーン容疑者が報酬額の決定に主体的に関わり、虚偽記載を主導していたとみて調べている。
「相談した外部の弁護士や会計士の事務所名も具体的に挙げているという。」
違法でなければ問題ないが、違法であれば弁護士や会計士はどのようなコメントをするのだろうか?
日産自動車の会長だったカルロス・ゴーン容疑者(64)が巨額の役員報酬を過少記載したとして逮捕された事件で、側近の前代表取締役グレッグ・ケリー容疑者(62)が、退任後の支払いにして隠したとされる分について、「前会長の秘書室が開示義務はないと外部に確認した」と供述していることがわかった。相談した外部の弁護士や会計士の事務所名も具体的に挙げているという。
特捜部は、2人を金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで逮捕。2010~17年度の8年間の年間報酬は各約20億円だったが、各約10億円は退任後の支払いにして計約90億円を隠蔽(いんぺい)し、退任後はコンサルタント料などの別名目に紛れ込ませて支出する計画だったとみている。
一方、関係者によると、ケリー前代表取締役は、前会長の退任後の処遇をめぐる計画は、役員報酬とは無関係だと主張。前会長の秘書室に指示して会計事務所などに法的な問題点を問い合わせたとし、「取締役として各年度に行った職務への報酬ではなく、開示義務はないと確認した」「日産として確認したということだ」と強調しているという。特捜部が有力な証拠とみる関連書類についても、「前会長に見せる時は『退任後の支払いを確約するものではない』と何度も言っていた」と説明しているという。
ゴーン前会長も「弁護士でもあるケリー前代表取締役から『合法的に開示しないでいい』と言われた」と述べ、違法性の認識を否定している。
建設業や造船業はヤクザと関係がある会社があるので民間に監視をさせる事は現実的に難しいと思う。問題があっても報復や嫌がらせの
リスクがあるのでまともに出来ないであろう。あと、民間だと仕事欲しさに甘い監視を売りにする会社は出てくると思う。
新しい部署を作って専門の公務員を維持すれば、コストが発生する。このコストは外国人労働者を雇う会社に負担させるべきだと思う。
入管難民法などの改正案による外国人労働者の受け入れ拡大を巡り、国土交通省は5日、建設業界で賃金未払いや過重労働といった問題がないかどうか監視する機関を創設する方針を固めた。適切な労働環境を確保し、失踪の防止にもつなげる狙い。造船業でも創設を検討し、政府が改正法の今国会成立を前提に来年4月を見込む法施行時の発足を検討する。
建設業では現在も、時間外や休日手当の未払い、家賃や食費の過徴収といった事例が頻発。長時間労働や休日の未取得という、過酷な労働環境も問題になっている。
スカイマークの男性機長から乗務前にアルコールの陽性反応が確認され、旅客便に遅れが出た問題で、国土交通省は4日、航空法に基づき、同社(東京都大田区)の運航管理施設などへ立ち入り検査に入った。
パイロットの飲酒に伴う旅客便の遅延発生をめぐっては、日本航空や全日本空輸グループも立ち入り検査しており、国交省は現場確認を踏まえて、各社に対する行政処分などを検討する。
スカイマークによると、機長からは11月14日、羽田空港でアルコールの陽性反応が出た。機長は同13日に自宅でビールを3.5リットル飲んでおり、機器の扱いにも不慣れで詳細な検査ができなかったため、乗務を交代した。この影響で羽田発新千歳行きの旅客便の出発が20分余り遅れた。
また、国交省は4日、国内航空25社の社長らを集め、飲酒問題の再発防止に向けた対策会議を5日に開くと発表した。
スカイマークの米国籍男性機長(49)からアルコールの陽性反応が確認され、旅客便に遅れが出た問題で、同社は22日、調査結果や再発防止策をまとめた報告書を国土交通省に提出した。遅れの原因として、同社のアルコール検査に関する管理が不徹底だったことが明らかになった。
機長からアルコール反応=前日大量飲酒、乗務交代-スカイマーク
スカイマークによると、機長は今月13日、自宅で缶ビール計3.5リットルを飲み、14日の羽田発新千歳行きの旅客便に乗務する前の簡易検査でアルコール陽性反応が確認された。
同社は、乗務できないアルコール濃度の規定値を呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上としている。陽性反応が確認されれば、本来は詳細な再検査が必要だが、検知器の取扱説明書が見つからず、機長は乗務を交代。旅客便は23分遅れて出発した。
大手の下で下請けとして働くメリットとデメリットがあると思う。同じデメリットとメリットでも下請け企業が違えば影響や受け取り方は違う。
営業能力や人脈でも違ってくると思う。なぜ、癒着や賄賂が存在するのか?効果的である、又は、効果的かは不明であるが効果があると癒着や
賄賂をオファーする側が効果的だと考え、相手が受け入れるからだと思う。
権限を持っている担当が、会社の利益になるのか、大した影響はないのかに関わらず、自己のメリットのために癒着や賄賂を受け入れれば成立すると
考える。経理が着服や横領する理由と似ていると思う。自己のためにやるのである。会社に対して損害を与えると考えていれば出来ない事である。
話を元に戻すが、大手の下請となる選択以外に規模は小さいがその他の顧客を相手にする選択がある。この選択もメリットとデメリットがあり、
個々の企業や経営者の能力や判断力でメリットとデメリットの対する評価が違ってくるであろう。
財務や時間にゆとりがあるのなら時間をかけて正しいと思う方向へ行けばよい。やってみなければ頭で考えているように行くのか、行かないのか
わからない事がある。運よく、苦しみながら試行錯誤の中で道が開ける事がある。失敗して我慢する事を決心する経営者や会社はあると思う。
ダメな上司や会社に見切りをつけるのが正しい場合もあるし、我慢する方が正しい場合がある。ただ、決断し、結果がでなければ最終的に
判断が正しいのかわからないことがある。単純に運が良い悪いが結果に影響する事があるので、結果だけを重要視すれば結果次第。
中小や零細企業の廃業が注目を浴びているが、下記のような現状は原因の一つとして影響はしていると思う。
大手企業による「買いたたき」「不当な労務提供の要求」といった“下請けいじめ”は、かつてないほど蔓延している。公正取引委員会による下請法違反の「指導」件数は近年増加の一途をたどり、2017年度は6752件を数えて過去最悪になった。日本の基幹産業である自動車業界も例外ではない。下請けいじめの実態、いじめられる側の声を聞くため、各地で訴えに耳を傾けた。(文・写真:フリー記者 本間誠也/Yahoo!ニュース 特集編集部)
「納入価格を一方的に2〜3割カットされました」
「価格交渉をすることなく、部品の単価をなぜメーカーが一方的に決めるんですか? おかしいでしょう? 下請けは今、どこも我慢比べ。どこが最初に音を上げるか、会社をたたむか……。そんな状況に置かれているんですよ」
憮然とした表情で、「社長」はそう切り出した。
埼玉、群馬、栃木の3県にまたがる「関東内陸工業地域」は、自動車産業の集積地だ。各メーカーの大工場が点在し、特に群馬県内には二次、三次下請けまで含めると、1000社を超える自動車関連の下請け企業がひしめく。
「社長」の企業もその一つだ。同じエリアに大規模工場を持つ自動車メーカーの二次下請けで、自動車部品を製造している。
社長によると、自社だけでなく、このメーカーの仕事を担う下請けの中小企業はぎりぎりの経営状態に陥っている。全ては、メーカー側が打ち出した「新ガイドライン」が原因だという。下請けとの取引条件などを示したもので、2年前、傘下の中小企業向けに出された。
社長が続ける。
「その新ガイドラインに沿って、部品原価の一律値下げが、二次下請けにも降ってきたんです。一次下請けは、うちらに対して『メーカー側の意向だから』と。有無を言わさず、2~3割カットを強制されました。それ以前は、社員にボーナスも出せたけど、今は預金を吐き出してる状態です」
この取材に際し、社長は「絶対に匿名で」と条件を付けた。「写真も絶対にダメだ」と。取材に応じたことが判明すれば、メーカー側からどんな仕打ちを受けるか分からないからだ、と。
事務所から見える工場では、社員が忙しく行き交っている。
「例えば、プレス機で製造した部品は、それに関わる人員や生産性の良し悪しによって加工費も変わってきます。ところが、部品の大小もコストも生産性も関係なく、設備の加工能力だけで部品の単価を一方的に決められてしまった。『世耕プラン』には期待したけど、メーカー側は守ろうとしていない」
下請法は、下請け企業と取引する「親事業者」に対し、発注後の代金減額、下請けに責任のない返品、買いたたき、特定の製品・サービスの購入や利用強制などを禁じている。「世耕プラン」とは、下請法の運用を強化するため、2016年秋に世耕弘成経済産業相が打ち出した施策だ。最も重要視した「価格決定の適正化」では、親事業者が「一律○%の原価下げ」といった要請を出さないよう徹底する、としていた。
実際はどうだったのか。この社長は言う。
「(親事業者であるメーカーは)価格交渉を許さないんだから、明らかに『世耕プラン』に反しています。3割もカットされたら原価割れです。同業者の中には、自動車業界に見切りをつける経営者も出始めているんです」
1人1時間で1000個のナット溶接「不可能だよ」
群馬県内で、別の二次下請け企業にも足を運んだ。この部品加工会社の経営者も、同じメーカーの「新ガイドライン」に弱りきっていた。
「例えば、ナットの溶接では、1本当たり4円だった単価が3円になったんだ。たまらないよ。ナット溶接の場合、従業員には1時間当たり3000円分働いてもらわないと経営は成り立たない。4円なら(1時間の溶接数は)750個が採算ライン。新ガイドラインでは、それが約1000個になる。1人が1時間に1000個。そんな作業は不可能だから、結局、赤字です」
この経営者もマイナスの影響を恐れての匿名取材である。取材が進むうち、「ほかにも苦しんでいることがある」という話になった。親事業者を経て一次下請けから押し付けられる「金型」の保管や管理だ。
金型とは、金属製や樹脂製の部品をプレス加工によって製造するための型をいう。一般に下請け業者は、親事業者から金型を借りて部品をつくる。製品の量産期が終わったり、モデルチェンジしたりすると、その金型は不要になる。ところが、不要になった金型を親事業者はなかなか引き取らない。廃棄もさせない。結局、立場の弱い下請け業者は何年もの間、無償で保管せざるを得なくなってしまう。
親事業者と下請けの悪しき慣習。これは日本のあちこちに残っている。この経営者も取材で怒りをぶちまけた。
「うちが保管している金型の中で最も古いのは30年前ですよ。あまりに量が多いから、金型保管のために月30万円ほどで土地を借りてます。大型部品を製造している知り合いの下請け業者の場合は、金型も大きいから、結構な大きさの倉庫を借りている。かなりの出費でしょう」
使用しないことが明白な、古い金型。メーカーや一次下請けに対し、引き取りや廃棄を要請できないのか。
「一次下請けに『廃棄してくれ』と頼んでも、その上にいるメーカーは『もしものために』と言って突っぱねる。メーカーにそう言われたら、こちらは先々の取引のことを考えて受け入れるしかありません」
下請け2社のこうした訴えについて、メーカーに直接取材したところ、部品単価の一律カットについては「より競争力のある原価構造の実現を目指したもの」「お取引先さまの納得、合意がなければスタートしない仕組み」と言い、金型保管については「政府、業界の諸制度にのっとり、お取引先さまと合意、協力の上で金型管理の合理化を進めています」との回答があった。
「支払いの遅れ」「買いたたき」「減額」……
“下請けいじめ”の広がりは、数字が物語っている。
公取委によると、2013年度に4949件だった下請法違反の「指導」は、年ごとにワーストを更新し続けてきた。17年度は前年度比450件増の6752件。その内訳は「支払いの遅れ」が54%で最も多く、「買いたたき」の20%、「減額」の11%と続く。
「指導」より厳しい「勧告」を受けると、企業名が公表される。13年度は10件で、14年度以降は7件、4件、11件と続く。そして、17年度の9件は全て、親事業者による支払い代金の不当な「減額」だった。「山崎製パン」「伊藤園」「セブンーイレブン・ジャパン」「タカタ」「DXアンテナ」などの社名が公表されている。
ここ数年、大手メーカーは「アベノミクス」による円安効果などで好業績を続けてきた。その陰で拡大するばかりの“下請けいじめ”。この実態を政府はどう見ているのだろうか。
東京・霞が関の中小企業庁を訪ねると、取引課の松山大貴・課長補佐は「下請けいじめは以前から潜在的には蔓延していたのだと思います」と切り出した。下請け業者の声を直接吸い上げようという施策を強く打ち出した結果、「表に出てこなかった問題が顕在化してきた」と話す。
「下請Gメン」が直接出向く
中小企業庁と各地の経済産業局は昨年4月、80人体制の専門チーム「下請Gメン」を全国で立ち上げている。この4月からは120人超に増員。年間約4000社もの下請け業者に足を運び、親事業者との取引の実態について耳を傾けているという。
自動車業界の“下請けいじめ”についても、同庁は改善を促しているという。
今年1~3月に実施した調査によると、「不合理な買いたたきや減額などが改善された」という回答は38%、「今まで保管していた金型を廃棄または返還することができた」は11%。松山課長補佐は「改善は進みつつある」と話す。
では、冒頭で紹介した群馬県の二次下請け2社については、中小企業庁はどう対応したのだろうか。
「下請Gメン」の中心メンバーの安田正一・課長補佐は「個別事例への回答は控えます」と話した。その上で、こう説明した。下請Gメンなどの活動によって、“下請けいじめ”の具体的な実例を個別に把握しており、事例によっては業界団体などに是正を促している、と。「だから、(下請けいじめ解消に向けた)親事業者や各業界団体の対応は従来とは異なっているはずです」
不要になった「金型」の保管も押し付け
下請け事情をさらに知るため、群馬県とは別の工業団地を訪ねた。首都圏のJR駅からバスで数十分。広大なエリアには、100社近い企業が工場や配送センターを構えている。
取材に応じてくれた自動車部品の製造会社は、複数のトラックメーカーにミッション部品などを供給している。社屋1階の事務室。取材に応じた社長は、こう口を開いた。
「アベノミクスの恩恵? うちには無関係です。メーカー側が人件費の安い海外から部品を調達したり、海外で現地生産したりする状況に変わりはないですから。この5年間で業績は上向いていません」
同社は昨年秋、一次下請けとして仕事をもらっているメーカー側から注文を大幅に減らされたという。メーカー側が部品の調達先を海外に切り替えたからだ。
「メーカーに言わせると、海外生産の部品は国内より3割ほど安いそうです。運送費を上乗せしても国内生産より安い、と。純粋な価格競争になったら負けてしまいます」
この会社は別のメーカーとも取引がある。そちらの対応も厳しい。
「口を開けば、コストダウン、コストダウン……。で、何の根拠もなく、協議もなく、『何パーセント下げてください』の繰り返し。口では共存共栄を言うけれど、技術部門のメーカー社員がうちに来て、価格の協議をしたことは過去に1度しかない。円安で材料や電気、ガス料金が上がっているのに、それについて考慮もしてくれません」
取材した下請け企業の中には「ここ5年間の売り上げは上昇カーブ。二次下請けで入っているメーカーの販売台数が伸びているからです」と話す経営者もいた。東京近郊の自動車関連の金属加工会社もその一つ。同社の加工技術は、国内外に競合他社が少なく、その影響も大きいという。
それでも、親事業者への要望は少なくない。
「第一は、量産が終了した後の金型保管の押し付けです」と言う。実際、この金属加工会社の敷地では、金型を積み上げた小さな山が何カ所もできていた。積み上げられた金型の高さは2メートルほど。面積は優に200平方メートルを超える。
「本来なら駐車場、駐輪場に使いたいけど……。土地や倉庫を借りてないだけ、ましなほうです。5年も10年も下請けに預けっぱなしで、1円も払わない、とか。そういう慣習はそろそろ終わりにしないと。『声を上げない業者が協力的な業者』という評価はおかしいと思う」
専門家「下請けは自ら動きなさい」
立場の弱い下請け企業は、大企業のメーカーにどう対応すればいいのだろうか。中小企業問題に詳しい神奈川大学法学部の細田孝一教授は言う。
「部材の単価について一律ダウンの要請などを受けた際は、ただ従うのではなく、コストの根拠をきちんと示させたうえで交渉してほしい。親事業者が『けんもほろろ』だったとしても、今は中小企業庁などによるフォローアップ体制もある。そうした下請けの声は、首相官邸の会議にフィードバックされるので、業界全体で取り組みの改善に向かうことになるでしょう」
――隠れた負担とされる金型の保管・管理については?
「何年前から預かっているのかを全てチェックし、メーカー側に要不要の回答をもらってほしい。そして不要なものは廃棄し、必要だと確認されたものに限って『保管費用の負担』を交渉すべきです。下請け側からも行動を起こさないと。受け身のままでは、状況は改善しません」
下請法や独占禁止法に詳しい本間由也弁護士(第二東京弁護士会)は「親事業者とは話し合いすらできないと思っている中小企業主が多い」と指摘する。下請け業者には、親事業者から契約を切られて初めて弁護士に相談し、闘おうとする人がいるという。でも、その前にアクションを起こすべき、と本間弁護士は助言する。
「下請けも『根拠ある提案』を示す必要があると思います。下請け業者のコスト意識を知ることは、親事業者にとってもメリットがあります。また自社製品の価値や技術力を見つめ直し、海外からの調達部材とどこが違うのか、競合他社と比べて自社の強みは何か、を見極める。下請け業者のそうした努力があれば、親事業者に追従するだけの関係ではなくなるかもしれません」
「親事業者に下請法を意識させながら、価格交渉でも金型保管でも積極的に意見や提案を発信しなければ、事態はなかなか動きません」
記事冒頭で紹介した群馬県の2社への取材は、10月上旬だった。その後、わずか2カ月足らずの間に、両社の経営環境は深刻さを増している。検査不正によるリコールの拡大のため、メーカー側が生産計画の見直しを公表したからだ。
2社のうち、部品製造会社の社長は電話でこう言った。
「一律の大幅コストカットで泣かされ、今度はリコールや不正問題の影響で泣かされる。おそらく、経営体力のない中小零細の倒産や廃業が続出する。そんな気がしています」
本間誠也(ほんま・せいや)
北海道新聞記者を経てフリー。
日本の法律、司法システム、検察の能力、ゴーン容疑者の弁護士の能力、そして日産が提供する資料や証言者で最終的に無罪か、有罪か 決まると思う。
日産自動車前会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)の役員報酬を巡る有価証券報告書の虚偽記載事件で、2009年3月期以降のゴーン容疑者の報酬の詳細が関係者の話で判明した。報告書の不記載分を含めると、実際の報酬はほぼ毎年右肩上がりに増額されており、不記載分は、役員報酬の個別開示制度が始まった10年3月期から直近の18年3月期までの9年間で、計約95億円に膨らんでいた疑いがある。
報酬の詳細は、ゴーン容疑者の指示で前代表取締役のグレッグ・ケリー容疑者(62)らが作成した「覚書」などに記されていたという。東京地検特捜部も同様の内容を把握しており、ゴーン容疑者が自らの報酬を詳細に決めながら、その一部を意図的に報告書に記載しなかったとみて調べている。
多くの外国人労働者の多くは働き甲斐よりはより多くのお金の会社にながれ、いろいろな副職やメリットが多い場所を好む。
選択肢があれば当然のことである。このような事を理解していないであれば、日本や日本人はとてもナイーブだと思う。
本当に、短期間で多くの外国人労働者を入れるのは危険である。まあ、わかっていない人達が多い、又は、目先の利益の事しか
考えていない日本人が多いのだから、仕方がないのかもしれない。外国人だけが悪いのではない、日本人達や日本の政治家達にも
問題があるからこのようなるのである。
参院で審議中の入管難民法改正案を巡り、新たな在留資格で受け入れる外国人労働者がより高い収入を得られる都市部に集中し、地方で人材が確保できないのではないかとの懸念が広がっている。衆院で修正された改正案には、大都市圏への過度な集中を防ぐため「政府は必要な措置を講じる」との規定が加わったが、具体的な対策は決まっていない。外国人技能実習制度では、九州で受け入れるはずの実習生が都市部に流れる事例もあり、関係者からは「本当に人が集まるのか」と不安が漏れる。
【図解】どう変わる?新たな技能実習制度案
技能実習生は来日時に受け入れ先が決められ、実習先(職場)の変更は原則認められない。一方、政府が来年4月の導入を目指す「特定技能」は就労目的の在留資格で、介護や農業など受け入れ業種の範囲内で勤め先を選べるようになる。
政府は具体策持ち合わせず
予想されるのは賃金の高い都市部への集中と、それによる地方への影響だ。安倍晋三首相は11月28日の参院本会議で「地方の人手不足解消策は政府全体として取り組むべき課題。必要な施策を検討する」と強調したが、政府は何も具体策を持ち合わせていない。
29日の参院法務委員会では、野党議員が「東京の時給は1200~1600円。都市部に集中するのでは」と質問。法務省の和田雅樹入国管理局長は「最初は地方でも受け入れが進むが、その後は都市への集中が危ぶまれる」との見方を示した。
人手不足の現場、広がる懸念
ただ、こうした論点は最近の国会審議で浮上し、検討が追いついていない。政府は年末に取りまとめる外国人との共生を目指す「総合的対応策」に対策を盛り込む方針だが、具体策を聞かれた和田氏は「申し訳ない。現在、明確に提示できる段階ではない」と述べるにとどまった。
人手不足の現場では懸念が広がる。建設会社など約35社に技能実習生140人を送り出す福岡県内の監理団体。ベトナム側に人材供給を要請しても「九州には行けない。建設なら東京、大阪がいい」と渋られるという。理由は賃金の差。団体幹部は「実習生は自分の労働力をどれだけ高く買ってくれるかを見極めている」と明かす。
「候補者たちが引き抜かれた」
実際、最低賃金(時給)は最高の東京都が985円。九州では福岡県が814円だが、鹿児島県は全国最低と同額の761円、他の5県が762円だ。途上国の物価水準を考えれば、こうした時給の差は日本人の想像以上に大きい。
人材獲得競争は既に厳しさを増している。九州北部の介護施設は昨年12月、ベトナムで実習生候補者の面接を実施。今夏に受け入れる段取りだったが、今春に急きょ取りやめになった。監理団体によると「関西の介護施設に、より高い賃金を提示され、候補者たちが引き抜かれた」という。
この介護施設の関係者は「日本人と同等か、それ以上の時給を出すつもりでも、大都市や体力のある事業者に人材が流れる。新たな在留資格でも同じことが起きるのではないか」と懸念を隠さない。
民間のヤードと輸出監督管理倉庫がイコールなのか専門でないのでよく分からないが、外国に積み込まれる車が保管されている場所の管理やチェックが
甘いと思われるエリアは存在する。税関職員が管理の甘い所を把握しているのはわからない。
「通関手続きを受けた地域と離れた港から輸出したり、通関後の貨物をコンテナの修繕などのために民間が管理する「ヤード」に一時的に運び込んだりすることも仕組み上は可能だ。その場合、輸出業者がトラックなどを手配して貨物を港まで運ぶ。」
港や場所によっては厳しい港や場所と違って驚くほど簡単なケースがる。「抜け穴」は存在するが、リスクを負ってまで「抜け穴」を利用する
日本の会社や日本人は存在すると思うが少ないと考えられる。そこにいざとなったら国外に逃げればよい外国人である自動車販売会社社長でパキスタン籍、チーマ・アティーク容疑者が目を付けたと思う。悪い事をしているとの自覚があれば、最悪の場合のために、海外にダミー会社などを
作り、お金などをプールしている可能性がある。日本の警察は外国、英語そして外国語に疎いので再起のための軍資金を探せない可能性が高いと
推測する。チーマ・アティーク容疑者の仕事や人脈を徹底的に調べ上げて出来るだけ関係した人間を調べ上げる事は出来るが、やはり、時間や
人材的に制限があり、ある所で終わりするのではないかと思う。
防犯対策に関して出来る事は限りがある。「抜け穴」があるのであれば、規制を厳しくするか、ずさんな業者や会社を指導や処分していくしかないと思う。
「レクサスLX」やトヨタ「ランドクルーザー」などの国産高級車を狙い、関西を中心に窃盗を繰り返していた窃盗グループが大阪府警捜査3課に摘発された。盗んだ車を海外で売りさばく際、格安の中古車をダミーに使って税関を通過し、出港直前に盗難車と積み替えるという前代未聞の手口が判明。盗難車は正規輸入の日本車として扱われていた。住宅街などで盗まれ、海外に運び出された盗難車は200台以上にのぼるという。
【図解】盗難車不正輸出の構図
■ターゲットは高級車
「ハコ屋を紹介してほしい」。主犯格の自動車販売会社社長でパキスタン籍、チーマ・アティーク容疑者(55)が旧知の仲だった堤修一容疑者(51)に持ちかけたのは平成28年6月のことだった。
「ハコ屋」とは、自動車専門の窃盗犯を指す。チーマ容疑者の言葉をきっかけに、川崎倫正容疑者(56)らの窃盗グループが構成された。
ターゲットとしたのは、国産の高級車、「レクサスLX」とトヨタ「ランドクルーザー」。海外でも人気が高く、チーマ容疑者は後の調べに「人気でよく売れた」と供述。住宅街などで物色を重ね、事前にターゲットを絞ってから犯行に及んでいた。
グループは電動ドリルやドライバーで運転席をこじ開け、特殊なコンピューターを使ってエンジンを起動。保管場所を定期的に移動させながら、茨城県まで持ち込んだ。
■思わぬ「抜け穴」
グループは横浜港から正規の貨物船に積み込んで輸出していた。盗難車は本来、車体番号などをチェックされるため、輸出は不可能。それをどのようにくぐり抜けたのか。財務省関税局によると、多くの場合、通関手続き後、コンテナは港近くの「保税地域」で保管され、業者が手を加えることは難しい。
盗難を防ぐため、コンテナには番号が振られており、輸出時にはこの番号で別のコンテナとすり替わっていないか確認する。ただ、実際は輸出するコンテナの数は膨大で、不審だとの情報などが寄せられない限り中身の確認は行わないという。
一方、通関手続きを受けた地域と離れた港から輸出したり、通関後の貨物をコンテナの修繕などのために民間が管理する「ヤード」に一時的に運び込んだりすることも仕組み上は可能だ。その場合、輸出業者がトラックなどを手配して貨物を港まで運ぶ。
ここに「抜け穴」があった。チーマ容疑者らは、格安の中古車をダミーとして用意した上で正規の手続きを行い、税関を通過。その後、横浜市内の民間のヤードに運び込んだ。管理会社によると、このヤードは業者が所定の費用を払えば出入りでき、中身をすりかえていた。
通関後にコンテナの中身を積み替える不正輸出事件は前例がないといい、同局は対応策を検討するとしている。
■巧妙化する手口
自動車盗の手口は巧妙化の一途をたどる。スマートキーの車に標準装備される「イモビライザー」を無力化する「イモビカッター」を使った手口の自動車盗も全国で相次ぐ。今回の事件でも、グループは自動車盗常習犯の間で使われる特殊な装置を使い、いとも簡単にエンジンを起動し、キーまで複製していた。
日本車は海外でも人気が高く、今回の盗難車の多くも、輸出先で売りさばかれていた。グループの1人で輸出の手続きを担った会社役員、伊丹彰一容疑者(49)が関与した自動車の輸出は、平成29年1~9月までの間で250台を超え、大阪府警はこのうち、少なくとも202台が盗難車だったとみている。
輸出先はパキスタン、イラン、アラブ首長国連邦など中東やアフリカが中心で、被害総額は実に約17億円にのぼる。ある捜査関係者は「自動車盗の手口はどんどん巧妙になっている。自動車の仕様だけに頼らず、防犯対策をとることが必要だ」と指摘している。
三菱電機の子会社によるゴム部品の品質不正で、問題の部品が三菱電機以外のメーカーや商社にも出荷され、エスカレーターや家電製品などに幅広く使われていることが新たにわかった。東海道新幹線を含む鉄道車両での採用がすでにわかっているが、不正の影響が一段と広がる見通しになった。社内調査は大詰めを迎えており、三菱電機は不正に関する調査結果を4日にも公表する予定だ。
問題のゴム部品を製造していたのは、三菱電機が100%出資する子会社のトーカン(千葉県松戸市)。
関係者によると、問題の部品の大半は三菱電機の製品向けに出荷されていたが、別のメーカーや商社を通じて、エスカレーターの手すりやローラー、家電やパソコンに使う電子機器の放熱絶縁ゴムなどにも使われている可能性がある。
社内調査を進めた結果、出荷先と取り決めた品質基準より緩い社内基準で出荷したり、一部の品質検査をせずに出荷したりする不正が判明。硬度などの性能面で仕様を満たさないおそれがあるゴム部品が出荷されていた。トーカンが手がけるゴム部品約1200種の2割ほどで不正があった可能性が高まったという。
同性愛者でなければ程度の違いはあれ、女性に興味を持っている男性は多いと思う。イケメンで女性の方から来る男性、イケメンではないが
面白い男性、魅力的ではないがお金持ちの男性、お金持ちではないが女性に尽くす男性、お金持ちでもないのにお金の全てを女性に使う男性、
いろいろな要素のコンビネーションの男性などいろいろな男性がこの世の中にはいる。
女性で人生を狂わす男性はこの世の中にたくさんいる。日本では完璧な人を期待したり、想像するが、実際には、ある部分に飛びぬけた才能が
あるから他の部分も問題ないと思うのは間違いかもしれない。いろいろな価値観、興味や趣味を持っていても演じたり、自身をコントロールする
ことにより他人が見る部分が違ってくる可能性があるのではないかと思う。
いろんな人と打ち解けて話す機会があるわけでも、人と会う事が多い仕事でもないのでテレビ、インターネット、その他の情報と実際に自分が話した人達から推測しているだけなので事実は知らない。リサーチ、統計、調査やメディアの情報にしても、調査方法、調査する側がある目的を持って調査する、
調査対象を限定する、予算がないために偏った調査をするなどの問題があれば、信頼性は低いし、バイアスがかかっているデータは現状や現実を
反映していない可能性がある。
今回の逮捕をきっかけに出てくる情報は事実かもしれないが、誇張された情報もあると思う。まあ、逮捕されるような事をたくさんしてしまい、
日産がゴーン氏を見限ったから仕方のない事だろう。
「5年間で約50億円もの報酬を隠し、同時に投資資金の不正な流用、経費の不正使用などを告発されたゴーン氏ですが、実はその背景には、彼の『女性問題』があると言われています。ゴーン氏は30年連れ添った前夫人のリタさんとの間で泥沼の離婚訴訟を抱えていますが、同氏に『世界各地に愛人がいた』ことを、リタさんが証言し告発しているのです」(全国紙経済部デスク)
日産自動車の経営をV字回復させ、カリスマ経営者とされていたカルロス・ゴーン氏が逮捕されたことで、全世界が激震している。容疑は有価証券報告書に、自分の報酬を少なく記載した金融商品取引法違反だが、同氏が日産を私物化し、「乱脈」とも言えるカネの使い方をしていた理由の一つが、「オンナ絡み」であった可能性は高い。
「ゴーン氏は世界中に日産のカネで豪邸を建てていたことが指摘されています。これらの場所に愛人を囲っているのではないか、と疑われていました。リタ前夫人との離婚訴訟でも巨額の費用が発生し、それも日産に負担させていた疑惑まで浮上しています」(別の経済部デスク)
FRIDAY 12月7日号には、’12年にニューヨークで撮影された、ゴーン氏と金髪美女のキス写真を掲載しているが、この金髪美女は、同氏が’16年に再婚した米国人のキャロル現夫人だ。
日産を劇的に立ち直らせたゴーン氏だが、一方で血も涙もないコストカッターとして知られていた。社員や関係者にそうした出血を強いる一方、自身は数十億円ものカネを隠して豪遊。逮捕劇は、日産内部からの告発が発端だった。ジャーナリストの伊藤博敏氏が解説する。
「今回の騒動は、内部告発者と、今年6月から始まった司法取引制度を使って実績を作りたい東京地検特捜部との利害が一致して起きたクーデター的告発です。今後は、ゴーン氏がいかに酷いことをしていたか、愛人問題などのスキャンダルが次々と出てくる可能性があります」
自ら家族思いの良き父親を喧伝していたゴーン氏だが、カリスマと持ち上げられ、美女らと派手な交遊を愉しんでいるうちに、人柄が変わってしまったのか。
同氏は逮捕後、容疑者として東京拘置所に送られた。世界有数のセレブが“丸裸“にされ検査を受け、キャビアやトリュフなど望むべくもない、“拘置所メシ“を食べる生活に転落した。
「金融商品取引法違反に加え、所得税法違反、特別背任罪での再逮捕の可能性があります。これらの余罪を組み合わせると、懲役15年までの刑が予想される。ゴーン氏は釈放を希望するでしょうが、保釈金はその人の収入によっても変わってくる。億単位の年収を得ている超高所得者なので、保釈金も10億円は下らないはずです」(弁護士の紀藤正樹氏)
日産という巨大企業を食い物にした代償はあまりにも大きい。
役員報酬過少記載の疑いで逮捕された日産自動車前会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)が私的な投資の損失を日産に付け替えようとした問題で、この取引に新生銀行が関わっていたことがわかった。問題があった2008年当時、同行には日本銀行の政井貴子審議委員が在籍していた。政井氏は29日、福岡市での講演後の会見で問題について問われ、「守秘義務の観点から新生銀が取引に関与していたかを含め答えは控える」と述べた。
29日発売の「週刊文春」は政井氏が新生銀で問題に関与したと報じた。政井氏は「この報道に関する質問の答えは差し控える」と述べるにとどめた。
同誌の記事で、当時の肩書を新生銀行キャピタルマーケッツ部長と報じられた点については、実際は「キャピタルマーケッツ部部長」で、それよりも下の立場だったと説明。しかし、問題の事実関係については答えなかった。
ゴーン前会長は06年ごろ、自分の資産管理会社と銀行の間で通貨のデリバティブ(金融派生商品)取引を契約したが、08年のリーマン・ショックで約17億円の損失が発生。この損失を日産に付け替えようとしたとされる。
秋田銀行支店の支店長になるのは簡単ではないと推測するがなぜ酒気帯び状態で無免許運転のリスクに対応しなかったのだろうか?
たぶん、今回が初めてではないような気がする。無免許運転は飲酒運転、又は、その他の交通違反で無免許状態になったのだろうか?
まあ、よほどのコネがない限り、出世の道は終わったのでは?
秋田県南部の秋田銀行支店の支店長の男(49)が3月、酒気帯び状態で無免許運転をしたとして道交法違反容疑で摘発され、在宅起訴されていたことが27日、秋田地検などへの取材で分かった。
起訴状などによると、男は3月18日未明、秋田県横手市内で軽乗用車を運転して買い物に向かう途中、パトカーで巡回中の警察官に停車を求められた。男からは酒気帯び基準値の約3・5倍に相当する呼気1リットル中0・53ミリ・グラムのアルコール分が検知され、無免許だったことが発覚した。男は6月、県警に同法違反容疑で書類送検され、地検大曲支部が8月、秋田地裁大曲支部に在宅起訴していた。
◇
地裁大曲支部は27日、男に懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。秋田銀行経営企画部は「本件を把握していなかった。詳細な経緯を確認中」としている。
シェアハウス向け融資などで組織的な不正が横行していたスルガ銀行は30日、金融庁に業務改善計画を提出し、執行役員ら計117人を停職や減給などの処分にしたと発表した。
改善計画では、一連の不祥事の背景について「長年の創業家支配により、創業家本位の企業風土が醸成された」と指摘。過度な短期的利益の追求により、企業統治や法令順守が機能しなくなり、「顧客本位の業務運営の姿勢を欠く状況となっていた」と説明した。
スルガ銀は10月、金融庁から一部の業務停止と業務改善の命令を受けた。11月末までに改善計画を提出するよう命じられていた。
業界の人間でもないので個人的な勝手な推測だが世界的にパイロット不足なので会社を選ばなければ仕事はあると思う。日本の会社は無理でも外国の航空会社であれば問題ないような気がする。
この世の中、需要と供給である。需要が高ければ、法律や規則上、問題なければ雇用する会社は存在する。違法や不正をする会社が存在するくらいだから大丈夫だと思う。
英国の空港で乗務前に基準値を超えるアルコールが検出されたとして、日本航空の男性副操縦士に有罪判決が出されたことを受け、日航は30日、副操縦士の懲戒解雇処分を決めたと発表した。
日航は組織の管理責任が避けられないと判断。赤坂祐二社長の月額報酬を12月分から20%減額(3カ月)、進俊則専務は10%減額(同)とする懲戒処分も併せて発表した。
また、副操縦士とともに乗務前のアルコール検査をした際に相互確認を怠ったとされる機長2人、副操縦士の上司に当たる幹部ら3人も懲戒処分としたが、これまでも賞罰に当たる人事情報は公表していないとして、具体的な処分内容は明らかにしなかった。
副操縦士に対しては26日、有罪判決が出た場合は懲戒解雇処分とすることを電話で伝達。副操縦士は「分かりました」と答えたという。
「弁護側は、実川被告が勤務により幼い子ら家族と離れる時間が長く、孤独を抱え、不眠症だったことなどを飲酒の理由に挙げた。」
罪を軽くしてもらう作戦で同情を引こうとしたのかもしれないが、JALに取ってはパイロットの健康状態や精神状態を適切に把握していない証拠の一例になると思う。
精神的な問題のはけ口や逃げ道としてアルコールに頼るのはパイロットして好ましくない。そして、今回のように逮捕され有罪になるほど乗務予定を把握しているのにアルコールを摂取する事は本人にとって有害であるばかりか、乗客を危険にさらす事になる。
不眠症であれば、十分な睡眠を取れない事により、判断能力が劣ったり、注意散漫になったり、眠気による正常な業務に支障を起こしたり、
緊急時に適切な対応を取れない事によるストレスや過度のプレッシャーにより間違った判断や対応を取る危険性がある。
2つの問題を抱えながらJALが全く問題を把握していない事は問題である。そして一緒に乗務する機長2人が問題に全く気付かない事も問題である。
「判決を受けて、日航は『個人の意識の甘さのみならず、弊社が管理監督責任を果たせていなかった結果でもあり、慚愧(ざんき)の念に堪えません。重大性を改めて認識し、再発防止に向けた取り組みを徹底します』とするコメントを出した。」
本音は別としても、第三者の専門家達に対して上記のようなコメントをしないと、会社としての体質や常識を疑われるであろう。
ロンドンから羽田に向かう旅客機の乗務直前に、基準を大きく超えるアルコールが検出された日本航空の副操縦士が、英国の運輸関連法令違反に問われた裁判で、ロンドン西部のアイズルワース刑事法院は29日午後、副操縦士の実川克敏被告(42)に禁錮10カ月の判決を言い渡した。
実川被告は10月28日、呼気検査で現地基準の10倍以上のアルコールが検出され、ロンドン・ヒースロー空港で英警察当局に逮捕された。マシューズ裁判官は、実川被告が乗務当日まで飲酒していたとの認識を示した上で、「酩酊(めいてい)状態により、搭乗する全ての人を危険にさらした。大変な悲劇を引き起こす可能性があった」と非難。同じ便に乗務予定で一緒にいた機長2人が異変に気付かなかったことにも疑問を呈した。
今回の法令違反では最長2年の禁錮か罰金、または両方が科される可能性があったが、実川被告が早い段階で罪を認め、反省していることなどを減刑理由に挙げた。刑期を半分終えれば条件付きで仮釈放される。
日航によると、実川被告は社内の呼気検査は不正にすり抜けたが、搭乗機への移動の際に乗ったバスの運転手が酒臭さに気づいた。
検察側はこの日の法廷で、駆けつけた警察官の印象では、実川被告はまっすぐ立てなかったと明かした。また、警察が実川被告に実施した呼気検査では、法令基準の1リットルあたり0・09ミリグラムを大きく上回る0・93ミリグラムのアルコールを、警察署に移動した後の血液検査でも法令基準の100ミリリットルあたり20ミリグラムの約9倍にあたる189ミリグラムのアルコールを検出した。
一方、弁護側は、実川被告が勤務により幼い子ら家族と離れる時間が長く、孤独を抱え、不眠症だったことなどを飲酒の理由に挙げた。本人は深く反省しているとも説明した。
実川被告は、勾留先からモニターをつないで判決を受けた。グレーのTシャツと長ズボン姿で、背筋を伸ばして座り、終始目を伏せていた。裁判官が退廷する際は深々と頭を下げた。
判決を受けて、日航は「個人の意識の甘さのみならず、弊社が管理監督責任を果たせていなかった結果でもあり、慚愧(ざんき)の念に堪えません。重大性を改めて認識し、再発防止に向けた取り組みを徹底します」とするコメントを出した。(ロンドン=下司佳代子)
日本航空は、10月にイギリスで乗務前に飲酒し、禁錮刑の判決を受けた副操縦士を懲戒解雇すると発表した。
日本航空は、イギリスの裁判所から禁錮10カ月の判決を言い渡された副操縦士・実川克敏被告(42)を、懲戒解雇の処分にすることを決めたと発表した。
実川被告は、10月28日にヒースロー空港で、乗務直前に基準値の9倍を超えるアルコールが呼気から検出され、逮捕されていた。
「禁錮10月の実刑判決」と言う事は英法令では「禁固10月」の処分が存在すると言う事。日本の航空法第七十条は曖昧で日本は処分が軽い事は明白だ!
日本航空の副操縦士、実川克敏被告は良い経験をしたと思う。
【ロンドン時事】乗務前の過剰飲酒で英ヒースロー空港で拘束された日本航空の副操縦士、実川克敏被告(42)が禁錮10月の実刑判決を受けたことを踏まえ、日航欧州・中東地区支配人室の菊地保宏総務部長は29日、日航が経営陣らの処分について日本時間30日午後に発表を行うことを明らかにした。
【ロンドン時事】ロンドン西部アイズルワースの刑事法院は29日、日本航空の男性副操縦士、実川克敏被告(42)が乗務前に過剰に飲酒し英ヒースロー空港で拘束された事件で判決公判を開き、禁錮10月の実刑判決を言い渡した。被告は先の公判で罪を認めていた。
日航副操縦士、英国で拘束=乗務前、アルコール基準超
裁判長は「飲酒により乗客の安全を危険にさらした。壊滅的な結果をもたらす可能性もあった」と指摘。被告は出廷せず、留置先と法廷を回線で結ぶビデオリンク方式が採用された。映像の中の被告はTシャツ姿。冒頭に「罪を認めます」と述べた後、身動きせず、緊張した様子で判決に耳を傾けていた。
英警察当局は10月28日、ロンドン発羽田行き日航44便に乗務直前だった被告の呼気から英法令で定められた基準値の10倍近いアルコールが検出されたとして、被告を拘束。同便は1時間余り遅れて出発した。
その後の調べで被告は、乗務予定日前日にワインやビールなどを大量に飲んでいたことが判明。日航は今月16日、乗務前のアルコール基準値や飲酒検査の厳格化など再発防止策を発表した。
外国人労働者が増えれば外国人による犯罪や逮捕は増えるであろう。海外からの注目を集めている今回の逮捕は改善や見直しの必要があるかを含め 興味深い。
11月19日、日産自動車のカルロス・ゴーン会長が、自らの報酬を実際より少なく記載していた、有価証券報告書の虚偽記載容疑で東京地検特捜部に逮捕された。
ルノーが本社を置くフランスだけでなくアメリカでも、今回の逮捕に対し批判的な見方が出ていることが日本のメディアで報道されている。欧米からすれば、容疑者の取り調べに弁護士の立ち会いを認めない日本の検察の捜査手法は、人権侵害に映る可能性があるのだろう。
だが、より問題なのは「人質司法」と呼ばれる、容疑者の勾留期間の長さだ。検察が思い描くストーリー(筋書き)に従わないかぎり、容疑者は身柄の拘束が続く、この問題については、2017年に国連人権理事会に、特別報告者が問題視する報告をしている。
否認すると勾留が続く日本の刑事司法
日本の刑事裁判では、法廷での証言よりも、取り調べ段階での供述調書が何よりも重視される。密室での長期間かつ苛酷な取り調べから解放されたいがために、事実に反する内容であっても、調書に署名してしまえば、法廷で否認に転じてもまず通らない。
通常、警察が容疑者を逮捕した場合、逮捕から48時間以内に一応の捜査を終え、身柄を管轄の地方検察庁に送る。検察は24時間以内に捜査内容を吟味、裁判所に容疑者を勾留請求するかどうかを検討し結論を出す。特捜部が逮捕した場合、勾留請求期限は逮捕から48時間以内。勾留期間は10日間で、さらに10日間の延長請求が可能だ。
この間に検察官は起訴して容疑者を裁判にかけるか、起訴しない(不起訴)で釈放するかを検討する。不起訴には、証拠が足りないことなどが理由となる嫌疑不十分と、比較的軽い犯罪で被害者との間で示談が成立していることなどが理由となる起訴猶予がある。
特捜案件の容疑者は、起訴になる場合は基本的に逮捕から22日後に起訴され、「被疑者(=容疑者を指す法律用語)」から「被告人」になる。特捜案件に限らず、日本ではひとたび起訴されると有罪になる確率は99.9%。諸外国と比較すると、これが異常な高確率であることは、テレビドラマのタイトルにもなるほど有名だ。
過去の事例では、経済犯の場合、容疑を認めて供述調書に署名していると、起訴と同時か起訴から短期間で裁判所から保釈が認められる。裁判を経て実刑が確定すれば、その時点で刑務所に収監され、再び身柄の拘束を受ける。もし、執行猶予がついた場合は、その期間中に執行猶予を取り消されるような事態にならなければ、再び身柄の拘束を受けることはない。
しかし、容疑の否認を続けている場合は、起訴後も身柄の拘束が続くことがほとんどだ。刑事訴訟法60条1項に、起訴後も証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合などは勾留を継続できることが定められており、この条項を理由とした勾留が続く。
実際、イトマン事件で逮捕された許永中氏は883日、鈴木宗男事件で逮捕された元外交官の佐藤優氏は512日も勾留された。
2009年の郵便不正事件で検察の捜査のあり方が批判にさらされたことを機に、近年は否認していても保釈が認められるケースも増えてはきたものの、それもあくまでかつてに比べての話にすぎない。実際、昨年7月に逮捕された森友学園の籠池泰典前理事長夫妻は298日間も勾留された。
もっとも、長期勾留は日本だけの問題ではないらしい。フランスの司法制度に詳しい神奈川大学法務研究科の白取祐司教授によれば、「日本の長期勾留は問題だが、フランスでも未決拘禁(起訴決定後有罪か無罪かを決めるにあたり、公判を開くかどうかを決めるまでの間の身柄拘束)の長期化は問題になっており、それ自体、日本固有の問題というわけではない」という。
また、まず任意同行をして事情聴取をするのが普通なのに、いきなり逮捕に及んだことについても、「外国人なので海外に逃亡されることを防ぐためにそうしたのでは」とみる。
外国人ゆえの配慮の可能性は?
そもそも日本語が堪能ではない外国人のゴーン氏の場合、取り調べはどのように行われるのかという素朴な疑問が湧く。検察官とのやり取りに通訳はつくのかつかないのか。日本語で書かれる供述調書の内容をどうやって理解させ、署名を求めるのか。
刑事被告人となった著名人が自らの経験をつづった書籍を読むと、必ず登場するのが検事から自らの供述とは異なる内容の供述調書への署名を強要される場面だ。書面自体を見せられることなく早口でざっと読み飛ばしただけという例もあれば、書面を渡され、じっくり読む時間を与えられている例もある。
足利事件で菅家利和氏を無罪に導いただけでなく、ロッキード事件、平和相互銀行事件、鈴木宗男事件、日興インサイダー事件など、特捜部事件も含め刑事事件全体で豊富な経験を持つ佐藤博史弁護士は、「今回は特捜案件なので、取り調べは録画されている。ゴーン氏が容疑を否認しているという報道が事実なら、有能な通訳を使って取り調べているはず」だという。
佐藤弁護士によれば、「日本語が話せる外国人の場合でも、外国人の取り調べは通訳なしで日本語で行われるが、調書を録取する際は通訳を使う。ただ、和文の調書の内容を通訳に口頭で説明させるだけで、容疑者の母国語に翻訳した文書を渡して読ませることはしていない」という。
それでは供述した内容と異なる内容の調書を作成された場合、日本人ならばそのことに当然に気づくが、外国人でも気づけるよう、通訳は調書の内容を正確に伝えてくれるのだろうか。
「署名させるのは和文なので、そこはさすがに後日、問題にならないよう、通訳には正確に伝えさせ、なおかつ録音もする。今回は特捜案件なのでそもそも可視化の対象。証拠が残るので、供述と異なる調書が作成されることはないだろう。調書は和文で作成され、通訳が口頭で説明する場面が録画されることになるはず。したがって、英文での調書は作成されないだろうが、ゴーン氏が、弁護士がチェックしたものでなければ署名しないと言えば、検察官は弁護士による和文調書のチェックを認めざるをえないのではないか」(佐藤弁護士)。
佐藤弁護士は、ロッキード事件で事情聴取を受けた、日系2世のシグ片山氏の弁護をした際、自ら英語で取り調べをし、英文で調書を作成した河上和雄検事(当時)から、和訳した調書のチェックを認められた経験を持つ。
片山氏が、弁護士による和文調書のチェックを英文調書への署名の条件にしたために実現した措置だった。
「今回、弁護士による和文調書のチェックが実現すれば、日本人にも同じことが認められるようになるはず。取り調べへの弁護士立ち会いは無理でも、一歩前進と言えるので、ゴーン氏にも、ゴーン氏の弁護人にも頑張ってもらいたい」(佐藤弁護士)
もっとも、「容疑者の運命を左右する調書を、母国語で作成して署名を求めるのは当たり前のことだし、これは現行制度下でも十分可能。それなのにやっていないことは大いに問題だ」(同)という。
検察が民間企業の権力闘争を利用することの是非
そして佐藤弁護士、白取教授ともに問題視しているのが、今回司法取引が使われた点だ。日本では今年6月に司法取引が導入されたが、日本版の司法取引は欧米諸国が導入しているものとは異なる。
欧米諸国が導入している司法取引には大きく分けると2つのタイプがある。1つは自分の犯罪を告白することで刑罰を軽減してもらう「自己負罪型」。もう1つが他人の犯罪を告白することで自分の刑罰を軽減してもらう「捜査公判協力型」。取引材料が前者は「自分の犯罪」であるのに対し、後者は「他人の犯罪」だ。それだけに捜査公判協力型はえん罪を生みやすいとされる。
厳密に言えば、捜査公判協力型にはさらに2つのタイプがあり、1つは自分が共犯の場合の情報を提供する「共犯密告型」と、自分が関与していない犯罪情報を提供する「他人密告型」がある。他人密告型は自分が関与していない分、共犯密告型よりもいっそう冤罪(えんざい)を生みやすいだけでなく、他人を陥れる目的で悪用されやすい。
アメリカでは自己負罪型、共犯密告型、他人密告型のすべてが導入されている。ドイツでは自己負罪型と共犯密告型のみ。フランスの場合は、司法取引といえば軽い罪の案件で手続きを簡素化する制度があるだけで、こういった形の司法取引は導入されていない。
これに対し日本は自己負罪型を導入せず、共犯密告型と他人密告型だけを導入した。今回、日産が応じた司法取引の類型がどちらなのかは現時点では不明だが、佐藤弁護士は結果として民間企業の内部抗争に検察が荷担することになる点を問題視している。
三つどもえの対立への影響
今回の一件が特異なのは、本件がルノーと日産、フランス政府の3社間に存在する、経営統合をめぐる三つどもえの対立関係に影響を及ぼす点にある。
佐藤弁護士は「検察は司法取引の2例目として、慎重に事案を選んだつもりだろう。しかし、今回のケースは背景に内部抗争があることは明白で、かつ司法取引は手を汚した者を見逃すことを意味する。つまり、検察はゴーン氏追い落としに荷担したことになる。それは民事不介入の原則に反するのではないか」という。
白取教授も「捜査のために今回使われたとされる司法取引が、企業内部の対立を利用したものだとしたら、その使われ方が妥当だったのか、今後問題とされる可能性がある」という。
ゴーン氏の代理人弁護士に、元東京地検特捜検事の大鶴基成弁護士が就任したことが報じられている。
一般に、検事出身の弁護士は、容疑事実は認め、情状酌量を求めるなど刑の軽減を狙う場合には適任だが、否認して徹底的に争う場合には適さないと考えられている。にもかかわらず、容疑を否認しているゴーン氏が選んだのは検事出身の弁護士だった。
はたして本件は、上記のような検事出身の弁護士に対する評価を変える機会になるのだろうか。
東京地検特捜部としては、ゴーン氏ほどの大物経済人を逮捕した以上、失敗は許されない。失敗すれば外交問題にも発展しかねない。そしてルノー・日産のアライアンスはどうなるのか。ありとあらゆる視点から、日本だけではなく、全世界の注目が集まっている。
伊藤 歩 :金融ジャーナリスト
中国のインチキぶりは人件費が安くてもとことん利益を追求するために起きている文化的、そして社会的価値観の結果なのかもしれない。
日本の人件費が上がらなければハイテクでなくてもまだまだやっていける日本の企業があり、中国は成長しても品質の甘さは思った以上に 改善されない可能性がある。日本は人件費が高騰しているのでどうなるのだろう。
クボタが金属加工部品のデータを改ざんしていた問題で、同社は29日、調査結果をまとめ、不正行為は約40年前の1977年から行われていたと発表した。「組織体制の機能不全」などが原因として、木股昌俊社長が2カ月間月額報酬の30%を返上する処分を決めた。同日夕、木股社長らが記者会見して詳しい経緯を説明する。
調査結果によると、既に公表済みの製鉄所などで使われる圧延用ロールのほか、圧縮機用シリンダーライナーでも硬度データの書き換えが行われていた。
ジャーナリスト 沙鴎 一歩
2016年のリオ五輪では「聖火ランナー」も務めた
日産自動車のカルロス・ゴーン前会長(64)=11月22日の臨時取締役会で会長職解任=が逮捕され、11月29日で10日が経過する。これまでの新聞やテレビの報道によってゴーン氏のお金に対する執着がわかってきた。とことん日産を食い物にする彼の拝金主義のすさまじさには、沙鴎一歩も驚いた。
「私物化」の象徴ともいえるのは、ゴーン氏がオランダにある日産の子会社「ジーア社」に、ブラジルのリオデジャネイロとレバノンのベイルートで高級住宅を購入させ、その住宅を家族に使わせるなどしていたという疑いだ。
なぜ、ブラジルとレバノンなのか。ゴーン氏はブラジルで生まれ、幼少期から高校まではレバノンで生活している。この2つの国との関係が深いのだ。
ゴーン氏の自叙伝には「私はブラジル人であることを忘れたことはない。レバノンの文化や歴史も大切だ」との内容が記されている。とくにブラジルでは2016年のリオ五輪で聖火ランナーも務め、次期大統領選に出馬するとの噂まで流れた。蓄財の「動機」として、政界への出馬資金に充てようとしていたのではないか、という指摘もある。
ヨットクラブの会員費や家族旅行の代金も出させた
これまでの報道を総合すると、オランダのジーア社は、日産が50億円超で設立した会社で、実体のないペーパーカンパニー2法人を通じて、2011年から翌年にかけてリオやベイルートの高級住宅を購入させていた。問題の2法人はいずれも「パナマ文書」などで問題にされたタックスヘイブン(租税回避地)に設立されていた。
住宅の購入費はリオが6億円で、ベイルートが15億円だった。この計21億円は、日産が投資名目で用意した。高級住宅はいずれもゴーン氏が私的に利用していたが、有価証券報告書にはゴーン氏の報酬としては記載されていなかった。
リオとベイルートだけではない。フランス・パリやアメリカ・ニューヨークでも同様に日産の資産を私物化していたとの疑惑が浮上している。
さらにデリバティブ取引で生じた損金を日産に負わせたほか、ヨットクラブの会員費や家族旅行の代金を出させたり、自分の姉にアドバイザー契約を結ばせたりして多額の資金を提供させていたという疑惑も報じられている。
これらの“私物化資産”は有価証券報告書に未記載だった。また日産の株価の上昇と連動した額の資金を受け取れるストック・アプリシエーション権(SAR)による報酬(4年間で40億円)も記載されていなかった。
「後払い」という言い分は通らない
ゴーン氏の直接の逮捕容疑は、2011年3月期~2015年3月期の5年分の役員報酬について、半分の計50億円と偽って有価証券報告書に記載をしていたという金融商品取引法違反の疑いである。
報道によると、ゴーン氏は東京地検特捜部の取り調べに対し、「高額な報酬に対する批判を避けるため、報酬の半分を役員の退任後に受け取ることにしていた」という趣旨の供述をしているという。ゴーン氏は半分にした記載の事実は認め、役員報酬の個別開示制度がスタートした2010年から、毎年半分の10億円(5年で計50億円)と記載していたというのだ。要するに「後払い」で報酬を受ける予定なので記載する必要はなく、違法性はないとの主張だ。
しかし金融商品取引法は、役員報酬を退任後に受け取る場合でも、確定した受領額を各年度の有価証券報告書に記載しなければならないと定めている。
ゴーン氏は「受領額は確定していなかった」と犯意を否定しているというが、そもそも開示制度が始まった時点から記載報酬が半分になること自体が不自然だ。しかも後払いの50億円の報酬が確実に支払われるように「覚書」まで作っていたというから容疑は濃厚である。
なお2016年3月期~2018年3月期までの直近の3年分についても計30億円少なく記載していた疑いがあるという。これは逮捕容疑には含まれていない。結局、8年間で計80億円の過少記載となるが、新たな30億円の過少記載については逮捕から20日後の起訴後に追起訴されるだろう。
より重い「実質犯」として立件する必要がある
今後、ゴーン氏の事件はどのような推移をたどるのか。事件の重大さを鑑みると、有価証券報告書に記入がないなどという「形式犯」ではなく、より重い「実質犯」として立件する必要があるだろう。
たとえば脱税(所得税法違反)罪だ。一般的に会社の資産を使っていた場合、会社からの報酬とみなされ、その会社が源泉徴収して税務署に申告するか、または個人が確定申告しなければならない。会社の資産の私物化は課税対象になる。
ゴーン氏は私物化した資産を公にはしていなかった。日産側もごく一部の幹部しか知らなかったという。私物化は逮捕後の新聞社やテレビ局の取材で分かってきたことだ。そこから考えると、ゴーン氏は税務当局に対し有価証券報告書に記載されている範囲内でしか申告していなかったとみられる。
未記載の計50億円(5年間)はゴーン氏が役員を辞めた後に支払われる約束になっていたというから、現時点ではこの50億円には課税されない。問題は私物化された資産である。
「年間3分の2は海外」のゴーン氏は「日本の居住者」か
通常、個人が3年間で計1億円以上の所得を隠しているとみられた場合、国税当局は査察と呼ばれる強制捜索でたまり(隠し資産)を見つけ出し、脱税(所得税法違反)の罪で検察庁に告発する。
ただし脱税で立件するにはゴーン氏を日本の居住者と認定する必要がある。ゴーン氏の国籍はブラジルとみられ、年間3分の2を海外で生活したという。本当に課税ができるのか。国税当局はこれまで1年の半分以上を海外に滞在していた人物に課税したことがある。
脱税罪以外にも「実質犯」には特別背任罪や業務上横領罪がある。逮捕から20日後の勾留満期までに東京地検特捜部はどんな容疑でゴーン氏を再逮捕するか。当局の動きに注目だ。
「日産の統治体制の異常さ」という指摘は遅すぎる
新聞の社説はどう書いているか。ゴーン氏が逮捕されたのは月曜日の11月19日。翌20日付の社説で取り上げたのはブロック紙の東京新聞(中日新聞東京本社発行)だけ。各紙は翌々日の21日付で一斉に書いた。それだけ各紙にとって「ゴーン逮捕」は寝耳に水だったわけだ。
24日付の日経新聞の社説はこう書き出している。
「日産自動車がカルロス・ゴーン容疑者を会長職から解任した。有価証券報告書の虚偽記載容疑でゴーン元会長本人が逮捕された現状を踏まえれば、解任は当然だが、企業統治の不全という日産の抱える問題がこれで消えるわけではない。透明性の高い経営の仕組みを早急に整える必要がある」
「世界中が驚いたゴーン容疑者の逮捕劇から5日がたち、改めて浮かび上がってきたのが日産の統治体制の異常さである」
「企業統治」を持ち出すのは、読者層に企業の幹部が多い日経らしい。事実、日経の記者は企業の大型合併などのスクープをものにしてきた。日産の内部事情やゴーン氏の「私物化」について通じていた記者はいなかったのだろうか。ゴーン氏が逮捕された段階で日産の統治体制を「異常」だと指摘するのは、日本の経済を専門にする新聞社としては遅すぎる。
日経は「日産の体質」を大上段から問うべき
さらに日経社説は書く。
「ひとつは過度な権限の集中だ。ゴーン容疑者は日産の会長という執行の立場と、取締役会議長という執行部門を監督する立場、さらには日産の筆頭株主であるルノーの会長兼最高経営責任者(CEO)の3ポストを1人で占めた」
「同じ人間が執行と監督の双方を兼ねる体制が機能するわけはなく、ガバナンスの不備がトップの暴走を許す土壌となった」
他の新聞やテレビ局が指摘している内容と同じである。経済専門紙らしい主張をすべきだ。
続けてこうも書く。
「日産はこうした問題に早急にメスを入れ、外から見て分かりやすい統治体制を整える必要がある。そのためには独立した社外取締役の拡充が不可欠だろう。幹部人事や役員報酬の決定に客観性を持たせるために、指名委員会や報酬委員会の設置も急がれる」
「外から見て分かりやすい」とか「社外取締役の拡充」「指名委員会や報酬委員会の設置」など言い古された文言だ。経済紙として日産の体質を大上段から問うような主張をしてほしい。
奇をてらって矛先をルノーに向けた産経新聞
「とくに今後は、日産株の4割超を握る筆頭株主、仏ルノーとの関係をどう位置づけるかが課題となる。そこでは日産の経営に大きな影響力を持ちながら、十分に監督できなかったルノーの責任も併せて問われなくてはならない」
「ゴーン会長解任 ルノーに責任はないのか」との見出しを掲げた11月23日付の産経新聞の社説(主張)だが、これも奇をてらって矛先をルノーに向けたのだろうが、ありきたりである。
産経社説は続けて「ルノーは日産の経営の重要事項に拒否権を発動できる筆頭株主であり、その経営を監督する責任がある。しかも今やルノーの利益の半分を日産が占めており、不正を見逃すわけにはいかなかったはずである」と指摘した後、こう主張している。
「何よりも優先すべきなのはルノーの責任を明確化し、同社の経営体制も抜本的に見直すことである。それを欠いたままでは、三菱自動車を含む3社連合の企業統治や法令順守は徹底できないと銘記すべきである」
「ルノーに経営を監督する責任がある」という指摘にしても、「ルノーの責任の明確化すべきだ」という主張も当然なことであり、日経社説と同じくパッとしない。残念である。
表面的な論考はもういらない。今後、日産やゴーン逮捕をテーマに社説を書くならば、「なぜゴーン氏が日産の私物化を進めることができたのか。日産はどうしてそれを許したのか」を解明し、事件の本質を深く捉えたものでなければ読者は納得しない。
「『新生銀行は担保の追加を求めたものの、ゴーン氏は損失も含めて日産側に権利を移そうとしました』(新生銀行元幹部)
そこで動いた一人が、当時、新生銀行のキャピタルマーケッツ部長だった政井貴子氏(53)だ。
『政井氏ら新生銀行側と日産の幹部が協議した結果、日産が取締役会での議決を行うことを条件にゴーン氏の取引を日産に事実上、付け替えたといいます}(同前)
上記が事実なら新しい問題が出てきたと言う事なのか?
日産自動車の会長だったカルロス・ゴーン容疑者(64)が約50億円の役員報酬を有価証券報告書に記載しなかったとして逮捕された事件で、この約50億円を退任後に受け取ることで日産と合意した文書は、秘書室で極秘に保管されていたことが、関係者への取材でわかった。東京地検特捜部は、文書作成に直接関与した秘書室幹部と司法取引し、将来の支払いを確定させた文書だという証言を得た模様だ。
【独占写真】ゴーン容疑者への捜査、羽田で動いた。動画も公開中
関係者によると、この文書は役員報酬を管理する秘書室で管理され、経理部門や監査法人には伏せられていた。退任後に支払うという仕組みは取締役会にも諮られなかったという。
ゴーン前会長と前代表取締役のグレッグ・ケリー容疑者(62)は、2014年度までの5年間の前会長の報酬が実際は約100億円だったのに、有価証券報告書に約50億円と虚偽記載したという金融商品取引法違反の疑いで逮捕された。
「関係者によると、前の代表取締役、グレッグ・ケリー容疑者(62)は、退任後に受け取る報酬を記載しなかったことについて、『外部の法律事務所や金融庁などに何度も相談し、記載義務はないとの回答を得た。そのうえで適切に処理した』と供述しているという。」
前の代表取締役、グレッグ・ケリー容疑者(62)は、外国人なので外部の法律事務所や金融庁に相談したのなら相談した担当者の名刺や名前のメモを
保存しているはずである。確認するのは簡単であると思う。本当だったら本当で外部の法律事務所や金融庁の担当者にも責任がある事が明確になるし、
嘘であるのならグレッグ・ケリー容疑者の供述に関して証拠や証明する資料がない限り信用する根拠は低く見られるかもしれない。
外部の法律事務所はコメントするかわからないが、金融庁は担当者がわかれば確認してグレッグ・ケリー容疑者からの相談に関してコメントするかもしれない。
日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者(64)による役員報酬の過少記載事件で、側近の前代表取締役が「金融庁などに相談していた」と供述していることがわかった。
ゴーン容疑者が日産の有価証券報告書に記載しなかった報酬の総額は、8年間でおよそ80億円にのぼり、これらの報酬は、退任後に受け取ることになっていたとみられている。
関係者によると、前の代表取締役、グレッグ・ケリー容疑者(62)は、退任後に受け取る報酬を記載しなかったことについて、「外部の法律事務所や金融庁などに何度も相談し、記載義務はないとの回答を得た。そのうえで適切に処理した」と供述しているという。
これらの回答は、書面で送られていたとみられている。
一方、東京地検特捜部は、押収した社内文書やメールなどから、記載義務はあったと判断しているものとみられる。
金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑いで逮捕された日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)が、退任後に受け取ることにした役員報酬を報告書に記載しなかったことについて、側近の前代表取締役グレゴリー・ケリー容疑者(62)が「金融庁に相談し、記載する必要はないとの回答を得た」と周囲に説明していることが29日、関係者への取材で分かった。
金融商品取引法を所管する金融庁の「お墨付き」をもらったことは、虚偽記載の意図がなかった裏付けになると主張するとみられる。東京地検特捜部は、ゴーン、ケリー両容疑者とも記載義務を認識していたとみて調べている。
「『新生銀行は担保の追加を求めたものの、ゴーン氏は損失も含めて日産側に権利を移そうとしました』(新生銀行元幹部)
そこで動いた一人が、当時、新生銀行のキャピタルマーケッツ部長だった政井貴子氏(53)だ。
『政井氏ら新生銀行側と日産の幹部が協議した結果、日産が取締役会での議決を行うことを条件にゴーン氏の取引を日産に事実上、付け替えたといいます}(同前)
上記が事実なら新しい問題が出てきたと言う事なのか?
11月19日、東京地検特捜部に金融商品取引法違反の疑いで逮捕された日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者(64)。役員報酬を有価証券報告書に約50億円分少なく記載した疑いのほか、会社の資金を海外の自宅用不動産の購入に流用していた問題が明らかになっている。
【写真】各国にあるゴーン氏の自宅
今回、新たに浮上したのが、私的な投資で生じた損失を2008年頃、日産に付け替えていた疑いだ。ゴーン容疑者は2006年頃、自身の資産管理会社と新生銀行との間でデリバティブ取引の契約を結んだものの、2008年秋のリーマン・ショックで約17億円の損失が発生し、担保不足に陥ったという。
「新生銀行は担保の追加を求めたものの、ゴーン氏は損失も含めて日産側に権利を移そうとしました」(新生銀行元幹部)
そこで動いた一人が、当時、新生銀行のキャピタルマーケッツ部長だった政井貴子氏(53)だ。
「政井氏ら新生銀行側と日産の幹部が協議した結果、日産が取締役会での議決を行うことを条件にゴーン氏の取引を日産に事実上、付け替えたといいます」(同前)
ところが証券取引等監視委員会が新生銀行や日産に検査に入ったことで状況は一変する。背任の恐れもあると指摘を受けて、最終的には、ゴーン氏との個人取引の形に戻したという。
その後、政井氏は執行役員に昇進した後、2016年6月、日本銀行政策委員会審議委員に就任した。6人いる審議委員は、日銀総裁、2人の副総裁とともに日銀の政策委員会を構成し、金利など、日本の金融政策の最高意思決定機関の一員。会社でいえば、取締役にあたる重要ポストを務めている。
新生銀行は「個別事案に関するお問い合わせにつきましては、弊行からご回答いたしかねます」。日本銀行は「2008年当時、新生銀行のキャピタルマーケッツ部部長の職にあったことは事実ですが、守秘義務の観点から、新生銀行における個別の取引に関するご質問については、事実関係も含め、お答えは差し控えさせていただきます」。日産自動車は「捜査が入っているので、何も答えられない」とコメントした。ゴーン氏の逮捕は、日本の中央銀行にも波紋を広げることになりそうだ。
11月29日(木)発売の「週刊文春」では、ゴーン容疑者の告発に動いた日産「極秘チーム」メンバーの実名や、約1年間にわたった内部調査の経緯などについて詳報している。
「週刊文春」編集部/週刊文春 2018年12月6日号
最終的には運が悪かった。そして自業自得!
JR東日本八王子支社は26日、駅で忘れ物の取り扱い業務にあたるグループ会社「JR東日本ステーションサービス」の男性社員(36)が、東京都の立川駅で忘れ物の現金を着服していたと発表した。同社は22日付で男性社員を懲戒解雇した。
同支社によると、男性社員は今月8日、現金9万100円入りのかばんが忘れ物として駅に届いたが、社内の管理システムに「返却済み」と入力した上で持ち帰った。翌日、持ち主が駅を訪れ、着服が発覚した。
「同社は17年2月、07~15年に元部長が約4億4千万円を不正流用していたと発表。社内の内部通報で発覚し、16年12月に懲戒解雇した。社内調査に不正を認め、個人的な遊興費として使ったと説明していたという。」
不正流用したお金は残っているのだろうか?ほとんど使ったのかな?
架空発注で勤務先から現金をだまし取ったとして、警視庁は27日、「カシオ計算機」(東京都渋谷区)元部長の柏木達雄容疑者(61)=東京都大田区田園調布5丁目=を詐欺の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
捜査2課によると、柏木容疑者は同社の開発部門の部長だった2014年10月~15年3月ごろ、架空の発注書類を提出するなどし、約400万円を詐取した疑いがある。警視庁は、同年までに同様の手口で約数千万円を詐取したとみて調べる。
同社は17年2月、07~15年に元部長が約4億4千万円を不正流用していたと発表。社内の内部通報で発覚し、16年12月に懲戒解雇した。社内調査に不正を認め、個人的な遊興費として使ったと説明していたという。
医者としての腕が良ければ、表の世界や裏の世界では生きて行けるだろうけど、これまで通りの生き方は出来ないと思う。
兵庫県尼崎市南城内の阪神高速神戸線東行き車線で、乗用車がトラックに追突し、トラックを運転していた男性が死亡した事故で、兵庫県警高速隊は26日、自動車運転処罰法違反(無免許過失致死)の疑いで、芦屋市、医師の男(50)を逮捕した。
【写真】酒気帯び?レーサー レース直前にパトカーと“一戦”
逮捕容疑は25日午後0時半ごろ、乗用車のポルシェを無免許で運転し、トラックに追突、運送会社社員(70)=明石市旭が丘=を死亡させた疑い。容疑について黙秘しており「弁護士にしかしゃべりません」と話しているという。
同隊によると、男は昨年3月に免許取り消し処分を受けているという。この事故で、男も足首骨折などの重傷を負ったが、退院した26日に逮捕したという。
「役員報酬を有価証券報告書に約50億円分少なく記載した疑いで逮捕された日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)が2008年、私的な投資で生じた約17億円の損失を日産に付け替えていた疑いがあることがわかった。証券取引等監視委員会もこの取引を把握し、会社法違反(特別背任)などにあたる可能性があると、関係した銀行に指摘していたという。」
10年も前の事で証券取引等監視委員会と銀行が知っていたのなら問題なのではないのか?それとも、証券取引等監視委員会と銀行が容認したことがもんだいなのか?それとも、この記事は不正とか違法とかではなく、ゴーン前会長の人間性を評価出来る出来事の一つとして紹介したのだろうか?
不適切であっても、倫理的に問題があっても、法的に問題がなければ処分されないのが現実。法的に問題があっても処分されてない事だった知らないだけでたくさん存在するとおもう。
役員報酬を有価証券報告書に約50億円分少なく記載した疑いで逮捕された日産自動車の前会長カルロス・ゴーン容疑者(64)が2008年、私的な投資で生じた約17億円の損失を日産に付け替えていた疑いがあることがわかった。証券取引等監視委員会もこの取引を把握し、会社法違反(特別背任)などにあたる可能性があると、関係した銀行に指摘していたという。東京地検特捜部も同様の情報を把握している模様だ。
複数の関係者によると、ゴーン前会長は日産社長だった06年ごろ、自分の資産管理会社と銀行の間で、通貨のデリバティブ(金融派生商品)取引を契約した。ところが08年秋のリーマン・ショックによる急激な円高で多額の損失が発生。担保として銀行に入れていた債券の時価も下落し、担保不足となったという。
銀行側はゴーン前会長に担保を追加するよう求めたが、ゴーン前会長は担保を追加しない代わりに、損失を含む全ての権利を日産に移すことを提案。銀行側が了承し、約17億円の損失を事実上、日産に肩代わりさせたという。
三菱自の業績回復に影響はすると思うが、なぜ3社連合になったのかを考えると三菱自動車はカルロス・ゴーン容疑者を責める事は出来ないと思う。
結果として前会長カルロス・ゴーン容疑者の逮捕が影響する可能性があるだけで、三菱自動車がしっかりとした車を設計し、生産していれば
3社連合に入る選択など必要なかった。まあ、三菱自動車の従業員や下請けとしては理由や経緯に関係なく業績に影響するのであれば心配になるのは
理解できる。
三菱自動車は26日、金融商品取引法違反容疑で逮捕された日産自動車前会長、カルロス・ゴーン容疑者の会長職を解任した。平成28年に燃費不正問題で経営危機に陥った三菱自は日産傘下に入って再出発し、業績は回復基調にある。だが、日産、仏ルノーとの3社連合の“要”になっていたゴーン容疑者の不在で、戦略の見直しを迫られる可能性もある。(田村龍彦)
【図解】カルロス・ゴーン容疑者をめぐる事件の構図
三菱自の足元の業績は好調が続いている。30年3月期連結決算は最終利益が1076億円で、2年ぶりに黒字転換した。直近の9月中間期も最終利益は前年同期比7・2%増となり、「V字回復」に近付きつつある。
スポーツ用多目的車(SUV)などの販売が伸びているほか、日産・ルノーとの提携を通じたコスト削減効果も寄与している。
三菱自が燃費不正で危機に陥った28年、事業拡大のチャンスとみて、資本業務提携を主導したのがゴーン容疑者だった。
日産・ルノー連合傘下に入った三菱自は日産から役員を受け入れるとともに、ゴーン容疑者自ら会長に就任。共同での部品調達や研究開発などを進めてきた。さらに、三菱自が得意とするプラグインハイブリッド車(PHV)の技術をルノーに提供することなども計画していた。
今回のゴーン容疑者の逮捕はそうした三菱自の成長戦略に水を差すものだ。
楽天証券の窪田真之チーフ・ストラテジストは「ゴーン体制の下で作られてきた3社連合は路線修正を迫られるだろう」と指摘する。
日産は筆頭株主であるルノーとの資本関係の見直しを視野に入れており、今後、ルノーではなく日産が主導する3社連合に変わるのか、それとも3社が独立志向を強めるのか、先行きは不透明だ。
仮にこれまでの協業関係が見直される事態になれば、三菱自の開発や生産などに影響を与えかねない。
電気自動車(EV)をはじめとした電動化や自動運転など自動車業界の垣根を越えた競争が激しくなる中、市場では「規模も小さく、体力のない三菱自が単独で生き残るのは厳しい」(アナリスト)との見方は少なくない。
ゴーン容疑者と良好な関係を築き、三菱自の再建をかじ取りしてきた益子修最高経営責任者(CEO)の手腕が改めて問われることになりそうだ。
天下りした元公務員達の中には似たような状況でそれなりの報酬を受けている人達がいるのでは?
彼らがセーフであれば元代表取締役のケリー容疑者が自供しない限りセーフなのでは?それとも、今後、天下りした元公務員達にも厳しく
対応するのか?
日産自動車の会長だったカルロス・ゴーン容疑者が逮捕された事件で、共謀したとして逮捕されたグレッグ・ケリー容疑者が、担当する実務がほぼないにもかかわらず、ゴーン容疑者の不正に関与するために日産にとどまっていたとみられることがわかった。
関係者によると、逮捕された元代表取締役のケリー容疑者は、2014年に社長室長を退いた後は、来日して出社するのは株主総会など年に数回で、担当する実務もほぼなかったという。
ケリー容疑者はゴーン容疑者から、報酬の額を少なく記載するよう指示を受けていたとみられている。また、ゴーン容疑者が無償で住宅の提供を受けていたオランダにある子会社の役員も務めていて、こうしたことに関与するために日産にとどまっていたとみられるという。
ケリー容疑者が代表取締役にとどまることで支払われていた役員報酬は、こうしたことへの関与の見返りだった可能性もあるという。
「その後の関係者への取材で、監査法人がゴーン容疑者の役員報酬について、『ストックアプリシエーション権』分が含まれていないことに気づき、『記載すべき』だと指摘しましたが、ゴーン容疑者は法律の専門家の助言を得るなどして『必要ない』と結論づけていたということです。」
事実なら法律の専門家に任意で聞き取りをしているのだろうか?専門家は任意だからと拒否しているのだろうか?任意は強制でないから
法的に報じる必要はない。法律の専門家であれば常識なので知っているだろう。
監査法人は素人ではないのだから、法律の専門家が誰なのか確認ぐらいはしていると思うので、法律の専門家が誰なのか知っていると思う。
弁護士の中に不正を行う人達が存在する。全てを明らかにして少しだけど
清浄化すれば良い。監査法人や法律の専門家は仕事のためだと割り切るのであろうが、グレーゾーンなら問題ないが、線を超えたらアウトに
なることを理解していると思うから、何か不正を行っていれば自業自得だと思う。
ちなみに東芝の監査していたのも 新日本監査法人! dea***** 10/25/18(Yahoo!ニュース)
東芝はあれだけ注目されたのに何とかなった。今回はどのようになるのだろうか?
虚偽記載をしてる訳では無いので、当然このような言葉になるでしょう。ただ、何故必要ないかは、説明していると思いますよ。だから、監査法人も納得したのだと思うし、監査法人だって色々と問い合わせはしてると思う。説明を受けずに、見逃したとなれば、監査法人も罪に問われる可能性もある。監査法人も他の役員に経緯は説明してると思う。問われているのは、虚偽記載であって、未記載ではない。0とか違う数字を記載すれば、虚偽記載だが、何も記載しなければ未記載。まさか「-」を数字と解釈するのは、無理がある。虚偽記載と未記載は意味合いが異なる。虚偽記載は罰せられるが、未記載は罰せられない。法律論の問題だが、法律とはそのようなものだろう。ゴーンが法律的な解釈を間違っていたとすれば、それは故意ではなく、ミス。ゴーンが記載しなくて、良いとケリーに指示してたのであれば、それは虚偽記載の指示ではない。 sna***** 10/25/18(Yahoo!ニュース)
「虚偽記載は罰せられるが、未記載は罰せられない。法律論の問題だが、法律とはそのようなものだろう。」が正しいのならやはり法律の専門家からの
アドバイス?
日産自動車・元会長のカルロス・ゴーン容疑者が逮捕された事件で、役員報酬を有価証券報告書に記載するよう監査法人から求められた際、ゴーン容疑者が「法律的な問題がない」と拒否していたことが分かりました。
カルロス・ゴーン容疑者(64)は、有価証券報告書に自らの報酬をおよそ50億円少なく記載したとして金融商品取引法違反の疑いで逮捕されました。
日産は役員報酬として「ストックアプリシエーション権」と呼ばれる、株価に連動して報酬を得られる制度を導入していて、これによりゴーン容疑者は数十億円を得ていましたが、有価証券報告書に記載されていませんでした。
その後の関係者への取材で、監査法人がゴーン容疑者の役員報酬について、「ストックアプリシエーション権」分が含まれていないことに気づき、「記載すべき」だと指摘しましたが、ゴーン容疑者は法律の専門家の助言を得るなどして「必要ない」と結論づけていたということです。
また、ゴーン容疑者の母親や姉が住む住宅を購入させたオランダにある日産の子会社についても、監査法人が日産側に「実態が不透明」と指摘していたことも分かりました。東京地検特捜部は、有価証券報告書の作成経緯を詳しく調べています。(
下記が事実としたら前代表取締役のグレッグ・ケリー容疑者はどのような処分を受けるのか?執行付きの有罪?
日産自動車前会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)らが金融商品取引法違反容疑で逮捕された事件で、前代表取締役のグレッグ・ケリー容疑者(62)が、前会長の役員報酬の過少記載を外国人執行役員に指示した際「他の役員に報告を上げないように」と伝えていた疑いがあることが、関係者への取材で明らかになった。また、前会長の報酬を年約20億円とした上で、不記載分の年約10億円を退任後に新たな肩書を得て受け取る形にしていた疑いも判明した。
【写真特集】カルロス・ゴーン会長 写真で振り返る
東京地検特捜部もこうした経緯を把握し、ゴーン前会長と「腹心」のケリー前代表取締役に不正の認識があったとみている模様だ。
2人は2010年度(11年3月期)~14年度(15年3月期)、前会長の報酬総額計約99億9800万円を計約49億8700万円と過少記載した有価証券報告書を提出したとして逮捕された。
関係者によると、ゴーン前会長らは逮捕容疑に続く15~17年度の報酬計約30億円についても同報告書に記載していなかった疑いがあり、8年間で計約80億円が不記載だったとみられる。
10年度には、年1億円以上の報酬を得る役員が氏名や金額などを有価証券報告書に記載するよう義務づける「個別開示制度」が始まった。以前から年約20億円の報酬を得ていたゴーン前会長は、高額報酬への批判をかわすため「記載は10億円程度」に抑えるよう、ケリー前代表取締役に指示したとみられる。
その際、ゴーン前会長は不記載分の約10億円を退任後に受け取る仕組みを考案したという。ケリー前代表取締役はメールで外国人執行役員に過少記載を指示した際、他の役員への報告をしないよう伝えたとされる。
ある日産幹部は「日産は本来、決裁基準がすごく細かく決まっているが、(前会長らは)そういうルールを全く守っていなかった。社内のガバナンス(統治)をいくら強化しても、トップが不正をしたらどうにもならない」と話す。【片平知宏、巽賢司、金寿英】
どんな選択や判断にもメリットとデメリットがある。また、メリットとデメリットに関しても、短期、中期、そして長期的にで見ると
メリットとデメリットのインパクトが違う。
仏、フランス政府、そしてルノーが今回の事件をどのように捉えているのかニュースで書かれている事からしか推測できないが、本当に
怒っているのなら、それだけ日産を取り込む旨味があったと推測して間違いはないであろう。そうであれば、日産の日本人役員達が
反発する理由はあったと思う。
フランス政府、そしてルノーが愚かな事をする日産は要らないとの対応を示したら日産は愚かな選択をしたと判断できるのであるが
そうでもないから問題は複雑だ。
こうなった以上、相乗効果は期待できないのでルノーと日産は利益が減る事は理解していると思う。日産従業員達や下請け企業は程度の違いはあるが
覚悟した方が良い。今回の事件をどのように乗り越えるか次第で、チャンスなのか、リスクだったのか判断が後で変わってくるであろう。
日産のV字回復を成し遂げたゴーン容疑者の電撃失脚を、フランスはどうとらえているのか。
22日の会長職の解任を受けて、日産とルノーの主導権争いが、さらに加速している。
フランスのシンボル、エッフェル塔に浮かび上がったのは、富士山。
そして、日の丸。
2018年は、日本とフランスの交流160周年となる節目の年。
そんなメモリアルイヤーに、フランスで大きく報じられていたのは、「ルノー・日産: 皇帝の転落」。
22日、およそ4時間にわたって行われた日産自動車の臨時取締役会。
日産自動車・西川広人社長は、「1歩少し進んだかなという実感。ルノーとは、密にコミュニケーションとりながらやっていますから、これからもそうする」と話した。
複数の日産関係者によると、全会一致でゴーン容疑者の会長職解任などが決まったという。
しかし、ゴーン容疑者の後任となる会長人事をめぐっては、水面下でバトルが勃発。
「ルノーに会長を指名する資格はない」。
アメリカの「ウォールストリート・ジャーナル」は、日産の取締役会がルノーの取締役会に宛てた書簡で、ルノーがゴーン容疑者に代わる会長を指名することを拒否したと報じた。
ルノーの本社があるフランスのメディアは、日産をV字回復させたゴーン容疑者が逮捕されたことについて、「日本人は恩知らずか」、「西川社長はブルータスのよう」などと報じた。
ニュース専門チャンネルの「フランス24」は、西川社長を古代ローマでカエサル将軍を裏切って暗殺した、腹心のブルータスになぞらえた。
また、一部のメディアは、ゴーン容疑者を追い出すための日産側による「陰謀」ではないかとして、日産によるクーデターとの見方を紹介している。
日本に来たフランス人は、「この事件に関して、申し訳ないと思っています。すぐ関係が回復してほしい」と話した。
一方、26日には、三菱自動車も臨時の取締役会を開き、ゴーン容疑者を会長から解任する見通し。
“ゴーン・ショック”の波紋は、さらに広がりそう。
日産が噛みついたのだからいろいろな問題が出てくるのは当然だろう。
まあ、今回の騒動が良かったのか結果次第であろう。日産の従業員はこれまで以上に頑張らないと同じ結果は出せないと思う。
22日に日産自動車の会長を解任されたカルロス・ゴーン容疑者(64)が逮捕された事件で、ゴーン容疑者が自身の母親の住宅についても海外にある子会社を通じて日産側に購入させていたことが、関係者への取材で分かりました。
カルロス・ゴーン容疑者は有価証券報告書に自らの報酬をおよそ50億円少なく記載したとして、金融商品取引法違反の疑いで逮捕されました。ゴーン容疑者は社長に就任した翌年の2002年ごろ、オランダにある日産の子会社を通じて、ブラジル・リオデジャネイロにある高級マンションを日産側に購入させ、自身の姉を住まわせていたことが分かっていますが、その後の関係者への取材で、ゴーン容疑者の母親の自宅も子会社を通じて購入させていたことが分かりました。
また、ブラジルにあるヨットを子会社の名義でおよそ600万円で購入し、その後、ゴーン容疑者の名義に変更するなど会社の経費を私的に支出させていた疑いもあるということです。
日産側は、こうした情報を東京地検特捜部に提供していて、特捜部は不透明な資金の流れを調べています。
また、ゴーン容疑者の報酬をめぐり、逮捕容疑とは別に直近の3年間についても有価証券報告書へのうその記載をした疑いがあることが関係者への取材で分かりました。ゴーン容疑者は2014年度までの5年間に、自らの報酬をおよそ50億円少なく記載した疑いで逮捕されましたが、2015年度から2017年度までの3年間でもおよそ30億円少なく記載していたということです。
特捜部は直近の3年度分のおよそ30億円の不記載についても、立件を検討するものとみられます。
現在、東京拘置所の単独室で過ごしているとみられる、カルロス・ゴーン容疑者。
高級住宅の購入に複数のペーパーカンパニーが関わっていたことが、FNNの取材で明らかになった。
衝撃の逮捕から4日目。
ゴーン容疑者は、22日も東京拘置所で取り調べを受けているものとみられている。
来日直後の19日に逮捕され、22日に会長職を解任される見通しのカルロス・ゴーン容疑者。
拘留中の東京拘置所は、高さ50メートルの12階建てで、刑事裁判の判決が確定しない未決拘禁者と、死刑囚が収容されている。
家族や弁護士が面会する入り口の向かいには喫茶店、さらには差し入れを販売する商店も並んでいる。
2018年6月に撮影が許可された、東京拘置所の内部。
複数の収容者が入る共同室は、畳敷きでトイレ、木のテーブルが設置されている。
一方、1人で入る単独室は、3畳ほどの広さ。
元刑務官・作家の坂本敏夫氏は、「(ゴーン容疑者は)単独室です、間違いなく。まだどちらかわからない身分だから、ほかの人とは一緒にしない。入る時の身体検査も含めて、今までやったことないような、経験のないような屈辱を味わったと思う」と話した。
午前7時起床で、消灯は午後9時。
また、拘置所の生活には、食事の面などに外国人向けの規則があるという。
坂本氏は、「食事が違う外国人は、特別な食事を出しなさいと。それがパンとサラダと卵料理とか、そういうふうに変える。1日の食事代も、日本人と外国人だと、外国人の方が高くなっている。寝具についてもベッドを利用しなさいとか」と話した。
およそ50億円の報酬を隠した疑いで逮捕された、ゴーン容疑者。
FNNは、その豪勢な暮らしぶりのために、ペーパーカンパニーが使われていたことを新たに突き止めた。
8年前、日産自動車がオランダのアムステルダムに、およそ60億円を出資して設立した子会社「ジア・キャピタル」。
関係者によると、この子会社のさらに下に設立されたのが、「ハムサ1」、「ハムサ2」という孫会社。
いずれもペーパーカンパニーとみられ、社長は、日産の外国人執行役員が務めている。
「ハムサ1」はブラジルのリオデジャネイロ、「ハムサ2」はレバノンのベイルートに、それぞれ高級住宅を購入していた。
ブラジルのリゾートビーチ、コパカバーナ。
ゴーン容疑者の家は、このビーチの目の前にある。
世界屈指の有名リゾート、ブラジルのコパカバーナの高級住宅。
その相場を、地元の不動産会社に聞いてみると、「(住宅の広さは?)海に面した不動産物件は、150~400平方メートルくらいになる。相場は、約533万ドル(約6億円)くらいだ」という。
2つの物件は、改修費用をあわせると、50億円になるとみられる。
こうした不動産の契約や資金の流れについては、ゴーン容疑者の指示のもと、側近のケリー容疑者が主導し、外国人の執行役員と日本人の幹部社員が実務にあたっていた。
また、ゴーン容疑者の姉にも、不正な資金が流れていたとみられることがわかった。
日産は2002年以降、ゴーン容疑者の姉と実体のないアドバイザー業務契約を結び、毎年、日本円にして、およそ1,100万円前後を支払っていたことも関係者の話でわかった。
22日午後から始まった臨時取締役会では、ゴーン容疑者の会長職解任が提案され、可決される見通し。
今後の見通しだが、ゴーン容疑者が2015年までの有価証券取引報告書の不記載で逮捕されたのが、19日。
今後、2016年3月期以降の分など、別の時期の不記載でも再逮捕されるかどうかが最初のポイントになる。
しかし、この報告書不記載は、法律で決めた形式的規定に反する犯罪、いわゆる「形式犯」のため、検察が、業務上の横領や特別背任といった、ゴーン容疑者個人に関わるより、重大な罪で逮捕できるかどうか、これが最大のポイントになる。
また、処分が決まったところで、保釈の話にもなる。
その場合には、保釈保証金の額の問題になるが、過去における保釈保証金、最高額は牛肉偽装事件などで逮捕された浅田ハンナン元会長の20億円。
東京地検特捜部の元検事・高井康行弁護士は、「保釈金は当人の資産状況にもよるが、報告書不記載だけなら単なる形式犯だから、50億円の不記載とはいえ、5億円から10億円ではないか。ただし、横領や背任が加われば、当然高くなる」と分析をしている。
日産はルノーやカルロス・ゴーン容疑者に助けられ、頼り切ってきた結果がこのありさまなのだから自業自得だと思う。
自分達で日産を動かすよりはルノーやカルロス・ゴーン容疑者に従う事を選んだわけだし、もっと前にさかのぼればルノーやカルロス・ゴーン容疑者を
受け要らなければならない状態になるまで問題を放置してきた日産や日産の従業員が悪い。
ルノーやカルロス・ゴーン容疑者達だけを悪者にするのはおかしいと思う。日産の検査の不正はカルロス・ゴーン容疑者からの直接な指示だったのか?
「イエスマン」しか生き残れない日産なので仕方のない選択だったのか?ルノーやカルロス・ゴーン容疑者だけでそのような日産になったのか?
カルロス・ゴーン容疑者の問題は事実であれば、人間的に問題がある。ただ、「清濁を併せて呑む」選択で日産のためにカルロス・ゴーン容疑者を受け入れてきたのではないのか?そうでなければ、なぜ、もっと早い時期にカルロス・ゴーン容疑者を追放する行動を取らなかったのか?いろいろな人達の
利益がやっと一致したのか、なんとか一つの方向への協力体制が整ったのか?
事実はどうであったのだろうか?
日産自動車の元取締役で自民党の奥野信亮(しんすけ)元総務副大臣(74)=衆院比例近畿=が産経新聞のインタビューに応じ、カルロス・ゴーン容疑者について「外資系の経営者だ。『世界は自分中心で動いている』『自分さえ稼げばよい』という感じがする」と語った。今回の事件の背景に関し「社内にイエスマンだけが残り、ガバナンスの問題につながった」とも指摘した。
奥野氏は昭和41年に日産に入社し、販売促進部長などを経て平成8年に取締役に就任。11年に当時の子会社の総合物流会社の社長となった。転身は、ゴーン容疑者が日産社長に就任する約2カ月前のことだった。
「日産の業績が悪く、(フランスの自動車大手)ルノーから『最強のコストカッター』がくると話題になっていた。当時の副社長に『(奥野氏が)いたら大げんかになる』と言われ、子会社に行った。日本は、みんなが納得できる収入を得て『幸せになろうよ』という文化だ。文化が違う」
奥野氏は日産本社を去った理由をこう振り返る。
ゴーン容疑者はコストカットと子会社株式売却による経営再建を進め、日産は「V字回復」を果たした。奥野氏は「やれることをやり、成果を出した。われわれ(旧経営陣)も悪かった」と評価した。
一方で、ゴーン容疑者の経営方針の欠点として、取引先会社との付き合い方をあげた。例えば、以前は複数の保険会社と取引関係にあったが、ゴーン容疑者は一番安い1社に絞ったという。奥野氏は「切られた他社は『それなら日産とは付き合わない』となる。コストは削れても、車は売れなくなる」と解説する。
奥野氏は13年にMBO(経営陣による企業買収)の形で日産から完全独立した。奥野氏は当時のゴーン容疑者について「買収額を提示したら、素直に受け入れた。金に換えられるからよかったのだろう。ビジネスライクだ」と指摘する。
日産関係者と話す際、よく話題に上るのはゴーン容疑者の高額報酬という。奥野氏は「日本企業は外国人に弱すぎる」と主張。「受け入れる際には『ゴーンに任せる』となり、社内は何も言えない状況だった。モノが言えそうな人は外に出され、イエスマンだけが残った」と振り返る。
受け入れを決めた「当時のトップがバカだった」とも語った。(沢田大典、佐々木美恵)
◇
【インタビュー詳報】
率直な感想?(カルロス・ゴーン容疑者は)外資系の経営者だな。海外の子会社の金で住宅を買ってもらっていたというが、事実なら、悪いやつだ。「世界は自分中心で動いている」「自分さえ稼げばよい」という感じがするよね。日本は違うだろう。みんなが納得できる収入を得て「幸せになろうよ」というのが日本文化だ。基本的には、文化の違いですよ。
日産の取締役だった平成11年、副社長から「ゴーンがくるんだけど、お前がいたら大げんかになる」といわれた。「そうだね」といって、ゴーンが日産社長になる2カ月前に辞め(子会社の社長になった)。上の人たちも配慮してくれたんだね。
「最強のコストカッターがくる」と話題になっていた。ゴーンが日産に来るのは(フランスの自動車大手)ルノーのチョイス。「強欲」という評判は当時は聞かなかった。経営会議などで議論はしたが、社長が「決めてきた」というのだから、しようがない。当時のトップがバカだった。
ゴーンを最初に見たのは11年5月。日産の役員食堂でひとりでピラフを食べていた。
〈12年3月、奥野氏は別の日産子会社と合併するためにゴーン氏と交渉。最初は難色を示していたが「1億円の利益を出す」「リスクは奥野氏側へ」などの条件で合意した。しかし1週間後にゴーン氏の側近から「利益は6億円」とハードルを上げられた〉
そういうこともあって、13年に日産から(子会社を買い取り)独立した。ゴーンは売らないと感じていたが、交渉したら割と素直に「いいよ」と。彼は自分の成果を出さなきゃいけないから、金に換えられるものはどんどん換えた。ビジネスライクだった。
日産でのコストカットは、僕らでも分かるアイデアだった。どんどん切った。でも、日本文化にそぐわないものがあった。ダメだよ、と思ったものもある。損害保険や自動車保険は、複数の会社と、お互いに助け合うというやり方をしていた。でも、ゴーンはいちばん安い1社だけ。他は切ってしまう。他社は「もう日産とは付き合わない」となり、車が売れなくなる。だから一時期、業績が悪化したでしょう。
ゴーンは自分の気に入らない人は捨てていく。抵抗する人は外に出す。周りにイエスマンだけが残る。自分と同じ意見の人ばかりだと世界が狭くなる。これがガバナンスの問題につながっている。
事件後、日産関係者とは話していない。こうなる前によく聞いたのは「しっかり経営している。ただし、給料が高すぎる」ということだ。日産に限らず日本企業は外国人に弱すぎる。日本人経営者にも同じように払えと思うよ。日本人の経営者を育てていかないと。
日産がルノーとの関係見直しなどを検討しているんだってね。腹の据わった人間が何人いるかだな。外部から人材を引っ張ってこないとできないとも思う。僕に「いつ、日産会長として戻るのか」と言ってくる人もいる。もちろん笑い話だよ。 (沢田大典)
【プロフィル】奥野信亮
おくの・しんすけ 昭和19年生まれ。慶応大卒。日産自動車取締役、総合物流会社、バンテック会長を経て平成15年の衆院選に自民党から出馬し初当選。衆院当選5回。父は奥野誠亮元法相
日産自動車の代表取締役会長カルロス・ゴーン容疑者だけの問題ではないと思う。
日産自動車の代表取締役会長カルロス・ゴーン容疑者(64)の役員報酬を巡る金融商品取引法違反事件で、日産が2002年以降、ブラジルに住むゴーン容疑者の姉とアドバイザー業務の契約を結び、毎年約10万ドル(現在のレートで約1120万円)の報酬を支払っていたことが22日、関係者への取材で分かった。姉の業務に実態はなく、不正な経費の支出だった可能性があり、東京地検特捜部は経緯を調べている。
ゴーン容疑者が社長兼最高経営責任者(CEO)に就任した直後の02年、日産は姉と業務契約を締結。その後の社内調査で、業務に実態がないことが分かった。
文科省は公平な扱いのために同じ問題を抱える大学を公表するべきだと思う。
大学の医学教育の質が国際水準に達しているかを評価する民間機関「日本医学教育評価機構」は22日、不正入試のあった東京医科大の認定取り消しを決めた。
同機構は医学教育の質改善を促す目的で2015年に設立され、全国の80医学部などが会員。昨年から認定制度を始めたが、東京医科大は一連の不正入試が判明したことから取り消しを決めた。
米国の医師国家試験受験には、機構に認定された大学出身者である必要があり、東京医科大卒業生らは米国で医師免許が取得できなくなる可能性もあるという。
日立製作所グループの化学大手、日立化成は22日、検査不正問題を巡り、副社長の降格や社長らの報酬返上など役員15人の処分を発表した。特別調査委員会がまとめた報告書では、不正発覚後も不適切な検査を続けたり、不正を隠したりしていたことが判明した。
日立化成は6月にビルなどの蓄電池について品質検査書のデータ捏造(ねつぞう)を公表。弁護士らによる調査委の報告書によると、不正は国内全7カ所の工場で行われ、一部は1970年代から続いていた。対象製品は半導体材料や自動車部品など30製品に及び、出荷先は延べ2329社。日立化成の連結売上高の13.9%を占めた。
22日付で野村好弘執行役副社長は代表権を失い執行役専務に降格、羽広昌信執行役を事実上解任した。月額報酬の減額は、田中一行会長と丸山寿社長が50%、その他の執行役11人は20~30%をそれぞれ12月から3カ月分減らす。田中会長は日立製作所の取締役を22日付で辞任した。
調査委が社内のメールを調べたところ、野村副社長は執行役だった2008年に不正検査の内容を示す添付ファイルを見落としていたことが判明。羽広執行役は同年に検査結果の改ざんと不適切な製品の出荷を決定していたため、それぞれ重い処分を下した。三重県名張市の工場では不正発覚後も不適切な検査を継続。埼玉県深谷市の工場では9月まで不正を隠し、品質保証部門以外に開発部門でも不正があった。
記者会見した丸山社長は「社員に顧客との約束より納期や効率を優先する文化が広がっていた」と謝罪した。【土屋渓】
日本の企業は外国企業や外国人と比べれば比較的に良いが、良い企業や人間ばかりではないと言う事であろう。
三菱電機が、社内の品質基準を満たさないゴム部品を使った製品を鉄道車両向けなどに出荷していたことがわかった。ゴム部品を製造する子会社が必要な検査を実施していなかった。問題のゴム部品は、工場の自動化支援機器やビル設備、電力関連機器、自動車部品など幅広い製品にも採用されていたとみられる。
問題の部品は、三菱電機が100%出資する子会社のトーカン(千葉県松戸市)で製造。大半は三菱電機向けに出荷されていた。
関係者によると、トーカンは少なくとも10年ほど前から三菱電機に約束した品質検査をせず、品質データを偽装していた疑いがある。三菱電機は、鉄道車両のモーターや推進制御装置などをつくる伊丹製作所(兵庫県尼崎市)を中心に問題の部品を仕入れていたという。三菱電機からの出荷先は数十社以上になる見通し。このゴム部品の検査不正が原因で、出荷先に約束した仕様を満たしていない疑いのある製品も見つかっており、三菱電機は一部の出荷先に説明を始めている。
三菱電機は1カ月以上前にトーカンから報告を受け、社内調査に着手。「今のところ安全性の問題は見つかっていない」(広報)としているが、問題の部品がどの製品に使われていたかは、調査中を理由に明らかにしていない。
外国人役員の報酬が高額なケースが多いのはわかった。つまり、日本人の役員は能力的に確実に劣ると言う事なのか?
もし、外国人役員と比べて日本人役員が能力的に劣ると言うのであれば、いつ、どこから能力的な差が開いていくのか?
日本の会社の教育方針や組織の体質問題に原因があるのか?
メディアはにはもっとわかりやすい説明をしてほしい。
「企業改革のため高額報酬で迎える外国人は、いわばプロ野球の“助っ人外国人”のような存在だという。」
ぜんぜん、説明になっていない。もし、給料は能力次第であるのなら、能力がない日本人は年功序列や勤続年数に関係なく、給料は低いままで
あっても仕方がないと思う。
日本のメディアはカルロス・ゴーン容疑者を悪者のように取り上げているが、確かに、彼は人間的に問題があったかもしれない。
カルロス・ゴーン容疑者はCEOを解任されるそうだが、もし、カルロス・ゴーン容疑者が解任された後に利益が極端に減れば、それは
日本人役員ではカルロス・ゴーン容疑者が達成してきた事が出来ない事を証明し、日産の従業員が一生懸命頑張っても
能力がある経営者がいないと大きな利益は出せないと証明する事になると思う。
日産従業員達はカルロス・ゴーン容疑者に裏切られたとか、騙されたとか言う前にゴーンがいなくても、これまで通りに利益を出せる事を証明しなければならないと思う。
報酬を過少記載していた疑いで逮捕され、衝撃を与えた日産自動車のカルロス・ゴーン容疑者。果たしてこのような“巨額報酬”は適切なのか、役員報酬という視点で、日本企業の実態に迫る。
【画像】上場企業の巨額報酬役員トップ20
トップ10は全員10億円以上
ゴーン容疑者が、2011年3月期からの5年間で得ていた報酬は、およそ99億9800万円。
では、日本の上場企業の役員トップは、いったいどれほどの報酬を受けているのか。1億円以上の役員報酬を得ている上場企業の役員は有価証券報告書で開示する義務がある。
そこで、今年4月までの1年間の『役員報酬ランキング』を見てみると、驚きの巨額報酬が明らかになった。
役員報酬のトップとなったのは、ソニーの平井一夫前社長で、総額は27億1300万円。ソニーの業績をV字回復させ、新型aibo発表などで話題をさらった平井氏。
2月にサプライズ退任を発表したが、11億8200万円もの株式退職金が支払われるなど、堂々のトップとなった。
2位はセブン&アイ・ホールディングス取締役のデピント氏で、24億300万円。3位から5位まではソフトバンクグループの外国人経営陣が入ったが、トップ10は全て10億円以上。
ゴーン容疑者の開示された報酬額は日産から7億3500万円で、全体の18位。同じく会長を務める三菱から2億2700万円と、日本企業からの報酬は合計しても10億円に満たず、突出して多い金額ではないことが分かる。
トップ20のうち半数以上が外国人役員
役員報酬額トップ20のうち外国人役員が半数以上を占め、21位にも、報酬額6億3200万円の日本マクドナルドのカサノバ社長が入るなど、多くの外国人役員が巨額報酬を得ていた。
なぜ、巨額報酬を受けている役員に外国人が多いのか?経済ジャーナリストの磯山友幸氏は「世界の経営者の報酬は数十億円という規模で、日本に比べると遥かに高い。その人たちを日本の企業に呼んで来ようと思うと、日本の給料よりかなり高額を提示しないと日本に来てくれない」「プロ野球で助っ人外国人を雇うためには世界標準、つまり大リーグと同じ給料を払わないと来てくれないというのと一緒」と解説する。
企業改革のため高額報酬で迎える外国人は、いわばプロ野球の“助っ人外国人”のような存在だという。
企業トップよりも役員が高額報酬のわけ
外国人役員が企業トップよりも報酬が高額なケースも多く、ソフトバンクでは、報酬額3位から5位を外国人役員が占めまたが、グループを率いる孫会長は、役員報酬額1億3700万円で、403位。
トヨタも豊田章男(とよだ)社長は、役員報酬3億8000万円で52位なのに対し、ルロワ副社長が3倍近い10億円以上の役員報酬を受け、10位に入っている。
こうした背景には、創業者に近い人は株を沢山所有しているので、株式の配当が年間何億円も入ってくる人が多い。そのため、企業トップの給料は役員よりも少ないケースが多いとみられる。
過渡期ならではの“貰い得”
磯山氏は“日本企業が転換期を迎えている”と指摘する。
磯山氏:
日本の場合はバブルが崩壊して、その後に日本の企業が経営改革に取り組んでいくようになる段階で、外国人を入れようという流れが出てきた。1999年の日産自動車がカルロス・ゴーンを入れるのも一つの流れだと思う。
いまは日本の報酬体系を変えていこうという過渡期だと思う。ゴーンさんの場合は、本当は短期間のリリーフ型だった人なのに、その人が19年間君臨してしまった。それは日本企業だからできる、そこが非常に問題の端緒なところ。
多額の給料は貰っているけど、それほど責任追及はされない、非常に過渡期ならではの、“貰い得”が起きている。
(「プライムニュース イブニング」11月19日放送分より
油圧機器大手「KYB」による免震・制振用オイルダンパーの検査データ改ざん問題で、説明会が全く開かれないなどマンションへの対応が遅れ、住民側が不信感を強めている。16日で問題発覚から1カ月が経ったが、15日には新たな不正の疑いが明らかになり、影響がさらに広域化、長期化する可能性も出てきた。
【一覧】不適切な免震用オイルダンパーの物件数
「大変心配されていることと存じますが、早期交換に向けての交渉を進めてまいります」。データが改ざんされたダンパーが使われた疑いがある東京都世田谷区のマンションで10月22日、このような文書が管理組合から入居者に配られた。築10年に満たず、組合はKYBとゼネコンに建物への影響や今後の対応について書面での回答を要求。KYBから回答はないが、ゼネコンから「KYBから不適合品は交換すると連絡を受けており、しっかり対応する」と返事があった。時期や費用など具体的な内容は知らされていない。
80代の男性は「不具合があれば交換は当然。工事中は一時的に退去しないといけないのか、いくらかかるのか、きちんとした説明を待ちたい」と話した。
東京都中央区のマンションでは10月下旬、ゼネコンの担当者が管理組合の理事会を訪れ、1時間ほど説明。「KYBに連絡しているが官公庁を優先に対応しているようだ」「長くても2年以内には対応を終えたい」などと述べたという。理事の男性は「資産価値が下がるのでは、と気にしている住民もいる」と話す。
KYBによると、不適合品が使われた疑いのある建物は974件。うち262件と最も多いマンションなど住宅について、住民説明会を開いた上で交換作業に入るとしているが、16日時点で説明会は1件も開かれていない。マンションは開発業者や管理会社を調べるのに時間がかかり、住民側への説明が遅れているという。
さらに同社は15日、改ざん行為が新たに見つかった疑いがあると発表。外部調査委員会の聞き取りに作業員らが説明したという。係数を不正に入力するこれまでの方法とは異なる手口だったといい、KYBは追加の調査を始めたことを明らかにした。今後、不適合品が使われた建物数が増える可能性もある。
また、2020年9月としていた交換終了予定時期について、「個別の話し合いが予想され、そこで終わるかは約束できない」(加藤孝明副社長)としていたが、さらに遅れる懸念が高まっている。
全日空のグループ会社の男性元機長(諭旨退職)が飲酒の影響で乗務できず、国内線5便が遅延した問題で、元機長が深酔いしていたとの連絡が宿泊先のホテル側から会社に寄せられていたことがわかった。
ANAウイングスの元機長は10月24日午後5時頃から、沖縄県石垣市内の飲食店4軒でビールなどを飲酒。翌朝の石垣発沖縄行き便に乗務予定だったが、体調不良で乗務できなかった。全日空によると、元機長は25日午前0時45分頃に定宿のホテルに戻ると、別の部屋のドアを開けようとするなどひどく酔っており、ホテル側が25日午前、その様子をウイングスに報告した。元機長は4軒目の店で泥酔してホールで寝ていた姿も確認されたという。
「乗務員の飲酒規制は航空法などで定められているものの、具体的な数値などは設けられておらず、運用は各社に一任されている。・・・内部調査の結果、日航は副操縦士が呼気検査の際に機器に吹きかける息の量や角度を変えるなどの不正を行っていたと認定。検査の様子を見ていた機長2人についても『相互チェックを怠っていた』と認めた。」
企業が本当にしっかりしていれば、アルコール検査をしっかりとするし、不正を行う操縦士は存在するとしても、内部チェックで見つけられて
組織から除外されるだろう。ただ、LCCの価格競争やパイロット不足など環境の変化が起きているなかで厳しい対応は難しいと思う。
LCCが成長してきた時点で国交省は航空法を改正し乗務員の飲酒規制に関して具体的な数値を示し、検査方法や検査記録の保管など明記するべきであったと思う。自分に関係なければ飛行機事故で何百人死亡しても大したことではないが、関係者や被害に遭った家族にとっては人生を大きく変える
出来事であり、賠償金や損害賠償で終わらせる事は出来ない。「飛行機事故で何百人死亡しても大したことではない」と残酷に書いたが、口には
ださないがそう思っている人達が航空業界や国交省に存在するから日本の航空法第七十条が改正されてこなかったのだと推測する。
口に出さなかったり、文書として残さなければ、証拠として残らないので裁判で責任を問われる事はないであろう。他の裁判の判決を見れば
簡単に推測できる。だからこそ、航空法の改正は必要だと思う理由の一つ。
日本航空は不正を行う操縦士はいないと判断して旧式のアルコール検査器を使い続けたのかよくわからないが、残全ながらそれは今回の副操縦士の逮捕で間違いであると証明された。
逮捕された副操縦士がアルコール検査だけで不正していたのか、それ以外でも不正していたのかわからない。横領や着服事件では小さい額の
横領がばれないのでどんどん着服額が大きくなるケースが多い。そう考えると重大事故を起こす可能性が高くなっていくリスクは存在したと思う。
航空業界で飲酒に絡む不祥事が相次ぐ中、日本航空と全日空が16日、不祥事の経緯や再発防止策をまとめた報告書を国土交通省に提出した。乗務員の飲酒規制は航空法などで定められているものの、具体的な数値などは設けられておらず、運用は各社に一任されている。国交省は規制強化を図る方針で、業界関係者は空の安全確保に向けて「意識改革も急務だ」と訴える。
■アルコール検査、義務付けなく
「絶対にあってはならない事例を引き起こした」。ロンドンで10月、搭乗予定の男性副操縦士が現地法令の約10倍のアルコールを検出され、逮捕された日航。この日記者会見した赤坂祐二社長は沈痛な面持ちで陳謝した。
内部調査の結果、日航は副操縦士が呼気検査の際に機器に吹きかける息の量や角度を変えるなどの不正を行っていたと認定。検査の様子を見ていた機長2人についても「相互チェックを怠っていた」と認めた。
日本では航空法などに基づき、アルコールで正常な業務ができない状態での乗務を禁じている。違反すれば懲役か罰金の刑罰があるほか、乗務開始前の8時間の飲酒も禁止しているが、アルコール検査の義務付けはなく、各社の判断に委ねている。
日航では、乗務の基準を呼気1リットル当たり0・1ミリグラム未満とし、国の基準より厳しい乗務開始12時間前の飲酒も禁じてきた。ただ、逮捕された副操縦士が検査で使ったアルコール検査器は、息を吹きかけるとランプが明滅する旧式タイプ。日航は昨年から、ストローで息を吹き込むとアルコール濃度の数値がデジタル表示される新式への移行を進めていたが、海外空港では配備が遅れていた。
一連の問題を受け、日航は飲酒の禁止を乗務開始前の24時間に広げ、滞在地での飲酒を原則禁止とするなど規則を厳格化した。国交省も、飲酒運転を厳格に規制する道交法や、海外の航空関係法令などを参考に、年内にも対策をまとめる方針。石井啓一国交相は「国民の信頼を損ないかねない」と強調した。
■業界に飲酒認識甘い風土
ただ、飲酒そのものは乗務員自身の判断で、具体的な飲酒時間や酒量を検証するのは事実上不可能だ。日航では昨夏以降、操縦士の「基準超」が発覚し、運航が遅れるなどしたケースが19件相次いだ。全日空でも平成25年度以降、乗務員の出発前の呼気検査で基準値を超えたケースが8件あった。
航空業界関係者は「飲酒への認識が甘い風土が業界にあり、過去に『見逃し』があった可能性は否定できない」と警鐘を鳴らし、意識改革の必要性を強調する。
一方、元日航機長で航空評論家の小林宏之さんは「多くの人の命を預かるパイロットは自己管理をして当たり前」と今回のケースを厳しく批判。「パイロットも一人の人間であり、疲れもあればストレスもある。日航は今回の不祥事を受けて、飲酒を乗務24時間前にするなど管理を厳しくしているが、パイロットのストレスや疲労へのケア、教育も並行して行うことで、初めて再発防止につながる」と話した。
■バスやタクシー、鉄道は…
運輸業界の飲酒対策をめぐっては、タクシーなどの運送業ではドライバーが乗車前に呼気検査を行うことが法令で定められている。航空業界と同様、運用が各社に任せられている鉄道業界では、より厳しい基準を設けて対応する企業もある。
国土交通省によると、バスやタクシー、トラックなどの運送業では、営業所ごとにアルコール検査器を設置し、乗る前の点呼で使用が義務づけられている。ある事業者は「乗務前にアルコール濃度を測るのは常識。基準値を超えれば運転手にはそのまま帰ってもらうし、評価に影響することもある」と話す。
鉄道では省令で酒気を帯びた状態で列車に乗務してはならないと規定されているが、検査方法や罰則についての具体的な取り決めはなく、各社ごとに独自の基準を設けている。
東急電鉄では管理者の前で運転士がアルコール検査器を使用している姿が自動で撮影されるシステムを導入。担当者は「身代わりなどを防ぐため」と説明する。JR東日本も管理者の面前で呼気検査を実施し、運転士や車掌が正常な状態か確認している。
「日本航空の副操縦士が乗務前の飲酒でロンドンの警察当局に逮捕された事件」がなければ、多くの日本国民は現行の日本の航空法の問題について
知らなかった。そして監督官庁である国交省が現状の問題及び日本の航空法の改正の必要性を把握していたのは知らないが、知っていたのなら知って
いたで問題だし、知らなかったのであれば管理及び監督が出来ていなかった事で大問題だ。
飲酒が影響する飛行機事故が起きる前に日本航空の副操縦士が飲酒でロンドンの警察当局に逮捕された事で見逃されてきた問題が注目されたのは良かった。ある意味、自業自得であるが、問題が注目される切っ掛けを作った日本航空の副操縦士は良い事をしたと思う。飲酒だけでなく、アルコール検査の
不正が存在し、不適切な体制の継続及び内部審査の可能性まで疑わせる事件のインパクトは多いと思う。
安全に対する対策が形骸化している可能性が疑われる。本来はお互いのチェックにより安全性が高められるはずが、ほとんど機能していない現状が
露呈した。
贄川俊、北見英城
報告書は、副操縦士の同僚機長2人が測定時に相互確認を怠っていたことも判明したとし、パイロットの乗務前検査が形骸化していた実態が浮き彫りとなった。
日本航空の副操縦士が乗務前の飲酒でロンドンの警察当局に逮捕された事件で、日航は16日、副操縦士が社内のアルコール検査では息を検知器に吹きかけず、意図的に不正を行った、などとする報告書を国土交通省に提出した。機長2人も相互確認を怠ったと認めた。同省を訪れた赤坂祐二社長は「再発防止策を迅速かつ的確に実行したい」と話した。
車で出勤してるなら…飲酒検査、航空会社の緩い危機意識
拘束のJAL副操縦士、社内呼気検査を不正にすり抜けか
JAL副操縦士、英で拘束 乗務前に基準超すアルコール
日航の副操縦士はロンドン・ヒースロー空港で10月28日、乗務前に現地の基準値の10倍以上のアルコールが検出され英国当局に逮捕されたが、直前の社内の呼気検査では検出されなかった。このため国交省は、詳しい経緯について日航に報告書の提出を求めていた。
日航は、副操縦士と対面でアルコール検査をした2人の機長から聞き取りを実施。その結果、検査時に副操縦士が2人と距離を置こうとしていたことや、副操縦士が検知器に息を吹きかける様子の確認を2人が怠っていたことが判明。検査に使った「簡易型」の検知器では不正ができることも確認できたことから、「必要な呼気を検知器に吹きかけず、意図的に不正な検査方法で検査を行ったと認識している」と結論付けた。副操縦士が「個人的な悩み」を抱えて過度な飲酒をした可能性も指摘した。
日航は再発防止策として、国内…
日本航空の男性副操縦士が、英国の空港で飲酒の影響により乗務できず、遅延が発生するなどした問題で、日航は16日午前、調査経過や再発防止策をまとめた報告書を国土交通省に提出した。副操縦士が乗務前、測定に必要な呼気をアルコール感知器に吹きかけず、不正に検査をすり抜けたとの認識を示した。
報告書は、副操縦士の同僚機長2人が測定時に相互確認を怠っていたことも判明したとし、パイロットの乗務前検査が形骸化していた実態が浮き彫りとなった。
副操縦士が乗務予定日の前日にワインやビールなどを多量に飲んだ要因については「個人的にさまざまな悩みを抱えていたようだ」としたほか、意識の低さ、アルコールの影響に関する認識の欠如などを可能性として挙げた。
日航は「組織全体の問題」として、副操縦士本人だけでなく、管理監督者に対しても厳正に対処するという。
「JACは機長2人が基準を超えたが、遅延に繋がったのは1件。『具体的な値は記録が残っていない』としている。」
記録が残っていないのは記録として残すと問題になるほどに値だったと推測した方が良いと思う。
旅客機乗務前のパイロットに対するアルコール検査で呼気から社内基準を超える量が検出されたことが原因で、昨年4月以降、日本航空など3社で計16件の遅延が生じていたことが15日、分かった。各社とも乗務前12時間以降の飲酒を禁止するなどの基準があるが、大量飲酒で体内にアルコールが残ったままだったとみられ、国土交通省は規制の強化に踏み込む。
遅延は日航で12件、グループ会社のジェイエア(大阪府)で3件、日本エアコミューター(JAC、鹿児島県)が1件。パイロットの交代や追加検査のために生じており、日航では1分から1時間11分だった。内訳は国内線10件、国際線2件。対象者は機長8人、副操縦士が4人。
日航の社内規定では、乗務の12時間前以降の飲酒を禁止し、さらに搭乗する全パイロットは乗務前のアルコール検査が必要。基準値は呼気1リットル当たり0・1ミリグラム未満。自動車の運転では0・15ミリグラム以上が酒気帯び運転として違反になるので、より厳しい基準だ。
ところが、検査では0・12~0・25ミリグラムのアルコールが検出。12件のうち8件はパイロットが交代した。加えて、遅れには繋がらなかったものの基準値超えが7件あり、このうちの5件でもパイロットが交代していた。
遅延ケースについて飲酒状況の聞き取りをしたところ、時間の規制は守られていた。ただ、最大500ミリリットル入り缶ビール5本程度に相当する量の飲酒をしており、乗務までに体内で分解できるアルコール量を超えたとみられる。
日航はアルコール検査厳格化のため、昨年8月以降、息を吹きかけて測定する検査機器から、ストローで息を吹き込む新型に更新。計19件は全て国内空港の新型機器による検査で判明した。
一方、ジェイエアは機長1人と副操縦士2人で0・16~0・25ミリグラムを検出。JACは機長2人が基準を超えたが、遅延に繋がったのは1件。「具体的な値は記録が残っていない」としている。
パイロットの飲酒問題が相次いでいることから、国土交通省は日航と全日空に16日までの再発防止策の報告を指示。さらに呼気中のアルコール基準値を新設するなどルールの厳格化を図ることにしている。
「パイロットの飲酒を巡っては10月末、日本航空の副操縦士がロンドン警察当局の呼気検査で英国の基準値以上のアルコールが出たとして逮捕された。一方、日本では現在、航空法にもとづき、通達で乗務前8時間以内の飲酒を禁じているものの、検知器の使用は義務ではなく、検査方法や基準は会社任せになっている。」
日本の航空法が世界や現状にあるように改正されていなかったので、「日本航空の副操縦士がロンドン警察当局の呼気検査で英国の基準値以上のアルコールが出たとして逮捕」は時間の問題、又は、運しだいで、起こる問題であったと言う事が良く理解できた。
国内の航空会社8社が、乗務前のパイロットに、検知器によるアルコール検査を義務づけていないことがわかった。朝日新聞が国内25社を対象に聞き取り調査した。残り17社のうち12社は、精度が低く検査逃れをしやすい「簡易型」の検知器を主に使用していた。
パイロットの飲酒を巡っては10月末、日本航空の副操縦士がロンドン警察当局の呼気検査で英国の基準値以上のアルコールが出たとして逮捕された。一方、日本では現在、航空法にもとづき、通達で乗務前8時間以内の飲酒を禁じているものの、検知器の使用は義務ではなく、検査方法や基準は会社任せになっている。
今回の調査で、検知器による検査を義務づけていないと答えたのは、ジェットスター・ジャパン、アイベックスエアラインズ、日本貨物航空、エア・ドゥ、新中央航空、東邦航空、オリエンタルエアブリッジ、天草エアラインの8社。
各社は乗務前に対面でチェックするなどと規定しているが、ジェットスター・ジャパンとアイベックスエアラインズの2社にはそもそも検知器がなかった。
ほかの6社は、対面のチェックで飲酒の可能性がある場合のみに検知器を使うと定めているが、いずれも検知器を使った実績はないという。
今年もあと残すところ1カ月半ほどになった。この1年も、相変わらずさまざまな不祥事が目立った。最近も、油圧機器大手の「KYB」とその子会社による免震制振オイルダンパーの検査データ改ざん、そして自動車メーカー「SUBARU(スバル)」の出荷前検査不正行為。大手出版会社「新潮社」による「『新潮45』休刊騒動」などなどだ。
さらに、日本大学や東京医科大学といった教育機関関係のトラブルも多かった。ボクシング協会やレスリング協会のパワハラ、セクハラといった問題も浮上した。
こうしたトラブルの背景には、市井の人々がTwitterやブログなどで、広く世に情報発信できるようになったことと関係があるのかもしれないが、それにしても日本全体のタガが緩んでいるような印象を持った人も少なくないのではないか。
トラブルの原因はさまざまだが、問題なのはその対応に時間がかかりすぎたり、あるいは対応法が間違っていたりすることが多かったということだろう。
たとえば、KYBの免震ダンパー問題も、15年以上もの間、データ偽装の事実がわかっていながら放置して発表してこなかった。組織ぐるみの確信犯と言われても、反論の余地がない問題だ。スバルの出荷前検査問題に至っては、偽装が明るみに出てリコールを連発した以降も偽装を続けていたことが明らかになっている。
■目の前のトラブル対応に終始する日本の悪い癖
もともと日本企業は、昨年あたりから不祥事が次々に明らかになって、その対応ぶりがコロコロ変わるなど大きな批判を受けてきた。印象に残っているケースでは神戸製鋼所や三菱マテリアルといった歴史のある古い企業が、記者会見で返答をくるくる変えるなど不適切な対応が目立った。
とりわけ批判されたのが、問題発生から解決に向かう際に初動ミスがあり、情報開示の姿勢が疑問視されたことだ。経営トップの不適切な発言や不透明な発言も数多く出てきて、日本企業全体の信用度、信頼度に疑問を持たれたケースも少なくない。
たとえば、三菱マテリアルの製品品質データ改ざん問題では、当初本社による記者会見では「偶発・軽微なミス」と主張していたのが、東京地検特捜部の強制捜査などが始まってからは、一転して子会社がデータ改ざん表面化以降も改ざんを続けており、資料隠蔽の指示が本社からあったことまで明るみに出ている。
日立化成や東レ、宇部興産といった伝統ある企業でも、検査データの改ざんなどが発覚。さらに、人事の不透明さといった面でもさまざまな批判が集中した。社長が責任を取って辞任するとしながらも会長職に就くなど人事面でも疑問が持たれる対応が目立った。
こうした企業風土は、現在もほとんど変わっていないような気がしてならない。KYBのデータ偽装事件にしても、スバルにしても日本企業の本質は変わっていないのだ。自ら不祥事を発表した企業も今年は多かったが、まさに「赤信号、みんなで渡れば怖くない」といった集団心理を連想させる。
日本大学の危険タックル問題は記者会見が油に火を注ぐこととなり、東京医科大学の不正入試問題も大学が当初意図した反響とは大きく違う方向に行ってしまったのではないか。 それだけ状況分析を各大学とも見誤ってしまった結果かもしれない。
ここ数年の日本企業や政府のトラブル対応を見ていると、その大半がとりあえず目の前の問題を何とかしよう、という場当たり的な解決策に終始している、という印象を受けてしまう。『新潮45』の休刊問題でも、当初は社長のコメント発表で、何とか目の前の状況を収拾しようとしたものの、結局は最悪の結果になってしまった。
■誠心誠意謝罪するのが問題解決の基本
問題が表面化した段階で、最初から非を認めて、その解決策を示したほうがよかったのかもしれない。
そもそも企業や政府の説明責任というのは、もし誤りがあればそれを正して人々に理解を求めることが大切になる。しかし、報道されていることが真実であった場合、あるいは言い逃れようがなく明白な事実であれば、ごまかすのではなく誠心誠意謝罪するのが問題解決の基本といわれる。問題解決のコンサルタントや専門家の間では、説明責任や謝罪で最も大切なのは「誠意」と言われている。こちら側にミスがあった場合には、誠意をもって謝罪する以外に方法はない、ということだ。
ところが日本ではその基本がないがしろにされることが多い。パワハラがあったのに「パワハラはない」と言い逃れをする、いじめが存在しているのが明白なのに、「調査中」という言葉で誤魔化そうとする。要するに、部分的には認めつつも大筋では認めないなど、誰もがうそだとわかる稚拙な言い訳が繰り返されている。テレビや新聞で忖度されて報道されている、近年の国会を舞台とした議論や言い訳と同じ光景だ。日本中がうそや矛盾に満ちた言い訳に対してマヒしつつあるのかもしれない。
一方、日大アメフト部で反則を犯した学生が記者会見をしたが、彼の誠実で誠意ある対応が日本中の人々に支持されたのも、誠意ある謝罪とその解決策の提示が問題解決への正しい方法であることを示している。
誠意ある謝罪をしたところで、犯してしまった間違いや失敗はそれだけでは許されるものではない。謝罪と同時に、トラブルへの対応や賠償への補償といったものをきちんと示す必要がある。加えて、二度とこうしたことが起こらないようにするための将来的なビジョンを示す必要がある。
こうした一連の問題解決のプロセスが日本の企業や大学、公共団体など、幅広い層に不足しているとみていいのかもしれない。こうした謝罪や説明責任は、個人に対しても同じことが言える。
昨年同様に今年ほど、トラブルの問題処理が問われた年はなかったのではないか。数多くの日本企業や教育機関の広報部門の質の劣化だけではなく、そうした問題解決に優秀な人材や資金を投じていないことも明らかになった。
しかし、それ以上に問われるのは「トップ」の資質だ。不祥事に対して組織のトップが最後まで公に顔を出さずに幕引きを図ろうとしたり、会見を開いたとしても誠意のない対応を見せたりするようなケースが目立つ。
背景にはあるのは、日本企業の多くが終身雇用制を取り、新卒一括採用で採用された社員が、派閥争いを生き抜いてトップに上り詰めたような人が多いからだと、個人的には考えている。イエスマンであることがトップになる条件であり、彼らには謝罪や反論は苦手なのかもしれない。
■結局はガバナンスの欠如とコンプライアンスの概念失墜
日本企業のトラブルが相次いでいる直接的な原因のひとつは、「コーポレートガバナンス(企業統治)」の欠如が原因と言っていいだろう。とりわけ、グローバル化が遅れている日本企業の中ではコーポレートガバナンスが欠けている企業や団体が目立つ。
最近になって教育機関のガバナンスも問題視されているが、これも海外との接触があまりない機関独特の問題と言っていいかもしれない。
コーポレートガバナンスというのは、東証などを傘下に持つ日本取引所グループの定義によると「会社が株主をはじめ、顧客や従業員、地域社会等の立場を踏まえたうえで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを意味する」となっている。
そのためには、「適切な情報開示と透明性の確保」という項目が基本原則として設けられている。適切な説明責任が、きちんとした情報開示とともに実施されることが、ガバナンスを維持する最大の要件の1つと言ってもいい。
コーポレート・ガバナンスは、企業が存続可能な成長を維持するために必要不可欠なものであり、そのためにどんなことをすればいいのかを企業は常に考えていかなくてはいけない。ちなみに、これは政府や自治体などにも言えることであり、ガバナンスができていない団体は今後もさまざまな問題を連発し続けることになるはずだ。
そしてもう1つのトラブルの原因の1つが、「コンプライアンス=法令遵守」という概念の確立だ。当たり前のことかもしれないが、最近の日本企業の不祥事を見ていると、明らかに法律に反していることを平気でやっているケースが目立ってきている。企業利益を追求するあまり法令遵守を怠るといったことは、ありえない話だ。個人よりも企業、といった歪んだ価値観が日本社会には根強く残っている。
内部告発制度が国際的に求められているのも、 こうしたコンプライアンスとの関係が大きい。サウジアラビアのジャーナリストがトルコ国内で殺害された事件も、以前なら絶対に表にできないことが、現在では簡単に表ざたになる。
最近のさまざまなトラブルの原因と問題解決を急がなければ、日本企業はますます世界から取り残されていくことになるかもしれない。
岩崎 博充 :経済ジャーナリスト
不正が個人レベルなら解雇して終わりであるが、ガンのように組織に不正が広がっていれば簡単には収拾できない。
油圧機器メーカーKYBは15日、免震・制振装置の検査データ改ざんを巡り、既に判明している手法とは別の手法で改ざんが行われた疑いがあると発表した。これまで、不正やその疑いのある装置が使われている物件は974件と公表していたが、さらに増える可能性がある。
KYBは、2000年以降に装置の検査結果が基準を逸脱した場合に、データを改ざんして許容範囲に収めていたことが判明している。これまでは一つの手法を用いてデータを改ざんしていたとしていたが、07年以降は別の手法を併用してデータ改ざんが行われていた疑いが、外部調査委員会の聞き取り調査で新たに判明した。
KYBは14日に国土交通省に、追加の調査が必要となったと報告した。KYB製の免震・制振装置が出荷された物件数は計1404件。引き続き調査を実施し、詳細が判明次第、事実関係を公表するという。【松本尚也】
自分達の事しか考えていない単純な業界や人々が多いのには驚いた!
単純に外国労働者を受けれる事しか考えていなければ外国労働者が入ってくる事で起きる問題に対応できない。全体的に考えないと
プラスと思っていたら、大したプラスでない割に問題が増えることになる。
日本人は自分達で一生懸命働くことには優れているのかもしれないが、全体的に周りを見て判断したり、長期的に見てメリットがあるかを
判断する能力は教育のレベルの割には低いのかもしれない。それとも、偽善的な良い人達なのか?つまり、人に良い人と思われたい、良い評価を
受けたいから行動しているだけで、評価されない分野や環境では自己中心的な判断や選択を選ぶ傾向があると言う事か?
もしかすると日本人と言う表現が間違っているのかもしれない教育レベル、生活レベル、そして居住エリアの違いで意見や考え方に違いが
あるが、数ではそのような日本人が多いと言う事か?それとも政治力を持つマイノリティーが動いているのか?
外国人労働者の新在留資格を巡り、14業種の受け入れ見込み人数を政府が示したことについて、対象業界からは「一歩前進だ」と歓迎の声が上がった。ただ人手不足の見込み数に比べ、圧倒的に少ないため「焼け石に水だ」との声も。希望していたのに対象外となった業界は、今後も粘り強く政府に働きかける構えだ。
5年後に職員30万人の不足が見込まれる介護分野では、外国人5万~6万人を新たな在留資格で受け入れる。全国老人福祉施設協議会の石川憲会長は14日、「外国人材は必要不可欠。一人でも多くの受け入れが実現することを願っている」との談話を発表した。
大手介護会社の担当者は「受け入れ数が少なすぎる。このまま人手不足が続けば事業継続が難しくなる」。国の施設基準を緩和して必要な職員数を減らしたり、介護報酬による賃金改善で日本人を集めやすくしたりといった対策を訴える。
社会福祉法人千里会(横浜市)の牧野裕子・法人統括部長は、受け入れる働き手の「能力」を懸念する。経済連携協定(EPA)に基づきインドネシアとベトナムから来日した外国人職員は、現地の看護課程修了などを条件としているため、特別養護老人ホームの即戦力になった。「新しい在留資格で日本語や技能の要件がEPAより緩和されると、介護の質を保てず現場でトラブルが起きかねない」と話す。
外食業界は初年度に4000~5000人、5年間の累計で約4万1000~5万3000人を受け入れる。業界団体である日本フードサービス協会の金丸康夫専務理事は「議論を進め、今国会中に成立させてほしい」と期待した。
ただ5年後には外食業界だけで29万人の人手不足が見込まれている。飲食店を運営する大戸屋ホールディングスの担当者は「5万人のうち、どれだけ自社で採用できるか。乗り遅れないようにしたい」と話す。別の飲食店幹部は「これでは全然足りない」と不満を漏らした。業界内での人材争奪戦が激しくなりそうだ。
一方、対象から外れたコンビニやスーパーは、将来受け入れ対象になることをめざし、経済産業省などと協議を続ける。縫製業務などで外国人技能実習生を多く抱える繊維アパレル業界も「認定されれば工場の安定的な操業につながる。ぜひ対象に加えてほしい」(ワコール)と求めた。【今村茜、原田啓之】
労働者不足の話は横において、外国人が急速に増えて問題が起きた国の事を考えてみるべきだ。アメリカはどうなった?
多くのアメリカ人が外国人の移民、不法滞在者、そして安い労働力の国からに輸入にうんざりして「アメリカ ファースト」を
唱えるトランプ大統領を選んだ。
安い労働力で儲けた経営者は多いが、仕事を失ったり、安い賃金でよく働く外国人との競争で経営者が外国人を選び仕事を失った
多くのイギリス人がEU離脱を投票で選択した。
なぜこのような事が起きたのか?外国人労働者が長期的に自分達の生活に与える影響を考えなかった、又は、軽く考えていた結果だと思う。
日本は綺麗ごとを並べてごまかすのは止めるべきだ。専門技術を教えるとか、夢を見せるのは止めるべきだ。綺麗ごとを言うから
騙されたとか、話が違うと反発する理由を与えるのである。事実に近い説明をしてお金のために日本で働くのか、技術を覚えるために
働くのか、きちんと説明するべきである。
日本人に対してもブラック企業とか、過労死とか、サービス残業とかいろいろと問題がある。このような問題を抱える企業や会社が
外国人であればもっと酷い扱いする可能性だってある。企業は利益を出さなければ存続できない。違法や違反を繰り返さなければ生き残れない
会社は消滅しても仕方がないかもしれない。企業が採用したいと思えない人材は雇ってもらえない事を国民は理解しなければならない。
また、能力がある、又は、他の企業が雇いたいと思う人材であれば、会社が違法や違反を繰り返している、又は、不当な扱いをしていると
思えば、転職すれば良い。流動化すれば、バランスが取れる状況で落ち着く。
多くの企業が採用したい人材でなければ、就職先や給料で妥協するしか就職する方法はない。資格を取ったりする方法はあるが、資格が優先される
ケース、経験が優先されるケース、そして両方が必要とされるケースなど会社や業界によって違う。答えは一つでないし、景気やその他の
状況で同じ結果となるとは限らない。
不公平かもしれないが、日本人労働者を優遇する方向で考えなければ景気が悪くなると内部的な不満は爆発すると思う。
「日本で技術学びたいです。働くために私、来ました、帰れと言われても帰れません」
中国人技能実習生の黄世護さん(26)は、3本の指が欠けた右手を見せながら訴えた。
来年4月からの外国人労働者の受け入れ拡大をめざす出入国管理法改正案の国会審議が今週にも始まる。しかし、国内では外国人技能実習生の失踪が相次いでいる。昨年は7089人と過去最高の失踪者が生まれ、今年も6月までで4279人と昨年を上回るハイペースで推移している。
冒頭の黄さんら実習生が労働実態を報告する野党合同ヒアリングが8日、国会内であった。涙まじりの報告に“もらい泣き”する議員もいた。
実習生を支援するNPO法人『移住者と連帯する全国ネットワーク』の鳥井一平代表理事は、
「現状の技能実習制度は奴隷労働と同じ構造。これを改める議論もなく、外国人労働者受け入れ拡大に舵を切るのはおかしい。技能実習生の受け入れシェルターもほとんどない現状です」
と、現状の問題点を明かす。
外国人技能実習制度の実態から目を背けたまま、新制度の議論は始まろうとしている――。
「私は物じゃない」
「働きたいのに(指にケガをしたから)帰れと言われました。働きたいのに、なんで私、帰るんですか」
黄さんは'15年12月に来日、岐阜県にある段ボール製造工場で働いていた。'16年7月、作業中に手を機械に挟まれて指3本を切断してしまう。
2か月入院する重傷だったが、治療を終えた黄さんに告げられたのは、まさかの解雇通告だった。
「(解雇の書類に)サインしろ、と何度も迫られました。私が(指を失って)使いものにならないからでしょう。私は物じゃないですよ。人間です」
「家族にたくさん仕送りができると思ったのに」
パワハラに耐えかねて自殺を図った実習生もいる。
「ニホンが大嫌いになりました」
涙を流しながら語るのは中国人の史健華さん(35)。昨年8月に飛び降り自殺を図り、一命はとりとめたものの腰など3か所を骨折。今もリハビリに通っている。
「私は一生懸命働きました。でも差別やいじめがあり“中国人だから”と馬鹿にされパワハラで身も心も壊した。豊かな日本に行けば家族にたくさん仕送りができると思ったのに」
史さんは夫と子どもを祖国に残して'15年1月に来日。静岡県富士市の製紙工場で働いた。朝8時から深夜12時まで働いて手取りはわずか月10万円。午後6時以降の残業代は時給300円だった。静岡県の最低賃金は同858円。確信犯的な低賃金労働だった。
「聞いていたお給料と全然違いました」
渡航前は、1か月の手取りは20万円と聞いていた。中国の送り出し機関に約60万円の借金をしており、切羽詰まった状況に追い込まれた。
「このまま中国に帰ることもできない、何かを訴えたくても日本語でうまく表現できない」
絶望感にとらわれた史さんは昨年8月、仕事中、発作的に会社のビルから飛び降り自殺を図った。
“安上がりな被ばく労働者”として扱われ
「専門技術を学びに来ました。除染作業をするなんて聞いていませんでした」
つたない日本語で懸命に訴えるベトナム人男性のグエンさん(仮名・26)。
福島県郡山市で建設作業員として働くはずだった彼がやらされたのは除染作業だった。作業に必要な特別教育は一切受けていない。日給は5600円で日本人作業員(平均日給1万6000円以上)の3分の1だ。1年以上にわたり安上がりな被ばく労働者として扱われ、雨天などの休業時は1日分の日給である5600円が引かれた。
グエンさんは、
「除染作業とわかっていたら日本に来ていません。専門技術を学ばせてください」
と訴えた。
黄さんや史さんらは現在岐阜県にある『外国人労働救済支援センター』で支援を受けているが、ほとんどの技能実習生は支援先や制度もわからないまま失踪をとげている。
「本来は労働契約で労働条件、賃金が決まるはずなのに、全然違うところ(技能実習生が知らないところ)で決まっている。ブローカー(悪質な労働者仲介業者)によって契約ががんじがらめになっている。今後どのようにブローカーを排除していくのか」
と、前出の鳥井氏。外国人労働者受け入れ拡大の課題は山積みで、来年4月からの施行なんてとんでもない話。
会合後、国民民主党の山井和則衆院議員に話を聞くと、
「政府は目先のことだけしか考えていない。もっと丁寧で慎重な議論が必要です」
と早急な法改正に待ったをかける。
「外国人労働者の受け入れは14業種だけと政府は言いますが、今回の法案では、人手不足ならば上限人数なく全業種の受け入れも可能です。そんなことをしたら外国人と日本人で仕事を奪い合い、賃金が下がりかねない。外国人を受け入れる以上、日本を好きになってもらいたいですよね。
今の悪い労働条件のままでは技能実習の外国人はもちろん、日本人だってハッピーじゃない状況。人間らしい働き方ができる環境をきちんと整えて上限人数を設けて外国人を受け入れるべきです」(山井議員)
さらに、安倍首相の拙速な姿勢を批判した。
「移民国家スイスでは『我々は労働者を求めたが、やってきたのは人間だった』という作家の言葉があります。まさにその通りで、人間としての尊厳がきちんと守られること、これが約束できないのならば私は反対です」
自分達の事しか考えていない単純な業界や人々が多いのには驚いた!
単純に外国労働者を受けれる事しか考えていなければ外国労働者が入ってくる事で起きる問題に対応できない。全体的に考えないと
プラスと思っていたら、大したプラスでない割に問題が増えることになる。
日本人は自分達で一生懸命働くことには優れているのかもしれないが、全体的に周りを見て判断したり、長期的に見てメリットがあるかを
判断する能力は教育のレベルの割には低いのかもしれない。それとも、偽善的な良い人達なのか?つまり、人に良い人と思われたい、良い評価を
受けたいから行動しているだけで、評価されない分野や環境では自己中心的な判断や選択を選ぶ傾向があると言う事か?
もしかすると日本人と言う表現が間違っているのかもしれない教育レベル、生活レベル、そして居住エリアの違いで意見や考え方に違いが
あるが、数ではそのような日本人が多いと言う事か?それとも政治力を持つマイノリティーが動いているのか?
外国人労働者の新在留資格を巡り、14業種の受け入れ見込み人数を政府が示したことについて、対象業界からは「一歩前進だ」と歓迎の声が上がった。ただ人手不足の見込み数に比べ、圧倒的に少ないため「焼け石に水だ」との声も。希望していたのに対象外となった業界は、今後も粘り強く政府に働きかける構えだ。
5年後に職員30万人の不足が見込まれる介護分野では、外国人5万~6万人を新たな在留資格で受け入れる。全国老人福祉施設協議会の石川憲会長は14日、「外国人材は必要不可欠。一人でも多くの受け入れが実現することを願っている」との談話を発表した。
大手介護会社の担当者は「受け入れ数が少なすぎる。このまま人手不足が続けば事業継続が難しくなる」。国の施設基準を緩和して必要な職員数を減らしたり、介護報酬による賃金改善で日本人を集めやすくしたりといった対策を訴える。
社会福祉法人千里会(横浜市)の牧野裕子・法人統括部長は、受け入れる働き手の「能力」を懸念する。経済連携協定(EPA)に基づきインドネシアとベトナムから来日した外国人職員は、現地の看護課程修了などを条件としているため、特別養護老人ホームの即戦力になった。「新しい在留資格で日本語や技能の要件がEPAより緩和されると、介護の質を保てず現場でトラブルが起きかねない」と話す。
外食業界は初年度に4000~5000人、5年間の累計で約4万1000~5万3000人を受け入れる。業界団体である日本フードサービス協会の金丸康夫専務理事は「議論を進め、今国会中に成立させてほしい」と期待した。
ただ5年後には外食業界だけで29万人の人手不足が見込まれている。飲食店を運営する大戸屋ホールディングスの担当者は「5万人のうち、どれだけ自社で採用できるか。乗り遅れないようにしたい」と話す。別の飲食店幹部は「これでは全然足りない」と不満を漏らした。業界内での人材争奪戦が激しくなりそうだ。
一方、対象から外れたコンビニやスーパーは、将来受け入れ対象になることをめざし、経済産業省などと協議を続ける。縫製業務などで外国人技能実習生を多く抱える繊維アパレル業界も「認定されれば工場の安定的な操業につながる。ぜひ対象に加えてほしい」(ワコール)と求めた。【今村茜、原田啓之】
不正が可能である制度を放置している、又は、改善しない政府や行政を信用して出入国管理法改正案を認める事は出来ない。
東京・新大久保。ここは多くの外国人が働き、暮らす街だ。そこでこんなことを聞いてみた。
「保険証を持っていますか?」
現在の法律では、日本に3か月以上滞在することで、外国人も健康保険に加入の義務が生じる。
パキスタン人・ネパール人…など、報道プライムサンデーの取材班が聞いたところ、ほとんどの外国人が自身の持つ健康保険証を見せてくれた。しかし先週、この外国人の健康保険の問題に焦点が当たった。
政府が来年4月から導入しようという「出入国管理法改正案」で、外国人労働者が多く日本に入って来た場合、健康保険制度を悪用されるのではないかという懸念があるのだ。
他人の保険証を不正利用して“なりすまし受診”
上の画像は、中国人観光客がSNSで日本に住む中国人に送ったメッセージだ。
「友達が日本に来ていて、子供が病気になりました。誰か保険証を貸してくれる人は、いませんか?」
保険証の不正利用をしようとしたのだ。
20年以上日本に住む中国人男性は、こうした“なりすまし受診”はよくあるとした上で、「保険証を人に貸すというのは、相当昔からあることなんです。中国では、なにか病気があっても見つけてくれないのではないかという、医療に対する不信感がある。不正使用だという事を分かったうえで、“なりすまし受診”している」とその実情を語った。
医療の現場で、そのような“なりすまし受診”は見抜けないものなのだろうか?
埼玉県川口市にある芝園団地。住民総数およそ4900人の内、2600人余が外国人。大半は中国人で、リトルチャイナとしても知られている。この団地で、地域医療を担うのが芝園団地診療所だ。この日も、この診療所をかかりつけにする中国人患者が多く訪れていた。
診療所の担当者に話を聞くと“なりすまし受診“を現場で見抜くのは、やはり難しいという。
「我々のところでは分からない。なにしろ見た時に、書面上、カード上に出ているものしか分からないので、受付せざるを得ない」と悩んでいた。
とはいえ、日本に滞在する外国人が携帯を義務付けられる在留カードと見比べて、防止できないのだろうか?
「それを言うのだったら、『健康保険証の記載法』と『在留証明書の記載法』をまず統一してほしい。名前が漢字表記だったりローマ字表記だったりするんですよ、お一人でも」と、現実的にチェックすることは難しいという。
「無料で治療を!」日本の保険制度を狙ったツアーまで!?
日本の健康保険制度では、高額な医療を受けても、一定以上の負担については税金から支払われる“高額療養費制度”もあり、この制度を利用すれば、ノーベル賞で脚光を浴びた高額なオプジーボによる治療も、格安で受けられることになる。この制度を使って、中国人が日本で医療を受けるツアーまであるという。
旅行代理店のホームページの書き込みを見ると、
中国人が、日本で無料の治療を受ける方法があります
とあり、ここではさらにクイズ形式で、日本の健康保険を使い治療費を浮かす方法を指南していた。
Q.日本の医療制度を利用して、自己負担は3割に抑え、さらに高額療養費制度を利用し、毎月の医療費が9万円を超えたら、その分は日本政府に払ってもらう方法はないのでしょうか?
A.実はあります。教えてあげましょう。日本の健康保険制度を利用するのです。
取材班は、この旅行代理店とは連絡はついたものの、ツアー担当者には取り次いでもらえなかった。
出産育児一時金も標的に?
外国人による健康保険の不適切とも思える利用は、これだけではない。
東京荒川区で区議を務める小坂英二氏がある資料を見せてくれた。それは荒川区が1年間に支払った出産育児一時金の件数。出産育児一時金とは、出産時に支払われる補助金の事。国民健康保険では子供一人につき42万円が支払われ、保険証を持つ在日外国人も対象だ。
2016年の荒川区での出産育児一時金の支払いは304件、1億2700万円が支払われた。しかし、304件のうち168人が日本人で、残りの5割近くが外国人と高い数字となっている。
ここに大きな問題が潜んでいた。
小坂区議が問題視しているのが、外国人が海外で出産した場合の出産育児一時金の受け取りだ。国民健康保険制度では、海外で出産しても一時金は受給できる。荒川区では2016年は49件が海外で出産し、一時金を受け取った。国別で見ると、アメリカで1件。タイで1件、オーストラリアは2件、ベトナムは少し多く7件。
その中、突出している国が…“中国”だ。
実に63%を占めている。一体これの何が問題なのだろうか?小坂区議はこう語る。
「それはまさにブラックボックスで、本当に生んだのかということを、役所の窓口では全く調べようがない。ウソの証明書を出されたら、それを信じて42万円出すしかない」
別の自治体では、実際に出産一時金の不正受給が明るみに出て、逮捕されたケースもある。
日本の社会保障制度の穴。
実は、この他にもある。
国民健康保険証と協会けんぽの保険証を見ると、どちらも写真がない。これが不正の温床となる理由の一つとなっているという指摘がある。
鎌田實(諏訪中央病院名誉院長):
私の病院は地方の病院なのでこのようなことはあまりないです。しかし、緊急に外国人の方が運ばれて治療を受けるケースがあるのだが、そこで未収、お金を払ってもらえないというのは、日本全体の病院の3分の1で起きているということで、経営的に非常に困っているという実態があります。
私は外国人労働者の導入についてはかなり積極的に賛成なんですけれども、日本の「国民皆保険制度」というのは世界でも類を見ない素晴らしい制度なんです。
しかし、この制度も現在かなり土俵際に来ていて、外国人労働者受け入れ拡大を目指す出入国管理法改正案が、国会できちんと議論されずに通ってしまうとますます大きな問題になって、国民皆保険制度が崩壊してしまうきっかけになりかねない。きちっと議論しないと、悪用しようとする穴がありすぎます。
年金制度にも存在する“穴”
荻原博子(経済ジャーナリスト):
年金は、10年日本にいれば外国人でも受給権が発生することになるんです。今は5年ですけど、来年4月から10年にしようとしています。何度か日本に来て10年満たせば、一生日本から年金を送り続けられることになるんです。
例えば奥さんと子供を国に残して、海外から日本にやってきた方が、入国してすぐであったとしてもその方が亡くなると、子供が18歳になるまでずっと日本から遺族年金を仕送りしなければならない。そういったところを議論しないといけない。
パトリック・ハーラン:
以前から移民を受け入れているアメリカでは、財政負担をあまり気にしていません。健康体で働きに来ている外国人の労働者は、公的サービスで一番お金がかかる“教育”を、自分の国で受けて来ているから、自らの国が教育費を負担した後で来て、それから働きに来て税金を納めてくれる。
収めた税金から公的サービスの受給額を引くと、差額が“収めた税金”の方が多い。例えばイギリスのロンドン大学(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン)が行った研究では、2001年から2011年の間で移民が納めた税金の額から、公的サービスの額を引くと、10年ほどで3兆円以上の財政貢献があったんです。
大前提の“日本に移民はいません”というのがおかしい
荻原博子:
日本は実は海外から働きに来ている人が128万人と、世界第4位の移民大国と言われています。ところがこの人たちを移民と認めていない。移民をどうするかという議論が全くされていないんです。
「移民を受け入れるんだ」ということを大前提として、認定しないといけない。今は移民はいませんということになっていますからね。
佐々木恭子:
移民を受け入れるという大前提をきちんと認めないで、付け焼き刃で穴だけ塞いでも立ち行かなくなるのではないですか?
鎌田實:
立ち行かないですね。
今の国会では政府がなんでも通せるから、法案成立後に省令で物事を解決していくというのは、あまりにも問題が大きすぎるからきちんともっと議論をしないといけません。
制度に穴があるのを対処療法で塞いでいるだけでは根本的な問題の解決にはならない。
外国人労働者を受け入れるのであれば、社会保障制度を根本から見直し、外国人が入ってくることを前提とした制度にしていく必要がある。さらに、日本が外国人にとって魅力のある「働きたくなる国」となるようにしていく必要もある。
そのために何をなすべきか、国会ではこうした議論が望まれる。
(報道プライムサンデー 11月11日放送より)
外務省が2017年3月から18年9月にかけ、日本の日本語学校への留学ビザ(査証)を申請したベトナム人学生約6000人を対面調査したところ、日本語能力が申請要件に満たない学生が1割超に上った。同省は、日本語能力の証明書を偽造した疑いが強いとして、申請を代行した12業者を10月から6カ月間の受け付け停止処分とした。日本語能力の審査方法は、外国人労働者の受け入れを拡大する入管法改正案でも焦点となっており、審議に影響を与える可能性がある。
独立行政法人・日本学生支援機構によると、日本語学校に在籍するベトナム人は約2万6000人(17年度)で、中国人に次いで多い。一方、警察庁によると、17年に摘発した来日外国人の犯罪は、ベトナム人が最多で約3割を占めた。このうち、在留資格別では「留学」が4割だった。
在ベトナム日本大使館は、留学ビザのずさんな申請が犯罪増加の背景にあるとみて、学生本人への面接を実施。ビザ申請に必要な日本語能力がない学生が少なくとも1割に達した。処分した12業者は、扱った学生の3割以上が「不適格」だった。
業者に仲介許可を出したベトナム教育訓練省にも通報した。
ベトナムでは「日本で稼げる」と若者を勧誘し、100万円以上の手数料を受け取って留学ビザの申請を代行する業者が活動中。ビザ申請時に提出する法務省の「在留資格認定証明書」を得るには、日本語能力試験N5(平仮名や片仮名、基本的な漢字で書かれた文章を理解できる)相当以上の能力などを証明する必要がある。
今後の審議では、日本語能力の審査を厳格にするよう求める声が強まりそうだ。【秋山信一】
「アルコールの陽性反応が出たのは14日午前7時50分ごろだった。機長のほか副操縦士らもその場にいたが、いずれも詳細な検査をする機器をうまく使えなかった。」
この点が問題だと思う。機長や副操縦士の両者とも「詳細な検査をする機器をうまく使えなかった。」
つまり、アルコールチェックが形だけ、又は、会社の内部審査が甘い可能性が否定できない。
国交省は事故が起きる前に日本の航空法第七十条を改正、又は、明確にする必要があると思う。
機体が落ちて機長や副操縦士が体がばらばらになった状態でアルコールの影響があったかなんて調べるのかな??
スカイマークは14日、羽田発新千歳行きの705便(乗客154人)に乗務予定だった米国人の男性機長(49)から、アルコールの陽性反応が確認されたと発表した。
機長は前日に大量の飲酒をしていた上、機器の扱いに不慣れでアルコール濃度の測定ができず、安全を考慮して乗務を交代。同便の出発は20分余り遅延し、到着も15分近く遅れた。
同社によると、機長は13日午後3~7時に500ミリリットル入りの缶ビール7本を飲んでいた。同社の規定では乗務前12時間以内の飲酒を禁じているが、705便は14日午前8時40分発の予定だったため、抵触しないという。
アルコールの陽性反応が出たのは14日午前7時50分ごろだった。機長のほか副操縦士らもその場にいたが、いずれも詳細な検査をする機器をうまく使えなかった。
乗務交代後に濃度検査をしたところ、同社が定めた乗務できない基準値は下回っていたが、前日の飲酒量が多いことなどから機長を厳重注意した。
スカイマークは「お客さま、関係の皆さまに迷惑をかけて申し訳ない」と謝罪した。
外国人による日本車の評価は非常に高い。ただ、日本の自動車メーカー同士を比べると品質に違いがある事を実感している外国人は少ない。
SUBARU(スバル)が自動車の完成検査の不正問題で揺れている。8日、1月から10月まで生産した約10万台をリコールすると国土交通省に届け出た。従来、不正は2017年末までだったと説明していたが、一転して不正が続いていたとして追加リコールした。
17年秋以降、データ改ざんなどの問題が相次いで発覚。一連の検査不正での累計リコール台数は約53万台になった。中村知美社長は「急成長の歪みが出た」と唇をかむ。
スバルは10年頃から米国を中心に世界販売を急拡大した。独自技術を訴求する手法を改め、その技術が実現する「安心と愉しさ」という価値やユーザーエクスペリエンス(顧客体験)を訴求。ブランド力を高めたことが奏功した。
「真面目だが地味な技術オタクが、個性光る人気者に脱皮した」といったところだろうか。しかし相次ぐ不正をみれば、真面目さが置き去りになったことは否めない。
あらゆる産業でハードウエアは成熟化が進み差別化が難しくなっている。スバルのようにブランドを磨いたり、競争軸をユーザーエクスペリエンスにシフトしたりすることは、多くのメーカーにとって検討すべき選択肢だ。ただ技術や品質の重要性はみじんも揺るがない。
「建築士の免許がないのに実在する2級建築士になりすまして建物の設計などをしたとして、神奈川県警は13日、横浜市戸塚区、脇坂佳幸容疑者(51)を建築士法違反と有印私文書偽造、同行使の容疑で逮捕した。・・・県の調査によると、脇坂容疑者は2013年10月以降、建築士になりすまして業務を請け負っていた。」
運が良いとなかなか違反及び違法行為を継続していても摘発されたり、逮捕されない事がある例だと思う。
建築士の免許がないのに実在する2級建築士になりすまして建物の設計などをしたとして、神奈川県警は13日、横浜市戸塚区、脇坂佳幸容疑者(51)を建築士法違反と有印私文書偽造、同行使の容疑で逮捕した。捜査関係者への取材で判明した。神奈川県が調査したところ、脇坂容疑者が55件の施工に関与していたことがわかり、県は今年8月、県警に刑事告発していた。
県や捜査関係者によると、脇坂容疑者は同県内に実在する2級建築士と建築士事務所の名義を使い、建築士の免許がないのに、同県茅ケ崎市と鎌倉市の木造住宅4軒の設計や工事管理をした上、建築に必要な書類を偽造して検査機関に提出した疑いがある。
今年4月、県に建築士免許がない脇坂容疑者が設計などに関わっているとの通報があり、発覚した。県の調査によると、脇坂容疑者は2013年10月以降、建築士になりすまして業務を請け負っていた。木造住宅など55軒の建築物を手がけ、そのうち茅ケ崎市や横浜市などの16軒が建築基準法に適合していなかった。柱とはりに取り付ける接合部の金属部品の強度が不足するなどしていたが、県は「倒壊の危険性があるものはない」としている。
脇坂容疑者は過去に建築会社で勤務した経験はあるが、建築士の試験には合格しなかった。なりすましていた実在の2級建築士とは面識があったという。【杉山雄飛】
「オリンパスは『故意ではない』(広報)としているが、当時の集計方法がわかる資料がないという。」
このコメントでは故意を疑いたくなる。
オリンパスは13日、過去に発表したカメラの販売台数に誤りがあったとホームページ上で公表した。「PENシリーズ」の販売実績は全世界で1700万台としていたが、実際には半分以下の800万台だった。
販売台数に誤りがあったのは、PENシリーズのフィルムカメラで、実際よりも900万台多い数字を公表していた。2019年に迎える創業100周年に向けて、社内資料の整理をしている中で発覚した。オリンパスは「故意ではない」(広報)としているが、当時の集計方法がわかる資料がないという。
オリンパスは1959年にフィルムカメラの初代PENを発売。2009年からはブランド名を残してミラーレスのデジタルカメラを発売している。
更新の担当者を決めていなかったのか?それともずさんな管理だったのか?
免許を受けずに簡易無線局を開設していたとして、総務省近畿総合通信局は13日、神戸大学を電波法違反で同日から50日間の簡易無線局1局の運用停止の行政処分とした。
通信局によると、神戸大は2008年10月に免許が切れていたにもかかわらず、簡易無線局6局を開設したままにしていた。通信局はこの6局を停止したうえ、免許が切れていなかった1局を停止処分とした。
神戸大は「うっかり手続きを忘れていた」と説明しているという。通信局が今年7月に、電波監視システムが受信した神戸大の簡易無線局の電波を解析して発覚した。
神戸大大学院海事科学研究科によると、「カッター」と呼ばれる約20人乗りの巡航訓練用船で使っている無線機の更新手続きを怠ったまま使用していたという。担当者は「重大性の認識に欠けており、重く受け止めている。今後、改めて免許申請をしたい」と話した。
出入国管理法改正案を通そうとして「政府、悪質仲介排除へ罰則=利用企業、5年受け入れ禁止」を提案したのかもしれないが、悪質な仲介業者や会社は処分を受けても、企業の名前を変えたり、新たに会社を作ったりして逃げるであろう。逃げるにしても簡単に逃げられないように
処分を受けた会社の代表者及び役員は、会社を変わろうとも5年間は仲介業の代表者や役員になれないように明記するべきだ。
明記しても影の経営者や裏方に徹する可能性はあるが、表に出てこれないので動きづらくなると思う。また、処分が終わるまでは悪質な仲介業者名、
代表者及び役員の名前をインターネットで公表しておくべきだと思う。名前を変える抜け道はあるが、何度も名前を変えると不審がられるので
効果はあると思う。
悪質な企業は基本的に悪質なので、悪質な手段や逃げ道を考えると想定して対応するべきだ。
JICAはなぜ人間的に問題がるアフガニスタン籍のイブラヒミ・モハマッド・ナージム容疑者を研修生として選んだのか? 人選に問題はなかったのか?税金で彼が来ているのなら、さっさとアフガニスタンに返せ!事件とお金の無駄!
来日してわずか2日後の犯行でした。
JICA九州のアフガニスタン人研修生が、JR八幡駅で女子大学生の胸を触るなどした疑いで逮捕されました。
強制わいせつの疑いで逮捕されたのは、JICA九州の研修生として日本に滞在中のアフガニスタン籍のイブラヒミ・モハマッド・ナージム容疑者です。
警察によりますと、イブラヒミ容疑者は10月16日午後10時すぎ、北九州市八幡東区のJR八幡駅構内で、女子大学生の胸を触るなどした疑いが持たれています。
イブラヒミ容疑者はこの2日後、北九州市内のスーパーマーケットで女性の腕を触った疑いで逮捕されていて、その捜査の中で今回の事件が浮上しました。
調べに対し、「行為はしたが嫌がってはいなかった」と容疑を一部否認しています。
イブラヒミ容疑者は、10月からJICA九州で北九州市のゴミ処理方法を学ぶ研修に参加していました。
政府は9日、外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法改正案に関し、悪質な仲介業者を利用して外国人材を受け入れた場合、その企業による受け入れを5年間禁じる方針を固めた。
受け入れ企業に対する罰則規定を設けることで、悪質な仲介業者を排除する狙いだ。罰則規定は法務省令で定める。
菅義偉官房長官は9日の記者会見で「悪質な仲介業者などの介在が判明した場合、当該企業は新在留資格による外国人材の受け入れ企業としない方向で法務省が検討している」と述べた。
安全をアピールしたい会社、又は、安全に厳しい会社であれば諭旨退職の懲戒処分はあり得ると思う。これは勝手な推測であるが、
本人だけでなく、他の機長達への飲酒に関する戒めのメッセージだと思う。
一番影響したのはJAL日本航空副操縦士がイギリスで飲酒で逮捕されて、日本の航空法第七十条が曖昧である事を多くの日本人達が知ってしまった
事だと思う。結果として、JALではかなり酔っていても検査をすり抜ける事が出来る状態である疑いが高くなった。操縦士の一人がかなり
酔っていてもすぐに重大事故が起きるわけではないし、飛行機が墜落するわけでもないが、安全性が低くなり、他の要因が重なれば
危険な状態や事故に繋がる可能性はある。
自己管理できない操縦士は排除されても仕方がない。事故が起きればとんでもない事になる。
パイロット不足なので条件さえ妥協すれば、資格がはく奪されない限り、すぐに仕事は見つかると思う。資格さえ持っていれば法的には
機長として飛行機を飛ばせる。問題ないと考える会社はこの世の中たくさんあると思う。一流に拘らなければ選択肢はたくさんある。
その意味ではLLCはリスクがあると言える。強運であれば問題ない。昔、アフリカで飛行機に乗った人が、整備士が出発前にテープを張っていたと
言っていた。それでも墜落しない事があるのだから強運であれば問題ない。
全日空グループのANAウイングスの40代男性機長が、過度の飲酒の影響で乗務予定の便に乗れなくなり、計5便に遅延が生じた問題で、機長が諭旨退職の懲戒処分を受けたことが8日、分かった。
全日空によると、機長は10月25日午前8時すぎの石垣発那覇行きの便に乗務予定だったが、前日に沖縄県石垣市内で飲酒。25日早朝になって「体調不良で乗務できない」と所属部署に連絡した。同社が調べた結果、飲酒の影響と判明した。
全日空では10月上旬、当時のパリ支店長が、出張で搭乗した自社便の機内で酒に酔って隣席の乗客にけがを負わせ、諭旨退職となった。
磁石を埋め込んだ健康グッズの預託商法を展開していた「ジャパンライフ」(本社・東京都、破産手続き中)について、警視庁は特定商取引法違反(不実の告知)容疑などで捜査する方針を固めた。捜査関係者への取材で判明した。同社の顧客は全国約6800人、負債総額は約2400億円に上るとされ、巨額の消費者被害は刑事事件に発展する見通しとなった。
捜査関係者によると、ジャパンライフは債務超過に陥った事実を隠して顧客を勧誘した疑いがある。警視庁は近く、同社の破産管財人に関係資料の提出を求める方針。被害者が多い愛知などの各県警と協力しながら、詐欺容疑も視野に捜査を進める。
預託商法は、顧客に磁石付きネックレスなどのグッズを数百万円で購入させる一方、同社がそのグッズを第三者に貸し出すことで、顧客にレンタル料(配当)を支払う仕組みだった。新しい顧客を勧誘すれば受け取る配当が増える仕組みもあり、被害者の顧客の中には、親しい人を誘い、被害者を増やしてしまったケースもあった。消費者庁は連鎖販売取引(マルチ商法)と認定していた。
同社は2016年12月以降、消費者庁から4回の一部業務停止命令を受けた。17年12月に経営破綻し、今年3月に東京地裁が破産手続きの開始を決定。同社役員の男性は今年1月、毎日新聞の取材に対し「法律に合わせてやり方を変えており、違反の事実はない」と違法性を否定していた。
同様の消費者被害としては、11年に経営破綻した和牛商法「安愚楽(あぐら)牧場」の被害者約7万3000人、総額約4300億円に次ぐ規模で各地で被害弁護団が結成されている。【安藤いく子】
【ことば】ジャパンライフ
社長・会長を務めた山口隆祥(たかよし)氏(76)が1975年に高級羽毛布団や健康器具の製造販売業として設立した。85年には売上高1509億円を計上したが、近年は200億円台で推移。2017年3月期は338億円の債務超過に陥っていた。37都道府県に約80店を展開していた。
山口氏は70年代から空気清浄機などの販売会社を経営していたが、「マルチ商法まがい」との批判を浴び、75年には国会に参考人招致されている。
権力や力次第では簡単には問題として扱われない例かもしれない。
NHK佐賀放送局の湧川高史局長(59)に「職員の服務規定に反する不適切な行為」があったとして、5日付で局長職を解任し、出勤停止14日間の懲戒処分にしたと発表したNHK。
湧川氏は籾井勝人前会長の在任時に秘書室長を務めた幹部だが、一体、何があったのか。
関係者によれば、解任理由は湧川氏の信じがたい、セクハラだという。
「佐賀放送局のスタッフらと、会合で出かけ、その打ちあげで、宴席があった。それが終わって、みんなが部屋に戻った。その後、女性スタッフたちが温泉に入っていた時、そこに泥酔して足どりもふらふらした湧川氏が入ってきたのです。温泉に悲鳴が響き、パニックになったそうです」(NHK関係者)
女性スタッフたちが訴え、とんでもない局長の行状をさすがに看過できないと、処分となったという。
だが、別のNHK関係者が余罪はまだあると訴える。
「セクハラは有名で、権力を振りかざすパワハラもすごい。広島局時代に、酔っ払ってアナウンサーのEに男はいるのか? どんなセックスがいいんだと絡んで彼女を泣かせるほどだった。いずれ、セクハラで刺されると思っていた。今回、処分を聞いた時も、どのセクハラなんだというほど、すさまじいものだった」
東大出身で、NHKに入り、経済系の記者で、花形の財務省担当の「財研」キャップも経験している湧川氏。籾井会長時代には、秘書室長となり、国会答弁で立ち往生する籾井氏に背後から紙を渡し回答の指示役をしていた。「二人羽織」と失笑を買ったが、黒子役に徹した。その後、籾井氏がゴルフ場に行くために、NHKの車を使っていた問題が浮上して、失脚。佐賀放送局長となっていた。
「とにかく酒が好きで、とことん酔っ払うまで飲む。飲みに行っても、局長と呼ばせて殿様気分を味わっていた。局長と呼ばないと、真っ赤な顔で怒鳴りたてる。女好きで入ったばかりの事務方の若い女性スタッフに執拗にLINE交換を迫り、2人で夜を楽しもうなどのセクハラメッセージを何度も送信。佐賀では、本当に秘書室長までやった人ですか?と呆れられていた。いずれ何かやらかすと思っていたら、この有り様。いま、詳細な調査が進められていますが、すごい数のセクハラの訴えが出てくると思いますよ」(前出のNHK関係者)
NHK広報はAERA dot.の取材に対し、言葉を濁し、こう答えるのみだった。
「(湧川局長が)どういうことをしたかという具体的なことに関しては、申し上げておりません。関係者のプライバシーに関することで、お答えは控えさせていただいております。本人に不適切な行動があり、局長としてふさわしくないと判断しております。(余罪については)具体的なことについてはお答えしていません。何度も同じ答えになってしまいますが、すみません」
(AERA dot.編集部)
経理を1人で担当するケースの横領が多いように思える。チェックの意味もかねてもう一人サブに仕事を時々させるべきかもしれない。
勤務先の会社から現金約3600万円を横領したとして、千葉市にあるリース会社の元社員の男が7日、警察に逮捕されました。
業務上横領の疑いで逮捕されたのは、千葉市緑区のリース会社リネン・テックの元社員鈴木徳之容疑者(63)です。警察によりますと、鈴木容疑者は2012年9月から2014年8月までの間、151回にわたり自宅のパソコンを使って会社の口座から現金計約3600万円を自分の口座に振り込み、横領した疑いが持たれています。
鈴木容疑者は当時経理を1人で担当し帳簿も全て管理していましたが、今年1月に領収書の内容を不審に思った税務署の調査で不正が発覚しました。会社は約7500万円の被害を訴え、今年3月に告訴しています。調べに対し鈴木容疑者は「ほとんど競馬の馬券購入に使った」と容疑を認めているということで、警察は余罪について詳しく調べています。さらに、鈴木容疑者は退職した去年6月以降にも会社の口座から現金約630万円を自分の口座に送金した疑いがあるとみて調べています。
チバテレ(千葉テレビ放送)
スルガ銀行の2018年9月中間決算の純損益が赤字に転落することが7日、分かった。赤字幅は最大で900億円程度に上る見通し。審査書類の改ざんなど不正が横行していた投資用シェアハウス向け融資で、貸し倒れに備えた引当金を大幅に積み増すため。財務の健全性を示す自己資本比率は、国内営業の銀行に求められる水準の2倍に当たる8%台を確保できる見込みだ。
14日に発表する。不正融資を見過ごしたとして、岡野光喜前会長ら旧経営陣に対し、同行は損害賠償を求めて提訴する方針。不正融資に絡む9月の第三者委員会報告は旧経営陣について、経営を任された取締役の責任を果たしていない善管注意義務違反を認定していた。金融機関では極めて異例の対応となる。
スルガ銀は、4月に経営破綻したスマートデイズ(東京)が運営していたシェアハウスの所有者らに購入費用を融資していた。3月末時点の融資残高は約2035億円に上り、18年3月期までに引き当てた約420億円から損失見積額が大きく膨らむ。第三者委の報告を踏まえ、シェアハウス向け融資の返済状況の他、物件の賃料収入、空室率などを精査した結果、引当金の積み増しが必要だと判断した。
最近、強く感じる事でだが、組織の体質や方向性は簡単には変わらない。人も同じ。人は人格や考え方が固まれば、簡単には変われない。 スバルやその他の企業の不祥事の根本は同じであると思う。簡単には変われない。変われないから問題は存在する。
SUBARU(スバル)の大規模リコール(回収・無償修理)や新たな検査不正が、自動車メーカーの経営の根幹である生産計画に波及してきた。発覚に歯止めがかからないだけでなく、複数の不正は先月まで続いていたことが判明し、改めて同社の“自浄能力”の弱さが浮き彫りにされた。中村知美社長は終結への覚悟を示すが、混迷に終止符が打たれるかは予断を許さない。(高橋寛次)
新車製造の最終工程である完成検査をめぐる無資格者の関与、燃費・排ガスデータの改ざん、不適切なブレーキ検査…。一つの問題の調査に区切りがつくと、国土交通省の立ち入り検査などでまた、新たな問題が発覚するなど、スバルの対応は後手に回ってきた。中村氏は5日、「収束させることができず残念だ」と苦渋の表情を浮かべた。
スバルは北米での販売が主力で、国内問題である完成検査に関する不正による影響は限定的だ。だが、今月には車の「心臓部」であるエンジンの部品に不具合の恐れがあるとして、国内外で約41万台の大規模リコールに踏み切った。費用は550億円と巨額で、販売減とともに平成31年3月期の連結業績予想を大幅に引き下げる主因となった。
不正とリコールを合わせて品質問題ととらえると、経営に深刻な打撃を与え始めた。31年3月期の国内生産台数を当初計画から1万6千台引き下げ、品質管理を徹底する方針だが、北米など需要が堅調な地域への輸出が減れば、販売の機会損失も生じそうだ。
中村氏は問題の背景に、「急成長のひずみがある」と話した。同社は、北米での販売が牽引(けんいん)し、24年3月期から30年3月期までに世界販売台数が約7割増えた。業容の拡大に法令順守意識の醸成などが間に合わなかった可能性がある。
スバルは今月2日に終日、国内の生産ラインを停止し、10月下旬以降、不正がないことを再確認したという。中村氏は終結宣言で、経営を通常モードに戻したい思いをにじませたが、社外チームに依存した調査に基づく再発防止策は危うさもはらみ、実行できなければ経営責任を問われる正念場を迎えた。
SUBARU(スバル)は5日、昨年秋以降に発覚した一連の検査不正問題に関連し、新たに約10万台をリコール(回収・無償修理)すると発表した。9月末に国土交通省に報告書を提出した後の10月まで不正が続いていた可能性があるため。品質管理の徹底に向けて国内外で2万台強減産し、2019年3月期業績予想を下方修正した。
対象は今年1~10月に製造した「インプレッサ」など9車種。費用は65億円を見込む。8日に国交省に届け出る。同社が検査不正でリコールするのは4回目で、累計約53万台に達する。
同社は検査不正が行われた期間は17年末までと説明していた。だが報告書提出後の同省の立ち入り検査を機に確認したところ、今年9~10月までブレーキ性能検査などで不正が続いていたとの検査員の証言が出てきた。さらに、バンパー部品を装着していないのに完成検査を実施するといった2項目の不適切行為についても、リコール対象に含めることにした。
同社は19年3月期の生産計画を見直し、国内唯一の完成車工場である群馬製作所(群馬県太田市)や米国工場で減産する。中村知美社長は記者会見で「心配と迷惑を掛け、改めて深くおわびする」と陳謝。「完成検査問題はこれで最後にする」と再発防止に全力を挙げる姿勢を強調した。
同時に発表した18年9月中間連結決算は、売上高が前年同期比7.5%減の1兆4868億円、純利益が47.9%減の443億円だった。19年3月期連結業績予想は、売上高を3兆2100億円(従来3兆2500億円)、純利益を1670億円(同2200億円)にそれぞれ下方修正した。リコール費用が重荷になるほか、不正の影響で販売も逆風を受ける。
データ改善のよるメリットと特損数百億円を考えた場合、最終的にメリットはあったのだろうか?
データ改ざんが発覚する、又は、公になるとは思っていなかったからメリットしかなく改ざんを継続したのだろうか?
本当の事実はたぶん公表されないのでここで幕引きだろう。
NHKは11月5日、佐賀放送局の湧川高史局長(59)が職員の服務規定に反する不適切な行為があったとして更迭。局長の職を解き、人事局付けとした。
【写真】籾井勝人会長(当時)にメモをわたす湧川氏
服務規定違反の内容について、同局広報局は、「プライバシーに関わることなのでお答えできない」「業務に関わる問題ではない」などとしている。
これは「週刊文春デジタル」取材班が、湧川氏のしでかした”ワイセツ事件”について、NHKに事実確認を求めた直後の発表だった。
実は、湧川氏はNHKのスタッフらと訪れた保養施設で酒に酔い、女性スタッフが入浴中の風呂に侵入した。この“事件”が発覚した後、湧川氏には出勤停止14日間の懲戒処分が科せられたが、その後に局長更迭が決まった。
湧川氏は秘書室長だった2014年当時、国会や記者会見で失言への対応に追われた籾井勝人会長(当時)に付き添い、籾井氏の背後から答弁のペーパーを渡す姿は「二人羽織だ」と揶揄された。
湧川氏の“女性風呂侵入事件”の詳細は「 週刊文春デジタル 」で報じている。
「週刊文春」編集部/週刊文春 2018年11月14日号
「現場でルール違反が横行していたこと、そしてそれを経営サイドが把握できなかったことに対し、丸山社長は『社内コミュニケーション高めようという運動をしてきた。上に言いづらい雰囲気はなかったと思うが、事実として広く起こった』と唇をかむ。」
会社ぐるみだったのか、それとも、現場が勝手にやっていたのか?事実は知らない。
経営サイドが本当に不正を知らなかったのであれば、現場は経営陣を信頼していないのか、事実を伝えたら不利益を受けると考えていたのではないかと思う。
出来ない事を利益が出来ていないからやれと経営陣から言われる、又は、事実を伝えれば、利益を出すためにリストラを考えると現場が考えれば
不正に手を染めるかもしれない。現場を理解せずに理論や流行りの経営で指示を出されても、現場が強ければ反発するかもしれない。
日立化成が今後どうなろうとも関係ないし、昔の事を思ったら気分が悪くなる出来事を思い出したので、ここで終わる。
日立化成が考えて行動すればよいだけの事。
「このように広い製品について不適切な行為を行っていたということで、経営者として慙愧の念に堪えないところでございます。関係者の皆様に深くお詫び申し上げます…」
この記事の写真を見る
近年、大企業の品質問題の発覚は珍しくもない中、「製品の広がり」という点で過去にない規模の不祥事が発覚した。
電子機器などに使われる特殊化学品大手の日立化成は11月2日、半導体材料など幅広い製品で検査不正が行われていたと発表した。同社は6月末に産業用鉛蓄電池で検査不正があったことを発表。7月から特別調査委員会を設け、調査を進めていた。
■不正は売上高の1割に相当
新たに判明した検査不正は、主力の29製品に及ぶ。2017年度の連結売上高6692億円の約1割に相当し、対象顧客は延べ1900社に達する。
「大変深刻な事だ。襟を正して一から信頼回復に努めないといけない」。同社の丸山寿社長は会見で何度も反省の言葉を口にした。一方、製品の性能や安全性については、「現時点では性能上の不具合、安全上の問題、法令違反は確認されていない」と強調した。
検査に不正がありながら、性能にも安全にも問題ないとはどういうことか。
判明した不正の内容は、「顧客と取り決めた検査を行っていない」「顧客との取り決めと異なる方法での検査」「検査報告書への実測値と異なる数値の記載」などだ。3番目のケースは規格値から大きく外れておらず、性能や安全上、問題になるようなものではない、という。
たとえば、半導体の製造工程で使われるCMPスラリーと呼ばれる製品。これはウエハの研磨に使われる薬剤で、品質上問題があれば半導体の歩留まりは悪化する。しかし、そういうクレームは入っていない。
同社が扱う数少ない最終製品である自動車用バッテリーも対象になっているが、多数の検査項目がある中で検査不正があったのは安全性に直結しない項目だという。
■国内全事業所で不正
もちろん、だから問題がないというわけではない。今回、国内の7事業所すべてで不正があった。古くは約10年前から行われた不正もあり、現場の担当者レベルだけでなく、所長が知っていたケースもあった。
現場でルール違反が横行していたこと、そしてそれを経営サイドが把握できなかったことに対し、丸山社長は「社内コミュニケーション高めようという運動をしてきた。上に言いづらい雰囲気はなかったと思うが、事実として広く起こった」と唇をかむ。
では、日立化成の今後にどういう影響が出るのだろうか。
日立化成と取引のある半導体メーカーの関係者は「製品段階で検査しているので深刻な問題とはとらえていない」と話す。調査費用や顧客対応費用が一定程度かかったとしても、同社の利益水準を考えれば経営が揺らぐことはなさそうだ。
だが、中期的な影響はあるかもしれない。現在の主力事業は、エレクトロニクス系の機能材料と自動車関連。特に自動車関連は品質に厳しい。簡単に取引先を変えることができないため、短期的にビジネスを失うことはないが、価格要求も含めて今後、取引が厳しくなることは間違いない。
また、同社は将来に向けた戦略領域として、ライフサイエンス分野でのM&Aを積極的に進めてきた。丸山社長は「(ライフサイエンスは)ここ1~2年で買収した会社で、日立化成の悪しき慣習に染まっていない」と話すが、より厳格な安全基準が求められる同分野の先行きは厳しいものになるだろう。
■親会社・日立との関係は?
同社株を51.2%持つ親会社、日立製作所との関係も揺らぐかもしれない。日立化成のルーツは、1952年以降に日立製作所から独立した日立絶縁物工場だ。70年に上場し、日立グループの中でも日立金属、日立電線と並び「御三家」と呼ばれる別格の存在だ。
日立製作所が8000億円近い最終赤字に陥った2009年3月でさえ、最終黒字を確保した優良会社で、日立製作所から役員の派遣も少なく、高い独立性を認められてきた。
リーマンショック直前に14社あった上場子会社を日立製作所は徐々に整理。日立物流や日立キャピタル、日立工機、日立国際電機の株式を売却した。上場会社の選別は今も進行中で、残る日立化成、日立金属、日立建機、日立ハイテクノロジーズの帰趨が注目されている。この4社は収益規模や時価総額が大きく、切り離すにしても取り込むにしても簡単にはいかない。
「それ(日立製作所が取り込むか切り離すか)はコメントする立場にはない。分離独立以来、ずっと独立して運営してきた」と丸山社長。今回の不祥事は日立製作所の判断にどう影響するのだろうか。
山田 雄大 :東洋経済 記者
データ改善のよるメリットと特損数百億円を考えた場合、最終的にメリットはあったのだろうか?
データ改ざんが発覚する、又は、公になるとは思っていなかったからメリットしかなく改ざんを継続したのだろうか?
本当の事実はたぶん公表されないのでここで幕引きだろう。
免震・制振装置の検査データ改ざん問題を巡り、油圧機器メーカーKYBは2018年9月中間連結決算で、関連費用として数百億円の特別損失を計上する方針を固めた。交換する装置の製造費や、工賃の現時点の想定額を盛り込む。
【KYBが発表した不正装置の建物名】
6日に発表する予定で、損失の詳しい内容や、改ざん問題の対応状況などについて担当役員らが説明する。
KYBは10月16日、免震・制振オイルダンパーの性能検査データを改ざんし、納品していたと発表した。国の基準や顧客との契約に適合しなかったり、その疑いがあったりする装置は、計980物件1万928本に上る。同社はこれら全製品を20年9月までに交換する方針だ。
ダンパーの価格は数十万~100万円程度で、同社は交換品の原価が数十億円になると試算。さらに過去の交換実績などから、建設業者などに支払う工賃を加えた数百億円を特別損失に計上する。ただ、一部の装置は建物の壁を壊して取り換えるなどの作業が必要で、費用は膨らむ可能性がある。【松本尚也】
「The airline said the co-pilot was arrested Sunday at Heathrow Airport for violating British aviation law.」
日本航空の副操縦士(Katsutoshi Jitsukawa)はイギリス航空法違反で逮捕されたそうだ。
JAL pilot admits being almost 10 times over alcohol limit NOV/02/18(Burnabynow)
JAL日本航空副操縦士の名前は実川克敏・じつかわかつとし 顔写真・画像あり facebook情報 アルコールで逮捕(育児でヘロヘロになりながら”時々”更新するブログ)
航空法第70条(酒精飲料等)でこう書かれています。 「航空機搭乗員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運行ができないおそれのある間は、その航空業務を行つてはならない。」
日本の航空法には
「第七十条 航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。」
と曖昧に書かれているだけで、パイロットの飲酒量に関する規定はないそうです。
実際には、航空会社が適正に運用していることに任せているというのが現状だとか。・・・
それにしても、飛行機の操縦士の搭乗前飲酒について、国が具体的な規定を持っていないということに驚きです。
11/02/2018(トレンド アップ エブリデー)
石井啓一国土交通大臣様、航空法は改正する必要があると思います。曖昧な規則は抜け道と誤解との言い訳の余地を残します。
LONDON — A Japan Airlines co-pilot arrested after failing a breath test shortly before a London to Tokyo flight pleaded guilty Thursday to being almost 10 times over the legal limit for alcohol.
London's Metropolitan Police force said Katsutoshi Jitsukawa appeared at Uxbridge Magistrates' Court in west London and admitted exceeding the alcohol limit.
The airline said the co-pilot was arrested Sunday at Heathrow Airport for violating British aviation law. The driver of a crew bus at Heathrow smelled alcohol on Jitsukawa and reported it to police, Japan's NHK public television said.
Tests found the 42-year-old first officer had 189 milligrams of alcohol per 100 millilitres of blood in his system, almost 10 times the 20 milligrams limit for a pilot. The limit for drivers in Britain is 80 milligrams.
Jitsukawa acknowledged he had drunk about two bottles of wine and a pitcher of beer the previous night, NHK said.
He was ordered detained until he is sentenced on Nov. 29.
JAL said the flight was delayed more than an hour and had to be operated by the remaining two pilots. It apologized Thursday for the incident.
The apology came a day after another major Japanese airline, All Nippon Airways, apologized for causing delays to five domestic flights after a pilot became unwell due to heavy drinking the night before.
日本人は思った以上にずるいと言う事がわかりました。
かなり日本人をやっているけど知っているようで事実を知らない事が理解できた。
学校に関して世間を知らない学生が教諭になるのだから世間とギャップがあっても仕方がない部分はある。 生徒が大人になり現実の世界を見るとギャップに戸惑わないのだろうか?戸惑うが村八分になりたくないから順応するのか?
世の中、知らない事はたくさんある。
不正は国内の全ての事業所で行われていたと発表した。
日立製作所グループの化学メーカー、日立化成は、これまで産業用鉛電池や半導体部品の検査データの改ざんを公表していたが、新たに、自動車用の電池部品などでも、顧客と取り決めた検査を行わず、検査データを改ざんしていたことを明らかにした。
また、検査の不正は、国内全ての事業所で、少なくとも5年以上にわたり行われていたという。
日立化成では、2018年6月にも、鉛蓄電池でのデータ改ざんを発表していて、今回の不正発覚により、対象となった製品が納入された取引先は、およそ2,400社にのぼっている。
韓国は日本以上に人件費を上げている愚かな国であるが、日本も同じ。
人件費を上げて国際競争に勝てるほど日本の製品や品質は良いと思っているのだろうか?
賃金を上げると人が増やせない。一人の仕事量が増えたり、緊急の場合に、負担がさらに覆いかぶさる。
人間はある一定のレベルを超えると効率が下がってしまう。無理をすると精神的にも、肉体的にも負担が正比例以上にかかる。
安倍首相は知っていて賃金を上げたのだろうか?
[東京 2日 ロイター] - 日立化成<4217.T>は2日、これまでに発表していた産業用鉛蓄電池の一部製品に加え、半導体用材料などで新たに不適切な検査を実施していたことが判明した、と発表した。
新たに不適切検査などが判明した製品は半導体用材料やディスプレー関連材料などで、連結売上収益の約1割に相当する。対象となる顧客数は延べ1900社に及ぶという。
もし日本の客船や貨客船が沈没したら、韓国船籍旅客船「セウォル号」(M/V"SEWOL", IMO9105205)のように救命いかだが固着していたり、浮いてこなかった可能性があると言う事?
韓国のような不幸な海難が起きなくてよかった。韓国に笑われる。
救命いかだではないが検査を受けたばかりなのに問題がある事がある。いくら検査を受けたばかりと言われても問題を見つけたら
嘘は書けない。運悪く問題が直ぐにおこったのか、それとも、改ざんだったのか、事実は業者しか知らない。
問題を指摘すれば、嫌な顔をされるし、仕事は確実に減っている。大きな事故になったり誰かが犠牲にならないと大きな流れは変わらないと思う。
しかし、大きな事故になっても犠牲者が出ても大きな流れは止まらないと思う。止めれるようだと既に多少は変わっている。建前だけの
コンプライアンスは偽善としか思えない。
国土交通省は2日、東証1部上場の協栄産業の子会社が船舶に搭載されている救命いかだなどの整備記録を改ざんしていたと発表した。同省は再整備や交換などを指示した。
発表によると、船舶用救命設備の販売や整備、点検を手掛ける協栄マリンテクノロジ(東京)は、2002年8月から今年6月まで、法律に基づく救命いかだなどの整備について、必要な整備項目を省略。実際には行われていないにもかかわらず、実施したように見せかけるため、整備記録を改ざんしていた。
「石井啓一国土交通相は2日の閣議後会見で、日本航空の副操縦士が乗務前の飲酒を巡り英当局に拘束されたことについて、『諸外国の飲酒に関する基準を踏まえて、飲酒に関する基準の強化を図る』と述べた。」
基準の強化はあまりしないほうが良い。まじめな人達やまじめな会社を苦しめるだけである。パフォーマンスとしての基準の強化は迷惑だと思う。
詳細な基準を明確にするのなら問題ない。今回、日本航空の副操縦士がどのようにアルコール検査で不正をした、又は、アルコール検査に通ったのかを
参考にして検査方法や検査のガイドラインを作成するべきだと思う。
結局、基準だけを厳しくしても規則、法、そして検査方法で抜け道や穴があれば本来の意図は達成できない。また、同時に、罰則や抜き打ち検査を
含めるべきである。いつでも抜き打ちでチェックされ、罰則が伴えば、よほど大胆な人間や会社でなければ不正は考えないであろう。
既にバスの運転手アルコールチェックでは、他人が代わりにおこなったり、吸気検査で息を吐かずに吸うなど不正が明らかになっている。
簡単に不正出来る、又は、ごまかす事が出来る検査では意味がない。事故で多くの犠牲者が出るまで適当な検査や国交省による甘い指導監督は
可能である。事故が起きても知られなくない部分を公表しな事は可能かもしれない。いろいろな事が考えられるが、本当に飛行機の安全を
考えるのであれば、基準をあまり厳しくせずに、検査方法を厳格にして、違反者の罰則を強化するべきである。まじめな人達まで巻き込んで
生活を窮屈にする必要はない。常習性がある問題のパイロットは資格のはく奪があっても良いと思う。パイロット不足の問題があっても妥協するべきではない。
石井啓一国土交通相は2日の閣議後会見で、日本航空の副操縦士が乗務前の飲酒を巡り英当局に拘束されたことについて、「諸外国の飲酒に関する基準を踏まえて、飲酒に関する基準の強化を図る」と述べた。海外では呼気や血液中に占めるアルコール濃度の基準値を規定しているといい、国内でも同様の規定を設けることを検討する方針。日本の法令では操縦士らに乗務前8時間以内の飲酒を禁止しているが、呼気検査での基準値はなく、詳細な基準は航空各社の社内規定に任せている。
石井国交相は会見で「航空機の運航の安全性に影響を及ぼしかねず、国民の信頼を損ないかねないものであり、誠に遺憾だ。航空会社に安全監査などを通じて厳格に指導監督を行う」と述べた。
航空会社の飲酒に関しては10月下旬、全日空子会社のANAウイングスの機長が飲酒で体調不良となり、乗務予定だった5便が遅延している。
日本航空の男性副操縦士が基準を大幅に超えるアルコールが検出されたとして、イギリスの警察に逮捕されました。副操縦士は保釈されず、今月末の裁判で審理されることになります。
1日の裁判では、副操縦士から基準の9倍以上のアルコールが検出された事実は非常に深刻だとして、29日に重大な事件を取り扱う刑事法院で審理することが決定しました。副操縦士は保釈されず、そのまま勾留されます。日本航空は、乗務前に社内で行われたアルコール検査を副操縦士がすり抜けていたことから、何らかの不正行為があったとみています。
コックピットの構造について良く知らないが普通、離陸すると酔いがひどくなると聞く。低酸素が原因と言われている。
この日航副操縦士は危険性やアルコールチェックに関して何も考えなかったのだろうか?
もしかして酔っていても上手く行った前例の経験者?
日本航空は1日、同社の男性副操縦士(42)が英ロンドンのヒースロー空港で、現地時間の10月28日、乗務前に同国の法令上の基準を超過するアルコールが検出されたとして、地元警察に拘束されたと発表した。
副操縦士は前日にワインや缶ビールなどを飲んでおり、その影響とみられる。日航は「ご心配とご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げる」と謝罪した。
日航によると、副操縦士は同28日夜にロンドン発羽田行きの日航44便に搭乗する予定だったが、拘束により、同便は予定時刻から1時間余り遅れて出発。パイロットは3人乗る予定だったが、2人での運航となった。
副操縦士は同日夕に同乗する機長ら2人とともにアルコール検査を実施。この際にはアルコールの反応はなかったという。
しかし、送迎バスの運転手がアルコールの臭いを感じ、空港の保安担当者に連絡。担当者が警察に通報し、実施された呼気検査でアルコールの値が基準を超えている疑いがあるとして、拘束された。
その後いったん釈放されたが、同31日に検査結果が判明。血中アルコール濃度が法令上の基準値を9倍以上超えていたことが分かり、再び地元警察に拘束された。
副操縦士はこの間の社内調査で、乗務前に適正なアルコール検査を実施したか問われ、「大変申し訳ない」と話したという。日航は「機器を正しく使えば検知できたはずで、不適切な取り扱いがあったと考えている」と説明している。同27日夜に宿泊先のホテルでワイン、缶ビールなどを飲酒していた。
スバルは1日、エンジンの部品が壊れる恐れがあるとして、インプレッサなど4車種10万1153台(2012年1月~13年9月製造)のリコール(回収・無償修理)を国土交通省に届け出た。米国など海外で販売した約31万台もリコールする。同社は10月23日に9月中間決算の営業利益予想を490億円引き下げており、計上する費用の大半をリコール費用に充てる。
スバルは昨秋以降、無資格検査問題や排ガス・燃費データの改ざん、ブレーキ検査の不正が相次いで発覚。検査不正では計約42万台をリコールし、250億円の関連費用を計上したばかり。今回のリコール対象の不具合情報は、5年以上前からあったという。
国交省やスバルによると、バルブスプリングというエンジン部品に過大な力がかかって壊れ、エンジンが停止する恐れがある。事故報告はないというが、12年4月以降に国内94件を含む計224件の不具合情報が同社に寄せられていた。
違法なのだから取り締まって処分しても良いと思う。
まあ、民泊仲介サイト世界最大手・米Airbnb(エアビーアンドビー)の韓国のコールセンターは違法を認識していたのだろうか?
「コールセンター業務は、ソウルの代行会社がAirbnbから委託を受けた。」
委託している部分がトリッキーだ。コールセンター業務に関する社員の採用を含めて委託していたのであれば民泊仲介サイト世界最大手・米Airbnb(エアビーアンドビー)は知らない可能性は高い。知っていたかどうかはソウルの代行会社との契約をどうするかで推測できるかもしれない。
民泊仲介サイト世界最大手・米Airbnb(エアビーアンドビー)の韓国のコールセンターで、約20人の日本人スタッフが就労ビザを取得せず、不法就労していたことが関係者への取材でわかった。韓国の警察当局は近く、スタッフら約20人と、採用に関わった韓国の代行会社の社員数人を出入国管理法違反(資格外活動)などの容疑で書類送検する方針だ。
関係者によると、日本人スタッフら約20人は昨年4月頃、ソウル近郊にある日本人観光客向けのコールセンターで、就労ビザを持たずに働いた疑い。
コールセンター業務は、ソウルの代行会社がAirbnbから委託を受けた。代行会社はインターネットの求職サイトで日本人スタッフを募集。「1年を見越した長期勤務が可能な方」を対象とし、待遇は週5日1日8時間勤務で、月給最低200万ウォン(約20万円)、退職金やボーナス、社員寮があるとしていた。
代行会社は採用の際、就労に必要なビザや申請手続きについては、「問題ない」と伝えていたという。日本人スタッフらは韓国警察の調べに対し、「代行会社の説明を信じ、違法と思わなかった。Airbnbの仕事なので大丈夫だと思っていた」と話している。
日本人スタッフの大半は20~30歳代の女性。Kポップが好きだったり、韓国人と交際していたりして、韓国で長期滞在を希望していた。
廃校再生計画がなければ建設当時の手抜きが発覚することなく解体で終わったであろう。
不正やインチキは最近の問題ではなく、昔からあったと言う事だろう。
群馬県内各地で行われてきた「廃校再生」の取り組み。英語村、宿泊施設、雇用創出の場--。しかし、中には再生計画が頓挫したケースもある。
みどり市は、統合で廃校となった旧神梅小(大間々町上神梅)に、魚の養殖や野菜などの水耕栽培をする民間企業を誘致したが、校舎(1974年完成)の改修工事中に施工不良が見つかり、10月22日に計画は白紙に戻された。
計画は、前任の石原条市長時代に浮上。太田市の総合建設会社と廃校の賃貸借契約を結び、この建設会社が校舎で魚の陸上養殖と野菜の水耕栽培を、校庭と校舎屋上で太陽光発電を手掛ける計画だった。
賃貸料は年間約100万円。施設改修費用などは建設会社が全額負担する契約を結び、2017年8月に着工した。みどり市側は「環境に配慮した事業内容で社会的な好感度も高く、交流人口の増加や雇用創出も見込める」(市幹部)と期待を寄せていた。
ところが、建設会社が校舎の改修に着手したところ、壁の厚さが本来の75%しかない部分や梁(はり)となる鉄骨が少ない箇所など設計と異なる施工不良が見つかった。建設時の手抜き工事だった。当時建設に携わった業者はすでに解散していた。
市は事業を継続してもらうため、今年度当初予算案に、校舎補修費用約6000万円を計上した。しかし、議会が金額の妥当性や負担することの是非を巡って難色を示したため、改修工事は頓挫した。10月22日、須藤昭男市長が記者会見で「このままでは市にも事業者にもメリットがない」として計画の取りやめを発表した。
建設会社との折衝などに当たってきた市学校計画課担当者は「廃校利活用のモデルになると期待していただけに残念。でも、こんな事態を予測できただろうか」と苦渋の表情を見せた。【高橋努】
「日本学生支援機構・遠藤勝裕理事長の見解
国の奨学金の保証人は、未返還額の半分しか支払い義務はない――。それを伝えないまま日本学生支援機構が全額を請求していることについて、遠藤勝裕理事長に10月25日、見解を尋ねた。
――『分別の利益』を伝えずに保証人に全額請求するのは妥当か。
『法的に問題はない。奨学金の原資は税金で、全額回収する責任がある。保証人から分別の利益を言われれば半額にしている』
――なぜ伝えないのか。
『奨学金を貸与する際、人的保証を選ぶのは毎年、約25万人。全員に伝えるには膨大な事務作業がいる』」
結局、「法的に問題はない。」が判断の基準になる。モラルや倫理は人間性の問題。
国の奨学金を借りた本人と連帯保証人の親が返せない場合に、保証人の親族らは未返還額の半分しか支払い義務がないのに、日本学生支援機構がその旨を伝えないまま、全額を請求していることがわかった。記録が残る過去8年間で延べ825人に総額約13億円を全額請求し、9割以上が応じたという。機構の回収手法に問題はないのか。
【写真】「分別の利益」を承認した旨を伝える日本学生支援機構の文書
機構は奨学金を貸与する際、借りた本人が返せない場合に備え、連帯保証人1人(父か母)と保証人1人(4親等以内の親族)の計2人が返還義務を負う人的保証か、借りた本人が保証機関に一定の保証料を払い、返せない時に一時的に肩代わりしてもらう機関保証を求める。最近は半分近くが機関保証を選んでいるが、約426万人の返還者全体でみると7割近くが人的保証だ。
法務省によると、この場合、連帯保証人は本人と同じ全額を返す義務を負うが、保証人は2分の1になる。民法で、連帯保証人も含めて複数の保証人がいる場合、各保証人は等しい割合で義務を負うとされるためだ。「分別の利益」と呼ばれる。
しかし機構は、本人と連帯保証人が返せないと判断した場合、保証人に分別の利益を知らせずに全額請求している。その際、返還に応じなければ法的措置をとる旨も伝えている。機構によると、2017年度までの8年間で延べ825人に全額請求した総額は約13億円で、9割以上が裁判などを経て応じた。機構は本人が大学と大学院で借りた場合などに2人と数え、「システム上、正確な人数は分からない」としている。
一方で、機構は保証人から分別の利益を主張された場合は減額に応じている。ただ、件数や金額は「(機構の)財産上の利益などを不当に害する恐れがある」として明かしていない。
こうした回収手法について、機構の担当者は「法解釈上、分別の利益は保証人から主張すべきものと認識している。主張せずに全額を払い、肩代わり分を連帯保証人らに求めることもできるため、選択は保証人に委ねている」と説明する。
これに対し、昨年の民法の大幅見直しで法制審議会(民法部会)幹事を務めた山野目章夫・早大法科大学院教授(民法)は「全額を払うよう求めること自体は違法ではないが、一般に法知識のない保証人に分別の利益を伝えないまま全額回収するのは妥当でない。奨学金事業を担う公的機関として社会的責任を問われるだろう」と指摘。取材に応じた専門家の多くも同様の見解だ。
機構を所管する文部科学省の担当者は「全額請求は法令上、誤ったものとは認識していない。ただ、分別の利益について丁寧に説明するなど、機構が検討する余地はある」と話す。(諸永裕司、大津智義)
■日本学生支援機構・遠藤勝裕理事長の見解
国の奨学金の保証人は、未返還額の半分しか支払い義務はない――。それを伝えないまま日本学生支援機構が全額を請求していることについて、遠藤勝裕理事長に10月25日、見解を尋ねた。
――「分別の利益」を伝えずに保証人に全額請求するのは妥当か。
「法的に問題はない。奨学金の原資は税金で、全額回収する責任がある。保証人から分別の利益を言われれば半額にしている」
――なぜ伝えないのか。
「奨学金を貸与する際、人的保証を選ぶのは毎年、約25万人。全員に伝えるには膨大な事務作業がいる」
――全額請求の際に保証人に伝える考えは。
「もう少し親切にというのもわかる。分別の利益が現実に問題となるのは法的措置に入るところなので、その前に保証人に伝えるのは一つの大きな改善点だと思う」
――人的保証制度についてどう考えるか。
「経済力のない年金生活者などが不幸になる事態は避けたい。そのため、人的保証を廃止し機関保証に一本化したい。奨学金制度に関わる文部科学省や財務省などに理解を求めたい」
■記者の視点 諸永裕司
「分別の利益」を主張しない保証人からは全額を回収し、主張した保証人には減額に応じる。自ら進んでは伝えない――。日本学生支援機構の回収手法は、国と個人の情報格差を考えれば公正とは言いがたい。その結果、法知識を得た一部の保証人だけが半額になる不公平が生じている。
機構は、保証人が全額払った後で、本人や連帯保証人に肩代わり分を求められると説明する。だが、機構や委託した債権回収会社ですら回収できなかったのに、保証人が取り戻せるとは考えづらい。
連帯保証人と保証人をともに立てる仕組みは、政府系や民間の金融機関ではほとんど例がないという。人的保証制度は奨学金が創設された戦中の1943年から変わらない。保証人の親族まで巻き込む人的保証制度は見直すべき時期にきている。
記事だけを読むと私立中高一貫校「世田谷学園」に問題があると思う。
私立だけに経営者の考え方が学校に反映されていると思う。
東京都世田谷区の私立中高一貫校「世田谷学園」で、担任教員から生徒へのパワハラ疑惑が持ち上がっている。学校側はいったん事実関係を認めたものの、関係者への処分は拒否。処分を求める被害者親子と対立している。4年間の不登校を強いられた親子の怒りに、学校側は向き合っているのだろうか――。
中2から4年以上も不登校のまま卒業
「私は教員からのパワハラが原因で、中学2年の終わりから卒業までの4年あまりを不登校のままで過ごしました。学校側は何が起きたのか調査もせず、関係者の処分も考えていません。原因は学校側にあるのに、出席日数の不足を理由に、2度転校勧奨もされました。学校から改めて謝罪と処分がない限り、私の怒りはおさまりません」
東京都世田谷区の私立中高一貫校「世田谷学園」を2018年3月に卒業したAさんはこう話す。Aさんは中学2年の終わり頃から不登校になり、そのまま学校に復帰できずに卒業。個別学習指導塾や予備校に通いながら勉強を続け、早稲田大学に現役合格。今年から大学生として学校に通っている。
Aさんに何が起きたのか。発端は中学2年生の冬。Aさんが風邪をひいて学校を休んだことを、担任の教員が「さぼって学校を休んだ」と誤解したことだった。
「お前は離婚家庭だから、心が弱い」
Aさんは当時、美術部と陸上部に所属。ただし陸上部は練習方針が変わったためやる気を失い、休みがちになっていた。ある日、陸上部と美術部の顧問を兼務していた担任から、陸上大会への参加を強く促され、会場に足を運んだ。しかし、行ってみると、陸上部は退部扱いになっていて、大会には出られなかった。その日は気温が低く、Aさんは風邪をひき、翌日から2日間学校を休んだ。
すると、休んだ2日目に、Aさんの携帯電話に担任から電話がかかってきた。担任はAさんが学校をさぼっていると誤解しているようだった。Aさんが「風邪で休んだだけです」と説明しても、怒気を含んだ口調で「学校へ来い」と繰り返す。さらにAさんが電話を切った後も、何度も電話をかけてくる。Aさんの携帯電話の番号を担任が知っているのも不可解だった。Aさんは怖くなり、担任と距離を置くため、美術部も辞めることを決意した。
登校したAさんが職員室で担任に「美術部を辞めます」と告げると、担任は激怒。大声で怒鳴りはじめ、「お前は離婚家庭だから心が弱い」と罵られた。
この日以降も、担任の暴言が続き、Aさんは慢性的な腹痛を発症。「担任に会いたくない」という思いから、不登校になってしまった。
「大人が謝ることの大きさをわかっているよね?」
中学3年生になって担任は変わったが、不登校は続いた。別居していた父親がAさんの深刻な状態を聞いて、学校側に元担任の謝罪を求めると、5月下旬に謝罪の場が設定された。
元担任が謝罪のために立ち上がったところ、同席していた学年主任が謝罪を制するかのようにしてこう述べた。
「Aくん、大人がこうやって謝ることの大きさをわかっているよね?」
Aさんの父親は「大人が謝るんだからこの件はもう終わりにするという意味に聞こえるが、子どもの心を傷つけた側が言うことではない」と問いただした。学年主任は「お父さんは頭がいいから」などといいながら、渋々、元担任による謝罪を認めたという。
「このまま不登校なら、別の高校に進学してはどうか」
このやりとり以降、Aさんの症状はさらに悪化した。腹痛に加えて、不眠などの症状も出るようになり、8月には適応障害と診断され、投薬治療を受けるようになった。
登校できないため、学習の遅れを取り戻そうと、Aさんは10月から個別学習指導塾に通い始めた。ところが約1カ月後、今度は担任からこう言われた。
「このまま不登校が続くようなら、中高一貫ではあるが高校部に進学しても卒業はおぼつかない。別の高校に進学したらどうか」
不登校の原因を作ったのは、学校側なのに、どうして転校勧奨を受けなくてはいけないのか。Aさんが転校を拒むと、高校には進学できたが、学校側への不信は強まった。
生徒は「非24時間睡眠覚醒症候群」を罹患
高校1年生になり、Aさんは登校しようと努力する。しかし、症状はおさまらず、登校できた日はわずかだった。新たに「非24時間睡眠覚醒症候群」と診断され、睡眠障害の治療も受けていた。
冬に学校側は父親を呼び出して、「このままだと出席日数が足りなくて留年してしまう。それが嫌なら転校するという選択肢もある」と通告した。通告してきたのは、前の年に元担任の謝罪を制そうとした学年主任だった。
再度の転校勧奨も、東京都に相談すると急転
父親が「不登校の原因となった元担任は処分されていないのに、留年させられるのは納得できない」と抗議すると、同席していた副校長は「ベストは尽くした。留年は将来を考えた教育的措置」と言った。
これに対し父親が「ベストを尽くしたというなら、なぜ息子が不登校になったのか、詳しい経緯を当然知っているはずだ」と尋ねると、副校長はしどろもどろになった。学年主任が割って入り、「副校長は昇格したばかりで事情を詳しく引き継がれていない」と釈明した。
このやりとりからAさん親子は「学年主任を中心に学校ぐるみでパワハラを隠蔽し、退学させようとしている」と感じ、監督官庁である東京都に相談した。するとわずか2日後、学校側は態度を一変させ、これまでの対応を謝罪。進級も認めるという。
後日、校長から受け取った謝罪文には、不登校になった経緯についての情報共有が不十分だったこと、元担任、中3の時の担任、学年主任の3人に口頭での厳重注意を行ったことが書かれていた。
文科省の通知に反して、転校を求めていた
世田谷学園は不登校のAさんに対し、留年や転校を迫った。その対応には問題がある。
文部科学省は児童生徒の不登校の増加が問題視されるようになったことを受けて、2003年、2009年、2016年と3度にわたって、不登校の児童や生徒への支援の在り方についての通知を出している。
特に2009年の通知では、高校生が不登校になった場合、学校以外の公的機関や民間施設で相談や指導を受けた場合には、出席日数と認めるなど、本人の進路形成のために支援するよう求めている。
世田谷学園の対応は、この通知に反する。Aさんの父親によると、学園の関係者は誰もその通知を知らなかったという。通知を把握せずに転校を求めていたのだ。さらに、不登校の原因は教員のパワハラだったのに、そのことを棚に上げて、転校や留年を迫っている。
公立の学校であれば、学校側のハラスメントは教育委員会が窓口になる。だが私立学校の場合、学校側に仕組みがなければ、被害を訴える窓口がない。再発を防げるかどうかも、その学校の体質次第だといえる。
「処分をすると学校に動揺が走って、教員が萎縮する」
Aさんは学校側に対し、関係者の処分を求めている。
「このような体質の学校では、また必ず自分と同じような被害にあう生徒が出てくるでしょう。そうならないためにも、学校に考え方を変えてもらいたいんです」(Aさん)
だが校長は、Aさん親子の問いかけに対し「懲戒処分は必要ない」と話したという。その理由は「処分をすると学校に動揺が走って、教員が萎縮する」というものだった。
Aさん親子は今年10月、世田谷学園に対し関係者の処分と原因究明に向けた調査を求める通知書を送付した。学校側は通知書の回答期限である10月29日に、「書面中で名前の挙がった教諭らに対して、あらためて弁護士2名による事情聴取を行った上で対応を協議する」「本件について11月6日に打ち合わせを行うため、その翌日以降で代理人を通じて話し合いに応じる用意がある」と返信している。
学校側は「事実認識に相違がある」との回答
また筆者が世田谷学園に、関係者を処分しない理由について聞いたところ、学校側は「事実認識に相違がある」との回答だった。
現在、Aさん親子は法的措置も含めた対応を検討している。これまで世田谷学園とは何度も話を重ねてきているが、進展が見られず、今回の返信にあった「話し合い」にも期待はできないという。
Aさんは大学に通っているが、いまも睡眠障害の治療を受け続けている。当時のことを思い出すと症状がぶり返すという。Aさんの怒りと悲しみを、学校はいまだに受け止めないままだ。
理由なしに飛行機は墜落しない。
原因を究明する事が重要!
(CNN) インドネシアの海上で乗客乗員189人を乗せたライオン・エアーのJT610便が墜落した事故で、納入されたばかりの新型機が墜落したことから専門家から困惑の声が出ている。事故を起こしたのは新型のボーイング737MAX8型で、8月に納入されたばかり。飛行時間も800時間に過ぎなかった。
画像:事故機の高度の推移を見る
同機は離陸から13分後に墜落した。航空情報サイト「フライトレーダー24」が公開したデータからは、離陸の最中に機体が通常ではない挙動を示したことがうかがえる。飛行機は通常、飛行の最初の数分間は上昇するが、同機は21秒間に約221メートル降下している。
航空専門家のフィリップ・バターワースヘイズ氏によれば、今回示されたデータは、特に通常は自動操縦システムによって機体がコントロールされることから、普通ではないという。バターワースヘイズ氏は「自動操縦のデータとは一致しない」と指摘。何らかの理由で自ら機体の修正を行おうとしたのではないかとの見方を示す。
高度が下がっているタイミングで速度が上がっていることから、その時点で、なんらかのコントロールの喪失が起きていた可能性があるという。
バターワースヘイズ氏は、機体が納入されてからわずか2カ月であることから、機械系の不具合である可能性は「非常に低い」とみる。それよりも、積乱雲からの下降気流や、鳥の群れが機体にぶつかるといった環境的な問題の可能性を指摘した。
同機は、離陸後約19キロの地点で管制塔に対して空港に引き返すことを要請していた。しかし、緊急事態を示唆することはなく、その直後に連絡が途絶えたという。
「30日午後、共同企業体の社長らが市役所を訪問。応対した野口広行副市長と市教委文化スポーツ振興課の玉城尚課長に対し、「除草剤のラウンドアップを使った」と謝罪したという。・・・『枯らすつもりはなかった。(除草剤を)薄めて使えば、成長調整剤と同じ効果があると思った』と弁明。」
除草剤のラウンドアップの取扱説明に薄めて使えば成長調整剤と同じ効果があると記載されていたのか?
除草剤 ラウンドアップマックスロード製品特長(日産化学)
「業者は31日に報告書を提出する予定で、市側は指定管理の取り消しも含め、対応を検討する方針だ。」
指定管理の取り消しは当然だと思う。
金融庁は、信用金庫大手の西武信用金庫(東京都中野区)に立ち入り検査する方針を固めた。不動産投資向け融資で、業者が書類を改ざんする不正があったことが明らかになり、金融庁は不正を見逃した審査体制にも問題があるとみて来月にも検査に入る。スルガ銀行(静岡県沼津市)のシェアハウス融資の不正問題を受け、金融庁は金融機関の不動産融資の監督を強化している。
【写真】西武信金で融資を受けた顧客の、改ざんされたネットバンキングの画面。預金額が実際の30倍の1500万円超になっている
西武信金は預金額2兆円超の信金大手。不動産融資への積極姿勢で知られる。
朝日新聞が入手した都内の不動産業者の内部資料によると、業者は不動産投資をしたい顧客の預金額などを水増しし、西武信金や大手銀行などから多額の融資を引き出していた。この業者は以前はスルガ銀からも不正な書類で融資を引き出していた。不正はスルガ銀の問題が発覚した今春以降も続き、融資が実行された。業者は10月初めに朝日新聞が問題を報じた後に事業を停止した。
西武信金は朝日新聞の取材に対し、当初は「(不正は)ないと認識している」としていたが、今月25日、「内部調査の結果、業者による資料の改ざんが疑われる事実が一部みられたので、調査を続け、不正防止策を強化していく」と回答した。
金融庁も、同信金が業者の不正を見抜けず融資を実行した例があるとみている。審査体制に問題があった可能性があるとして、11月中にも立ち入り検査に入り、融資の経緯について詳しく調べる方針。
「30日午後、共同企業体の社長らが市役所を訪問。応対した野口広行副市長と市教委文化スポーツ振興課の玉城尚課長に対し、「除草剤のラウンドアップを使った」と謝罪したという。・・・『枯らすつもりはなかった。(除草剤を)薄めて使えば、成長調整剤と同じ効果があると思った』と弁明。」
除草剤のラウンドアップの取扱説明に薄めて使えば成長調整剤と同じ効果があると記載されていたのか?
除草剤 ラウンドアップマックスロード製品特長(日産化学)
「業者は31日に報告書を提出する予定で、市側は指定管理の取り消しも含め、対応を検討する方針だ。」
指定管理の取り消しは当然だと思う。
沖縄県浦添市の浦添運動公園(ANA SPORTS PARK浦添)内の広場に農薬がまかれ、草や芝生の一部が枯れた問題で、散布した業者が市側に虚偽報告していたことが30日分かった。業者は成長調整剤を使用したと説明していたが、実際は「発がん性の懸念」も指摘される除草剤をまいたという。業者は31日に報告書を提出する予定で、市側は指定管理の取り消しも含め、対応を検討する方針だ。
同公園は今年4月から5年間、那覇市の「てだこサンサン共同企業体」が指定管理している。実務を担う業者(同市)によると、9月17、18の2日間、のり面を中心に農薬を散布した。所管する浦添市教育委員会は今月19日、近隣50世帯に文書を配布。散布された薬品について「無害」と説明していた。
30日午後、共同企業体の社長らが市役所を訪問。応対した野口広行副市長と市教委文化スポーツ振興課の玉城尚課長に対し、「除草剤のラウンドアップを使った」と謝罪したという。その後、市は業者に安全対策を指示。業者は同日夕、農薬散布地点への市民の立ち入りを制限するために、支柱を打ち付けた。
業者の現場責任者は本紙取材に対し、虚偽報告の理由を「後に引けなかった」と釈明した。その上で「枯らすつもりはなかった。(除草剤を)薄めて使えば、成長調整剤と同じ効果があると思った」と弁明。さらに除草剤散布前の8月には、成長調整剤を1度使用したことも認めた。「これ以上迷惑を掛けたくない」と公表したという。
農薬科学が専門の多和田真吉琉球大名誉教授によると、ラウンドアップは「ほとんどの植物を枯らす除草剤」。海外では「発がん性がある」と指摘する学者もいるという。
30日夕、嵩元盛兼教育長が農薬散布後、初めて運動公園を視察した。同行した玉城課長ともども、「個別の取材には答えられない」「報告書が出てから」などと繰り返し、取材に応じなかった。
志願者確保のためにお金で受験者を釣るのか?体質や組織の人間達の考え方は簡単には変わらないと言う事だろう!
まあ、それで助かる入学者は実際にいるわけだから、個々が考えれば良い事。
東京医科大(東京)が、2020年度以降に入学する学生について授業料などの学費を6年間で総額1000万円減額する方向で検討していることが分かった。同大では、入試で女子や浪人を重ねた受験生の得点を操作し、不利に扱ってきたことが分かっており、志願者の減少を抑える狙いがあるとみられる。
東京医科大によると、現在の年間授業料は250万円。他に教育充実費として50万~250万円、施設整備費100万円などがかかり、学生は6年で計2940万円を納めている。20年度以降は授業料を半額の125万円に、教育充実費を20万~135万円に下げ、総額は1000万円減の1940万円になる。
学費の大幅減額は10月9日に就任した矢崎義雄理事長の方針で、評議員会で説明した。学内には異論もあるという。同大の広報担当者は「現状の学費は高額で、学生は高所得者の子弟に偏る傾向がある。入試の件を反省し、様々な出身の学生が入学できる大学づくりを進めたい」と説明した。
日本の設計能力が落ちてきたのか、営業が技術をあまり理解せずに契約を取ってきているのではないのか?
過去のプロジェクトに似ている設計や利用できる部分が多い受注だといろいろな部分で予測が簡単だし、問題がない。しかし、
新しい設計に近い、又は、過去のプロジェクトとは違う受注だと試行錯誤、予測できない問題、下請けや外注との打ち合わせなど
いろいろな面で負担が大きくなると思う。
技術に精通している営業だと出来る事と出来ない事が理解できるのでストレスや気苦労が多いが、技術を理解していない営業だと
精神的には楽かもしれないが、技術的なバックグランドを知らずに打ち合わせや了解すると後で会社や技術者達に負担が来る。
まあ、今回の損失が純粋に資材費増加や設計変更(契約書はどのようになっていたのか?)であれば運が悪かっただけかもしれない。
川崎重工業の金花芳則社長は30日、鉄道車両事業の採算性向上を図る社内委員会を設置を発表し、「自助努力で難しければ、他社との協業や撤退も検討する」と表明した。同日発表した平成30年9月中間連結決算では、米国案件などで受注時の想定を上回る資材費増加や設計変更が相次いだため、同事業で計165億円の損失を計上。最終損益が35億円の赤字(前年同期は108億円の黒字)に転落した。
金花氏は「国内市場も縮小傾向だ。投下資本利益率8%の達成を判断基準とし、年度内に結論を出したい」と述べた。
自業自得!
公立昭和病院(東京都小平市)の空調設備をめぐる入札談合事件で、警視庁捜査2課は30日までに、公契約関係競売入札妨害容疑で、施設管理会社「東京ビジネスサービス」(新宿区)の役員長崎久貴容疑者(60)=埼玉県川口市上青木=を新たに逮捕した。
容疑を認めているという。
逮捕容疑は8月ごろ、同病院が発注した空調設備の保守管理業務の指名競争入札で「大協設備」(大田区)に落札させるため、他の業者が同社を上回る価格で入札するよう調整するなどした疑い。
LLCはコスト削減によって実現されている会社や機体と違法、規則違反、そして安全性に関する部分のコスト削減を行っている会社や機体があると思う。
機体の予備がないと言う事は経営的な負担やトータルコストは少ないが故障がフライト時刻までに直せないとフライトのキャンセルか、飛ぶしかない。
安さで納得しているのであれば利用者の自己判断だと思うが、単純に現状やリスク知らないのなら利用する前に知った方が良い。
最終的に運が良ければ、飛行機は墜落しない。安全率が上がっても運が悪ければ飛行機は墜落する。機体に問題がなくても、操縦側に問題があれば
墜落はある。機体に問題があっても操縦側が良ければ、大事故は回避できる可能性は。全てはいろいろな可能性のコンビネーション。
初めての搭乗で事故に遭う人もいれば、頻繁に乗っていても事故に遭わない人がいる。可能性は減らせても、最後は全ては運しだい。
29日に発生したジャカルタ発のライオン航空機(ボーイング737マックス8型)墜落事故で、この前日にこの航空機の計器に問題があったことが、BBCが入手した記録から明らかになった。
同機は28日にバリ島からジャカルタへ飛行したが、その時の記録によると、計器が「信頼できず」、機長が副操縦士と交代する事態になっていた。
バンカ島パンカルピナン行きのJT610便には乗員乗客189人が乗っていたが、離陸直後に海に墜落した。生存者は確認されていない。
救助隊はすでに遺体や遺品を回収しており、中には乳児用の靴もあった。乗員乗客の家族は、遺体確認のために病院へ向かうよう指示されている。
ライオン航空はインドネシア最大の格安航空会社。BBCの取材に対し、ライオン航空は回答していない。
今回の事故は、ボーイング737マックスが関わった初めての大規模な事故となった。
計器の問題とは? BBCが入手した前日の運航記録によると、機長が確認していた対気速度計の数値が信頼できなかったほか、機長と副操縦士の高度計の数値が異なっていた。このため機長は、操縦を副操縦士にゆだねる羽目になった。
乗務員は飛行を続ける判断を下し、飛行機は無事にジャカルタに到着した。
ライオン航空グループのエドワード・シライト最高経営責任者(CEO)は、同機はバリ島のデンパサールからジャカルタへ向かう間に未特定の「技術的な問題」があったと認めた一方、問題は「解決していた」と話していた。
「もし機体が壊れていたら、デンパサールからの離陸が認められていなかったはずだ」
「乗務員からの報告を受けて、直ちに問題を解決した」
ライオン航空はボーイング737マックス8型を11機保有しているが、他の機体には同様の問題が起きていない。このため、運用を停止する予定はないとシライトCEOは付け加えた。
JT610便に何が起きた? JT610便は29日午前6時20分(日本時間同8時20分)にジャカルタのスカルノ・ハッタ空港を出発した。
同便はバンカ島パンカルピナンのデパティ・アミル空港へ向かう予定だったが、離陸から13分後に連絡が途絶えた。
当局によると、操縦士にはジャカルタの空港へ戻るよう指示が出されていたという。
インドネシア国家防災庁のストポ・プルウォ・ヌグロホ報道官は、海上から回収された、墜落機の破片や乗客の荷物とみられる写真をツイートした。
https://twitter.com/Sutopo_PN/status/1056746231777550337
乗員乗客について分かっていることは? ライオン航空によると、機長と副機長は経験豊富で、2人合わせて1万1000時間以上の飛行経験があった。
乗務員のうち3人は訓練中の客室係員で、1人は技師だった。
インドネシア財務省から少なくとも職員20人が搭乗していたことが、BBCの取材で分かった。
財務省報道官によると、パンカルピナンの財務省事務所スタッフで、週末にかけてジャカルタにいたのを戻るところだった。
ボーイング737マックス8型ボーイングの737マックス・シリーズは7から10まで4種類があり、マックス8型はボーイング史上最も売れている機種だ。
ボーイング737マックス8型は2016年に商用運用が始まったばかり。
今回事故を起こした機体は2018年製造で、短距離便向けのシングルアイル機(通路が1本の航空機)だった。
ボーイングは声明で被害者や遺族に追悼の意を示し、「事故捜査のため技術支援を提供する用意がある」と述べた。
一方でオーストラリアは政府職員などに対し、調査報告が発表されるまでライオン航空を使わないよう指示を出した。
ライオン航空の安全性は多くの島から成り立つインドネシア列島の人たちにとって、飛行機は欠かせない移動手段だが、多くの航空会社は安全面の問題を指摘されている。
1999年創業のライオン航空は、国内だけでなく東南アジアやオーストラリア、中東などとの間を結ぶ国際線も運航しているが、過去に安全や運営で問題を指摘され、2016年まで欧州空域への飛行を禁止された。
2013年にはバリ島の国際空港に着陸する際、滑走路で停止できず海中に落下。乗っていた108人は全員無事だった。2004年にはジャカルタ発の便がソロシティ着陸の際に地面に激突し、25人が死亡した。
2011年と2012年には、操縦士が覚せい剤を所有しているのが相次ぎ見つかった
(英語記事 Crashed jet 'had prior instrument error')
辞任すると言う事はかなり度を越えた接待会食だったのか?
百十四銀行(高松市)は29日、取引先との会食に同席した女性行員が、取引先から不適切な行為を受けたことを巡り、責任を取るとして、代表取締役会長の渡辺智樹氏(66)が今月末で退任すると発表した。11月1日付で相談役に就く。
【株価チャート】百十四銀 直近の値動き
同行によると、渡辺会長と執行役員、女性行員が参加して今年2月に開かれた取引先との会食で、女性行員が取引先から不適切な行為を受けたにもかかわらず制止できなかった。同行は「個人の特定につながる」として詳細を明らかにしていない。
5月に問題が発覚し、同行は6月、会長と執行役員に対し報酬と賞与を減額する処分をした。しかし社外取締役から調査の徹底を求める声が上がり、弁護士らが調べた結果、不適切行為を制止できなかったことに加え、女性行員同席の会食を設けたこと自体が問題と指摘された。渡辺会長は今月28日に辞任を申し入れたという。
渡辺会長は1974年に百十四銀に入行。2009年に頭取に就任し、17年4月に会長に就いた。【岩崎邦宏】
規制緩和は価格競争や生き残る力のない業者の淘汰を意味する。規制緩和によって成長する業者は存在するが、一方で、競争の中で消えて行く業者が
出る事を理解するべきだ。過剰に守られてきた環境で規制緩和に移行すれば、淘汰や力のない業者の消滅を意味する。
もっと儲けたい業者や競争で生き残れない業者は不正に手を出しても不思議ではない。安さや短い所要時間が効率が良いシステムを考えたり、
同じ事を繰り返すことにより改善できる個所を気付いたりしたりする事により実現できたのなら良いが、不正やチェックせずに検査を終える
業者が存在するのなら行政が監督及び処分するべきだと思う。
検査にしても検査には通る基準なのか、次の車検までには部品の交換や不具合が発生しない状態の基準なのかでも違う。次の検査までにどのくらい
走行するのか、頻繁に使用する条件で、判断基準が違ってくる。安さで勝負出来ないところは丁寧さとか、安心を売りにしたり、インターネットなど
で調達できる部品を使う事により総額を安くするなど努力は必要だと思う。インターネットを利用すると部品販売会社は影響を受けるかもしれないが
時代の流れなので仕方がないと思う。インターネットにより流通革命と言うか、過去のシステムが維持できない時代だと思う。
変わらずに生き残れる業者は少ないと思う。環境の変化に対応しながら生きて行くか、ゆとりがあるのなら思い切って業種を変えるしかないと思う。
指定自動車整備工場が不正車検を行ったとして警察に摘発されるケースが近年、静岡県内で相次いでいる。いずれも法定検査をしないことで時間短縮や費用削減につなげたり、不正改造車を受け入れたりして顧客を獲得していた。車検業界ではフランチャイズ展開する大手企業やガソリンスタンドなどの参入が相次ぎ、県内でも指定工場数が増加。家族経営など小規模事業所で経営が圧迫されることが、不正車検の背景にあるとみられる。
「町工場のような指定工場は、どこも資金繰りが苦しいはず」。静岡市内で指定工場を経営する男性は、知名度のある大手チェーンの事業拡大により、顧客が流出している現状に不安を吐露する。手続きの早さと安さを求める顧客が多く、「サービスをできる限り削ってニーズに応えているが、新規顧客の獲得は困難。経営は常にぎりぎり」と明かす。
県内では2014~18年、不正車検を行ったとして島田市や静岡市内の3社が県警に摘発されている。いずれの業者も短い所要時間や整備費の安さなどを売りに、口コミで顧客を獲得していたとみられる。
国土交通省静岡運輸支局によると、1989年度に661だった県内の指定工場数は、2016年度には1007と約1・5倍に増加。自動車性能の向上や点検作業の効率化などにより、規制緩和が進んだことが影響している。
「あまりに無理な値段や短期検査を求める顧客はお断りしている」。静岡市内にある別の指定工場の担当者は、車検には未来の故障を回避する「予防整備」の意味合いもあると強調する。「信頼できる検査をすれば、顧客も安心して車に乗れる。もう一度、車検の意義を考えてほしい」と呼び掛ける。
<メモ>指定自動車整備工場 国の指定を受け、国の検査場に代わって自動車の保安基準適合証を交付できる工場。民間車検場とも呼ばれる。みなし公務員に当たる「自動車検査員」の国家資格を持つ工員を、工場内に1人以上配置する必要がある。指定工場のほかに、検査機関がある運輸支局などに車両を持ち込んで検査を受ける認証工場もある。
記事を読むと自業自得だし、こうなるのは時間の問題だったかもしれない!
「うち(の会社も)含めて、連鎖倒産する可能性があるんです」「1億2000万円の借金ですよ、耐えられますか」「(経営陣は)家売ってないでしょ。工事会社は身を削っているんですよ」
この記事の写真を見る
10月4日、東京都内のある貸し会議室は怒りと悲哀にあふれていた。議題の中心にいるのは、この3日前に民事再生手続きを申し立てたゼネコン。取引先が一同に介し、今後の対応を経営陣や代理人弁護士に追及した。
倒産したのは、さいたま市に本社を構える中堅ゼネコンの「エム・テック」。負債総額は253億円。建設やリース会社を中心に債権者が887名いる。10月初旬にはJASDAQ上場の暁飯島工業や麻生フオームクリートが貸倒引当金を計上したほか、メインバンクである東和銀行も民事再生申立書に約23億円もの債権を提出している。
「5日後に手形が落ちる。このままでは不渡りになる」。会場では下請け会社からの悲痛な叫びがこだました。
■我が世の春から一気に転落
エム・テックは強化コンクリート工事を祖業とし、近年は不振の建設会社を買収したり、東日本大震災に伴う復興工事を相次いで受注したりするなど、急成長を遂げて業界内で話題の会社だった。2017年7月期の単体売上高は244億円と、5年前に比べて約1.5倍に増えた。
好景気の波に乗り、破竹の勢いで業績を伸ばしていた同社だが、昨年末から立て続けに不祥事に見舞われた。
発端は昨年12月に発覚した建機販売・リース会社「PRO EARTH(プロアース)」の破たんだ。エム・テックは約10億円の筆頭債権者だったが、本来であればゼネコンはリース会社に代金を支払う債務者であるはず。プロアースで循環取引などの不正を取り沙汰される中、エム・テックが債権を有することに対して「金融機関から不信の目を向けられ、融資姿勢が厳しくなった」(エム・テックの向山照愛社長)。
さらに今年3月には無許可で港湾工事を行ったとして、東京地検が同社と従業員を起訴。これを受けて全国200以上の自治体から指名停止を食らい、受注寸前だった工事も取り消しとなった。同社の事業内訳を見ると、公共機関からの発注がほとんどの土木や強化コンクリート工事が6割を占める。公共工事からの排除は、会社の息の根が止まることに等しかった。
こうした状況の中、資金繰りは急速に悪化した。「今年に入ってから、現金から手形へ支払い条件を変更できないかと打診された」(下請け業者)。途中で元東証一部上場の冨士工から合計15億円の出資を受けるも改善には至らず、倒産に至った。
■破産で発注者に契約解除の通知
ここまでだけなら、一つのゼネコンの倒産劇で終わるはずだった。だが、10月22日、事態は急変する。民事再生スキームが行き詰まり、破産手続へと移行したのだ。再生に向けたスポンサーが見つからなかったためだ。
当初は冨士工がスポンサーとして有望視されていたが、「15億円の出資に応じたのは、トップ同士にお付き合いがあったから。それ以上の支援を検討したことはない」(同社)。他社にも支援を仰いだが、スポンサーのなり手は見つからなかった。
事業を継続しつつ会社を再建する民事再生であれば、スケジュールの遅延はあれど工事が中止になることはない。だが、破産となれば会社が清算され、工事を行うゼネコンがいなくなる。
今月1日時点でエム・テックは全国の現場88カ所に約300億円もの工事を抱えていたが、22日に発注者に対して契約解除の通知を発した。そこで懸念されるのが、東京五輪の競技施設工事の行方だ。
同社はカヌー・スラローム会場の管理棟建設と、有明テニスの森公園の屋外テニスコート改修工事を行っていた。「民事再生手続き申立て後も工事を続ける意向を示したので、再開を待っていた。今後は別の業者への発注を含めて、対応を検討している」(東京都オリンピック・パラリンピック施設整備課)。現場は建設途中のまま放置されており、工事予定表は破産した22日を最後に更新されていない。有明テニスの森公園の現場事務所の電話番号はすでに使われていなかった。
取り切れないほど仕事があり、採算が良い工事を選別できるほど好況に沸くはずの建設業。そんな中での倒産は業界にどんな教訓を遺したのか。
エム・テックを破産に追い込んだ要因の1つは、コンプライアンス(法令遵守)の軽視だ。
たとえば、指名停止につながった港湾工事。同社は2016年12月に東京都から橋の撤去工事を受注した。港湾工事では工事によって船の往来が阻害されるため、工事の日程や時間帯は許可制になる。2017年4月から6月末まで工事の許可が下りたものの、同社は許可更新を怠り、7月に入っても工事を行っていた。さらに日の出から日没までという条件を破り、深夜まで工事を続けるなど違反が重なった。
■東北の支店を次々に閉鎖
もう1つは、エムテックの急成長を支えた、東日本大震災の復興工事の収束だ。破たん時点でも宮城県発注の工事を契約総額で80億円も抱えていたように、同社は東北地方での工事に注力していた。
同社の業績を見ても復興工事への依存は明らかだ。2012年7月期に4億円だった営業利益は、2015年7月期には19億円まで増加した。だが、その後の営業利益は震災前の水準に逆戻りしている。
好採算の復興工事が収束し、採算性の劣る工事にシフトしていったことで、「貧乏暇無し」の状態に陥った。取引のあった東北地方の測量会社社長は「ここ数年は東北地方の支店を次々に閉鎖し、営業地域を南下していった」と話す。
債権者説明会会場から出てきた下請業者の社長は「支払い遅延が起きていたとは聞いていたが、まさか潰れるとは」と肩を落とす。今回の倒産劇は自業自得か、はたまた建設業の異変をさえずるカナリアか。
一井 純 :東洋経済 記者
結局、正直者は損をする可能性が高い。
電子部品などを手がける日立化成で、半導体向け素材の検査データを巡る不正の疑いがあり、取引先に通知していたことがわかった。この素材は、パソコンや家電、自動車など幅広い製品に使われるもので、日立化成は取引先に連絡を取り、安全性などについて調査を進めている。
日立化成は日立製作所の子会社。関係者によると、不正は半導体のICチップを覆う樹脂の素材で行われた。日立化成は、顧客と交わした契約とは異なる方法で検査を行っていたという。
日立化成は、エポキシ樹脂を使った半導体用封止材と呼ばれる素材で世界トップクラスのシェア(占有率)があるとされる。産業界に影響が拡大する可能性がある。
半導体は、計算機能を担うICチップを封止材で覆うことで、光や熱、ほこりや衝撃などから保護している。封止材は、携帯電話やパソコンを分解すると、半導体を黒いカバーのように覆っている樹脂状のものだ。耐熱性や耐湿性に優れた製品が求められている。
この封止材に問題がある場合、長い期間、使われている間に不具合が生じる可能性が考えられる。
日立化成は読売新聞の取材に対し「現時点では何も申し上げられない」としている。
日立化成は29日、産業用鉛蓄電池の一部製品で検査成績書の数値記載に不正があったと発表した。電池容量などの測定を顧客との取り決め通りに行わず、独自基準の検査に基づき架空のデータを記載していた例が2011年4月から18年6月の期間で約6万台見つかった。対象企業は500社。性能と安全性には問題ないとしている。外部専門家で構成する特別調査委員会を設置し原因究明を行う。
設計段階や量産前に問題に気付かなかったのだろうか?
自動車の品質にかかわる不正が相次いで発覚したスバルが、一連の不正とは別の大規模なリコール(回収・無償修理)を近く国土交通省に届け出ることになった。車の心臓部にあたるエンジンの部品が対象になる。リコール作業の手間がかかり、費用もかさむとの見方が出ており、業績に及ぼす悪影響への懸念が広がっている。
不具合の恐れがあるとしてリコールされるのは、「バルブスプリング」と呼ばれるエンジン部品。動力を生み出すために燃料を燃やす際に、燃料と空気を混ぜたガスを「燃焼室」に吸入したり排出したりするバルブ(弁)を閉じる役割を果たす重要な部品だ。
万一、不具合が生じれば、走行中にエンジントラブルを起こして車が停止する恐れがあり、事故を招きかねない。スバル車の品質への信頼がさらに揺らぐのは避けられそうにない。
主力の日米市場で販売した複数車種の少なくとも数十万台がリコール対象になる模様だ。世界販売台数が約107万台(2017年度)のスバルにとって、リコールの規模は極めて大きい。スポーツカー「BRZ」や、トヨタ自動車と共同開発し、BRZと同じエンジンを搭載するトヨタのスポーツカー「86(ハチロク)」も対象に含まれる。SMBC日興証券の木下寿英シニアアナリストは「重要部品のバルブスプリングの不具合なら影響は大きい」と指摘する。
スバルでは昨秋以降、出荷前の完成車の検査で相次いで不正が発覚。9月には安全性能にかかわるブレーキの検査での不正も明らかになった。無資格の従業員が完成車の検査をしていた問題では、今年2月までに計約42万台のリコールを届け出て、作業はいまも続いている。その中で新たに大規模なリコールを迫られることになった。
スバル車に搭載されている独特の水平対向エンジンは、バルブスプリングが横向きに並んでいて、交換などの作業をするにはいったんエンジンを取り外す必要があるという。1台当たりの作業時間が長くなり、対応の長期化も避けられそうにない。リコール費用が膨らむ恐れもある。スバルの独自技術で、熱心なファンがいる水平対向エンジンが大規模リコールの対象になれば、スバルブランドへの打撃となるおそれもある。
10年7月には、バルブスプリングに異物が混入して折れる可能性があるとして、トヨタ自動車がクラウンと高級車レクサスの計4車種を対象に、国内で9万1903台、世界で約27万台のリコールを届け出た。
スバルが、エンジンの部品が壊れる恐れがあるとして、複数の車種について大規模なリコール(回収・無償修理)を近く国土交通省に届け出ることがわかった。国内だけでなく、海外で販売した車種にも影響が及ぶ可能性がある。対象は少なくとも数十万台にのぼる模様だ。
バルブスプリングというエンジン部品が不具合を起こし、エンジンの作動に影響が出る恐れがあるという。日米の市場で販売した戦略車種が対象になるとみられる。スポーツカー「BRZ」も対象に含まれる。
トヨタ自動車と共同開発し、「BRZ」と同じエンジンを搭載しているトヨタのスポーツカー「86(ハチロク)」もリコールの対象になる。
スバルでは昨秋以降、無資格検査問題や排ガス・燃費データの改ざん、ブレーキ検査の不正などが相次いで発覚。さらに今月23日、2018年9月中間期の利益予想を大幅に下方修正し、営業利益が5月時点の予想を490億円下回る610億円になる見通しだと発表した。品質関連費用の計上が下方修正の主因で、一連の不正とは別の品質問題に伴う費用だと説明。11月5日に予定している18年9月中間決算の発表時までに新たな品質問題の内容を公表するとしていた。
将来の日本は暗いかもしれない。貧富の格差がさらに広がるのは確実だと思う。
日立製作所が笠戸事業所(山口県下松市)で働くフィリピン人技能実習生に実習途中で解雇を通告し、実習生側と賃金補償で大枠合意したことについて、経団連の中西宏明会長(日立製作所会長)は24日の定例記者会見で、「不適正なものはないという認識でやっていたところが、不適正だと言われて困ったなと。雇用には責任が伴うから、解雇通告を出したが、このくらい(の補償)は、と決めたのだと思う」と述べた。
鉄道車両を製造している笠戸事業所は、実習生に目的の技能が学べない作業をさせている疑いがあり、技能実習制度を所管する法務省や国の監督機関「外国人技能実習機構」の検査を受けた。中西氏は、賃金補償に応じたのは雇用主としての責任からであり、不適正な実習をさせていたかどうかとは「全然ちがう次元の判断」だと強調。「(実習生に)一生補償するわけではないが、それ相応の折衝をして決めたと思う」と説明した。
中西氏は9日の経団連の定例会見では「適法うんぬんのことはいっさいまだ結論が出ていない」「違法性はいま現在、ないと信じている」と述べていた。法務省や実習機構は、日立に対して改善を求める処分を検討しており、国側が実習の適否をどう判断するかが注目される。
笠戸事業所では、3年間の実習のため昨年7~8月に入国した実習生ら40人が今年9~10月に解雇を通告された。日立は、実習機構から2年目以降の実習計画の認定を得られず、「出入国管理法により就労が認められないため解雇とし、一時的に雇用契約を終了した」(広報)と説明している。
実習生らは不当解雇だと主張し、個人で加盟できる労働組合に入り、十分な賃金補償などを求めて日立と団体交渉を重ねてきた。日立が19日の団交で、国側から実習中止の処分を受けた場合、残りの実習期間約2年分の基本賃金を補償する考えを示し、実習生側と大枠合意した。
一方、政府が進める外国人労働者の受け入れ拡大策について、中西氏は24日の会見で「経団連の意見を相当反映した方向で、決めていっていただいている」と評価。この日始まった臨時国会で出入国管理法(入管法)改正案が成立し、来年4月から外国人の新たな在留資格が導入されることに期待を示した。
日立などの大企業でも技能実習制度をめぐるトラブルが相次ぐなか、新在留資格を導入するのは拙速ではないかとの質問には、「拙速だと思わない。半年かけて議論すればよいのでは」「制度は仮説を立ててつくって、試して、直していく。そのぐらいのスピードでやらないと日本は変わっていかない」と反論した。(内藤尚志)
京都中央信用金庫(本店・京都市下京区)は26日、京都府和束町内の出張所の営業係長だった男性(5月に自殺、当時58)が、顧客12人の口座から計1億5500万円を着服していたと発表した。すでに別の顧客11人から計9370万円を着服したことが判明しており、5月に懲戒解雇されていた。
信金によると、男性は2001年から今年3月にかけ、顧客から預かった現金を口座に入金したように偽ったり、定期預金を無断で解約したりする手口で、勤務していた府内6店の顧客の口座から着服を続けていた。被害に遭った顧客には信金が全額を返した。
顧客から5月8日、「残高が足りない」と信金に連絡があり、問題が発覚。この日を最後に男性と連絡がつかなくなり、数日後に府内で自殺しているのが見つかった。
信金は7月、白波瀬誠理事長を含む役員や幹部の計31人を減給や昇給停止の処分にした。
不正や違反のチキンレースと横並び社会の日本が生み出した問題だと思う。
「KYBは再検査となった場合、検査のやり直しに5時間近くかかるという。」テレビ番組で見たが、これに加え再検査に通るようにするために分解し(時間の説明はなかった)、調整して組み上げるのに7時間と言っていた。つまり、検査に通らなければ一日がかりの仕事になると言う事。
また、これだけ検査に通らない確率が高ければ、2度目の検査で検査に通る確率も高くないはずである。
納期の問題を(カヤバ工業)と川金ホールディングスは問題の原因としているが、納期が長くなるのは予測できることである。予測不可能な事故や
失敗で納期が遅れるので、データを改ざんしたのであれば一度きりの改ざん、又は、数回の改ざんで終わる。
今回の改ざんは、納期が守れない事がわかっている事を営業や設計に伝えれば、商談の段階で本当の納期を伝えるだけでよいし、再検査を繰り返して
いたらコストがかかるのであれば、価格設定を変えればよいだけで問題は解決できた。ただ、現実問題として、価格が高ければ他のメーカーの製品を
選ぶ顧客が増える事が考えられるし、納期が長ければ、他のメーカーが商談で納期が短い事をアピールして仕事の取れないかもしれない。
しかし、だからと言って継続的な不正やデータの改ざんを選択するのは問題だし、モラルの問題である。
「検査通過率に合わせて、検査に人員を割くなど現場の負担を減らすことはできなかったのかと悔やまれる。」
個人的に思うのが会社の体質だと思う。事実が言えない、又は報告できない環境であったとしても、それは会社の体質の一部である。
現場の負担を減らすことはできなかったのか
KYBが免震や制振用オイルダンパーの検査データを改ざんしていた問題で2003―15年に生産した免震ダンパーのうち半分以上が再検査になっていたことが分かった。確認できた性能検査データによると同期間に免震ダンパーを約4000本生産し、その間の検査合格率は約45%だった。15年以降に製品の改良が進み、17年に合格率は86%前後まで改善。そのため、不正やその疑いがある製品は15年以前に集中している可能性がある。
KYBの不正は00年3月から18年9月まで続いていた可能性があり、その間に免震ダンパーは合計1万369本を出荷した。このうち不適合品やその疑いのある製品が7550本。免震ダンパーに関しては約70%以上がデータ改ざんされていた可能性がある。そのため、業界では「市場に投入された当初から、製品が性能を満たしていたのか疑問だ」という声があった。
免震ダンパーは「15年以降の製品から初回の検査通過率が8割を超えた」(斎藤圭介KYB専務)とするが、データが確認できる03―15年は半分以上が再検査となっていた。同期間でもデータが確認できず判断不明な製品も存在する。そのため正確な検査率は把握できないが、残存するデータ上では最低でも2000件以上の再検査が行われていたことになる。
KYBは再検査となった場合、検査のやり直しに5時間近くかかるという。不正を行った理由についても「時間がかかるため(改ざんを)行ってしまったのではないか」(中島康輔KYB会長兼社長)と人件費の削減などを挙げている。15年以前に再検査数が膨大だったため、不正に手を染めた可能性が高い。
<記者の目>
KYBによれば、問題の検査データ改ざんは、検査工程で引っかかった製品の数値を、記録し、再検査で通過できるように係数を加え改ざんしていたという。免震ダンパーのような大型製品は内部の部品搭載も多く、再検査のために、部品をばらして、最初から点検するのは大変であり、その間の作業ももちろんやり直しとなる。実際、一つの製品の再検査には3―5時間近くかかるようだ。
そのため、再検査の対象が多ければ、現場の負担は比例して重くなる。実際、不正行為の理由については会見で「なかなか製品の適切な性能が出づらく、改ざんしてしまったないか」と説明している。再検査になってしまうこと自体は製造現場では仕方ないことだ。だが、検査を通過しづらい、もしくはバラツキが大きすぎる製品を投入したことは問題の要因だった可能性がある。もちろん、免震用ダンパーは自動車用ダンパーほどの生産量はないため、生産の自動化による品質改善などは難しかったのかもしれない。
だが、KYBは17年には免震ダンパーの検査合格率86%まで改善している。改ざんをしなくても、初回検査を通過させる性能とその技術は潜在的にはあったとみられ、当初からもう少しバラツキを抑えた製品を市場投入すべきだったのかもしれない。または、検査通過率に合わせて、検査に人員を割くなど現場の負担を減らすことはできなかったのかと悔やまれる。
(日刊工業新聞・渡辺光太)
大学名非公表を判断した文科省が一番問題があると思う。文科省がこのような対応を組織である以上、大きな改善や改革を期待するのは 間違い。
出願時から現役生に加点。補欠合格で特定の受験生を優遇-。大学医学部の入試問題をめぐる調査で、文部科学省が23日に公表した中間報告では、入試の各段階で、性別や浪人年数などによって合否に差異を設けていた実態が明らかになった。出願時期が迫る中、受験生への影響は大きく、ぎりぎりでの志望校変更などの混乱が予想される。予備校関係者からは、不正の疑いのある大学名などを公表しなかった文科省の対応にも疑問の声が上がっている。
【グラフ】大学入試 出願数に対する男女別入学者の割合
「面接などで女子や多浪生を不利に扱っているというのは、受験業界では知られていたが、出願時の書類審査から現役生に加点していたとは驚きだ。まじめに勉強してきた受験生がかわいそう。大学名が明らかになれば、志望校変更の動きが当然出てくるだろう」
大手予備校の関係者はこう話し、入試の入り口段階から不適切な扱いがみられたことに憤った。
中間報告によれば、不適切とはいえないまでも「誤解を招きかねない事案」として、補欠合格や繰り上げ合格の決定を学長や学部長らに一任しているケースや、面接で多浪生を慎重に検討することをマニュアル化しているケースなど、グレーゾーンが多い実態も判明した。
別の予備校関係者は「こうしたグレーゾーンも、不適切な扱いと同列だ。受験生には対応のしようがなく、とくに多浪生のショックは大きいだろう」と懸念。文科省が大学名などを明らかにしなかったことについては、「多くの私立大医学部は12月から出願が始まる。その時期が近づくほど、大学名が明らかになることへの受験生への混乱は大きい。考慮すべきだ」と話す。
医学部入試をめぐっては、東京医科大(東京)の1次試験で特定の受験生を不正に加点したり、2次試験で女子や3浪以上の合格を抑制する得点操作を繰り返したりしたことが判明。昭和大(同)でも2次試験で現役と1浪の受験生に加算する得点操作などをしていたことが分かり、両校とも陳謝している。
ただ、大学によって対応は分かれており、文科省から不適切な扱いの疑いがあるとして説明を求められている順天堂大(同)では、第三者委員会による調査結果を11月下旬をめどに公表することにしている。
下記の記事について個人的には違う意見を持っている。
高齢や年上の人達と話すと昔から不正はあったようだ。ただ、自分の信念や技術者根性を持っている人達が損得勘定関係なしに関与しているケースが
あったからストッパー的に機能したのではないかと思う。
最近は、自己中心的な人や関係者が黙っていれば問題が発覚しないと思う人達が増えて、損得関係なしで衝突する人達が減ったと思う。
過去のバランスが変わり、隠蔽に関わる人達が増えたのではないかと思う。だから問題が初期段階で改善されず、問題が発覚したら大変なことになるから隠蔽し続けなければならない、又は、問題が発覚すれば処分されるから隠蔽を巧妙にするようになったのではないかと思う。
病気でも、問題でも初期段階であれば、深刻でないレベルで治癒出来たり、簡単に解決できる。初期段階を過ぎて、中期から、末期になると
簡単に後戻りは出来ないし、事実を知る事が恐ろしくなる。
また、データ改ざんや問題が発覚する確率を考えて、低ければ不正を選択するずる賢い人々が増えたと思う。昔の日本人がどのような人達であったのかは知らないが、損得や確率で判断する人達が増えたと思う。
学校教育にしても、貧困とか塾とか言って騒ぐが、塾に行かなくても、多少、現状の学力が劣っても、大学で意欲的に学びたい生徒が学べる
環境を整備するべきではないのか?入学したら勉強しなくても良い大学があっても良いが、勉強しなくては卒業できない変わった大学が
あっても良いのではないのか?会社や社会がそのような大学を卒業した学生を評価し、採用すれば、出世のため、自分のため、そして会社のために
インチキをする社員は減ると思う。会社のためだけに働く社員が欲しければ、そのような大学を卒業する生徒を採用しければよい。
ただそれだけだと思う。
油圧機器大手「KYB」(旧カヤバ工業、東京都港区)と子会社カヤバシステムマシナリーによる免震・制振装置の検査データ改竄が大きな問題になっています。2015年に東洋ゴム工業(兵庫県伊丹市)による免震ゴムのデータ改竄が発覚し社会問題化しましたが、わずか数年の間に相次いだ免震装置絡みの不祥事に、憤りを感じている人も少なくないのではないでしょうか。
ダンパー改ざん、不正は許されないが安全への過度な心配は不要、技術への信頼失墜は重大
建築家で、文化論に関する多数の著書で知られる名古屋工業大学名誉教授・若山滋氏は、相次ぐ不正について「現代日本のものづくり技術が壁に突き当たっている」と指摘します。そして、その背景には、時代とともに技術者の置かれている立場が変化してきたことがあるのでは、と問いかけます。若山氏がこの問題について論じます。
ダンパーのデータ不正と安全
フィリピンのボホール地区における防災プロジェクトに参加して「日本の建築耐震技術は高度化しているが、災害は常に人知を超えていくので、野生的ともいうべきサバイバルの意志が重要だ」と述べて日本に戻ったら、大変なことが起きていた。
建築の免震・制震装置に使われる油圧ダンパーの製造にデータ改竄があったというのだ。その分野のトップメーカーであり、供給されたダンパーの数が多く、しかもきわめて重要な建築に使われていたことから、日本社会の安全を揺るがす大問題となっている。
もともと滅多にない大きな地震が来たときに揺れをコントロールする装置であり、地震に対する建築安全のメカニズムは複雑多様なものであるから、そのまま致命的な危険性に直結するわけではなく、取り替えも可能ということで、パニックに陥る必要はないと思われるが、人命に関わるデータ改竄であるから、由々しき問題であることは間違いない。
しかもKYB(カヤバ工業)という歴史のある技術力の高い企業だ。
マスコミ報道は過熱気味だったが、先日のヤフーニュースに名古屋大学減災連携研究センター教授の福和伸夫氏のコメントが出た。僕もよく知っている人で、建築防災の権威でもあり、専門的な説明としてはそちらを参照するのがいいと思われる。
ここでは少し視点を変え、一般的な建築専門家として、現代日本の安全技術に関する社会文化論的な見解を展開してみたい。
不正は検査員の申し送りだったという。つまり幹部の指示による会社ぐるみの組織的不正というわけでも、一部特異な技術者の個人的不正というわけでもなさそうで、責任者の特定が難しく、日本の産業技術の網の目に潜在する構造的な歪みが露呈したものと思われるからだ。
ブームとしての免震・制震
阪神淡路大震災の惨状以来、建築界では「免震・制震」の技術がブームのようになり、東日本大震災でさらに拍車がかかった。
これまでの耐震構造設計とは異なる考え方であり、コストアップになるのだが、安全第一を唱える(税金でつくる)官公庁を中心に、売れ行きに直結する高層のオフィスビルやマンションにも浸透していった。ブームというのはつまり、地震に対する安全を原点から検討するというより、免震・制震でありさえすればいいという状況であったといえる。
ひとことでいえばこの技術は、建築の安全を「機械」に頼るものだ。
ゴムやバネや油圧といったもので構成されている機械は動きもあり、コンクリートや鉄筋やガラスで構成されてほとんど動かない建築と比べて、耐用年数が圧倒的に短い。経年劣化のメンテナンスや大きく動いたあとの副作用など「本当に大丈夫だろうか」という若干の危惧があった。理論と実験だけではなく、実際の大地震を何回か経験するには百年単位の時間が必要なのだ。
案の定というべきか、2015年、東洋ゴム工業の免震ゴムに、今回、KYBの油圧ダンパーにデータ改竄問題が起きた。ブームによって急増した需要に供給が間に合わないことが原因の一つと思われる。
喉元が熱いうちに将来の方針を決めるな
考えてみれば、阪神淡路、東日本と、大きな犠牲者を出す震災が続く中、日本全体が防災ブームのようになっていたのではないか。政府の方針とマスコミ報道が防災意識を高める方向に傾くのは仕方ないにしても、安全の問題がブームになるのはどうだろうか。恐怖は合理的判断を曇らせるものだ。
一例が、東日本大震災のあと、被災地に築いている高大な防潮堤である。その論理を、想定される南海トラフ地震などに当てはめれば、日本中の海岸を高い壁で囲わなくてはならない。それよりも、いざという時には避難に使える鉄筋コンクリート構造あるいは重量の鉄骨構造の建築(例外を除いて津波には流されていない)を点在させる方がはるかに合理的であり、少し経過した時点では、専門家も地元も防潮堤に対する反対意見が多くなっている。喜んでいるのは巨大な復興予算を使いきれなかった政府自治体とゼネコンだけだが、一度決定した政策は簡単には変えられない。「喉元過ぎれば熱さを忘れる」という言葉の逆に「喉元が熱いうちに将来の方針を決めるな」という格言も成り立つように思う。
日本は過剰管理社会
もちろん、正確なデータとその扱いは科学技術者の命であり、改竄などあってはならないことであるが、それにしても、老舗トップメーカーにこれだけの不正と杜撰が相次ぐことに、現代日本のものづくり技術が壁に突き当たっていることを感じざるをえない。三つの理由が思い浮かぶ。
第一に、日本が過剰管理社会になり技術者が窒息ぎみであること、第二に、技術がブラックボックス化し多分野化していること、第三に、若い技術者が良い子になり現場が忖度社会になりつつあることである。
産業技術に関して、何か問題が起きるたびに、マスコミが集中的に批判し、監督官庁がそれに対応するので、次々に規制が厳しく細かくなっていく。近年は過剰管理というべき状況だ。管理、監督、検査、報告の業務が肥大して、技術者はその対応に疲弊し、本来の仕事に専念することができない。しかもその管理データはある一面の数字であり、現場技術の微妙な問題を反映しているとはいいがたいので、老練で自信がある技術者ほど、管理の数字を軽視することになる。
たとえば道路の速度制限でも、ほとんどの車が制限を超えて走る。制限どおりに走ると後ろから煽られて却って危険であり、多少の速度超過では捕まらないという妙な常識ができているのと同じように、規制の数字を軽視して「この程度までは大丈夫」とタカをくくるのだ。
設計事務所から大学の教官に転職した僕の経験でいえば、60年代までは規制が不十分で、いい加減な設計と工事が多かった。70年代、公害が問題となり、労働者と使用者の安全が重視され、さまざまな規制が設けられ、日本の建築業界はこれに応えて、安全で高性能な建築をつくりつづけた。しかし70年代後半から80年代には、その規制がやや過剰な様相を呈してくる。日影規制や排煙設備など日本特有の複雑な法令が成立し、外国の設計者や施工者はとても参入できず、アメリカはこれらを非関税障壁として攻撃した。90年前後が日本のものづくり技術のピークであったか。やがて日本の産業から競争力が失われていった。かつては日本に習おうとした海外の技術者も、今は「日本の技術管理は厳しすぎて参考にならない」といい出した。規制緩和の掛け声もあるが、容積率緩和など景気浮揚効果とデベロッパーの利益につながるものばかりで、産業技術に関しては規制強化一辺倒である。マスコミと政治家と官僚が一体となって、この国を管理化に向かわせる趨勢は簡単には止められない。
現在、大手設計事務所の仕事の多くは、本来の建築設計ではなく、合意形成のための調査と計算と図面書類づくりだ。決断力のない政治と経営のシワ寄せがすべて技術者に押し付けられている。
ブラックボックス化する社会システム
また、技術が高度化し複雑化するにしたがって、構成部分のパッケージ化が起き、その内部は誰にもチェックできない、いわゆるブラックボックスとなる。特にコンピューター制御によってそれが加速された。
研究開発においても、昔はデータと計算の間違いをチェックできたが、現在はまったく不可能だ。コンピューターの膨大迅速な処理プロセスを人間が追いかけるのは、スズメがジェット機を追うようなものである。STAP細胞事件もそういう下地から起きてくる。
現代は大量のデータが瞬間的に処理されて社会が運営されている。ものづくり技術ばかりでなく、社会システムそのものがブラックボックス化しつつある。システムに事があれば、航空や銀行や株式市場の混乱も起きる。
そして技術の高度化によってさまざまな分野の複合が起きている。物理学と化学、機械工学と電気工学の境界も曖昧になり、生物も機械に組み込まれ、医療も介護も物理化している。ロボットやAIがこれを加速する。
免震・制震のシステムは前述のように、建築技術を機械技術に置き換えることで、これまでは建築安全の全体に責任をもっていた構造技術者も、機械部分は分からないという。その部分に強い機械技術者も、建築全体のことは分からない。その境界に問題が起きる。
福島第一原子力発電所の事故のとき、当該ゼネコンの技術者は、電力会社が主導していたので全体の安全に責任がもてず、しかもアメリカのスペックだったと発言した。ある学者は、屋上屋を重ねるように安全の委員会をつくったが、実に単純素朴な問題を見落としていたと発言した(いずれも私的な場であるが)。分野をまたいで組織が肥大したときに、安全技術のスキマができるのだ。
技術者の良い子化と現場の忖度社会化
さらにもうひとつ、現代日本人の性格の問題がある。技術者が良い子ばかりになっているのだ。
昔の技術者は意固地なところがあった。自分の専門に何か問題を感じたときは躊躇なく発言したが、今の若い人は周囲をおもんばかって異論を唱えない傾向がある。技術者には、それまでの慣行を破ってでも改善する勇気ある行動が必要だ。職場の平和を乱しても、上司にたてついても、筋を通す必要がある。今はそういうヤンチャだが本質を突く技術者が少なくなっている。平和で豊かな時代が続き、技術の現場にも、島国特有の忖度社会が復活しているということだろうか。
日本再野生化を考える
KYBという老舗のトップメーカーが問題を起こしたことは、衝撃であったが、こう考えてくるとむしろ「老舗大企業なのに」ではなく「老舗大企業だから」なのではないか。小さな町工場では起こらないような気がするのだ。
過剰化した管理の網の目を簡素化し、重要点に絞る必要がある。
日本社会にもう一度野生の活力を取り戻す必要がある。
日本再野生化だ。
モデルは、山口県周防大島町で、警察と消防の組織された捜索団に先んじて3日間行方不明だった幼児を発見した、スーパーボランティアの尾畠春夫さんだろうか。野生のプロが一人で、組織管理のプロ集団を凌駕したのだ。
フィリピンのボホール地区で素朴な防災避難訓練に集まった人々の笑顔が思い浮かぶ。
「赤信号、皆で渡れば怖くない!」は凄い!日本文化を良く説明していると思う。
地震による建物の揺れを抑える免震・制振用のダンパーをめぐり、これまでに検査データの改ざんが明らかになっている油圧機器大手の「KYB」グループとは別の会社でも、データの改ざんが行われていたことが新たにわかりました。
改ざんが行われていたのは、「川口金属工業」が前身の「川金ホールディングス」の子会社の「光陽精機」が生産し、「川金コアテック」が出荷した免震・制振用のダンパーです。
川金ホールディングスの鈴木信吉社長が、23日夕方記者会見し、「所有者や建設会社などの関係者に多大なご心配とご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げる」と陳謝しました。
会社によりますと、改ざんは、ダンパーの出荷を始めた平成17年2月からことし9月にかけて行われ、顧客と契約した基準を満たしていない場合に、検査データを書き換えていたということです。
改ざんされたダンパーは、全国の93の物件に設置されていて、地下に設置する免震用が4件、柱やはりなどに設置する制振用が89件となっています。
用途別では学校・教育施設が31件、事務所が16件、庁舎が13件などとなっています。
このほか改ざんされたダンパーは、台湾にも出荷されていたということです。
個別の物件名は、建物の所有者などに連絡し了解を得たものについて公表するとしています。
改ざんの理由について鈴木社長は「動機については調査中だが、製品の性能や納期で顧客の満足のために行われたと認識している。目先の納期に目が行ってしまい、品質に対する感覚がおろそかになっていたのではないか」と説明しました。
また、検査は、検査担当の社員と補助する係の2人で行われ、検査担当の社員が書き換えをしていたということです。
国土交通省は、会社側にダンパーの交換などを速やかに行うとともに、改ざんの理由を明らかにし再発防止策をまとめるよう指示しました。
岡山の中学校で
岡山県総社市の中学校の校舎で、この会社のデータが改ざんされたダンパーが使われていることがわかりました。
岡山県や総社市によりますと、総社市駅前にある総社西中学校の校舎でこの会社の検査データが改ざんされたダンパーが使われていると、国土交通省から連絡があったということです。
校舎には、この会社が製造したダンパーが32本使われていて、このうちの4本で検査データが改ざんされていたということで、教育委員会は今後、保護者に説明することにしています。
また、県や総社市によりますと、校舎の耐震性に問題があるかどうかはこれまでのところ確認できていないということで、市は、メーカーに詳しい説明や適切な対応を求めていくことにしています。
さいたま市役所でも
埼玉県内では問題のダンパー14件が設置されていてたことがわかりました。
このうちの1件はさいたま市浦和区にある市役所の本庁舎で、2年前から進められている耐震補強工事で導入された122本のダンパーのうち12本が問題のダンパーを使った装置だということです。
さいたま市庁舎管理課は「信頼して発注したものなので改ざんがあったことは誠に遺憾です。どの部分に使われているか早急に事実確認をし交換など適切な対応を求めたい」としています。
このほか埼玉県によりますと、県内では県庁第二庁舎や集合住宅など県有の施設で4件、また川口市の公立中学校や川越市の市役所庁舎など市の施設で4件、それに寺院や工場など民間の施設5件で問題のダンパーが使われているということです。
現在製造・販売は全国で4社・3グループだけ
国土交通省やメーカーなどへの取材によりますと、今回、問題となっている「免震オイルダンパー」を現在も、製造・販売しているのは全国で4社・3グループだけです。
このうち、今月16日に検査データの改ざんを最初に公表した油圧機器大手の「KYB」グループは新規の受注を停止する方針を示しています。
また、23日改ざんを明らかにした「川金ホールディングス」の子会社2社も、今月20日から新規の出荷を停止する対応をとっていて、今後の生産体制はこれから検討するとしています。
改ざん問題の発覚によって、新規物件のダンパーを生産しているのは、東京に本社がある「日立オートモティブシステムズ」だけとなっています。
国土交通省は23日、光陽精機が製造し、川金コアテックが出荷した免震・制振用装置に、顧客との契約内容に適合しないものが93件あったと発表した。
検査データが書き換えられていたという。
「実際には、基準を満たしている製品についても、顧客に対して性能をよりよく見せるため一部でデータを改ざんしていたことが新たにわかりました。」
仕事を取るためにやったのであれば詐欺ではないのか?相手が被害届を出せば、犯罪になるのか?
油圧機器大手の「KYB」グループによる免震・制振用ダンパーの検査データの改ざん問題で、基準を満たしている製品についても、性能をよりよく見せるために改ざんを行っていたケースが新たに108の物件であったことがわかりました。
KYBグループは地震の揺れを抑えるダンパーの検査結果を改ざんしたことを明らかにし、改ざんやその疑いがあるダンパーは全国で987の物件に設置されていると公表しました。
KYBはこれまで、改ざんしたのは検査結果が国の基準や契約した際の基準を満たしていない場合だと説明していました。
しかし実際には、基準を満たしている製品についても、顧客に対して性能をよりよく見せるため一部でデータを改ざんしていたことが新たにわかりました。
こうした目的で改ざんされたダンパーは108の物件に設置され、「東京スカイツリー」でも一部でデータの書き換えが行われていました。
スカイツリーの運営会社は「安全性に問題がないことを確認した」としていて、交換の対象にはなっていないということです。
改ざんやその疑いのあるダンパーが設置された物件数はこれで1095件となります。
KYBは「安全上の問題はないと判断し公表していなかった。個別には対応しており隠すつもりはなかった」と説明しています。
「実際に、免震ダンパーの性能について、国の建築基準法では「基準値のプラス・マイナス15%以内」の幅を認めているが、KYBは顧客契約で「10%以内」にあえてハードルを上げながら、最大で42.3%も基準を超過した製品を「適合品」と偽り出荷していた。」
会社組織の体質や担当者達の人間性に疑問を感じる。
全国に影響が波及している油圧機器メーカーのKYBと子会社による免震・制振装置の検査データ改竄問題。平成27年にも東洋ゴム工業が性能データを改竄していたことが発覚し、国は調査・管理の厳格化を図っていたが、今回も不正を見抜けなかった。「実質的な安全につながる体制が必要だ」。専門家は指摘している。
「このような不適切事案を事前に把握できなかったことは、私どもとしても残念」。石井啓一国土交通相は19日午前の閣議後記者会見で、KYBの改竄問題について遺憾の意を示した。
国交省は27年の東洋ゴム工業の免震ゴム装置のデータ改竄を受け、関係する法令を改正し、審査体制を強化。製品の認定基準を厳しくしたほか、抜き打ちのチェックを行うなど対策を進めていた。
ただ、今回不正が発覚した免震オイルダンパーは東洋ゴムの免震ゴムとは種類が違い、対応が甘くなったとみられる。耐震・免震に関わる製品の対象企業が多く、KYB側には未着手で、今後の検討にとどめられていた。国交省幹部からは「最悪の事態。後手に回った」と悔いる言葉も漏れた。
KYB側の対応も遅れた。KYBは8月上旬ごろに従業員から不正の報告を受けたとしているが、事実の公表に踏み切るまでには2カ月以上を要した。「調査で改竄が確実だと分かるまで時間かかった」と説明するが、当初は施設名を公表せず、混乱に拍車をかけた。
一方、ある耐震技術研究者は、品質基準が実際に安全を担保する基準ではなく安全を対外的にアピールする基準になっていると指摘。「規範意識が下がっているのではないか」と警鐘を鳴らす。
実際に、免震ダンパーの性能について、国の建築基準法では「基準値のプラス・マイナス15%以内」の幅を認めているが、KYBは顧客契約で「10%以内」にあえてハードルを上げながら、最大で42.3%も基準を超過した製品を「適合品」と偽り出荷していた。
相次ぐ不正の背景には、人件費も含めた過度のコスト圧縮の影響を指摘する声もある。
名古屋大減災連携研究センター長の福和伸夫氏は「国、業界、有識者も一緒に合意して作り上げた基準を守らなければならないのは当然だが、実質的な安全につながる制度になっているかどうか検討する必要がある」と話している。
「データ書き換えの方法は口頭で引き継がれ、少なくとも8人が関与。『納期に間に合わせるためだった』。8人は不正に手を染めた理由をこう説明しているという。」
データ書き換えの方法は口頭で引き継がれたと言う事は、引き継ぎで説明した検査担当者は不正である事を十分に自覚していたからこそ、
証拠として残らないように口頭で引き継ぎを継続していたのだろうか?
証拠さえ残らなければ、多くの会社の社員、公務員そして政治家達が言う「覚えていない」とか、「記憶にない」が使える事を認識していたのではないのか?もしかすると、弁護士からのアドバスでもあったのだろうか?グレーであれば処分される事はない。「疑わしきは罰せず」が良い例だと思う。
疑わしきは罰せず(コトバンク)
正確には「疑わしきは被告人の利益に」の意味で,なんぴとも犯罪の積極的な証明がないかぎり有罪とされたり,不利益な裁判を受けることがないとする法諺 (ほうげん) である。刑事裁判では,犯罪事実など要証事実の挙証責任は原則として検察官が負う。したがって,ある事実につき,存否いずれとも証明がつかない場合には検察官に不利益な認定がなされることになるが,ことにそれが犯罪事実にかかわるときには,たとえある程度の嫌疑があっても,その点につき裁判所が確信を得るにいたらない以上,「疑わしきは罰せず」として被告人は無罪とされなければならないということ。最高裁判所は,この原則は再審の請求に対する審判手続においても適用されるとした。
KYBによるデータ改竄(かいざん)問題で、不正を誘発した背景には相次ぐ震災で自治体などが建物の免震化を進め、装置の需要が急激に伸びたこともあるとみられる。KYB側は需要増に応じた適切な人員配置をせず、納期に間に合わせるため、不適合品を調整し直さないままデータを改竄していた。
【写真で見る】建築物が掲載されたリストのプリント
免震装置は平成7年の阪神大震災を契機に需要が急増。その後、16年の新潟県中越地震や23年の東日本大震災などもあり、防災拠点となる役場庁舎や警察署で採用が普及した。
KYBが免震・制振装置の生産を強化したのは12年ごろ。需要増に伴い、国土交通省の基準や顧客の性能基準に合わない装置も増えたとみられるが、検査は基本的に1人だけで実施されていたという。
装置は建物に応じた調整も必要で「手作り品」に近いものだとされる。基準に適合しなかった場合は5時間前後かけて部品を分解。調整し直した上で再試験する必要がある。検査員はその労力を惜しみ、基準値内に収まるようにデータを書き換えて検査記録を提出し、装置を出荷していた。
データ書き換えの方法は口頭で引き継がれ、少なくとも8人が関与。「納期に間に合わせるためだった」。8人は不正に手を染めた理由をこう説明しているという。
油圧機器大手の「KYB」グループによる免震・制振用のダンパーの検査データの改ざん問題で、社内には検査結果を確認する担当者がいたにもかかわらず、チェック機能が働かずに長年にわたって改ざんが続けられていたことがわかりました。
KYBとその子会社は、地震の揺れを抑えるダンパーの検査結果を改ざんしていたことを明らかにし、改ざんが確認されたかその疑いがあるダンパーは、全国で1000件近くの物件に設置されています。
KYBによりますと、ダンパーの検査担当者は1人しか配置されておらず、検査結果が国の基準などを満たさなかった場合、データを書き換えて適合するように装っていました。
社内調査に対して、平成15年の時点で、検査を担当していた従業員が「自分が不正を始めた」と話していて、これ以降の検査担当者7人も全員、改ざんを行っていたということです。
一方、社内には、検査結果を確かめる別の担当者もいましたが、改ざん後のデータが書かれた記録用紙で確認していたため、チェック機能が働かずに長年にわたって改ざんが続けられていました。
KYBは、不正が行われた背景についてさらに調査を進めるとともに、19日午後にも交換の対象となるダンパーが使われた物件のうち、不特定多数の人が出入りし所有者などの了解が得られた建築物について、名前を公表することにしています。
なるようにしかならない。このような問題はたぶん日本文化や日本社会の一部だから仕方のない事。もし、問題を解決するべきと思うのなら
個々が真剣に対応しないと解決しない。
見て見ないふり、面倒な事には関わらない人達が多ければ、問題はやはり解決されずに残ると思う。問題は完全に解決される事はないが、
改善する事は可能だと思う。
油圧機器メーカーKYBによる免震・制振装置のデータ改ざん問題で17日、公共施設をはじめ、九州でも不適合な装置の設置確認などが相次いだ。
【写真】埼玉県立がんセンターに設置されているKYB子会社製の免震用オイルダンパー
熊本市によると、2年前の熊本地震で被災し建て替え工事中の災害拠点病院「熊本市民病院」で、16基の免震装置の使用が判明。長崎市では災害拠点病院「長崎みなとメディカルセンター」の2棟に23基の免震装置、北九州市ではコンサート会場などを備え福祉団体事務所も入居する市の多目的施設「ウェルとばた」に42基の制振装置が使用されていたという。
福岡市は、事務所の入るテナントビルやマンションなど民間施設15棟で、不適合装置の使用疑いがあると発表。佐賀県では、県医療センター好生館(佐賀市)と佐賀大医学部付属病院診療棟(同)に、不適合なオイルダンパーが使われている疑いがあることが明らかになった。
福岡県嘉麻市と大分県宇佐市では、それぞれ建設している新庁舎に今後、免震装置を導入する予定だったという。
熊本復興に水「許せぬ」 九州に動揺拡大
油圧機器メーカーのKYBによる免震・制振装置のデータ改ざんは、情報提供の不足もあって、全国の企業や地方自治体を不安に陥れている。不都合な数値を書き換えて顧客をだます行為は、2005年に発覚した耐震偽装事件や、15年のくい打ちデータ改ざん事件などで繰り返されてきたが、教訓は生かされなかった。九州では熊本地震から再建中の病院や、福祉団体などが入る公共施設でも免震不正が確認され、動揺が広がる。
「災害に強い病院を一日も早く再建しようとしているさなか、(不適合問題のある)装置が使われていたのは非常に残念だ」
16年4月の熊本地震で被災した熊本市民病院(熊本市東区)。市の担当者は肩を落とす。市によると、17日朝、建設工事を請け負うゼネコンから連絡があり、不適合装置の設置が発覚したという。
災害拠点施設でもある同病院は、熊本地震で全3棟のうち病棟2棟が使用不能になり、現在は規模を縮小し診療を行っている。新病院は鉄骨造り7階建てで病床数388床を備える。現病棟から約2キロ離れた場所に移転させる計画で、来秋予定の開業を心待ちにする患者も多い。
市民病院で次女(4)が心臓手術などを受けてきた熊本市の向井美奈子さん(33)は「多くの患者が市民病院を使えず困っている。来秋の開院が遅れないか心配」と顔を曇らせる。市は今後、KYB側に装置の交換を含めて対応を求める方針だが、現在4階部分まで進んでいる工事への影響は不明だという。
大西一史市長は「まさか、熊本地震で被災し災害に最も強い病院を目指しているのに免震ダンパーが不適合とは。被災自治体の長として怒りでいっぱいだ。報告を受けて手が震えた」と語気を強めた。
長崎市の病院「長崎みなとメディカルセンター」でも不正のあった免震装置が確認された。運営する独立行政法人「長崎市立病院機構」の山下幸治総務課長は「国は『安全性に問題はない』としているが、不安はぬぐえない。早急な対応を求めたい」と話す。全ての交換をKYB側に要求する考えだが、その間も業務は続けるという。
制振装置の不正が確認された北九州市戸畑区の多目的施設「ウェルとばた」には、市の児童相談所や福祉団体の事務所も入る。よく利用するという70代男性は「不正があった製品が全国に広がっているのは恐ろしい。ごまかし続けてきた姿勢には腹が立つし、情けない」と憤った。
他社と比較しない、調べるのが面倒だと思う人なら「ジャパネットたかた」で買う可能性は高いかもしれない。
消費者庁は、大手通信販売会社「ジャパネットたかた」が、広告で、景品表示法に違反する不当な価格表示をしたとして、再発防止を求める行政処分を出した。
消費者庁によると、「ジャパネットたかた」は、去年5月から、エアコンやテレビについて、会員カタログやチラシ、ダイレクトメールなどで、「ジャパネット通常税抜き価格」に加え、「2万円値引き」などとした値引き後の安い価格をあわせて表示していた。
しかし、実際には「通常価格」での販売が終わってから時間がたっていたり「通常価格」での販売期間が短かったりしたという。
親会社のジャパネットホールディングスはホームページで「今回の措置命令を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努めて参ります」とコメントしている。
KYB改ざん免震装置で騒いでいるが、大きな地震が起きなければ部品に問題があろうが、なかろうが関係ない。
油圧機器メーカーKYBと子会社による免震・制振装置のデータ改ざんが悪いとメディアは言っているように思える。実際、
検査が簡単な方が検査を受ける側に喜ばれる。問題が起きなければ形だけの検査、又は、問題を見逃すような検査を期待する日本の会社は多いと思う。
事実を記載するだけで問題になったり、仕事の依頼がなくなったり、現場で納期の遅れや追加の費用が発生するなどの理由で
厄介者扱いされたことは多々あるので、やはり、日本の社会的な問題であると思う。検査が本来の目的を満足していない事は日本だけでなく、
海外でも起きている。結果(改ざん後の数値)だけが焦点になれば改ざんするのが簡単である。どうせ改ざんするのなら最初から計測や試験など
せずに改善してしまうのがコストや労力を考えればベストだと思う。
問題は問題や改ざんが発覚し、損害や責任が発生した時だ。誰が責任をとるのかと、誰が損害賠償に関して責任があるのかで揉めると思う。
損害賠償の金額が大きい場合、これまでの儲けは吹っ飛んでしまう。
東京五輪を見に行く予定はないし、東京には行く事はほとんどないので、油圧機器メーカーKYBと子会社による免震・制振装置のデータ改ざん問題は
個人的には大きな影響は受けると思えない。検査の不正はたくさん見てきたので驚きはない。知らないだけでいろんな会社が改ざんしていると
確信が強まっただけ。何十年も検査の問題を改善しようとしてきたが抵抗や報復を受ける事が多かったので、最近ではこれが日本社会の本音だと思っている。行政や監督官庁にしても問題を知ろうとしないし、報告しても面倒な事を言うなと言っているように思えたので、このような問題が
日本で存在し、引き継がれていると思う。
地震が起きなければ問題にならないのだから心配で仕方のない人達以外は心配する必要はないと思う。免震装置について詳しくないが、設計された
通りにダンパーが動かなければ、免震装置の意味はないと思う。ダンパーの周期や動く速度を想定して振動をコントロールしようとするのだから
想定してない周期や個々のダンパーが想定とは違った動きをすれば、最悪の場合、ダンパーがないほうが良い結果となるかもしれない。
油圧機器メーカーKYBと子会社による免震・制振装置のデータ改ざん問題で、不正の疑いのある装置の交換は最短でも2020年9月までかかることが18日、分かった。
同社は不正の疑いがある装置を原則全て交換する方針だが、交換用部品の生産が追いつかないため。KYBの装置は2020年東京五輪の競技施設「東京アクアティクスセンター」「有明アリーナ」にも使用されているが、五輪開催までに交換が完了しない恐れもあり、不安解消が遠のいた。
交換対象となる装置は合計約1万本に上る。KYBは装置の工場の生産能力を段階的に5倍まで引き上げるが、月産は500本程度にとどまる見通しだ。当面は新規受注を取りやめ、交換を優先させる。免震偽装の東洋ゴム工業は発覚から3年以上が過ぎた今も、交換作業が続いている。
装置が使われた物件は、不正が疑われるものも含め東京が最も多く250件で、大阪や愛知など都市圏が続く。
この日も高知市や福井市など全国各地の自治体から、庁舎などに同社製装置を導入していたとの発表が相次いだ。性能検査記録データが改ざんされた製品かどうか確認を進めるなど、対応に追われている。
KYBは、不正な装置や不正の疑いがある装置を使っている全国の建物のうち、所有者の了解が得られた物件名を19日午後に公表する。
また、製品の性能をチェックする検査員が1人しかいなかったことが新たに判明した。特定社員への過剰負担が不正行為の常態化につながった公算が大きい。性能検査の基準を外れた製品のほぼ全てを改ざんして出荷していたことも分かった。免震・制振装置で4割程度のシェアを持つ国内トップメーカーでありながら、安全性を軽視していた実態が明らかになった。
≪組織委「注視したい」≫競泳会場「東京アクアティクスセンター」と、バレーボールなどの会場となる「有明アリーナ」にKYBの免震・制振装置が使われていることを受け、大会組織委員会幹部は18日、交換の必要性などが分かっていないことから、今後について「注視したい」と述べた。大会関係者は「交換の作業自体は工期に大きく影響するものではない」とみるが、肝心の交換用部品の生産が追いつかない可能性があるという。日本バレーボール協会幹部は「もし工期が遅れたりすれば、テスト大会をどうするかなどの問題が出てくる」と会場整備への影響を懸念した。
「KYB子会社の元従業員:
上司に相談したところ、本当はこんなことをやったらいけないが『こうやって数値を変えて書類を出すようにしろ』と指示があったみたいで…
この従業員は現場の責任者との改ざんをめぐる生々しいやり取りの音声を記録していた。」
部分的には組織的だと思う。ただ、幹部や役員まで知っていたかは、徹底した調査がなければ断定する事は出来ない。幹部や役員まで知っていたと
しても、証言する人、又は、証拠がなければ立証する事は出来ないと思う。
少なくとも誰が始めたのかは調べる事が出来ると思う。引継ぎされていたのだから、勤務履歴を調べるだけで簡単に絞る事が出来る。
また、ダンパーを設計した社員は立ち会ったり、検査結果を見る事があると思うので、データの改ざんが始まった時の設計者達を調べるべきであろう。
現場からの設計変更、設計改善要求、現場での問題など何らかの情報は設計に行っていると思う。
KYB子会社の元従業員がFNNの取材に証言
データ改ざん問題が発覚したKYB子会社の元従業員はFNNの取材に対し、こう語った…
KYB子会社の元従業員:
上司に相談したところ、本当はこんなことをやったらいけないが「こうやって数値を変えて書類を出すようにしろ」と指示があったみたいで…
この従業員は現場の責任者との改ざんをめぐる生々しいやり取りの音声を記録していた。
(やり取りの音声記録より)
元従業員:
会社のためじゃないですか。本当に心を入れ替えてゼロからスタートすればいいだけなんです
現場責任者:
スタートできるできないというレベルに…
元従業員:
なりますよね。公になれば
東京スカイツリーや通天閣も?…「疑い」も含め全国986件の建物に
建物の免震・制震装置を製造するKYBが性能検査データの改ざんを行っていたのは、地震の揺れを軽減し建物と命を守る「オイルダンパー」という製品だ。
改ざんがあったKYBの「オイルダンパー」は「疑い」も含めて全国986件の建物で使われていて、各地で影響が広がっている。
約100年前の姿に復元工事が完了した東京駅の赤レンガ駅舎にもKYBの装置が使われている。
また、東京スカイツリーでもタワーの揺れを抑えるシステムにKYBの制振オイルダンパーが225基使用されていて運営会社は不適切なものかを確認中だとしている。
さらに、大阪の通天閣や、名古屋駅前の名古屋ミッドランドスクエアといった各地のランドマークや公共施設でも問題の装置が使われている可能性があるということだ。
KYB川崎康輔会長兼社長:
“品質は経営の基盤である”という精神のもと物づくりに取り組んでまいりました
KYBの川崎康輔会長兼社長は16日の会見でこう話していたが、免振ダンパーで国内トップシェアを持つKYBで、なぜこれほどの不正が行われていたのだろうか?
本来必要な分解・再調整を行わずパソコン上で数値を改ざん
「オイルダンパー」の性能検査では揺れを抑える能力が国土交通省の基準に達しない場合、本来は分解するなどして再調整することが必要だ。しかし…
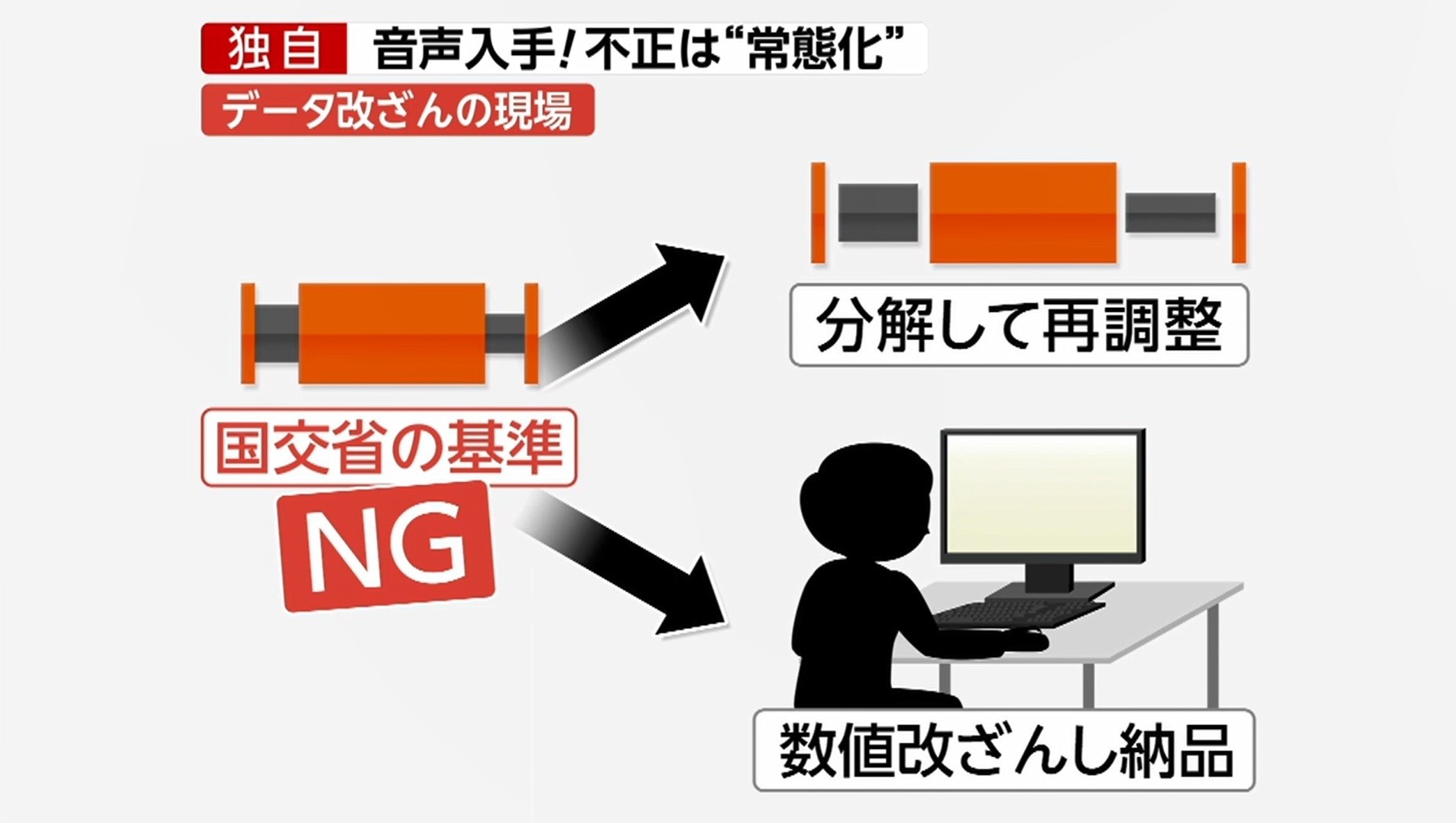
(やり取りの音声記録より)
元従業員: 結局隠ぺい隠ぺいじゃないかここは 隠し事しかしない。
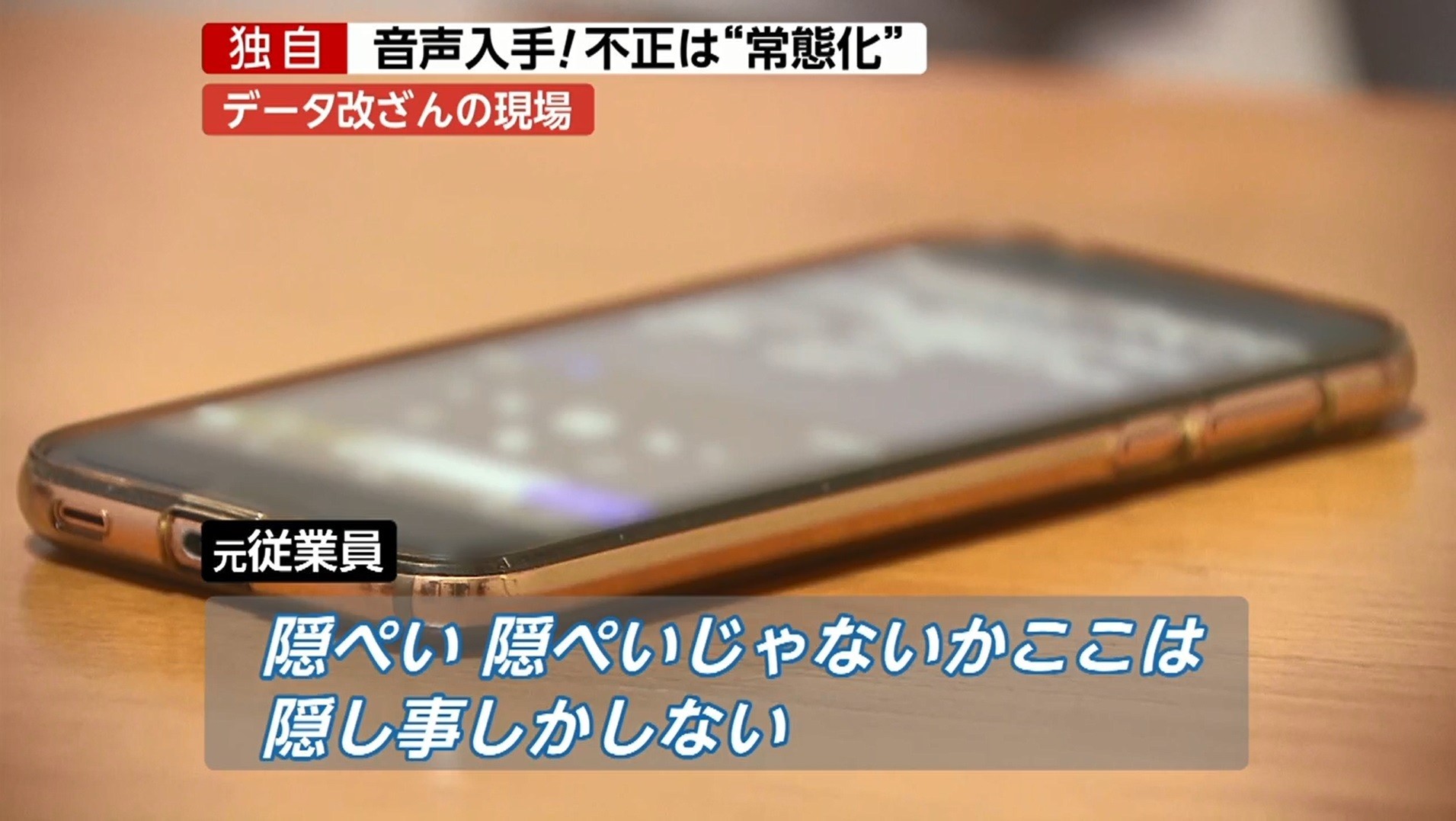
(やり取りの音声記録より)
元従業員:
試験データをパソコン上で数値変えるのはこれは何ですか?いいんですか?
現場責任者:
誤解を招くことがあると思うけど…
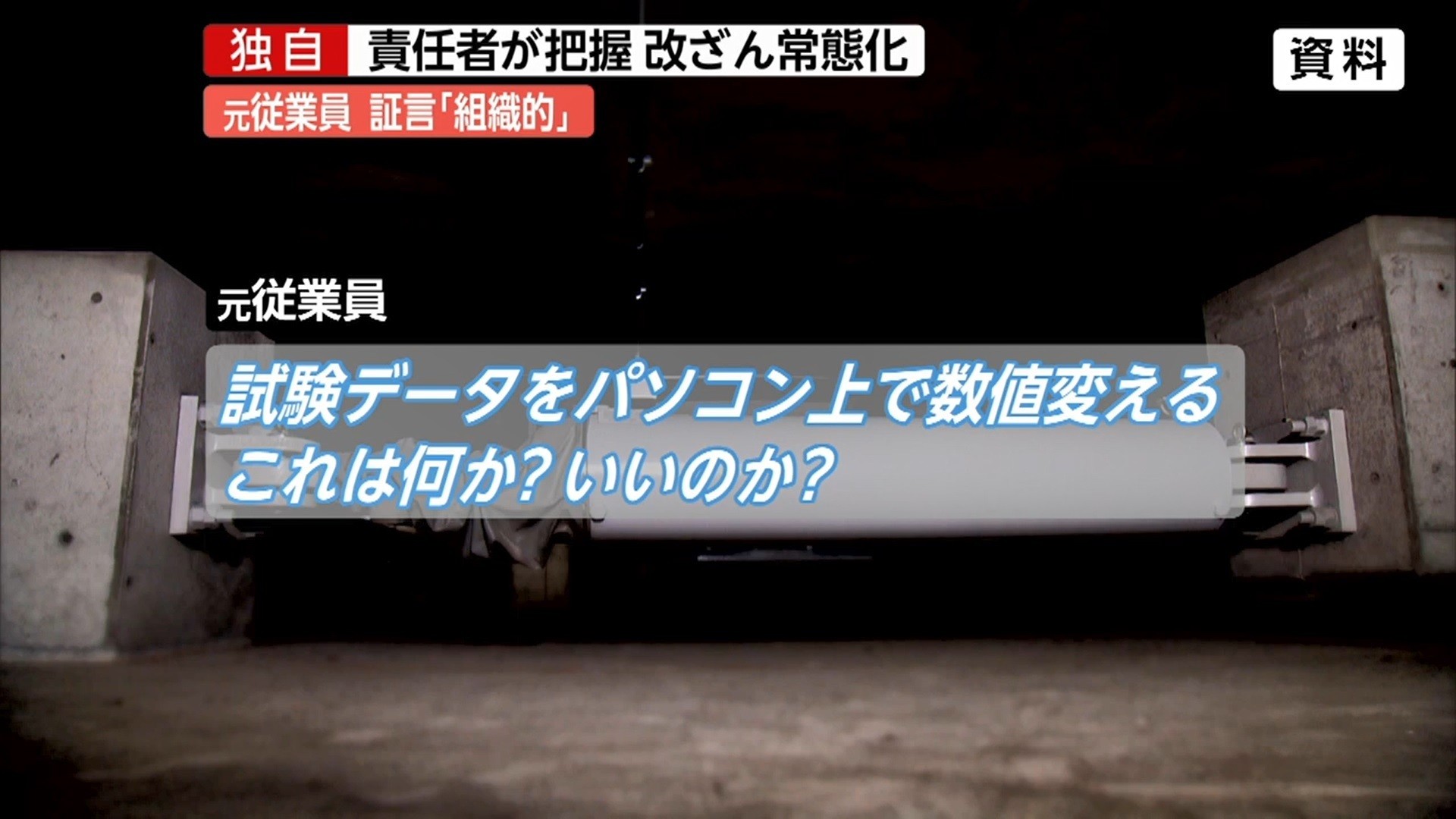
元従業員:
正直限界ですわ。悪いことしてるの目につくのが嫌だし、改善されないのが嫌。世間に知れたら問題になる。改ざんか 改ざんじゃないかで言ったらどっちですか?
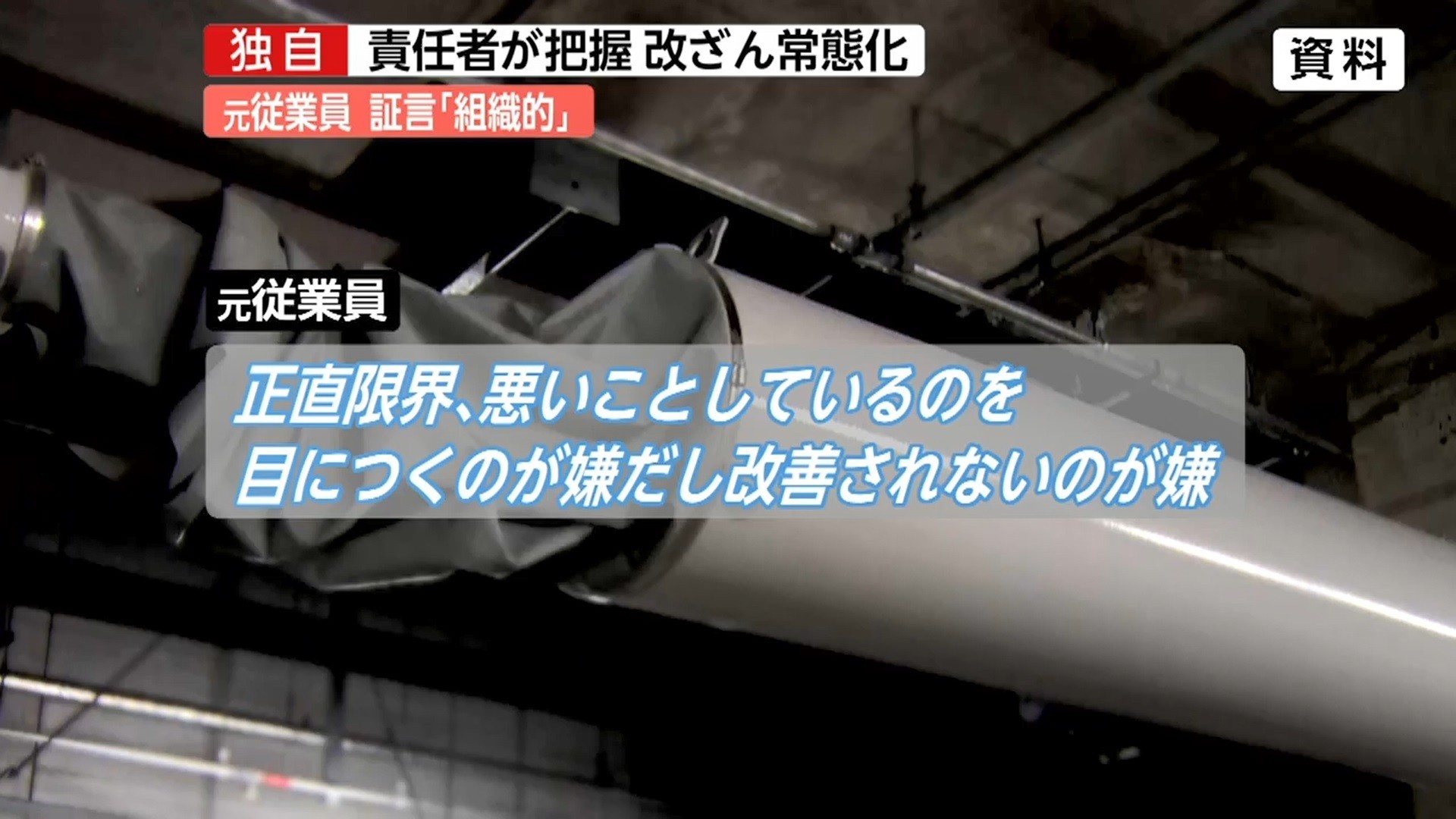
現場責任者: 問題にはなるわね
元従業員: いつまでたってもこの体制がなおらない。若いものへ若いものへ悪いことを教えていく。その仕事の体制がおかしいから言ってる。どこかでクギをささないと
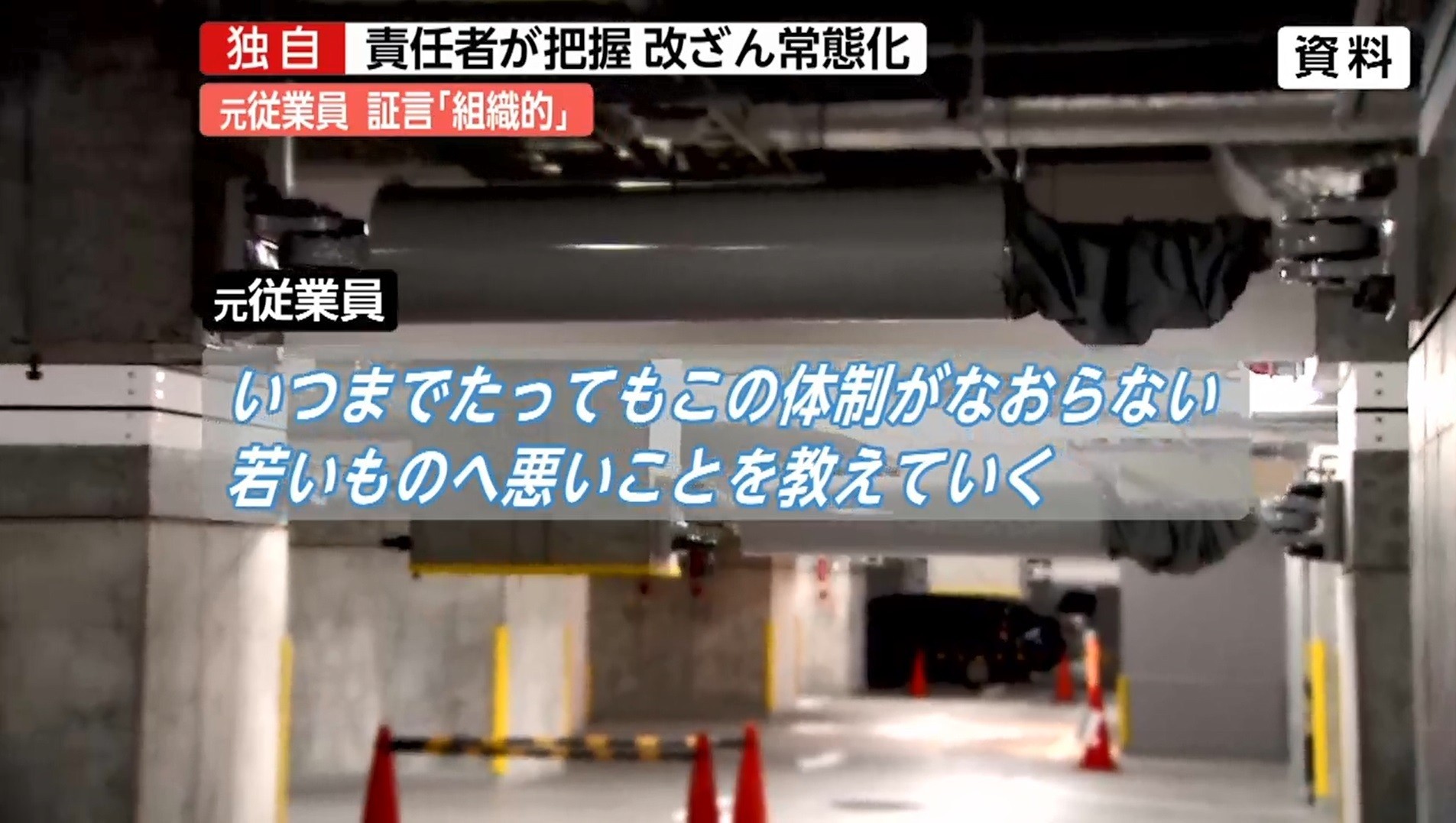
データの改ざんは少なくとも8人の担当者が行っていて、担当者が変わっても口頭で後任に伝えられていたことをKYB側も認めている。

元従業員:
ダンパーは建物を守るだけじゃなくて、最終的には人の命を守ってるんでしょう?おかしくないですか?会社ぐるみで黙っていれば それでいいという話でしょう?
現場責任者:
そういう解釈もできる
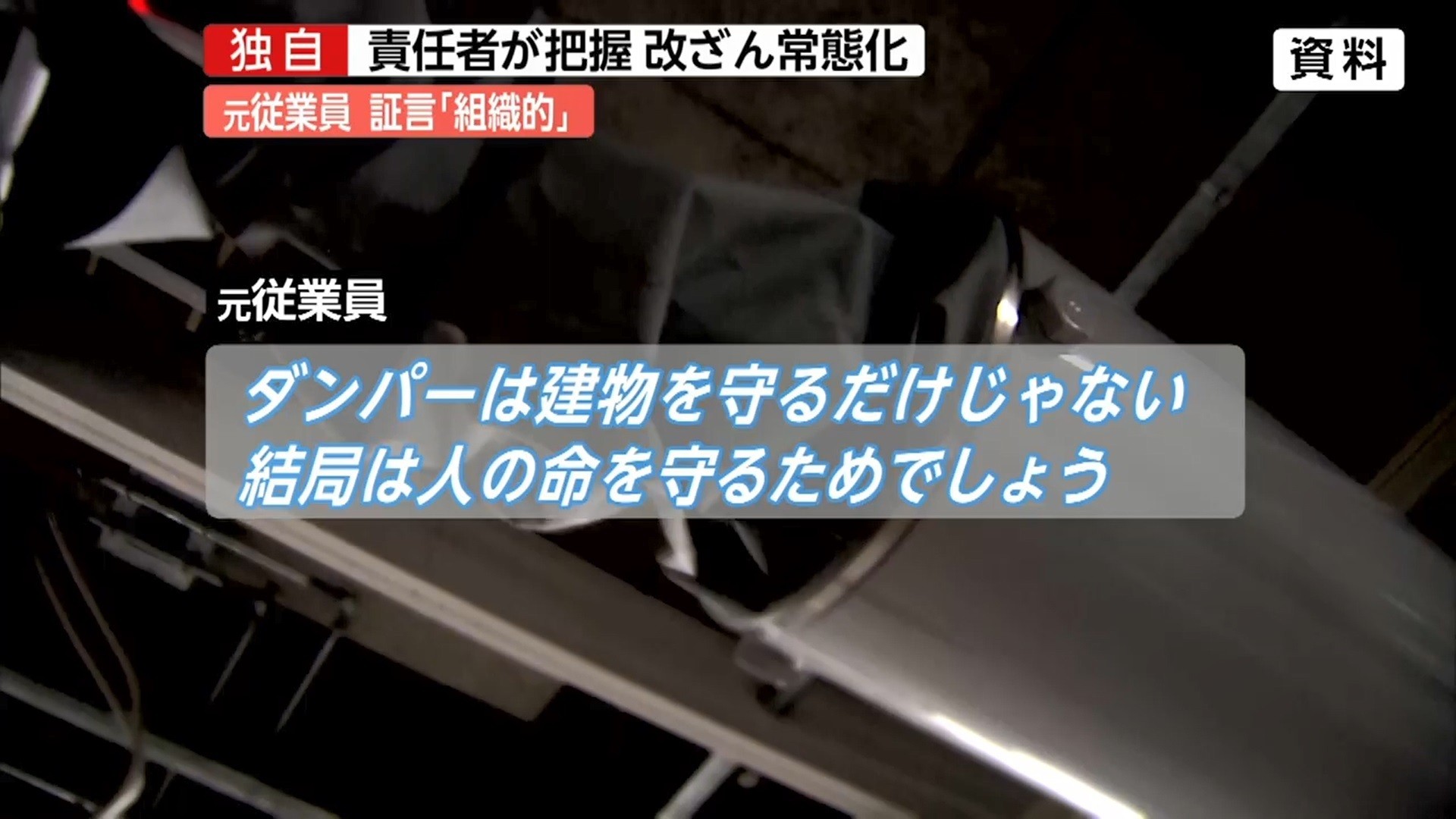
実態の把握と安全性の確認が急がれるなか、KYBは今後、外部調査委員会の助言を受けながら速やかに社内調査を進めるとしている。
(プライムニュースイブニング10月17日放送より)
能力が高い女性で勝気な正確な場合、暴力は振るわなくても、精神的にはかなりダメージを与える対応や言葉を浴びせる事がある。
能力が高いので、相手が強気な性格でなければ、勝てない可能性が高い。全ての女性が優しいと思うのは幻想である。女性は優しくあるべきだと
教えられているだけで現実は違うと思う。
今年9月の“出直し選挙”で東京医科大の学長に選出された林由起子氏(56)。裏口入学をはじめとした7月以降の不祥事に対するイメージ払拭を期待されているが、そんな林氏のパワハラ疑惑が「週刊文春」の取材によって明らかになった。
【写真】神経生理学講座の学生による告発文
「林先生のパワハラのせいで家から一歩も出られなくなってしまい、病院で受診したところ、環境的要因による鬱状態という診断が下りました。いまだ深刻な後遺症に悩まされています」
苦しい胸の内を語るのは、かつて林氏が主任教授を務めていた神経生理学講座の元学生・A子さんである。
林氏は1986年、東京医大を卒業後、順天堂大学や国立精神・神経医療研究センターに勤務。そして2013年8月、古巣の東京医大に戻り、神経生理学講座の主任教授に着任した。
当時、A子さんは修士課程1年生。研究室に不協和音が響いたのは、林氏の着任直後だったという。
「林先生は、部屋にやってきては『ここを早く明け渡せ!』と喚き散らすようになったのです」(A子さん)
結局A子さんは15年3月に研究室を去ることになるのだが、実は、林氏が主任教授に着任後、計4人の助教、学生、技官が相次いで大学を離れている。
東京医科大は次のように回答した。
「4名、および教授を含めた5名が神経生理学講座を離れていることは事実です。その原因が、パワーハラスメントやアカデミックハラスメントをおこなったことによるものとの認識は林にも本学にもありません」
10月18日(木)発売の「週刊文春」では、東京医大の再建を担う林氏の人となりや解決金200万円を支払うに至ったマタハラ訴訟についても詳報している。
(「週刊文春」編集部/週刊文春 2018年10月25日号)
16日夕、東京・霞が関の国土交通省で開かれた記者会見で、KYBの小川尋史専務は苦渋の表情で語った。
発覚のきっかけは、休憩中のカヤバシステムマシナリーの従業員同士の会話だった。検査担当者から改ざんの話を聞いた1人が上司に報告したという。
KYBが両社の歴代担当者を聴取した結果、遅くともKYB岐阜南工場(岐阜県可児市)でオイルダンパーを作るようになった2000年3月には改ざんが始まった可能性があるという。
07年にはカヤバ社に製造事業が移り、工場も津市に変わったが、不正は引き継がれた。これまでに少なくとも計8人が改ざんを認めたという。「納期に間に合わせるためだった」「検査で不適合になれば、部品を分解して再検査まで5時間前後かかる」。8人は理由をこう述べているという。
「不正が組織的だったかについて、中島社長は「組織としてどこまで知っていたのかは継続して調べる」と述べるにとどまった。」
不正が組織的でなかったら関係した社員達を処分したり、損害賠償を請求するのだろうか?損害だけで関係した社員達の退職金の合計を
上回るような気がするがどのような展開になるのだろうか?
ものづくりの現場で、また不祥事が明らかになった。油圧機器大手「KYB」が建物の安全性を高める免震・制振装置の検査データを改ざんしていた。同社は16日の会見で、不正は長期間にわたって行われていたと公表。一方、問題の装置が使われた施設は明らかにせず、商業施設や病院の関係者に不安が広がっている。
国土交通省であった会見の冒頭、KYBの中島康輔社長は深々と頭を下げた。その後、明らかにされたのは、少なくとも15年にわたって、同社と子会社の検査員が続けてきた改ざん行為の実態だ。
同社によると、改ざんした記録が明らかに残っていたのは2003年1月。国交省の基準や顧客の性能基準に合わなかった検査データを、基準内に書き換えるための係数が社内で保管されていたという。こうした行為は07年1月に生産拠点がKYBの工場から子会社の工場に移った後も、検査員が口頭で引き継いでいた。
不正が組織的だったかについて、中島社長は「組織としてどこまで知っていたのかは継続して調べる」と述べるにとどまった。
ただ、データが改ざんされた装置を使っている建物名は「所有者の許可が必要」と一切明らかにしなかった。このため、同社製のオイルダンパーを使う建物の関係者は、安全かどうかの確認が取れず、気をもんでいる。
検査データ改ざんの理由次第では、適切な免震や制振装置を作成するのも難しいのでは??
国土交通省は16日、自動車や建設向けの油圧機器で大手のKYB(本社・東京、中島康輔社長)と子会社のカヤバシステムマシナリー(同、広門茂喜社長)が、共同住宅などの建物で地震の揺れを抑える免震や制振装置の検査データを改ざんしていた、と発表した。改ざんの疑いがあるものを含めると、全国の共同住宅や事務所、病院、庁舎など986件で使われているという。KYBの中島社長らが16日夕に都内で会見して問題について説明する。
【写真】不正問題について謝罪するKYBのホームページ画面
KYBは1919年創業で、自動車向けショックアブソーバーで世界シェア2位の大手メーカー。今回不正を起こした建物用の免震や制振ダンパーでは国内シェアトップ。同社のホームページによると、東京スカイツリーの制振装置にも使われているという。鉄道や航空機向けなどの油圧機器も幅広く製造している。戦時中は戦闘機「零戦」の主脚部品も製造した。2018年3月期の売上高は3923億円、グループ従業員数は約1・5万人。
KYBが改ざんしたのは、地震の際に建物の揺れを抑える「免震用オイルダンパー」と「制振用オイルダンパー」で、2000年3月から18年9月までに出荷された製品。出荷前に行う検査では、国交省の基準や顧客の性能基準に合わない値が出ていたのに、基準値内に収まるように書き換えて出荷していたという。
KYBが検査をした結果、震度6強から7程度の地震でも倒壊の恐れはないといい、国交省は安全性に問題はないとしている。国交省はKYBに対し、免震装置を速やかに交換する計画を立て、報告するよう求めた。(北見英城)
◇
■データが改ざんされた不適合品の免震用オイルダンパーが使われた物件数(都道府県別)
北海道 9
青森 2
岩手 5
宮城 49
秋田 3
山形 3
福島 9
茨城 17
栃木 6
群馬 4
埼玉 34
千葉 36
東京 222
神奈川 67
新潟 10
富山 5
石川 2
福井 5
山梨 3
長野 9
岐阜 14
静岡 57
愛知 86
三重 14
滋賀 1
京都 5
大阪 98
兵庫 26
奈良 1
和歌山 5
鳥取 3
島根 3
岡山 4
広島 8
山口 5
徳島 9
香川 4
愛媛 6
高知 11
福岡 23
佐賀 2
長崎 2
熊本 4
大分 5
宮崎 1
鹿児島 1
沖縄 4
不明 1
合計 903
◇
■データが改ざんされた不適合品の制振用オイルダンパーが使われた物件数(都道府県別)
北海道 3
岩手 1
宮城 2
福島 1
茨城 2
群馬 4
埼玉 4
東京 28
神奈川 4
福井 1
山梨 1
岐阜 2
静岡 2
愛知 7
大阪 9
兵庫 5
香川 1
福岡 3
不明 3
合計 83
中途半端な救済措置で問題をうやむやにするよりは将来の方針や不正に対する処分などを定義して明確にするべきだと思う。
関係者にはとっては将来の事や方針よりも救済措置で入学できるのかが重要になるのであろう。
昭和大学医学部の入試不正問題で、柴山昌彦文部科学相は、不利益を受けた受験生を救済するよう大学側に求める方針を明らかにした。
昭和大学は15日、記者会見で、2013年の医学部入試から、2浪以上の受験生が不利になるような得点操作をしていたことを認めた。
柴山文科相は、「不適切な操作はないと回答を得ていたにもかかわらず、このような事態に至ったことは大変遺憾」と述べた。
柴山文科相は、昭和大学に対して、不利益を受けた受験生について、救済措置を講じるよう促す意向を明らかにした。
「不正認識なかった」は厳しい言い訳だと思う。長年、継続されてきた不正は不正の認識がないと言っているようなものである。
誰も疑問に思わないし、誰も不思議に思わないのであれば、日本の教育は完全に間違っているとも言える。つまり、医者になれるほどの
優秀な能力を持ち合わせても、倫理やモラルを理解できてない、又は、間違っている可能性がある事について適切な判断が出来ない事を部分的に
証明したと言える。
日本の教育が詰め込み、又は、知識だけの記憶、倫理やモラルの習得を軽視して、受験に合格する事を重視した教育であったことを部分的に
証明していると思う。
教育の方針を決める、そして管理及び監督する文科省がどのような判断やコメントをするのだろうか?
医学部入試における差別の実態が、東京医科大(東京)に続き、昭和大(同)でも明らかになった。昭和大は、2浪以上の受験生が不利となる得点操作を続ける一方、卒業生の子弟を優遇していた。「必死に勉強してきたのに」。同大の学生や浪人生からは悔しさや憤りの声が相次いだ。
「ずっとやっていることなので、不正という認識はなかった」。15日午後5時半から東京都品川区にある同大の講堂で開かれた記者会見。小川良雄医学部長はそう述べ、「文部科学省から指摘を受けて、初めて不適切だと認識した」と続けた。
会見で浮かび上がったのは、公正な入試や差別に対する同大の認識の甘さだ。
同大は2013年から、受験生には知らせずに、一般入試の2次試験で現役と1浪の受験生に一律に10点と5点を加算。一方、補欠合格者の中から卒業生の子弟を優先的に合格させていた。こうした運用は、入試について審議する学内の委員会で決めたという。
小川医学部長は「現役や1浪の方が活躍できる、伸びてくれる」「(現役や1浪の)将来に対して加点しただけで、(2浪以上の受験生を)減点したわけではない」と主張。優遇の根拠として医師国家試験の合格率などを挙げたが、具体的なデータは示さなかった。
同大はこれまで文科省の調査などに対し、差別を否定していた。その理由について、小川医学部長は「大学の理解と、質問の意図が異なっていたのではないか」と語った。また、報道陣から不正の認識があるかどうかを問われた小出良平学長は「そこは見解の違い。学力だけでなく、総合評価したいと思ってやっていた」と述べた。
後悔先に立たずの良い例だと思う。
石川県警金沢西署は13日、同県かほく市、私立高校の教頭の男(62)を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)と道交法違反(事故不申告)の疑いで逮捕した。
発表によると、男は12日午後6時頃、金沢市近岡町の県道で乗用車を運転中、渋滞で停車中のかほく市の30歳代男性の軽乗用車に追突し、けい部むち打ちなどの軽傷を負わせ、男性が110番している間に車で逃走した疑い。
調べに対し男は「相手の男性の体が大丈夫なように思えて、許してほしいと思って離脱した」と話しているという。同署の検査で男の呼気から基準値を超えるアルコール分が検出された。男は「家に帰って酒を飲んだ」と話しているという。
「医学部受験予備校を運営するプロメディカス(東京都)の武林輝代表は「不正を行った学校名が明らかになれば、さすがに来年の入試はクリーンなものになるのではないか」と語った。」
文科省が不正を行った学校名を公表する可能性はかなり低いと思う。根拠は政治的な理由と天下りが影響しているから。
文科省に関しては将来の天下り先の確保、既に天下りしているOBからの依頼、最近、頻繁に使われる忖度、そして学校から献金や支持を受けている政治家からの依頼や圧力などいろいろなコンビネーションがあると思う。
日本社会には多くの問題が存在すると思う。今回は、東京医大前理事長の臼井正彦被告(77歳)を贈賄側、佐野、谷口の両被告を収賄側とする裏口入学事件が明るみになり、大きく注目を受けたから大規模な捜査で男女差別の問題と事実が
出てきた。普通の裏口入学ではここまで大きくなることもないし、捜査も踏み込んでいなかったと思う。
深く踏み込まずに表面だけの捜査で終わり、隠れた問題は表に出てこない事はたくさんあると思う。
文科省の天下りが過去に注目を受けた。学校への天下りのルートがあったと言う事は、現在も、何らかの関係を持っている文科省職員や不適切な
関係を維持している職員がいてもおかしくない。又は、天下りの復活を望んでいる職員がいてもおかしくない。
ここで恩を売っておこうと考える職員達が存在しても不思議ではないし、文科省と呼ばれる組織の意思ではなくても、見えないところで職員が
動いていても不思議ではない。人間である以上、学歴とは関係なく、自己利益や自己中心的な理由で動くことは考えられる。
スタンス的に学校側に近い文科省職員達は着地点のシナリオを考えているのではないかと思う。
東京医科大の不正は氷山の一角だったのか。医学部の入試で女子や浪人中の受験生を不利に扱う不正を行っていたのは同大以外にも広がっていたことが12日の文部科学相の会見で明らかになった。現役の医学部生や医学部を目指して勉強中の受験生からは驚きや憤りの声が上がった。
【大学への道】順天堂大学(JR御茶ノ水駅から)
不正があった疑いが新たに明らかになった順天堂大医学部。東京都文京区のキャンパスには戸惑いが広がった。医学部4年の男子学生(22)は「まさか男女で差別があると思わなかった。確かに女子寮が少ないので友だちと話題になっていた」と話した。
受験生からは憤りの声が上がった。10月末には、出願する私立大医学部の絞り込みが始まる。都内の医学部予備校に通う浪人中の女性(20)は「とてもショック。入試くらいは男性と平等に見てほしい。合格点を超えたら、大学は性別によらず入学させるべきだ」と語気を荒らげた。
冷ややかに受け止める受験生もいた。医学部を目指している浪人中の男性(19)は「浪人生や女子が私立大の入試で不利を受けることは知られていた。医師として活躍する期間を考えれば、仕方がないかもしれない」とあきらめ顔。それでも「これを機会に差別がなくなれば」と期待する。
駿台予備学校によると、医学部の志願者数は減っている。東京医科大の不正が発覚したことで受験生が敬遠した可能性もあるという。9月の模擬試験で志望校を集計したところ、全国の私立大医学部の志願者は前年同期比7%減。東京医科大が11%減となる一方、女子医大系は志願者数が増えていたという。
駿台教育研究所の石原賢一部長は「東京医科大以外でも、性別や年齢別の合格率の差をみれば、何らかの作為が推測され、受験生は不信感を抱いている。きちんとした採点の基準を示さなければ、受験生が可哀そうだ」と話した。
毎日新聞が文科省の調査で男女の合格率の差が大きかった首都圏の私立大医学部に取材したところ、日本大や慶応大は「不正はない」と明確に否定した一方、「文科省が調査中。回答は差し控える」とする大学もあった。
医学部受験予備校を運営するプロメディカス(東京都)の武林輝代表は「不正を行った学校名が明らかになれば、さすがに来年の入試はクリーンなものになるのではないか」と語った。【川上珠実、水戸健一、金秀蓮】
柴山昌彦文部科学相は12日の会見で、文科省が全国81大学の医学部医学科を対象に実施している入試をめぐる調査で、「複数の大学で性別や浪人年数で合格率に差をつけたり、特定の受験生を優先的に合格させたりしているとみられる事例があった」と明らかにした。すでに入試不正が判明している東京医科大を除く80大学を訪問調査し、年内をめどに結果を公表するという。柴山氏は、疑いがもたれている大学名を明らかにせず、大学側の自主的な公表を求めた。
医学部入試をめぐっては、文科省幹部が起訴された汚職事件をきっかけに、東京医科大で一部の受験生への点数加算や、女子や浪人回数の多い男子への不利な扱いが発覚。文科省は他大学についても、男女別の合格率や、受験生によって合否判定に差をつけていないか報告を求め、男女の合格率の差が大きい大学は訪問などをしている。
柴山氏によると、これまでの調査の結果、「合理的な理由が必ずしもないにもかかわらず、差異を設けていることが客観的に見て取れる」大学が複数あったという。東京医科大を除いて不適切な得点操作を認めた大学はないが、文科省は80大学すべてを訪問して調査し、確認する方針。月内に中間報告を出し、年内に最終報告を出すとした。
9月上旬に公表した同省の第1次報告によると、多くの大学で男子の合格率が女子を上回り、過去6年間の平均では男子の合格率が女子の約1・2倍だったことが判明。また、年齢別では主に1浪が多い19歳の合格率が最も高く、20歳以上になると合格率が下がる傾向も明らかになった。(矢島大輔、増谷文生)
違法でないのなら日本学生支援機構(JASSO)が制度を見直せば今後の問題は解決できる。
多くの人達が「裏技」を使うようになったらそれは日本学生支援機構(JASSO)にも責任がある。「裏技」に気づいた時点で
制度の改正を直ちに行うべきだった。
不公平な制度であっても違法でなければ制度を見直さない日本学生支援機構(JASSO)にも責任がある。「裏技」の指南サイトを
問題視する前に直ちに手を打つべきであろう。
この世の中、最終的には違法であるか、どうか?例え違法であっても、十分な証拠がないために処分されないケースは多くある。
グレーゾーンであれば、黒でない限り、処分されない。日本学生支援機構(JASSO)は制度を見直すしかない。
大学在学中は奨学金の返済が猶予される制度を使い、卒業後に学費の安い通信制大学などに在籍して、返済を免れ続ける「裏技」がネット上に紹介され、問題になっている。返済延滞が社会問題化するなか、実際に裏技を利用する人も出ている。
【写真】男性の返済額を示す書類には、「480万円」の数字が記されている=川津陽一撮影
「奨学金 裏技」でネット検索すると、多くのサイトがヒットする。サイトには「最後の手段」「違法でないのなら仕方がない」「奨学金返済なんてヘッチャラ」などの言葉が踊り、いずれも、通信制大学に籍を置いて返済を「猶予」するやり方が紹介されている。
九州地方に住む30代のフリーター男性は、私大在籍中に日本学生支援機構(JASSO)から有利子・無利子合わせ約700万円の奨学金を借りた。返済額は月約3万円だが、約6年間返済していない。今はアルバイトの傍ら、資格取得の勉強に精を出す。月収約15万円での生活はギリギリで「借りた金を返すのは筋だが、返済すると生活できない。『裏技』は自衛の手段。違法ではないので、利用している」と話す。
JASSOには、大学などに在学中は返済が猶予される制度があり、男性は私大卒業後、通信制大学に在籍することで返済を猶予されている。通信制大学の学費は、入学金と授業料を合わせても年数万円程度で、返済額より大幅に安い。在学期限は10年までだが、「生涯学習」をうたう同大は何度でも再入学が認められている。一般の大学と異なり、単位取得が在学の必須条件ではない。
JASSOの規定には、本人が死亡した場合、返済が免除される条項もあり、籍を置き続ければ、最終的には奨学金が免除される。
「裏技」の指南サイトについて、JASSOの内部には、問題視する声もあるという。
菊川南陵高校(静岡県菊川市)の後藤雅典校長は11日、高校を運営する学校法人南陵学園の理事長と学園長を、県の補助金約1900万円を不正に流用したとして、背任と補助金適正化法違反容疑で県警に刑事告発した。
理事長と学園長は夫婦で、学校法人とは別に産業廃棄物処理会社「青幸」(焼津市)を経営している。告発状によると、夫婦は昨年12月、私立高の教職員給与などの経費を補助するため県が支給した約1900万円を、学園の理事会の承認を得ないまま産廃処理会社の口座へ入金したとされる。
同校関係者が入手した産廃処理会社の帳簿によると、夫婦は記録が残る2015年5月~今年4月の間だけでも、2億円以上の資金を学園から同社の口座に移していた。同社の運営に充てられたとみられる。資金の一部は回収が難しくなる可能性が高いという。
11日に他の同校幹部らと記者会見した後藤校長は、同校内に産廃処理会社の事務所が置かれている状況などを説明し「夫婦が学園を私物化している。職員及び生徒を守るため、学校を正常化するために告発した」とコメントした。
2018年年10月12日に「ビビッド」で放送された『農業アイドル自殺は事務所のパワハラ…遺族が提訴へ』をちょっと見たが、
事務所は終わったと思った。
全国規模でいろいろな事実が公になったらまともな活動は出来ないであろう。もちろん、騙すことが前提であれば今後も活動は可能だと思うが??
愛媛県のご当地アイドルだった16歳の少女が自殺したのは、事務所のパワハラなどが原因と主張し、遺族がおよそ9,300万円の損害賠償を求めて、12日に提訴する。
愛媛県のご当地アイドル「愛の葉Girls」のメンバーだった大本萌景さん(当時16)は、2018年3月に自殺した。
大本さんが、事務所のスタッフにLINEで、学業を理由に休むことや脱退について相談すると、スタッフから「次また寝ぼけた事言いだしたらマジでブン殴る」、「お前の感想はいらん」、「世の中ナメるにも程があるぜ」などと返信された。
また、過密なスケジュールから脱退を申し出た大本さんに、社長が「辞めるのであれば1億円支払え」と発言したという。
大本さんの母親は、「(自殺の)前日から当日までのことは、社長自身が一番よくわかっていると思う。それを、『自分たちに全く非がない』は通らないと思う」と話した。
遺族は、パワハラ行為を受けたなどと主張、社長らに慰謝料など、およそ9,300万円を求め、12日に松山地裁に提訴する。
当時大本さんが所属していた事務所の社長は、2018年6月、「大変反省している。改善しなくてはならない」と答えていたが、提訴については取材に応じていない。
(テレビ愛媛)
愛媛県を拠点にアイドル活動をしていた少女(当時16歳)が今年3月に自殺したのは過重労働やパワーハラスメントが原因として、遺族が12日、松山市の芸能事務所「Hプロジェクト」などに対し、慰謝料など約9268万円の損害賠償を求め、松山地裁に提訴する。
原告弁護団によると、少女は同市の大本萌景ほのかさん。13歳だった2015年にオーディションに合格し、農業の魅力を発信する5人組アイドル「愛えの葉はGirlsガールズ」の中心メンバーとして活動していたが、3月21日、自宅で自殺しているのが見つかった。
弁護団によると、大本さんは1日の拘束が12時間を超えることもあり、遅刻すると報酬が減額された。学業との両立に悩み、17年8月、事務所に脱退の意向を伝えると、従業員から「また寝ぼけたことを言い出したらぶん殴る」とLINE(ライン)でメッセージが届き、今年3月には社長から「辞めるなら1億円払え」と告げられたという。
大本さんは通信制高校を辞めて今春、全日制高校に入る予定だったが、弁護団は、事務所から必要な費用を借りる約束が果たされず、入学を断念したとしている。
その上で「事務所には健康や職場環境に配慮する安全配慮義務があった」と指摘。特に配慮が必要な未成年者を過酷な労働環境で強制的に働かせ、「自殺するほど苦しい精神状態に追い詰めた」と主張している。一方、事務所側は取材に、「責任者がおらず応じられない」としている。
行政は検査の定義や資格など最低限を定める必要がある。実際に、資格などを取得しても、検査する人間達が故意に検査を通したり、
改ざんした後に判なり、サインすれば同じ結果かもしれないが、資格の取り消しや資格を数年、取得出来ないなどの処分を出せば、
全く処分しないよりは不正は減ると思う。
人間が人間である以上、不正や犯罪はなくならない。千年以上経っても犯罪がなくならないのと同じ。だからと言って犯罪に対する
処分を廃止する国はない。処分をするほうが、処分しないよりも結果が良いからだと思う。
スバルが自動車の性能を出荷前に確かめるブレーキなどの検査で不正を行っていた問題で、同社が11日、国土交通省にリコール(回収・無償修理)を届け出たことが関係者への取材でわかった。
同社は9月末にブレーキ検査での不正が見つかったと発表していたが、ほかの検査で安全性能が保たれていることなどを理由に、リコールをしない方針を示唆していた。その後の国交省とのやりとりなどから、リコールが必要だと判断したとみられる。リコールの対象は数千台規模になる見込み。
スバルをめぐっては、無資格者が完成車の検査をしていた問題をめぐり、昨年から今年にかけて約42万台のリコールを届け出ている。(贄川俊)
生きて行くため、生き残るためには何でもやると言う事だろう。
後は行政が管理及び監督するしかない。
ダメな会社や組織には引導を渡すしかない。公務員と違うのだから会社が社会や環境に対応できなくなり、違法な行為に手を染めれば
引導を渡すのが行政の役目。利害関係なく、中立な立場で判断できる立場はそのためだろう。
賄賂や便宜を受けている公務員は存在するがそのような公務員は退場してもらうしかない。
近畿地方にあるIT系専門学校は、300人を超える学生の大半が、アジア圏出身の若者だ。20年以上前は、地元の高校生らが中心だったが、次第に学生が集まらなくなった。外国人に活路を求めるようになったのは10年ほど前という。
このIT系専門学校の経営者は「授業内容は行政のチェックも受けており、問題ない」と強調する。ただ、入学時には日本語が十分理解できない留学生も多く、パソコンソフトの使い方とともに初歩的な日本語も教えている。
長野県内のビジネス系専門学校は、かつて受験予備校だったが、留学生向けに業態変更した。関係者は「地方の予備校は経営が苦しい。学校存続のため、時代に合わせた選択だった」と打ち明ける。
留学生の取り込みを狙い、新規開校する専門学校もある。数年前に開校した西日本の専門学校の母体は日本語学校で、400人を超える学生の中に日本人はゼロ。学校の幹部は「日本人を集めるつもりはない」と本音を漏らす。
学校教育法に基づく認可を受けた全国の専門学校のうち、外国人学生の割合が9割以上の学校が少なくとも72校に上ることが、読売新聞の調査でわかった。このうち35校は全員が外国人だった。専門学校は、日本の若者の職業教育を目的に認可を受けていることから、文部科学省は実態調査に乗り出す。
大阪市の「日中文化芸術専門学校」では、定員超過でベトナム人らを入学させ、今夏、100人以上が在留資格を更新できずに退学になる問題が発覚した。
読売新聞は、各校から毎年5月1日時点の外国人数の報告を受けている都道府県に調査。東京は集計が未完了だったが、残る46道府県から回答を得た。
その結果、約2400校のうち外国人が5割以上なのは139校。9割以上の学校は、神奈川、千葉両県の8校が最も多く、広島県は7校あった。東京は昨年、全員が外国人の学校が9校あり、実数はさらに多い可能性が高い。
淀川製鋼所は21日、鉄鋼メーカーや製紙会社などに出荷している生産設備の部品で検査データを改ざんする不正があったと発表した。部品の硬さなど顧客と取り決めた品質を満たしていない製品で、検査成績表に実際とは異なる虚偽の数値を記載していた。現時点で47社への納入が確認されているという。
問題があったのは、鉄鋼や紙、ゴムなどに圧力をかけて薄く延ばすのに使う「ロール」と呼ばれる部品。改ざんは慣習化していたとみられ、少なくとも5年前から行われたことが分かっている。大阪市の工場で製造され、2017年度のロール事業の売上高は37億円。
サクラに騙される学生をほしい企業は問題だと思うし、サクラに騙されて就職を決める学生は愚かだ!
社会人になる前に騙される学生は将来、騙される可能性が高いと思う。
目先の事しか考えられず、インチキな手段を取る会社は運が良くなければ将来成長するはずがないと思う。何かあるたびにインチキや
将来の大きな損失よりも目先の利益に注目していれば、無駄な事や間違った方向へ進んでも不思議ではない。
スマホとSNSが普及したことで、口コミを偏重する不思議な風潮が生まれている。学生の就職活動についても同じような現象が起きていて、それを利用した裏バイトが学生インフルエンサーの間で広がっている。いまは2020年卒の学生たちがインターンシップなどに取り組み、来年春に始まる企業説明会やセミナーなどの情報を一学年上の先輩から得ている頃だろう。ライターの森鷹久氏が、企業セミナーに出席するサクラが増えた経緯と、サクラになったインフルエンサーたちの本音をレポートする。
* * *
「とにかく人が集まりません。学歴フィルター云々と言っているのは、超一流企業と、そんな企業にエントリーする一流大の学生たち。私たちとしては、なりふり構わず学生を集めるしかないのです」
こう語るのは、東京都某区にある中堅商社の採用担当者・M氏。昨年、一昨年と十数名の新卒採用枠を設けたが、実際に入社したのは10名にも満たなかった。採用担当者として上司からは「集め方が悪いのではないか」と叱責され、あらゆる就職サイトの担当者とも協議を重ねてきたが、インターン応募者も、採用試験応募者も一向に伸びない。「人不足」を肌で実感せざるを得ない状況の中で、とある広告代理店から持ち掛けられた“秘策”に、M氏は茫然とした。
「そこまでしないと人は来ないのかと…。あまり気は進みませんでしたが、背に腹は代えられずやってみると、確かに人が来たのです。私としては本当にうれしかったが、正しいことなのかと問われると、まあ…」(M氏)
その“秘策”とは、会社説明会などにサクラを雇うという禁断の手法だった。
サクラ達は、ただ頭数をそろえるだけでは意味がない。ネット社会で「インフルエンサー」とも呼ばれる、モデルや芸能活動をしたことがある人、ブロガーやサークルの代表として活躍する学生たちにサクラになってもらうのだ。彼らは、SNSなどで多くのフォロワーを持ち影響力がある。その口コミによって説明会に人を呼び込む、という寸法だったというのだが…。
「いくら費用がかかったか…多くは言えませんが、以前よりだいぶかかったとだけ…。でも、彼らの影響力は本当にすごい。一人のインフルエンサーが弊社についてのポジティブな情報をSNSで発信し、会社説明会に行くと投稿すると、そこには"私も行く、俺も行く"との返信が相次ぎました。そしてそのうちのほぼ半数以上が、実際に説明会に参加した。すごいことです」(Mさん)
当初、Mさんはこのやり方について大いに疑問を抱いていたが、実際にたくさんの学生が会社に来て、説明会に参加した後には「きっかけは何でもいい」と考えるようになった。インフルエンサーは単なるサクラではなく、人を呼び込むための「コンサルタント」とも言えるのではないか、筆者にそう思いを吐露するまでになったのだ。
確かに、採用担当者にしてみれば、まずは人が集まれば良い、という思考に陥りやすいことは理解できなくもない。分母が多ければ多いほど、優秀な人材を獲得できる可能性は高まるのである。しかし、こうした採用に関する"インフルエンサー業務"を行ったことがある学生側は、単なる仕事、もしくは小遣い稼ぎとしてしか考えていないらしい。
「サークル内向けのSNSや、個人SNSへフォロワー限定ポストで“××会社は期待できる”とか“採用試験受けるつもり”と書いたことがあります。すでに某メディアに就職が決まっていましたが、広告会社に勤めるサークルの先輩からお願いされたので、仕方なくって感じですね。報酬は五~六回、××会社のことをつぶやいたりして、3万くらい。あとは打ち合わせの時に焼き肉に連れてってもらった(笑)」
このように打ち明けたのは、現役の大学4年生で、大手運輸系企業に来春から勤務する予定のU君だ。難関国立大に在籍するU君は、今年春にはすでに内定をゲットしていたが、そのことを公表せずに、自身が「就職活動中」である体で、このような依頼を受けたというのだ。顔立ち端正なU君は、かつて雑誌の読者モデルとしても活躍していた。インスタグラムでは数千人のフォロワーを持ち、投稿には毎回数百の「いいね」が付き、十数件のコメントが寄せられる。フォロワーにはU君と同世代の学生がたくさんいるから、U君の一挙手一投足が彼らに与える影響は小さくない。まさに「インフルエンサー」なのだ。
国内大手の保険会社に勤めるTさんも、昨年同じような「業務」を経験した一人だが、U君同様に「あくまでも仕事だった」と明かす。
「私の場合は今の会社から内定をもらった後も、三社くらいの会社説明会に出かけました。アパレル系、音楽系、あとはなんだったかな…。忘れちゃいましたが、合計で10万くらいは貰ったと思いますね。今の会社の人事担当者にバレて大変でしたが、代理店に勤める先輩から頼まれてと弁解して、何とか事なきを得ました(笑)。社会人になって冷静になって考えると、そうまでしないと人が集まらない企業ってどうなのかな?とも感じます。はっきり言ってダマしじゃないですか。
私が宣伝した会社名をネットで調べると“ブラック”とか“激務”みたいなキーワードが出てくる。そんな会社に人が集まるわけがない。あと、今だから言えるけど、私なんかの宣伝に影響されてくる学生って、結構情報に疎いというか、微妙な感じじゃないのかなって思ったりしますよ、正直」(Tさん)
TさんもSNS上では少なからず影響力を持っていた一人だが、就職を機にSNSへの投稿が減り、今では立派なビジネスマンとして、毎日激務に励む。「単なるバイトでしたよ」として、わずか一年前の事ながら、記憶も薄れているほどなのだ。
さらに、こうした「事情」を知った学生の中から、さらなる強者が産まれている。有名私大四年のIさんもまた、すでに大手広告代理店から内定を得ている立場であるが、“先輩”からのあっせんにより、多くの企業にエントリーしたり、説明会に参加して、割の良いアルバイトをこなしていると明かす。
「内定先の先輩から頼まれて、企業の説明会に参加したり、エントリーしたりして一件につき五千円くらい貰っています。エントリーだけでもらえることもあれば、説明会に行ったり、実際に採用試験を受けて、もっと多くのバイト代もらえることもあります。友達を連れて行けばさらに金額が増えますね。SNSの友人限定の投稿で募集して、10人から20人くらいが集まります。悪いことかって言われると…うーん、社会勉強って感じですかね」(Iさん)
つい先日も「遺伝子組み換え食品」に関するイベントに関し、複数の「サクラ」とみられる学生が、遺伝子組み換え食品について肯定的かつ紋切り型の…いや単なる「コピペ」にしか見えない投稿をSNS上に上げていたのではないか、そんな疑惑が話題になった。
SNSの世界での強者はフォロワーが多いインフルエンサーで、そのインフルエンサーによる発信がステマ(※ステルスマーケティング、広告であることを伏せた宣伝)であろうがなかろうが、強い者やそれに近い者だけは真実の情報をつかんで生き残る。インフルエンサーの情報を疑わずに従うだけのフォロワーは、偽りの情報に人生まで振り回される可能性があるが、それには気づいていない。
かつて、ある家電製品の使い心地の良さを語った芸能人ブログのエントリーが、実は広告料をもらった宣伝だったとわかったとき、世間はブログを書いた芸能人に対する非難一色になった。それからしばらくの間は、広告だと告げないネット投稿を、読者はもちろん、広告主も敬遠した。ところが、スマホとSNSがコミュニケーションツールとしての比重を増してきた最近では、この、ずるい広告に対して鈍感になってきてはいないか。
そしていま再び、目につき始めたインフルエンサーを利用した「サクラ」を呼び込むフェアではない手法は、広告会社やPR会社を通じたオーダーということで「プロモーション代金」という名前に化ける。この、いかにもきれいな名目で決済ができるからか、広告主側の感覚までもがマヒしているといった実情でさえ散見されるのだ。
情報強者は強者とだけ組み、富める者は富むが、情報弱者は弱者のまま、持たざる者はさらに無くしていくといった様相だ。階層化を固定するようなこの傾向は、この社会が内側で食い合うだけであり、犯罪者にも簡単に悪用される。社会に出る前の現役の学生諸君に、目の前に危機が迫っていることを、ぜひ知っておいてほしいところだ。
スルガ銀行の不正融資問題で、金融庁が一部業務の停止を命令しました。こうした中、スルガ銀行の元幹部が預金通帳の改ざんなど不正の実態について初めてカメラの前で語りました。
「給料泥棒、バカヤロウ、銀行辞めてしまえ。そういったことは普通に横行していた」(スルガ銀行の元幹部 リオパートナーズオフィス 荻野周一代表)
こう話すのは、スルガ銀行の元幹部で、コンサルティング会社の代表を務める荻野周一さん。
Q.改ざんは知っていた?
「そういう事案は直接目にしています。数字を達成するためには全てを犠牲にする。それが当たり前だというのが、営業店の現場には確実にあった」(スルガ銀行の元幹部 リオパートナーズオフィス 荻野周一代表)
スルガ銀行の元幹部が実名でインタビューに答えるのは、これが初めてです。シェアハウスのオーナーの預金残高の資料を改ざんし、組織的に不正な融資を行っていたスルガ銀行。金融庁はスルガ銀行に対し、内部管理体制に重大な欠陥があったとして、投資用の不動産向けの新たな融資を6か月間停止するよう命令しました。半年にも及ぶ業務停止命令は異例です。
「おわび申し上げます」(スルガ銀行 有國三知男社長)
組織的な不正はなぜ行われたのか。荻野さんは、背景に異常なまでの利益至上主義があったと指摘します。
「利益至上主義で、数字をあげられなかった者は、人格も人間性そのものも否定される。逆に数字を達成できた者は、支給される給料も上がりますし、社内的な立ち位置も非常に強くなります」(スルガ銀行の元幹部 リオパートナーズオフィス 荻野周一代表)
さらに、売り上げを伸ばすためには何をしても良いという雰囲気が行内に蔓延していたというのです。
「威圧的な発言を部下にすることが後ろ向きなことではなくて、かえってそれが評価されるような雰囲気さえありました。要するにどんな手段を使ってでも数字をあげなければ生き残っていけない」(スルガ銀行の元幹部 リオパートナーズオフィス 荻野周一代表)
スルガ銀行は、創業家と関係の深いファミリー企業への500億円近い融資や、反社会的な勢力に新たな口座を開設していたことも明らかにしました。
「(スルガ銀行には)新しく生まれ変わっていっていただければと願っている」(スルガ銀行の元幹部 リオパートナーズオフィス 荻野周一代表)
今回の問題で経営の悪化が懸念されているスルガ銀行は、他の銀行との資本提携などについて、「選択肢として否定しない」としています。
金融庁は5日、シェアハウス向け融資などで組織的な不正が横行していたスルガ銀行に対し、投資用不動産向けの融資と一部の住宅ローンの新規受け付けを今月12日から6カ月間停止するよう命令した。執行役員を含む多数の行員が審査書類の改竄(かいざん)などの行為に関与し、経営陣も不正を見抜けなかったことを問題視し、法令順守や経営管理体制に重大な欠陥があると判断した。
経営責任の明確化や顧客本位体制の確立などを求める業務改善命令も出し、改善計画を11月末までに提出するよう命じた。全行員に融資業務などに関する研修を実施することも求めた。
金融庁はシェアハウス問題の発覚を受け、今春からスルガ銀に立ち入り検査を実施していた。国内の銀行への一部業務停止命令は、系列の信販会社による反社会的勢力への融資を放置していたとして、2013年にみずほ銀行に出して以来となる。
引責辞任した岡野光喜前会長ら創業家の関係企業への融資に関し、保有資産の実態を把握していないなど管理が不適切と認定。反社会的勢力やマネーロンダリング(資金洗浄)対策の不備も指摘した。
シェアハウス向け融資の債務者に対し、金利の引き下げや返済条件の見直しなど適切な対応を行う体制の確立も求めた。
シェアハウス問題をめぐっては、外部弁護士からなる第三者委員会が9月7日、調査報告書を公表し、審査書類の偽装や無担保ローンの抱き合わせ販売といった組織的な不正が横行していたと認定した。
◇
■スルガ銀行の不正融資問題をめぐる経緯
・2012年8月
シェアハウスを運営するスマートデイズの前身が設立
・2014年春
「かぼちゃの馬車」のブランドで女性専用シェアハウスの事業を開始
・2018年1月
スマートデイズがシェアハウスオーナーへの賃料支払いを停止、トラブルが表面化
・2018年4月
オーナーの大半に融資を行っていたスルガ銀に金融庁が立ち入り検査
・2018年5月15日
スルガ銀が「偽造・改竄が相当数行われていた」とする社内調査結果を公表。外部弁護士による第三者委員会を設置
・2018年5月22日
オーナーの弁護団が、スルガ銀の行員らが審査書類を改竄した疑いがあるとして警視庁に告発状を提出
・2018年8月9日
スルガ銀が18年4~6月期連結決算を発表。6月末の不良債権額が前年同期の4.6倍に
・2018年9月7日
第三者委員会が報告書を公表。不正が組織的に行われていたことを認定
・2018年10月5日
金融庁が不動産融資業務などの業務停止を命じる行政処分
「スルガ銀行の営業担当者の人事評価は、営業目標の数字を達成したかどうかに偏った制度になっていた。」
営業目標の達成で判断される偏った制度は原因とされているが、上手くやれば問題ない。ただ、将来に発生する問題の無視や軽視、内部監査を
行わない、適切な、又は、合法な方法による基準達成などのいろいろな要素で将来の破滅に影響する事が高いと思う。
不適切な、又は、違法なやり方は将来、問題になる可能性があると思う。ただ、不適切な、又は、違法なやり方で多少の問題はあったが
多くの人達が成功した人と評価するケースがあるので、不適切で違法な手段=将来の破滅や報いを受けるわけではないと思う。個人的には
報いを受けて失敗してほしいが、現実は現実なので仕方がない。
実際に、問題が起きた人々や会社は自業自得だと思う。世の中は公平ではないので複雑で完全に納得できるように理解するのは難しいと思う。
スルガ銀行で不正な融資が多発した原因の一つとして、同行の不正融資を調査した第三者委員会は利益偏重の人事評価制度があったと指摘する。そして、同行の評価制度の決定的な欠陥にも言及する。第三者委員会の調査報告書をもとに詳しく報告する。【毎日新聞経済プレミア】
スルガ銀行の営業担当者の人事評価は、営業目標の数字を達成したかどうかに偏った制度になっていた。担当者は上司と面談し半年ごとに営業目標値を設定する。例えば「半年間に不動産ローン10億円」といった目標だ。その達成率が自分の人事評価ポイントの1項目になる。ほかに法令順守や顧客満足度を含む項目があった。
営業担当の場合、目標達成率を人事評価ポイントの最大7割に設定できた。数値目標さえ達成すれば、評価ポイントはかなり高くなる。その制度に基づき、多くの営業担当者は目標達成率を自分の評価ポイントの5~6割という高い割合に設定し、目標達成に励んでいた。その分、法令順守や顧客満足度が含まれる項目の割合は低くなった。
第三者委員会の報告書は「半年間というごく短期の営業成績が、人事考課全体の最大7割を占めるというのはさすがに行き過ぎなように思われる」と指摘する。
◇延滞や回収不能は人事考課の対象外
そして、この評価制度の最大の欠陥は、その融資の返済があとで延滞になろうが回収不能になろうが、営業担当者の人事評価に影響しなかったことだ。融資が焦げ付いても人事評価が変わらないなら、返済が可能かどうかを厳しく見ようとしなくなる。
そうした偏った人事評価制度のもとで、業者が紹介するシェアハウスや中古マンションへの融資を1件でも多く実行しようという意識が、営業担当者に働いたと報告書は指摘する。
人事評価は、ボーナスに直接反映された。スルガ銀行のボーナスは評価に基づき、半年ごとに基本月給の2カ月分から6カ月分の間で決められた。ボーナスを査定するいくつかの項目のうち、営業担当者は営業目標の達成率が最大5~7割、支店長は30%から45%程度の割合で寄与していた。
◇営業へのボーナス傾斜配分を要求
この制度のもと、投資不動産向けローンを伸ばしていた営業部門のボーナスの平均支給率は「総じて高め」だったと報告書は指摘する。加えて、営業部門担当の麻生治雄・専務執行役員が、営業部門は業績への貢献度が高いことを理由に、配分を大きくするよう毎回強く要請していた。
多額のボーナスを支給される営業担当者に、行内から嫉妬の目が向けられることは必ずしもなかった。「あれだけ働かされるのだから、それなりにボーナスがもらえないとやっていられないし、人が辞めてしまう」といった声や「異動すると、死ぬほど働かされるので、できれば行きたくない」といった声が出ていたというのだ。
外国人が技能を学べる機会を与えるとの建前で、労働者として使う事に限界があるのではないのか?
日立は技能実習の機会を与えたいのではなく、単純に安い労働者が惜しかったが、他の中小、および零細企業のように無茶苦茶や嘘が付けなかった
、又は、日立のネームブランドを汚してまで、大嘘を付けなかったと言う事ではないのか?
サブスタンダード船の船主や運航者の中には、違法を承知の上で便宜を図る、又は、
違法を潜り抜けれる事を営業トークでアピールする旗国(便宜置籍国)に船を登録する
傾向が高い。金融業界の節税やタックスヘイブンのように船や海運にも合法やグレーゾーンが存在する。そのような部分とは別な
滅茶苦茶な世界がサブスタンダード船とブラックリストに掲載される旗国(便宜置籍国)で説明できる。
同じようなシステムに見えても度が過ぎると悪質としか思えないケースになる。今回の日立製作所のケースは大手であるが故の戒めと
問題を放置すると技能実習制度を継続できないと国の監督機関が判断したからではないのか?
観光ガイドや通訳を育成する「日中文化芸術専門学校」(大阪市天王寺区)が定員超過で学生を受け入れたため、留学生計約360人が退学(毎日新聞)になったケースでは悪質であると思った。大阪府の対応に問題があった結果、
問題が放置された。一番、悪いのは日中文化芸術専門学校であるが、行政の怠慢が問題を大きくする例がある。
監理団体「協同組合フレンドニッポン」(本部・広島市)が日立製作所の実習生の問題についていつ知ったのか、どのくらいの間、問題を放置していたのか記事に記載されていない。監理団体「協同組合フレンドニッポン」のライバル会社がどこになるのか知らないが、競争が過熱すれば、
どこまで違法や問題を放置するのかのチキンレースになる可能性がある。ライバル会社や競争相手が、違法な行為まで容認すれば、同じように
違法を容認しなければ仕事を競争相手に取られてしまう。チキンレースの競争は果てしなく続く。行政や監督機関が介入して処分するまで
止まらないだろう。今回のケースは「技能実習適正化法違反の疑い」。
スルガ銀、6カ月の一部業務停止に 国内銀行で5年ぶり 10/05/18(朝日新聞)は、長い間、行政や監督機関が問題を放置する、又は、問題に気付かなかった結果だと思う。
日立製作所の技能実習生の問題では対応次第では日立製作所の組織としての問われる可能性があると思う。
日立製作所が、鉄道車両製造拠点の笠戸事業所(山口県下松市)で働くフィリピン人技能実習生20人に実習途中の解雇を通告したことが同社などへの取材で分かった。国の監督機関から実習計画の認定が得られず、技能実習生としての在留資格が更新されなかったため。実習生は今月20日までしか在留できず、帰国を迫られるが、個人加盟の労組に加入し、日立に解雇の撤回などを求めている。
【写真】日立製作所が実習生に渡した「解雇予告手当支払通知書」(画像の一部を修整しています)
実習生は監理団体「協同組合フレンドニッポン」(本部・広島市)が紹介し、日立が雇用した。労組や実習生によると、20人は全員20代で、昨年7月に3年間の実習のため入国した。今年9月20日付で在留資格が技能実習から30日間の短期滞在に変更され、日立から同日、解雇を通告された。「解雇予告手当」として月給相当の十数万円が実習生に支払われたという。
笠戸事業所では実習生に目的の技能が学べない作業をさせている疑いがあり、法務省や監督機関「外国人技能実習機構」が7月、技能実習適正化法違反の疑いで実地検査した。技能実習制度では実習生ごとの実習計画に機構の認定を受ける必要があるが、法務省関係者によると、日立については、適正な実習を行えるのか検査中のため、新たな計画を認定できないと判断。20人の2年目以降の計画も認定できず、在留資格を短期滞在に変更した。実習生が帰国しても、日立が適正な実習計画を出せば、国は再入国を認めるという。
解雇通告を受けた複数の実習生は朝日新聞の取材に、新幹線の排水パイプ付けなど「本来の『電気機器組み立て』技能が学べない単純作業ばかりだ」と主張。「突然解雇を言い渡された。私たちに非はなく、不当だ」と訴えている。
通告を受けた実習生らは広島市の個人加盟労組「スクラムユニオン・ひろしま」に加入し、救済を求めている。実習生によると、今回の20人を含め年末までに在留資格の更新が来る実習生99人に解雇の恐れがあるといい、うち65人が同労組に入った。「日立がいい加減な技能実習をしていなければ、実習生が帰国する事態にならなかったはずだ」として、身分保障や十分な賃金補償がなければ、日立を相手取り訴訟を起こすことも検討している。(前川浩之、橋本拓樹、嶋田圭一郎)
■日立「認可が下り次第、再度就労してもらう」
日立製作所広報・IR部は「一時的に雇用を終了したことは事実であるが、(実習の)認可が下り次第、再度就労していただく考えである。なお、現状、認可が下りていない理由については、会社としては承知していない」とコメントしている。
By Tadayuki YOSHIKAWA
全日本空輸(ANA/NH)は10月5日、杉野健治パリ支店長兼ブリュッセル支店長(当時、52)を諭旨解雇処分にしたことを明らかにした。現地時間2日にパリを出発した羽田行きNH216便(ボーイング787-9型機、登録番号JA873A)の機内で酒に酔い、隣席の乗客にけがなどを負わせたため。
ANAによると、前支店長は日本時間3日午前7時40分ごろ、出張でNH216便のビジネスクラスに乗っていた際、通路を挟んで隣席の50代女性に頸椎(けいつい)捻挫のけがを負わせた。前支店長はワインをグラスで6杯飲み酔っていたという。
けがをした乗客はその後、別の席に移り、羽田空港へ到着後に病院で全治2、3日との診断を受けた。前支店長は到着後、警察から事情聴取を受け、5日に会社側の処分が決まった。
この問題を受け、ANAは片野坂真哉会長と平子裕志社長の役員報酬を20%減給1カ月とした。ANAグループ社員も、空港ラウンジとANAグループ便機内での飲酒を当面禁止とし、飛行中の巡回強化、客室責任者であるチーフパーサー(主客室乗務員)資格者に対してアルコール提供や保安サービスについて、再教育を実施する。
前支店長は1988年4月入社。今年4月1日付で、販売部門からパリ支店長兼ブリュッセル支店長に着任した。
自業自得!
金融庁は5日、シェアハウス融資で多数の不正があった地方銀行のスルガ銀行(静岡県沼津市)に対し、不動産投資向けの新規融資を6カ月間禁じる一部業務停止命令を出した。スルガ銀ではすでに判明しているシェアハウス融資などでの資料改ざんといった不正に加え、創業家に関係する「ファミリー企業」への不透明な融資、さらに反社会的勢力への融資といった問題があると判断。企業統治(ガバナンス)上の重大な欠陥があったとした。
業務の停止期間は今月12日から2019年4月12日までの6カ月間。国内銀行に対する一部業務停止命令は2013年、暴力団組員への融資を放置していたみずほ銀行に出して以来の異例の措置だ。
一部業務停止の対象業務は投資用不動産向けの新規融資に限定し、預金の引き受けや払い戻しなどの窓口業務や既存顧客に対するサービスは継続を認める。
シェアハウスなど不動産投資向け融資では、多額の融資実績を上げるため、顧客の年収や資産状況について改ざんした書類を作成していた。執行役員を含む多数の行員が不正に関与し、審査部門についても、「実質的に形骸化している」と認定した。
組織に体質的な問題があると、問題を隠すだけで解決するわけではないので、このような問題が漏れ出すのかもしれない。
政府は教育勅語を教育
の現場で使って行くとか言うのであれば、村社会的な問題を同時に何とかするべきだ!
まあ、日本に拘りがなければ、外国で永住権を取得して生きて行く事は可能だ。ただ、簡単な事ではないし、
外国には違った形の問題がある。個々が判断してどちらが良いだけの話だと思う。
社内の不正をただしたい、働く環境を良くしたい、消費者の利益を守ろう――。そう考えた末に内部告発しても、解雇されたり降格させられたりといったケースが後を絶たない。なぜ、こんなことが繰り返されるのか。なぜ、公益通報者保護法は機能しないのか。過酷な労働時間を前に「このままでは誰かが事故を起こすのではないか」と考え、労働基準監督署に内部告発したバス運転士の話から始めたい。告発後、報復を受けた彼の「会社もひどいが、労働組合も内部告発者を守ってくれません」という訴えは、この法律の欠陥も浮き彫りにしている。(フリー記者・本間誠也/Yahoo!ニュース 特集編集部)
「いつ、事故が起きてもおかしくない」
「私が(内部告発の報復として)『追い出し部屋』ならぬ『追い出し業務』に飛ばされても、不当な降格を命じられても、組合幹部らは会社と一緒になって面白そうに眺めてました。『いつ辞めるのかな』って。うちの組合は会社の方針に従うだけですから」
首都圏の大手バス会社に勤務する大塚雅明さん(56)は、そう明かす。
バス事業の規制緩和によって年々、労働環境が厳しさを増している。入社歴33年の大塚さんは2016年10月から翌年にかけ、同じ営業所の同僚と2人で、勤務先の過酷な労働実態を労働基準監督署に内部告発した。
2人は首都圏各地と羽田空港や東京ディズニーランドなどを結ぶ中距離路線バスの運転士として働いていた。
バス運転者の労働時間について、厚生労働省は「改善基準」を告示しており、「1日15時間以上の勤務は週2日まで」「勤務と次の勤務の間の『休息期間』は継続8時間以上」などと示されている。
ところが、2人が勤務していた営業所では週3日以上、「1日15時間以上の勤務」があった。「休息期間」が4時間程度しかない勤務ダイヤも多い時で週2日。運転士不足を理由に、休日出勤も頻繁に強いられていたという。
大塚さんは言う。
「告発せざるを得なかったのは、社内の運転士の誰がいつ、大きな事故を起こしてもおかしくない状況だったからです。『改善基準』に違反する勤務が常態化しているのに、組合は声を上げないし、会社も是正しようとしない。告発時も今も、運転士はみんな疲れ切っています」
大塚さんと共に内部告発したのは、同じ職場の運転士で嘱託採用だった松岡亮さん(42)だ。
松岡さんも「自分たちのためにも、乗客のためにも、状況を変えたかったんです」と話し、こう続けた。
「例えば、15時間以上もの運転が真夜中の1時に終わり、次の業務開始が朝の5時だった場合、すぐには熟睡なんかできません。1〜2時間、ウトウトする程度です。そんな状態で運転士がハンドルを握っているなんて、お客さんは思っていないでしょう?」
内部告発後、突然の配置転換
2人は何度も労基署に足を運び、勤務ダイヤなどの“物証”を示して「会社を指導してほしい」と伝えた。しかし、話の相手はいつも「相談員」で、立ち入り調査などの権限を持つ「労働基準監督官」は対応してくれない。3カ月近くが過ぎたころ、2人は「労基署はそもそも動く気がないのかもしれない」と感じるようになった。
さらに悪いことに、一緒に労基署へ行くはずだった同僚が、土壇場で翻意し、逆に会社幹部に接近するようになっていく。2人は「私らの行動は会社に筒抜けだったでしょう」と振り返る。
労基署を何度か訪ねた後の2017年4 月、松岡さんが配置転換を命じられた。次の仕事は「添乗指導」。自社のバスに乗って運転士のハンドルさばきや身だしなみ、マイクの使い方などをチェックする業務だ。
松岡さんは言う。
「この会社に採用される前も、私はバスの運転士を15年以上やってきました。それが突然、添乗指導とは……。納得できないままの配転のうえ、大幅に減らされる給料などのことで悩み、体調を崩してしまって」
その後、松岡さんは「適応障害」と診断され、休職。そのさなか、会社から「(2017年の)8月で嘱託雇用期間満了」とする雇い止めの通告を受けた。口約束とはいえ、「正社員にする」と言われていたが、それも反故にされた。
ドライブレコーダーで監視
松岡さんが会社を去った2017年8月以降、大塚さんへの報復も激しくなった。
まず会社側は「車内を映したドライブレコーダー(DR)をチェックしたら、携帯電話の操作があった」として、大塚さんを停職3日の懲戒処分にした。実際には、バスの車庫入れ直前、信号待ちの間にバッグからスマートフォンを取り出してダッシュボードに置いただけで、操作はしていない。
ところが、である。
この時点までスマホや携帯電話に関する規定が就業規則になかったにもかかわらず、会社側は、懲戒理由を後付けの形で「運転席でスマホに触れば、それだけで操作に当たる」とした。
さらに1カ月ほど後、今度は「DRを見たら、運転席周りで携帯を触っていた」として、会社側は4日間、会議室での反省文書きを命じた。大塚さんは「携帯を触っていたのは、車庫内の駐車スペース。しかも休憩中でした。理由をこじつけてでも、会社側は私をいじめて辞職させたかったのでしょう」と振り返る。
それから間もなく、大塚さんは運転業務から洗車業務に配置転換となり、同時に降格となった。これによって給料は手取りで6割もの減額。住宅ローンを支払うと何も残らない。
「懲戒処分も配転も降格も不当なものですが、労組も力になってくれなかった。見て見ぬふりというより、冷ややかに見ている感じでしたね。つらいし、給料も激減したけど、負けてたまるか、と」
大塚さんと松岡さんは2017年末、個人加入の労働組合「プレカリアートユニオン」(東京)の一員となった。事情を聴いた同ユニオンは会社側に団体交渉を申し入れたほか、街頭での活動やSNSを通して「2人への処分は不当だ」と拡散させていく。
会社側は18年3月、大塚さんを運転業務に戻した。それでも、降格は撤回していない。そして2人は同年6月、雇い止めとなった松岡さんの地位確認、および大塚さんと松岡さんの減額された給料の支払いなどを求める民事訴訟を東京地裁に起こした。
大塚さんら2人が語る内容や裁判について、このバス会社の本社総務部は「係争中なのでコメントは控えたい」としている。
「労働組合は目を覚ませ」
バス運転士の勤務実態を告発した2人は今、こう口をそろえる。
「私たちの内部告発は正当なものだし、報復的な処分の数々は不当だと思っています。水面下ではありますが、私たちの裁判を応援してくれる社員は少なくないし、今の過酷な勤務体制を変えるため、『自分もユニオンに入りたい』と連絡してくる社員もいます。会社も労組も目を覚ましてほしい」
労組は目を覚ませ、という声は他にもある。
例えば、内部告発を理由に雇用契約を更新しないのは法律違反だ、と主張した京都のタクシー運転手。この男性は2007年10月、地位保全を求めた仮処分申し立てが認められ、京都地裁の決定後、報道陣に「労働組合とは名ばかり。会社と一体となって不正のもみ消しや労働者いじめをする労組も許せませんでした」と語っている。
公益通報者保護法に詳しい中村雅人弁護士(東京)は、こう話す。
「内部通報は労働者の権利に関する問題です。公益のために通報した従業員に対し、会社が報復した場合、その従業員を守るのは誰か。誰もが一番に思いつくのは労働組合でしょう」
だが、現実の労働組合は、必ずしもそうではない。内部通報に関する民事訴訟をいくつも担当してきた中村弁護士は、報復された従業員の労組幹部と面会したことがある。そこでは、こう訴えたという。
「もし、みなさんが社会的に有意義な通報をしたとして、その報復で『おまえは配転だ、解雇だ』と言われたら、どうしますか。全ての労働者に共通する問題なんだから、労組こそが応援しなければいけないでしょう?」
この労組は結局、何もしなかったという。
「企業内労組の幹部たちは『内部通報者に味方したら自分はどうなるだろうか』『自分も報復されるかも』と考えてしまう。自分の保身を優先するわけですよね」
労組も頼りにならず、1人で会社を提訴
労組が敵に回った実例もある。内部通報の報復として不当な配転命令などを受けたオリンパス社員の浜田正晴さん(58)の体験も壮絶だ。
浜田さんは2007年、上司の不正を知り、それをやめるようその上司に直接伝えた。その進言を受け入れてもらえなかったため、今度は社内のコンプライアンス窓口に通報した。ところが、窓口の担当者は当の上司や人事部長に対し、浜田さんの氏名や通報内容を漏洩してしまう。
“組織ぐるみの報復”が始まったのは、その後だ。
専門外への配転や最低水準の人事評価、上司らからの恫喝……。浜田さんが配転命令に関して労組に相談したところ、幹部は「私たちが浜田さんを守ります」と言ってくれたが、逆に会社と一体になって敵に回った、と浜田さんは言う。
「うちの組合は御用組合とは思っていたけれど、ここまでひどいとは、と驚きました」
たった一人で会社と対峙することを決意した浜田さんは08年、オリンパスと上司を相手に配転無効とパワハラに対する損害賠償を求めて訴訟を東京地裁に起こした。4年余りもの期間を費やした訴訟は、12年に最高裁で浜田さんの勝訴が確定。16年には別に起こした「名誉回復」のための訴訟で会社側と勝訴的な和解をした。巨額損失隠し事件で旧経営陣はすでに一掃され、オリンパスは新体制になっていた。
海外駐在勤務の経験を生かして、現在は本社人事本部でグローバル教育のチームリーダーを務める浜田さんは、自身の経験を振り返ってこう言う。
「今のオリンパス労組は、パワハラに加担しなくなったという意味では良くなったと思います。でも、当時の労組はそうじゃなかった。正当な内部通報をした私を退職させようと陰湿に動きました。コンプライアンスの窓口が情報を無断漏洩し、それが社内規則に反することが明白になっても、です。当時の会社の体質もありますが、労組は極めて異常だったと思います」
そして、こうも言った。
「労組の軸足を会社寄りから通報者側へ移すには、やはり公益通報者保護法を改正し、違反企業に罰則を科すことが大前提です。この法律の最大の欠陥は違反企業に罰則がないこと。少なくとも改正によって罰則付きになれば、通報によって会社から不利益を受けた私のような従業員を、労組が一緒になって追い詰めるようなことはなくなるでしょう」
「報復には罰則を」に霞が関も抵抗
公益通報者保護法は「公益のために通報を行った労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止する」(消費者庁)役割を持つ。一方では、まさにオリンパスの浜田さんらが言うように、内部通報者に報復しても企業側には罰則がないため、「ザル法」と言われてきた。
施行から12年が過ぎ、この法律は現在、内閣府消費者委員会の公益通報者保護専門調査会で改正の議論が進んでいる。改正法案の提出目標は来年の通常国会で、年内には大まかな方向が打ち出される見込みだ。
企業側の報復に対し罰則を設ける案には、経済界が強く抵抗してきた。それだけでなく、「マン・パワー不足という理由から、霞が関でも抵抗は強い」と中村弁護士は明かす。
実際、官僚たちの消極姿勢を見せ付けた場面があった。今年6月の同専門調査会。報復措置を行った企業に行政措置や罰則を科すよう法を改正したらどうなるか。それについて、厚労省の幹部はこう述べた。
「公益通報者保護の実効性ある仕組みづくりの必要性に異を唱えるものではありませんが、私どもの(労働法など)他の法律で、不利益取り扱いの処理は一件一件、非常に手数が掛かることを経験しております……。職員数の事情が現状でも非常に厳しく、通報者保護について(消費者庁と)連携してこなしていくには客観的に非常に厳しい情勢だと思っています」
この法律の所管官庁は消費者庁だが、罰則などを法律に盛り込んだ場合、事実関係の詳しい調査が必須になる。全国に出先機関を持たない同庁は単独で対応できず、労働行政を所管する厚労省の手厚い支援は欠かせない。
そうした声に対し、同省は公開の会合で、抵抗する姿勢を示したのだ。
法改正に向けて議論を重ねる専門調査会は、7月の会合で中間的な論点整理を実施した。その中では、企業に対して強制力を持たない「行政措置」(指導、勧告、公表)を導入する方向性を示す一方、最大の関心事である刑事罰については「今後の検討課題」とし、先送りした。
法改正で罰則規定を盛り込めるか
専門調査会の議論はこの秋、法改正に向けた取りまとめに入っていく。「内部告発者への報復をどう防ぐか」の議論のヤマ場である。
法案作成を担う消費者庁の担当者は「委員の要請によっては、再び厚労省の方に出席を求め、『(厚労省から)どのくらいのサポートを望めるのか』について踏み込んで検討してもらうことも考えています」と言う。
しかし、議論の行方を見守ってきた中村弁護士は「消費者庁も刑事罰まで踏み込まず、手近なところで改正法案をまとめようと考えているのではないか」と懸念する。
オリンパスで復権を果たした浜田さんは「現行の公益通報者保護法は究極のザル法です」と言い続けている。「不当な報復を会社と労組から受けた場合、私のように会社を相手取って、会社に身を置いたまま、一人で長い年月と費用をかけて民事訴訟を闘わねばならない」からだ。
「一刻も早く、報復を抑止するための罰則規定を導入し、私のような被害者を出さないような法改正をしてほしい。そう願っています」
本間誠也(ほんま・せいや)
北海道新聞記者を経てフリー。
組織に体質的な問題があると、問題を隠すだけで解決するわけではないので、このような問題が漏れ出すのかもしれない。
日大の不祥事が止まらない。5月のアメフト部・悪質タックル事件、8月のチアリーディング・パワハラ被害に続き、今度は水泳部の暴力事件が発覚した。諸問題は今年に入って一気に噴出したかのようだが、実は日大では2年前に学生の命にかかわる大事件が起きていた。しかもその事件は未解決のままだ。
「暴力事件が発覚したことは謝罪したい。申し訳ありませんでした」
強烈なシャッターを浴びて深々と頭を下げる男性。9月26日、日本大学水泳部の上野広治監督(59才)が都内の寮で記者会見し、『週刊文春』(10月4日号)が報じた、水泳部内の“パワハラ”行為を認めた。
上野監督によると、9月上旬に練習会場で居眠りした2年生の男子部員に対し、3年生の男子部員が注意するとともに暴行を加え、被害者の左腕にあざができた。この3年生部員は、昨年5月にも同じ2年生部員の腹部を殴り、部内で厳重注意を受けていた。
今回、上野監督は、指導者が誠実に対応せず問題が長期化したアメフト部とは異なり、迅速に謝罪した。その背景には「裏事情」があるとスポーツ紙記者が指摘する。
「日大水泳部はバルセロナ五輪・金メダリストの岩崎恭子も在籍した名門です。来春には東京五輪での大活躍が期待される池江璃花子選手(18才)の進学が確実視されており、上野監督は不祥事を長引かせたくない一心で謝罪に踏み切り、早期の幕引きを図ったのでしょう」
だが、監督が謝罪しても一件落着とはいかず、火種はくすぶる。最近、日大水泳部の関係者の間では、「ある事件」の話で持ち切りだという。日大水泳部OBが声をひそめて打ち明ける。
「水泳部の部員による暴力事件が明らかになり、OBの間では2年前の“あのこと”が再び話題になり始めています。実は2年前の夏、日大水泳部の部室で当時1年生の部員が首つり自殺をしました。これは世間には公表されていませんが、釈然としないことも多い。一連の日大に関する不祥事の中で、『ちゃんと調査をすべきではないか?』という声もあがっています」
関係者の話をまとめると、2016年7月に当時1年生だったAくんは、東京都目黒区にある日大水泳部の部室内で自ら命を絶ったという。
「遺書はありませんでしたが、Aくんの死は自殺であり、事件性がないと警察は判断しました。入部3か月での突発的な死に、いじめなど部内でのトラブルが原因ではないかと疑われましたが、日大の体育会系部活を統括する体育局は寮生を聴取し、『多少のからかいはあったが問題ないレベル』だったと結論づけました」(日大関係者)
Aくんが命を絶った翌日も水泳部は休むことなく練習を行った。大学側が「いじめはない」と判断したため、部としての責任は問われなかった。
だがAくんを知る関係者は、部内に「問題」があったのではないかと指摘する。
「入部後、寮で生活するようになったAくんは、『水泳部は思ったより大変だ』と漏らしていました。もちろん強豪大学なので厳しい練習は覚悟していたでしょうが、練習以外の面で躓きがあったようです。現に彼は、『この部の雰囲気になじめない』と漏らしていた」(Aくんを知る関係者)
◆シンナー、マリファナ 違法薬物の使用疑惑
実際、日大水泳部ではAくんの自殺のほかにも、不審な出来事が多発していた。
「部員は基本的に寮生活ですが、正月や春先は部員が実家に帰省するなどで寮が空になります。その時期に部員の水着が盗まれる事件が何度も起きましたが、犯人はいまだに見つかっていません。何度目かの盗難後、寮内には監視カメラが設置されました」(前出・日大水泳部OB)
部員同士の“不穏すぎるやりとり”も見られている。日大水泳部の部員は、グループLINEを作って連絡を取り合うことがあるという。Aくんの死後、ある学年のグループLINE上で、違法薬物の名前が飛び交った。
「複数の部員が、『シンナー』『マリファナ』などの名を出していたLINEが流出したんです。しかも、『〇〇もシンナー思いっきり吸っていた』『〇〇がマリファナを吸っている』など、部員の実名をあげた具体的な内容でした。LINEを知ったOBらが、大学側に伝えたそうで、調査が行われたはずです」(前出・日大水泳部OB)
多発する問題に、「部内の風紀は大丈夫か?」と心配の声をあげる関係者は多い。もちろん、Aくんの自殺と部を取り巻く環境に因果関係があるかどうかは不明だ。
「大学側はAくんのいじめについて、“多少のからかいはあったが、問題ないレベル”としています。ただし、どの程度の“からかい”があったのかは一切明らかにしていません。この対応を聞いて、“またか”と残念に思った関係者も多い」(前出・日大関係者)
2013年に日大では、ボート部の3年生男子部員が合宿所で首つり自殺をしている。日大ボート部は全国大会で何度も優勝した強豪であり、死亡した部員は副主将を務めていた。
この時も「部内でトラブルがあった」と部員が自殺前に漏らしたとの情報があり、大学側がいじめの有無を調査した。その結果、大学側は「からかったり、ちょっかいを出す“いじり”はあったが、許容される限度を超える“いじめ”はなかった」と判断し、自殺の動機や原因は「不明」と結論づけた。
それから3年後、再び悲劇が繰り返された。別の日大水泳部OBが言う。
「Aくんの遺族は大学側に調査結果の詳細を開示するようにお願いしたそうですが、それはいまだに叶っていないと聞いています。OBの中には、こうした大学側の対応に不信感を抱き、『Aくんの自殺や薬物使用疑惑について』スポーツ庁に投書した人がいます」
Aくんの実家を訪れると、母親が言葉少なに「息子の件については何も話すことはありません。すみません…」と語るのみだった。
日大にAくんの自殺の調査結果と、部員たちの薬物使用疑惑について尋ねた。
「(調査結果については)本人及び家族のプライバシーのため、詳細についてはお答えを差し控えます。(薬物使用は)調査の結果、使用事実は認められませんでした」(企画広報部)
冒頭のパワハラ謝罪会見で上野監督はこう語った。
「今後、“日大を目指して(保護者が)私に預ける”というお子さんのことは裏切りたくない」
大学スポーツの現場では、選手を鍛え、輝かしい成績を残すことばかりが重要視され、選手を守ることが軽視されてはいないか。上野監督のこの言葉が空虚なものにならないよう切に願う。
※女性セブン2018年10月18日号
運が良い例もあるが、不正に手を染めると、不正によるメリットと不正なしで競争に勝てる可能性がなければ、不正を続けるか、商売を
やめるしかなくなる。
不正を行っても問題が長期間、発覚しなかったり、処分が軽いケースがあったのを知っているので、不正=地獄行きと言うわけではないから、
同じ事を繰る返す会社や人達が存在するのだろうと理解している。個人的な経験から言えば、世の中には、白黒だけでなく、グレーな部分が存在する。
グレーな部分がある事を知らない、または、経験していない人達はある意味、幸せかもしれない。グレーな部分を知らずに死ねたら幸せだと思う。
スルガ銀行(静岡県沼津市)でシェアハウス融資を巡る不正が相次いだが、同行の問題が明らかになっていた今春以降も、他の金融機関の不動産投資向け融資で、不動産業者が資料を改ざんして多額の資金を引き出す不正が続いていることがわかった。金融機関は審査を厳格化してきたが、チェック態勢が不十分で、不正を防ぎきれていない。
朝日新聞が都内の不動産業者の内部文書を入手した。同社は従業員が数十人規模で、社長は不動産投資の入門書を複数出版。セミナーで会社員らを勧誘して中古1棟マンションなどを販売する。購入資金は昨年までスルガ銀が多く融資したが、不正問題で融資できなくなり、その後は大手銀行や地方銀行、信用金庫が融資する割合が増えた。
内部文書や従業員の証言によると、業者は顧客のネットバンキングの預金残高を水増しする不正を繰り返している。今年4月から夏にかけ、三井住友銀行やりそな銀行、西武信用金庫(東京)などに不正な融資資料が提出され、一部で融資が実行されている。
チェックが甘い金融機関には残高を水増ししたコピーを提出していた。最近は行員の目の前でログインを求められることが増えたが、そうした場合は偽造したホームページにログインし、水増しした残高を見せている。顧客も多額の預金があるように銀行に説明する「口裏合わせ」を行っているという。
業者の社内には、改ざんに不自然な点がないかをチェックする「点検シート」まであり、不正が発覚しないよう徹底していた。業者は朝日新聞の取材に「現時点ではノーコメントとしたい」としている。
自業自得!
金融庁が、シェアハウス向け融資で不正が横行していたスルガ銀行に対し、週内にも不動産融資業務などの一部停止命令を出すことが2日、分かった。外部弁護士からなるスルガ銀の第三者委員会が審査書類の偽装など組織的な不正の横行を認定。金融庁も今春からの立ち入り検査の結果、企業統治上の重大な欠陥があるとして、厳しい行政処分に踏み切る。
業務停止期間は数カ月になるとみられる。顧客本位の業務運営の確立などを求め、業務改善計画の提出も求める。
スルガ銀をめぐっては第三者委が9月7日、不正融資に関する調査報告書を公表し「極端な法令順守意識の欠如が認められた」と指摘し、組織的な不正を認定。創業家出身の岡野光喜会長や米山明広社長ら取締役5人が引責辞任し、有国三知男氏が社長に就任した。
金融庁はシェアハウス投資を巡る不適切融資が発覚したスルガ銀行(静岡県)に対し、週内にも一部業務停止命令を出す方針を固めた。執行役員1人を含む多くの社員が審査書類の改ざんなどに関与し、経営陣も不正の横行を防げずに企業統治(ガバナンス)が機能不全に陥っている点を問題視した。
対象となるのは、資料の改ざんなどが相次いだシェアハウスを含む投資用不動産向けの新規融資とみられる。停止期間は数か月に及ぶ可能性がある。通常の預金の引き出しなどの窓口業務は営業を継続する見通しだ。
一連の問題を巡っては、外部の弁護士らでつくる第三者委員会が9月7日、調査報告書を公表した。過大なノルマを課された社員が融資基準を満たすように投資家(オーナー)の年収や預金残高を水増しする書類の改ざんなどを行ったことが明らかになった。
五島産業汽船は良い船(かっこよい、高そう)を持っているようだ。どれくらいの利益を見込んでいたのだろう。
双胴船は安定が良いが、ドックの時に幅が広い船台を持っている造船所に限定されるし、ウォータージェットの船は燃費は悪いし、
整備費は高くなる。
コスト重視であれば、船速が遅くてもランニングコストが安い船が良いと思う。まあ、民間の会社だから自己責任でどんな判断も可能。
「今年4月期決算で2億9千万円の最終赤字を計上。8月には1回目の不渡りを出すなど資金繰りが悪化しており、再開のめどは立っていないとみられるという。」
五島市や五島列島の地方自治体が第三セクターを立ち上げ、たぶん、解雇される船員達を雇って船を運行するしかないであろう。
どこの銀行が船を差し押さえるのか知らないが、一番安い船で交渉するべきであろう。
五島列島周辺で運行されている船は五島産業汽船以外の船もあるようなので、他の船会社とも交渉するべきであろう。
騒いでも、何とかなるし、なるようにしかならない。周りがどこまで妥協するのか、周りがどのように対応するか次第。

五島産業汽船(@GotoSangyoKisen)さん | Twitter)



株式会社 五島産業汽船

海上交通バリアフリー施設整備助成制度 (交通エコロジー・モビリティ財団)
五島産業汽船(長崎県新上五島町)は2日、五島列島と長崎市や佐世保市などを結ぶ高速船やフェリーの運航を休止した。九州運輸局に1日夜までに航路事業の廃止や来年10月末までの休止を届け出た。民間調査会社によると、収益の低迷に加え、船舶の修理費などがかさみ、資金繰りが悪化していたという。
同社は1990年設立。長崎港(長崎市)―鯛ノ浦港(新上五島町)、佐世保港(佐世保市)―有川港(新上五島町)、佐世保港―福江港(五島市)の三つの定期航路をもつ。「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界文化遺産登録に合わせ、長崎港―崎津漁港(熊本県天草市)で高速船の試験運航を実施。毎週金、土、日曜に1日1往復していた。
しかし、民間調査会社の東京商工リサーチ長崎支店によると、船舶のエンジン修理費などがかさみ、今年4月期決算で2億9千万円の最終赤字を計上。8月には1回目の不渡りを出すなど資金繰りが悪化しており、再開のめどは立っていないとみられるという。
地元の自治体には1日、同社から運休の連絡が入った。長崎県の担当者は「経営上の理由としか説明を受けていない」、新上五島町は「昨日、船が出せなくなるかもと連絡を受けたが、それ以上の情報が入ってこない」と困惑する。
高速船やフェリーの乗り場がある佐世保港では、運休を知らせる貼り紙が同社の窓口に貼られていただけで、新上五島町へ向かうフェリーに乗る予定だった男性会社員は「先方と約束があるのにどうしたらいいのか」とぼうぜんとした表情で話した。(堀田浩一、福岡泰雄)
会社には連絡取れず「本日の営業は終了しました」 10/02/18(HUFFPOST)
安藤健二

五島産業汽船の高速船「ありかわ8号」(同社の公式Facebookより)
五島列島と九州を結ぶ航路を運行している五島産業汽船が10月2日から全船運休した。理由は不明だ。同社の公式サイトには「会社都合につき しばらくの間運休いたします。ご迷惑をお掛けして誠に申し訳ございません」と告知されている。
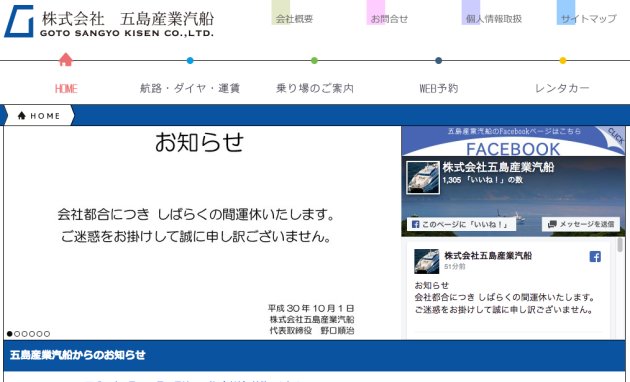
五島産業汽船の公式サイトより
長崎県庁の新幹線・総合交通対策課の担当者は2日、ハフポスト日本版の取材にこう答えた。
「昨日の夕方、五島産業汽船から運休すると連絡が入りました。理由は明かされなかったが、経営上の問題だと思われます。再開の見込みは不明です。長崎港に午前7時半から担当者を派遣して、情報収集中です」
■五島産業汽船とは?
五島産業汽船は1990年に設立され、新上五島町に本社を置いている。計4ルートの航路で、フェリーや高速船を運航している。長崎〜上五島(鯛ノ浦港)、佐世保〜上五島(有川港)、佐世保〜下五島(福江港)、長崎〜天草(﨑津漁港)だが、2日は全て運休している。
長崎県庁によると、五島列島には空路でアクセスできるほか、長崎〜上五島、佐世保〜上五島へのアクセスについては、競合会社の九州商船がフェリーや高速船で結んでいるという。
ハフポスト日本版は、五島産業汽船に電話をかけたが、本来の業務時間中にもかかわらず「本日の営業は終了しました」というアナウンスが流れるだけだった。
単なる説明不足なのか、それとも、悪意のある説明だったのか?事実は関係者のみ知る。事実や真実は知ることは出来ないが、福島に
住んでいなくて本当に良かったと思う。
事実について影響を受ける可能性が一番高いのは福島に住んでいる人達。
東京電力は28日、福島第一原子力発電所のタンクで保管している放射性物質トリチウム(三重水素)が入った「処理水」の大半に、トリチウム以外の放射性物質が国の排水基準値を上回る濃度で残留していると発表した。処理水を処分する場合は、再浄化する方針も明らかにした。
東電によると、今年8月7日時点の処理水の総量89万トンのうち、84%の75万トンが基準を満たしていない。現在の浄化能力は1日最大1500トンのため、再浄化には年単位の時間がかかる見通し。
政府や東電はこれまで処理水について、汚染水に含まれる放射性物質のうち、トリチウム以外は除去済みと説明してきた。28日に記者会見した東電の松本純一・廃炉推進室長は「説明が不十分だった。反省している」と謝罪した。
陸上自衛隊目達原駐屯地(佐賀県吉野ケ里町)所属のAH64D戦闘ヘリコプター
が2018年2月に整備後に墜落した。
この事故がオスプレイの整備に影響を与えていると個人的に推測する。スバル車の検査問題が取り上げられているが、車は故障しても
簡単には大事故には繋がらない。飛行機やヘリコプターは浮力を失う、または、推進力に問題があれば、墜落してしまう。
オスプレイは高価な機体だ。墜落すれば損害賠償が大きいし、信用も失うであろう。オスプレイは最新の機体であり、これまでには
存在しないタイプで、軍事機密だからいろいろな情報は得られないであろう。ヘリコプターや飛行機の整備の実績はあるのだろうが、
整備の想像がつかない個所がオスプレイに存在し、困っているのであろう。
古城博隆
米空軍輸送機オスプレイ5機の横田基地(東京都)への正式配備が10月1日に迫る中、整備態勢への不安が浮上している。日米共通のオスプレイの整備拠点とした陸上自衛隊木更津駐屯地(千葉県)で実施されている米海兵隊機の定期整備が、1年7カ月たっても完了していないのだ。関係者は「整備の遅れは費用増や訓練頻度の低下につながる」と懸念する。
航空機は一定の飛行時間ごとの定期整備が必要で、米軍オスプレイは5年に1回程度とされる。2015年策定の日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の「共通装備品の修理・整備の基盤の強化」に沿って、防衛省は同駐屯地を共通の整備拠点に選んだ。
実際に整備しているのは自動車メーカーのスバル。航空宇宙部門が自衛隊の固定翼機やヘリの製造・修理で実績があり、米軍の入札で選ばれた。駐屯地内の格納庫で昨年2月から1機目の整備に着手。機体を分解し、腐食や損傷の修復、部品交換、塗装のやり直しなどを進めてきた。通常は3、4カ月で終えるが、今回は初整備のため7カ月を予定。だが1年7カ月が経過しても完了していない。今月、格納庫での整備は終えたが、試験飛行に至っていない状況だ。
防衛省によると、部品や専用工…
スバルの車は思った以上に問題が存在したわけだ。
いろいろなメーカーの車に乗って思った事は、乗った事がないメーカーの新車は買わない事。足として中古車を買って経験するのが一番。
中古なので耐久性や品質の違いを実感できる。それでも、最近はインターネット上にいろいろなメーカーの問題や特定の車種の問題が
書かれているサイトがあるので明らかに問題がある場合、車の状態に比べて安くないと買わない。買った後の修理、部品交換、やその工賃を
ゆとりを持って考えていないのなら、評判の良いメーカーや車種で色や数年古い車を買うほうがコスト重視であれば得になるからだ。
価格がかなり安ければ多少の不具合や運転に関する問題は我慢できる。頻繁に修理を経験した事があるので、購入前に購入した人達が
経験した問題を知っておく事は重要だと思う。国土交通省がどのような調査や基準を使おうが関係ない。購入者からの口コミ、相談、
故障の見積もり、不具合の疑問などを検索して調べるほうが、中古車の購入に関しては重要だ。
情報の入手が面倒だし、車に詳しくないから高くても新車が良いと言う知り合いがいる。お金で問題を片づけたい人は違う基準で判断
しているのだから判断が違うのは当然。
自己責任、個人の基準や価値観でいろいろな判断がある。
スバルは28日、自動車の性能を出荷前に確かめる検査での不正が、ブレーキやステアリング(ハンドル)をめぐって新たに見つかったと発表した。これまでの不正は排ガスや燃費で判明していた。車メーカーではさまざまな検査不正が相次ぐが、安全性能での不正発覚はスバルが初めて。
【写真】会見の冒頭、謝罪して頭を下げるスバルの中村知美社長(中央)=2018年9月28日午後6時1分、東京都渋谷区、山本壮一郎撮影
リコール(回収・無償修理)は現時点ではしない方針。安全性に支障がないか、国土交通省が今後の立ち入り検査で調べる。
先に発覚していた排ガスや燃費性能での測定データの改ざんを受け、スバルが委託した社外の弁護士らが調査。国交省にこの日、報告書を提出した。
報告書によると、新たな不正は、群馬製作所(群馬県太田市)が、ここで組み立てた全車を対象に行ってきた「全数検査」で見つかった。この製作所はスバルの国内唯一の完成車工場だ。
測定値が社内の規格を外れていたのに収まっているかのように測定方法を変えたり、測定をやり直さなかったりする不正が複数あった。
例えば、後輪のブレーキの制動力を確認するのに、ブレーキペダルだけを踏むべきところをハンドブレーキも引いていた。逆に、ハンドブレーキの制動力を確認する検査では、ブレーキペダルも踏んでいた。報告書は「タイヤの制動力を不当にかさ上げする行為」と指摘した。
ハンドルを切ってタイヤの動く範囲が社内の規格に満たない場合、車体やタイヤを手で押して規格内だと装った例も見つかった。
検査員への聞き取りではブレーキをめぐる不正は1997年からあった、との証言も出たが、測定値などの記録が残っていないため台数や時期の特定は困難、としている。
スバルの中村知美社長はこの日夕に記者会見し「信頼を損ね、ブランドを傷つけた。申し訳ない気持ちでいっぱいだ」と陳謝した。
スバルの車も乗ったけど、品質や耐久性で言えば、トヨタの車が他のメーカーと比べられないほど良かった。まあ、長期間及び長距離運転
なので違いがわかる。長距離運転を頻繁にしない、車が古くなる前に買い替える人は大きな違いに気づかないかもしれない。
使い方次第で大きな違いを体験できない場合は、個々が自己責任で個々の優先順位で判断して購入すればよいと思う。
SUBARU(スバル)が28日に公表した燃費・排ガスの不正検査に関する調査報告書は、同社のずさんな検査態勢を浮き彫りにした。中村知美社長は同日の記者会見で「不正は出し切った」と強調したが、無資格者による新車の検査が発覚した2017年10月以降、同社が「最終」と称して報告書を公表するのは今回で3度目だ。不正の連鎖を断ち切れるかは見通せない。
「昔から品質ナンバーワンでやってきた自負があったが、間違いなく信頼を損ねる結果となってしまった。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいだ」。中村社長は28日の会見で、苦渋の表情を浮かべた。
報告書は、安全性を担保するための検査を軽視する社内風土を次々に明らかにした。燃費データなどの測定では、屋内に設けた検査装置に車両を載せ、国が定めた速度などの基準に基づき試験を実施する。その試験中に検査員が居眠りして大幅に基準を逸脱したと見られるケースが判明したほか、一定に保たなければならない湿度を逸脱したり数値を書き換えたりしたケースもあった。1960年代に建てられた工場はすきま風が入り、空調設備も古かったため、基準値に調整するのが難しかったとみられる。
不正の原因については、検査員の業務量の多さや他部署への「そんたく」などを挙げ、安全性の確認が後回しになっていた実態が浮かび上がった。
スバルは再発防止策として、検査態勢や業務量の見直しなどを発表。老朽化した施設の整備など、今後5年間で1500億円の投資を実施する方針を説明した。
しかし、再発防止策の実効性には疑問符がつく。スバルは17年10月の無資格者による完成検査や18年3月の燃費・排ガスデータの改ざん、同6月の基準外検査データの有効化など、不正が発覚するたびに再発防止策などを盛り込んだ調査報告書を公表。そのたびに経営トップが会見で謝罪を繰り返してきた。
2度にわたる社内調査では不正の全容を洗い出せず、今回は外部の弁護士らに調査を委託した。今年6月に就任した中村社長は28日の会見で「今回の調査で現在把握しうる不適切行為は抽出できた」と述べたが、報告書は「課題に対する経営陣の認識やその改善に向けた関与が十分でなかった」と厳しく指摘しており、改革の道のりは平たんではない。
自動車メーカーによる燃費・排ガスの一連の不正では、スバルや日産自動車で問題が発覚。国交省は7月、他の自動車メーカー23社に同様の不正がないか調査を求め、8月にスズキ、マツダ、ヤマハの3社で不正が発覚した。アウディ、フォルクスワーゲン、ボルボの輸入業者3社については28日に結果が公表され、アウディで不正が発覚した。26日に新たな不正を報告したスズキを除き、調査結果が出そろった形だが、失墜した信頼の回復には時間がかかりそうだ。【松本尚也、川口雅浩、竹地広憲】
「赤信号、みんなで渡れば怖くない」の例として使えるかも?
SUBARU(スバル)は28日、6月に発覚した新車出荷時の燃費・排ガス検査の不正について、国土交通省に報告書を提出した。新たに、速度の基準を逸脱した時間を書き換えた事例が1685台で判明。検査室の温度や湿度の改ざん、ブレーキ性能など他の検査で行われたルール違反も明らかになった。
中村知美社長は国交省に報告書を提出した際、「顧客や社会に心配を掛け、大変反省している」と陳謝した。
不正はスバルの群馬製作所(群馬県太田市)で発覚。燃費や排ガスを検査する際、速度などが定められた条件を満たしていないにもかかわらず、再測定を行わなかった例が見つかった。
スバルでは昨年秋に新車の無資格検査が判明して以降、品質関連の不正が相次いで明るみに出ており、法令順守体制の強化が課題となっている。
台車の亀裂が生じた原因では、製造を担う外注先の企業の変更に伴って、加工方法の情報共有が不十分だったり、設計上の注意点が伝わらずに現場従業員が鋼材の削り込みの許容範囲を知らなかったりした不備を挙げた。」
外注先が変わった理由は何であったのだろう。コスト?コネやその他の理由で変わったのか?理由がないと外注先を変える必要はないのでは?
川崎重工業は28日、同社が製造した新幹線のぞみの台車に破断寸前の亀裂が見つかった問題を受け、再発防止策を発表した。台車の製造過程で鋼材を薄く削り過ぎていた原因について、加工方法の変更などの情報が製造現場で共有できていなかったためと説明。リスク管理態勢や部門間連携の強化を柱とした対策をまとめた。
現場従業員が削り込みの許容範囲知らず
金花芳則社長は同日、神戸市内で記者会見し、「多大なるご迷惑とご心配をおかけしたこと改めて深くおわび申し上げます」と謝罪。そのうえで、「過度な製造現場依存で品質管理に脆弱な点と、不具合を防止するリスク管理不足があった」と述べた。
台車の亀裂が生じた原因では、製造を担う外注先の企業の変更に伴って、加工方法の情報共有が不十分だったり、設計上の注意点が伝わらずに現場従業員が鋼材の削り込みの許容範囲を知らなかったりした不備を挙げた。
再発防止策では、設計上の注意点を書類に反映し、製造工程の変更を明確化して記載することを盛り込んだ。部門間連携に向けて組織を超えたチームでの議論なども行い、今年3月から導入した独自の品質管理技法を徹底するなどとしている。
台車のトラブルは昨年12月11日、博多発東京行きのぞみ34号で発生。運輸安全委員会が新幹線初の重大インシデントに認定した。
川崎重工は今年4月、外部有識者や同社役員などでつくる全社品質管理委員会を立ち上げ、原因究明をしていた。
2月には、金花社長が月額報酬の5割を3カ月返上することを発表。経営責任を明確化する事実上の更迭人事として、車両部門の責任者を務めた小河原誠取締役常務執行役員が5月、退任している。
全ては運しだい。運がない人は事故にあったり、事故に巻き込まれて死亡する事だってある。仕事も運がない人間は同じことをしても 報われない。正しい事をしても、上が融通が利かないと判断すれば、悪い評価を受ける。
人生そのものが川に流れている葉っぱのように流れに逆らえない事がある。しかし、今回は行政がどのような対応を取るか次第で 多少は変わるであろう。
国土交通省は28日、ドイツ高級車大手アウディの日本法人アウディジャパン(東京)から、燃費や排ガスの抜き取り検査で不適切なケースがあったと報告を受けたと発表した。
同様の不正検査はSUBARU(スバル)や日産自動車、スズキなどでも発覚しており、問題が拡大している。
同省によると、2014年7月~今年7月、燃費や排ガスに関する抜き取り検査をした37台で測定に失敗したのに、やり直さず有効として処理した。同期間に検査した692台の約5%に当たる。
同省が不適切な検査がないかを調べ、報告するよう求めていた。
アメリカらしい対応だと思う。
アマゾンは盗みを働いている配送ドライバーを捕まるために、偽の荷物を使っているとこの件を良く知る情報提供者は語った。
アマゾンは、同社内で「ダミー」パッケージと呼ばれる荷物をランダムに配送トラックに仕掛けている。ダミーパッケージには、偽ラベルが貼られ、しばしば中身は空。
重さを持たせるために「何かを入れておくこともある」と同社の元ロジスティクス・マネージャーはBusiness Insiderに語った。この人物は、会社からの報復を恐れて匿名を希望し、シアトルにあるアマゾン本社からこの施策の指示が届いたと語った。
「これは、いわば罠。ドライバーの正直さをチェックすることが目的」と同氏。
この件についてアマゾンは、「確認と監査は全体的な品質管理プログラムの一環で、ランダムに実施している」と述べた。
関係者によると、以下のような手順で行われる。
配達中、ドライバーは自分が運ぶパッケージのラベルをすべてスキャンする。ダミーパッケージの偽ラベルをスキャンすると、エラーメッセージが表示される。
この場合、ドライバーはこの問題を上司に電話して報告するか、あるいは、ダミーパッケージを積んだまま戻り、勤務時間の最後にアマゾンの配送センターに戻す。
しかし、ドライバーは仕組み上、ダミーパッケージを盗むこともできる。エラーメッセージは、アマゾンのシステム上でパッケージが検知されていないことを意味する。つまり、パッケージが行方不明になっても、気づかれない可能性がある。
「パッケージを戻せば、無実。戻さなければ、悪人」とアマゾンの荷物の配送を請け負うDeliverOLの元マネージャー、シド・シャー(Sid Shah)氏は語った。
ダミーパッケージはあくまでも、盗難問題に対するアマゾンの施策の1つに過ぎない。この問題は同社をはじめ、すべての小売業者にとって大きな悩みの種となっている。
全米小売業協会(National Retail Federation)によると、シュリンケージ(盗難、エラー、不正による商品ロスを表す業界用語)の被害額は2017年、470億ドル(約5兆3000億円)近くにのぼった。
アマゾンは最近、ユーザーの車や自宅の中まで荷物を届けるサービスを開始した。どちらのサービスも配達の選択肢を増やしてユーザーの利便性を向上させることと同様に、盗難率を減らすことが目的。
また、2016年のブルームバーグの報道によると、同社は商品の盗難を未然に防ぐために、配送センターの作業員に、同僚が盗みで捕まる瞬間の動画を見せている。
アマゾンは毎年、どれくらいの荷物が盗まれているかを明らかにしていない。2017年、同社が世界中のプライム会員に配送した荷物の数は50億個を超える。
梱包会社Shorrが2017年に行った調査では、31%の回答者が荷物を盗んだことがあると回答した。
アマゾンの元ロジスティクス・マネージャーによると、「ダミー」パッケージを使った罠は、窃盗犯を捕まえる効果があった。
「我々は、誠実ではない人たちを捕まえた」と同氏は語った。
[原文:Amazon plants fake packages in delivery trucks as part of an undercover ploy to 'trap' drivers who are stealing]
(翻訳:Yuta Machida、編集:増田隆幸)
コスト削減のために基準をぎりぎりで満たすように計画し、設計したため、安全サイドのゆとりがなく、少しの誤差でも基準を満たさないような
車になっているのではないのか?
基準を満たさない車は、検査が間違っていない限り、何度、検査しても検査に通るわけがない。個人的な推測であるが、事実を言えないから
疑問を抱かせる言い訳しか出来ないのでは??
スズキもデータ改善、疲弊深刻な生産現場 (1/3)
(2/3)
(3/3) 09/27/18(東洋経済 ONLINE)
「新たな事案が判明し、重く受け止めている。心よりお詫び申し上げます」。9月26日夜、スズキが開いた記者会見で、鈴木俊宏社長は深々と頭を下げた。
この記事の写真を見る
スズキは新車の出荷前の燃費・排ガス検査不正問題に関して、新たな不正が判明したと発表した。不正が見つかったのは、新車の出荷前に燃費や排ガスなどを100台に1台の割合で調べる抜き取り検査という工程だ。
スズキは8月9日、この工程で検査条件を逸脱したデータを有効としていたと発表し、再発防止を誓ったばかりだったが、今回の発表で対象台数が増えたほか、新たに燃費測定値などを不正に書き換えていたことも判明。軽自動車などの4輪車だけでなくオートバイでも不正検査が発覚。再び社長が謝罪する事態に追い込まれた。
■国からの指摘がきっかけ
不正な書き換えが行われていたのは、スズキの湖西、相良、磐田の3工場で2009年5月~今年7月に検査をして測定データが残っていた自動車1万8733台のうち、全体の14.6%に当たる合計2737台。排ガスや燃費、温度・湿度、大気圧など何らかの書き換えがされていることが判明した。
8月に問題を発表した際には、「書き換えはない」と明言していた鈴木社長だが、立ち入り検査を行った国土交通省から指摘を受け、社内調査を進めていた。鈴木社長は「社内調査が極めて不十分だった」と陳謝した。
日産自動車やSUBARUでもデータの書き換えが行われていたが、いずれも900台規模。スズキの書き換えは3倍近い規模となる。もっともスズキによると、意図を持った書き換えと、そうでない書き換えがあると認識しており、現時点で2名の検査員が、測定結果の燃費値が社内の管理平均値を下回った場合に二酸化炭素(CO2)の排出量を小さくする意図的な書き換えを行っていたことがわかっている。
一方で、分析器のエラーなどにより排ガス値が異常であった場合に手入力で書き換えるなど検査員が書き換えとの認識がないままに処理していたものもあり、今後、社外の専門家による調査・検証により全容の解明を図っていく方針だ。
検査条件を逸脱したデータを有効としていた不正の対象台数は、8月の発表から482台増えて6883台となり、調査対象車種32車種のうち、31車種でデータ不正が発覚。いずれのケースでも、計測器の上で車を走らせて燃費・排ガス試験を行う際に規定された速度から外れている時間が、国が定める許容範囲を超えていた。自動車メーカーが「トレースエラー」と呼ぶ事象だが、当然、再測定をしなければならない。
対象台数が増えたのは、8月の報告後に行われた国土交通省による立ち入り検査で指摘を受け、スズキが排ガス・燃費抜き取り検査に従事する検査員に追加の聞き取り調査を行った結果だ。工場内のサーバーやハードディスクなどの記録媒体を調査したところ、報告書に記載した調査期間以前のデータも残っていることがわかって修正した。
■検査員への過度な負担が背景
新たな聞き取り調査では、これまで把握していなかった声も次々上がった。「業務量が多く再測定を行う余裕が無かった」、「再測定を実施すると仕事が増えて皆に迷惑をかけるという雰囲気があった」、「抜き取り検査計画をノルマと考えた」などの証言だ。総じて検査員が業務量を多いと感じ、精神的負担になっていたことが伺える。こうした検査員の過度な負担が不正の一因になったことは否めない。
スズキは業務量の増加に対応するため、検査員を増員したり、担当管理職を配置したりするなどの対策を講じているという。スズキは2016年にも燃費データ測定で不正が発覚しており、そのときも鈴木社長は再発防止を誓っていたはずだ。
今回の会見では「当時と企業風土が変わっていないのではないか」との質問も出たが、鈴木社長は「企業風土が変わっていないという指摘はそう映るかもしれない。だが、すべての部門でそうなっているかというと違う。部門ごとに取り組みに温度差があった。もう一回しっかりと見直していく。私がリーダーシップを持ってやっていく」と力を込めた。
一連の完成車検査不正の発端となった日産は9月26日、燃費・排ガス検査の不正に関する調査の最終報告書を国土交通省に提出した。今年7月に明らかにしていた燃費・排ガス検査の不正だけでなく、別の検査でも新たに不正が発覚。
日産の規範意識の欠如が改めて露呈した格好だが、会見した山内康裕チーフ・コンペティティブ・オフィサー(CCO)は「これで膿は出し切った」と強調。西川廣人社長の記者会見や関係者の処分公表もなく、一連の不正問題に対して幕引きを図りたい日産側の思惑が透けて見えた。
報告書によると、燃費・排ガス検査の測定値書き換えなどに加え、別の抜き取り検査でも試験を実施していなかったり、測定値を改ざんしたりするなど複数の不正が判明した。国内6工場のうち4工場で、少なくとも253台あった。ブレーキ液残量警告灯の検査を3工場で未実施だったほか、騒音試験の風速条件を書き換えるなどしていた。
■背景に過度のコスト削減追求
日産は報告書の中で、抜き取り検査における不正が相次いだ原因や背景として、完成検査員の人員不足、検査員への教育不足、不十分な設備、計画通りの生産出荷を優先することによる完成検査軽視の風潮など、10項目を挙げた。これらの根底には日産による過度なコスト削減の追求がある。
法律事務所が作成した報告書でも「効率性向上やコスト削減に力点を置くあまり、本来であれば切り捨ててはいけないものまで切り捨てた」と日産の経営姿勢を批判。記者会見で山内CCOも「(コストと品質管理の)優先順位が正しく判断されていなかったと言える」と認めざるをえなかった。
コスト偏重の一例に、抜き取り検査で不具合が見つかった場合に車両の検証や設計部門との調整などをする技術員が現場からいなくなったことがある。かつては完成車の組み立て工場ごとに配置されていたが、工場の人件費を削減するため技術員の所属先を本社部門に変更。人員補充もされず、定年退職などで徐々に減少していった。その結果、工場と本社間のコミュニケーションが減り、検査の測定値が基準から外れた場合の技術的なサポートも得られず、検査員が不正に手を染める遠因になった。
法律事務所が作成した報告書は「2000年代以降、排ガス検査の測定値書き換えが常態化した」と指摘しており、カルロス・ゴーン現会長が主導した日産の再建時期と重なるのは偶然ではない。新車の生産工場を決める際に国内外の工場で生産コストや品質などをコンペで競わせる手法は現在も続いており、人件費の面で不利な国内工場に対してプレッシャーを与えた可能性も考えられる。
「良い商品を出すためにコストダウンは不可欠」(山内CCO)というように、仕様や機能を高め、不断のコスト低減努力をする姿勢はメーカーとして必要だろう。ただ、ルールを逸脱したものづくりは到底認められるものではない。日本車メーカーで相次ぐ不正は、経営の優先順位は何かという重大な問いを投げかけている。同様のデータ書き換え問題が発覚したスバルは、明日にも最終報告書を国交省に提出する予定だ。その内容にも注目が集まる。
冨岡 耕 :東洋経済 記者/岸本 桂司 :東洋経済 記者
10月から 「年間通じた授業開講の義務づけ」などが柱
外国人留学生の増加とともに増えている「日本語学校」について、法務省は設置要件を定めた告示基準を来月から厳格化する。年間を通じた授業開講を義務づけることなどが柱。教育の質の低下を抑制する▽アルバイト目的などで長期間休めるような授業日程を組めないようにする--などの目的がある。【和田武士】
日本学生支援機構などによると、外国人留学生は昨年5月時点で、大学などの高等教育機関約18万8000人▽日本語学校約7万8000人--で計約26万7000人。5年間で10万人以上増加し、日本語学校に限ると約3倍となる。日本語学校自体も増え続け、現在710校を数える。
日本語学校は大学や専門学校などと違い、法務省が定める授業時間や教員数などの要件を満たせば、株式会社や個人などでも開設できる。現行の告示基準は授業時間について、1単位を「45分を下回らない」とした上で、1週間で20単位以上▽1年間で760単位以上--などと規定している。
しかし、一部の日本語学校では短期間で年間の授業時間を確保し、残りを長期休業期間にしようとする動きが顕在化。留学生の就労は原則として週28時間までと定められているが、長期休業中は1日8時間まで可能になるため、アルバイトに充てる時間をより多くできる。一部の日本語学校はこうした授業日程を強調し就労目的の留学生を呼び込もうとしたとみられる。
そこで法務省は、告示基準を一部改正。年間の授業が35週にわたるよう義務づける規定を新設し、10月以降に開設される学校に適用する(既存の学校には2020年10月から適用)。また、管理体制強化のため、1人が複数の日本語学校の校長を兼務する場合、新設・既存ともに20年10月以降は副校長を置くことも義務づけた。同省の担当者は「日本語学習を目的とした本来の姿に戻したい」と話している。
政府は建設や介護など人手不足が深刻な業種を想定し、外国人労働者の受け入れ拡大を図る法改正を検討している。これとは別に外国人留学生について、日本の4年制大学の卒業生▽「クールジャパン戦略」の関連分野(アニメや漫画、日本料理、ゲームなど)の専門学校の卒業生--などが国内で就職しやすくなるよう在留資格の範囲を広げる方針。こうした中、今回の日本語学校の告示基準の改正は留学生全体の「質」を確保する狙いもあるとみられる。
「アルバイトで稼げる」などとアピールする学校も
留学生の増加を背景に各地で増え続けている日本語学校。法務省関係者によると、就労目的の留学生を念頭に「アルバイトで稼げる」などとアピールする学校も存在する。中には、留学生に法定時間を超える不法就労をさせたとして、日本語学校運営者が警察に逮捕される事件も起きている。
栃木県足利市の日本語学校理事長で、群馬県館林市の人材派遣会社社長は2016年11月、入管法違反(不法就労助長)容疑で栃木・群馬両県警に逮捕された。ベトナム人留学生2人を倉庫に作業員として派遣し、法定上限の週28時間を超えて就労させたとされ、2人も同法違反(資格外活動)容疑で逮捕された。
17年5月には、京都市の日本語学校に通っていたスリランカ人留学生2人に週28時間を超えて違法に長時間労働をさせたとして、学校を運営する建物管理会社の代表取締役ら2人が京都府警に入管法違反(不法就労助長)容疑で逮捕された。
一方、留学生の不法残留者数をみると、15年から増加傾向にあり、今年1月1日時点で4100人。国籍・地域別ではベトナムが急増しているという。また、新たに不法残留となった留学生を所属している教育機関別にみると、日本語学校が最多の51%(16年)だった。
「同校は取材に『府の調査に協力し、指導に基づいて改善したい』と答えた。
府によると、同校は2年制。留学生対象は3学科のうち1学科のみで、主に日本人を対象とした学校として認可を受け、2015年4月に開校した。しかし初年度に入学した107人はいずれも留学生で、今年5月時点での在校生584人のうち、559人がベトナム人や中国人などの留学生で占められていた。」
観光ガイドや通訳を育成する「日中文化芸術専門学校」はかなりおかしいと思う。「府の調査に協力し、指導に基づいて改善したい」と言っても、
かなりの改善が見られなければ承認を取り消すべきだ。
「定員418人を大幅に上回る559人が在籍」は予測を間違えたとか、試験があるのなら合格者を出しすぎたとか、納得の行くレベルの言い訳では
ない。悪意、又は、金もうけしか感じられない。こんな学校は要らない。
観光ガイドや通訳を育成する「日中文化芸術専門学校」(大阪市天王寺区)が定員超過で学生を受け入れたため、昨年度から今年度にかけてベトナム人などの留学生計約360人が退学になっていたことが大阪府への取材で分かった。同校は府に「学生の進路変更や学業不振」と説明したが、府は学校の対応や在籍管理に問題がなかったか実態を調べる。
府によると、同校には昨年5月時点で、定員418人を大幅に上回る559人が在籍しており、同10月に府私学課が定員超過の是正を求めた。大阪入国管理局も同校に対し、在留資格の更新申請を認めないこともあるとして、適正な在籍管理をするよう指導。すると昨年度に194人、今年4~8月に165人が退学した。退学後に在留資格を更新できずに帰国した学生も多数おり、ベトナム人7人は月内にも学校側に慰謝料などを求めて大阪地裁に提訴するという。
同校は取材に「府の調査に協力し、指導に基づいて改善したい」と答えた。
府によると、同校は2年制。留学生対象は3学科のうち1学科のみで、主に日本人を対象とした学校として認可を受け、2015年4月に開校した。しかし初年度に入学した107人はいずれも留学生で、今年5月時点での在校生584人のうち、559人がベトナム人や中国人などの留学生で占められていた。【藤顕一郎】
スズキの車も何十年と乗った事がない。スズキの車を買う事はないと思うのでさらなる不正が発覚しても関係ない。
「検査員に対するスズキの聞き取り調査で、『業務量が多く再測定を行う余裕がなかった』『再測定をすると車両の納期が遅れ営業に迷惑をかけると考えた』などの証言も確認された。」
納期が遅れるほど何度も測定を行わないと検査に合格する数値が出来ない車が多かったと言う事なのか?検査に通る車の方が少なかったと言う事?
スズキが出荷前の自動車で排ガスなどの検査を不適切に行っていた問題で、同社は26日、測定値の改ざんもしていたと明らかにした。
今年8月に問題を発表した際は否定していたが、実際は2009年5月~今年7月に国内三つの工場で、計2737台の排ガスや燃費、温度などの測定値が書き換えられていた。故意に不正が行われたケースもあったとされるが、詳細は究明できていないという。
鈴木俊宏社長は26日、東京都内で記者会見を開き「ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ない」と謝罪。8月の発表から問題が拡大したことについて「調査のやり方が不十分だったと反省している」と述べた。辞任は否定し、不正についても「現時点で組織的だとは思っていない」と主張した。
国土交通省は同日、自動車局長名で指示文書を出し、道路運送車両法に基づき、スズキに徹底調査と速やかな報告を求めた。
スズキによると、2人の検査員が、二酸化炭素の排出量を実際より少なく書き換えた不正があることが判明した。温度計や湿度計の測定で異常値が出た場合などでも書き換えが行われていた。
また、排ガスの抜き取り検査で有害物質量の測定に失敗したのに、やり直しをせずに有効としたケースが6401台あったと8月に発表していたが、新たなデータや調査対象期間の拡大によって、不適切な例は計6883台に増加。調査対象の32車種中、31車種で検査に問題があった。
検査員に対するスズキの聞き取り調査で、「業務量が多く再測定を行う余裕がなかった」「再測定をすると車両の納期が遅れ営業に迷惑をかけると考えた」などの証言も確認された。
軽乗用車などの四輪車だけでなく、オートバイ2台でも不適切な検査が行われていたことも明らかになった。
スズキは26日、完成車の燃費測定などに関して新たな不正が見つかったと発表した。新たに二酸化炭素(CO2)の排出量を意図的に小さくするなどした不正な改竄(かいざん)が2737台、32車種で確認された。スズキは現場の検査員の数に対し業務上の負担が大きかったと釈明、再発防止策を徹底する方針だ。
国土交通省が燃費測定に関する不正を8月に報告していたスズキを改めて立ち入り検査した結果、新たな不正が判明した。
スズキは、これまで静岡県内3工場で、車速や走行状態など燃費測定に必要なデータを基に調査していたが、新たに平成21年5月以降のデータが確認できた。測定環境の条件を満たさない無効なデータを有効と判断していた台数が482台増え計6883台に達した。現時点で不正な書き換えには2人の検査員が関与していたことも判明。風通しの良い組織に見直す必要性も浮き彫りにした。
26日に東京都内で記者会見したスズキの鈴木俊宏社長は謝罪した後、再発防止に向けて全容解明に努める姿勢を強調。「社外の専門家による客観的・中立的な調査と検証を進めて会社を直していくことが経営責任だ」と述べ、辞任を否定した。
一度だけ日産の車に乗った事がある。他のメーカーでは経験しない問題を経験したので、もう日産の車を買う事はないと思うので さらなる不正が発覚しても関係ない。
「日産自動車」が燃費や排ガスの検査データを改ざんしていた問題で、社内調査の報告書を国土交通省に提出しました。
報告書では、今回の燃費不正以外にブレーキ液や騒音の測定など新たに11の事案で、検査自体を行わない不正やデータの改ざんなどが確認されたとしています。また、不正の背景として、「現場の管理者や人員が不足していた」と分析し、「コストを重視して現場の把握が不十分だった」などと指摘しています。
一度だけ日産の車に乗った事がある。他のメーカーでは経験しない問題を経験したので、もう日産の車を買う事はないと思うので さらなる不正が発覚しても関係ない。
「日産自動車」が燃費や排ガスの検査データを改ざんしていた問題で、社内調査の報告書を国土交通省に提出しました。
報告書では、今回の燃費不正以外にブレーキ液や騒音の測定など新たに11の事案で、検査自体を行わない不正やデータの改ざんなどが確認されたとしています。また、不正の背景として、「現場の管理者や人員が不足していた」と分析し、「コストを重視して現場の把握が不十分だった」などと指摘しています。
しわ取りなどに使われる未承認医薬品「ニューロノックス」を不正に輸入・販売したとして、大阪府警は26日、大阪市淀川区の輸入代行会社「エスエムディグローバル」の社長(47)ら5人を医薬品医療機器法違反と有印私文書偽造・同行使の疑いで書類送検した。社長は約10年前から未承認医薬品の販売をしていたことを認め、「販売実績を伸ばしたかった」と供述しているという。
法人としての同社も医薬品医療機器法違反の疑いで書類送検した。容疑は昨年8月、知人の医師免許証のコピーを無断で使うなどして輸入に必要な書類を偽造。同11月、韓国から輸入したニューロノックス10箱を東京都目黒区のクリニックに販売したとしている。
府警によると、同社はニューロノックスを含む医薬品などを計39カ所の医療機関に販売していた。未承認医薬品は国内販売が禁止されているが、医師が個人輸入して治療に使うことはできる。府警は同社が医師の輸入を偽装して販売していたとみている。【宮川佐知子】
「しわ取りなどの美容目的で使われる国内未承認の医薬品『ニューロノックス』を不正に輸入・販売したとして、厚生労働省が大阪市淀川区の輸入代行会社を医薬品医療機器法違反の疑いで大阪府警に刑事告発していたことが、捜査関係者への取材で明らかになった。知人の医師免許証のコピーを無断で使って輸入していた疑いもあり、府警は同社を家宅捜索するなどして捜査している。」
悪質であると判明した場合、かなり高額な罰金を科すか、会社を解体出来るように法改正をするべきだと思う。
しわ取りなどの美容目的で使われる国内未承認の医薬品「ニューロノックス」を不正に輸入・販売したとして、厚生労働省が大阪市淀川区の輸入代行会社を医薬品医療機器法違反の疑いで大阪府警に刑事告発していたことが、捜査関係者への取材で明らかになった。知人の医師免許証のコピーを無断で使って輸入していた疑いもあり、府警は同社を家宅捜索するなどして捜査している。
健康被害を防ぐため、同法は国が安全性を確認していない未承認医薬品の国内販売を禁じている。医師が個人輸入して治療に使うことはできるが、医師免許証のコピーなどを厚労省に提出して許可を得る必要があり、譲渡や転売はできない。
捜査関係者などによると、この会社は2017年、韓国製のニューロノックスを韓国から輸入し、美容クリニックに販売した疑いが持たれている。
輸入の際、知人の医師免許証のコピーを無断で使用し、輸入手続きに必要な書類として厚労省に提出していた。販売先は、医師免許証を悪用された医師とは関係のないクリニックだった。府警は、同社が医師の個人輸入を装い、販売目的で輸入したとみている。
同社は1990年設立。ホームページによると、美容医療機器の販売や美容クリニックの開業支援などを手がけ、こうした未承認医薬品については、医師の個人輸入に限定して輸入手続きを代行すると記載している。
同社は毎日新聞の取材に対し、弁護士を通じて「刑事事件に発展する可能性があるので答えられない」としている。【宮川佐知子】
【ことば】ニューロノックス
ボツリヌス菌が作り出すたんぱく質(毒素)を成分とする韓国製の薬剤。筋肉を緩ませる効果があり、目尻や眉間(みけん)などに注射し、しわを取る目的で使われることが多い。韓国では認められているが、日本では未承認。同様の効果がある米国製の「ボトックスビスタ」は日本でも認可され、広く知られている。ただ毒素を含むため、保存や廃棄などの際は厳重に管理する必要がある。
◇基準あいまい、横行 買う側の医師にも責任
未承認医薬品が不正に輸入・販売されたとみられる今回の事件。ある業界関係者は「輸入制度がビジネス目的で悪用され、未承認医薬品が全国にかなり出回っている」と指摘する。
厚生労働省によると、医師などの医療従事者が患者の治療に緊急性があると判断し、国内に代替品がない場合などに限って輸入が認められる。ただ実際に緊急性があるか、代替品がないかを判断する基準はあいまいだ。厚労省の担当者は「医師が必要だと書類に記載すれば実際は拒否できない」と明かす。
同省が2016年度、医師らに対して医薬品の個人輸入を認めたのは計8万1694品目。うち、美容目的が最多の1万8178品目(22.3%)で、アレルギー・免疫治療(6.1%)やがん治療(5.5%)を上回った。美容関係では、ニューロノックスを含むボツリヌス毒素が3263品目あった。
医療関係者によると、美容関係の未承認医薬品は承認薬より安価な場合が多いが、仕入れルートが不透明になり、保管時の安全性が保証されない問題もある。関係者は「コスト削減目的で安全がおろそかになれば問題だ。自ら申請せずに買う側の医師も、不正に流通した薬だということを知っているはずで責任がある」と指摘した。【宮川佐知子】
性的少数者(LGBTなど)の価値観は理解できないし、理解したいとも思わないが、新潮社の月刊誌「新潮45」の対応はかなり悪かったと思う。
また、その後の対応も悪いと思う。
新潮社が今後、今回の休刊にきっかけに急速に衰退しても個人的にはどうでも良い事。
自民党・杉田水脈衆院議員の意見は偏っていると思うし、本当に彼女が発言や思想に信念を持っているのなら、逃げずに大きな声で発言し続ける
べきだと思う。そして、その結果、選挙で落選しても後悔するべきではないと思う。
性的少数者(LGBTなど)への差別的な表現について批判を受けていた月刊誌「新潮45」が25日、最新号の発売からわずか1週間、また佐藤隆信社長によるコメント発表から4日で休刊に追い込まれた。回収や続刊号での謝罪などを飛び越えた突然の決断の背景には、同社の予想を超えた批判の広がりがある。
出版不況を背景に「右傾化路線」を取る出版物は増加傾向にあり、「新潮45」も反リベラル色を強めてきた。だが、保守系の雑誌だけで経営している出版社と異なり、文芸が中軸の新潮社がマイノリティーを蔑視しているととれる極端な特集を組んだことの波紋は大きかった。経営面への影響も懸念され、同社は迅速な処理をせざるを得なかった。
ノンフィクション作家で同誌に多数の作品を発表してきた石井光太さんは「総合月刊誌が生き残るためには、ある程度偏った固定層の読者を確保する必要がある。そうでなければ、経営的に雑誌自体が立ちゆかない。『新潮45』はノンフィクションを載せる数少ない老舗月刊誌。そうした苦渋の中、バランスを保って刊行してきたが、今回はそれを崩してしまった」とみる。
過度に偏らない編集が可能なのか。石井さんは「新潮社だけでなく、出版界全体の課題」と話している。また出版ニュース社の清田義昭代表は「文芸出版社から始まった新潮社は、もともと政治とは一定の距離を置いていた。だが、経営的に厳しいところから、話題になるような右傾化した特集を選んだのではないか」と指摘。その上で「今回の『休刊』は、ヘイト的な表現を許すような世の中の風潮ではなくなったことを示している。LGBTなどマイノリティーへの差別に対する人々の意識の高まりを感じる」と話した。
記事の内容についての批判を受け、雑誌が廃刊に至った例は1995年、ホロコーストを否認する特集を組み国内外の批判を受けた月刊誌「マルコポーロ」(文芸春秋)がある。【大原一城、最上聡】
◇出版社の責任を放棄
特集に寄稿した教育研究者、藤岡信勝・元東京大教授の話 新潮社の声明には特集に「常識を逸脱した偏見」があったとしているが、7人の筆者のうち誰のどの部分が該当するのか明らかにしないのは卑劣だ。また圧力をかければ、雑誌の一つくらい吹っ飛ぶ、という前例を作ってしまった。言論の自由を守るべき出版社の責任を放棄している。
◇論戦の場失い損失
過去に「新潮45」に連載を持っていた評論家の武田徹・専修大教授の話 今回の企画が弱い立場の人たちを傷つけるグロテスクな言論であったことは認めざるを得ない。雑誌ジャーナリズムは、人間や社会の醜い部分をあえて見せ、議論を巻き起こすことで存在価値を示す傾向があったが、徐々に節度を見失った面があったのだろう。とはいえ、言論を戦わせる舞台としての雑誌の存在までなくした損失は大きい。批判する人たちは、同誌に反論の場を用意するよう求めるなど、慎重な対応があってもよかった。議論はまさにこれからなのに残念だ。
◇圧力強まる契機に
近現代史研究者、辻田真佐憲さんの話 いきなり休刊という対応は極端だ。次号で編集長の見解を示したり、LGBTの問題に理解のある人物に寄稿を求めるなど多様な意見を紹介したり、言論で対応すべきだった。杉田(水脈)議員も何の反論もしていない。今回の件は言論弾圧ではないが、小川(栄太郎)氏らを支持する人々には、そう主張する口実を与えることになる。「何か問題があったら即休刊」なら、今後リベラル系の雑誌が問題を起こした時も、圧力が強まる結果になるだろう。
一番悪いのはバスの運行会社「イーエスピー」。しかし問題のある会社を監視及び監督できなかった行政にも責任はあると思う。
個人的な経験から言えば、悪質な会社は平気で嘘を付く。問題のある体質や対応を見逃す、又は、放置する行政にも責任はある。
悪質な会社にとっては権力を持つ行政しか怖いものはない。一般のお客はお客のうちの一人でたいした存在でないと思っている。
苦情を言っても行政がこちらが期待する対応や取締りを行うとは限らない。不満はたくさんあるが、長野県軽井沢町のスキーバス事故の
ように家族や親族が死亡したわけではないので怒りは感じるが、かなりの時間を費やすほどの行動を取ろうとは思っていない。
大きな損害や家族を失った人達には行政に適切な調査、処分そして法改正を要求する権利があるし、多くの人達が要求する事を
容認すると思う。だから、行政に厳しい対応や処分を強く働きかけるべきだし、働きかけるのは当然だと思う
おととし、15人が死亡した長野県軽井沢町のスキーバス事故の遺族が12月にも損害賠償を求めて訴訟を起こすことが分かりました。
大学生ら15人が死亡したスキーバス事故の遺族会「サクラソウの会」は22日に都内で会合を開き、12月半ばにバスの運行会社「イーエスピー」などを相手に損害賠償を求めて提訴する方針を固めました。請求額やイーエスピー以外の相手方などは今後、詰めるということです。
サクラソウの会・田原義則代表:「再発防止策が出てますけれども、まだ完結しているわけではありません。どこに(事故の)責任があったのか」
田原さんは運行会社の社長らの処分が出ていないことについて、「早く起訴してもらい、刑事裁判で責任の所在を明確にしたうえで提訴したい」と話しました。
自業自得!
シェアハウスなど不動産投資向け融資で多数の不正があったスルガ銀行(静岡県沼津市)の創業一族が、関係会社を通じて保有する同行株を売却する方針であることが、20日わかった。創業家出身の岡野光喜氏は会長兼CEO(最高経営責任者)を7日付で引責辞任。創業家関係会社への不透明な融資も指摘され、一族が会社から完全に身を引き、早期再建を進める狙いがあるとみられる。
スルガ銀は1895年に岡野氏の曽祖父が設立し、創業一族が実権を握ってきた。有価証券報告書によると、創業一族の関係会社や団体が大株主として計15%超の株式を保有する。
シェアハウス問題を調べたスルガ銀の第三者委員会は調査報告書で岡野氏の経営責任を厳しく指摘。金融庁は立ち入り検査で創業家関係会社への不透明な融資を問題視した。業務の一部停止を含む厳しい行政処分の可能性があり、創業家は名実ともに経営から身を引かざるを得なくなった。(山口博敬)
仮想通貨交換サイト「Zaif(ザイフ)」を運営するテックビューロ(大阪市)は20日、同社のシステムが不正アクセスされ、ビットコインなど取り扱う3種類の仮想通貨計67億円相当が外部に流出したと発表した。このうち顧客資産は約45億円で、同社は全額を返還する方針。入出金等のサービスは停止しており、捜査機関に被害を届けた。
金融庁は3度目の業務改善命令などの行政処分を視野に調査を始めた。同社は「bitFlyer(ビットフライヤー)」(東京)などと同様、金融庁に登録を済ませた交換業者の1社だが経営管理態勢の不備などを指摘され、既に2度の業務改善命令を受けている。
牧師は懺悔すれば許されるのか?
東京の聖路加国際病院で心のケアを担当する牧師の男が、女性に対する強制わいせつの疑いで警視庁から書類送検された。
聖路加国際病院の40代の牧師の男は2017年5月、病院内にある牧師の控室で、治療にともない、心のケアを受けていた女性の胸を触るなどした疑いで書類送検された。
男は調べに対し、「胸は触りました」と供述しているという。
FNN
週刊文春に『「癒着アナと書いたわね」宮嶋泰子憤激 富川・小川アナ呆然』という記事が載りました。
これは日本体操協会の幹部である塚原夫婦が宮川紗江選手にパワハラで告発された問題で、テレビ朝日の宮嶋泰子さんが塚原夫婦を報道ステーションで擁護して、司会の富川アナと小川アナを呆然とさせたってお話です。
宮嶋さんは周りに速見元コーチは最悪なやつだとテレビ朝日内で吹聴して回っているようです。宮嶋さん63歳なんですね。もっと若いと思っていた。2015年に退社してテレビ朝日とは嘱託契約を結んでいるそうです。
宮嶋さんはアスリートや競技団体に食い込む力はあるけども、バランスを欠くケースも目に付くそうです。でも、スクープを持ってくるからスタッフも文句言えないのだとか。
実は散々塚原夫婦をかばっていた宮嶋さんですが、どうやら塚原夫婦のパワハラを認識していたというのです。なぜなら、音声データーの完全版を体操関係者から入手しているはずだからだというのですね。
その音声データーってのは何かというと、塚原夫婦に宮川選手が7月15日に面談を受けたのですが、その時のやり取りを録音した音声データーを塚原千恵子氏はテレビ局に提出していたのです。それは一部抜粋したものだったのですが、宮嶋さんだけは完全なものを入手していたはずだというのです。そこにはパワハラされていると分かる会話も含まれていたらしいのです。
そこで文春は宮嶋さんに直撃します。宮嶋さんは前に文春に「癒着アナ」と書かれていたことを根に持っているようです。
文春に最初は嫌味を言っていた宮嶋さんですが、音声データーの話を持ち出されると都合が悪いのか、私は関係無いと言い出し、広報を通さないとコメントできないと言って逃げた。
さすがは宮嶋さんテレビ朝日出身、自身に不都合な事実は知っていても公表しないんですね。
非鉄大手・三菱マテリアル(本社・東京)の子会社などで検査データが改ざんされていた事件で、東京地検特捜部は12日、法人としての子会社3社を不正競争防止法違反(虚偽表示)で東京簡裁に起訴した。このうち2社については前社長2人を同法違反で在宅起訴した。
特捜部が起訴したのは、三菱マテリアルの子会社の「三菱電線工業」(東京)▽「ダイヤメット」(新潟)▽「三菱アルミニウム」(東京)。また、個人で起訴されたのは三菱電線工業の村田博昭前社長(61)とダイヤメットの安竹睦実前社長(60)。
三菱マテリアルは昨年11月以降、子会社が自動車や航空機用に出荷するゴムや銅製品の検査データを顧客の要求などに合っていなかったのに、適合するよう改ざんしていたと公表。不正は、起訴された3社のほか、子会社の三菱伸銅(同)と、三菱アルミニウムの子会社・立花金属工業(大阪)でも行われていた。不正品の出荷先は延べ841社に上る。
関係者によると、特捜部は7月、これらの会社や、関係先として本体の三菱マテリアルを同法違反容疑で捜索。担当者らから任意で事情聴取するなどして捜査を進めていた。
同様のデータ改ざん問題で特捜部は7月、法人としての神戸製鋼所を不正競争防止法違反(虚偽表示)で起訴しており、大手メーカーが相次いで刑事責任を追及される事態となった。【巽賢司、遠山和宏、金寿英】
ドラッグと同じで、不正や違反に慣れてしまうと常識が麻痺してしまう、又は、止める事が出来なくなると言う事であろう。
融資で不正が横行したスルガ銀行(静岡県沼津市)で、従来は比較的低リスクの「住宅ローン」とされていた融資に、よりリスクがあるとされる不動産投資向けが含まれていたことがわかった。同行の第三者委員会の調査では、シェアハウスなど不動産投資向けは融資全体の3分の2近くを占め、多くで不正があったことが判明しており、今後焦げ付きで損失が膨らむ可能性がある。
スルガ銀が今年2月に公表した2017年4~12月期決算では、融資残高3・3兆円のうち、住宅ローンが2・1兆円、個人向け有担保ローンが6400億円だった。5月公表の18年3月期決算では、融資残高3・2兆円のうち有担保ローンが2・7兆円とされ、住宅ローンは開示されなかった。
一方、第三者委が今月7日公表した調査報告書では、18年3月期の融資残高3・2兆円のうち、不動産投資向けは1・9兆円を占めた。内訳は、シェアハウスや中古1棟マンションなど土地付き物件が1・5兆円、区分マンションが4千億円。他の融資の詳細は示されていない。
不当表示を見抜くなんてすごい!舌が肥えているのか、良い肉を頻繁に食べているし、舌の感覚も良いのであろう。
「運営するレストラン「ステーキカッポー恒づね」で雌牛として提供していた肉の大半が雄牛だった。業者から仕入れた肉の確認を怠っていたのが原因という。」
微妙な言い訳。単なる言い訳なのかよくわからないが、少なくとも「ステーキカッポー恒づね」の人間は肉の味で不当表示を見抜けることが出来ないか、
不当表示に気付いていた人間がいたかもしれないが、隠ぺいしたのどちらかであろう。
大阪府枚方市でステーキレストランなどを経営する「恒(つね)づね」が最高級のA5ランクと表示し販売していた牛肉の中に低いランクの肉が含まれていたなどとして、府は11日、景品表示法に基づき再発防止を求める措置命令を出した。
府などによると、恒づねが平成27年11月~今年1月にインターネット通販サイトでA5ランクと表記し販売していた和牛の中に、低いランクの肉が混入していた。また、運営するレストラン「ステーキカッポー恒づね」で雌牛として提供していた肉の大半が雄牛だった。業者から仕入れた肉の確認を怠っていたのが原因という。
恒づねは28年から、枚方市のふるさと納税の返礼品としてA5ランクの牛肉を提供。今年1月、返礼品の肉を食べた関東地方の男性から「おいしくない。A5ではないのではないか」と市に指摘があり調査したところ、A4ランクだったことが発覚した。同社は当初、「業務繁忙による誤送付」と市に説明していたが、その後の府の調査で違反が明らかになったという。
「恒づね」はホームページで「お客様や関係者に多大なご迷惑をおかけしたことをおわびします。再発防止に取り組みます」とコメントを出した。
宮川選手がメディアを通して国民にアピールして大きな変化があった。協会に言うよりもメディアを通して事実を公表したほうが良いと
思う選手が出てきても不思議ではない。
そう言った意味では宮川選手の行動は今後、大きな影響を与えた事になるであろう。日本体操協会が迅速に適切に動いていれば、このような結果にならなかったであろう。
アマチュア競技団体に、またパワハラ疑惑が浮上である。メダル有力種目の一つであるウエートリフティングの選手が日本協会幹部による嫌がらせを告発していたことが日刊ゲンダイの取材で分かったのだ。
【動画あり】ボクシング連盟・山根前会長の大放言
「幹部」とは日本ウエイトリフティング協会会長で、女子日本代表監督を兼務する三宅義行氏(72)。五輪の女子48キロ級で2大会連続メダル(ロンドン銀、リオ銅)を獲得した三宅宏実(32)の父親でもある。三宅会長が真相を問いただされた今月初めの常務理事会は大紛糾した。
■「俺にあいさつもないのか」
9月1日に東京・渋谷区の岸記念体育会館で行われた協会常務理事会。滞りなく進行していた会がにわかに不穏な空気に包まれたのは1人の常務理事の発言がきっかけだったという。全ての議事が終了した直後、三宅会長によるパワハラ疑惑の真偽を問う発議があったのだ。
問題となった告発文は、数年前に協会に提出された。告発したのは女子のトップ選手。そこには、三宅会長から受けた嫌がらせが列挙されていた。その一例を挙げると「練習メニューが気に入らない」という理由でコップを投げつけられたり、合宿地である「ナショナルトレーニングセンター(NTC)から出て行け」と命じられたこともある。さらにNTCの食堂で三宅会長にあいさつせずに食事を取ると、「俺にあいさつもないのか」と怒鳴られたことなどが記されているという。
この文書の存在を明らかにした理事が三宅会長を問いただすと、告発文書の存在を認めたうえで、「選手のコーチが持参した。事務局長と専務理事と会長(本人)でそれを全部読んだ。(パワハラ行為が)いっぱい書いてありましたが、ほとんどが嘘だった。だから、パワハラはなかったと認定しました」と答えたという。
押し問答となり、理事会は紛糾。常務理事会は通常、午後4時から始まり、2時間程度で終了するが、この時は結論が出ないまま8時すぎまで続いたという。
当日の常務理事会について協会に聞くと、担当者は「協会としてはコメント致しかねます」とのこと。
■「当事者の話を聞かないのは違法」
日刊ゲンダイの取材で、三宅会長を追及したのは、協会常務理事の古川令治氏であることが分かった。古川理事は元慶応大学ウエートリフティング部監督で、現在は公益社団法人・経済同友会の幹事を務めている。その古川氏に話を聞くと、「三宅会長を筆頭に協会幹部がもみ消しを図ったと言わざるを得ません」とこう続ける。
「協会の規定では、トラブルが生じた際には、まず訴え出た当事者の話を聞き、そのうえで倫理委員会を開いて、調査を行うと記されているんです。今回の件では、会長以下、協会幹部数人が文書に目を通しただけで、本人にヒアリングすら行わずに『パワハラはなかった』と認定した。これでは欠席裁判です。ろくに調査もせずに終えたとするのは明らかに違法ですよ。当日の常務理事会で、弁護士、会計士を入れた倫理委員会を開いて、改めて調査するように提案しましたが、三宅会長は『もう、終わった話だから』の一点張り。聞く耳すら持ちませんでした。そもそも、パワハラはなかったと認定した協会の専務理事、事務局長、それに、告発文書を持参したコーチは全て、三宅会長の母校(法政大学)の後輩です。大学の後輩ばかり集めてパワハラがなかったと結論付けるのは公平性に欠けます。明らかな規約違反にもかかわらず、常務理事会では終わったことになっている。次回の理事会で改めて問題提起したいと思っています」
レスリングにしろ、ボクシングにしろ、パワハラの当事者は対応を誤って後手を踏み、自らの首を絞めた揚げ句、最後は解任や辞任に追い込まれた。同じアマチュア競技団体のトップとして同じ轍を踏まないためにも、三宅会長と協会は早急に公正に調査し、事実を明らかにする必要がある。
聞き手=藤田知也
スルガ銀行のシェアハウス融資の不正を調査した第三者委員会の報告書は、書類改ざんなどに執行役員や支店長、多数の行員が関与したと認定し、「組織的だった」と断じた。不正はシェアハウス以外の不動産投資向け融資全体に広がり、経営への深刻な影響が懸念される。金融庁は厳しい処分を検討し、今後の信頼回復は容易ではない。スルガ銀は立ち直れるのか、識者2人に聞いた。(聞き手=藤田知也)
「オマエの家族皆殺し」スルガ銀、上司による壮絶な恫喝
サッカー・美術館・住宅街…スルガ銀と密着、地元に動揺
元東京地検検事の落合洋司氏
今回の不正は、デタラメぶりがすごすぎて、コンプライアンス(法令や社会規範の順守)を論じる以前のレベルだ。もはや銀行の体さえなしていないのではないか。
第三者委が認定した不正行為だけでも、多くの行員が私文書偽造や詐欺、背任などの罪で刑事責任を問われる可能性がある。これから信用を回復していくには、まずは銀行が率先して責任追及する姿勢を示し、刑事告訴や告発にも踏みだすべきだ。スルガ銀が捜査に非協力的なようだと、構図が複雑なだけに事件化が難しくなるおそれがある。
貸し倒れのリスクで銀行業績は大幅に悪化し、株価の暴落で株主にも大きな損失を与えた。不正を許した経営陣も含め、民事上の責任を明確にすることも避けて通れない。これだけ悪質で組織的な不正をうやむやにしようとすれば、銀行として再建することもままならなくなるだろう。
■マネックス証券チーフ・アナリ…
宮川紗江選手は19歳だから経験がないかもしれないが、衝突する相手や対立する相手が正々堂々、クリーンに対応すると思っていたのだろうか?
負けないためには手段を選ばない相手は存在する。
「『改めてあのような映像を公開することの意味が理解できません』とコメント。」
暴力の映像を流す事で、暴力はいけないと思う人は増えるだろうし、言葉よりも映像の方がイメージ悪化には効果的、宮川選手や速水コーチが
嫌な思いをして対立を考え直す可能性などが考えられる。
映像は流す理由は意味がない事はなく、相手にとってはいろいろなメリットがあると思う。
「『コーチはすでに暴力を認めて処分も全面的に受け入れ、反省しています。そのような中、改めてあのような映像を公開することの意味が理解できません。私の叩かれている姿を許可もなく、全国放送されたことに怒りを感じています』と訴えた。」
心にもない反省や謝罪を行う人達はたくさん存在する。衝突や対立は精神的に辛いことが多い。だから衝突や対立を避ける選択を選ぶ人達は存在する。
どのような選択を選ぶにしても人生勉強だと思う。
相手が勝とうとすればするほど、弱点や問題点があれば、そこを攻撃するだろう。仕方の無いことだ。謝罪したり、反省しても、許してくれない
人達は存在する。理想と現実は全く違う。体操は争う相手とのコンタクトがないスポーツだからイメージ出来ないかもしれないが、日大の
悪質タックルを考えれば、汚い世界が存在する事に気付くであろう。勝つためには手段を選ばない人達は存在する。
体操女子で2016年リオ五輪代表・宮川紗江(19)が10日放送の日テレ系「情報ライブ ミヤネ屋」(月~金曜・後1時55分)の取材に応じ、速見佑斗コーチ(34)による宮川への強烈な平手打ち映像が一部で報じられたことに「私の叩かれている姿を許可もなく、全国放送されたことに怒りを感じています」とコメントした。
【写真】殴って抱きしめる…速見コーチと宮川は「DVカップルの構図」
一部テレビ局で報じられた映像は速見コーチが3年前に宮川へ行った暴力行為の瞬間で、直立不動の宮川に右手でほおをビンタし次に左手でビンタしていた。「ミヤネ屋」の取材を受けた宮川は「叩かれた時は親に話していました。また、コーチから親に連絡していました」とし、「改めてあのような映像を公開することの意味が理解できません」とコメント。
また「色々と話し合いはしていますが、いろんなことに対応するのが精一杯です。速見コーチとは電話やLINEでコンディションについてやり取りしています」と現状を報告し、「コーチはすでに暴力を認めて処分も全面的に受け入れ、反省しています。そのような中、改めてあのような映像を公開することの意味が理解できません。私の叩かれている姿を許可もなく、全国放送されたことに怒りを感じています」と訴えた。
日本バドミントン協会は10日、都内で理事会を開き、金銭的な不正があったとされた再春館製薬所の今井彰宏元監督を「日本協会の会員登録を無期にわたり認めない」処分とすることを決めた。今井氏は現在、日本協会への会員登録がなされていない状態。登録がなければ、チームの監督などの立場で公式戦へ参加できない等の制限がかかる。再春館製薬所元コーチの吉冨桂子氏も、金銭的不正により会員登録の無期限抹消が決まった。銭谷欽治専務理事は「(より重い)『除名』という意見も出たが、今後の熊本県警の捜査の成り行きも見て、処分を解除したり逆に重くしたりする可能性もある。指導実績をあげている両名。同じ仲間を処分するのは断腸の思い」と神妙な表情で話した。
今井氏が在籍する岐阜トリッキーパンダースには、18年世界選手権女子ダブルス銀メダルの福島由紀、広田彩花組が所属している。会員登録ができなくても、試合以外でフクヒロペアを指導することは可能だ。銭谷専務は「精神的に少なからず動揺があると思うので、(協会として)2020年へ全力でサポートしたい。代表でのスケジュール(合宿や遠征)が年間240日くらいあるので、今までと変わらず、朴(柱奉)HCや中島(慶)コーチの指導を強化したい」と述べた。
フクヒロペアは今年4月まで再春館製薬所に所属していたが、師事する今井氏の後を追って岐阜トリッキーパンダースへ移籍した。現在、世界ランキング1位。8月のジャカルタ・アジア大会でも48年ぶりとなる団体金メダルに貢献し、19年世界選手権、20年東京五輪へ活躍が期待されている。次戦はジャパン・オープン(11~16日、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ)に、第1シードとして参戦予定となっている。
最近、体操界の暴力が注目を集めているが、指導中の暴力がなくなっていない状態での、暴力を全否定すると 勝手な推測だが影響を受ける人達がたくさんいると思う。
日本体育大陸上部の渡辺正昭駅伝監督(55)が部員への暴言や暴力などを繰り返していたと一部メディアで報じられた問題で、日体大は10日、報道の前から、渡辺監督のパワハラを訴える学長宛ての投書が1件あったことを明らかにした。
投書の時期や内容、対処について、大学広報課は「詳細については、公にできない」としている。渡辺監督や選手への聞き取り調査は7日で終了し、事実認定や処分の可能性については、部活動を統括する「学友会」の倫理委員会で、引き続き審議しているという。
大正製薬の経営者やスタッフがどのような情報を把握し、どのような理由で判断したのか関係者にしかわからない。短期、中期、又は長期的な
判断次第で、同じ状況でも判断結果は違ってくると思う。
プロセスは重要だが結果次第で、評価や批判は違ってくる。時が来れば良い判断であったのか、間違っていたのかわかるであろう。
栄養ドリンク剤「リポビタンD」や風邪薬「パブロン」などで知られる大衆薬最大手、大正製薬ホールディングス(HD)の大幅な人員削減が話題になっている。
【グラフ】大正製薬、ヒトは増えても利益は上がらず!
同社は5月に早期退職優遇制度の実施を発表しており、8月末にその結果を公表した。応募は943名。10年以上勤務、40歳以上の従業員約3000名が対象で、そのおよそ3割が手を挙げた計算になる。
■1人当たりの費用は約1290万円
中堅として現場の中核を担うべき40歳以上の社員が一気に3割も抜けてしまうことになる。会社側は割り増し退職金と再就職支援費用として特別損失122億円を計上するが、1人当たりの費用は約1290万円。2000万円以上の“高額”な割り増し退職金が珍しくない製薬業界にあって、決して手厚いわけではない。
大正製薬HDの2018年3月期の営業利益は前期比16%増の369億円。非常時とは言えない中での大量退職だ。会社は「想定内」と言うが、同業関係者からは「普通では考えられない」という声が多く聞かれる。
もともと優遇制度は今回の募集のため新設した。退職呼びかけは、1912年の創業以来初めてのことだ。
今回の早期退職はグループの中核会社、大正製薬の上原茂社長(HDの副社長を兼務)の意向が反映されているようだ。茂氏は、上原明・現HD社長兼会長の長男で、次のグループ総帥となることがほぼ確実視されている。2012年に36歳の若さで大正製薬の社長に就任した。慶応大学卒で、米国の著名なビジネススクールであるケロッグ経営大学院で学んだ国際派だ。
■大胆なショック療法
「意識改革をするためには、仕事を変えればよい」。これまで茂氏は役員・幹部級社員の人事で、研究開発から営業担当への異動など、大胆な配置転換を実施してきた。今回の早期退職にも、ショック療法によって社員の意識改革を促す意味合いがあるようだ。
確かに、大正製薬はこうした動きに出ざるをえない状況にある。
長期トレンドを冷静に分析すれば、利益のピークは18年も前。利益は長期低下中なのに、従業員は増え続けた。従業員1人当たり利益は半分以下になっている。
少子高齢化と人口減で柱の国内の大衆薬市場は今後も伸びない。さらに厳しいのは、弱点である医療用医薬品だ。2000年代から進めたM&A(合併・買収)や提携戦略は実を結んでいない。今年7月末には保有する富山化学工業の全株(34%)を富士フイルムHDに売却。富山化学とは合弁販社だけが残されており、同販社の従業員は今回の早期退職の対象に含まれている。
早期退職で人員の水膨れは是正されるが、それは一時的。問題は次の稼ぎ頭をどう作るかだ。会社の方向性が見えない中での“ショック療法”は、人心が離れるリスクもはらんでいる。
大西 富士男 :東洋経済 記者
「台風21号で関空vsタンカー、損害賠償めぐる第2の衝突」となれば、タンカーがいつ接岸して、いつ離岸したかも重要になる。
タンカーの荷物であるジェット燃料の荷役予定は関空、又は関空が委任している会社や組織が決めているはずである。接岸時間や離岸時間予定など
燃料を受け取る側が決定するし、施設の安全や保護のために予定を変更して船に離岸を要請する事も出来る。
タンカーの船長よりも関空、又は、関空から委託されている会社や組織の方が力関係でははるかに強いはずだからいろいろな指示は出せると思う。
ただ、個人的な感じではあるが、学歴や基本的な能力は高いが経験や専門知識がない若い人が増えているので適切な指示が出せない、又は、
どのような指示を出して良いのかわからない人達は増えていると思う。わからないから馬鹿みたいに必要のない指示をたくさん出したり、
これは問題ではと思う事には気付いていないような事がある。規則を満足していなくても、指摘されると仕事が増えるから何も知りたくない人達は
いるし、とにかく仕事が増える事を嫌う人達はいる。問題があっても自分の責任にならなければ無視する人はいるし、自己中的に自分の事しか
考えない人はいる。これで良いのかと疑問に思う事はあるが、問題や事故が起きなければ誰も気にしないように思える事がある。これだけの
損害が発生すると、次回は、馬鹿かと思うくらいくだらない対応や基準で対応する可能性がある。そして無駄、時間や努力が要求される可能性は高い。
日本人は基本的に勤勉だと思うが、時々、とてつもなく愚かな集団とも思える事がある。今後、いろいろな情報が明らかになると思うが、
情報次第では、部分的に愚かな人達の存在が判明するかもしれない。
内航タンカーを運行する会社の中には任意ISM(安全管理システム) (一般財団法人 日本海事協会)を取得する会社が存在する。
安全管理システム(任意 ISM コード)運用の効率化
では「同社は愛媛県にて、内航タンカーの貸渡業(内航海運業)を事業展開している。 内 航海運においては、1980 年代後半以降に多発した海難事故の未然防止を目指して、外航 海運に義務付けられた「国際安全管理規則(ISMコード)」の内航海運版といえる「任意ISM」 の取得が事実上の事業継続の前提条件となってきている。 一方で、内航海運事業者(および社員)も、船舶の安全を守る事の重要性と、ISM の有 用性を周知/徹底しているが、任意ISMの維持に必要な「安全管理マニュアルの維持管理、 チェックリスト・記録紙の作成/保管など」は、運航業務/荷役業務に加えられた新たな 業務として大きな負荷となっている。 そこで、船舶の安全を維持しつつ、管理業務を効率化する事が喫緊の課題として挙が っていたが、有効な対策が打てない状況であった。」と記載されている。
開けない人はここをクリック
参考情報:
任意によるISMコード認証取得について運輸省告示「船舶安全管理認定書等交付規則」を制定- (国土交通省)
内航海運グループ化について (国土交通省)
ISMコードではマニュアルを作成し、社員及び船員の教育、記録、記録の管理、内部及び外部審査など
に関してコードの要求を満足する必要がある。外航船で外部審査に合格しても、実際に問題がない状態であるかと言えばそうでもない。特に
船の運航で必要なので仕方がないと思っている船や会社では問題が存在する可能性が高い。外部審査に問題があれば、問題があっても審査に合格するまれなケースがある。
審査のために辻褄が合うように準備すれば審査に合格する事は可能。審査をパスできない会社はそれさえも出来ない能力のない会社か、くそ真面目過ぎてその場限りの対応をしようとしないから大きな負担になりパス出来ない会社。本当は通常の状態で審査にパス出来るのが理想であるが、審査に
通る事だけが重要になれば無駄な努力と時間が費やされ、本来の効果は通常オペレーションでは期待できない事がある。
見栄のためにりっぱなマニュアルを作成しすぎて、社員や船員達が理解できないだけでなく、辻褄合わせの書類作成が負担になっているケースがある。
本末転倒であるが、ISMコードや内部審査の担当者がスリム化のために何が必要で、何を妥協するべきか
判断出来なければ、スリム化は難しい。実際に、不正や違反する会社や人々が存在するので、義務のためだけに苦しんでいると、馬鹿らしいと思う人達がいるかもしれない。大きな事故が起きると防止策として新たな負担が増える可能性がある現実がある。守らない、又は、守れない形だけの対応は
無駄に思える。時間が経てば本来の意味は理解されず、本来の目的も忘れられ、形だけが意味もなく繰り返されることがある。今回の件で
任意によるISMコード認証取得について運輸省告示「船舶安全管理認定書等交付規則」を制定- (国土交通省)について触れられていないが、防止策と一緒に考える必要があると思う。
素人や経験のない人達には判断や計画が妥当であるかの判断は出来ないと思うので、船長や船員経験者や
海事補佐人などがそれぞれのサイドに
立って争うのであろう。
海事補佐人の登録を希望する方へ (国土交通省海難審判所)
近畿地方を通過した台風21号は、その爪痕を大きく残した。9月4日、高潮で滑走路が冠水した関西国際空港と対岸を結ぶ唯一の連絡橋にタンカーの宝運丸(長さ89メートル、2591トン)が衝突し、関空の利用客ら約8000人を孤立させた。
関空は7日から国内線の一部の運用を再開したが、全面的な再開のメドは立っていない。観光や物流など関西経済の打撃は必至で、アジア太平洋研究所によると関西のインバウンド消費だけをみても、経済損失は500億~600億円にのぼるという。「アジア防災センター」センター長の濱田政則・早稲田大学名誉教授はこう話す。
「問題はタンカーが衝突した連絡橋。報道映像を見た範囲ですが、橋桁は造り直す必要があるはずで、そうなると完全復旧までに1~2か月は必要です。基礎の部分まで損傷している場合にはもっと時間がかかりますし、概算ですが費用も100億円を超えると思います」
そうなると、気になるのが連絡橋を壊してしまった責任の“賠償額”だ。いったいどこが負担することになるのか。海難事故を専門とする田川総合法律事務所の田川俊一弁護士は言う。
「船舶一般において、船長にはアンカー(錨)をおろして船が流されないように守錨をする義務があります。その義務を怠った場合の事故などは船長の過失であり、その賠償は船主(海運会社)が支払うことが民法の特別規定によって定められています。船舶はPI保険(船主責任保険)に入っているのでそこから補償に充てられますが、上限は通常、数十億円に設定されています」
宝運丸は、3日に航空機用の燃料を運んだ後、錨をおろして停泊中に風に流されて橋に衝突したと報じられている。田川弁護士はこの措置をめぐって情勢が変わる可能性を指摘する。
「関空からタンカーに停泊位置など細かく指示が出ていたはずですが、仮にその指示などで関空側にも過失があった場合、過失相殺が認められ、タンカー会社の賠償負担が減る可能性もあります。もっとも、自然災害という不可抗力によるものと認められれば、賠償責任そのものが免除されます」
過失があるのはタンカーか関空か、それとも自然災害か──。在阪の社会部記者はこう話す。
「責任問題についての議論はまだ先のようですが、関空側はもし損害賠償を請求されたらタンカー会社の過失を主張するとみられています。自然災害と認められればいいが、今のところは互いに牽制している状況のようです」
第2の“衝突”は、これからのようだ。
※週刊ポスト2018年9月21・28日号
誰にでも間違いや失敗はある。船長の判断ミス、又は、対応が間違っていたとは個人的に思うが、台風や悪天候の時にアンカーに関する規則や条例が
ないのだから怒りをぶつけるのはおかしいと思う。
空港の建設と開港後の設置・管理は、国・地方自治体・民間が共同出資する政府指定特殊会社「関西国際空港株式会社(Kansai International Airport Co., Ltd.、英略称:KIAC)」でスタートしたのだから、その時に、事故を防止する対策や条例を準備しておけばよかった。
適切な規則、条例、そして燃料を運ぶタンカーに対するガイドラインを準備してないから、運悪くこのような結果となった。
過去に問題がないから今後も問題がないと考えるのは間違い。
「同庁によると、関空周辺では、いかりを下ろしたまま流される『走錨(そうびょう)』が過去に多発。島に座礁する危険があるため、同庁は台風接近時などに『関空島の岸から原則3マイル(約5・5キロ)以上離れた場所』に避難するよう注意喚起している。法的な義務はない。」(09/09日/18(読売新聞)
判断に自由度があるのだから間違いが起きても仕方がない。誰も万が一のために船を移動させるべきだと誰も考えなかったのであれば、
それも仕方がない。
結果として松井知事、衝突に怒りを表すのではなく、今後、同じ失敗が起きないように指示したり、対策が取られているのかを確認するべきだと思う。
「人災」と言うのであれば、直接的には判断を下した船長であるが間接的に大阪府や新関西国際空港株式会社にも責任はあると思う。
台風21号で大きな被害を受け、全面復旧が見通せない関西空港について、地元・大阪府の松井一郎知事は9日、「(連絡橋への)タンカーの衝突さえなければ、今の時点で復旧がかなっている。関空が今の状況に至っているのは人災と思う」と述べた。愛知県常滑市の中部国際空港で記者団に語った。
地元では、訪日外国人客の窓口になっている関空の被害が関西経済全体に影響を及ぼす懸念がある。松井知事は「人災」という表現を使うことで、空港へのアクセスルートを破壊したタンカーへの怒りをにじませた格好だ。
関空は今月4日、台風21号の直撃に伴う高潮で第1滑走路がある1期島が広範囲で冠水。さらに、風で流されたタンカーが連絡橋に激突し、南側車線と鉄道線路が損傷した。9日までに国内線、国際線とも運航が一部で再開されているが、全面復旧の時期は見通せていない。
松井知事はこの日、「タンカーの避難失敗。これがなければ、もう関空は今、多分、8割方は回復しているという状況だと思う」と話した。
一方、松井知事は大阪誘致をめざす2025年万博の会場予定地である大阪市湾岸部の人工島・夢洲について「(台風21号の影響は)全く大丈夫。夢洲は関空より地盤が高いし、夢洲への(行き来できる)ラインは2系統ある。関空の今回のことを受けて、夢洲の防災機能化に疑問符がつくということにはならない」と強調した。(坂本純也)
朝日新聞社
10年以上も前に台風の時に知っている船長はアンカーを落とさないエリアで台風から非難していた船が走錨により座礁し、
沈没を恐れて救命艇で退避しようとして救命艇が途中で落下して数人の船員が死亡した船に乗っていた船員と話したことがある。
船員によると船長が避難したエリアに不慣れで湾にアンカーして避難していれば大丈夫だろうと思っていたら、走錨で
かなり流され座礁した。船が二つに折れ始めたので沈没すると思い、救命艇で退避しようとしたが強風で外板に打ち付けられて
損傷し、船員が死亡したと言う事だった。
「法的な義務はない。」と言う事なので、船長の判断が結果として最悪の事態となったと言うなのだろう。
「重しとして海水を積んだ後に離岸した」となっているが、写真や動画を見る限り、そんなに船は沈んでいるように見られなかった。
荷物を下せばバラストをフルに張ってもそんなに沈まないので注意する必要はあると思う。多くの外航船の船長は荷物を積んでいる
時の方が悪天候では安定度は高いと言う。
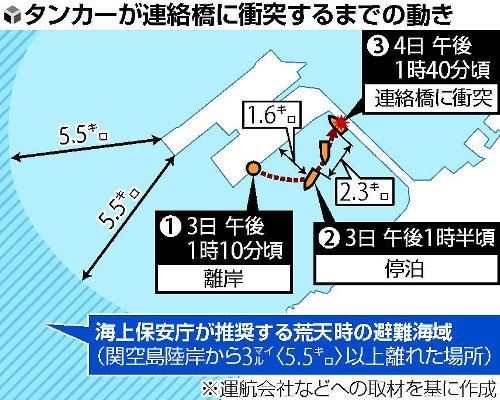
関西空港の連絡橋にタンカー「宝運丸」(2591トン)が衝突した事故で、タンカーが事故前、荒天時に避難するよう推奨されている海域ではなく、関空島に近い位置に停泊していたことが、海上保安庁や運航会社への取材でわかった。船長は海域外だと認識していたが、「安全だと思った」と説明しているという。同庁は停泊位置と事故の関係について調べている。
同庁によると、関空周辺では、いかりを下ろしたまま流される「走錨(そうびょう)」が過去に多発。島に座礁する危険があるため、同庁は台風接近時などに「関空島の岸から原則3マイル(約5・5キロ)以上離れた場所」に避難するよう注意喚起している。法的な義務はない。
運航会社によると、タンカーは3日、関空島に燃料を荷揚げし、重しとして海水を積んだ後に離岸したが、台風21号に備えて午後1時半頃、岸壁の南東約1・6キロにいかり(約2・5トン)を下ろし停泊した。
関西国際空港と対岸を結ぶ連絡橋にタンカーが衝突した影響で、道路下にある鉄道橋も約50センチ横ずれしていたことが、明らかになった。レールにもゆがみが見つかり、電気を送る架線も損傷。鉄道橋を保有する新関西国際空港会社は、「鉄道の再開には相当の時間がかかる」と話した。
同社などによると、連絡橋の道路(下り線)の橋桁が、タンカー衝突で数メートル押し込まれた。この部分の道路から約2.5メートル下にある線路は、鉄板で囲まれた鉄道桁に敷設されている。上部の道路桁とともに鉄道桁も押し込まれ、約50センチ横ずれしたとみられる。この影響で上下線2本のレールもゆがみ、架線も損傷したという。
鉄道桁(長さ98メートル)そのものに損傷はなく、鉄道再開には桁を元の位置に戻し、線路や架線などを補修する必要がある。鉄道桁の補修工事は同社などが実施。JR西日本と南海電鉄が鉄道橋を共用しているが、線路や架線については、JR西が修理することになるという。
新関空会社によると、鉄道桁の補修は、より損傷が激しい上部の道路桁の修理後になる見通し。ただ同社は同時に補修する方法も模索している。担当者は「鉄道再開のめどは立っていないが、なるべく早く復旧させたい」と話した。【山下貴史】
宮川紗江選手及び宮川の代理人を務める山口政貴弁護士が全てを知った上で、判断しているのであれば、自己責任を自覚していれば良いと思う。
相手側にとっては迷惑な話であるのは間違いないが、火のない所に煙は立たない。
強い対応を取れば、弱点を突かれるのは想定出来ると思う。暴力がいけないと言っているが、体操関係だけでなく、一般のスポーツをする人の
多くが暴力を受けている。自分だって殴られた事はたくさんある。暴力が本当にいけないのであれば、体操の世界だけでなく、スポーツの
世界でもっと注目をするべきではないのか?
両サイドに問題があるなかで叩き合いのような状態になっているように思える。
7日放送のフジテレビ系「バイキング」(月~金曜・前11時55分)で体操女子で2016年リオ五輪代表の宮川紗江(18)へのパワハラ問題などを特集した。
番組では、宮川がパワハラを告発した日本体操協会の塚原光男副会長(70)と妻の塚原千恵子強化本部長(71)からの謝罪を受け入れないことを議論した。
MCの坂上忍(51)は、6日放送の同局系「直撃!シンソウ坂上」(木曜・後9時)で塚原副会長をインタビューした。その上で坂上は「ボクは塚原さんとお話しさせていただいて思ったのは、宮川さんサイドって頑なというか徹底抗戦の構えを崩していなくて、どこか感情的な印象があって、それを塚原さんサイドは察しているから、謝罪って言うのも、アッお上手だなっていう戦法としてですね。あとは告発されている側だから、いろいろな証拠たり得るものみたいなも恐らくお持ちだと思うんです。でも、そこをご本人の言葉によると、宮川選手のことを考えたいから、大事にしたいから貴重な存在だからということを言葉では言ってらっしゃるので、その手持ちのものがどういう形で第三者委員会に出されていくのかなというのは、ちょっと興味深いところ」と指摘した。
さらに暴力行為を認めた速見佑斗コーチ(34)について「あんだけ暴力をふるっちゃった人が選手と一緒に告発しちゃったわけじゃないですか、パワハラを。暴力ふるった人がパワハラを告発しているわけだよ。オレ、だったら他にもパワハラしているんだって塚原夫妻はっていうんだったら、もっと身ぎれいな人が告発してくれたらもっとスッキリするんじゃないかと思う」と持論を展開した。
体操取材歴40年のテレビ朝日スポーツコメンテーターの宮嶋泰子氏(63)の対応は本当に中立性に欠けると思う。当人がどのような考えや利益の
ために動いているのかわからないが、偏っていると思う。
「その上で「私自身も5年前の柔道の女子ナショナルチーム暴力事件から全柔連の「暴力根絶プロジェクト」にかかわっていました。現在も全柔連コンプライアンス委員会のメンバーです。40年間スポーツの仕事をしてきて、かつては当たり前であった暴力やセクハラをなくすことが私の重要な仕事の一つであると信じています。」
40年間スポーツの仕事してきて当たり前であった暴力やセクハラを見たり、聞いたりしたのでしょうか?そうであるのならテレビ朝日の立場や
考えは別としていつ頃から個人として暴力やセクハラはいけないと思うようになったのでしょうか?
暴力やセクハラの問題を見たり、聞いたりしたのはいつでしょうか?その時に問題を記事にしたり、公表したのでしょうか?記事に出来ない、又は、
公表できない圧力はあったのでしょうか?財務省の福田淳一・前事務次官によるテレビ朝日女性記者に対するセクハラ問題ではテレビ朝日の対応は
遅いように思えた。宮嶋泰子氏はいつ、スポーツ界の暴力やセクハラを知ったのか?スポーツ界が広ければ、体操界の暴力やセクハラをいつ知ったのか?もし最近まで知らなかったのあれば、体操界は隠ぺい体質がある事になる。知っていたのであれば、体操界は隠ぺい体質だけでなく、メディアにも
圧力をかけていた可能性があると思う。
チャイルドアビューズやドメスティックバイオレンスの典型的な例では、長期的なマインドコントロールで被害者が適切な判断が出来ないケースが
あるのは知っている。だから、このケースが宮川選手のケースに当たる可能性を言いたいと思う。一般的に暴力はいけないが、関係者達が問題と
しなければ問題ない場合はあると思う。ただ、税金が使われ、公共の目が当たる体操界では控えるべきだとは思う。
「続けて『SNSによる誹謗中傷だけでなく、テレビ朝日にもたくさんのクレーム電話がかかってきているようです。
私たちメディアの人間には、正しいことをきちんと伝える使命があるのです。・・・テレビを見て、塚原バッシングをうのみにしていた方も、そろそろ目を覚ましませんか』と呼びかけていた。」
そこまで言うのであれば、本当にメディア、少なくともテレビ朝日や宮嶋泰子氏は中立的な立場で、政府、スポンサーや利害関係団体からの影響や
圧力を受けずに、正しい事を伝えているのでしょうか?テレビ朝日や宮嶋泰子氏セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント問題について適切に
公表したり、対応しているのでしょうか?テレビ朝日やあなたは事実を伝える事について目を覚ましていますか?宮嶋泰子氏は朝日新聞の慰安婦報道問題をいつ知ったのでしょうか?なぜ、朝日新聞は、1980年代〜90年代にかけて報じた慰安婦問題関連記事の捏造や誤報をようやく認め、その一部を訂正するまでにかなりの時間がかかったのでしょうか。うのみにせずに目を覚ませとグループ組織に何かを言ったのでしょうか?もし言ったのであれば
無視されたのでしょうか?「私たちメディアの人間には、正しいことをきちんと伝える使命があるのです。」は組織の中ではケースバイケースなのでしょうか?
体操取材歴40年のテレビ朝日スポーツコメンテーターの宮嶋泰子氏(63)が6日、自身のフェイスブックを更新し、フジテレビが独占で入手した女子体操の宮川紗江(18)が速見佑斗コーチ(34)による宮川への強烈な平手打ち映像について自身の見解を示した。
フジテレビが入手した映像は、3年前に宮川へ行った速見コーチの暴力行為の瞬間で同局の取材に関係者は「今から3年ほど前、当時、宮川選手と速見コーチが所属していた埼玉県内の体操クラブでの練習場で撮影されたもので、撮影したのは同じクラブに通っていた関係者です。関係者によると、こうした行為は頻繁に行われていたということでコーチから抱きかかえられた状態から投げ飛ばされたこともあるということで宮川選手は暴力行為後に流血したり頭痛を訴えていたこともあります」と明かしていた。
宮嶋氏はFBで「速見コーチが宮川選手を思いっきり殴る映像がTVで流れました。体が揺れるほどのひどさです。この状態でも「私はパワハラと思っていない」といった宮川選手や、暴力を知りながら速見コーチを信頼しているという宮川さんのご両親に申し上げたい。夢をもってスポーツをする子供たちに、「こういう暴力がなければナショナル選手になれないんだ」という考えを容認せよというのでしょうか」と疑問を投げかけた。
さらに「何も知らない体操OBのタレントが口から出まかせに、「宮川さんと速見コーチを引き離すために仕組んだ陰謀説」を振りまいていましたが、とんでもない! ナショナルチーム内で起きる暴力の事実をどう処理したらよいかと塚原強化本部長は必死だったのです」と訴えた。
その上で「私自身も5年前の柔道の女子ナショナルチーム暴力事件から全柔連の「暴力根絶プロジェクト」にかかわっていました。現在も全柔連コンプライアンス委員会のメンバーです。40年間スポーツの仕事をしてきて、かつては当たり前であった暴力やセクハラをなくすことが私の重要な仕事の一つであると信じています。ですからスポーツ関係者を対象としたハラスメントの勉強会なども行ってきました。今回も速見コーチの暴力に関する相談をかなり早い段階でから受けていました。ですので6月から一部始終を見ていました。これらのことを見てもいないし、いきさつも知らない体操OBのタレントやコメンテーターと称する人が、勝手な思い込みによるコメントを垂れ流し、塚原千恵子強化本部長を攻撃するのにはあきれました。もちろん塚原さんたちにも日頃の態度には問題もあったでしょう。しかし、今回の件に関しては、塚原さんたちの宮川さんに対する聞き取りは、「勧誘や引き抜き」ではありません」と持論を展開した。
続けて「SNSによる誹謗中傷だけでなく、テレビ朝日にもたくさんのクレーム電話がかかってきているようです。今日、スポーツ局の若手に、「取材がしにくくなるので追及をやめてほしい」と言われました。これにはあきれてものが言えませんでした。私たちメディアの人間には、正しいことをきちんと伝える使命があるのです。暴力は誰が何と言おうとダメです。する側と受ける側がお互いに暴力を認め合う関係は異常です。きちんとカウンセリングを受け、必要によっては精神科の治療を受けることも必要です。そこからしか再生は行われません。テレビを見て、塚原バッシングをうのみにしていた方も、そろそろ目を覚ましませんか」と呼びかけていた。
宮川紗江選手及び宮川の代理人を務める山口政貴弁護士が全てを知った上で、判断しているのであれば、自己責任を自覚していれば良いと思う。
相手側にとっては迷惑な話であるのは間違いないが、火のない所に煙は立たない。
強い対応を取れば、弱点を突かれるのは想定出来ると思う。暴力がいけないと言っているが、体操関係だけでなく、一般のスポーツをする人の
多くが暴力を受けている。自分だって殴られた事はたくさんある。暴力が本当にいけないのであれば、体操の世界だけでなく、スポーツの
世界でもっと注目をするべきではないのか?
両サイドに問題があるなかで叩き合いのような状態になっているように思える。
7日放送のフジテレビ系「バイキング」(月~金曜・前11時55分)で体操女子で2016年リオ五輪代表の宮川紗江(18)へのパワハラ問題などを特集した。
番組では、宮川がパワハラを告発した日本体操協会の塚原光男副会長(70)と妻の塚原千恵子強化本部長(71)からの謝罪を受け入れないことを議論した。
MCの坂上忍(51)は、6日放送の同局系「直撃!シンソウ坂上」(木曜・後9時)で塚原副会長をインタビューした。その上で坂上は「ボクは塚原さんとお話しさせていただいて思ったのは、宮川さんサイドって頑なというか徹底抗戦の構えを崩していなくて、どこか感情的な印象があって、それを塚原さんサイドは察しているから、謝罪って言うのも、アッお上手だなっていう戦法としてですね。あとは告発されている側だから、いろいろな証拠たり得るものみたいなも恐らくお持ちだと思うんです。でも、そこをご本人の言葉によると、宮川選手のことを考えたいから、大事にしたいから貴重な存在だからということを言葉では言ってらっしゃるので、その手持ちのものがどういう形で第三者委員会に出されていくのかなというのは、ちょっと興味深いところ」と指摘した。
さらに暴力行為を認めた速見佑斗コーチ(34)について「あんだけ暴力をふるっちゃった人が選手と一緒に告発しちゃったわけじゃないですか、パワハラを。暴力ふるった人がパワハラを告発しているわけだよ。オレ、だったら他にもパワハラしているんだって塚原夫妻はっていうんだったら、もっと身ぎれいな人が告発してくれたらもっとスッキリするんじゃないかと思う」と持論を展開した。
スルガ銀は終わりだろうか?調査すればするほど、闇が出てくる。
スルガ銀行が創業家の関連企業に対して数百億円の融資をしていることが4日、分かった。金融庁は融資先に実体のない企業が含まれている可能性もあるとして、企業統治上の問題がないか解明を急いでいる。
創業家の関連企業は、スルガ銀行の株式を保有する企業もある。こうした企業に対する融資の一部にも、経緯や資金使途が不透明な部分があり、創業家側に流れていた可能性もあるとみている。立ち入り検査中の金融庁はスルガ銀に対し、説明を求めたもようで、複数のファミリー企業に融資が実行されていることをその過程で把握したとみられる。
今後、スルガ銀と創業家関連企業の関係に問題があると判断すれば、スルガ銀の株主構成が変化することになる。
一方、スルガ銀の「シェアハウス」向けの不適切融資をめぐっては、外部弁護士で構成する第三者委員会が調査結果を7日に公表する。
TBSテレビの社員・余郷容疑者(30)はプロヂューサーなんですか?
情報源:
少女誘拐の疑いでTBS社員逮捕 09/03/18(Don't Disturb This Groove)
10代の少女を東京の自宅に連れて行くなどしたとして、TBSテレビの社員の男が未成年者誘拐の疑いで逮捕された。
・「TBS社員 少女誘拐疑いで逮捕 札幌市内で発見」を動画で見る
TBSテレビの社員・余郷容疑者(30)は、8月中旬から9月2日までの間、静岡県中部に住む10代の少女が未成年者と知りながら、東京・渋谷区の自宅に連れていくなどした誘拐の疑いが持たれている。
少女の家族から行方不明者届が出されていて、2人で北海道・札幌市内の路上を歩いているところを警察官が発見し、逮捕した。
警察は、認否を明らかにしていない。
TBSテレビは、「社員の逮捕は誠に遺憾で、被害者やご家族に深くおわびいたします」とコメントしている。
体操女子の宮川紗江選手が日本体操協会副会長の塚原光男氏と女子強化本部長の塚原千恵子氏によるパワハラ被害を訴えている問題で、同体操協会幹部が3日午前、スポーツ庁を訪れ、対応策を報告した。
【1991年に塚原独裁を報じた週刊朝日誌面はこちら】
協会はパワハラ問題の有無を調査するため、第三者委員会設置を決め、10月末までに結論を出したいとしている。
訴えられた側、塚原夫妻は当初、協会と協議せずに「声明文」を勝手に出し、録音データなど証拠があるとパワハラを否定。だが、ここにきて一転して、「宮川選手に謝罪したい」と態度を翻し、何が真実なのかわからず、混迷を深めている。
日本体操協会の元役員はこうう打ち明ける。
「8月に日本ボクシング連盟の山根明前会長の独裁問題があったでしょう。体操でも、同じような構図の塚原問題が長年、ささやかれており、『今度はうちじゃないか』と声が出ていたんですよね」
宮川選手は8月29日、専属である速見佑斗コーチに関する暴力騒動について都内で会見を開き、コーチの処分の撤回、軽減を求めた。その際、塚原夫妻のパワハラ問題についても訴え、宮川選手は以前から塚原夫妻が率いる朝日生命体操クラブに移籍を持ち掛けられていたことを暴露した。
前出の元役員によると、そこに問題の根底があるというのだ。
朝日生命体操クラブは、日本代表、五輪選手などを長年、次々に排出してきた体操界の“ガリバー”のような存在だ。
しかし、その影に選手の「引き抜き」が横行していたという。
前出の元役員は自身の体験も含めて、こう話す。
「私の教え子が全日本でトップ10クラスに入るようになった。すると、突然、子供の親から『朝日生命に行きたい』と移籍を求めてきたのです。合宿の時に、塚原夫妻から『うちにくればもっと実力が伸びる』『オリンピックも夢ではない』『大学、社会人とうちからなら、いいところに入れるよ』と誘われたそうです。選手の親がすっかり舞い上がってしまい、移籍したいという。だが、選手は今の練習環境のまま、続けたいという。その前にも、うちから朝日生命に移籍した選手がいた。その選手は朝日生命ではあまり活躍できず、やめてしまった。そこで、一度、活躍できなかった選手とその選手の親を合わせ、話をしてもらったら、移籍しないことに決まりました」
だが、問題はそこからだったと前出の元役員は続ける。
「移籍しないと塚原夫妻に伝えたところ『あんたなんかもうこれ以上、伸びないわ』『太っている体型見てもダメだ』『オリンピックなんて選ばれるわけない』などと罵詈雑言、言われてショックを受けたそうです。試合会場で、千恵子氏に会うと『よくもうちを断って、ここにこれたな』と嫌味を言われ、以来、選手は挨拶しても無視されるようになった。今回の宮川選手も、移籍を断ったことで塚原夫妻がいやがらせしたと多くの体操の指導者、選手は思っています」
実は、朝日生命体操クラブ、塚原夫妻の「移籍」をめぐる問題は以前にもあった。
1991年には、塚原夫妻の“独裁”に抗議し、全日本選手権に参加した女子体操選手91人中55人が大会をボイコットするという内紛が勃発した。
当時、ボイコットにかかわった、有名クラブのコーチはこう話す。
「体操は採点競技です。そこが一番の理由でした。簡単に言えば、朝日生命や塚原夫妻の息がかかっている選手は高得点。明らかに、技も決まっている選手が低い点数に抑えられる。日本ボクシング連盟で“奈良判定”という話がありました。体操でいえば、“塚原判定”。自分の教え子らを、審判に配置して有利に進めるのです。それに激怒した、選手、指導者が大会をボイコット。オリンピック候補選手も含まれていて、社会問題になりました」
今の宮川選手のパワハラ問題と構造はそっくりと指摘する体操関係者は多いという。
この時の責任を取って光男氏は女子競技委員長を辞任、ボイコットした選手らの試合出場を認めることでなんとか、収拾した。
だが、2012年には光男氏がロンドンオリンピック日本選手団の総監督を務めるなど、塚原夫妻が完全復活して、同じような問題を引き起こしているのだ。
「塚原夫妻は、1991年のボイコット問題でも、最初は強気なことを言いながら、形勢不利となると、辞任すると言い出しはじめる。今回、急に宮川選手に謝罪すると言い出したのとそっくり。塚原夫妻のこれまでの体操界の貢献は認めます。しかし、やり方が狡猾。
例えば、体操は国際ルールで技の加点など、ルールがよく変わります。体操競技の幹部でもある塚原夫妻には、世界の情報もいち早く、キャッチできる。そこで、情報を独り占めにして、先に自分のチームの選手に新ルールの加点の技などを練習させてから、それを他の選手に伝える。そりゃ、とんでもない差がつきます」(前出の役員)
さらに宮川選手の告発については、こう述べた。
「18歳の宮川選手を矢面に立たせて、申し訳ない気持ちでいっぱい。本当はわれわれ、指導者が声をあげるべきだった。しかし、塚原採点などで前途ある選手が嫌がらせされるかもと思うと、声をあげることができなかった。実際、私の教え子はオリンピックに出場できると思っていたが、明らかに塚原判定で、機会を失ってしまったことがある。これを機会に塚原夫妻は体操界から去ってほしい。そして、透明性の高い、日本体操界に生まれ変わってほしい」
(取材班)
84年ロス五輪の体操で金メダルを獲得した森末慎二氏(61)が3日放送のフジテレビ系「バイキング」(月~金曜・前11時55分)に出演し体操女子で16年リオ五輪代表の宮川紗江(18)からパワハラを指摘された日本協会の塚原千恵子・強化本部長(71)と、夫の塚原光男副会長(70)が2日、代理人を通じて声明を発表し、「宮川紗江選手に対して直接謝罪をさせて頂きたい」と謝罪したことに「これで謝るんでなくて、ちゃんと記者会見、かたや18歳の女の子が記者会見をしているんですから、大人なんですから、ちゃんと表に出て来て記者会見をまずしていただきたい」」と示した。
さらに森末氏は声明文の中で「今年の10月25日から11月3日までカタール・ドーハで開催される、東京オリンピックの出場権のかかった第48回世界体操競技選手権大会を控え、さらには、その大会に向けた9月24日から9月30日まで及び10月7日から10月13日までの2回の合宿を控え、現在、とても大事な時期にある日本代表候補選手の皆様に対し、この度の一連の問題で、落ち着いて練習できない状況を招き多大なるご迷惑をおかけしていることについて、深くお詫び申し上げます」と世界体操と東京五輪に触れていることに「これ必要ですか?」と疑問を投げかけた。
その上でこの部分を「完全に関わりたいがために載せている。謝罪文、なんら関係ないコメントですよね。これで自分が行こうとしているわけですよね。これに行けないのは誰なんですか?宮川選手なんですよ。その人の気持ちを考えて、それを載せていること自体がどういう神経の持ち主なのかな」と断じた。
さらに「謝罪文で辞任があるのかなと読んでみると、端から自分が五輪まで行くということをしていること自体がこれを見て協会は何をしているんだと」と訴えていた。
テレビ朝日スポーツコメンテーターの宮嶋泰子氏は本当に下記のように考えているのならおかしいと思う。今回の件まで彼女の事について
全く知らなかったが、このような人がテレビ朝日スポーツコメンテーターであるのなら、バイアスがかかった情報が発信される危険性があると
思う。
宮嶋泰子氏は速見氏が認めた暴力だけをアピールするが、パワハラに関しては関心がないように思える。
宮嶋泰子氏は27年前の女子55選手ボイコット事件について知っているのならこの件について詳しく説明してほしい。
「清廉潔白。汚いことが嫌いな人」がどのような点で現れているのか説明してほしい。
体操取材歴40年のテレビ朝日スポーツコメンテーターの宮嶋泰子氏(63)が3日、自身のフェイスブックを更新。女子体操の宮川紗江(18)が日本協会の塚原千恵子・女子強化本部長(71)らからパワハラを受けたと主張した問題について「私のところにSNSでの誹謗中傷もかなり来ています」と明かし、自身の見解を改めて示した。
【写真】日本体操協会の塚原光男副会長(左)と塚原千恵子女子強化本部長
宮嶋氏は「今回の体操暴力&パワハラ事件に関して、何やら、私のところにSNSでの誹謗中傷もかなり来ています。テレビで体操協会の暴力事件は塚原夫妻の陰謀であるという意見を体操OBがテレビで伝える中、私は塚原陰謀説を否定してきました」とコメント。その上で「偶然この事件の発端からじっとそばで見ておりましたので、今日は私なりの見解をお伝えします」「男子体操OBたちが色々な番組に自ら出演を申し出て主張を繰り返してされていました。しかし、私の見解は異なります。ここにそれを整理してお伝えします」とつづった。
まずは「なぜ数年にわたって繰り返し行われてきた速見コーチの暴力が今頃急に問題になったのか?」との点について、「以前の所属先やナショナルトレーニングセンター(NTC)などで繰り返し行われてきた速見氏の暴力ですが、同じ練習場所でトレーニングをしていた選手やコーチが、このことについて塚原千恵子強化部長に報告しました」「すると偶然これと同じ時期に、別ルートから日本スポーツ振興センター(JSC)にも速見氏の暴力の報告と調査依頼が提出されていました」と説明。
「慌てたのは体操協会です。自分たちがこの問題をきちんと処理しなければ、JSCがこの暴力問題を徹底的に調査し始めます。JSCから調査が入り体操協会の不祥事が明るみになればこれは体操協会の不名誉な出来事となります。そこでまずは、日本体操協会内でこれを徹底的に調査するので、JSCの調査はそれが不十分だった場合に行ってもらうようにしたのです」とし、「山本専務理事による選手やコーチ及びクラブの聞き取り調査が始まり、多くの目撃証言が寄せられ、早い決断で、無期限資格停止となりました。この処分は本人が悔い改めしっかりした指導がなされれば戻ってくることも可能というものです。大会への出場やNTCでのトレーニング指導はできませんが、一般の体育館での指導は可能です。その指導者の生活権までは奪わないというものです。この迅速な処理によって、JSCからの調査は行われないこととなりました。生半可な結論ではJSCからの再調査が行われる可能性があったのです。これが、なぜ急にこの暴力問題が取りあげられ早い処置がなされたかという理由です。塚原夫妻が選手とコーチを離す意図で早い処置をしたという推測は間違いだとお分かりになると思います」とした。
次は「宮川紗江選手が感じた恐怖の下地は引き抜き?」という点。宮川と塚原氏が話し合いを行った7月15日に現場で取材していたという宮嶋氏は「宮川さんや速見コーチは以前から、塚原夫妻の引き抜きが頻繁に行われていると信じていました。そして今それが行われていると思っていたのです。実は私はこれは『思い込み』だと感じています」と主張。「確かに朝日生命体操クラブには日本全国から優秀な選手が15歳ぐらいで移籍してくるケースがありました。しかしそれは自分で望んだり、移籍した選手の好成績を見て後を追って移籍して来たり、または親同志のコネクションで移籍して来たりするケースが多かったようです。塚原千恵子さんは『自分で勧誘したことは一度もない』と言っています」と明かし、「又、昨日私のところに入った元朝日生命選手からのコメントによると、7年間の在籍中に引き抜かれてきた選手は一人もいなかった。テレビで男性体操OBが話している『引き抜き』は思い込みに過ぎない、きちんと調べてから発言してほしいと明言していました」と記した。
3点目は「塚原夫妻のハラスメント」について。「もともと、自分の考えを前面に押し出す塚原千恵子さんは、『おかしいものはおかしい』とはっきり口に出すタイプでした」と明かし、「ですから体操界でも塚原さんから嫌われている人も多くいました。反対に、塚原千恵子さんを嫌う人も多くいたことになります。こうしたことも、今回、体操OBが塚原攻撃に出た一つの要因でしょう。『おかしいものはおかしい』と言ってしまうことも、今の時代はハラスメントにつながると指摘する弁護士もいます」とつづった。
4点目は「専属コーチの暴力問題から、協会幹部へのハラスメントへ」。「今回宮川紗江さんと並んで記者会見などに臨んだ山口弁護士の手腕は見事でした。コーチの暴力問題を協会幹部から選手へのハラスメントへ移行させてしまったのですから。顧客である宮川サイドの応援という意味では完璧だったでしょう」と宮嶋氏。「ただ、だからと言って、暴力問題が薄まるわけではないということです。これは絶対にダメなのです。そして暴力を受けた選手が『私は大丈夫です』などと言ってもいけないのです」と強調。「そして組織の幹部もハラスメントにもっと意識を向けなくてはいけないということです。昔の体育会の上意下達の世界で育ってきた幹部連中には選手がコーチの指示を聞くのは当たり前という思いがあります。しかし時代は変わり、選手とコーチが話し合いながら、よい方法を考えて実践していく時代に入ってきているのです。そこを認識する必要があるでしょう。昨夜塚原夫妻のお詫びのコメントがファクシミリで流れました。そのあたりに二人が気付いてくれたとしたのならうれしいことです」とつづった。
5点目は「これからの宮川紗江さん」について。「宮川さんは高校を卒業して今年春、『私は内村航平さんと同じプロです』と公言しています」とし、「現実的には練習環境の確保や資金繰りなど難しい面も多々あったのでしょう。この記者会見の時には所属先も決まっていない状態でした。宮川さんは大阪体育大学ダッシュプロジェクトの4年契約がありましたが、それもどうなったのかわからないままで、さらには2か月ほど所属したスポンサー企業から外れることを宮川さんサイドが強く要望し、8月下旬に外れています。こうした、今、自分が置かれている状況を打開したいという思いもあったでしょう。今回の件で、スポンサーがつき、安心してトレーニングができることになればこれ以上のことはありません」と記述。
「10月下旬から11月にかけて行われる世界選手権を辞退し、ナショナル合宿にもいかないということなので、次回宮川選手を見るのは4月の大会になるはずです。私はこれはとても良い決断だと思っています。ゆかと跳馬が得意であるにも関わらず、試合の度に足首を痛め、思うように着地ができず、7月1日の全日本種目別では7位に終わってしまっています。根本的な治療とトレーニングの改善を行い、4月に向けて基礎からやり直していくことが求められます。体操協会から練習場所の斡旋などがあると望ましいのでしょう。今から来春の宮川選手の演技が楽しみになっているファンも少なくないと思います」とつづった。
最後に宮嶋氏は「この事件をきっかけに、みんなが一致団結して世界選手権でメダルを獲るという目標に向かい、東京オリンピックの団体出場権を獲得してほしいと思っています」と願った。
日本協会の塚原光男副会長と塚原千恵子・強化本部長の人間性が疑われるような対応を取る当人が悪いと思う。
女子体操のリオ五輪代表、宮川紗江選手(18)からパワハラを告発されていた日本体操協会の塚原千恵子女子強化本部長(71)と、その夫である塚原光男副会長(70)が2日、代理人弁護士を通じて連名で新たなプレスリリースを発表、宮川選手へ直接謝罪したい考えを公表した。
8月31日に出した「一部謝罪と反論、弁解」のプレスリリースが矛盾点だらけで、宮川選手へさらなる不安と恐怖心を与え、世論の大反発を受けたことに対しての緊急コメント。「二人の大人が与えてしまった影響は計り知れず、宮川選手を深く傷つけてしまったことは許されるものではない」と反省しているが、パワハラ行為について認めるコメントはなく、何に対して、どう直接謝罪したいのかという重要な点についても明確にされていない曖昧で不透明な直接謝罪表明だった。現時点で宮川選手が、直接の謝罪を受け入れることは難しい内容で、事態の沈静化を目的とした“火消し謝罪”への疑惑が浮かんだ。
2日の夜になって急遽、出されたプレスリリースは「宮川紗江選手に対する謝罪」と題されたもので、全編が塚原女子強化本部長と塚原副会長の共同コメントという体裁になっていた。
まずは、8月31日に出したプレスリリースが「反撃」「反論」「徹底抗戦」と報道されたことに対して「信じて頂けないかもしれませんが、私たちには、そういった意図は一切ございません」という全否定から入った。そして、その矛盾にあふれた「反論と弁解」のプレスリリースが生んだ宮川選手の困惑について「私たちのプレスリリースにより、さらに宮川選手を傷つけ、誤解を与え、恐怖心を抱かせ、不信感、不快感を与えてしまったのであれば、全ては私たちの責任であり、本当に申し訳なく思っております」と謝罪。
テレビ番組に出演して、そのプレスリリースに対する不信感を語る宮川選手の様子を見ていたようで、「私たちの配慮不足や自分たちの名誉を少しでも回復したいという勝手な考え等のため、さらに宮川選手を深く傷つけたと知り大変申し訳なく思っております」と続けて謝罪した。
さらに「体操協会の副会長及び強化本部長という立場であり、一人一人の選手に敬意を持たなければならない立場にあります。また、何よりも「一人の大人」として、私たちの落ち度も認め、私たちの正当性を訴えることよりもまずは宮川紗江選手に誠実に謝罪し、向き合うことが大事であるにもかかわらず、宮川紗江選手を深く傷つけてしまったことに対して、重ねてお詫び申し上げます」とも続けた。
また様々なテレビ番組で司会者やコメンテーターからプレスリリースに対して批判が集中したことに対しても「そのようなご意見等も全て真摯に受け止めております」とした。
世論の逆風と反発を受ける最大の原因となった塚原女子強化本部長の「黙ってないわ」、塚原副会長の「全部うそ」発言についても、「私たちの感情に任せた自分勝手な発言等により、宮川選手と対立姿勢にあるとの印象を与えてしまいました。このような発言につきましても宮川選手やご家族に対して恐怖心や不快感等を与えてしまったと思っており、本当に申し訳なく思っております」と反省、謝罪の意を示した。
そして「今回の一連の報道につきましては、その過程はどうであれ、私たちの落ち度が大きな原因と考えております」とした上で「私たちは、今回の一連の件につきまして、宮川紗江選手に対して直接謝罪をさせて頂きたいと考えております」と直接謝罪したい考えであることを明らかにした。
だが、宮川選手が告発したパワハラ行為を認めるコメントは一切なく「ハラスメント問題につきましては、日本体操協会が立ち上げる第三者委員会の調査活動に全面的に協力し、その判断を待ちたい」と、依然“対決姿勢”であることを明記している。
今回のコメントでは、正当性を訴えた前回のプレスリリースの不備については全面的に謝罪してはいるが、宮川選手が、訴えているパワハラ発言、行為の何をどう認めて、何に対して謝罪をするのか、という肝心な部分がまったく明記されていなかった。
何について謝罪するのかの理由が、「今回の一連の件」では、あまりに曖昧で不透明だ。「私たちの落ち度が原因」とも書かれたいたが、その落ち度が、具体的に何を示すのかも書かれていなかった。
宮川選手には、山口政貴弁護士がついているため、何について謝罪するのかの重要な部分が明らかになっていない以上、単なる事態の沈静化を目的としたような謝罪は受け入れないと見られる。
そのあたりを塚原夫妻も、代理人弁護士の“差し金”で予測しているのか、「もちろん、宮川紗江選手は私たちに会いたくないかもしれません。まだ18歳という年齢であり、さらに将来を期待されている宮川選手に対して、私たち二人の大人が与えてしまった影響は計り知れず、宮川選手を深く傷つけてしまったことは許されるものではないと思っております。それは、取り返しのつかないことかもしれません。しかしながら、もし、私たちに直接謝罪をお伝えできる機会を頂けるのであれば、宮川選手に対して直接謝罪をさせて頂ければと思っております」とも書かれていた。
そして、あろうことか、「このプレスリリースの内容に関しましても、私たちの配慮や想像力不足等により、さらに宮川選手を傷つけてしまうかもしれず、また多くのご批判又は厳しいご意見、そしてまだまだご納得いただけないこともあるかと思いますが、その点につきましても真摯に受け止めたいと思っております」と“予防線”までを張っているのである。
何も、1億総“魔女狩り裁判”をしているわけではない。ただ、こうも、コロコロと主張と謝罪が繰り返されていれば、何をどう信じていいのかもわからないし、肝心のパワハラ部分を認めないのだから、直接謝罪の希望に疑いを覚えるのは当然だろう。しかも、今回のコメントをよく読むと、自分たちの落ち度が何であり、そもそも18歳の少女を傷つけ、その彼女が勇気ある告発をするに至った根本の問題に関しての具体的な説明や理由などが発信されていないのだ。
両夫妻が、直接謝罪の前にすべきことは、第三者委員会の調査よりも、先にまずパワハラ行為を認めることだろう。そして速見佑斗コーチを唐突に除外しようとした理由と背景も明らかにしなければならない。
もっと言えば前回のプレスリリースの矛盾点に対しての説明をしてもらいたい。
宮川選手は、無期限の登録抹消処分となった専属コーチの速見氏の処分軽減と、塚原夫妻が協会を去り、協会の体制が一新されることを求めている。具体的なパワハラ行為を認め、協会の役職を辞任する考えをセットで明らかにした上で、直接謝罪をしなければ、ただの逆風を沈静化するだけの“火消し謝罪”だという疑惑の目を向けられてもおかしくないのである。
(文責・本郷陽一/論スポ、スポーツタイムズ通信社)
「ちょっと思い込みが強い」のか、性格で強い部分が宮川紗江さんにはあると思う。そうでなければ、単純に日本協会の塚原光男副会長と塚原千恵子・強化本部長に問題があると思うだけでここまで出来ない。
テレビ朝日局スポーツコメンテーターの宮嶋泰子氏(63)のコメントや判断について多くの人が中立性や判断力に疑問を抱いたり、批判していること
に気付いているのだろうか?
もし気付いているのなら、意図的にやっているのか?気付いていないのならそういう人なのだろう。
2日放送のテレビ朝日系「サンデーLIVE!」(日曜・前5時50分)で女子体操の宮川紗江(18)が日本協会の塚原千恵子・女子強化本部長(71)らからパワハラを受けたと主張した問題を特集した。
スタジオには体操取材歴40年の同局スポーツコメンテーターの宮嶋泰子氏(63)が出演し今回の問題について宮川と塚原氏が話し合いを行った7月15日について「パワハラがあったといわれる15日、私はここにいたんですよ。30人ぐらいの選手とコーチがいて、カメラもいて、私はドキュメントを撮っていたので宮川さんが部屋に入っていくのを見ているし、出て行くのも見ているし、多分、一番近くで見ていたと思います」と明かした。
その上で宮川の告発を「宮川さんがみなさん18歳の少女っていうんですけど、彼女は高校を卒業した後、自分は内村航平と同じプロ選手ですって宣言した初めての女子選手なんですね。そういう意味でいろんなことを自分で意識的に持っている人だと思うんですけど。それと同時に私が思ったのはちょっと思い込みが強いかなと感じていて。今回のきっとそうに違いない、私は感じましたというコメントいっぱいありましたけど、本当にそうなのかって。今回、いろんなところで話が交わされていますけど、ほとんどが、多分、そうなんだろうという思い込みをベースにみんな話しているんですね。私は、真実、ファクトとかこれはこうだっていうものを少しづつ検証したいなと思っていろんな取材を今、続けています」と見解を示していた。
「テレ朝宮嶋泰子氏、塚原千恵子氏は『清廉潔白。汚いことが嫌いな人』」
夫のの日本協会の塚原光男副会長がなぜ全部嘘と発言したのか、ズバッと言ってほしい。清廉潔白なら言えるはずだ。
痴呆症の初期段階なのか?
昔の話はいつのことか?元アナウンサーなのだからもっと具体的に言うべき。5年ぐらい昔、10年ぐらい前?そしてこの件から
清廉潔白で汚い事が嫌いな人と断定する根拠なのか?
人を説得させるために根拠としては不十分だと思う。
2日放送のテレビ朝日系「サンデーLIVE!」(日曜・前5時50分)では女子体操の宮川紗江(18)が日本協会の塚原千恵子・女子強化本部長(71)らからパワハラを受けたと主張した問題を特集した。
スタジオには体操取材歴40年の同局スポーツコメンテーターの宮嶋泰子氏(63)が出演し塚原千恵子氏について「軽くポンポンって言っちゃうタイプの人なんで、それはいつものことなんですけど」と明かした。
その上で「ただここで私、ひとつ言いたいのは、千恵子さんというのは物凄く実は清廉潔白というか汚いことが嫌いな人なんですよ。だいたいパワー持ってお年寄りっていうとダキーッていうイメージあるでしょ。そうじゃなくて、例えば昔、遠征に行った時に当時の会長が選手にお小遣いあげようしたら、お金で選手を釣らないでくださいって言って、それで大げんかして協会を辞めたというプロセスがあるんですけど」と紹介し「そうやってズバッ、ズバッて言っていくので、選手の中にもコーチの中にも塚原さんを嫌いな人はいます。本当のことをズバッと言っちゃうから、えってドキっとしちゃうんですね」と指摘した。
この発言に対して、他の出演者から「だからこそ、パワハラが生じる余地があるんです。だからこそご本人はもっと注意しないといけない」と指摘されると宮嶋氏は「そうかもしれないですね」とうなずいていた。
状況が不利だと思って謝罪して、調査を中断する作戦に変更したのか?
宮川紗江選手は事実関係の調査が終了するまで、直接的なコンタクトは取るべきではないと思う。汚い人間達は心に思っていない事を口にするし、
嘘を平気で付く。力関係で大きな差がない限り、相手に情けや同情は禁物だ!抜け穴を見つけると直ぐにでも噛みついてくる。
城で例えるなら、全ての堀が埋められ、兵糧がない状態にしておかないと気を許す事は出来ない。油断するとそこを突かれて苦しめられる。
下手をするとこちらが瀕死の重傷を負わされる。
「ごめんなさい。これからは仲良くしましょう。」で終わるような人間であれば、初期の段階であのような選択をしなかったと思う。
汚い人間は機会を与えると今度はもっと姑息に反撃してくる。戦いを選択した以上、中途半端で終わらせるべきでない。
事実が判明し、公表され、彼らの処分が決まってから、謝罪の機会を与えるべきだ。本当に謝罪の気持ちがあるのなら、処分を受け入れ、
処分後でも謝罪するはずだ。処分後に謝罪をしないのであれば、やはり、心にもない処分を回避するための口実だったと判断して間違いない。
体操女子でパワハラを指摘された日本協会の塚原光男副会長と塚原千恵子・強化本部長は2日、報道各社へFAXを送付し「宮川紗江選手に対する謝罪」のコメントを発表した。
【写真】パワハラを告発した宮川紗江
塚原夫妻は前回のプレスリリースにより、一部で「反撃」「反論」や「徹底抗戦」と報道されたことについて、「そういった意図は一切ございません」とした上で、「私たちのプレスリリースにより、さらに宮川紗江選手を傷つけ、誤解を与え、恐怖心を抱かせ、不信感、不快感を与えてしまったのであれば、全ては私たちの責任であり、本当に申し訳なく思っております」と謝罪した。
さらに「私たちは、体操協会の副会長及び強化本部長という立場であり、一人一人の選手に敬意をもたなければならない立場にあります。また、何よりも『一人の大人』として、私たちの落ち度も認め、私たちの正当性を訴えることよりもまずは宮川紗江選手に誠実に謝罪し、向き合うことが大事であるにもかかわらず、宮川紗江選手を深く傷つけてしまったことに対して、重ねてお詫び申し上げます」「もし、私たちに、直接謝罪をお伝えできる機会を頂けるのであれば、宮川紗江選手に対して直接謝罪させて頂ければと思っております」などと塚原光男、塚原千恵子の連名でコメントを発表した。
体操女子の世界選手権(10~11月、カタール)代表候補で、2016年リオ五輪代表の宮川は、自身への暴力行為で日本協会から無期限の登録抹消などの処分を受けた速見佑斗コーチ(34)に関する会見を開き、速見氏の暴力行為の事実があったことは認め、改めて師事する意向を示した。また、日本体操協会の塚原千恵子・女子強化本部長が背後にいると指摘し「権力を使った暴力。パワハラだと思う」と8月29日に告発していた。
体操の2016年リオデジャネイロ五輪女子代表、宮川紗江(18)が日本体操協会幹部からパワハラを受けたと主張した問題に体操界が大揺れだ。宮川が「勇気を振り絞って」告発した対象の1人、女子体操界の女帝、塚原千恵子強化本部長(71)の横暴ぶりに現役選手、OBらがツイッターなどのSNSで援護射撃し、一斉蜂起した。協会の副会長で夫の塚原光男氏(70)が宮川の主張を「全部ウソ」と全否定したことも火に油を注いだ格好で、怒りの炎が燃え広がっている。塚原夫妻は31日、反論の文書を公表した。
パワハラ行為を受けたのは信頼する速見佑斗コーチ(34)からではなく、塚原本部長からです-。女子体操界を支配し、協会の常務理事でもある女帝に真っ向勝負を挑んだ衝撃の告発。同じ心境だった選手らが一斉に反応、宮川を応援し、エールを送る言葉などが相次いでいる。
《いろんな形での助け方があります。私もさえのためにも、選手たちのためにも、協力します。心配で仕方がない》と30日にツイートしたのは元日本代表の田中理恵さん(31)。宮川にエールを送った元体操選手らの投稿も相次いでリツイート(拡散)した。
田中さんは27日付のブログで、塚原本部長が女子監督を務めた12年ロンドン五輪の代表メンバーたちとの食事会の写真をアップし、《懐かしい話で盛り上がったり、体操以外の話で盛り上がったり》とコメントをした。
宮川が、速見コーチについて「パワハラされたと感じていません」とする手記を20日付で発表するなど、速見コーチの登録抹消問題が大きく注目を集めていた時期だけに「体操以外の話」というくだりに関心が集まっていた。
リオ五輪団体金メダリストで「ひねり王子」こと白井健三(22)も敏感に反応。宮川は体操教室を運営するレインボー(愛知)に所属し、20年8月末まで契約を残していたが22日になって突然、契約解除となった。この事態を受け、高須クリニック(東京)の高須克弥院長が支援宣言する内容をツイートしたところ、これをリツイートした。
体操界に関わる複数の関係者が同調、賛同する姿勢をみせていることから、「#MeToo」の動きは今後加速するのは確実だ。
妙な動きもあった。宮川と同じくリオ五輪の代表でチームメートだった寺本明日香(22)=ミキハウス=が30日夜、「緊急会見を行う」との情報が流れ、報道陣が急きょ、宮川が使用を制限されていると明かした「味の素ナショナルトレーニングセンター」(NTC=東京)に駆けつけた。
だが、開始時間が過ぎても始まらない。10分程度がたった時、協会の女性職員が現れ、「寺本さんは(報道陣の)みなさんの前でお話ししたかったんですけど、協会から取材の許可が下りないということで、今日はお話できません」と説明し、中止になった。
「誰が会見を止めたのか」と詰め寄る約30人の記者らに、女性職員は協会広報からの報告とだけ話し、寺本の様子については「混乱していると思います」と一言。寺本のほかにもう1人、女子代表候補選手が会見に同席するという情報もあったが、うやむやのまま終わった。
一方、協会がこの日午後、都内で開いた会見では、具志堅幸司副会長(61)が約2時間半にわたって取材に応じた。宮川の告発については「18歳の少女がウソつくとは思えない」と同情し、「宮川さんの(パワハラの)件は本当に初めて知りました」と強調した。
実のところ、この会見が終了したのは、寺本が今にも緊急会見を敢行しようとしていた午後6時だった。
夕刊フジが具志堅副会長に「寺本選手が緊急会見を行おうとしているが」と問うと、みるみる表情が変わり「本当ですか、本当に?」と絶句した。寺本の会見が宮川に続くパワハラの内部告発だったとすれば、体操協会が受けるダメージは計り知れず、協会幹部が中止を指示した可能性がある。
「全部、膿を出して再出発しないと、東京五輪はあり得ない」とも明かした具志堅副会長。だが、それができるガバナンスが利いた体制なら、そもそもこのような状況に直面することもないのだが…。
日本体操協会の塚原千恵子女子強化本部長(71)の夫である塚原光男副会長(70)の全部嘘発言について一切触れていないが、なぜ?????
なぜ「全部嘘」と質問された時に答えたのだろう???
副会長の役割をこなす能力はないのではないのか?金メダルと取ったご褒美なのか?
全部嘘発言に説明をしてほしい!
女子体操のリオ五輪代表、宮川紗江選手(18)からパワハラを告発されていた日本体操協会の塚原千恵子女子強化本部長(71)と、その夫である塚原光男副会長(70)が8月31日、連名の書面で一部謝罪を含めた弁解、反論をプレスリリースした。文書は、5枚にわたる長文で、謝罪から始まり、「1.塚原千恵子の言動について」「2、塚原光男の言動について」「3.今回の件及び今後について」という3つの項目にまとめられていた。
冒頭では、報道による関係者への迷惑や強化合宿中の選手へ与えた精神的動揺などを謝罪。
「まだ18歳という宮川紗江選手にこのような会見をさせてしまったことにつきましても、私たちにも責任があることは確かであり、宮川紗江選手に対して、心からお詫びを申し上げます。私たちの言動で宮川紗江選手の心を深く傷つけてしまったことを本当に申し訳なく思っております」と宮川選手への謝罪の言葉を綴った。
だが、ここから先は、その言葉とは、裏腹に「決して宮川選手を脅すための発言はしていません」という自分たちの正当性を訴える弁解、反論、否定だった。宮川選手の主張を認めた部分がある一方で、その弁解、反論、否定のほとんどが説得力に欠ける矛盾したものだった。
塚原夫妻が“説明文”で認めている点と弁解、反論、否定している点を整理してみる。宮川選手の主張を認めたのは以下の5箇所だ。すべて塚原女子強化本部長の発言に関しての部分である。
(1) 宮川選手の専属である速見コーチに対する「あのコーチはダメ」発言。
7月15日の合宿中に宮川選手は塚原夫妻に個室に呼び出され、速見佑斗コーチの暴力行為について「あのコーチはダメ、だから伸びないの。私は速見より100倍よく教えられる」と発言したと暴露された事実に対して「確かに宮川選手も認めているとおり速見コーチに暴力行為があったため『あのコーチがダメ』とは言いましたが、私が『100倍よく教えられる』とは言っておらず、このような発言をした事実はありません」と説明。「あのコーチがダメ」との発言についてだけは認めた。速見コーチの暴力行為は肯定されるものではないが、宮川選手に「私と速見コーチを引き離そうしている」と感じさせるに十分な発言だ。
(2)「家族でどうかしている。宗教みたい」発言。
同じく7月15日の2対1の聴取で「家族でどうかしてる。宗教みたい。」と発言した点について、「私は暴力について、宮川選手に対して『家族も暴力を認めているの?』と確認したところ『家族もコーチの暴力を認めている』と言っていたため、思わず、たとえとして『宗教みたい』とは言ってしまいました。この言葉については不適切だと大変反省しております」と、反省を込めて認めた。だが、これは宮川選手の家族の人権や名誉を侵害する問題発言である。
(3)「五輪に出られなくなるわよ」発言。
この強烈なパワハラ発言については、「確かに宮川選手にそのようにお伝えしたのは事実です」と認めた。ただ、この発言についても「脅していない」との弁解が付け加えられた。
(4)「2020に申込みをしないと今後協会としてあなたには協力できなくなるわよ」発言。
2016年12月19日に塚原女子強化本部長は宮川選手に電話をかけ「2020東京五輪強化選手」に参加していないことに対して、こう発言したことは認めたが、その理由についての弁解があった。
(5) 速見コーチの暴力行為を認めさせるための誘導質問の存在。
「暴力はあったんだよね、あったんだよね。」と繰り返し誘導尋問のような発言をした行為については「正確にこの時のことをお伝えいたします」と記述。「私は宮川選手に対して、まず、『速見コーチによる暴力はあったの?』という質問をしたところ、宮川選手は無言だったため、私が再度『速見コーチがあなたに暴力をふるっているところを見た人がいるんだけど、暴力はあったんだよね?』と質問したところ、宮川選手が速見コーチの暴力を認めました。ただ、この点について誘導と言われてしまうのであれば、私の確認の仕方に落ち度があったと思っております」と、この発言や、その問答に問題があったことを認めた。
以上の5箇所を認めただけで十分にパワハラ認定されるべきだろう。
だが、一方で、宮川選手の主張に対して、真っ向反論、否定した部分が6箇所ある。ただ宮川選手の主張を認定した発言部分に関して弁解を付け加えるという矛盾したものが多く説得力に欠ける反論が目立った。
(1)「100倍よく教えられる」発言の完全否定。
「『100倍よく教えられる』とは言っておらず、このような発言をした事実はありません」と否定した。おそらく速見コーチと引き離して朝日生命体操クラブへ勧誘しようという意図があったことを否定するために、この発言部分のディティールにこだわって否定したのだろう。
だが、宮川選手は、この日、フジテレビの「グッディ!」のインタビューに答えて、その際、発言をすぐに母に伝え、母がノートにメモで残していることを証言した。
(2)朝日生命体操クラブへの勧誘工作の否定。
宮川選手は7月20日に塚原女子強化本部長の付き人から「NTCで練習できない場合は朝日生命でできる」「朝日生命の寮がひとつ空いている」「朝日生命で練習すれば(塚原)本部長もいる」と優しい口調で言われ、朝日生命の専門コーチの電話番号を渡されたことなどから、「朝日生命へ入れようとしていることを確信した」と、明らかにしたが、この“引き抜き工作”に関しても真っ向否定した。
「宮川選手が、私の付き人から朝日生命体操クラブへの加入を勧められたと、ご主張されておりますが、この点についても真実と異なります。私たちは、宮川選手に関して、一切、勧誘を行っておりません」
だが、過去にも有力選手の朝日生命体操クラブへの引き抜きの例があるだけに説得力に欠け、宮川選手が塚原女子強化本部長の付き人から、このような言葉を投げかけられた場合、直接的な勧誘のアクションではなくとも、その裏の狙いを勘ぐるのは自然だろう。「一切、勧誘を行っておりません」ではなく、そう受け取られるようなアクションを付き人が起こしたことを反省すべきなのだ。
塚原女子強化本部長は、この後の文書で、海外派遣や五輪選考への影響力もなく、独占的な権力を持っていないことを強調しているが、そもそも、相撲部屋や体育会系の学生寮でもないのに自らが“付き人”と称するような人物が存在すること自体、塚原女子強化本部長が、いかに権力を持っているかを象徴する事象でないか。
(3)「五輪に出られなくなるわよ」発言の弁解。
その発言をしたこと事態は認めたが、以下のように弁解した。
「宮川選手の直近の成績が振るわず、足首を怪我していたことを踏まえ『グラスゴー以来、活躍できていない。だんだん成績が落ちてきているでしょう。そして、このような成績や現状のままだと五輪に出られなくなるわよ』という内容を伝えたのです。具体的には今年の全日本種目別選手権で、宮川選手は、得意の跳馬やゆかで成績が振るっていませんでした。また宮川選手は7月4日から10日までのオランダ遠征に選考されて現地に派遣されていましたが、直前の足首のケガで現地の大会の競技には参加することができませんでした」
確かに宮川選手は6月の全日本種目別選手権の跳馬7位、床7位に終わっている。だが、7月15日の面談の目的は、宮川選手の現状に関するカウンセリングではなく、速見コーチの暴力行為に関する聴取だった。
呼び出された目的と話の流れを考えると「五輪に出られなくなるわよ」発言を宮川選手が速見コーチの暴力行為を否定したらどうなるのか?との恐怖を感じたパワハラ発言と捉えるのが自然だ。
(4)「2020に申込みをしないと今後協会としてあなたには協力できなくなるわよ」発言についての弁解。
塚原女子強化本部長は「2020東京五輪強化選手でないと利用できない支援、例えば、女性コーチではない速見コーチでは、指導が難しいゆかの振付等を同強化選手の指導にあたっている女性コーチに行わせるなどの支援を利用できない状態でした。そこで強化本部長であった私は、上記のような発言をした」と弁解した。だが、これは2020東京五輪強化選手のメリットを説明しただけで「協会として協力できない」となぜ言ったかの理由説明にはなっていない。またNTC利用に制限を加えたことへの説明はなかった。
(5)高圧的態度の否定。
宮川選手は、高圧的な態度に「恐怖を抱いた」と主張したが、その点については「そのように宮川選手に対して思わせてしまったのであれば、私の態度に問題があったかと考えており、大変申し訳なく思っております。ただ、今後、第三者委員会に提出予定である、私たちが保有している宮川選手との録音内容をお聴きいただければ、私が決して高圧的な態度ではないということはお分かりいただけると思っております」と、宮川選手との面談の録音があることを明らかにしたのだ。
だが、この録音についても大きな矛盾が存在する。
7月15日の面談に同席した塚原光男副会長は、(3)の項目にこういう弁解を掲載した。
「『速見コーチが除外されたら困るのは、あなた。今すぐ(コーチとの)関係を切りなさい』との発言をしたと、お話されておりましたが、正直に申し上げて発言内容について正確に覚えていないところもあります。言い訳に聞こえるかもしれませんが、大変申し訳ございません」
録音があるのならば、なぜ正確に覚えていないのだろうか?
テレビ朝日系の「報道ステーション」では、塚原夫妻が提供した録音データが公開されたが、問題とされるやりとりの部分ではなかった。おそらく合宿の途中辞退を伝えた7月16日の面談のものと見られる。高圧的な態度を否定する証拠であるはずの録音が、宮川選手が、そう感じた7月15日の面談のものでないのならば、何の証拠にもならない。
最後の「今回の件及び今後について」の項では「私たちの言動が宮川選手を傷つける結果になってしまったことは事実であり、選手を監督・指導する立場にありながら、宮川選手の心を傷つけていることに気づくことができなかったことについて猛省しております」と、否定、弁解、反論の一方で、謝罪するという矛盾した文章が載せられていた。宮川選手をなぜ傷つけたのか?を考えれば、こういう弁解や反論は出てこないだろう。
塚原夫妻は、日本体操協会が立ち上げる第三者委員会の調査に全面協力する姿勢と、今後の進退については「第三者委員会の結果等も踏まえ、各関係者と協議することも検討しております」とも記した。
ただ、「体操の関係者たちが私たちに対して厳しい目を向けており、かつての選手たちからも大変厳しいご意見をいただいております。これは、全て私たちの今までの行いに原因があると思っております」とも書かれており、こういう反省が本当にあるのならば、必然、現職を辞任するべきであるし、18歳の勇気ある告発をした宮川選手を、さらに困惑させるような弁解、反論は避けるべきではなかったか。テレビメディアに、塚原副会長は「(宮川選手の主張は)全部ウソ」とまで喋っているのだ。
しかも、具志堅幸司副会長を中心とした協会が示した、この問題への早急な解決姿勢に反するような動きを行ったことへの疑念も浮かぶ。協会の副会長でありながら、その方針に同意できないのであれば、メディアに意見を述べる前に協会内での議論を最優先すべきだった。納得がいかないのならば協会を去るべきだろう。
(文責・本郷陽一/論スポ、スポーツタイムズ通信社)
体操の84年ロス五輪金銀銅の3つのメダルを獲得した森末慎二氏(61)が30日放送のTBS系「ビビット」(月~金曜・前8時)に生出演し、体操女子の世界選手権(10~11月、カタール)代表候補で、2016年リオ五輪代表の宮川紗江(18)が29日、自身への暴力行為で日本協会から無期限登録抹消などの処分を受けた速見佑斗コーチ(34)に関する会見を東京都内で開き、処分軽減を求めた問題について見解を示した。
会見で宮川は、速見氏の暴力行為は認めた上で、改めて師事を表明。処分を下した日本協会の意図を「コーチと私を引き離そうとしている」と述べた。塚原千恵子・女子強化本部長(71)の関与を指摘し「権力を使った暴力。パワハラだと思う」と告発した。
この宮川の告発について塚原氏の夫で協会の塚原光男副会長(70)は30日朝に「全部ウソ」と発言した。これに森末氏は「あれだけしっかりした言葉でしゃべってそれを聞いて、あんなウソを言うのかわからないと言っていること自体が怪しいですよ。どっかで聞いたフレーズかなと」と塚原氏の発言に疑問を呈した。
2018年8月30日の報道ステーションが宮嶋泰子氏の塚原千恵子本部長に対する電話インタビューと発言を見た。中立な立場で発言しているとは
全く思えなかった。話し方や顔の表情などを見ると単純にその人の人間性が出るのかもしれないが、演技しているように思えた。報道ステーション
を見た人はどう思ったのだろうか?
「宮嶋 泰子(みやじま やすこ、旧姓・増山 / ますやま、1955年1月9日 - )は、テレビ朝日スポーツコメンテーター、元同局アナウンサーで、編成局アナウンス部エグゼクティブアナウンサー兼編成部。富山県高岡市生まれ、神奈川県鎌倉市で2歳から25歳まで過ごす。早稲田大学スポーツ科学部で非常勤講師(2006年から2011年まで)。日本女子体育大学招聘教授(2015~2016)。順天堂大学客員教授(2015~2018)・・・テレビ朝日アナウンス部副部長→アナウンス部・編成部(部長待遇→局次長待遇)→上級マネジャー→エグゼクティブアナウンサー→定年退職→テレビ朝日スポーツコメンテーター・・・2015年6月~ 公益社団法人日本新体操連盟理事」(情報源:宮嶋泰子(ウィキペディア))
元テレビ朝日のアナウンサーであり、大学でも教える立場の人間が中立的な立場で話す事が出来ないとは驚いた。まあ、あのような発言をして
多くの人が宮嶋 泰子氏を信じると思うのか?いろいろな肩書を持っているけれど、人間的には薄っぺらい人間なのかもしれない。学歴や
教養があり、いろいろな経験しても、歪んだ視野に気付けないのは、人間性に問題があると思う。まあ、テレビを見た人達が判断すれば良い事。
流れ的には日大の悪質タックルのように思える。なんとか抑えようと対策する事自体、悪いイメージを増幅しているように思える。
宮嶋泰子が体操協会と塚原夫妻を擁護する理由!横野レイコのようだと話題に 08/30/18(トレンドな情報について語るブログ)
宮嶋泰子(ウィキペディア)
“体操エリート一家”が渦中の人に
女子体操の宮川紗江(18)選手にパワハラではないかと名指しされた塚原光男・千恵子夫妻はどのような人物なのか?
2人の経歴や体操関係者の証言から、その実像に迫る。
40年以上の長きにわたり、日本女子体操界を牽引してきた日本体操協会の塚原千恵子女子強化本部長(71)。
現役時代は、1968年のメキシコシティオリンピックに出場し、女子団体で4位入賞を果たした。
【画像】協会からのパワハラを告発した宮川紗江選手の表情は…
引退後に結婚した相手は、鉄棒の大技「月面宙返り」の生みの親で3大会連続の金メダリスト、現在、体操協会の副会長を務める塚原光男氏だ。
息子の直也さんも2004年のアテネ五輪で金メダリストとなるなど、塚原家は“体操エリート一家”として名を馳せている。
千恵子氏は、息子の金メダル獲得に「まだ1つだけどね。本当に感激しました」と涙目で語っていた。
しかし今、その塚原夫妻が騒動の渦中に立たされている。
「塚原千恵子本部長に嫌われると大変」
30日午前8時半ごろ、無言で車に乗り込み自宅をあとにした千恵子氏。
一方、その約1時間前に家を出た夫の光男氏は…
塚原光男氏:
なぜ彼女(宮川選手)がウソを言うのか分からない
と答え、 8月29日の会見で宮川選手が訴えた千恵子氏らによるパワハラ行為を全てウソだと否定した。
宮川選手は29日の会見で、
宮川紗江選手:
最初から速見コーチの過去の暴力を理由に、速見コーチを排除して、(私を)朝日生命に入れる目的なんだと確信に変わりました。私はこれこそ権力を使った暴力だと感じます
と発言している。
千恵子氏は、結婚後、夫とともに朝日生命体操クラブを率いるとともに、女子日本代表チームのコーチなどを歴任。
北京五輪やロンドン五輪では女子代表の監督も務めた千恵子氏について、ある体操関係者は、番組の取材に次のように語った。
「塚原本部長に嫌われると大変。宮川選手以外にも『今日はナショナルトレーニングセンター使わせてもらえなかったんだよね』という選手もいた。ただ、いま携わっているコーチもそれを言うと、自分の選手もはじかれてしまう。それが怖くて、塚原に意見を言えない」
全日本選手権での“採点操作”疑惑も…
日本体操協会の要職とクラブチームという2つの力を持つ千恵子氏。
1991年の全日本選手権では、審判が千恵子氏率いる朝日生命の選手に有利な採点をしたとの疑惑が浮上し、出場選手の半数以上がボイコットする事件も起きた。
この騒動について、ロサンゼルスオリンピック金メダルの森末慎二さんは、次のように語る。
森末慎二氏:
この時も塚原千恵子さんがある程度力を持った状態で、選手ではなくて審判も自分のテリトリーに入れてしまった。自分のところの選手に点数を出すように、みたいなことをやられてしまった
騒動の末、当時、女子競技委員長だった夫の光男氏が辞任する事態となった。
森末慎二氏:
というか、ご夫婦で協会にいること自体がおかしい。他の協会ではあんまり聞いたことがないですね
と話す。
宮川選手「一緒に体操界を変えるためにも真実を明らかに」
塚原千恵子氏と光男氏に呼び出されたことを朝日生命クラブへの強引な勧誘だったのではないかと告発した宮川選手。
光男氏がこの発言を全てウソとしたことについて、宮川選手は30日午後0時半ごろ、フジテレビの単独インタビューに応じ、次のように語った。
宮川紗江選手:
そういうことを言ってくるんだろうな、というのは想像していたし、だろうなとは思ったんですけど。自分のしたことは認めてほしい。一緒に体操界を変えるためにも真実を明らかにして欲しい
体操界を揺るがすパワハラ疑惑を受け、30日に対策会議を開いた日本体操協会の具志堅幸司副会長は、会議終了後の会見で、第三者委員会を設置することを発表した。
具志堅幸司副会長:
体操協会とは全く関係のない人たちに集まっていただいて調査をしていただくと。当然、宮川紗江さんのほうにもお話を聞くでしょうし、塚原さんのほうにも話を聞くでしょうし。あるいは、本部長の方にも副会長の方にも話を聞くと思います
東京オリンピックまであと2年。
スポーツ界の新たなトラブルは、泥沼化の様相を呈している。
プライムニュース イブニング
31日放送のフジテレビ系「バイキング」(月~金曜・前11時55分)で体操女子で16年リオ五輪代表の宮川紗江(18)が、日本体操協会の塚原千恵子・強化本部長(71)からパワハラを受けたと告発した問題を特集した。生出演した体操のバルセロナ五輪銀メダリストの池谷幸雄氏(47)が号泣する場面があった。
番組では、暴力を振るったとして日本協会から無期限の登録抹消などの処分を受けた速見佑斗コーチが東京地裁に行っていた地位保全の申し立てを取り下げることを発表したことを報じた。速見コーチは代理人を通じ、コメントし「処分を全面的に受け入れ反省し、それを皆様に認めてもらった上で、一刻も早く正々堂々と宮川選手の指導復帰を果たすことこそが選手ファーストだという結論に至りました。そこで私は協会からの処分を全面的に受け入れることと反省している証しとして、本日、仮処分の取り下げ手続きに入ることを表明いたします」とつづった文書を公開した。
この速見コーチの思いに池谷氏は号泣。思わぬ姿にMCの坂上忍(51)が「池谷、どうした?」と声をかけ「でも池谷しか分からない、速見さんの思いがあるから、そうなるわけでしょ」と思いやった。
池谷は涙を流しながら「どういう思いで取り下げるのか、どうするのか相当悩んだと思います」と絶句。さらに「宮川選手の指導をどうしたら早くできるのかってそれが一番、望んでいることだし、そのために、どれが一番正しいのかっていう選択を相当考えたと思います」と声を震わせ「これしかないと思ってこうしたと思いますけど、そういう気持ちを考えると早く復帰させて欲しいなってことだけなんですけど」と言葉を振り絞った。
その上で池谷氏は「なんでこの時期にっていうのがずっとあるんですけど」と前置きし、速見コーチの暴力行為を協会に報告した人物について言及し「誰が報告したのかってこの時期にこんな大事な時期に。発言を見るとどうしてもボクは塚原先生しか思えないなっていう。千恵子先生にしか思えないっていうところがすごく残念で。なんでこの試合を目前にしたすごい大事な時期になんでっていう…すみません」と怒りをにじませながら再び号泣していた。
個人的な意見であるが日本体操協会はかなり公平な対応を取らないと信用されないと思う。日大アメフトの結末を考えれば、
中途半端な嘘は信用を失い、イメージが悪化するだけ。
宮川の告発に塚原副会長の「全部ウソ」発言で、もし、宮川紗江さんの発言がほぼ事実である事が判明する、又は、信用できるような
回答が塚原千恵子・女子強化本部長から出てくなければ、夫婦そろって人生の終わりに大きな汚点を残すだろう。
18歳の勇気ある行動は報われるのか。
29日、体操女子リオ五輪代表の宮川紗江選手が都内で会見を開いた。
発端は宮川選手への指導中に暴力行為があったとして、日本体操協会が速見佑斗コーチ(34)に無期限登録抹消処分を科したことだ。これに宮川選手が文書で反論。この日、暴力があった事実は認めた上で「(1年以上前の)暴力のことを使って、私とコーチを引き離そうとしているのではと考えている」と言い、「何日も自分の気持ちと向き合ってきた。嘘偽りなく話します」と宣言した宮川選手の口から飛び出した内容は、想像を絶する協会のパワハラの数々だった。そして、常にその中心に君臨していたのが、「朝日生命体操クラブ」の監督を務める塚原千恵子女子強化本部長(71)だ。
■引き抜きの常套手段
宮川選手によれば、ナショナルトレーニングセンター(NTC)で代表合宿中だった今年7月、塚原強化本部長とその夫である塚原光男体操協会副会長(70)に呼び出され、本部長から速見コーチの暴力行為を認めるよう執拗に求められたという。
否定を続けると、副会長から「除外されたら困るのは、あなた。今すぐ(コーチとの)関係を切りなさい」と迫られ、本部長からも「暴力を認めないと、あなたが厳しくなる。あのコーチはダメ。だから伸びないの。私は速見より100倍よく教えられる」と証言を強要された。
これに宮川選手が改めて「家族と先生(速見コーチ)を信頼して一緒にやっていく」とクビを横に振ると、本部長は「家族でどうかしている。宗教みたい」といよいよ高圧的になり、延々2時間に及んだ説得の中で、「五輪に出られなくなるのよ」と脅しまで受けたという。
いずれも協会による速見コーチへの聴取すら行われていない段階だったという。
体操関係者の話。
「その後、宮川選手は塚原本部長の付き人から朝日生命体操クラブへの加入を勧められたと言っていましたが、これは塚原本部長の常套手段です。朝日生命は自力で選手を育てる力が乏しく、他のクラブで実力をつけてきた選手を獲得する手法でクラブを強化してきた。代表合宿に呼ばれた有望選手に『うちの方がうまくなる』『あのコーチはダメ』と声をかけて勧誘する手口は業界内で有名です。リオ代表の宮川選手も東京五輪の有望株。高校卒業をきっかけに、朝日生命へ入れようと画策したフシがある。宮川選手と速見コーチの所属先で、今回の一件で2人を解雇した『株式会社レインボー』は当初、塚原本部長と無関係だったが、徐々に塚原夫妻に取り込まれていったと聞いています」
塚原夫妻も暴力指導を容認か
今回と酷似した事件は以前にもあった。
2013年当時「羽衣体操クラブ」の井岡淑子コーチが指導中、女子選手2人に暴行したとして、傷害容疑で書類送検された。1人は10年に階段から突き落として打撲。もう1人は11年に髪を掴んで振り回し、鼻を殴って骨折させた。井岡氏は15年に無期限登録抹消処分に。この日、協会が会見の冒頭で口にした「本会は平成25年以来、一貫して暴力撲滅に取り組んでおり……」というのは、この事件を指している。前出の体操関係者が言う。
「井岡コーチの場合、今回の件と違って本当に暴力がヒドかった。被害者選手の親が助けを求めたことで発覚、妥当な処分といわれました。けれども事件には裏があった。当時、『羽衣体操クラブ』で井岡コーチが教えていた選手の中に杉原愛子という選手がいました。現在、朝日生命に所属する代表候補選手です。コーチの不祥事を機に、『それならうちで練習しなさい』と本部長側が声をかけ、朝日生命に引き取られる形で移籍している。つまり、塚原本部長は事件を利用して有望選手の引き抜きに成功したことになるのです」
宮川選手は会見で、代表選手とは別件で協会に定められた「2020年東京五輪特別強化選手」(以下、2020)についてこう話していた。
「代表選手を追い抜いて海外派遣を受けたり、ナショナル選手より上の立ち位置で優遇される。トライアウトを受けて、強化本部長に許可されると(「2020」に)なれるが、すごく不透明。詳しく調べてもらいたい」
戦略が不透明だったため宮川選手が参加を拒むと、NTCの利用を制限されたという。圧力に負け、6月にメンバー入り。「五輪に出られなくなると言われて入った。活動する中で、合宿という実態がなかったり、あまりにも不透明なところが多く、脱退を希望しているところ」と話した。
■「日本のコーチはクレージー」
今年度の体操女子ナショナルコーチの中には朝日生命所属のコーチや塚原本部長と親しい指導者も在籍している。別の体操関係者が言う。
「朝日生命のコーチはナショナルコーチとしてJOCから給料をもらっているのに、普段は朝日生命でチームの指導をしている。NTCでも朝日生命の選手しか熱心に指導しないそうです」
宮川選手の告発から1時間半後、体操協会が会見。山本専務理事は「たとえ五輪のためだったとしても暴力は断じて許さない。暴力の根絶を徹底していきたい」と語気を強めた。しかし、あろうことか、塚原夫妻もその暴力指導を容認していたというウワサもある。
「朝日生命の選手や出身者が被害者です。試合中にもかかわらず選手を陰に連れていってビンタしている現場は複数の人に目撃されている。昔はもっとヒドかった。演技に失敗して頭から落ちて脳震とうを起こしている選手を、心配するどころか裏でボコボコにしていたという話まであるほど。そういった暴力指導を看過していたというのです。国際大会だったので、海外の選手は『日本のコーチはクレージーだ』と目を白黒させていました」(前出の関係者)
こんな話も聞こえてくる。
「朝日生命の試合に出場できるかどうか瀬戸際の選手の親は、塚原夫妻への付け届けが必須だといいます。中身によって優遇されたり、渡さなければ出場の可能性が低くなるともっぱら。お中元やお歳暮を贈ったら、気に入らなかったのか、送り返された人もいるそうです」
宮川選手の投じた一石は果たして、体操界の闇にメスを入れることになるのかどうか。
体操の84年ロス五輪金銀銅の3つのメダルを獲得した森末慎二氏(61)が30日放送のTBS系「ビビット」(月~金曜・前8時)に生出演し、体操女子の世界選手権(10~11月、カタール)代表候補で、2016年リオ五輪代表の宮川紗江(18)が体操協会の塚原千恵子・女子強化本部長(71)からパワハラを受けたと告発した問題に関連し体操協会の人事に疑問を呈した。
【写真】27年前の女子55選手ボイコット事件
現在の協会は塚原本部長の夫の塚原光男氏(70)が副会長を勤める。こうした体制に森末氏は「協会の中に夫婦でいて、この立場にいること自体がおかしい」と見解を示した。さらに「今、ナショナルのコーチ陣も、ほとんど朝日生命の監督コーチ陣が何人も入ってきていると考えると、すべてノーという人を排除してイエスマンだけを置いていくということでしょうね」と塚原氏が所属する朝日生命人脈で組織が運営されていることを指摘していた。
体操の84年ロス五輪金銀銅の3つのメダルを獲得した森末慎二氏(61)が30日放送のTBS系「ビビット」(月~金曜・前8時)に生出演し、体操女子の世界選手権(10~11月、カタール)代表候補で、2016年リオ五輪代表の宮川紗江(18)が29日、自身への暴力行為で日本協会から無期限登録抹消などの処分を受けた速見佑斗コーチ(34)に関する会見を東京都内で開き、処分軽減を求めた問題について見解を示した。
会見で宮川は、速見氏の暴力行為は認めた上で、改めて師事を表明。処分を下した日本協会の意図を「コーチと私を引き離そうとしている」と述べた。塚原千恵子・女子強化本部長(71)の関与を指摘し「権力を使った暴力。パワハラだと思う」と告発した。
この宮川の告発について塚原氏の夫で協会の塚原光男副会長(70)は30日朝に「全部ウソ」と発言した。これに森末氏は「あれだけしっかりした言葉でしゃべってそれを聞いて、あんなウソを言うのかわからないと言っていること自体が怪しいですよ。どっかで聞いたフレーズかなと」と塚原氏の発言に疑問を呈した。
日本体操協会を“パワハラ告発”した女子体操の宮川紗江の会見について、30日の朝のワイドショーでは各局、大きく取り上げた。体操関係者もワイドショーに生出演し、宮川の告発に「よく頑張った」「(体操協会の問題が)出て欲しいと思っていた」など、その勇気をたたえるコメントを発した。
【写真】塚原副会長の「全部ウソ」に…宮川紗江「想像していた」と苦笑
フジテレビ系「とくダネ!」では、自身もジュニアを指導する池谷幸雄氏が生出演。宮川の会見について率直に聞かれ「本当によく頑張ってくれたなということと、勇気がいること。パワハラを受けたという中で、これを発言するというのは、18歳の選手にとってどれだけの負担だったかと」と、宮川の会見を「勇気」があったと評価。そして「ぼくらとしても信じられないほど赤裸々に語ってくれたので、それは素晴らしい。よく頑張った」ともコメント。
一方の体操協会の会見については「残念としかいいようがない。僕も体操協会の下の方で働いている人間ですけど、なんで昨日やってしまったのかなと、すごく感じてしまう会見だった」とも話した。
TBS系「ビビット」にはロス五輪メダリストの森末慎二氏が生出演。今回のパワハラ問題について、国分太一から「こういう問題は遅かれ速かれ体操協会では出て来るものだと?」と聞かれると「出て欲しいとは思っていた、逆に言うと」と問題が露呈することを希望していたとコメント。
「これまで30年ぐらい前から、そういう噂はありましたから、そういう部分で出て欲しいとは思ってましたが、なかなかこういう発言をする選手はおられなかった」と、以前から協会内部にパワハラなどの噂があったことを指摘していた。
日本体操協会の山本宜史専務理事と弁護士の会見は酷いものでした。宮川選手の塚原強化本部長からパワハラを受けたという告発があまりにも突然だったからか、協会が置かれた状況が一転してしまったことへの認識が甘く、事前に用意していた速見コーチの処分問題の説明以上のコメントはありませんでした。知らぬ存ぜぬ、宮川選手が協会に申し立て、訴えろでは話になりません。
言ってみれば協会は正義を守りつらぬく立場のつもりで記者会見に望んだわけですが、宮川選手の証言で、一転して、パワハラを行った被告側にまわったにもかかわらず、それに対するコメントが不十分というのでは、拙速も甚だしく、事態をこじらせます。
テレビ報道でも何人かの専門家が指摘していたように、そもそも、常識的に考えて、速見コーチの暴力問題についても、協会はいくつかの間違いを犯しています。
第一は、コーチの暴力に関して、宮原選手からの聞き取りを行っておらず第三者の告発だけだったことです。
第二は、いきなり速見コーチを処分したことです。スポーツに関する暴力問題は、それを是正する動きはほんの最近に始まったことで、その指導を速見コーチに行ったのか、なんらかの警告を行い、従わないから処分した疑いがあります。
第三は、警告のための処分としては重すぎることです。二番目に重い処分であり、いくら協会が速見コーチから指導を受けても良いと言っても、実質的にはそうではありません。
宮川選手の告発のように、どうも最初から速見コーチ外しの意図があったと見られてもしかたありません。
体操女子パワハラ問題は「速見元コーチを追い出したいありき」「権力闘争の駒という疑念」 モーリー氏が指摘 - 芸能社会 - SANSPO.COM(サンスポ)
日大アメフト部の宮川選手の告発から始まり、スポーツの問題がつぎつぎと発覚してきましたが、そして体操も同じ姓の宮川選手だったというのも皮肉な話です。しかも、18歳の宮川選手が訴えた勇気と比べ、パワハラ疑惑の渦中にある肝心の塚原強化本部長が会見に出てこず、逃げたという印象を残してしまったことは、パワハラ疑惑を深める結果になったのではないでしょうか。協会側が、パワハラ疑惑に、宮川選手が協会に提訴しろという態度をとってしまったこともまずかったのではないでしょうか。
こういった問題対処は「クイック・イズ・セーフ」です。対処のスピードが混乱を収拾する鍵となってきます。そうできなかったのは協会の危機意識の薄さでしょう。そのツケが尾を引きそうです。
日本体操協会の山本専務理事、みらい総合法律事務所の岩寺弁護士と山口弁護士 達の対応は信頼性に関して薄く感じた。なぜ、速見佑斗コーチの答弁を聞かなかったのか、公平性に欠けると思った。 速見佑斗コーチが嘘を付くのか、事実を話すのか、見極める機会を与えるべきだし、体操協会が入手している証言や証拠と 一緒に検証するべきだと思った。

日本体操協会は29日午後7時、速見佑斗コーチのパワハラ問題に関連し、都内で会見。暴力行為を受けた宮川紗江選手が同コーチからのパワハラを否定し、逆に協会から圧力をかけられていると指摘したことに対し、山本専務理事は「報道は初めて知ったが、そんなことは一切、関係ない」と否定した。
また、宮川が7月中旬、日本協会の塚原千恵子・女子強化本部長、夫で日本協会副会長の塚原光男氏に呼び出され、暴力行為の証言を求められたが、宮川が拒否。これを受け、塚原本部長から「五輪に出られなくなる」と言われたと宮川が主張していることについて、山本専務理事は「そのことは分からない。ここでは回答を控えさせていただきます」と保留した。初めて聞いたとして、「(協会側へ)宮川さんに訴えてもらい、『聞いてください』と言ってもらえたら粛々と調査します」と語った。
協会は速見コーチの暴力行為を断罪。山本専務理事が「本会の基本的な考え、たとえオリンピックのためとしても暴力は断じてゆるさない。暴力の根絶を徹底していきたい」として、速見氏の処分の正当性を主張した。
繰り返し、速見氏が暴力していたことを明かし、「複数の指導者、選手たちに恐怖感を与えた。決して許されるものではありません。裁判では必要に応じて証拠を出すつもりです」とした。真摯(しんし)に反省して、実績を積んだ後は再登録も検討するとし、「いち早く元の姿に戻ってほしい」と語った。
同問題では女子日本代表を指導していた速見コーチが練習中に宮川の頭をたたいたり髪を引っ張ったりするなどしたとして、無期限の登録抹消処分となった。しかし、宮川本人がパワハラを受けていないと表明し、問題は泥沼の様相となった。
宮川はこの日、午後4時に都内で会見。10月から行われる世界選手権などの出場辞退を表明し、体操協会側の対応にも疑問を投げかけた。小学校時代から師事してきた速見コーチから暴力行為があったことは認めたものの「馬乗りになって殴打したという部分は一度もありません」などと、一部を否定。速見コーチの処分軽減を求め、体操協会に対して「私とコーチを引き離そうとしているのではないか」と主張した。また、協会側の設定した強化プログラムに従わなかったことで不利益な扱いを受けたと主張した。
【問題の経過】
◆8月14日 体操協会が、速見コーチに暴力行為があったとして無期限での登録抹消、味の素ナショナルトレーニングセンター(NTC)での活動禁止の懲戒処分を伝える。
◆21日 暴力行為を受けた宮川が、速見コーチへの見解について代理人弁護士を通じて文書を発表。同コーチの名誉を守りたいとして処分への疑義や、引き続き同コーチの指導を望む意向を示した。代理人弁護士には同コーチが処分を不服とし、東京地裁に仮処分を申し立てたことも明かした。
◆29日午前 体操協会が報道各社へFAX。宮川が速見コーチからパワハラを受けていないとしたことに対し、処分は変わらないと表明。
◆29日午後4時 宮川が会見。世界選手権などの出場辞退を表明。体操協会側に自身と速見コーチを引き離そうとしている意図があるのではないかと指摘。
◆29日午後7時 体操協会が会見。

速見氏処分に関して会見を行う、左から日本体操協会の山本専務理事、みらい総合法律事務所の岩寺弁護士、山口弁護士(撮影・足立雅史)
本体操協会が29日、都内で、体操女子リオデジャネイロ・オリンピック代表の宮川紗江(18)への暴力行為で無期限の登録抹消と味の素ナショナルトレーニングセンター(NTC)での活動禁止処分を下した、速見佑斗コーチ(34)に関する一連の騒動について会見を開いた。
山本宜史専務理事は「例えオリンピックのためだと言えども、暴力は断じて許さない。これからも暴力の根絶は徹底したい。本人が許容していたとしても、認められない。この考えに基づくものであります」と断言。その上で速見コーチの暴力について、事実確認を行った。
同専務理事は、7月11日に関係者による証言に端を発し、速見氏本人含め、複数の関係者の聞き取り調査を行ったとした。その結果「13年9月から18年5月までの間、元所属先の練習場、NTC、その他において他指導者、選手がいる前で顔をたたく、髪の毛を引っ張る、体を引きずる、長時間立たせる、他の指導者や選手などが萎縮するほどの暴言の事実が認められた」と明らかにした。具体的には
◆13年9月 NTCでの国際ジュニア合宿の時に顔をたたく。
◆15年2月 海外合宿での、大声でのどなりつける行為。
◆16年1月 海外の試合で顔をたたき、顔が腫れ、練習中に怒鳴った。他のコーチからの引き留めもあった。
◆同3月 国際大会中、Tシャツをつかみ、引きずり降ろす行為。
◆同5月 前所属先で頭をたたく、怒鳴る行為で注意された。それらの行為は日常的に実施されていた。
◆同7月 海外合宿中、1時間以上の長時間、立たせていたことで厳しく注意を受けた。
◆17年1月 前所属先で暴力があり、無期限の謹慎処分。
◆同8月 NTCで髪を引っ張り、出入り口まで引きずり出した。
◆同9月 NTCで髪を引っ張り、倒すなどの行為。
◆18年4月 NTCで指導中に大声で怒鳴る。
◆同5月 東京都体育館のサブ会場でも、同様の怒鳴る行為があった。
山本専務理事は「まだ、いろいろとございますが、このような暴力を是正しようという関係者がおり、是正の機会があったにもかかわらず、繰り返し暴力を行った速見氏の行為は、倫理規定に反すると判断し、今回の処分に至った」と処分の正当性を強調。さらに「暴力は複数の指導者、選手に恐怖感を与えた。被害者本人が我慢できたからとしても、決して許されるものではない」と断じた。また「複数の情報が、それ以外にも寄せられているが本日は控えさせていただく」とも語った。
その上で、同専務理事は宮川サイドが協会の処分を不服として、20日に東京地裁に仮処分の申し立てを行ったことを踏まえ「裁判では必要に応じて証拠を出す予定」とした。そして「これらの事実を元に懲戒委員会、常務理事会で審議し、今回の処分に至った。一方、宮川選手への影響を懸念しましたが、代表候補の指導者だからといって暴力が許されるわけじゃない」と重ねて暴力の根絶という目的を強調した。
また「宮川選手が速見氏の指導を受けられないという認識は間違い。指導を続けることが出来ますが、NTCでは速見氏は規則上(指導)出来ない。他の練習場所を確保する必要はある。宮川選手はNTCは使用できます」と、宮川が速水コーチの指導を受けられないことはないことを、重ねて強調した。その上で「真摯(しんし)に反省し、都道府県協会から申請されれば再登録を検討する」とも話した。
また宮川について「宮川選手と今後のサポートについて話し合いたかったが、代理人の両親となった。16日に両親に対し、NTCの練習や、指導者をつけるサポートを提案したが、残念ながら選手と話を持つ間もなく。サポートについて協議させていただく準備はある」とも語った。【村上幸将】

会見を終え席を立つ、手前から日本体操協会の山本専務理事、みらい総合法律事務所の岩寺弁護士、山口弁護士(撮影・足立雅史)
日本体操協会が29日、都内で、体操女子リオデジャネイロ・オリンピック代表の宮川紗江(18)への暴力行為で無期限の登録抹消と味の素ナショナルトレーニングセンター(NTC)での活動禁止処分を下した、速見佑斗コーチ(34)に関する一連のパワハラ騒動について会見を開いた。
山本宜史専務理事は、速見の宮川に対する暴力行為が13年9月から18年5月の間に行われたとし、その内容を会見の中で列挙した。それらが発覚した経緯について、同専務理事は「協会から上がった話じゃない。指導者の間から話が出てきたので、事実認定して調査し、処分した」と説明。調査したのは誰かと聞かれると「調査したのは私です」と答えた。
一方で、協会として13年度から暴力撲滅を訴えてきたことも強調した。そのことに対し「暴力撲滅を進めながら把握していなかった?」と質問が出た。同専務理事は「その通りです。結果論でしょうけども、本来、暴力はあってはならないし、暴力指導が今は許されない。そういうことがある。平成25年度から暴力撲滅を訴えている。悪いと思って認識してやったことが判明した以上、根絶を前提に処分した。見てないところであったかもしれない」と協会として把握し切れていなかったことを認めた。
また速見コーチが協会の処分を不服として、20日に東京地裁に仮処分の申し立てを行ったことについて「異議申し立てが協会ではなく直接、裁判所にいった。裁判のところでお話しするしかない。今の時点で協会は温情など考えられない」とも語った。【村上幸将】
宮川紗江さんは腹を決めたように堂々としていた。18歳ながら凄いと思った。例え、報復でスポーツ生命が18歳で終わったとしても
今回の経験で終わることなく、何かに応用して更なる飛躍をしてほしいと思う。
一般的に、人は年を取るとしがらみや今持っている物を失う事が怖くなり、思い切った事が出来なくなる。悩みながら、妥協しながら、
中途半端な状態で現実逃避したり、後悔する事がある。人が簡単に出来ない事をやったのだから凄い。そして、会見で語った事が
ほぼ事実であれば、権力を握る塚原女子強化本部長に対して制裁を下したことになると思う。勝手な解釈であるが体操の世界で今回のような対応を
取れる人はほぼいないと思う。
スポーツ庁長官、 鈴木 大地(スポーツ庁)
とスポーツ庁は必要ないのではないか?スポーツ庁はこのように問題に介入して公平な調査や判断を下すべきではないのか?
体操女子リオデジャネイロ・オリンピック代表の宮川紗江(18)が29日、自らへの暴力行為で日本体操協会から無期限の登録抹消と味の素ナショナルトレーニングセンター(NTC)での活動禁止処分を科せられた、速見佑斗コーチ(34)に関する一連のパワハラ騒動について、都内で会見を開いた。
宮川は会見の中で、日本体操協会からパワハラ行為があり、塚原千恵子女子強化本部長が女子監督を務める、朝日生命体操クラブに加入させられそうになったなどと語った。
宮川はNTCで7月11日から強化合宿が行われた際、塚原女子強化本部長らから速見コーチは参加できないと連絡があり、部屋に呼ばれ「(速見コーチの)暴力を認めないと、あなたが厳しくなる。あのコーチはダメ。だからこそ伸びない。私は速水より100倍良く教えられる」などと言われたと証言した。
宮川は「怖くて何も言えない先生でなく、言いたいことを言える先生です。これからも家族と先生を信頼して一緒にやっていく」と答えたが、塚原女子強化本部長からは「家族でそういうのはおかしい。宗教みたい」「オリンピックに出られなくなるのよ」と言われたという。宮川は「家族とコーチを否定され、全てがおかしくなりそう」になり16日、塚原女子強化本部長に「精神的限界…帰りたい」と言ったというが、それ以上は言えず合宿に残ったという。
さらに、21日に塚原女子強化本部長の付き人から「朝日生命で練習で出来るし、朝日生命の寮も借りられる」「何かあったら相談しなさいよ」などと言われ、電話番号を渡されたという。宮川は「本部長からは入れと言う話は、受けていません。付き人からお話しするような感じで電話番号を渡された。パワハラとは感じていないですけど、その方が本部長の付き人ですので、やっぱり何か関係がある…私を朝日生命に入れるために、心を動かそうとしていると思った」と、塚原女子強化本部長からの勧誘ではないものの、朝日生命入りへ心を揺さぶってきたと感じたと語った。
その上で「速水コーチの聴取すら行われていない段階で、最初から過去の暴力を理由に朝日生命に入れる目的だと確信し絶望した。強化本部長が大きく関わっていたのは間違いない」などと語った。「私の意志は朝日生命に入ることではなく、コーチと一緒にやっていくことなので、心は動かなかった」とも強調した。
そして「権力のある人には、1人の選手の人生は関係ないんだと思った。言いたくても言えば、何をされるか分からない選手、コーチ、審判もいると思う。それは権力を使った暴力。純粋に強くなりたい」と訴えた。さらに「協会にはパワハラの事実を認めていただきたい。18年しか生きていませんが勇気を持って立っています」とまで言い切った。【村上幸将】
準大手ゼネコンが進めていた倉庫建設工事をめぐる恐喝未遂事件で、湖東生コン協同組合(滋賀県東近江市)の加盟業者と契約するよう商社の支店長を脅したとして、滋賀県警組織犯罪対策課は28日、恐喝未遂容疑で、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部執行委員長、武建一容疑者(76)=大阪府池田市=を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。
県警は今月9日に同容疑で同支部執行委員兼政策調査部長、城野正浩容疑者(57)=兵庫県西宮市=を逮捕しており、同支部が組織的に事件に関与した可能性もあるとみて、全容解明を進める。
逮捕容疑は昨年3月~7月、東近江市内で行われていた清涼飲料水メーカーの倉庫建設工事にからみ、同支部幹部や湖東生コン協同組合幹部らと共謀し、生コンクリート調達を担う大阪市内の商社の男性支店長に対し、湖東生コン協同組合の加盟業者と契約を結ぶよう要求。断られたため「大変なことになりますよ」などと複数回、脅して契約させようとしたとしている。
この商社は準大手ゼネコンの関連会社。捜査関係者によると、武容疑者らは逮捕容疑の他にも、工事現場を訪れて「カラーコーンが道路使用許可なしで置かれている」「仮囲いが1センチほど境界を超えている」などと因縁をつけ、圧力を加えるなどしていたという。
この事件では、これまでに同容疑で城野容疑者を含めて7人が逮捕され、うち3人が今月8日に同罪で起訴されている。
交渉記録映像が残っているのだから下記の記事は事実だと思う。
順天堂大学医学部付属順天堂医院相手に十分な資金がない状態で対応するのは大変だと思う。順天堂大学医学部付属順天堂医院が
良心的であれば問題ないだろうがそうでなければ大変だと思う。
ヤフーニュースのコメントには弁護士を付けないからこのようになったとコメントしている人がいるが、弁護士は腐るほどいる。
個人的な経験で言えば、専門が違えば素人よりもまし程度。相手の弁護士の能力や弁護士事務所のスタッフの能力が高ければ
勝てない。ドラマみたいに本当に弁護士なのかと思えるような人が結構、切れる部分を持っているような事はないと思う。
弁護士や弁護士事務所が有能であれば依頼があるだろうし、忙しい。弁護士に依頼をしたことがないない人は戸惑うだろう。
勝てなければ、弁護士はお金の無駄遣いでしかない。
下記の記事が事実だとすれば本当に酷いと思う。「2017年1月10日 第7回目の交渉記録映像」の順天堂側医師は「理事には学長以下が入っていない。理事長はワンマン、はっきり言って。学長の上に存在する。」と言っているが、本当に理事長の判断なのだろうか?嘘も言い訳もあり得る。
本当に理事長の判断なのであれば、コメントに理事の情報が記載されている。
学校法人順天堂 理事長(第9代堂主)
小川秀興
独立行政法人 国立がん研究センター 顧問
08/27/18(Yahoo!ニュース)
組織が大きいから組織のトップの判断で争うのであれば個人レベルで戦えるとは思えない。多くの人が知る事によって厚労省が踏み込み、
事実が調査により明らかになれば良いと思う。ただ、相手が相手なので対抗手段を考えていると思うので、厚労省が介入しなければ、
事実は公にならないと思う。
順天堂大学医学部付属順天堂医院で51年前に起きていた新生児の取り違え事件。
今年4月に週刊誌報道などで明らかとなり、順天堂側も認める事態となったが、今回「報道プライムサンデー」は、取り違えられた被害男性と順天堂側との交渉を、30時間に渡って記録した映像を独自に入手した。そこには被害者男性が「裏切りばかり」と語る、順天堂側の驚きの対応が記録されていた。
【画像】順天堂側の対応や発言が何度も変わるため証拠を残すべく記録した映像の数々
1967年、取り違えは出産直後、順天堂医院のミスで起こった。
被害を受けた男性は鈴木良夫さん(51歳・仮名)。壮絶な人生の始まりは今から44年前の1974年、良夫さんの小学校入学の際に行われた健康診断だった。
その結果報告書には血液検査の結果があり、母・昭子さん(76歳・仮名)が確認したところ、良夫さんの血液型は両親からは絶対に生まれないものだった。
「子供の取り違えではないのか?」
真実を知りたかった昭子さんは、分娩した順天堂医院に行き、新生児の取り違えを指摘した。しかし、病院の回答は驚くべきものだった。
母親に「あなたが浮気したんじゃないですか?」
ーー順天堂医院は取り違えを認めたのですか?
良夫さんの母・昭子さん:
認めません。順天堂医院はこれだけ立派な病院です。そういう変なことが起こるわけがありませんと言われて。絶対に生まれてこない血液型だったけれど、それでも『あなたが浮気したんじゃないですか?』とか言われるんですよ。絶対に取り違えを認めませんでした。
病院側は、母の浮気が原因ではと指摘した上で、「異議があるなら裁判にすればいい」と門前払いにしたという。
結局、夫から身に覚えのない浮気を疑われるなど夫婦仲はぎくしゃくし始め、病院を訪れた半年後に夫婦は離婚。良夫さんは母親に引き取られたが、間もなく母親は体調を崩し、子育てに支障が出るようになった。そのため良夫さんは親戚に預けられ、転々とすることになった。
親戚宅で良夫さんは、「お前のせいで、親は離婚したんだ」「よその子だから、親と顔が似てない」などと言われ、幼心に“自分の両親は本当の親ではないのではないか”と悩み続ける、辛い子供時代を送ったという。
時は流れ、3年前の2015年、良夫さんは母親から事実を告げられる。
「あなたは本当の子供ではないのだ」と。
良夫さんは母親の告白を確認するためDNA検査を行った。すると、実の親子である可能性0%という結果が出た。良夫さんと母親は、やはり実の親子ではなかった。
実は、良夫さんが産まれたころの日本では、全国各地で、新生児の取り違え事件が起きていた。1974年に行われた調査によると、1957年から1971年までの15年間で32件の取り違えが判明。もちろんこの数は判明した数で、実際にはもっと多いことは確実だ。良夫さんの取り違えもこの32件には入っていない。
時間が経って取り違えが判明し、病院を相手取った裁判に発展したケースも起きている。2013年には、1953年に別の赤ちゃんと取り違えられた男性が病院を提訴し、3800万円の賠償金を得ている。
良夫さんは“実の親を知りたい”という思いと賠償を求め、2年前の2016年4月から順天堂側と交渉を始めた。交渉の際、順天堂側の対応や発言が何度も変わるため証拠を残すべく映像で記録していた。その記録から交渉過程の詳細が今回初めて明らかになった。
病院側は真摯な対応だったが…
【2016年12月9日 第5回目の交渉記録映像】
良夫さん:
7歳の時に(母が)1回来ているから。
順天堂側医師(危機管理担当):
そうですね。
良夫さん:
こちらでも、分かっていることですからね。
順天堂側医師(危機管理担当):
逆に言いますと、それがあるので悪い方にも行ってます、我々にとっては。あそこ(44年前)で、何とかしておくべきだった。
良夫さん:
そうですね。
順天堂側医師(危機管理担当):
当時主治医であった医師が、そういう事で(お母様が)来られたということを、はっきり記憶してましたし、(病院側が)言った内容と、鈴木様のお母様の言った内容が一致してますので、裁判を起こしてくれということまで。
なんと、順天堂側は母親の言い分を認めていた。
こうして交渉は進んでいく。そして、順天堂側の危機管理担当の医師がついにこう切り出す。
「実の親の情報も提供する、賠償もする」と“約束”
【2016年12月9日 第5回目の交渉記録映像】
順天堂側医師(危機管理担当):
最終的には病院の学長が…その意見をまとめろということで。実は、今朝まとめてきました。学長、医学部長、院長、副院長…コアメンバーです。総勢13名で最終決定をしました。それに向けて急ぐということで。
良夫さん:
いわゆる記録ですよね。(取り違えた相手の)出生記録、その書類を私にだけいただいて。目的はお墓参りと(自分の)ルーツを知っておきたい。
順天堂側医師(危機管理担当):
反対する人もいると思いますが、裁判にして(当時の分娩記録を)差し押さえするだけ。(差し押さえて)これを見る手段が鈴木さん側にあるわけだから別に上を通さなくても問題ないと判断します。何の問題もない。最高の終わり方。
出生時の分娩記録が残っていて、それを良夫さんが見れば、実の親の情報も分かるというのだ。およそ9カ月に及んだ交渉は、良夫さんの希望通りにまとまったかに思えた。ところが、その19日後の第6回目の交渉で、突然同じ危機管理担当の医師がこう切り出したのだった。
まさかのどんでん返し…いままでの交渉はなかったことに
【2016年12月28日 第6回目の交渉記録映像】
順天堂側医師(危機管理担当):
(新しい)代理人と手続きをするという方向で話をしています。本当に謝りますが、ゼロから進むことは絶対にありませんので。
良夫さん:
また新たな弁護士の先生なんですか?
突然、順天堂側が用意した別の弁護士が、良夫さんとの交渉を改めて行うと言い出したのだ。それは理事長の決定だという。
順天堂側医師(危機管理担当):
(賠償の)額とか、その辺りは理事会で決めること。いわゆる法人として決めるというか…。理事には学長以下が入っていない。理事長はワンマン、はっきり言って。学長の上に存在する。
良夫さん:
何をしたいんですか?理事長は。前回の話では、もうみんなで会ってOKになったという話じゃないですか!
順天堂側医師:
要するにあれは学長以下ですよ。理事長はもっと上なので。
良夫さん:
また今から、金額の話からやり直しなんですか?
順天堂側医師:
それはわからない、私も。
良夫さん:
向こう(新しい弁護士)の見解は何ですか?
順天堂側医師:
それはわかりません。(新しい弁護士からは)要するに交渉をしないでくれと、大変申し訳ないんですが、私も伝えています。間違いなく伝えています。全部伝わっています。
良夫さん:
ものすごい怒りがもう…。ここまでやってきて、ここまで話してきて、1年という時間を使って何も進んでいないですもん。結局また弁護士じゃないですか、新しい。
順天堂側医師:
憤りはあると思いますが…。
良夫さん:
またこの気持ちで正月を迎えなければいけない。
順天堂側医師:
大変申し訳ありません。
良夫さんは憤ったが、12日後の2017年1月10日、第7回目の交渉が行われた。そこにはこれまで交渉してきた医師の姿はなく、新たに順天堂側の代理人弁護士2人が現れたのだった。
「実の親の情報提供はしない、賠償額は大幅に下げる」
【2017年1月10日 第7回目の交渉記録映像】
順天堂側新たな弁護士(男性):
病院側としては 本件については謝罪をする、ということです。取り違えについては示談という形で一定の和解金をお支払いすると。(取り違えの)相手方の関係についてですが、現在の平穏な生活環境であるとかプライバシーにも配慮して、相手方の調査は行わない。金額の話ですけども、どのような検討をしたかを少し説明しますと…。
2人の新たな弁護士は、12月9日の第5回交渉で最終決定とした金額を大幅に減額した賠償額を提示。さらに実の親の情報も出さないという今までの交渉を完全にひっくり返すものだった。
良夫さん:
(交渉は)今まで正式じゃない人たちだったんですか?正式じゃない人たちと1年間私に時間を使わせて、話し合いをさせてきたと…病院は。
順天堂側新たな弁護士(女性):
(担当医は)最終的な法人の決定ではないと、何度も言っています。
良夫さん:
(担当医は)任されているのは私たちですからと言っていましたよ。
順天堂側新たな弁護士(女性):
それは個人的な気持ち…。
良夫さん:
個人的って、何人もいますから、証人が!一人で話しているわけではないですから。
順天堂側新たな弁護士(女性):
『そうしたいと思います』と言っているとすればそれは『思います』なのであって。
順天堂側新たな弁護士(男性):
(前任者の医師は)自分の立場で考えたのだろうと。
良夫さん:
私たち家族としてはお金で納得する事案じゃないんです、本来。母親に(実の)息子を持ってきてくれ、そこからです、話し合いは。まずは、きちんとした対応を取っていれば、こういうことにならなかった。1年経って誰も出てきてない、決定権を持っている方が。一人の挨拶もなければ、謝罪もなければ…。
およそ1年かけた交渉がまた振り出しに戻ったことで疲れ果てた鈴木さんは、「もう信頼関係もなくなり、このままうやむやにされるより取り違えの事実だけでも残したかった」として、結局、順天堂側と大幅に下げられた賠償金をもらう合意を結ぶことになる。
その合意文書には「取り違えの事実を第三者に知らせない」という守秘義務の条項があったが、今回、「報道プライムサンデー」の取材を受けた理由について、良夫さんはこう話す。
「私も出るつもりは全然なかったのですが、『順天堂としてホームページに発表します』ときた。その内容を見たら、50年たった今、分かったことなので、いまさら、探すことはしないという内容だった。いや私が7歳の時に(母が病院に)行って、(病院側は)追い返しているでしょ。それをまず隠しているのと、謝罪したと書いてあるが(順天堂は)謝罪にも来てない」
鈴木さんは順天堂側の説明があまりにも一方的だと感じたので、取材を受けたのだという。
この合意文書について、医療過誤に詳しい貞友義典弁護士は憤る。
「真の本当の親を知る権利を放棄させることを考える方がおかしい。そもそもお金では買えないです。人の道に反する合意書だと思います」
実の母は幸せに生きてくれたのか…写真一枚でもいい
最後に良夫さんは、今の思いをこう語る。
「私は病院に行っても自分の先祖がガン家系であるとか糖尿病であるとか、そういうことが伝えられない。相手(実の親)の生活を壊すことはしたくないので、こちら側にだけ教えてもらえばいいこともあると思う。相手が望まなければ会わなくてもいい。ただこちらにも知る権利というものがあると思う。(実の)母は幸せに生きてくれたのか…時間はもう取り戻せないので。せめて幸せだったのか、どういう人生を送ったのか、写真の1枚でもいいから知りたいです」
家族問題に詳しい池内ひろ美氏(家族問題評論家)は、「病院が“会わせる”“会わせない”を決めるのはおかしいと思います。取り違えは医療ミスです。医療ミスがあったわけだから、もう一方の家族も含めて、まず両方の家族に謝罪をすべきです。順天堂は『相手側の平穏な生活を乱すので、お知らせしないことにした』と主張するが、病院が言うことではない」とスタジオで語った。
今回、番組では順天堂に取材を申し込んだが、HP上に見解は載せているので取材は一切受け付けないと回答を拒んだ。
「自分は何者なのか?」
良夫さんの願いが叶う日は来るのだろうか。
不正は麻薬と同じだと思う。麻薬と違うのは、不正が長期間、発覚しない可能性があること。麻薬は体に害が蓄積されるが、
宝くじに当たるように、運が良ければ、負債にならず不正が発覚しない可能背がないわけではない。
しかし、上手く行かなければ負債や損となる。一時的な現実逃避は大きな問題となって現れる。
スルガ銀行の幹部や行員が関与しているのだから、スルガ銀行の名前が消えても自業自得だと思う。
スルガ銀行(静岡県沼津市)のシェアハウス投資向け融資で多数の不正があった問題で、融資審査で約99%の案件が承認されていたことがわかった。審査が機能せず不正を見逃し、2千億円超のシェアハウス関連融資額に対し、400億円超の焦げ付きが懸念されている。問題を調べる第三者委員会(委員長=中村直人弁護士)も把握し、ずさんな融資を許した経営責任を追及する方針だ。
第三者委は行内の電子データの分析や経営陣を含む関係者らへの聞き取りをほぼ済ませ、近く調査結果を公表する。
シェアハウス投資では、不動産業者らが長期の家賃収入を約束して会社員らをオーナーに勧誘した。業者らは貯蓄や年収を水増しし、1棟あたり1億円前後の融資をスルガ銀から引き出した。関連融資は2035億円、1258人分にのぼる。
シェアハウス投資をめぐるスルガ銀行のずさん融資問題で、新たに投資用アパート向けの融資でも不正が行われていたことが22日、分かった。
スルガ銀は投資トラブルを起こしているシェアハウスへの融資が総額で約2000億円、借り手は計1200人強に上るとの実態調査をまとめているが、これがさらに膨らむ可能性が高い。外部弁護士の第三者委員会が月内にまとめる調査報告書に盛り込まれる見通しで、調査は大詰めを迎えている。
顧客が不動産業者に託した融資関連書類が改竄(かいざん)され、融資条件に合うように見せかけられていたなど不適切な融資が横行していたことが既に判明している。こうした不正な融資はシェアハウスだけでなく、「一棟売り」など個人の投資用アパートでも実施されていたもようだ。
具体的には、個人が購入した物件について不動産価値を高く見せかけ、より高い賃料がとれるように装うなどの方法をとっていたとされる。
スルガ銀行の投資用不動産融資は、アパートなども含めると全体で2兆円に上る。今回、新たに判明した不正で「不適切融資」は2000億円から大幅に拡大するとみられる。スルガ銀は2018年3月期決算で、155億円の貸倒引当金を追加計上しているが、さらに積み増す可能性も出てきている。
ずさんな融資をめぐっては、元専務執行役員が営業部門責任者として融資拡大を主導した経緯や、取締役会が審査書類改竄など不適切な融資の横行を防げなかったといったガバナンスの欠如がこれまで明らかになっている。スルガ銀は、第三者委員会の調査報告書の結果を受け、経営体制の刷新などに迫られることは必至だ。
「高田容疑者には妻子がいるが、少女には独身を装って『結婚しよう』などと話していたという。」
同じ違法でもお金を払って関係を持つよりも嘘を付いて関係を持つ方が悪質だと思う。
今後も仕事が出来るかはテレビ局の判断次第!
女子高生にわいせつな行為をしたとして、警視庁巣鴨署は、東京都青少年健全育成条例違反容疑で、世田谷区の自営業、高田大介容疑者(34)を逮捕した。東京MXテレビによると、高田容疑者はフリーの番組ディレクターで、平成25年から同社のバラエティー番組「5時に夢中!」の制作に携わっていた。
逮捕容疑は7月中旬、足立区内のホテルで、高校2年の少女(16)が18歳未満であることを知りながら、わいせつな行為をしたとしている。高田容疑者は「悪いことだとは分かっていたが、性的欲望を満たすために関係を続けた」と容疑を認めているという。
同署によると、2人はツイッターを通じて知り合い、これまでに複数回会っていた。高田容疑者には妻子がいるが、少女には独身を装って「結婚しよう」などと話していたという。少女の母親が6月、警視庁に相談して発覚した。
大学入試で合格するためにはモラルや人間性は関係ない。エリートだから尊敬される人間でない事があると言う一例だと思う。
「三菱マテによると、これら子会社3社では2016から17年までに、三菱マテへの内部通報や監査などをきっかけに、データに関する社内の不正が発覚。しかし、その後も三菱マテへの報告を怠ったり、データが改ざんされた製品の出荷を続けたりしていた。ダイヤ社では、不正の発覚後、前社長が関連資料を隠蔽(いんぺい)するよう指示していたという。」
前社長が隠蔽指示を出した。それが問題にならない組織は間違っていても上には逆らえない、又は、問題を報告したらデメリットしかない問題の
ある組織である可能性が高い。
取引が企業相手だから消費者が判断できることはないであろう。就職しようとする人が減るかどうかであろう。
非鉄金属大手・三菱マテリアルグループの品質データ改ざん問題で、東京地検特捜部が、不正が発覚した複数の子会社を7月に不正競争防止法違反(虚偽表示)の疑いで家宅捜索していたことが関係者の話でわかった。三菱マテ本社(東京)も関係先として捜索した。特捜部は担当社員らから事情聴取するなど改ざんの実態解明を進めている。
特捜部は7月、製品の品質データ改ざん行為を巡り、法人としての神戸製鋼所を不正競争防止法違反(虚偽表示)の罪で起訴している。三菱マテも神鋼と同様に、製品の安全性は確認済みとしていたが、不正の規模が大きく、納品先も広範囲にわたることなどから、特捜部は強制捜査が必要と判断したとみられる。
関係者によると、捜索対象になったのは子会社の三菱電線工業(東京)、三菱アルミニウム(同)、ダイヤメット(新潟市)など。
三菱マテの最終報告書などによると、不正はこの3社と子会社の三菱伸銅(東京)、立花金属工業(大阪市)、本社直轄の直島製錬所(香川県直島町)で行われていた。子会社の不正は古いもので1970年代からあり、製品の出荷先は延べ825社にのぼっていた。関西電力大飯原発や高浜原発、航空機に使われるゴム製品などで、強度や寸法が顧客の求める基準に達していないのに、不正に検査の測定値などを書き換えて出荷したケースもあったという。
また、不正が確認された子会社5社のうち、少なくとも三菱電線工業や三菱伸銅、三菱アルミでは、社内に改ざんを指南するマニュアルや書類が残されていたこともわかっている。特捜部は捜索で押収した関係書類をもとに、不正の期間や規模などについて、裏付け捜査をしているとみられる。
三菱マテでは今年6月、本社精錬所の不正発覚を受け、竹内章氏(63)が社長を引責辞任し、代表権のない取締役会長に就任している。同社は23日、「司法手続きに関する質問については、回答は差し控える」とコメントした。
非鉄金属大手・三菱マテリアルの子会社などによる品質データ改ざん問題で、東京地検特捜部が7月に複数の子会社を不正競争防止法違反(虚偽表示)の疑いで捜索し、強制捜査に乗り出したことが関係者の話でわかった。捜索が明らかになった子会社は社内調査で発覚後も不正を続けていたという。特捜部はこういった対応を悪質とみて、押収資料などをもとに実態解明を進めている。
関係者によると、捜索を受けたのは子会社の三菱電線工業(東京)、三菱アルミニウム(同)、ダイヤメット(新潟市)など。三菱マテ本社(東京)も関係先として捜索されたという。
三菱マテによると、これら子会社3社では2016から17年までに、三菱マテへの内部通報や監査などをきっかけに、データに関する社内の不正が発覚。しかし、その後も三菱マテへの報告を怠ったり、データが改ざんされた製品の出荷を続けたりしていた。ダイヤ社では、不正の発覚後、前社長が関連資料を隠蔽(いんぺい)するよう指示していたという。
お役所が厳しすぎるのかもしれないが、出鱈目な報告はだめだと思う。
役所は小さな問題であれば、是正措置が提出されれば、咎めない方が良いと思う。
「東邦航空」の対応は信頼を失い、常識を疑ってしまう。
群馬県の防災ヘリコプター墜落事故で、県からヘリの運航を受託していた「東邦航空」(東京都)の宇田川雅之社長が23日、同県庁に大沢正明知事を訪ね、「このたびは、申し訳ありませんでした」と謝罪した。
大沢知事は、事故は「痛恨の極みだ」と述べた上で、同社の社員2人が亡くなったことに哀悼の意を表明。宇田川社長に事故原因の調査に「しっかりとご協力いただきたい」と求めた。
東邦航空は2002年から県防災ヘリの運航を受託し、操縦士や整備士らを県防災航空隊に派遣していた。今回の事故では、社員が実際とは異なる飛行計画を国土交通省に提出した上、墜落したヘリが行方不明と知りながら同省に帰着を連絡していたことが分かっている。
県の防災ヘリ「はるな」は10日午前、登山道の視察飛行中に群馬県中之条町の山中に墜落。同社の社員2人を含む乗員9人全員が死亡した。
宇田川社長は知事らとの面会後に取材に応じ、ヘリが帰着したと報告した社員が「(行方不明を)このまま放置しておくと混乱が生じると判断した」と話していることを明らかにした。同社は近く、実際とは異なる飛行計画を提出したことなどについて、調査結果を県に提出する方針。
非鉄金属大手・三菱マテリアルグループの品質データ改ざん問題で、東京地検特捜部が、不正が発覚した複数の子会社を7月に不正競争防止法違反(虚偽表示)の疑いで家宅捜索していたことが関係者の話でわかった。三菱マテ本社(東京)も関係先として捜索した。特捜部は担当社員らから事情聴取するなど改ざんの実態解明を進めている。
特捜部は7月、製品の品質データ改ざん行為を巡り、法人としての神戸製鋼所を不正競争防止法違反(虚偽表示)の罪で起訴している。三菱マテも神鋼と同様に、製品の安全性は確認済みとしていたが、不正の規模が大きく、納品先も広範囲にわたることなどから、特捜部は強制捜査が必要と判断したとみられる。
関係者によると、捜索対象になったのは子会社の三菱電線工業(東京)、三菱アルミニウム(同)、ダイヤメット(新潟市)など。
三菱マテの最終報告書などによると、不正はこの3社と子会社の三菱伸銅(東京)、立花金属工業(大阪市)、本社直轄の直島製錬所(香川県直島町)で行われていた。子会社の不正は古いもので1970年代からあり、製品の出荷先は延べ825社にのぼっていた。関西電力大飯原発や高浜原発、航空機に使われるゴム製品などで、強度や寸法が顧客の求める基準に達していないのに、不正に検査の測定値などを書き換えて出荷したケースもあったという。
また、不正が確認された子会社5社のうち、少なくとも三菱電線工業や三菱伸銅、三菱アルミでは、社内に改ざんを指南するマニュアルや書類が残されていたこともわかっている。特捜部は捜索で押収した関係書類をもとに、不正の期間や規模などについて、裏付け捜査をしているとみられる。
三菱マテでは今年6月、本社精錬所の不正発覚を受け、竹内章氏(63)が社長を引責辞任し、代表権のない取締役会長に就任している。同社は23日、「司法手続きに関する質問については、回答は差し控える」とコメントした。
前川浩之、嶋田圭一郎 贄川俊
自動車大手で発覚した外国人技能実習生の不正な働かせ方が、電機大手の日立製作所の現場にも広がっている疑いが明らかになった。技術者を夢見て来日した実習生からは、日立と監理団体に対する不満の声が上がる。国から実習の監査を任されている、この監理団体は、日立グループへの実績を元に実習生を「安い働き手」として他の企業に売り込んでいた。
日立も技能実習不正か 目的外の職場に配置の疑い
日立製作所笠戸事業所(山口県下松市)で技能実習中の、あるフィリピン人男性の仕事は窓の取り付けだ。男性によると、実習生らが4人1組で重さ120キロ超の窓を運び、鉄道車両に手作業で取り付ける日々を繰り返しているという。男性は「電気機器組み立て」の実習目的で昨春来日したが、「これで技能が学べるのだろうか」と不安をもらす。
男性はフィリピンの理科系大学…
技能実習制度を大義名分として労働者を使おうとする意図があったからこのような問題が発生していると思う。
本当に実習させる意図で受け入れたのであればこんな事は起きない。
不公平とか、残酷とか思う日本人はいると思うが、大学に進学する意志がない生徒には直ぐに労働市場で必要とされる資格や経験を
高校で教える方が会社にも企業にも良いと思う。単純労働は短期間限定で外国人を使っても良いかもしれない。
「日立の実習生は、三菱自や日産と同じ「協同組合フレンドニッポン」(本部・広島市、FN)が紹介していた。FNは国の許可を得て実習状況を監査する「監理団体」で、法務省と外国人技能実習機構は、FNが適正に監査をしていたかどうかも調べている。」
最後に「協同組合フレンドニッポン」は問題に気付いていたか、適切に監査を行っていなかったと思う。そうでなければ、このような問題が
複数の企業で起こらない。
法務省と外国人技能実習機構が本気で調査すれば事実はわかるであろう。マニュアルとか、手順は存在するはずである。それを無視していたのか、
どうかと言う事だ。何もない状態であれば、外国人技能実習機構が「監理団体」と認めないはずだ!
「FNは「現在、職種不適合になっているといった事実はございません」と文書でコメントした。」
「協同組合フレンドニッポン」は事実を言っているのか、嘘を付いているのか調査で分かるであろう。
日立製作所笠戸事業所(山口県下松市)で、一部のフィリピン人技能実習生が、目的の技能が学べない職場で働かされている疑いがあることが分かった。技能実習制度を所管する法務省は7月、技能実習適正化法に違反している可能性があるとみて、国認可の監督機関「外国人技能実習機構」と合同で笠戸事業所を検査した。法務省は日立と実習生を紹介した団体に対して、同法に基づき改善を求める処分や指導を検討している模様だ。
実習目的とは違う職場で技能実習生が働かされている問題の構図
複数の実習生が朝日新聞に実習状況を証言した。笠戸事業所は鉄道車両の製造拠点で、新幹線や、官民一体で受注した英国高速鉄道の車両製造などを手がけてきた。実習生によると、フィリピン人実習生が数百人働いているという。
実習生の証言によると、配電盤や制御盤を作る「電気機器組み立て」の習得のために昨春から日立で働いている複数の実習生が、英国向けの高速鉄道や日本の新幹線の車両に、窓や排水パイプ、カーペットやトイレを取り付ける作業しかしていないという。複数の実習生は法務省と実習機構による聴取にも同じ内容を訴えたという。
国の基準は、電気機器組み立ての技能習得に配電盤や制御盤の加工などを「必須業務」と定めており、窓などの取り付けは該当しない。法務省は、1年目に必須業務を一切させない場合は不正行為にあたるとみている。
技能実習を巡っては、三菱自動車と日産自動車で実習生に実習計画外の作業をさせていたことが発覚している。日立の実習生は、三菱自や日産と同じ「協同組合フレンドニッポン」(本部・広島市、FN)が紹介していた。FNは国の許可を得て実習状況を監査する「監理団体」で、法務省と外国人技能実習機構は、FNが適正に監査をしていたかどうかも調べている。(前川浩之、嶋田圭一郎)
◇
日立の広報・IR部は、朝日新聞の取材に「一部会社(事業所)で監査を受けているが、その内容等については、お答えできない」とコメントした。
FNは「現在、職種不適合になっているといった事実はございません」と文書でコメントした。
■実習生の権利保障、議論を(視点)
外国人技能実習生を実習計画と違う仕事につかせている疑いはこれまでも指摘されてきた。日本を代表する大手製造業で相次いで発覚したことで、制度の「建前」と「本音」が大きくかけ離れているとされる矛盾が改めて浮かび上がった。
日本の優れた技術を海外に移転し、国際貢献するというのが1993年に始まった制度の建前だ。だが、実習生を受け入れる現場の多くでは、労働力として活用されている。建前と本音がずれたままで制度がスタートしたのは、80年代後半に経済界の要望を受けて外国人の受け入れ政策を検討した際、労働力としてとらえる考え方を政府内で合意できなかったからだ。
実習生は、職場を自由に変えることも家族を呼び寄せることもできない。一定期間を過ぎれば確実に帰国する。都合のいい労働力として活用され、対象職種が広がって人数も増えている。建前と本音のずれが抱える矛盾のしわ寄せを受けているのは、実習生だ。
政府は「移民政策とは異なる」としつつも、来年度にも新たな在留資格を設ける方針。最長5年間の実習を終えた実習生がさらに5年間滞在できるようにもする。労働者としての権利や人権を保障し、待遇を改善する視点で議論する時期に来ている。(編集委員・沢路毅彦)
スルガ銀行のシェアハウスをめぐるずさんな融資問題は思っていたように氷山の一角だったようだ。
ここまで不正がはびこってしまった以上、組織による再起は無理だと思う。どこかの銀行の吸収されて地獄を見ながら
変わっていくしかないであろう。転職できる行員は転職していくだろう。苦しくて不正を始めると止める事が出来なくなる。
人も会社も同じだと思う。
スルガ銀行を終わりにして、関係のない人達が関与して膿を出すしかないと思う。影響を受ける企業は存在すると思うが
スルガ銀行の寿命は長くないと思うので、影響を受ける融資先の選別を行い、問題の無い融資先は助けるべきだと思う。
スルガ銀行のシェアハウスをめぐるずさんな融資問題で、個人の投資用アパート向け融資でも数多く不正が行われていたことがわかった。「不適切融資」は大幅に拡大するとみられる。
スルガ銀行では投資用にシェアハウスの購入を希望する客らに融資する際、通帳などの書類が改ざんされていることを知りながら複数の行員が不正な融資を実行していたことがわかっている。
関係者の話で、不正な融資はシェアハウスだけでなく、「一棟売り」などの個人の投資用アパートでも、10以上の支店を通じて大規模に行われていたことがわかった。
個人が購入した物件について不動産の価値を高く見せかけ、より高い賃料がとれるように装うなどの方法をとっていたという。
スルガ銀行の投資用不動産融資はアパートなども含めると全体で2兆円に上り、新たにわかった不正で「不適切融資」は大幅に拡大するとみられる。
「県警などによると、昨年夏、一部業者から寄せられた情報を基に同社が内部調査したところ、元社員の男による詐欺の疑いが浮上。」
一部の業者から情報がなければ、新日鉄住金広畑製鉄所は原料納入の架空伝票に全く気付かなかったと言う事なのか?
結構、ずさんな対応に驚く。森に行って木を見てないようなものか?
「元社員の男の上司や姫路市内の別の業者も関与が疑われたが、詐欺罪の時効を迎えていたという。同社は2月、元社員の男と上司を懲戒解雇した。」
総額5億円を奪い取れば、懲戒解雇されても上司は優雅に生きていけるかもしれない。お金をどこに保管しているか次第。姫路市内の別の業者は
時効になって運が良いと思う。悪事の片棒の見返りは大きいに違いない。
鋼材原料の鉄スクラップを業者から納入したとする架空の伝票を作り、会社から代金をだまし取ったとして、兵庫県警捜査2課と網干署は21日、詐欺の疑いで、新日鉄住金広畑製鉄所(姫路市広畑区)元社員の男(43)=住所不定=を再逮捕し、新たに鉄スクラップ販売業者の男2人を逮捕した。同社が総額約5億円の被害を受けたとして刑事告訴していた。
2業者は46歳の男=大阪市淀川区=と38歳の男=姫路市岡田。元社員の男は、同様の手口で昨年1~11月に同社から計約3400万円をだまし取ったなどとして詐欺容疑で、スクラップ販売業の男(70)=明石市=と逮捕されていた。
再逮捕容疑は、46歳の男と共謀して2015年7~8月に計約440万円を、38歳の男と共謀して同年10~11月に計約330万円を同社からだまし取った疑い。
同課によると、元社員の男と業者の男2人は、架空伝票を基に同社から業者に支払われた代金を山分けしていたという。3人の認否は明らかにしていない。
県警などによると、昨年夏、一部業者から寄せられた情報を基に同社が内部調査したところ、元社員の男による詐欺の疑いが浮上。11年以降に計約5億円をだまし取られたとして刑事告訴した。元社員の男の上司や姫路市内の別の業者も関与が疑われたが、詐欺罪の時効を迎えていたという。同社は2月、元社員の男と上司を懲戒解雇した。
一部の儲かっている零細企業や中小企業を除けば、ある程度、名が通っている企業の問題。
日本の企業は一般的に優等生だと思うが日本人の多くは信念を実行できないので、姑息にずるをする傾向があると思う。
建前と本音の応用バージョンだと思う。事実は確認する事はほぼ不可能であるが、サントリーグループの子会社、ジャバンビバレッジは
この問題に気付いていたが、問題が大きくなれば支店長の責任にすれば良いと考えていたのではないのか?
サントリーグループの子会社、ジャバンビバレッジは顧問弁護士を抱えているだろうし、もしいないのであれば、サントリーグループの
能力がある弁護士がアドバイスをするだろうから、規則や法の盲点や逃げたかについては熟知しているであろう。
グレーゾーンでは処分されない。あくまでも事実が公表される事による企業イメージの悪化しか出来ないと思う。さらなる企業イメージの
悪化を避けるために改善する可能性もあるが、最終判断は企業で判断する権限を持つ人達次第。
サントリーグループ子会社、又はジャバンビバレッジに入社したい人はたくさんいると思えば、無視か、放置もあり得る。
就職活動する学生は多くの企業の内情をSNSやインターネットによる裏情報を調べる事は出来るだろうが、情報が事実であるのか、
推測だけで確認を取る事はほどんど無理であろう。また、企業がほしい人材と評価されなければ、情報を集めても採用されない。選択の
余地がない。
個人的な意見であるが、日本人は企業の名前に拘り過ぎて、自分で自分の首を絞めていると思う。個人の経験から言えば、
残念ながら日本の零細企業や中小企業は一部を除いては零細企業や中小企業の体質である。零細企業や中小企業なのに
従業員が手際が良いとか、感心する働き方と思う事はほどんどない。それほど儲かってなくても、ゆとりのある働き方を
していると思えるケースはある。お金が全てなのか、お金を優先させプライベートでストレスを発散させるのか、ゆとりのある
労働環境ではたらくのか、コンビネーションなのか、選択の余地などないなどいろんなケースはあると思う。中には
従業員が弛んでいる、又は、非効率な働き方を変えないのかと思う事もあるが、当事者達の問題だし、自分が知らない背景が
ある場合もあるので何も言わない。
サントリーグループ、又はジャバンビバレッジ入社したいと考えている学生や人は参考にすれば良いと思う。
「全問正解で有給チャンス」――サントリーグループの子会社、ジャバンビバレッジの支店長が従業員に送ったとされるメールが「ヤバすぎる」「どんなブラック企業だよ」と物議をかもしています。Twitterでメール画像を公開したブラック企業ユニオン(総合サポートユニオン)の担当者と、ジャパンビバレッジに話を聞きました。
【回答メール画像:全員不正解で「よかった。よかった」】
「そもそも有給は取れないのが当たり前」「分かっていても悔しい」
話題になった「有給チャンスクイズ」メールの画像は、ブラック企業ユニオンのTwitterアカウントが8月17日にツイートしたもの。メールは2016年に送られたもので、標題は「Re: 有給 チャンス クイズ」。本文では「全問正解で有給チャンス」「不正回答は永久追放します。まずは降格」といった文章とともに、15ある都内の駅名を売上の高い順に並び替えるクイズが出題されていました。にわかには信じ難い内容ですが、有給休暇を取得するにはこのクイズに正解しなければならない――ということのようです。
また後日送られてきた「Re: 有給チャンス 回答です。」というメールでは、「残念ながら全員はずれでした。よかった。よかった」と支店長(しかも問題にミスがあり、絶対に正解できなかった)。Twitterではこれに対し「有給チャンスとかいうパワーワード」「従業員はおもちゃじゃない」「労働基準監督署に訴えたら一発でアウト」など、会社側への批判が相次ぎました。
ブラック企業ユニオンの担当者によれば、メールの画像はジャパンビバレッジで働く従業員から提供されたもの。公開したメールはあくまで一部で、他にも社員に腕立て伏せを強要したり、「公開処刑メール」と称して失敗した社員をさらし上げたりと、同社では以前からこうしたパワハラが常態化していたといいます。
「ジャパンビバレッジは過去、 労働基準監督署から4回に渡って是正勧告を受けているにもかかわらず、まったく改善の色がみられません。今回の件も支店長1人の問題ではなく、会社全体の問題と捉えるべきです」(ブラック企業ユニオン 担当者)
また、メール内容については同日(8月17日)夜に行われた団体交渉でも追求されましたが、ジャパンビバレッジ側は「事実かどうか分からない」「確認します」との回答。また当初は支店長も同席予定でしたが、急きょ来られなくなり、電話で本人に確認してほしいと言っても応じてもらえなかったそうです。
クイズについては、「そもそも有給は取れないのが当たり前という状態なんです。無理やり有給を取ろうとして異動させられたケースもある。『取れないのが当たり前』というのを遠回しに言っているだけ」とブラックユニオン担当者。「それでもみんな有給取りたいから答えるんです。もしかしたら取れるかもしれない。でも正解者は1人もいない。分かっていても悔しいですよ」。
メール送付は事実、今後は「会社規定にのっとり適切に処分」
またジャパンビバレッジに問い合わせたところ、次のような回答がありました。
・・・・・
―― メール内容は事実でしょうか。送付の有無や、内容について確認は行いましたか。
ジャパンビバレッジ:当該支店長へのヒアリングを含めた調査を実施し、ご指摘のメールについて事実確認を行いました。その 結果、当人がメールを送付した事実および内容について概ね認めたため、厳重注意を行うとともに、今後、 会社規定にのっとり適切に処分いたします。
―― 「クイズに正解しないと有給を取らせてもらえない」「不正解だと降格」などの事実はありましたか。
ジャパンビバレッジ:そのような事実はございません。
―― 有給を取らせない、有給をとろうとしたら左遷するなどの事実はありましたか。
ジャパンビバレッジ:そのような事実はございません。
―― 社員への日常的な暴力、パワハラなどはありましたか。
ジャパンビバレッジ:その件に関しては、3年以上前のことでもあり、現在調査中であり、当時の状況確認等、少し時間がかかりますが、同様に不適切な行為が認められれば、会社規定にのっとり、適切に処分いたします。
―― 労基準署から4回に渡り是正勧告が出されているが、なぜ改善されないのでしょうか。
ジャパンビバレッジ:同一労基署から4度是正勧告を受けたわけではなく、同じ内容について、異なる4カ所の労基署より是正勧告を受けましたが、一部を除いて支払いは完了しております。
・・・・・
ジャパンビバレッジといえば、今年(2018年)4月にも残業代未払い問題を巡って東京駅で順法闘争が行われ話題になったばかり。編集部では現在、親会社であるサントリーにも対応について問い合わせ中です。
個人的な推測であるが、近海から遠洋漁業はさらに厳しい冬の時代が来ると思う。養殖及び沿海漁業以外は将来がないと思う。
日本が中国相手に規則を守らせる事は出来ない。中国はお金のためなら規則を守らないメンタリティーも持っている。中国経済が
衰退すると言われているが、衰退したとしても近海及び遠洋漁業は食料確保のために伸びるであろう。
日本の消費者が高くても欲しいと思わなければ、業界が行けるとこまで我慢するか、縮小していくしかないと思う。
東日本大震災からの復興を目指す三陸の浜が、深刻な漁業不振にあえいでいる。主力魚種の記録的不漁に貝毒禍が養殖漁業を襲う。活気が失われていく浜で今、何が起きているのか。東北有数の水産基地・大船渡から報告する。(大船渡支局・坂井直人)
【グラフ】大船渡市魚市場の総水揚げ量と1kg当たりの平均単価
地域経済をけん引してきた老舗企業の、まさかの倒産だった。
創業の地大船渡市に今も主力工場を構える水産加工「太洋産業」が7月、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。
加工用サンマの記録的不漁が響いたという。東京商工リサーチ盛岡支店によると負債総額は約49億円。岩手県の水産業者の倒産では過去最大規模だ。
当面は操業や雇用が維持され、連鎖倒産は回避される見通し。影響は最小限にとどまりそうだが「震災からの復興に向かう中、非常に暗いイメージになる」と斉藤俊明大船渡商工会議所会頭の表情はさえない。
市魚市場の総水揚げ量と1キロ当たりの平均単価の推移はグラフの通り。2017年度も3万7604トンと低迷する一方、単価は16年度の158円から186円に上昇。原料不足と魚価高が浜の加工業者を苦しめる。
水産庁によると、岩手の水産加工業が挙げた震災復興の課題は「原料確保」が13年度の13%から17年度は31%に跳ね上がり、「販路確保・風評被害」(15%)を上回った。
人件費などの経費増に、震災前の債務や新たな借金がのし掛かり「どこも、明日はわが身だ」(大船渡市内の水産加工業者)。
イカの加工を手掛けるサンコー食品は近年、原料を求めて輸入割合を引き上げた。しかし、イカもまた世界規模で資源の奪い合いが始まっていた。
今年から安価な地元産フグの加工を始め、生産ラインの複線化に取り組む小浜健社長。「顧客が求めるものづくりをして、大きい会社ではなく強い会社を目指す」と話し、生き残りを懸けた模索を続ける。
水産加工団体も動く。7月末には大船渡市を含む気仙地域の業者が勉強会を初めて開いた。「各業者に業務を割り当て、地域で一つの商品に仕上げたらどうか」。企業間連携に活路を見いだそうというアイデアも示された。
大船渡に水揚げされた魚介類の流通は鮮魚出荷や冷凍処理が9割以上を占め、より高度な加工に回るのは1割に満たない。
「これまで大船渡は豊富な漁獲に頼り、付加価値を高めることに後れを取っていた」と、水産加工会社「森下水産」社長で大船渡湾冷凍水産加工業協同組合の森下幹生組合長は語る。
不漁のただ中で、水産加工業が自己改革を迫られている。
「役職員の安全意識とコンプライアンスを定着させる具体的な施策がなく、情報共有もされなかったため、国交省から厳重注意を受けた際に十分な対策を講じることができなかったという。」
日本郵船は船の管理能力に関してはナンバーワンだと思うが、なぜ日本貨物航空(NCA)に関してはこれほどずさんであったのか?
飛行機は船以上に適切な整備や管理が必要だと思うのに、安全意識とコンプライアンスが定着していないとは理解できない。推測であるが
役員は高学歴だと思うが、安全意識とコンプライアンスを理解出来ないほど間違った人事が行われていたのだろうか??
日本郵船は17日、子会社の日本貨物航空(NCA)が整備記録の改ざんや隠蔽によって国土交通省から業務改善命令を受けたことに関連し、日本貨物航空が同日、改善措置を提出したと発表した。
日本貨物航空は現在、全11機のうち2機の運航を再開しているが、残る機体についても健全性を確かめて耐空検査を受けた後、段階的に復帰させる方針。
提出した改善措置の中で、日本貨物航空は今回の問題が起きた要因について、2012年から新たな機体を導入したことで、1機種のみを運用していた時期に比べて整備業務量が増加したこと、機数が5年間で60%増えたにもかかわらず、整備部門の人員が微増にとどまったことを背景に、運航規模に対して人員数が徐々に不足していった、と説明。
また、業務量の増加から管理部門が現業部門に十分なサポートを提供できなくなり、現業部門が独自判断・解釈する環境が醸成され、「経験・知識を備える者に対し意見が言えない組織風土」が生まれたことが、記録の改ざんや隠蔽につながった、とした。
さらに、役職員の安全意識とコンプライアンスを定着させる具体的な施策がなく、情報共有もされなかったため、国交省から厳重注意を受けた際に十分な対策を講じることができなかったという。
こうした反省を踏まえ、同社は人員規模に見合った運航規模への見直しを図るため、ボーイング747-8Fへの「1機種化」を検討。4月には、提携先の全日本空輸(ANA)から5人の人的支援を受け、整備スタッフ部門と整備現業部門の強化を図っていることや、9月1日から追加で3人の人的支援を受け、品質保証部門・技術部門・現業部門のマネジメント強化を図ること、整備現業部門へのサポート強化、社長・安全統括管理者による全部署との直接的な対話機会を創出し、安全意識とコンプライアンス意識の醸成・徹底を図ること――などの改善措置をまとめた。
日本郵船でも、日本貨物航空による改善措置が確実に実行されるよう、再発防止の徹底に取り組むことを監督・支援していく、とした。
「日本大アメリカンフットボール部の選手が悪質なタックルをした問題で、同部の複数の部員が警視庁に対し『監督の指示があった』という趣旨の説明をしていることが17日、日大関係者への取材で明らかになった。」
裁判で証明されれば、内田正人前監督は社会的に信頼を失い、有罪とされると思う。
日本大アメリカンフットボール部の選手が悪質なタックルをした問題で、同部の複数の部員が警視庁に対し「監督の指示があった」という趣旨の説明をしていることが17日、日大関係者への取材で明らかになった。内田正人前監督と井上奨元コーチは任意の事情聴取に指示を否定しているといい、警視庁は経緯を慎重に調べている。
捜査関係者によると、警視庁は部員やチーム関係者らから経緯を聞いている。複数の部員が反則行為について「監督の指示があった」と説明した一方、前監督らは聴取に対して否定したという。
問題のプレーは5月6日、東京都調布市であった日大と関西学院大の定期戦で起きた。日大選手のタックルで関学大選手は負傷し、警視庁調布署に傷害容疑で被害届と告発状を提出していた。
タックルをした選手は記者会見で、内田前監督、井上元コーチの指示だったと説明していた。日大が設置した第三者委員会は、内田前監督について「相手に対する傷害の意図があったと認めるのが相当」、井上元コーチの指示も「傷害の意図を含んでいた」と結論づけている。【春増翔太、山本佳孝、土江洋範】
実績の基づいてボーナスや給料がアップするのは問題ないと思う。但し、不正を行った場合は、厳しい処分を行う事をセットにしていれば良い。
もし、不正を関与した場合の厳しい処分がなければ、トップが不正を含めて実績を求めていた可能性がある。トップは問題が発覚した場合、
不正を想定していなかったと言い訳をすれば、明確な証拠や複数の証言者が見つからなければ、グレーゾーンで逃げれる可能性がある。
実績だけを強調すれば、不正に手を染める行員が出る事が想定出来ても、それを口外しなければ予測していたと証明する事は困難。
経営陣の責任を問われても、悪意のある計画や指示と無能である経営陣のケースでは処分に大きな違いがあると思う。
恥をかいても無能である経営陣と判断される方が処分が軽いと思われる。
最終的には金融庁がどこまで踏み込んだ調査を行い、その結果に対してどのような処分をするか次第。
スルガ銀行のシェアハウスをめぐる、ずさんな融資の問題で、背景には融資の実績がボーナスに直結する利益至上主義があったことが日本テレビの取材でわかった。
スルガ銀行では、シェアハウス購入を希望する個人に十分な自己資金がなくても、改ざんされた通帳などをもとに融資を行っていた。
関係者によると、ずさんな融資の背景には、融資額が行員のボーナスに直結する制度があったことが新たにわかった。ボーナスの額が融資の契約額に応じて変動する仕組みで、年間で月給の4か月分から1年分までの幅があったという。
スルガ銀行では、問題発覚後にボーナスの制度を変更しているが、金融庁では利益至上主義がずさんな融資をうんだとみて、経営陣の責任を問う方針。
「全剣連の中谷行道・常任理事は『トラブルが続いたことを、真摯しんしに反省している。再発防止に取り組みたい』と話した。」
日本語は曖昧。「再発防止に取り組みたい」=「問題を解決する」ではない可能性がある。建前だけの再発防止の取り組みであれば、
問題は改善しないし、解決しないであろう。時が経って、人々が忘れるのを待つだけかもしれない。
全日本剣道連盟(全剣連)の「居合道」部門で、審査の際に、受審者が審査員らに現金を渡す行為があったことが17日、わかった。全剣連が同日、こうした金銭授受の不正行為が常態化していたことを認めた。
全剣連の居合道は八段まである段位のほか、六段以上の段位を持つ者にしか受審資格がない錬士、教士、範士という「称号」がある。それぞれ審査で合否が決まるが、全剣連によると2012年、最高位である範士の「称号審査」で、受審者1人が審査員ら7人に1人10万~20万円ずつ、計約100万円の現金を渡した。また16年にも、八段の昇段試験で、ある男性が、審査員に渡すために200万円を指導者に預けていたことが発覚。指導者は審査員に渡さず、本人に返却した。
全剣連では12年の関係者7人を段位・称号の返納処分にした。全剣連の中谷行道・常任理事は「トラブルが続いたことを、真摯しんしに反省している。再発防止に取り組みたい」と話した。
今度は、剣道界で不正。
全日本剣道連盟の居合道部門で、昇段審査などの際に、審査員らに金銭を渡して合格させてもらうことが横行していたなどとする告発状が、内閣府などに提出されていたことがわかった。
内閣府やスポーツ庁に提出された告発状では、鞘(さや)から刀を抜き放つ武術の「居合道」で、最上位となる八段など高段者の審査の際に、審査員などに金銭を渡して合格させてもらうことが横行していたと指摘している。
内閣府の公益認定等委員会は、6月に告発状の提出を受け、剣道連盟に監督権限がある日本オリンピック委員会と日本スポーツ協会に対して、事実関係の確認や、今後の対応を報告するよう求めている。
一方、全日本剣道連盟は17日午前、取材に対応し、金銭を授受する慣例を認め、「審査に近い時期に金銭を授受する、不適切な慣行が古くから存在した」ことを認めている。
「建築士」不足が現場の問題に成りつつなっているのか、それともたまたまブラック職種として取り上げたのかよくわからない。
周りが問題を放置したければそれはそれで良いと思う。時代が変われば仕事のニーズや人気の職種は変わる。それで良ければ
時代の流れ。
需要と供給にはタイムラグが存在するケースがある。供給が過剰であるから、需要側はそれを利用するパターンは多くある。
供給が減り、需要があれば逆転現象になることもある。需要が減り、供給が減ればそれは時代が必要としていない事。
「加えて2005年に明るみになった耐震偽装事件を受け、建築基準法だけでなく試験制度を規定する建築士法も大きく改正された。信頼回復のために新しい試験制度では法規や構造についての設問が増えたほか、
新たに『環境・設備』の設問が追加された。・・・建築士の労働環境には構造的な理由もある。・・・『一級建築士は足の裏の米粒。取らないと気持ち悪いが、取っても食えない』(建設業関係者)。」
行政がどのような対応するかも影響する。既に業界にいる人達は簡単に業界から去らないが、業界に入っていない人達はいろいろと
考える。他の選択の方が良い選択と思えば、建築士を選ばない。「建築士」だけの問題ではなく他の業界でも同じ問題を抱えている。
日本は無駄に働きすぎている、又は、隠された無駄がある。原因は日本社会、そして、それを容認している多くの日本人達。自分達で
自分の首を絞めながら、何がおかしいのか気付いていない。「おもてなし」は本気でおもてなしをしたくないのなら「おもてなし」など
しなくてよい。日本だから「おもてなし」は止めた方が良い。オリンピックバージョンの凄くマイルドな「刷り込み」と「洗脳」のコンビネーションだと思う。
「今の事務所で働き始めて2年ほどになるが、月の残業時間は200時間以上」――。関東に住む20代男性はそうこぼす。彼が所属する「事務所」とは、設計事務所のことだ。
この記事の写真を見る
建物の設計図を描く設計事務所だが、図面は描いたら終わり、とはいかない。大まかな形やデザインを考える基本設計、契約に必要なレベルまで詳細詰める実施設計のほか、工事業者や役所との打ち合わせ、場合によっては自ら現場に出向くなど、建築士の仕事は幅広い。
「時間をかけるほど良いものになるので、どうしても残業時間が長くなる」(男性)。
■足りない? 足りてる? 建築士の今
働き方改革が叫ばれる昨今、建築士業界への風当たりも強いと思いきや、業界は別の角度からの逆風にさらされている。
6月5日、建築士や建築事務所で構成する3つの業界団体は「建築士資格制度の改善に関する共同提案」を公表した。文書の一文にはこんな記載がある。「将来を担う世代の建築士の確保が懸念される」。
念頭にあるのは、減り続ける一級建築士試験の受験者数だ。建物の設計や工事監理を行ういには建築士の免許が必要で、扱える建物の種類や規模によって一級・二級・木造に分かれる。中でも一級建築士はすべての建物を扱うことができるため、建築士としてのキャリアのゴールには一級建築士を置くのが通常だ。
ところが、その一級建築士を目指す人数が減り続けている。一次試験(学科)の受験者数は、直近20年間では1999年の5万7431人をピークに、昨年には2万6923人と半分以下にまで減少した。その上、「一級建築士のうち約6割が50代以上。後継者不足が懸念される」(日本建築士事務所協会連合会の居谷献弥専務理事)と焦りを隠さない。
受験者数減少の原因として挙げられたのは、仕事が忙しすぎて受験勉強の時間が十分に取れないことだ。資格取得ルートは複数あるが、一般的な建築系学科の学生が一級建築士の資格を取得するには、卒業後2年間の実務経験が必要。だがいったん仕事を始めてしまうと試験勉強との両立ができず、資格取得のハードルとなっているというわけだ。
冒頭の男性も二級建築士の資格を持っているが、「好きでこの仕事をやっているので、辞めたいとは思わない。ただ土曜出勤はもちろん日曜も自宅で仕事をすることもあり、試験勉強は通勤時間くらいしかできない」と嘆く。
一級建築士の試験は司法試験や公認会計士試験ほどではないものの、決して生易しいものではない。学科試験の合格率は約2割。加えて2005年に明るみになった耐震偽装事件を受け、建築基準法だけでなく試験制度を規定する建築士法も大きく改正された。信頼回復のために新しい試験制度では法規や構造についての設問が増えたほか、新たに「環境・設備」の設問が追加された。
学科試験を突破しても今度は製図試験が待ち受け、最終的な合格率は1割強に留まっている。製図試験に3回不合格になると、また学科試験を受けなおす羽目になる。
建築士資格の予備校である日建学院の講師で、一級建築士資格試験の参考書の編集も手掛ける二宮淳浩氏は「重箱の隅を突くような問題も多く、独学では相当厳しい。ほとんどの受験生が予備校に通っているが、仕事が忙しくて欠席が続く学生も少なくない」と指摘する。建築士法の改正で試験全体が難化したという声も上がるなど、耐震偽装事件の「古傷」は未だ癒えない。
そこで今回の共同提案では、2年間の実務経験は試験合格の後に積んでもいいことを盛り込んだ。また製図試験を手書きでなくCAD(コンピューター利用設計システム)で行うことや、2回不合格になると振り出しに戻る制度の廃止なども提言した。
「試験のための試験になっているうえ、建築士法の改正(による試験制度の改正)を受けて門戸が狭くなった。試験をもっとチャレンジしやすい形にしたい」と、日本建築家協会の筒井信也専務理事は意気込む。
■試験制度だけが問題なのか
こうした提案について、現場の建築士には「基本的には賛成だが、課題は試験制度に留まらない」という雰囲気が漂う。
資格試験の受験者数を増やしても、建築士が増える保証はない。建築士資格を取っても設計事務所に勤めるとは限らず、工事を手掛けるゼネコンはもちろん、工事を依頼する側の不動産会社や果ては自治体の職員に至るまで、建築の知識を得るために資格を取得する人は多い。
従業員が数十人、数百人といった大所帯の組織設計事務所やゼネコンの設計部門は「一級建築士に不足感はない」(設計事務所で最大手の日建設計)とする一方で、苦境にあるのは従業員が数人の個人事務所。「募集をかけてもまったく人が集まらない」(首都圏の設計事務所代表)のが実態だ。
厚生労働省の「平成29年賃金構造基本統計調査」によれば、従業員10~99人の事業所で働く一級建築士の平均年齢は54.3歳で月収は約41.1万円で、ボーナスなども加えれば年収は532万円。大手事務所やゼネコン、不動産会社所属の一級建築士が主な対象である従業員数1000人以上の事業所と比較すると100万円以上も低く、人材の奪い合いになれば、大手に太刀打ちすることは難しい。
さらに実情は、統計の対象にすらなっていない10人未満の個人事務所が大半を占める。約1万5000もの設計事務所が加盟する日本建築士事務所協会連合会でも「半数以上が従業員数1~3人の事務所」(居谷専務理事)という。
冒頭の男性は「初めに面接に行った個人事務所で提示された月給は10万円。これではさすがに働けないと今の事務所に所属しているが、それでも月給は額面でも20万円を切るうえに、ボーナスもない」。加えて厳しい労働環境がのしかかる。
建築士の労働環境には構造的な理由もある。一般的な戸建て住宅の場合、国土交通省告示による報酬基準はあるものの、およそ建築費の1割が設計料の相場感として存在する。ところが実際には「1割ももらえることはほとんどない。せいぜい6%くらい」(ある一級建築士)。
4000万円の家に対して設計料が400万円だとしても、基本設計から工程監理まで結局、1年以上物件に張り付かざるをえないこともあり、当然事務所は火の車だ。
建設会社の中にはその後の受注を見込んで「設計無料」を掲げる会社もあり、顧客も見積もり無料の感覚で設計の依頼をかける例も多いという。むろん設計だけで食べている設計事務所にとっては受け入れられない話だ。
公共施設の場合は報酬が安定している代わりに設計コンペがあり、採用されなければ設計にかかった時間と労力は水の泡。著名な建築家になれば「先生にぜひ建ててほしい」と高い設計料でも仕事が舞い込むが、それはほんの一握りだ。
神奈川県で個人設計事務所「TERRAデザイン」を主宰する寺本勉氏は、「設計には形がなく、顧客に価値を認められにくい。形なきものにも対価を支払う文化が必要だ」と指摘する。
「東日本大震災での高台移転の際、本来なら地元の事情を理解し、普段から建物と向き合っている地元の建築士がもっと活躍するべきだった。だが住宅ならずっと住宅を手掛けていると、いつしか業務と直接関係のない知識が薄れていってしまう。結果的に都市計画を専門とする学者や開発業者に主導されてしまった」(寺本氏)
単に依頼された建物を設計するだけでなく、まちづくりなど公益への貢献を通じて、建築士の存在意義を社会に認知していくことが、建築士の価値が認められる第一歩となりそうだ。
■脱「足の裏の米粒」資格
「一級建築士は足の裏の米粒。取らないと気持ち悪いが、取っても食えない」(建設業関係者)。弁護士や公認会計士のような同じ「士業」とは異なり、資格を取っても仕事の範囲が急に広がるわけではない。
好きな仕事という一心で寝食を忘れて没頭しさえすればいい、というのは今や昔。今回の共同提案を基に建築士法を改正する議員立法が検討されているが、建築士業界の揺れを止めるためには、試験制度だけでなく自らの働き方から存在意義に至るまで根本的に見つめ直さなければ、業界を襲う揺れが収まることはない。
一井 純 :東洋経済 記者
金融庁による検査やチェックが厳しくなっているのか?
京都銀行(本店・京都市)は16日、西山科支店(同市山科区)に勤務していた30代の男性行員が顧客11人の口座から計5634万円を着服していたと発表した。13日付で懲戒解雇処分にしたという。
同行によると、この行員は京都府内の4支店に勤めていた2006年6月から今年5月に計43回、投資信託などの購入や運用といった虚偽の名目で、顧客に口座から現金を引き出させて着服。顧客から今年7月、運用について問い合わせがあり調べたところ、行員が「飲食代などに使った」と着服を認めたという。全額を返済済みで刑事告訴はしないという。
検査結果次第であるが、努力してなんとかなる状態ではないと思う。
シェアハウス投資を巡るずさん融資問題で、金融庁がスルガ銀行に不動産融資業務の一部停止命令の検討に入ったことが14日、分かった。経営陣が現場の実態を把握せず、問題融資のまん延を防げなかった点を問題視し、厳しい行政処分が必要と判断した。ガバナンス(企業統治)に重大な欠陥があるとして、経営体制の刷新も求める方針。
シェアハウス関連の融資業務の新規取り扱いを一定期間取りやめさせるといった処分を検討しているとみられる。金融庁は今春から行っているスルガ銀への立ち入り検査を近く終了する予定で、検査結果を精査した上で最終判断する。
シェアハウス融資に伴う不良債権の影響でスルガ銀の業績は低迷しており、株価は10日から3営業日連続で取引時間中の年初来安値を更新した。
スルガ銀が設置した外部弁護士による第三者委員会は今月下旬にも調査報告書をまとめる。これまでの第三者委の調べで、元専務執行役員が営業部門責任者として融資拡大を主導した経緯や、取締役会が審査書類改ざんなど不適切な融資の横行を防げなかったといったガバナンスの欠如が明らかになっている。
金融庁もこうした内容を把握しているもようで、スルガ銀に対し、法令順守体制の強化や再発防止策の策定といった対応も強く求めていく方針だ。
騒動の発端となったのは入居低迷で1月に運営が頓挫したシェアハウス「かぼちゃの馬車」向けの融資。スルガ銀の横浜東口支店を舞台に、会社員ら約700人に物件購入費として1件当たり1億円超を貸し込んでいた。融資に伴う審査書類の改ざんや無担保ローンの抱き合わせ販売が発覚している。
不適切な融資拡大問題が組織の問題であるのであれば、氷山の一角が見えただけで、見えていない問題の塊が存在するかもしれない。
スルガ銀行(沼津市)は14日、顧客3人の定期預金を不正に解約して約1億6500万円を横領したとして、本店営業部の男性行員(40)を懲戒解雇したと発表した。処分は13日付。
同行によると元行員は平成27年4月から今年6月にかけて、顧客3人の定期預金計約1億6500万円を勝手に解約し、その大半を自分が担当する取引先への融資金として流用していた。今年6月に顧客からの問い合わせで発覚し、同行が調査していた。元行員は事実関係を認めているという。
同行は金融庁に報告しており、今後元行員を刑事告訴する方針で、関係者の処分も検討している。
動態管理システムやその他のリアルタイムなシステムはあくまでも人をサポートするシステム。
高いシステムやサービスを導入しても上手く利用しなければコスト対効果でコストだけがアップする。
40分早くヘリコプターの位置のロストに気付いていたら乗員の命が助かったのかはわからないが、
推測であるが動態管理システムは維持管理費用まで含めると結構高価な買い物だったと思う。
便利なシステムであると思うが、コストは高いと思うので、導入したのであれば
しっかりと運用するべきだと思う。
防災ヘリと失った人命を考えればかなりの損失である。原因を突き止め防止策に生かすべきだと思う。
群馬県の防災ヘリが墜落した事故をめぐり、県が異常に気づいたのは、GPSを使ってヘリの位置が確認できる「動態管理システム」の記録が途絶えてから約40分後だった。
県消防保安課によると、動態管理システムで、ヘリとの通信が終了したのは10日午前10時1分。県の防災航空隊事務所にいた隊員がこれに気づいたのは、午前10時40分ごろだったという。無線や携帯電話などでヘリとの連絡を試みたがつながらず、午前11時45分に消防保安課に報告した。
消防保安課は午後0時24分に総務省消防庁に、県危機管理室は午後0時58分に陸上自衛隊に、それぞれ連絡。知事から自衛隊への正式な災害派遣要請は午後1時43分だった。
動態管理システムは昨年4月に導入。記録する時間間隔は変更可能で、今回は20秒おきの現在地を記録する設定にしておいたという。運用ではシステムを常時監視することにはなっていなかったが、県の担当者は「システムがいかされなかったのでは」と報道陣に問われ「おっしゃるとおり。残念だと思う」と述べた。(寺沢尚晃)
■ヘリ墜落までの経緯(群馬県の説明による)
午前9時半ごろ 群馬県長野原町内の病院を離陸
午前10時1分ごろ 動態管理システムの通信が終了
午前10時40分ごろ 県防災航空隊が動態管理システムの通信終了に気づく。その後、無線、携帯電話の順でヘリに連絡をするが応答なし
午前10時45分ごろ 前橋市内のヘリポートへの着陸予定時間
午前11時ごろ 県防災航空隊が吾妻広域消防本部に依頼し、ヘリに無線連絡をしてもらうが応答なし
午前11時45分ごろ 県防災航空隊から群馬県消防保安課にヘリが行方不明と一報
行員に悪意があれば、現状のチェック機能やシステムでは不正が可能である事が証明されたケースだと思う。
特定の行員なのか、指示を出していた幹部が存在するのか知らないが、ここまで巧妙に悪意のある融資を実行する必要があったのか?
金融庁は今回の件から何を学んで、どのような改善策を実行するのだろうか?
スルガ銀行(静岡県沼津市)のシェアハウス関連融資で、同行の行員がダミー会社を次々に設立して融資を拡大させていた実態が10日、明らかになった。ある不動産業者が販売するシェアハウスへの融資を当時の幹部が禁じたものの、別会社の案件のように装い行内審査をくぐり抜けていた。
企業統治の機能不全ぶりをうかがわせる内容で、弁護士らで構成する同行の第三者委員会も調査を通じ、こうした実態を把握しているもよう。組織ぐるみかどうかも含めた全容と改善策を盛り込んだ報告書を月末までにまとめる。
家賃の安さが魅力のシェアハウスは若者の間で人気がある。これに目を付けた不動産会社が投資物件として個人に販売。同行などがこうした個人投資家に購入資金を融資した。同行のシェアハウス関連融資は2014年後半から急増した。
関係者によると、15年2月ごろ、ある不動産業者の資質を問題視して告発する文書が同行や金融庁に届いた。これを創業家出身の岡野喜之助副社長(当時、故人)が知り、この業者が絡む融資をやめるよう指示した。
だがごく短期間の停止後、ある支店長(当時)の指示により、実際にはこの業者が販売したシェアハウス案件なのに、ダミー会社を使って別会社の案件と偽り融資を再開。審査部門に見つかると、新しいダミー会社を次々作って、シェアハウス関連融資を続けたという。
同行は、17年10月にシェアハウス向けを含む不動産担保ローンの審査要件を厳格化したが、一部のシェアハウス向け融資は同年12月まで続いたもようだ。こうした融資では、外部にローンの審査基準が漏れたずさんな事例も多数見つかっている。
天下りは天下りの目的なので経験や能力が適しているわけではない証拠。
コンコルディア・フィナンシャルグループ(FG)傘下の東日本銀行(東京)は10日、取引先から根拠不明の手数料を取るなど不適切な融資が見つかった問題で、内部管理体制の確立を柱とする業務改善計画を金融庁に提出した。2011年から今年6月まで頭取を務めた石井道遠会長(元国税庁長官)(66)は今月末で退任する。
東日本銀では、石井氏が頭取だった15年から17年にかけ、不適切な融資が多数発生していた。同行は石井氏が自ら退任を申し出たと説明しており、不祥事の責任を取ったとみられる。
記者会見した東日本銀の大神田智男頭取(61)は「このような事態を二度と発生させないため、計画遂行に全力で取り組み、信頼回復に努める」と強調した。
大神田頭取は続投し、会長職は空席とする。また、石井氏、大神田氏のほか、コンコルディアFGの川村健一社長と寺沢辰麿前社長(元国税庁長官)らは役員報酬の一部を削減・返上する。
金融庁は経営力強化を狙い、ここ数年、地銀に対して「天下り体制」脱却を促してきた。横浜銀行、東日本銀行を傘下に持つコンコルディアFGに対しても同様だ。旧大蔵省(現財務省)出身の石井道遠(みちとお)氏は6月に頭取を退いたばかりだが、今回の処分を受けてわずか2カ月で会長職も退くことになり、天下り体制は終わる。
横浜銀の頭取は旧大蔵省OBの“指定席”で、天下り体制はこれまで約70年続いてきた。東日本銀も平成5年から受け入れてきた。
「地域金融をめぐる環境はめまぐるしい。低金利環境が続くので、それを乗り越えられる現場経験が必要だ」。コンコルディアFGの川村健一社長は、10日の記者会見で天下り脱却の狙いを説明した。
地銀はかつては許認可権限を握る旧大蔵省とのパイプが重視され、OBを起用するケースがあった。だが、現在は日銀の大規模金融緩和による超低金利で利ざや(貸出金利と預金金利の差)が稼げなくなっており、人口減少もあって貸し出しの先細りは目に見えている。金融庁は旧大蔵省が母体だが、かつての金融行政の失敗を教訓に、全国の地銀にコーポレートガバナンス(企業統治)改革を促している。
天下りを放置していれば、旧大蔵省OBに手心を加えているとの批判を浴びかねず、地銀の“甘え体質”を払拭できないとの懸念もあったようだ。
6月には、島根銀行で頭取や会長など取締役を16年にわたって歴任した田頭基典(たがしら・もとのり)取締役相談役が退任した。今後、旧大蔵省出身者が経営者として残る西日本フィナンシャルホールディングスや佐賀共栄銀行などについて、金融庁がどう判断するのかが注目されている。(飯田耕司)
不適切営業などの問題があった東日本銀行は10日、金融庁に業務改善計画を提出した。企業統治改革などを推進する組織を新設したり、親会社のコンコルディア・フィナンシャルグループ(FG)やFG傘下の横浜銀行から20人程度の派遣を受けたりすることなどが柱。経営責任を明確にするため、東日本銀の石井道遠(みちとお)会長は8月末で退任。役員ら7人とFGの社長ら2人の計9人を処分する。
記者会見した東日本銀の大神田(おおかんだ)智男頭取は陳謝した上で、「法令順守や顧客本位のサービスなどを再確認し、組織全体に浸透させる」と述べた。
業務改善計画では、司令塔となる「経営改善会議」を設置。大神田氏ら同行役員とFG役員、外部専門家らが参加し、内部管理体制の強化の進み具合などをチェックする。
また、「営業企画部」を新設して顧客本位の業務運営を徹底。営業店の不正に本社が歯止めをかけられなかった反省も踏まえ、営業店の権限を縮小する。経営改善に注力するため、中期経営計画で掲げた新規出店は当面凍結し、収益目標も見直す。
不祥事が多発した原因について大神田氏は「規模に合わせた内部管理体制の整備が不足していた」と説明。平成28年に統合した地方銀行首位の横浜銀行にのみ込まれないよう経営陣が過度なノルマを課し、現場を不正に駆り立てたとの見方については、「そういうプレッシャーが強かったわけではない」と否定した。
木村聡史、近藤郷平 箱谷真司
スバルと日産自動車で明るみに出た排ガス・燃費のデータ測定をめぐる不正が、スズキやマツダ、ヤマハ発動機にも飛び火した。スズキは2年前にも燃費測定をめぐる不正が発覚しており、再発防止策に実効性が乏しく、チェック機能が働いていない実態が浮き彫りになった。
日本車の品質不正、拡大の様相 スズキなど3社で判明
検査基準、甘い認識
「書き換えや改ざんはなかった」。スズキの鈴木俊宏社長は9日、東京都内で開いた記者会見で重ねてそう強調した。検査データの改ざんが明るみに出たスバルや日産自動車に比べ、悪質な不正ではないとの思いが透けて見えた。だが、今回のスズキの不正は、改ざんをするかしないか以前の問題をはらんでいる。
検査に詳しい管理職を配置していなかった▽検査員の速度基準の認識が不十分だった▽基準を逸脱した時の再試験などのルールがない▽1台ずつの検査時にモニターに表示される基準逸脱を示す数値が、検査の終了後にすぐ別の画面に切り替わってしまう――。スズキが明らかにしたのは、こんなずさんな検査実態だった。
不正は静岡県内の3工場で見つかった。国内で自動車を組み立てる全工場で不正があったことになる。調査対象のほぼ半数にあたる6401台が検査条件を逸脱し、湖西工場での不正は調査対象の7割超に及んでいた。にもかかわらず、検査員19人に聞き取り調査したところ、「不正の認識があった」と答えた検査員は一人もいなかったという。検査条件を大幅に逸脱した不正も見つかっており、スズキは社内調査を続ける。
スズキは2016年5月にも、三菱自動車に続いて燃費不正が発覚した。燃費測定の元データとなる「走行抵抗値」を違法な方法で測定し、正しい方法で測ったように記した書類を国に提出していた。他社に供給した車を含めて計26車種、計214万台で不正が見つかった。不正の責任をとって鈴木修会長がCEO(最高経営責任者)職を返上した。
鈴木社長は当時も再発防止を誓…
「菖蒲田専務は、検査で許容されている速度の超過時間を一部超えていたにもかかわらず、データを無効にしなかった案件が一部あったと説明した上で、『意図的ではない』と強調。6カ月間の研修を経て認定を受ける検査員は自負を持って検査作業に取り組んでおり、時間を超えたものがあったことに「ショックを受けている」と話した。
今回の事案はデータ改ざんや組織ぐるみの不正ではなく、品質を確保するプロセス、システムに課題があったとして『不正とは考えていない』とも指摘。経営陣や従業員への処分なども現時点で『考えていない」とした。』
「意図的ではない」が事実であれば6か月の研修では十分でない可能性を意味していると思う。間違った解釈かもしれないが「認定」は最低限の
基準を見たしていると評価された事実であって、「自負」とは全く関係ない。「認定」されても認定するプロセスや認定する人間に問題があれば、
認定された人のレベルにばらつきがあり、最悪の場合、ばらつきの上の下の人間でかなり差が出てくることになる。
品質を確保するプロセス、システムに課題があったのであれば、品質管理や人材教育の担当者や責任者は処分されるべきだと思う。
組織的に意図的にやったのであれば、処分される人達は不満を持つから処分しないと判断したとも考えられる。
トヨタの車に乗っているので、トヨタがしっかりローモデルとしてしっかりしてくれれば問題はない。後は国土交通省がどのようにあ対応するか次第。
[東京 9日 ロイター] - 燃費・排出ガスの抜き取り検査で無効な測定を有効と処理していたマツダ<7261.T>が9日夕、東京都内で会見した。出席した菖蒲田清孝専務執行役員は、事態を「重く受け止めている」とし、ステークホルダーに深くお詫びすると述べた。ただ、意図的な行為ではなく、「不正とは考えていない」とも語った。
本来は無効とすべき測定を有効としていた事案が見つかったのは、2014年11月から18年7月に抜き取り検査を実施した1875台のうち72台で、小型車「アクセラ」など計10車種。ただ、対象車の排出ガスや燃費への影響はなく、リコール(回収・無償修理)も考えていないという。同社では国内で生産する車両すべての燃費・排出ガス検査を本社工場(広島市)で実施している。
菖蒲田専務は、検査で許容されている速度の超過時間を一部超えていたにもかかわらず、データを無効にしなかった案件が一部あったと説明した上で、「意図的ではない」と強調。6カ月間の研修を経て認定を受ける検査員は自負を持って検査作業に取り組んでおり、時間を超えたものがあったことに「ショックを受けている」と話した。
今回の事案はデータ改ざんや組織ぐるみの不正ではなく、品質を確保するプロセス、システムに課題があったとして「不正とは考えていない」とも指摘。経営陣や従業員への処分なども現時点で「考えていない」とした。顧客からの信頼を失わないよう、「今回の事案をしっかり説明し、販売に影響しないよう取り組む」と語った。
(白木真紀)
言い訳のように思えるが、これが現実なのであろう。「検査員の感覚頼み」とは上手い言い訳だ。規則があろうが、マニュアルがあろうが、
実際にチェックするのは検査員。規則やマニュアルを無視して、合格条件を満たしていなくても検査員が合格させる意思があれば合格する。
検査員の能力や経験不足で条件を満足していないケースでも合格する事があるから、ニューマンエラーとして扱えば、故意であっても
多少は誤魔化す事が出来ると思う。ただ、多くの検査ミスが起きれば、個々の検査員の問題であるとの説明は信じてもらえない可能性が高いし、
多くの人達は信用しないであろう。
その極端な例が今回の「検査データ不正」であろう。
大手であれば、ゆとりがあれば不正のリスクは取らないであろうが、コストや技術的な問題で簡単に解決できないケースで他のメーカーが不正を
行っているが、問題として発覚しなければ、自分達も同じ事をしても良いのではないか、例え、問題が発覚しても、自分達だけではないと
言えば、何とかなるのではないかと考えるようになっても不思議ではない。
20年の経験を通して、正直者がばかを見る傾向が高いと思う。不正を行っていても簡単に問題として発覚する事は少ない。他社や他人よりも
何かで優れていなければ、不正を行っている会社や人達には勝てない。時々、問題が大きくなり人生を棒に振る人達や大きな損をする会社は
あるが、確率で言えば、少ないと思う。
不正を行っている人達や会社が成功しているのを見ると何が正しいのかわからなくなる。多くの人達は何を思いながら働き、生きているのだろうか?
新車の品質検査を巡る不正が拡大した。スズキ、マツダ、ヤマハ発動機が9日、出荷前に新車の排ガスや燃費を調べる検査で一部データを不正に処理していたことを公表。いずれも検査員の感覚に頼った曖昧な検査体制が背景にあり、各社の対応の甘さが浮き彫りになった。日産自動車やSUBARU(スバル)など製造業では不正が相次いで発覚し、メーカーの品質管理に改めて厳しい視線が注がれている。
◆目算で全判断
「皆様に多大な迷惑をかけ、心よりおわび申し上げる」。最も不正の件数が多かったスズキの鈴木俊宏社長はこの日の記者会見で頭を下げた。
新車は出荷前に燃費などのデータを確かめるため、一定の台数の車を検査装置に乗せて走行状態を再現する。走行速度などが国の定めた基準を外れた場合、その測定データは無効としなければならない。だが、各社とも検査員が目算で逸脱の有無を判断し正確な測定ができていなかった。国土交通省の指示で改めて装置に残った実測値を確認したところ、基準からの逸脱が判明した。
◆明文化されず
スズキとヤマハは、基準から逸脱した時の対処法など検査の手順が明文化されていなかった。走行時のデータをリアルタイムに把握し試験を中断するシステムもなかった。マツダは、逸脱したデータを無効にするルールを把握していたが、「訓練した検査員の技量に依存していた」(同社)といい、現場判断に頼り切っていた。スズキの鈴木社長も「検査工程を管理職が把握できていなかった」と甘さを認め、「逸脱が起きた場合に自動で中断するシステムを入れるなどして再発防止を図る」と強調。ヤマハも「必要なルール作りが欠落したのが一番の問題だ」(渡部克明副社長)と反省した。
◆「水準から外れた例はなし」
各社の検査は、新車の1%程度を抜き取って品質を調べ、その計測値の平均から、国に届け出た燃費や排ガスの水準に達しているかを裏付けている。各社は今回の不正を受け、無効な数値を除いた上で改めて平均値を計算。届け出た水準から外れた例はないといい、リコール(回収・無償修理)の必要はないと判断した。ヤマハは「問題の数値を除外しなくても排ガスの数値は1000分の1程度しか違わない」と説明した。
◆経営責任に触れず
これまで、スバルや日産でも排ガスや燃費を巡る検査不正が表面化した。両社の場合は、成分や計測値などを改ざんした事例があった。今回の3社はいずれも「意図的な不正はなかった」と主張。経営陣の責任については、各社とも「まずは管理体制をどう直すかを優先して決めたい」(鈴木社長)などと述べるにとどめた。
車の品質検査に詳しい早稲田大の大聖泰弘名誉教授(自動車工学)は「燃費や排ガスの規制が非常に厳しくなっている中、社内に検査の重要性を認識させられなかったことが問題だ。メーカーの負担は重いが、教育や法令順守に対する経営陣の認識が甘かったのではないか」と指摘する。【竹地広憲、柳沢亮、横山三加子】
自動車の完成検査
工場での組み立てを終え、販売店などに出荷する前の新車の安全性を最終確認する工程。ヘッドライトやクラクション、ブレーキ、速度計などの性能のほか、排ガスの濃度などが、国から指定を受けた「型式」としての性能に見合うかどうかを調べる。
本来は国が運輸支局で検査する必要があるが、大量生産される市販車は手間がかかるためメーカーが代行している。
排ガスに関する測定などは特に時間がかかるため、全車両を対象に検査することは現実的に難しい。そのため、国は一定の基準を満たし、検査方法を明確にすることなどを条件に、抜き取り検査を認めている。抜き取る台数や具体的な検査項目は各社で定めている。
スズキとマツダ、ヤマハ発動機は9日、出荷前の新車の排ガスや燃費を調べる抜き取り検査で、不適切な計測があったと発表した。検査の条件に合わず無効とすべきデータを有効と扱っていた。対象は3社で計6480台に上り、スズキは2012年6月以降に検査した新車の約半数で不適切な計測を行っていた。いずれもデータの改ざんはなく、燃費などへの影響はないとしてリコール(回収・無償修理)はしない。
【新車の排ガス検査に関する各社の不適切事案】
抜き取り検査は国の規則で決められた速度や走行時間で行わなければならないが、3社は条件に合っていない場合も検査データを有効と扱っていた。スズキやヤマハは検査員が規則を正しく理解していなかった。マツダは規則を認識していたが、検査条件に合っているかどうか確認作業をしていなかった。
スズキは12年6月~今年7月、自動車1万2819台のうち49・9%に当たる6401台で不適切な検査をしていた。マツダは14年11月~今年7月、自動車1875台のうち3・8%に当たる72台で、ヤマハは16年1月~今年7月、二輪車335台のうち2・1%に当たる7台で同様のケースがあった。
3社は9日、東京都内でそれぞれ記者会見を開いて陳謝した。16年にも燃費データの不正が発覚したスズキの鈴木俊宏社長は「社内のチェック態勢ができていなかった」と謝罪した。
7月までに日産自動車やSUBARU(スバル)で検査不正が発覚。これを受け、国土交通省が他のメーカーに調査を求めていた。【竹地広憲、横山三加子】
今回、新車出荷時の抜き取り検査で不正が見つかったスズキ、マツダ、ヤマハ発動機は「排ガスや燃費への影響はない」として、リコール(回収・無償修理)は行わない方針だ。各社とも抜き取り検査のやり方にミスはあったものの、リコールの条件となる排ガスそのものに問題はなく、カタログの燃費にも誤りはないと判断したためだ。
同じく抜き取り検査で一部データの書き換えなどが発覚した日産自動車とSUBARU(スバル)も、排ガスには問題がなかったためリコールしていない。ただ、両社は新車の完成検査を無資格の従業員にさせていた問題では、安全性を確認するため昨秋リコールを行った。
2016年に発覚した三菱自動車の燃費データ改ざん問題でも、三菱自はユーザーに補償金を支払ったが、排ガスに問題はなかったためリコールしなかった。
抜き取り検査の一部データを書き換えていたもののカタログ燃費に影響はない日産やスバルと異なり、三菱自は軽4車種などのカタログ燃費を良く見せるため、意図的に燃費測定の基礎データを改ざん。実際の燃費はカタログより最大約16%悪かった。だが、燃費は保安基準の対象外のためリコールしなかった。【川口雅浩】
半沢直樹の世界の現実版?
スルガ銀行がシェアハウス投資を巡って不適切な融資を行っていた問題で、外部の弁護士らで作る第三者委員会による調査の概要が、明らかになった。営業部門を統括する元専務執行役員が不適切な融資の拡大を主導していた。審査部は問題を認識していたものの、最終的に黙認していた。
第三者委は月内にも報告書をまとめ、公表する方針だ。金融庁は報告書の内容も踏まえ、業務改善命令などの行政処分を行うことを検討している。不適切な融資の横行を防げなかった経営トップの監督責任も問われそうだ。
関係者によると、元専務執行役員は自らシェアハウス関連の案件を精査し、融資実行の可否を決めていた。審査部は、入居率の低さなど疑問点を何度も指摘していたが、業績拡大を優先する元専務執行役員の意向に逆らえなかったという。取締役会の議論も形骸化していた。
ボクシング連盟・吉森副会長の発言をテレビで見たが、本当に東大卒の弁護士なのかと思った。まあ、弁護士と言っても専門分野で発揮する能力は
違うだろうし、弁護士のイメージとは違うだけで、弁護士の資格を持っているのは間違いない。弁護士である全ての弁護士が全ての分野で有能で
あるはずはないだろう。まあ、有能でロジカルであれば、山根明前会長の下で15年間も上手くやっていないかもしれない。
東大ボクシング部のレベルがどの程度なのか知らないが、ボクシング部の割には現状の審判についてあまり知らない、又は、興味がないような
発言なのが気になった。
吉森照夫副会長の学歴(出身高校・大学)!結婚した嫁(妻)や子供は? 08/08/18(教えて?あんなコト!こんなコト調査団!)
名前:吉森照夫(よしもり てるお)
生年月日:1946年
年齢:72歳(推定)(2018年の現在)
出身地:不明
血液型:不明
職業:日本ボクシング連盟副会長
吉森法律相談事務所
役職:副会長 ・専務理事
アマチュア資格審査委員会委員長
会計理事
助成金流用や不正審判の疑惑がある日本ボクシング連盟の吉森照夫副会長(73)が9日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」(月~金曜・前8時)に生出演した。
過去の暴力団関係者との交際や不正疑惑が問題視されている山根明前会長(78)が8日に辞任を表明したが、山根氏は同連盟の理事、関西ボクシング連盟の会長も務めている。このため8日の会見で報道陣から「どの役職を辞任するか」などの質問が集中した。
これを受け吉森氏は8日に山根氏に電話し辞任は「会長職と日本連盟の理事。理事を辞めるっていうことは、日本連盟の中で強化委員長をやっておられました。その他、それぞれの委員、医事委員会とかスポーツ科学委員会とか、そういうところに関する監督監視は一切辞める」と話し、日本連盟には一切関わらないと語ったという。
一方で関西ボクシング連盟の会長について「それは関西連盟が会長個人が考えることですので、私はタッチしない、ないしは分かりません」と示した。
また、吉森氏は、自身の経歴を東大法学部を卒業し東大ボクシング部出身で同連盟の「専務理事になったのは平成15年です」と明かした。
スポーツは持っている才能、努力、精神力、選手の性格、そしてメンタル的な安定などが複雑に影響し合っていると思う。
選手のメンタル面や性格について本人が望んでいなければ引っ張って成長させなくても良いと思う。ただ、監督は学校から
結果を求められていれば、単純に他の部分で問題があっても才能や現時点でのパフォーマンスで優れていれば良い結果を出すために
使いたいと思う気持ちはあるかもしれない。
選手のために厳しくするのと自分の実績のために厳しくするのは動機の部分では全く違うが、やる事に関しては同じに見えるかもしれない。
厳しくしながらも経験から押したり引いたりするのと単純に厳しくするのは同じに見えるかもしれない。また、生徒がどのように
捉えるかも生徒の視点で考えると違ってくる。
アメリカでもコーチと選手の不適切な問題が暴露されているので結果を出さないと評価されない厳しい世界の問題だと思う。
結果を出すために実績のあるコーチ、監督、又は組織の下で学ぶ。結果を出したい、もっと上に行きたいので問題に目を瞑る選手がいる可能性がある。
人間的には良くても結果を出せないコーチや監督は必要とされない。やはり、結果が大きな影響を与える。
国家レベルで国際大会やオリンピックに勝てる選手を生み出そうとしている国々がある。結果に最優先にしてしまうと他の問題に目を瞑る
可能性がある。
日本大応援リーダー部(競技チアリーディング)の女性監督が女子部員にパワハラをしたと、学内の人権救済機関に認定された。関係者への取材で判明した。部員は精神的に追い詰められて適応障害と診断された。運動部を統括し、アメリカンフットボール部の内田正人前監督が事務局長だった保健体育審議会(保体審)に解決を求めたが対応しなかったという。日大のパワハラ体質とガバナンス(組織統治)の欠如が再び露呈した。【川上珠実、銭場裕司】
【学校の恥、今すぐ脱げ】日大チア監督の女子部員への主な言動
監督は2011年ごろまで同部選手だったOGで15年度に就任した。女子部員らによると2月5日、全部員の前でこの部員を名指しし「大雪の日に事務員に頼んで練習をなくそうとした」と事実でないことで叱責した。
この前後にも、部員が強豪である出身高校のジャージーをはいていたことを見とがめ「学校の恥。今すぐ脱げ」と怒ったほか、けがからの復帰が遅れているのをうそだと疑い大会に出場させようとした。他の部員からも責められて自殺を考えるほど追い詰められ、大学に通えなくなった。
女子部員側は保体審に監督との仲裁を求めた。当初は応じる姿勢を示したものの「監督と直接話してください」などと態度を変えたため、3月に人権救済機関に相談した。関係者によると、具体的内容は公表していないが、調査をして監督の言動がパワハラに当たると認定したという。
5月に起きたアメフット部の問題で日大は対応が批判されたがその間もチアの問題は解決せず、監督は7月に女子部員に謝罪した。毎日新聞の取材に日大企画広報部は「事象の有無を含めてお答えできない」と回答。監督は指導を続けている。
アメフット部の問題では、日大が設置した第三者委員会が7月末、悪質タックルを指示した内田前監督=懲戒解雇処分=の指導を「独裁」「パワハラ」と批判。部活動を監督すべき保体審の事務局長を内田前監督が務めていたことが独裁を許し、ガバナンスが機能しなくなったと指摘した。
競技チアは組み体操のような「スタンツ」や宙返りなどの「タンブリング」といった技で演技を構成し、難易度や正確性などで競う団体の採点競技。日大は02年創部で、過去10年の日本選手権最高順位は4位(大学部門)。
東京医科大学(東京都新宿区)の入試で女子受験生が一律に減点されていた問題で、その措置に「ある程度理解できる」とした医師が6割に上ったことが8日、医師向け人材マッチングサービス大手「エムステージ」(東京都品川区)が約100人の医師に行った緊急調査で分かった。「周りに負担をかけているため仕方ない」という諦めの声が多く寄せられ、同社は「妊娠・育児を経る医師が働き続けることのできない医療現場に課題がある」と分析している。
一律減点に対し、「理解できる」が18・4%、「ある程度理解できる」が46・6%だった。その理由について、「女子の離職率や勤務制限があるのは事実であり、男性や未婚女性への負担が大きくなっているから」(放射線科医)、「妊娠・出産での欠員を埋めるバックアップシステムが不十分であることも事実」(小児科医)などの声が寄せられた。
医師になってから受けた不当な差別については、「外科系の医局は女子というだけであまり熱心に勧誘されることがなく、悔しい思いをした」、「『女のお前には何も教えてやる気にならない』と言われた」などの意見もあった。
同社は「単なる入試での差別として帰結させるのではなく、その状況を生み出している医療現場の過酷な労働環境に社会の目が向けられれば」と指摘している。
不正である事、そしてやってはいけない事の認識がある事が証明できるケースだと思う。
何とか裏口入学が可能になるように巧妙に考えられた事がわかる。
東京医科大が7日公表した調査報告書は、同大が長年行ってきた「裏口入学」の経緯も明らかにした。
報告書によると、同大の合格者の調整は、臼井正彦前理事長(77)が入試委員会のメンバーを務めていた1996年頃に始まった。
当初、調整は合否判定に関わる教授会にも非公開だったが、2008年に同大の「入試疑惑」が週刊誌で報じられ、1次試験の得点などが教授会に開示されることになり、同窓生の子弟の合格が難しくなった。一時は2次試験の小論文で得点操作を試みたが、小論文はあまり点数に差がなく、また、複数で採点することから操作が発覚してしまう可能性もあり、依頼を受けた受験生を思うように合格させられない事態が生じた。
そこで、同大が新たに採用した手法が、1次試験の結果が教授会に開示される前に、事前に関係者リストなどで指定された特定の受験生の得点を、秘密裏に不正加点する得点操作だった。
「2次試験における得点調整はこうだ。まず採点結果に0.8を掛ける。だから仮に100点を取っても、素点は80点だ。1ケタの点数は0点か5点に調整する。その次に属性に応じて自動的に加点。現役~2浪の男子には20点が加点される。3浪男子なら10点、4浪以上の男子なら加点はゼロ。女子は現役でも浪人でも加点はゼロだ。これらはプログラミングされていて、自動的に出てくる。」
このプログラムは誰が作ったのか?外注?それとも内部の人間?
外注であれば、前理事長ら3人の誰かが発注しなければならない。それ以外、このプログラムはどのような目的があるのかと思う職員がいてもおかしくはない。
内部の人間であればプログラムに関与した職員は公平な評価方法でないと気付くはずだ。
捜査でどこまで解明つもりなのか次第で新たな事実が出てくるかもしれない。
裏口入学が発覚した東京医科大学の内部調査委員会が8月7日に調査結果を公表した。東京地検特捜部は現在、文部科学省科学技術・学術政策局前局長の佐野太氏の公判を東京地裁に請求している。容疑は、文科省が東京医大を「私立大学研究ブランディング事業」に指定した見返りに、佐野氏の子息(以下S君)を同大学に合格させるために行われたとされる贈収賄だ。
調査報告書に記された得点テーブル
内部調査報告書はこの経緯を生々しく再現している。東京医大を今年2月に受験したS君の1次試験の成績は400満点中226点。全受験生中で282位だった。451位まで1次試験を通過していることから、不正な加点を行わなくてもS君は”足切り”を食らうことはなかった。
だが、臼井正彦前理事長らは「あと10点加点すれば2次試験が普通の出来である限り、少なくとも補欠で繰り上げ合格ができる」として、S君に10点を加点した。その結果、1次試験の成績は236点にカサ上げされ、順位も169位に繰り上がった。
S君の2次試験(小論文)の成績は100点満点中55点だった。そしてS君は以下に示す得点調整で「1浪男子」という属性により、2次試験の結果に20点が加点された。この結果、S君の成績は1次試験との合計で301点で87位。「少なくとも繰り上げ合格する可能性が高い」として、2次試験でのさらなる不正加点は行われなかった。適性検査や面接による不合格者などがいたことから、S君は最終的に74位となり75人の正規合格の1人になった。
■「0.8を掛けて20点を足す」
2次試験における得点調整はこうだ。まず採点結果に0.8を掛ける。だから仮に100点を取っても、素点は80点だ。1ケタの点数は0点か5点に調整する。その次に属性に応じて自動的に加点。現役~2浪の男子には20点が加点される。3浪男子なら10点、4浪以上の男子なら加点はゼロ。女子は現役でも浪人でも加点はゼロだ。これらはプログラミングされていて、自動的に出てくる。
S君の場合、55点に0.8を掛けると44点。1ケタの点数の調整で45点になる。それに1浪男子の20点の加点で65点になった。S君の成績を式に表すと以下のようになる。
1次試験226点+不正な加点10点+2次試験の結果×0.8+属性加点20点=301点
S君の成績は1次試験での不正な加点10点がなければ、合計点は291点で151位。2次試験での属性加点がなくても281点で173位なので、「繰り上げ合格は226位までだったから、不正加点や属性加点がなくても繰り上げ合格となっていたと思われる」(報告書)。ただし、これはあくまでも結果論である。S君よりも成績が良かった受験生が東京医大を蹴っていなければ、繰り上げ合格にはならない可能性があった。
■前理事長の動機はやはり「カネ」
S君は現役時代にも東京医大を受験している。そのときの成績は1次試験が400点満点中200点で全体の1051番。当時の2次試験の満点は60点であり、合格ラインに届かせるには相当のゲタを履かせなければならないため、臼井前理事長らは断念したのだという。その翌年度に当たる2018年度入試で、2次試験の満点は100点に改められたばかりだった。
さらにS君と同期入学の東京医大生のうち、少なくとも5人が不正加点を受けていた可能性があるという。S君と同じ10点加点が最低で、ほかは15点、32点、48点、49点。つまり、S君よりも多く加点されて入学した学生がいる。うち32点の不正加点を受けた学生は、その学生よりも高い点数の学生がいたのにもかかわらず、繰り上げ合格となった。
その前年度には少なくとも13人が不正加点を受けている。8点が最低で45点が最高。13人のうち7人が30点台の不正加点をしてもらっていた。前年度は2次試験の際にも、属性加点に加えて、さらに不正加点を受けた学生もいたという。
東京医大では、不正入試は悪しき慣行となっていたようだ。
たとえば臼井前理事長が入試委員だった1996年には、合否判定をする教授会に受験生の得点を開示せず、教授会の前に開催される入試委員会で、入試委員同士が話し合って合格者の調整を行っていた。1次試験の得点がようやく教授会に開示されるようになったのは、2009年から。それまでは、理事長や同窓会長が入試委員に接触することも禁止されていなかった。
報告書によれば、臼井前理事長らが不正を犯した動機はカネと見て間違いない。ブランディング事業指定も計4089万円の助成金の受領が狙いだった。不正合格によって大学は寄付金を得たほか、臼井前理事長は個人的にも複数回にわたり、受験生の親などから謝礼金を受け取っていた。
報告書を受けて会見を開いた東京医大の行岡哲男常務理事や宮澤啓介学長職務代理は、「一律に(0.8を)掛けるとか、そういうことにわれわれは関与していない。承知しておらない。女子や多浪生を差別していることも知らなかった。報告書で知って驚愕した。東京医大は女子学生が多いことで有名な大学なのに」と驚くとともに関与を全否定。あくまでも臼井前理事長や鈴木衛前学長のしたことであるという立場を崩さなかった。
本当に何も知らなかったのだろうか。報告書には、看護学科学務課課長の証言として「2017年の入試委員会で『属性による得点調整に関する資料』を提出しているので当時の入試委員会のメンバーは皆、この調整について知っているはずである」と記載してある。
入試委員だった宮澤学長代理は、「私は見たことがない。委員会で配られたとしても、綴じてある中の1枚ですぐ回収されたのではないか。そうでなければその場で十分議論されていたはずだ。今後組織される第三者委員会で調査をきちっとしていただいて、身の潔白を証明していただきたい」と気色ばんだ。
事件発覚後、S君は大学に来ていないが、夏期休暇前の試験を受けないと自動的に留年になるために、他の学生とは別の部屋で、1人で試験を受けたという。調査報告書はS君に対して「自主退学を勧めるという選択肢もありうる」と指摘したが、宮澤学長代理は「大学の不正で入学し、大学が入学許可証を発行した以上、責任は大学にある。自主退学を勧めるつもりはない」と断言した。ただし、贈収賄事件なので、贈収賄物は返還しなくてはならない。本件ではS君の合格が贈収賄物に当たるが、「それは大学の判断することではない」(宮澤学長代理)。
■合否を判断する資料は押収されたまま
報われないのは、本来は正規合格や補欠合格となるところを、あおりを受けて不合格となった女子や多浪生である。
大学側は「過去の女子受験生や多浪生について誠心誠意対応する。今年度中をメドに精査し追加合格としたい」と言う。一方で調査委員会は、合否を判定する資料が東京地検に押収されたままで、公判中の1~2年は戻ってこない可能性があるとする。宮澤学長代理は、「押収物の一部返還を求める一方で、学内に合否の判断できる資料が残っていないか探す」と言うが、現実的には厳しい状況と言わざるを得ない。
今回の内部調査を受任したのは、東京医大の顧問弁護士である鈴木翼氏が所属する田辺総合法律事務所だった。鈴木弁護士が調査委員会に加わらない、調査報告書に加筆しないことを大学側が約束する、逆に田辺総合が公正中立に調査することを大学側に約束するなどの条件を付けることで、「第三者委員会的な委員会になったので、第三者委員会の設置は不要だろう」と調査委員会の中井憲治弁護士(元最高検検事)は胸を張った。
だが、東京医大は調査書を文科省に届け出た直後に、第三者委員会の設置を決定した。今後の真相解明は、東京地裁と第三者委員会に委ねられることになる。
東京医大の調査結果を受けて、林芳正文科大臣は全国の国公私立大の医学部の入試で不正がないか緊急調査する考えを示した。第2、第3の東京医大が現われれば、医大入試への不信はさらに高まることになる。
山田 雄一郎 :東洋経済 記者
「前理事長ら3人のみ把握」と言う事は、データベース作成や受験生の情報の入力など3人で行ったのか?
凄くできる3人だったのか?
入試を担当する学務課長が実際、全ての作業を行ったのか?それとも臼井正彦前理事長(77)と鈴木衛(まもる)前学長(69)も
作業を手伝ったのか?
信じることが出来るストーリーではないように思える。もっと作業に関わった人達がいると思う。
東京医科大(東京)が医学部医学科の一般入試で、女子と3浪以上の男子受験者の合格者数を抑制していた問題で、得点操作の方法を記したマニュアルを作成していたことが、関係者の話でわかった。マニュアルは入試を担当する学務課長の間で引き継がれ、臼井正彦前理事長(77)と鈴木衛(まもる)前学長(69)の3人だけが把握していた。
東京地検特捜部も、文部科学省の私大支援事業を巡る汚職事件を捜査する過程で、このマニュアルを入手している。
関係者によると、同大は今年の一般入試で、2次試験の小論文(100点満点)の得点に「0・8」を掛けていったん全員を減点した後、現役と1、2浪の男子に20点、3浪の男子には10点をそれぞれ加点。女子と4浪以上の男子は加点せずに減点したままにする操作を行い、合格者数を抑制していた。
スポーツ界の問題と言うよりも日本の古い問題と考える方が良いと思う。
スポーツ界では閉鎖された社会なので日本の古い体質が維持される傾向が高いと言う事であろう。
特に外国人や外部との接点が少ないスポーツが強く古い体質を維持すると思う。外国人が入れば、問題として排除されない限り、
外国人により日本の古い体質が指摘されるし、時間がかかっても外国人が理解できない事は改善されて行くと思う。
オリンピックで盛り上がっているが、スポーツ庁が問題を放置している証拠だと思う。
またしても、スポーツ界を揺るがす不祥事が表面化した。日本ボクシング連盟による助成金流用や審判の不正判定疑惑。内部告発は、背景に連盟の山根明会長の強権的組織運営があったと強調している。スポーツ界を巡っては、日本大学アメフト部の前監督らが悪質な反則を指示していた問題、日本レスリング協会前強化本部長によるパワーハラスメント、女子柔道のロンドン五輪前監督らによる暴力・暴言などが相次いで発覚している。アスリートと指導者の間に、何が起きているのか。(事件ジャーナリスト 戸田一法)
● トップ選手へのリスペクト欠如
一連の不祥事の発覚で共通して見られる問題は何か――。
それは、問題を起こした指導者がいずれも圧倒的に強い立場で組織や選手を支配し、逆らえない環境を構築。不祥事が発覚してもその地位を離れようとしない点。さらに、世界トップ選手らに対するリスペクトが著しく欠如している点だ。
今回のボクシングでは山根会長が、ロンドン五輪金メダリストで世界ボクシング協会(WBA)世界チャンピオンでもある村田諒太選手がフェイスブックに「そろそろ潔くやめましょう。悪しき古き人間達、もうそういう時代じゃありません」と投稿したことを受け、「生意気だ」と発言。レスリングの栄和人前強化本部長は、五輪4連覇で国民栄誉賞も受賞した伊調馨選手に「よく俺の前でレスリングができるな」などと恫喝。女子柔道では監督やコーチがロンドン五輪代表らを殴ったり蹴ったりした上「死ね」「ブス」「ブタ」などと暴言を吐いていた。
いずれの指導者も、ある程度の実績を残した元アスリートかもしれないが、一般の感覚からしたら「選手としてのあんたなんか知らないよ。何様だよ」ではないだろうか。
ではなぜ、スポーツの世界でこうした“勘違い”した権力者が生まれてしまうのか。全国紙の運動部デスクに話を聞いた。
「スポーツの世界も政治や役所、一般企業と一緒。引退した後は暇だから、それぞれのスポーツ団体で熾烈な派閥争いや出世競争、権力闘争に明け暮れる。そして、政治や役所、一般企業よりもタチが悪いのは、外部の目にさらされないこと。一度、その最高権力の地位に就いてしまうと、周りには誰も意見できる者がいない“裸の王様”になってしまう。さらに悪いことには、スポーツの世界は戦前の軍隊のように、上位の指示には絶対服従の雰囲気がある。そこで『自分は偉い。何をやってもいい』と勘違いしてしまう」
こうした上層部や指導者らは、なぜ、不祥事が発覚した後でも言い訳がましく事実関係を否定し、その地位にしがみつこうとするのか。
「その地位が最高に心地いいから。王様だから。一度君臨した権力の座は明け渡したくない。そして、その地位にしがみつこうとし、潔く去れないから、あんなみじめったらしい引導の渡し方をされてしまう」のだという。
もう1つの疑問。なぜ今、こうも相次いで最高権力者たちの不祥事が明るみに出ているのか。告発が相次ぐのか。
「村田選手が投稿した通り『そういう時代』じゃないということ。昭和のころはそうした空気を是認する風潮があったが、今では通用するわけがない。村田選手の投稿通り『悪しき古き人間達』は去る時期に来たということだ」
さらにこう続ける。
「推測だが、反則指示問題で、日大アメフト部員の記者会見が影響を与えたのではないか。『子どもがあんな立派な態度を取っている。俺たち大人がこれでいいのか』と。もう1つ、東京五輪の影響もあるのではないか。やはり、膿(うみ)は出しておきたい。一方で、スポーツ・平和の祭典と言いながら、五輪はその実、スポーツを利用したただの商業活動に成り下がってしまった。大きなカネが動く中で『何もしないでふんぞり返っているだけのアイツの懐に、ジャブジャブとカネが流れ込んでいくのは許せない』という義憤もあったのだろう」
今回、山根会長の不正を告発した「日本ボクシングを再興する会」は選手や関係者333人が名を連ねた。同会代表で、6月まで連盟理事だった鶴木良夫氏は新聞やテレビの取材に「誰も何も意見できない状況が長く続いていた。みんな我慢の限界だった」と話している。
● 強大な権限で勝敗を左右、進路、人生も
今回のボクシングに関しては、告発で、山根会長の出身母体である奈良の選手に有利になるよう、審判が不正な判定をしていたとの「奈良判定」疑惑が取り沙汰されている。山根会長は「絶対にない」と否定しているが、2016年岩手国体では、岩手県代表の選手に2度のダウンを奪われた奈良県代表の選手が判定勝ち。連盟は「プロと異なり、ダウンはクリーンヒットの1つ。ヒットの数でポイントが決まる」と判定は正当だったと強調しているが、前述の運動部デスクは「何を言っているのやら。ワンサイドゲームだよ」と一笑に付す。
実は、アマチュアはプロ以上に、勝敗で人生が大きく変わることが多い。プロはその試合に敗れても、次の試合で勝てばいいという「取り返し」が利く。
アマチュアは一発勝負のトーナメントがほとんどで、負ければその時点で競技人生が終わりになることもある。特に学生の場合、高校生であれば大学推薦の基準は戦績だし、大学でも競技した選手なら「どこまで勝ち上がったか」は一生ついて回る。
「金にならない“たかがアマチュア”」ではない。アマチュアだからこそ「1勝」は大きいのだ。それを権力者の横暴で左右されたら、選手としてはたまったものではない。
勝ち負け以前に、出場できるかどうかが、一連の発覚した不祥事の根底にもある。ボクシングでは当然、東京五輪に代表選手として出場できるかどうかは連盟の意向で決まってしまうから、最高権力者に逆らえるはずもない。
女子レスリングで伊調選手が実力通りの成績を収めていれば、パワハラがあろうと代表を外されることはないだろうが、有形無形の圧力で練習環境を潰されていた。
女子柔道も同様、ロンドン五輪に代表として出場できるかどうかは監督の発言が強大だった。アメフト部の問題でも選手はフェニックスというチームでプレーすることに憧れたからこそ日大を選んだのであり、「試合に出さない」と恫喝されたら、もはや従うしか術はない。
一方、プロの試合は基本的には「外部の目」があり、おかしなジャッジはできない。試合への出場も個人競技ではエントリーするかどうかは自身の判断だし、団体競技もある程度の監督・コーチの好き嫌いは反映されるだろうが、完全に実力の世界だから、そこまで露骨ではない。
アマチュアの場合、所属団体に強権者がいれば、選手生命や進路、それどころか人生さえも全て握られていると言っても過言ではないのだ。
● 「問題」ではなく「事件」
ボクシングの助成金不正流用「問題」、アメフトの悪質反則「問題」、レスリングのパワハラ「問題」、柔道の暴力・暴言「問題」……。
いずれも「問題」と認識されているが、実はレスリングを除くといずれも立派な犯罪なのだ。
ボクシングでは、助成金流用や不正判定疑惑、過剰な接待要求疑惑などがクローズアップされている。不正判定や接待要求は周囲が勝手に忖度しただけで犯罪ではないが、助成金流用は日本スポーツ振興センター(JSC)が2015年にリオデジャネイロ五輪代表選手に交付した助成金240万円を、3等分してほかの2選手にも分配していた。山根会長も事実関係を認めているが、助成金は国費が投入されており、これは「補助金適正化法」違反に該当する。
アメフトの悪質反則は日大の内田正人前監督と井上奨前コーチが選手に、関西学院大の選手にけがをさせるよう指示したとされる。監督とコーチは事実関係を否定しているが、日大の選手が記者会見で2人の指示と明言。関東学生連盟と日大第三者委員会も事実と認定した。負傷した関学の選手側は傷害容疑で被害届を提出し、既に受理され警察が捜査している。実行行為者である日大選手は反省している点と被害者の選手側が処罰を望んでいないことから、起訴猶予になるのではないかとみられる。一方で、教唆した監督とコーチは社会的影響の大きさから略式起訴されるのではないかと見方がある。
女子柔道の暴力・暴言問題では、五輪代表を含む15人が2012年末、園田隆二前代表監督や徳野和彦前コーチ(いずれも発覚後、辞任)からの被害を日本オリンピック委員会(JOC)に告発。負傷していなくとも、暴力を振るっていればこれも立派に暴行罪が成立する。ほかにも、この問題が浮上した直後には全日本柔道連盟(全柔連)がJSCからの助成金を不正受給していたことが発覚。第三者委員会の調査で受給資格のない27人が総額3620万円を不正に受給していたことが明らかになったが、これはもう補助金適正化法違反ではなく詐欺罪が成立するレベルの悪質さで、全柔連の上村春樹会長の辞任に発展した。
2020年東京五輪まで、あと2年。村田選手が言うように旧態依然とした「悪しき古き人間達」には去ってもらい、アスリートが競技に専念できる環境になってほしいと切に願う。
戸田一法
臼井正彦前理事長に対する処分はどうなっているのか?辞任したからもう終わり?
東京医科大(東京)が医学部医学科の一般入試で、女子と3浪以上の男子受験者の合格者数を抑制していた問題で、臼井正彦前理事長(77)が担当課長に女子や浪人生の得点を減点する操作を指示した上で、「誰にも言うな」と口止めしていたことが、関係者の話でわかった。大学を運営する学校法人のトップ自らが、秘密裏に不公正な入試を進めていた構図が浮かび上がった。
同大は、一般入試をマークシート方式の1次試験(400点満点)と、小論文(100点満点)と面接による2次試験の2段階で実施。関係者によると、今年の小論文では、すべての受験者の得点に「0・8」を掛けて減点した後、現役と1、2浪の男子には20点を加点。3浪の男子にも10点を加点する一方、女子と4浪以上の男子については減点したままにする操作を行っていた。
3浪以上の男子受験生は留年する確率が高く、医師国家試験に一発合格する確率が低いので、3浪以上の受験生は自動的に減点すると 事前に説明すれば良かった。事前に説明されていれば受験しない生徒もいたであろう。不利な条件でも東京医科大に行きたいと思う人は 自己責任で受験すれば良い。
女子受験生の合格者数を抑制していた東京医科大(東京)医学部医学科の一般入試で、3浪以上の男子受験生の合格者数も恣意しい的に抑えられていたことが、同大の内部調査で新たに判明した。背景には、浪人生の医師国家試験の合格率が低いことから、優秀な現役生を増やして合格率を上げ、大学のブランド力を高める思惑があったとされる。
「受験に失敗して何度も浪人を重ねた生徒は、大学に入った後も成績が伸び悩む傾向がある」。同大関係者はそう明かす。
関係者によると、同大は、2011年度までの数年間に入学した学生の入学後の状況を調査。その結果、現役で合格した学生の94・6%が留年せずに卒業し、その全員が医師国家試験に一発合格していた。これに対し、留年せずに卒業した浪人生は81・8%にとどまり、そのうち数%は医師国家試験に一発合格しなかった。
日本は公平な世界と思われていたが、思ったよりも現実は違うかもしれない可能性を考えさせるケースだと思う。
医師はある一定程度の能力があれば、人間性、患者や病気に取り組む姿勢、自己犠牲も顧みない姿勢があれば、現場で伸びると思うし、
外科医など特定の分野を除けば、優秀でなければならないとは思わない。
試験は客観的で公平な方法であるが、医師として向いている人間なのか、倫理や人間的に問題がないかについては全く関係ない。
差別と言うか、公平な評価以外で合格を判断するのであれば、医師として立派になりそうな人間にチャンスを与えるべきではないのか?
医師や医大生の不祥事が注目を受けた。示談と言う合法的な選択があるが、能力があっても問題のある医師や医大生は排除する機能があっても
良いと思う。
女性医師に向かない分野があるのは事実であると思う。そうであれば試験の時に漠然とした医学部でなく、変更は可能であっても、詳細な
専門別に合格点を変えれば良いと思う。透明性を失うが、公平である建前で、不公平な合否判定よりはましだと思う。
「試験は公正に行われていると信じていた。浪人生が差別されているのなら、不公平で残念だ」。医学部進学を目指し、都内の予備校に通う千代田区の男性(20)は、今回新たに発覚した東京医科大による得点操作についてそう嘆く。今年2浪目で東京医科大の受験も検討しているが、「試験が不公平なら考えてしまう」と話した。
今年3浪目で国立大医学部を目指す江戸川区の男性(21)は「一部の私立大医学部が女子と浪人生に厳しいことは、予備校生や講師の間では半ば常識のように語られている。もし差別があっても驚きはなく、その中で戦っていくしかない」と冷静に受け止めた。
一方、大手予備校のベテラン講師は「小論文も学力試験と同様に客観的に評価されるべきで、点数が裏で操作されているとすれば深刻な問題だ」と指摘。「女子や浪人回数の多い受験生に不利なことを告げずに受験させ、受験料を徴収していたのであれば、到底納得できない。このような裏のルールが存在すれば、高校や予備校の受験指導も成り立たなくなる」と憤った。
犠牲者の数を考えると罰金30万円は軽すぎるけど法や規則がそうなっているのであれば仕方がない。
長野県軽井沢町で2016年1月、大学生ら15人が死亡したバス事故をめぐり、立川区検は3日、運転手に違法な残業をさせたとして、労働基準法違反罪でバス運行会社「イーエスピー」(東京都羽村市)と同社の運行管理者だった元社員(50)を略式起訴した。
立川簡裁は同日、同社と元社員にそれぞれ罰金30万円の略式命令を出した。
起訴状によると、同社は事故直前の15年10~12月、必要な労使協定を結ばずに運転手8人に対し、183回にわたり法定の1日8時間を超えて計約230時間の違法な残業をさせたとされる。事故で死亡した運転手は8人に含まれていない。
認識がなければ罪が軽くなると弁護士に言われたのか?
「これについて、入試業務に携わっていた東京医大元幹部が取材に応じ、『どこの医大でもやっている。不正という認識はなかった』と話しました。」
文科省はこの発言について裏を取る必要があると思う。「どこの医大でも」と言うのであるなら電話でも良いからどこの大学なのか聞けば良い。
東京医科大学が入学試験で女子受験生の得点を一律に減点していた問題で、大学で入試業務に携わっていた元幹部が取材に対し、「不正という認識はなかった」と話しました。
この問題は、東京医大が今年2月の入試で女子受験生の得点を一律に減点し、女子の合格者を3割程度に抑えていたものです。これについて、入試業務に携わっていた東京医大元幹部が取材に応じ、「どこの医大でもやっている。不正という認識はなかった」と話しました。その上で、「体力的にきつく、女性は外科医にならないし、へき地医療に行きたがらない。入試を普通にやると女性が多くなってしまう。単なる性差別の問題ではなく、日本の医学の将来に関わる問題だ」と述べました。また、閣僚からは批判が相次ぎました。
「一般的に女子を不当に差別するような入学者選抜が行われるようなことは、断じて認められないと考えている」(林 芳正 文科相)
「極めて深刻に受け止めている。いまの時代はそういうことではなくて、女性の医師が継続して働きやすい環境を整備することが重要」(野田聖子 総務相<女性活躍担当>)
一方、東京医大は「内部調査を行っているので、適宜公表します」とコメントしています。(03日11:57)
スポーツ庁は今回の件で介入するのか?
一時、「アスリート・ファースト」とか頻繁に使われていたが、これって、「アスリート・ファースト」がいかに言葉だけが独り歩きしている
証拠だと思える。
スポーツ庁は問題解決に介入できないのなら、スポーツ庁は廃止で良い。
日本ボクシング連盟の助成金不正流用問題にからみ、平成28年に開かれた「希望郷いわて国体」のボクシング競技で判定不正があったとの疑惑が出ていることについて、達増拓也知事は2日の定例会見で「連盟内部からの告発という形で指摘され、それに対するやりとりの中で事実関係が明らかになっていくことを期待する」と語った。
問題の試合は同国体の成年男子バンタム級1回戦。岩手県の選手が奈良県の選手と対戦、2度ダウンを奪いながら、1-2の判定で敗れた。試合の様子はテレビで放映されており、達増知事は「目にしている」と明かした上で、「競技団体には社会的責任がある。民主的な運営がなされなければならない」と述べた。
その上で、「県民も含めて、対外的に信頼が回復されるように、(日本ボクシング連盟は)努めてほしい」と語った。
優秀な学生のやる気を削ぐかもしれないが、医師なるメリットやデメリット、結婚後に医師を続ける時の問題など医師を目指して受験する前に
説明するべきだと思う。中には医師になりたいと思ったが、メリット及びデメリットを考えて、他の人生設計を目指す可能性はあると思う。
病院グループから支援を受けている政治家や業界は女性医師が業界の問題を公で話す事を望んでいなければ、そのような事は実現しないかもしれない。
個人的な意見だが、日本ではあまり仕事の説明を子供達にしない。説明があったとしても良い部分だけを選んで話していると思う。
業界の問題(デメリット)が公になるのを嫌っている、又は、必要以上に業界以外の人達が知る事に消極的だと思う。業界の人間だと
業界を去る決意がなければ、問題を公にする可能性は少ない。たぶん、今、注目を集めている日大の悪質タックルやアマチュアのボクシングの
問題と同じである。業界内では多くの人達が知っていたり、問題は改善されるべきだと思っていても、声を上げれば抹殺されるリスクを
取る事が出来ない人達が多いと言う事である。
医療グループからの支援や献金があるから政治家も簡単には動かないであろう。だからこの問題は、徐々には良くなっても簡単には改善されないと
思う。
ただ、今回の件で思った事は、能力的には女性医師の方が優秀な確率が高いと言う事。医師になってからの人事や処遇で良い医師になれるか
疑問であるが、能力的には優秀である事はかわらないと思う。
「妊娠、出産は当然の権利」「性別が理由で減点なんてひどすぎる」
東京医科大が一般入試で、女子受験者の得点を意図的に一律で減点していたとみられることが明らかになった。結婚や出産で医師を辞める例が多い女性の合格者数を抑えて医師不足を防ぐ目的があったとみられ、医師を目指す道内の受験生や女性医師らからは「妊娠、出産は当然の権利なのに」「性別を理由にした差別は許されない」と憤りの声が上がった。
「努力しているのに、性別が理由で減点されたならひどすぎる」。医師志望の札幌市東区、札幌北高3年井沢莉子さん(17)は怒りを込めた。予備校に通い、1日約10時間は受験勉強に励んでいる。「同級生にも医師志望の女子は多い。男女で差別されるのは許せない」と話す。
浪人しながら医師を目指す札幌市手稲区の西山綾音さん(19)は「妊娠や出産は当たり前の権利。こんな時代でも男女差別があるなんてショック」。私立大医学部を目指す同市中央区の古畑花さん(21)は「女性だからこそできる医療もある。性別で差別されるのは理不尽。『女性は結婚して仕事を辞める』とみられる風潮はまだある」と憤る。
道の16年の調査によると、道内の女性医師の割合は15・2%。年々増加しているものの、都道府県別で全国最低水準だ。女性医師の約6割が20~40代前半に集中する。定年がないことを考えると、出産や育児で離職を余儀なくされ、職場復帰できていない例が多いとみられる。
中山祐次郎
東京医科大学が裏口入学をしていたという疑惑に加え、今度は女子受験者の点数が一律に減点されていたというニュースが報道された。
東京医大、女子受験生を一律減点…合格者数抑制(YOMIURI ONLINE 2018.8.2.)
これは断じて認められない男女差別である。特に「教育」という社会の公共財を提供する大学が、たとえ私立大学とはいえこのような男女差別をしていることはあってはならない。早急に問題を解明する必要がある。
しかしなぜこのような問題が起きたのか。医師の立場から、原因として三点を指摘する。
1, 大学病院経営と繋がる医学部の特殊性
2, 病院現場の劣悪な労働環境という特殊性
3, 女性医師キャリアへの不十分な支援
1, 医学部の特殊性
大学にはいろいろな学部があるが、医学部医学科はかなり特殊な学部・学科である。なぜなら、医学部医学科は医師という職業の養成学校という側面を強く持つためである。卒業生の9割は臨床医(病院で白衣を着て患者さんの治療を行う医師)になる。そのため、病院現場での実習は一年半~長い大学では二年にも及ぶ。
実習は非常に医師に近いものだ。大学四年生で試験に合格した医学生は「スチューデントドクター」という資格を得て、白衣を着て実際に患者さんの診察・治療に参加し、カルテを書くのである。
そして多くの医師は、卒業後臨床研修を経て、大学医局に入局する。入局とはすなわち、大学病院の一員になるとほぼイコールである。若手のうちは関連病院に出て働くこともあるが、基本的には大学病院に紐づいている。
つまりおおざっぱに言えば、医学部医学科の学生は、将来の大学病院の構成メンバーを嘱望されているのである。
大学病院(あるいは大学法人)はそのアピアランスを増やし、経営を安定させるため、一人でも多くのメンバーが欲しい。
ここで、女子学生の問題が出てくるのだ。女子学生は産休・育休を取り、将来的に大学病院のメンバーとして長年定着しないことが多い。それゆえ、今回のような問題が出てきたのである。
教育と大学(病院)経営がどうしても切り離せないのが、東京医大のような医学部単科大学には特に色濃いのだ。創立102年の伝統があり、愛校心教育をしっかり行なっている東京医大では、特に医大存続と繁栄への思いが強いかもしれない。
2, 病院現場の劣悪な労働環境
2点目として、病院現場の劣悪な労働環境という特殊性を挙げたい。
病院では、科によっては男性・女性医師に関わらず産休・育休を取得することが容易ではない。これが意味するのは、制度としてはあるが、現実的に産休・育休を取得されると現場が回らない、である。
そして批判を覚悟で言えば、女性医師の取った休みの分の仕事は、容赦なく男性医師に乗せられる。例えば外科医10人チームの病院で月に3回当直をしていた外科医は、一人抜けると月に4, 5回は当直をしなければならなくなる。ここで重要な点は、病院ではこのような場合、医師を補充して業務負担を増えないようにする対応はほとんどないという点だ。非常勤医師の補充でもあればこういった問題は起きにくいが、しかし病院経営の立場からはそんな予算がない。医師確保にはかなりのコストがかかる。
病院の収支を決めているのは、大雑把に言えば国だ。規制産業の一部である病院経営は、強く行政に左右される。大儲けがない代わりに、大損もない。その代わり、点数(=診療報酬)という名の、国が決めた政策にきちんと従わなければならない。事実、厚生労働省が「こういう政策をしよう」とした場合、高い診療報酬で誘導することはしょっちゅうある(ジェネリック医薬品、在宅医療など)。
だから、この問題の奥の奥には、女性医師の抜けた分をカバーしない診療報酬体系にある可能性がある。
病院経営の視点からは、現状では、日本で労働法的に適法に病院を経営することは難しい。そして女性医師の増加はこれに拍車をかけるだろう。これを解決するには医師数を増やすしかないが、医師養成には費用がかかる。そしてそのお金は医療費として国民が負担することになる。
その上、医師の業務の性質上「今日からパートでこの人が手伝います」がしにくいのだ。病院には独特な文化があり、独自のルールを持っている。間違えると医療事故の危険がある。だから、同じ医師とはいえ「その病院に」慣れた医師でないと、なかなか部分的に手伝ってもらうことが難しい側面もある。
3, 女性医師キャリアへの不十分な支援
3点目として、女性医師キャリアへの不十分な支援が挙げられる。
ここで女性医師の全体像を見てみよう。
厚生労働省によると、全医師数に占める女性医師の割合は増加傾向にあり、19.7%(平成24年時点)を占める。また、世界でみると日本の女性医師数が少ないことがわかる。
一位のエストニアに続き上位にはヨーロッパ各国が並び、日本は最下位だ。
これほど少ないのは、医学界の古い男性優先の体質だけではなく、女性医師の働く環境が整っていないことが原因だろう。
今でも筆者は、女性の医学生や若手医師に「将来専門にする科を決めるにあたり、私は結婚をしたいのですが女性だとどこがオススメですか」などという質問をよく受ける。いかに産休・育休を含む女性医師のキャリアへの理解と体制がないことがわかる実例だ。
実際のところ、女性医師は出産・育児でキャリアを分断され、その後元のキャリアに戻れないことが多い。私の知人の女性外科医師の苦悩については、過去記事(「子育てもオペもしたい」ある女性外科医の苦悩)に書いた通りだ。業界全体に女性医師を歓迎しない土壌があることは否めない。
このような、女性医師が働きにくい環境が、本件の遠因になっていると考える。
他の医大でも、面接試験の点数などで女子が合格しづらいような調整をしている可能性は十分にある。
今後、女性医師は増えていくことが予想されている。女性医師がいかにキャリアを閉ざさず一生医師として働ける環境を作るかが、これからの課題である。
3点見てきたように、この問題は東京医大だけの問題ではなく、女性医師だけの問題でもない。日本の医療全体に関わる問題が、一つの形として表出してきたのが本件なのだ。
(引用・参考文献)
厚生労働省ホームページ
「性的関係を結ばないと指導が受けられない」「育休を取ったら解雇された」 2018/02/16 (BuzzFeed News)
岩永直子
性暴力の被害に遭った人が声をあげ、性暴力を許さないという意志を社会に示す、MeTooというムーブメント。日本でもジャーナリストの伊藤詩織さんがレイプ被害を実名で告発したのをきっかけに、Twitterのハッシュタグで「#metoo(私も)」と被害を告白する人が増えている。
この動きに対し、30代前半の女性医師、ミカさん(仮名)が、「私も声をあげたい」とBuzzFeed Japan Medicalに連絡をくれた。
「医療現場でもセクシュアルハラスメントがあり、これ以上、見過ごしていたくないのです」
最も難しい国家資格の一つで、実力がものを言うように見える医師の世界でも、理不尽な被害に苦しめられている人がいる。この女性医師と、複数の医師に被害の実態を伺った。
手術室でセクハラ発言、プライベートでも誘われる
数年前まで外科医として働き、今は大学院で研究しているミカさんは、トップクラスの女子校の出身だ。関東の医大に進学し、公立病院の外科で研修医としてスタートを切った。
指導医は40代の男性医師だった。手術中でも休憩中でも、性的な発言が飛び出すのは日常茶飯事だった。
「ちょっと化粧をしたり、夕方に歯を磨いていたりすると、『これから婚活か?』と言われ、遅くまで仕事を頑張っていると、『仕事と結婚するのか?』『お前、夜の生活はどうなってるんだ』とからかわれる。自慢話のつもりか、『俺の若い頃はやった女の数だけバッジをつけていたぞ』と言われました」
「私もその時は『いい人いたら紹介してくださ〜い』『先生すごいですね』と笑って受け流していました。物分かり良く話を聞いてあげる女の子を演じることで、目をかけて指導してもらいたかった。結果的にセクハラがエスカレートしてしまいました」
別の既婚者の指導医には、プライベートでも頻繁に誘われるようになった。
「当時は恋愛感情だと思い込み、『気に入られて嬉しい』とも思っていたのですが、今思うとセクハラでした。外科の世界では、指導医に難しい症例を回してもらえるか、教科書では身につかない実技をやらせてもらえるかが勝負です。教えてもらいたかったし、チャンスを与えてほしかった。そういう気持ちにつけ込んで相手も誘ってきたのだと思います」
その関係は、指導医が女性医師が担当している患者にも手を出していることが発覚して終わった。後に、その指導医は院内の様々な医療職と性的関係を持っているという噂も聞いた。
次に勤めた総合病院の男性外科医も、手術の腕は抜群で尊敬を集めていたが、セクハラ発言がひどかった。
「手術室で患者さんに麻酔をかけた後に、『胸が小さいな』『胸が大きいな』『デブだな』と、医療上の必要はないのに患者の身体的な特徴を言う。麻酔をかけた後に男性患者の陰茎が勃起したのを私に見せて、『どう?こういうの?』と聞かれたこともあります。『こんなこと、患者さんが寝ている間に言うんですね』と陰で研修医から呆れたように言われ、『そうだね。ごめんね』と私がなぜか謝っていました」
独身のミカさんが男性医師に「いつか留学したい」と夢を話すと、「結婚相手もいないのにいいの?」「子供はどうするの?」と聞かれるのが常だった。
「医師の世界では留学がキャリアアップのステップになるのは常識ですが、希望の分野や大学を聞かれるのではなく、プライベートなことを聞かれる。女性はアカデミックなキャリアアップを求められていないのだと思い、悲しくなりました」
指導と引き換えのセクハラ
こうした被害は、ミカさんに限らない。多いのは、指導と引き換えにセクハラを黙って受け入れさせられるという構図だ。
「関東の大学病院に勤務していた時、指導医に性的関係を迫られました。『嫌なら指導しない』と。この業界は狭く、次が見つかるあてもないので、嫌でしたがしばらく関係を続けることになりました。後にわかったのですが、その医師は同じ手口でセクハラを繰り返し、後輩の女性医師も相当被害に遭っているようです」(40代産婦人科医)
「そのうち職場でも露骨に体を触られるようになり、耐えられないと思って女性上司に相談し、別の女性医師がトップの研究グループに入れてもらえることになりました。しかし、セクハラ医師と同期だったその女性医師から『セクハラとか主張して、実際は不倫していただけだろう』とセカンドレイプのようないじめを受け、辛い思いをしました。」(同上)
小児科医の女性(30代前半)は、「医療界に限らず、日本社会ならどこにでもある通過儀礼です。セクハラやパワハラを乗り越えた人間だけが愛されて指導を受けられるから、泣き寝入りせざるを得ない」と話す。
この女性医師は、研修医時代、産婦人科の指導医に、他の男性研修医と一緒にキャバクラに連れて行かれ、女性だけキャバクラ嬢の女性と一緒にそばに座らされた。
「飲んでいる間、順番に女性だけが胸をタッチされるのです。指導医は病院では怖い先生で通っていたのですが、裏で『エロ先生』と呼ばれ、看護師もよく同じことをされていたと聞きました。私は当時、傷ついていながらも、『そんなにシリアスに捉えることではない、指導を受けられなくなる』と自分に言い聞かせ、自分の中で笑い話にして処理していた気がします」
この女性医師は、別の病院に勤務していた時も、上司の男性医師に、頻繁に海外出張への同行を誘われた。既婚で子供もいる上司だった。
「国際学会に行くと、夜に私の部屋に来て入ろうとするので、上司を無碍にもできず色々理由をつけて追い返しました。別の国際学会にも『上司がいた方が安心だろう』とついてこようとするので、『一人で行けます』となんとか阻止したのです。帰って報告した時に、『一緒に行っていたら、俺たちどうなってたと思う?』と囁かれ、気持ち悪くてたまりませんでした」
「出産は地獄行きのチケット」
妊娠・出産に伴う嫌がらせであるマタニティー・ハラスメント、マタハラも深刻だ。
関東地方に住む別の女性医師(30代)は、自分の所属していた大学の医局では、妊娠を希望する女性は医局の会議で“妊活宣言”をしなければならなかったという。
「放射線を浴びる検査があるので、検査ができない医師は医局人事の頭数から外して、他の病院から補充を得たいということなんです。でも妊娠するかどうかわからないのに、みんなの前でわかるように言うなんておかしい話です。実際に妊活宣言をした人は、その場にいた男性医師から『子作り頑張れよ』などと言われたりして、とても不快だったそうです」
「出産してよかったという話を女性医師から聞いたことがありません。出産はこの国では地獄行きのチケットかと思うことがある」と話すのは、子供が二人いる西日本の女性皮膚科医(30代)だ。
診療科の症例検討会議は夕方から始まり、その後の患者への手術の説明は夜になる。子育て中の女性医師は保育園のお迎えのために手術説明には参加できない。周りのスタッフは、子供がいない女性医師や看護師も含め、「重要な場面にいない人」とその医師を低く評価していた。
「朝の回診や処置の時間も、子育て中の女性医師が間に合わない朝7時頃に行われてしまうので、皮膚科にとっては重要な傷口の確認ができず、その時の患者さんの状態も教えてもらえない。経過がわかりにくいので、自然と患者さんに積極的に関われなくなりました。これはいじめだと思いました」
この女性医師は、妊娠中に当直の回数を月2回から1回に減らした際、「サボっている」と上司に陰口を言われた。
また、妊娠中に前から決まっていた学会発表の準備をしている時に、「大変なのはわかるけれども、仕事と家庭が両立できないのなら、他の人に譲るとかしてもらわないと」と別の医師がいる前で嫌味を言われたという。
「長時間働けない人はやる気のない人と評価し、丁寧に指導しなくなる上司でした。若い医師は上司に教えてもらえないと技術や知識が習得できませんから、子供を持つと不利になります」
当直が必須となる分娩を行う産婦人科は、産休・育休、子育て中などで人手がきちんと補充されないと他の医師に負担のしわ寄せがいく。マタハラも一段と深刻だ。
「大学病院と有名な都内の産院で育休中に解雇となった女性医師を二人知っています。一人は保育所が見つからなくて、もう一人は午後6時以降も働ける医師を雇ったからという理由で、問答無用の解雇だったそうです」(40代産婦人科医)
「『専門医の資格をとるまでは妊娠するな』はよく言われます。一方で、医学部の産婦人科実習の時には、高齢出産の患者の羊水検査をしている時に、『こうならないように君たちは若いうちに出産するように』と言われました」(30代産婦人科医)
男社会の医療界 社会との隔絶も
厚生労働省によると、2016年12月末現在で、全国の医師数31万9480人のうち、女性医師は6万7493人と21.1%でしかない。最近では医学部に占める女子学生の割合は3分の1まで増えているが、依然として男社会であることには変わりない。
日本の37病院、619人の研修医に虐待や嫌がらせに関するアンケートをとった国立国際医療研究センターなどによる調査では、回答した355人中、85%に当たる301人が虐待やセクハラを受けた経験があった。
全体では言葉の暴力(72.1%)が最も多く、アルコール関連のハラスメント(51.8%)がそれに続いたが、女性医師だけで見ると、セクシュアルハラスメント(58.3%)が最も多かった。
冒頭でセクハラを訴えたミカさんは、医療界でセクハラが多いのは、医師が若い頃から置かれてきた環境に要因の一つがあると見ている。
「学歴社会のヒエラルキーのトップにいて、幼い頃から家庭でも学校でもチヤホヤされ、医師免許を取れば看護師や製薬会社の人に『先生、先生』ともてはやされる。医学生時代から男性医師との結婚を狙う外部の女子学生におだてられ、働き始めれば自分の指示で他の医療職を動かせる存在になります。周りもつけあがらせるし、増長する要素が揃っています」
医学部時代にもそれを補強する文化があったという。
ミカさんの出身大学では、文化祭の前夜祭で体育会系サークルの男子学生が複数で全裸になり、女子学生もいる前でマスターベーションをして精液を飛ばすのが盛り上がる出し物となっていた。
「女子高を卒業したばかりの自分は驚いて泣きました。医学部は他の世界と隔絶されていると思います。他の学部や大学と交流することも少なく、ずっと狭い世界にいるのでその文化や雰囲気に飲まれています」
さらに、ミカさんは証言する。
「特に医学部の体育科系サークルでは、BuzzFeedでも書かれていたように、先輩後輩の関係性で診療科に入る文化が残っています。狭い上下関係が医師になってからも維持され、下品なことを一緒にやることで男性同士の共犯関係を深め、結束力が強くなる。セクハラに疑問を持つ人がいても外部に話さず、誰かが反逆した場合、一気にその人への攻撃が強まるので何も言えない状況にあります」
妊娠・出産と仕事の兼ね合いが自分ごとである女性医師が教授や部長など、組織で指導的な立場になるまで残っていないーー。そんな現状も、セクハラやマタハラが蔓延する原因の一つだと証言してくれた女性医師たちは口を揃える。
「研修医時代、ベテラン女性医師がいた診療科は男性医師がセクハラ発言をすると、『また先生はそんなことを言って!』と釘を刺してくれました。笑って受け流していた私にも『先生も乗っちゃだめよ』と言ってくれた。そんな守ってくれる女性医師が上司にいたら、セクハラが延々と受け継がれることもなかったと思います」とミカさんは言う。
前出の小児科医は、小児科医同士で結婚した先輩夫婦が子供を産んだとたん、妻の女性医師の方ばかりに育児の負担が強くかかっているのを痛ましい思いで見ていたという。病院側のサポートもほとんどなかった。
「最初は、両方の両親が泊まり込みで孫の世話をしていたのです。でも、夫の方が『東京の病院で勉強したい』と言い出して家族で転勤したところ、両親のサポートがなくなり、妻の女性医師の方が1年でバーンアウトしていました」
「女性活躍が言われながらも、母親神話は強く、育児は女性がこなすものだという社会的圧力はまだ強いです。女医の割合は増えても、勤務を調整してくれる上司は少ないですし、産んだら女医が一線から退くのが当然のように受け止められています」
男性もセクハラを感じている
きちんと触れておきたいのは、もちろんセクハラをする男性は一部だし、こうした文化に抵抗感を抱いている男性も多いということだ。
医学部出身で、規模が大きく歴史も長い運動部に所属していた同僚の朽木誠一郎記者は、こうした文化の中に身を置いてきたが、同時に違和感も感じていたという。
「私の出身大学では、OB・OGも多数参加する飲み会の席など、折に触れて先輩の言うことは絶対だと叩き込まれ、この文化の中で生き残るにはそれに従うしかない。イベントの時に裸になったり、飲み会に同じ学年の可愛い女の子を連れて行ったりすることで、忠誠心が試されます」
「違和感を持ちながらも、先輩に気に入られれば、高い教科書を譲ってもらったり、ご馳走してもらったり、大きなメリットがありました。そして、それは医師になった後にもずっと続くコネとなることがわかっていました」
運動部で大学対抗の大会があると、主催大学がホテルの大広間などを借りて「レセプション」と呼ばれるパーティーを取り仕切る。そこで低学年の学生が芸を披露するのが慣例だったが、裸になるのは男性の先輩やOBに確実にウケる鉄板芸だった。
「女子選手や女子マネージャーも会場にいましたから、きっと見るのは嫌だったと思います。でも多数派の男性の先輩やOBの医師はえぐい芸ほど喜ぶし、当時はウケたり、ノリのいいやつと思われるのが単純に嬉しかった。この文化の中にいると、自分がおかしなことをしているということさえ気づけなかったんです」
低学年でそうした文化を仕込まれ、先輩になればそれを引き継ぐように後輩に指導していく。それが医師になってからも続く縦社会を強固にしていく一面もあるのではないか、という。
「そういう文化がいやになって、僕は新たにそんな関係性がない運動部を作り、別の世界を知りたいと進路を迷いました。きっと今もそんな思いを抱えている男性医師や男子学生は少なくないと思います」
受け流すことで加担 次世代が苦しまないように
この記事を書くきっかけになったミカさんは、声を上げようと決めた理由についてこう話す。
「自分もセクハラを助長してしまい、加担したという後悔があります。こんな文化を後輩に残してしまったという責任を感じていますし、これがセクハラだと気づかずに苦しんでいる人もいるかもしれない。男性もセクハラ被害はあるでしょうし、まず表に出して、医療現場からセクハラをなくしていきたいと思ったのです」と話す。
また、ミカさんは、男性医師の方も、長時間労働や男性上司からのパワハラ、医療事故や訴訟に対する不安、医療事務の増加でストレスが大きくなっていると指摘する。
「だからと言ってセクハラをしていいということにはなりませんが、イライラや疲弊がたまり、抵抗ができない弱い者へ発散している可能性もあります。根深い問題だと思います」と話している。
BuzzFeed Japanはこれまでも、性暴力に関する国内外の記事を多く発信してきました。Twitterのハッシュタグで「#metoo(私も)」と名乗りをあげる当事者の動きに賛同します。性暴力に関する記事を「#metoo」のバッジをつけて発信し、必要な情報を提供し、ともに考え、つながりをサポートします。
新規記事・過去記事はこちらにまとめています。ご意見、情報提供はこちらまで。 japan-metoo@buzzfeed.com
医療界の性暴力に関しても引き続き情報提供を募ります。
UPDATE
2018/02/16 14:36
一部表現を修正しました。
簡単な認可や甘い監督が少子化と重なって悪い結果となっていると思う。
「各大学には建学の精神に基づき教育や運営面で幅広い裁量が認められており、文科省は自主性を尊重しながら経営改善を求める方針。」
文部科学省が上記の方針を決めたのであればそれでも良いが、財務が悪化した時の基準を明確にして廃止や法人の解散を出せるようにするべきだと思う。
経営破たんするような大学はレベルが高くないと思われるので、他の大学に編集できるシステムを準備し、自宅からの通学が困難となる場合には、
奨学金のシステムを作るべきである。
費用対効果でメリットがなく、財政的に問題のある大学や短大は存在させる意味はない。
文部科学省は平成31年度から、少子化などで経営悪化が深刻な私立大を運営する学校法人に対して新たな財務指標を用いて指導し、改善しない場合は募集停止や法人解散など撤退を含めた対策を促す方針を決めた。国として厳しい姿勢で臨むことで、赤字が続く大学側の危機意識を高め、経営改革を加速させる狙い。
私立大の経営は地方小規模校を中心に悪化傾向が続き、全国で4割程度が既に定員割れしている。各大学には建学の精神に基づき教育や運営面で幅広い裁量が認められており、文科省は自主性を尊重しながら経営改善を求める方針。
文科省によると、今回の指導強化は(1)経常収支が3年連続赤字(2)借入金が、預貯金や有価証券などの資産より多い-といった財務指標の新設が柱。双方に該当し、経営難とみなされた際には、最初に専門家を法人に派遣し内部書類をチェックするなどして、3年程度で業績を上げられるよう助言する。
それでも改善しなければ、次の段階として学部の削減や学生の募集停止、設置大学・短大の廃止や法人の解散など、経営判断を伴う対策を取るよう通知する。法人側には対策の内容を事業報告書などの公表資料に明記するよう求めるとともに、文科省も資料を公開して注意喚起する。
指導の結果、一定の改善がみられた法人は、通知の対象とせず、必要に応じて助言を続ける。
文科省の担当者は「経営破綻で学生が困らないよう、法人には早めに経営チェックを進めてほしい」と話している。
大学経営をめぐっては、6月15日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針の中で、撤退を含め早期の経営判断を促す経営指導の強化や破綻(はたん)手続きの明確化を進めることが明記されている。
「最終報告書によると、問題発覚後の5月、理事だった井ノ口忠男氏が反則をした選手に、監督らの指示がなかったと説明するよう暗に要求。『(同意すれば)私が、大学はもちろん、一生面倒を見る。ただ、そうでなかったときには日大が総力を挙げて潰しに行く』と言ったという。日大職員による口止めも認定した。」
残念だけど、日本社会の一部は日大と同じ体質があると思う。日大だけが特別ではないと思う。
土居新平、山田暢史
学生を守る姿勢がなく、説明責任も果たしていない――。日大の悪質タックル問題で第三者委員会(委員長=勝丸充啓弁護士)は問題発覚後に「隠蔽(いんぺい)工作」をするなど後ろ向きな対応に終始した姿勢について指摘した。
「日大理事長の事後対応は不適切」 第三者委の最終報告
問われる日大理事長の説明責任 権限集中の背景に全共闘
「内田氏の弁護費用、大学で」 第三者委、上申書を発見
「学生ファーストの視点があれば大学も真相に迫れただろう。だが、実際に行われたのは口封じだった」。第三者委の勝丸充啓委員長は約100人が集まった会見で、こう指摘した。
最終報告書によると、問題発覚後の5月、理事だった井ノ口忠男氏が反則をした選手に、監督らの指示がなかったと説明するよう暗に要求。「(同意すれば)私が、大学はもちろん、一生面倒を見る。ただ、そうでなかったときには日大が総力を挙げて潰しに行く」と言ったという。日大職員による口止めも認定した。
また、第三者委は田中理事長にもヒアリングを実施。勝丸氏は「アメフト部任せにして放置した。あまりに無責任」とし、「公の場に出ることも含めて説明できる方法を考えてほしい」とした。ただ、報告書では、田中理事長に「反省と説明」を求める一方、経営責任については言及しなかった。勝丸氏は「第三者委の責務は提言。処分する権限は持っていない」と説明した。(土居新平、山田暢史)
日大からこれ以上は期待できないと思う。個々の日本人がどのような対応を取るか次第で、日大の対応が変わるかもしれない。
日本大学アメフト部の悪質タックル問題で30日、日大の理事会に田中英寿理事長が出席し、理事長としての対応を問われて「会見はしない」と明言していたことがANNが独自に入手した音声データで分かりました。
日大の第三者委員会は30日に公表した最終報告書のなかで、悪質タックル問題が発覚してから公の場に一度も出ていない田中理事長について「適切な事後対応を行っていなかった」などと指摘し、説明責任を果たすよう求めました。一方、日大は最終報告書が公表される前に理事会を開いていました。
理事会の出席者:「理事長としては今後、会見はいつごろ、どのような形で行うのですか?」
田中英寿理事長:「8月の前半、ホームページで答えを出します。会見はしません」
31日夜には関東学生アメフト連盟が理事会を開き、日大アメフト部の公式戦出場停止の処分解除について協議します。
日本大がアメリカンフットボール部の悪質タックルの事実解明のために設置した第三者委員会(委員長・勝丸充啓弁護士)が30日午前、大学当局に最終報告書を提出した。これを受け、日大は同日午後、東京都内で臨時理事会を開き、内田正人前監督(62)と井上奨【つとむ】元コーチ(29)を懲戒解雇処分とした。大学の信頼を著しく損なわせたことが理由という。
第三者委は同日夜、都内で勝丸委員長らが記者会見して最終報告書を公表した。その中で、内田氏の指導体制を、選手に対し一方的で過酷な負担を強いる「独裁」「パワハラ」と批判した。経営トップの田中英寿理事長(71)の責任についても「自ら十分な説明を尽くすべきところ、今も公式な場に姿を見せず外部に発信していない」と指摘した。
日大関係者によると、田中理事長は臨時理事会で、最終報告書を受け入れる意向を示したが、記者会見は予定していないという。
最終報告書では、悪質タックルが5月中旬に社会問題化して以降、学内のガバナンス(組織統治)を中心に問題点を列挙した。大学当局がアメフット部内の話と片付け、事実関係の調査を怠るなど「当事者意識が希薄だった」とした。
口封じに選手親子どう喝「つぶしにいく」
また、6月29日の中間報告で指摘した当時理事でアメフット部OBの井ノ口忠男氏による隠蔽(いんぺい)工作にも踏み込んで言及した。同氏が反則行為をした選手と父親を呼び出してタックルの指示の「口封じ」を図り「(同意してくれれば)私が、大学はもちろん一生面倒を見る。ただそうでなかったときには、日大の総力を挙げてつぶしにいく」と脅迫したことも明らかにした。井ノ口氏は内田氏と近しい関係で知られ、今月4日付で辞任した。第三者委は部の再建には「内田氏、井ノ口氏らの影響力を完全に排除した状態」が必要だと強調した。
内田氏は5月30日に常務理事職を辞任し、日大は最大6カ月の自宅待機を命じていた。【村上正、田原和宏】
「同署やコベルコ建機によると、26日夕、移動式大型クレーンの性能検査で、約130トンの重りを提げて旋回しているときにアーム(最長約200メートル)が根元から折れたという。」
「自走可能なクレーン車で、最大1250トンまで運べる。」が事実であれば、130トン程度の重りでアームが根元から折れるのはおかしい。
神戸製鋼所高砂製作所(兵庫県高砂市荒井町)で大型クレーンが倒壊し作業員1人が死亡した事故で、高砂署は27日、重傷だった男性1人が死亡したと明らかにした。この事故による死者は計2人となった。同署は同日午前、業務上過失致死傷容疑で現場検証に入り、兵庫労働局も対策本部を設置して調査を始めた。
【写真】神戸製鋼所高砂製作所で倒れた大型クレーン
加古川市の男性(23)で、27日未明に搬送先の病院で死亡が確認された。神鋼の子会社「コベルコ建機」(東京都)の協力会社「ウェイズ」(神戸市灘区)の社員で、倒壊したクレーンとは別のクレーンの塗装作業で現場にいたという。
同署やコベルコ建機によると、26日夕、移動式大型クレーンの性能検査で、約130トンの重りを提げて旋回しているときにアーム(最長約200メートル)が根元から折れたという。アームは付近の建物の屋根などを押しつぶし、ばらばらになったクレーンの部品などが周辺にいた男性らに当たったとみられている。
事故ではほかに、付近にいた塗装業の男性(56)=加古川市=が死亡。「ウェイズ」社員の男性(59)が重傷、屋内にいた神鋼高砂製作所の男性従業員(53)が軽傷を負った。
兵庫県高砂市にある神戸製鋼所の工場敷地内で、大型のクレーン車が倒れ4人が死傷した事故で、警察が現場検証をしています。
26日午後、高砂市の神戸製鋼所の工場敷地内にある「コベルコ建機」の作業場で、長さが約200メートルまで伸びる大型クレーン車が倒れました。この事故で、作業をしていた加古川市の塗装業・山口忠司さん(56)と会社員の西田秀平さん(23)が死亡。59歳と53歳の男性が重軽傷を負いました。クレーン車は納品前のもので、当時、性能に問題がないか動作の確認中だったということです。27日午前から警察が現場検証に入り、業務上過失致死傷の疑いも視野に、安全管理などに問題がなかったか調べています。
運転室に近いクレーンのブームが折れているように見える。強度不足か、製造に問題があったのではないのか?

26日午後3時50分ごろ、兵庫県高砂市荒井町新浜2の神戸製鋼所高砂製作所で大型クレーンが倒れ、クレーンの近くで作業をしていた1人が死亡、1人が意識不明の重体、2人が重軽傷を負った。製作所の敷地内東側で、出荷前のクレーンの旋回性能などを試験していた際、ブームと呼ばれるつり上げる部分が工場の屋根に倒れ、工場が一部損壊した。
県警高砂署などによると、死亡したのは同県加古川市、塗装業、山口忠司さん(56)。下請けの会社員の男性(23)が重体で、同じ社員の男性(59)が重傷。50代の男性も軽傷。
クレーンは神戸製鋼所の関連会社・コベルコ建機が製作。自走可能なクレーン車で、最大1250トンまで運べる。コベルコ建機は、何らかの理由でブームが折れ、クレーンが倒れたとみている。4人は試験運転とは別の業務をしていた。
現場は山陽電鉄荒井駅から南西約1.3キロの臨海部の工場地帯。神戸製鋼所によると、高砂製作所は船舶用エンジンに用いられる鉄や航空機の部材のチタンなどを作っており、同社の主力工場の一つ。【広田正人、幸長由子、待鳥航志】

26日午後4時ごろ、兵庫県高砂市荒井町新浜2丁目の神戸製鋼所高砂製作所で、作業員から「クレーンが倒れ、けが人がでている」と高砂市消防本部に119番通報があった。県警によると、同県加古川市の自営業山口忠司さん(56)が死亡。ほかに1人が意識不明の重体、1人が重傷、1人が軽傷とみられる。
倒れたのは、神戸製鋼所の関連会社「コベルコ建機」(本社・東京)が製造した移動式大型クレーン。同社が敷地内にある試験場に持ち込んで性能のテストをしていたところ、クレーンが折れて倒れ、近くにあった建物の一部も壊したという。
下記の記事が事実であれば、指揮者・田中雅彦氏に引導を渡すしかない。早稲田大学交響楽団の学生が終わりのスイッチを押せばよい。
100年余の伝統を誇る早稲田大学公認の有名音楽サークル、早稲田大学交響楽団(通称ワセオケ)で、指揮者・田中雅彦氏(83)のパワハラや不透明な金銭のやり取りを巡りトラブルが起きていたことが、「週刊文春」の取材でわかった。
【動画】「1300万、じゃあ分割で払ってみ?」……学生が録音した音声の一部を公開
「ワセオケは入学式、卒業式など大学の正式行事の演奏だけでなく、学外で定期演奏会も行っています。日本を代表する学生オーケストラと言ってよく、今年3月にも田中氏の指揮のもと、ドイツのベルリン・フィルハーモニーで演奏しています」(早大幹部)
「週刊文春」が入手した音声データによれば、2016年6月、田中氏は1300万円の支払いを学生に要求。〈1300万も含めて覚書の一部だからね。それを忘れんな。覚書は契約書と同じだからな。請求し続けるぞ〉などと発言している。
海外公演などでの各団員の演奏の出番や選曲に絶対的な権限を持つ田中氏は、一部で「尊師」と呼ばれ、3年間で3000万円をワセオケが田中氏に支払う覚書が交わされていたという。
早大広報室に一連の問題について聞くと、書面で概ねこう答えた。
「団員の保護者からの通報を受け16年9月に調査委を設置。弁護士を入れ、田中氏、複数の団員、OBらから話を聞いた。(3年で3000万円を支払っていることについて)調査委としては、経済的に自立していない学生のサークル活動としては適切とは言い難いと判断。同氏への業務委託契約を終了するよう勧告した」
7月26日(木)発売の「週刊文春」では、田中氏のパワハラ的言動や税務処理への疑惑も詳報、また「 週刊文春デジタル 」では上記の音声も公開する。
「週刊文春」編集部
「同社は、ブロック肉と成形肉は、工程は違うが品質は変わらないと強調した上で、『今後、お客さまには正しく、分かりやすい広告表現を行う」とコメント。再発防止に向け、広告表示に関する社内の勉強会を実施するなどとしている。」
本当に広告表示を理解できない社員達が関与しているのならマクドナルドは要注意かもしれない。たぶん、単なる言い訳だと思う。
どっちにしても消費者は考える事を学ばないといけないと思う。
日本マクドナルドの期間限定商品「東京ローストビーフバーガー」の広告で、加工肉をつなげた成形肉なのに、ブロック肉のスライスを使ったように表示したとして、消費者庁は24日、景品表示法違反(優良誤認)で同社に再発防止を求める措置命令を出した。
消費者庁によると、同社は「東京ローストビーフバーガー」と「東京ローストビーフマフィン」の2商品をテレビCMやウェブサイトの動画などで宣伝。この際、赤身の加工肉を結着させた成形肉なのに、あたかも肉塊から切り出した牛肉を使ったように表示していた。
同社は開発段階で、食材にブロック肉を使った製品化を計画していたが、肉の量を増やすため成形肉も調達するようになった。結果的に、商品の約6割で成形肉が使われていた。
同社によると、2商品は昨年8月9日から9月上旬までの期間限定で販売。キャンペーン広告が話題の人気商品で、全国で約490万個販売された。
同社は、ブロック肉と成形肉は、工程は違うが品質は変わらないと強調した上で、「今後、お客さまには正しく、分かりやすい広告表現を行う」とコメント。再発防止に向け、広告表示に関する社内の勉強会を実施するなどとしている。
複数の韓国人審査員が審査を担当した件で不正があった件について、記事は触れていないが、なぜ?
韓国人審査員が関与していた事実は、韓国の品質や検査体制にも飛び火するリスクがあるから触れなかったのか?
日本の工業製品の国家規格である日本工業規格(JIS)が不正審査議論に巻き込まれた。昨年神戸製鋼と三菱マテリアル、本田技研工業など日本の大企業の品質不正事件が摘発されたのに続き品質管理認証機関の不正まで明らかになり日本の製造業の信頼性にも打撃が避けられなくなった。
朝日新聞は23日、JISと国際規格(ISO)の認証審査機関である英国系ロイドレジスタークオリティアシュアランス(LRQA)日本支店が不正審査を行ってきた事実がわかったと報じた。
LRQAの内部資料によると、昨年航空宇宙関連企業3社から依頼を受けLRQAが実施した国家工業規格「JIS9100」関連審査で不正があった。経歴が不十分で無資格だったり検査に必要な訓練を受けていない非適格者などが審査作業に参加した。
JISは工業製品の品質や管理体系基準を定めた国家規格で、2005年までは国が審査・認証を直接担当していた。その後は民間認証機関が委託を受けて審査・認証をしている。現在日本で50余りの機関が年間6万件以上の品質認証作業をしているという。
朝日新聞は「認証機関の不正も明らかになったことで、国際的に高い評価を得てきた日本の製造業に対する信頼を一段と損なうおそれがある」としている。
副題:認証機関の審査員が無資格との呆れたニュース。認証機関自体の品質がQMSに反しているとの皮肉な現象である。
呆れたニュースを目にした。
その朝日記事(*1)の見出しは「◆JIS認証機関が無資格・手抜き審査 英大手の日本支店」である。
朝日記事のトーンとしては、昨年あたりにニュースとなった神戸製鋼所グループ、三菱マテリアルグループや東レなどの素材メーカーでの検査データの改竄問題と同列の問題の様に語っている。
しかし、これら素材メーカーの検査データ改竄問題と、今回の認証機関側の不正による問題は次の2点に於いて同列には語れない問題だと考えている。
1つは、今回の問題は、メーカー側の責任ではなく、認証機関側の不正であるという点である。そして、もう1つは、対象が「航空宇宙産業」であることだ。
最初の「認証機関側の不正」という点は、朝日記事によれば「複数の韓国人審査員が審査を担当したが、経歴が不十分で無資格だったり、所定の訓練を受けていなかったりする人物が含まれていた。審査員がまとめた報告書が適正かどうかをチェックする工程を省略した不十分な審査も複数見つかった。」というものである。
これを分かり易く例えれば「W杯サッカーの審判がド素人で資格がなかったでござる」という問題だ。
サッカーならば観客側の目も肥えているので、審判がオカシイと直ぐに分かるのだが、今回対象となっているのはサッカーではなく、航空宇宙産業の品質保証体制・プロセスである。それを審査して、OK or NO及びNOとなった部分に対して、何が、何故、どの様にNOなのかの指摘、その改善すべき点の改善方向性の明示等を判断・指摘する審査員である。
そういう審査が出来る審査員には、W杯サッカーの審判員と同様に、その道のプロとしての能力の有無を判断される資格審査を受け、それに合格することが必須なのである。
今回の件は、資格審査に合格していない審査員による審査が行われた、というものである。
そうなると、無資格者が審査して出した「認証」は、認証足り得ないので無効、正規の審査員で認証の再審査を受ける事が必要になる。
これを分かり易く例えれば、自動車学校に行って運転免許を取ろうとしたのだが、そこが非公認教習所だったので鮫洲で技能試験を受けるはめになったでござる、という話である。
認証を受ける為の審査を受けたのだが、その審査員が無資格審査員だったので、有資格審査員による審査を再度受けることになる、という話は、認証を受ける側にとっては大変迷惑な話で、「受かったんだからいいじゃん」という気持ちにもなろう。
しかし、そのメーカーの部品を使う側やその部品が組み込まれた製品のユーザー他の視点からは、「正規の認証を受けていないメーカーの製品」では価値がないのである。
これが「航空宇宙産業」であるのだから、尚更である。
飛行機やロケット等の特性・メリットは、主として、その移動速度が他の手段に比して桁違いに速いところにある。
その速さが第一宇宙速度を超えると、人工衛星の打ち上げ母体として利用できるし、第二宇宙速度を超えると地球重力圏外へと飛翔可能となる。
一方、その最大の弱点は、「機動中は止まることが出来ない」ことにある。
自動車ならば、何か異常があれば路肩に寄せて停車すれば良いのだが、飛行機は、そうはいかない。自動車については、その設計・製作上の車両安全基準があり、車検制度にて、個別車両毎の基準適合性検査が法定されている様に、飛行機についても型式証明制度(車両安全基準に相当)・耐空証明制度(車検に相当)があるのだが、その対象項目・要求事項には差異がある。
今回の認証対象の基準は「JISQ9100」である。
この文字列からは、これはJIS(日本工業規格)のQシリーズであることが分かる。
このシリーズは、ISOを根源とするJIS版だと理解して良い。
何年も前にあったISOブームで知っている方もいると思うが、代表的には品質保証のISO9001、環境保証のISO14000があり、それらの認証を受けないと、取引先からの注文がなくなってしまうと言われたアレである。
これらISO基準のJIS版がJISQ9001、ISOQ14000である。
今回対象のJISQ9100は、要するにISO9100のJIS版だと考えてよい。
ISO9001には品質マネジメントシステムの要求事項が書いてあるのだが、その品質保証上の要求事項だけでは「航空宇宙産業用」には不充分であり、「航空宇宙産業用」の品質保証に必要な事項を加えたISO9100が策定された。
そのJIS版がJISQ9100である。このJIS基準の名称は「品質マネジメントシステム-航空,宇宙及び防衛分野の組織に対する要求事項」である。
要するに、「一般的品質保証基準だけでは航空宇宙産業用としては不充分」ということは、それだけ航空宇宙産業での対象項目・要求項目が多い=複雑である、ということだ。
「飛んでる間は一時停止して難を逃れるとかができない飛行機」という特性からは、そうなってしまうのである。
飛行機やロケットの完成品を作る組織だけが、JISQ9100の認証が必要な訳ではない。完成品に組み込まれる部品のメーカーも認証が必要なのである。
これは当たり前で、完成品の自動車や飛行機は、その機能を発揮するには、構成部品毎に要求仕様に合った性能を発揮することが必要だからだ。
パッキンやVベルトが劣化・破損するだけで自動車は、安全な動きが出来なくなるのだから、部品メーカーは完成品メーカーからの要求仕様に合致した部品の納入することが求められる。
その際に、納入部品全品の詳細検査を自動車メーカー側がやっている訳ではない。
そんな事をしていたら、コスト的に引き合わなく、経済性が喪失する。
現実には、部品メーカーが認証を得て、その手順に則り検査して、要求仕様を満足させている旨を保証して納入している。
最初に書いた素材メーカーの話は、その検査データを改竄したとの問題だ。
信頼性を裏切る改竄をした事でアウトなのだが、実際の製品は、要求仕様を上回る安全マージンを乗せたオーバースペックな製品が多く、安全性で危機的状態になることは、まずないと見られている。とは言え、そんな理屈は通用しない。
完成品が、安全性・耐久性を含めた性能を発揮することを完成品メーカーが製品保証する為に実際に行われていることは、各部品メーカーが完成品メーカーと同様に、各部品が、その要求仕様通りに製作されている必要があり、それを「○○規格の認証メーカーが製作・検査したものだから」ということで、要求部品がちゃんと納入されていると看做す、との建て付けによっている。
つまり、「認証機関が正しく認証していなかった」という問題は、その建て付けの前提が崩れてしまったことを意味しており、実際の納入部品が「使えない部品」となってしまう問題なのである。
これを解決する為には、再度の認証獲得の為の審査を受けることになるのだが、それで失われる時間は、完成品である飛行機の完成時期の遅れとなって現れる。
現在、我が国は、戦後の「航空機開発禁止」(*2)の悪影響を脱し、我が国独自の航空機を生産することが可能となってきている。
三菱重工グループの旅客機MRJなどである。
型式認定は民間機に対してであるが、軍用機に於いても、国産機の開発・生産・装備は続いている。国産輸送機C-2や国産対潜哨戒機P-1などである。
そういう航空宇宙産業に悪影響が出ないかと憂慮している状態だ。
今回のニュースは、認証機関の審査員が無資格だったとの呆れたものであるが、認証機関自体がQMSに反しているとの皮肉な現象として表れたものだ。
しかし、その事によって、我が国の産業のうち、成長産業と目されている航空宇宙産業の足を引っ張る形になっているのが、どうも気になって仕方がない。
どの様な事が原因で、この様なことが起こったのであろうか?
それこそ、その分析は品質保証の考え方の重要部分なのだから、しっかりと報告していただきたい。
「複数の韓国人審査員が審査を担当したが、経歴が不十分で無資格だったり、所定の訓練を受けていなかったりする人物が含まれていた。審査員がまとめた報告書が適正かどうかをチェックする工程を省略した不十分な審査も複数見つかった。
・・・内部資料によると、LRQAは審査の手続きが不十分なまま、依頼を受けた企業に認証文書を発行しており、こうした不正行為は日本支店の代表者(当時)も了承していた。」
元英国の大手機関「ロイド」で働いていた日本人は、ロイドで働いていた時はどうだったか知らないが、他の仕事をはじめてからでたらめな検査で
大成功した。今でも成功している。パナマビューロー(マリンビューロー)
全ての顧客とは言わないが、高い割合の顧客は信用を得るため、又は、規則や契約で検査に合格する事を求められているから仕方がなく検査を受けている
わけで、検査が簡単な事を望んでいる場合が多い。コストから考えてもコストが下がるし、効率も上がる。
最終的に、検査は信頼が全てだと思う。信頼を失えば、高いお金を払い、コスト、対応するための人件費や労力を負担して依頼する意味がなくなる。
信頼は目に見えないし、不正があっても発覚しなければ、多くの人達は信頼を疑わない。
多くの不正やごまかしを見て来たし、問題にならない事は多くあった。規則上は何が正しいかわかるが、現実の世界では何が正しいか、何が利益に
繋がるのかは正しさだけでは判断できない。これが現実。実際、まともに検査をすれば仕事を他社に対して失う事がある。そして、一旦、他社が
受注すれば何かしらの大きな問題が起きない限り、仕事の依頼が来ることはない。現実は厳しい。綺麗ごとだけでは利益は出せないし、生き残るのも
大変だ。国交省はせっかく職員(PSC)が検査を行っているのだからもっと目を開けて事実を見てほしい。
検査に合格した船や審査に通過した管理会社が管理している船がなぜサブスタンダード船に
なるのかを考えれば、検査に問題があると推測できるであろう。ISO ISMコード
人間が人間である限り、不正はなくならない。ただ、不正は減らす事は出来る。
英国の大手機関「ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド(LRQA)」の日本支店とは違うが、グループ会社は
2010年5月に日本籍の外航船の検査が行える承認を国交省から得ていたと思うが(勘違いかもしれない)、どうなるのだろうか?(参考情報:
アメリカン・ビューロー・オブ・シッピング船級船の日本籍化について 2014年08月26日(川崎汽船株式会社))
英大手ISO認証機関ロイド・レジスター・クオリティ・アシュアランス(LRQA)が認証で不正。無資格者による審査、手続き省略等(各紙) 07/23/18(一般社団法人環境金融研究機構)
ISOマネジメントシステム認証制度は「オワコン」なのだろうか?! 12/11/17(自分を変える”気づき”の話)
工業製品の品質やその管理体制の基準を定める国家規格「JIS」や国際規格「ISO」の認証機関が、不十分な審査で企業に認証を与える不正をしていたことがわかった。大手素材メーカーなどの品質不正が相次ぐなか、企業の品質管理をチェックする認証機関の不正も明らかになったことで、国際的に高い評価を得てきた日本の製造業に対する信頼を一段と損なうおそれがある。
不正な審査をしていたのは、世界75カ国以上で規格の認証を手がける英国の大手機関「ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド(LRQA)」の日本支店(横浜市)。18世紀に船級協会として創立され、品質管理に関する認証機関の草分け的存在であるロイドレジスターグループの子会社だ。国内の審査件数も多い。
朝日新聞が入手した内部資料によると、航空・宇宙関連企業3社から依頼を受け、品質管理の仕組みを定める国際規格「ISO9001」に、航空宇宙産業で必要な項目を追加した規格「JISQ9100」に関する審査を昨年実施。複数の韓国人審査員が審査を担当したが、経歴が不十分で無資格だったり、所定の訓練を受けていなかったりする人物が含まれていた。審査員がまとめた報告書が適正かどうかをチェックする工程を省略した不十分な審査も複数見つかった。
内部資料によると、LRQAは審査の手続きが不十分なまま、依頼を受けた企業に認証文書を発行しており、こうした不正行為は日本支店の代表者(当時)も了承していた。
認証機関が適正に活動しているかをチェックする公益財団法人「日本適合性認定協会(JAB)」が問題を把握し、意図的な不正で重大な悪質性があったと結論づけた。同協会はLRQAに対し、認証機関としての認定を取り消す処分を今月12日に出した。処分をしたことはホームページで同19日に公表したが、機密情報にあたるとして詳しい処分理由は説明していない。
協会の処分には審査業務を停止させる強制力がないため業務は継続できるが、LRQAは6月、「JISQ9100」の認証業務から撤退すると表明した。
LRQAは昨年11月、アルミ製品の検査データ改ざんが発覚した神戸製鋼所大安工場(三重県いなべ市)に対し、JISとISOの認証を一時停止する処分を出していた。銅管を製造する北九州市の神鋼子会社についても、今年2月にJISとISOの認証を取り消している。
LRQAは不正や処分について、「お客様との守秘義務の関係上、情報をご提供することは差し控えます」としている。(野口陽)
◇
〈JISとISO〉 JISは日本工業規格の略称。工業標準化法に基づき、鉱工業品の種類・形状・品質・性能などを定める国家規格だ。ISOはスイスに本部を置く国際標準化機構が制定した国際規格。製品やサービスの品質やレベルの基準を世界中で同じにして、国際的な取引をスムーズにする狙いがある。組織の品質管理や環境活動を管理する仕組みについて定める「ISO9001」「ISO14001」が有名。JISは国際規格との整合化を図っており、ISOと同内容のものも多い。
野口陽、上地兼太郎
大手メーカーで品質データの改ざんが相次いで発覚したのに続き、工業製品の品質や企業の品質管理をチェックする「番人」である認証機関でも、不十分な審査で企業に「お墨付き」を与える不正が明るみに出た。製造業の品質不正は底なしの様相で、国際的に高い評価を得てきた日本のものづくりへの信頼が揺らぎかねない事態に発展した。
英国の大手認証機関「ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド(LRQA)」の不正は、製品やサービスの品質を維持・向上させるための組織の仕組みや手順(品質マネジメントシステム)を定める規格の審査で見つかった。国際規格ISOの中でも「品質保証のモデル規格」として広く普及する「ISO9001」をもとにした規格だ。
JISやISOには、企業の製品やサービスが満足できる水準にあると第三者がお墨付きを与えることで、国内外の取引先がその水準を確認する手間やコストを省き、取引を円滑にする狙いがある。国内外で企業の製品やサービスへの信用を高めることで、最終製品を利用する消費者が、安心して製品やサービスの提供を受けられる効果も期待できる。こうしたメリットは公正な審査が前提になっていることは言うまでもない。
国内では昨年以降、神戸製鋼所や三菱マテリアルなど日本の製造業を代表する大企業で品質データを偽る不正が次々と発覚。両社などがJIS認証取り消しの処分を受け、規格の信頼性に傷がついた。さらに企業にお墨付きを与える認証機関のずさんな審査が発覚したことで、認証制度自体が疑念を持たれかねない。
「(今回の不正を放置すれば)認証を受けて商売に活用しているメーカー、特に中小企業にとって大きなダメージになる。きちんと処分すべきだと考えた」。LRQAの不正を調べ、処分を決めた公益財団法人「日本適合性認定協会(JAB)」の関係者は朝日新聞の取材にこう明かした。
企業活動のグローバル化が進む…
野口陽、上地兼太郎
大手メーカーで品質データの改ざんが相次いで発覚したのに続き、工業製品の品質や企業の品質管理をチェックする「番人」である認証機関でも、不十分な審査で企業に「お墨付き」を与える不正が明るみに出た。製造業の品質不正は底なしの様相で、国際的に高い評価を得てきた日本のものづくりへの信頼が揺らぎかねない事態に発展した。
JIS認証機関が無資格・手抜き審査 英大手の日本支店
英国の大手認証機関「ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッド(LRQA)」の不正は、製品やサービスの品質を維持・向上させるための組織の仕組みや手順(品質マネジメントシステム)を定める規格の審査で見つかった。国際規格ISOの中でも「品質保証のモデル規格」として広く普及する「ISO9001」をもとにした規格だ。
JISやISOには、企業の製品やサービスが満足できる水準にあると第三者がお墨付きを与えることで、国内外の取引先がその水準を確認する手間やコストを省き、取引を円滑にする狙いがある。国内外で企業の製品やサービスへの信用を高めることで、最終製品を利用する消費者が、安心して製品やサービスの提供を受けられる効果も期待できる。こうしたメリットは公正な審査が前提になっていることは言うまでもない。
国内では昨年以降、神戸製鋼所や三菱マテリアルなど日本の製造業を代表する大企業で品質データを偽る不正が次々と発覚。両社などがJIS認証取り消しの処分を受け、規格の信頼性に傷がついた。さらに企業にお墨付きを与える認証機関のずさんな審査が発覚したことで、認証制度自体が疑念を持たれかねない。
「(今回の不正を放置すれば)認証を受けて商売に活用しているメーカー、特に中小企業にとって大きなダメージになる。きちんと処分すべきだと考えた」。LRQAの不正を調べ、処分を決めた公益財団法人「日本適合性認定協会(JAB)」の関係者は朝日新聞の取材にこう明かした。
企業活動のグローバル化が進む…
文部科学省前局長、佐野太容疑者が有罪にならなかったら法改正が絶対に必要だと思う。
文部科学省の私立大学支援事業を巡る汚職事件で、受託収賄容疑で逮捕された同省前局長、佐野太容疑者(59)の息子を不正合格させたとされる東京医科大の臼井正彦前理事長(77)が数年前、新たに就任した同大の入試担当課長に「裏口入学がある」と伝えていたことが関係者への取材で明らかになった。東京地検特捜部は24日にも佐野前局長を受託収賄罪で起訴し、臼井前理事長らも贈賄罪で在宅起訴するとみられる。
【特捜部が描く事件の構図】
臼井前理事長とともに、同大の鈴木衛前学長(69)も在宅起訴されるとみられる。前理事長から裏口入学について伝えられたとされる入試担当課長や部下らも、不正の実態について特捜部から任意の事情聴取を受けている模様だ。
関係者によると、入試担当課長は数年前の就任直後、臼井前理事長から「裏口入学があるから承知しておいてほしい」などと告げられたという。不正合格の実務などを、前任者から聞くよう前理事長に指示されたといい、今年度の不正にも携わった可能性がある。特捜部の聴取に対し「トップからの指示で断れなかった」といった趣旨の説明をしている模様だ。
佐野前局長は官房長だった昨年5月、同省の「私立大学研究ブランディング事業」の対象大学選定で、臼井前理事長から便宜を図るよう依頼を受けた見返りに、今年度の同大の入試で息子を不正合格させてもらった疑いがある。
同大の入試はマークシートの1次と小論文などの2次があり、最終的な合否は学長や副学長らで構成する入試委員会が判断する。今年度の合否判断は鈴木前学長が関与し、臼井前理事長の指示で佐野前局長の息子の点数を不正に加点したとみられる。【巽賢司、遠山和宏、金寿英】
愛知県愛西市の佐織土地改良区が発注した工事入札を巡る贈収賄事件で、同改良区理事長の太田芳郎容疑者(80)=土地改良法違反(収賄)容疑で逮捕=が2012年、贈賄側の福岡建設(愛西市)が入札に参加できるよう取りはからっていたことが、捜査関係者らへの取材でわかった。太田容疑者が福岡建設側に工事の予定価格を漏洩(ろうえい)する約3年前から、両者の間で癒着があったとみられる。
【写真】佐織土地改良区の事務局に家宅捜索に入る愛知県警の捜査員=2018年7月22日午前10時2分、愛知県愛西市石田町
捜査関係者や同改良区関係者によると、加藤辰実容疑者(66)=土地改良法違反(贈賄)容疑で逮捕=が顧問を務める福岡建設は12年度から、同改良区が発注する工事の指名競争入札に参加するようになった。この際、太田容疑者が福岡建設を指名業者に加えることを決定。総会などに諮ることなく新規参入が認められたという。
その後、福岡建設は同改良区の工事を昨年度までの6年間で計16件落札。当時を知る同改良区関係者は「色々な判断を太田容疑者の一存にゆだねる雰囲気があった。押しが強く、反対する人はほぼいなかった」と話した。
県警は22日、同改良区事務局と福岡建設本社などを家宅捜索した。太田容疑者が事件以前から工事の予定価格を加藤容疑者に漏らした可能性もあるとみている。
法を守らない会社や人々はたくさん存在する。
これまでの経験ではこのような会社や人々はいなくなくならない。しかし、減らす事や減らすように法やシステムを改善する事は出来る。
運悪く事故に巻き込まれたり、被害者になる人々は存在する。個々が出来るだけ被害者や被害者の関係者にならないように努力するしかない。
そして最後は運次第。
違法行為を繰り返しても直ぐに事故や死亡事故が起きるわけではない。運が良ければ、長期間、事故は起こらない。事故が起きて調査した時に
もしかすると事故は防ぐ事が出来たかもしれないと言うレベルだと思う。
行政や監督官庁がしっかりと対応していくしかない。
日本郵船傘下の日本貨物航空(千葉県成田市)が20日、国土交通省から事業改善命令を受けた。整備記録の改ざん・隠蔽いんぺいを3件、不適切整備を9件も指摘されるというずさんな安全管理ぶりに、識者からも「組織として安全を守る姿勢が欠如している」と厳しい声が上がった。
同社の大鹿仁史社長は20日午後、命令を受けた直後に東京都内で記者会見。「一から再生する気持ちで安全運航に向け、全力を尽くしたい」と述べ、深々と頭を下げた。
改ざんの背景には何があったのか。国交省によると、「より多く機体を飛ばすため、追加の点検作業が発生するのを避けたかった」など、整備より運航状況を優先させるかのような説明をした社員もいたという。
航空機の整備記録改ざんが明らかになった日本郵船傘下の日本貨物航空(千葉県成田市)に対し、国土交通省は20日、航空法に基づく事業改善命令と業務改善命令を出した。整備記録の改ざん・隠蔽いんぺい3件と不適切整備9件を認定。「組織的な悪質性が認められる」として、同社に対する「連続式耐空証明」を取り消し、これまで認めてきた安全性証明の自動継続を打ち切った。
国交省によると、同社は4月、潤滑油の補給量の値を改ざんしたほか、4~5月には、雷を受けた機体の損傷の大きさを計測していないのに、行ったかのように記載。改ざんを整備責任者らも把握していたが、隠蔽し、国交省へ報告しなかった。
不適切整備は、マニュアルに基づかない整備や、社内資格を持たない社員による操縦機能試験の実施など9件が確認された。
日本貨物航空(NCA、千葉県成田市)の貨物機の整備記録に事実と異なる記載が見つかるなどした問題で、国土交通省は20日午前、同社に対し、同日午後に事業改善命令と業務改善命令を出すと明らかにした。同省は安全管理体制に重大な問題があると判断。機体ごとに交付する耐空証明について、同社に認めていた毎年の検査を免除する「連続式耐空証明」を取り消す。
同省は、法令順守や適切な整備記録の徹底に加え、安全管理体制と機体の修理体制を整備することや事故の恐れがある事案に適切な措置を取るよう指示。修理体制が構築できるまでの間は、社内での機体整備を禁じる。航空事業者への連続式耐空証明の取り消しは初めてで、証明の有効期間を1年に変更する。
同省によると、同社は4月、貨物機の整備記録で翼に補給する潤滑油の量を実際より少なく記載。潤滑油の注入時、一定量より多く入った場合には油漏れが疑われるため細かな点検が必要になるが、点検をせずに済むよう注入量が少なかったようにデータを改竄(かいざん)していた。平成29年4月に雷が当たって機体が損傷した際にも、計測していないへこみの深さを記すなど、同社はずさんな機体整備を続けていた。
昨年1月と今年3月に鳥との衝突で生じた機体の損傷について、同社は小規模な修理と処理していたが、同省の調査で大規模な修理が必要だったと判明。同省は5月に航空事故と認定し、その後の立ち入り検査で複数の記録改竄が確認された。
同社は貨物機11機を保有。6月17日から全機の運航を停止していたが、7月に入り安全性が確認されたとして2機の運航を再開している。同社は大鹿仁史社長が20日午後に都内で会見すると明らかにした。
同社は昭和53年に設立された国内唯一の貨物専門航空会社で、海運大手の日本郵船(東京)の連結子会社。米国や欧州、アジアに食品や薬品、精密機械などを運んでいる。
どのレベルの管理職まで問題を知っていたのか知らないが、知っていれば自業自得だし、知らなければ現場を管理及び監督していない管理職に
責任はあると思う。
「連続式耐空証明」の取り消しのインパクトについて知らないが、整備記録のデータを改ざんするほどのプレッシャーが現場にあったのなら
インパクトは大きいと推測する。
航空機の整備記録改ざんが明らかになった日本郵船傘下の日本貨物航空(千葉県成田市)に対し、国土交通省は20日、航空法に基づく事業改善命令と業務改善命令を出した。整備記録の改ざん・隠蔽(いんぺい)3件と不適切整備9件を認定。「組織的な悪質性が認められる」として、同社に対する「連続式耐空証明」を取り消し、これまで認めてきた安全性証明の自動継続を打ち切った。
国交省によると、同社は4月、潤滑油の補給量の値を改ざんしたほか、4~5月には、雷を受けた機体の損傷の大きさを計測していないのに、行ったかのように記載。改ざんを整備責任者らも把握していたが、隠蔽し、国交省へ報告しなかった。
不適切整備は、マニュアルに基づかない整備や、社内資格を持たない社員による操縦機能試験の実施など9件が確認された。
「赤信号、皆で渡れば怖くない。」が通用する一例であろう。
神戸製鋼所による品質検査データ改ざん事件で、東京地検特捜部は19日、不正競争防止法違反(虚偽表示)で法人としての同社を立川簡裁に起訴し、社員4人を不起訴処分とした。特捜部は組織で不正が慣行的に行われていた点を重視し、特定の社員個人の刑事責任は問わないと判断した模様だ。
起訴内容は、同社のアルミ・銅事業部門の社員は2016年9月~17年9月、真岡製造所(栃木県真岡市)、大安製造所(三重県いなべ市)、長府製造所(山口県下関市)で、製品の検査結果が顧客と合意した仕様を満たしていないのに、満たしているとする虚偽の証明書計305通を作成し、東京都府中市など6カ所で顧客側に交付したとしている。【巽賢司、遠山和宏、金寿英】
「ブロック塀定期点検、形骸化か・・・大阪府北部地震で小学校のブロック塀が倒壊し女児が死亡した問題に絡み、神奈川県教育委員会による県立学校の緊急点検で危険性が指摘された42件のうち、9割近くが業者による定期点検の結果と食い違っていることが10日、分かった。専門知識があるはずの業者が建築基準法に基づく不適合を見抜けず、点検が形骸化している可能性が浮上。」
学校のブロック塀定期点検の現状については知らないが日産でさえ数値改ざんを行っていた。他の業界で現状を知っている検査でも形だけの場合が
結構ある。事実を書けば問題になったり、費用が発生したり、追加が発生したりするし、問題を放置すれば責任問題になるので、都合の良いように
記録や検査レポートでは問題のないように書く業者は存在する。問題が発覚する確率は低いし、例え、発覚しても処分されるとは限らない。
大阪の小学校のブロック塀が倒壊して死亡した少女の件にしても、何年の間、問題を放置して死亡事故が起きたのかを考えれば、かなり低い
確率である。この死亡事故をきっかけに多くの学校が点検を行い、結果は、すさんな検査が行われていた事が証明された。
「専門知識があるはずの業者が建築基準法に基づく不適合を見抜けず、点検が形骸化している可能性が浮上。」
人間がチャックする以上、間違いや見落としはあると思う。ただ、多くが「不適合を見抜けず」には疑問だ。個人的な経験から言えば、例えば、
図面や施工指示書がなければ、鉄筋がどれぐらいの間隔で、どのくらいの高さまではいっているのか、目視では確認できない。図面や施工指示書が
存在しても、現場の人間や請け負った会社が手を抜いたり、能力がない下請けに任せていれば、図面や施工指示書通りに仕上げていないかもしれない。
事実を書けば問題になったり、費用が発生したり、追加が発生したりするし、問題を放置すれば責任問題になるので、業者の責任で綺麗な(問題が記載されていない)
報告書を書いてくれる業者を選びたい学校は存在するはずである。実際に、大阪で女児が死亡した事故で、点検した業者の責任について書いている
記事は見かけない(もしかすると責任を問う記事を見ていないだけかもしれない)。
結局、これがおもてなしの国である日本の現実なのである。問題や事故がなければ、適当に前の通り、又は、前の業者と同じようにやっていれば良いのである。
適切にやるよりも、上手く、適当にやる方が仕事は増えるし、仕事を依頼する方も喜ぶのである。仕事を依頼する方は、問題や事故が起きたら
専門でないので、専門家に依頼していると言えば、責任は問われない。法律に詳しいわけではないが日本の法律や規則では、責任を問う事は難しいと思う。
実際に、責任を問う事は、明らかに検査をしていないとか、誰かが問題に気付き、写真などの証拠を残しているケースを除いてはないと思う。
良くも悪くもこれが日本。行政だって、今回の件で、どこまで事実を把握しようと調査するのか疑問。形だけの現状把握や報告書の提出で終わる可能性もある。
日本の矛盾を多く見てきて、部分的には何とか良くなるように努力してきた部分もあるが、20年経って振り返ると問題や事故が注目されるまで
周りの関心や理解は低い。死亡事故が起きないと注目されない。安全、人命、そして規則順守と言っても、結局は相手の都合や利益が優先になる
事が多い。これが現実。被害者や被害者の家族にならないと問題や原因について考える事もない。日本は日本。多くの人達が変わろう、又は変えようと
行動を取らなければ変わらないと思う。継続されてきた環境やシステムを変えるには努力やエネルギーが必要だ。良い事だとわかっていても、
現状を支持する人達が存在し、抵抗勢力になる事もある。変える事が出来なければ、出来るだけ被害者にならないように気を付けるだけである。
大阪府北部地震で小学校のブロック塀が倒壊し女児が死亡した問題に絡み、神奈川県教育委員会による県立学校の緊急点検で危険性が指摘された42件のうち、9割近くが業者による定期点検の結果と食い違っていることが10日、分かった。専門知識があるはずの業者が建築基準法に基づく不適合を見抜けず、点検が形骸化している可能性が浮上。全国で実施している法定点検のあり方を巡り、波紋を広げそうだ。
県教委によると、高校や特別支援学校など県内の172校で実施した点検結果を同法12条に基づく定期点検と比較したところ、14校計42カ所のうち全校の計36カ所で不一致が判明した。塀を補強する「控え壁」の間隔が基準(3・4メートル以内)を満たしていないケースのほか、傾きやひび割れといった劣化による倒壊の恐れがあったにもかかわらず、「問題ない」と見過ごしていた可能性が高いという。
県教委は現行法に改正される前に設置した「既存不適格」のブロック塀が数多くあるとした上で、「児童生徒の安全の観点から耐震強度の是正が必要にもかかわらず、報告がないと『問題ない』と判断してしまう」と指摘。各業者に経緯や内容を再確認するなどして課題を整理し、今後の対策に生かすとしている。
同法12条に基づく点検は各施設で3年に1回の実施が義務付けられており、2011年度には建築士資格がある専門家による点検に厳格化された。県教委は県内の設計事務所など地域別で5業者に委託しており、設備点検も含めた年間委託総額は約5千万円。不一致が生じたのは15年度は2業者、17年度は4業者だった。
銀行の監査では見つける事が出来なかったと言う事か?
東京を地盤とするきらぼし銀行の男性行員が、約3億7500万円を着服して失踪していることが分かりました。きらぼし銀行はこの行員を8日付で懲戒解雇処分にしました。きらぼし銀行は5月に八千代銀行など3行が合併して発足した、地方銀行として東京都内最大の店舗数を持つ銀行です。
きらぼし銀行によりますと失踪した36歳の男性行員は東京・練馬区の石神井支店に在籍していて、2016年5月から18年5月にかけて、元・八千代銀行だった石神井、上石神井両支店の顧客の法人1社と個人2人から定期預金を作るために受け取った普通預金の払戻請求書を使って預金を引き出し、着服したとみられています。被害に遭った顧客には偽造した定期預金証書が渡されていました。
これまで分かっている被害額は3億7500万円ですが、きらぼし銀行は他にも被害がないか調査を続けています。また、刑事告発することも含め、警察に相談しているということです。
規模拡大だけのための統合であれば、思ったほどメリットはないかもしれない。
システムや企業体質や理念が違う会社が一緒になっても、結果を出すために妥協できなければ、2つの方法が残り、混乱や
副作用を引き起こすかもしれない。判断基準が違えば、正しい選択であるのかの評価も違ってくるはず。
民主党の歴史を見れば理解できるはず。数を優先させて一緒になっても、いつもどこかでばらばら。
まあ、成功しようが、失敗しようが、個人的には関係ないのでどうでも良い事。
石油元売り大手の出光興産と昭和シェル石油は10日、2019年4月に株式交換を通じて経営統合する合意書を締結したと発表した。出光が、統合に反対していた創業家側の主要株主から賛同を取り付けた。3年越しの統合協議が事実上決着したことで、国内石油業界は首位JXTGホールディングス(HD)との2強体制に再編される。
出光は株式交換で昭和シェルを完全子会社化する。統合後の社名は登記上は「出光興産」とし、事業上の通称は「出光昭和シェル」を使う。統合後の取締役は出光側から5人、昭和シェル側から3人を出す。両社は、それぞれ今年12月をめどに臨時株主総会を開き承認を求める。
両社は15年に経営統合で基本合意したが、計約28%の出光株を保有する創業家の反対で実現できずにいた。出光の月岡隆会長は記者会見で「収益改善や経営理念について相互理解を進める中で大株主(創業家)の懸念が解消された」と述べた。昭和シェルの亀岡剛社長は「エネルギー業界の置かれた環境から統合は待ったなしだ」と語った。
出光によると、創業家の主要株主とは統合後3年間累計の純利益で5000億円以上、配当と自社株買いを合わせた総配当性向で50%以上の株主還元を目指す方針で一致。「物言う株主」として知られる村上世彰氏が経営側と創業家側の間を仲介した。
出光の経営側は統合後の新会社の取締役に創業家側の2人を起用する方針などを示し、創業家の資産管理会社で筆頭株主の「日章興産」と、出光昭介名誉会長の長男から賛同を得た。これを受け、出光と昭和シェルは臨時株主総会で統合に必要な3分の2以上の承認が得られると判断した。
出光創業家側も代理人を通じて10日にコメントを発表。日章興産などが賛同したことを認めた上で、「統合後も創業者の理念が維持されることが確認できた」と説明した。ただ創業家側の株主全員が経営側提案を受け入れたわけではないとも指摘している。
国内のガソリン販売シェアは、JXTGHDが5割を占める。出光と昭和シェルのシェアは計3割を超え、統合を機に追撃する構えだ。
日産の車は購入するリストに入っていないので、何が起きようが個人的な選択プロセクには影響ない。
無資格の従業員が完成車の検査を行う不正が昨年秋に発覚した日産自動車で9日、検査の測定値を書き換えるという新たな不正が発覚した。日産は昨秋の不正発覚を受けて法令順守体制を強化すると説明していた。しかし、その後も別の不正が生産現場で行われていたことになり、同社の自浄能力の低さや問題の根深さが改めて浮き彫りになった格好だ。原因究明や再発防止策の策定が急務で、信頼回復の道のりは険しい。
「原因の深掘りをして、絶対に問題が起きない仕組みを作るのが第一義的な責任だ」。この日、横浜市内の本社で記者会見した山内康裕執行役員はこう強調した。
新たな不正は、出荷前の新車の一部を抜き取り、燃費や排ガスの数値などを室内で試験する「完成検査」で発覚した。車両をローラー型の測定装置に乗せて走行させる検査の中で▽規定の速度を逸脱した無効な検査データを有効な数値に書き換えた▽試験室の温度や湿度が許容範囲外でも有効なデータとして処理した--などの内容だ。いずれも今年4月にSUBARU(スバル)が公表したデータ不正の内容と似ている。
今回の不正は国内の製造拠点全6カ所のうち5カ所に上った。不正がなかった日産自動車九州では検査業務の経験が豊富な監督者がいた。一方、他の工場には十分な知識のある上層部がおらず、不正の背景には構造的な問題がありそうだ。不正には少なくとも10人が関わっていたという。動機や背景について、山内氏は「法令順守の意識が希薄だった。(無資格検査問題と)根っこは同じだ」と語った。
スバルで同様のデータ不正が公表された4月以降も、一部の工場で不正が続いていたことも判明。他社の事例がなければ問題を見つけられなかった可能性もあり、問題は深刻だ。山内氏は「(問題を)自ら検出できる管理体制に変えていきたい」と述べるにとどめた。
再発防止に臨む同社の姿勢には厳しい目が注がれる。石井啓一国土交通相は9日、「昨年9月に判明した完成検査問題の再発防止に取り組む中、ごく最近まで続いていた点で問題の深刻さを示すものであり、極めて遺憾だ」とのコメントを出した。不正が重ねて発覚したスバルでは、吉永泰之・前社長兼最高経営責任者(CEO)=現会長=がCEO職の退任を迫られた。日産の西川広人社長らの経営責任も問われることになりそうだ。【竹地広憲、川口雅浩】
「動機については『法律に抵触しないと思った』などと説明しているということです。」
「法律に抵触しない」のなら時間と労力の無駄である検査を止めて全く同じの検査レポートを打ち出して添付すれば良い。
その分、値段を下げて日産車を売れば良い。納得して買う人は買うと思う。製造する方も、買う方も、やっちゃえ、日産で
良いと思う。
事実を知らずに日産の車に満足しているのなら事実が明らかになっただけで、現状は何も変わらない。
何も心配する事もないし、何も変わらない。
ほとんどの工場でデータの改ざんが行われていました。
日産自動車・山内康裕CCO:「深くおわびを申し上げます。申し訳ございませんでした」
日産は国内の5つの工場で排出ガスや燃費の測定試験を行った際、データ書き換えなどの不正行為があったと発表しました。不正があった台数は1171台で、10人が不正に関わっていました。動機については「法律に抵触しないと思った」などと説明しているということです。日産は今後、原因究明や再発防止に努めるとしていますが、現時点では「カタログなどで公表している燃費の数値には誤りはない」としています。
日産自動車は9日午後5時過ぎ、緊急会見を開き、車の排ガスや燃費の検査データを改ざんしていたことを明らかにした。日産では去年、資格のない検査員に車の検査をさせていたことも発覚しており、管理体制が改めて問われそうだ。
日産自動車・山内康裕氏「お客さまはじめ、関係者の皆様に深くおわびを申しあげます。申し訳ございませんでした」
日産によると、不正があったのは神奈川県の追浜や栃木など国内の複数の工場。新車を出荷する前に無作為に選んで排ガスや燃費の検査をする際、社内の基準に満たない結果が出ても、基準に合う都合の良い数字に書き換えられていたという。
このほか、国が定めた基準とは異なる条件で検査を行っていたこともわかった。
こうした不正は少なくとも2013年ごろから行われ、検査した車の半数を超える車で不正があったとしている。
日産は品質には問題ないとしているが、去年、無資格の検査員が不正な検査をしていたことが発覚しており、ずさんな品質管理に会社としての経営責任も改めて問われることになりそうだ。
「定められた試験条件を満たしていなかったり、測定値を改ざんしたりしていた。抜き取り検査対象の完成車のうち、53.5%に当たる1171台で不正があった。」
かなり厳しい数字だと思う!50%の車に何らかの不正があるのであれば、設計やプロトタイプで既に問題を予測できたのでは???
日産自動車は9日夕、国内工場で新車出荷前に実施している排ガス測定で不正行為があったと発表した。定められた試験条件を満たしていなかったり、測定値を改ざんしたりしていた。抜き取り検査対象の完成車のうち、53.5%に当たる1171台で不正があった。昨年秋の無資格検査問題に続く不祥事の発覚によって日産のイメージ悪化は避けられず、西川広人社長の経営責任を問う声も強まりそうだ。
不正は国内工場のうち、グループ会社の日産自動車九州(福岡県苅田町)を除く5工場で行われていた。記者会見した、生産部門トップの山内康裕チーフ・コンペティティブ・オフィサー(CCO)は「関係者に深くおわびする」と陳謝した。
日産では、昨年9月に無資格の従業員による完成車の検査不正が発覚した。国内工場のうち、京都府の工場を除く5工場で不正が常態化していたことが判明し、国土交通省から2度にわたって業務改善の指示を受けた。
今年6月の株主総会では、西川社長が陳謝した上で、「法令順守体制を強化していくのが私の責務だ」と再発防止に努める姿勢を強調していた。
日産自動車の複数の工場で、新車の出荷前に行う排ガス性能の検査結果を、都合よく改ざんする不正が行われていたことがわかった。この検査は昨年、無資格者の従事が発覚した「完成検査」の工程のひとつで、日産の品質管理への姿勢が改めて厳しく問われることになりそうだ。
【写真】日産自動車本社=横浜市西区高島1丁目
関係者によると、今回不正が発覚したのは、出荷前に車の性能をチェックする「完成検査」の中で、数百台から数千台に1台の割合で車を選んで実施する「抜き取り検査」という工程。そこで行われる排ガス性能の測定で、思わしくない結果が出た場合、都合のいい数値に書き換える不正が国内の複数の工場で行われていたという。今春以降に社内で発覚したという。
この検査は、メーカーが車を量産する際、国に届け出た設計上の性能通りにつくられているか確かめる重要なもの。メーカーは適正な実施を前提に、車の量産を国から認められている。測定値が設計上の性能からずれていれば、出荷ができなくなることもある。
日産では昨年9月、完成検査を実際は無資格の従業員が担ったのに、有資格者が行ったように偽装する問題が発覚。検査体制を改善するため、全6工場の出荷を1カ月弱停止し、生産や販売に影響が出た。一連の不正に絡み、国土交通省からは2度の業務改善指示を受け、今年3月には西川広人社長が石井啓一国交相に直接、「法令順守をさらに徹底していく」と、再発防止を誓ったばかりだった。
同様に無資格者による検査が発覚し、その後、排ガスデータの不正も明るみに出たスバルでは、責任を取る形で吉永泰之社長(当時)が6月の株主総会で社長を退いた。新たに不正が明らかになった日産でも、西川社長の経営責任が改めて厳しく問われることになりそうだ。(伊藤嘉孝、木村聡史)
田舎で生まれ育ったからこの手の話は理解できる。田舎で生まれ育った人達は井の中の蛙である傾向が高い。そして、生まれ育った地域で一生を
終える人達もいる。同じ日本人であっても違う価値観や体験を持った日本人達と深く接触する機会がなければ、知っている世界が全てなのである。
部分的には生まれ育った環境に影響されている、そして、部分的には他の世界や人々を知ろうとしないので、全て彼らが悪いわけではない。
言い方を変えれば、東京での生活や常識が日本の常識と勘違いしている都会人達は、ある意味で、逆バージョンの田舎の人達なのである。
自分達の価値観や常識が、正しいとは限らない。都会の良い部分と悪い部分を知り、田舎の良い部分と悪い部分を知った上で、個々の価値観や
優先順位でどちらを選択したいかだと思う。あと、いくら情報を集めて分析しても、想定外の出会い、予測できない人達との出会いで、
結果や印象が大きく違ってくる場合がある。運次第的な部分もある。
それらを含めてどう判断するのかだと思う。もし田舎の生活が最高であれば、なぜ、過疎化や人口減少が起きるのか?単純に都会に憧れる
若者が影響しているのかもしれないが、いろいろな理由があるからだと思う。
都会にも済んだし、海外にも住んだ。今は、田舎暮らし。田舎暮らしが良かったわけでもないし、満足しているわけでもない。ただ、
生活を変えるだけの気力や新しい生活を受け入れるだけの気力がないので、もうこのままでも良いかと思うだけだ。もしかすると、
生活する場所や仕事を変えるともっと幸福感を得られるかもしれないと思うが、必ず良い結果が出るとは限らない。
今の生活が嫌で嫌でたまらないのであれば、少しの好転でも満足できるし、新しいスタートを選択し、新しい環境を受け入れるだけの気力も生まれだろうし、
リスクを受け入れる決心が着くだろう。
リスクを受け入れ、新しいスタートを選択する事は選択である。リスクを選択しない人は良い結果を諦める、又は、悪い結果を避ける選択を選んだ事になると
思う。深く考えず、決断する人もいるが、運よく成功と考えられる人生を送る人もいる。最終的には結果次第。
都会育ちの人達の悩みと個人的に思う。
いま、田舎暮らしに憧れる人が、退職後にIターン、Uターンするシニアだけでなく、都会の若者にも増えています。しかし、都会暮らしの長い人にとって、田舎暮らしはいいことだらけではありません。旧態依然のムラの掟、想像以上にかかるおカネ、病気やケガをしても病院がない……。
実際、「移住すれども定住せず」が現実です。都会の人は、田舎暮らしをあきらめたほうがいいのでしょうか? 最近、『誰も教えてくれない田舎暮らしの教科書』を出版した移住歴20年のベテラン・イジュラーに、田舎暮らしの現実と、都会の人が田舎暮らしを満喫する方法を、実例をもとに語ってもらいました。
盛り上がる「地方創生転職」ブームにご用心
■天国だと思っていた憬れの地が…
子どもが産まれたら、人も土地も開放的なところで育てたい──。
東京生まれの東京育ちだった石沢友美さん(仮名)は、子どもを身籠もったと同時に、東京・吉祥寺から山梨県峡北地域のある集落に移住を決めた。3年前、32歳のことだった。
マンション育ちだった友美さん夫婦は、「空き家バンク」で見つけた築60年の古民家に移り住むことになった。友美さん自身が幼少期から憧れていた待望の「田舎暮らし」だった。
「自分が小学生の頃、八ヶ岳の林間学校に来たことがあったんです。その頃から、いつかは白樺を眺めながら鳥の声を聴いて暮してみたいって、ずっと思っていました。子どもができたときに主人に相談したら、やっぱり東京の真ん中、中央区で育った主人も大賛成してくれたんです」
古民家とはいえ、直前まで家人が住んでいたために、手入れは行き届き、生活に不便はまったくなかった。
「夏場になると、カメムシとかカマドウマとか、都会じゃほとんど見たことのない虫がとにかくどこから湧いてくるのか、いっぱい出てくるんです。だけど、それも高気密じゃない古民家ならではのよさと考えて我慢できました」
なによりも、眺望がすばらしかった。
背には標高2900メートルの赤岳を擁する八ヶ岳連峰が一望でき、右手に南アルプスの山並み、左手には富士山が見える場所だ。
日本のワンツースリーの眺望に囲まれ、移住人気ナンバーワンとも言われる場所であることが実感できた。
「子どもが産まれてからまもなくは、授乳に疲れてもその眺望を観れば、すぐに気分転換もできて最高だったんです」
夫は月に何度か新宿の本社に顔を出せばいい。新宿まではわずか150キロほど。中央線の特急でも、高速道路でも楽にアプローチできる距離だった。
「気持ち的には東京の郊外に住んでいるのとまるで変わらない距離で、日本で最高の眺望と開放的な空気が手に入るなんて。こんな天国みたいなところが日本にあったなんて、と思ったんです」
古民家の家賃も、吉祥寺の賃貸マンションに較べれば3分の1。それで、古民家とはいえ戸建てが借りられ、間取りの何倍も広い庭までついているのだ。
■有料のゴミ袋を購入したのに…
だが住み始めてほどなく、最初の“事件”に直面する。ゴミが出せないのだ。
移住に当たっては役所の窓口にも何度か足を運び、生活の仕方などをいろいろと聞いたつもりだった。だが、ゴミが出せない、というのはまさかの展開だった。
「高さは人の背丈ほどもあって、幅はそれこそプレハブ小屋並みの長さの立派なゴミ集積所があるのは知っていたんです。市の有料のゴミ袋を買ってそこに出せばいいものと、頭から考えてしまっていて……」
移住して間もなく、ゴミ出しに出向いたとき、目の合った人から「あんた、名前は?」と訊かれ、丁重にあいさつを返した。
するとほどなく、自宅に地元集落の役員だという初老の男性が現れたのだ。
「あれ(ゴミ集積所)は組(集落)のもんだから、組に入っておらんもんはあそこには出せん」
友美さんはこう応じた。
「では、ちゃんと会費をお支払いして組に参加させていただけませんか」
だが、組長(町内会長)と相談してきたという男性が再び自宅を訪れ、こう告げた。
「悪いけんど、組長がうちの組にはよそから来たもんは入れんっちゅうとるから」
「じゃあ、ゴミを出せないの? そんなバカなことって……」
呆然とした友美さんが役所に駆け込むと、それまで移住の相談に乗っていた担当者もそっけなくこう繰り返すだけだった。
「ああ、あそこの組長さんはもう……何を言ってもダメですから……」
〈えっ、なに? じゃあ、うちはあそこに住んでいる限り、もう地元でゴミを出せないってこと? 〉
聞けば、役所ではこうしたゴミ出しを拒否された移住者のために、役所の駐車場に特設のゴミ集積所を作っているという。
地域に住んでいる者が、有料のゴミ袋を購入しながら、ゴミ収集のサービスを受けられない。この状況に異議を唱えた友美さんに、役所の言い分はこうだった。
「集落のゴミ集積所は集落の私有地にある私有財産で、公共財ではないのでどうしようもできません。もし、移住の方が何世帯か集まって新たにゴミ集積所を作ってもらえれば、そこに回収には行きます。新たにゴミ集積所を作るに当たっては補助金も出しています」
「移住者こいこい、と謳う一方で地元でゴミひとつ出せない状況を変えられないのは役所の怠慢、不作為ではないのか。この時代に『あそこの組長は頑固だから……』で行政指導ひとつできない場所が、日本の移住人気ナンバーワンだなんてふざけたことを謳わないで欲しい」
友美さんはそう繰り返したが、担当者は「でも、あの組長はどうしようもない」と繰り返すばかりだったという。
後から知れば、その役所の担当者も、その頑固な組長を擁する集落の「若い衆」であったのだ。役所の人間である以前に、地元の若い衆であることが先に立つ。そうした土地では、まともな行政指導、行政サービスひとつ、地元の旧態依然とした因習の前には成立しないのだ。
そんな田舎特有の「暮しにくさ」や「ムラの因習」を、移住相談会や、役所の移住担当者らは、転入前には教えてくれなかった。地獄を見たのは、移住後、ということになる。
■質問しただけでブラックリスト入り!
友美さんを愕然とさせる“第二の事件”が勃発したのは、昨年の春だった。
子どもは無事に新天地で2歳を迎え、地元保育園に通うようになっていた。都会の待機児童問題などどこ吹く風。地方の保育園は、希望者はほぼ「全入」。それもまた田舎暮らしならではの良さとも感じた矢先のことだった。
保護者会の役員を引き受けることになった友美さんにさっそく、仕事がまわってきた。春の親子遠足の運営である。バス4台に親子と先生が乗って、広い公園へ1日かけて遊びにいくのだ。そのバスの乗車割り当て表を眺めていた友美さんは、あれっと思う。
本来、1号車に乗るべき園児の親御さんがなぜか、4号車に集められている─―。保護者会の執行役員らが全員そろって1号車に集中している─―。
気づいたその晩、保護者会長に電話をしてその主旨を告げたが、それが保護者会長ら執行役員の逆鱗に触れたのだった。
友美さんの意見は汲まれることはなかったが、親子遠足が無事に終わってほどなく、友美さんに「物申す」などと称して、会長とその側用人らしき執行役員の保護者が友美さんに「呼び出し」をかけたのだった。
いずれも集落生まれの集落育ち。当然、旦那も地元集落の若い衆である。
彼らは呼び出す直前、友美さんの夫の職業をあちらこちらで訊ねて回っていた。地方では役所、農協、警察署が「三大産業」であり、さらに言えば「官軍」。その他は“賊軍”さながら。夫の職業が「官軍」であれば、その女房をとっちめることは、日頃の商売や生活にも差し障ってくるのだ。女房の格は亭主の商売で決まってくると言わんばかりである。
友美さんの夫はITエンジニア。横文字の商売であることを確認したうえで「この集落では差し障らねえな」とでも踏んだのだろう。周辺を巻き込んでの騒々しい“身辺調査”を終えた執行役員らは友美さんを呼び出した末、結果、次のような実態を暴露するに至った。
地元保護者会では代々、陰に陽に保護者の「ブラックリスト」なるものを引き継ぎ、そこでは「厄介者」と呼ばれる夫婦が申し送りされていたのだ。
その「厄介者」がどれほど厄介かと聞かされた友美さんは仰天した。
「厄介者とされている人たちは、決していわゆるモンスターペアレンツとかクレーマーとはまったく違う、ごくごく一般的で常識的な人たちなんです。保護者会なんかで、手をあげて質問したり発言したりすると、一律『厄介者』と認定していくんです。田舎の集落は極めて狭いですから、保育園の面々がそのまま、小学校、中学校、場合によっては高校までそのまんま行きます。ブラックリストだ、厄介者だなんていわれた家庭は、ずっとそうして敬して遠ざけられるんです。実態は村八分です」
陰口で済むならば、まだましかもしれない。
友美さんが、この親子遠足で気づいた、本来1号車に乗るべき親御さんらがなぜか4号車に集められていた件。それは皆、執行役員らがいうところの「厄介者」であったから驚かされた。
そんな露骨な差別を……。開いた口がふさがらなかった。
■洗濯物の内容まで、生活のすべてを見られている
集落は夏祭りの準備に消防団の集まりと、夏場にかけて参加強制の作業が目白押しだ。仮に組や区などの町内会に入れたとて、仕事を理由に毎月の定例会などに参加できないと、1回の欠席当たり数千円の「罰金」を払わされる。
友美さんの友人で、やはり東京から集落に移住してきた30代の和子さんなどは、夏祭りでは地元婦人らの、まるでパシリである。やれ飲み物を買ってこい、あれ運べ、これ運べの傍らで、地元婦人らは手ぶらで悠々の光景を嫌というほど見てきた。
「まるで、時代遅れのスケバングループ? ですか」と、友美さんはそう爆笑する。
「でもね、あたしもあのまま集落にいたら、今はこうして笑い話なんかにはできないですよ。だって、地域の掟に背いたら、それこそ村八分でしょう。それがリアルな場所では反抗なんかできないですよ、こわくて」
もちろん、都会のPTAにもイジメはあるし、気の合わない保護者同士の嫌がらせだってさんざんある。でも、田舎、こと集落は都会と違って逃げ場がない。上下関係、優越意識にそれこそ死ぬまで従わされかねない。それが怖いから、若い世代にも強力な同調圧力をもたらすのだ。
友美さんに笑顔が戻ったのにはワケがある。
集落で数々の恐怖体験をした末に、友美さんはやはり移住者夫婦の紹介で、わずかな距離にある、移住者が多い別荘地域に転住したのだ。そこには大阪や東京から来て子育て、田舎暮らしを満喫する多くの移住者が集まって住んでいる。
ゴミ出しはもちろん大丈夫だし、なにより「もの申す」などと称して人気の少ない神社の境内や公園に呼び出されることもなく、「厄介者」などという時代錯誤の暗い表現などとも無縁の新天地だ。
「ほんとに転住してよかった」と、友美さんはいう。
「古民家にいるときは、今日は洗濯物が干してあったな、今日は少なかったなとか、縁側に干してある洗濯物の内容から量まで、集落の皆が皆、そんなのを全部見てて、見てても黙ってればいいのに、それをまた全部、会うたびに言葉に出すんですよ。車があれば、なんで晴れてるのに家にいる、車がなければ、どこに行ってたって。誰かの親が遊びにくれば、菓子折を持って行くふりして、どんな親か様子を見てこい、ですからね。都会暮らしを経験した人が、そんな習慣のなかで生きるのは大変なストレスだと思いますよ」
そんな実態を、役所の移住担当者はおろか、田舎暮らしの本や、テレビの移住番組なんかでは教えてくれない。
「よかったですよ、集落を出て。だって子どもが大きくなると、組に入ってない家の子どもはお祭りにも参加できないんですから。お祭りは組のものだから。ゴミと一緒ですよ」
不都合な真実は決して教えない、移住礼賛、田舎暮らし礼賛とは、いかに罪深いものだろうか。
■集落移住にはもう懲り懲り
友美さんは今、ようやく集落の目を気にせず、別荘地のなかで東京や大阪からの、さらに地元出身でありながら、やはり集落暮らしは耐えられないと別荘地域へと転住してきた同世代の友人夫婦らと、週末は楽しく、心豊かな日々を過ごしている。
そこには、因習悪弊とは無縁の、心から望んだ田舎暮らしの開放的な空気が満ちているという。
友美さんの転住先では、夕方にはフクロウが鳴き始める。そんな声を聞きながら、バルコニーで野菜を調理しご主人と缶ビールを開ける。夜は隣家を気にすることなく月明かりに浮かぶ、南アルプスから富士山へと連なる稜線を眼下にハンモックに揺られる。明日への気力が漲る瞬間だという。
これこそが、都会で夢描いていた田舎暮らし、であろう。今はただ、田舎暮らしを考えたかつての瞬間に、もっと早く「不都合な真実」を教えてもらえていれば、と思うだけだ。田舎暮らしが一大ビジネスになってしまっている今、それは誰も教えてくれない。自分自身でもがいた末に理想の田舎暮らしを得た友美さんは今、こう考えている。
「もう少ししたら、近くにもう一軒買って、都会の両親を呼び寄せてもいいかな」
もちろん、集落移住にはもう懲り懲りだ。
清泉 亮 :移住アドバイザー
待遇が良すぎるとは思うが、オファーする側が出世払いというか、将来に見返りがあると考えているのなら納得できる事である。
ただ、借りが後で大きな負担となる、又は、感じる場合があるので、個人的には借りをあまり作るべきではないと思う。
王室を持たない米国は、つくづく「ロイヤル」の冠に弱いようだ。
〈ケイ・コムロ、プリンセスマコの婚約者が入学へ〉
【写真】眞子さまと明暗?絢子さまの婚約者の守谷慧さん
7月5日、米フォーダム大学ロースクールがホームページの「ニュースルーム」にこんな見出しで始まる文章を掲載した。
年間5万500ドル(約660万円)の学費は奨学金により全額免除する、と書かれている。
海外事情に詳しい八幡和郎氏はこう話す。
「海外の大学では、個人情報という概念が薄いので、王室のメンバーが入学するなど学校の宣伝になる情報をHPにアップすることは、珍しくありません」
小室圭さん(26)は、皇室のメンバーでもない一般人。加えて、一般の婚約にあたる「納采の儀」が延期された状態で、まだ婚約者ですらない。大学側の前のめり感は、否めない。
おまけに、これまでフォーダム大学における返済義務のない奨学金は、年間2万ドル(約220万円)の枠だけであった。ところが、ホームページには、「100%学費免除を受けられる新しい奨学金」として今回、小室さんが給付される「Martin Scholarship」の説明がアップされていた。
そして年間300万円を超える寮生活費や教科書代についても、小室さんが、パラリーガルとして勤務する都内の法律事務所が支援することが決まっている。重なる「王子さま待遇」に、驚きを隠せないといった様子で話すのは、ニューヨーク州の弁護士資格を持つ、日本人の国際弁護士だ。
「日本の弁護士資格を持たない小室さんが、米国の州の司法試験を受験しようとすれば3年間のJulias Docter(JD)の法務課程のコースで学ぶ必要がある。所属する弁護士の学費と生活費を支援する弁護士事務所は、いくらでもありますが、事務職員のパラリーガルを3年間も支援する例は、極めて異例ですよね」
パラリーガルとして勤務する小室さんの仕事は、英語の書類の翻訳や弁護士の仕事のアシスタントといった事務職で、年収は300万円程度だとみられる。
事務所は給与をそのまま支給し、それが生活費に充当されるのだろう。
「米国のロースクール時代の同級生のなかには、霞が関の官僚や研究者や弁護士など日本人もいましたが、公務員の留学は2年が限度ですし、外国の弁護士ならば1年間の課程で司法試験を受験できます。ビジネスパーソンで、3年間留学する、一般の日本人に、個人的には会ったことはありませんね」(前出の国際弁護士)
所属法律事務所が小室さんへかける期待値の高さを物語っているようだ。
偶然なのだろうが、小室さんの勤務先の法律事務所の所長は、秋篠宮さまが名誉総裁を務めるWWF(世界自然保護基金)ジャパンの理事を務めており、知らない仲ではない。
だが、このやや強引とも思える「王子さま待遇」について、首をかしげる宮内庁関係者も少なくない。
たとえば、秋篠宮家は、学校など教育の場において、皇族であろうと、「特別扱いさせないでください」と学校側にも伝えてきた。長女の眞子さまも佳子さまも大学受験は、一般と同じ条件で挑戦している。佳子さまに至っては、現役時に他大学を受験したが、不合格になっている。
「小室さんには秋篠宮邸への出入りに、ハイヤーを使わせるなど、不自然なほどの特別扱いが、宮内庁内でも不興をかっていたのは、事実です。さらに、フォーダム大学がわざわざ眞子さまの婚約者と小室さんの留学をインフォメーションしたやり方にも違和感がありますし、重なりすぎる『特別待遇』についても同様です。秋篠宮両殿下が、ご存知ないところでことは運んだのでしょうが、しかし、宮家にとってよい風評にはならないのではないでしょうか」(宮内庁関係者)
一昨年夏の、眞子さまと小室さんの、婚約内定の記者会見。ふたりのメッセージのなかで、小室さんを「太陽」に、眞子さまを「月」に例えたことや、日付を元号ではなく西暦を使ったことに対して、他の宮家が、眉をひそめたとも言われる。
3年間の留学ののち、再び日本に戻り、同じ法律事務所で勤務する予定の小室さん。眞子さま描く未来予想図は、なにやら霧が晴れないままである。(本誌・永井貴子)
※週刊朝日オンライン限定記事
人間が人間である以上、不正はなくならない。ただし、不正が発覚した時に厳しく調査し、処分する事は出来る。
どれだけ腐敗やダブルスタンダードが社会構造や社会常識の中に浸透しているか次第で調査や処分に差が出てくると思う。
鳥集 徹
7月4日、文部科学省科学技術・学術政策局長(解任)の佐野太容疑者(58)が、私立大学支援事業の選定を見返りに、自分の子どもを東京医科大学に合格させたとして、受託収賄容疑で東京地検特捜部に逮捕された。
辞任した東京医科大学の理事長、学長も含めた組織ぐるみの「不正入試」が明らかになる中、長年、医療問題を取材し、今年3月に 『医学部』 (文春新書刊)を上梓したジャーナリストの鳥集徹氏が緊急寄稿した。
医学部入試をめぐり、トンデモない事件が起きました。
教育機関の不正を監督・是正する立場である文科省のエリート官僚が、自分の職権を悪用して自分の息子を医学部に「裏口入学」させるとは、開いた口がふさがりません。
近年、医学部入試はどこも超狭き門となっており、かつて「金さえ積めば入れる」と揶揄されたような新設の私立医大でも、早慶の理系学部に合格できるぐらいの学力がないと入れなくなりました。
戦前の旧医学専門学校の流れを汲む伝統校である東京医大も例外ではなく、昨年の全入試倍率も10倍以上でした。厳しい受験勉強に耐えてやっと合格した人も、合格できずに悔しい思いをした人も、真正面から東京医大に挑んだ人はみんな腹立たしい思いでこのニュースを見たのではないでしょうか。
金を積んで入学した学生たちの末路
この不正入試には、大学の理事長、学長を含めた複数の人物も関係していたと伝えられています。人の命を預かる医師を育てる医学部で、このような不公正かつ非倫理的な行為が横行するのは許せません。ぜひとも不正入試の実態の詳細な解明が進むことを期待します。
それにしても、今どき医学部入試で裏口入学があるなんて、驚いた人も多かったのではないでしょうか。医療現場を長く取材してきた私も驚きました。というのも、拙著『医学部』の取材で、ある私立大学の医学部名誉教授や現役の医学部長などから、こんな話を聞いていたからです。
「かつて、医大が点数の足りない受験生の保護者に金を積ませて、合格させるような不正が横行していたのは確かです。しかし、今のご時世、そんな不正がバレたら大きな社会問題になりますよね。大学側としても、信頼を失墜させるリスクを負ってまで、学力の低い学生を取りたくありません。
なぜなら、成績不良の学生を入学させたとしても、結局は大学の授業についていけず、医師国家試験(国試)にも通らないからです。むかしも国試に通らない学生はいました。彼らは親の病院の事務長かなにかになったのではないでしょうか。でも医学部に入ったのに医者になれなかったなんて、恥ずかしくて言えませんよね。
多額の寄附金や授業料も全部、無駄になってしまいます。教授会でもそういうことが問題となり、うちの大学では入試の不正はなくなっていきました」
成績によって入学金や寄附金の額が変わる
医学部の裏口入学が社会的に大きくクローズアップされたのは、田中角栄内閣の「一県一医大構想」によって新設の医科大学が次々に設立された70年代から、その後の80年代のことでした。
一県一医大構想は医療の地域格差の解消が主な目的でしたが、新設された私立医大には「開業医の跡継ぎを育てる」という裏のミッションもありました。とはいえ、開業医の子どもたちみんなが、学力が高いわけではありません。そのため、「点数が低くても多額の寄附金を払えば入学を許す」、逆に「点数が高くても一定以上の寄附金を払えない人は門前払いする」ということまでが横行していたのです。
その当時の様子を、ある新設医大の医学部名誉教授が次のように証言してくれました。
「むかしは、成績によって入学金や寄附金の額が違うことはザラでした。たとえばA君の成績なら500万円だけど、Bさんは点数が足りないので1000万円、C君は1500万円なら入学OKという具合です。当時はウチだけでなく、私立大学はみんなそんな感じで、それが当たり前だと思っていたんですね」
しかし現在では、たとえお金で下駄を履かせてもらって医学部に入ったとしても、学生本人が必ずしも幸せになれるとは思えません。なぜなら、2001年に医学部の教育カリキュラムが改革されたために、医学部の勉強がとても大変になったからです。ある大学の医学部長によると、かつてに比べて6年間に学ぶ内容が2倍以上にもなり、国試も格段に難しくなったそうです。
そうしたこともあって、勉強についていけない学生が大量に留年・転部したり、国試浪人が100人単位で溜まっている私立大学もあります。お金で下駄を履かせてもらったとしても、最低限の学力がなければ医師になれないどころか、卒業も危ういのが今の医学部の世界なのです。
それに、まわりは正々堂々と入試を突破して医学部に入った人ばかりなのに、裏口から入った学生本人にとっても、本当にそれでいいのでしょうか。入学後に真面目に勉強して医師になったとしても、厳しくプロフェッショナルとしてのモラルが問われ続けるのが医療界です。一生、心に闇を抱えて、生きていかなくてはいけません。
昨年、耳にしていた不正入試の「噂」
このように、「金権入試」が横行していた昔とは大きく様変わりしたので、私も医学部の裏口入試はほとんどないだろうと考えていました。ただ、昨年『医学部』の取材を続ける中で、こんな噂も耳にして、本に書いていました。
「(一部の私立大学では)理事長が入試担当の教授に、特定の受験生に(点数の操作しやすい)小論文と面接で下駄を履かせるよう言ってくる」
その噂の大学こそ、どうやら東京医大のことだったようです。同大での不正入試はこの1件だけだったのか。さらには、これは氷山の一角で、実は他にも不正入試に手を染めている大学があるのか……。事件の進展によっては、医学部入試全体の総点検も必要となるかもしれません。医学部や医療界の信頼を損ねないためにも、ぜひここで膿を出し切ってほしいと思います。
辞任と言う事は処分を受ける前に逃げたのか?
それともトカゲのしっぽ切り?
日本大アメリカンフットボール部の選手による危険なタックル問題で、日大は6日、同部OBの井ノ口忠男理事が4日付で辞任したと発表した。日大が設置した第三者委員会(委員長=勝丸充啓・元広島高検検事長)は、危険なタックルの指示について複数の人物が学生に口止めしていた事実を明らかにしたが、大学関係者によると、井ノ口氏は口止めした一人だという。
6日に開かれた日大の理事会で、執行部が辞任を報告した。理由については「(大学内外に)ご迷惑をかけた」と説明があり、田中英寿理事長が出席者に一連の騒動に関して謝罪したという。
井ノ口氏はアメフト部の内田正人前監督(62)に近く、田中理事長の側近としても知られている。日大が100%出資し、各学部や付属校などへの物品納入などを行う関連会社「日大事業部」の運営も実質的に任されていた。
役員が関与しているのが事実であれば、この幹部を銀行から排除するべき。また、米山明広社長がこの事実を知っていたのであれば
社長にも退陣してもらうべきだ。
金融庁がスルガ銀行をどこかの銀行の傘下に入れるなどして終わらせるのであればそれも良いであろう。
スルガ銀行(静岡県沼津市)によるシェアハウス向け不正融資問題で、営業担当の役員(当時)が融資申請書類の改ざんを主導した疑いが強いことが明らかになった。審査部門の役員も不正を把握しながら融資拡大に協力し、経営トップらに虚偽の説明をしていたとみられる。金融庁は組織ぐるみの不正が横行していたとみて、一部業務停止命令を含む厳しい行政処分を検討している。
本店幹部ら複数のスルガ銀関係者が明らかにした。不正融資問題を調査している第三者委員会(委員長・中村直人弁護士)は7月末をめどに報告をまとめる方針で、こうした構図を認定するとみられる。
関係者によると、個人向け融資の営業を当時担当していた元役員は、スマートデイズ(東京)などが運営するシェアハウス用の不動産の購入者について、販売業者と協力して融資の手続きを進めるよう窓口の支店に指示。融資審査を通りやすくするため支店長らに預金残高や年収を水増しすることを促し、審査を担当する役員には改ざんを見逃すよう強く要求したという。
当時の副社長は、シェアハウス向け融資の急拡大を疑問視していたが、審査担当役員は、預金残高などを改ざんした申請書類や、収益見通しを高く偽った報告書を提示するなどして決裁を取り付けていたという。
スルガ銀は5月に発表した内部調査報告書で、「営業部門の幹部が融資に難色を示す審査部の担当者を恫喝(どうかつ)していた」と指摘。しかし米山明広社長は組織的不正を否定していた。スルガ銀によるシェアハウス向け融資は3.5~4.5%と高金利で、2018年3月末時点で融資残高は約2035億円に上っている。【鳴海崇】
医療関係の組織で人の命に係わるのに体質に問題があるのはとても危険だ!
受託収賄容疑で逮捕された文部科学省科学技術・学術政策局長の佐野太容疑者(58)の子どもを、不正に合格させたとみられている東京医科大(新宿区)では、過去にも不祥事が相次いで発覚した。同大関係者は「体質は変わっていない」と指摘している。
「恥を知れ」「フェアに」=学生から怒りの声-東京医大
同大をめぐっては2004年、心臓手術を受けた患者が死亡した医療事故が表面化。以降、生体肝移植での高い死亡率や、診療報酬の不正請求、学位審査をめぐる金品授受などが立て続けに明るみに出た。学内の対立を背景に、学長が長期にわたり不在になった時期もあった。
同大は10年に第三者委員会を設置。委員会は同大の体質が不透明だと厳しく批判し、抜本的な改革を求めた。同大関係者は「委員会の提言は取り入れられなかった」と振り返る。
この関係者は「体質が変わらない方がいいと考えている人たちがいる。今回の問題でも、学内の自浄作用は働かないのではないか」と批判した。(
日本通運は4日、非常時に供給するために政府が備蓄するコメの保管を巡り不正行為があったと発表した。同社広島支店の社員が2014年から16年にかけ、保管中に外装が水にぬれたり破れたりした政府米計266袋を新しい袋に詰め替え、偽造した検査印を押印。事故を隠蔽していた。
このうち外装がぬれた15袋は飼料用米として16年に出荷したが、主食用としては流通しておらず健康被害の報告はないという。
検査印の偽造については農産物検査法に違反する可能性があり、農林水産省が調査している。
日通によると、14年6月に倉庫での保管中に雨漏りで外装がぬれた12年産政府米計450キロが入った15袋について、広島支店の社員が新しい袋に詰め替えた上、偽造の検査印を押印。15年2月と16年9月ごろにも、保管中の荷崩れなどで紙製の包装が破れた14年産政府米7530キロが入った251袋で同様の不正行為があった。
251袋は日通が保管しており、同じ倉庫内の他の政府米と合わせ計4万3854袋を焼却処分する。
この問題を受け農水省は5月末、政府米の保管や運送を日通に委託していた三菱商事に業務改善命令を出した。同社は7月2日付で同省に再発防止策を報告した。
日通や三菱商事は4日、「社会と関係の皆様に深くおわびする」(日通)などと謝罪。管理手法の見直しや社員教育などで再発を防ぐとしている。
「15年2月と16年9月ごろには、日通が保管を委託した同県内の業者の倉庫で、14年産米約7500キロが入った米袋約250袋に破損やネズミの被害が見つかった。営業課長らは業者とともに新たな袋へ詰め替え、偽造印を押印したという。」
処分されても仕方がない行為を行ったと思う。
非常時の供給用として政府が備蓄する米の保管を請け負う日本通運(本社・東京)が、水ぬれやネズミの被害に遭った米袋をひそかに取り換え、一部を出荷していたことがわかった。新しい米袋には偽造した検査証明印を押印していたといい、農林水産省が農産物検査法違反の可能性があるとして調べている。
問題があったのは国産玄米約8千キロ分。三菱商事を通じて農水省から管理を請け負った日通が自社や委託先の倉庫で保管していた。
日通によると、2014年6月、広島県内の社有倉庫で保管中の12年産米450キロが入った15袋の紙製米袋が、雨漏りでぬれた。広島支店の営業課長らは、上司や農水省に報告せず、事故を隠蔽(いんぺい)するため新しい紙袋に中身の米を詰め替えたという。さらに、米の等級などの検査をしたことを証明する印章を偽造し、新しい袋に押印。15袋は16年5~6月、飼料用として出荷された。
15年2月と16年9月ごろには、日通が保管を委託した同県内の業者の倉庫で、14年産米約7500キロが入った米袋約250袋に破損やネズミの被害が見つかった。営業課長らは業者とともに新たな袋へ詰め替え、偽造印を押印したという。
この業者から今年3月に指摘を受けた日通は、関係者への聞き取り調査を実施。出荷した15袋分については「中身の米はぬれていなかった」と説明があったという。約250袋分は出荷されておらず、すべて焼却処分するという。(田内康介)
田内康介
政府の備蓄米を管理していた日本通運で、保管中の事故の隠蔽(いんぺい)が行われていたことが明らかになった。非常時には食用となる備蓄米の管理には、高い安全性が求められる。日通は「社会や関係する皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げます」と謝罪した。
政府は非常用として、90万~100万トンの国産米を民間の倉庫などで備蓄している。保管を始めて5年ほどの間に使わなければ、飼料用などとして販売する。日通は、雨漏りでぬれた米袋の中身を、別の米袋に詰め替えて出荷していた。
今年4月、日通側から問題の報…
正直なのか、大学の教授の中には頭が良くても常識がない人が含まれているのか、もっと情報がないと判断できない。
短文投稿サイト「ツイッター」で、香川大学の教授が投稿した「セクハラ」発言がインターネット上で波紋を呼んでいます。この教授がKSBの取材に応じ、発言を認めました。
問題になっているのは、香川大学に勤務する実在の教授の氏名に「じゃないかも」と付け足されたアカウントから投稿された一連のツイートです。
中でも今年4月の「僕の趣味はセクハラです。気持ちいいじゃないですか」「女の子の肌を触るのが好き」といった投稿は、現在インターネット上で大きな波紋を呼んでいます。
この教授は3日、KSBの取材に対して「自分が投稿したものだ」と認めました。
その上で、「財務省の前事務次官によるセクハラ問題を受け、国会議員が『セクハラはしません』と宣言していることがナンセンスだと感じ、反発した。研究者として表現の自由が守られるべきだ」と主張しました。
香川大学の筧善行学長は「教育上の観点から不適切な内容であり誠に遺憾。学内規則などに照らして、適切に対処を行うとともに再発防止を徹底する」とコメントを発表しました。
技能実習生制度が隠れ蓑に使われているケースが多くあると推測する。
三菱自動車岡崎製作所でもこのような状態であれば他の会社はもっと問題がある可能性が高い。
技能実習生を労働者として見ている限り、根本的な問題は解決しない。まあ、制度が技能実習を大義名分として労働者を確保する事を
含んでいれば、問題は解決しないであろう。
三菱自動車岡崎製作所(愛知県岡崎市)がフィリピン人技能実習生に実習計画外の仕事をさせていた問題で、三菱自は3日、実習生24人が途中で実習をやめ、週内に帰国すると明らかにした。本来の実習期間である来年2月まで働いたと見なし、基準給与相当分を補償したという。総額は明らかにしていない。
三菱自によると、途中帰国する24人は「溶接」技能を学ぶ目的で2016年2月に入国した。だが、このうち20人は溶接作業がない職場に配属され、車の組み立て作業などをさせていた。残りの4人は溶接ができる職場だが、「同じ時期の入国で連帯意識が強い」といい、一緒に帰国してもらうことにした。
三菱自には他に、溶接技能の習得を目的とする実習生が13人おり、溶接が学べない職場にいるが、溶接作業のある他の企業へ移籍させるという。これで、三菱自にいる65人のうち、残るのは主に「塗装」技能を学ぶ28人になった。実習生を途中帰国させる事態となり、三菱自は今後の実習生の受け入れについても見直しを検討している。
国認可の監督機関「外国人技能実習機構」は「技能実習制度の適切な運営のため、計画外の作業事例は指導する。三菱自の実習生の途中帰国についてはコメントを控える」(企画・広報課)としている。(前川浩之)
たぶん氷山の一角で運悪く「技能実習計画認定初の取り消し」となったのであろうが、自業自得!
働きながら技術を身に付ける「外国人技能実習制度」をめぐり、法務省と厚生労働省は3日、昨年11月に施行された技能実習適正化法に基づき、愛媛県宇和島市の縫製会社「エポック」の技能実習計画を取り消した。取り消しは同法施行後初めて。同社は今後5年間、技能実習生の受け入れができなくなる。
法務省によると、エポックは今年2~4月、短期滞在の資格で入国した中国人2人を不法に縫製工場で働かせていた。5月に入管難民法違反の罪で罰金30万円の略式命令が確定している。
技能実習適正化法では、技能実習生を受け入れるためには技能実習計画の認定を受けなければならず、不法就労させるなどして有罪が確定すると、計画を取り消すことができると定められている。
エポックでは3人の技能実習生が実習を受けていたが、1人は別の会社に移って実習を続けるという。
技能実習制度は、技術移転のために外国人に日本の技術を学んでもらうことを目的としているが、外国人を「安い労働力」としか捉えない会社が多かった。このため、受け入れ側の監督強化などを柱とした技能実習適正化法が昨年11月に施行された。
「関東学生連盟の監事で、日大アメフト部問題の報告書をまとめた1人、寺田昌弘弁護士は『みんな一丸となり、同じ方向をめざす上意下達の軍隊的なメンタリティーは、戦後の復興や高度経済成長には効果的だった』という。」
「みんな一丸となり、同じ方向をめざす上意下達の軍隊的なメンタリティー」は結果を出す事が優先であれば問題ない。個々が違う方向に向かうよりも
力学的に考えても同じ方向に、同じタイミングで力が加えれれば結果は明らかに違う。精神的なメリットが重なれば、もっと良い結果が出せるであろう。
ただ、皆をまとめて同じ方向に向かうのは簡単ではない。立派なリーダーやカリスマ性を持つトップが不在であれば、かなり難しい。
立派なリーダーやカリスマ性を持つトップが不在でどうしてもある方向に向かわせたければ、反対するものをねじ伏せ、反対するものを排除し、
権力、金、恐怖、恫喝などの方法で目的を達成しようとする。
このようなケースは現在では受け入れられなくなっている。本人が望んでいる、又は、望むように洗脳されていれば、会社にとっては会社人間が都合が良い。
会社が最優先で判断や選択が行われる。会社にゆとりがあり、努力と自己犠牲に応えるために会社員達が望む元をリターンすれば、ギブアンドテイクで
会社員達は会社人間になった選択を間違いとは感じない傾向が高いであろう。
社会の価値観が変わったり、ギブアンドテイクと考えられなくなると会社人間になった選択を疑問に思ったり、拒否反応を見せると思う。
日大が変わらなければ、今回の件を問題と思う人達が終わらせればよい。多くの人々が同じ考えであれば、日大の衰退は目に見える形でわかると思う。
波聞風問
「アメフト部の悪質タックル問題、君はどう思う?」。採用面接で聞かれる日本大の4年生たちに、ある学部の就職指導の担当者はこうアドバイスしているという。「『第三者委員会の報告書をみてください』と答えて」
就活生を気づかったわけではあるまいが、日大の第三者委は6月29日、中間報告書を発表した。日大の選手が関西学院大の選手に危険なタックルをしたのは、前監督と前コーチの2人による指示だったとようやく認定した。
遅きに失した感もある。約1カ月前、日大アメフト部が所属する関東学生連盟は調査報告書を出している。「相手を潰すんで、試合に出してください」と申し出た日大の選手に対し、前監督は「やらなきゃ意味ないよ」と答えた。この言葉を「立派な指示」と断じ、関東学生連盟は前監督らを除名処分にした。
上の指示が認められるのは珍しい。不祥事の幕引きを図る報告書の多くは、知りたい肝心の部分はあいまいにしてすませるからだ。
たとえば、公文書改ざん問題をめぐる財務省の調査報告書は、森友学園との応接録の廃棄についての「指示」をこう記している。
当時の理財局長は、国会で「交渉記録はない」「行政文書の管理ルール通り対応している」と答弁した。その後で部下の総務課長に「文書管理の徹底を念押し」した。ルールは保存期間を1年未満と定めていたため、総務課長は「適切に廃棄するよう指示されたものと受け止めた」。
「廃棄しろ」とはっきり言ったわけではない。ただ、「空気を読め」とばかり、個人に同調を求める圧力が組織ぐるみの暴走につながっていった。「悪質タックル」はひとごとではない。
3年前、東芝の不正会計問題に対する第三者委の報告書は、経営トップが「チャレンジ」という表現で、決算数字の改善を求めたと指摘した。「東芝には上司の意向にさからえない企業風土が存在していた」。その「意向」に従った幹部や社員たちが、目標達成のために不正な会計処理をひたすら続けていた。
関東学生連盟の監事で、日大アメフト部問題の報告書をまとめた1人、寺田昌弘弁護士は「みんな一丸となり、同じ方向をめざす上意下達の軍隊的なメンタリティーは、戦後の復興や高度経済成長には効果的だった」という。
「成功したワンマン経営者の会社には、そのメンタリティーが風土として根づいていることが少なくない。だが平成も終わる現代では、もはや通用しない」。よしあしの見境なく、場の雰囲気を忖度(そんたく)させる風土が変わらないと、組織は再び暴走する。
日大の第三者委は大学のガバナンスの問題も調べる。部活の問題にとどまらず、ワンマンのトップを生んだ巨大組織の病理にまで、7月中にまとまる最終報告書は斬りこめるのだろうか。(編集委員・堀篭俊材)
日本大アメリカンフットボール部の選手が関西学院大の選手に試合で危険なタックルをした問題をきっかけに、さまざまな問題が噴出、日大のドン田中英寿理事長の進退問題も取り沙汰されていた。
そんな中、アメフト問題で設置した日大の第三者委員会(委員長・勝丸充啓弁護士)が6月29日、都内で記者会見し、中間報告を発表した。
【中間報告会見の様子】
「このタックルは内田正人前監督と井上奨前コーチの指示で行われたものである」とようやく事実認定したものの、ドン田中理事長については触れずじまい。記者から田中理事長のヒアリングはしないのかと突っ込まれると、歯切れ悪くこう答えた。
「学長も理事長もまったく無関係ということではございません。しかしながら、基本的に組織ラインとしては運動部のラインは学長のライン。理事長のラインは人事とか経営でまたラインが違う」(勝丸委員長)
中間報告を見たアメフト部員はこういう。
「内田前監督、井上前コーチの指示が認定されたのはよかった。内田前監督、井上前コーチの好き勝手な振る舞いはずっと以前からあった。それで他の大学に転校を余儀なくされた部員までいた。それを放置してきた学長、理事長ら大学の責任はないのか? 内田前監督の理事長べったりは部内でも有名。直立不動で携帯電話で喋っていて珍しいなと思ったら、相手が田中理事長だったことも。今回の事件、社会問題に発展し、就活などにも影響が出ていて、アメフト部だけじゃない。日大全体にかかわるものだ」
第三者委員会はアメフト部員約140人に対し、アンケートを実施し、内田前監督、井上前コーチから危険タックルの指示の有無などを尋ねたが、田中理事長に関する項目はなかったという。
「今回の問題で田中理事長に責任があるか、という設問があれば、みんな、あると答えたはず。内田前監督らの暴走は田中理事長がお墨付きを与えていたからです。理事長に責任は当然ある」(前出のアメフト部員)
日大経済学部OBもこう疑問を呈する。
「アメフト問題の根本は、田中理事長が自分のお気に入りの取り巻きを作ったことにある。側近の内田氏を抜擢し、人事担当の常務理事に据え、日大の体育会系の部を束ねる保健体育審議会の局長にした。その内田氏が暴走した結果、タックル問題が起こった。やっぱり田中理事長の責任も大きいと思います」
日大の非常勤講師の雇い止め問題を告発した、首都圏大学非常勤講師組合の日大ユニオン準備会代表で、日大ドイツ語講師の志田慎氏はこう語る。
「アメフト問題は氷山の一角なんですよね。日大の中で同じようなパワハラとか、下の者に責任を押しつけて上の者は知らん顔をするということが、至るところにあるわけですよ。トカゲのしっぽ切りでいいのか。雇い止め問題とアメフト問題の根源は同じなんです。私たちは最終的には田中理事長と闘っています」
田中理事長が会見を開かず、マスコミから逃げているのには理由があるという。
「彼は相撲部出身で、ごっちゃんの世界なんですよ。それに、大勢の人を前にしゃべるのが大の苦手。もともと大学のトップに立つ人じゃないんですよ。それなのに、彼がなぜ権力を持ったのかというのはその背景に何があるかということを見極めていかないといけません」(日大元教授)
ドンの座を降りる日は来るのか。(本誌・上田耕司/今西憲之)
※週刊朝日 2018年7月13日号より加筆
日本大学アメリカンフットボール部の重大な反則行為をめぐる問題で、原因の究明を行う日大の第三者委員会は29日、中間報告を行い、反則行為が内田正人前監督らの指示で行われ、けがをさせる意図が含まれていたと認定したうえで、問題の発覚後に「日大関係者が学生に不当な圧力をかけてもみ消しを図ろうとした」と指摘しました。
この問題は、先月行われた日大と関西学院大学の定期戦で、日大の選手が相手選手に後ろからタックルする重大な反則行為してけがをさせたもので、関東学生連盟は内田前監督と井上奨前コーチを除名処分にしました。
この問題について、元検事などで作る日大の第三者委員会は29日、都内で中間報告の記者会見を行い、選手などおよそ150人へのアンケートや聞き取りなどから、タックルは内田前監督や井上前コーチの指示で行われ、相手選手にけがをさせる意図が含まれていたと認定しました。
アンケートでは、回答があった120人のうち104人が、試合後のミーティングで内田前監督が「あのプレーは俺が指示した。俺が責任をとる」などと発言したのを聞いたと答えたということです。
一方で、問題の発覚後、日大関係者が選手に内田前監督の指示と話さないよう求めたとして、「不当な圧力をかけてもみ消しを図ろうとした」と指摘し、第三者委員会は見過ごすことができない事実だと非難しました。
アンケートで、反則をした選手の説明と前監督や前コーチの説明はどちらが正しいと考えているか聞いたところ、前監督らの説明が正しいと答えた人は1人もいなかったということです。
また、内田前監督は勝利至上主義のもと、ふだんから反則行為を容認するかのような指導を行っており、ほかの選手にも似たような指示が繰り返し行われていたと指摘しました。
第三者委員会は今後、日大の幹部からも聞き取りを行い、大学内の統治の在り方を検証するとしていますが、田中英壽理事長を調査の対象とするかについてはコメントを避けました。
第三者委員会は来月末をめどに再発防止策を盛り込んだ最終的な報告をまとめることにしています。
日大「深くおわび申し上げます」
日本大学アメリカンフットボール部の重大な反則行為を巡る問題で原因の究明を行う第三者委員会が29日、中間報告を行ったことを受けて、日本大学は「本学職員による反則行為の指示が存在したことは誠に遺憾であり、被害選手、保護者および関西学院大学アメリカンフットボール部の関係者の皆様、並びに反則行為の指示を受けた本学の選手および保護者に対し深くおわび申し上げます」とするコメントを発表しました。
そのうえで、「中間報告書において認定された事実関係等を尊重し、これを真摯に受け止めるとともに引き続き第三者委員会による調査に全面的に協力して参ります。中間報告書で指摘された事後対応上の問題点についても真摯に受け止め、本学のガバナンスのあり方について迅速かつ適切に検討して参る所存です」とコメントしています。
立命館大アメリカンフットボール部が通学路見守りをどのくらい継続するかで、単なるイメージアップのパフォーマンスなのか、
何らかの信念や考えておこなっているのか判断できるであろう。
日大アメリカンフットボール部がいろいろな善意ある活動や行為をおこなっている記事を頻繁に目にするが、試合が早くできるように行っている
パフォーマンスに思える。
立命館大アメリカンフットボール部と男子バスケットボール部の学生たちが、南笠東小(滋賀県草津市南笠東4丁目)の通学路で、登校する児童たちの見守り活動を続けている。屈強な学生たちは「子どもたちから元気をもらえる。目が届きにくいところまで気を配りたい」と安全を願い、交通量の多い道路や横断歩道に立っている。
「おはようございます」。午前7時45分、黄色のベストを着た学生が車道に背を向けて立ち、集団登校する児童たちに声を掛けた。通勤ラッシュと重なり、車やバイクがひっきりなしに行き交う。アメフット部マネジャーの4年平塚弘樹さん(21)は「道幅が狭く、危険な所が多いと感じた」と率直に話す。
見守り活動を始めたのは昨年6月。「地域とつながり、応援されるチームに」と、びわこ・くさつキャンパス(同市)を拠点とするアメフット部有志が週に1度、保護者や地域住民とともに通学路に立っている。
今春からは同部の呼び掛けに応じた男子バスケ部も週に2度参加。西村洋校長(55)は「本当にありがたい。学生の姿は子どもたちのお手本になる」と感謝する。
同小は国道1号と京滋バイパスの間にあり、通学路は抜け道として使われる。学生たちは児童が車道にはみ出ないよう両手を広げたり、ドライバーにも合図を送ったりして注意を払っている。「行き違いが難しくなるほど混雑することもあるが、譲り合い、誰もが気持ちよく通行してほしい」と話す平塚さん。
「子どもたちと触れ合うといい刺激になる。活動を他の部にも広げていきたい」と意気込む。
有名な企業の系列会社による不祥事を最近頻繁に起きているように思えるが、過去からの不正が公になっているのか、それとも
不正を行わないと利益が出ないような環境になってきているのだろうか?
「不正は少なくとも2011年4月から今月までで約6万台」
2010年ごろから既に厳しい状況が始まっていたのだろうか?
日立化成は29日、名張事業所(三重県名張市)で生産している鉛蓄電池の一部製品で、顧客へ提出する検査成績書に実測値とは違う値を書いたり、顧客と約束していない手法で検査をしたりしていた、と発表した。
不正は少なくとも2011年4月から今月までで約6万台に及び、約500社に出荷されたという。同社は29日夕から東京都内で記者会見を開き、詳細を説明する。
証券大手の三菱UFJモルガン・スタンレー証券でさえもルールを守る余力がなくなった来たのか、それともモラルよりも 利益が優先になってきているのか?
証券大手の三菱UFJモルガン・スタンレー証券が昨年、日本の長期国債の先物取引で不正に価格を操作したとして、証券取引等監視委員会は29日、金融商品取引法違反(相場操縦)の疑いで同社に約2億2千万円の課徴金を科すよう金融庁に勧告し、発表した。
監視委によると、同社は昨年8月25日、大阪取引所に上場されていた日本の長期国債の先物取引で、実際に取引する意思がないのに売買の注文を大量に出し、取引が活発であると誤解させ、不正に相場を操縦した疑いがある。
同社は29日、監視委の発表を受け「このような事態が発生したことは極めて遺憾で、大変重く受け止めている。市場の公正性、透明性を損なう行為で、関係者に多大なご迷惑をおかけしたことを心よりおわびします。勧告を厳粛に受け止め、再発防止に取り組みます」とコメントした。
日本人は本当におとなしいと思う。
目先だけの給料が上がっているが、副業の容認は将来、給料が上がらない、使えない社員に勤務年数により給料を上げる事が出来ない可能性がある事を
含んでいるように思える。
問題が見える形になった時では遅いと思うが、多くの人は体験するまで身近に問題として感じないのであろう。
「また下がった」「切り詰めるのも限界」──、2か月に1度の年金支給日に、そうため息をつくシニアも多いのではないだろうか。一方で、公的年金の保険料は、これまで10年以上にわたり引き上げが続いてきた。
現役世代2・2人でお年寄り1人を支えている
一体いつまで、そもそもどうしてこんなことが続くのか? “年金博士”としておなじみの社会保険労務士・北村庄吾さんが解説する。
「なぜ年金保険料がアップし続けたのか、まずはそこからご説明しましょう。
そもそも日本の年金制度は、現役世代が納めた保険料や税金を、お年寄りの年金として配る“世代間扶養”という仕組みになっています。現役世代は自分で年金を積み立てているのではなく、お年寄りに仕送りをしているというイメージですね。ところが少子高齢化によって、この仕組みを維持することが難しくなってきたのです」
高度経済成長期と呼ばれる1955年、現役世代11・5人でお年寄り1人を支えていたのが、いまは現役世代がたったの2・2人でお年寄り1人をサポート。高齢化はさらに進み、内閣府の高齢社会白書(H30年版)によれば、2060年には1・3人で支えることになると予測されている。
「お年寄りを支える世代が減る中で、仕送り方式の年金制度を維持するには、3つの方法しかありません。すなわち、(1)年金の給付を減らす、(2)保険料を上げる、(3)年金をもらい始める年齢を引き上げる。
'04年の年金制度の改正では、保険料の段階的な引き上げと年金給付の抑制が決まりました」
現役世代と年金世代それぞれが負担を分け合う、痛み分け的な改正が行われたというわけだ。
しかし、'04年の改正以前から年金保険料は負担増の一途をたどってきた。保険料の値上げはいつまで、どこまで続くのだろうか?
年金制度はさらなる改悪の可能性大
「会社員が加入する厚生年金の保険料率は年々アップしてきましたが、昨年9月を最後に引き上げが終了しました。厚生年金保険料は、収入に対してひとまず18・3%で固定されます。国民年金の保険料についても、すでに昨年4月で引き上げが終了しています。
来年から月額100円アップしますが、これは自営業者やフリーランスが産前産後の際、保険料が免除になるためのもので、これまでの値上げとは種類が違います」
だが、安心するのはまだ早い。
「少子化はどうにも止まらず、労働者人口は減り、高齢化は加速するばかり。そんななか、世代間扶養の仕組みを維持しようだなんて、どだい無理な話なのです。今後、年金制度はさらなる改悪を余儀なくされることでしょう。次の年金制度改革で、また負担増の話が出るかもしれません」
少子高齢化の進行とともに、年金給付も引き下げが続いてきた。そのため、年金の受給額に世代間格差が生じている。
「団塊の世代は“年金逃げ切り世代”などと現役世代からうらやましがられていますが、実はそうとも言い切れません。人数の多さゆえに、給付引き下げの対象になっています。
1985年の年金制度改正では、生年月日に応じた給付水準の引き下げを実施。昭和21年4月2日以降に生まれた人の年金額は、大正15年4月1日以前に生まれた人と比べると、同様に働いていたとしても約30%も引き下げられています」
もちろん、その後の世代も、あの手この手で年金が減らされていく。
「平成6年、平成12年の年金制度改正で、老齢厚生年金の受給開始が60歳から65歳に段階的に遅らされました。60歳からもらえた世代と比べると、65歳からもらう世代(男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれ)は、5年分の年金をもらい損ねることになります。
その額、モデルケースでは計1200万円! もらえると思っていたものがもらえなくなるわけですから、加入者にとっては詐欺みたいな話です」
若ければ若いほど損をする年金制度、なんとか正す方法はないのだろうか。
「世代間格差を是正しようという動きはあります。かつては物価や賃金の上昇に合わせて年金額が引き上げられていましたが、'15年からは『マクロ経済スライド』という仕組みが発動し、賃金や物価の伸びほどには年金額が伸びないようになっています。
年金世代にはたまったものではありませんが、残念ながら、それでも制度が維持できるようになるわけではありません。この30年間、有効な少子化対策が打てなかったので、年金制度そのものに無理が生じているのです」
年金がもらえない!?
頭に来るのは、年金が減らされるばかりか、手続きミスなどできちんともらえないケースがあること!
'07年に発覚した「消えた年金記録」問題の解決は道なかば。昨年9月には約10万人が年金を過少支給されるという「未払い年金」の問題が発覚した。
これは、主に元公務員の妻のうち、「振替加算」という加算金がもらえるはずの人が、日本年金機構と共済組合の連携不足や機構の処理ミスなどが原因で、もらえていなかったというもの。いったい、どうなっているのか。
「国民ひとりひとりの何十年にもわたる年金データを管理する責任は重大です。なのに、それを取り扱っていた旧社会保険庁、その職員の意識がとんでもなく低かった。年金記録問題が発覚して旧社会保険庁が解体され、日本年金機構に変わってからも、その無責任体質は変わらなかったということですね。
以前からの年金記録問題については、会社員の年金手続きが各企業にゆだねられていて、そこでのミスも多発したという事情もあるでしょう。元号改正も控えていますから問題が出ないか心配になります」
これから年金制度はどうなっていくのだろうか。保険料アップや給付減、受給開始年齢の引き上げがささやかれているが、いつ実施されるか気になるところ。
受給開始年齢は70歳に?
「まず検討されるのが、年金の受給開始年齢の引き上げでしょう。すでに法律面での外堀は埋められつつあります。例えば雇用保険。かつては“年金を受給できる65歳からは不要”として64歳までしか加入できなかったものが、昨年1月から65歳以降の人でも加入できるようになりました。
これは、“年金に頼らずにすむよう働けるうちは働いて”という国からのメッセージです。年金受給者が働いた場合、収入しだいで年金が減らされる『在職老齢年金』も、高齢者の働く意欲を損なうとして、廃止することを政府が検討し始めたところです。65歳以降も働ける環境が整えば、現在の年金受給開始年齢も引き上げられるでしょう」
そのXデーは着実に迫りつつある。
「さしあたっては67歳か68歳あたりになるでしょうか。私は、オリンピックに関心が集まる来年あたりから本格的な検討が始まるのではないかとにらんでいます。
自分の意思で受給開始を遅らせて年金額をアップさせる『繰り下げ受給』についても、従来は70歳までしか遅らせることができなかったのが、それ以降の年齢も選べるよう検討されています。
いずれは、受給開始年齢そのものを70歳にすることも視野に入れていることでしょう」
さらにトンデモないプランがある。自民党が6月にまとめた「一億総活躍社会の構築に向けた提言案」によれば、老齢基礎年金の目減りを補うため、高齢者住宅の提供など現物給付を検討するというのだ。
「実現性は低いと思いますが、それだけ財源不足が差し迫っているということ。年金だけでは暮らしていけません、生涯働き続けてくださいというメッセージだと、私はとらえています」
先が見えない年金制度。私たちにできる対策は?
「まず、もらえるはずの年金はきっちりもらうこと。年金記録に保険料未納扱いになっている空白期間がないかチェックしてみましょう。日本年金機構の『ねんきんネット』や年金事務所の窓口で調べられます。
また、年金給付ダウンを見越して、自分でも年金を用意しておくこと。個人年金保険やiDeCo(個人型確定拠出年金)を活用すれば、節税メリットも受けられます。そして、長生きリスクを考えて、心と身体の健康を維持するよう心がけましょう」
大学と呼ぶのか、教育機関と呼ぶべきなのかよくわからないが、とにかく大学に入れば、専攻に関係なく就職出来るし、大学の学費を払う事による
費用対効果が成立した時代に終わりに近づいているので、改革、又は、変わるべき時期が来ていると思う。
これまでは大学と呼ばれていた大学は学術や学問を追求する大学と就職やこれから仕事で必要とされる知識や技術を教える教育機関に分かれても
良いと思う。
大学を卒業しても全く専攻と違う分野に就職する人が多い。企業がそれでも良いと思えば良いが、企業にゆとりがなくなり、出来るだけ即戦力に
近い新卒が欲しいのであれば、二流から三流の大学では仕事で必要とされる知識や技術を教える教育機関に変わる割合が多くて良いと思う。
講師や教授達には大きな影響と与えると思うが、大学に行けば何とかなる時代は終わりつつあると思う。後進国や発展途上国の学生の追い上げも
ある。生活水準が上がり、教育にお金をかけれるようになると、無駄な事をしている日本の大学生に追いつくし、最悪の場合、追い抜いて行くかもしれない。
グローバリゼーションは無視できない。日本だけを考えずに、もっと広い視野で見るべきだと思う。自分の目先の事しか考えないから、日本は
沈んでいくのである。
「2040年の大学のあり方」などを議論している中央教育審議会の部会が25日、大学が連携・統合するための3パターンを打ち出した。18歳人口が減り、社会構造も変わることを見据え、一つの国立大学法人が複数の国立大学を運営できる仕組みを提言するなど、大学の「生き残り」を意識した内容となった。
連携・統合案は、中教審大学分科会の将来構想部会(部会長=永田恭介・筑波大学長)の中間まとめに盛り込まれた。部会は25日に了承し、中教審は今秋、林芳正文部科学相へ答申する予定だ。
中間まとめは具体案として(1)複数の大学が国公私立の枠を超えて「大学等連携推進法人」(仮称)を作り、単位互換などをしやすくする(2)一つの国立大学法人が、複数の国立大学を「アンブレラ方式」で運営できるようにする(3)私立大が、他大学に一部の学部だけを譲渡できるようにする――の3パターンを提示。文部科学省が関係の法令改正などに取り組むべきだとした。
このうち(2)は既に名古屋大と岐阜大、静岡大と浜松医科大、北海道の帯広畜産大・北見工業大・小樽商科大の三つの計画が明らかになっている。国からの運営費交付金が減少傾向にある中、他の国立大も追随する可能性がある。(増谷文生)
検索してみるとカネミ倉庫は現在でも存在しているようだ。
下記のサイトには技術倫理とか技術者の責任とか書いてあるが、技術倫理とか技術者の責任の責任も重要であるが、技術者以外の人間で
問題を隠そうとした人間、適切な対応を歪めた人間が存在したから、結果として問題が拡大したり、解決が遅れる。
法律や規則が経営者に有利になっていれば、違反したり、違法行為を行った方が得なケースがあると思う。このような環境があれば、
技術者だけの責任であろうか?グレーであれば罪には問われない。有罪となっても、処分を受けても、処分が軽ければ、企業イメージを損なうだけで
大した問題にならない場合がある。
最近の不祥事、品質や検査の問題を考えてみれば良い。本当に技術者だけの問題であろうか?違うと思う。
弁護士は正義の味方なのか?そうでもあるが、弁護を依頼したお金持ちの味方にもなる。だから、社会のために全ての弁護士が働いていると
考えると間違いである。世の中は複雑で不透明だと思う。
カネミ油症事件とは
カネミ油症事件は 森永ヒ素ミルク中毒事件 と並ぶ我が国有数の食品公害事件の一つである。 事件の概要については 杉本泰治氏がPL法について書かれた本に詳しくまとめられている。 こちら を参照してもらいたい。
ここでカネミ油症事件を取り上げるのは、 技術者、科学者に育っていく諸君に、この問題を第三者の目で捉えるのではなく、 自分たちも関与したかもしれない問題として考える材料にしてもらいたいからである。
被害者の立場で考えることも大切である。 また、この事件では刑事裁判、民事裁判の被告として登場する人たちもいる。 その人たちについて考察することも大切であろう。 しかし、ここではそれ以上に、そのような表舞台には直接登場しないところにも 多くの関係者がいたことに思いをめぐらしてもらいたい。
カネミ倉庫株式会社には試験室もあれば研究室もあった。 そこには技術者、科学者がいたのである。 もちろん鐘淵化学工業株式会社にはずっと多くの技術者、科学者がいた。 カネミ倉庫に装置を納入したメーカーにだっていたのである。
このような表には表れない技術者、科学者のうちのだれか一人の人による 抑止があれば、この悲惨な事件は起きなかった、あるいは、被害者が少なくてすんだ のである。 それを忘れることなく、諸君は技術者、科学者として成長してもらいたい。
詳しくは 杉本泰治氏によるこの文 を読まれたい。
第547回
制作: NBC 長崎放送
ディレクター: 古川 恵子
社名が事件名になった会社「カネミ倉庫」。今も福岡県北九州市に本社を置き、物資を預かる倉庫業と油を作る精油業を続けています。
1968(昭和43)年。油を加熱する為に使っていた化学物質「PCB」がパイプから漏れ出して混入。西日本一帯で、油を口にした1万4千人以上が、皮膚・爪・目・内臓…全身に及ぶ異常を訴えた「カネミ油症事件」。加害企業となったカネミ倉庫は「賠償金を支払う余裕はない」と訴えました。損害賠償請求訴訟を起こした原告患者らとの和解に基づき、治療費の実費分負担を約束し、現在に至ります。
このカネミ油症事件をめぐって、発覚から40年目の2008年5月、新たな裁判が始まりました。原告は「新認定」の油症患者達。遅れて認定されたため、過去に起こされた一連の裁判には参加できなかった人達です。カネミ倉庫は全面的に争う構えを示し、民法724条「除斥期間」によって、不法行為時から20年で損害賠償請求権は消滅していると反論、そして再び「賠償金を払う余裕はない」と訴えました。
5年の審理を経た2013年3月、「原告の請求を棄却する」。除斥期間を適用した原告全面敗訴の判決が言い渡されました。認定が遅れた責任を全て被害者に押し付ける極めて形式的な判決と原告が反発。
この裁判所の判断を、カネミ倉庫の主張と共に考えます。
「安か油」を購入したのが全ての始まりだった。
1968(昭和43)年春。当時29歳の松本正江(79)=仮名=は、長崎県五島市内の小集落に、漁師の夫と3人息子の家族5人で暮らしていた。巻き網船に乗る夫は海に出ている期間が長く、正江は子育ての傍ら、1人で畑を耕し、野菜を育てた。近くに住む義父母の食事作りも役目だった。
そのころ、商店を営む親戚から格安で食用油を購入した。「一升瓶10本が入る木箱を3ケース。1本当たり30円安かった」。裕福とは言えない生活。油は日本酒や焼酎の空き瓶に移し替えられていて、どんな会社の油か分からなかったが、安価なのは助かった。
「あんたのとこ安か油のあっとね。分けてくれんかな」。すぐにうわさが広まった。正江は親戚や近所の人に油を配った。
「どうも変な油だった」。加熱するとブクブクと泡が出る。ねっとりして、すり身や天ぷらがカラッと揚がらない。「おかしい」と話題になった。正江は近くの店で別の油を買い、混ぜて使った。結局、義父母を含め、家族で一升瓶3本分の油を消費した。
その年の夏。家族と義父母の体に、大小さまざまな吹き出物ができた。正江は首やふくらはぎ、夫は背中、子どもたちは頭皮に強く症状が現れた。頭痛、腹痛、手足のしびれに襲われ血尿も。慌てて息子たちを病院に連れて行ったが、飲み薬と塗り薬を処方されただけだった。
数カ月後、通っていた病院の医師が言った。「あなたたちはカネミライスオイルを食べていないか」。医師によると「毒の入った油」が五島で出回っているという。言われるまま、役場で子どもと検診を受けたが原因は不明。症状に苦しみながら歳月が流れた。
検診を5、6回受診した後の75(昭和50)年、息子3人は「カネミ油症」と認定された。油を食べて7年。正江はあの油が原因だったとようやく理解した。
夫は漁が忙しく検診を受けていなかったが、弁当には頻繁にすり身揚げや天ぷらなどの揚げ物を入れていて、家族で最も多く油を食べているはずだった。「お父さんも受けたら」。検診を勧めると、夫は突然怒鳴った。「おまえがそがん油を買うけん悪か!」。普段は温厚な夫の怒りに、正江は動揺した。
「買った私が悪か。でも悪い油と知って食べさせたんじゃない。ごめんね、許して」。正江は畑で一人泣いた。毒入りの家庭料理を食べさせ続けた悔恨。妻として母として、気が狂いそうだった。
◇ ◇ ◇
正江が、家族とカネミライスオイルを食べてから8年がたった1976(昭和51)年、検診を渋っていた漁師の夫を何とか説得。翌年、夫は正江と共に油症認定された。
夫は高血圧症を患い、薬を手放せなくなっていたが、弱音をはかない性格。頭痛や下痢でつらくても、生活のため漁に出ていた。夫の背中は、大きい吹き出物が無数にあり、肌着は膿(うみ)でいつも黄色く汚れていた。
次男は、症状が重かった。小学生のころは朝布団から起き上がれないほど。体を抱えてトイレに連れて行くと、血の混じった尿が出た。入退院を繰り返し、学校も休みがちで、ふさぎ込んだ。体調は季節や天候に左右され、梅雨や秋口に悪化した。
正江自身も当初から吹き出物と血尿、年齢を重ねると自律神経の乱れから目まいや吐き気、食欲不振など多様な症状に襲われた。特に悲しかったのは、30代で計7回も経験した流産。生理不順かと思っていると、突然出血。驚いて受診すると流産だと告げられた。出血があると入院し処置を受け、自宅に帰る。この繰り返しだった。
7回目の流産の後、医師が言った。「このまま流産を繰り返すと、貧血で体が危ない」。夫も交えて話し合い、卵巣を摘出。ずっと女の子を望んでいたが、諦めるしかなかった。
差別も家族を追い詰めた。集落の母親たちはわが子に「あの家で食べ物をもらっても食うな」と言い、正江の息子たちはのけ者にされた。ただ正江が油を配った親戚や近所の人は押し黙り、油を食べたことや自らの症状もひた隠しにした。「田舎の習慣というかね。人聞きの悪いことは隠そう隠そうとした」。義父母も決して検診を受けようとしなかった。被害者は皆、口をつぐみ、孤立していた。
85(昭和60)年、47歳になった正江は、毒油を売ったカネミ倉庫や原因物質ポリ塩化ビフェニール(PCB)を作ったカネカ、国の責任を問う集団訴訟に第5陣原告として加わった。夫と共に救済や謝罪を求め、東京や千葉などで窮状を訴える抗議行動にも参加。だが2年後、責任の所在が判然としないままカネミ倉庫と和解。わずかなお金を受け取って終わった。
2004(平成16)年、正江は知り合いに頼まれ、体験や思いをA4サイズの紙2枚に書き、五島市内の被害者集会で読み上げた。「36年という年月は、私たち家族には長く、心身共に不安におびえ、苦しい苦しい毎日です。私たちを助けてください」
カネミ油症は、健康な体も幸せだった家庭もずたずたにした。数十年続く目まいや体のだるさ。ここ数年は不整脈や腰痛で散歩すら満足にできない。一日中起き上がれないこともある。連れ添った夫は13年前、膵臓(すいぞう)がんで亡くなった。
正江は今も思う。「なぜ、私たち家族はここまで苦しまなければいけないのか」と。=文中敬称略=
◆
長崎県など西日本一帯で広がったカネミ油症は、発覚して今年で50年。被害者の証言をシリーズで随時伝える。
◎カネミ油症
カネミ倉庫(北九州市)が食用米ぬか油を製造中、熱媒体のカネカ製ポリ塩化ビフェニール(PCB)が混入し一部はダイオキシン類に変化。長崎県など西日本一帯で販売され被害を広げた。1968年10月、新聞報道で発覚。当初約1万4千人が被害を届け出た。2018年3月末の認定患者数は全国で2322人(死亡者含む)、長崎県964人(死亡、転居含む)。
ダイレクトメール(DM)の発送料金を不正に安くした見返りに発送代行会社から接待を受けたとして、茨城県の郵便局の元課長2人が摘発された事件で、2人が同社から持ち込まれたDMの検査を同社に一任するなどし、少なくとも60回程度、正規料金の1割程度しか徴収していなかったことが22日、神奈川と茨城県警の合同捜査本部への取材で分かった。
日本郵便株式会社法違反(加重収賄)容疑で逮捕、送検されたのは、土浦郵便局元課長の男(61)=茨城県土浦市=と、筑波学園郵便局元課長の男(46)=同県龍ケ崎市=の両容疑者。ほかに、発送代行会社「ティーティーオー」(東京都中央区)の元役員ら5人が、同法違反(贈賄)容疑で逮捕、送検された。
日本郵便によると、DMは数量や規格で料金が異なり、一定量以上が持ち込まれた場合は、全体とサンプルの重さを量って枚数を計算する検査を行い、料金を決める。その際、不正を防ぐために、内規で複数の局員が立ち会うことが定められている。
2人はティー社側とDMを郵便局に持ち込む時期を事前に調整していたことが捜査関係者への取材で判明。ティー社側に検査を一任することもあったという。捜査本部は、検査が形骸化していた可能性もあるとみて、捜査を進める。
また、61歳の男が3年前にティー社による接待の場で、46歳の男を紹介したことも捜査関係者への取材で分かった。不正な割引による日本郵便の損害額は6億円を超えるとみられる。
三菱マテリアルの株主で三菱マテリアルの対応に納得いかなければ株を売る選択もある。
組織や組織の常識は簡単には変わらないと思う。ただ、組織に問題があっても利益が出る事もある。後は株主が利益や配当のために
株を保持するのか、その他の理由で株を保持するかだと思う。
非鉄金属大手の三菱マテリアルは22日、本社の工場で品質不正が発覚して竹内章社長(63)が引責辞任を発表した後、初めて記者会見を開いた。本社の不正を伏せたまま問題の幕引きを図ろうとした同社の姿勢には、この日の株主総会でも厳しい批判が相次いだが、会見した新社長の小野直樹氏(61)は一連の対応は適切だったと繰り返し、批判に耳を貸さなかった。
【写真】会見に臨む三菱マテリアルの小野直樹社長=2018年6月22日午後、東京都千代田区、恵原弘太郎撮影
社長交代の発表から11日後。記者会見は小野氏の社長就任を説明する場として開かれ、辞任して取締役会長に就いた竹内氏はこの日も姿を見せなかった。
竹内、小野両氏は、子会社の不正に関する最終報告書を3月末に公表した際、本社直轄の直島製錬所(香川県直島町)の製品で日本工業規格(JIS)を逸脱したものがあることを知りながら、公表しなかった。その理由について小野氏は、社内基準に照らして、関係者に周知して素早く対応する問題ではないと判断したと説明した。
小野氏は5月の決算発表会見で本社にも不正があることを否定していたが、「データの改ざんがないという意味で説明した」と釈明。6月8日になって一転公表したのはJISの認証機関から不備を指摘されたためだとし、「(公表に至る)判断は適切だった」と繰り返した。
竹内氏は代表権はなくなるが経営陣に残り、ガバナンス(企業統治)強化のための指導や監督にあたるという。この処遇を疑問視する声について、小野氏は「取締役会の同意は得られている」と正当性を主張した。(野口陽、上地兼太郎)
非鉄金属大手、三菱マテリアルの株主総会が22日、東京都内で開かれ、品質データを巡る一連の不正について竹内章社長が陳謝した。株主からは責任の所在を問う声や首脳人事への疑問が出た。
【写真】三菱マテリアルの株主総会会場に入る株主=東京都中央区
三菱マテでは今月、本社の生産拠点での不正が発覚。竹内社長が引責辞任して代表権のない会長に就き、後任の社長に小野直樹副社長を昇格させることを発表した。
出席した株主によると、竹内社長が不正の経緯について説明。責任者や処分についての質問が出たが、会社側は悪質性の低いミスだと説明。竹内氏が会長として経営陣に残ることを疑問視する意見も株主から出たが、会社側は業績が好調なことを理由に妥当な人事だと説明したという。
総会に出席した男性株主は「竹内氏が会長になって品質管理を担当するのはおかしい。不正が起きた原因がはっきりわからないまま総会は終わった。社会的責任はとらないといけない」と話した。女性株主(55)は「新社長も内部昇格なので、今後同じことが起きる可能性はあると思う」と話した。
三菱マテでは昨年11月以降、子会社5社で品質データの改ざんが相次いで発覚。一連の問題の最終報告書を3月に発表し、本社は不正に全く関与していないと説明していた。だが、竹内、小野両氏はこの時点で、本社の生産拠点である直島製錬所(香川県直島町)が日本工業規格(JIS)を逸脱した製品を、規格を満たした製品として出荷していた疑いを把握していた。
着服した1億円を返す事が出来るか次第で、被害届を出すのか決めると言う事か?
千葉県松戸市にある、JAとうかつ中央の支店で50代の女性係長がおよそ1億円を着服していたことがJAの内部調査でわかった。女性係長は着服を認めているという。
JAとうかつ中央によると、松戸南支店に勤務する50代の女性係長が、去年7月からの1年間ほどで、金庫から現金およそ1億円を着服していたことが、今月18日に行った内部監査でわかったという。
女性係長は当時、出納事務を担当していて、日常的に金庫を扱っていたということで、JAの調査に対し、着服を認めているという。JAは女性係長に自宅待機を命じていて、すでに警察に相談しているという。
JAは「信頼回復に努める」とコメントしている。
調査の方法が調査機関により大きく違うのはびっくりした。日本には調査にガイドラインとか、最低限はチェックする項目はないのか?
ある意味、日本は調査の後進国かもしれない。
京都大iPS細胞研究所の論文不正問題で、同研究所の調査委員会が不正を認定した決め手となったのは、責任著者が使っていたノートパソコンから見つかったデータ改ざんの痕跡だった。パソコン内のデータは消去されていたが、調査委が復元して判明した。3人の調査委員が毎日新聞の取材に応じ、調査の詳細な内容を明らかにした。【須田桃子】
◇100万円かけデータ復元 浮かんだ改ざんの跡
問題の論文(既に撤回)では計11個の図で捏造(ねつぞう)・改ざんが認定され、筆頭著者で責任著者の山水康平助教が3月に懲戒解雇処分を受けた。取材に応じたのは、調査委員長を務めた同研究所副所長の斉藤博英教授、委員だった高橋淳教授、山本拓也准教授。
斉藤副所長らによると、調査ではまず、論文を構成する棒グラフなどの図について、実験に使った測定機器に残っていた0次データや、実測値をパソコンに書き出した1次データと、1次データにさまざまな解析を施した2次データを比較し、図が正しく作成されたかを調べた。同研究所のルールに基づき、1次、2次データは論文投稿時に研究所に提出されていたが、調査委は他に、元助教が使っていた複数のパソコンやハードディスクに保存されていたデータも確保し、精査した。
多くの図で0次や1次データと2次データとの間に齟齬(そご)があり、数値が意図的に操作されたことは明らかだったが、誰の手によるものか明確な証拠はなかった。調査委は専門業者に依頼し、約100万円をかけて元助教専用のノートパソコンで消去されたデータの復元を試みた。復元されたデータの中に、1次と2次の中間の、改ざんの試行錯誤の跡とみられる複数のデータが含まれていた。
◇著者は検証実験希望も、却下
元助教への聞き取り調査では、こうした「1・5次」のデータの存在も提示。元助教は他の人の関与はなく、自らがデータを操作したことを認めた。斉藤副所長は「データを復元したことで初めて検証できた内容もあり、迅速な調査につながった」と振り返る。高橋教授も「(不正認定は)客観的な事実と本人の自白の両方で成り立つ。本人のノートパソコンから不正の痕跡が見付かったことで、認めざるを得なくなったのだろう」と推測する。
また、調査の過程で元助教は検証実験の実施を求めたが、調査委は「その必要はない」と判断し、あくまで論文の基になったデータを精査する姿勢を維持した。山中伸弥・同研究所長も同じ方針だったという。調査は4カ月で終わった。斉藤副所長は「論文に不正があったとしても結果が再現できれば問題ない、という考え方になっては良くない。論文中のデータの調査で完結させなければ調査も長引き、世界中の研究者に迷惑をかける」と説明する。
◇STAP問題ではPC提出されず
一方、国内の過去の研究不正問題では、研究者の使ったパソコンを調査できなかった事例が複数ある。2006年に教授と助手が懲戒解雇処分を受けた東京大の論文不正疑惑では、助手が実験記録を保存していたというパソコンが廃棄されていた。理化学研究所を舞台に14年に起きたSTAP細胞論文問題では、論文の筆頭・責任著者だった小保方晴子氏が論文作成に使ったノートパソコンの提供を調査委が求めたところ、私物であることを理由に提出されなかった。いずれの問題でも検証実験が実施され、STAP問題では検証実験に1700万円余りの費用と9カ月半の時間を要した。
「JR西は、異常を感じた際は関係者に伝えるよう改めて意識を徹底させるとしています。」
運転士も駅員も直ぐに連絡できなかった。表向きには「徹底でも」、実際は、別の指示があるのかもしれない。
新幹線が駅に入ってくる時、あれだけ損傷していれば確認作業が必要な事は思いつくはずである。空力から考えても
あれだけ損傷すれば確認作業は必要と思わなかったのか?
運転士の説明は事後に辻褄を合わせるために考えた言い訳のように思える。まあ、国土交通省が検証をするだろうから疑わしい
点については質問されると思う。まあ、若い運転士であれば、若いからとか、マニュアルに精通していないとか、言えるけど
14年のベテランになると、ダイヤ優先にしたのか、経験だけはあるが、基本的な能力に問題がある事以外、納得の行く
説明は出来ないと思う。
山陽新幹線「のぞみ」の人身事故で、運転士が異音を聞いていたにもかかわらず、運行を続けていたことが分かり、JR西日本が謝罪しました。
「深くお詫び申し上げます」(JR西日本 平野賀久 副社長)
14日、山陽新幹線の「のぞみ176号」が博多駅と小倉駅の間で人と接触し、ボンネットが大きく破損。この影響で76本が運休、4万人に影響がでました。運転士は衝突時に異音を聞いていましたが、マニュアルで定められている運転指令への報告などをしませんでした。
「本人(運転士)は動物とぶつかった経験があり、停止させる必要はないと判断」(JR西日本 平野賀久 副社長)
また、途中で停車した小倉駅の駅員も列車の先頭部分に血やひび割れを確認しましたが、運転指令に連絡したのは出発後でした。その後、反対側を走っていた別の列車の運転士が破損に気付いて指令に連絡し、ようやく「のぞみ」は次の新下関駅で臨時停車しました。
「走行中であっても小倉駅到着前に、仮に東京の司令員と運転士が会話をしていれば、小倉で降りて点検してくれということに至った可能性はあったと」(JR西日本 平野賀久 副社長)
JR西日本は去年12月、「のぞみ」の台車の亀裂による異常に気付きながら運転を継続。新幹線初の重大インシデントに認定されました。これを受け、今年2月、「異変を察知したら躊躇なく列車を止める」など、再発防止策を盛り込んだ安全計画を発表していました。JR西は、異常を感じた際は関係者に伝えるよう改めて意識を徹底させるとしています。
山陽新幹線博多-小倉間で起きたのぞみ176号の人身事故で、JR西日本は15日、運転士が異音を感じながら、マニュアルで規定する運転指令への連絡について「必要があるとは考えなかった」として報告しなかったことを明らかにした。小倉駅の駅員が、先頭車両の異常に気付きながら発車を止めなかったことも判明。昨年末には、新幹線の台車が破断寸前の状態で走行を続ける「重大インシデント」が起きており、会見した平野賀久副社長は「(再発防止の)働きかけが、社員に響いていなかった」と謝罪した。
JR西によると、事故は14日午後2時すぎ、北九州市八幡西区で発生。のぞみ176号の50代の運転士は「ドン」という音を聞いたが、「小動物と接触した」と思った。JR西のマニュアルに異音による停止義務はないが、東京の運転指令へ伝えるよう定めている。しかし、運転士は連絡の必要性がないと思い込み、情報を共有せずに運転を続けたという。
停車駅の小倉で、30代の駅員は、車両先頭のカバーに血痕が付着し、ひびが入っているのに気付いたが、詳しい点検をせず、発車後に運転指令に報告した。
平野副社長は、運転士や駅員の対応に問題があったと認め、検証する意向を示した。ただ、カバーの破損が重大事故につながった可能性は否定した。
また、はねられた男性は高架橋の検査用足場を上って線路に入ったとみられるが、「侵入防止用カバーを設置するなど適切な対応をとっていた」とした。
山陽新幹線を巡っては、昨年12月、博多発のぞみ34号が台車が破断寸前の状態で走行を続け、国の運輸安全委員会が新幹線で初となる重大インシデントに認定。乗務員らが異音などに気付きながら放置し、JR西は「安全が確認できない場合は迷わず列車を停止させるよう徹底する」としていた。(竹本拓也、小川 晶)
異常時対応マニュアルの理解が出来ていないと言う事は、優先順位の高い緊急時の対応への認識が徹底されていない、又は、建前だけで
実際の優先順位が低かった可能性もある。
規則を建前上、守らなくてはならない面倒な物とか、監査や検査に通れば問題ないと思っている会社や人は規則を守らない傾向はある。
今回の件についてはわからない。
山陽新幹線のぞみが人をはねた事故をめぐり、JR西日本が15日に開いた会見では、運転士と駅員が異常に気づきながら、走行を続けていたことが明らかになった。のぞみでは昨年12月、車掌らが異常を感じながら走らせ続けた台車亀裂問題が起きたばかり。なぜ繰り返されたのか。
博多―小倉間で外部から人侵入か 山陽新幹線の人身事故
「伝えるということに関し、大きな課題があった」。JR西の平野賀久(よしひさ)副社長は、問題の原因についてこう説明した。
JR西によると、異常時対応マニュアルで、運転士は走行中に異音を聞いた場合、東京の指令所に報告しなければならないと定めている。今回、50代の運転士は「通常と全く違う音」を耳にしながら報告していなかった。「マニュアルを誤認したか、気が動転して伝える行為を抜かした可能性がある」という。
さらに、のぞみが人をはねた後…
大きな事故が起きた時には会社は倒産で、幹部は少なくとも5年ほど刑務所に行く事を前提で飛行させる規則があっても良いと思う。
形だけの検査や記録を行っている会社はたくさん存在すると思う。
貨物専門の航空会社、日本貨物航空は、航空機の整備記録に事実と異なる記載が見つかったことから、16日以降のすべての便の運航を一時的に停止すると発表しました。
日本貨物航空は、機体が大きく損傷する事故を起こしながら報告を怠ったとして、先月から国土交通省の立ち入り検査を受けていました。
この検査の中でジャンボ機の潤滑油の補給に関する整備記録に事実と異なる記載が見つかり、他の機体にも同様の問題がある可能性が否定できないとして、日本貨物航空は16日以降のすべての便の運航を一時的に停止すると発表しました。
日本貨物航空は、「安全の確認には少なくとも1週間程度かかる見込みで、運航の再開に向けて全力を尽くします」としています。
「JR西は今後、シミュレーター訓練に異音感知時の状況を追加し、係員に視線移動の面から教育するなどの対策を充実させる方針という。」
建前だけの対応では次の時の事故には違う言い訳と対応策だけである。本部や司令部と連絡できるのに、なぜ、連絡し、相談、又は、
指示を求めなかったのか?
シミュレーター訓練を何度やっても基本的な指示が徹底されていなければ意味がない。
「「線路は基本的に侵入できない」(JR西日本)という新幹線の『安全神話』に盲点が浮かんだ形。専門家は『他の場所でも起こり得る事故。さらなる安全対策が必要だ』と警鐘を鳴らす。」
「線路は基本的に侵入できない」ではなく、誰も無理に侵入しようとしなかっただけだと思う。JRだけでなく、いろいろな問題が存在するが
コストを考えると、今まで問題ないのだから今後もないと判断して対応している事はたくさんあると思う。
命が最も重いと思っていない偽善者であるが、言葉にするとイメージ悪化のリスクがあるので本音を言えないのだと思う。
具体的な安全対策を述べて、例えば、ケース1だといくらのコストがかかるのかを公表してお客の反応を見る、又は、アンケートを取るなど
新しい試みを試すべきだ。
山陽新幹線博多-小倉間で起きた人身事故では、運転士が異音を感知しながらも運転指令に報告しなかった「内規違反」が明らかになった。JR西日本は昨年末にも、異常音に気付きながら台車亀裂の発見が遅れたトラブルが起きたばかり。運転士に染みついた“ダイヤ至上主義”を指摘する声もあり、安全対策への姿勢が改めて問われそうだ。
⇒【画像】死亡した男性が線路に侵入したとみられる新幹線の橋脚と足場
「情報共有を徹底させてきたが、社員への働き掛けが足りなかった」。15日、大阪市のJR西本社であった記者会見で、平野賀久(よしひさ)副社長は何度も謝罪した。
社内マニュアルでは、異音を感知した段階で運転士が東京にある運転指令に連絡するとされている。昨年末の台車亀裂を受けて今年2月に発表した安全計画でも「安全を確認できない場合は迷わず止める」と明記した。運転士は50代で運転歴14年程度のベテラン。過去に動物と衝突した経験もあり、今回も同様のケースと判断していたという。
車体よりもホーム上を注視、連絡が後回し
東海道・山陽新幹線は日本の大動脈。あるJR西社員は「全ての場合で止めてしまえばダイヤに大きく影響することになり、程度の判断は難しい」と漏らす。
今回の事故では、小倉駅の係員もホームに入ってきた車両の先頭部分についた血のりなどを確認していたが、運転指令への報告は発車の後。乗客の乗降確認を優先し、車体よりもホーム上を注視していたため連絡が後回しになったという。
「少ない人員の中、全てを求めるのは酷だ」(JR西社員)との声もあるが、関西大の安部誠治教授(交通政策論)は、車両の運行を止めた新下関駅での破損状況を見る限り「あれだけ大きな破損は珍しく、見過ごしたこと自体が不思議」と指摘する。
社員への内規の徹底と安全対策求める声も
15日の会見で「運転士と駅係員の中にダイヤを絶対に乱してはいけないという感覚があったのではないか」と問われた平野副社長は「本人たちとのやりとりでは確認していない。(ダイヤ優先の)感覚はなかったと思う」と述べるにとどめた。
一方、JR九州は、走行中に通常とは異なる原因不明の音がした場合、車両をその場で停止すると規定。15日にも、九州新幹線さくらが新八代-熊本間を走行中、運転士が「コン」という異常音を感じて緊急停止させた。現場や熊本駅で車両に異常がないことを確認した上で走行を再開し、乗客には博多駅で後続列車に乗り換えてもらっている。
JR西は今後、シミュレーター訓練に異音感知時の状況を追加し、係員に視線移動の面から教育するなどの対策を充実させる方針という。鉄道技術に詳しい工学院大の高木亮教授(電気鉄道システム)は「あのまま走行していた場合、カバーが車両の下に入り込み、脱線していた恐れもある」と指摘、社員への内規の徹底と安全対策を求めた。
線路侵入対策どこまで 安全強化、費用に課題も
福岡県内で起きた山陽新幹線のぞみ176号の人身事故で死亡した男性は、自ら足場を登り、高架線路内に侵入したとみられる。足場の周辺には柵、線路には防音壁があるが、「線路は基本的に侵入できない」(JR西日本)という新幹線の「安全神話」に盲点が浮かんだ形。専門家は「他の場所でも起こり得る事故。さらなる安全対策が必要だ」と警鐘を鳴らす。
JR小倉駅(北九州市小倉北区)から南西約15キロの同市八幡西区上香月。住宅地や田畑が広がる郊外で事故は起きた。周辺の線路は高さ約15メートルの高架区間と、柵と壁を設けたのり面上に線路がある区間がある。現場周辺では15日も、福岡県警の捜査員が男性の遺留物の捜索に当たった。
事故現場近くには地上から高架へつながる足場
事故現場近くには地上から高架へつながる足場があった。JR西日本は「柵や施錠があり、新幹線の線路は通常は入れない構造」と説明するが、近くに住む70代男性は「簡単に柵を乗り越え、足場をよじ登ることができる場所はある。入ろうと思えば線路内への侵入は可能だ」と話した。
大阪大の臼井伸之介教授(産業心理学)は「今回の事故を教訓に、故意に侵入できる箇所がないかの点検作業は最低限必要だ」と話す。一方で、金沢工業大の永瀬和彦客員教授(鉄道システム工学)は「トンネルが通る山間部や丘陵地では侵入しやすい場所が増える。このような区間には、侵入者を検知して警報を鳴らすようなシステムを導入するのが望ましい」と指摘。「費用面で課題があり、安全性をどこまで確保するかは国の方針や社会的な合意も必要になる」と話した。
=2018/06/16付 西日本新聞朝刊=
出荷前の自動車の排ガスや燃費の測定をめぐり、国が定める基準を逸脱した検査をしていたスバルは15日、国内向けに生産している乗用車全9車種の検査で不正があった疑いがあることを明らかにした。20人以上の社員が不正に関与したとみられるという。
不正な検査があったのは群馬製作所(群馬県太田市)の2工場。排ガスや燃費のデータを測定する際、道路運送車両法の保安基準が定める速度を逸脱しても測定をやり直さず、測定値を書き換えたり有効なデータとして処理したりしていた。測定する部屋の湿度が基準を外れても、有効な測定値としていた。3月に公表した排ガス・燃費の測定値改ざんとは別の不正で、今月5日に発表した。
スバルは同日の記者会見で、不正があった車種は「調査中」としていた。排ガス・燃費の測定値の改ざんは乗用車全9車種に及ぶと4月に明らかにしているが、新たな不正も全車種に及ぶ疑いが強まった。傷ついたブランド力の回復が遠のくおそれもある。
事実であれば自業自得!
がん検査に使われる放射性医薬品をめぐり、製造大手の「日本メジフィジックス」(東京都)が他社の事業を不当に制限した疑いがあるとして、公正取引委員会は13日、独占禁止法違反(私的独占)容疑で立ち入り検査をした。公取委は、同社が他社の参入を妨げることで市場を独占し、薬剤の価格を高止まりさせるおそれがあると判断した模様だ。
日本メジ社は、がん細胞を見つけるための「PET」(陽電子放射断層撮影)検査で使われる薬剤を2005年に国内で初めて販売し、その後は市場をほぼ独占してきた。
関係者によると、同社は富士フイルムが14年に新規参入を発表すると、薬剤の投与装置を開発するメーカーに対し、富士フイルムの薬剤に対応する改良を行わないよう圧力をかけたほか、両社の薬剤に対応できる装置が開発されると、病院側に「この装置は自社の薬剤には使えない」とうその説明をして装置を使わせないようにし、富士フイルムの事業を妨げた疑いがある。
また、卸売会社に「富士フイルムと取引をするなら、うちの薬剤は扱わせない」と伝え、日本メジ社より低価格で納入しようとした富士フイルムを排除しようとした疑いがある。
日本メジ社は取材に対し、「検査には真摯(しんし)に対応する」と回答した。(矢島大輔)
悪性がんの早期発見に使われる陽電子放射断層撮影(PET)検査の診断薬をめぐり、ライバル社の新規参入を妨害した疑いがあるとして、公正取引委員会は13日、独占禁止法違反(私的独占)の疑いで、放射線医薬品大手の日本メジフィジックス(東京)を立ち入り検査した。
関係者によると、PET検査診断薬の市場をほぼ独占する日本メジフィジックスは、新規参入を排除するため、診断薬を投与する機械のメーカーに対し、ライバル社の製品に対応するための改良をしないよう圧力をかけた疑いなどが持たれている。
PET検査は、がんなどの早期発見を目指して、医療機関が積極的に導入を進めている。
日本メジフィジックスは、住友化学とGEヘルスケアがそれぞれ50%を出資し、1973年に設立された。取材に対し「立ち入り検査には協力していく」とコメントした。
九州運輸局の加賀至局長は12日の記者会見で、西日本鉄道が運行する電車と高速バスで相次いだトラブルについて「利用者の安全上、重大な事案だ」と述べ、監査を実施して厳重に指導、警告したことを明らかにした。国土交通省も今秋をめどに経営トップらの聞き取りを行い、安全管理体制の改善を求める運輸安全マネジメント評価を実施する。
西鉄グループでは5月10日夜、「西鉄バス北九州」の高速バスが九州自動車道の若宮インターチェンジ付近でバス停を誤って通過し、約15メートルをバックで逆走。天神大牟田線では同15日夕、普通列車がドアを約40センチ開けたまま少なくとも約8分間運行し、国の運輸安全委員会が事故に至る恐れがある「重大インシデント」と認定した。
加賀局長は「乗務員のとっさの判断に(逆走などの)ヒューマンエラーがあった」と指摘した。【石田宗久】
利益を追求しても問題はないが、違法行為を行う企業は処分されても自業自得!
【フランクフルト時事】ドイツ運輸当局は11日、独自動車大手ダイムラーの高級車ブランド「メルセデス・ベンツ」の一部車種で、違法な排ガス制御ソフトウエアの搭載が確認されたと発表した。
欧州全体で約77万4000台に上るという。
独当局はこのうち国内の約23万8000台について、リコール(回収・無償修理)を命じたと明らかにした。違法ソフト搭載車には「Cクラス」やスポーツ用多目的車(SUV)「GLC」などの人気車種が含まれている。
大体、弁護士だから公平であると考える方がおかしい。弁護士の前に人間である。しかも、弁護士の役割は弁護する人や依頼者の利益を優先にするわけだから
公平と言っても公平に出来るわけがない。
もちろん、公平にこだわる弁護士や、弁護士の信念やポリシーに反する依頼を断る弁護士は存在すると思うが、何割の弁護士達がそのような弁護士なのか
わからない。
悪質タックルの被害を受けた関学大QBの父親が、その聴取の仕方に不信と疑念を抱いた日大の第三者委員会が、意図的にその構成メンバーにアメリカンフットボールに見識のある専門家を入れていないという驚きの方針が、複数の関係者の話で明らかになった。予断を挟まず、あえて客観的な“素人目線”で事実認定を重ねて合理的に結論を導きたいというのが理由のようだが、これは明らかに日弁連が定めている「第三者委員会ガイドライン」から逸脱している行為だ。警察の捜査ならば、いざしらず再発防止策も含めて真相に迫らねばならない第三者委員会としての姿勢に疑問と問題を感じる。果たして、こんな方針で調査を進めている第三者委員会に真実を導き出せるのだろうか?
日大の第三者委員会の構成メンバーには設置当初から問題があった。
日大は「その独立性、中立性を担保し、中立公正な立場から調査を実施していただくために、学校法人日本大学とは、これまでに利害関係の一切ない弁護士に委員長を依頼することと致しました」と、元広島高検検事長の“ヤメ検”弁護士である勝丸充啓氏に委員長を依頼。「委員の選任を一任された」勝丸弁護士は、7人全員を弁護士で構成した。自らが所属する芝綜合法律事務所からも2人選任した。
日弁連が策定した第三者委員会ガイドラインには「第三者委員会の委員には、事案の性質により、学識経験者、ジャーナリスト、公認会計士などの有識者が委員として加わることが望ましい場合も多い。この場合、委員である弁護士は、これらの有識者と協力して、多様な視点で調査を行う」とある。
まさに今回はアメフットという専門競技のフィールド上で起こった事件が発端となっており、それらの専門家を委員に加えるべき事案の性質を持つ。それなのに勝丸委員長は意図的に専門家を入れなかったのである。
関係者の話を総合すると、意図的に専門家を入れなかった理由として“専門家を入れると、その人の意見に委員会が引っ張られてしまう危険がある。メディアの情報や、これまでの情報をすべて排除して、予断を持たず、まったくのゼロから中立の立場で、客観的に事実認定だけを積み上げていきたい。だからあえてアメフットの素人だけで固めた”ということらしい。
驚きの理由だ。
10日に、勝丸委員長と磯貝健太郎弁護士のヒアリングを受けた被害QB選手の父である奥野康俊さんが、「あのタックルは怪我を軽くするためのタックルだったのでは?」と、意味不明の質問を受けて、「不愉快になった」とフェイスブックで報告した。QBがパスを投げた後の無防備な状況で背後から行われた危険なタックルを「怪我を軽くさせるために腰のあたりに行ったのでは?」と感じたのは、ルールもまったく知らない素人が7人集まって映像を見た感想だったのだろう。防具で固め、100キロを超えた人間がタックルで与える衝撃やダメージは、あの引いた位置から撮影された映像では決してわからない。
さらに奥野さんは、「何を守るための第3者委員会なのだろうか、事実を確認するだけで、真相究明する気は全くない。息子に怪我をさせた理由を知りたい」とも訴えたが、そう感じたのも、第三者委員会が、素人目線で客観的な事実だけを積み重ねていくという方針なのだから無理もなかったか。
日大側でもなく、被害者QB、当該守備選手側でもなく、中立の立場を守り、一切の予断を入れないことは非常に重要である。だが、今回の案件は、アメフットの競技特性や練習過程、チーム構築過程などを理解していなければ、聴取や調査さえ満足にできない特殊性を持っている。その影響が、いきなり関学サイドへのヒアリングで露呈したわけである。
もっと驚くのは、先月、関東学生アメリカンフットボール連盟の規律委員会の出した調査内容や結果を読み込むことも参考にすることもせず、一切、情報をシャットアウトした上で、ゼロから調査、聴取を進めているように見受けられる点だ。
関東学連は、日大、関学の当事者の聴取だけでなく、映像の実に細かい分析、当日のスタンドにいたファンの証言、当日の試合を裁いた審判の証言、通信記録、各種の音声データまで集めて多角的に調査していた。これらも規律委員会がアメフットの経験者で構成されているからこそできた調査で、その経験則をもとに「内田正人前監督、井上奨前コーチから反則タックルの指示があった」と事実認定した。
日大のチームに「はまる」という隠語で呼ばれる“試合に出さずに干す”という一種のパワハラ行為が蔓延していたことをつきとめたのも専門家だからこそ聞き出せた話だ。
これらの関東学連の出した事実認定を参考にしないことが、中立を守る、客観性を担保するということになるのだろうか。
これまでに第三者委員会の聴取を受けた関係者の中からは、「今回の問題に関して何の下調べもしてきていない様子が見受けられた」という意見さえある。
また最終報告を出すスケジュールが7月下旬にずれこんだ理由も、この“すべてをゼロから始める”という第三者委員会の方針とつながっている。一切の事前情報を入れず、自分たちで調査したことだけの事実認定を、素人が積み重ねていくのだから当然、時間はかかる。
関係者の中からは「アメフットをゼロから理解、勉強するだけで半年以上が必要になるのでは」という皮肉めいた声さえある。チームに来年3月31日までの1シーズンの出場停止処分を科した関東学連は、その処分を解除するための救済条件をつけたが、9月の今季開幕に間に合わせるためのデッドラインは7月下旬。
「今季のチームの試合出場に間に合うように調査を急ぐ」という考えは、はなから第三者委員会にはなかったのである。
第三者委員会は、事件の真相究明と同時にチームの再発防止策も提案することになっている。アメフットの年間スケジュールやチーム作りの過程、或いは、日々の練習が、どう行われ、監督と各ポジションコーチの役割が何で、その関係性はどうなっているのか、などをまったく熟知しない素人が、ゼロから事実認定を積み重ねるだけで再発防止策の答えなど導き出せるものなのだろうか。
もし彼らがアメフットの専門家を委員に入れることで結論を誘導されることを危惧したのであれば、日大と利害関係のない専門家を複数加えればいいだけの話ではなかったか。
今回の案件では「反則タックルの指示はしていない。選手の受け取り方に乖離があった」と主張している監督、コーチ側と、「反則タックルを指示された」という当該守備選手の意見が真っ向から対立している点をどう判断するかが焦点となっている。
関東学連の規律委員会は、「アメフット経験者としてのプレーヤー感覚、または指導者感覚、これまで経験、見聞きしてきた現場感覚および経験値を十分勘案しつつ、経験則をもとに最も合理性が高いと認められる事実を認定していった」との手法で、内田前監督、井上前コーチの発言を「虚偽、信用がおけない」とまで踏み込んで結論づけていた。
だが、第三者委員会の方針は、そのアメフットの経験則を一切排除して事実認定を積み重ねるだけで合理性を求めて結論を導こうとしているわけだから「灰色決着」に行き着く可能性も出てきた。そうなれば、内田前監督、井上前コーチが刑事訴追を避けるための追い風ともなり、日大トップにとっては最高の結論となるのだろう。日弁連は「社会の期待に応え得るものとなるよう」に「第三者委員会ガイドライン」を策定したのだが、日大の第三者委員会は、その精神をどう理解しているのだろうか。
(文責・本郷陽一/論スポ、スポーツタイムズ通信社)
「報復が恐ろしい」とか「怖くてできない」と思っていても、結局、日大で働いている人達が多いということか?
そうであれば、強い飴とムチが存在するのかもしれない。
日大の組織構造が日本社会の全てを反映しているわけではないが一部である事に間違いはない。
日大が変わらなければ、日本人が日本人の首を絞めているようなシステムや制度は簡単に変わらない方が良いであろう。
日大アメリカンフットボール部の部員による悪質タックル問題で、日大教職員組合が11日、文科省で会見を開き、田中英寿理事長らの会見での説明と辞任などを求め5月31日に大学側に提出した要求書への賛同署名活動の途中状況を報告した。
【写真】取材に応じる日大の大塚学長
同組合では、31日から日大の専任教員、付属高校の専任教員を対象に署名活動を開始。8日までに実施した学部と高校のうち、44・6%にあたる752人から署名が集まった。うち公開可とした署名は296人分、公開不可の署名が456人分と上回った。署名活動は引き続き27日まで実施し、実施した学部・高校の教員数の半数以上を目指す。後藤範章委員は「ここまで多くなったことに驚いている。それだけ強い危機感を持っていると受け止めている」と手応えを語った。
組合によると、教員からは「授業で学生たち全員から拍手され、思わず涙が出てしまった」「報復が恐ろしいけど、当該学生がこの何倍もの恐怖を感じていたかと思うと、教員が名前を出さないわけにはいかないと考えた」などの声が寄せられた。署名できなかったという教員からは「名前を非公開にしても、署名をすれば、本部のことだから署名の洗い出しもするのではないかと思い、怖くて怖くて、とても署名することはできません」という声もあったという。
吉原令子副委員長は「たくさんの方から応援をいただいている。今回は教職員の署名だが、現役の学生や保護者、卒業生や他大学の方にも賛同いただく手段も考えていきたい」と話した。山本篤民書記長は「オープンキャンパスでも影響は出ており、学部によっては前年比6割減というところもある。深刻な状況だ」と現状を語った。
三菱マテリアルは11日、竹内章社長(63)が辞任すると発表した。後任には小野直樹副社長(61)を充てる。22日の株主総会後に就任する。グループ企業だけでなく、今月に入り三菱マテ本体の工場でも品質不正が発覚。経営責任の明確化が必要と判断した。
竹内氏は会長に就任する。代表権を返上するが、経営陣に残ることについては批判が出そうだ。本体での品質不正では役員2人が報酬を一部返上。7月から3カ月間、鈴木康信専務が報酬の30%、酒井哲郎執行役員が10%をそれぞれ返上する。また同社は、問題を起こした直島製錬所(香川県直島町)の池沢広治所長を15日付で更迭する。
竹内氏は「一連の品質問題の経営責任をより明らかにするため、経営体制を変更する」とのコメントを発表した。今後はグループ全体の企業統治体制の強化に関する指導などを行うという。
昨年11月以降、三菱マテの子会社で品質データの改ざんが相次いで見つかり、今年3月に調査報告書と再発防止策を公表した。竹内氏は月額報酬全額の3カ月返上を表明したものの、引責辞任を否定していた。
その後も品質不正は止まらず、三菱マテは8日に本体の直島製錬所で必要な検査を行わないままJIS認証のコンクリート材料を出荷していたと発表。認証機関がJIS認証を取り消す事態となっていた。
批判の声を上げられないほど組織からの圧力がかかっていると言う事であろう。
日大のような組織は無くなるべきだと思う人は、子供は日大関連の学校に行かせないなど行動を起こせばよいと思う。多くの人が同じ考えや行動を
起こせば、日大は結果として無視できなくなるであろう。
今後、どのようになるのかは日大だけでなく、どれだけの批判的な人達が行動を起こすか次第である。行動を起こさず、批判だけする人達は
いつか本人達が被害者になったら自業自得だと思う。
日大アメリカンフットボール部の反則タックルが行われてから1カ月余りたちます。選手の発言や部員の声明文が、率直に事実を語り反省しています。それに対して、大学側の不誠実な対応に、多くの人があきれています。こうした状況に、ジャーナリストの川井龍介さんが日大内部からなぜ執行部批判の声が広がらないか、疑問を投げかけます。【毎日新聞経済プレミア】
◇「加害者側」の自覚を感じない学長
関東学生アメリカンフットボール連盟は、日大の前監督、元コーチが反則タックルを指示したと認定し、前監督、元コーチの説明にウソがあったと結論づけました。これに対し、日大の大塚吉兵衛学長は、「どうしてあそこまで否定されるのか」と不満を表しました。
前監督は大学を代表する常務理事という職にありました。また、日大は、関西学院大の選手にけがをさせた加害者であり、自分の大学の選手を加害者に仕立てあげた疑いが濃厚であるという点でも加害者です。しかし、大塚学長の言葉や態度にはとてもその自覚を感じ取れません。
◇部員に「第三者委員会は必要ない」との声も
関東学生連盟は前監督、元コーチの説明をウソと結論づけた理由をいくつかあげています。反則を見ていなかった、落としたインカム(ヘッドホン)を拾っていたという前監督の発言に対して、映像で視線を確認した、インカムを拾う動作をしていない、といった主張です。その認定に不満なら、具体的に反論すべきです。
日大は第三者委員会を設置しました。ですが、そのように問題を複雑にする意味があるのでしょうか。第三者委員会を「隠れみの」にし、ほとぼりが醒めるのを待っているのではないでしょうか。アメリカンフットボール部員からも「第三者委員会は必要ない、前監督や元コーチが本当のことを話せばすむことだ」という声が上がっているようです。
第三者委員会のヒアリングに対して選手や部員は正直に語るでしょう。しかし、前監督、元コーチが、強制力のないヒアリングに、自ら不利になることを正直に語るとは思えません。意見や認識の違いといった結論になれば、学生の勇気ある発言が報われることはありません。
◇危機管理やガバナンスの専門家がずらり
いま話題になっている日大危機管理学部のホームページを見ると、「多彩な危機と向き合う研究者教員と、危機の現場に精通した実務家教員」がそろっていると書いてあります。「企業広報論」「憲法と人権」「ヒューマンエラー論」など、まさに実社会と密接な関係をもつ研究を担当している教授陣がいます。
危機管理学部は今回の件に直接関係ないのはわかります。しかし、日大に対して社会がここまで厳しい目を向けているなかで、なぜ、日大内部から声があがってこないか不思議でなりません。同学部だけではありません。法学部には企業ガバナンス、文理学部には教育学や社会学など、今回の問題と密接に関係するテーマで教べんをとる人たちがいます。
日大の教職員組合の人たちが取材に応じて大学の対応を繰り返し批判しています。そうした声がなぜ広がらないのでしょうか。一番不利益を被っているのは何の責任もない日大の学生です。こうした専門家の方々に、学生のためにひと言語ってほしいものです。
日本大学アメリカンフットボール部の危険タックル問題で、内田正人前監督(62)は常務理事を辞任するところまで追い込まれた。さらに6日には、日大が出資し、大学のグッズ販売や保険代理店業務などを行う企業「日本大学事業部」の取締役も5月30日付で辞任していたことがわかった。
【写真】公の場での説明をしていない田中理事長
だが、連日メディアを騒がせたこの問題が幕引きになるわけではない。むしろ、日大の内情をよく知る人であればあるほど危機感は強い。元理事の一人は、悲愴な面持ちでこう話す。
「理事会の仕組みを根本的に改めない限り、この問題が解決することはない。大塚吉兵衛学長(73)は、会見で自分自身が大学のトップであると強調しているが、そんなはずはない。日大のトップは田中英寿理事長(71)で、内田前監督の最大の後ろ盾。内田前監督がいなくなったとしても、理事長がそのままでは問題は何も解決しない。大学の対応が遅れた背景にも、理事長の存在があることは関係者はみんなわかっている」
内田前監督が取締役を務めていた日大事業部も、田中理事長の肝いりで2010年に設立された。民間の信用調査会社によると、2012年の売上は約5億円だったが、17年は約70億円に急成長。だが、利益は約5400万円しかない。日大関係者は「多額のカネが集まっているのに、それがどこに行っているのかは職員でもわからない」と話す。
日大の総学生数は11万人以上、年間予算2620億円(2018年度)、うち補助金の収入は150億円を超える。その中心にいる田中理事長は、日大の“ドン”とも呼ばれている。大学の資金に大きな権限を持ち、政敵には非情な人事をすることで知られている。
「田中理事長は、自らに敵対した人間は徹底的に外す。気に入らない職員は異動で本部から遠ざけ、元教授で退職後に大学に入れなくなってしまった人もいる。それが怖くて周囲はイエスマンばかり。理事会も評議会もほとんどが田中派で占められている」(前出の元理事)
田中理事長は、1969年に日大を卒業した後に日大職員になり、相撲部の監督も務めた。99年に理事、2002年に常務理事、08年に理事長に就任。運動部を束ねる保健体育審議会の局長もつとめ、学内の権力基盤を固めたといわれる。だが、近年は独断専行も目立っていたという。そのきっかけの一つとなったのが、総長制から学長制への移行だ。
「田中理事長が学長制に変更したのは2013年。これで田中理事長の権限が強くなり、自分勝手な人事も最近は目立っている。日大事業部の人事でも相撲部出身とアメフト部出身が優遇され、学内では不満も出ていた。それでも、誰も何も言えない。『もの言えば唇寒し』どころか、『もの言えばクビが飛ぶ』という状況ですから」
理事長の巨大な権限を示す象徴的な例がある。日大は田中理事長が中心となり、16年に危機管理学部とスポーツ科学部を新設。両学部とも三軒茶屋(東京都世田谷区)にキャンパスを置くが、事務方のトップである事務局長クラスのポジションに、田中理事長自身がついているのだ。また、田中理事長を後ろ盾として日大ナンバー2の地位にあった内田前監督は、常務理事であると同時に、人事部長と保健体育審議会局長も兼任していた。
「理事長が事務局長クラスにつくことも、常務理事が人事部長を兼ねることは日大の歴史では異例なこと。私は聞いたことがない。大学のトップが現場の中心にいるようなものですから、大塚学長が大学の運営に意見できるわけがないんです」(前出の日大職員)
関西学院大との交流戦で危険タックル事件が起きたのは、5月6日。その後、メディアで繰り返し日大批判が起きても、大学は内田前監督をかばうような発言を続けた。それもそのはず、日大の内部において「田中理事長と内田前監督は、何をやっても治外法権」(前出の日大職員)だからだ。田中理事長は公の場で説明もしていない。前出の元理事は、「学生を守ることよりも、理事長への責任論が及ぶことを避けているとしか思えない」(前出の元理事)と憤りを隠さない。
それにしてもなぜ、田中理事長はこれほどの権力を得ることができたのか。そこには、日大の過去の総長選で起きた激しい権力闘争があった。前出の元理事は言う。
「田中理事長が頭角をあらわしたのは、瀬在幸安総長(96~05年)の時。ただ、在任中から二人は対立し、特に05年の総長選挙は激しいものでした。瀬在さんの自宅には03年に銃弾付きの脅迫状も届き、そこには『晩節を不名誉と血で汚すな』『辞職を勧める』と書かれていました。結果は、田中理事長が支持した小嶋勝衛先生が勝利し、瀬在元総長が推した候補を退けました」
田中理事長は、とにかく選挙に強い。瀬在総長以来、4代にわたって田中氏が支援してきた候補が選挙で勝利してきた。日大の総長選は現金が乱れ飛ぶと言われ、その中で無類の選挙の強さを持っていた田中氏は、自らの推した候補を当選させることで出世を重ねてきた。
だが、田中氏のもとからは次々に人が離れていく。瀬在氏だけではなく、小嶋氏やその後任である酒井健夫元総長も、就任後に田中理事長と距離を取るようになった。田中理事長の周りに人がいなくなるのは、“黒いウワサ”が絶えなかったからだ。
「田中理事長は、学内の建設工事で業者からリベートを受け取ったり、暴力団関係者との付き合いが疑惑として持ち上がるなど問題が多かった。それで、歴代の総長は就任後は田中理事長の学内の影響力を削ごうとしてきた」(前出の日大職員)
田中理事長の疑惑については、検察出身の弁護士など6人による特別調査委員会が学内で立ち上がったこともある。05年8月には、中間報告書もまとめられた。校舎新築工事に関連して田中理事長が業者からリベートを受領したことや、暴力団関係者との交際についても疑いの強い事実として認定され、同様の内容はメディアで報道されたこともある。
だが、瀬在総長が05年8月末で退任したことで、中間報告書が「最終報告書」になることはなかった。そして13年6月、学内で再度設けられた別の調査委員会が、新たな報告書をまとめたと日大が公表。そこでは中間報告書の記述はすべて事実ではないと否定された。現在も日大広報部は中間報告書の記述について「事実ではありません」と回答している。
裏金や黒い交際などの疑惑が問題になりながらも、田中理事長は権力の階段を登り続けた。そして、最後に理事長に就任することになる。その時も激しい選挙闘争が展開された。
「08年に就任した酒井先生は、理事長を教員から任命しようとした。それに対して、当時、常務理事だった田中氏が理事長選に出たことで選挙になった。理事長選びが選挙になったのは初めてです。結果は、16対13の僅差で田中氏が勝利。以来10年間にわたって理事長の座に君臨してきました」(前出の元理事)
その田中理事長も、すでに71歳。数年のうちに退任するとの話も出ていたが、日大幹部の間では田中理事長の意向で「次の理事長は内田正人」というのが共通認識でだったという。
長い年月をかけて日大のトップとなった田中理事長。それでも、学校法人を経営するにふさわしい見識のある人であれば、危険タックル問題は起きなかったかもしれない。ところが、そうでないことが日大の悲劇だった。
「理事長に大学運営に関する教養があるとは思えない。そもそも、漢字の読み間違いが多くて、学内のスピーチで『道半ば』を『みちはんぱ』と読んだり、日大豊山(ぶざん)高校を『とよやま高校』と読んだこともあった。これでちゃんとした大学運営ができるのかと、理事長の話を聞いた大学の教員たちもあきれていました」(前出の元理事)
日大広報部は、AERA dot.編集部の取材に対して、漢字の読み間違いについて「事実は確認されておりません」と回答した。
被害を受けた関西学院大のアメフト部選手の父親は、自身のフェイスブックで「ここまでの社会問題となった事に対して、大学としてのガバナンスについて、代表である田中理事長の記者会見を希望する」と述べている。一度も表舞台で説明をしていない田中理事長に対し、説明を求める声は日増しに高まっている。
(AERA dot.編集部・西岡千史)
テレビ朝日の対応次第では、悪質タックルの日大ほどではないが、イメージを落とすであろう。
〈家に誘われる〉
〈身体を触られる。キスを迫られる〉
〈社内での過度なボディタッチ〉
──生々しい「被害報告」の数々。これは、テレビ朝日で行われたセクシャル・ハラスメントに関するアンケート結果に記された文言である。そこに書かれた衝撃的な実態からは、テレビ朝日のセクハラに寛容な体質が浮かび上がってくる。
アンケートは、テレビ朝日労働組合が4月27日から5月11日の2週間にわたって実施したものだ。4月、財務省の福田淳一・前事務次官による同社女性社員への「胸触っていい?」「手縛っていい?」といったセクハラ発言が大きな問題となったことを受けて、組合がハラスメントの実態を把握するためにアンケートを行なったのである。
調査はセクハラだけではなく、パワー・ハラスメントや、それ以外のハラスメント被害、会社への意見なども問われるものだった。また、セクハラは「社内関係者からのセクハラ」と「社外関係者からのセクハラ」に分けて聞かれた。
その結果は5月中旬、『ハラスメントに関するアンケート調査報告』と題されたA4版10ページにわたる「組合ニュース No.054」という資料にまとめられ、組合員向けに配布された。
まず驚くのは、セクハラを受けたことがあると答えた社員の割合だ。アンケート対象者は組合員706人(男性507人、女性199人)。結果によると、「セクハラを社内関係者から受けたことがある」と答えた人は、回答した462人中92人で約20%となっている。
ところが女性だけにしぼってみると、回答者126人中71人。実に56.3%が社内関係者からのセクハラ被害に遭っていることが判明した。
◆一般的な企業の「2倍」の被害
この数字をどう見るか。独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が25~44歳の女性労働者を対象としたアンケート調査の結果(2016年)によると、セクハラを経験したことのある人の割合は28.7%となっている(※)。テレビ朝日の女性社員がセクハラを経験した割合は、「社内関係者」からの被害だけで言ってもざっと世間一般の2倍と言える。
具体的な被害内容は冒頭の3例のほか、
〈交際関係を暴露される〉
〈恋人の有無やタイプを聞かれる〉
〈卑猥な言葉を浴びせられる〉
といったものがあった。さらに〈性的な誘いをされる〉といったケースも(いずれも前出の「組合ニュース」より)。
同社総合編成局の若手社員が明かす。
「最近まで、局幹部によるセクハラが実際にありました。番組関係者の飲み会の席で、局幹部の隣によく座らされる若手の女性社員がいるんです。男性幹部は酔ってくるといつもその女性社員にボディタッチをしていて……明確に嫌がっていて、それを見ている人もいるはずなのに、みんな見て見ぬふりです。かくいう私も何も言えないのですが」
福田氏によるセクハラ問題では、テレビ朝日が“被害者”として財務省へ抗議文を提出しているが、少なくともテレビ朝日にはセクハラについて“見て見ぬふりをする土壌”があったのではないか。それが世間一般の「2倍」という被害につながっているのではないか。
◆「官舎に入るように」のセクハラも
社外関係者からのセクハラ被害も深刻だ。前出の「組合ニュース」には、〈官舎に入るように言われる〉、〈性的関係を迫られる〉、〈取材相手と1対1で飲んだ後のエレベーター内で迫られる〉、〈取材先から身体を触られたりしたが、重要局面で情報を得ねばならず我慢〉したというケースが報告されていた。最後はまさに福田氏のセクハラと同じ構図である。
テレビ朝日広報部に、「アンケート結果をどう考えているか」「普段行っているセクハラ・パワハラ対策」「ボディタッチなどのセクハラを現在進行形で受けている被害についての対応」などを問うた。以下、回答全文を掲載する。
〈労働組合が独自に行ったアンケート調査であり、調査結果についての個別具体的なお答えは控えさせていただきます。調査結果は従業員の声として受け止め、今後のハラスメント対策の参考にしていきます。
セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント対策については、プライバシーに配慮したハラスメント・ホットライン(通報窓口)を設け、通報に対応しています。また、毎年発行するコンプライアンスハンドブックを使った職場ごとの研修、コンプライアンスセミナーの実施、就業規則における懲戒規定などの対策を講じています。前財務事務次官によるセクハラ問題を受けて、現在、社内の特別チームがセクハラ・パワハラ対策について総合的に検討しており、その結論を踏まえ、さらに対策を進めていきます。
現在の具体的なハラスメント被害については把握していませんが、対応すべきものがあれば、適切に対応してまいります。〉
では、組合側はどう捉えるか。テレビ朝日労働組合に「アンケートを行った目的」「社内・社外関係者からのセクハラについての見解、対策」「今後、会社側へどんな働きかけを行っていくか」などを聞いた。こちらも回答全文である。
〈今回のアンケート調査は、労働組合として会社に労働環境改善を求めていくうえで、ハラスメントに関して過去も含めて実態を把握するために実施したものとなります。アンケート調査は率直に記入してほしいため個人や職種が特定されない無記名で行いました。ハラスメントについては、労働組合としても看過できない問題として捉えています。アンケート調査の結果を組合員の声として会社に伝え、労働環境改善に向けた対策の一助になればと考えています。
労働組合は、会社が設置している相談窓口とは別のものとして、「会社には直接相談しにくい」、「まわりに相談できる人がいない」など会社の窓口に相談するのをためらう組合員のための相談窓口の役割を担っている認識でいます。
今回のアンケートでは、過去の被害も含めて全てを受け止めることで、今まで相談できなかった組合員や相談をためらっていた組合員に対して、労働組合は全てを受け止め真摯に対応するというメッセージも込めています。
今後、労働組合の窓口が相談しやすいものとするために、情宣等の対策がさらに必要だと感じています。労働組合としては、「ハラスメントがない会社」を実現したいと考えており、会社も同じ方向を向いていることを確認しています。今後も組合員の声を大事にしながら、会社の動向を注視しつつ、協議していくことが必要だと考えています〉
テレビ朝日は、一般的な企業で働く女性の“2倍”というセクハラ被害の蔓延に一刻も早く手を打つ必要があるだろう。
※労働政策研究・研修機構の「妊娠等を理由とする不利益取扱い及び セクシュアルハラスメントに関する実態調査結果」(2016年5月)より。
5月6日の関西学院大学との定期戦で、宮川泰介選手に悪質タックルを指示したとされる日大アメフト部の内田正人前監督(62)。日大アメフト部OBであるA氏が、内田氏からの依頼で裏金を渡したことを「週刊文春」のインタビューで明らかにした。
【写真】内田氏への送金が記されたA氏の通帳
「私は2004年から8年間にわたり裏金作りを手伝ってきました。内田前監督に銀行振り込みや現金手交という形で、1回100~200万円、総額で1500万円を超える裏金を渡してきたのです。今回の問題で日本大学アメフト部、さらには日本大学の権力構造について様々な問題が指摘されています。これを機にあらゆる膿を出し切って、母校に再生してもらいたいという気持ちから、自戒を込めてすべてをお話しすることを決意したのです」
A氏が裏金工作を持ちかけられたのは、03年に内田氏が監督に就任して間もない頃だった。アメフト部に備品などを納入する会社を経営していたA氏は水増し請求によって裏金を作っていたという。
日大広報部は「本学の施設などの建設、備品購入は、すべて本部管財部が行っており、不正購入などの余地はないと判断しております」と回答。内田氏が取材に応じることはなかった。
6月7日(木)発売の「週刊文春」では、A氏の独占インタビューを5ページにわたって掲載。さらに悪質タックル事件の事態収拾にあたる別の常務理事の金銭トラブルも詳報している。
「週刊文春」編集部
日本年金機構からデータ入力を委託され、大量のミスをしていた「SAY企画」(東京都豊島区)が解散し、清算手続きに入っていることが分かった。
同社が5日に株主総会を開き、会社法に基づき解散を決議したことが6日付の官報に公告された。
機構は昨年8月、所得控除に必要な個人情報の入力などを同社に委託したが、同社は契約に反して約500万人分の個人情報の入力を中国の会社に再委託したほか、約95万2000人分で入力ミスもあった。
機構によると、同社のミスで生じたおわび状や相談電話の受け付けの費用などで、機構の損害額は約2億円に上り、機構は同社に支払う予定だった委託費と相殺した約1億6000万円の賠償を求めている。
スバルは5日、出荷前の自動車の排ガスと燃費の検査の測定値を改ざんしていた問題で、新たな不正が見つかったと発表した。不正の台数は従来の903台から1551台に増えた。スバルは、改めて社外の専門家による再調査をして、国土交通省に報告する予定。
【写真】測定値改ざん問題で新たな不正が見つかったことを受け、会見の冒頭で謝罪するスバルの吉永泰之社長=2018年6月5日午後5時4分、東京都渋谷区、越田省吾撮影
スバルによると、データを測定するときに、道路運送車両法の保安基準で決められた速度を逸脱したのに、測定をやり直さず、有効なデータとして処理していた。測定室内の湿度が基準外だったにもかかわらず、有効としたケースもあった。
4月下旬に国交省に提出した調査報告書では、書き換えは基準内だったと説明していた。
一方、今月22日の株主総会後に代表権のある会長に就いて最高経営責任者(CEO)も兼務すると表明していた吉永泰之社長は、代表権を返上し、CEO職も兼務しないと発表した。後任の社長に就く予定の中村知美専務執行役員がCEOを兼務する。吉永氏が対内業務に専念して企業体質の改革を強力に進め、中村氏が経営全般を指揮するためという。
関西アーバン銀行(大阪市)は1日、男性行員(34)が顧客から預かった現金約1億7千万円を着服していたとして、5月31日付で懲戒解雇処分にしたと発表した。元行員は「競馬などの遊興費に使った」と話しているという。同行は大阪府警に通報したという。
同行によると、元行員は寝屋川支店(大阪府寝屋川市)と生野支店(大阪市)で営業担当だった2013年9月~今年4月、顧客に対して定期預金を勧誘。預かった23件分の普通預金の払い戻し請求書などを悪用し、不正に現金を出金していた。現金は後日戻していたが、発覚した時点で約9200万円が未返金だったという。同行は「本件事態を厳粛に受け止め、深く反省している」としている。
学校法人「加計学園」の獣医学部新設をめぐり愛媛県が国会に提出した文書に対し、学園側が「県と今治市に誤った情報を与えた」とコメントを出した問題で、学園の渡辺良人事務局長が31日午前、愛媛県庁を訪れ、「多大な迷惑を掛け、誠に申し訳ない」と謝罪した。
中村知事は台湾へ出張中で不在のため、担当部長が対応したという。午後には今治市も訪れる。
愛媛県が21日、国会に提出した文書には、平成27年3月3日に県と今治市職員が学園関係者と意見交換した際、学園側から受けた報告として、同年2月25日に安倍晋三首相と加計孝太郎理事長が面談し、獣医学部の新設について安倍首相が「そういう新しい獣医大学の考えはいいね」とコメントしたと記されている。
ただ、安倍首相は加計理事長との面談を否定。学園側は今月26日、「実際にはなかった総理と理事長の面会を引き合いに出した」と報道機関宛てにファクスでコメント、誤った情報だったと認めた。中村時広知事は「県への説明がない」などと不快感を表していた。
31日放送のTBS系「ひるおび!」(月~金曜・前10時25分)では、日大アメリカンフットボール部の悪質タックル問題を特集した。
【写真】関東学連の罰則規定と日大関係者の処分内容
番組では元アメフト部員を取材し、同部の暴力の実態について証言した。証言したのは昨年までアメフト部に所属していた男性で「殴る、蹴る、つねる、はたく、投げ飛ばすとか独裁国家みたいな感じになっていますし、それ従わなかったら、次はないぞと地獄のような日々でした」と振り返り「コーチの思い通りの動きが出来ずにボコボコに殴られたり、腕とか胸をつねられるのは日常茶飯事で、ここで辞めたらお前、もう二度とないぞみたいなプレッシャーをかけてきたりしてましたね」と証言した。
練習では「コーチがグラウンドに出てきた時にやっぱり雰囲気で分かるもので、そのイライラの矛先が誰に行くのかみんなピリピリしながら練習をやって、一人がターゲットになった時は今日はアイツだから俺じゃないのかみたいな日々でした」と告白。さらに「元チームメイトとかはあごを手のひらで殴られて、そのまま壁まで持って行って、顔面を壁に叩きつけられて、おなかにパンチを食らってうずくまっているところに背中から肘打ちで殴られたりして、すごいリンチみたいになっていましたね」と明かした。一方で「中にはコーチに嫌われたくないとか好かれたい思いで、コーチの体罰を手伝っている選手もいました」とし暴力だけでなく言葉でも「死ねなどは日常茶飯事でお前みたいなやつを育てるなんて、親もクズだなとか」と罵倒されたという。
こうした現実を男性は親にも相談できず「親に相談するというよりも選手間で解決したりとか自分の中で泣き寝入りとかして過ごしていました」と振り返った。男性は昨年3月に退部したが、この時に「部屋の中で怒鳴られながら、おかしいと思わんのか?とか考え方やばいぞ、みたいなそこまで否定されて、中には家まで来て夜中の遅い時間とかにも家の扉や窓をたたかれている選手もいて、家にいるなら出て来いよと」という実態を明かしていた。
日本にこんなにも偽善者達が存在し、平気で公に嘘を付いているのを見ていると、個人的に人を基本的に信用してはいけないと考えてしまう。
加計(かけ)学園による獣医学部新設に関連して愛媛県が国会に提出した文書をめぐり、文部科学省は30日、学園側の発言として「文科省が獣医学の専門家に意見照会をしている」と記されていることが、事実と符合すると認めた。この記述は、安倍晋三首相と加計学園理事長が面会したことと関連づけた書き方となっている。首相と学園側はそれぞれ面会を否定しているが、文書の他の記載の信用性が改めて示された形だ。
県が21日に出した文書では、2015年3月3日に加計学園から「2月25日に理事長と安倍首相が面会した」と報告があったと記されている。さらに15年3月15日に県、今治市と協議した際の学園側の発言として「文科省から獣医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議委員に対する意見照会を実施している模様」と記述。続けて「2/25に学園理事長と総理との面会時の学園提供資料(略)を抜粋したアンケート形式の資料を示して、短期間での回答を求めている」と書かれている。
30日の衆院文部科学委員会で、立憲民主党の川内博史氏がこの記載について質問。文科省の義本博司・高等教育局長は「愛媛県から獣医学部を新設した場合に取り組むべき事項について提案」があり、「専門的な知見からの意見をうかがうため、15年3月ごろ、有識者会議の委員に意見照会をした」と認めた。
県文書に登場する「資料」について、義本氏は「確認中であり改めて報告する」と述べるにとどまった。川内氏は「(首相と理事長が)面談していなければ、ここまで具体的に書けない」と指摘した。
レオパレス21は1996年から2009年に建てられた施工物件の一部に、建築基準法違反の疑いのあるものが発見されたと発表しました。耐火や遮音のため、共同住宅の各住戸間に設置される「界壁」が施工されていない、もしくは施工が不十分なものが発見されたとのこと。
「ゴールドレジデンス」「ニューゴールドレジデンス」など6つの物件シリーズで、棟数1万3791棟のうち5月26日時点で290棟の調査が完了。17棟が界壁なしの状態で、21棟が施工不備の状態だったといいます。また4月27日、「確認通知図書と施工内容が一部異なっている」と発表していた集合住宅「ゴールドネイル」と「ニューゴールドネイル」についても、調査対象915棟のうち184棟の調査を完了し、168棟に界壁が設置されていなかったとしています。
発生原因として、物件のバージョンアップが頻繁に行われていたことや、図面と施工マニュアルの整合性に不備があったことが確認されている他、社内検査体制も不十分だったとしています。今後は施工物件3万7853棟について順次調査を進める他、問題が確認されたものについては順次補修工事を行い、2019年10月の工事完了を目指すそうです。
日大アメフト部OBの50代男性が29日、フジテレビ系「直撃LIVEグッディ!」(月~金曜・後1時45分)にVTR出演し、昨夏、日大・内田正人前監督(62)から暴行を受けていたことを赤裸々に語った。
番組の大村正樹(51)フィールドキャスターが28日、30年前、当時コーチだった内田前監督と選手の関係だったというAさんにインタビューした。
Aさんの息子は有力アメフト選手だったが日大の付属高校ではなかったこともあり、日大以外のアメフト強豪大学への進学を決意したという。だが、その情報を聞き入れた内田前監督から、息子の高校の監督経由で日大アメフト練習場に呼び出された。
内田前監督から「OBの息子なんだからなんで(日大に)来させないんだ」と問われたAさんは謝罪し、「息子も他大学に行くのが決まっていましたので…」言い返さなかったという。しかし、内田前監督は場所を移し、一方的にAさんに殴る蹴るの暴行を振るったという。
同年代の大村キャスターは「50代のお父さんが監督に暴力を受けたということですか?」と聞き返すと、Aさんは「『ふざけんな』という形で手が出て来た。口の周辺とあと蹴りが何発か合計5発前後…。結果としては口の中が切れています。事実です」と告白した。
Aさんの告白に「50代になって人から手を挙げられるってない。私も50代ですけど考えられない」と驚いた大村キャスター。
Aさんは「私もこんな年になってまで、『シメられる』とは思っていませんでした。正直、頭にきました」。大村キャスターが「立派な事件ですよね」と聞き返すと「事件と言えば事件なのかもしれないですけど、私としましてもその辺で、例えば訴えるとか告発するとか、そういう手も当時はあったと思うんですけど、現役の選手たちに迷惑をかけたら申し訳ないと思った」と振り返った。
高校の監督に日大への誘いの話はあったが「大学側から息子へのスカウトの話はなかった」。また、息子が母校に進学することについては「ちょうど日大の方で20名くらい大量退部者が出たといううわさも耳に入っていましたので、普通の話じゃないと思った。自信を持って『行け』と言える状況ではなかった」と当時を回顧した。
最後に「まず現役選手たちが、またフットボールをできることを願っての今回のお話で、正直に言いまして、内田監督が何らかのかたちで学校に残るようになれば、それはそれで部にかかわってくる可能性が将来的にあるので、潔く全てから立ち去って頂いて、監督自体もOBなので、部が復活してくれることに協力していただきたい。選手を守って下さい」と同大学アメフト部OBとして訴えた。
MCの安藤優子キャスター(59)は「聞けば聞くほど理不尽すぎて、こんなこと本当にあったんだっていう。びっくりすぎて言葉を失いました」と内田前監督の暴行にあぜんとしていた。
最近は昔のように力や圧力だけで幕引き出来なくなったと思う。力や圧力で幕引きして来た時代の人は、理論的に納得させることが出来るような 説明が出来ないと思う。なぜなら、反論や口答えを許さない環境で生きてきたのであれば、そのような能力は必要とされない。
話せば話すほど、ボロが出る。だから、隔離する、又は、逃げる口実として入院する可能性もある。
担当医師か、事実は知らないし、多少、オーバーに判断してくれる医師も存在すると思う。
「肉体的には屈強そうなスポーツの指導者たちですが、メンタル面は弱くなって逆境に耐えきれなかったのだと推測できます。」
肉体的に過ぎれている事とメンタルが強い事はイコールでもないし、正比例や反比例でもないと思う。
メンタル的に弱くても肉体的に圧倒的に強ければ、メンタル的に弱くても試合には勝てると思う。しかし、肉体的、又は、そして、能力的にも 大きな差がなければ、メンタル的に弱い方が負けると思う。委縮した人間がほぼ同じ能力の条件で勝てる可能性は低いと思う。
信じる力やどうしても勝ちたいを思う気持ちが強ければ多少の能力の違いであれば、勝てる場合もある。メンタル的に弱くても、 恐怖心や負けた後の体罰を上手く利用すれば、嫌な思いをしたくないとの気持ちの方が強ければ通常の状態よりも良い結果が出せる事もあると 思う。たぶん、50%以上の確率で、この方法が有効だと思う指導者が存在するから、恐怖、体罰、肉体的、又は、精神的な苦痛を与える 方法が広まったし、残っているのだと思う。
メンタル的に弱い人間ほど怖、体罰、肉体的、又は、精神的な苦痛を与える方法ほど有効だと思う。悪質タックルを行った選手は精神的に 弱い面があるから圧力に屈したと思うし、汚い人間として生きていくことも出来ないが、事実を公表した後のリスクを理解した上でする公表する勇気が あったのであろう。
パワハラもケースバイケースであるが似たようなケースもあると思う。
アメフトの関係組織やスポーツ庁の対応次第で、日本社会の一般的な反応を推測できるかしれない。適切な対応を取らないのであれば、違いの程度は あれ、日本社会の現実を反映すると思う。
日本中をあきれさせている日本大学のお粗末な対応と組織の異常さ。日大のアメフト部の内田正人前監督やコーチ陣の真実を一切語らない姿勢。そして、日大関係者がタックルをした学生のみに罪を被せるような姿勢を取りづける事に、あいた口が塞がらないと感じた人も多いでしょう。この異常事態の根本原因は「体育会系」のコミュニケーションにあります。今回は『1秒で気のきいた一言が出るハリウッド流すごい会話術』の著者が、体育会系コミュニケーション起こす弊害、会話の断絶の危険性について解説します。
● 「結果が出たら俺の手柄、失敗は部下の責任」が 体育会系上司の本質
世間をあきれさせているアメリカンフットボールの試合における悪質タックルに端を発する日本大学の対応。もはや試合におけるルール違反行為そのものよりも、日大関係者の隠ぺい体質やパワハラ体質、そして組織の腐敗ぶりに世間の怒りは向かっています。
まだ真相は解明されていませんが、1つ言える事があります。それは、この事件の大きな原因の1つが、「日大アメフト部が、体育会系コミュニケーションを行っている組織」であるという事です。今回は、わかっていない事が多いので、日大タックル問題の根本原因についての私の推論を述べさせていただきます。
さて、実際にタックルをした学生は、日大指導者から悪質なタックルをするように指示されたと告白しています。一方で、指導者たちは自分たちの責任ではあると言いながらも、それは意気込みの話であって、悪質なタックルをしろという意味ではないと主張しています。
仮に双方の主張が事実だとしましょう。なぜ、こういう意思疎通のズレが起こるのでしょうか。それは、一般的に体育会系を自負する上の立場の人は、下の立場の人に非常に曖昧な、最小限の指示しか与えない傾向があるからです。
それにも関わらず、下の立場の人からの簡単な質問に対してすら、「口答えするな」と受け付けない傾向があります。これでは、下の立場の人は、上の顔色を伺いながら、ある意味、カンや忖度で動くような状態に追い込まれてしまいます。
なぜ、上の立場の人が、こういう状態を作るのでしょうか。それは、この手法が彼らに非常に強力なパワーもたらすからです。なぜなら、こういう意思疎通の方式で下の人に指示を与えている人は、結果が出れば自分の手柄にする事ができ、悪い結果が出れば部下の責任にする事が可能になるからです。
また、そういう構造ゆえ、上の人は組織の現状を把握しにくくなっていき、何が事実なのかが分からなくなりがちです。さらに、下の人間への適切な指示を行う能力も低下していきがちです。
● リーダーシップがない人間ほど 忖度を強いる体育会系を好む
よく、「日本企業は下々の現場の人の能力は高いのに、組織の上の人の能力が低い」と嘆かれる事があります。その原因の1つが、体育会系コミュニケーションにある事が、これでわかったと思います。絶対に無理と多くの人が思っていても、「アメリカに勝てる!」としか発言できなかった戦前と、まだ日本のコミュニケーションレベルは、たいして変わっていないです。
さて、仮定の話ですが、今回の悪質タックルがここまで大問題にならず、大学アメフト界だけのプチトラブル程度だった場合はどうなっていたでしょうか。おそらく当該選手の出場停止などの処分で片付けられたのではないでしょうか。あるいは、「監督の手腕でチームを有利な状況に導いた」という評価になっていたという可能性もあるでしょう。
しかし、今回のように事が大きくなってしまうと、こういう体育会系組織は大崩壊します。なぜなら、前述のように、多くの上の人間は下の人間に忖度させて組織を動かしているので、いざという時にリーダシップを発揮できないからです。また、普段から自分の周りにイエスマンばかり並べていると、メンタルが弱まってしまい、逆境に非常に弱くなっているからです。
● 会見直後に入院した内田氏、 パワハラ発覚後に入院した栄氏
だから、大学関係者は、危機対応がシドロモドロになっていて、内田元監督に至っては、メンタルがやられて入院するまでの話になってしまうのです。ちなみに、最近、似たような事例があるのが思い出されませんか?レスリングの伊調馨選手へのパワハラが認定された栄和人氏も、自分に対する世間からのバッシングが起きたら、すぐに入院してしまいました。
これも、自分の心を弱くする「体育会系コミュニケーション」を駆使していた事が、大きな原因の1つだと思われます。肉体的には屈強そうなスポーツの指導者たちですが、メンタル面は弱くなって逆境に耐えきれなかったのだと推測できます。
このように、「体育会系コミュニケーション」は、人間も組織も弱体化させ、いずれ大問題を引き起こす要因となりますので、取り入れてはいけないコミュニケーション方法なのです。今回の日大タックル問題は、いまだ日本では広く普及して、礼賛する声も多い「体育会系コミュニケーション」を見直すきっけかとなるのではないでしょうか。
もし、自分は体育会系だと自覚していたら、まずはできる限り「話しかけやすいオーラを出す」という意識を持つようにしてください。「話しかけやすいオーラ」については次回、詳しく解説します。
渡辺龍太
ビバックがPROEARTHに続く
5月7日、建設機械販売・レンタルのビバック(東京都品川区)が東京地裁へ自己破産を申請、同日破産手続き開始決定を受けた。負債総額は子会社と合わせて約195億円と今年2番目の水準に達した。
倒産理由は2017年末に倒産したPROEARTH(神奈川県厚木市)に対する連鎖倒産だ。両社ともに、銀行から融資を受けて建機を仕入れ、リース会社と組んで物件を貸し出すレンタル事業を手がけ、東日本大震災の復興需要なども追い風に会社設立から10年余りで年商200億円に迫る急成長を遂げていた。
だが、彼らがあまりに高くメーカーから買い過ぎ、在庫を持ち過ぎていることを危惧する声は多かった。他社の顧客を奪う強引な営業など傍若無人さも敵をつくった。
在庫は両社間で、もしくはグループ会社やそのほかの親密取引先と融通、転売し合う。循環取引であったかどうかはともかく、相当に危うかった。
PROEARTHに対する焦げ付き額は8億1800万円。「16年秋から段階的に取引を縮小、17年春には完全に取引を解消した」と言明していたにもかかわらず、ふたを開けてみると実質債務超過に転落する巨額損失だったことで、信用は完全に失墜した。
年末からは債権者が押し寄せ、資金繰りのために建機をたたき売り、手形ジャンプでも何でも不渡り回避のためには何でもすることとなる。
4月に入ると、騒ぎは沈静化したが、大口の手形決済をクリアできたからではない。1―3月の間、会社側からはPROEARTHとの取引の経緯や債務整理の方針などに明確な説明がなかった。
多くの債権者は、この間に見切りをつけたのだ。スポンサーはつかず、事業継続型の民事再生でもなかった。債権者説明会も淡々としていたという。信用を失った17年末の時点で、既に倒産していたのかもしれない。
帝国データバンク情報部
だから騒ぐだけ騒いで、大きな改革はなく曖昧なまま進んで行くと思う。
アメリカンフットボールの日本大学と関西学院大学の定期戦で、日大の選手が相手選手に危険なタックルをしてケガをさせた。この問題に関して、米スタンフォード大学アメフトチームで、唯一の日本人コーチ(オフェンシブ・アシスタント)として活躍する河田剛さんは「監督や大学の理事長ら個人の責任追及だけで終わらせず、日本のスポーツのシステムを根本的に見直すときだ」と話す。(浜田理央 / ハフポスト日本版)
スタンフォード大のアメフトチームの写真はこちら
河田さんは、城西大や旧リクルートシーガルズでアメフトの選手やコーチとして活躍。2007年に渡米し、2011年よりスタンフォード大のアメフトチームの攻撃面を支えている。
アメリカでは、選手へのリスペクトがあり、ルール違反が起きたら、一般企業と同じように厳しい対応を取るという。日本は、古い体質が残る「体育会系スポーツ」と決別することは出来るのか。
日大の危険タックル問題から見える、日本のスポーツ界の課題を河田さんに聞いた
プロか、ボランティアか
日大の選手は定期戦で、1プレー目で無防備な関学大の選手に背後からタックルし、その後もラフプレーを続けて5プレー目で退場処分となった。本人は記者会見で「監督やコーチから指示があった」と説明しているが、監督やコーチ側は「けがをさせることを目的としては正直言っていない」などと否定。両者の言い分が食い違っている。
一連の問題に対して河田さんは、「アメリカであれば、ガバナンスがしっかりしているのでこんなことが起きるのはありえない」と話す。その理由についてこう説明する。
「あれほどラフプレーであれば、1回目の反則で審判が一発退場にします」
「チームが所属するリーグ側が、悪質なラフプレーをしたチームの監督・ヘッドコーチに対して、多額の罰金や試合出場停止など厳しい処分を課します。ラフプレーが起きてから、3日以内にはけりがついているでしょう」
アメリカではリーグに権威があり、スタンフォード大が所属するPAC12リーグのコミッショナーの年棒は数億円。審判も1試合数十万円の報酬を受け取っているという。その分、リーグ・試合運営上の影響力や責任も大きく、チーム側に対して説明を求めたり厳しい処分を課したりすることができるという。
一方で、日本の学生スポーツの場合はどうか。
「アメフト関東学生連盟のトップや審判の報酬は、ほぼゼロです。審判は休日を返上して、ボランティアでやっています。ボランティアでやっている以上、チーム側へ影響力やガバナンスが機能しているとは言えませんし、問題が起きても厳しい対応に臨むことが難しいでしょう」
関東学生アメリカンフットボール連盟によると、理事や役員に対する報酬はなく、理事会などに参加した際の交通費だけが支給される。日本アメリカンフットボール協会によると、審判への日当も、交通費を含めて1試合数千円程度で、ほとんどが他の仕事しながらボランティアで行なっている。
日本では、スポーツが、企業や大学の「PR」のひとつと見られてはいても、きちんとした地位が与えられず、問題が起きても自浄作用が働かない、と河田さんは見る。一般社会とは切り離された、ガラパゴス的なスポーツ業界の姿が浮き彫りになっている。
社会から取り残されたスポーツ界
タックルをした選手は記者会見で「やるしかないという状況でした」と語っている。アメフト部から退部の意向を示し、「今後アメフトをする権利は自分にはない」と競技からの引退も表明。日本代表クラスの実力を持った、将来ある若者の未来が奪われてしまう可能性がある。
河田さんは、メリーランド大学アメフトチームのヘッドコーチD.J.ダーキン氏から言われた言葉を紹介しながら、指導者の立場としてこう話す。
「いくら指示されたとは言え、ここまでするのは、選手が相当追い込まれていたとしか思えません。威圧や脅しで選手をコントロールしようとするのは、自分にコミュニケーション能力がないと言っているようなもので、自傷行為です」
「指導者が選手に関わるせいぜい3、4年間は、その人の人生から見たらごく一部です。人生が大きな円だとしたら、その中の一つの点のようなものです。それだけしか関わらないのに、選手の人生を奪う権利などありません」
「日大の内田前監督や井上奨コーチは、度を越したパワハラがおかしいと感じる機会がなかった。残念ながら、認識していなかったのではないかとも思ってしまいます」。
威圧的な態度で部下らに接するパワハラは、大きな社会問題となっている。企業では管理職の研修も開かれ、問題が発覚したら加害者が厳しく処分される。日本のスポーツ界は、そうした社会やビジネスの「常識」と切り離されている点が特徴だ、と河田さんは指摘する。
「社会やビジネスでの常識が、スポーツの世界には遅れて入ってきます。それは、スポーツの地位が低いからです。アメリカでは、有名企業のCEOがスポーツ球団経営の打診を受けたりします。そうすることで、ビジネス界の知識や常識がスポーツ界にも浸透し、逆にスポーツのいいところがビジネスにも活かされ、双方向です。ところが日本は一方通行で、変化もすごく遅い」
レスリング女子で五輪4連覇を達成した伊調馨選手がパワハラの告発状を提出した問題では、栄和人監督や、監督が所属する至学館大学の谷岡郁子学長がパワハラを否定すると受け止められる発言をした。日本のスポーツ界は、パワハラへの認識が甘いとされる。
他の国のスポーツ事情を「知るのが大事」
河田さんによると、日本の部活や学生スポーツは、選手を一つの競技に特化させる「ガラパゴス型の育成」に特徴があるという。指導者がスポーツの楽しさを伝えるよりも、生徒や学生を「教育」しようとする傾向もみられ、非科学的な指導やハラスメントの温床になっている面が指摘されている。
一方、アメリカでは小さいころから、選手がほかの競技やスポーツ以外の分野も学ぶ仕組みがある。そうすることで、選手が自分に向いているスポーツを考えて選ぶ機会を作りだし、問題のある指導に気づくきっかけにもなる。
「アメリカのアスリートは小さい頃から、数カ月に一度、プレーする種目を変えることが多い。アメフト選手が野球やサッカー経験者であることも珍しくありません。ベースボールやサッカーなど複数の指導者を見て育つので、ある競技でパワハラ的な振る舞いをした監督やコーチがいたら、おかしいと気づく。そこには健全な競争が生まれ、おかしな指導者がいたら、選手間で情報が出回りみんなにシェアされます。日本ではモンスターペアレントと言われてしまうかもしれませんが、問題があれば親が指導者に文句を言うこともありますね」
「またスポーツだけでなく、ビジネスなど他のことも学ぶよう教育を受けています。日本のアスリートは一つのスポーツにしか出会えないので、自分に本当に向いているスポーツや分野に出会う権利を奪われています」
プロ、学生を問わず、日本スポーツ界における暴力・パワハラ問題が後を絶たない。こうした“体育会系“の体質は、どうやったら変えていけるか。河田さんはこう話す。
「知ることが大事だと思います。例えば日本の有名大学のラグビー部は、ラグビーが盛んなオーストラリア、ニュージランドなどに視察に行きます。ところが、そのオーストラリアやニュージランドのラグビー界のトップは、アメリカに行って情報収集をします。ラグビーの強豪国ではありませんが、アメリカがスポーツビジネスの先進国だからです。日本のスポーツ界では、暴力やパワハラが未だに恒常的な問題となっており、ガラパゴス化しています。スポーツ先進国と言われる国々で何が起きているのかを知るべきです」
浜田理央 / ハフポスト日本版
京都中央信用金庫(京都市)は25日、加茂町支店和束出張所(京都府和束町)に勤務していた男性係長(58)が顧客11人の定期預金などを無断で解約し、約9370万円を着服していたと発表した。同金庫は10日付で係長を懲戒解雇としたが、11日になって自殺したことが分かったという。
同金庫によると、元係長は和束出張所に勤務していた2014年10月~今年3月、顧客の男女11人(50~80代)の定期預金や普通預金を無断で解約し、計9373万円を着服した。被害者には同金庫が全額を賠償する。
今月8日に顧客が残高不足を指摘して発覚した。
同金庫は「元係長から聞き取りはできていないが、上司の印鑑を勝手に使うなどし、遊興費などに充てたとみられる」と説明した。【飼手勇介】
日本大学アメリカンフットボール部の悪質な反則行為をめぐる問題で、日大アメフト部の現役部員が近く発表する声明文について、現役部員らが「内田前監督らの嘘を暴く内容になる」などと話していることがわかりました。
日大アメフト部の選手が関西学院大学の選手に悪質なタックルをした問題で、24日夜、日大アメフト部の父母会の代表が会見し、タックルをした選手を守るために現役部員が声明文を出すことを明らかにしました。
この声明文について、JNNの取材に応じた現役部員は「内田前監督の嘘を暴く内容になる」と話していて、近く公表する方針だということです。内田前監督は23日の会見で、「私の指示ではございません」「ボールを見ていて反則を見ていなかった」などと主張していましたが、現役部員らは問題の試合のビデオと照らし合わせて矛盾点を指摘するということです。
「日大の方で設置される第三者委員会で速やかに事実の解明・究明これが行われることを強く望んでいます」(林芳正文部科学相)
また、林文部科学大臣は25日朝の閣議後の会見でこのように述べ、日大に対し、「大学の理事会が責任をもって対応していく必要がある」と伝えたと述べました。
日本大学のアメリカンフットボール選手による悪質な反則行為について、24日、スポーツ庁の鈴木大地長官が、「我々がリーダーシップを取って真実を解明する」と調査に乗り出す方針を示しました。
「信じていただけないと思うが、私からの指示ではございません」(日大アメフト部 内田正人前監督・23日夜)
日大アメフト部の内田前監督と井上コーチは、23日夜、会見し、反則の指示について、改めて否定しました。
一方、反則行為をした宮川泰介選手は会見で、「監督から『やらなきゃ意味ないよ』と言われた」などと証言し、双方の主張は対立しています。こうした事態を受け、スポーツ庁の鈴木大地長官が、国として調査に乗り出す方針を明らかにしました。
「我々がリーダーシップを取って、きっちり真実を解明していくしかないのかなと」(鈴木大地スポーツ庁長官)
スポーツ庁は「日大の内田・前監督や宮川選手ら、日大関係者へのヒアリングを検討している」としています。
また、内田・前監督が心身の疲労を訴えて、都内の病院に入院したということです。
24日放送のフジテレビ系「直撃LIVEグッディ!」(月~金曜・後1時45分)で日大アメリカンフットボール部の悪質タックル問題で、同部OB3人の緊急座談会を行った。
【写真】井上奨コーチ
内田正人前監督(62)についてOBのCさんは「怖いイメージしかない」とし、Bさんは「例えば下級生のレギュラーの子がしっかりやらない場合ですと、幹部の上級生の方に監督が直接、あいつにやらせろと言って幹部の方から直接、殴らせる。監督の指示で殴る蹴るの暴行を加えるというのもありました」と証言した。
さらにBさんは「この人に逆らってはいけないんだなと。ある種の恐怖心にはなりますよね」と明かした。監督への感謝や尊敬の念を聞かれ、Cさんは「誰も正直、あの人に関して、誰も感謝してないよねっていうことしか聞かない」。支持率は「100%で言えば20%ぐらい」とし「実際、恨みを持つというか、されたこと、理解できる仕打ちだったら分かるんですけど、理解できないので関わりたくないっていう風に思っている者は多いんじゃないかなと思います」と明かした。
一方で3人に内田氏の良いところを聞いたが3人は無言だった。
今回の悪質タックルが起きたことにBさんは「監督があれをやれって言ったら絶対やらなくてはならない。やらなかったら干される。試合に出してもらえない。練習にも来るなと言われるようなので」と証言した。
さらに今回のタックルが内田氏からの指示があったかを問われると3人は全員が手を挙げた。Aさんは「アメフトをやっていれば分かりますが、考えられない本当に大きな反則プレーなので、あれを選手個人の判断でやることは本当に考えられないんですね。何かの指示であったり圧力であったりとかないとあれは、やらないプレーです」と指摘していた。
6日の定期戦で関学大QBを負傷させた日大アメリカンフットボール部の内田正人前監督(62)と井上奨DLコーチ(30)が、23日に都内の大学本部で会見した。
【写真】日大ブランドは「落ちません」 質問を制止する司会者
◇ ◇
日大の会見には200人近くの報道陣が詰めかけ、質問を求める挙手が収まらない中、司会を務めた日大広報部の米倉久邦職員が何度も会見を打ち切ろうとして、報道陣と衝突した。
開始から1時間30分が経過した午後9時30分ごろ、米倉氏は「もう十分聞きました。もうやめてください。これだけ聞いたら。もうしゃべらないでください。あなたはしつこい」などと発言。報道陣の1人から「そういった姿勢が日大のブランドを落とすことになる」と言われると「落ちません」と断言。記者団から失笑が漏れた。
その後も日大の対応は後手に。広報担当は会見後、早々と会場を後にした。その際、米倉氏は名前や役職も名乗らず退席。残された他部署の職員が、後から調べて報道陣に伝達した。会見に同席した弁護士の名前を尋ねても「そういうことは答えるなと言われている」と明かさなかった。
この世の中、建前と現実がある。そして、文化、環境、個々が背負っている物、育った環境そして国が違えば基準や考え方が違って当然である。 日本はいつも正解はひとつ、現実はひとつと考える傾向が高いようであるが、現実は違う。海外での経験、生活、海外の人達と接する機会が なければ理解するのは難しいかもしれない。現実が事実であり、これまで経験した事や見た事は事実はではあるが、それ以外の事実や世界がある。 結論に至る基準や考え方を説明して、意見を言うしかない。答えは一つではないし、基準や考えが違えば、意見や結論は違ってくる。そこに、 規則、モラル、一般的な常識、ある社会や狭い組織の常識などが複雑に影響し合う。
今回の悪質がどのような結果になるのかは知らないが、結論に失望した若いアスリートは他のスポーツに転向したければ転向すればよい。 将来は変わるかもしれないが、近い将来のアメフトがどのような世界なのか想像は出来ると思う。
これまでの努力や時間が無駄になったと考えず、大学に入学してから現実を知る前に、方向転換を考えるきっかけとなったと考える事も出来る。
今回は日本のアメフトの問題であるが、この世の中には知らないだけで似たような問題がたくさんあると思う。その意味では、自分が進んでいる、又は、 進む方向を考える事も必要だと考えさせる良い機会になったと思う。
アメリカンフットボールの日本大と関西学院大の定期戦(6日、東京)で、日大選手が関学大選手を悪質なタックルで負傷させた問題で日大が開いた会見を受けて、日大の選手の一人は「監督(当時)、コーチが『私からの指示ではない』『けがを目的で言ったのではない』と語ったのは、本当に真実なのかなという思いがしています。もう何が本当で何がうそなのか分からない」と話した。
問題が起きた試合後に日大と対戦した関西大の松浦雅彦監督は、会見での2人の説明について「僕が今まで選手たちと向き合ってきた世界とは、かけ離れていると感じた。理解が出来なかった。自浄作用に期待して(日大と)戦ったが、もう何とも言えない。ショックを受けた」と語った。
日大と同じ関東大学リーグ1部に所属する法政大の有沢玄ヘッドコーチは「戦術的にタックルするという意味で『潰せ』という言葉を使うことはある。ただ、チームの理念、目的がしっかりしていれば誤解は無いし、あのような反則は起きえない」と話した。特に最初の反則に対する衝撃は大きく、法大の選手からは「怖くて(日大とは試合が)できない」という声も上がっているという。
関東学生アメリカンフットボール連盟は月内に臨時理事会を開き、日大の処分などを判断する方針だ。規律委員会がすでに関係者の聴取を終えている。事件が起きた背景や再発防止策をまとめて、理事会に提出する。前川誠事務局長は「処罰を下すのは難しくない。きっちり次のスタートへの道筋まで示し、選手たちやアメリカンフットボールをやっている中高生の不安を取り除くことが大事だ」と語った。
関学大は、日大が「24日を目処(めど)」としていた、抗議文に対する2度目の回答について、26日に兵庫県西宮市で記者会見を開いて説明すると23日発表した。鳥内秀晃監督、小野宏ディレクターに加え、被害選手の父親の奥野康俊さんも同席する。会見では日大からの再回答の内容や、それへの関学大や被害選手側の対応や見解を明らかにするという。
関学大は日大に対し、10日付で抗議文を送付。日大からの最初の回答書(15日付)には、悪質なタックルについての事実関係、経緯、それまでの指導内容、試合後の対応などについて詳しい言及がなく「誠意ある回答とは判断しかねる」とした。関学大は再回答を待ち、「ルールを逸脱した行為を監督・コーチが容認していた」などの疑念に対する説明も求めている。
日本大学アメフト部の選手が危険なタックルなどの反則行為で関西学院大学の選手を負傷させた問題で、内田氏と井上奨コーチが5月23日夜に東京都内で記者会見し、謝罪した。
会見を見た人たちからは、司会者の対応を批判する声が出ている。Twitterでは「司会者が最悪」「火に油を注ぐような対応」という声が相次いだ。
当初、会見は特に混乱もなく進んだ。ただ、開始から1時間半ほど経つと、司会者が質問を制する場面が目立つように。
「もう終わりにします」「もうやめてください」と会見の打ち切りを宣言する司会者と、質問を続ける報道陣とのやり取りは次第に熱を帯びるように。「打ち切りますよ、会見」と質問する記者を声を荒げて制する場面もあった。
司会者が「やめてください。もうこれ以上やっているとキリがないし、だいたい同じ質問が繰り返されているので、これで会見の質問は終わりとします」と発言すると、報道陣からは「違う質問をします」「納得いかないから同じ質問なんじゃないんですか」と声が出た。
だが、司会者は質問に答えようとする内田氏や井上氏を遮り、「記者会見はこれで終わります」「もう十分(質問を)聞きました」と、打ち切る姿勢を崩さない。
「この会見は、みんな見てますよ」という声に対して、司会者は会見を「見てても見てなくてもいいんですけど。同じ質問を繰り返されたら迷惑です」と発言した。
さらに、「司会者のあなたの発言で、日大のブランドが落ちてしまうかもしれない」という声に対しては「落ちません。余計なこと言わず」と言い張る場面もあった。
元大阪市長の橋下徹氏は「何よりもあの司会者が最悪だね。危機管理対応の記者会見なのに、あの司会は何なんだ?ほんと日本大学の危機管理能力は全くないな」と酷評。5700RT以上されている。
ハフポスト日本版
「田中ファミリー」
日本初の危機管理学部を創設したのがブラックジョークとしか思えない、日本大学の遅くて稚拙な対応に対し、関西学院大学のクオーターバックの選手を負傷させたアメリカンフットボール部の宮川泰介選手(20)が行なった謝罪会見は、その真摯で誠実な受け答えと合わせ、負傷した選手と家族、関西学院関係者、そして騒動を知る国民を、十分に納得させるものだった。
本来、危機管理とは、何を守り、何を守らないかを迅速に判断したうえで、公表すべきは公表し、謝罪すべきは謝罪するもの。許されないのは、保身に走って情報を小出しにし、謝罪や会見を後回しにすること。そうすれば、対応が後手に回って炎上する。
今の日大がまさにそうだ。まして「責任は俺が取る」と、宮川選手に試合後、語り、「すべては私の責任」と、19日の会見で述べながら、「責任」の中身に言及せず、宮川選手が前に出ざるを得ない状況に追い込んだのは内田正人前監督であり、教育者としては、まさに万死に値する。
内田氏は、そして日大は、なぜ稚拙な対応しか取れないのか。日大関係者が口を揃えるのは田中英寿理事長の存在である。
「昨年9月、4選を果たした田中さんはドンとして君臨、逆らう者がいない体制を固めている。それを公私にわたってサポートしているのがアメフト部OBなんです。内田さんと井ノ口(忠男)さん。だから田中さんは、アメフト部の問題にしたくないし、それを承知の内田さんは、やり過ごそうとして墓穴を掘った」(日大元理事)
田中理事長は、現役時代、学生横綱、アマ横綱など34のタイトルを獲得したアマ相撲の実力者で、引退後は相撲部監督として後輩を指導、大翔鳳、舞の海など多くの力士を育て上げる一方、学校経営にも参画。スポーツ部を束ねる保健体育審議会事務局を足場に、理事、常務理事と順調に出世し、08年、理事長に就任した。
体育会気質で情に厚く、人望もあって人脈は広いが、その清濁併せ呑む人柄が仇となり、これまで広域暴力団の住吉会会長や山口組組長との写真が流出、その交遊が国会で問題になったことがある。また、常務理事時代には建設業者からのバックリベートが取り沙汰され、内部調査を受けた。
いずれも決定的な証拠はなく、疑惑の指摘にとどまっているが、それだけ敵が多いのも確かで、長期政権を敷く間に理事を仲間や側近で固めて、支配権を確かなものにした。その際、自分との距離感を計るのに使うのが、優子夫人が経営する阿佐ヶ谷の「ちゃんこ料理たなか」である。
「そこを頻繁に利用して、田中理事長だけでなく、優子夫人にも認められるのが出世の条件。ばからしいと距離を置くのは健全だが、それでは田中ファミリーの一員にはなれず、出世しない」(日大関係者)
その田中ファミリーの筆頭が内田氏。「フェニックス」の愛称があるアメフト部OBの内田氏は、田中氏より10歳下で、その足跡を踏襲して出世してきた。フェニックスには篠竹幹夫という名物監督がいて、日大をアメフト界の名門校に育て上げたが、内田氏は篠竹監督をコーチとして支え、03年、後を継いで監督に就任した。
その一方、田中氏の後を受けて保健体育審議会事務局長となって体育会を支配、理事を経て、昨年9月、田中4選が決まった理事会で常務理事に就任し、実質的なナンバー2として田中体制を支えることになった。
この理事会で理事に抜擢されたのが井ノ口氏。内田氏の2年後輩のフェニックスの主将だが、井ノ口氏は田中ファミリーと近くなってから大学の内側に入るという特異なケースを辿っている。
「井ノ口さんは大阪でスポーツ関係の事業会社を経営しているんですが、広告代理店を営む実姉が優子夫人と懇意になって、田中ファミリーの一員となった。それで井ノ口さんと田中さんとの関係が生まれ、内田さんとの縁も復活した。彼が、日大に深く食い込むのは、日本大学事業部の起ち上げからです」(前出の日大関係者)
ある種の防御壁
株式会社日本大学事業部は、学生と教職員を合わせて10万人のマンモス学校法人の福利厚生面を事業化することによって、その収益を日大に還元しようというもの。田中理事長の発案で、9年7月に開設準備室を設け、10年1月、設立した。
保険代理業、人材サービス、キャンパス整備、学生生活支援などを事業化、提携する会社がマンモス学校法人に配慮するのだから収益力は高く、例えば、全国のキャンパスに設置する自動販売機は、設置台数、販売本数とも膨大で、それが収益に直結する。
この担当役員が内田氏で、事業手腕のある井ノ口氏がそれを支える。井ノ口氏は、当初、田中氏の推薦を受けてアドバイザーとして関与し、11年9月からは事業企画部長に就いた。その際、名刺には「理事長付相談役」と刷り、内外に田中理事長との関係をアピールした。
この日大事業部の1期生として新卒採用されたのが、フェニックス出身の井上奨氏。宮川選手に「相手のクオーターバックを1プレー目で潰せ」と、指示したコーチである。井上氏には、ビデオ出演に絡むスキャンダルがあったとされ、その過去を封印するように内田氏が日大事業部に迎え入れた。
その後、井上氏は保険代理店出向などを経て退職。大学職員となり、日大豊山高校のアメフト部監督を務めて宮川選手を指導。フェニックスでもコーチを務めている。宮川選手にとっては逆らえない存在で、試合前、井上氏に「できませんでしたじゃ、済まされないぞ!」と、ハッパをかけられると、「殺人タックル」を仕掛けざるを得なかった。
同じフェニックスコーチの井ノ口悠剛氏は、井ノ口氏の子息で、子供のいない田中夫妻、ことに優子夫人に可愛がられ、運転手を務めることもあるという。
こうして、相撲部出身の田中理事長を公私にわたって支えているのがフェニックスOBたちである。学内外に敵も多く、メディアの攻撃を受けることの多い田中氏を、内田氏、井ノ口氏、井上氏らが、日大事業部という会社をある種の「防御壁」にして守っているわけで、このつながりは深い。
したがって殺人タックル事件は、4期12年体制を固めた田中体制を、内側から揺さぶる危険性があった。
内田氏としては「私が指示した。私の責任です」と、全てを受け止めることはできなかった。その躊躇が、遅すぎる対応となって宮川選手を追い詰め、国民的指弾を受ける結果となったのである。
伊藤 博敏
ただ、やはり両者の回答を聞いている限り、狡いと感じた。司会者は誰なのか知らないが、会見の印象をさらに悪くしたと個人的には思った。 インターネットで検索すると日大の広報の男性らしいが、日大は何かを隠していると受け取られても仕方がないような対応に思えた。 広報の仕事には向いていないと思ったが、日大が自己責任で決めた事なので日大の自業自得!
6日に行われた学生アメリカンフットボールの試合で日大の選手が無防備な関西学院大選手に後方から悪質なタックルをして負傷させた問題で、日大は23日、東京都内で内田正人前監督(62)、井上奨(つとむ)コーチ(30)が緊急会見を行った。
【写真】会見で深々と頭を下げる井上コーチと内田前監督
内田前監督と井上コーチは謝罪したが、QBをつぶせという指示については改めて否定した。前日22日に加害者側の日大DL宮川泰介選手(20)が開いた記者会見で反則は監督、コーチからの指示だったと主張していた。
悪質なタックルは宮川選手の認識でやったのかという質問に、内田前監督は「彼は力がある選手だが、10の力があるのに5ぐらいでやってしまうときがある。そのときにハッパをかけます。もっとできるんじゃないかという思いがあった。僕の考えからすると、ルールから逸脱することではない。まさか、ああいうプレーをするとは予想できなかった」と答えた。
試合前に「できなかったらすまされないぞ」と宮川選手に伝えたことについて井上コーチは「彼に対する言葉、表現の仕方、試合までの彼の(気持ちの)持っていき方で、彼自身がとんでもない重圧を受けていた。目の前のことがしっかりと見えなくなってしまったのではないかと思っています」といい、最初のワンプレーを見たのかという問いには「見ましたが、正直彼を次のプレーでも使いたいと思った。判断ミスです」と語った。
朝日新聞社で、上司が女性記者にセクハラをした疑いがあることがわかった。週刊文春の取材によれば、3月、経済部の歓送迎会が開かれた。女性記者は幹事の一人で、その後、男性の上司とバーに流れた。朝日新聞の中堅社員が証言する。
【写真】「沈黙しているあなたへ」……被害者に寄り添う姿勢を示した朝日社説
「そこで上司は女性記者に無理やりキスを迫り、自宅にまで上がりこもうとしたそうです。女性記者は、後日、被害を同僚記者らに打ち明けたとか」
その後、上司は論説委員となり、以前と変わらず働いているという。
女性記者に取材を申し込むと、「ごめんなさい、広報を通していただけますか」。上司の男性は「それは広報に聞いて頂けますか」と回答した。
朝日新聞広報部に確認を求めると、次のように回答した。
「ご質問いただいた個別の案件につきましては、お答えを控えます。当事者の立場や心情に配慮し、保護を優先する立場から、ご質問にお答えできない場合があることをご理解下さい」
セクハラ行為について、否定しなかった朝日新聞。紙面では、福田氏や財務省を厳しく批判しており、セクハラ問題にどう対応するのか、注目される。5月24日(木)発売の週刊文春では、“疑惑”の詳細や、「箝口令疑惑」などについて詳報している。
「週刊文春」編集部
日本ガイシは23日、碍子(がいし)製品などで顧客との契約で定めた通りの検査を実施していない不備が見つかったと発表した。不備は1990年代からあったとみられ、電力会社や重電メーカー向けに販売していた。品質上の問題はないと確認しているという。
碍子は電線を流れる電気が鉄塔などを伝わないよう絶縁する部品。昨年10月からグループ全製品の品質について自主検査を進めていたところ、1月16日に判明した。
大島卓社長は名古屋市で記者会見し「お客さまをはじめ関係各位に多大なる迷惑をお掛けし、深くおわび申し上げる」と謝罪した。
◇東京地検特捜部と警視庁捜査2課
神戸製鋼所による品質検査データ改ざん問題で、不正競争防止法違反(虚偽表示)容疑で捜査を進めている東京地検特捜部と警視庁捜査2課は、近く同社を家宅捜索する方針を固めた模様だ。関係者が明らかにした。特捜部などは既に任意で関係資料の一部提出を受けているが、全容解明には強制捜査が必要と判断したとみられる。
同社は昨年10月、自動車や航空機メーカーなどに納入したアルミ板や銅製品の強度や寸法について、顧客が示した仕様をクリアしたように見せかけるため、検査証明書を書き換える不正が見つかったと発表した。同社が今年3月に公表した最終報告書などによると、不正は1970年代から続き、役員経験者5人を含む40人以上が不正を認識していたとみられている。
問題の発覚時に役員だった3人のうち、2人は改ざんが行われた工場で勤務した経験があり、不正を認識しながら上司に報告していなかった。残る1人は昨年に認識したが、製造工程の改善などを指示するにとどまったという。またOB2人はいずれも不正に直接関与していたが、役員就任後も取締役会に報告せず、中止したり、改善措置を講じたりしていなかった。
同社は、特捜部などの捜査が始まったことが明らかになった後の4月27日の記者会見で「(捜査に)真摯(しんし)に協力していく」とコメント。同問題による影響額は約120億円に達したと発表していた。
日本大学アメリカンフットボール部の選手による悪質な反則行為についてです。問題の試合のあと、コーチが「俺が追い打ちをかけた」と反則行為の指示を認めるような発言をしていたことが現役部員の証言でわかりました。
日本大学アメリカンフットボール部の宮川泰介選手は今月6日の関西学院大学との定期戦で、悪質なタックルをした件について、22日の記者会見で、内田前監督とコーチから「反則をするように指示があった」と証言していました。このうち、会見で名指しされた井上奨コーチが関学との試合のあとに行われたミーティングで、「俺が宮川に追い打ちをかけた」と反則の指示を認めるような発言をしていたことが現役部員への取材で新たにわかりました。
一方、日大は22日の宮川選手の会見のあと、コーチの言葉としてあった「潰せ」は「最初のプレーから思い切り当たれ」という意味だとして、反則行為の指示を否定しています。
「出した大学のコメントも、ありえないなと。ないなと」(日大学生)
「監督にもちゃんと話してほしいと思って、真実を」(日大学生)
この問題を調査している関東学生連盟によりますと、監督やコーチへの調査はすでに終わっていて、今月中にも臨時理事会を開催し、日大アメフト部への処分を決定するということです。
事実は一つかもしれないが、証拠がなかったり、証言者の信頼性やその他の証言者の不在で、結果は事実とは同じになるとは限らない。
アメリカンフットボールの日本大と関西学院大の定期戦で日大の選手が関学大の選手を悪質なタックルで負傷させた問題で、けがをした関西学院大の選手が大阪府警に提出した被害届が、警視庁調布署に移送されたことが分かった。警視庁は今後、日大の関係者から事情を聴くなどして慎重に捜査し、傷害容疑などでの立件の可否を判断するとみられるが、専門家は「指導者も傷害罪に問われる可能性がある」と指摘する。
立件の可否で重要なのは行為の故意性だ。悪質なタックルをした日大の選手は22日の記者会見で、井上奨(つとむ)コーチが「1プレー目で潰せば出してやると監督が言っている」、内田正人前監督が「自分がやらせた」などと言ったことを明かし、故意の反則を認めた。スポーツ法政策研究会事務局長の西脇威夫弁護士は「指示があったとしても、本人の責任がゼロになるわけではない」と指摘する。
今後は内田前監督ら指導陣の刑事責任の有無が焦点となる。「潰す」の表現が、故意の反則行為で相手を負傷させる意味で使われていたかどうかがポイントだ。スポーツ事故に詳しい間川清弁護士は「『潰せ』という指示だけでは具体性に欠ける」と指摘。指示を録音した音声データがなければ立件は簡単ではないとみる。
一方、西脇氏は「日頃の指導方法や指示の状況などがカギ」とみる。スポーツ法学に詳しい辻口信良弁護士は「(今後の捜査で)内田前監督やコーチの指示が明らかになれば、共謀共同正犯や教唆犯に問われる可能性がある」と指摘。暴力団組織の支配と服従の関係のような上意下達の縦社会の存在が背景にあった可能性もあるとして、日頃の部内のコミュニケーションや雰囲気はどうだったのか、部員らが前監督やコーチの言動をどう受け取っていたのかなど実態を解明していくことが必要という。
その上で前監督やコーチによる異様な支配の状況が証明されれば、「社会的責任もかんがみ、問題選手よりもさらに重い刑事責任が問われる可能性がある」と話した。
これだけ両サイドの話に食い違いがある以上、当事者全員が真実を話す事はないであろう。最近、大嘘を平気で話すケースが多いと感じるし、 曖昧のままで不透明な状態も多い。
スポーツ庁が事実を確定させたいと思う場合、どのような方法で事実である可能性を確認するのだろうか?刑事事件の警察のように、 権限がないといろいろな事で踏み込めないのではないのか?司法取引のような制度も必要になると思う。司法取引のような制度も 含め、罰則や処分を見直すべきだと思う。
日本大学アメリカンフットボール部の選手が自身の悪質な反則を謝罪し、監督とコーチの指示があったと明言したことを受けて、スポーツ庁の鈴木長官が取材に応じました。
「指示あった旨の会見でしたが、もし本当であれば、とてもあってはならないことだと思います」(スポーツ庁 鈴木大地長官)
悪質なタックルをした日大の宮川泰介選手は会見で「指示されたとしても自分自身がやらないという判断ができなかったことが原因」と話す一方で、内田前監督については「何か意見を言える関係ではなかった」とも話しました。
「指導者と選手のコミュニケーションのあり方とか、こういったところをスポーツ界全体で考えていかなくてはいけないのかなと、このように思っています」(スポーツ庁 鈴木大地長官)
鈴木長官は「当事者全員が真実を話し、事実を確定させた上で対応していきたい」としています。
アメリカンフットボールの定期戦での悪質なタックルで関学大の選手を負傷させた日大の宮川泰介選手(20)が22日、都内の日本記者クラブで会見した。
【写真】たくさんの記者に囲まれながらも、新事実を説明する宮川選手
弁護士とともに丸刈り頭のスーツ姿で記者団の前に現れたた宮川選手は終始、硬い表情のまま。冒頭、関学大の被害選手に向けて「大きな被害と多大な迷惑をかけたことを深く反省しております」と深々と頭を下げた。そして、問題となった試合の数日前に「やる気が足りない」などとして練習から外された後、コーチから「相手のクオーターバックを1プレー目で潰せ」などと言われたという。
内田正人監督に試合当日、「潰しにいくから(試合で)使って下さい」と申し出たところ、「やらないと意味がないぞ」と言われ、コーチからも「できませんでは済まされない。分かってるな」と念を押されたという。
選手の代理人弁護士が会見の冒頭で説明した内容は以下のとおり。
* * *
代理人の西畠正弁護士:私、ご本人から、それからご本人のご両親から、本件の様々な折衝、解決について委任を受けております弁護士の西畠正と申します。
同じく、横におりますのが、薬師寺孝亮弁護士です。二人で担当させていただいております。
それでは着席させていただきます。まず、冒頭ですが、このような形でご本人が、いわゆる顔出し、要旨の撮影をあえて受けてお話をするということは、異例かと思います。特に、さきほど司会の方がおっしゃったように、二十歳を過ぎたばかりの、いわば未成年に近いような方が、顔を出すことについてのリスクは私どもずいぶん承知をしておりますし、ご両親ご本人にもお話をいたしました。
しかし、ご本人、ご両親とも、この会見が事実について詳らかにするだけではなくて、むしろ被害者、被害選手とそのご家族、それから関西学院大学アメリカンフットボールチームに対する謝罪の意味が強いという捉え方をしていますので、一言で言うと、顔を出さない謝罪はないだろうと。顔を出さなくて何が謝罪だろうということを考えて、あえて撮影を受けることにいたしました。
氏名についても、あえて秘匿するまでもないということをおっしゃってます。しかし、私どもとしては、代理人としては長い将来のある若者です。この先、どのような不測の事態があるとも限りませんし、被害が被らないとも限りません。そういうことにぜひご配慮いただいて、できればずっとアップで撮るようなことは避けていただいて、格別のご配慮をいただければと。冒頭にこれを申し上げておきたいと思います。
それで私の方からは、この会見の主旨と、この会見に至った経緯を簡単にご説明します。お手元に配布資料が配られていると思います。どちらが表かはわかりませんが、日付が入っている方に、本日の記者会見の主旨と開くに至った経緯、経過表というのが記載してございます。これに基づいてお話をさせていただきます。若干の時間をいただきます。
この会見にいま申し上げたおわかりかと思うのですが、今年の5月6日に行われた日大アメフト部と関大アメフト部との第51回定期戦において、日大チームの選手、この当該選手が行った反則行為によって、関学大のチームのクオーターバックが負傷した件について、当該選手に対して、監督コーチから、その反則行為の指示があったことを明らかにし、その具体的対応についてご説明をするのが目的の一つです。
さきほど申し上げたように、それは関係者、特に被害選手とそのご家族に対する謝罪の第一歩であるという捉え方で、この会見をあえて開かせていただきます。
これから先の呼び名ですけれども、私の方から、「本人」ないし「当該選手」と呼ばせていただきます。それから、大変失礼かとは存じますが、関西学院大学アメリカンフットボール部のことを関学アメフト部、それから日本大学アメリカンフットボールチームのことを日大アメフト部と略称することはご容赦ください。
本件に至った経緯を、その下の経過表にしたがって説明をいたします。
5月6日以降の経過を日を追って書いてございますけれども、大きな動きがあったのが、5月6日の後、5月10日でございました。5月10日に関学大アメフト部から、日大アメフト部に対して申し入れ文書が出されました。これを受けて、本人とご両親は、監督を訪ねました。実は、この時まで監督、コーチ、チームメイトと会ったのは、本件の2日後、グラウンドに行って話をしたのが最初です。
被害者が身を守るための証拠保全か、オフレコや取材源の秘匿など報道倫理の遵守か。被害者が記者という職業だったからこそ、問われることになった。
■被害者に謝罪したいと伝えたが、内田監督に却下された
この5月11日は、いわば監督と会う2回目でした。この時、本人とご両親は監督に対して、個人として直接謝罪をしたいと申し上げたのですが、監督からはそれは止められました。具体的な話は後で本人が申し上げます。この時、事実関係について監督からもコーチからも質問は一切ありませんでした。「なぜ、君はああいうことをやったのか」という理由の説明を求められたことは一切ありません。あえて言えば、今まで一度として、部の上の方から求められたことがありません。
5月12日、本人とコーチが関学に謝罪に参りましたけれども「申し入れ文書に対する回答がない限りは謝罪は受けられない」と言って断れています。
5月14日月曜日ですが、本人と父がOBから呼び出されて、日大のある校舎に参りました。この時、呼び出されてお話をしたのですが、その後、学生連盟の規律委員会から事情を聞きたいという申し出がありまして、そこに本人とお父さんが伺いました。ここで規律委員会には、これから本人が申し上げる事実の経過をかなり詳しくお話しています。事実経過についてお話をしたのは、この5月14日の19時以降が最初でございます。
5月15日になって、お父さんが私の所に相談にお見えになりました。私が関与したのはこの時が初めてです。お父さんがお見えになったのは、5月15日に、関学大の申し入れ書に対する日大の側の回答書が出た。これを受けて、お父さんとしては、個別にでも謝罪をしたいんだけれども、それが認められていない。それから事実について報道をみる限りは、監督・コーチからの指示があったということは否定されている。あまつさえ、本人が指示がなかったと否定しているというような報道さえありました。そういうのをご覧になって、このままでは事実が明らかにならない、本人が勝手に突っ込んでケガをさせたことになってしまうということと、謝罪そのものが認められないのは納得がいかないということで、この二つを主として早めに実現したいということで、私の所に相談にお見えになりました。
4月4日、福田氏から呼び出され、取材のため飲食をした際にもセクハラ発言があったため、途中から録音を始めた。
氏名についても、あえて秘匿するまでもないということをおっしゃってます。しかし、私どもとしては、代理人としては長い将来のある若者です。この先、どのような不測の事態があるとも限りませんし、被害が被らないとも限りません。そういうことにぜひご配慮いただいて、できればずっとアップで撮るようなことは避けていただいて、格別のご配慮をいただければと。冒頭にこれを申し上げておきたいと思います。
それで私の方からは、この会見の主旨と、この会見に至った経緯を簡単にご説明します。お手元に配布資料が配られていると思います。どちらが表かはわかりませんが、日付が入っている方に、本日の記者会見の主旨と開くに至った経緯、経過表というのが記載してございます。これに基づいてお話をさせていただきます。若干の時間をいただきます。
この会見にいま申し上げたおわかりかと思うのですが、今年の5月6日に行われた日大アメフト部と関大アメフト部との第51回定期戦において、日大チームの選手、この当該選手が行った反則行為によって、関学大のチームのクオーターバックが負傷した件について、当該選手に対して、監督コーチから、その反則行為の指示があったことを明らかにし、その具体的対応についてご説明をするのが目的の一つです。
さきほど申し上げたように、それは関係者、特に被害選手とそのご家族に対する謝罪の第一歩であるという捉え方で、この会見をあえて開かせていただきます。
これから先の呼び名ですけれども、私の方から、「本人」ないし「当該選手」と呼ばせていただきます。それから、大変失礼かとは存じますが、関西学院大学アメリカンフットボール部のことを関学アメフト部、それから日本大学アメリカンフットボールチームのことを日大アメフト部と略称することはご容赦ください。
本件に至った経緯を、その下の経過表にしたがって説明をいたします。
5月6日以降の経過を日を追って書いてございますけれども、大きな動きがあったのが、5月6日の後、5月10日でございました。5月10日に関学大アメフト部から、日大アメフト部に対して申し入れ文書が出されました。これを受けて、本人とご両親は、監督を訪ねました。実は、この時まで監督、コーチ、チームメイトと会ったのは、本件の2日後、グラウンドに行って話をしたのが最初です。
日大DL宮川泰介選手が嘘を言っていない限り、日大広報部のコメントは信頼度は低いと思う。
既に弁護士に相談した上でのコメントだと思うし、日大DL宮川泰介選手がコーチとの会話を録音していない限り、
どろどろの戦いになれば、金がある日大の弁護士の方が有利のような気がする。
ただ、一般人を敵に回せば、日大はイメージでかなりのダメージを受ける可能性もある。日大が弱い者いじめをしたと映れば
多くの人々が同情したり、非力な立場の人達が応援する可能性がある。
アメリカンフットボールの悪質タックル問題で、関学大QBを負傷させた日大DL宮川泰介選手(20)が22日、東京・千代田区の日本記者クラブで謝罪会見を開き、経緯や心境を赤裸々に告白。これを受け、日大広報部はこの日夜、文書でコメントを発表した。
【写真】問題となっているタックルの場面
宮川選手は悪質プレーの背景に、19日付で辞任届が受理された内田正人前監督(62)とコーチの指示があったことを明らかにしたが、日大広報部は「コーチから『1プレー目で(相手の)QBをつぶせ』という言葉があったということは事実です」と認めたがものの「ただ、これは本学フットボール部においてゲーム前によく使う言葉で『最初のプレーから思い切って当たれ』という意味です」と説明。「誤解を招いたとすれば、言葉足らずであったと心苦しく思います」と弁明。言葉足らずにより「つぶせ」の捉え方の違いが招いた結果だとし、監督の指示を否定した。
日大は15日付の関学大への回答書でも「指導と選手の受け取り方に乖離(かいり)が起きたことが問題の本質」としていたが、宮川選手は会見で「(乖離はなかった?)はい。自分としては、そういう意味(相手にケガをさせること)としか捉えられなかった。もうやるしかないと…」と当時の心境を率直に語った。
宮川選手が顔や氏名を公表して会見に臨んだことについて、日大広報部は「厳しい状況にありながら、敢えて会見を行われた気持ちを察するに、心痛む思いです。本学といたしまして、大変申しなく思います」と“謝罪”。内田前監督との関係について、宮川選手が「そもそも、お話する機会が本当にないので、信頼関係と呼べるものは分からないです」と語った通り、日大広報部も「本人と監督は話す機会がほとんどない状況でありました」と認め「宮川選手と監督・コーチとのコミュニケーションが不足していたことにつきまして、反省いたしております」と釈明した。
日大広報部のコメント全文は以下の通り。
アメリカンフットボール部・宮川選手の会見について
2018年5月22日
本日、本学アメリカンフットボール部の宮川泰介選手が、関西学院大学フットボール部との定期戦でルール違反のタックルをし、相手選手にケガを負わせた件につきまして、心境を吐露する会見を行いました。厳しい状況にありながら、敢えて会見を行われた気持ちを察するに、心痛む思いです。本学といたしまして、大変申しなく思います。
会見全体において、監督が違反プレーを指示したという発言はありませんでしたが、コーチから「1プレー目で(相手の)QBをつぶせ」という言葉があったということは事実です。ただ、これは本学フットボール部においてゲーム前によく使う言葉で『最初のプレーから思い切って当たれ』という意味です。誤解を招いたとすれば、言葉足らずであったと心苦しく思います。
また、宮川選手が会見で話された通り、本人と監督は話す機会がほとんどない状況でありました。宮川選手と監督・コーチとのコミュニケーションが不足していたことにつきまして、反省いたしております。
日本大学広報部
試合に出たくても井上コーチの言う事を聞くべきでなかった。
結果として井上コーチを言葉を無視して試合を出られない選択の方が今回のような結果となって退部を選ぶより良かったのではないのか?
これからの生き方と結果次第では、あの時には苦しかったが、悩み苦しんだから今の自分がある言える時が来るかもしれない。
最悪の場合、後悔だらけの人生かもしれない。考え方を変えるだけで、同じ結果でもポジティブに生きれる事もある。
前向きに人生を歩んでいってほしいと思う。
今回はスポーツの世界であるが、社会人なっても、会社に入社しても、運が悪い人は似たような状況で悩むと思う。
日本社会の現実の一部だとして、注目するべきだと思う。
アメリカンフットボールの試合で日本大学の選手が関西学院大学の選手に悪質なタックルをした問題で、22日、加害者の宮川泰介選手が都内で会見を開いた。
【動画】宮川選手の会見
代理人弁護士の経緯説明によると、試合後の11日、本人と両親が内田正人監督を訪ね、個人として直接謝罪したい旨の話をしたが止められ、さらに選手の父にはOBからの呼び出しもあったという。結局、18日になり、本人と両親が被害選手とその両親、関西学院大アメフト部のディレクターに面会して謝罪したという。
そして21日、日本大学側の対応が遅いこと、報道向け文書には“宮川選手と監督の認識に乖離がある“としていたにも関わらず、部としての聞き取りの予定がないことから、宮川選手側が記者会見を決意。20歳になったばかりの宮川選手が顔を出すリスクについて代理人弁護士が進言したというが、宮川選手側は「この会見が事実について詳らかにするだけでなく、むしろ被害選手やそのご家族、関西学院大学アメフトチームに対する謝罪の意味が強いという意味から、顔を出さない謝罪はないと考え」、あえて顔と実名を出して会見に臨むことを決めたという。
宮川選手による陳述書は、試合の3日前である5月3日から始まった。内田監督から「やる気があるのか無いのかわからない。辞めていい」、そして井上コーチからは「お前が変わらない限り出さない」と言われ、この日から実戦練習を外されたという。
そして5日の練習後、井上コーチに「お前をどうしたら試合に出せるか監督に聞いたら、“相手のクオーターバックを1プレー目で潰せば出してやる“と言われた。“潰しに行くんで僕を使って下さい“と監督に言いに行け」との指示を受けたという。井上コーチはさらに「関学との定期戦が無くなってもいいだろう。クオーターバックが怪我をして秋の試合に出られなかったらこっちの得だろう。これは本当にやらなくてはいけないぞ」と念を押され、「髪型を坊主にしてこい」とも指示されたという。
こうした指示について宮川選手は「追い詰められ、悩んだ」というが、「これからの大学のフットボールにおいて、ここでやらなければ後がないと思い会場に向かった。試合のメンバー表に自分の名前がなかったので、試合前のポジション練習時に監督に対して、“相手のクオーターバックを潰しに行くんで使って下さい“と言いに行った。監督からは“やらなきゃ意味ないよ“と言われた。戻って井上コーチに報告すると“思い切り行ってこい“と言われた。さらに試合前の整列のとき、井上コーチからは“できませんでしたじゃ済まされないぞ、わかっているな“と念を押された」と振り返った。
試合後、内田監督からは「周りに聞かれたら俺がやらせたんだと言え」、後日にも「お前の罰は罰退になって終わっている。世間は監督を叩きたいだけで、お前じゃない。気にするな」と言われたといい、コーチ陣からも退部を思いとどまるよう説得を受けたと明かした。
その上で宮川選手は「私自身がやらないという判断をせず指示に従ったことが原因。思い悩み、反省してきたが、真実を明らかにすることが償いの第一歩だと決意して陳述書を書いた。相手選手、そのご家族、関西学院大学アメリカンフットボール部の方々、私の行為によって関係者の方々に大きなご迷惑をおかけしたこととを改めて深くお詫び申し上げます」と頭を下げ、今後について「(アメフトを)続けていくことはないと思っている。この先アメリカンフットボールをやるつもりもありません」と話した。
アメリカンフットボールの日本大―関西学院大の定期戦(6日、東京・アミノバイタルフィールド)で日大の選手が悪質なタックルなど反則を繰り返して退場となった問題で22日、この選手自身が記者会見を開くことになった。辞任した内田正人前監督による反則行為の指示があったのかどうかについて、選手本人が何を語るのか注目される。
【動画】アメリカンフットボールの日大―関学大の定期戦で起こった反則行為
あの日、私は試合会場にいた。関学オフェンスの最初のプレー。テレビなどで繰り返し流れているシーンだ。私は関学QBが投げたボールをカメラで追っていたため、日大の守備選手の反則は見ていなかった。二つ目の反則もボールと関係のない場所だったので見ていない。ただ、立て続けに最も重い15ヤード罰退の反則をした選手をベンチに下げないのは変だなと感じていた。そして三つ目。これもボールから離れたところで関学の選手に小競り合いを仕掛け、ヘルメットを殴った。5プレーで三つもの反則。私には、彼が何かにとりつかれているかのように見えた。
彼はここで資格没収(退場)の処分を受けた。去年の甲子園ボウルでの彼の活躍をはっきり覚えていたので、いったい何が起こったのかと感じた。フィールドから出てきた彼はスタッフに促され、ベンチ奥にあった負傷者用のテントに入った。私はそこに近づいた。
彼は泣いていた。声を上げて泣いていた。同じポジションの選手が肩に手を置いて、言葉をかけていた。関学側に回って、テントの入り口からのぞく彼の背中を撮った。
テレビで流されている動画を見る限り、クウォーターバックを故意に潰しに行った行為で退場だと思うのだが、
フットボールの規則では許容範囲なのか?
テレビであの危険な行為は退場に値すると誰もいっていないので、退場のようなレベルではなかったのか?
これだけ騒いでいるのだから、審判によるルールの解釈が甘かった事はないのか?ルールに従い、ルールの解釈に問題が
ないのなら、スポーツマンシップには反するが許容範囲と言う事なのか?
「虚偽公文書作成罪の成立には、作成や決裁権限を持つ者が文書の趣旨を大幅に変える必要がある。」との解釈で佐川宣寿前国税庁長官は不起訴、
そして、福田淳一前事務次官がセクハラ問題に関して麻生太郎財務相の「セクハラ罪っていう罪はない」発言で厳しい処分はない。
悪質タックルがスポーツマンシップだけの問題であるのなら財務省の不祥事のように思った以上に軽い処分で幕引きになる可能性もある。
報道は、事実と適用される規則を丁寧に説明してほしい。ルールの解釈や審判の判断に問題があるのなら、解釈を改正するべきだと思う。
アメリカンフットボールの日大の選手が危険すぎるタックルで関学大のQBを負傷させた問題で、負傷させた日大の守備選手が22日に東京都内で記者会見し、内田正人監督とコーチの指示に基づいて反則をしたと主張することが分かった。関係者が21日、明らかにした。
日大は16日までに関学大に届けた回答書には「意図的な乱暴行為を選手へ教えることはない」と内田正人監督(62)の指示はなかったとしていた。内田監督は関学大に謝罪した19日に、指示については明言を避けていた。
関学大・小野宏ディレクターは17日の会見で、悪質な反則行為を繰り返した日大選手に対して「本人(日大選手)がこのことについての真実を自分の口から話すことが、彼のこれからの人生のためにも必要なんだろうと思います」と話していた。
金融庁がどのような対応を取り、判断するか次第だ!
対応を誤ると、似たような金融機関を延命させ、生き残れるチャンスがある金融機関まで巻き込んで終わらせることになるかもしれない。
経営破綻も起きたシェアハウス向けで融資実績を伸ばしていた地方銀行、スルガ銀行(沼津市、米山明広社長)の内部統制の不全が際立っている。オーナーに融資とローンのセット契約を迫っていた疑いも浮上。与信費用の積み増しで先行きも不透明だ。(東京商工リサーチ特別レポート)
◆営業幹部が審査担当者を恫喝
スルガ銀行は5月15日、2018年3月期の決算を発表した。経常収益(連結)は、1562億7800万円(前期比7.2%増)で、貸出金利息の増加や株式等売却益が寄与した。
一方、経常利益は308億7100万円(同46.9%減)、当期純利益は210億6500万円(同50.5%減)と半減した。これはシェアハウス関連融資等で貸倒引当金を積み増し、与信費用が増加したため。
スルガ銀行は、5月15日に東京地裁から破産開始決定を受けたスマートデイズが展開していた「かぼちゃの馬車」などのシェアハウス向けで融資実績を伸ばしている。同日、スルガ銀行危機管理員会が公表した資料によると、シェアハウス向け融資の顧客数は1258名、融資総額は2035億8700万円に上っている。
危機管理委員会は、同行の横浜東口支店の複数の行員がオーナーの自己資金水増しを認識していた可能性を指摘。同時に、「営業が審査部より優位に立ち、営業部門の幹部が融資の実行に難色を示す審査部担当者を恫喝するなど、圧力をかけた」と内部統制の不全を公表している。
◆融資の倍以上の金利のフリーローン契約を強要?
スルガ銀行から融資を受けたシェアハウスのオーナーの一人は、東京商工リサーチ(TSR)の取材に応じ、「シェアハウス取得に際し、スルガ銀行から金利3.5%で融資を受けたが、金利7.5%のフリーローン契約を同時に迫られた」と話している。
これがどこまで広がっていたか不明だが、融資とフリーローンを実質セットにして高い収益性の原動力の一つにしていた可能性も浮上している。
2019年3月期の業績予想(連結)は、経常利益365億円、当期純利益250億円と増益を見込んでいる。
15日夕方、TSRの取材に応じたスルガ銀行の担当者は、「シェアハウス関連の貸倒引当金は2018年3月期で現状のすべてを見積もっており、2019年3月期の業績予想にシェアハウス関連の影響は現状のところ考慮していない」と説明。
その上で、担当者は「これまでも想定外(の貸倒引当金)があったので、現状のところ、としか言えない」と先行きの不透明さを含ませた。
◆スマートデイズ以外のシェアハウスにも融資
TSRの取材では、同行の融資はスマートデイズ以外にもSAKT Investment Partnersやゴールデンゲイン、ガヤルドなどのサブリース業者が手がけるシェアハウスやミニアパート向けでも確認されている。
スマートデイズ被害弁護団にオブザーバーとして参加する加藤博太郎弁護士(わたなべ法律会計事務所)は6日、TSRの取材に対し、「融資申し込み資料が改ざんされており、スルガ銀行はオーナーの実際の資産背景をすべて把握できていないはずだ」と指摘。
そのうえで、加藤弁護士は「シェアハウスの担保価値も著しく低く、積み増された貸倒引当金は何を根拠に算出したのかわからない」と話した。
また、「ゴールデンゲインと関係者の集団提訴も予定しており、この中でゴールデンゲインとスルガ銀行の関係の解明を進めたい」と述べた。
◇
《東京商工リサーチ特別レポート》大手信用調査会社の東京商工リサーチが、「いますぐ役立つ最新ビジネス情報」として、注目の業界や企業をテーマに取材し独自の視点に立った分析をまとめた特別レポート。随時掲載します。
みちのく銀行(青森市)は17日、本店と青森県内の7支店で2012~17年、男性行員7人が、融資の際に信用保証機関に提出する書類を偽造するなど計17件の不正があったと発表した。不適切な融資は約2億5000万円に上った。融資を受けた顧客の金銭的被害はないとしている。
同行によると、7人は同県内の15の個人や法人に融資する際、見積額の変更で実際の融資額が減るなどしたにもかかわらず、融資先に保証を出した信用保証機関に対して必要な修正手続きを取らないで、偽造した領収書などを提出していた。7人は「(修正が)面倒だった」などと話しているという。
同行は7人を懲戒処分とした。昨年12月、内部監査で発覚した。【岩崎歩】
日大が悪意のある対応を取っているのなら解体しても良い。人生が狂う、将来に影響が出る学生や関係者もいるだろうが、悪意のある対応を日大が取り続けるのであれば、 うやむやにしようとしなければどうなるのか処分する事によってスポーツ関係者に理解させるべきであろう。
学生アメリカンフットボールの試合で日大の選手が悪質なタックルを見舞った一件で、関学大の抗議文書に対する日大の回答に内田正人監督(62)の辞任が盛り込まれていないことが16日、関係者の話で分かった。17日に会見する関学大は16日夜に協議した。また、世間の厳しい目に加え、日大の部員にも現体制に疑問を持っている者も少なくないもようで、名門チームは空中分解の危機に立たされている。
関学大の抗議文書に対する回答を日大のコーチは兵庫県西宮市の同大学に15日夜に持参した。だが、その中には内田正人監督が辞任するといった文言は盛り込まれていないことが判明した。
今回の件は6日の定期戦で日大の選手が関学大QBに見舞った悪質なタックルが発端だった。関係者の話では、試合前のハドル(作戦会議)で内田監督が当該選手に指示を出したとされている。内田監督が責任を取っての辞任は確実とみていただけに、誠意ある内容を期待した関学大としては“大甘回答”と受け取らざるを得ない。負傷したQBに対して相手監督から謝罪の言葉がないことも不信感に拍車をかけている。関学大は17日の会見に備え対応を協議。51回の歴史を誇る伝統の定期戦打ち切りなど厳しい姿勢を打ち出すことが予想される。
さらに別の関係者の話で、内田監督が“続投”した場合、部員が練習をボイコットする動きがあることも分かった。「3年生以下が中心となって話が出ている」。2015年まで日大を率いた指揮官は1年のブランクを置いて17年に復帰。あまりに厳しい練習を課したため、就任直後に20人あまりが部を離れた。ただ、今回の“心離れ”は、あまりに状況が異なる。
日大広報部はこの日、学内の調査に内田監督が「監督は“必死で頑張ってこい。戦え。厳しくやれ”など厳しいことは言ったが、違反しろという指示は出していない」と証言したことを発表。調査に応じたコーチや主将らも指示を否定したという。ただ、一方で反則を犯した選手が「“反則をやるなら出してやる”と監督から言われた」と周囲に話していたことも分かった。この選手は下級生の頃から主力だったが、関係者によると最近は監督から精神的な部分で苦言を呈され「チーム内で干されている状態」。定期戦前に「やるなら出す」と反則行為を条件に出場の機会が与えられたとして両者の主張は対立している。
外部から厳しい目が注がれ、内部には不満がたまっている。21回の大学日本一を誇る名門は崩壊の窮地を迎えた。
厳しいノルマを達成しないと生き残れない銀行には退場してもらうべきだ!
どれほどの銀行がまともに業務を行っているのか知らないが、多くの不正が発覚した以上、不正を黙認する、又は、間接的に知らないふりをする
金融機関はどのようになるのか処分する事により理解させるべきだ!
シェアハウス投資向け融資の不正を巡り、多くを融資した地方銀行のスルガ銀行(静岡県沼津市)が15日、初めて現状を説明した。多くの行員が不正を認識した可能性があると謝罪したが、不正への関与は不明だとして、今後第三者委員会が調べる。業績至上主義の下、ずさんな審査で融資した姿勢に批判が強まっており、監督する金融庁の厳しい処分は必至だ。
スルガ銀は静岡県2位の中堅地銀ながら、県内にとどまらず全国で個人向け融資を伸ばし、その経営手法は金融界で注目された。その裏で、ノルマに追われた行員らによるリスク軽視の融資が続いていた。
スルガ銀が15日公表した調査結果では、シェアハウス融資が多い横浜東口、渋谷、二子玉川の3支店に焦点が当てられ、不正が指摘された。こうした首都圏の店舗が、スルガ銀の業績拡大の要だった。
行員らによると、静岡県外の多くの店舗では、新規融資の目標額が1カ月ごとに設定され、達成度合いがボーナスや出世に響く。未達が続くと厳しく叱られ、営業部門から外されることもあるという。
ある元行員は、シェアハウス以外の中古1棟マンション投資向け融資でも不正を容認したと明かす。「物件を売りたい業者と買いたい顧客がそろい、あとは改ざんに目をつぶれば業績も伸びる。逆に不正を認めないとノルマも達成できないことは上司たちもわかっていたはずだ」と話す。
藤田知也、福山亜希
スルガ銀は2018年3月期決算に合わせてシェアハウス問題について初めて説明。米山明広社長は「シェアハウス問題で多大なる迷惑と心配をかけた。おわび申し上げる」と謝罪した。関連融資は3月末時点で計2035億円、1258人分に達する。
シェアハウス投資では、不動産業者が賃料収入を約束し会社員らを勧誘。スルガ銀が1人あたり億単位を融資した。しかし賃料不払いで返済は滞り社会問題化。融資過程での不正も相次ぎ発覚し、スルガ銀の責任が追及されていた。
スルガ銀は社内調査の結果、融資基準を満たすため、オーナーの預金を多くみせかける通帳コピーの改ざんや、売買契約書での物件価格の水増しがあったと説明。不正を「相当数の行員が認識していた可能性がある」という。ただ、行員が不正を指示したかは確認できていないという。
行内では増益へのプレッシャーが強く、不正を認識しても融資が実行され、審査部門の歯止めも利かなかった。営業幹部が審査担当を恫喝(どうかつ)した事例もあった。
また、横浜東口支店では不動産業者と一体となり、高金利のフリーローンを「融資の条件」としてセット販売した。米山社長は「銀行員の良識としてあり得るか。反省している」と話した。
今後は第三者委で詳細を調べる。監督する金融庁はすでに立ち入り検査に入っており、第三者委の動向もみながら業務改善命令などの行政処分を検討する。米山社長は経営責任について、今後の調査なども踏まえ「厳しい対応をとるつもりだ」としている。同行の2018年3月期決算は純利益が前年比50・5%減の210億円。シェアハウス融資関連の貸し倒れ引当金が大幅に増えた。(藤田知也、福山亜希)
◇
〈シェアハウス投資問題〉 不動産業者らが一括借り上げによる長期の家賃保証をうたい、会社員らをシェアハウスオーナーに勧誘。多くは自己資金ゼロで、スルガ銀行で1棟あたり1億円程度のお金を借り、相場より3~5割高く物件を買った。昨秋以降、家賃減額や不払いのトラブルが目立ち始め、融資過程で通帳コピーなどの改ざんが横行していたことも発覚した。
多くのシェアハウスを売った不動産業者「スマートデイズ」(東京)は4月に経営破綻(はたん)。オーナーは億単位の借金返済に窮している。被害弁護団は不動産業者やスルガ銀行の責任を追及している。
◇
【スルガ銀が15日公表したシェアハウス融資の状況】
・2018年3月末時点の融資は、顧客1258人に計2035億円
・通帳コピーの改ざんなどの不正は相当数の行員が認識していた可能性がある
・増収増益のプレッシャーから営業が審査より優位に立ち、営業部門が審査部に圧力をかけるなど、審査機能が発揮できなかった
・一部の支店(横浜東口支店)でフリーローンを「融資の条件」としてセット販売していた
・営業成績を重視し、目先の成績追求に走り、コンプライアンス意識が低下した
・今後は通帳原本を確認するなど審査態勢を強化する
・営業成績の比重が大きい人事評価で、定性評価項目の割合を大きくする
・第三者委員会(委員長=中村直人弁護士)を設置して原因究明を行う
・第三者委や金融庁検査の結果を踏まえ、役員の経営責任には厳しい対応をとる
[東京 16日 ロイター] - SUBARU(スバル)<7270.T>が提出した新車出荷前に行う完成検査でのデータ不正問題に関する調査報告書の内容が適正かどうかなどを確認するため、国土交通省は16日午前、同社の本社(東京・渋谷)へ立ち入り検査を開始した。
係官7人が立ち入り検査を行い、スバル側は吉永泰之社長らが対応する。
出荷前に新車の安全性や品質を最終確認する完成検査において燃費や排ガスデータの改ざんがあったことが判明し、同社は4月27日に国交省へ調査報告書を提出した。
不正は主力生産拠点である群馬県太田市の工場で見つかり、報告書では現場が組織ぐるみで不正を行っていたと認定。確認できただけで903台でデータの改ざんがあり、2002年ごろには始まっていた可能性が高いという。ただし、本来の正しい測定値を前提にしても、法令に定められた保安基準などは満たしており、品質に問題はないとしている。
少なくとも複数の行員が関与しないと今回のような結果にはならない。これはスルガ銀の体質なのか?
スルガ銀の対応次第で、現場の行員達だけの問題なのか、幹部の一部も知っていたのかを推測できるであろう。
マンションの大規模修繕工事をめぐり、国土交通省が初の調査結果を明らかにした。「相場」を示して管理組合に役立ててもらうほか、工事業者らにリベートを要求し、代金をつり上げるなど、一部の設計コンサルタントの行為に警鐘を鳴らす狙いもある。
マンション修繕、割高契約に注意 国交省「相場」を公表
大規模修繕をめぐる問題は、「マンションリフォーム技術協会」が一昨年、会報誌で訴え、注目されるようになった。国交省も昨年1月、同様の指摘をした際、「コンサルが自社にマージンを支払う施工会社が受注できるよう不適切な工作をして、管理組合に損失を及ぼしている」などの例を挙げた。
「何でこんなに高いのだろう」。横浜市内の大型団地で管理組合理事長を務める加藤統久さん(60)は3年前、修繕工事の見積書を見て疑問に思った。
事前の下調べでは6億5千万円程度で済むと思っていたが、計10社から上がってきた見積もりは7億~9億円。確認すると、避難用はしごなど複数の設備で相場の倍の値段が計上されていた。
落札する業者が決まっていて、費用をつり上げているのでは――。そんな疑問を胸に契約していたコンサルに質問を重ねたが、何を聞いてもはぐらかされた。数カ月後、200万円余りの着手金を支払って解約。別のコンサルに頼むと当初の予想に近い金額で工事ができた。
設計事務所「シーアイピー」(東京)の須藤桂一代表によると、悪質なコンサルの手口はこうだ。
まず、安い料金を示して管理組…
少なくとも複数の行員が関与しないと今回のような結果にはならない。これはスルガ銀の体質なのか?
スルガ銀の対応次第で、現場の行員達だけの問題なのか、幹部の一部も知っていたのかを推測できるであろう。
女性向けシェアハウス「かぼちゃの馬車」の運営会社スマートデイズ(東京)が破綻した問題で、スルガ銀行(静岡県沼津市)は、複数の行員が審査書類の改ざんを知りながら物件所有者に融資していたとする社内調査の結果をまとめた。少なくとも数十人が関与したとみられる。報告を受けた金融庁は、不正が組織的だった可能性が高いとの見方を強めており、行政処分を検討している。
【図でわかりやすく】サブリースの仕組み
2018年3月期の決算を発表する15日に、調査結果を公表する見通し。スルガ銀は個人向け融資を担当した行員約500人に対し、記名式のアンケートを実施。資金の借り入れ希望者を審査する際、預金残高や年収を水増しした書類が提出されたことを知りながら、融資を決定したという趣旨の回答が数十人にのぼった。融資を実行する見返りとして、物件の販売業者から金銭を得たり、接待を受けていたケースもあった。スルガ銀の広報担当者は「アンケートの結果を踏まえ、外部の有識者による第三者委員会などで調査を進める」とコメントした。
スマートデイズは、シェアハウス用の物件をローンを組ませて1億円以上で販売。物件を借り上げて転貸する「サブリース」を展開していた。しかし入居者が集まらず、所有者に保証していた賃借料の支払いを停止して4月に経営破綻した。関係者によると、スマートデイズは販売代理店を介し、ほとんどの購入者に横浜市内のスルガ銀支店で融資を受けるよう指示していた。
シェアハウス所有者の弁護団は、スルガ銀の行員らが融資の審査書類の改ざんに関与した疑いがあるとして刑事告発する考えを表明している。【鳴海崇】
船で大きな損失が発生し、飛行機は損失が進行形。技術大国、日本は傾き始めているのか?
三菱重工業は8日、国産初のジェット旅客機「MRJ」(三菱リージョナルジェット)を開発する子会社の三菱航空機が資本増強すると正式発表した。同社は開発費がかさみ約1000億円の債務超過に陥っている。三菱航空機の他の株主と具体策を協議した上で、2018年度中に債務超過の解消と財務基盤の強化を図る。
三菱重工の宮永俊一社長が同日、決算発表の会見で明らかにした。MRJの初納入は当初は13年の予定だったが、設計の見直しなどで5度延期し20年半ばにずれ込んだ。1800億円と見込まれた開発費も6000億円規模に膨らんでいる。この結果、三菱航空機は17年3月末に510億円の債務超過に転落。債務は、この1年でさらに約500億円膨らんだ。
宮永社長は「20年度までにまだ開発費用がかかる。債務超過の状態は良くないので早く解消したい」と説明。国が機体の安全性を認める「型式証明」の取得に向けて必要な追加の試験機も19年初めに投入する予定で、「もやは晴れつつある。長期的に事業を続ける体制を敷くまで私が責任を持つ」と強調した。
三菱重工がこの日発表した18年3月期連結決算は、売上高が前期比5.0%増の4兆1108億円、最終(当期)利益は同19.6%減の704億円と増収減益だった。また、20年度までの事業計画も発表。新事業への投資や航空用エンジンなどの収益拡大を進め、20年度に売上高で5兆円を目指す。
原子力事業ではトルコの新型原発建設計画の事業化に向けた調査を進めているが、安全対策費などが膨らみ採算性が危ぶまれている。宮永社長は「調査はあと数カ月かかる。その上で日本とトルコ政府などと今後を検討する」と述べるにとどめた。【竹地広憲、小倉祥徳】
「スルガ銀は不正には関与していないとしているが、金融庁の検査などで不正の原因がどこまで解明されるかが焦点だ。」
組織的な不正でないとすれば、管理・監督が出来ないほど組織が痛んでおり、人材のモラルや教育もコントロールできない状態の可能性もある。
どちらであっても、銀行としえは致命傷だと思う。
シェアハウス投資などへのスルガ銀行(静岡県沼津市)の融資で資料改ざんが相次ぎ見つかった問題で、改ざんされた資料をもとにした融資が同行の11支店・出張所で行われていたことが、朝日新聞の取材でわかった。銀行側は通帳原本などの確認を行員に求めていたが、広範囲にわたって多数の不正が見逃されたことになる。スルガ銀は不正には関与していないとしているが、金融庁の検査などで不正の原因がどこまで解明されるかが焦点だ。
シェアハウス投資では、少なくとも5業者が昨年以降に約束した賃料をオーナーに払わなくなった。5業者すべての物件で通帳コピーなどが改ざんされ、貯蓄や年収が水増しされた資料をもとに首都圏にある同行の7支店・出張所が融資を実行した。
約700人の顧客を集めて倒産したスマートデイズ(東京)の物件は、横浜東口支店(横浜市)の取り扱いが多い。数十~100人の顧客を集めたほかの業者の物件は渋谷、二子玉川(いずれも東京)など特定の支店に集中している。
中古1棟マンションへの投資では、少なくとも4業者が売却・仲介した物件で同様の不正があった。都内のある業者は十数人分の通帳コピーを改ざんし、新宿(東京)や仙台など6支店で融資を受けた。京都支店に出した資料を改ざんしたと証言した業者もいる。
重複を除くと、同行が都内に置く5支店を含む計11支店・出張所で不正が見逃され、貯蓄や年収が基準に満たない会社員らに過剰な融資が実行された。
違反した業者には処分は必要。違反した業者が得をする事は許すべきでないし、甘い処分であれば、違反して仕事を取る方が得になる。
年金の所得控除に関するデータ入力ミスなどで過少支給が相次いだ問題を巡り、日本年金機構が委託先の「SAY(セイ)企画」(東京都豊島区)に約4400万円の損害賠償を求めていることが分かった。応じない場合は提訴する方針だ。
機構と同社は昨年8月、扶養親族等申告書のデータ入力作業を契約。10月の作業開始後、月ごとの納品数に応じて対価を支払う単価契約で、契約金は総額約1億8千万円だった。
中国の関連企業に再委託するなど、同社の契約違反が判明したのは今年1月。機構は年金の支払いが遅れないよう、代わる業者が見つかるまで同社に委託を続け、2月中旬に契約を打ち切った。同社に対しては、10~12月の納品分の費用を支払った。
2016年11月に名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請、2018年3月に再生計画の認可を受けていた(株)日本コンタクトレンズ(TDB企業コード:400132762、資本金3億6820万円、愛知県名古屋市中川区好本町3-10、代表水谷純氏)と、子会社の(株)日本コンタクトレンズ研究所(TDB企業コード:982196995、資本金4840万円、東京都中央区日本橋箱崎町1-7、同代表)は、5月1日に名古屋地裁に民事再生手続きの廃止を申請した。
今後、破産手続きに移行する見込み。
申請代理人は若杉洋一弁護士(大阪府大阪市北区中之島2-3-18、弁護士法人大江橋法律事務所、電話06-6208-1500)ほか。
(株)日本コンタクトレンズは1964年(昭和39年)5月に設立したコンタクトレンズの卸業者。ディスポレンズを主力に扱っていたほか、ハードコンタクトレンズ「ニチコンRZX」などの自社製品を製造、さらに点眼薬や眼内レンズなどのケア用品の製造や卸も手がけていた。創業者の水谷豊氏はコンタクトレンズの研究・開発分野の先駆者で、中部地区の眼科医を中心に「ニチコン」ブランドの製品を供給、円錐角膜用や角膜移植後の角膜不正乱視向けハードコンタクトレンズ、遠近両用ハードコンタクトレンズなど他社の参入が少ない分野に特化し、ディスポレンズの普及が進んだ96年2月期には年売上高約38億7000万円をあげていた。
しかし、以降は同業他社や海外メーカーの参入による低価格化やソフトレンズへの需要の高まり、廉価メガネとの競合などとも相まって販売数量は漸減し、2016年2月期の年売上高は約20億1000万円にとどまっていた。金融機関からの資金調達のメドも立たず、9月には決済不履行となり自力再建を断念。2016年11月15日に名古屋地裁に民事再生法の適用を申請、今年3月には再生計画の認可を受けていた。
しかし、スポンサー企業との間で締結していたスポンサー契約に定める条件を満たせず、支援が受けられない事態となったことから、今回の措置となった。
日本コンタクトレンズ研究所は1960年(昭和35年)5月創業、1964年(同39年)2月に法人改組したコンタクトレンズの卸業者。「ニチコン」ブランド商品を扱っていたが、親会社と同様の措置となった。
民事再生法申請時の負債は、日本コンタクトレンズが約14億2000万円、日本コンタクトレンズ研究所が約4億7000万円で、2社合計約18億9000万円だが、変動している可能性もある。
時代と共に環境が変わる事がある。環境に適応できない、又は、運悪く環境の変化がかなり影響する立場にあったのであろう。
大学行っても、企業を取り巻く環境は変化しているので、就職した会社で退職出来るとは限らない。もう、学歴だけで安泰の時代は
日本では終わりつつあるのかもしれない。
変化に対応できる人材が、生き残れる時代になりつつあるのかもしれない。時代と共に必要とされる人材は変化する。
戦国時代では、戦で実績を残し、誰に仕えるのか考える事が出来る、又は、運よく勝ち組に仕える武士が出世した。徳川の時代になると
平和になり、戦での実力は評価されないし、実績を証明する機会もない、学問や組織内政治に才能がある、又は、権力者に取り入るのが
上手い武士が出世した。
同じ能力を持っていても、環境の違いで結果や出世が違ってくる。環境に適応できない、又は、運が悪い人達は下に流されるしかない。
民間調査会社の帝国データバンク太田支店は27日、大泉町吉田のエアコンおよび食品ショーケース向けパイプ加工業「ナガヌマ」が事業を停止し、自己破産申請に向け準備に入ったと発表した。負債は13億円。
同支店によると、ナガヌマは昭和43年創業。地元の大手家電メーカー向けに業績を伸ばし、平成3年7月期には売上高約60億円を計上していた。
しかし、得意先が一般家庭用エアコン部門の大半を海外生産にシフトしたため受注が激減。縮小均衡をはかる中、得意先の経営不振による受注減で減収が続き、27年7月の年間売上高は約8億円まで落ち込み、資金繰りが悪化していた。
「米軍機はなぜ低空飛行をするのか」の回答を理解できる日本人はほとんどいないと思う。
実際に戦闘を経験していない、そして、戦闘をしない日本の自衛隊には必要のない事。ただ、訓練でもしない事を実践で
行えるのか?レーダーにキャッチされ、スクランブル、地対空ミサイル、そしてその他の防衛手段により高額な戦闘機と
高額なお金をかけて育てたパイロットを失うリスクを考えると判断基準次第では必要と考えられる。
アメリカが本当に日本を守ってくれるのかは疑問だが、日本がアメリカに守ってもらおうと考えているのなら、多少の妥協は
仕方がないと思う。
日本の自衛隊が本当に戦闘で結果を出す訓練が必要と考えるなら、同じ訓練をするしかない。
雪の山間をカッ飛ぶF-16
2018(平成30)年4月2日、動画投稿サイト「YouTube」にアメリカ空軍三沢基地所属のF-16「ファイティングファルコン」が、岩手県の山間部上空を低空飛行する映像が公開され、大きな反響を呼んでいます。なぜアメリカ軍はこのような低空飛行訓練を行うのか、そしてこのような飛行が許されるのかについて簡単に解説します。
【写真】三沢基地、裏方スタッフも訓練の成果を
F-16といえば、全長約15m、全幅約10m、全高約5mという比較的小型の機体ながら、優れた機動性や兵器運用能力によって高い空対空/空対地戦闘能力を誇る機体として知られています。
実は、今回話題に上っている三沢基地所属のF-16は、一般のF-16を運用している部隊とはひと味違う特殊な任務を負っていて、これが今回の低空飛行映像と密接にかかわっていると思われます。その特殊な任務とは、敵防空網の制圧です。
「敵防空網制圧(Suppression of Enemy Air Defense:SEAD)」とは、文字通り敵が配備しているレーダーや対空ミサイルの位置を特定してこれらを攻撃、破壊することを指します。これは、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争などを経て確立した手法で、敵が配備している防空システムにわざと自らの機体をさらすことで、装備するセンサーによって逆に敵の位置を特定し、そこにミサイルなどで攻撃を行うことによって敵防空網を無力化するというものです。三沢基地にはこのSEADを専門とするアメリカ太平洋空軍唯一の部隊である第35戦闘航空団と、この任務を実施する航空機としてF-16CJ/DJが配備されています。
そもそもそこまで低く飛んでいいものなの?
ではなぜ三沢基地のF-16は低空飛行をする必要があるのでしょうか。それは、敵のレーダーによる探知を避けるためです。
基本的に、レーダーから放出される電波は直進します。そのため、地上に設置されているレーダーによって水平線や地平線の上を飛んでいる航空機は探知することができますが、海面や地表ギリギリの高さを飛行する航空機は水平線や地平線の下に隠れてしまい、だんだんとレーダーとの距離が近づいてきて機体が水平線や地平線の上に現れなければ、その探知は非常に難しいのです。また、山間部や渓谷を低空飛行することで山陰に隠れながら飛行を行うことができるため、同様にレーダーによる探知を回避できます。このようにしてレーダーによる探知を回避しながら敵の懐に飛び込み、自機が装備する兵器によって敵の防空システムや施設を破壊するのです。
ではこうした低空飛行に関して、法的な問題点は存在しないのでしょうか。そもそも日本には「航空法」という法律があり、その第81条には航空機の飛行高度について次のように規定されています。
「航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない」
ここにある「国土交通省令で定める高度」とは、以下とされています。
●国土交通省令で定める航空機の飛行高度
・人又は家屋の密集している地域の上空:当該航空機を中心として水平距離六百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度
・人又は家屋のない地域及び広い水面の上空:地上又は水上の人又は物件から百五十メートル以上の距離を保って飛行することのできる高度
・それ以外の地域の上空:地表面又は水面から百五十メートル以上の高度
つまり、原則的に日本では上記の高度より低高度を飛行することはできないのです。
しかし、在日アメリカ軍の場合には事情が異なってきます。
ここでも顔を出す「日米地位協定」、航空法は適用除外!
日本とアメリカとのあいだには、「日米地位協定」というものが結ばれています。これは、日米安保条約に基づき日本に駐留する在日アメリカ軍について、その運用の円滑性を確保するために、日本国内における施設、区域の使用やアメリカ軍の地位について規定したものです。そして、その協定に基づいて在日アメリカ軍が日本国内で実用的、実戦的な訓練を行う環境を整備することで、パイロットなどの技能向上を可能とし、またそうすることで即応体制を維持するために、上記の航空法の一部規則の適用をアメリカ軍機などに関して除外するという内容の「航空特例法(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律)」というものが存在します。これによって、アメリカ軍機に関しては航空法の規制が適用除外となっているのです。
しかし、アメリカ軍も自由に低高度を飛行しているわけではなく、飛行ルートにおける危険物などのチェック、低空飛行を運用即応態勢上の必要性から不可欠と認められるものに限定、原子力エネルギー施設や民間空港の回避、人口密集地などに関する考慮、パイロットや機体整備員なども含めた飛行前の事前準備、航空法規定の自発的な適用など、さまざまな影響最小限化策や安全対策などを施しています。
ただし、それと同時に騒音や安全に関する不安を抱える地元住民への配慮についても、より一層強化していくべきでしょう。
稲葉義泰(軍事ライター)
「不正の動機について、報告書は、数値にばらつきがあると、上司への説明に手間がかかることや、検査員が技量を疑われることを恐れた点などを指摘した。不正は現在の検査装置が導入された02年以降から始まった可能性が高いという。」
数値のばらつきは、検査員の技量の問題か、品質の問題だと思う。どちらも事実を理解して対応策を実行しないと改善は見られない。
検査員の技量に問題があれば、技量がある検査員が再度、検査を行えば技量の問題なのか、数値の変化でわかる。技量の問題であれば、問題のある検査員の
教育や指導で改善できる。
「16年の三菱自動車による燃費データ不正問題発覚後には、現場で「書き換えはまずい」との声も上がったが、管理職の現場への関心が薄かったため、問題を把握する機会を逸した。報告書は『検査の公益性に対する自覚の乏しさ』を批判した。」
基本的に組織の価値観及び企業の社員教育に問題がある可能性がある。人は環境で良い方向、又は悪い方向に影響を受ける。そして、長期間、同じ
環境にさらされると、カルトではないが、価値観や考え方がおかしくなる事がある。
品質や組み立てのバラツキによる数値の違いであれば、問題は更に深刻だ。コストにも影響する。事実は知らないが、企業としては認めたくない
ケースである。
SUBARU(スバル)は27日、新車の出荷前に行う燃費や排ガスの検査データ改ざん問題に関する調査報告書を国土交通省に提出した。検査員を統括する班長の指示でデータが書き換えられており、報告書は「組織的な行為」と認定した。改ざんは確認できただけで全9車種、903台にのぼった。国交省は報告書の内容を精査し、業務改善指示を出すかどうか検討する。【竹地広憲、和田憲二、川口雅浩】
スバルでは昨秋、新車の無資格検査問題も発覚しており、相次ぐ不正は、同社のコンプライアンス(法令順守)意識の欠如ぶりを浮き彫りにした。報告書は改ざんによる品質への影響は否定しており、スバルはリコール(回収・無償修理)をしない方針。ただ、ユーザーの不信感は拭えず、販売への打撃も予想される。
報告書によると、不正は、主力工場の「群馬製作所」(群馬県太田市)で出荷前に完成車両の一部を抜き取って行う検査で見つかった。燃費や排ガス計測値にばらつきがあった場合、検査員が数値を適正値に書き換えていた。
具体的には、2012年12月から17年11月までの検査対象車6939台のうち903台で不正が行われていた。不正は看板モデルの「フォレスター」や「レガシィ」「インプレッサ」など9車種に及び、トヨタ自動車に供給しているスポーツカー「86(ハチロク)」も含まれていた。
不正の動機について、報告書は、数値にばらつきがあると、上司への説明に手間がかかることや、検査員が技量を疑われることを恐れた点などを指摘した。不正は現在の検査装置が導入された02年以降から始まった可能性が高いという。報告書は、不正は現場の班長と検査員による「組織的な行為」と認定した。
16年の三菱自動車による燃費データ不正問題発覚後には、現場で「書き換えはまずい」との声も上がったが、管理職の現場への関心が薄かったため、問題を把握する機会を逸した。報告書は「検査の公益性に対する自覚の乏しさ」を批判した。
国交省への報告後に東京都内で記者会見した吉永泰之社長は「背景は無資格検査と同じで企業風土から生じた。多大なご迷惑を掛けた」と謝罪。6月に社長を退き、会長兼最高経営責任者(CEO)に就くことを踏まえ、自らが社内教育の徹底など再発防止に注力する方針を示した。「もう一度問題を起こしたらブランドがアウトになる」と危機感もにじませたが、顧客の信頼を取り戻す道は険しそうだ。
◇キーワード:スバルの不正
SUBARU(スバル)は昨年10月、「群馬製作所」の本工場などで出荷前の新車を国に代わって点検する「完成検査」を長年にわたり無資格の従業員にさせていたと公表。
外部の弁護士の調査によると、社内で知識や技能があると見なした従業員に資格がないまま検査させ、正規検査員の印鑑を代わりに押させるなどの不正行為が1990年代から横行していたことが判明。スバルは昨年12月、国土交通省に報告した。
一部の社員が調査で「出荷前の検査時に燃費データを改ざんした」と証言していることも分かり、国交省は追加調査を指示していた。スバルは無資格検査問題に関連し、計約41万7000台のリコール(回収・無償修理)を届け出ている。
「報告書は『本来の測定値を前提にしても基準を満たしている』として、品質への影響は否定した。」
品質への影響がないのであれば、なぜ新車出荷前に行う燃費と排ガスの検査データ改ざんが行われたのか?
SUBARU(スバル)は27日、新車出荷前に行う燃費と排ガスの検査データ改ざん問題に関する調査報告書を、国土交通省に提出した。群馬県の主力工場で、検査員を統括する班長の指示でデータ書き換えが行われており、報告書は「組織的な行為」と認定。確認できただけで903台のデータ改ざんがあった。ただ、報告書は「本来の測定値を前提にしても基準を満たしている」として、品質への影響は否定した。
吉永泰之社長が同日、国交省を訪れ、奥田哲也自動車局長に報告書を手渡した。奥田局長は「国民に自動車メーカーへの不信感を与えるもので、あってはならない」と法令順守の徹底を求めた。
同省への報告後、東京都内の本社で記者会見した吉永社長は「多大な迷惑、心配をかけたことを心よりおわびする」と陳謝。「改革を全うすることが経営責任だ」と述べ、再発防止に全力で取り組む考えを示した。
改ざんは完成車両の一部で実施している自主検査で発覚。2012年12月から17年11月までの検査対象車6939台のうち、903台で不正が見つかった。不正は「フォレスター」や「レガシィ」、「インプレッサ」など9車種に及んだ。
結局、メディアは権力に逆らえない?メディアは権力の顔色を伺いながら中途半端なジャーナリズムをやっているのか?
セクハラオヤジから“口撃”された女性の告発の舞台が、なぜ本誌(「週刊新潮」)なのか――。騒動を扱う情報番組でコメンテーターや司会者が口にしている、この単純な疑問に頷いた視聴者も少なくなかろう。お説ごもっとも。ならばいま一度、端的に説明させていただきます。(※記事内容は「週刊新潮」4月26日号掲載時のもの)
速報「平尾脱獄囚」をパシリにした受刑者リーダーが明かす「スパルタ刑務所」の実態
たとえば、4月15日のTBS系「サンデー・ジャポン」。「今回ちょっと思ったのはね」と、テリー伊藤。
「本当だったらああいうことがあったら自分が属しているメディアに対して言えばいいのに、(中略)事務次官の方だって当然、誰だってことは分かるわけじゃない。彼女自身がやりにくくないのかなあと思って」
この翌日。日本テレビ系の「ミヤネ屋」では、
「女性記者の方だったら、なんでそれを週刊新潮さんに持っていくんですかね。自分でできないんですかね」
元読売巨人軍の宮本和知がこう言い、宮根誠司は、
「だから結局そうなってくると、特定されてしまうってことがあるんですかね」
これらを約(つづ)めれば、「被害女性たちは、なぜ自社で報道できないか」となる。
それにはまず、「自社」に訴えたことのある女性の声をご紹介しよう。彼女は40代、大手新聞社の勤務だ。
「社会部記者でした。情報源からのセクハラを受けいれてネタを引いているとか、ただならぬ関係にあるんじゃないかと疑われて口惜しい思いをしたので、会社に相談したのです」
すると、どうなったか。
「幹部に呼び出され、“ひとりの人間を潰す気か”と叱責されました。情報源の勤務先に洩れて迷惑がかかったらどうするんだ、と」
記者クラブと会社の看板
次官の件とはいささか異なるが、そもそもの問題は、
「日本は、組織ジャーナリズムで動いていますから」
と、上智大学の碓井広義教授(メディア文化論)。
「記者クラブのような組織に属し、会社の看板を背負うからこそ取材ができるのです。そういったなかで自らが属する媒体で被害を報じれば、同僚が取材現場でなんらかのリミットをかけられることは火を見るより明らか。福田次官の件がそんな相手の立場の弱みを巧みに利用した、卑怯な手口だったといっても、彼女たちもセクハラを受けて、そこで帰ってしまえば、会社から“なにやってんだ”と言われてしまうんですよ」
具体的に言えば、こういうことだ。財務省を担当するデスクの解説。
「セクハラに反発したりすれば、その女性記者が所属する社は財務省から嫌がらせをされて“特オチ”(※他社は報じているのに、自社だけが逃したニュース)が待っている。そうなると同僚にも迷惑がかかります」
これは検察や警察、各省庁の記者クラブにもあてはまる。政治家相手も然り。
「新聞やテレビの記者がもっとも避けたいのが特オチです。特オチは会社の看板に泥を塗るだけでなく、記者の評価にも直接、響く。つまり、ひとりの女性記者がセクハラで声をあげると、その社のクラブ員が特オチし、評価を下げられる可能性がある。それが分かっているから、女性記者は多少のセクハラにもニコニコ笑って耐え、取材相手に愛敬を振りまくわけです」
たとえば、財務省担当の至上命題のひとつに、日銀総裁人事がある。
「それで特オチしようものなら、それこそ地方の支局に飛ばされます。最強官庁と呼ばれる財務省は情報の出し入れがうまく、記者を使った情報操作にも長けている。日ごろから財務省の意に沿う原稿を書いていないと、日銀総裁人事が取れないといった仕打ちを受けるおそれがあります」
いかがでしょう? なぜ自社で報道できないか、お分かりいただけたのでは。
特集「嘘つきは財務官僚の始まり セクハラをしらばっくれた『福田次官』の寝言は寝て言え!」より
時代や技術革新で生き残れない企業と変化しながら生き残る企業がある。
銀行も胡坐をかいていては生き残れない環境が到来したと言う事であろう。
「かぼちゃの馬車」のスマートデイズ社が経営破綻
4月18日、女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」を展開するスマートデイズ社が、東京地裁から民事再生法の申し立てを棄却され、破産手続きに移行することが発表されました。同社は4月9日に民事再生法を申請していたのですが、結局は事業再生が困難と判断されたようです。
スルガ銀行の株価チャートを見る
帝国データバンクによれば、債権者911人に対して負債総額が約60億円となっています。今後、大きな社会問題に発展するかもしれません。
最近人気が高まってきたシェアハウスとは?
同社が手掛けていた女性専用シェアハウス「かぼちゃの馬車」の事業内容について、ザックリですが説明しましょう。
まず、シェアハウスとは、自分の部屋とは別に、他の入居者と共同利用できる共有スペース(キッチン、浴室、トイレなど)を持った集合賃貸住宅を言います。共同住宅ならではの「交流」を楽しめ、加えて、通常の賃貸住宅に比べると初期費用や月々の賃貸料を抑えたリーズナブルな価格であることも大きな魅力とされ、日本でも人気が高まっています。
多くの投資家から集めた購入資金で事業を展開
同社は、こうしたシェアハウス建設資金を多くの投資家(所有者、オーナー)から集めました。そして、建設後は一括借り上げという形を取り、入居者からの賃貸収入が主な売上高となります。その賃貸収入から自社の取り分(手数料や代行費用など)を除いた金額を、投資した所有者に支払うというモデルです。
また、資金を拠出した所有者も、月々一定の収入を確保できるという目論見です。今流行りの“サラリーマン大家さん”事業と類似しており、実際にそうした所有者も数多くいた模様です。
最大のリスク要因だった入居者数の激減が現実に
この事業の最大のリスクは、入居者の減少(=“空室率の高まり”)です。入居者が少なければ、同社に入る賃貸収入が減って、それがそのまま所有者が受け取る収入の減少に繋がります。
今回、当初は“女性専用”という目新しさに人気が集まったものの、その後は入居率が低下の一途を辿り、結果的には計画を大幅に下回って資金繰りに行き詰ったということのようです。
また、同社が破産手続きに入ることから、所有者も投資回収の目途がつかなくなりました。
ビジネスモデル自体はごく普通の不動産投資だが…
“なんだ、普通の不動産投資と同じじゃないか。なぜ社会問題になるのか?”と思った人も多いでしょう。
そうです、その通りです。
確かに、同社が投資資金を集める際の違法性(虚偽説明、断定的判断の提供、利益保証など)があったかどうかは、今後明らかになると思われます。しかしながら、同じような不動産投資は数多く行われており、ビジネスモデル自体に違法性を見出すことは難しいでしょう。
では、一体何が大きな社会問題になる可能性が高いのでしょうか?
多額の資金融資を行ったスルガ銀行に大きな批判が集まる
最大の問題は、多くの所有者が購入資金を銀行からの融資(早い話が借金)で工面したことです。しかも、所有者の財務実態に見合っていない過剰融資だった可能性も高まってきました。
今回、所有者に最大の資金融資を行ったのがスルガ銀行であり(注1)、審査を含めたその融資態勢に大きな批判が集まっています。そして、ついに4月13日から金融庁による一斉立ち入り検査が始まったと報じられました(注2)。
立ちり検査が進み、同行による資金融資の問題点、あるいは、一歩進んで何らかの違法性(スマートデイズ社との関係含む)が明らかになるのか、今後一層の注目が集まるでしょう。
注1)スマートデイズ社の債権者説明会で、スルガ銀行以外にも複数の銀行が資金融資を行ったことが明らかになっている。
注2)各報道機関が一斉に報じたものの、現時点ではスルガ銀行からの正式発表はない。
スルガ銀行株は3カ月間強で半値以下に大暴落!
今回の「かぼちゃの馬車」問題が表立って明るみになったのは、2017年晩秋以降だったように思われます。スルガ銀行の株価を見ると、年が明けた2018年から下落基調が鮮明となり、直近安値(1,200円、4月19日)は年初高値(2,569円、1月10日)の半値以下に暴落しました。
株価が3カ月間で半値以下というのは尋常ではありません。今回の一連の問題による何らかの重い行政処分を織り込み始めたと考えられますが、十分に織り込んだかどうか予断を許さない状況です。なお、4月23日の終値は1,334円でした。
地方銀行が置かれた厳しい収益環境が背景に
さらに、これはスルガ銀行に限った問題ではない可能性もあります。現在、地方銀行の収益環境は、かつてない厳しさとなっています。あのメガバンクですら大リストラ実施を余儀なくされているのですから、人口減少の加速や地域経済活動の低下による影響が大きい地方銀行が、さらに苦しい収益環境であることは当然と言えましょう(注3)。
注3)2017年10月に金融庁が地方銀行の収益減少のスピードが予想以上に速まっているとの報告書を発表済み。
実際、スルガ銀行以外の地方銀行株も軒並み低迷を余儀なくされています。
その結果、地銀の合併や経営統合が相次いでいるのはご承知の通りですが、一方で、従来の柱だった企業への貸出業務に代わる新たな収益源も求められています。今回問題となった不動産投資への融資拡大、とりわけ、個人向け融資の拡大がその取り組みの1つだったことは容易に想像できます。
「かぼちゃの馬車」問題は“氷山の一角”なのか?
今回明るみなったスルガ銀行による一連の不動産融資の問題が、“氷山の一角”なのか否か、今後の調査進展が待たれるところです。ただ、スマートデイズ社が破産手続きに向かうことで、その実態が明らかになるのはそう遠くはないと思われます。
投信1編集部
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設工事を受注した大成建設から海上警備を委託された警備会社「ライジングサンセキュリティーサービス」(東京都渋谷区)が、業務に当たった人数を水増しし、人件費約7億4千万円を過大請求しようとしていたことが24日、防衛省への取材で分かった。同省は、不正把握後も同社を指名停止処分にせず4件で計約70億円の契約を結んでいた。
防衛省によると、大成建設は平成26年8月、ライジング社に海上警備業務を委託。27年1月、沖縄防衛局に同社従業員を名乗る人物から通報があり、同社による過大請求の疑いが発覚した。仕様書よりも少ない人数で業務に当たり、人件費を事実上水増しした実績を提出していたが、実際には請求には至っておらず、過払いはなかった。
「神戸製鋼所がアルミなどの製品で強度や耐久性のデータを改竄(かいざん)していた問題で、改竄が違法行為に当たる疑いがあるとみて、東京地検特捜部と警視庁捜査2課が刑事責任追及に向け、近く捜査に乗り出す方針を固めたことが24日、捜査関係者への取材で分かった。」
他の企業のデータ改ざんと何がどう違うのか?他の企業も捜査されるのか?
神戸製鋼所がアルミなどの製品で強度や耐久性のデータを改竄(かいざん)していた問題で、改竄が違法行為に当たる疑いがあるとみて、東京地検特捜部と警視庁捜査2課が刑事責任追及に向け、近く捜査に乗り出す方針を固めたことが24日、捜査関係者への取材で分かった。不正競争防止法違反容疑などの適用を視野に捜査を進めるとみられる。日本を代表する企業による改竄問題は、刑事事件に発展する見通しとなった。
同社に対しては、米司法省が書類提出を求めるなど違法性の有無に関心を持っているとされるほか、米国やカナダの消費者から集団訴訟を起こされるなど問題は国外にも波及しており、日本の捜査当局が同社の刑事責任を追及する必要があると判断したもようだ。
改竄は長いもので約40年以上にわたって行われており、特捜部と2課は同社が改竄に手を染めた経緯を解明する。
同社が今年3月、公表した外部調査委員会の最終報告書などによると、同社本体でアルミや鉄粉などで改竄が確認され、グループ会社でも行われていた。データが改竄された製品は600社以上に納入されており、三菱航空機の国産ジェット機「MRJ」や国内自動車メーカーの乗用車にも使われていた。
改竄は「遅くとも1970年代以降」に始まったものもあり、中には役員が役員就任前に改竄に関与したり、知っていて黙認したりしていた例もあったという。また、正規のデータをシステムに入力した後、品質保証部門などで数値を改竄していたことも明らかになった。こうした改竄は「トクサイ(特別採用)」の隠語で呼ばれて長年引き継がれてきたという。
データ改竄をめぐっては昨年3月、免震装置ゴムの性能データを改竄したとして、大阪府警が不正競争防止法違反(虚偽表示)容疑で東洋ゴム工業などを摘発。大阪地検は同社の子会社のみを同罪で起訴した。
神戸製鋼の改竄公表後には、三菱マテリアルや東レの子会社でも改竄が発覚している。
あまりホリエモンの意見には賛成できないが、この件に関してはホリエモンは正しいと思う。
週刊新潮が報じた、財務省の福田淳一事務次官がテレビ朝日の女性記者に対してセクハラ発言をした問題について、実業家の堀江貴文さんが2018年4月19日、過去にテレビ朝日を含む複数のテレビ局の記者から受けた取材についてツイッターに投稿し、20日の「5時に夢中!」(TOKYO MX)でも詳細に語った。
心配を装った電話を録音、パーティを隠し撮りといった方法で集められた音声や映像を逮捕後に流されたことについて、「テレビ局の記者にはロクなやつがいないな笑」と振り返り、テレビ朝日側への批判も展開した。
■逮捕直前に「美人記者」から心配の電話が来るも...
週刊新潮が報じた事務次官のセクハラ問題は、女性記者からセクハラを訴えられたものの、結果として無断で録音された音声が他社に渡ることになったテレビ朝日側の一連の対応に関しても、議論の的となっている。
そうした中、堀江さんは19日、テレビ局記者の取材方法について、「財務次官の問題の真相はわかりませんが」とし、過去にライブドア事件(2006年)で逮捕される直前に、
「私は検察に逮捕する直前に親しいテレビ朝日の女性記者から心配してる事を装って携帯電話に電話がかかってきて会話を全部録音されて逮捕後に放送された経験あります」
と、テレビ朝日の女性記者に無断で会話を録音され、報道に使われたという体験を明かし、2万6000回近くリツイートされるなど、ネット上で大きな注目を集めている。
堀江さんは当時を振り返り、
「強制捜査されて心が弱ってる時にそれだからね。テレビ朝日の元女性記者は本当にひどかった」
と、大きな負担となったともつづった。20日にも、ほぼ同様の内容を投稿し、当時の会話が取材としてのものではなかったことを補足した。
また、堀江さんは20日に放送された「5時に夢中!」(TOKYO MX)でもこの発言に触れると、
「実際最後、逮捕される前々日くらいに『堀江さん本当に大変ですね、心配してます』みたいな電話かかってきたの。美人記者からね、テレビ朝日の。それ全部録音されてて。しかも電話してるのが社内で、全部カメラで撮ってたらしいんですよ。それを僕が逮捕されたら、『逮捕されたからいいだろう』みたいな感じで全部流されて」
と、詳細を明かし、その際に吐いた弱音が放送されたようだと語り、
「ひどくないですか!? 」
と同意を求める場面もあった。
日本テレビ、TBSの記者にも言及「テレビ局の記者にはロクなやつがいないな」
また、ツイッターではほかにも、
「あと、これは日本テレビの男性記者にですが逮捕される一ヶ月くらい前に女子アナ合コンに誘われて、机の下に隠したテレビカメラでその様子を盗撮されやはり逮捕後に放送されたことあります」「ちなみにTBSの男性記者は収監前の仲間内のパーティに潜入して盗撮してたし、フジテレビの長谷川元アナは高速道路で箱乗りしながら身体をほとんど窓から出して追っかけてきてたな。全部犯罪行為やで笑」
と、日本テレビとTBSの記者についても言及し、そうした取材方法や、それで得られた情報を放送したことに対して、
「私が逮捕されたからドサクサに紛れて放送してたみたいだけど、これって犯罪行為なんじゃないの?って思いますけどね」「そだよ。盗撮時は容疑者でもなんでもないのにそれを堂々と流すのってどうなの?ってね」「テレ朝被害者ぶるのも微妙だよな。女性記者を鉄砲玉みたいに都合よく使ってんのミエミエじゃん。取材する側も取材される側もどっちもどっちやろ。その力関係が崩れたってだけでさ」「無断録音野郎、盗撮野郎、潜入盗撮野郎、高速で箱乗り野郎、、、テレビ局の記者にはロクなやつがいないな笑」
と、持論を展開した。
このうちTBSの件については、11年にもツイッターで、収監前の送別会に招待していないTBSの記者が参加してビデオを回していたこととして、記者の実名を挙げて不快感をぶちまけている。なお当時、J-CASTニュースではTBS関係者の話として、記者側は正式な手続きを踏んだと反論しているものの、送別会に水を差して悪かったと話していた――と報じている。
田舎は良いところもあるが、悪い慣習も継続する傾向がある。その一例だと思う。
加藤美帆
鹿児島市の鹿児島相互信用金庫(稲葉直寿理事長)は20日、2001年3月~昨年12月に顧客の預かり金を着服するなどの不正行為が計約1600件あったと発表した。職員計23人が関わり、不正に扱われた額は計約5億4千万円にのぼる。解雇を含め計144人を懲戒処分にしたという。
九州財務局は同日、法令順守態勢などに重大な問題があるとして、同信金に業務改善命令を出した。
同信金では昨年12月に職員3人による計約5千万円の着服が発覚。外部有識者による第三者委員会が調査した結果、この職員2人を含む計17人が顧客の預金や積立金などから計約4900万円を着服・流用していたことが新たに判明した。
着服・流用以外にも、ノルマ達成を目的に不必要な融資をしたり、ローンを組ませてその利息を職員が払ったりするなどしていた職員も複数確認された。
同信金は3月末付で、計23人のうち9人を解雇、3人を停職の懲戒処分にした。11人は依願退職した。職員の上司らは減給や降格などの懲戒処分とした。顧客への被害弁済を終えており、刑事告訴はしない方針。稲葉理事長は役員報酬を返納し、業務引き継ぎ後に引責辞任するという。
稲葉理事長は会見で「15年以上発覚しなかったのは私の責任。しっかりと内部統制を行って立て直したい」と陳謝した。
財務省の福田淳一事務次官からセクハラを受けたと複数の女性記者が名乗り出たら、福田淳一事務次官は確実に逃げられないと思う。
テレビ朝日が、女性社員がセクハラを受けていたと公表した会見。情報がほしい、もっと近づきたいという思惑が負い目となり、取材活動を通して記者が受けてきたセクハラは表面化してきませんでした。でも、変えなければ。6人の記者が、実態を話してくれました。【BuzzFeed Japan / 小林明子、伊吹早織、貫洞欣寛、籏智広太】
こんな処世術、なくなるといいなあ
凶器に使われた刃物の柄は、どんな状態だったのか。
絶対に他社に特ダネを抜かれたくない。そのために、女性は深夜のホテル街にいた。ほどよく酔っ払った警察幹部の男性と、ホテルに入る入らないで腕を引っ張り合い、押し問答をしていた。
「こんなネタのために、私、何やってるんだろう...」
財務省の福田淳一事務次官から女性社員がセクハラを受けたと、4月19日未明にテレビ朝日が記者会見で発表した。ある民放局の女性記者Aさんは、ふたをしていたはずの数年前の体験が脳裏に蘇り、会見を冷静に見られなくなった。
過去と向き合い、後輩記者たちが自分と同じ目に遭わないよう、報道の現場を変えたい。そんな思いから、BuzzFeed Newsに経験を話してくれた。
「見えない女子枠」があった
当時、配属されたのは、社内でも花形である警視庁記者クラブ。配属後の「1カ月ルール」というものがあり、1カ月以内に特ダネが取れなければ「飛ばされる」と聞いていた。
担当チームで、女性記者は1人だけ。Aさんは女性記者から引き継ぎを受け、女性記者に引き継いだ。そこにはきっと「見えない女子枠」があったのだ。
Aさんは、事件取材をしたいわけでも、特ダネを取りたいわけでもなかった。テレビ局に入社したのは、ドキュメンタリーを制作したかったから。事件取材で頑張って実績を出せば、次のチャンスがもらえるはずだと信じていた。
実際、独自ネタをとったら、それを元に番組の企画枠を担当させてもらえた。目の前にぶら下げられた小さなごほうびが、Aさんをプライベートがほとんどない取材活動に駆り立てていった。
「もうレース感覚ですね。その日その日の運動会で、1位を取ろうと必死でした」
同時に、もう一人の自分が常にささやいていた。
「このレースのルールは、本当に公正なの?」
セクハラを笑って流せる娘キャラ
特ダネをとるためには、他社の記者がいないところで、警察幹部と2人きりで話す機会をつくらなければならなかった。
警察幹部を自社のハイヤーに乗せ、自宅まで送り届ける間、車内の後部座席で捜査情報を聞き出すことが多かった。普通に話をしていたのに、暗がりにさしかかった途端、手を握ろうとしたり胸を触ろうとしたりする人もいた。運転手に昼食をおごり、不審に感じたら急に道を曲がったりカーラジオの音量を大きくしたりして雰囲気を変えてほしい、と頼んだ。
Aさんは、特ダネをとるためにどこまでするか、自分なりのルールを決めていた。
・男性と2人で話すのは、OK。
・2人きりでゴルフに行くのは、OK。
・2人きりで飲みに行くのは、OK。
・飲食店の個室に入るのも、OK。
・手を握られるのは、NG。
・キスをされるのは、NG。
・ホテルに行くのも、NG。
NGラインに入りそうになったときは、「笑って流せるキャラ」を演じてかわしてきた。まさに、元日経新聞記者でジャーナリストの中野円佳さんが名付けた「コイツには何言ってもいい系女子」。下ネタやセクハラも冗談にして受け流すキャラのことだ。
万一、相手を不快にさせて、先輩記者から脈々と受け継いできた取材先との関係、つまりネタのパイプラインを絶つようなことは、あってはならなかった。
「最初は、とにかく特ダネがほしくて、どのラインまで許容するかを決める余裕すらありませんでした。女としてではなく、男キャラや娘キャラとして接すると、身を守りながらもガンガンネタがとれることがわかってきて、ここまでならOKというラインが見えてきました」
「ただ、それまでの自分とはまったく違うキャラに変わらなきゃと真剣に考えたのは、記者クラブの飲み会に出たことがきっかけです」
きれいごとではない現実
その飲み会でAさんは、思い出すだけで吐き気がするような酷い集団セクハラを、先輩や同僚から受けた。女性記者だけでなく若手の男性記者もいじられ、笑いながら耐えていた。このレベルのセクハラを笑って乗り切れないと、この世界にはいられないんだ。そう悟った。
「なぜ私はそこで、この世界で生き延びなきゃいけない、と信じ込んでいたんでしょうね...。就職を喜んでくれた親の顔や、ドキュメンタリーを撮りたいという夢、いろいろなことが頭に浮かんでいました。記者になってまだ何も成し遂げていないのに負けてたまるか! という気持ちも大きかったんだと思います」
2年半後。異動する自分の後任となる女性記者を同伴した飲み会で、Aさんは服を脱がされた男性記者を笑い、ひたすら盛り上げ役に徹していた。もうすっかり「この世界」に染まっていた。ふと気づくと、後任の女性が店から姿を消していた。
「いたたまれなくなったんでしょうね。今ならわかります。でもそのときに私が思ったのは『ヤバい。早く戻ってきてよ。相手を怒らせたらどうするつもりなの』でした。今となっては顔から火が出るほど恥ずかしく、申し訳ない気持ちでいっぱいです」
テレビ朝日が、女性社員がセクハラを受けていたと公表した会見は、Aさんに当時の不快感と罪悪感の両方を思い出させるものだった。生き延びるために、セクハラの被害者にも加害者にもなった。どんな場面であろうとセクハラは許されない、というのは正論だが、現実はきれいごとでは済まなかった。
「記者にも下心がある」
全国紙で警察を担当している20代の女性記者Bさんは、取材先との微妙な距離の取り方に、常に気をつけているという。
「記者としては、ネタがほしいという下心があって取材先に近づいています。性的な関係になりたいわけじゃないけど、仲良くなって情報を得たいという微妙な思惑がある。だから自衛するしかないと思うんです」
スカートは絶対に履かないし、胸元があいた服も絶対に着ない。お酒を飲む量にも気をつけている。面倒なことになりそうだったら、トイレに駆け込んで先輩に『電話してもらえますか』と連絡し、呼び出されたことにして消える。
記者の仕事は、取材とプライベートの線引きが難しい。だからこそ、いざというときはネタ元を切ってでも、自分で自分の身を守るしかないと思っている。
女性記者は約2割
日本新聞協会の2017年4月の調査によると、加盟している新聞・通信社の記者数は1万9327人。そのうち女性記者は3741人で、全体の19.4%だ。管理職となると、女性の割合はますます少ない。
「この業界はどこまでいっても男社会で、上司も取材先も男性です」
10年ほど前、取材先の男性からセクハラを受けたという全国紙の女性記者Cさんは言う。セクハラ行為だけでなく、被害を新聞社の上司に訴えたときの対応に、深く傷ついた。
セクハラの加害者は、担当する行政機関の幹部だった。態度は常に紳士的で、いつも妻の話をする「愛妻家」。娘は自分と同い年だとも聞いていた。
この幹部と別の記者と3人で飲むはずの席で、もうひとりの記者が急に来られなくなり、2人きりになった。「珍しいビールがある。二次会はうちで」と自宅に誘われた。
家族がいると思って幹部宅に向かうと、家族は旅行中で無人だった。突然、幹部に後ろから羽交い締めにされた。突き飛ばしてなんとか逃れた。自宅に戻りドアを閉めた途端、涙が溢れた。
「その気にさせたお前が悪い」
翌日、職場の上司に相談した。「とにかくこの話は誰にも言うな。絶対に週刊誌にも言うな」。慰めるどころか、高圧的な態度だった。考えてもいなかった週刊誌へのリークの話までされて、呆然とした。
後日、上司から「幹部と直接会って、話をつけてきた。『両想いだと思っていた。勘違いだとすると申し訳ない』と頭を下げてきた」と伝えられた。具体的に何をどう話をつけたのか、それ以上の説明はなかった。
次の春、この幹部は定年退職した。「無事退職できたのはあなたのおかげです」というメールを送ってきた。自分の行動に罪の意識があり、もしCさんが告発していたら懲戒処分は免れなかったということが分かっていたのだ。
合わせてCさんも転勤になった。職場の送別会の二次会で、上司は冗談めかして言ってきた。
「その気にさせたお前が悪い。そういうところは気をつけろ」
「上司に言ってもダメだったのだから」と社内で訴えることも諦め、すべてを心の中に封じ込めてきたが、今でも思い出すと、悔しさに体が震えることがある。
元毎日新聞記者の上谷さくら弁護士によると、セクハラの裁判では、加害者の責任はもとより、会社の対応のまずさが問われることが多い。使用者責任や安全配慮義務違反として、上司の対応などが厳しく判断される。
それはつまり、報道現場でセクハラが起こる構造的な背景が問われているということだ。
地方紙が自治体と全面対決
BuzzFeed Newsは現在、大手新聞社、放送局、通信社、BuzzFeed Japanを含めたネットメディアの計15社に、社員がセクハラを受けた場合の対応や、性犯罪の報道指針についてアンケート調査を依頼している。回答をまとめ、記事化する予定だ。
セクハラの対応として注目されたのは、2017年12月、岩手県の地方紙「岩手日報」の報道だ。自社の女性記者が岩泉町長からわいせつな行為をされた、と自ら報じた。
その日の紙面では「岩手日報社は問題発生直後から、町長に対し厳重に抗議し、代理人を通して事実関係を認めるとともに謝罪するよう求めている」とも記している。地元に密着した地方紙でありながら、ひとりの記者を守るために町のトップと全面対決の姿勢を表明した。町長はその後、辞職した。
テレビ朝日は4月19日の会見で、セクハラ発言をされた女性社員が「セクハラの事実を報じるべきではないか」と相談したが、上司が「本人が特定され、二次被害が予想される」との理由で報道しなかったという一連の対応を明らかにした。同日、財務省に抗議文を提出している。
記者の #MeToo を会社は守れるか
セクハラを許さない組織をつくるために、労働組合による実態調査を提案するなど社内で問題提起を始めたのは、20代の女性記者、Dさんだ。
「警察官や政治家が悪びれずに女性記者に対してセクハラ発言ができるのは、長々と続いてきた環境、習慣によるもので、それを再生産してきたのはマスコミ業界だと思います」
テレ朝の女性社員は、セクハラを自社で報じることを止められたため、週刊新潮に連絡を取り、告発記事が掲載された。記者の#MeToo だ。テレ朝は会見で対応のまずさを認め、「女性社員の人権を徹底的に守っていく」と述べた。
#MeToo と声を上げることは、被害者に負担がかかることだ。実際、声を上げたことによる二次被害に苦しむ人もいる。それでもDさんは「被害者が声を上げ、追及することが、今の状況を変える一番効果的な方法だと思います」と訴える。
「悲しいけれど、ハラスメントをしたら社会的制裁を受けるということを痛感してもらうしかないからです。そういう意味で、個々の記者対加害者ではなく、所属している組織が記者を守っていく姿勢が必要です」
一つひとつのセクハラが記者をすり減らす
記者へのセクハラは、警察や政治家など、権力と情報を持った取材先によるものだけではない。事件取材で現場周辺の住民に話を聞いていたときに、名刺を渡しただけの相手から執拗に連絡が来たり、災害取材で性的な言葉を投げかけられたりすることもある。社内や、同業他社の記者たちが集まる記者クラブでも起こりうる。
Dさんは続ける。
「一つひとつ声を上げていったらキリがない。費用対効果が悪すぎます。その場で受け流せば済んでしまうセクハラがいっぱいある。でもそういうものが、少しずつ自分たちをすり減らしているんです」
声を上げづらい背景には、そのリスクとコスト以外に、女性記者ならではの”負い目”もあるという。
「実際、若い女性記者を相手にするとガードが緩くなる取材先がいるのも確かです。その経験って、女性記者はみんな少なからずある。だから『女を使ったことは一度もありません』と言えなくなっちゃうというか、変な負い目になってもいるんですよね」
男性記者と対等に戦いたいがために、あえて被害を口にしない女性記者もいる。
「でもそれってセクハラの免罪符にはならないですよね。改めるべきは女性のほうではなくて、加害するほう。Twitterに『セクハラされてでもネタを取ってこいと言われるとしても、相手がセクハラしなければ、セクハラされずにネタを取ってこれるはずだ』と投稿している人がいて、その通りだと思いました」
弁護士の上谷さんは、こうも指摘する。
「どんなにセクハラやパワハラをされようが、記者は取材先との関係構築のため、明日も明後日も取材に行かなければならない。取材先は、ハラスメントをしても記者が何度も来るから、自分のやっていることは嫌がられていないし許されている、と本気で思っていることがあります」
男性記者に替えれば解決するのか
全国紙の20代の女性記者Eさんは、警察幹部から無理やりキスをされたことがある。耐えられないと感じ、すぐに会社の上司に報告した。上司もすぐに動き、女性を担当から外して、代わりに男性記者をあてたという。
「上司が理解があったので担当を外してもらいました。セクハラを受けても続けなければいけなかったテレビ朝日の彼女は、精神的に相当キツかったんじゃないでしょうか」
30代の全国紙記者Fさんは、度重なるセクハラに会社が対応してくれたと感謝する一方で、過度な警戒心を抱かれることの息苦しさも感じている。
取材先を信頼して、フェアな関係を築いてきたつもりだった。それなのに「誤解を与えるから」と、先輩の男性記者と同じように夜回りをさせてくれない取材先がいたことに、もどかしさを覚えた。
「信頼関係ではなく性別で区切られてしまうのは、たとえ配慮であったとしても悲しくなります。性別関係なく、記者として見てもらいたいだけなのに…」
取材活動の制限がもたらすこと
4月19日発売の週刊新潮によると、麻生太郎財務大臣は「セクハラされるのが嫌なら、男性記者に替えればいい」という趣旨の発言をしたという。
セクハラを防ごうとすると、このような議論になりがちだ。
女性記者を取材先と1対1で会わせない、特ダネをとるような取材はさせない、そもそも配属しないーーそれは「スカート姿で夜道を歩かない」と同様、女性記者の活動の幅を狭めることにつながる。同時に、加害者となりうる側は何も変わらないでいいということになる。
取材先と信頼関係を築くために絶妙なバランスで距離を縮めようと努力している記者に「嫌なら2人きりにならなければいい」「呼び出されても行かなければいい」といった言葉を投げかけるのは、記者倫理を捨てろと言っているのと同じだ。そもそも、2人きりになったからといって、セクハラが起きても仕方がないと言えるはずがない。
それに、ネタ元となる取材相手が女性のこともあれば、男性記者が被害に遭うこともある。性別に関する被害に矮小化していては、抜本的な解決にはならない。
冒頭の民放局の女性記者Aさんは、多くの警察幹部と話す中で、社会正義を目指すスタンスなどに共感することが多かった。記者と警察官、職種は違うとはいえ「熱くて純粋で、青臭い気持ち」で通じ合える人にたくさん出会えた。その信頼関係は、宝だ。
「取材相手と記者は、そうした漠然とした思いを、事件や事故といったネタをフックにして共有しているのではないでしょうか。逆に言うと、ネタをとるための取材活動は、よりよい社会に向かって一歩ずつ進んでいると信じて、やり続けることだと思うんです」
取材は、取材相手と記者との共同作業だ。そこに必要なのは、目先だけの単純な規制ではない。互いの立場を尊重した、対等な関係性だろう。
-------
BuzzFeed Japanはこれまでも、性暴力に関する国内外の記事を多く発信してきました。Twitterのハッシュタグで「#metoo(私も)」と名乗りをあげる当事者の動きに賛同します。性暴力に関する記事を「#metoo」のバッジをつけて発信し、必要な情報を提供し、ともに考え、つながりをサポートします。
新規記事・過去記事はこちらにまとめています。
https://www.buzzfeed.com/jp/metoojp
ご意見、情報提供はこちらまで。 japan-metoo@buzzfeed.com
財務省を敵として一女性記者が戦えると思うのでしょうか。テレビ朝日でも財務省と争って得はないと判断したから、女性記者から相談を受けても 対応を取らなかった。テレビ朝日としては、女性記者の代わりはいくらでもいると思っていたと思う。少なくとも一部の幹部はそう思っていたと思う。
弁護士に相談しても、財務省を敵に回す覚悟がある有能な弁護士は少ない、又は、ほとんどいないと思う。財務省の福田淳一事務次官は東大卒、 先輩、後輩、そして同期がいろいろな組織の幹部やトップになっているであろう。警察組織でも同じである。多少の圧力をかけたら、動かないであろうし、 その前に、警察官が面倒だと思って対応しない可能性は高い。
そうなれば行動を起こして、何も変わらないが、失った物は増える結果となる。記者だからジャーナリストとして大きな影響を与えられると思うのであれば 考えが甘いと思う。
新潮に行ってもここまで問題が注目されるとは予想していないし、新潮も同じだったのではないのか?
ここまで問題が大きくなったのは、当事者や新潮の予測を超えたとは思うが、良かったと思う。財務省の問題とメディアの問題が注目を受けた。 時が経てば、問題は元に戻ろうとするだろうが、大きな一撃だったと思う。だからこそ、簡単に幕引きさせてはならないと思う。
TBS系「ひるおび!」(月~金曜・前10時25分)でテレビ朝日の女性記者が18日夕方に事実上更迭された福田淳一・財務省事務次官(58)によるセクハラの被害について特集した。
落語家の立川志らく(54)は、女性記者が情報を週刊新潮に持ち込んだことに「難しい問題だとは思いますけど、被害にあわれた方は本当に辛い思いをしたというのは重々わかります。でも一応記者であり、ジャーナリストの端くれならば、会社と戦って欲しかったですね」と指摘した。
その上で「新潮に売るっていう。じゃあ文春に売りゃいいのかってもんじゃないけどね。会社と戦って、テレ朝からきっちりやった方が気持ちが良かったんじゃないですか。あるいは弁護士に相談するとか警察に行くとか。新聞社ならまだ良かったんじゃないですか。なんでみんな新潮に行くのかなって、そこが解せないと言えば解せない」と持論を展開していた。
綺麗ごとでは情報を取れない事は現実的にあるだろう。営業、接待、そして癒着や賄賂は同じ線上にあると思う。有利や取り計らい、仕事を取るプロセスで 手段を選ばないのであればいろいろな方法がある。
取材は営業と比べれば、はるかに倫理とか、公平性は重要視されると思うが、結局、特ダネを得たいと思い、手段を選ばなければ女性を武器にするとか、 今回は女性記者がセクハラの対応に拒否反応を見せたが、お金、接待、プレゼントなどいろいろな選択が相手次第であると思う。
「フィフィは『任務中で受けたセクハラであれば、通常なら社内に訴え、そこから財務省に抗議するなり、その上で自分たちが報道機関であるのだから、自らの機関で報じたらいいのに』とした上で、『これを他者にリークするって一体どういう状況が考えられるだろう』とつづった。」
女性記者が上司にセクハラについて相談したが、対応を取らなかった。自社は守ってくれないし、問題が公になればテレビ朝日が不利な扱いを受ける事を 理解していたから、対応を取ってくれる期待が持てた週刊新潮に音源データの一部を提供したと思う。
フィフィがどの程度まで考えてコメントしたのかは知らないが、芸能界にいるのに、そのような事を考える事は出来ないのだろうか?
コメンテーターで活躍するタレントのフィフィ(42)が19日、自身のツイッターを更新。18日に事実上更迭された福田淳一・財務省事務次官(58)からセクハラ被害を受けていたとして、テレビ朝日の女性記者が週刊新潮に音源などを持ち込んだ問題について「他者にリークするって一体どういう状況が考えられるだろう」(原文ママ)と疑問を呈した。
【写真】セクハラ疑惑を否定している財務省の福田事務次官
フィフィは「任務中で受けたセクハラであれば、通常なら社内に訴え、そこから財務省に抗議するなり、その上で自分たちが報道機関であるのだから、自らの機関で報じたらいいのに」とした上で、「これを他者にリークするって一体どういう状況が考えられるだろう」とつづった。
19日午前0時から会見した同局の篠塚浩・取締役報道局長によると、女性記者は1年半ほど前から数回、取材のため福田氏と1対1で会食をする機会があったが、そのたびにセクハラ行為を受けていたため、自衛手段として発言内容を録音するように。今月4日にも福田氏から連絡を受け1対1での飲食の機会を設けたが、セクハラ発言が多数あったため、発言を録音。後日、女性記者の上司に相談し、行為を報じるべきだと申し出たが「本人が特定されるおそれがある。報道は難しい」などと諭され、同局で放送することはなかった。
しかしながら女性記者は「社会的に責任の重い立場にある人物による不適切な行為が表に出なければ、今後もセクハラ被害が黙認され続けてしまうのではないか」という思いを強く持っていたため週刊新潮に連絡。録音データの一部も提供したという。
自民党の伊吹文明元衆議院議長(80歳)は19日、所属する二階派の会合で、女性記者へのセクハラ疑惑で辞任を表明した財務省の福田事務次官の問題について、「その通りであれば非常にとんでもない話で、福田君の道義的責任は非常に重大だ」と、テレビカメラの前で厳しく批判した。
【写真】セクハラ疑惑で伊吹氏が苦言
一方、録音テープを週刊誌に提供したテレビ朝日の記者の行動について、伊吹氏は次のように指摘した。
「記者の人たちの対応は、こうして(公の場で)話している時はテレビを入れてもいい。正式の官房長官の会見の時も構わない。インタビューを1対1で記事にする時は、話した内容が出るのは当たり前のことだ。
しかし、それ以外に、非公式に例えば懇談をしようかと言って、水割りでも飲みながら話している。あるいは、歩いている時に横からぱっと(記者が)来て話をする「ぶら下がり」、懇談、夜回り(※夜に記者が取材相手の家の前で待ち、話を聞く取材)はオフレコであるという当たり前の道義をもって形成されている」
そして、伊吹氏は「何回も何回も嫌なことを言うから、こいつは危ないと思ってテープを後のために撮っておきたいという気持ちはよくわかる。そういう気持ちにさせた人が、一番道義的責任があるというのは確かだ」と、一番の原因は福田事務次官にあり、セクハラ発言は断じて許されないとの認識を示した。
その上で「しかし、その記者はわざわざ上司に報告して、わが社でこの事を取り上げてくださいと言ったのに、二次的なプレッシャーがかかるからいけないと、取り上げられないよと、しかも、それを後で(週刊誌の報道がされた後に、テレビ朝日が記者会見で)発表するのはどういうことなんだと。私は非常に疑問に思う」と述べた。
女性記者による告発報道を認めなかった上、この段階で事実関係を公表したテレビ朝日の対応と、記者が、取材内容を、第三者である週刊誌に提供したことに疑問を呈した形だ。
伊吹氏は、「恥ずかしい発言を多分した可能性が高いの(福田次官)と、道義にもとるメディアの取っ組み合いだ。これじゃあ日本国として恥ずかしい。記者は記者の道義を守り、政治家そして官僚は、その道義をしっかり守った品性のある日本国であってもらいたい」と嘆いた。
セクハラ行為は断じて許されるものではない。
会社や上司に相談できない、自ら進んで声を挙げられない、訴えることができない人たちは、大勢いるだろう。その人たちが最後の手段として、自らを守るために、発言を録音する行為を咎めることはできないというのは、伊吹氏も同じ思いではないか。
その上で、当事者が声を挙げたにも関わらず、会社自らが「適切ではなかった」と振り返るような対応をとり、記者が最終的に禁じ手ともいえる方法で世間に公表する形になった今回のケースをどう見るか。
オフレコ取材のあり方も含め伊吹氏の指摘が的を射ているかはともかく、政界のご意見番であり、大蔵省出身で財務大臣も務めた伊吹氏としては、一言言わずにはいられなかったということなのかもしれない。
「2013年7月に過労死したNHK首都圏放送センターの記者、佐戸未和さん(当時31)は母親に、メモや録音がとれない取材の大変さを漏らしていた。
ーー取材先との酒に付き合うことが多かったが、そこで得た情報を忘れずすぐ報告できるよう、宴席後は酔いを冷ますために喉に指を突っ込み、トイレで吐く。それを日々、繰り返す。いつの間にか、その指には『吐きダコ』ができていた、という。」
NHKでの就職を決断した時、佐戸未和さんは記者がどのように働き、どのようなライフスタイルになるのか理解していたのだろうか?
理解していた、又は、記者としての生活が理解出来た時、何を考えていたのだろうか?記者としてのメリット及びデメリットを理解しても
記者を続けたかったのか、それとも記者以外の生きたかにも興味があったが、決断できなかったのか?
記者の才能は全くないと思うが、記者として働いても良いと言われても、個人的には記者にはなりたいと思わない。
だから、佐戸未和さんの記者としての大変さを読むと、なぜ、NHK、なぜ、転職しないのかと思う。困難や大変さがあっても記者の仕事が好きであるのなら
記者の仕事を続ければ良い。しかし、記者が嫌になれば、他の生き方を選択しても良いと思う。
女好きな取材対象者であれば、ガードが下がるかもしれない。女を武器にする、又は、性的な欲求を満たしてくれるのであれば、情報を流す取材対象者は
いるであろう。ハニートラップが極端な例である。メディアが、エサをチラつかせて情報を得る、取材相手は情報をチラつかせて性的欲求を満たすので
あれば、後はどちらが勝つかの問題。
メディアが女性記者からセクハラの相談を受ければ、男性に変えるべきだった。男性であれば情報を入手しづらくても、ライバルのメディアが女性記者を
当用しても、問題がある取材対象者であれば、男性にするべきだったと思う。
キャリア達の多くがノーマルで性的欲求を見たいしたのなら、公務員専用のソープランド「記者クラブ」とキャバクラ「記者クラブ」を設置すればよい。
ただ、外国のメディアから日本の官僚と日本は酷く叩かれるであろう。
情報のリークをチラつかせておかしな事をするのであれば、解決方法としては悪くないと思う。風俗に言っていると大きな声では言えないが、合法だし、
問題はない。問題を起こす、又は、性犯罪に関わるぐらいなら、良いのではないかと思う。ただ、一部、又は、多くの女性有権者から支持されないし、
非難されるかもしれない。東大生、医学部生や医師のレイプは、高学歴や能力の高さに関係なく、動物的な性欲を抑えられない人達が関与したと思われる。
優秀な人間であればいろいろな事が許されると思う、又は、能力が高ければ、人間的な欠陥に目を瞑るべきだと日本や日本政府が考えているのなら
公務員専用の風俗店を福利厚生として設置すればよい。その代り、男性公務員の給料と退職金は2割カットにするべき。日本は女性軽視の野蛮な
社会だと先進国のメディアからはバッシングされるだろうが、日本の官僚達の性的欲求が非常に高ければ、仕方の無い選択かもしれない。
現状はこの方法で対応するにしても、勉強が出来る、又は、偏差値が高ければ人間性の問題には目を瞑る傾向は変えなければならない。
採用試験や大学入試に公平性は必要であるが、人間性を考量する必要はあると思う。
財務省の福田淳一事務次官のセクハラ問題は徹底的に調査して、国民が知らないメディアと官僚の関係も含めて公表するべきだ。
福田淳一事務次官が嘘を付いていれば、特例として退職金は払うべきではない。
テレビ朝日の女性社員が受けたセクハラ被害をめぐる記者会見で、録音した音声データが週刊新潮に渡ったことについて同社は「報道機関として不適切で遺憾だ」と述べた。身を守るための証拠保全か、報道倫理の遵守か。被害者が記者という職業だったからこそ、問われることになった。【BuzzFeed Japan / 小林明子】
テレビ朝日の女性社員が財務省の福田淳一事務次官からセクハラの被害を受けた、と発表された記者会見。
テレ朝の篠塚浩報道局長は「被害者である社員の人権を徹底的に守る」と述べた一方、女性社員が録音した音声データを週刊新潮に渡していたことについて、「報道機関として不適切で遺憾だ」と述べた。
被害者が身を守るための証拠保全か、オフレコや取材源の秘匿など報道倫理の遵守か。被害者が記者という職業だったからこそ、問われることになった。
なぜ録音データを提供したのか
テレ朝によると、女性社員は1年半ほど前から取材目的で、福田氏と1対1で食事をするようになった。福田氏から頻繁にセクハラ発言をされるようになったことから、「身を守るため」に会話の録音を始めたという。
4月4日、福田氏から呼び出され、取材のため飲食をした際にもセクハラ発言があったため、途中から録音を始めた。
女性社員は上司に「セクハラの事実を報じるべきではないか」と相談したが、上司は「本人が特定され、二次被害が予想されることから報道は難しい」と答えた。女性社員は、セクハラが黙認され続けてしまうのではという危機感から、週刊新潮に連絡。取材を受け、音声データの一部を提供した。
週刊新潮は4月12日発売号でセクハラ発言を報道し、音源を公開した。新潮は女性記者の所属を秘匿したが、18日に福田氏が辞職に際して改めてセクハラを否定したその夜、テレ朝が被害にあったのは自社の記者だと会見した。
テレ朝の会見では他社の記者から、女性社員が福田氏に無断で録音していた理由を聞いたり、問題視したりする質問があった。篠塚局長は「自らがこのような行為を受けているということを、会社や上司に説明する際に必要になるだろうということで録音していた。取材目的ではない」と述べた。
また、女性社員が週刊新潮に音声データを提供したことについては「取材活動で得た情報が第三者に渡ったことは、報道機関として不適切で、遺憾だ」。女性社員がどのように話しているかについては、「不適切な行為だったという私どもの考えを聞いて、反省をしております」とコメントした。
「取材活動そのものに支障が出る」
無断録音や音声データ提供を問題視するメディアもあった。
産経新聞は19日の朝刊で、「データ社外提供、過去にも問題」との見出しで、「一般的に『隠し録り』という取材手法や、他媒体に情報を提供する行為は通常の報道活動とは異なるものだ」と説明。オウム事件の弁護士一家殺害事件など、ビデオや音声データを社外に提供したケースはいずれも「報道姿勢が問われる事態になった」と書いている。
読売新聞も、「テレ朝『録音提供 不適切』」との見出しで、報道倫理に詳しい元通信社記者の春名幹男・元早大客員教授の「取材で得た情報が自らの報道目的以外に使われたことで、今後、記者が取材先から信用されなくなり、取材活動そのものに支障が出るおそれがあるのではないか」というコメントを掲載した。
一方、セクハラ被害に詳しい弁護士たちは19日、「会話の録音は身を守るために必要な手段だった」「やむを得ずとった手段だった」との認識を示している。
元毎日新聞記者の上谷さくら弁護士はBuzzFeed Newsの取材に、こう話す。
「無断録音も音声データ提供も、報道倫理が問われる可能性はありますが、違法性はありません」
取材時の録音にルールはあるのか
そもそも、記者が取材中に録音をするときには、どんなルールがあるのか。
テレ朝によると、福田氏からセクハラ発言があったのは、取材のために1対1で飲食をしていたときのことだ。
記者は、取材対象から公式の会見などでは聞けない深い情報を聞くために、早朝や夜に取材対象の自宅に行ったり、1対1で食事をすることがある。「夜討ち朝駆け」などと呼ばれるごく一般的な取材活動だ。
他社が得ていない特ダネ情報を得るためには、1対1での取材も多くなる。その際、「オフレコ(オフ・ザ・レコード=記録禁止)」と呼ばれるルールが適用されることがある。
オフレコといっても、いろいろある。録音禁止や公表禁止、「情報元を明らかにしなければ一部引用可」など取り決めを個別に交わすこともあるが、現実的にはこれらのルールが取材で事前に明言されることは少ない。雰囲気で「オフレコ前提」となることも多い。
2013年7月に過労死したNHK首都圏放送センターの記者、佐戸未和さん(当時31)は母親に、メモや録音がとれない取材の大変さを漏らしていた。
ーー取材先との酒に付き合うことが多かったが、そこで得た情報を忘れずすぐ報告できるよう、宴席後は酔いを冷ますために喉に指を突っ込み、トイレで吐く。それを日々、繰り返す。いつの間にか、その指には「吐きダコ」ができていた、という。
オフレコルールはどう教えられているか
ある民放局の女性社員は、録音禁止のルールは教わったことがなかったが、取材相手の男性から「俺の前でメモなんかとるなよー」と親密さを強調するような発言をされ、メモをとると腹を割って話してもらえない、と気づいたという。
テレ朝の複数の社員によると、取材中の録音の可否について社内で明文化されたルールを教わった記憶はないが、取材先との飲み会などでの録音禁止ルールが、先輩から後輩へ引き継がれている部署があるという。
同社のある女性社員はこう話す。
「会見やオンレコ以外の取材では、聞いたことをすべて記憶しなければならないんだ、と最初は驚きました。無断録音がダメだということを多くの記者は共有しているはずです」
「それでも録音して証拠を残そうとしたのは、多くの性犯罪やセクハラで、証拠がないと認めてもらえない、助けてもらえない、という前例があり、自分の身は自分で守るしかない、と追い詰められたからではないでしょうか」
「ネットの反応を見ていると、セクハラ問題が報道倫理の問題にすり替えられていくことに、同じように働く立場として危機感を覚えます」
録音がなければ「シロ」になるケースも
前述したが、上谷弁護士は「無断録音も音声データ提供も、報道倫理が問われる可能性はあるが、違法性はありません」との見解だ。さらに今回はセクハラを告発する過程から、無断録音と音声データの提供は緊急避難的だった、との見方がある。
「無断録音も音声データ提供も報道倫理の問題にとどまりますが、記者にとっては、記者生命にかかわるほど重要な倫理です」
「今回のケースは、その報道倫理を破らざるをえないほどの、やむを得ない経緯があったと考えるべきです。セクハラ被害を告発することには公益性があり、社内でちゃんと順序も踏んでいます」
「社内での順序」とは、この女性記者が最初に「セクハラを自社で報道しよう」と上司に相談していることだ。上司から止められたことで、セクハラの実態を訴えるためにやむなく新潮社に連絡し、音声データを提供している。
犯罪被害者支援に詳しい上谷弁護士は、スマホなどで録音や撮影がしやすくなった今、セクハラ被害を立証する際に、録音データの有無が重視されるようになってきている、と指摘する。
「セクハラの認定については、加害者が否認している場合、録音があれば『クロ』、なければ『シロ』くらいにまでなってしまっています」
「今回の場合、相手は事務次官で、そんな発言はしていないと言われたらおしまい。上司に訴えても報じることができませんでした。週刊新潮だって、彼女の証言だけではあそこまでの記事は書けなかったでしょう。セクハラ被害が闇に葬り去られないために、じゃあ他にどうすればよかったの、という話です」
「無断録音も音声データ提供も違法性はなく、今回の音声データの証拠能力にはまったく問題がありません。今後、もしもテレ朝が財務省を相手に裁判をするということがあれば、セクハラを立証する決め手になりうると思います」
報道倫理が果たす役割とは...
録音をめぐる議論の行く末を、上谷弁護士は危惧する。
「まさか録音してないよね、と取材のたびに言われるようになるかもしれません。取材する側と取材される側の信頼関係に影響が出るのも問題ですが、とりわけ女性記者の取材活動に影響が出ることがなければよいのですが」
4月19日発売の週刊新潮によると、福田氏のセクハラ発言を報じた際、麻生太郎財務大臣は担当記者たちとの懇親会の席で、記者に「次官のセクハラ、さすがに辞職なんじゃないですかね」と問われてこう答えたという。
「だったらすぐに男の番(記者)に替えればいいだけじゃないか。なあそうだろ?だってさ、(週刊新潮に話した担当女性記者は)ネタをもらえるかもってそれでついていったんだろ。触られてもいないんじゃないの」
男性であろうと女性であろうと、記者としての仕事に真剣に取り組みたい。セクハラが嫌なら男の記者に替えればいいという論理では、女性記者が活動する場は制限される。
テレ朝の会見では、女性社員のコメントが読み上げられた。
「福田氏がハラスメントの事実を認めないまま辞意を表明したことについて、とても残念に思っています」
「財務省に対しては今後も調査を続け、事実を明らかにすることを望んでいます。全ての女性が働きやすい社会になってほしいと、心から思っています」
セクハラが起こる構造的な問題にきちんと向き合わないまま、報道倫理の問題として議論されたり、配慮の名目で女性記者の活動を制限するような言説が生まれたり。これは、福田氏だけ、テレ朝1社だけの問題ではない。報道倫理という名のもとの「特別ルール」で覆われた、報道現場だけの特殊な問題でもない。
シェアハウス投資などへのスルガ銀行(静岡県沼津市)の融資で資料改ざんが相次いで発覚した問題で、新築アパートへの投資でも融資資料が改ざんされた例があることが朝日新聞の取材でわかった。スルガ銀は多くの不正を見逃した事態を重くみて実態調査を進めるが、一部のアパートオーナーは調査対象から外れている可能性も浮上した。
不正がわかったのは、シェアハウスを約100人に売ったとされるサクトインベストメントパートナーズ(東京)が売り主の新築アパート。40代の男性会社員が賃料収入を約束され、1億円超で購入する契約を結んだが、まだ建築中だった昨年夏に「賃料が払えなくなった」と通告されて借金返済が困難に。スルガ銀に返済猶予などを求める過程で資料改ざんが判明した。
男性は勧誘された不動産仲介業…
女性専用シェアハウスの運営会社スマートデイズ(東京)が経営破綻した問題で、物件所有者がスルガ銀行(静岡県沼津市)から購入費用の融資を受ける際に提出した書類のうち、少なくとも約20件に改ざんの疑いがあることが17日、分かった。物件所有者を支援する弁護団は、スルガ銀に返済免除などを求めているが、同行は応じない考えを示しているという。弁護団が同日、明らかにした。
弁護団は17日、東京都内でスルガ銀と融資返済をめぐって協議。弁護団は同行が開示した審査書類34件のうち、約20件に改ざんの疑いがあることを確認した。改ざんが疑われる書類はいずれも同じ支店の取り扱いで、預金通帳のコピーに記載された残高が水増しされるなど、保有資産を大きく見せるような手が加えられていたという。
改ざんは、物件販売を仲介した業者が行っていた可能性も指摘されており、現時点でだれが改ざんを行ったかは特定されていない。ただ、弁護団の河合弘之弁護士は「スルガ銀は書類のコピーだけで融資していた」と指摘し、銀行の責任を追及していく考えを示した。
テレビで見たが、野党は安倍政権の打倒にだけ集中しているようだが、問題の適切な調査と事実の公表、そして関係した官僚及び職員の
処分までされなければダメだ!
辞任したり、辞職したら、問題の追及を止めるのはダメだ!何も変わらない。事実が公表されない。また、同じ事が繰り返される。
財務省が公文書を改竄、自衛隊も日報を隠し、そしてまた新たな問題が浮上した。炎上続きの安倍政権に対し、突き放す声が自民党内でも大きくなってきた。
【資料公開】安倍政権がひた隠す「決定的文書」はこちら
「私を嘘つき呼ばわりするなら、証拠を示していただきたい」
テレビで全国生中継されている国権の最高機関の場で居直ろうとした日本国総理大臣に驚いたのは、答えを引き出そうと質問した野党議員だけではあるまい。そもそも「首相案件」と記した文書が「新証拠」として見つかったことを受けての質問である。森友学園、自衛隊の活動記録(日報)、加計学園。次々と政権の急所をえぐるような新証拠が現れるのに、それがズブズブと底なし沼に沈んでいく。国家が、溶けていく。
学校法人「森友学園」への国有地売却を巡って、財務省が決裁文書を改竄し、大幅値引きの「根拠」となるごみの搬出量も捏造して学園側に口裏合わせを依頼していた問題に続いて浮上したのは、安倍晋三首相の親友、加計孝太郎氏が経営する学校法人「加計学園」の獣医学部新設を巡る文書だ。朝日新聞などが4月10日に報じたこの文書は、2015年4月2日に官邸で柳瀬唯夫首相秘書官(当時。現在は経済産業審議官)と藤原豊内閣府地方創生推進室次長(同)に面会した愛媛県職員が作成し、同年4月13日の日付と「地域政策課」の文責が記してある。
●力の入った助言を列挙
文書では柳瀬秘書官の主な発言として「本件は、首相案件となっており、内閣府藤原次長の公式のヒアリングを受けるという形で進めていただきたい」と始まり、構造改革特区より国家戦略特区の方が勢いがある▽自治体がやらされモードではなく、死ぬほど実現したいという意識を持つことが最低条件▽四国の獣医大学の空白地帯が解消されることは農水省・厚労省も歓迎する方向──など力の入ったアドバイスを列挙。さらに「加計学園から、先日安倍総理と同学園理事長が会食した際に、下村文科大臣が加計学園は課題への回答もなくけしからんといっているとの発言があったとのことであり、その対応策について意見を求めたところ、今後、策定する国家戦略特区の提案書と併せて課題への取組状況を整理して、文科省に説明するのがよいとの助言があった」と記されていた。藤原氏との面会内容として「かなりチャンスがあると思っていただいてよい」など、この段階で「内々定」とも取れる有利な扱いを受けて、担当者もパソコンに向かって軽やかにキーをたたいたに違いない。
報道の当日、愛媛県の中村時広知事は記者会見を開き、この文書が「備忘録」だと認めた。非公式文書のため保管はしていないものの、担当職員による「真正」であることを発表した。一方、昨年7月の衆参予算委員会でこの15年4月2日の愛媛県職員との面会について「記憶をたどる限り、会っていないと思う」と繰り返した柳瀬氏は、今回も重ねて面会を否定した。この二項対立の解は一つしかない。愛媛県職員と、キャリア国家公務員の柳瀬氏のどちらかが、嘘をついているということだ。そして、中村知事は会見で「県の職員は文書をいじる必然性は全くない」と強調した。
面会内容を忘れまいと記録した文書と、記録のない柳瀬氏の記憶。4月11日の衆院予算委員会集中審議で複数の野党議員から、どちらが正しいのかと追及を受けた安倍首相が放ったのが、冒頭の言葉だ。証拠となる記録をもとにした質問に「証拠の証拠を出せ」と子どもじみた感情を爆発させたようなものか。
●文書が正しいと致命傷
真実は一つだが、愛媛県職員の文書のほうが正しいと、安倍首相には致命傷になる。これまで繰り返してきた答弁が全てひっくり返り、国民に「嘘つき首相」だと証明してしまうことになるからだ。この4月、愛媛県今治市に開学した加計学園の岡山理科大学獣医学部は、県と同市が07年から14年にかけて構造改革特区として計15回申請し、全て却下されてきた経緯がある。これに対し、首相主導の国家戦略特区は第2次安倍内閣の経済政策として14年に指定が始まった。そして15年6月4日、今治市が国家戦略特区での獣医学部新設を提案し、16年1月に同市が国家戦略特区に決定。前川喜平・前文部科学事務次官によれば、同9月には内閣府が「官邸の最高レベル」からとして文部科学省に「18年4月開学を大前提に」と指示をした。17年1月4日、獣医学部新設を18年度開設の1校に限って募集。加計学園のみが応募し、同1月20日に事業者として認定された。愛媛県職員が残した「備忘録」の通り、国家戦略特区はとてつもない勢いがあった。
安倍首相は加計学園の獣医学部新設計画を初めて知った時期を、この事業者として認定された日であると、昨年7月の衆参予算委員会で説明し、以降も一貫してそう主張してきた。加計氏とは米国留学時代から続く40年来の親友で、頻繁にゴルフや会食を繰り返してきた間柄なのに、である。ある自民党関係者はこう呆れる。
「前川さんもコメントを出していましたが、この文書にあるように安倍首相と加計理事長が15年4月2日以前に会食した際に、獣医学部設置に関する下村文科大臣(当時)の『課題』について話し合ったのでしょう。首相も柳瀬氏も嘘をついているのではないかと国民の大多数に疑問を持たれた以上、自民党総裁選で3選などあり得ない」
自民党内では、こうして突き放すような声が大きくなってきた。重鎮が、
「安倍首相が辞めない限り、あちこちから延々と追及を受け続けるということだ。それだけだ」
と言えば、別の幹部もこう漏らす。
「ベテランこそ危機感は強い。内閣総辞職してくれるのが、ベストなんだけどな」
●やっちゃいけないこと
今回報じられた、愛媛県職員による柳瀬氏らとの面会記録文書は、農林水産省でも保管されていたことが明らかになった。文書改竄に揺れる財務省では、女性記者相手にセクハラ発言を繰り返していたと週刊新潮に報じられた福田淳一事務次官が4月12日、麻生太郎財務相から口頭注意を受けた。なかったはずの自衛隊の日報は次々見つかり、森友学園絡みの証拠や証言も次々に出てくる。明日は何が出てくるのか、官邸は戦々恐々とし、どこを見て仕事をしたらいいのかわからない役人は途方に暮れ、正義を見いだすことのできない国民はイライラを募らせる。著書『安倍三代』で祖父の安倍寛、父の安倍晋太郎、そして安倍晋三首相の3代にわたる政治家としての足跡をたどったジャーナリストの青木理氏は言う。
「安保法制をゴリ押しして反発を食らったときも、昨年の森友、加計問題のときも、いったん支持率を落としながらしばらくすると持ち直すことを繰り返してきたから、高をくくるのが官邸の習い性になったのでしょう。安倍首相は昭恵夫人とそっくりで、もともとは思想も信念も悪意もなく、周囲の影響を受けやすい人物という印象です。しかし、官僚機構の人事まで引っかき回した揚げ句、反発した役人にはスキャンダルめいた報道を仕かけ、心中しようと徹底的に服従した部下も都合が悪くなると切り捨てた。やっちゃいけないことをやりすぎて、さすがに官僚も黙っていられず、反乱に歯止めがかからなくなりましたね」
「美しい国を取り戻す」
そう息巻いて首相に返り咲いた安倍氏の目には、この国は美しく映っているのだろうか。(編集部・大平誠、ジャーナリスト・村上新太郎)
金融庁がスルガ銀行への立ち入り検査に踏み切ったのは、同行の融資が、女性向けシェアハウスを展開するスマートデイズの投資トラブルの被害を拡大させた可能性が高いとみているためだ。スルガ銀は、独自の商品や審査基準で他行との差別化を図り、高い収益につなげてきたが、現場に大きな権限を与える経営が裏目に出た可能性が指摘されている。
スルガ銀は、1980年代に法人向け融資中心の従来型業務から、「リテール(小口)バンキング」に切り替え、個人向け融資に事実上特化するなど独自のビジネスモデルを展開してきた。
不動産向けのローンでは、建物の耐久年数を大幅に超える長期融資など、投資用物件への融資メニューも積極的に展開。早い審査も好評で、大手行では最短でも2週間かかる審査を5営業日で終わらせるほどだった。
金融庁幹部は「融資の回答が早いうえ、期間は長くて金利は高い。地方銀行の中で注目株だった」と語る。地銀の再編を進めたい森信親長官も、講演でスルガ銀の名前を挙げながら「大きくなることが唯一の解決策ではない」と、高収益のビジネスモデルを評価していた。
だが、スマートデイズの問題では、こうした審査体制が裏目に出た。同社は、シェアハウスオーナーに関心を持つ会社員らの大半に、スルガ銀の横浜市内の支店の融資を勧めていた。関係者によると、預金などの少ないオーナー候補については、スマートデイズが通帳のコピーの数字を改ざんするなどして資産を多く見せかけ、審査を通していた。金融庁はスルガ銀の融資審査体制に問題があっただけでなく、こうした不正行為に、スルガ銀行側の担当者が関与した疑いもあると見ており、両者が結託して被害を拡大した可能性も視野に調査を進める。
サブリース(借り上げ家賃保証)と呼ばれる仕組みでシェアハウスのオーナーとなり、多額の借金を抱えた所有者は約700人におよび、現在訴訟を準備中だ。スルガ銀に対しても、不正な手続きで融資が行われたとして返済猶予などを求めている。スルガ銀は現在は行内調査を進めているが、所有者らへの対応は「検討中」とするにとどめている。【鳴海崇】
今回の資料と証言で武藤栄元副社長の罪は確定するのだろうか?確定すればどのような処分となるのだろうか?民事訴訟が
起こされれば、どうなるのだろうか?既に起こされているのだろうか?
資料や証言者が正しいとすれば、武藤元副社長は嘘を長年、付いていた事になる。武藤元副社長はどのような人物であろうか?
東京電力福島第1原発事故を巡り、東電が事故前に津波対策の必要性を記載した資料を作成していたことが分かった、東京地裁で11日開かれた業務上過失致死傷の罪に問われた東電の旧経営陣3人の公判。東電の津波対策を担当していた社員は武藤栄元副社長(67)が事故直前まで、第1原発の津波想定について当時の原子力安全・保安院の意向に関心を持っていたことを証言した。
証言や公判で示された資料によると、この社員は事故直前の2011年3月7日、保安院の耐震安全審査室長らと面会し、長期評価を考慮すると最大15.7メートルの大津波が第1原発を襲う可能性があるとの計算結果を初めて報告。社員は保安院側から「厳しい口調」で「場合によっては(津波対策に関する)口頭での指導もあり得る」と言われた。社員はすぐに保安院とのやり取りを武藤元副社長にメールで報告したが、返信はなかったという。
武藤元副社長はこれに先立つ同年2月26日、この社員に「(保安院との)話の進展によっては、大きな影響があり得る」とメールで伝え、保安院の対応に関心を示していたという。
対策保留「方針変更」
この社員が所属していた土木調査グループは、既存の原発の耐震性を確認して原子力安全・保安院に報告する作業(耐震バックチェック)に従事していた。証言の社員によると、2008(平成20)年3月の他社との打ち合わせ資料には「長期評価の否定は決定的な根拠がない限り不可能」との記述があり、津波対策について保留の指示が出た08年7月以降の社外打ち合わせ資料にも「方針を変更することになった」と記載していた。
この社員は09年7月、部署を横断して津波対策に取り組む社内体制(津波対策ワーキンググループ)の設置を上司に提案し、「考える必要はない」などと却下されていたとも証言した。上司の人事異動などを経て10年8月、同グループを設立し、原発事故までに複数回の会合を開催。メンバー間では、12年4月までに現実的な対策工事や工程をまとめる方向で合意していたという。
東京電力福島第1原発事故の約3年前の2008(平成20)年9月、東電内で「津波対策は不可避」との社内資料が作成されていたことが11日、分かった。東京地裁で同日、業務上過失致死傷の罪で強制起訴された東電の旧経営陣3人の第6回公判が開かれ、08年当時から事故まで津波対策を担当した現役社員が証言した。この社員によると、被告の一人の武藤栄元副社長(67)から津波対策の保留を指示された後も現場レベルで対策を検討していた。
東電が少なくとも事故の3年前には津波の危険性を認識していたことを示す資料。地裁はこの資料を証拠採用しており、判決の事実認定に影響する可能性がある。旧経営陣の「大津波は予測も対策も不可能だった」との主張と大きく食い違う証言で、この社員から津波対策の必要性について報告を受けていた武藤氏の認識が今後の公判の焦点となりそうだ。
証言したのは事故前に同社の新潟県中越沖地震対策センターの土木グループで課長を務めた男性社員。証言や公判で示された作成資料によると、この社員は08年6月、津波地震に関する政府見解(長期評価)を基に、最大15.7メートルの津波が第1原発の敷地を襲うとした試算を武藤氏に報告した。
武藤氏は翌7月、長期評価に基づく津波対策について保留を指示。しかし、この社員らは「長期評価を完全に否定するのは難しい」「津波対策は不可避」などと記した資料を作成し同年9月、第1原発で説明会を開催。長期評価を採用した場合に想定される津波高などを当時の第1原発所長らに説明した。
東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された勝俣恒久元会長(78)ら旧経営陣3人の第5回公判は10日、東京地裁(永渕健一裁判長)で開かれた。事故前に第1原発の耐震チェックに携わった東電の男性社員が被告の武藤栄元副社長(67)から津波対策の保留を指示され「対策に必要な許認可を調べるよう指示を受けていたので、保留の指示で体から力が抜けた」と証言。武藤元副社長らの「大津波は予測できなかった」との主張と食い違いを見せた。
証言したのは、事故前に同社の新潟県中越沖地震対策センターの土木グループで課長も務めた現役の東電社員。政府が2002年に示した津波地震に関する長期評価などに基づき、第1原発に到来する可能性がある津波高について検討していた。
この社員は08年6月、長期評価に基づいて東電子会社が計算した結果、第1原発の敷地南側に最大15.7メートルの津波が到来する可能性があるとの試算を武藤氏に報告。対策例で示した防波堤の設置について武藤氏から「必要な許認可を調べるように」と指示を受けた。
しかし武藤氏は翌月の会議で長期評価に基づく津波対策について社外の土木学会に妥当性の検討を依頼する方針を示した。社員は「これまでの方針が保留されたと思った」と述べた。
社員は長期評価は地震学者も重要視する見解だったとも証言。「長期評価を否定するのは難しかった」とした。
次回公判は11日午前10時から、この社員の証人尋問を続ける。
「番組では6日の理事会後に谷岡氏を名古屋市内で直撃。『栄監督のパワハラの件でこの前断言されていましたけど、この点については?』の記者の質問に、谷岡氏は『(伊調の)5連覇の阻止はなかったですよね』とだけ答えると、足早に去っていく様子が放送された。」
このコメントは理解できない。
吉田沙保里選手は誰かに阻止されたから5連覇出来なかったのか?それなら調査が必要だ!
三菱マテリアルの子会社で、自動車向け金属製品の品質データを改ざんしていた「ダイヤメット」(新潟市)が、不正を隠蔽(いんぺい)した前社長の安竹睦実非常勤顧問(59)を、5月1日付で契約社員とすることがわかった。
安竹氏は不正の責任をとり2月に辞任。その後、ダイヤ社が顧客への対応を理由に4月1日付で顧問にしたが、不正を主導した幹部の処遇として問題視されていた。顧問就任から1カ月で異例の変更となる。
契約社員とする方針は6日に決定した。ダイヤ社は「新任役員への引き継ぎにめどが立ったため、契約社員とした。批判を受けての降格処分ではない」としている。安竹氏は元三菱マテ幹部。ダイヤ社の社長だった昨年5月にデータ改ざんの報告を受けたが黙認したため、その後も不正品の出荷が続いた。(野口陽)
「番組では6日の理事会後に谷岡氏を名古屋市内で直撃。『栄監督のパワハラの件でこの前断言されていましたけど、この点については?』の記者の質問に、谷岡氏は『(伊調の)5連覇の阻止はなかったですよね』とだけ答えると、足早に去っていく様子が放送された。」
このコメントは理解できない。
吉田沙保里選手は誰かに阻止されたから5連覇出来なかったのか?それなら調査が必要だ!
レスリング女子で五輪4連覇の伊調馨(33)=ALSOK=が日本協会の栄和人強化本部長(57)らからパワーハラスメントを繰り返し受けたことを、日本協会の第三者機関が認めたことで、協会副会長で至学館学長の谷岡郁子氏(63)がテレビ朝日の直撃に対してコメントした。
【写真】「伊調馨さんは選手なんですか」発言も
谷岡氏は6日に都内で行われた緊急理事会に出席。栄本部長の辞表を持参して提出したが、理事会後の会見には出席していなかった。
番組では6日の理事会後に谷岡氏を名古屋市内で直撃。「栄監督のパワハラの件でこの前断言されていましたけど、この点については?」の記者の質問に、谷岡氏は「(伊調の)5連覇の阻止はなかったですよね」とだけ答えると、足早に去っていく様子が放送された。
谷岡氏は騒動を受け3月15日に同大で会見。「訳の分からない風評被害で深く傷付けられていることに本当に心を痛めております。これ以上、甘受することはできないという思いに至った」とコメントするとともに伊調について「選手なんでしょうか」と発言したことで大きな反響を呼んでいた。
至学館大は至学館大のスタンスを表明した。人々が独自の判断で至学館大のスタンスを評価すれば良い。
レスリング女子五輪(オリンピック)4連覇の伊調馨(33=ALSOK)を巡るパワーハラスメント問題で、日本レスリング協会の強化本部長を辞任した栄和人氏(57)が監督を務める至学館大が9日、報道陣向けに文面を発表した。
「学生、選手たちが穏やかな環境でそれぞれの夢を追うことができること、これを確保することが私の仕事であり願いです。至学館レスリング部においては、現役の選手たち全員が今後も栄監督の指導を受けることを望み、健全なチームづくりの当事者としての責任を果たす意志を表明しております。これら選手たちの想いを尊重し、今後も栄監督には、至学館レスリング部の指導を託します。尚、伊調馨氏が練習再開の表明をされたことは喜ばしく、今後の活躍を期待します」と記した。
「 4日に京都府舞鶴市で開催された大相撲春巡業で、倒れた多々見良三市長を助けようとした女性に土俵から下りるよう促す場内放送があった問題で、現場に居合わせなかったとされた春日野巡業部長(元関脇栃乃和歌)が7日、救急搬送などを見守っていたなどと当初と違う説明をした。」
大きな嘘は本人だけでなく、相撲に対して不信を生む。
嘘がばれた以上、厳しい処分が必要だ!相撲に興味がないので元力士なのかしらないが、元力士であれば恥ずべき嘘だ!
4日に京都府舞鶴市で開催された大相撲春巡業で、倒れた多々見良三市長を助けようとした女性に土俵から下りるよう促す場内放送があった問題で、現場に居合わせなかったとされた春日野巡業部長(元関脇栃乃和歌)が7日、救急搬送などを見守っていたなどと当初と違う説明をした。巡業先の愛知県刈谷市で取材に応じた。
春日野部長は市長が倒れた後の状況について、何が起こったか把握できていなかったという趣旨の説明をしていた。
しかし、インターネットに同部長とみられる人物が会場奥で見守る画像が掲載され、自身であることを認めた。「幕内の取組を見に行く準備をした時。心配していた。市長が担架で運ばれた後は玄関まで一緒に行った」と話した。場内放送については、その後の報告で知ったという。
「完全歩合制は、外資系生命保険会社でも採用されており、契約の件数や金額によって年数千万円を稼ぐ社員もいる。ただ成果給のため収入は安定せず、これが不祥事が起こる一因となっている可能性もあり、金融庁は固定給を手厚くする国内大手生保の賃金体系と比較するなどして、保険業界全体の給与形態についても見極める方針だ。」
歩合制だから不祥事になると結論付けるのはどうかとおもう?確かに仕事が出来ない社員には不正の誘惑に駆られるかもしれない。
その前に、歩合制で自信がない人は生命保険での就職を考えるように大学やハローワークでも説明するべきだと思う。
どうしても生命保険で就職したいと思わない限り、仕事はいくらでもある。
「ソニー生命保険の社員から架空の生命保険契約で現金をだまし取られる被害が相次いだ問題で、金融庁が同社に立ち入り検査に入っていることが5日、分かった。」
少なくとも他の生命保険で同じような被害がないのであれば、ソニー生命保険の採用方法や基準そして管理監督能力や体制に問題があると疑う
べきだと思う。
ソニー生命保険の社員から架空の生命保険契約で現金をだまし取られる被害が相次いだ問題で、金融庁が同社に立ち入り検査に入っていることが5日、分かった。業務の成果に応じて賃金が支払われる「完全歩合制」の給与形態が事件を招いた可能性があるとして、実態の把握に乗り出した。
被害は、顧客からの問い合わせで発覚し、ソニー生命が昨年7月に発表した。香川県内で営業を担当していた元男性社員が2009年9月~17年4月、6人の顧客と架空の生命保険契約を結び、計1億3521万円をだまし取ったという。昨年9月には、広島県内の元男性社員が同様の手口で複数の顧客から現金数千万円をだまし取っていたことも判明。広島県内の男性社員は今年1月に逮捕された。
金融庁は、一連の事件を受けて昨年秋から検査官をソニー生命に派遣し、同社の完全歩合制の給与形態に問題がなかったかなど、検査を行っている。同社の社員が「契約の取れない月に現金をだまし取って補填(ほてん)していた可能性もある」とみているためだ。5月末までに検査を終え、問題があると判断した場合は業務改善命令を出す。
完全歩合制は、外資系生命保険会社でも採用されており、契約の件数や金額によって年数千万円を稼ぐ社員もいる。ただ成果給のため収入は安定せず、これが不祥事が起こる一因となっている可能性もあり、金融庁は固定給を手厚くする国内大手生保の賃金体系と比較するなどして、保険業界全体の給与形態についても見極める方針だ。
一方、ソニー生命は4月から、支社のコンプライアンス(法令順守)強化を目的に「コンプライアンスオフィサー」を40人配置。また、過度な競争を招きかねないとして年2回の販売強化月間を廃止した。営業成績が優秀な社員を表彰し、海外旅行を授与する報奨制度の廃止も検討している。
どちらが悪いのか知らないが、なぜ、このような展開になったのだろう。
東京電力ホールディングス(以下、東電)の元副社長・石崎芳行氏(64)が「週刊文春」の取材に応じ、福島県内に住む被災者A子さんと不適切な関係にあったことを認め、その後のトラブルについて語った。
【画像】「5000万で手を打ちましょう」「未来永劫を考えたら、安いお値段」……石崎氏に送られたメール
「この半年間、悩み続けてきました。どうしたら死ねるのかという考えも頭をよぎりました。ただ文春から取材の連絡がきたときに決心しました。もう洗いざらいお話ししようと。そのために昨日、会社に退職願を提出しました。会社や家族、被災地の方々にご迷惑をかけてしまい、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」
1977年、東電に入社した石崎氏は、福島第二原発所長や副社長を経て、2013年1月に福島復興本社の初代代表に就任。昨年6月からは福島担当特別顧問だった。東電の最高幹部であり、“福島復興の顔”でもあった石崎氏は、3月28日に辞表を提出。同月31日付で福島担当特別顧問を退任している。
石崎氏のお相手は50代の独身女性A子さん。彼女は福島や東京を拠点に、被災地支援の活動を精力的に行う運動家でもある。A子さんが主宰する団体の活動はマスコミに度々取り上げられ、震災復興に尽力したとして、「日本復興の光大賞」を受賞したこともある。
15年7月、東電の復興本社があったJヴィレッジで2人は出会った。翌16年4月に男女の仲となり、交際は1年半ほど続いた。
だが昨年11月頃から2人の関係は悪化。A子さんが石崎氏に対し、〈口止め料、精神的慰謝料5000万で手を打ちましょう〉〈子孫の代まで汚名を背負わせる〉といった内容のメールを送る事態となった。
東電の広報部は「(2人の関係、公私混同については)会社として承知しておらず、回答を差し控えたい」と答えた。4月5日(木)発売の「週刊文春」では、石崎氏、A子さんへの長時間のインタビューにより、福島の復興に水を差しかねないトラブルについて詳報している。また「 週刊文春デジタル 」では、石崎氏の告白動画《完全版》を同日朝5時より公開する。
「週刊文春」編集部
一般消費者が購入する製品でないからこれぐらいで良いだろうと判断したのだと思う。
非鉄金属大手・三菱マテリアルの子会社で、自動車向け金属製品の品質データを改ざんしていた「ダイヤメット」(新潟市)が、不正を隠蔽(いんぺい)した責任をとり辞任した安竹睦実前社長を、同社の非常勤顧問につけたことがわかった。ダイヤ社は三菱マテグループの不正が公表された後も改ざんを続けていた経緯があった。経営責任のあり方が問われそうだ。
ダイヤ社によると、顧問就任は1日付。「顧客との交渉の助言をしてもらう」ことが狙いといい、報酬や任期は未定。親会社の三菱マテも承認した。
ダイヤ社では1977年ごろから製品の検査成績書の改ざんなどが続いていた。安竹氏は三菱マテの岐阜製作所長を経て、2015年12月にダイヤ社社長に就任。17年5月には、全ての常勤取締役が集まる会議で改ざんの報告を受けたが、「(不正品の)件数も多く、すぐに改善することは難しい」などとして、不正を黙認。不正品は今年1月までにのべ113社へ出荷された。問題の発覚を受け、安竹氏は今年2月に社長を辞任していた。
三菱マテの問題では、処分の甘さを指摘する声がある。先に品質データの改ざんが発覚した神戸製鋼所は社長らが引責辞任。一方、同様の問題を起こした三菱マテは、竹内章社長ら首脳の処分を報酬の返上にとどめた。3月の会見で竹内氏は処分の甘さを繰り返し問われたが、「総合的に検討した」と繰り返した。(高木真也、上地兼太郎)
東レは30日、昨年発覚した子会社での製品検査データの改竄(かいざん)問題を受け、グループ全社を対象に実施してきた品質データ調査の結果を発表した。法令違反や安全性に問題がある事案はなかったとして、東レグループの対外公表方針に従えば、新たに公表すべき案件はないと結論づけた。
東レは、グループ内で、データを取り扱う従業員や管理監督者ら約9700人を対象に不正の有無をアンケート方式で調べ、法令違反がなかったことと、安全性で影響がある案件はないとした。その上で、弁護士で構成する有識者委員会がこの調査を評価し、方法や結果を「妥当である」と判断した。
この調査は、東レ子会社の東レハイブリッドコード(THC、愛知県西尾市)で、製品データの改竄があり、発覚したことが契機。THCでは、改竄があったものの、安全性には問題がないとしていた。
今回のグループの調査結果では、法令違反の事実と安全性には問題がないことを確認したが、改竄がTHC以外にあったかについては言及していない。
結果から判断すれば、儲けるはずが、大損になったと思う。まあ、このような人達が存在しないと、不正をする人達が増える事は あtっても減る事はない。
不適切な保育実態が明らかになり、こども園の認定を取り消された姫路市の「わんずまざー保育園」が、同市に廃止届を出していたことが、29日までの同市などへの取材で分かった。
同市などによると、元園長の代理人弁護士が、今月6日に市監査指導課へ認可外保育施設の廃止届を提出し、受理された。休園中のため、昨年12月31日付での廃園になった。同課は「こういう残念な終わり方をする施設は最後であってほしい」とコメントした。
一連の問題では兵庫県と同市による特別監査で、同園が定員を超過して園児を受け入れていたことが発覚。通常より少ない給食を提供していたほか、保育士に無給勤務をさせるなど不当な雇用実態も明らかになった。県は昨年4月1日付で認定を取り消した。
また、同市は昨年10月、正規の園児に使うべき給付費を不正流用するなどしたとして計4693万円の返還を請求、同園は応じた。(井沢泰斗、伊藤大介)
にいかわ信用金庫(富山県魚津市)の元男性職員(53)が顧客の定期預金などを着服していた問題で、信金は29日までに、小林茂太理事長(70)が引責辞任し、後任に富山信用金庫(富山市)の常務理事を務めた岸和雄氏(68)が就任したと発表した。トップを外部から招きコンプライアンス(法令順守)体制を強化する。
28日に開いた臨時総代会と理事会で決定した。経営陣の処分としては、4人の常勤役員の月額報酬を8月まで6カ月間、10~20%減らすことも決めている。
にいかわ信金を巡っては、2017年11月以降、元職員が顧客の定期預金など計約4600万円を着服していたことが発覚。県警に通報するとともに、元職員に損害賠償を求める訴えを同年12月に富山地裁魚津支部に起こした。
組織の体質と人は簡単に変わらないと思う。
三菱マテリアルが28日公表した品質データ改ざん問題の最終報告書は、不正に手を染めた子会社が事態を改善できず、新たな不正を繰り返す実態を浮き彫りにした。子会社のダイヤメットは三菱電線工業と同様、当時の社長が不正を知りながらも会社の存続を優先し、製品の出荷を止めなかった。三菱マテリアルは現経営陣の下、ガバナンス(企業統治)体制の強化を誓うが、長年の企業体質を改められるかどうかは不透明だ。
報告書によると、ダイヤメットで一連の不正発覚のきっかけになたのが、同社社員による2015年2月の三菱マテリアルへの内部通報だった。社員相談室に「製品の製造場所について、事実と異なる表示がされている」との情報が寄せられた。
三菱マテリアルはダイヤメット社長に事情を聴くなどの対応を取ったが、同年7月、16年3月にも「改善しない」との通報が寄せられた。このため、三菱マテリアルが調査したところ、通報の指摘通り不正表示が発覚。このことから、16年9月に社内調査委員会を設置して本格調査に乗り出したところ、製品の品質について検査の未実施やデータ改ざんなどの不正が明らかになった。
ダイヤメットは調査と並行して再発防止に乗り出したものの、その間にも新たな不正が発生。しかし、この報告を受けたダイヤメットの安竹睦実社長(当時)は、隠蔽(いんぺい)するよう指示した。
同社は一時債務超過になるなど経営状態が悪く、報告すれば三菱マテリアルから支援を受けられなくなる恐れがあった。安竹社長は「顧客に報告した場合は対応に追われ、ライン停止などの迷惑をかける」と判断し、今年1月まで不正な製品の出荷を続けていた。
三菱マテリアルの竹内章社長は会見で「極めてゆゆしき行為で誤った判断だ」と述べるしかなかった。だが、親会社として一度は不正を把握しながら、断ち切ることができなかった。グループ各社に染みついた不正体質を抜本的に改めるのは容易ではなさそうだ。【川口雅浩、和田憲二】
◇社長続投に厳しい目
三菱マテリアルが特別調査委員会の最終報告書を発表した28日の記者会見では、竹内社長の経営責任を厳しく問う質問が相次いだ。竹内社長は役員報酬の一部返上を発表したが、社長を続投する考えを表明。グループの品質データ改ざん問題で引責辞任するのは、不正を働いた子会社2社(三菱電線工業とダイヤメット)の社長にとどまったからだ。
「最終報告を厳粛に受け止め、不退転の覚悟で再発防止に取り組みたい」「グループ全体でリスクに対する感度を高め、ガバナンス(企業統治)の向上に努めたい」
竹内社長は記者会見で自身の経営責任や進退問題を問われると、あらかじめ自分で用意したという原稿に目を通し、何度も同じ答弁を繰り返した。昨年11月に発覚した三菱マテリアル子会社の品質データ改ざん問題で引責辞任した経営トップは、三菱電線工業の村田博昭社長とダイヤメットの安竹睦実社長の2人のみ。いずれも不正を知りながら、親会社への報告や製品の出荷停止など適切な対応を取らなかった悪質性が問題となった。
竹内社長は「(引責辞任の)判断基準は不正への関与があったかどうかだ。電線社とダイヤメットの社長は辞任が適切と判断した」と説明。自身は直接、不正には関与していないため、引責の必要はないとの考えをにじませた。
しかし、同じく子会社を含むグループ各社でデータ改ざんが見つかった神戸製鋼所は川崎博也会長兼社長が引責辞任を表明した。子会社の社長のみに責任を押し付ける竹内社長の今回の対応が、投資家や取引先の理解を得られるかは疑問だ。【川口雅浩】
◇キーワード・三菱マテリアル
三菱グループの創始者である岩崎弥太郎が手がけた炭鉱・鉄鋼事業をルーツとし、1990年に三菱金属と三菱鉱業セメントが合併して誕生した。セメント▽金属▽加工▽電子材料▽環境・エネルギー▽アルミ--の6事業からなる非鉄大手。自動車や航空機部品、アルミの加工や製缶、家電向けの電子デバイスなど、幅広い素材や部品を扱う。事業の独立性を担保するためにカンパニー制を採用し、グループ会社は200社を超える。
昨年11月に子会社3社で素材製品の検査データを書き換えていたと発表し、調査が続いていた。2017年3月期の連結売上高は1兆3040億円、連結最終(当期)利益は283億円。グループの従業員数は約2万5000人。
日本人は正直者が多いが、日本人は正直者と言う事ではないと、最近の不祥事の報道を見て思う。
SUBARUが車の出荷前の検査で燃費データを改ざんしていた問題で、複数の従業員が改ざんに関与していたことがわかりました。
関係者によりますと、燃費データの改ざんをめぐり、SUBARUが過去数年分の検査記録を調べたところ、複数の従業員がデータを不正に書き換えていたことが確認できたということです。SUBARUはこれまで、「データの改ざんは組織ぐるみではない」と説明していましたが、一連の不正が組織的に行われていた可能性もあります。
SUBARUは今月末までに、最終の調査結果を公表するとしていましたが、調査が長引き、公表は来月以降にずれ込む見通しです。
SUBARUをめぐっては、資格のない従業員による不正検査の問題などを受け、今月、吉永社長を含む経営陣を刷新することを発表しています。
自業自得!
結果から判断すれば、儲けるはずが、大損になったと思う。まあ、このような人達が存在しないと、不正をする人達が増える事は
あtっても減る事はない。
兵庫県明石市立明石商業高校で昨年6月に行われた実用英語技能検定(英検)で、同校が監督者を規定通りに置かず、生徒2人がカンニングをしていた問題で、同校が準会場の指定を取り消されたことが26日、分かった。当面、同校では受験できなくなる。処分を決めた日本英語検定協会によると、取り消しは異例という。
同校によると、試験は、2級と準2級を2教室で実施。協会の規定では各教室に1人以上の試験監督が必要だが、教員1人が両教室を行き来していた。準2級の教室を不在にした際、生徒2人がカンニングをした。
協会は、同校が2016年も同様に監督1人で試験を実施していたことを問題視。「教育現場にあるまじき、ずさんな体制」として、処分を決めた。一方、答案を再調査するなどした結果、受験生26人の合否には影響がなかったと判断した。
市教委の石田圭治次長は「今後の受験生に影響が大きく、申し訳ない」と謝罪。校長らを月内にも処分する方針という。(藤井伸哉)
組織の腐敗が酷ければ、一つの不祥事は更なる不祥事の鍵となるだけ。
中途半端に終わらせれば、改革のチャンスを潰す事になる。問題なのは、改革しても生き残れない企業や組織が存在するリスクである。
政府系金融機関の商工中金で新たに約600件の不正行為が確認されたことが23日、分かった。国の支援を受けた危機対応融資で新たな不正が見つかったほか、地方自治体の制度融資でも審査書類の改ざんが判明した。不正融資に関する調査結果を同日公表する予定だったが、「内容を精査する必要がある」(広報部)として延期した。
「加藤勝信厚生労働相は20日、水島理事長に再発防止策の実施を指示。機構は、実態を調べた上で情報処理会社に3年間の入札参加資格停止を課し、損害賠償の請求も検討する。」
「する」と「検討する」は同じではない。検討したが、しないと判断する可能性がある。
日本年金機構が個人データ入力を委託した東京都内の情報処理会社が、契約に違反して中国の業者に再委託していた問題で、同機構は20日午後記者会見し、1月上旬に違反を把握しながら、2月13日まで委託契約を続けていたことを明らかにした。
500万人の情報が中国業者に=年金受給者データ入力を再委託
機構の水島藤一郎理事長は謝罪し、「繁忙期で他に肩代わりできる業者が見つからなかった」と釈明した。
東京都豊島区の情報処理会社「SAY企画」は昨年8月、機構から年金受給者延べ1300万人分の個人情報の入力業務を一般競争入札で請け負った。しかし、データ入力を怠り、約8万4000人が申告書通りに所得控除を受けられず、2月分の年金支給額が本来より数万円少なくなった。
機構によると、誤入力も31万8000人分になり、年金額に影響が出る見込みだ。情報処理会社のこうした問題は、昨年末の内部通報を受け、今年1月に特別監査を実施して把握。契約に違反して中国・大連の関連業者に年金受給者の扶養親族500万人分の氏名部分の入力を再委託したことが分かった。中国業者を現地で監査した結果、入力ミスはなく、個人情報も外部流出していなかった。
加藤勝信厚生労働相は20日、水島理事長に再発防止策の実施を指示。機構は、実態を調べた上で情報処理会社に3年間の入札参加資格停止を課し、損害賠償の請求も検討する。会見した水島理事長は、自身の進退について「きちんと対処するのが当面の責務だ」と述べ、辞任を否定した。
契約に違反し、最大で約500万人分の個人情報を中国の業者に渡して入力業務を再委託していた東京都内の情報処理会社との
契約を更新するべきではない。
罰則や罰金についてよく知らないが日本年金機構は契約の時に違反のケースでは罰則や罰金を取るべきである。
日本年金機構からデータ入力業務を委託された東京都内の情報処理会社が契約に違反し、最大で約500万人分の個人情報を中国の業者に渡して入力業務を再委託していたことが厚生労働省への取材でわかった。
この会社は、約130万人の年金が過少支給となった問題でも、データを入力せずに放置していたことが判明したばかり。同機構は中国の業者に再委託された経緯を調べている。
同省によると、同機構は昨年8月、東京都豊島区の情報処理会社に、約500万人分のマイナンバーや配偶者の年間所得額などの個人情報の入力業務を委託した。この会社は、個人情報の一部を中国の業者に渡し、入力業務を任せていたという。
機構と同社が交わした契約では、個人情報保護のため、別の業者への再委託を禁止していた。同省は、「中国の業者から個人情報が外部に流出した事実は今のところ確認されていない」としている。
「ネット事業者などに放送事業の門戸を開放すれば、地上波キー局をはじめとする放送事業者の地盤沈下につながる。」
ネット事業者に放送事業の門戸を開放する事は良い事だと思う。ただ、間接的にネット業者との競争に負けた民放は縮小したり、
どこかのネット事業者に吸収される可能性もある。
自由な報道や放送が確保されていれば問題ないと思う。自由な報道や放送が確保されれば、今以上にいろいろな事実が発信される
可能性も出てくる。新聞がテレビに負けたように、時代が変わればプレイヤーが変わってもおかしくはない。
安倍首相が目指す放送事業の見直しは、放送法4条などの規制の撤廃が目玉となる。背景には、首相に対する批判的な報道への不満があるようだ。
今回の規制緩和は、AbemaTVに代表されるような「放送法の規制がかからないネットテレビ」(首相)などの放送事業への参入を狙ったものだ。首相は衆院選直前の昨年10月、AbemaTVで1時間にわたり自説を述べた経緯もある。政治的中立性の縛りを外せば、特定の党派色をむき出しにした番組が放送されかねない。
ネット事業者などに放送事業の門戸を開放すれば、地上波キー局をはじめとする放送事業者の地盤沈下につながる。首相の動きに、放送業界は「民放解体を狙うだけでなく、首相を応援してくれる番組を期待しているのでは。政権のおごりだ」と警戒を強めている。
「学校法人『森友学園』(大阪市)への国有地売却問題で、約8億円の値引きにつながった地中ごみを試掘した業者が、ごみは実際より深くにあると見せかけた虚偽の報告書を作成した、と大阪地検特捜部の調べに証言していることがわかった。学園や財務省近畿財務局側から促された、
という趣旨の説明もしているという。値引きの根拠が揺らぐ可能性があり、特捜部は証言について慎重に事実確認を進めている模様だ。」
学園や財務省近畿財務局側から促された事が事実であれば学園の罪が重くなり、財務省近畿財務局が組織ぐるみで動いていたことも確実になる。
当時の佐川宣寿・理財局長が気の小さい人間であれば自殺するかもしれない。佐川氏が自殺しないように監視を付けるべきだ。財務省や
事実が明らかになって困る人間達にとっては自殺のよる幕引きがベストと考えているかもしれない。
学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却問題で、約8億円の値引きにつながった地中ごみを試掘した業者が、ごみは実際より深くにあると見せかけた虚偽の報告書を作成した、と大阪地検特捜部の調べに証言していることがわかった。学園や財務省近畿財務局側から促された、という趣旨の説明もしているという。値引きの根拠が揺らぐ可能性があり、特捜部は証言について慎重に事実確認を進めている模様だ。
【表でわかりやすく】佐川氏の国会招致で想定される論点
学園は2015年5月、大阪府豊中市に小学校を建設するため、国と借地契約を結んだ。16年3月、深さ9.9メートルのくい打ち工事中に地中から「新たなごみ」が見つかったとして国に対応を要求。国はごみの撤去費を価格に反映させて土地を売却する方針を決め、学園にごみに関する資料提出を求めた。
学園側は4月11日、建設業者が8カ所を試掘した結果、最深で地下3.8メートルにごみがあったとする写真付きの報告書を提出した。国はその3日後、報告書などを基にごみ撤去費を約8億2000万円と算定。6月20日、土地評価額から同額を引いた1億3400万円で学園に売却した。
捜査関係者によると、業者は3.8メートルの記載について過大だったと認め、「事実と違うことを書かされた」「書けと言われてしょうがなくやった」などと説明。当時、学園は小学校の開校時期が翌年の4月に迫っているとして、損害賠償をちらつかせて国に対応を迫っていた。
ただ、業者はごみ撤去費については「周囲の汚染土壌も撤去する必要がある」として約9億6000万円と試算し、検察にも説明している。
財務省や国土交通省は国会で、深さ3.8メートルのごみは16年4月5日に写真で確認したと説明。一方、直前の3月30日に国と学園の協議を録音したとされる音声データでは、学園側が「3メートルより下からはそんなにたくさん出てきていない」などと発言。国側の職員が「言い方としては混在と。9メートルまでの範囲で」などと応じ、ごみの深さの認識をすり合わせたような会話が記録されていた。
会計検査院は昨年11月に公表した検査結果で、業者の試掘報告書について「3.8メートルを正確に指し示していることを確認できる状況は写っていない」と指摘している。
特捜部は財務局職員らが不当に安く土地を売却したとする背任容疑などで告発を受け、捜査を進めている。【岡村崇、宮嶋梓帆】
「深さ3.8メートルのごみ」はあったのか、なかったのか。学校法人「森友学園」への国有地売却問題で、約8億円もの値引きの根拠にもなった、ごみ試掘の経緯が揺らいでいる。国と学園が協議した際の音声データなどからは、安倍晋三首相の妻昭恵氏の名前や損害賠償をちらつかせる学園に対し、国が「値引きありき」で交渉を急いだ様子が浮かび上がってくる。【岡村崇、宮嶋梓帆】
【表でわかりやすく】佐川氏の国会招致で想定される論点
「あの方自身が愚弄(ぐろう)されている」。小学校開校を翌年春に控えていた学園前理事長の籠池泰典被告(65)が強い口調で、財務省に乗り込んだのは2016年3月15日。その4日前、大阪府豊中市の予定地で深さ9.9メートルのくい打ち工事中、地中から大量のごみが出た。籠池被告は「昭恵夫人の方からも聞いてもらったことがある」などと名誉校長だった昭恵氏の名前を出し、対応を求めた。
翌16日、財務省の指示で学園を訪れた近畿財務局の職員は「仮に(ごみが)深く地中にあれば(売買の)評価で反映させていく」と発言。過去の調査で判明していた地下3メートルより深い場所のごみは国に責任があるとの考えを打ち出した。
国の説明では、業者が試掘したのは3月25日と30日の2回。8カ所を掘り、1カ所から地下3.8メートルのごみが見つかったとされる。
しかし、30日に録音されたとされる音声データで業者は「3メートルより下から出てきたかどうかは分からない」と疑問を口にした。国側の職員も「虚偽にならないように『混在している』と。3メートル超も一定あると。出るじゃないですか、ということ」と発言し、これからごみを探すような口ぶりで応じていた。
毎日新聞が入手した学園の内部資料では、業者は3月22日、籠池被告に「掘削のポイントは合計6カ所にて3メートル程度の深さとさせていただきます」とのメールを送っており、8カ所とする国側の説明とは掘削の数や深さが食い違う。
また、業者が撮影した写真では、掘削した穴に地下3.8メートル地点あたりまでメジャーが差し込まれ、途中にはごみのようなものが写っているが、底の方は泥の塊が大半で、一見してごみと分かるものではなかった。
学園が、この試掘報告書を国に提出したのは4月11日。そのわずか3日後に、国土交通省大阪航空局はごみ撤去費を約8億2000万円と積算した。同局は取材に、3.8メートルのごみが試掘された時期や経緯は「承知していない」としている。
一方、財務省による改ざんが判明した14件の決裁文書でも、ごみが見つかった経緯はあいまいだ。16年3月29日付の文書には「(過去の)地下埋設物除去工事は地下3メートルまでの範囲で行われたため、3メートル以深の廃棄物は撤去されずに今回の作業で噴出したもの」と記載されていたが、改ざんで削除されていた。
事実は一つであっても、記者や新聞社のスタンスや信念により表現の結果に違いが出てくる。
財務省は部分的には愚かで、傲慢な集団である事が確定したと思う。
「森友学園」の国有地売却をめぐり、財務省が14件の決裁文書を「書き換え」ていたと認めた。これは、前例のない事態だ。新聞各紙は、それぞれの社説でどう論じたのか。【BuzzFeed Japan / 籏智広太】
【写真】森友学園問題のこれまでの経緯を振り返る
国有地売却問題が国会で取りざたされるようになった後、2017年2月下旬から4月にかけて、国会議員らに開示された文書で書き換えられていた。
当時の佐川宣寿・理財局長の答弁に合わせ、「一部の職員」が行ったとして、責任は佐川氏にあるとの見解だ。政府は「改ざんではなく書き換え」との認識を示している。
朝日新聞「財務省の文書改ざん 民主主義の根幹が壊れる」
この問題をスクープし、独走で報じてきた朝日新聞は「公文書の改ざんは、幾重もの意味で、民主主義の根幹を掘り崩す行為である」と強く批判している。
公文書は国民が行政の政策決定の是非を判断するために必要であることを強調。「改ざんは国民の『知る権利』を侵し、歴史を裏切る行為である」と言い切った。
さらに、「財務省のふるまいは『全体の奉仕者』としての使命を忘れ、国民に背くもの」と断言。背景に「指示や忖度」がなかったのかと指摘。
また、加計学園をめぐる「総理のご意向」文書や、南スーダンPKOの日報問題にも触れながら、「安倍1強下での行政のひずみが、公文書管理のずさん極まる扱いに表れている」とした。
そのうえで、「問題の全容解明なくして、政治の信頼回復はあり得ない」とし、佐川氏と昭恵氏の国会招致を求め、「与野党ともにその覚悟が試されている」と結んだ。
読売新聞「森友書き換え 行政への信頼を失墜させた」
読売新聞も「行政に対する国民の信頼を傷付ける浅はかな行為」と批判。
佐川氏の責任を強く批判し、「事実をゆがめた答弁を繰り返した佐川氏の辞任と懲戒処分は当然」と指摘。安倍首相と麻生財務相の任命責任にも言及した。
さらに、「責任の所在を明らかにした上で、関係者の処分や再発防止策に取り組むべき」と財務省に求めている。
また、そもそもの土地値引き問題にも言及。政治家の働きかけについて、「政府には納得のいく説明が求められる」と指摘した。
そのうえで、各省庁が「行政文書の管理・保存のあり方を改めて見直し、徹底することが不可欠」と結んだ。
毎日新聞「財務省の森友文書改ざん 立法府欺く前代未聞の罪」
毎日新聞は「民主政治の根幹を揺るがす前代未聞の事態」と断言。
政府が公文書を「都合よく変え」たことは、「国権の最高機関である立法府を欺き、ひいては国民を侮辱する行為にほかならない。罪は極めて重い」と言い切った。
「朝日新聞批判を国会で繰り返してきた」安倍首相や、麻生財務相の政治責任に触れながら、「財務省のみの責任だというような説明は無理がある」と批判。
南スーダンPKO日報、加計学園の文書、裁量労働制のデータ問題に触れ、「不都合な事実には目を向けようとしない姿勢が、一連の問題に表れている」と指摘した。
そのうえで、「佐川氏だけの責任で終わらせるのは到底不可能」とし、今回表に出た原本とともに「佐川氏や昭恵氏らの証人喚問が必要」と結んだ。
産経新聞「公文書書き換え 国民への重大な裏切りだ 『信なくば立たず』忘れるな」
3月11日に「改竄ではなく訂正」との見出しを掲げていた産経新聞も、「国が根底から揺さぶられている」「都合の悪いことを隠すため、公文書をこっそりと書き換えるのは改竄というべき」と厳しいタッチだ。
冒頭では、「公文書とは、国などの行政機関の活動の基盤となり、歴史の証しともなるもの」としたうえで、正しい取り扱いが「民主主義の根幹を成す」と強調。
安倍政権の説明が「事実に基づかない」ものだったと批判し、「関係者の国会招致などにも積極的にあたるべき」と求めた。
また、「書き換えや土地売却をめぐり、佐川氏以外に政治家の働きかけ」の有無を解明する必要がある、とも指摘している。
そのうえで、佐川氏の「辞任は免罪符にならない」として国会招致を求め、さらに「適材適所」と擁護してきた麻生氏の責任にも言及。「安倍首相には、重大な失政と認識して対処してもらいたい」と結んでいる。
日経新聞「行政の信頼損なう『森友文書』の解明急げ 」
慎重な報道姿勢を見せていた日経新聞は、問題そのものを「書き換え」とし、「国会での追及をかわすため、不都合な記述を組織ぐるみで隠蔽した構図」との疑念を突きつけた。
「行政への信頼を失墜させる行為である」と批判。そのうえで、「政府内のどこまでが知っていたのか」など、全容解明の必要性を訴えた。
また、そもそもの土地取引に「政治の働きかけや官僚の忖度があったのかどうかが焦点」とも指摘。野党が「佐川氏や昭恵首相夫人らの証人喚問を求めている」ことに触れた。
やはり南スーダンPKO日報、加計学園の文書、裁量労働制のデータ不正に触れ、公文書管理や情報公開制度の「趣旨に反するような不祥事が続出」と批判。
今回のケースも「財務省の一部局の問題とは言い切れ」ないとして、政府全体での「事実解明や再発防止」を求めて結んでいる。
東京新聞「森友文書改ざん 国民を欺いたのは誰だ」
東京新聞は、「決裁文書改ざんは議会制民主主義を脅かす背信行為」と冒頭から厳しく批判。「あまりにも広範にわたる公文書の改ざんに驚きを禁じ得ない」と感情をあらわにした。
「安倍政権と国会が負う解明の責任は重い」とし、その責任が「財務省にとどまらず佐川氏の答弁を許容していた内閣全体に及ぶ」と指摘している。
問題の本質が国有地値引きの問題にあると強調。1年にわたって「事実関係を隠した資料に基づいて議論が行われていた」ことを批判し、与野党には「佐川氏や昭恵氏の証人喚問」を求めている。
また、売買への関与があれば「首相も国会議員もやめる」としてきた安倍首相には、文書に「自身や昭恵氏の名前があり、それが消されたことをどう説明するのか」と詰め寄った。
そのうえで、「安倍一強」の政治状況が「官僚らに政権中枢への忖度を促す要因」になっているのではないかとし、「議会制民主主義が、長期政権の弊害によって根腐れを起こしているとしたら、深刻だ」と結んだ。
言葉の使い方ひとつをとっても、報じ方が違うことがよくわかる。
たとえば読売と日経は「書き換え」としているが、朝日や毎日、東京は「改ざん」と見出しで強調している。さらに、産経も見出しでは「書き換え」としながら、「書き換えではなく改竄というべき」との認識を示している。
責任の所在についてもニュアンスに差がある。政権の責任を強く指摘する朝日や毎日、東京は佐川氏と昭恵氏の証人喚問を求めており、日経は、野党がそうした要望をしていることに触れている。
産経は佐川氏の喚問のみを強調しており、読売はどちらの証人喚問への言及も載っていない。この2社に関しては、財務省の責任を強く意識した書き方に読める。
また、朝日と毎日、日経が今回の改ざんを「公文書管理の問題」として、南スーダンPKOの日報黒塗り問題、加計学園「総理のご意向」文書問題、裁量労働制をめぐるデータ不正問題と同じ文脈に位置付けていることも特徴的だ。
広辞苑によると、「改ざん」は「多く不当に改める場合に用いられる」とある。
今回の大規模な「書き換え」では、明らかに一連の文書を「不当に改めている」とみることができる。BuzzFeed Newsでは今後「改ざん」という言葉を用いて報道する。
無免許で運転し、発覚すればどうなるのか、理解出来ないはずはない。優秀な頭で、事故を起こす確率と無免許が発覚する確率が 極めて低いと考え、リスクを取ったのであろう。
万が一を考えれば、タクシーを利用する、又は、学生に多少のお金を払って運転してもらうなどを選択できる。しかし、それらの 選択を除外した。
免停中であるが、仕事で必要なために、違法行為を選んだ判断は正しかったのだろうか?失うものが少ない人には安易に同じ選択が出来るが、 失うものが大きければ、安全な選択を取るべきだと思う。もう少し深く考える事が出来ていれば結果は変わっていただろう。
最終的には、東大が判断する事だ。
きっとチャンスに変わります。
(竹谷 純一 教授 ・ 岡本 敏宏 准教授 研究室|新領域創成科学研究科 物質系専攻|東京大学大学院 )

運転免許の取り消し中に車を運転したとして、千葉県警は8日、東京大学大学院教授の竹谷純一容疑者(51)=埼玉県三郷市中央1丁目=を道路交通法違反(無免許運転)の疑いで現行犯逮捕し、発表した。「免停中だと分かっていたが、仕事で必要なため運転してしまった」と供述しているという。
流山署によると、逮捕容疑は、8日午前8時35分ごろ、千葉県流山市南の県道で、無免許で乗用車を運転したというもの。信号待ちをしていて前の車にぶつかる物損事故を起こし、通報で駆けつけた警察官に事情を聴かれ、明らかになったという。
竹谷容疑者は有機半導体研究が専門。画面を自由に曲げられるLEDディスプレーをつくる技術を開発した東京大発ベンチャーで最高技術責任者を務めるなど、メディアにもたびたび取り上げられている。
東大は「事実関係を把握できていない」としている。
神戸製鋼だけの問題ではないように思えるが、このような問題は証拠が出て来ないと判断できない。
神戸製鋼所が6日公表した外部の調査委員会の調査結果を踏まえた報告書は、品質データ改ざんの原因が神戸製鋼の収益重視の経営や閉鎖的な企業風土などにあると指摘した。不正は1970年代から始まったことも明らかにした。不正根絶に向けた再発防止策として、取締役会の刷新やグループ会社の再編にまで踏み込む厳しいものとなった。
「役員を含む多くの者の認識や関与の下、長期間にわたって不正が継続してきた。当社は組織風土や役員・社員の意識面で根深い問題を抱えていると言わざるを得ない」。川崎博也会長兼社長は記者会見でそう述べ、現職の執行役員3人が不正を認識し、元役員2人が就任前に直接関与していたことを認めた。
神戸製鋼が調査し、昨年11月に発表した報告書では役員の関与を解明できなかった。しかし今回の報告書は弁護士ら外部調査委の調査結果などを反映したため、神戸製鋼に対しても厳しい内容となった。
その報告書によると、不正の直接的な原因として、能力に見合わない顧客仕様に基づいた製品の受注・製造▽改ざんが容易にできる環境▽品質コンプライアンス(法令順守)意識の鈍麻--があったと指摘。その上でカンパニー制が導入され、それぞれに「受注獲得と納期達成を至上命題とする風土」が根付き、本社の管理・監督が難しくなっていった。現場では「仕様を逸脱しても一定程度なら安全性の問題はないため出荷しても構わないという誤った考え方」が浸透し、機能不全の状態が長期化する結果となったという。
一方、神戸製鋼グループでは2006年以降、今回と類似するデータ改ざんなど不祥事が相次ぎ発覚。不正をただす好機だったが、報告書は「全社的かつ抜本的な対応はとらず、対症療法的だった。経営陣のコンプライアンス意識も十分でなかった」と批判した。
こうした利益最優先や、一部の経営幹部が把握しつつも不正を黙認する企業風土の下、一部の工場では「トクサイリスト」と呼ばれる事実上の不正マニュアルが作成され引き継がれるなど現場の品質管理意識はまひしていた。報告書は「わずかに顧客仕様を外れたに過ぎない場合は問題ない」など現場担当者の品質への低い意識も指摘しており、川崎社長は「外部の報告を受けた時にがくぜんとした」と、辞任の引き金となったことを明らかにした。【川口雅浩、古屋敷尚子】
神戸製鋼だけの問題ではないように思えるが、このような問題は証拠が出て来ないと判断できない。
神戸製鋼所による不正のうち、日本原子力研究開発機構は6日、神戸製鋼と同社の子会社「コベルコ科研」に委託して実施された原発から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の地層処分に関連する分析データなど16件で改ざんや捏造(ねつぞう)などがあったと発表した。神戸製鋼に再試験の実施を求めている。
原子力機構によると、不正があったのは2012~16年度に原子力規制委員会や経済産業省が原子力機構に発注した核燃料の被覆管や放射性物質を入れる容器に使う金属の腐食の進み具合を示した分析データなど。ほとんどのデータで実験記録がなかったり、意図的に記録を改ざんしたりしていたという。
資源エネルギー庁などによると、改ざんデータを使った分析結果をまとめた報告書を一部修正する。神戸製鋼は「問題を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に最大限努める」としている。【鈴木理之】
最近のいろいろなデータの改ざんや隠ぺいは長期に隠ぺいを行ってきた人々が退職したり、引継ぎに失敗したケースなのだろうか。
それとも入社した企業で人生を終える考えが薄れて来たので、そこまで隠ぺいに関わる必要はないと思う人が増えたのだろうか?
企業にゆとりがなくなり、隠ぺいに関わる人々の待遇が悪くなり、ほころびから問題の発覚となったのか?
道徳教育やモラルを意識した若い世代が生涯を通じて守ってくれるかわからない企業に対して隠ぺいに関与したくないと思う傾向が高くなったのだろうか?
理由はわからないが何かが変わっているのは事実のように思える。
神戸製鋼所は、川崎博也会長兼社長(63)が社長職を退任する方向で調整に入った。アルミ・銅製品などの検査データの改ざん問題で、外部調査委員会が近く最終的な調査内容を神鋼に報告することを受け、経営責任を明確にする。退任する時期は今後つめる。
川崎氏は2013年に社長に就任。神戸製鉄所(神戸市)の高炉の休止を決め、電力事業を強化するなど経営の多角化を進めた。
だが昨夏、社内調査によって真岡(もおか)製造所(栃木県真岡市)などの検査データ改ざんが発覚。子会社を含めて17工場で、検査データの改ざんや顧客と約束した検査の未実施が長年続いていたことがわかっている。
製品の出荷先は緊急の安全点検を余儀なくされ、関西電力大飯原発(福井県おおい町)なども再稼働を延期。製品の日本工業規格(JIS)の認証取り消しも相次いだ。米司法省も調査に乗り出している。
こうした影響の広がりで経営責任を明確にする必要に迫られていた。川崎氏が会長職も同時にやめる案があがっている。神鋼はすでに、改ざんが目立ったアルミ・銅事業部門の執行役員3人について、担当を外して事実上、更迭している。
「燃費が一定の範囲におさまるよう不正に測定値を改ざんしていた。吉永氏は記者会見で『カタログ値が変わることではないが、大きな問題だ』と話した。」
微妙だね!カタログ値が実際に生産されている車とかけ離れていれば、問題だと思う。なぜ、カタログ値と抜き打ちで検査した量産タイプの燃費が
一定の範囲でおさまらないのか?そこを明確にする必要があると思う。
スバルの吉永泰之社長は2日、完成した車の燃費を確認するために行う「抜き取り検査工程」の一部で、測定値の書き換えがあったと明らかにした。燃費が一定の範囲におさまるよう不正に測定値を改ざんしていた。吉永氏は記者会見で「カタログ値が変わることではないが、大きな問題だ」と話した。
スバルが無資格者に完成車の検査をさせていた問題で、外部の弁護士による抜き打ち検査で昨年12月に測定値の不正の疑いが発覚。外部の弁護士らが調査を進めていた。同社によると、品質への影響はないという。3月末までに最終的な調査内容を報告するという。
この件に関してしっかりと説明しないと信頼を失うかもしれない。
博多発東京行き「のぞみ34号」(N700系)の台車亀裂問題で、JR西日本は台車の溶接部に傷がある川崎重工業製の車両の運行継続を決めたが、こうした溶接部に傷がある台車は、JR西とJR東海の台車製造元の中で川重製に集中していることが1日、分かった。川重製では6・9%に上り、他社製(0・8%)の8倍以上だった。溶接部の傷は亀裂の起点になったとされており、川重のずさんな製造管理体制が改めて浮かび上がった。
JR2社は同型の台車について、目視できない内部の状態を確認する超音波の探傷検査を実施。川重製の検査を終え、日立製作所など他社製の検査を継続している。
JR西によると、川重製全303台のうち溶接部分に微細な傷があったのは22台で7・2%に上った。一方、他社製は検査済みの165台中2台(1・2%)だった。JR東海では、川重製で傷があったのは全130台中8台(6・1%)で、325台のうち2台(0・6%)だった他社製を大きく上回った。
JR2社の台車を合計すると、川重製では433台のうち30台(6・9%)に傷が確認されたが、他社製は現状で490台のうち4台(0・8%)にとどまっており、製造品質に大きな開きがあることが確認された。
同型の台車はJR西に921台、JR東海に約3900台ある。問題の台車は、川重が製造した台車枠の底面に、台車枠と車軸を介する「軸バネ座」という部品を溶接していた。溶接部の傷は施工時に発生し、亀裂のもとになったとされる。
川重は台車枠底面と軸バネ座の溶接面を平らにして隙間を1ミリ以内に抑えるため、社内規定に違反して台車枠底面の鋼材を削っていた。底面の板厚が薄くなったことで強度不足になり、台車枠が破断寸前になるまで傷が進展したとみられている。
川重の広報担当者は「台車の一部に傷があったことは確かだが、他社製の台車については承知しておらず比較できない」とコメント、今後も調査を進めるとしている。
この手の問題は氷山の一角なのか?
筑波大は1日、同大の女子学生の体に触るなどのセクハラ行為をしたとして、60代の男性准教授を懲戒解雇したと発表した。被害者の特定につながるとして、大学は准教授の氏名や所属を明らかにしていない。処分は2月28日付。
大学によると、准教授は昨年3月、学外での調査が終了した後、女子学生と2人で帰路に就き、自分の別荘に女子学生と宿泊。2人は別々の部屋で寝たが、その後、女子学生の部屋に侵入し、体を触るなどした。
女子学生が大学に相談して発覚した。大学側の聞き取り調査に対し、男性准教授は事実を認めた。
永田恭介学長は「教育、指導する立場の教員が今回のような事態を起こし、極めて遺憾。再発防止に向けた啓発活動や大学の信頼の維持向上に努める」とコメントした。
やれやれと言った感じ。日本企業の歪が隠ぺいが難しくなってきた今の時代に噴出していると思える。昔であれば、同じ事が起きても
隠ぺいはやり易かったと思う。
メーカーの品質を信用できないと判断した場合、発注者がチェックする事は可能なのか?可能だとしても、コストと人件費はかなりアップになると思う。
JR西日本の新幹線の台車に破断寸前の亀裂が見つかった問題で、台車には製造メーカーから納入した段階で「ひび割れ」が生じていました。
去年12月、破断寸前の亀裂が見つかった新幹線「のぞみ」の台車は、2007年に川崎重工業から納入した段階で、すでに台車の枠に亀裂につながる「ひび割れ」が生じていたことがわかりました。さらに、川崎重工業は、台車の製造工程の中で設計基準より薄くなるまで台車枠を削っていましたが、JR西日本は納入時の検査を川崎重工業に任せていて、チェックを行っていませんでした。JR西日本によりますと、製造時に不備があった川崎重工業製の台車は100台あり、今後は、超音波検査を実施しながら順次交換していくということです。
朝日放送
日本の製品や日本の企業が素晴らしいのではなく、外国の企業や製品が日本と比べると、さらに悪い品質や仕上がりであると言う事が事実のように
思えて来た。
日本の神話が崩壊したのではなく、問題が発覚しなかったので、事実以上に品質をアピールしたり、過大評価していただけなのかもしれない。
◇金花社長「多大なご迷惑」と謝罪、引責辞任は否定
新幹線「のぞみ」の台車に亀裂が見つかった問題で、メーカーの川崎重工業は28日、台車枠の製造過程で底部を不正に削り、鋼材の板厚が最も薄い箇所で基準の7ミリを下回る4.7ミリとなり、溶接不良もあったと発表した。いずれも亀裂の原因になったとみられる。神戸市の本社で記者会見した金花(かねはな)芳則社長は「新幹線利用者やJR西日本、東海の関係者に多大なご迷惑をおかけした」と謝罪したが、引責辞任は否定した。
基準を下回る台車はJR西日本と東海で他に計146台。JR西は100台(1両に2台)あり、超音波検査の結果、強度に問題はないとし、運行を続けながら順次交換する。JR東海の46台も安全性を確認しており年内に交換する。他のJR3社では該当がなかった。
川崎重工やJR西によると、2007年、兵庫工場(神戸市)でコの字形鋼材同士を合わせてロの字形の台車枠に溶接した際、コの字鋼材の曲げ方が不足し、底部が平面にならなかった。「軸バネ座」と呼ばれる部品を溶接で取り付ける必要があり、本来の作業手順にない削る対応で平面にし、板厚が基準を大幅に下回った。さらに溶接の際、底部2カ所の鋼材内部を傷付けるミスも加わった。
台車枠の鋼材は製造の際、削る加工を原則禁じる決まりがあるが、同工場の班長が従業員約40人に徹底させなかった。従業員は軸バネ座をしっかり取り付けようと削ってしまい、そのまま出荷したという。
台車枠は運行を続けるうち、溶接不良で傷付いた2カ所を起点に金属疲労が進み亀裂が広がった。起点は亀裂発覚の相当前に生じたとみられるが、その後は一気に広がったとみられる。
亀裂が生じた台車以外にも、基準以下の100台の台車で7ミリ未満に削り込まれていた箇所が見つかり、最も薄いもので4ミリだった。JR東海も46台のうち6・5ミリ未満の箇所が確認された16台は優先して3月中に交換する。
のぞみは亀裂で台車枠が破断寸前となり、国の運輸安全委員会は新幹線初の重大インシデントとして調査を続けている。川崎重工に先立って28日会見したJR西の来島達夫社長は「製造時の超音波検査を求め、安全な車両を提供してもらいたい」と話した。トラブルで生じた費用の川崎重工への請求は今後検討する。川崎重工は3月から3カ月間、金花社長が月額報酬50%、車両製造を担当する小河原誠常務取締役が同30%を返上する。
この問題では、昨年12月11日に博多を出発したのぞみで、乗務員が異音や異臭などを確認しながら運行を続けていたJR西の対応が厳しく批判されていた。【根本毅、服部陽、宇都宮裕一】
理系とかならまだ多少理解できるが、大学院国際公共政策研究科の教授とは情けない限りだ!
人間的に問題のある教授が大学院で国際公共政策研を教えるとは偽善や薄っぺらさをく感じる。
「阪大のハラスメント相談室には11年度以降、教授のハラスメントに関する相談が寄せられていた。」
阪大は体質的にかなり古い組織なのか?しかも「国際」が付くとは何ともはずかしい。阪大は底辺の国立大学ではないのにこのような状態なのか?
大阪大(大阪府吹田市)は22日、大学院国際公共政策研究科の60歳代の男性教授が、複数の大学院生やスタッフにハラスメント行為をしていたとして、停職3か月の懲戒処分にしたと発表した。
阪大は教授の名前を明らかにしていない。
発表によると、教授は2013年9月、学外のホテルで研究集会が行われた後、懇親会の2次会を、大学院生やアルバイトを含む女性スタッフらが宿泊する部屋で約2時間にわたって開いた。また、翌日の懇親会の2次会でも、入浴を済ませていた女性スタッフらに対し、繰り返し出席するよう求め、参加させた。
また、同年度の演習授業後の懇親会に関して、スタッフらに準備や後かたづけを強制。求人情報と労働実態に隔たりがあることを口にしたスタッフらの一人に対し、「不満があるなら辞めればよい」という内容の発言をしていた。阪大は「教授の行為はアカデミック・ハラスメントやセクハラ、パワハラが複合している」と判断した。
教授は大学の調査に「2次会への参加や懇親会の準備を強要した事実はない」などと話しているという。
阪大のハラスメント相談室には11年度以降、教授のハラスメントに関する相談が寄せられていた。西尾章治郎学長は「教育研究に従事する立場にあるべき者がその資質さえも疑われるような行為に及んでいたことは、誠に遺憾」として、再発防止に努めるとしている。
弁護士でも検察でもないので専門的な事はわからないが、このようなケースでは民事で争う事はあっても、詐欺などの刑事事件に
なる事はほとんどないと聞く。
過去に中古物件を買って成功した人達の例をインターネットやテレビで見たことがあるが、本当に上手く行ったケースだったり、
運が良かったり、ビジネスの勘と言うか、センスがあったのであろう。失敗した人達が取り上げられる事が少ないので、割合的には
どうなのだろうか?
シェアハウスに投資した会社員らのオーナーに賃料が払われないトラブルが相次ぐ問題で、オーナー約700人を抱える不動産業者スマートデイズ(東京)の前社長、大地則幸氏が20日、朝日新聞の取材に応じた。賃料不払いの状況に陥っていることについて「だますつもりはなかった」と釈明した。
スマートデイズは長期の賃料収入を保証してシェアハウスのオーナーを勧誘。割高な物件を売って利益を上げた。昨秋から賃料支払いが滞り、年初からは不払いになっている。大地氏は1月12日付で退任した。
大地氏は、オーナーへ物件を売って得た利益で約束した賃料を払う「自転車操業」だったことを認めた。「(事業の)スタート段階では『自転車操業』の時期も必要。規模を増やせば家賃以外の収入で軌道にのせられた」とした。自らもシェアハウス2棟を買って賃料が未払いになったとし、「だます人が自分では買わない」と主張した。
シェアハウス投資では、多くのオーナーが地方銀行のスルガ銀行(静岡県沼津市)から融資を受けた。その融資関係書類の改ざんなどが確認されている。大地氏は「(不正は)聞いたことはあるが、不正をする会社は排除した」と話し、売買や融資関連の実務は仲介業者任せで関わっていないとした。スルガ銀の融資が多いのは「審査が早く融資額も大きいからだ」と説明。同行の支店幹部と定期的に情報交換もしていたと明かした。
オーナーが物件購入の融資と同時に、フリーローンを受けるケースなどが多いのは「ノルマが大変だからだろう」と語った。(藤田知也、久保智)
課税はないわけだし、約5億円の収益があればとてもリッチに生活できたと思う。
佐賀県の宗教法人がヤミ金融を営み、約5億円の収益を上げていたとして、兵庫県警は、法人と代表らを国税当局に課税通報する方針を固めた。
代表らは資金の貸し付けと同時に、借り主に陶器などを高値で買わせるなどし、その代金で実質的に利息を得ていたという。県警は、宗教活動を装っていたと判断した。
法人は、佐賀県伊万里市の寺院を所在地とする「至誠光魂寺しせいこんごうじ」。代表の立石扇山せんざん被告(77)(公判中)ら5人は昨年11月、出資法違反(超高金利)容疑などで兵庫県警に逮捕され、その後、起訴された。
起訴状などによると、立石被告らは2015~16年、兵庫県内の中小企業など7社に計430万円を貸し付け。利息は、借り主に花瓶などを高値で買わせたり、架空の女神像建立計画に寄付させたりして得ていたといい、法定利息(1日当たり0・3%)の十数倍にあたる計約85万円を利息として受領した、とされる。
新しい形態の投資やビジネスはリスクが伴う。上手くいけば、競争率が低い時に儲けられる。しかし、問題や罠の傾向がわからないから、 失敗も高い。今回はそのようなケースに思える。
会社員らが投資目的で建てたシェアハウスで約束された賃料が払われなくなった問題で、融資関係資料の改ざんなどの不正が多発していたことがわかった。預金額の水増しなどで信用力を上げ、多額の融資を受けやすくしたとみられる。融資の多くは地方銀行のスルガ銀行(静岡県沼津市)が行っていた。
問題になったのは、首都圏を中心に急拡大した「シェアハウス投資」。トイレなどが共用のシェアハウスで会社員らが1棟丸ごとオーナーになる。長期の賃料収入を約束する「サブリース」で勧誘され、副収入目当ての会社員らが1棟1億円超を借りて建てる例が多い。不動産業者らは土地紹介や建築請負、入居者募集なども担う。だが、800人超が賃料が払われないトラブルに巻き込まれている。顧客が多い不動産会社スマートデイズ(東京)は1月から約700人への支払いを停止した。多くはスルガ銀でお金を借りていた。
シェアハウス投資では、不動産会社と提携する数十社の不動産仲介業者が窓口の場合が多い。会社員らは融資を受ける際、仲介業者に預金通帳の写しなどを渡し、銀行との手続きを一任。ところが一部の融資で書類が改ざんされていた。
預金残高を10倍以上に膨らませたり、業者に多額の頭金を振り込んだりしたように書き換えた例もある。多額の預金や頭金の支払い能力があるように見せかけ、融資を引き出しやすくした可能性がある。
シェアハウス賃料の支払い停止後、融資返済が厳しくなった会社員らがスルガ銀に返済猶予を求める中で不正が発覚。多くの改ざんは会社員らが知らぬ間に行われていたとみられる。
仲介業者の一部は朝日新聞の取材に不正の存在を認めた。誰がどのように行ったかは明かしていない。スマートデイズは「金融機関とオーナー間のやり取りは答えられない」という。
スルガ銀は、シェアハウスへの融資について「収益性不動産投資の新しい形として有望と考えた。具体的な融資額はお答えできない」とし、預金水増しなどは「融資実行後に一部そのような例が判明した」としている。「当社の手続きの不備によるか否かに関わらず許されることではない」とし、現時点で行員が関与した形跡はないとしている。(藤田知也、久保智)
自業自得!
三菱マテリアルの子会社が製品の検査データを改ざんしていた問題で、子会社3社で新たに同様の不正があったことが7日、わかった。
不正が発覚したのは、三菱アルミニウムと立花金属工業、ダイヤメットの3社で、8日にも公表する予定だ。
3社は取引先と契約した品質基準を満たしていない製品のデータを書き換えるなどしていた。製品の安全性などに問題はないという。三菱マテリアルは昨年11月、子会社の三菱電線工業と三菱伸銅、三菱アルミでの不正を発表。三菱アルミは今回重複しており、不正が発覚したのは計5社となる。
岐阜県大垣市のJAの男性職員が、客から預かった定期積金などおよそ950万円を着服していたことがわかりました。
大垣市に本店がある「JAにしみの」によりますと、去年12月と今年1月、複数の契約者から、定期積金の証書に書かれた金額と実際に預けた金額が違うなど不審な点があると問い合わせがありました。
JAが調べたところ、この契約者を担当していた大垣市内の支店で渉外担当だった30代の男性職員が着服を認めたということです。
着服は10人の契約者から預かった定期積金や自動車共済の掛け金の一部など、あわせておよそ950万円にのぼります。
男性職員はJAに対し「遊興費や生活費に使っていた」と説明した上で、「全額弁済する」としています。
JAは今後、男性職員を処分するとともに、刑事告訴についても「弁護士と相談し決める」としています。
東海テレビ
自業自得!
顧客の口座から現金を不正送金してだまし取ったとして、千葉県警捜査2課などは7日、電子計算機使用詐欺などの容疑で、元三井住友銀行新松戸出張所主任の橘高ゆかり容疑者(35)=同県松戸市幸谷=を逮捕した。
容疑を認めているという。同課は、橘高容疑者が2009年ごろから総額約4億8000万円を不正に引き出したとみて捜査している。
逮捕容疑は11年3月30日~4月21日、オンライン業務端末機を使い、顧客の口座から同容疑者が管理する口座に不正送金するなどし、計約1800万円をだまし取るなどした疑い。
同課によると橘高容疑者は、長期間にわたり銀行に来ていない人や、高齢者らの口座を狙って現金を詐取していた。引き出した金は外国為替証拠金取引(FX)への投資に使っていたという。
自業自得!
寂しく暗い余生があるだけだろう。
経営破綻した格安旅行会社「てるみくらぶ」(破産手続き中)の融資金詐取事件に絡み、個人資産の現金約1000万円を自宅に隠したとして、警視庁捜査2課は7日、破産法違反容疑で、社長の山田千賀子容疑者(67)=詐欺罪などで起訴=を再逮捕した。
山田容疑者は4度目の逮捕で、「差し押さえられないように(会社から)持ち出した」と容疑を認めているという。
逮捕容疑は、同社の破産手続きが始まる直前の昨年3月下旬ごろ、差し押さえを逃れる目的で、社内に保管していた役員報酬約1000万円を自宅などに隠匿。個人としての破産手続きに際し、破産管財人に対し、保有している現金を実際よりも少なく申告した疑い。
経団連は6日、神戸製鋼所などで品質管理が問題となったことを受け、1500の会員企業・団体に呼びかけた自主的な不正調査の結果を発表した。昨秋以降、検査データの改ざんが見つかった神戸製鋼、三菱マテリアル、東レのほか、大手5社で不正が見つかった。いずれも各社が既に内容を公表している。
不正が見つかった5社は、東北電力▽日立製作所と子会社の日立ビルシステム▽三菱電機▽ガラス最大手の旭硝子の子会社AGCテクノグラス▽石油元売り大手コスモエネルギーホールディングスの子会社丸善石油化学。
日立は国土交通省が認定した基準に適さないエレベーターを製造、販売するなどしていた。三菱電機は荷物用エレベーターの安全装置に不具合が見つかった。東芝グループの東芝エレベータも昨年12月26日、国交省の認定に必要な申請に不備があったと発表したが経団連には「不適切な事例には当たらない」として報告しなかった。
経団連はいずれも「安全性に問題はなく、再発防止に取り組んでいる」としている。昨年12月4日に調査し、速やかに公表するよう呼びかけていた。神戸製鋼や東レなどは呼びかけ前に不正が発覚したため、報告対象に含まれていない。【川口雅浩】
経済状況や景気を無視して規則を強化するとこのようなケースは起こる可能性がある。
基本的に国際的な競争力が向上するような政策なしに、労働者保護を強化すると逆効果になる事がある。
それを承知の上で、与党も野党も「改正労働契約法」を通したのだから仕方がない。
東北大学が非正規の職員約3千人を来月末から順次「雇い止め」にする問題で一部の非正規職員が雇用継続を求め、1日、仙台地裁に労働審判を申し立てました。大学側は「全員を正職員として雇用するのは経営上難しい」と主張しています。
労働審判の申し立てを行ったのは、東北大学で非正規の職員として働く40代から60代の男女6人です。
6人は「有期雇用契約の更新を重ねて5年から20年間勤めたにも関わらず、来月末で雇い止めされるのは「改正労働契約法」に違反するとして、撤回と雇用の継続を求めています。
「改正労働契約法」では通算5年を超えて有期契約を更新した人は、今年4月以降、期間に定めのない「無期雇用」に転換できると定めています。
ところが東北大学では2013年から5年を超えて契約を更新できないよう規則を変更したため、5年を迎える来月末以降、3千人規模の非正規職員を順次、雇い止めにする方針です。
東北大学職員組合 片山知史 執行委員長
「(長年)働き続けてきた東北大学でまた安心して働き続ける。その意思はやっぱりどうにかしたい」
東北大学では勤務時間などを制限した上で無期雇用に転換する「限定正職員制度」を4月から導入しますが、すでに行われた採用試験の合格者は669人だけです。
大学側は「全員を無期雇用へ転換することは経営上困難」との見解を示しています。
弁護団では非正規職員からの追加の申し立てを、随時、受け付けるということです。
不正には2つの異なるタイプがある
日本の製造業の信頼が揺らいでいる。日産自動車で無資格の社員が完成検査をしていた問題に続き、神戸製鋼と三菱マテリアルの子会社、東レの子会社による性能データ改ざん問題も発覚した。
これらのコンプライアンス違反に共通するのは、明らかに不正の意図をもった「首謀者」が見つからないことである。度重なる担当者の引き継ぎを経て不正が「慣行化」しているケースや、上層部の意向を「忖度」して、現場が微妙な不正を行ってしまっている。前者は神戸製鋼と三菱マテリアルのデータ改ざん問題、後者は東芝の不正会計が典型である。多くの場合、この両方が入り混じっている。
いずれも、不正に関与した人々が明らかな悪意を持って上司や顧客を騙そうとしたのではない。むしろその逆で、現場の慣行や上司への忖度の結果として生じた「行動の歪み」によるものである。こうした不正を「慣習・忖度型」の不正と呼ぼう。
こうしたタイプの不正は、アメリカ企業では見受けられない。例えば、エンロン事件やバーナード・マドフの詐欺事件は、明らかに悪意を持つ誰かによる意図的な不正である。このように、悪人が主導するタイプの不正を「意図・計画型」の不正と呼ぼう。このタイプの不正は、個人の懐を満たすことを目的として行われることがほとんどである。
ただし、日本でもこのタイプが少ないわけではない。例えば、2017年に発覚したバンダイの元社員による2億円の横領事件や、2015年に発覚したコマツで元社員による4億円の横領事件である。また、2011年に発覚したオリンパスの不正(経営陣による損失隠し)もこのタイプに近い。逮捕された7人の経営陣は、直接個人の懐にカネを入れたわけではないが、粉飾によって株価を不正に釣り上げた。そのメリットを最も享受したのは、他ならぬ逮捕された経営陣である。このように、日本では「意図・計画型」の不正が少ないのではなく、「慣習・忖度型」の比率が高いだけである。
では、「慣習・忖度型」の不正は日本企業に固有の現象なのだろうか。必ずしもそうではない。
例えば、2015年に発覚したドイツのフォルクスワーゲン社(以下、VW社)による「排ガス規制逃れ問題」がそれに該当する。その概要は、排出ガス検査時だけ合格するように設計された不正ソフトウエアを1千万台以上に搭載していたというものである。この事件は同社の屋台骨を揺るがせた。
このタイプの不正は首謀者が見つかりにくいため、長い間逮捕者が出なかったが、2017年になって米国で1名、ドイツで1名の現場責任者が逮捕され、ドイツでは開発担当(当時)の取締役が逮捕された。しかし、彼らは個人の懐にカネを入れたわけではない。排ガス規制が厳しくなる一方で、開発スケジュールは延期できない状況に置かれていた。こうした状況下で、社内のプレッシャーに耐えきれずに現場が手を染めてしまったゆえの不正だろう。
実際には、完全にどちらか一方になるわけではなく、両方の要素を含むケースが多い。東芝とVWは「慣習・忖度型」だが、「意図・計画型」の要素も入っている。オリンパスは「意図・計画型」だが、「慣習・忖度型」の要素も入っている。
企業のコンプライアンス違反に対する処方箋
企業のコンプライアンス違反を防ぐための制度には様々なものがある。オリンパスの粉飾のような「経営者の不正」であれば、コーポレート・ガバナンスの強化が有効である。具体的には、社外取締役を増やし、社長を指名する際に社外の指名委員の比重を高めるといった制度を導入すれば、世間や株主の意見が経営に反映されやすくなる。
しかし、いち早くこうした制度を導入していた東芝で、不正会計問題が起こってしまったのは皮肉である。同社は2003年に「委員会設置会社(取締役会の中に指名委員会、監査委員会、報酬委員会を置く)」を採用できるようになった際、他社に先駆けて委員会設置会社に移行し、先進的なコーポレート・ガバナンスを行っている企業と見なされていた。
では、なぜこうした不正を防げなかったのだろうか。なぜなら、これらの制度は「意図・計画型」の不正を防ぐためものだからだ。つまり、意図的に悪事を働く者がいることを前提に制度が設計されている。ここで用いた「悪事」の意味は、隠ぺいや虚位の報告などの不正行為を通じて、自己の利益を最大化することを指す。ちなみに、当時の東芝の社長や会長は現場に「チャレンジ」を求めたが、オリンパスの経営陣のように意図的に粉飾を主導したわけではない。この例のように、コーポレート・ガバナンスの仕組みをいくら強化したところで、「慣習・忖度」型の不正には全く効かないのだ。
これは経営陣以外の社員による不正にも同じことが言える。仮に内部統制のルールを充実させたとしても、それが効力を発揮しやすいのは横領やハラスメントなどの、「意図・計画型」の不正である。「慣習・忖度型」の不正は、内部統制をすり抜けてしまう。
例えば、日産の工場における最終検査工程の問題では、工場全体でルールが形骸化(ルール無視が慣習化)していたので、発覚までに時間を要した。また、神戸製鋼の場合は10年以上前から不正が行われていた(一説には40年前からという話もある)。三菱マテリアルの子会社の不正については、経営陣が不正を認識した後も出荷を続けたという。「慣習・忖度型」の不正に対して、いかに内部統制が予防につながらないのかが分かる。
「慣行・忖度型」のコンプライアンス違反を防ぐのが難しい理由
日本の上場企業はここ10年でコーポレート・ガバナンス(コーポレートガバナンスコード,2015年)と内部統制(日本版SOX法,2006年)を強化してきたにもかかわらず、こうした不正を防げていない。それどころか、近年になって頻発している状況である。その最大の理由は、「慣習・忖度型」の不正を予防するための処方性が見当たらないためである。
ゆえに、昨今頻発している「慣習・忖度型」の不正に対して、「意図・計画型」に適応した仕組みを強化するという処方箋は的外れである。むしろ企業内の管理コストを高めるだけで、不正を巧妙化させるだけだ。では、どうすればいいのか。そのためには、「慣習・忖度型」が起こる仕組みを理解する必要がある。
続き:首謀者不明な「コンプライアンス違反」に対する処方箋>>
前回は、企業のコンプライアンス違反を2つの類型に整理した。そして、「慣習・忖度型」の不正に対しては有効な手を打てておらず、それが神戸製鋼や三菱マテリアルの不正、東芝の不正会計などのコンプライアンス違反を防ぐことができなかった理由だと論じた。
ではなぜ、日本企業では「慣習・忖度型」の不正が多いのだろうか。
その最大の理由は、日本企業の「共同体性」にある。共同体とは地縁や血縁、友情などで深く結びついた自然発生的な組織である。具体的には、血縁・氏族的共同体(家族)、地縁(村落)・部族的共同体、宗教的共同体などである。企業は利益の獲得や企業価値の最大化を目的として集まった集団なので、当然ながら共同体ではない。以下の整理に従えば、「機能体(機能集団)」である。しかし、日本企業は機能体でありながら、共同体的な特徴を色濃く備えているという。それはなぜなのか。
そのひとつは、産業構造の変化に伴う村落共同体の衰退である。第一次産業から第二次産業へのシフトが進んだ結果、地方から都市部や工業地帯に多くの若者が集まった。こうした人たちは血縁共同体や地域共同体から離れて暮らしていたため、個人が共同体から切り離されてしまった。そこで受け皿になったのが、「会社」である。
もうひとつは、宗教的な「国家共同体」の終焉である。明治~太平洋戦争中までの日本国は、神聖なる天皇を頂点とした宗教的共同体(国家神道)であった。しかし、敗戦によって、日本国は共同体ではなくなってしまった。これに敏感に反応したのが三島由紀夫である。天皇陛下が象徴天皇となり、国家共同体が過去の幻となってしまった後、国民が広く共有できた幻想は「経済成長」であった。こうして兵士だった男たちの多くは企業戦士となり、国家共同体が後退した空白を埋めた。こうしてますます「会社」が共同体としての役割を担うことになった。
ちなみに、戦勝国のアメリカでも都市や工業地帯への人口集中はあったが、会社は共同体にならなかった。その最大の理由は、宗教的共同体が残っていたからである。アメリカ建国の父たちは、英国国教会から迫害されたカルヴァン派のキリスト教徒たちであり、現在でも統計上は80%がキリスト教、かつ非カトリックが多い国である。そのため、日本ほど急速に共同体から切り離された人は増えなかった。
こうして日本の企業、特に大企業は「共同体化」していった。日本の典型的な大企業の社員は、新卒一括採用で入社してから約40年間も勤め上げる。社内結婚で家庭を持ち、社宅に住み、残業後は会社の仲間としばしば飲みに行き、休日は会社の仲間とゴルフというのが、サラリーマンのステレオタイプであった。日本の会社とは、共同体的機能体であった。
「共同体的機能体」としての日本企業の強みと弱み
共同体的機能体である日本企業には、強みもあった。アドラー心理学で有名なアルフレッド・アドラーによると、「共同体感覚が発達している人は、自分の利益のためだけに行動するのではなく、自分の行動がより大きな共同体のためにもなるように行動する」という。その一方で、「共同体感覚が未熟な人は、自分の行動の結末や影響を予測することをやめて、自分の利益だけしか目に入らないようにする」という。
アドラーの言う「共同体感覚」とは、他者と深く結びついている感覚であり、そうした他者を「仲間」だと感じることある。共同体感覚を持っている人たちは、仲間に貢献することで貢献感を持ち、それを通じて自分にも価値があると思えるような人間関係を築くことができる。昭和時代の日本企業の会社員たちは、新入社員として入社した後、会社共同体の中で仲間を作り、共同体感覚を養っていった。
こうした日本企業の共同体性は「すり合わせ型」のモノづくり(自動車や産業機械、複写機、高機能化学品など)で強みとなった。また、サービス業の分野でも現場の緻密なオペレーションによって、極めて時間に正確な高速鉄道(新幹線など)や、日本型コンビニエンスストアなどの独自で優れたサービスを開発し、普及させてきた。
しかし、バブル経済崩壊後の90年代半ばから、日本企業から共同体性が徐々に失われていった。企業のリストラと非正規雇用の増加である。1990年に881万人だった非正規雇用者数は、2014年には1962万人と2倍以上になった。その結果、上場している大企業の多くは、機能体にも徹しきれず、共同体としての絆も崩れた「中途半端な共同体」と化してしまった。
こうした一連の変化により、会社の共同体性が徐々に崩れていき、「共同体感覚」を失った社員が増えてしまった。仲間との絆が薄れてしまった今の日本企業では、各々が自分の立場を守ることを第一に考えるようになる。こうして、上長の顔色や慣習に流されやすい社員が増えたと考えられる。
加えて、共同体の特徴である「内と外の二重規範」が、こうした不正の温床となった。内と外の二重規範とは、社内や特定の部門でしか通用しない規範が存在するということであり、それが時には社外の規範に抵触する場合もあることを意味する。例えば、「若手女性社員は、宴席では幹部にお酌をせねばならない」などである。神戸製鋼の不正もこれに当たる。同社では過去に納入して問題とならなかった不合格品の事例を「トクサイ(特別採用)範囲」と称するメモにして申し送りし、歴代担当が無断納入の判断基準に使っていた(神戸新聞10月19日)。一般的に「特別採用」とは、軽微な性能不足などがあった場合に、顧客に了解を得た上で引き取ってもらうことを指す。まさに内部と外部の規範がズレていた。
こうした二重規範に加え、上司やトップに対して対等に口を利きにくいことが「忖度」を生み、共同体感覚の薄れが保身による思考停止を促したのだろう。
「慣習・忖度型」のコンプライアンス違反を防ぐためには
キーワードは、「流動化」「標準化」「宗教化」である。上場している大企業であれば、この3つがセットで必要である。非上場の中小企業であれば、3つ目の「宗教化」だけで十分だ。なお、宗教イコール怪しいというイメージがあるが、ここで示す「宗教化」の狙いは共同体感覚の回復である。
■流動化
慣習による不正を防ぐには、人材の流動化が有効である。社内の異動のみならず、中途採用者を増やすなど人材を流動化させれば、前任者の不正など、おかしな点に気付きやすくなる。しかし、流動化にはデメリットもある。それは新たな職場や仕事に適応するまでの手間がかかる点である。日本では同じような仕事内容なのに会社や職場が変わるだけで、適応が難しくなる場合が少なくない。それは共同体性に基づく「ローカル・ルール」が存在しているからである。こうしたルールは企業単位のみならず、企業内でも事業単位、工場単位、職場単位で存在する。これが人材の流動性を妨げている。
日本企業にローカル・ルールが生まれやすい理由は、もうひとつある。それは、日本に特徴的な「組織の編成原理」である。日本では人々の社会的位置づけが「場」によって行われる傾向があり、場で作られた枠が集団の認識に大きく関っている。例えば会社や出身校である。アメリカ・西欧やインドでは、「資格」によって社会集団が構成される傾向にある。例えば、欧州の王室は欠員が生じた場合に民族や国家という場を超えてヨコ(他国の王室)とつながろうとする。しかし、日本は決してそれをしない。
こうした特徴ゆえに、工場や事業部などの「場」単位で組織がサイロ化しやすくなる。また、ヨコ(資格)の組織編成原理が弱いので、社員の採用も職種別ではなく、事務系・技術系のような大まかな分け方になってしまう。ゼネラリストを育成するほうが人材を流動させやすそうだが、いったんサイロにはまると脱出しにくくなる。各人の専門領域をある程度決めてキャリアを歩ませた方が人材を動かしやすいはずだ。
■標準化
流動化のコストを下げるために必要なのが、業務の標準化である。つまり、ローカル・ルールを極力減らすということである。日本企業は欧米企業に比べてローカル・ルールが多いと聞く。例えば、日本企業ではERPなどの業務ソフトを導入する際、欧米企業に比べて自社に合わせたカスタマイズ要求が多くなる傾向がある。しかし、あえてカスタマイズをせず、むしろ自社の「業務プロセス」や「ルール」を標準形に合わせていけば、外から来た人材がローカル・ルールに戸惑いにくくなる。
こうした標準化はERPだけではなく、経営幹部に対する経営大学院(MBA)教育の導入などもそのひとつである。MBAは各校でカリキュラムに特徴はあるものの、例えば会計のルールなどは各校で教える内容に違いはない。MBAホルダー同士であれば、経営の意思決定の際に意思疎通が容易になる。
■宗教化
業務の標準化を行い、人材の流動化を進めていくと、社員から「その会社で働くことの意味」を常に問われるようになってくる。そして、優秀な人材ほど、外に流出していく危険が高まる。こうした状況で必要なのが、その会社に対する合理性を超えた「思い入れ」や「熱狂」である。これを私は「宗教化」と呼んでいる。ただし、呪術的(まじない的)な部分を除いた、宗教化である。米国では大統領選挙でプロテスタントのメガ・チャーチ(大規模な伝道集会)と同じ手法を用いているが、企業内のイベントでもしばしばこうした手法を用いることがある。
日本企業も例外ではない。経営の神様と呼ばれた松下幸之助(松下電器・現パナソニック創業者)は天理教からヒントを得ている。会社はカネを払って従業員に働いてもらっているが、宗教はカネを払っていないにもかかわらず信者が自ら進んで活動する様を見て、理念経営の重要性に思い至ったという。現代では稲盛和夫氏(京セラ創業者)は仏教の僧侶としての顔も持っており、京セラは理念浸透に力を入れている企業として有名である。
このように、「宗教化」はカネをかけずに社員をひきつける力を持つ。これに加えて、倫理的な行動を促す役割も持つ。宗教では「聖典」やそれに書かれた「戒律」が、法律では裁けない道徳的・倫理的な規範を与えてくれるが、企業の行動指針もそれと同じ役割を持つ。社員たちが、宗教における倫理規範と同じように行動指針を信じて行動すれば、内発的に倫理的な行動が促される。そうすれば、内部統制のコストもかからない。つまり、宗教化とは機能体のメンバーに対して、アドラーの言う「共同体感覚」を養ってもらうことに他ならない。
では、こうした「宗教化」を行うためにはどうすればよいのだろうか。
「宗教化」のカギ
当たり前のようであるが、ヒントは世界宗教にある。例えば、行動指針やWAYには「助け合い」の要素を含むことが必須である。それも内部だけでなく、外部も含めて助け合うことが重要である。例えば、キリスト教は隣人愛、仏教は慈悲がそれに相当する。こうした規範は、仲間との協力を促すと共に、不正を抑止する働きを持つ。また、行動指針の数は多くしすぎない方がいい。キリスト教なら十戒、仏教なら五戒のように、重要な項目を絞り込む必要がある。
では、理念や行動指針、WAYを浸透させるにはどうすればよいのだろうか。そのカギを握るのは、リーダーの選抜と育成である。リーダーは社内に対する理念や行動指針のエバンジェリスト(伝道師)でなければならない。ゆえに、ハイ・パフォーマーが必ずしもリーダーにふさわしいのではなく、正しいあり方を実践し、それを説ける人をリーダーにする必要がある。そうしたリーダーは自動的には育たないので、早めに選んで内部で育成するしかない。早めに選ぶ理由は、リーダー候補人材の外部流出を止めるためである。そして、リーダー自らがリーダーを育てることを最重要課題として取り組む必要がある。
これを実践している企業がアメリカのGEである。GEではクロトンビルにある研修施設でリーダーに対してGEバリューを徹底的に伝えている。その熱の入れ方は半端ではない。CEOのジェフ・イメルトを含むGEのシニアリーダー達は執務時間の3分の1を人材教育に充てており、人材育成の投資額は年間10億ドル(約1,200億円)に上るという。GEの幹部候補生は、シックスシグマなどの経営手法やMBAの知識を学び、リーダー候補に選抜されたのちに、クロトンビルで「GEバリュー」の伝道師になるべく教育を受ける。
まとめ
最後に、3つの処方箋の中では「宗教化」が最も難しい。なぜなら、過去はその必要性に迫られてなかったからだ。昭和時代の日本企業は、社員を理念や行動規範で束ねなくても、自然と共同体的になってしまっていた。社員たちは会社に愛着を持ち、同僚や上司を仲間だと感じていた。会社を基盤とした共同体感覚を持っていたのだ。しかし、現在の日本企業はそうではない。
地道な方法だが、会社が内外に掲げる規範に対して義しい(ただしい)リーダーが、自らの時間を使って次のリーダーを育成するしかないのだ。
日本の警察と政府は、真剣に外国人、又は、在留許可を持つ、そして日本に帰化した外国人犯罪組織に対して大規模な対策を取らないと
収拾できない状態になると思う。日本語以外の同じ言語を使い外国に逃亡出来れば捕まえる事が困難な外国人を使っての犯罪は日本人の
犯罪組織よりも対応が難しい。
加速度的に広がるのを防止するために日本の警察と政府は形だけでなく、効果のある対策を取るべきだと思う。
中国出身の会社経営者を拉致し現金を脅し取ったとして、在日中国人で構成するグループが、大阪府警に摘発された。逮捕された主犯格の男は中国から帰化し、在日同胞のトラブル処理を生業(なりわい)にしていたという。捜査関係者によると、グループは暴力団には属していないが、粗暴な行為を繰り返す、いわゆる「半グレ」とみられる。こうした組織は他にも存在する可能性があり、捜査関係者は「在留外国人の経済活動の活発化に伴い、勢力がさらに拡大する恐れもある」と警戒を強める。
高級車で急襲
「女性が車で拉致されたようだ」。目撃者の男性からの通報が事件の端緒となった。
一昨年の12月末の夕方、大阪市城東区の駐車場。貿易会社を営む中国籍の40代女性が車を止めて降りたところを、6人組の男が急襲した。男らは乗ってきたトヨタ・クラウンの座席に女性を押し込め、さらにベンツ、BMWに分乗して走り去った。
男らは車内で女性の顔を殴ったうえ、「息子の命はないぞ」と脅迫。市内のコンビニまで連れて行き、店内のATM(現金自動預払機)で現金10万円を引き出させたうえで、女性を解放した。
男らはさっそくこの金で飲食し、滞在先の宿泊費などで使い切ったという。
トラブル処理屋
この事件で、ベンツに乗って犯行を主導したのが飲食店員の男(50)=逮捕監禁致傷罪などで起訴=だった。
捜査関係者によると、男は中国残留孤児の母親を持ち、平成19年に日本に帰化。元妻が経営する市内の串揚げ店を拠点に、在日中国人の若者を率いて、同胞の金銭トラブルの解決などを請け負っていた。
今回の事件は、被害女性と金銭トラブルになった在日中国人の会社経営の男性が28年9月に「女性から約1400万円を取り返してほしい」と男に依頼したのが発端。男は手付金など計約150万円で仕事に取りかかった。
男は、手下として使っている愛知県内の20~23歳の中国籍の男6人に招集をかけた。男らは大半が無職。主犯格の男は自らの過去の“武勇伝”を誇示し、服従を強いていたという。
依頼を受けた男は同年10月、手下に命じて女性宅の玄関扉に、ペンキで「金を返せ」と落書きさせた。
一方で自身は中国・上海まで行き、女性の両親に対して「金を払わなければ娘を廃人にしてやる」と脅したうえ、計約370万円を奪った。
男はこの現金を依頼者に一切渡さず、ベンツの購入費用に充てた。そして女性拉致事件の際、この車で現場に乗り付けていた。
大阪府警国際捜査課によると、男のグループは今回の事件以外にも、中国人ホステスが勤務する大阪・ミナミのスナックで物を壊すなどしていた。
同課は昨年8月に女性拉致事件で男を逮捕、同12月までに手下の中国人ら6人も摘発した。
捜査幹部は「グループと暴力団の関係は判然としないが、組織的に暴力行為を繰り返していた。在日中国人による半グレ集団とみられる」と語る。
外国人半グレ多数存在?
「半分グレている」の略語で、暴力団組織に属さない不良集団の「半グレ」。日本で外国人の経済活動が活発化する中、水面下で不良行為を重ねる中国人グループは他にもいるようだ。
たとえば、関東を拠点とする半グレ「怒羅権(ドラゴン)」。元暴力団関係者は「怒羅権は中国残留孤児の2、3世らで組織され、似た境遇同士の強いつながりと、警察当局に反発する凶悪さで知られていた」と話す。
大阪府警の捜査関係者は「ミナミの飲食店を牛耳る不良集団もいると聞くが、実態はつかめていない。同じようなグループの情報は多数あり、今回の事件は氷山の一角にすぎないだろう」とした。
経営者増加の裏側で…
中国人半グレ組織の存在は、日本国内で外国人の経済活動が活発になった裏面ともいえる。
法務省によると、国内で事業を起こす場合に取得する「経営・管理」の在留資格で日本に滞在していた外国人は2万1877人(28年末現在)に上り、前年度末から実に20%以上も増加した。国別では中国が1万1229人で最多で、2位は韓国の3039人だった。
こうした経営者の存在は国内需要の拡大や雇用促進といった好影響の反面、外国人経営者による事業所が不法滞在者の受け皿になるなどマイナス面もある。
大阪市西成区のあいりん地区では中国人の女性が接客する「カラオケ居酒屋」が近年急増。大阪府警は28年、留学の資格で入国しながら、カラオケ居酒屋で長時間働いていた中国人の女らを摘発している。捜査関係者は「人件費を安く抑えるため、不法滞在者を雇う業者もいる」と指摘した。
西成のカラオケ居酒屋をめぐっては、中国人女性経営者の会社設立登記を無資格で代行したとして、大阪入国管理局元次長の行政書士の男が1月24日、大阪府警に司法書士法違反(無資格業務)で逮捕される事件にも発展した。男は他にも複数の中国人の会社設立登記を行っていたとみられ、府警が実態解明を進めている。
約580億円分の損害は保険か何かでカバーされるのか?損失がカバーされないとなるとコインチェック(東京)の存続には影響しないのか?
約580億円相当の仮想通貨「NEM(ネム)」が流出した問題で、取引所大手コインチェックが加入するサイバー保険では、同社の被害の補償が受けられない可能性が高いことが31日、分かった。同社はネムの保有者26万人全員に日本円で計約463億円を補償する方針だが、資金の裏付けは不透明な状況となっている。保険で補償されなければ自己資金で賄う必要があり、返金方法や時期について同社の説明責任が改めて問われそうだ。
同社に保険を提供するのは東京海上日動火災保険。契約内容は非公表だが、コインチェックが過去に公表した内容では、保険の範囲は利用者がサイバー攻撃を受けて損失を受けた場合に限られており、補償額の上限は100万円。補償は昨年6月に開始される予定だったが、東京海上との契約はまだ完了していないとみられる。完了していたとしても、取引所がサイバー攻撃を受けた今回のようなケースは補償の対象外になる見通しだ。
サイバー保険は企業がサイバー攻撃を受けた際、事業が停止して本来得られたはずの利益の喪失や、復旧費用、損害賠償が生じた際の賠償費用などを補償する商品だが、今回のようなケースはあまり想定されていない。
取引所からの流出に備えた保険も存在するが、リスクが大きすぎるため「数十億円程度で上限を設けるのが一般的」(大手損保担当者)だ。今回のような大規模流出では、保険で全額が補償されることは難しそうだ。
改善がみられない場合、事業停止や施設閉鎖は仕方ないと思う。
千葉県は、市川市の認可外保育施設について、安全管理などを繰り返し指導したにもかかわらず、改善しなかったとして行政処分を行った。
千葉県によると、千葉県市川市にある認可外保育施設「あすなろベビーホーム」は、法律に定められている子どもの身長・体重測定などの発育チェックや健康診断などを行っていなかったという。
また、3年前の9月には、預かっていた2歳の子どもが夜中に建物の外に1人でいるところを通行人が発見し、警察が保護していた。この子どもは、2階にある、この保育施設の窓から転落していたとみられていて顔にかすり傷があった。
この施設を一人で運営している女性施設長は、この子どもが転落した当時、別室で食事をしていたという。
千葉県は、当時の利用者から相談を受け、立ち入り調査を行い、健康状態の把握をほぼしていないこと、施設の衛生状態の悪さや必要な帳簿が作られていないことなどについて指導したが、改善されなかったという。
千葉県は今後も指導を続け、改善がみられない場合は事業停止や施設閉鎖もありうるという。
仮想通貨取引所大手のコインチェック(東京)の自己責任によるマルチシグを使わない判断だから仕方がない。
約580億円分の損害は保険か何かでカバーされるのか?損失がカバーされないとなるとコインチェック(東京)の存続には影響しないのか?
「お金を返して」「早く情報を」。仮想通貨取引所の運営大手「コインチェック」が取引サービスを停止した26日、同社が入る東京都渋谷区のビルの前は、将来の取引を不安視する利用者らでごった返した。
コインチェックに100万円を預けたというプログラマーの男性(28)=世田谷区=は、取引が停止しているとの情報をインターネット上で見つけ、仕事帰りに立ち寄ったという。
仮想通貨をめぐっては、ビットコイン取引所のマウントゴックスで巨額のコイン消失事件が起きるなどした。男性は「こうした事態はある程度想定していた」とする一方で「まさか自分が巻き込まれるとは…」とうなだれた。
豊島区に住む金融業の女性(28)は約80万円を取引。普段からサーバーダウンなどのトラブルが多かったといい、「セキュリティーが弱いと感じていた」と振り返った。「預けていた全資産が引き出せなくなっている。お金を返してほしい」と表情をこわばらせていた。
仮想通貨取引所大手のコインチェック(東京)で顧客から預かっている約580億円分の仮想通貨が流出した問題で、同社が、採用を推奨されていたセキュリティー技術を導入していなかったことが27日、分かった。不正アクセス対策が不十分で、利用者保護が後手に回っていた格好だ。
金融庁は聞き取りなどを実施し、利用者保護が十分だったか調べる方針だ。
流出したのは、仮想通貨「NEM(ネム)」。この仮想通貨技術の普及を目指す国際団体は2016年、取引の際に複数の電子署名が必要で、より安全性が高い「マルチシグ」と呼ばれる技術を採用するよう推奨。コインチェックもこの呼び掛けを認識していたが、「他に優先すべきことがあった」(大塚雄介取締役)と、対応を後回しにしていた。
また、仮想通貨を扱う取引所では不正アクセス対策として、顧客の口座に当たる「ウォレット」をインターネットに接続していないコンピューターで管理するケースが多い。
しかし、コインチェックでは、常時ネットにつながっている状態で顧客のNEMを管理していた。和田晃一良社長は26日の記者会見で「(ネットに接続しない管理手法は)技術的に難しく、対応できる人材が不足していた」と釈明。システム開発に着手していたが、今回の問題発生に間に合わなかった。
マルチシグを使わず、ネットにもつなげておくずさんな管理実態に仮想通貨業界では「通常では考えられない」(関係者)と批判の声が上がっている。
仮想通貨取引所の運営大手コインチェック(東京都渋谷区)は26日、取り扱う仮想通貨の一種「NEM(ネム)」が日本円で約580億円相当、取引所から不正に外部へ送金されたと発表した。ハッキングの疑いもあるという。同社は仮想通貨の入金や出金、売買といった取引サービスを一時停止。仮想通貨が消失した理由を調べており、金融庁や警視庁に報告した。
不正による仮想通貨取引所の損失額は、約480億円だった平成26年のマウントゴックス(東京)を超え、最大規模となる。
コインチェックの和田晃一良(こういちろう)社長と大塚雄介取締役らは同日深夜に東京都内で記者会見。冒頭、和田氏は「皆さまをお騒がせしていることを深くおわび申し上げます」と陳謝した。不正送金された仮想通貨はすべて顧客分という。補償は「今後、検討する」との考えを示した。一方、現在停止している入出金などの取引の復旧時期は未定という。
コインチェックは不正送金を受けて26日正午過ぎ、インターネット上でネムの入金を一時停止すると公表した。その後、ネムの売買と出金に加えて、取り扱うすべての仮想通貨と日本円の出金を一時停止した。
仮想通貨取引所をめぐっては、テックビューロ(大阪市)が今月上旬、不正出金などにより仮想通貨の出金を一時停止。安定運営を求める声が強まりそうだ。
国内では昨年、改正資金決済法が施行され、現金と交換する取引所に登録制が導入された。コインチェックは関東財務局に登録を申請中で審査が続いていた。
下記の記事の内容が事実であれば、大手広告会社の電通は組織として変わっていないと言う事だと思う。
まあ、人や組織は変わったふりは出来るが、簡単には変われないと思う。特に、問題が長期にわたって、継続され、当然と思われていたのであれば
尚更変われないと思う。
記事が事実であれば平気で嘘を付く事も染み付いているようなので、問題はさらに厄介だと思う。
大手広告会社の電通(東京)が昨年春の採用試験で、学生にセクハラと受け取れる発言をしていた疑いがあることが25日、分かった。違法残業事件で過労死した新入社員、高橋まつりさん=当時(24)=の遺族代理人である川人博弁護士が明らかにした。電通側は「(そうした事実は)確認できていない」としている。
川人弁護士によると、電通は昨年春の採用面接で、入社を希望する女子学生に対し、複数の面接官が「高橋まつりさんが亡くなったことについてどう思うか」という趣旨の質問をした。この際、まつりさんの過労死について、「報道されている事実が必ずしも事実だとは思っていない」などと過重労働が原因ではないと受け取られかねない発言をしたという。
また、「君みたいな容姿がきれいな人がはきはき意見を言うのが気に入らない」「女を武器にしている」「スカートが短い」といったセクハラと受け取れる発言もあったという。
川人弁護士は、これらの発言をした役員ら一部の社員の名前や発言があった日時を特定。他にも同様の情報を把握しているとして調査を進めるとともに、電通に質問書を提出した。
電通は産経新聞の取材に、「面接官から、ご指摘のような発言があったという事実は、確認できておりません」と答えた。
自業自得!
神奈川新聞社(本社・横浜市)は23日付の同紙朝刊で、横須賀支社長の男性(59)を懲戒解雇処分にしたと明らかにした。女性のスカート内を盗撮した疑いで神奈川県警から任意で事情聴取を受けたという。
同社によると、前支社長は18日午前、出勤途中の電車内で女性のスカート内を盗撮したとして、県迷惑行為防止条例違反容疑で横須賀署から事情聴取を受けた。同社の調査に容疑を認めたといい、22日の臨時取締役会で処分を決めた。
同社の並木裕之社長は「報道機関である弊社幹部が盗撮容疑事件を起こしたことは誠に遺憾で、読者、県民におわび申し上げます」などとするコメントを出した。(鈴木孝英)
国立研究開発法人「新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)」のチェックも甘い!
スーパーコンピューター開発会社「ペジーコンピューティング」(東京都千代田区)を巡る国の助成金詐欺事件に絡み、同社が外注費を水増しする方法で助成金を含む約8億円の所得を隠し、法人税約2億円を脱税した疑いのあることが関係者の話でわかった。
東京地検特捜部と東京国税局は、同社が隠した所得の一部を関係会社が抱えていた自動車レース事業の損失補填(ほてん)に充てていたとみて法人税法違反容疑で捜査している。
ペジー社は、国立研究開発法人「新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)」が2012~13年度に実施した二つの助成事業で、事業費を水増しした実績報告書をNEDOに提出し、計約11億3300万円の助成金を受給。助成金は「雑収入」による所得として税務申告するが、関係者によると、同社は、電子部品を開発する関係会社「ウルトラメモリ」(八王子市)などへの外注費を約8億円水増しして支払い、ペジー社の所得を圧縮していたという。
ウルトラ社は06年の設立時、「EMSマネージメント」の社名で全日本F3選手権などに参戦。ペジー社の代表取締役・斉藤元章被告(50)(詐欺罪で起訴)はEMS社に多額の資金を貸し付けており、参戦するレースや購入するレーシングカーなどを事実上決めていたという。
問題のきっかけはかなり昔であるが、それが植物が成長するように徐々に大きくなり、最近になって、環境の変化と重なって形にとして現れただけであろう。
物事には、短期、中期、そして長期の目標の違いでやり方が違ってくるケースがある。短期的なメリットを優先して、長期的に見ればデメリットになる ケースもある。今の現状を見て判断するのか、将来に判断するのかで、正しいから間違いになる場合もある。
今の日本を見ていると、個人的には利益の先食いのように思えるケースも多くある。多くの日本人は同じように感じているのか、違う感じ方なのか、 それともほとんど考えていないのだろうか?
自己責任と言うのであれば、ほとんど考えていない人達が悲惨な現状から逃げられなくなった時には、自業自得で苦しむのも仕方がないとなるのだろうか??
日本の製造業界に対する信頼が今、急速に揺らぎ始めている。
昨年末、日産自動車では無資格の従業員が車両の完成検査をしていたことが国交省の抜き打ち検査で発覚し、神戸製鋼所ではアルミ・銅製品などの強度に関するデータを改ざんしていたことが明らかになったというニュースは記憶に新しい。東芝が衰退した一因にも、過去の不正会計という不祥事が絡まる。
「メイド・イン・ジャパン」の代名詞にもなるような企業で相次いだ昨年の不祥事は、日本国内はもとより、海外の消費者や投資家に「日本ブランドの異変」を確信させてしてしまった。というのも、海外ではこうした日本の製造企業における経営管理体制を問題視する声が、今回よりも数年も前から強く上がっていたのだ。
そのきっかけになったのは、タカタのエアバッグだ。車両衝突時に作動したエアバッグから金属片が飛び散り、乗員を死傷させるというニュースは、世界中に大きな衝撃を与えた。
日本でも一連の流れは報じられてきたものの、その扱いは他国に比べると小さく、実際に筆者が日本の工場マンと話していても、この問題が世界にもたらした影響は、日本国内にいまいち伝わりきれていないという印象を受ける。
が、とりわけここ自動車大国アメリカでは、リコール対象を高温多湿地域に限定した当初のタカタの頑なな態度に批判が噴出。死者18人のうち、13人がアメリカ人だったことから、「本来、人命を助けるはずのものである安全装置が、逆に危険装置として乗員の前に常時取り付けられている」と、連日ニュースでも大きく取り上げられ、その度に「メイド・イン・ジャパン」という言葉が“経済”ではなく、“事故”に関連するワードとして多く聞かれるようになった。
タカタにも独自の見解や言い分があったとはいえ、安全装置を売っているはずの企業が、自ら「安全の線引き」をしてしまったのは、やはり対応としてはまずかったといえる。結局アメリカのリコール対象車は、同国史上最多の4,200万台におよび、タカタは今年6月、経営破綻した。
こうした流れからの、昨年の一連の不祥事。「What’s wrong with Japan Inc?(どうした日本企業)」といった、日本の製造に携わる人間にとっては、屈辱以外のなにものでもない見出しで、各企業の問題を紹介しているメディアもある。
とはいえ、タカタは本来、エアバッグの世界シェア2位の超優良企業だった。タカタだけではない。現在、不祥事や経営不振の渦中にあるその他の日本企業も、世界が認めた有名企業ばかりだ。
では、どうして日本の大手製造企業はここまで急激に弱体化していったのか。その要因は、主に二つあると考える。
1:過去にすがる体質
最も大きな要因の1つは、「過去の栄光にすがる日本企業の体質」にある。
現在「メイド・イン・ジャパン」で連想される「高品質」というイメージは、過去に生み出された技術による功績であるところが大きい。
それがこの10年、団塊世代の退職や、リーマンショックによる景気低迷、働き方や安全性に対する世相の変化などで、ヒト、企業、経済の構図が激変し、企業はその度に対応を迫られてきた。
しかし、古い体制にある日本企業は、「先送り」や「検討」、「茶濁し」でその場を凌いできたため、結果的に世間の抱く「ブランドイメージ」がひとり歩きし、「現場の現実」とのギャップが生じてしまったのだ。日本企業はもはや「企業ブランド」に依存できない状況にある。
だからといって、こうした日本の製造企業が、大胆な新規事業開発に積極的なのかといえば、そうでもない。
「我々には古くから守ってきた従来品がある」、「リスクを追ってまで行動する必要なし」と、先々を計算して腕組みし、なかなか動こうとしない。
が、そんな企業を尻目に、世間のニーズは目まぐるしく変わり続け、近年は「完璧な従来品」よりも、「若干の改善の余地ありでも新しいもの」がもてはやされるようになってきた。
ちなみに敢えて加筆するが、その世間のニーズには、“改善の余地のある従来品”という選択肢は、無論皆無である。
一方、こういった世間のニーズに敏感に反応した諸外国は、ベンチャー企業への最大限のサポートを約束することで世界中から多くの技術を呼び寄せ、官民一体となって成長し続けている。その国の筆頭が、中国だ。今や中国は、「作る国」から「作らせる国」に移行しつつある。
◆機密情報の扱い方が甘いのも問題
2:情報管理体制
日本の大手製造企業が弱体化したもう1つの要因は、過去の工場シリーズでも度々言及している「情報の扱い方」にある。
2014年度に製造業界で発生した情報漏えい事件の被害総額は、分かっているだけでも1,000億円以上に及ぶ。
中でも最も避けたい海外への流出においては、目先ばかりを見た結果、工場を人件費の安い海外へ移転させ、現地採用の従業員に長年培ってきた企業の技術やノウハウを指導したことで、それら「社宝」をその国全体に拡散させてしまったケースが少なくない。
こうしてカネと技術を得た“やる気満々の諸外国”が、その後どう動くかは、火を見るよりも明らかである。前出の「ベンチャーに協力的な国」が、「かつて日本が工場を移転させた国」と面白いほどに一致することは、察するに難くないところだ。
その一方、「上から下」への情報共有においては、業務に支障が出るほど厳しく、下請けはたとえその指示の目的やゴールが分からなくとも、元請けに従うしかない。
とりわけ、3万点のパーツによって1つの商品を産み出す自動車製造現場は、見事なまでのトップダウン型だが、こうした体制は、日本の技術力やブランド力を構築しやすい反面、130万人もの自動車製造従事者が1つのピラミッドに収まる現場では、「情報が下りてこない」「上に物申せない」が常態化し、結果、昨年のような「上の不祥事」を引き起こす環境に陥りやすいのだ。
筆者が訪問するアメリカ国内の各オフィスには、韓国製やアメリカ製のパソコンばかりが並べられ、家電量販店のテレビ売り場でも、韓国製、台湾製が広くスペースを占領する。
マンハッタンのまっすぐ伸びた道路を走るクルマには、日本ではあまり見ないようなメーカーのものも多い。
日本にいると、「メイド・イン・ジャパン」を選ぶことに特別大きな理由は考えないが、海外では、こうした「消費者に与えられた選択肢の幅広さ」や「日本びいきのない競争社会」、そして、その中で消費者がどうして「メイド・イン・ジャパン」を選んだのかを深く考えさせられる。
「What’s wrong with Japan Inc?」という言葉は、海外が日本企業に張った「別れに向けた最初の伏線」のように響く。「日本のモノづくりはまだ大丈夫だ」と国内で傷をなめ合う余裕は、もはやないと思った方がいい。
過去の栄光からの脱却と、未来を見据えた挑戦。「改善待ったなし」の状況で、引き続き「先延ばし」や「腕組み」で対応すれば、近い将来、メイド・イン・ジャパンは誇れなくなる。
【橋本愛喜】
フリーライター。大学卒業間際に父親の経営する零細町工場へ入社。大型自動車免許を取得し、トラックで200社以上のモノづくりの現場へ足を運ぶ。その傍ら日本語教育やセミナーを通じて、60か国3,500人以上の外国人駐在員や留学生と交流を持つ。ニューヨーク在住。
ただ、再試験が学内規定に違反しているので、発覚すれば問題になるとの認識はあったのだろうか?
違反は違反なので、処分されても文句は言えない。
処分を覚悟で規定に違反して再試験を行ったのであれば、この教授は優しい人であったのであろう。ただ、違反が 発覚した以上、処分する側が処分を決定すれば従うしかない。規定と処分の基準が存在すれば、文句は言えない。 温情をかけることは出来る。ただ、その判断は権限を持つ人間や組織次第。
卒業が懸かった試験に合格できなかった学生に対し、学内規定に違反して再試験を受けさせて単位を取得させようとしたとして、東北芸術工科大(山形市)から停職8カ月の懲戒処分を受けた60代男性教授が16日までに、処分の無効確認と停職中の給与など約778万円の支払いを求める訴えを山形地裁に起こした。
教授側提出の準備書面などによると、教授は2017年1月、担当科目でノート持ち込み可の試験を実施したが、友人に貸したノートが返却されなかったため合格できなかったとする美術科4年の男子学生から再試験の依頼を受けた。学生は既に就職先が決まっていたが、この試験に落第すれば卒業できない状態だったという。
教授は同2月、学生のために再試験を実施。大学側には採点を間違えたとして、単位を認める成績変更を申請した。大学は同3月末、特定の学生に再試験をしたことなどが規定に反するとして、教授を停職8カ月の懲戒処分とした。
教授側は「処分には合理性と相当性がない」と主張。同大の担当者は「事実関係を確認し、適切に対応していく」と話した。
破産手続き中の旅行会社「てるみくらぶ」(東京都渋谷区)の社長山田千賀子被告(67)(詐欺罪などで起訴)の自宅から、警視庁が現金約700万円を押収していたことが捜査関係者への取材でわかった。
破産管財人に申告していない金で、同庁は、隠し資産の疑いがあるとして、破産法違反(詐欺破産)容疑で捜査している。同庁は、山田被告らを融資金の詐欺容疑で再逮捕した後、資産隠しの捜査を本格化させる。
同社は昨年3月27日、東京地裁に破産申請し、破産手続きの開始決定を受けた。翌4月には、山田被告個人も破産手続きの開始決定を受け、破産管財人が現金と預金計数百万円を回収した。
同社の負債は、旅行代金など約151億円に上るとみられているが、昨年11月時点の資産は総額で約1億8800万円とされていた。
破産法は、破産者の財産は裁判所が選任した破産管財人が管理すると規定しているが、山田被告は自宅で発見された約700万円について、破産管財人に申告していなかった。同庁は、没収されないよう、現金を隠匿していたとみている。
全てはJR東日本に問題があったと言う事か?
立ち客210人を含む約430人の客を乗せた普通電車は駅を発車してわずか2分後、約300メートル進んでストップした。JR信越線が立ち往生したトラブルは、乗客が約15時間半も車内に閉じ込められる異例の事態に。JR東日本や行政は一体何をしていたのか。
JR東日本新潟支社によると、管内には積雪の運行停止基準やマニュアルはなかった。問題の電車は11日午後7時前、無人駅の東光寺駅(新潟県三条市)を出発。降雪でダイヤが乱れ運休が続出したため乗客が集中し、“運転強行”に判断が傾いた可能性がある。
現場付近では日中の除雪は実施されておらず、1本前の電車は約2時間前に通過。電車は雪をかき分け進んだが、2分ほどで運転席の窓近くまで雪がたまり停車した。同支社は人海戦術での除雪を決め、近隣にいた社員らを現地に派遣したが、除雪は難航。最終的に除雪車で線路を開通させることにした。
除雪車は上り線を逆方向から進み、除雪を終えたのは12日午前10時半前。「除雪車の出動はダイヤの調整が必要で時間がかかる。雪が固く、除雪も進まなかった」(同支社)。現場にバスを向かわせることも検討したが、バス会社から「雪で近づけそうにない」と難色を示され、タクシーなどで乗客全員を運ぶには時間がかかるため断念したという。
東光寺駅側にバックするという選択はなかったのか。踏切の警報トラブルや後続車と衝突する危険性もあり、同支社は「後方に戻るという認識はなかった」とする。ただ、鉄道技術に詳しい工学院大の曽根悟特任教授(78)は、電車を後進させて主要駅まで引き返すべきだったと指摘。「警備要員の派遣など安全確認に数時間かかったとしても、乗客の苦痛を少しでも早く取り除くことができた」との見方を示す。
乗客への対応も後手に回った。見附駅に乾パンなどが届いたのは、12日午前2時22分。乗客にペットボトルの水が渡されたのは同2時43分だった。
一方、県や市は大雪への警戒態勢をとるなどしていたが、トラブルに自ら動こうとはしなかった。県の担当者は、避難所の開設など具体的な要請があれば対応できたが、「依頼がなく動きようがなかった」と説明。自衛隊への災害派遣要請は検討対象にもならなかったという。
帰宅するため後続の電車に乗った自民党県議は、「最初から電車を止めるという判断があってもよかったのではないか」と疑問を呈し、「米山隆一県知事の対応をただす人が出てくるかもしれない」と話した。
「今回の問題で、異常を受けて乗り込んだ車両保守担当者と、東京にいる指令員が運転停止の判断を互いに相手任せにしていた点が厳しく批判されている。」
は推測であるが、嘘の言い訳で、実際は「遅延に対する恐れはある」が主な原因と思う。
効率と突き詰めると、生産性は上がり、利益は増える。しかし、ゆとりがなるなるので想定外の問題や問題が起きた時の対応を想定していない場合、
大きな問題になる、又は、大きな影響が出る可能性がある。経営者や幹部達がリスクを認識したうえで、効率の向上を考えないと問題が起きる。
同じ事は人や従業員にも言える。効率と利益のアップのために従業員や下請けを減らした場合、緊急の事態が発生した場合、現状の人員で対応できれば
良いが、出来ない場合は、人材はどこからも調達できないので十分な対応が出来ない事となる。
最悪の場合は我慢できる、又は、仕方がないとあきらめる事が出来るのであれば問題ないが、そうでない場合は、違う方法で利益アップを考える
必要があると思う。
時間が制限されると、担当に対するストレスやプレッシャーを感じた環境による間違いのリスクがアップするので、給料を上げるよりは人員にゆとりを
持たす方が良いと個人的には思う。まあ、安倍首相の給料アップには無理があると個人的には思うので、似たような原因の問題は今後も起こると思う。
最終的に、事故のレベルは運次第。
◇11日で発見から1カ月 「5分の遅れ、取り戻せず…」
東海道・山陽新幹線「のぞみ」の台車に亀裂が生じたまま運転が続けられた問題で、JR西日本の現役社員が毎日新聞の取材に応じ、「運行時間や車両数に余裕が少ないことが背景にある」と証言した。11日で亀裂発見から1カ月。JR西は再発防止策を進めるが、亀裂の原因解明や異常を見過ごした体質の改善など課題は多い。
【写真】台車枠の側面に入った亀裂
新幹線の本数が多く遅れが出やすい時間帯は、標準の所要時間に「余裕時分」を上乗せしてダイヤを組む。JR東海によると、のぞみは東京-新大阪(552キロ)を最速2時間22分で走るが、昼間は10分程度の余裕を持たせている。
一方、JR西が管轄する新大阪-博多(644キロ)は最速2時間21分。現役社員は「余裕時分は数分程度だけ。ぎりぎりでやっている」と話す。乗客106人が犠牲になった福知山線脱線事故(2005年)でも、スピードアップのため余裕時分をゼロにしていたことが問題になった。
新大阪以西は高架やトンネルが多くスピードが出せるため、余裕時分を短くしているとみられる。だが、社員は「5分でも遅れていたら取り戻せない。遅れを東海に引き継ぐのには心理的な負担がある」と説明する。
車両数も大きな差がある。東海道と山陽にまたがって運行する列車は、新幹線を中心に運賃収入を稼ぐJR東海は133編成あるが、在来線の割合も高いJR西は40編成のみ。異常があった時の代替車両のやりくりに影響しやすい。社員は「対応の柔軟性に欠け、ダイヤの乱れが東海に比べて多い」と指摘する。
今回の問題で、異常を受けて乗り込んだ車両保守担当者と、東京にいる指令員が運転停止の判断を互いに相手任せにしていた点が厳しく批判されている。
JR西は問題を受けて4回の記者会見を開き、運転を続けた要因について「遅延に対する恐れはある」と、現場社員にかかる定時運行のプレッシャーを認め、異常なしと確認できない場合は、ためらわず停止させる方針を打ち出した。だが、来島達夫社長は会見で「止めるのは勇気がいる」とも述べ、ダイヤ優先主義からの脱却が容易でないことも浮き彫りになった。
同社の再発防止策は「異常時は現場判断を最優先する価値観の徹底」など抽象的なものから、台車の異常を検知する設備の設置などハード対策まで計15項目。車内の異音などが複合する場合の対処ルール策定など6項目は既に実施したという。
亀裂の原因調査は国の運輸安全委員会や鉄道総合技術研究所が続けており、結果次第でさらに対策が迫られる。亀裂は金属疲労で生じたとみられるが、検査で見逃していた場合、手法や周期の見直しが早急に必要になる。【根本毅】
◇東海道・山陽新幹線「のぞみ」の亀裂問題
2017年12月11日、博多発東京行き「のぞみ34号」で、JR西日本の車掌らが30件の異音や異臭を確認したが、名古屋駅で点検するまで3時間以上運転を続けた。断面が「ロ」の字形の台車枠(鋼鉄製)は底面から両側面にかけて計約44センチの亀裂が生じ、上部約3センチしか残っていなかった。国の運輸安全委員会が新幹線初の重大インシデントと認定し、JR西の対応なども調査している。
これが事実なら部分的に会社ぐるみなのか?検査に必要な試薬を入手出来なくなる事が分かった時点で、会社として対応するべきだと思う。 少なくとも担当検査員以外にも問題をしっていた人間はいるのではないのか?担当者以外、誰も知らなかったのであれば、ガラス最大手の旭硝子は10日、子会社「AGCテクノグラス」 は旭硝子グループであっても、まったく体質の違うとても小さい会社なのであろう。
ガラス最大手の旭硝子は10日、子会社「AGCテクノグラス」(静岡県吉田町)が、製品の試験管について、顧客と取り決めた一部の検査を実施せずに、約80の大学や研究機関に出荷していたと発表した。
不正の全容を解明するため、弁護士を交えた実態調査を行う。
発表によると、問題となったのは、遠心分離器で物質を分離するのに使う実験器具「遠沈管」。AGCテクノグラスは2015年2月から17年12月まで、遠沈管にDNAを分解する酵素が混ざっていないかを調べる検査を実施しないまま、品質保証書を不正に付けて出荷していた。検査に必要な試薬を入手できなくなったことが理由だとしている。
普段担当している検査員が不在だった17年12月上旬に、別の検査員が不正を見つけた。同12月20日に製品の出荷を停止し、22日に顧客への説明を始めたという。
今回の人為ミス(ヒューマンエラー)に関して故意でなく、悪質性もないかもしれないが、JR西日本と呼ばれる組織及び指令長と指令員に問題があったと思う。組織が本当に変わろうとしなければ 違う形で再度、問題は起きるだろう。運が良ければ、長い間、問題は起きないかもしれない。
博多発東京行き新幹線「のぞみ34号」の台車に亀裂が入ったまま走行を続けた問題を受け、JR西日本の来島達夫社長は5日午後、会見し、来島社長の月額報酬を3カ月、5割返上するなど役員ら計12人の社内処分を発表した。また、吉江則彦副社長鉄道本部長が降格し、後任に緒方文人総合企画本部長が昇格するなど計6人の人事異動も併せて発表した。人事異動は5日付。
当該の乗務員らについては人為ミス(ヒューマンエラー)を非懲戒とする原則に照らし、来島社長は「故意でなく、悪質性もないので、懲戒処分としない」と述べた。
また来島社長は、学識者らから同社の検証内容に対する評価や提言を求めるため、安部誠治関西大教授を座長とする「新幹線重大インシデントに係る有識者会議」を8日に設置する考えを示した。
亀裂は、11日午後に博多駅を発車した「のぞみ」の台車枠の上部約3センチまで入っており、破断寸前だった。新大阪駅でJR東海に運行を引き継ぐまでの約3時間、乗務員らが異音や振動など30件の異常に気付きながら運行を継続した。
社内調査で、保守担当社員から「新大阪駅で床下(点検)をしようか」との提案があったが、指令員が聞き逃すなどしていた事実が判明。来島社長は昨年12月27日の会見で「(乗務員ら)個々人よりも、経営側としての責任を役員の処分も含めて検討していきたい」と言及していた。
指令長と指令員の対応が疑わしい。JRはとても大きな組織である。重要なコミュニケーションで間違いや聞き洩らす事が発生しない教育や対応が取られていると推測する。
例えば、アメリカの軍隊では、指示を繰り返すことによって相手が指示に誤りや誤解がないか確認できる。受話器から耳を離した時、受話器を耳から話した事を伝え、再度、繰り返す事をお願いするべきだと思う。 指令員がそのような対応をしなかったら、するように指令長は指示、又は、指摘するべきである。
JR西では伝達の間違いや勘違いを予防する対応や考え方が欠けているのか、指令長と指令員に問題があると思える。
博多発東京行きのぞみ34号の台車で亀裂が見つかり、運輸安全委員会が新幹線で初の重大インシデントと認定した問題で、JR西日本は27日、車両保守担当社員が新大阪駅で停車後に床下点検するよう要請したが、運行を管理する東京指令所の指令員が別の応対中だったため聞き逃していたと明らかにした。保守担当者と指令員の双方が確認を怠り、異常が放置されていた状況が浮き彫りになった。
今回のケースでは、乗務員が車両の異常を認識しながら約3時間にわたって運転を続けたことが問題視されている。JR西は、当時乗車していた運転士1人と車掌4人、車内販売員3人、岡山駅から乗り込んだ車両保守担当社員3人と、東京指令所の指令員3人の計13人に聞き取り調査を実施し、経緯を調べていた。
JR西によると、保守担当社員は岡山-新神戸間で指令員に対し「新大阪(駅)で床下(点検)をやろうか」と申し出たが、指令員は隣にいた指令長の問い合わせに応じるため、受話器から耳を離していた。保守担当は要請が受け入れられたと思い込み、「どこで点検するか調整している」と認識していたという。
その後、指令員は新神戸-新大阪間で別の保守担当に「走行に支障があるのか」と尋ね、「走行に異常がないとは言い切れない」と返答されたが、「保守担当者は車両の専門家なので、点検が必要ならはっきりと言ってくる」と思い、対応しなかったという。
また、乗務員らは走行中に異音や異臭などの異常を計30回確認。台車に亀裂が見つかった13号車で不自然な振動を感じていた乗務員がいたことも判明した。
記者会見した来島達夫・JR西社長は「リスク管理が不十分だった。新幹線の安全に対する信頼を大きく損ね、深くおわび申し上げます」と謝罪した。
のぞみ34号は11日午後1時33分に博多駅を出発。途中、乗務員らが異音などに気づき、もやが車内にかかるなど異常が相次いだため、名古屋駅で運転を取りやめた。台車枠に見つかった亀裂は底面に16センチ、両側面に約14センチに及び、破断寸前だった。
博多発東京行き新幹線「のぞみ34号」の台車に亀裂が見つかった問題で、JR西日本の来島達夫社長ら役員3人が27日、大阪市北区のJR西本社で会見した。異常に気付きながら運行を続けた経緯について調査結果を公表し、関わった担当者らに「認識のズレがあった」とした。
【写真】新幹線の台車枠に入った亀裂
JR西の聞き取りによると、岡山駅で添乗した保守担当社員は、異音を感知して「床下を点検したいんだけど」と東京の指令員に連絡。指令員が走行への影響を確認したところ「そこまではいかないと思う、見ていないので現象が分からない」と答えた。
このやり取りを通じ、指令員は「床下点検の必要性はない」と捉え、一方で保守担当社員は「点検実施の要請が伝わった」と考えたという。
問題の新幹線は、今月11日午後に博多駅を出発。途中、焦げたような臭いやうなり音が確認されながら、結果的に3時間以上走行を続け、新大阪駅で引き継いだJR東海が名古屋駅で運行を取りやめた。
この担当者はさらに「安全をとって新大阪で床下をやろうか」と提案したが、指令員は隣に座る指令長から報告を求められ、耳から受話器を離したことで聞き逃していた。 」
「耳から受話器を離したことで聞き逃していた。 」の点だがこれが事実なのか凄く疑問。指令員の嘘である可能性はあるが、指令長も関与している可能性も ある。ここに関してはしっかりと事実確認するべきだと思う。ただ、指令員が事実を言うかは????
JR西日本の来島社長「今後はためらいなく列車を止める」
「新大阪で床下(点検)をやろうか」--。車両保守担当者の提案は指令員の耳に届かなかった。異常を抱えたまま3時間以上運行を続けた東海道・山陽新幹線「のぞみ」(16両編成)で何があったのか。27日記者会見したJR西日本の来島達夫社長は「今後はためらいなく列車を止める」と言い切ったが、公表された調査結果からは、乗客約1000人の命を預かりながら、コミュニケーションを欠いて走り続けた危うい体質が浮かんだ。
11日午後1時35分。異常事態は博多を出発した直後に始まっていた。台車の亀裂が判明する13号車デッキで「甲高い音」を聞いたのは客室乗務員(25)。だが、確認しにいった車掌長(56)は異常なしと判断する。小倉駅を出た同50分ごろから、7、8号車付近で車内販売員らが次々と「鉄を焼いたような臭い」などに気付く。同様の臭いは11号車でも確認された。
広島駅到着前の午後2時半ごろ、報告を受けた指令員は保守担当者を乗せるよう指示。担当者3人の乗車は3駅先の岡山駅だったが、異変は広がっていた。福山-岡山駅間の15分間には13号車の乗客3人が臭いに加え「もやがかかっている」と申告。臭いは4、10号車にも及んでいた。
保守担当者3人はそんな状況の中、乗り込んだ。13号車で「ビリビリ伝わる」振動や異音を感じ取り、「床下を点検したい」と打診。「走行に支障があるのか」。指令員(34)が問うと、保守担当者の一人(60)は「そこまでいかない。見ていないので現象が分からない」。曖昧とも取れる返事だが、指令員は支障なしと受け取った。
この担当者はさらに「安全をとって新大阪で床下をやろうか」と提案したが、指令員は隣に座る指令長から報告を求められ、耳から受話器を離したことで聞き逃していた。
指令員が点検実施を調整してくれている--。保守担当者は専門家なので危険なら伝えてくる--。互いに思い込みを抱えたまま判断を人任せにし、のぞみは名古屋駅まで走り続けた。
会見は約3時間に及んだ。乗客106人が犠牲になった2005年の福知山線脱線事故後、JR西は安全憲章として「判断に迷ったときは、最も安全と認められる行動をとらなければならない」と定めており、「守れなかった」との指摘が再三飛んだ。来島社長は「現場の切迫したリアルな情報を正しく伝えきれなかった。足りなかったことを率直に受け止める。安全憲章を呼びかけるだけでなく、各職場で具体的な行動につなげたい」と答えるのが精いっぱいだった。【千脇康平、宇都宮裕一、根本毅】
スーパーコンピューター開発会社「ペジーコンピューティング」(東京都千代田区)を巡る国の助成金不正受給事件で、詐欺容疑で逮捕された同社代表取締役・斉藤元章容疑者(49)。
ペジー社や関連会社には、国から約100億円の資金が注ぎ込まれることになっていた。
NEDOは、逮捕容疑となった事業など5事業で計約39億5070万円以上の助成金の交付を決定。これまでに少なくとも計約16億6070万円を交付した。文部科学省所管の国立研究開発法人「科学技術振興機構」(JST)も今年1月、斉藤容疑者が会長を務める別のスパコン開発会社「エクサスケーラー」(千代田区)に60億円の無利子融資を決め、約52億円を提供した。
JSTによると、この融資はスパコン開発に成功すれば全額を返済する必要があるが、失敗すれば1割の返済で済むという。JSTは16年10月の公募時に融資額の上限を原則50億円としたが、大学教授らによる評価委員会が10億円の上乗せを決めた。
スーパーコンピューター開発会社「ペジーコンピューティング」(東京都千代田区)を巡る国の助成金不正受給事件で、詐欺容疑で逮捕された同社代表取締役・斉藤元章容疑者(49)らが、東京地検特捜部の調べに対し、別の助成事業でも不正を認める供述をしていることが関係者の話でわかった。
斉藤容疑者側には、国から総額約100億円に上る助成金や融資が認められており、特捜部は不正受給の全容解明を進めている。
斉藤容疑者と同社元事業開発部長・鈴木大介容疑者(47)は2014年2~3月、経済産業省所管の国立研究開発法人「新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)」が2013年度に実施した新興企業向けの助成事業「メモリデバイスの実用化開発」で、事業費を約7億7300万円とする虚偽の実績報告書をNEDOに提出。助成額約5億円から先払い分を除いた約4億3100万円をだまし取ったとして、今月5日に逮捕された。
企業のDNAとして多くの人々の価値観や考え方に定着している。多くの人々がおかしいと思わないほど、当然のように普通の価値観や考え方に なっていると推測する。
おかしいと思う人達は外に追いやられるか、企業を去ると思う。似たような問題は多くの企業で存在するから、会社を変わっても似たような 問題に直面するかもしれない。給料とか、待遇を妥協すれば、比較的に良い体質の企業を見るける事は出来るであろう。
神戸製鋼所のアルミ・銅製品など品質データ改ざん問題は、現職の執行役員3人が不正を認識していたことがわかり、新たな局面に入った。3人は不正の事実を知りながら、取締役らに報告しておらず、同社の隠蔽(いんぺい)体質は工場などの現場だけでなく、役員レベルにも広がっている実態が浮き彫りになった。データ改ざんが組織ぐるみで行われていたのは明らかで、今後の外部調査委員会の調べでさらに不正が拡大する可能性がある。
3人の執行役員が不正を認識していたことが明らかとなり、21日の記者会見では「一連の不正は組織ぐるみだったのではないか」などの質問が相次いだ。梅原尚人副社長は「3人の執行役員が直接、不正に関与していたとか、指示していたという報告は外部調査委から受けていない」と弁明したが、「すべての調査が完了したわけではない。その他(の役員や社員)については今後、調査が進んでいくだろう」とも述べ、外部調査委の最終報告を待つ考えを明らかにした。
外部調査委は3人を監督する立場の取締役や配下の社員がどのように不正にかかわったのか調査を進めている。今後の調査の進展しだいでは、執行役員だけでなく、取締役ら経営陣も不正を認識していたことが判明する可能性もある。
3人の執行役員は不正の事実を知りながら、取締役会など経営陣に報告しておらず、同社の隠蔽体質が改めて問われる結果となった。梅原副社長も「こういう情報がなぜ執行役員から上がってこなかったのか。ガバナンス(企業統治)上、大きな問題だ」と認めざるを得なかった。
神戸製鋼は年内に予定していた外部調査委の最終報告が来年2月末にずれこむことも明らかにした。執行役員が不正を知りながら報告しないなど、不正の解明は道半ばで、外部調査委が「さらに徹底した調査が必要」と判断したためだ。梅原副社長は「現時点では新たな問題が起きているという報告は外部調査委から受けていない」と説明したが、社内の内部通報窓口には複数の案件が寄せられ、外部調査委が調査を進めている。神戸製鋼の闇は深く、実態解明にはなお時間がかかりそうだ。【川口雅浩】
◇ことば【神戸製鋼所のデータ不正】
新日鉄住金、JFEスチールに次ぐ国内鉄鋼3位の神戸製鋼所が、自動車や航空機などに使うアルミなどの製品を取引先に納入する際、顧客から仕様書で求められている品質に足りていないのに、満たしているように品質データを改ざんするなどしていた。2016年6月にグループ会社で、ばね用ステンレス鋼線の試験データ改ざんが発覚し、全社的な自主点検を進める中で今年8月、アルミや銅製品でも改ざんがあると経営陣が把握し、10月に公表した。不正はその後、鉄鋼など他製品にも拡大。これまでに納入先延べ525社中、500社で一定の安全性確認作業を終えている。
神戸製鋼所は21日、製品検査データ改ざん問題で、アルミ・銅事業部門の執行役員3人が不正行為の一部を認識していたことを明らかにした。
【表】「原因は組織風土」。神鋼が11月にまとめた報告書骨子
同日付で3人の担当業務を外し、同事業部門長付とした。外部調査委員会による調査は年内の完了を断念し、点検作業の徹底のため2018年2月末ごろにずれ込む見通し。
スバルのデザインは良いと思うので後は性能と品質の向上だろう。トヨタがついているのなら可能なのでは?
SUBARU(スバル)は20日、燃費検査でデータ変更がなかったか調査を始めると発表した。社員の一部から指摘が出たため。同社では10月、新車の性能を最終チェックする完成検査業務を無資格者が行う不正行為が判明。燃費検査でも不正が裏付けられれば、スバルの信頼をさらに揺るがすことになる。
燃費データの変更に関しては、無資格者による検査問題の調査を依頼した弁護士事務所が社内のヒアリングを行った過程で、一部の社員から指摘が出たという。
同社はこの指摘の公表を見送ってきた理由について、「具体的な計測値の変更の有無、範囲などを客観的に確認できていないため」と説明している。
一点集中が良いのか、方向転換が良いのか、それとも多角経営が良いのかは、会社、業界、経営者の能力や経験、そして運など複雑なコンビニ の結果なので難しいと思う。
旭フォトマイクロウエア、M&Aによる拡大路線で財務悪化
伝統産業である印章は、今や機械で彫刻・大量生産され、店舗もフランチャイズ(FC)化、ネット販売が主流となった。景気に左右されないビジネスとされる一方、人口減、行政手続きの簡素化、インターネットの普及などで印章の需要が減少傾向にある。
印章関連の総合サービスを手がけた旭フォトマイクロウエアは、11月29日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。同社は、化学大手による紫外線を照射すると硬化する樹脂を用いた独自のスタンプシステムの東日本における代理店として、1982年に設立された。印章の彫刻を機械で行える自動彫刻機の開発・販売を手がけ、樹脂印では約25%の全国シェアを持ち、年商は約5億円あった。
90年代に大手量販店や通販業者が登場したことで印章小売店の経営状況が悪化し、印章製造や卸業などの業況も厳しくなると、2006年に印章関連事業を手がけていた企業5社を吸収合併した。それに伴い、FC店への印章の受注販売などにも手を広げ、07年5月期に約16億3600万円の売り上げを計上した。
しかし、それまで無借金経営だったが、合併に伴い銀行借り入れ約8億円を引き継ぐことになった。総合的に印章サービスを手がけるようになり、FC店からの受注も安定していたが、市場の縮小で売り上げは右肩下がり。ネットサービスの普及に伴う市場環境の悪化をもろに受け、11年以降は赤字決算が続き、17年5月期の売上高は約6億5300万円に減った。
そうしたなかで、借り入れ負担が年々重くなり、10年頃より資金繰りが苦しくなった。こうした企業の吸収合併などに際しては、「何をどこまで引き継ぐのか」が重要なポイントとなる。吸収する企業の負債状況やそれをどの程度引き継ぐのかによって、吸収合併後の企業の財務を損なう恐れがあるためだ。
帝国データバンク情報部
三菱電線工業が、三菱マテリアルによる不正公表(11月23日)後も不正を隠していた事実が明らかになり、グループの隠蔽(いんぺい)体質が改めて問われる結果となった。不正な製品の出荷先は約260社に拡大。今後の調査でさらに増える可能性もあり、信頼回復は前途多難だ。
三菱マテリアルは11月23日に三菱電線など子会社の不正を発表し、同24日に記者会見を開いた。しかし、翌25日には、三菱電線のパッキンなどシール材で一部の検査をしないまま製品を出荷していた事案が判明。コイル状の電子部品「平角マグネットワイヤ」のデータ改ざんについては、社外の弁護士らを交えた三菱電線の調査委員会が把握するまで表面化せず、12月12日にようやく三菱マテリアルに報告があったという。
三菱電線の高柳喜弘社長は19日の記者会見で「11月23日の不正公表後、我々が(すべての出荷先である)462社の2万品目を調べていた過程で(新たな不正が)出てきた」と弁明した。しかし、「現場が不正を隠していたのではないか」との質問に対し、「11月23日の時点では我々に(報告が)来ていなかった。指摘の通りだと思う」と認めざるを得なかった。現場が隠蔽した理由については「コメントは控えたい」と述べ、調査委に委ねる考えを示した。
不正があった子会社3社のうち、安全性の確認を終えた三菱アルミニウムを除く三菱電線、三菱伸銅の2社では、調査委による調査が続いている。
さらに新たな不正が発覚する可能性について、三菱マテリアルの小野直樹副社長は「今の時点ではないと考えているが、調査結果を待ちたい」と述べるにとどまった。
日本のものづくりへの信頼が揺らぐ中、経団連は12月4日、1500の会員企業・団体に品質管理で不正がないか年内に自主的な調査を行い、法令違反などが見つかった場合は速やかに公表するよう求めた。
今のところ、自主調査で見つかった不正は、東北電力が送電線の鉄塔の基礎部分の寸法を社内基準内に収まるよう改ざんしていた1件のみにとどまる。だが、不正の拡大に歯止めがかかるのかは予断を許さず、調査結果が注目される。【川口雅浩】
子会社3社が製品の検査データを改ざんしていた三菱マテリアルは19日、3社のうち三菱電線工業で新たに電子部品のデータ改ざんが発覚したと発表した。油や水の漏れを防ぐパッキンなどのシール材で、これまで発覚していたデータ改ざんに加え、一部の検査を実施していない不正があったことも判明。いずれも三菱マテリアルが当初、不正を発表した11月23日時点で三菱電線から報告はなく、現場が隠蔽(いんぺい)していたという。
新たにデータ改ざんが発覚したのは、携帯電話やパソコンなどに使われるコイル状の電子部品「平角マグネットワイヤ」。昨年12月1日~今年11月30日に5社に出荷した製品について、部品を覆っている膜の厚さなどの寸法を、顧客が求める基準に合致するよう書き換えていた。社内の調査委員会の調査で今月12日に発覚した。
シール材では、これまで229社にデータを改ざんした製品を出荷した可能性があると説明していたが、一部の検査をしていなかった製品を約230社に出荷していた可能性が新たに分かった。重複を除くと、不正なシール材の出荷先は従来の229社から計約260社に拡大する。
また、三菱マテリアルが直近2年間を対象にグループ全体を臨時調査した結果、本社工場と子会社で、測定方法の誤りといった検査手続きの不備が計11件あったことも明らかにした。
三菱電線は不正な製品の安全性の確認を進めている。社内調査委による調査結果の報告は年明け以降になる見通し。同様にデータ改ざんが発覚している子会社の三菱伸銅は12月末までに調査結果を報告する予定。
三菱マテリアルの竹内章社長は東京都内で記者会見し、「ご迷惑をおかけし、深くおわび申し上げる」と陳謝した。【小川祐希】
三菱マテリアルは19日、製品の性能データなどを改竄(かいざん)した子会社で、新たな不正が見つかったと発表した。11月23日に子会社の三菱電線工業、三菱伸銅の2社でデータ改竄があったと発表していたが、その後の調査で、新たな不正が発覚。19日に東京都内で開いた記者会見で、三菱マテリアルの竹内章社長は「顧客のみなさまや株主に多大な迷惑を掛け深くおわびする」と陳謝した。
今回、不正が発覚したのはいずれも三菱電線の製品。新たに発覚したのが、モーターなどのコイルに使われる「平角マグネットワイヤ」で、皮膜の厚さなどの寸法データを書き換えていた。43ロットで、顧客5社に出荷している。すでに顧客には連絡している。
さらに、すでに不正があると発表していた「シール材」では、顧客数、アイテム数が拡大。当初は229社の顧客に対し、性能改竄品を供給していたとしたが、その後に調査で、計462社が供給対象だったことがわかった。アイテム数もこれまで1万点程度だったのが、2万1400アイテムに拡大したという。
三菱マテリアルは早期の原因究明、再発防止策の策定を進めるとしていたが、新たな不正の発覚で、遅れる可能性が高まっている。
SUBARU(スバル)は19日、新車の性能を最終チェックする完成検査業務を無資格者が行う不正行為が1980年代に始まっていたとする調査報告書を公表した。国による監査の際には隠蔽(いんぺい)行為が行われていたほか、有資格者に登用する過程で試験解答の漏えいなどがあったことも判明。日本のものづくりへの信頼を傷つける結果になった。
吉永泰之社長は東京都内の本社で記者会見し、「多大な迷惑を掛け、心からおわびする」と謝罪した。社外取締役などを除く全役員が12月から4カ月間、報酬の一部を自主返納する。
報告書は、スバルが調査を依頼した外部の法律事務所が作成した。それによると、有資格者に登用される前の従業員が行える「補助業務」の範囲が拡大解釈され、無資格者による単独検査が80年代から始まっていた。
また国土交通省による監査の際、有資格者の指示で無資格者を完成検査ラインから一時的に外し、適正な検査を装う隠蔽が行われていた。資格試験の解答を試験官が教えるなどの不正もあった。
報告書は問題の背景として、製造現場でのルール軽視の姿勢や、現場と管理部門のコミュニケーション不足を指摘。吉永社長は自ら率先して意識改革や監査体制強化に取り組む意向を示した。
スバルの検査問題は、日産自動車による同様の不正発覚を受けて実施した社内調査で判明。スバルは11月、約39万5000台のリコール(回収・無償修理)を国交省に届け出た。
吉永社長は会見に先立ち、国交省を訪ね、報告書を提出した。
[東京 19日 ロイター] - SUBARU(スバル)(7270.T)は19日、無資格者が新車出荷前に完成検査を行っていた問題について、弁護士による外部調査報告書と再発防止策を発表した。同報告書によると、完成検査員を登用する社内の試験で、試験官が受験者に回答を漏らす事例などが新たに判明した。
報告書は「経営陣から現場に至るまで完成検査業務の公益性および重要性が十分に理解されていなかった」などと不適切な実態を指摘した。
吉永泰之社長は19日午後、記者会見し、完成検査の不適切な対応について「全てのステークホルダーに多大な迷惑」をかけたとして謝罪した。今回の問題を受けて、社外取締役と監査役を除く全役員を月額報酬を一部返上するという。期間は12月から3月まで。
報告書によると、登用前の検査員が他の検査員の印鑑を受け取り、完成車品質保証票に押印する不適切行為が認められた。同報告書は、不適切な検査は1980年代から運用されていた可能性があり、90年代には定着したもようだと指摘した。
一方、外部調査によって、完成検査員の登用では社内規定に従った運用がされていなかった実態が判明した。具体的には、完成検査員登用のための修了試験で、試験官が受験者に回答内容を教えた例などのずさんな運営・監督の実態があったという。また、国土交通省やスバル社内の上位者による監査の場合、資格を持たない検査員が検査ラインから一時的に外れるなど、隠蔽(いんぺい)とみられる工作があった事例も判明した。ただ、吉永社長は「組織ぐるみで隠蔽していたわけではない」と強調。吉永氏は「私自身が現場の実態についての理解が不足していた」と述べた。
報告書は完成検査の現場において「必用な技術を備えていればよい、という過度な技量重視の風土」の存在を指摘。「昭和時代の会社のような、古い徒弟制度みたいな風土を変えていかないといけない」(吉永氏)としている。
調査報告書を受けて、スバルは再発防止策を発表。登用前検査員の完成検査工程への配置を10月3日から取り止めた。登用前検査員に貸与されていた予備の印鑑は全て廃棄し、押印管理表を作成、管理を強化した。
組織的な体制強化策として、生産者適合性に関する専門部署を12月1日付で設置したほか、現在は製造品質管理部長が任命し、品質保証部長が承認する完成検査員の人事管理を人事部門で一括して行うことを検討する。吉永社長は「会社の体質を根本から全面的に刷新する」と強調した。
今回の問題を受けて、国内販売は足元では受注が前年に比べ7割程度に落ち込んでいるが、同社の経営の屋台骨である北米市場では「今のところ影響は出ていない」(吉永氏)という。
*内容を追加しました。
(浜田健太郎)
[東京 19日 ロイター] - 三菱マテリアルは19日、子会社の三菱電線工業(東京都千代田区)の平角マグネットにおいて、新たなデータ改ざんが判明したと発表した。また、シール材においても、検査の一部を実施していないことで、不適合品を出荷した先が広がる可能性があるとした。
平角マグネットは、電気機器の巻線用電線(商品名「メクセル」)。2017年12月12日にデータ改ざんの疑いがあるとの報告を受け、2016年12月1日から17年11月30日までの1年間に出荷した製品に関する調査を実施したところ、改ざんの可能性のある製品43ロット・出荷先5社を特定したという。データを改ざんした製品は、この期間の「メクセル」の売上高7億8400万円の約1%にあたる。現在、安全性の確認を進めている。
また、シール材では、11月23日時点で不適合品を出荷した可能性があると確認していた出荷先229社に連絡し、安全性の確認を進めていたところ、検査の一部を実施していないことで不適合品の出荷先が拡大する可能性があることが判明。現在、特定作業を進めており、18日現在、一部検査未実施による不適合品出荷の可能性があるのは約230社となっている。これは、23日時点で可能性があるとしていた出荷先と重複している出荷先もあるという。同社では、年末までに特定作業を完了させる予定。
*内容を追加しました。
リニア中央新幹線建設工事を巡る不正受注事件で、JR東海(名古屋市)の社員が東京地検特捜部の任意の事情聴取に対し、非公開の「上限価格」を大手ゼネコン・大林組(東京都港区)側に漏らしたことを認めていることが、関係者への取材で分かった。特捜部は、価格漏えいにより公正であるべき受注業者の選定手続きがゆがめられたとみて、受発注者のやり取りの経緯を調べている。
【写真特集】大林組が請け負うリニア中央新幹線の工事現場
上限価格が漏らされた疑いがあるのは、名古屋市中区の「名城非常口」の工事。同工事の業者選定手続きは、広く希望企業を募る「公募競争見積もり方式」で実施された。この過程で、JR東海の社員が大林組側に上限価格を漏えいし、限度内の約90億円を提示した大林組が受注にこぎつけたとみられる。競合した鹿島(東京都港区)の提示額は約100億円だった。
同方式は、価格だけでなく工法などの総合評価を経てJR東海が業者と契約する仕組みになっている。しかし、特に工事費は重要な判断要素になっていたとみられ、上限価格を知ることは受注に極めて有利に働いたとみられる。
JR東海の幹部は毎日新聞の取材に対し「価格の漏えいなんてするわけがない。いくら(工事費を)安くできるか、各社に競争してもらった結果だ」と漏えいを否定。鹿島の幹部は「鹿島が提示できる金額は頑張って(抑えて)も100億円だった。大林組は『名城非常口』を取れば、そこを起点とするトンネル工事もJR東海がやらせてくれると踏んだのではないか」と話す。
大林組の幹部は「JR東海側から安全性に関わる設計変更が示され、提示額を(約90億円に)下げた経緯はあったと聞いている」としている。
【巽賢司、松浦吉剛、森健太郎】
メンテナンスや点検が容易でない場所への点検は問題があると思う。メンテや点検にお金が掛かれば思ったほど太陽光パネルのお得感はないと思う。
しかし、太陽光パネルの保守点検会社は危険や注意事項について説明していたのだろうか?リスク又は危ない仕事は時給が良くないと割に合わないと 思う。まあ、高校無償化を利用して学校で遊んでいる若者よりも、選択の余地なくこのような仕事を選んだのか知らないが、バイトであっても働いて いたこの少女は立派だ!勉強が嫌いだったのか、家庭の事情で働いていたのかは知らないが、引きこもりと比べればはるかに立派。
政府は高校とか、大学とか夢物語を誤魔化すが、現場で働く人達も重要なので現場で働く人達のための教育を考えた方が良い。高学歴化が進んでも 誰かが現場で働かないといけない。ロボットや外国人で置き換えるつもりであれば良いが、簡単にはいかないと思うよ。
15歳の少女がアルバイトの作業中、13メートル下に落下して死亡しました。
警察によりますと、茨城県古河市の工場で14日午前、秋山祐佳里さんが屋根に取り付けられた太陽光パネルの点検などをしていたところ、天窓のガラスが割れて13メートル下のコンクリート製の床に転落し、死亡しました。秋山さんは当日、太陽光パネルの保守点検会社のアルバイトとして作業にあたっていました。警察が安全管理に問題がなかったかなど調べています。
「働くのが怖い」。4カ月連続休みなしで働かされ、脅され包丁で刺されたという飲食店での超絶“ブラックバイト”を経験した大学4年生の男性(22)はこう語った。損害賠償を求めていた訴訟は11月に和解が成立。無事に大学を卒業できる見込みとなり、別の会社に就職内定を得たものの、抱えたトラウマ(心的外傷)は深い。(社会部 天野健作)
「ブラックバイトの象徴的な事件だった」。男子学生を支援してきた労働組合「ブラックバイトユニオン」の坂倉昇平さんはこう振り返った。男子学生は平成26年5月、求人誌を見て、飲食チェーンの千葉県内にある支店(現在は閉店)でバイトを始めた。当初は1カ月間で約70時間働いて月5万円ほど稼ぎ、男子学生は「比較的まともな状態だった」と話す。
その時期は別の20代の男性が犠牲になっていた。あらゆる作業をその男性が行っており、「仕込みが遅い」とよく怒られていた。その男性が同年12月に急に姿を消し、他のバイト5人ほども退職すると、人手不足が深刻化。男子学生の休日は月3日程度となった。
大学へ行くこともままならなくなり、店長に辞めることを伝えると「ミスが多いので懲戒免職にする。懲戒になると、就職に影響が出るからな」と脅された。27年4月から休職した8月までの4カ月間、無休で働かされた。大学の実習や試験を受けられず、同年前期の単位を全て落としてしまった。
このまま泣き寝入りか…。状況が一変したのは、千葉県警が昨年11月、バイト中にこの男子学生の顔を殴ったなどとして、暴行容疑で店の元従業員を逮捕したことだった。学生は日常的に暴行を受け、実際に左肩には医師の診断で「全治3カ月」とされた包丁で刺されてできた刺し傷もあった。その後、元店長が書類送検され、両者とも暴行罪などで罰金刑が確定した。
事件を受けて、このチェーンの代表者は産経新聞の取材に「店舗で働いていたときの事件で大変遺憾。店には頻繁に行っていて男子学生のことも知っていたが、(事件には)気付かなかった」と話した。昨年9月には、フランチャイズ運営会社に対して未払い賃金や慰謝料など計800万円の支払いを求めて千葉地裁に訴訟を提起した。第1回口頭弁論で、男子学生は「人生を大きく狂わされました。留年したら退学するしかない。将来の夢が閉ざされてしまう」と訴えた。
今年11月にようやく和解が実る。男子学生の代理人弁護士によると、運営会社が解決金を払うとともに、元店長や元従業員が暴言や暴力を振るったことなどを認め謝罪することなどが決められた。解決金の額は明らかにしていない。「2年以上たったが、ようやく終えることができた。今後、このようなことが起きないように、できる限り、被害者が声を上げられるようにしてほしい」。民事、刑事事件ともに晴れて解決に至った男子学生は安堵(あんど)の表情を見せた。
ただ将来的に「働くのが怖いという気持ちがある。バイトと仕事として働くのとは違いがあり、これから頑張って努力して、ちゃんと働けていけるよう、できる限り克服していきたいと思います」と語った。
リニア中央新幹線の建設工事を巡る不正入札事件で、発注元のJR東海の担当社員が、名古屋市内の非常口建設工事の入札にあたり、大手ゼネコン「大林組」(東京)に工事費に関する情報を漏らした疑いのあることが関係者の話でわかった。
東京地検特捜部は、既にこの担当社員を任意で事情聴取しており、同社が担当社員の情報を基に、工事を不正受注した疑いがあるとみて調べている。
不正の疑いが持たれているのは、「名城非常口」の建設工事。名古屋市内の公園跡地に深さ90メートル、直径約40メートルの縦穴を開け、リニアが走る地下トンネルから地上への非常口を設置する。
入札は、広く参加企業を募る「公募競争見積方式」で行われ、企業から施工方法などの技術提案を受けたJR東海が、見積価格などと合わせて総合評価。その上で評価の高い順に企業と契約価格を協議し、最終的に大林組と戸田建設(同)、ジェイアール東海建設(名古屋市)の共同企業体(JV)が2016年4月に約90億円で受注していた。
関係者によると、JR東海の担当社員は受注企業の選定過程で、工事費の見積もりに関する情報を大林組に漏らしていたという。参加企業は、非公開の情報を把握すれば、発注者の予算内に収まる見積価格を提示するなどして、受注を優位に進めることができる。
大林組は、担当社員から得た情報を基に見積価格を算出し、契約価格についてJR東海と協議したとみられる。特捜部は、担当社員から関係資料の任意提出も受けたという。
名古屋市のリニア中央新幹線建設工事で、大林組が受注を見送るよう他社に働きかけていた疑いが浮上した。「10年前に痛い目を見たのに、また名古屋か」。大林組OBは嘆息する。平成19年に名古屋市発注の地下鉄工事をめぐる談合事件でも、大林組が入札で受注調整を取り仕切っていたためだ。東京地検特捜部はスーパーゼネコンの旧態依然とした入札不正体質に切り込み、全容解明を進める。
大林組などの共同企業体(JV)が工事を手がける「名城非常口」新設工事の現場は、名古屋市中区の公園跡地。名古屋城の異名「名城」を冠しているように、名古屋城にほど近い市中心部の官庁街にある。
リニア中央新幹線の大深度地下区間のトンネルに、深さ約90メートル、直径約40メートル規模の地下構造物を造る計画で、事業費は約90億円にも上る。建設中はトンネルを掘削する円筒状のシールドマシンの基地として活用。開業後は地上に避難する非常口として、リニアの安全を守る要の施設となる。
名古屋に住んで40年以上になるという女性(82)は「日本の技術は世界一だと思うけど、昔から大なり小なり不正があったんだろうね」と話した。名古屋市民にとって、大林組と聞いて思い出すのは10年前の地下鉄談合事件。タクシー運転手の男性(73)も「ここの工事がニュースで見た不正と関係しているとは知らなかったが、地下鉄談合は覚えている」。
大林組など大手ゼネコンが17年末に出した「談合決別宣言」。部長級以上の社員から「談合しない」との誓約書を出させたり、他社との接触を原則禁止したりするほど徹底され、談合との決別を図ったはずだったが、大林組ではその後も不正が繰り返されていた。19年の名古屋市の地下鉄談合では、関係者が相次いで起訴され、副社長ら取締役3人が引責辞任。同年の大阪府枚方市の清掃工場建設をめぐる談合事件では、顧問や社員が逮捕され社長が引責辞任した。
大林組は当時、「全社を挙げてコンプライアンスの徹底に取り組み『新生大林組』への努力を続ける」とも誓い、改革へ「大なた」を振るったはずだった。
だが関係者によると、大林組は今回の名城非常口新設工事で、受注に関心を示したゼネコン他社に受注を見送るよう「協力」を要請していたという。大林組のある幹部は「国を挙げた一大プロジェクトだから取りたいという思いはあったと思う」と話したが、大林組OBは「名古屋の地下鉄談合や枚方の談合で、経営陣は総取っ換えになった」と振り返り、こう続けた。
「リニアという大事業とはいえ、不正をしてまで仕事を取らないとつぶれるような会社でもないのに。結局、大林組は何も反省していなかったのだろうか」
東洋ゴム工業(兵庫県伊丹市)による免震ゴムの性能データ偽装事件で、不正競争防止法違反(虚偽表示)罪に問われた子会社「東洋ゴム化工品」(東京都新宿区)に対し、枚方簡裁(原司裁判官)は12日、求刑通り罰金1000万円を言い渡した。
原裁判官は判決で、「上層部が問題を認識した後も出荷を停止せず、偽装を続けた。会社ぐるみの犯行で、業界の信用を失墜させ、社会に不信や不安をまん延させた」と指摘した。
判決によると、同社は2014年9月、枚方寝屋川消防組合(大阪府枚方市)の新庁舎に設置する免震ゴムについて、国の基準に適合しているように偽装した性能検査成績書を作成し、施工業者に交付した。
事件では、基準に適合しない免震ゴムが自治体の庁舎やマンションなど全国154棟で使われていたことが判明。親会社の東洋ゴム工業と山本卓司前社長ら18人も書類送検されたが、7月にいずれも不起訴となった。
東洋ゴム工業は「判決の内容を厳粛に受け止め、コンプライアンスの徹底を図り、事件を風化させないよう努める」とのコメントを発表した。【岡村崇、宮嶋梓帆】
北海道は農業や酪農、そして部分的な観光以外は魅力はないし、人口が減る事はあっても増える事のない日本では生活場所に選ぶ魅力は 少ないと思う。
皆が納得できる対応は出来ない事を理解して抜本的な対応を取らないともっと厳しい状況になると思う。
国の除染事業が私物化されていたのか。福島第1原発事故の除染事業を担う清水建設のJV(共同企業体)で、除染作業員が、除染の対象地域ではない清水建設の執行役員の実家で、草むしりなどを行っていたことが、FNNの取材でわかった。執行役員は事実を認め、辞任した。
2016年8月の平日、清水建設JVに入る下請け企業の作業員が、JVを統括する清水建設の執行役員の実家の草むしりをする様子を撮影した写真。
実家は、新潟県との県境の福島・西会津町にあり、除染の対象地域ではないが、作業員12人が、草むしりを行っていた。
また、冬には3年にわたり、4回、雪かきを行っていたという。
作業車でやってきた除染作業員たちは、この執行役員の実家裏庭などを、およそ5時間かけ、作業道具を使って草むしりしたという。
「草むしり」に参加した除染作業員は、「『清水建設の偉い人の実家だから、気をつけてやれ』と。『ガラスとか割ったり、家を傷つけたりすればクビになるからな』って。みんな集められて、きょうは大熊で(の除染作業として勤務に)つけていいからって」と語った。
このJVの除染では、作業員は、国から危険手当1万円を日当に上乗せして受け取れるが、参加した作業員によると、下請け企業の幹部の指示で、草むしりを除染作業として勤務報告していたという。
「草むしり」に参加した除染作業員は、「除染で出た廃棄物と一緒に処分という形でやりました。おかしいなと思いました」と語った。
写真には、黒い袋を持つ作業員が映っているが、参加した作業員によると、袋は除染専用のもので、刈り取った草は、下請け企業の幹部の指示で、国の除染廃棄物の仮置き場に捨てたという。
一方、下請け企業の代表は、仮置き場への投棄と、危険手当の国への請求を否定している。
下請け企業代表は「(作業員は、勤務につけろと指示されたと)ふーん」、「(草を仮置き場に廃棄したと)そんなことないでしょうよ、そんなのあり得ない。(実家がどこにあるかも知らない)会津だとは、わかってますよ。(どうしてご存じなんですか?)われわれの得意先ですからね」と話した。
しかし、下請け企業の代表は、このあと、作業員に執行役員の実家の草むしりなどをさせた事実を認め、「深く反省している」と話した。
この下請け企業は、原発事故の翌年に設立され、清水建設の下請けとして、年間100億円を売り上げるまでに急成長している。
下請け企業との癒着があったのか、清水建設の執行役員は「(これは育った実家ですよね?)広報通してお願いします。(指示されたんですか)指示してないです」と話した。
執行役員は、指示したことを否定する一方、「草むしり」などをしてもらった事実を認めた。
そして、FNNの取材が進む中、その費用を個人負担で下請け企業に支払ったうえで、執行役員を8日付で辞任した。
清水建設は、内部調査を始めていて、「疑義を持たれるような行為があったことは誠に遺憾です」とコメントしている。
また、除染事業の発注元である環境省は、この問題について、「事実関係を調査中です」とコメントしている。
■原発関連疑惑・情報募集
フジテレビでは福島第1原発をめぐる問題や疑惑を継続取材しています。
内部情報をお持ちの方で情報提供して下さる方は、下記リンクからご連絡下さい。
https://wwws.fnn-news.com/nsafe/goiken/index.html
大手企業にとっては優秀な従業員の代わりはたくさんいる。逆に中小の方が高く評価してくれれば働きやすいケースもある。ただ、中小はやはり 安定度は数値で言えば低く、大手の下請けであれば、大手の景気やクッション材として厳しいコストカットを要求されることもある。 競争力のある中小以外は、現実を見れば厳しいかもしれない。ただ、改革をするのであれば規模が小さいから結果を出しやすいし、給料だけを 考えなければ、総合的には同じ、又は、それ以上の環境は見つけられる可能性はある。多くの学生が注目しないからこそ、掘り出し物の企業を 探しやすい可能性もある。
経験しなければ、比較できない事もある。完ぺきな選択がなければ、個々により評価も違う。給料が上がれば、それに見合う結果が伴わなければ、 誰かに負担させるか、皆で負担をシェアするしかない。国際競争を無視する事は出来ない。国内だけで解決する問題ではない環境である。
長時間労働や賃金不払いなど労働関係法令に違反した疑いのある企業名を、今年5月から厚生労働省がホームページで公表しはじめてから約半年。政府が「問題あり」と認定したブラック企業のリストは毎月更新され、その数は最新版(11月15日発表)では496社にのぼっている。
【表】あの有名企業も! 厚労省発表の“ブラック企業”一覧
リストは各都道府県の労働局別に公表されている。企業名の公表期間は原則1年で、改善が認められ、公表を続ける必要性がなくなったと判断されると1年以内でも削除される。
ブラック企業名の公表は、労働環境が悪い企業を“見せしめ”にすることで改善を促す目的がある。だが、現時点で抑止効果が現れているとはいえないようだ。
グラフでわかるように、企業名公表の基準となる書類送検日を月ごとに見ると減少傾向は見られない。むしろ9月が46件、10月が61社、11月が76社と増加傾向にある。
ブラック企業の問題が改善されないのは、少子高齢化や景気回復による人手不足、利益確保への圧力などの要因から、労基法を軽視する企業が後を絶たないためだ。リストには中小企業が目立つが、パナソニック、電通、ヤマト運輸、エイチ・アイ・エスなどの有名企業も多数含まれている(表参照)。
もちろん、厚労省の発表に含まれていない企業であれば、安心というわけではない。若者の労働環境の改善に取り組むNPO法人「POSSE」の坂倉昇平さんは、こう話す。
「公表された企業は、遺族や当事者の訴えによって、過労死・過労うつや死亡事故を含む重大な労災事故が認定された企業が多い。実際には、違法な長時間労働が恒常化している企業でも、労働基準監督署から指導を受けた段階で是正報告書を提出すれば、書類送検されることはほとんどありません」
ある大手住宅メーカーでは、労働基準監督署から複数の是正勧告を受けたあと、イメージ回復のために労働環境の改善への取り組みをさかんにテレビやホームページなどでアピールをしていた。
だが、社員の数が増えたり、業務量が減ったりしたわけではない。会社からは夜になると強制的に退社させられるが、結果的に社内のイントラネット環境に接続できる駐車場の車の中で仕事をしたり、夜間でも営業しているモデルルームなどで仕事が続けられていたという。こういった「隠れ残業」や「持ち帰り残業」は労働基準監督署では発見しづらい。ブラック企業の手口はさらに巧妙化しているといえる。
また、若手社員の役割にも変化があるという。
2017年10月に有罪判決が出た大手広告代理店電通の違法残業事件では、常態化した長時間労働により新入社員の女性が自殺した。坂倉さんは言う。
「過去の過労死では、たくさんの仕事を一人で抱え込んだ40代以上の中堅やベテラン社員が死に至ることが多かった。それが近年は、業務のマニュアル化が進み、誰にでもできる仕事が増え、新入社員にも膨大な業務量が任せられるようになった。それに耐えきれずに体を壊したり、うつ病になったりするケースが目立っています」
ブラック企業では、労働組合が労働環境の改善を求める組織として機能していない企業も多い。もし、悪質な労働環境に悩んでいる人がいれば、「ブラック企業ユニオン」など外部の労働組合に相談することも手段の一つだ。また、就職の前に公開されている情報を精査することで、ブラック企業の罠にはまらないことも大切だ。(AERA dot.編集部・西岡千史)
富山県は山形県に近く、山形県や山形大学にも閉鎖的な問題は存在するのだと思う。山形大学に関しては部分的に閉鎖性が証明されたと思うケースだ。
関東よりも南側に住む人間としては、地理的には富山であろうが、山形であろうが、地理的には大きな違いはない。県が違う、同じ県であっても、 都市部や農村部なので、違いがあるのは想像できるが、やはり、地域が近いと、県や国が違っても、植民地などの歴史的な点以外は、距離が近ければ 文化や価値観も共通点が多くなる。この点から考えれば、富山であろうが、山形であろうが、似たような問題は存在すると思う。
山形大xEV飯豊研究センター(山形県飯豊町)のパワハラ疑惑で、同大が11月、ようやく調査に乗り出す方針を表明した。疑惑発覚から1カ月余り。センター長の男性教授が職員の机に残したとされる侮辱的な書き置きの画像が公開され、重い腰を上げた。真相究明と情報開示に消極的な大学の姿勢は、アカデミックハラスメント(アカハラ)を受け、工学部生が自殺した問題でも批判を浴びた。真摯(しんし)な調査ができるのか、大学の自浄能力が問われている。
【写真】<山形大パワハラ疑惑>関係者証言「知っているだけで10人辞めた」「怒鳴り声にビクビク」
「報道で初めて見て驚いた。センター長の筆跡なら大変なことだ」
小山清人学長は11月15日の定例記者会見で、同大職員組合が公表した書き置きなどの画像について、こう述べた上で、学内規程に基づき特別対策委員会を設置したことを明らかにした。
職員組合が公表した画像は4枚。いずれもセンター長によるパワハラを訴えて退職した職員の机に残されていたとされ、それぞれ「役立たず」「ボケが!!」などと書き殴られていた。
疑惑が報じられた直後の10月初旬、小山学長は定例記者会見で「パワハラがあれば処分している。処分はしておらず、パワハラとしては把握していない」と曖昧な説明をして、記者たちの質問をかわしていた。
今回表明した調査の方針も、決定的な「証拠写真」を突き付けられ、追い詰められた末の苦し紛れとの疑念が付きまとう。
センターを退職した職員らから相談を受けた職員組合は、既に5月には小山学長宛ての質問書で「一方的な非難や侮辱的な言動が執拗(しつよう)に行われている」として「深刻なパワハラが常態化していたことは疑いの余地がない」と指摘していた。
この段階で組合の訴えを正面から受け止めて事実確認をしていれば、これほど教職員や学生、地域社会の不信を招かずに済んだはずだ。
外部の声に対する感度の鈍さと情報開示を軽視する体質は、工学部の男子学生が2015年11月、指導教員の助教によるアカハラを苦に自殺した問題でもあらわになったばかりだ。
大学が設置した第三者調査委員会は16年6月、アカハラと自殺の因果関係を認める報告書を作成。助教は16年10月に研究室内でのアカハラを理由に停職1カ月の処分を受けた。
ところが、大学は助教に対する懲戒処分の発表時に男子学生の自殺を公表していなかった。問題が表面化したのは、学生の遺族が損害賠償訴訟を起こした後のこと。調査委の報告書も現在に至るまで明らかにしていない。
今回のパワハラ疑惑調査で、特別対策委は18年1月をめどに大学側に結果を報告する。大学はこれまで委員の構成について説明を拒んできたが、調査の透明性の確保などを文書で求めてきた職員組合の意向を酌み、複数の学外専門家を委員に加える考えを示した。
疑惑の現場となった飯豊研究センターは、国内最先端のリチウムイオン電池の研究開発拠点として産業界から注目されている。それだけに、信頼回復につながる誠実な調査を期待したい。(山形総局・吉川ルノ)
[山形大パワハラ疑惑]リチウムイオン電池の研究開発拠点「山形大xEV飯豊研究センター」(山形県飯豊町)の職員3人が今年3~5月、センター長の男性教授からパワハラを受けたとして相次いで退職した。複数の職員から被害相談を受けた同大職員組合は5月以降、3回にわたり、学長宛てに実態を把握しているかどうかを問う質問書を提出した。センターは16年5月に開所。自動車、ロボット関連企業など約50社が研究開発に加わっている。
北海道は農業や酪農、そして部分的な観光以外は魅力はないし、人口が減る事はあっても増える事のない日本では生活場所に選ぶ魅力は 少ないと思う。
皆が納得できる対応は出来ない事を理解して抜本的な対応を取らないともっと厳しい状況になると思う。
負債額は約280億円、北海道で今年最大
(株)小樽ベイシティ開発(TSR企業コード:020060742、法人番号:4430001049790、小樽市築港11-5、設立平成3年11月、資本金1億2700万円、橋本茂樹社長、従業員20名)は12月7日、札幌地裁に民事再生法を申請した。申請代理人は高木大地弁護士(弁護士法人関西法律特許事務所、大阪市中央区北浜2丁目5-23、電話06-6231-3210)ほか。
負債総額は約280億円。
JR小樽築港駅貨物ヤード跡地の再開発を目的に設立。平成11年3月、約400億円の巨費を投じ、当時国内最大と言われた大型複合商業施設「マイカル小樽」(15年3月「ウイングベイ小樽」に改称)をオープンした。しかし、13年9月14日、当時の親会社だった(株)マイカル(TSR企業コード:570154022、大阪市)が民事再生法を申請したことに連鎖し同月27日、当社も民事再生法の適用を申請した(負債総額約492億円)。
その後、再生計画に則り債務弁済を行う一方、日本政策投資銀行を筆頭債権者とする担保付債権を(株)ポスフール(現:イオン北海道(株)、TSR企業コード:010157050、法人番号:4430001015958、札幌市白石区)が一括取得したことで約194億円の債務が残された。これの返済が進まなかったため、19年8月に特定調停を申請し約29億円まで債務圧縮の合意を得た。しかし、スポンサーを確保できず、金融機関から資金調達が進まなかったため、21年1月に調停を取り下げた。22年11月、再度特定調停の申し立て合意を得ものの、期日までに弁済金を用意できず不履行となっていた。
この後もテナント誘致を行う一方で新たなスポンサー獲得や売却交渉を進めていたが、企業再生ファンドのルネッサンスキャピタル(株)(TSR企業コード:298060450、法人番号:8010001127123、東京都千代田区)がスポンサーとして名乗りを上げ、29年12月5日、イオン北海道が保有する債権188億円1500万円(貸付金:129億1200万円、敷金保証金の返還請求権:約59億300万円)を取得していた。
東京商工リサーチ
あとは弁護士の能力と証拠を残さないように対応してきた、又は、証拠を既に抹消しているか次第であろう。
スーパーコンピューター開発会社の助成金不正受給事件で、受給手続きをして逮捕された元部長が「社長の指示だった」と供述していることが関係者への取材でわかりました。
この事件は、東京のベンチャー企業「PEZYComputing」社長の斉藤元章容疑者(49)と、元事業開発部長・鈴木大介容疑者(47)の2人が、2014年、経済産業省所管のNEDOから助成金およそ4億3000万円をだましとったとして逮捕されたものです。
関係者によりますと、受給の手続きをした鈴木容疑者が特捜部の調べに対し、「社長の斉藤容疑者の指示だった」と供述していることがわかりました。また、斉藤容疑者は自らが経営に携わるメモリー開発会社などに外注費を水増しする手口で、助成金をだましとった疑いがあることがわかり、特捜部が詳しく調べています。
神戸製鋼、東レの子会社や三菱マテリアル子会社は海外との取引もあるし、零細企業ではない。日本国内の企業としか取引をしていない企業でもない。
「日本の企業文化には顧客が要求した品質は満たしていないが不良品とまではいえない製品については、特採(特別採用)として一時的に出荷を容認する慣習がある。」
契約書に上記の事が記載されていれば相手側も納得しているか、見落としたと思うが、そうでなければ不良品とは言えないから、データの改ざんをしました。 これは日本の習慣ですと事後報告で外国企業が納得するだろうか?
屁理屈としか思えない。また、許容範囲であると思うなら、発注先が判断できるようにデータを改ざんするべき出来はない。顧客が要求した品質は満たしていない 件について、データを見て相手が判断出来るが、改ざんは判断する機会を奪ってします。
規則や設計は、誤差が生じる事を想定して対応している。しかし、あまりゆとりを見ていない規則や設計であれば、問題となる場合がある。 事実を相手に伝えていない事はやはり問題があると思う。
「素材メーカー3社のデータ改ざんの合間に、日産やスバルなどの自動車メーカーによる無資格者の検査問題というものも浮上しているが、 それも新車を一台一台検査する必要があるのかというそもそも論を横に置いたままの「不正」論争になっている点に、疑問があると郷原氏は指摘する。 そもそも検査員の資格は社内的なものであり、実際の検査の内容も資格を要するような難易度の高いものではなかったのだ。」
難易度が高くないのに、なぜ、日産は試験で不正をしてまで合格させようとしたのか?社内基準なのだから、試験自体も必要なかったのではないのか? プライドや見栄があったのか?
生産や製造過程で、問題になるが、規則や安全に関係なければ、なぜ改正や修正を行わなかったのか?問題として取り上げられてから、意味がないとか、 安全とは関係ないと言うのであれば、問題として取り上げられる前に変えるべきであろう。そこにが疑わしく思えるのである。
神戸製鋼に続き、東レの子会社や三菱マテリアル子会社など日本を代表する素材メーカーで製品検査データによる改ざんが発覚し、衝撃が広がっている。
不正が発覚した会社ではいずれも「安全性に問題はない」と説明しているが、不正を行った東レ子会社の東レハイブリッドコードと三菱マテリアル子会社の三菱電線ではいずれも社長が更迭されているし、そもそも長年にわたる不正が発覚した以上、その言葉に疑義が生じるのは避けられない。相次ぐ老舗企業による不正の発覚に、日本ブランドの信用の失墜につながることを懸念する声も上がり始めている。
なぜここに来て日本の有名企業の不正発覚が相次いでいるのか。そもそもそれは本当に「不正」だったのか。
企業コンプライアンスに詳しい弁護士の郷原信郎氏は、一連のデータ改ざんは問題だとしながらも、商品の安全性に直結するレベルの不正と、安全性には影響しないが、取引企業間の取り決めからは逸脱していたというレベルの形式的不正は区別して考える必要があると指摘する。そして、経産省が企業間の取り決めから逸脱したレベルの不正についても、積極的に社会に向けて公表するよう指導するようになったため、これまでは表沙汰にならなかった形式的な不正までがメディアに大きく取り上げられ、あたかも安全性に問題があるかのような不安を煽る形になっていることには問題があると言う。
日本の企業文化には顧客が要求した品質は満たしていないが不良品とまではいえない製品については、特採(特別採用)として一時的に出荷を容認する慣習がある。納期や数量を勘案すれば、誤差の範囲として取り扱ったほうが得策だということで、これまで企業間で例外として処理されてきたものだった。特採は最終製品の品質に影響を与えないことを前提とする一時的な措置であることが前提だったが、一流メーカーの中には自社ブランドに対する信頼に胡坐をかき、特採レベルの「誤差」についてはデータを改ざんする慣習が常態化していたところも少なからずあった。それがここに来て、一気に露呈しているのだ。
郷原氏はこうした一連の「不正」や「データの改ざん」に問題がないと言っているわけではない。しかし、最終製品に安全上の問題が生じないことを前提に、あくまでB to B(企業間)の契約上処理されるべき問題が、本質的な安全問題として社会問題化すれば、企業側に過剰コンプライアンス心理が働き、結果的に形式的不正を生む構造がますます覆い隠されることになりかねないと郷原氏は言う。内容やレベルに関係なく「不正」や「改ざん」といった言葉が一律に使われることで、構造的な不正が修正される方向ではなく、隠蔽される方向に向かってしまう可能性が高いというのだ。
素材メーカー3社のデータ改ざんの合間に、日産やスバルなどの自動車メーカーによる無資格者の検査問題というものも浮上しているが、それも新車を一台一台検査する必要があるのかというそもそも論を横に置いたままの「不正」論争になっている点に、疑問があると郷原氏は指摘する。そもそも検査員の資格は社内的なものであり、実際の検査の内容も資格を要するような難易度の高いものではなかったのだ。
これは日本に限ったことではないかもしれないが、日本のとりわけ製造業の現場では長年、職人気質の技術者の「経験や勘」に頼った品質管理が行われてきた。しかし、国際化が進み、コンプライアンスが叫ばれるようになった結果、そうした明文化されないノウハウに頼った品質管理ではなく、より明文化された客観基準による管理が必要になった。管理職は対外的な必要性からそうした基準の制定を進めるが、現実を反映しない基準や守れるわけがないような基準を押し付けられた現場では、そうした基準が空文化しているケースも多い。
そもそも企業間の取り決めに基づく特採の公表を求める経産省の判断が妥当なものなのか。一連の「不正」をメディアは正しく報道し、それは社会に正しく理解されているのか。法令の安全基準に現場の声を反映させ、より現実的で遵守が可能な製品基準をつくらなければ、今後も形式的な不正はなくならないだろうと指摘する郷原氏と、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
-----
郷原 信郎(ごうはら のぶお)
弁護士
1955年島根県生まれ。77年東京大学理学部卒業。同年三井鉱山入社。80年司法試験合格。83年検事任官。公正取引委員会事務局審査部付検事、東京地検検事、広島地検特別刑事部長、長崎地検次席検事などを経て2006年退官。桐蔭横浜大学法科大学院教授、名城大学教授などを経て2012年郷原総合コンプライアンス法律事務所を設立し代表に就任。著書に『思考停止社会』、『法令順守が日本を滅ぼす』、『青年市長は“司法の闇”と闘った』など。
-----
東レ子会社の東レハイブリッドコード(THC、愛知県西尾市)による品質データの改ざん問題で、東レは1日、同日付で鈴木信博社長(64)が辞任したと発表した。後任には、東レの青木正博・生産技術第1部長(56)が就任する。鈴木氏は常勤嘱託に就き、問題の調査や再発防止にあたる。
1日に開かれたTHCの臨時株主総会で決めた。同社がタイヤ補強材などの品質データを不正に書き換えていた問題を受けて東レは、経営責任を取らせる必要があると判断した。
THCは、2008年4月から16年7月に製造した製品で149回書き換えが行われ、タイヤメーカーなど13社に出荷していた。16年7月にTHC社内で発覚。同年10月に東レの日覚(にっかく)昭広社長に報告されたが、法令違反ではなく顧客との契約上の問題だとして公表していなかった。
繊維・化学大手の東レは、製品の検査データ改ざんが明らかになった子会社の社長が経営責任をとって、1日付けで辞任する人事を発表しました。
東レは今週、子会社の東レハイブリッドコードが、タイヤの補強材などの製品で顧客と決めた強度などの基準を満たしているように検査データを改ざんして出荷していたことを明らかにしました。
この問題で、東レは1日、東レハイブリッドコードが臨時の株主総会を開き、経営責任をとって鈴木信博社長が1日付けで辞任する人事を決めたと発表しました。後任の社長には親会社の東レの部長が就任し、社長を辞任した鈴木氏は今後、常勤の嘱託社員として不正の調査や再発防止策の検討にあたるということです。
一方、同じく検査データの改ざんを明らかにした三菱マテリアルの子会社の三菱電線工業も1日、村田博昭社長を取締役に降格する人事を発表しました。
後任の社長には親会社の三菱マテリアルの役員を充てて、問題への対応を迅速に進めるとしています。
製品の検査データをめぐって相次いだ不正は、企業トップの進退にも波及する形となっています。
かなり前の着服だけど、公表していなかったと言う事?
中国銀行高松支店の男性行員が客の金、約2億円を着服していたことが分かり、懲戒解雇処分となりました。
30日付で懲戒解雇処分を受けたのは、中国銀行高松支店に勤めていた31歳の男性行員です。
男性行員は2015年7月から10月までの間、渉外係として担当していた客11人に、金融商品への運用話を持ちかけるなどして預かった現金を着服していました。着服の総額は合わせて約2億円です。
中国銀行では不祥事を未然に防ぐため、行員に年に1度、連続休暇を取得することを義務付けていて、休暇中に客からの問い合わせがあり発覚しました。
中国銀行が禁止している外為FX取引を始めたことで損失が膨らみ、その穴埋めに使ったと話しているということです。約7600万円は運用益として客に返金していて、残りは男性行員と中国銀行ですべて弁済しました。
中国銀行は業務上横領の容疑で、香川県警に刑事告訴する方針です。
KSB瀬戸内海放送
東京大は30日、2013年3月に大学院学際情報学府の周倩氏(当時中国籍、女性)に授与した博士号(学際情報学)を24日付で取り消したと発表した。
日中の新聞を比較分析した博士論文に、他者の著作物からの引き写しや不適切な利用が計320カ所あり、調査委員会による調査や関係者からの聴取の結果、不正行為と認定した。東大の博士号取り消しはこれで6人目。
東大によると、周氏は不適切な引用を認めたが、悪意や故意ではなかったと説明したという。東大は、論文提出時の指導教員だった園田茂人教授を訓告、前任の指導教員の吉見俊哉教授を厳重注意とするなどの処分を行った。
石井洋二郎副学長は「極めて遺憾。教職員・学生に対し、研究倫理のさらなる周知徹底を図り、再びこのような事態が生じないよう全学を挙げて取り組む」とコメントした。
品質保証室長が改ざんに関与するのはかなり悪質だと思う。
この二人の処分次第で会社の姿勢や体質がわかると思う。長期の降格や長期の減給でなければ、運が悪かったな程度の認識だと思う。
会社の中には品質保証部門が顧客に対するごますりや接待、顧客を何とか諫める事までやっていて、個人的には製品に対する品質保証や管理ではないと 思う。外国から導入された制度が日本バージョンになった一例だと思う。チェック機能や製品保証の機能は無くなっている。本来、品質をいかに保証する、又は、 問題のある製品が出荷されるのを防ぐのではなく、会社の利益を考えて辻褄があるように工作する部門である限り、いつか問題を起こすと思う。
「次々と発覚する不正。企業不祥事に詳しい郷原信郎弁護士は、素材メーカーの製品の一部では品質がばらつくことがあり、『他の企業でもデータの書き換えは起こりうる』と話す。」
企業の利益アップよりもブランドの信頼性の維持そして製品の品質を優先する考え方が定着している企業であれば、間違いやヒューマンエラーによる 欠陥品のすり抜けはあっても、故意に欠陥品が通る事はない。企業の体質やモラル次第だと思う。
人間も企業も似たような部分がある。一度、ズル(不正)をすると簡単には止めれない。ズル(不正)なしに良い数値を出すにはもっと努力するか、 改善策を見つけない限り、同じ数値は出せない。製品の一部では品質がばらつくことがある事を知らない企業は少ないと思う。ばらつきや欠陥品を 減らすために多くの企業が努力していると思う。製品のばらつきがあるからデータの書き換えが起こると考える郷原信郎弁護士は現実のケースから言っているのかも しれないが、普通にデータの書き換えは起きると考えるのはどうかと思う。言い方を変えれば、性善説は日本では成り立たない社会になっている、 又は、社会に鳴りつつあるとも解釈できる。
神戸製鋼所や三菱マテリアルで発覚した検査データの改ざん問題が、経団連会長の出身企業である東レにも飛び火した。しかも消費者への公表は、不正が分かってから1年以上経ってから。日本経済を支えてきたものづくり企業の信頼が大きく揺らいでいる。
【写真】素材メーカー3社で発覚したデータ改ざん
「煩雑な作業をしたくない、段取りを省きたいという動機があった」「契約に対する認識の甘さ」
データを改ざんしていた東レ子会社の東レハイブリッドコード(THC)の鈴木信博社長は28日の記者会見で、改ざんの背景に、現場責任者が品質を軽視していたことを挙げた。
THCは出荷前に行う品質検査で、契約内容にあっているかを確かめるため、1製品あたり約10項目の検査を行っている。検査データは「検査成績書」に記され、品質保証室長が最終的に承認するが、2008年以降の室長は2代にわたり改ざんを行った。検査データの管理システムを操作する権限を悪用した。
日々の製造作業では、品質が基準に満たない製品が全体の1~2割ほど発生する。本来なら品質を再測定し、契約内容と多少異なっていても顧客の了承を得られれば「トクサイ(特別採用)」という手法で出荷できる。しかし2人はこうした作業を省いた。
神鋼の不正では、「品質より納期」の風土が背景にあったと指摘された。THCの鈴木社長は、同様に納期の圧力が不正を招いた可能性を示唆している。
東レで発覚した不正は、同社相談役でもある経団連・榊原定征会長が、同社の社長、会長在任中に行われていた。
榊原会長は、神鋼のデータ改ざん問題などについて「メイド・イン・ジャパンへの信認を毀損(きそん)しかねない」と繰り返し発言。27日の定例の会見でも、三菱マテリアルのデータ改ざんに、「日本の製造業に対する信頼に影響を及ぼしかねない深刻な事態だ」と言及したばかりだった。榊原会長は28日、東レの不正について無言を貫いた。
次々と発覚する不正。企業不祥事に詳しい郷原信郎弁護士は、素材メーカーの製品の一部では品質がばらつくことがあり、「他の企業でもデータの書き換えは起こりうる」と話す。
愛知県西尾市のTHCでは28日、同社幹部が従業員に問題を説明した。ある女性従業員は「複雑な気持ちだが、とにかく今は信頼を取り戻すためにできることをやらないといけない」と話した。(山口博敬、友田雄大)
個人的な経験から不正をしても見つからない、発覚しない、又は処分されない事は多くあると思う。だから、不正に手を染める人達は多いと思う。これらの不正は 氷山の一角だと思う。それではなぜ日本の製品は良い評価を受けるのか?単純に日本の文化や日本社会で育った人達のパフォーマンスが海外の文化や国で 育った労働者よりも真面目に働く傾向が高いと言う事だと思う。
ISO:国際標準化機構についてそれほど詳しくはないが、学歴や教育レベルが高くない底辺の労働者を使って 製品を作ると品質にムラがある。そこで、どのように品質を想定の基準内にするプロセス、又は、最低限の信頼を証明する方法としてISO:国際標準化機構 が発展したと思う。単純に歯車として外国人労働者を使う、外国の工場で製品を生産する、その他の理由で製品の管理が十分に行き届かない環境では 品質にムラが出来る。実際の製品の品質は別としても、工程やマニュアルを作成し、現場が理解し、マニュアルを守ればムラや品質が大きく違う 製品が出来ないと考えられるので、安定した品質や品質を心配する企業にISO:国際標準化機構の認定を 受ける事が最低限度の保証だと言う事になったと思う。
日本で職人気質の経営者で管理能力が十分にあれば個人的にはISO:国際標準化機構の認定など必要ない、 柔軟性が失われる可能性もあるからISO:国際標準化機構の認定などない方が良いとも思うが、 神戸製鋼所、三菱マテリアルや東レグループのデータ改竄のケースもあるので最低限の要求や信用する理由としてISO:国際標準化機構 が必要であるとも考えられる。しかし、ISO:国際標準化機構の認定で不正やその場限りのパフォーマンスも 可能なのでISO:国際標準化機構が完ぺきだとは思わない。
問題が明らかにある会社、企業、又は工場ではISO:国際標準化機構の認定を受ける事が出来るレベルでさえも ないので、大きく外れた会社、企業、又は工場の排除と言う意味では良いかもしれない。ただ、ISO:国際標準化機構の認定を 受ける事が出来なくても良い製品は作れる。ISO:国際標準化機構の要求する項目の中には製品の品質とは 全く関係ない部分もある。品質の良さではなく、あくまでも品質のムラを減らす目的や機能が強調されていると感じる。
本当に重要な部分でも不正をするようになったら杭打ち工事のデータ改ざんや偽装のように目に見える問題が起きるケースもある。
メキシコ・熊本地震を体験、驚いた避難の違い「すぐ外に出るなんて」 崩れた新築、「おおらかさ」の功罪10/21/17 (withnews) の記事のように手抜きを受け入れる文化や国民性があれば日本の手抜きは問題ないと言う事になる。実際、ラテン文化の国で成功した工業立国はないと 思うので、どのような方向へ向かいたいのか次第だと思う。
日本も大らかさを取り入れる事も出来る。ストレスやプレッシャーから解放される労働環境も可能かもしれない。しかし、現在の人件費の高い環境の 維持は非常に困難だと思う。信頼性もない、高品質でもない製品に誰が高いお金を払うのか?結局、国際的に高い給料を求めるのであれば、利益が出せる 製品、又は、効率的に仕事が出来る能力や教育レベルが必要とされると思う。それが出来ないのなら、長時間労働や危険な環境での労働などどこかで 妥協しないと高い給料は無理だと思う。
神戸製鋼所と三菱マテリアルに続いて東レグループでもデータ改竄(かいざん)が発覚し、素材メーカーの不正が相次いでいる。これらの不正からは、現場のモラル低下や消費者軽視、縦割り組織の弊害といった、共通の問題が浮かび上がる。世界有数の技術を誇り、自動車など幅広い産業を支えてきた素材産業が力を失えば、日本のモノづくりの根幹が揺らぎかねない。
「特別採用という慣習も動機になった」
不正を行っていた東レハイブリッドコードの鈴木信博社長は28日の会見で、特別採用(トクサイ)と呼ぶ日本独自の商慣行が隠れみのになったとの見方を示した。
同社は、顧客が了承すれば契約の品質に満たなくても納められるトクサイを悪用。性能が満たないのに正規品と偽っていた。同様の悪用は神戸製鋼と三菱マテリアル子会社でも発覚、契約順守や安全優先の意識が薄れつつあることがうかがえる。
日本の素材各社は、衰退が目立つ電機に比べると経営が安定している。だが近年はM&A(企業の合併・買収)で世界規模の巨大メーカーが相次ぎ誕生し、中国勢も台頭。押された日本メーカーは、技術頼みの姿勢を強めている。
東レの不正は、再検査などの煩雑な作業を嫌ったのが動機という。収益確保が難しくなり、技術的なハードルも高まる中、納期順守のプレッシャーを感じていた可能性もある。
神戸製鋼は、傘下にアルミ・銅など7つの事業部門を抱える。三菱マテリアルは事業別に4つの社内カンパニーを設け、権限を大幅に委譲していた。東レも多くの事業を抱え、子会社を含む事業部間の人事交流はあまりないという。縦割りの組織は閉鎖的な風土を生み、経営陣の監視の目も行き届きにくい。
さらに、消極的な情報開示姿勢でも3社は共通している。東レの日覚昭広社長は「神戸製鋼などの問題がなかったら公表しなかったのか」との問いに対し、顧客企業との契約であることを理由に挙げつつ「しなかった」と述べた。そこには企業相手のビジネスを手がける素材メーカーが陥りがちな、消費者軽視の姿勢も見て取れる。(井田通人)
東レの日覚昭広社長と子会社、東レハイブリッドコードの鈴木信博社長の記者会見の一問一答は次の通り。
-不正の動機は。
鈴木氏 規格値からの外れが僅差で、品質上、異常でないという勝手な解釈から行われた。(不適合製品を顧客の了承を得た上で納入する)特別採用という慣習も動機になった。
-公表が遅れたのは。
日覚氏 昨年に不正を把握していたが、安全性に問題はないため、発表は考えていなかった。ただ、今年11月にネット掲示板で書き込みがあり、正確なことを公表すべきだと考えた。
-神戸製鋼所や三菱マテリアルの問題がなかったら公表しなかったのか。
日覚氏 しなかった。
-今後の対応は。
日覚氏 厳粛に受け止め、コンプライアンスの強化や信頼の回復に全力で取り組んでいく所存だ。
東レは28日、自動車用タイヤの補強材などを製造する子会社の東レハイブリッドコード(愛知県西尾市)が製品検査データを改ざんしていたと発表した。2008年4月から16年7月に、顧客と取り決めた規格からはずれた製品のデータ149件を規格内に書き換え、タイヤメーカーなど13社に出荷していた。
データ改ざんをめぐっては、神戸製鋼所、三菱マテリアル子会社で発覚したばかり。経団連の榊原定征会長らを輩出している名門企業グループでも不正が明らかになったことで、日本の製造業に対する信頼がさらに揺らぎそうだ。
日覚昭広社長は同日、記者会見し、「大変なご迷惑をおかけし、申し訳ございません」と陳謝した。不正行為が起こらないよう、16年10月から品質保証体制を改めていた。しかし過去の不正については公表してこなかった。日覚社長は、神戸製鋼のデータ改ざん問題がなければ公表しなかったとの考えを示した。
約4万件のデータを調査したところ、書き換えが見つかった。規格値からの乖離(かいり)はごくわずかで、規格内製品との実質的な差はなく「現時点で法令違反や製品安全上の問題のある案件は見つかっていない」としている。また顧客に現在報告中で、いまのところ「問題がある」との指摘は寄せられていないという。製造過程で同社の品質保証室長がデータを書き換えていたが「規格値からのはずれが僅差で、製品の品質上、異常レベルではない」と勝手に解釈していたという。
不正を行った製品について、顧客に不具合が生じた場合は、誠意をもって真摯(しんし)かつ迅速に対応するとしている。全容が判明したあと、関係者の処分を行う。
同社は東レの合弁会社として61年に設立された東洋タイヤコードが源流。71年に東レの完全子会社となり、14年に現社名に変更した。【川口雅浩】
三菱マテリアルの子会社(三菱電線工業、三菱伸銅、三菱アルミニウム)が自動車や航空機向けなどに出荷した素材製品の検査データを書き換えていた問題は、出荷先が274社と広範囲に及んだ。神戸製鋼所に続く品質データ改ざんで、改めて日本のものづくりのあり方が問われそうだ。
「不具合があるかもしれないと認識しながら製品の出荷を続けていた」。24日の記者会見で三菱電線の村田博昭社長は、不正を把握した今年2月以降も、10月23日に停止するまで不適合品の出荷を続けていたことを認めた。
会見では「出荷を止めるのが当然で、売り上げ優先ではなかったか」などと厳しい質問が相次いだ。村田社長は「全容把握に時間がかかってしまった。親会社に報告して支援を仰ぐべきだった。反省している」と陳謝したが、三菱マテリアルの竹内章社長は「詳細にわたることはコメントする立場にない。把握していないので答えようがない」などと人ごとのように述べ、会場の記者をあぜんとさせる場面もあった。
子会社3社の出荷先は計274社に及び、10月に発覚した神戸製鋼所(525社)とデータ改ざんの手口が酷似している。「測定した記録をパソコンに入力する時、実際のデータと違う数字を入れていた。なぜ起きたのかは、弁護士が入った調査委員会に究明をお願いしている」。村田社長は記者会見で不正の実態についてこう述べた。ゴム素材のパッキンなどの寸法や材料の特性が納入先の要求や社内基準を満たしていないのに、現場の社員が基準に合うよう入力していた。
神戸製鋼は納期やコストを優先した結果、「クレームがない限り、検査や製品の強度などの仕様が軽視され不正につながった」と説明している。この点についても質問が相次いだが、竹内社長は「弁護士らの調査結果を待ちたい」の一点張りだった。
神戸製鋼では、事業所ごとの専門性を重視し、人事異動が少ないなど「閉鎖的な組織運営」も不正の要因となった。三菱マテリアルは不正が発覚した金属事業とアルミ事業のほか、セメント、電子材料など事業ごとに組織が分かれる「社内カンパニー制」を採用している。竹内社長は「社内カンパニー間の組織の壁が高く、人事の交流はほとんどなかった」と述べており、やはり閉鎖的な組織運営が不正の温床となった可能性が高い。
「不正が組織ぐるみだったのではないか」という質問に、竹内社長は「本社の関与はないと思う」と強調したが、こちらも子会社の調査委員会にゲタを預けた格好で、真相解明はこれからだ。不正発覚後も不適合品を出荷していた事実は重大で、今後の対応次第では、神戸製鋼と同様に納入先から部品交換の費用負担や損害賠償を求められ、経営問題に発展する可能性もある。【川口雅浩、小原擁】
経営コンサルタントの小宮一慶氏は「競争が激化するほど質を高め、利益につなげるのが日本のものづくりの強み。逆に品質をごまかすのは日本を代表する企業としての矜持(きょうじ)を欠き日本製の信用を裏切る行為だ」と批判。「取引の開始時には品質をチェックするが、その後は『大企業だから安心』とみなす取引慣行が甘えを許している面もあるのでは」と指摘する。
一般人の考え方ではないのだろうか?商品や企業の選定には、グループ関係、判断する人の人脈や学閥、単純に品質と価格ではなく判断する人と判断される側の担当者の 関係など単純でない場合も多いと思う。それに、品質を簡単に判断は出来ないと思う。現場の人間がいろいろな製品を使った後のデータを持っていないと 比較できない。耐久性が要求される製品は、何年後、何十年後にならないと結果はわからない。わからないからブランドの信頼性が重要な判断基準と なるわけだが、多少誤魔化しても、誰もわからないからとズルをすると意思が強くないと止める事が出来ないくなると思う。
裁判になっても、弁護士や裁判官は技術や理系関係については理解できないから、専門家の信頼性だけの戦いになると思う。業界で力があれば 圧力をかける事も出来るかもしれないから、強いものが勝つ。
三菱マテ系不正とは関係ないが、日本は人件費を上げすぎだと思う。能力があり、結果を出した社員又は結果を出したチームにはそれなりの給料や待遇を 出すべきだと思う。貧富の格差が広がるかもしれない。そこは学校教育の改善で対応するべきだと思う。後は、学歴だけで会社での社員のパフォーマンスが 決まるわけないと思うので、会社が評価方法を改善するべきだと思う。
人件費が上がると生産コストの改善や合理化が出来なければ、コストアップがどこかに歪がでるのは自然な流れだ。見えないのか、見えなくしているだけで 歪は生まれる。安倍首相はこの点について理解は出来るのだろうか?
三菱マテリアルの子会社(三菱電線工業、三菱伸銅、三菱アルミニウム)が自動車や航空機向けなどに出荷した素材製品の検査データを書き換えていた問題は、出荷先が274社と広範囲に及んだ。神戸製鋼所に続く品質データ改ざんで、改めて日本のものづくりのあり方が問われそうだ。
問題の三菱マテリアル子会社3社が扱う素材は鉄道車両や航空機、自動車などに幅広く使われており、取引先各社は不適合品の使用状況や安全性の確認に追われている。相次ぐ「品質偽装」が日本のものづくりへの信用低下に拍車をかける事態となっている。
JR東海の柘植康英社長は24日、東京都内での記者会見で「(不適合品の使用は)1次製品、2次製品、いろいろな可能性がある。調査しないと(不適合品の使用の可能性は)何とも言えない」と述べ、事実確認を急ぐ構え。MRJ(三菱リージョナルジェット)を開発する三菱重工業子会社も「取引の有無を含めて確認中」という。英紙フィナンシャル・タイムズ(電子版)は、航空機大手の米ボーイングと欧州エアバスも自社製品への使用状況を調査中と報じた。
自動車では、トヨタ自動車が国内工場への不適合品の納入がないことを確認したほか、マツダは3社からの直接購入はないと明らかにした。ホンダも二輪、四輪と芝刈り機などの汎用(はんよう)製品では直接購入はないという。他の自動車大手は状況を確認中だが、取引先経由で購入している部品も含めた安全性の検証には時間がかかりそうだ。
東京商工リサーチによると、三菱マテリアルと子会社3社の直接取引先は仕入れ先で1617社、販売先で1052社に上り、7~8割は中小企業。「安全確認や出荷停止で取引が見直されたりすれば、経営体力の乏しい企業の業績への影響が懸念される」(同社)。世耕弘成経済産業相は、24日の閣議後の記者会見で「公正な取引の基盤を揺るがす不正事案」と批判、実態把握とともに出荷先への対応を急ぐよう指示した。
先に不正が発覚した神戸製鋼所では、三菱重工が調達先の変更を検討する考えを表明。川崎重工業やJR西日本が費用負担を請求する姿勢を示している。
経営コンサルタントの小宮一慶氏は「競争が激化するほど質を高め、利益につなげるのが日本のものづくりの強み。逆に品質をごまかすのは日本を代表する企業としての矜持(きょうじ)を欠き日本製の信用を裏切る行為だ」と批判。「取引の開始時には品質をチェックするが、その後は『大企業だから安心』とみなす取引慣行が甘えを許している面もあるのでは」と指摘する。【和田憲二、古屋敷尚子】
中国は不正は当たり前、韓国は不正は他にもやっているから自分だけではないと言う印象は受ける。まあ、現場に行った時の印象と製品や制作された物を見ての個人的な 感想。
今は製品ばかりが非難されているが、研究のデータ、調査方法、調査結果、データの報告書などいろいろな分野で問題があるのではないかと推測する。 行政やお役人がチェックして見つけられないから、問題が放置されているケースが多いのではないかと思う。
法や規則の改正が必要な分野やエリアは存在するのに、行政や役人が仕事をしたくない、自分達の無知や知識不足が露呈する、問題が起きた時に責任を 取りたくないなどの理由で手を付けないケースが多く存在すると思う。
どちらがどれほど悪いのかわからないが、泣いている人達と笑っている人達が存在するのは確実だと思う。
◇三菱電線、2月にデータ改ざん把握、3月に経営陣に報告
23日発覚した三菱マテリアル子会社の三菱電線工業などによる検査データ改ざんは、日本経済を支えてきたものづくりの信頼をさらに揺るがす事態だ。今秋以降、神戸製鋼所の検査データ改ざんのほか、日産自動車やSUBARU(スバル)で無資格者が完成検査をする不正が次々と発覚しており、日本ブランドの信頼回復には時間がかかりそうだ。
三菱電線は、今年2月に水漏れなどを防ぐシール材でデータ改ざんを把握し、3月には経営陣に報告していた。ところが、問題製品の出荷を止めたのは10月23日、三菱マテリアルに報告したのは25日だった。神戸製鋼が10月8日に不正を発表し、批判が高まったことを受けて慌てて親会社に報告し、今回の公表に追い込まれたと見られる。
三菱電線は公表が遅れた理由について、「製品数が非常に多く、事実関係の確認に時間を要した」としているが、結果的に不正を隠蔽(いんぺい)したまま半年以上も取引先に不適合品を出荷し続けたことになる。特に、今回三菱電線などでデータ不正が見つかったのは、航空・宇宙、産業機器など向けに使われる部材だ。信頼性が特に要求される分野でのデータ改ざんだけに、厳しい反応が予想される。
先に不正が発覚した神戸製鋼は、新幹線車両や国産主力のH2Aロケットやボーイング製ジェット機、国内の大手自動車メーカーなどに部材を出荷していた。不正発覚後、三菱重工業が国産初ジェット旅客機のMRJ(三菱リージョナルジェット)のアルミ部品の調達先を変更することを検討する考えを表明したほか、新幹線車両や航空機エンジンを製造する川崎重工業や、新幹線を運行するJR西日本が費用負担を神戸製鋼に請求する姿勢を示している。
三菱マテリアル子会社は23日の発表で、「現時点で法令違反や安全性に疑義が生じる事案は確認されていない」としているが、最終的に安全性が確認されたとしても、取引先から費用負担を請求される可能性は高い。法令違反があったかどうかも、今後の重要なポイントとなる。神戸製鋼の不正問題では、一部製品が日本工業規格(JIS)の認証を取り消された。その結果、今後の取引を見直す企業が出ている。今回のケースでも同様に、顧客離れなど経営への打撃が予想される。【安藤大介】
「三菱電線では今年2月に不正が発覚して3月には経営陣に報告されたが、親会社に報告があったのは10月25日だった。『製品数が非常に多く、確認に時間を要した』という。」
神戸製鋼や日産の不正を見て、公表する気になったのだろうか?
非鉄大手の三菱マテリアルは23日、子会社の三菱電線工業(東京都千代田区)と三菱伸銅(同)の2社が製品の品質データを改ざんしていたと発表した。不正があったのは、三菱電線では航空機や自動車に使われる「パッキン」と呼ばれるゴム部品。三菱伸銅では銅製で薄い板状の「銅条」と呼ばれる自動車向けなどの部品。強度や寸法で顧客が求める基準に達していないのに、不正に測定値などを書き換えていた。
問題の製品の出荷先は、三菱電線が229社(約2・7億個、約68億円分)、三菱伸銅が29社(879トン、6・7億円分)で計258社。2社は問題製品の出荷を停止し、顧客への説明を進めている。現時点で不具合は確認されていないという。
三菱電線では今年2月に不正が発覚して3月には経営陣に報告されたが、親会社に報告があったのは10月25日だった。「製品数が非常に多く、確認に時間を要した」という。三菱伸銅では10月16日に不正がわかったという。
三菱マテは24日に記者会見して不正の詳細を説明する。(野口陽)
朝日新聞社
自動車整備会社に不正な車検を依頼した罪などに問われている仲介業者の男の2人の初公判が、鹿児島地方裁判所で開かれ、いずれも起訴内容を認めました。
虚偽有印公文書作成などの罪に問われているのは、鹿児島市下荒田のカー用品販売業黒岩修一被告56歳です。
起訴状などによりますと黒岩被告は鹿児島市宮之浦町の松村自動車・社長の松村和昭被告らに、必要な整備や検査をしないまま車検を通す、いわゆるペーパー車検を依頼したなどとされています。
22日の初公判で黒岩被告は起訴内容を認めました。
冒頭陳述で検察側は「利益が多く得られると考えペーパー車検を依頼した」と指摘。「不正車検を200台以上行い民間車検の信頼を損ねた」などとして、黒岩被告に懲役1年6か月を求刑しました。一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。
また、不正車検を依頼した罪などに問われている、霧島市隼人町西光寺の板金塗装業、花蔵悦男被告60歳の初公判も行われ、被告は起訴内容を認めました。
九州運輸局はきょう付けでペーパー車検を行ったとして松村自動車に国の指定工場の取り消しなどの行政処分を行いました。
MBC南日本放送 | 鹿児島
商工中金は22日、国の低利融資制度「危機対応業務」の不正による損失が、78億6500万円に上ったと発表した。不正に国から支給を受けた利子負担金などを返還する。
2017年9月中間連結決算に計上した。損失の内訳は、国から受け取った負担金を返還した分21億100万円▽弁護士ら専門家の報酬などの不正調査費24億5500万円▽融資先が倒産した際に政府が一部肩代わりした分の返還10億4100万円--など。
不正の対象となった危機対応融資の9月末時点の残高は、不正調査で営業人員を抑制したことなどで、今年3月末比で約4000億円減となった。中間期の最終(当期)利益は、景気回復であらかじめ倒産を想定して計上していた与信関連費用が戻ってきたことから前年同期比約2倍の207億8900万円と過去最高となった。
危機対応業務は、災害などで一時的に業績が悪化した企業に国が利子の一部を負担する制度。商工中金は、業績書類の改ざんなどの不正をほぼ全店で計4802件(総額2646億円)行っていた。【小原擁】
38年間の長期にわたって日産無資格検査は「完成検査員が不足し、工場ごとの事情を踏まえた検査員の配置も行わなかった」が理由とは言えない。 問題解決さえもしようともしなかった結果だと思う。
ここまで根が深いと日産無資格検査の問題は解決されるであろうが再発防止策で発見されていない、又は、今回してきされていない問題は改善されない であろう。組織の体質のDNAまでしみ込んでいると思える。人間は年を取ると変化を嫌い、現状を基準にする傾向がある。これは日本人だけの 話ではない。日産の上層部がかなりの時間と努力を費やさない限り、DNAのレベルまでしみ込んだ価値観や考え方は変わらないと思う。
日産自動車は17日、国の規定に反して無資格の従業員が完成車の検査に関わっていた問題で、実態調査の結果や再発防止策をまとめた報告書を国土交通省に提出した。報告書によると無資格検査は、38年前の1979年から栃木工場(栃木県上三川町)で行われていた可能性があり、90年代には全6工場のうち5工場で常態化していた。経営陣は実態を把握できず、長期間にわたる不正を許す結果になった。
この日、記者会見した西川(さいかわ)広人社長は「皆様の信頼を裏切った。改めて深くおわびしたい」と陳謝した。経営陣の処分は発表せず、西川氏自身が月額報酬の一部を今年10月から自主返納していることや、他の経営幹部も自主返納する方針であることを示すにとどめた。
報告書によると、不正行為は栃木工場で「79年から実施されていた」との証言があったほか、主力工場である追浜(おっぱま)工場(神奈川県横須賀市)では89年から続いていたことが書類上で確認された。これまで国内全6工場で無資格検査があったとしていたが、このうちオートワークス京都(京都府宇治市)では不正は確認されなかった。
製造現場では、正当な検査と見せかけるために資格者の印鑑を管理する帳簿が作成され、上司の指示で無資格者に貸し出されていた。不正の発覚を免れるため、各工場では国交省などの監査当日に限り無資格の従業員を完成検査から外したり、上司の指示で無資格者が資格者のバッジを付けた上で完成検査をしたりする隠蔽(いんぺい)工作の事例も報告された。
不正の背景については、資格を持つ完成検査員が不足していたことや、工場や日産本社の管理職が無資格検査の常態化に気づいていなかったことなどを挙げた。そのうえで、「工場幹部や日産本社が、有資格者のみが携われる完成検査の業務を踏まえた人員配置を検討せず、人員不足を招いた」などと指摘した。
再発防止策として、日産は既に各工場で完成検査の実施場所をゲートで区切り、有資格者以外の立ち入りを制限。今年度中に、顔認証による入出場管理システムを導入するほか、107人の有資格者を養成する方針だ。
一方、国交省は報告書提出を受けて、「内容を精査し、6工場に立ち入り調査した結果と合わせて厳正に対処する」と説明。「法令に照らし行政処分も検討する」としている。【安藤大介、工藤昭久】
◇日産自動車が公表した報告書の骨子
<不正の原因>
・完成検査員が不足し、工場ごとの事情を踏まえた検査員の配置も行わなかった
・国に代わって完成検査を行う重大性の認識や法令順守意識が欠如
・本社の管理職層と検査を行う現場に距離があり、本社などが不正を見抜けなかった
<再発防止策>
・生産台数を前提とした、完成検査員の育成計画の策定
・完成検査員全員に、検査制度や法令順守について再教育
・国内工場全体を統括する役員職を新設し、本社と工場間の連携を強化
【ことば】無資格検査問題
日産自動車が国内工場で、国内出荷前の新車を最終チェックする「完成検査」の一部を無資格の従業員にさせていた問題が9月に発覚。本来は、必要な知識と技能があるとしてメーカーが資格を与えた従業員が検査しなければならないが、資格のない従業員が従事していた。対策を講じたと公表した後も、違反が続いていたことが社内調査で判明し、全工場の生産・出荷を一時停止した。SUBARU(スバル)でも研修中の無資格者が検査していた問題が発覚している。
日産自動車の無資格検査問題を受け、品質管理の国際標準規格「ISO9001」の認証機関が、同社の国内向け車両の生産に関する認証を取り消したことが分かった。検査データを改ざんした神戸製鋼所の子会社も日本工業規格(JIS)の認証を取り消されている。今後見込まれる影響などについてまとめた。
Q ISO9001やJISとは。
A ISO9001は企業に一定水準の品質管理体制が備わっているかを評価する国際標…
「ISO9001」を取得する多くの企業は信用が理由であるケースもあるであろうが、多くの場合、規則や相手先の要求のために取得している場合が 多いと理解している。
影響が出るのは確実のように思える。故意に不正が行われていているのだから、ISOが要求するトレーサビリティ、内部監査、記録の保管、社員の対する 教育、マニュアルの遵守、そしてこれらが機能しているのか確認する内部監査に不備があるのは明らか。ISOは良い製品を作るためのものではない。 マニュアル通りにプロセスが守られ、品質にムラがないようにするシステムである。本来、計画された品質通り、又は、許容範囲内で出来ていれば 良いのである。
ISOの基準で行くと、日本の文化的な問題で今回の問題が起きたと認める事は、通常業務でISOの要求が満足していなかったと認めるようなものである。 まあ、個人的な意見なので、他の人達や日本品質保証機構(JQA)がどのような考えているのかはわからない。
[東京 15日 ロイター] - 神戸製鋼<5406.T>子会社コベルコマテリアル銅管(KMCT)秦野工場(神奈川県秦野市)の銅管製品(外面被覆銅管)において、製品の寸法や品質、性能や安全性を定めた日本工業規格(JIS)の認証が取り消された。JIS規格から外れた製品にJISマークを付けて出荷していた。
また、国際標準化機構(ISO)の品質管理に関する国際規格「ISO9001」の認証についても取り消された。
JIS表示制度の登録認証機関である日本品質保証機構(JQA)が10月19、20日に同工場で臨時の審査を実施。その結果、JIS規格値を満たさない製品にもJISマークを付けて出荷が続けられていたことがわかり、「その内容が重大であると認められたため」認証取り消しに至ったという。
秦野工場では、10月26日に銅製品の一部(銅及び銅合金の継目無管)でJIS認証が取り消されている。KMCTの販売重量全体に占めるJISマーク表示製品の割合は4割程度。最初にJIS認証を取り消された製品が大半を占めているという。
神戸鋼では「JIS認証の取り消しにより、KMCT社は対象商品にJISマークを表示して出荷することはできないが、性能的には、JIS規格相当の製品を提供することは可能」とし、顧客に対して説明を行っていくとしている。
また、製品データ改ざん問題に関して外部調査委員会が現在進めている調査の報告を踏まえ、再発防止策を取りまとめることとしており「これらの再発防止策を着実に実行することで問題を是正し、できるだけ早期にJIS認証の再取得と顧客の信頼回復を目指す」とコメントしている。
経済産業省は認証機関に対し、JIS認証を受けている20拠点について再審査の検討を求めている。JQAの広報担当者によると、JQAは秦野工場を含む8拠点を認証しており、秦野工場以外の7拠点についても再審査を行っている。
「ISO9001」の認証取り消しについて、神戸鋼の広報担当者は「品質管理体制に関する1つの信用がなくなることにはなるため、何かしらの影響がでるだろう」としながらも、具体的な影響度合いについては不明とした。
*内容を追加しました。
(清水律子)
病的な追っかけが存在するからアイドルは成り立っていると思うが、よほど追っかけていたアイドルが好きだったのか、 追っかける事により人生で欠けている隙間を埋める、または、その部分を振り返る時間を追っかけで誤魔化していたのかもしれない。
兵庫県内の美容院経営者が加盟する「県美容業生活衛生同業組合」(神戸市兵庫区)で事務局員だった50代女性が約1400万円の組合費を着服した問題で、女性が兵庫県警の調べに「男性アイドルグループの追っかけに使った」という趣旨の供述をしていたことが13日、捜査関係者らへの取材で分かった。組合には当初、「親の介護疲れによるストレス」などと釈明していた。神戸地検は女性を不起訴としたが、告発した組合員らは処分を不服として検察審査会に申し立てる。
関係者らによると、女性は出納業務に従事していた2009~16年ごろ、各店舗から集められた組合費計約1400万円を着服し、懲戒解雇処分となった。
女性は今年5月の総代会で動機について「親の介護や一部組合員から嫌がらせを受け、ストレスがたまっていた」と組合員らに説明したが、使途については語らなかった。組合は理事会での決定事項として女性を告訴していない。
捜査関係者によると、同6月に組合員4人の告発を受理して捜査すると、女性が大量のコンサート半券を保管していたのが発覚。女性はアイドルの追っかけを続けるため、チケット購入などに使ったと明かしたという。地検は同10月、女性側が全額を返済したことなどを踏まえて起訴猶予と判断したとみられる。
不起訴処分への不服を申し立てる組合員らは「組合が使途について責任を持って追及しておらず、真相を公判で明らかにしてほしい」などとしている。神戸新聞社は9日に組合へ取材を求め、13日にも再度申し込んだが「理事長が出張中で連絡が取れず回答できない」としている。
鼓膜が破れたから、事件が公になったと言う事か?まあ、自業自得!
四国電力(高松市)の50代の男性営業部長が部下3人を殴り、うち1人にけがをさせていたことが10日、分かった。同社は1日付で営業部長職を解き、出勤停止2カ月の懲戒処分とした。
同社によると、暴行は10月中旬、高松市内の飲食店でグループ会社従業員を含む約40人が参加した懇親会後に発生。店を出た前部長がタクシーが来ていないことに腹を立て、手配担当の男性社員3人の顔をそれぞれ1回平手打ちした。このうち30代の社員は耳の鼓膜が破れたという。
会社側が事情を聴くと、前部長は事実を認め、男性社員に謝罪したという。前部長は過去にも部下に暴力を振るったとして2回厳重注意されていた。
広報部は「あってはならないこと。管理職を含め、しっかりと従業員教育していく」とする。【植松晃一】
他の会社でも理由と効果を考えて判断して継続しているのか思う事が多々ある。ある大手企業の件で、なぜ高学歴の人材がいながら問題を指摘できないのかと 若い頃に質問した事がある。指摘して間違った場合、出世コースからはずれるらしい。また、問題を指摘する事で派閥で力がある人の機嫌を損ねると そこで出世コースから外れるらしい。間違った事でも、間違っていても、他の人達が容認していたり、批判していなければ、それに従うのが無難らしい。 例え、失敗しても、大損害を出しても、誰も問題を指摘しなかったのだから、誰も非難されない。問題が発覚したり、隠せないくなると、痛みや損害を皆で 全体責任として受け入れる。
これって神戸製鋼所や東芝と全く同じとは言えないが、共通部分はあると思う。日本的なのだから、運が悪ければ他の企業も同じ事は起きる。 仕方の無い事。
底辺の人間で理由と効果の事など一切考えずに、上から言われたからと繰り返す人間が多くいる事も経験から知っている。このような人間は 話にならない。考える力は子供には必要と考える機会が必要。しかし、実際は、運が悪かったとか、〇〇部門が悪いとか、管理職が愚かとか非難して 自分の問題には気付かない人々もいるだろう。
日産の検査不正は、国交省の規則に問題があれば声を上げるべきだった。納得行かないから黙って不正するのは良くない。しかし、声を挙げれば 不利な立場になるかもしれないと思ったのなら、国交省にも責任がある。
結局、日本的な問題でお互いは損をする。
最後に、原発問題で文系のコメンテータや批評家がデータや報告が正しいとの仮定で判断している。データや報告に対して問題があるとか、おかしい などの判断は出来ないと言っていた事を思えている。誰かが悪意や自己利益のためにデータや報告の一部を改ざんしたり、事実とは違うメイキングを 含めると間違った判断や結論に達する。プロセスを確認できない場合、間違った方向へ、多くの人々が正しいと思いながら進む。とても滑稽であるが 日本で起きそうな、又は、一部では起きているような事である。
現在は、神戸製鋼所、東芝や日産の問題であるが、形を変えて他の企業でも起きる事だと思う。
アルミ製品などの性能データ改ざんが相次いで発覚した神戸製鋼所。原因と再発防止策をまとめた社内調査委員会の報告書を発表しました。社内の規格は厳しすぎ、そもそも守れないものとして認識されていたということです。
報告書によりますと、最初に不正が見つかったアルミ・銅部門は品質をチェックする側とチェックされる側の両方の部署が不正に関与、少なくとも5年以上の長期にわたっていたということです。原因としては、閉鎖的な組織風土に加え厳しすぎる社内規格がそもそも守れないものとして認識されていた点などを挙げました。
「経営管理構造、そのものが工場において、声を上げても仕方ないという閉鎖的な組織風土を生んだ主要な要因」(神戸製鋼所 川崎博也社長)
今後、事業所間の人材交流や検査データ記録の自動化などで、再発防止に努めたいとしています。
毎日放送
データ改ざんはなぜ起きたのか。神戸製鋼の川崎社長が先ほど調査結果を公表した。
神戸製鋼は不正の背景に経営が利益を重視するあまり、工場の困りごとを解決する姿勢を見せず、現場は声を上げられない、声を上げても仕方ないという風土があったとした。さらに、社内の規格が厳しすぎて、そもそも守れないルールが常態化していたとしている。
工場で何が起きていたのか。現役の従業員が日本テレビの取材に応じ、工場で製造できる範囲を超えた受注があったと証言した。その結果、社内の規格から外れても厳しい品質基準で作ったのだから「まあいいじゃない」となっていたという。
また別の元社員は「納期が迫るとあうんの呼吸で不正が行われたのではないか」と話した。
神戸製鋼所は10日午後、アルミ・銅製品を中心にした検査データ改ざんに関する調査報告書を経済産業省に提出。同日、川崎博也社長らは都内で会見を開き、その内容について説明した。
10月8日に改ざんの事実を公表して以来、同社は原因究明と再発防止の観点で調査を行ってきた。結果はA426枚にまとめられている。
報告書の原因分析では、大きく5つの特徴を上げて、それぞれの対策についても触れた。
(1)収益評価に偏った閉鎖的な組織風土
(2)バランスを欠いた工場運営
(3)不適切行為を招く不充分な品質管理手続き
(4)契約に定められた仕様順守に対する意識の低下
(5)監視機能の欠如、品質ガバナンス機能の弱い本社を持つ不充分な組織体制
これらの対策として、品質検証の制定、品質保証部の新設などを講じるほか、品質監査部(仮称)を立ち上げて、品質ガバナンス再構築委員会と共に、グループ会社も含めたガバナンス強化策などについて検討を進める。
今回の報告書は同社内の原因究明タスクフォースが調査分析を行い作成した。経産省に対して提出するためのもの。同社の自主点検・緊急監査の方法や内容などについての検証や、さらなる原因究明と再発防止は、同社社員を除いた外部調査委員会で継続中で、今回の報告書は「現時点でのできる範囲の対策」(川崎社長)、中間方向のような位置づけだ。
川崎社長は会見冒頭で「不適切行為で多くの皆様に多大な迷惑をかけ、深く深くお詫び申し上げます」と改めて謝罪した。
《レスポンス 中島みなみ》
「偏差値40」の大学か、高校は、レベルで言えば低い。履歴書で学歴の偏差値は記入しないが、学校名は記載されている。山形大が履歴書に偽りがなく、
履歴書と面接で採用したのなら、当人にも問題はあるかもしれないが、山形大にも採用に関して責任はあると思う。
山形大学は国立なのだからもう少し公平に対応するべきだと思う。
教授なのだから、偏差値で人物評価する社会が日本に存在するのは知っているが、あまり露骨にアピールしなくても良いと思う。
山形大の偏差値よりも高い偏差値の大学を卒業した人達が、山形大卒を見下しても反論出来ないと思うよ。別の意味で山形大卒は
偏差値の高い大学卒に山形大卒のくせに文句を言うな、山形大卒のくせしてと言われても、仕方がなく受け入れろと言っているようなもの。
そうなると、帝大の教授達に「山形大の教授をやってて恥ずかしくないか」と言われても、「お前はその程度のレベル」と言われても反論できない。
偏差値も評価方法の一つだけど、偏差値だけで人間の価値が決まるわけではない。
山形大のリチウムイオン電池研究施設「xEV飯豊研究センター」(山形県飯豊町)で、職員の机などに「役立たず」「ボケが」などと書かれた書き置きが残されていたことが10日までに、分かった。同大職員組合は4枚の書き置きの画像を公表し、センター長の男性教授によるパワーハラスメント(パワハラ)と主張している。
組合によると、4枚は昨年9月ごろ、職員の机の上に置かれるなどしていた。筆記具がそろっていないとして「マジックくらい買っとけ!!《役立たず》」と罵倒。コピー機の選定について「誰が選んだこのコピー ボケが!! 遅くて使えん」と書き殴られていた。 掲示物を貼る位置が悪いとして「ここに はるな!!」との内容もあった。いずれもセンター長の筆跡とみられる。
組合によると、ある職員は今年2月8日、センターに来訪した顧客企業の関係者の前で、センター長から「偏差値40」「偏差値40」などと罵倒された。別の職員は昨年9月、学内のパワハラ窓口に相談したところ、大学側が雇い止めを言い渡してきたという。
センター長からはさみを投げつけられたとか、職員が退職して生じるセンターの損失を穴埋めするための寄付を求めてきたという声も組合に寄せられており、把握しているだけで3人の職員が「精神的に続けられない」などとパワハラを理由に辞めたという。
組合はこれまでに3回、パワハラの実態把握や対策などを問う質問書を小山清人学長宛てに提出したが、大学側は「個別の事案には個人情報保護の観点から答えられない」などと回答している。
小山学長は10月5日の定例記者会見で「パワハラがあれば処分している。パワハラは把握していない」などと述べた。
組合の品川敦紀委員長は「職員の机に残した書き置き画像や『偏差値40』などという暴言は、名誉毀損(きそん)でありパワハラの一端で、職員がハラスメント委員会に訴えても公正に取り扱わない大学の体質に問題がある。センター自体を改善する対策を早急に考えるべきだ」と話している。
山形大xEV飯豊研究センターは、山形大と山形県飯豊町が民間工場だった建物を改修して平成24年につくった国内最先端のリチウムイオン電池研究開発拠点。自動車、ロボット関連企業など約50社が研究開発に加わっている。
日産の不正は長年行われていたようなので、安倍首相が給料アップの要請が直接不正に影響しているとは思わないが、辻褄が合わない状況が 発生していれば歪はどこかに現れると思う。
日産車体湘南工場(同県平塚市)でも、今年9月の2交代制導入が人手不足の原因とする証言が多く、「『コストがかかるから人を減らせ』と会社は言う。それで無理をしてしまった」と話す従業員もいた。
上記は給料アップの要請が影響しているかもしれない。
自動車「無資格検査」(日テレNEWS24)
日産自動車の無資格検査問題で、第三者調査の全容がわかった。近年の生産拡大に伴うシフト改編や、団塊世代の退職などで各工場の検査員が不足したのに、有効な手段を講じなかった実態が判明。工場に何人の有資格者がいるのかすら把握しないなど、経営陣の検査に対する意識の薄さが、現場の規範意識を鈍らせた疑いも浮かんだ。
日産は近く、この調査結果などをもとに改善に向けた報告書をまとめ、国土交通省に提出する。
調査によると、無資格者による検査は1980年代から続いていたとの証言がある一方、近年、生産拡大に伴って検査員が不足したことが、無資格検査の原因・背景になっているとの証言が多かった。
国内向け生産が多い追浜(おっぱま)工場(神奈川県横須賀市)には2016年秋、国内生産拡大を目指す社の方針のもと、主力車種「ノート」の生産が移管された。昼だけだった生産体制が昼夜の2交代制になり、検査員が不足した。工場にとっては活気を取り戻す好機で、人員不足を理由に移管を断れない状況だったという。
その後無資格の従業員を検査に従事させることが増え、有資格者しか押せないはずの検査印は「予備印」を購入するなどして、無資格者に貸し出していた。
日産車体湘南工場(同県平塚市)でも、今年9月の2交代制導入が人手不足の原因とする証言が多く、「『コストがかかるから人を減らせ』と会社は言う。それで無理をしてしまった」と話す従業員もいた。
試験に規定がないのなら、同じ問題を出せばほとんどが受かるであろう。少なくとも復習すれば良いだけの事。
結局、全ては再試験の内容次第。
青山直篤、伊藤嘉孝
日産自動車の工場では、ものづくりのプロとしての意識を疑わせる偽装や不正が続いていた。経営陣は、それを放置して生産拡大を現場に求め、世界の自動車産業の覇権争いを演じてきた。第三者調査から浮かび上がったのは、「現場軽視」の姿勢だった。
無資格の従業員が完成検査をしていた問題で、日産自動車は検査員の社内試験で事前に解答を教えるなど不正があったことを明らかにしました。
日産自動車によりますと、第三者による調査で明らかになったもので、完成検査員になるための社内試験で講師が試験内容や解答を事前に受験者に教えるなどしていたということです。日産は、すでに資格を与えているすべての検査員約300人に対して約5時間の講習を受けさせ、再試験をしたうえで完成検査にあたらせることにしました。日産は7日、国土交通省の立ち入り検査で改善が確認された神奈川県の追浜工場など5工場で国内向けの生産を再開しました。
こんな現状の日産の車でもアメリカ人の多くはアメ車よりも日産の車の方が良いと言う事が多い。トランプ大統領、アメ車が日本で売れないと 不平を言うよりも、日産の車よりも安くて良い車を作る方が最優先課題では?
日産自動車の無資格検査問題に絡み、複数の工場では国が監査に入る際、その日だけ無資格者を検査業務から外すなど、組織的に適正を装う工作が行われていたことが新たにわかった。日産は6日、出荷停止していた全6工場のうち京都を除く5工場で7日から出荷を順次再開すると発表したが、安全や法令順守の姿勢を問う声が上がりそうだ。
こうした工作は、関係者への取材で明らかになった。日産は弁護士らを交えた内部調査を進めており、近く国土交通省に提出する報告書でも、指摘される見通しだ。
関係者によると、関東や九州の複数の工場で、従業員から「国交省による監査があるときだけ無資格者を作業ラインから外す隠蔽(いんぺい)工作が横行していた」との証言が示された。一部の工場では、監査時に有資格者であることを示すバッジを無資格者に配り、問題がないと見せかけていた。
日産の無資格検査問題で、国の立ち入り検査の時だけ無資格者を休ませるなど不正を隠ぺいしていたことがわかった。
関係者によると、日産の工場では問題発覚後も無資格の検査員が検査していたが、国土交通省による立ち入り検査が行われる日だけ無資格者を休ませたり、完成車の検査とは異なる生産ラインに配置したりするなどして適切に検査を行っているように見せかけていたという。
日産は検査体制が整ったとして国内の5つの工場で7日から生産を再開しているが、まずは不正の全容解明が求められる。
どんな不正を行っていたのか?
「試験官が受験者に答えを見せており、試験が形骸化していたという。」
試験に通る事が出来ない人間が完成検査員になれるのに、検査員になれない人材とはどの程度の能力や知識があるのか?
日産、発覚後も無資格検査…社長会見を現場無視 10/18/17(読売新聞)の記事だと 凄く簡単な検査しかしないので完成検査員になるのは簡単ではないの?
[東京 7日 ロイター] - 石井啓一国土交通相の7日の閣議後会見で、日産自動車<7201.T>が完成検査員になるための試験で不正を行っていたことについて「完成検査員の育成プロセスをないがしろにする極めて不適切な事案だ」と述べ、再発防止の徹底を求めた。その上で「今回発覚した事案の再発防止策の検討、実施を含めて完成検査が適切かつ確実に実施されるよう指導していく」と語った。
日産自動車は6日、完成検査員任命・教育プログラム運用面で瑕疵が発見されたとして、再教育・再試験など追加の改善措置を講じると発表した。
日産自動車をめぐっては、国交省の立ち入り検査時に、完成車検査が適切に行われているかのように装っていたとの報道も出ている。これについて石井国交相は9月の立ち入り検査時に「日産側の不適切な対応があった」ことを明らかにした。すでに9月29日に日産自動車に対して指摘しており、その後、経過報告も受けているという。
石井国交相は「過去の立ち入り検査時の対応を含め、これまでの経緯や事実関係について徹底的な調査を指示し、1カ月をめどに報告を求めている。今後出される報告の内容を詳細に把握、検討した上で、厳正に対処していきたい」と語った。
刑事告発の可能性については「日産の報告書の内容を精査するとともに、立り入り検査でわかった事実と突き合わせながら、しかるべき事実が認められた場合には厳正に対処していく」と述べた。
日産自動車の検査不正では、制度の問題点も指摘されている。石井国交相は「完成検査について今後見直すべき点はないか、試験のあり方も含めて、検討していきたい」と語った。
(志田義寧)
日産自動車で無資格の従業員が完成車両の検査をしていた問題を巡り、有資格の従業員の一部は、資格を取得する社内試験を受けた際、事前に関係者から試験の解答を教えてもらっていたことが、弁護士など第三者を含む社内調査チームの調査でわかった。
日産は資格取得制度についても厳しく批判を浴びそうだ。
資格取得を目指す従業員は検査の基礎知識などを問う試験を通過した後、資格を持つ「完成検査員」の指導を受けながら現場で研修を行う。その上で最終試験が実施され、合格者に「完成検査員」の資格を与えている。
日産によると、試験解答の漏えいが判明したのは国内6工場のうち、追浜(おっぱま)工場(神奈川県横須賀市)、日産車体湘南工場(神奈川県平塚市)、日産自動車九州(福岡県苅田(かんだ)町)、日産車体九州(同)、栃木工場(栃木県上三川(かみのかわ)町)の5工場。「オートワークス京都」(京都府宇治市)だけ試験の不正がなかった。
日産自動車は6日、車両の完成検査を担う資格者を社内で認定する筆記試験をめぐり、受験者に解答を丸写しさせる不正行為が一部で行われていたと発表した。日産は再発防止策を追加で講じた上で、京都府のグループ会社工場を除く5工場で7日から新車の生産・出荷を順次再開する。
日産は、無資格検査問題を受けて国内全6工場で生産・出荷を停止していた。京都の工場も近く再開が認められる見通しだ。
不正行為は、弁護士らを交えた第三者による調査で見つかった。試験官が受験者に答えを見せており、試験が形骸化していたという。完成検査員の教育では、自動車の構造に関する基礎知識を習得させる講習について規定の72時間より短縮していたケースもあった。国土交通省は完成検査員の再教育・再試験を条件に、生産・出荷の再開を認めた。
無資格検査問題で日産は3日までに、完成検査工程を柵で囲って資格を持たない従業員が入れないようにしたり、業務の運営状態を1日4回確認したりする再発防止策を国内6工場に導入した。国交省は立ち入り検査などを通じ改善状況を確認した。
神戸製鋼所によるアルミニウム製品などのデータ改竄問題で、過去に複数の役員らも不正を黙認していたことが6日、関係者への取材で分かった。神戸製鋼は上層部の関与は認めていないが、不正は会社組織全体にまん延していたことがあらためて浮き彫りとなった。
神戸製鋼のOBが共同通信の取材に応じ「技術系出身の役員らは不正の事情は知っている」と証言した。神戸製鋼はこれまで工場長レベルが関わっていたとしてきた。
不正を巡っては、性能などの仕様を満たさない製品を顧客に無断で納入していたことが判明している。仕様不足が軽微な場合、顧客の了解を得て購入してもらう「特別採用」という慣行があり、神戸製鋼はこれを悪用していた。別のOBの証言では、不正の許容範囲をメモにして歴代の担当者が引き継いでいた。
経済産業省は原因究明と再発防止策をまとめるよう求めており、神戸製鋼は今週中にも報告する見通し。
英領バミューダ諸島に拠点がある法律事務所などから流出した膨大な電子ファイル「パラダイス文書」には、KDDIが過去に公表していた香港子会社の不正経理の内幕が垣間見える資料もあった。不正に関わったとされる子会社の当時の役員が発覚前、KDDIが求める監査法人の変更に抵抗。結局、変更は1年余り後になり、新たな監査法人が不正を見つけていた。
【写真】香港にあるDMXテクノロジーズ・グループの事務所=10月19日、木村健一撮影
この子会社はシンガポール上場のシステム開発会社「DMXテクノロジーズ・グループ」(登記上の所在地はバミューダ)。両社の公表資料によると、KDDIは2009年に買収した。監査法人の変更は14年。新たに契約した米大手会計事務所は14年12月期決算の監査の際、中国の会社に通信機器などを売る取引で架空取引の可能性を指摘。役員は英領バージン諸島に設立した会社を取引に介在させていた。
15年2月、DMXの役員2人が香港の警察に逮捕された。KDDIは3月に不正経理を発表し、5月に337億円の特別損失を計上した。
パラダイス文書には、これに先立つ12年11月のDMXの監査委員会議事録がある。KDDIから派遣された幹部が、円滑なコミュニケーションのため全グループ会社の監査法人を同一にする方針を説明。費用が10%安いとの指摘もあった。これに対し、DMXの役員らは「費用は変更の正当な理由ではない」「株価に悪影響を与えかねない」と反論。議論は持ち越された。
取材に対し、KDDI広報部は「子会社の監視体制が不十分だった」と説明。不正経理の動機や目的については「旧経営陣に事情を聞けなかったため分からない」としている。(木村健一)
■監査法人変更、なれ合い防ぐ
KDDI子会社の不正経理について、会計監査に詳しい八田進二・青山学院大教授は「子会社などの現場側は業務効率が落ちるなどとして監査法人の変更に抵抗しがちだ。海外企業を買収した日本企業がイニシアチブを取れないこともよくある。親会社は指揮命令系統を明確にして意思を貫く必要がある」と指摘する。
監査法人の変更をめぐっては、企業とのなれ合いを防ぐために一定期間ごとに変更させる制度の導入が欧州で進んでいる。国内でも導入に向けた議論が始まっており、金融庁が今後、企業や機関投資家から聞き取るなどして調査を進める。
経済界には変更に伴う引き継ぎコストが大きいとして慎重な意見が根強いが、八田教授は「制度の導入は、企業と監査法人の緊張関係を持たせるための一つの方法だ」と話す。(北川慧一)
池田直渡がどのような人物か全く知らないが、かなりこじつけ、又は、自分の考えを正当化するために書いているだけのじゃれ事のように思える。
「本来的なコンプライアンス」の意味がどうであれ、現在、規則を遵守する意味で日本では「コンプライアンス」が使われている。 日本でよく使われる「リベンジ」は再挑戦の意味として使われているが、英語では復讐や報復の意味でよく使われる。
許認可権を握る監督官庁(国交省)の法律や規則が今の時代にあっていないと思うならば、理由を公に説明し、国民や消費者にアピールすればよい。 そして、監督官庁(国交省)に法や規則改正を要求すべきだ。黙って違法行為を継続するのは大手企業の対応としては問題があるのではないのか?
多くの人々が納得しないから、法や規則を守らなくなったらどうなるのか?外国で大麻が合法であるから、日本で吸って良い理由になるのか? 捕鯨をなぜ日本は継続しようとするのか?多くの西洋の国々から批判されているではないか?
「池田直渡」で検索すると下記のサイトを見つけた。他の人々は池田直渡の意見や信用度をどのように評価しているのだろうか?
池田直渡氏の記事に違和感を覚えました(その2)(BMW@FUNブログ)
完成検査問題で日本の自動車産業が揺れている。日産自動車では不祥事を受けて2週間をめどに国内市場向けの車両出荷を停止した。各ディーラー店頭にある流通在庫を含め115万台がリコール対象となり、影響は100億円とも試算されている状態だ。スバルでも同様の問題が指摘された。
メーカーでの品質チェックの様子
問題となっているのは、生産の最終過程において、国土交通省の指定する完成検査が無資格者によって行われていたことである。法令順守の問題だ。「法律を破ってはいけない」。そこには明確にアウトとセーフの判定基準があるので、とても分かりやすく、批判もしやすい。完全な思考停止をしていても「悪いことです」と言えてしまうからだ。さらに「安全をないがしろにするのですか?」とでも言い足せば反論も封殺できる。非常に簡単である。
●アップデートされない規制
しかしながら、世の中には笑ってしまうような法律もある。国内でよく話題になるのは「軽犯罪法第1条20項」。ここには「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」とある。法令順守の観点から言えば、誰か1人でも「はしたない」と思えば、体の一部である太ももを露出するミニスカートは違法ということになる。
制定された1948年(昭和23年)の秩序としてはそうだったかもしれないが、平成の世も30年になろうとしている今、それは滑稽でしかない。無駄で無意味な規制だ。ある日、ミニスカートが出荷停止になり、出荷済みのスカートを膝丈に改修する作業をメーカーが行なったら、それは誰が見ても異様に感じるだろう。
だが、自動車の場合、同じ苔の生えた古いルールにも関わらず、そうはなっていない。メディアがこぞって「太ももの露出する服を売るのはコンプライアンス違反で、日本のものづくり神話は崩壊した」と叫んでいるのである。神話時代から連綿と続くカビ臭い法律を大事にするという意味では、なかなか風刺の効いたコントである。余談だが、道路運送車両法の制定は51年(昭和26年)である。後ろに挙げる項目を見ればそれが実感できるだろう。
さて、となると筆者はここで「ゼロ回目の車検」となる完成検査が、いかにポンコツで古臭く、無意味なルールであるかを説明しなくてはならない。
●完成検査の実態
バカバカしいその内容を書き出してみよう。項目数だけは多いので、冗長にならないように抜き出すが、それでも法律のほうが冗長なのは筆者の責ではない。なお、抜き出す際には、できるだけまともなものを選ぶようにする。つまり、抜き出されてないものはこれよりバカバカしい。
車検証と実車の同一性確認
(厳密には車検証ではなく完成検査証)
車体番号
エンジンの型式
車体寸法
エンジンルーム内の検査
潤滑装置の油漏れ
プレーキ配管の緩みや液漏れ
冷却装置の水漏れ
パワステベルトの緩み
キャブレターなどの燃料漏れ
排ガス減少装置の取り付け状態
バッテリーの取り付け
外観の検査
バックミラーの視野と取り付け
警報機(クラクション)の音量
ランプ類の性能・取り付け・光軸
最低地上高
ワイパーの取り付け
車体の傾きと突起物の有無
窓ガラスの透明度や歪み
タイヤやホイールの歪みや損傷
車室内の検査
ハンドルの遊びとガタ
ペダル類の遊びとガタ
メーター類の取り付けの有無と状態
座席の寸法と間隙
ヘッドレストの有無
検査機器による検査項目
ブレーキの効き
スピードメーターの誤差
サイドスリップの量
排気騒音
ランプの光軸と光度
排気ガスの濃度
と、まあこんな感じで、他にどうでもいいから省いたものがどんなものか例を挙げておくと「サンバイザーの取り付け」とか「ウィンカーの点滅速度」とか無限にある。ざっと見渡して一番に感じるのはバランスの悪さだ。特定の部品を散発的に取り上げて取り付けの確認を曖昧に指定しているに過ぎず。相当原始的なクルマが想定されている感じを強く受ける。エンジンや車両制御に用いられるコントロールユニットなどの電子部品に関する記述がほぼない。日本では1970年代から取り入れられてきた部品である。
工業高校の授業で生徒が作ってみたクルマだとか、ユーザー車検の時に注意する項目だというならまあ分からないでもないが、世界で戦う自動車メーカーの製品をチェックするに際してこの項目のバカにしたようなレベルの低さはどうだろう?
プロの料理人に包丁の持ち方やコンロの着火方法のテストを受けさせるようなもので、全部できているのは最低以前の条件である。そんなものを有資格者が検査しなくてはならないとする規定そのものがアホ臭い。小泉構造改革で規制緩和が叫ばれてから17年。こんな規制が残っているから数十年の時が失われているのだ。
●メーカーの品質担保手法
現実はどうか? メーカーの生産現場へ取材に行ったことがあるが、すべての部品の組み付け段階で、厳密なチェックが行われている。
必要な部品が部品トレーから取り出されたか、その部品を取り付けるために適正な工具は作動したか、組み付けに油脂類が必要なら、その油脂のフィラーはホルダーから取り上げられたか。そして組み付け段階が終わるとロボットアームに取り付けられたカメラがグルグルと周囲全方位から撮影し、リアルタイム画像チェックによって部品の位置と角度が適正かどうかが判別される。それもすべての工程ごとにリアルタイムでチェックされ、異常があればラインは止まる。
生産効率が高い工場であればあるほど、ミスが起きたら、瞬時に察知してラインを止めないと膨大な量の不良品を作ってしまう。それは死活レベルでメーカーの首を絞める。だから万全の体制を持って厳しい検査が行われている。その精度と細かさは役所の指定するチェック項目の比ではない。21世紀の現在、そんな低レベルのことができていなければとっくにメーカーはつぶれている。
そもそも世界の国々では日本のようなバカバカしく厳しい車検制度がない。米国などは定期的な排ガス検査しか行わないので、完成検査をクリアしていなくてもリコールにはならない。役所のお墨付きなどなくてもメーカーの検査を当たり前に信頼して製品を買っているわけだ。
法令を順守しなかったことは悪くないとは言わない。しかしケースとしては実害が発生しない単純に形式的な違反である。神戸製鋼のケースとは次元が違う。これほどまでに社会を揺るがす問題にする必要があるだろうか? 元はと言えば形骸化したルールが安全に貢献するかのように語っていることの方が問題で、完成検査も購入後の車検も無駄にクルマの維持コストを増大させている。被害者はユーザーである。安全は常に手間も含むコストとのバランスで考えるべきで、「命がかかっているから」という理由で、通勤電車に航空機並みの手荷物検査をできるかどうかを考えてみれば分かるだろう。厳重であることを必ずしも是とはできないのだ。ましてや実際の安全に寄与しない検査など、ユーザーに無駄に負担コストを掛けるだけである。
●2つの悲劇
今、日本には2つの悲劇が起きようとしている。まずは1度決まったら、時代に合わせてアップデートする気がまったくない規制。そして「コンプライアンスとは単純に法令順守のことである」という誤解である。
これについては弁護士の郷原信郎氏が2007年に表した名著『「法令遵守」が日本を滅ぼす』(新潮新書)で10年も前に喝破していた話である。郷原氏は、「コンプライアンスとは単に法を守ることではない。それは法を守ってさえいれば良いという誤解を世間にまん延させ、この国の根幹を深く着実に蝕んでいる」とまで言う。
こうした表面的な法令順守の圧力が強まれば、経営者はひたすら法令順守に躍起になり、現場の従業員は新たな試みを敬遠する圧力になる。どちらも事なかれ主義の思考停止に向かうのだ。ダイナミックに変化し続ける世界経済の中で日本企業が戦っていく中で、老朽化した規制は足を引っ張ることにしかならない。
こうした問題に際しての日本の特殊性として、特に問題なのは、客観的な安全性よりも消費者や監督官庁との信頼関係の喪失問題に主眼が置かれてしまう点だ。今回の無資格者による完成検査は、より厳しいメーカー規定による検査をクリアしている以上、安全性に問題が起きているとは到底思えない。単純に、法令順守をしなかった点について「ルールを破った信頼できないメーカー」という烙印が押されていることになる。
もちろんメーカーはそうしたステークホルダーから信頼されることは重要なことだ。そこに際して外野であるメディアが、完成検査の内容も知らずに「コンプライアンス違反」と騒ぎ立て、その結果、日本企業が信頼を失っていくとしたら、日本のものづくり神話を崩壊させているのは果たして誰なのだろうか?
なお、書き添えておけば、許認可権を握る監督官庁(国交省)が怖くて、バカバカしいと思いつつ、こんな旧弊な規制の緩和を進めるべく努力しなかったメーカーの側にも責任はないとは言えない。力関係を考えると少し酷な言い方だとは思うけれど。
では、本来的なコンプライアンスとはどうあるべきかについて、郷原氏はこう言う。「本来のコンプライアンスとは、組織に向けられた社会的要請に応えて、しなやかに鋭敏に反応し、目的を実現していくこと」。そのために必要なのが「社会的要請に対する鋭敏さ」と、「目的実現に向けての協働関係」であると言う。
つまり、日本企業が世界で勝ち抜いていくためには、役所もまた「社会的要請に対する鋭敏さ」と、「目的実現に向けての協働関係」を強く自覚し、新時代の要請に向けて企業の真のパートナーとして規制をアップデートしていかなくてはならない。サンバイザーの取り付けに権力を振り回している場合ではないのだ。
願わくばこれを読まれた読者が問題の本質を理解し、真のコンプライアンス時代が一歩ずつ進んでいくことに力を貸していただけることを。
(池田直渡)
アフリカは綺麗ごとでは生きていけない世界があると言う事を意味しているのかもしれない。
【AFP=時事】国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)は、2014~16年に西アフリカでエボラ出血熱が流行した時期に、職員が不正を働いた事例を数件確認したと発表した。不正による損失は推計600万ドル(約6億8000万円)に上るという。IFRCは「憤慨している」と述べ、「関与した職員の責任を問う」と強調した。
エボラウイルスは主にギニアやシエラレオネ、リベリアで1万1300人を超える死者を出し、推計2万9000人が感染した。
IFRCによると、シエラレオネで元職員が銀行と「共謀」し、IFRCに210万ドル(約2億4000万円)の損失を与えた可能性を示す証拠が発見された。ギニアでは通関サービス業者による水増し請求や請求書偽造により120万ドル(約1億4000万円)の損失が出ており、別の事例2件についても調査中。IFRCはリベリアでも、支援物資の価格や人件費が270万ドル(約3億1000万円)水増しされていたことを確認したという。
IFRCは2014年以降、「高リスク状況」での支出に制限を設けたり、訓練を受けた監査役を救援チームに派遣したりするなど、業務上の不正対策を強化しているという。【翻訳編集】 AFPBB News
指導を無視し続けたのだから仕方がない。自業自得。もし、無視したのが単純に悪意だけでなく、会社の財務問題が理由であればこの会社は終わりかもしれない。
あくまでも勝手な想像だが、改善を無視し続けた理由は何か?
運が良くて回収費用の損害負担、運が悪ければ、回収費用の損害負担、商品の損害賠償、そして取引停止。
いわき市の食品製造会社「営洋」が保健所の許可を得ずにカップ麺の具材となる食肉製品を製造した問題で、営洋から具材のチャーシューを仕入れている大手食品メーカーの明星食品は3日、4種類のカップ麺計67万4千個を自主回収すると発表した。明星のほかにも大手食品メーカーが営洋と取引しており、無許可製造の影響が広がる可能性もある。
自主回収を受け、営洋の女性従業員は福島民友新聞社の取材に対して「責任者が不在のため、答えられない。明日(4日)以降に社内で協議して対応する」と話した。
営洋を巡っては、いわき市保健所が本社工場の立ち入り検査を行い、無許可製造を確認。衛生上の配慮が必要な魚肉ねり製品と、製造許可のない食肉製品の製造を、本社工場で行っていたため、同保健所は製造場所を区切って許可申請するよう複数回、指導していた。だが、改善されなかったため、市はいわき中央署に刑事告発していた。同署は10月31日、食品衛生法違反の疑いで本社工場や小名浜工場を家宅捜索した。
市や同署によると、営洋は小名浜工場の設備改修のため、7月中旬頃から、カップ麺用乾燥チャーシューの製造を、製造許可がない本社工場の一角で行っていた疑いがある。
同社幹部はこれまでの福島民友新聞社の取材に、本社工場での無許可製造についての事実を認めている。
明星は「商品に使用しているチャーシューが、食肉製品製造許可のない工場で製造された疑いがある」として回収を発表。「食べても健康に影響を及ぼすことはないが、万全を期す」としている。
福島民友新聞
責任を明確にしたくない力が作用すれば、最近、はやりの「忖度」と言う言葉か報告書には使われそうな気がする。
神戸製鋼所の検査データ改ざん問題で、複数の元役員が在職中に不正を認識していたことがわかった。これまで神鋼は、工場の管理職を含めた従業員数十人の関与を認めていた。不正を知りながら役員が長年放置してきたことになり、神鋼の法令順守の姿勢がさらに厳しく問われそうだ。
神鋼の役員経験者の中には、アルミ・銅製品の製造拠点の工場長など、生産現場にいたOBが複数いる。関係者は「(不正を知っていたのは)1、2人ということはない」と話した。
工場勤務時代に現場で改ざんを知った後も、役員会などでこうした事実を報告せず、黙認してきた可能性が高い。役員たちが黙認してきたのは、「不正製品でも品質には問題がない」との判断があったとみられている。
神鋼のこれまでの調査では、現場の管理職がかかわる組織的な不正が行われていたことがわかっている。10年前に行われていた例もあった。一方で、川崎博也会長兼社長と梅原尚人副社長は、アルミ・銅製品をつくる工場でのデータ改ざんについて知ったのは、今年8月末が初めてだったと記者会見で説明してきた。
一連の不正について、弁護士でつくる外部の調査委員会が現在、全容解明や原因究明を急いでいる。役員経験者による不正の認識や関与の度合いも調べると見られる。
朝日新聞社
国交省を完全に馬鹿にしているのか、それとも、日産は対応できるような組織ではないと言う事なのか?
「関係者によると、2日までに福岡県苅田町にある2つの工場や神奈川県平塚市にある工場で、日産側が示していた完成検査の手順が整っていないなどの不備が複数確認されたという。」
建前のマニュアルと現場が通常に行っている手順が大きく違いすぎて、パニックや混乱が起きていると言う事なのか?
三菱と違って日産は国交省の検査対応が出来ていないと言う事なのか?三菱の検査対応とは、要するに誤魔化しが仕事の一部となっていたという意味。
日産自動車の無資格検査問題で、生産再開に向けた国土交通省の立ち入り検査でも改善策が徹底されていなかったことが判明し、国交省は3日、福岡県の2つの工場に対し異例の再検査に乗り出した。
日産は、一連の無資格検査の問題を受け、現在国内にある6つの工場全てで国内向けの生産を停止している。生産再開に当たり、日産は、検査が確実に行える態勢が整った工場について国交省に報告し、国交省が1日から順次、立ち入り検査を行っている。
しかし、関係者によると、2日までに福岡県苅田町にある2つの工場や神奈川県平塚市にある工場で、日産側が示していた完成検査の手順が整っていないなどの不備が複数確認されたという。
こうしたことから国交省は3日、福岡県の2つの工場で異例の再度の立ち入り検査に乗り出していて、引き続き日産に対して改善を求める方針。
知らないだけで他の会社も一長一短があると思うし、個人の価値観や働き方の合う、合わない、又は、他の会社よりもましの場合もある。
個人的な意見だが、報道やメディア関係で働きたいと思った事は一度もない。
電通に続いて、またも若い命が過労で失われるというショッキングな事実が発覚した。平成25年7月に過労死したNHK首都圏放送センターの記者、佐戸未和さん=当時(31)。4年余り経って公表したNHKは、対応のずさんさもあって佐戸さんの両親と対立するという不幸な事態を招いた。両親は「NHKは社会の木鐸(ぼくたく)として世の中に警鐘を鳴らしてきたが、自らに起こったことは棚上げしたままではないか」と怒りの目を向けている。(社会部 天野健作)
■「誰も責任を取っていない」
「娘の過労死はNHKが(10月)4日に公表したが、私たちの思いが正確には伝えられていないことや、事実誤認もある」。13日に記者会見した佐戸さんの父親の言葉には怒気がこもっていた。
佐戸さんの死後、母親は精神的に不調になっていたが今年に入って回復し、過労死のシンポジウムなどに行けるようになった。しかし、取材に来ていたNHKの記者やカメラマンに話しかけるも、娘の過労死の事実を知らなかったことに驚く。さらに、命日の7月24日の前後には毎年、NHKの幹部が自宅を訪れていたが、「今年はなしのつぶてだった」というのも不信に拍車をかけた。父親は次のように訴える。
「このままでは未和の足跡がNHKには何も残らず、過労死の事実も伏せられたままいずれ風化し、葬り去られるのではないかという危機感があった。記者の過労死は不名誉な案件として表に出さない方針にしているのではないか。NHK内で自己検証もされておらず、誰も責任を取っていないのではないか」
NHKは4年間、過労死を公表しなかった。その理由を「遺族側代理人から、家族が公表を望んでいないと聞いていた」と説明していたが、父親は「そんな事実はない」と否定。代理人の川人博弁護士も「私が公表しないでほしいと言ったことはない」と述べた。
■同僚が法要で暴言
なぜ佐戸さんは死なねばならなかったのか。
平成17年にNHKに入局し、最初の赴任地は鹿児島だった。22年から首都圏放送センターに所属し、父親は「24時間臨戦態勢のような記者の勤務は肉体的にも精神的にも過酷。あの小さな体でよくがんばっているな」と感心していたという。
担当していた都庁は激務だった。25年は6月の都議選、7月の参院選と続き、候補者や陣営関係者への取材、獲得票数を予想する票読みなど多忙を極めた。佐戸さんは参院選の投開票3日後の24日に都内の自宅で死亡、発見時には携帯電話を握りしめていたという。
当時の都庁を担当するNHKの記者クラブには、5人の記者がいた。佐戸さんのほかには、男性キャップと男性のベテラン記者3人。佐戸さんは一番の若手で独身ということもあって身軽のため、寝る暇も惜しんで駆け回っていたようだ。
「チームとして問題がある。普通の会社の組織であれば、若い女性社員が連日連夜の残業、土日出勤がずっと続けば、誰かが協力して助け合うはずだ」。佐戸さんの父親はそう嘆く。
労働基準監督署の認定では、亡くなる直近1カ月の時間外労働は159時間に上ったが、遺族側が勤務記録を調べたところ、この月は209時間。ただNHKは記者に対し「みなし労働時間制」を適用していたため、正確には「残業時間」というものはない。
これがNHK側の勘違いを招いた。NHKの関係者は「記者の仕事は個人事業主のようなもので、休憩も出勤時間も自由にできる」と両親に告げたという。確かに自営業者などであれば労働基準法の規制は及ばないが、記者は労基法で保護される労働者だ。雇用主には労働者の健康確保を図り、適正な労働時間管理を行う責務がある。
法要の際にさらに追い打ちをかける場面があった。弔問に訪れたNHKの元同僚に対し、佐戸さんの母親が「未和はわが家のエースでした」と話すと、元同僚は自分の手帳を見せながら「要領が悪く、時間管理ができなくて亡くなる人はエースではない」と返してきたという。
■拉致問題の取材に傾注
佐戸さんが亡くなった後、同僚らがつづった文集がある。そこには佐戸さんの仕事への熱い思いや、優しい人柄があふれていた。
ある同僚が、東京に異動してから夏休みを利用して鹿児島へ行くという佐戸さんにその理由を尋ねると、「拉致被害者の両親に招かれて、泊まりに行く」と答えた。鹿児島では熱心に北朝鮮の拉致問題について取材していたという。同僚は「両親からの信頼が厚く、実の娘のようにかわいがられていたようだ」と記した。
首都圏放送センターでも幅広い取材活動に打ち込んだ。留学生の雇用問題のためウズベキスタン出身の学生に密着取材したり、鶏卵が高騰した際には築地の老舗の卵焼き店に突撃取材したりした。茨城県の取手駅前で発生したバス通り魔事件では、乗車していた女性の生々しい証言を取った。
ある同僚は佐戸さんの死後、がん患者のNPOやダウン症の子供の支援の現場を取材した際、「前、佐戸さんに取材してもらって」と言われ、「佐戸の優しさが取材先にも届いている」と感じたという。
NHKは「ご両親には過労死を防げなかったことを心からおわび申し上げます。ご両親の思いを真摯(しんし)に受け止め、働き方改革に不断の取り組みを行ってまいります」とコメント。
木田幸紀放送総局長は23日の定例会見で、非公表の理由を両親らが「事実と異なる」と否定していることについて、「私たちはそう聞いていた。ただご両親の発言は重く受け止めたい」と語った。
■みなし労働時間制 (1)事業場外みなし労働時間制(2)専門業務型裁量労働制(3)企画業務型裁量労働制-の3種類があり、記者職は(2)にあたる。実際の労働時間数とはかかわりなく、労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなしている。
日産自動車が無資格の従業員に新車の検査をさせていた問題で、国土交通省は1日、日産自動車九州の工場(福岡県苅田町)への立ち入り検査を始めた。日産側から「再発防止策が整った」と報告があったため、停止中の出荷を再開できるか確認している。
午前9時半すぎ、国交省自動車局の職員ら6人が工場に入り、日産九州幹部らから約30分説明を受けた。その後、検査工程の確認を始めた。日産は、問題ないと判断されればこの工場の出荷を再開する方針。出荷停止中の全6工場のうち、残り5工場ではまだ是正作業が続いているという。
石井啓一国交相はこの日の閣議後会見で、改善の自己申告では不十分で「国交省としても確認の必要がある」と、立ち入りの狙いを説明した。また、同じく不正が発覚したスバルの群馬製作所(群馬県太田市)については、立ち入りにより改善を確認済みだと明らかにした。(田幸香純、伊藤嘉孝)
朝日新聞社
能力や学歴も重要であるが、簡単には判断できない人間性は重要であると思う。
仮定であるが、給料の割には仕事がキツイとか、仕事は一般的にキツイはないが当人がそう思っていない、又は、キツイと感じると 「検査がしにくい」との理由で検査をしない可能性がある。「検査がしにくい」と解決方法を上に相談するよりも、黙って誤魔化す方が 良いと感じさせる雰囲気や上司の存在があったかもしれない。仮定の話なので何とも言えない。
ある会社は問題を上に報告しない雰囲気があった。社長室に問題を上げると無視しなくなったが、最後まで、担当は問題を文書にしなかった。 この会社の従業員数は当時で約4000人、どれくらいのカテゴリーに入るのかは知らないが、このサイズでもこの程度である。
組織が上手く機能していないと事なかれ主義で問題を隠す、又は、報告しない。問題が発覚した時には問題が大きくなっている事が多い。 チェックや管理を行った組織にも問題があると思うから、自業自得だと思う。
工事を請け負ったグループ販売店「東京ガスライフバルTAKEUCHI」(練馬区)の作業員が正社員、契約、又は派遣社員なのか知らないが 真剣に解決策を考えないと似たような問題は起きると思う。まあ、どんなに頑張っても絶対又は問題なしはないと思う。問題を早期に発見できる、 又は、拡大を防げれば良いと考えるべきである。
東京ガスは31日、ガス栓を交換する工事の際に必要なガス漏れ検査を作業員が省略したことで、実際に火災が起きていたと発表した。経済産業省は同日、東京ガスに厳重注意処分を出すとともに、同じガス栓の交換工事をした約16万件について、不正がなかったかを調べるよう指示した。
東京ガスは昨年12月以降、空気穴があるタイプのガス栓約45万件について、空気穴のないタイプに付け替える工事をしてきた。このうち、東京都練馬区内で今年10月12日、交換工事をした日にガス漏れが原因とみられる火事が起き、ガスコンロなどが焼けた。
調査の結果、工事を請け負ったグループ販売店「東京ガスライフバルTAKEUCHI」(練馬区)の作業員が、ガス漏れ検査を省略し、検査をしたかのように記録用紙を書き換えていたことが分かった。
その後の調査で、この作業員が「検査がしにくい」といった理由で、記録用紙を書き換えたり別の検査結果を転用したりして、86件で検査を省いていたことが分かった。さらに、別の作業員2人が実施したガス漏れ検査2件についても、記録用紙を転用していたことが判明したという。
経産省は不正のあった計88件について1週間以内に巡回して安全を確認することや、交換工事済みの16万件について不正がなかったかを3週間以内に報告すること、原因究明・再発防止策を1カ月以内にまとめることなどを求めた。(斎藤徳彦)
朝日新聞社
横浜市立大学付属市民総合医療センター(横浜市南区)は30日、1月に70代の男性患者にCT検査を行い膵臓(すいぞう)がんの疑いを発見したのに、院内の連携不足で5カ月間放置され、患者が今月亡くなったと発表した。後藤隆久病院長は「医師・部門間の情報共有ができていなかった」と述べ、謝罪した。
同センターによると、男性は動脈瘤(りゅう)の治療で定期的に通院、1月にCT検査を受けた。心臓血管外科医がCT画像を見て動脈瘤の診断をし、その数日後には放射線科医もCT画像を確認、検査目的とは異なる膵臓にがんの疑いを発見したことから、画像診断書に書き込んだ。
男性患者は2月14日に診察に訪れた。遅くともこの時点で心臓血管外科医が画像診断書を確認するべきだったが、画像を見ただけで診断書は確認しなかった。このため放射線科医の診断は放置され、患者は5月に動脈瘤の手術を受けた。
6月27日、患者は定期的に通っている別の病院を受診し、腹部の痛みを訴えてCT検査を受け、膵臓がんの疑いが発覚した。がんが進行して外科手術が難しい状態で、緩和ケアを受け、今月死去したという。
同センターは「1月に適切に判断していれば外科的な治療が可能だったと考えている」と説明。画像診断を見なければメッセージが表示されるよう、電子カルテのシステムを改修するなどの再発防止策を取り、外部委員を入れた事故調査委員会で検証する方針という。(太田泉生)
朝日新聞社
悪魔を信じる文化だと思うけど、日本は「魔が差した」との言い訳はよく使われるが、悪魔を信じる文化ではないと思うけど?
魔が差すとは、悪魔が心に入り込んだかのように誤った行動や判断をしてしまうという意味で、悪事を働いた者が「私は通常は善人であるが、そのときだけ悪魔にそそのかされて悪人になってしまった」と、まるでその犯行は自分の責任ではないかのように、相手に情状酌量を求めるために用いる。 (笑える国語辞典)
「まるでその犯行は自分の責任ではないかのように、相手に情状酌量を求めるために用いる」
上記が正しい説明であれば、「魔が差した」を使う人は反省していない可能性が高いとも思える。悪魔のせいにする時点で反省しているとは思えない。
なぜ多くの人が「魔が差した」と説明するのだろう?
関西医大病院(大阪府枚方市)の副院長の男性教授(63)が、海外の学会に行ったと偽ったカラ出張で、計約100万円を不正に受け取っていたことが30日、大学への取材で分かった。教授は事実を認めており、大学は31日付で諭旨退職処分にする。
大学によると、教授は米国とオーストリアで開催された学会に参加したと虚偽申告し、飛行機代や宿泊費などを不正に受け取っていた。9月に外部から情報提供があり大学が調査。教授は「魔が差して請求した。申し訳ない」と話している。
教授は肝胆膵外科が専門で平成2年から大学に勤務。25年に副院長となった。
スバルは近く、国交省に正式報告する。対象車のリコール(回収・無償修理)を実施するかどうかは今後、判断する。27日にも発表する。
大量生産される車の完成検査は国に代わって各自動車メーカーが行い、必要な知識と技能を持ちメーカーが指名した完成検査員が担うこととされている。関係者によると、無資格検査が行われていたのは、「群馬製作所」と呼ぶ生産拠点の本工場と矢島工場で、国内の全完成車工場に当たる。スバルには約250人の完成検査員がいるが、一部の検査は指名を受ける前の研修中の従業員数人が行っていたという。
石井啓一国交相は27日の閣議後の記者会見で、新車の無資格検査は「制度の根幹を揺るがす行為で極めて遺憾」と述べた。
スバルの社内規定では、検査資格を得るための試験に合格した上で、2~6カ月間の実務研修を経た者を完成検査員として指名している。今回の無資格者は試験そのものには合格しており、一定の知識と技能があると判断して検査を担わせていたとみられる。
9月29日には、日産が国内6カ所の完成車工場すべてで無資格検査を行っていたと発表。10月6日、新車購入後の初回車検を受けていないと見込まれる直近3年間に販売した約116万台を対象にリコールを実施した。ところが、問題発覚後も4工場で無資格検査が続いていたことが明らかになり、今月25日、3万8650台の追加リコールを国交省に届け出た。
国交省は9月末、日産の問題発覚を受け、他の自動車メーカーに検査体制を確認し10月末までに報告するよう指示していた。トヨタ自動車、ホンダ、マツダ、三菱自動車、スズキ、ダイハツ工業などは問題がないとの結果を報告している。
スバルも問題だが、国交省も問題だ!
SUBARU(スバル)は27日、新車を出荷する前に安全性などを最終チェックする完成検査に資格のない従業員が関わっていたと発表する。リコール(回収・無償修理)を検討しており、対象は30万台以上に上る見通しだ。無資格検査は常態化していたとみられ、約30年に及ぶ可能性がある。
吉永泰之社長が同日午後、東京都内で記者会見する。国内の乗用車メーカー8社のうち、完成検査のルールが守られていなかったことが判明したのは日産自動車に続き2社目。日本車の高品質イメージに影響を及ぼしそうだ。
コストや利益を優先すれば答えは出る。けど、スバルの車を乗る事を考えると考えてしまう。初期には問題として発生しなかったら、それで問題 ないのか?規則を満足すれば品質を妥協するのかと思うと、規則さえも満足しない対応はどうなのか?
日産に続き、スバルでも出荷前の車の検査を資格のない従業員にさせていた。スバルでは、日産の問題が発覚した後も無資格検査を続けていたことが新たに明らかになった。
無資格検査が行われていたのは、群馬県太田市にあるスバルの群馬製作所。関係者によると、日産の無資格検査の問題をうけ、スバル社内で調査したところ、資格のない研修中の従業員数人が、出荷前の完成車の検査を行っていたという。
さらにスバルでは、日産の問題が発覚した後も無資格検査を続けていたことも新たにわかった。
スバルは早ければ今月中にも国土交通省に報告する予定で、すでに販売されている車についてリコールが必要かどうかは、今後判断するとしている。
日産に続く無資格検査問題で、日本の自動車メーカーの信頼が揺らいでいる。
神戸製鋼所の性能データ改竄(かいざん)問題で、日本原燃(本社・青森県六ケ所村)は26日、神戸製鋼から納品されたウラン濃縮のための遠心分離機に使われている部品の品質確認用検査データに改竄が確認されたと報告を受けたと発表した。
原燃によると、この部品は組み立て前で、現在設置されている遠心分離機には使用されていないという。
報告があったのは25日。神戸製鋼が原燃に行った説明によると、平成25年に検査データを測定するための装置を更新した際、測定結果が更新前より低い値になったため、差分を足して記録を作っていたという。原燃は詳細について「核物質に関わる情報のため明かせない」としている。
設計や計算で安全係数が高いケースでは、ゆとりが高いので多少の問題があっても問題ないだろう。安全係数が低い航空などでぎりぎりで 高額数値を出している場合はアウトの可能性は高い。
神戸製鋼所で26日、新たな不正がまた発覚し、一部の銅製品で日本工業規格(JIS)の認証が取り消された。同社は不正があった製品の納入先の8割超で安全性を確認したと発表したが、全容解明が終わらないうちに新たな不正が次々に見つかる事態となり、信用失墜は免れない。顧客離れなど経営への影響が懸念される。
「慚愧(ざんき)の念に堪えない」。神戸製鋼の川崎博也会長兼社長は26日の記者会見で、昨年に続きJIS認証を取り消されたことについて、苦渋の表情を浮かべた。
認証を取り消されたのは、子会社の「コベルコマテリアル銅管」が生産した熱交換パイプに使われる銅管で、「強度の下限を外れたのに数値を書き換えていた」という。川崎氏は会見で、一連の不正について「JISの規格内であれば、法令違反にならないという認識を持っていた」と釈明したが、この案件はJISの規格外で、明らかな法令違反。トップ自身の現状認識の甘さが浮かび上がった。
認証取り消しにより、同社はこの銅管にJISマークを表示できなくなる。取引先には動揺が広がっている。
同社から素材を仕入れている関東の金属加工会社の社長は「金属加工はもの作りの基礎となる部分。信用ある会社から仕入れることが大事」と強調する。また、関西のある商社は「製品として問題があるならば取引中止を検討したいが、情報がなく判断できない」と困惑する。
神戸製鋼は、納入先の8割超で安全性が確認されたことを強調したが、相次ぐ不正発覚で信頼性は低下しており、取引先が発注先を他社に変更する動きが広がる可能性がある。海外では米司法当局が調査に乗り出し、罰金や制裁金を科されるリスクもある。
2年連続最終赤字の神戸製鋼は、2018年3月期に3年ぶりの黒字転換を予想していたが、現状では不確定要素が多いことから、30日発表の9月中間連結決算で通期の業績予想を「未定」と修正する見通しだ。【川口雅浩、古屋敷尚子】
◇「安全性確認」残る疑念
神戸製鋼所は納入先の8割超で製品の安全性が確認されたと発表した。しかし、強度が基準を下回っていたにもかかわらず「安全」という説明はわかりづらい面もあり、最終製品を利用する消費者の疑念を払拭(ふっしょく)できるかも課題となる。
神戸製鋼がデータを改ざんした製品は、すでに出荷先で加工されて安全性の確認が困難なケースが多い。そのため、神戸製鋼は改ざん前の元データを出荷先に提供するなどして、取引先に安全性の確認を求めている。
JR東海は、一部の新幹線で問題のアルミ部材が使われていた。過去10年分の元データを神戸製鋼から取り寄せて確認した結果、強度が最大3%程度不足していた。JR東日本も、新幹線の一部の部品の強度がJIS基準に対し約0.4%不足していた。ただ、両社ともに設計段階で高い強度を設定しており、「安全上は問題ない」という。
大手自動車各社も、神戸製鋼の提供データを基に調査した結果、アルミ板などの安全性は確保されていたと説明する。しかし、強度不足の程度などは公表していない。「車の性能を左右し、競争力に直結する部品のデータは明かせない」(業界関係者)からだという。ただ、日本の製造業で不祥事が続く中、消費者に分かりづらい「安全宣言」では不信がぬぐえない懸念も残る。【安藤大介、井出晋平、和田憲二】
◇キーワード・神戸製鋼所
神戸の総合商社「鈴木商店」が鉄鋼会社「小林製鋼所」を買収し、1905年に「神戸製鋼所」として創業した。鉄鋼業界では新日鉄住金、JFEスチールに次ぐ国内3位。事業の多角化を進めており、鉄鋼やアルミ・銅などの「素材事業」、建設機械などの「機械事業」、「電力事業」を3本柱に据えている。
登記上の本社は神戸市。東京都品川区にも東京本社を置く。ラグビー部は社会人ラグビーの強豪チームとして知られる。安倍晋三首相が79年から3年間、社員として在籍していた。2017年3月期の連結売上高は1兆6958億円、最終(当期)損益は230億4500万円の赤字。赤字は2年連続。連結従業員数は3万6951人(17年3月末)。
かなり厳しく処分に、チェック機能を高めないと、間違った企業組織の常識の職員は今度はもっと巧妙にするだけだと思う。
政府系金融機関の商工中金の危機対応融資をめぐる不正問題で、審査書類の改ざんがこの融資制度ができた2008年度から行われていたことが24日、明らかになった。これまで11年度以降とされてきた不正が当初から確認されたことで、ずさんな業務実態が改めて浮き彫りとなった。
危機対応融資は、08年のリーマン・ショックを契機に制度化された。国の助成を受けて、金融危機や自然災害の影響により、経営が悪化した中小企業に低利で融資する仕組みだ。
商工中金の第三者委員会が4月に発表した調査では、11~15年度に不正が発覚した。しかし、その後の社内調査で、支店や出張所など全国100拠点のほぼ全てで不正を確認。08年度から既に一部で不正があったことが判明した。
関係者によると、関与した職員は500人前後に達し、不正に実行された融資件数は計4500件前後に上る見通しだ。監督する立場の上司らを含め処分者は1000人前後に膨らむもようで、全職員約3900人の4分の1が処分される異例の事態に発展する。
商工中金は24日、国の低利融資制度「危機対応業務」を巡る不正問題で、元経済産業省事務次官の杉山秀二氏(69)ら過去の正副社長4人に対し、受け取った報酬の一部返納を求める方針を固めた。過去のトップの経営責任を明確化することで、再発防止への姿勢を示す。不正の全容に関する自主調査結果と合わせて、一両日中にも発表する。【小原擁、小川祐希】
今回、不正の温床となった危機対応業務は、2008年10月から取り扱いを始めた。杉山氏は08年10月から約5年間を副社長、13年6月から3年間を社長として経営を担っており、この時期の報酬や退職慰労金の一部返納を求める。社長だった3年間の報酬額は計約7000万円にのぼり、退職時には少なくとも約540万円の退職慰労金を受け取っていた。
杉山氏の他に一部返納を求めるのは、08年10月から8年間副社長を務めた財務省出身の木村幸俊氏(68)▽13年6月から3年間副社長を務めた生え抜きの森英雄氏(62)▽08年10月~13年6月に社長を務めた新日本製鉄(現・新日鉄住金)出身の関哲夫氏(79)。さらに当時の役員数人にも報酬返納を求める。
商工中金は、第三者委員会の抽出調査によって全国35支店816件の不正が判明した今年4月、安達健祐社長が報酬月額の3割を自主返納する処分を決定。杉山氏ら過去の社長・副社長に対しても、報酬月額の3割を2カ月分返納するよう要請していた。その後の自主調査によって、不正がほぼ全店で行われ件数も約4000件に達していたことが判明した。このため、返納要請額を大幅に上積みする方針だ。
商工中金は、前社長らへの報酬返納要請と合わせて、不正に関与した職員とその上司を含む社員約1000人の処分も実施する。また、不正の再発防止策として、危機対応融資が適正に行われているかをチェックするための新たな部署を本部に設置する方針も公表する。これまで一部を支店で行っていた融資審査をすべて本部の専門部署に一本化し、不正防止を徹底する。
経産省や金融庁などは調査結果を受けて、月内にも商工中金に2回目の業務改善命令を出す方針。
世耕経済産業相は24日の閣議後の記者会見で、神戸製鋼所の検査データ改ざん問題を受け、日本工業規格(JIS)の審査や認証を行う登録認証機関に対し、神戸製鋼が認証を取得している全ての工場などの再審査を検討するよう指示したことを明らかにした。
経産省によると、神戸製鋼は子会社も含め国内20か所の工場・事業所で、JISの認証を取得している。登録認証機関の一般財団法人日本品質保証機構などが認証しているが、JIS法違反の疑いが強まった。
日本品質保証機構はすでに神戸製鋼子会社の秦野工場(神奈川県秦野市)について、品質管理体制に問題があるとして再審査を行っている。週内にもJISに適合しているかどうかを判断する見通しだ。
ノルマが原因とも新聞記事には書いてあったが、ノルマ達成するのに不正を行った職員の問題が発覚しない、よって処分されない事の方が 重大だと思う。職員の中には、不正を行っても見つからない、又は、発覚や処分もされないのであれば、自分もやっても良いだろうと思う職員が 出てくる。また、不正を行ったが発覚もしないし、処分されない職員が、同僚や部下に、同様の不正を行っても大丈夫だと言っていたかもしれない。 そして、同じ事が繰り返され組織に広がったのかもしれない。
不正を知っている職員が上司や審査に関わる立場になった時、多くの人達がやっていると考えるかもしれないし、問題を指摘したら貧乏くじを 引くから見て見ぬふりをしたほうが良いと考えた職員もいるのではないか?
商工中金に勤めたこともないし、知り合いもいないから個人的な推測であるが、推測が全くの見当外れであれば、不正が広がった理由と見逃されてきた 理由を公表してほしい。
商工中金は、国の低利融資制度「危機対応業務」を巡る不正問題で、不正に関与した職員とその上司を含む約1000人を一斉に処分する方針を固めた。週内にも発表する。全職員約3800人の約4分の1が処分対象となる異例の事態で、改めて不正が全社的に横行していたことが浮き彫りになった。
関係者によると、処分対象者約1000人のうち、不正に直接関与した職員がほぼ半数を占める。残りは、その上司や本部で審査などに関わった職員。不正がほぼ全店で行われていることから、長期にわたって不正を見落としてきた管理職らについても責任を問い、企業体質の刷新を図ることにした。経済産業省出身の安達健祐社長も、責任を取って辞任する。
商工中金では今年4月、第三者委員会による抽出調査で、業績関連書類を改ざんするなどして全国35支店計816件(融資額約198億円)の不正があったことが発覚した。
全容解明に向けた自主調査で、危機対応業務の不正が数千件に達し、その他の制度融資や経済統計調査でも不正があったことが判明している。【小原擁、小川祐希】
危機対応融資をめぐる商工中金の不正がほぼ全店に広がっていた背景には、金融・経済情勢が「危機」と言えない状況でも拡大解釈で融資が可能となるずさんな制度の問題がある。経済産業省などは、危機の認定を厳格化するなどの制度改革や、商工中金の業務全体の見直しにも着手する方針だが、「政府系金融機関の役割を改めて問い直すべきだ」との声も出ている。【小原擁、小川祐希】
経産省「危機認定」見直しへ
「企業が危機的状況ではないにもかかわらず、行員に融資獲得のノルマが課せられ、プレッシャーを受けて改ざんを繰り返した」。監督官庁のある幹部は、不正拡大の背景をこう説明する。
危機対応融資は、2008年のリーマン・ショックや、11年の東日本大震災などの経済・社会の混乱を、「危機」と認定し、日本政策金融公庫を通じて利子の一部(約0.2%分)を国が負担する公的制度。利子補給分は国民の税金が元手だ。
問題は、世界的な金融市場の混乱から、大規模災害、物価が継続的に下がる「デフレーション(デフレ)」まで、広く「危機」と認定している点だ。危機対応融資の予算は政府の補正予算編成のたびに「経済対策」として計上され、それに合わせて対象が拡大してきた経緯がある。不正発覚を受けて行われた第三者委員会の調査にかかわった関係者は、「そもそも危機の定義を広げて、低利融資をばらまいてきた政治にも問題がある。一政府系機関の不正というだけの単純な問題ではない」と指摘する。
一方、商工中金も、融資実績を積み上げるため、制度の甘さに乗じていた。商工中金は「経営トップは一切不正を指示しておらず、知らなかった」と説明しているが、経営幹部らが現場にノルマを課したことが、不正を誘発したとの指摘は多い。業績が一時的にでも悪化さえしていれば「デフレのため」と解釈して融資することも可能なため、「上手に稟議(りんぎ)書を『作文』して融資をした行員が評価されるようになり、やがて数値の改ざんなどにエスカレートしていった」(関係者)という。経産省幹部は「危機対応融資以外に自らの存在意義を見いだしにくくなっていた」と背景を指摘する。
経産省などは不正の一因が危機認定プロセスにあったとして、融資基準の見直しや客観的評価を聞いた上で認定解除を機動的にできる新たな制度の設置を検討している。商工中金についても「地銀と敵対して民業を圧迫するのではなく、補完関係を築く」(経産省幹部)ことを念頭に、民間金融機関との協調融資など、危機対応融資に代わる業務へのシフトを進める方針だ。
全国農業協同組合連合会兵庫県本部(JA全農兵庫、神戸市中央区)は23日、神戸・三宮の直営レストラン「神戸プレジール本店」で、メニューに表示した「神戸牛フィレ肉」を注文した顧客の一部に、格付けが低い「但馬牛フィレ肉」を提供していたと発表した。判明した偽装は2016年4月から今年10月15日までの約3200食分。正規料金との差額は約1千万円とみている。
神戸市内で会見した曽輪佳彦兵庫県本部長は「神戸ビーフの信用に傷つけ、多大なご迷惑をおかけしたことを反省し、おわび申しあげます」と謝罪した。同店を当面休業し、第三者を交えた調査委員会を設けて、原因究明と再発防止を図る。
JA全農兵庫によると、10月16日に内部通報があり、料理長への聞き取りで判明した。動機について、曽輪本部長は「神戸牛が恒常的に不足し、在庫がない場合は注文を断っていたが、近年の来店者の増加に対し、要望になんとか応えたいという意思が働いたと考えられる」と話した。
神戸プレジールは2008年4月、初の直営店として開業。神戸牛をメインに県産食材を使ったコース料理などに人気がある。16年10月に東京・銀座で開業した2号店「神戸プレジール銀座」では偽装は確認されていないが、再点検のため休業する。(辻本一好、内田尚典)
神戸製鋼所は20日、グループのアルミ・銅事業部門の長府製造所(山口県下関市)で、性能データ改竄(かいざん)問題を自主点検する過程で、管理職を含む従業員が不正を隠蔽(いんぺい)する行為があったと発表した。鉄鋼製品の「厚板」の加工を手掛ける子会社で、新たに測定データを捏造(ねつぞう)する不正が見つかったことも発表した。
◇
神戸製鋼は、新たに複数の第三者のみで構成する「外部調査委員会」を設置し、原因を究明する。経済産業省の担当課長は同日夜記者会見し、「自主点検を通じた事実調査の信頼性を根本から損なうものだ」と批判した。
自主点検の際、管理職を含む従業員が、顧客企業と約束した製品の基準を外れた寸法となっていたにもかかわらず、検査データを提出せずに発覚を免れていた。社内通報で判明した。数量は確認中としている。
一方、新たな不正は、厚板の切断加工を手がけるグループ会社の神鋼鋼板加工(千葉県市川市)で発覚。平成27年11月から今年9月まで1社に出荷した3793トンについて、顧客の求める厚さ測定の一部をせず、データも捏造していた。
ただ、厚さそのものは神戸製鋼の加古川製鉄所(兵庫県加古川市)で原料の板を製造した段階で確認している。加工後も厚さに変更はなく、同社は安全性に問題はないと説明した。
同日、東京都内で記者会見した梅原尚人副社長は、新たな不正判明などを「改めておわびする」と謝罪した上で、「非常に残念というのが正直な気持ち」と述べた。取引先数社から対応にかかった費用の負担を請求されていることも明らかにした。川崎博也会長兼社長が出席しない理由については「体調を崩している」と説明した。
一方、JR東日本は同日、神戸製鋼がデータを改竄したアルミ製品が使われた新幹線車両の台車部品について、約1年ごとの定期点検で順次交換すると発表した。最終的に神戸製鋼の費用負担が発生することも予想される。
問題の製品は、同社が運行する東北新幹線「はやぶさ」や秋田新幹線「こまち」などの車軸の回転を滑らかにする「軸箱」として、計48個が使われた。JR東は「安全性に問題はない」としている。
証明が出来なことは昔から既にそうなっていたとか、昔の事で覚えてないと言うであろう。
原因究明は難しい。確実に白黒付ける事が出来るのは引き継ぎや新しい社員に教育や指導した人間達になぜ継続したのか、 疑問に思わなかった、なぜ疑問に対して質問をしないのかぐらいであろう。
最近は性能の良いプリンターが安価に購入できるので、証明証書の偽造は簡単であろう。中国の偽札や大学の卒業証書の事件、そして 日本の偽造された教員免許のコピーが提出された事件を考えれば理解できるであろう。偽造在留カードでも簡単に偽造できるようだ。
規則で製品のデータの保存を少なくてとも数年は保存する事を要求し、抜き打ちで記録が存在するかチェックするなどして、不正を行えば 発覚する可能性がある事を自覚させるしかないかもしれない。
神戸製鋼所の防止策も重要だが、JIS認証機関の検証やチェック方法は改善の必要があると思う。
神戸製鋼所の品質データ改ざん問題で、製品検査に使用される測定装置の数値を自動的に検査証明書に記録するシステムが一部工場で整っていなかったことが21日、分かった。装置が示したデータを社員がいったん紙に手書きし、証明書作成時に改ざんした数値をパソコンに入力していたという。神鋼は人手が介在する旧来型の仕組みが不正の温床になったとの見方を強めており、記録の自動化を再発防止策に盛り込む方向だ。
神鋼が8日にアルミ・銅製品のデータ改ざんを公表してから、間もなく2週間。同社はこの間、工場に残る資料を調査したり、OBも含めた社員に聞き取りを行ったりして、全容解明を進めてきた。
検査は、出荷時に製品の強度などが顧客の求める仕様に合っているかどうかを調べるために行われる。神鋼幹部はこれまでの調査を踏まえ「(証明書作成が)全ての工場で完全に自動化されておらず、『何か』をしてしまう機会はあった」と指摘。同社は、不正が発覚した工場ごとに異なる改ざんの手口が存在していたとみて、詳しく調べている。現在のところ、改ざんを「指南」するマニュアルなどは見つかっていないという。
調査では、顧客の要求水準を下回った規格外の製品を、本来は必要な顧客の了承を得ないまま出荷していたケースがあることも判明した。規格外製品の出荷は「特別採用(トクサイ)」と呼ばれ、商慣行としては一般的なもの。しかし、別の神鋼幹部は「一部の現場では、データを改ざんした製品もトクサイと呼んでいた」と説明。契約内容を軽視する企業風土が、長年にわたり不正を放置してきた一因になった可能性をうかがわせた。
神鋼は経済産業省の要求を受け、月末をめどに追加の不正の有無や安全性の検証結果をまとめる一方、11月中旬にも不正の原因究明や再発防止策の策定を終える方針。ただ、過去の資料が残っていなかったり、事情に詳しいOBの所在が分からなかったりするケースがあり、調査が難航する懸念もある。
■不法滞在・就労の横行懸念
国内に滞在する外国人の身分証明書となっている「在留カード」の偽造品を所持、提供したとして昨年1年間に入管難民法違反容疑で摘発された件数が過去最多の11件だったことが県警のまとめで分かった。県警は、外国人による凶悪犯罪の“温床”ともなってきた不法滞在や不法就労が横行しかねないと事態を深刻に捉えており、カードの偽造から不正取引に至る地下ネットワークの解明を急いでいる。
県警外事課によると、偽造在留カード関連の摘発件数は平成26年は6件、27年は5件だったが、昨年初めて10件を超え、今年も7月末までに6件が摘発された。全国的にも28年は313件、今年は7月末までに198件の摘発があり、増加傾向にあるという。
在留カードは24年7月に、それまでの外国人登録証明書に代わって導入され、当初は中国人による偽造が目立っていたが、ここ数年はベトナム人やインドネシア人の摘発も多く、県警は、さまざまな国籍の外国人によって組織化された地下ネットワークが各地にアメーバ状に分散し、偽造カードが拡散しているとにらんでいる。
県警は昨年4月、境町で不法残留していたインドネシア人の男を逮捕した。男は「技能実習」の資格で入国したが、県警が自宅を捜索したところ、「定住者」と記載された偽造在留カードを発見。その後の捜査で、偽造カードを売り渡したインドネシア人と日本人の男2人を割り出し、逮捕した。不法残留していた男の供述によると、カードは1枚約8万円で購入したという。
県警によると、偽造カードは在留資格欄を「永住者」「日本人の配偶者等」といった就労制限のない資格に書き換えている手口が多いという。
真正なカードと偽造を見分けるために、在留カードにはICチップが埋め込まれたり、傾けると絵柄の色が変化したりするなど、さまざまな工夫が施されている。しかし、「詳しくない人が一目見ただけでは気づかない」(外事課担当者)ような偽造カードも出回っているという。
県警は、偽造カードの捜査を進めると同時に、外国人を雇う事業者らに対して在留カードの確認の徹底を呼びかけている。入国管理局では、在留カードの番号と有効期限を入力すれば、実在する番号かどうか確認できるホームページを開設している。
県警は「雇用主はカードをしっかりと確認し、もし不審な点があったら警察か入管に相談してほしい」と呼びかけている。(鴨川一也)
「納期を優先させたのだろうか」「プライドを持って仕事をしていたのに」-。アルミ製品などの性能データ改竄(かいざん)問題で揺れる神戸製鋼所のOBらが集まる「神鋼社友会」の定例会が20日、神戸市内で開かれ、集まったOBからは相次いで事態を憂う声が漏れた。相次ぐ不正発覚に同会は毎年1月、経営幹部を招いて開いていた新年会を来年は自粛するという。
「取引先の多くが安全を確認したことは救いだ」
この日開かれたのは神戸製鋼のOBが所属する神鋼社友会の年に数回開かれる定例会で約20人が参加したという。報道陣の取材を遮るように足早に会場のあるビルに入っていくOBもいる中、長く鉄鋼部門に勤めた80代男性は「神戸製鋼製の部品を使った機械や乗り物で事故がないことを願っている。取引先の多くが安全を確認したことは救いだ」と話した。別の70代男性は「いつの間にか納期を優先するような風潮に流されたのだろう」と悔しそうに話していた。
「プライドを持って仕事をしていたのに」
不正が広がった背景に、責任感、プライドを持って仕事に臨む企業風土や現場の姿勢の変化をみるOBも多く、機械部門だったという70代男性は「取引先も検査して問題が起きなかったことで、ずるずると改竄を続けてしまったのではないか」と指摘。チタンの営業だったという80代男性は「昔の技術職は、上司にも食ってかかり品質にこだわっていた。今の現場は、以前ほどに強く言えなくなったようだ」と話した。
また社友会に参加しなかった神戸市内の70代男性も「昔と比べて品質要求も高くて労働管理も厳しい。プレッシャーは相当なものになっている」として、「再発防止には、企業風土に踏み込んだ改革が必要。よいものを作っていたはずなのだから、立ち直ってほしい」と注文を付けた。
企業風土刷新へ経営陣の退陣は必須
企業統治に詳しい保田隆明(ほうだ・たかあき)・神戸大学大学院経営学研究科准教授の話
「日産自動車も神戸製鋼所もいずれも日本を代表する企業。組織は巨大化、複雑化しており、そのことで経営陣の意思がうまく現場に伝わらなくなる状態を招いていた。不正がただされなかった理由にも、現場と経営陣の意識の乖離(かいり)が挙げられるのではないか。
2社とも不正発覚後も工場は操業し続けていたため、現場は納期に追われ、欠品を恐れる状態は以前と変わりがなかった。工場はマニュアル化され自己裁量が許されない場所なので、指示が行き届かなければ従来通りの仕事を続けざるを得ないかもしれない。
一方で、不正発覚後の経営陣は取引先や担当省庁などへの対応に追われており、足元の対処までは思いが及ばず、工場ごとに任せているつもりだったのではないか。社内のコミュニケーションの不足が招いた結果だ。
企業風土の刷新は、コンプライアンス(法令順守)などの徹底だけでは、決して実現できないだろう。経営陣の退陣も必須になる。もし、このまま経営陣が退かなければ、現場は『なんとかやりすごせる』という印象を受け、不正を隠蔽(いんぺい)する体質は変わらない」
政府の「危機対応融資制度」を巡る商工組合中央金庫(商工中金)の不正融資問題で、社内処分の対象者が全職員(約3900人)の約2割に相当する800人規模に膨らむ可能性があることがわかった。
不正に関わった職員の上司も、書類の改ざんなどの不正を黙認していた可能性があるためだ。
商工中金は、月内にも約22万件に上る全ての危機対応融資についての調査結果と、処分内容を公表する見通しだ。上司も対象に含めることで、異例の大規模処分になることが避けられない状況となっている。
関係者によると、不正に関与した職員は、4月時点の99人から、400人規模に及んでいる。こうした職員の上司についても聞き取りを行っており、不正を認識していた場合などは、処分対象に含める方向だ。不正の件数は、3000~4000件程度に達したとみられる。
政府系の商工組合中央金庫(商工中金)が国の制度融資で不正を繰り返して隠蔽(いんぺい)した問題で、安達健祐(けんゆう)社長(元経済産業事務次官)ら代表取締役3人が引責辞任する見通しとなった。不正への関与がほぼ全店で数百人に広がり、制度融資以外の不正も明らかになり、経営体制の刷新は不可避となったためだ。今後民間出身者を中心に後任を選ぶ。
安達氏、稲垣光隆副社長(元国税庁長官)、商工中金出身の菊地慶幸副社長が辞任する方向。月内にも不正の全容調査の結果を発表する。人事は年内にも正式決定する。
商工中金は景気悪化時に国が行う「危機対応業務」の実績を上げるため、書類を改ざんして国の資金を不正に受け取り、取引先に低利融資した。一部調査で35店の99人が関与したことがわかり、全体調査ではほぼ全店、数百人の関与が判明。経済統計の捏造(ねつぞう)や営業書類の改ざんなど、不正は制度融資以外の業務全般に広がっている。(福山亜希)
現場が勝手にやっていたのであれば会社としての組織的隠ぺいのイメージを少しでも払拭するために懲戒免職処分もあるのでは?
神戸製鋼所は、20日午後から、都内でデータ改ざん問題について会見し、自主点検の際、従業員による妨害行為があったことを明らかにした。
神戸製鋼所の梅原尚人副社長は「あらためて、おわび申し上げます」と述べた。
妨害行為が行われたのは、山口・下関市の長府製造所。
本社による自主点検の際、管理職を含む従業員が、顧客が指定した基準を外れた製品の品質検査データを報告しなかったという。
また、グループ会社のデータ改ざんで、安全性を示すJIS(日本工業規格)の認証機関から検査を受けていることも明らかにした。
[東京 20日 ロイター] - 神戸製鋼所<5406.T>は、日本工業規格(JIS)の認証機関が19日から同社の工場に立ち入り検査に入っていることを明らかにした。広報担当者がロイターに述べた。
経済産業省によると、JIS認証機関である日本品質保証機構(JQA)が秦野工場(コベルコマテリアル銅管)に検査に入っている。
調査の結果、是正措置や一時停止、最悪の場合は認証取り消しとなる。認証が取り消された場合、JISマークを付けることができず、一部製品の出荷ができなくなる可能性がある。
神戸製鋼では昨年、グループ会社の神鋼鋼線ステンレスが生産するばね用ステンレス鋼線について、強度試験データの改ざんがあり、JISマーク認証が取り消されている。
*内容を追加しました。
まあ、中国製は証明書や書類は信用ならないと、外国人でも知っている事。それでも中国製を購入する人達は存在する。日本製も人件費を削減して コストを安くすれば多少の品質の低下はあっても、顧客は購入するのではないのか?
韓国の造船所が付加価値を強調して仕事を取ったが、付加価値のある船を建造する能力がなく、逆に負担になり大きな損失を出してしまった。三菱重工の 客船による損失もたぶん、原因で同じような部分はあると思う。
付加価値製品は理屈のように想定内で現実可能であれば問題ないが、可能でなければリスクになると考える方が安全だと思う。問題は、判断が 難しい。技術と現場を知っている大企業の経営者はいるのであろうか?叩き上げで急成長した初代、そして運が良ければ2代目ぐらい以外では、 そのような経営者はいないと思う。
神戸製鋼所は20日、アルミ・銅事業の長府製造所(山口県下関市)で、現場の管理職らが製品の不正を報告せず、隠蔽(いんぺい)していたと新たに発表した。
部署ぐるみで10人近くが関与していたという。子会社で主力の鉄鋼事業が扱う厚板の加工品でもデータの捏造(ねつぞう)などが見つかった。
経済産業省は社内調査では限界があるとして、社外の有識者だけで作る外部調査委員会を早急に設置するよう神戸製鋼に指示した。
長府製造所では、顧客が指定した基準を外れたアルミ製品があったのに、社内調査で報告していなかった。社内の相談窓口に19日に情報提供があり、発覚した。8日に一連の不正を対外的に公表した後も隠蔽を続けていたとしている。
一方、日本工業規格(JIS)の認証審査を行う一般財団法人「日本品質保証機構」は、品質管理などに問題があるとして、19日から子会社「コベルコマテリアル銅管」の秦野工場(神奈川県秦野市)への再審査に入った。
神戸製鋼所は20日、子会社のコベルコマテリアル銅管(KMCT)が販売した銅管について、日本工業規格(JIS)の認証機関である日本品質保証機構から品質管理に問題があるとの指摘を受けたことから、同子会社でのJISマーク表示と、JISマークのついた製品の出荷を自粛すると発表した。
問題があったのは2016年9月から17年8月にKMCTの秦野工場から顧客4社に対して出荷した25トンの銅や銅合金を使った継ぎ目のない管。JIS規格よりも厳しい社内規格を満たすために強度などのデータを改ざんしていた。しかし、改ざん前の計測値はJIS規格を満たしていることから、安全性には問題ないとしている。この改ざんについては8日の発表分に含まれているという。
都内で会見した同社の梅原尚人副社長は、JIS規格を満たしていても、認証機関からは品質管理体制が十分とは判断されていないとし、「法令違反と認識している」との見解を示した。また、KMCTが1年以上前に生産した製品ではJIS規格を満たしていないものがあったとの指摘も受けているという。詳細については調査中とした。
神戸鋼は13日までに銅やアルミ、鉄粉、線材などの製品で検査データの改ざんなど不正な行為が行われていたと発表。さらに一部の製品では10年以上前から行われていた可能性があることも分かっている。米司法当局からは、米国で販売した製品に関する書類の提出を求められた。不正行為が明るみに出たことで同社の株価は約4割下落している。
経済産業省によると、品質管理体制に不適合があると認められた場合、 JISマーク表示の停止、あるいは取り消しという事態になる。取り消しとなった場合には、秦野工場におけるJISマーク製品の出荷ができなくなる。JIS規格を規定している現在の工業標準化法(JIS法)が04年に成立してから、立ち入り検査は初めてのケースという。
神戸鋼はこのほか、子会社で厚板の計測値をねつ造していたことなどが20日までの自主点検で分かったと発表。しかし、加工を専業とする同子会社に出荷される前の段階で厚さは保証されているために、安全性に問題はないとしている。
管理職がデータ隠蔽
さらにアルミ・銅事業部門の長府製造所(山口県)で行っていた自主点検の中で、顧客との間で契約した基準を満たさないアルミ押出品の寸法の検査データがあったことを工場の管理職などが隠蔽(ぺい)し、発覚を逃れていた事実があったと発表した。
これを踏まえ、同社は社内に設置していた委員会の代わりに外部の委員だけで構成する調査委員会を設置することも発表した。不適切行為に関する調査や原因の究明、再発防止策を検討する。
経産省の小見山康二金属課長は同日夜の会見で「自主点検を通じた事実調査の信頼性を根本から損なう」と指摘。これまでに判明した事例の安全検証については、12日の指示通り2週間程度をめどに発表すること、外部の専門家で構成された調査委員会を速やかに立ち上げ、事実調査や原因究明、再発防止を行うことを指示したと説明した。
同社はこれらの案件が業績に与える影響については不明としている。しかし、梅原氏は顧客の一部が取引を見直しており「ビジネスへの影響はある」との見解を示した。すでに数社からはコスト負担を求められていることも明らかにした。データ改ざん製品をめぐって、安全性に問題があるとして至急の部品交換の要請はないというが、定期的な検査の際に部品を交換したいとの要請は受けているという。
川崎博也会長兼社長は体調を崩しているとして、記者会見には出席しなかった。
経産省の発表内容を追加して記事を更新します.
Ichiro Suzuki, Masumi Suga
本当に日産が「無資格検査の要因を課長と係長のコミュニケーション不足にあると繰り返している」と説明しているのであれば、日産は終わっている 組織だと思う。理由は、このような信じられない言い訳が通用すると思っている組織、又は、このような問題を予防できない組織は他のエリアや 箇所でも発覚していないだけで問題を抱えている組織である可能性が高いと思えるからだ。
人材不足やプレッシャーは多くの企業が経験していると思う。だから、今回のような選択を取るのは日産の組織的な体質だと思う。
日産の無資格検査問題を受け、現役の社員が日本テレビの取材に応じ、工場の実態を語った。
日産の工場でエンジンに関わる作業をしていた現役社員は、工場では人手不足やプレッシャーがあったと話した。
日産の社員「人手不足の中で、今までは2人、1.5人でやっていた仕事は、極端な話、1人でやらないといけない。あっちの班はできているぞとか、今月のマイナス面はうちばっかりだぞっていうんです。で、グラフ化されて。きついのが生産にきているのかなと」
さらに、組み立てを担当する別の従業員も、作業量の多さを指摘する。
組み立て担当の従業員「一人当たりの仕事量が多めでして、やはりきつくは感じますね。人の入れ替わりが激しくて、日によっては人手が足りなくなることもある」
日産は、無資格検査の要因を課長と係長のコミュニケーション不足にあると繰り返しているが、人員や作業量に無理はなかったのかも含め検証する必要がありそうだ。
日産自動車が無資格者に車を検査させた問題は、不正が発覚して西川(さいかわ)広人社長が是正を公言した後も、大半の工場で続いていた。日本を代表するグローバル企業で明らかになった深刻な経営の機能不全。西川氏は、不正の背景について「現場」の不手際を強調したが、経営陣の責任問題への発展は避けられない。
「言い訳のしようがない」「現場のコントロールが課題だ」
西川氏は19日夜に横浜市の本社で開いた記者会見で、自身が謝罪した後も続いた不正を、厳しい表情で説明した。同じ場で今月2日夜に、「9月20日以降は認定した検査員が100%行うようになった」と語ったばかりだった。
国から委託された形で、車両の最終チェックにあたる「完成検査」での不正。西川氏は「常態化し、組織的な取り組みだった」と認めた。ただ、自身の進退を含めた経営責任について問われると、「生産を正常に戻し、信頼を取り戻し、会社を従来の成長に戻すのが一義的な役割だ」として、答えを避けた。
代わりに西川氏が、不正が繰り返された背景として強調したのが、「現場」の不手際だ。「工場長から部長、課長から係長へと指揮命令が伝わっていたが、その過程で課長と係長のコミュニケーションのギャップが大きかった」と話した。
ただ、国土交通省の立ち入り検査があり、西川氏が記者会見で謝罪してからは、不正は社内外の誰の目にも明らかだったはずだ。それなのに、国内で完成車をつくる組み立て工場全6工場のうち4工場で漫然と不正が続いていた事態は、現場の不手際だけでは説明が難しい。
4工場のうちの一つ、日産車体湘南工場(神奈川県平塚市)では、指導的立場の従業員が無資格者に対し、「作業が遅れているからやってくれ」という内容の指示をしていたことがわかっている。19日に新たに判明した3工場では、国交省に届け出が必要な工場の生産ラインを勝手に変更していたことも判明した。法令軽視の姿勢は根深い。
不正が起きたラインでは完成検査とは別に、日産独自の商品検査も実施している。独自検査は商品の競争力に直結する「1丁目1番地」。そこで働く従業員の資格が混乱したままで、ずさんな検査が横行していたことになり、商品の信頼性にも傷がつきかねない。
上記の条件だと組織の名前が変わっただけで組織を構成する人達は変わらない。日本年金機構は基本的に名前が変わっただけ。そして不祥事や問題は 定期的に起きている。
神戸製鋼の問題は現在までの記事を読んでいると、不正のDNAが人の移動と共に拡散している。
熊本市の医薬品メーカー「化学及(および)血清療法研究所」は上記のケースとは違うと言える理由はどこにあるのだろうか?
痛みを伴わない改革があれば良いが、痛みを伴わずに多くの人々は学べるのか?痛みや苦しみを経験するから同じような事を避けるために モラルや倫理とは関係なしに同じ行為を行いわないケースはあると思う。レベルが低い話であるが、その低いレベルを乗り越えられなかったから 不正が発覚する前に不正を止める事が出来なかった。個人的にはそのように思っている。
厚労省はどのように考えているのか知らないが、人間を人間として考えるのも良いが、人間も動物である。動物的な部分もある。 個人の欲求や自己の利益を優先させる場合やそのような人間がいる事を理解しなければ同じ事は繰り返される。
国の承認と異なる方法で血液製剤を製造していた熊本市の医薬品メーカー「化学及(および)血清療法研究所」(化血研)が、ワクチンや血液製剤などの製造事業の譲渡先として、新たに株式会社の設立を検討していることが、関係者への取材で分かった。
新会社は熊本県内の企業連合や県が51%、県外の大手製薬会社が49%を出資する構想で、19日午後に開かれる化血研の評議員会で方針が説明される予定。
関係者によると、県内企業は地銀など、県外企業は明治ホールディングス(東京)傘下の製薬会社が浮上しているという。木下統晴(もとはる)理事長は事業譲渡の条件に、従業員約1900人の雇用維持▽本社機能の県内維持▽ワクチン生産など主要3事業の継続--を挙げており、県内企業連合と県で過半数を出資して従業員の雇用確保につなげたい意向だ。
化血研や出資する予定の企業などは今後、譲渡額などを検討するとみられる。
化血研は厚生労働省から事業譲渡を求められ、製薬大手のアステラス製薬と事業譲渡交渉をしていたが昨年10月に決裂。今年5月に明治製菓(現Meiji Seikaファルマ)執行役員を務めた木下氏が理事長に就き、譲渡先や譲渡方法などを検討していた。【中里顕】
衝動を抑えられないぐらいタイプの少女だったのか?それとも、同じような行為をした事があったが逮捕されなかったのか?
人気スマホアプリ「SUSTINA」を運営する会社役員の男が、強制わいせつの疑いで逮捕された。
逮捕されたのは、洋服やアクセサリーなどを月額制でレンタルするスマートフォンアプリ「SUSTINA」を運営する会社の取締役、斉藤貴志容疑者(34)。
警視庁によると、斉藤容疑者は先月、東京・足立区の路上で、小学6年生の女子児童に「かわいいね。うちの事務所に入らない?」などと声をかけ、服の上から胸を執拗(しつよう)になでまわすなどわいせつな行為をした疑いが持たれている。
調べに対し斉藤容疑者は、「髪をなでたあと胸の付近を触った」などと話しているという。
スマートフォンアプリ「SUSTINA」は若者を中心に人気のサービスで、斉藤容疑者もメディアのインタビューなどに答えていた。
古い案件は法的には時効だと思う。神戸製鋼所と呼ばれる組織が変われるのかが重要な点だと思う。長い間に染み付いた価値観、考え方、働き方 そして組織の形は簡単には変えられないし、変えようとしても変わらない。それでも変われるのか次第だと思う。
神戸製鋼所のアルミ・銅部門で1990年代に働いていたOBが18日、共同通信の取材に応じ、仕様を満たさない製品を顧客に無断で納入しても問題とならない許容範囲をメモにして歴代の担当者が引き継いでいたと証言した。不正の手口を継承する事実上の「手引書」の存在が裏付けられた。組織ぐるみのデータ改ざんが見つかった部門で、不正の常態化が明確になった。
軽微な性能不足など、顧客との間であらかじめ取り決めた仕様に満たない製品は、了解を得た上で「特別採用」として引き取ってもらうケースがある。しかし、神戸製鋼では過去に納入して問題とならなかった不合格品の事例を「トクサイ(特別採用)範囲」と称するメモにして申し送りし、歴代担当が無断納入の判断基準に使っていた。
同じく90年代にアルミ・銅部門にいた別のOBは無断納入を続けてきた背景に関し、顧客との取引長期化に伴って「大丈夫だろうと、なれ合いみたいなところがあった」と説明した。
さらに別のOBは、特別採用は40年以上前から業界の慣習として存在したと指摘した。神戸製鋼は可能な限りさかのぼって調査するとみられる。ただ関連資料が廃棄された製品もあり、今月下旬をめどに経済産業省に報告する安全性の検証結果は不十分なものにとどまる恐れがある。
関係者によると、調査は元の製品データと安全基準の資料を突き合わせて行う。保存期間は製品の種類や取引先によって異なる。原発や防衛産業関連は原則、永久保存される。不正はアルミ・銅製品から鉄粉、鋼線、特殊鋼に拡大。自動車や鉄道、航空宇宙、家電まで幅広く使われている。神戸製鋼は17日、米国子会社が、米司法省から問題製品の関連書類を提出するよう要求されたと発表した。
神戸製鋼所がアルミニウム製品などの検査データを改ざんしていた問題で、不正が見つかった5カ所の海外拠点は、いずれも国内の関連工場でデータの改ざんがあった。過去から引き継がれた組織の慣行をそのまま海外に持ち出したり、急速な海外展開に伴い検査態勢の不備があったりしたためとみられる。同社は原因究明につながると重視し、社内調査を進めている。
これまでにアルミ・銅部門の真岡(もおか)製造所(栃木県真岡市)や鉄鋼部門のグループ会社など国内10拠点で検査データの改ざんが発覚している。中国と東南アジアでも、アルミ・銅部門の3拠点、鉄鋼部門の2拠点で不正が見つかった。機械や溶接など他の事業部門では発見されていない。
空調機器向けの銅管を作るタイの子会社では、試験片を引っ張って強度を調べる試験をせず、硬さの試験だけを実施。そこから推定される引っ張り強度のデータを捏造(ねつぞう)し記入していた。自動車向けのばね用鋼材を作る中国の子会社は、納入先とあらかじめ決めた外観検査をせず、製品を出荷していた。
神戸製鋼のアルミ・銅部門は歴史的に独立性が高く、データ改ざんという組織内の慣行を海外でも続けていた可能性がある。
一方、神戸製鋼は2000年代、自動車メーカー向けに材料を供給する拠点として海外工場の新設を進めた。増え続けるアジアの自動車需要を取り込むためで、アルミ・銅、鉄鋼の両部門で現地法人16社を新設。近年も製造設備を増強してきたが、検査態勢の充実は結果的に後回しになった。
川崎博也会長兼社長は13日の会見で「過去の経験からできあがった仕組みや、(受注量に見合った)製造工程の余力があったのかなどに注目している」と話し、原因究明を急ぐ考えを示した。(高見雄樹)
外部の人間達で基本的に真面目で公平で、能力がある人達と商工中金で真面目で内部情報に多少の知識がある人達が補佐として協力 する形でなければ、全容解明は無理だと思う。
商工中金幹部の多くは不正について程度の違いはあれ知っていると思う。不正に全く気付かないような人間がに昇進する事はないと思う。 そう仮定すると、自分達の責任を追及する材料集めする人達を選ぶのに、不利になるような人材は選ばない。たとえ、妥協しても 出来るだけ自分達に有利になるように考えて人選すると思う。
株式会社商工組合中央金庫(しょうこうくみあいちゅうおうきんこ、英: The Shoko Chukin Bank, Ltd.)は政府と民間団体が共同で出資する唯一の政府系金融機関 であるはずなのに無茶ぶりが凄い。
最近の不祥事や不正は、「赤信号、皆で渡れば怖くない!」の心理があるような気がする。
国の低利融資制度「危機対応業務」を巡る不正が発覚した商工中金で、同社が毎月実施している経済統計調査でも、担当職員が数字を捏造(ねつぞう)するなどの不正があったことが18日、明らかになった。融資以外にも不正が判明したことで、ずさんな業務実態が改めて浮き彫りになった。
問題の統計調査は「中小企業月次景況観測」。同社の取引先1000社を対象に、景気の変化や売り上げ実績などの聞き取り調査を実施し、その結果を基に企業の景況感を示す判断指数(DI)などを毎月公表している。
関係者によると、ある支店の担当者が、実際には企業に聞き取りをしていないにもかかわらず、架空の売上高を記入するなどして、調査書を捏造していたという。危機対応業務不正の全件調査を進める中、他に不正がないか報告するよう全店に呼びかけたところ、本人が申告したという。
商工中金はこの統計について、「中小企業の景気動向を示す調査としては我が国唯一の悉皆(しっかい)(包括的な)調査を実施しており、国内、海外からも注目されている」とPRしていた。不正の事実を認めたうえで、「全容解明を進めている」としている。担当者がいつから捏造をしていたかや、他の支店で不正がなかったかどうかについても調査を進めている。
商工中金では今年4月、国の制度融資である「危機対応業務」を巡り、全国35支店計816件(融資額約198億円)で業績関連書類を改ざんするなどの不正があったことが第三者委員会による調査で判明。その後の全口座調査で、ほぼ全店で数千件の不正が行われていることが分かっている。
また、危機対応融資以外の制度融資でも不正があったことが判明し、現在全容解明に向けた自主調査が続いている。【小原擁、小川祐希】
国の低利融資制度「危機対応業務」を巡る商工中金の不正問題で、書類改ざんなどの不正がほぼ全店で行われていたことが商工中金の自主調査で明らかになった。件数は数千件に達している。所管する経済産業省などは不正が多かったデフレ脱却名目の融資の今年度での打ち切りを検討する。商工中金は役職員の大量処分を行う方針で、経産省出身の安達健祐社長(元事務次官)の辞任は避けられない情勢だ。
危機対応業務は、リーマン・ショックや東日本大震災など政府が「危機」と認定した事象によって、一時的に経営が悪化した中小企業に低利融資する制度。
これまでの調査で不正の多くが、2014年2月に「危機」に認定された、デフレと原材料・エネルギーコスト高(現在はデフレのみ)に対応するために実行された融資だったことが判明。商工中金の全約22万件の危機対応融資のうち、約5万9000件(融資額約280億円)をこの融資が占める。関係者によると、商工中金は「デフレ」の定義があいまいなことを利用して、本来は危機的状況でない企業にまで低利融資を行っていたという。経産省などは「危機」の拡大解釈によって融資実績を水増しする不正が商工中金に浸透していたとみており、不正の全容が分かり次第、抜本的な業務改革策を検討する。
危機対応融資を巡っては、今年4月の第三者委員会による調査で、業績関連書類を改ざんするなどして全国35店で計816件(融資額約198億円)の不正が発覚した。ただ、調査対象は2万8000件と92本支店の口座の約1割に過ぎなかったため、商工中金は現在、残りの全口座を調査中。5月からは金融庁などが立ち入り検査し、不正を生んだ組織体制などの実態解明も進めてきた。
商工中金の全融資のうち、危機対応融資は約3割を占めており、経産、財務、金融の所管3省庁は10月末にも終える商工中金の調査結果を待って追加の行政処分を行う。さらに11月にも有識者会合を設けて、政府系金融機関の本来の役割を改めて確認した上で、民間銀行と競合しないよう企業再生支援を強化するなど商工中金の業務内容の見直しに向けた議論を始める。
【小原擁、小川祐希】
「トップは外部から迎えるべき」は会社の判断だと思う。会社が偏った考え方を持っている、又は、社内ポリティクスでしがらみのために問題を 認識していても手を付けれない事がある。そのような場合には、かなり有効であるが、何も知らない外部に説明する時間や努力、短期間にしか いない外部者にいろいろな背景を説明する必要が発生する。
問題が発覚していない企業は日本でもたくさん存在すると思う。問題が発覚して、消滅、又は、他の会社に吸収合併されるようになるのは運次第。 他の企業や会社に行きたい人達がいれば、実行できるのなら実行すればよい。判断の結果は、結果が出るまでわからない。ここがかなりトリッキー だと思う。判断のプロセスが正しいのかまでは判断できるが、結果として正しかったのかは結果次第。これも運次第のところがある。
エアバッグのタカタにしても同じ。結果として現在のようになると理由はいろいろと考えられる。ただ、このようになると高い確率で予測できたのなら あのような判断をしたのか?この件で答えは公表されていないのでわからない。まあ、なるようになるしかない。
影響を受ける、又は、振り回される企業や従業員達は存在する。影響を受けない人達にとっては大した問題ではない。悲しいけれどこれが世の中で、 人生。
身内で固める日本企業の共通項
神戸製鋼という巨大企業が、大掛かりな性能データ改ざんを続けていたとは、信じ難いですね。なんと60年前から、改ざんに手を染め、不正は主力の鉄鋼製品にまで及ぶと聞くと、絶句します。米司法当局も書類の提出を求めたそうで、どこまで疑惑が広がるのか分からず、日本企業の信頼を損なわせる深刻な事態です。
日本の多くの企業にみられる共通項は、トップが生え抜きの日本人で、採用されてからひたすら出世し、社長に上り詰めたという点です。欧米系企業では、外部から経営トップが迎えられ、それを機会に企業体質を徹底的洗いなおし、経営計画をリセットします。その段階で不祥事が発覚すれば、手をいれます。
日本では、日本人で企業組織を固め、そこから育った社員が社長にたどりつくのですから、今回のような不祥事を解明し、うみを出し切るという意思を持ちません。一過性の不祥事ならともかく、今回のように悪しき企業慣行を何十年も続けてきたとなると、さらに手を下せません。
いつかはばれると恐れない不思議
神戸製鋼の川崎会長・社長は京大工科出身で、加古川製鉄所の現場経験もありました。データ改ざんを知らなかったでは通りません。疑問に思うのは、こんな大掛かりな改ざんを長期間、続けていれば、「いつかはばれる」、「ばれる時がいつか必ず来る」と思うのが普通です。
実際、そうなりました。社内では、とっくに不正に気がついていた多くの担当者、責任者はいたに違いありません。社長を含めての話です。8月末に現場から経営陣にデータ改ざんの報告が上がったといいます。それまで社長は知らなかったのか。そんなはずはないはずです。
品質偽装が常態化し、ばれないをいいことに黙殺を続け、対策を立てなかったか。明るみになれば、企業の致命傷になるとの認識を持ったはずです。そうした黙殺がもう通らなくなったと思ったのは、日本工業規格(JIS)に違反した製品の出荷が発見されたことのようです。それを機に、民間契約ベースでも違反がないを全社的な検査を始めざるを得なくなったというのが外部への説明です。
グローバル化経済の怖さ
粉飾決算を3代の社長が続け、その背後には原発事業の失敗が潜んでいた東芝も似ています。3代の社長が自分に好都合な後継者を後釜に据えるものですから、不祥事がなかなか発覚しませんでした。死亡事故が続いた欠陥エアバッグのタカタは創業者一族の経営でしたから、リコール対応も遅れ、一瞬にして経営破綻しました。
神戸製鋼については、各事業部が「タコつぼ化」し、情報の風通しが悪い。総会屋への利益供与、工場から排出するばい煙データの改ざんなど、過去にも数々の不祥事があり、経営幹部の意識や資質に問題がある、などなど。こういった企業であるからこそ、トップは外部から迎えるべきなのです。
社外役員、監査役、社長指名委員会の設置など、外部からのチェック体制を強化する企業は増えています。問題は経営トップに面識があり、近い関係者が就任することが多く、形骸化しています。
経済がグローバル化し、製品はもちろん、素材や部品が国内外またがって、供給される時代です。神戸が拠点でも、不正や不祥事が起きた場合、その被害、損害も巨大化します。貿易によって利益が大きくなる一方、経営上の失敗があると、企業破綻に追い込まれることと背中合わせです。チャンスも危機も大きいのです。
日本経済、企業の低迷をみるにつけ、身内だけで固める企業は、危険がいっぱいなのです。神戸製鋼の不祥事は日本型の閉鎖社会の怖さを見せつけてくれています。
編集部より:このブログは「新聞記者OBが書くニュース物語 中村仁のブログ」2017年10月17日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、中村氏のブログ(http://blog.goo.ne.jp/jinn-news)をご覧ください。
中村 仁
政府系金融機関の商工中金が国の制度融資で不正を行っていた問題で、金融庁など所管3省庁は、24日に立ち入り検査を開始した。背景や狙いなどをQ&Aでまとめた。
Q なぜ検査に入ったのか?
A 不正の原因を徹底的に調査し、特定するためです。商工中金は、震災や金融危機などで経営難に陥った中小企業に低利融資をする「危機対応業務」で、企業の財務関連書類を実際よりも悪く書き換えるなどして、融資件数を水増ししていました。これまでに35支店、816件(約198億円)もの不正が判明しています。
これほど多くの不正が起きた原因や、なぜ見過ごされてきたのかを突き止め、これからの業務改善、不正防止につなげることが検査の狙いです。
Q 検査の注目点は?
A 焦点は、経営陣がどこまで不正に関わっていたかです。2014年12月には、池袋支店の内部監査で110件もの不正の疑い事例が経営陣に報告されたにもかかわらず、当時の経営陣は、「問題無い」と結論付け、中小企業庁にもそのように報告していました。実際は、調査を行ったコンプライアンス(法令順守)担当部門が、不正に関与した職員に問題がなかったかのように証言させる「誘導質問ペーパー」を作成するなどして隠蔽(いんぺい)していたのです。
商工中金が依頼した弁護士で構成する第三者委員会は、不正をもみ消す組織ぐるみの「隠蔽行為があった」と認定する一方で、経営陣については「直接的な隠蔽指示や指揮命令の存在はなかった」と関与を認定しませんでした。ただ、「『場の空気』で不正を隠蔽するとは考えにくい」(金融庁幹部)との声もあります。
Q 今後は?
A 経済産業、財務、金融の3省庁は今月9日、商工中金に対し業務改善命令という行政処分を出しています。商工中金は、不正再発防止策などを盛り込んだ業務改善計画を6月9日までに提出します。3省庁は、検査で得た結果と改善計画を分析した上で、追加処分が必要かどうか判断します。悪質と判断されれば、業務停止や役員解任などの厳しい追加処分が出る可能性もあります。【小原擁】
大手鉄鋼メーカーの神戸製鋼所が追い詰められている。アルミニウムや銅などの品質を、偽って出荷していたことが10月8日に発覚した。13日には、新たに国内外のグループ9社でも、不正があったと公表。川崎博也会長兼社長は「神戸製鋼の信頼度はゼロに落ちた」と謝罪した。
出荷先は当初、自動車や電機メーカーなど約200社だったが、約500社まで膨らんでいる。出荷前の検査データが改ざんされた素材が、自動車や家電などさまざまな製品に使われている。全体像は大きすぎて把握できず、安全確認はこれからだ。
不正は10年以上前から続いており、管理職を含む数十人が関わっていた。一部の不正について、取締役会も把握していたが、公表はしなかった。
「KOBELCO」のブランド名で知られ、安倍晋三首相が社員だったこともある名門企業で、偽装行為が広がっていたのだ。
一方の日産自動車は、無資格の従業員に新車の検査をさせていたことがばれて、38車種、約116万台の大量リコールを届け出た。
不正を隠すために、有資格者の印鑑を複数用意し、無資格者に貸し出して書類を整えていた。燃費偽装問題で三菱グループから見放された三菱自動車は日産の傘下に入ったが、その受け皿でも不正が横行していた。
両社とも不正がばれるのを恐れるあまり、組織的な隠蔽(いんぺい)が行われていたようだ。企業としての説明責任も問われている。問題を公表した最初の会見では、神戸製鋼は副社長、日産は担当部長らが対応し、社長の姿はなかった。その後、社会的な批判が高まる中、社長の会見に踏み切った。日産と三菱自、仏ルノー3社の会長を兼ね、今年3月末まで日産の社長だったカルロス・ゴーン氏は、13日時点で公の場で説明していない。
企業不祥事やコンプライアンスに詳しい郷原信郎弁護士は、こうした不正は氷山の一角だと指摘する。
「問題の根本には、規制や取引先の要求が実態に合わない面があったのだろう。悪意のない形式上の不正だったのが、世の中が厳しくなるにつれ、発覚しないように偽装し、さらに隠蔽(いんぺい)することにつながった。それが恒常化することで“カビ”が広がるような根深い問題になる。こうした不正は他の大手企業にも蔓延(まんえん)している」
内部監査や内部通報のシステムもあるが、不正を発見するのは困難だ。
「組織的な不正は巧妙に隠蔽されるので、監査で発見するのは難しい。内部通報は通報する側にメリットがなく、犯人捜しをされかねない。行政やマスコミ、取引先への情報提供で、初めて発覚するケースがほとんどだ」(郷原氏)
こうしたカビ型の不正行為を発見する有効な方法は、問題発掘型アンケートだというのだが、
「社員から率直な自由回答を得る方法ではあるが、経営者の『覚悟』がないとできない。国が主導してアンケートを一斉に実施するなど、潜在化している不正への対策を集中的に行わないと、いつまでたっても同じようなことが繰り返される」(同)(本誌・多田敏男、太田サトル、秦正理/柳原三佳、佐々木亨、黒田朔)
※週刊朝日 2017年10月27日号
日産自動車が無資格の従業員に新車を検査させていた問題は、同社が国の指摘を受けて体制を見直し、約116万台のリコール(回収・無償修理)を届け出た後も続いていた。生産現場の規範意識の低さに加え、企業としての組織管理の甘さも再び露呈した形。失った信頼の回復は遠のきそうだ。
一連の無資格検査問題は、国土交通省が9月中旬に行った抜き打ちの立ち入り調査で発覚した。その後も違反状態が続いていたのは日産車体湘南工場(神奈川県平塚市)で、国内6カ所の完成車工場で最初に立ち入りを受けた工場だ。日産はただちに検査体制を改め、「無資格者が検査の工程に交ざらないよう監視員を立たせるなど厳戒態勢を取っていた」(幹部)というが徹底されていなかった。
違反があったのは、ハンドルの性能検査。機械が自動で計測・判定した結果の確認や記録は有資格者が行っていたが、ハンドルを回す作業は本来は携わってはならない無資格者2人が行っていた。対象となった車は4000台弱に上るが「保安基準には適合している」としてリコールも届け出ない方針という。
日産は弁護士ら外部識者を交えた社内調査チームの現地調査で今月11日に問題を把握。国交省には報告したものの、対外公表はしておらず、改めて情報開示に対する姿勢も問われそうだ。
日産の西川広人社長は2日の記者会見で「(国から問題を指摘されて以降は)すべて認定した検査員が行う体制に100%なっている」と述べていたが、事実は違った。今月末にも再発防止策を公表する予定だが、その実効性が疑問視される事態となった。早期に信頼を回復しブランドイメージへの打撃を最小限に食い止めるシナリオは崩れつつある。【和田憲二】
「タイヤが左右に曲がる角度をチェックするためにハンドルを回す作業を、資格のない『補助検査員』と呼ばれる社員2人が担当していた。基準を満たしているかどうかは機械が判定。 正規の検査員はその結果だけを見て検査済みの印鑑を押していた。」
資格のない補助検査員の仕事がこれだけなら、将来、AIに置き換えられる仕事でなく、今でも検査補助員は必要ない。ただ、違法な行為なので、 自動化すれば、組織ぐるみの不正である事は否定できないし、国交省の検査で簡単にばれてしまう。
数値データで判断、又は、数値データを認識して、結果が良ければ、書類に印鑑を押すようにプログラミングをするだけで良い。
装置に問題があったりした場合、結果に問題がなくても経験や勘で問題を疑ったり、発見できるのが熟練の人間の良い点だと思うが、 素人でも良いのなら、規則さえ満足すれば、必要のない人間や従業員はたくさんいるのではないのか?
人材不足であるのなら、改善や改革で人口は増やせないが、労働者を必要な部署にシフトは可能ではないのか?
日産自動車で無資格の社員が完成車両の検査をしていた問題を巡り、9月に国の立ち入り検査で問題が発覚した後も、一部工場では無資格検査を今月11日まで続けていたことが分かった。
無資格検査で新たに出荷されたのは約3800台。日産の西川(さいかわ)広人社長は2日の記者会見で再発防止に取り組む姿勢を示していたが、現場が無視した格好で、管理体制が厳しく問われそうだ。
日産によると、無資格検査を継続したのは、日産車体湘南工場(神奈川県平塚市)。タイヤが左右に曲がる角度をチェックするためにハンドルを回す作業を、資格のない「補助検査員」と呼ばれる社員2人が担当していた。基準を満たしているかどうかは機械が判定。正規の検査員はその結果だけを見て検査済みの印鑑を押していた。
日産自動車が無資格の従業員に新車の検査をさせていた問題で、9月に問題が発覚した後も、一部工場で無資格検査が続いていたことが18日、分かった。対象は約3800台。日産は改善策を講じたと説明し、西川広人社長も今月2日の記者会見で謝罪したが、その後も無資格検査が行われており、ずさんな管理実態を改めて示す形となった。
日産によると、無資格検査を続けていたのはグループ会社、日産車体の湘南工場(神奈川県平塚市)。弁護士らを含む日産の社内調査チームが11日に同工場の実態を調べたところ、ハンドルを左右に回して性能を検査する工程を無資格の従業員2人が行っていた。ハンドル性能は機械で自動計測され、結果は資格を持つ従業員が確認していたが、計測のためハンドルを回す作業は有資格者の指示で無資格の従業員が担当していたという。
これを受け、日産は湘南工場の出荷を一時停止し、12日に国土交通省に報告したが、公表は見送っていた。正規の作業手順の徹底を指示した上で、16日に出荷を再開したという。
湘南工場は、問題発覚後の9月20日から10月11日までに、無資格の従業員が検査に関わった約3800台を出荷した。ただ、保安基準に適合しているとして、新たなリコール(回収・無償修理)は実施しないという。
神戸製鋼(5406)がアルミ・銅・鉄鋼製品で品質データを改ざんしていたと発表しました。供給先は約500社に上り、10年以上前から組織ぐるみの不正が行われていたことになります。企業の不正に詳しくオリンパスや東芝の事件を暴いてきた刺激的な金融メルマガ『闇株新聞プレミアム』は、神戸製鋼の闇をどう見ているのか――。
真相が小出しにされている可能性も神戸製鋼単独なら容赦なく叩かれる
神戸製鋼が唐突に不正を公表したのは連休中の10月8日。顧客の求める品質基準を満たさないアルミ製部材や銅製品をデータを改ざんして出荷していたこと、供給先が航空・防衛・鉄道・自動車関連など約200社に上ること、管理職を含む数十人が関わり組織ぐるみであったことが梅原尚人副社長らから発表しました。
さらに13日に2回目の記者会見が行われ、当初否定していた主力の鉄鋼製品にも不正がおよび、供給先は約500社に上ること、内外子会社や品質保証担当者の関与も明らかになってきました。さすがにこの記者会見には川崎博也会長兼社長が登場しましたが、自身を含む経営陣はまったく認識していなかったと繰り返しています。
神戸製鋼は事業ごとの独立会社の集合体のようなものですが、もし本当に経営陣がまったく把握してなかったのだとすると、各事業部門がたまたま別個に・同時期に・同じような不正を、経営陣のまったく関知しないところで行なっていことになります。そんな話が信じられるでしょうか。真相が小出しにされているようで、今後どこまで大きくなるか想像がつきません。
ポイントとなるのは、同じような不正が同業他社でも行われている可能性です。経験的には不正が業界全体に広がっている場合は、意外にも問題は大きくなりません。2016年初めに発覚した旭化成子会社による杭打ち偽装事件は、同業他社にも同じような不正があると囁かれたものの、結局それ以上には広がらず沈静化しました。
海外では、欧州自動車メーカーのほとんどがディーゼル車の燃費検査不正にかかわっていましたが、結局は発端となったフォルクスワーゲンだけで止まり問題そのものも忘れられつつあります。最近急に広がり始めたEV(電気自動車)は、これ以上問題が拡大しないよう欧州自動車メーカーが一丸となった結果であるはずです。
今回の件が神戸製鋼単独の不正であれば、今後とことん叩かれるでしょう。
経産省も不正を知っていたのでは!?情報を漏らせば神戸製鋼は潰される
もう1つ経験的に感じることは、この手の問題が発覚するきっかけはだいたい内部告発であるということです。だとすると、管轄官庁である経済産業省も以前から把握しており、公表するタイミングも指導していた可能性があります。
こうなると経済産業省は責任逃れをするので、これから神戸製鋼から少しでも経産省の関与を伺わせる情報が漏れれば、潰されてしまう恐れも出てきます。
そんな大袈裟なと思われるかもしれませんが、1990年代の証券会社の損失補填も、山一證券の「飛ばし」も、すべて事前に大蔵省(当時)に相談していたため、その責任逃れのために証券会社が一方的に悪者となり、山一證券は消滅させられました。
今後の神戸製鋼の命運は、政治的なものになるはずです。最終的にどういう決着となるかは現時点で想像できませんが、この辺も頭に入れて今後の発表や報道を見ていく必要があります。
神戸製鋼の株価は不正発覚から急落し一時40%以上も下落したものの、774円(10月16日安値)を底に反発しています(10月17日現在)。悪材料が小出しにされているのだとすれば下げ止まったと楽観はできないところ。闇がどこまで深いのか、同業に広がっていく可能性も含め今後の成り行きが注目されます。金融メルマガ『闇株新聞プレミアム』では引き続き、この問題について取り上げていくことになりそうです。
闇株新聞編集部
「コベルコ科研は、2011年11月以降に出荷した10万枚超のうち6611枚について、基準値をはみ出した際に再検査をせず、検査証明書に虚偽の数値を記入していたと発表している。」
マンションの杭打ちデータの改ざんはデーターの貼り付けや他のデーターのコピーを張り付けたケースがあった。印刷出来ないから 検査データ不正になるのは言い訳だと思う。
事実は良く知らないが、会社の体質を良く知っているのは従業員や幹部達だと思う。
神戸製鋼所の検査データ不正を巡り、データを改ざんしていた子会社「コベルコ科研」(神戸市中央区)の高砂市の工場では、担当者が検査装置に表示された数値をノートに手書きし、検査証明書にはそのノートを基にパソコン入力していたことが17日、分かった。神戸製鋼は容易に改ざんできる古いシステムが不正を拡大させた要因とみて、11月にも公表する再発防止策に対応を盛り込む方針だ。
問題の製品は、銅やアルミニウムなどを溶かして固めた「ターゲット材」という板や筒状の金属材料。これにビームを当てて加工すると、液晶やDVDの材料になる。
コベルコ科研の高砂市の工場では、この金属に炭素や窒素などの不純物がどれだけ含まれているか、3台の装置で検査している。担当者は装置に表示された数値をノートに書きとめ、一定の量をまとめてパソコンに入力する。この入力データが検査証明書に自動的に記入されるという。
製造部門の社員は約90人。うち2~3人が検査担当だが、原料の金属を溶かすなど他業務を兼ねている。検査結果を確認する上司も製造部門に所属している。
コベルコ科研は、2011年11月以降に出荷した10万枚超のうち6611枚について、基準値をはみ出した際に再検査をせず、検査証明書に虚偽の数値を記入していたと発表している。
神戸製鋼の川崎博也会長兼社長は13日の会見で「品質保証(検査)の自動化の実態などを総合して原因分析する」と話し、不正の要因として注目しているとみられる。(高見雄樹)
神戸製鋼・製品検査データ不正(3)
神戸製鋼所の検査データ改ざん問題は、アルミ・銅製品だけでなく、同社主力事業の鉄鋼製品に広がった。川崎博也・同社会長兼社長が10月13日、問題発覚後初めて記者会見し、鉄鋼製品でも不正があったと発表した。鉄鋼製品の不正は取締役会に報告されていたものの、対外公表をしていなかったという。同社は不正を隠蔽(いんぺい)しようとしていたのか。
今回の不正発覚の経過を振り返ってみよう。アルミ・銅製品の不正は8月下旬、同社の製品品質検査で見つかり、8月30日に川崎会長兼社長ら経営陣に報告された。同社は過去1年間の不正について調査し、9月28日に経済産業省に報告したうえで、10月8日に不正の事実を公表した。ところが、不正はアルミ・銅製品にとどまらず、3日後の11日に、鉄粉と光ディスク用材料でも不正があったことが発表された。
翌12日、不正に関する説明のため経産省を訪れた川崎氏は、記者団の取材に対して「鉄鋼製品に不正はない」と説明した。ところが、「鉄鋼でも不正」とメディアが報道し、川崎氏は13日の記者会見で前日の発言を翻し、事実と認めた。神戸製鋼の対応は後手後手だった。
過去に不祥事を起こした子会社で
鉄鋼製品の不正はグループ企業4社で行われていた。国内の子会社2社、中国の子会社2社だが、より悪質な不正は国内の子会社の案件だった。
神戸製鋼の発表によると、子会社で東証1部上場企業である日本高周波鋼業は、2008年6月~15年5月、特殊鋼の硬さの検査データを改ざんしていた。持ち分法適用会社の子会社の神鋼鋼線ステンレスは07年4月~16年5月、ステンレス鋼線の引っ張り強度の検査データを改ざんしていた。
この2社は、過去に不正が発覚している。日本高周波鋼業は08年に日本工業規格(JIS)で定められた試験をせずに鋼材を出荷していた事実が明るみに出た。神鋼鋼線ステンレスでは16年に家電などに用いるばねの鋼材強度の試験値を改ざんしていた不祥事があった。同じ会社で繰り返し不正が起きていたことになる。
13日の会見で川崎会長兼社長は、鉄鋼製品の不正は、納入先に説明し、納入先とともに安全性に問題がないことを確認していたと説明した。「鉄鋼製品の不正を隠していたのか」との記者の質問に対し、「隠していたわけではない。取締役会や社内のコンプライアンス委員会に報告した。法令違反かどうかという判断で公表しなかった」と答えた。データ改ざんは法律違反にはあたらず、納入先との話し合いで問題は解決した、だから公表しなかったという説明である。
検査担当者の異動で発覚
記者会見で、不正が見つかった経緯に関する説明もあった。検査担当者が別の部署に異動し、後任の担当者が検査を行うために検査機器を動かしたところ、壊れていて検査できなかった。前任者が壊れたまま放置し、データを捏造(ねつぞう)して出荷を続けていたことがその時点でわかったという。
記者から「公表しなければならない案件ではないか。(鉄鋼製品の不正は)アルミ・銅製品で不正が見つからなければ隠していたのか」と追及され、会見に同席した勝川四志彦常務執行役員は「原因は会社の管理ミスと考えている。悪質性を我々なりに判断してコンプライアンス委員会にかけた」と答えるにとどまった。
神戸製鋼は今回発覚した不正について、川崎氏を委員長とする品質問題調査委員会を設置して調査にあたっており、外部の法律事務所にも事実関係の調査を依頼しているという。鉄鋼製品の不正が取締役会や社内のコンプライアンス委員会にどのように報告され、なぜ対外公表されなかったのかが調査のポイントの一つになる。当事者がトップに座った調査委員会で、公正中立な調査ができるのだろうか。
神戸製鋼所による製品データ改ざん問題で、同様に自社製品のデータを改ざんした同社子会社「コベルコ科研」(神戸市中央区)が、神戸製鉄所(同市灘区)で計画されている石炭火力発電所増設を巡る環境影響評価(アセスメント)の現況調査などを担当していたことが、16日分かった。既に兵庫県は「神戸製鋼の信頼性が大きく損なわれた」として環境データ検証の必要性を挙げ、計画審査の手続きを延期している。
神戸製鋼は11日、コベルコ科研がDVDや液晶画面などの材料「ターゲット材」の必要な検査をしていなかったり、検査データを書き換えたりしていたことに関与したと公表。2011年11月以降、対象製品は約6600枚、出荷先は70社に上るという。
石炭火力発電所増設の環境アセスに必要な環境影響評価準備書作成に当たり、現況調査や予測評価などを専門の企業などに委託。コベルコ科研は、大気環境や水環境の分野を担当した。この計画を巡っては、大気汚染物質の排出量増加への懸念を理由に、市民団体などから見直しを求める声が出ている。
神戸製鋼は「コベルコ科研は当社が委託した企業の下請けとして調査を担当した。委託先がチェックしているので、信頼性は確保されている」、コベルコ科研は「アセスの数値を含め、全社でデータを再点検している。調査のやり直しなど今後のことは、現時点で分からない」としている。(小林伸哉、高見雄樹)
神戸製鋼所の品質検査データの改ざん問題で、不正が数十年前から続いていたことがOBなど同社関係者への取材で分かった。同社は約10年前から改ざんがあったと説明しているが、開始時期はさらにさかのぼることになる。組織的に不正を繰り返す同社の体質が改めて浮かび上がった。
「少なくとも40年前には、製造現場で『トクサイ(特別採用)』という言葉を一般的に使っていた。今に始まった話ではない」。1970年代にアルミ工場に勤務していた元社員は40年以上前から不正があったと証言する。取引先が要求した基準から外れた「トクサイ」であるアルミ板を「顧客の了解を得ないまま出荷していた」と説明。その際、「検査合格証を改ざんしていたようだ」と話す。
また、90年代にデータ改ざんされた合金を部品加工会社に納入し「品質がおかしいのではないか」と指摘された元社員は、代替品をすぐに納入できたため問題が表面化しなかったという。この元社員は「工場長や工場の品質保証責任者も不正を把握しているケースもあり、不正は組織的に行われていた」と証言する。
一方、関西に住むベテラン社員は「鉄鋼製品では30年以上前から検査データの不正が続いている」と証言。自動車部品などに使われる鉄鋼製品の製造には熱処理が必要だが、処理の仕方によって品質に差が出ることがある。「品質検査の結果、一部で合格に達するデータが得られれば、適合品として出荷している」といい、「検査データの改ざんに当たる」と指摘する。
同社はアルミ・銅製品などで基準に合わない製品を計約500社に出荷していたと公表。8日の記者会見で梅原尚人副社長は品質データの改ざん時期を約10年前と説明したが、組織ぐるみの不正は数十年前から常態化していたとみられる。
一方、同社は17日、米国子会社が米司法当局からデータ不正を行っていた製品の関連書類を提出するよう要求されたと発表した。同社は「当局の調査に真摯(しんし)に協力する」としているが、同社による一連のデータ不正は海外当局による調査に発展した。【安藤大介、黒川優】
京都府公立大学法人以外による医療関係組織による 調査は可能なのか?
暴力団が絡んでいるし、運営している組織であれば関係が近すぎて公平な判断が出来るのであるか?
京都府立医大病院(京都市上京区)が暴力団組長の病状を検察庁に虚偽報告したとされる事件で、大学を運営する府公立大学法人の調査委員会は16日、前学長が組長と面会したことについて「社会通念上、許されるものではない」とする調査結果を発表した。
委員会は、前学長が組長と学長室で面会したり、組長の診療を指示したことについては「道義上の責任を指摘せざるを得ない」としたが、金品の授受などは確認できず、調査の範囲では法令に反すると判断できるものはなかったとした。
診断については、検察側への回答の根拠となるカルテの記載が不十分だったと指摘した一方、収監の状況や刑務施設の衛生環境などの情報が不足しており、組長が「収監に耐えられない」としたこと自体は「医師の判断としては妥当」で、虚偽や過大評価などは含まれていなかったと結論づけた。
その上で、カルテの記載基準の見直しや反社会的勢力に対する基本方針の明確化などを提言した。
事件をめぐっては、京都府警が今月6日、前病院長と当時の担当医を虚偽有印公文書作成などの疑いで書類送検した。前学長は3月に退職し、同容疑では書類送検されていない。
仕事で短い時間であるが、いろいろな組織や会社の一部分を見るようになってそう思うようになった。メリットがある会社ではデメリットに思えたり、 デメリットを会社や社員で最小限にしていると感じる事もある。人事やどのような人材を採用するのか、採用後の教育、採用された人材が会社で どのように変化しているのかも、長いタイムスパンでは影響してくる場合もあると感じる。
神戸製鋼所がどのような組織であるのか知らないが、歴史が長い企業や業界は比較的に体質が古い、変化を嫌う傾向があると思う。良い事や良いシステムを 維持する事は重要であると思う。ただ、時代や環境の変化によりシステムの軌道修正、改善そして廃止が必要な場合があると思う。その時に、上下関係 が厳しいシステムや会社の利益よりも自分達又は自分達の部署だけの利益を優先する環境である場合、変化の抵抗勢力になると思う。
それでも他の要素で成長するケースもあれば、衰退する場合もある。強いリーダーが存在すれば、問題をカバーしたり、一時的に悪い影響を 最小限に留める事が出来るかもしれない。
結局、他人事だし、なるようにしかならない。当事者達がどのような選択を取り、実際に、何をして、何が出来るかだと思う。
■子会社213社、情報共有されず
神戸製鋼所がグループ会社9社による不正を新たに公表したことで、関連会社を含むグループ全体への不信が広がっている。建設機械、プラント製造などへ多角化を推し進め、子会社200社以上を抱える神戸製鋼。しかし関連性の薄い事業が並ぶ縦割り構造が企業統治の機能不全を招き、不正の温床となってきた。
「報道で知ってびっくりしている。うちにも影響がないか心配だ。しかし(不正の公表は)神戸製鋼本体のことなので分からない」
ある有力グループ会社の幹部は、一連の不正について情報が共有されていないことに不安を募らせた。
一方、不正が公表された別の子会社の幹部は「グループ内の他の不正は、ちょっと想像できない」と語り、他の部門の情報を持っていないことを明かした。
鉄鋼メーカーで国内3位の神戸製鋼は、業界の世界的再編や中国などとの競争激化が進む中、規模の劣勢を事業の多角化で補う「複合経営」に取り組んできた。
主要事業は鉄鋼、アルミ・銅、建機、溶接、発電など7分野に及ぶ。同社によると、平成29年3月時点で子会社は213社、それ以外の関連会社も56社に上る。
ただ、企業経営に詳しい青木英孝・中央大学教授は「グループが複雑、巨大化すると、不正も隠しやすい状況に陥る」と指摘する。
また、専門性の高い部署の間で連携や情報共有ができない「縦割り経営」の弊害も生まれた。楽天証券の窪田真之・チーフ・ストラテジストは、「神戸製鋼は独立会社の集合体のような特性がある。グループ内の問題に全社で対応できていたのか」と疑問を投げかける。別部門の不祥事は人ごとと受け流され、反省や教訓が共有されなかった可能性があるというのだ。
実際、グループ内では18年から昨年までに、製鉄所の煤煙(ばいえん)データ改竄(かいざん)、グループ会社の鋼材試験データ捏造(ねつぞう)、ばね用鋼材のデータ改竄が相次いで発覚したが、教訓が生かされないままさらに不正が重ねられた。
川崎博也会長兼社長は13日の記者会見で、不正が同時並行的に行われていたことについて「その分析がキー(鍵)だと考える。原因分析の最中」と説明。本社部門のマネジメントに問題があったと認め、「風土的なものを感じられるのも仕方ない」とも述べた。
神戸製鋼は1カ月以内に原因分析と対策を経済産業省へ報告するが、その先には企業文化の刷新という難しい課題も待ち受けている。
神戸製鋼所がグループ会社9社による不正を新たに公表したことで、関連会社を含むグループ全体への不信が広がっている。建設機械、プラント製造などへ多角化を推し進め、子会社200社以上を抱える神戸製鋼。しかし関連性の薄い事業が並ぶ縦割り構造が企業統治の機能不全を招き、不正の温床となってきた。
「報道で知ってびっくりしている。うちにも影響がないか心配だ。しかし(不正の公表は)神戸製鋼本体のことなので分からない」
ある有力グループ会社の幹部は、一連の不正について情報が共有されていないことに不安を募らせた。
一方、不正が公表された別の子会社の幹部は「グループ内のほかの不正は、ちょっと想像できない」と語り、他の部門の情報を持っていないことを明かした。
鉄鋼メーカーで国内3位の神戸製鋼は、業界の世界的再編や中国などとの競争激化が進む中、規模の劣勢を事業の多角化で補う「複合経営」に取り組んできた。主要事業は鉄鋼、アルミ・銅、建機、溶接、発電など7分野に及ぶ。同社によると、平成29年3月時点で子会社は213社、それ以外の関連会社も56社にのぼる。
ただ、企業経営に詳しい青木英孝・中央大学教授は「グループが複雑、巨大化すると、不正も隠しやすい状況に陥る」と指摘する。
また、専門性の高い部署の間で連携や情報共有ができない「縦割り経営」の弊害も生まれた。楽天証券の窪田真之・チーフ・ストラテジストは、「神戸製鋼は独立会社の集合体のような特性がある。グループ内の問題に全社で対応できていたのか」と疑問を投げかける。別部門の不祥事は人ごとと受け流され、反省や教訓が共有されなかった可能性があるというのだ。
実際、グループ内では18年から昨年までに、製鉄所の煤煙(ばいえん)データ改竄(かいざん)、グループ会社の鋼材試験データ捏造(ねつぞう)、ばね用鋼材のデータ改竄が相次いで発覚したが、教訓が生かされないままさらに不正が重ねられた。
川崎博也会長兼社長は13日の記者会見で、不正が同時並行的に行われていたことについて「その分析がキー(鍵)だと考える。原因分析の最中」と説明。本社部門のマネジメントに問題があったと認め、「風土的なものを感じられるのも仕方ない」とも述べた。
神戸製鋼は1カ月以内に原因分析と対策を経済産業省へ報告するが、その先には企業文化の刷新という難しい課題も待ち受けている。
国の制度融資「危機対応業務」を巡る商工中金の不正問題で、危機対応業務以外の制度融資でも書類改ざんなどの不正があったことが、金融庁などの立ち入り検査で明らかになった。所管する経済産業省などは、不正行為が幅広い業務に広がっていたことを問題視し、危機対応融資以外の不正についても新たに行政処分の対象にする方針を固めた。【小原擁、小川祐希】
関係者によると、新たに不正が判明したのは、地方に投資を行って活性化に貢献した企業や、競争力強化の取り組みを進める企業などを対象に、国が税金を元手に商工中金の融資に利子を補給する制度。危機対応融資の不正と同様、担当者が融資関連書類の改ざんなどを行って、本来は対象ではない企業に利子補給が行われていたとみられる。
金融庁などの検査や商工中金の自主調査では、他にも不適切な行為が見つかった。中小企業の「ものづくり関連企業向け補助金」を巡り、支店の担当者が申請書類を改ざんし、実際は別の金融機関の職員が支援に関わっていたにもかかわらず、自らの実績であるように報告していた事例があった。また、税金が適正に使われているかなどを調べる会計検査院の検査の際に、危機対応融資関係書類の一部を修正するなどしていたほか、検査前に一部を破棄した可能性もあるという。
商工中金を巡っては、第三者委員会が今年4月に公表した調査で、危機対応融資の業績関連書類を改ざんするなどして全国35店計816件(融資額約198億円)の不正があったことが判明。その後の商工中金の自主調査で、ほぼ全店で数千件規模の不正が行われていたことが分かっている。
経産省などは、10月末にも終える自主調査の結果を待って、追加の行政処分を行う方針。商工中金は元経産次官の安達健祐社長の辞任を含め、行政処分に合わせて役職員の大量処分を行う方向だ。
放漫経営のケースはあるが、個人的に思うのは倒産する会社の従業員はやはり倒産する会社の従業員と思う事が多かったと思う。
大手になると政治家の力を借りて何とか出来るのかもしれないが、倒産した中小の会社の元従業員と話すと成長している会社の社員とは 考え方や対応が違うと感じた。
今回の神戸製鋼の問題、問題の割合としてはどのような配分なのであろうか?
下記の記事に書いてあるように、苦しみを感じていない限り一般的に人は変化を否定する。変化は良くなることばかりではない。全体的に 、又は、将来的に良くなるとわかっているケースでも、当事者にとって楽でない、又は、順応するために努力が必要であれば否定する人達も 存在する。良くなる可能性はあるが、悪くなる可能性があれば尚更、否定する傾向が高い。
単純に学歴や能力だけでなく、時にはリスクを取ろうする人、変化に順応する能力が高い人の方が、同じレベル、又は多少、レベルが劣っていても 必要な時や状況はあると思う。それを判断したり、登用する決断をするのは企業次第。将来を見通すのは難しいが、過去の失敗を検証し、理由を 探すのは簡単ではないが、将来を見通す事に比べればはるかに簡単。
神戸製鋼は今後、どのように変わっていくのだろうか?
「こんな話、従業員にもしたことないんですけどね……」
和歌山県出身の若手ビジネスパーソンが集まる「わかやま未来会議」の講演で、川崎博也社長は何度かそう言いながら神戸製鋼所で進む大改革について語った。改革を進めるトップとして、強い風当たりとプレッシャーを感じながら、支えにしてきたものとは?
会社の存続を考えるのが社長の仕事
神戸製鋼所は社名に「製鋼」の文字が入っていますから、もちろん鉄鋼メーカーであることに間違いはありませんが、鉄鋼事業の比率は連結売上比率で4割弱であり、他に非鉄事業や機械・エンジニアリング・建機事業を有した複合事業を特徴としております。また、粗鋼生産量で言えば世界の中で53番目、シェアは0.5%に過ぎません。日本に限定しても7%です。アルミや機械の事業はここまでではありませんが、やはりグローバルにはメジャーとは言えません。
また、私が社長に就任する2013年の1~2年前はひときわ厳しい時期でした。11年度及び12年度の2期連続で最終赤字を出しました。当時は新日本製鉄と住友金属工業が合併し、アルミ業界でも古川スカイと住友軽金属工業が一緒になり、マスコミからは「神戸製鋼所は業界の再編に乗り遅れた」と書かれたものです。社内でも、「わが社の将来は大丈夫なのか」という危機感が強くなっていました。
会社が消えないようにするにはどうしたいいかを懸命に考えるのが社長である私の仕事です。私が佐藤(廣士)会長から社長就任の話を受けたのが13年1月中旬。それから4月1日までの2カ月半くらいは、「ここをどう切り抜けるのか」を四六時中考え、悩み、夜中にハッと目が覚めることもしばしばありました。
これまでは景気循環を見ながら、悪いときがあっても必ずいつかは儲かるはずだと事業をつづけてきました。しかし、もはやそういうトレンドが通用しない時代に入っています。確実に日本の人口は減っていきます。若者の嗜好が変化し、自動車を買わなくなっているので鉄鋼も売れません。海外マーケットを目指しても中国や韓国が台頭しています。中国はつくり過ぎるほど生産している。しかも、以前はつくれなかった高級鋼を生産できるレベルになってきました。
そうした状況を考えると、今までの延長では会社はなくなってしまいます。大胆に変化していくしかありません。
復興のシンボルを廃する苦渋の選択
変える必要があるとわかっていても、人間は基本的に保守的な存在なので、いつかは業績が戻るとか、今変えてもリスクがあるだけだとか、変化を拒みがち。トップでさえ、なぜ自分の代で変えなくてはいけないのか、変えなくてもいいのではないかと思ってしまうものなのです。
しかし、決断が遅れたときには、会社はつぶれます。早く変えれば変えるほど、チャンスにつながると自分に言い聞かせなければなりません。
変化を嫌う気持ちに打ち勝てるかどうかは、従業員や株主への思いをいかに強く持てるかにかかっています。以前、雑誌の記事で、ある会社の経営者が「私は会社を“変える”ために“カエル”を飼うことにした」と話しているのを読んで、感銘を受けたことがあります。さすがに生きたカエルを飼うのは抵抗がありましたので(笑)、代わりにカエルの人形を買って社長室に置きました。いつもそれを見ながら、「変える、絶対に変えるんだ」と気持ちを強くしています。
変革の1つが高炉の休止です。製鉄にはスクラップを電炉で溶かす方法と、鉄鉱石と石炭を原料に高炉で鉄をつくる方法があります。当社には高炉が4本あり、そのうちの1本、神戸製鉄所の高炉を止めることに決めました。13年の5月に発表し、実際に休止するのは17年です。
実は高炉を止め、電炉に代えたほうがいいのではないかという考え方はすでに20年くらい前からありました。でも、ずっと踏み切れずにいました。高炉は製鉄所にとってシンボルであり、鉄をつくるプロセスの最初につかう設備です。しかも神戸製鉄所の高炉は復興のシンボルでもあります。阪神淡路大震災が起きたとき、神戸製鉄所も被災し、1000億円強の被害を出しましたが、当社は神戸の地で生まれた会社だから製鉄所も復興しようと決め、復旧に半年かかると言われましたが、頑張って2カ月で立ち上げました。
従業員やOBからは「復興のシンボルをなぜ止めるんだ」と反対されました。これには、かなり悩みました。しかし11年、12年の時点で同業上位2社との間に利益率で大きな差が生じてしまっていました。鋼材事業が生き残れなかったら、機械事業もアルミ事業もバラバラになり、神戸製鋼所は解体の危機に陥ります。それは従業員の幸せにつながりませんから、社長として絶対にしてはいけない。存続するためには鋼材事業の収益力をあげざるを得ません。
NHK首都圏放送センターの記者で2013年に過労死した佐戸未和さん(当時31)の両親が10月13日、「私たちの思いは正確には伝えられていない」と東京・霞が関の厚労省記者クラブで会見を開いた。
冒頭、会見を開いた経緯について両親は、「各メディアからNHKの発表内容に基づいた報道がされてきましたが、私たちの思いが正確には伝えられていないことや、事実誤認もあります。未和と同じ記者の皆様には、私たち夫婦の口から直接お話をさせていただいた方が良いと考えました」と説明した。
●局内で公表されず、募る不信感
両親によると、毎年、未和さんの命日の前後にかけては、親交のあったNHKの同期や同僚が多く見舞いに訪れるという。しかし彼らからは、「過労死の事実について局内で伝えられていない」「NHKの働き方改革が進んでいるのは、未和さんの過労死があったからだということは知られていない」という声ばかりを聞いた。
「不名誉な案件として出さない方針にしているのではないか。過労死がなぜ起こったのか局内で自己検証もされておらず、誰も責任をとっていないのではないか」。未和さんの死が、NHKの働き方改革推進の礎になっていることを知って欲しいと強く感じていたという。
未和さんの死が明らかに伝わっていないーー。両親がその思いを強めたのは、今年に入ってからだ。未和さんの母は「全国過労死を考える家族の会」を通じて会合やシンポジウムに参加する中で、取材に来ていた記者たちに「自分の娘もNHKで過労死でなくなった」と打ち明けた。その際にNHKの記者もいたが、「そんなことがあったのか」と初めて聞く話に驚愕していた。
「NHKで長時間労働や過労死を実際に取材する報道現場の人でさえ知らない。声を上げなければ未和のことはNHKで埋もれてしまう。それは許せないと感じた」。
さらに、NHKの対応も拍車をかけた。毎年未和さんの命日1か月前には、勤務していた首都圏放送センターから電話があり、命日の訪問について連絡があった。しかし、今年は4日前になっても何の連絡もなかった。「来て欲しいということではないが、未和のことが局内で周知されていないのではないか」。代理人の川人博弁護士にそう連絡をしたところ、川人弁護士を通じて、ようやくNHKから両親の元に連絡が来た。
NHKは電通の過労自殺事件をはじめ、特番を組んで長時間労働による過労死問題を熱心に報道していた。その一方で、未和さんが過労死したという事実は局内に伝えられてこなかった。そういった特番を見ながら、両親のNHKに対する不信感は募っていった。
「NHKは自らに起こったことは棚上げにしたままではないか。NHKが未和の過労死を忘れず、遺族の心情に寄り添ってくれていると感じたことはない」。未和さんの死に真摯に向き合わないNHKに、怒りの目を向けるようになった。
●「2014年にお詫びを申し上げた」は事実ではない
NHKは報道陣に対し、2014年の労災認定後、謝罪したと説明しているが、両親は「事実ではありません」ときっぱり答えた。
両親によると、2014年7月の命日に、当時の首都圏報道センター長が弔問し、文書を出したという。しかしその内容は、「一周忌を迎え、謹んで哀悼の意を評しますとともに、ご遺族の方々にお悔やみ申し上げます」などと始まり、最後まで一言のお詫びも記載されていなかった。
●「遺族が公表を望まない意向を示していた」は事実ではない
NHKは未和さんの過労死の公表について、「当初は遺族側から公表を望まないとの意向を示されていたので、公表を控えていた」と説明していた。しかし、それに対して両親は、「事実ではありません」とはっきりと述べた。
未和さんの父は「未和の急死後、妻が体調を崩し、私も24時間張り付くという状況が続いていた。そうした状況だったので、川人弁護士はそっとしておいて欲しいと(NHK側に)伝えたと思う」。
また川人弁護士は、「労災認定された時点で記者会見を開くということは(遺族の状況から)考えていなかったので、『(そのような記者会見を開くことは)考えていない』という趣旨の話はした。しかし、公表しないで欲しいという申し入れをしたことは全くない」と説明した。
●公表にいたるまでの経緯
両親は未和さんの過労死について、NHKの中での周知徹底を望んでいた。内部で公表されればその情報が外部に漏れ、外部から未和さんについての記事が出されることも予想された。そこで、「きちんとした取材もせずに記事が出てくるのは私たちの思いとは違う。NHKとしてきちんと公表して欲しい」と公表に向けての話が進んでいった。
しかし、NHKから両親に示された公表内容は、
・自分たちは労基署から法律違反という指摘は受けていない
・みなし残業ということで、記者に残業時間という概念はない
・お詫びは2014年8月にやっている
といった内容を含んだものだった。到底承諾できるものではなかったため、打ち合わせを重ねた。
公表までにNHKは3回打ち合わせに来たが、その中で放送の仕方について未和さんの母が尋ねたところ、「我々はプロの集団ですからプロに任せておいてください。10月3日までに公表ドラフトを送ります」と言われたという。
そうして内容のすり合わせを行っていたが、未和さんの過労死の事実は10月4日に突然公表されることになった。実はこの4日午後にも、両親はNHKと公表内容について打ち合わせをしていた。内容で折り合いがつかない部分もあったため、両親は後日また話し合うというつもりでいたが、自宅に帰った夕方に突然「今日の夜の9時のニュースに出します」とNHK側から連絡があった。
その理由について、「事実かどうかは分かりませんが、未和さんの件で数社から取材申し込みがあったため」と説明があったという。今回の公表の仕方について、未和さんの母は「9時のニュースの最後に2分ほどちょろちょろと流された。がっかりしました。今まで打ち合わせしてたのはなんだったのだろうか」と振り返った。
●「未和のことを自分のこととして考えて」
過労死を繰り返さないために、何を望むかーー。会見の最後にそう問われた未和さんの母は、その場に集まった記者にこう問いかけた。
「未和のことを自分のこととして考えていただき、過労死で亡くなるいうことは絶対ないようにして欲しい。1分でも早く(選挙の)当確を出すことが、本当に大事なことか原点に立ち戻って考えて欲しい」
弁護士ドットコムニュース編集部
日本放送協会(NHK)の記者だった佐戸未和(さど・みわ)さん(当時31)が4年前に過労死していた問題で、佐戸さんの両親が13日、東京・霞が関の厚生労働省内で記者会見を開いた。佐戸さんの父は「未和は記者として、自分の過労死の事実をNHKの中でしっかり伝え、再発防止に役立ててほしいと天国で望んでいると信じる」と語り、再発防止の徹底をNHKに改めて求めた。
佐戸未和さんは2013年7月24日、うっ血性心不全を起こして急死。過重労働が原因で死亡したとして、14年に労災認定された。亡くなる直前1カ月の時間外労働(残業)は約159時間にのぼった。
NHKは今月4日夜のニュース番組で、佐戸さんの過労死と労災認定の事実を公表した。佐戸さんの死後4年余りにわたってこの事実を公表しなかった理由について、NHKは「遺族側の要望で公表を控えていた」と説明しているが、佐戸さんの父は会見で「事実ではない」と反論した。
また、NHKが「労災認定後に(佐戸さんが所属していた)首都圏放送センターの責任者が遺族に謝罪した」と説明していることについても、「我々は謝罪とは受け取っていない」と言及。これまでの経緯についてのNHKの公表内容に不正確な点があると指摘した。(牧内昇平)
NHKを含め、メディアとか報道で働くと不規則な労働パターンになる可能性が高い事は理解するべきだと思う。メディアや報道がリアルタイムの報道を する以上、不規則な労働形態は避けられない。
本人の希望があるから親の意見が就職活動で反映されるのかはケースバイケースだと思うが、親が不規則な労働パターンがある企業での就職を望まないのであれば 就職活動をする前や就職を決定する前に子供と真剣に話し合うべきだと思う。子供の中には親に黙って就職先を決めるかもしれないが、大人として判断を 尊重するのか、親子の絆がおかしくなるリスクがあっても話し合うべきだと思う。
ただ、NHKが問題を認識し公表したのが4年後と言うのは企業の闇を疑わせる事実だと思う。
NHKの対応に疑問を持つ親がいれば、子供がNHKを選択肢として含めているケースがあれば反対すれば良い。ただ、他の選択肢の企業が良いかはその企業次第。 NHKよりも体質的にもっと悪い企業だってある。選択肢の中で比較して、希望や優先順位を考えて決めるしかない。入社しないと見えてこない問題が あると思うので、何が正しいかは個々の価値観と運しだい。
NHK記者の佐戸未和さん(当時31歳)が2013年に過労死した問題で、佐戸さんの両親が13日、記者会見し、「労働時間の管理をしっかりやれば、死なずに済んだはず」と訴えた。NHK側が両親に謝罪したのは、亡くなってから4年以上が経過した今年9月だったという。
NHKによると、佐戸さんは13年7月に自宅でうっ血性心不全で亡くなり、渋谷労働基準監督署が14年5月に労災認定した。直前1カ月の時間外労働は、過労死ライン(直前1カ月100時間)を上回る159時間に達していたと認定された。【古関俊樹】
国の低利融資制度「危機対応業務」を巡る商工中金の不正問題で、書類改ざんなどの不正がほぼ全店で行われていたことが商工中金の自主調査で明らかになった。件数は数千件に達している。所管する経済産業省などは不正が多かったデフレ脱却名目の融資の今年度での打ち切りを検討する。商工中金は役職員の大量処分を行う方針で、経産省出身の安達健祐社長(元事務次官)の辞任は避けられない情勢だ。
◇デフレ名目融資中止も
危機対応業務は、リーマン・ショックや東日本大震災など政府が「危機」と認定した事象によって、一時的に経営が悪化した中小企業に低利融資する制度。
これまでの調査で不正の多くが、2014年2月に「危機」に認定された、デフレと原材料・エネルギーコスト高(現在はデフレのみ)に対応するために実行された融資だったことが判明。商工中金の全約22万件の危機対応融資のうち、約5万9000件(融資額約280億円)をこの融資が占める。関係者によると、商工中金は「デフレ」の定義があいまいなことを利用して、本来は危機的状況でない企業にまで低利融資を行っていたという。経産省などは「危機」の拡大解釈によって融資実績を水増しする不正が商工中金に浸透していたとみており、不正の全容が分かり次第、抜本的な業務改革策を検討する。
危機対応融資を巡っては、今年4月の第三者委員会による調査で、業績関連書類を改ざんするなどして全国35店で計816件(融資額約198億円)の不正が発覚した。ただ、調査対象は2万8000件と92本支店の口座の約1割に過ぎなかったため、商工中金は現在、残りの全口座を調査中。5月からは金融庁などが立ち入り検査し、不正を生んだ組織体制などの実態解明も進めてきた。
商工中金の全融資のうち、危機対応融資は約3割を占めており、経産、財務、金融の所管3省庁は10月末にも終える商工中金の調査結果を待って追加の行政処分を行う。さらに11月にも有識者会合を設けて、政府系金融機関の本来の役割を改めて確認した上で、民間銀行と競合しないよう企業再生支援を強化するなど商工中金の業務内容の見直しに向けた議論を始める。
【小原擁、小川祐希】
危機対応融資をめぐる商工中金の不正がほぼ全店に広がっていた背景には、金融・経済情勢が「危機」と言えない状況でも拡大解釈で融資が可能となるずさんな制度の問題がある。経済産業省などは、危機の認定を厳格化するなどの制度改革や、商工中金の業務全体の見直しにも着手する方針だが、「政府系金融機関の役割を改めて問い直すべきだ」との声も出ている。【小原擁、小川祐希】
◇経産省「危機認定」見直しへ
「企業が危機的状況ではないにもかかわらず、行員に融資獲得のノルマが課せられ、プレッシャーを受けて改ざんを繰り返した」。監督官庁のある幹部は、不正拡大の背景をこう説明する。
危機対応融資は、2008年のリーマン・ショックや、11年の東日本大震災などの経済・社会の混乱を、「危機」と認定し、日本政策金融公庫を通じて利子の一部(約0.2%分)を国が負担する公的制度。利子補給分は国民の税金が元手だ。
問題は、世界的な金融市場の混乱から、大規模災害、物価が継続的に下がる「デフレーション(デフレ)」まで、広く「危機」と認定している点だ。危機対応融資の予算は政府の補正予算編成のたびに「経済対策」として計上され、それに合わせて対象が拡大してきた経緯がある。不正発覚を受けて行われた第三者委員会の調査にかかわった関係者は、「そもそも危機の定義を広げて、低利融資をばらまいてきた政治にも問題がある。一政府系機関の不正というだけの単純な問題ではない」と指摘する。
一方、商工中金も、融資実績を積み上げるため、制度の甘さに乗じていた。商工中金は「経営トップは一切不正を指示しておらず、知らなかった」と説明しているが、経営幹部らが現場にノルマを課したことが、不正を誘発したとの指摘は多い。業績が一時的にでも悪化さえしていれば「デフレのため」と解釈して融資することも可能なため、「上手に稟議(りんぎ)書を『作文』して融資をした行員が評価されるようになり、やがて数値の改ざんなどにエスカレートしていった」(関係者)という。経産省幹部は「危機対応融資以外に自らの存在意義を見いだしにくくなっていた」と背景を指摘する。
経産省などは不正の一因が危機認定プロセスにあったとして、融資基準の見直しや客観的評価を聞いた上で認定解除を機動的にできる新たな制度の設置を検討している。商工中金についても「地銀と敵対して民業を圧迫するのではなく、補完関係を築く」(経産省幹部)ことを念頭に、民間金融機関との協調融資など、危機対応融資に代わる業務へのシフトを進める方針だ。
いばらの道であろうが、東芝のようになる前の状態であるのなら良かったのかもしれない。新聞の記事しか知らないので、本当の状況は知らない。 今後の情報次第で、状況や深刻度は違っているのかもしれない。
神戸製鋼所がアルミ・銅製品などの性能データを改ざんしていた問題で、同社主力の鉄鋼製品のうち、自動車のエンジン部品やサスペンション、ボルト、ナットなどに使用する「線材」でも新たにデータ改ざんが見つかったことが13日、分かった。鉄鋼製品ではこれまで、自動車部品などの材料となる鉄粉で改ざんが判明していたが、同社が強みを持つ主力鉄鋼製品の一部に不正が広がったことで、納入先企業の不信感はさらに高まりそうだ。
川崎博也会長兼社長は13日中にも記者会見を開き、新たな改ざん判明の経緯や事業への影響などについて説明する見通し。不正行為が主力の鉄鋼製品でも見つかったことにより、同社の不適合品の出荷量はこれまで想定されていた2万トン強からさらに増えることが確実だ。
神戸製鋼所の川崎博也会長兼社長が12日、「新たな不正事案」を近日中に公表する考えを示したのは、経済産業省から早期の全容解明と情報公開を強く求められたからだ。神戸製鋼は8日にアルミ・銅製品の不正を発表した後、マスコミ報道を受けて11日に鉄粉製品、光ディスク材料でも品質検査のデータに不正があったと発表した。同社の調査と結果の発表が後手に回っているため、経産省は期限を設けて川崎氏に事実を公表するよう求めるなど、今回の不祥事は異例の展開となった。
「製品の安全性の検証結果は2週間程度で公表」「徹底的な原因分析と再発防止策の立案は1カ月以内」
経産省の多田明弘製造産業局長は12日、一連の不正について説明に訪れた川崎氏に期限を設け、公表するよう求めた。経産省が不祥事を起こした民間企業に、ここまで具体的に指示するのは異例だ。多田局長は今回の不祥事で日本の製造業全体の信頼が傷つくことを懸念。「社長のリーダーシップの下、法令違反の有無や安全性への影響などを究明してほしい」と強く要請した。
川崎氏が記者団に「今後、新たな不正事案が発生する可能性がある」と発言したのは、多田局長との面会直後。8日の記者会見には梅原尚人副社長を登壇させた川崎氏だが、「説明責任を果たす必要があると考えた。近々に私から会見させていただきたい」と一転し、近日中に自ら説明する考えを示した。
不祥事発覚後に不正があったアルミ・銅製品の安全性などに関する情報が不足したこともあり、神戸製鋼株は10日の東京株式市場で売り注文が殺到し、値幅制限の下限(ストップ安)で取引を終えるなど混乱した。
今回、川崎氏は経産省に背中を押される形で、遅まきながら情報公開と説明の責任を経営トップが果たす必要があると判断した模様だ。川崎氏は「神戸製鋼の信頼度はゼロに落ちたと考えている。私をトップリーダーとして、早い段階での信頼回復に努めたい」と述べたが、果たして発言通りの説明責任を果たして失墜した信頼を取り戻せるか。リーダーとしての真価が問われることになる。【川口雅浩】
◇新幹線部品も強度基準未満
東海道・山陽新幹線「N700A」の台車の部品に、検査データの不正があった神戸製鋼のアルミ製品が使われ、日本工業規格(JIS)で定められた強度の基準に届いていなかったことが分かった。設計したJR東海は仕様書で「JIS基準に準拠するように」と求めていたが、実際はJIS基準の強度を最大10%下回っていた。車両を持つJR東海とJR西日本によると、強度は安全面で必要な水準を大きく上回っており、「走行の安全性に影響がない」という。
神戸製鋼が残していた過去5年分のデータを両社が確認したところ、JR東海の車両では台車の部品2種類310個がJIS基準を満たしていなかった。JR西日本でも部品2種類148個が基準未達だった。両社とも定期検査などで適正な部品に取り換える方針だ。
JR東日本は過去、東北新幹線で走る「E5系」1編成の骨組みに、問題となったアルミ製部品を使用していた。調査の結果、該当の部品は同社の要求基準よりも厚さが厚かったといい、同社は「車両の強度への影響はないと判断している」という。
N700AはJR東海が設計し、JR西日本も加えた2社が個別に仕様書を作成。鉄道車両大手の日立製作所や日本車輌が製造し、JRの両社に納入している。
今回、JR東海とJR西日本は仕様書で、問題の部品についてJIS認証を受けることまでは求めておらず、数ある品質データ検査の一部としてJIS規格に準拠することとしていた。このため、神戸製鋼は法令違反とはならず、川崎博也会長兼社長は12日、記者団に「違法性はないということで、(納入先と)共通認識が得られている」と述べた。
一般的に神戸製鋼がメーカーから受注する仕様書は、JIS規格よりも規格が厳しく、要求品質が高いという。JIS規格はかなり余裕をみて強度の基準を決めており、今回のように基準を下回ったとしても、安全性に問題はないという。
だが、JIS規格並みの強度を求めたJR東海の仕様書に神戸製鋼が違反したのは明白で、今後は部品の交換に必要な費用の負担などを巡り、製造した鉄道車両大手を巻き込んだ交渉になるのは必至だ。【宇都宮裕一、川口雅浩】
[東京 12日 ロイター] - 神戸製鋼所<5406.T>の川崎博也会長兼社長は12日、経済産業省内で記者団に対して、アルミ・銅製品などで性能データを改ざんしていたことについて「品質不正で神戸製鋼の信頼度はゼロに落ちた」と厳しい現状認識を示した。
その上で、まだデータの突合せ作業が終わっていないことから「今後、新たな不正事案が発生する可能性がある」と述べ、実際に国内外で複数の「疑わしい事案がある」ことを明らかにした。神戸製鋼の品質不正問題はさらに広がりを見せる可能性がある。
川崎社長は12日午前、経産省を訪れ、品質不正問題の経緯について報告した。川崎社長は「多くの方々にご心配をおかけしていることを深くおわびする」と謝罪。その上で「安全検査と確認を最優先課題として、万全の体制で取り組んでいく」と述べ、安全性の確認を急ぐ考えを示した。
対応した多田明弘製造産業局長は「公正な取引の基盤を揺るがす誠に遺憾な事態。一部には日本の製造業全体の信頼にもかかわるとの指摘もあり、私どもとしては重く受け止めている」と語った。
経産省は同社に対して、1)新たな不正の特定・調査を早期に完了させる、2)安全性の検証結果を2週間程度をめどに公表する、3)徹底的な原因分析と対策立案を1カ月以内をめどに完了させる――の3点を指示した。
<経営責任の言及避ける>
川崎社長は会談後、記者団に対して、自らの経営責任について「今は原因究明と対策、安全性の検証に最大限努力することが私の責任だ」と述べ、事態の収拾を優先させる考えを示した。収拾後の辞任の可能性については「外部の意見や今回の影響度を総合して決めたい」と述べるにとどめた。
神戸製鋼の品質不正は過去1年間に出荷したアルミ・銅製品の4%、出荷先は約200社に上る。川崎社長は約100社に戸別訪問して状況を説明したことを明らかにした上で、残りの100社についても「可能な限り早く情報提供、安全性の検証・確認に入っていきたい」と語った。
リコール(回収・無償修理)の可能性については「現時点でその可能性があるとは聞いていない」という。
神戸製鋼の品質不正問題は日本の製造業全体の不信感につながる可能性もある。川崎社長は「われわれの会社だけの信頼低下だけにとどまらないのは十分理解している。本当に申し訳ない」と重ねて謝罪した。
業績への影響については、賠償請求など費用がどれくらいかかるかわからないため「見積もれない」と指摘。資産売却も「今のところ考えていない」と語った。
*内容を追加しました。
日産自動車で無資格の社員が完成検査をしていた問題は、約116万台という大量リコールを出しただけでなく、同社の信頼とブランドイメージを損ないかねないほどの事態となった。そもそも完成検査とは何か、なぜ問題が発生したのか。根本的な理由や背景を探った。(ジャーナリスト 井元康一郎)
● 「好調ぶり」に水を差した事件 そもそも完成検査とは何か
昨年秋に三菱自動車を傘下に入れ、今年9月にはロングレンジEVの新型「リーフ」を発売するなど、好調ぶりをアピールしていた日産自動車にとって、無資格者による完成検査の横行が発覚したことは、まさに好事魔多しと言うべき事件であった。
9月29日に無資格者検査の事実を公表してから1週間後の6日には過去3年間に国内販売した38車種、106万台についてリコールの届け出を行うなど、早期の事態収拾を図っているが、「実態の把握と原因究明には1ヵ月ほどかかる」(日産自動車関係者)と、傷ついたブランドイメージの回復についてはまだ途上にある。
完成検査とは、製造したクルマが公道を走る要件を満たしているかどうかのチェックで、いわば「0回目の車検」にあたる。スピードメーターの誤差は基準値以内か、ブレーキはちゃんと利くか、ライトの光軸は狂っていないか、警笛はちゃんと鳴るか等々、チェック項目も車検に準じたものだ。初めてクルマを登録するときに運輸支局にクルマを持ち込んで検査を受ける新規検査を、自動車メーカーが代行すると考えればわかりやすい。
自動車メーカーは自社の製品について、エンジンや車体などの仕様が一定で、環境性能や保安基準などの要件を満たしているという認定、すなわち型式指定を国道交通省から受ける。
その指定を受けたクルマについては、車検を行う運輸支局にいちいち持ち込まずともディーラーでナンバーをつけてそのまま走らせることができるのだが、それにはメーカーがちゃんとチェックをしましたよと証明する完成検査終了証が添付されていることが条件だ。ちなみに、この証書には9ヵ月という有効期限があり、ディーラーが売れ残りなどで未登録の新車をそれ以上長期にわたって在庫してしまった場合は、新車であっても運輸支局であらためて予備検査を受ける必要がある。
完成検査はチェック項目こそ決められているが、やり方は自動車メーカーによって異なっている。国交省が唯一求めているのは、「公的な車検場における検査官と同等技量を持つという資格制度を社内で設け、資格があると認定された人物が検査を行え」ということだ。
日産自動車が不正を行ったとされるのは、有資格者ではない人物が完成検査を行っていたということ。
「運輸支局にクルマを持ち込まなくてもいいという型式指定制度の信頼を揺るがす」(国交省関係者)と、国がおかんむりになっているのもむべなるかなで、日産の違法行為は糾弾されて当然である。
● なぜ日産は初歩的な 不正をやってしまったのか
ここで、どうしても解せないのは、なぜ日産がそんな初歩的な不正をやってしまったかということだ。筆者は日産の工場を何度も見学したことがある。日産は高級車ブランドであるインフィニティの世界展開を目指していることもあってか、品質検査を行う熟練職人の養成については、自動車メーカーのなかでもことのほか熱心な方だった。
ライトを当てただけで、ほとんどわからないような小キズや塗装ムラを発見したり、手で触れただけで0.1mm単位のドア、ボンネット、トランクなどの取り付け誤差を検知できるような人材は、一朝一夕に育つものではない。その人材を育成するため、ベテランが若手を教育し、日々テストを行って一人前にしていくのである。最終到達地点は、数万点の部品の役割をすべて理解し、自分ひとりでクルマを組み立てられるというものだ。
ところが、完成検査は商品検査と違ってそういう“匠の技”のようなものではない。クルマが保安基準に適合しているかどうかを見るだけだ。
「ウチは完成検査はすべて有資格者がやるよう、昔から徹底してきた。ただ、完成検査はクルマの品質がちゃんとしているかどうかを見る検査とは違う。有資格者と言っても、車検レベルの検査能力を習得するのは難しくはないし、社内の認定基準もそう厳しいものではない。そもそも検査工程は正規従業員であろうと期間工であろうと、かなり経験を積んだ人材が配置されるという実情を考えると、日産さんも検査工程に振り向ける人材については早い段階でどんどん完成検査の資格を取らせればよかったのではないかと思う。なぜそうしなかったのか」
生産に詳しいライバルメーカーの幹部は、日産の生産体制についてこう不思議がる。
日産はこのところ、グローバルでの販売が好調で、生産台数を急激に増やしてきた。2017年上半期の国内生産台数は前年同期に比べて実に23%も多い53万2800台であった。リーマンショック直後、神奈川の追浜工場の様子を見たことがあるが、その時はクルマの売れ行きが悪く、生産ラインは止まっているのではないかというほどスカスカだったのだが、今はフル生産に近い状態だという。
「生産台数が急に増えた時というのが、制度にきしみが出るリスクがいちばん高まる時。品質がいい加減にならないようにするにはどうしたらいいかという点については、現場が一所懸命工夫するので、それほど大きな問題にならない。
それに対し、必要な人材をどうしたら確保できるか、現有の陣容で生産増にどう対応したらいいかといった制度面については、経営者や工場をコントロールする生産担当役員、工場長などが現場ときちんとコミュニケーションを取り、やり方を現実に即したものに柔軟に変えてあげないと、現場の側の工夫だけではいかんともしがたい。
ライバルのことなのであくまで想像ですが、品質ではなく完成検査なんかで問題を起こしたのを見ると、日産さんにはそこが足りなかったのではないでしょうか」(前出のライバルメーカー関係者)
● 「危機意識がなかった」と 非難されても致し方ない
今回の不祥事は、日産にとってはブランドイメージの低下という点で痛い失点だ。昨年の三菱自動車買収の際、当時日産の社長だったカルロス・ゴーン氏は「ダメな三菱自動車を完璧な我々が再生させる」と言わんばかりであった。
その日産が違法行為を行っていたというのでは失笑を買うことは避けられない。が、そればかりでなく、せっかく新しい企業統治体制を敷いた三菱自動車においても、「日産の言うことなど聞けるかと」いうレジスタンスが出てくる隙をみすみす見せてしまったのもいただけない。
品質問題ではなく完成検査の問題ということで事態を軽く見すぎたのか、今回の問題で、日産は最初に西川廣人社長や生産担当役員ではなく、一般の従業員に会見を任せた。
これはいくら何でも「危機意識がなかった」と非難されても致し方ない。
実際には技能を持っている人材がやるのだからと、勝手な法解釈にもとづいてクルマづくりをやったというのは事実で、この件が露見した段階で同じように法運用や企業統治に乱れがあるのではないかと疑い、その部分も含めて速やかに対処法を出すのがトップの仕事だからだ。
● 昔のまま法や規則を 放置していた国交省の制度設計
こうした日産個社の問題の一方で、国交省側の制度設計もあらためて問われる。
昨年の三菱自動車の燃費不正問題では、本来はイコールコンディションで審査をすべき走行抵抗(燃費を計測するうえでの重要な項目)の計測をメーカー任せにしていたのが不正を許す要因になっていた。
今回の完成検査については逆に「クルマの品質がごく低かった60年前ならいざ知らず、今の自動車工学の水準のもとでは完全に形骸化している。法は守るべきだが、昔のまま法や規則を放置していたのも問題」(自動車業界事情通)という側面もあるのだ。
国交省はこのところ高速道路のトンネル崩落、耐震偽装、燃費不正、今回の完成検査と、まさに失態続きだ。前身である旧建設省、旧運輸省は、ともに許認可意識が非常に強いのが特徴であった。
これまでは責任問題に発展しかねない事件が起きるたびに、華麗に批判をかわしてきた同省だが、そろそろ謙虚に、時代に即した制度設計に抜本的に取り組む柔軟性と謙虚さを持つべきだろう。
井元康一郎
野口陽 村井七緒子、辻森尚仁
神戸製鋼所グループで11日、新たに鉄粉や液晶部品向け合金の検査データの偽装が明らかになった。性能データを改ざんしていたアルミニウム・銅製品とは別の部門で問題が発覚。新幹線の台車に使っているアルミ製品の一部が日本工業規格(JIS)の基準に届いていなかったことも明らかになった。不正の影響が広がり続けており、経営陣の責任問題に波及するのは必至だ。
11日夜、神鋼は記者会見を開き、液晶部品向け合金と鉄粉の検査データを書き換えたり、検査を怠ってデータを捏造(ねつぞう)したりしていたことを新たに発表した。8日に発表したアルミ・銅製品の性能データの改ざんに続く発表に、勝川四志彦常務執行役員は「決して隠そうとしていたわけではない。報道があったので、調査中だが発表した」と釈明した。
8日の会見では、アルミ・銅の製造部門と四つの工場で検査結果の組織的な改ざんがあったことを明らかにしたが、経済産業省が10日、アルミ・銅以外にも2製品で改ざんがあったと発表。これを受けて再び会見を開くことになった。
アルミ・銅製品の改ざんは8月…
ただ、隠ぺいを継続した場合、問題が発覚した時には再スタートが非常に難しい状況になる事もある。最終的には企業の判断次第。
東芝の問題がそのようなケースになるのでは?
アルミと銅製品の性能データ改竄が発覚した神戸製鋼所では、経営トップから全社員に対し、コンプライアンス(法令順守)強化を促すメールが送信されるなどの対応に追われた。同社をめぐっては、過去にも不祥事が相次いでおり、モラル軽視が浮き彫りになっている。川崎博也会長兼社長ら経営陣の責任論が浮上するのは必至とみられる。
神戸製鋼がデータ改竄を発表して最初の営業日となった10日、川崎会長兼社長は全社員にメールを送信した。事実の経緯を説明した上で、再度、法令順守徹底を促す内容だったが、どこまで社員の心に響いたかは疑問だ。
昨年6月には、グループの神鋼鋼線工業の子会社が、ばね用鋼材で日本工業規格(JIS)を満たしているように試験データを改竄したことが発覚。神戸製鋼は公表から1カ月もたたないうちに、法例などの順守状況の一斉点検結果をまとめ、「新たな不正はなかった」と安全宣言した。
しかし、1年数カ月後に今回のデータ改竄が発覚。8日の記者会見で、梅原尚人副社長は「前回はJISに関連するため、法的規格に関しての監査を厳しくした。その一方で(今回問題となった)民間同士の取引に対する意識が乏しかった」と釈明したが、取引先の信頼を失いかねない発言で、企業統治(コーポレートガバナンス)崩壊の危機だ。
神戸製鋼では、平成21年に政治資金規正法に違反したとして犬伏泰夫社長(当時)が引責辞任しており、度重なる不祥事は経営に深刻な打撃を与えそうだ。
「不祥事企業」のイメージがつきまとう中、法令順守の欠如に真剣に向き合い、徹底した原因究明と再発防止策が求められる。(平尾孝)
神戸製鋼所がアルミニウム製品の性能データを改ざんしていた問題で、JR東海は11日、東海道新幹線の車両「N700A」の台車に使っている製品の一部の強度について、同社の仕入れの基準として準用している日本工業規格(JIS)の基準を下回っていたことを明らかにした。
JR東海によると、問題のアルミ製品は、車輪を円滑に回すベアリングを支える軸箱体(じくばこたい)やそのふたに使用してきた。
神戸製鋼が残していた過去5年分のデータをJR東海が確認したところ、軸箱体(じくばこたい)やそのふたに使っているアルミ製品の一部にあたる310個について強度が基準を下回っていた。その結果、問題の310個を使った軸箱体(じくばこたい)やそのふたの強度も基準を下回っていたという。
経済産業省によると、JIS基準を満たしたと認証されないまま製品にJISマークをつけると違法になるが、そうでなければ法には触れない。JR東海は、そうした基準を自社の仕入れに基準として準用していたという。
JR東海の柘植康英社長が11日の定例記者会見で明らかにした。柘植氏は「実際にかかる力より相当高い強度があるので安全」とした上で「不適合の製品が納入されたことは誠に遺憾」と述べた。
問題の製品は、年1度ほどのペースで実施する車両の定期検査にあわせ適正なものに交換していく。交換の費用負担や調達先の変更については「今後話し合うので現段階では検討できない」と話した。
JR東海はほかに、車両の揺れを吸収する部品に付けるダンパー受けや窓枠、行き先表示器の枠にも神戸製鋼製のアルミ製品を使っている。ダンパー受けはJR東海の調査の結果、JISに適合していたが、窓枠などは現在確認中という。
神戸製鋼の勝川四志彦・常務執行役員は11日夜、東京都内での記者団の取材に「JR東海が発表した事実は存じ上げていない。この場ではお答えいたしかねる」と述べた。(友田雄大)
周りは困惑するかもしれない。しかし、仕方の無いこと。
大学は全ての教授及び教員の免許の有無、免許の有効期限をチェックする事は出来るかもしれないが、子供ではないのだからそこまでする必要が あるのかは疑問。
このような状況になると免許の有無や有効期限を確認する大学が増えると思う。チェックする時間よりも、事故が起きてからの対応に費やされる 時間の方が比べ物にならないくらい多いはず。
岐阜県警加茂署は11日、自動車運転処罰法違反(無免許過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、同県山県市西深瀬、岐阜大教授辻泰秀容疑者(59)を逮捕した。
逮捕容疑では、4日午後2時35分ごろ、同県七宗町神渕の県道で、乗用車を無免許で運転中、道路左側に停止していた同町のパート女性(66)の軽乗用車に追突し、そのまま逃げたとされる。女性はむち打ちや両腕打撲のけがを負った。
署によると、「身に覚えがない。自分は辻泰秀ではない」と容疑を否認している。目撃情報などから辻容疑者を特定し、自宅近くの修理工場で左前部が破損した車も見つかった。辻容疑者は2011年10月、免許失効となっていた。
岐阜大広報によると、教育学部教授の辻容疑者は小中学校の美術教育が専門。教師を目指す学生に、実際に子どもたちと工作をさせるなど実践的な授業をしている。広報の担当者は「事実関係を確認中」と話した。
常識を疑われるし、常識や人間性を疑われると、信頼や信用にも影響を与える。
岐阜県警は11日、岐阜大教育学部教授の辻泰秀容疑者(59)=同県山県市西深瀬=を自動車運転死傷処罰法違反(無免許過失運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕し、発表した。名前を名乗らず、容疑を否認している。県警は乗っていた乗用車の所有者などを調べ、本人と特定したという。
加茂署によると、辻容疑者は4日、同県七宗町神渕の県道で、無免許で乗用車を運転。道路左側に停車した軽乗用車に追突し、乗っていた同町のパート女性(66)に首がねんざするなどの重傷を負わせ、そのまま逃げた疑いがある。辻容疑者は2011年10月から免許が失効していた。
岐阜大によると、辻容疑者は美術教育学の専攻。同大は「全く把握しておらず、今後事実を確認する」とコメントした。
電気自動車(EV)新型「リーフ」の量産開始を祝うオフライン式が、神奈川県横須賀市の日産自動車追浜工場で盛大に開催されたのが9月19日のことだ。
この日、西川廣人・日産社長は集まった約1000人の従業員を前に「万全の品質でリーフをお届けしていく」と誓ったが、実際にはこれとほぼ同時期、追浜工場を含む国内六つの全工場で国土交通省の立ち入り検査が行われ、資格のない従業員が完成検査を行って出荷していたことが次々に発覚したのである。
オフライン式のわずか10日後に日産は無資格検査の実態を発表。その後、2014年10月から17年9月までに生産し国内販売した24車種、約121万台について、リコール(回収・無償修理)を国交省に届け出ることが説明された。リコール対象車は日産販売会社のサービス工場などで再点検を行い、その費用総額は250億円を超える見通しだ。
日産や国交省によれば、型式指定を受けた自動車については、メーカー自らが国に代行して1台ごとに完成検査を行うことになっている。その際、日産は必要な検査項目を全て実施していたが、一部の項目については社内で認定された検査員として認められていない補助員が担当していた。
その原因について西川社長は、有資格者が検査をしなければならないとの「認識が(現場で)多少薄まっていたのかもしれない」と説明したが、いつごろから見過ごされていたかなどの詳細は明らかになっていない。
一工場の単純なミスではなく、全工場で発覚したことから長年にわたって慢性的に行われていた可能性もあり、日産は第三者を含む調査チームにより原因究明を急ぐ考えだ。
販売攻勢一転、尻すぼみ
日産がEV再発進の象徴として大々的に売り出すはずだった新型リーフの販売にも、今回の問題が影響を及ぼすのは必至だ。
一部は納車が遅れる見通しだが、何よりも消費者の信頼回復や生産現場の混乱を収拾するのに一定の時間を要し、当面は販売の重い足かせとなるに違いない。
不幸にも西川社長がリコールを発表した10月2日は新型リーフの発売日で、本来ならその日を華々しく迎えるはずだった。
それが謝罪会見に変わってしまったことは、誰よりも西川社長が悔やんでいるに違いない。6日に予定していた記者向けの試乗会も延期となり、“リーフ祭り”の様相は一気に尻すぼみとなり、自粛ムードになってしまった。
EV新時代を先駆けるはずだった新型リーフの思いがけぬ失速。最大の敵は、米テスラの「モデル3」でもトヨタ自動車の「プリウスPHV」でもなく、自らのずさんな検査体制にあったといわざるを得ない。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 重石岳史)
アルミ・銅製品の検査データの改ざんが判明した神戸製鋼所で、同様の改ざんを鉄粉でも行っていた疑いがあることが10日、分かった。
問題のある製品の種類が拡大する可能性が高まった。一方、経済産業省は同日、自衛隊の防衛装備品にもデータが改ざんされたアルミ製品が使用されていたと発表した。
関係者によると、新たに鉄粉についても、顧客と交わした仕様書に適するようにデータを改ざんした疑いが浮上したという。鉄粉は、自動車のギアなどの複雑な形状の部品を作る素材として供給されている。
アルミ・銅製品に関しては、経産省幹部が10日記者会見し、9月28日にデータ改ざんの報告があり、神戸製鋼に対し、安全性の証明や再発防止策の提示などを指示したことを明らかにした。防衛装備品への使用については、三菱重工業やIHI、川崎重工業、SUBARU(スバル)から報告を受けたという。IHIによると、航空機用のエンジンの一部でアルミ製品が使用されていたという。川崎重工は民間向けか防衛向けかは明らかにしないものの、航空機のエンジンや部品に使われたことを認めている。
しょうもない言い訳だ!
少なくとも、対応しなかったのは、故意なのか、故意でないのかは公表するべきだ!故意でないのなら、システムや担当者や責任のフロチャートを 公表して説明するべきだと思う。
財務省みたいにHDDのデータを定期的に復旧できないシステムになっていると報告をするのだろうか?
NHKの記者だった佐戸未和(さどみわ)さん(当時31)が4年前に過労死していた問題で、NHK執行部が今月4日に公表するまで、経営委員会に対して正式に報告していなかったことがわかった。10日にあった経営委員会後に石原進委員長(JR九州相談役)が記者団に明らかにした。
経営委は、NHKの最高意思決定機関で執行部を監督する権限がある。月に2度のペースで開かれる委員会で、執行部側から事業の運営状況などの報告を受ける。委員は企業の幹部や大学の研究者ら外部の12人で構成されている。
石原氏は同日の委員会で初めて佐戸さんの過労死に関する報告があったと記者団に説明。「今回の事案は委員会に報告して頂きたかった」と語った。
一方、上田良一会長は5日の定例記者会見で、佐戸さんが亡くなった当時はNHK監査委員を務めており、「その立場で亡くなったことは承知していた。執行部側で適切に対処していると理解していた」と述べた。当時は経営委員も兼ねていたが、委員会全体に情報を共有していなかった。
佐戸さんは2013年7月に心不全で急死し、翌年に労災が認定されている。
当事者達はそんな事を考えるような状態ではないと思うが、答えは将来にわかるであろう。
アルミ・銅製品の検査データに不正が見つかった神戸製鋼所は、鉄鋼では新日鉄住金、JFEスチールに次ぎ国内3位、アルミではUACJ(旧古河スカイ)に次ぎ、国内2位の大手メーカーだ。今回の不正を受け、自動車メーカーがリコール(無料の回収・修理)に踏み切った場合、神戸製鋼はリコール費用を請求される可能性があり、経営に大きな打撃を受けることになる。
神戸製鋼の2017年3月期連結決算は、230億円の最終(当期)赤字で、2期連続で最終赤字を計上した。部門別には鉄鋼が原料高などで295億円の経常赤字だった。これに対し、今回問題となったアルミ・銅部門は120億円の経常黒字で、電力事業と並んで同社の稼ぎ頭。軽量化で自動車の燃費改善に貢献するアルミは、各メーカーの採用が増えているためだ。
神戸製鋼は18年3月期の業績について「自動車向けを中心とする旺盛なアルミ需要を背景に、販売数量の増加やコスト削減などでアルミ・銅部門は増益を見込む」としているが、不正が発覚した工場は「納期を守り、生産目標を達成するプレッシャーがあった」(梅原尚人副社長)とされ、拡大路線が組織ぐるみの不正につながった可能性もある。同社は18年3月期で3期ぶりの最終黒字を見込むが、今回の不正で自動車メーカーとの取引が減るなどすれば、目標達成は困難になる。【川口雅浩】
◇アルミ素材
アルミは鉄に比べて比重が3分の1と軽く、熱伝導性(冷却機能)に優れているため、自動車などのエンジンにはアルミ合金が幅広く使われている。しかし、強度が要求されるボディーの骨格は現在も鉄が主流で、アルミの多くはボンネットやドア、トランクリッドなど「フタもの」と呼ばれる部材にとどまっている。
世界的に自動車の燃費規制が厳しくなった2000年代以降は、日欧米のメーカーが軽量化で燃費を改善するため採用を増やしている。バッテリーを積む電気自動車は重量がかさむため、アルミの採用が進むとみられる。コスト高や鉄との溶接が難しいなど課題もあるが、軽量化のため航空機や鉄道車両への採用も進んでいる。
行政は可能なエリアや項目は規制を緩和して、絶対に守らないといけない項目を違反した場合にはこれまでの2倍から10倍ぐらい厳しく 処分及び罰金をかければ良いと思う。
守られない法や規則はないよりはましなだけ!どうせ守られないのなら、法や規則を緩和して、絶対に守らない法や規則を違反した企業を厳しく 罰したほうが良いかもしれない。問題は、厳しくすると隠ぺい工作が巧妙になる可能性があるし、口裏合わせや内部告発者に対する圧力が 厳しくなり、刑事事件としないと行政では解決できない部分が増えると思う。
神戸製鋼所が納入したアルミ・銅製品の検査データで、10年以上前から組織ぐるみで改ざんが行われていた。同社は今後、納入先のメーカーと品質や安全性への影響を調査するが、結果次第では、自動車の大規模リコールに発展する可能性もあり、ずさんな検査管理への批判が高まりそうだ。
神戸製鋼はメーカーの要求に基づき、アルミ・銅製品を生産しているが、検査の結果、「強度や寸法がちょっと足りないものでも、ごまかして出荷していた」(同社幹部)という。納入したアルミ・銅製品の強度が不足していた場合、部品メーカーや自動車メーカーによる加工、組み立ての工程で耐えられなくなり、破損するなどのトラブルが発生するが、今のところトラブルは発生していない。同社は「信頼を裏切る行為だった」として、メーカーと安全性を調査する。
今回の不正を受け、トヨタ自動車はじめメーカー各社は、神戸製鋼との取引の有無や時期、調達部品の種類などの確認に追われている。自動車を構成する約3万点の部品の中でもアルミはボディーのほか、エンジン、吸排気管、変速機などに幅広く使われているからだ。トヨタは一部の車種のボンネットなどで該当のアルミ製品を使用していることを認め、「現在対象となる車種や部位などを確認しており、今後の対応策を検討している」と説明した。そのうえで、「従来仕入れ先に対し、コンプライアンス(企業の法令順守)の徹底をお願いしてきた。今回コンプライアンス違反があったのは重大な問題」との認識を示した。
JR東海は、神戸製鋼所が強度などを偽って出荷した部品が、東海道新幹線の車両の台車部分に使われていることを明かした。JR東海は「実際の検査データを確認したところ、十分な強度を持っていることが確認された」とし、安全上は問題がないとした。今後の定期検査などに合わせ、適正な部品と交換するという。
神戸製鋼では2016年6月にグループ会社の神鋼鋼線ステンレス(大阪府泉佐野市)が、家電や日用品など幅広い製品のばねに使われるステンレス鋼線の試験値を9年以上にわたって改ざんし、日本工業規格(JIS)を満たすように偽装していた法令違反も発覚。相次ぐ不祥事で神戸製鋼の法令順守や企業統治体制が厳しく問われるのは間違いない。【川口雅浩、和田憲二、金寿英】
神戸製鋼所でまた品質データの改ざんが発覚した。
8日に明らかになったアルミ・銅製品の検査証明書のデータ改ざんは、現場の管理職が黙認するなど組織的に行われていた。
神戸製鋼の製品はトヨタ自動車の一部車種やJR東海の東海道新幹線、三菱航空機のジェット旅客機「MRJ」など幅広く使われており、影響が懸念される。
神戸製鋼の梅原尚人副社長は8日の記者会見で、「管理、監査、(ルールを守る)教育が抜けていたと反省している」と陳謝した。
神戸製鋼は2008年に子会社で鋼材の強度偽装が発覚し、16年にはグループ会社でもバネ用鋼材のデータ改ざんが明らかになった。今回は、取引先と決めた強度などの基準に合っていないのに、適合しているかのように検査証明書のデータを書き換えていたもので、梅原氏は「(現場の)管理職は関わっているか、知っていた」と、組織ぐるみだったことを認めた。
神戸製鋼所の梅原尚人副社長の記者会見での一問一答は次の通り。
-性能データを改ざんした製品の納入先は。
「名前は言えないが、当社の製品は自動車や航空機、飲料用の缶など幅広く使われている。安全性を含めて個別に顧客と協議している」
-法的に違反しているのか。
「現時点で法的な違反はない。民間同士の契約で顧客と約束した強度や寸法があるが、製品の仕様に違反した書き換えを行っていた」
-最終製品の安全性に問題は。
「あるかないかと言えばあり得る。ただ、求められている強度や性能を満たしていなければ、顧客がプレスなどで加工する際に問題が出る。現時点で問題は起きていない」
-関与した社員の規模は。
「管理職も含めて国内3事業所と(子会社の)コベルコマテリアル銅管で合わせて数十人が関与していた」
-組織ぐるみの不正という理解でいいか。
「はい」
-原因は。
「現場は納期、生産目標のプレッシャーがある中でやってきた。工場ごとに人事異動がなく、閉鎖的な環境だった」
-不正はいつごろからか。
「10年近く前から改ざんをやっていた」
-製品を使っていた車のリコールは。
「顧客にデータを提供して共同で検討している。全くあり得ないとは言えない」
アルミと銅製品の性能データの改ざんが発覚した神戸製鋼所は、過去にも深刻な法令違反や不正が発覚し、トップの辞任に発展したこともある。昨年のグループ会社でのデータ改ざんを受け、神戸製鋼は川崎博也会長兼社長の指示で今年5月、社員の行動規範を改めて定めたが、負の連鎖は止められなかった。
神戸製鋼は1999年、総会屋への利益供与が発覚。金銭提供などの商法違反で、元役員らが有罪判決を受けた。この事件では専務ら3人と、利益供与当時の会長だった亀高素吉相談役が辞任した。
2006年には、神戸、加古川両製鉄所で環境基準を超える窒素酸化物などを含むばい煙を排出しながら、測定データを改ざんしていた不正が発覚。排ガスの基準値が超えそうになると、担当者が自動記録装置の記録ペンを手で浮かせて印字できないようにするなど悪質な手口も明らかになった。
09年には、加古川製鉄所、高砂製作所のほか、今回のアルミ製品不正も発覚した長府製造所(山口県下関市)で、地方議員の後援会に政治資金規正法が禁じている寄付をしていたことが明らかに。当時の犬伏泰夫社長と水越浩士(こうし)会長の辞任に発展した。
13年に川崎氏が社長となってからも、16年にグループの神鋼鋼線工業(尼崎市)の子会社で、日本工業規格(JIS)を満たしているように試験値を改ざんしていた問題が発覚。川崎氏は法令順守の徹底を一番の経営課題に挙げ、今年5月には行動規範「KOBELCOの6つの誓い」を公表。誓いには「法令、社内ルール、社会規範を遵守(じゅんしゅ)することはもちろん、高い倫理観とプロとしての誇りを持って、公正で健全な企業活動を行います」とうたった。企業風土を変えられなかった経営陣の責任が問われそうだ。(高見雄樹)
タイミング的には単独で発表するよりは良いと思う。
神戸製鋼所でもこのような強度偽装が起きるのだから、やはり、ネットで書き込まれているように隠ぺいや偽装は多くの業界や企業で行われているのであろう。
日本でこのありさまだから、外国人からかなりの不評を受けている中国製品は「ウルトラ」が着くほど隠ぺいやインチキを行っているのであろう。
トヨタ自動車は8日、神戸製鋼所が強度などを偽って出荷していた部品を自社製の自動車に採用していたことを明らかにした。「仕入れ先でコンプライアンス違反があったことは重大な問題であると認識している」とするコメントを発表した。
トヨタ広報によると、国内工場で組み立てた一部車種のボンネットやバックドアの周辺部に採用していたとみられるという。「お客様の安全を最優先に考え、対象となる車種、使用部品の特定と車両への影響を早急に確認するとともに、今後の対応策について検討している」とのコメントも出した。
◇
三菱重工業は8日、神戸製鋼所の問題の部品について、開発中の国産初のジェット旅客機、MRJに採用していることを明らかにした。
当該の部品をMRJのどこに使っているか、試験を行っている5機のうち何機に使用しているかは、明らかにしていない。
三菱重工の広報は「設計には安全面でもともと余裕を持たせており、強度を含めた部品の安全性は問題ない範囲と確認した。開発スケジュールへの影響は今のところないとみているが、継続して情報収集に努める」としている。
同社はMRJの航空会社への納入を2020年から始める計画だ。
◇
神戸製鋼の問題の部品について、JR東海は、東海道新幹線の車両の台車部分に使われていることを明らかにした。
同社広報は「実際の検査データで確認したところ、走行安全上は十分な強度が確認でき、問題はない」としている。今後の車両の定期検査にあわせて適正な部品と交換するという。
神戸製鋼所でまた、品質管理の不祥事が発覚した。自動車に使われるアルミニウム製品の強度などを偽って出荷。1年前、グループ会社でばね用ステンレス鋼線の強度偽装の不祥事が起きたばかり。不正は本体を含む「組織ぐるみで常態化」していたことになる。信頼性は損なわれ、経営責任が厳しく問われる。
8日に記者会見した梅原尚人副社長は、「実際に手を下したり、黙認したりしていたのは管理職を含めて過去1年間で数十人」と語り、「組織ぐるみか」と問われ、「はい」と答えた。
不正の背景は、「納期を守り、生産目標を達成するプレッシャーの中で続けてきた」と分析。一方で、「品質に関する意識が弱いとは考えていない。(納入先との)契約を守る意識が低かった」と釈明した。
不正は、今秋の社内監査を控え、工場での自主点検で見つかった。梅原氏は「かなり古い時期から(不正が)あった」とも話した。10年前から改ざんが続いているケースも確認され、常態化の可能性を認めた。今回、検査回数を少なくする手抜きも発覚した。
昨年の不祥事発覚で、「一気に是正すると影響が大きく、踏み切れなかったようだ」と説明した。再発を防ぐ取り組みが不十分だったと認めた形だ。
経営責任について梅原氏は「経営陣も、もちろん責任を考えていく」とした。
同社は国内3位の鉄鋼メーカー。不正の対象製品は自動車、航空機、電子機器など幅広い分野に及ぶ。トヨタ自動車や三菱重工業グループ、JR東海など出荷先は約200社。品質軽視の組織ぐるみの不正は、日本のものづくりの土台を揺るがしかねない。トヨタは8日、「安全を最優先に考え、影響を早急に確認する」とコメントを出した。(小室浩幸、野口陽)
◇
神戸製鋼所は8日、アルミや銅製品で強度や寸法などを偽装していた問題で、梅原尚人副社長が記者会見を開いた。問題のある製品は、真岡(栃木県)など4工場から自動車メーカーなど約200社に出荷されていた。主なやりとりは次のとおり。
――関与した社員は。
「調査中だが数十人。この1年間で、のべ人数ではない。管理職も含まれている。実際に手を下した、知りながら黙認していた、うすうす知っていた。いろんな段階がある。いまは第三者の法律事務所が入って事実調査や再発防止策を考えている。われわれ経営陣も責任を考えていく」
――組織ぐるみか。
「はい」
――2016年にもグループ企業でデータの改ざんが発覚したのに、なぜまた起きたのか。
「法的規格に違反していないかは、かなり高い関心をもって教育や監査をした。今回は法的規格ではなく、民間のお客様から求められた仕様を逸脱して書き換えた。民間同士の契約に関する管理、監査あるいは教育が不十分だったと思っている」
――安全性への問題は。
「あり得る。お客様にも検証していただいている。現時点で何か安全性で疑いを生じさせることは起きていない」
――いつ報告があったのか。
「アルミ銅部門が自主的に点検して発覚した。われわれが知ったのが8月30日。アルミ銅部門の管理職が幹部に言い、それが取締役レベルに上がってきた。調査中だが、現場の管理職にはすでに知っていたという人たちがいる。わけがあって言い出せなかった、という」
「納期を守らないといけない、生産目標を達成しないといけない、というプレッシャーの中で続け、相当悩んでいたようだ。是正しないといけないが、一気にやると影響が非常に大きい。それで踏み切れなかったという姿が少しずつ浮かんできている」
――なぜ公表まで1カ月超もかかったのか。
「まず事態がどんなものか、われわれが把握しないといけない。お客様にも一報をしないといけない。これだけ重大なことなので、何らかの形で早く公表しようと考えていた。ただ、お客様がいろいろな動きをされたので、中途半端だが、今日緊急に発表した」
――国への報告は。
「経済産業省に報告し、いくつか指摘をいただいた。法令違反や安全性の事実関係の究明、お客様への丁寧な誠意ある対応、こういう形でのみなさまへのお知らせ、可能な限り原因究明と再発防止策を、と」
――出荷先の業界は。
「個社はいえないし、業界もご容赦いただきたい。自動車が含まれるかどうかも私どもからはいえない」
――自動車に使われていれば、リコール(回収・無償修理)に発展するのでは。
「お客様と協議中。可能性はゼロではないが、現時点ではうかがっていない」
――決算は17年3月期まで2年連続で純損益が赤字。経営陣からのプレッシャーがあったのでは。
「むちゃな形で生産目標、業績目標を徹底的に追求して、未達成なら懲罰をするというマネジメントはなかったと思う。一方で、納期を切らすとお客様の生産ラインがとまる。そちらのほうがプレッシャーがかかる」
「不適切な製品を出荷したことで、すぐにクレームにつながったわけではない。これぐらいなら何とかお客様が使いこなしてくれるのでは、問題ないのではと経験的に感じて、人事異動の少ない工場で長年やっていたのではないか」
内部監査のマニュアルの見直し、内部監査を行う人材の任命方法や基準、内部監査のチーム編成など改善する理由と改善が必要である認識について 検討する必要がある。まあ、会社が故意に行っていれば、マニュアルや改善などは形だけなので、欠陥だらけであろうが、完成度の高いものなのかは 関係ない。
日産自動車が無資格の従業員に新車の検査をさせていた問題で、工場では書類の偽装に使われる有資格者の印鑑を複数用意し、帳簿で管理のうえ無資格者に貸し出していたことがわかった。こうした行為はほぼ全ての工場で行われ、組織的に偽装を慣行していた疑いが浮上した。
完成検査は通常、資格を持つ検査員が項目ごとに車体の機能を確認して、書類に自身の印鑑を押す。だが日産では資格のない補助検査員による検査が常態化。その際、書類には有資格者名の印鑑を押し、正しく検査が行われたかのように偽装していた。
関係者によると、有資格者の印鑑は工場で複数用意され、無資格者はそれを借りて書類に押す仕組みだった。どの印鑑を誰に貸したかは、各工場が帳簿で管理していたといい、工場内では偽装工作が公然と行われていたとみられる。
日産自動車の内部監査がどのように行われるのか知らないが、たとえ、書類が偽装されても、従業員らにランダムでマニュアルや個々の所掌や責任を 聞いたり、担当者や責任者がどのようにマニュアルが実行されているかを質問すれば、質問された全ての正社員や期間従業員が口裏を合わせないと 疑問点や矛盾点が出てくると思う。
現場が内部監査と外部監査(国交省の抜き打ち検査を含む検査)に関して偽装工作を行っていると仮定すれば、どこまで品質は維持されているのか わからないし、本社の担当本部の資料やデータは信用できない可能性も高い。
「外部の弁護士ら第三者を含む調査チームが10月末をメドに事実関係と再発防止策をまとめた報告書を国交省に提出することになっている。」
書類上、又は、形式上のチェックは出来るであろうが、技術や工程を理解していない人達で構成された調査チームでは本当の問題はわからないで あろう。たとえ、優秀で公平な弁護士であっても、技術や工程が理解できる人の補佐なしでは無理であろう。
無資格検査は見つけられないし、見つからなかったし、そして今後も見つからないと思ったから国内全ての完成車工場で行わるまで継続されたと 思う。初期の段階で見つかれば、広がらなかった、又は、もっと巧妙に隠ぺい工作が行われたであろう。
外国製品の品質と比べれば、これぐらいの手抜きでは多くの消費者は違いに気付かないと言う事であろう。大したことないと考えるか、 他の選択があるのなら、他のメーカーを選択するかは消費者次第。ただ、ブランドイメージの点からするとかなり損失が大きいような気がする。 心配性で、技術的な事がわからない人は、確実に他のメーカーを考える可能性が高いと思う。
資格を持たない従業員によるずさんな検査が日産自動車の国内全ての完成車工場で発覚した。品質に厳しいとされる日本のものづくりの現場で、なぜ不適切な検査体制が見過ごされてきたのか。ポイントを整理した。
Q 不備が見つかったのはどんな検査工程だったのか。
A 大量に生産する車を効率良く消費者に届けるために、本来は国の機関で1台ずつ実施するブレーキなどの安全性の検査を車メーカーが代行することが認められている。日産のずさんな検査はこの工程で見つかった。
法令に基づく通達では、社内の認定を受けた従業員だけが検査できることになっている。日産では認定を受けていない従業員が検査に携わっていた。ルール通りに検査することを前提にメーカーに検査を任せていたことで、結果的にチェックが甘くなった。石井啓一国土交通相は「制度の根幹を揺るがす行為だ」とのコメントを出した。
Q 不正はなぜ見過ごされた。
国土交通省の立ち入り調査では、日産の各工場で有資格者の名前の判子を資格のない従業員に貸し出していたことが判明している。無資格者が単独で検査した場合でも有資格者が検査したように書類が偽装されたため、内部監査などでは発覚しなかった可能性がある。
Q 不正は組織的だったのか。
無資格者による検査が行われるようになった時期や、全工場で書類の偽装が常態化していた理由について日産は「調査中」としている。
10月2日に記者会見した西川広人社長は「工程そのものの意味が(従業員らに)十分に認識されていなかったところが大きい」と述べ、法令順守の意識の低さが原因との見方を示している。
Q 日産車の保有者はどうなる。
A 日産はまだ1回目の車検を受けていない車両を対象に、検査をやり直すためのリコール(回収・無償修理)を週内に国交省に届け出る方針だ。
リコール対象となるのは14年10月から17年9月までに生産した24車種121万台で、軽自動車を除く日産の国内販売の3年分に相当する。該当する車両の保有者が車両を最寄りの販売店に持ち込めば検査のやり直しを受けられる。
Q 今後の展開は。
外部の弁護士ら第三者を含む調査チームが10月末をメドに事実関係と再発防止策をまとめた報告書を国交省に提出することになっている。
16年4月に発覚した軽自動車の燃費不正問題で、三菱自動車は必要な審査を受け直すために、該当車種の生産を2カ月半にわたって停止する事態に追い込まれた。
国交省は日産に対し業務改善を指示しており、同社からの報告の内容次第では新たな措置を講じる可能性があるとしている。
問題のない車であれば、資格者が検査しても、素人が検査しても結果は同じ。ただ、問題がある場合、素人では見抜けない。
運悪く問題のある車に当たった人が被害を被るだけ。まあ、問題が存在しても、直ぐに症状が現れる場合と時間が経つ、又は、ある程度、 運転しないと症状がでない場合もある。
最終的には消費者の判断。現在は知らないが、昔、アメリカに住んでいたころ、車を購入するときにコンスーマーガイドの車の評価を参考に する人が多くいたのを覚えている。車に精通していなくても、評価やユーザーの意見を参考にして判断していた。
日産の車に乗った事はあるが、個人的な経験から、もう日産は選択肢に入っていない。やはり、人が作るからあたり、はずれはある。 しかし、それを考慮しても、はずれが多いメーカーや不評の多い車は選択から外す。どうしても欲しい車でなければ、ニューモデルは買わない。 マイナーチェンジ後の車は安定しているし、問題点や不評な点が改善されている可能性が高い。
外国の車はもっと品質が甘いと言うから、外国人にとっては、メーカーが違っても日本車は良いと言うイメージを持っている場合が多い。 結局、消費者の価値観や期待度次第。品質が悪くても、外車を好む人もいる。品質ではなく、デザインや外車である事実、又は、人とは違う 車を乗っている自分の個性のためなどいろいろな理由がある。日産に乗りたい人は日産に乗れば良いと思う。日産が嫌であれば他のメーカーの 車を乗れば良いと思う。幸い、日本には多くの自動車メーカーが存在する。
日産自動車で、資格のない従業員が出荷前の車の検査を行っていた問題で、資格取得訓練中の従業員や、研修を受けていない、短期契約の従業員も検査を行っていたことが新たにわかった。
日産自動車は、国内6つ全ての工場で、完成した車の出荷前検査を、無資格の従業員が日常的に行っていたことがわかっている。
関係者によると、出荷前検査の資格を取得するために訓練中の従業員のほか、研修や訓練を全く受けていない、短期契約の「期間従業員」も検査を行っていたことが新たにわかった。
その際、検査に携わっていない資格のある社員の印鑑が複数用意されていて、複数の検査項目に同じ検査員の印鑑が使われていたという。
国土交通省は日産に対し、社内調査の報告を求めている。
「NHKでは、佐戸記者の死亡後、13年9月から報道現場での『ノー残業デー』の徹底や勤務制度の見直しなど、記者を対象にした働き方改革を進めてきた。」
やらないよりは良いが、「ノー残業デー」よりも本当に体がつらい時や体調の理由で無理が出来ない時に休める、又は、誰かが代われる体制が重要だと 思う。個人的には調子が良い時は残業しても、土日に休まなくても問題ないが、本当に体調が良くなくつらいのに、誰も代わりがいないので休めない状況の 方がつらい。無理をすればさらに疲労や回復が遅いように感じる。
事実を知ってしまうと、就職する事を躊躇する学生は増えるかもしれないが、行政は企業にもっと労働形態や事実を話すようにするべきだと思う。
企業イメージで就職したら労働形態についていけない人の辞職や過労死になる可能性は高いと思う。
NHKは4日、首都圏放送センターに所属していた佐戸未和さどみわ記者(当時31歳)が2013年7月、東京都内の自宅で亡くなり、翌14年5月に渋谷労働基準監督署から長時間労働による過労死と認定されていたと発表した。
NHKによると、佐戸記者は05年入局。10年に同センターに異動し、当時は東京都庁の担当。13年6月23日の都議選、7月21日の参院選などを取材後、同24日にうっ血性心不全で死亡した。同労基署が算出した、亡くなるまでの1か月の時間外労働時間は約159時間で、休みは2日だった。
NHKは14年6月10日、佐戸記者の両親の代理人を通して労災認定を把握したが、3年以上たって発表した理由を、両親が当時、外部への公表を望んでいなかったから、などとしている。また、同労基署から、NHKが是正勧告を受けるような法律違反の指摘はなかったという。
今回の公表は、電通社員の過労自殺などが注目される中、娘の死を無駄にせず、再発防止につなげてほしいと、両親から要望があったためとしている。
NHKでは、佐戸記者の死亡後、13年9月から報道現場での「ノー残業デー」の徹底や勤務制度の見直しなど、記者を対象にした働き方改革を進めてきた。根本佳則理事は4日、報道陣の取材に対し、「過労死の労災認定を受けたことを重く受け止めています。職員の健康確保の徹底をさらに進めていきます」と話した。
NHKは同日、「4年経たった今でも娘の過労死を現実として受け入れることができません。志半ばで駆け抜けていった未和の無念さ、悔しさ、遺族の悲しみを決してむだにすることなく、再発防止に全力を尽くしてもらいたい」との遺族のコメントも発表した。
役員と言う事は社長ではないと言う事?
逮捕された役員だけが中学生をコンパニオンとして酒に派遣されていた事を知っていたのか?
北海道中央バスの男性運転手が「替え玉」を使って運転前のアルコール検査を受けさせていた問題で、バス事業を監督する北海道運輸局は、5日、会社に監査に入りました。北海道運輸局が監査に入ったのは北海道中央バスの札幌北営業所です。 営業所に所属する54歳の男性運転手は今年6月、釧路発札幌行きの高速バスに乗務する前のアルコール検査で社内規定の基準値以上のアルコールが検出されました。運転手は、やり直しの検査を交替要員の同僚に受けさせて検査を通過し、そのまま乗務していました。 北海道運輸局は乗務員らから詳しい話を聞いて検査での不正が日常的だったのかなどを調べるとともに検査を厳格に行うよう指導する方針です。
札幌市-釧路市間の都市間バスの運転手が、運転前の検査でアルコールが検知されていたにも関わらず、そのままバスを運転していたことが分かりました。
不正行為をしていたのは、北海道中央バスの54歳の男性運転手です。
この運転手は2017年6月、釧路市発、札幌市行きの都市間バスに乗務する際、事前のアルコール検査で、0.061ミリグラムのアルコールが検知されました。
運転手は、その後の再検査を別の運転手に受けさせて、検査をすり抜け、そのまま都市間バスを運転したということです。
運送業者の乗務前のアルコール検査は、法律で義務づけられていて、濃度に関わらず、検知された場合、乗務ができないことになっています。
北海道中央バスでは、今後の指導を徹底するとしています。
UHB 北海道文化放送
役員と言う事は社長ではないと言う事?
逮捕された役員だけが中学生をコンパニオンとして酒に派遣されていた事を知っていたのか?
中学生をコンパニオンとして酒席に派遣したとして、派遣会社「ノースバンケット・プロデュース」(札幌市中央区)の役員(42)が逮捕された事件で、同社が酒席の経験がない中学生らに向けた「接待マニュアル」を作成していたことが、道警への取材でわかった。
マニュアルでは、ビールとワインの注ぎ方をイラストで説明。焼酎の割り方を教えたり、日本酒については「あつかんになさいますか? ひやになさいますか?」などと、ひらがなで接客方法を伝えたりしている。
さらに、「お客様の飲み物を空にしない」「灰皿を新しいものと交換する」「2時間ずっと笑顔で」などと、酒席での振る舞いについても具体的に指示したりしていた。
道警によると、中学生らには2時間で5500円、3時間で8000円の報酬が支払われていた。中学生らは「先輩や友達から紹介された」と話しており、1人紹介すると、報酬とは別に会社から1000~2000円が支払われていたという。
法的にどのように判断されるのかはよく知らないが日本学生支援機構の審査に問題はあったように思える。
お金を貸す以上法的に問題が発生しないようにチェックするべきであった。法的に問題点があり、裁判に勝てないような申請を審査してお金を貸したのは 日本学生支援機構。今後、審査プロセスやマニュアルそして審査員の教育や指導に生かすべきだと思う。
日本学生支援機構は警察に被害届を出すべきだ!
このケースからわかるように高等教育の学費無償化は問題がある。真剣に勉強をする、そして、能力があるが、経済的に問題がある生徒に限るべきだ。
4日大阪地裁で、奨学金の返済をめぐってある裁判が起こされました。奨学金に頼らざるを得ない学生が増えている中、トラブルも増えています。
「『あなたは保証人になっています』という電話(があった)。はじめは奨学金ってなんのことかと思っていました」(原告の女性)
訴えを起こしたのは大阪府に住む60代の女性です。訴状によりますと、女性の息子は1999年から大阪市内の専門学校に通い、その間に奨学金約480万円を借りました。契約書には連帯保証人の欄に母親であるこの女性の名前が記載されていました。
しかし、女性はこのことをまったく知らなかったといいます。息子とは現在連絡が取れない状態になっていて、女性のもとには日本学生支援機構から利息も含めて返済するよう通知が届きました。女性は自分には返済義務がないと訴えています。
「どのような審査があったのかわかりませんが、(返還誓約書の)本人、連帯保証人、親権者の字(筆跡)が何の小細工もなく3か所とも同じでした。奨学金はとてもありがたい制度、丁寧な運営をお願いしたい」(原告の女性)
奨学金を貸している日本学生支援機構は「個別の案件についてはコメントできない」としています。
毎日放送
日産自動車が無資格の従業員に新車の検査をさせていた問題で、結果を記す書類には実際に検査に関わっていない有資格者の名前が示され、押印もあったことがわかった。こうした偽装はほぼ全ての工場で行われていた。国土交通省は3日、一部工場への立ち入り検査を実施。不正への組織的な関与の有無など、詳しく調べる。
日産では、資格を持たない補助検査員による検査が、国内向けに車両を組み立てる全国の工場で日常的に行われていた。検査の結果や誰が検査したかは書類に残す必要があるが、関係者によると、有資格者が実施したように押印などで記載内容が偽装されていた。
同省は検査に不備がないか定期的に監査しているが、有資格者の責任で作成されたことを示す押印がある書類自体が偽装された場合、不正を見抜くことは難しい。同省関係者は「不正が発覚しないよう、意図的に書類を偽装したのであれば大きな問題」と話す。
同省は3日、栃木と京都の工場に抜き打ちで立ち入り検査に入った。関係書類の提出を求めるとともに、従業員からの事情聴取にも着手。今後、不正の実態解明を進める。
完成検査は、工場で車の生産時に、ブレーキの利き具合やライトの点灯などを最終的にチェックするもの。検査をパスしなければ出荷はできない。道路運送車両法などに基づき、各社が厳格に認定した「検査員」が実施することで安全性を担保する制度だ。
西川(さいかわ)広人社長は2日の記者会見で「(不正を)全く認識していなかった」と経営幹部の関与を否定したうえで、社内で制度の重要性が「十分に認識されていなかった」ことが背景との認識を示していた。石井啓一国交相は3日の会見で「使用者に不安を与え、制度の根幹をゆるがすことできわめて遺憾。厳正に対処する」と話した。(伊藤嘉孝、青山直篤)
■国交省、他社にも報告要求
日本の「ものづくり」の先頭集団にいるはずの日産自動車で、無資格者が書類上は資格者を装い、検査の実態を偽る慣行が続いていた可能性が強まった。生産性を競うあまり、安全確保の認識が甘くなっていた可能性がある。同様の事態がないか、他社も確認を急ぐ。
メーカーは車の完成段階で、国の手続きを代行する形で「完成検査」に当たる。各社で認めた検査員が担当するのが決まりだ。日産は資格を与えた「完成検査員」だけでなく、現場でサポートする立場の無資格の「補助検査員」に完成検査の一部を担当させていた。
他の自動車メーカーについては知らないが、他の業界でも似たような事はある。資格を持っていても、資格がなくても、能力的には同じ場合もあるが、 それを許してしまうと、過剰解釈や極端な違反を行うケースが出てくる事がある。そのようなリスクを防ぐためにはやはり基準は必要。
資格の基準を緩和して、抜き打ち検査を増やす方法はあるが、チェックする側がチェックする人員を増やし、本当にチェックできる知識と能力を持って いる事を維持するためには、行政の負担は増す。チェックする人員を増やさず、抜き打ち検査で引っかかった企業に重い罰則を科す事で、リスクを避ける 企業が増える事を期待することは出来るが、企業の存続や収益減による社員のリストラが起きるリスクがある。多くの選択にはメリットとデメリットが 存在する。割り切って選択するしかない。
日産自動車は組織的偽装を行う前に考えるべきであったと思う。
日産自動車が無資格の社員に完成した車両の検査をさせていた問題で、検査結果を記載する書類の多くに、実際には検査に関わっていない有資格者の社員の名前が記載され、判子も押されていたことが関係者の話でわかった。
多くの工場には、偽装用の判子が複数用意されていたといい、国土交通省は、組織的な偽装工作が常態化していたとみている。
関係者によると、偽装が行われていたのは、車両が完成した際、ブレーキの利き具合など車両の安全面などの最終的なチェックを行う「完成検査」の結果を記載する書類。同省は、これまで同社の国内工場への立ち入り検査を複数回行っているが、その過程で実際には検査に関わっていない社員の名前が書類に記載され、判子も押されていたことが判明した。
日産自動車の工場で、出荷前の車の検査を無資格の社員が行っていた問題は、約121万台に上る大規模リコールという事態に発展した。
日産は燃費データ不正で経営が悪化した三菱自動車を傘下入りさせ、再発防止を主導していた。しかし、日産自体で検査ルールを守る意識の低さが明らかになり、企業イメージが悪化する恐れがある。
「9月に国土交通省から指摘をいただくまで、全く認識していなかった」
日産の西川(さいかわ)広人社長は2日、横浜市の本社で開いた記者会見で、無資格検査の把握について、こう弁明した。
日産は車両を生産する国内の6工場で、社内の認定を受けていない検査員が、出荷前のチェックを行っていた。本来は、国交省の通知に基づいて検査資格のある社員が担当しなければならず、日産の場合はバッジをつけている。
全工場で同じような書類が存在するのであれば、書類を作成した人間、書類を確認した人間、実際に関与していなくても判を押した人間、そして 内部監査チームの人間たちは不正に関与した可能性が非常に高い。
ISOなど外部監査を受けていれば、外部監査を行った人間は問題を知っていたのか、それとも、外部審査の準備のために、資料、書類、記録、そして 現場視察の準備に関与した人間達が存在している可能性もある。
「補助検査員はバッジの有無で簡単に識別できる。西川氏はこうした慣行が続いてきた理由について、『国と約束をしてやらせていただいている工程そのものの意味が十分に認識されていなかったのでは』との見方を示した。内部告発はなく、経営陣も把握していなかったという。」
内部告発をする人間は日産にはいなかったのか、それとも内部告発が出来ないほど内部の締め付けが厳しかったと言うことか?
調査結果次第では更に信頼を失う結果になるかもしれない。嘘を付いてもダメ、保守のスタンスを取りすぎてもダメ、難しいと思う。
日産自動車が無資格の従業員に車の検査を担当させていた問題は、約121万台に上る大規模リコール(回収・無償修理)に発展した。日産は安全性に問題はないとの認識だが、書類上は正規の従業員が検査していたように装っていた疑いもあり、全社的な安全管理の甘さが際立っている。
「日産を信頼して頂いている皆さまにおわびを申し上げたい。背景にある従業員の認識について徹底的に検証し、対策を立てたい」
2日、横浜市の日産本社で記者会見した西川広人社長は陳謝。1カ月間をめどに第三者を交えたチームで原因究明に当たる。自身を含めた経営陣の責任のとり方については「調査の後で考える」と明言を避けた。
問題が起きたのは車をつくる最終段階の「完成検査」。メーカーが国の手続きを代行する形で、自社の基準で認めた検査員に担当させることになっている。しかし日産工場では、正規に認められた検査員を支援する役割にとどまる「補助検査員」も従事していた。
補助検査員はバッジの有無で簡単に識別できる。西川氏はこうした慣行が続いてきた理由について、「国と約束をしてやらせていただいている工程そのものの意味が十分に認識されていなかったのでは」との見方を示した。内部告発はなく、経営陣も把握していなかったという。
ただ、関係者によると、補助検査員が担当した部分も、書類上は正規の検査員が確認したように装っていた可能性がある。組織的関与が疑われる事態に発展すれば、消費者の信頼をより大きく損なう。
[横浜 2日 ロイター] - 日産自動車<7201.T>は2日、国内全ての車両組み立て工場で資格のない従業員が完成検査をしていた問題で、再点検のため販売済みの約121万台をリコール(回収・無償修理)する方針を発表した。同日夕に本社で会見した西川廣人社長は、車検相当の点検を行い、リコール費用が約250億円かかるとの見通しを明らかにした。
リコール対象は初回の車検をまだ迎えていない2014年10月から17年9月までに製造された車で、国内で販売された24車種(軽自動車除く)。同社は今週中に国土交通省に届け出る予定で、全国の日産販売会社のサービス工場約2100カ所で点検を実施する。
顧客に引き渡される前で登録を一時停止していた約3万4000台の21車種については、再検査を実施したうえで10月3日から登録を再開する。こちらの対象車には2日発売された電気自動車の新型「リーフ」も含まれている。
西川社長は「心からおわびしたい。今回起こったことはあってはならないこと」と陳謝した。また、自らの責任も含めた関係者などの処分については「私自身が納得できるまで(原因や背景を)調べる。そのうえで、どう責任を取るか処分を決めたい」と述べた。
今回の不正は国交省の抜き打ちの立ち入り検査で発覚。西川社長は同省から指摘を受けるまで「まったく認識していなかった」とし、国内6カ所すべての車両組み立て工場で行われていた実態について「非常にショックだ」と語った。
いつから無資格者が完成検査の一部に従事していたかなど詳細はまだ不明。第三者を含むチームによる原因や背景などの調査には1カ月程度かかるとしている。
ただ、西川社長はこうした事態が起きた背景の一因について、資格のある検査員がしなければいけないという認識が現場で「多少薄れていたのかもしれない」との見方を示した。また、今回の問題にあたっている企画・監理部の杠(ゆずりは)直樹氏は、現時点の調査では人手不足が原因で発生したということではない、との認識を示した。
完成検査は道路運送車両法に基づき実施されるもので、国交省は各社が社内規定で認定した者が行うよう定めている。しかし、日産ではこの認定を受けていない「補助検査員」だけで一部の検査を実施していた。
*内容を追加しました。
(白木真紀)
上記は事実であると思う。管理の不徹底とは考えらない。最近、流行りの「忖度」又は、誰かの指示以外に考えられない。不徹底ではなく、無資格の従業員による完成検査に メリットがあるから見過ごした、又は容認したと考えるべきだと思う。問題なのは、小さな妥協が安全にも影響を及ぼす部分への妥協に変わる危険性がある。 危険性は、事故が起きてから認識される事が多い。かなり危険な事が見逃されても、事故にならなければ注目を受けないし、危険に鈍感になる事もある。
「国交省は国内のほかの車メーカーにも検査に不備がないか調査を指示した。」
仮に同じような行為を行っているメーカーが存在したとしてもよほど間抜けなメーカーでない限り、問題はコストや人材不足に関係なく日産の問題が記事になった直後に是正されたと思う。
日産自動車の国内6工場で発覚したずさんな検査体制は法令順守意識の低さを示し、ブランドイメージに打撃となりそうだ。改善できなければ仏ルノーと企業連合で進める世界市場での拡大戦略に響きかねない。今後、販売済みの車両の大規模リコール(回収・無償修理)に発展すれば業績に影響する可能性もある。
日産による記者会見から一夜明けた30日、全国に約2100ある日産系列の販売店に混乱が広がった。首都圏のある販売会社では「報道より詳しい情報は得られていない」と言い、「再検査が必要な車両の番号や再検査の方法などについて、日産からの情報提供を待っている」という状況だ。
納車待ちの顧客から「いつ車両が手元に届くのか」といった声が寄せられているが、30日の段階で回答できていない。日産は既に検査体制を是正して国内各工場で生産を続けており、この販売会社は新型の電気自動車(EV)「リーフ」を含む受注活動を続けている。
資格を持たない従業員が新車の出荷前に必要な完成検査に携わっていた問題は、国土交通省による9月18日以降の立ち入り調査で発覚した。追浜工場(神奈川県横須賀市)など国内6つの完成車組み立て工場の全てで同様の不備が確認された。
大量生産車の安全性などを審査する型式指定制度では本来1台ずつ国が行う検査を、工場から出荷する直前の完成検査を通じて車メーカーが肩代わりしている。国の信頼を裏切ったという意味で三菱自動車が燃費データを水増しして届け出た問題に似ており、石井啓一国土交通相は「制度の根幹を揺るがす行為だ」と日産を厳しく批判するコメントを出した。国交省は国内のほかの車メーカーにも検査に不備がないか調査を指示した。
日産は無資格の従業員による完成検査が見過ごされた理由や始まった時期について「調査中」としている。検査責任者は法令を認識しながら、現場では有資格者を示すバッジをつけない従業員が交じって完成検査を行っていたことが分かっており、管理の不徹底が背景にあるとの見方もある。
日産は既に顧客に届いた車両についても完成検査のやり直しが必要と判断した場合は国交省にリコールを届け出る方針。対象は最大で100万台規模になる恐れがあり、かかるコストは見通せない。ただ海外工場に関しては安全性を審査する制度が異なるため「全く問題はない」としている。
日産はルノーや三菱自と合わせた世界販売が2022年に16年比4割増の1400万台になると予測する。今回の問題はグローバルマザー工場と位置づける追浜工場でも見つかっており拡大戦略が揺らぐ可能性もある。
国内での日産の販売は16年11月に部分改良して発売した小型車「ノート」のヒットなどで今年8月まで10カ月連続で前年実績を上回った。収益源である米市場の勢いに陰りが見え、日本市場の重要性は増している。業績への打撃を最小限に抑えるには原因究明と情報開示を急ぐ必要がある。
問題であるが、発覚しなければ問題ないと思っていれば、悪い事であるが、いろいろな事は知っていると言う事になる。
しかし、認定又は社内認定さえもなしに検査できると認識していた検査官が存在するのであればそれはとてもひどい事だ。
普通免許で大型トラックを運転して、免許を持っているのに大型トラックを運転して何が悪いのか?事故は起きていないと言っているようなものである。
真実は関係者達にしかわからない。ストーリーやシナリオは外部調査が入るまではいくらでも書き換えれるし、書類なども差し替えや偽造は出来るであろう。
信頼や信用に関しては上手くランディングしないと現在と将来の売り上げに影響するであろう。
日産自動車は29日、新車の出荷前に必要な完成検査を、無資格の従業員がしていたと発表した。道路運送車両法に違反する可能性があり、同社は在庫車の登録手続きを一時停止した。対象は軽乗用車を除く約6万台。国内販売の21車種全てが含まれる。再検査が終わるまで登録ができず、販売契約済みの在庫車は納車が遅れる可能性がある。
約6万台のほか、検査に不備があったのにすでに販売され、一般のユーザーに渡っている車も多数あるとみられ、これらも再検査する。対象の顧客には今後連絡するという。再検査が必要な台数は「100万台に上る可能性がある」とし、同社はリコール(回収・無償修理)を検討している。
完成検査はブレーキの掛かり具合などを最終的に確認するもので、法律に基づき、各メーカーの認定を受けた検査員がしなければならない。だが同社は追浜工場(神奈川県横須賀市)や栃木工場(栃木県上三川町)、日産九州(福岡県苅田町)など、国内全6工場で無認定の従業員が実施していた。国土交通省が今月18日、工場に立ち入り調査し、判明した。
同社は、いつから無認定者が検査をしていたか「特定できていない」としつつ、「検査自体はしているので安全性に問題はないと思う」と説明。問題の背景については「どうしても甘さがあって結果的にそうなったと思う」と述べた。従業員は同社に「自分は検査をできると思っていた」と説明しているという。
日産自動車は国内のすべての工場で検査に不備があるまま車を出荷していたとして、21車種、少なくとも6万台の販売を一時、停止すると発表しました。検査に不備がある車の台数はさらに膨らむ可能性があり、日産は、ずさんな検査が常態化していた原因の究明を進めることにしています。
日産自動車は29日夜、記者会見し、国内にあるすべての工場で、完成した車に問題がないか、調べる検査を資格がない従業員が実施し、出荷していたと発表しました。
検査に不備があったのは「ノート」や「キューブ」、それに電気自動車の「リーフ」など21車種、少なくとも6万台で、日産は対象となる車の販売を一時、とりやめ、検査をやり直すとしています。
ただ販売済みの車については台数が特定されていないため、検査に不備がある車の台数は、さらに膨らむ可能性があり、日産は不備があった車が特定されしだい、リコールを実施する方針です。
日産によりますと、不備が見つかったのは出荷前の車の品質を最終的にチェックする「完成検査」で、国のルールに基づいて、一定期間、研修を受け資格を得た従業員が実施することになっていました。
会社側の聞き取り調査に対し、無資格で検査を実施していた従業員は、「疑いなくやっていた」などと話しているということで、国内のすべての工場で検査のルールが徹底されず、ずさんな検査が常態化していたことが明らかになりました。
日産は、こうした事態を重く見て第三者を交えて原因の究明を進めるとともに、国土交通省に再発防止策を報告することにしています。
日産自動車が国内の新車在庫約6万台の販売一時停止を発表した翌日の30日、販売店は顧客への状況説明に追われた。現時点で販売への目立った影響はないが、原因となった検査不備の背景や再検査の進め方などには確定していない点も多い。販売現場では顧客の信頼が低下しかねない状況に懸念が広がる。
日産は29日、国内全6工場で生産したリーフやノート、エクストレイルなど計21車種の完成検査で、一部を未認定の検査員が行っていたとして、軽自動車を除く新車在庫約6万台の販売を一時停止したと発表した。対象車は検査をやり直すため、全国の販売店で購入者への納車が遅れる可能性が生じている。
「ご心配をおかけし申し訳ありません。詳しいことが分かり次第ご連絡します」。神奈川県内のある店舗では、従業員総出で、納車待ちの顧客や納車間もない顧客らに謝罪の電話をかけ続けた。
日産は「車検に合格していれば国の規定に基づく検査を経たことになり、安全性は担保されている」との認識だが、同店の営業担当者は「新車購入後、初回車検が必要となる3年を過ぎた顧客からも『自分の車は大丈夫か』と問い合わせがある」と話し、不安の大きさを気にかける。
埼玉県内のある店舗によると、現時点で客足に変化はなく、注文のキャンセルや購入延期といった直接の影響は出ていないという。ただ「我々にとって一番大切な顧客の信頼が傷つかないか心配。問題が長引けば営業の士気にも関わる」(担当者)と不安を隠さない。
日産は、国土交通省の指示を受け、事実関係の把握と再発防止策の策定を1カ月以内に行う。外部有識者を交えた第三者委員会を設置して、詳しい原因を調査している。
だが、検査の不備は国内全工場で発覚したほか、日産の社内調査によると、未認定のまま検査に関わることが問題だと認識していなかった検査員もいるという。品質管理の甘さが日産のブランドイメージを傷つけ、販売に悪影響を及ぼす恐れもある。
問い合わせは「お客さま相談窓口」0120・315232。【和田憲二】
日産自動車の幹部や補助検査員らが確認犯ではなく、本気で上記の事を言っているのであれば、日産自動車の管理はかなりずさんで、手が付けられない ほど腐敗していると思う。
日産自動車の幹部の誰一人として現場を訪れ、現場を見て質問や資料をチェックしていないと言う事になる。そして、補助検査員らは少なくとも マニュアルを読む機会もなく、マニュアルについて教育される機会がない事になる。補助検査員らに指示を出す部署や担当者達も同様に同じ理解度で あれば、救いようがないほど日産自動車の組織は腐敗していると言う事になる。
以前、日産の車に乗っていたが、耐久性に疑問を感じたのでそれ以来、日産の車は選択から外しているので個人的には日産の車がどんな車であろうが 個人的には影響は全くない。
日産自動車は勝ち組と思っていたが、利益優先のためには何でもやる体質だったのか、それとも何でもやらないと簡単には勝てないと言う事だったのか? メディアは調査して記事にしてほしいと思う。
「完成検査員が検査を担当するよう指示している。いつからか、なぜこのような態勢になっているのか分からない」。29日の会見で、日産自動車の幹部はこう繰り返した。ただ、車両製造の最終工程「完成検査」での規定違反は国内全6工場で継続しており、同社の管理態勢の甘さが露呈。販売済みの車両についても「検査自体は実施しており問題はない。念のため改めて検査する」と述べたことは規範意識の欠如も浮き彫りにした。
国土交通省によると、各自動車メーカーは新型車を大量生産するため国交省に対し、事前に「型式指定」を申請。メーカー側は指定を受けた車両を組み立てた後、1台ごとに完成検査員が最終的な検査を実施する。国交省側は完成検査員の指定をメーカー側に委ねており、信頼を裏切った形だ。
日産では問題が発覚した9月中旬、約300人の完成検査員のほか、認定を受けていない補助検査員約20人が完成検査に関与。だが過去に担当していた補助検査員の人数などは不明。認定には研修や面接が必要で、工場ごとに認定を取り直さなければならず、過去に別工場で認定を受けた補助検査員や研修中の補助検査員もいたとみられる。
同社の聞き取り調査に対し、補助検査員らは「何の疑いもなくやっていた」「検査してよいと思っていた」などと説明したという。国交省は10月末までに過去の運用状況や再発防止策の報告を求めた。
昨年、燃費データで不正を行った三菱自動車を傘下に入れ、三菱の「お手本」にならなければならない立場の日産自らが規定違反を行っていた事実は重い。検査は全工場で行われていたことも判明し、全社で組織的な違反が恒常化していた疑いもある。
自動車評論家の菰田潔氏は「日産に対する消費者の信頼が損なわれるのは間違いない。検査に不備があったのがブレーキなど安全に関わる装置だったり、不備を認識しながらの検査が常態化していたりしたなら極めて重大な問題だ」と指摘する。
青山直篤、木村聡史
日産自動車で、国内で車両を組み立てる全工場でのずさんな運営が明るみに出た。本来は社内で検査員と認められた従業員が完成車を検査する必要があるが、守られていなかった。新車登録前の6万台の検査がやり直しとなり、ユーザーに渡った100万台規模も対象の可能性がある。法令軽視の批判は免れず、ブランドイメージや業績への悪影響は避けられない。
日産、新車6万台の登録停止 21車種、完成検査で不備
自動車メーカーは、工場で車を生産する最終段階で「完成検査」を行う。本来は国が行う検査を、工場で代行しているような形だ。完成検査を受けた証明が、安全に路上を走る車としての「お墨付き」となる。その後、販売店に出荷され、ナンバーを付けてユーザーに引き渡される。こうした仕組みは、道路運送車両法や関連の実施要領などで定められている。
国が定めた実施要領では、各社が知識や技能を考慮し、自社であらかじめ指名した従業員が検査するよう求めている。しかし日産では、認定されていない「補助検査員」が一部の検査を行っていた。全工場で日産が認めた正規の「完成検査員」は約300人で、補助検査員は約20人。この補助検査員が、完成検査員が行うべき業務を行っていた。
完成検査員かどうかは、バッジの有無で判別できる。補助検査員は作業に習熟しているが、レベルには個人差があるという。日産の社内調査では、補助検査員が検査をすることが問題だという認識もない従業員もいた。
安全性が重視される自動車の生産現場で、法令を守る認識が欠けていたことになる。この状態がどれだけ続いていたかについて、日産は「調査中」としており、長期にわたって常態化していた可能性がある。
問題があったのは、追浜工場(神奈川県)、栃木工場(栃木県)、日産九州(福岡県)、日産車体(神奈川県)、同社傘下のオートワークス京都(京都府)、日産車体九州(福岡県)で、国内の車両組み立ての全6工場だ。9月18日、国土交通省が日産車体湘南工場(神奈川県平塚市)に抜き打ちで立ち入り検査して発覚した。日産はその時点まで事態を把握していなかった。
現時点で、ユーザーへの引き渡…
死んだ人間は生き返らない。新国立競技場建設工事のごたごたに関して今回の無理はある程度、想定できたのでは?
行き当たりばったりで、コストに注意を払ってこなかった行政にも責任はあると思う。直接的ではなく、法的には責任は取れないと思う。 しかし、行政がもっとしっかりとする、又は、コストに関して注意を払っていればドタバタ劇はなかった。
命が大切と本気で思うのなら行政は良く考えてほしい。残念であるが、失われた命は元に戻せないが、代わりの人間はいると思う人達は 存在するし、関係ない人達は深くは考えない。これが現実だと思う。
2020年東京五輪・パラリンピックのメインスタジアムになる新国立競技場建設工事に従事していた東京都内の建設会社の男性社員=当時(23)=が自殺し、遺族が労災申請した問題で、男性を含む複数の従業員に違法な長時間労働をさせていたとして、新宿労働基準監督署(東京)が同社に対し是正勧告していたことが29日、分かった。
厚生労働省は同日、競技場の建設工事に関わる約760社を調査した結果、同社を含む37社で違法な時間外労働が確認され、是正勧告したと明らかにした。
37社のうち時間外・休日労働が1カ月で80時間を超えた従業員がいたのが18社、150時間超も3社あった。厚労省は元請けの大成建設に従業員の労働時間を適切に把握するよう行政指導した。
遺族側弁護士によると、自殺した男性は昨年4月に入社し、12月から工事の現場監督になったが、今年3月に失踪し、4月に長野県内で遺体で発見された。失踪前1カ月では212時間の残業が確認されていた。計画の見直しによる工期の遅れを取り戻すため、精神的に追い詰められていた可能性があるという。
遺族は「過重労働が原因で鬱病などの精神疾患になり自殺した」とし、7月に労基署に労災申請した。労基署が男性の自殺が「業務上の死亡」に当たるかどうか調べている。
勧告を受けた建設会社は「今回のことを真摯(しんし)に受け止め、こうしたことが二度と起きないように対策を講じていく」とコメントした。
人材不足で資格を持った検査員が不足をしていたのであろうと考える。そして誰か、又は、一部の部署が黙認、又は、検査の一部を未認定の「補助検査員」を行わすことを 上及び関連部署に報告しなかったと推測する。
完成度の高い車であれば、完成車の検査はダブルチェックで安全性に問題はないのかもしれないが、会社の体質そして管理体制、そして法令順守に 関しては問題があると考えられる。
日産自動車は29日、出荷前の車両の完成検査を未認定者が行っていたことを発表した。同社と立入検査した国土交通省によると、その拠点は以下のとおりだ。
・日産自動車(追浜工場、栃木工場、日産自動車九州)
・日産車体(湘南工場、京都工場、日産車体九州)
出荷前の検査は、自動車会社が自主的に決めた検査経験や知識を持つ検査員が行わなければ、検査を完了したことにはならない。国交省はこれを通達で定めてはいるが、保安基準に適合しない車両が検査不備で生み出されなければ、直ちに法令違反には問われないため、同社はリコール制度などを使って、再度、完成検査をやり直す必要に迫られる。
生産時期や担当した検査員を調べることで今後、対象となる車両は絞り込まれていくが、対象となる車種は以下の21車種だ。
シルフィ、ノート、ジューク、キューブ、リーフ(新旧)、マーチ、GT-R、シーマ、フーガ、フェアレディZ、スカイライン、セレナ、ティアナ、エクストレイル、NV200バネット、ウィングロード、シビリアン、パラメディック(救急車)、アトラス、エルグランド、キャラバン。
国交省の指摘後、同社は9月19日と20日の2日間で正規検査員に確実に検査を行わせる体制を整えたため、それ以降に生産された車両については、再検査の必要はないため販売店には影響はない。対象車両については車体番号を特定して販売店に通知、登録をすることなく差し戻すことを求めた。
検査済みと言えない検査が、どの時期からどの車両で行われたかは特定できていない。ただ、ユーザーが車検を実施した車両については、車検で不備が指摘されていなければ、さかのぼって完成検査でも同等の基準は満たされているとみなして、問題はないという考え方だ。
一度もユーザーが車検を受けたことのない新車についても、国交省は「既に販売・登録された自動車についての市場措置等の対応を、速やかに検討し報告すること」と指示した。日産は車体番号の特定を始め、今後ユーザーに通知する方法を公表する予定だ。
《レスポンス 中島みなみ》
日産自動車で未認定の検査員が完成車の検査に関わっていた事実が29日、発覚した。日産は安全性については「問題ない」としているが、原因は「調査中」で、再検査の対象台数も増える可能性が高い。品質管理体制に対する信頼低下は避けられず、影響が長引けば好調な国内販売にも打撃が及びかねない。
自動車メーカーは、認定検査員による完成車の検査を実施し、検査終了証を発行して国に届ける必要がある。道路運送車両法の「型式制度」に基づく手続きで、メーカーはこれにより新車を車検を通さずに出荷できる。
日産は国内全工場で、検査の一部を未認定の「補助検査員」に行わせていた。日産によると、補助検査員が検査した車でも、購入から3年後の車検に合格していれば国の規定に基づく検査をパスしたことになり、問題はないという。日産が過去3年で販売した対象車、つまり初回車検をまだパスしていない対象車は計約90万台に上るといい、日産は少なくとも約90万台の再検査を迫られる可能性がある。
販売を一時停止する車種は、独自の自動運転技術や電動化技術を搭載し、販売が伸びている新型「セレナ」、新型「エクストレイル」など国内で販売するほぼすべての車種だ。10月2日に全面改良して発売する主力電気自動車(EV)の「新型リーフ」も含まれる。日産は業績への影響について「現時点では何とも言えない」としているが、特に新型リーフは販売計画を上回る事前受注を集め、日産がEV市場をリードするための旗艦車種と位置づけているだけに、イメージ悪化が販売減につながれば深刻だ。
日産は2016年、燃費不正問題を起こした三菱自動車を傘下に収め、親会社ルノーを合わせた3社連合の17年上半期の販売は526万台と初の世界トップに立った。10月16日には、4月に就任した西川広人社長が率いる新体制になって初となる中期経営計画を発表する予定だが、品質管理に対する信頼回復という重大な課題を背負った。【和田憲二、石山絵歩】
これが事実であれば、社長名に社印がおされているが、社の正式な物ではないのであれば、私文書偽造及び行使と解釈できるのでは?
そして、本当に本社がこの文書について知らないのであれば、会社のマニュアル、又は、文書管理に関する方針が存在しない、又は、形だけのマニュアル又は 文書管理の方針があると考えられる。
もし、配送後に故意に髪の毛やプラスチックが混入されたと思うのであれば、偽計業務妨害罪で警察に被害届を出して警察に捜査してもらえば良いと思う。
警察に被害届を出しても事実が明らかになるとは限らないが、少なくともうやむやな発言や対応は出来なくなると思う。
町内に2校ある大磯町立中学校の学校給食で異物混入が相次いだ問題で、町の委託を受けている給食業者が提供先の幼稚園など約30カ所に事実とは異なる内容の文書を配布していたことが22日、分かった。事実誤認のほか、責任逃れとも受け取られかねない記述もあり、町側は委託先の変更も含めて検討に入った。
文書は、給食業者が提供している県西部の私立幼稚園などから問題の説明を求められ、19日に配布。社長名に社印が押され、▽異物混入が100件とあるが90%以上は髪の毛。弊社で混入したと考えにくい案件も含む▽(大磯町の)1校にのみ100件の異物混入は製造比率からみてもおかしい-などとしている。だが、町は20日の会見で「異物混入は84件。工場での混入が明らかな15件のうち髪の毛は3件あった」などと発表していた。
また、文書には「(弁当との)選択制であれば、食べたくなければ注文しなくていいで済んだ話。半ば強制的に始まった全員給食。反対派の声も多く、反対派からのリークで騒ぎになった」などの記述もあった。都内の給食業者の本社社長室は取材に対し「神奈川県内の役員が事後報告で出した書面で、社の正式なものではない。おわび状を出して対応し、町には状況を説明したい」と釈明した。
一方、文書は22日の町議会でも取り上げられ、町教育委員会は「われわれとしても残念な文書。契約そのものについて顧問弁護士と相談を始めた」と述べた。
町教委によると、デリバリー方式の学校給食は2016年1月に導入。委託先の給食業者は綾瀬市内の工場で製造したものを配送・提供している。食べ残しの多さが問題視されていたが、その後、髪の毛やプラスチック片などの混入があったことが明らかになった。
調査担当者を選ぶプロセスで中立性や問題のない職員が選ばれていたはず。そのような状況で、調査担当者が不正に関与していた事は 非常に深刻だ!もし、調査担当者が不正に関与している事を知りつつ、任命した人間が存在すれば、それも重大な問題だ!
政府の「危機対応融資制度」を巡る商工組合中央金庫(商工中金)の不正融資問題で、商工中金による内部調査の担当者のなかに、かつて在籍した支店で不正に関与した職員がいたことが22日、わかった。
調査をやり直す必要があることから、調査結果の公表は、当初予定の9月末から1か月程度遅れる。同日午後にも発表する。
この問題をめぐっては、外部の有識者らでつくる第三者委員会が全22万件の危機対応融資のうち約13%を抜き出して調査しただけで816件、計198億円の不正融資が発覚。6月から、商工中金の職員約600人に弁護士10人や会計士100人を加えた計700人超の態勢で、約22万件の全融資に対象を広げ調べている。
長時間労働でうつ病を発症する医師がいるなかで、女性の看護師や女性と遊んだり、合コンに来た女性をレイプするゆとりのある医師も存在する。
勤務する病院や親が病院を経営しているかで、それほどの違いが可能であるのか?医師だけの問題ではなく、病院の経営方針や病院の体質やシステムの 問題があるのではないかと思う部分もあるが、医者でもないし、病院や医療関係者でもないので良くわからない。もし、関係者であれば、問題を理解していても、 利害関係の問題で指摘できない見えない圧力があるのかもしれない。
単純に長時間労働の問題として解決方法を探しても、いろいろな関連があるので、厚労省が調査するべきだと思う。ただ、厚労省にしがらみがなく、 問題を見つけ、原因を把握できる職員がいるのかは疑問。高学歴であっても、病院の問題に関して知識がないと無理、能力があってもやる気が無ければ無理、 先輩や出身大学からの圧力の跳ねのけるだけの正義感がなければ無理。事実を見つけて問題を公表して担当者に何のメリットがあるのか?例え、問題を 報告書にまとめる事が出来ても、上の権力や決定力を持つ厚労省幹部が何らかの圧を掛けたらそれで終わりのような気がする。
◇病院を運営するJA岐阜厚生連を相手取り
岐阜県瑞浪市の病院に勤めていた鈴田潤さん(当時26歳)が自殺したのは、長時間労働でうつ病を発症したためだとして、両親が21日、病院を運営するJAグループの県厚生農業協同組合連合会(JA岐阜厚生連)に約9000万円の損害賠償を求め岐阜地裁に提訴した。
国体強化指定選手だった鈴田さんは長崎県出身。大学卒業後、JA岐阜厚生連に就職。岐阜で2012年にあった国体のライフル射撃で優勝した。
訴状によると、鈴田さんは13年から瑞浪市の東濃厚生病院に勤め、救急外来の対応など長時間働かされた。当直明けから翌日深夜まで連続39時間近く勤めた日もあった。うつ病を発症し、14年1月に自殺しているのが見つかった。病院側が安全配慮義務を怠ったと訴えている。
多治見労働基準監督署は自殺を労働災害と認定している。
父俊信さん(64)は「責任の所在を明確にし、それ相応の責任を取っていただきたい」、母京子さん(62)は「人命を助ける病院で職員、医師の長時間労働は許されるのか」とのコメントを代理人弁護士を通じ発表した。
同厚生連は「訴状が届いておらず、コメントは差し控える」としている。【沼田亮】
衆参両院の厚生労働委員会は20日、元公務員の配偶者ら10万人超に計約598億円の年金支給漏れがあった問題をめぐり閉会中審査を行った。
日本年金機構の水島藤一郎理事長は昨年11月に支給漏れを把握していたが、加藤勝信厚労相に全容が報告されたのは今年8月24日だったことが判明。年金機構の対応の遅さが露呈した。
支給漏れは、「振替加算」という基礎年金の上乗せ部分で発生。対象者の大半が夫婦のどちらかが共済年金を受給する元公務員だった。一度に発覚した支給漏れでは人数・額ともに過去最大で、厚労省が9月13日に公表した。
両委員会の冒頭、加藤厚労相は「ご迷惑をお掛けし、誠に遺憾」と陳謝し、再発防止策に取り組む考えを強調した。
質疑では、水島理事長が支給漏れ問題の端緒について「昨年11月ごろ、部下から報告を受け、厚労省にも連絡した」と述べた。しかし、厚労相らの答弁で、同相が全容の報告を受けたのは公表の3週間前だった。同相は「総点検する(昨年12月の)段階で(当時の)大臣に連絡した方がよかった」と指摘。これに民進党の委員らは「公表を遅らせようとしたのではないか」などと批判した。
相手が独身で低所得の男性であれば、変な男に引っかかった。変な男に悪い影響を受けたで終わるかもしれない。
慶応大学の教授となるとさらに問題となるであろう。
大学時代、一般教養の授業の時に、カルト集団がどのように信者を洗脳していくのか聞いたことがある。まず、家族、友達、その他の近い関係の 人達から切り離し、正常な判断が出来ない、誰も助言してくれない環境を作り、カルト集団と一緒に住んでカルト集団の考え方が普通であると 時間を掛けながら洗脳して行く方法だったと思う。
極端な例で言うと、日本企業の合宿や研修の一部は同じ基本や理論を利用していると思う。良い方向であるから誰も批判しないが、プロセスは似ていると思う。
第二次世界大戦中の隣組は、部分的に洗脳プロセスの一部とも思える。
洗脳プロセスの応用形はいろいろな所で見る事が出来ると思う。
「洗脳」で女子大生を支配した「慶応大」ムスリム教授の不倫講座(2)
立場を利用して女子学生を「洗脳」し、不倫関係に――慶応大学総合政策学部の奥田敦教授(57)が、同大2年生の斉藤菜穂さん(21)=仮名=に接近を始めたのは昨年10月のことだった。以降、菜穂さんはサークルを辞め、頻繁に外泊をするように。心配した両親が大学に相談するも改善は見られず、大学側は事実上、問題を放置。ついに本年8月には、奥田教授のマンションに菜穂さんの両親、そして奥田教授の妻らが集まり、菜穂さんの“奪還劇”が繰り広げられた。
***
実は7月に一度、両親は菜穂さんを自宅に送ってきた奥田教授をつかまえ、話す機会を持ったという。
「教授は“お嬢さんは重度の精神病。教員生活で出会ったなかで一番重症だから相談に乗っている”と善意を強調。そのうえ“妻と別れて結婚したい”と言い放つ一方で、“妻とも良好な関係なんです”なんて平気で言います。イスラム教は一夫多妻だとでも言いたいのか。後日、教授から届いたメールにも“重症の子に救済の実験をしている”と書かれていました」
と明かすのは、菜穂さんの母親だ。
「カウンセラーに相談したら、娘は教授への全面的な依存症で、医療機関などで早く適切な治療をしないと救えないと言われた」
実際、洗脳問題に詳しい紀藤正樹弁護士も、「聞いた事情が事実だとすれば」と前置きしたうえで、こう説明する。
「教授と学生の間には上下関係があり、その関係を使って教授が学生に接近したのなら、セクハラと言えるし、この場合、不倫でもある。次に洗脳かどうかですが、教師と教え子、年齢差という上下関係がある以上、洗脳が起こりやすい状況です。洗脳かどうかの目安は、家族や知人など、社会との断絶を引き起こしたかどうか。洗脳とされるケースでは、例外なく対象を自分の方に引き寄せています」
菜穂さんが家族に懐疑的になったことは、前回で述べたが、彼女は「友達と遊んだっていいじゃん」というメモも残している。電話も奥田教授にしかかけない彼女は、友人関係も断ち切られているのだろうか。
セクハラ委員会で不問の末
さて、8月の奪還劇に至った経緯に、そろそろ触れなければなるまい。菜穂さんの母親の知人が語る。
「菜穂ちゃんは去年、奥田研究会のヨルダン研修に参加し、今年も行こうと自分でビザをとった。しかも大学も参加を許可したのです。調査委員会の結論が出ていないので、彼女を参加させるという判断は不当でない、というのが大学の言い分で、両親はたまらず旅券を取り上げました。そして、奥田教授が出発する前夜は彼のマンションで過ごすだろうと踏んで、みんなで彼女を奪還しに行ったんです」
ところで、その場に奥田教授の妻がいたことを、不思議に思った方もいるだろう。当初は取材を拒んでいた彼女が、重い口を開いてそのわけを語った。
「奥田は一昨年も学内でセクハラ委員会を立ち上げられています。主人が言うには、7月ごろに湘南台のマンションにゼミの女子学生を連れてきて、一晩中話したとのこと。問題になった行為は、ほっぺたにちょんと触ったことだと言うのですが、自宅に連れ込んで一晩中、という時点で教員としてアウトだと思う。不審に思った男子がその子を連れて大学に訴えたそうで、彼ら二人のほか、同調する学生が何人もゼミを集団退会したと聞いています」
13年前にも…
事実、奥田研究会の出身者に聞いても、
「私が入る直前の一昨年8月ごろ、先生のセクハラがあって、ゼミ生が1、2名を残してごっそり辞めたと聞きました」
教授の妻の話に戻る。
「しかも、問題になった後も夫は、その彼女とLINEが繋がらなくなると、下宿先の外に何時間も張り込んだそうです。私が奪還作戦に協力したのは、妻の私まで参加すれば、夫も事の重大さに気づいてくれると思ったから。でも、実際には女の子を奪われて暴れるだけでした。奥田は13年前にもゼミ生に同じことをしています。奪還の夜、私は菜穂さんに奥田とその女性とのメールの記録を見せ、“同じ手口でしょ”と伝えました。奥田は彼女の家族も、うちの家族も壊している。何を考えているのか、さっぱりわかりません」
継いで言えば、慶応大学が考えていることもさっぱりわからない。一昨年、奥田教授に厳正な処分を下していれば、同じことは起こらなかったはずなのだ。
***
(3)へつづく
「週刊新潮」2017年9月14日号 掲載
こんな東京都でオリンピックは大丈夫なのか?
豊洲市場の地下水調査で、有害物質ベンゼンが、これまで最大となる環境基準の120倍検出された。
東京都によると、2017年5月から8月にかけ、豊洲市場内の46地点で地下水を調査した結果、これまで基準値の100倍のベンゼンが検出されていた地点で、120倍のベンゼンが検出されたという。
これは、当初の土壌汚染対策が行われて以降、最も高い値。
まあ、下記の記事が事実なら自業自得のように思える。
「週刊文春」9月7日発売号で明らかになった山尾志桜里衆院議員(43)の“禁断愛”。お相手のイケメン弁護士、倉持麟太郎氏(34)による婚約不履行事件が明らかになった。
学生時代から倉持氏を知る人物が語る。
「若い頃から彼の女癖の悪さは有名でした。かつて倉持氏には結婚を約束したAさんという女性がいた。交際期間は3年を超えていました」
2012年に弁護士登録した倉持氏だが、彼の下積み時代を支えていたのが婚約者のAさんだった。
「お金がない彼のためにお弁当を作ってあげたり、旅行の費用を出してあげていたと聞きました。弁護士事務所開設の際には、その準備のため彼女が奔走していました。その頃までには、お互いの両親に挨拶も済ませており、2人は結婚を前提に同棲生活をしていました」
だが2015年、倉持氏は突然の心変わりを見せたという。
「仕事が忙しいといっては、倉持氏は同棲中の自宅にあまり帰ってこなくなったのです。結局、彼から別れを切り出し、婚約は破談。実は、倉持氏は航空会社勤務の客室乗務員と浮気をしており、子供まで作っていたのです。その女性と結婚するため、彼は婚約者のAさんを捨てたのです」
Aさんの母親は本誌の取材に「そういう事はありました」と婚約不履行の事実を認めた。倉持氏にも取材を申し込んだが、回答はなかった。
「週刊文春」9月14日発売号では、倉持氏による「婚約不履行事件」に加え、山尾氏と倉持氏がホテルに宿泊したことを示す“新証拠”の存在などを詳報している。
「週刊文春」編集部
授業を通して女子学生を「洗脳」し、不倫関係に……。そんな身の毛のよだつ所業が明るみに出た慶応義塾大学総合政策学部の奥田敦教授(57)だが、大学は今も問題を放置したまま。しかも、教授の余罪は多数あった。
***
「週刊新潮」先週号が報じたのは、2年生の奥田ゼミ生・斉藤菜穂さん(21)=仮名=が教授から受けた被害の実態である。報道後に奥田教授の研究室のHPは事実上の非公開となっているが、教授への処分はいまだ下されていない。
こうした大学の放置の姿勢が、菜穂さんの被害を生んだとしたらいかがだろう。奥田教授は過去にも同様の過ちを犯していたのだ。
「一昨年7月、ゼミの1年先輩の山田友里さん=仮名=から事情を聞いて、事態を知りました」
と語るのは「奥田研究会」に在籍していた4年生である。当時、山田さんは奥田教授に粘着質に付きまとわれ、電話やメールが何百件と寄せられたという。
「山田さんのマンションはオートロックだったのに、ある日、ドアを開けたら奥田先生が立ってて、慌てて閉めたそうです。完全なストーカーですよね」(同)
山田さんは大学のハラスメント防止委員会に訴え出たが、教授は“厳重注意”されるのみで、ゼミも存続した。山田さん本人にインタビューを申し込むも、取材を拒否。その理由は「この件に関しては一切他言しないことを約束させられたので」と、不祥事を隠す大学の口封じの姿勢が見え隠れする。
教授の“女子学生には優しく男子学生にはキレる”という態度ゆえ、一種のハーレム状態にあったという奥田ゼミ。お気に入りの学生に教授が送ったという2004年のメールには、イスラム法の権威である奥田教授らしい、こんな文言が。
〈「アッラーにおける愛」をともに実践する相手として、アッラーがわたくしにおあたえくれたのがアンティ、○○さんということになります。(中略)あつし〉
今回の菜穂さんのケースは、こうしたハレンチ教授を長年放置し続けた大学による人災とさえ言えるだろう。
***
9月13日発売の「週刊新潮」では、大学が放置する「ハレンチ教授」と「ハーレムゼミ」について詳しく掲載する。
「週刊新潮」2017年9月21日菊咲月増大号 掲載
新潮社
産業機械製造の郷鉄工所(岐阜県垂井町)が11日、岐阜地裁に自己破産を申請すると発表した。売り上げが低迷して資金難に陥っていたためで、同日付で従業員79人を解雇し、事業を停止した。負債総額は40億円程度で、9月末に破産申請する見通し。
1931(昭和6)年の創業で、破砕機や焼却炉、廃材処理プラントなどの製造を手がけてきた。帝国データバンク名古屋支店によると97年3月期に約92億円の売上高があったが、近年は取引先の設備投資が落ち込み、受注が減少。2016年3月期に負債が資産を上回る債務超過に陥った。17年3月期は期限までに有価証券報告書を提出できず、9月11日に東京、名古屋の両証券取引所第2部への株式上場が廃止になった。
同社の業務をめぐっては不適切な会計処理が取り沙汰され、第三者委員会が調査。今年6月にまとめられた報告書では「内部統制をはじめとするコーポレートガバナンスがほとんど機能していなかった」と指摘された。
菅義偉官房長官の会見をめぐり、首相官邸報道室が9月1日、東京新聞官邸キャップに抗議書を送ったことが波紋を広げている。
【写真】官邸報道室長が東京新聞へ宛てた抗議書はこちら
官邸が問題視したのは、加計問題で菅官房長官へ厳しい質問を浴びせ、注目された東京新聞社会部の望月衣塑子記者の発言だ。
官邸資料によると、8月25日午前の菅官房長官会見で望月氏は、「加計学園獣医学部設置の認可保留」に触れ、次のように質問していた。
望月氏「最近になって公開されています加計学園の設計図、今治市に出す獣医学部の設計図、52枚ほど公開されました。それを見ましても、バイオセキュリティーの危機管理ができるような設計体制になっているかは極めて疑問だという声も出ております。また、単価自体も通常の倍くらいあるんじゃないかという指摘も専門家の方から出ています。こういう点、踏まえましても、今回、学校の認可の保留という決定が出ました。ほんとうに特区のワーキンググループ、そして政府の内閣府がしっかりとした学園の実態を調査していたのかどうか、これについて政府としてのご見解を教えてください」
菅官房長官「まあ、いずれにしろ、学部の設置認可については、昨年11月および本年4月の文部科学大臣から大学設置・学校法人審議会に諮問により間もなく答申が得られる見込みであると聞いており、いまの段階で答えるべきじゃないというふうに思いますし、この審議会というのは専門的な観点から公平公正に審査している、こういうふうに思っています」
官邸は望月氏の質問が、文科省が加計学園に「認可保留」を正式発表(解禁)する前であったことを問題視した。
7日後の9月1日、東京新聞官邸キャップ に対し、官邸は文書で〈官房長官記者会見において、未確定な事実や単なる推測に基づく質疑応答がなされ、国民に誤解を生じさせるような事態は、断じて許容出来ません〉〈再発防止の徹底を強く要請いたします〉と厳重注意した。
官邸の抗議書に対して望月氏は、こう反論する。
「文科省の正式発表前に質問しましたが、加計学園獣医学部設置の『認可保留』という事実関係自体が誤っていたわけではありません。うちの担当記者が取材で大学設置審議会の保留決定の方針を詰めて、記事も出ていたため、菅官房長官会見で触れたのです。ただし文科省の正式発表であるかのような印象を与えたとすれば、私の落ち度といえるでしょうが……」
官邸のこの抗議書に対し、加計問題を取材した多くの報道関係者、国会議員らが違和感を覚えたという。
「認可保留」という公知の事実を、文科省の正式発表よりも少し前に質問で触れたところで、国民に誤解を生じさせるとは考えられないからだ。
ちなみに文科省の正式発表は8月25日午後で、望月氏の質問はわずか2時間足らずのフライングに過ぎない。
しかも加計学園に対し、「認可保留」を決定した文科省の設置審議会が開かれたのは8月9日で、テレビや新聞はすでにその直後から「認可保留」の方針決定を繰り返し、報じている。
官邸の抗議文を一刀両断に批判したのは、民進党の小西洋之参議院議員だ。ツイッターで官邸が送った書面を公開し、〈不当な言論弾圧そのもの。東京新聞は断固抗議すべきだ〉と記している。
東京新聞に対し、官邸はなぜ、このような抗議書をわざわざ出したのだろうか。
“謎”を解くカギは、望月氏が質問した8月25日から抗議文が出る9月1日までの7日間のタイムラグだ。
望月氏は8月31日の菅官房長官会見で、北朝鮮のミサイル発射前夜に安倍晋三首相が公邸に過去2回(8月25日と28日)、宿泊したことなどについて次のように質問している。
「(安倍首相が公邸で待機したということで)前夜にある程度の状況を政府が把握していたのなら、なぜ事前に国民に知らせなかったのですか」
「Jアラートの発信から逃げる時間に余裕がない。首相動静を見て、(首相が)公邸に泊まると思ったら、次の日はミサイルが飛ぶのですか」
こうした望月氏の発言を「トンデモ質問」と一部のメディアが取り上げ、批判した。この日の質問について望月氏は、こう補足解説をする。
「金正恩委員長が米韓合同軍事演習の中止を求めたのは『斬首作戦』が含まれていたからです。アメリカの攻撃で国家が崩壊したイラクやリビアの二の舞いにならないように、自国防衛のために核武装をしようとしている。相手の立場に立って考えることが重要。北朝鮮に核ミサイルを連射されたら日本全土を守り切ることは難しい。悪の枢軸として圧力をかけるだけではなく、北朝鮮との対話を模索してほしいとの考えから質問をしたのです」
北朝鮮情勢が緊迫する今、安倍政権と異なるスタンスで記者が質問をしたとしても何ら問題はない。
官邸の抗議に屈せずに望月氏が今後、菅官房長官会見でどんな質問を続けていくのか。注目される。(横田一)
短期的に見て否定し続けるのか、長期的な視点で公務員が信頼されるために、関係者を処分するのか、権限や権力を持つ人達の判断次第。
大阪地検特捜部は、11日にも森友学園の籠池泰典前理事長(64)らを、詐欺などの罪で起訴する方針。国有地の売却問題では、FNNが独自に入手した音声データから、新たに口裏合わせの疑惑が浮上した。
大阪地検特捜部は、森友学園の前理事長、籠池泰典容疑者と妻の諄子容疑者(60)を8月、大阪府から補助金およそ9,250万円をだまし取った疑いで再逮捕し、11日にも起訴する方針。
一方、国が森友学園に国有地を8億円値引きして売却した問題では、国は、地中深くから新たなごみが見つかったため、撤去費を値引きしたと説明してきた。
しかし、FNNが入手した音声データには、校舎の建設が始まった直後に、国側と学園側が、新たなごみが見つかったように口裏合わせしたとも取れるやり取りが記録されていた。
国側の職員とみられる人物「3メートルまで掘ってますと。そのあとで土壌改良というのをやって、その下からごみが出てきたというふうに理解してるんですね。その下にあるごみっていうのは、国が知らなかった事実なんで、そこはきっちりやる必要があるでしょうという、そういうストーリーはイメージしてるんです」
工事業者とみられる人物「そういうふうに認識を統一した方がいいのであれば、われわれは、合わさせていただきますけれども、でも(3メートルより)下から出てきたかどうかっていうのは、わたしの方から、あるいは工事した側の方から、確定した情報として伝えていない」
池田 靖国有財産統括官(当時)とみられる人物「資料を調整する中で、どういう整理をするのがいいのかということで、ご協議、協議させていただけるなら、そういう方向でお話し合いをさせていただければありがたいです」
不透明な取引について、近畿財務局で40年以上国有地の売却などに携わっていた元職員は、「『本当にまずい処理だった』というのは、複数の(現役)職員から声が出てますね」と語った。
工事関係者は、口裏合わせの疑惑について、「8億円値引きするということは最初から決まっていた」と証言しているが、近畿財務局は、「録音状況などが確認できないので、コメントできない」としている。
1人、自殺したので話の辻褄を合わせやすくなったと思う。本人の意思で自殺したのだろうか?自殺前に話をした人はいるのだろうか?
東京電力福島第1原発事故後の工事をめぐり清水建設の社員が工事費を架空請求した疑惑で、清水建設は9日までに、作業所長を務めていた男性社員が下請け業者と共謀して不正取引を行っていたと発表した。
同社の損害額は約3900万円に上るという。
男性社員は8日朝、東京都中央区の社員寮で死亡しているのが確認された。自殺の可能性があるとみられる。
初めて聞く大学の名前だし、興味はない。ただ、個人的に経営問題を抱える大学は助ける必要はないと考えるのでこの大学が当てはまるのなら 救済の必要はない。
城西大学は、去年退任した前の理事長の在任中に「4億円あまりの不適正な支出があった」とする調査結果を8日に公表した。
城西大学の会計調査委員会の報告書によると、水田宗子前理事長は、母親である名誉理事長に対し、勤務実態がないにもかかわらず、9年間で2億円あまりの報酬を支払ったほか、理事会の決議がないまま退職金1億6800万円を支出するなど、総額で4億円あまりの不適正な支出を行ったという。
大学側は、今後民事訴訟で返済を求めるとともに、前理事長の刑事告訴も検討するとしている。
一方、水田前理事長側は「事実無根」として、すでに大学側を提訴していて、8日の報告書についても「極めてずさん。水田氏を狙い撃ちにしたもので、断固とした対応を検討している」とコメントした。
ヤマトホールディングスのグループ会社の社員だった男らが、会社からおよそ2,700万円をだまし取った疑いで、警視庁に逮捕された。
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン元社員の坂口高智容疑者(48)は、下請け会社の役員と共に、2012年以降、架空のタイヤ保管料を、二十数回にわたって会社に請求し、およそ2,700万円をだまし取った疑いが持たれている。
調べに対して、坂口容疑者は「ほとんど風俗店などで使った」と供述している。
ヤマトホールディングスは、「元社員が詐欺を行ったのは誠に遺憾です」としている
「両親が探偵に調査を依頼すると、「研究室」と言っていた行先は奥田教授のマンションだったことが発覚する。ところが、大学は両親の再三の訴えにもかかわらず、事態を事実上、放置したままだった。」
上記が事実なら自分が持っていた慶応義塾大学のイメージが間違っていたのか、慶応義塾大学が時間とともに変わりつつあると言う事なのだろうか?
日本の“私学の雄”慶応義塾大学で、教授が女子学生と不倫していた。しかも、教授は立場を利用して一方的に学生を洗脳。それを大学は見て見ぬふりで……。
***
慶応大学2年生の斉藤菜穂さん(21)=仮名=に、アラビア語などの講義を担当する総合政策学部・奥田敦教授(57)が接近し始めたのは、昨年の秋だった。
「(奥田教授に)勉強に集中するように言われてサークルも辞め、帰宅も遅くなり、“研究室に泊まるから”と、帰らないことも増えました。ボーイフレンドとも別れ、冬休みも研究室に通うようになった。“思い出も捨てなきゃいけない”と、クローゼットからぬいぐるみを出して捨ててしまい、年が明けると“こんな自分にした親が悪い”と、私たちをなじるようになりました」
と、菜穂さんの異様な振る舞いを明かすのは、彼女の母親である。以来、菜穂さんは頻繁に外泊するようになり、2月下旬には妻子のある奥田教授と二人きりで沖縄に行くこともあったという。
“先生とだったら世界征服もできそう”“死ぬのが怖くなくなってきた”とのメモを残すようになり、人格まで変わり始めた菜穂さん。両親が探偵に調査を依頼すると、「研究室」と言っていた行先は奥田教授のマンションだったことが発覚する。ところが、大学は両親の再三の訴えにもかかわらず、事態を事実上、放置したままだった。
母親が相談したカウンセラーは、“菜穂さんは教授への全面的な依存症”と指摘。8月17日には、菜穂さんの両親、そして教授の妻が奥田教授のマンションに集まり、“奪還劇”が繰り広げられた。部屋では、菜穂さんが震えていたという。
奥田教授は過去にもゼミ生に同じことをしていた、と教授の妻は語る。
「奥田は彼女の家族も、うちの家族も壊している。何を考えているのか、さっぱりわかりません――」
「週刊新潮」の取材に対し、奥田教授は「ノーコメント」の一点張り。慶応義塾広報室は「大学としてできる限り真摯に対応をさせていただいておりますが、現在対応中の案件であり、これ以上の詳細は回答を控えさせていただきます」との回答だった。
***
9月7日発売の「週刊新潮」では、奥田教授の“不倫講座”を4ページにわたって特集。阿鼻叫喚の奪還劇の様子や、教授の“洗脳”、それを放置した慶応大学の責任について、詳しく報じる。
「週刊新潮」2017年9月14日号 掲載
新潮社
チェックしても相手がごまかす意思があれば、ごまかしは可能と言う事。能力や資格も必要であるが、人間性も重要。 ただ、全てにおいてチェックするとコストアップは避けられない。これが現実だと思う。
名鉄観光バス(本社・名古屋市熱田区)は4日、刈谷営業所(愛知県刈谷市)の男性運転手(49)がバスツアーの宿泊先で飲酒したうえ、同僚を身代わりにしてアルコール検知をすり抜け、運転していたと発表した。宿泊先では社の内規に違反して、運転手計10人が飲酒。社内で調べたところ、他に十数人の運転手が過去に出先で飲酒していたことを認めたという。
同社によると、ツアーは8月14~16日、愛知、岐阜両県の中学生と引率者約4千人が参加。バス106台に分乗し、長野県の志賀高原で勉強合宿を開いた。運転手106人が乗務した。
49歳の運転手は15日夜に宿泊先ホテルの一室で同僚8人と酒を飲み、自身は500ミリリットル缶のビールを3、4本飲んだ。16日午前6時すぎに携帯型検知器で検査すると微量のアルコールを検出。このため一緒に飲んだ同僚に頼んで通信式の検知器に息を吹き込ませ、異常のない呼気データを営業所に送ったという。
観光バス大手「東京ヤサカ観光バス」(東京)の少なくとも12人の運転手が、中学生の「林間学校」などの送迎をした際、社内規定に違反して宿泊先で飲酒し、さらに一部の運転手は運転前のアルコール検知を不正に免れていたことがわかった。国土交通省は貸し切りバスの運転手に乗務前のアルコール検知を義務付けており、同省の規則に違反する恐れがある。
検知器2個使いデータ送信 観光バス運転手、不正の手口
朝日新聞に寄せられた同社関係者からの情報を元に、同社が運転手に聞き取り調査をして判明した。
それによると、40~50代の男性運転手12人は2013~14年、中学生の「林間学校」で長野県の八ケ岳に行った際などに宿泊先で飲酒。数人は翌朝、乗務前の携帯型アルコール検知器を使った呼気チェックの際に、同僚に息を吹き込ませるなどしてアルコールが検知されないようにした。その後、客を乗せて運転したという。
国交省は旅客自動車運送事業運輸規則で、貸し切りバス事業者などに運転手への乗務前のアルコール検知を義務付けている。
宿泊先では、未成年者を含む女性ガイドが運転手らとともに飲酒したこともあったという。同社は規定で、運転手とともにガイドにも宿泊先での飲酒を禁じている。
同社の調査では、12人とは別に、2人の男性運転手が宿泊時のアルコール検知を免れるため、検知器に呼気を吹き込むチューブに小型ポンプを取り付け、呼気の代わりに空気を送る細工をしていたことも判明した。2人は「うまく空気を送れず失敗した。結局、ポンプは捨てた」と説明したという。
同社は、こうした運転手らの一部を既に数日間の出勤停止処分にした。今後、さらに追加の処分も検討するという。
また、同社は営業所への出勤時もアルコールの点検をしているが、今春に男性運転手3人から呼気1リットルあたり0・15ミリグラム超のアルコール分が検知された。この状態で車を運転すれば、道路交通法違反(酒気帯び)に当たる可能性がある。3人は3日間の出勤停止処分にしたという。
同社は「飲酒に関わる不正を今後なくすため、従業員の教育を徹底する」とコメントしている。
民間信用調査会社によると、東京ヤサカ観光バスの2015年9月期の売上高は約35億円。都内で2番目に多い158台のバスを所有している。同社によると、小中学校の修学旅行や林間学校の送迎を多く請け負っているという。(中村信義)
清水建設は怪文書を調査した文科省と同じ。やる気がない。組織の問題である事は明らかだろう。
多額の税金が東京電力につぎ込まれているのだから国が本気であるなら清水建設の調査とは関係なく、調査に乗り出すべきだ
福島第1原発の廃炉に向けた工事で、清水建設のJV(共同企業体)の責任者が作業員の人数を水増しして架空請求した疑いがある問題で、清水建設本社が2016年、内部通報を受けたものの、本格的な調査を行っていなかったことがわかった。
清水建設JVの責任者の清水建設社員は、東京電力から請け負った福島第1原発工事の作業報告書に、作業員の人数を延べおよそ1,500人分水増しし、およそ4,000万円を架空請求した疑いがあることが、JVの関係者への取材でわかっている。
清水建設JV作業員は、「いやもう、ずっとですよね。3年ぐらいなのかな。ずっとこういう人(作業報告書には)いるけど、宿舎にはいないんですよね]と話した。
JVの関係者によると、清水建設本社は2016年、内部通報を受けた際、書類の調査は行ったが、作業員からのヒアリングなど、本格的な調査を行わなかったという。
清水建設は、FNNの取材に対し、内部通報の事実を認めたうえで、「書類を中心に調査したが確認できなかった。あらためて外部の専門家を交えて、関係者のヒアリングなど調査を進めている」とコメントしている。
■原発関連疑惑・情報募集
フジテレビでは福島第1原発を巡る問題や疑惑を継続取材しています。
内部情報をお持ちの方で情報提供して下さる方は、下記リンクからご連絡下さい。
https://wwws.fnn-news.com/nsafe/goiken/index.html
福島第1原発で、原発事故後の工事を行っている清水建設の共同企業体・JVの作業報告書に、実際にはいない作業員が記載され、およそ4,000万円が架空請求された疑いがあることがFNNの取材でわかった。虚偽の記載には、JVの責任者の清水建設社員が関与している可能性があり、清水建設は内部調査を始めた。
清水建設JVは、福島第1原発事故の水素爆発で壊れた、1号機を覆う建屋カバーの取り外し工事を東京電力から請け負っている。
FNNが入手した、2016年10月の作業報告書と、健康管理表に記載されている作業員22人のうち、下の部分に記載された2人は実際にはいなかったと、複数の作業員が証言している。
清水建設JVの作業員は「見たこともない人間の名前が、ある書面上に書いてあった。全てが同じ屋根の下で生活しているものですから、(2人が)いないのは間違いない」と話した。
清水建設JVの別の作業員は「この方(2人)はいらっしゃらないですね。朝の朝礼で、きょうは何の作業をする、このヤード(現場)は何の作業をするとか言っているので。朝、言っているのに、誰も(現場には)いないのに、何でかなと」と話した。
また、実際に作業にあたった20人は、原発の敷地内が作業場所で、報告書にもそのように記載されていたが、いなかったという2人は、東京電力に把握されるのを避けるためか、線量計の貸し出しを受ける必要のない、原発の敷地の外が作業場所と記されていた。
架空の作業員は、原発からおよそ25km離れた広野町などで働いていたことになっていた。
別の清水建設JVの関係者によると、作業報告書への架空の記載は、この責任者の指示で行われていて、2014年1月から2016年11月までのおよそ3年間にわたり、7人の名前を使って、延べおよそ1,500人分にのぼり、作業員代およそ4,000万円が架空請求された疑いがあるという。
清水建設JVの責任者は「(作業報告書に架空の記載をしたか)そういう文書については、会社から連絡しますので。(架空請求も行ったか)そんなのもう、会社からお答えしますから」と話した。
清水建設は、FNNの取材に対して、「ご指摘の件が事実であれば、大変遺憾です。外部の専門家を交えて、詳細な調査と確認作業を行っています」とコメントしている。
また東京電力は、「ご指摘の件について把握していませんが、清水建設から話を聞かせてもらいたい」とコメントしている。
逮捕された!それで有罪になればどのような処分を受けるのか?
乗用車など8台の車検を不正に通したとして、逮捕・起訴された鹿児島市の自動車整備会社の社長ら3人について、県警は31日、別の車の車検も不正に通した疑いで再逮捕しました。容疑者の1人は「4、5千台くらい不正をした」と供述しているということです。
虚偽有印公文書作成などの疑いで再逮捕されたのは、鹿児島市宮之浦町の「松村自動車ユニカー車検センター」の社長・松村和昭容疑者(57)と、いずれも整備士の清水朋宏容疑者(40)と福泰宏容疑者(47)です。
警察によりますと、3人は今年5月、共謀して必要な整備や検査をしないまま、乗用車や大型バイクなど3台の車検を通した疑いがもたれています。3人は、自動車検査員などの「みなし公務員」にあたり、松村被告が経営する会社は国の指定工場として車検を行っていました。警察の調べに対し3人は容疑を認めているということです。
3人は今月8日、必要な整備や検査をしないまま、乗用車など8台の自動車の車検を通したとして逮捕・起訴されています。容疑者の1人は「これまでに4、5千台くらい不正をした」と供述しているということで、警察では不正に車検を通した車が多数あるとみて捜査を続けています。
MBC南日本放送 | 鹿児島
無通告調査がどれだけ行われるか次第で問題は改善できると思う。ただ、本当に問題が改善すればバス料金は上がる結果となると思う。
無通告調査が適切の行える民間機関は少ないと思うので、その点が疑問?
無通告で調査
国土交通省は2017年8月22日(火)、貸切バス事業者を対象に、法令が遵守されているかどうかの調査を無通告、覆面で今後行うと発表しました。
現在、貸切バス事業者に対しては、国の監査官が営業所や街頭で監査を行っていますが、さらなる輸送の安全確保を調査するため民間機関に調査を委託。調査員は一般の利用者を装って実際に運行される貸切バスに乗り込み、現場でしか分からない休憩時間の確保状況やシートベルトの装着、交替運転者の配置、危険運転の有無、車内・車外表示などをチェックします。
調査を行うにあたり貸切バス事業者への通告は行わず、また、実施時期は「随時」といいます。この調査で法令違反の疑いが確認された場合は、後日、国による監査が実施されます。
乗りものニュース編集部
「残業代は最大で年8兆5000億円減少する。」の計算が正しいのかわからない。ただし国民の所得が減ると税収は落ち込むし、消費は減るであろう。
まあ、これぐらいは政府も考慮していると思うから、問題としては認識していないのであろう。
もし考慮してなくて困ったと思っているのなら間抜けだと思う。
まあ、企業が抜け穴を探したりするから最大の数値にはならないと思う。ただ、時間内に仕事を終わらす圧力が広がりそうだから、
収入は減るのにストレスやプレッシャーは増える悪循環が生まれる可能性もある。違った意味で精神的に病む人達が増える可能性もある。
残業時間の上限が月平均で60時間に規制されると、残業代は最大で年8兆5000億円減少する―。大和総研は、政府が掲げる働き方改革で国民の所得が大きく減る可能性があるとの試算をまとめた。個人消費の逆風となりかねないだけに、賃金上昇につながる労働生産性の向上が不可欠となりそうだ。
政府は働き方改革の一環として、罰則付きの残業上限規制の導入を目指している。実現すれば繁忙期を含め年720時間、月平均60時間が上限となる。
試算によると、1人当たりの残業時間を月60時間に抑えると、労働者全体では月3億8454万時間の残業が減る。年間の残業代に換算すると8兆5000億円に相当する。
残業時間の削減分を新規雇用で穴埋めするには、240万人のフルタイム労働者を確保する必要があるが、人手不足の中では至難の業だ。
関連又はinterfaceでシステムの一部になっているアイテムが100%で問題なければ良いが、不安定であったり、不具合があるとこのようなケースも起きる。
これは宿命。アップデートするたびに関連する機器やソフトで不具合が起きない事を確認していない場合、運が悪ければいつでも起きる事。
非常に大切な部分はコストを掛けてでも事前の確認を行うか、あまりハイテクよりも安定と信頼を優先にするべきだと思う。
玄関ドアなどのスマートロックシステムを手がけるLockStateの顧客(およそ500人に上る)が先日帰宅したところ、ドアの錠に取り付けた同社のロックシステム「RemoteLock LS-6i/6000i」が、ファームウェアアップデートの失敗によって操作できない状態になっていた。
LockStateの最高経営責任者(CEO)Nolan Mondrow氏は顧客に宛てたメールの中で、「ソフトウェアのアップデートがユーザーのロックに配布されたが、その後、当社のサーバへ再接続することができなくなった。このため、リモートで修正することができなくなった」と説明した。
この事故からは、いわゆるIoT(モノのインターネット)と自宅での居場所を争うようにして急増しているアプリで動くガジェットや機器の、安全性(と信頼性)に対する懸念が浮かび上がる。われわれが日常で使うデバイスにクラウドベースで機能するものが多くなればなるほど、ユーザーが期待する安全性とスムーズな操作性を保証するというプレッシャーがメーカーにはのしかかる。これは、インターネットスピード、スマートホームプラットフォームの競合、さまざまに異なるスマートフォンやその他のデバイスがあらゆるものをコントロールするのに使われていることなど、可変要素を考えると容易な課題ではない。
Mondrow氏は影響を受けた顧客に対して、2つの解決策から選んでもらうよう申し出ている。ロックを切断してLockState本社へ郵送し、同社が1週間内に修理して返送するか、または同社が代替品のロックを発送するまで2週間待つかのどちらかだという。いずれの方法にしても、ねじ回しでもってロックをドアから引きはがすことになる。それでどうにか解決はするかもしれないが、1週間以上もドアに鍵が無い状態で待つことが大きな問題になるのは明らかだ。
さらに悪いことに、LockStateはAirbnbの「ホストアシスト」に参加していた。ホストアシストとは、Airbnbで住居を貸し出すホストを支援することを目的とした、民泊サービスのパートナー企業だ。実際に、この件で影響を受けた約200人の顧客がAirbnbのホストであるとThreatpostは報じた。中には、休暇シーズンの繁忙期中に、予約を変更したりキャンセルしたりしなければならなかったホストがいたかもしれない。
壊れたロックを修理して交換するだけでなく、LockStateは影響を受けた顧客に対し、同製品を操作するためのサブスクリプションサービス「LockState Connect Portal」を1年間無料で提供する予定だ。
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
「日本救急医学会の指導医の太田祥一医師は『死戦期呼吸と普通の呼吸とを見分けるのは、一般市民には難しい』と指摘する。死戦期呼吸の認知度が低いことも、AEDでの素早い処置に思いが至らない要因の一つとみる。」
自動体外式除細動器(AED)の設置に関してどこの責任でどのように考えて指導しているのか知らないが、事故が起きてからこんなコメントがあると言う事は今まで設置だけにしか
拘ってこなかった。取扱いに不慣れな人の事を想定していなかったと言っているようなものである。
自動体外式除細動器(AED)の使用が緊急事態を想定しているのなら、その場にいる素人、又は、未経験者にも使えるように指示書を近く、又は、目につく
場所の置いておくべきだろう。使える人を探していたら時間が経過してしまうかもしれない。あと、疑問に思うが、素人や未経験者が善意で使用を試みた場合、
残念な結果となっても法的には守られているのか?もし過失などを問われるのであれば、リスクを負いたくない人もいると思う。
これらの問題を解決するべきである。そうでなければ将来似たような悲劇は起こるであろう。
新潟県の加茂暁星高校の野球部でマネジャーをしていた女子生徒(16)が練習直後に倒れ、今月5日に死亡した。家族によると、生徒は倒れた時に心室細動を発症していた。自動体外式除細動器(AED)を使えば、救える可能性がある症状だ。AEDの設置が広がっても突然死が後を絶たない背景には、AEDの性能についての理解が深まっていないことや、卒倒などの場面に遭遇すると、落ち着いて使いこなせない実態がある。
■認知度低い「死戦期呼吸」
「AEDを使ってほしかった。助かったかもしれないと思うと、つらくて悔しい」。生徒の父親(42)は朝日新聞の取材に苦しい胸の内を語った。明るくて面倒見のいい性格。部活が大好きだったという。
生徒は7月21日午後、練習があった野球場から学校まで約3・5キロを走った後に倒れた。野球部の監督は「呼吸はある」と判断し、AEDを使わずに救急車の到着を待った。
しかし、その呼吸は、「死戦期呼吸」というものだった可能性がある。心停止の状態になっても、下あごだけが動いたり、しゃくり上げるようなしぐさをしたりして、呼吸をしているように見えることがある。生徒が搬送された新潟市内の病院の医師は「心室細動が起きていた」と生徒の家族に説明したという。
AEDは、心臓がけいれんしたような状態(心室細動)になり、血液を送り出せなくなっている状態を、電気ショックを与えて正常なリズムに戻すための機器だ。校内のAEDは、生徒が倒れた玄関に近い事務室の前など計3カ所あった。加茂署によると、病院に運ばれた生徒は今月5日、低酸素脳症で死亡した。
日本救急医学会の指導医の太田祥一医師は「死戦期呼吸と普通の呼吸とを見分けるのは、一般市民には難しい」と指摘する。死戦期呼吸の認知度が低いことも、AEDでの素早い処置に思いが至らない要因の一つとみる。
もうまともな芸能活動は出来ないだろう。今後はAVとか、セクシー関係の方向へ行くのだろうか?
趣味と実益が重なりそうなので本当に方向転換しそう?
熊本などでご当地アイドルをプロデュースしていた男が、女子高校生に酒を飲ませて性的暴行をしたとして逮捕された事件で、警察は14日午後、この男を送検した。男は「相手が酒に酔ったのに乗じてやりました」と供述していることがわかった。
逮捕されたのは、熊本市東区のタレント事務所経営・塚本伸也容疑者(30)で、14日午後、身柄を熊本地検に送られた。塚本容疑者は、熊本県外に住む女子高校生(16)に酒を飲ませて酔わせ、抵抗できない状態で性的暴行をした疑いがもたれている。
警察の調べに塚本容疑者は「計画的ではなかった」としたうえで、「相手が酔ったのに乗じてやりました」と供述していることがわかった。
塚本容疑者はこれまで、熊本県などを中心にご当地アイドルのプロデューサーとして活動していた。
「JA福井市(本店福井市渕4丁目)の支店勤務の40代男性職員が、過去15年間にわたり顧客の貯金など約1億6千万円を着服、流用していたことが14日分かった。同JAが同日発表した。」
JA福井市は15年間、職員の着服に気付かなかったのか、それとも、ある事件で問題に気付いたが気付かぬふりをしていたのか?
どちらのケースでも、JA福井市に問題がある事には間違いない。監査が甘い、又は、形だけの監査になっているのか?それとも、
監査やチェックする職員達に問題があり、事実を認める事により責任及び調査を明確にすることを役員達が避けたのか?
事実はどうなのだろうか?
「職員は着服を認めた上で「自分の自動車を購入する資金などに使った」と説明しているという。」
かなりの高級車を乗らないと約1億6千万円は必要ない。高級車に乗ると、着服や横領を疑う人達がいてもおかしくないと思う。
JA福井市(本店福井市渕4丁目)の支店勤務の40代男性職員が、過去15年間にわたり顧客の貯金など約1億6千万円を着服、流用していたことが14日分かった。同JAが同日発表した。
同JAによると、職員は2002年から今年まで、複数の支店で顧客渉外を担当。組合員2世帯から預かった定期貯金など計約1億6千万円を着服したとしている。
職員は着服を認めた上で「自分の自動車を購入する資金などに使った」と説明しているという。
同JAは被害について県警福井署に相談している。
坪内知佳さんのやり方はどの業界や企業にも応用できるわけではないが、現場を理解し、現状を良くするためにはどうしたらよいか考えながら
修正して行く事は重要であることを示していると思う。
現場に問題があれば、基本的に2つの方法があると思う。何とか出来るケースだけを選んで助ける。トライアンドエラーを繰り返しながら
改善点や改良できる点を見つける。
時代により、ニーズが変わって来る。環境が変わる事により解決方法が見つかる事もある。頭で考えても実際にやって見ると、想像していたように
出来る部分と思っていたように出来ない部分がある事に気付くであろう。解決方法をわからない状態で、がんばるのはたいへん。多くの人は
残るよりも、去る方を選ぶ。選択権が無ければ、去りたくても去れない事がある。
彼女のような人が増えれば日本は良い方向へ向かうと思う。ただ、単純に大学へ行けば良いとか、そう言う問題ではない。やはり人間の個性と
知識や経験のコンビネーションだと思う。
「海が青いうち、しょっぱいうちは魚が取れる」―。そんな漁師たちの意識を変える必要があった。山口県萩市から北西の沖合約8キロにある人口約750人の大島(同市)。坪内知佳さん(31)=福井市出身=は、ここで操業していた三つの巻き網船団を一つにまとめ、2011年に「萩大島船団丸」を設立。14年に株式会社に衣替えし、社長に就いた。
名古屋の大学で英語を学び、結婚を機に引っ越した。経営コンサルタントだった09年、大島の巻き網漁師、長岡秀洋さん(58)と出会い「このままだと漁師の仕事はなくなる。何とかしてほしい」と頼まれた。漁業は素人だったが、悩んだ末に依頼を引き受けた。
大島の漁獲量は10年で約4分の1に減っていた。売り上げ増には魚に付加価値を付ける必要があった。船上でサバやアジの血抜きをし箱に詰めて、そのまま都市部の飲食店に直送する「鮮魚BOX」ビジネスを提案し実践した。
■ ■ ■
課題は顧客開拓だった。関西の飲食店に飛び込み営業をかけた。お客としてカウンターに座り、食事の最中に「実は私…」と切り出した。小口注文システムを説明し、漁業を通して島を盛り上げたいという思いも伝えた。料理長の多くは賛同し、顧客は100軒を超えた。「顧客の声を聞くのは私だけではダメ」。漁師にも営業や注文の受け付けを任せた。
仕事は煩雑になった。「魚を取る人間が一番偉い」という感覚の漁師からは「よそ者が何も知らんで」と疎まれたが「50年先を見据えた漁業はこの形しかない」と譲らなかった。漁師が数を適当に箱詰めしたときは「いい大人が数も数えられんのか」、冷蔵便と冷凍便を間違えて出荷したときは「ふざけんな」と怒鳴りつけた。「私が男だったら、殴り合いで終わっていたかも。でも仕事への思いは男女関係ない」と話す。
長岡さんは「クレームが自分の耳に直接入ってくるようになった。箱にスポンジを詰め、魚を傷つけないように出荷するなど、魚を商品として扱うようになった」。実績を重ねるうちに、漁師の意識は変わっていった。
■ ■ ■
坪内さんは現在、小学4年の息子を持つシングルマザーだ。講演やビジネスモデルの全国展開で月に半分は自宅を空けるが、同じシングルマザーを会社の事務員として雇い、自宅で一緒に住むなどして家事や育児を分担してきた。
「誰かが勉強会に行きたいと言えば、1人の親が家に残ればいい。近所のおばちゃんがくれたタマネギやみそを1人が調理し、みんなで食べればいい。助け合いの精神が残る地方だからこそ、少しの工夫で子育て中の女性も生き生き働けるはず」と話す。
取れた魚を地元の市場に卸し、再び買い戻して顧客に売ることもある。「自分の会社が独り勝ちしても意味がない。目的はあくまで地域を衰退させないこと。いずれは古里福井で6次化モデルを展開することも考えていきたい」
やめていく漁師もいたが、Iターンを含め10人以上の若者が集まってきた。香川県出身の小西貴弘さん(29)は「僕が望む漁業の道を切り開いてくれた」。坪内さんの取り組みは若者の共感を呼んでいる。
国家戦略特区への獣医学部新設に関する学校法人「加計学園」について問題は全くないと言っている人達もいるが、問題がないのであればなぜ 全てをオープンに出来ないのか理解できない。なぜ、全てをオープンに出来ないのか、理由を知りたい。何か不都合な事があるのか?
愛媛県今治市の担当者らが2015年4月に首相官邸を訪問した際、当時の柳瀬唯夫・首相秘書官が面会し、学校法人「加計学園」の幹部が同席していたことが関係者の話で明らかになった。加計学園による獣医学部新設。長年、実現しなかった計画が動き出したのは、この面会の後だった。
県と今治市は07年11月~14年11月、小泉政権で始まった構造改革特区での獣医学部新設を計15回提案したが、拒まれ続けた。今治市の担当者が「獣医師養成系大学の設置に関する協議」のために上京したのは翌15年4月2日のことだ。
このとき首相官邸を訪問したことは、今治市が開示請求に応じて公開した出張記録で明らかになった。
記録によると、市の企画課長らは当初予定していた特区担当の内閣府に加え、「急きょ決まった」として首相官邸を訪問。経緯を知る関係者によると、この際に課長らと面会したのは当時の柳瀬・首相秘書官で、加計学園の事務局長も同席していた。
訪問から2カ月後の15年6月、県と今治市は「国家戦略特区」での獣医学部の新設を提案した。第2次安倍政権になってできた新たな制度だ。
提案の翌日には特区ワーキンググループ(WG)のヒアリングが開かれ、県や市の幹部が出席。今治市は翌16年1月に特区に指定され、今年1月に加計学園が事業者として認められた。
一方、政府は今治市の官邸訪問やWGの情報公開に消極的な姿勢を見せる。
官邸訪問は関係書類が「廃棄」されたとし、「訪問先を確認することは困難」と国会で答弁。柳瀬氏も、今治市職員らとの面会の有無を尋ねられると、「記憶する限りは会っていない」と繰り返した。
WGには加計学園が運営する千葉科学大の吉川泰弘教授らが同席していたが、内閣府が公表した議事要旨には吉川氏の名前や発言が載っていないことが明らかになっている。
首相は7月24日の衆院予算委員会の閉会中審査で、加計学園による獣医学部新設の計画を知った時期について、「今年1月20日」だと明言している。学部新設の事業者を加計学園とすることが正式決定した日だ。しかし、15年4月の段階で加計学園幹部が首相官邸を訪れ、首相秘書官と面会した事実が明らかになったことで、首相の答弁に対する疑念が深まった。
「政府が公開した国家戦略特区ワーキンググループ(WG、八田達夫座長)の議事要旨に学校法人・加計(かけ)学園の幹部らの発言が記載されなかった問題をめぐり、菅義偉官房長官は8日午前の記者会見で、『ルールに基づき行っている』と述べ、問題はないとの認識を示した。」
「ルールに基づいている」に基づいているのは確かなのであろう。しかし、国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨のルールに透明性の問題が
あると疑われるのに、ルールを改正しないと言うのは誠実さに欠けるし、透明性の点から判断すると、あえて抜け穴を残しておいたとも考えられる。
後悔したくない団体や人物は説明補助者として呼べば問題ない。そして発言に対して個々がどのように考え、そして忖度しても圧力でも、公式な発言でも
ないと終わらせる事が出来る。実にトリッキーなシステムである。
説明補助者は、参加者として扱っていない。議事要旨に記載する公式な発言を認めるということはしていない」から判断して、説明補助者を招く事
自体、必要ないと思う。記録にも残らない、公式な発言としても認識されない人物を招き入れないとするべきだったと思う。
悪法でも法は法と言えば、それは正しい。ただ、悪法は改正されなければならないと思う。そして、悪法と気付いたのであれば、改正するべきだと思う。
政府が公開した国家戦略特区ワーキンググループ(WG、八田達夫座長)の議事要旨に学校法人・加計(かけ)学園の幹部らの発言が記載されなかった問題をめぐり、菅義偉官房長官は8日午前の記者会見で、「ルールに基づき行っている」と述べ、問題はないとの認識を示した。
また、菅氏は、国家戦略特区への獣医学部新設の提案者は愛媛県今治市であることを念頭に、2015年6月にWGが行った今治市などに対するヒアリングで、「加計学園は共同提案者ではなく、(説明)補助者だった」と指摘。議事要旨に学園幹部らの発言を記載する必要はないとの考えを示した。
八田氏も7日の記者会見で、議事要旨の取り扱いについて説明。「説明補助者は、参加者として扱っていない。議事要旨に記載する公式な発言を認めるということはしていない」と述べ、議事要旨に学園幹部らの発言を記載しなかったのは「通常の取り扱い」だとした。ただ、WGの運営要領には、議事要旨や議事録の取り扱いルールは明記されていないという。
「林大臣は、獣医学部新設で政府が示した4条件を満たすか検証することは法律に定められていないとして、大学設置の認可について審議会の判断に沿って決める考えを示しました。」
もっともらしく聞こえるけど、それでは「4条件」の意味や必要性はなんだったのか?政府又は文科省の気まぐれ?明確でわかりやすい説明がなければ、
納得できない。
「加計学園の新たな獣医学部の設置認可については、今月下旬にも文科省の審議会が結論を示し、林大臣が最終決定をします。」
これまでは茶番、こらからは、新しい茶番。政府は時間と税金の無駄の騒動を起こし、最後は、新しく就任した林大臣が決める。
早く幕引きをして終わらせようと言う事に思える。後は、国民がどのように幕引きを評価するのかと言う事だろう。
加計学園の獣医学部新設を巡り、林芳正文部科学大臣は、いわゆる4条件を検証せずに認可の判断をする考えを示しました。
林芳正文部科学大臣:「しっかりと専門家に審査して頂いたうえで、出てきた答申を最大限尊重するということが私のやるべきことだというふうに思っております」
林大臣は、獣医学部新設で政府が示した4条件を満たすか検証することは法律に定められていないとして、大学設置の認可について審議会の判断に沿って決める考えを示しました。加計学園の新たな獣医学部の設置認可については、今月下旬にも文科省の審議会が結論を示し、林大臣が最終決定をします。
原則に基づいており、透明性は確保されていると反論した。
獣医学部新設計画をめぐり、政府の国家戦略特区ワーキンググループ座長の八田達夫大阪大学名誉教授は7日、記者会見し、2015年6月にワーキンググループが行ったヒアリングに、学校法人「加計学園」の関係者が出席していたことを認めた。
議事要旨には記載されておらず、民進党などは「加計隠し」と批判している。
これについて、八田座長は、ヒアリングは提案主体の愛媛県と今治市を対象に行い、加計学園関係者は、今治市が同席させた「説明補助者」という非公式な立場だったとして、八田座長は「議事録、議事要旨では、提案者の発言を採用することが原則。したがって、補助者の発言を入れていない。したがって、これは原則に基づいて行ったこと」と述べた。
八田氏は「通常、説明の補助者は参加者として扱っておらず、議事要旨に記載したり、公式な発言を認めることはない。通常の取り扱い通りだ」と述べ、加計学園を特別扱いしたものではないと強調した。
「WGについて、八田氏は7月24日の衆院予算委員会で『議事を公開している。一般の政策決定よりはるかに透明度の高いプロセスだ』と強調していた。コメントでは議事要旨に残さなかった理由を『今治市が説明補助のため同席させた。説明補助者は参加者と扱われず、公式な発言も認めていない』としている。」
八田達夫・大阪大名誉教授がどのような人物か知らないが、「一般の政策決定よりはるかに透明度の高いプロセス」と言うのが事実であれば、一般の
政策決定はもっとブラックボックスで透明性がないと考えられると思う。
「説明補助者は参加者と扱われず、公式な発言も認めていない」から出席者の名前も発言も記録に残らないのは透明性が高いとは考えられないし、
検証や公平性から考えればおかしいと思う。ただ、これが普通であるのなら、政府の国家戦略特区ワーキンググループ(WG)は透明度は低いし、
一般の政策決定はもっと隠ぺい体質があると言う事だろう。公平性であるように見せかけたダミー戦法とでも言うのだろうか?
政府の国家戦略特区ワーキンググループ(WG)が平成27年6月、獣医学部の新設を提案した愛媛県と同県今治市にヒアリングした際、学校法人「加計学園」(岡山市)の関係者3人が「説明補助者」として同席していたにもかかわらず、公開された議事要旨には記録がなかったことが6日、分かった。WGで座長を務める八田達夫・大阪大名誉教授が、政府が設けた特区のホームページにコメントを掲載し明らかにした。
WGについて、八田氏は7月24日の衆院予算委員会で「議事を公開している。一般の政策決定よりはるかに透明度の高いプロセスだ」と強調していた。コメントでは議事要旨に残さなかった理由を「今治市が説明補助のため同席させた。説明補助者は参加者と扱われず、公式な発言も認めていない」としている。
ヒアリングは27年6月5日に東京都内で開かれ、WGの委員4人や愛媛県や今治市の担当者らが出席した。
昔、大学で心理学の授業を取った事があるが、洗脳と言うか、特定の組織の価値観を受け入れさせる時には、飴とムチとか、人格否定から
始めると効果的だと書いていた実験の記事を読んだことがある。
製薬会社・ゼリア新薬工業がそのような方法を理解し、望んでいたのか、又は、了承していたのか知らないが、程度の違いはあるが、苦痛、ストレス、
辛い経験のリスクはあるが、効果があるのは確かだと思う。
それが会社の方針であるのなら、その会社に入社したいと思う学生は覚悟を決めるべきだと思う。記事になった以上、多くの学生や就職活動中の学生の
親は調べれば製薬会社・ゼリア新薬工業に関する問題を知る事が出来る。方針に学生、又は、親が嫌であれば、面接を受ける必要はないと思う。
行政が介入するのかはよく分からないが、個々が事故責任として記事を知った上で面接を受けるかを判断すれば良いと思う。耐えられる人もいれば、
耐えられない人もいる。自身がない人はゼリア新薬工業を避ければよい。ゼリア新薬工業だけでなく、個々に合わない体質の会社は存在すると思う。
だから、学生は給料や知名度だけでなく自分の生き方や優先順位を考えた方が良いと思う。良く知らないから「隣の芝生は青く見える」的な事は
この世の中たくさんあると思う。
製薬会社・ゼリア新薬工業に勤めていた男性Aさん(当時22歳)が、新入社員研修で「過去のいじめ体験」を告白させられ「吃音」を指摘された直後の2013年5月に自死し、「業務上の死亡だった」として2015年に労災認定を受けた。【BuzzFeed Japan / 渡辺一樹】
Aさんの両親は8月8日、ゼリア新薬と研修を請け負った会社、その講師を相手どって、安全配慮義務違反や不法行為に基づく損害賠償、約1億円を求める訴訟を東京地裁に起こした。千葉県在住の父親(59歳)と代理人の玉木一成弁護士が厚生労働省で記者会見し、明らかにした。
原告側によると、Aさんが亡くなるまでの経緯は次のようなものだ。
Aさんは早稲田大学を2013年3月に卒業後、4月からゼリア新薬工業で働き始めた。新入社員研修は4月1日から始まり、8月9日まで続くはずだった。
この間、Aさんは会社の指定した宿泊施設に缶詰状態だったが、5月18日に異常行動があったとして帰宅を命じられた。そして、その途中、東京都新宿区内で自死した。
何が起きていたのか。
中央労基署の認定によると、労基署が注目したのは、4月10日~12日の3日間、ビジネスグランドワークス社が請け負って実施した「意識行動改革研修」。その中で、Aさんの「吃音」や「過去のいじめ」が話題になった。講師から過去の悩みを吐露するよう強く求められた上で、Aさんはこうした話をさせられていたという。
Aさんは、研修報告書に、次のように書き残していた。
「吃音ばかりか、昔にいじめを受けていたことまで悟られていたことを知った時のショックはうまく言葉に表すことができません」
「しかもそれを一番知られたくなかった同期の人々にまで知られてしまったのですから、ショックは数倍増しでした。頭が真っ白になってその後何をどう返答したのか覚えていません」
「涙が出そうになりました」
一方、研修の講師は、Aさんの報告書に赤字で次のようなコメントを残している。
「何バカな事を考えているの」「いつまで天狗やっている」「目を覚ませ」
どのような研修だったのか。
原告たちの聞き取りに対し、ゼリア新薬の新人研修担当者は、「自分も受講したことがある」として、次のように供述したという。
「軍隊みたいなことをさせる研修だなと感じました」
「いつも大きな声を出す必要があり、機敏な動きを要求され、指導員が優しくない」
「指導員は終始きつい口調」「大きな声で命令口調だということです」
「バカヤローといった発言も多少はあった」
「最終的には感極まって涙を流す受講者も出るような研修」
「研修会場はある種異様な空間でした」
「個人的にはもう受けたくない」
「途中で体調不良者が出ることもあります」
中央労基署は、このビジネスグランドワークス社の実施した「意識行動改革研修」の中で「相当強い心理的負荷があった」と認め、それが原因でAさんは統合失調症を発症して、自死に至ったと結論付けた。
なお、ビジネスグランドワークス社の研修は3日間だけだったが、それ以外の研修期間中、土日に帰るにも外泊許可が必要だった。会社が、他の研修生たちに面談した結果として、「私も当時は3時間しか寝られなかった」という告白があったという。
Aさんは入社後、自宅にゆっくり帰ってきたのは、ゴールデンウィークの期間中だけだったという。玉木弁護士は「宿泊施設にほぼ拘束され、6時間の睡眠も確保できないような長時間研修を受けていた」と指摘する。
「やっとここまで来られた」
記者会見した父親(59歳)は「亡くなってから約4年、やっとここまで来られたという実感です」と、話を切り出した。
「息子は缶詰で研修を受けさせられ、ほぼ自宅には帰ってきていませんでした。ですから、事故が起きたときには、家族は全く事情がわかりませんでした」
家族は最初、もしかしたら、Aさんが会社に迷惑をかけていたのではないかと不安も感じていた。しかし……。
「いろいろ調べると、実態が見えてきました。たとえば私たちは、息子が毎日書いていた研修日誌を亡くなった後、研修のために泊まっていた部屋でたまたま発見しました。この研修日誌は、あやうく会社側に回収されるところでした。これによって徐々にどういうことが起きていたかわかりました」
「もうひとつの証拠が、息子の携帯です。息子はLINEで、学生時代の友達や同期にいろんなことを詳細に書いていました。LINEで時間もわかるので、深夜や早朝に何かをしていたことがわかる。それを追いかけていって、いろんなことがわかってきたんです」
労災認定の最大のポイントとなったのが、Aさんが書いていた研修報告書だった。
父親はこう語る。
「報告書は、当時の人事部長宛てに出されたもので、複写用紙で書かれていて、複写の2枚目なんです。これが見つかったからこそ、労災申請に至ったんですが……」
この報告書(写し)は、息子の自室を整理する中で、本棚の中に挟んであるのをたまたま発見したのだという。
「これまで事実を知りたいということで、会社と交渉してきました。しかし、この原本は、会社にあるはずなのにいまだに出てきていません」
家族の疑問
家族が疑問視するのはAさんの「吃音」や「いじめ」がなぜ研修で話題にのぼったのかだ。
父親を含め家族は「生まれて22年付き合っていて、吃音なんて、一切思ったことがなかった」という。「妻も娘も幼少時からピアノをやっていて、絶対音感があるので、絶対わかる」「いじめも聞いたことがない」と父親は断言する。
父親によると、Aさんは文学部出身だったが、空手の有段者。筋トレが趣味で、自室にはバーベルやプロテインが置いてあったという。
会社側はAさんの側に問題があったのではないかと疑問視してきたという。父親は、これは「Aさんの弱さ」から起きた事件ではないのだと、力を込めて反論していた。
Aさんは、社交的で非常に友人が多いタイプだった。亡くなった友だちが、6月8日に追悼文集を作ってくれたという。
「どれだけ皆さんから愛されていたか、その証拠として持ってきました」
父親はそう語り、誇らしげに文集を掲げた。
会社側は……
一方、ビジネスグランドワークスの宮崎雅吉代表は、BuzzFeed Newsの取材に次のように回答した。
「研修内容は問題がないものでした。労基署からは事情聴取がなく、労災認定は事実誤認です。当社の研修が問題なく終了した後、ゼリア新薬で実施した研修中に不幸があったと認識しています」
研修は3日間の日程で、4月10日が朝9時から夜9時まで、4月11日は朝6時から夜9時まで、4月12日は朝6時からで、午後4時に解散した。
宮崎代表は「いつまで天狗やっている」「バカヤロー」等の言葉はあったと認めたが、それは「本人に気付いてもらうため」だと説明。研修中に泣き出す人もいるという点については、「審査暗記したものを時間内に発表する審査があり、その審査に合格した人が感激して泣き出す人はいます」とした。
BuzzFeed Newsは、ゼリア新薬工業にも取材を申し込んでいる。回答があれば追記する。
高学歴で安定だけを求める人材に何が期待できるのか?使えない上司や幹部を組織は取り除く事が出来るのか?取り除かれる人達も全くの馬鹿では ない。抵抗したり、妨害したりするはず。スムーズな改革や組織の整理が出来るかが課題だと思う。より良い方法はあるかもしれないが、誰もが 納得する方法はほとんどないと思う。
金融庁の森信親長官(60)が毎日新聞のインタビューに応じ、経営環境が悪化している地方銀行について、「このまま人口減少が進むと(金融サービスが)供給過多になり、放っておいても県内の3行が2行に、2行が1行に減る」と指摘し、経営体力のあるうちに持続可能な経営モデルへの転換を急ぐよう求めた。地銀再編については「強くなり、より良いサービスを提供できるなら悪くはない」と述べ、有効な選択肢の一つになるとの認識を示した。
7月で省庁トップでは異例の3年目に入った森長官は、金融機関の企業統治改革や、金融商品の手数料開示などを巡る積極的な発言で知られ、業界に強い影響力を持つ。監督官庁トップが銀行数の減少に言及するのは異例で、地銀に対し、強い危機感を持つよう促した形だ。
森長官は、超低金利や人口減少で、「地銀の経営は、難しくなっている。単に担保や保証のある企業に貸すだけではもうからない」と警告。適切な助言で取引先の成長を後押しし、新たな資金需要を掘り起こす努力を銀行に求めた。
地銀の再編については、経営強化の有効な選択肢との見方を示す一方で、「統合して地域で独占的な利益を上げて、地元の顧客から高い金利を取るような統合では意味がない」とも述べ、資産規模を増やすだけの安易な統合はすべきではないとくぎを刺した。
また、過剰融資が問題になっている銀行の個人向けカードローンについて、「業界が自主的に(改善に)取り組んでいるが、それが十分でなければ、放置するわけにはいかない」と問題意識を表明。貸金業者に課せられた融資の上限(総量規制)から銀行が除外されていることを踏まえ、「返済余力を判断した適切な資金供給ができないなら、強い規制も必要だ」と述べ、今後の動向次第で制度を見直す可能性に言及した。【小原擁】
政府の国家戦略特区ワーキンググループ(WG、八田達夫座長)が2015年6月、獣医学部の新設提案について愛媛県と同県今治市からヒアリングした際、内閣府が公表した議事要旨の出席者に記載のない学校法人・加計(かけ)学園の幹部が同席していた。学園の教員確保の見通しをめぐる質疑もあったというが、議事要旨に記載はない。政府はWGの議事内容を「すべて公開し、透明性が高い」と説明するが、公表資料では十分に検証できない状態だ。
ヒアリングには、加計学園系列の千葉科学大の吉川泰弘教授(現・加計学園新学部設置準備室長)らが出席した。政府側、提案者側双方の出席者が朝日新聞の取材に認めた。
内閣府が今年3月になってホームページで公表した7ページの議事要旨には、ヒアリングの出席者として八田座長ら計12人が記載され、提案者側は愛媛県の地域振興局長、今治市の企画課長ら3人。吉川氏らの名前はない。
複数の出席者によると、吉川氏はヒアリングの場で、既存の大学の獣医学教育では、獣医師の新たなニーズを満たしていないなどと述べたという。政府側の委員からは教員確保の見通しなどの質問があり、吉川氏が答えたという。
特区WGのヒアリングは非公開で、議事内容はまず、会合後速やかに作られる「議事要旨」で公表される。議事要旨は概要版で、すべてのやりとりが記載されたものではない。議事の詳細が分かる「議事録」の公表はヒアリングから4年後と決められている。
自業自得と運が悪いが重なった結果だと思う。
学校法人「森友学園」(大阪市)の前理事長、籠池泰典容疑者(64)が2015年、小学校の設置を認可する大阪府に財務状況を良く見せるため、約4億円の寄付を受けたように偽装していたことが分かった。学園関係者によると、「大口寄付者」とした3社の入金は実際にはなく、別のコンサルタント会社の名義で約4億円が入金されていた。一時的に資金があるかのように装う「見せ金」だった疑いがあり、大阪地検特捜部も資金の流れを調べている。
学園は14年10月、府私立学校審議会(私学審)に小学校の設置認可を申請した。建設費については金融機関の融資を受けず、寄付金などでまかなうと説明。既に寄付した約350人の名簿(計約1700万円)のほか、2社の役員がそれぞれ2億円と7000万円を寄付するという「寄付申込書」も提出した。
12月に開かれた私学審の定例会では、学園の財務に懸念があるとして認可を見送ったが、15年1月の臨時会では寄付金の状況などを報告させるとの条件で「認可適当」とした。
関係者によると、府は3月下旬の定例会を前に寄付状況を確認。籠池容疑者は2月末で約4億円の残高があるとした銀行口座の記録を示し、「2社の大口寄付の他、約1億円の寄付もあった。複数ある寄付用の口座を一つにまとめた」と説明した。
しかし、2億円を寄付したとされる府内の会社社長は毎日新聞の取材に寄付を否定。社長によると、府議を通じて知り合いになった籠池容疑者が3年前に会社を訪れ、「2億円を寄付する」という書面への署名を求められた。「寄付がどれくらいあるのかという数字合わせで、悪用はしない」と迫られ、社長は判を押したが「1円も寄付していない」と証言した。
学園関係者によると、他の2件の「大口寄付」も入金が確認できないという。
一方、コンサルタント会社から学園口座への4億円の入金は15年2月27日付で、その後、出金された。会社は登記簿上、大阪市内のマンションが所在地だが、現在は既に転居している。学園関係者は「実態のないペーパー会社」とみている。一連の疑惑発覚後、学園は今年3月に認可申請を取り下げた。
特捜部は、籠池容疑者が財務状況を粉飾し、小学校の認可を得ようとしたとみて関係者の聴取を進めている。【三上健太郎、岡村崇】
63億円は大きな額だ!
積水ハウスは2日、分譲マンションの建設用地として購入した東京都内の土地代金の大半に当たる63億円を支払ったのに、所有権移転の登記ができなかったと発表した。同社は、書類を偽造し他人の土地を無断で売却する犯罪に巻き込まれた可能性が高いとして、警察に被害届を提出した。
積水ハウスが契約している不動産業者が土地所有者から購入し、直ちに積水ハウスに転売する形式の取引。積水ハウスは6月1日に63億円を契約業者に支払い、法務局に所有権移転の登記を申請した。
しかし所有者側が提出した書類に偽造が見つかったため、同月9日に登記申請が拒否されたという。
積水ハウスは「警察の捜査に全面協力するとともに、支払い済みの代金の回収手続きに注力する」とコメントしているが、契約業者から購入代金の支払いを受けた所有者側とは連絡が取れなくなっているという。
秋田県大館市の病院で会計窓口を担当していた女性が、9年間にわたり診療費あわせて1億円余りを着服していたことが分かりました。
着服が発覚したのは秋田県の大館市立扇田病院の会計業務委託先に勤務していた40代の女性です。
病院によりますと、この女性は扇田病院の窓口を担当していた2008年3月から今年4月まで、およそ9年間にわたり患者の領収書の控えを隠し、レジの入力を改ざんするなどして、診療費の自己負担分の一部を着服していたということです。着服は9年間で3万回、総額1億1700万円余りに上っています。女性は病院の調べに対して着服を認めています。
病院は今後、女性を刑事告訴するかどうか検討しています。
学校法人「加計(かけ)学園」(岡山市)の獣医学部新設計画をめぐる国会の閉会中審査などで、獣医師の地域偏在という本質的な問題が浮き彫りになってきた。誘致を進めた愛媛県の加戸守行前知事は国会で獣医師不足の苦衷(くちゅう)を明かしたが、和歌山県にとっても人ごとではなく、鳥インフルエンザや口蹄(こうてい)疫といった伝染病対策に不可欠な公務員の獣医師には欠員も出ている状況だ。
「大事なことは獣医師が足りているのかどうかということだが、『お友達』に口をきいたとか、そういうことばかりが問題になっている」。安倍晋三首相が出席した参議院予算委員会の閉会中審査と同じ25日に開かれた定例会見で、仁坂吉伸知事は、加計学園の一連の問題で、安倍首相と加計学園の理事長との関係性ばかりが報道でクローズアップされていることを嘆いた。
閉会中審査では加戸前知事が愛媛県の獣医師不足の現状を繰り返し説明。6月の産経新聞のインタビューでも「県庁への志願者が不足しているゆえに公務員獣医師を採用できない。そのため、鳥インフルエンザや狂牛病やらで獣医師が手いっぱいなのに人手が足りない」などと語っていた。
しかし、獣医師不足に悩んでいるのは和歌山県も同様で、県に所属している獣医師は現在、定員割れをしている状態だ。仁坂知事は「県でも本当は獣医師をもっと雇いたいのに、獣医師がいない。このような状態を正当化する人たちのセンスの方がおかしい」と訴えた。
県畜産課によると、27、28年度の獣医師採用ではいずれも1回目の募集で予定人員に達さなかったため、追加募集をかけている。28年度には確保した獣医師の中から辞退者が出たという。このため、県は新たな手当を上乗せするなど、獣医師確保のために腐心している。
県の場合、採用された獣医師は、本庁のほか家畜保健衛生所や畜産試験場などに配属される。鳥インフルエンザや口蹄疫といった伝染病対策も重要な職務の一つで、23年に紀の川市の養鶏場で鳥インフルエンザが発生した際には、所属する獣医師たちが不眠不休で消毒や防疫措置、周辺の養鶏場の検査などにあたったという。
同課の担当者は「新たな伝染病の予防対策など業務はどんどん増えており、現在の人員で対処していくのはかなり厳しい」と指摘。その上で、「獣医師志望の学生はほとんどがペットなどの診療を目指すため、公務員の獣医師の志願者は他地域との奪い合いになってしまう。獣医師の偏在は、地方にとって共通の問題だ」と語った。
東洋ゴム工業(兵庫県伊丹市)の免震装置ゴムのデータ改竄(かいざん)事件で、大阪地検特捜部は27日、不正競争防止法違反(虚偽表示)の罪で、製造元で子会社の東洋ゴム化工品(東京)を起訴した。東洋ゴム工業の山本卓司前社長(60)ら書類送検された18人については刑事責任を問えないと判断し、不起訴処分とした。
18人の送検容疑は平成26年9月上旬、大阪府枚方市の枚方寝屋川消防組合の新庁舎建設工事で、免震ゴムが国土交通省の大臣認定に合格したとする虚偽の「性能検査成績書」を作成し、交付したとしていた。両罰規定に基づき、法人としての東洋ゴム工業と東洋ゴム化工品も送検されていた。
東洋ゴム工業は「子会社が起訴されたことを大変重く受け止めている。免震ゴムの交換改修を最後まで責任を持って遂行し、引き続き信頼回復に努める」とのコメントを発表した。
仕事とか、義務とか、責任等で記載されていない事はしない、負担になる事はしないと多くの人達が思っている、又は、考えている組織では 運が悪いと起きる事。最近、つくづく思うが、答えややり方はひとつではない。問題が存在しても運が良ければ事故は起きない。
上田清司知事がどこまで踏み込んで対応するのか知らないが、組織に問題があれば簡単には変わらない。
上尾市戸崎の障害者支援施設「コスモス・アース」で送迎車に取り残された知的障害のある同市の男性(19)が熱中症とみられる症状で死亡した事故で、事故のあった13日に男性の不在に気付いた職員が複数いたことが25日、分かった。上田清司知事が定例会見で公表。事故原因について「内部の統制ミスだ」と指摘した。
県によると、25日までに職員への聞き取り調査を3回実施。13日に勤務していた15人中14人から話を聞き、複数人が男性の不在に気付いていたことが分かった。また、施設で働いている運転手4人中3人は送迎時以外も施設で生活支援員の仕事などをしていたというが、13日に担当した男性運転手(73)は送迎時以外は自宅で待機していたという。
県は、運転手が確認を怠った上、男性の不在に気付いた職員がいても確認しなかったことで事故が起こったとみている。上田知事は「所在が分からない方がいたのに追っかけをしていなかった。内部のコントロールミスだ」と指摘した。
今後、県は施設の資料をさらに調べるなどし、施設への処分や再発防止策を検討する方針だ。
後は選挙にどれくらい影響が出るかの問題だと思う。
参院予算委員会の閉会中審査で25日、安倍内閣の3閣僚が昨年8月から9月にかけて、学校法人「加計学園」の加計孝太郎理事長の訪問を相次いで受けていたことを明らかにした。3閣僚は、共産党の小池晃氏の質問に答えた。
山本有二農水相は昨年8月23日、加計氏の訪問を受けたと答弁。5~10分間会い、官僚は同席しなかったという。山本氏は加計氏から「獣医学部の話はお聞きした」と語った。
山本幸三地方創生相は昨年9月7日に加計氏の訪問を受け、「今治市に獣医学部の提案をして、やっていきたい」と言われたことを紹介。山本氏は「公正、中立にやる。最終的に公募で決める」と伝えたという。
松野博一文科相は昨年9月6日に加計氏の訪問を受けたが、学部新設の話は出なかったという。
質問した小池氏は加計氏の面会について、「なぜ次々と大臣に会えるのか」と疑問を呈した。
ロジカルな説明とは思えない。支持率が下がってもこの程度の説明しか出来ないと言う事は、クロと判断しても間違いではないかも?
白黒をはっきりする事が出来なくても、白と明確に説明できない状況にあるのは確かだと思う。
学校法人「加計(かけ)学園」の獣医学部新設問題について、安倍晋三首相や側近が24日、衆院予算委員会で答弁した。学部新設への首相官邸の関与が焦点になる中、キーパーソンは「記憶がない」などと繰り返し主張。裏付けについても「記録がない」といった答弁に終始し、あいまいさは否めない。
獣医学部の新設について、和泉洋人・首相補佐官から「総理は言えないから私が言う」と言われたと証言した前川喜平・前文部科学事務次官。この日も「私の記録と記憶に基づいて」と前置きし、和泉氏と面会した日時、当時のやりとりを詳しく語った。
一方、和泉氏は前川氏と会ったことは認めたが、「記録がないため、どういった意図であったかは確認できない」と答弁。前川氏が証言した発言については、「こんな極端な話をすれば、私も記憶に残っています。そういった記憶はまったく持っておりません。したがって言っておりません」と否定した。
さらに、野党議員から「言わなかったのか、言った記憶がないのか」と確認を求められた和泉氏は、「記憶に残っていないので、私の記憶に従って答えるしかないわけだが、言わなかったと思う」と答えた。
しかし、当初の予算よりも遥かに膨れ上がった新国立競技場のプロジェクトに関わった文科省及び国の関連組織にも責任はあると思う。 その上、責任はうやむやにして、適当にごまかした。
「この問題をめぐっては、東京労働局が新国立競技場の事業所にすでに立ち入り調査をしていて、自殺した男性の会社は『真摯に受け止め、二度とないようにしていきたい』としています。」
綺麗事を言っていたら、スケジュール通りにはいかないであろう。それでも、規則を守る事を優先させるのであれば、妥協できる部分は妥協するべきだと 思う。優先順を明確にして進行させないと現場や関係者は混乱するし、手違いや発注ミスが起きる。
新国立競技場の建設現場で働いていた男性が自殺した問題で、同じ現場で働いていた建設作業員が取材に応じ、現場の過酷な状況を初めて証言しました。
「そこ(自殺)まで本当に追い詰められてしまったんだろうなあと」(新国立競技場の建設現場で働いていた作業員)
こう話すのは、新国立競技場の建設現場で働いていた作業員の男性です。同じ現場では、東京都内の建設会社の23歳の男性社員が今年3月に失踪した後、自殺しました。
この社員が失踪する直前の月の残業時間は200時間を超えていましたが、取材に応じた作業員の男性は、新国立競技場の建設現場が工期に追われ、混乱している実態を次のように証言しました。
「現場の動きがどんどんどんどん変わりまして、朝決まっていたことが何時間かすると突然変わって、それに対応するために、いろいろなことが発生して。尋常じゃない。(自殺した男性以外も)突然、来なくなっている人いました。『限界ですよ』と言っていたら、2~3日後くらいに、そういえば来ないと」(新国立競技場の建設現場で働いていた作業員)
工事に携わる人全体が「ギリギリの状態」だったといいます。
「みんな必死です。使命感ですよね、オリンピック。結構ギリギリのところでやっていましたし、ベテランの人でもいっぱいいっぱいになりながらやってましたので、もう、みんながみんな同じような状況で、いろいろ感覚がまひしたと思う」(新国立競技場の建設現場で働いていた作業員)
この問題をめぐっては、東京労働局が新国立競技場の事業所にすでに立ち入り調査をしていて、自殺した男性の会社は「真摯に受け止め、二度とないようにしていきたい」としています。
もしそうなら恐ろしいな!しかし、人の心や考えを確実に見通すことは出来ない。結局、基準をどう決めるかであろう。 安全と人材選びの間で妥協点を見つけるしかない。無料ほど高い物はない事もある。皆が善人であれば良いが、現実には 無理。
結局、人間関係のコミュニケーションを避けると、相手の人物像を見抜く事が難しくなる。楽な選択肢もあるが、短期的に楽な選択肢が 長期的に良い結果に結びつかないケースもあるので、いろいろと考える必要があると思う。
女子児童2人にわいせつな行為をしたとして逮捕された男は大阪で警察署に地域の要望を伝える協議会の会長を務めていて、小学生の登下校を見守る活動もしていました。
展示用の白バイにまたがる男。23日逮捕された自営業の内山義弘容疑者(57)です。今年3月、自分が経営する店の倉庫で当時10歳と11歳だった小学校の女子児童2人の胸などを触ったとして、強制わいせつの疑いがもたれています。内山容疑者は地域の要望を警察署に伝える協議会の会長を務め、子どもたちの登下校の見守り活動にも参加していたということです。
「『おはよう』っていう感じでハイタッチしたり、『きょう遠足やなー』とか心こまやかに」(近所の住民)
さらに内山容疑者は以前から店で子どもたちにお菓子を配ったり、宿題をみたりしていたということです。
「(店の)前を通りかかったときにワイワイしているのは見たことありましたけど。雑談の延長でひと息ついているのかなって、子どもたちが。比較的女の子のほうが多かったような印象ですけど」(近所の住民)
取り調べに対し容疑を認めているという内山容疑者。警察が内山容疑者の自宅から押収したパソコンにはわいせつな画像が保存されていたということで、警察がさらに詳しく調べています。
毎日放送
小学生の女の子2人にわいせつな行為をした疑いで、警察署協議会会長の男が逮捕されました。
強制わいせつの疑いで逮捕されたのは、大阪府警天王寺警察署協議会会長の内山義弘容疑者(57)で、ことし3月、自宅の倉庫で当時11歳と10歳の女の子の胸を触った疑いなどが持たれています。
警察署協議会は地域住民の意見を警察に伝える役割で、内山容疑者は犯行当時はメンバーで、先月から会長に就任していました。
警察によると内山容疑者は登下校の見守りのボランティアをしていたほか、地域の女の子を集めて宿題を教えていたということです。
内山容疑者は容疑を認めています。
キャンパスでの教諭と女子学生の不倫愛。今どき、そんなシチュエーションは珍しくないかもしれないが、関西のある国公立大の40代の男性准教授の場合は明らかに“行き過ぎ”があった。最初はメールのやり取り。そして食事やデート。妻子がいることを隠して教え子の女子学生と交際を続け、関係を持ってからは裸の写真を要求したり、研究室でも行為に及んだり。こうした行動は大学側の知るところとなり、「学内の秩序や風紀を乱した」として懲戒解雇処分が下された。ところが男性は「関係は合意に基づくもの。処分は懲戒権の濫用(らんよう)で無効」などと大学側を相手取り、地位確認請求訴訟を起こした。裁判を通じて明らかになった“禁断の行為”の数々。司法は男性の言い分をどう判断したか。
授業で「○○ちゃんと合体」
問題が発覚したきっかけは、平成26年11月、大学内の「相談ポスト」に、「授業中に(准教授の)不適切な発言があった」とする匿名のカードが投じられたことだ。
大学が調査したところ、准教授の男性は、(1)親しい女子学生をファーストネームや「ちゃん」付けで呼んでいた(2)出欠確認をする際、学生の髪形や服装についてコメントをしていた(3)頭や肩に触れられた学生がいた-などの不適切な言動が確認された。
男性の専門は社会保障や社会福祉など。授業では、男女の性について説明する際、こんな発言をしていたことも分かった。
「僕の精子と○○ちゃん(学生の名前)の卵子が合体して子供が生まれたとしよう」
「僕が夫で○○ちゃんが妻だったら」
大学がこれらの言動について男性に確認したところ認めたため、ハラスメント行為と認定した。
2人きりの食事から
だが、ハラスメント行為はこれだけではなかった。調査が進むにつれ、男性が特定の女子学生と関係を持っていたことも分かった。
きっかけは24年5月、当時2年生だった女子学生から、講義に関する感想や質問などについてメールがあったこと。その後、2人の間でメールの交換が続いた。
7月、男性は講義終了後に学生らとの食事会を予定していたが、参加を希望したのはこの女子学生のみだった。「2人で食事をするのは気まずいでしょう。あなたが良ければ、甘いものでもどうですか」。男性がこうメールしたところ、女子学生から「甘いものが食べたいです」と返信があり、2人でケーキを食べて食事にも行った。
食事中は交際相手や結婚、恋愛、好きな異性のタイプなどについて話し合った。メールのやりとりはその後も続き、次第に「心情的なメール」に変わっていったという。
妻子の存在を隠し
一線を越えたのは翌月。男性は「(自分の)ゼミを履修する可能性のある学生には話しておかなければならないことがある」と兵庫県尼崎市のホテルに女子学生を呼び出し、行為に及んだ。このとき、学生は「避妊してほしい」と頼んだが、男性は応じなかったという。
男性には妻子がいたが、女子学生には「大切な女性がいる」とメールでほのめかした程度で、学生は男性が独身だと思っていた。後日、大学側の調査に対し、学生は「妻子があると知っていたら、(性行為は)しなかった」と話したという。
ヌード撮影、校内デート、研究室でも
男性はその後、2人でライトアップを見に出かけたり、クルージングを楽しんだりしてデートを重ねた。さらに「カメラでもビデオでも、『僕だけの宝物』がほしい」と学生の裸の写真を要求。当初はかたくなに拒んでいた学生も、次第に応じるようになったという。
大学内での“校内デート”も行っていたが、9月には学生が就職活動の相談に訪れた際、研究室でも関係を持った。
大学は処分理由を明かさず
交際は約1年4カ月に及んだ。別れた後、男性は学生の求めに応じ、裸の写真などのデータは処分したという。
大学側の調査に対し、男性は2人の交際や写真の撮影など、これまでの行為を認めており、大学への投書から約1年後に学内で開かれた「セクシュアル・ハラスメント等防止・対策委員会」で、男性の女子学生に対する不適切な行為が認定された。
これを受け大学側は28年2月、「特定の学生と性的関係をもって裸の写真等を撮影し、教育研究の場として学生が安心して指導を受けるため供与されている教員の研究室で性行為を行ったという各事実は、大学の風紀・秩序を著しく乱す重大なハラスメント行為で、在職させておくわけにいかない」などとして、准教授だった男性の懲戒解雇処分を決定した。ただ、報道発表では「個人のプライバシーにかかわる」として詳しい理由は明らかにしなかった。
こうして大学を去った男性だが、2カ月後、「処分は懲戒権を濫用し無効」などと主張し、地位確認と処分後の給与の支払いを求めて地裁に提訴。大学が非公表とした内容が、司法の場で公にされる格好となった。
「セクハラではない」
男性は大学側の調査に対する事実関係は認めた上で、こんな主張を展開した。
「学生と性的関係をもったことは極めて不適切な行動ではあるが、あくまでも両者の合意に基づくもので、他の学生の目に触れないよう、大学内の秩序を乱さないよう十分配慮していた」
「裸体の写真等の撮影も同意を得て行ったもので、そもそも労働契約とは関係のない個人の趣味・嗜好(しこう)の問題」
「各行為は学生の意に反していたものではなく、学生が修学・就労上の不利益を受けたり、環境が害されたこともなく、セクハラには該当しない」
これに対し、大学側は「仮に合意の外形的事実があったとしても、心理的圧迫か、独身と誤解させた詐術によるもので、合意があったとは評価できない」と反論。「教員という立場、妻子ある身でありながら学生と各行為をしたことは就業規則、倫理規定、セクハラ防止規定に違反するもので、教員としてあるまじき行為で許されない」とし、処分には客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められ、解雇権の濫用には当たらないとした。
地裁の判断は
争点は、処分が懲戒権の濫用に当たるか否かという一点。今年4月の地裁判決は、「(男性の行為は)学内の秩序や風紀を乱し、他の教員と学生の信頼関係や教育研究環境に悪影響を及ぼす極めて不適切なものであることは明らかで、大学の社会的信用を著しく害するもの」として、大学側の処分は妥当と判断。男性の請求を棄却した。
判決では、「大学の教員として高度の専門的学術文化及び理論を教授、研究し、学生の社会進出、学術文化の進展に寄与することを目的に教育研究活動を行うべき立場にもかかわらず、学生と各行為に及んだのは本来の目的や使命に反する」とも指摘。
男性が重ねて強調した「合意」についても、こう断じた。「それによって、他の教員と学生の信頼関係や教育研究環境に及ぼす悪影響の程度、大学の社会的信用性の毀損(きそん)の程度などがそれほど減少しないから、合意の有無は結論を左右するものではない」
自由恋愛のつもりだったのか。「合意の上で、迷惑をかけているわけではない」として学生と関係を続けた男性だったが、立場をわきまえない思慮に欠けた行為の代償は高くついたようだ。
合成写真と知っていてこのコメントをしたのか、それとも、それほど霊能力がないのか?どちらなのだろうか?写真を見て写真から何かを感じるのであれば、 合成写真に対しては何も感じないのではと思うのであるが、事実はどうなのか?
池田武央は胡散臭いやらせ心霊研究家ってマジ?嘘か本物か考察! 03/27/16(しぐ☆ぴよ)
池田武央は本物それともやらせ?心霊研究家の評判と収入はいくら? 03/30/16(考察ダイアリー)
7月19日、TBS系列にて放送された「生き物にサンキュー&世界の怖い夜 合体3時間SP」。その中で紹介された心霊写真が問題視されている。【BuzzFeed Japan / 播磨谷拓巳】
ロンドンブーツの田村淳さんがMCを務める人気の心霊番組。19日放送回では、青森県に住む“イタコ”を紹介したり、霊が出るとされる廃ホテルをタレントが訪れた。
問題視されているのは番組終盤の「心霊写真」のコーナーだ。
“とある展望台を訪れたときに撮影された写真”として紹介された写真には、男性3名が写っており、その後ろには女性のような顔が写っていた。
番組はこれを霊とし、心霊研究家・池田武央氏はこの場所で事故死した女性の霊と説明。この世に強い未練を残しており、すぐにお焚き上げすることを勧めた。
「合成です!」心霊写真に指摘。
しかし、放送直後、Twitter上で写真に写っている男性たちの友人らから「合成です!」「テレビの闇」など指摘する声があがった。
Twitterには元の写真も投稿されており、そこには番組にあった顔は写っていない。BuzzFeed Newsにも画像を提供してもらい、確認をしたが顔らしきものはみられなかった。
写真に写っている男性本人によれば、これは昨年5月頃に神奈川県の湘南平の展望台で撮影したもの。
男性は「写真に顔など写っていません」と心霊写真であることを否定した。また番組側から事前に使用許諾はなかったとのこと。
ほか2名の男性も「俺、(テレビに)写っているんですか?」「テレビ怖い」と話している。
TBSは回答を拒否。
BuzzFeed NewsはTBSに対し、写真の出典元や元画像と違う箇所があること、許諾の有無などの回答を求めたが、広報部は「お答えすることはない。回答は控えさせていただく」とコメントしなかった。
幼い男の子にわいせつな行為をし撮影するなどした罪に問われた元小学校の教諭の男に対し、横浜地裁は懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
元小学校の教諭・橋本顕被告(45)は、去年3月、東京・立川市にある公園のトイレ内で当時4歳の男の子にわいせつな行為をした上、腕時計型のビデオカメラで撮影するなどした罪に問われています。
19日の判決で、横浜地裁は「自己の性的欲求を満たしたいという身勝手な動機である」と指摘。その上で、「小学校教諭という職責に真っ向から反し、社会への影響は無視できない」として、懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
橋本被告は他の児童ポルノ愛好者グループとSNSを通じて知り合い、撮影した画像を交換していました。
当時の事務局幹部ら3人に対して重い処分を出すべき!簡単に処理しては同じような事が繰り返される。
一般社団法人日本新聞協会は19日、事務局の職員ら2人が平成19~24年に、協会などの会計から計約4700万円を着服していたと明らかにした。当時の事務局幹部らは事態を把握した後も、協会会長や理事会に事実関係を報告せず隠蔽していた。
協会によると、経理担当の職員が19年9月~21年2月、自身の株取引の損失を埋めるため、協会の会計から約3314万円を流用。また別の嘱託職員も20年3月~24年7月、協会が業務委託を受けている団体の会計から約1473万円を着服していたという。
当時の事務局幹部ら3人は、21年と24年にそれぞれの事案を把握。表沙汰になるのを避けるため、民事訴訟や刑事告発の手続きを取らないことを条件に返却させ、自主退職させていた。
協会は6月、国府(こうの)一郎前事務局長らが部下にパワーハラスメントをしていたと発表。今回の着服は、パワハラに関する調査の過程で判明した。国府前事務局長は職員へのパワハラで5月に辞任しており、着服の隠匿にも関与していたという。
架空発注などで自社から多額の現金をだまし取ったとして、東京地検特捜部は19日、ソニー子会社の半導体設計会社「ソニーLSIデザイン」(神奈川県厚木市)の元役員・萩原良二容疑者(58)(昨年10月に解任・懲戒解雇)ら男3人を詐欺容疑で逮捕した。
他に逮捕されたのは、いずれも同社元社員・金子浩之(51)(昨年10月に懲戒解雇)と飯泉邦夫(52)(同)の両容疑者。発表によると、3容疑者は2013年10月頃~16年2月頃、取引先に架空の業務を発注し、同社から現金1億700万円と約46万ドル(現在のレートで約5152万円)を詐取したほか、14年11月頃~15年3月頃には、取引先の業務委託料を月額1万1000ドル水増しし、計5万5000ドル(同約616万円)をだまし取った疑い。
事実と仮定して、それでは、なぜ、今回は実現可能になったのか?そこをクリアーに説明する必要があると思う。
文科省が綺麗な組織であるとは思っていない。天下り問題が部分的に証明している。ただ、文科省に問題があるから、今回のように適切な説明をしないのは おかしい。
第1次安倍晋三政権当時の平成19年2月。東京・赤坂の料亭「佐藤」で、日本獣医師会顧問で元衆院議員の北村直人は、学校法人「加計学園」(岡山市)理事長の加計孝太郎と向き合っていた。
「愛媛で獣医の大学を作りたいんですよ。ぜひ協力してくれませんか?」
加計がこう切り出すと、北村は強い口調で「なぜそんなことを言い出すんですか?」と聞き返した。
加計が「息子の鹿児島大獣医学科の入学式に行き、設備をみたら20億~30億円でできそうなんですよ」と説明すると、北村は怒気をはらんだ声でこう説いた。
「そんな動機で獣医学科を作りたいなんて、とんでもない話だ。獣医学部創設には500億円はかかりますよ。教育を金もうけに使われたらたまらない。やめた方がいい!」
さらに北村が「親しい政治家はいるんですか」と問うと、加計はこう答えた。
「強いていえば安倍首相ですが…」
北村の脳裏に、安倍への疑念が刻まれた瞬間だった。北村は今も「全ては加計学園ありきなんだ」と息巻く。
だが、愛媛県今治市に加計学園が運営する岡山理科大の獣医学部を新設する構想は、安倍と加計の親交とは全く無関係の切なる地元事情から始まっていた。
昭和50年、今治市は高等教育機関を誘致する学園都市構想を打ち出した。タオル産業の衰退などにより、人口減が続く地域を活性化させることが目的だった。松山大や東海大などの名も挙がったが、いずれも誘致には至らなかった。
加計学園の名前が浮上したのは平成17年の正月だった。今治市選出の愛媛県議、本宮勇は市内の友人宅で、小学校から高校まで同級生だった加計学園事務局長と久々に再会した。本宮はこう水を向けた。
「今治市で大学を誘致しているがどこも来てくれないんだ。お前のところの大学が来てくれないか?」
だが、事務局長は「少子化の時代に地方に大学を進出させるのは難しい」と首を縦に振らなかった。それでも本宮はあきらめず、その後も説得を続けた。事務局長はついに根負けして「人気があり、競争率の高い獣医学部だったら考えてもいいよ」と応じた。
同じ頃、知事の加戸守行は県内の公務員獣医師の不足に頭を悩ませていた。
11年の知事就任後、鳥インフルエンザなどの家畜伝染病が相次いだ。22年に口蹄(こうてい)疫が発生した際には各港で検疫態勢をとり、四国への侵入は水際で阻止したが、獣医師たちに不眠不休の対応を強いねばならなかった。
そんな中、本宮がもたらした加計学園による獣医学部新設の話は願ってもない朗報だった。加戸は「地域活性化と公務員獣医師確保ができ、一石二鳥じゃないか」と小躍りした。
加戸の大号令の下で愛媛県と今治市は獣医学部新設に向け、タッグを組んだ。目をつけたのが、元首相の小泉純一郎が肝煎りで創設した構造改革特区だった。
愛媛県と今治市は19年に構造改革特区に獣医学部新設を申請したが、あっさり却下された。農林水産省は「地域・分野に偏在はあるが、獣医師は足りている」とにべもなく、文部科学省は、歯科医師や獣医師に関する大学設置を認めないとする「15年文科省告示」を盾に聞く耳さえ持たなかった。
× × ×
愛媛県と今治市はそれでもあきらめず、毎年のように特区申請を続けた。
これに業を煮やしたのか、北村は22年春、獣医師会の権威で日大総長の酒井健夫と連れだって愛媛県庁の知事室に乗り込んだ。
「獣医学部を作るのなんかやめた方がいい。公務員獣医師の待遇をよくしたり、愛媛県出身の学生に奨学金を出したりした方が安上がりですよ」
北村がこう言うと、酒井は「奨学金をつけて東京まで学生を送ってくれたら日大で立派に育てて愛媛にお返ししますよ」と合いの手を入れた。
相手の声を聞き、急いで電話を切った。
加戸は「こっちは手当たり次第、獣医師を採用しても足りないんだ」と説明したが、2人は納得しない。酒井は「加計学園が獣医学部を作っても、どうせろくな教育はできっこないですよ」と言い放った。これにカチンときた加戸は怒りを隠さずこう迫った。
「こっちは別に加計学園でなくてもいいんだ。じゃあ、あなたのところで愛媛に第2獣医学部を作ってくれるか?」
酒井と北村は押し黙ったままだった。
× × ×
加戸が獣医学部新設にこだわったのは、獣医学部・学科が東日本8割、西日本2割と偏在しているからだ。加戸は旧文部省出身で官房長まで務めた人物だ。文科省と日大、そして獣医師会の密接な関係は十分承知しているだけに、文科省や獣医師会の対応には怒りが収まらない。
「(現在のように)定員を水増しすれば、少ない教授で安上がりな授業ができる。ドル箱じゃないか。自分たちの大学で定員を増やすのはよいが、他の大学にはやらせない。商売敵ができるとおまんまの食い上げになるからじゃないのか」
第2次安倍内閣の国家戦略特区により、ようやく風穴が開き、10年越しの悲願がかなった。にもかかわらず、獣医学部新設にからみ、あたかも不正があったかのように報じられるのは我慢できない。
「『加計学園ありき』と言われているが、愛媛県と今治市は10年以上前から『加計学園ありき』でやってきたんだ。本質の議論がなされないまま、獣医学部がおもちゃにされるのは甚だ残念だ」
文科省から流出したとされる「首相の意向」などと記された文書に関しても加戸は「安倍さんと加計学園理事長が友達だと知っていたら、直訴してでも10年前に獣医学部を作ってもらっていたよ」と一笑に付す。
「行政が歪(ゆが)められたのではない。歪められていた行政が正されたんだ」
=敬称略。肩書は当時
そう言った意味では「朝日・毎日の紙面では“存在しなかった”加戸氏証言」は驚く事ではない。
「愛媛県にとっては、12年間加計ありきだった。今さら1、2年の間で加計ありきじゃない」
事実であると仮定しても、文科省の資料を個人メモとか、怪文書が実際に文科省に存在した事実など、なぜ隠す必要があったのかが 説明されていない。加戸氏証言は運よく、説明するプロセスで良い事実であったとしか思えない。
なぜ、「愛媛県にとっては、12年間加計ありきだった。今さら1、2年の間で加計ありきじゃない」の説明が早い段階で出来なかったのか? 説明に困っている最中に、誰かが加戸氏の件を提案したようにも思える。
朝日の慰安婦問題の記事など事実を認めるまで何年かかったのか?日本人は正直?日本人は嘘を付かない?日本人は良い人?は全体的な 評価であって、全ての日本人がそのような人々ではないと思う。
衆参両院で10日に開かれた学校法人「加計学園」の獣医学部新設計画をめぐる閉会中審査の白眉は、加計学園誘致を進めた加戸守行・前愛媛県知事の証言だったのは間違いない。
「愛媛県にとっては、12年間加計ありきだった。今さら1、2年の間で加計ありきじゃない」
「10年間、我慢させられてきた岩盤規制にドリルで穴を開けていただいた。『ゆがめられてきた行政が正された』というのが正しい発言ではないか」
加戸氏はこう切々と述べ、文部省(現文部科学省)時代の部下であり、首相官邸の意向によって「行政がゆがめられた」と主張する前川喜平・前文部科学事務次官に反論した。
これまでの経緯を熟知する当事者の言葉は重く、説得力があった。テレビで国会中継を見た多くの人は、加戸氏の説明にうなずいたのではないか。
ところが、在京各紙の翌11日付朝刊を読むと、加戸氏の発言の扱いは小さかった。特に朝日新聞と毎日新聞は、閉会中審査に関して大きく紙面を割いたにもかかわらず、一般記事の中で1行も加戸氏を取り上げなかった。
まるで、自分たちの安倍晋三政権批判の筋書きに合致しない加戸氏の証言は、存在しなかったかのようである。半ば予想していたことではあったが、あまりの露骨さに恐れ入った。
国会中継を見ていない朝日と毎日の読者は、事実関係が分からないように目をふさがれたも同然である。インターネット上で常々批判される「報道しない自由」も、ここに極まれりである。
あまつさえ、毎日は第1社会面のトップ記事に「『印象操作』かわす 前川氏追及に淡々と」との見出しをつけ、こう書いていた。
「発言内容の信ぴょう性を低下させようとする与党側の『印象操作』をかわした格好だ」
自分たちは加戸氏の主張について読者に知らせず、前川氏の言い分だけをクローズアップする印象操作を行っておきながら、与党側が印象操作をやったと決め付けている。これには、勝海舟の次の言葉を思い浮かべた。
「世の中に無神経ほど強いものはない。あの庭前の蜻蛉(とんぼ)を御覧(ごらん)。尻尾を切って放しても、平気で飛んで行く」
ただでさえ「マスゴミ」と呼ばれるようになって久しいマスコミは今後、いよいよ信用を失い、軽蔑の対象となっていくのだろう。森友学園や加計学園をめぐる一連の報道を見るに付け、その懸念は深まるばかりである。
ともあれ、加戸氏は産経新聞のインタビュー(6月16日付朝刊掲載)に対し、政治が行政をゆがめた実例として昭和57年夏の「教科書誤報事件」を挙げている。教科書検定で日本の「侵略」が「進出」に書き換えられたとマスコミが一斉に報じ、国際問題化した騒動である。
「官邸が、教科書を政府の責任で是正するという宮沢喜一官房長官談話を出した。文部省がやる検定を官邸が無理やりに、理不尽にも。鈴木善幸首相の中国訪問が予定されているから円満にという政治の思惑なんて見え見えだったが、行政の筋が曲げられたと思っても言いませんでした。それが役人の矜持(きょうじ)ですよ」
加戸氏がインタビューで「そこのところが、前川君は則(のり)を超えちゃったのかな」とも語っていたのが印象的だった。
結局、「侵略」を「進出」に書き換えさせた事実はなかったことが判明し、産経は7段組みの大きな訂正記事を出し、謝罪したが、ほとんどのマスコミは訂正しようとはしなかった。
そしてこの誤報事件をきっかけに、教科書検定基準に近隣諸国に配慮することを定めた「近隣諸国条項」が加わり、教科書記述がゆがめられていく。当時からゆがんでいたマスコミは、さらにゆがみねじ曲がった。(あびる るい)
なぜ、成功を溝に捨てるようなことをしたのか?経営が苦しかったのか??
商売は信頼が重要!銀行だって融資を渋るのでは?しかし、なぜ、偽エルメスを販売したのか? 経営にゆとりがあれば、 危ない橋や素性が見えない相手を避ければ良いと思うが??
有名ブランド「エルメス」の超高級バッグ「バーキン」にそっくりの商品を販売したとして2人を逮捕です。
逮捕されたのは、新潟市のドレス販売会社の社長・清水彩子容疑者(35)と社員(38)の2人です。警察によりますと、清水容疑者らは2015年6月上旬、高級ブランド「エルメス」のハンドバッグ「バーキン」に似せたバッグを長野県に住む女性に販売し、商標権を侵害した疑いがあります。警察の調べに対し、清水容疑者は「エルメスの類似品を販売したとは思っていない」と容疑を否認しています。清水容疑者は「地方で成功した年商10億円の女性社長」などとして、度々、メディアに取り上げられていました。
青森県が実施したがん検診に関する調査結果について、NHKが「がん検診で4割の患者が見落とされていた可能性がある」と報道したことに対し、国立がん研究センターは13日、「調査は予備的なもので、結果から検診の見落としを評価することは困難」との声明を発表した。
NHKは6月29日のニュースで「青森県が県内10町村の検診受診者を調査した結果、胃がんで40%、大腸がんで42.9%、子宮頸(けい)がんで28.6%でがんが見落とされた可能性がある」と報じた。
これに対し、声明は「40市町村ある青森県の10町村を対象にした予備的調査で、見つかったがんもそれぞれ10例以下。2011年度の検診受診者に対し観察期間が11~12年末と短く、結果から検診見落としを評価することは困難」としている。
青森県の調査の目的は、胃、大腸、子宮頸部など五つのがん検診者の台帳と、がん患者の登録データの予備的な照合。調査の中で、胃がんで60.0%、大腸がん57.1%などと、それぞれの検診で、がんと診断できた割合が明らかになった。
報道は、これらの割合を100%から引き算して、残りを「見落とし」の割合とした。しかし、国際的には検診受診後、一定の間隔をあけて次の検診までの間にがんと診断されたケースを「見落とし」と定義。4割を「見落とし」とした報道は不適切としている。
がん検診では、がんではない人をがんと誤って診断して不利益を与える可能性もある。このため、ある程度発見できない割合を許容している。乳がん検診の場合、70~85%でがんと正しく診断できれば有効とされている。
がん研究センターの斎藤博検診研究部長は「検診の精度調査の意義は大きいが、小規模の予備的なもの。それを確定的に扱うのは不適切」と話している。
NHK広報部は「今回の調査は青森県ががん対策に役立てるため全国に先駆けてがん登録データを活用して行ったもので、放送は調査結果に基づいてお伝えしました。その中では、県内10町村のデータであることや、青森県がサンプル数が少ないとして『今後、市部も含め複数年度調査を行うこと』もお伝えしています」とコメントした。【高野聡】
◇「放送は調査結果に基づいたもの」NHK
NHK広報部は「今回の調査は青森県ががん対策に役立てるため全国に先駆けてがん登録データを活用して行ったもので、放送は調査結果に基づいてお伝えしました。その中では、県内10町村のデータであることや、青森県がサンプル数が少ないとして『今後、市部も含め複数年度調査を行うこと』もお伝えしています」とコメントした。【屋代尚則】
中堅の監査法人アリアのWebサイトには現在、このような文言が公表されている。
「金融庁の公認会計士・監査審査会が、平成29年6月8日に公表した勧告は、大多数の事実誤認に基づく、虚構の不当な文章であり、当監査法人は、司法の場でその事実を明らかにすべく訴訟を行っております」
この記事の写真を見る
■史上初、監査法人が金融庁を提訴
6月8日に公認会計士・監査審査会(以下、CPAAOB)が、監査法人アリアに対し行政処分を行うよう金融庁長官に勧告、冒頭の”闘争宣言”はこれを受けて掲出されたものだ。金融庁を訴えた監査法人はアリアが史上初となる。
CPAAOBは2003年の公認会計士法改正によって2004年4月1日に金融庁内に誕生した組織で、公認会計士試験の実施機関であるとともに、監査証明業務や日本公認会計士協会の事務が適切に行われるよう、監査法人や公認会計士、公認会計士協会への行政処分について、調査・審議して金融庁長官に勧告する機関でもある。
実際に処分を下すのは金融庁長官だが、事実上公認会計士と監査法人の懲戒権を握る監督機関で、常勤の会長1名と委員9名からなる有識者の合議体だ。
誕生からの13年間で行った処分勧告件数はアリアも含めて30件。CPAAOBが金融庁に行政処分を勧告をし、金融庁が処分を行うのが通例だ。
実際の処分は大半が業務改善命令のみに留まり、業務停止を受けてもその範囲は新規の獲得業務に限定されているものがほとんど。監査業務にも業務停止命令を出してしまうと、結果的に監査先の上場会社が突然監査法人の変更を余儀なくされるなどの不利益を被るからだ。
新規の獲得ができないだけとなると、殺生与奪の権限を握る監督官庁に法廷闘争を挑み、敵対することで得られる利益は限られる。
今年3月末時点で、アリアは上場会社8社の監査を担当していたが、今回の勧告によって1社が契約解除になり、新規に契約する予定だった2社が白紙に戻った。
■勧告は内部文書で、差し止めは不可
CPAAOBが公表した勧告文は、独立性の確認をしていない、新規契約時の対応に不備がある、残高確認で入手した回答を検討していない、大会社の監査経験がない者を審査専任担当者に任命している、経験ある定期検証責任者が定期検証に十分関与していない、などなど、かなり苛烈な書きぶりになっている。
これに対し、アリアの茂木秀俊統括代表社員は「チェックシートにチェックマークを付け忘れたり、一部のページで押印が洩れていたことをもって確認をしていないとか、検証していないとか指摘されている。また、5年前の検査時には全く問題視されなかったことが今回は問題視されており、甚だ不本意。結論ありきでいいがかりを付けられているとしか思えない」と憤る。
茂木代表によると、今回の勧告の対象になった検査が始まったのは昨年の1月。5年前の前回検査時よりも長期化する中、昨年6月、CPAAOBから「検査結果の確認事項(案)」が提示される。
CPAAOBが検査結果を検査対象の監査法人に対して知らせるもので、監査法人側は内容に不満があれば、「意見申し出」ができる。
アリア側の説明とは異なる内容になっていたため、「意見申し出」を行ったものの聞き入れられることはなく、年が明けると「CPAAOBから勧告を出す手続に移る、と言ってきた」(茂木氏)ので、今年3月27日、金融庁を相手取り、勧告と勧告内容の公表を差し止める訴訟を起こした。
行政事件訴訟法では、提訴と同時に「仮の差し止め」手続をとることができるので、同手続をとったものの、東京地裁の判断は「却下」。理由は「勧告は行政の内部文書であり、差し止めの対象にならない」というもの。内容の審理以前の問題として門前払いされた形だった。
勧告が公表されたのは棄却から約2週間後。勧告とその公表の差し止めを求めていたのに、勧告され、公表もされてしまった。
そこで7月3日付で「勧告内容がCPAAOBのHPに載り続けているので、これの差し止めと、違法な勧告と違法な公表によって受けた損害の賠償、加えて違法な公表によって受けた名誉毀損への謝罪広告請求に変更した」(代理人の倉科直文弁護士)という。
■公表そのものが「社会的制裁」効果
CPAAOBの勧告は、行政処分が決まる前にその事実が公表される。このことはステークホルダーが、早期にその事実を知ることが可能になる一方で、処分が決まらないうちに勧告対象者は社会的制裁を受けてしまう側面を持つ。
同様のことは、証券取引等監視委員会が金融庁長官宛てに勧告をする、課徴金制度にも言える。
本来、勧告段階で公表するという制度の主旨は、議論を表に出すことにある。結果的に実際の処分が行われる前に社会的制裁を与えてしまうのは、国民が行政の判断を盲信すること、加えて処分対象者が反論しないことで起きてしまう。
もう1つ、今回の一件が示しているのは「仮の差し止め」に対して裁判所が下した判断は、「勧告及びその公表は、対象者に甚大な被害を与えるにもかかわらず、止められない制度になっている」(茂木氏)という点にある。
ただ、アリアには業績不振企業の監査を手掛ける機会が多く、「業績不振企業の駆け込み寺」との風評がついて回っている。
その点は代表社員の茂木氏も認識しているが、「監査は公認会計士の独占業務。やりたくないからやらないなどと言っていいわけがない。業績不振企業でも上場会社ならどんな会社にも監査を受ける権利がある。だが、不正は許さない。引き受けたからには徹底的にクリアにする。そのせいで上場廃止になってもそれは仕方がないこと」と言い切る。
それだけに、「不当に傷つけられた信用は回復したい。泣き寝入りはしない」(茂木氏)という。
監査法人が監督官庁の金融庁を訴えるという前代未聞の裁判は一体どうなるのか。そして勧告の位置付けも変わって行くのか。制度そのものが問われている。
伊藤 歩 :金融ジャーナリスト
「その経営トップが、富山生まれを否定するかのような持論を語り、県内企業、行政関係者は『出身地などでレッテルを貼るのはおかしい』『侮辱だ』などと怒りをあらわにした。」
富山に限らず、やはり地方は閉鎖的な考えの人が多い。単純に否定するだけでなく、田舎の良さをアピールするだけで良い。
なぜ、地方の人が閉鎖的な傾向にあるのか考えればわかるし、いろんな場所を訪れたり、住んだことが事があれば感じる事だと思う。これは日本だけでは ない。自分がアメリカに住んでいた時もそれを感じたし、州外から来たアメリカ人生徒も感じていた。
地方で生まれそこで住み続ける事は悪い事ではない。ただ、「よそ者(他の地域や県外から来た人達)」は説明もなく、納得出来る理由もなしに 「郷に入っては郷に従え」と言われても納得しないケースもある。新しい考え方、違った基準や視点を持った人材が欲しい企業であれば、 同じ場所で刺激がない環境で同じような経験や考え方を持った人材は必要としないであろう。いろいろな出身者がいる企業の方がよそ者にとっては 入りにくい。富山人同士で固まったグループに入りやすい環境はあると思うのか?
真面目で勤勉な地元の人間を欲しい企業はあるはず。同じ物差しで考えること自体、地方的で、閉鎖的だと思う。
単に学歴だけでなく、経験やその人の考え方や視点を評価する企業もあれば、単純に学歴や卒業大学にこだわる企業もある。学生は企業名だけに こだわる必要もないし、学生の経験や個性を高く評価してくれる企業を選ぶことが出来る。
いろいろな経験をしないと理解できない事はある。同じ場所に住み続ける人達は県外の価値観やよそ者として住んだ経験がないと、 無意識でよそ者に対して不適切な発言や行動を取っている事に気付かない。東京の人間も同じ。東京で育っただけで地方の人間よりも 上だと思っていたり、東京の生活に適合していないだけで、馬鹿にする人達も多い。しかし、海外に行くと、静かになる人間もいる。
「富山中央法律事務所の丸山哲司弁護士の話 出身地を採用の判断基準の一つにするのは公正とは言い難く、就職差別につながる。公平な採用選考が重視される中、近年は出生地や本籍、家族構成といった 本人の能力や適正とは関係のない事項を尋ねる企業は、減少している。」
採用基準や欲しい人材は企業ごとに違う。社会心理学では一人っ子と兄弟と育った人の行動パターンに何らかの傾向があるのかを調査している人も いるし、過去の経験が現在の人格に影響を及ぼすことは心理学では常識。人材評価にいろいろな方法を採用しても問題ないし、 企業のとって人材が重要と思っている場合、採用する人材の評価は重要。採用した人材が大きく成長するかが会社の成長や存続にも影響する。 企業の選択なのだから企業の責任で決めれば良いと思う。人気のある電通でも自殺者は存在する。それでも就職したい学生はいるし、就職している。 学生が電通に対しネガティブな印象を持っていれば面接を受ける必要はないし、内定を貰っても就職する必要もない。それだけ!
総合機械メーカーの不二越の社長の発言や企業体質に問題があると思えば、面接を受ける必要もないし、就職必要もない。望まれない企業で働くよりも 評価してくれる企業で働けばよい。過剰に反応する必要はないと思う。
■「不適切」と怒りの声
総合機械メーカーの不二越(富山市不二越本町)が5日、本社の東京一本化を発表した会見の席上、本間博夫会長(71)が採用に関し「富山で生まれ地方の大学に行ったとしても、私は極力採らない」「偏見かも分からないが、閉鎖的な考え方が強い」などと発言した。1928(昭和3)年に富山市で産声を上げた不二越。その経営トップが、富山生まれを否定するかのような持論を語り、県内企業、行政関係者は「出身地などでレッテルを貼るのはおかしい」「侮辱だ」などと怒りをあらわにした。学校関係者からは「富山の若者が閉鎖的とは思わない」と戸惑いの声が上がった。
本間氏は東京都出身、青山学院大経営学部卒。1970年に入社し2009年に社長、今年2月に代表権のある会長に就いた。
発言があったのは5日、富山市の富山商工会議所ビルで開いた17年5月中間期の決算発表会見。本間氏は、富山と東京の2本社体制から、8月に本社を東京に一本化する理由について、ロボットを核とした事業拡大に向け「最先端の情報や優れた人材を獲得するため」とし「富山に優秀な人材がいないわけではないが、幅広く日本全国、世界から集めたい」と説明した。
その上で「富山で生まれて幼稚園、小学校、中学校、高校、不二越。これは駄目です」と述べ、「富山で生まれて地方の大学へ行った人でも極力採りません。なぜか。閉鎖された考え方が非常に強いです」と明言。一方で「ワーカーは富山から採ります」とも話した。
県内の経済団体トップや企業経営者からは、批判や異論が相次いだ。富山経済同友会の米原蕃代表幹事(米原商事会長)は「地方創生の機運が高まる中、時代に逆行している。富山県民を侮辱していると言わざるを得ない」と語気を強めた。
富山市出身で富山大OBの電子機器メーカー社長と電子部品メーカー社長はそれぞれ「極端な意見で賛同できない」「出身地でレッテルを貼るのは理解しがたく、不適切」などと疑問視した。釣谷宏行CKサンエツ社長は「富山県民はまじめで素直。これまでに閉鎖的だと感じたことはない」と話す。
富山大OBで富山経済同友会特別顧問の中尾哲雄アイザック取締役最高顧問は「富山が工業立県として発展したのは不二越の力が大きい。本社一本化は経営判断であり、やむを得ない」と理解を示す一方、県出身者を「閉鎖的」と表現したことは「極めて遺憾。上場している大企業のトップとしてふさわしくない」と苦言を呈した。
■不二越経営企画部、県出身者採用「抑制せず」
不二越は来年春、大学と大学院卒、短大、高卒を合わせて今春より22人多い166人の採用を計画している。同社経営企画部は「採用は人物本位。富山の出身者の採用を抑えるということではない」とした。現在、社員約3千人の多くは富山県出身者で占めるという。
北日本新聞は本間氏の発言の真意について取材を申し入れたが、同経営企画部は「コメントを控えたい」とした。
◆本間会長の会見発言要旨(抜粋)◆
不二越は2020年に(売上高)4千億円を目指しており、うち約4割をロボットで担おうとしている。大きな飛躍を狙う中で必要なのは、ソフトウエアの人間だ。特に不二越は機械メーカーのイメージが強く、富山にはまず来ない。富山で生まれて幼稚園、小学校、中学校、高校、不二越。これは駄目です、駄目です。変わらない。
ことしも75名ぐらい採ったが、富山で生まれて地方の大学に行ったとしても、私は極力採らないです。学卒ですよ。地方で生まれて、地方の大学もしくは富山大学に来た人は採ります。しかし、富山で生まれて地方の大学へ行った人でも極力採りません。なぜか。閉鎖された考え方が非常に強いです。偏見かも分からないけど強いです。
閉鎖的な考え方が強いです。いや優秀な人は多いですよ、富山の人には。だけど私の何十年、40年くらいの会社に入ってからの印象は、そういう印象が強いです。ですから全国から集めます。ただしワーカーは富山から採ります。
■公正とは言い難い
富山中央法律事務所の丸山哲司弁護士の話 出身地を採用の判断基準の一つにするのは公正とは言い難く、就職差別につながる。公平な採用選考が重視される中、近年は出生地や本籍、家族構成といった本人の能力や適正とは関係のない事項を尋ねる企業は、減少している。
■トップとして不見識
宮井清暢・富山大経済学部経営法学科教授(憲法学)の話 企業に採用の自由はあるが、法の下の平等や職業選択の自由を不当に侵害しないことが前提だ。発言は出身地による採用差別のように聞こえ、法的に不適切と言われてもやむを得ない。企業トップしては不見識で不用意な発言だ。
北日本新聞社
法令上、禁止されていないのなら自己責任だと思う。最終的には法令上、禁止されているのかが焦点になると思う。
高松市内の家具店にあるエスカレーターで車椅子が転落し、後方にいた76歳の女性が巻き込まれて死亡した事故で、香川県社会福祉協議会は12日、エスカレーターで車椅子を使う方法などを挿絵とともに解説していた介助の手引きをネットのホームページ(HP)から削除した。協議会は「今回の事故にかんがみた」と説明している。
【写真】現場にはエスカレーターに車椅子やベビーカーを乗せないよう求める表示が
県社協によると、削除したのは「街で障害者に出会ったら 知っておきたい援助の仕方」。少なくとも2010年ごろには冊子版(A4判、25ページ)を発行し、HPにも掲載していた。エスカレーターでの車椅子使用については「危険を伴いますので注意が必要です」としたうえで、上りに乗る際は「キャスター(前輪)を上げてステップに乗る」などと記載していた。
県社協は12日、市町の社協に冊子が残っている場合、配布を中止するよう要請。担当者は「エレベーターのない建物もあるので安全に使う方法を掲載していた。今後、障害のある方の移動をどう考えるか関係者で話し合いたい」と説明する。
国土交通省建築指導課によると、車椅子をエスカレーターに乗せることは法令上、禁じられていない。しかしエスカレーターは基本的に車椅子を乗せる設計になっておらず、同省はエレベーターの使用を求めている。担当者は「過去数年の事故を調べたが、同様の事故はなかった。通常の使い方ではない」と指摘した。
一方、高松南署は12日、司法解剖の結果、女性の死因が腰椎(ようつい)骨折による出血性ショックだったと発表した。【植松晃一、岩崎邦宏、山口桂子】
人材紹介・建設業特化|株式会社ワールドコーポレーションの事?
38歳で部長は普通、それとも、ラッキーな方?
人材派遣会社の営業部長の男が、18歳未満と知りながら女子高校生とみだらな行為をしたとして逮捕された。
児童買春の疑いで逮捕されたのは、人材派遣会社「ワールドコーポレーション」の営業部長・金谷慎一容疑者(38)。警視庁によると金谷容疑者は今年5月、東京・葛飾区の自宅で、都内の高校1年生の少女が18歳未満であることを知りながら現金2万円を渡す約束をしてみだらな行為をした疑いが持たれている。
金谷容疑者は4月に携帯電話の掲示板アプリを通じて少女と知り合い、5月には計3回、みだらな行為をし、合計5万円を渡したという。調べに対し金谷容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているという。
変化がある時、良い意味でも、悪い意味でも、影響が出る。喜ぶ者もいれば喜ばない者もいる。
もし残業時間減で会社の利益が減らば、後で、ボーナスカット、給料カット、効率アップの圧力などネガティブな影響が出るであろう。
オフィスで終業時刻に音楽を流し、帰宅を促す試みが広がりつつある。お店が閉店まぎわに「蛍の光」のメロディーを流すのと同じ手法だ。長時間労働を減らす「働き方改革」は、待ったなしの課題。はたして効果はあるのだろうか。
東京・新宿のオフィスビルに入居する三井ホーム本社。社員約100人が机を並べるフロア。ゆったりとしたピアノ曲が流れる。
午後6時に突然、映画「ロッキー」のテーマ曲に切り替わった。終業時刻を告げる合図だ。
社員が次々と立ち上がり、「私は7時までかかります」「私はこれで帰ります」。机を接する同じ班で順番に宣言していく。残業が長くなりそうな社員には、上司がアドバイスしたり、周りが手伝いを申し出たりして、早く帰宅できるよう協力し合う。
オフィスで決まった時間帯に音楽を流す取り組みは、総務、経理、人事などの部署で2014年10月から始めた。社員のリラックスや、メリハリをつけて働いてもらうのが狙いだった。最後が「ロッキー」なのは、勇壮な曲調で「残りの仕事もがんばろう!」と奮い立たせるためだ。残業は「減ってくれたらよい」ぐらいの期待感だった。
昨年10月に対象部署の勤務時間を調べたところ、「意外な効果の大きさに仰天した」(人事部の町山誠人事グループ長)。取り組みを始めて残業時間の合計が2~3割ほど減った。
総務部の加藤卓郎さん(34)は「音楽が区切りになってだらだらと職場に残らなくなり、帰りやすい雰囲気になった。帰宅は2時間ぐらい早くなった」と喜ぶ。経理部の若林敏行さん(35)は「常に『ロッキー』から逆算して段取りなどを考えるようになった」。オフィス外でも「ロッキー」を聞くと無意識に「仕事は何が残っているか」と考え出すという。
朝日新聞社
過去の事を振り返っても映画やドラマのようにやり直す事は出来ないけど、「もし」があれば大手広告会社の電通に入社する前にもっと 電通について入れべていれば、又は、入社に反対していれば自殺は免れていたかもしれない。
不起訴処分となった上司の男性幹部のような人間はこの世の中にたくさんいるのでこのように対応していくのか考えるべきだと思う。
国が馬鹿見たいに労働時間について厳しくなったが、抜け道を探す企業はたくさん存在するだろう。だからサービス残業を取締る方が 見せかけの労働時間を取り繕う会社の社員にとってはお金が貰えない労働が増える可能性が増した。
労働時間や過労の問題は簡単には解決できない。それよりは簡単に会社を変われる環境になるように努力した方が良いかもしれない。 会社が嫌であれば、又は、会社に問題があれば会社を変われば良い。無理にその会社に付き合う必要はない。ただ、実力や魅力がなければ 仕事を見つけるのは簡単ではないかもしれない。会社のレベルを下げるとか、条件を下げれば、再就職が簡単かもしれない。
命を優先とするなら、諦める事が必要な時もあるであろう。
大手広告会社の電通(東京)の違法残業事件で、東京地検が労働基準法違反罪で同社を略式起訴したことを受け、違法残業で過労死した高橋まつりさん=当時(24)=の母、幸美さんは7日、「刑事処分を受けることは、至極当然であり、改めて一刻も早く電通の社風と労務管理の改善を行うように求めます」とコメントした。弁護士を通じて、報道機関にコメントを送付した。
【写真で見る】まだ24歳だった…過労死した高橋まつりさん
高橋さんは、書類送検されたまつりさんの上司の男性幹部が不起訴処分(起訴猶予)とされたことについて、「この上司が労働基準法違反の指示をしていたことは明確であり、刑事処分が妥当であると考えていたので、検察官が上司個人を不起訴処分としたことには納得できません」とした。
その上で、「入社してわずか半年の新入社員に対して、正社員に登用した月から連日の深夜労働や徹夜勤務、休日出勤をさせたことは絶対に許せない、悪質な行為であり、上司個人が罪に問われないことは、誠にやりきれない思いです」と訴えた。
日本原子力研究開発機構の体質や今回の事故がなぜ起こったのかを考えれば、理解できると思う。
安全かどうかよりも、安全な状態を維持できるかで失敗している。安全対策は実行し、維持できなければ、意味がない。
日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター(茨城県大洗町)で作業員5人が被ばくした事故は6日で発生から1カ月。原子力機構は当初、事故を「想定外だった」と説明したが、事故は想定できたにもかかわらず、不十分な体制のまま作業をしていたことが調査で明らかになってきた。【岡田英、鈴木理之】
【図説】内部被ばく事故、どのようにして起きたのか
原子力規制委員会は保安規定違反の可能性が高いとみている。
事故は6月6日午前11時15分ごろ、同センターの燃料研究棟で金属容器を点検で開封中、中に入っていたプルトニウムなど核燃料物質入りのビニール袋が破裂した。金属容器は1991年以来、26年間一度も開けたことがなかった。
「中がどうなっているか分からないので、おっかなびっくり作業していた」。規制委の立ち入り検査で、原子力機構はこう説明した。作業員は長期間放置したビニール袋の劣化は認識していたという。また、機構の別の施設で同様にビニール袋が膨らんだケースがあったことも、今年1月には把握されていた。
しかし、作業員は作業前の安全チェックで「爆発・破裂・飛散の恐れ」という点検項目に「該当なし」と判断し、上司も承認。室内には密閉型の作業台が5台あったが、密閉されていない簡易な作業台で開封した。必要な作業計画書も作成されていなかった。
原子力機構の担当者は「密閉型の台を使っていれば、事故は明らかに防げた」と悔やむ。
事故後、作業員の除染用の仮設テントを設置できたのは発生から3時間後。燃料研究棟に必要な資材がなく、組み立て訓練もしていなかった。放射性物質を洗い流すシャワーが故障していたことも判明した。
規制委の田中俊一委員長は今月5日の定例会で「プルトニウムを扱う際、慣れや根拠のない判断があってはいけない。安全文化が欠けている」と批判した。
ユナイテッドが近い将来倒産しなかったら、結局は運悪く批判されているだけで、他のエアランインもどんぐりの背比べか、価格で妥協する客が多いと 言う事かもしれない。
乗客を機内から無理矢理引きずり出し、多くの非難を浴びた米ユナイテッド航空が、またしても同じ轍を踏んでしまったようだ。
ハワイ在住の教師シャーリー・ヤマウチさんは、ボストンで行われる会議に出席するため、搭乗日の3カ月前に、帯同する2歳の息子・タイゾーくんの分と併せて2人分のチケットを購入した。
フライト当日、ヒューストンでの乗り継ぎを済ませて離陸を待っていると、タイゾーくんの座席番号と同じチケットを持った男性を伴って、フライトアテンダントがやってきた。彼女はあろうことか、タイゾーくんの席をその男性に案内したのだ。
ヤマウチさんは子どもの分の席も購入してある、と説明したが、この男性は「空席待ちでここが取れたんだ」と言い張り、無理矢理ヤマウチさんの隣に座ってきたという。彼女はしかたなくタイゾーくんを膝に乗せたまま、3時間半のフライトを耐えなければならなかった。
「彼は体重11キロで、身長は私のほぼ半分くらいあります。すごく辛かった。手と左脚は壁に押し付けられて、感覚がなくなっていました」と地元紙の「ハワイ・ニュース・ナウ」に語った。彼女は抗議したかったが、最近のユナイテッド航空に関する報道を思うとおとなしく従わざるを得なかったと悔しさを滲ませる。
「ユナイテッドのニュースを思い出したんです。あの暴力。歯も折られていた。私はアジアンです。だから同じような目に遭うのではないかと恐ろしくなってしまって」
ヤマウチさんは自分の膝の上で窮屈そうに眠るタイゾーくんの写真を公開し、当時の心境を吐露。
ユナイテッド航空の広報担当者は「タイゾーくんの搭乗券がきちんと処理されていなかったため、彼の座席に空席待ちの乗客を入れてしまいました。ヤマウチさんと彼のご子息に、心から謝罪致します。タイゾーくんのチケット代金は返金し、旅行券を進呈しました。再発を防ぐため、搭乗口のスタッフの教育を徹底します」と声明を発表した。
Twitterでは、「誰も驚いていないと思うよ。これがユナイテッドだ」「ユナイテッドに乗っちゃいけない理由がまた一つ増えた」「あいつらは何も学んでいないんだな」と呆れる声が多く見られる。
成田国際空港会社にチェック機能がない、又は、機能していないから問題のある職員が不適切な行為を継続できた。詳細な理由は調査すれば 明確になるが、調査しなくても組織の問題があったと推測するのは難しくない。
2003年7月11日、第156回通常国会にて「成田国際空港株式会社法」が成立し、これにより新東京国際空港公団(NAA)は04年4月1日に全額政府出資の株式会社に移行、早期に株式上場を目指すこととなりました。(一般財団法人 港湾空港総合技術センター)
成田国際空港会社の全株式を日本国政府が所有する組織なのにこんなに風投資の悪い企業なのはなぜなのか?
国土交通省は株主として定期的にチェックしているのか?
成田空港を管理する「成田国際空港会社」(千葉県成田市、NAA)の発注業務を巡る汚職事件で、同社の元上席執行役員栗田好幸容疑者(64)(成田国際空港株式会社法の収賄容疑で逮捕)が、業者から受け取った現金をクレジットカードのローン返済に充てていたことが捜査関係者への取材でわかった。
栗田容疑者は、この業者からほかにも現金を受け取っていた疑いがあり、警視庁が金の流れを調べている。
発表によると、栗田容疑者は1月下旬、NAAが発注する事務用品の納入業務を巡って、越川勝典容疑者(47)(同法の贈賄容疑で逮捕)の建築会社が受注出来るように便宜を図った見返りなどとして、現金60万円を受け取った疑い。
栗田好幸容疑者は、保安警備部門のトップを異例の長期にわたって務めるなど社内では辣腕ぶりが評価されていた。その一方で、業者との癒着の噂が絶えず、競争入札なしで業者との随意契約が可能になる「少額随契」の制度を悪用する“裏の顔”も持っていた。2020年東京五輪・パラリンピックを控え、空の玄関口の「安全」を担うべき幹部の不祥事に成田国際空港会社(NAA)に対する信頼は大きく揺らいだ。
「誠に遺憾であり、痛恨の極み」。栗田容疑者の逮捕を受けて5日午後に開かれたNAAの緊急会見。出席した夏目誠社長は、幹部3人とともに頭を下げ、こう陳謝した。
同社によると、栗田容疑者は大学卒業後の昭和50年に前身の新東京国際空港公団に入社。平成20年には、空港内の警備や航空保安を担う部門のトップである保安警備部長に就任し、27年からは上席執行役員を兼任するなど、9年という異例の長さで警備保安部門に君臨していた。
在任中の27年3月には、成田空港で昭和53年の開港以来続いてきた身分証確認を伴う検問を廃止し、監視カメラなどによる警備に切り替える「ノンストップゲート化」を実施。夏目社長によると、この事業は「開港以来の悲願」で、「功績は大きかった」という。
「安全」を担う部門を長年仕切ってきた人材の逮捕に、栗田容疑者と仕事をしたことがあるというあるNAA社員は「仕事ぶりはパワフルかつ繊細。豪腕だが、社内外と粘り強く交渉して事業を実現させる力がある」と評価する。夏目社長も「日常的に警察と接している部署にいる人がまさかこういうことをしているとは」と漏らした。
しかし、同じ職務に長期間留まったことが不正の芽も生んでいた。
夏目社長は、逮捕容疑以外にも「不正が疑われる取引は相当の件数ある」と認めた。同じ部門で管理職の立場に留まっていることを利用し、業者から長期にわたって金品を受けていた疑いがある。それを見過ごしていたのなら、NAAのチェック機能も問われる。
ある関係者は「高級車に乗るなど羽振りも良く『業者から金をもらっているのでは』との噂は絶えずあった」と振り返る。栗田容疑者自身は捜査が及んでいることを知り、6月に行われた内部調査で「取引先からもらってはいけないお金をもらってしまった」と告白したという。
NAAは外部の有識者による検証委員会を設置し、原因究明と再発防止を進める意向を示した。社内のチェック体制の強化を進め、「二度とこのような不祥事を起こさない」としているが、信頼回復までの道のりは長く、遠い。
法律や規則については知らないが、評価額がある基準を超えれば、2人の不動産鑑定士による評価が必要をすれば良い。1人よりは2人の方が 不正を働きにくいし、逮捕、又は、不正の調査の時に、2人の言い分に食い違いがあれば、問題点に気づきやすい。
「負の連鎖を防ぎ、鑑定制度の信頼性を保つため、国交省は関連規定の中に『不当な鑑定評価を依頼された場合に、当該依頼を受託してはならない』と明示することにした。」
国交省はこんな明示で問題が改善できると思っているのか。「不当」の定義も明確化するのか?市場の一般価格よりも3割高くなれば、不当なのか、 5割高くなれば不当なのか、それとも2割高くなれば不当と解釈するのか?
防止策を考えるのなら逆側の立場に立ってどうやったら不動産の価値を過大・過小に評価する事が難しいのか考えるべきだ。 性善説は成り立たないし、法や規則があっても、不正を行いやすい、又は、不正が発覚しにくい、又は、チェックが甘ければ、不正は起きる。 起きないと思うほうが間違い。
財務省の佐川宣寿理財局長佐川氏は学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却問題の国会答弁で事実確認や記録の提出を拒み続けた。(朝日新聞) が良い例だ。逃げる組織や逃げる人間は何でもやるのである。
財務省でもこれぐらいは平気でなるのであるから、民間はもっとひどい対応を取ってくる事を想定するべきだ。
政治家や企業が不動産鑑定に不当な圧力を掛け、評価をつり上げたり引き下げたりする――。「依頼者プレッシャー」と呼ばれる問題が深刻化しているとして、国土交通省が対策に動き出した。不当な要求をされた不動産鑑定士は仕事を拒むよう、明文で規定する方針だ。
不動産鑑定評価は、地形や用途、時代によって上下する不動産の価値を、専門的な見地から適正に評価する制度。国家資格を持つ不動産鑑定士が担っているが、国土交通省はここ20年間で14件、不動産鑑定士を懲戒処分しており、少なくとも8件は不動産の価値を過大・過小に評価したことが理由とされた。例えば2015年9月のケースでは、開発・造成の難しい林地について、超高層マンションを建てる前提で土地価格を計算していた。
別の理由で処分された事案の中にも、斜面が含まれているのに平地として評価したり、議員関係者の土地を相場の10倍にあたる1億3千万円以上と鑑定して自治体側に買わせたりしていたケースがあった。
国交省が公認会計士や税理士らに行ったアンケートでは、65%が「依頼者に都合の良い鑑定評価額となっている可能性も否定できない」と回答した。
鑑定がゆがめば、自治体が高値で公共用地を買わされたり、企業の資産価値が過大に評価されて経営実態が隠されたりしかねない。こうした負の連鎖を防ぎ、鑑定制度の信頼性を保つため、国交省は関連規定の中に「不当な鑑定評価を依頼された場合に、当該依頼を受託してはならない」と明示することにした。法律や基準などのどこに盛り込むかは、有識者や業界関係者の意見を踏まえて検討する。日本不動産鑑定士協会連合会は「明文化により、不当圧力を断りやすくなる」と歓迎している。(赤井陽介)
政治家や企業が不動産鑑定に不当な圧力を掛け、評価をつり上げたり引き下げたりする――。「依頼者プレッシャー」と呼ばれる問題が深刻化しているとして、国土交通省が対策に動き出した。不当な要求をされた不動産鑑定士は仕事を拒むよう、明文で規定する方針だ。▼30面=二束三文の土地が
不動産鑑定評価は、地形や…
本当に全容解明は出来るのか?
成田国際空港会社(NAA、千葉県成田市)の業務をめぐり、便宜を図った見返りに業者から現金数十万円を受け取った疑いが強まったとして、警視庁捜査2課は5日、同会社法違反(収賄)容疑で、元同社上席執行役員の男(64)の取り調べを始めた。
容疑が固まり次第、逮捕する。同課は癒着構造の全容解明を進める。
千葉県多古町の建築会社社長(47)らについても同法違反(贈賄)容疑で逮捕する。
捜査関係者によると、元役員は今年1月、NAAが発注する物品納入業務に関し、同社が受注できるように便宜を図った見返りとして、現金数十万円を受け取った疑いが持たれている。
社長は他に、運送業や事務用品を扱う会社も経営している。元役員は空港運用部門副部門長で保安警備部担当を務めていたが、6月に退職した。元役員は業者選定に関する権限を有していたという。
まあ、時間が経てば結果は嫌でも出る。それまで待つしかないのかもしれない。
政府の国家戦略特区制度を活用した学校法人「加計(かけ)学園」の獣医学部新設問題を巡り、日本獣医師会の蔵内勇夫会長(自民党福岡県連会長)が西日本新聞の単独インタビューに応じた。蔵内氏は、政府の国家戦略特区諮問会議が昨年11月に獣医学部新設計画の方針を決定する以前に、文部科学省に近い複数の大学関係者が「加計で決まる」と話していたと証言。「最初から『加計ありき』で話が進んでいると思わざるを得なかった」と語った。
一連の問題について蔵内氏が報道機関の取材に応じたのは初めて。東京都議選の自民党惨敗を受け、野党は疑惑追及に攻勢を強めており、国会の閉会中審査で取り上げられる可能性がある。
加計学園が国家戦略特区の事業者として認定されたのは今年1月。政府はこれに先立ち、昨年11月9日に獣医学部新設を認める規制緩和を決めている。
インタビューで蔵内氏は、昨年11月以前に開かれた地方の獣医学会の会合などで、複数の大学関係者から「加計で決まる」「加計が教師を集めている」との話を聞いたと証言。「あの手この手の根回しがあった」と言い、「水面下で加計(の学部新設)を認める方向で進んでいると分かった」と述べた。
さらに規制緩和が獣医師の地域偏在解消になるとする安倍政権の主張について「国家資格の獣医師は日本中で働ける。処遇の悪い場所に行くはずはなく、特定地域の人材不足解消にはならない」と批判。文科省を「獣医師は充足しているとのデータに基づき、新設ではなく既存大学の改革に当たってきた」と評価し「指示が下りてくれば(新設を)認めざるを得なかったのだろう。行政がゆがめられたのは当然だ」と語った。
獣医師会は一貫して学部新設に反対。首相官邸は「抵抗勢力」と非難したが、蔵内氏は「われわれは長年、獣医師の処遇改善や獣医学の充実などに当たってきた改革勢力だ。(学部新設が)決定した以上、反対はしないが、教育水準の劣化が起きないかなどチェックを続けていく」と述べた。
=2017/07/04付 西日本新聞朝刊=
日本獣医師会の蔵内勇夫会長は西日本新聞とのインタビューで、学校法人「加計(かけ)学園」の獣医学部新設に向け「あの手この手で根回しみたいなこともあった」と証言した。主なやりとりは次の通り。
-獣医師は不足しているのか。
「全体として充足しているし、将来的な需要も増えない。最もいい例は犬。日本で1千万頭くらい飼われているが、15年後には600万~700万頭に減るといわれている。開業獣医師の大半はペットを診察している。犬が減るのに獣医師を増やしてどうするのか」
-学部新設は獣医師の都市部偏在を変えることにならないか。
「国家資格を取って、処遇の悪い場所で働くはずはない。偏在解消を図るなら、まず獣医師の処遇改善を行うべきだ」
-昨年11月に決定した「広域的に獣医学部が存在しない地域に限り新設を認める」との政府方針により、事実上加計学園に事業者が絞られたとの指摘がある。安倍晋三首相は国会で「獣医師会の意見に配慮した」と答弁したが。
「規制緩和が決まった後は、確かに『1校にして』とお願いした。新設を回避できないなら、せめて1校に限るべきだと思ったからだ。しかし、それ以前はそもそも新設に反対で、要望したことはない」
-この時点で、事業者は加計学園に絞られたと思ったか。
「思った。複数の大学関係者から『加計が準備している』と聞いていた。あの手この手で根回しみたいなこともあった。加計になるんだなと分かっていた」
-文部科学省の前川喜平前事務次官は「行政がゆがめられた」と言っている。
「特区で強引に大学をつくることは、文科省と獣医師会が取り組んできた既存大学の改革の流れに逆行する。行政がそこでゆがめられたというのは当然だ」
-首相は獣医学部新設について「全国展開を目指す」と明言したが。
「特区そのものに反対するわけではないが、動物の命を守り人の健康を支える獣医学と都市開発の規制緩和を同列に論じるのはおかしい。学術は特区になじまない。それに教師をどうやってそろえるのか。全国展開できるとは思えない」
◇ ◇
■県政界の有力者 蔵内氏 麻生氏と協力も
日本獣医師会の蔵内勇夫会長(63)は8期30年にわたり福岡県議を務め、県政界の有力政治家としても知られる。
2015年に自民党県連会長に就任。昨年10月の衆院福岡6区補欠選挙では、県連推薦候補の長男を麻生太郎副総理兼財務相とともに支援したが、菅義偉官房長官らが支援した鳩山二郎氏に敗れた。
日本大農獣医学部卒。県獣医師会長や県動物福祉協会理事長を歴任し、10年には九州大大学院で博士学位も取得。13年に九州から初めて日本獣医師会長に選出された。
同じ福岡県出身の横倉義武・日本医師会長と連携し、日本初となる世界獣医師会と世界医師会の合同国際会議を計画。昨年、北九州市で開催を実現させた。
=2017/07/04付 西日本新聞朝刊=
勤務先だった会社の資金を着服したとして、兵庫県警東灘署は3日、業務上横領の疑いで、神戸市西区池上の会社員、佐々木誠容疑者(41)を逮捕した。被害額は平成27年10月ごろからの約9カ月間で、計約1億2800万円に上るとみて裏付けを進めている。
逮捕容疑は昨年6月、経理担当をしていた会社の預金口座から14回にわたり計1770万円を引き出し着服したとしている。「ギャンブルに使った」と容疑を認めている。
東灘署によると、入社した26年4月から経理を1人で担当。発覚を防ぐため、架空の取引で支出があったかのように帳簿を改竄(かいざん)していた。昨年7月に依願退社。決算書類で不正が発覚し、今年3月に会社が告訴した。
結果としてタカタは倒産した。それ以上でもないし、それ以下でもない。
最大の原因は問題がアメリカ相手になった事だと思う。問題が日本国内だけであれば、全く同じ状況で同じ問題が起きたとしても 国交省や日本政府の対応はここまで厳しくなかったであろうから倒産とはならなかったと思う。
創業家オーナーやタカタ社員に問題があったのは明らかであるが、割合は分からない。問題の初期の段階で適切な対応が取られていれば このような事態にはならなかったと思うが、なってしまったのだから仕方がない。責任のある社員達や責任のない社員達は存在するが、 倒産に至った時点で運命を受け入れるしかない。
タカタの倒産を教訓に学びたい企業、経営者、そして創業家オーナーは学べばよいと思う。利害関係のない企業や人々にとっては、 どんな事も他人事である。
鈴木貴博:百年コンサルティング代表
タカタ「1兆円倒産」の衝撃
創業家支配で語られない真の問題
大手自動車部品メーカーのタカタが、民事再生法の適用を申請した。負債総額は1兆円を超す、日本最大の倒産劇となった。
今回の倒産の引き金となったエアバッグ問題については、タカタの対応が後手後手に回った結果、最悪の結果につながったという意見が多い。確かに、最初にエアバッグの不具合が報告されたのが2005年、アメリカでの最初の死亡事故が2009年のことで、その間もその後も、タカタの説明とは異なる事故が相次ぎ、自動車メーカーも運輸当局も不信感を強めるという展開が続いた。
もっと経営トップがきちんとした対応をとれていれば、今回のようなことにはならなかったのではないかという意見は根強い。そして倒産という最悪の結果になった背景には、タカタが創業家が支配する会社だったという影響が色濃く見られる。
私は職業柄、オーナー企業独特の経営メカニズムについては何度も経験してきている。その経験から、なぜ創業家支配の企業ではこのようなことが起こりやすいのか、そのメカニズムを説明してみたい。
創業家支配の会社で「エアバッグのリコール問題」のような大事件が起きると、そこで連鎖して起きる問題が3つある。1つめに、オーナー経営者は今回のような問題が起きた際に被害者意識を持つということだ。
意外に思われるかもしれないが、タカタのエアバッグが異常破裂して死亡事故を起こすというような事件が起きた場合に、オーナー経営者は当事者ではなく「部下が引き起こした問題に巻き込まれた被害者」だと自分のことを思ってしまう傾向があるのだ。
なぜそうなるのか。今回の事件の場合、ポイントはタカタにとってエアバッグが新規事業であったことが背景にある。タカタは本来、シートベルトのメーカーである。しかし、世の中にエアバッグが登場して、その部品を安定供給してほしいメーカーの強い要請を受け、同社は新規事業としてエアバッグ製造を始めた。
本来は、完成車メーカーからの依頼を請け負った時点で経営者の責任になるはずなのだが、オーナー経営者の思考では「神輿に乗せられているうちに、部下や周囲から説得されてやり始めた」という受け身の考えが根っこに生まれてしまう。
そのうちに、「ぜひやってみせます」と言って始めたはずの部下たちの様子が変になってくる。「問題が起きまして」「損失が発生してしまいました」といった報告が上がるたびに、「最初に聞いていた話と違うじゃないか」とオーナー経営者はますます被害者意識を持っていく。おかしな話ではあるのだが、創業家オーナーはそういう心理に囚われがちなのである。
対応が後手後手に回った責任は
オーナー社長だけにあるのか?
2つめの問題として、オーナー経営者は責任をとるべき立場でありながら、判断材料を持っていないことが多い。特にうまくいっていない事業で問題が発生した場合、オーナー企業では部下が問題をきちんと細部まで報告しようとしない。これはオーナーを怖れるがゆえの部下の行動が引き起こすことで、結果としてオーナーは判断のための重要な情報を知らされないという状況に追い込まれる。
タカタの対応が常に後手に回った原因は、オーナー経営者が正しい判断材料を持っていなかったからではないかという疑念が、節目節目で感じられる。
なにしろ、今でもエアバッグの不具合の原因が完全に解明されていないという問題があるのだが、それでもここまでのニュースを総合すると、おそらくタカタ問題の論点は以下のようになるだろう。
(1)タカタのエアバッグが他社とは違う火薬を用いる構造で設計されている。
(2)それがアメリカのフロリダ州のような高温多湿な地域では、一定の時間が経つと変質し、爆発力が強くなる。
(3)それと同時に、部品の金属の製造過程ないしは設計上の問題があって、金属部品が火薬の爆発で吹き飛んでしまうことがある。
ところがオーナー経営者は、最初に問題が起きた当時は、原因は上記(3)だけだと報告を受けていたのではないかと思われる。私がそう考える理由は、当時その範囲に限定した対応しかタカタがとっていなかったからだ。
しかし、実際に死亡事故が起きたのは、上記(3)の問題とは関係ない部品を搭載した車だった。それで改めて、(1)や(2)の問題への対応を経営トップが迫られることになった。
それでもタカタは、「極めて例外的な環境下で起きる事故だ」と主張して、その後の対応を限定してきた。そのうちに複数の爆発事故が起きて、1つの事故現場で車内に金属片と血が散乱するという悲惨な映像が全米に流れ、タカタのイメージは地に落ちていく。
オーナー経営者が強い力を持つ企業では、不祥事が起きると部下がその影響を過小に歪曲化してオーナーに伝える傾向がある。少なくともタカタが下してきた経営判断を見る限りは、それと同じことがタカタのトップとその周辺で起きていたのは間違いないのではなかろうか。
タカタのトップ自身が
被害者意識を持ち続ける可能性
そして3つめの問題は、状況が極めて悪化した段階で、たとえトップが間違った行動をとっても、誰もそれを諌めることができなくなることだ。
タカタの場合は、ここ数年、アメリカの運輸当局や取引先の自動車メーカーが求める行動と、同社が実際にとっている行動のギャップがあまりに開きすぎていた。
創業家オーナーが正しいと考えて下している意思決定が、外部関係者の期待から外れた状態になっていく。しかしその段階で、それを諌めることができる人が近くにはいない。
それはそうだろう。そもそも正しい情報がきちんと上げられていない状況で、しかもオーナー経営者がそのことや事件そのものに対して被害者意識を持ってしまっていたら、諌めた人間は逆に強く叱られたり、攻撃されたりするのがオチだからだ。
こうして情報を知らされず、間違った対応を諌められずに状況を悪化させ、最悪の日を迎えるというメカニズムが、タカタの社内では予定調和のように回り続けたのだろう。そして創業家の高田重久会長兼社長は、責任をとってなお、心のどこかに被害者意識を持っていてもおかしくはないと私は思うのだ。
(百年コンサルティング代表 鈴木貴博)
調査しないと原因はわからないし、適切な対応策は取れないと思う。田舎特有のケースのように 長崎県漁業公社(同県佐世保市)の60代男性管理職はかなり強いコネを持っているのか?
長崎県漁業公社(同県佐世保市)の60代男性管理職が、部下に威圧的な言動を浴びせるなどのパワハラをした疑いがあることが28日、公社に出資する県への取材で分かった。管理職は「業務指導で感情が高ぶった」と説明し、反省しているという。
県によると、2013平成25年6月に就任したこの管理職の下で、昨年12月までに課長級の40代男性職員2人がうつ病を発症して退職した。県はこれを受け、今年1月時点で在籍していた全職員19人に聞き取り調査を実施。その結果、2人が管理職から威圧的な言動をされたと回答。8人が管理職のパワハラを見聞きしたと答えた。
公社や県は、相談窓口を設けるなどの再発防止策を取っていることを理由に、管理職の言動と職員のうつ病発症との因果関係を調査しない方針。
公社は長崎県が株式の約6割を保有する第三セクター。浜本磨毅穂副知事が社長を兼務する。
勤務先の知的障害児向けデイサービスを利用する女子中学生とみだらな行為をしたとして、神奈川県警少年捜査課などは28日、児童福祉法違反容疑で、児童支援員を務める社会福祉法人職員山口隆央容疑者(39)=同県寒川町宮山=を逮捕した。
容疑を認めているという。
逮捕容疑は5月27日、同県茅ケ崎市内のホテルで、中学2年の女子生徒(14)にみだらな行為をさせた疑い。
同課によると、女子生徒は軽度な知的障害があり、放課後に施設で自立支援を受けていた。山口容疑者は児童指導員の資格を持ち、女子生徒が利用するクラスで支援員を務めていた。みだらな行為を「3、4回した」と話しているという。
女子生徒の母親が、休日に娘と山口容疑者が一緒に出掛けるのを目撃し、施設に相談して発覚した。
和歌山市の大手原薬メーカー「山本化学工業」が、解熱鎮痛薬アセトアミノフェン(AA)の製造過程で、安価な中国製AAを無届けで混入していた問題で、和歌山県は28日、医薬品医療機器法(薬機法)に基づき、同社に29日から7月20日まで22日間の業務停止命令と、業務改善命令を出した。同社の山本隆造社長は県庁で、「世間の皆さまをお騒がせし、大変申し訳ない」と謝罪した。
和歌山県や厚生労働省によると、同社は市内の工場で作った粉末状のAAに、中国から輸入したAAを混ぜて製薬会社に出荷。また、てんかん発作やパーキンソン病の治療薬としても使われる抗てんかん薬ゾニサミドの製造でも、使用する薬剤を数年前に一部変更していた。
薬機法では製造方法を変更する際は医薬品を承認審査する独立行政法人「医薬品医療機器総合機構(PMDA)」に届け出る必要があるが、同社はいずれの薬剤についても必要な手続きを怠っていた。
5月下旬に県と厚生労働省が合同で立ち入り調査を実施。薬の品質自体に問題はなかったが、調査後、同社は全製品の出荷を自粛している。
徹底的に調べれば良いだろう!
中国産ウナギを「国産」と偽り提供したとして、愛知県警は水産物輸入販売会社の社長ら2人を、27日逮捕しました。
逮捕されたのは名古屋市中区金山の水産物輸入販売会社社長、村井三雄容疑者(47)と元従業員、駒田英之容疑者(56)です。
警察によりますと、村井容疑者らは、今年1月、福井市内で経営する「うなぎ割烹・曙覧(あけみ)」で、中国産ウナギにも関わらず、店のメニューやのぼりに「三河産ウナギ」などと表示し、国産ウナギと誤認させる表示をした不正競争防止法違反などの疑いが持たれています。
去年12月、保健所が「村井容疑者が輸入したウナギから基準を超える農薬が検出された」と告発し、今回の件が発覚しました。
調べに対し、2人は、容疑を否認していて、警察は、余罪などを詳しく調べています。
中国のレアメタル問題と同じ。不可避な問題が起きれば、それを克服しようする力や動きが必然的に発生する。
泣く人もいれば、笑う人もいる。数の多さは比較できないし、調べる事は出来ないが、一般的には両サイドは存在すると思う。
タカタが経営破綻という最悪のシナリオに追い込まれたのは、自社の責任逃れに終始して欠陥エアバッグ問題の早期解決への努力を怠り、消費者軽視で説明責任からも逃げ回った創業家3代目の高田重久会長兼社長の罪が大きいといわざるを得ない。
◆原因の所在認めず
「こういう経緯に至り、非常に責任を感じている」
26日、東京都内で記者会見した高田氏は、タカタを経営破綻に追い込んだ自身の経営責任をこう認めた。
タカタ製欠陥エアバッグの異常破裂が原因とみられる死者は米国だけで少なくとも11人に上る。しかし世界で多くの死傷者を出しながらタカタは「異常破裂が起きることは製造当時は予測困難だった」と逃げ続けた。装着状態などで自動車メーカーにも一定の責任があるとの見方すら示し、責任を押しつけた。高田氏はこの日の会見でもエアバッグの不具合について「なぜ、これが起きたのか分かっていない」とし、不具合の原因の所在が、なおタカタにあると認めなかった。
問題発覚後、高田氏は説明責任をほとんど果たしてこなかった。決算や株主総会などの機会があったにもかかわらず、実際に会見したのは2015年6月と同年11月、そして今回の3回だけだ。会見を開かなかった理由について、高田氏は「(再建計画の策定を昨年2月に委託した)外部専門家委員会が検討する再建計画に直接コメントするのは適切でない」とした。
専門家委にスポンサーを含めた再建計画策定を任せたからとはいえ、客観的な途中経過の説明くらいはできたはずだ。説明責任を果たさなかった高田氏に国内自動車首脳は、民事再生法適用前、「ふざけるな」と怒りをぶちまけた。「結果的に説明責任を果たせなかったのは、個人的に申し訳ない」。高田氏は会見で小さな声で謝っただけだった。
高田氏に責任逃れの経営が許されたのは、タカタ株の約6割を高田氏や親族らが保有しているためだ。大株主と経営トップが同じであるため、他の株主ら利害関係者の意見が反映されにくい構図だった。昨年6月の株主総会でも、高田氏ら取締役の再任議案は難なく採択され、一般株主からは「問題だと思う」という批判が集中していた。
しかも、高田氏は経営再建策の策定を専門家委に一任するとしながら、再建策の検討過程では口を挟んだ。裁判所が関与する法的整理ではなく、当事者間で再建策を協議する私的整理を求め続けた。法的整理を行えば信用不安に陥り、取引先からの部材の供給が滞って、エアバッグなどの安定供給に支障を来す恐れがあると主張した。
高田氏は会見でも「われわれがやっている部品の供給が停止すれば自動車業界全体に非常なインパクトを与えると考えた」と述べ、なおも正当性を強調してみせた。
◆埋められた外堀
しかし、専門家委が2月にスポンサー企業として推薦した米自動車部品会社キー・セイフティー・システムズ(KSS)と、取引先の自動車各社の考え方は違った。まずKSSが支援の条件として法的整理を求めた。再建支援には、裁判所が関与して債務を確定させることが不可欠としたためだ。自動車各社も、タカタの責任があいまいになる私的整理を選んで、話し合いによって債権放棄をすれば、株主代表訴訟を起こされる恐れがあった。加えて、事故被害者からの損害賠償請求といった将来のタカタ関連損失リスクを断ち切るためにも、債権放棄になっても、法律にのっとった手続きを求めることが不可欠と判断され、タカタの外堀は完全に埋められた。
タカタにとって追い打ちとなったのが今月中旬、民事再生法の適用申請方針が伝わったことだ。資金繰りを支援してきた金融機関にも取引条件を厳しくする動きが広がり、タカタには私的整理という選択肢は残っていなかった。(今井裕治)
和歌山市の大手原薬メーカー「山本化学工業」が、風邪薬の成分として使用される解熱鎮痛剤アセトアミノフェン(AA)の製造過程で、安価な中国製AAを無届けで混入して水増し製造し、製薬会社に出荷していたことが22日、厚生労働省への取材で分かった。薬の品質に問題はなく、健康被害の恐れもないという。医薬品医療機器法(薬機法)違反の疑いがあり、指導権限を持つ和歌山県が近く処分する方針。
AAは、市販の風邪薬などに含まれ、解熱や鎮痛の効果がある。同省によると、山本化学は和歌山市内の工場でAAを製造していたが、自社で作った粉末状のAAに中国から輸入したAAを混ぜて出荷していた。製造コストを下げる狙いがあったとみられる。
薬機法では、薬を製造する場合、名称や成分、製法などを、独立行政法人「医薬品医療機器総合機構(PMDA)」のデータベースに登録する必要がある。登録内容を変更する場合は新たな届け出が必要だが、山本化学は中国製AAを使用する製法を機構に届け出ていなかった。また、販売先の製薬会社にも中国製を使用していることは伝えていなかった。
「中国製AAが混ぜられている」との情報が同省に寄せられ、5月下旬に同省と県が共同で立ち入り調査を実施。中国製を混入したとみられるAAの品質などを調べたが、目立った問題はなく、使用した場合も健康被害が発生する恐れはないという。調査後、同社はAAを含む全製品の出荷を自粛している。
山本化学は取材に対し、「社長が会社に来るかどうか分からない。話せない」などと答えた。
医薬品原料メーカーの山本化学工業(和歌山市)が風邪薬に使われる解熱鎮痛剤アセトアミノフェンを製薬会社に出荷する際、別に仕入れた中国製品を無届けで自社製品に混ぜて水増ししていたことが22日、厚生労働省への取材で分かった。
中国製のアセトアミノフェンは品質面に問題はなかったが、同社は全製品の出荷を自粛。和歌山県が近く業務停止命令を出す見通し。
厚労省によると、同省が情報提供を受け、5月に医薬品医療機器法に基づき和歌山県と立ち入り調査を実施した。会社側は「注文が相次いで製造能力を超えてしまい、数年前から中国製を輸入するようになった。国産数ロットにつき中国製1ロットを混ぜて出荷していた」と説明したという。
山本化学は社員約30人規模だが、アセトアミノフェンの製造では国内シェアの8割を占め、少なくとも数十社に出荷している。
中国で適切に保存されていなかったインフルエンザや水痘などのワクチン約200万本が違法販売され、学校や病院などで子供らに投与されていた問題が波紋を広げている。不安を抱いた市民が本土外でワクチン接種を希望するケースが急増。これに危機感を抱いた香港当局が接種制限を設ける事態へと発展しているという。日本への影響も懸念されている。
新華社電などによるとワクチンは、正規企業の製造だったが、低温保管などの規定を守っていなかった。適正に扱われていないワクチンの接種は効果がなく、副作用の可能性もあるという。
違法ワクチンの販売は計24の省・自治区・直轄市で計25種類約200万本に上り、取引額は計5億7000万元(約98億円)に達していた。
最高人民検察院は捜査に乗り出し、販売に関わったとみられる一部を拘束。違法ワクチンを医薬品会社などから安く入手し、ネットで転売していた山東省の元薬剤師の女(47)と元医大生の娘も拘束された。
中国のワクチン管理の杜撰さはこれまでも指摘されてきた。中国事情に詳しいジャーナリストの奥窪優木氏は「農村部などで多いのは、医療関係者が金を巻き上げる目的で生理食塩水などをワクチンと偽り、子供に接種するといったケースだ。『麻疹のワクチンを接種したのに麻疹になった』といった話題も多い。ワクチン接種が原因とみられる死亡事案や障害が出たとする事案も発生しており、ワクチンに対する不信感は中国全土で広がっている」と話す。
中国メディアなどによると、事件を受け、本土市民らが、医薬品の管理が厳しいとされる香港の病院でワクチン接種を希望するケースが急増。一部地域では、4月分の予約がすべて埋まるといった現象も発生している。
危機感を募らせたのが香港市民だ。香港衛生署は、市民に優先的にワクチンを分配するため、31カ所の公的医療機関では4月1日から、香港以外の地域の子供に提供するワクチンは「月120回までとする」と発表。平均すると、各院の上限は4回までということになるという。
日本を目指す動きも出始めている。東京都内の医療機関では問題が発覚した3月下旬頃から「子供にワクチンを接種したいが、予約は可能か」といった中国人からの問い合わせが相次いでいる。
「今のところ、急を要する風ではなく『旅行のついでに』といった気軽なものが多い。個人の他に、エージェントを通じた問い合わせも来ているので、数は増えることも予想される」と担当者。
ワクチンは外国人も国内での接種は可能。ただ香港のように中国本土から予約が殺到すれば、市民の予約に支障が出てくる恐れもある。
都内のクリニックは、「うちは完全予約制なので仮に予約が殺到しても在庫数を予想して購入をかけていくため、ワクチンが底をつくということは考えにくい」と説明。「ただ、多くが外国人の予約で埋まり、日本人の接種予約が難しくなるといった事態は想定していない」と語る。
中国では近年、食品や薬品の安全に関わる事件が頻発。2008年には国有企業が生産する粉ミルクに有毒物質メラミンが混入していたことが分かり、国産の粉ミルクを買わず、日本産のものを購入する保護者が急増したという過去もある。同様の現象はワクチン接種でも起るかもしれない。
財務省や文科省の隠ぺい体質が伝染したのか?そんな事はないと思うが、わからなければ嘘や隠ぺいで対応する考え方は良くないと思う。
氷山の一角であれば、他の製品や他の原薬メーカーでも行われている可能性も高い?
下記のサイトでは心配する必要はないと書いているが、中国だから何があってもおかしくない。運良く、問題となっていないだけかもしれない。
問題がなければ、中国製のAAを使う事を申請すれば良いと思う。ただ、申請が受け入れられるのか、許可で出るまでの期間については全く知識が
ないので、簡単には申請しない理由があったのかもしれない。
薬と加計学園の獣医学部新設を同じレベルで考えることは間違っていると思うが、あれだけおかしな対応や調査がまかり通るのに、「風邪薬成分、安価な中国産で水増し」
は問題だと言うのであれば、どうして基準が違うのかと思う。権力やお金の話と言う事なのか?
山本化学工業の評判とアセトアミノフェンを使った薬は?安全性も注目 06/22/17(FXから地元ネタまで学ぶ!1年目総務の学習日記)
沢伸也、杢田光
多くの風邪薬で使われている解熱鎮痛剤のアセトアミノフェン(AA)製造で国内最大手の原薬メーカー「山本化学工業」(和歌山市)が、自社で作ったAAに安価な中国製AAを無届けで混ぜて水増しし、製薬会社に出荷していたことがわかった。医薬品医療機器法(薬機法)違反にあたり、厚生労働省が5月に立ち入り調査を実施。指導権限を持つ和歌山県が近く処分する方針だ。
民間調査会社によると、国内でAAを製造しているのは2社で、山本化学が国内シェアの約80%を占めている。AAを仕入れた製薬会社が調合して風邪薬をつくり、病院で渡される薬や市販薬として広く販売している。厚労省の立ち入り後、同社はAAのほか全製品の出荷を自粛している。
関係者によると、山本化学は、米国産の原料などを使い、和歌山市内の工場でAAを製造している。しかし、これとは別に中国で作られた安価なAAを輸入し、自社で作ったAAに混ぜて出荷していたという。費用を節減し、生産量を上げるためとみられる。
山本化学の関係者は「少なくとも数年前から、中国製を1~2割混ぜていた」と話している。
薬の製造方法や使用原料は、医…
基本的に相手を信用してはいけない。騙されても仕方がない、又は、何も出来ないと感じる時は受け入れるしかない。答えは一つではないし、 正解であると確認できないケースはこの世の中に存在する。やはり、正直者は馬鹿を見る傾向が高い。
今回の件に関して多くの国民はどう感じているのだろうか?
加計学園の獣医学部新設をめぐり、文部科学省は萩生田官房副長官が局長と面会した時の発言を記録したとする新たな文書の存在を認めましたが、個人の備忘録だとして行政文書ではないと主張しました。これに対し、専門家は「省内で複数の職員が共有した文書であり、行政文書であることは法的に疑いがない」と指摘しています。
加計学園の獣医学部新設をめぐり、文部科学省は、去年10月21日に萩生田官房副長官が文部科学省の局長と面会し、官邸や内閣府の考えを伝えた発言をまとめたとする文書について、20日存在を認めて公表しました。
この文書の性質について、文部科学省は「職員の個人的な備忘録で不正確な内容が含まれている。本来、共有すべきものでない」として行政文書ではないと主張しました。
公文書の管理について定めた法律では、行政文書は「職員が職務上作成し、組織的に用いるため行政機関が保管しているもの」と定義されています。今回見つかった文書は専門教育課の共有フォルダーから見つかり、3つの部署の少なくとも6人の職員にメールで送られ、共有されていたと文部科学省も認めています。
東京のNPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は「書かれている内容の正確性にかかわらず、職務上作成したものを複数の職員が共有しており、法的に行政文書であることに疑いはない。第三者による調査を実施して不透明な決定過程を国民に明らかにすべきだ」と指摘しています。
このような対応は間違っていると思し、卑怯で狡いと思う。ただ、これが現実であるのなら、改善されるべきだと思うし、 公務員や公的組織を簡単に信用してはいけないと思う。
菅義偉官房長官は21日午前の記者会見で、学校法人「加計(かけ)学園」の獣医学部新設計画を巡り、萩生田光一官房副長官が早期開学を文部科学省に迫ったとする同省の文書について「作成した本人(専門教育課課長補佐)の意識としては個人のメモということで、行政文書のつもりではなかったと聞いている」と述べた。情報公開法などに基づき、保存・公開の対象となる行政文書には当たらないとの認識を示したものだ。
また、菅氏は今回の文書の取り扱いについて「文科省で適切に対応する」と語った。【田中裕之】
メモや文書の方が信頼性が低く、正確性が劣るのであれば、文書やメモの必要はなくなる。文書やメモは全ての記憶がロングタームメモリー(長期記憶)でない場合の補足、忘れかけた記憶を結び付けて 思い出させるなどの機能がある。
それを否定すればこの世の中の多くを否定する事になると思う。
短期記憶のメカニズムを説明する基礎理論 (総合心理相談 ES DISCOVERY)
「総理は『平成30年4月開学』とおしりを切っていた」――。加計(かけ)学園の獣医学部新設計画に揺れた国会が閉会した2日後の20日、計画を巡る文部科学省の新たな文書がまた明らかになった。政権幹部や閣僚らは終日弁明に追われたが、苦しさも見える。
「正確性の面で著しく欠けていたメモが外部に流出した。副長官には大変迷惑をかけたと考えています」
20日午後。松野博一・文部科学相は新たに公開した萩生田光一・官房副長官の「ご発言概要」と題した文書について、こう言った。
萩生田氏と文科省の常盤豊・高等教育局長との面会内容を記したという文書。その存在を認める一方、松野氏が謝ったのは「副長官の発言でない内容が含まれている」との理由だ。
松野氏は今回の文書について、萩生田氏と常盤氏の発言に加え、作成者の課長補佐が内閣府などから集めた情報の「三つの内容が混在している」と説明。文書を公表した午前中の会見ではなかった「(文書は)正確性に著しく欠けていた」という表現を用い、文科省の落ち度をより強調した。
しかし、萩生田氏でなければ、文書に盛り込まれた発言は誰のものだったのか。この点について、松野氏らから明確な説明はないままだった。義本博司総括審議官は「(局長らの)記憶が定かでない」などと繰り返した。
午後にあった菅義偉官房長官の会見では具体的な言及を避ける姿が目立った。
「萩生田副長官が発言を否定しているが、なぜ文科省からこうした文書が出てくるのか」との質問に、菅氏はこう答えた。「私が聞きたいです」。文書の内容について印象を問われると、「萩生田副長官がコメントを発したとおりだと思う」とだけ述べた。
文書には加計学園事務局長の実名などが記されている。獣医学部の新設計画が「加計ありきだったのでは」との質問には、「今治市は設置のきちんとした提案を出している。話題として出るのは当然」と強調。そのうえで「文書の詳細については文科省から確認してほしい」と繰り返した。(根岸拓朗、岡戸佑樹)
■「ご注進」の職員、実は連絡役
「直接の担当者でもない。陰で隠れてご注進した」。山本幸三・地方創生相にそう非難された内閣府の職員が、実は特区について他の省庁との連絡役を務める担当職員だったことが明らかになった。20日午後にあった民進党の調査チームの会合で、内閣府の担当者が認めた。
一般人かも知れないが、新聞や報道関係の仕事でこのコメントは?????文書の編集や日本語の知識はかなりあるのかもしれないが、 記者やジャーナリストとしてはアウトだと思う。
ご先祖さまも被災した 震災に向きあうお寺と神社 小滝ちひろ/著 (オンライン書店e-hon)
著者紹介
小滝 ちひろ (コタキ チヒロ) 1962年、福島県いわき市生まれ。朝日新聞編集委員(大阪本社在勤、古社寺、文化財担当)。 上智大学新聞学科卒業後、朝日新聞社に入り、AERA編集部員、大阪本社地域報道部員、松山・高松両総局デスク、奈良総局員兼編集委員(古社寺、文化財担当)を経て現職 (本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
朝日新聞大阪本社の小滝ちひろ編集委員が、静岡県・伊豆半島沖で米海軍のイージス駆逐艦とコンテナ船が衝突した事故について、同社公認のツイッターに「不明の乗組員にはお気の毒ですが、戦場でもないところでなにやってんの、と。」と書き込み、その後削除して謝罪していたことが20日、分かった。
小滝氏は17日に投稿、19日に削除し、ツイッター上で「米軍・コンテナ船事故に関するツイートを削除します。事故に遭われた方やそのご家族への配慮に欠け、不適切でした。不快な思いをされた方々におわびします」と謝罪した。
同社広報担当によると、インターネット上に批判が集まり、社内からも不適切との指摘があったという。
小滝氏は1986年に入社、高松総局次長などを経て、2006年から編集委員を務め、社寺や文化財の取材を担当している。
◇
■古川伝(つたえ)・大阪本社編集局長の話 「多くの犠牲者が出た事故であり、ご遺族や関係者のみなさまへの配慮に欠けた投稿だったと受け止めており、おわび申し上げます」
伊藤嘉孝
格安航空会社(LCC)のバニラ・エアは19日、成田空港で18日夜、香港から到着した国際便の乗客34人が入国審査を素通りするミスがあったと発表した。着陸後、バスが誤って国内線到着口に客を運んだ。不審に思った客の通報で発覚。同社の館内放送での呼びかけに応じ、24人は戻って審査を受けたが、残り10人はそのまま空港外に出たとみられ、同社が連絡を取ろうとしている。
トラブルがあったのは、18日午後10時13分に到着した香港発便。乗客168人は着陸後、バス3台に分かれ、入国審査のため国際線到着口に向かうはずだったが、うち1台が誤って国内線到着口に客を降ろした。乗っていた34人は、入国審査を受けないまま空港の制限区域外に出た。
その後、誤りに気づいた客の1人が空港職員に申し出て発覚した。すぐに同社が館内放送で客に戻るよう呼びかけ、24人が戻って入国審査を受けたが、残り10人は現れなかった。日本人9人と米国人1人だという。すでに空港外に出ているとみられ、同社が手続きを呼びかける連絡を取ろうとしている。
成田空港では昨年4月にも、台北から到着した同社便の客47人が、入国手続きを済ませないまま入国するトラブルがあった。今回と同様、バスが誤って国内線到着口に客を届けていた。
国土交通省は19日午後、同社を厳重注意する方針。(伊藤嘉孝)
東京電力福島第一原発事故の除染事業を巡り、準大手ゼネコンの安藤ハザマ(東京都港区)が福島県田村市などから受注した事業の宿泊費を水増ししたとして、東京地検特捜部は19日までに、詐欺容疑などで同社などの関係先を家宅捜索した。特捜部は同社関係者から事情聴取を進めており、押収した資料をもとに、水増しの経緯などを調べる。
水増し請求が明らかになっているのは、2012~15年に福島県いわき市と田村市がそれぞれ発注した除染事業。同社の説明によると、いわき市の事業では、下請け業者に対し、作業員1人当たりの宿泊単価を2500円、人数も約4300人分水増しした領収書を作成するよう指示した。田村市の事業でも、同じ下請けに対して宿泊単価を500円、人数を約4500人分水増しした領収書を作らせたという。
東日本大震災の復旧事業では、国が労働者の宿泊費について最終的に実費精算することを認める通達を出している。この精算の際には、領収書など支払いを証明する書類を提出するよう求められている。
特捜部は、安藤ハザマの担当社員らに対し、宿泊費をだまし取る意思がなかったかどうかなどについて任意聴取していた。
辞めてしまえば、失うものがなくなる。もう悩む必要がないから、言えることもある。
卑怯だと言うのであれば、森友学園に関する財務省だったり、調査をあえて限定的に絞った文科省幹部ではないのか?
適切な調査も行わず、国民の批判が強くなったから再調査を行い、怪文書と呼ばれるものが見つかった。怪文書と呼び、適切な調査を行わなかった、 又は、間接的に指示した人々の方が卑怯と呼ぶにふさわしいのではないのか?
内閣支持が下がって来ているのは、多くの国民が納得できていないし、正しいと主張している人達を信用していない事を反映しているのでは?
自民党の下村博文幹事長代行は18日、学校法人「加計学園」の獣医学部新設問題をめぐり、野党が求めている閉会中審査の開催について「新たな事実が出てくればあり得る。今の段階でやることは考えていない」と述べた。
都内で記者団に語った。
これに先立つNHKの討論番組で、野党側は前川喜平前文部科学事務次官らの証人喚問も要求。この中で、下村氏は「役人の時に言うべきことを言わず、辞めた後にああだこうだ言うのはひきょうだ」と前川氏を批判。同氏の国会招致に関しては「いまさら国会で聞くことはない」と否定した。
このような事態になる前に他の選択肢はなかったのか?アメリカ相手に強硬な対応を取って勝てる見込みがないのであれば、別の選択肢を取るべきでは なかったのか?
まあ、個人的に関係ないのでどうなっても良いが、中国企業に食い物にされるのは残念。
問題を初期段階で対応していれば、このような事態は避けられたと思う。まあ、組織全体の責任なので直接的に責任が無くても、社員達は負の影響を受け入れるしかない。
[東京/ニューヨーク/ワシントン 16日 ロイター] - 欠陥エアバッグの大規模リコール(回収・無償修理)問題で経営が悪化しているタカタ<7312.T>が早ければ来週にも民事再生法の適用を東京地裁に申請する方向で準備に入った。複数の関係筋が15日までに明らかにした。負債総額は1兆円超とみられ、タカタは事業を継続しながら裁判所の管理下で再建を図ることになる。
関係筋によれば、米国子会社のTKホールディングス(ミシガン州)も日本の民事再生法に当たる米連邦破産法11条の適用を申請する方針。タカタは出資を伴う支援企業として中国・寧波均勝電子<600699.SS>傘下の米自動車部品メーカー、キー・セーフティ・システムズ(KSS)と協議を続けているが、日米での適用申請前にKSSとの最終合意に至らない可能性もあるという。
再建計画ではKSSがタカタのシートベルトなど主要な事業を総額2000億円弱で買収して新会社を設立。一方、リコール費用などの債務は旧会社に残し、債権者への弁済を担う。部品の安定供給を維持するため、取引金融機関はタカタの下請け会社などへの資金支援を続ける。
タカタ製エアバッグのリコール問題をめぐっては、関連事故で米国など海外で死亡者が16人、負傷者が180人超に上っている。リコール対象は世界で1億個規模に膨らみ、費用の総額も1兆円を超える見通し。
タカタはこれまで不具合の責任の所在が特定できておらず自動車メーカーとの費用負担の割合を「合理的に見積もるのは困難」としていた。そのため、ホンダ<7267.T>など国内外の自動車メーカー各社はリコール費用の大半を負担しており、今後は同費用を債権として届け出る予定だ。
タカタは昨年2月、弁護士などからなる外部専門家委員会を発足させ、再建計画の策定を委託。同委員会と最大債権者である自動車メーカーは、法的整理を前提としたKSS主導の再建策を練っていた。
しかし約6割の株式を保有する高田重久会長兼社長らタカタ創業家は、法的整理に踏み切れば下請け会社からの部品供給が滞るとして、日本のタカタについて裁判所の関与しない当事者間の話し合いによる私的整理を主張し続けてきた。
ただ、私的整理で大口債権者と合意できたとしても、事故の被害者などからの損害賠償請求による財務悪化は避けられず、創業家も法的整理を受け入れざるを得なくなったとみられる。
タカタの2017年3月期の連結決算は最終損益が795億円の赤字(前期は130億円の赤字)で3年連続の最終赤字だった。自己資本は約302億円。自己資本比率は前期の27.5%から17年3月期は7.0%と急減していた。
*内容を追加しました。
(Jessica DiNapoli,David Shepardson, 白木真紀)
LE VELVETS 黒川拓哉 出身高校の彼女と結婚、離婚?理由は身長? 06/15/17(タケちゃんのレロレロポンチ)
ボーカルグループ「LE VELVETS」のメンバー・黒川拓哉容疑者(32)は去年9月、川崎市のホテルで、女子中学生(当時15歳)に現金1万3000円を渡してみだらな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、黒川容疑者はSNSの無料通信アプリを使い、援助交際を呼び掛けるような書き込みをしていましたが、「ホテルに行ったことは間違いないが、身に覚えがない」と容疑を否認しています。黒川容疑者は、歌手としての活動の他にミュージカルにも出演していたということです。
◇今治市議会の資料で分かる
安倍晋三首相の友人が理事長を務める学校法人「加計学園」が愛媛県今治市で獣医学部を新設する計画を巡り、内閣府が昨年2月の時点で「学生が集まるのか」と懸念を示していたことが、今治市議会の資料で分かった。ところが、競合する大学もある中、内閣府はその後も市側と連携しながら2018年4月開学を推し進めていた経緯が浮かび、野党側は加計学園を前提に手続きを進めていたとして批判を強めている。【松井豊、小林祥晃、遠藤拓】
毎日新聞が入手した資料によると、昨年2月9日に市議4人が内閣府の藤原豊地方創生推進室次長(現審議官)らと国会内で面会。内閣府側から「(市の)新設大学への財政支援による今後の財政悪化や、人口減少により学生が本当に集まるのか」との指摘を受けたとされる。ところが、昨年3月8日の市議会本会議では菅良二市長が「最速で平成30(18)年4月の開学となれば大変ありがたい」と表明。同4月21日に市議会特別委の協議会で配布された資料のスケジュール表にも「最速でH30・4開学(予定)」と書かれている。
さらに、情報公開条例に基づき開示された市の資料では、市が特区に指定される以前の15年4月2日の時点で、市の担当課長らが獣医師養成系大学の設置に関する協議のため首相官邸と内閣府を訪問したことも判明。今月8日の参院農林水産委員会で自由党の森裕子氏が資料に基づき事実関係をただしたが、萩生田光一官房副長官は「記録が保存されていないため確認できなかった」と答弁。藤原氏も「自分が会ったかどうかも含めて市との面談は確認できていない」とし、森氏は「これで公正に加計学園が選ばれたなんて国民が納得するのか」と批判した。
獣医学部新設を巡っては、京都産業大も京都府内での新設を希望していたが、京都府側は「18年4月開学」について内閣府が昨年11月18日に公式に発表して初めて把握し、準備が間に合わないとして見送った経緯がある。特区を担当する山本幸三地方創生担当相は国会で「(開学時期を)事前に今治市に対しても、京都府に対しても一切申し上げていない」と答弁している。
お金が無ければほしい商品があっても購入できないが、カードが使えれば、衝動や欲望を抑える事が出来ない人達が購入する。 返済問題が起きても、世間体や子供や親戚のためにお金を出したり、貸す親や親戚がいるので、親は親、子供は子供と割り切る文化の国よりも 回収できる確率は高いであろう。
全国銀行協会がカードローン審査見直しと言ってもチェックして思い罰則を実行しないと効果は限定的だと思う。
富士フイルムホールディングス(HD)は12日、グループ企業の富士ゼロックスの海外販売子会社で不適切な会計処理が2010年度から15年度まで6年間行われ、損失額が累計375億円に上ったと発表した。富士ゼロックスの山本忠人会長と吉田晴彦副社長を22日付で解任し、富士フイルムHDの古森重隆会長と助野健児社長が役員報酬の10%を3カ月間返上して責任を明確化する。
海外会社で不適切会計=決算を延期-富士フイルムHD
富士フイルムHDは12日、弁護士らで構成する第三者委員会の調査報告書を公表した。数年間で220億円と見込んでいた損失が拡大。富士ゼロックスの吉田副社長が不適切会計の隠蔽(いんぺい)を指示していたことが判明した。報告書は内部統制に問題があり、売り上げ至上主義の社風もあったなどと指摘した。
記者会見した富士フイルムHDの助野社長は「決算発表が遅れ、ステークホルダー(利害関係者)に心配を掛けた」と陳謝した。富士ゼロックスは75%を出資する子会社だが、「独立の気概が強く、細かいことを言ってこなかった」と説明。ガバナンスを強化するため、古森氏ら5人を取締役として派遣することを決めた。富士ゼロックスでは古森氏が会長を兼務。栗原博社長が賞与30%と役員報酬の20%を3カ月間カットする。
不適切な会計処理は富士ゼロックスのニュージーランドとオーストラリアの販売子会社で見つかった。複写機などのリース取引で、機器本体を売り上げに計上後、使用量に応じて代金を回収する契約だったが、これに該当しない契約を含める形で売り上げをかさ上げしていた。
お金が無ければほしい商品があっても購入できないが、カードが使えれば、衝動や欲望を抑える事が出来ない人達が購入する。 返済問題が起きても、世間体や子供や親戚のためにお金を出したり、貸す親や親戚がいるので、親は親、子供は子供と割り切る文化の国よりも 回収できる確率は高いであろう。
全国銀行協会がカードローン審査見直しと言ってもチェックして思い罰則を実行しないと効果は限定的だと思う。
全国銀行協会は12日、個人に無担保で貸し付けるカードローンの過剰融資防止に関する調査結果を公表した。審査を厳格化するため、3月以降、年収に対する貸付総額の割合を貸金業法と同じ3分の1にするなどした銀行は、全体の7%(8行)にとどまり、60%(73行)が「検討中」と回答した。
全銀協は、カードローンで過剰な貸し付けが行われているとの指摘を受け、配慮に欠けた広告や宣伝の抑制、審査の見直しなどを3月に申し合わせた。調査は会員行のうち、カードローンを扱う123行を対象に5月に実施し回答を得た。
調査によると、3月以降、貸し付けの際に年収証明を求める融資額を引き下げたのは、11%(13行)で、検討中は83%(102行)。従来の「200万~300万円超」を「50万円超」に引き下げるケースが多いとみられる。広告については、123行全てが「見直し」または「見直しを検討する」と回答した。
個人の自己破産の申請が2016年に前年比1.2%増の6万4637件となり、13年ぶりに増加したことが10日、最高裁の統計(速報値)で明らかになった。自己破産はこれまで、消費者金融などへの規制強化で減少が続いてきた。増加に転じた背景には、無担保で個人に融資する銀行のカードローン事業の急拡大があるとみられる。
個人の破産申請は、1990年代後半に急増。03年に24万2357件まで達した後、翌年から15年までは12年連続で減少した。
急増した当時、返済目的で別の借金を繰り返す多重債務者の自殺などが社会問題化した。消費者金融への批判が高まり、06年にはノンバンクからの借り入れを年収の3分の1までに制限する改正貸金業法が成立。利息制限法の上限を超える過払い利息の返還請求も相次いだ。
この結果、ノンバンクの消費者向け無担保貸付残高は、05年度末の17兆6399億円から15年度末に4兆4438億円まで減少した。しかし、これに代わって11年ごろから銀行のカードローン残高が急伸。日銀の統計によると、16年末は5兆4377億円で、5年間で1.6倍に拡大した。
道徳の授業を最低200時間ほど取らせる必要がある。道徳の授業は無駄とも思えるのでやめた方が良い。
加計学園の獣医学部の新設計画をめぐり、去年9月、加計学園側が獣医学部の構想を松野文部科学大臣に直接伝えていたことが、同席していた関係者への取材でわかりました。
安倍総理の友人で加計学園・理事長の加計孝太郎氏は、去年9月6日、文部科学省を訪れ松野文部科学大臣と大臣室で面会したことが分かっています。松野大臣はこの面会について、「大臣就任を受けての挨拶で獣医学部に関する話は一切なかった」と説明しています。
しかし、面会に同席した加計学園の当時の幹部がJNNの取材に対し、加計学園側が獣医学部の構想を大臣に直接、伝えていたことを認めました。その際、加計学園側は「今度、四国に考えているのでよろしく」などと伝えたということです。
「去年9月6日にお会いになった際に、加計理事長と獣医学部の話をしてますよね?」(記者)
「してません」(松野博一 文部科学相)
一方、松野大臣はJNNの取材に、去年9月の面会では獣医学部に関する話はなかったと否定しています。
学校法人「森友学園」(大阪市)が大阪府と国の補助金を不正受給した疑いが強まったとして、検察当局が籠池泰典・前理事長(64)を詐欺と補助金適正化法違反の両容疑で立件する方針を固めたことが分かった。大阪地検特捜部は任意で関係者の聴取を進めているが、今月中にも強制捜査に踏み切る方向で検討している模様だ。国有地の売却をきっかけとした一連の疑惑は、刑事事件に発展する見通しになった。
◇月内にも強制捜査
不正受給の疑いがあるのは、学園が運営する塚本幼稚園(大阪市)に交付された大阪府の補助金と、大阪府豊中市の国有地で開校を計画していた小学校建設に伴う国土交通省の補助金。
府によると、籠池前理事長は在職中の2011~16年度、勤務実態のない教員を補助対象とする虚偽の書類を提出するなどして、幼稚園の専任教員数に応じた補助金約3440万円と、障害などで支援が必要な園児数に応じた補助金約2740万円をだまし取った疑いがある。
府の調査で、学園側が申請した教員のうち延べ25人は勤務実態がなかったり、系列保育園の職員を兼務したりしていた。障害児についても、補助金交付の条件となる支援をしていないなどの不正が判明。府は5月、学園に返還を命じ、詐欺容疑で特捜部に告訴した。
一方、国交省の補助金は木材を生かした建築物を対象に工事費などを補助する仕組み。15年7月、学園は工事費を約23億円と見積もって補助金の適用を申請。その後、約15億円で建設業者と工事請負契約を結んだが、国側にはこの契約書を提出せず、工事費を約23億円とする別の契約書を提出し、今年2月までに約5600万円を不正に受け取った疑いがある。
学園が小学校の設置認可申請を取り下げたことに伴い、国交省は補助金の返還を命令。学園は3月に全額を返還した。
特捜部は高松市内の男性から告発を受け、補助金申請の代理人だった設計業者や建設業者らを任意で聴取。府の補助金についても府職員や園児の保護者らから聞き取りを進めていた。
特捜部はこの他、財務省近畿財務局が国有地を不当に安く学園に売却したとする背任容疑での告発などを受理し、捜査を進めている。【三上健太郎、岡村崇】
学校法人「加計(かけ)学園」の獣医学部新設を巡り、「総理のご意向」と記された文書の存在が表面化した後、前川喜平・前文部科学事務次官が在任中に「出会い系バー」に出入りしていたと報道した読売新聞が、3日朝刊に「次官時代の不適切な行動 報道すべき公共の関心事」との見出しの記事を掲載した。原口隆則・東京本社社会部長が署名入りで、報道への批判に対して反論を展開する異例の内容だ。記事は「公共性・公益性がある」と強調するが、「説得力を欠く」とする声が出ている。
読売新聞は「前川前次官 出会い系バー通い」と題した先月22日朝刊の報道について、3日の記事は「不公正な報道であるかのような批判が出ている。こうした批判は全く当たらない」とした。さらに「一般読者の感覚に照らしても、疑念を生じさせる不適切な行為であることは明らかである」「次官在職中の不適切な行動についての報道は、公共の関心事であり、公益目的にもかなうものだと考える」と論じた。
読売新聞社会部記者出身のジャーナリストの大谷昭宏さんは、反論は説得力を欠いて新聞の信用性を損なうものだと指摘する。「社会部長は『公共性・公益性があった』と説明するが、新聞記事はすべてが公共性・公益性があると考えて書かれるものであるはずだ。記事は批判されることも、おほめをいただくこともあるが、そのたびに説明する記事を書くだろうか。このような反論記事は新聞の自殺行為だ」と話す。
服部孝章・立教大名誉教授(メディア法)は「まるで社告のような記事で、読んだ人は違和感を覚えただろうし、批判していた人は納得できないだろう」と話す。先月22日の報道については「加計学園を巡る文科省の内部文書の報道後に、スキャンダルで本質的な問題を薄めるような記事で、むしろ公共の関心事をゆがめている。問題の渦中ではどちらか一方に加担していると取られないように慎重になるべきだ。『出会い系バー』報道は、前川氏に違法行為があったかのような印象を与える書き方をしているが、十分な裏付けが書かれていない。名誉毀損(きそん)が成立する可能性がある」と指摘する。
前川氏は先月25日の記者会見で、読売新聞の報道について「(バーに)行ったのは事実」と認めたうえで違法行為を否定し「個人的行動をなぜあの時点で報じたのか、全く分からない」と述べた。
読売新聞グループ本社広報部は「当社の見解は紙面に掲載した通りだ。5月22日の記事について名誉毀損に当たる恐れはないかとのおたずねだが、記事の内容は真実であり、公共性・公益性があることも明らかなので、名誉毀損に当たるとは考えていない」とコメントした。【青島顕】
安藤ハザマだけの問題なのか、それとも氷山の一角なのか?
東京電力福島第1原発事故をめぐり、複数の自治体が発注した除染事業を元請けとして受注した準大手ゼネコン「安藤ハザマ」(東京)が平成26~27年、作業員の宿泊人数や宿泊単価を改竄(かいざん)した領収書を作成し、自治体側に提出していたことが6日、複数の関係者への取材で分かった。領収書上の改竄額は8千万円を超える。除染事業完了後の最終精算時に、改竄された領収書に基づいて除染費が不正に取得された疑いがある。産経新聞の取材に、同社は社内調査を始めたとした上で「現時点では回答できない」としている。
除染費を不正に取得していた場合、安藤ハザマの行為は詐欺罪や有印私文書偽造・同行使罪に抵触する恐れがある。また、公共工事に一定期間参加できなくなる指名停止などの行政処分が科される可能性もある。除染費の原資は国費。
安藤ハザマは福島県内の自治体や国が発注した除染に共同事業体を組むなどして参加。国が実施中の浪江町の除染も手掛けている。
領収書の改竄が確認されたのは、いわき市が発注し、24年10月に同社が落札した除染事業(約27億円)と、田村市と同社が25年8月に随意契約を結んだ除染事業(約40億円)。
産経新聞が入手した安藤ハザマと、1次下請け会社の1社(千葉市)の担当者間の電子メール記録によると、いわき市での除染終了後の26年9月、安藤ハザマ側から1次下請け側に「宿泊費の領収書を指示通りに作成してほしい」との依頼があった。
この1次下請けは除染事業への参入に当たり、いわき市内の旅館を買い取り、作業員用の宿舎として運営する子会社を設立。1次下請けと子会社は一体で、領収書の作成は自在だった。
元請け会社は下請け会社の経費を一時的に肩代わりし、最終的に取りまとめて行政側に請求する。安藤ハザマはこの1次下請けに対し、作業員の宿泊費として1人1泊5千円を支払っていたが、領収書上は同7500円を支払っていたように改竄。宿泊人数の総計も1万1千人から1万5千人に修正された。改竄前後の差額は約5300万円。
また27年4月、田村市での除染終了後にも同様に、宿泊費は5500円に、宿泊人数も5600人から1万人に改竄された。改竄前後の差額は約3千万円。
安藤ハザマは1次下請けに実費分の宿泊費を支払う一方、1次下請けから受領した改竄領収書を行政側に提出。領収書は最終精算時に宿泊費を算出する際の資料として使われ、実態とは異なる宿泊費が支払われた疑いがある。
東日本大震災の復興事業では、早期の復興実現のため、通常は最終精算の対象とされない宿泊費について、特例として最終精算できるようにする通達を国が出しており、この仕組みが悪用されたとみられる。
1次下請け幹部と、改竄を指示した安藤ハザマ担当者や上司が面談した際の録音記録によると、安藤ハザマ側は改竄を指示したことを認めつつ、「領収書は行政側に出していない」と述べた。しかし産経新聞の取材で、該当の領収書が行政側に提出され、保管されていることが確認された。
■元請けゼネコン主導 異例の発覚
東京電力福島第1原発事故に伴う除染事業は、平成29年4月時点で3兆円を超す巨額の予算が計上されている。除染をめぐっては過去にも問題や疑惑が浮上しているが、元請けのゼネコンによる大がかりな不正の証拠が明らかになるのは極めて異例だ。
除染には国が直轄で実施する場合と、自治体が実施する場合がある。自治体の除染でも費用は国が肩代わりする仕組み。国は当初、行政側が負担した費用を東電に請求する方針だったが、昨年12月、一部は東電に請求しないことを閣議決定した。
国の除染では、受注者側から請求された宿泊費を領収書に基づき実費で精算。自治体の除染では、領収書に基づき実費で支払うか、領収書などから妥当な宿泊費を割り出して支払うかは、自治体判断となっている。
除染事業に絡み、これまで「手抜き除染」疑惑や作業員に支払われる手当てのピンハネ疑惑などが指摘されてきた。3月には除染事業への参入をめぐる贈収賄事件が発覚し、環境省職員らが逮捕、起訴された。5月にも福島市発注の除染で、下請け会社が除染費を不正受給した疑いが浮上している。
■録音やメール生々しく
「やっちゃいけないとは分かりつつ、領収書の改竄(かいざん)をお願いした」-。東京電力福島第1原発事故の除染事業をめぐり、6日に発覚した準大手ゼネコン「安藤ハザマ」による除染費の不正取得疑惑。領収書改竄を指示された1次下請け会社の男性幹部と安藤ハザマ側が面談した際の録音記録には、そうした発言が記録されていた。電子メールにも、安藤ハザマ側が改竄を指示するやり取りが生々しく残っている。
1次下請け会社の男性幹部によると、安藤ハザマ側との面談は、同社の除染拠点となっている福島県浪江町の事務所で複数回にわたって実施。今年4月にも行われたという。
この幹部は面談を持った理由について「宿泊費を実費分しかもらっていないので、領収書上の出入金額と実際の金額が合わないことが社内で問題になったため」と説明した。
録音記録によると、幹部が「なぜ改竄領収書を作る必要があったのか」と質問した際、安藤ハザマ側はこう弁明している。
「支出の事実はあるが、裏付ける領収書が残っていない支出がある。その穴埋めというとおかしいが、宿泊費ならということで」
一方で産経新聞は、安藤ハザマと、1次下請けの担当者間の電子メールも入手した。
1次下請けの男性担当者によると、いわき市での除染事業完了後の平成26年9月、安藤ハザマの男性担当者から電話があり、「宿泊費の領収書を指示通りに作成してもらいたい。その前に実際のデータを送ってほしい」と伝えられた。実際のデータをメールに添付して送付すると、安藤ハザマ側からは「添付の通り(データを)修正しました。処理願います。但(ただ)し書きに人数の記載をお願いします」との返信があった。
安藤ハザマはこの1次下請けに対し、作業員1人当たり1泊5千円を支払っていた。しかし修正データでは、1人1泊7500円に変更され、宿泊人数も水増し。安藤ハザマが実際より5千万円以上多く支払ったかのように修正された。
1次下請けの担当者は、改竄領収書とともに、裏付けとなる宿泊単価などを記載した契約書なども作成して安藤ハザマ側に提出。これに対し、安藤ハザマ側からは「確認しました。ありがとうございました」と返信があった。
同様のやり取りは、田村市の除染事業でも行われた。27年4月、安藤ハザマ側からの依頼で1次下請け側が実際のデータを送ると、安藤ハザマ側からは「添付の通り変更しましたので、領収書の作成をお願いします」と返信。1次下請け側は前回同様、改竄領収書を作成した。
1次下請けの担当者は「なぜ領収書の改竄が必要なのか、安藤ハザマ側から説明はなかった。領収書の偽造自体が良くないと思っていたが、ゼネコンに逆らうと仕事を切られてしまうのではないかと思い、断れなかった」と複雑な心境を明かした。
1次下請けの男性幹部は「結果的に不正に加担してしまったとすれば遺憾だが、1次下請けはうちだけではない。問題は氷山の一角かもしれない」と話した。
メッセージを送信したら特定される可能性を理解しなかったのか?学歴高くてもこんな事は入試や入社試験に出なかったのか?
コネだから学歴や能力は関係なかったのか?アカウントを乗っ取られて遠隔操作された場合を除き、アウトだろ!
無理やり女性の体を触るなどしたとして、警視庁大塚署は6日、強制わいせつ容疑で電通社員の高橋知也容疑者(29)=東京都新宿区山吹町=を逮捕した。
「身に覚えがない」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は4月27日午前0時20~25分ごろ、文京区内の路上で帰宅途中の20代の女性に声を掛け、立ち去ろうとする女性の右手首をつかんで胸を触るなどした疑い。
同署によると、女性は同容疑者を無視しようとしたが、ビルの陰に連れ込まれた。女性から無料通話アプリの連絡先を聞き出してメッセージを送信したため、アカウントから同容疑者が浮上した。
景気は重要だけど、それだけじゃないと思う。
◇直撃インタビュー【上】
元TBS記者でジャーナリストの山口敬之氏(51)を準強姦(ごうかん)罪で告訴も、不起訴処分となったことを不服として検察審査会に審査を申し立てたジャーナリストの詩織さん(28)が31日、都内でスポニチ本紙の取材に応じた。圧力があったとも感じさせた捜査、性犯罪被害者に不利に働く現在の法的・社会的状況を、時折、涙で声を詰まらせながら訴えた。
名前を明かし顔も出した29日の会見で気丈な対応を見せたのとは対照的に、この日は涙を抑えられない場面が幾度となくあった。
「今後も同じ思いをする方が出てきてほしくない」と開いた会見。見たくない部分に触れざるを得ないことから「猛反対」していた家族の反応を聞かれた際、「大切な妹がいるんですけど」と切り出すと、言葉を詰まらせた。「彼女にも未来があるのに、私が(表に)出ることによって迷惑がかかるんじゃないかと心配していたんですけど、やはりつらかったみたいで」
“実名・顔出し”を決意した裏には、「黙っていたら(事件が)消されてしまう」との思いもあった。相手は安倍晋三首相に最も近いとも言われるジャーナリスト。捜査がゆがめられたのではないかとの指摘も出ている。
捜査に消極的だった警視庁高輪署だが、「(現場の)ホテルには防犯カメラがあるから、データが消される前に必ず見てくださいと話してやっと見てくれて、事件性ありとみなされて、そこから少しずつ捜査がスタートしたんです」。ようやくこぎ着けた逮捕状の取得。しかし、それが執行されることはなかった。現場の捜査員からは電話で「上からの指示」と告げられた。
執行にストップをかけたのは当時の警視庁刑事部長。菅義偉官房長官の秘書官を務めたこともある人物だった。「高輪署は捜査1課に話をしているし、著名人の捜査は大変だと聞いていたので、逮捕状を取る時もしかるべきところを通されているわけで…」と所轄と本庁とで情報共有がなされていたとした上で、突然の“捜査指揮”に言及。「誰に聞いても答えを教えてくれない。異例だとしか。本当に知りたいと思い自分でも調査をしていくと、(官邸人脈と刑事部長の)名前がリンクしたんです」
扱いが1課へ移ると、警視庁から示談を勧められるという「極めて異例」(代理人弁護士)な展開を迎えた。準強姦罪は親告罪。大きな意味を持つ。「彼らの車で彼らが同席する中で示談の話を勧められるというのは…。警察の方は捜査する方たちで、示談を勧める立場ではないし、起訴できないと決めつけるところでもない」と切り捨てた。
「2年前からストレスで髪が抜けるようになりました」と打ち明けた詩織さん。傷つきながらも心はなお闘おうとする一方、体には無理が表れてしまっているらしい。友人は「それほどつらい状況なのです」と察した。
安倍晋三首相は30日の参院法務委員会で、友人が理事長を務める学校法人「加計学園」(岡山市)の役員を過去に務めていたと明らかにした。同学園の獣医学部新設に関しては、「(理事長が)知り合いだから頼む、と(政府内で)言ったことは一度もない」と述べ、便宜を図ったことはないと改めて否定した。
首相は役員就任について「(1993年の衆院選で初めて)当選した当初、相当昔だが数年間、監査かそうしたものを務めた。1年間に14万円の報酬を受けた」と説明。「はるか昔のことだ」として問題はないとした。首相が2000年に衆院に提出した書類によると、99年に加計学園グループの学校法人「広島加計学園」の監事を務め、所得報告書に報酬を受けていたと記載している。
また、首相は野党が求める文部科学省の前川喜平前事務次官の証人喚問について「委員会(国会)が決めることだ」と改めて述べた。これに先立ち、自民、公明両党の幹事長は東京都内で会談し、前川氏の喚問には応じない方針を再確認した。【高橋恵子、高橋克哉】
ここまで来るとX氏とY部長の対外的な評価は下がっているだろう。まあ、正社員と契約社員では力関係で同等であるわけがない。 二流や三流の会社ならいろいろとあるだろうが、今度は新日鉄住金ソリューションズのプライドの問題になってきたのかもしれない。
日本は仕事の業務以上に人間関係で疲れると言っていた脱サラ留学生が多かったのはこう言う事を言っていたのだろうか?
"エロ対決"のセクハラ受けた女性、怒りの告白 「会社の和を乱す存在として雇い止めにされた」 05/31/17(HuffPost Japan)
セクハラ被害について相談したのに会社の不当な対応で休職を余儀なくされたとして、東京都内の30代の女性が26日までに、契約社員として働いていたシステム開発大手「新日鉄住金ソリューションズ」に慰謝料500万円の支払いなどを求めて東京地裁に提訴した。
訴状や原告側の主張によると、女性は職場の別のグループの男性課長から「ホテルに行こう」と言われたり、交流サイト(SNS)のメッセージで性的な関係を求められたりした。個人的な連絡を断ると、課長は自身のSNSに中傷の書き込みを繰り返した。
女性は「上司に相談したが、自分が悪いと決めつけられた」と説明。相談後の人事異動で男性課長のアシスタントを務めることになって体調が悪化し、休職を経て雇用契約を打ち切られた。
女性は不当に雇い止めをされたとして、契約終了の無効も訴えている。
新日鉄住金ソリューションズ広報・IR室は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
大手製薬会社「バイエル薬品」(大阪市)は26日、製造販売している血栓症治療薬「イグザレルト」について、医薬品医療機器法で必要とされる国への副作用報告を怠った事例が12件確認されたと発表した。厚生労働省は26日までに同社から報告を受けたとし、「命に関わる重要な事例はなかった」と説明。ただ他に同様の事例がないかどうか、全製品を対象にする調査を求める。
バイエル社によると、未報告事案は、イグザレルトを使った患者へのアンケート結果の一部。「鼻血や皮下出血が起こりやすい」「胃腸が痛かったり、むかむかしたりする」「湿疹など皮膚症状が出る」といった指摘があったが、副作用として報告しなかった。
事実を究明する事はとても重要だと思うが、ここまで省や省の職員が事実をぼやかそうとしているのを見ると、事実の一部しか明らかにならないと思うので 気分が悪い。
▼国有地投げ売り「核心の共謀メール」
森友学園問題で「新証拠」が浮上する一方、安倍晋三首相の「腹心の友」が経営する加計学園についての疑惑が表面化した。両学園には接点があり、彼らを結びつけたのは、ほかならぬ安倍昭恵氏だった。
「私が思っていたのと違うので、皆さんにお見せしないといけないと思った」
森友学園(大阪市淀川区)の籠池泰典前理事長は5月16日、再び民進党のヒアリングに応じ、“安倍晋三記念小学校”の建設用地として取得した国有地(大阪府豊中市)の価格交渉についての関係者の電子メールを公表した。
メールは複数ある。昨年4月1~10日、近畿財務局、大阪航空局の担当者、森友学園から受注した藤原工業(大阪府吹田市)、設計業者、そして当時の学園の顧問弁護士、酒井康生氏の間でやり取りされたものだ。学園が運営する塚本幼稚園のアドレスにも参考で送られており、それが残っていたという。
なぜ今、公開したのか。籠池氏はこう説明した。
「私はメールを一切、やらないもので、幼稚園の事務方が紙にプリントして見せてくれていた」
つまり、最近になってメールの存在を思い出したということらしい。
メールのやり取りがあった時期について振り返ると、昨年3月11日に校地の深い層から「新たなごみ」が出たと業者から聞かされた籠池氏は、財務局に対応を要請。財務局や航空局の担当者が、現地を視察し、積み上げられた「新たなごみ」を確認したとされる。
こうした動きの中で、籠池氏は「新たなごみがあるのなら、値引きされるのでは」と考え、定期借地契約を結んでいた国有地の購入を改めて申し出た。価格交渉については、酒井弁護士に一任したという。
役人が「小学校開設ありがとう」
政府は、くい掘削工事中に、想定外のごみが大量に見つかったと説明している。ところが、弁護士と設計業者間の「作戦会議」メールには、「新たなごみ」を客観的に示す資料がないことから、苦心する様子が記されていた。
昨年4月9日、酒井弁護士が設計業者に宛てたとされるメールにはこうある。
〈柱状図がないことは不自然でしょうか。求められてから提出するようにできるのであればしたいです(中略)柱状図ではあらわれていないが、廃棄物が混じっているということを、付記するとか理屈を考えることはできませんでしょうか〉
財務局から、建設前に学園が実施したボーリングデータの提出を求められていたが、データにごみの存在が反映されていないことから、躊躇(ちゅうちょ)していたことがうかがえる。設計業者からの返信はこうだ。
〈実際のボーリングデータで産廃が3m(メートル)以深では無い→敷地全体でも無いであろうと推測できる→実際にボーリングしましょう→産廃が3m以深では無い→じゃあ、そんなに引けないですよね、、、、という正論で負けてしまいそう〉
詳細に調査すれば、「新たなごみ」など存在しないことが明らかになると、恐れているように読める。本誌が繰り返し指摘した通り、新たに出たごみは、前年の土壌汚染除去工事の際に取り除かれなかった廃棄物である可能性がより強くなったと言えるだろう。
メールについて、酒井弁護士や設計業者は取材に応じなかった。財務省理財局は次のように答えた。
「財務局担当者は、詳細は覚えていない。早急に対応する必要がある中、関係者とメールのやり取りをしたことはあった。メールは既に削除している」
その財務局の担当者が設計業者に送ったとされるメールは、さらに違和感を感じさせるものだった。
〈瑞穂の國記念小學院開校に向けご協力いただきありがとうございます〉
要するに、国有地を売る側の役人が、学園側に謝辞を述べているのだ。ヒアリングでは、民進党議員から「国立安倍晋三小学校じゃないか」との揶揄(やゆ)の声が上がった。揶揄はいうまでもなく、小学校の名誉校長だった首相の妻昭恵氏を意識したものだ。
土地取得に関する交渉がスムーズになってきた時期について、籠池氏は「顕著になったのは、昭恵夫人が名誉校長に就任してから。それまでも風はあったが、台風みたいになった」と語っている。
ヒアリングの翌17日、『朝日新聞』のスクープに注目が集まった。学校法人・加計(かけ)学園(岡山市北区)が愛媛県今治市の国家戦略特区で開設を計画している岡山理科大獣医学部について、特区を担当する内閣府から「総理のご意向だと聞いている」などと言われたとする文書を、文部科学省が作成していたと指摘したのだ。
首相と同学園の関係について、自民党議員は「理事長の加計孝太郎氏と総理は、南カリフォルニア大留学時に知り合った。たびたび、ゴルフを楽しむ仲です」。今治市が、約17ヘクタールの市有地を建設用地として無償提供したうえ、96億円の補助金を出すことから、「第二の森友学園疑惑」ともいわれてきた。
実は、両学園には接点があった。森友学園関係者によると、現理事長の籠池町浪(ちなみ)氏と職員が2015年10月14日、保育施設「御影インターナショナルこども園」(神戸市東灘区)▽泰典氏と町浪氏らが昨年2月15日、「英数学館小学校」(広島県福山市)――を視察している。いずれも、加計学園の系列施設だ。
森友関係者が明かす。
「昭恵夫人はこども園の名誉園長であり、『すごく良い教育をしている学校があるから見学しては』と勧められた。広島の小学校も同様です」
首相にとって加計学園とは、夫婦ぐるみで「ずぶずぶの関係」というわけだ。加計学園を巡る文書について、松野博一文科相は「確認できなかった」とした。だが、記載内容から信憑(しんぴょう)性は高いとみられる。
「書いたものが物を言う」ということわざがある。どう言い繕っても、二つの疑惑にまつわる文書が政権をじわじわと追い詰めているのだ。
(本誌・花牟礼紀仁)
(サンデー毎日6月4日号から)
医師免許なしに美容整形手術をしたとして、偽医師とクリニックのオーナーが、医師法違反の疑いで逮捕された。偽医師の男は、10年間にわたり100人以上に美容整形手術をしていた。
23日午前、医師法違反の疑いで逮捕されたのは、高知市の医療法人「西武クリニック」の職員・森 勉容疑者(61)と、オーナーの谷川延洋容疑者(71)。
警察によると2人は共謀し、2016年2月、高知市の49歳女性に対し、医師免許がないのに麻酔注射を打ち、二重まぶたの整形手術を行った疑いが持たれている。
森容疑者は逮捕前、FNNのインタビューに応じた。
医師法違反の疑いで逮捕された森 勉容疑者は「(医師免許が必要な手術をした?)しました。(何人に?)100人以上。(整形手術の技術はどこで?)見よう見まねで覚えた」と話していた。
森容疑者は以前、愛知・名古屋市の病院で、事務職員として勤務していた経験を基に、高知市のクリニックで見よう見まねで、2005年から10年間にわたり、100人以上に美容整形手術をしたという。
高知県警は、余罪について調べている。
国の制度融資で不正が発覚した商工中金に対し、金融庁が24日にも本店などへの立ち入り検査に入ることが23日、分かった。麻生太郎財務相は同日の閣議後会見で、「資料分析を行っている段階で、準備ができ次第立ち入り検査を行うと決めている」と述べた。経済産業省や財務省と協力し、不正の背景や企業統治に問題がなかったかどうかを重点的に調べる。
国の制度融資で不正を繰り返した商工中金は、財務省や経済産業省など3省庁から9日に業務改善命令を受けた。6月9日までに再発防止に向けた業務改善計画を提出するよう求められている。
商工中金の自主的な調査では原因究明が徹底されないとの懸念もある。商工中金のトップは経産省からの天下りで、金融庁が検査を主導することで責任の追及などを徹底する狙いがある。
政府系金融機関の商工中金が国の制度融資で不正を行っていた問題で、金融庁は、24日にも本店などへの立ち入り検査を実施する方針を決めた。書類改ざんなどの不正が全国的に行われた背景や、経営陣の関与の有無などを調べ、原因の解明を図る。不正融資発覚後、監督当局による本格的な立ち入り検査が行われるのは初めて。
検査は金融機関の検査ノウハウを持つ金融庁が主導し、共同で所管する経済産業省と財務省の協力も得て行う。金融庁の主任検査官をトップに、同庁の検査官約10人と両省の担当者数人でチームを編成。商工中金関係者から不正の経緯や内部管理体制などを聞く。
不正があったのは、2008年のリーマン・ショック後に国が創設した「危機対応業務」。金融危機や震災で経営難に陥った中小企業に対し、商工中金が低利融資などを行い、国が利子補給や損害の補填(ほてん)を行う。商工中金では、制度の対象になるよう審査書類を改ざんして業績を悪くみせかけるなどして実績が水増しされていた。一連の不正は、商工中金が昨年11月に鹿児島支店職員の不正融資を発表したことで発覚。商工中金が依頼した第三者委員会の調査で全国92支店のうち35支店、816件(約198億円)に不正が及んでいたことがわかった。
所管3省庁は今月9日、商工中金に業務改善命令を出し、商工中金は6月9日までに不正再発防止策を盛り込んだ業務改善計画を提出することになっている。これまでの調査は対象が全危機対応融資の1割強にとどまり、全容解明にいたっていない。金融庁は本格的な検査に踏み切ることで、商工中金に徹底調査を促す考えだ。【小原擁】
◇商工中金
国と中小企業団体が共同出資して1936年10月、組合員の中小企業に融資する金融機関として設立した。正式名称は「商工組合中央金庫」。2008年に株式会社化され、現在は国が株式の46%、残りを中小企業団体などが保有する。政府は株式会社化後に完全民営化する方針だったが、15年に国の保有株式の全面売却期限を撤回した。16年9月末の貸出金は9兆4910億円。職員は約4000人。
ドコモやauなどの大手通信事業者から回線を借りる格安スマホ(MVNO)は、料金の安さで利用者を急激に増やしているが、それ以上にトラブルも増えている。国民生活センターへの2016年度の相談件数は前年度比2.8倍にもなった。ケータイジャーナリストの石野純也さんがリポートする。【毎日新聞経済プレミア】
調査会社・MM総研によると、2015年3月末には326万契約だった市場規模が、16年9月末には657.5万へと拡大。1年半でほぼ倍増した格好だ。一方で、急成長ゆえのひずみも浮き彫りになりつつある。
国民生活センターは4月13日、格安スマホに対する注意喚起を発表した。同センターに寄せられた相談件数は、16年度が1045件と、前年度の380件から大幅に増加。増加率は2.8倍で、単純比較すると市場規模の拡大以上に相談件数が伸びているのが現状だ。
◇料金は安いがトラブルも多発
公表されている相談内容は、「実店舗がなく、不明な点を問い合わせようとしても電話がつながらない」「修理中の代替機貸し出しがなかった」「端末にSIMロックがかかっていて使えなかった」といったものが挙げられており、サポート関連でのトラブルが目立つ。MVNOはサポートにかかるコストを抑えて格安を実現しているが、それが国民生活センターの相談件数増加に直結してしまった格好だ。
大手通信事業者と同様のサポートは期待できないということは、消費者側もあらかじめ知っておくと、この種のトラブルは防げる。
国民生活センターの発表を受け、MVNOなどからなる業界団体・テレコムサービス協会は、消費者向けに事前に知っておくべきチェックポイントを発表している。チェックポイントは、「料金・提供条件」「端末」「SIMカード」「設定」「メール」「サポート」「携帯電話会社からの乗り換え」「利用開始日」の8項目。MVNOの契約前には、目を通しておきたい内容となっている。
安さばかりを強調し、デメリットを周知してこなかったMVNOも、対応の変更を求められそうだ。デメリットを周知しないばかりか、宣伝文句の前提条件が抜けているなど、いき過ぎたアピールを行っていたMVNOもある。
◇フリーテルにいき過ぎた宣伝文句
消費者庁は4月21日、プラスワン・マーケティングのMVNOブランドであるフリーテルに、再発防止を求める措置命令をくだした。同社のサイトに記載されていた「SIM販売シェア1位」や「業界最速の通信速度」などの文言が、景品表示法に定める「不当な表示」にあたるためだ。
プラスワン・マーケティングによると、シェア1位はヨドバシカメラ限定でのデータだったといい、通信速度についても、平日12時台の限られた条件でしか調査をしていなかった。
再発防止を求められた同社は、すでにサイトの文言を修正しているが、いき過ぎた宣伝をするMVNOはほかにもある。過去にはドコモからネットワークを借りていることを強調し、「通信品質が同じ」とうたっている会社もあったが、これも実態とは異なる。MVNOは帯域単位でネットワークを借りているため、利用者の通信量が増えると、そのぶん通信速度が落ちることがあるからだ。
こうした過大な宣伝が、国民生活センターへの相談急増につながっている側面もある。利用者の信頼を失えば、市場の拡大に急ブレーキがかかってしまうおそれもあるため、早急な改善が求められそうだ。
もっとも、MVNOは大手通信会社より料金が大幅に安く、最低利用期間を設けている会社はあるが、縛りも緩い。その安さがなぜ実現しているのかを理解しながら使えば、節約につながる。消費者も上記のサイトを参考にしながら、メリット、デメリットの両面を把握するようにしておきたい。
安倍晋三首相の友人が理事長を務める学校法人「加計学園」(岡山市)が国家戦略特区に獣医学部を新設する計画について、朝日新聞が入手した一連の文書の中には、獣医学部新設に反対していた日本獣医師会の関係者と文科省幹部が接触していたことを示すようなものもある。この文書に実名が出てくる北村直人・日本獣医師会顧問(元自民党衆院議員)は18日、朝日新聞の取材に対し、「文書に書かれていることは事実だ」と語った。
文書の題は「北村直人元議員(石破元大臣同期)→専門教育課○○」=○○部分は文科省職員の実名。日付は「10月19日(水)」となっており、昨年とみられる。北村氏の発言として「石破(茂)元大臣と会って話をした」「政治パーティーで山本(幸三)国家戦略特区担当大臣と会って話をした」などと書かれている。
文書には、石破氏が北村氏に「党プロセスを省くのはおかしい」などと獣医学部新設をめぐる手続きに言及。また、山本氏は北村氏に「(新設のための)お金がどうなるのかを心配している」などと語ったと記されている。北村氏によると、昨年秋に石破氏や山本氏に会ったという。石破氏とは学部設置をめぐる自民党内の手続きについて、山本氏とは学部の開設費用や設置される愛媛県今治市の財政負担について、それぞれ話したという。
行政のチェックの甘さに問題があると思う。不正が見逃されているのを知っていれば、自分も大丈夫と考えるかもしれないし、正直者が馬鹿を見ると考え、考えを変えるかもしれない。
まあ、今回はトヨタ車ディーラーが不正をした事がインパクトが大きいと思う。トヨタ車ディーラーがやっているのなら、氷山の一角かもしれないと思わせる事だ。
最近は、いろいろな所が車検事業に参入している。検査に通り、安ければ良いと考える人が多ければ、高い車検費用を提示している処には影響が大きいであろう。
多少、車の知識があれば、何を重点に置くのか、判断できるだろうが、車の事が判らない人達は、違いなどわからないであろう。サービスを提供する側と顧客の両方が 考えるべき問題だと思う。
不動産大手、三井不動産の子会社が、決算で赤字を黒字に見せかける不正をしていたことが、17日わかった。費用の先送りなどで、2015年3月期と16年3月期の営業利益を計10億3千万円分水増ししていた。
不正をしたのは「三井不動産リフォーム」(東京)。三井不が70%、三井ホームが30%を出資する。三井不によると、営業赤字だったのに、取引先に払う工事費の先送りや、未完成の工事の売り上げを前倒しで計上していた。15年3月期は約1400万円の黒字、16年3月期は約3200万円の黒字を装っていた。
不正は3月に内部告発で発覚。収益目標を達成するためだったという。三井不は、12日の決算発表では不正を公表しなかった。「決算全体への影響が軽微なため」(広報)という。三井不動産リフォームで不正にかかわった幹部数人を処分したが、三井不の関与はないとして、同社幹部の処分は見送った。
三井不を巡っては、昨年も子会社の三井ホームでリフォーム部門の不正会計が発覚した。(石山英明)
行政のチェックの甘さに問題があると思う。不正が見逃されているのを知っていれば、自分も大丈夫と考えるかもしれないし、正直者が馬鹿を見ると考え、考えを変えるかもしれない。
まあ、今回はトヨタ車ディーラーが不正をした事がインパクトが大きいと思う。トヨタ車ディーラーがやっているのなら、氷山の一角かもしれないと思わせる事だ。
最近は、いろいろな所が車検事業に参入している。検査に通り、安ければ良いと考える人が多ければ、高い車検費用を提示している処には影響が大きいであろう。
多少、車の知識があれば、何を重点に置くのか、判断できるだろうが、車の事が判らない人達は、違いなどわからないであろう。サービスを提供する側と顧客の両方が 考えるべき問題だと思う。
大阪のトヨタ車ディーラーで、不正が発覚した。法律で義務付けられた点検作業の一部を省略した上、その作業分を含めた代金を請求するという不祥事である。
舞台になったのはネッツトヨタ新大阪のくずは北山店(枚方市)。ある顧客が、この店に十二カ月点検を依頼、作業の一部始終をガラス越しに見ていた。この人物は自身も整備士の資格を持っていたため、店側が点検を省略したことに気づき、クレームを入れたというのが経緯だ。
ネッツトヨタ新大阪は三月二十四日付で「十二か月点検における不正行為について」と題した一枚の紙を、同社ホームページ上に掲載した。事実関係を認めた上で詫びるとともに、「関係省庁と今後の対応について協議をはじめている」とした。また、原因究明や社員の再教育についても言及しており平身低頭している。
ただ、これは「氷山の一角」である可能性が高い。今回の事件は、分解しなくても目視で確認できる部分が対象だったようだ。だとすれば、分解を伴う細かい作業であれば、見えないところで不正を行うことはたやすい。ましてや、車検作業などが集中して多忙を極める三月であれば、可能性が高くなる。これを一ディーラーの不祥事で早々に片付けるかどうか、トヨタの企業態度が問われている。
選択出版(株)
「市は、業者が竹を伐採したように見せる写真を捏造(ねつぞう)し、JVを通じて工事完了報告書を提出して除染費用の一部を不正に受け取ったとみて、刑事告訴を検討している。」
刑事告発を検討だから、まだ、告発するか決まっていない。刑事告発しても、有罪に出来るの?返金の要求は可能なのか?
東京電力福島第1原発事故に伴い福島市が共同企業体(JV)に発注した森林の除染事業で、3次下請けの業者が工事単価を通常の10倍に水増しするため竹林で除染作業を行ったように偽装していたことが11日、市への取材で分かった。市は、業者が竹を伐採したように見せる写真を捏造(ねつぞう)し、JVを通じて工事完了報告書を提出して除染費用の一部を不正に受け取ったとみて、刑事告訴を検討している。【曽根田和久】
市除染企画課によると、現場は福島市松川町の森林で、市内の建設3社(晃建設、古俣工務店、ノオコー建設)で作るJVが受注した。2014年9月~16年3月、宅地や農地などの「生活圏」から20メートル圏内の計18万5000平方メートルを除染し、市からJVに計約6億2000万円が支払われたという。
森林除染の工事単価は通常、1平方メートル当たり約500円。しかし、竹林の場合は竹が密生しているため伐採しないと除染できないなど手間がかかる。このため、単価に約4600円が上乗せされ約10倍に設定されている。
3次下請けだった福島県二本松市内の業者「ゼルテック東北」(現在は廃業)は、除染を終えた報告書に添付する写真を撮影する際、地面に短く切った竹筒を突き立て、竹林を伐採したように偽装。作業員が切った竹を担いで運ぶ写真も添付するという念の入れようで、複数の除染現場の写真としてトリミングして使い回していた。
市は昨年11月、関係者からの内部告発で事態を把握。JVからの聞き取りを進めている。市除染企画課の土田孝課長は「書類ベースの確認なので意図的な偽装を見抜くのは難しい」と説明している。
愛知県や横浜市で老人ホームなどを運営する社会福祉法人「愛生福祉会」(名古屋市北区)で、常務理事を務めていた50代の男性が9年間にわたり、法人の運営費計約1300万円を着服していたことが10日、同会への取材で分かった。
同会によると、老人ホームなどの施設長をしていた男性は、平成19年に会計責任者を兼務。法人名義のクレジットカードを使って私的な飲食費や遊興費に流用し、経費と偽って処理していた。
昨年春ごろ、内部から会計に不審な点を指摘され、調査を開始。男性は着服を認め、同8月に自ら退職した。内部調査に「生活費の足しにしたかった」と話している。今後、民事訴訟などを通じて返還を求めるほか、刑事告訴も検討する。運営費は介護保険料や入居者の利用料で賄っている。
同会は名古屋市を中心に東京都や横浜市で、老人ホームやデイサービスセンターなど21拠点を構える。同会は「会計のチェック体制を整え再発防止に努めたい」としている。
外国などは書類が本物か証明するものとか、資格のコピーや番号を要求するが、日本でも確認する必要があるだろう。
テレビ熊本(TKU、熊本市)の派遣社員だった40代男性が、カメラマンをしていた数年にわたり社有車を無免許で運転していたことが10日、同社と派遣元のTKUヒューマン(同市)への取材で分かった。男性は昨年12月、業務中の交通違反で無免許が発覚して熊本県警に摘発され、諭旨解雇された。
両社によると、男性は平成18年からTKUで報道の仕事に携わり、解雇時まで少なくとも5年以上、カメラマンをしていた。TKUヒューマンの聞き取りに「運転免許は取ったことがない」と話したという。
両社は男性の採用時に免許証の提示は求めておらず、履歴書と口頭で保有を確認するにとどまっていた。両社は「免許証の確認を厳しく行うなど、再発防止に努める」としている。
逮捕される職員がいることで、汚職を踏みとどまる人がいる事を祈る!
兵庫県加古川市の市民病院の工事を巡る汚職事件で、逮捕された職員の男が別の業者にも不正な取引を持ちかけていたことが分かりました。
「アイミツ(相見積)ではこれより不利な条件で出すんで、まあ、ほぼ御社で決まりなんで」
これは収賄の疑いで逮捕された加古川市民病院機構の係長、熊野真智容疑者(48)が兵庫県内の廃棄物処理業者に取り引きを持ち掛けた際の音声です。熊野容疑者は去年12月、病院機構が発注した工事を巡り、宝塚市の業者から現金120万円の賄賂を受け取った収賄の疑いで逮捕されました。
「御社に振ってもメリットないんやったら、これ以上取引を拡大しようと思ってないので」
熊野容疑者はこの処理業者に廃棄物の買い取り額の見積書を提出させた後、買い取り額の一部を親族名義の口座に振り込むよう要求、その口座には贈賄容疑で逮捕された業者も金を振り込んでいたということです。警察は熊野容疑者が他の業者にも不正取引を持ちかけていたとみて詳しく調べています。
毎日放送
川内原発の安全性などを検証する鹿児島県の専門委員会の宮町宏樹座長が、座長就任後に九州電力からおよそ2億円の経費が見込まれる研究を受託していたことが分かりました。県の専門委員会で座長を務める鹿児島大学の宮町宏樹教授によりますと、九州電力から受託したのは、姶良カルデラを含む大隅半島から甑島周辺にかけての東西160キロの地下の構造を、地震波を使って調査する研究です。期間は今年度から3年間の予定で、宮町教授を中心に全国の研究者が参加し、およそ2億円の経費が見込まれるということです。宮町教授が受託したのは去年12月の専門委員会の座長就任後ですが、「研究の中立性は確保できる」としています。宮町教授はこれとは別に、今年度、甑島周辺海域の地震活動に関する研究もおよそ1500万円で九州電力から受託していて、原発の稼働に反対する市民グループは「研究を続けるなら委員を辞めるべき」と指摘します。九州電力は宮町教授に「県内の地震・火山研究において専門性と知見を持ち、一番の適任者と判断して依頼した」としています。一方、県は、「委員個人の研究について意見を言う立場になく、今後も原発関連企業からの研究の受託について申告を求めたり公表したりする予定はない」としています。
朝日新聞は慰安婦問題の記事の反省からなのか記事の担当者を記載するようなっていると思う。
新聞社が取材なしに記事を書くぐらいなら、記事を新聞に載せない、又は、取材の部分を載せるべきではない。
政治でも商売の世界でも、信頼を失うと、取り戻すのはたんへんだと思う。イソップ童話の中の 「狼少年」と同じように 人々が本当なのかと疑い始めると他の選択肢があれば、元に戻る事は限りなく無理だと思う。
仙台市青葉区の市立中2年の男子生徒(13)が自殺した問題で、朝日新聞仙台総局の50代の男性記者が生徒の母親に取材せず、談話をデジタル版に掲載したことが1日、分かった。同社広報部は「行き違いがあり一部修正した。捏造(ねつぞう)には当たらない」などと説明。河北新報社の指摘後、ウェブ記事から母親のコメントをいったん全て削除した上で、遺族のコメントとして一部を掲載し直した。
【仙台中学生自殺】男子生徒の机に「死ね」
修正したのは、1日午後4時44分配信の朝日新聞デジタル版に掲載された「いじめ自殺、遺族語る 『あったかどうか』腹が立つ言葉」の記事。「生徒の母親が関係者を通じて朝日新聞の取材に応じた」とした上で母親のコメントを詳しく紹介した。
記事は「中学に入学して以来、何度も学校にいじめを伝えていた」「息子が自ら命を絶ってから、混乱した日々が続いています。助けてやれなかった自分を責めるばかりです」などと、母親が間接的に心情を打ち明けた形式を取っている。
遺族関係者によると、母親が朝日新聞に対してこうした心情を話した事実はなく、記事の内容にも事実誤認が多く含まれているという。
同社広報部は「母親の関係者に取材し、内容をまとめた。配信した内容の一部について、関係者とのやりとりの中で行き違いがあり、その部分は修正した」とのコメントを出した。
仙台市青葉区の市立中学2年の男子生徒(13)が26日に高層マンションから飛び降り自殺していたことが分かった。29日に記者会見した市教育委員会によると、昨年度実施の校内のいじめに関するアンケートに、この生徒を複数の男子生徒がからかうなど「集団によるいじめ」を示唆する指摘がありながら学校側が把握していなかった可能性がある。市教委は、いじめの実態や自殺との因果関係のほか、学校の対応についても調べる。
男子生徒は1時限目の授業が終了した午前9時35分ごろ、姿が見えなくなり、自宅近くのマンションの下で倒れているところを近所の住民に発見された。遺書は見つかっていない。
市教委によると、学校は昨年6月と11月にいじめに関するアンケートを実施。男子生徒は「悪口を言われたり物を投げられたりする」「冷やかしや悪口を言われ、無視される」と回答していた。しかし、当時の担任教諭はこの生徒とトラブルを抱えていたとされる男子生徒6人から事情を聴いたものの、回答した生徒側にも原因があったとみなし、双方を指導したという。さらに、今年3月に担任教諭が生徒にその後の状況を尋ねたところ、「もうない」と答えたといい、教諭は問題は解消したと判断したという。
このため、市教委は29日の会見の当初はいじめとみられる行為があったとみなしておらず、自殺した生徒と他の生徒との「1対1のトラブル」との認識を示していた。しかし、その後の質問にアンケート結果を読み返し、「複数の生徒から、からかいなどがあったとする記述があった」と新たに確認。集団によるいじめを示唆した記述を学校側が見逃していた可能性を明かした。【本橋敦子】
………………………………………………………………………………………
◆相談窓口
◇児童相談所全国共通ダイヤル
189=年中無休、24時間
◇24時間子供SOSダイヤル
0120-0-78310(なやみ言おう)=年中無休、24時間
◇チャイルドライン
0120-99-7777=月~土曜日の午後4~9時(18歳まで)
◇子どもの人権110番
0120-007-110=平日午前8時半~午後5時15分
時代とともに環境や技術などが変わってくる。規則や法はいつも事故や被害の後に改正される。昔は、「メイド・イン・チャイナ」を 想定そして予測していなかったと思う。行政は規則の改正をするべきだと思う。
消費者は行政の対応の遅さを予測して消費行動を考えた方が良いと思う。お金で全ての話が付くわけでもないし、お金をもらっても事故の前の 状態にはならないこともある。
消費者は一般的に安い方に行く傾向がある。ただ、大量消費も良いが、良いものを長く使う事も考えて生活するべきだと個人的には思う。 中国のメンタリティーは製造及び生産には向かないと思う。その不向きである国で生産されるのだから注意して消費行動を考えた方が良い。 そして、日本の無駄な部分を無くして、消費者と実際に生産、製造する人達の間の企業や卸を出来るだけ省いた関係を考えた方が良いと思う。 日本の人件費は高い。だから、簡素化する必要があると思う。それ以外、コストを下げる手段は日本にはないと思う。
突然自転車が壊れる。そんな事例が続発している。運転中にハンドルが折れたり、あるいはタイヤが外れたり…。自転車に見えない爆弾がついていて、ある日いきなり大破する、そんなイメージだ。車と違って国が定める安全基準がなく、型式指定審査のようなチェックシステムもない。輸入自転車の9割を占める中国をはじめ、海外から欠陥商品が流入している問題も指摘されているが、国産製品も例外ではない。けがをした人がメーカー側の製造物責任を問い、訴訟に発展するケースも相次いでいる。“自爆自転車”を見抜くにはどうしたらいいのか-。
突然ペダルが空回り…
一瞬のことだった。
平成26年12月13日の昼下がり。大阪市城東区で集金業務にあたっていた内山俊平さん(52)=仮名=は気がつくと、路上に投げ出されていた。左肩に激痛が走り、起き上がれなかった。
直前まで、2日前に購入したばかりの自転車をこいでいた。トップギアの6段に変速した瞬間、ペダルの空転現象が起き、バランスを崩したのだ。
「何が起こったのか…」。内山さんは苦痛に耐えながら、通りかかった女性に救急車を呼んでもらい、病院に搬送された。診断結果は左腕骨折など全治1年3カ月。それから休職を余儀なくされた。
内山さんは憤る。「この事故で私の生活は一変した。本当に許せない気持ちだ」
自転車は国内メーカーのものだった。メーカー側が行った調査により、内山さんの自転車のギアに欠陥があったことが判明する。6段に設定された際、ギアがギア台に十分に締結されず、ペダルが空回りするようになっていた。
販売会社は調査結果を経済産業省に報告。独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のホームページにも掲載された。欠陥があったのは内山さんの1台のみだったという。
販売会社とメーカーはともに損害賠償責任を認めたが、具体的な金額については明らかにしなかった。内山さんは昨年10月に「自転車が通常有すべき安全性を欠き、製造物責任法違反に当たる」として2社を相手取り、約8100万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。会社側は賠償額について争う姿勢を見せている。
代理人を務める豊永泰雄弁護士(大阪弁護士会)は「このケースは行政に重大事故として報告されているのに、解決まで非常に時間がかかっている。『ものづくり大国』といわれた日本も、今は昔」と話す。
ひざ下のまひ、サッカー選手の夢絶たれ…
「マジで死にかけたんですけど…」
「買ってから2週間なんですけど…」
昨年、ハンドルの支柱部分が取れた自転車の画像がインターネット上に投稿され、話題となった。
「走行中にフレームが突然折れて転倒し、歯を8本折った」
「電動アシスト自転車のフレームが真っ二つに折れけがをした」
欠陥自転車による被害の書き込みは、ネットのあちこちで見られる。
内山さんのように訴訟に発展したケースも少なくない。
イタリアのブランド自転車に乗っていた当時63歳の男性は、出勤中に突然前輪が外れて転倒し、首から下がほぼまひする障害を負った。男性は自転車の輸入元に計約2億4千万円の損害賠償を求めて提訴。東京地裁は25年3月、「通常備えるべき安全性を欠いていた」と認定し約1億8900万円の支払いを命じている。
若者の夢が奪われたケースもある。
自転車で走行中にシャフトと呼ばれる部品が折れて転倒した20代の男性はメーカーに約820万円の損害賠償を求めて大阪地裁に訴訟を起こし、昨年7月に解決金400万円を支払う内容で和解が成立した。男性は右ひざ骨折や靱帯(じんたい)損傷などの大けがを負い、サッカーのプロ選手になる道が断たれたと訴えていた。
統一基準なく
事故が相次ぐ一つの要因として、輸入自転車の増加も挙げられている。
自転車産業振興協会によると、国内の市場に出回っている自転車の9割が輸入品で、その大半が中国で生産されているという。日本メーカーの現地工場も多く、日本メーカーの製品であっても、メイド・イン・チャイナということが少なくない。
同協会の担当者は「部品の精度が低い輸入自転車もある。消費者も定期点検への意識が低く、壊れたら直す、という人が多い」と指摘する。国が統一した安全基準を定めていないことも一因といえる。
NITEによると、20年度から24年度までの5年間に報告を受けた自転車の交通事故以外の事故件数は実に493件に上る。そのうち自転車の欠陥による事故は162件で全体の32・9%を占めた。
原因を詳しく見ると、溶接や接合の不良、強度不足などで走行中に部品が破損したケースが66件で最多。組み立て段階でハンドルやチェーン、ペダルがしっかり固定されていない締め付け不足も目立った。モーターの電流制御に異常が発生し、急発進したり、バッテリー制御部から発煙したりといった電動アシスト自転車特有のものもあった。
自転車マークを参考に
欠陥自転車をどう見分ければよいのか。
専門家によれば、自転車の車体に貼られている「自転車マーク」が一つの目安になるという。
マークは事業者団体が任意でいくつか設けている。約90項目の検査にクリアした自転車のみに貼られる「BAA」マークや、自転車安全整備士によるメンテナンスを受けたことを示す「TSマーク」などがそれだ。こうしたマークの有無をチェックするのも欠陥自転車を避け、事故を防止するのに役立つ。
NITEによると、自転車の製品事故は使用開始から1年未満に多くが発生しているという。自転車産業振興協会は「新しい自転車を購入したら1~2カ月以内に販売店などで自転車技師、自転車安全整備士による初期点検を受けてほしい」と呼びかけている。
(1月27日掲載)
◇
■産経ニュースが日々お届けするウェブ独自コンテンツの「プレミアム」。人気のあった記事を厳選し、【メガプレミアム】として再掲します。人物の年齢や肩書き、呼称などは原則として掲載時のままとなっております。
日本経済新聞(4月23日付)に気になる記事が出ていた。
「アパート融資で利益相反か 建築業者から顧客紹介料」「一部の大手地銀 金融庁が是正へ」という見出しだ。「利益相反」というのだから、大手地銀が何か悪いことをしていたんだろうということは想像できる。しかし、「是正へ」という程度だから、犯罪ではないし、それほどの大きな話ではないなという印象を抱いてしまう。
しかし、ことの詳細を知れば、おそらく多くの人は、こんな見出しじゃ済まないと感じるだろう。実態をより的確に表す見出しにすれば、「顧客を食い物にする大手地銀! 業者と結託してアパート融資詐欺」「金融庁が是正指導へ」というところだろう。
では、何がそんなに酷いのか。わかりやすく解説してみよう。
上記日経記事によれば、拡大している賃貸アパート向けの融資で、一部の大手地銀が顧客を建築業者に紹介する見返りに手数料を受け取っていることが金融庁の調べでわかったということだ。
手数料はアパート建築請負金額の0.5~3%だというから、請負額が5000万円の場合、顧客を紹介しただけで150万円も銀行が請負業者から手数料をもらうことがあることになる。
ここで、実際に顧客と銀行の間で、どういうやり取りが行われているか想像しよう。
銀行員:「お客様がお持ちの土地を有効活用してみませんか。今アパート経営に関心をお持ちのお客様が急激に増えているんですよ」
顧客:「土地はあるけど現金はないしね。借金までしてやるのはねえ。本当に儲かるんですかね」
銀行員:「もちろん、当行から資金はお貸しできます。しかも、その金利は、マイナス金利時代ですので、今は最高の借り時です。アパートを建てれば、相続税対策にもなりますし、とても有利なお取引になります」
顧客:「アパート経営はやったことないし、リスクがあるんじゃないの?」
銀行員:「最近は安かろう悪かろうの業者も増えていますが、当行が取引している業者で、信頼できるところを紹介させていただきます。建設からその後のアパートの管理運営まで全てやってくれますし、賃料保証契約もできますので、お客様には大きなお手間を取らせずにアパート経営が可能です」
顧客:「そんなうまい話があるのかなあ」
銀行員:「もしよろしければ、ご紹介させていただきます。業者の方から連絡させますので、話だけでも聞いてみたらいかがでしょうか。もちろん、ご納得がいかなければ、お断りいただいて全くかまいませんので」
顧客:「じゃあ、話だけでも聞いてみるかな。土地を遊ばせておくのももったいないし、相続税も上がったっていうからね」
東証1部上場の機械商社「椿本興業」の名古屋支店で働いていた元社員、籾井(もみい)新一郎容疑者(56)。工事の発注から工事代金の支払いまで実務を一手に任されていた。与えられた大きな権限を悪用し、椿本興業に架空の工事を下請け企業に発注させ、工事代金をだまし取っていたという。
こんなやり取りで業者につなげば、そのうちの何割かが契約に至り、アパート融資の実績もできる上に、業者からの手数料も入る。こんなに楽で儲かる商売は今時珍しい。
紹介を受けた顧客は、銀行が推薦する業者だからと安心して、請負金額が少し高いなと感じても、安心料だと思って契約してしまう。しかし、実際には、銀行への手数料分だけ、建築コストとは別に建築費に上乗せされているわけだ。
「利益相反」だと金融庁が問題にしたのは、銀行が、表向きは「顧客のため」と称してアパート経営を勧め、業者を紹介するのに、実際は、建築費が高くなればなるほど自分が儲かり、顧客が損をする仕組みになっているからだ。
顧客は銀行のカモにされているということになる。
セールストークの「信頼できる業者」も、「顧客にとって信頼できる」業者ではなく、紹介した対価として確実に手数料を払ってくれるという「銀行にとって信頼できる」業者なのである。ひどい話ではないか。
地銀にとっての「神風」となった相続税の増税
アパート融資の問題は、手数料だけにとどまらない。
そもそも、人口減少社会で、アパート経営を「これからの儲かる商売」だとして推奨し、そのために借金をさせるという行為自体が詐欺的商法ではないのかという疑いがあるからだ。
アパート経営が流行っている背景には、マイナス金利政策と相続税制の変更という二つの要因がある。
マイナス金利政策で、これまで余剰資金を国債に振り向けていた銀行は、その道も塞がれ、ますます資金を持て余すようになる。何とか融資を増やしたいが、景気は今一つだし、優良な融資先を見いだす目利き能力もない地銀などは、どうしても従来型の不動産担保融資に頼らざるを得ない。そこで、「マイナス金利時代に入りました。今が借り時です」というセールストークでアパート融資に顧客を誘導するわけだ。
顧客の側は、どうせ家を建てるなら金利が安い今が有利だと考えて、その誘いに乗るパターンが生じる。
もう一つのパターンが相続税対策だ。2015年から、相続税の基礎控除が下がり、これまでほとんど相続税のことを心配しなくてよかった人も相続税を払わなければならなくなった。元々相続税を払う人でも、その額は大きく増える。そこで、相続税の節税対策のニーズが高まった。これが、融資先探しに悩んでいる地銀にとっては、神風になったのだ。土地を持っている顧客に、「アパート経営をすれば、相続税が減りますよ」と言えば、多くの顧客が関心を示すという。
孫請け先となったのは、利昭容疑者が個人事業を営んでいた「豊田メディアネットワークス」。
ご存知の方も多いと思うが、通常のケースでは、財産を現金で持つよりも不動産にした方が相続税の評価額が安くなる。その分相続税は減る。また、銀行からの融資は債務となるため財産額を圧縮できる。さらに、土地の上に賃貸物件があると、それだけで、普通の土地よりもさらに評価額が下がる。したがって、普通の持ち家よりもアパート経営をすると相続税が大きく減る可能性が高いのだ。
ここまで聞いて、「なるほど、アパート経営は得するんだな」と思った人は、銀行の紹介する建築業者の話を聞くことになる。そこでは、顧客の持っている土地に合わせた、アパート建築プランを含めた詳細な将来の収支計画が示される。相続税の軽減額なども具体的な金額で教えてもらえる。
「アパート経営を始めるなら、今しかありません。いつ金利が上がるかわかりませんから」などとせかされて、「これはいいことばかりだから、乗った方がいいな」と思って、銀行から借金をして、アパート経営に乗り出した膨大な数の人が日本中にいるのだ。こういう顧客はまさに銀行にとっての「最優良顧客」である。
●アパート経営にはこれから逆風の時代
しかし、この話には大きな落とし穴がある。それは、提示されたシミュレーションが、現在の貸家の賃料相場が今後長期間にわたって継続することを前提としていることだ。もちろん、これには、市場の需要要因、供給要因双方から見て無理がある。
日本は、ご存じのとおり、長期的な人口減少時代に入っている。それでも、単身世帯の増加などで、世帯数は全国で見れば今年も増え続けている。それは、住宅需要も減少はしていないということを意味する。
しかし、この傾向は、2019年ごろから逆転する見通しだ。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、世帯総数は2010年の5184万世帯から2019年の5307万世帯まで増加するが、それをピークに減少に転じ、2035年には4956万世帯まで減る。地域別にみると、2015年にはすでに15県で減少に転じているが、20年までには34道県、25年までに42道府県で、25年以降は沖縄以外はすべて減少に転じるという予想だ。
今後は必要な住宅の数が減り続けることになるわけで、これは、アパート経営にとっては、完全な逆風の時代の到来ということを意味する。
すでに大きな話題になっているとおり、日本中に空き家が増えていて、2013年には、空き家率が13.5%と過去最高を記録。山梨県の17.2%が最も高く,次いで四国4県がいずれも16%台後半となっている。この数字はどんどん増えることが確実だ。ここまでは住宅の需要側から見たリスクだ。
一方、供給側から見ても大変なリスクがある。最近、全国の貸家の建設は異常な増加を続けている。
国土交通省統計では、2016年の新設住宅着工戸数は前年比6.4%増で96万7000戸を超え、2年連続増加となったが、持ち家の3.1%増加に対して、貸家は10.5%増とはるかに伸びが大きい。08年(46万4851戸)以来8年ぶりの高水準だという。異常とも言えるアパートブームである。
もちろん、その裏にはアパート融資がある。日銀によると2016年12月末のアパート融資残高は前年同月比4.9%増の22兆1668億円。09年の統計開始以来、過去最高を更新した。
●顧客の錯覚を悪用する銀行と業者は詐欺商法の共同正犯?
こうした需給両面での異常な状況を反映して、一部の地域では、すでに家賃が下がり始めている。アパート建設から間もないのに契約した家賃収入が入らず、業者との間でトラブルになっているケースがどんどん増えているという。
個人の視点、短期の視点で見れば極めて合理的な選択でも、集団で同じ行動をとる前提で中長期的視点から見ると全く違った絵が見えることに、実は、銀行も建築業者も気づいているはずだ。
しかし、顧客は、巧みなセールストークに乗せられて、「錯覚」に陥っている。それを知っていながら、むしろ助長しているのだから、銀行と建築業者は詐欺的アパート経営勧誘の共同正犯と言っても良いだろう。
実は、アパート融資で大きな役割を果たしているのは銀行だけではない。ノンバンクによるさらに悪質なアパート経営勧誘が猛烈な勢いで展開されている。
業者によっては、「ゼロ円の資金であなたもアパート経営者」などというキャッチフレーズで、ほとんど詐欺のような商売を展開しているものもある。頭金ゼロで始めると、返済負担が大きいため、少しでも賃料収入の見込みが崩れると、すぐに返済が滞りやすく、さらに、地価が少し下がっただけで、担保を換金しても借金が返済できない事態に陥ることになる。
アパート融資は、早晩、大きな社会問題になるであろう。
●アリバイ作りに動く日銀は「銀行本位」
事態がどんどん深刻化する中、4月24日に新しいニュースが流された。
日銀が、地銀の不動産業者向け融資が過剰になっているという内容の報告書をまとめたという内容だ(NHK)。不動産業者向けという言い方だが、その増加分の大半はアパート融資である。同報告書では、空室が目立つ地域もあるなどとして、市場動向を十分に把握して融資の審査を行うべきだと警鐘を鳴らした。
多くの人が知らないだけで2016年の長野県で15人死亡のスキーバス事故以前はもっとひどかったのであろう。事故が起きる環境や問題が存在したが、
大きな事故が起きないので、注目を受けなかったし、多くの人が知らなかっただけであろう。
「行政処分の強化後も法令違反3割強」と言う事は、問題は簡単には解決できない。現状の制度では、これ以上の改善は期待できないと言う事だ。
力を持っている企業が、価格を決定する権限を持っていれば、処分の対象に含めなければ、バス運行会社だけでは無理であろう。規則や法制度を
含めて国土交通省は対応しなければならない。ただ、個人的に思うに、問題が完全にはなくならない。どこまでを目標にして制度、規則そして法を
改正するのか次第だと思う。
貸し切りバスの法令違反に対する行政処分が昨年末に強化されて以降、4月半ば現在で国が監査した146のバス事業者のうち、3割強で違反があったことがわかった。規定より安い金額での受注など安全軽視の内容が目立った。
乗客7人が死亡した関越自動車道のバス事故から4月29日で5年がたった。昨年1月には長野県で15人死亡のスキーバス事故も起き、国は安全対策を進めてきたが、法令順守が徹底されない業界の現状が浮き彫りとなった。
関越道の事故は、運転手の居眠りでバスが側壁に衝突。行きすぎた価格競争や無理な運行が問題となり、運転手の研修など安全に関わるコストを運賃に上乗せする新料金制度の導入や、運転手1人が運転できる距離の引き下げなどの対策が講じられた。それでも4年後、長野で大事故が発生し、国土交通省は昨年12月、安全に関する法令に違反した事業者への行政処分を強化。不正が見つかった場合に使用停止とする対象を保有台数の一部から8割へ拡大、内容によってはその場で全車両の使用を停止させるようにして、業界に法令順守を促してきた。
だが4月半ばまでの約4カ月で、全約4500の事業者のうち146事業者に監査を実施したところ、49社で法令違反が発覚。内容は、安全確保に必要な運賃の下限より安く契約▽運転手に対する乗務前の健康確認などを怠る▽乗務記録に運転した時間を実態より短く記入する――など。安全を管理する運行管理者を置いていない会社に対し、昨年末から可能となったその場での全車両の運行停止を命じたケースも2件あった。国交省自動車局は「軽微な違反も見落とさない姿勢で臨んでいるため、監査での違反件数が多くなった部分もある。安全をないがしろにする業者には退場してもらうつもりで臨む」としている。
総務省が昨年9月に全国の事業者に実施したアンケートでも、旅行会社との間に入る手配業者と取引経験がある937のバス事業者のうち、3割弱の252業者が、下限割れ運賃での契約について「常にある」「時々ある」と答えていた。(伊藤嘉孝)
横浜市に対して「土曜日も給食を出している」と虚偽の報告をしていた戸塚区の認可保育所「戸塚芙蓉(ふよう)保育所」が今春、本や雑品の購入などに充てる実費の徴収額を、5歳児で従来の7・5倍にあたる年1万8千円に値上げしていたことが市への取材でわかった。突然の大幅値上げに保護者が反発。市は必要最小限の実費徴収を認めているが、額の規定がないことから、全市で実態調査を始めた。
市は26日、戸塚芙蓉保育所など、社会福祉法人「ももの会」が運営する六つの保育施設に特別指導監査に入り、保育の実態を調べている。この日の職員からの聞き取りで、戸塚芙蓉を含む認可保育所4施設で事前の報告に反し、土曜給食を出していなかったことがわかったという。
市によると、戸塚芙蓉保育所は昨年度は「教材費」として年齢を問わず年2400円を徴収。だが今年度は年齢で徴収額を変え、最も高い5歳児は毎月1500円ずつ、年間合計で1万8千円と7・5倍に値上げした。
「なぜ高くなるのか」との保護者の指摘に対し、保育所側は内訳を説明。月刊本12カ月5040円▽写真アルバム・保育証書など4800円▽ひらがな練習帳900円▽お楽しみプレゼント2千円▽制作費用(画用紙、のり、絵の具)1500円などとしている。
ももの会の上山福恵子理事長は、朝日新聞の取材に対し、「従来は教材費とは別に実費を頂いており、手間を省くためにまとめた。保護者が払う額は変わらない」と説明した。
一方、関係者は「昨年度は月刊絵本や写真は希望者のみで、最低限払う実費は年3千円程度だった」と証言。保育所側は今月になり、月刊本とアルバムは希望者のみにすると、利用者側に説明したという。
横浜市戸塚区の認可保育所「戸塚芙蓉(ふよう)保育所」が、市から支払われる委託費などで用意すべき土曜日の給食を提供せず、保護者に弁当を持参させていたことが市への取材でわかった。市の調査に対し、虚偽の記載をした給食日誌を示し、給食を出したように装っていたことも判明。市は26日朝、芙蓉保育所など社会福祉法人「ももの会」が運営する五つの認可保育所に対する特別指導監査を始めた。
横浜市はすべての認可保育所に対し、土曜の保育時にも平日と同様に給食を提供するように指導している。市によると、保育所は昨年11月の定期監査で、土曜日の給食について「主食、副菜、汁物、飲み物、果物」を提供していると報告していた。
ところが、保護者から土曜日の給食がないと相談があり、市は今年2月に保育所を調査。保育所側は、土曜日も報告通りの給食を提供していると説明し、献立や食べた人数などが記された「給食日誌」を提示した。
だが市側が質問を重ねると、保育所側は実際は申告した給食を出さず、弁当を持参させていたことを認めた。市によると、食中毒が出た場合に原因を特定するため、給食は2週間冷凍保存するルールだが、立ち入り調査時には平日の給食だけが冷凍保存され、土曜日の分はなかったという。
保育所の施設長で、法人理事長の上山福恵子氏は市に対し、「軽食を提供していた」と主張。「給食日誌に内容が正しく記載された状態で自分は押印したが、その後に職員が土曜日の主食と汁物を追記した」という趣旨の説明をしたという。「軽食」について、上山理事長は朝日新聞の取材に対し、「弁当に合わせて、蒸し野菜などを提供していた」と説明した。
保護者らは「軽食の提供はなかった」と証言しており、市は虚偽の疑いが強いと判断。児童福祉法などに基づく特別指導監査に入り、法人全体の運営実態を調べる方針を決めた。
市はすでに、「施設長の押印後に職員が書き加えた」との点について、虚偽記載にあたるとして厳重に注意。保育所側は3月から土曜日の給食の提供を始めた。保育所の定員は60人で、3月の土曜日の利用者は1日6~8人という。
保育施設の給食をめぐっては、兵庫県姫路市の認定こども園「わんずまざー保育園」が、園児数を大幅に下回る給食しか用意していなかった問題が明らかになっている。(山下寛久、太田泉生)
東芝は、決算の会計監査を担当するPwCあらた監査法人を変更する方針を固めた。東芝は2016年4~12月期連結決算について、同監査法人から「決算内容は適正」との意見を得られないまま異例の発表に踏み切っていたが、その後も意見対立が続き、解消のめどが立たないため。既に準大手の監査法人に後任となるよう打診しており、17年3月期決算で適正意見を得ることを目指す。
東芝とPwCあらたは、経営破綻した米原発子会社ウェスチングハウス(WH)の元幹部が、損失を少なく見積もるよう部下に圧力をかけたとされる問題などを巡って意見が対立。過去にさかのぼってさらに詳細な調査を求めるPwCあらたに対し、東芝は「不適切な圧力は調査で判明したが、決算への影響はない」と結論付け、監査法人の意見なしで16年4~12月期決算を発表した。
その後も東芝はPwCあらたと協議を続けてきたが、溝は埋まらないと判断した模様だ。東芝は5月に17年3月期決算を発表する予定で、「意見不表明」のまま決算を提出すれば上場廃止になる可能性もあるため、監査法人を変更して適正意見を得ることを目指す方針だ。
ただ、大手企業の東芝の監査は作業量が多いため、決算発表は大きく遅れる懸念がある。また、東芝の会計基準は米国基準なのに対し、準大手の監査法人は日本基準を採用しており、会計基準変更につながる可能性がある。その場合、作業量はさらに増えることになり、決算発表は数カ月単位で遅れる可能性も出ている。【安藤大介】
実力や知識で問題を回避できることもあるが、運が一番重要と言う事だろう。
マンションという、庶民の人生で一番大きな買い物で欠陥品を掴ませながら、売り主も建設会社も考えているのは責任逃れだけ。旭化成建材の杭問題に巻き込まれた住民たちの「悲劇」は続く。
補償金の押し付け合い
「今年2月、管理組合の理事長宛に旭化成建材から、大手弁護士事務所を通して文書が届いたんです。開けてみると『(マンションの)建物の調査をさせてください』と。このひとたちはいまさら何を言ってるんだろうと、呆れましたよ」
こう語るのは、横浜市都筑区にある、三井不動産レジデンシャルの分譲マンション「パークシティLaLa横浜」の住民だ。
全705戸、ショッピングセンター・ららぽーと横浜に隣接する好立地に位置するこのマンションの名を全国的に有名にしたのが、約1年半前に起きた「傾きマンション騒動」だった。
「『二つの棟をつなぐ手すりがずれている』という住民の指摘から三井側が調査したところ、傾いた棟を支える杭のうち、安定した地盤である『支持層』に届いていないものが多数見つかりました。
当初、三井不動産側は『東日本大震災の影響である』と責任逃れをしていたが、その後の調査で杭打ちを担当した旭化成建材の担当者による虚偽データの使用が発覚。問題が大きくなると一転、全棟建て替えを表明しました」(不動産業界紙記者)
翻弄された住民たちは、昨年の9月に集会を開催し、建て替えを決議。全住民の引っ越しも完了し、この4月中に、建て替え工事の第一歩がまさに始まろうとしている。
三井不動産側が表明した慰謝料一戸あたり300万円は「破格の条件」と大きく取り上げられ、誠実な対応と持ち上げる向きもあった。
「『十分すぎる補償で結果的に住民は得した』という報道もありましたが、そんなことはまったくない。お金以外の失ったものが多すぎるんです。
700世帯以上が近隣で引っ越し先を探したものだから、便乗値上げが始まり家賃が高騰。子供がいる家庭では、学区内で引っ越そうとしても補償される家賃では家が見つからない人もいた。転校させるのは忍びないと、住民側が行政とかけあってなんとか越境通学を実現させました。
また、80代のある男性独居住人は、収入や孤独死の心配をされて入居審査に落ち続け、地方へ身を寄せざるを得なくなった。そうした労力や時間的な負担に対する売り主側のサポートはお粗末なものでした」(前出の住民)
既存建物の解体を含む工事費用は約300億円、居住者の仮住居や引っ越し費用などの補償金は約100億円が見込まれ、新しいマンションの完成までにかかる諸経費は合計400億円にのぼるとも言われている。
この巨額を、誰が、どのくらい負担するのか。実はそれについて、売り主の三井不動産、施工した三井住友建設、そして杭打ちを担当した旭化成が、いまだ激しい「押し付け合い」を繰り広げているのだ。
それぞれが責任逃れ
騒動から1年半も経過したのに、責任の所在がはっきりしない。
耳を疑うような事態だが、そんなことがあり得るのか。本誌は三社に取材を申し込んだ。
「400億円の業者間の負担割合は決まっていません」(三井不動産)
「今の段階ではまだ何も決まっていません。今後建物の解体が始まってその上で杭などの詳細な調査が行われ、各社話し合いで決まっていくという流れになると思います」(三井住友建設)
「何も決まっていません」(旭化成広報)
補償の負担の話し合いが進んでいないことを三社ともはっきり認めた。
「旭化成建材には『杭の施工不良は認めるが、建物が傾いた原因がすべて杭のせいというのはおかしい。他にも施工不良があったはずだから調べたい』という要望がある。
ところが、三井不動産や三井住友建設は自分たちの不利になる資料は当然見せたくない。そこで、我々住民に改めて調査をさせてくれ、と泣きついたわけです。本来、補償の金額が決まれば、その内訳は彼らの身内だけでカタをつけるべき話でしょう。
傾きの原因を探ることは住民にとっても必要だと思い了承はしましたが、彼らの自分本意な体質はやっぱり変わらないな、と」(前出・住民)
実際、この3月に発表された三井不動産の決算短信には以下の様な文言がある。
〈レジデンシャル社は、上記合意書に基づく当マンションの建替え費用、建物工事期間中の仮住まい費用等発生費用のすべてについて、施工会社である三井住友建設株式会社並びに杭施工を行った株式会社日立ハイテクノロジーズおよび旭化成建材株式会社に対し、不法行為責任、瑕疵担保責任等に基づき求償いたします〉
要するに、「すべての責任は三井住友建設と旭化成建材にある」と公言しているに等しい。400億円もの巨額負担になると、業績を大きく左右しかねないだけに、各社なりふり構わぬドロ沼の「責任逃れ」闘争に血道をあげている。
大手設計事務所で長年、多くのマンションの設計と工事監理を手がけてきた一級建築士が言う。
「彼らの『責任のなすり合い』はいつまでも続きます。仮に三社の負担割合が決まっても、今度は旭化成が下請けに付け回す。その下請けは更に孫請けに付け回すはずで、事業規模の小さな下請けは倒産するかもしれない。業界の構造的な問題が露呈した形です」
弁護士に電話してみると
一方、同じ旭化成の杭打ち不正問題をめぐって、いまだ住民と施工主とが争いの真っ只中にあるマンションの存在が、本誌の取材で明らかになった。
問題のマンションは、東京都足立区にある『ビジュー青井』。つくばエクスプレスの青井駅から徒歩2分の好立地で、築年数は10年の47戸。売り主は大興ネクスタで、施工は九州に本社を置く松尾建設が担当した。
このマンションの住民の一人が言う。
「杭の工事を請け負った旭化成建材によるデータ流用があったことが発覚し、松尾建設側に安全性のチェックを求めていたのですが、ある時から突然やり取りに応じてもらえなくなり、困っています」
一昨年の10月、前出のLaLa横浜における杭打ち偽装を受け、国交省は旭化成と元請け会社に対し、旭化成建材が杭打ちを担当した全物件の施工データを調べ直すように要求。全国で大規模な調査が行われた。
その結果、昨年の2月、「全3052物件中360件の施工データに流用があった」という衝撃的な調査結果が国土交通省から公表され、同社の浅野敏雄社長(当時)が引責辞任するに至った。
だが、この「ビジュー青井」は、データ偽装があったにもかかわらず、その「360件」という調査結果の数字には含まれていない。なぜなのか。
「当初、国交省が定めた約2週間の報告期間には、松尾建設からウチのマンションについて『データ流用はない』という報告がなされていたのです。
報告までの経緯があまりにも慌ただしかったために訝しく思い、我々住民の側で第三者機関に対して施工データの再調査を依頼したところ、『根固め液の注入量に不自然な同一数値がみられ、偽装が疑われる』という結果が出ました」(前出の住民)
住民側がこの結果をつきつけると、松尾建設側は「偽装を見落としていた」と認めて謝罪、国交省への追加報告をした。
とはいえ、杭データの流用がすなわち、建物そのものが危険な状態にあることを意味するわけではない。だが、このマンションでデータ流用が確認された杭の真上にある部屋の内部を見ると、天井には亀裂が入り、部屋の角にもひび割れが見える部分もある。
前出の住民が言う。
「昨年の9月の時点で大興ネクスタと松尾建設の取締役が我々のもとを訪れ、もともと求めてきた他の設備不良の修繕と、第三者機関のもとでの杭の再調査を約束しました。
その二点について誓約書の提出を求めると、両社共に非を認め、住民に寄り添う姿勢を見せてくれた。それで安心していたのですが……」
売り主である大興ネクスタは誓約書へ捺印、施工不良の工事費用を全額拠出する姿勢を表明した。
だが、その後突如として松尾建設側からの音沙汰がなくなる。
それから約1ヵ月後、管理組合のもとに松尾建設の代理人の弁護士からFAXが送付された。
「『誓約書の内容は認められない』という内容でした。なぜ、認めないのか。具体的な理由も何も書かれていない。再度、松尾建設側に誓約書を送付しましたが、『住民との間に契約関係がないから』という素っ気ない内容の数行のFAXが再び送られてきただけ。
以後、松尾建設の担当社員にメールや電話をしても一切対応してくれなくなった。考えがあるならあるで、『回答できない』とか『ここが飲めない』とか理由を説明して欲しい。連絡を無視するのは、われわれ住民をあまりにも蔑ろにしているとしか思えません」(前出の住民)
大興ネクスタの担当者も「住民の方々が一刻も早く平穏な生活を取り戻すことを最優先に、松尾建設さんとも話し合いをしたいのですが……」と困惑する。
本誌は、松尾建設東京支店の担当社員に複数回問い合わせるも、いずれも不在とのことで、話を聞くことはできなかった。
そこで、松尾建設の代理人となっている光石俊郎弁護士に問い合わせた。
以下はその一問一答。
――松尾建設に取材をしようと連絡しているが、連絡が取れない。
「だって、もう話すことはないんじゃないんですか」
――住民側も連絡が取れないと困っている。
「(取材をするなら)住民側から聞いたらどうですか。私どもから話すことはもうないですよ」
――住民の方々と話すつもりはないのか。
「一応、施主(大興ネクスタ)のほうが住民の方といろいろやっていますから、そちらと話したらどうでしょうか」
――大興ネクスタも(松尾建設側に)連絡が取れないようだが。
「そりゃあ施主の方は住民の方と一緒に、今度の補修工事をやるのに契約書をやっているみたいですから。私どもはその契約を結んでませんから」
――少なくとも、杭打ちの調査については松尾建設の義務ではないのか。
「これ以上話さないから。終わります」
ここで、電話は一方的に切られてしまった。
このやりとりからも、松尾建設側の「我関せず」の姿勢が感じ取れる。
国交省は業界の味方
前出の住民がやりきれない表情で言う。
「この問題が世間に注目されていた時期ならば、松尾建設ももっと真摯な姿勢で対応してくれたかもしれませんが、国は『データ流用問題は安全性に問題がなかった』と結論づけ、幕引きを図ってしまった。我々は、誰も助けてくれないなか、素人だけで大手の建設会社と交渉していかなければならないわけで、みんな消耗しています」
昨年末には、杭打ち工事会社の業界団体が、旭化成建材のケースの他に「16社が担当した238件の建物で杭打ちデータの改ざんがあった」とひっそりと公表。ずさんな施工体制が、業界全体の深刻な問題であることが浮き彫りになった。
「結局、国交省による調査も形だけでまったく意味はありません。そもそも、大手や準大手のデベロッパーは国交省出身者を受け入れており、官民が馴れ合う慣習は昔から変わらない。調査結果を提出させて『問題なし』という結論さえ出せばそれでいい、という考え方です。
悲しいけれど、国交省も住民の味方ではない。結局は、住民自ら施工体制を監視し、問題があれば闘っていくしか、自分たちのマンションを守る方法はありません」(前出の一級建築士)
ビジュー青井の住人のひとりはこう嘆く。
「このマンションの資産価値の低下を心配して不動産業者に相談したら、『下落うんぬんの前に、安全性が確認されなければ売りに出すことさえできない』と言われてしまった。出るにせよ留まるにせよ、杭の問題が片付かなければ我々は身動きがとれないのです」
大企業である施工主や、建設会社の理屈が優先され、国は役目を果たさない。そして、住民が置き去りにされる。その構図はあの事件があってもまるで変わってはいない。
「週刊現代」2017年4月29日号より
週刊現代
現場の仕事の中には多少の学歴よりも、現場での経験や現場で働く事により得た知識が重要な事もある。
学歴により賃金が違うのはデータで明らかであるが、高卒から大卒に学歴が変わっても、現場で必要な経験や独特な知識は教えないので、
仕事が出来るかは別の問題である。
今後、経験を重視する現場が出てくるかもしれない。ただ、働いた経験なしに経験は積めないので、問題となるであろう。ブラック企業の仕事でも
3Kの仕事でも、働かないと得るものはない。外国人労働者を使うにしても、教育したり、指示を出せる人材がいなければ仕事は進まない。
行政や国はどこまで分かっているのだろうか??
神戸市北区で昨年4月22日に架設中の新名神高速道路の橋桁が落下し、作業員10人が死傷した事故から1年。現場がある区間は開通の時期が延び、周辺の渋滞緩和や地域振興の期待は持ち越しに。工事現場ではほかにも事故が相次いでおり、有効な安全対策が求められている。
■熟練工引退に懸念も
「事故が続発し、おわび申し上げる。さらなる安全対策を講じる」。NEXCO西日本の村尾光弘・関西支社長は昨年11月、大阪市内であった近畿2府4県の労働局との労働災害防止会議で再発防止を誓った。会議は労働局側が呼びかけた。橋桁の事故後も新名神の工事現場で事故が続くことを重く見た。
関西支社などによると、橋桁の事故後、新名神の全工事約70カ所で安全点検を実施。だが翌5月、大阪府箕面市で橋桁工事中に仮設の支柱が倒壊し、下を走る箕面有料道路をふさいだ。同年10月には兵庫県猪名川町で足場撤去中の作業員1人が転落死。ほかにも、高さ約4メートルの足場から転落して1人が重傷を負うなど、今年1月までに4人が重軽傷を負ったという。
工事現場で重大な事故が後を絶たないことについて、労働局幹部は「熟練作業員が引退し、安全に対するノウハウが引き継がれていない懸念が、建設業界にいま共通する課題としてある」と指摘している。
■開通1年延期、渋滞なお
開通延期になったのは高槻(大阪)―神戸間の約40・5キロ。西日本高速道路(NEXCO西日本)は今年3月だった開通目標を延期し、高槻―川西(兵庫)間の約23・6キロは今秋、残る神戸までの約16・9キロを来年3月とした。
開通で期待されるのは、並行す…
人は機械ではない。スペックや型式が同じであれば、仕様の能力や生産性を維持するわけではない。仕事をしながら成長する人、 一生懸命に働く人、いろいろと注意して仕事をする人などが存在する。他方では、仕事をさぼる、権利や主張を強調し、他の人に仕事を 押し付ける、向上する意思も気持ちもない人がいる。
経験がある人は同じ時間により多く仕事をこなし、指示を出さなくても仕事を完了できる人もいる。ある人は、仕事になれてなく、 指示や教育する必要もある。高学歴であれば、高能力だと推測できるが、高学歴であれば、仕事が出来るとは限らない。 小さい時から塾に行って良い大学に入学した学生と塾はほとんど行かずに他の活動を経験し、同じ良い大学に入学した学生では、 同じ学歴であっても、トータルのキャパは違う。仕事によっては、卒業大学よりも、性格やこれまで経験した活動が影響したり、 強みになる事もある。学歴=高収入=安定した生活はこれまで日本の常識であったと思うが、結果や成果を重視した場合、かならずしも この関係が当てはまらない事もあると思う。ただ、規則で高卒や大卒の最低賃金や基準があるから、多くの人が誤解するのだと思う。
あと思うのが、日本人は安定やサラリーマンを望む。日本の社会構造がサラリーマンが安定し、楽である傾向が高いし、学歴がない人が 自営業や下請けの地位を受けいるイメージや結果を示したからかもしれない。残念ながら自営業は厳しい事が多いが、もしもっと多くの人が 自営業を起こして、大手のしがらみの影響を受けない分野で広がったらもっと自由度が高い生活が出来ると思う。
企業に勤めれば、企業の方針や規則に従うしかない。企業の窮屈さに不満を持ちながら、企業での就職を望む。矛盾していると思う。 変えようとすると多くの困難があるので、多くの人が行動を起こさないと現実的に変化を起こすのは難しいと思う。多くの人には手遅れだろうが、 早い時期に留学して、海外で就職できるのであれば就職して日本の環境から飛び出す方法もある。
同じ給料でもどこで暮らすのか、どのように暮らすのかでも多少の違いはあるかもしれない。日本では極端な例しかテレビで取り上げられないが 個々で考えながら挑戦するのも良いかもしれない。単純に給料よりもストレスを感じる事が少ない環境を望む人もいるはず。新品の自転車でなくても 中古の自転車でも乗るだけなら問題ない。実際に実行してみないと頭で考えているだけでは発見できない事もある。いろいろやってみて比較して ある選択の方が自分にとっては良いと感じる事もある。個人的には、あまり苦しくなる前にいろいろ挑戦した方が良いと思う。選択肢がなくなった 状態やゆとりがなくなった状態では、精神的によくない。外的に同じ状況でもいらいらやストレスをより強く感じる。
政府が3月28日、働き方改革実行計画案を発表し、懸案の「同一労働同一賃金」について、「非正規雇用の割合が高いシングルマザーや単身女性の貧困問題の解決のためにも重要である」と記しました。シングルマザーの雇用や賃金は改善されるのでしょうか。藤田結子・明治大商学部教授(社会学)の報告です。【毎日新聞経済プレミア】
母子世帯の母親の平均年収は223万円で、シングルマザーの多くが貧困状態です。母子世帯の母親の8割が就業していますが、「正規の職員・従業員」は約4割で、「パート・アルバイト」「派遣社員」などの非正規雇用が5割を超えています(2011年度全国母子世帯調査)。
経済学者の遠藤公嗣さんは、正規雇用の賃金が高く、非正規雇用の賃金が安いのは、「男性が外で稼ぎ、女性は家事・育児」という性別役割分業と関係しているからだと指摘しています。家族を養うのは正社員の夫であって、パート主婦は家計を補助するために働いているので、賃金は低くてもかまわないと考えられてきました。しかし今では、シングルマザーを含め、家族を養わなければならない非正規雇用者が増えています。
◇高学歴でも年収は正社員の2分の1以下
渡辺沙織さん(仮名、30代)もその1人。難関大学を卒業後、ある企業に正社員として就職しました。20代で結婚し、娘を出産して退職しましたが、その後離婚しました。今後は1人で稼いで、まだ幼い娘を10年以上育てていかなければなりません。
沙織さんは育児と両立できる仕事を探すため、転職支援サービスに登録しました。しかし、定時に帰れる正社員の職はみつかりませんでした。とりあえずは契約社員でもよいと考え、O社で非正規の事務職に採用されました。しかし契約社員なのに繁忙期にサービス残業をしなければならないほど、仕事量が多い職場でした。
仕事と保育園の送り迎え、育児を1人でこなし、いつも朝から晩まで働き詰めでヘトヘトです。何度も過労で倒れそうになりました。それでも正社員への転換の可能性があると言われたため、残業も進んでやりました。沙織さんは正社員とほぼ同じ業務を担当していますが、年収は正社員の2分の1以下で300万円に届きません。
◇突然会社から届いた雇い止め通知
そんなある日、突然、人事から数人の非正規雇用の女性たちにメールで雇い止めの通知がきました。上司や人事に抗議をしたものの、さらりと受け流されるだけ。正社員登用をちらつかされたうえに放り出され、ストレスで体調を崩しました。
沙織さんは転職活動を再開し、ハローワークにも行きました。が、今度も子育てをしながら、自分と娘を養っていけるような職が見当たりません。
そこで今度は手に職をつけて、専門職をめざすことにしました。医療系資格の専門学校に入学することを考えましたが、授業料とその間の生活費を払うことができません。これから1年間は再び非正規雇用で働き、お金をためる必要があります。
再就職口は見つからず、学校に入りたくてもお金がないという八方ふさがりの状態に陥りました。仕方なく、事務のパートを二つかけもちすることで、一時しのぎをすることに。時給1200円で手取りは十数万円。生計をたてるには厳しいですが、泣き言はいっていられません。
「娘に十分な教育を受けさせたいし、大学を出るまで教育費を稼がなければなりません。手に職をつけて長く働けるようがんばるしかないんです」
◇「同一価値労働同一賃金」の導入を
沙織さんのように、1人で子育てをしながら、残業のある正社員として働き続けることは困難です。子どもの世話のために早く帰れる非正規雇用で働かざるを得ず、賃金の低さから貧困に陥りやすいといえます。
非正規の賃金はヨーロッパでは正規の8割程度です。これに対し日本では6割程度と低くなっています。この不平等な状態を変えるため、野党は「同一価値労働同一賃金」原則の導入を提案しています。これは、同じ職務に同じ賃金を支払う「同一労働同一賃金」と同じではありません。
「同一価値労働同一賃金」の原則は、仕事が違っても、その価値が同じであれば同じ賃金を支払うべきだ、という考え方です。「知識・技能」「責任」「負担」「労働環境」の4要素で職務を評価します。国際労働機関(ILO)が提唱し、欧米で普及しています。
「同一価値」の原則がなぜ重要なのでしょうか。その理由の一つは、男性と女性では異なる職につく傾向があり、介護士など女性が多く就いている仕事は過小評価され、賃金が低い傾向にあることです。
◇「仕事の価値」で賃金が決まる仕組み
職務が同じ場合にだけ同じ賃金が払われたとしても、女性が多数を占める仕事の賃金が低いままだと、家族を養う女性の貧困はなかなか解消されないでしょう。そこで「同一価値」の原則が重要になるのです。
働き方改革で示された「同一労働同一賃金」を実現するため、「実行計画」は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すとしています。しかし、そのガイドライン案に実効性はあるのか、非正規雇用の女性の貧困問題を解決するには不十分ではないか、という声もあがっています。
「欧州諸国に遜色のない水準を」と提言するならば、相応の覚悟で実現してほしいものです。
記事の記載は中途半端に思える。銀行側が紙幣の番号を記録する必要があるのか、それは規則なのか、一般常識なのか?
規則であるのに記録していないのなら問題。常識の範囲であるのなら、問題ない。
ただ、大金が引き出された時に記録がなければ、マネーロンダリングや足のつかないお金に形が変わる可能性はある。まあ、それを 金融庁なり、財務省が規制していないのなら、多少の見逃しの余地を与えていると言う事になる。テロとか、セキュリティーと 騒ぐわりには、このような逃げ道に寛大と言う事になる。
もし記録が規則による要求であるのならメディアははっきりと記録する必要があったのに記録していなかったと報道するべきだと思う。 専門性や知識がないのでわからない。報道とはわかりやく伝える事ではないのか?
福岡市で20日、現金3億8,000万円が奪われた事件で、銀行側が紙幣の番号を記録していなかったことがわかった。
この事件は20日午後、福岡市天神の駐車場で貴金属販売会社の男性が、2人組の男に催涙スプレーのようなものを吹きつけられ、銀行から引き出したばかりの現金3億8,400万円を奪われたもの。
その後の調べで、奪われた紙幣の番号を銀行側が記録していなかったことが、捜査関係者への取材で新たにわかった。
また、2人組の男が逃走に使ったワゴン車のナンバープレートは、別の車から盗まれ、付け替えられた疑いがあることもわかった。
一方、21日には、7億円を超える現金を国外に持ち出そうとした疑いで、韓国人の男4人が逮捕されている。
警察は、関連について慎重に捜査している。
買収に関して判断や決定に関係した人々を処分するべきである。退職金やボーナスも減らせばよい。日本郵政は郵便事業を行っているのだから 投資や買収には他の企業以上に気を付けないといけない。
日本郵政は4月20日、海外子会社に絡み巨額の減損処理を迫られる可能性が浮上しているという一部報道について、「減損の要否を含め現在検討中」というコメントを発表した。
日経ビジネスの報道によると、2015年に6200億円で買収したオーストラリアの物流会社「Toll」(トール)が当初計画通りの利益が出せなくなったため、のれん代の減損処理を迫られる可能性があるという。のれん代は16年末で4000億円近くが計上されている。
日本郵政は、トールについて「業績が計画に達していない」ことを認め、減損の要否を含め検討中とした。
日本郵政は、収益拡大の柱にしたい国際物流事業の拡大を図り、トールの買収に踏み切った。だが買収効果が未知数という声は当初から出ていた。日本郵政の17年3月期の連結純利益は3200億円を見込んでおり、仮にのれん代の一括減損を迫られた場合、大幅な業績悪化につながる恐れがある。
日本郵政は15年11月に株式公開したばかり。報道が伝わった4月20日午後、同社株価は急落し、年初来安値を更新した。
大阪市の学校法人「森友学園」が近く、大阪地裁に民事再生法の適用を申請する方向で準備を進めていることが21日、関係者の話で分かった。学園は大阪府豊中市の旧国有地で目指していた小学校の開設を3月に断念。多額の負債を抱えており、同法の手続きの下での再建を目指す。
小学校の建設工事を請け負った「藤原工業」(同府吹田市)によると、契約額は約15億5千万円だが工事費がかさみ、実際の工事費は約20億円に上り、未収額は計約16億円以上という。
学園が大阪市で運営する「塚本幼稚園」の土地と建物のほか、系列保育園の土地、豊中市にある籠池泰典前理事長の自宅の土地、建物については、藤原工業が仮差し押さえを申し立て、大阪地裁が既に認めている。
【民事再生法】
経営危機に陥った企業や法人の倒産処理を迅速化し、再建を容易にするための手続きを定めた法律。破産や特別清算のような「清算型」の破綻処理と異なり、「再建型」の枠組みに属する。裁判所が選任する管財人に経営権や財産管理権が移る会社更生法と違い、経営陣はそのまま残って事業を継続しながら再建計画をつくることもできる。
◇17年3月期連結決算 海外企業買収でつまずいた形に
日本郵政は、2015年に買収したオーストラリアの物流会社の業績不振に伴い、17年3月期連結決算で数千億円規模の損失を計上する。近く発表する。米原発子会社の巨額損失で経営難に陥った東芝に続き、日本郵政も海外企業買収でつまずいた形だ。
損失が発生するのは、約6200億円を投じて買収した豪物流最大手「トール・ホールディングス」。日本郵政傘下の日本郵便の子会社になっている。
15年11月に株式上場を果たした日本郵政は、国内の郵便事業が低迷する中、収益力強化に向けて国際物流事業に活路を見いだそうとトールを買収した。しかし、資源価格低迷の影響でオーストラリアの資源貿易が停滞したことなどから、トールの業績は計画を下回る状況が続いている。買収価格に比べてトールの企業価値が大きく低下しており、日本郵政は損失計上が必要と判断した。
日本郵政は17年3月期連結決算を5月15日に発表する予定で、2月時点の最終(当期)利益の予想は3200億円。数千億円規模の損失を計上すれば、この予想を下回る可能性が高い。同社広報部は「トールの業績が計画に達していないことから(損失計上の)要否を含めて検討中」とコメントしている。
政府は日本郵政の上場後も約80%の株式を保有している。7月以降、東日本大震災の復興財源を調達するため、株式を追加売却する予定。日本郵政は追加売却前に損失を計上することでうみを出し切りたい考えだが、投資家の理解を得られなければ、追加売却計画の見直しを迫られる可能性もある。【浜中慎哉、小川祐希】
◇トール・ホールディングス
1888年に石炭運搬会社として設立された国際的な物流会社。本社はオーストラリア・メルボルン。アジアや欧州、北米を中心に、世界50カ国以上に約1200の拠点を持つ。従業員は約4万人。
告発した社員はばかじゃない。証拠がないと九州支店長のような人間は嘘を付いた挙句、こちらを嘘つき呼ばわりする可能性が高い。 嘘を付いたとしても立証できなければ、経済的に時間的に大手製薬会社「バイエル薬品」の顧問弁護士相手に勝つのは難しい。
証拠があっても勝てるのかよくわからない。全ての弁護士が正義の味方ではない。依頼者や多額の報酬を払う依頼者の味方である。
「内部告発をした社員に退職を勧めたことについて、バイエル薬品は『外部の専門家を交え、さらなる事実関係を検証している』としています。」
「外部の専門家」と言っても、大手製薬会社「バイエル薬品」に籍がないだけで、「バイエル薬品」に不利になる対応、又は、公平な立場の対応を 取るような専門家には依頼しないであろう。「利害関係のない外部の専門家」と言っていないので、そう言う事だと思う。
「社員は「会社に訴えても事態は変わらない」と判断し、去年7月、厚生労働省に告発しました。」
今回は、厚生労働省の担当者又は権限を持っている職員が真剣に取り組んだ、又は、医療費が膨らんでいる問題に関して薬の価格を下げる事に影響すると判断したのだろうか?
まあ、理由はどちらであれ、厚生労働省が踏み込んだアクションを取る事は良い事だ!
岡山大医学部と製薬会社の癒着を告発した2教授が停職処分に 10/21/2014(NEWSポストセブン)
大手製薬会社「バイエル薬品」が患者に無断でカルテを閲覧していた問題で、社内で内部告発した社員に対し、上司が「会社に法的責任はない」と話したうえで、会社を辞めるよう勧めていたことがわかりました。
この問題はバイエル薬品の社員が新薬の販売をめぐって、上司から指示を受け、宮崎県の開業医に依頼して、およそ200人分のカルテを患者に無断で閲覧していたものです。
この社員は2年前、「問題のある行為が行われている」と会社のコンプライアンス室に訴えていました。しかし、その後、バイエル薬品の当時の九州支店長は「法的問題はない」と話したうえで、社員に会社を辞めることを勧めていたことがわかりました。
【社員が録音した音声データより】
「法的には問題ないですよ」(九州支店長〔当時〕)
「問題ないわけないじゃないの」(内部告発した社員)
「(再就職先を)なんとか1回相談してみようか」(九州支店長〔当時〕)
「クビにするかどうかですか?」(内部告発した社員)
「円満に辞められるように」(九州支店長〔当時〕)
さらに、九州支店長は後日、退職一時金の額まで提示していました。
【社員が録音した音声データより】
「450万というのは退職一時金や。再就職支援、退職支援、もし希望があればな」(九州支店長〔当時〕)
「ないです。ないです」(内部告発した社員)
「ないの?」(九州支店長〔当時〕)
「ない。会社は一切責任をとらずに、僕にだけこうやって押しつけるというか、辞めさせ方の常とう手段としか思えないんですよ。僕に(カルテの閲覧を)やらせた人たちはそのまんま。結局、僕にだけ責任をとらせて、とかげのしっぽ切りじゃないですか」(内部告発した社員)
こうしたやりとりの結果、社員は「会社に訴えても事態は変わらない」と判断し、去年7月、厚生労働省に告発しました。体調を崩し休職していますが、現在も現役社員のままです。
大手製薬会社「バイエル薬品」が患者に無断でカルテを閲覧していた問題で、社内で内部告発した社員に対し、上司が「会社に法的責任はない」と話したうえで、会社を辞めるよう勧めていたことがわかりました。
この問題はバイエル薬品の社員が新薬の販売をめぐって、上司から指示を受け、宮崎県の開業医に依頼して、およそ200人分のカルテを患者に無断で閲覧していたものです。
この社員は2年前、「問題のある行為が行われている」と会社のコンプライアンス室に訴えていました。しかし、その後、バイエル薬品の当時の九州支店長は「法的問題はない」と話したうえで、社員に会社を辞めることを勧めていたことがわかりました。
【社員が録音した音声データより】
「法的には問題ないですよ」(九州支店長〔当時〕)
「問題ないわけないじゃないの」(内部告発した社員)
「(再就職先を)なんとか1回相談してみようか」(九州支店長〔当時〕)
「クビにするかどうかですか?」(内部告発した社員)
「円満に辞められるように」(九州支店長〔当時〕)
さらに、九州支店長は後日、退職一時金の額まで提示していました。
【社員が録音した音声データより】
「450万というのは退職一時金や。再就職支援、退職支援、もし希望があればな」(九州支店長〔当時〕)
「ないです。ないです」(内部告発した社員)
「ないの?」(九州支店長〔当時〕)
「ない。会社は一切責任をとらずに、僕にだけこうやって押しつけるというか、辞めさせ方の常とう手段としか思えないんですよ。僕に(カルテの閲覧を)やらせた人たちはそのまんま。結局、僕にだけ責任をとらせて、とかげのしっぽ切りじゃないですか」(内部告発した社員)
こうしたやりとりの結果、社員は「会社に訴えても事態は変わらない」と判断し、去年7月、厚生労働省に告発しました。体調を崩し休職していますが、現在も現役社員のままです。
この発言はとても危険だ!嘘であっても、本当であっても、厚生労働省による調査が必要と思われる。
「バイエル薬品からの接待が特に高額だとか、回数が多いということもない」のが事実であれば、製薬業界が医師に対して高額接待する事が常識になっていると 考えられる。高額接待の経費は薬の価格に含まれるはずだ!
ある意味、森友学園問題の公務員の対応としている。忖度ですませてしまえば、問題と見なされない可能性もある。 つまり、高額接待の見返りを言葉で明確にしないが、例えば、製薬会社の社員が資料を見れるようにして席を外すとかすれば、見ても良いとは言っていないが、 勝手に見る事が出来る。情報を得る事が出来れば、何も言わずに、また接待をする。確実な証拠はないが、お互いにバーター・トレードが出来る。
製薬業界と厚生労働省職員の一部は不適切な関係を持っているかもしれない。推測の世界なので何とも言えない。医者に高額接待を行うのであれば、 お役人にも行うかもしれない。
厚生労働省が今回の問題をどこまで踏み込むかで厚生労働省の体質の一部が見えるかもしれない。製薬業界と厚生労働省幹部の一部が癒着関係にあれば 深く立ち入らないと思う。自分達にも危険が及ぶ可能性があるからだ。
製薬会社営業マンによる医師への接待の実態 11/01/11(予防接種の参考本:ティム オシアー著(科学的根拠のない予防接種。))
製薬業界に「MR(エムアール=医療情報担当者)」という言葉があります。バイエル薬品が患者に無断でカルテを閲覧していた問題で、このMRが重要な役割を果たしていました。カルテを見せた医師に対するクラブ・料亭での接待の実態を、MR本人が告白しました。
「接待が大好きな先生で、高級店にしか行かなかった」(内部告発した現役社員)
こう証言するのは、バイエル薬品の営業担当だった現役社員。医師に医薬品の売り込みを図る営業社員はMR=医療情報担当者とも呼ばれます。この社員を含む複数のバイエル薬品の社員が宮崎県の開業医に依頼し、およそ200人分のカルテを患者に無断で閲覧していた問題。その後の取材で、バイエル薬品は、この開業医をクラブや料亭でたびたび接待していたことが分かりました。
「製薬会社と持ちつ持たれつの関係にある先生の1人。メシを食ったり飲んだりして、その後はクラブに行く。必ずタクシーで来る、会社が用意したチケットで」(内部告発した現役社員)
開業医は取材に対し、接待を受けた事実を認めたうえで「自分から要求したことはないし、バイエル薬品からの接待が特に高額だとか、回数が多いということもない」と回答しました。
接待で築いた関係のもとで得られたカルテのデータを使って何が行われていたのか。これはバイエル薬品の血栓症治療薬「イグザレルト」の広告です。そこには問題の開業医の名前が記されています。広告には開業医の名前で書かれ、医学誌に掲載された論文が使われていました。しかし、実際には、この論文を書いたのは開業医ではなくバイエル薬品側だったというのです。これは、バイエル側が書いたという論文の元原稿。開業医は、赤い文字でわずかに2か所、添削しただけでした。
「私がカルテを閲覧してデータを収集し、(バイエル薬品)本社に提出すると、こういった論文の元原稿が出来上がってきた」(内部告発した現役社員)
つまり、社員がカルテを閲覧して集めたデータを本社に報告。そのデータをもとに本社が論文の元原稿を作って開業医にチェックさせ、雑誌に投稿していたのです。
「このように会社が全部作成して、あとドクターが添削してというのは初の経験。これはもう驚がく、驚きでした」(内部告発した現役社員)
こうした論文作成の経緯について開業医は認めていますが、バイエル薬品は「検証中」と回答するにとどまっています。専門家は・・・
「製薬会社が(調査を)実施して研究の中身の論文も書いて、だけど医師の名前を借りて非常に悪質なケース。製薬企業と医師との不健全な経済的な関係は社会問題化している」(薬害オンブズパースン会議 水口真寿美 弁護士)
厚生労働省は製薬会社と医師の癒着がカルテ閲覧の背景にあったかどうかについて詳しい経緯を調べています。
製薬企業と医師との「不適切な関与」が疑われる事案がまたも発覚した。バイエル薬品によるカルテの無断閲覧では、社員が「アンケート」を名目に自社製品をアピールする意図がうかがわれた。
厚生労働省によると、人の健康に大きな影響を与える医薬品の広告や宣伝は、法律で厳しく規制されている。医師の処方箋が必要な医薬品について効能や効果を宣伝することは禁止されており、直接の商品名でなく会社や病気について理解を求める内容の宣伝が流されているのはそのためだ。
製薬企業は自社製品について、医療機関に情報提供する必要があるが、過剰な接待や利益提供は業界の自主基準で規制されている。ただ、業界が自主基準を厳格に順守しているとは言い難い。
東大病院などで行われた白血病治療薬をめぐる臨床研究では、複数の製薬企業の社員が、資料を作成したり研究計画に関わったりする不適切な関与をしていた。高血圧治療薬「ディオバン」の臨床研究事件では、研究にノバルティスファーマの社員が関わり、データの改竄(かいざん)をしたとされる。
事件を受け、不正を防止する臨床研究法が7日、成立。ただ、今回のアンケートのように、臨床研究の形を取らない場合は法律の対象外だ。
研究不正に詳しい医療ガバナンス研究所の上(かみ)昌広理事長は「血栓症治療薬はライバルの多い熾烈(しれつ)な業界。だが、医師には患者の情報を守る守秘義務があり、カルテを見せるなどあってはならない」と話している。
大手製薬会社のバイエル薬品(大阪市)が、患者に無断でカルテを閲覧していたことが11日、わかった。同社はホームページで事実関係を認めて謝罪。厚生労働省が事実関係の調査に乗り出した。
同社の社員が昨年、厚労省に内部告発していた。塩崎恭久厚労相は同日の閣議後の記者会見で「きわめて遺憾。必要に応じてしかるべき対応をとる」と述べた。
同社によると、2012年と13年に行った血栓治療薬に関する調査で、患者の同意を得ずにカルテの一部を書き写していた。医師の同意は得たとしている。調査結果は国内の医学誌に掲載されたが、16年1月に取り下げられた。
厚労省は今後、社内でどのような指示があったかなどを調べる。
同社は「このような事態を二度と繰り返さぬよう、外部の専門家を交えて問題の原因を徹底的に検証した上で、社員への教育を一層強化していく」としている。
大阪の製薬会社「バイエル薬品」が、5年前、新薬を発売する際、他社の薬の使用状況を事前に把握するために、患者のカルテを無断で閲覧していたことがわかりました。
会社側は、事実関係を認めたうえで、「二度と繰り返さないよう、社員への教育を強化していく」とコメントしています。
大阪・北区にある製薬会社「バイエル薬品」などによりますと、平成24年に、脳や肺などの血管が詰まりやすくなる「血栓症」の治療薬「イグザレルト」を発売する際、ほかの製薬会社の薬がどれくらい使われているかを事前に把握するため、複数の社員が、宮崎県内の開業医に依頼して、無断で患者のカルテを閲覧していたということです。
去年8月に当時の社員が「上司の指示でおこなってしまった」などと厚生労働省に内部告発し、会社が調査を行って判明したということです。
この開業医は、会社側の依頼を受けて患者への聞き取り調査を行っていたということですが、社員にカルテを閲覧させることについて患者から許可は得ていなかったということです。
バイエル薬品は事実関係を認めたうえで、「二度と繰り返さないよう、事実関係や問題の背景などを徹底的に調べて、社員への教育を強化していく」とコメントしています。
厚生労働省は、個人情報保護法などに違反する可能性もあるとみて、詳しい経緯を調べています。
常識の範囲なのか知らないが「昔は、結婚したら信用される。」とかテレビのドラマとか言っていたが、昔は、そんなものなのかと思っていた。 今は、結婚する事により、家族と言う人質を取られると思う事がある。家族を大事に思えば、思うほど、仕事に執着したり、 正しくてもリスクが伴うと行動が起こせない弱点が出来る。家族の正義漢が強ければ、内部告発で報復として首になっても理解してくれるかもしれない。 私立でなく、国立しか選択肢が狭まっても、努力して勉強して合格してくれるかもしれない。ただ、がんばったら結果が出るわけでもないし、 親の勝手な正義感で迷惑をかけられたと思うかもしれない。どのような家族関係を持っていたかが見えるかもしれない。もしかすると、 その時には理解されなくても、就職して同じような状況になると親の立場や気持ちがわかるかもしれない。
一般的に言えば、大手製薬会社「バイエル薬品」との戦いに勝ちはないと思う。
厚生労働省の対応次第で善戦は可能かもしれない。ただ、業界が病んでいる場合、厚生労働省にも手が回ると思うよ。極端な韓国を見ればわかる。 平等でも、公平でもない。弁護士はテレビドラマのような正義の味方ばかりではない。この世の中、綺麗ごとを言っている人達は現実を知ったうえで、 言っているのか、現実を知らずに行っているのか、偽善者なのか、嘘つきなのか、本物なのかといろいろと考える時もある。
厚生労働省には大手製薬会社「バイエル薬品」だけでなく、業界にまで踏み込んでほしいが、お金を持っている企業が多いから、無理なのだろうね!
大手製薬会社「バイエル薬品」の社員がおよそ200人分のカルテを患者に無断で閲覧していたことが私たちの取材でわかりました。そのわけは、ライバル社の薬の効き目を調べるためでした。
「患者さんには申し訳なかった」
こう話すのはバイエル薬品の50代の現役社員。患者本人に無断でカルテを見ていたと、去年、厚生労働省に内部告発しました。
「やってはいけないことはノーと言える自分でいたかった」(バイエル薬品の社員)
バイエル薬品が5年前に発売した血栓症治療薬「イグザレルト」。年間の売り上げが640億円にも及ぶ大ヒット商品です。発売直前の2012年2月ごろ、ライバル社の薬の効き目に関するデータを集めるため、つながりのあった宮崎県内の病院でおよそ200人分のカルテを閲覧し、データを書き写したといいます。この中には「がん」や「認知症」など目的とは関係ない個人の病歴に関する情報も多数含まれていました。
「アルツハイマー型の認知症も出てきて、自分の家族がそうであっても誰にも知られたくない」(バイエル薬品の社員)
カルテを閲覧させた医師は、取材に対し、「書面ではないが、患者の承諾は得ていた」と回答しました。しかし、実際に患者を取材すると・・・
「(承諾は)なかったと思います」
「何も話はない。(承諾がないのは)良くない。勝手に(カルテを)見られるのは、もしも悪い方に利用されたらおしまいだからね」(カルテを閲覧された患者)
バイエル薬品は10日、不適切なカルテの閲覧があったと認めました。個人情報保護法などの法律に違反する可能性もあり、塩崎厚生労働大臣は11日朝、極めて遺憾と述べました。
「バイエル社に対して本件の状況説明をまず求める。必要に応じてしかるべき対応をとらなければならない」(塩崎恭久厚生労働大臣)
バイエル薬品は3人の社員が関与した可能性があるとしていますが、内部告発した男性は会社からの命令だったと話します。
「(命令した上司にカルテの閲覧を)『やりたくないんですが』と言ったら、ちょっとキレられて(バイエル薬品)本社がやってはいけないことをやらせるわけないでしょう、だから早くやってくださいと」(バイエル薬品の社員)
上司の営業所長は・・・
Q.(カルテの閲覧を)無理やり社員に押しつけませんでしたか?違ったら弁明してください
「違います」(バイエル薬品の宮崎営業所長)
バイエル薬品は、外部の専門家を交え、検証するとしていますが、厚生労働省は会社組織の関与があったかどうかについても調べるとしています。
まあ、法的には問題がないとしても、程度の違いはあれどこのような状況になると思っていた。株価はそのうちに戻ってくるかもしれないので 時価総額約10億ドル(約1000億円)が確定したわけではないが、企業イメージの低下そしてイメージアップのためのコストを考えると もっとましな選択をするべきだったと思う。
まあ、誰も反対しなかったのだから米ユナイテッド航空の従業員達に問題がある、米ユナイテッド航空による従業員に対する締め付けが 厳しい、又は、そのコンビネーションだろうと思う。
謝罪して何事もなかったようにはなるとは思えない。
(CNN) 米ユナイテッド航空便に搭乗した乗客が、定員オーバーを理由に無理やり引きずり降ろされた問題で、オスカー・ムニョス最高経営責任者(CEO)は11日、改めて謝罪の談話を発表し、徹底検証を行うと表明した。
乗客は弁護士を通じ、引きずり出された際に負傷して病院で手当てを受けていることを明らかにした。ユナイテッド航空に対する抗議の声は止まらず、株価は11日の取引で4%急落、時価総額約10億ドル(約1000億円)相当が吹き飛んだ。
騒ぎは9日の米シカゴ発ケンタッキー州ルイビル行きの便で発生。降りることを拒んだ男性乗客が保安要員に両手足をつかまれて通路を引きずられて行く姿を映した動画が公開され、ユナイテッド航空に非難が殺到していた。航空関係者によると、この男性はデービッド・ダオさんという医師だった。
ムニョスCEOは11日の談話の中で、「強制的に降ろされた乗客と、搭乗していた全乗客に謝罪する。誰であれ、これほど不当な扱いを受けることがあってはならない」と強調した。
ダオさんの弁護士は11日、ダオさんがシカゴの病院で手当てを受けていることを明らかにした。「ダオさん一家は、気遣いや支援の言葉が多数寄せられたことにとても感謝している」「ダオさんが退院するまでマスコミの取材には応じない」としている。
この問題では当初、ユナイテッドのムニョスCEOが社内文書で乗員の対応を称賛していたことも明らかになった。同文書によれば、乗客は引きずり降ろされた後も抵抗を続けて機内に駆け戻っていたといい、「乗員は定められた手順に従って対応した」とムニョスCEOは評価。「こうした状況になったことは遺憾だが、私はあなた方全てを断固として支持する」と強調する一方で、「この経験から学ぶべき教訓もある」と指摘していた。
ジョール・グンター記者、BBCニュース(ワシントン)
航空会社が定員以上の乗客の予約を受け付けるオーバーブッキングは良くあることだが、9日夜の米ユナイテッド航空の場合、男性が無理やり座席から降ろされ、口から血を流しながら通路をひきずられるという事態に発展した。ただでさえ問題山積の同航空はさらに悪評を重ねることになったわけだ。いったいどうして、こんなひどいことになってしまったのか。
フライトのオーバーブッキングはしょっちゅうある。航空会社にとって、空席は費用負担になるため、乗り損ねる乗客がいる可能性を見越して定員以上のチケットを売るのだ。
今回の場合、ユナイテッド航空が出発直前になって、社員4人を中継地まで移動させることにしたのが原因だった。この4人を乗せるため、乗客4人を降ろす必要があると判断したのだ。
オーバーブッキング問題の対応として、航空会社がまず最初にやるべきは、後のフライトに移ってもらうために乗客に何かを提示することだ。9日夜の乗客には、400ドル(約4万4000円)とその夜のホテル宿泊と翌日午後のフライトが交換条件として提示された。
乗客が誰も手を挙げなかったため、提示額は800ドルに倍増された。それでも誰も応じなかったため、マネージャーが機内に乗り込み、降りる乗客4人をユナイテッド側が選ぶと告げた。
このような場合に誰を残すか誰を降ろすかは様々な条件で判断するが、頻繁に利用する得意客(フリークエント・フライヤー)や高額なチケットで乗っている客は優遇されると、ユナイテッド航空の広報担当は確認した。
選ばれたカップルは、自発的に降りると同意した。3人目の女性も同意した。この女性は、無理やり降ろされた男性の妻だと言われている。しかし4人目の男性は、自分は医師で翌朝には患者の診察があるからと、降機を拒否した。
この時点でユナイテッド航空は、別の乗客を選んで降ろすか、提示額を最大1350ドル(約14万8500円)まで引き上げることもできた。
同航空のエリン・ベンソン広報担当は、他の乗客に声をかけたのかどうか確認できないと話した。一方で、800ドル以上の提示がなかったことは確認したが、その理由については説明しなかった。
複数の目撃者によると、降機を拒否した男性は自分は医師で翌日に変更できない予定があると説明していた。この内容は確認されていない。問題のフライトは9日夜のもので、代わりに提示された次の便は10日午後3時出発だった。
目撃者は、自分が降ろされるかもしれないと分かった男性は「とても動転して立腹」し、弁護士に連絡しようとしたという。ユナイテッド航空のマネージャーは男性に、降りなければ治安当局を呼ぶと告げた。
この時点で航空治安当局の係官が男性のもとへやってきた。最初にまず1人、次いでさらに2人。ビデオからも明らかなように、係官たちはやりとりの末に男性を席から強引に降ろさせ、通路をひきずっていった。男性は口から流血しているのが見える。
ユナイテッド航空は規定上は、降機を拒否した男性を無理やり降ろさせる権利がある。その上での対応手続きは、同航空の運航指針に定められている。しかしこのようなケースはきわめて珍しい。
米運輸省によると、2015年に主要な米航空会社を利用した6億1300万人のうち、本人の意志に反して搭乗拒否されたのは4万6000人。全体の0.008%以下だ。
交通機関の利用者の権利を掲げる団体「トラベラーズ・ユナイテッド」の創設者チャールズ・リオチャさんは、搭乗できなかった人のほとんどは、実際に機内に入る前に乗れないと伝えられたはずだと言う。乗客が強引に引きずりおろされる様子など見たことがないとリオチャさんは言い、「胸が悪くなった」と話した。
加えて、離陸直前になってスタッフのために乗客を降ろさせるなど、異例中の異例だとリオチャさんは指摘。スタッフを移動させる必要があるなら、それは事前に把握して予約受付の時点で配慮すべきだという。
米国の旅客機利用者は慢性的なフライト遅延と劣悪な接客を諦めて受け入れている状態だと、リオチャさんは話す。さらに、利用者としての権利について情報が簡単に得られないため、このような状況では航空会社の担当者の言いなりになってしまいがちだという。
「これまでの経験から私たちの期待値はとことん低くなっているので、乗客は受け入れるようになってしまっている。しかし社員の席を作るために乗客を引きずりおろすなど、乗客は受け入れてはならない」とリオチャさんは強調する。
ユナイテッド航空の最高経営責任者(CEO)は声明を出し、事実関係を調査すると述べた。オスカー・ムニョスCEOは、「ユナイテッドの全員が困惑し動揺しています。乗客を振り替えなくてはならなかったことを謝罪します」、「喫緊に当局と協力し、事実関係を詳細に調査する」と表明している。
ムニョスCEOはさらに、「この乗客と直接話をして、問題にさらに対応して解決するため、男性に連絡をとっている」と書いた。しかし広報担当は、実際に男性に連絡をとったかどうか確認できないと話した。
ユナイテッド航空に呼ばれて男性を引きずりおろした航空治安当局の係官3人のうち、シカゴ航空局は1人について「停職扱い」にしたと発表。係官の行動は「もちろん、航空局が容認するものではない」と表明したほか、「我々の通常手続きの基準に見合っていない」ため、事実関係を調査すると述べた。
9日夜のユナイテッド航空3411便で実際に何があったにせよ(詳細は当然ながら数日の内に表面化するだろう)、ユナイテッドにとって悪い日だったとリオチャ氏は言う。同航空はつい先月末、レギンスの着用を理由に少女2人の搭乗を拒否して物議を醸したばかりだ。
「今回のことから教訓を得るべきは、実際には乗客ではなく航空会社の方だ」とリオチャ氏。「乗客が学ぶべきことはたったひとつ。セキュリティーが乗ってきたら両手を上げましょう。でないと唇を腫らして、通路を引きずられる羽目になるから」。
(英語記事 United Airlines incident: What went wrong? )
米原発子会社ウェスチングハウス(WH)を買収した後は、勝ち組とか、優れた経営判断とか雑誌やメディアで取り上げられていたが、 時が経つと評価も、結果も変わってくると言う事だ。
逆を言えば、今、良い評価を得られなくても将来、良い評価を得られる事もあると言う事。人生、終わってみないとわからないと言う事だろう。
東芝は、2度にわたって延期していた2016年4~12月期決算を、国が認めた期限の11日に発表した。ただ、通常の決算につくはずの監査法人の「適正意見」は得られず、代わりに「意見不表明」という信頼性を欠いた異例のものとなった。経営破綻(はたん)した米原発子会社ウェスチングハウス(WH)をめぐる調査で監査法人との溝が埋まらなかった。
東芝を担当するPwCあらた監査法人は、原発事業の損失を小さくみせようとして、WHの経営幹部が「不適切な圧力」を部下にかけたことを問題視。損失を経営陣が早くから認識していた可能性も調べていた。
だが、詳しい調査の必要性を訴えるPwCに対して、東芝の綱川智社長は11日夕方の記者会見で「これ以上調査を続けても意味がない」と突き放した。PwCは報告書のなかで「調査結果を評価できておらず、財務諸表に修正が必要か否か判断できなかった」とした。
「意見不表明」は十分な監査の証拠が手に入らない場合に監査法人が出す見解で、大手上場企業ではきわめて異例だ。綱川社長は「適正意見のめどが立たないことから、これ以上、ステークホルダー(利害関係者)に迷惑をかけられない」と話した。
最近はiPhoneなど持っている人が多いから簡単に動画や録音を取る事が出来る。事実の動画が流れると法的には問題なくても 企業イメージは悪くなるあろう。
利用者や将来の顧客がユナイテッド航空の対応をどのように評価し、どのような行動を起こすのかはアメリカ人や利用者次第。
アメリカでオーバーブッキングとなったユナイテッド航空の機内から出発便の変更要請を拒否した乗客が引きずり降ろされ、強引な対応に批判が集まっています。
警察官につかみかかられ、飛行機の座席から無理やり引っ張り出される男性。このまま通路を引きずられ、飛行機から降ろされました。
アメリカメディアによりますと、9日、イリノイ州シカゴ発のユナイテッド航空の便がオーバーブッキングとなり、コンピューターで任意に選ばれた4人が出発便の変更を要請されました。しかし、この男性は医師で「患者の診察がある」として拒否したため、強制的に機内から出されたということです。映像がインターネット上に投稿されると強引な対応に批判が集まり、ユナイテッド航空は乗客に謝罪したうえ、早急に調査するとしています。
AP通信によりますと、キャンセル客を見越して航空券の予約を過剰に受け付けるのはよくあることで、去年1年間、アメリカの航空会社でオーバーブッキングのため予約を取り消された乗客は4万人に上るということです。
[AP通信] オーバーブッキングを理由に警官が米ユナイテッド航空の旅客機から乗客の1人を引きずり降ろす様子を収めた動画が4月10日、SNSに投稿され、物議をかもした。ユナイテッド航空の広報担当者は「この男性に降りてもらうためには警察を呼ぶしかなかった」と説明している。
問題が起きたのは、9日夕方にシカゴのオヘア国際空港で離陸準備に入っていたケンタッキー州ルイビル行きのユナイテッド航空3411便。動画には、窓側の座席で叫び声をあげる男性を複数の警官が肘掛け越しに引っ張りだし、両腕をつかんで通路を引きずっていく様子が映っている。ユナイテッド航空は提携航空会社の乗務員4人のために席を空ける必要があったのだという。
機内では乗客が、「ああ、何てこと!」「何をやっているんだ?」「これはひどい」「自分が何をしたか分かっているの?」「唇が切れている」といった非難の声を上げている。
この動画をFacebookに投稿したのは、乗客の1人、オードラ・ブリッジズさんだ。夫のタイラーさんによれば、ユナイテッド航空は当初、400ドルのバウチャーにホテル1泊無料をつけて別便への振り替えに応じてくれる人を募っていたが、その後、乗客の搭乗が済み、バウチャーを800ドルに増額しても、志願者は1人も出なかった。すると、ユナイテッド航空の責任者が機内に乗り込んできて、「降りてもらう乗客を無作為に選ぶ」と説明したという。
「人質に取られたような気分だった。既に機内に乗り込んでいたので、旅行客としては何もできない。航空会社に任せるしかない」とタイラーさん。
ユナイテッド航空の乗務員が4人の乗客の名前を読み上げると、そのうち3人は求めに応じた。「だが4人目の乗客が動こうとしなかったので、警察を呼んだ」とユナイテッド航空の広報担当、チャーリー・ホバート氏は説明する。
「適切な手順を踏んだ。飛行機は離陸する必要があった。私たちには搭乗客を目的地まで運ぶ義務があった」。ホバート氏はAP通信の電話取材に応じ、そう語った。
ユナイテッド航空のオスカー・ムニョスCEOは、今回の件で「社内の皆が動揺している」と述べ、「一部の乗客の便を振り替えなければならなかったこと」に対し、謝罪した。同氏によれば、ユナイテッド航空は今回の事態について調査を進めており、状況を把握し、問題解決を図るべく、この乗客に連絡を取っているところだという。
タイラーさんによれば、この男性客はユナイテッド航空の責任者に対し、自分は医師であり、翌朝に患者を診る必要があると語っていたという。
「男性は、自分が選ばれたのは中国人だからだ、というようなことを言っていた」とタイラーさん。ユナイテッド航空の責任者はアフリカ系アメリカ人だったという。
男性客は、「これがどういうことか分かっているのだろうな」とも発言していたという。
AP通信は、この乗客の身元については確認できなかった。
タイラーさんによれば、最初は2人の警官がこの男性の説得を試みた。そこへ加わった3人目の警官がこの男性に指をさし、「あなたは飛行機から降りなくてはならない」というようなことを言ったという。そこで、口論となった。
シカゴ航空局は10日、機内で対応に当たった警官の1人を休職処分としたことを明らかにしている。
この男性客が降ろされた後、提携航空会社の乗務員4人が機内に乗り込んできたという。
「乗客はそれを容認したが、中には『恥を知れ。こんな会社に勤めているなんて』と言っている人もいた」とタイラーさんは語る。
ホバート氏によれば、4人はリパブリック航空の乗務員。ユナイテッド航空と提携し、地域路線「ユナイテッドエクスプレス」を運行している地域航空会社の1社だ。この4人の乗務員をケンタッキー州まで運ばなければ、彼らが乗務を予定しているその後の便がキャンセルになるところだったという。だが、振り替えの志願者も確保せず、必要分の予約取り消しもしないまま、なぜゲート係員は乗客の搭乗を開始したのか。ホバート氏はその点については説明できなかった。
タイラーさんによれば、4人の乗務員が搭乗した数分後に、先ほどの男性客が戻ってきて、取り乱した様子で「家に帰らなければならない」と訴えたという。
動画では、男性客は機内後部の通路とみられる場所に立ち、「家に帰りたい」と訴えている。口から血を流し、あごや頬に血がついている。
タイラーさんによれば、男性の後を追って、警官らも機内後部に入ってきたという。そのとき、高校生たちと旅行中の別の男性が立ち上がり、「降りたい」と訴えたという。
このグループに続いて、半数ほどの乗客が降機。中国人医師だという男性も再び機内から降ろされた。
ユナイテッド航空はその後、「機内を清掃する必要がある」として、乗客全員に対し、機内からいったん降りるよう促した。
タイラーさんの妻のオードラさんは、中国人医師だという男性が担架で運ばれていくのを見たという。
3411便は結局、この男性を乗せずに、予定より3時間遅れて離陸した。機内では、ユナイテッド航空の職員の1人が乗客らに謝罪したという。
航空券を予約しても空港に現れない乗客がいることから、航空会社は実際の座席数よりも多くの航空券を販売することを認められており、オーバーブッキングは日常的に行なわれている。
別便への振り替えに自発的に応じてもらうために、航空会社が無料航空券を提供するのはよくあることだ。その手順にルールはない。乗客に別便への振り替えを強制する場合には、航空会社は補償金を支払うことを義務付けられている。補償金額は、振り替え便が当初の便より1〜2時間後に目的地に到着する場合は675ドルを上限として片道運賃の2倍、それ以上の遅れとなる場合は上限を1350ドルとして片道運賃の4倍に定められている。
さらに、航空会社が乗客の予約を取り消す場合には、対象となる乗客に対し、賠償請求権について説明した書面を渡すことが義務付けられている。
ホバート氏は現場の乗務員から詳細な報告を受けていないとして、今回3411便を降ろされた乗客への補償に関するコメントを断っている。
「オーバーブッキングがあったのなら、機内への搭乗を開始すべきではなかった」。タイラーさんはそう指摘し、次のように語る。
「ユナイテッド航空は対応を誤った。警官は困った立場に置かれていた。もっと良い対処法があったはずだ。今回のやり方はまずかった」
「小島座長の案は、築地市場を7年かけて改修する計画で、総事業費は734億円。豊洲市場を約150億円かけて解体し、跡地は最大4370億円で売却する。」
これらの数字は誰が、どのようにしてはじき出したのか説明するべきだと思う。小島座長が出した数字ではないと思う。
東京・築地市場(中央区)の豊洲市場(江東区)への移転問題について、都と市場業界が意見交換する「新市場建設協議会」が11日、築地市場で開かれた。
両市場を所管する都中央卸売市場の村松明典市場長は、都の「市場問題プロジェクトチーム(PT)」の小島敏郎座長(弁護士)が8日に発表した築地市場を移転させずに改修する案について、「想定通りできるか疑問だ」との見解を述べた。
小島座長の案は、築地市場を7年かけて改修する計画で、総事業費は734億円。豊洲市場を約150億円かけて解体し、跡地は最大4370億円で売却する。
村松市場長は「(改修案は)小島さんの私案と聞いている」とした上で、「業界調整がうまくいくのか、都市計画上の問題点はないか、豊洲市場の売却価格は想定通りか、議論しなければいけない」と複数の課題を挙げた。
東京都の築地市場(中央区)からの豊洲市場(江東区)への移転問題を巡る都議会の百条委員会は4日、都庁の元幹部3人の証人喚問を終えて一つの区切りを迎えた。石原慎太郎元知事をはじめとする計24人を喚問したものの全容解明にはほど遠く、この日の証人も「自分に権限がない」との説明に終始。市場関係者は、百条委そのものに批判の矛先を向けた。
「時間の無駄だった」。百条委について、築地市場にある東京魚市場卸協同組合の伊藤淳一前理事長(63)は切り捨てた。「議員もいろんなストーリーに証人をはめ込もうとしていたが、議論が全くかみ合わなかった。都議選(7月2日投開票)をにらんだ単なるアピールの場だったのでは」と語り、「何より小池百合子知事が移転の可否を早く決断してほしい」と求めた。
築地市場の水産仲卸会社「大仲」の今井千鶴専務(65)も「もっと徹底的に追及してほしかったが、いずれの証人たちもけむに巻いたり、責任をうやむやにしたりして、逆に疑惑が深まった」と指摘。「(東京ガスからの)用地買収の裏で何かあったんじゃないかと豊洲市場に対するイメージがますます悪化した。このまま移転するのは無理」と嘆いた。
この日は、石原元知事が「交渉のキーマン」と名指しして後に訂正した練馬区長の前川燿男(あきお)元知事本局長ら3人が証言した。
前川氏は、浜渦武生元副知事の「関わったのは(東京ガスとの)基本合意までで、以降は全く分からない」との証言が偽証ではないかとする議員の質問に対し、「浜渦さんが最高責任者だった」と強調。「(石原元)知事がほとんど登庁しない中、浜渦さんに権力が集中していた。浜渦さんにお手紙を出さないと会えない状況がつくられてきた。所管外の部課長も指揮していた」と、当時の都庁の内情を明かした。
この日を含め3日間傍聴したという目黒区の男性(69)は「証人の多くは、問題や責任のありかをあやふやにしていた。消化不良だ」と不満を漏らした。【森健太郎、円谷美晶】
◆都議会百条委が喚問した証人
<元都首脳陣>3人
石原慎太郎・元知事、浜渦武生・元副知事、福永正通・元副知事
<元中央卸売市場長>5人
大矢実氏、森沢正範氏、比留間英人氏、岡田至氏、中西充氏
<東京ガス>9人
上原英治・元会長、市野紀生・元会長、岡本毅会長、広瀬道明社長、
伊藤春野・元副社長、志水巨宜・元開発グループマネジャー、
高木照男・元活財推進室長、丸山隆司・元大規模用地プロジェクト部長、
柴田理・元「東京ガス豊洲開発」事業部長
<都財産価格審議会など>4人
新藤延昭・元都財価審会長、松浦隆康・都財価審会長、不動産鑑定士の川藤等氏、近藤克哉氏
<4日喚問の都幹部>3人
前川燿男・元知事本局長、赤星経昭・元政策報道室理事、
野村寛・元知事本部首都調査担当部長
学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却問題で、安倍晋三首相の夫人昭恵氏付の政府職員だった職員が学園の籠池泰典前理事長にファクスで送った文書について、政府は4日、行政文書に該当しないとの答弁書を閣議決定した。民進党の逢坂誠二衆院議員の質問主意書に答えた。
答弁書では、籠池氏から問い合わせを受けた夫人付の職員が、職務に関係しないにもかかわらず財務省に問い合わたうえで結果を情報提供したことを、「公務員として丁寧に対応したが、職務として行ったものではない」と説明。文書についても、「職務上作成したものではなく、組織的に用いるものとして保有していたものでもない」とし、行政文書にはあたらない、と結論づけている。
理解不能。無免許運転を繰り返していると事故を起こした時に全てを失うと考えなかったのか?
立命館大学の産業社会学部・社会学科メディア社会を専攻していたそうだが、立命館大学では倫理やモラルを教えなかったのか? 教えていたのなら、悪質、又は、思考能力に問題ありと判断するしかないだろう。
静岡第一テレビの管理体制の甘さにびっくり!!
「静岡第一テレビ ”藤原アナウンサーの免許 入社時には持っていたこと確認”」
もしかすると、偽造免許をテレビ局に見せたのか?そうだとするとさらに悪質だ!

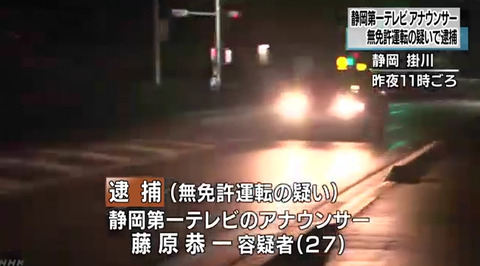
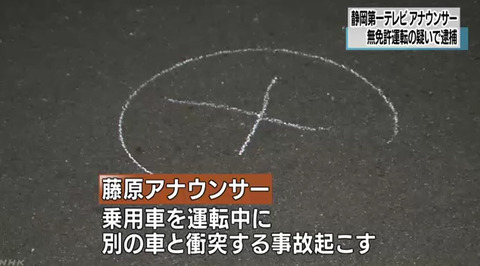

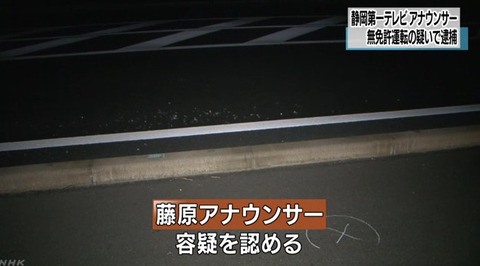

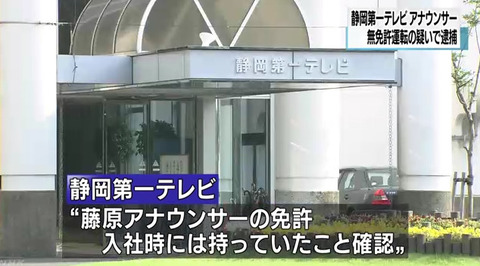
04/02/2017 (なんでもnews実況まとめ)
無免許運転の疑いで逮捕された静岡第一テレビの男性アナウンサー(27)が今まで運転免許を一度も取得していないことが新たに分かりました。
静岡第一テレビの男性アナウンサーは1日、静岡県掛川市内で無免許で車を運転した疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、男性アナウンサーは免許の有効期限が切れていたのではなく、普通運転免許を過去に一度も取得したことがなかったということです。警察は長期間、無免許運転を繰り返していたとみて調べています。男性アナウンサーは容疑を認めていて、警察は3日に男性アナウンサーを釈放しています。
静岡県警掛川署は1日、道交法違反(無免許運転)容疑で、静岡第一テレビ(SDT)のアナウンサー、藤原恭一容疑者(27)=静岡市駿河区=を現行犯逮捕した。藤原容疑者は「無免許です。間違いありません」と容疑を認めている。
逮捕容疑は、1日午後6時20分ごろ、同県掛川市長谷の市道で、乗用車を無免許運転したとしている。
藤原容疑者は片側1車線の市道で交通事故を起こし、駆けつけた同署員が現場で免許証を確認したところ、無免許だったことが発覚した。
静岡第一テレビによると、藤原容疑者が乗っていたのは同社の社有車で、同県袋井市内のサッカーJリーグの試合を取材した帰りだったとみられる。
同社は「当社社員が逮捕されたことは遺憾だ。事実関係を調べたうえで厳正に対処する」としている。
◇「幼稚園」と「保育園」立ち入り調査
大阪府は31日、学校法人「森友学園」が府から補助金を不正に受け取った疑いなどがあるとして、学園の「塚本幼稚園」(大阪市)に立ち入り調査した。大阪市も同日、学園系列の「高等森友学園保育園」(同)の調査に入った。市の調査で、学園の籠池泰典理事長は一部の補助金受給で不正を認め、2年度分計約250万円を返還する考えを表明した。ただ府や市が提示を求めていた学園の資料がそろわず、府や市は改めて再調査する。
府の調査の際、籠池理事長が退き、長女町浪(ちなみ)氏が4月1日付で新理事長に就任すると説明した。籠池氏は理事からも退く。
塚本幼稚園は、保育園でも勤務する職員を「幼稚園の専任教員」と報告、専任教員数に応じて支給される補助金を実際より多く受け取った疑いがある。特別な支援が必要な子の在籍数に応じて交付される補助金の受給でも不適切な点があった疑いも浮上している。
府は職員出勤簿などの原本を確認し、不正の有無を調べる予定だった。しかし、学園は府が求める職員出勤簿について「国会の証人喚問で東京に運んだものがある」として、一部しか示さなかった。
小学校計画を巡り、学園は国や府など申請窓口に応じて額の異なる3種類の工事契約書を用意していた。府には財務状況を良く見せるため額の安い契約書を示したとされる。府は説明を求めたが、学園側は大阪地検が捜査を始めたことを理由に「説明を控えたい」と、回答を避けた。
一方、大阪市によると、籠池氏は保育園に専任の栄養士を配置したとして受給した補助金について受給要件を満たしていなかったことを認め、2015~16年度に受け取った補助金計252万円を返還する意向を示した。
保育園の園長は籠池氏の妻で、15~16年度、常勤園長を配置する前提で交付される市の「所長設置加算」約1000万円を受け取ったが、妻は塚本幼稚園の副園長を兼ねており、不正に受給した疑いもある。籠池氏は「昼食時は幼稚園にいたが、大半は保育園にいた」と不正を否定したという。【津久井達、藤顕一郎、米山淳】
まあ、自民党の自己責任であるから政治不信を増大させたければこのままの対応を続ければ良いと思う。
兵庫県姫路市の認定こども園が定員を大幅に超える園児を受け入れていた問題で、勤務実態のない保育士を水増しして市に報告していたことなどから30日、労働基準監督署が立ち入り調査を行いました。
「労働基準監督署です!」
30日、労働基準監督署の職員らが兵庫県姫路市の認定こども園「わんずまざー保育園」に立ち入り調査に入りました。こども園を巡っては46人の定員を大幅に超える68人の園児を市に隠して受け入れたり、勤務実態のない保育士を水増しして市にうその報告をしていたなどとして認定の取り消し処分が決まっています。
保育士らによりますと0歳児12人を1人の保育士で見ていたときもあったということです。立ち入り調査では園長や保育士らから保育実態の聞き取りなどを行ったとみられます。
毎日放送
まあ、自民党の自己責任であるから政治不信を増大させたければこのままの対応を続ければ良いと思う。
森友問題の焦点となっている手紙の全容が私たちの取材で明らかになりました。籠池理事長が安倍昭恵夫人付きの政府職員に送ったとされる手紙。それには学園側からの事細かな要求が記されていました。
「すばらしい幼稚園だなと」(安倍昭恵夫人 2014年12月6日)
2014年、森友学園が経営する塚本幼稚園を昭恵夫人が訪れたときの映像。教育勅語を暗唱する子どもたちを笑顔で見つめる昭恵夫人。夫人付きの政府職員・谷査恵子氏の姿も見えます。この10か月後、谷氏のもとに籠池理事長から1通の手紙が届きます。その手紙の全容が明らかになりました。
「早い時期に買い取るという形に契約変更したいのです。でないと安心して教育に専念できない。買い取り価格もべらぼうに高いのでビックリしている」(籠池氏が送った手紙)
さらに・・・
「安倍総理が掲げている政策を促進する為に国有財産(土地)の賃借料を50%に引き下げて運用の活性化を図るということです。学校の用地が半値で借りられたらありがたいことです」(籠池氏が送った手紙)
手紙には、できるだけ安く国有地を手に入れたいという籠池氏の意向が示されています。政府は先週、籠池氏のこの手紙に返答した谷氏のファクスを公開。「ご希望に沿えない」と回答していることから「ゼロ回答であり、忖度をしていないことは明らかだ」と主張してきました。しかし・・・
「実は一番の眼目は早く買い取ることはできませんかということ」(共産党 大門実紀史参院議員 今月28日)
共産党の大門議員は、手紙に書かれた籠池氏の要望は全てかなえられていて、結果的に「満額回答」だったのではないかと追及しました。
「その後、2016年6月20日、半年後に実現しているわけです。ゼロ回答どころか満額回答ではないかと言える」(共産党 大門実紀史参院議員)
満額回答ではないかという大門氏の指摘に対して、菅官房長官は・・・
「私は(手紙を)読みました。しかし、内容からして、まさにゼロ回答であったと思っております」(菅義偉官房長官)
自民党は「ゼロ回答というよりマイナス回答」だとしており、手紙とファクスの解釈をめぐって意見が鋭く対立しています。
◆秘書がすべてやったことに!?
今、世間を賑わしている森友学園への国有地払い下げ問題。安倍首相と思想信条を共にする森友学園に向けて、国有地が不当に安い価格で売却された真相の究明を期待したい。
安倍首相は「私も妻も一切この認可にも、あるいは、この国有地の払い下げにも関係ない。私や妻が関係していたということになれば、間違いなく総理大臣も国会議員も辞めるということははっきりと申し上げておきたい」と言い切っている。
疑惑の追及で開かれた3月23日の国会証人喚問で、森友学園の籠池泰典氏は、安倍首相の妻の昭恵夫人が元秘書(経産省からの出向)のT氏に指示して、国有地を巡る対応をさせていたと述べた。ところが翌日24日に菅義偉官房長官は、昭恵夫人はまったく関知せず、秘書のT氏が勝手にやったことであるとの見解を言ってのけた。
首相や夫人の関与がないものとするために、秘書にすべての責任を押しつけたのだ。どう考えてもオカシイ。恐ろしいほどの詭弁だ。これは国家による一個人へのパワハラであり、イジメである。
◆昭恵夫人と元秘書のT氏の関係は「信頼し合う友人」のようだった
実は昭恵夫人は、私の経営する小さなBarに何度となく来店されている。その折、秘書(当時)のT氏も同行されて一緒に楽しく和気あいあいと飲食したこともある。一般に国会議員の「秘書」というと政策アドバイザー的なイメージもあるが、T氏を含む昭恵夫人付の秘書の方々は、昭恵夫人の周辺サポート的な存在であって、国会議員の秘書とはまるで違う種類のものだ。みなとても素直で、素朴な女性ばかりである。
昭恵夫人とT氏はファーストレディと秘書の上下関係というより、信頼し合う友人のように、互いに心を開いて話し合える間柄だった。ある雑誌の特集で、私が昭恵氏にインタビューの聞き手としてお会いすることがあった折も、安倍政権に批判的なことを言う私を、昭恵氏もT氏も屈託のない笑顔で迎えてくれた。
またその段取りについても、T氏は丁寧で誠実な対応をしてくださった。そんな経緯から、T氏については明るく真面目で誠実な女性であるという印象が残っている。その彼女が、職責的にもお人柄的にも、安倍首相や昭恵夫人の指示や意向なしに、国有地払い下げに関われるわけがない。
◆突然、大事件の汚名を一人で着せられた気持ちは……。
突然、政府という権力にこれだけの大事件の汚名を一人で着せられたT氏は、さぞ悔しくやるせないだろう。彼女はさまざまな上からの指示に忠実に誠実に丁寧に職務を遂行しただけだ。彼女が省庁で今後も働いてゆく以上、心の奥に真実を封印し、内なる絶望と世間からの白い目にさらされながら、生き抜いてゆかねばならない。これからの人生を翻弄されてしまうにちがいない。
昭恵夫人の秘書だったT氏にこの記事は届くだろうか。責任を負わなければならないのが誰か、卑怯な人間が誰かは、わかる人にはわかっている。国民のおおかたはわかっている。理不尽な責任を負わされてしまったが、あなたは一人ではない。生きる道は、今いる職場だけでもない。もし省庁の中で働くことに限界が来たとき、私を覚えていてくださるなら、いずれ訪ねてきてほしい。
昭恵さん、もし私のこの記事を読むことがあるなら、何かを感じることでしょう。
お立場はわかります。そして昭恵さん自身が本当に辛い立場になっていることもわかっています。
私が書いたことは間違っているかもしれません。
でもどうであれ、
首相も官房長官も、そしてそれに準じて昭恵さんも、Tさんを見捨てて利用したことは明らかです。昭恵さんが彼女の汚名を晴らさない限り、真実をきちんと語らない限り、彼女の人生を翻弄してゆくでしょう。
そして、昭恵さん自身がずっと苦しんでゆくことになるでしょう。
<文/髙坂勝>
認定取り消しはほぼ決定だから、何も言いたくないし、報道関係者にも質問されたくないと言う事かもしれない。
借金はないのであればこのような終わり方も良いかもしれない。
兵庫県姫路市の私立認定こども園「わんずまざー保育園」の不適切保育問題で、兵庫県は29日午前、同園の認定の取り消し手続きに入った。同日午前10時から、園側の意見を聞き取る「聴聞」を県庁で行う予定だったが、小幡(おばた)育子園長は訪れなかった。早ければ午後にも決定する。認定取り消しは全国初。
県によると、前日までに小幡園長から出頭しないという連絡があり、この日の県による確認にも同様の意向を示したという。
同園を巡っては、定員を超過して園児を受け入れていたことなどが県と姫路市による2月の特別監査で判明。園児数より少ない給食を人数分で分けて提供し、保育士数を実際より多く報告するなどして、公費を不正に受給していたことが分かっている。
県は、認定取り消しが同園にとって不利益処分に当たるため、法律に基づく弁明の機会として聴聞を設定。小幡園長が出頭せず、県は認定取り消しに向けて協議に入った。
同園は認可外保育施設として設立され、2015年3月、県からこども園の認定を受けた。虚偽の報告に基づき年額約5千万円の公費が給付されている。
姫路市も29日午後に聴聞を予定しているが、同園の代理人によると、園長は出席しないという。
小幡園長はこれまでに代理人を通じ、4月以降に閉園する意向を明かしている。(斉藤正志)
志村英司
■きょうも傍聴席にいます
不倫相手の女性にマンションを買い与え、自宅には現金3億円を秘匿。気づけば勤務先の銀行から着服した金は約11億円にのぼっていた――。勤続37年、メガバンクの副支店長だった男(55)の金銭感覚はなぜおかしくなったのか。
2016年12月22日、東京地裁の810号法廷。黒のスーツに短髪の被告が、刑務官に伴われて法廷に入ってきた。被告は半年前までメガバンクの副支店長を務めていた。傍聴席には銀行関係者も姿を見せ、被告は神妙な顔で頭を下げた。裁判長から起訴内容について尋ねられると、「間違いありません」と答えた。
被告は11~16年、支店にあるオンライン端末機を96回にわたって不正に操作し、約9億6700万円をだまし取ったとして電子計算機使用詐欺の罪で起訴された。銀行の内部調査によると、ほかに約1億円が時効となっており、だましとった総額は約11億円にのぼるという。
冒頭陳述などから事件の経緯をたどる。
被告は鹿児島県生まれ。生家の家計は苦しかったという。被告人質問。
弁護人「実家の経済状態は」
被告「あすのご飯を食べるのにも汲々(きゅうきゅう)としていた」
弁護人「どのような子どもだったのか」
被告「母親には迷惑をかけてはいけないと思い、おねだりをしませんでした」
弁護人「高校は?」
被告「奨学金とアルバイトです。普通に生活する同級生がうらやましかったです」
1980年に地元の高校を卒業し、都市銀行に就職した。その後、銀行は合併を重ね、メガバンクに。被告は主に関東地方の支店に勤め、支店の課長、部長、副支店長と昇進。プライベートでは、結婚し、子どももできた。
弁護人「東京に来て、ほかの人の生活はどう映ったか」
被告「うらやましいと思いました。劣等感と嫉妬です」
弁護人「支店での生活は」
被告「部下におごったり、ごちそうしたりしていました」
弁護人「飲み会は?」
被告「毎日です」
被告は金があるように振る舞った理由について、「見えです」と答えた。
弁護人「おごっていくうちにどうなった」
「1番
人生楽ありゃ苦もあるさ
涙の後には虹も出る
歩いてゆくんだしっかりと
自分の道をふみしめて
2番
人生勇気が必要だ
くじけりゃ誰かが先に行く
あとから来たのに追い越され
泣くのがいやならさあ歩け」
何とか今回の不運を乗り越えれば、「ああ人生に涙あり」も思い出の一部として受け入れられるかもしれない。
格安を謳っていた旅行会社てるみくらぶが3月27日、資金繰りの悪化を理由に東京地方裁判所に破産を申請し、手続き開始決定を受けた。既に渡航中の人には「自力で帰ってきて」というなど、利用者は散々な巻き込まれ様だが、旅行者を上回る困難に追い込まれているのが、4月に入社予定の新卒内定者たちだ。
「入社予定だった僕の先輩がいます。かける言葉がみつかりません」
ツイッターでは24日ごろから、
「てるみくらぶ逝ったあ 俺の内定先なのに」 「祖父母に何て言えばいいんやろ… 就職も卒業も決まって喜んでくれたのになー」
など、悲しみと諦めの声が聞こえ始めていた。テレビ朝日の報道によると、てるみくらぶは現在の従業員数が80人程度であるのに、50人もの内定者を出していた。3月27日に内定者向けの説明会を行い、全員に内定取り消しを通告したと報じている。
まさか入社5日前に内定先が倒産するなど、夢にも思わなかっただろう。ツイッターでは「200人も従業員いない会社だよな。それで採用50人?」との批判もある。就活生向け情報提供サービスのみん就の掲示板では
「まぁ……仕方ないですよね。これも運命だと思います プラスにとらえて僕は再スタートをしようと思います。前途多難な人生になりそうですよ」
と、思ってもいない事態に困惑する内定者の様子が見られた。先輩が入社予定だったという学生は
「ここに入社予定だった僕の先輩がいます。実家からは距離的に通えないため、勤務先に近い家を借りて引越しも既にすんでいるそうです。かける言葉が見つかりません」
と、他人事ながら辛そうだ。
2018年卒業者向けの説明会は当日朝に急きょ中止 1月には中途採用の募集も
同社の採用サイトは現在すでに閉鎖されているが、2018年の卒業者向けの新卒採用も実施していた。24日にみん就掲示板に書き込まれた、
「3/23の説明会がいきなり中止になったのですが、同じように当日の朝に説明会の中止メール来た方いらっしゃいますか?」 「私も急なことで驚きました。直接的な理由かはわかりませんが、ツイッターで会社名を検索したところ何か問題が起こったようですね」
というやりとりからも、先週あたりから就活生の間に不穏な空気が流れ始めていた様子が伺える。「2018卒採用サイト無くなってますね……せめて出した履歴書ちゃんと処分してくれるといいんですけど」と、個人情報の取り扱いを心配する声も聞かれた。
今年1月にはリクナビNEXTで総合職の中途採用も募集しており、「全くの未経験から挑戦できる道があります」と謳っていた。
内定者は失業保険も適用にならない。卒業要件を満たしていても卒業を延期できる制度のある大学でも、手続き期間は軒並み過ぎている。なにより、財務状態が事前に分かっていたのであれば、採用数を抑えたり、控えたりすることもできたはずだ。第二新卒や既卒への門戸が開かれつつあるとはいえ、一日で急に人生が変わってしまった内定者の心痛はいかばかりか。
キャリコネニュースでは、内定者へのフォローや今後の対応について取材を試みたが、営業時間内にも関わらず、代表電話、お客様相談室ともに「ただいま営業時間外です」との音声が流れた。破産管財人の弁護士が所属する法律事務所へも問い合わせたが、「返金手続きなどの専用窓口に電話をしてほしい」とのことだった。
破産手続きの開始が決まった旅行会社「てるみくらぶ」が、社員が80人程度しかいないにもかかわらず、50人もの内定者を出していたことが分かりました。
てるみくらぶの内定者:「だいたい50人ぐらいはきのうの説明会に来ていたので、(内定者は)50人ぐらいはいます」「(破産について)あと5日後には社会人になるんだという気持ちで準備を進めていたし、そういう思いでいたのでこれから先どうしたらいいのか先が見えない状態で、どうしたらいいのか分からない気持ちでいっぱいでした」
てるみくらぶは、来月1日に入社予定だった約50人の内定者を、27日に本社の近くに集めて説明会を開きました。山田社長が破産に至った経緯を説明し、全員の内定取り消しを通告しました。内定者のなかには、すでに地方から東京に引っ越してきて、家賃を払えない可能性がある人もいるということです。一方、てるみくらぶの契約件数は約3万6000件で、旅行が中止になったり予約金が返金されなかったりするなどの影響が懸念されています。
財務省と大阪府の担当者達が何かを隠しているのは事実ではないかと思う。おかしな対応がありすぎる。勝手に忖度して動いた職員達を 処分したら良い。忖度したのであれば、確認もせず、明確な指示もなく、不適切な対応や判断をしたことに対して責任を取らせる必要はある。
大阪市の学校法人「森友学園」の問題を巡り、大阪府の松井一郎知事は28日、「学園と安倍晋三首相、夫人の昭恵さんは関係がある」と述べる一方、「不正には関与していない」として、退陣や議員辞職は必要ないとの考えを述べた。首相が事態打開のため衆院解散に踏み切るのではないかとの一部の見方には「森友学園の件で国会に空白をつくるのは、政治家として無責任だ」と述べた。
府庁で記者団の質問に答えた。松井氏は学園が国有地を格安で取得した際の国の対応について、地下にごみが埋まっている可能性があることなどを挙げて「学園は得をしていない。(引き下げは)法の範囲内だったと思う」と指摘した。
さらに「メディアが面白おかしくやるから、世の中の人が関心を示している。それがなくなれば(学園を巡る騒動は)自然と終息するだろう」と推測した。【青木純、藤顕一郎】
3月27日に東京地方裁判所の破産手続きの申立てを行い、即日で開始決定を受けた旅行会社、てるみくらぶの山田千賀子代表取締役社長は、午前11時30分から国土交通省で記者会見を行った。
てるみくらぶは、かつては新規就航や機材の大型化、重症急性呼吸器症候群(SARS)など需要の急変時に生まれた余剰座席を航空会社から安く買い取り、格安ツアーを造成、販売することで多くの利用者を獲得した。近年は航空会社が直販を強化し、機材を小型化するなど、割安な仕入れが難しくなったことなどの経営状況の変化から、2015年からシニア層に向けたクルーズ商品の販売や、新聞を通じた販売などにも手を広げた。新聞広告による顧客の獲得コストが高かったことや、手間がかかったことなどから想定通りの顧客獲得が難しかったという。
近年は仕入れが難しくなったため、大手旅行会社に匹敵する金額での仕入れやチャーター便を確保するなど、利幅を削っていたという。一方で、大阪発の国内旅行を数コース行ったほか、団体旅行も2015年から手掛けはじめ、「他社が20人くらいで催行するものを我が社は80人といった数で催行することもできた。」(山田社長)という。
国際航空運送協会(IATA)を通じた航空会社へ3月23日に支払う予定の約3億7,100万円の支払いが滞ったことが経営破綻の引き金となった。てるみくらぶなど旅行会社は、約5億円の銀行保証があることを条件に、IATAと契約することで自社で航空券の発券ができるようになる。自社発券が可能となることで、旅行会社は航空券代金の後払いが可能となることから資金繰りに余裕が出るものの、IATAへの支払いが滞ると自社発券ができなくなり、他社に航空券の発券を依頼する必要が出てくるため、仕入れコストが大幅に増加し、資金繰りに窮することになる。てるみくらぶではスポンサーや銀行融資に奔走し、支払い前日の22日には支払いの目処が立ったものの、同日夕方に話は破談となったという。23日深夜から、利用者に対して、出発ができない旨の連絡を行った。山田社長は同席した弁護士に、「銀行のことは言ってはだめですか」と尋ねる場面もあったが、それ以上の話を聞くことはできなかった。
てるみくらぶの3月23日現在での集計では3,000名が旅行中で、ハワイ、韓国、東南アジア、イタリアを中心としたヨーロッパ周遊などが中心だという。すでに発券済みの航空券は約款に基づき、航空会社と搭乗者との間の契約になるため、追加の支払いなく利用できるという。国土交通省では、日本国内に乗り入れる全航空会社に改めて通達を行った。一方で、航空会社によっては通達がうまく伝わらず、「搭乗を拒否される可能性がないとは言えない」と話した。ホテルや現地移動などのランドオペレーターの利用はできない場合があり、現地で追加の支払いが必要になるとした。
負債総額は約151億円で、内訳は旅行者が99億円、IATAが4億円、その他の取引先が14億円、金融機関は32億円。旅行者への補償は、日本旅行業協会(JATA)に弁済業務保証金制度に基づき1億2,000万円まで、旅行者からの申し出に応じて、債権額の割合に応じて分配される。申し出の期間は60日間で、JATAのホームページで告知される。返金される金額は、支払額の約1%程度になる見通し。
経験した事はないが、例え、倒産や破産が避けられないとわかっていても、一部の人達を除けば、その時を引き延ばしたいと思うに違いない。 その時が来た時には地獄がさらなる厳しい地獄となると思われるからだ。
株式会社てるみくらぶの口コミ(カイシャの評判)を見たが、参考になるが、情報の信頼性についてはやはり辞めた人達のほうがより参考に なるかもしれない。理由は辞めているので書き込みで特定されてもさほど問題にならないから。会社に籍があれば、良い事は書けるが、悪い事は 書きにくいだろうと推測する。
東京地裁から破産手続き開始決定を受けた旅行会社「てるみくらぶ」は3月27日午前、東京都内で記者会見を開いた。山田千賀子代表取締役社長は「私の不徳のいたすところです。誠に申し訳ありませんでした」と謝罪した。また、財務内容が悪化した理由について、「一昨年の春から、新聞広告を打ちはじめたことによって、媒体コスト、経費がかさんだ」などと説明した。
同社の代理人の弁護士は、影響を受ける旅行客数や旅行客に対する負債がどうなるかについて、「かなり精査しているが、はっきりした数字は申し上げられない。正確な数字ではないが、(一般の旅行者に関して)約3万6000件、99億円あまりと試算している」と述べた。負債総額は、計約151億円という数字もあがっているという。
同社の販売したツアーをめぐっては、チケット代金を振り込んだにもかからず、発券できないといったトラブルが起きていた。記者から「詐欺ではないか」と問われると、山田社長は「詐欺をはたらくとか、毛頭考えておりません。お客さまに安くて良い商品をと思ってやってきました」と答えた。
利用客から航空券が発券できないという苦情が相次いでいた、東京の旅行会社、てるみくらぶは資金繰りが悪化し、営業の継続が難しくなったとして、27日に東京地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けました。会社は、利用客がすでに支払ったツアー代金などの返還について、今後、業界団体の日本旅行業協会などと協議したうえで進めるとしています。
インターネットを通じて海外旅行の格安ツアーを販売する、東京・渋谷区の中堅の旅行会社、てるみくらぶは、利用客から「航空券が発券できない」などの苦情や問い合わせが相次ぎ、観光庁が旅行業法に基づいた立ち入り検査に入りました。
こうした中、てるみくらぶは27日、資金繰りが悪化し、営業の継続が難しくなったとして東京地方裁判所に破産を申請し、破産手続きの開始決定を受けました。
てるみくらぶは27日午前11時半から、山田千賀子社長らが国土交通省で記者会見し、一連の経緯や利用客などへの対応について説明することにしています。
一方、観光庁などによりますと、てるみくらぶを通じてツアーを購入した人は相当な数に上るということで、観光庁で確認を急いでいます。
利用客がすでに支払ったツアー代金などについて会社側は、日本旅行業協会が旅行各社から預かっている保証金の仕組みなどを使って返還するよう、協議を進めるとしています。
利用客「こういう事態になるとは…」
東京・渋谷区にある、てるみくらぶ本社の入り口には、27日も、臨時休業と書かれた紙が貼り出され、早朝から従業員が出入りする様子は見られませんでした。
先週、東南アジアへの旅行を申し込んだという男性はNHKの取材に対し、「以前に1度利用したことがあり、極端に安いと思いましたが、まさかこういう事態になるとは思いませんでした」と戸惑ったようすで話していました。
「同月、夫の事務所で籠池夫妻と国側の話し合いに立ち会った。話の冒頭、籠池氏の代理人でも顧問でもないが、要請があったので話し合いに同席だけすることになったとの趣旨を述べ、その後はほとんど発言しなかったという。」
理由がないのにその場にいる必要がない。稲田夫妻は弁護士である。一般人であれば不適切であるがそう言う事はあるかもしれないが、 弁護士が理由もなく時間を割くことはありえないと思う。
稲田朋美防衛相は24日、学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却問題で証人喚問された学園の籠池泰典氏が2016年1月に稲田氏の夫である弁護士の事務所で、弁護士立ち会いのもと、近畿財務局と大阪航空局の職員と会ったと証言したことについて、コメントを発表した。稲田氏の夫が籠池夫妻と国側との話し合いに同席したことを認めたが、「(その場で)ほとんど発言していない」と釈明した。
稲田氏は過去の国会審議で「夫からは本件土地売却には全く関与していないことをぜひ説明してほしいと言われている」と述べており、稲田氏の夫をまじえ、国側との間で国有地を定期借地していた際の土地改良費をめぐる話し合いをしたとの籠池氏の証言との整合性が焦点になっていた。稲田氏は、話し合いは「(国有地)売却の話ではなく、借地の土壌汚染対応の立て替え費用の返還の話」だったと説明した。
コメントによると、稲田氏の夫は顧問契約終了後の16年1月、学園が開設を予定していた小学校の用地に関し、「土壌汚染対応の立て替え費用を国が返してくれない」と籠池夫妻から連絡を受け、国側との話し合いに立ち会うように求められた。同月、夫の事務所で籠池夫妻と国側の話し合いに立ち会った。話の冒頭、籠池氏の代理人でも顧問でもないが、要請があったので話し合いに同席だけすることになったとの趣旨を述べ、その後はほとんど発言しなかったという。
稲田朋美防衛相は24日、学校法人「森友学園」への国有地売却問題で証人喚問された学園の籠池泰典氏が2016年1月に稲田氏の夫である弁護士の事務所で、弁護士立ち会いのもと近畿財務局と大阪航空局の職員と会ったと証言したことについて、コメントを発表した。コメントの全文は以下の通り。
◇
私はこれまで、夫の稲田龍示弁護士からは、「自分(稲田龍示)は土地売却には一切関係していない、君(稲田大臣)は森友学園の顧問になったことはない」との説明を受けておりました。昨日(3月23日)の証人喚問における籠池氏の証言をおききして、急遽(きゅうきょ)、稲田龍示弁護士に確認しましたが、今の説明に間違いはございません。
福山議員の質問に対して籠池氏は、平成28年1月に稲田龍示弁護士に相談に行き、今回の土地の事柄について相談したと証言しましたが、稲田龍示弁護士によれば、本件土地の売却について相談を受けたことはなく、以下のとおりとのことです。
「籠池夫妻が平成28年の1月年明け早々に弁護士法人光明会に平成21年8月ごろの顧問契約終了以来いきなり連絡してきて、すぐに相談を聞いてほしいということでした。
まず、1月8日に、籠池夫妻が光明会事務所に来られました。詳細は不明ですが、小学校を作るということ、そのために土地を借りているが土壌汚染対応の立て替え費用を国が返してくれないというような内容でした。
この日はそのような話で終わり、その後、籠池氏から再度連絡があって、立て替え費用について財務局や航空局の方と話がしたいから、その場に立ち会ってほしいという依頼がありました。
光明会としては、前提事実や経緯の詳細も知らないことから、代理人として話を聞くことはできないし、本件について発言することもないが、それでよければ構わないという話になり、27日に事務所の会議室で話をしてもらうことにしました。
同月27日に、財務局や航空局のどなたが何名来られるかもわからなかったところ、大勢で来られたので、急遽椅子をたくさん入れて対応しました。光明会としては、稲田龍示弁護士他2名が立ち会いました。
話の冒頭、私(稲田龍示弁護士)たちは、籠池氏の代理人でも顧問でもないが、立ち会ってほしいという要請があったので話し合いに同席だけすることとなったといった趣旨のことを述べ、その後はほとんど発言しておりません。
その後の話の詳細については、記憶も曖昧(あいまい)であって詳細は不明ですが、小学校建設のために借りている土地の土壌汚染対応の立て替え費用をいつになったら返還してくれるのかという話の繰り返しだったように記憶しています。
籠池夫人が立て替え費用が払われないことなどに激しい怒りをぶちまけていたことが印象に残っています。要は、同じ豊中の土地に関することですが、売却の話ではなく、借地の土壌汚染対応の立て替え費用の返還の話でした。
なお、この件について費用は受け取っておらず、これ以降、先方からは何の連絡もありません。」
とのことでした。
また、枝野議員の質問に対して籠池氏は、私(稲田大臣)を顧問弁護士として認識している、かつて法律事務所において夫の稲田龍示弁護士と私に会ったことがある旨、証言するとともに、私が抵当権抹消訴訟以外の案件にも関わっていると示唆する証言もなされておりました。
籠池氏との顧問契約については、「西梅田法律事務所 弁護士稲田龍示」個人が締結しており、森友学園の顧問弁護士であったのはあくまでも夫であって、私が顧問弁護士であったわけではありません。また、当該顧問契約は、平成21年8月ごろに終了しております。
また、狭い事務所でもありますので、籠池氏が夫に会いに事務所に来た際に、私もお目にかかったことがあるかもしれませんが、いずれにしても、10年以上前、私は籠池氏と疎遠になる前の話であろうと思います。
さらに、国会でも答弁したとおり、私が弁護士として関わった籠池氏に関する事案は、森友学園を原告とする抵当権抹消訴訟の一件のみです。この件については、私が訴訟の準備書面に途中まで名を連ねていたこと及び第一回口頭弁論に出廷していたことは事実ですが、本件訴訟の担当弁護士は夫であったこと、また、夫の代わりに出廷した第一回口頭弁論では実質的な議論が行われなかったこと、平成18年2月からは名前も除かれ、和解調書に名前も記載されていないことから、私には籠池氏から法律相談を受けたとの認識はありません。なお、枝野議員が言及されたポートタウン福祉会事件には、私も稲田龍示弁護士も関与しておりません。
以上が、昨日(3月23日)の籠池氏の証人喚問における、私に関わる部分についてのコメントです。
安倍首相は24日午前の参院予算委員会で、学校法人「森友学園」(大阪市)の問題をめぐり、首相自身と昭恵夫人が国有地の売却や小学校の設置認可に関与していないことを改めて説明した。
売却交渉当時の財務省幹部が参考人として出席し、政治的な関与や配慮はなかったことを明言した。民進党は、首相夫人付の政府職員による国有地をめぐる関与について、政府に対する不当な圧力や働きかけにつながったとみて追及したが、首相は否定した。
首相は答弁で「国有地売却や学校認可に私も妻も事務所も関与していない」と述べ、学園の理事長退任を表明した籠池かごいけ泰典氏が23日の証人喚問で行った発言内容を否定した。
籠池氏は証人喚問で、国有地の借地契約について昭恵氏に相談し、当時の首相夫人付の政府職員、谷査恵子たにさえこ氏が財務省に問い合わせた結果をファクスで受け取ったと述べた。これに対し、首相は、昭恵氏は籠池氏から具体的な相談内容を聞いていなかったと説明したうえで、「籠池氏の奥さんから、(谷氏宛ての)手紙で問い合わせがあり、(谷氏が)事務的な問い合わせをした。制度上、法律上どうなっているかの問い合わせであり、働きかけ、不当な圧力ではない」と反論した。
野党は、谷氏の対応によって政治的配慮が働いたかどうかを焦点に追及した。民進党の福山哲郎氏は、谷氏が籠池氏側からの相談を受けて財務省に問い合わせた行為について、「公務としてやったのか」とただした。政府は昭恵氏を「私人」と位置づけており、土生はぶ栄二内閣審議官は「厳密に言えば公務ではない」と述べた。
籠池氏は、昭恵氏から100万円の寄付を受け、昭恵氏には10万円の講演料を渡したと主張している。首相は、昭恵氏と籠池氏の妻とのメールのやり取りに触れ、「籠池夫人からは、10万円を払ったという話はないし、100万円についてもない。メールを見てもらえればよく分かる」と指摘し、「事実と反することが述べられたことは誠に遺憾だ」とも語った。
売却交渉当時に財務省理財局長だった迫田さこた英典国税庁長官は、「当時、(問題の国有地について)報告を受けたことはない。局長まで報告、相談がされる案件は極めて限定的で、政治的な配慮をするべくもなかった。政治家、秘書からの問い合わせなどは一切ない」と証言した。近畿財務局長だった武内良樹財務省国際局長も、「政治家、秘書から問い合わせなどは一切なく、政治的な配慮は一切していない」と述べた。
石井啓一国土交通相は24日の記者会見で、森友学園が計画していた小学校建設に絡み、国に対する補助金申請の代理人を務めた設計事務所に、追加で説明を求める考えを示した。
学園が国や大阪府などに建設費の金額が異なる三つの工事請負契約書を提出した問題で、関係者の話が食い違っているため。
石井氏は「(補助金申請手続きの)不正は確認されていないが、不明な点が残る」と述べた。
学園の理事長退任意向を表明した籠池泰典氏は23日の国会証人喚問で「設計士の助言に従い、契約書が3種類作成された」とした上で「刑事訴追の可能性がある」として詳しい説明をしなかった。
もし証人喚問に呼ばないのであれば、やはり言えない不都合な事実があると推測する。
昭恵夫人はこの世の中には彼女の立場を利用する人達が存在すると言う事を理解したと思うが実際はどうなのだろうか?
◇国有地売却問題巡り 衆参両院の予算委が証人喚問
衆参両院の予算委員会は23日、大阪市の学校法人「森友学園」への国有地売却問題を巡り、学園の籠池泰典理事長に対する証人喚問を個別に行った。籠池氏は国有地に関し、安倍晋三首相の昭恵夫人付きの官邸職員が財務省に問い合わせをしていたと明らかにした。籠池氏は財務省の回答内容が職員からファクスで送られたとし、政府はその後、文書を公表した。籠池氏はまた、2015年9月に、学園が運営する幼稚園で昭恵夫人から100万円の寄付を受け取ったと語った。
籠池氏は「小学校建設用地の定期借地契約をもっと長くできないか助けをいただこうと考え、15年10月に夫人の携帯に電話した」と説明。留守電にメッセージを残し、11月に職員からファクスが届いたと述べた。
政府が公表した文書は2枚。1枚目は送信状で、「財務省に問い合わせ、国有財産審理室長から回答を得た。現状では希望に沿えない」と要望には応じられないとする一方、「引き続き当方としても見守る。本件は昭恵夫人にも既に報告した」と記されている。2枚目は財務省の回答の説明で、(1)学園が買い受けを前提に結んだ10年間の借地契約のさらなる長期化は「難しい」、(2)定期借地を最長50年とする制度の学校法人への適用も「検討されていない」と返答。(3)土壌汚染や埋設物(地下のごみ)の撤去費用は「買い受けの際に考慮される」、(4)学園が実施したごみ撤去の工事費用について「16年度での予算措置を行う方向」と回答していた。学園側には16年度に1億3200万円が国から支払われた。
籠池氏は「昭恵夫人の寄付」に関し、「園長室で2人きりになり、『安倍晋三からです』とおっしゃって封筒に入った100万円をくださった」と証言。国有地取得を巡る政治家の介入を問われると「政治的な関与はあったのだろう」と語った。昭恵夫人の関与については「(夫人付き職員が)財務省に多少働きかけいただいた。急転直下、物事が動いたという考え方もあろうかと思う」との推測を示した。一方、小学校の工事請負契約書が3種類ある問題では、「刑事訴追を受ける可能性があり、お答えしない」と繰り返した。
首相は2月の答弁で「私も妻も認可や払い下げには関係ない。関係していたら首相も議員もやめる」と述べ、事務所の関与も否定していた。野党は昭恵夫人の証人喚問を求め始め、民進党の蓮舫代表は記者会見で「夫人による口利き、あっせんの恐れが浮かび上がった。夫人にも証人喚問で話してもらいたい」と述べた。【光田宗義】
森友学園問題で、安倍昭恵夫人がコメントを発表した。コメントは以下のとおり。
本日の国会における籠池さんの証言に関して、私からコメントさせていただきます。
(1)寄付金と講演料について
私は、籠池さんに100万円の寄付金をお渡ししたことも、講演料を頂いたこともありません。この点について、籠池夫人と今年2月から何度もメールのやりとりをさせていただきましたが、寄付金があったですとか、講演料を受け取ったというご指摘はありませんでした。私からも、その旨の記憶がないことをはっきりとお伝えしております。
本日、籠池さんは、平成27年9月5日に塚本幼稚園を訪問した際、私が、秘書に「席を外すように言った」とおっしゃいました。しかしながら、私は、講演などの際に、秘書に席を外してほしいというようなことは言いませんし、そのようなことは行いません。この日も、そのようなことを行っていない旨、秘書2名にも確認しました。
また、「講演の控室として利用していた園長室」とのお話がありましたが、その控室は「玉座の間」であったと思います。内装がとても特徴的でしたので、控室としてこの部屋を利用させていただいたことは、秘書も記憶しており、事実と異なります。
(2)携帯への電話について
次に、籠池さんから、定期借地契約について何らか、私の「携帯へ電話」をいただき、「留守電だったのでメッセージを残した」とのお話がありました。籠池さんから何度か短いメッセージをいただいた記憶はありますが、土地の契約に関して、10年かどうかといった具体的な内容については、まったくお聞きしていません。
籠池さん側から、秘書に対して書面でお問い合わせいただいた件については、それについて回答する旨、当該秘書から報告をもらったことは覚えています。その時、籠池さん側に対し、要望に「沿うことはできない」と、お断りの回答をする内容であったと記憶しています。その内容について、私は関与しておりません。
以上、コメントさせて頂きます。
平成29年3月23日
安倍 昭恵
元名古屋大女子学生(21)の裁判員裁判の判決を24日に控え、元名大生が通っていた仙台市の私立高校の現職教員が河北新報社の取材に応じ、高校の隠蔽(いんぺい)体質を批判した上で「どこかで事件を防げなかったのか」と複雑な胸中を明かした。
元名大生は高2だった2012年5~7月、隣の席だった同級生の男性(21)の飲み物に硫酸タリウムを混入し、殺害しようとしたとされる。男性は12年12月、タリウム中毒と診断された。
主治医は「日常生活でタリウムを摂取することはあり得ない」と高校に調査を依頼したが、学校は教職員間の情報共有や生徒への聞き取りなどをしなかった。
教員は「教えてくれたら、凶悪事件や薬物に興味を示していた元名大生をもっと注意して見ていた。警察や児童相談所に連れて行くこともできた」と指摘する。
高校はクラス別に国公立大を目指す特別進学、大学進学を目標とする準特別進学、一般コースに分かれる。元名大生は難易度が2番目のクラスから名大に現役で合格した。
教員は「彼女のクラスから旧帝大への現役合格は画期的。高校側が生徒募集のために合格実績を優先させ、事件をうやむやにしたかったのかもしれない」と振り返り、当時、徹底した調査をすれば殺人事件へ発展しなかった可能性を示唆した。
校長は元名大生が逮捕された15年1月以降、職員会議などで「学校は隠蔽(いんぺい)していない」と繰り返してきたという。教員は「体面を守ろうとしている。本来なら第三者委員会を立ち上げ、検証するべき案件だ」と学校の体質を批判した。
タリウム混入事件から約2年半、殺人事件にまで発展した。教員は「高校が止めることはできなかったのか。タリウムを飲まされた男性に対しても本当に申し訳ない」と語った。
名古屋市で知人の高齢女性を殺害し、仙台市で同級生2人に劇物の硫酸タリウムを飲ませたとされる元名古屋大女子学生(21)=仙台市出身、事件当時未成年=の薬品収集癖を巡り、母校の仙台市内の私立高が2013年3月までに、警察沙汰にまで発展していた事実を把握していたことが20日、学校関係者の証言で分かった。校長は、元名大生の薬品への執着について記者会見で「(在学中は)一切把握していなかった」と説明する一方、教職員にかん口令を敷いていた疑いも出ている。
証言によると、高校側は元名大生がオウム真理教などの凶悪事件に強い興味を示しているとして13年3月中旬、母親を呼び出し、家庭でも適切に対応するよう指導した。
母親は面談の際、「娘が親のクレジットカードで薬品を購入している。(12年5月に)夫が仙台北署に連れて行き、相談した」と打ち明けた。父親は元名大生を伴い、警察に行った際に劇物の亜硝酸ナトリウムやナイフ類などを持参した。
応対した教職員は遅くとも13年3月の時点で、元名大生の凶悪犯罪への高い関心、薬品収集癖、警察の厳重注意などを把握していたことになる。
元名大生は12年5月、高校に遅刻した理由を担任に尋ねられた際に「警察に行っていた」と届け出た。担任はそれ以上詳しい事情を聴いていなかったことも新たに判明した。
一連の経過は逮捕直後の15年2月中旬、男性幹部職員が全教職員対象の会合で説明した。校長は「今日聞いたことは外で話してはいけない。これは隠蔽(いんぺい)ではない」などと繰り返し口止めした。
24日に判決を控える元名大生の裁判員裁判では、母親が出廷し、「教職員から『視力が急激に低下した同級生がいる。心当たりはないか』と聞かれた」と証言。当時、高校側が元名大生の関与を疑っていた可能性を示唆した。
高校側は取材に対し、「これまでの見解と変わらない」と語り、元名大生の薬品への執着ぶりを在校時は把握していなかったとの認識を改めて示した。
事実と理想を混合したレベルではない。松井三郎理事は現実と非現実を勘違いするほど問題を抱えているのか?認知症の症状? 公益社団法人「日本国際民間協力会」の松井三郎理事は京大名誉教授だそうだが、引退する時期かもしれない。それとも、 不都合な事実だったのだろうか?
昭恵夫人から安倍首相への口利き疑惑に新たな証言!「夫人に頼んだら首相から連絡が入って8000万円の予算が…」
2017.03.20
森友学園問題では、安倍首相からの100万円の寄付金がクローズアップされているが、この疑惑の核心は国有地の不正取引と小学校設置認可をめぐる口利き問題だ。その口利きをめぐっては様々な政治家の名前があがっているが、永田町で根強くささやかれているのが、安倍昭恵夫人から安倍首相へのルートだ。
「口利きは複数あったと思われますが、昭恵夫人から安倍首相へ直接の働きかけがあり、首相が迫田(英典)理財局長を動かしたのがもっとも強かったのではないかといわれていますね」(全国紙政治部記者)
実は、それを間接的に裏付けるような動画が、先週金曜日夜くらいからネット上で話題になっている。何かのシンポジウム会場で、白髪まじりの男性がプロジェクターを指し示しながら講演をしているのだが、男性はこんなことを語るのだ。
「外務省の役人は、なかなか理解してくれなくてですねえ。
えいやとばかりに、先ほどの理事長と私が、安倍夫人とこに行きました。安倍夫人に、首相官邸に行きまして。そしたら、安倍夫人が会ってくれましてね、聞いてくれました。あの人、すごいですね。その晩に、首相と話をしてですね、首相からすぐ連絡が入ってですね、ぐぐぐっとまわって、今年予算つきました。8000万円もらいました。それで、今年この2つの村に入りました。あのご夫婦のホットライン、すごいですね」
外務省の役人は理解してくれなかったが、首相夫人に会って話したら、首相に話してくれて、8000万円もらえた――。これがもし事実なら、明らかに昭恵夫人の首相への口利きではないか。
この発言が飛び出したのは、今年2月11日に京大でおこなわれた「もったいない学会」と「縮小社会研究会」の合同シンポジウムでのこと。このセリフを話しているとみられるのは、公益社団法人「日本国際民間協力会」で理事をつとめる京大名誉教授だ。
この日、この公益社団法人理事は「アフリカにおける勿体ない実践成功例」というテーマで、ケニアに「エコサントイレ」という環境にいいトイレを広める事業について語っていたのだが、このエコサントイレの活動を外務省は理解してくれず、補助金かなにかの協力をなかなか得られなかったらしい。それで思い切って、首相夫人である昭恵夫人に会いに行き話をしたところ、その晩に首相に話をしてくれて、すぐに首相から連絡が入り、最終的に8000万円の予算がついた、といっているのだ。外務省と交渉してもNGだったものが、昭恵夫人に話したら、一晩で8000万円の予算がついたというのである。
日本国際民間協力会のホームページで公開されている、2013年度から2015年度までの決算報告書、2016年の事業計画・予算には、この「外務省からの8000万円」に当たるものは確認できないが、今年2月に「今年、予算がつきました」と話しているので、現段階ではこうした書類に反映されていないということなのだろうか。
仮に8000万円もの予算が、昭恵夫人の鶴の一声で決まってしまったのだとしたら、民主主義国家としてあり得ないことだろう。外務省の予算というのは言うまでもなく、国民の税金である。エコサントイレ事業の良し悪しの問題でなく、どのような事業にどれだけ税金が投入されるかは、公正に審議されるべきものだ。首相夫人個人が、「親しいから」「頼まれたから」「感動したから」などという理由で、決められていいはずがない。
政府は14日「首相夫人は公人でなく、私人である」とするとんでもない答弁書を閣議決定したが、これでも私人だなどと言い張るのだろうか。あるいは私人だというなら、それこそ韓国のパク・クネ前大統領とチェ・スンシル被告と同じく、私人による政治介入ではないか。
同様のことが森友学園でも行われた可能性は十分あるだろう。実際、昭恵夫人が日常的に役所に圧力をかけていることが明らかになっている。「週刊新潮」(新潮社)3月23日号では、第二の森友学園といわれる加計学園の獣医学部新設認可や、安倍首相の遠戚である斎木陽平氏が代表を務める団体が主催する全国高校生未来会議への支援について、昭恵夫人から文科省へ要請があったことを文科省関係者が明かしている。
しかも、このエコサントイレ問題で明らかになったのは、こうした口利きに安倍首相自身も関与しているという可能性だ。動画によると、昭恵夫人の口利きを明かした京大名誉教授は、「その晩に首相に話してくれて」「すぐに首相から連絡が入って」と語っている。
森友学園の名誉校長や100万円寄付の件に関して、安倍首相や官邸は「首相の関知しないところで、昭恵夫人が勝手にやったこと」というイメージ操作をしているが、本当にそうなのか。
日常的に行っていた安倍首相への口利き問題、さらに森友学園問題への安倍首相の関与を明らかにするために、昭恵夫人を証人喚問し徹底的に追及すべきだ。
(編集部)
(リテラより)
京都市の公益社団法人の理事が、環境に優しいトイレを海外に普及させる事業について安倍首相の昭恵夫人に依頼したらすぐに予算がついたとする内容の講演をしていたが、公益法人は22日、事実ではなかったとして発言を撤回した。
これは公益社団法人「日本国際民間協力会」の松井三郎理事が先月、シンポジウムで、アフリカでエコトイレを普及させるプロジェクトをめぐり、発言したもの。
松井三郎理事「外務省の役人はなかなか理解してくれなくてですね、(首相公邸で)安倍夫人が会ってくれまして、聞いてくれまして、あの人すごいですね、その晩に首相と話をして、首相からすぐ連絡が入ってですね、ググググっと回って、今年予算がつきました。8000万円もらいました」
この発言をめぐっては、国会で野党議員が事実関係をただしたが、外務省は答弁で「今年8000万円の予算をつけた事実はない」と否定した。
また、日本国際民間協力会は、松井理事が去年12月、昭恵夫人に首相公邸で面会したのは事実としながらも、あっせんを依頼したことはなく、外務省から8000万円の援助を受けたこともないと訂正した。
理由について、協力会は「講演の場ということで、松井理事が事実と理想を混同して話してしまった」などと説明している。
京都市の公益社団法人の理事が、環境に優しいトイレを海外に普及させる事業について安倍首相の昭恵夫人に依頼したらすぐに予算がついたとする内容の講演をしていたが、公益法人は22日、事実ではなかったとして発言を撤回した。
これは公益社団法人「日本国際民間協力会」の松井三郎理事が先月、シンポジウムで、アフリカでエコトイレを普及させるプロジェクトをめぐり、発言したもの。
松井三郎理事「外務省の役人はなかなか理解してくれなくてですね、(首相公邸で)安倍夫人が会ってくれまして、聞いてくれまして、あの人すごいですね、その晩に首相と話をして、首相からすぐ連絡が入ってですね、ググググっと回って、今年予算がつきました。8000万円もらいました」
この発言をめぐっては、国会で野党議員が事実関係をただしたが、外務省は答弁で「今年8000万円の予算をつけた事実はない」と否定した。
また、日本国際民間協力会は、松井理事が去年12月、昭恵夫人に首相公邸で面会したのは事実としながらも、あっせんを依頼したことはなく、外務省から8000万円の援助を受けたこともないと訂正した。
理由について、協力会は「講演の場ということで、松井理事が事実と理想を混同して話してしまった」などと説明している。
「他の園でも同じことがある」と言うのが事実であれば、姫路市は多くの問題をざるのように見逃していると言う事になる。姫路市は事実確認を絶対に するべきである。
兵庫県姫路市の私立認定こども園「わんずまざー保育園」の認定取り消しは当然だと思う。今まで問題に気付かなかった姫路市職員達は反省するべきだ。 騙されるには騙される人が存在しないと成立しない。騙す人も悪いが騙される人にも問題があると思う。
不適切な保育実態が明らかになった兵庫県姫路市の私立認定こども園「わんずまざー保育園」の小幡育子園長は問題発覚前、神戸新聞社の取材に応じていた。特別監査で指摘された不正を認めた上で、こども園に移行後の体制整備について「知識がなく、何が必要かも把握できていなかった」と釈明。兵庫県や市による認定過程での適格性判断やチェックの甘さが問われそうだ。
同園は、2003年に認可外保育施設として設立され、12年間運営。待機児童の解消や保育と幼児教育の質向上を目指す「子ども・子育て支援新制度」が始まった15年度、認定こども園に移行した。年間5千万円の公費を受給していた。
約1時間にわたり取材に応じた小幡園長は、認定を目指した理由を「(公費補助で)保育料が安くなり、保護者も助かると思った」と説明した。
定員を22人超過する園児を不正に受け入れていた点は、「ここは認可外の基準なら70人まで可能な広さがある。保護者に『助けて』と言われ、受け入れてしまった」と弁明。「認可外時代の甘い考えが抜けず、事の重大さに気付いていなかった」とした。
無資格でベビーシッターを行い、保育士にさせていたのも「認可外時代からやっていた。保護者へのサービスのつもり」と語った。
県内の認定こども園は322カ所(16年4月時点)。公立や学校法人、社会福祉法人の運営が97%を占め、個人経営の認可外から移行した例は珍しい。
小幡園長は、認可の基準を満たす体制整備について「大きなところは知識のある人がいるが、ここは私だけ。知識がなかった」と、適格性に疑問を抱かざるを得ない弁明に終始した。
一方、21日夜に同園であった保護者説明会では、保育士が園長に逆らえなかった実情を涙ながらに説明。子どもを預ける女性(29)は「園長の話は信用できない。本当のことを語ってほしい」と求めた。(金 旻革、木村信行)
■小幡育子園長との主なやりとりは次の通り。
-兵庫県は認定を取り消す方針だが、どう受け止めているのか。
「原因をつくったのは私なので責任を感じている。ただ、最初は他の園でも同じようなことがあると聞いていたので、事の重大性を分かっていなかった。指摘され、『あ、ひどいことやったんやな』と。本当に浅はかなんですけど」
-他の園でもやっているとは、私的契約や保育士の水増しのことか。
「他もあるから自分もというのは言い訳になるので。そこは、やはり自分が悪いなと思っています。取り消しは当然だと」
-定員を大幅に超える園児を受け入れていた理由は。
「保護者に『先生助けて』と言われると『じゃあじゃあ』ってなる。認可保育園に行ける方は認可に行ってくださいと言えるが、難しい人もいる。認定こども園なら1人当たり3・3平方メートルの保育室が必要だが、認可外なら70人までいける。正直、そういう甘い気持ちがあった」
-収益のために、多くの園児を受け入れた面はあるのか。
「そう思われても仕方がないと思います」
-そのつもりもあったのか。
「ないっていうと『うそやん』となるし、あるって言うと…。自分の資金でお金をためて、園を大きくするしかなかった。もらったお金は園児や保護者に還元するつもりだった。保育の仕事はボランティア精神がないと絶対できないと思う」
-40人前後の給食を70人ほどで分けていた。おかしくないか。
「おかしいです」
-どういう考えだったのか。
「給食が余る時期があり、じゃあ減らそうか、となった。昼から来る子や、一時保育で午前中に帰る子もいたので」
-栄養面で問題はないと。
「いやいや、そういうふうには。何もそこまで考えては…」
-なかった?
「正直、給食に必要な量とかカロリーとか、正直そこは分かっていなかったので…」
-保育士の水増し計上の理由は。
「土曜日は保育士の休み希望が多く、人員が足りなくなった。どうしても3人必要だったので、私の判断で帳尻合わせをした」
-監査の中で保育士にベビーシッターをさせていたという指摘があった。
「事業ではなく、個人的な付き合いで受けていた。学童保育の小学生を保育士に車で送迎してもらっていたのも同じだが、インフルエンザで寝込んでいるとか、おばあちゃんしか家にいないとか言われると、行くしかなかった」
-実際は発注していない私的契約の園児からも給食費を取った。
「正直、いただいていた。流用はいけないと思い、個人でプールしていた。ごめんなさい。個人では何の知識もなかった。多くの認定こども園は学校法人や企業が運営し、知識のある人が(管理面を)担当している。姫路市から1カ月でこれだけ細かい書類を書いてと言われても、何が必要か、そこの把握ができていなかった」
-なぜ、認可外から認定こども園にしようと思ったのか。
「保育料が安くなり、保育士の給料面も違ってくるのかなと思った」
-認定が取り消されても、保育を続けるつもりか。
「必要としてくれる人がいるなら、認可外に戻っても続けていきたい」
不適切な保育実態が指摘されている兵庫県のこども園「わんずまざー保育園」をめぐり、市の監査をクリアするためのものを含め、入園のための“しおり”が3種類あることがNNNの取材で明らかになった。
「わんずまざー保育園」が作成した3種類の「入園のしおり」。正規に入園した園児の保護者に渡していた「しおり」には、「入園料」という名目で本来、徴収してはいけない1万円を徴収する記載がある。しかし、市に提出した「しおり」には対象者を1号認定のみと記載し、監査をクリアするためのものとみられる。
しおりを作成したとされる小幡園長に対しては、保護者からの非難の声が相次いでいる。
園長「この度はご迷惑をおかけして本当に申し訳ございません」
保護者「謝るんやったら土下座せんかい」「子どもは動物か、ペットか、飼育か」
園長「(給食の)写真に写っていたものには私と正直、保育士もびっくりしております」
保護者「びっくりした?あんたが知らんかったんか?ずっと知らんかったんか?」
園長をめぐってはこれまでに、入園料という名目での現金徴収や、給食費の不当な徴収などが判明している。
学校法人「森友学園」(大阪市)が小学校新築に関して、金額の異なる契約書を国土交通省や大阪府に提出し補助金を受給していた問題で、石井啓一国土交通相は21日の閣議後記者会見で、同日付で補助金の交付決定を取り消し、返還命令の文書を送付すると明らかにした。
30日までに既に交付した約5600万円の返還を求めるという。
国交省によると、木をふんだんに使った校舎建築に当たり約6200万円の交付を2015年に決めたが、森友学園から補助対象となった事業を中止するとの通知が19日に届いた。石井国交相は「(受給経緯について)不明な点を明らかにするために追加資料の提供を求めている」と述べた。
単なる言い訳としか聞こえない。
行政側にも問題がある事はある。綺麗ごとだけ、現場を知らないし、知ろうとしない、行政側の都合だけを押し付ける、行政側はリスクを負わない、 行政側の人事に問題がある等が例だ。
しかし、助成金や補助金を悪用する人間や会社が存在するのは事実。行政側は自分達にも問題がないのかを考えながら、悪質な人間や会社には厳しく 対応するべきだと思う。
定員を大幅に超える園児を自治体に隠蔽(いんぺい)して受け入れ、劣悪な環境下での保育を続けていたとして、兵庫県と姫路市は18日までに、認定こども園法などに基づき、同市の私立認定こども園「わんずまざー保育園」(小幡育子園長)の認定を3月中にも取り消す方針を固めた。定員超過分の保育料を独自設定し、不当に受け取っていたほか、1人分の給食の量を減らすなどして経費を削減していたとみられる。市などは保育施設の適性を欠く行為と判断。運営費の公費負担を打ち切る。
内閣府によると、2015年の子ども・子育て支援新制度の導入に伴い、こども園の普及が進んで以降、認定の取り消しは全国初という。
市などによると、同園は正規の定員として園児46人を保育。これに加え、市に隠して直接保護者と契約した22人を受け入れ、定員の約1・5倍の園児を預かっていた。
園の利用料は、市が保護者の所得や園児の年齢に応じて徴収するが、22人分は同園が独自に料金設定。園児1人当たり月額2万~4万円を得ていたという。
給食は68人の園児に対し、40食前後を発注。これを分けていたため、栄養・量とも不十分な状態だったとみられる。乳児には主食と汁物などを一つのわんに入れ提供していた。
市などは、同園が行政からの給付金を満額受け取るため、保育士の人数を水増ししていた実態も把握。保育士は少人数で仕事を強いられていたとみられ、保育の安全性も問われる状態だったという。
県と市が2月23日、情報提供を受けて同園に特別監査を実施し、発覚した。同園は2003年11月に認可外保育施設として設立。15年3月、県の認定を受け、翌4月から年間約5千万円の公費が運営に充てられている。
小幡園長は神戸新聞の取材に「預け先のない保護者の要望に対応してきたつもりだが、監査で指摘された内容については、見直さなければいけないと思っている」と話した。(金 旻革)
【認定こども園】 幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設。保護者の就労の有無にかかわらず0~5歳児を受け入れるのが特徴で、保育の受け皿が広がると期待されている。待機児童の解消を目的に2015年4月に始まった子ども・子育て支援新制度は、こども園の普及を柱に位置付け、幼稚園と保育所からの移行が進んだ。16年4月時点で、全国に4001園あり、最多は大阪府の376園。兵庫県は2位の322園が認定を受けている。
村山祐一・全国保育団体連絡会保育研究所長の話 (兵庫県姫路市の私立認定こども園「わんずまざー保育園」の)認定取り消しは大変重い判断だ。事態を招いた園側の責任は当然だが、こども園として認定した自治体にも責任がある。新制度に移行後、こども園の普及を急ぐあまり、設置者の適性を見極める際に甘さはなかったか。取り消すなら、認定に至った経過も見直すべきだ。
兵庫県姫路市の私立認定こども園「わんずまざー保育園」に勤務する複数の保育士が、神戸新聞の取材に同園の実態を証言した。
「子どもに愛される保育士を夢見ていた。今は後悔しかありません」。同園に勤務して数年目の保育士は振り返った。
特につらかったのが食事だったという。魚のフライを切り分け、尾っぽしかもらえない子がいた。バナナ5本を輪切りにし、20人の園児で分けたこともある。「発育に大事な時期。ずっと疑問だったが、指摘できる雰囲気ではなかった」と打ち明けた。
別の保育士も重い口を開いた。「掃除や洗濯など保育以外の仕事も指示され、学童保育やベビーシッターに無給で駆り出される人も。常に人員不足だった」
保育士2人で園児約20人の面倒を見て、トイレの世話などをしている間、子どもが鍵を開けて道路に飛び出したこともあった。「いつか取り返しのつかないことが起きないか、常にプレッシャーだった」と語る。
多忙な勤務実態などで心身が不安定になり、退職する保育士もいたという。「行政の対応が遅すぎないか。こんな認定こども園を二度と出さないでほしい」と訴えた。
園児40人余りで発注された給食を約70人で分け、おかずがスプーン1杯だけの子も…。兵庫県と姫路市の特別監査で、異常な保育実態が明らかになった私立認定こども園「わんずまざー保育園」(同市飾磨区加茂)。定員を大幅に超える園児を受け入れる一方、保育士の人数を水増しし、虚偽の報告でつじつまを合わせていた。
県と市が抜き打ちの特別監査に踏み切ったのは2月23日。関係者の情報提供がきっかけだった。
市などによると、施設の面積などから算定された同園の定員は46人。だが、園内には0~5歳の約70人がひしめいていた。
特別監査があった日、同園が外部発注した給食は42人分。おかずを取り分けたが、0、1歳児にはスプーン1杯分しか行き渡らなかったという。
給食の不足は常態化し、土曜日に限っては10食のみに固定し、これを園児40人前後に分配。おやつは午後1回だけで、4、5歳児は「ビスケット3枚」もしくは「かっぱえびせん6本」に制限した。
余った給食は冷凍保存し、足りない日に解凍して提供。1カ月以上過ぎても使うケースがあったという。
また、給付金を水増し請求するため、架空の保育士3人を計上し、給与分は園長が個人的にプール。同じ敷地内で運営する学童保育の小学生らの送迎を保育士にさせたり、夜間のベビーシッターを兼務させたりしていたことも確認された。
同園はこうした実態を隠すため、市への報告書類などを改ざんしていたという。
小幡育子園長は神戸新聞の取材に対し、特別監査で指摘された項目を認め「(認定を受ける前の)認可外保育所だった時代の感覚で運営していた。プールしたお金は遊具購入などで園児に還元するつもりだった。認定こども園としての自覚が足りなかった」と謝罪した。
県こども政策課の担当者は「認定以前の問題で衝撃を受けている。厳しく対処したい」としている。(金 旻革、木村信行)
次から次へと疑惑や謎が噴出する学校法人「森友学園」による国有地取得問題は、学園の籠池泰典氏への偽証罪の適用もあり得る証人喚問で真相解明につながるかが注目されている。籠池氏が主張する安倍晋三首相側からの100万円の寄付に加え、問題の発端となった国有地の8億円“値引き”、政治家の関与の有無…。何が真実で、何が偽りなのか。
「100万円寄付」発言は、大阪府豊中市の小学校建設予定地を16日に訪れた参院予算委員会のメンバーらに籠池氏が突然明かした。詰めかけた報道陣に聞かせるかのように、大声で安倍首相の名を出すふるまいに周囲は騒然とした。
17日になって首相は「私は寄付を行っておらず、妻個人としても寄付を行っていない」と明言。言い分は真っ向から食い違うが、籠池氏は16日に「全ては国会でお話しする」と語った以降は沈黙を続けている。
一方、学園をめぐる問題では、ごみ撤去費用などを理由に評価額約9億円から値引きして約1億3千万円で売却された、いわゆる“8億円値引き”問題の疑問も解消されていない。
籠池氏は政治家への「口利き要請」を一貫して否定する一方で、寄付集めの際に「安倍晋三記念小学校」の名前を一時使用。鴻池祥肇(よしただ)参院議員(自民)に「あいさつ名目」の商品券を渡そうとしたり、複数の政治家に相談をしたりしたことは認めている。
財務省は、既に記録を廃棄したとして学園側との具体的交渉経過の詳細を明らかにしていない。官僚側が、学園の背後に政治家の影を感じ忖度(そんたく)して優遇していたのではないかとする指摘もある。籠池氏が国有地取得に至る過程で、どのように国や政治家に接触していたのかも喚問ではポイントとなる。
さらに、小学校建設をめぐって国や大阪府に補助金申請などのために提出された金額の異なる3つの工事請負契約書の問題もある。
ただ、喚問されるのは籠池氏一人で、その証言だけでどこまで真相に迫れるかは不透明だ。
つまり、8回目までの検査を行った検査機関は全く能力がなかった、又は、故意に検査数値をコントロールするように検査を行ったと言う事なのか?
東京都の豊洲市場に関する東京都職員達の対応、そして、学校法人「森友学園」に関する大阪府職員達の対応はいかにある特定の職員達が偽善者であり、 ずる賢く、立ちまわっている事を示しているように思える。
東京都の豊洲市場の地下水から環境基準の最大79倍のベンゼンなどが検出された問題で、都の専門家会議が複数の検査機関に依頼して再調査した結果、市場敷地内の複数地点で基準超の有害物質が検出されたことが分かった。築地市場からの移転を延期した小池百合子都知事は、検査結果などを参考にする考えで、移転について難しい判断を迫られることになる。
豊洲市場の地下水については、土壌汚染対策工事が完了した2014年から都が検査を実施。昨年9月公表の8回目には基準をわずかに超すベンゼンなどが初めて検出されたが、今年1月公表の最終9回目に全201地点のうち72地点で、基準の最大79倍のベンゼンなどを検出。安全性を検証している都の専門家会議が4機関に依頼して再調査をしていた。
関係者によると、再調査対象の29地点のうち、複数地点で基準を超す有害物質が検出された。濃度は9回目の検査結果と大差ない程度という。都は敷地内の地下水位を一定に保つ管理システムを昨秋に本格稼働しており、地下水の変動が影響したという見方が出ている。
結果は19日の専門家会議で公表される。
朝日新聞社
大阪府や財務省の逃げ腰な対応も事実の追求を難しくしていると思う。
「安倍さん、さっき言ってたけど、“証人喚問になってよかったよ“と。ここまで来たら公明正大に、お互い正直に言うからと。(19日からの訪欧で)非常に難しい交渉があるから、頭の中はそれでいっぱいで、あんまり興味がないようだった。籠池さんとは全く面識がないので、よく知らなかったらしい」。
17日夜、元TBSワシントン支局長で、昨年出版した『総理』がベストセラーになった山口敬之氏が『AbemaPrime』に出演、直前に森友学園問題について安倍総理と電話で話した内容を明らかにした。
「“安倍総理からです“と昭恵夫人から100万円をもらった」。
きのう、森友学園の籠池理事長が明かしたこの爆弾発言。午後の衆院外務委員会で安倍総理は「一方的に名前が出され、私は大変当惑をいたしております。私自身、かねてから国会で答弁をしている通り、籠池氏とはですね、一対一などでお目にかかったことはなく、これは、何回も答弁をしている通りでありまして、個人的な関係はないわけでございます。そうした方に、これだけ価格の寄付を私自身が行うということは、これ、あり得ない話でございまして。また妻や事務所など、第三者を通じても行ってはおりません」と反論した。
山口氏は「普通の口利きや贈収賄事件は、政治家がお金を取るもの。今回のように、“もらった“という人が安倍さんを貶めようとしているのは珍しい構造だ。もし寄付したとしても選挙区外であれば構わないし、“あげました“と言えば済む話。土地取引に介入したとしたら総理も議員も辞めると言ったが、寄付については言及していない。それに、なんで籠池さんがこのタイミングで言うのかもピンとこない。不思議な事案だ」と首をかしげる。
「安倍さんという人は、大盤振る舞いはせず、基本的には“割り勘“の人。一緒に食事に行ってもゴルフに行っても完全に割り勘だし、ポンとお金を出す人ではない。特に総理になってからはそういうことはされていないはず。昭恵さんも総理夫人になってからはポケットマネーを出すことには慎重。海外で学校を建てる時も、少しずつみんなで浄財あつめよう、とか」と証言。「籠池さんは、安倍さんの許可なく寄付金を集めたり学校を建設していたようだ。推測でしかないが、籠池さんがもしウソをついていると仮定したら、“安倍さんから寄付金もらったんだ“という話は、他での寄付金集めや行政への働きかけの際にメリットがある」と指摘した。
同じく今日の衆院外務委員会で民進党の福島伸享議員は「先ほどYahoo!ニュースで、最近話題が沸騰している著述家の菅野さんという人が、物証の現物を入手したという報道が流れています。昭恵さんが講演した2日後に、淀川新北の郵便局から100万円を学校法人森友学園に振り込んでいて、その森友学園の入金元のところは修正液で消されていて、そこには“安倍晋三“って書かれてるっていうのが載ってるんですよ」と畳み掛けた。
福島議員の言う「菅野」氏とは、おととい籠池氏を匿い、報道陣の前に出てきた人物だ。この菅野氏が「安倍晋三」の文字が見える修正済みの振替払込み用紙を籠池氏本人から入手、その写真をアップしたのだ。激しいヤジの中、安倍総理は「すみません、私自身もですね、それは承知をしておりませんので、お答えのしようがないということでございますが、ないものはないと、こう答弁をさせていただいている通りです」と訴えた。
この振替用紙の問題についても山口氏は「書いたのは森友学園側。だから安倍事務所からの振込があったとか、その証拠にはなりにくいのではないか」とし、「今、森友学園側が昭恵さんの講演料として100万円現金で用意したが、昭恵さんはそれを受け取りませんから、それを寄付という処理にしたんではないかという憶測が流れている。昭恵さんが100万円を用意して大阪に行ったというのは無く、籠池さんが用意したものではないかと言う推測があって、それ以外考えられないのではないか、というのが僕の受け止め。森友学園内の処理だったということではないか」と推測した。
さらに国会での野党からの追及は、昭恵夫人と籠池夫人の関係にまで及んでいる。福島議員によると、籠池夫人は今回の問題が発覚した後の先月28日と今月8日昭恵夫人からメールを受け取ったと主張しているというのだ。安倍総理は答弁でメールのやりとりがあったことを認め、「先方もよければ、詳細について公開させていただいてもいいと思います。全文をですね。これは全く問題のない中身だと思っております」と答えた。
「このメールのやりとりも知っている」という山口氏。「昭恵さんが、私は頂いてないですよねと再確認する意味で、籠池さんの奥さんにメールをした、そのやりとり」と明かした。
昨日、急転直下で籠池氏の証人喚問が決定した今回の問題。
山口氏は「注目したいのは、参院予算委員会のメンバーで、籠池さんが自宅に向かい入れたのは野党の4人だけ。籠池さんと5人でぶら下がり取材に応じていた中には、教育勅語はやるべきではないといった共産党の小池晃議員と社民党の福島瑞穂議員がいた。4人は籠池さんの教育方針についても、骨太な話をきちんとしたのだろうか。それとも“寄付金をもらってたんですか“という政権批判のための道具についてのやりとりしてただけなのか。“与党を排除したのは倒閣運動なんでしょ“という見方をされてもしかたない。国会でダメージを与えたいという意思があるようだから、自民党も“いい加減なことを言われても困る“と、出席に強制力があって、偽証罪が問われる証人喚問にしたのではないか」と話し、「安倍さんが怒ったから証人喚問ということではない。安倍さんは今もピンときてない感じだ」と明かした。(AbemaTV/AbemaPrimeより)
ところで、辻川靖夫裁判長はどんな人たのだろう?
辻川靖夫裁判官≪40期≫ (日本の刑事裁判官)
「山田被告もビールやレモンサワーをジョッキで飲んだ上に白ワインをグラスで5、6杯一気飲みするなど『いつも以上に飲んだ。つぶれる一歩手前だった』という。」
「『かなり酔っていて覚えていない部分もある』。山田被告はそう述べた上で、事件の核心へと証言は続く。犯行までの経緯について、トイレに行こうとしたが酔ってよろけた女性を吉元、山田両被告で肩を持つなどしてトイレに連れて行き、酩酊状態の女性を吉元被告が『ここは俺が面倒見ておくから』といったため山田被告は宴席に戻った。
そして、20~30分ほどたっても2人が戻らないことが気になった山田被告がトイレの扉をたたいて中の2人に声をかけると、開いたドアの向こうに吉元被告が立っていて、女性に乱暴したなどと話したという。
『自分もいいだろうと思い女性の体を触るなどしているうちにエスカレートし、犯行に及んでしまった』」
「つぶれる一歩手前だった」と言うのが事実であれば、「トイレに行こうとしたが酔ってよろけた女性を吉元、山田両被告で肩を持つなどしてトイレに連れて行き」は可能であろうか?
「つぶれる一歩手前だった」の表現もつぶれるの状態がわからない。歩けないほど酔いつぶれていたのか?立ち上がれないほど酔いつぶれていたのか?
立ち上がれないほど酔いつぶれていれば、女性に乱暴する事は困難だろう。
「酔っていたのでうまくいかなかった」と言うのは、興奮してあそこが勃起したが酔っていたので上手く挿入できなかったのか?お酒の影響であそこが
勃起しなかったので挿入できなかったのか?
酔い方は人それぞれであるが、つぶれる一歩手前であれば、女性を送った増田被告の家に行く事はかなり難しいのではないのか?
「検察側に『女性を増田被告の家に連れて行ったのはなぜか』と問われると、『女性が酔って自力で帰れなかったため、一番近い増田被告の家に送った』と答えた。」
下心がないとそんな選択はしないね!既に飲食店で女性に対して乱暴した後ならなおさらだ!
「自分もいいだろうと思い、エスカレートしてしまった」。千葉大医学部生らが20代の女性に集団で乱暴した事件で、集団強姦罪に問われた医学部5年の山田兼輔被告(23)=千葉市中央区=は証言台でそう述べ、うなだれた。
千葉地裁(吉村典晃裁判長)で1日に山田被告に対する被告人質問が行われ、共犯の同級生、吉元将也被告(23)=同罪で公判中=が女性にわいせつな行為に及んでいるのを見て、自制がきかなくなっていった様子を再現した。
山田被告は、実家が弁護士や法律家を輩出している法曹一家としても、今回の事件では注目されていた。
起訴状などによると、山田被告は昨年9月20日深夜、吉元被告と共謀して千葉市の飲食店の女子トイレ内で、飲酒で酩酊(めいてい)し抵抗できない状態の女性を乱暴したとしている。
山田被告によると、この日は同大病院の研修医、藤坂悠司被告(30)=千葉市中央区、準強制わいせつ罪で公判中=が主催した医師などが参加する飲み会が開かれた。弁護側によると、飲み会は次第に白ワインの一気飲みなどが始まり、記憶をなくしたり座敷で寝込んだりする参加者が出るほど激しさを増していった。
山田被告もビールやレモンサワーをジョッキで飲んだ上に白ワインをグラスで5、6杯一気飲みするなど「いつも以上に飲んだ。つぶれる一歩手前だった」という。
また、宴席では山田被告が被害女性や藤坂被告に白ワインの一気飲みをけしかける場面や、酔った藤坂被告が山田被告に被害女性の体を触らせるなどした場面もあったといい、「セクハラまがいのこともあった」と述べた。
「かなり酔っていて覚えていない部分もある」。山田被告はそう述べた上で、事件の核心へと証言は続く。犯行までの経緯について、トイレに行こうとしたが酔ってよろけた女性を吉元、山田両被告で肩を持つなどしてトイレに連れて行き、酩酊状態の女性を吉元被告が「ここは俺が面倒見ておくから」といったため山田被告は宴席に戻った。
そして、20~30分ほどたっても2人が戻らないことが気になった山田被告がトイレの扉をたたいて中の2人に声をかけると、開いたドアの向こうに吉元被告が立っていて、女性に乱暴したなどと話したという。
「自分もいいだろうと思い女性の体を触るなどしているうちにエスカレートし、犯行に及んでしまった」
山田被告は当時の心境を「予想外でびっくりした」と述べたが、女性に声をかけても反応がなく、吉元被告が酩酊して抵抗できない状態の女性の体を触るなどしているのを見て、乱れた雰囲気の飲み会で深酒をしたことも相まって「自分もいいだろう」などと考えたという。
吉元被告と女性の体を触るなどするにつれて興奮した結果、犯行に及んだが、「酔っていたのでうまくいかなかった」などと述べた。
その後、女性は山田被告らに、飲み会にも参加していた同学部の増田峰登被告(23)=同区、準強姦罪で公判中=の家に連れて行かれ、増田被告からも乱暴を受けたとされる。検察側に「女性を増田被告の家に連れて行ったのはなぜか」と問われると、「女性が酔って自力で帰れなかったため、一番近い増田被告の家に送った」と答えた。
山田被告は自分の犯行について、「雰囲気に流されてやった自分の性格が悪かった」と振り返り、「女性や女性の家族に取り返しのつかないことをしてしまった。本当に申し訳ない」と述べた。
この日は、山田被告の情状証人として父親らが出廷。父親は「逮捕を知り、頭が真っ白になった。その場の雰囲気に流され人を傷つけるなど、23歳くらいの男なら普通しないのではないかと思う。犯行に及んでしまったのは私たちにも至らなかった点がある。被害者におわび申し上げたい」と述べた。
検察側によると、示談を申し入れている山田被告側に対し、被害女性は示談の意思はないという。法廷では、山田被告の父親が、妻と2人で手紙を書いて被害者に渡そうとしたが、受取を拒否されたことも明らかにされた。
ところで、辻川靖夫裁判長はどんな人たのだろう?
辻川靖夫裁判官≪40期≫ (日本の刑事裁判官)
製薬大手ノバルティスファーマの降圧剤ディオバンを巡る臨床研究データ改ざん事件で、薬事法違反(誇大広告)の罪に問われた元社員白橋伸雄被告(66)に、東京地裁は16日、無罪(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。法人としてのノ社も無罪(求刑罰金400万円)とした。
辻川靖夫裁判長は、被告がディオバンに有利となるよう患者データを意図的に改ざんしたと認定する一方、「論文を学術雑誌に掲載してもらった行為は、顧客に購入意欲を喚起させる手段とは言えない」と指摘し、虚偽や誇大な広告を規制する薬事法違反は成立しないと判断した。
(共同)
製薬大手ノバルティスファーマの高血圧治療薬「ディオバン」をめぐる論文データ改ざん事件で、薬事法(現医薬品医療機器法)違反(誇大広告)罪に問われた元社員白橋伸雄被告(66)の判決が16日、東京地裁であり、辻川靖夫裁判長は無罪(求刑懲役2年6月)を言い渡した。
法人としての同社も無罪(求刑罰金400万円)とした。
弁護側は「意図的な改ざんをした事実はない」と無罪を主張していた。
白橋被告は京都府立医科大の医師らが実施したディオバンの臨床研究で、データの統計解析を担当。同社に有利に改ざんしたデータを医師に提供し、2011、12年に論文を発表させたとして起訴された。
参議院予算委員会は、学校法人「森友学園」が元の国有地で建設を進めていた小学校の認可をめぐって、大阪府から聞き取りを行い、担当者は政治家からの働きかけは一切なく、府と財務省近畿財務局が、小学校の認可と国有地の売却に向けて、審議会の進め方を協議していたと説明しました。
参議院予算委員会は、大阪・豊中市の国有地が、学校法人「森友学園」に鑑定価格より低く売却されたことをめぐって、事実関係の解明につなげたいとして16日、山本委員長と与野党の理事らが視察のため大阪を訪れています。
このうち午前に行われた大阪府への聞き取りで、大阪府教育庁の橋本正司私学監は、学園が建設を進めていた小学校の認可をめぐる政治家からの働きかけについては、「当時の担当者に聞いたが、そうした事実は一切ない」と述べました。
一方、橋本私学監は、学園側から小学校の設置に向けて相談があった平成25年の9月から11月にかけて、財務省近畿財務局から府に対して、認可に向けた手続きの進捗(しんちょく)状況などに関して、複数回問い合わせがあり、府の私学審議会と国有財産の処分などを審議する近畿財務局の審議会の進め方を協議していたと説明しました。
ただ、橋本私学監は私学審議会が答申を出す、平成27年1月までの1年余りの近畿財務局との詳しいやり取りについて、「メモを取っていなかった」と述べました。
また、橋本私学監は「森友学園」に対して、国や大阪府などにそれぞれ提出された3つの契約書の内容などを確認するため、来週21日に改めて現地調査を行うことで、学園側と調整していることを明らかにしました。
結局変わろうとはしない
情報まとめ(キュレーション)サイト問題を引き起こし、第三者委員会の調査を受けていたディー・エヌ・エー(DeNA)は、3月13日、報告書を受領して記者会見を開き、関係者の処分とともに、創業者である南場智子会長の代表取締役復帰と今後の対応方針について明らかにした。
その3時間にも及ぶ会見に出席して得た正直な感想は、「監督もプレイヤーも変わらないのに、新たなゲームを組み立てられるのか」というものだった。
対応した南場会長と守安功社長は、「利益優先主義」を反省、「法令遵守」の確立を何度も繰り返し、DeNAの体質改善を約束したが、主要なプレーヤーに変化はなく、新生DeNAをイメージできない。
DeNAのキュレーションサイトで行われていたのは、記事で最大2万件、画像で最大74万件という数字が示すように、組織的な著作権侵害であり、「マニュアル」を作成して、盗用を見破られないように“コツ”を伝授するなど悪質だった。
しかも、抗議が来れば、自分たちのサイトは「メディア」ではなく、記事に責任をもてない「プラットフォーム」だと説明していた。
DeNAメディア事業の出発は、村田マリ氏の「iemo」、中川綾太郎氏の「MERY」の二つのサイトを50億円で買収したところから始まっており、二人を会社に引き入れ、統括責任者とすることで、事業化のスピードを速めた。
今回、そのビジネスモデルを確立した二人は処分を受け、退任してメディア事業から離れたものの、会社には「本部付」という無任所で残る。
創業経営者としての責任の取り方が、「代表に戻って、社長の守安とともに複眼的なチェック体制を敷くこと」だという南場氏は、「メディア事業の再開は白紙」といいつつも、「(村田、中川という)二人の有能な若者を指導できなかった」と気遣っているだけに、再開に含みを持たせたというべきだろう。
要は、高い時価総額と利益目標を掲げ、それに向かってひた走る「永久ベンチャー」の南場商店・DeNAは、今後も変わらないのである。
厳しい第三者委の報告と新生DeNAの決意表明に合わせたように、『DeNAと万引きメディアの大罪』(宝島社)が上梓された。ITジャーナリストを中心にした執筆陣が、今回の事件の背景を様々な角度から検証、私も「DeNAの体質」と「ネット広告のカラクリ」の二本を寄稿した。
会見で感じた「変わらなさ」は、これまでにも繰り返されてきた。
2010年12月、ゲーム事業にシフト、携帯用ゲーム「怪盗ロワイヤル」が大ヒットしていた時、「競合他社の事業者との取引」に圧力をかけたとして、公正取引委員会の立ち入り検査を受けた。
また12年5月には、レアカード欲しさにカプセル入りおもちゃ(ガチャ)をランダムに買っていくコンプガチャ商法が問題になり、消費者庁は景品表示法違反の見解を示した。業界全体の問題でもあったが、東証一部に上場、プロ野球球団まで持ち、社会的認知度が高いDeNAには、より厳しい批判の声が寄せられた。
その時、会社は変革に踏み切らなかった。南場氏は自著『不格好経営』のなかで、コンプガチャ問題を「新しい遊び方、新しい事業には、新しい課題が発生し、事業者は軌道修正を求められる」という一般論で締めくくっている。
「コンプガチャに何十万円も投じるような中毒患者を生み、育て、そこから収奪する」というビジネスモデルの持つ反社会性には思い至っていない。
覚悟を感じられない
一方で、今回の事件は「情報(記事)が正しく評価されない」というネット社会が抱える根源的問題を示唆している。
DeNAは、収益至上主義によって著作権を侵し、情報の価値を毀損、信頼性を奪ったという意味で、メディア全体を汚した。
だが、それはDeNAだけの問題ではない。キュレーションサイト全体が抱える問題であり、もっといえば情報が検索エンジンに連動して評価を上げ、それに従ってネット広告収入に結びつくというビジネスモデル全体が、情報の価値を貶めている。
DeNAは、1文字1円前後という破格の安さでライターを雇用、大量に記事を書かせて検索エンジンの上位を確保、クリック数を多くすることで広告収入に結びつけた。
グーグルが問題サイトや剽窃記事の氾濫を放置したのは、そうしたネットの見せかけの活況が、広告業者でもあるグーグルの収益に結びつくからであり、DeNA問題発覚後の今年2月、グーグルが検索アルゴリズムを変えて、「品質の低いサイトは上位に来ないようにする」としたのは、批判が自分たちに向かうことを察知したからだろう。
そして、サイト記事の品質の善し悪しが、営業収益につながらないネット広告業界にとって、情報の「質」は興味の対象外である。むしろ大切なのは「量」であり、DeNAキュレーションサイトのビジネスモデルは、ネット広告業界の利益に適う。
さらに、日々、進歩を遂げるアドテクノロジー(アドテク)もまた「質」より「量」だ。
ネット広告は、クリック単価や入札金額などを含めて調整できる運用型が主流だが、運用型において、業者にとっては質が高く広告料が高い情報(記事)よりも、粗製濫造でも安い情報の方が、どこにでも当てはめられるので使い勝手がいい。
そのうえ、広告料を安く上げ、媒体への支払いを安くすれば、その分、自分たちの利益につながるので、アドテクを駆使してそう仕向ける。
DeNAが批判されたのは、「質より量のもうけ主義」であり、そう報じられたのだが、ネット社会における情報の提供は、アドテクとの連動もあって「質」が評価されず、正当な価値を認められず、だから情報の価格破壊が起きている。これは情報に携わるすべての産業が直面している問題であり、DeNAはそれを垣間見せただけである。
だが、進化し続けるネット社会は、「質」の前に、まず効率と収益を優先して既存秩序を破壊、新しい社会環境を築く。その習性は変わらず、これからもネットを主戦場に「ベンチャーの良さは継続したい」(守安氏)というDeNAは、今後も「質」を後回しにするという矛盾を抱える。
「コンプラと社会管理体制の強化」を何度も口にした二人だが、不祥事を受け流してきた過去を思えば、その相克を真摯に乗り越える覚悟があるとは、とても思えなかった。
伊藤 博敏
世の中は金や力が物を言う世界なのかもしれない。踊らされる人達は道化!
【AFP=時事】フランスの自動車大手ルノー(Renault)が25年以上にわたり、ディーゼル車とガソリン車の排ガス試験で不正行為を行っていたことが15日、AFPが入手した仏不正捜査当局の報告書で明らかになった。カルロス・ゴーン(Carlos Ghosn)最高経営責任者(CEO)を含む経営幹部もそれを認識していたとしている。ルノー側は不正を否定している。
報告書は、ゴーン氏を含むルノーの経営陣全体が「詐欺的な戦略」に加担していると指摘。この報告書に基づき、仏検察当局は1月に同社の捜査に着手している。
ルノー側は疑惑を全面的に否定している。AFPの電話取材に応じたティエリー・ボロレ(Thierry Bollore)チーフ・コンペティティブ・オフィサー(CCO)は「ルノーは不正を働いていない」と述べ、ルノー車はすべて法定の基準に従っていると強調した。
報告書はルノーの排ガス制御に関する決定に関して、ゴーン氏が承認を他の人物に任せた形跡がない以上、最終的には同氏の責任になると記している。
報告書によると、試験中に有害物質の排出量を少なく見せる装置が「多くの車両」に搭載されていた。路上走行時の排出量は試験時に比べ最大で377%多かったという。
報告書は最近の車を主な対象としているが、捜査当局はルノー元従業員の証言も踏まえ、こうした不正が1990年から行われていたとみている。【翻訳編集】 AFPBB News
ローコスト住宅のハウスメーカー「秀光ビルド」の物件に建築基準法違反など“欠陥住宅”が続出していることが週刊文春の取材で分かった。秀光ビルドは1991年に石川県で創業し、北陸から関西、中部、東北へとシェアを拡大。現在までに手掛けた住宅は全国に1万戸弱ある。年間売上げは300億円を超え、5年以内の株式上場も見据えている。
中堅ハウスメーカーの営業マンが明かす。
「秀光ビルドは一棟1000万円を切るようなローコスト住宅が売りですが、現場監督は常に一人で10件程度の案件を抱えて疲弊している。そのうえ、単価が安いため腕のいい大工が確保できずにトラブルが頻発している。施主が支店に怒鳴り込むことも多く、会社側は訴訟になる前に補償金を支払い、クレームを抑えている」
秀光ビルドが昨年3月に完成させた物件の施主A氏から、家に問題がないか調査を依頼された「タウ・プロジェクトマネジメンツ一級建築士事務所」の高塚哲治氏はこう語る。
「A氏の家は土台の下に基礎が築造されていない部分や土台と基礎が10センチもズレている部分があり、明らかに建築基準法に違反していました。
また、一階と二階の柱や壁の位置がズレており、耐震を強化する“ダイライト”と呼ばれる耐力面材が継ぎ接ぎで貼り付けられていた。これでは何の効力もありません」
この物件の現場監督(現在は退社)を直撃すると次のように語った。
「私は会社に在籍した約3年間で約70件の物件に関わりましたが、その1割に問題があったのは事実です。残りの物件がどうかと言われれば、正直自信がない部分もあります」
創業者でもある檜山国行会長にも聞いた。
──施主が気付いていないだけで建築基準法に違反している住宅があるのでは?
「検査は出来る限りやっていますが、その可能性は否定できません。気になることがあれば誠実に対応したいと思います」
3月16日(木曜日)発売の週刊文春が詳細を報じる。
「週刊文春」編集部
森友学園の理事長退任を表明した籠池泰典氏の東京での記者会見が予定されていた2017年3月15日、朝方から会見のドタキャンに始まり、その背後に財務省からの圧力をうかがわせる発言が出るなど、籠池氏をめぐる騒動が繰り広げられた。
記者会見をキャンセルしたにもかかわらず、15日午前に大阪から上京した籠池氏と都内で面会した著述家が、報道陣の前で財務省(国税庁)幹部らを名指しで批判する一幕もあった。籠池氏が持っているもの(情報・資料)が全て表に出ると、「内閣が二つ分ぐらい飛ぶ」との爆弾発言も飛び出した。
■「財務省から身を隠せと電話」
籠池氏が、都内の日本外国特派員協会で2017年3月15日14時30分から会見することが公表されたのは3月14日昼。ところが15日朝になり、同協会が会見のキャンセルを会員に通知。理由は明らかにされていない。
同じ15日の朝には、情報番組「あさチャン!」(TBS系)が、籠池氏のあいさつ音声録音データを公表した。前日にあった同学園の塚本幼稚園での修了式で話された内容だ。籠池氏は、国有地売却問題が表ざたになった2月8日、「財務省の方から『身を隠しといてください』」と言われ、10日間「雲隠れ」していたと話していた。
この録音データ報道は早速、同日朝の国会(衆院・財務金融委員会)の質問で取り上げられた。財務省の佐川宣寿・理財局長は「(籠池氏に)隠れてくれ、と言った事実はありません」と答弁し、省からの指示を否定した。
また、昼前の11時ごろには、都内での会見は中止になったはずの籠池氏がマスク姿で羽田空港に降り立ち、報道陣の質問にほとんど答えることなく車に乗って立ち去った。
午後に入ると、また動きが出た。14時30分ごろ、情報番組「ゴゴスマ~GOGO!Smile!」(TBS系)が、籠池氏が入っていったとみられる都内のマンション前から生中継を行った。カメラの前に立っているのは、先日、籠池氏とのインタビュー記事を公表した著述家の菅野完氏。『日本会議の研究』の著書でも知られる。
「内閣二つ分ぐらい飛ぶと思うんです」
籠池氏と面会した菅野氏は、当日会見の急なキャンセルの理由について、「僕は言えない」としつつも、
「いろんな事情があります。ご想像の事情もあります」
と、いわゆる「圧力」があった事を示唆するような説明もした。
また、籠池氏の話を聞きたいという記者らに対し、籠池氏からの「交換条件」があるとして、国有地売買の当時の責任者、財務省理財局長だった迫田英典・現国税庁長官の顔写真を掲げながら、迫田氏の単独インタビューをとってくれば、そのメディアに話をしてやる、と言っていると明かした。迫田氏の顔写真の上には「森友問題の発端を作ったのは、この男」との表記も。菅野氏は、国有地売買に問題があったならば、
「この迫田が問題を起こした、ということでしょ」
と解説した。
また、「あさチャン!」などが伝えた、財務省から籠池氏への「雲隠れ指示」について、籠池氏が「佐川理財局長から(籠池氏らの)顧問弁護士に電話があった」と、具体的な「指示」について認識している、とも話した。
その後、菅野氏は松井一郎・大阪府知事の顔写真も示し、「この人たち(迫田氏と松井氏)こそが悪いヤツらです」と話し、マスコミは、私人である籠池氏を追い回すのではなく、公人であるこの2人に迫るべきだと主張した。
さらには、籠池氏が「持ってるもん(編注:情報や資料か)」が全て表に出ると、
「内閣二つ分ぐらい飛ぶと思うんです」
「安倍晋三みたいの、どうでもエエという話になってしまう」
と、安倍政権の存亡に発展する可能性も示唆した。
菅野氏の生中継前、「ゴゴスマ」コメンテーターの東国原英夫・元宮崎県知事は、籠池氏の当日会見の急遽キャンセルについて、圧力の可能性に言及する司会者の質問に答え、「(圧力を)勘繰らざるを得ない」と話していた。
「圧力」の有無について、籠池氏本人の口から説明はあるのか。15日にキャンセルになった籠池氏の会見については、延期説と中止説が報じられている。
14日、『AbemaPrime』に出演した評論家の竹田恒泰氏が、森友学園の姿勢を批判した。竹田氏は、保守系の著名論客たちとともに、同学園のウェブサイトに賛同者として掲載されていた。
実際に、平成23年と25年の二度、森友学園系列の「塚本幼稚園」での保護者向け講演会に講師として登壇したという竹田氏。「園児たちが教育勅語をバーッと暗唱してましたから、凄い幼稚園だと思いました。色々悪く言われてますけれど、園児たちはビシーッと整列してて、ハキハキと挨拶していて。保護者たちも講演を聞き入るような感じでちゃんとした印象を持ちました」。
その一方、「問題なのは、2回目の講演が終わった後、“小学校を作るので金を出してくれ、応援してほしい“と言われた。そのときは検討しますと答えたのですが、お金の集め方が強引でした。さらに見てみると、“安倍晋三記念小学校“となっていて、これはまずいだろう、許可は取っているのかなと思って。下手に寄付金出して応援したら、宣伝に使われてしまうかもしれない。責任取れないですから。それでお断りをして、お金も出さなかったですし、協力は一切しませんと言ったんです。それなのに私の名前が“推薦者“として推薦の言葉もウェブサイトに載ってて。許可を得ないでそういうことをやるところなんですよ」と、森友学園への不信感を露わにした。
学校法人「森友学園」(大阪市)の小学校設置認可をめぐる問題で、大阪府の松井一郎知事と松井氏の前任の橋下徹氏が15日朝までに、一連の小学校認可の手続きについて、「明らかにミス」などとツイッターに投稿し、自身らの責任を認めた。
ツイッター上で、橋下氏は府の私学審議会が平成27年1月に、学園の小学校開設を条件付きで「認可適当」と答申した際、府による財務状況の確認がなかったとして「明らかにミス」と指摘。これについて、松井氏は「大阪府の審査が100点満点では無いと捉えている」とした上で、「認可判断にミスがあるとすれば、私学新規参入の規制緩和実施後の審査体制を見直さなかった僕にある」と手続きの不備に言及した。
府は学園側からの要望を受け、平成24年4月に新規の小学校設置をしやすいように基準を緩和。要望があった当時の知事だった橋下氏は「規制緩和と審査体制強化をワンセットでやらなければなりませんでした。ここは僕の失態」とフォロー。松井氏は「申請者の財政シュミレーション丸呑みで、銀行の残高証明書等、証拠となる付属書類を求めていなかった」と府の対応の反省点を分析した上で、「今後はこれらを見直す方向で教育庁が検討しています」とツイートした。
読売新聞は「取材せず談話捏造」はだめだと言う事を記者教育に含めていないのか?まあ、記者としての問題以前の問題だと思う。
読売新聞の記者達に教育を徹底しないと常識な事も判断できないのであればかなり深刻な問題だと思う。それとも建前の言葉なのか?
読売新聞社の福島県・いわき支局の男性記者(25)が取材せずに他紙の記事を後追いし、町長の談話も捏造(ねつぞう)していたとして、同社は15日朝刊に「重大な記者倫理違反と認識している」としたおわび記事を掲載した。
談話部分を削除し、記者の懲戒処分などを行うとしている。
同社によると、捏造があったのは今月7日夕刊と8日の朝刊一部地域で掲載された記事。2015年9月に東京電力福島第1原発事故の避難指示が解除された福島県楢葉町の町長が、昨年11月の庁議などで「避難先から帰還しない職員は昇格・昇給させないようにする」という趣旨の発言をしていたとする内容。
男性記者は、町などに内容を確認しないまま他紙の情報を参考に記事を執筆し、町長の談話も本人に取材せずに捏造した。「締め切りが迫る中、取材しないまま安易に書いてしまった」と話しているという。
読売新聞社はおわび記事の中で「記者教育を徹底して再発防止に取り組み、信頼回復に努めます」としている。
森友学園問題をめぐり、安倍昭恵総理夫人(54)に注目が集まっている。今月1日の予算委員会では、安倍総理から「妻は私人」「犯罪者扱いするのは不愉快」との発言も飛び出したが、以下の振る舞いをもってしても「私人」と言い張ることができるのか――。
***
「全国高校生未来会議」なるイベントが衆院第一議員会館、そして総理公邸で行われたのは昨年3月のことだった。18歳選挙権の実施を前に模擬投票などを行う趣旨の催しだが、文部科学省と総務省が後援、優秀者には総務大臣・地方創生担当大臣、そして内閣総理大臣の各賞が贈られるという大盤振る舞いだ。
これほどの規模でイベントを行うことができた背景には、主催する一般社団法人「リビジョン」と昭恵夫人との密接な関係があった。
「安倍昭恵さんから、未来会議をバックアップしてほしいという打診があったのです」
と語るのは文科省の関係者である。昭恵夫人からは“文部科学大臣賞”を出してほしいとの要請があり、大臣賞までは出さなかったが、後援することに。
「実績に乏しい団体が主催するイベントを後援していいのかと、省内で議論になったのは事実です」
前出の大臣賞についても、“昭恵夫人からの要望で認められた”と別の関係者は明かす。
どこの世界に、賞を出してくれるようにと大臣に直接掛け合うことができる「私人」がいるというのだろうか――。今月27日と28日には「未来会議」第2回の開催が予定されており、会場は参議院議員会館となっている。
3月15日発売の「週刊新潮」では、「リビジョン」代表と昭恵夫人との関係や、私企業の宣伝にも使われた先のイベントの実態についても掲載する。
「週刊新潮」2017年3月23日号 掲載
新潮社
防火シャッターの作動点検、又は、定期点検が要求されていなければ、なぜ要求されていなかったのか?
防火シャッター設置後の作動確認検査は法又は規則で要求されているのか?
防火シャッターが作動しなければ、防火シャッターの意味はないと思える。
三芳町の事務用品通販会社アスクルの物流倉庫で起きた火災で、一部の防火シャッターが正常に作動していなかったことが分かりました。
この火災は先月16日、三芳町上富にあるアスクルの鉄骨3階建ての物流倉庫で発生したもので、火はおよそ4万5,000平方メートルを焼き、発生から12日経った先月28日に完全に消し止められました。
3階建ての倉庫内には火災のときに自動的に床まで下りて火の回りを防ぐ防火シャッターが設置されていましたが、一部のシャッターが全く下りていないなど、正常に作動していなかったということです。警察や消防は、広い範囲に延焼した要因になったとみて、詳しい状況を調べています。
入間東部地区消防組合によりますと、現場の調査は今週をめどに終わる予定で、調査結果をもとに火災の全容解明を進める方針です。
一方、総務省消防庁は火災が長期化した原因を分析し、同じような規模の建物の防火対策や消防活動のあり方を議論するため、大学教授のほか消防庁や県、物流関係の団体などで構成された検討会を設置し、14日夕方、都内で初会合を開きました。
会議では実際に消火活動にあたった入間東部地区消防本部の職員も参加し、一部の防火シャッターが作動しなかったり荷物などの影響で閉鎖しなかったりしたこと、そして消火器やスプリンクラーの設置数など建物自体が関係する法律の基準を満たしていたことが管轄する省庁から報告されました。
検討会は、6月をめどに会議としての報告書をまとめることにしています。
テレ玉
勉強だけ出来れば良いとの考えは重い処分により修正されないと、社会の秩序は崩れてしまうと思う。
医療業界は秩序を重んじるのか、コネ、金、人脈などからかなりの影響を受けるのか知らないが、これぐらいの処分は必要だと思う。
千葉大医学部生が飲み会に参加した女性を集団で乱暴したとされる事件で、千葉大は14日、飲み会中に女性にわいせつな行為をしたとして準強制わいせつ罪に問われ公判中の千葉大病院研修医、藤坂悠司被告(30)を懲戒解雇にしたと発表した。
起訴状によると、千葉大医学部5年の吉元将也被告(23)=集団強姦罪で公判中=らと共謀し、昨年9月20日夜、千葉市の飲食店で酒に酔った女性の体に触るなどしたとしている。2月20日の初公判では「間違いありません」と起訴内容を認めた。
事件をめぐっては藤坂、吉元両被告の他、集団強姦罪で山田兼輔被告(23)、準強姦罪で増田峰登被告(23)=いずれも千葉大医学部5年=が公判中。千葉大は医学部生3人についても処分を検討している。
石井国交相は14日、閣議後の会見で、大阪の学校法人「森友学園」の小学校建設に対する補助金の交付決定を取り消し、既に支払った5600万円余りの返還を求める考えを示した。
「補助金交付決定の取り消し、補助金返還に向けて手続きを進めたい」―また、石井国交相は必要があれば森友学園と施工業者に直接ヒアリングを行い、補助金の申請内容に不正がなかったか、調べるという。
隠す問題などなければ早く問題を片付ければ良いだけだと思うのだが?
稲田朋美防衛相が平成16年12月、籠池泰典氏が理事を務めていた大阪市の学校法人「森友学園」が起こした民事訴訟の第1回口頭弁論に、原告側代理人弁護士として出廷したことを示す裁判所作成記録があることが13日、関係者への取材で分かった。
稲田氏は同日の参院予算委員会で「籠池氏の事件を受任し顧問弁護士だったということはない。裁判を行ったこともない」と述べていた。
学園が16年10月18日に大阪地裁に提訴した同市淀川区の土地と建物の抵当権抹消登記請求訴訟で、訴状の「原告訴訟代理人」には稲田氏と夫の龍示氏、もう1人の計3人が記された。また同地裁が作成した第1回口頭弁論調書には、同12月9日の初弁論に龍示氏を除く稲田氏ら2人の名前が「出頭した当事者等」に記載されていた。
稲田氏は昭和60年に弁護士登録し、夫妻で大阪市内の法律事務所に所属していた。
南彰
国有地売却問題で揺れる学校法人「森友学園」(大阪市)について、13日の参院予算委員会で、稲田朋美防衛相との関係が取りざたされた。理事長を退任する意向を示した籠池(かごいけ)泰典氏はインターネットで、稲田氏がかつて籠池氏の顧問弁護士を務めていたと証言。同日の参院予算委では、野党側が稲田氏が同学園の代理人弁護士をしていたとする訴訟資料を取り上げたが、稲田氏はいずれも否定した。野党は、稲田氏の答弁の信頼性が疑われるとして追及を強めている。
「10年ほど前から、もう全くお会いしていないし、関係を絶っているんです」
13日の参院予算委員会。民進の小川敏夫氏に籠池理事長との関係を問われた稲田氏は語気を強めて反論した。この日朝にネット上で公開されたインタビューの動画で、籠池氏が「ご主人と稲田朋美先生で私に対する顧問弁護士でした」と語った新証言は、「全くの虚偽だ」と切り捨てた。
稲田氏は学園の国有地売却問題が発覚した先月以降、国会で「籠池氏とはここ10年来全く会っていない」「弁護士時代を通じて、籠池夫妻から何らかの法律相談を受けたことはない」「裁判を行ったこともない」と関係を否定し続けている。
この日の予算委では、小川氏から「森友学園訴訟代理人弁護士 稲田朋美」と書かれた2005年10月11日付の裁判資料とされる書類を示されると「いま初めて見ました」と答弁。委員会室が「え~」とどよめく中、「共同事務所の場合、連名で(代理人弁護士を)出すことは多くある。私は一切、籠池氏から法律相談を受けたことはありません」と強く打ち消した。
籠池氏がインタビューで「2年ほど前、お目にかかって直接話した」と証言したことについても「記憶にない」と重ねて否定した。
稲田氏は06年10月号の雑誌…
学校法人「森友学園」(大阪市)の国有地売却問題をめぐり、稲田朋美防衛相は14日の閣議後会見で、一部報道で稲田氏が同法人が起こした民事訴訟で原告側代理人弁護士として出廷した記録があると指摘されたことについて、「(弁護士の)夫の代わりに出廷したのでは、と推測している」と釈明した。
一連の問題を受けて同法人の理事長を退任する意向を示した籠池(かごいけ)泰典氏との関係について、稲田氏はこれまでの国会答弁で「籠池夫妻から何らかの法律相談を受けたことはない」「裁判を行ったこともない」などと繰り返してきた。稲田氏はこの日、出廷記録が事実なら「答弁を訂正したい」と語った。
稲田氏は13日の参院予算委員会でも籠池氏との関わりを強く否定。野党は答弁の信頼性が疑われるとして追及を強めている。稲田氏はこの日の会見で記者団から虚偽答弁だった可能性を指摘されると、「自分の記憶に基づいて答弁した。虚偽の答弁はしていない」と述べ、引責辞任は否定。「国有地の問題と本当に何の関係もない」などと語った。
一部報道によると、稲田氏は2004年12月、森友学園が起こした民事訴訟の第1回口頭弁論に、原告側代理人弁護士として出廷したことを示す大阪地裁作成の記録があることがわかった。同地裁が作成した第1回口頭弁論調書には、12月9日の初弁論に稲田氏ら2人の名前が「出頭した当事者等」に記載されていたという。(相原亮)
朝日新聞社
大阪市の学校法人「森友学園」の小学校新設計画を巡り、学園側が目的に応じて虚偽の工事契約書を作成していた疑いが強まったとして、大阪府は学園に対し、私立学校法に基づく立ち入り検査も視野に、本格的な調査に乗り出した。小学校の設置認可を府に申請していた学園側は10日、認可の見通しが薄いことなどから申請を取り下げたが、府は「契約書の問題は残っており報告を求める」として調査を進める。
学園側は、私立学校の設置認可事務を担う府私学課に7億5600万円▽小学校建設に伴う補助金の受給に向けて国土交通省に23億8400万円▽大阪(伊丹)空港の騒音対策助成金を受けるために空港運営会社「関西エアポート」に15億5500万円--と、額の異なる3種の工事契約書を用意して提出していた。施工業者は府の調査に「当初に見積もった正しい工事費は15億円だった」と説明し、学園側の要望に応じて虚偽の契約書を作成したと話している。
しかし、学園の籠池泰典理事長(辞任)は申請取り下げ後の記者会見で、契約書について虚偽の認識を否定。府は「虚偽ではないなら合理的な説明をすべきだ」としており、立ち入り検査も視野に、引き続き学園側から説明を求める。
一方、籠池氏は10日の会見で、小学校設置認可の再申請を目指す意向を示した。国の大学設置審査の際には虚偽申請があれば最長5年間は申請できないが、府はこうした例を私立学校審議会に伝え、対応策を検討するという。【津久井達】
麻生グループの「麻生鉱山」(福岡県飯塚市)が、自社の医療廃棄物リサイクル工場「エコノベイト響」(北九州市若松区)で請け負った廃棄物処理を、排出元の医療機関に無断で山口県の産業廃棄物処理業者に再委託していたことが北九州市の調べで分かった。
産廃の運搬や処理経路の管理票(マニフェスト)には自社工場で処理したと虚偽記載していたという。北九州市は再委託を原則禁じた廃棄物処理法違反にあたるとして、麻生鉱山に今月中にも産廃処理業の業務停止処分を出す方針。
市によると、同工場は2002年に稼働を始め、北部九州などの医療機関から収集した医療廃棄物を年間約6000トン処理。使用済みの注射針やガーゼ、紙おむつなどを破砕し、高周波で加熱、滅菌処理して固形燃料やセメント原料などにリサイクルしている。
いかに不適切なプロセスに役人達や政治家達が関わっていると疑問に思わせるケースだ。
学校法人「森友学園」と昭恵夫人のコンビネーションがなければここまで注目を浴びることはなかったであろう。そう言う意味では 意図しなかった結果であるが、昭恵夫人は功労者だ。
学園理事長の教育者としての資質が問われる事態になりつつある。
学校法人「森友学園」が大阪府に提出した、豊中市に建設中の小学校の設置認可申請を巡る資料に、事実と異なる点が次々と発覚した。
資料には、校舎などの建築費に関し、国土交通省への補助金申請書類と異なる金額を記載した契約書が含まれる。府には「7億5600万円」、国交省には「23億8400万円」と報告していた。
別の金額の契約書も、大阪空港の運営会社に提出された。
学園側は、建築費の増額分を見込んで申請したというが、より多くの補助金を受け取るために虚偽の契約書を提出したのなら、学校法人としてあるまじき行為だ。
資料は、愛知県の私立中高一貫校の推薦入学枠を確保したとも記載していた。相手校が「事実無根」と否定すると、ミスを認めた。
松井一郎府知事は学園側の姿勢に不信感を募らせている。府は申請内容を精査し、設置の不認可も検討する。当然の対応だろう。
国会で野党は、森友学園の問題で政府を追及している。
小学校用地の国有地が評価額を8億円余も下回る価格で学園に売却されたことについて、財務省などは、国有地内のゴミ撤去費用を差し引いたと説明する。
現地調査を踏まえ、公共事業に使用される積算基準に基づき、ゴミの処分量と作業単価から国交省大阪航空局が算出したという。
膨大な廃棄物が埋まった土地である以上、売却価格の減額は正当であり、政治家の関与はなかった、という見解は理解できる。
自民党の鴻池祥肇・元防災相は森友学園の籠池泰典理事長から、財務省への働きかけを要請され、謝礼を渡されそうになったことを明らかにした。ただ、仲介については明確に否定している。
野党は、衆参両院予算委員会での籠池氏の参考人招致を求めているが、狙いはどこにあるのか。
首相夫人の安倍昭恵氏と森友学園との関係も、国会審議の焦点の一つとなっている。
昭恵氏は、問題の小学校のホームページに名誉校長として高く評価する挨拶文が掲載された。2014年12月と15年9月には、学園の運営する幼稚園で講演し、政府職員も同行している。
首相夫人は政府の公式行事や外交活動に参加する機会が多く、その発言の影響力は大きい。単なる「私人」では済まされない。そのことを自覚し、より慎重な振る舞いに努めねばならない。
ここの原因究明が大問題!関与した人達の逃げ方が尋常でない。何があるのは明らか!しかし、信じられない言い訳や答弁ばかり。 キャリアは学歴が高く、能力があっても人間性に関しては?????????と思わせる対応ばかり。これでは平行線、又は、下っている 日本経済を立て直すことは出来ない。狡く、自分達だけの安定だけを姑息に準備するのであろう。
愛国心どころか、不信感と不誠実と言った感じだ。
学校法人「森友学園」の籠池(かごいけ)泰典理事長が代表を務める社会福祉法人が運営する「高等森友学園保育園」(大阪市淀川区)が、勤務実態を偽って補助金約1000万円を受給した疑いがあるとして、大阪市は8日、調査を始めた。
不正を確認すれば、補助金返還を求める方針。
市によると、同園は、常勤で運営管理業務に専従する園長を置けば加算される国の補助金を、2015年度に562万円、16年度に509万円受給。だが、大阪府関係者によると、園長である籠池氏の妻は、森友学園運営の塚本幼稚園(同区)でも副園長として勤務しているという。
市は、保育園長と幼稚園副園長の兼務は、常勤・専従の規定に違反する可能性が高いとみて、実態の調査を進める。
奔放に飛び回る妻を自由にさせる、理解ある夫――安倍総理のそんなスタンスが女性からの支持率を上げてきた。だが、総理も今度ばかりは後悔しているかもしれない。この疑惑は簡単には晴れない。
問題だらけの土地取引
「近いうちに、あの小学校にどんな人物がいくら寄付をしていたか、リストが出てくるでしょう。ここに名前が挙がる人脈を精査されれば、安倍総理は大ダメージを受ける。トランプ政権ともまずまずうまくやれているし、当分政権は安泰だと思っていたけど、これは本当にまずいかもしれない」
ある官邸スタッフはこう漏らした。
誰がどう見ても、真っ黒な土地取引――それがこともあろうに、安倍総理を直撃し、官邸に激震が走っている。
件の土地は、大阪府豊中市に4月開校予定の私立小学校「瑞穂の國記念小學院(以下、小學院)」の用地。
同校の経営母体が、「教育勅語」を園児に毎朝暗唱させる「愛国教育」で有名な、大阪市の塚本幼稚園を運営する学校法人森友学園であること、さらに、同校の名誉校長に安倍総理の妻・昭恵夫人が就任していることは、本誌先週号でも報じた通りだ。
森友学園がこの小學院の用地を、評価額のおよそ10分の1という不当な安値で購入した疑惑で、衆院予算委員会は大紛糾している。
「土地は広さ8770平方メートル、鑑定評価額9億5600万円。もともとは近くにある伊丹空港の騒音防止のための緩衝地帯として国が買収していましたが、'05年以降区画整理・集約され、売りに出されたという経緯があります」(民進党衆院議員)
これに対して、森友学園による購入価格は1億3400万円。8億円あまりの割引は、「土地の地下に埋まったゴミ処理費用を補填するためのもの」というが、同学園の理事長・籠池泰典氏は「(ゴミ処理にかかった費用は)1億円くらい」と証言しており、金額が明らかに食い違っている。
以下のやりとりは、取引について'15年2月に行われた、国有財産近畿地方審議会の議事録からの抜粋だ。
〈近畿財務局管財部次長「きちんと期日までに小学校が実際にできるかどうかというところでまず、もしできなければ事業予定者とはいえ(中略)土地を更地にして返して下さいよということを義務づけています」
委員「来年の4月にもう開校になっているのですね(中略)それから寄附金で建物を作ると。これだけでも10数億はかかるはずですよね。(中略)非常に異例な形だなという感じの印象を持っています」「今までの案件と随分、性格を異にするような案件のように私は思っています」〉
この時すでに、取引について「問題ない」と強弁する財務局官僚に対し、審議委員たちが強烈な違和感を抱いていたことがうかがえる。
しかしその後、森友学園には、校舎・体育館の木造化による国土交通省からの補助金6200万円なども出されることが決まった。これらを合わせて、同学園はほぼ「実質負担額ゼロ円」で土地を取得したというから、疑念は深まる。
安倍総理にとって大きな誤算だったのは、昭恵夫人がこの森友学園に、思った以上に肩入れしていたことだ。
「普通の公立学校の教育を受けると、せっかくここ(注・塚本幼稚園)で芯ができたものが揺らいでしまう」「日本を誇りに思える子供たちがたくさん育っていってほしい」
昭恵夫人は一昨年9月に行われた小學院の設立記念講演会で、森友学園の教育方針をこう褒め称えていた。さらには小學院のホームページにも、
〈籠池先生の教育に対する熱き想いに感銘を受け、このたび名誉校長に就任させていただきました。
瑞穂の國記念小學院は、優れた道徳教育を基として、日本人としての誇りを持つ、芯の通った子どもを育てます〉
と記している。総理の妻でありながら、公立学校の教育を否定している点が、「アッキー」らしい暴走と言えよう。
安倍晋三の名前でカネ集め
さらに今回、昭恵夫人と以前から親しかった籠池氏が、総理夫妻からの「お墨付き」を最大限に利用し、ロビイングに励んでいたことも分かった。すでに氏が「安倍晋三記念小学校」という名前を使って寄付金集めをしていたことが判明しているが、他にも不自然な動きが見られたと話すのは、ある自民党議員だ。
「森友学園が大阪府に建設計画を提出したのが'14年8月。それからわずか半年後の'15年1月には、『認可適当』の判断が下っています。
この間、籠池氏は府の担当課に足しげく通って陳情していたと聞きます。当然、小學院のパンフレットも持ち込んでいましたが、そこには昭恵さんの顔写真とメッセージ、また自民党の大物議員・平沼赳夫氏のメッセージも載っています。
府の職員によれば、籠池氏があまり『認可を急げ』とせっつくので、庁内でも問題視されていたそうです。しかも、安倍総理と昭恵さんの後ろ盾をちらつかせていた。これは『圧力』と見られても仕方がないでしょう」
「全国で初めての神道の小学校」をうたう小學院には、敷地内に「瑞穂神社」なる神社を設ける予定だという。また、籠池氏は周囲に、「校舎には、伊勢神宮の建物に使われる木のすぐ近くでとれた木材を使う」と豪語していた。それが前述した6200万円の補助金の根拠というわけだ。
しかし、大阪府庁関係者はこう言う。
「入学希望者は1年生の定員80名に対して50名、2年生にいたっては5名しか集まっていなかった。いずれにせよ、開校は厳しかったのではないか」
焦点は今後、誰がどのように全体像を描いて、この土地取引をリードしたのかという点に絞られてくる。いくら安倍総理夫妻の名前という「印籠」があったとはいえ、それだけで籠池氏が、自らの要求をゴリ押しできたとは思えないからだ。
ここにきて、安倍総理に近い大物の名が取り沙汰されている。
「籠池氏が安倍総理を支持する政治団体『日本会議』関西支部の幹部であることはすでに報じられていますが、それ以外にも、学校法人加計学園理事長の加計孝太郎氏が、安倍総理夫妻と籠池氏の『つなぎ役』になったのではないか、という話が永田町では出ています。
加計氏は安倍総理が若手議員の頃、一緒にアメリカ留学をした親友。しょっちゅう総理のゴルフにも付き合っているので、新聞の動静欄で名前を見たことがある人も多いでしょう」(野党衆院議員)
加計学園は現在、愛媛県で土地を取得し、獣医学部の新設を進めている。この用地は、安倍政権が'13年以降に定めた「国家戦略特区」に含まれる。
「考えてみると、安倍政権下では千葉の国際医療福祉大学成田キャンパス、宮城の東北医科薬科大学の医学部新設など、私学の新学部設立や認可が多い。こうした学校の許認可の背景が、次の火種になるかもしれない」(前出・野党衆院議員)
冒頭に引いた国有財産審議会の中で、財務局の担当者は、森友学園への土地売却を強行する理由として「小学校という公共性が高い事業だから」と繰り返していた。
しかし、森友学園が運営する塚本幼稚園では、
〈邪な考えを持った在日韓国人・支那人〉〈韓国人とかは、整形したり、そんなもの(注・炭酸飲料)を飲んだりしますが、日本人はさせません〉
などと書いた文書を保護者に配布していたことがすでに判明している。こうした教育が、国有地を格安で売り払ってでも進めるべき「公共性が高い事業」かと言われれば、多くの人が首をかしげるのではないだろうか。
「一連の事態を受けて、大阪府は2月22日に臨時私学審議会を開き、認可の再検討を始めました。しかし小学校の開設認可を正式に下ろすどころか、森友学園の学校法人資格そのものを剥奪することも、すでに府の視野には入っている」(在阪の全国紙社会部記者)
なお今回、本誌は森友学園と籠池氏に取材を申し込んだが、媒体名を告げると「お断りします」と一方的に通話を切られてしまった。
あの理事長は国会に呼ばれる
今のところ、安倍総理と昭恵夫人が、この小學院用地の取引に直接かかわっていたことを示す物証はない。だが、総理が国会で「妻から森友学園の先生(注・籠池氏)の教育に対する熱意は素晴らしいと聞いている」と述べたのは事実だ。
一方の昭恵夫人は、親しい知人に対して、
「(小學院の件は)ちゃんと確認したので大丈夫よ」
と明言していたという。つい最近まで昭恵夫人も、安倍総理自身の関与が疑われる大問題に発展するとは、夢にも思っていなかったのである。
仮に安倍総理や昭恵夫人、あるいは政権に近い政治家が森友学園の疑惑にかかわっていれば、総理の進退が問われる。国有地が国民の公共財産である以上、コネを使ってこれを不当に安く売却していたならば、国民に対する背任だ。
しかも小學院が開校できない場合、前述した審議会での財務局官僚の発言にもある通り、森友学園は用地を更地にして国に返還しなければならない。すでに校舎が建っていることを考えれば、なかなか難しい条件である。子供の入学を希望していた保護者たちも黙っているはずがない。
そもそも「瑞穂の国」という言葉は、安倍総理が演説や著書の中で、日本のことを指して繰り返し使ってきた言葉。籠池氏が国会に証人喚問される可能性が出てきたこともあって、官邸は戦々恐々としている。
「土地そのものを担保に、大手銀行が森友学園に5億円の融資をしたという情報も出回っています。この件はスキャンダルが次から次に出てきすぎる。正直、今のところは黙殺するしか対処法がない」(前出・官邸スタッフ)
また、この一件で、安倍総理の考えていた政権戦略も大幅に狂ってしまった。せっかくトランプ大統領との会談でアップした支持率に、悪影響が及ぶばかりではない。自民党と公明党のすきま風が強まる中で、これから政権を支える一大勢力になると期待していた、大阪維新の会の関与が疑われていることも大きな理由のひとつである。
「維新内部では、すでに複数の地方議員がこの件の『実働隊』になっていたという話が出ています。
自民党の側は、『大阪維新の松井(一郎代表・大阪府知事)が勝手にやったことだ』という形で幕引きを図ろうとしている。しかし、財務局と国交省の双方を巻き込んで、スピード認可を下ろすなんて芸当がウチだけでできるのか。しかるべき『上』の介入もあった、と見るのが自然ですよ」(維新の会関係者)
大阪の有権者は、カネにまつわる不正には敏感だ。仮に官邸が「シッポ切り」に成功して責任を維新に押し付けても、維新の支持率急落は免れない。与党寄りの野党、「ゆ党」である維新のサポートを失うのは、政権にとって大きな痛手だ。
さらには、大阪に多いとされる公明党支持者まで離れかねない。こうした事態を防ぐために、これまで安倍政権では、菅義偉官房長官や二階俊博幹事長らが水面下で各党と通じてきたのである。
これは疑獄事件だ
今回の一件が意味すること――それは、維新の会に代わる新勢力・小池新党へのシフトが、安倍政権にとって喫緊の課題になったという事実だ。小池百合子東京都知事を取り込めるか否かが、政権の浮沈を左右する。すでに始まった重鎮たちの「小池シフト」について、自民党議員はこう言う。
「おくびにも出しませんが、当然、菅さんは小池さんのことを意識していますよ。下手にしゃべるとマスコミに騒がれるし、何も言わないほうが小池陣営の疑心暗鬼も誘えるので、言わないだけ。菅さんの性格ですから、『あくまでもイニシアチブ(主導権)はオレが持つ』ということです」(中堅)
「二階さんも菅さん同様、小池さんについては沈黙を守っていますが、二階・小池ラインが常に裏で意思疎通していることは間違いありません。
二階さんは幹事長だけど、夏の都議選はあくまで地方選挙ですから、都連会長の下村(博文党幹事長代行)さんに丸投げして自分は黙っていようと考えています。
安倍総理は去年の都知事選のときから『(自民党の公認候補は)増田(寛也元総務相)じゃなくて小池がいいんじゃないか』と言っていたほどだし、大阪維新を補完勢力にしたのと同様に、小池新党を取り込みたいと思っています。
実務を担う二階さんは、そういう安倍総理の考えも当然織り込んで小池シフトを進めている」(ベテラン)
まだ、安倍総理はあくまで「自分が小池を利用する側なのだ」という意識でいる。しかし「瑞穂の國記念小學院」と昭恵夫人の「暴走」に端を発する疑惑は、単に安倍政権の補完勢力の交替を促すだけのものではない。下手をすれば、安倍総理の「退陣」の二文字さえちらつく疑獄事件に発展しかねないのだ。
この潮目の変化を、政界の魑魅魍魎たちが見逃すはずはない。
「菅さんや二階さんのような『オッサン』の怖いところは、風向きが変わったと見たら即座に小池さんに乗り換えるであろうところ。二人とも、これまで何人のボスを渡り歩いてきたことか」(前出・自民党中堅議員)
これまで安倍総理は、昭恵夫人がいくら勝手な行動をとろうと、「家庭内野党」と言って済ませてきた。しかし今回ばかりは、それでは乗り切れそうにない。
「週刊現代」2017年3月11日号より
週刊現代
大阪の学校法人「森友学園」が開設予定の小学校をめぐる問題で大阪府に提出した雇用予定の教員リストに、本人に無断で府内の小学校校長の名前を載せていたことがわかりました。
「森友学園」は先月22日、来月から開設する小学校の教職員として、籠池泰典校長を含め18人の教職員リストを大阪府に提出していました。しかし、この中に校長や教頭に次ぐ総括教員として、60歳の男性を本人に無断でリストに載せていたことがわかりました。男性は現在、大阪府南部の公立小学校で校長を務めています。
JNNの取材に対し、男性は、今年1月、共通の知人を通じて籠池理事長と面会し、「図工の先生になってほしい」と依頼されましたが、態度を保留したということです。その後、男性は先月25日に正式に依頼を断っていて、「リストに載っていることは知らなかった」と話しています。
「(男性と森友学園の)どちらが真実なのか、当事者に聞くしかないので」(大阪府 松井一郎知事)
森友学園の小学校をめぐっては、校舎の建築費や提携校についても、虚偽の書類を提出した疑いが指摘されています。
「補助金の申請の前提となる工事の内容ですね、不正があったということであれば、これは取り消しも含めて検討されるということでよろしいでしょうか」(民進党 宮崎岳志衆院議員)
「そういう可能性もあろうかと思っております」(末松信介 国交副大臣)
国会では、森友学園が国と大阪府に伝えた小学校の建築費の金額が大きく異なっていた問題について、末松国土交通副大臣は、国が補助金としてすでに森友学園に支払った5640万円の返還を求める可能性もあるとの考えを示しました。
一方、自民党と公明党の幹事長が、8日朝、会談し、野党4党が求めている森友学園の籠池理事長の国会への参考人招致は、困難との認識で一致しました。
安倍総理の昭恵夫人は今回の件で何かを学び、政治利用されるリスクを理解したのだろうか?学んだのであれば、今後に生かしてほしい。
今回の件では何かを隠していると思わせる展開だ。なぜ事実を最初から話せないのか?ここに問題があると思う。
公務員達も信用できないと思わせる展開にとてもがっかりしている。イメージ、理想、そしてあるべき姿とは違い、これが事実なのであろう。
政府は、大阪の学校法人「森友学園」が運営する幼稚園で、安倍総理の昭恵夫人が講演した際に政府職員が同行していたことについて、「職員の私的活動」としてきたこれまでの説明を修正し、「公務」だという考えを示しました。
「『平成27年9月5日につきましては、たしか土曜日であったと思いますけれども、勤務時間外でございまして、これは職員の私的活動に関することでございますので』と答えている。職員の私的活動が何で連絡調整で公的活動にいつから変わってるんですか」(民進党 玉木雄一郎 衆院議員)
「休日、土曜日に行っておって、最初は私的なものかという風に色々と考えておるんですけども、そのあとに理屈として、別な行事のための連絡調整として、付いていくこともありうるということをあわせて検討させていただきまして、両方とも可能性の問題でしたので、そのあとに調べまして、これは公務による出張というかたちで整理させていただいたと」(内閣官房 内閣参事官)
民進党の会合で政府側は、学校法人「森友学園」が運営する幼稚園で昭恵夫人が講演した際に、政府職員が同行していたことについて、「私的活動」から一転「公務」と答弁を変えた理由をこのように説明しました。
ただ、職員の旅費について、「国からの支出はない」と説明したため、出席した民進党議員からは、「公務だというなら、交通費が出ないとおかしい」などと疑問の声が相次ぎました。
民進党は引き続き「森友学園」に国有地が格安で払い下げられたのではないかとされる問題について、政治家の関与がなかったのかどうか追及していく方針です。
大阪の森友学園の問題をめぐり、安倍首相の昭恵夫人が2015年に森友学園が運営する幼稚園に講演に行った際、政府の職員が「公務」として同行していた事が分かった。
昭恵夫人に対しては外務省と経産省出身の計5人の職員が秘書役としてサポートしているが、2015年9月、昭恵夫人が幼稚園で講演をした際には、経産省出身の職員が同行していた事が分かっている。
これについて内閣官房は7日、民進党が行ったヒアリングで、この職員が「公務」として昭恵夫人に同行していた事を明らかにした。その上でこの職員の旅費などについて公費からの負担は無かったと説明している。
内閣官房側はこれまで国会で、職員が同行した日は土曜日で「勤務時間外で、私的な行為として同行していたということはあると考える」などと答弁していた。
森友学園が校舎建築費について、国には大阪府の3倍近い金額を示していた問題で、学園が双方に提出した資料は同じ請負契約書で、金額のみ異なっていたことがわかりました。大阪府は、いずれかが虚偽とみていて、認可しない可能性が高まっています。
大阪の学校法人「森友学園」は、来月開校予定の小学校の校舎建築費について、学校の経営状況をチェックする立場の大阪府には7億5600万円と報告する一方、国には21億8000万円と3倍の額で申請し、既に5600万円の補助金を受けていました。
これについて府が確認すると、学園側は、こう釈明したといいます。
「補助金の申請のために最大限の建築費用を申請した。実際に減額になったら、補助金を返す約束だった」(森友学園)
そして、府がさらに学園に資料の提出を求めたところ、国、府に提出した資料は、いずれも契約日や形式が同じ工事請負契約書で、金額だけが書き換えられていたことがわかりました。
「間違った請負契約書をゼネコン側も出すんですかね。それらを考えれば、ミスというレベルではないと僕は感じています」(大阪府 松井一郎 知事)
大阪府は、いずれかが虚偽だとみて、小学校の認可について先送りするのではなく、不認可とする可能性が高まっています。
「(森友学園は)何とか逃げきろうということで、必死になっているのかなあと。全て虚偽だったということであれば、教育者として失格だと思います」(大阪府 松井一郎 知事)
また、今月23日に予定されている認可を検討する審議会について、前倒しする方向で調整しています。
大阪府豊中市の国有地を小学校建設用地として、評価額より大幅に安い価格で国から売却を受け、国会で集中砲火を浴びている学校法人「森友学園」(大阪市)。理事長の籠池(かごいけ)泰典氏(64)が、性急に小学校設立に動いた背景には運営する幼稚園が休園に追い込まれるなど同学園の経営難が関係しているという。与野党の人脈に度を超した陳情攻勢をかけてまで目的達成を図ろうとしたこの教育者はどんな人物なのか。取材を進めるとさまざまな雑音が聞こえてきた。
関係者によると、休園しているのは大阪市住之江区の「開成幼稚園」。1982年に開園し、剣道やラグビーなどのスポーツ、珠算などを指導したほか、大阪市淀川区にある系列の「塚本幼稚園」と同様に愛国的な教育にも力を入れていた。
近くの主婦(32)は「幼稚園は先生が厳しくて有名だった。籠池園長が園から車で出るときには全ての先生が園の前の歩道に出て、車が見えなくなるまで頭を下げ続けていた。普通の幼稚園では見られない異様な光景だった」と振り返る。
2012年ごろには、塚本幼稚園で教職員らの退職が相次ぎ、人員が不足。登園した園児をスクールバスで開成幼稚園まで片道1時間ほどかけて往復させていたこともあったという。
相前後して、開成幼稚園でも園児の退園や入園児の減少で定員割れが深刻化。14年春に休園となり、現在も再開できておらず、施設が残されたままになっている。
塚本幼稚園の元園児の保護者は「学園が開催する運動会では塚本幼稚園と開成幼稚園の園児が合同で参加していた。数年前から開成幼稚園の園児だけが参加しなくなったが、学園の方からは何も説明がなく不思議に思っていた」と話す。
今年4月に開校をめざしている「瑞穂の國記念小學院」をめぐっては、学園側は借入金のある学校法人でも小学校参入が可能になるよう府に基準改正を要求。12年4月の改正を受けて豊中市の国有地取得を計画し、開成幼稚園の休園直後の14年10月、府に認可を申請していた。
ただ、認可の是非を検討する府の私立学校審議会では同年12月、委員から学園の財務状況について、借入金が資産を超えている点が指摘されており、小学校新設で経営難を脱却しようとしていたとみられる。
開成幼稚園は12年までは「南港さくら幼稚園」として運営。運営法人も「森友学園」ではなく「籠池学園」としていた。
学園の籠池理事長も当時、名を「靖憲」としていたが、現在は「泰典」で、いずれも本名ではなく通名とみられる。
教育関係者は「籠池氏だけでなく、妻の塚本幼稚園副園長も知らない間に別名を名乗るようになった。開成幼稚園では職員の給料未払いなどの問題があったようで、経営失敗のイメージを払拭するためではないかとうわさされていた」と話している。
仕事上とはいえ、名前をコロコロ変えながら教育ビジネスを展開する籠池氏とはどのような人物なのか。
親族や知人によると、籠池氏の自宅は問題の国有地がある大阪府豊中市の閑静な住宅街の一角にある。10年ほど前に2階建ての中古住宅を買い取って改装し、学園が運営する「塚本幼稚園」近くから転居してきた。
「引っ越してきた当初は息子さんもいましたが、今はご夫婦と塚本幼稚園に勤める娘さんが暮らしているようです。奥さんは幼稚園で子供を相手に仕事をしているからか、よく家の外まで大きな声が響いてくる。祝日には玄関先に欠かさず国旗が掲げられているのが印象的です」(近くの主婦)
籠池氏は香川県出身で関西大学に進学後、奈良県庁に入庁。当時は周囲に思想的な発言をすることはなかったが、学園の前理事長の娘と結婚し、運営に参画し始めたころから様子が変わり、前理事長が他界した1995年ごろからは園児に「教育勅語」を朗唱させるなどしていった。
妻との間には3男2女をもうけ、園児たちと同様に、自身の子供たちにも幼いころからスポーツに取り組ませるなど熱心に教育していたようだが、近年はとくに息子たちとの関係が疎遠になっているという。籠池氏は幼稚園で園長を名乗るものの、実質的な運営は、副園長の妻に任せ、政治団体の活動などに積極的だったという。問題の小学校「瑞穂の國記念小學院」でも当初、校名を「安倍晋三記念小学校」にしようとし、昭恵夫人を名誉校長に据えるなど、首相夫妻の名を園の運営に利用してきた。
小学校新設のため、園児や卒園児の保護者らにも1口1万円で複数口の寄付を募り、親族や親しい知人にもことあるごとに寄付を募っていたが、多額の援助にも感謝を伝えることはほとんどなかったという。
教育者の名を借りた荒っぽいビジネスマン。そんな横顔が浮かび上がってくる。
たしかに直接、個人的に関係ないのに中傷や偏見を経験するだろうことは想像できる。
転職出来るのなら、転職した人もいるかもしれないし、待遇や給料などを考えると留まる決断をした社員もいるだろう。
多くの社員は中立な立場で考えられないと思うが、東電の対応や説明で、事実を言っているのか、誠意のある対応をしているのかと
感じるのであろうか?東電の利益を優先すると事実を言えない、言い訳をする傾向が高いであろう。しかし、東電側でない人達、まして、
被害を受けた人達から見れば、不誠実で、ずるい人達としか思わないだろう。
だから仕方がない。嫌であれば、東電から離れて関係のない世界や会社で働く選択もある。ただ、いろいろな要素が絡み合っているので
選択肢として選べるかは別の話。何を優先にして、どのような選択があるのかは個々によって違う。
福島第一、第二原子力発電所で事故後も働く東京電力社員の心の傷は、津波や知人を亡くした被災体験よりも、中傷などの批判によるものが根強く残るとする分析結果を、順天堂大学などのチームがまとめた。英医学誌に7日発表する。
チームは、事故直後から現地で社員の心の健康をサポートしてきた。社員1417人に2014年11月まで計4回、震災で受けた心の傷に関する記述式のアンケートを実施。津波からの避難、家族や同僚の死亡、財産喪失などに関するストレスの大きさを分析した。
医療機関で受診を拒否されたり、避難先で住民に問いつめられたりするなどして心に傷を受けた社員は、11年時点で12・8%にあたる181人。事故から3年以上が過ぎても、こうした経験をしていない社員に比べて、約3倍も非常に強いストレスが残っていた。
また、発電所の爆発や同僚の死亡といった現地社員特有の経験によるストレスも、時間が経過しても強く残ることが確認された。
研究をまとめた順天堂大の谷川武教授(公衆衛生学)は、「現地社員の抱えるストレスは大きく、心理面のサポートを考えるべきだ」と話している。
政府は6日の参院予算委員会で、森友学園の国有地取得問題で、学園側が国有地を2016年6月に購入する前の賃貸期間中、賃料の滞納があったことを明らかにした。
辰巳孝太郎氏(共産)が追及。学園は購入前、月額227万5000円で国有地を借り受けていたが、国土交通省の佐藤善信航空局長は「支払期日までに払われなかった月もあった。その後、延滞金も含めて全額支払い済みだ」と語った。一方、参院予算委は6日、国会法に基づき会計検査院に対する検査要請を議決した。【大久保渉】
安倍晋三首相の妻昭恵氏が2014年12月に大阪市の学校法人「森友学園」の幼稚園で行った講演に政府職員が同行していたことが、政府が7日に閣議決定した答弁書で明らかになった。これまでの国会審議では、昭恵氏が15年9月に学園の幼稚園で講演した際の職員同行が確認されている。
民進党の辻元清美衆院議員の質問主意書に対する答弁書によると、14年12月6日と15年9月5日の2回の講演に職員が同行した。公用車は使用していないという。昭恵氏の15年9月5日の講演や、学園が新設予定の小学校の名誉校長就任をめぐる経緯などについては、「特定の個人が行った私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない」とした。
また、民進党の逢坂誠二衆院議員への答弁書では、教育勅語を学校や幼稚園で活用することが教育基本法や学校教育法に違反するかどうかについて、「個別具体的な状況に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難だ」とした。学園の幼稚園では、子どもたちに教育勅語を素読させていることが問題になっている。
問題は補助金がどれだけつぎ込まれるか次第のように思える。
アッキーが名誉校長を務めるはずだった“愛国”小学校を建設中の森友学園が国有地を激安で手に入れた疑惑が連日、国会で取り上げられている。そんな中、「第2の森友疑惑」が急浮上した。
愛媛県今治市議会で3月3日、可決された2016年度補正予算案の内容が、にわかに注目を集めている。
この決定は、今治市内の土地を、新設される岡山理科大獣医学部の用地として無償で譲渡するというもの。広さ16.8ヘクタール、約36億7500万円相当の広大な土地をタダであげ、さらに23年までの学校の総事業費192億円のうち、半分の96億円を市の補助金で負担するという。まさに至れり尽くせりの厚待遇である。
この一件に首を傾げるのは、地元選出の自民党・村上誠一郎衆院議員だ。
「過疎地の今治に大学をつくって採算が合うのか。党獣医師問題議員連盟会長の麻生(太郎)財務相や文教族の大物なんかも当初は認可に反対していたのに、同地が国家戦略特区に選ばれて認可が決まった途端に何も言わなくなった。財務相が反対していた案件がひっくり返るのだから、よほどの『天の声』があったとしか思えない」
事情を調べると、またも安倍首相夫妻の“お友達”人脈が浮かび上がる。
岡山理科大を運営する学校法人加計学園(岡山市)グループは岡山県を中心に全国で大学、専門学校、高校、中学校、小学校、幼稚園など29の教育施設を運営する一大組織。その2代目である加計孝太郎理事長は、安倍首相の40年来の旧友として知られる。日経新聞の「交遊抄」(10年9月21日付)によると、加計氏は安倍首相が大学卒業後に米カリフォルニア州立大ロングビーチ校に語学留学した際に知り合って以来のゴルフ友達だという。
朝日新聞の首相動静からも、親密ぶりがうかがえる。加計氏は13年11月以降の約3年間で安倍首相と14回も面会。昭恵夫人も同席で夕食をとったり、山梨県鳴沢村の安倍首相の別荘に招かれてゴルフをしたりと、家族ぐるみの親密な付き合いであることがわかる。安倍首相は14年5月、加計学園が運営する千葉県内の大学の行事で「どんな時も心の奥でつながっている友人、私と加計さんもまさに腹心の友だ」と語っている。
さらに、最近何かと話題の昭恵氏がここでも登場する。15年9月、昭恵氏は加計学園が運営する認可外保育施設「御影インターナショナルこども園」を訪問し、保護者らを前に名誉園長就任を受けた講演を行っている。どことなく、森友学園問題を連想させるような親密ぶりだ。だが、今治市に新設する大学の認可をめぐる流れを見ると、さまざまな疑問が湧き上がる。
そもそも大学の獣医学部には全国で定員枠があり、学部新設のハードルは高い。
「07年から加計学園の知見もお借りし、規制を解くため国に構造改革特区の設置を提案しましたが、日本獣医師会の反対などもあり、膠着状態でした」(今治市)
長年の膠着状態が急変するのは第2次安倍政権の誕生以後だ。16年11月、安倍首相が議長を務める国家戦略特区諮問会議が「広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り」獣医学部の新設を認めるとの決定を行い、翌17年1月には岡山理科大獣医学部の今治市への誘致がトントン拍子で決定したのだ。
新設に反対してきた日本獣医師会の境政人専務理事はこう不満を口にする。
「今回の国家戦略特区会議やその下の分科会にも私たちは一切呼ばれず、直接意見を述べる機会がなかった。パブリックコメントの募集に対し、反対意見を出しただけです。非常に短い期間で決められてしまった。初めから結論ありきのようで、大変残念でした」
一方、同会議の今治市分科会には前愛媛県知事の加戸守行氏が出席。同氏は「日本会議」関連の行事に出席し、安倍首相が本部長の「教育再生実行会議」の有識者メンバーを八木秀次氏、曽野綾子氏らとともに務めたこともある、首相の「右派人脈」のお仲間である。
政府が特区で獣医学部を設置する事業者を募集したのは17年1月4~11日のたった8日間で、応募したのは加計学園のみ。まるで加計学園のための制度改正だったようにも見える。
ちなみに、加計理事長は政府の決定と時期が近い16年10月2日と12月24日に、安倍夫妻らと夕食を共にしている。今年1月の国家戦略特区諮問会議では首相自らが誇らしげにこう語った。
「1年前に国家戦略特区に指定した今治市で、画期的な事業が実現します。(中略)獣医学部が、来年にも52年ぶりに新設され、新たな感染症対策や先端ライフサイエンス研究を行う獣医師を育成します」
急展開の誘致決定をめぐっては、地元からも疑問の声が上がっている。今治市選出の愛媛県議・福田剛氏(民進党)はこう語る。
「10年も動かなかった話が突然、戦略特区に決まって、来年4月にはもう開校予定だという。あまりに拙速で腑に落ちませんし、政治の力が動いたのかな、とも感じます。タオルと造船の町の今治で岡山の名を冠した獣医学部というのも違和感がありますし、コストパフォーマンスにも疑問がある。補助金には県からの資金も投入されるというので、本格的に調査します」
加計理事長の愛媛県の関係者もこういぶかしむ。
「獣医学部新設の件は農水省に行けば文科省に行け、文科省に行けば農水省に行けとたらい回しにされるような案件。安倍さんと加計さんの近すぎる関係があるから、今回の認可は大丈夫かと逆に心配されてます」
民進党は、この問題も国会で取り上げる構えを見せる。調査チームの福島伸享衆院議員はこう語った。
「募集期間がたった1週間で突然、許可申請を下す手続きは適正なのか。教育関係者はみんな新規に学校をつくりたがっていて、総理に近い人だからつくりやすいということなら大問題です」
今治市企画課は本誌の取材に対し、こう説明する。
「土地の無償譲渡の方針は遅くとも1989年には決まっていた。人口減対策のためで、他の大学とも交渉していた。長い積み重ねがあってのことで、安倍政権だからということではない」
加計学園は取材に対し、「学校用地の取得については法令の手続きに従って適正に行っているところです」と回答した。
(本誌・小泉耕平、村上新太郎、大塚淳史/今西憲之)
※週刊朝日 2017年3月17日号より抜粋
国会では6日も、大阪府の学校法人「森友学園」への国有地売却問題が取り上げられ、安倍総理は、4月開校予定の小学校の名誉校長に就いていた昭恵夫人の道義的な責任に議論が及ぶと強く反論しました。
「森友学園問題、これ調べていくと、はっきり言いまして、えん罪である」(自民党 西田昌司参院議員)
自民党は6日、大阪府の学校法人「森友学園」への国有地売却問題を予算委員会の質疑で初めて取り上げ、国交省や財務省は、ごみの撤去費用8億円の見積もりは一般的な方法で合理的に算出したもので、将来、この土地でどんな問題が起きても国の責任を免除する特約を付けた適正な契約だったと改めて強調しました。
一方、民進党の質疑では、新たな金額が出てきました。
「今、建っている建物(小学校)、国が補助金入れてますね」(民進党 福山哲郎幹事長代理)
森友学園が建設中の小学校は、国交省が行っている建築物の木造化を図るプロジェクトの支援対象となっていますが、これまでに国から5640万円が支出されたことが明らかになりました。
安倍総理は6日も、「私も妻も売却や認可には一切関わっていない。関わっていれば職を辞す」と強調しましたが・・・
「総理が関わっていないという。昭恵夫人も関わっていない。ひょっとしたら被害者なのかもしれない。私もそのようにも考えたいと思います。しかしながら、大阪の財務局の立場でいえば、安倍昭恵夫人が名誉校長に就任している小学校を、手続きができないからといって、先送りなんかして、開校を延長したら、それは昭恵夫人に恥かかせたのか、安倍首相に恥をかかせたのか、近畿財務局だって、財務省だって、忖度(そんたく)するでしょう、それは」(民進党 福山哲郎幹事長代理)
昭恵夫人の行動の道義的な責任を問われると、安倍総理は強く反論しました。
「名誉校長に安倍昭恵という名前があれば、印籠みたいに『恐れ入りました』ってなるはずがないんですよ。それを忖度した事実が、事実がないのにですね、まるで事実があるかのように言うっていうのは、これは典型的な印象操作なんですよ。さんざん福山さんは今、え、しかしね、さんざん今、福山さんは私と妻の名誉を傷つけたわけでありますから。私と妻がここにまるで関わっているかのごとくですね、まるで大きな不正があって、犯罪があったかのごとく言うのはですね、これは大きな間違いでありますから」(安倍首相)
「昭恵夫人は被害者かもしれないと申し上げたんです。犯罪扱いなんかしていません。それこそ印象操作だと私は思いますよ。何そんなにムキになってるんですか?」(民進党 福山哲郎幹事長代理)
また、安倍総理は、その後の質疑の中で、「若干、妻のことだからムキになっているかもしれないが、私や妻が許認可に関わったかのごとく印象を与えるのはどうかと思う。それを前提に質問するのは遺憾だ」と述べました。
大阪市の学校法人「森友学園」が4月に大阪府豊中市に開校を予定する「瑞穂の国記念小学院」の設置認可を巡る問題で、「こういう状況になったので、もう諦めていました」と、4月から「瑞穂の国記念小学院」に子どもを入学させようとしていた会社役員の男性は嘆息する。入学金や制服代などは既に振り込んだが、このまま入学させても子どもの経歴に影響すると考え、別の学校に進ませることにした。
学園が運営する大阪市淀川区の塚本幼稚園に子どもを通わせていたが、問題が相次いで表面化してからは通園させていない。4月からの開校は事実上不可能だが、男性は淡々とこう話した。「何とも思わない。学園のことはもう仕方がない」
2012~13年度、孫が塚本幼稚園に通っていたという大阪市の男性(71)は園の行事で園児が軍歌を歌う様子に違和感を抱いた。小学生にも戦前のような教育をするんじゃないか--。そう懸念していた男性は「開校を認めるべきではない」と考えている。
大阪市の40代女性は子どもを塚本幼稚園に通わせたが、途中で自主的に退園した。園の幹部から「子どもの目つきが悪い」と指摘されるなど嫌がらせを受けたというのが理由だった。女性は「もう教育には携わってほしくない」と突き放した。
「いやあ、ちょっとひどい。ここまでひどい教育機関というのは……」。続出する問題に、松井知事も恨み言を連発した。
2月22日の府私立学校審議会で、愛知県の進学校「海陽中等教育学校」への推薦枠があると説明した学園。ところが海陽側はホームページに事実無根と否定するコメントを掲載した。府も「もう学園は信用できない」として海陽に連絡して、そうした事実がないことを確認した。
設置認可を審査する機関に虚偽の説明をした疑いが強まったが、これで生徒を集めてきたとすれば、信義則に反する。知事はそう強調して「子どもたちもだまされていることになる。教育者としての根幹でもある正直さが全くない」と断じた。
さらに学園は、小学校の校舎と体育館の建築費について、国と府に別の金額を提示していたが、知事は「ダブルスタンダードや」と批判。学園は幼稚園も経営しているが、知事は現に通園している児童に配慮した上で「学園の経営体質を徹底的に見直させてもらう」と強調した。
府私学課は6日、推薦枠の話など一連の問題について、学園に釈明を求めた。対応したのは学園側の代理人弁護士。双方のやり取りは夜まで続いた。午後8時半ごろから、私学課はその内容を記者団に説明したが、担当者は苦渋の表情で「納得できる内容ではない」と話した。
なぜ「推薦枠がある」と説明したのか。代理人は「中等学校の出資企業の役員とそういう方向で話し始めた」などと話したが、私学課がその役員は誰かと問うと、代理人は「教えません。現段階では答えられない」と答えたという。【池田知広、念佛明奈、小林慎】
大阪の学校法人・森友学園が「愛知県の中高一貫校に推薦枠がある」と大阪府に報告したものの学校側が否定していた問題で、森友学園は府に対しコンサルティング会社が誤って載せたと釈明していたことがわかりました。
国有地を評価額の7分の1以下で購入していた学校法人・森友学園は小学校の認可を巡り大阪府に対し「愛知県の中高一貫校・海陽学園に推薦枠を提供してもらうことで合意している」と報告していました。しかし海陽学園側が「事実無根」などと否定したことから府が確認したところ、森友学園は法人が依頼したコンサルティング会社が誤って記載したと釈明し、訂正する意向を示したということです。また森友学園は校舎の建築費について国に対し約21億円と申請し5600万円の補助金を受け取っていましたが、実際には府に示していた7億5600万円だったこともわかりました。
森友学園は多く受け取った補助金は返還すると話しているということです。
毎日放送
私学なので自由度は高いであろう。しかし、今回の疑惑を多くの人が持つような問題を引き起こしたのは学校法人「森友学園」(大阪市)。問題が 注目を受けたらこのような結果になるのは想像できたであろう。
「意外と普通の幼稚園」の意味が分からない。人格形成や思想が定着するまでに反復教育である特定の価値観や思想を繰り返せば、そのまま人格の 一部となる可能性が高いと思う。他国の文化で育った外国人は人間的には悪くないのかもしれない。しかし、育った環境、周りの価値観や思想に より個人の基準がある程度個人の一部となったしまうと他国の文化、価値観そして思想が変だと思うようになる。一部の人達は後の経験や情報で 変わるかもしれないが、多くの人達は簡単には変わらない。そこが問題と思う。そこに、このインタビューに答えた関係者が気づいていない、 又は、故意に触れていないのであれば、やはり「意外と普通の幼稚園」は隠れ蓑としか思えない。
「『土地の問題は、きちんと明らかにすべきだが、子供に罪はなく大人の事情で教育の機会をつぶされるのはふびんだ』。関係者は、こう漏らしている」
「子供に罪はなく」と言っている時点で、関係者達は悪くないと言っているのと同じだと思う。そして、子供を利用した表現だと思う。 もし土地の問題を明らかにするべきだと思うのであれば、はっきりと明らかにしてから言うべきである。実行してから言うべき。
学校法人「森友学園」(大阪市)の国有地取得問題が波紋を呼ぶ中、学園が運営する塚本幼稚園(同市淀川区)の園児のイベント出演が5日、取りやめになった。主催者側によると、園児の心理的負担を考慮したという。国会論戦などでは学園の教育内容の一部分だけを取り上げて批判する意見も出ており、関係者からは「子供に変なレッテルが貼られる」と、不安の声が漏れている。
イベントは、大阪・南港で開かれた「OSAKA防衛・防災フェスティバル2017」(大阪防衛協会主催)。園児が参加して、歌や演奏を披露する予定だったが、急遽(きゅうきょ)、4日に出演の取りやめが決まった。主催者側は「園児への心理的、物理的な諸問題を検討した結果だ」と説明している。
こうした動きに、関係者らは不安を募らせる。長男を幼稚園に通わせていたという40代の女性は「園児らは、出演するために、たくさん練習したはずなのにかわいそうだ」と訴える。
幼稚園では、毎朝の朝礼で教育勅語を朗唱し、君が代を斉唱。国会などでの問題の追及過程では、こうした面を批判的に取り上げる意見が出ている。
ただ、女性は「保守的といわれるが、目上の人へのあいさつの徹底などを評価する保護者は多い。教養を高められ、面接がある小学校受験を視野に入れて通わせる人もいる」と話す。
厳しい教育方針も定評があり、公立学校に進学した際のギャップを懸念し、小学校開校を待望していた保護者もいたという。
幼稚園をめぐっては、園児が「安倍首相がんばれ、安保法制、国会通過よかったです」と宣誓。学園側が「政治的中立性が疑われるような事例で不適切だった」と認め、コンプライアンス室を立ち上げて対策を取るとしている。
関係者は「私学なので一定の裁量はあっていいと思う。宣誓だけが繰り返し報道されると、おかしな子供だと思われ、変なレッテルを貼られる。来てもらえば分かるが、意外と普通の幼稚園なのに…」と不安を口にする。
4月からの小学校開校は厳しいとの見方が、大阪府側からは出ている。「土地の問題は、きちんと明らかにすべきだが、子供に罪はなく大人の事情で教育の機会をつぶされるのはふびんだ」。関係者は、こう漏らしている。
大阪府豊中市の国有地が学校法人「森友学園」(籠池泰典理事長)に格安で払い下げられた問題で、売却交渉が進められた平成25~26年当時、財務省近畿財務局長だった枝広直幹広島県福山市長が4日、「当時、森友学園や籠池氏の名前も知らなかった」と語った。
枝広氏は次の局長に案件を引き継ぐことはなかったと説明。同氏の退任後、近畿財務局は国有地の賃料引き下げやごみ撤去費の差し引きに応じており、枝広氏の後任局長時代に局内で国有地問題が重要案件になった可能性がある。
用地取得を目指していた籠池氏は同時期、鴻池祥肇元防災担当相の事務所に繰り返し陳情。双方の交渉や、財務局とのやりとりなどの経過を記録した事務所の文書についても「事実かどうか分からない」とした上で「この件に関して鴻池先生の(名前が挙がった)記憶もない」と話した。
これぐらいの意識であれば、被害報告がないだけで過去にも同様な行為が行われた事はないのかと思われても仕方がないような発言。
「犯行について『被害者が泥酔していたので良いと思った。罪の意識はなかった』と述べた。」
弁護士が家族にいるのに法的なことについて一切の知識や考えがなかったのだろうか?建前と本音が非常にかけ離れた話題が多かったから、 罪の意識を感じなかったのか?事実は関係者にしかわからない。
教育レベルが低い人達の世界ではありそうなこと。失う代償も高くない。罪の意識はあると思うが、大丈夫とか、捕まらないと思っていると思う。 非行に走った人達は小さいことからある程度の事まで個人の差はあっても何かしら経験している場合が多い。だから今更とか、これぐらいと なると思う。まあ、根性なしなので非行に走った事がないのであくまでも聞いた話のレベル。
千葉大集団強姦で一般的な事件と違うのは医大生であると言う事。
千葉市中央区の飲食店で昨年9月、飲み会で千葉大医学部の男子学生らが20代の女性を乱暴したとされる事件で、集団強姦(ごうかん)罪に問われた同学部5年、山田兼輔被告(23)の第2回公判が1日、千葉地裁(吉村典晃裁判長)で開かれた。被告人質問で山田被告は、飲み会が「セクハラまがいの行為が行われ、乱れた雰囲気だった」と振り返り、犯行について「被害者が泥酔していたので良いと思った。罪の意識はなかった」と述べた。
山田被告は飲み会の参加者に「ワインの一気飲みをけしかけた」といい、自身はいずれも中ジョッキで「ビール2杯とレモンサワーを2~3杯飲み、白ワインをグラスで5~6杯飲んだ。酒に強くないので、つぶれる手前だった」とした。
犯行については、同級生の吉元将也被告(23)=同事件の集団強姦罪で公判中=の行為に触発され「酔って気分が高揚し、自分も良いだろう、被害者が寝ているから覚えていないだろう-と思った。雰囲気に流されやすい弱さが一番の原因。取り返しのつかないことをした」と悔いた。
大阪府豊中市の国有地が学校法人「森友学園」(大阪市)に、国の鑑定評価額を大幅に下回る価格で売却された問題で、大阪府が、同学園が建設している小学校の設置認可の延期を検討していることが2日、関係者の話でわかった。
同学園は買い取った土地に、小学校「瑞穂の国記念小学院」を4月に開校することを予定している。2014年10月に府に認可を申請し、府私立学校審議会(私学審)が15年1月、「開校の準備状況を追って説明する」との条件付きで「認可適当」との答申をしていた。
しかし、今年2月の私学審で、入学予定者が定員を大きく割り込んでいることなどが報告され、経営面などを懸念する声が相次いだ。3月上旬に府が現地で再確認し、同下旬に私学審に報告した上で、決定する予定になっている。
東京都の豊洲市場(江東区)の土壌汚染対策工事を巡り、交渉初期の2001年、土地所有者の東京ガスと都の間で、汚染処理の範囲などについて公になっていない合意があった可能性があることが、都の開示文書や関係者の証言からわかった。土地の売却に慎重だった東ガスとの交渉が一転して加速するきっかけとなったとみられる。
「取扱注意」と記された03年の都と東ガスの交渉記録によると、売却前に広範囲に汚染土壌を除去するよう求める都の担当者に、東ガスの担当者は再三、01年の約束を持ち出して反論した。
「01年7月の『2者間合意』で、土壌汚染対策は今の計画で良い旨確認した」「文書で約束すると文書開示の話もあるからということで、口頭でいろいろ確認させてもらってきた事実もある」(5月29日)
「合意」の詳細は交渉記録に残っていないが、東ガス側は「2者間合意」と「(土壌汚染を巡る)Q&A形式のやりとり」の存在を強く示唆している。
99~01年に都中央卸売市場長だった大矢実氏は、朝日新聞の取材に「2者間合意という文書があるうわさはあった」と明かした。文面は見たことはないというが、関わったのは交渉担当の副知事だった浜渦武生氏と東ガス首脳と話している。
東ガス工場跡地の取得交渉は、当時の石原慎太郎知事が浜渦氏を担当にしてから大きく動いた。開示文書によると、浜渦氏は00年10月、東ガスを訪れ、土地価格や開発者負担について「水面下でやりましょう」と持ちかけ、01年7月には「基本合意」にいたった。「基本合意」に汚染処理を巡る文言はない。
01年以降、何度も土壌汚染がみつかり、都はその度に東ガスと汚染処理の範囲や負担を協議し、最終的に860億円を投じることになる。なぜ、汚染が残る地に市場を造ったのか。石原氏は3日、記者会見し、19、20日には都議会調査特別委員会(百条委員会)の証人喚問で、石原氏と浜渦氏が証言台に立つ。
「2者間合意」などについて、浜渦氏は1日、朝日新聞の取材に「百条委の前に話すことはできない」と話した。(小林恵士、別宮潤一)
朝日新聞社
学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却問題をめぐり、自民党参院議員の鴻池祥肇元防災担当相が1日、東京都内で記者会見した。同学園の籠池(かごいけ)泰典理事長から封筒のようなものを差し出されたことなどを証言し、「あんなの教育者にしたらいかん」「野党頑張れ、(小)学校を作らせたらいかん」などと語った。やり取りは以下の通り。
◇
森友学園の件であらぬ疑いがマスコミの皆さんにあるのではないかと思い、きちんと話をしないといけない。
どんな関係かと言えば、何年前か忘れたが、「講演に来て」と言われて行った。父兄の前で、その時の子供たちの態度が素晴らしいと思った。私の思想と合うと思った。それから(籠池氏には)会っていないが、神戸事務所に出入りするようになった。鴻池の事務所は金融、不動産、大嫌いで、29年、30年やったことがない。しかし、なんかそういうことで依頼に来た。「うちは不動産屋違うぞ」と、報告あったからね。「不動産屋と違いますからね」と言って断ったみたい。
でも、「どうしても会いたい」と言って、3年前の4月、委員会をちょっと失礼して、質問していない一委員でしたから、(議員)会館事務所に戻って会った。夫婦で来ていたように思う。籠池さんと奥さんと。その時、財務省か大蔵省かようわからんが、「お願いの儀がある」というようなことをちらっと聞いた。同時に紙に入ったものを「これでお願いします」と言った。おばはんのほうが。
一瞬で「金だ」とわかった。だからそれを取って、「無礼者」と言った。「男の面を銭ではたく、政治家の面を銭ではたくのは教育者違う。帰れ」と言って私は委員会室に戻った。それが、カネか、コンニャクだったか、天ぷらか、ういろうか、知らん。確かめてへんのだから。しかし現実として、私が手に持って投げ返した。
その後、出入り禁止やん、当然。ところが、報告やなんかで1、2回(籠池氏は)行ったみたいやね。神戸の事務所に。僕は思いましたよ。「クソっ」と思って、すぐに投げ返した。歩きながら、人生でこんな汚物を投げられたようなことは初めてだけれども、反省しよう、と。それは俺に貫禄と徳がなかったのだと。「こいつならカネで動くかもしれない」と思われたということが、腹が立ったけど、これが俺が徳がない。ずっと黙っておったが、この問題や。
野党のある男が関係しているよ…
暴力団組長をめぐる京都府立医大付属病院(京都市上京区)の虚偽診断書類作成事件で、組長の主治医(44)が京都府警の任意の事情聴取に対し、「病院長の指示で事実と異なる内容を書いた」と話していることが関係者への取材でわかった。主治医は2月、虚偽書類の作成を否定するコメントを発表していたが、一転、関与を認めたという。府警は容疑を裏付ける重要な証言とみている。
組長は、恐喝罪などで懲役8年の実刑判決が確定した指定暴力団・山口組の直系組織「淡海(おうみ)一家」総長の高山義友希(よしゆき)受刑者(60)。主治医は吉村了勇(のりお)病院長(64)らと2014年7月、組長の腎移植手術を担当した。術後の状態について「収監に耐えられない」とする診断内容の報告書を大阪高検に提出した。
府警は診断内容が虚偽だったとみて、府立医大病院などを2月14日に虚偽有印公文書作成・同行使容疑などで家宅捜索したが、吉村病院長は同16日の記者会見などで「刑事施設では感染症にかかる危険性が高かった」と診断の正当性を強調。主治医も同23日に発表したコメントで「(病院長とも)相談のうえ、拘禁に耐えられないとの回答書を作成した。回答内容に一切虚偽はない」としていた。
一方、捜査関係者によると、主治医は昨年10月にも府警に対し、虚偽書類の作成と病院長の指示を認める供述をしたとされる。吉村病院長は現在も指示などを認めていないといい、府警が慎重に捜査を進めている。
学校法人「森友学園」への国有地売却問題をめぐり、国土交通省は1日の参院予算委員会で、土地の鑑定価格からの値引きの根拠となったごみの撤去費を約8億円と積算した同省大阪航空局について、「(過去に)ごみの撤去費を算定したことはない」と積算実績がなかったことを認めた。民進党の藤末健三氏の質問に、佐藤善信・本省航空局長が答えた。
藤末氏は「常識的に専門家に委託するのではないか」と尋ねたが、佐藤航空局長は「小学校開校の予定時期が迫っている中、第三者に依頼をしていると、入札手続き等、時間を要することから(近畿)財務局から依頼があった」と説明。積算の知見の有無も問われたが、「大阪航空局の職員は公共事業の仕事を通して、国交省全体の知見を蓄積している」と述べた。
一方、自民、公明両党の幹事長、国会対策委員長は1日午前、都内で会談し、森友学園を巡る問題について、政府を中心に説明責任を果たすよう求める考えで一致した。自民の竹下亘国対委員長は「色々な問題が指摘をされ、役所なり学園側なりにしっかりと答えてもらいたい。我々も本当のところがよく分からない部分がある」と記者団に語った。(南彰)
朝日新聞社
学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地払い下げ問題に関し、財務省の佐川宣寿理財局長は28日の参院予算委員会で、同地売却前の昨年3月、理財局の担当者が同法人の籠池泰典理事長と面会していたことを明らかにした。
財務省はこれまで、国有地売却に至るまでの面会などの交渉記録は廃棄済みと説明してきた。民進党の小川勝也参院幹事長らへの答弁。
安倍晋三首相は森友学園について、第1次安倍内閣退陣後に昭恵夫人を介して知ったと説明。「籠池氏と個人的関係は全くない」と強調した。同法人が同地で今春開校する小学校建設のため、安倍晋三記念小学校名で寄付金を募っていたことに関しては、「寄付金集めにも全く関わっていない。(名前の使用を)断った以上、責任の取りようがない」と述べた。
一方、森友学園の教育方針については、名誉校長を務めていた昭恵夫人から話を聞き、「しつけ等をしっかりしているところに共鳴した」とも語った。
民進党の舟山康江氏は、学園が運営する塚本幼稚園(大阪市)のPTA収支決算報告書に、昭恵夫人に対する「社会教育費」名の支出があると指摘。講演料などの報酬は全く受け取っていないとする首相答弁との整合性をただしたが、首相は「全く承知していない」と述べるにとどめた。
安倍首相は2月27日の衆院予算委員会で、民進党・福島のぶゆき議員から出た「この安倍昭恵夫人は、名誉校長としてなんらかの報酬を貰っていたんでしょうか? また、何度か講演に行っているようでありますけども、そのときに講演料というのはどのくらい受け取っているのでしょうか?」という質問に対し
「えー、報酬も講演料もまったく受け取っていないと、聞いております」
と、答弁した。再度確認するが、やはり安倍首相の答弁は
「えー、報酬も講演料もまったく受け取っていないと、聞いております」
であり、昭恵夫人が森友学園の経営する塚本幼稚園から、講演料を受け取っていないと言明している。
しかしこれはどう言うことだろう?
この写真は、塚本幼稚園PTAの決算書だ。40万円の支出のある「社会教育費」科目の摘要欄に「6/21姫路城(親子遠足) 11/26京都御所(社会見学)」と言う記述に続き、「社会講座 7/11谷川浩司先生 9/5首相夫人安倍昭恵先生」との記述がある。
40万の支出のうち、遠足・社会見学と社会講座の費用がどのように振り分けらているのかこの決算書からは読み取れない。しかし、日付の並びから、遠足や社会見学の費用と「社会講座」なる活動の費用は「別」と考えられていることが見て取れるだろう。社会講座 7/11谷川浩司先生 9/5首相夫人安倍昭恵先生」なる記述からは、谷川浩司氏と安倍昭恵氏にいくばくかの金銭が渡されていたとしか読み取りようがない。
となると、安倍首相の答弁は虚偽答弁と言うことになる。少なくとも、「受け取っていない」とは、この決算書が有る限り、断言できないはずだ。
本件を含め、事実関係を塚本幼稚園に確認するため、連日取材依頼を行なっているが、今の所塚本幼稚園からの返答はない。
名誉校長を辞任したとはいえ、昭恵夫人と森友学園の関係については、今後も徹底した検証がくわえられるべきだろう。
<文/菅野完(Twitter ID:@noiehoie)>
小学校建設のため大阪市の学校法人「森友学園」に売却された大阪府豊中市の国有地を巡る問題で、府が2012年、学園側の要望を受けて私立小学校設置認可基準を緩和していたことが、27日分かった。幼稚園しか設置していない学校法人が、小学校の開設に借入金を充てることを容認する内容。基準の緩和後、小学校認可の申請は森友学園の1件だけだが、現在も財務面での不安を解消できない異例の展開をたどっている。
府は、森友学園が借入金を学校開設に充てているかは明らかにしていないが、14年12月に開かれた府私立学校審議会の議事録によると、学園の財務状況について委員から「借り入れが今持っているものよりオーバーしている」と指摘されていた。また、今月22日にあった私学審の臨時会では、入学希望者が定員の半数程度にとどまっていることが報告され、学園の財務状況を懸念する声が出た。
府私学課によると、森友学園の籠池泰典理事長が11年ごろ、小学校や中学校などを設置済みの学校法人にしか借入金による小学校設置が認められていないことを問題視し、府に見直しを要望した。府は12年1月に府民から意見を募集し、同4月1日に基準を改正。幼稚園のみを設置していた同学園は14年10月、府に小学校設置認可を申請した。
従来の基準は、小規模な幼稚園しか設置していない学校法人は資金繰りに問題が生じる可能性が比較的高いとして設けられていた。私学課は「同様の要件を設けている都道府県がほとんどなく、合理的でないと判断した」と説明。森友学園の他に同様の要望はなかった。
教育の規制緩和を進めていた府側の意向と一致した形となったが、松井一郎知事は25日、自身のツイッターで「新規参入を促し競争による質向上を目指して高いハードルを他府県並みに引き下げたまでだ」と説明した。また、取材に対し、籠池理事長と「会ったことはない」と話している。【青木純】
暴力団組長をめぐる京都府立医大付属病院(京都市上京区)の虚偽診断書類作成事件で、組長との交際などを理由に大学の評議会から辞任の勧告を受けた吉川敏一学長(69)が27日午前、辞任を拒否する意向を大学側に正式に伝えることが大学関係者らへの取材でわかった。これを受け、評議会が改めて学長解任を請求し、「学長選考会議」(委員6人)で審議されるが、関係者によると、解任に否定的な声は少なく、吉川学長は退任に追い込まれる可能性が高い。
組長は、指定暴力団・山口組の直系組織「淡海(おうみ)一家」総長の高山義友希(よしゆき)受刑者(60)。捜査関係者らによると、吉川学長と京都市の繁華街で会食している姿がたびたび目撃されていた。一連の報道を受け、重要事項を審議する教育研究評議会は24日、「大学に対する府民の信頼が大きく損なわれている」などとして吉川学長に全会一致で辞任を勧告し、27日正午までの回答を求めた。
勧告を受けた吉川学長は24日に報道各社に対しコメントを発表。高山受刑者と「特別に親密な関係にあるわけではない」「飲食店で偶然2度ほどあった」などとし、「私の行動が学長を辞任するに値するほどのものか疑問を持っている」との考えを示していた。学長の代理人弁護士によると、改めて辞任しない考えを27日午前に回答する。
評議会は、吉川学長から辞任拒否の回答が届けば、学長人事の権限を持つ学長選考会議に解任を請求する方針を既に決めている。選考会議で、吉川学長は自身の見解を述べる意向を示しているが、会議の委員からも道義的責任を問う声が上がる見込み。委員の過半数が賛成すれば解任が決議される。ある大学関係者は「自ら辞職しない限り、解任に追い込まれる可能性が高い」と指摘する。
大学を運営する府公立大学法人の長尾真理事長が解任を最終決定するが、理事長も会議の決議を尊重するとみられ、吉川学長の退任は避けられない情勢だ。
ここまで来たら多くの都民や国民はもう東京都職員達を簡単には信用しないだろう。善人ぶった詐欺師のような職員や偽善者が存在する事は証明された に近い状態だと思う。
関係者や関与してしまった人間達は問題をはぐらかそうとするし、覚えていないと嘘を付くかもしれない。関与した職員達が妨害したり、抵抗したりするから 本当の調査はなかなか進まないだろう。関与した東京都職員達の抵抗は既に明らかだ。だからこそ、不信を持った都民や国民の小池百合子都知事への 評価は上がる。これまで誰も出来なかったパンドラの箱を開いたからだ。
■小池百合子は総理の器にあらず 「石原慎太郎」独占インタビュー第一弾(上)
喧嘩殺法で向かうところ敵ナシの小池百合子都知事(64)。都議会制覇に、女性初の総理大臣と夢は膨らむが、小池劇場に引っ張り出された「元都知事」も黙っちゃいない。因縁の敵・石原慎太郎氏(84)が逆襲に転じた。
***
「小池知事には、豊洲の『安心』と『安全』をごちゃ混ぜにして不安ばかりを煽り、問題を宙ぶらりんにしてしまった責任があると思う」
石原慎太郎氏が語気を強めるのも無理はなかろう。今月5日投開票の千代田区長選で、小池百合子都知事の支援した現職の石川雅己氏は、自民推薦の候補にトリプルスコアの大差をつけて圧勝。その余勢を駆って都庁の「おんな城主」は、
〈「記憶にありません」と逃げる姿勢を見せることは、それも国民の方がしっかりご覧になるだろうと思います〉(知事定例会見・2月10日)
などと、次なるターゲットである石原氏への攻勢を強めている。
「小池知事は『石原さんは逃げ回っている』と言うけれど、これは私にとって一番嫌な言葉なんだ。個人的な動機かもしれないが、やはり、その屈辱を晴らしたいという思いはある。
しかも、全く正確さを欠く表現です。私は月刊『文藝春秋』(昨年12月号)で、東京都との文書での質疑応答の全文に、自らの見解を添えて公表している。それは当時、都側が私の回答を全文公表していなかったからです。都議会の特別委員会でも、きちんと話をさせてもらいたいと考えていますよ」
■「とにかく豊洲ありきだった」
「そもそも、築地市場の豊洲への移転は、私が知事に就任した1999年4月の時点で既定路線となっていました。先代の青島(幸男)君からの『引き継ぎ事項』があって、そのなかに豊洲移転に関する項目も含まれていたと思う。都庁の各担当部局には当時の資料が残されているでしょうから、ぜひ確認してもらいたい。
私自身は市場を移すにしても、豊洲のような海沿いの場所に候補地を限定する必要はないと考えていた。たとえば、フランスのパリ郊外には、生鮮食品を扱う市場として世界最大級のランジス市場があって、トラックで運び込んだ海産物を扱っているわけです。東京にも環状線の沿線に広い土地はあるし、利便性が確保されれば三多摩地区でも構わないんじゃないか。そう言ったけれど、都庁の各担当部局の職員は『それではダメです』の一点張り。とにかく豊洲ありきだった。つまり、総合的な判断により豊洲移転への機運は私の就任前に既に整っていたと認識している。
無論、築地市場は老朽化して、冷暖房の整備も覚束ないため衛生面の不安も残る。それに、工期・工費そして、アスベスト問題もある。市場として存続させるのが好ましくないというのは、全くその通りだと思いました。
そこで、福永正通副知事(当時)が、豊洲の土地を所有する東京ガスとの取得交渉に当たったわけです。彼は温和な性格でね。ただ、なかなか議論が前に進まなかったようで、リリーフとして濱渦(武生特別秘書、後に副知事)に一任することにしたのです。
私の知事就任当初、都は借金が膨れ上がって財政再建団体に転落寸前。職員の歳費カットが急務だったところ、当時の組合委員長を説得したのが濱渦だった。実際、この歳費カットが実を結び、3年間で大幅な財政再建を進めることができた。それほどの『タフネゴシエイター』だから、東京ガスとの交渉も彼に委ねたのです。その結果、豊洲移転を巡る最初の合意にまで漕ぎ着けることができたのでしょう。
その間の交渉内容については、彼に一任していたから微細な報告は受けていません。ただ、確かに土壌の汚染についての議論はあったと記憶しています。移転関連費を盛り込んだ予算案を巡っては都議会も紛糾して、63対62という僅差で可決された経緯もある。
そのため、都の幹部が『議会の承認が得られたので裁可をお願いします』と言ってきた際、私は『汚染の問題があるようだけど、本当に大丈夫なのか』と尋ねています。
その時、都の幹部は『いまの日本の技術をもってすれば問題ありません』と答えた。
また、ここに来て浮上している『瑕疵担保責任の放棄』については、私も問題だと思う。一般的な不動産の売買契約においても、やはり売り手側の瑕疵担保責任は問われるべきものだから。とはいえ、なぜ免責されるに至ったかについての報告は私まで届いていないし、濱渦も分からないと言う。そこは都庁の責任で、審議会の記録などを精査して明らかにしてもらいたいと思います」
■「厚化粧の大年増には…」
当初4000億円弱とされた豊洲新市場の整備費用は、およそ6000億円に膨れ上がっている。都政担当記者によれば、「施設の建設費と、土壌汚染対策費が嵩んだことも一因です。なかでも、石原氏の元秘書が専務執行役員を務める鹿島は多くの工事を受注していた。しかも、その大半で応札率は90%を超えている」。談合疑惑が囁かれたこの件について、石原氏はこう語る。
「元秘書を通じて口利きした事実はありませんし、そんなことができる時代ではない。しかも、施設の入札が行われたのは私が知事を辞職してから」
一方、小池氏も「黒い噂」と無縁ではない。石原氏は「小池知事の疑惑に口を出すつもりはない」と言うが、小誌(「週刊新潮」)でも、彼女の金庫番を務めてきた元秘書に絡む不透明な不動産取引や、闇金業者から便宜を図られた疑惑を報じてきた。
「今回の都知事選でも、彼女の対抗馬だった増田(寛也)君の応援に回りました。彼には岩手県立大学の学長だった西澤潤一さんを首都大学東京の学長に迎える際に仲介役になってもらった。それで、増田君の応援に呼ばれた時に、思わず余計なひと言が出ちゃったんだ。『厚化粧の大年増には困ったもんだ』というね。これは本当によくなかった。やはり女性の化粧のことは言っちゃいけない」
***
「石原慎太郎」独占インタビュー第一弾(下)へつづく
特集「『石原慎太郎』独占インタビュー70分! 『小池百合子は総理の器にあらず』」より
「週刊新潮」2017年2月23日号 掲載
新潮社
学校法人「森友学園」が購入した大阪の国有地をめぐる疑惑。10億円級の土地ですが、学園側が支払っていたのは実質200万円。この土地にできる小学校の名誉校長は安倍晋三首相の妻、昭恵さんです。【BuzzFeed Japan / 籏智広太】
この土地には4月、森友学園が運営する「瑞穂の國記念小學院」が開校します。「日本初で唯一の神道小学校」だそうです。
この小学校のサイトの「ごあいさつ」の欄には、昭恵さんが「名誉校長」として、顔写真とあいさつ文が掲載されていました。
しかし、それが2月23日までに、削除されていました。
たしかに、丸ごと削除されていることがわかります。
現段階であいさつが残っているのは、校長の籠池泰典氏(森友学園理事長)のもの。政権に近く、改憲を目指す保守団体「日本会議」の大阪支部役員です。
また、衆議院議員の平沼赳夫氏の言葉も残っています。
ただ、サイトの「ソースコード」を覗いてみると。
指定した範囲をブラウザに表示させないことができる「!--」というタグを使って、見えないようにしていただけでした。削除ではありません。
2月24日午前0時現在、もともと掲載されていた昭恵氏の顔写真もサーバーに残っています。
「削除」された昭恵氏のあいさつには、こんなことが書かれていました。
“籠池先生の教育に対する熱き思いに感銘を受け、このたび名誉校長に就任させていただきました。
瑞穂の國記念小學院は、優れた道徳教育を基として、日本人としての誇りを持つ、芯の通った子どもを育てます。
そこで備わった「やる気」や「達成感」、「プライド」や「勇気」が、子ども達の未来で大きく花開き、其々が日本のリーダーとして国際社会で活躍してくれることを期待しております“
なぜ、突如として「!-」のタグが使われたのか、説明は掲載されていません。
森友学園の不明瞭な土地取引については、昭恵さんが名誉校長だったこともあり、政治家ぐるみの疑いの声が高まっていました。そうした疑念を配慮したのかもしれません。
週刊ポスト(3月3日号)には、「安倍夫妻と日本会議と私の関係」という特集が組まれています。
インタビューに応じている森友学園の籠池泰典理事長は、昭恵氏について「3~4回ほど幼稚園に来ていただきました」と語っています。
森友学園は海外メディアが注目する「塚本幼稚園」も運営していて、籠池理事長はその園長。
この幼稚園は、園児に教育勅語を暗唱させることなどで知られています。
テレビ東京が2月17日に報じた映像では、昭恵氏がこの幼稚園で講演を開き、その教育方針を肯定するあいさつしていることが、明らかになりました。
籠池氏は前出のポストのインタビューで、小学校の名称を当初「安倍晋三記念小学校」として寄付を募っていたことを認め、こうも語っています。
「学校名に安倍さんの名前を冠することは、総理(自民党総裁)になる前に、昭恵夫人を通じて内諾をいただいたんです」
一方、安倍首相は2月17日の衆院予算委員会で、売買との関与をこう否定しています。
「妻が名誉校長になっているのは承知している。私や妻が(売却に)関係していたとなれば、首相も国会議員も辞める」
BuzzFeed Newsは、今後もこの疑惑に関する取材を継続します。
情報をお持ちの方は、BuzzFeed Japanのニュースチーム(japan-report@buzzfeed.com)までご連絡ください。
大阪市の学校法人「森友学園」が小学校用地として取得した国有地の取引の異例さが際立っている。24日の衆院予算委員会では、開校時期や財務状況に配慮した前例のない手続きが明らかになり、野党は「政治家が関与していると国民が疑念を持つ」と批判した。焦点は大阪府豊中市の土地の鑑定額9億5600万円から、ごみ撤去費など8億2200万円を減額した財務省の裁量だ。【光田宗義】
問題の国有地は約8770平方メートル。近くの伊丹空港の騒音対策区域だったが、航空機の性能向上で役割が終わり、2013年に売却先を公募。森友学園が手を挙げた。
審議での焦点の一つは、減額算定した約8億円に相当するごみの撤去が実際に行われたかを、政府として確認する必要がない、とする政府側の答弁だ。
財務省の佐川宣寿理財局長は24日の答弁で「新たにどんな地下埋設物が出てくるか分からない中、土地の売買契約で『隠れた瑕疵(かし)』(想定外のごみ)も含め免責する、という特約付きで適正に時価を反映した」と説明。「どう撤去したか確認する契約上の義務はない。学校建設の中でどういう状況になっているかは学校側の経営判断だ」と答弁した。
野党は猛反発する。民進党の玉木雄一郎氏は「8億円ディスカウントしておいて、ダンプで(ごみを)運び出す作業をしているかは知らないし、調べる義務もない、という答えだ」と批判した。
売買契約、類例少なく
売却前の賃貸契約も異例だ。23日の質疑で佐川局長は、売却を前提にした「買い受け特約付きの定期借地契約」と呼ばれる契約事例が、過去に2例しかなかったと答弁。財務省の事務処理要領に基づくもので、(1)その後の買い受けが確実(2)賃貸借契約をすることがやむを得ないと財務局長らが認める--との要件を満たしたと説明している。
さらに24日の質疑では、土地代金の分割払いを認めて当面の支払額を年額約1100万円とし、賃貸時と同額程度に抑えた今回の取引の前例がなかったことも分かった。
佐川局長は「建設途中で新たな埋設物が出た事例はなく、(学園の)財務状況を勘案して分割払いにした。初めてだ」と認めた。
前例ない国直接算定
23日の質疑では、大阪航空局が行った約8億円の減額算定に関し、国が直接算定した前例がなかったことも判明。佐川局長が「今のところ(同様の)事例は確認できなかった」と明かした。
また、佐川局長は24日の答弁で、学園側の要望に沿ったと説明。「(新たにごみが確認された)昨年3月から今年4月の開校まで1年で、国が全部撤去すると入札が必要だ。先方は『待てない。撤去費用を控除した値段で買って、(ごみ)撤去も建設も(自分で)して一気にやりたい』という意向だった」と明らかにした。こうした手続きには「普通は不動産鑑定士ら第三者に頼む」(日本維新の会の足立康史氏)などの批判が出た。
200万円で実質取得?
また、売却前の昨年4月に政府が学園側にごみの撤去費用として約1億3200万円を支払っていたことも野党は問題視している。政府の調査で判明したヒ素や鉛による土壌汚染と地下ごみに関し、学園側は土地取得前の借地契約の段階で独自に撤去や除染を行い、その費用を後で受け取った。民進の玉木氏は24日の質疑で「1億3400万円の土地代金との差額の約200万円で土地を手に入れている」と指摘した。これに対し、佐川局長は「性質が異なり、比較して計算するのは適当ではない」と反論した。
教育勅語を朗唱
森友学園が運営する幼稚園は、戦前の教育勅語を唱和させる独特の教育内容で知られ、差別的発言の疑いがある言動には懸念が出ている。
学園が運営する「塚本幼稚園」(大阪市淀川区)のホームページ(HP)には「毎朝の朝礼において、教育勅語の朗唱、国歌“君が代”を斉唱します」とある。右派論客を招いた教育講演会にも力を入れている。
幼稚園の保護者への配布文書に「よこしまな考え方を持った在日韓国人や支那人」などと記載していたことや、HPで一時、元保護者とのトラブルに関連して「韓国・中国人等の元不良保護者」と表現していたことが分かり、府が1月、籠池泰典理事長から事情聴取。その後、HPの表現は削除された。
府私立学校審議会の22日の会合では委員から文書配布の件で懸念が出たほか、23日の衆院予算委員会では民進党の今井雅人議員が、園から「私は差別をしておりません。ですが心中、韓国人と中国人は嫌いです」との内容の手紙を保護者が受け取ったことを紹介した。
元園児の保護者からは訴訟も起きており、保護者らは元園児は幼稚園の職員から「犬臭い」と非難され、「犬を処分しなさい」と言われたと主張している。【武内彩、湯谷茂樹】
大阪市の学校法人「森友学園」が小学校用地として大阪府豊中市の国有地を鑑定額より大幅に安く取得した問題を巡り、民進党の玉木雄一郎氏は24日の衆院予算委員会で、土木業者の証言を基に、建設現場から掘り出したごみの一部が敷地内に埋め戻されたのではないかと改めて追及した。財務省の佐川宣寿理財局長は「契約上、確認する義務はない」と答弁した。一方、国有財産を管理する財務省近畿財務局が学園側との交渉記録を既に廃棄したことも明らかになった。
玉木氏によると、業者は昨年11月から12月まで約2週間、建設現場で作業。掘り出した約2000立方メートルの汚染土のうち半分程度しか敷地外に搬出せず、残りは運動場予定地に埋め戻したという。
この業者は毎日新聞の取材に対し、建設現場には生活ごみなどが交じった土が山積みになっていたと語り、「発注元の指示で敷地内に穴を掘り、その土を埋めた」と証言した。ごみは空になったしょうゆやマヨネーズの容器、靴、衣類などだった。土はアンモニアのような異臭を放ち、食事はのどを通らなかったとも説明した。
大阪府の松井一郎知事は24日、こうした処理が適正だったかどうか、調査権限のある豊中市に事実確認を求める考えを示した。
また共産党の宮本岳志氏は24日の衆院予算委で、2015年9月4日午前10時から正午にかけて近畿財務局9階の会議室で、同局幹部が森友学園と撤去費用などを具体的に議論したという独自の調査結果を示した。
佐川氏は「一般的に随意契約をする場合にはいろいろな会議を開く」と会合があったかどうかを明言せず、「近畿財務局と森友学園の交渉記録はなかった」と答弁した。
財務省の行政文書管理規則によると、面会などの記録の保存期間は1年未満で、事案の終了時に廃棄するという。佐川氏は「16年6月の売買契約締結で事案は終了したので、記録は残っていない」と説明した。菅義偉官房長官は記者会見で「著しい弊害があれば見直す必要があるが、そこについてはなかった」と述べ、近畿財務局の対応に問題はないとの見解を示した。【光田宗義、藤顕一郎、津久井達】
森友学園の小学校用地として売却された大阪府豊中市の国有地を巡る問題で、地下のごみ処理に関わったという関西地方の土木業の男性が24日、毎日新聞の取材に応じた。建設用地には生活ごみなどが混じった土が山積みになっていたといい、男性は「敷地内に穴を掘り、その土を埋めた」と証言した。
この証言は国会審議で取り上げられ、国側は産業廃棄物として撤去費を見積もったと明らかにした。
男性は昨年11月、知り合いの業者に紹介され、建設現場に出入りするようになった。校舎は既に建ちつつあり、敷地南側に約2000立方メートルの土が山積みで、空になったしょうゆやマヨネーズの容器、靴、衣類などが混じっていた。発注元の業者からの指示で、周囲の地面を2~3メートル掘っては土を埋める作業を繰り返したという。
ごみが混じった土はアンモニアのような強い異臭を放ち、昼食などはのどを通らなかったという。男性は「子供が遊ぶ場所で問題だと思った」と語った。
大阪府の松井一郎知事は24日、調査権限のある豊中市に事実確認を求める考えを示した。府は学園に確認したが「工事で出たごみを埋め戻すなんてあり得ない」と否定したという。豊中市は「掘り起こして調査する予定はないが、速やかに業者に処理状況を確認したい」としている。
府私学課は「今の状況で問題ないと言い切るのは難しい」としており、松井氏は「認可権限は教育長にある」とした上で「入学希望者が別の学校に行く手続きができる時期に、答えを出すことになるだろう」と話し、開校認可の先送りや不認可の可能性に言及した。
また、安倍晋三首相が24日の予算委で、学園が寄付金を集める際に「安倍晋三記念小学校」の名称を使用していたことに不快感を示したが、松井氏は「首相の発言が認可に直結することはない。ごみ処理が適切か、学校運営の財務状況はどうなのかを冷静に判断すべきだ」と強調した。【藤顕一郎、津久井達、青木純】
大阪府豊中市内の国有地が近隣国有地の約1割の価格で学校法人「森友学園」(大阪市)に小学校用地として売却された問題に絡み、稲田朋美防衛相は23日の衆院予算委員会分科会で、同学園の籠池泰典理事長に防衛相感謝状を贈ったことを明らかにした。そのうえで、同学園が差別的な表現を記した文書を保護者に配布していたことなどを受け、取り消しを検討する考えを示した。
民進党の辻元清美氏が、同学園が運営する大阪市内の幼稚園で在日韓国人らに対する差別的な表現を記した文書を保護者に配布していたことを指摘。感謝状贈呈について再考を求めたことに対し、「事実関係を踏まえ、取り消すことも含めて適切に対応してまいる」と答えた。
稲田氏によると、稲田氏は昨年10月22日に「交流等を通じて防衛基盤の育成と自衛隊員の士気高揚に貢献した」との理由で籠池氏に感謝状を贈った。稲田氏は籠池氏と面識があることを認めたが、差別的な表現を記した文書などについては「認識していない」と説明した。(南彰)
日立と東芝、歴代社長の出身学部は?
連日、東芝 <6502> の経営危機が報じられていますが、あらためて経営トップの重要性というものを多くの方が実感されているのではないかと思います。そうした中、時折耳にするのは「メーカーは文系出身者が経営トップになると振るわなくなる」という都市伝説のような俗説です。
実際、東芝の経営危機の発端とされるウエスチング・ハウス社の買収時の社長であった西田厚聰氏は、早稲田大学第一政経学部出身の文系社長でした。
とはいえ、東芝は創業から142年、東芝の前身である東京電気と芝浦製作所が合併して東京芝浦電気(1984年に現在の東芝に改称)になってからでも78年の長い歴史を持つ会社です。今回は歴史をさかのぼり、また同業の日立製作所 <6501> と比較することで、この「俗説」の信ぴょう性を確認できるのではないかと考え、検証してみました。
東芝のトップには文系が多く、日立は全員が理系
まず、東芝の結果から見てみましょう。1939年に東京芝浦電気が発足後、現在の社長である綱川智氏は19代目の社長となりますが、このうち経歴が確認できなかった1人を除くと、理系社長は7人、文系社長は11人と、文系社長のほうが多いという結果になります。
一方、日立は創業社長である小平浪平氏から数えて現在の社長の東原敏昭氏は11代目の社長となりますが、この間、全員が理系出身者でした。
ちなみに、両社には社長の在任期間でも大きな違いが見られます。単純計算では、東芝は約4年(1939年から現在までの78年間÷19人)、日立は約8年(1928年から2017年までの89年÷11人)と、2倍もの開きがあるのです。それだけ、日立のほうが長期政権の社長が多く、東芝は社長の入れ替わりが頻繁であったということになります。
このように、歴代社長の出身学部と在任期間だけを見ても、同じ重電メーカーではあるものの東芝と日立には大きな違いがあることがわかります。
大切なことは経営者の資質
このように、現在の東芝の置かれている状況を見る限り、冒頭で述べた「俗説」が当てはまるように見えます。とはいえ、理系社長であればメーカーは良くなるという単純な話ではないことには注意が必要です。
実際、東芝の綱川現社長や、昨年6月に退任した前社長の室町正志氏も理系ですが、これまでのところ東芝を立て直すことには成功していません。
また、言うまでもなく、技術に優れていてもそれが必ずしもビジネスの成功には結びつかないように、理系社長であればこれからも日立は安泰だということでもありません。つまり、出身学部が文系か理系かということではなく、あくまでも「優秀な経営者」であるかどうかが最も大切なポイントです。
また、変化が激しい時代であるため、歴史の長い会社であればあるほど過去にとらわれ過ぎないことも重要です。日立でも、わずか1年という短さで社長を退任した川村隆氏の存在があってこそ経営改革に成功したことは忘れるべきではないでしょう。
まとめ
いかがでしたか。社長の出身学部、在任期間という切り口からだけでも、それぞれの会社に特色があることがご理解いただけたかと思います。
ただし、繰り返しになりますが、個人投資家、ビジネスマン、就活生などのいずれにおいても、会社を見極めるうえで最も大事なことは、その会社のトップが経営者として優れているかどうかであって、理系か文系か、長期政権か短期政権かではないことを強調しておきたいと思います。
本当に「悪い習慣」が原因であれば、役員の降格や人事の見直しで解決できる可能性はあるが、「悪い習慣」と赤字問題が存在するのであれば、問題を解決するのは かなり困難だと思う。 つくばエクスプレス線を運営する「首都圏新都市鉄道」(東京都の将来は暗いと思う。
つくばエクスプレス線を運営する「首都圏新都市鉄道」(東京都)が実施した調査の結果、複数の幹部が安全確認のために行う駅構内の巡回をしていないのに「巡回した」と虚偽報告をしていたことが21日、同社への取材で分かった。巡回していれば防ぐことができた可能性のあるミスもあり、同社は「悪い慣習があった」として再発防止策を講じる方針だ。
同社が1月、駅の助役ら駅幹部約30人のうち半数程度を対象に聞き取り調査をしたところ、うち過半数が「巡回していないのに巡回したと記録簿に記載したことがある」と答えた。
守谷駅(茨城県守谷市)担当の駅幹部は、勤務ダイヤで4回巡回するように定められていたにもかかわらず1回しか巡回しなかったが、記録簿には4回とも巡回したことを示すチェックを付けていた。「事務作業があり、時間がなかった」と話しているという。
同線では昨年10月、新御徒町駅(東京)のホームドアが全て開いたまま始発電車が進入。同11月には、秋葉原駅(同)の男性用トイレの個室で男性が首をつっていたのが見つかった。いずれも駅職員が巡回を怠っていながら、記録簿上は実施したことにしていた。
同社は「駅構内巡視の意義を改めて理解させ、内規などを基に徹底させる。作業ダイヤの見直しも行う」とした。国土交通省鉄道局は「会社は規則を守らせる責任がある」と指摘した。
ここが大問題だと思う!
財務省近畿財務局が大阪府豊中市の国有地(8770平方メートル)を近隣国有地の約1割の価格で学校法人「森友学園」(大阪市)に売った問題について、私立学校を認可する立場の松井一郎知事は21日、「国民の財産ですから、きちんと疑念を抱かれないようにしないといけない」と述べ、同財務局などの説明が不十分との認識を示した。府庁で記者団に語った。
国が鑑定価格9億5600万円から地下のごみ撤去費として見積もった8億1900万円などを引き、1億3400万円で売る一方、土壌汚染除去費1億3176万円も負担したことについて、松井知事は「ごみ撤去費用を誰がどう見積もったのかを明らかにするべきだ。ここが一番問題」と述べた。
朝日新聞社
千葉大医学部学生による女性への性的暴行事件からもわかるが、人間性に問題があるや医者としての倫理が欠如していれば 医学部に合格できる、又は、医師になれる能力があっても、問題を起こす。
病気を理由に刑執行が停止された暴力団組長を巡る京都府立医大付属病院(京都市上京区)の虚偽報告書作成事件で、この組長と府立医大の吉川敏一学長(69)が京都市内でたびたび会食していたことが15日、捜査関係者らへの取材で分かった。この2人を引き合わせたのは京都府警のOBだったという。府警は病院と暴力団との関係について詳しく調べている。
暴力団組長は、指定暴力団・山口組の直系組織「淡海(おうみ)一家」総長の高山義友希(よしゆき)受刑者(60)。大学関係者らによると、2人は府警を数年前に依願退職した人物の仲介で知り合ったといい、京都市・先斗(ぽんと)町の茶屋などで一緒に会食する姿が目撃されていたという。
吉川学長と高山受刑者の個人的な接触について、14日夜に記者会見した府立医大病院の荒田均事務部長は「病院の敷地内では会ったと聞いている」とする一方、「病院の外で会ったとは聞いていない」と説明していた。
一方、高山受刑者を知る人物によると、高山受刑者は昨年2月に大阪高検が刑執行を停止した後も、同市左京区にある自宅から頻繁に外出。組員とみられる男数人と車で買い物に出かけたり、市内の喫茶店で人と会ったりする姿を見たという。この人物は「自力で歩き、病人という印象を感じることはなかった」と話した。
◇別病院、虚偽否定
府立医大病院に続いて新たに虚偽診断書作成の疑いで15日に家宅捜索を受けた「康生会 武田病院」(同市下京区)の内藤和世院長は、「医師が虚偽の診断内容を書くことはないと信じているが、病院内に捜索が入ったことを厳粛に受け止めている」とのコメントを発表した。
病気を理由に収監されなかった暴力団幹部について、京都府立医大病院(京都市)が虚偽の報告をしたとされる事件で、民間大手「康生会武田病院」(同)でも幹部の病状について虚偽の報告書を作成した疑いが強まったとして、京都府警は15日午前、虚偽診断書作成容疑などで同病院の家宅捜索を始めた。同病院は府立医大病院が医師を派遣する関係病院の一つ。府内に9つの病院を持つグループの中核病院で、病院と暴力団の癒着が疑われる事件は民間大手にも波及した。
一方、武田病院で指定暴力団山口組系淡海(おうみ)一家(大津市)総長、高山義友希(よしゆき)受刑者(60)の診察を行っていたのは心臓病治療を専門とする医師で、府立医大病院の吉村了勇(のりお)院長(64)の紹介で武田病院に勤務していたことも関係者への取材で判明した。
府警は、府立医大病院の前に高山受刑者が受診していた武田病院への家宅捜索で、一連の虚偽報告の全容解明を進める方針。
捜査関係者によると、武田病院は、平成27年6月に懲役8年の実刑が確定した高山受刑者について、昨年2月の刑の執行停止が決まる直前に、医師が「重症心室性不整脈」だと大阪高検に報告。命に関わる重篤化の危険性を指摘していた。この指摘が虚偽であり、高山受刑者の収監を妨げた疑いが持たれている。
専門医によると、重症心室性不整脈は、生活態様にかかわらず発作が起きた場合突然死の危険性がある。
高山受刑者の病状をめぐっては、府立医大病院の吉村院長らは「BKウイルス腎炎」を発症したなどとし、「刑事施設での拘禁に耐えられない」と報告していた。BKウイルス腎炎は、腎移植後に免疫抑制剤を服用すると発症することがある。重症化すれば治癒が困難で、移植した腎臓が機能しなくなる可能性が高まるとされる。
府立医大病院と武田病院のいずれも高山受刑者の病状について重篤さを指摘する内容の報告となっているが、府警が医療データを別の医療機関の複数の医師に依頼して分析した結果、重篤さを否定する見解が示されたという。
武田病院の家宅捜索は15日午前10時ごろ、病院の裏口に府警の車両が到着、捜査員が次々と中に入った。
病院関係者は「警察以外は入らないで」と大声を張り上げ、入り口を白いシートでふさいだ。
武田病院グループのホームページによると、昭和36年の夜間診療開業が創立で、京都府内に9つの病院のほか、健診施設、介護・福祉施設などを経営する。康生会武田病院はグループの中核。
日本サプリメント(大阪市)の特定保健用食品(トクホ)が表示通りの成分を含まず、許可を取り消された問題で、消費者庁は14日、景品表示法違反(優良誤認)で同社に再発防止などを求める措置命令を出した。
課徴金については調査を継続する。
消費者庁によると、同社は遅くとも2011年8月以降、「ペプチドエースつぶタイプ」など8商品の成分検査を怠った。14年9~10月には、宣伝している効果の関与成分を特定できないことが判明したのに、包装容器や新聞広告などで表示を続けた。
問題があったのは、かつお節オリゴペプチド配合をうたった5商品と、豆鼓(とうち)エキス配合をうたった3商品で、「血圧が高めの方に適する」「糖の吸収を穏やかにする」などと表示していた。
消費者庁は23日、日本サプリメント(大阪市)が販売する特定保健用食品(特保)「ペプチドエースつぶタイプ」など6品について、関与成分の含有量が記載値に満たず、公表も怠っていたとして、表示許可を取り消すと発表した。特保認定の取り消しは、制度開始後初めて。
問題があったのは同製品など「かつお節オリゴペプチド」を含む4品と、「豆鼓エキス」を含む2品。前者は「血圧が高めの方に適する」とうたい約850万袋、後者は「糖の吸収を穏やかにする」として約650万袋が売れた。
消費者庁によると、商品はかつお節オリゴペプチドの「LKPNM」という成分が効果をもたらすとして認可を受けたが、実際にはほとんど含まないことが、2014年の自社検査で判明。その後、豆鼓エキス商品にも同様の問題が分かったが、同庁に今月15日に報告するまで、2年以上公表せずに販売を続けていた。
同社は「別の成分が効果をもたらしているとみられ、商品の有効性や安全性は問題ない」としているが、効果のある成分が特定できておらず、今後は一般の健康食品として販売する方針。
魚沼産コシヒカリに中国産を混入? 「週刊ダイヤモンド」の記事を卸会社が否定、提訴へ 02/13/17(BuzzFeed News )
農水省が検査をしないのなら消費者相談センターが対応するべきではないのか?実際、ある件で消費者相談センター連絡を取った事はあるが、消費者相談センターの 対応には疑問を感じた。独立行政法人国民生活センター)はもっとしっかりと 仕事をするべきだと思った。
「魚沼産こしひかり」などとして売られていたコメに中国産米が混入していた疑いがあることを報じた週刊ダイヤモンドの報道(週刊ダイヤモンド2017年2月18日号特集「儲かる農業」より)を受け、農水省がJAグループ京都系の米卸「京山(きょうざん)」に立ち入り検査を実施したことが分かった。山本有二農相が14日の閣議後会見で明らかにした。
本誌は京山のコメを購入し、産地判別で実績がある同位体研究所に検査を依頼。その結果、「滋賀こしひかり」の10粒中6粒、「魚沼産こしひかり」の10粒中4粒、「京都丹後こしひかり」の10粒中3粒が中国産と判別された。
山本農相は会見で本誌報道について、「事実であれば大変重大な問題だ」との認識を示し、「産地偽装というのは食の信用や安全に反するものだ。徹底的に、厳正に対処する」と厳しい姿勢で検査を行う方針を表明した。
京山のように主に県域で事業を行う米卸への検査は、通常、都道府県が行う。今回、農水省が検査に乗り出すことからも、同省が京山のコメの偽装疑惑を重要視していることが分かる。
一方、京山は13日、中国産米の混入疑惑を否定する文書を公表した。文書の中で同社は「現在、農水省に調査を依頼しており、いずれ事実が明らかになる」との考えを示した。
これに対し、通知なしの立ち入り検査を実施している農水省は「そんなことはあり得ない。業者から依頼されて身の潔白を証明する検査などしない」(食品表示・規格監視室)と検査に関する京山の見解を否定した。
農水省は今後、疑惑のコメに関する取引伝票などを、京山と取引のある複数の業者の分も含めて調べる。中国産と疑われる米がどこの流通段階で混入されたのか、組織的に産地偽装が行われたのかが焦点となる。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 千本木啓文)
聖マリアンナ医科大(川崎市)は14日、同大病院の神経精神科で行った22件の臨床研究のうち7件で不正があったとする調査報告書を公表した。
うち1件はすでに研究を中止しており、残る6件についても中止を勧告する。同大は関わった医師らを処分する方針。
関わったのは同大の准教授2人と講師1人。7件はいずれも複数の薬の効果などを比較する研究で、本来は患者に薬を無作為に割り振る必要があるのに、医師が自分で決めるなどしていた。
このうちすでに中止された1件では、医師がデータの開示を求めた患者にカルテの内容を改ざんして渡したり、データの原本を「破棄した」とうそを伝えたりしていた。
性欲が強いのなら日本には風俗がある。得る物と失う物を考えれば妥協と言う選択肢もある。
性的乱暴や素人に対する乱暴がどうしてもやりたかったのであれば、こうなるリスク、お金による示談や合意との理由で無罪を主張して勝てるなどを 受け入れたのだろう。
文部科学省の天下りが注目を受けているが、コントロール出来ない人達に対する罰則や処分は重要で 必要だと思う。
千葉大医学部生らが女性に集団で乱暴した事件は1月31日、千葉地裁で被告の学生3人の初公判が開かれ、犯行の一部始終が検察側の冒頭陳述で明らかになった。一部の被告は起訴内容を否認しており、事件の全貌が確定したわけではない。だが、検察側が立証しようとする事件の筋書きからは、酒に酔って理性を失い、欲望に対するブレーキが利かなくなった学生らのおぞましい所業があぶり出された。
「同意の上だった」-。集団強姦罪に問われた千葉市中央区の医学部5年、吉元将也被告(23)は、初公判で吉村典晃裁判長を見据えてきっぱりとした口調で無罪を主張した。同罪で起訴された山田兼輔被告(23)も、起訴内容の一部を否認。増田峰登被告(23)=準強姦罪で起訴=はすべて認めたが、世間の注目を集めた名門医学部生による卑劣な事件の裁判は、検察側と真っ向から対決する構図で始まった。
名門医学部の学生から一転、被告人席に座ることになった吉元被告と山田被告、そして増田被告は、千葉大医学部5年生。彼らが異なる態度を見せた検察側が描く事件の全容とは、どんなものだったのだろう。1月31日午後、千葉地裁802号法廷で始まった吉元、山田両被告の裁判。吉元被告は上下黒のスーツに丸刈り姿、山田被告は黒いダウンジャケットにスラックス、寝癖姿で、それぞれ法廷に姿を見せた。地裁広報によると、この日の裁判には158人の傍聴希望者が集まり、一般傍聴席での傍聴を許されたのは28人。倍率約5・6倍という関心の高さだった。
検察側の冒頭陳述によると、吉元、山田両被告らは、他の同大医学部生らとともに、研修医の藤坂悠司被告(30)=同区、準強制わいせつ罪で起訴=が指導する実習に参加。その打ち上げとして、昨年9月20日に千葉市内の飲食店で行われた飲み会に参加した。ここが犯行の舞台になった。吉元、山田の両被告は、被害者女性に繰り返し白ワインの一気飲み競争を持ちかけ、多量の飲酒をさせた。トイレに行こうとした女性が酔いのためよろけ、自力で歩行できない状態であることに気付くと、両被告は被害者の両脇を抱えるなどし、犯行場所の女子トイレ内に連れ込んだ。
ここで吉元被告は山田被告に対し、女子トイレの外に出るよう指示。山田被告が立ち退くと、トイレの個室を内側から施錠し、女性の体を触るなどのわいせつな行為を始めた。女性が酒に酔って抵抗できないことが分かると襲いかかり、衣服や下着をずらすなどして、女性を最初に乱暴した。一方、いったんその場を離れた山田被告は、酒席に吉元被告が戻ってこないことから、様子を見るために女子トイレに戻った。そこで、トイレ内で足を投げ出して横たわったまま、動かない女性を発見する。「やったよ」。吉元被告がズボンをたくし上げながら乱暴した旨を告げられた山田被告は、それまでに起きた出来事がピンときた。吉元被告はそのまま、山田被告の目の前で、動かない女性にキスをし始める。
山田被告も、“衝動”を抑えられなくなったのか、吉元被告に習って女性にキスをしたり、体を触るなどし始めた。検察側は、この時点で、「2被告は共同して女性に乱暴することとした」と、共謀関係を指摘した。抵抗できない女性。2人に体を触られるがままとなり、ほどなく山田被告が乱暴を始めた。山田被告の「行為」が終わると、数分後に研修医の藤坂被告が女子トイレの近くに現れる。その際も、吉元と山田の両被告は、藤坂被告の目の前で女性にキスをするなどの行為を止めなかった。「やったよ、お前もどうだ」「大丈夫だぜ」。吉元、山田の両被告は、トイレの個室に来た藤坂被告の後にトイレにやってきた増田被告に対しても、わいせつ行為をするように勧める。山田被告は背後で、女子トイレの床の上であおむけになっている女性の写真をスマホで何枚か撮影。衣服がはだけた女性の写真を藤坂、増田両被告に送った。
店での打ち上げは、翌21日午前0時半ごろまで続いた。女性は歩くこともできず、3被告が増田被告の家にタクシーで連れて行った。吉元、山田被告が立ち去ると、女性から「救急車を呼んでほしい」と頼まれたにも関わらず、増田被告は無視し、女性を乱暴してしまうのだった。法廷での吉元被告は、いくぶん緊張した表情で証言台に立ちながらも、廷内に響き渡るようなはっきりとした口調で、「被害者は酒を飲んだが、酩酊(めいてい)して抗拒不能の状態でなかった」と主張。検察側が読み上げた起訴内容を全面的に否認し、無罪を主張した。
一方、山田被告は、「入った時には終わっていた」などと、先に吉元被告が女子トイレ内で行った犯行に関しては無関係と主張。自身の暴行の行為そのものは認めたものの、起訴内容を一部否認した。吉元、山田両被告とは別の裁判で初公判が開かれた増田被告は、上下黒スーツ姿に整えられた短髪で出廷。はっきりした口調で「間違いありません」と、起訴内容を全面的に認めた。検察側の冒頭陳述からは、吉元被告がまず被害者の女性に性的暴行を加えた後、トイレに入ってきた友人や研修医らに次々と犯行を打ち明けていった様子が描かれている。
吉元被告が自らの罪の意識を薄めるかのように友人らにわいせつ行為を促し、それに呼応した山田被告らが、次々と女性に襲いかかっていったとの「事件の流れ」を読み取ることができるだろう。検察側の描く筋書きの真偽はどうなのか。全面否認した吉元被告の次回公判は2月20日に行われる。同日には、研修医の藤坂被告の初公判も行われる予定だ。
「事件を起こすようには見えなかった」「派手に遊んでいるようには見えなかった」と、吉元、山田、増田の各被告を知る同級生は初公判を前に指摘し、真面目で将来を嘱望された「医者の卵たち」だった。いずれも体育会の部活動に所属し、運動部所属の学生特有の「激しい酒の飲み方」が、“暴走に”歯止めが掛からなかった一因ともみられている。学費が高い医学部に在籍しながらも、3人にアルバイトなどに忙殺される素振りは見られなかったという。運動部は遠征などで部費がかさむが、頻繁に飲み会に参加し、アルバイトにも追われていなかったことから、3被告は周囲から、「実家は相当な金持ちなのではないか」とみられていたようだ。実際、山田被告の実家は、弁護士や法律家を輩出している法曹一家。山田被告は神奈川県の有名高を卒業し、大学近くの新築マンションで暮らしていた。
カシオ計算機は10日、50代後半の開発部門の元部長が2007年から15年までに、約4億4000万円を横領していたと発表した。
昨年末に懲戒解雇し、近く刑事告訴する。
同社によると、元部長は取引先と共謀して試作品を架空発注し、代金を自身に還流させ私的に流用したという。発注業務を部長が最終的にチェックする体制だったため、発覚が遅れた。昨年6月に内部告発を受けて調査し、不正が判明。元部長も認めているという。
「有罪」でも将来医者になれるのか? (1/4) (2/4) (3/4) (4/4) 02/07/17(週刊現代)
千葉大医学部レイプ事件 捕まったエリートたちのこれから
国立大医学部。彼らは「約束された人生」を歩んでいたはずだった。だが、酔って女性をレイプするという卑劣な行動によって、すべてが崩れた。たった一度の過ちと悔やんでも、時は元には戻らない。
父親が心境を語る
「一度、千葉大学のほうには謝罪に行かせていただきましたが、その後まだ処分については何もお話をいただいていません。司法の判断を待ってということなんでしょうね。
保釈はされてないです。当初から被害者の方に謝罪をしたいと思っているのですが、それが叶っていないというのが状況です。ご本人様のご心情なり、ご家族の方も含めて、受けた傷を考えると、同じ親として申し訳ない気持ちでいっぱいです。
とにかくお詫びすることしかできない。それがやらなくてはいけない最初のことだと思っています」
千葉大学医学部レイプ事件で昨年12月に逮捕された増田峰登被告(23歳)の父親は本誌に心境をそう語る。
同事件は昨年9月に発生した。いずれも千葉大学医学部5年生の吉元将也被告(23歳)、山田兼輔被告(23歳)、前出の増田の3人が飲み会で酩酊した女性に集団で性的暴行を加えたとして、集団強姦致傷容疑で逮捕された。
後日、彼らを指導すべき立場だった千葉大学附属病院の研修医・藤坂悠司(30歳)も準強制わいせつ容疑で逮捕されている。
学生3人が国立大学、しかも入試の難易度では慶応大医学部よりも上の千葉大医学部生という超エリートだったため、世間の反響は凄まじかった。
なかでも山田は神奈川県にある超進学校・聖光学院高校出身。しかも中央大学の創立者である高祖父から父親まで、東京大学法学部卒の弁護士が4代続いた華麗なる家系に生まれている。曾祖父は最高裁判事まで務めた人物だった。
「父親は企業法務のヤリ手で有名企業の監査役を務めています。ただし今回の息子の弁護には関わっていないようです」(全国紙担当記者)
吉元は長野県屈指の名門・長野高校卒、増田は筑波大学附属高校卒で、3人とも実家近所では秀才として知られ、大学では山田と増田は医学部のラグビー部、吉元はスキー部に所属していた。藤坂は千葉大ではなく、金沢医科大学出身である。
学生3人はあと1年で卒業し、前途洋々たる未来が待っていたはずだったが、性犯罪で逮捕されたことにより、人生は大きく変わることになる。
昨年12月12日、千葉地検は吉元と山田を集団強姦罪で、増田を準強姦罪でそれぞれ起訴した。続いて、同月22日に藤坂も準強制わいせつ罪で起訴された。学生3人に関しては逮捕時の集団強姦致傷容疑と罪状が異なっている。
「逮捕当初の報道では、飲み会で泥酔した女性を介抱するフリをして、居酒屋のトイレの個室内で、4人で次々に性的暴行を加えた後、さらに藤坂を除いた3人で増田の自宅マンションに女性を連れ込んで、性的暴行を続けたとありました。
ですが、起訴状によれば、居酒屋のトイレでは吉元と山田が共謀して、順番に被害者を姦淫。マンションでは、増田だけが被害者に姦淫に及んだとあります。
加害者と被害者が酒に酔っていて、犯行当時の記憶が曖昧なので立証が難しいということもありますが、3人で同時に輪姦し続けたというわけではないようです。
また被害者の傷は全治5日程度で、『致傷』は外れています。藤坂に関しては飲み会で触っただけと主張しているようです」(全国紙担当記者)
たとえ罪状が軽くなったからと言って、彼らの行為が許されることは決してない。
示談は成立していない
3人は取り調べで、
「酒の勢いで酔ってやってしまった」
「まさか逮捕されるとは思っていなかった」
と口を揃えているという。彼らはいったいどんな罰を受けるのか。性犯罪などの刑事事件に詳しい古海健一弁護士が解説する。
「準強姦罪は3年以上の有期懲役、集団強姦罪は4年以上の有期懲役と規定されています。今回の事件は今後も示談が成立するかどうかがポイントになります。示談は、裁判が始まってからでも可能で、判決が出る前に成立すれば、刑期が短縮されるでしょうし、集団強姦罪でもまれに執行猶予が付くこともあります」
だが、示談交渉は暗礁に乗り上げているようだ。
「加害者それぞれに弁護士がついて示談交渉していますが、被害者側は一切受け入れるつもりはないようです」(前出・記者)
このままでは、執行猶予がつかない実刑判決を受けることになりそうだ。
一方、千葉大学広報室は4人の処分について、本誌にこうコメントする。
「今後裁判が行われ、何らかの明確な判断が出た段階で、大学側と病院側が処分を決定することになるかと思います。まだ開廷もされていないので、具体的な処分の内容についてはなんとも言えない状況です」
千葉大は明言を避けたが、学生3人の退学処分は時間の問題だ。また藤坂は病院を解雇、そして医師の資格を失うことになるだろう。
「医師法では、罰金刑以上の刑を処せられた場合には医師免許を取り消される可能性があると規定されています。犯罪の悪質性から考えると、取消の可能性が高いと思います」(前出・古海弁護士)
3人は再び医師を目指すのか
実は犯行のきっかけとなった飲み会には藤坂以外の医師も複数いたというが、彼らは罪に問われていない。
「被害者は別のもう一人の医師も告訴していました。しかし、頬や手を触った軽微なものだったとされて、その医師の立件は見送られるようです。藤坂とはわずかな行為の差で、人生を分けることになりましたね」(前出・全国紙記者)
では、判決後、罪を償った学生3人が再び医師を目指すことはできるのだろうか。
'99年に婦女暴行容疑で逮捕された慶應大学医学部の学生5人のうちの一人、主犯格のAは医師になっている。
Aは逮捕直後に大学を退学処分になるが、被害者との示談が成立し、不起訴処分で釈放された。Aの父親は東大の医学部教授、母親もクリニックを経営している。
そしてそのわずか1年後、Aは琉球大学医学部に合格して、再入学を果たす。
当時の琉球大学医学部の受験には履歴書の提出も面接試験もなく、筆記試験だけで入学できた。
Aは当時、週刊文春のインタビューにこう答えている。
「大学の願書を見たときも、ボクらのためにある学校なんだなあって思いました。自分を受け入れてくれる試験形式の大学を受けるという行為を、間違っているとはまったく思いません」
「ボクが考えたのは、医者になって一人でも患者さんを治せば、ボクの能力を社会に還元できることになる、一年でも早くそうしたほうが、社会のためにもなると思ったんです」
「もし医者になっても、過去よりも実力で勝負したいと思っています」
さらにAは国家試験にも合格し、医師免許も取得している。Aの父親は医療界に隠然たる影響力を持っていた。現在、Aはどこかの病院で、診察をしていることだろう。
厚生労働省医政局医事課試験免許室担当者はこう説明する。
「医師国家試験を受けて合格した人に、医師免許申請の書類を提出してもらいます。申請に問題がなければ免許付与という流れとなります。
申請書類には、罰金刑以上の刑罰を受けたことがあるかを問う項目があります。あると書かれた方は、免許を与えていいかどうかの判断を個別に下します。不起訴や示談といった場合には申告義務はありません。ただし執行猶予中の場合は申告が必要です」
車を運転中のスピード違反は申告しなければならないが、婦女暴行なら逮捕されても、不起訴ならば特に問題はないというのである。
では、刑罰について虚偽の申告をした場合はどうなるのか。
「後々に申告していない犯罪歴があったことが判明した場合、虚偽申請という扱いになります。免許取得後であっても行政処分の対象になる可能性があります。一番厳しい処分は医師免許剥奪で、一番軽い処分は厳重注意です。身辺調査まではしていません。あくまで申告されないかぎりはわかりません」(前出・担当者)
まさに抜け穴だらけと言わざるをえない。
昭和大学横浜市北部病院・心臓血管外科教授の南淵明宏氏もこう言う。
「全国の医学生は入学式で『警察のご厄介になると医師国家試験が受けられません。そういうルールなんです』と厳しく諭されます。『例えば飲酒運転。一発退場です!』なのに、実際はレイプ事件の加害者が不問にされたのならこんな制度は支離滅裂。女性蔑視も甚だしいデタラメ。
『お医者さんて特権が認められていて、いつもそんなふうに甘やかされているんでしょ』と社会から思われてしまいそうで心配です」
ただしAと違って、起訴されている千葉大の3人が医師になれる可能性はかぎりなく低い。
「Aの件があって、琉球大学医学部も受験の際に、履歴書の提出と面接試験が必須になりました。かつてはそういった面接ナシの医学部がいくつかありましたが、現在のところ私大では皆無、国立では九州大学医学部のみです。
たとえ養子縁組などで姓を変えたとしても、医療関係者には履歴書と面接で千葉大レイプ事件の加害者だとわかりますから、合格は難しいでしょう」(医療関係者)
前出の古海弁護士もこう言う。
「医師法上、罰金以上の刑に処せられた者には医師免許を与えないことがあると規定されています。性犯罪の加害者である学生が罰金以上の刑に処せられた後、たとえ再び別の大学の医学部に通って医師国家試験に合格しても、犯罪の悪質性からすると医師免許が与えられない可能性は高いと思います」
自業自得。たった一晩、酒に酔って過ちを犯したことで、彼らの人生は取り返しのつかないほど変わってしまった。
本誌はエリート弁護士である山田の父親に都内の自宅前で取材を申し込んだが、沈痛な表情で、「申し訳ありません」と言って頭を下げるのみだった。
「裁判長が決めること」
増田被告の父親は本誌に静かな声でこう語った。
「私も最初に連絡を受けたときは衝撃でした。『まさか自分の子供が』という気持ちがありました。本人から手紙ももらっていますが、やはり絶望を感じていますよね。幼い頃から医者になりたいという思いでずっとやってきましたから。面会では『弟や妹に申し訳ない』ということを一番に言っていました。
裁判の中で被害者の方、他の加害者の方の供述が出てくると思うので、事実関係がわかってくると思います。事実関係をはっきりさせて、まずは被害者の方への謝罪ですよね。そして、罪を償わなくてはいけない。まだ人生四分の一。絶望していると思いますが、心が折れないように前を向かせたい。それだけです」
広島県で開業医としてクリニックを経営している藤坂の父親は息子に対して、厳しくこう語る。
「普通の方が感じるように、被害者に対して非常に申し訳ない。同じ学校の中で先生と生徒の関係で、なんでそういうことになるのか。息子はコップ一杯で真っ赤になるほど、アルコールに弱いということがあります。酔っぱらいやすいので、正常な判断ができていなかったのか。うちの息子は馬鹿ですよ。
逮捕後は一度も会ってないです。よく反省してほしいという意味で会いに行っていません。親が行ったら、たぶん助けてくれってなる。それに従いたくない。罪の重さとか、色んなことを考えてほしい。やったこと自体が許されることではないので。
やっぱり人の命に係わるような勉強をしているのだから、そこの原点を忘れてはいけない。医者がすべきことではないですよ。
裁判にしても私は行きません。本人が30歳ですからね。今後は自分で考えることじゃないですかね。貯金もあるでしょうし、弁護士費用を支援することもないです。反社会的なことをした結果は、裁判長が決めることです」
事件の初公判は1月31日から始まった。エリート学生と研修医は法廷で何を語るのか。
(文中一部敬称略)
「週刊現代」2017年2月11日号より
東洋ゴム工業は7日、産業用ゴム製品の検査でデータ偽装があったと発表した。同社は免震ゴムや防振ゴムでもデータを偽装するなど過去に3度の不正を起こし、その度に信頼回復と再発防止を誓ってきた。しかし、染みついた不祥事体質から脱しきれず、企業風土改革の難しさが浮き彫りになった。
「非常に忸怩(じくじ)たる思いだ。仕組み、ルール作りで足りないものがある。全社員に浸透するのが非常に難しいと痛感している」。東洋ゴムが大阪市内で開いた記者会見で、小野浩一取締役常務執行役員らは反省の弁を繰り返した。同社は2007年から15年にかけて断熱パネルの性能偽装、性能不足の免震ゴムの使用、防振ゴムのデータ改ざんと相次いで不正が判明。2人の社長が引責辞任している。15年12月には一連の不正を総括し、外部監査機関の指導を仰いで再発防止に向けてガバナンス(企業統治)の強化に取り組んでいる最中だった。
しかも、過去3回とも子会社の明石工場(兵庫県稲美町)で起きた。東洋ゴムによると、免震ゴムの不正発覚を受け、同工場のシートリングの工程に対する不正について複数回検査していたが、気付かなかった。この工場は製造する商品が多いため、業務管理の新たなシステムを導入したばかりだったという。
データを偽装した30代の男性社員は不正の理由について「忙しくてやってしまった。面倒くさかった」と話しているという。シートリングの検査は通常男性1人で担当しており、必要に応じて要員を補充していた。小野常務は「品質管理システムが完全に浸透していなかった」と釈明。今後は常時2人以上の体制にするという。
会見では「なぜ不祥事が連続するのか」と厳しい質問が相次いだ。小野常務は「いろいろな取り組みでかなりレベルは上がっている実感はある。コンプライアンス(法令順守)の教育を続けて社員一人残らず高い意識を持った会社作りに取り組む」と述べるにとどまった。
免震ゴムのデータ改ざんでは、大阪府警が不正競争防止法違反(虚偽表示)の疑いで捜査しているほか、株主代表訴訟も起こされている。今回のシートリングの年間売上高は数億円に過ぎず、同社の業績への直接的な影響は少ないが、今度こそ抜本的な再発防止に取り組まなければ、ブランドイメージの低下は進むばかりだ。【土屋渓、宇都宮裕一】
東洋ゴム工業は7日、船舶に使う産業用ゴム製品で、必要な検査をせず、データを偽装していたと発表した。同社は2007年以降、断熱パネルや免震ゴムの性能偽装などが相次ぎ、今回が4度目の不正公表となる。国土交通省は東洋ゴムに対し、原因究明や再発防止策を実施するよう指示した。
不正があったのは、タンカーなどの配管バルブに使うシートリングと呼ばれる輪状のゴム製品。配管の内側に張り、液体の流れを止める際、弁と配管の隙間(すきま)をうめる機能がある。子会社の東洋ゴム化工品(本社・東京)の明石工場(兵庫県稲美町)で製造し、代理店を通して国内のバルブメーカー1社に納入している。
東洋ゴムによると、製品10~5個に1個の頻度で製品の寸法や硬さを検査するようバルブメーカーと取り決めていた。しかし、30代の男性検査員が検査頻度を20個に1個などに伸ばし、検査の不足分は過去のデータをコピーして報告していた。同社では、同製品を09年以降約13万個生産しており、そのうちの最大半数程度が検査をせずに流通した可能性がある。東洋ゴムは「納入先からは性能面での問題はないと聞いている」としている。
東洋ゴムでは07年に断熱パネルの耐火性能を偽っていた問題が発覚。15年3月には建物などの免震ゴムの性能データ改ざんが判明し、さらに同10月、鉄道車両などで使われる防振ゴムでも不正行為が明るみに出た。記者会見した小野浩一取締役常務執行役員は「信頼回復に努めている中で問題がおき、重く受け止めている」と陳謝した。【久野洋】
愛知県警は4日、同県豊橋市江島町の私立高校教諭、大塚章仁容疑者(29)を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕したと発表した。容疑を認め、「仕事に間に合わなく、急いでおり、気が動転していた」と話しているという。
豊橋署によると、大塚容疑者は3日午前7時50分ごろ、乗用車で豊橋市つつじが丘3丁目の丁字路交差点を右折しようとした際、前方のダンプカーに衝突。ダンプカーは道路沿いの車庫にぶつかり、乗っていた男性会社員2人に首のねんざなどのけがを負わせ、そのまま逃げた疑いがある。自宅から学校に向かう途中だったという。
その後、レッカー移動されている大塚容疑者の車が関係者に目撃されたことが逮捕につながったという。
富山市民は見て見ぬふりの環境に疑問を抱かないほど不正や権力に従うに慣れているのだろうか?富山市に住んだことがないので全くわからない。
富山市議会の政務活動費不正問題で、宮前宏司元市議の依頼で領収書を偽造したとして、日本郵便北陸支社が1日までに、郵便局長を処分したことが分かった。処分内容や処分日は非公表。
同社広報室によると、調査の結果、局長が社内規定で禁止されている領収書の再発行や自作をしたと確認した。局長は聞き取りに「違反との認識はあったが元市議に頼まれて断れなかった」と話したという。
同社は「誠に遺憾。他の郵便局にも指導を徹底する」としている。宮前氏は偽造領収書による請求を認め、昨年11月に辞職した。
富山市議会の政務活動費不正問題で議員辞職した自民会派前会長の中川勇氏(69)が朝日新聞の取材に対し、自身の不正発覚前、「市議会事務局職員から、地元民放テレビ局が政活費について情報公開請求していると聞いた」と証言した。中川氏はこの情報をきっかけに、業者と不正を隠す「口裏合わせ」をしていたという。
中川氏は2011~15年度に政活費(旧政務調査費)約695万円を不正取得。旧知の印刷会社から束で受け取っていた白紙領収書を使い、市政報告会の資料の印刷代を装って架空請求を繰り返していた。
中川氏によると、今夏、市議会内を歩いていた際、市議会事務局の職員から、地元民放から政活費の領収書などの公開請求があり、コピーを地元民放に渡したと告げられたという。
中川氏は職員から聞いた情報をきっかけに、印刷会社を訪ね、報道機関からの取材があれば取引の実態があったと答えるよう「口裏合わせ」を求めたという。
中川氏は「通りかかったら(職…
東広島市に拠点を置く医療法人好縁会のグループが、広島市内の複数の事業所で、介護報酬の不正受給を繰り返していたことが2日、分かった。訪問介護サービスなどの報酬を介護保険法に基づく基準より多く請求したり、実態と異なる事業内容を記載した申請書を提出して介護事業所の指定を受けて報酬を受け取ったりしていた。不正に得た額は数千万円に上り、同法に基づく事業所の指定権限を持つ広島市が3日にも関係した事業所の指定を取り消す。
関係者によると、不正があったのは、グループ会社ウェルケア(東広島市)が運営する「やすらぎ訪問介護ステーション」(広島市西区)や、好縁会が運営する「ケアプランサポートふれあい段原」(南区)。
やすらぎ訪問介護ステーションは、広島市内の老人ホーム内で業務をしていたにもかかわらず、ホーム外に移転したとする虚偽の届けを提出。ホーム内で業務をする場合は、介護報酬を減額する必要があったのに、それをしていなかった。
ケアプランサポートふれあい段原は、居宅介護支援事業所として指定を受けた場所と違う市内の施設に機能の一部を移してサービスを提供していたにもかかわらず、2013年にこれらを隠して虚偽の申請書を提出し、指定の更新を受けて事業を続け、報酬を不正に受給した。
やすらぎ訪問介護ステーションは17年1月15日から、ケアプランサポートふれあい段原は16年12月1日から、それぞれ運営を休止している。
好縁会法務課は中国新聞の取材に「行政の正式な(処分の)発表を受けて内容を検討した上で報告とおわびをしたい」とする。広島市介護保険課は「処分した場合は公表するが、現時点では何も答えられない」としている。
◇3社と都環境公社の再調査分は計1076万円
東京都議会の豊洲市場移転問題特別委員会が31日午前始まり、最終9回目の地下水モニタリングで国の環境基準値を大幅に超える有害物質が検出されたことを受け、都が地下水モニタリングの採水・分析業者との9回分の契約額と、30日に始まった再調査の契約額を公表した。
【水がたまった青果棟地下空間。水はくるぶしまで】
それによると、1~9回目の採水・分析に関わった延べ9社の合計は約65億3270万円(一部施設工事費含む)で、3社と都環境科学研究所が担当する再調査分は計約1076万円だった。
9回の地下水モニタリング調査などについて質疑が行われ、都側は「豊洲市場の地下水は飲用ではないため汚染の除去などの措置は求められておらず、モニタリングも実施の義務はない」として、モニタリングは土壌汚染対策法上義務付けられたものではなく、都が任意で実施したと説明。「生鮮食料品を扱う市場として安心・安全を確保するため」と述べた。菅野弘一議員(自民)の質問に答えた。
都は2014年から豊洲市場の計201カ所でモニタリングを実施。7回目までは基準値を超える有害物質は検出されなかったが、8回目は3カ所で、9回目は72カ所で検出された。この経緯について菅野議員は「これまでの調査に対しても疑念を抱かざるを得ない状況だ」と指摘した。【川畑さおり、森健太郎】
立証するのが難しい点を突いてきたのでは?弁護士の手腕と検察の能力不足で不起訴となっても、こんな人達は今後、医療に関係するべきではないと思う。
千葉大学医学部の男子学生3人が女性に性的暴行を加えたとして逮捕された事件。31日の初公判では、3人のうち1人は「合意の上だった」と無罪を主張しました。
千葉大学医学部5年の吉元将也被告(23)、山田兼輔被告(23)、増田峰登被告(23)の3人の被告。3人は、去年9月、千葉市の飲食店で、千葉大学病院での実習後に開かれた飲み会に参加していました。このうち、吉元被告と山田被告は酒に酔って抵抗できない女性(20代)に性的暴行を加えたとして集団強姦の罪に問われ、増田被告は飲食店から出た後、同じ女性を自宅に連れて行き、性的暴行を加えたとして準強姦の罪に問われています。
31日の初公判。3人のうち、吉元被告は、黒いスーツに白いシャツを着用し坊主頭で法廷に入りました。
裁判長に起訴内容を問われると・・・
「女性は酔ってはいたが、抵抗できない状態ではなかった。合意のうえだったと考えています」(吉元被告)
吉元被告は起訴内容を否認し、無罪を主張しました。
一方、山田被告は、起訴内容の一部に誤りがあるとしたものの、「吉元被告にそそのかされた」として集団強姦罪の成立については認めました。
また準強姦の罪に問われた増田被告は、「間違いないです」と起訴内容を認めました。
検察側は、冒頭陳述で、犯行の詳細についてこう指摘しました。
「被害者に白ワインを一気飲みさせて自力で歩けないと分かるや脇を抱え、女子トイレに連れて行き、まず吉元被告が性的暴行を加えた」(検察側)
そして山田被告については・・・
「トイレに横たわって動けない被害者に性的暴行を加えたうえ、あおむけで倒れていた被害者の写真を撮った」(検察側)
さらに増田被告については、性的暴行を行う前に、被害者から助けを求められていたことを明らかにしました。
「被害者から酔いがひどいので救急車を呼んでほしいと言われたが、第三者に知られてしまうと言って救急車を呼ばなかった」(検察側)
一方、山田被告の弁護側は、冒頭陳述で、「飲み会は研修後に行われた打ち上げであり、極めて特殊な状況だった」「山田被告自身も飲酒酩酊状態だった」と主張しました。
31日の初公判。法廷では、被害者の女性の供述調書も読み上げられました。
「3人のことは許すことができません。厳しく処罰していただきたいです」(女性の供述調書)
「合意の上だった」-。千葉大医学部生らが女性に集団で乱暴した事件で31日に千葉地裁で開かれた初公判。集団強姦罪に問われた千葉市中央区の医学部5年、吉元将也被告(23)は、吉村典晃裁判長を見据えてきっぱりとした口調で無罪主張した。一方、同罪で起訴された山田兼輔被告(23)も起訴内容の一部を否認。世間の注目を集めた名門医学部生による卑劣な事件の裁判は、検察側と全面的に対決する構図で始まった。
同日午後、千葉地裁802号法廷で始まった吉元、山田両被告の初公判。吉元被告は上下黒のスーツに丸刈り姿で、山田被告は黒いダウンジャケットにスラックス、寝癖姿で、それぞれ法廷に姿を見せた。地裁広報によると、この日の裁判には158人の傍聴希望者が集まり、一般傍聴席での傍聴を許されたのは28人と、倍率約5・6倍となる関心の高さだった。
吉元被告は、いくぶん緊張した表情で証言台に立ちながらも、廷内に響き渡るようなはっきりとした口調で「被害者は酒を飲んだが、酩酊して抗拒不能の状態でなかった」と主張。検察側が読み上げた起訴内容を全面的に否認し、無罪を主張した。
一方、山田被告は、「入った時には終わっていた」などと、先に吉元被告が女子トイレ内で行った犯行に関しては無関係と主張。自身の暴行の行為そのものは認めたものの、起訴内容を一部否認した。
吉元、山田両被告のほか、準強姦罪で起訴された増田峰登被告(23)=同学部5年、同区=の初公判も、両被告とは別の裁判としてこの日、同じ法廷で行われた。増田被告は上下黒スーツ姿に整えられた短髪で出廷。はっきりした口調で「間違いありません」と、起訴内容を全面的に認めた。
起訴状などによると、両被告は9月20日深夜、共謀して千葉市の飲食店内で、飲酒で酩酊し抵抗できない状態の県内に住む20代女性を乱暴したとしている。 事件をめぐっては、千葉大病院の研修医、藤坂悠司被告(30)=同区=も準強制わいせつ罪で起訴されている。
大手旅行会社エイチ・アイ・エス(HIS、東京都新宿区)が従業員に違法な長時間労働をさせていたとして、東京労働局の過重労働撲滅特別対策班(通称かとく)が、労働基準法違反の疑いで同社を強制捜査していたことが31日までに分かった。
東京労働局は法人としての同社と労務担当幹部の書類送検に向け、捜査を進めている。
関係者によると、HISは従業員に対し、労使協定で定めた上限を上回る違法な残業をさせた疑いが持たれている。東京労働局は昨年夏ごろに同社を強制捜査。従業員の勤務状況などを調べるとともに、違法残業への幹部らの関与について捜査を続けてきた。
HISは1980年の設立で、格安航空券や低価格の海外ツアーなどで業績を伸ばし、昨年10月期の売上高は約5200億円。グループ全体の従業員は約1万4000人に上る。
検定を主催する公益社団法人「全国経理教育協会」は調査して事実の解明と原因を公表するべきだと思う。
中央医療歯科専門学校(群馬県太田市東本町)で行われた「社会人常識マナー検定」の試験で、問題の漏えいがあったことが、同校などへの取材で分かった。
校内の管理がずさんで、女性教員が事前に問題をコピーし、受験予定の学生に予想問題として漏らした。検定を主催する公益社団法人「全国経理教育協会」(東京都豊島区)は、今回の同校での試験を無効とし、受験した学生49人の再試験を行う。
同協会によると、漏えいがあったのは、21日に全国一斉に行われた同検定3級の試験。社会常識やマナーなどを問うもので、全国で3647人が申し込んだ。合格発表は2月の予定。
同協会は、事前に各会場へ問題を送付し、試験当日まで開封せず、鍵のかかる場所で保管するよう求めている。同校は16日に届いた問題を、職員室にある鍵付きの戸棚に保管。しかし、この鍵を無施錠の別の棚に入れていた。多くの教員が鍵の置き場所を知っていたという。
女性教員は17日、無施錠の棚から鍵を取り出し、戸棚を開けて、試験問題をコピーした。パソコンを使って、全18問のうち図形問題を除く16問を載せたプリントを作成。18日の講義で、1年生全50人に予想問題として配った。このうち49人が受験した。
試験後、学生から同協会に「事前に試験問題と同じ問題を解かされた」などと申告があり、漏えいが発覚した。女性教員は同校の調査に対し、「検定の指導をするのが初めてで心配だった。全員を合格させたかった」と話したという。同校は26日付で、女性教員を15日間の出勤停止処分とした。
今回の検定試験で、同校が、全国一律の開始時間を「学校にとって都合が良いから」と3時間半繰り上げていたことも判明した。同協会は「公正に試験を実施するための最低限のルールを守っておらず、極めて遺憾。改めて聞き取り調査を行い、学校への何らかの処分を検討する」としている。
同校は中央カレッジグループに所属し、歯科衛生士を養成している。新井孝副校長は「教育の現場であってはならないことで、学校の信用を落とす行為だった。学生や保護者に申しわけない」と話している。
東京慈恵会医科大学付属病院(東京都港区)が、検査で肺がんの疑いを発見された70代の男性患者に検査結果を伝えないまま約1年間放置していたことが31日、関係者への取材で分かった。男性のがんは進行して手術できない状態となり、病院は患者側に謝罪した。
関係者によると、男性は肝臓に持病があり、慈恵医大病院の消化器肝臓内科で治療を続けていた。昨年10月、貧血などのため同病院に入院した際、胸部CT検査で肺がんと診断された。
ところが、12月になって担当医から「1年前に撮影した胸腹部CT検査で肺がんの疑いがあると放射線科医が診断していたが、放置していた」と説明を受けた。病院側の説明によると、男性は平成27年10月に入院した際にCT検査を受けており、放射線科の医師が画像報告書に「原発性肺がんは鑑別となり、短期間でのフォローが望まれます」と書き込んでいた。
しかし、当時の担当医やその後の外来を担当した主治医は、報告書を確認しないまま肺がんの疑いを1年にわたり放置。その間にがんは進行し、男性は手術や抗がん剤治療ができない状態になった。
病院は「今回の事実を大変遺憾に思います。現在、全力で対応し治療に当たっております。改善策を検討し、再発防止に務めたいと思います」とコメントした。
「担当者は元高等教育局長の再就職を受け入れた早稲田大に年間100億円を超える私学助成金などが支出されていたことを明らかにし『(元局長には)当然、大学と利害関係があるとは分かっていたが、認識が甘かった』と述べた。」
「認識が甘かった」で済ますのか?処分をもっと重くするように法律を改正するべき。教育に深く関与する省がこのありさま。 もっと深く調査する必要がある。
天下り規制への理解が足りなかった--。文部科学省が元局長の天下りを組織的にあっせんした問題で、早稲田大学は20日、教授に再就職した吉田大輔・元高等教育局長の辞職を明らかにした。記者会見で陳謝した鎌田薫・早大総長は、再就職等監視委員会の調査を巡り大学の人事担当者が文科省と口裏合わせをしたと認めた。文科省との「癒着」は否定したが、官僚の再就職への不信が広がっている。
「恥ずかしい限り。文科省が、違法な指導をすることはあり得ないという前提でいた」。鎌田総長は東京都新宿区の大学キャンパスで記者会見。監視委の調査結果の発表を受け、経緯を説明した。
早大によると、2016年8月、吉田氏の再就職が規制に抵触していないかを確認するとして、大学人事部に対する監視委のヒアリングが行われた。担当職員は、文科省人事課から事前に渡されたA4判3~4枚程度の「想定問答」をもとに対応した。文科省は大学側に「(ヒアリングは)形式的なものだから」と想定問答を渡したという。大学が口裏合わせに加担するかたちになった。
その後、2回目のヒアリングを行うとの通知が大学に届き、大学が内部で調査したところ、最初のヒアリングで職員がうその説明をしたことが判明。11月に行われた2回目のヒアリングで、大学が口裏合わせの事実を監視委に認めた。
吉田氏の採用を巡り、早大は15年9月、内部で審議を行った。この時、大学を監督する立場にある文科省の高等教育局のトップを受け入れることを疑問視する意見が出ていた。だが文科省人事課から「再就職の規制には抵触しない」「採用手続きが文科省退職後に開始されたのであれば問題ない」と説明され、受け入れを決めたという。
鎌田総長は「08年の改正国家公務員法施行後に文科省出身者を専任の教授として採用したのは初めてで、不当な癒着はない。不適切な利益供与を求めたことも、受けたこともない」と述べた。【岸達也】
「信用できぬ」民進が批判
問題を受けて国会内で20日、開かれた民進党のヒアリングでは、文部科学省の担当者に「信用できない。省外の第三者の調査を受け入れるべきだ」などの厳しい意見が相次いだ。
ヒアリングには文科省の担当者2人が出席。官房長をトップとする態勢で省内の調査を実施すると説明した。議員からは「お手盛りの調査になる」「また隠蔽(いんぺい)するかもしれない」などと批判が上がり、担当者が「ご指摘は受け止めます」と表情をゆがめて答える場面もあった。
また20日に発表された文科省の処分に関し、「ノンキャリア」の人事課室長級の職員が最も重い停職処分を受けたことについても、議員から「他にも上に関わった人間がいるのではないか」「トカゲのしっぽ切りでは」などの声が上がった。
担当者は元高等教育局長の再就職を受け入れた早稲田大に年間100億円を超える私学助成金などが支出されていたことを明らかにし「(元局長には)当然、大学と利害関係があるとは分かっていたが、認識が甘かった」と述べた。【杉本修作】
信頼回復努める 松野文科相
松野博一・文部科学相は20日の記者会見で「国民の皆さまにおわびする。省を挙げて信頼の回復に努めていきたい」と陳謝した。自身の監督責任を認め大臣報酬6カ月分を返納することを明らかにした。組織的な不正の背景について問われ「省として再就職の規制に関する理解が不十分だった。関係法令の順守の意識も不足していた」と語った。【岸達也】
文科省天下り問題調査結果(要旨)
再就職等監視委員会は文部科学省職員及び元職員による再就職等規制違反行為が疑われた事案について、国家公務員法に基づき調査を実施した。
<調査結果>
ア 文科省大臣官房人事課職員2人は、上司である当時の藤原章夫人事課長に報告の上、役職員である吉田大輔元高等教育局長を、元局長にとって利害関係企業等に該当する早稲田大に再就職させることを目的として、元局長の履歴書を作成・送付し、早大と採用面談の日程調整をするなどし、藤原課長も職員2人と共同して、国家公務員法106条の2に違反したものと認定した。
イ 吉田元局長は、利害関係企業等に該当する早大に再就職することを目的として、人事課職員2人とともに履歴書を作成し、職員が元局長の履歴書を早大に送付した。また、元局長は職員2人を通じて早大との面談日程の調整をした。これらは、いずれも元局長が在職中に行われ、実質的に元局長の早大に対する求職活動であり、元局長は国家公務員法に違反したものと認定した。
ウ 文科省大臣官房人事課職員2人は、先輩職員と協議の上、再就職等監察官に対し、当時の藤原人事課長と職員2人及び吉田元局長の再就職等規制違反行為が発覚することを免れようと、文科省OBで早大に再就職していた元職員を仲介とする虚偽の再就職等経緯を作り上げ、その旨関係者に供述させるなど、関係者と当該事案の隠蔽(いんぺい)を図った。
エ 豊岡宏規人事課長は、上記ア及びイの再就職等規制違反行為を認知し、部下である人事課職員によるウの隠蔽行為を認知したにもかかわらず、かえってこれを黙認し、上記ウの隠蔽行為に加担した。
オ 当委員会の上記アからエまでの調査過程において、文科省大臣官房人事課は、元人事課職員の文科省OBに対し、法人等からもたらされた求人情報や、現職・退職予定者・OBの個人情報等、さまざまな情報を伝え、OBによる再就職あっせんを行わせていたことが判明した。これは、法が定める再就職等規制違反を潜脱する目的をもって、当該枠組みを構築して運用していたものであった。
カ さらに、当時の前川喜平文科審議官は、上記オの枠組みを利用して再就職あっせんに関わっていたほか、ある法人に再就職していた文科省OBに対し、後任に他の文科省OBを再就職させることを目的として、その退任の意向の有無を確認して、再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、また、文科省退職予定の出向職員に退職後の再就職先を示して意向を打診し、それをOBを介して再就職先に伝えるなど、法106条の2に違反したものと認定した。
また、同様に人事課職員3人も上記オの枠組みを利用した再就職のあっせんにおいて自ら違反行為を行ったものである。
東芝製品が家には多いが、今後は徐々に減っていくと思う。アフターサービスや将来を考えると切り替えている方が良さそうだ。
東芝が抱える闇は深い。昨年末、1000億円単位の特別損失発生が明らかになり、上場廃止の瀬戸際に立たされている。その窮地を救うため、みずほ銀行など主力3行が1月10日に資金支援の継続を表明した。だが、実は、東芝はメインバンクはおろか、マスコミも一切知らない“データ捏造事件”を隠蔽し続けているという。
エネルギー関連機器を製造する東芝京浜事業所。去る12月28日、「コンプライアンス問題と再発防止並びに会社状況」なる説明集会が開かれた。
「京浜事業所では、深刻な問題が発生しています」
会の冒頭、京浜事業所の所長が発した言葉に、出席した部長級の管理職たちは表情を強張らせた。
「水力発電所の機器に対する非破壊検査、NDEにおいてデータの捏造がありました。顧客の立会検査の数日前、品質保証部の担当者が機器の一部でNDEがなされていないことに気づき、上司である主務に報告。ところが、その上司は実際には実施していないNDEデータの捏造を指示したことを確認しました」(同)
ちなみに、主務は係長クラスのベテラン社員。データの捏造を行った担当者は、非正規社員だった。所長が沈痛な面持ちで続ける。
「さらに、その担当者が溶接部分の外観不良にも気づいたので、改めて上司である主務に報告すると、“そこは検査項目に入っていない。見つからないのを期待して、検査に臨もう”といっていたのです」
だが、そんな愚かな期待は呆気なく砕けた。東芝の技術職社員がこう嘆く。
「案の定、立会検査で顧客が溶接の不具合を指摘。挙句、その場でNDEが行われてデータ捏造も発覚したわけです。捏造は言語道断ですが、素人でもわかるような溶接の不良品を納入しようとしたとは……。“技術の東芝”のプライドは、どこへ行ってしまったのでしょうか」
■原発へも波及
東芝社内で“最後の砦”と呼ばれる品質保証部での捏造事件。その衝撃は決して小さくなく、京浜事業所の所長は水力部門の“ストップワークオーダー”を指示したという。東芝本社の管理部門に所属する社員も困惑顔で、
「ストップワークオーダーは、顧客から注文のあった仕事をすべて中止することで、操業停止に等しい大事件。上層部は、この捏造事件の責任を品質保証部の2人に押し付けようとしているのです」
確かに、データを捏造したのは品質保証部の2人。だが、溶接など他部門の社員も関わっていたことは否めないはずだ。しかも、東芝は捏造事件を闇に葬ろうとしているフシがあり、現在も公表していない。
「データ捏造が発覚した直後、役員が客先へ出向いて平謝りしたそうです。機器を作り直して納入しましたが、それで顧客が納得するはずがない。というのも、その企業は水力発電のみならず、原子力発電事業も手掛けているので、“原発は大丈夫か”となったのです。早ければ今月下旬から、その企業に納入している原発機器のデータ確認作業を実施するように指示されています」(先の技術職社員)
東芝へ水力発電機器を発注した企業は、“捏造事件”の事実を認めている。では、当事者はどうか。
「データ捏造が発覚したのは昨年11月末頃。公表しなかった理由は、個別のお客様との取引に関する内容だからです」(東芝広報・IR部)
目下、東芝株は投資家へ取引の注意喚起を促す「特設注意市場銘柄」。その解除を目指して、東芝は“企業統治改善”の確認書を3月15日以降に東証へ提出する見通しだ。しかし、隠蔽はこの通りまだ行われているのだ。
「週刊新潮」2017年1月26日号 掲載
男は女子高校生の隣に座っていた母親に取り押さえられました。
農林中央金庫の副部長の男は16日夜、JR総武線の新小岩駅から市川駅までの電車内で、約4分間にわたって16歳の女子高校生の下半身を触った疑いが持たれています。警察によりますと、女子高校生は席に座って寝ていましたが、男に尻を触られていることに気付いて目を覚まし、隣に座っていた母親に「痴漢に遭っている」とささやきました。母親が確認すると、男が尻を触り続けていたため、男をその場で取り押さえたということです。男は「酒に酔っていて自分を抑えられなかった」と容疑を認めています。
「詳細は言えない」(広報)の部分が仕方がなく処分したと受け取れる感じがする。
広告大手の電通は18日、新入社員の過労自殺問題で、労務担当の中本祥一副社長ら役員5人を、3カ月間20%の報酬減額処分にすると発表した。電通の長時間労働問題を巡っては、石井直社長が昨年12月に引責辞任を表明している。
電通では2015年12月、新入社員の高橋まつりさん(当時24)が過労で自殺。東京労働局が16年12月、社員に違法な長時間労働をさせた労働基準法違反の疑いで、法人としての電通と、東京本社の幹部を東京地検に書類送検していた。
電通は18日、高橋さんの上司だった部長級以下3人の社員についても社内規則によって処分したと公表。ただ、「詳細は言えない」(広報)として内容は明らかにしなかった。
東京・築地市場の移転先となる豊洲市場の第9回地下水モニタリング調査の最終結果が14日、発表され、検出されないことが環境基準の猛毒の有害物質「シアン」が初めて検出された。環境基準の79倍のベンゼン、同3・8倍のヒ素も検出され、豊洲移転は、危機的状況に陥った。土壌汚染対策を検討する「専門家会議」は今回の数値を暫定扱いとし、3月までに再調査すると明言したが、次回も同様の結果が出た場合、豊洲移転は白紙となる可能性もある。
検査は、市場の敷地内201か所で地下水1リットルあたりの濃度を観測。この日発表された数値では、前回までの計8回で一度も検出されなかったシアンが、39か所で最大1・2ミリグラムが検出された。ベンゼンは基準値以上を35か所で、ヒ素は20か所で検出された。
「シアン」は、今回の場合は「全てのシアン化合物」のことを指す。特に有害性の強い物質とされ、青酸カリとして知られるシアン化カリウムなども含まれる。今回の調査の基準値は、ベンゼン、ヒ素、鉛は0・01ミリグラム、水銀が0・0005ミリグラムなのに対し、シアンは検出されるだけで即アウト。それだけ、出てはいけない代物だった。
この日午後に行われた専門家会議で、平田健正放送大和歌山学習センター所長は「異常な数値でビックリしている」と戸惑いを隠さなかった。過去7回目まではいずれも基準を下回っていた。8回目(昨年9月公表)の調査でもベンゼンは環境基準の1・4倍だっただけに「なぜこんなに急に上がったのか。こういう経験は今までない」と平田氏。あまりにも高すぎるため、今回の数値を「暫定値」とし、3月までに再調査する意向を示した。
委員からは前回調査後から地下水管理システムを稼働させたことや水を採取した観測用の井戸に原因があった可能性が挙げられた。精度を高めるため、次回は3団体に調査を依頼するという。
小池百合子知事(64)はこの日「厳しい結果で、想定を超える高い数値が出て驚いている」と険しい表情で語った。「専門家会議の議論を参考にしたい」と述べるにとどめたが、次回の調査で同様の結果なら、豊洲移転自体がとん挫する可能性もある。
白紙撤回を避けることができたとしても、移転時期は大幅に遅れることは確実。最短で今年末に開場する見通しだったが今回の「暫定値」がそのまま確定となり、6月の環境アセスメントをクリアできなかった場合は、19年春以降にずれ込むことになる。
築地市場の業者には「これでは、とても移転できない」など憤りと動揺が広がった。水産仲卸会社社長の山崎康弘さん(47)は「(都が)改ざんしていたと疑われても仕方ない。何より消費者が納得しない」と語気を強めた。豊洲移転問題の出口は、まだ見えない。
「タカタの米国拠点があるミシガン州の連邦大陪審が、昨年12月7日付で起訴した。米司法省は『身柄の確保に向けて、日本の警察当局と協力する』としている。」
チリ人の男が殺人の疑いで国際手配されている事件で、日本政府はチリ政府に協力を要請するため、外務省の薗浦副大臣を現地に派遣 するらしいが、日本は米司法省に協力するのだろうか?
元幹部、ナカ・シンイチ(59)、ナカジマ・ヒデオ(65)、チカライシ・ツネオ(61)は覚悟をした方が良いだろう。
【ニューヨーク=有光裕】タカタ製エアバッグの欠陥問題で、米司法省は13日、タカタの元幹部3人を詐欺罪などで起訴したことを明らかにした。
エアバッグの欠陥を知りながら、それを隠して自動車会社に販売し続けたという。3人は「橋を一緒に渡るしかない」との認識のもと、メールでのやり取りなどでは、欠陥隠しが外部に漏れないよう暗号を使っていた。
起訴状によると、元幹部3人はタナカ・シンイチ(59)、ナカジマ・ヒデオ(65)、チカライシ・ツネオ(61)の各氏。タカタの米国拠点があるミシガン州の連邦大陪審が、昨年12月7日付で起訴した。米司法省は「身柄の確保に向けて、日本の警察当局と協力する」としている。
運転中や運転可能な全国の商用原発42基のうち40基で、重要設備である中央制御室の空調換気配管の詳細な点検が行われていなかったことが14日、原発を保有する電力9社と日本原子力発電への取材で分かった。
中国電力島根原発2号機(松江市)の換気配管では腐食による穴が多数見つかっており、事故が起きた場合に機能を維持できない恐れがある。
中国電は昨年12月、運転開始後初めて島根2号機で配管に巻かれた保温材を外し、腐食や穴を発見。必要な機能を満たしていないと判断し、原子力規制委員会に報告した。再稼働した九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県)や関西電力高浜原発3、4号機(福井県)、四国電力伊方原発3号機(愛媛県)の点検でも保温材を外していない。点検方法は各社の判断に委ねられており、規制委は全国の原発の実態を確認する。
中央制御室は原発を運転・監視する中枢施設で、運転員が24時間常駐する。通常は配管を通じて外気を取り入れ換気するが、事故発生時には外気を遮断し、機密性を保つ機能が求められる。
原発を保有する各社によると、島根2号機と北陸電力志賀原発1号機(石川県)を除く40基で、保温材を外さないまま配管の外観点検が行われていた。40基には東京電力福島第2原発の4基も含まれる。外気取り入れ口付近の目視点検や異音検査などが実施された例はあったが、配管の保温材を全て外した上での目視確認は行っていなかった。
一方、北陸電は2003年に志賀1号機の配管でさびを発見。保温材を外して点検し、08年に取り換えた。
規制委は島根2号機で見つかった腐食について「規制基準に抵触する可能性がある」とみている。中国電は「海に近いため塩分を含んだ空気が配管に流れ込み、腐食が進んだ可能性がある」と説明している。
日本の原発は発電用タービンを回した蒸気を海水で冷却し循環させるため、海辺に立地している。
40基の内訳は北海道電力泊原発1~3号機、東北電力東通原発1号機、同女川原発1~3号機、東京電力福島第2原発1~4号機、同柏崎刈羽原発1~7号機、中部電力浜岡原発3~5号機、北陸電力志賀原発2号機、関西電力美浜原発3号機、同大飯原発1~4号機、同高浜原発1~4号機、四国電力伊方原発2、3号機、九州電力玄海原発2~4号機、同川内原発1、2号機、日本原子力発電東海第2原発、同敦賀原発2号機。
【パリ=三好益史、ニューヨーク=有光裕】フランス自動車大手ルノーが、ディーゼル車の排ガス規制を逃れるため不正を行っていた疑いがあるとして、仏検察当局が捜査に乗り出したことが分かった。
AFP通信などが13日、報じた。
同通信などによると、独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)による排ガス不正問題を受け、仏不正監視当局が昨年1月、パリ郊外のルノー本社などに立ち入り調査を実施。ルノーがVWと同様に、排ガス試験の際に有害物質を減らす違法なソフトウェアを搭載するなどして規制を逃れていた疑いがあるという。
米環境保護局(EPA)も12日、欧米自動車大手フィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCA)が、一部車種に、ディーゼルエンジンを制御するソフトウェアを無届けで搭載していたと発表した。
過去に調査した会社と今回調査した会社を呼んで公開で説明させて、聴衆やメディアを通して見た人達に判断してもらうとべきだと思う。おかしな事をしている 調査会社の説明で矛盾やおかしな所を指摘するメディアや人が出て来るはずである。
東京都の豊洲市場(江東区)の地下水モニタリング調査で環境基準値を大幅に超える有害物質が検出されたことが公表された14日の専門家会議(平田健正座長)。歯切れの悪い説明が続き、会場の築地市場(中央区)講堂に詰め掛けた市場業者ら約100人は「これでは(市場ではなく)実験場だ」「都は信用できない」などと憤った。傍聴者の質問は途切れず、会議は4時間半に及んだ。
【写真で見る】怒り渦巻く…専門家会議の様子
「暫定値」「慎重に調べる必要がある」と繰り返す都の職員や有識者に対して発言の口火を切ったのは、移転推進派の伊藤裕康・築地市場協会会長。「これまで(のモニタリング)は惰性でやっていたのか。『大丈夫だろう』と安易な取り扱いをしていたんじゃないか」と、環境基準内に収まっていた過去の結果を疑問視。「なぜこうなったか包み隠さず知らせてほしいが、都に言っても適当にやるに決まっている」と不信感をあらわにした。
移転に慎重な立場の水産仲卸、山崎康弘さん(47)も「(過去の結果に)改ざんがあったと疑われても仕方がない。(豊洲市場に)行った後にこの数字が出なくて本当に良かった」と皮肉を込めた。
業者以外の傍聴者が「築地の方が豊洲よりも食品衛生上のリスクは高い」「地上(の汚染)はないから引っ越しても問題ない」と意見を挟む場面も。
一方、業者のいらだちは専門家会議にも向けられた。ある男性は「我々も(再調査に)専門家を推薦すべきじゃないか。その上で(豊洲に)行けると言われれば、安心できる」と発言。別の男性が「市場として移る場所じゃない。あそこはいくら(調査を)やっても無理だ」と突き放すと、同調して「無理だ、無理だ」とつぶやく業者もいた。想定外の結果に都の職員は「これでは都民の安心や納得を得られない。どうしたものか」と頭を抱える。
会場を後にした伊藤会長は報道陣に、あくまで年度内の移転判断を求めるとした上で、「早く(今回の結果の理由を)解明してほしい。風評(被害)とはこういう中で出てくる」と述べた。山崎さんは「僕らは安心も含めて魚を売っている。この状況で知事が安心宣言なんてできない。ならば(豊洲に)行くべきでない」と訴えた。【林田七恵、平塚雄太】
◇「理由分からない」専門家会議
平田座長らが会議後に開いた記者会見の主な内容は次の通り。
平田氏 高い値が出たので、どう受け止めるかというのがある。これまで月1回開催してきた会議は来月休会にして調べ直す。理由が分からないので、私たち自身も調査に立ち会って改めて調べ、納得した説明ができるようにしたい。
--報告書のとりまとめは遅れるか。
平田氏 若干遅れると思う。
--見通しは。
平田氏 何とも申し上げられない。
--今回は暫定値。どう理解すればいいのか。
都の担当者 まだ確認中ということ。
--数値は信じられないということか。
平田氏 そういうわけではない。今までと大きくかけ離れているので、何が起こったか含め、検証したい。
--これまでと違う会社が調査した。数値が調査会社によって大きく変化することはあり得るのか。
平田氏 基本的には変わらないはず。ただ採水の仕方などはいろいろある。
--事前に検証した上で、ちゃんとした数値を出すべきではなかったか。
平田氏 本日に出すと告知しており、そのままの数値を出すべきだと考えた。オープンに行っている。
--過去の調査についても調べ直すのか。
平田氏 試料がないものもあるだろうし、そこまではできない。
東京都の調査は明確な計測条件を少なくともメディアでは説明していない。誰がどのような経験や資格を持って計測しているのかもわからない。 データーを隠蔽しなくとも数値をコントロールする事は出来る。計測方法、計測場所、その他の条件を変更するだけで数値が変わる時は変わる。
今回は計測した担当が違う、計測した会社が違う、注目を浴びているので変な事をしたくない、ごまかしをしなかった、これまで指示を出した人が指示を出さなかった等の環境の変化が あると推測できる。
これまでの東京都職員の対応を考えると、不都合な件については適切な対応を取らないと考えた方が良いだろう。ここまで状況が進展している以上、中止するべきではないと思う。 ただ、ここで簡単に許すと前例が出来てしまうので、築地関係者達にとってはどうでも良いことかもしれないが、責任を追及して責任を取らせる(重い処分をする)で 幕引きするしかないと思う。重い処分を出すことによって、将来、不正に関与する職員の数は減るだろうし、重い処分を不服に思う職員が他にも関与した職員の名前や情報を 提供する可能性もある。これまでのようには簡単にごまかせない事を強く理解させる必要があると思う。
築地市場の移転先である豊洲で続いていた地下水調査の最終結果として、環境基準を大幅に上回る有害物質が検出されたことが発表された。その意味は何か。東京都の小池百合子知事が強調してきた「安全安心」は確保できるのか。【BuzzFeed Japan / 瀬谷 健介】
調査結果は、外部有識者からなる「専門家会議」が1月14日、築地市場で公表した。地下水の一部から、環境基準を上回る有害物質が検出された。
早期移転が期待されていたことから、発表会場は落胆の声に包まれた。
今後、専門家会議の立会いのもとで短期間のうちに追加で地下水を調査し、慎重に検証した上で、移転の可否を最終判断する方針が確認された。
建物の安全は確認されていた
築地市場の移転問題は、混迷している。
主要な建物の下に、あるはずの「盛り土」がないとわかって大騒ぎに。そこには、コンクリートに囲まれた「謎の空間」が設けられ、水が溜まっていた。
都のウェブサイトなどでは、敷地全体で盛り土がされている完成図が公表されていたこともあって、計画や発表と異なる実態に非難が相次いだ。計画と異なる建築の安全性とともに、溜まった水は「汚染された水ではないか」との指摘も出た。
豊洲市場の安全性を検証する都のチームは昨年10月、まず建物の安全性に関して「安全」だとの認識で一致した。地下空間が耐震性を下げるわけではなく、重機や水の重さで床が抜けることはない、と設計を担当した日建設計が説明。チームの専門家たちも、その考えに同意し、建物の安全性を確認した。
残るは、環境面への不安を払拭するだけだった。
そもそも環境基準とは
最終結果で基準値を上回った「環境基準」は、環境省が定めている。飲用を前提に、達成するのが望ましいとする値だ。
環境リスクマネジメントを専門とする横浜国立大名誉教授の浦野紘平さんは、BuzzFeed Newsの取材にこう語っていた。
「そもそも、あの地下水を飲むわけではないし、市場で使うわけでもないのだから、危険か安全かの議論で言えば、安全であると言えます」
「飲み水ではない地下水から、環境基準以上の数値が出ることは頻繁にある。『排水基準』を満たしていれば、河川などに流しても問題はありません」
この「排水基準」とは、工場などの設備から排出しても問題がないかの基準値のこと。環境基準のおよそ10倍の基準となっており、基準値以下なら外部に流しても良いという指標だ。
豊洲では地下水を使うことはない。飲用ではない地下水から環境基準を超える数値が出ても「安全」だ。
しかし、豊洲市場は念には念を入れ、建物下の地下水を環境基準以下に、建物外の地下水を排水基準以下にし、さらに処理をして将来的に環境基準を下回る値にする方針となっていた。
「安心」のためだ。
最終結果で急上昇した値に「ショッキングな状況」
地下水の最終調査では、昨年11月から豊洲の201カ所の井戸から採取した水を民間の検査機関が分析した。
その内、72カ所の井戸で、ベンゼンとシアン、ヒ素に関して環境基準を上回る数値が出た。ヒ素以外のものは10倍を上回る数値もあり、ベンゼンは最大で79倍が検出された。
シアンに関しては不検出であることが基準だが、最後の調査で初めて確認した。
これまでの調査で濃度が低かったが、最後の調査で急上昇している場所が多くあり、試料の採取方法などについて確認するために「暫定値」とした。
結果に対し、専門家会議の座長を務める平田健正・放送大和歌山学習センター所長はこう語った。
「かなり今までの傾向とは違った数値が出て、なんでだろうと思っている。なぜ急激に濃度が上がったのかを検証し、原因を究明する必要がある。移転ありきではないし、調査に少し時間をいただきたい」
事務局の土壌汚染対策に詳しい国際航業の中島誠フェローもこう落胆した。
「こんな上昇は経験がないし、ショッキングな状況。データは慎重に扱った方がいいし、暫定値で扱うのが妥当だ。全て確認する必要がある」
もう限界の築地に待ったなし
1935(昭和10)年に開場した築地市場は、もう限界を迎えている。
多くの施設は老朽化し、雨漏りだって日常茶飯事だ。「ターレー」と呼ばれる運搬車やフォークリフトが走り回る通路には、大小のくぼみがところどころにあるし、東日本大震災で本館の壁にひびが入るなどの被害に遭った。今後、予想される大地震に備え、耐震性への懸念もある。
応急処置に年間約1.5億円が費やされているが、修復が追いついていない現状にある。
築地市場の設備課長を務める吉田順一さんは、BuzzFeed Newsにこう諦めの声を上げていた。
「『築地は持ちますか』と質問されれば、現場で働く身からすると、『非常に厳しい』と答えるしかありません」
作業スペースが不足し、半屋外で魚をさばいたり、荷物を屋外に置くのも当たり前の光景だ。すぐ横では、トラックがアイドリングしており、吹きさらしの施設内に排気ガスが入り込む。
都の8月の調査では、空気中のベンゼン濃度は、環境基準を超えないまでも築地市場の方が豊洲よりも高い。
豊洲と同じように、建物や環境面の安全性に対する懸念があったから、移転が決まった。
移転は、いったいいつになるのか
小池百合子知事は、今夏に移転の可否や時期を決め、早くても2017年冬に豊洲に移転する見通しを示していた。
1月12日に知事就任以来、初めて築地市場の営業日に視察した時には、市場関係者の代表らと懇談し、移転時期を3月末までに決定するよう要請を受けた。
地下水の調査結果次第だとした上で、判断を前倒しする可能性も示していた。ところが、環境基準を上回る結果が出たこの日、地下水の追加調査が決まり、まず数値が急上昇した原因を究明する方針で決まった。
市場関係者から嘆きの声
築地市場協会の伊藤裕康会長は、会議でこう苦言を呈した。
「都の職員のやり方を信用してここまできたのに、(調査の)やり方を変えるのはおかしいんじゃないか。今になってこういう事態になって驚いているし、早くきちんと実態をつかんで、対策を考えてもらいたい」
ある仲卸業者の男性は、BuzzFeed Newsにこう嘆いた。
「環境基準を下回る最終結果が出て、さまざまな問題はあったけれども安全が担保できた、というのが、小池さんが望んだシナリオだったはず。でも、それが崩れ、延期を決めた小池さん自身を追い込む形になったのでは」
豊洲への移転が白紙になれば大きな混乱を招き、莫大な費用がさらにかかることや市場として設計された豊洲の買い手が見つからない不安も口にした。
「もう築地は限界を通り越している。移転が先延ばしにされればされるほど、市場関係者に金銭的な負担がのしかかる。小池さんが謝罪をして一から再スタートを切り、環境基準を排水基準に変えて、安全宣言を出すのが一番なんじゃないかな」
声を落としながら、小池知事の科学的な判断に期待を寄せる。
「どう冷静に対処するのかを見守るしかないね。都政の長として、市場関係者や都民を納得させるのも仕事のはずだ」
スマートフォンの出会い系アプリで知り合った10代の専門学校生の女性に車内で乱暴したとして奈良県警西和署は12日、強姦容疑で同県天理市西井戸堂町、団体職員、山田昌功(よしのり)容疑者(47)を逮捕した。「無理やり押さえつけてやったつもりはありません」などと容疑を否認しているという。
逮捕容疑は昨年11月中旬の午後10時ごろ、同県河合町内の施設駐車場に止めた軽自動車内で、助手席に座っていた10代後半の専門学校生の女性を押し倒し、性的暴行を加えたとしている。
同署によると、2人は出会い系アプリで知り合い、この日午後9時ごろに県内の駅で初めて会った。山田容疑者は「ドライブしよう」などと誘い、犯行に及んだという。
NHKは12日、福島放送局の20歳代の男性記者が、業務用タクシー券の不正な使用を繰り返していたと発表した。
この記者は、虚偽の勤務申請をして早朝や深夜の手当も不正に受け取っていた。不正額は、タクシー券の使用分と合わせて約20万円に上るという。NHKは内部調査を進め、近く記者を処分する方針。
NHKによると、タクシー券の不正使用は昨年の内部監査で発覚し、2015年7月頃から16年9月頃まで、約150回行われた。自宅から取材現場に行くなど、内規で認められていない用途で使用し、実際に乗降していない場所を記載するなどしていた。虚偽の勤務申請は約20日分あった。
NHKでは15年、さいたま放送局の記者3人によるタクシー券の私的使用が発覚。
厚生労働省神奈川労働局の藤沢労働基準監督署は11日、元社員の男性(31)に違法な長時間労働をさせたとして、大手電機メーカー三菱電機(本社・東京都千代田区)と労務管理担当の社員1人を労働基準法違反の疑いで横浜地検に書類送検し、発表した。三菱電機は「真摯(しんし)に受け止めている。改めて適切な労働時間管理を徹底していく」とのコメントを出した。
同局によると、同社は情報技術総合研究所(神奈川県鎌倉市)で働いていた研究職の男性に対し、2014年1月16日から同年2月15日まで、労使で定める上限(60時間)を超える違法な時間外労働(約18時間超過)をさせた疑いがある。
男性側によると、男性は精神疾患で同年6月から休業し、去年6月に解雇された。藤沢労働基準監督署は去年11月、月100時間を超えることもあった時間外労働など、長時間労働が精神疾患の原因だったとして、労災を認定した。
男性は2013年4月に三菱電機に入社。家電などに使うレーザーの研究開発を担当していた。労働時間の管理は自己申告制で、時間外労働は労基署に届け出た上限以内に抑えるように、上司から虚偽申告を指示されていたという。
組織や経営者は簡単には変わらない。
愛媛県の東予地区にある社会福祉法人の運営する保育園が、乳幼児突然死症候群(SIDS)の対策マニュアルの中で、園児の死亡事故が起きた場合は職員へ箝口(かんこう)令を敷くようにしていたことが、県の監査で分かった。また、東予地区の二つの社福法人の運営する高齢者介護施設では、入所者の死亡事故を県条例通り適切に報告していなかったことも判明。県はいずれについても改善を求めて指導した。
毎日新聞の情報公開請求に県が開示した監査に関する文書によると、社福法人が運営する東予地区の保育園で使われているSIDSマニュアルには、園児が死亡する事故が起きた際の職員の対応として、「(死亡事故についての)発言を一切控える(箝口令)」と記載されていた。
県は「組織的に情報発信を止めるのではなく、透明性の確保のため正確な情報発信に努める」ことを求め、マニュアルは不適切として改善を求めた。
県は条例や内規で、子どもや高齢者などが利用する施設などで死亡などの「重大事故」が起きた場合は、市町だけでなく県にも報告するよう定めている。
しかし、別の社福法人が運営する老人ホームでは、入浴中に心筋梗塞(こうそく)で入所者が死亡する事故が起きたのに、県に事故報告書を提出していなかった。さらに別の養護老人ホームでも、心筋梗塞による死亡事故を市には報告したが県には報告していなかった。
一方、県の文書によると、県は2016年4~10月、中核市の松山市にある施設を除く県内100の社福法人に定期監査を実施。事故に至らなかったものの、あと少しで事故になっていた「ヒヤリハット」の事案を報告書にきちんとまとめていなかった施設もあり、指導した。「事故に至るリスクを把握して事故を未然に防ぐため、ヒヤリハットを拾い上げる職員の意識向上を図ること」を求めた。【黒川優】
NHKの対応の不自然さに組織の自浄能力の欠如を感じる。中立性を一番保ちやすい組織であるはずなのにダークな部分を感じるのはなぜなのだろう。
昨秋、NHKで現役職員による「受信料着服」という前代未聞の事件が起きていたことが「週刊文春」の取材で明らかになった。
「横浜放送局営業部の職員A氏が受信料をネコババしていました。これまでにも制作費や取材費などの着服が発覚したことはありますが、現役の職員が受信料をそのまま懐に入れた事例は聞いたことがありません」(横浜放送局関係者)
別の横浜放送局関係者が、着服の手口を明かす。
「通常、視聴者は受信料を前払いしていますが、解約する場合、払い戻しのお金が発生します。A氏はそこに手をつけた。本来は解約者へ払い戻すべきお金を、自分の口座に振り込まれるよう操作していました」
事件の発覚直後から、NHK本部にある総合リスク管理室が調査に乗り出していたが、1回目の事情聴取を受けた直後、A氏は自殺を遂げていた。
問題なのは、その後のNHKの対応だ。
「着服事件、そして自殺の事実は徹底的に隠蔽されています。最大の問題は、明らかに懲戒処分に相当する事件にもかかわらず、A氏はもちろん、直属の上司から役員に至るまで、誰一人、処分を受けていないことです」(同前)
NHK広報局は、「すでに本人が亡くなっているため、お話しできることはありません」と回答した。
2004年7月、本誌が「紅白歌合戦」担当プロデューサーによる制作費着服事件を報じた際には、視聴者の間で受信料不払い運動が広がり、当時会長だった海老沢勝二氏が引責辞任に追い込まれている。NHKの経営陣は同じ過ちを繰り返すのだろうか。
籾井勝人会長(73)、次期会長である上田良一氏(67)、受信料を管轄する最高責任者の堂元光副会長(65)への直撃取材など、「週刊文春」1月11日発売号が詳報している。
<週刊文春2017年1月19日号『スクープ速報』より>
NHKは10日、横浜放送局営業部に所属していた40代の男性職員が受信料数十万円を着服していた疑いがあると発表した。職員は、NHKが調査を進めていた昨年10月中旬に死亡したという。
NHKによると、職員は平成27~28年、受信契約に関する架空の伝票を複数回にわたって作成。受信料を先払いしている受信契約者らの個人情報を悪用し、契約を解除したように装うなどして払戻金を着服していたとみられる。NHK広報部は、個人情報を悪用された契約者への影響は「ない」としている。
NHKは昨年10月に内部調査を始めたが、直後に職員は死亡した。NHKは今後も調査を続け、被害額を確定させた上で、遺族らに弁済を求める方針。NHKは「誠に遺憾であり、再発防止に努めます」としている。
政府系金融機関の商工組合中央金庫で景気悪化や災害時の国の制度融資の審査で不正が常態化している事は非常に残念だ。
しっかり調査して関与した職員を処分してほしい。不正に関与する職員は不正に関与する時点で不正を認識しているわけだから自業自得。
不正の「理由について『内部評価を得ること』『業績評価の対象となっていた』などと説明している。」
つまり、自己中心的な理由。処分を軽くする理由はない。
政府系金融機関の商工組合中央金庫(商工中金、社長=安達健祐元経済産業事務次官)は6日、景気悪化や災害時の国の制度融資の審査で不正があったと発表した。制度の適用を受けるため、職員が融資先の企業の資料を改ざんしていた。件数は判明した分だけで221件にのぼる。融資総額は公表していない。
不正は昨年10月に発覚し、12月に第三者委員会を設置した。現時点で鹿児島、岡山、名古屋、松本(長野県)の4支店で不正があったことが判明しているという。計15人の職員が、融資先の財務状況を示す資料などを改ざんしていた。業績が大きく悪化していないのに悪化したように見せかけるなどして、危機対応融資の適用を受けていた。今後の調査で不正の件数が増える可能性がある。
同融資は自然災害などで業績が悪化した企業に運転資金などを貸す制度。商工中金は国から利子補給が受けられ、貸し倒れの際の穴埋めもある。急な資金が必要な企業に貸しやすくする制度だが、基準を満たさない企業でも適用されるように不正を行っていた。理由について「内部評価を得ること」「業績評価の対象となっていた」などと説明している。
もしかすると良い部分しか見せない大学なのかもしれない。良い部分も悪い部分も知らないと正確な判断は下せない。情報操作を行って問題をソフトランディングさせても 根本的な問題は解決されないし、防止策を個々の生徒が考える事も出来ない。私立の大学であれば、経営者の意向が強く影響を与えるかもしれないが、国立大学で このような圧力が存在するのはおかしいと思う。
平穏な学習環境保持の考え方にも疑問を感じる。日本で紛争が起こってなければ平和なのであろうか?文化の違い、価値観の違い、政府の教育方針の違いが存在すれば、 相手がオープンマインドである、又は、文化の違い、価値観の違い、政府の教育方針の違いを外国での生活や外国人の友人や知り合いを通して知っていなければ、 相互理解は難しい事を理解できないであろう。自分達の常識や価値観が正しいと思えば、違いがある相手を理解する、又は、妥協点を提案する事は出来ない。
次に同じような悲劇が起こればダメ押しになるので、筑波大も何かを学ぶであろう。まあ、同じような状況が存在しても、今回と同じような結末になるとは限らないので 外部の人にとっては何もわからないかもしれない。
5日朝、筑波大学の学生に2人の副学長から相次いで一斉メールが届いた。いずれも同大の女子学生がフランス留学中に行方不明になった事件に関するものであり、日本語が得意でない外国人学生に対する配慮から、日本語だけでなく、英語でも書かれていた。草の根国際交流の最前線にいる学生の身の安全に配慮した注意喚起かと思って読み進めると、あまりにも予想外の内容にこの学生は驚かされた。
まず、広報担当副学長からのメールは、不明学生を知る学生、教職員からのコメントを求めるマスコミからの要請に拒否を貫いていることを明らかにしていた。拒否の理由として、家族の心情、捜査段階であること、平穏な学習環境保持の3点への配慮が挙げられている。
さらに、構内における無許可の取材が複数確認されたとしたうえで、「学生の皆さんにあっては、マスコミからの問い合わせ等でお困りのことがありましたら、ご遠慮なく広報室にご相談ください」と締めていた。
次の学生担当副学長からのメールは「メディアからのインタビューに対しどのような対応をしていいのか悩んでいる人も多いかと思います」という文章で始まっていた。続けて、フランスの捜査当局が殺人事件として捜査していることを根拠にして、「情報の第一の提供先はメディアではなく捜査当局です」(英文:Information must be first provided to the investigating authorities and not the media.)と教示している。
さらに、メディアに提供した情報が思わぬ形で伝えられたり、不明学生の家族や容疑者にも伝わったりする可能性を指摘したうえで、「皆さんが報道機関の問い合わせに答えなくても、ネガティブに考える必要はありません」として、取材に応じないことを是としている。
これら2本のメールに書いてあることを要約すれば、マスコミというのは大学当局の言うとおりに取材も報道もしてくれない迷惑な存在であり、学生の皆さんも報道機関は相手にせず、情報は捜査当局に伝えてくださいということである。メディアに対する敵意に近い感情が伝わってくる。
筑波キャンパスは塀や壁に囲まれていない構造のため、誰でも自由に中に入ることができる。2016年5月時点の外国人留学生の数は2326人であり、全学生のほぼ7人に1人を占める。キャンパスを歩けば、国際色の豊かさが容易に感じられる。不明学生を知る学生、教職員からのコメントを大学当局に拒否されたメディアがキャンパスでコメント取りに走ることは自然な成り行きであろう。
大学が情報公開を拒否すれば、インターネット上で不確実な情報が飛び交う事態も招いてしまう。実際、ネット上では仏当局から手配されているチリ人男性の名前などが、流れている。
そもそも大学当局はなぜそこまで取材を嫌がるのか。もし国際指名手配されているチリ人男性についての過去の情報を持っているのであれば、大学として公開すべきではないか。それを説明することで、捜査に悪影響が生じ、学習環境が乱されるとは考えにくい。筑波キャンパスでの不明学生の積極的な活動ぶりを伝えることも、家族が了解するなら可能だろう。
さらに、今後、学生の国際交流を推進するためにも今回の事件が持つ意味は大きい。何が起こったのか、何に注意すればよかったのか、情報を正確に伝えることで、事件の再発を防ぐことができる。
それが報道機関の役割であり、筑波大学にもそうした職にあこがれる学生は少なくない。取材に応じるかどうかは学生個人の自由だ。中高生相手ならまだしも、ソーシャルメディアに習熟し、ある程度の学力があると考えられている大学生に対する今回の「教育」はあまりにお粗末だ。
筑波キャンパスに塀や壁がないことにはすでに触れたが、元霞が関官僚によると、このことは大学の歴史と関係があるという。同大学が発足した1973年は激しかった学生運動の記憶が生々しく残っていた時代である。そのときの経験から、機動隊が容易に突入しやすい構造が好まれたという。
事の真偽はともあれ、それがいまや筑波大のオープンな空気につながっているのだから、情報に対しても大学はオープンな姿勢を保つべきだろう。
大崎薫(フリーライター)
大阪大と企業の共同研究を巡る汚職事件で、贈賄側の3社が、同大大学院教授の倉本洋容疑者(57)=収賄容疑で逮捕=に共同研究に対する謝礼金の支払いを持ちかけていたことが6日、捜査関係者への取材で分かった。金額も3社が提示し、倉本容疑者は私的な口座を入金先に指定して受け取っていた。
大阪府警は、建築耐震工学の権威だった倉本容疑者との共同研究に対する謝礼として、企業側が技術指導料などの名目で賄賂を振り込んだとみている。
捜査関係者らによると、建設部材会社「JFEテクノワイヤ」(千葉市)の担当社員らは2014年ごろ、半年当たり約60万円を「技術指導料」として支払うと提案。倉本容疑者は、妻が代表を務めるCES構造研究所の口座に入金を指示し、3回にわたり計約190万円を受け取った。
倉本容疑者は15年から大学に無断で共同研究を開始。共同研究では本来、大学が管理する口座に研究費を支払わなければならず、府警は研究費とともに入金されたこの約190万円を賄賂と判断した。
倉本容疑者は中堅ゼネコン2社からも賄賂を受け取ったとして逮捕・起訴されている。倉本容疑者はこの2社の担当社員からも指導料などの名目で共同研究の謝礼を提示され、CES社と個人口座に計約780万円を振り込ませていた。
一方、テクノワイヤ社は「技術指導料は大学外で受けていたアドバイスへの対価で、共同研究への謝礼は一切ない」と釈明している。【池田知広、戸上文恵】
大阪大と企業との共同研究を巡る汚職事件で、収賄容疑で再逮捕された同大大学院教授の倉本洋容疑者(57)が、大学に無断で進めていた建設部材会社「JFEテクノワイヤ」(千葉市)との共同研究を途中で正式な研究に切り替えていたことが5日、捜査関係者への取材で分かった。この直前、同大で別の教授の不正経理問題が発覚しており、大阪府警は倉本容疑者が自身の不正な研究の発覚を隠そうとしたとみている。
大阪大と企業の共同研究を巡る汚職事件で、同大大学院教授の倉本洋被告(57)=収賄罪などで起訴・休職中=が、建設部材会社「JFEテクノワイヤ」(千葉市)と共同研究を進める見返りに計約190万円の賄賂を受け取ったとして、大阪府警捜査2課は5日、倉本被告を収賄容疑で、同社役員ら2人を贈賄容疑で逮捕した。倉本容疑者は別の汚職事件でも立件されており、逮捕は3回目。贈賄容疑で逮捕されたのは、同社常務取締役の藤本隆史(62)=千葉県市川市=と同社担当営業部長の坂下幹雄(61)=千葉市=の両容疑者。
逮捕容疑は2015~16年、耐震技術の共同研究を同社と進める見返りに、計約190万円を3回にわたって受け取ったとしている。共同研究は当初、大学に届けずに無断で実施された。
同社は鉄鋼大手「JFEスチール」(東京都)の子会社で、15年以降、鉄筋を補強する金属の強度を検証するなどの共同研究を倉本容疑者と続けていた。賄賂は「技術指導料」名目だったが、同社は倉本容疑者への謝礼として正式に決裁して支払っていた。【池田知広、戸上文恵】
「警察によると、企業側は倉本容疑者に対し『技術指導料』として賄賂を渡すなど積極的な手続きを会社ぐるみでしていて、組織的な関与が強いことが新たにわかりました。」 JFEテクノワイヤ がJFEグループだったら恥ずかしい事だ。K(工場は)I(一流)R(利益も)A(安全も)R(R&D:研究開発も)I(1番に) の中にはモラルとか、コーポレートガバナンスが記載されていないから、利益1番との理由で賄賂を決断したのだろうか?
JFEテクノワイヤは2000年10月にISO9001認定を取得している。 ISO9001認定の範囲がどこまでかは知らないが、大学の実験施設を利用する活動は認定に部分的に入っているような気がする。 もしそうだとすれば、内部監査や記録も偽装したのか?
JFEグループは大きいので大学の実験施設を使用する費用を節約する必要などないと思う。何らかの理由で大阪大学大学院工学研究科教授・倉本洋容疑者との関係を深めるために 個人的な利益の提供が賄賂となったのではないのだろうか?
事実は警察が捜査して公表するだろう。
共同研究をめぐり、建設会社から賄賂を受け取ったとされる大阪大学の教授が、別の企業からも賄賂を受け取っていた疑いが強まり、再逮捕されました。
会社ぐるみの関与が疑われています。
収賄の疑いで再逮捕されたのは、大阪大学大学院工学研究科教授・倉本洋容疑者(57)です。
また千葉市に本社を置くJFEテクノワイヤの常務・藤本隆史容疑者(62)ら2人も、贈賄の疑いで逮捕されました。
倉本容疑者はおととし6月からの1年間、JFEテクノワイヤと共同研究を行い、大学の実験施設を利用させたりした見返りに、約190万円を受け取った疑いがもたれています。
また警察によると、企業側は倉本容疑者に対し「技術指導料」として賄賂を渡すなど積極的な手続きを会社ぐるみでしていて、組織的な関与が強いことが新たにわかりました。
警察は他にも余罪がないか追及する方針です。
「摩耶堂製薬は去年2月、違反行為を県に自主申告していて、商品の回収も既に完了したということです。」
神戸市西区の「摩耶堂製薬」は製薬会社。有効成分が最大4割減っていると言う事はありえるのか?原料の購入量、使用量、製造のマニュアルや記録で間違いが起こったとすれば 直ぐにわかる事。理由が企業側での調査で分からない事自体が信用できない。実行者や指示を出した人間をかばっているとしか思えない。
自主申告まで誰も問題に気付かなかったと言う事は行政によるチェックは機能していないと言える。これば不正の原因の一部ではないのか。摩耶堂製薬の誰かが 問題を指摘して不正を告白したと個人的な推測をする。自主申告だったので行政も重い処分はしないと言う事ではないのか?
有効成分を最大4割減らして薬を製造していたなどとして、神戸市の製薬会社が業務停止命令を受けました。
医薬品医療機器法違反で17日間の業務停止命令を受けたのは、神戸市西区の製薬会社「摩耶堂製薬」です。
兵庫県によると、摩耶堂製薬は男性向けの精力剤「金蛇精」などについて、厚労相の承認を受けた内容よりも有効成分を最大4割減らして製造・販売したなどとされます。
「金蛇精」は1965年に承認を受けていますが、有効成分を減らした理由などについては企業側の調査でも分からず、県は長期間にわたって違反行為が行われていたとみています。
摩耶堂製薬は去年2月、違反行為を県に自主申告していて、商品の回収も既に完了したということです。
摩耶堂製薬は「再発防止と信頼回復に全力で取り組む」とコメントしています。
被害者や被害者家族はいつもでも忘れる事は出来ないだろう。しかし、問題は知らないだけでいろいろな所に潜んでいると思う。問題が原因でどのような事件が起こるのか、 被害が出るのか出ないかの結果が未来形だけの多くの人が気付かない事はたくさんあると思う。
長野県軽井沢町で大学生ら15人が死亡したバス事故で、運転手が大型バスに不慣れなことを知りながら指導せず、運転させたとして、長野県警が業務上過失致死傷の疑いで、バスを運行した「イーエスピー」(東京)の幹部や当時の運行管理者を立件する方向で捜査していることが2日、捜査関係者への取材で分かった。
〔写真特集〕軽井沢でスキーバス転落~15人死亡、27人重軽傷~
検察と最終的な協議をした上で、立件の可否を判断する。
県警は、イー社が適切な指導を怠り、重大な事故が起きる可能性を予見できたにもかかわらず、乗務させたとみているもようだ。死亡した運転手=当時(65)=については、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)容疑で容疑者死亡のまま書類送検する方針。
事故は2016年1月15日未明、長野県軽井沢町の峠の下り坂カーブで発生。スキーバスがガードレールをなぎ倒し、崖下に転落した。乗客の大学生13人と乗員2人が死亡、26人が重軽傷を負った。
県警が実況見分やバスを検証した結果、バスの転落直前の時速は制限速度50キロを大幅に超える96キロで、ギアがエンジンブレーキの効かないニュートラルになっていたことが判明。県警は大型バスに不慣れな運転手が運転操作を誤り、下り坂でバスを制御できなくなり、カーブを曲がり切れず転落したとみている。
運転手は15年12月、イー社の採用面接の際、「大型車の経験は少なく、中型車に乗っていた」「大型バスの運転は苦手だ」などと話していたとされる。また、同社が同運転手に行った実車訓練は1回だけだったという。
新入社員の高橋まつりさん(当時24歳)の過労自殺問題で揺れた国内最大手の広告代理店・電通。12月28日、緊急の記者会見を開き、石井直社長が、一連の過労自殺など長時間労働問題の責任を取るとして、辞任する意向を示した。
現役社員は、この会見をどう受け止めたのか?【BuzzFeed Japan / 石戸諭、播磨谷拓巳】
社員に送られたメール
BuzzFeed Newsは、石井社長から社員にあてられたメール全文を入手した。そこにはこんな言葉が並ぶ。
**
当社が、過去に当局から複数回にわたる指導・勧告を受けていたにもかかわらず、当社における過重労働、長時間労働問題を根本的に解決できなかった責任は、改めて申し上げるまでもなく、経営にあります。そして、必要な変革を十分に達成できなかった全ての責任は、社の経営において最も重い責任を担っている私にあると考えています。
そのため、私は、その全ての責任を取り、2017 年1 月に開催される取締役会をもって、社長執行役員を辞任することを決意致しました。株主への説明責任を果たすため、社長執行役員辞任後も、取締役としては留まりますが、来年3 月に予定している定時株主総会の終了をもって、取締役も退任します。
**
「あれから電通はまったく変わってない」 突然の社長辞任、現役社員はどう受け止めた?
現役社員は何を思うのか?
現役の男性社員がBuzzFeed Newsの取材に応じた。
この日は、例年と違う仕事納めの1日だった。報道が先行し、電通の対応やコメントはすべてニュースを通じて入ってきた。いつもなら、午後3時には仕事を切り上げ、残った社員でケータリングで食べ物や酒をいれて、社内で乾杯をする。
今年は前と同じように、とはいかなかった。辞任の一報はすぐに社内を駆け巡った。
「驚いている社員が多かったけど、自分はむしろ、どうでもいいと思いました。それは、仕事の内容が変わらないからです。電通はまったく変わっていません。仕事内容は変わらずに残ったままなのです」
「だから、私も、他の社員も会社にはいないけど、持ち帰って残業しています。仕事は変わらずにありますからね」
「時間を減らせ」と会社から指示があっても、現場に人は増えていない。記録には残らないだけで、むしろサービス残業は増えているのではないかという。
電通社内ではこんな囁きも聞こえてくる。法令違反をしていたら、国の仕事がとれなくなる。だから、なんとしても法律は守らないといけないのだ、と。
「結局、リリースをみても、会見を聞いても、経営は手を打っているのに、社員が方針を守ってくれなかったという風に聞こえます。社員のために法律を守れというなら、人を増やすべきです。仕事は変わらないけど、時間は減らせ、人は増やさないでは掛け声で終わります。本当に必要なのは、根本的な改革ですよ」
根本的な改革とはなにか?
「(会見で)『未熟な新入社員』という言葉を連呼していましたよね。でも、新入社員が未熟なのは、当たり前じゃないですか?どう教育するかが本質なのに……」
「適切な教育がなかったら、先輩の背中をみて学べというスタイルから、いつまでも脱却できない。新人教育については、いまでも社内では議論されていません。社員が財産というなら、そこを語ってほしいです」
そして、こう付け加える。
「私は、いまでも電通の提供する仕事には価値があると思っています。だからこそ社員自身も法令違反当たり前、時間際限なく使って当たり前、を改めながら改革したいと考えていますし、実際に動いている。少しでもよくしたいと思うのです」
「120%の成果を求める、仕事を断らない矜持……そのすべてが過剰だった」
電通はプレスリリースのなかで、長時間労働の原因をこう総括した。
原因としては、「過剰なクオリティ志向」「過剰な現場主義」「強すぎる上下関係」など、当社独自の企業風土が大きな影響を与えていると考えております。
石井社長は記者会見の中で、日本社会の働き方と企業風土をどうみているか問われ、こう答えた。
「日本人の勤勉さは高く評価しているし、大事なことだと思います。しかし、心身あわせた健康を考えることが大事だと思っています」
「(電通は)プロフェッショナリズムを社員が強く意識している。120%の成果を求めようという傾向がある。仕事を断らないという矜持があった。そのすべてが過剰だった。過ぎていたということ。そのことに対して根本的なところで歯止めをかけられなかった、経営の責任がある」
記者がどのような意図でこのような表現にしたのだろうか?
真実はわからないであろう。愛情を持っていたが厳しいタイプ、特に理由のない体育会系タイプ、自己中心的で他人に厳しいタイプ、過去に自分が受けた体験又は周りが受けていた体験を 実行しているタイプなどいろいろなタイプがある。これにストレスを受けている環境とか、出世が気になっていた、個人的に高橋さんが好きでないタイプだったとか、他の 条件などで複雑に絡み合っているうえに、高橋さんが反応が最悪の結果で終わったと思う。
証拠、証言、他人に話した話として表に出ていない部分については闇の中。
これだけ注目を浴びても入社したいと思う学生が極端に減らなければ会社だけの問題ではなく、日本の社会そして個人の価値観の問題にもあると思う。 このような会社や組織でも名前さえ有名であれば問題ないと思う考え方が蔓延していると思う。
高橋まつりの親は広告代理店最大手「電通」の真の姿を知っていたのか?知らなかったから娘が「電通」に入社する決断をした時に反対しなかったのか?知っていたが まさか娘がこのような結末を迎えるとは思わなかったのか?この事件が法的な終わりとなったら記事か、何らかの形で公表してほしい。
石井直社長の辞任表明に報道陣がざわつき、カメラのストロボが次々たかれる中、会見は質疑応答へと移った。主なやり取りは以下の通り。
◇
--サービス残業や勤務時間の過少申告は、上司の命令で行われていたのではないか
中本祥一副社長 基本的には「三六協定」に違反する以上に、労働への対価を払わないことの方が良くない、悪いことだというのが会社の意識だった。したがって、三六協定の違反者に対しても残業手当は無制限に支給していた。
管理職が残業時間を登録しないよう指示したという事実は、外部調査でも見つかっていない。自らサービス残業をした人もいたが、「上の命令に基づくものではない」との報告を受けている。
--「パワハラとの指摘も否定できない行き過ぎた指導」とは?
中本副社長 一つの事例として、新入社員に対する仕事の与え方として不適切だった。
具体的には「仕事の報告を明朝までに仕上げるように」との指示を、深夜または朝に近いような時間帯に行ったりしていた。物の言い方、言う場所、時間帯も高橋さんにとって重荷になっていた。
上司にも「高橋さんを早く一人前にしたい」との思いはあったかもしれないが、業務に未熟な社員であることを踏まえ、もう少し愛情を持って、いたわるような指導ができたのではないかと考えている。
石井社長 入社間もない社員が懸命に仕事をしている中で、ベテランの社員に対するのと同様の指導が行われていた。そうした点は「パワハラ」と指摘されても仕方ないと思っている。
--12月25日の一周忌にご遺族を弔問したとのことだが、どんなやり取りを
石井社長 ご遺族にお会いし、ご冥福をお祈りすると共に、心から謝罪を申し上げた。ただ詳しいやり取りは控えさせていただきたい。
--高橋まつりさんの母が今月25日に手記を公表したが読んだか。感想は?
石井社長 読ませていただいた。私どもの「制度」以前に、まず「意識」を変えなくてはいけないと痛感した。
--きょう書類送検された人物は
中本副社長 高橋まつりさんの当時の上司だった男性社員である、と理解している。それ以上は控えさせていただきたい。
--石井社長が辞意を固めたのはいつか
石井社長 この数日間です。まずご遺族に謝罪させていただけるよう、再三お願いしていたが、なかなか許可をいただけなかった。しかしこの25日に直接おわびを申し上げることができた。また本日、当局による処分、書類送検が行われた。こうしたことから辞任を決意した。
--新社長は誰に
石井社長 まだ白紙です。
大手広告代理店・電通は9月23日、緊急の記者会見を開き、インターネット上の広告掲載をめぐって、虚偽報告など、不正な取引があったことを認めた。対象は111社、その中にはトヨタ自動車など大手企業も含まれ、総額は2億3000万円に達する。ネット広告関係者の間では「業界に不透明な取引が横行していることが背景にある」と声が上がっている。【BuzzFeed Japan / 石戸諭、井指啓吾】
ネット広告の信頼を揺るがした電通
この日、東京証券取引所の会見場に姿を見せた電通の中本祥一副社長は終始、厳しい表情を崩さなかった。「(広告主に)虚偽の報告をしたことも、正しくないという意味で、不正ともいえる。不適切としているが、言葉の使い方という意味では、不正」と、一連の問題で不正な取引があったことを認め、謝罪をした。
最大の問題は、広告主と広告を出す企業の中間にいる、電通がありもしない成果を報告し、ネット広告の信頼を揺るがしたことにある。
広告主の疑問「掲出されているはずの期間なのに、掲出されていないのではないか」
今回の経緯を整理する。
発端は今年7月だ。広告主から指摘が入ったことにある。
電通側は記者会見で、この広告主を「新聞に書くことは避けていただければ」と言いつつ、「トヨタ自動車さんからの指摘が最初であります」と語った。
BuzzFeed Newsは電通側の証言が事実なのか、トヨタに取材した。トヨタの広報担当者は「(電通から)デジタル取引において問題があったとの報告はありました。それ以上のことはお答えできません」とコメントした。
電通の会見に戻る。なぜ広告主は指摘をしたのか。
「広告が掲載されることによる効果を期待されていたが、効果が一向に上がらない。本来効果が上がるべきところに、広告を出しているはずなのに、効果が上がらない。正しく、期待通りの広告の掲出ができているかという疑義が生じたことが発端だとうかがっている」(電通)という。

そもそも「広告が掲出されているはずの期間なのに、掲出されていないのではないか、という指摘があった」。
故意のレポート改ざん「悪意が認められる」
日本の広告業界では、広告主がトヨタのような大企業の場合、広告を掲載するネットメディアが直接取引をすることは、あまりない。これはインターネット広告の世界に限らないが、電通など広告代理店が、双方の中間に立って取引をしている。
電通は、広告主から予算と目的にあわせてネットメディアから広告枠を購入する。ネットメディアからは、広告主にかわって広告の成果(表示回数、クリックされた回数など)を受け取り、運用レポートをまとめて報告する。ここまでが一連の流れだ。
広告主が期待した効果がでなかった場合、問い合わせは電通に向かう。
ここで、電通の不正が発覚した。社内調査で、実際には達成できなかった成果、偽った成果で、架空の報告、請求書が広告主に送られていたことが判明。疑義がある案件は、1社にとどまらず、111社分に広がった。
電通側の説明はこうだ。
「最初から悪意が認められたものはない。力量や時間の余裕が足りていないことを原因とした単純なミスから始まって、後からそのミスに気づいて、それに対して、故意にレポートを改ざんしていく、という悪意は認められている」(山本敏博常務)
レポート改ざんの背景
なぜ、故意にレポートを改ざんできるのか。背景にネット広告の仕組みがある。
インターネット広告は、テレビや新聞などと違い、独特の広告枠購入の仕組みがある。現在、主流となっている運用型広告がそれだ。枠ごとにオークションをして、より高く入札したところが、その枠を買う。決まった料金はなく、価格は常に変動する。
競争相手よりも高く入札しないといけないので、予算枠のなかで、希望した広告枠が買えないというデメリットがある。その一方で、顧客情報を集約し、性別ごと、年齢ごと、時間帯ごと、検索している言葉ごと、細かいターゲット設定が可能になるというメリットもある。
例えば、どこか出張にいこうと思って、大阪のホテルを検索したとする。その後しばらく、検索するたびに、広告枠に旅行や大阪に関連する情報が流れてくるという経験は、多くの人にあるだろう。
なんの関心もない人に広告を流すよりも、クリックされる回数も増える。
幅広い層をターゲットに「薄く・広く」広告を打つよりも、必要としている人をターゲットに「狭く・深く」流す。そのほうが、効率がよく、広告効果もあるというわけだ。
ネット広告の強みは情報。それが改ざんされていたら……
ネットメディアは、実際に広告がどれだけ表示されたのか、どれだけクリックされたかなど、可視化された情報を持っている。広告主はこれを知れば、もっと効率的に広告を流すことができ、ネットメディアは自分たちが広告を流すに価する企業であることもアピールできる。
広告主側もメリットを感じているのだろう。電通が毎年まとめる「日本の広告費」によると、2015年の国内ネット広告費は前年から10%以上伸びて、約1兆1594億円。テレビ(1兆9323億円)には及ばないが、5679億円だった新聞以上の規模に成長している。
しかし、その実態はどうか。広告主とネットメディアに直接の取引がない場合は、広告主が直接配信の実績を確認できないため、代理店が数字を変えようと思えば、変えられるということが明らかになった。
代理店が「不透明な情報」を流すデメリット
電通が例え話として説明したのが、次のようなケースだ。
100万円の予算で30日間広告をだしてほしいという依頼があったとする。100万円では25日しか広告を出せなかったが、正直に25日分で終わったとせず、「30日まで配信をしていたと報告したケースがある」(電通)。
期間中に入札がうまくいかず、広告が配信できなかったにも関わらず、あたかも「期間中すべて広告配信されていたことにして、レポートした」(電通)こともあったという。
つまり、入札がうまくいっていたと偽ったということだ。
いずれも、現状のネット広告業界の問題が凝縮されている。広告主は、正確な情報、効果を知ることができず、不透明な根拠のレポートが出回る。ネット広告のメリットを享受できないままに。
「これは氷山の一角」
あるネット広告関係者は、こう証言する。
「いずれもネット広告でしか起き得ない業界全体の問題。不透明な情報、レポートが横行する。これは氷山の一角ではないか」
電通側も「個人の問題」とは捉えていない。中本副社長はこう述べた。
「人為的なミスも含めて、この責任は、特定個人というより、業務を統括するマネジメント、我々も含めた経営の問題であると考えています。深く反省し、信頼回復に向け、全力で調査し、原因究明、再発防止に努めていく所存です」
電通は、年内をめどに再発防止策をまとめるという。
社員に違法な長時間労働をさせていたとして、厚生労働省東京労働局が、労働基準法違反の疑いで法人としての電通と、労務管理を担当していた幹部社員を28日にも書類送検する方針を固めたことが27日、分かった。関係者によると、捜査は年明け以降も継続。上層部の関与の有無についても全容解明を進めるという。
捜査関係者によると、複数の社員の実際の労働時間と会社に申告していた勤務記録とが乖離していた。幹部社員らの指示により、社員が過少申告を強いられていた疑いがあるという。
入退館記録などを調べたところ、残業が100時間以上に及ぶ社員についても、申告では労使協定で上限となっている月70時間以内に収まっている社員が複数いたという。
電通では新入社員だった高橋まつりさん=当時(24)=が昨年12月、過労自殺した。鬱病を発症する直前、労使協定で定めた上限を超える月100時間以上の残業をしていた。
東京労働局などは10月、電通本社(東京都港区)や大阪など3支社と主要な子会社を立ち入り調査。11月には強制捜査に移行した。
電通では、平成3年にも入社2年目の男性社員=当時(24)=が過労自殺。過去には本社や大阪、名古屋の支社などが違法な長時間労働で是正勧告を受けている。労働局などは勧告後も長時間労働が是正されていないことを問題視して捜査を進めていた。
「東進衛星予備校」が生徒に提供するサービスに問題があればインパクトが大きいように思えるが、フランチャイズで経営する経営者とその社員となると、 「東進衛星予備校」がどこまで契約でどこまで踏み込めるのかを明らかにしないとインパクトがぼやけてしまうと思う。フランチャイズ方式だから、契約の更新や 契約解除の条件などは明記されていると思うが、経営する某企業の社員の扱いまでは記載されていないような気がする。
このケースはどこまで自由表現が許されるかと、最近注目を受けている過酷な労働環境に関して厚生労働省が踏み込むのか次第のような気がする。
株式会社ナガセがフランチャイズ(FC)方式で運営する特定の「東進衛星予備校」の過酷な労働環境を「私は」という1人称を使って告発した体験ルポをめぐり、東京地裁(原克也裁判長)は11月28日、ナガセが直営・FC方式の両方によって全国で運営する「東進」予備校のすべてかその多くで同様のことが起きているような印象を与える――とする曖昧な理由で、記事を掲載した「マイニュースジャパン」(MNJ)に対して見出し削除と40万円の賠償を命じた。真実性は不問、「印象」で「クロ」と決めつけた。明治政府が政府批判を弾圧した讒謗律さながらの乱暴な判決だ。
問題の記事は、2014年10月にMNJがインターネット上で発表した〈「東進」はワタミのような職場でした――ある新卒社員が半年で鬱病を発症、退職後1年半で公務員として社会復帰するまで〉と題する報告。ナガセとFC契約を結んで「東進衛星予備校」を経営する在阪の某企業に就職し、休日もろくにない長時間労働でうつ病を発症した男性の体験記だ。
ナガセは16年1月、この記事が虚偽だとしてMNJに3000万円の賠償などを求める民事訴訟を起こす。「東進」予備校のすべてかその多くで同様のことが起きているかのような印象を与えるが、それは嘘だ――という奇妙な理屈だった。
記事を少し読めば特定の「衛星校」における特定の体験だとはっきりわかるではないか。MNJの反論に、ナガセは見出しだけの削除を求める内容に変更。その見出しも、会話の引用であることを明示しており、やはり、特定の体験だと誤解なく読めるではないかと主張したが、原裁判長らは「印象」を根拠として虚偽認定した。書かれた事実と読み手の内心の「印象」をごちゃまぜにして「適法」「違法」と分ける思想はまさに検閲だ。MNJ側は控訴して争う方針。
(三宅勝久・ジャーナリスト、12月16日号)
電通の実態は知らないが、入社したい人がたくさんいるのだから仕方がない。入りたい会社に入社して苦しむのは愚かな事。
その意味では高橋まつりさんが電通に内定をもらった時、母親は反対しなかったのかと思う。入社してしばらくしてから電通の体質がわかったのであれば、 その時に残るのか、転職するのか決断するべきだったとお思う。
「高橋さんの母幸美(ゆきみ)さんは手記で『形のうえで制度をつくっても、人間の心が変わらなければ実行できません』と警告している。」
本当に会社が変わろうと思わなければ、形だけになるのは当然。それでも今回の事件で電通はかなりの痛手を負ったと個人的には思う。
個々の学生がいろいろな事が報道されても電通に入社したいと思うかどうかである。入社希望者が多ければ、この事件の風化も早いだろう。 代わりなどたくさんいる大手では企業が社員を使い捨てと思っていれば、折れれば次の代わりが来るだけ。
広告界のガリバー、電通が厚生労働省による強制捜査や、新入社員だった高橋まつりさん(当時24歳)の過労自殺による批判の広まりに危機感を募らせている。残業抑制のため午後10時以降は本社全体を消灯するなど、次々と社内改革を打ち出す。だが社員からは「迷走している」との声も。高橋さんの母幸美(ゆきみ)さんは手記で「形のうえで制度をつくっても、人間の心が変わらなければ実行できません」と警告している。
危機感の表れは随所に見える。社長が例年1月に全国5カ所で取引先を招く「電通年賀会」を中止。社風を象徴する「鬼十則」を来年の社員手帳から削除した。「鬼十則」は1951年に当時の社長が書いた10カ条。「取り組んだら放すな、殺されても放すな、目的完遂までは……」の一文は、1991年に男性社員が過労自殺した際「長時間労働を容認、助長する内容」と批判を浴びたが、その後も掲載し続けていた。
さらに来月1日付で過重労働是正に専従で取り組む執行役員を置き、同時に管理職の考課に部下からの評価を導入。全社員の1割の約650人を異動させ、全社的な労働時間削減と業務負担の平準化を図る。
ただ、社内では締め付けもある。本社が家宅捜索を受けた11月7日に路上でテレビのインタビューを受けて「自浄能力のない会社だと思う」と答えた社員が後日、社内処分を受けた。別の社員は「見せしめだ。社内は重苦しい雰囲気で、上層部は迷走している」と批判。「現場は働き方を良くしたいと思っているが、上は火の粉を払いたいだけ。食い違いがある」と嘆く。【早川健人】
広告代理店最大手・電通の新入社員だった高橋まつりさん(当時24歳)が過労自殺した問題で、厚生労働省は労使協定の上限(月70時間)を超える違法残業が社内で常態化していたとみて、少なくとも数十人の電通幹部や社員を対象に事情聴取を進めている。会社と幹部らを労働基準法違反容疑で書類送検する方針だが、大量の勤務記録と社員の入退館記録を照合する必要があり、捜査は越年する。(社会面に関連記事と遺族の手記全文)
東京労働局などは10月14日、電通東京本社に対し立ち入り調査「臨検監督」を実施。11月7日には強制…
広告代理店最大手・電通の新入社員だった高橋まつりさん(当時24歳)が過労自殺した問題で、厚生労働省は労使協定の上限(月70時間)を超える違法残業が社内で常態化していたとみて、少なくとも数十人の電通幹部や社員を対象に事情聴取を進めている。会社と幹部らを労働基準法違反容疑で書類送検する方針だが、大量の勤務記録と社員の入退館記録を照合する必要があり、捜査は越年する。
東京労働局などは10月14日、電通東京本社に対し立ち入り調査「臨検監督」を実施。11月7日には強制捜査に切り替え、本社と関西、中部、京都の3支社を家宅捜索し、勤務記録などを押収した。
労基法事件としては異例の規模とスピードで捜査は進んでいる。だが、検察幹部は「立件のハードルは高い」と慎重だ。違法残業を指示した管理職自身も過重労働をさせられていた可能性があり、「最終的な指示者は誰か、という認定が難しい」と話す。過去に立件された他の企業と同程度の悪質性を証明する必要もあるとしている。
電通では1991年、入社2年目の男性が過労自殺。2010年以降も本支社や子会社が、労務管理について労働基準監督署から是正勧告を繰り返し受けたが、長時間労働は解消されなかったとみられる。上司が労働時間の過少申告を指示していたケースもあるという。【早川健人、石山絵歩】
東電社員達が痛みを受けるべきだ。倒産したら国費で処理すればよい。
政府は20日、東京電力福島第1原発事故で立ち入り制限されている福島県の帰還困難区域内に整備する「特定復興拠点」の除染費用を国が負担することなどを盛り込んだ「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」を閣議決定した。
安倍晋三首相は、閣議前に官邸で開いた原子力災害対策本部会議で「関係閣僚は密接に連携し、一日も早い福島の復興・再生に向け道筋を具体化してもらいたい」と指示した。
除染費用はこれまで原則東電の負担だったが、東電が帰還困難区域の全住民への賠償を実施している経緯などを踏まえ、特定復興拠点の除染については東電に求償せずに、国の負担とする方針にした。国が前面に立って復興に取り組む姿勢を示す狙いもある。除染費用として、平成29年度予算に300億円程度を計上する方向だ。
復興拠点は、5年後をめどに避難指示解除を目指し、除染とインフラ整備を一体的に行う。整備費用は当面、東日本大震災復興特別会計でまかなう。
政府は、復興拠点を整備するための税制特例措置などを包含した福島復興再生特別措置法改正案を、来年の通常国会に提出する。
▼ペナルティーで「東京五輪」から締め出しも?
広告代理店最大手「電通」の新人女性社員の過労自殺を受け、厚生労働省東京労働局などは、労働基準法違反容疑で同社を家宅捜索した。前代未聞の強制捜査。“労働ルール不毛地帯”とされる同社の実態があらためて浮き彫りになった。
電通への強制捜査は、新人社員の高橋まつりさん(当時24歳)が昨年12月に過労自殺をしたことに端を発する。労働局側は、会社側が高橋さんら社員に違法な長時間労働を強いた疑いがあるとみており、本社(東京都港区)と関西支社(大阪市)、京都支社(京都市)、中部支社(名古屋市)を捜索。押収した資料を分析し、法人としての電通と人事担当者らの刑事処分を求める構えだ。
巨額の広告取り扱いを背景にメディアににらみを利かせてきた電通だが、9月30日に高橋さんの自殺が労災認定されると、にわかに批判にさらされることになった。高橋さんが月100時間以上の残業を強いられていたうえ、上司のパワハラ言動も明るみに出たからだ。現役社員は「(取材に応じるのは)禁止令が出ているので……」と口が重い。
この間、さすがに電通も企業体質を変革すべく、改善策を打ち出した。時間外労働は〈月70時間以内〉とする労使協定を〈月65時間以内〉に変更。10月下旬からは、深夜残業ができないよう、本支社とも午後10時で全館消灯となった。ただ、これらの改善策にも「抜け道はある」と指摘するのは数年前に辞めた40代の電通OBだ。営業(スポンサー担当)経験者のこのOBが続ける。
「本社入り口のゲートに社員証をかざすと、出退勤時間が労務管理システムに反映されます。時間外に社内にいた場合は、目的を自分で登録する仕組みです。残業が月70時間を超えそうになると、『私的利用』と登録していました」
上司も言外に“圧力”をかけてくるという。このOBが証言する。
「20年くらい前は残業が月100~200時間は当たり前。それぐらいの仕事量がこなせないとダメだ、という雰囲気でした。上場(2001年)した頃から労働基準監督署がうるさくなり、部長は部下たちに『うまくやれよ』と。『命令』と捉えられてはならないことは心得ている」
こうして、「持ち帰り残業」が増えることになる。前出のOBが実態を明かす。
「本社の周囲には広告制作会社や関連会社が集まっている。制作会社での打ち合わせの後、『会議室貸してね』と、そこで仕事をすることはよくありました。パソコンがあれば社内システムに接続できますから」
スポンサーの“わがまま”も丸抱え
なぜ、恒常的に長時間労働が続くのか。
「業界の構造的な問題」と指摘するのは、広告業界2位・博報堂OBで作家の本間龍さんだ。
「電通や博報堂では、営業担当がCMなどの全体の計画を練り、それに基づいてデザイナーやテレビ局担当社員が動きます。営業は昼間は外回りで、各部門が顔をそろえるのはどうしても遅くなる。社内の打ち合わせが深夜の11時、0時からということも珍しくない」
さらに、スポンサーの“わがまま”を丸抱えする古い体質も一因という。本間さんが説明する。
「年間数十億円の仕事をくれるスポンサーの中には、報道発表文の作成やクレーム処理まで押しつけてくる企業がある。私も営業時代、大手航空会社の発表文を書きました。外資系の広告代理店はこうした雑用には別料金を請求しますが、『電博』は丸抱え。受注額の2~3割が代理店の取り分なので、大口スポンサーに苦言は呈さないのです」
自殺した高橋さんは、インターネット広告を担当する部門に所属していた。電通が毎年発表している統計「日本の広告費」の2015年版によると、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ(マスコミ4媒体)の広告費はいずれも対前年比で1・2~6・2%減少する中、ネット広告は10・2%の成長を見せ、広告費全体をけん引している。ただ、ネットの場合、売上単価はマスコミ4媒体よりも大幅に低いとされる。電通とも取引のあるネット広告業界関係者が解説する。
「ネットでは、個人でも広告を出せるし、『きょうの夕方で広告を止めて』といった注文にも即対応しないといけない。24時間対応が必要であり、電通が得意としてきたマスコミ広告とはまるで違う。幹部らはその辺を理解しておらず、『ネットはテレビCMのクライアントへのおまけ』程度の認識です。ITに詳しいスタッフが必要なため、ネット広告部門は関連会社からの出向者らも多い。こうした環境で、高橋さんは孤立を深めていったのではないでしょうか」
今回、労働局側の動きは迅速だった。10月14日に電通本社などへ立ち入り調査をし、11月7日には家宅捜索を行った。貧困問題に詳しく、ブラック企業大賞の運営にも関わる水島宏明・上智大教授はこう分析する。
「根底には、大手企業に厚労省が踏み込むことで、企業のブラック体質を一掃しようという安倍政権の意思があるのではないか。女性を管理職に登用して男性優位社会を改め、育児休暇などを社会全体で受け入れるよう見直さなければならない」
ちなみに、今年も年末にブラック企業大賞が発表される。電通がノミネートされるかは現時点では不明だが、有力候補であることは間違いないだろう。
仮に、電通が刑事責任を追及される事態になれば、東京五輪にも影を落とすことになるかもしれない。
公益財団法人東京五輪・パラリンピック組織委員会には、電通の社員がスタッフとして参加し、組織委から関連事業を受注しているからだ。問題企業が世界的祭典に携わるのは、いかにも体裁が悪い。だが、組織委の広報担当者は「発注先企業に法令違反があった場合について、取り扱い基準の有無も含めて公表していない。捜査の推移を見守りたい」と言葉少なだ。
東京五輪・パラリンピックの招致活動を巡る疑惑でも、その存在が取りざたされた電通。「五輪のような巨大イベントは電通しか仕切れない」(広告業界関係者)と評される存在だからこそ、自浄作用が求められている。
(本誌・花牟礼紀仁)
(サンデー毎日2016年11月27日号から)
大学生時代、元IBMに勤めていた講師がいた。IBMの業績が悪かった時で生まれたばかりの子供がいたころだった言っていた。同僚がリストラで去っていく人が多くなっていたころ。 リストラのリストに載せられないように、進んで残業を続けて子供が寝た後に帰宅していたら、子供が自分になつかなくて生まれたばかりの子供がいる家族の為に無理して残業して 子供が父親として認識してくれない事にショックを受けたそうだ。アメリカの企業でアメリカ人がそんな事を言うなんてと思った記憶がある。
仕事をしていて思う事がある。外国人は基本的に、週末や祝日は働かいない。だからこそ、仕事の順序を考えて、週末前に連絡する事、返事がなければ週末前に再度、催促したり、 考慮して対応する。不便だと思うかもしれないが、逆の立場になれば、週末や休日は仕事をしなくて良いと言う事になる。外国人は働かいないと感じる日本人が多いと思うが、 それでも、企業や国の経済が成り立つのであれば、問題ないと思う。日本人はアメリカ人を勤勉とは思わないが、ヨーロッパに比べれば比較的に勤勉だ。ヨーロッパは 昼休みが長い、シエスタがある、又はライフスタイルがスローである傾向がある。ヨーロッパにはドイツがあるので、ヨーロッパと一括りには言えないが、特に南側にある 国はラテン文化で工業に向いているとは思えない。
日本は、繊細とか勤勉と言えばよく聞こえるが、細かく注文が多い、長時間労働を基本としているとも言える。
教師をしている人が自分の仕事は終わっているので帰りたいが、仕事をしている人達がいると帰れない、又は、帰れない雰囲気があると言っていた。すると、教師である人が 同調していた。これは、日本の問題、又は、学校や教育委員会の問題だと思う。仕事がない人でも帰れない環境や雰囲気はおかしい。これは日本社会の問題。 過去の学校の体質を受け継ぐ必要はない。変えるにはかなりの努力と変化に反対する教師達に対応する問題に直面するだろう。教師だって出来る人と出来ない人が 存在するはずである。単純に忙しいでは片づけられない。それに、公務員を見て思うのであるが、効率的に仕事をこなす努力をしていない人達も多くいる。 スローな環境でスローな同僚や上司しか見ていないので、公務員の職場以外を知らない。比較する対象が限られているので公平な比較でもない。
仕事をしたい人は仕事をすればよい。家庭を優先させたい人は家庭を優先させるような働き方をすれば良い。出世や給料に違いが出ても受け入れられるのならそれで良いと思う。 能力がある人は妥協しなくても仕事が出来るだろう。能力はないが目標が高い人は何かを犠牲にしてかんばるしかない。優先順位、給料、家庭、出世、自分の能力そして運などを 考慮して判断したらよい。他人との違いを受け入れらない、又は、他人と違う選択を出来ない日本の社会にも問題があると思う。
マスコミに興味を持っている学生で下記の記事を読んで自分の人生を想像すればよい。それでもマスコミの仕事をしたければ何かを犠牲にしてでもマスコミの仕事がしたいと 思う人であろう。職人のドキュメンタリーを見るとなぜあそこまで出来るのかと思う事がある。いろいろな障害があっても好きだからであろう。だから才能も必要かもしれないが 好きであることも重要だと思う。職人が長時間労働を言い始めれば話にならない。職人なるプロセスが大変だから、今の時代、候補者がいないのだと思う。
就職氷河時代もあったから何とも言えないが、大学は学生に入社したい企業の労働パターンについて調査して学生に情報を提供し、学生は自己責任で調べるべきだと思う。 入社して間違いだと思えば辞めても良いと考えているぐらいであれば、調べなくても良い。全ては個々の判断だと思う。
電通の新入社員、高橋まつりさん(当時24)が自殺したのは、2015年のクリスマスの朝だった。それから1年が経った。高橋さんが苦しんでいた問題についてメディアが一斉に報じたことをきっかけに、「働き方」をめぐる議論が加熱している。【BuzzFeed Japan / 籏智広太】
報道各社は当初、電通の労働体制や働き方の問題点などを批判的に指摘。ほかの企業における長時間労働にフォーカスを当てた記事も多く伝えた。
でも、報じる側はどうだろう。マスコミの働き方には問題がないのだろうか。BuzzFeed Newsは、新聞と雑誌業界で記者として働いてきた20代の女性に話を聞いた。
本当に辛かったサツ回り
「電通の長時間労働を批判する記事を書いているのは、自己矛盾じゃないかなと感じました」
全国紙の新聞記者として働いてきた20代女性は、BuzzFeed Newsにこう語る。伏し目がちなまま、こう続けた。
「社会にいくら訴えても、自分たちが変わらないと説得力がないですよね」
彼女自身も、長時間労働に苦しんできた一人だ。現状を少しでも訴えたいと、今回の取材に応じてくれた。
特に大変だったのは、事件事故の担当をしていた時だった。特に、毎月のように事件があったある1年間は、「本当につらかった」と振り返る。
全国紙の新聞記者は、ほとんどの場合、入社後すぐに地方に配属され、警察取材、通称「サツ回り」で鍛え上げられる。あらゆる事件の情報が集まる警察署で、取材力を磨き、なにかが起きた時の瞬発力をつけるためだ。
その日に事件や事故が起きるかどうかは、神のみぞ知る。人口が多い地方に配属されれば、忙しさは確実に増す。
火事や大事故、殺人事件が起きれば、いつどこにいようが現場や警察署などに駆けつけないといけない。寝ていても、飲んでいても、お風呂に入っていても、恋人と過ごしていても。
「移動の自由」はなかった
「事件、ニュースに動かされる仕事なんだから、仕方がないとも思ってきました。入る前から想像していた通りでした」
たとえば朝5時に起きて、口紅だけをつけて30分で家を出る。8時に警察幹部の家の前にたどり着く。笑顔であいさつをしたら、そのまま記者クラブへ向かう。
午前中に記事を執筆。昼休みは1時間。その後はいろいろと雑務をこなし、夕方から朝の12~1時まで、再び警察幹部の家を回る「夜回り」だ。
そう、すべては「ネタ」のため。
食事はコンビニのおにぎり。家に帰ってするのは、シャワーを浴びて、寝ることだけ。
深夜2時ごろに布団に入ると、「なにをやってるんだろう」と、自然と涙が出る日も多かった。常に携帯が鳴っている気がして、なかなか眠れなかった。
ほっと一息をつく休みだってない。今になって当時を振り返ると、鬱だったんじゃないかと思っている。
「休日も、なにかがあっても呼び出されることばかりでした。それに、地方支局の人が減らされていて、土日の出番(当直勤務)を回されることも多かったですね。もちろん、平日に代休なんか取れません」
それでも誰かに相談しようと考えたことはなかったという。「実情を訴えてもなにも変わらない」と、諦めていたからだ。
もう一つ彼女を悩ませたのは、「移動の自由」だったという。新聞記者の多くは、たまの休日にも、基本的には自分が管轄する県(エリア)から自由に出入りすることはできない。
いつ、何が起きても対応できるようにするためだ。上司に理由を伝え、許可を得ることが必須だ。「友達の結婚式がある」と言ったが、上司から県外に出る許可を得られなかったことだってある。
「デスクには、『葬式なら納得できるけど』と言われました。こんなに移動とネットが発達した時代に、なんでだろうと思いましたね」
遠距離恋愛をしていた彼氏とは、長くは続かなかった。
仕事熱心=働いている時間
数年ほどして、部署が変わった。警察担当だった頃よりは、忙しくはなくなった。ただそれも、当時と比べてみれば、という話だ。
正確な残業時間はわからない。ただ、家に出て家に帰るまでの時間を計算してみれば、毎月100時間を超えるのは当たり前だという。
「12時から飲み会をすることとかもあるし、時間の感覚が社会からズレてる感じがするんですよね。プライベートも仕事も境目がなかったし、それが良しとされている。仕事熱心=働いている時間という感覚なんですよ」
「ニュースを追う仕事をする限り、誰かがどこかにいないといけないなのはわかっています。でも、潤沢に人がいたり、若い記者がたくさんいたりした時代と今は違う。もう新聞社の働き方のシステムは回っていないと思います」
会社が変わるなんて思っていないし、「結婚や子育てをしながら働く、ワーク・ライフ・バランスの実現なんて無理だ」という絶望しかなかったという。
長時間労働の温床となる「みなし労働制」
長時間労働がメディア業界に蔓延している事実は、データからもわかる大きな課題だ。
16年に始めて発表された「過労死防止白書」には、厚生労働省が企業約1万社(回答1743 件)、労働者約2万人(回答1万9583人)を対象に昨年、実施したアンケート結果が載っている。
これによると、1年で残業が一番多い月の残業時間が「過労死ライン」とされている80時間以上だった企業の割合は、テレビ局、新聞、出版業を含む「情報通信業」が44.4% (平均22.7%)と一番高い。
ただ、オフィスの出入りが激しい記者や編集者は労働時間を把握しづらいため、労働基準法に基づく裁量労働制(みなし労働制)を取り入れている職場も多い。
労使協定によってあらかじめ所定労働時間を決める制度だが、それが実質的な長時間労働の温床となっていることもある。
たとえば朝日新聞社では、裁量労働制職場の記者が記録した2016年3~4月の2ヶ月分の出退勤時間を、所属長が短く書き換えていた。BuzzFeed Newsが11月に報じている。
常に締め切りに追われる仕事だった
「この間、知り合いと会ったら、こんな笑い話をしていました。『うちは電通のことを書けないね、ブーメランになって返って来るから』って」
ある雑誌社で記者経験のある女性は、BuzzFeed Newsの取材にそう語る。
常に締め切りに追われる仕事だった。終電で帰れることは、まずなかった。
「ネタを探すのが仕事。でも、実にならない時間がほとんどでした。普段は絶対に会食があるし、休日も取材関係の人と会ったり、飲んだり。丸一日休むことはあまりなかったですね」
目の前で当時の手帳を開いて、勤務時間を計算してもらった。毎月だいたい、140~150時間は残業をしていたという。
そういう経験をしたことがあるからこそ、高橋さんのツイートには共感を覚えるものが多かった。「眠りたい以外の感情を失った」という言葉も、そのうちのひとつだ。
「普段はほとんど寝られないですし、体力的にもきつい。頭も働かないし、落ち込んでやる気がなくなって、仕事がうまくいかないという負のスパイラルに入ってしまうんですよね」
「アルコールがはけ口というか、飲まないと寝られないこともある。次のネタが見つかるか、1日1日を乗り越えられるかが不安でした」
そんな飲み会でのストレスも大きかった。政治家やジャーナリスト、評論家、芸能関係者などの飲みの席でセクハラされることなんて、日常茶飯事だったからだ。性的な関係を迫られ、断ると激昂する男性もいた。
我慢しながら続けても
「なんというか、むなしくなるんですよね。情報ってすぐに食い尽くされて、話題は消える。一体何の達成感があるんだろうって。楽しいと思えればいいんですけれど、やらされている仕事が多いからかもしれません」
自分でネタを取らないと始まらないという強迫観念に苛まれ、もはや立ち止まることすらできなかった。相談できる上司もおらず、毎日のように限界を感じていた。起きてから会社に行くまでが、つらかった。
高橋さんが自死を選んだ理由もわかる。自身も「ふと、ここで死んでもよいと思う気持ちになることがあった」という。
「ワーク・ライフ・バランスを求める人は、別のところにいけばいいんじゃないかっていう空気があるんです。仕事を楽しめないのは、その人自身の問題だって。そう思われるのが悔しいから辞めなかったし、休日は仕事を持ち帰って取材もする。休めないまま日々が過ぎる」
そう語る女性は、ギリギリのところでなんとか前を向こうとあがいていた。
「特ダネが取れたらいいな、と思ってたんです。ここで何もできなくて辞めるのは嫌だ。そう我慢しながら、続けていました」
この2人のような働き方は、マスメディアの記者の世界では珍しくない。BuzzFeed Japanには私(籏智)を含め、新聞、雑誌、テレビの世界で働いてきた記者やライターたちがいる。その多くが同じような経験をしたと語る。
命より大切な仕事はない
日々のニュースの仕事を左右される記者、ひいてはメディア業界全体の働き方は、往々にして過酷になりがちだ。
大事件や災害など、それが止むを得ない時もある。私が朝日新聞で記者をしていたときも、同じだった。日々の事件事故、熊本地震などの大災害、高校野球や選挙。多忙を極めた時期はいくらでもある。
そういう働き方を辛いと思わず、楽しめているときだってあった。世の中のためだと思って踏ん張ることもあった(死ぬほど嫌だったときもあったが)。でも、それが当たり前だ、としてはいけない。
高橋さんの母親・幸美さんは11月、シンポジウムでこう語っている。
「命より、大切な仕事はありません。娘の死はパフォーマンスではありません。フィクションでもありません。現実に起こったことなのです」
「自分の命よりも大切な愛する娘を突然亡くしてしまった悲しみと絶望は、失ったものにしかわかりません。だから同じことが繰り返されるのです」
BuzzFeedでは可能な限り効率的に、短時間で働けるように取り組んでいる。一方的に長時間労働について報じているだけではなく、まずは自分たちから。
自分たちを含む社会全体の問題と捉え、改善策を探る必要がある。これ以上、犠牲者を出さないために。
大手広告代理店・電通の新入社員だった高橋 まつりさんが、過労が原因で自殺してから、12月25日で1年となる。内定直後に書かれた、夢と希望にあふれた彼女自身のメッセージが明かされた。
2014年春、高橋 まつりさんが、電通に内定した直後、アルバイト先の元上司に送ったメッセージ。
メッセージは「やはり、マスコミ関係の仕事であること、職種の異動があり、出来る事の幅が広いこと。新しいコンテンツをつくりだしていけること...などを重視して会社を選びました」と書かれていた。
フェイスブックを通じて、職場への期待を伝えていた高橋さん。
2015年4月、電通に入社してから、アルバイト先の元上司の「落ち着いたら連絡して。飯でも食いに行きましょう!」というメッセージに、高橋さんは「今月は、まだ分からないので、いろいろと具合が分かったら連絡します!!」と返していた。
アルバイト先の元上司のアサヒカメラ・佐々木 広人編集長は「『同僚と研修に励んでいる』と『土日もあまりない』と書いていたけど、非常に夢にあふれている感じがあって...」と話した。
夢にあふれていたという高橋さん。
しかし、抱いていた「期待」は、次第に「つらさ」へと変わっていった。
高橋さんは、ツイッターに「土日も出勤しなければならないことが、また決定し、本気で死んでしまいたい」、「今日も寝られなかった」、「がんばれると思ったのに、予想外に早くつぶれてしまって、自己嫌悪だな」と投稿していた。
そして、2015年のクリスマス、母親に送ったメールには「仕事も人生も、とてもつらいです。今までありがとう」と書かれていた。
10月7日、高橋さんの母・幸美さんは「『死んではだめよ』と話したら、力はなかったけど、『うん、うん』と...」と話した。
入社から、わずか9カ月。
高橋さんは、飛び降り自殺を図って亡くなり、その後、過労が原因の労災と認定された。
高橋さんの死から、25日で1年。
電通は、2017年から、年間10日の有給休暇取得を義務づけるなど、労働環境の改善に努める方針。
日本の働き方改革が進むかは、これからが正念場となる。.
ここまで親密となり警視庁も情報を把握しているし、記事にもなれば、記者としての信頼性はなくなったと思うけど、世間はどう見ているのだろう。
フジテレビの男性記者が、暴力団関係者に乗用車の名義を貸すなどの利益供与をした疑いがある問題で、男性記者が「高額な接待を受けていたので依頼を断りきれなかった」と説明していることがわかりました。
山口組系暴力団関係者に乗用車の購入に必要な名義を貸すなどの利益供与をした疑いが持たれているのは、フジテレビで去年まで暴力団に絡む事件などを担当していた30代の男性記者です。
男性記者は暴力団関係者と取材を通じて知り合い、フジテレビによりますと、おととし春ごろから去年までに都内の高級飲食店で20回以上接待を受けていたということです。その後の取材で、男性記者はフジテレビの調査に対し、「高額な接待を受けていたので名義貸しの依頼を断りきれなかった」と説明していることがわかりました。
警視庁はこれらの情報を把握していて、詳しい事実関係を調べています。
その歪んだ選民意識 (1/3) (2/3) (3/3) 12/19/16(週刊現代)
高祖父は中央大学を設立した「法曹界の父」で、曾祖父は岸信介の学友の最高裁判事本人は神奈川の超名門・聖光学院高校出身……。
銀のスプーンをくわえて生まれ、名門医学部に進んだ容疑者は、二十歳そこそこにして「全能感」に満ちていたのか。女性に対する傲慢かつ卑劣な接し方から、その歪んだ選民意識が滲み出ている。
祖父も父も東大法卒の弁護士
5月の東京大学、10月の慶應大学に続いて、またも高偏差値のエリート大学生による集団レイプ事件が発生した。
千葉大学医学部(6年制)の5年生3名が11月21日に集団強姦致傷の容疑で逮捕された。12月5日には彼らの実名が公表され、さらに3人を指導する立場であった研修医も共犯として準強制わいせつの容疑で逮捕。医学部に学ぶ医師の卵らによる卑劣な犯罪が名門大学を激震させている。
千葉大学医学部は、国立大学医学部の偏差値ランキングではTOP10に入り、関東では東京大学、東京医科歯科大学に次ぐ存在である。
「千葉大の他の学部は県内および隣県の出身者が中心ですが、医学部には全国の名門高校出身者が集まっています。慶應大学医学部を蹴って、千葉大を選ぶ人も少なくありません」(千葉大生)
逮捕された3人の千葉大生のなかでも、とくに山田兼輔容疑者(23歳)が世間の注目を集めている。
山田は神奈川県の超名門私立・聖光学院高校出身。同校は、'16年度の大学入試で東京大学合格者数71名という全国トップクラスの進学校である。
そして、そうした学歴に加え、山田が日本屈指のエリート法曹一家に生まれ育っていることが、さらなる波紋を呼んでいる。
高祖父の山田喜之助は、明治時代の傑物。東京大学法学部を卒業し、法律家として活動する傍ら、大隈重信率いる立憲改進党の結党に参加。東京専門学校(現・早稲田大学)の創設に関わり、同校の教壇に立った。
同校の職を辞した後は、英吉利法律学校(現・中央大学)の創立者18人に名を連ね、授業も担当。法科の名門の礎を築いた。法律書や英国の法律に関する翻訳書も数多く刊行し、まさに日本法曹界の父だった。それだけでなく大審院(現在の最高裁)の判事や、衆議院議員として衆議院書記官長、大隈内閣の司法次官など公職も歴任している。
曾祖父・作之助も東京帝国大学法学部出身で、元首相の岸信介とは学友だった。神戸地裁の判事から弁護士に転身し、神戸弁護士会会長を経て、最高裁判事を務めた。
「山田の祖父も東大出身で、上智大学法学部助教授や第一東京弁護士会副会長を務めた大物弁護士。父親も東大卒の弁護士です。企業法務が専門で、いくつもの一流企業で監査役を務めるヤリ手ですよ」(法曹界関係者)
東大卒の弁護士が4代も続いた家系で、しかも実兄も一橋大学卒の弁護士。さらに言えば祖母や伯母も弁護士で、伯父は公認会計士である。
「千葉県警は3人を逮捕した当初は実名を発表しませんでした。表向きの理由は共犯者の捜査を継続中であることと、被害者女性の特定につながるからとしています。しかし、山田容疑者が大物弁護士一家の次男であるため、慎重にならざるをえなかったというのが、大きな理由の一つでしょう」(全国紙社会部記者)
都内の閑静な高級住宅地の一角にある山田の実家は、ロマネスク風の瀟洒な一軒家。本誌は山田宅を訪ねたが、人気はなく、終日インターフォンに応じることもなかった。
「マスコミが来るようになってから、ずっと不在が続いています。兼輔君はどこにでもいる普通の学生という印象しかありません」(近隣住民)
山田は千葉大医学部のキャンパスから徒歩10分ほどのマンションで一人暮らしをしている。
「今年2月に新築されたばかりで、もちろんオートロック。周辺の単身者向けのマンションの中では一番家賃が高いですね」(地元の不動産業者)
本誌は山田の父親が代表パートナーを務める法律事務所にも取材を申し込んだが、受付担当者が「コメントできない」と回答するのみだった。
男3人で朝まで性的暴行
逮捕された他の医学部生2人も、山田に劣らない偏差値エリートだ。
増田峰登容疑者(23歳)は筑波大学附属高校出身。
「お父さんは埼玉県内の特定郵便局局長で、地元の名士です。お母さんも学校の先生で、峰登君は3人兄弟の長男。みんな小学校の頃から勉強ができて、近所でも秀才一家と評判でした」(近隣住民)
吉元将也容疑者(23歳)は鹿児島県出身で、中学時代に長野県に転校した。
「県内屈指の名門公立校・長野高校卒です。成績は校内でもトップクラスで、昔から医者になると公言していました。でも、ただのガリ勉ではなく、中学時代から彼女もいましたし、運動神経もバツグンで陸上部に所属していました」(知人)
大学で山田と増田は医学部内のラグビー部、吉元はスキー部に所属していた。だがスポーツマンであるはずの彼らの犯行は卑劣そのものだ。
9月20日夜、千葉市中央区内の居酒屋で、実習の打ち上げという名目で、同大の学生ら十数人が参加して飲み会が行われた。
「飲み会は5時間続き、泥酔してしまった参加者の女子学生を山田らはトイレに連れ込んだんです。4人は時間差でトイレに入り、集団でわいせつ行為におよびました。犯行現場になった可能性が高い男女兼用のトイレは二畳程度の広さ。
ただし、この居酒屋はわりと高級なチェーン店で照明は明るく店員も多い。トイレは店内の中央付近にあって、頻繁に人の出入りがあった。女子学生を介抱するフリをしていたとはいえ、かなり大胆な犯行です」(前出・全国紙記者)
もともと、この飲み会は逮捕された千葉大学附属病院の研修医、藤坂悠司容疑者(30歳)が企画したもの。藤坂は容疑者の学生に「先生もどうですか?」と誘われて、犯行に加わったというから、呆れるほかない。
しかもレイプは居酒屋だけで終わらなかった。
「彼女が酒に酔ったので、家まで送る」
他の参加者にはそう告げて、藤坂を除いた3人は被害者女性をタクシーに乗せて、増田の自宅マンションに連れ込んだ。
「そこで3人で早朝まで被害者に性的暴行を加えたあげく、軽傷を負わせたんです。女性は3人が寝たところで、ようやく逃げ出して病院に駆け込み、関係者が警察に通報しました」(前出・記者)
逮捕された3人は取り調べで容疑を認めながら、動機については、
「酒に酔った勢い」
と供述しているという。
あまりに愚かである。なぜ彼らは知人だったはずの女子学生を集団でレイプしたのだろうか。
同大医学部の6年生はこう語る。
「医学部は5年生から実習が始まります。実習期間中は各病院と自宅を往復する毎日で、朝早くから夜遅い時間まで課題は山積み、自宅でもレポートを書かなければならない。彼らは実習が終わって緊張感から解放されて、酒を飲んでハメを外し過ぎたんでしょうね。学内はいまピリピリしていて、学生は皆、自主的に飲み会を中止していますよ」
別の医学部の2年生が語る。
「彼らが逮捕される1ヵ月くらい前から、僕たちの周りでは『ラグビー部が女性を襲ったらしい』という噂は流れていました。実際に逮捕されても、意外性はなかったですね。というのも、医学部のラグビー部は、飲み会で過激な下ネタが飛び交うような雰囲気なんです。
もともと千葉大の医学部生はエリートで遊び慣れていない男子学生が多いのですが、入学してしばらくすると大学デビューというのか、看護学部や近隣にある女子大の学生から急にそこそこモテるようになるので、勘違いしやすいんですよ。
また、千葉大は『東医体』という東日本の大学医学部の体育会による連合組織に参加しています。そこの大会で慶應や東京医科歯科大と対戦すると、その後の飲み会で仲良くなるんですが、やっぱり都心のキャンパスで遊んでいる彼らが羨ましくなるんですかね。
高校時代の偏差値で言えば同じレベルの奴らに『俺たちも負けられない』と邪な対抗意識を持ってしまう。今回、逮捕された学生の3人はその傾向が強かったようです」
彼らの歪んだ自尊心と性欲が、今回の事件を引き起こしたのか。
「女性をモノとして見る」
数多くの性犯罪の裁判を傍聴してきたライターの高橋ユキ氏が語る。
「今年5月に発生した東大生集団わいせつ事件で、起訴された被告3人が、公判で異口同音に語っていたのは、『自分たちの行為は許されると思っていた』ということでした。東大生である自分に女性は下心があって近づいてくると考えており、そういう女性を軽蔑する気持ちもあったとも語っています。
そうした東大生の思い上がった意識が引き起こした事件でした。今回の千葉大学医学部生にも同じような背景があったのではないでしょうか」
高橋氏によれば、東大生集団わいせつ事件の河本泰知被告は裁判でこう証言したという。
「仲間の間で女性をモノ、性の対象として見て人格を蔑んでいる考え方が根本的にあったと思う。大学に入学してサークルなどで他大学の子と接して、彼女らはアタマが悪いからとか、バカにして、いやらしい目でばっか見るようになり……という、男たちの中でそういう考え方が形成されてきたように思います」
山田ら3人にはどんな罰が待っているのか。刑事事件に詳しい弁護士法人・響の徳原聖雨弁護士が説明する。
「集団強姦致傷は親告罪ではありませんが、示談が成立するかどうかがポイントになる。20日間程度の勾留期間中に示談がまとまれば釈放ということもありえます。また、被害者の協力が得られずに裁判を維持するのが難しいとなれば、検察側は不起訴の判断をせざるをえない。
逆に起訴されて有罪となれば、懲役7年前後の重い実刑になると思われます。ただし示談では、金銭だけでなく、『大学の自主退学』といった厳しい条件になることも考えられます」
一方、千葉大学側は司法判断を待ったうえで、彼らの処分を検討するとしている。
「起訴の有無にかかわらず、学生3人はもっとも重い退学処分、研修医は解雇というのが妥当でしょう」(全国紙社会部記者)
華麗すぎる家柄に生まれた山田ら3人の学生は、本来ならばあと1年数ヵ月後には医学部を卒業し、輝かしいキャリアを歩むはずだった。だが、彼らは医師になるべき人間ではなかった。
「週刊現代」2016年12月24日号より
一般財団法人・化学及および血清療法研究所(化血研、熊本市)による血液製剤などの不正製造問題で、新たに二つの血液製剤の製造実態が、国の承認書と食い違っていることが14日、明らかになった。
厚生労働省の専門家部会は同日、安全性に重大な影響はないとして、2製品の出荷継続を認めた。
同省によると、相違が見つかったのは、「アナクトC」と「バイクロット」。検査用の試薬の規格が異なっていたり、誤記が見つかったりした。この2製品は昨年、重大な食い違いが発覚し、化血研側は是正の手続きを行ったが、その際の確認が不十分だったという。
マイナンバー(共通番号)カードの管理システムでトラブルが相次ぎ、交付が遅れた問題を受け、システムを運営する地方公共団体情報システム機構は12日、システムを設計・開発した富士通やNTTデータなど5社に対し、総額約1億9450万円の損害賠償を求めることを決めた。
5社側は受け入れる意向を示したという。国や同機構が復旧に要した費用を負担しない形で決着する見込みだ。
システム障害は、カードの交付が始まった1月に計6回発生した。カード発行手続きを行う全国の自治体と同機構のシステムが最大で約3時間20分つながらなくなり、自治体で手続きが出来なくなった。
当て逃げは良くない。お金を積んで示談にするのかもしれないが、お金で何でも解決すると言う事を世間に広めてしまう結果となってしまった。 例え、示談にするとしても事務所に電話して弁護士に連絡するか、警察に連絡するなどの対応を取るべきだったと思う。
人格を疑われる対応だったと思う。
お笑いコンビ「NON STYLE」の井上裕介さん(36)が、東京都世田谷区でタクシーに当て逃げ事故を起こし、運転手にけがを負わせていたことが、警視庁世田谷署への取材でわかった。
同署が道路交通法(救護義務)違反などの容疑で調べている。
同署によると、井上さんは11日午後11時45分頃、世田谷区若林の都道で乗用車を運転中、左を走っていたタクシーに接触し、そのまま走り去った疑い。タクシーの40歳代の運転手が首と腰に軽いけがを負った。乗用車のナンバーから井上さんが浮上し、同署員が12日未明に任意同行を求めた。
井上さんは仕事先から世田谷区内の自宅に戻る途中で、「タクシーの前に入ろうとしてぶつかってしまった。事故を起こしたことを世間に知られたら大変なことになると思った」と話しているという。
三重大医学部の学生たちはカラオケボックスなどで数回にわたり「王様ゲーム」を行い、負けた女子大生たちの服を脱がせるセクハラ行為を繰り返していただけで 男子学生5人が退学処分を受けた。
千葉大医学部はどのような処分を出すのであろうか?
飲み会で女性に集団で性的暴行を加えたなどとして、千葉大学医学部の学生らが逮捕された事件で、12日、学生3人が起訴された。
千葉大学医学部5年の吉元将也被告、山田兼輔被告、増田峰登被告の3人は、今年9月、千葉市の飲食店などで、20代の女性に性的暴行を加え、ケガをさせたとして逮捕されていたが、千葉地検は12日、集団強姦などの罪で起訴した。
吉元被告と山田被告は、酔った20代の女性に対して飲食店で集団で強姦した罪に問われ、増田被告は、自宅で同じ酔った20代の女性を強姦した罪で起訴された。千葉地検は3人の認否を明らかにしていない。
また捜査関係者への取材で、増田被告の自宅で女性が体調不良を訴えた際、3人が性的暴行の発覚を恐れ救急車を呼んでいなかったことも新たに分かった。
この事件では、同じ女性にわいせつな行為をした疑いで、千葉大学医学部附属病院の研修医、藤坂悠司容疑者が逮捕されている。
千葉大学医学部の男子学生3人が女性に集団で性的暴行を加えたとして逮捕された事件で、千葉地検は12日、いずれも千葉市中央区の同大医学部5年生、吉元将也(23)、山田兼輔(23)両容疑者を集団強姦(ごうかん)罪で、増田峰登容疑者(23)を準強姦罪でそれぞれ起訴し、発表した。
3人は、女性に集団で性的暴行を加えてけがをさせたとして集団強姦致傷容疑で逮捕されたが、地検は「致傷罪として評価することはできなかった」と説明した。
発表などによると、吉元、山田両容疑者は9月20日午後10時ごろ~21日午前0時半ごろ、千葉市内の飲食店で、酒に酔って抵抗できない状態の20代の女性を店内の周囲から見えない場所に連れていき性的暴行を加えたとされる。増田容疑者は21日午前0時40分ごろ~5時ごろ、自宅で同じ女性に性的暴行を加えたとされる。捜査関係者によると、3人はいずれも計画的な犯行ではなかったとの趣旨の供述をし、一部は「酒に酔ってやってしまった」などと話しているという。
事件では、学生を指導する同大医学部付属病院の研修医、藤坂悠司容疑者(30)も飲食店で被害女性の体を無理やり触るなどしたとして、準強制わいせつ容疑で逮捕されている。
戦後医療史
慶応大医学部・集団レイプ事件 平成11年(1999年)
平成11年7月31日、慶応大医学部の男子学生5人が集団レイプ事件により警視庁四谷署に逮捕されていたことが明らかになった。この事件は、同年5月6日、医学部ヨット部の学生を中心としたグループが、新宿でほかの大学の女子大生たちと合コンを行ったことがきっかけであった。合コンが終わると、新宿区内にある男子学生のマンションに女子大生2人を連れ込み、そのうちの1人の女子大生(20)を集団でレイプしたのだった。もう1人の女性はマンションから逃げ無事であった。
暴行を受けた女子大生は翌日、警視庁四谷署に婦女暴行の被害届を提出。四谷署は7月5日に5人を逮捕した。逮捕されたのは医学部4年生(23)、医学部2年生(19)3人、医学部1年生(18)であった。この逮捕後に5人と女子大生の間で示談が成立し、女子大生が告訴を取り下げたため23歳の男子学生は不起訴処分で釈放され、残りの4人は未成年のため身柄を家庭裁判所に送られた。
慶応大医学部は臨時教授会を開き、事件にかかわった5人全員を退学処分にすることにした。猿田享男医学部長は退学の理由として、「将来、患者を助ける立場にありながら不当な行為に及び、慶応大医学部という立場を無視し、非人間的、非倫理的なことを行った」と述べた。5人を人間性において、医師になる人間として不適格としたのだった。慶応大では、前年11月にセクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)防止を目的に「ハラスメント防止委員会」を発足させ、翌4月にはパンフレットを配布して学生を指導していた。
この集団レイプ事件は、学生たちの蛮行もさることながら、子供にマンションを与えていた親の財力、男性のマンションに深夜ついて行った女子大生の非常識が話題になった。慶応大医学部という名門で起きた事件だけに、やっかみも加わり大きく報道された。
集団レイプが起きたマンションは、信濃町駅から歩いて数分の場所にあった。慶応大医学部に近い新宿区の1等地で、群馬県の病院の院長であるA学生の叔父が1棟を所有しているマンションで、Aの家族は親子3代にわたる慶応出身の医師だった。
主犯格とみられる4年生のB学生の父親は東大医学部教授で、母親も女医という家庭環境にあった。また2年生のC学生の父親は、人権派弁護士として知られていた。C学生はこの事件で退学後、千葉大医学部を受験して合格したが、過去を知った千葉大が再入学を拒否したという後日談がある。
強姦(ごうかん)は親告罪なので、女性側の告訴がなければ起訴はできない。また起訴前に示談が成立して、告訴が取り下げられれば起訴はできない。しかし本件のような輪姦(りんかん)は親告罪ではないため、被害者の告訴がなくても起訴となった。
今回、5人は退学という制裁以外に、刑事事件において輪姦の罪を問われることになった。慶応大医学部で起きたレイプ事件は、受験戦争で勝利した学生が、患者を診る医師としてふさわしいかどうかが問題となり、試験の成績と人間としての常識は必ずしも一致しないことを示していた。
この慶応大医学部生の集団レイプ事件と前後するが、平成11年5月、三重大医学部でも学生によるセクハラ事件が起きている。三重大医学部の学生たちが津市内のカラオケボックスなどで数回にわたり「王様ゲーム」を行い、負けた女子大生たちの服を脱がせるセクハラ行為を繰り返していたことが発覚したのである。王様ゲームとは「割りばしに番号を書き、当たり番号を引いた者が王様となり、ほかのメンバーに好きな命令を下す」というもので、当時の若者の間で流行していた。
被害を受けたのは女子学生が、医学部の人権問題委員の教官に相談したことから事件が発覚。男子学生らは女子大生を呼び出し、被害を受けた女子大生は4人であった。平成11年7月22日、三重大医学部はセクハラ行為があったとして男子学生5人に退学処分、4人に無期停学、4人に厳重注意の処分を下した。
三重大医学部の珠玖洋学部長は「医学部という高い倫理観が求められる学部で起きた事件で、また患者という弱者を守るべき医学を目指す学生として許されない行為」として、重い処分にした。この事件の処分は学内にとどまり、刑事事件には発展していない。
三重大医学部は医学部学生を対象に、事件の経緯について3時間に及ぶ説明会を開いた。学生からは事実関係や処分の妥当性について質問が相次いだ。退学処分となった1人は「あれはゲームの延長でセクハラではない。退学処分は事実誤認に基づいたもので不当である」として津地方裁判所に提訴した。
セクハラや痴漢行為は女性の受ける印象によって決まるという曖昧(あいまい)さがある。女性の訴えが本当であっても、相手を陥れようとする作為的なものであっても、男性側の弁解が通用しないのである。医師を志す者はそれだけ高い倫理観が求められ、この心構えの欠如が事件を引き起こしたであるが、可能性は低いものの冤罪を否定することはできない。言えることは、くれぐれも注意することである。
大学生が言っても厳しい言い訳だが、30歳の研修医が言う事だろうか?言いたい事は言うべきだと思うが、人格を疑われるし、 余罪はないのかと疑ってしまう。
このようなタイプの人間だと、ミスを犯しても正直に報告するのだろうか、権限を持った時に権限を乱用しないか、製薬会社と癒着しないか、 セクハラやパワハラをしないかなど、いろいろなリスクを想像してしまう。
大学や業界がどのように対応するかで、日本の医療の現実の一部が見えてきそうだ。
千葉大学医学部の学生3人と研修医が女性に性的暴行を加えたなどとして逮捕された事件で、研修医が「学生に誘われその場の雰囲気に流されてしまった」という趣旨の供述をしていることがわかりました。
この事件は、千葉大学医学部5年の吉元将也容疑者(23)ら学生3人が飲食店での飲み会で女性(20代)に性的暴行を加えて、けがをさせたとして、先月21日に逮捕されたものです。
この女性の体を触った疑いで5日逮捕された千葉大学病院の研修医、藤坂悠司容疑者(30)の身柄が7日朝、千葉地検に送られました。
その後の捜査関係者への取材で、藤坂容疑者が「学生に誘われその場の雰囲気に流されてしまった」という趣旨の供述をしていることが新たにわかりました。
飲み会には、藤坂容疑者とは別の男性の医師などあわせて10数人が参加していたということで、警察は当時の状況を詳しく調べています。
財政問題が起きればレガシーと共に公益財団法人 日本バレーボール協会の責任も名前を残すだろう。
有明アリーナが建設されれば、横浜アリーナでバレーボールの大会を開かれなくなる、又は、稼働率で共倒れ?
2020年東京五輪・パラリンピックのバレーボール会場の候補地となっている横浜アリーナ(横浜市)について、同アリーナを所有する横浜市の林文子市長は7日、定例記者会見で「開催は困難」との考えを明らかにした。
競技団体の理解が得られていないためで、バレーボール会場は、現行計画通り有明アリーナ(東京都江東区)を新築する見通しとなった。
林市長は「(競技団体に)納得してもらうには時間が短く、開催はかなり難しい」と述べた。この日は、同市役所で、都の調査チームの上山信一慶大教授や都の担当者と市の担当者が、横浜案の課題を検討したという。
林市長の発言を受け、日本バレーボール協会関係者は「横浜アリーナ開催は技術的に難しいことが当初から言われていた。有明アリーナの実現に向けて、小池(百合子)都知事は早期に決断してほしい」と求めた。
前院長や医師は無資格を認識しながら計12件の中絶手術が行われたのに、処分もなしに退職したのか?トカゲのしっぽ切りのような感じだ。
病院の管理者は誰なのだろうか?もし、院長に任せていたので管理していないのであれば、違う形の問題が起きる可能性はある。 管理者がいたのであれば、前院長に投げ任していたのだろうか?チェック機能が機能しているとかの問題ではなく、機能自体がないことになる。
医療や命に関わる人達がこのような体制や環境に疑問を抱かないのであれば、日本の医療は基本が蝕まれているかもしれない。
あるジャーナリストの名刺に記載された肩書きと住所の謎 疑惑の『水口病院』 遺族が医師を刑事告発 その4 12/06/16(天国に届くといいなぁ)
水口病院
当院に関する報道について 平成28年12月6日(水口病院)
開けない人はここをクリック

東京都武蔵野市にある産婦人科の「水口病院」で、母体保護法に定められた資格のない医師が人工妊娠中絶の手術をしていたことがわかった。病院によると、この医師は今年3月から10月まで水口病院に勤務し、無資格のまま計12件の中絶手術を担当したという。
母体保護法では、都道府県の医師会が指定した医師しか中絶手術をできない。東京都はこれまで複数回、病院への立ち入り検査を実施、無資格医師による中絶手術を把握している。無資格医師による手術を受けた6日後に死亡した女性(当時23)の遺族が6日、この医師について業務上堕胎の疑いで警視庁武蔵野署に告発状を提出し受理された。
遺族側代理人の中川素充弁護士…
東京都武蔵野市の産婦人科病院「水口病院」で、母体保護法に基づく指定医の資格のない男性医師が妊娠中絶手術を行ったとされる問題で、7月の手術後に死亡した西東京市の女性(当時23歳)の遺族は6日、警視庁武蔵野署に業務上堕胎容疑で告発し、受理された。
堕胎は刑法で禁じられているが、母体保護法で都道府県医師会の指定医だけに中絶手術が認められている。
遺族側代理人によると、女性は7月8日に手術を受け、同14日に自宅で死亡。行政解剖で、死因は「急性うっ血性心不全」とされ、手術との因果関係は不明だが、女性に持病や目立った外傷はなかったという。
女性の夫は6日、都内で記者会見し、「執刀医が指定医でないと知っていれば、手術に同意しなかった。妻の死亡は手術が原因ではないのか、ちゃんと調べてほしい」と声を震わせた。
千葉県内に住む26歳の女性の自宅に侵入して乱暴したとして、47歳の医師の男が逮捕されました。男は長野市の病院で、患者の女性にわいせつな行為をしたとして起訴されています。
医師の伊藤樹容疑者は2011年12月の深夜、千葉県内に住む女性の自宅に侵入し、乱暴した疑いが持たれています。警察によりますと、伊藤容疑者は部屋で寝ていた女性に暴行を加えて脅すなどして犯行に及んだということです。取り調べに対し、伊藤容疑者は容疑を否認しています。伊藤容疑者は9月、勤務していた長野市の病院で抵抗できない状態の10代の女性患者にわいせつな行為をしたとして逮捕され、起訴されています。病院によりますと、伊藤容疑者は精神科医で、先月、懲戒解雇されたということです。
人生は安定のようで、不安定。不安定のようで、安定。ピンチがチャンスになったり、チャンスがピンチになる事もある。単純に運次第もあれば、 運と本人の努力や判断力の場合もある。
人それぞれで価値観も違う。人生の答えは一つでない。自分には正解であっても、他人には不正解かも知れない。その逆もある。岐路に立った時、 どのような判断をするかで、人生は違ってくると思う。何が正しいかも時代、立ち位置、価値観で違ってくる。人は人。自分は自分。それで良いと思う。
森田岳穂
広告大手の電通に勤めていた新入社員の女性が過労自殺した問題を機に、労働環境を巡る問題があらためて注目を集めています。2年半前までテレビ番組制作会社に勤めていた都内の女性(28)は、自殺した女性のツイッターを見て、自身の過酷な体験と重ねています。上司から「ゴキブリ以下だ」と言われた、労働の実態とは? 記者が取材をしました。(朝日新聞東京編集センター記者・森田岳穂)
在京キー局の子会社に就職
女性は都内の有名私立大学を2012年に卒業。小さい頃から大好きだったテレビの世界で働きたいと、テレビ局を中心に十数社の面接を受けた。
希望の局からの内定は得られなかったが、在京キー局子会社の番組制作会社から総合職の内定をもらうことができた。「激務だ」とは聞いていたが、テレビ業界で働けることがとにかく嬉しく、就職を決めた。
週に2日は徹夜 寝ずに出勤も
バラエティーの特別番組のチームにADとして配属されると、出演者の控室の準備、再現ドラマへの出演、食事の手配など様々な仕事を任された。
数十人いる先輩たちの好みを把握し、毎朝コーヒーを入れるのも女性の仕事。銘柄を間違えるときつく怒られることもあった。一方、同期の男性がお茶くみをさせられることはない。疑問を感じつつも「どんな仕事でも必要なこと。頑張ろう」と言い聞かせた。
上下関係は絶対。時には理不尽なことでも責められた。コーヒーチェーンで買ったコーヒーを席に置いていたら、女性の先輩に「お金があるのね。私はコンビニのコーヒーなのに生意気」と嫌みを言われた。それからは中に何が入っているか分からない入れ物を用意して飲み物を飲むようにした。
勤務時間は長時間に及んだ。午前10時~午後10時が平均的な勤務だったが、お昼休憩は15分程度。トイレなどでの離席も5分まで。先輩が目をひからせ、少しでも長く離席すると嫌みを言われ、離席する際はホワイトボードに名前を書くように命じられた。
複数の番組を任されるようになると、週に2日は徹夜した。先輩の中には後輩に仕事を命じ、夜の街で飲み歩いてから仕事が終わっているか確認しに来る人もいた。
常に先輩におびえながら、怒られないように仕事を進めた。朝5時まで働き、始発で帰宅。家でシャワーをあびて1時間ほど仮眠をして出社した。起きられずに遅刻してしまい、先輩の叱責を受けてからは、仮眠をやめた。そんなときは、個室トイレに座ったまま寝てしまったこともある。
一カ月に徹夜明けの1日しか休みがもらえないこともあり、残業時間はひどい時で月に170時間近かった。給与は額面で40万円を超えたこともあったが、時給に計算しなおせば、コンビニのアルバイトより低かった。
体重は9キロ増 全身にじんましん
ストレスから深夜勤務の合間に夜食を重ね、先輩が離席した隙を見計らって甘い菓子を大量に食べた。気づけば入社から半年もせず体重が9キロも増えていた。朝起きると全身にじんましんが出ていたこともある。
番組完成後の打ち上げは毎回朝まで。男性社員から、居酒屋で誰も食べたがっていないバニラアイスを注文され「エロっぽくなめて食べろ」と命令されたこともあるが、かたくなに断った。ディレクターから「ADなんてゴキブリ以下だ」と言い放たれたこともある。
理不尽な言動に接し、余裕を失っていく中、体だけでなく、心にまで変調が出始めた。常に情緒不安定で、道で人とぶつかると怒りがこみ上げた。今では信じられないが、相手を蹴り返したこともある。
人に会う時間もなく、友達は減っていった。久しぶりに会っても、「人相が変わった」「怖い」と言われたが、「そんなことない」と強く反論した。「今思えば異常な状態だった。当時はそんなことないと思っていましたが、顔つきまで変わっていたのだと思います」
病院に行かせてもらえず後遺症
体も悲鳴をあげていた。寝不足のまま、ロケ現場で重い荷物を持って走っていた時に道路の段差につまずき、足首をねんざ。痛みに耐えられず会社に戻ったが、先輩に話すと、「歩いたなら大丈夫だろ」と病院には行かせてもらえなかった。
そのまま3日働いたが、足の腫れはおさまらない。痛みで眠れなかった。部長に直談判して許可をもらい、4日目に病院に行けた。医者からは驚かれ「手遅れだ」と告げられた。痛みは治ったが、足首の下の骨は、治療せず働き続けたせいで変形し、今でも出っ張ったままだ。
「好きな靴を選べなくなりました。細めだった足首が、自分で言うのもなんですが自慢だった。それが太くなってしまって、今でも悲しいです」。女性は出っ張りにあたらないように選んだスニーカーをはいた足首を記者に見せ、悲しそうに話した。
先輩「忙しくても死なないから大丈夫」
「これでは健康を害していい番組が作れない」。上司や先輩に職場環境を改善した方がいいと伝えたこが「これがうちの業界。ルールに従え」と口々に言われた。
あまりの忙しさを先輩に相談しても「どんなに忙しくても死なないから大丈夫。まだ死んでいないから大丈夫」「テレビで生きて行くなら、思いきり染まるしかない。まずは性格から変えないとダメだ」と言われた。
「ああ、これがここでの普通なんだな」と思う半面、女性には違和感しかなかった。あこがれていた世界とは言え、体も心ももたない。辞めたいと何度も思った。
それでも、女性を踏みとどまらせたのは、大きな仕事も少しずつ任されるようになっていったからだ。応援してくれる両親にも、いい報告をしたい。頑張り続ければいつか本当に評価してもらえるかもしれない。昔から曲がったことが大嫌いな性格。自分が声を上げ続ければ、職場環境が改善されるかもしれない。そんなことも思った。
評価が裏目 先輩から嫌がらせ
1年目の冬。初めて撮影現場の責任者を任された。収録後、アナウンサーら出演者からは「あなたのおかげでやりやすくできた」「ありがとう」と評価してもらえた。「会社に入って初めて、ほんとに嬉しくて、泣きました。今まで色々あったけど、やっと認めてもらえるんだって」。
ところが、そのことが気にくわなかったのか、女性の先輩社員からの嫌がらせが始まった。休日に呼び出され、週明けでも間に合う仕事を命令され、編集室にカギをかけられ閉じ込められた。
「枕営業している」「どうせコネがあるんだ」。こんな根も葉もないうわさをされたこともあった。「頑張ってやっと評価してもらったのになんでこんな仕打ちを」。あまりにも理不尽だと感じ、いつかは辞めようと決心した。
それでも、春前には新しい職場への異動が決まり、「まだもう少し頑張れる。きっと本当に認められるはず」と自分に言い聞かせた。
◇
高学歴の人が憧れの職業に就くと、劣悪な労働環境が見えにくくなることがある。
甲南大学准教授の阿部真大さんは、朝日新聞の取材に「高学歴の『エリート』といわれる層の長時間労働には冷たくなかったのか」と問題提起する。
阿部さんは、専門性があり転職が容易な外国のエリートと違い、他社に移りにくく人材の流動性が低い日本の雇用環境の中では「組織で経験を積むことが最大のキャリアアップになっている」と指摘している。(朝日新聞11月30日「(耕論)過労をなくすには」)
独立行政法人労働政策研究・研修機構がまとめた長時間労働者の割合の国際比較(2014年)によると、日本は21.3%。北欧スウェーデンの約3倍、ドイツと比べても2倍も多さになっている。
日本 21.3%
アメリカ 16.6%
カナダ 11.8%
イギリス 12.5%
ドイツ 10.1%
フランス 10.4%
イタリア 9.7%
オランダ 8.9%
デンマーク 8.3%
スウェーデン 7.3%
フィンランド 7.9%
香港 30.8%
韓国 32.4%
オーストラリア 14.6%
ニュージーランド 15.1%
森田岳穂
職場での嫌がらせや異常な長時間勤務。テレビ番組制作会社に2年半前まで勤めていた女性(28)は、体も心も限界に近づく中、退社することを決めた。せっかく入れた憧れの業界。正社員の職を3年も待たずに辞めることに抵抗がなかったわけではない。電通新入社員の過労自殺が「他人事ではない」と語る女性は「仕事は続けることが大事なんじゃない」「辞める選択肢もある。命を絶たないでほしい」と強く訴える。
異動しても、劣悪な環境は変わらず
新人時代は、午前10時から午後10時、昼休みは15分という過酷な環境だった。番組を担当すれば週に2日は徹夜した。それでも「まだもう少しがんばれる」と耐えた。
入社から1年後の2013年春には、撮影用カメラなどを扱う技術系の部署に異動。新たな人間関係ができ、何かが変わるかも知れない。わずかな希望を胸に、働き続けたが、状況は変わらなかった。
女性の訴えに耳を貸さない上司。職場での嫌がらせを見て見ぬふりする同僚たち。パワハラやセクハラを訴える窓口は会社になかった。就職面接でお世話になった総務部の社員に相談したり、上司に直談判したりしたこともある。話を親身に聞いてくれる人はいたが、何も変わらなかった。
「愚痴とか言われると迷惑」
悩みを共有できる同期もいなかった。同期も過酷な勤務状況だったはずだが、会社での雰囲気は「同期は競争相手」。別々の部署に配属後は激務の中で接する機会もなかった。
その上、ある同期から呼び出しを受け「おまえが愚痴とかネガティブなことを言うと同期全体の印象が悪くなるから迷惑。同期のためにも絶対に言うな」と言われたことがあり、なおさら相談はできなかった。
ただ、いくら追い詰められても自殺を考えたことはなかった。心身ともに弱る中でも先輩たちへの怒りや哀れみのほうが大きかった。「自分が死ぬなら、先輩たちに死んでもらいたい。あの人たちは手のかかる子ども。愛情不足な子が、いびつな表現をしてしまうように、この仕打ちも自分への愛なんだろう」。そんな風に思うと、理不尽な言動に触れても少しは心が落ち着いた。
テレビ業界へのあこがれは強かったが、自分への仕打ちはどう考えても理不尽だと思った。母親から「他の人たちががんばれているなら、もしかしたらあなたにも問題があるかも」とアドバイスされたこともあったが、「自分はこの業界のルールには染まれない」。だんだんと、仕事を辞めることに心が傾いていった。
会社、辞めます
「俺の時はもっとひどかった」で済ませる上司では話にならない。会社の幹部に直接相談すると、真剣に話を聞いてくれ、「考え直してみて」と引き留められた。
会社自体が嫌いなわけでも、仕事が嫌いなわけでもない。よくしてくれた先輩たちもいる。それでも「このままだと失うもののほうが大きい」と、13年末に退社を決め、幹部に伝えた。それから3カ月は、撮影現場の仕事も続けながら本社で退社への事務手続きや幹部との話し合いを重ねた。
退社 開放感しかなかった
14年春。手続きを終え、ついに退社の日を迎えた。送別会はなかった。「お疲れ様。これからも頑張って」。幹部にねぎらわれ、本社の建物から出ると、開放感が胸にわき上がった。「ここから人生が始まるんだ」。
その日は実家で家族とともに食事した。移動中やトイレの個室で食事をかきこんだ日を思い出すと、家族とのんびりすごす時間がうれしくてしかたなかった。「こんなに早い時間に夕食が食べられるなんて」。
今は親からの支援と貯金で学費を払い、大学院で学び直しながら、就職先を探している。勤めていた会社のそばを通ることもあるが、窓からもれる明かりを見ると「もうあそこに戻らなくていいんだ」と嬉しくなるという。
選択肢ある 人生絶たないで
30歳も近づき、この先の不安がないわけではないが、「悔いはない。辞めることは逃げることじゃないと思う」。大学時代は、「お金も稼ぎたい。すごい仕事をしていると思われたい」という気持ちもあったが、今は違う。企業の知名度や給与にとらわれず、自分らしく働ける新しい職場を見つけたいと思っている。
もしも、あのままだったら限界を迎えていた。がんばり続けて心を病んでしまった同業者も見てきた。テレビ業界全体が悪いとも、会社が悪いとも思わないが、過酷な職場があるのも現実。他人事と思わず、もし自分だったらと置き換えて、周囲への優しさを持ってほしいと願い、今回は取材に応じてくれた。
友人に会うと、顔つきが前のように戻ったと言われるといい、「今は本当に幸せ。自分を取り戻せた気がする」と晴れ晴れとした表情で話す。だからこそ、電通の新入社員の過労自殺のニュースを見た時は胸が痛んだという。
「私は自分を責めすぎずに、相手がおかしいのではと思えたけど、真面目な人ほど自分を責めてしまうんだと思う。会社のためになんか死なないで。仕事は続けることが大事なんじゃない。自分らしく生き生きと働けないと、大切なものを失う。お願いだから、人生を絶たないで、別の選択肢があることも、考えてほしい」
1人で悩まず相談を
新入社員や若手社員などは社内での立場も弱く、悩みを一人で抱え込んでしまうことも多い。過労死等防止対策推進法が2014年に施行されたことなどを受け、仕事上での人間関係や長時間労働の悩みなどの相談に、社会保険労務士や保健師、臨床心理士らが対応する電話窓口を厚生労働省が設けている。
同省によると、2015年9月の開設から半年で約3千件の相談が寄せられたという。
「こころの耳電話相談」(0120・565・455)で、受付日時は月・火曜日の午後5時~午後10時と、土・日曜日の午前10時~午後4時(祝日、年末年始のぞく)。
10月13日発売の週刊新潮などで女性問題や組合費の私的流用疑惑を報じられた日本教職員組合の岡本泰良やすなが委員長(56)が辞任の意向を固めたことがわかった。
関係者によると、岡本委員長はすでに日教組に辞意を伝え、了承されており、30日午後にも発表する。
岡本委員長は記事が出た後も報道内容について対外的な説明を一切行わず、組合の職務も体調不良を理由に休んでいた。そのため、地方の組合から不満の声が上がるなど、進退問題が浮上していた。岡本委員長は大分県教組出身で、今年4月に書記長から委員長(任期2年)に就任した。
日教組は1947年に結成された日本最大の教職員組合。組合員数は約25万人。
「週刊新潮」が報じた日教組委員長のラブホ不倫と組合費での豪遊。どう説明責任を果たすかと思えば、委員長は雲隠れし、日教組は“犯人探し”に奔走している。
***
10月3日、日教組の岡本泰良(やすなが)委員長(56)は、東京一ツ橋の日教組本部前でタクシーを拾い、池袋に乗りつけた。ホルモン専門店でホステス兼歌手の小谷彩花さん(44)=仮名=と食事すると、2人で歩いて向かった先はラブホテル。そこで3時間半以上過ごしたあと、一緒にタクシーに乗り込み、岡本氏が先に降車すると、女性は料金を日教組のタクシーチケットで精算。同じ週の7日にも、その女性が勤めるガールズバーでどんちゃん騒ぎをし、やはりタクシーで帰宅して同じように精算していた。
むろん、岡本氏は既婚者で、妻子を出身地の大分県宇佐市に残して単身赴任中。彩花嬢も夫と2人の子持ちだから、“ダブル不倫”ということになる。そもそも岡本氏は、赤坂や銀座の高級クラブで、接待も含め、ひと晩に数十万円を使うこともザラで、今年2月、1000万円の使途不明金が問題になったこともあったという――。
■即刻、お辞めになるべき
言うまでもないが、豪遊の元手は、センセイ方が虎の子の給料から差し出した組合費である。組合員は憤りを隠さない。たとえば、大阪府の養護学校教諭は、
「あの記事は私の周りはみな読んで憤っています。人間だから愛人ができることがあっても、委員長の立場でそれをやったらお終いです。やっぱり日教組は終わっている。最低限の緊張感すら失ってしまった。この際、消えてなくなったほうがいいんじゃないですか」
と突き放す。また、神奈川県の中学校教諭も、
「周りの先生方も相当に腹を立て、“不愉快だ”“ふざけんな”という声が方々から聞こえてきます」
と言って、こう続ける。
「毎月、8000円も組合費を払って、多くが日教組本部に吸い上げられているのに、“それが女遊びや遊興費に使われているなんてたまらない”という話です。それに岡本さんは、日教組教育新聞とかでは“常に子供に寄り添い”とか、清廉潔白であれみたいな正論を述べているくせに、自分がやっていることは破廉恥そのもの。即刻、お辞めになるべきだと思います」
■“取材を受けた人はいますか”
岡本委員長に、記事への説明責任があることは論を俟たない。ところが本誌(「週刊新潮」)の発売後、姿をくらましたままだ。しかも日教組が必死なのは、情報を流した“犯人探し”で、動揺する現場の教師たちさえも置いてけぼりにされているのである。
「先週水曜日の午後、事務局に勤める全員に急に呼び出しがかかりましてね」
と、日教組本部で働く職員のひとりが打ち明ける。
「6階会議室に30人ほどが集まると、前方のひな壇に清水秀行書記長や瀧本司書記次長らが怖い顔で並んでいて、清水さんから“明日発売の『週刊新潮』に、岡本委員長の愛人とお金の問題に関する記事が出る。みなさんも取材されたり、記者に張り込まれたりする可能性がある”という説明がありました。続いて瀧本さんが“僕にも電話がかかってきた。この中に取材を受けた人はいますか”と、全員を睨みつけながら、脅すように問いかけました。もちろん、私を含めてみな黙り込んでいました。続いて、顧問弁護士から“みなさんには取材に答える義務は何ひとつありません”という指示がありました」
だが、岡本委員長の姿はない。別の職員が語る。
「清水書記長からは“このような状況なので、岡本委員長はしばらく事務局に顔を出しません”という説明がありました。“雲隠れしたんだ”と、みなヒソヒソと話していましたね」
日本教育会館
■組合費で遊び放題
それにしても、疑惑の張本人はどこかに匿(かくま)ったまま、真相究明よりも犯人探しと口封じを優先する日教組とは、返す返すも最低の組織である。また、組合費による豪遊については、日教組はメディアに「事実無根だと断言します」と答えていたが、今回、清水書記長が本部職員たちに向かって、
「今後は外部の人と飲むとき、会費をとるように」
と注意したという。すなわち、これまで組合費の私的流用が横行していたと認めたようなものだ。
日教組の幹部クラスの関係者が言う。
「赤坂のTやJなど日教組の“御用達”の店を使ったときは、日本教職員組合宛ての請求書を送ってもらい、利用者が、だれとどういう目的で飲んだのか、請求書に裏書きして、関連部署に出します。政治家や役人と飲んだら、政治担当の書記から書記次長、書記長と経て決裁が下りる。それ以外の店のときは立て替え、領収証をもらって、同様に裏書きします。場合によっては“なに、これ?”と突き返されることもあります」
要は、組合費で遊びほうけても、領収証を突き返されることは滅多にない、ということらしい。
「日教組が“(組合費の流用は)事実無根”とコメントしていて、びっくりしました。みな私的な飲み食いで領収証をもらって内部で通している。『週刊新潮』に、カラオケに興じる岡本委員長と野川孝三さんの写真が載りましたけど、あれ、ホントに自分たちで払ったのか、ということです」(同)
ちなみに、「週刊新潮」が直撃した際、岡本氏はこのカラオケ三昧を、「教育総研です」と、うそぶいた。教育総研とは、元神奈川県教組委員長の小林正氏によれば、
「教育文化総合研究所の略称で、日教組のシンクタンクです。07年度には約1億1000万円がここに入っていました。有識者に話を聞いた体にして、飲食代を研究費に計上できたりするのです」
野川氏は今、教育総研の事務局長である。さて、幹部クラスの関係者は、こんな話もする。
「よく監査委員から怒られたのは、裏書きのない領収証です。僕らは指摘されるたびに書いていましたが、それでも書かない人がいるのが不思議でした」
どうやら、滅多なことがなければ、領収証さえもらえば組合費で遊び放題、ということのようだ。
■前委員長の証言
「お金の使い方、とくに飲食に関しては、委員長時代、厳しく指導していました」
と、こう打ち明けるのは加藤良輔前委員長である。
「仲間うちで飲んでも、重要な打合せなら経費で落としていいけど、私的な集まりなら自腹がスジ。私の場合、赤坂のJで業務の接待をし、終了後、執行委員が合流したときはママに頼んで、前半の業務と後半の私的な飲みで請求書を分けてもらい、私的な分は自分で振り込みました。“自腹で払うんですか”と、ママがびっくりしていましたよ」
いきおい、ほかの幹部は組合費を“私的流用”しているのがバレてしまった格好だが、加藤氏が続ける。
「日教組委員長の年収は1200万円くらい。ほかの産別労組とくらべると安いほうですが、業務と私的な飲食の境界は、金額や目的やお店、人数などから自分で判断すべきです。これは委員長時代、みんなに口を酸っぱくして言ってきたことで、退任時には岡本さんにも言いました」
ちなみに、Jなるクラブは、赤坂芸者が集う黒塀の料亭「金龍」からほど近い雑居ビルにあり、扉を開けると4席のカウンターと奥にテーブル席が4つ。壁に沿ってソファが連なり、金や茶を基調としたシックな雰囲気。上品な着物を着たママとチーママが座っていた。通いつめれば、とても自腹では払えないだろう。
特集「歴代委員長から『もう辞めろ』の大合唱 ラブホで不倫『日教組委員長』放蕩三昧の検証」より
しかし、被害者が出ないと偽サイトの運営関係者を逮捕できないのでは??
以前、確実に偽サイトと確信できるケースで消費者相談センターに連絡を取った事がある。結果は、たらい回しと被害者は出ていないとの事だった。 被害者にならないと動くような感じではなかった。消費者相談センターはアクティブではなく、受動的であるとの印象を受けた。サイトのアドレス 及び偽サイトであると判断する根拠まで教えても、被害の報告はないだった。偽サイトであれば、放置すれば被害者が出ると予想は出来ないのか? やる気がないのか、間抜けな人材の集団なのかと思った。
価格が安いが偽サイトと思われる時は、サイトで使われている文章で検索して確認したり、住所で検索したりする。偽サイトは他のサイトの情報と 重なる事が多い。確認できないように、電話番号がなく、メールだけの場合も多い。メールだと実際にどこに受信者がいるのかわからない。
県警はおとり捜査で利用者を装って少額の商品を購入して、口座が開設された銀行に捜査に入れば良いのではないのか?銀行口座が売買されている けれど、売買に関わった人は少なくとも1人は捕まえられるはずである。まあ、神戸県警がどのような対応を取りたいのか次第だと思う。逮捕も いたちごっこだろうが、偽サイトもだんだん巧妙になるし、楽天が蓄積する偽サイトの情報だけでは不十分だと思う。
「新技術は、この組み合わせを自動的に正規のサイトと比較することで偽物を見分ける仕組みで、テストでは98%の確率で判別に成功した。当面は楽天の偽サイトを対象に、閲覧時の警告表示などの開発を進めるが、他社サイトへの応用も視野に入れている。 」
テストと言ってもテストの方法次第で結果は変える事が出来る。楽天の偽サイトを対象に開発するよりも、偽サイトを運営者又は銀行口座の売買に 関与した人達を逮捕した方が良いと思う。パフォーマンスであるのなら、無駄に税金を使わないようにやるべきだろう。どうせアプリを開発するのは 兵庫県立大学の教授や生徒ではなく、どこかの民間業者に委託するのだろう。
実際の通信販売サイトに似せた「偽サイト」の詐欺被害を防ごうと、兵庫県立大学と県警、インターネット通販大手の楽天が、自動的に偽サイトを検知する新技術を開発した。見た目は本物そっくりのためだまされて注文する人が多く、「商品が届かない」といった被害が県内でも急増する。今後は利用者が偽サイトを閲覧すると警告が表示されるアプリを開発するなど、技術の実用化を目指す。(初鹿野俊)
県警サイバー犯罪対策課によると、偽サイトによる県内の詐欺被害は今年1~6月で110件、被害額計約230万円に上り、昨年同期から倍増した。偽サイトで商品の大幅割引などをうたい、購入代金を支払っても商品が届かないという被害が目立つという。
県警に寄せられる偽サイトの情報は、警察庁などを通じて民間のウイルス対策ソフトに反映されている。だが、消えては別の偽サイトが作られる“いたちごっこ”の状態が続き、楽天だけでもロゴが無断使用されるなどの偽サイトが6500以上確認されている。
そこで、県立大の申吉浩教授(応用情報科学)が中心となり、県警と楽天が蓄積する偽サイトの情報を分析。サイト作成に必要な「コンピューター言語」の組み合わせに着目した結果、偽サイトに多いパターンが発見された。
新技術は、この組み合わせを自動的に正規のサイトと比較することで偽物を見分ける仕組みで、テストでは98%の確率で判別に成功した。当面は楽天の偽サイトを対象に、閲覧時の警告表示などの開発を進めるが、他社サイトへの応用も視野に入れている。
県警は「被害が発生してからの事後対応ではなく、先回りして偽サイトの被害を未然に防げる」と意義を強調する。
頭が良く、医者は高収入と言う事だけで、医学部を選択したのであれば、不思議に思う事はないと思う。
医師は人を救う立場の人であることは間違いないが、倫理的に、人間的に優れていないと医者になれないわけでない。改善する必要が あると思えば、厚生労働省)が動くべき。
千葉大医学部の学生らによる集団強姦(ごうかん)致傷事件で、逮捕された学生らは事件後の10月、普段通り授業に出席していたとみられることが、同大学に通う学生の証言で分かった。研修医が逮捕される事態となり「人を救う立場の人がなぜ」と、学内では動揺が広がっている。
千葉大は6日、同大で記者会見。中谷晴昭筆頭理事は4人の処分について、内部に設置した懲戒委員会で「(判決など)司法の判断を待ってから検討したい」とした上で、退学や免職も含め厳しい態度で臨むことを明らかにした。
同大によると、新たに準強制わいせつ容疑で逮捕された研修医の藤坂悠司容疑者(30)は、一昨年に石川県の金沢医科大学を卒業。今年の4月から千葉大病院で研修医として勤務していた。
集団強姦致傷容疑で逮捕された同大医学部5年、吉元将也(23)、山田兼輔(23)、増田峰登(みねと)(23)の3容疑者とは「研修を通じて知り合ったのではないか」(中谷筆頭理事)という。
中谷筆頭理事は4人の犯行について、「指導する立場の研修医が犯行に及んだことは医師や人として恥ずべき行為。学生も、5年生という卒業も近い中でこのような行為に及ぶなんてショックだ」と述べた。
「(逮捕された3人の学生は)体育会系で、はきはきした人たちだ」。3人と面識があるという同大の学生は驚きの表情でそう話した。
3人の印象については、「10月にも授業で見かけたが、派手に遊んでいるイメージもなく、悪い印象は抱いたことがない」という。3人と同じ医学部に通う1年の男子学生(19)は「将来医師として人を救う立場の人たちなのに残念だ」と肩を落とした。
千葉大医学部集団強姦】千葉県警「圧力があったというのは失礼だ」「容疑者のエリート一家は捜査に全く関係ない」 日刊ゲンダイの直撃取材・華麗なる山田一族【氏名・顔写真・山田兼輔・増田峰登・吉元将也の3人か?集団レイプ】 12/04/16(メラ速報~めらそく)
千葉大医学部5年の男3人による集団レイプ事件。容疑者の1人は超エリート法曹一家の子息であることが分かった。しかし千葉県警は容疑者の氏名どころか、事件の概要さえ発表していない。ネット上では、「圧力がかかっているのではないか」との臆測が飛び交っている。日刊ゲンダイは千葉県警捜査1課課長代理に疑問を直接ブツけた。
■「取材拒否の事実はない」
──なぜ氏名を公表しないのか。
マスコミはいろいろ言ってきていますが、現在捜査中で(発表すると)どうしても影響が出るので発表していないということ。また被害者のこともあるので、必要な時期がくれば当然、発表していく考えです。
──「氏名を公表しないのはおかしい」という声が数多く上がっているのは把握していますか。
報道では知っています。
──公表できない事情でもあるのですか。
(容疑者は)官僚の息子ではないかとかいわれていますが、そんなのはまったく関係のない話であって、捜査が進めば対応していきます。
──容疑者の1人は超の付くエリート法曹一家の子息ですが、ご存じですよね。
そこまで(すごいとは)把握できていませんでした。ただ把握していようがしていまいが、捜査にはまったく関係ありません。
──圧力があったということは一切ありませんか。
まったくないです! そんな圧力があって警察がひるむようなら、日本の警察も終わりです。そう言われること自体が私はちょっと気分が良くない。そんな気持ちで仕事をやっている警察官はいない。そんな失礼なことを言うなんて。ほんと失礼だと思いますよ!
──医学部生がこのまま社会的制裁を受けずに、将来医療に携わるようなことがあれば世間は許しません。
その通りだと思います。捜査を進める中で、共犯者の有無がネックになっているところです。一部報道に取材を拒否しているとありましたが、そんな事実はない。必要であれば、きちんと対応していきます。
◇ ◇ ◇
写真週刊誌には3人の顔写真が載り、ネット上でも実名が流れ始めている。世間はもう待ってくれないだろう。
「看護学部3年の女子学生(20)が『ニュースで知ってびっくりした。医学部生とも関わりがあるが、優秀でみんないい人だと思っていたのに……』と驚いた様子。医学部3年の男子学生(22)は『医学部だからではなく、人間として間違っている』と憤った。」
医学部に合格した生徒は合格するだけの最低限の能力がある事は証明されていると思うが、「いい人」である事を確認する事は一切行われていないし、 入試試験では問われていない。高校生時代の社会活動をした事や高校時代のいろいろな活動を合格判断に参考にするとかはない。まあ、社会福祉活動等を強制にしたら 偽善的に仕方なく活動に参加する人もいるだろう。
「患者に寄り添い、命を救う医師の卵が、女性の体も心も傷つけたとされる事件に、学生や教員からは『人間として間違っている』『学生への教育を考え直す必要がある』との声が上がった。」
医者としての理想と現実は違うと言う事だ。千葉大学が医学部の方針として倫理及びモラルの教育を強化したいのであればそうすれば良いと思う。しかし、 医学部を持つ大学は多くある。日本の医師達の現状は変わらないであろう。
厚労省や国が今回の千葉大生集団強姦事件についてどのように理解し、評価し、対応するのか一番重要だと思う。厚労省が対応する必要もない事件と思えば、 今後も単純に頭さえ良い医学生、又は、最低限の能力とお金にゆとりのある医者の子供達が医者になるであろう。患者に寄り添うのは一般人達が抱く医者に対しての 理想や願望であって、医者の義務ではないはずである。もしかしたら、医療業界を良く知らないので間違っているかもしれない。
「命を救う医師の卵」にしても命に関わる医師もいるが、直接、そこまで関わらない医師も多いはずである。「命を救う」に関して、例え、国家試験に 受かった医師であっても、能力や経験には差があるはずである。病院の規模や場所によっては、能力が高い方が良いが、患者に接する姿勢や 患者の立場に立って考える医師の方が望まれる場合もある。単純に「命を救う」ではなく、医療レベルが下がっても「命」と「心」をバランスを取る対応の 方が感謝され、高く評価される場合もあると思う。
生命学的に命が維持されるだけでなく、違う形の対応の仕方もあると思う。医者としてのステータスや開業医を継ぐことしか頭にない医大生や医者には関係の ない事ではあるが、考えるべき事だと思う。
女性に集団で性的暴行をしたとして、千葉大医学部5年の20代の男子学生3人が集団強姦(ごうかん)致傷容疑で逮捕された。患者に寄り添い、命を救う医師の卵が、女性の体も心も傷つけたとされる事件に、学生や教員からは「人間として間違っている」「学生への教育を考え直す必要がある」との声が上がった。
医学部がある千葉市中央区の亥鼻キャンパスでは22日、看護学部3年の女子学生(20)が「ニュースで知ってびっくりした。医学部生とも関わりがあるが、優秀でみんないい人だと思っていたのに……」と驚いた様子。医学部3年の男子学生(22)は「医学部だからではなく、人間として間違っている」と憤った。
教員の男性は、千葉大の学生だった寺内樺風被告(24)が2年近く少女を監禁したなどとして未成年者誘拐や監禁の容疑で逮捕された事件に触れ、「3月に監禁事件が発覚したばかりで、もう驚きもない。レベルの低い大学ではないが、このような事件が起きてしまう。大学は学生への責任ある教育や支援のあり方をもう一度捉え直さないといけない」と語った。
この日午後2時から記者会見した渡辺誠理事と中山俊憲・医学部長は、午前中に調査委員会と処分を検討する懲戒委員会を設置したことを明らかにした。事件は飲食店で開かれた学生らの飲み会で起きたが「報道で初めて知った」「逮捕された学生が特定できていない」などと説明し、調査の具体的方法や期間は明言しなかった。
中山医学部長は「非常に驚きを持って捉えている」などと第三者的な発言にとどめていたが、報道陣から当事者としての受け止めを何度も問われ、「事実であるとすれば非常に残念で、社会的責任を感じている」と述べた。被害者支援や再発防止策については「調査結果を待って対応したい」「真摯(しんし)に対応したい」と繰り返した。【渡辺暢、田ノ上達也、信田真由美】
「男性は国立大大学院の博士号を持っている。」
三菱電機の期待には応えられなかったと言う事実は博士号は評価としてのポイントは高いが、結果を出せる根拠にはならない事もあると証明してしまった。 企業としては、博士号の人間を取るよりも、可能性がある人間を大学に戻して博士号又は研究させる選択肢のメリットを感じたかもしれない。
学生は無理をさせても働かせる企業なのかを見極める方法を、先輩やインターネットの情報などを参考にして自己責任で探すべきだと思う。 名前や知名度だけで選ぶのか、自分の生き方を考えて企業を決めるのかを考えるべきだと思う。まあ、実際に飛び込ん見ないといろいろな事が わからない事もあるので、あくまでもリスクを減らす手段でしかないかもしれない。
三菱電機の元研究職男性(31歳)が、精神疾患になったのは長時間労働が原因だったとして、藤沢労働基準監督署に労災認定された。男性は11月25日に厚生労働省で記者会見し、解雇の撤回と職場環境の改善を訴えた。男性は会社から「病気休業の期間が終わった」として解雇されている。【BuzzFeed Japan / 渡辺一樹】
2014年1月以降、著しく業務量が増加
男性は2013年4月、研究職として入社した。配属先は、神奈川県鎌倉市の情報技術総合研究所。半導体レーザーの研究開発をしていたという。
労基署は、男性が2014年4月上旬ごろ、「適応障害」を発症したと認定。2014年1月以降、研修論文作成業務で著しく業務量が増加し、それまでの倍以上、月100時間を超える時間外労働があるなど、心理的負荷が「強」だったとして、11月24日付で労災を認めた。
ところが男性の場合、会社に記録された残業時間は、2015年11月16日~12月15日が37時間30分。翌月以降も37時間、59時間30分、52時間、32時間だった。
男性は、残業時間を「自己申告」するルールだったが、時間通りの申告が許されなかったのが原因だと主張。「会社による残業隠しだ」と批判している。
IDカード「入退室記録」と「残業記録」に大きな差
男性の職場はIDカードで入退室が管理されていた。その「入退室記録」と、残業記録の数字には大きな差があった。
例えば2014年6月13日、男性は職場に午前8時17分に入室、午後11時19分に退室していた。しかし、残業記録は2時間だった。
なぜこんなに差があるのか。組合との交渉の場で会社は、残業になっていない分は「自己啓発時間」だと説明したという。勝手にやっていることだから、労働時間にはならないという理屈だ。
男性が所属する労働組合、よこはまシティユニオン書記次長の川本浩之さん「もっと仕事をしろと叱責されていたのに、会社で自己啓発する時間があったはずはない」と指摘する。
時間通りの申告「許されなかった」
男性は2014年2月に、およそ月160時間の残業をした。その月は休みが2日間しかなく、その休みの日にも寮で仕事をしていた。この時には上司が「70時間まで付けていい」と伝えてきたので、59時間と申告したという。
男性は「『残業は40時間未満でつけろ』と、直属の上司から言われていました」と語る。39時間、39時間、39時間だと怪しまれるので、35時間とか、36時間とか、不自然にならないようにしろ、とメールで指導されたこともあった。
同じ職場の先輩たちに、みんなちゃんと付けているのかを尋ねたところ、「ごまかしている」との答えがあった。自分より仕事ができる先輩たちが時間通りに付けていないのに、新人の自分は付けられないと、考えたそうだ。
さらに、時間通り申告した先輩が、上司から「なんでだ」「ブラックもクソも関係あるか」と怒られているのを目撃したこともあったという。
「ちゃんと付けたら、自分もどやされると思って、嘘を書いていました」と男性は語った。
「記録を義務付けなければ、規制の意味がない」
男性の代理人・嶋崎量弁護士は、「こんなものは『自己申告』ではない」と力を込めて話した。
「みんな会社員として、自分の未来を考えています。申告した瞬間にどやされるなら、そう書けるわけがない」
「労働時間をきちんと把握する仕組みを、大企業の三菱電機が作れないわけがない。作らないんですよ」
「こういうことは、あきれるぐらい、そこら中で行われている。労働時間の上限規制をしたって、インターバル制度を作ったって、肝心の記録がなければ、意味がありません」
上司「俺が死ねと言ったら死ぬのか」
男性は上司からパワハラも受けていたという。
男性は会議室に呼び出されて、何時間も叱責されていた。「お前の研究者生命を終わらせるのは、簡単なんだぞ」と言われたこともあった。
上司の指示に従って失敗した際には、「言われたことしかできないのか。じゃあお前は俺が死ねと言ったら死ぬのか」などと詰め寄られたこともあったという。
書類を「これじゃダメだ」と突き返され、「お前、いつになったら書けるんだ」と言われながら、夜中の3時まで作らされた。そして「こんなのは中学生でも書ける」とか「そんなんでよく博士取れたな」と罵倒された。
男性は国立大大学院の博士号を持っている。
14年4月に教育担当者がいなくなると、上司のパワハラは悪化した。男性は4月、病院でうつ病と診断され、薬を飲みながら仕事をしていた。しかし、6月にドクターストップがかかり、休職することになったという。
「解雇を撤回してほしい」
会社は当時、「休業期限は2017年6月まで」と文書で説明していた。しかし、今年の2月になって、「間違いだった」「今年5月15日までに復帰しないと解雇だ」と連絡してきた。
実家で療養中の男性は2016年4月、会社に休職期間の延長を申し立て、労基署に労働災害請求をした。
今回、労災認定されたことを受けて、男性は「労災で休んでいる最中に、解雇するのは違法だ」として、解雇の撤回を求めた。
「逃げたいと思っていた」
男性は会見で、うつ病と診断された頃のことを次のように振り返った。
「不眠で、寝ている最中に目が覚めました。勤務後、何もする気になれませんでした。人間関係に対する不安を強く感じ、早く死んで楽になりたい、逃げてしまいたいと思っていました」
男性は、電通の新入社員だった高橋まつりさんが過労自殺をした事件にも言及し、次のように語った。
「彼女と自分は紙一重だと思います。パワハラにあったり、ものすごい量の残業を強いられた時、どこに相談をしていいかわかりませんでした」
「私は、際限なく働くことを強いられました。これは三菱電機だけではなく、日本社会に蔓延する問題です。同じような過重労働の被害者や、その家族には、『あきらめず、迷わず、相談しよう』と伝えたいです」
「過労で病気の人に諦めるなというのは、残酷かもしれません。私も病気になった当初は、先行きがない、二度と働くことができないのではないかと思いました。長く険しい道のりで、なんどももう無理かなと思いました。でも、大勢のご支援のおかげで、ここまで来ることができました」
「医者やカウンセラー、弁護士、立ち向かう労働組合など、心ある人たちが少なからずいます。自分を責めないで、どこかおかしいんじゃないかなと思って、諦めないで納得するまで行動を起こしてほしい。私も諦めなかったことが、労災認定につながったのではないかと思います」
嶋崎弁護士は「労働時間をきちんと記録しないのは『犯罪的』です。しかし今の日本ではまだ犯罪ではない。日本社会の問題として、法律を作って取り締まらないといけない」と話していた。
三菱電機広報部はBuzzFeed Newsの取材に対し、「労基署の判断を確認のうえ対応を検討いたします」とコメントした。
警察に逮捕されても名前が出てこないと言う事は、逮捕された医大生の親が権力を持っているか、お金を持っていると言う事では?
学生の噂話、又は、インターネットでの情報からヒントは得られるかも?
すごい弁護士が付いているから逮捕=有罪ではないと言っているのかも?まあ、それでも完全な情報封鎖は出来ないような気がするけど?
女性に集団で暴行したとして、千葉大医学部の男子学生3人が集団強姦ごうかん致傷容疑で逮捕された事件で、同大は調査委員会を設置したが、学生3人を「特定できていない」とした。
3人とも成人にもかかわらず、千葉県警が名前など事件に関する情報を発表していないことが、学内の調査の支障となる可能性もある。
千葉大は22日、記者会見を開き、医学部の副学部長をトップとする調査委員会を設置したと発表した。21日に報道機関から取材を受けて事件を把握したといい、会見した渡辺誠理事(国際・教育担当)は「逮捕されている学生が分からない。警察から情報をいただくなどして調査したい」と話した。また、県警から、捜査協力依頼や照会はないとした。
会社の体質は簡単には変わらないと思う。名前が公表されれば、こう言うたぐいの男性の扱いが上手い女性は気にせずに入社してくるので、 良いのではないのか?
男性にとってもセクハラの心配がなくて良いのではないのか?飲み屋でキャバクラでセクハラ訴訟がないのと同じ。
「おれの女になったら給料を上げてやる」。男性管理職から社内や無料通信アプリ「LINE(ライン)」で9カ月にわたってセクハラを受け続けた女性社員は、勤務先の会社と管理職に慰謝料など計約770万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こした。判決は徹底抗戦した管理職側の主張を退け、約57万円の支払いを命じた。今回は身体接触でなく言葉によるものだったが、セクハラ訴訟の賠償額は妥当なのか。
◆フラれた腹いせか
原告の女性は20代後半。平成26年8月、商用車の買い取り・販売会社に新入社員として入社し、九州支店に配属された。妻子を神戸に残して単身赴任していた部長からセクハラを受けるようになったのは、そのわずか2週間後だった。
判決などによると、9月8日、女性のLINEに「付き合って」「女として好き」とメッセージが届き、その後も「夜景見に行こう」などと誘われ続けた。女性は10月22日、LINEで「好きな人がいます」と伝えたが、部長は「ばか!」「あほ!」などと返信。セクハラは次第にエスカレートしていく。
11月に入ると、女性を自宅に連れ込み、「おれの女になったら役職とかつけて給料上げてやる」と宣言。業務時間中に「胸触らせろ」「脱がすぞ」といった性的発言も連発した。
27年4月、2人きりになった職場で「おれにもっと甘えろ」と迫り、6月には「お前がかわいいからそばに置いておきたい」と隣席への席替えを強いた。
◆「違和感」部長が反論
女性は6月30日以降、取締役に被害を直訴して休職。会社側が事実をきちんと調査せず、社長が部長に口頭注意する対応にとどまったことに失望し、8月に神戸地裁に提訴した。
会社側は当初争う姿勢を示したが、今年4月に100万円を支払う内容で女性と和解。これに対し、部長側は代理人弁護士を選任し、セクハラの意図はなかったと反論した。準備書面で性的発言などを事実と認めた上で「職場の雰囲気を明るくするための冗談。原告だけを対象にしたわけではない」とし、「原告は性的な冗談にも嫌そうな素振りを見せず、むしろ盛り上がっていた」と主張した。
「原告にセクハラを主張されることには違和感がある」とまで言及した陳述書も提出したが、代理人が7月に辞任した後は新たな代理人を選任せず、裁判の期日にも出廷しなかった。
9月の判決は部長側の主張をほぼ退け、女性側の勝訴を言い渡した。女性側が証拠提出したLINEなどからセクハラ被害の主張が信用できると指摘。「原告だけを対象にしたわけではない」とした部長の弁明を不法行為の成立を否定する事情にならないと断じ、執拗(しつよう)なセクハラ・パワハラがあったと認定した。
一方、慰謝料についてはキスをされたり体を触られたりする身体的被害がなく、大半が言葉によるセクハラだった点を重視。「権利侵害の程度がさほど大きくない言葉が多い」として女性が求めた600万円から50万円に大幅に減額し、弁護士費用などと合わせた約57万円の支払いを部長に命じ、確定した。
◆損害回復に疑問視
「言葉のセクハラは軽く、身体接触型のセクハラは重いという日本の一般的な認識が反映された判決だ」。セクハラ訴訟に詳しい山田秀雄弁護士(第二東京弁護士会)は指摘する。
大阪市港区の海遊館が男性管理職2人に対し、女性従業員へのセクハラ発言を理由に出勤停止とした処分を妥当とした昨年2月の最高裁判決を引き合いに「言葉のセクハラにも厳しい姿勢で臨む方向性が示されていただけに、原告女性の損害回復が十分でない印象を受ける」と疑問視した。
山田弁護士によると、日本でのセクハラの賠償額は100万~300万円の範囲が最も多い。近年はセクハラへの認識が厳しくなったため1千万円を超える賠償額も珍しくないが、慰謝料でなく、休職や転職に伴う逸失利益で高額化しているのが現状という。
山田弁護士は賠償額の妥当性について「米国のように億単位の賠償額は行き過ぎとしても、日本は女性の精神的苦痛を考慮すれば低すぎる」と語る。再考すべきか否か、幅広い議論が求められる。
100億円を溝に捨てるような事はもったいないが、「長沼ボート場」(宮城県登米市)に決まれば、東京都の負担は一切なくなる。しかも、 関連費用もなくなる。だから、実質的な損失は100億円は切るであろう。もし、「海の森」に決まると想定外のコストが発生するリスクが残る。 「海の森」工事中止がベストであろう。
「日本で初めての海の中のボート場なのでその分お金はかかってしまうと春日さんは話した。」
こんなプリミアムは必要ない。海の中のボート場のために1000億円もかけようとしたメンタリティーが気に入らない。自分達が良ければ、 他の人々に負担をかけるのは平気であると思う態度は大問題。「海の森」工事中止がベスト。
2020年東京五輪・パラリンピックのボート、カヌー・スプリント会場として東京都が整備を進めている「海の森水上競技場」(東京湾岸)の工事を中止した場合、約100億円の損失が出ることが分かった。18日の都議会オリンピック・パラリンピック特別委員会で都の担当者が明らかにした。
「海の森」は7月に着工済みで、担当者は競技予定地内にあったごみ揚陸施設の撤去・移設工事に38億円、調査設計に9億円を投資したと説明。中止の場合は損害賠償や原状復旧工事費も必要となり、損失は計約100億円に上ると試算した。
同会場を巡っては、都の都政改革本部の調査チームが「海の森」の恒設整備と仮設整備、「長沼ボート場」(宮城県登米市)への移転の3案を提言。30日に開かれる都、国際オリンピック委員会(IOC)、大会組織委員会、政府の4者協議で採用案が決まる。担当者は海の森について、結論が出るまで工事を一時中断することも明らかにした。
また、調査チームがバレーボール会場候補の一つに挙げ、7億円とした「横浜アリーナ」(横浜市)の整備費は、試算を上回るとの見解を示した。
水泳会場「オリンピックアクアティクスセンター」(江東区)の年間収支については、調査チームが提言した「観客席5000席」「1万5000席」「2万席」の3案は、いずれも5億9700万~8億5400万円の赤字になるとした。【柳澤一男】
東京五輪
東京五輪のボート・カヌー会場見直し問題をめぐり、森会長率いるオリンピック・パラリンピック組織委員会が小池百合子都知事と対立。組織委員会は小池都知事の進め方を痛烈に批判している。東京五輪の開催費用に関しては当初7340億円だったものが2115年には2兆円に増大。先月には都政改革本部が3兆円超えの試算を出した。組織委員会のスポンサー収入は5000億円ほどでそれ以外は都や国などが負担することになるという。
スタジオで東京オリンピック・パラリンピック組織委員会を巡る相関図について解説。鈴木は組織委員会にはIOCからもらっているお金も含め5000億円しかないと説明。オリンピックの仕組みとして政治からの独立・自立がある。東京都は組織委員会へ監理団体になるよう要請し、都が強い権限を持てる仕組みとなっている。
東京五輪の費用について。阿川佐和子はエスカレートしているので前回の東京開催のときのように原点に戻る必要があると話した。大竹まことは4者会談で止めることができるのは東京都の小池さんだけだと主張する。
現状は政府は何も口出ししていないが安倍首相がマリオで登場したことにより波紋が広がっているという。本来はIOCが文句を言うことだという。さらに安倍総理の着替えについてもダメ出しが出た。
相関図では組織委員会が中心にいて金を出し放題だと言うことになる。東京都は金を出すだけなのかということで怒っていると言うことになる。東京だからできることで他の場所だとどうやって親近を捻出するのかという事になり使い方も他にあるだろうとなる。
元JOC職員の春日氏は長野五輪のときは費用分担がはっきりしていたと主張する。会場を作るのに半分を国が出し残りを県と地方自治体が出すと決まっていた。鈴木知幸氏は長野の負債は現在でも返しきっていないと話す。
たけしの母はカーリングのチケットで見たらいつ行っても掃除していると話していたという。
レガシーと言っているが本当にちゃんとした遺産になるのかも疑問なところは一杯ある。維持費もかかるためその後の使用方法を考える必要がある。長野オリンピックでも多くは市民が活用する施設になっているがボブスレーとリュージュの会場は年間維持費が約2億円で赤字となっている。
小池都知事の本当の目的は?海の森水上競技場が500億から300億に減らしていて、付け替えなども入っているだろうと北川氏は指摘する。五輪施設の整備工事の入札方法は金額ではなく技術力で選ぶようになっているという。その為大手しか手を出すことが出来ずなあなあで決まってしまっているという。金額を安くすると安かろう悪かろうという事になり、それより技術があるからお金がかかるという話になりそれでも東京は金が余っているから進んでしまったことになる。
ボート会場の他に問題が出てくるのではないか?東国原氏はバッハ会長が来たことはそこに釘を差した意味もあると指摘する。利権の問題などを解決しようとしたら地検や警察が動くようなことにもなりかねないという。
東京五輪
東京五輪の開催費用3兆円の内訳について解説。阿川佐和子はどうしてそんなにかかるのかと指摘。ロンドン大会も招致時に7484億円と提示していたが、結局2兆1000億円を越していた。
春日良一は五輪は平和運動であるからお金を使うべきだと指摘。鈴木知幸らはボート・カヌーの会場は海の森に仮設で建てることを提案した。ビートたけしは五輪は経済破綻したギリシャに頼ればいいのではと話した。
東国原英夫はボート・カヌー競技を韓国で開催するとの案が出ていることについて、アジェンダ2020で開催国以外での競技開催を容認していることが関係していると話した。
杉村太蔵はオリンピックの東京開催が決まった時、建設株に注目したところ儲かったというエピソードを披露した。
東京五輪
ボート・カヌー会場に3施設の候補があり、すべての試算は都が行ったものだという。ビートたけしは海の森水上競技場の整備について、組織委が推す背景には豊洲市場と同じゼネコンの働きかけがあるのではと指摘した。東国原英夫はゼネコンが関係あるのではと同意した。大竹まことは、特定の企業を思わせる発言は問題になるのではと指摘した。田嶋さんはここまで論じているのに請け負った人たちはなぜ顔を出さないのかと話した。鈴木さんは会場整備費の内訳を説明したが、アバウトでしっかい調べなければ、海の森を仮設にして五輪が終わればなくせばいいのにとした。
競技者に不利と言われている海の森に固執するのは、ボート・カヌー競技団体がこういう機会がなければマイナースポーツにお金をかけてもらえないからチャンスを逃したくということだと春日さんと鈴木さんは話した。風と水質の問題を解決できることが前提で海の森となった、そういうものは最新技術を投入して基盤をつくって行かなければならない、日本で初めての海の中のボート場なのでその分お金はかかってしまうと春日さんは話した。
埼玉と宮城が誘致しているが、誘致成功したら東京都のお金が埼玉もしくは宮城に流れるということなのか杉村さんが質問すると、ご当地が出すので東京都は出さないという。
もしボート・カヌー会場が宮城県に決まった場合費用は宮城県が工面することとなる。その財源はどう捻出するのかは、国の補助金や地方債に加え震災復興の寄付金などを検討にしている。復興の象徴として競技開催を目指すという。会場見直しで注目される「復興五輪」。
2011年3月11日に災害が起きて、その6月石原元知事が立候補の声明を出したがその時にオリンピックは復興の証をつくるという大義名分を見つけ国会の決議まで行く。しかしこれは国内事情であるためグローバルな話にはならないので、プレゼンテーションの時には一言も記載していないという。春日さんは宮城にオリンピックがきたら特有のパワーで元気になる、ただIOCとIFなどが決めた場所に小池知事がお金の問題でクレームをつけてきたとした。
終わっても使えるのかというものはIFの考えに入っていて新しい施設を作る時、その時一番水準が高い競技場をつくることがスポーツを進行している団体にとては常に考えにあることだと春日さんは話した。
オリンピックは3兆円超えるかについては鈴木さんは答えられないとしたが、内部では2兆円で収まるのではという声もあるという。施設の値段で叩かれているが、施設整備費は3兆円の3分の1以下で、テロ対策などのソフト経費がまだ読み切れていないという。
長野五輪
ゲストには東京五輪招致活動の推進担当課長だった鈴木知幸氏、元JOC職員で長野五輪の招致を担当した春日良一氏らを迎える。
情報タイプ:イベント URL:http://tokyo2020.jp/jp/
・ビートたけしのTVタックル 2016年10月23日(日)11:55~12:55 テレビ朝日
豊洲盛り土問題が良い例。調査すれば、事実が明らかになるわけではない。
福岡市のJR博多駅前で起きた大規模な道路陥没事故で、現場の地下鉄工事のトンネル天井部分が他より約1メートル高く掘られていたことが市への取材で分かった。上下線のトンネルが合流する地点のため、広い空間を確保する必要から設計段階では2メートル高く掘る予定だったが、掘削前に上部の岩盤が薄いことが判明した後も1メートル低くする変更にとどめていた。専門家は「岩盤が薄い中で天井を高く掘ったことが陥没の一因ではないか」と指摘している。
市によると、事故現場は市地下鉄七隈線を天神南駅から博多駅まで延伸する工事区間の中間駅(仮称)付近。博多駅に向かって上下線のトンネルが合流する地点にあたり、それぞれのトンネルを円筒状の掘削機を使った「シールド工法」で掘り進んでUターンする折り返し点でもあった。このため広い空間が必要となり、空間を少しずつ掘り広げる「ナトム工法」を採用して博多駅から中間駅に向かって掘削していた。
当初は博多駅側のトンネルよりも天井部を約2メートル高く設計していたが、昨年10月に施工業者がボーリング調査をしたところ、トンネル上部の岩盤が掘削方向に向かって左側へ低くなるように傾斜していることが判明。下降している部分の岩盤が当初の想定より最大約1メートル薄いため、専門家で作る委員会に諮った上で今年8月に天井高を約1メートル低くする設計に変更していた。
事故は天井を高くする場所を掘り始めて約5メートル進んだ場所で起きた。市は「事前に地質のデータなどを入念に確認しながら掘削したが、岩盤にもろいところがあったのかもしれない」としている。
谷本親伯(ちかおさ)・大阪大名誉教授(トンネル工学)は「典型的なトンネル事故と言えるが、岩盤層が薄いのに天井を高く掘っており、設計や施工技術を過信していたのではないか」と話した。【吉川雄策】
簡単には悪しき慣行はなるなりそうもない。長いスパンで、厚生労働省がどのように対応するかであろう。
「働き方改革」を実現する上で、過重労働の横行は見過ごせない。政府の危機感の表れだ。
大手広告会社の電通に対し、厚生労働省が労働基準法違反の疑いで強制捜査に乗り出した。全社的に違法な長時間労働が常態化していた可能性が高いとみて、立件する方針だ。
昨年末に24歳の女性新入社員が過労自殺した問題で、電通は10月に任意の立ち入り調査を受けた。それから1か月足らずで、捜査のメスが入った。労使協定の上限を超える残業や、時間を過少申告させる「残業隠し」が疑われる。
長時間労働がはびこる日本企業全体への一罰百戒の意味もあるだろう。徹底した捜査により、実態を明らかにして、悪あしき慣行を断ち切ってもらいたい。
電通では1991年にも、入社2年目の男性社員が過労自殺している。2013年には30歳の男性社員が病死し、過労死と認定された。10、14、15年には、違法な長時間労働があったとして、労働基準監督署の是正勧告を受けた。
勧告後に「ノー残業デー」を設けるなどしたが、実効性は上がらなかった。立ち入り調査を受け、午後10時以降の全館消灯などを始めたものの、社員からは「今回も掛け声倒れではないか」といった冷ややかな声も上がる。
企業体質の改善を怠った経営陣の責任は重大である。
こうした企業風土は、電通に限らない。10月に公表された過労死白書によると、過労死ラインとされる「月80時間超」の残業があった企業は23%に上る。
厚労省は昨年、大企業の過重労働を専門に取り締まる特別対策班を新設した。靴販売チェーンの運営会社や大手ディスカウント店など5社を、違法な残業をさせた疑いで書類送検している。引き続き、厳しく監視すべきだ。
労働基準法は、労働時間の上限を1日8時間、週40時間と定めているが、労使協定を結べば残業が認められる。協定で決めた延長時間を超えると違法になる。
しかし、上限規制がないため、実質的には青天井だ。100時間を超える協定さえある。法規制が機能していないことは明らかだ。政府が上限規制の導入を検討しているのは、当然だろう。
業務量や人員配置を変えないまま、規制を強めるだけでは、サービス残業が増えかねない。働き方全体の見直しも不可欠だ。
過重労働で若手社員が精神的に追い込まれないよう、各企業の真摯な取り組みが求められる。
長崎県長与町(ながよちょう)岡郷の三菱重工長崎造船所堂崎(どうざき)工場で8日午前9時半ごろ、従業員から「爆発音がした」と119番通報があった。
同社によると、堂崎工場では魚雷などの作動試験をしており、現場では当時、開発中の魚雷のエンジンの試験中で、「ボンッ」という爆発音がしたという。エンジンの部品などが一部焼けたが、工場の建物への延焼や建屋の損傷はなかったという。約50メートル離れた場所で作業を遠隔操作していた数人の従業員も無事だったという。
同社などが、爆発の詳しい原因を調べている。
常態化した長時間労働に対し、ついに強制捜査のメスが入った。厚生労働省の東京労働局などは7日、大手広告会社の電通に再び乗り込んだ。残業時間を隠すため勤務表に嘘を書くよう指示していた疑いがあるほか、「女子力がない」など上司のパワハラも報告されており、電通の労働環境の悪質さが際立っている。
◇
「君の残業時間の20時間は会社にとって無駄」「会議中に眠そうな顔をするのは管理ができていない」「髪がボサボサ、目が充血したまま出勤するな」
昨年12月に過労自殺した電通の新入社員、高橋まつりさん=当時(24)=は、上司のパワハラをうかがわせるメッセージを残していた。長時間労働でむしばまれていく肉体に加え、上司の言動が精神的に追い打ちをかけた形だ。
電通では「残業隠し」のような勤務表作成が横行していた疑いがある。労使協定では、残業時間の上限は70時間(所定外)。高橋さんが自殺する直前に自己申告した勤務表には「69・9時間」(10月)、「69・5時間」(11月)とぎりぎりで記載されていた。東京労働局などの調査では、ほかの社員にも同じような記載が見られたという。
さらに高橋さんの遺族側弁護士は、電通の企業風土を問題視し、1950年代に当時の社長の遺訓とされる「鬼十則」が背景にあったと指摘する。
《取り組んだら「放すな」、殺されても放すな》《周囲を「引きずり回せ」》《頭は常に「全回転」、八方に気を配って、一分の隙もあってはならぬ》。電通の社員手帳に掲げられていたという鬼十則にはこのような過激な表現が並んでいた。
電通は「捜索が入ったことは事実。調査には全面的に協力しています」とコメントしている。
テレビも原発も、そしてオリンピックも、仕切ってきたのはすべてこの会社
陰の支配者、タブー……これほどイメージが先行し、多くが語られてこなかった巨大企業も珍しい。本当はどういう会社で、どんな権力を持っているのか。当事者たちがその生々しい実像を明かした。
社長が出した文書の中身
「本当に反省をしているのか」「ただの死んだフリではないのか」――。
いま電通社内で話題になっているのが、この10月半ばに石井直社長名義で社員に宛てられた文書である。
電通の新入社員だった高橋まつりさんの自殺が長時間労働による労災だと認定されたのは9月末のこと。その後、労働基準監督署などが電通に立ち入り調査をする事態に発展し、騒動は日に日に大きくなっている。
そんな最中に出されたこの文書はまず、
〈当社は先週10月14日(金)の午後、東京労働局による「臨検監督」を受けました〉
との一文で始まる。
〈今回の当社に対する臨検監督は、東京だけでなく、関西と中部でも同時に実施されました。
臨検監督が、このような広範な規模で実施されることは前例がなく、また、東京における臨検監督には「過重労働撲滅特別対策班」も参画したことは、当社の労働環境に対する当局の関心の高さの表われであり、社はその事実を極めて厳粛に受け止めています〉
文書ではまず、電通が当局からどのような調査を受けているかを詳述。さらに、〈法人としての当社が書類送検されることも十分に考えられる〉とし、社員に危機感を訴えかけている。
文書にはこうした現状が赤裸々に書かれていると同時に、公には語られないトップの「本音」が記されていて興味深い。
〈先週金曜日から週末にかけて、マスメディアを中心に、当社が臨検監督を受けた一件が、極めて大きく取り扱われています。
そして、その論調は、電通という企業を糾弾するものです。
一連の報道に接し、心を痛めている社員の皆さんの心情を思うと、私自身、社の経営の一翼を担う責務を負っている身として、慙愧に堪えません〉
たとえばこの一節は、電通がメディアに必要以上に糾弾されていると言わんばかりで、「被害者」のような書きぶりである。
〈高橋まつりさんに関する労災認定の一件に加え、先日の臨検監督、さらにはその後の一連の報道における論調は、当社が現在直面している事実を如実に表しています。
それは、これまで当社が是認してきた「働き方」は、当局をはじめとするステークホルダーから受容され得ない、という厳然たる事実に他なりません〉
これも文面通りに読めば、当局とメディアが「NO」を突きつけてきたから、伝統的な働き方を変えざるを得ない。逆に言えば、これまでは長時間労働体質も社として見過ごしてきたと認める文面となっている。
「この文書には電通幹部の戸惑いが滲み出ている」と言うのは、元電通社員で現在はインターネット広告を手がける株式会社Lamir代表の藤沢涼氏である。
「電通の不祥事は過去にも数々ありましたが、これほど大々的に報じられたことはありません。私の在職中にも痴漢事件を起こした社員がいましたが、報道では社名も実名も出ませんでした。同僚は、『これが電通の特権だ』と言っていました。
電通には政官界からナショナルクライアント幹部の子息などが入社していて、警視総監の子息もいた。各界のトップ層に網を張り、なにか起きた時に問題を封じることができる態勢ができていました。
しかし、今回はその抑えがきかない。行政もメディアもこぞって電通を攻撃し始めた事態に、幹部たちが戸惑っている様が目に浮かびます」
テレビは電通と喧嘩できない
電通はいま、かつてない異変に直面している。その実態については後で詳述するが、その前に電通がこれまでどれほど絶大な権力を誇示してきたのかを、当事者たちの証言から明らかにしよう。
電通とメディアの関係について、前出の藤沢氏が「体験談」を明かす。
「たとえばクライアント企業の不祥事についてメディアが報じようとしているという情報を察知した際、これをもみ消しに動くということがありました。クライアントからは『口止め料』として追加の出稿をもらい、これをエサにしてメディアには記事の修正などをお願いするわけです。
実際、メディアに『今後半年の出稿を約束する』と言って、記事が差し替わったことがありました」
中でも、電通が強い影響力を持つのはテレビ。新聞や雑誌と違い、テレビ番組は広告料金だけで稼ぐビジネスモデルで、そのスポンサー集めを電通に大きく「依存」しているためだ。
たとえば、テレビ朝日が『ニュースステーション』を始める際に、電通がCM枠の半分を買い切ったのは有名な話。そもそも、テレビの視聴率を調査する唯一の会社であるビデオリサーチ自体、電通が主導して作ったもので、電通が約34%の株を保有している。
元博報堂社員で著述家の本間龍氏も言う。
「結局、テレビ局はスポンサーの意向に反する番組は作れないし、そのスポンサーを集めてくれる電通とも絶対に喧嘩はできない。番組の企画会議にはスポンサー代理として広告代理店社員が出席することがありますが、彼らから『この内容ではスポンサーが納得しない』と言われれば、企画は通らない。
実際、私があるローカル局を担当していた際、その幹部は『電通のことを気にせざるを得ない』と漏らしていた」
このような電通のメディア支配を最も象徴するのが、原発報道だろう。
かつて原発報道によって電通の圧力を経験したジャーナリストの田原総一朗氏が、その実体験を明かす。
「私がテレビ東京に勤めていた時、原子力船『むつ』の放射能漏れ事件が起きました。私はこのときに原発問題を取材したのですが、当時原発を推進する市民運動の裏に電通がいることがわかったので、そのことを雑誌に書きました。
すると、電通がテレビ東京に抗議をしてきたのです。会社は私に執筆を止めるか会社を辞めるかと言ってきたので、私は会社を辞める羽目になった」
8億円の「ロビー活動費」
「原発広告」といえば、電力各社や電気事業連合会などの業界団体が「原発は安全」「原発はクリーン」と謳う広告に巨額を投じ、国民に「原発神話」を信じ込ませてきた。原発推進広告には、タレントから文化人までが笑顔で登場し、原発の安全性を語ってきた。前出の本間氏が言う。
「電力9社がこうした広告に1970年代から3・11までの約40年間に費やした広告費は、約2兆4000億円に及びます。特にバブル崩壊後に大手企業の広告出稿が激減する中、電力会社は安定出稿したためにメディアはこれに飛びついた。
一度この広告費を受ければ『麻薬』のように次からは断れなくなり、おのずと反原発報道で電力会社の機嫌を損ねることを自粛する空気が生まれて、日本全体に『安全神話』が刷り込まれた。
そうしたメディアの特性をよく理解したうえで、電力会社とメディアの間に入って動いていたのが電通や博報堂を頂点とする広告会社でした。中でも電通は原子力推進の立場にある社団法人『日本原子力産業協会』の会員に以前から名前を連ね、東京電力についてはメイン担当として仕切っていた」
メディア、原発……電通が仕切ってきたものをあげればきりがないが、大きなところでいえばオリンピックもその一つである。
国際的プロモーターとして知られる康芳夫氏は、オリンピックの権利獲得をめぐって電通と闘った「内幕」を明かす。
「初の民間運営方式で開催されたロス五輪で、私はテレビ朝日と組んで独占的放映権を取ろうと動いていました。私はオリンピック組織委員長だったピーター・ユベロス氏に接触して色よい返事までもらっていたのですが、ここで対抗馬としてNHK-民放連合が出てきて、そこに電通がついたのです。
電通もまた独自にユベロス氏と接触し、攪乱工作を仕掛けてきた。ユベロス氏は最終的に電通と喧嘩をするのはまずいと判断したようで、私たちに『君たちとは契約できない』と言ってきた」
このロスオリンピックで大儲けしたあたりから、スポーツイベントにおける「仕切り役」としての電通は一挙に花開いていく。『電通とFIFA』などの著書があるノンフィクション作家の田崎健太氏が言う。
「電通のスポーツビジネスを切り開いてきたのは元専務の高橋治之氏で、本物のネゴシエイターといえるでしょう。高橋氏はFIFA(国際サッカー連盟)がスポンサーを集めて商業化を進める過程において、当時のジョアン・アベランジェ会長らに大きく力を貸しました。そして、電通は世界のサッカービジネスに深く関与していったのです。
'02年のサッカーワールドカップ招致の際には、電通はスイスのマーケティング会社ISLに対して、同社の株式売却益の一部である約8億円を『ロビー活動費』として渡しています。国際的ロビー活動に弱い日本にあっては珍しく、高橋氏はこうした交渉を得意としていた。彼が電通に、スポーツビジネスという広告以外の収益の柱を作り上げたと言える」
どんなところにも食い込んでいき、気付いた時には「仕切り屋」として舞台を裏で回している――電通はそうして「日本を動かす中心」として君臨するようになっていったのである。
「'90年代にNHKが電通から米大リーグの放映権を買う際、ひと悶着があって、NHKは安値で電通から買えたことがありました。この時、赤字になりかねなかった電通は、NHKが中継するMLBの映像に実際にはない日本企業の広告を合成して入れ込むことの了解を取り付けてきた。すぐにスポンサーも集めてきて、その手腕には脱帽しました」(元NHK職員の立花孝志氏)
電通の手にかかればこうした差配もお手の物なわけだが、実はここ数年はそんな電通の権勢にも陰りが出てきたと関係者たちは口を揃える。
虚像が崩れ落ちる日
まず、元電通社員でスポーツ総合研究所所長の広瀬一郎氏が言う。
「かつての電通ではリスクを恐れない破天荒な社員がたくさんいて、会社としても彼らが好き勝手に動くのを許容しながら、時にとてつもない大きな仕事を手に入れてきた。しかし、'01年に上場してからこの風土が大きく変わり、なにより失敗が許されなくなって、小粒な仕事が増えてきた。電通マンたちも普通のサラリーマン化して、電通の『得体のしれない恐ろしさ』が消えていった」
時を同じくして、電通の「稼ぎ場」であるテレビが視聴者から飽きられるようになって、テレビ広告市場も縮小。電通が'09年3月期決算で106年ぶりの最終赤字に落ちる中、追い打ちをかけるようにインターネット市場が急激に膨張して猛威を振るい出した。
「電通はいまだテレビ広告依存型のビジネスモデルで、ネット市場では後手に回っています。ネット市場が拡大していることを聞いた当時の社長が、『買い切れ』と言ったという話が語り草になっているくらい、旧来の成功体験から脱し切れていない」(前出・藤沢氏)
そうして本業がじり貧になる中、コンプライアンスを逸脱した労働問題が噴出してきたのはある意味で象徴的といえる。今秋には電通が手掛けるネット広告で不正を働いていたことも発覚した。元博報堂社員でネットニュース編集者の中川淳一郎氏は言う。
「そもそも、これまで電通に関しては虚実ない交ぜの伝説が様々に語られ、隠然たる力を持ったモンスターのようなイメージが作られてきました。電通としてもそれらをいちいち否定せず、むしろ放置してきたのは、そのほうが都合がよかったからでしょう。クライアントは勝手に電通を頼ってくるし、メディアも勝手に萎縮する。しかし、いまやその虚像は崩れようとしています。
気付いた人たちが電通をこれまでのように恐れなくなり、今回の過労自殺問題ではメディアが電通を批判するようになった。こうした神通力はもはや通用しなくなってきたのです」
落日はもう始まっている。これが電通の偽りのない「正体」なのである。
「週刊現代」2016年11月12日号より
週刊現代
厚生労働省の対応次第。見えない力が動くかどうか?
新入社員の女性(当時24歳)が過労自殺した大手広告会社・電通に7日、厚生労働省東京労働局などの強制捜査のメスが入った。
電通本社(東京都港区)と、関西(大阪市)、中部(名古屋市)、京都(京都市)の3支社に対し、一斉捜索に当たった厚労省の労働基準監督官は計約90人。異例の大規模捜査を受けた電通は同日、全社員に対し、働き方の改革を求めたが、社員からは「上層部の意識改革こそ必要だ」と冷ややかな声が上がった。
「社が直面する課題を共に克服し、新しい電通を作り上げていこう」。7日午後、捜索が続く電通本社で、石井直ただし社長がホールに集まった社員を前に、1時間にわたって働き方改革の方針を説明した。
今回の捜索に労働基準監督官ら88人が何を見つけるか次第で厚生労働省の能力、又は、本気度がわかるであろう。
広告代理店最大手・電通の新入社員、高橋まつりさん(当時24歳)が昨年12月に過労自殺した問題で、厚生労働省東京労働局などは7日、東京都港区の電通本社と関西(大阪市)、京都(京都市)、中部(名古屋市)の3支社を労働基準法(労働時間)違反の疑いで家宅捜索し、労務管理の記録などを押収した。組織的に違法な長時間労働が存在するのに残業時間が過少申告されるなど悪質とみており、法人としての電通と人事責任者らを書類送検して刑事処分を求める方針とみられる。
同労働局などが10月14日以降に電通本社と3支社、地域子会社5社に対して行った「臨検」(抜き打ちの立ち入り調査)は、是正勧告(行政指導)のために実施することが多い。一方、家宅捜索は刑事立件を視野に証拠隠滅などを防ぐため、裁判所の捜索差し押さえ令状を請求して行う。
今回、同労働局などが強制捜査に踏み切ったのは、自殺者が出た▽高橋さんだけでなく、複数の社員が違法な長時間労働を強いられていた可能性が高い▽勤務記録の改ざんによる残業時間の過少申告を上司が指示していた疑いが強い▽度重なる是正勧告でも改善が進まなかった--ことなどから、書類送検の対象となる「重大・悪質」なケースと判断したためとみられる。
残業記録の過少申告を巡っては、亡くなった高橋さんの遺族側も「会社から労使協定の上限を超えないように記録を付けるよう指示があった」と主張。同労働局などは今後、押収した勤務記録や社員の証言を通じて、違法性の立証を進める。
厚労省は今回の捜索に労働基準監督官ら88人の「異例の大規模態勢」(同省関係者)で臨んだ。電通は「捜査に全面的に協力する」としている。【早川健人】
◇業務の見直し、社長呼び掛け
電通の石井直社長は7日、本社内で社員にこれまでの取り組みなどを説明。「電通においては人が唯一にして最大の財産」として、働き方の変革や業務の見直しなどを呼び掛けた。
必要以上の要求を削除し、違反した場合は思い罰則、チェックは厳しくするなどで対応するべきだったと思う。規則を厳しくしても、チェックが甘い、又は罰則が軽ければ 違反した方が得。正直者がばかを見る。このような愚かな現状を放置するのは厚生労働省にも責任があると思う。
広告業界のガリバー、電通で新入社員の女性が過労自殺した問題は7日、東京労働局などによる大規模な強制捜査に発展した。刑事事件として立件される可能性が高まり、石井直社長は社内の説明で長時間労働の改善を呼び掛けた。だが、社員らには戸惑いや懐疑的な受け止めも広がっている。【早川健人】
7日午前、東京都港区の電通本社。東京労働局の労働基準監督官ら約30人が2列に並び、家宅捜索に入った。捜索が続いていた午後、本社ホールで元々予定されていた社長の説明が始まり、一部の支社にも同時中継された。「社が直面する課題を共に克服し、新しい電通を作り上げていこう」。石井社長は改革姿勢を強調した。
石井社長は長時間労働の背景として、環境の変化や仕事量の増大に加え、「いかなる仕事も引き受ける気質」を挙げた。その上で、「業務量自体の削減と分散化」「業務プロセスの見直し」「時間の使い方の改善」などを社員に求めた。
広告業界では、インターネットの普及などに伴い仕事量が増えているとの認識が一般的だ。電通労組も加盟する広告労協は10月末、電通社員の高橋まつりさん(当時24歳)の過労自殺を受けて、ホームページに所感を掲載。「環境変化のスピードに会社も対応できず、業務はより専門的、複雑化して現場社員の一人一人に負荷がかかっている」と指摘した。
石井社長の説明もこうした現状を踏まえた形だが、社員らからは戸惑いの声も漏れる。
50歳代の男性社員は「『電通人』の行動の基本原則は鬼十則。それに沿った行動を求められてきたのに、社長の説明は改革というより自己否定とも取れる内容。違和感を覚える」と首をひねる。
「鬼十則」とは、4代目社長で「広告の鬼」「電通中興の祖」と呼ばれた故吉田秀雄氏が1951年に定めた10カ条で、社員手帳に今も記されている。「取り組んだら放すな、殺されても放すな、目的完遂までは……」の一文は、25年前に男性社員が過労自殺した際、「長時間残業の助長」だと問題視された。
先の50歳代の社員の受け止めは複雑だ。「『いかなる仕事も引き受ける気質』は鬼十則の『難しい仕事を狙え』『取り組んだら放すな』そのものだったはずなのに」と社長説明に不満を漏らしつつ、今回の強制捜査が労働時間も含めた職場環境の改善につながってほしいとも思う。「(電通では)これまで部下の評価は上司の好き嫌いが唯一の基準だったが、こうしたことが見直されるようになれば」と言う。
30歳代の元社員の男性は電通勤務時代、残業時間をごまかすために本社の入退館をICチップ入り社員証で記録するゲートを「入退出が記録されないようにほふく前進でくぐり、残業をしていた」と振り返る。電通は10月24日から午後10時で全館消灯するようになったが、男性は「10時に仕事が終わるわけがない」と断言する。
電通子会社で勤めた経験がある30歳代の元社員の女性は長時間労働などに疲れ、辞めた。電通の体質に対する見方は冷ややかだ。「今はいろいろ(改善策に)取り組んでいるが、根本のビジネスモデルが変わらない限り、ほとぼりが冷めたらまた元に戻るしかないのでは」
ブラック企業被害対策弁護団の戸舘圭之事務局長は強制捜査を「日本の労働行政の中で象徴的な出来事だ」と評価。その上で「電通は氷山の一角。賃金未払い残業は横行しており、取り締まりも弱い。労働局が強い姿勢で臨めば企業も態度を変える」と望んだ。
【ことば】労働基準監督官
厚生労働省の専門職員で、警察と同様に家宅捜索や逮捕の権限がある。労働基準法や労働安全衛生法などに基づいた安全体制や健康被害の防止措置が職場で取られているか、賃金不払いはないかなどを調べる。現在、監督官は全国で3241人。今回、電通を強制捜査した「過重労働撲滅特別対策班(かとく)」は15年4月、東京、大阪の労働局に設置。大企業による違法な長時間労働の監督指導に専従する監督官で構成している。
国内最大の広告代理店・電通でこの状態のなのだから、問題は氷山の一角と考えて間違いないと思う。東京オリンピックの詐欺的な試算に腹が立つので言うけど、 「おもてなし」をアピールするが、出来る以上の無理をしてまでの「おもてなし」は自分の首を絞めると言う事。
仕事も同じ。「対応が早い。」「柔軟に対応してくれる。」は良い事だが、それが能力以上、無理をしてまでの対応であれば、その過程に社員の犠牲を伴う。 社員に無理をさせなくてどのように対応するのか?
日本人は外国人は対応が遅いと良く言う。言い方を変えれば、無理をしない結果であるかもしれない。たしかに、外国人の対応を見ていると、効率が悪い、 デリケートでない、おおざっぱと思う事もある。何が正しいかは、価値観や個人によって違ってくるが、度が過ぎる対応は間違いと思う。
チキンレースを止めないと問題は解決しない。他社がここまでするのなら弊社も同じようにする。他のメリット、他社にないメリット、より高い品質など 無理をする以外に強みがなく、勝負できないのであれば、賃金を下げてでも勝負をするのか?従業員は給料よりも、無理がない、ストレスが減る選択に同意するのか? いろいろな選択肢はある。今の時代に全てを手に入れる事は難しい。学生や働く人は何を優先させるのかを考えて選択する必要があると思う。
国内最大の広告代理店・電通の新入社員だった女性が、過労で自殺した問題。厚生労働省は労働基準法違反の疑いで電通の捜索に入り、強制捜査に乗り出した。複数の社員がBuzzFeed Newsの取材に「残業時間を少なく調整していた」と証言している。過少申告が常態化していたと見られる。【BuzzFeed Japan / 籏智広太】
厚労省によると、今回の捜索対象は東京本社や大阪、名古屋、京都の支社。総勢88人体制、「異例」とも言える大規模な捜査だという。
書類送検へ
捜査を指導調整する厚労省労働基準局監督課の担当者は、BuzzFeed Newsの取材に対し、強制捜査の目的をこう語る。
「先月実施した『臨検監督』の結果、労働時間に関して労働基準法に違反しているのではないかという疑いが強まったため、強制捜査に切り替えました」
「労使交渉で決められた労働時間を超えた実態があったのかを含め、強制捜査でしっかりと入手した資料から分析していきたい」
同省はこれまで任意で捜査を続け、10月14日には「臨検」と呼ばれる立ち入り調査を実施していた。日経新聞などによると、押収した資料を分析し、書類送検する方針だ。
実態とかけ離れた労働時間
一連の捜査の発端は、昨年12月に自殺した、新入社員の高橋まつりさん(当時24)が、労災認定を受けたことだった。高橋さんは長時間労働やパワハラなどに苦しんでいたとされている。
高橋さんの残業時間は、昨年10月に「69.9時間」、11月に「69.5時間」と、上限だった70時間ギリギリに申請されていた。しかし、労災認定された昨年10月9日~11月7日の労働時間は約105時間だった。遺族側は「会社が過少申告をさせていた」と主張している。
そもそも電通では、社員がゲートを出入りする時間を管理している。1991年、入社2年目の男性社員が過労自殺した「電通事件」を受け、再発防止策として導入された仕組みだ。
同社によると、管理されている退館時刻と、申請された終業時刻との間に1時間以上(現在は30分以上)の差があると、社員それぞれが理由を「私事在館」として申請するシステムになっているという。
常態化していた過少申告
この制度を使った残業時間の過少申告が、同社では常態化していたとみられる。
BuzzFeed Newsの取材に応じた複数の社員は「決められた残業時間以上がつけられなくなったときのために利用している」と証言する。
食事していた、本を読んでいた、勉強をしていた、私用で電話やインターネットを利用していた……。「自己研鑽」「自己啓発」などのための時間という名目だったが、実態は残業時間を基準内に調整するためだったという。
同社は先月末から、長時間労働対策として、残業時間の上限を削減したり、22時に全館を消灯したりするなどのルールを策定。これに際し、私事在館も禁止された。
BuzzFeed Newsが入手した社内メールでは、人事局からこんな呼びかけがされている。
「『自己啓発』『私的情報収集』『私的電話・私的メールのやりとり・SNS』による私事在館を禁止とします」
厚労省も問題視
ブラック企業被害対策弁護団代表の佐々木亮弁護士は、BuzzFeed Newsのメール取材に対し、「私事在館」の制度をこう批判する。
「この制度は最悪の制度だと思います。実態をみないで、一律にこのようなやり方をすること自体に企業としての甘さ、狡猾さが見えます。禁止されることは、当然といえるでしょう」
厚労省もこの制度の存在をこれまでの調査や報道により把握しており、問題視しているようだ。先出の担当者は言う。
「私事在館が実際どう運用されていたのかを含め、捜査をしています。長時間労働の実態を明らかにしていきたい」
BuzzFeed Newsは同社に対し、「残業時間の調整に使われていた、などの問題点はなかったのでしょうか」という質問をしたが、明確な回答はなかった。
社長は何を語ったのか
強制捜査のあった11月7日、再び同社に今後の対応を問うと、FAXでこう回答があった。
「捜索が入ったことは事実です。調査には全面的に協力してまいります」
奇しくもこの日の午後1時からは、石井直社長が全社員に向けて、「我々の働き方の進化に向けて」と、1時間にわたって自らの考えを示している。
会合自体は「社内向けのため」として公開されなかったが、報道向けに「要旨」を発表した。
それによると、石井社長は先月末から実施している長時間労働対策を改めて説明。「労働時間が長くなってきた背景」として、以下の理由をあげた。
・仕事量の増大(環境の変化、課題の変化、難易度の高まり)
・いかなる仕事も引き受ける気質(期待に極力応えたいという姿勢)
・現場主義の尊重(真摯な使命感)
また、「仕事量に関する見直しの3つの視点」として、こんなことも提示した。
・業務量自体の削減と業務の分散化
・業務プロセスの見直し
・時間の使い方自体の改善
その上で石井社長は「電通においては人が唯一にして最大の財産、経営資源」とも語り、最後にこう呼びかけたという。
“「世の中に活気やよろこびをもたらす仕事に関わりたい」「時代を動かす仕事に挑戦したい」「自らが時代の変化を創り上げたい」といった想い、志に立ち返り、それを大切にしてほしい。
チーム力を結集し、社が直面する課題を共に克服し、新しい電通を作り上げていこう“
「中日新聞・東京新聞が子どもの貧困を扱った連載記事「新貧乏物語」で事実と異なる記述があった」
貧困記事捏造は中日新聞の体質か、少なくとも関与していた部門に問題がある事を明らかにした。メディアは信用できないと言う事なのか?
慰安婦問題で朝日新聞がやっと問題を認めたが、他社の話で、中日新聞には関係ないと思っていたのか?もしかすると、注目や記事になっていないだけで、
いろいろな記事が信用できないのかもしれない。
情報が氾濫している。だからこそ、事実や現場での情報が重要な時もある。独立性や中立性が保てないのなら、合弁、又は、吸収合併される新聞社が出て来ても
仕方のない事かもしれない。時代は変わる、浮き沈みはある。新聞社のあり方や存在意義も変わりつつあるのかもしれない。
広告代理店最大手・電通の新入社員、高橋まつりさん(当時24歳)が過労自殺した問題で、東京労働局などは7日、東京都港区の同社本社と、関西(大阪市)▽京都(京都市)▽中部(名古屋市)の各支社を、労働基準法違反の疑いで家宅捜索した。 同法に基づき10月に立ち入り調査したが、関連書類を差し押さえるために捜索が必要と判断したとみられる。
無期停学処分は曖昧で中途半端とも思います。理由は下記の理由。
無期停学ってだいたい何ヶ月くらいですか? 11/16/06(Yahoo!知恵袋)
無期停学とは、予め期間を定めず出席を停止する処分ですので、だいたいどれくらいという相場は存在しません。
無期の場合には、停学を解除すべきか否かの会議が行われた上で、出席停止処分の解除が行われますので、その会議で「出席停止を解除すべきだ」と決定されない限りは、いつまでも停学のままです。
とは言え、懲戒に至った経緯と過去の事例に鑑みて、その会議は行われますので、大体の相場は見えてくるはずです。
詰まらない理屈は置いておいて、質問にお答えしますと、無期停学の期間の相場は「留年しないギリギリ」になります。
それ以上、つまり停学によって留年が確定する場合は、素直に退学処分になる事が殆どです。
結局、学校側は「無期停学の期間をどれくらいにするか」を考えているのではなく、「それ以降の欠席を許可しない」か「留年させる」か「退学させる」の選択をしている訳です。
ただし、最終的には学校側の判断になりますので、少しでも正確な予想を立てたいのでしたら、過去に無期停学処分を受けた生徒の停学期間と、停学に至った経緯をお調べする事をお勧めします。
ちなみに、わたくしは1ヶ月くらいでした。
罪状は、取り立ての免許で派手にスピード違反。
家庭裁判所送りです。
停学の期間、家でゆっくり受験勉強ができたので良かった・・・なんて言ってはいけませんね。
神奈川県葉山町の合宿施設で、慶応大学の10代女性が同大広告学研究会(広研)に所属する男子学生数人から乱暴を受けたとされる問題で、関わったとされる4人の男子学生に対し、同大が無期停学などの処分を出していたことが4日、分かった。処分は3日付。
問題をめぐっては、未成年者に飲酒を強要していたなどとして、同大が10月4日に広研に解散命令を出しているが、学生個人への処分は初めて。
同大広報室によると、処分を受けたのは▽商学部2年の学生▽理工学部1年の学生2人▽環境情報学部2年の学生-の4人。商学部と理工学部の学生は無期停学、環境情報学部の学生は譴責(けんせき)とした。
無期停学の処分理由は9月2日、葉山町の広研が借用していた合宿所で、未成年飲酒やサークルでの性行為、その行為の撮影など「気品を損ねる行為をした」などとしている。今後「学生の本分に著しく反する事実」が確認された場合、処分の変更もあり得るという。環境情報学部の学生の処分理由については、広研の責任ある立場にも関わらず、監督責任を怠ったなどとしている。
関係者によると、現場には6人の学生がいたというが、同大は「処分について、詳しい内容は答えられない」と話している。
慶応大学は、公認学生団体「広告学研究会」所属の男子学生4人が、未成年者の飲酒をあおるなどしたとして、今月3日付で無期停学などの処分を行った。
無期停学になったのは、商学部2年生1人、理工学部1年生2人の計3人。9月の懇親会で未成年者に飲酒をさせたほか、性行為の様子を撮影するなど「気品をそこね、学生としての本分にもとる行為」をしたという。また、責任ある立場にありながら監督責任を怠ったとして環境情報学部の2年生1人をけん責とした。
同大は10月、同団体に解散を命じ、同団体が11月の学園祭で主催予定だった「ミス慶応コンテスト」は中止された。同大は、「今後、学生の本分に著しく反する事実が新たに認められたときには処分を変更することがある」としている。
「『これでは慶応は“罪を憎む姿勢”にまったく欠けた大学としか言いようがありません』 と断じるのは、同大OBで危機管理コンサルタントの田中辰巳氏である。 『加害者も被害者も同じ慶応の学生ですが、被害者の証言は明らかに重大犯罪である可能性を示唆するものです。公益の見地から見れば、被害者を支え、一緒に警察に向かっても良いくらい。捜査が始まるまでは、全面的に彼女をバックアップすることが、コンプライアンス精神を持つ者が取るべき姿勢です。“被害者任せ”ではあまりに保身的かつ無責任で、およそ法学部を設置している大学が行うべき態度ではありません』」
「『私も大学側の対応は守りに入り過ぎていると思います』 と述べるのは、メディアジャーナリストで、当の慶応大SFC研究所の上席所員を務める渡辺真由子氏である。渡辺氏も慶応OGで、在学時代、広告学研究会に所属し、ミスコンで賞に輝いた経歴を持つ。」
慶応大の対応に対して社会や一般の人々がどのように考えるかを考慮した上での判断であれば問題ないと思う。ただ、下記の記事とは矛盾があると思うが、単なる広告アピールのための言葉 であると思えば個々の学生や保護者が判断する事なのであろう。
「社会を支える学問のために」 慶應義塾大学塾長 清家篤先生 (大学ジャーナル)
・・・ 大学とは、自分の頭で考える能力を身につけるところ
大学での学びは、高校までのように「勉強」といわずに「学問」といいます。大学とは一言でいうと、「自分の頭で考える能力を身につける」ところだからです。勉強が、先人の解決したことを習うことであるのに対して、学問は、答えのない問題を自分自身で見つけて新しい答えを生むことを目的にします。そのためには、見つけた問題について因果関係を考えて仮設を立て、それを検証していくための実証的な方法を学ぶことも必要です。
そのために大学には、大きく分けて三つの機能があります。
一つは、幅広い教養、学問に必要な語学や情報に関するスキルを身につけることです。これらは、一般教育とか教養教育と呼ばれ、大学で考えるべき問題、取り組むべきテーマを見つける際の手助けとなり、問題を掘り下げ、仮説を検証していくための論理力のベースとなります。また、理工系なら実験、社会科学系なら統計、人文科学系なら文献調査を通じて、主に3年生以上では専門のテーマを深く掘り下げていくわけですが、その際に必要な基礎的な知識や技術、手法を身につける場でもあります。さらにそれらは、過去に誰かが頭で考えたことが結実したものですから、それを学ぶことは過去の学者の考えた過程を追体験することであり、自ら考える際のシミュレーションにもなります。
二つ目は、各専門、専攻に進み、自分で選んだテーマについて学び、最終的にはそれについて卒業論文を書いたり、卒業研究を行ったりすることです。これまで誰も答えを見つけていない問題を見つける、つまり課題探求に始まって、次にその問題に関する仮説を立て、それを検証して最後には結論を出します。まさにここには、自分の頭で考えることのあらゆる要素が入っています。
こうした授業や研究に取り組むことに加えて、課外活動を行うことも、大学でのもう一方の柱です。例えば体育会活動。慶應の体育会の多くは選手が自主的に活動していて、どういう技術を高めるか、どんな戦術を立てるかなどについて、監督、コーチだけでなく、選手自らも考えています。練習で試したもののうち最も有効なもの、成功確率の高いものを試合に使う。つまり仮説を作りそれを検証し結果を出している。体だけでなく頭も鍛えることになりますから、考える能力を磨くとてもよい訓練になります。実際、これまで私の見てきたところでは、こうした活動を経験していることがビジネスの世界でも大いに役立ち、評価もされているようです。
闇に埋もれそうだった「事件」が明るみに出ようとしている。「週刊新潮」が報じた、慶応大女子学生の「陵辱」事案。その本格捜査が始まったのだ。そこで問いたいのは、大学の姿勢。被害者を突き放し、事を「未成年飲酒」に矮小化した姿を見て、福沢翁は何を思うのか。
***
慶応大が公認サークル「広告学研究会」の解散を命じたのは、10月4日のことである。告示された処分理由は「未成年者による飲酒」だが、その裏には6人の男子学生による凌辱事件があった。被害女子学生・京子さん(19)=仮名=の母は、「加害者には厳しい処罰を」と語る。
この案件が法的にどのような結末を迎えるかは、今後の捜査を待つしかない。
しかし確実に言えるのは、京子さんの心中が察するに余りあること。必要なのは彼女への配慮である。家族はもちろん、活動の主たる場である大学の心遣いが重要なのは論を俟たない。
ところが、だ。
その慶応大が、被害者の母がはじめに相談に行った9月6日、「我々は司法機関ではないので、まずは警察に届けてください」と異常な対応を見せたのは、本誌(「週刊新潮」)が記した通り。サークルの解散理由にも、「陵辱」に関わることについては一言も触れられなかった。
その後も、これを「握りつぶし」と本誌が報じた直後の10月12日には、HPで大要、以下のような声明を発表した。
〈今回の解散処分にあたっては、複数回にわたり関係者に事情聴取を行う等、可能な限りの調査を行いましたが、事件性を確認するには至りませんでした。捜査権限を有しない大学の調査には一定の限界があります。違法行為に関しては、捜査権限のある警察等において解明されるべきであると考えます〉
■一般市民以下の遵法精神
反論とも思える主張だけれど、
「これでは慶応は“罪を憎む姿勢”にまったく欠けた大学としか言いようがありません」
と断じるのは、同大OBで危機管理コンサルタントの田中辰巳氏である。
「加害者も被害者も同じ慶応の学生ですが、被害者の証言は明らかに重大犯罪である可能性を示唆するものです。公益の見地から見れば、被害者を支え、一緒に警察に向かっても良いくらい。捜査が始まるまでは、全面的に彼女をバックアップすることが、コンプライアンス精神を持つ者が取るべき姿勢です。“被害者任せ”ではあまりに保身的かつ無責任で、およそ法学部を設置している大学が行うべき態度ではありません」
捜査はもちろん当局が行うこと。しかし、一般の「市民」は誰でも違法性がある行為を知りえた場合、それを当局に伝えることは、「義務」として理解していることであろう。
が、天下の慶応大は、重大犯罪の可能性のある事案が被害者本人から詳細に伝えられていても、安易に「事件性は確認できない」と判断するなど、その責任を放棄して恥じない。これでは一般市民以下の遵法精神と言われても仕方あるまい。
■古びた感覚
さらには、
「私も大学側の対応は守りに入り過ぎていると思います」
と述べるのは、メディアジャーナリストで、当の慶応大SFC研究所の上席所員を務める渡辺真由子氏である。渡辺氏も慶応OGで、在学時代、広告学研究会に所属し、ミスコンで賞に輝いた経歴を持つ。
「性犯罪を告発するハードルが非常に高いのは知られたところ。告発すれば、落ち度を責められたり、好奇の目に晒されたりする『セカンドレイプ』と言われる悪しき風潮もある。そんな中、被害者は勇気を持って声を上げた。だからこそ、大学は真摯に対応すべきだったのではないでしょうか」
先の田中氏もこれを受けて言う。
「被害者が警察はおろか大学にすら、申し出るには勇気が必要だったでしょう。それを“警察に!”というのは、まるで無神経な対応。セクハラや性犯罪の被害について、これだけ世間が敏感になっている時代においてこれですから、はなはだ感覚が古すぎる。これでは今後、女子高生の保護者たちから、慶応には娘を預けられないと思われても仕方がないと思います」
■大学は「警察任せ」
京子さんの母親は、これまで電話や面談で何度も大学の学生部とやり取りをしている。しかし、彼女の知人によれば、
「“加害者に事情を聞いても、結果は知らせません”と言われたり、“仮に加害者の処分が決まっても、それは連絡しません。お嬢さんが掲示板を見ればわかります”等々言われたりと、あまりに他人事の対応をされたそうです。また、今回の報道が出た後、大学にマスコミが殺到し、京子さんの名前も出回ってしまった。これへの対応を依頼しても、大学側は“検討します”と述べただけで、終始、生返事。気遣いの一言もなかったそうです」
彼女の動画や写真を拡散させることは違法性が強い。それを学内に周知徹底するなど、いくらでも行うべきことはあるはず。が、そうした動きも見せない代わりにこの対応だから、あくまで慶応大は被害者女性を突き放すおつもりらしいのである。
これらの点について、改めて大学に質問したが、HP上と同じ「警察任せ」の見解を繰り返す。ならば、と清家篤塾長にも伺ってみたが、家人を通じて「広報に任せております」と言うのみ。この大学は余程他人任せがお好きなようだけれど、では、一身の「独立自尊」を謳ったのは、一体、どちらの大学の創立者か。これでは常套句だけど、福沢諭吉が泣いている、と記さざるをえない。
被害者である京子さんが重い口を開く。
「警察にはどうか正義と真実を追求してほしいと願っています。そして、私は一日も早く元の平穏な生活に戻り、学業や好きなスポーツに専念していきたいと思っています」
この思いが受け止められるか否か。今まさに慶応大の姿勢が試されているのだ。
特集「被害女子学生を突き放して保身! 福沢諭吉が泣いている『慶応大学』がけしからん!」より
「週刊新潮」2016年10月27日号 掲載
新潮社
貧困記事捏造は中日新聞の体質か、少なくとも関与していた部門に問題がある事を明らかにした。メディアは信用できないと言う事なのか? 慰安婦問題で朝日新聞がやっと問題を認めたが、他社の話で、中日新聞には関係ないと思っていたのか?もしかすると、注目や記事になっていないだけで、 いろいろな記事が信用できないのかもしれない。
情報が氾濫している。だからこそ、事実や現場での情報が重要な時もある。独立性や中立性が保てないのなら、合弁、又は、吸収合併される新聞社が出て来ても 仕方のない事かもしれない。時代は変わる、浮き沈みはある。新聞社のあり方や存在意義も変わりつつあるのかもしれない。
中日新聞・東京新聞が子どもの貧困を扱った連載記事「新貧乏物語」で事実と異なる記述があったとして記事を削除し、おわび記事を掲載した問題で、両紙を発行する中日新聞社(名古屋市)は、同社の検証結果を両紙の30日付朝刊に2ページにわたり掲載した。
検証は、編集局から独立した紙面審査室が担当した。関係者から聞き取りなどし、外部委員4人らの入る「新聞報道のあり方委員会」に報告した。
検証によると、中日新聞名古屋本社発行の5月19日付朝刊記事に事実でない内容が3カ所あった。(1)病気の父を持つ中学3年少女の家庭では冷蔵庫に学校教材費の未払い請求書が張られているとして「絵具800円」などと架空の品目や金額を書いた。(2)少女が両親に「塾に行きたい」と繰り返したという事実はない。(3)「合宿代1万円が払えず」と書いたが、払われていた。
記事は地方から取材班に加わった男性記者(29)が執筆した。捏造(ねつぞう)は家族からの指摘で発覚した。
また、名古屋本社発行の5月17日付朝刊の写真は、この男性記者の指示でカメラマンが撮った自作自演であることが、記者自身の発言で印刷開始後に判明。後日掲載予定だった東京新聞や北陸、東海本社発行の紙面では写真やキャプションを差し替えた。また、男性記者の他の記事を再点検したが、捏造を見抜けず、問題の記事は名古屋本社などいずれの紙面も掲載された。
検証は、記事のチェック体制などを問題視し、取材班や編集幹部に「読者や取材先よりも作り手の都合や論理を優先する姿勢」があったと指摘した。
同社は、管理・監督責任として臼田信行取締役名古屋本社編集局長を役員報酬減額、寺本政司同本社社会部長と社会部の取材班キャップをけん責、執筆した記者を停職1カ月とする懲戒処分を決めた。いずれも11月1日付。
『中日新聞(東京新聞)』朝刊に衝撃的な「おわび」が載ったのは10月12日だった。おわび記事などによると、5月の連載「新貧乏物語」で、病気の父親を持つ中学生の少女が、教材費や部活の合宿代も払えないといった虚偽のエピソードを報じたり、生計を賄うためパンの移動販売を手伝う少年の後ろ姿の写真に「知らない人が住むマンションを訪ね歩く」という説明を付けたが、実際は記者が関係者の自宅前で撮影するようカメラマンに指示していた。
外部の指摘で始まった社内調査に対し、記者は「原稿を良くするために想像して書いてしまった」と話したという。おわびが掲載されると、ネット上には「誤報ではなく捏造(ねつぞう)だ」など、厳しい批判があふれた。
問題の記者は20代の男性。これまでも取材姿勢の「甘さ」が社内で問題になっていたという。中日関係者が明かす。
「2014年には県警の行事を伝える記事で、本部長の名前を前任本部長と取り違えておわびを出しました。恒例行事だったため、社内データベースから過去記事をコピペ(切り貼り)したのではないかと疑われましたが、本人は『昨年の記事を見ながら書いたら間違えた』と釈明したようです。事実としても初歩的なミスにあきれます」
コピペ疑惑はこれだけにとどまらない。
「恒例のイベントで、その年には登場していないロボットが登場したと誤報したり、会議に出席していない人が発言したことになっていたりと、危ない記者として有名だった」(前出の関係者)
コピペ疑惑について、中日新聞名古屋本社編集局は「お答えできません」とし、「事態を極めて重く受け止めている。検証を進めており、結果を紙面で公表する」と回答した。
「新貧乏物語」は奨学金問題などに取り組み、「国会議論を巻き起こした」として今年9月、貧困ジャーナリズム賞を受けていた。
「危ない記者」を看板企画に起用した代償はあまりにも大きかった。
(本誌・本田晋作)
(サンデー毎日2016年10月30日号から)
「働きやすい企業」に認定される基準、認定のための審査、審査した厚労省職員達のどこか、又は、コンビネーションに問題があったのは明確だ!
厚生労働省は検証して問題点を公表するべきだ。問題を発見、理解、認識して対応しなければ同じような問題は繰り返される。
例えば、認定基準や認定のための審査に問題がなければ、審査した職員達に問題がある可能性が高い。審査した職員達に問題がなければ、認定基準や認定審査に 結果に大きな違いが出るような曖昧な規則、定義、いろいろな解釈が出来る箇所などが存在する可能性が高い。規則、定義やいろいろな解釈が出来る箇所は、 審査員達がかなり優秀で教育を受けていなければ、結果に大きな誤差を生じさせる。
厚生労働省が対外的に「働きやすい企業」を増やしたいのであれば、審査を簡単にするかもしれない。電通が広報の方針、良い企業イメージ、他の企業も認定されているなど 本来の目的以外の理由で取得を考えていれば、事実や現状は別として認定を取得するための準備や努力をするであろう。それが隠蔽や形だけの記録であったとしても 認定が最優先であれば、不都合や事実は隠される、又は、審査員に見せないであろう。このような事を考慮して厚生労働省審査員達が認定のための審査をおこなったのかは 不明。
別に全ての企業が「働きやすい企業」でなくても良いのではないのか?ある企業に就職すると長時間労働があると学生が認識していれば、それでも良いと思う学生、 体力や持久力に自身のある学生、ストレスに強いと思う学生が集まるので、勘違いして学生が就職する確率は低くなる。
高給よりもストレスやノルマが高くない企業に就職したい学生も存在する。効率が良い、今の時代に合った企業でなければ、なりふり構わずに仕事している社員がいる 会社と競争して勝てるわけがない。人材の教育が上手い、人材の適性を見抜いて人事が出来る、カリスマの高い管理職や社長が存在する、運よく時代に合った会社などの 理由がなければ、同じ条件でそれ以上の結果など出せるわけがない。スター選手を集めたチームが、注目を受けていない選手を育成したり、選手のポテンシャルを見抜いての 練習やポジションを決めてベストな指示が出せる監督のチームに勝てない事もある。それはいろいろな条件が違うからだ。同じ条件ではスター選手のチームが勝つだろう。
厚生労働省は現実を理解して対応するべきだ。まあ、出来ないから自殺者を出す企業に「働きやすい企業」や「子育てサポート企業」の認定を出すのだろう。
新人社員が過労自殺した電通が厚生労働省から「働きやすい企業」に認定されていることについて、塩崎恭久厚労相は28日の閣議後会見で「認定の取り消しを含めて厳正に対処しなければならない」と述べた。
厚労省は2005年に施行した「次世代育成支援対策推進法」に基づき、労働時間の短縮や子育て支援などに取り組む企業を子育て支援企業と認定し、「くるみん」マークを与えている。企業は広告などに「くるみん」マークを使って働きやすさをPRできる。
厚労省は07、13、15年に電通を「くるみん」認定している。だが、電通は15年に三田労働基準監督署から長時間労働についての是正勧告を受けていた。今月14日には、違法な長時間労働が常態化していた疑いがあるとして、東京労働局などが電通本社に立ち入り調査に入った。厚労省は労働局の調査結果などを踏まえ、電通の「くるみん」認定取り消しを検討する。
塩崎氏は「(「くるみん」の)認定基準についても、より適切なものにしていきたい」と改善する考えを示した。
塩崎厚生労働相は28日の閣議後の記者会見で、違法な時間外労働が行われていたとして是正勧告を受けていた大手広告会社・電通を、働きやすい「子育てサポート企業」として厚労省が認定していたことについて、「取り消しを含めて、厳正に対処しなければならない」と述べた。
認定基準についても改善を検討するという。
電通は2007、13、15年に同サポート企業として選ばれていたが、14年6月、関西支社(大阪市)が是正勧告を受けたほか、3度目の認定直後の15年8月にも、本社(東京都港区)が同様に是正勧告を受けている。
高野真吾、大内奏、編集委員・沢路毅彦
バブル経済の終わりが近い1991年8月。電通に入社して2年目のラジオ局(当時)の男性社員が自宅で自殺した。24歳だった。
長時間労働でうつ病になったのが自殺の原因だとして、遺族は電通の責任を問う訴訟を東京地裁に起こした。遺族側は、深夜の退館記録などをもとに、男性が長時間労働を強いられていたと主張。会社側は男性の自己申告による記録をもとに、「時間外労働が突出して多いわけではない」「在館時間がすべて業務にあてられていたわけではない」などと反論した。
地裁判決は、男性が亡くなった8月に10回、前の月も12回、東京の本社を午前2時以降に退社していたと認定。こうした事実をもとに、「常軌を逸した長時間労働をしていた」として遺族の訴えを認めた。
裁判は最高裁まで争われ、2000年3月、電通に安全配慮義務違反があったと認定された。「長時間の業務で疲労が蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは周知のところだ」「会社は労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務がある」。初めてこう言い切った最高裁判決は「過労死問題のバイブル」(岩城穣弁護士)になった。
電通は責任を認めて遺族と和解。再発防止に向け、「長年にわたって適正な勤務管理、長時間勤務抑制、社員の健康維持のための取り組みを実施してきた」(広報部)と説明する。
しかし、14年6月に関西支社(大阪市)が、昨年8月には東京・汐留の本社が、違法な長時間労働をさせたとして労働基準監督署から是正勧告を受けていた。その4カ月後、男性と同じ24歳で新入社員の高橋まつりさんが過労自殺した。
さらに、本社勤務だった男性社員が3年前に亡くなり、過労死を認められたと関係者は明かす。「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子代表は「過労死を繰り返す企業には社会的な監視が必要だ」と憤る。
違法な長時間労働が常態化していた疑いがあるとみて、東京労働局の「過重労働撲滅特別対策班(かとく)」などが今月14日、本支社に抜き打ち調査に入り、刑事事件としての立件も視野に調べを進めている。
「取り組んだら放すな、殺されても放すな、目的完遂までは……」。電通の4代目社長で、「広告の鬼」と呼ばれた故吉田秀雄氏が1951年に書いたという10カ条の遺訓「鬼十則」の一節だ。長時間労働を助長しかねない電通の企業風土を象徴する社員の心得として知られ、高橋さんの遺族側が問題視している。
「鬼十則」は今も、電通の社員…
大内奏、編集委員・沢路毅彦
25年前に若手社員が過労自殺し、責任を認めた電通。再発防止を誓ったが、再び悲劇が起きた。教訓はなぜ生かされなかったのか。
◇
「もう4時だ 体が震えるよ…… しぬ もう無理そう。つかれた」
昨年10月21日早朝。広告大手、電通の新入社員だった高橋まつりさんは、SNSにこんなメッセージを残した。東京・汐留の本社ビルの入退館記録などによると、この日退社したのは午前3時38分。前日の午前8時56分に出勤してから、19時間近くが過ぎていた。
その4日後。日曜日だった25日は午後7時27分に出社。28日午前0時42分に退社するまで約53時間、ほぼ連続して社内にいた記録が残る。11月5日にはこう書き込んだ。「タクシー乗ったなり へろへろ」
この日の退社時刻は午前2時7分。前日から続けて17時間近く社内にいた。深夜勤務や休日出勤が続いたこのころ、高橋さんはうつ病を発症したとみられる。
12月25日朝、都内の電通の…
大手広告会社の電通(東京都港区)について、厚生労働省は、違法な長時間労働が行われていたとして同社関西支社(大阪市)が労働基準法違反で是正勧告を受けていたにもかかわらず、労働時間短縮に取り組み、働きやすい「子育てサポート企業」に認定していたことがわかった。
認定は、2005年に施行された「次世代育成支援対策推進法」に基づいており、今年6月時点で、2570社が選ばれている。
認定されるには時間外労働の削減などに取り組み、法令に反する重大な事実がないことなどが基準で、電通はこれらをクリアしたとして07、13、15年の3回認定されていた。
しかし、電通では14年6月、関西支社で労使協定の上限を超えて違法な時間外労働が行われていたとして、天満労働基準監督署(同)から是正勧告を受けていた。
一般の人達が知らない慶応大学の一部が公になってきている。
女子アナの登竜門として知られる慶応大学の「ミス慶応コンテスト」の中止が決まったのは10月4日。中止理由は、ミスコンを主催するサークルでの飲酒を巡る不祥事とされているが、これにはウラがある。その晩、1人の女性が複数の男から陵辱されていたのだ。
***
その肩書をひっさげ、多くの才媛が狭き門であるキー局女子アナの座を勝ち取っていった。元フジテレビの中野美奈子、日本テレビの鈴江奈々、元TBSの青木裕子、テレビ朝日の竹内由恵、TBSの宇内梨沙……。彼女らが誇る「ミス慶応」という輝かしい勲章は、今回の騒動によって決定的に汚されたのである。
「ミス慶応コンテスト」を主催してきたのは大学の公認サークル「慶応義塾広告学研究会」。会の公式HPで今年のミス慶応コンテストの中止が発表された10月4日、大学は塾生HPに清家篤塾長名の告示を掲出。そこには、広告学研究会に解散を命じたことが記されていたのだが、その理由としてこう説明されていた。
〈当該団体は平成二十八年九月二日、活動の一環で滞在していた宿泊先にて懇親会を催し、複数の未成年者が飲酒に及びました。その場において、互いを指名して飲酒するよう囃し立てる、或いはゲームの勝敗により酒を呷る等の危険な行為があったことが確認されています〉
この告示からは、極めて重大な事実が抜け落ちている。サークルのメンバーはただ飲酒して騒いでいたわけではない。問題の夜、彼らは1人の女子学生に無理やり酒を飲ませた上、筆舌に尽くし難い乱行に及んでいたのだ。被害に遭ったのはサークルのメンバーだった18歳の女性。ここでは仮に京子さんとしておこう。
■海の家の“手伝い”
京子さんの母親が語る。
「娘と私が会えたのは事件の翌日、9月3日の午後8時頃。娘が救急車で搬送された先の病院でした。憔悴しきった娘の身に、あの夜、何が起こったのかを私が聞いたのは会計を済ませようとしていた時です。男6人、それに女の子は娘1人だけと聞いて、まさかとは思ったのですが……」
男6人はいずれも慶応の学生で広告学研究会に所属。事件の全貌を明らかにしよう。
神奈川県の葉山町―─。広告学研究会は毎年夏、「慶応義塾学生CampStore」という海の家をオープンするが、その際、サークルのメンバーたちが活動の拠点にしている古びた合宿所で事件は起こった。
「娘はいくつかのサークルに所属していて、広告学研究会の活動にはこれまであまり参加してこなかった。ところが、8月末、サークルのメンバー数人から、海の家の後片付けを手伝うようにとしつこく誘われたそうです。これまであまり活動に参加していなかったのにわざわざ呼ばれたという事は、最初からそういう目的だったのでしょう」(同)
合宿所は家というよりは小屋といった雰囲気の建物で、中には雑然と荷物が置いてある。9月2日午後6時半頃、京子さんは合宿所に到着して初めて、女性は自分1人であると知った。
■テキーラを強制
京子さん本人が重い口を開く。
「7時半頃に皆で夕飯を食べた後、誰かが“上で飲み会をしよう”と言い出してお酒を2階に運び始めた。私は初めて合宿所に行ったので、状況がいまいちつかめないまま、そういうふうに過ごすのがいつものスタイルなのか、と思って2階に上がりました」
2階には6畳ほどの狭いスペースがあり、メンバーは背の低いテーブルを囲んで座っていた。そこに加わった京子さんが手渡されたのは、ショットグラスに入ったテキーラだった。
「口をつけた瞬間にすごく強いお酒だと気付いて、あまり飲みたくないと思っていました。8時半頃、私はメンバーに命じられて1階にトランプを取りに行ったのですが、2階に戻った時、みんなが顔を見合わせて目配せをしている感じだったので不審に思いました」
同じ頃、6人目の男性メンバーが到着。彼は2階で少し飲んだ後、1階に降りて寝てしまった。つまりその時点で2階にいたのは男5人と京子さんということになる。彼らの行動がエスカレートし始めるのはその頃からである。
「誰かが“京子が飲むゲーム!”などと言って私の名前でコールをかけて、みんながそれに合わせて煽り、“3秒で飲め!”などと命令されてテキーラを何杯も飲まされました。もう限界だし飲みたくないと抵抗すると、誰かが私の手を掴んでショットグラスを無理やり口にもっていかれて飲まされた。5杯くらいは連続で口にもっていかれ、飲むことを強制されました」
京子さんを酔い潰そうとしているのは明らかだった。頭は朦朧としてくるが、しかし、彼女は自らの身に危険が迫っていることを察知した。目の前で男2人が服を脱ぎ始めたのだ。
「怖くなって逃げようとしたのですが、“階段は危険だから”などと言って、私の手を思い切り引っ張って引き戻されてしまいました。さらに、メンバーの1人が私を押し倒し、服を脱がせようとしたのです。私は、その日は生理中だったこともあって下を脱がされるのが嫌で嫌でしょうがなくて、力いっぱい抵抗してもみ合いになりました。ですが、向こうの力が強くて、逃げることができず、服を全部脱がされてしまって……」
■凌辱の様子を撮影
恐怖、絶望、屈辱――。京子さんはその後の悪夢について、一語一語を絞り出すようにして、こう話した。
「抵抗する私を1人が組み伏せ、倒れてる私の上に別の2人がかぶさってきて、本当に辛くて、苦しくて……。彼らは、混乱して抵抗しようとする私に対して無理やり性行為をするだけではなく、口に性器を突っ込んできたり……」
さらに、メンバーの1人は、彼女が陵辱される様子をスマートフォンで撮影していたというが、絶句する他ない事実は他にもある。
「私が動けずに床に横になっていると、突然、私の顔とか首に生温かいものがかかってきました。誰かが、私にまたがって、おしっこをかけていたのです。私はびっくりして、怖くなって、叫んで逃げました」
それからの記憶は曖昧だが、翌朝気付いた時、京子さんは1階のベッドに寝かされていた。
「メンバーはすでに外に作業に出ていたようでしたが、私はなんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろう、なんでこんなことされなくちゃいけないんだろう、と思いました。そして、今しかチャンスはない、逃げよう、と考え、近くのバス停まで行きました」
だが、バスを待っているとメンバーの1人が現れ、
「合宿所を出るなって言ったのに、何で出たんだ!」
と言い放ったが、京子さんはそれを無視してバスに乗り込んだ。
「とにかく家に帰りたかった。ですが、新逗子駅で限界がきて、途中下車して路地まで行き、そこで嘔吐しました。どうしても動けなくて、30分くらいうずくまっていました。それから何とか電車に乗ったのですが、また気持ち悪くなり、上大岡駅で降りて駅の救護室に駆け込み、そこで動けなくなりました」
救急車で病院に搬送された京子さんは点滴を受けながら母親が来るのを待っていた。自分が性的暴行の被害に遭ったと知ったら、とてもショックを受けるに違いない─―。そんなことを頭に思い浮かべながら。
2、3流の大学ならこれほどまでに注目を受けなかったであろう。しかし、舞台は慶応大学!
慶応大学の対応も、注目されていると思う。
「未成年に飲酒させ、90年以上続いたサークルを途絶えさせてしまったことは、残念で申し訳ありません」
多くの女子アナを輩出した「ミス慶応コンテスト」の主催者である「慶応義塾広告学研究会(広研)」。その所属学生が起こした集団レイプ事件で、10代の女子学生が神奈川県警に被害届を提出、受理された。加害学生は広研の関係者を通じ、こうコメントを寄せた。
疑惑がもたれているのは、6人の慶大男子学生だ。9月2日、広研が神奈川県葉山町で運営する「海の家」の後片づけのため、近くの合宿所に学生が集まった。そこに女子学生は呼び出され、テキーラを約10杯飲まされ、酩酊したところを襲われたという。
しかし広研の関係者によれば、加害者の学生たちは、冒頭のように未成年飲酒については反省しているものの、強姦については否定し、彼女の主張に「反論」しているというのだ。
まず、女子学生は合宿所にいた学生に、LINEで呼び出されたとしているが、それについてはこう話している。
「彼女のほうから『私も行っていい?』と連絡してきたんです。彼女は6人のうちの1人と友人でした。無理やり彼女を呼び出したつもりはありません」
また、学生たちはアルコール度数の強いテキーラを、あらかじめ用意していたというが……。
「『海の家』では、テキーラのような強いお酒も提供しますが、ビールなどと違って、どうしても余ってしまいます。それで、打ち上げなどのときに余ったお酒を飲むんです。わざわざ用意したのとは違います」
そして、女子学生は強姦されたうえに尿までかけられた、という報道があったが、「そのようなことはけっしてない」というのが、彼らの言い分だ。
しかしどれだけ弁解しようと、彼らのやった行為は絶対に許されるものではない。女子学生が酩酊後、6人のうち2人が同時に彼女と性行為を始めた。その様子は、別の学生によって動画として撮影までされていたのだ。もし動画が流出したら、強姦罪だけでなく、リベンジポルノ防止法違反にも問われる。
「撮られた動画は、30秒ほどのものが4本。『その場のノリで撮ってしまった』と言っていました」(広研関係者)
じつは学生らは、そのとき撮った動画を、自ら大学に提出したのだという。
「『自分たちの行為は強姦ではない』ということを証明するために、提出したと聞いています」(同前)
慶大側は動画や画像について「確認したという事実はいっさいない」と否定。さらに「報道されているような事件性を確認するに至らなかった」と本誌に回答した。
サークルが解散しても、女性の「傷」が癒えることはない。
(週刊FLASH 2016年11月8日号)
慶応大学の広告学研究会(以下、広研)の男子メンバーによる“集団強姦事件”で、鬼畜すぎる新事実がまた明らかになった。
加害者グループは「性行為は合意の上だった」とアピールするため、あろうことか被害者の女子学生Aさん(18=当時)とのセックス動画を捜査当局に証拠提出。
さらに複数の慶大OBにまで動画を拡散し、潔白を訴えているという。実際に動画を見た慶大広研OBが本紙に語った。
逮捕秒読みと言われながら、なかなか動く気配のない今回の事件。捜査当局の間で物議を醸しているのが、
加害者グループが撮影した被害女性Aさんの陵辱動画だ。
Aさんは先月2日、広研メンバーに誘われ、神奈川県葉山町にある通称「合宿所」に招かれた。表向きの理由は夏に営業していた海の家の後片付け。
しかし実際はメンバーがAさんをレイプするための集まりだった。
同日夜に合宿所2階で始まった飲み会では、男性5人が未成年のAさんにテキーラの一気飲みを強要。Aさんが酩酊状態になったところで、
新入生2人が強引に服を脱がせ、性行為に及んだ。その模様は上級生がスマートフォンで撮影し、他のメンバーに生中継。
うつろな表情のAさんに男性が放尿したことも明らかになっている。
まさに鬼畜の所業。しかも加害者グループは姑息で卑劣すぎる印象操作をしているというから開いた口がふさがらない。
合宿所にいた男は計6人。うち1人は早々に1階で眠ってしまったため、犯行現場にいたのは5人だった。…
主犯格はX。20日発売の「週刊文春」によると、Xは合宿所に残った証拠物を処分したり、Aさんに口止めメールを送るなどしていたという。
当局の調べにXは「新入生がヤッただけで自分は見ていた。性行為は合意の上だった」と主張。そのうえで、
加害者グループは問題のセックス動画を当局に提出したという。被害者ならまだしも、加害者サイドが率先して証拠提供するとは異様だ。
しかも、加害者グループは卒業した広研OBにも同様の動画を流していたという。そこにはある目的があった。
「今回の事件で伝統ある『ミス慶応コンテスト』が中止となった。莫大な損失で、これには現役生だけでなく、広研OBも激怒。
焦った加害者グループは『この動画を見てください。全然レイプではないでしょ』とアピールしたかったのだろう。警察の捜査に対しても
『動画を見てもらえれば、合意なのがわかる』と豪語しているそうだ」(事情を知る関係者)
カギを握るのは動画の中身。ここで詳細は明かせないが、実際に映像を見た広研のOBによると「アダルトビデオを見ているようだった」。
Xらがそれを「合意」があったという証拠にしたいとしても、Aさんは酩酊しており、仮に無抵抗に見えても「合意」とは断定できない。
しかも拡散行為はリベンジポルノ防止法に抵触する可能性もある。
広研はセックス目的の“ヤリサー”との評判でも有名だったが、一方で上下関係やOBとのつながりを大事にしてきたという。…
慶大関係者は「広研OBには卒業後、テレビ局や大手代理店に就職する人も多い。現役生は彼らOBを“接待”し、自分たちが就職するときに口をきいてもらう。
広研が就職に強いのも、そうしたつながりが脈々と受け継がれてきたから。今回の事件はそれを台なしにした。Xたちが焦っているのはその部分で、
被害者に対する謝罪の気持ちはないのです」と語る。
事件を受け、広研のOB会組織にも大学側から“解散命令”が出されたという。
Xら加害者グループは合意の立証に必死なようだが、捜査当局は準強姦致傷のほか、
Aさんを心身ともに傷つけた暴行、未成年と知りながら飲酒を勧めた強要など、
複数の容疑での立件を目指しているという。5人は震えながらXデーを待つほかない。
男女関係なく、お金を持っている人に近寄る、権力を持っている人に近寄る、又は利用できる人に近寄る人達が存在するのは事実である。
玉の輿、友達に自慢するため、高価なプレゼントをもらうため、お金持ちだから、又は、高級車に乗っているから等、いろいろな理由でよっている
女性がいるのも事実。しかし、下記のような事をして、被害届を出されたら代償を支払うリスクが発生する。
少なくとも東大生は学業では素晴らしいかもしれないが、人間的には素晴らしいとは限らない事を証明した事件だと思う。
「この判決を受けて東大が何らかの処分を出すかと思われたが、3人の判決が出そろってから処分を決め、かつその内容を『発表する予定はない』(同校広報)とのことである。」
東大の対応を見ると大学として尊敬できるような大学ではなさそうだ!
慶應大生による輪姦事件が大きな騒ぎになっているなか、東京地裁では5カ月前に起きた東大生による集団わいせつ事件の審理が進み、これまでに2人の判決が出た。残る1人の判決は10月25日に下されるが、それを前にこの事件の深層に迫るレポートが新潮45・11月号に掲載された。傍聴ライター・高橋ユキ氏による「東大生集団わいせつ事件 『頭の悪い女子大生は性的対象』という人間の屑たち」という記事である。高橋氏は裁判傍聴に加えて事件の周辺にいた人物から内情を聞きだし、事件の暗部を抉っている。
■東大生は何をしたのか?
事件は5月10日、ゴールデンウィーク明けの火曜日に起きた。東大生で作る「誕生日研究会」のメンバーは午後8時に池袋駅で待ち合わせ、近所の居酒屋でコンパを行った。五月雨式に人が増え、男6名女2名となったこの場でも、羽目を外した振る舞いがあったが、問題はその二次会だった。
一次会は午後11時30分に終了。1人を除いて、同じ「誕生日研究会」メンバーの河本泰知が待つ、巣鴨にある彼の下宿へと移動した。そこで男たちはターゲットを一人の女性に絞り、彼女を裸にして徹底的に辱めたのだった。
「松見は悲鳴を気に留めることなく、さらに川岸さん(仮名)の背後から胸を揉み、腰に手を回してズボンを脱がせようとした。川岸さんは身を捩ったりズボンをつかむなどして抵抗したが、松本が川岸さんの前からそのズボンをつかんで引っぱって、2人で無理矢理下着ごと脱がせてしまう」
松見謙佑は東大工学部システム創成学科4年、松本昂樹は同学科から進学して大学院の1年生だった。ちなみに部屋を提供した河本泰知も松見と同学科の4年生だ。
一人の女性が帰ったあと、彼らの行動はエスカレートする。みなが代わる代わる体を触り、ドライヤーで陰部に熱風を当てたり、割り箸で肛門をつつくなどする。
記事では、裁判での供述や捜査資料をもとに1時間に及ぶ凌辱を再現している。
なぜ彼女だけが狙われ、このような目にあったのか。裁判では思わぬ事実が明かされた。ある時点まで被害者は松本と付き合っており、その松本が彼女の全裸写真をメンバーに見せたり、その日も「こいつオレのセフレだから何してもいいよ」とメンバーに言っていたのだ。
記事には松本の供述調書の一部が紹介されている。
「自分のポジションは被害者を泥酔させる目的で率先して飲ませる雰囲気を作り煽ることだった。焼酎のコップを無理矢理被害者の口に持って行って飲ませたり、被害者の胸がGカップと煽り、松見が触るなどしていた。山手線ゲームで知らないお題を設定して飲まないといけないように仕向けたりした」
こうしたことから、被害者に「そういうことをしても許される」とメンバー全員が思っていたという。例えば、河本の被告人質問ではこんな発言があった。
「被害者は明らかに嫌がってましたが、初対面だったのと、以前にもそういうことをしてたと聞いて、いいように解釈して……」
■思いあがったエリート意識
事件の背景には、東大生の思い上がったエリート意識があった。記事にはこうある。
「私の女性観ですが、(近づいてくる女性は)個人的に私を好いてくれるのではなく、下心があって近づいているのではないかと。そういう人たちに対して苦手意識、軽蔑する気持ちがありました」(松本の被告人質問)
「仲間の間で女性をモノ、性の対象として見て人格を蔑んでる考え方が根本にあったと思思う。大学に入学してサークルなどで他大学の子と接して、彼女らはアタマが悪いからとか、バカにして、いやらしい目でばっか見るようになり……という、男たちの中でそういう考え方が形成されてきたように思います」(河本の被告人質問)
記事では、彼らがわいせつ目的で作ったサークル「誕生日研究会」や、その母体となった、東大の3、4年生が他の女子大の1、2年生を勧誘して作る“本郷系サークル”のしくみなどを説明しながら。彼らが他の女子大生をランク付けしながら、付き合っていた実態を浮かびあがらせていく。
この事件で逮捕されたのは5人だが、うち2人は示談となり、3人が起訴された。
松見、河本の2人には9月20日に判決公判があり、それぞれ懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)が言い渡された。この判決を受けて東大が何らかの処分を出すかと思われたが、3人の判決が出そろってから処分を決め、かつその内容を「発表する予定はない」(同校広報)とのことである。
残る1人の松本は懲役2年が求刑されている。冒頭にも触れたが、判決公判は10月25日、東京地裁で行われる。
「新潮45」2016年10月20日 掲載
強気な対応?秘策か、宝刀でもあるのか?
血液製剤を不正に製造していた製薬会社・化血研の事業の譲渡先として交渉がすすめられてきたアステラス製薬が、交渉を打ち切る方針を固めたことがJNNの取材でわかりました。
化血研は、およそ40年前から国の承認とは異なる方法で血液製剤を製造したほか、事実を隠蔽したとして、厚労省が今年1月、過去最長の110日間の業務停止命令を出しています。塩崎厚労大臣が化血研に対し、組織の抜本的な見直しを求めたことから、製薬大手のアステラス製薬に事業を譲渡する方向で交渉が進んでいました。しかし、関係者によりますと、化血研側が「事業の譲渡は難しい」などと難色を示し、交渉は難航、アステラス製薬は交渉を打ち切る方針を固めたということです。
「ワクチン産業の業界再編の推進など、抜本的見直しに向けた提言をいただいた」(塩崎恭久 厚労相)
塩崎大臣は18日、「国内のワクチンメーカーは、組織形態の見直しでガバナンスを強化する必要がある」などとする「業界再編」を求める有識者からの提言を受け、化血研に対し、速やかに事業を譲渡するよう改めて求めました。
化血研の事業をめぐっては国内外の複数の企業が関心を示していて、今後、改めて事業譲渡に向けた交渉が本格化することになります。
全国で保育園などを運営する社会福祉法人「夢工房」(兵庫県芦屋市)の男性理事長(57)らによる資金不正流用問題について、調査していた同法人の第三者委員会は19日、流用額は少なくとも約1億4千万円に上ると発表した。姫路市、東京都港区からの補助金などの不正受給は約4600万円。第三者委は理事長ら創業者一族が法人を私物化していたとして、法人からの排除を求めた。
第三者委の調査報告書によると、理事長の母と義母、長男、長女、母の家政婦は、法人本部や姫路保育園(姫路市)、同園分園(同)などで勤務したと装い、2010~15年度に給与計約5960万円を受けた。長女や長男が通う大学院、専門学校の学費など約420万円も払っていた。
私的使用も、保護者から集め理事長の個人口座に入金していた教材費200万円▽長女が使う高級車購入費約740万円▽長女の結婚時に購入した家具、家電代約210万円-など、計1330万円に上った。理事長が経費でアダルト商品を買ったケースもあった。
このほか、理事長個人の資金と装った法人の簿外債務約6300万円も判明。理事長が理事会の議事録を偽造して借り入れており、不正流用と認定した。
補助金については、常勤の園長を置いた際に支給される加算など、姫路市から13~15年度に約3700万円を不正に受けていた。
第三者委は、理事長に逆らえない体質や理事会の形骸化、利用者軽視の利益優先主義などを指摘。理事長、総括園長の解任や理事会の一新などを提言。法人は今後、理事長らの刑事告訴などを検討するという。(斉藤正志)
一つ下の記事と矛盾しないか?
「労災認定されても娘は戻ってこない」
電通の新入社員だった高橋まつりさん(当時24)の自殺が、9月30日付で三田労働基準監督署から過労によるものと認定された。母親の幸美さんは10月7日に開いた会見で、悲しみを押し殺すように話した。高橋さんは東京大学生時代、本誌編集部でアルバイトをしており、皆から妹分として可愛がられていた。
2010年から11年にかけて、高橋さんは本誌のインターネット生放送番組(12年に終了)に出演していた。キャスター役を務めていた山口一臣元編集長は振り返る。
「テレビ番組に彼女が出ていて、『将来は週刊朝日の記者になりたい』と答えていたんです。『この子を探そう!』と見つけ出し、アルバイトしてもらうことになった。明るく聡明で、何事にも前向きな頑張り屋でした」
番組アシスタントとして本誌最新号の内容紹介だけでなく、時には突撃リポーターにも挑戦。当時の編集部スタッフはこう話す。
「相手が大物政治家だろうが、有名人だろうが、物おじしない。機転が利いて、根性もある。あの子を精神的に追い込むことのほうがよっぽど難しい」
だからこそ当時を知る関係者は一様に高橋さんが自殺を選んだのを信じることができない。背景に一体何があったのか。
電通では1991年に、入社2年目だった男性社員(当時24)が自殺。遺族が起こした裁判で、最高裁は長時間労働によるものと認定し、会社の責任を認めた。その教訓は生かされなかった。取材で電通に再発防止策について聞くと、
「長年にわたって適正な勤務管理、長時間勤務抑制などに取り組んでいた」
とし、深夜勤務を行った翌日の早朝勤務原則禁止などを推進してきたという。
しかし、昨年暮れに会社の寮で自殺した高橋さんの残業時間は、認定されただけでも月100時間を超えていた。
さらに高橋さんはツイッター上で、上司のパワハラを思わせるような文面を投稿していた。パワハラ有無の認識についても電通に問い合わせたが、
「ご遺族との間で協議を継続中ですので、個別のご質問についてはお答えしかねます」
と答えるのみ。
14日、東京労働局と三田労働基準監督署は電通の本社に立ち入り調査に入った。関西(大阪市)、京都(京都市)、中部(名古屋市)の3支社にも各地の労働局が同日までに調査に入った。違法な長時間労働が常態化していた疑いがあるとみて、立件を視野に調べるという。
※週刊朝日 2016年10月28日号
24歳の女性社員が、長時間労働の末に自殺した大手広告代理店「電通」が、2015年8月にも、労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかった。
電通の社員だった高橋 まつりさん(当時24)が長時間労働の末、2015年12月、飛び降り自殺を図り、労災が認定されたことを受けて、東京労働局の特別対策班などは、先週、東京・港区の電通本社に抜き打ちの立ち入り調査に入っていた。
関係者によると、2015年8月にも、違法な時間外労働が行われていたため、労働基準監督署が、是正勧告を行っていたという。
高橋さんは、亡くなる前、労働時間を実際より少なく申告していたということで、厚生労働省は、過少申告が、いつごろから行われていたのかなど、実態を調査している。.
長時間労働がある事は知らなかった、又は、どのような会社であるのか調査しなかったのだろうと思える。会社も規則違反となる長時間労働は表に出せないので、 業界にいる先輩や彼女の人脈から実際の実情を聞くことが出来なかったのかもしれない。
間違ったと思った時の対応の仕方は受験勉強には出てこない。日本しか知らない、又は、日本人の友達しかいない場合、いろいろな価値観や選択肢がある事を知らなかった かも知れない。別に普通に日本に育って、日本人の友達しかいなくても問題は起きない。運悪くどうして良いかわからない、友達にも相談できない、親にも相談できない 状況で最悪の結果を引いてしまったと言う事だろう。
最近は職業体験とかあるが、現実を見せないから勘違いする人達もいるのだろう。
これだけメディアに取り上げられいる分だけ、幸せとも言えるかもしれない。記事にもならない、注目も受けないまま、自殺して終わりと言うケースも多いのでは? 労働環境が悪い事も原因だと思うけど、自分に合っているのか、考える機会を学校で与えるべきではないかと思う。
過酷電通に奪われた命、女性新入社員が過労自殺するまで (1/4ページ) (2/4ページ) (3/4ページ) (4/4ページ) 10/18/13 (dot.)
入社1年目の電通社員高橋まつりさん(当時24)が、過労自殺に追い込まれた。その死は電通だけでなく、私たちの働き方、日本社会も大きく揺さぶっている。
2014年の春、当時東京大学文学部の4年生だった高橋まつりさんは、広告大手、電通の内定を決め、SNSで知人にこう報告した。
「マスコミ関係の仕事であること、職種の異動があり出来ることの幅が広いこと、新しいコンテンツをつくりだしていけること…などを重視して選びました」
そんな希望を語っていたわずか1年半後の15年12月25日金曜日、高橋さんは都内にある電通の女子寮4階の手すりを乗り越えて飛び降り、亡くなった。今年9月、三田労働基準監督署は高橋さんの自殺は長時間の過重労働が原因として労災を認定。
当時、彼女はインターネット広告を担当する部署に所属していた。試用期間後に正社員になると、10月以降1カ月の時間外労働が労基署認定分だけでも約105時間に。過労死ラインとされる80時間を大きく上回った。母親の幸美さんは今月の記者会見で、「労災認定されても娘は戻ってこない」と訴えた。
高橋さんは静岡県の私立高校から東大に入学。母子家庭に育ち、塾にも通わず時には1日12時間も猛勉強して大学合格を決めた。マスコミに興味があり、「週刊朝日」で配信していたインターネット動画番組のアシスタントを務めたことも。当時の高橋さんを知る知人が振り返る。
「おしゃれもするし、ミスチルが好きな今どきの大学生という雰囲気。でも番組ゲストの下調べもきちんとするし、叱られてもへこたれない芯の強さがあった。裏方の仕事もきちんとできる、本当に頑張り屋さんでした」
●SNSに激務の記録
ハードワークに耐えられないような子ではなかった、とこの知人は強調する。だが電通では、そんな彼女すら死に追いやるほどの激務が課せられた。高橋さんのツイッターには、長時間労働の実態が垣間見える書き込みがひんぱんに登場する。
<休日出勤えらいなぁとか思って出社したけど、うちの部に限っては6割出社してた。そりゃ過労で死にもするわ>(10月12日)
<誰もが朝の4時退勤とか徹夜とかしてる中で新入社員が眠いとか疲れたとか言えない雰囲気>(10月15日)
<やっぱり何日も寝られないくらいの労働量はおかしすぎる>(10月27日)
<土日も出勤しなければならないことがまた決定し、本気で死んでしまいたい>(11月5日)
<1日20時間とか会社にいるともはや何のために生きてるのか分からなくなって笑けてくるな>(12月18日)
電通のライバル、博報堂出身で、ネットニュース編集者の中川淳一郎さんは、広告業界全体の残業が多い体質を指摘する。
「広告はサービス業。クライアントの要望を聞き続けないといけなくて、100点を取り続けようとしてしまう。定時に帰る概念がないし、特に新人はサボってはいけないと頑張りすぎてしまう構造がある」
その中でもインターネット広告業界は単価が安いうえに作業量がほかの媒体に比べて非常に多い。とりわけ激務になる傾向が強いと別の関係者が指摘する。高橋さんは1年目で自動車火災保険と証券会社のデジタル広告業務を担当し、データの分析とクライアント向けリポートの作成を任されていた。ウェブデータは膨大で分析も難しく、専門的な知識も必要。この関係者は、「1年目でそんな仕事を1人で任されたら追い込まれるに決まっている。事実、ウェブ広告部門に配属されて数年でやめる若手社員は結構いる」と指摘する。
●生々しいパワハラ上司
高橋さんは通常業務に加えて、職場の宴会のための出し物作成や映像作成など休日返上で対応を求められていた。ツイッターの書き込みを見ると、高橋さんを追い詰めた職場環境の悪さも見えてくる。
<部長「君の残業時間の20時間は会社にとって無駄」(中略)「今の業務量で辛いのはキャパがなさすぎる」>(10月31日)
<いくら年功序列だ、役職についてるんだって言ってもさ、常識を外れたこと言ったらだめだよね>(11月3日)
ある若手の電通社員は、高橋さんが配属された部署は「若手社員のなかでも評判の『行きたくない部署』だった」と言う。
「関連会社からの出向社員が多く、本社の若手社員が『本社なのに、その学歴なのに、こんなこともできないのか』と叱責(しっせき)されたり、意図的に間違えた指示を出されたりと、パワハラが常態化していたと聞いています」
電通はネット広告分野については今年7月に発足した「電通デジタル」などの子会社に業務を任せることも多く、電通本社に子会社から大量の出向者が来ていたと関係者は証言する。
「そんなにつらい職場なら、やめればよかった」というのはたやすい。だが、筑波大学大学院人間総合科学研究科教授で、職場のメンタルヘルスに詳しい松崎一葉医師はこう言う。
「過労による自殺のほとんどは睡眠不足の状態で起こっている。論理的に見えても脳は疲れ、判断能力が低下して、小さなきっかけでもう死ぬしかないと思ってしまうのです」
●他人事に思えない事件
高橋さんはうつ病も発症していたとみられる。松崎さんは「推測だが、真面目で根性がある彼女は、うつにかかるリスクが高かったのでは」と分析する。
「嫌々過重労働をするのではなく、いい仕事をするために、進んで仕事をする。他者を気遣い、手助けは申し出るが、自分からは援助を求めない」
真面目であるために、パワハラもまともに受けとめやすい。
「上司のむちゃな要求も多くの人が受け流したり、10のうち8で諦めたりするのに、睡眠時間を削って最後までやってしまう」
そんな高橋さんの事件はとても他人事ではない、という声は多い。本誌で今年4月、ヤフーと協力して行ったウェブアンケートでは、「仕事が理由で体調を崩したり、家庭が壊れたり、人生が狂ったりした経験がありますか」という質問に約2800人中、約2100人が「ある」と回答。長時間労働、休日出勤があると答えた人は約1200人に達した。
SEの男性(37)は3年前、10年以上勤めた職場をやめた。2、3年に一度、同僚が「突然死」する環境が嫌になった。
「プロジェクトはいくつも並行して走り、トラブル対応もこなさなければならない。スキルのある人に仕事は集中し、月の残業は80時間超が普通で、100時間を超える月もありました」
会社は「月残業80時間を超えないように」と指示したが、業務量は変わらず、人も増えない。社員は残業時間を少なめに申告して働き続けたという。
広告会社でプランナーとして働いていた女性(32)は5年前、3年働いた会社をやめた。
「自分の企画が競合に勝つ達成感とやりがいに支えられ、深夜残業も土日出社もいとわず週に3日はタクシーで帰り、翌日9時半には出社する毎日でした。時には1人で20件以上の案件を抱えることもありました」
●死を防げなかった教訓
だが、会社は裁量労働制をたてに残業代を1円も払おうとしなかった。長時間労働で心と体はむしばまれ、ストレス性の皮膚炎を発症し辞表を書いた。
「命よりも大切なものはないと気づいたんです」
個人の使命感ややりがいをたてに労働力を搾取するやり方は、決して許されるものではない。電通では1991年にも男性社員が深夜や早朝に及ぶ長時間労働をくり返した末に自殺しており、その最高裁判決(00年)以降、匿名での電話相談や先輩が相談に乗るメンター制度などサポート体制が充実していたという。「先輩が常に気にかけ、よくしてくれる」(若手社員)との声もある。それでも死は防げなかった。03年まで電通に勤めた、事業創造大学院大学客員教授の信田和宏さん(72)は、「電通は部単位のマネジメントを上層部が管理する体制にはなっていない。コンプライアンスが浸透しにくい組織だ」と語る。過労死問題に詳しい玉木一成弁護士は、「社内の宴会の幹事までさせる長時間労働に意味があるとは思えず、状況が改善されたようには思えない」と指摘する。
松崎さんは、こう語った。
「学歴の高い人は知らない人に相談しない傾向もある。日頃から社員が産業医と親密に話す環境をつくるなど、機能するメンタルサポート体制が必要です」
電通は高橋さんの自殺に関して「厳粛に受け止めており、誠に残念」、労災認定について「極めて重く、厳粛に受け止めております」と回答した。
(編集部・熊澤志保、山口亮子、福井洋平)
※AERA 2016年10月24日号
化学及血清療法研究所(化血研、熊本市)が国の承認と異なる方法で日本脳炎ワクチンを製造していたとされる問題で、化血研の木下統晴理事は18日、熊本市内で記者会見し、社内調査の結果、不正な製造は行われていなかったとの見解を示し、厚生労働省の指摘に反論した。
厚労省は4日、9月に行った抜き打ちの立ち入り検査の結果、承認と一部異なる方法による日本脳炎ワクチンの製造が確認されたとして、経緯を調査して報告するよう化血研に命じていた。
会見で化血研側は、ワクチン製造のため日本脳炎ウイルスを培養する際、ウシの胎児の血清の一部で毒性などを失わせる「不活化」がされていなかったとする同省の指摘について、「2005年に厚労相に提出した承認申請資料に記載した通りに製造していた」と主張した。
抜き打ち検査で確認したとする厚労省側の指摘についても、「申請資料の記載に誤解されかねない部分があったため、8月に厚労省に報告、相談していた」と説明。隠蔽(いんぺい)などはなかったと訴えた。
化血研は18日、社内調査結果の報告書と弁明書を厚労省に提出。化血研によると、同省が近く予定している業務改善命令について、同席した弁護士が見送るよう申し入れたという。
宮城県が見積もった整備費が150億~200億円以内であるなら、宮城県登米市の長沼ボート場で良いのではないのか。最終判断の前に、宮城県知事には念書を書かして 置くべきだ。整備費を含む合計が200億円を超えた場合は、宮城県が負担するとの誓約書が必要。
東京都職員達を見れば理解できるであろう。嘘つきが多い。東京都職員を信用する理由が見当たらない。
東京都は18日、2020年東京五輪・パラリンピックのボート、カヌー・スプリント会場「海の森水上競技場」の整備費を現行計画の491億円から300億円程度まで圧縮できるとの試算をまとめたと明らかにした。
都によると、海の森水上競技場で整備する屋根付きの観客席「グランドスタンド棟」や艇庫棟の規模を縮小したり、仮設で整備したりしてコストを削減。追加工事が生じた場合の費用として準備していた約90億円が必要なくなり、テレビ撮影で利用する仮桟橋の設置も見送る。
施設の見直しには、国内外の競技団体や国際オリンピック委員会(IOC)と協議する必要がある。海の森の代替候補地となっている宮城県登米市の長沼ボート場で開催する場合、宮城県が見積もった整備費は150億~200億円。
女性を酔わせて暴行する事は新しい手口ではない。問題は慶応に入学できるような学生であってもそのような行動を取る事が事実かどうか?
東大生も強制わいせつの罪で世間を騒がした事件があったのだから偏差値や大学は関係ないと 考えるべきなのか?
慶応大学の10代の女子学生が、ミスコンなどを運営するサークルの数人の学生から集団で性的暴行を受けたとして被害届を出し、警察が捜査を始めている。その後の取材で、女子学生が「複数の男子学生に服を脱がされた」などと訴えていることがわかった。
関係者によると、慶応義塾大学に通う10代の女子学生は先月上旬、神奈川県葉山町にある合宿所で、「ミス慶応コンテスト」などを運営する「広告学研究会」に所属する、同じ大学の数人の男子学生に集団で性的暴行を受けたとして、15日に被害届を出した。警察は被害届を受理し捜査を始めている。
その後の関係者への取材で、女子学生が警察に対し、「複数の男子学生に服を脱がされた」「抵抗したが押さえつけられた」「男子学生2人に暴行されその様子を撮影された」などと訴えていることがわかった。また、女子学生は未成年だったが、暴行を受ける前にテキーラを10杯以上飲まされたと話しているという。
慶応大学は、女子学生とその場にいたとされる男子学生6人の双方から聞き取りを行ったが、主張が食い違っているとしており、「性行為があったとは聞いているが事件性は確認できなかった」と説明している。
警察は今後、事件当時現場にいた6人の男子学生から話を聞くなどして、慎重に捜査を進める方針。
豊洲問題の東京都のように甘い調査なら時間の無駄!
慶応大学の学生団体「広告学研究会」に所属する男子学生数人から性的暴行を受けたと10代の女子学生が警察に相談をしていましたが、警察は16日までに被害届を受理していたことが分かりました。
関係者によりますと、先月上旬、神奈川県葉山町の合宿施設で行われた慶応大学の学生団体「広告学研究会」の親睦会で、10代の女子学生が男子学生数人に酒を飲まされたうえ性的暴行を受けたと警察などに相談していました。その後の関係者への取材で、警察が女子学生からの被害届を16日までに受理していたことが分かりました。
慶応大学は今月4日、未成年者に飲酒を強要したことなどを理由に「広告学研究会」に解散を命じていますが、暴行の事実については「事件性を確認するには至らず、警察などにおいて解明されるべきと考えます」とのコメントを発表していました。
外国人選手達ともコミュニケーションを取っているのか?テレビでオリンピック選手達が他の外国人選手と話す機会がないだけでなく、日本人選手達とも話すことはあまりないと答えていたぞ。全ての選手とは 言えないが、勿体ぶった話など必要ない。
大体、保尚武会長はなぜ100億円以下の見積もりが1000億円になるのか、説明をしてほしい。
「風や波の影響を緻密に計算し、レースに影響が出ないように会場を設計した。プロ中のプロが3年をかけて調べた。」と言う事は、費用が100億円では不足する事を 推測出来ていたのではないのか?皆で口裏を合わせて工事を進めて、後で言い訳を付けて追加費用を公表しようと思っていたのではないのか?
そして、アスリートファーストとか、レガシーとか言葉をすり替えて国民や都民を騙すのか?
日本ボート協会の大久保尚武会長が13日、河北新報社のインタビューに答え、2020年東京五輪・パラリンピックのボートとカヌー・スプリント会場を巡り、東京都が都内から宮城県長沼ボート場(宮城県登米市)への変更を検討していることについて「選手たちの五輪への思いが無視されている」と批判した。長沼開催には会場を五輪用に仕上げる作業の難しさを指摘し、「工事が五輪に間に合うだろうか」と懸念を示した。(聞き手は東京支社・剣持雄治)
◎日本ボート協会 大久保尚武会長に聞く
-東京都の調査チームによる五輪会場見直し作業をどう受け止めているか。
「一言の相談もなかった。(小池百合子)知事はアスリートファースト(選手第一)と言っているが、まともに選手の意見を聞いていない。経費削減が優先され、アスリートの五輪への思いを無視している」
-都内の海の森水上競技場の代替地に長沼が浮上した。
「国際ボート連盟の施設責任者が20回ほど来日して長沼を含む国内9コースを視察し、海の森を最適と判断した。風や波の影響を緻密に計算し、レースに影響が出ないように会場を設計した。プロ中のプロが3年をかけて調べた。(変更案は)長沼を直接見たことない人たちが書類上でやっているように感じる」
-村井嘉浩宮城県知事が「復興五輪」の意義を強調し長沼開催を要望した。
「復興五輪には事前合宿の誘致などで協力したい。選手村が分村となって他競技と切り離されれば世界選手権などと変わらなくなってしまう。選手村は他競技の選手から学ぶ貴重な場だ。私は射撃の選手が早朝から伏射の姿勢で練習を積んでいた姿が忘れられない。重量挙げの三宅義信さん(宮城県村田町出身)とも話し、競技に懸ける意気込みを知った」
-仮設住宅を宿泊施設に再利用する案が出ている。
「世界中の選手がどう受け止めるか心配だ。海外の選手は身長2メートルほどがほとんど。普通のベッドでは過ごせない」
-長沼開催には、観客席や伴走路など五輪専用設備が必要になる。
「コースの中央部に風の吹き抜ける部分があり、横風の影響を抑えるための対策なども必要になる。準備工事が五輪に間に合わないのではないかと懸念する」
-海の森開催の意義は。
「五輪後にも国際大会を誘致しやすくなる。国際連盟は日本で(恒久的に)五輪レベルの大会が開催できることを望んでいる。人気が高い欧州だけでなく、アジアでもボートを普及させようとしている」
「もとより、捜査権限を有しない大学の調査には一定の限界があります。一部報道にあるような違法行為に関しては、捜査権限のある警察等において解明されるべきであると考えます。大学としては自ら事件性を確認できない事案を公表することはできず、したがって、一部報道されているような情報の『隠蔽』の意図も事実もありません」と隠蔽を否定。 引用終わり**
建前なのか、逃げているのか、今後の展開で明らかになるかも??
コンテストを運営する慶応義塾広告学研究会に所属する未成年学生の飲酒が発覚したため、11月20日開催予定だった今年の「ミス慶応コンテスト」が中止になった件で、女子学生への性的暴行事件があったとする一部週刊誌報道について、慶大は12日、大学公式サイトで見解を発表した。
「『広告学研究会』の解散命令に関わる一部報道について」と題し「さる10月4日、公認学生団体『広告学研究会』の解散を命ずる告示文を学内掲示およびウェブサイトで公表しました。その後、告示文に明記した解散事由以外にも違法な行為があった、と一部報道がなされております。今回の解散処分にあたっては、複数回にわたり関係者に事情聴取を行う等、大学として可能な限りの調査を行いましたが、報道されているような事件性を確認するには至りませんでした」と報告した。
「もとより、捜査権限を有しない大学の調査には一定の限界があります。一部報道にあるような違法行為に関しては、捜査権限のある警察等において解明されるべきであると考えます。大学としては自ら事件性を確認できない事案を公表することはできず、したがって、一部報道されているような情報の『隠蔽』の意図も事実もありません」と隠蔽を否定。
「なお、事件性が確認されるような場合には、捜査等の推移を見守りつつ、厳正な対処を行うというのが、従来からの慶應義塾の方針です」としている。
広告学研究会は9月2日、活動の一環として宿泊したホテルで懇親会を開催。ゲームの勝敗や、飲酒をあおって大学1年生ら未成年の学生が酒を一気飲みしていた。大学は会に解散を命令した。
13日発売の「週刊新潮」(新潮社)は性的暴行事件があったとし、大学側が事件を“握りつぶした”としている。
自動化やIT化は良いが、あくまで利用する、最終的な判断をする、一般的に想定されていないケースが発生した場合、最終的には人が判断しなければならない事を理解していない 事例ではないのか?
誤認識や認識しない場合、システムを通して情報を共有していれば、問題が発生している事を共有できなければ、問題がスタートする。多くの人が問題が発生した事を知らずに、 システムは正しいと判断して作業を継続すれば問題はさらに悪化する。
今回の問題は修正されなければならないだろう。今回のように問題を故意に発生させれば、セキュリティーを破って飛行機内に搭乗できる事が証明された。テロに利用できる 事が明らかになった。
これまで以上にスタッフに高い対応能力が必要であることが明らかになった。高い対応能力の人間を採用しようとするとコストアップになる。訓練には限界がある。 一般でない状況が発生した時に、対応能力が高くないと対応できない。状況を把握し、必要な情報を入手し、判断して対応するのは特定のやはり人間にしか出来ない。
コストを考えると多少のリスクには目をつぶるのか、問題が起きるまで見て見ぬふりをするのか、優先順位を決めて対応するしかないと思う。
産業総合研究所 知識情報研究チーム長 中田亨
乗客1人が立った状態のまま、全日空機が駐機場から滑走路へ向かって移動を開始――。福岡空港で9月30日、定員超過のままで飛行機が始動するミスが発生した。駐機場を出た直後に発覚し、飛行こそしなかったが、立ったままの搭乗客がいる状態で離陸する前代未聞のミスにつながりかねない事態だった。複数回のチェックが行われる飛行機の搭乗手続きで、なぜこうしたミスは防げなかったのか? ヒューマン・エラーに詳しい中田亨氏が分析する。
〈全日空機で起きた定員超過の経緯〉
別々の席を予約していた父親と息子が、同じバーコードを使って搭乗手続きをしようとした。父子は別々のバーコードで搭乗手続きをする必要があったが、息子が誤って父親の席のバーコードをスマートフォンにダウンロード。保安検査場と搭乗口のそれぞれで、同じ人物が2度通過したとされる「再通過」の警告メッセージが出たが、係員は何度も機器にタッチしたためと勘違い。1枚の搭乗券で父子2人が乗り、もう1人分は搭乗手続きが行われていない状態となった。
「11人いる!」
父子2人の乗客が「1人搭乗、1人空席」とされたため、席が1つ余ったように認識された。余った席はキャンセル待ちの人に提供されたが、実際には父子は2人とも搭乗しているため、当然、機内で席が足りなくなった。
このニュースを聞いて、萩尾望都の傑作漫画「11人いる!」を思い起こさずにはいられなかった。10人が乗り込むはずの宇宙船なのだが、出航後に数えてみるとなぜか11人乗っている。余分な1人は、密航者か、あるいは敵なのか、とにかく好ましからざる人物であるに違いない。だが、誰もが自分は正規の乗客だと言い張るので、誰が招かざる客なのか特定できない、というサスペンスである。
飛行機も同じで、乗っている客と名簿との勘定が合わなかったら大変だ。ハイジャック犯が紛れ込んでいるかもしれないから、離陸を取りやめ、いったん全員を下ろすしかない。
ミスは心意気の証し
とはいえ、飛行機の乗客管理というものは、四角四面にやっているだけではダメで、融通を利かさなければならない。どうしても飛行機に乗らなければならない急用がある人のためには、航空会社が呼びかけて、正規の乗客が席を譲るという習慣もある。
ただし、これは出発間際で行うデータ変更であるから、管理を難しくするリスクである。
運航上の管理だけを考えるなら、出発直前の乗客変更は断った方がよい。しかし、このリスクを引き受けねば、公共交通機関の名折れである。
世のため人のために、あえて便宜をはかり、難しい管理を引き受けているからこそ、たまにミスが起こるとも言えるのだ。もちろんミスは迷惑なことだが、考えた上でリスクテイクしている。その心意気は評価してあげたい。
原因の一つは認識のズレ
今回の一件を見るに、「システムについての認識のズレ」という典型的な事故の元凶がうかがえる。
乗客のバーコードを照合するチャンスは、保安検査場と搭乗口との2つの場面である。そのどちらでも、システムは「このバーコードが通ったのは2回目だ」とか「座席が重複している」と、警告メッセージを出したという。
しかし、係員は「バーコードのかざし方が悪くて、ダブルカウントされただけで、本当は大丈夫」と勘違いして、父子2人を通してしまった。
こうしたミスを避けるには、システムが「このバーコードは20秒前にも見ました。その時の映像はこれです。2度かざしではありません」などと、時間間隔や場面の状況について教えられればよかったのである。
システム開発者は「ちょっとやそっとでは、バーコードをダブルカウントできないように作ってある」と思っているのかもしれない。その性能が周知されていれば、システムもここまでくどくど言わなくてもいいだろう。
しかし、係員は「2度かざしのダブルカウントがありえる」と思っていた。システムの性能について、認識のズレがあったのだ。このズレこそが、今回ミスが起きた第1の要因と言える。
これは、我々の日常生活でもよくある話だ。
例えば、パソコンでファイルを「完全消去」すると、データは永久に消滅したと思って当たり前である。しかし多くの場合、データは残っていて復元することが可能だ。完全に消すには、粉砕するといった、かなりの努力を要する。
うっかりパソコンをこのまま廃棄すると、データを復元されて情報漏洩につながる。
道具の作り手と使い手との間には、道具の認識についてのズレが必ずあり、そこから事故は起きる。
当たり前のことにあるリスク
事態が勝手にスイスイと進むことは、多くの場合、ろくなコトにならない。
空席があればキャンセルと判断され、キャンセル待ちの人に割り当てる。この一連の流れは効率的で当たり前ように見えるが、実はかなりリスキーである。
大病院で各病室に薬を配る作業を考えよう。全室に配り終わったはずなのに、かごの中に何か薬が残っていたとしたら、直ちに全館放送を入れねばならない。勘定が合わないということは、薬を配り間違えている可能性がある。つまり、投薬ミス寸前の状態である。
大空港の搭乗口は、あまり正確に仕事が進む場とは思えない。
大きな荷物を抱えた乗客が我先にと押しかける場所だ。ある人はバーコードを印刷した紙で通過し、別の人はICカードをかざす。慣れない機械にとまどう高齢者もいれば、持ち込み禁止の手荷物を乗務員に預ける若者もいる。そして、ようやくゲートを通り抜けていく。
これは、実に不安定な作業なのだ。
こうした作業の結果、たとえ空席を発見したからといって、即座にキャンセル待ちに再利用という早手回しは危なっかしい。数え間違えをしている可能性は捨てきれない。
一石二鳥は諸悪の根源
搭乗口の確認作業が整然と進めば、この問題のリスクはかなり解決される。素早いゲート通過は、時間の節約となるから、航空会社としても切望しているところである。
設計工学の世界には「一石二鳥は諸悪の根源」と考える学派がある。一つの部品に複数の役目を負わせると、事故はそこから始まることが多いのだ。
今回の場合、飛行機の座席が「一人二役」を背負わされている。飛行中に座るものとしての役目と、乗客を数えるための道具としての役目である。
今回は機内で席が足りなくなったから、おかしいぞと気がついたのである。つまり、座席を使って客数を数えたのだ。
ミスをなくすには、「一人二役」を分離することが望ましい。
乗客を数えるための役目は、搭乗口手前の待合室にある椅子に背負わせるべきだ。椅子が機内のレイアウトで並べてあり、乗客は自分の席に相当する椅子で待つというふうにする。こうすれば、搭乗口が開く前から、どこの席が空席なのか見て取れる。ダブルブッキングもすぐ分かる。
こうして乗客を整列させておき、後方の客席に座る搭乗者から機内へ誘導すれば、乗り込みも整然となって楽ではないだろうか。現状のようなゲートに直接詰めかける方式は、競争心をあおってしまう。
ヒューマン・エラーと呼ぶべきか?
空港の搭乗口の周りはそんなにスペースがないから、この案の実現は難しいかもしれない。しかし、並ばずにスムーズに乗れ、すぐ飛び立つ飛行機は、乗客にとっても航空会社にとってもありがたく、多少の投資をしても引き合うのではないかと思う。何より、ゲートを通る乗客に整然とした環境を提供することが、おもてなしの心である。
これは、ゲートを守る係員にも優れた作業環境を与えることにつながる。
現在のような乱雑な状況では、ヒューマン・エラーは起こって当たり前だ。「ヒューマン・エラーがこのトラブルの原因だ」と責めることすらナンセンスだと思う。作業環境が悪ければ、いくら人間が頑張ったとしても限界がある。
「11人いる!」はサスペンスである。
今回、全日空のミスで浮かび上がった「抜け穴」が、誰かによって悪用されないとも限らない。ミス対策や混雑対策という枠を超えた、セキュリティー問題でもあるのだ。雑然としたゲートの状況を放置するのは、今後は許されないだろう。
中日新聞社は子どもの貧困をめぐる連載記事を書いた記者に今後、記事を書かすべきではない。新聞記者でなくても、「想像」で記事を書いてはいけない事を知っている。
ジャーナリズムの基本だし、人間性を疑う。中日新聞がこの記者を雇い続けたいのであれば、新聞社の勝手であるが、記事を書かすのはやめてもらいたい。
話を盛るのは、バラエティーか、個人的な趣味でやってもらいたい。
「想像で書く」と言う事はフィクションであり、ノンフィクションではない。大体、想像で貧困の記事を書く理由とは何か?貧困に関する取材で事実を確認できないほど
貧困はないと推測する事も出来る。大体、インターネットでも絶対的貧困と相対的貧困とは違うと議論されている。
自分の専門に関する事で、間違った情報がテレビで流されている番組を見るたびに、一体、どれほどの情報が正確なのかと思う。専門でない事に関して、新聞やテレビ等の
メディアに頼るしかない。メディアはもっとしっかりしてほしい。
◇マンション購入費など
三井住友銀行を巡る巨額詐欺事件で、電子計算機使用詐欺容疑で逮捕された同行大森支店(東京都大田区)の元副支店長、南橋浩容疑者(54)が、交際していた女性にマンション購入費などとして約1億円を使っていたことが捜査関係者への取材で分かった。2007年から総額で11億円をだまし取ったとされ、警視庁捜査2課は金の使途についても調べている。
南橋容疑者は昨年11月~今年6月、外貨取引のオンラインシステムを不正に操作し、同行から十数回にわたって約166万米ドル(約1億9000万円)を詐取したとして、12日に逮捕された。口座などに約5億円が残っていたことも判明。南橋容疑者は「将来のために残しておいた」との趣旨の供述をしているという。
捜査関係者によると、南橋容疑者は同行の成城支店(世田谷区)の課長だった07年、同支店に架空の建設会社名義で普通預金と外貨預金の2口座を開設。口座を使ってドルを購入する際、システムに水増しした金額を入力し、増額したドルで円を買い戻す不正を繰り返していたという。
不正は借金の返済のために始めたとみられ、だまし取った金は子供の教育費や外国為替証拠金取引(FX)に充てていた。また交際していた女性に都内の高級マンションを買い与えるなど約1億円を使っていた。
同行は7月に南橋容疑者を懲戒解雇し、9月に警視庁に刑事告訴した。【宮崎隆、黒川晋史】
話を盛るのは、バラエティーか、個人的な趣味でやってもらいたい。
「想像で書く」と言う事はフィクションであり、ノンフィクションではない。大体、想像で貧困の記事を書く理由とは何か?貧困に関する取材で事実を確認できないほど 貧困はないと推測する事も出来る。大体、インターネットでも絶対的貧困と相対的貧困とは違うと議論されている。
自分の専門に関する事で、間違った情報がテレビで流されている番組を見るたびに、一体、どれほどの情報が正確なのかと思う。専門でない事に関して、新聞やテレビ等の メディアに頼るしかない。メディアはもっとしっかりしてほしい。
中日新聞社(名古屋市)は、中日新聞と東京新聞に掲載した子どもの貧困をめぐる連載記事に事実とは異なる記述などがあったとして、両紙の12日付朝刊におわびを掲載し、当該記事を削除した。
同社によると、問題となったのは、5月に中日新聞朝刊で6回連載した「新貧乏物語」第4部のうち、父親が病気の女子中学生を取り上げた19日付朝刊の記事。生活が厳しくて教材費や部活の合宿代が払えない、とした部分など3カ所が事実ではなかったという。
記者は家族らに取材して取材メモをつくっていたが、この部分は「原稿をよくするために想像して書いてしまった」と説明しているという。家族から指摘があり、同社が社内調査をした。同じ記事は6月に東京新聞にも掲載された。
5月17日付の中日新聞に掲載したパンの移動販売を手伝う少年の写真も、同じ記者が、実際とは異なる場所でカメラマンに撮影させていたという。
両紙は、臼田信行・中日新聞取締役名古屋本社編集局長名で「記者が事実と異なることを自ら知りながら書いたことは到底許されません。深くおわび申し上げます。厳正に処分するとともに、記者教育に一層力を入れていきます」とするコメントを掲載した。
慶応大学の「ミス慶応コンテスト」の中止が発表されたのは、10月4日のことだった。大学側はその理由を「複数の未成年者の飲酒」と説明し、主催サークル「慶応大学広告学研究会」の解散を命じたが、その裏にはサークルメンバーたちによる性的暴行事件があった。
***
被害に遭ったのは、広告学研究会に所属していた18歳の女性。9月初旬、神奈川県の合宿所にて泥酔した彼女に、複数の男性メンバーが性行為を強要したという。
「抵抗する私を1人が組み伏せ、倒れてる私の上に別の2人がかぶさってきて…」(被害女性)
男たちは、凌辱される様子をスマートフォンで撮影したほか、それ以上の絶句する他ない行いも。女性の母が大学に被害を訴えるも、慶応大学の学生部は“警察に行け”の一点張りの対応で、性的暴行事件は“なかったこと”にされていたという。
慶応大学は取材に対し「今回の処分は適正なものと認識しております」とコメント。10月13日発売の「週刊新潮」では、女性のより詳しい証言の掲載と併せ、大学が握りつぶした事件の全容を明らかにする。
「週刊新潮」2016年10月20日号 掲載
10月4日、“女子アナの登竜門”とも称される「ミス慶應コンテスト」の中止と、同コンテストを企画・運営する公認学生団体「広告学研究会」(以下「広研」)の解散が発表された。
慶應大学側は、「告示文」においてその理由を「未成年飲酒」によるものとだけ説明したが、小誌取材により、大学側が明かさなかった「広研」の男子学生が引き起こした重大な事件が明らかになった。
事件が起きたのは9月2日、現場となったのは、神奈川県葉山町内にある広研の「合宿所」だった。事件の全貌を知る広研所属の学生が語る。
「この日は、広研が夏の間に運営している海の家の撤収を行う作業のため、6人の男子学生が合宿所に泊まっていました。作業終了後、酒を飲むことになり、呼び出されたのが6人と顔見知りだった1年生のA子さんです」
そして深夜、男子学生たちは酒で意識のなくなったA子さんに襲いかかったのである。しかも、あろうことか、その様子を別の学生が撮影し、実況まで行っていたという。
男子学生の一人は小誌の直撃に対して最初は偽名を名乗ったが、「何も答えられないです」と言いながら、本人であることを認めた。「謝罪の気持ちは本当に……。時が来たら連絡します」と言い残すのが精一杯だった。
一方でA子さんの母親は、小誌取材に対して、警察に被害届を提出したことを認めた。
上記事実の確認を慶應大学に求めたところ、「今回の解散命令の基礎になった事実は告示文に記載されているとおりです。なお、今回の処分は、関係者に複数回にわたる事情聴取を行う等、大学として可能な限りの調査を行ったもので、適正なものと認識しております」との回答があった。
詳細は、10月13日発売の「週刊文春」10月20日号で報じている。
<週刊文春2016年10月20日号『スクープ速報』より>
最近、AIと呼ばれる言葉が頻繁に使われるが、AIと人間や人間活動が協調しなければ思うほど良い結果はないであろう。
9月30日午後2時20分ごろ、全日本空輸(ANA/NH)の福岡発羽田行きNH256便(ボーイング777-200型機、登録番号JA742A)で、搭乗手続きが済んでいない乗客が搭乗した。機体は駐機場に引き返し、当該客らが降機。およそ50分遅れで出発した。国土交通省航空局(JCAB)の高野滋安全部長は10月11日、ANAを厳重注意とし内薗幸一副社長に改善策の提出を指示。10月25日までに原因究明と再発防止策の文書での提出を求めた。
◆同一の搭乗券でスキップサービス
搭乗手続き未了の事象は9月30日、福岡空港で発生した。午後2時10分福岡発羽田行きNH256便(乗客405人、幼児3人、運航乗務員2人、客室乗務員11人)に搭乗する40代と10代後半の男性親子が、搭乗手続きを済ませないまま保安検査場と搭乗ゲートを通過。そのまま機内に乗り込み、午後2時15分に出発した。機内では客室乗務員が、親子のうち父親の座席がないことに気がつき、直後に出発ゲートに戻った。当該便は満席だった。
親子は、空港での手続きなしで搭乗できる「スキップサービス」を利用。それぞれのスマートフォンにQRコード付きの搭乗券を保存した際、息子が父親の搭乗券を誤って保存した。父親は自身の搭乗券を保存していたため、同じ搭乗券を異なる端末に保存したことになる。
親子はほぼ同時刻に保安検査場を通過。父親が先に、息子が後から通過したところ、同一コードでの通過を示すエラーが発生し、ANAの地上係員を呼び出す旨の用紙が出力された。保安検査場の係員はこれを「搭乗手続き済みの二度かざし」と誤判断。保安検査をそのまま実施し、息子を通過させた。
その後、搭乗ゲートでは息子が先に、父親が後から通過。息子は通過できたが、父親には「座席重複エラー」が発生した。地上係員はこれを「携帯端末の二度かざし」と誤判断。本人確認の上、そのまま機内に案内した。
一方、当該便には空席待ちが発生。保安検査を未通過扱いだった息子の席が空席となり、空席待ちをしていた利用客に割り振られた。割り振られた利用客と親子は、それぞれ機内に乗り込んだ。空席待ち客は元・息子の席に、息子は父親の席に座り、父親は離れた場所で手荷物を収納していた。
客室乗務員が立ちっぱなしだった父親に気づき声をかけたところ、座席がないことが発覚。客室乗務員は機長に報告し、駐機場に引き返した。引き返した当該機からは親子2人が降機。47分後の午後2時57分に福岡を出発した。親子は次の便で羽田に向かった。
ANAは福岡空港での保安検査を、福岡市の警備会社「にしけい」に委託している。
◆搭乗券「複数回ダウンロード可能」
QRコード付きの搭乗券は確認番号やクレジットカード番号などと照合し、ダウンロードする。ANAによると端末の電池切れなどを想定し、複数回ダウンロードできる仕組みだという。また機器の反応が悪く、繰り返しタッチすることは比較的多くあるという。
機内では、搭乗客が着席できる状態を確認できたら出発することができる。着席していない場合でも、手荷物の収納中やトイレ利用中など、「座ることができる状態」であれば出発するという。
搭乗客は出発10分前までに保安検査場を通過することを求められている。10分を過ぎたら空席待ちの利用客に開放する。今回の事象では、午後2時1分に開放した。
また、息子はQRコード付きの搭乗券を誤ってダウンロードしたことを認めているという。
ANAは今後、エラー発生時には保安検査場の係員がANAの地上係員に対応を要請することを再徹底。各空港の検査場にANAの地上係員を配置し、エラー発生時にすぐに確認できる体制を整える。また搭乗ゲートでは、係員の手順見直しと確認事項を強化することで、未然に防止する再発防止策を実施する。
◆続く保安検査場のトラブル
空港の保安検査場に関連した事件では、8月に新千歳空港で若い女性客1人が保安検査場の金属探知機を通過しないまま、エア・ドゥ(ADO/HD)に搭乗した事案が発生した。
同便が出発後、女が金属探知機を通過していないことが判明し、保安検査場を閉鎖。国内線全便の運航を停止し、機内や搭乗待合室など、制限エリア内にいた約1000人にのぼる全乗客がエリア外に出され、再検査を受けた。再検査のため、各社合計で欠航11便と遅延159便の計170便、2万2397人に影響が及んだ。
JCABは9月、航空各社や全国の空港管理者などに対し、保安検査場でのすり抜けへの再発防止策を指示。国交省は「不正入場などにより生じる旅客の再検査、航空便の欠航や遅延などの損害は、賠償請求の対象となり得る。発見次第、警察に通報する」としている。
◆続くANAのトラブル
ANAは2016年に入り、トラブルが頻発している。8月25日には、787に搭載されている英ロールス・ロイス(RR)社製エンジン「トレント1000」内にある中圧タービンのニッケル合金製タービンブレードで破断するトラブルを公表。2月以降、国際線で2件発生後、国内線でも1件起きた。
これにより787で運航する国内線計18便が欠航した。
また8月12日には、手荷物搬送装置の不具合により、羽田発便の一部で利用客の受託手荷物を搭載しないまま出発する事案も発生している。
3月22日朝には国内線予約システム「エイブル」で障害が発生。復旧までに約12時間要した。ANAの国内線だけで146便が欠航し、約1万8200人に影響が出た。遅延便も391便にのぼり、約5万3700人に影響が及んだ。
Yusuke KOHASE
福岡空港で先月30日、全日空機に搭乗しようとした男性客が、保安検査場での搭乗手続きで正しいバーコードをかざさずに検査場を通過し、同機が定員超過のまま移動を開始していたことが国土交通省への取材でわかった。
客室乗務員が異変に気付き、離陸はしなかった。8月にも北海道・新千歳空港で検査場のすり抜けが発生しており、同省は全日空に厳重注意して再発防止を求める方針。
同省によると、父親に続いて搭乗しようとした男性客が、端末にスマートフォンをかざした際、同じ画面に表示された父親のバーコードを誤ってかざした。端末からは「再通過」のレシートが出たが、検査員は男性を通過させたという。
男性の席はキャンセル扱いとなり、他の乗客が搭乗したため定員超過となった。駐機場を離れた際、父親が立ったままの状態だったため、引き返したという。
野球にそれほど興味がないので間違っているかもしれないが、良い選手を集めてチームを作れば必ず優勝するわけではないと言う事にしているのではないのか? 監督の能力や指導力、又は、コーチの能力やコーチの人選などで時間がかかるかも知れないが、良い選手ばかりでなくても、将来性のある選手を見抜き、育てるとか、 選手の問題を克服するサポートをするとか、長所を伸ばすとか、人選を選ぶ、チームの統率力を上げるとか、他の部分で出来る事はあると思う。
基本的な戦略や方針でも影響はあると思う。ただ、一般的に、条件がほぼ同じであれば、既に結果を出している良い選手のチームが勝つのであろう。
三菱も長い間に、このような状態となり、最近、形として、結果として問題が露呈しているだけなのではないのか?
「一民間企業の経営ミス」では済まされない
日本の防衛産業で異変が起こっている。
その一つが、昨年秋に実施された2020年に竣工予定の新型イージス艦(1番艦)の入札で本命視されていた三菱重工業がジャパンマリンユナイテッド(JMU)に敗れたのに続き、今夏に行われた2番艦(21年竣工予定)の入札でも同様に三菱重工がJMUに負けたことだ。
現在6隻就役しているイージス艦のうち5隻を三菱重工が建造している。残り1隻はIHI(石川島播磨重工業)製。JMUとは、IHI(石川島播磨重工業)、住友重機械工業、日立造船、旧日本鋼管の造船部門が統合して発足した造船会社である。
日本の防衛産業で圧倒的な存在感を誇ってきた三菱重工の凋落は、「異変」の大きな要因だ。
2015年度の防衛装備庁の「中央調達実績額」によると、三菱重工は、川崎重工に追い抜かれて2位に転落した。ちなみに川崎重工に対する調達額は2,778億円、三菱重工は1,998億円だった。防衛産業の関係者はこうもらす。
「これまでに三菱重工がトップから転落したという記憶がない。おそらく初めてのことだろう」
三菱重工はこれまで自社のプライドをかけて、コストを無視してでもイージス艦の受注を獲得してきたとされるが、経営状況がそれを許さなくなっている。
「これまでは日本の防衛産業を牽引してきたとの自負から赤字覚悟で受注してきたのを、今の経営陣が絶対に認めなくなったからではないか」(前出・関係者)
三菱重工の造船部門は火の車だ。外資から豪華客船を約1,000億円で受注したが、仕様変更を度々繰り返して基本設計に見込み以上の日数がかかったうえ、製造現場で納入直前の今年1月に不審火が3回連続で発生したため、納入が遅れた。
この客船事業では受注額約1,000億円に対して、14年3月期から16年3月期までに逐次的に特別損失を計上し、その総額は2,374億円に達した。これを受けて三菱重工では16年4月、社長直轄の事業リスク統括部を新設したほどだ。
さらに16年8月には、三菱重工はこれまで他社と提携していなかった造船事業の方針を転換、中堅の3社、今治造船、大島造船所、名村造船所と商船事業で提携する方針を発表した。中堅3社のコスト削減などのノウハウを取り込みたい考えだ。
技術力の低下も目を覆うばかりで、13年には三菱重工建造のコンテナ船がインド洋を航行中に就航からわずか5年しか経過していないのに、世界初の素材を使ったとされる船体が二つに割れて沈没する事故も起きた。
造船以外でも苦境は続く。約40年ぶりの日本独自の旅客機生産となる「MRJ(三菱リージョナルジェット)」は昨年、開発から7年を経て初飛行に成功したものの、当初計画から4年も遅れた。設計変更を繰り返しているため、18年半ばとされた納入時期もさらに延期される見通しだ。これによって受注キャンセルというリスクも浮上している。
遅延が繰り返される主な理由の一つは、部品などを仕入れる欧米の民間企業とうまく交渉できなかったため、とされる。
MRJの開発には、三菱重工の年間営業利益額に匹敵する3,000億円を超える資金が投入された。納入時期が遅れれば売上の回収も遅れ、キャッシュフローが苦しくなる。
三菱重工の凋落は、「一民間企業の経営ミス」では済まされない。三菱は戦前から日本の軍需・国防に貢献してきた企業だ。今後の日本の防衛戦略にも影響しかねない。
「三菱は国家なり」――。これは三菱財閥の祖、岩崎弥太郎が政商として国家に深く関わり、国家の発展に寄与したイメージから語られる言葉だ。
戦前に「ゼロ戦」や「戦艦武蔵」を造り、戦後もイージス艦、H2Aロケットなどを生産、つねに国家プロジェクトに貢献してきた。日米のミサイル防衛計画にも深く関与しているとされる。三菱重工の経営が悪化すれば国家プロジェクトの進捗にも大きく影響するだろう。
防衛産業の基盤強化も安全保障の一部
三菱重工に限らず、IHI、川崎重工といった防衛産業を支える企業の経営も楽ではない。一般論として、経営が苦境に陥ると、設計図面など知的財産を切り売りする傾向が出る。重工メーカーの経営が悪化すれば、日本の軍需情報が海外に漏れるリスクは高まる。
かつてIHIと川崎重工が一層の合理化を進めるために、合併計画を進めたが、それをキャッチした防衛省が計画を潰した経緯もある。
その理由は、川崎重工が中国の造船メーカーに技術供与しており、経営統合によってイージス艦「ちょうかい」を建造したIHIの設計情報が中国に漏洩するリスクがあると判断したからである。
安保法制の改正、武器輸出の拡大など、安倍政権は国会での数の力を背景に安全保障政策の変更を強硬に推し進めてきた面がある。しかし、日本の安全保障を支える自衛隊の装備を造る防衛産業の基盤をどう維持していくか、といった視点が欠けている。少なくとも筆者はそう感じている。
日本は海洋国家であり、食糧・エネルギーの輸入でも船舶は欠かせない。船の開発・建造能力が衰えれば、軍事の安全保障ではなく、「食糧・資源安保」の問題にもかかわってくるだろう。
航空機でも多額の税金を投入しながら防衛産業の基盤づくりに繋がらない愚策を防衛省は犯した。「F4」の後継として自衛隊に配備される最新のステルス戦闘機「F35」。1機あたり181億円と「F15」に比べて5割増しの世界最高級の戦闘機を米国から42機調達する。その契約手法が屈辱的とも言えるのだ。
これまでは、上流の部品生産から下流の検査までを日本側が一貫して受け持つ、ライセンス生産によって米国の戦闘機を日本側が製造していた。三菱重工が「MRJ」に取り組む要素技術は米軍機をライセンス生産することで培われてきたとも言える。
しかし、今回の「F35」は、「FMS(対外有償軍事援助)」と呼ばれる契約で購入。この契約手法は、平たく言えば、契約上の価格や納期などの諸条件を米国の都合で変更でき、契約も一方的に解除できるというもの。しかも金は前払い。いわば「不平等条約」のうえに、技術やノウハウも得られない。
もちろん「F35」は最新技術なので、同盟国日本といえども米国がそれを出し渋ることは分からないではない。だが、巨額の税金を投じる割に、それが日本の防衛産業の発展につながらないことは課題だろう。
武器輸出の拡大も、日本の防衛産業の基盤強化にはつながらないだろう。ある重工メーカー幹部はこう指摘する。
「武器輸出を積極的に推し進めて市場を拡大することで、日本メーカーの生産量が増えるので、その分防衛省向けの価格を抑制しろということでしょうが、メーカーとしては簡単には了承しづらい」
その意味は、実際、海外に武器を輸出して数量的に増えても、メンテナンス対応などを考慮すれば、そんなに利益が出るものではなく、赤字に陥るリスクもあるということだ。
最終的には入札競争で仏企業に敗れたが、オーストラリア向け潜水艦の売り込みでも、メーカーの本音は「現地対応を考えればコストに見合わない」だったようだ。しかも、入札に絡む現地の情報戦で日本側は完敗した。国益が絡む軍事ビジネスは、「平和ボケ」の日本が思うようにできるほど簡単な商売ではない、ということだ。
そもそも、オーストラリアのターンブル首相は「親中」であり、そこに日本の潜水艦を出していいのかといった議論がもっとあっていいはずだ。もし日本が入札で勝っていたら、日本の潜水艦技術がオーストラリア経由で漏れるリスクもあったであろう。
太平洋進出を目論む中国海軍は、「スターリングエンジン」などを搭載する優れた日本の潜水艦技術を分析したいと言われているのだ。防衛省内には「オーストラリアに潜水艦を売り込むのは絶対に良くない」といった意見もあったと、同省OBがいう。
やっていい武器輸出と、避けるべき武器輸出が、戦略的に判断されていないのではないか。
井上 久男
横浜市都筑区の傾斜マンションに端を発したくい打ちデータ偽装問題を受け、国土交通省が近く、建設工事の「一括下請負」(丸投げ)を禁止する新通達を出すことが8日、分かった。曖昧だった丸投げの判断基準を廃止した上で、新たな基準を示し明確化。丸投げ業者を排除し、“無責任の温床”とされる「重層下請け構造」を解消するのが狙い。建設業界団体などにも通知し、施工不良の未然防止を図る。
この問題では、元請け建設会社の「三井住友建設」からマンションのくい打ち施工を「日立ハイテクノロジーズ」が下請けし、さらに「旭化成建材」に丸投げしていたことが判明。重層下請け構造の中で責任の所在が不明確になり、施工不良やデータ偽装を招いたとされた。
このため国交省は、実質的に施工に携わらない企業の排除を徹底する必要があると判断。丸投げを明確に定めていなかった現行通達を廃止した上で、新たな通達で元請け業者と下請け業者それぞれの役割を明文化する。具体的には、元請け業者に対し、工事全体の施工計画や進捗(しんちょく)・品質管理、下請け業者への技術指導、発注者との調整協議などを義務づける。一方で、下請け業者にも担当工事の管理や元請け業者への報告、2次下請け業者の指導などの役割を課す。
丸投げは、施工不良だけでなく、中間搾取や労働条件の悪化も招くことから建設業法で禁止されている。違反した場合、営業停止などの行政処分を受ける。新通達について国交省幹部は「商社的な存在の業者が請負契約に入れないようにするのが狙い」と説明する。
国交省はこれまで、くい打ち施工のルール整備や民間工事の請負契約の適正化など再発防止策を講じてきた。新通達は建設業界団体、地方公共団体などにも通知する方針だ。
会社が消滅するまで変わらないだろう。人によっては会社が消滅しても、消滅した会社を「うちの会社」と呼び、 消滅した会社を比較対象の基準とする。簡単には思考や基準は変えられないと言う事であろう。
滋賀県湖南市の社会福祉協議会の女性職員が、認知症などの利用者の口座から、約200万円を不正に引き出していたことがわかりました。
湖南市の社会福祉協議会は、去年1月から先月にかけて、認知症や知的障害のある利用者5人の口座から、合わせて約200万円が不正に引き出されていたことを明らかにしました。
この口座を管理していた生活支援員を務める40代の女性職員は、金を不正に引き出したことを認めていますが、ほとんど返していないということです。
【湖南市社会福祉協議会 谷口三彦事務局長】
「管理体制の意識が低かったとは思います。通帳と印鑑の両方を預かりながら、本人が触れたので」
社会福祉協議会は女性職員にかわって金を返す方針で、警察への刑事告訴も検討しているということです。
会社が消滅するまで変わらないだろう。人によっては会社が消滅しても、消滅した会社を「うちの会社」と呼び、 消滅した会社を比較対象の基準とする。簡単には思考や基準は変えられないと言う事であろう。
血液製剤を不正に製造していたとして業務停止処分を受けたばかりの製薬メーカー「化血研」に対し、厚生労働省が4日午後、新たな行政処分を行うことが分かりました。
熊本市の製薬メーカー「化血研」をめぐっては、40年前から、国の承認とは異なる方法で血液製剤を製造していたうえ隠蔽していたとして、厚労省は今年1月、過去最長となる110日間の業務停止命令を出しました。
化血研はその後、製造を再開しましたが、厚労省が先月、医薬品医療機器法に基づいて、抜き打ちで立ち入り検査をした結果、問題が見つかったということです。そのため、厚生労働省は4日午後、化血研に対し新たな行政処分を行う方針を固めました。
化血研は先月、存続を目指す方針を厚労省に伝えましたが、塩崎厚生労働大臣は事業を他の企業に譲渡するよう求めています。
宮城県白石市に作画スタジオがあるアニメ制作会社「旭プロダクション」(東京都練馬区)が、東日本大震災の緊急雇用創出事業を利用して雇った従業員を別会社に派遣し、アニメ制作とは無関係の農作業に従事させていたことが1日、分かった。事業を委託した宮城県と白石市は、同社が人件費の一部を不正受給した疑いがあるとみて調査している。
県によると、旭プロは2012年11月~今年3月、県が発注した「アニメむすび丸」の制作などを計約8610万円で受注。県内在住の男女39人をアニメ制作名目で雇った。
ところが、同社は少なくとも10人を10日間、宮城県蔵王町の農業生産法人「GFC」に派遣し、アニメ制作とは無関係の農作物の収穫に当たらせた。GFCの男性社長は旭プロの役員を兼務しており、GFCは旭プロの事実上の子会社とみられる。
白石市も旭プロに国の緊急雇用創出事業を活用したアニメやフリーペーパー制作などの事業を委託。同社は12年12月~15年1月、17人を雇ったが、少なくとも5人が1週間、GFCへ派遣されたという。
県と白石市は今年2月、「(旭プロが)不適切な労働者派遣をして、目的外の業務に当たらせている」との情報提供を受け、調査に着手。旭プロは県や市の調べに、従業員の一部をGFCに派遣し、農作業に従事させた事実を認めたという。GFCは県と市の調査後の今年3月末に事業所を閉鎖した。
県と白石市はGFCへ派遣された人数や回数が現時点の調査より増え、不適正な人件費の受給額はさらに膨らむ可能性があるとみている。
旭プロは河北新報社の取材に「県が調査中であり、コメントは控えたい」と話した。
[旭プロダクション] 1973年設立。人気漫画「ワンピース」のアニメ映画や「ジョジョの奇妙な冒険」のアニメ制作などの実績がある。本社は東京都練馬区。2010年4月、白石市の市情報センター「アテネ」内に宮城白石スタジオを開設した。
約40年にわたり、血液製剤などを国の承認と異なる方法で製造していた「化学及血清療法研究所」(化血研、熊本市)をめぐる問題が、再び熱を帯び始めている。今年1月以降、事業譲渡を念頭に「体制の抜本的見直し」を求めてきた厚生労働省に対し、化血研側が今になって事業の存続希望を伝達したからだ。これに対し、塩崎恭久厚労相が記者会見で不快感をあらわに再考を促す事態に発展している。関係者の証言からは「患者のため」という言葉を錦の御旗に、存続を模索する姿勢も見え隠れする。(伊藤弘一郎)
■「『指導』を継続」
「何をされて、このような事態になっているか。胸に手を当てて、考えていただいた方がいい」
今月6日、厚労省で行われた閣議後会見。普段は淡々とした口調で話す塩崎厚労相が色をなし、語気を強めた。同日、一部で報じられた化血研側の「事業存続の意向」に質問が及んだ際のことだ。
塩崎氏は続けた。「化血研としての医薬品製造販売業の継続を前提としない見直しを、当初から求めてきた。もう一回、思い出していただき、その通りやっていただくことが大事だ。私どもも指導を継続する」
厚労省には、一企業に事業譲渡や合併などを命じる法的権限はない。ただ、塩崎氏は言葉の端々に「存続は絶対に認めない」という強い意思をにじませた。
■会合翌日に検査
関係者によると、事の発端は今月5日。
化血研側は不正製造問題を受け、製薬大手のアステラス製薬と、ワクチンや血液製剤の事業譲渡交渉を続けてきた。この日は都内で、厚労省と化血研担当者が会合を持った。進捗状況などの確認で行われたものだが、その場で化血研側が「事業継続を目指したい」との意向を厚労省幹部に伝えたという。
厚労省は塩崎氏の発言にとどまらず、すぐさま手を打った。
閣議後会見が行われたのと同じ6日。化血研本社に、厚労省担当者数人が訪れ、医薬品医療機器法に基づく「抜き打ち」の立ち入り検査を実施したのだ。
そもそも、この抜き打ち検査は化血研の不正製造問題で「事前通告して立ち入りを行っていたことが不正を見過ごす原因となった」と指摘され、厚労省が新たに運用を始めたもの。厚労省は抜き打ち検査について「会合内容とは無関係」(同省担当者)とするが、額面通り受け止める人は少ない。
ある製薬業界関係者は「『わかってるのか』という厚労省の“意趣返し”だろう。化血研としては熊本地震で設備が損傷し、資産算定などが難航したこともあるが、『血液製剤などを安定供給できるのはウチだけ』というプライドが、また顔をのぞかせているのかもしれない」と推測する。
■不信感払拭できず
化血研は不正製造問題で1月、厚労省から過去最長となる110日間の業務停止命令を受けた。その後、理事長ら経営陣を一新。事業譲渡をはじめとした改革の緒についたはずだった。
ただ、全国薬害被害者団体連絡協議会代表世話人の花井十伍(じゅうご)さんは今回、表面化した事業継続意向は「少なくとも8月時点で念頭にあったのではいか」とみる。
薬害HIV訴訟の被告企業の1つでもある化血研は同月、理事長らが花井さんら薬害被害者団体と面談。化血研側は、改めて不正製造を謝罪した上で「患者を第一に考え、(HIV訴訟で和解した)3月29日を毎年、社内で反省をする日として、今後もずっとやっていきたい」と話した。花井さんが「事業譲渡するのではないのか」と問うと言葉を濁したという。
花井さんは言う。「言葉では『患者が第一』というが、事業存続のため、患者や被害者を味方に付けようとしているだけではなのか。第一に考えているのはやはり社員であり、地元・熊本のことなのだろう。不信感は全く払拭されていない」。
化血研は、塩崎氏や花井さんの言葉をどう受け止めるか。取材に広報担当者は「今はコメントすることはない」としているが、関係者は「胸に手を当てた」結果を注視している。
独立行政法人「日本スポーツ振興センター」(JSC)が内部の規則に反し、2019年に日本で開催されるラグビー・ワールドカップの大会組織委員会に対し、約1年半にわたって無償で本部事務所の事務室などを利用させていたことが、会計検査院の調べでわかった。
検査院は、賃料や水道光熱費として約500万円が徴収されておらず、「不当」と指摘する方針。
関係者によると、JSCは14年9月~16年3月、管理・運営する秩父宮ラグビー場(東京都港区)の敷地内にある本部事務所の事務室など3部屋、計約120平方メートルを、契約を結ばずに組織委に無償で利用させていた。JSCの内部規則では、施設を他の団体に貸す場合は、特別な事情がない限り、賃貸契約を結ぶと定めている。
損害賠償請求訴訟を起こし、勝ったとしても相手に支払い能力がなければ、刑事事件として刑事告発するのか?
8600万円を簡単に返済出来るほど設備保全担当者の給料は良いのか、取引先事業者にも返済させるのか?
日新製鋼は4日、呉製鉄所(広島県呉市)での補修設備工事をめぐり、同社の設備保全担当者と取引先事業者が共謀し、実体のない補修工事などによって、日新製鋼に8600万円の損害を与える不正行為があったと発表した。同社は関係者に対し損害賠償請求訴訟を起こすほか、関係した従業員には厳正な社内処分を実施するとしている。
平成24年2月から26年11月にかけて、取引先事業者2社が、現場担当者の口頭確認だけですむ夜間や突発の工事で、実体のないものや、水増しした案件など計数百件を不正に請求した。同時に、これらの工事の現場での決済権限を持つ日新製鋼と100%子会社である日新工機(広島県呉市)の設備担当者に、接待や数万円の現金、旅行費用の肩代わりなどの金品授受によって、不正請求を認めさせていたという。内部告発によって発覚し、その後の調査で、不正の実体が明らかになった。刑事告発についても検討している。
同社はすでに夜間や突発の工事でも、すべて書面で確認し、設備保全部門の監督者が決済する体制に切り替え、再発防止を図るとしている。過去の財務諸表や29年3月期業績予想に与える影響はないという。
NHK静岡放送局の副局長が、去年12月に静岡市内で自転車を盗んだとして窃盗の疑いで警察に逮捕された。
逮捕されたのは、NHK静岡放送局の副局長・小林達彦容疑者(53)。警察によると小林容疑者は去年12月中旬、静岡市葵区の歩道にとめてあった高校生の自転車を盗んだ疑いがもたれている。
今月、パトロール中の警察官が小林容疑者の自宅付近で自転車を発見し、小林容疑者に話を聞くと「捨てられていたのを拾った」と話していたという。以降も任意の事情聴取を受けていたが、22日夜、警察署に出頭し自供したため逮捕となった。小林容疑者は泥よけカバーにあった生徒の名前や高校のステッカーをテープで隠し、通勤などで使い続けていたという。
NHKでは「事実関係を調べた上で厳正に対処します」とコメントしている。
教え子の男子生徒にわいせつな行為をしたとして、滋賀県青少年健全育成条例違反の疑いで、立命館守山高(守山市)の元教諭の男(29)=神戸市中央区港島中町6丁目=が逮捕された事件で、同高の副校長が被害者の母親に、警察に通報しないよう口止めを依頼するメールを送っていたことが20日、京都新聞の取材で分かった。
メールは被害者が5月に警察に事件を届け出た翌日に、母親の携帯電話に送信された。元教諭が学校法人からの処罰を受けることを示し、「警察事案となれば更(さら)に彼(元教諭)の将来の道もたたれます。彼のことを想(おも)うなら警察は避けるべきです」と書かれていた。
母親は「謝罪の言葉もなければ、文面も非常に上から目線で腹が立つ。事件を隠そうとする学校の態度は許せない」と話している。
元教諭は3月28日から4月2日の間、当時住んでいた草津市の自宅で2回にわたり、18歳未満であることを知りながら男子高校生=当時17歳=の下半身を触るなどした疑いで20日、大津署に逮捕された。学校関係者によると、元教諭は事件発覚後、5月下旬に高校を依願退職したという。
立命館守山高を運営する学校法人立命館(京都市中京区)は取材に対し「個別的なことは答えられないが、こちらが知っている情報は警察に協力して渡しており、捜査の推移を見守りたい」とコメントした。
東芝の不正会計問題で、証券取引等監視委員会が、田中久雄元社長ら歴代3社長が粉飾を認識していた疑いが濃厚だとする調査結果をまとめ、検察当局に伝えたことが19日、証券業界関係者への取材で分かった。監視委は今後、3人の刑事告発に向けた調査を本格化させるもようだ。7月に刑事訴追に否定的な見解を示した検察には、正式な告発協議を求めるとみられる。
監視委によると、東芝はパソコン事業で、部品の調達価格が外部に漏れないよう一定金額を上乗せした価格で台湾の製造委託先に販売し、その分を上乗せした価格で完成品を買い取る「Buy(バイ)-Sell(セル)取引」を悪用。四半期ごとの決算期末に大量の部品を販売することで、一時的に得られる上乗せ分を利益として計上していた。監視委はこの利益計上が粉飾に当たるとして、田中元社長と西田厚聡(あつとし)、佐々木則夫両元社長の3人について、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)罪での告発に向け、調査を進めてきた。
証券業界関係者によると、パソコン事業では佐々木社長時代の平成21年以降、バイセル取引の悪用によって得られる一時的な利益を見込んだ予算を作成していた。予算は各事業部門ごとに作成していたが、パソコン事業だけは会長だった西田元社長と佐々木、田中両元社長が主導して作っていたという。
昨年、外部の弁護士らで構成する東芝の第三者委員会の調査に対し、3人はいずれも不正会計の指示や認識を否定したが、監視委は予算作成を主導していたことから粉飾を認識していた疑いが濃厚だと判断。関係証拠とともに調査結果を検察当局に伝えた。
監視委が告発する場合、検察と「告発問題協議会」を開くが、事前の情報交換で検察が刑事訴追する方針を固めた場合に限られるのが通例。今回は検察が7月に「証拠上、疑問点が多く、立件は困難」との見解を監視委に伝えており、開かれない見通しだったが、監視委は「新たな証拠が加わった」として開催を求めるとみられる。
東京都の築地市場(中央区)が移転する予定の豊洲市場(江東区)の主要建物3棟の建設工事で、1回目の入札不調後、都当局が入札予定の大手ゼネコン側にヒアリングを行い、積算を事実上聞いていたことが、都幹部や受注ゼネコン幹部の証言で分かった。その後の再入札で3棟工事の予定価格が計407億円増額され、いずれも予定価格の99%超で落札された。
また、受注ゼネコン幹部は「再入札前に予定価格を引き上げるから落札してほしいと都側からヒアリングとは別ルートで要請があり受け入れた、と社内で説明を受けた」とも証言した。都幹部はこうした要請を否定している。
都とゼネコン側のなれ合いの中で建設費がつり上がっていた可能性が浮かび、小池百合子都知事が発足させた「市場問題プロジェクトチーム」の調査でも解明のポイントとなりそうだ。
結果が病院の本気度を示すであろう。
腹腔鏡や開腹手術を受けた患者が相次いで死亡し、高度医療を提供する「特定機能病院」の承認が取り消された群馬大医学部附属病院(前橋市)について、一連の問題の影響による補助金や収入の減少が2014~15年度で10億円超と推定されることが15日、会計検査院の調べで分かった。信頼回復に向け、病院は安全管理体制の強化など改革を急いでいる。
検査院は「医療事故は信頼を傷つけ、経営や機能に影響を与える」として、各大学病院に安全管理態勢の充実を求めた。
検査院によると、群馬大病院は15年6月に特定機能病院の承認を取り消され、診療報酬基準が変わって入院基本料などが下がった。承認取り消し以降の患者数に基づいて試算すると約2億4400万円の減収。がん診療連携拠点病院の指定が更新されなかったことによる15年度の減収も約8600万円と試算された。また、補助金は約7億2700万円分の申請を実際に取り下げた。
病院の統計によると、患者数は近年ほぼ右肩上がりで増えていたが、問題が明らかになった14年度、入院患者は微増にとどまり、外来患者は減少に転じた。15年度の延べ患者数は13年度と比べ入院患者で約6800人、外来患者は約2万6千人少なかった。
群馬大は「患者数減は医療事故の影響もあると考えている。影響額も非常に重く真摯(しんし)に受け止めている」としている。
問題の影響を重く見た県は本年度、群馬大病院をがん診療の「中核病院」に独自に指定。群馬大病院が、がん診療連携拠点病院の国指定を外れた影響で、地域の医療機関が受けられなくなっていた診療報酬加算が一部復活した。5月には群馬大と医療安全体制の構築や信頼回復の方法を話し合う協議会を設置し、特定機能病院の再承認を目指している。
群馬大病院の問題を踏まえて検査院は、今年3月末時点で特定機能病院である41国立大学病院(群馬大病院を除く)の死亡事案の報告・検証態勢も調査。8病院では一部死亡事案を医療安全管理部門に報告しておらず、3病院は死亡事案を報告していたものの、原因の検証は一部にとどまっていた。これらの11大学は取材に対し、態勢を整備したり準備したりしていると回答した。
三菱自動車が燃費データの不正発覚後、社内で行った燃費の再測定について、担当者が不正を認識しながら測定を続けていたことが15日、国土交通省の立ち入り検査の結果報告でわかった。
不正は対象の9車種のうち8車種に及び、国交省は「常軌を逸する事態」として厳しく指弾した。三菱自の企業体質が改めて問われている。
三菱自は今年4月に軽4車種の燃費不正が発覚後、販売中だった別の9車種について社内で燃費値の再測定を実施した。しかし、結果が国が測定した燃費値とかけ離れていたため、今月2日、国交省が三菱自本社などに立ち入り検査をしていた。
国交省の検査結果によると、三菱自は不正発覚後、国の審査機関から燃費測定に必要なデータの測定法について改めて説明を受けていた。しかし、現場担当者は国の測定法と異なることを知りつつ、良い燃費が出るデータを意図的に選んでいた。さらに、燃費に有利なデータを自動的に選ぶプログラムを使用し続けていた。
「厳密に言えば違法ではない」のであれば問題はないと考えるのが、国際的なスタンダード。違法でない限り、合法。外国人は規則や基準で判断する。外国人と議論してみると良い。 違法でないのにどこが悪いのかと根拠を求められる可能性が高い。国交省は法令を改正するべきである。この件に関しては、法令を改正しない日本国にも責任があると思う。
[東京 2日 ロイター] - 国土交通省は、三菱自動車<7211.T>の燃費不正問題に絡み販売中の8車種の燃費で都合の良い試験データを抜き出していたことが判明したのを受け、同社の本社(東京都港区)と名古屋製作所(愛知県岡崎市)に2日午前9時から立ち入り検査を実施した。石井啓一国土交通相が同日の閣議後会見で明らかにした。
問題発覚以降、同社への立ち入り検査は3回目で、経営陣や担当者への聞き取りを行う。石井国交相は「経緯を徹底的に調査する」と述べた。
同省によると、本来は往復3回ずつの走行で得たデータの平均値を取るべきところ、最大60回の往復を繰り返し、都合の良いデータを使って算出していた。石井国交相は「データの平均値を取るのが通常の考え方だが、三菱自はいいとこ取りをしている」と指摘。法令ではどの数値を取るのかまでは規定されておらず、「厳密に言えば違法ではないが、常識的に言って極めて不適切」と語った。
燃費算出に必要な路面との摩擦や空気抵抗を示すデータの測定方法については、同省は燃費審査基準全体の見直しの一環として、データのばらつきを抑える趣旨がより明確にされた新たなルールを2018年10月に導入することを予定していた。ただ、石井国交相は今回の事案を受けて、新ルール導入時期の前倒しを検討することも明らかにした。国内外の自動車メーカーにも1日、燃費測定で不正を行わないよう文書で指示したという。
三菱自は4月20日に発覚した軽自動車4車種での燃費不正を受けて、独自に燃費を再測定。その結果、販売中の8車種についても燃費とカタログ値との乖離(かいり)は問題ない範囲だったとして販売を続けてきた。しかし、同省の再測定ではいずれも燃費がカタログ値との差が最大で8.8%、平均で4.2%あったため、国が燃費値の修正と対象車種の販売を一時自粛するよう要請し、三菱自は2週間程度、販売の一時中止を決めた。
*内容を追加しました。
(白木真紀)
長野県の佐久浅間農協は10日、顧客の定期貯金など4700万円余りを着服したとして、40代の女性職員を懲戒解雇したと発表した。
業務上横領容疑で刑事告訴する方針。
同農協によると、職員は2007年5月から今年6月、佐久町中央支所と野沢支所で通帳と申込書を偽造し、定期貯金を解約するなどして、顧客23人から計48件、総額約4708万円を着服した。
顧客が6月に定期貯金の確認を依頼し発覚。職員は「生活費に充てた」と話し、主にクレジットカードの決済に使っていた。被害は全額弁済した。
ジブラルタ生命保険は8日、秋田支社の男性社員(56)が、秋田県内に住む男女26人に架空の保険契約を結ばせて、現金約1億9000万円をだまし取っていたと発表した。
同社によると、男性社員は営業担当だった2009年頃から16年8月にかけて、保険料の名目で現金をだまし取っていた。実際には保険に加入せず、被害者には偽造した保険証券を手渡していた。同社は警察への告発を検討している。
8月に被害者から同社のコールセンターに保険の内容を問い合わせる連絡があり、発覚。男性社員は「借金の返済や生活費の足しにした」と話しているという。
同社はほかにも被害がないか、確認作業を進めている。問い合わせは同社コールセンター(0120・981・088)へ。
[ワシントン 6日 ロイター] - 独フォルクスワーゲン(VW)<VOWG_p.DE>の排ガス不正問題で、VW車所有者の弁護団は、独自動車部品メーカーのボッシュ[ROBG.UL]がVWによる不正なソフトウエアの利用を隠ぺいしていたと主張した。2日にサンフランシスコ連邦地裁に提出した書類で明らかになった。
弁護団は8月、ボッシュがVWの排ガス不正を「認識し、積極的に関与していた」と訴えており、今回はその主張に肉付けしたもの。ボッシュ側は同月、根拠のない主張だと反論している。
新たな提出書類で弁護団は、ボッシュが「違法な不正装置についての知識を米当局に一切公表しなかった」と指摘した。
また、ボッシュが2008年、同社が設計したソフトウエアの使用に関して法的な問題が生じた場合、同社を免責とするようVWに要求していたことを、当時の電子メールを引き合いに明らかにしている。
ボッシュはVWにソフトウエアと部品を納入したが、ソフトをどう使うかは自動車会社に責任があるとの立場を先に表明した。
米国のボッシュの広報とVWはコメント要請に答えなかった。
東京都足立区にある足立西郵便局が、配達物として特定の業者から受注したダイレクトメール(DM)の数を実際より少なく見積もり、不正な値引き契約を結んでいた。郵便局を統括する日本郵便(東京都千代田区)の内部調査で明らかになった。局幹部が不正への関与を大筋で認めているといい、日本郵便は刑事告訴を検討している。
郵便関係者によると、値引きされていたのは、都内の発送代行業者から請け負ったDMが中心で、手紙やはがきなどの「郵便物」と重さ3キロまでの印刷物などを送る「ゆうメール」。持ち込まれたDMの数量を実際より少なく見積もることで、業者の支払う額を不当に低く抑えていたという。郵便物については、勝手に値引きできないよう郵便法で定められている。
この業者からは、ここ数年間で約20億円分の配達業務を受注しており、不正な値引きにより日本郵便に億単位の損害を与えた可能性もある。
遥か昔のことのようにも感じるが、三菱自動車工業(三菱自工)の燃費データ改竄が発覚したのはわずか4カ月ほど前のことだ。この不祥事に対して、三菱自工の益子(ますこ)修会長兼社長(67)は社是でもある“お客様第一”を掲げてユーザーへの補償を約束している。だが、補償は遅々として進まず、親会社になる日産自動車の顔色を窺うのに忙しい様子なのだ。
〈当社製車両の燃費試験における不正行為の内容に関するご報告〉
こんなタイトルの手紙が、三菱自工のユーザーに届き始めたのは8月初頭のことだった。差出人は三菱自工の益子会長兼社長で、A4二枚に不正を行った経緯と謝罪が綴られていた。全国紙の経済部デスクによれば、
「三菱自工は、『eKワゴン』や日産自動車向けに製造した『デイズ』など軽自動車4車種のユーザーに10万円、製造年度により小型車『コルトプラス』など5車種の所有者には3万円を補償すると発表しました。益子さんは支払内容を記した書類を顧客に郵送し、8月から支払いを開始すると明言しています」
だが、三菱車を所有する都内在住の40代女性はこう憤る。
「うちの車はコルトプラスですが、お盆を過ぎても自宅には支払いに関する書類は届いていません。ディーラーに問い合わせても、“補償に関してはメーカーから何の説明もありませんし、我々も新聞報道などで知る程度。ですから、お客様が購入した車種が支払い対象車なのかはお答えできません。そもそも三菱自工とは別会社ですから、うちに聞かれても困ります”と言われてしまいました」
そのディーラーは、「関東三菱自動車販売」。三菱自工の100%子会社で、国内販売部門トップの服部俊彦取締役がかつて社長を務めていた。
■ユーザーより親会社
益子会長兼社長の掲げる“お客様第一”は、ディーラーには十分に浸透していないようだが、三菱自工本体はどうか。
「ウソだと言われても仕方がないでしょう」
こう語るのは、自動車専門誌の記者だ。
「日産自動車の関連会社で、『日産東京販売ホールディングス』という一部上場企業があります。三菱自工製の軽自動車『デイズ』なども販売していたので、燃料データ改竄が原因で販売停止に追い込まれました」
自動車業界では、日産東京販売HDの今期4月~6月の第1四半期決算は苦戦が予想されていたが、
「蓋を開けてみると、純利益は1億7600万円で前年同期比5100万円増。純利益を底上げした特別利益3億3900万円が、三菱自工からの補償金だったのです」(同)
日産自動車が、2370億円で三菱自工株34%を取得して“子会社化”を発表したのは5月12日で、三菱自工の日産東京販売HDへの補償金支払いは遅くとも6月末。つまり、益子会長兼社長は、ユーザーよりも親会社のディーラーを優先したことになるのだ。
そこで三菱自工の広報部に話を聞くと、
「関東三菱自動車販売の対応は我々が指示したものではありません。ですが、お客様にご不快な思いをさせたのなら、それはすべて三菱自工の責任です」
で、“日産”に優先して補償したことは、
「悪意を持って作為的に行ったわけではなく、手続き上の問題。“お客様第一”が言葉ばかりで実がないとのご指摘があれば、その通りかもしれません。真摯に反省致します」
益子会長兼社長の手紙はこんな一文で結ばれている。〈今後とも、三菱自動車をご愛顧賜りますよう、何卒お願い申し上げます〉。
「週刊新潮」2016年9月1日号 掲載
8月25日夕刻、関東信越厚生局麻薬取締部が俳優の庄司哲郎(49)を覚せい剤取締法違反(所持)容疑で逮捕した。この庄司を金銭的に支援していたのが、フジテレビの情報番組「とくダネ!」のキャスター・小倉智昭(69)であることが「週刊文春」の取材により明らかになった。
庄司は逮捕当日の昼頃も、お台場で「とくダネ!」の放送を終えた小倉と食事をし、少なくない額の金を受け取っていた。庄司は、かつては小倉と同じオーケープロダクションに籍を置いていた。
「庄司は小倉さんに向けて『俺に頼れるのは兄貴しかいないんです』といった文面のメールを送っていました。要は金をせびっていたわけです」(庄司の知人)
小倉の事務所に事実確認を求めたところ、小倉本人はインタビューに応じなかったものの、資金援助の事実を認めた。庄司は薬物常習者だった可能性が高く、結果的に小倉からもらった金で薬物を購入していたとも考えられる。
詳しくは9月1日(木)発売の「週刊文春」で報じる。
<週刊文春2016年9月8日号『スクープ速報』より>
虚偽の記載でないかぎり、ブラッドオレンジ果汁の成分やデータは提出されていると思う。成分やデータをチェックせずに 契約したのであればキリンの管理体制が甘いと言う事になる。
キリンビールは、来月20日に予定していた「キリン氷結ハロウィンオレンジ」の発売を中止すると発表しました。「氷結」はウォッカベースの酎ハイで、果物のストレート果汁を使用していることを商品の特徴としています。しかし、今回の商品の原料としてイタリアから輸入したブラッドオレンジ果汁に水が加えられている可能性が高く、「ストレート果汁」として使用できないと判断したということです。.
下記の人は同一人物?それとも別人?「美健ファーマシー」の情報が少ないので確認できない。
中国人観光客向けに処方箋が必要な医療用医薬品を横流ししたとして、警視庁が、医薬品卸売会社「美健ファーマシー」(東京都千代田区)の社長や医師の男ら計4人を、医薬品医療機器法違反容疑で逮捕したことが、捜査関係者への取材でわかった。
中国人ブローカーの自宅からは2万6000点を超える医薬品が押収されており、同庁は、同社が大量の薬品を組織的に横流ししていたとみている。
捜査関係者によると、逮捕されたのは同社社長の財間英信容疑者(49)のほか、40歳代の社員と60歳代の仲介役、40歳代の医師のいずれも男計3人。社員の男が、インターネットの掲示板を通じて中国人ブローカーと知り合い、財間容疑者に紹介したのがきっかけだったという。
「同省航空保安対策室などによると、5日昼、女性客が保安検査場で搭乗券の代わりにスマートフォンの画面を機械にかざしたが、反応しなかったため、検査員は女性客に待機してもらい、航空会社の案内係に対応を頼んだという。だが案内係はほかの客の対応中で、検査員も検査業務に戻ったため、女性客は数分間、空港職員の目に触れない状態だった。」
セキュリティーに関して不備だと思う。引継ぎの確認が出来ていない。案内係に対応を頼んでも、実際には女性客のところに来た事を確認していない。
セキュリティーが求められない状況では、接客としてはこれで問題ないと思う。ただ、案内係が客を必要以上に待たすのであれば、サービスとしては
不備と考える事も出来る。
「同省は女性客がその間に探知機横をすり抜けたとみており、全国の空港に対し、検査場での監視体制の強化を指示した。」
具体的な指示を出すとか、抜打ちで監視体制をチェックするとかしないと、実際には問題は発見、及び解決されないと思う。
新千歳空港の保安検査場で5日、女性客が金属探知機を通らずに保安区域(搭乗待合室)に入ったトラブルで、機械で搭乗券が読み取れなかった女性客に対して、警備会社の検査員や航空会社の案内係が数分間にわたり目を離し、別の業務をしていたことが9日、国土交通省などへの取材で分かった。同省は女性客がその間に探知機横をすり抜けたとみており、全国の空港に対し、検査場での監視体制の強化を指示した。
同省航空保安対策室などによると、5日昼、女性客が保安検査場で搭乗券の代わりにスマートフォンの画面を機械にかざしたが、反応しなかったため、検査員は女性客に待機してもらい、航空会社の案内係に対応を頼んだという。だが案内係はほかの客の対応中で、検査員も検査業務に戻ったため、女性客は数分間、空港職員の目に触れない状態だった。
案内係が到着した際には女性客はおらず、防犯カメラで探知機横の通路をすり抜けていたことが判明。女性客は既にAIRDO(エア・ドゥ)の羽田便に搭乗し、出発していたという。同社はその後、搭乗券の購入記録などから女性客を特定した。
関係者によると、女性客は電話での聞き取りに対し、「出発時間が迫っていて焦ってしまった。どう保安区域内に入ったかは覚えていない」などと話しているという。
国交省のセキュリティー関する規則や監査がどうなっているのが現状を知らないが、甘いと判断できる。
「職員が対応を検討するため目を離した隙に、女性は金属探知機横の通路を通って中に侵入。」
「目を離した隙」とは持ち場から離れた言うことでは?そうだとすれば、セキュリティーの点でいえば、持ち場を離れなければならないのであれば、
トランシーバー等で代わりのスタッフを呼ぶべき。これは一般的にはマニュアルに記載されているのでは?もし記載されていないのであれば、
同省新千歳空港事務所の管理及び監督に問題があると思う。もしマニュアルに記載されているのであれば、スタッフに対する教育不足及び訓練不足。
ただ、「新千歳空港の国内線保安検査場で、乗客の女性が金属探知機を通らず搭乗待合室に侵入したトラブルを受けて、国土交通省は、探知機横の通路にチェーンを張り、
通り抜けを防ぐように全国の空港に指示した。」となっているので、マニュアルには記載されていない可能性が高い。通り抜け防止にチェーンをしても、
乗り越えられるような程度では、同じような状況で通り抜けたければ、通り抜けは可能。
「通路は幅約1メートルで、本来は車いすや心臓ペースメーカーを装着している人が通るスペースとなっていた。」はセキュリティーに関係ない。
「目を離した隙(持ち場を離れるとき)」の対応を考えなければならない。まあ、国交省のセキュリティーに関する規則は甘いので、実際にテロなどで
犠牲者が出ない限り改正されることはないであろう。
新千歳空港の国内線保安検査場で、乗客の女性が金属探知機を通らず搭乗待合室に侵入したトラブルを受けて、国土交通省は、探知機横の通路にチェーンを張り、通り抜けを防ぐように全国の空港に指示した。
同省新千歳空港事務所は、搭乗確認がないまま乗客の手荷物検査が行われた点についても問題とし、検証を進めている。
同事務所によると、女性は5日午後0時15分頃、検査場で搭乗券のQRコードを読み取らせた際、エラーが出た。職員が対応を検討するため目を離した隙に、女性は金属探知機横の通路を通って中に侵入。手荷物検査の済んだ自分の荷物を持って、午後0時28分発のエア・ドゥ羽田便に乗った。
通路は幅約1メートルで、本来は車いすや心臓ペースメーカーを装着している人が通るスペースとなっていた。
北海道の新千歳空港で女性客が保安検査場をすり抜けた問題で、女性客はそのまま旅客機に搭乗して目的地で降りていたことが分かった。ネット上では、警備の不手際を指摘する声とともに、この女性客も罪に問われるべきだとの声が上がっている。
「本人は予定通りの便に乗っていたなんて信じられない」「簡単にテロも起こせると世界に知らしめてしまった」
検査やり直しで、2万人に影響の大混乱に
問題の女性客を空港が逃してしまったことが報じられると、ニュースのコメント欄などには、こんな厳しい指摘が次々に寄せられた。2020年の東京五輪が近づく中で、こんな緩い警備で大丈夫なのかと心配する声も出ている。
各メディアの報道によると、20代ぐらいの女性客は2016年8月5日正午過ぎ、手荷物を調べる国内線の保安検査場でスマートフォン画面の搭乗券を見せ、空港の警備員がQRコードを読み取ろうとしたがエラーが出た。女性客は、「必要があるのか」と警備員に詰め寄り、警備員が担当者に相談しようと現場を離れたすきに、女性は検査場をすり抜けて搭乗待合室に向かった。
その様子は、防犯カメラの映像に残っており、金属探知機の横にある車いす用レーンを通ったとの報道もある。女性客は、男性客と一緒だったといい、その約10分後に出発するエア・ドゥの羽田空港行きの便に乗ろうと急いでいたらしい。
搭乗口では、女性客は、「搭乗券をなくした」と係員に話し、本人確認ができたことからそのまま通されていた。
空港ではその後、保安検査がやり直しとなり、約1000人が検査場外に出されて待つ事態になった。夏休み期間ともあって長蛇の列ができ、疲れでぐったりする人も多かったという。この影響で、計11便が欠航したほか、計159便に最大で約3時間の遅れが出て、約2万人に影響した。
過去には、建造物侵入で逮捕されたケースが
空港職員が女性客を見失ってからは、捜すのに時間がかかるなどして、国交省の空港事務所に連絡するまで約30分かかった。このため、女性客は、検査やり直しのときはすでに新千歳空港を発ってしまっていた。羽田への連絡も遅れて、女性客はすでに降りており、後の祭りだった。
この女性客は、空港で大混乱を起こし、航空会社に損害を与えており、今後何らかの罪に問われることはないのか。
過去に保安検査場をすり抜けたケースとしては、香川県の高松空港で2007年7月、37歳の男が空港警備員の声掛けを無視して搭乗待合室に入ったことがある。搭乗口でも係員の制止を無視して通り抜け、旅客機の座席にいるところを建造物侵入の現行犯で駆け付けた警察官に逮捕されている。
このときは、男が搭乗券を持たず、「刑務所に入りたかった」という動機だったが、今回も、空港職員の「少々お待ち下さい」という声掛けを無視している。一部報道では、北海道警が建造物侵入の疑いがあるとみて女性の行方を追っているともされ、罪に問われる可能性もありそうだ。
なお、国交省は、問題が起きた8月5日、エア・ドゥと警備会社に管理態勢を強化するよう行政指導している、という。
「空港関係者によると、女は保安検査場で搭乗券を読み取り機にかざした際、エラーが出たという。警備員が対応を協議するために離れた隙に、無断で通り抜けた。」
現場を離れた警備員、警備員歴は長いのか?セキュリティーを考えれば誰もいない状態で現場を離れてはいけないと考えなかったのか?
警備員は研修を受けたことがあるのか?最後の研修はいつか?研修を受けたとすれば、研修を行った組織は適切な研修をおこなったのか?
「保安検査場の警備会社からは、同便の出発までにエア・ドゥへ連絡はなく、女は搭乗口の係員に『搭乗券をなくした』と話し、購入履歴や本人確認がとれたことで、同便に搭乗した。」
新千歳空港は保安検査場の警備会社との契約を見直すべだ!警備会社としての対応がだめだ!警備員はすぐにエア・ドゥへ連絡するべき。
一度だけでなく、二度の不適切な対応は、適切な警備会社ではない。契約の更新はするべきではない。入札で契約を決めたのかについては知らないが、
問題があることは明確だ。
警備員でもないし、警備員として働いた経験もないが、セキュリティーに関して誰もいない状態で持ち場を離れては絶対ダメなことはわかる。
警備員及び警備会社の対応は理解できない。こんな会社は警備などしなくて良い。相手が善人相手の対応しかできない警備会社はテロ対応は出来ない。
危機管理が警備会社のくせに全くできていない。
検索を掛けても警備会社の名前が出てこない。警備会社、保安警備、と新千歳空港で検索すると
株式会社ジェイ・エス・エス (Japan Security Support Co., Ltd.)が出てきた。
この会社が警備会社なのか確信が持てないので、興味がある人は調べてみてください。
新千歳空港で8月5日午後0時10分すぎ、若い女性客1人が国内線ターミナルの保安検査場で金属探知機を通過せず、羽田行きに搭乗して出発するトラブルがあった。この影響で機内や搭乗待合室など、制限エリア内にいた約1000人にのぼる全乗客がエリア外に出され、保安検査がやり直しとなり、欠航や大幅な遅延が発生した。
空港関係者によると、女は保安検査場で搭乗券を読み取り機にかざした際、エラーが出たという。警備員が対応を協議するために離れた隙に、無断で通り抜けた。
女はエア・ドゥ(ADO/HD)の札幌午後0時20分発羽田行きHD20便の航空券を購入していた。保安検査場の警備会社からは、同便の出発までにエア・ドゥへ連絡はなく、女は搭乗口の係員に「搭乗券をなくした」と話し、購入履歴や本人確認がとれたことで、同便に搭乗した。
HD20便は午後0時28分に札幌を出発。羽田には定刻より3分早い午後1時57分に到着した。エア・ドゥによると、この段階でも警備会社から同社に連絡はなく、女は身柄を拘束されることなく降機したという。
この影響で、全日本空輸(ANA/NH)や日本航空(JAL/JL、9201)など、合わせて15便が欠航。30分以上の遅延便も含めると、約2万人に影響が生じた。新千歳空港では、保安検査態勢の見直しなどを進めている。
警察では事件性はないとしている。このため、エア・ドゥでは今のところ、女の今後の利用を拒否する決定には至っていないという。同社では、女の氏名については個人情報として公表していない。
Tadayuki YOSHIKAWA
【千歳】5日午後0時10分ごろ、新千歳空港の国内線ターミナルで、女性の乗客1人が保安検査場の金属探知機を通らずに、保安区域(搭乗待合室)に入るトラブルがあった。安全確認のため機内や搭乗待合室にいた全乗客千人が保安区域外に出され、検査をやり直した。同空港では国内線全便の出発を一時見合わせ、欠航や遅延などの影響が終日続いた。女性客が乗った飛行機は再検査前に離陸していたことが後で分かった。
道警や空港関係者によると、AIRDO(エア・ドゥ)の午後0時20分発羽田行きに搭乗する女性客が検査場で搭乗券を出す際、QRコードに機械が反応しなかった。女性客は「(搭乗券確認の)必要があるのか」と警備会社の社員に詰め寄り、社員が対応を検討するためにその場を離れた間に、いなくなっていたという。
検査場のカメラには、女性が探知機を通らずに待合室に入る姿が映っていた。エア・ドゥによると、搭乗口では「チケットをなくした」と言って、航空機に乗り込んだという。
国土交通省新千歳空港事務所によると、警備会社側から連絡があったのは約30分後で、女性客を乗せた飛行機はその前に離陸していた。国交省航空局は「危機管理準備室」を立ち上げ、経緯などを確認している。
国内線の出発便全便が午後1時ごろから約2時間にわたり運航を停止。事務所職員らが保安区域内に不審物がないかを確認後、午後2時半から保安検査をやり直した。運航は午後3時すぎに再開したが、11便が欠航し、150便以上に最大3時間の遅れが出た。
検査やり直しなどで出発ロビーは夏休み中の旅行客らであふれた。登山のため道内を訪れていた千葉県の主婦川崎晴美さん(65)は原因となった女性客について「身勝手なことをして迷惑だ。早く帰りたいのに」と憤っていた。
「近畿大医学部付属病院(大阪府大阪狭山市)の救命救急センターと小児科、産婦人科で、府の補助金など少なくとも計2200万円が、大学会計ではなく、医師個人名義の『裏口座』にプールされていたことがわかった。」
厳重注意処分は甘いと思うが??
近畿大医学部付属病院(大阪府大阪狭山市)の救命救急センターと小児科、産婦人科で、府の補助金など少なくとも計2200万円が、大学会計ではなく、医師個人名義の「裏口座」にプールされていたことがわかった。
一部は飲食費などに流用されており、同病院は「不適切な会計処理だ」として、同センター長ら教授4人を病院長による厳重注意処分とした。
病院関係者によると、記録が残る2011年度からの5年間に、救急医療体制の充実を図る府の事業の協力費約1440万円と、周辺市町が救急救命士に対する医師の指導について支払っている「指示料」約610万円が、センターで勤務する2人の医師名義の口座に入金されていた。
小児科と産婦人科では、妊婦などの救急搬送の受け入れ実績に応じて府などから支払われる協力金計約150万円を、医師名義の口座で管理していた。
このうちセンターの2口座は、医師らが私費を積み立てる「医局費」の管理を兼ね、多くは物品購入など医局の運営経費に使われたが、約360万円は、懇親会や当直時の飲食、弔電、タクシーチケットなどに充てられていた。府の実施要綱では、協力費は「人員配置や当該業務の遂行の必要経費に充てる」と定められており、同病院は大学会計への返金を求める。
大阪府立急性期・総合医療センター(大阪市)など府立2病院で3月以降、救急救命士への指導料などを個人口座にプールしていた問題が発覚したのを受け、近大病院が調査していた。
近大病院は「補助金の管理に対する意識が低かった。再発防止に努める」としている。
これまでも三菱自動車の車に乗ったことはないし、今後も乗ることはないので、個人的には関係ない。
三菱自動車は三菱グループの支援があるから問題はないのであろう??
三菱自動車は2日、燃費データ不正問題を検証した特別調査委員会(委員長・渡辺恵一弁護士)の報告書を公表し、2011年の社内アンケートで開発現場の問題として「品質記録の改竄(かいざん)」など不正を指摘する声が複数あったことを明らかにした。アンケート結果は経営陣にも報告されたが問題を見過ごしていた。
益子修会長兼社長は記者会見で「私を含め歴代の経営陣は現場の生の声にもっと向き合う努力をすべきだった」と述べた。
報告書は、15年型の軽自動車「eKワゴン」の燃費試験に使われた数値が「恣意(しい)的に引き下げたもので、不正な作出」などと認定。原因として法令の軽視に加え、04年のリコール(回収・無償修理)隠し問題後の経費削減で技術開発が停滞したことなどと指摘した。社内アンケートで「評価試験の経過、結果の虚偽報告」などの声が上がったが、担当部長が調査して「問題なし」として対応を取らなかった。調査委は「表面的なやり取りだった」と経営陣の関心の低さを批判した。05年には法令と異なる走行試験を繰り返すことに対し当時の新人社員が適切な方法の採用を提言していたことも明らかになった。
改革は無理。
まるでメルトダウンのマニュアルが存在しながら、気づかなかったと言う東電と同じ。
「菱自動車の燃費不正問題で、2005年に同社の新人の社員が不正行為をやめるよう社内で提言したのに、幹部が放置していたことが分かった。」
そんな言い訳を言うこと自体、組織として修復不可能な状態。
三菱自動車も同じだと思う。
報告書で明らかになる前に公表しなければならない事。
三菱自動車の燃費不正問題で、2005年に同社の新人の社員が不正行為をやめるよう社内で提言したのに、幹部が放置していたことが分かった。燃費不正を調べていた特別調査委員会が2日公表の報告書で明らかにした。調査委は、不正に鈍感な体質を示す事例として問題視している。
調査委は燃費不正を客観的に調べるため三菱自が4月25日に設置、弁護士ら4人で構成する。報告書によると、新人社員は社内の発表会で、国のルールと異なる方法で燃費データを測っており、改めるべきだと提言した。不正行為を続けていた部門の幹部ら20人余りが聞いていたという。
幹部らは調査委に対し、記憶にないと答えた。しかし、当時の資料も入手した調査委は、「新人社員の指摘というインパクトを考えても、記憶がないという説明は容易に受け入れがたい」と結論づけた。
11年の社内アンケートでデータ偽装を示唆する複数の回答が寄せられたが、開発部門の「問題なし」という報告を経営陣がうのみにしたことも指摘した。
三菱自の益子修会長兼社長は2日の記者会見で、新人社員の提言と社内アンケートについて会社側の調査では把握していなかったと説明、「非常に重く受け止めている」と陳謝した。改めて詳細に調べるという。(木村和規)
「提訴を受けて国は、『訴状を見てから対応したい』。製薬会社の『グラクソ・スミスクライン』は、『今後も有効性と安全性の確保に努める』。もう一つの製薬会社『MSD』は、『主張の内容は根拠がないと信じている』などとそれぞれコメントしています。」
集団訴訟を起こしても科学的にリスクを証明し、闘うのはかなり難しいだろう。しかも、製薬会社の親会社はイギリスとアメリカ。簡単には妥協しないであろう。
問題を隠蔽するために研究を実施した教授に裏金を渡す工作まで行っていた。これでは裁判に勝つのは難しい。
実際、メディアや国は症状とワクチンの因果関係がわからないと言っている。長い、裁判になりそうだ。
子宮頸がんワクチンの接種の前にワクチンのメリットとデメリットを考えるべきだと思う。被害者達は最悪のケースで、現在のところ、補償はいっさいないと考えるべき。
子宮頸がんワクチンに限らず、急ぐ必要がなければ、結果を見て判断すると言うのが被害者にならない防御策だろう。確率とは関係なく、副作用が起きた時に受け入れられると
思わなければ、自己責任で接種しない判断もある。
子宮頸がんワクチンの副作用で健康被害を受けたとして、愛知・岐阜・三重に住む女性6人が、国や製薬会社に損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴しました。全国でも同様の集団訴訟が起こされました。
名古屋地裁に訴えを起こしたのは、東海3県に住む15歳から21歳の女性6人です。
訴状などによりますと、原告の女性たちは、子宮頸がんワクチンを接種した後、失神や歩行障害などの症状が出たのは、ワクチンの成分が原因だと主張しています。
その上で、海外で重い副作用の報告事例があり、国は被害を予見できたにもかかわらず、2種類のワクチンの製造販売を承認した上、定期接種の推進などで被害が拡大した。
また、製薬会社2社は製造責任があるとして、1人あたり1500万円の損害賠償を求めています。
提訴後の会見.....
「様々な症状が出て来て、現在も治療中です。大事な高校生活もほとんど送れず、国と製薬企業に、責任のありかを明確にしてもらいたい」(原告の母親・谷口鈴加さん)
提訴を受けて国は、「訴状を見てから対応したい」。製薬会社の「グラクソ・スミスクライン」は、「今後も有効性と安全性の確保に努める」。もう一つの製薬会社「MSD」は、「主張の内容は根拠がないと信じている」などとそれぞれコメントしています。
全国では27日、他にも57人の女性が、同様の集団訴訟を起こしました。
住宅リフォーム番組「大改造!!劇的ビフォーアフター」もそろそろ終わりかも??
約5000万円あれば、田舎であれば結構な家が建てられる。
人件費が高く、作業範囲や作業効率に問題が多い日本でリフォームはケースバイケースかも?
朝日放送(大阪市)が放送する住宅リフォーム番組「大改造!!劇的ビフォーアフター」で、リフォームを請け負った愛知県東海市の建設会社が26日、追加工事費が未払いになっているとして、朝日放送や番組制作会社などに約2900万円の支払いを求め、名古屋地裁に提訴した。
訴状によると、建設会社は2013~14年、岐阜市の築50年の2階建て店舗兼住宅のリフォームを請け負い、名古屋市の建築士の指示に従って改修。リフォーム代金は当初、2200万円だったが、建築士や制作会社から耐震補強や床暖房などの追加工事を指示され、約5000万円にまで膨らんだという。
建設会社の社長(54)は「放送では予算内に収まったと表示されたが、全く事実と違い、納得できない」と話している。
実際、全くメリットがないのであれば、継続などしないと思う。間接的、または、親睦を深めていくステップの通過点。そこで使えそうな人間か、お金で動く人間なのか等を 見極めるのかもしれない。
文部科学省は26日、高校の教科書会社4社が2012~16年、19都府県の高校140校に総額約330万円の教師用指導資料や教材を無償提供するなど、業界団体「教科書協会」の自主ルールに違反する行為が計187件あったと発表した。検定中の教科書を教員に見せ、意見を聞いた謝礼として現金約1万円を渡した社も1社あった。
文科省は6月、大修館書店(東京)による英語ドリルの無償提供問題を受け、高校教科書を発行する計39社に不正行為の有無について報告を求めていた。今後、各教育委員会に不正が教科書採択に影響しなかったかどうか確認を求め、9月に結果を公表する。新たに不正が発覚した場合は17年度の教科書発行を認めないなど厳しい措置も検討する。
文科省によると、指導資料などの無償提供が明らかになったのは教育芸術社(東京)▽新興出版社啓林館(大阪)▽第一学習社(広島)▽大修館書店。
教育芸術社は16年、自社の音楽教科書を採択した高校など46校に対する生徒用教材や音楽CD提供が47件あった。啓林館は12~14年、数学など3教科の教科書を採択した6校に教師用の指導資料を提供したケースが13件あった。
第一学習社は14、15年、国語や地理歴史など5教科の教科書を採択した41校への指導資料提供が57件確認された。大修館書店は公表済みの英語ドリル以外に、保健体育など2教科の教科書を採択した52校に指導資料や教材を提供した事例が70件あった。
また、日本文教出版(大阪)は11年、検定中の情報科の教科書を大阪府の府立高校教員1人に見せ、意見を聞いた対価として謝礼や交通費約1万円を支払った。
文科省によると、各社はいずれも「採択の継続などを意識した行為ではなく、教員とのなれ合いの中で渡した」などと説明したという。このうち教育芸術社は毎日新聞の取材に「ルール違反の意識がなく認識の甘さがあった」、啓林館は「採択に疑念を持たれる行為で深く反省している」などと釈明した。【佐々木洋、伊澤拓也】
つがるにしきた農協(本店・青森県つがる市)の元つがる統括支店長による着服事件で、つがる署に電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕された元支店長が、不正に得た現金の返済に充てるために架空の貸し付けを繰り返す「自転車操業」に陥っていた可能性があることが22日、複数の捜査関係者への取材で分かった。
つがる署と県警捜査2課は100万円分の詐取容疑が固まったとして、21日に元支店長を逮捕したが、不正操作は計約5千万円に上るとみられている。
捜査関係者によると、着服の発覚を免れるために犯行を繰り返していた可能性も視野に入れ、捜査を続けている。
逮捕容疑は、同支店金融課長だった2011年9月、親族男性から借り入れの申し込みがあったように装って端末を操作、男性の共済金を担保に100万円の貸し付けを行い、男性名義の口座に振り込むなどして不法な利益を得た疑い。
県警は22日、同容疑で元支店長を五所川原署から青森地検弘前支部に送検した。
「試験運航についてホン社長は『拒否をしたわけではない』と述べ、乗用車の車検証に当たる『船級』が平成26年12月に失効しており、実施できなかったと説明。性能などの情報は事前に伝えたという。」
この人達は素人の集まりなのか??5億円ものお金を動かす人間がこの程度??
売買契約を結ぶ前に船級証書(乗用車の車検証に当たる『船級』)確認しなかったのか??これは基本中の基本。これさえも確認せずに契約したのであれば、
失敗して当然。しかも、「セウォル号」(M/V"SEWOL", IMO9105205)の沈没で注目を受けた船の一隻。
普通、船級証書が切れた船を買おうとする人は少ない。よほど安いか、現状の状態を確認して安いと判断しないと買わない。検査に合格するのか、合格するための整備しようが
どれほどかかるのか見当が付かないからだ。
一般的な第三セクターの経営能力や知識については知らないが、このようなレベルの人達が肩書や過去の学歴で任命されていれば、巨額の負債や失敗して当然だと思う。
ロシアと新潟を結ぶ日本海横断航路計画で使うフェリーの契約トラブルをめぐり、売り主の韓国企業、ソドン・マリタイムのホン・ドンキュ社長(39)が21日、県庁で記者会見し、買い主のナフジェイ・パナマが仲裁判断で命じられた約1億6千万円の支払いについて、同社の親会社で県が筆頭株主の第三セクター、新潟国際海運(新潟市中央区)が応じなければ、法的措置も辞さない構えをみせた。
ソドンは6年前に設立され、釜山市に本社を置く。資本金は10万ドル(約1千万円)で、ホン社長ら6人で船舶を売買している。
会見でホン社長は「仲裁判断を素直に履行してほしい」と要求。パナマと昨年8月に契約した理由について「新潟県が関係しているからだ」と述べ、新潟国際海運に3億円を出資している県の存在を強調した。
五十嵐純夫社長らパナマと同海運の役員は同じだと指摘した上で「県がコントロールし契約を決めたと考えている」と述べた。
パナマは、フェリーは事前に試験運航ができず、購入後に速度不足が判明したため受け取りを拒否したとしている。試験運航についてホン社長は「拒否をしたわけではない」と述べ、乗用車の車検証に当たる「船級」が平成26年12月に失効しており、実施できなかったと説明。性能などの情報は事前に伝えたという。
ソドンは100隻ほどの取引実績がある。子会社が破産手続きをし、親会社が契約で債務保証をしていないことを理由に支払い義務はないと主張する今回のようなケースは「聞いたことがない」と憤りを見せた。
ソドンは仲裁判断後、パナマ側に支払いを2度求めたが、回答はないという。ホン社長は今後、法的措置を取る際に県も訴訟対象にするかは「弁護士と相談して決めたい」と述べるにとどめた。
なぜ、今まで放置したのか?
公益財団法人山梨県林業公社(TDB企業コード289000660、甲府市武田1-2-5、代表理事荒井洋幸氏、従業員8名)は、7月15日に甲府地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。申請代理人は野間自子弁護士(東京都千代田区内幸町2-1-4、三宅坂総合法律事務所、電話03-3500-2912)ほか2名。監督委員には石川善一弁護士(山梨県甲府市相生1-20-13、石川善一法律事務所、電話055-222-0200)が選任されている。
当法人は1965年(昭和40年)9月に山梨県の全額出資により設立した林業公社。国の「拡大造林政策」に沿って、県や公庫、信金借入金を財源として森林整備を行い、伐採収入で返済することとし、森林土地所有者から受託して県内の人工林(国有林・県有林を除く)の約9%に当たる約8393ヘクタールの人工林を造成、管理・保育を行ってきた。設立当初は国産木材価格が上昇傾向にあったが、輸入木材の拡大などによって国内木材価格は下落が続き、収益が悪化。2015年3月期の年売上高は約5億8800万円にとどまっていた。こうしたなか、新規募集の中止、事業費の削減、低利資金への借り換えなど経営健全化に向けた対策を講じていた。
しかし、円高傾向による海外からの低価格木材の輸入増加により、国産木材価格が長期低迷するなか、分収林の販売収益は好転する見込みはなく、その資産価格の低下によって200億円を越える大幅な債務超過に陥っていた。このため、山梨県は2011年に当法人を2017年3月に解散することを決定していた。金融機関からの借入金については、県が損失補填契約を締結しており、これに第三セクター等改革推進債を活用する方針で、同債の活用には債務処理の公平性・透明性を確保する見地から、法的な債務処理手続きを行う必要があり、今回の措置となった。
負債は債権者約15名に対し約260億4400万円(うち山梨県が約194億6700万円、金融債務が約65億7400万円)。
人工林の造成や管理事業を行ってきた山梨県林業公社は19日までに、甲府地裁に民事再生手続きを申し立てたと発表した。負債総額は約260億円にのぼり、2016年度末での解散が決まっていた。県は約148億円の債権を放棄する。
県の全額出資で1965年に設立。土地所有者の代わりに人工林の造成と管理を行い、成長した木材の伐採で得る収益を前提に事業費をまかなってきた。しかし、海外からの低価格木材の輸入増加で国産木材の価格が下落し収益が悪化、約208億円の債務超過に陥っていた。
「事故後、大阪航空局の監査で担当官に指摘され、未受検が発覚。同社の内部調査に対し、副操縦士は『身体検査で付加検査も実施したと思った』と述べ、管理担当者は『検査証明書を熟知してなかった』と述べたという。」
たぶん、事故後の言い訳だと思う。国土交通省が言い訳なのか、それとも事実なのか、事実をチェックしていけばある程度判明すると思う。
LCCブームで人材不足になると問題を隠蔽するリスクが高くなるので要注意。
昨年8月、第一航空(大阪府)のプロペラ機が粟国空港の滑走路を外れてフェンスに衝突し11人が負傷した事故で、着陸時に機体を操縦していた副操縦士=当時(62)=が、62歳以上の操縦士に義務付けられた身体検査を受けていなかったことが17日、分かった。
操縦士の定年は従来60歳だったが、人材不足から国は68歳未満まで引き上げた。運航の安全確保のため、国土交通省は2015年3月、航空運送事業者に対し、62歳以上の国内線操縦士には通常の身体検査に加え、心電図や脳波などを調べる「付加検査」の受検・合格を義務付けた。
関係者によると、副操縦士は同年採用された際、身体検査証明書と「付加検査」とは別の証明書を同社に提出。同社の担当者は「付加検査」と思い込み、運航に当たらせていた。
事故後、大阪航空局の監査で担当官に指摘され、未受検が発覚。同社の内部調査に対し、副操縦士は「身体検査で付加検査も実施したと思った」と述べ、管理担当者は「検査証明書を熟知してなかった」と述べたという。
同社は今年3月、操縦士の訓練記録の改ざんや、不適切な形態で着陸を繰り返したとして、大阪航空局から事業改善命令を受けた。
粟国空港で昨年8月、プロペラ機DHC6が着陸時に滑走路を外れてフェンスに衝突、11人が負傷した事故で、運航する第一航空(大阪)沖縄事業所の操縦士6人が会社の安全体制に疑問を訴えて退社したことが12日、分かった。事故当時にいた13人のほぼ半数が辞め、運休中の那覇―粟国便の再開や、遅れている石垣―多良間便などの就航に影響しそうだ。
同社関係者によると、事故後、社内でDHC6の飛行訓練計画が浮上。しかし、DHC6が滑走路を外れる事故を海外で複数回起こしていたことが社内調査で判明し、操縦士の一部が「原因究明まで飛ばすべきでない」などと反対した。
会社はそのうち4人に異動を命じ、全員が2月に退社。別の2人も3月に辞め、今月末にも1人退社する。退職した1人は取材に「異動は反発する人を排除する報復人事だ」と主張。別の操縦士は「安全より運航再開を優先する姿勢が明らか」と述べた。訓練計画は国の許可を得ておらず、訓練は実施されなかった。
同社の木田準一取締役は「事故で減収となり、余剰人員に異動を命じた。安全を軽視したのではない」と説明している。
JALであっても甘い管理体制??
機長も副操縦士も規則を守っていない。
CA(客室乗務員)達と同じホテルかどうかは知らないが、同じホテルが多いと思う。誰一人として、機長も副操縦士が飲酒していたところを見なかったのだろうか。
たぶん、運悪く今回だけでなく、乗務12時間前の飲酒を禁じている運航規程を頻繁に違反していたのではないのか??
飲酒を通報すれば特定は可能だと思われる。通報により人間関係の問題を引き起こすので、誰も通報しなかったのか、それとも通報をもみ消されたケースが過去にあるのか??
JALでこの程度なら、他の航空会社は問題になっていないだけで、似たような問題はあると思われる。
日本航空は13日、2010年に飲酒トラブルで逮捕され、国土交通省から「断酒」を条件に乗務を認められていた副操縦士(42)が、定期検査で虚偽の報告をし、飲酒を続けていたと発表した。
この副操縦士は先月下旬、酒に酔って警察官を殴り、公務執行妨害容疑で逮捕されており、国交省は13日、同社に厳重注意した。
同社の発表によると、副操縦士は10年11月、米国のホテルで酒に酔って暴れ回るなどし、現地警察に逮捕された。その後、懲戒処分を受け、国交省からは「断酒」が乗務の条件とされていた。
日本航空(JAL)の副操縦士(42)が宿泊先の金沢市で泥酔し、駆けつけた警察官を平手で殴って公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕された問題で、国土交通省は2016年7月13日、「運航乗務員の不適切な行為及び不十分な運航乗務員管理が認められた」としてJALを厳重注意したと発表した。
JALや国交省の発表によると、今回問題を起こした副操縦士は10年11月にも滞在先のサンフランシスコで飲酒による問題を起こし、11年5月に「社内管理」及び「断酒」の条件付きで、いわゆる「操縦免許」の一部とも言える航空身体検査証明を受けたが、14年夏頃から飲酒を再開。航空身体検査証明を更新する際も、「断酒を継続している」とうそをついていた。
「乗務前12時間以内の飲酒NG」を破っていたのは、機長と副操縦士の両方
副操縦士をめぐる問題では、同じスケジュールで移動していた機長と副操縦士が16年6月27日の乗務終了後に金沢市内の飲食店で飲酒し、副操縦士が機長を殴るなどして暴行。目撃者が警察に通報し、2人は22時15分頃に駆けつけた警察官から職務質問を受けていたが、副操縦士が警察官を平手で殴ったため、公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕された。副操縦士は身柄を拘束され代わりの人員を手配できなかったため、6月28日7時35分に小松空港を羽田空港に向けて出発予定だったJL182便(ボーイング737-800型機)を欠航。搭乗予定だった81人は後続便や他社便に振り替えた。
JALでは国交相の認可を受けた運航規程で「乗務開始の12時間前以降は飲酒をしてはならない」と定めている。機長と副操縦士の両方が、この規程に違反していたことが新たに明らかになった。
JALでは再発防止策を早急に検討し、社内処分については「今後会社として厳正に対処します」としている。
日本航空(JAL/JL、9201)は7月13日、公務執行妨害の疑いで逮捕された巽(たつみ)創一副操縦士(42)が、乗務12時間前の飲酒を禁じている運航規程に反していたと発表した。JALは今後、巽副操縦士を厳正に処分するとしている。
国土交通省航空局(JCAB)が定める運航規程審査基準では、乗務8時間前の飲酒を禁止している。JALは社内規定で12時間前からの飲酒を禁じている。
巽副操縦士は6月27日に乗務を終え、金沢市内のホテルに宿泊。同じスケジュールの機長とともに市内の飲食店で飲酒後、ホテル前で機長を暴行した。午後10時15分ごろ、通報を受けて現場に駆けつけた警察官から職務質問を受けた際、警察官を平手で殴り、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕され、石川県警金沢中警察署に留置された。翌28日は、午前7時35分小松発羽田行きJL182便に乗務する予定だった。
巽副操縦士には2011年5月の航空身体検査証明の交付時、産業医との面談と「断酒」の条件が付されていた。2年前の2014年夏ごろから、飲酒していたことが本人への聞き取りにより発覚した。また、航空身体検査証明の更新時、巽副操縦士は断酒を継続していると虚偽申告し、航空身体検査証明の交付を受けていたことも発覚した。
産業医は1カ月に1度の面談で、血液検査やストレス検査などを問診。直近では6月15日に受診していた。
JALは今後、再発防止策の策定を検討。当面はすべての運航乗務員を対象に、規定順守と飲酒による影響、飲酒のリスクを理解するための教育を8月末までに実施する。
巽副操縦士は7月8日、金沢簡易裁判所から略式起訴された。同裁判所に罰金40万円を納付し、即日釈放された。
Yusuke KOHASE
逮捕まで結構な時間がかかる。普通なのだろうか?
カレーチェーン「CoCo壱番屋」を展開する壱番屋が、廃棄を依頼したビーフカツが横流しされた事件で、警察は廃棄物を商品と偽って転売したなどとして産廃業者の会長ら男3人を逮捕した。
逮捕されたのは、産廃業者ダイコーの会長・大西一幸容疑者(75)と製麺業者・みのりフーズの元実質的経営者・岡田正男容疑者(78)、食品販売会社に勤めていた木村正敏容疑者の3人。
警察によると、大西容疑者は壱番屋が異物混入の恐れがあるとして廃棄を依頼したビーフカツを食肉販売の許可を得ずに転売していた。また、ほかの2人はこれを転売し代金をだまし取った疑いがもたれている。
大西容疑者は逮捕前、「岡田容疑者から持ちかけられた」としていた。岡田容疑者も逮捕前の取材に「廃棄物とは知らなかった」と話している。
警察は、容疑の裏付けを進めるとともに、3人がほかにも廃棄物と知りながら食品の転売を繰り返していた疑いもあるとみて経緯などを追及する方針。
カレーチェーン「Co(コ)Co(コ)壱番屋」を展開する壱番屋(愛知県一宮市)が廃棄を依頼した冷凍ビーフカツが、食用として横流しされていた事件で、愛知、岐阜両県警は12日にも、産業廃棄物処理業者「ダイコー」(愛知県稲沢市)の会長ら3人を食品衛生法違反などの疑いで逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。
両県警などによると、壱番屋は昨年10月、製造過程で異物が混入したとして、ダイコーに冷凍カツの廃棄を依頼。だが、同社会長はカツを「食品」として扱い、許可なく食肉を販売した疑いが持たれている。
また、ダイコーからカツを仕入れて転売した「みのりフーズ」(岐阜県羽島市)の実質的経営者と、みのりフーズからカツを買って別の業者に転売した仲卸業者(名古屋市)の取締役についても、廃棄物と知りながらカツを売り、代金をだまし取ったとして詐欺などの疑いで逮捕する方針。
予算の制限があるのは当然。安い報酬でもNHKで働きたいと思っている人が多いから、成り立つ。NHKも悪いかもしれないが、安い報酬で仕事を取る人達にも
責任がある。まあ、経験を積むために安い仕事でも取る、または、知名度を上げたいと思って安い仕事を取るのであれば、ギブ・アンド・テイクの
関係が成り立つので、NHKだけが悪いとは言えない。
同一労働、同一賃金となれば、NHKのコストは跳ね上がるかもしれない。
契約アナのリスクをもっと多くの人に公表するべきだと思う。それでも女子アナになりたいのであれば、個人の選択。
俳優や女優の中には、売れない時期を経験している人達がいる。諦めて他の仕事で働く人もいる。同じではないが、似ていると思う。
天下のNHKが度重なる下半身スキャンダルに見舞われている。NHK甲府放送局でのアナウンサー同士の不倫騒動に続き、『週刊新潮』(新潮社)などが、室蘭放送局に勤める現役女子アナAの“愛人クラブ”スキャンダルを報じたのだ。
同誌によれば、Aは「清楚なロングヘアーが印象的な25歳」の現役女子アナ。東京や大阪、福岡、札幌など、全国各地に拠点を持つ「愛人クラブ」に男性が50万円以上を払う“最高級クラス”の女性陣の中に名前を連ねていた。疑惑を報じられた本人は同誌を含めた複数のメディアに事実関係を認めており、インターネット上では早くも本人のプロフィールが特定される事態になっている。
NHKといえば、『フライデー』(講談社)が車内での決定的瞬間を捉えた写真とともに報じたアナウンサー同士の不倫が記憶に新しい。今回、またもや局のお堅いイメージにそぐわない醜聞が発覚してしまった格好だ。
「2つのスキャンダルともに共通しているのが、女性側がNHKの職員である局アナではなく、地方局の契約アナウンサーだったこと。この点がNHKの体質と現状を如実に表している」(放送業界関係者)
■契約アナはブラック企業ぶりの薄給?
「女子アナ」と一括りにされることが多いが、実は局アナと契約アナではその待遇は天と地ほども違う。局アナが20代から「1000万円近く」(前出・関係者)ともいわれる高給を手にするのに対し、契約アナが手にする対価はごくわずかだ。
かつて「スイカップ」と呼ばれた豊満などバストが話題を呼んだ元NHK山形放送局の古瀬絵理アナ(38)が今年1月に発売された『週刊ポスト』(小学館)でその実態を赤裸々に明かしている。
古瀬は、「年収400万円には届かない、という程度。ボーナスもない」とブラック企業並の薄給ぶりを告白。さらに地方ごとに契約期間が決まっている「スタッフ契約」と、1年ごとに更新される「出演者契約」があることも明らかにされている。
「女子アナとしてテレビに出るにはメイク代や衣装代も必要で、出費もかさばる。都内から地方局勤務になった場合は一人暮らしの費用も。契約アナの多くはギリギリの生活を強いられている。こうした実情を踏まえると、自分の地位を守るために同僚の局アナと不倫したり、愛人クラブに登録して小遣い稼ぎしたりするのも仕方がない気がします」(週刊誌記者)
今回のスキャンダルはテレビ業界の暗部をも浮き彫りにしたようだ。
文・海保真一(かいほ・しんいち)※1967年秋田県生まれ。大学卒業後、週刊誌記者を経てフリーライターに。週刊誌で執筆し、芸能界のタブーから子供貧 困など社会問題にも取り組む。主な著書に『格差社会の真実』(宙出版)ほか多数。
共にNHKの地方局の契約アナウンサーから全国区のスターダムにのし上がった「スイカップ」こと古瀬絵理アナ(元山形放送局)と「パイナップル乳」こと竹中知華アナ(元沖縄放送局)が初対談。現在は共にフリーで活躍する2人だが、NHK時代はどんな契約内容だったのだろう?
竹中:古瀬さんはスタッフ契約? 出演者契約?
古瀬:私は出演者契約。年俸制でした。
竹中:私も同じです。スタッフ契約は契約期間に満期があって、沖縄放送局は5年。出演者契約は1年ごとの更新。ニュースを1本読んでいくらという計算です。
古瀬:出演者契約のほうが額はいいですよね。
竹中:スタッフ契約だと手取りで月に20万円未満というのもザラですし。
──お2人の年俸はいくらぐらい?
古瀬:言えない(笑い)。年収400万円には届かない、という程度。ボーナスもないし。局アナとは明らかに違いますよ。
竹中:全然違う!
古瀬:例えばアナウンス部の部長と1歳上の局アナと食事に行ったとします。1万5500円の支払いだとすれば、部長が1万円、局アナが5000円を払って「じゃあ、古瀬君は500円ね」と言われる。局員と10倍も差はないだろうけど、倍以上は違う。
竹中:その分、局アナは危険な仕事もしてます。台風中継は契約アナは担当しない。万が一のことがあったら責任を取れませんから。契約アナは使い勝手がいいので契約更新は容易です。でも、次のステップを考えなければいけない立場。常に「いつ辞めるか」を考えていました。
──先日、NHK山形放送局で、気象予報士の女性が突然泣き出し、話題となりました。局内のイザコザなども指摘されていますが、何があったと思いますか?
古瀬:実際の理由はわかりませんが、同じような立場の人が集まれば、揉め事はつきもの。契約キャスターはテレビに映る分、お互いライバル心があって、表向きは仲良くするけど、腹の中では何を考えているかわからない(笑い)。スタッフ間のイザコザはよくあるとは思います。
竹中:沖縄はおおらかな人が多くて、契約スタッフ同士でも仲は良かったですよ。
古瀬:私の場合、先に「スイカップ」という名前が出てしまった分、接するのが難しかったのかもしれません。
【プロフィール】
ふるせ・えり/1978年山形県生まれ。2000年にNHK山形放送局の契約アナウンサーになる。2003年頃に山形名産のスイカに引っ掛けた“スイカップ”という愛称をつけられ全国区に。2004年にフリーに転身し2011年に結婚。現在はラジオや講演などで活動中。
たけなか・ともか/1982年広島県生まれ。2005年に青森朝日放送に入社。2008年にNHK沖縄放送局の契約アナウンサーになり、7年間にわたり朝のニュース番組を担当。2011年頃から“パイナップル乳”と呼ばれるようになる。2011年に結婚、2015年4月からフリーアナウンサーに。
※週刊ポスト2016年1月15・22日号
NHK室蘭放送局に勤める現役女子アナ・Aさんが、“愛人クラブ”に登録していたと11日、ウェブニュースサイト「デイリー新潮」が報じた。
同サイトによれば、Aさんは清楚なロングヘアーが印象的な25歳。愛人クラブでは容姿ごとにランクわけされており、Aさんは男性が50万円以上を払う“最高級クラス”に属しているという。本人は記者の直撃に対し、クラブに登録していたことは認めたものの、「愛人クラブだとは知らなかった」「結婚相談所みたいなものだと思った」と釈明している。
NHK室蘭放送局公式サイトのアナウンサー紹介コーナーには、これまで1人の男性アナウンサーと、4人の女子アナのプロフィールが掲載されていたが、12日現在は「リニューアル中」として、全アナウンサーが見られない状態となっている。さらに、11日には、同サイト内にAさんとみられる女子アナの写真が散在していたが、12日にはきれいさっぱり削除されていることがわかる。
しかし、「デイリー新潮」に掲載されたAさんの目線入り顔写真を元に、ネット上では個人名を確定。Aさんの釈明に対し、「苦しい言いわけ」「援助金もらえる結婚相談所なんて、あるかよww」といった書き込みのほか、「バレないとでも思ったのか?」「お金が大好きなんだろうね」「NHKのアナウンサーって、そんなに給料低いの?」という声も。また、「NHKにしたらトンデモナイ話だけど、現役NHKアナ在籍愛人バンクって利用者からすると超絶優良店だったのでは?」との書き込みも見受けられる。
「NHKといえば、NHK甲府のイブニングニュース『まるごと山梨』でコンビを組んでいた斉藤孝信と早川美奈が、先月30日に突如、番組を降板。この翌日、両アナに激似の男女による“路上不倫カーセックス”現場が『フライデー』(講談社)に報じられた。さらに、NHK所属の女子アナではないものの、2014年12月には『NHKニュース7』でお天気キャスターを務めていた気象予報士・岡村真美子のあられもない“変態二股不倫”が報じられ、彼女の“裏の顔”が世間に衝撃を与えた。こうも続いてしまうと、NHKは性的に乱れた社風だと視聴者に思われても仕方ない」(芸能記者)
NHKの品行方正なイメージからはかけ離れた自由奔放な素行が次々と明らかとなっている、同局の女子アナ。視聴者の視線も変わりそうだ。
アナウンサーを目指していたのだろうか?そうであれば、高級愛人クラブ嬢として働くとまずいと思わなかったのだろうか?
【画像あり】高級愛人クラブ嬢のNHKアナ、山崎友里江ってどんな人?文春砲直後、NHK室蘭放送局がプロフィール削除・・・ 07/14/16(MTALK!)
NHKの某地方局に勤める現役女性アナウンサー(20代)が、「愛人マッチングサービス」を謳うデートクラブに登録していたことが、週刊文春の取材で明らかになった。
問題の人物は地方局採用の契約キャスター・高田陽子アナ(仮名)。高田アナ本人は週刊文春の直撃取材に「登録しました」とその事実を認めた。当初は会ったのは一人だけと繰り返したが、取材を進める中で、今年2月から既婚男性を含む4人の男性とデートしたと説明した。
彼女が登録していた高級愛人クラブは日本全国に支店を持つ「X」。男性会員は支払う年会費に応じて4段階にクラス分けされており、最高クラスの場合、入会金30万円、2年目以降は年会費として16万円が必要となり、そのほかに女性とのデートセッティング費用(2万~10万円)が発生する。
デートが実現したあとの関係については、男女間の自由意思によるが、ホームページに掲載された女性会員たちのプロフィール欄には、“交際”に発展する可能性についても、「初日からスマートにお誘い頂ければ交際に発展する可能性があります」などと5段階に分類されている。現役会員によれば、「女性と一晩をともにする値段は、デートセッティング費用と同額が目安とクラブ側から聞いている」という。
この「X」について売春防止法に詳しい服部梢弁護士が指摘する。
「ホームページにも、『愛人マッチングサービス』『タレントの卵からAV女優まで』といった文言があり、単に男女が会ってお茶を飲むのではなく、その先に性行為があることをクラブ側も認識しているはず。このようなケースでは、売春の周旋を禁止する売春防止法に違反する可能性があり、2年以下の懲役、または5万円以下の罰金、またはその両方が課される可能性があります」
NHK広報局は高田アナのデートクラブ登録について、「スタッフのプライベートなことについては承知しておらず、お答えできません」と回答。「X」の代表者は「売春の定義は『不特定の相手』であり、不特定になってはいけないと気をつけている」と会員制の同クラブに違法性はないと説明した。
高田アナがクラブに登録するまでの経緯や出会った男性たちとの関係などについては、週刊文春7月14日発売号で詳報する。
やはり半沢直樹の世界のようにどろどろした世界なのであろう!
三菱東京UFJ銀行の複数の行員が、昨年暮れに経営破綻(はたん)した融資先企業から過剰な接待を受けていたことがわかった。7日発売の週刊文春が報じた。同行は社内規定に違反していたことを認め、接待を受けていた行員を処分する方向で検討している。
経営破綻した融資先は、船舶運航管理会社ラムスコーポレーション(東京都港区)を中心とするグループ企業。市況の低迷で資金繰りが悪化し、昨年末に東京地裁から会社更生手続きの開始決定を受けた。負債総額は1千億円超で、このうち三菱東京UFJ銀が数百億円を融資していた。
同行の社内調査で、幹部を含む複数の融資担当者が飲食店や高級クラブなどで頻繁に接待されていたことがわかった。更生手続きの進捗(しんちょく)などをみながら処分を検討するという。同行広報は「社内規定に照らし、ルール違反があったのは事実。適正に対処したい」とコメントした。
昨年最大の破綻となった船舶会社の倒産事件で、メガバンクトップの三菱東京UFJ銀行の幹部を含む複数の行員が、銀座の高級クラブなどで接待を繰り返し受けていたことが、週刊文春の取材でわかった。
ユナイテッドオーシャン・グループ(UOG)は、昨年11月、三菱などの銀行団によって会社更生法適用申請を申立てられ、大晦日に更生手続き開始が決定。負債総額約1400億円の昨年最大の大型破綻となった。三菱は、UOGに10年間で約730億円を融資し、当時の小山田隆副頭取(現・頭取)が融資契約の調印式に出席するなど蜜月関係にあった。UOGの社長によれば、こうした融資の過程で、新橋支社長(当時)を含む6人の行員に対し、銀座の寿司屋や割烹、高級クラブなどで接待。さらに、社長の海外出張中には、行員は自分たちだけでクラブに飲みに行き、その飲み代をUOGにツケ回しするなどしており、単純計算でその総額は1000万円を超えるという。
三菱東京UFJ銀行広報部は、次のように回答した。
「接待に関しては、これまでの社内調査の結果、社内規定に照らして、ルール違反の事例があったことは事実であり、適正に対応しております」
ただ、当該の行員たちは、今も処分を受けないまま働いているという。UOGの破綻を巡っては、150億円もの“不適切融資”があったことも週刊文春の取材で判明しており、自ら融資に関わってきた小山田頭取も含め、三菱の説明責任が求められている。
<週刊文春2016年7月14日号『スクープ速報』より>
言葉は時として信用できない。結果を待つしかないであろう。
銀行窓口で販売される貯蓄性の高い保険商品について、金融庁が、10月に予定していた銀行の受け取る手数料の開示を見送った。日銀のマイナス金利政策に苦しむ地方銀行などに配慮して軌道修正したのかと思いきや、理由はまったく別。開示に反発する地銀の姿勢に金融庁の森信親長官が激怒し、一旦仕切り直して広範囲に及ぶ保険商品の手数料の透明化を徹底的に行おうとしているのが実態で、“虎の尾”を踏んだ金融業界は戦々恐々としている。
生保業界「恨み節」
「なぜ、こんなことになってしまったんだろう」。生命保険業界関係者はこう恨み節を口にする。
生保業界は今回の手数料開示に当初から協力的だった。金融庁が顧客の立場に立った金融商品の販売・提供を意味する「フィデューシャリー・デューティー」を強く打ち出す中、顧客の利益に資する制度の見直しは避けることができない大きな潮流となっている。
金融庁が問題視していたのは銀行窓口販売の手数料だ。透明化は手数料の下げ圧力になり、銀行側の販売意欲の低下にもつながりかねないが、ここは素直に協力することで、保険の乗り合い代理店など他の販売経路に透明化が見境なく波及するのを食い止める狙いがあった。だが、結果的に生保業界の恐れた方向になってしまった。
そもそも、金融庁はなぜ銀行窓口の保険販売に絞り、手数料の開示を求めたのか。
対象になった運用結果や為替相場で受け取る額が変わる変額年金保険や外貨建て保険などの貯蓄性の高い保険商品は、銀行の窓口で売れ筋だ。保険会社が銀行に支払う販売委託手数料は顧客の保険料に含まれているが、その金額は開示されていない。このため、手数料が10%程度と過度に高い商品もあるという。一方、同じく銀行窓口で売られる投資信託の手数料は2~3%が一般的で、開示もされている。
金融庁が懸念したのは、貯蓄性保険の手数料が非開示のままであれば、銀行が高い手数料収入目当てに、不要な商品を顧客に勧めかねないという点だ。同じく銀行窓口で売られている投信と同様に手数料開示を義務付ければ、顧客には商品選びの参考になる情報が増え、過度に高い手数料が下がることも期待できると判断したわけだ。
「これは長官マター」
金融庁は今年に入り、生命保険業界に手数料を開示するよう求め、銀行業界も含めて調整してきた。そして、5月20日には手数料開示に関する監督指針改正案を公表して、10月から開示を実施する予定だった。しかし、監督指針改正案公表の2日前に事態は一変。金融庁は突然、銀行業界や保険業界に指針改正を凍結する旨を通告した。
背景には、調整を進める中で地銀業界から「銀行を狙い撃ちにするのは不公平」と反対の声が強まったことがある。
地銀はマイナス金利政策で貸し出しの利ざやが縮小し、金融商品販売などの手数料稼ぎに力を入れている。手数料開示で「ドル箱」の保険販売のうまみがなくなれば、収益低迷の危機にひんすることから、「保険の代理店が対象にならないのはおかしい」との理屈も持ち出して反発した。
指針改正の凍結は一見、金融庁がこうした意見に配慮したようにみえるが、内情はむしろ逆だ。金融庁担当者は「業界に反対されようが、僕らはやるべきことはやる。これは長官マターになった」と語る。
■銀行、生保 問われる「本気度」
「地銀はまだそんなことを言っているのか。顧客本位でないことの表れだ」。凍結の舞台裏では、開示に否定的な地銀の姿勢に金融庁の森長官が怒りを爆発させていたのだ。
森長官は昨年7月の長官就任以前から、フィデューシャリー・デューティーの徹底に事あるごとに言及し続けてきた。長年の取り組みにより、ある程度は成果が上がってきたとみていたはずだが、蓋を開けてみれば、地銀から飛び出してきたのは顧客目線を欠いた正反対を行く言動だったからだ。
金融庁が手数料開示を一旦取り下げたのは、森長官が手数料の透明化を徹底的に行う腹を決めたとの向きが強い。それを裏付けるように、首相の諮問機関である金融審議会の「市場ワーキング・グループ」では7月初めからフィデューシャリー・デューティーの議論を行う予定で、手数料開示も議論される見込みだ。自主的にできないのであれば、金融審で根本から検討するとの狙いが垣間見える。
金融業界は森長官の逆鱗(げきりん)に触れたことで、逆に行政の圧力を強められかねない事態となったことに危機感を強めている。銀行業界や生保業界では金融庁の矛先をかわそうと、善後策を練り始めており、業界同士の意見交換も活発になってきた。
一部の大手銀行は、10月から自主的に銀行窓口で扱う全ての保険商品の手数料開示を行う検討を始めているという。
生保業界も、業界団体である生命保険協会が手数料開示の協会ルールを策定する方針だ。
金融庁が事業指針を定めた金融行政方針には、フィデューシャリー・デューティーについて「民間の自主的な取り組みを支援することで徹底を図る」と明記している。銀行や生保は、金融庁が凍結した監督指針改正の方向に沿った取り組みを実施する姿勢を示すことで、事態を収束させたいとの思惑だ。
生保協会は協会ルールについて金融審の議論を踏まえ、金融審の成果として示すようだ。
銀行業界や生保業界は今のところ、協会ルールを示すより前に、各社が個別に自主的に開示に踏み切るか、それでは開示の対象範囲などをめぐって各社の足並みがそろいにくいため、協会ルールが示された後に実際に開示を行うかなど、複数の案をつくり、どれがベストか業界間の調整を行っているという。
当面は生保、銀行業界の双方が納得できる協会ルールづくりを調整することができるかが今後の焦点になるが、その結果に金融庁の森長官は矛を収めることになるのか。それぞれの立場でフィデューシャリー・デューティーへの本気度が改めて問われる。(万福博之)
今後、事実が明らかになるであろう!
大阪市内の歯科医院による診療報酬の不正受給に関与した疑いが強まったとして、大阪府警が詐欺容疑などで50代の府警OBの男ら少なくとも数人の逮捕状を取ったことが26日、捜査関係者への取材で分かった。近く事情を聴く方針。府警は3月下旬以降、OBが経営する会社事務所や医院など関係先を家宅捜索。押収した資料を分析するなどして事件の解明を進めていた。
捜査関係者などによると、OBは大阪市内の歯科医院の法人代表らと共謀。昨年秋ごろまで、協力者から提供を受けた保険証を悪用し、診療報酬の架空請求を繰り返すなどした疑いが持たれている。法人代表は府警の任意での取り調べで、昨年秋ごろまでの約2年間で数千万円規模の診療報酬を請求し、一部の不正を認めていたという。
法人代表によると、OBは昨年7月上旬ごろから医院の経営を実質的に支配。同10月下旬に法人代表との間で金銭トラブルが発生し、OBらが医院の経営を離れるまでの約3カ月間、医院で診療報酬約500万円を不正受給したという。
法人代表は「(OBらに)無理やり診療報酬の不正請求をさせられた」と主張。「(不正請求分のうち)約300万円は昨年10月下旬にOBらに渡した」と答えた。
これに対し、OBは産経新聞の取材に対し、不正受給への関与を否定。「(法人代表に)運転資金を無心された。知人に頼まれて医院の運営を手伝い、その過程で貸した金を返してもらっただけだ」と説明していた。
大阪市の歯科医院の診療報酬を不正に受給したとして、大阪府警刑事特別捜査隊は27日、詐欺容疑で、医院を運営する医療法人理事長の歯科医師賀川幸一郎容疑者(45)ら数人を逮捕した。他に50代の元府警巡査部長らの逮捕状も取っており、容疑が固まり次第、逮捕する方針。
捜査関係者によると、賀川容疑者と元巡査部長らは共謀し、昨年夏ごろ、大阪市浪速区の歯科医院で複数の患者の歯を治療したように装って診療報酬を請求し、十数万円を不正に受け取った疑いが持たれている。
府警や医院関係者によると、医療法人は徳島市や大阪市で歯科医院を運営し、浪速区の医院は昨年9月に閉鎖された。
元巡査部長は暴力団捜査を主に担当し、2002年に不適切な飲食接待を理由に懲戒処分を受け、依願退職。賀川容疑者とは昨年、保険請求を巡るトラブルで知り合いになり、医院の経営にも関与していたとみられる。
これまでの取材に賀川容疑者は「トラブルに絡み元巡査部長から金銭を要求され、昨年7~9月ごろ、診療報酬計約500万円を架空請求した。このうち売り上げと合わせ約380万円を渡した」と説明。一方、元巡査部長の関係者は「(賀川容疑者から)医院の建て直しを依頼され300万円を貸し付け、その返済を受けた。詐欺には関わっていない」と話している。
府警は今年3月、医院や元巡査部長の関係先を家宅捜索し、押収資料の分析を進めていた。
資金不足で解散するしかないのであるのなら自業自得。
東京・銀座のコンサルティング会社の信用について調査したのか?
公益財団法人「日本サイクリング協会」(東京都品川区)が都内のコンサルティング会社に資産運用を委託した約3億円のうち、約2億7000万円が回収できなくなっていることが、協会関係者への取材でわかった。
協会は資金不足に陥っており、「資金が戻らなければ解散せざるを得ない」(協会幹部)としている。コンサルティング会社は協会に「別事業に投資して失敗した」と説明。協会側は、当初の説明が虚偽だったとして、警視庁への告訴なども検討している。
協会によると、2011年3月頃、資産運用を相談した東京・銀座のコンサルティング会社から「シンガポールの銀行の割引円建て債を約2億6000万円で購入すれば、3年後に3億円になる。その他、約4000万円の利息も入る」などと持ちかけられた。協会は同月、同社と資産運用のコンサルティング契約を結び、約2億6000万円を同社の口座に入金した。
嘘つきは存在する。誰かはうやむや!
これでは誰を信用すれば良いのか??
東京電力福島第一原発事故で炉心溶融(メルトダウン)の公表が遅れた問題で、東電が再発防止策を発表した。第三者検証委員会が推認した「官邸の指示」については、東電として再調査しないという。真相の解明は、新潟県との合同検証委員会にゆだねられる。
炉心溶融の言葉使わぬよう指示、隠蔽と認める 東電社長
21日、都内の本社で会見した広瀬直己社長は「社会の皆様、とりわけ(原発の)立地地域の皆様におわびしたい」と謝罪した。当時、核燃料が溶けている可能性が高いとすでに認識していたのに、社長の指示で「炉心溶融」との言葉を避けたことを隠蔽(いんぺい)と認め、「今後は事実を伝える姿勢を貫く」と語った。
ただ、再発防止策の前提となった第三者委(委員長=田中康久・元仙台高裁長官)の報告書が問題の背景に「官邸の指示」があったと推認し、当時の官房長官だった枝野幸男・民進党幹事長らの反発を招いたことについては「調査するつもりはない」と繰り返した。
第三者委は当時の官邸関係者への聞き取りをしないまま「官邸からの圧力」を推認しており、枝野氏らは「党への信用毀損(きそん)」などとして法的措置も検討している。広瀬社長は「推認は推認として受け止めた」とし、その理由についても「(真相の解明を)しなくても済む対策をとった」と繰り返すのみだった。
真相の解明は柏崎刈羽原発を抱える新潟県の泉田裕彦知事も求めており、東電と同県は今後、合同で検証を続けていく。広瀬社長も「今後、委員の先生がたと合同で相談させて頂きながら(やり方を)決めていく」としており、検証の対象に「官邸の指示があったかどうか」が含まれる可能性は否定しなかった。
こうした東電の姿勢に対し、民進党の岡田克也代表は同日、記者団に「東電も第三者委を作ったわけで、知りませんでは済まない。これは政治家の名誉のかかった問題だ」と反発した。 企業の不祥事に詳しい郷原信郎弁護士も「官邸の関与をにおわせて責任を逃れるシナリオが最初からあったのでは。東電には期待できず、当時の官邸や立地自治体の方で解明に取り組むべきだ」としている。
東京電力福島第一原発事故で炉心溶融(メルトダウン)の公表が遅れた問題で、広瀬直己社長は21日、当時の社長が炉心溶融という言葉を使わないよう社内に指示していたことについて隠蔽(いんぺい)と認め、謝罪した。東電の第三者検証委員会が指摘した「官邸の指示」については追加調査しないという。その上で、新潟県に「炉心溶融の定義はない」などと誤った回答をしたとして、広瀬社長を減給10%(1カ月)とするなどの処分を発表した。
東電は、当時の清水正孝社長が指示したことは「社会の皆様の立場に立てば隠蔽と捉えられるのは当然」と発表。広瀬社長は会見で個人の見解を問われ、「隠蔽です」と認めた。その上で、情報発信を社長に直接提言することや、外部からの圧力があっても事実を公表できるよう訓練するといった再発防止策を発表した。
元社長が指示した理由について、東電の第三者委は16日、「元社長が官邸側から要請を受けたと理解していたと推認される」とする報告書を発表し、菅直人元首相らが「指示したことはない」と否定している。
また、広瀬社長はこうした「要請」の経緯について、東電として調査する考えがないことを明らかにした。「圧力に左右されない対策を取ることが重要だ」と判断したという。
炉心溶融の公表遅れをめぐっては、新潟県が2012年から調査を求め、東電は今年2月、「炉心の損傷が5%を超えた場合は炉心溶融とする」との判断基準がマニュアルに明記されていたと公表した。
福島原発事故は真実の隠蔽の存在と専門家が事実を口に出せない事実を明らかにした。
結果として最悪の事態にならなかったからこそ、カミングアウト出来るのだろう。この世は結局、お金と圧力と言う事であろう。
東京電力の広瀬直己社長は21日、本社で記者会見を開き、原子炉内の核燃料が溶け落ちる「炉心溶融(メルトダウン)」の公表が遅れた問題について、「社会の皆さまの立場に立てば隠蔽(いんぺい)ととらえられるのは当然であり、深くおわび申し上げる」と謝罪した。
東電が設置した第三者検証委員会(委員長=田中康久・元仙台高裁長官)は16日、当時の清水正孝社長が炉心溶融の言葉を使わないよう指示していたなどとする報告書を公表していた。
信用と信頼について三菱が復活できるのか、このまま沈むのかで推測する材料となると思う。
燃費データの不正が発覚してから約2カ月。三菱自動車が顧客への具体的な賠償方針を示した。データ改ざんがあった車への賠償額は1台あたり原則10万円や3万円で、ユーザーからはため息が漏れる。下請け会社からは、信頼回復に時間がかかりそうだという声があがった。
三菱自動車が記者会見を開いた17日夕、東京都内の販売店は客が1人で、燃費データ不正があった「アウトランダーPHEV」や「アウトランダー」が展示されていた。賠償方針について、従業員は「全く聞いていない」と繰り返した。
別の販売店でも、従業員が「ニュースで知ったばかり。会社から詳しい連絡はなく、対応できない」と硬い表情で話した。
ユーザーからは不満の声が漏れる。名古屋市北区の40代女性は、三菱自が日産に供給した「デイズ」を1年半前に新車で買った。熊本地震の後、車内でゆったり寝られる車に買い替えようとして、下取り価格が20万円ぐらい下がっていると友人に聞かされた。「10万円じゃ納得できません」
5年前に「eKワゴン」を新車で買った愛知県春日井市の主婦(43)は、他社と比べて低燃費が決め手だったという。「あきれているだけ。もう中古では売れないだろうし、乗り潰すしかない」とあきらめ顔だ。
すぐにはカミングアウト出来なかったのだろうか??
国交省は今後も性善説を基本にシステムおよび規則を維持および改正していくのか??
三菱自動車の燃費不正問題をめぐり、販売が終了した「コルト」など3車種の燃費データ捏造(ねつぞう)に、三菱自本社の複数の部署が関与していたことがわかった。三菱自が近く、国土交通省に報告する。
国の燃費試験では、空気抵抗や路面との摩擦を示す「走行抵抗値」をメーカーが測定し、それを基に国が燃費値を出す。
関係者によると、3車種のうち「コルト」と「アウトランダー」の走行抵抗値の捏造は、認証部で行われた。国に提出する直前の社内確認で、目標の燃費値を達成できない可能性が浮上したため、架空の数値を国に提出したという。
他の企業でも似たような事はやっていると思う。氷山の一角だろう!
神戸製鋼所は9日、関連会社「神鋼鋼線工業」(兵庫県尼崎市)の100%子会社「神鋼鋼線ステンレス」(大阪府泉佐野市)が製造しているばね用ステンレス鋼線の一部について、強度の試験値が書き換えられていたと発表した。
神戸製鋼などによると、書き換えが確認されたのは、平成19年4月~今年5月に出荷されたばね用ステンレス鋼線55・6トン。日本工業規格(JIS)を満たしていないのに、試験値を改竄(かいざん)してJIS表示した製品として出荷していたという。
用途は、家電・家庭用品向け74%▽給湯器などのガス設備向け12%▽自動車向け6%▽未判明8%。
神戸製鋼は「関係者にご迷惑をかけ、深くおわびする。一般的なばねの設計余裕度を考えると、市場折損リスクは極めて低いと想定しているが、引き続き調査や確認を進める」としている。
今回の件で、問題のある候補者を当選させると、法律を悪用されるケースでは、任期が終わるまで何も出来ない事を多くの国民に教えたと思う。
「弁護士が政治資金規正法や政党助成法に違反しないとしたのは、そもそも両法とも支出の内容の是非について規定がないからだ。収支報告書に、事実を書かなかったり、事実と異なる記載をしたりしていれば、『不記載』や『虚偽記載』として処罰の対象になり得る。だが、疑わしい支出でも正しく金額や支出先などを記載していれば、違法性を認定するのは相当にハードルが高い。」
政治資金規正法や政党助成法が穴だらけの法律で、捕まらないように骨抜きにされている。国民を小ばかにした制度であると言う事では??
「公私混同」の疑いが指摘されていた舛添要一・東京都知事の政治資金について、弁護士が調査結果を公表し、多くの支出について「不適切」と判断した。宿泊費、飲食費、美術品代や書籍代など多岐にわたった。だが、政治資金規正法などには支出内容に関する規定がなく、「違法とは言えない」との結論に。7日からの都議会での質疑でも追及が続きそうだ。
調査した弁護士は、一部の宿泊費などについて「不適切」とし、事実上「公私混同」を認めたが、一方で「違法とは言えない」とも繰り返した。
弁護士が政治資金規正法や政党助成法に違反しないとしたのは、そもそも両法とも支出の内容の是非について規定がないからだ。収支報告書に、事実を書かなかったり、事実と異なる記載をしたりしていれば、「不記載」や「虚偽記載」として処罰の対象になり得る。だが、疑わしい支出でも正しく金額や支出先などを記載していれば、違法性を認定するのは相当にハードルが高い。
認可外保育施設のメリットとデメリットを考えさせるケース。自由度が増えるという事は、悪意があれば悪いほうへの自由度も増える。
抜き打ち検査やおよび重い罰則でコントロールしないと自由度が増すと被害者も増える。
栃木・宇都宮市の認可外保育施設で赤ちゃんが死亡した事件の裁判で、被告の元施設長の次男が出廷し、死亡した赤ちゃんも「ワイシャツで縛られていた」などと証言した。
宇都宮市の認可外保育施設「といず」元施設長・木村 久美子被告(59)は、2014年7月、宿泊保育中に、下痢や高熱を発症した山口 愛美利ちゃんを放置して死亡させた、保護責任者遺棄致死の罪に問われ、無罪を主張している。
7日の裁判で、「といず」の従業員だった木村被告の次男が、検察側の証人として出廷し、当時、愛美利ちゃんも、ほかの保育中の子どもと同じように、「ワイシャツで縛られていた」と述べた。
また、愛美利ちゃんの死亡前後の木村被告の行動について、「出かけていたことや、(証拠隠滅のため)遺体にシャワーを浴びせたことは、話さないように言われた」と、口裏合わせをしたことを証言した。
「三菱自動車の燃費偽装問題で、同社が、国が定める測定法と異なる方法で燃費算出の基となるデータを得るため、不正なプログラムを開発していたことがわかった。・・・今年4月の問題発覚後、同社は社内調査を開始。関係者によると、高速惰行法は、同社が自動車の開発段階で走行試験のために91年以前から使っていたもので、このデータを惰行法で計測したと見せかけるため、プログラムを開発し、25年間使っていた。」
会見はパフォーマンスか、それとも演技だったのか?
従業員の給料レベルの利益を出す事が出来ない体質だったのか?それとも単なる組織の体質問題、又は軽いカルト的な企業価値観が存在したのか?
三菱自動車の燃費偽装問題で、同社が、国が定める測定法と異なる方法で燃費算出の基となるデータを得るため、不正なプログラムを開発していたことがわかった。
国の測定法は1991年に導入されたが、プログラムはその直後に開発され、担当者の間で長年使用され続けた。制度導入当初から違法性の認識を持っていたことになり、国土交通省幹部は「悪質性が高く、厳正に処分する」としている。
国が定めた測定法は「惰行法」と呼ばれるもので、各メーカーが車をテストコースで走らせて走行抵抗値を測定し、燃費算出のためのデータを取っている。しかし、同社は「高速惰行法」という手法でデータを測定していた。
今年4月の問題発覚後、同社は社内調査を開始。関係者によると、高速惰行法は、同社が自動車の開発段階で走行試験のために91年以前から使っていたもので、このデータを惰行法で計測したと見せかけるため、プログラムを開発し、25年間使っていた。
24億円を着服し、「着服金は複数の女性との交際費や競馬、株への投資などに使っていた」と言うのであれば、それなりに人生を謳歌できたと思う。
なかなか豪遊する人生は経験できないので、今後は地獄かもしれないが、それなりの思い出は出来たであろう。
しかし、「昨年5月に取引のない銀行から郵便物が届き、内部調査を実施したところ、不正が発覚。」との事実は、組織のチェック機能が働いていない証拠。24億円が大金なのか、大した金額でないのか知らないが、誰かが尻拭いをしなければならない。
北越紀州製紙の子会社から不正に小切手を振り出して現金を横領したとして、警視庁捜査2課は1日、子会社の「北越トレイディング」(新潟県長岡市)の元総務部長、羽染政次容疑者(60)=川崎市高津区=を業務上横領容疑で逮捕した。北越紀州製紙によると、羽染容疑者は2000年4月から昨年4月まで、計約24億7600万円を着服した疑いがあり、捜査2課は全容の解明を進める。
逮捕容疑は、13年2~3月、自身で不正に作成した小切手を使って、数回にわたり子会社の口座から約6600万円を振り出して、横領したとしている。調べに対し容疑を認めているという。
同課などによると、羽染容疑者は00年以降、子会社の経理を担当し、預金口座を管理していた。着服金は複数の女性との交際費や競馬、株への投資などに使っていたとみられる。昨年5月に取引のない銀行から郵便物が届き、内部調査を実施したところ、不正が発覚。羽染容疑者は同月に懲戒解雇された。
北越紀州製紙は「深く反省してグループを挙げて再発防止策に取り組んでいる。今後もコンプライアンスを最重要課題として徹底していく」とコメントした。【宮崎隆、黒川晋史】
自業自得!
陸上自衛隊東富士演習場(静岡県)の一部を所有し、防衛省から賃貸料を得ている一般社団法人「須走すばしり彰徳山林会」(同県小山町)と同会の関連法人が名古屋国税局などの税務調査を受け、2015年3月期までの3年間で計約3億2000万円の所得隠しを指摘されていたことが分かった。
追徴税額は重加算税を含め約1億円とみられる。
関係者によると、同会は帳簿に架空経費を計上して所得を圧縮し、経費の一部を会員に現金で配っていた。また、会員らが出資して設立した関連会社「クリーン・サポート」(山梨県)は、山林整備などの業務を同会から請け負い、会員に発注していたが、作業日数を水増しし過大に日当を支払うなどしていたという。
信用調査会社などによると、同会は演習場内の山林などを管理するため、1955年に設立された。会員は約80人。約480ヘクタールの土地を防衛省に貸し、年間約7億円を得ていた。
県商工信用組合(本店・郡山市)は27日、須賀川支店の男性職員(21)が顧客の預金口座から勝手に現金をおろすなどして、計約265万円を着服していたと発表した。同組合は職員を3月末で懲戒解雇し、今月23日、須賀川署に被害届を提出した。
同組合によると、渉外係だった職員は2014年8月から今年1月にかけ、偽造した顧客の印鑑などを使い、計31回にわたり無断で普通預金をおろしたり、定期預金を解約したりするなどして265万7804円を着服。パチンコや飲食などの遊興費のほか、着服分の穴埋めに使っていたという。
今年1月、顧客から「預金が減っている」などと問い合わせがあり、同組合が内部調査した結果、職員が事実関係を認めた。その後、職員は着服金を全額弁済したという。
人事次第では金太郎飴が切り方によって微妙に違って見えるだけ。三菱自動車をみればわかる。組織の体質は簡単には変らない。
一般財団法人・化学及および血清療法研究所(化血研、熊本市)が国の承認を受けない方法で血液製剤などを製造していた問題で、厚生労働省と熊本県が化血研に対し、経営陣の刷新案を示すよう行政指導していたことが、わかった。
5月20日付の文書で行い、5月末までに回答するよう求めている。
関係者によると、化血研が5月6日、9人の理事全員を6月下旬に退任させる方針を明らかにしたことを受けた措置だという。化血研に対して、早期に後任人事案を固め、厚労省や県に報告するよう促す狙いだとみられる。
化血研は不正製造の全容が判明した昨年12月、新経営陣に現経営陣の一部を残す人事案を公表した。これに対して厚労省は、組織体制の抜本的な見直しを求めていた。
ひとつ上手く行けば、今度も大丈夫?人も組織も安易なほうへ流れていく。これは自然な流れかも?
三菱自動車に続き、スズキでも燃費データを巡る不正行為が明らかになり、自動車業界に危機感が広がっている。
スズキが不正なやり方で測定していた車種はマツダなど3社にも供給しており、車種は計27車種に上る。国内の乗用車メーカー8社のうち4社で不正測定車種を売っていることになり、日本車全体のイメージダウンにつながりかねないからだ。
「競争が厳しい中で仕事をするのは当然で、不正をするのは論外だ」
自動車メーカーが加盟する日本自動車工業会の西川広人会長(日産自動車副会長)は19日の就任記者会見で語気を強めた。三菱自は経営陣が掲げた高い燃費目標を開発現場が達成できず、軽自動車4車種の燃費を良く見せかけており、「信頼を揺るがす不正」(西川会長)と三菱自の行為を厳しく批判した。三菱自の相川哲郎社長は19日付で、自工会の副会長を辞任した。
ひとつ上手く行けば、今度も大丈夫?人も組織も安易なほうへ流れていく。これは自然な流れかも?
東亜建設工業(東京都新宿区)が羽田など3空港の地盤改良工事の施工データを改ざんしていた問題で、同社が受注した港湾工事でもデータが改ざんされていた疑いのあることが20日、分かった。
国土交通省が調査を指示しており、同社は同日午後に調査結果を報告する。
東亜建設は、2008年に開発した工法で、国が発注した港湾の地盤改良工事を14件受注。関係者によると、これらの工事でデータを改ざんした疑いがあるという。
同社は14年1月~16年5月に羽田、福岡、松山の3空港で行った工事で、施工データを改ざん。地盤を固める薬液を計画通り注入していなかったのに、書類などを偽装して完成したように見せ掛けていた。
「せっかく、燃費の試験をするのだから、ランダムで他の自動車メーカーも最低1台選んで、比較してほしい。」と以前に書いたが、やはり多少の横並び的な問題があるのであろう。
国交省の性善説が基本であるとの考え方を見直す時期が来たと思う。
三菱自動車の燃費データ不正問題を巡り、スズキも三菱自と同様に法令と異なる方法で燃費データを計測していた疑いがあることが18日、分かった。スズキの鈴木修会長が同日午後に国土交通省に報告する。
燃費データ不正を巡っては、三菱自動車が4月20日、軽自動車4車種で燃費性能の基礎データ「走行抵抗値」(空気抵抗などを数値化したもの)を故意に改ざんし燃費を実態より良く見せていたと発表。軽4車種を含む1991年以降に国内販売したほとんどの車種で、道路運送車両法の定めと異なる方法で抵抗値を計測していたことも判明した。
国交省は他の自動車メーカーに対しても同様の不正がないかを報告するよう求めていたが、スズキが内部調査した結果、法令と異なる方法でデータを計測していたことが分かった。ただ、スズキは「燃費性能には影響はない」と、意図的なデータの改ざんは否定している。
トヨタ自動車やホンダ、日産自動車などは決算会見などで同様の不正はなかったと説明しており、国交省に報告する方針。【宮島寛、内橋寿明】
企業も苦しくなって、ざるのような性善説を基本にしたシステムの抜け穴を利用するようになったのか?
東亜建設工業(東京都新宿区)が、羽田空港滑走路の液状化を防ぐための地盤改良工事で施工データを改ざんしていた問題で、同社は13日、福岡空港(福岡市)と松山空港(松山市)でも同様の不正があったと公表した。国土交通省によると、通常の発着に問題はないが、地震の際に液状化の恐れがあるという。同省は他の工事で不正がないか報告を指示した。
同社によると、3空港とも2008年に開発した工法で施工され、いずれの不正にも開発を担当した本社社員が関与。施工データを改ざんし、設計通り完成したと虚偽報告していた。
同社は08年9月以降、同じ工法で他に、国発注の港湾工事14件、民間の26件を請け負っており、不正がなかったか調べている。
13日記者会見した松尾正臣社長は「ざんきの念に堪えない」と陳謝し、社内調査を急ぐ考えを示した。同社長は5月末で相談役に退く。
施工を始めて約1週間で滑走路のひび割れや隆起が発生し、同社が国交省に報告したという。完成検査を行っていたが偽装を見抜けず、同省幹部は
「検査方法の見直しも検討する」と話した。
同工事では地盤を固める薬液の注入が必要だが、福岡空港の滑走路工事2件(14年6月~16年5月)で、注入量が計画の約38~43%、松山空港の誘導路工事(14年9月~15年3月)では約52%だった。羽田空港でも新たな不正が見つかり、誘導路工事(14年1月~15年3月)で約45%だった。
無料通信アプリ大手「LINE」はどのような対応を取るのでしょうか??
無料通信アプリ大手「LINE」(東京都渋谷区)のスマートフォン用ゲームで使う一部のアイテム(道具)が資金決済法で規制されるゲーム上の「通貨」に当たると、同社を立ち入り検査していた関東財務局が認定したことが分かった。通貨の場合、未使用残高が1000万円を超えれば半額を発行保証金として法務局などに供託する義務があるが、これまで同社は供託せず、財務局は同法違反に当たると指摘。供託不足額は3月末時点で約125億円に上る。【藤田剛】
同社は「検査結果などの開示は当局の要請によりできません。なお、従前の通り、当局からの指摘に誠実に対応します」とコメントした。
関係者によると、同社は供託などを進める方針を財務局に伝えたという。
財務局が通貨に当たると認定したのは、パズルゲーム「LINE POP(ラインポップ)」で使われるアイテム「宝箱の鍵」と、別のゲーム「LINE PLAY(ラインプレイ)」内のミニゲームで使われるアイテム「クローバー」。
このうち宝箱の鍵は1本当たり約110円相当で、宝箱を開ける用途以外に、使用数に応じてゲームを進めたり、使えるキャラクターを増やしたりできる仕様だった。資金決済法では、利用者が代金を前払いし商品やサービスの決済に使うものを「前払式支払手段」と規定。プリペイドカードなどのほか、通貨として使われるアイテムも該当する。発行会社は倒産などに備えて保証金を供託し利用者保護を図る義務がある。
宝箱の鍵は昨年5月、社内で通貨と指摘されたのに同社は用途制限など仕様を変え「通貨に該当しないという説明が可能」と判断。財務局に届け出なかった。財務局は今年1月から立ち入り検査し、その結果、2アイテムを前払式支払手段(通貨)と認定、供託や届け出を怠った資金決済法違反に当たると判断した。
供託の不足額は昨年9月末時点で約148億円、今年3月末時点で約125億円。ただ、同社が銀行と保全契約を結ぶなどの方法を用いれば、数千万円の保証料を銀行に支払うことで供託に代えられるという。この場合、万一の際は銀行が供託を肩代わりする。
同社は昨年7月、問題のアイテムを通貨と記した資料を作りながら、その後、記載を削除して財務局に提出。財務局は、役員らが通貨の疑いを報告されたのに適切に対応しなかったことを問題視し、「経営陣が担当者任せだった」として管理体制の改善も求めた。
利用者保護の配慮求める
資金決済法に詳しい渡辺雅之弁護士(第二東京弁護士会)の話 スマートフォンなどで課金型ゲームが普及する中、利用者保護の配慮が事業者に厳しく求められることを今回の検査は示した。課金の仕組みは複雑化しており、疑義があれば事業者は金融当局に確認し、当局は適否の線引きを周知する努力をすべきだ。
組織が腐っていれば時間が経てば人も腐っていくと言う事なのかも知れない。
三菱自動車の燃費偽装問題で、三菱自が2013年に発売したプラグインハイブリッド車(PHV)「アウトランダーPHEV」の燃費を調べるための走行データを測る際、法令で定められた重量より軽い車両を使い、机上計算で補正していたことがわかった。
4月20日に軽自動車の燃費偽装が発覚した後に行った社内調査で判明した。5月11日の記者会見では公表していなかった。
三菱自はこれまでアウトランダーPHEVについて、法令で定めた「惰行法」という走行試験のやり方で測定していた3車種の一つで、正しい方法で測定していたと説明し、現在も販売中だ。新たな不正が見つかり、三菱自のずさんな実態が改めて浮き彫りになった。
関係者によると、タイヤと路面の摩擦や空気抵抗のデータ「走行抵抗値」を測る際、本来は荷物を積んだ状況などを再現するため、車両重量に一定の重さを加えて走行試験を行う必要がある。三菱自は、この手順を怠り、重量の違いによる測定値の変化を机上で計算したデータを審査機関に提出したという。
「同整備局は結果的に東亜の偽装を見抜けなかったが、工事の確認方法について、加藤部長は『不正を前提にしておらず、受注者を信頼していた。必要であれば見直しを考えたい』と話した。」
「不正を前提にしておらず、受注者を信頼していた。」との理由で偽装を見抜けなかったのだから見直しが必要なのでは??
このような展開で国土交通省関東地方整備局や国土交通省は不正を前提としたチェック体制に移行するのか、それともこれまで通りなのか?
◇羽田空港に続き、地盤改良工事で不正発覚
東証1部上場の東亜建設工業(東京都新宿区)が羽田空港滑走路の地盤改良工事でデータを改ざんしていた問題で、同社が関わった福岡、松山両空港の滑走路の地盤改良工事でも同様の不正が行われた疑いが強いことが13日、関係者への取材で分かった。報告を受けた国土交通省が詳しく調べる。
同社が担当したのは、大地震が起きた場合を想定して滑走路の液状化を防ぐ工事。羽田空港では昨年5月から今年3月までの工期で、C滑走路の地中に管を通じて薬液約1250万リットルを注入し、地盤を強固にする計画だった。
ところが、地中にコンクリート片などの障害物があったことで掘削がうまくいかず、地中に埋めた管はいずれも計画した位置と異なっていた。そのため、薬液が予定の5.4%しか注入できないという施工不良が生じたが、同社は当時の東京支店長の指示で、仕様書通りの工事ができたように装った虚偽報告を国交省に行っていた。
羽田空港の問題を受け、発注者の国交省は同様の工法を使った他の空港の工事についても、同社に調査を指示していた。その結果、福岡、松山両空港の滑走路でも不正が行われていた可能性が高まったという。
両空港とも航空機の利用に問題はないとみられるが、国交省は実態を調べた上で、同社に対する営業停止などの処分を検討する。
羽田空港の滑走路で行われた地盤改良工事で、中堅ゼネコン「東亜建設工業」(東京都新宿区)が施工データを改ざんしていた問題で、同社は13日、同様の工事を行っていた福岡空港と松山空港の滑走路や誘導路でも施工不良があったと発表した。
羽田空港の誘導路工事でも新たに不正が判明し、データ改ざんなどは計5工事で行われたとしている。
さらにイメージダウンになると思うが、なぜ会見で話せなかったのか?
三菱自動車が軽自動車の燃費を偽装していた問題で、新車開発にあたって燃費データを算出する性能実験部の管理職社員が、データ測定を委託した子会社に対し、燃費目標を達成できる都合の良いデータを使うよう指示していたことが分かった。
国土交通省は13日、道路運送車両法に基づき、三菱自本社(東京都港区)を立ち入り検査した。
国交省は不正発覚後、開発統括部門がある名古屋製作所・技術センター(愛知県岡崎市)を立ち入り検査したが、本社を対象とするのは初めて。国交省は、益子修会長や相川哲郎社長にも聞き取り調査を行い、経営陣の関与を含めて実態の解明を急ぐ。
関係者によると、測定を委託された子会社「三菱自動車エンジニアリング」が2013年1~2月にタイで走行試験を行った際、タイヤと路面の摩擦や空気抵抗のデータである「走行抵抗値」について、燃費目標に届く値が得られなかったとして、同社の担当者が三菱自性能実験部の管理職社員に相談した。管理職社員は、試験で得られた複数のデータのうち、法令で定められた中央値ではなく、燃費目標を達成できる低いデータを使って構わないと指示したという。
横浜市都筑区の傾いたマンションで、強固な地盤に届いていたくいについても施工が不十分で、強度が不足している可能性があることが12日、建設元請けの三井住友建設が実施した調査の結果(速報値)で分かった。同社が、住民に説明した。住民からは「ほかのくいも同じように強度が不足していたら、安全性はどうなるのか」と懸念の声が上がっている。三井住友建設は取材に対し、「調査中」としている。
住民によると、強度が不足しているのは、くいを補強する「根固め部」。地中に埋められたくいの先端にあり、セメントを流し込んで作る球根状の構造体で、建物の耐震性を高める効果がある。
三井住友建設は横浜市の指示で、傾いた棟とは別の棟のくい2本について強度の調査をしていた。
三井住友建設が住民に行った説明によると、くいの強度は建築基準法上、力の単位であるニュートン(N)の値が1平方ミリメートル当たり7・2あることが必要で、大地震に対しては4・9を満たす必要があるとしていた。
しかし、同社が依頼した試験機関の調査の速報値では、2本のくいの根固め部の強度は、5・2と4・8。住民側の試験機関では4・0と4・1と判定された。
今回の調査は、根固め部のうちくいの内部に入り込んだセメントを調べたもので、工事の過程で泥が混ざった可能性もある。
三井住友建設は当初、この方法で十分に調査が可能としていたが、結果を受け、根固め部本体の調査をすることを申し出ている。住民側は当初から、本体の調査をするよう求めていたという。
同マンションでは、くい計8本が固い地盤に未到達か、十分に届いていない施工不良があった上、くい打ち施工のデータ偽装も明らかになっていた。横浜市は大規模地震でも倒壊しないと判断していた。
横浜市都筑区の大型分譲マンションで杭くいの施工不良が見つかった問題で、建物を支える杭の先端部分にあるセメントの一部に強度不足が見つかったことが分かった。
元請けの三井住友建設などが12日までに、調査結果の速報を住民側に提示した。三井側は今回の結果を踏まえ、6月までに横浜市に報告書を提出する予定。
旭化成建材による同マンションの施工不良問題で、セメントの強度不足が確認されたのは初めて。今回の調査は4~5月に実施。昨年の調査で、マンション全4棟(705戸)のうち西、南、中央3棟の杭45本について、杭先端を強固な地盤(支持層)に固定するセメントの量のデータ流用が判明したため、このうち調査可能な中央棟の2本の強度を調べた。
関係者によると、マンション管理組合と三井側がそれぞれ試験機関にデータ解析などを依頼。その結果、組合側の調査では、三井側が「震度7の大地震でも安全」とする基準を2本とも下回り、基準値の8割ほどにとどまった。三井側の調査でも、1本が基準に足りなかったという。
一方、別の調査で、これまでデータ流用が見つかっていなかった北棟でも、深度不足の杭があることが確認された。今年1月に、深度不足が疑われる杭4本が見つかり、調べたところ、少なくとも1本が、支持層に入り込んだ深さが足りない「根入れ不足」と判明した。
住民の一人は調査結果について、「データ流用があった3棟はどこも同様の強度不足の可能性がある。北棟も含む全棟で杭に問題があったことを直視し、三井側は建て替えを進めるべきだ」と話した。
同マンションを巡っては昨年10月、一部の杭が支持層に届いていないことが発覚。西棟では傾きが確認された。三井側は、杭工事を担当した旭化成建材の現場責任者が、杭のデータを別の杭から流用していたことを明らかにした。
管理組合は今年2月、全4棟を建て替える方針を住民の賛成多数で可決。販売元の三井不動産レジデンシャルは今月10日、建て替えなど是正工事が正式に決議されれば、補償を含めて費用を負担することで管理組合と合意したことを公表した。(戸田貴也)
さらにイメージダウンになると思うが、なぜ会見で話せなかったのか?
三菱自動車の燃費偽装問題で、三菱自動車が「本社から子会社に不正の指示があった」との報告書をまとめていたことが分かった。
燃費データの測定は三菱自動車の子会社が行っていて、他社との燃費競争の中、データが改ざんされた4車種は、目標が5回にわたり引き上げられていたことが分かっている。
日本テレビが入手した三菱が社内調査の結果をまとめた報告書によると、データを改ざんした子会社の当時の管理職が三菱自動車本社・性能実験部の当時の管理職に、燃費目標達成に必要なデータが取れなかったことを相談した際、都合の良いデータを抽出するよう不正を指示されたとしている。
また、この子会社の管理職は社内調査に対し、「過去の経験から目標達成は厳しいと認識し、再三の目標の引き上げに疑問を持っていた」などと話していることも分かった。
さらに報告書では、2012年の会議の席で当時の開発本部長が「発売時に燃費が一番でなくてはならない」と発言していたなどとしていて、改ざんの背景には「燃費目標達成のプレッシャー」や「性能実験部の閉鎖性」「開発部門上層部の高圧的な言動によるもの言えぬ風土の醸成」などがあったとしている。
三菱自動車は11日の会見で、不正の指示については「調査中」と明言を避けるなど報告書の詳細な内容については明らかにしていないが、国土交通省には11日に報告していて、国交省は今後、報告内容の事実関係を調べる方針。
会見を見た消費者がどのように判断するか次第。多くがポジティブに捉えれば、三菱の勝ち。多くがうそ臭い、多くを隠しているとネガティブに捉えれば三菱の負け。
三菱自動車の燃費偽装問題は、軽自動車以外の車種へ広がる可能性が高まった。
同社が11日に行った記者会見で、スポーツ用多目的車「RVR」などでもデータ偽装の可能性があることや、燃費試験を行っていた同社子会社の担当者が不正への関与を認めたことも明らかになった。だが、依然として不正にかかわった人数などについては「調査中」と繰り返すのみで、歯切れの悪い回答に終始した。
問題発覚後、初めて会見に出席した益子修会長は、冒頭、相川哲郎社長らとともに数秒間、頭を下げた。そのうえで、「今後、再発防止に万全を期す」と社内改革への意欲を強調した。
燃費データ不正の全容解明には遠い調査結果だった。三菱自動車は11日に開いた記者会見で、高い燃費目標を背景に子会社の社員がデータ不正を行ったことを説明した。しかし、三菱自側の関与など不正の全体像については「調査中」「確認中」を繰り返した。益子修会長も自分たちの説明内容を「歯切れが悪い」と認めざるをえなかった。
11日夕、予定時刻より約10分遅れで始まった記者会見。益子会長は「多数の皆さまにご迷惑をかけた」と陳謝。相川哲郎社長、横幕康次開発本部長と立ち上がり、頭を下げた。着用していたスリーダイヤのバッジに言及し、「三菱のバッジをつけておきながら…」と悔やむ一幕もあった。
データ改竄(かいざん)が確定しているのは、平成25年以降に発売した「eKワゴン」など4車種で、空気やタイヤの抵抗など燃費性能を左右する走行抵抗値を操作した。
法的には天候による影響を補正するために複数回走行させ、その中央値を国側に申告することが義務づけられているが、実際には走行抵抗値を低くして燃費性能が良くなるようにするため、最も有利な値が中央値になっていた。
開発の段階で社内の燃費目標を23年2月から25年2月の間に5回引き上げられており、相川社長は「競合車の燃費を強く意識したもので、現実的には達成が困難でありながら安易な見通しで開発が進められた」。
三菱自によると、データ改竄を行ったのは子会社の「三菱自動車エンジニアリング」の管理職で、「燃費目標を達成できると思ったが、最後の最後に達成できなかった」との趣旨の説明をしているという。
会見では三菱自側の関与や認識について質問が集中。横幕本部長は、データ測定は三菱自と子会社の社員が相談しながら進めたとする一方、三菱自の社員が不正を把握していたかについては「調査している」と言葉を濁した。
三菱自側が明言を避ける理由として、関係者が多くヒアリングが終わっていないことを挙げたが、相川社長は役員の関与や把握については「(燃費目標を達成したとする)報告を会議で承認する形をとり、知り得なかった」と言い切った。
リコール隠しなど不祥事が続く三菱自。益子会長は「閉鎖的な社会の中で仕事が行われているのが原因。意識改革ができていなかった」と声を落とした。
ついに、三菱自動車工業(三菱自工)に対する国の「技術的な強制調査」が始まった。
大型連休の中日にあたる、5月2日(月)の午前7時、埼玉県熊谷市の郊外。独立行政法人・自動車技術総合機構・交通安全環境研究所(通称:交通研)の自動車試験場の正面玄関前は、在京テレビ局全社のカメラや、新聞社・通信社の記者たちが集まるという異例の事態となった。
我々報道陣が待ち構えていたのは、1台の車両運搬車。そこには、三菱「eKワゴン(スポーツ仕様のeKカスタムを含む)が2台、同「eKスペース」が1台、合計3台の軽自動車が搭載されていた。
この3台は、石井啓一国土交通大臣が4月26日の会見で述べた通り、28日に設置の同省自動車局と独立行政法人・自動車技術総合機構による「三菱自工の燃費不正問題」に対応するタスクフォースの指示により、三菱自工が持ち込んだ車両の一部だ。
これら車両を使って、交通研が5月2日から「型式指定の燃費試験」を行い、その結果はタスクフォースが6月中に発表予定の「取りまとめ」の中で明らかになる。その初日の試験が始まる前の時間にあたる、午前7~8時にかけて、報道陣向けに「燃費・排出ガスの確認試験の実施について」と題して、走行抵抗値の測定試験(惰行法)の説明とデモンストレーションが行われた。
● 異例の、国による走行抵抗の測定試験 錯綜する報道のなかで規定と技術を再確認すべき
一連の三菱自工による燃費不正問題。その発端は、同社が20日に記者会見で発表した「実際より燃費を良く見せるため、型式指定の燃費試験に際して提出を求めている走行抵抗値について不正行為を行っていた」(国交省HPの石井大臣談話より抜粋)ということだ。
そして三菱自工は、その不正行為とは、国が定める「惰行法」ではなく、アメリカ市場向けの「高速惰行法」を採用し、それを基に走行抵抗値を算出し、さらにそれら値を意図的に操作し、実際の燃費よりも優れた値が出るようにした、と説明した。
この20日の会見以来、メディアでは「燃費不正フィーバー」状態となっており、その多くが、不正はいつから、誰の指示で行い、経営陣を含めて社内でどのような意思決定プロセスによって決まったのか、といった「犯人探し」の視点で報じている。そのなかに、技術論が中途半端な状態で散りばめられているように感じる。
そこで本稿では、認証審査を行なう交通研の説明を基に、議論を規制、規定、そして技術に集約したい。
● 燃費と排出ガスの試験は同じ!? 「惰行法」測定はメーカー任せ
まず、「型式指定」とは何か。自動車メーカーが自動車を発売する際、エンジンの仕様や車体構造の変更が伴う場合、新しい「型式」を国から得る必要がある。そのために、国が定める衝突安全試験、燃費試験、排ガス試験などの規定にクリアし、認証されなければならない。
その審査を行なうのが、交通研だ。本部と研究施設は東京都調布市にあるが、自動車認証審査は、テストコースと各種審査用の機器設備がある熊谷市の自動車試験場でのみ行っている。
前述のように、交通研が今回行なった確認試験は、燃費と排出ガスに対するものだ。つまり、両者の試験方法の流れは基本的に同じなのだ。
その試験は大きく2つのステップに分かれる。ステップ1は、走行抵抗値の測定。これは自動車メーカーが各社の所有地内などで、実車を使って行う。得られたデータを交通研が指定する用紙に書き込み、保安基準など「型式指定」に必要な他の用紙と共に電子ファイルで、自動車メーカーが交通研に提出する。
ステップ2は、交通研が走行抵抗値データを、台上試験機(シャーシダイナモメーター)のソフトウエアに打ち込む。同機器は、再現性と公平性を重んじるために使用し、ローラーの上でクルマの駆動輪がその場で回転する仕組み。こうした走行において、日米欧それぞれで各地の走行実態を反映させた「モード」を設定している。日本では「JC08(ジェイシーゼロハチ)モード」で測定する。
このような流れのなかで、自然環境のなかで行なうため、手間と時間を要するステップ1の「走行抵抗値の測定」について、国は自動車メーカーの自主性に任せてきた。そのなかで今回、不正が起こったのだ。
交通研・自動車認証審査部からは「シンプルな試験であり、そこで不正が起こるとは想定していない」と本音が漏れた。
● 惰行法は「国とメーカーの信頼」で成り立つ 自前の「高速惰行法」をかざす三菱自工の功罪
交通研が「シンプル」という、「惰行法」による走行抵抗値を求める試験。試験結果の記入書式には、上から90、80、70、60、50、40、30、20km/hと8つの指定速度がある。それぞれの指定速度に対して、往路と復路それぞれ3回の惰行時間、それらの平均惰行時間を計測、そこから走行抵抗を求めるという流れだ。
まず、指定速度に対する惰行時間とは、指定速度を中央として前後5km/hでの10km/h域の通過時間を指す。例えば、指定速度70km/hの場合、75km/hから65km/hに減速するまでの時間だ。
実際のデモには「eKカスタム」を使った。ルーフにGPSアンテナ、車内には車速計、パソコン、計測データ確認用の大型ディスプレイなどを交通研が装着した。
コースは、全長1200m×幅60mのアスファルト路面の直線路。その両端にある角度が急なバンクコーナーで加速。直線路に入ってから、ギアをニュートラルに入れて惰行開始だ。
最初の指定速度90km/hに対応する、95km/h時点で後席に乗る係員が計測スイッチを押す。続いて、85km/h、75km/h、65km/hに減速した時点で計測スイッチを押していく。だが、直線路が短いため、車速が60km/h程度で計測を一旦中断。これを2往復・4回行なった。
次に、初速65km/hから20km/hまでの1往復・2回、さらに初速45km/hから1回、合計7回走行した。
つまり、自動車メーカー所有を含めて、直線路の全長が1km程度の一般的なテストコースでは、8つの指定速度での惰行時間を一気に計測することは不可能なのだ。
「8つの指定速度を何回に分けて取るべきという規定はない」(交通研・自動車認証審査部)という。
試験の条件として、最も重要視されるのは、走行抵抗に直接的な関与する風の影響だ。規定では、直線方向に毎秒5m以下。風の影響を加味して、最低3回往復する。また、直線路に対して垂直方向に毎秒2以下としている。
だが、路面状況に対する規定は特にないなど、自動車メーカー側にとって「ある程度の自由度」があり、事実上の「抜け道」はいくつかあるように感じる。
こうして計測した平均惰行速度を基に、走行抵抗値を求める。計算式は、走行抵抗値=(1.035×試験車重量)÷(0.36×平均惰行時間)。得られた走行抵抗値をY軸に、各指定速度をX軸にとり、二次曲線を描き、「空気抵抗+ころがり抵抗×速度の二乗」という走行抵抗値を決める。なお、走行抵抗値は、大気圧や気温による補正を行い、摂氏20度相当の値を採用している。
今回の三菱自工による燃費不正では、達成目標とする燃費を出すための走行抵抗式を想定し、それを実現するために各指定速度での惰行時間を捏造したい疑いがある。また、「型式」が違えば、走行抵抗の計測試験はそれぞれの車種で行なうべきだが、それを怠っていたことはすでに三菱自工側が認めている。
交通研側は今回、走行抵抗値の計測試験について「メーカーへの信頼の上に成り立つ」と繰り返し言った。そのうえで「今後は、自動車メーカーが行なう走行抵抗試験に交通研が立ち会う方向で調整している」(自動車認証審査部)と、試験に対して「信頼関係を見直すこと」を示唆した。
もう1点気になることがある。三菱自工の会見で「惰行法ではなく、アメリカ市場向けを考慮した高速惰行法」との発言があった。ところが、交通研・自動車認証審査部は「高速惰行法という言葉を聞いたことがない」とキッパリ。つまり、これは三菱自工の社内用語、または一部の自動車関係者が使う俗語だ。
また、アメリカの場合、米自動車技術会(SAE)が2008年3月に規定したJ2263のなかで、「惰行法」に相当する「Coastdown Method」がある。その場合、計測開始の速度は毎時80マイル(128km/h)であり、日本との規定に差があることは事実だ。
ただし、「三菱自工の高速惰行法は、(SAEの)アメリカ規定でもないオリジナルのようだ」(交通研関係者)との声がある。
● 燃費・排ガスで世界調和の重要性高まる だから、この時期、国は焦っている
国としては、三菱自工の燃費不正問題がこのタイミングで表面化したことを苦々しく思っていることだろう。
なぜなら、国連による自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において2014年3月、乗用車の燃費と排出ガスについて国際調和(WLTP:ワールドワイド・ハーモナイズド・ライト・ヴィークル・テスト・プロシージャ)が採択され、日本では2014年6月24日に閣議決定した規制改革実施計画のなかで、JC08からWLTPへの早期移行を決めているからだ。
現在、日本でのJC08モード、アメリカでのLA4モード、そしてEUでのNEDCと、排出ガス・燃費の試験方法は国や地域で異なっている。アメリカのCAFE(企業別平均燃費)や欧州CO2規制などが厳しさを増すなか、排出ガスと燃費における世界統一が急がれる。
そうした社会背景のなかで、独フォルクスワーゲンの排出ガス不正問題が発生。さらに、今回の三菱の燃費不正問題が後追いした。また、「WLTPのなかで、走行抵抗値を計測する惰行法についても、規定を世界統一する方向で現在調整している」(交通研・自動車認証審査部)と明らかにした。
日本政府としては、三菱自工の事案について早期に原因を究明し、厳しい行政処分を課すことが、WLTP移行に伴う世界各国に向けた「信頼の回復」に繋がるはずだ。
桃田健史
フランス産と中国産の品質にどのくらいの違いがあるのか?業界団体はこの点について説明してほしい。品質に大きな違いがないのであれば、
良い品質の中国産で価格が安ければそれで良いと思う消費者もいるはず。
フランス産が単純にブランドやステータスだけの事であれば、フランス産にこだわらない人もいるだろう。
結局、お金にゆとりのある人、羽毛布団にこだわりのある人、違いがわかる人意外は、安い羽毛布団でも良いのではないのかと下記のサイトを読んで思いました。産地偽装は素人には見抜けない事。信用できる会社であるのかさえも、素人にはわからない。他の商品の中には、余り安くしない方法があるそうです。多くの人が安すぎる商品は問題がないかと疑うからとの理由です。だから、値段を手ごろな値段よりも少し安くすると売れた安いワインの話を読んだ事があります。
結局、嘘やインチキが多くなると、人間性やモラルのある会社にゆとりがある消費者は戻っていくのでしょうか?
羽毛布団の製造業者など約100社でつくる日本羽毛製品協同組合(東京)が、羽毛の原産地の偽装表示が横行している可能性があるとして、加盟各社に適切な産地表示を求める警告文書を送っていたことが7日、分かった。フランス産としている羽毛布団の「半分以上は偽装と思われる」としている。
組合によると、羽毛布団の国内販売枚数は約320万枚で、約半数がフランスやハンガリーなどの欧米産として販売されているという。しかし財務省の統計では、2015年の羽毛の輸入実績は中国が最も多く、完成品の布団として輸入された約190万枚のうち約165万枚を占めた。また国内での製造に使う原料の羽毛も約48%が中国産だった。
文書は2014年5月と15年1月の2回出された。1回目は原産地の適切な表示を要請。しかし、改善されなかったとして2回目は、原産地の偽装は「景品表示法違反や詐欺罪が適用される」と指摘、法令順守の徹底を求めた。
海外の産地が偽装された羽毛布団が流通している疑いがあり、業界団体が検査の厳格化を検討していることがわかった。
羽毛布団メーカーなどでつくる、日本羽毛製品協同組合によると、国内で1年間に販売される羽毛布団320万枚のうち、およそ半数で、羽毛の産地として欧米が表示されているが、輸入実績などから、価格の安い中国産を混ぜるなどして販売が行われている可能性があるという。
日本羽毛製品協同組合・山本正雄専務理事は「販売価格が競争の世界に入ってしまって、値段を通すために原料のところで、そういう調整があったのではないかと危惧している」と話した。
組合は、これまで、加盟社に対し、フランス産との表示は「半分以上は偽装と思われる」、などと警告する文書を出して、適切な対応を求めているが、改善が見られないことから、検査の厳格化などの対策を検討している。
「同整備局は結果的に東亜の偽装を見抜けなかったが、工事の確認方法について、加藤部長は『不正を前提にしておらず、受注者を信頼していた。必要であれば見直しを考えたい』と話した。」
「不正を前提にしておらず、受注者を信頼していた。」との理由で偽装を見抜けなかったのだから見直しが必要なのでは??
誰が「見直し」を判断するのか?「必要」とはどのような基準や定義において必要と判断されるのか?単純に見直しするつもりはないが、言葉の飾りとしての追加文章??
羽田空港C滑走路の地盤改良工事を発注した国土交通省関東地方整備局は6日記者会見し、改ざんの詳細な経緯や是正工事の計画を早急に提示するよう東亜建設工業に求めたことを明らかにした。加藤雅啓港湾空港部長は「事実関係を確認した上で、しかるべく厳正な措置をとりたい」と述べ、刑事告発の検討も示唆した。
同整備局が過去10年で発注した同様の地盤改良工事で東亜が携わったのは計8件で、他の工事でのデータ改ざんがなかったかどうかを来週中に報告させるとしている。
同整備局は改ざん発覚後、C滑走路で航空機が着陸する際の衝撃を再現した試験を実施。安全性が確認されたため通常の運用に問題はなく、運航制限はしないという。
工事は薬液を注入する管を地中に275本通す計画だったが、指示通りの場所に通した管は一本もなかった。地中に障害物があり、工事が難しい場合は事前協議する方針だったが、相談は一度もなかったという。
工事中も同整備局の職員が現場にたびたび立ち会い、薬液の注入量などを示すモニターを確認していたが、東亜はモニター表示を改ざんし、計画通りに工事をしたという虚偽報告書を出した。
同整備局は結果的に東亜の偽装を見抜けなかったが、工事の確認方法について、加藤部長は「不正を前提にしておらず、受注者を信頼していた。必要であれば見直しを考えたい」と話した。
羽田空港のC滑走路で、巨大地震に伴う液状化現象を防ぐための地盤改良工事で施工不良があり、これを隠蔽する施工データの改ざんが行われていたことが6日、わかった。
施工した中堅ゼネコン「東亜建設工業」(東京都新宿区)が明らかにした。同社東京支店長(当時)の判断で仕様書通りに施工したかのようにデータを書き換え、発注者の国土交通省に報告していた。
同省は、C滑走路の通常利用に安全上の問題はないとする一方、現状では液状化対策が取られていないため、同社から原因究明や再発防止策の報告を待ち、再工事の実施を検討する。
同社や同省関東地方整備局(横浜市)によると、工事は同社が主体の共同企業体(JV)が約33億円で受注し、昨年5月28日~今年3月18日の工期で施工した。
施工不良があったのは、同社の担当区域のうち、幅60メートルあるC滑走路北西端の長さ計75メートルの地盤。同社は独自工法の「バルーングラウト工法」を採用。滑走路脇から滑走路直下へ地中を斜めに掘削して管を通し、薬液計約1250万リットルを注入する計画だった。薬液を地中に注入すると、地下水がゲル化して直径約2メートルの球状の塊(バルーン)となり、地盤を強固に改良するものだった。
しかし、地中に想定外の障害物があったことなどから掘削がうまくいかず、地中に275本の管を通すはずだったが、231本にとどまり、いずれも計画位置とずれていた。このため薬液も予定の5%程度の約67万リットルしか注入できず、計1万450個できるはずだったバルーンも5825個だけで、直径2メートルまで膨らんだものは一つもなかったという。
同社などの工事担当者らは昨年9月に同区域で工事を始めて間もなく問題を把握したが、当時の東京支店長で現常務執行役員(60)の判断でデータを改ざん。後任の東京支店長(58)も改ざんを続け、工期中、複数回あった同整備局の検査の度に、薬液の注入量や地盤強度の数値を仕様書通りに報告書類に記入していた。
今年4月14日、2次下請け会社の作業員が1次下請けに報告して問題が発覚。常務執行役員は「失敗の許されない工法で、プレッシャーがあった」などと話し、改ざんを認めたという。同整備局は「一貫して虚偽データを報告され、見抜けなかった」としている。
東亜建設工業は6日、松尾正臣社長らが横浜市内で記者会見して陳謝。松尾社長は6月の株主総会後に代表権のある会長に就任予定だったが、任期満了前に辞任し、会長にも就かない意向を示した。常務執行役員ら改ざんに関わった社員の処分も検討しているという。
同社は同様の工法で福岡、松山空港の工事も行ったというが、「詳細は調査中」と説明しており、同省は両空港についても調査・報告を求めている。福岡空港では熊本地震による影響は確認されていないとしている。
三菱自動車が燃費試験データを操作し、主力軽自動車の燃費をかさ上げしていた。測定方法は、25年前から道路運送車両法の規定に違反。問題車種の販売停止で、4月の軽販売台数はほぼ半減した。2000年、04年のリコール(無償回収・修理)隠しに次ぐ3度目の不正で、三菱自は存続の危機にひんしている。全容解明では、不正の広がりと経営陣の関与の有無が焦点となる。
◇5回引き上げ
国土交通省は、不正の再発防止に向け燃費審査の体制強化に着手。2日からは外郭団体「交通安全環境研究所」で三菱自が不正を認めた4車種の燃費・排ガスの再試験を始め、「6月中に結果を公表する」(藤井直樹自動車局長)方針だ。この結果によって同省は、量産に必要な国の型式指定を取り消す必要があるか判断する。
三菱自がデータを操作したのは、タイヤと路面の摩擦や車体が受ける空気抵抗で決まる「走行抵抗値」だ。13年6月に発売した「eKワゴン」(日産自動車名「デイズ」)の最良燃費タイプの開発では、当初はガソリン1リットル当たり26.4キロだった燃費目標を、社内会議の承認で5回も引き上げ、最終的に29.2キロとした。これを国の試験で達成できるよう、実測値の中央値ではなく、有利な走行抵抗値を意図的に選び提出していた。
さらに派生タイプと一部改良タイプでは走行抵抗値を実測せず机上で算出。目標燃費から逆算してデータを作っていた。最良燃費タイプとつじつまを合わせた疑いもある。
燃費目標の引き上げをめぐって、中尾龍吾副社長は「開発責任者が可能と結論を出した時に提案する。上からやれという格好ではない」と説明しつつも、「結果から見れば、プレッシャーがかかった」と認める。
◇違反は数百万台?
測定方法の規定無視は25年前にさかのぼる。中尾副社長は「1978年から『高速惰行法』で走行抵抗値を出し、91年に日本の測定法が『惰行法』に変わったが(対応)しなかった」と説明。相川哲郎社長は「これでいいと思ってやり始めたのが伝承された可能性もある」と推定するが、01年には二つの方法でどの程度の差が出るか計算しており、遅くともこの時期には違法性を認識していた疑いがある。
測定方法が違反だった車両について、三菱自は「調査中」と繰り返し、正規の方法で測定したと明言するのは「アウトランダーPHEV」などわずか3車種にとどまる。91年以降の国内販売車は70車種を超え、数百万台規模に上る。
◇「いい軽」責任者
相川社長は「いい軽(eK)」をつくろうと01年に発売した初代「eKワゴン」で開発責任者だった。測定方法違反については「全く承知していなかった」といい、「(走行抵抗値測定は)実務的な仕事で担当部署以外は通常関与しない。知らないと開発の取りまとめができないわけでない」と釈明している。
不正への組織的関与の有無は、外部の弁護士による特別調査委員会の解明を待つことになる。相川社長は「特別調査委の報告を聞くまで社長の責任を果たす。会社の存続に関わる大きな事案だ」と当面続投し、問題の収拾後に進退を明らかにする考え。燃費目標の引き上げを重ねた当時の社長だった益子修会長とともに経営責任は不可避だ。三菱自は11日までに、不正の調査状況を同省に再報告する。
今日もテレビで韓国の加湿器殺菌剤被害が取上げられていた。企業にも責任があるが、行政にも責任があるとテレビのある人がコメントしていた。
日本では同じ、又は、同等の製品は流通していないそうだが、英国に本社を置く多国籍企業レキットベンキーザー(Reckitt Benckiser)及び韓国法人、オキシー・レキットベンキーザー(Oxy Reckitt Benckiser)の対応には不信感を抱く。運良く、日本で販売されていないだけで、日本で販売されていたら行政は問題に気付いただろうか?疑問である。
「殺菌剤の生殖毒性に関する研究を実施したソウル大学教授A氏に研究費のほかに、数千万ウォンの裏金を与えたことが明らかになった。」との事実も衝撃的だ。ソウル大学は日本で言う東大のような大学。その大学の教授が裏金を貰っている。まあ、日本でも迂回とか、間接的に似たような事があるかもしれないので、韓国だけを批判できないが、この世の中、お金は強いと言う事なのか??
韓国の行政の対応が遅いのには驚いた。これが普通なのか、それとも、特別な例であるのだろうか?
桜が咲き乱れていた2006年の春。
ソウルの有名な総合病院の一つであるソウルアサン病院で勤務していた洪(ホン)・スジョン教授(小児青少年呼吸器アレルギー科)は妙な既視感を経験した。毎年、冬から春に移る時期に理由の不明な奇病性肺疾患の患者たちが相次いで病院に運ばれてきた。肺繊維化(肺が硬くなって呼吸ができない状況)が深刻に進行されて顔が真っ青になった赤ん坊たちは、抗生剤を使った治療も甲斐なくこの世を去り、親と医師団は無力感にさいなまれた。
「なぜ同じ時期に原因不明の疾病が広がるのか?」この疑問に対する答えを探すため、洪教授は同僚の医師らと自分が担当した15人の乳幼児患者の事例を集めて論文を書いた。しかし、学界は「原因不明」とみなした。しかし翌年にも患者の名前が変わっただけで、同じことが再び繰り返された。彼が二番目の論文を書いて伝染病などの予防責務を負った国家機関である疾病管理本部(ジルボン)にこのような状況を報告して全国的なモニタリングを要請したが、「特定のウイルスではなさそうだ」との安易な答えが返ってきたのみだった。
それから4年が過ぎた。今回は免疫力が低い乳幼児患者ではなかった。 今回は妊婦達だった。重患者室に入院して人工呼吸器に頼っていた患者らはお腹の子供たちとともに死亡した。2011年4月、ソウアサン病院は、正式にジルボンに調査を要請した。ジルボンと保健福祉部はやっと問題の深刻さに気づき、大々的な調査を行ったが、胎児を含む少なくとも142人がすでに病名さえわからないままこの世を去った後だった。
『空気中に漂う「何か」が気管支に入り炎症を誘発し、気管支が閉塞して呼吸困難の症状に陥る。(その結果)呼気が体外に排出されず、肺の圧力が高まって肺に深刻な損傷が生じ、患者は死亡する。』洪教授の仮説は数回の実験や疫学調査を通じて立証された。
その何かとは「加湿器殺菌剤」であることが明らかになった。正確には殺菌剤に入った有毒物質である「PHMG(ポリヘキサメチレングアニジン)」が呼吸器を壊したと報告された。同年8月、ジルボンは「加湿器に入れた殺菌剤が肺の組織に傷を負わせた要因と推定される」と発表し、大型スーパーなどでの加湿器殺菌剤の販売を禁止した。
その時から再び5年が経った2016年の春。昨年10月から同事件を捜査し始めたソウル中央地方検察庁は先週から加湿器殺菌剤を製造・販売したオキシー・レキット・ベンキーザー(以下、オキシ― Oxy Reckitt Benckiser : 現RBコリア)ら会社関係者らを呼んで、業務上過失致死容疑について調査している。
被害者や遺族など110人余りが殺菌剤の製造会社を告発してから3年ぶりのことだ。しかし、主な被害者らの死亡から10年が経った今になって始めたためにまともな証拠が残っていないという点が問題視されているが、捜査関係者によると、この会社の元代表の身柄拘束もありうる、と報道されている。
このように検察が乗り出すと、被害者が一番多いオキシーは被害者たちに「申し訳ない」と頭を下げた。被害者と遺族のために100億ウォンを出したが、むしろ逆風を浴びている。余りにも遅すぎた謝罪のためだ。特に、加湿器殺菌剤のマーケットシェアが一番高かったオキシーは死亡・負傷の被害者も多いにもかかわらず、責任を取ろうとしない態度を見せて非難の対象となった。「黄砂・花粉・間接喫煙なども肺の損傷の原因になるかもしれない。加湿器殺菌剤は人々の死とは因果関係がない」という内容の報告書を検察に提出し、弁明していた。
また、殺菌剤の生殖毒性に関する研究を実施したソウル大学教授A氏に研究費のほかに、数千万ウォンの裏金を与えたことが明らかになった。そして多くの韓国人は、英国系企業であるオキシー製品の『不買運動』を開始した。
しかし全国的な不買運動が繰り広げられても、被害者と遺族の心にはしこりが残るはずだ。オキシーをはじめ他の製造販売会社(ロッテマート、ホームプラス、テスコ、イーマートなど)が、検察捜査の前に一言の謝罪もなく5年間この事件を放置したからだ。幹部らが検察に出頭するまで公式な謝罪の発表を引き延ばし、しぶしぶ開いた記者会見で頭を下げる企業の姿を市民団体は『謝罪のコスプレ』と呼び、問題視している。今後の刑事・民事裁判や賠償まで含め、この企業幹部らが心からの謝罪をするのかまだ疑問だ。生活用品に殺された人々の戦いはまだ終わらない。
(編集部注:レキット・ベンキーザーの幹部は5月2日、同社製の殺菌剤が原因で肺が損傷し死者を出した問題で、謝罪会見をソウル市内で開いた。同社が公に責任を認めるのは初めて。)
【参考】
◆会社別の被害状況(出処:ソウル中央地検)
オキシー・レキット・ベンキーザー 177名(内、死亡 70名)
ロッテマート 41名(16名)
ホームプラス 28名(12名)
セピュー 27名(14名)
◆韓国の加湿器殺菌剤とは?
加湿器の噴霧液に添加して加湿機噴霧液を殺菌する物質。これに含まれた毒性物質はPHMG、PGH、CMIT、MITなどだが、皮膚に毒性が他の殺菌剤に比べて5~10分の1程度に過ぎず、シャンプーとウェットティッシュなどに使用されるが、呼吸器でこれらの物質が吸入される場合に発生する毒性については2011年までに、きちんとした研究が実施されず被害を増幅させた。
現在PHMG、PGH成分は、有害性が確認された状態だ。 PHMG系列にオキシーサクサク(オキシー・レキット・ベンキーザー)、ワイジュルレク(ロッテマート)、ホームプラス(ホームプラス)があり、PGH系列にはセピュ(バタフライエフェクト)、そしてMCIT系列には、愛敬(エギョン)加湿器メート(エギョン)、イープラス(イーマート)などがある。
◆オキシー・レキット・ベンキーザー(Oxy Reckitt Benkiser)
英国系生活用品メーカーのレキット・ベンキーザーグループが2001年、東洋化学グループの系列会社であるオキシーの生活用品事業部を買収し、設立した会社。
イ・スミン(韓国大手経済誌記者)
日本大学教授 堅尾和夫
三菱自動車でまたも、不正行為が発覚した。激しい国際競争が続く自動車業界で、同社は技術力やデザイン力、生産性などで先頭集団の 後塵 こうじん を拝していたと言われる。そうはいっても、発覚すれば市場退場もありうる不正になぜ手を染めてしまったのだろうか。元通産官僚で自動車環境対策にも携わった日本大学の堅尾和夫教授が、どの自動車メーカーでも起きうる不正の発生メカニズムと、形骸化しているという国の指導行政にメスを入れる。
三菱自動車は何をしたのか
三菱自動車株式会社の相川哲郎社長が4月20日の記者会見で、実際よりも燃費を良く見せる不正行為をやっていたことを明らかにした。車にそれほど関心がなくても、「またか」という感想を多くの人が抱いたと思う。
伝えられるところによると、燃費不正の対象は軽自動車4車種で、これまでに62万5000台が販売された。もちろん対象車種は直ちに生産販売が中止されたという。
厳しい燃費競争の中で劣後にあったための「焦りの末の不正」、あるいは2000年以降に発覚したリコール隠しを念頭に「相次ぐ不正」と報道されている。
同社が発表した対象となる4車種に限っても、ユーザーに対して余計に消費したであろうガソリン代の補償、エコカー減税の返還、さらには買い取り請求に今後応じるとなると数千億円規模になるとの試算もある。これは同社の15年3月期の最終利益(1181億円)、数年分にも匹敵する。
外部有識者による第三者委員会を新設し、原因究明にあたるといわれているが、続報では他の車種についても規定の方法で計測していない、あるいは机上の計算で済まして申告しているなどの疑惑が浮かんできている。
こうなると、2、3か月程度で全容が解明できるかどうか甚だ疑問で、この問題は長期化することは必至の情勢である。再び三菱自動車の屋台骨を揺るがすことになるかもしれない。
不正の対象となった軽自動車は、11年に設立された三菱自動車と日産自動車の合弁会社で企画・開発された。開発・生産は三菱側が請け負い、日産側はOEM(相手先ブランドによる生産)を受けて販売するという形態で、販売台数は日産ルートの方が多い。三菱自動車が国土交通省に4月26日に報告したところによると、社内会議において設定された燃費目標値が、14型「eKワゴン」「デイズ」は当初(11年2月)、リッター当たり26.4kmだった。それが短期間に、幾度か段階的に引き上げられ、最終的(13年2月)には同29.2kmにまで引き上げられている。
これから生産・販売しようと計画された車のスペックは、日産も合意のうえで設定されているはずだ。開発は三菱が担ったとはいえ、こうした目標値の短期間の引き上げは、日産サイドの要求や競合他社の開発動向などが背景にあったはずである。
14型「eKワゴン」「デイズ」は13年6月、合弁事業で最初に開発された軽自動車として世に送り出された。
再建、選択と集中どころか自壊の危機
三菱自動車は長年のリコール隠しが00年と04年の2回にわたって発覚した。経営陣の刑事責任まで追及されるにおよび、提携先のダイムラーからも支援を断られ、倒産の窮地に立たされたことを覚えておられる方も多いと思う。その倒産の瀬戸際に三菱重工業、東京三菱銀行(現・三菱東京UFJ銀行)、三菱商事を中核とする三菱グループが救済に名乗りを上げ、同グループの支援のもと再建に乗り出したのである。
同社の業績は、14年度までの最近3期には過去最高の利益を記録するまでに回復してきていた。これは生産車種の絞り込みや海外事業の再編などのコスト低減の取り組みの効果があったからだと思うが、最近の為替の好転に支えられている側面も多分にある。
BR>
15年度は、為替相場の好転による効果はなくなった。それとともに、劣勢となっている日本国内市場の立て直しが急務となっていることや、世界市場、とりわけ同社が今後注力しようとしている東南アジア諸国連合(ASEAN)やロシアの経済低迷によって、同社のかじ取りには暗雲が垂れこめてきていたといってもいいであろう。
その矢先の今回の不正発覚である。
BR>
燃費不正の対象車種が今後、SUV(スポーツ用多目的車)や乗用車などに拡大するようであれば、海外のユーザーからも各種の補償要求や、規制当局からの高額のペナルティーが同社に賦課されるといったことも懸念される。
BR>
競争環境下で劣後となった焦りなのか?
国内外の自動車メーカーが世界の市場で、燃費性能や排出ガスのクリーン度、衝突安全性などについて激しく競争し、消費者に自社製品の優秀さをアピールしている。政府の規制も年ごとに厳しくなり、規制値を大きく達成した車には税制上の恩典を与え、競争上優位に立つよう支援・誘導している。今回の不正行為は、このように国自らがその製品の普及に関与するという業界特有の事情が生み出したものなのだろうか?
昨年、米国で発覚したドイツの自動車メーカーVW(フォルクスワーゲン)の不正排ガス制御ソフトによる規制逃れも、その悪質さと規模の大きさ、さらにVWの名声から世界に衝撃を与えた。VWのようにトヨタと世界市場で生産台数を競い合う大企業であっても、置かれている市場の競争条件によっては競争劣位になり、不正手段によってしか対処できないほど、社内の開発等の部署に大きな圧力がかかってしまったのだろうか?
三菱自動車は、他社に比して圧倒的優位に立つ技術やデザイン力、生産性などの武器となるものがなく、軽自動車市場でスズキとダイハツの2強に追い詰められたため、こうした圧力ははるかに大きなものとなっている。それゆえ報道にあるように、長年にわたって不正に手を染めて窮地をしのいでいたのであろうか?
調査はこれからで真相は明らかになっていないが、これらの仮説が事実だとすると、競争劣後になっている国内外の他の自動車会社でも同様の不正手段によって、急場をしのごうとする焦りが恒常的に働いているかもしれないのである。
BR>
こうした観点に立ち、これまでに伝えられた三菱自動車の発表から、今回の問題点を考えてみたいと思う。
ガバナンスの欠如だけでは済まない怠慢
三菱自動車の発表では、原因と責任の所在について調査を続けていくとしている。
このような不祥事が明らかになった時、責任の所在は明らかにするものの、「組織ぐるみではない」として、責任を特定の部署、あるいはその責任者に局在化しようとすることが過去多くみられた。今回もそのような意図を感じさせる。
「トップは知らない」「指示していない」「組織ぐるみではない」「ただし監督責任、道義的責任は認める」という具合である。しかしながら、リコール隠し以来、再度の不正を防げなかった、あるいは同時並行で行われていたかもしれない不正を正すための社内の組織、体制、社員教育などが不十分であったということだけでも、社内の経営陣の怠慢は明らかである。
国の監査体制にも問題があることが判明したと思う。こういう場合、監督官庁は決まって、「我々は騙だまされた」「けしからん」とばかり、自らは「正義のナイト」としてふるまう。
監督官庁として会社に追加情報の報告を求め、時には他社にも同様に調査・報告を指示するのが通例であり、これは至極当然のことであるかもしれないが、国の制度運用そのものに問題はなかったのだろうか。国土交通省は、燃費不正があったとされる4車種について自ら測定に乗り出した。しかし、こんなことでこれまでの制度運用の問題が改善されるのであろうか?
BR>
これまでの経緯を振り返ると、以上のような疑念を抱かざる得ないのである。
燃費実測の現場に直接、検査官を派遣して計測法や実測データの有無、その処理の仕方などを調べれば、もっと早い段階(販売前)に是正できたはずである。メーカーの申告データをそのまま受け取って書類審査だけで済ませているようにも思える。今回の三菱自動車の発表から、型式承認という行政事務がいかに形骸化しているか覗い知れるというものである。
間違いに真剣に向き合え
人間が、あるいは人間の集合体である組織が、達成しようとした目標から意図せずに逸脱してしまい、期待に反した行動をとってしまうことを「ヒューマン・エラー」という。
その特徴は、一生懸命やったのに、導かれた結果が間違いになるということである。
この場合、当事者や当事者が属する組織は、「間違ったことをしてしまった」という記憶ではなく、「一生懸命に会社のためにやったのに」という記憶しか残らない。不正に直接関与していない周辺の人間も、同一組織の人間として、こうした認識を無意識に共有する。「努力の仕方にもう一工夫必要だったかもしれない」という反省の仕方をするのである。
したがって、責任者を探し出して、あるいは決めつけて処罰しても、再発防止はできない。後から再び、会社のために、あるいは自らの立身出世のために「一生懸命」やる人間が出てくるし、会社も相変わらず、そういう人材を求め、育成し続けているからである。
肝心なことは、間違ったことをした、あるいはそれが組織として通ってしまった背後要因を探求し、それを排除することが必要なのである。
自動車会社各社は、最新の技術を駆使し、高機能を搭載した車の開発にしのぎを削っている。どこの会社も、そういう開発部署や開発を支援する部署には、経験豊富な熟達の技術者や監督者を配置しているはずである。
しかし、こうしたセクションは仕事の性格上、秘匿性が高く、部外者の目がなかなか届かないところでもある。その結果、同じ仕事を長年繰り返していることによる慣れ、仕事の内容をよく知っていることからくる「この程度なら許される」という臆測や思い込み、頻繁な目標数値の上方修正にも期限内にいつもうまく対処してきたとうい自惚うぬぼれ、独善的に仕事の要不要を断じて「現在の経営幹部が現場にいた昔からやっていたことだ」などといった自己正当化が得てして、組織内に醸成される。
そこから、ヒューマン・エラー発生の連鎖が始まるのである。
組織の失敗は一般的に、監視や設計、製造(製造、組み立て、設置)、オペレーション、保守・点検、危険兆候の見落とし、リスク管理(リスクの把握・評価と低減失敗)、教育訓練(経営方針、目標などを含む)などの各段階で生じる可能性がある。
特に、三菱自動車の長年の不正行為には、監視やオペレーション、危険予知と是正、教育訓練などの段階のチェック機能が不備、または存在していなかったように感じる。
会社が設置するとしている第三者委員会では、単に原因と責任の所在を明らかにするだけでなく、こうした組織エラーを防止するために何が欠けていたのか、再発を防止するための対策はどうあるべきかについて、踏み込んだ分析と提言を期待したい。
提言を受けて、三菱自動車がそれを実行し、信頼を回復するには多くの努力と時間を要するかもしれない。あるいは、もうそうした余裕は残っていないかもしれない。「市場から退場せよ」という厳しい声も聞かれるが、自動車業界はじめ他の業界各社も、今後の改革に向けた教訓として肝に銘じてもらいたいと、切に願う。
英国に本社を置く多国籍企業レキットベンキーザー(Reckitt Benckiser)の韓国法人、オキシー・レキットベンキーザー(Oxy Reckitt Benckiser)がとんでもない事件を起こしている。朝のテレビを見ていたら70人も死亡している加湿器殺菌剤が取上げられていた。70人以上も死亡するまで問題を放置し、ソウル大学に殺菌剤の有害性についての研究データを捏造していたらしい。日本ではこの会社の製品はないのかと心配になって調べてみた。レキットベンキーザー・ジャパン株式会社と呼ばれる支社がある。社長が外国人だから、イギリス本社の資本が入っていると思います。
BBCのニュースでは約100人以上の犠牲者(死亡者)が出た事を本社が認めているようである。ウル大学に殺菌剤の有害性についての研究データの捏造を含めて、この企業の体質を疑ってしまう。個人的な経験から言えば、いくらホームページやカタログで良い事を書いても、実際の企業の体質とは違う場合もある。このような場合、結局、何か(事故や事件)が起きないと一般の人にはわからないことである。この問題が韓国支社内で隠蔽され、本社には一切報告されていないケースでなければ、レキットベンキーザー・ジャパン株式会社について注意したほうが良いと思う。なぜなら、本社は同じなので問題が起きれば同じ、又は、似たような対応を取る可能性がある。日本人従業員が働いているのだから、無茶な事をしないだろうと思うのなら、三菱自動車の燃費不正は起こらないことになる。
多国籍企業レキットベンキーザー(Reckitt Benckiser)であれば企業やブランドイメージが重要である事は理解していると思う。
「検察はオキシーが問題のPHMGの成分が入った加湿器殺菌剤を発売した時点が2000年10月と明らかにしました。」(世界の憂鬱)の情報が事実とすれば、この間に、社長や幹部は変ったはずだ。情報が一切、本社に届かないとは思えない。情報を知ろうとしない、又は、見て見ぬふりをしたと推測する。
レキットベンキーザー・ジャパン株式会社(エン転職)
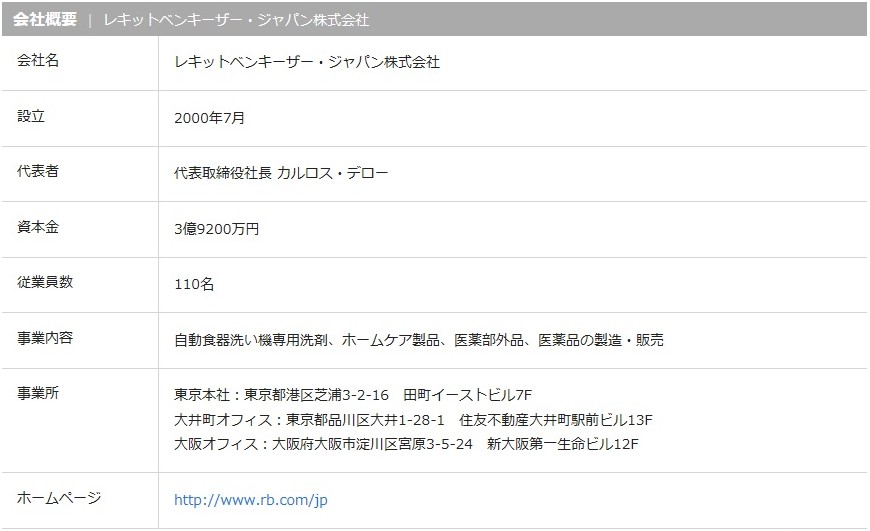
これらの記事の読んだ韓国人の反応の訳されたものを見たが、日本には噛み付くのに、イギリスに対しては日本みたいにおとなしいと思えた。 あと、指摘されたように韓国の行政機関は、製品や商品に対する承認やチェックが甘い、又は、賄賂が効くのかと疑問に思った。韓国は福島の農産物の輸入禁止を取っているが、キットベンキーザーの加湿器殺菌剤が発売されたのが、2001年、多くの死者が出ているのに何をしているのかと思う。公平性や客観性が欠如しているのか?日本もずさんであると思うが、韓国はそれ以上のざる状態、又は、不正が見逃される環境がある言う事なのか?
「検察は、これまで明らかになったオキシーの証拠隠滅と隠蔽行為に対し、英国本社が介入しているか、調べています。」(世界の憂鬱)と書かれているが、適当な捜査になるのではと思う。証拠を集めたとしても、イギリスに本社がある企業に対して法的処分は下せないと思うからだ。韓国国内で登記又は登録されている韓国支社以外に対して法的な処分は無理だと思う。
オクシー・レキットベンキーザーの社長が2日に会見を開き「加湿器殺菌剤による全ての被害者とその家族の皆様に心から謝罪したい」と述べた。
同社は韓国政府が加湿器殺菌剤の有害性を認めた後も、4年半にわたり被害者との面会に1回も応じなかった。その間に被害者らが行った抗議行動は380回以上に上る。また先月にはメディアからの取材要請に対し「被害者の要望をしっかりと理解し(今後もその声を)傾聴したい」という内容と、担当者の連絡先が記載された電子メールを1回送ることしかせず、その対応には全く誠意が感じられなかった。反省の素振りは示しているが、被害者に対してはその傷に塩を塗りつけるような行動しかしなかったのだ。今回の社長の会見も、見方によっては市民団体による不買運動を阻止するため仕方なくやったという印象も受けた。そのため被害者が会社側の誠意を感じるまでには当然のことながらまだ至っていない。
オクシーが加湿器殺菌剤の製造を開始するにあたり、英国本社がどこまで関与していたのか今のところ確認できていない。英国企業に買収される前の段階で、オクシーの担当者らは毒性物質(PHMG)が体内に吸収された影響を調べる実験を計画していたが、これを後に英国本社がやめさせた疑惑も指摘されている。またオクシーが英国レキットベンキーザー社に買収された後、加湿器殺菌剤の有害性に関する資料やデータが隠蔽(いんぺい)あるいはねつ造された兆候も様々な形で露呈している。消費者が同社のホームページに胸の痛みや呼吸困難を訴える書き込みを行うと、これを即座に削除し、ソウル大学に殺菌剤の有害性について研究を依頼した際にも、その結果の中で自分たちに不利な部分は公表しなかった。そのため検察は英国本社の責任についても明確にせざるを得なくなった。
オクシーは「被害者が公正に保障を受けられるよう、包括的な計画を準備していきたい」と表明はしたものの、一方でその対象については「政府が認めた1級と2級の被害者」に限定した。他社製品とオクシー製品を同時に使ったケースや、被害が軽くオクシー製品が原因であることの立証が難しい場合、これらにどう対処するかは明確にしなかった。ちなみに加湿器殺菌剤が原因で死亡したことが確認された143人のうち、103人はオクシーの製品を使用していた。オクシーは今からでも新たな被害者の解明に向け積極的に協力し、また被害が明らかな場合は最後まで責任を取る姿勢を明確に示さねばならない。
オキシー英国本社が有害性を知りながら黙殺。オキシ英国本社の捜査可能か?
英国のオキシー本社が問題を報告されたが、韓国支社の製品販売を黙認したかどうか、検察の捜査が英国本社に拡大されるかに関心が集まっています。
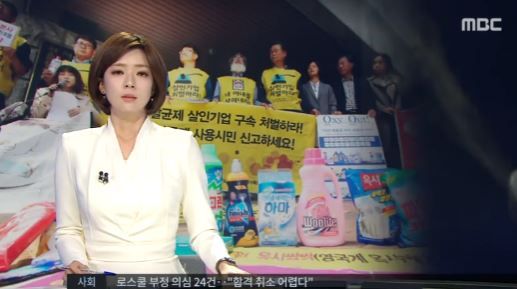
検察はオキシーが問題のPHMGの成分が入った加湿器殺菌剤を発売した時点が2000年10月と明らかにしました。
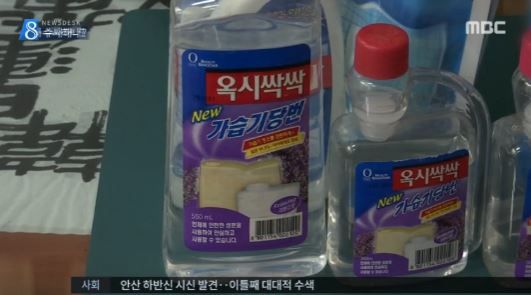
本社である英国レキットベンキーザーがオキシーを買収したのは発売後の2001年3月です。
オキシーが英国レキットベンキーザーに買収される5ヵ月前から問題の殺菌剤を売っていたという意味です。
このような理由で検察は、英国本社に製品開発と販売責任を問うことが難しいという立場です。
検察関係者は「まだ、英国本社の責任があると確定するような嫌疑はつかめなかった」と明らかにしました。

しかし、英国本社がオキシを買収した2001年から2011年まで、加湿器の殺菌剤を販売する際、副作用被害の苦情が相次いで寄せられ、オキシーが本社に有害性を報告したにもかかわらず、これを黙殺したという事実が確認されると、英国本社で捜査が拡大されことができます。
検察は、これまで明らかになったオキシーの証拠隠滅と隠蔽行為に対し、英国本社が介入しているか、調べています。

このような中、加湿器殺菌剤の被害者と家族の会などは「英国本社も製造販売元である」とし、殺人教唆と証拠隠匿などの疑いで本社理事陣8人を検察に告発しました。
この記事を読んだ韓国人の反応
・韓国もまともに検査できなかったのに、よく英国本社の捜索ができるものだね
・オキシーも問題だが、これを安全と販売承認した関連機関も問題ではないか? その当時担当した公務員らの責任は?
・政府も黙殺しました。 本当に残酷だ...(泣)
・英国を相手にできることは不買だけだ
・良心がない企業は未来もない
・これは我々国民を相手に生化学実験をしたのではないか?死んだ人も苦しかったが、生き残った人も生き地獄を味わっている。これが人を殺した生物化学兵器と何が違うんですか(泣)
・毒性物質があるという事実を知りながら、販売中止されるまで年間60万個を売り飛ばした
・ところで英国のメディアはこの事件を報道しているの?
・21世紀に生体実験対象者になっても我々は黙って居なくて成らないのか?
・2-3日前にロッテマートに行ったが、依然としてオキシ製品が、最前列で販促イベントをしていて、勧める人を見ると、情けなく感じました。 こんな商品を勧めるのを見て、くらくらしました。 オキシー製品を勧めないでください
・オキシーはこの国から退出させなければならない企業だ
・私が本当にとんでもないことが、大韓民国食品医薬品安全庁は、一体何を根拠にこの製品の市販を許可したのか?有害性を検査して安全性を確保しなければならない政府機関は、一体何を言ったんだが?
・無条件に買わない、私たちができる報復はそれだけ..
・国民がオキシーに丸太を受けている間、政府は何をしたのか
・人が100以上死んだんですよ、私はもう涙しか出ない
・すでにあの物質は欧州諸国をはじめ、様々な国で殺菌力を持った物質として販売が不可能だった。 しかし、韓国国内には関連法規がないことを知り、販売を開始した。これを例えてみると、オキシーは有害性を知って欧州で制限された物質をまだ国内には制限がないということを知って販売した。つまり有害性があることを知っていたのだ
・オキシーは直ちに、韓国から消えろ
・逆に、我が国企業が英国で同じ様な商品を作って販売し、人が100人が死亡し、500人余りが障害になったら、英国人はどうなさったんでしょうか?
・731部隊の丸太実験を思い浮かべて鳥肌が立つ。オキシーだけでなく、ロッテなど、加湿器殺菌剤製造会社の責任者を全部殺人罪で起訴しなければならない
・米国ならどうなっていたでしょうか?韓国のお粗末な法律が本当に情けない
・米国なら、損害の賠償が天文学的になって会社が倒産するだろう。で、韓国は?
・英国オキシー本社よりこの大きな事件を、これまで報道もしなかったマスコミから叩いて行くべき、検察、警察、政府関係部署大統領府大統領は、いずれもたたかれなければならない
引用元記事:http://goo.gl/pHrAaV
投稿者: 米山 慎吾
韓国でとんでもない事件が起きました。
イギリスの大手トイレタリーメーカー、レキット・ベンキーザーの韓国法人が販売してた液体の加湿器用消毒剤「オキシ―サクサク」(PHMGを使用)を使用して、103人もの人が亡くなってしまいました。レキット・ベンキーザーは日本にも支社をおいていますが、「オキシ―サクサク」は販売していないそうです。事件の原因は、含まれているPHMGと言われていますが、確認してみました。
韓国の事件の経緯
5月2日のAFPで発表された記事はこちらです。
問題が明るみに出たのは2011年、妊婦4人が原因不明の肺疾患で死亡したことだった。その後の政府による調査で、肺疾患と家庭用加湿器の消毒に用いられていた製品との間に「著しい関連性」が認められた。
被害者の大半が、英国に本社を置く多国籍企業レキットベンキーザー(Reckitt Benckiser)の韓国法人、オキシー・レキットベンキーザー(Oxy Reckitt Benckiser)が国内で2001年から販売していた液体の加湿器消毒剤「オキシー・サクサク」を使用していた。この製品が原因とみられる死者は103人に上り、大半が女性や子供となっている。
(出展:AFP BB NEWS) "
加湿器の水の中に入れて使うタイプのものですね。
細菌、インフルエンザとかノロウイルスが流行していたので、日本でも流行ってきていましたが、この「オキシ―サクサク」は、日本では販売はされていなかったようです。
ただMお土産とか、ネットなどで取り寄せた方が居れば、すぐに廃棄した方が良いと思います。
ただ、驚きなのは、この事件、実は2011年に妊婦の方が亡くなられていたことです。
それから5年後の今になって、調査の結果「オキシ―サクサク」が悪かったことと、やっと謝罪会見が開かれたことです。
しかも、販売は2001年から行われていました。
日本では、このニュースはほとんど聞こえてこなかったですし、ㇾキッド・ベンキーザー・ジャパンという支社も、日本には存在しているんです。
なので、2011年には販売中止されて原因調査をしていたようです。
ちなみに、2001年から2011年までに販売された個数は、約450万個にも上ると言われています。
そして、今回、韓国企業の「オキシー・レキットベンキーザー」のアタル・サフダール代表が、ソウル市内のホテルで謝罪会見をして、数百万ドルの補償を行うことを明らかにしました。
遺族らは、平手打ち、小突いたりなどして詰め寄ったそうです。
では、「オキシ―サクサク」に使われている、何がいけなかったのでしょうか?
オキシ―サクサクの原因物質
消毒剤として「オキシ―サクサク」に使われていた物質は、
PHMG(ポリヘキサメチレングアニジン塩酸塩)
という物質です。
ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩 は、身体の洗浄(おしぼり、ブラシ) や繊維製品への有機化合物の付着処理 などの分野において活用されるもののようです。
また、病院などでの院内感染のよぼうにつかわれる洗浄成分の様です。
また、Medicomという医療系のサイトでは、このように書かれていました。
比べているのは、アルコールと次亜塩素酸ナトリウムです。
このさいとでは、これからの洗浄剤は、このPHMGが主流となっていくと書かれています。
韓国の調査では、PHMGを吸い込むことによって、肺が膨らんで呼吸困難になり、致命的な障害をもたらすとされています。
どちらが正しいのか、これからの政府の機関とか、保健所の調査などを待たないといけないかもしれません。
ただ、言えるのは、疑わしいのは使わない方が良いと思うということです。
何かを買う時には、品質表示をしっかり確認することが、これからの時代に、健康に生きて行く秘訣になるかもしれません。
とりあえず、分かった範囲でお伝えしました。
さらに、詳しいことが分かったら、追記します。
British-based firm Reckitt Benckiser has admitted for the first time selling a humidifier disinfectant that killed about 100 people in South Korea.
The head of its South Korean division was attacked by angry relatives as he apologised at a Seoul hotel.
Reckitt Benckiser is among several firms whose products are blamed for the deaths.
It has offered compensation to the families of those who died, as well as the hundreds more who were injured.
Reckitt Benckiser withdrew its product from the market after South Korean authorities suggested a link between chemicals to sterilise humidifiers and lung conditions in 2011.
"This is the first time we are accepting the fullest responsibility, and we are offering a complete and full apology. We were late, five years have passed," Ataur Safdar said.
He added that the company was setting up a multi-million dollar humanitarian fund for the victims and their families.
Many are said to be children or pregnant women.



His apology was rejected by relatives at the news conference, at least one of whom hit him shortly after he took to the stage, and he was jostled and heckled.
About 500 people are reported to have died or been injured after inhaling poisonous chemicals used in humidifier disinfectants manufactured and sold by several companies in South Korea from 2001 to 2011.
Reckitt Benckiser: Who are they?
◾Tagline: "Healthier lives, happier homes"
◾Pre-tax profit (2015): $3.2bn (£2.2bn)
◾Key products: Dettol, Nurofen, Durex, Cillit Bang, Vanish, Clearasil
◾Founded: 1819-1823 in UK by millers Isaac and Thomas Reckitt, and Johann A Benckiser, industrial chemicals business owner
◾Presence: 60 countries, with 37,000 employees
Sources: RB website, financial statements
Reckitt Benckiser has been criticised for previously refusing to take responsibility.
Patty O'Hayer, a spokesperson for Reckitt Benckiser, told the BBC that the South Korean government had so far linked 177 cases to its product.
But the process of identifying possible victims was not yet complete.
She said the firm would compensate those who were "likely or very likely" to have been made ill by its humidifier steriliser.
The company, which also makes painkiller Nurofen, was fined last week in Australia for misleading customers.
A court ruled that products marketed as targeting specific pains, such as migraine, were actually identical.
発信地:ソウル/韓国
大型スーパーでは相変わらず販促セール
朴元淳市長「ソウル市も不買」
「なんだそれ、オクシじゃないか!」
29日午後、ソウル・蓬莱洞のロッテマート・ソウル駅店で買い物をしていた会社員のキム・チョンモ氏(32)は、「水を飲むカバ」(タンス除湿剤)の「7+1」販促商品を手に取り、友人のこの“指摘”を聞いて商品を棚に戻した。同日、ロッテマートでは除湿剤や除毛剤などのオキシー製品を並べて追加で商品を入れたり、商品券を贈呈する販促イベントが行われていた。「加湿器殺菌剤の死亡事件に関連したニュースを見た後、オキシー製品は買わないことにしました。ロッテマートは国民向け謝罪をしておきながら、こんな販促イベントまでしてもいいんですか。だから謝罪の真意が疑われるのです」とキム氏は語る。
加湿器殺菌剤死亡事件で問題になっているオキシー・レキットベンキーザーに対する消費者の不買運動が広がっている。オキシーが安全性検査を捏造して虚偽報告していた事実が続々と明らかになっているうえ、家族を失った被害者の深刻な事情まで知られ、消費者の怒りが強まっている。
被害者の大半が、英国に本社を置く多国籍企業レキットベンキーザー(Reckitt Benckiser)の韓国法人、オキシー・レキットベンキーザー(Oxy Reckitt Benckiser)が国内で2001年から販売していた液体の加湿器消毒剤「オキシー・サクサク」を使用していた。この製品が原因とみられる死者は103人に上り、大半が女性や子供となっている。
韓国の代表的なインターネット妊婦コミュニティ「マムズホリックベビー」は「オキシーは本当にやりすぎです」と題した書き込みをはじめ、「オキシー不買運動」に参加しようという書き込みが40件あまり掲載された。ネットユーザーはSNSなどを通じて市販中のオキシー製品125のリストと代替品の情報を急速に広めている。請願サイトの「ダウムアゴラ」に掲載された不買運動参加の請願には、同日まで1228人(午後6時基準)が署名に参加した。これに先立ち、朴元淳(パクウォンスン)ソウル市長は前日、フェイスブックで行われた動画の「元淳氏のXファイル」で加湿器殺菌剤の死亡事件を「お茶の間のセウォル号」と比喩し、「今後ソウル市はオキシー製品を使わない」と宣言した。
一部の薬剤師らが「ゲビスコン」や「ストゥラップシル」などオキシーの医薬品を売らないと宣言するなど、販売者のオキシー拒否の動きも出ている。ソウル・新林洞で「ヌルプム薬局」を経営する薬剤師のパク・サンウォン氏(29)は、「安全性が重視されなければならない制約会社オキシーが有害成分であることを知りながら加湿器殺菌剤を販売した。抗議の意味で26日から製品を販売しないことにした」と話した。大韓薬剤師会の全国16の市・道の部長協議会も「国民の健康と安全を無視する企業の製品を拒否する」という声明を発表した。
しかし、ロッテマート、イーマート、ホームプラスなど大手スーパー各社は、特別の陳列台まで設けてオキシー製品の販促キャンペーンを行い顰蹙を買った。イム・ウンギョン消費者団体協議会事務総長は「大型スーパーが問題企業の商品の販促行為をすることも反倫理的」と批判した。大手スーパーの広報担当者は「予定されたイベントを進行したもので、一方的にイベントを中止できない部分があった」と釈明した。
発信地:ソウル/韓国
【5月2日 AFP】韓国で英家庭用品メーカーの現地子会社が販売していた加湿器用の消毒剤が原因で子どもら100人以上が死亡したとされる問題をめぐり、この会社の代表が2日、記者会見を開き、自社の責任を認めて謝罪した。被害者の家族が代表に平手打ちを食らわせたり怒声を浴びせたりするなど、会場は一時騒然となった。
問題が明るみに出たのは2011年、妊婦4人が原因不明の肺疾患で死亡したことだった。その後の政府による調査で、肺疾患と家庭用加湿器の消毒に用いられていた製品との間に「著しい関連性」が認められた。
被害者の大半が、英国に本社を置く多国籍企業レキットベンキーザー(Reckitt Benckiser)の韓国法人、オキシー・レキットベンキーザー(Oxy Reckitt Benckiser)が国内で2001年から販売していた液体の加湿器消毒剤「オキシー・サクサク」を使用していた。この製品が原因とみられる死者は103人に上り、大半が女性や子供となっている。
オキシー・レキットベンキーザーのアタル・サフダール(Atar Safdar)代表はソウル(Seoul)市内のホテルで謝罪会見を行ったが、遺族らは英語で「遅すぎる」「許さないぞ」などとサフダール代表に怒声を浴びせた。一部は代表に詰め寄って平手打ちをしたり小突いたりしたため、会場は混乱に陥った。
ようやく会見が再開されると、代表は被害者全員に「心から謝罪する」と述べ、数百万ドル規模の補償を行う方針を明らかにした。
せっかく、燃費の試験をするのだから、ランダムで他の自動車メーカーも最低1台選んで、比較してほしい。
三菱自動車が軽乗用車の燃費を偽装していた問題で、石井国土交通相は30日、車の量産・販売に必要な「型式指定」の取り消しについて、「今回の不正の全容を把握した上で、どうするべきかを判断したい」と述べた。
熊本市内で記者団の取材に答えた。
三菱自の燃費偽装問題では、不正なデータの操作が行われた軽乗用車4車種の実際の燃費が、カタログなどに記していた公表値と大幅に異なる可能性が出ている。三菱自はこれまで「5~10%ぐらいの乖離かいりがある」と説明しているが、大幅に異なる場合には型式指定の取り消しも視野に入るとみられる。
国土交通省は、2日から4車種の燃費や排出ガスの再試験に乗り出す。その上で、型式指定に必要な一定の性能が保たれているかを検証する。
4車種以外に三菱自が生産・販売中の車種でも、近く再試験を行う方針だ。
「三菱自は不正の経緯などを調べるため、渡辺恵一弁護士を委員長とする特別調査委員会を設置し、7月下旬をめどに結果を報告する方針。」
特別調査委員会は法的に強制的な調査が出来るわけでもないし、明確な調査基準による調査でもないと理解している。渡辺恵一弁護士の人間性、技術や調査能力次第で報告書に違いは出てくるであろう。
調査に関係なく、購入する選択をする一般消費者が三菱自動車を選択肢として今後、選ばなければ衰退は止められないと思う。負のサイクルからは簡単には抜け出せないと思う。
三菱自動車の燃費データ不正問題は、かつての不祥事から再生への道筋が付いた直後に発覚した。2000年、04年の2度のリコール(回収・無償修理)隠しなど相次ぐ不祥事で厳しい批判を受けたが、歴代の経営トップは四半世紀に及ぶ不正を根絶できなかった。今後の調査では、益子修会長や相川哲郎社長ら経営陣を含め組織的な関与があったかどうかが焦点になる。
「(15年度は)新車投入計画を発表し、ブランド復活のスタートを切った年だった」。相川社長は27日の決算会見でこう述べ、肩を落とした。三菱自は1970年に三菱重工業の自動車部門が独立して発足した。スポーツ用多目的車(SUV)の先駆け「パジェロ」などヒット商品を生み出し、一時は国内販売70万台を誇った。だが、三菱重工出身の河添克彦氏が社長時代の2000年に、部品の欠陥へのクレームを隠して内密に回収・修理するリコール隠しが判明。02年にも欠陥による死傷事故が横浜市と山口県で起き、河添氏は起訴され、有罪判決が確定している。
ブランドの失墜で業績が悪化する中、02年に当時の筆頭株主の独ダイムラー・クライスラーからロルフ・エクロート氏が社長に就任した。三菱グループ外から初の社長だったが、経営を立て直せず、ダイムラーが04年に資本提携を解消したことで退任している。その後、再びリコール隠しが明らかになり経営危機に陥った。これに対し、三菱重工、三菱商事、三菱東京UFJ銀行の「御三家」を中心とする三菱グループが、三菱自の優先株を引き受けるなど支援。再生への陣頭指揮を執る社長に05年に就任したのが、三菱商事出身の益子氏だ。
益子氏は経費削減や海外事業の強化で業績を回復し、14年には優先株の大半を消却した。一方で、リコール隠しをめぐり、元役員に損害賠償を求めるなど不正を断ち切る姿勢を見せていた。14年のインタビューでは、「経営者の対応が一番の問題だった」と語っている。しかし、リコール隠しの裏で、今回の国内法令と異なる走行法で燃費試験を行う不正は1991年から約25年間にわたり続いていた。試験のデータ改竄(かいざん)も、2013年から販売する軽自動車の開発段階で行われていた。
後任の相川社長は「(不正を)全く承知していなかった」と関与を否定する。三菱自は不正の経緯などを調べるため、渡辺恵一弁護士を委員長とする特別調査委員会を設置し、7月下旬をめどに結果を報告する方針。経営陣から不正の指示や組織的な情報隠しがなかったかどうか。徹底的な原因究明が、不正の歴史を断ち切る第一歩になる。(会田聡)
「開発部門の社員は、物言わぬ風潮が戻ってきているのではないか」「コンプライアンス(法令順守)という言葉が宙に浮いてしまっている」。三菱自動車が燃費データをめぐる不正を発表した翌日の21日、東京都内の本社で開かれた同社の企業倫理委員会。問題について「調査中です」と繰り返す相川哲郎社長に対し、委員から厳しい声が飛んだ。
同委員会は2回にわたる三菱自のリコール(回収・無償修理)隠し問題を受けて2004年に設立され、委員会の開催はこの日で141回目を数える。
「甘えの構造、文化があり、消費者より社内の論理が優先される風土があった」。05年当時の益子修社長は三菱自の企業風土を断罪し、再発防止に向けた企業改革に乗り出した。外部有識者で構成された倫理委はその「切り札」に位置づけられ、約12年にわたってコンプライアンスの確立に向け助言などを続けてきた。
しかし、三菱グループの支援を受けて深刻な経営危機からの再起を図る三菱自が直面したのが、厳しい製品開発・販売競争だ。
今回、データ不正が発覚した三菱自の軽自動車「eKワゴン」は13年6月に発売されたが、役員が出席する「商品会議」などで5回にわたり燃費目標が引き上げられたことが判明している。11年2月時点の目標は1リットル当たり26・4キロだったが、ライバル社の動向を見ながら段階的に引き上げ、発売直前の13年2月に燃費目標値を29・2キロに引き上げた。その直前にはダイハツの「ムーヴ」が、29キロの燃費を達成している。
三菱自の中尾龍吾副社長は26日の記者会見で「技術的な裏付けのある目標だった」と説明したが、実際には捏造(ねつぞう)したデータによって燃費はかさ上げされていた。中尾氏は「(開発担当が)プレッシャーを感じてそういった方向に走ったと考えられる」と述べ、厳しい競争の中で過大な目標を達成するために社員が不正に走ったことを示唆した。
また、経営再建の過程で、三菱自が潤沢な資金を製品開発に投入できなかった事情も背景にありそうだ。15年度の三菱自の研究開発費は787億円。トヨタ自動車の10分の1以下で、販売台数が同規模の富士重工業の1015億円と比べても見劣りする。しかし、燃費性能などで他社を上回る製品開発が求められ、「背伸びをしすぎた」(三菱重工幹部)との見方が出ている。
燃費不正問題の真相究明は緒についたばかりだが、リコール隠しの際に指摘された「社内論理を優先する物言わぬ風潮」は、今回の問題に共通している可能性がある。倫理委は一定の役割を果たしたとして、今年6月に解散する予定だった。委員の一人は「中枢幹部は三菱グループの商事、重工、銀行に占められたため、おとなしい三菱自社員は萎縮してしまったのだろうか」と肩を落とす。コンプライアンスの確立と業績回復の両立は、三菱自にとっては重い使命だったのだろうか。【工藤昭久、浜中慎哉】
大阪桐蔭中学・高校(大阪府大東市)の裏金問題で、大阪地検特捜部は28日、運営する学校法人・大阪産業大や教職員組合から業務上横領容疑などで告訴、告発されていた元校長(75)と進路指導部主事だった元教師(52)、元事務長(74)の3人を嫌疑不十分で不起訴にした。
特捜部は「犯罪を認定するだけの証拠がなかった」と説明している。組合は、起訴を求めて検察審査会に審査を申し立てる方針。
昨年9月に病死した別の元事務長(当時50歳)は容疑者死亡で不起訴になった。
元校長らは、保護者から徴収した模試の受験料などを簿外口座にプールし、「裏報酬」として計約1700万円を着服したり、学習塾関係者らへの贈答用として計約600万円分の高級バッグなどを購入したりしたとして、昨年4月以降、告訴、告発された。
捜査関係者によると、元校長らは任意の事情聴取に「経理は担当者に任せていた」などと説明。裏金データが入っているとされる教職員用のパソコンが壊れていたり、元事務長が事情聴取前に死亡したりして、捜査は難航したという。
学校法人・大阪産業大は「地検から正式な通知を受け取っていないのでコメントできない」としている。
国が独自走行試験
国土交通省は燃費の算出に必要なデータを測定する走行試験をやったことはあるのか?あるのなら何年前になるのか?
「改ざんがあった4車種で本来の抵抗値を測定し、正しい燃費と排ガス性能を算出し、6月中に内容を公表する。」
個人的な意見であるが三菱自動車だけをやっても正しい燃費であるとの結果はわからないと思う。他のメーカーの車もランダムに選んで、メーカーが提出したデーターと国土交通省が得たデーターが許容範囲である事を確認しないと国交省の計測方法が正しいとは言えないと思う。
比較によりメーカーごとの誤差の比較も出来る。これらの走行試験及び比較により三菱のデーターの誤差が他所よりもかなり大きければ、軽自動車だけでなく普通車の燃費データーもチェックする必要があると判断できる。
国土交通省は今回の走行試験により多くの事を学べると思う。
三菱自動車が燃費データを不正に改ざんしていた問題で、石井啓一国土交通相は28日の閣議後記者会見で、同省が燃費の算出に必要なデータを測定する走行試験を独自に実施することを明らかにした。改ざんがあった軽自動車4車種から始め、現在市販されている全9車種でも実施する。国による試験は異例で、4車種の調査内容は6月中に公表する予定。
石井国交相は「メーカーが提出した値を信頼していたが、三菱自動車は信頼を損なった」と国自らが試験に乗り出した理由を説明した。
同省は5月2日から独立行政法人「自動車技術総合機構」がブレーキなどの認証試験に使っている埼玉県熊谷市のコースなどで試験を始める。
測定するのはタイヤと路面の摩擦や空気抵抗などの「走行抵抗値」。走行抵抗値は本来はメーカーが自社で走行試験を実施して測定し、国に提出。同機構が屋内にある測定器に抵抗値を入力して、燃費や排ガス性能を算出する。
改ざんがあった4車種で本来の抵抗値を測定し、正しい燃費と排ガス性能を算出し、6月中に内容を公表する。その後、現在販売されている9車種でも試験する。
抵抗値が小さいほど燃費はよくなるが、三菱自動車は「eKワゴン」など軽自動車4車種で抵抗値を改ざんし、燃費を実際より約5~10%良く見せかけていた。各車種での年式変更時には走行試験をせず、改ざんした抵抗値を基に机上で計算して算出していた。
抵抗値を測定する走行試験の方法を巡っても、同社は国が定めたものと異なる不正な方法で1991年から実施していたことが既に判明。
国交省は一連の問題を受けて作業部会を設置し、28日午後に初会合を開催。燃費の測定方法についての見直しなど再発防止策を議論する。三菱自動車から受けた報告についても内容が不十分だとして、来月11日までに現在発売している全車種でデータ改ざんがなかったかどうかなど再報告を求めている。
三菱自動車の燃費データ不正問題で、同社のずさんな管理態勢が改めて浮かび上がった。26日、同社は国土交通省に経過を報告。25年前から燃費データの改ざんが恒常化していたことを明らかにした。1リットル当たりの走行距離29・2キロの低燃費を売り文句にしていた車種では、本紙が入手した内部文書によると新車でリッター10キロを下回る驚きの結果も上がっていたことが判明。エンストや加速不良も続出しており、重大事故にもつながりかねないエンジン周辺の不具合も指摘されていた――。
過去にあったリコール隠しに続く不祥事に揺れる三菱自動車は、国交省への報告後に記者会見。国が法令で定める方法とは異なる手法で1991年から燃費データを測っていたと明かした。
国が実施する燃費試験で使う「走行抵抗値」は本来、中央値を国に提出すべきところを、意図的に有利な数値を算出。法令外の試験方法でデータを取得していたことも判明。燃費目標は社内会議で繰り返し、上方修正していたという。
当初不正が発覚したのは、2013年6月発売の「eKワゴン」や共同開発相手の日産自動車向けに生産する「デイズ」など軽自動車4車種で、対象は62万5000台だった。
それが今回、標準車や4WD車でも、本来は走行抵抗値をそれぞれ実測すべきところを、先の目標燃費に合わせ、机上で算出していたことが明らかに。不正開始が25年前にまでさかのぼることから、燃費データ不正の車が今後大幅に増えることは間違いない。
相川哲郎社長は、25年前から法令外のデータ取得法を採用していたことについて「私自身、全く承知していなかった。社内で長期間疑わず伝承された可能性がある」と会見で述べたが、“知らなかった”では済まされない。本紙が極秘入手した内部文書には、燃費に関するユーザーの問い合わせが列挙されている。文書は画像で読者にお見せできないが、驚きの内容が記されている。
eKワゴンとデイズは「業界トップクラスの1リットル当たり29・2キロの低燃費」が売りだったが、発売直後から「燃費が悪い」「カタログの数値と全然違う」という意見が殺到。なかには「納車して初めてガソリンを給油した時の燃費が9・95キロだった」という驚きの内容もあった。
同社は燃費不正の幅は「実際より5~10%良く見える程度」と説明したが、そんなレベルの改ざんではない。
「発売直後から燃費に関する意見が寄せられていたが、本社は見て見ぬフリ。本来ならリコールするべきだが、販売店に『個別対応で何とかしろ』と指示を出していた」とは事情を知る関係者。
怪しいのは燃費だけではない。同じ時期に「信号で停車後、発進したら突然エンストした」、加速不良を示す「坂道を上る力がない」などといった問い合わせも寄せられた。
さらに疑惑は車の心臓部にまで及ぶ。前出の関係者によると「エンジン部のオイル漏れを防ぐためのオイルシールにも、かすかに隙間が生じるなどの不具合が続出していた。その時はさすがにリコールして対応したが、それでも販売店からは『完全に密封されていないのでは?』という疑念の声が上がっていた」。
自動車は精密機械。わずか数ミリでも部品にズレが生じれば、重大事故につながりかねないが…。
「会社全体に『何とかなる』という空気が充満している。上層部の命令は絶対で、出世する人はごますり上手のイエスマンばかり。過去のリコール問題後も体質は変わらず、優秀な技術者は次々と辞めていった」(別の関係者)
そうしたツケが一気に回ってきた形だが、同社には今後“賠償地獄”が待っている。購入者への補償について、同社は対象車の買い取りはせず、燃費偽装分のガソリン代を払う方針だが「購入者がそれで納得するとは思えない。三菱が今回行ったのは詐欺と言っていい。集団訴訟も想定される」(業界関係者)
デイズを販売する日産との関係も見直されそうで、補償費用は数百億円規模に上る。国も動く。今回の問題で、燃費に応じて自動車購入時の税金が安くなるエコカー減税の額が変わることが想定され、その差額分は購入者ではなく、三菱側が負担することになる。
巨大財閥の三菱グループには銀行もあるが「度重なる不祥事にあきれている」(金融関係者)との情報もあり、三菱自動車に救いの手を差し伸べるかは未知数。
一部で同社の身売りまで噂されているのも当然だろう。
コストに合わない現状での選択した手段であるのなら、国はきれいごとだけを言わず、サービスや評価ランクで料金を変えれば良いのではないのか?
防火構造やその他の要求も選択者が納得しているのであれば良いのではないのか?規則は規則、同一基準と言うのであれば、今回の件を徹底的に調査し、処分すれば良い。
埼玉県春日部市銚子口の特別養護老人ホーム施設「あすなろの郷」で3月下旬、女性入居者(当時101歳)が死亡した際、医師が不在だったにもかかわらず、施設で老衰の死亡診断書を作成していたことが27日、県などへの取材でわかった。
施設の嘱託医は、事前に日付を空欄にした死亡診断書を施設に渡していたという。県は26日に施設の立ち入り検査を実施して調査しており、医師らの行為が医師法に抵触する可能性があるとみて、県警にも報告する。
県などによると、死亡した女性入居者は、3月18日に危篤状態に陥った。嘱託医は19日から旅行の予定が入っており、死因を「老衰」と記載して署名し、日付を空欄にした死亡診断書を作成して、施設に預けた。
20日に女性が死亡し、施設職員が嘱託医に連絡を取ったが、施設に戻れなかったため、看護師が死亡診断書の死亡年月日と発行年月日を記入した。診断書は遺族に渡されたという。
医師法では、死亡診断書の作成について、医師以外できないと定めている。県医療整備課によると、入居者が死亡した際に、担当の嘱託医が不在であれば、救急車を呼ぶなどして、他の医師の診断を受ける必要がある。
県福祉監査課によると、施設に嘱託医は2人おり、施設のマニュアルには、1人に連絡がつかない場合、残る1人に連絡を取るよう定めていたが、施設の職員らはそれを順守していなかった。
施設によると、この看護師は「他の医師を探している間、女性を連れ回したくなかった」などと説明したという。看護師は3月末で退職した。
日付を空欄にした死亡診断書を施設に渡したとされる嘱託医は、読売新聞の取材に対し、「話すことはない」としている。施設によると、この医師は26日、5月末で嘱託医を辞めると伝えてきたという。
施設を運営する社会福祉法人「あすなろ会」の斎藤美嗣専務理事は「悪いことをした認識はある。職員の責任の範囲を超えた行動だった」と説明している。
今回の問題について、県や保健所への報告がなく、県福祉監査課は「報告を怠るなど、事後処理も問題がある。必要に応じて調査を行い、再発防止に向けて速やかな報告などの指導を行う」としている。
同課によると、「あすなろの郷」は2008年4月設立。定員90人の特別養護老人ホームのほか、ショートステイ(定員10人)、デイサービス(定員25人)、居宅介護支援を行っている。
上手く今回の難題を乗り切れたとしても、消費者が信用しなければ復活はないであろう。全ては消費者次第。三菱グループは下請けや関係者に三菱自動車の車の購入を強制としているので、他のメーカーと比べると状況は良いかもしれない。それだけで生き残れるのかは??
弁護士=正義、学者=専門家は思考停止の発想
燃費試験の不正行為で揺れる三菱自動車は27日、相川哲郎社長が記者会見して2016年3月期決算を発表した。決算発表の冒頭、相川社長は、客観的かつ徹底的に(原因の)調査を行うために第三者委員会を設置したことを明らかにした。
しかし、筆者は敢えて言いたい。三菱自動車の関係者を全く入れない第三者委員会を構成することで、一見、客観性は担保できるかもしれない。ただし、世間受けは良くても本当の原因を突き詰めることができるのだろうかとの疑問がある。検事・弁護士=正義、学者=専門家という安易なイメージから法曹界の人や大学の研究者を使う発想自体が思考停止していると思う。
三菱自動車では2000年と04年にリコール隠しが発覚、会社存亡の危機に陥り、三菱グループ御三家(三菱商事、三菱東京UFJ銀行、三菱重工業)が中心となって財務的な支援などを行うことでどうにか生き延びてきた。その過程では元社長が逮捕されるなど衝撃が走った。だから、世間的には「三菱自動車は反省しただろう」と思われていた。その矢先に、再び今回の不祥事が起こった以上、同社の体質に何らかの問題があったと言わざるを得ない。
一方で、三菱自動車の中には、まだ志の高い人材は残っているはずだ。こうした人材は、自分の会社を今度こそは本当に再生させたいと思っているに違いないと筆者は信じたい。そういう人材はどんな人材かというと、仕事はできるが上司にたてついたことで社内評価が低いとか、日の当たらない仕事を入社以来30年こつこつやっているとかいうイメージだ。
あるいは役員や社長に反抗するなんて朝飯前の人かもしれない。健全な精神をもった「異端児」は三菱自動車にもいるはずで、社内をよく知るこうした人材に今回の不正の原因を調査させ、その調査プロセスや調査結果が妥当かを第三者員会に検証してもらうのが理想ではないか。
朝日新聞でも起こった問題
不祥事が起きた際には、独立性を担保された社内の調査部門がまず調査を行い、その調査手法が適切か否かを第三者に監督してもらう方が、調査の内容もより実態に近いものが浮かび上がってくるはずだ。会社の実態や企業風土、人間関係を知らない第三者が不正の本当の理由を探ることができるとは到底思わない。
自社内部できっちり検証し、何が問題だったのかを組織に学習させていくことが一種の自浄能力である。三菱自動車はその自浄能力がないから度々不祥事を起こすとも言える。第三者員会はあくまで自浄能力のための補助的手段であり、それが「主役」になること自体、組織に自浄能力がないことを示している。
企業で不祥事が発生した際に、第三者委員会を設置して問題を解明しようとする手法には限界がある。一見利害関係者ではない第三者に調査させることや、元検事など法曹関係者をそのトップに起用することで客観性を担保しているように見えるが、「第三者と言いながら、実は何らかの形で会社の息がかかっているのではないか」との見方もある。
先述したように内部事情を知らず、しかも時間にも制約がある中で外部の第三者委員会に調査を依頼しても、真相を探ることには無理がある。
最近でも粉飾決算をした東芝の第三者委員会が発表した報告書には、なぜあのようなことが起こったのかの本質的な理由が記載されていない。それは、当時のトップの人間性や考え方、企業風土などにまで踏み込んだ調査がされていなからだ。
さらに言えば、監査法人と東芝側がどのようなやり取りをしたのか、肝心な点も説明されていない。東芝の第三者委員会による報告書に対しては、危機管理の専門家からも内容を疑問視する声が多く出ている。
筆者の古巣である朝日新聞でも「池上彰コラム掲載問題」など一連の不祥事が起こった際、第三者委員会が立ち上がり、社内調査が行われたが、「実際には事務局が用意した資料をベースに関係者を尋問するだけで、その資料が本当に正しいか否かは分からなかった。危機を収拾したい会社が目論む結論を誘導するための第三者委員会だった」(朝日新聞関係者)との指摘もある。
このため、朝日新聞社内では今でも第三者委員会が導き出した結論に対して、根強い不信感が残っているそうだ。
今回の不正の原因が解明され、三菱自動車が今後も存続できるとするならば、企業内の自浄能力を持つことが重要になるだろう。そのためにはまず、危機において、しっかり機能する広報部の存在も重要になる。
社内の情報収集を確実に行い、同時に社外(マスコミ等)が自社をどのように見ているのかも把握することも求められるが、こうした一朝一夕ではできない。有能な広報マンを育てていく思想が求められるのだ。
ここで言う有能な広報マンとは、会社の為に敢えて「社内野党」になれる人物であろう。
国土交通省は米当局のように三菱自動車に追加試験を要求するのか???
畑中徹=ニューヨーク、田中美保
三菱自動車が燃費試験データを不正に操作していた問題で、米国で販売した車の燃費データの追加試験をおこなうよう、米環境保護局(EPA)が命じることがわかった。米メディアが26日伝えた。
報道によると、EPAは三菱自に対し、米国内で売った車についての情報提供はすでに求めたという。三菱自は、海外で販売した車の燃費データについては「調査中」としている。米国での販売台数は2014年度に8万2千台で、国別では日本、中国、インドネシアに次いで4番目に多かった。
EPAは昨年9月、独自動車大手のフォルクスワーゲン(VW)による排ガス規制逃れを指摘したことで知られ、三菱自動車に対しても厳しい追及をする可能性がある。日本で発覚した燃費の偽装問題が米国にも広がれば、三菱自の経営にさらに打撃となりそうだ。(畑中徹=ニューヨーク、田中美保)
中田絢子
三菱自動車の燃費偽装問題で、同社は26日、法定の方法と異なるデータ測定を1991年から続けていたと明らかにした。競合他社を意識した燃費目標を達成するため、一部の車種で実測したデータを使って、架空のデータを机上計算していたことも判明。相川哲郎社長は「会社の存続に関わる事案」と謝罪した。
三菱自は同日、国土交通省にこれらの事実を報告したが、同省は不正の全容が明らかになっていないとして、5月11日までの追加報告を求めた。記者会見した相川社長は、外部調査委員会の結果を聞くまで「社長の責任を果たす」と述べ、当面の辞任を否定した。
燃費性能の基となるタイヤの摩擦や空気抵抗などの「走行抵抗値」のデータは、道路運送車両法に基づき「惰行法」で測定するよう91年に定められた。だが三菱自によると、この時から「高速惰行法」と呼ばれる米国車向けの試験方法で実施していた。高速惰行法は試験時間が短く済むというが、法律に反してまで使った理由は「調べて回答したい」という。この方法が関係した車種や台数について、中尾龍吾副社長は「調査中で現時点では公表できない」とした。
神戸市北区の新名神高速道路の工事現場で橋桁が落下し、作業員10人が死傷した事故で、「橋桁の西側を支えていた土台が、事故前に約18センチずれていた」と工事関係者が証言していることが分かった。土台のずれなどが判明後、現場で関係者が対応を協議したが、作業を継続したという。地盤沈下などの影響で土台のずれが生じ、橋桁がバランスを崩した可能性があり、現場の対応に問題がなかったか、兵庫県警が捜査を進めている。
工事を発注した西日本高速道路によると、落下したのは上り線の橋桁で長さ124メートル、重さ1350トン。東端は門型クレーンでつられた状態で、西端はジャッキ4台と土台で支えていた。22日午後4時27分ごろに橋桁の西側が落下し、ジャッキも南側の2台が崩れていた。
関係者によると、東側の門型クレーンが約2センチ沈んでいることが事故前に現場の調査で判明。西側の土台も定位置より東方向に約18センチずれていることが分かった。さらに、落下していない下り線の橋桁も東側が沈んでいたという。
工事関係者らは、地盤が沈下したとみて対応を協議したが、作業は進められた。事故当時は周辺で約50人が作業し、死傷した10人は東西の橋桁の上や足場にいたという。
工事は、三井住友建設と横河ブリッジの共同企業体(JV)が請け負い、落下した工区は横河ブリッジが担当。下請けとして汐義(しおよし)建設工事(兵庫県尼崎市)などが関わっていた。
県警は関係者から事情を聴き、安全管理に問題がなかったか詳しく調べている。【矢澤秀範、山下貴史】
このような問題はコストや利益に直結する。バス業界だけの問題でもないと思う。
今回、騒がれている三菱自動車の燃費データ不正問題も同じ事。コストや利益が直接なのか、間接なのか影響を与えている。
全てはチェックできないが、消費者や利用者が出来るだけ情報を集め、チェックしようとする姿勢が広がれば、企業や行政も無視できなくなると思う。
29日で4年
群馬県藤岡市の関越自動車道で2012年4月に乗客7人が死亡、38人が負傷した高速ツアーバス事故は29日、発生から4年を迎える。「二度と事故が起きてほしくない」。そう願い続けてきた遺族の思いは1月の長野県軽井沢町のスキーツアーバス事故で裏切られた。一人娘の胡桃(くるみ)さん(当時17歳)を失った石川県白山市の会社員、岩上剛さん(44)は「価格最優先というバス事業の根本を変えない限り、事故はまた起こる」と訴える。【山本有紀】
看護師になることを夢見ていた胡桃さんは「奨学金を借りて大学に行きたい」と父に相談した2日後、東京ディズニーリゾートに向かう途中に関越道で事故に遭い、帰らぬ人となった。楽しみにしていた娘の看護師姿も、ウエディングドレス姿も見ることはかなわなくなった。
追い打ちをかけるように事故後、バス会社のずさんな管理体制が次々と明るみに出た。運転手の日雇い。名義貸し。壊れたシートベルトの放置。運行指示書の未作成−−。「事故の起こらない安全な世の中にしたい。親として、死んでしまった娘のためにできることは、そのくらいしかもうない。何か一つでも変わってくれれば娘は喜ぶんかな」。その思いで、つらくても取材に応じてきた。
しかし、悲劇は繰り返された。大学生ら15人の命が奪われた軽井沢のバス事故。犠牲者の多くは、胡桃さんが生きていれば同年代だった。バスの運行会社は、関越道の事故をきっかけに引き上げられた基準運賃を大幅に下回る価格でツアーを受注。運行指示書の不備や、運転手の健康診断未実施なども発覚した。「安全対策を徹底した上で起きたなら『事故』だが、怠った結果として起きたなら『事件』だ」。岩上さんの憤りは収まらない。
ツアーバスなどの貸し切りバス事業は00年に免許制から許可制に変わり、規制緩和によって新規参入が大幅に増加した。低価格競争の裏で、おろそかにされる安全面。国の規制強化が事後対応になっていることにもいらだちが募る。「事故が起きてから変えるのでは遅い。自動ブレーキ機能の義務化などあらゆる安全対策の徹底と、違反時の罰則の強化を図り、それに耐えられるバス会社のみが運行すべきだ」
結局、コンプリアンス、技術屋としての倫理規定(Code of Ethics as an Engineer)、モラルなどどうでも良いと言うこと。どれも機能していない。
三菱自動車にも技術士(公益社団法人 日本技術士会)
の資格を取得している従業員がいると思うが、不正について全く知らなかったのか??
もし、技術士(公益社団法人 日本技術士会)の資格を持っている社員が関わっていれば、まさに技術士(公益社団法人 日本技術士会)は「絵に描いた餅」と言うことか?
三菱自動車の燃費データ不正問題で第三者委員会が設置され、いよいよ本格的な原因究明へむけた調査がスタートした。
【燃費試験の不正行為について】
相川哲郎社長ら経営陣は、「当時の性能実験部長が『私が指示した』と言っている」と繰り返し説明したが、このようなダイナミックな不正を一個人の裁量だけで進められるのかという疑問があちこちのメディアから指摘されている。
部長に詰め腹を切らせてウヤムヤにしようとしているのでは――。そんな「疑惑」も囁(ささや)かれる背景には、昨年あった部長級社員2人の諭旨退職がある。平成28年度に発売を予定していた新型SUVの開発が遅れていることを上司に報告していなかったことが発覚し、新型車の投入が遅れた「責任」をとらされたのである。
こういう話を聞けば、誰でも「ミスを上に報告できない空気なんじゃないの」と思う。実際、今回の不正発覚後の21日に開かれた同社の企業倫理委員会でも、同様の指摘があったという。
「風通しの悪さ」が今回の不正に結びついているか否かは、第三者委員会が明らかにしてくれるはずだが、三菱自動車が自分たちではどうすることもでないほど深刻な「セクショナリズム」に侵されていることだけは間違いないと思っている。
根拠は、「不正」を明らかにした20日の記者会見だ。
経営陣は「これから本格的な調査をしていく」を繰り返すのみで、積極的に情報開示をしなかったスタンスに、マスコミ各社は痛烈に批判していたが、個人的にはそこよりも注目したポイントがある。
それは、社長への報告スピードだ。
●三菱自動車の「常識」
燃費データに届出値との乖離(かいり)があることを指摘したのは日産自動車だ。昨年の11月ごろに気付き、12月に合同調査をしたいと三菱側に申し入れをした。それを受けて今年2月に2社の合同調査を実施し、分析結果で走行抵抗に差があるということが判明したのが3月末。その結果を踏まえて、4月から社内調査を行い、「不正」が判明して、品質統括部門長開発担当の中尾龍吾副社長に届いたのが今月12日。その翌日に相川社長が知ることになった。
「不正」だと確定してからは早いような印象を受けるかもしれないが、日産側が「乖離」を指摘してからは5カ月、自分たちもかかわる合同調査の結果が出た後も2週間も経過している。
共同開発した軽自動車の燃費データが届出値と違うというのは、自動車メーカーにとって、経営トップが陣頭指揮をとって、全力でマネジメントにあたるべき「危機」である。その兆しが見えているにもかかわらず、2週間も社長への「不正の可能性」を進言しないというのは、三菱自動車的には「常識」なのかもしれないが、一般人の感覚では理解に苦しむ。
当然、会見場にいた記者からも、日産とやりとりをしている間になぜ社長に報告しなかったのかという質問が飛び出た。中尾副社長はやや戸惑いながら以下のように答えられた。
「日産とウチの開発のトップ同士がやっているので、普通ならそこで解決しているはずなんです。それが解決できていないからここまできたということ」
あくまでこれは「開発」が解決すべき事案で、それを差し置いて経営トップが強制介入するのは筋が違うというのだ。この主張を聞いて、すぐに「セクショナリズム」という言葉とともに、2000年のリコール隠し事件のことが頭に浮かんだ。
●三菱自動車は「隠蔽体質」
当時は記者になりたてでとにかく無我夢中だった。ボンネットから火がでたというデリカユーザーに話を聞いたり、経営陣の乗った三菱デボネアを追いかけ回したりしたことしか覚えていないが、ひとつだけ強烈な印象に残ったのが、当時の三菱自動車を覆っていた強烈な「セクショナリズム」だ。
例えば、会見で、当時の河添克彦社長は当初、意図的なリコール隠しを全面否定していた。しかし記者たちにそんなわけないだろと吊るし上げられると、たまらずひとりの幹部が、リコール隠しを認めてしまう。
「報告と違うじゃないか」
記者たちの前で動揺して幹部に問いただす社長の姿は、「君、それは本当か?」と工場長に詰め寄った雪印乳業の石川哲郎社長と丸かぶりだった。
その後、小説『空飛ぶタイヤ』のモデルになったタイヤ脱落事故も起こした2004年のリコール隠しでもこの流れは変わらない。記者会見した三菱ふそうトラック・バスのビルフリート・ポート社長は、自分のところにまったく情報をあげてこない社員たちに対して怒りをあらわにした。
「これは隠蔽のコーポレートカルチャーの結果だった」
報告をしない。事実と異なる報告をする。そして、不正を隠す――。こうした三菱自動車社内の空気を、メディアはポート社長のように「隠蔽体質」と報じていた。
が、よくよく考えてみると、「上」に情報をあげないというのは、「上」を信頼していないということであり、もっと言ってしまえば、「自分たちしか信じない」という現場のセクショナリズムのあらわれのような気がする。
実際、経営評論家の故・梶原一明氏が評した言葉が、不正続きの三菱自動車の「空気」を的確に表現しているような気がしている。
よく言えば、個を尊重して他人の仕事に口出ししない。悪く言えば徹底的なセクショナリズム。これは三菱重工以来の伝統で、他部門に口を挟まないのが企業文化として定着している。その結果、社内批判がなくなった。(週刊朝日2000年9月8日)
●「技術屋」という世界の「正義」に基づいて動く
開発部門に「個」を尊重するカルチャーが強ければ、「組織」のルールを軽んじる空気、つまり不正に対する罪悪感のまひがあったというのは容易に想像できる。事実、かつてそのようなルールを破り、それを誇らしげに語っていた三菱自動車の技術屋がいる。
なにを隠そう、相川社長だ。
2014年に社長になった相川氏は、父・賢太郎氏が重工の会長、社長を歴任したピカピカの三菱サラブレッドだが、その一方で開発畑を歩んできた「技術屋」としても知られた。だから、新社長就任の際には、こんな職人気質がアピールされた。
リコール隠し事件発覚後、「仲間のエンジニアが相次いで会社を去ったのはつらく悲しかった」と語るが、ダイムラー傘下で開発中の軽自動車「i(アイ)」に開発停止命令が下ったときは「開発コード」を変更してまで極秘裏に続行。誠実で偉ぶらない性格だが、iのボディーをベースにした世界初の量産電気自動車「i-MiEV」も「あのとき、中止していたら作れなかった」と、技術屋魂を燃やす頑固さもある。(PRESIDENT 2014年4月14日)
カッコいいエピソードに仕立てあげられているが、これは冷静に考えれば「命令無視」だ。コードを変更してまで開発を続行したのも「隠蔽」ととれないことはない。
「上」の命令に従わず、「技術屋」という世界の「正義」に基づいて動く。このようなカルチャーが燃費データの改ざんというユーザー目線の欠如した不正に走らせたことはないのか。
NASA(アメリカ航空宇宙局)でかつて興味深い調査が行われた。現役の操縦士と副操縦士をフライトシミュレーターに乗せて、事故の可能性を知らせるシグナルを発してから、事故が起きるまで彼らがどのような行動をとるのかモニタリングしたのだ。
そこで、誤った判断を下す確率が多いのは、「腕に覚えがある親分肌の操縦士」だったという。
●頑固な技術屋が陥る「落とし穴」
なぜ「徹底的なセクショナリズム」が蔓延(まんえん)するのかといえば、「個」が腕に覚えがあるからだ。他人の仕事に口出しをしない。その代わり、オレたちのやり方にも口を出すな――。そんな「頑固な技術屋魂」が、「ミスを上に報告しずらい空気」を生み、「報告できないミスを隠蔽してしまえ」という不正につながった可能性はないか。
「技術」こそが社会の発展を支えてきたという考えが強い日本では、「職人」というだけでなにやら聖人君子のようにあがめたたられることが多い。頑固だが、自分たちの技術に誇りをもっているので、とにかく「不正」などに手を染めるわけがない、と思われている。
個人的には「果たして、そうなのか」と首をかしげる。「頑固な技術屋」だからこそ、柔軟な対応ができず「自分の欲しい答え」がどうやってもでないときに「不正」に走ってしまうのではないのか。
第三者調査委員会が真相をすべてつまびらかにすることを期待したい。
(窪田順生)
目下、世間の注目を集めている三菱自動車の「燃費データ不正操作問題」について、“三菱グループの天皇”と呼ばれた三菱重工相談役・相川賢太郎氏(88)が「週刊新潮」の取材に答えた。
***
三菱自動車が突如として記者会見を行ったのは4月20日のこと。「燃費の数字を良く見せ意図的に操作したのは確かだ。経営責任を感じている」と謝罪した相川哲郎社長は、賢太郎氏の長男である。
賢太郎氏は三菱重工の社長を1989年から3期6年、会長を2期4年務め、今も三菱グループ全体に影響力を持つ。そんな賢太郎氏が取材で語った内容は、もはや“放言”に近いものだった。まず不正そのものについては、
「あれはコマーシャルだから。効くのか効かないのか分からないけれど、多少効けばいいというような気持ちが薬屋にあるのと同じ(略)軽い気持ちで出したんじゃないか、と僕は想像していますけどね」
つまり、カタログ記載の公表燃費性能は“コマーシャル”で、それを良く見せるために軽い気持ちで不正を働いた、という見立てである。さらには、
「買う方もね、あんなもの(公表燃費)を頼りに買ってるんじゃないわけ」
「実際に乗っとる人はそんなに騒いでないと思うんだけどね」
といった調子で、「週刊新潮」のインタビューに答えた“相川天皇”。過去の度重なる不祥事で倒産の危機に陥るも、その都度立ち直ってきた三菱自動車だが、今回はどうだろうか……。
***
そのほか、「(不正を行った従業員は)心根が悪いわけではない」「三菱自動車は潰さない」といった発言も飛び出したインタビューの全容を4月27日発売の「週刊新潮」が掲載する。
「週刊新潮」2016年5月5・12日ゴールデンウイーク特大号 掲載
三菱自動車は26日、燃費不正問題に関する社内調査の状況を国土交通省に報告し、公表した。国の規定と異なる方法で燃費試験データを収集する法令違反を、25年前の1991年から行っていたことを明らかにした。記者会見した相川哲郎社長は「知らなかった」と釈明したが、2000年に発覚したリコール(回収・無償修理)隠しで社会的な批判を浴びても違反を続け、自浄作用が働かなかった同社の企業体質が厳しく問われることになる。
法令に違反して燃費試験データを収集した対象車種は「調査中」と説明するにとどめたが、数十車種、数百万台規模に上る可能性がある。国交省は5月11日までに再度報告するよう求めた。
道路運送車両法は91年に走行抵抗の測定法を指定したが、三菱自はこれとは違う従来方法を継続。07年には社内の試験マニュアルだけ法令に沿った測定法に改定し、実行していなかった。
今回の報告では、燃費目標達成のため不正が行われた軽自動車「eKワゴン」と日産自動車向け「デイズ」について、燃費の最も良いタイプの開発目標燃費を、社長以下の役員が出席する会議で5回上方修正していたことも明らかにした。
11年2月の開発当初は、ガソリン1リットル当たりの走行可能距離26.4キロを目標に設定したが、ダイハツ工業の「ムーヴ」などとの競争を意識して上方修正を繰り返し、13年2月に最終目標を29.2キロに引き上げた。同社の中尾龍吾副社長は記者会見で「結果から見れば社員にプレッシャーがかかった」と述べた。
長続きするとは考えにくい M&Aの可能性を探る方が有効
4月20日、三菱自動車の相川社長は、同社が製造する4車種の軽自動車について燃費を良く見せるために不正を意図的に行っていたと発表した。実際には、タイヤの抵抗などの数値を意図的に操作していたという。
三菱自動車と言えば、2000年、2004年にもリコール隠しが発覚し、利用者などの信頼を大きく裏切った前歴がある。今回のケースでも、今回不正の対象となる車の数は約62万台にのぼり、同社の販売台数の約6割を占めるという。
今回の報道を見ると、「これだけ何度も不正を繰り返す三菱自動車という企業は、社会にとって本当に必要なのだろうか」という素朴な疑問が出る。
リコール隠しが表面化した後、同社の業績は顕著に悪化し、一時期、その存続すらも怪しくなる状況だった。それに対し、三菱グループを中心に強力な支援策が講じられ、何とか命脈を保った経緯がある。
それにもかかわらず、また不正行為を繰り返してしまった。
その背景には、競争の激しい軽自動車の分野で、ダイハツやスズキといった2強の後塵を拝したことがあるようだ。その遅れを取り戻すために、同社自身が焦りを持ち不正行為をせざるを得なかったという説明には、それなりの説得力があるかもしれない。
しかし、ある分野で競争力を失った企業は、ごまかしの不正行為で一時的に淘汰を避けることができても、それが長続きするとは考えにくい。むしろ企業経営者とすれば、他の企業とのM&Aの可能性を探る方が有効な経営戦略であるはずだ。
不正行為を繰り返す三菱自動車は社会のために本当に必要なのか、真剣に考えてみる時期が来ていると思う。
● 不正行為を繰り返した 三菱自動車の歴史
三菱自動車は、1970年に三菱重工業と米国のクライスラー社の合弁事業として発足した。その後、クライスラーはドイツのダイムラー社と資本関係を結んだ。それに伴い、ダイムラー・クライスラー社は、三菱自動車の筆頭株主になった。当時の三菱自動車は、トヨタ・日産・ホンダに次ぐ国内第4位の自動車メーカーだった。
ところが、2000年に同社のリコール隠ぺい行為が発覚した。具体的には、三菱自動車は1977年から23年間にわたって、乗用車約45万台とトラック約5万台に関する部品の不具合のクレーム情報を外部に公表しなかったのだ。
クレーム情報を社内で隠ぺいする一方、直接、ユーザーに連絡して、不具合のある部品を回収したり修理する、いわゆる“闇リコール”を行ったのである。
しかし、不具合部品の公表を行わなかったため、部品の取り換えなどが間に合わず、実際に人身事故が発生するケースもあった。このリコール隠ぺいによって同社はユーザーの信頼を失い、販売台数は大きく落ち込んだ。当時の一部の経営者は退陣を余儀なくされ、ダイムラー・クライスラーから人材を入れて再建を目指した。
さらに、2002年に三菱自動車から分社化したトラック・バス部門である、三菱ふそうの大型車のタイヤが脱落する事故が発生した。その事故をきっかけに、同社のトラックなど大型車の構造上の欠陥や、それに係るリコール隠しの疑いが取りざたされるようになった。
その結果、2004年4月、筆頭株主であったダイムラー・クライスラーは財政支援を打ち切り、同社から派遣された社長が任期を待たず引き上げてしまった。また、5月にはタイヤ脱落事故に関連して、三菱自動車と三菱ふそう経営陣の一部が起訴されることになった。
日産からの指摘がなければ 隠蔽行為は続いていた可能性が高い
そして今回、三菱自動車が作る軽自動車=ekワゴン、ekスペース、デイズ、デイズクルーズの4車種について燃費に改ざんがあることが発覚した。しかも、発覚のきっかけは、提携先の日産自動車からの指摘だったという。
仮に日産自動車からの指摘がなければ、三菱自動車の隠ぺい行為は今でも続いていた可能性が高い。人の命にかかわる問題を隠す、同社の姿勢には一般の理解を超えた要素があるようだ。それを考えると、身の毛がよだつほど恐ろしく感じる。
過去の三菱自動車の歴史を振り返ると、同社の企業文化の中に「都合の悪いことを社内で隠してしまう」という慣習があるように見える。しかも、その遺伝子は簡単には排除することができないくらい強力だった。
その証拠として、2000年以降、幾度となくリコール隠ぺいなどの問題が指摘され、監督官庁からの検査や勧告を受けてきた。しかも、消費者の不信の高まりによって、同社の販売台数が大きく減少し、一時、業務を継続することにも支障が出る状況まで追い込まれた。
そうした苦境を、三菱グループのプライドをかけた強力な支援体制で何と凌いできたとも言える。三菱グループ企業に勤務する友人の一人は、「三菱グループの企業をつぶすわけにはいかない」と言っていたことが印象に残る。
また、不祥事発生の都度、経営者は国民に向かって再発防止を誓約してきた。それにもかかわらず、今回、前と同じような不正行為が発覚した。
これだけ同社から不祥事が起きると、国内外の顧客から「他の日本企業もそうした隠ぺい行為を行っているのではないか」との疑義が生じることも考えられる。それは同社のみならず、他の自動車メーカー、あるいは他の日本企業の信用にも悪影響が及ぶことも懸念される。その罪は非常に重い。
● 改革のチャンスがありながら 企業文化を変えられない企業
ここで冒頭に上げた疑問点に戻る。
三菱自動車という企業は、わが国社会にとって必要だろうか。今から十数年前に証券会社で自動車メーカーのアナリストをしていた友人は、「これまでの三菱自動車であれば、社会は必要としない」と指摘していた。
三菱グループの有力企業である同社が淘汰を受けたり、別の企業に買収されて社名がなくなることを寂しく思う人は多いかもしれない。特に、強力な三菱グループの人々にとっては、大きなショックになるかもしれない。
しかし、社会のルールを守ることができず、他の企業にも無視できないマイナス効果を与え、しかも幾度となく改革のチャンスがありながら、その企業文化を変えられない企業が社会の中で、そのままの姿で存続を続けてよいだろうか。
経済合理性の観点から考えると、そうした企業に関しては、信用の失墜による収益力の減少などによって、株式市場のマーケットメカニズムで淘汰を受ける可能性が高いはずだ。
ところが、株主の中にはグループ企業も多く、マーケットメカニズムが働きにくい面もある。
見方を変えてわが国の産業を見回すと、多くの分野で産業の再編が進んでいない。世界クラスと比較すると規模の大きくない企業が、同一の分野でひしめく構図になっている。わが国の有力な完成車メーカーを見ても、トヨタ、日産自動車、ホンダ、富士重工業、スズキ、マツダなど多くの企業がしのぎを削る状況になっている。
世界経済のグローバル化が進むと、主な市場では力の強い、大きな企業が世界市場で高いシェアを維持することが想定される。そうした状況に対応するためには、わが国企業もある程度、合従連衡を進めて、体力のある規模の大きな企業を作ることが重要だ。
そうした動きを促進する意味でも、経営が上手くワークしない企業などは、十分な経営能力のある企業と一緒になることも有効な選択肢の一つだ。何が何でも、企業の名前を存続させることが目的になることは、合理的ではない。
真壁昭夫
三菱自動車が軽自動車の燃費を偽装していた問題で、同社が1990年代から、法令で定められた方法とは異なるやり方で燃費データの測定を行っていたことがわかった。
これまで同社は少なくとも2002年から現時点では計11車種で法令違反があったと説明しており、違反していた車種や台数の規模がさらに広がる可能性が強まっている。
関係者によると、調査では燃費偽装が問題になった軽自動車4車種について、四輪駆動車の走行試験の結果を提出する代わりに二輪駆動車の試験結果を基に机上の計算で算出したデータを検査機関に提出していたことも判明したという。
三菱自は今月20日、13年以降に生産、販売していた「eKワゴン」など4車種の軽自動車で燃費を良く見せかけていたと発表した。さらに、燃費測定の基になる「走行抵抗」を測定する際にも、日本では認められていない方法を02年から採用していたことを明らかにした。
燃費性能を高く見せるため、データを改ざんしていた三菱自動車が、不正を行った4車種以外にも、1990年代から同様の手口で、データの改ざんを行っていた可能性があることが、関係者への取材で明らかになった。
三菱自動車は、4車種のあわせて62万5,000台で、燃費性能試験に使用されるデータを意図的に改ざんしていたほか、2002年ごろから、10車種で、国の定める走行試験とは違う試験を実施していた。
このうち、データの改ざんは、2輪駆動車のデータを流用したり、走行試験をせずに、机上の計算だけの数値を国に提出していたことが、新たに明らかになった。
また、これまでの国の立ち入り検査などで、こうしたデータの改ざんが、リコール隠しが発覚した以前の1990年代から行われた可能性があるという。
三菱自動車は、こうした内容の調査結果を26日午後4時に国土交通省に報告し、そのあと、記者会見を行う予定。
三菱自動車の燃費データ不正問題で、国土交通省が同社の燃費試験用データの測定方法を「社内評価用の方法」と判定したことが24日、分かった。測定方法は道路運送車両法に基づいて定められているが、同社は米国の法令で定める方法を自社用にアレンジしたものを使っていた。国交省は同法違反の疑いがあるとみて、実施方法などを詳しく調べている。
新車を発売する前に受ける燃費試験は、自動車が走行する際のタイヤや空気の抵抗値を入力して行われる。自動車メーカーが同法で定められた「惰行法」と呼ばれる方法で測定して審査機関に提出するが、三菱自動車は米国の法令で定められた方法を基に、速度や算出の仕方を若干変えて測定していた。
同社はこの方法を「高速惰行法」と呼び、平成14年から、軽乗用車や乗用車など計27車種の抵抗値の測定方法として採用。燃費試験用データの不正操作が行われた軽自動車4車種も、同じ方法で測定されていた。
高速惰行法は、惰行法の半分の時間で測定できるが、燃費に与える影響は不明。国交省は、高速惰行法を単なる「(同社の)社内評価用の測定方法」と判定。同法が定める手続きに違反する疑いがあるとみている。
「徹底的な原因究明が必要」と言うのは簡単であるが、それが出来るのは 国交省だけ。なぜなら、能力や経験とは関係なく、権限を持っているのは国交省。
適切にチェックが出来ていれば問題がここまで放置される事もなかった。つまり、権限を持っているのは国交省が徹底的な原因究明が能力的に出来るのかも疑問???
三菱自動車が自動車の燃費試験で性能を実際より良く見せる不正行為をしていたことが分かった。同社は過去にも大規模なリコール(無料の回収・修理)隠しが発覚して社会問題となったことがあり、企業体質に重大な疑念を感じる。徹底的な原因究明に努めるとともに、経営責任を明確にするべきだ。
相川哲郎社長が20日に記者会見して明らかにしたところによると、三菱自は2013年以降、国土交通省に報告する燃費試験のデータに手を加えて5~10%程度良く見せかけていた。対象は軽自動車4車種の計62万5千台で、生産・販売を停止した。安全性には問題なく、リコールは実施しない見通しという。
三菱自の不正行為が明らかになったのはこの十数年で3回目で、またもや消費者の信頼を裏切った。あしき企業体質は改善されていなかったと見られても仕方がない。
三菱自は00年にリコールにつながるクレーム情報を隠していたことが発覚し、04年にも過去に同様の不正をしていたことが判明した。これらの不正でタイヤ脱落による死傷事故が発生するなどして販売台数が激減。経営危機に陥ったが、三菱グループの支援を受けて再建し、15年3月期連結決算で過去最高の純利益を上げた。
しかし、今回の不正でブランドイメージは再び大きく傷ついた。問題の4車種はエコカー減税の対象から外れる可能性もあり、三菱自はその場合に生じた負担は穴埋めするとしている。補償の金額はともかく、自動車の販売に影響が出るのは必至で、業績に大きな打撃を受けるのは避けられないだろう。
4車種は13年6月から生産を開始し、当時の担当の部長が不正を指示したという。三菱自は外部識者による調査委員会を設置し、誰が関与したかなど不正に至る経緯を調査する方針だ。ユーザーの信頼回復と再発防止のためには、不正が行われた過程を解明することが必要だ。
三菱自では現場の社員が上役の顔色をうかがう傾向が強く、それが不正を生む土壌になったのではないかとの指摘もあり、調査委には同社のガバナンスの在り方にもメスを入れてもらいたい。相川社長をはじめ経営陣は、調査委の報告を得た上で、責任の取り方を考えるべきだ。
燃費性能は消費者が自動車を購入する際に重視する要素の一つで、売り上げに大きく影響するため、燃費を巡るメーカー間の競争は激しい。三菱自は「社内の目標値を達成するため不正をした可能性が大きい」と説明している。
ドイツのフォルクスワーゲン(VW)の排ガス規制逃れは、燃費とは異なるが、自動車業界の激しい競争の中で起きた不正で、構図は同じだ。三菱自以外にも、また燃費性能以外でも、類似の不正が行われていないかという疑いを招きかねない。
国交省は三菱自に不正の詳細報告を求めるとともに、他の自動車メーカーにも、同様の不正がないかを報告するよう指示した。各社は足元を徹底的に点検し、消費者の疑念を払拭(ふっしょく)してほしい。一方でメーカーの試験に国交省の担当者が立ち会うことはなく、不正を見抜くのは不可能だという。試験の在り方を見直すことも考えるべきだろう。
三菱自動車が軽自動車の燃費を実際より良く見せかけていた問題で、同社が軽以外の7車種でも、燃費を調べるための走行データを国内では認められていない方法で測定していたことがわかった。
道路運送車両法違反にあたり、少なくとも2002年から行われていた。7車種について燃費の偽装は確認されていないが、三菱自のずさんな管理体制が浮き彫りになった。
違法な方法で測定していたのは、燃費の偽装が明らかになった軽自動車「eKワゴン」などの4車種に加え、スポーツ用多目的車(SUV)の「アウトランダー」、「パジェロ」、「RVR」や、電気自動車(EV)の「i―MiEV(アイ・ミーブ)」など。
車の燃費を調べるには、まず自動車メーカーが、タイヤにかかる抵抗や空気抵抗などのデータを測定する。そのデータを国土交通省に提出し、専門機関に燃費を出してもらう。
三菱自動車が燃費データを不正に改ざんした軽自動車に関し、内装やデザインの一部を変更する際、法令上必要な車両の走行試験をせずに、机上の計算だけで走行時のデータを算出するケースがあったことが23日、分かった。最初に改ざんしたデータとの矛盾で、不正が露見することを恐れたとみられる。
三菱自動車は少なくとも2002年以降、法令と異なる試験方法で燃費データを取得していたことも判明しており、多くの不正を重ねていたことが浮き彫りになった。
三菱自動車によると、13年6月から生産を始めた「eKワゴン」など、軽4車種の燃費に関する走行試験のデータ「抵抗値」を改ざんし、実際よりも燃費を5~10%程度良く見せかけていた。
関係者によると、こうした軽4車種の一部の車で、「マイナーチェンジ」など比較的小幅な仕様変更の際、抵抗値を机上で算出するケースがあったという。時間がかかる走行試験をしない場合もあり、社内の燃費試験の時間短縮を図った可能性もある。
マイナーチェンジでも、車両の重さや空気抵抗が変わる場合などは走行試験を実施し、抵抗値のデータを検査機関に提出することになっている。
国土交通省は27日までに今回の不正の詳細を報告するよう三菱自動車に求めており、報告を受けた上で、実態解明を進める。(共同)
「三菱自動車が燃費試験のデータを不正によくみせかけていた問題で、不正を指示したという元部長は、作業方法などを指示した書類では正しい方法での計測を記載したものの、実際には口頭などで不正を指示していたとみられることが分かった。
関係者によると三菱自動車では、燃費を調べるための試験は通常、作業指示書に基づき行われる。しかし、不正を指示したという元部長は、作業工程を指示する書面上は、法律に基づいた正しい方法で行うよう記載する一方、口頭などでは不正を指示していたとみられることがわかった。」
悪質な確信犯であることは間違いない。証言者が出てこなければある程度は逃げれるであろう。しかし、消費者は許すのであろうか?
国交省はどのように対応するのか?裸の王様を続けるのか?規則や制度を抜本的に見直さないと現状では大した処分は出来ないと思う。なぜなら証拠がのこらないように口頭で指示し、書面上では辻褄を合わせている。
一般財団法人・化学及および血清療法研究所(化血研、熊本市)が行ったような巧妙な隠蔽工作は成功し、約40年間もチェックをすり抜ける事が出来た。性善説の制度は機能しない事が事実により証明されてきていると思う。
三菱自動車が燃費試験のデータを不正によくみせかけていた問題で、不正を指示したという元部長は、作業方法などを指示した書類では正しい方法での計測を記載したものの、実際には口頭などで不正を指示していたとみられることが分かった。
関係者によると三菱自動車では、燃費を調べるための試験は通常、作業指示書に基づき行われる。しかし、不正を指示したという元部長は、作業工程を指示する書面上は、法律に基づいた正しい方法で行うよう記載する一方、口頭などでは不正を指示していたとみられることがわかった。
また、三菱自動車では元部長が交代した以降も不正が続いていたことなどから、不正行為が習慣として続いていた可能性があるとみて詳しい背景について調べている。
横河ブリッジの親会社「横河ブリッジホールディングス」(東京都港区)の高木清次総務部長は「なぜ、このようなことが起きたのか、正確なことは分からない。大変な事故を起こし、誠に申し訳ありません」と報道陣に話し、頭を下げた。担当役員が現地に向かうなど情報収集を進めており、「明日(23日)、会社として分かっている情報を公表する」と述べるにとどめた。
横河ブリッジは1997年9月、今回と同じ送り出し架設工法を用いた北海道横断自動車道千歳ジャンクション(千歳市)でも、橋桁を落下させる事故を起こしたことがある。注意義務を怠って作業員5人を死傷させたとして、総括責任者らが業務上過失致死傷容疑で書類送検された。【山田奈緒、平川哲也】
三菱自動車が軽自動車の燃費データを偽装していた問題で、国土交通省が、新車を市場で発売する前に審査する際の燃費試験の方法を見直す検討を始めたことがわかった。
自動車メーカーが国交省に提出するデータについて、無作為に抽出した燃費データが正しいかを実際に道路で走行試験をして確認し、裏付け資料をそろえることを求めることが軸となる見通しだ。
また、国交省は、問題となった三菱自の計4車種の検証を検討している。他社についてもすでに売り出している車種の一部を抽出して調べる方向だ。確認には時間がかかるため、すべての車種を対象とすることは見送るとみられる。
自動車各社は新車発売前、燃費などを調べる国交省の外郭団体の審査を受けている。燃費は、施設内の測定装置に車を固定し、エンジンを動かしたり、タイヤを回転させたりして算出する。
「走行モードを限って測定した燃費が実際の燃費と大きく乖離していることをはじめ、そもそもクルマに関する行政は、「グレーゾーンが多すぎてフェアではない」という印象を持たれている。三菱自の一件を機に、自動車業界と行政が協力して新しいフェアなシステムの確立に動くべきだろう。」
自動車業界に対してだけ行政が甘いとは思わない。横浜のマンションの杭打ちデータ偽装の例や耐震補強工事に使われた部品の溶接部分の検査を検査会社が故意に見逃した例を考えても、行政のチェックが厳しければもっとはやく発覚していた事。
“性善説”を基本とする行政自体が問題が発覚した時のための言い訳としてあえて残していると思える。“性善説”で考えているから対応できない、騙した方が悪く、行政は騙された被害者とのスタンスで言い訳できる。“性悪説”を基本とすると行政の甘さや対応の悪さで非難される。大きな違いだ。
井元康一郎
20日に発覚した三菱自動車の燃費不正問題。この会見では、不正問題以外にも驚くべき事実が明らかになった。クルマの許認可に関する権限を持つ国土交通省は、なんと自ら審査することなく、自動車メーカーからの自己申告に任せていたというのである。同様の不正は他社にも波及する恐れがありそうだ。(取材・撮影・文/ジャーナリスト・井元康一郎)
走行抵抗値を改ざんした三菱自
ここ10年ほどの最大競争領域の技術
三菱自動車がクルマ(軽自動車)の燃費および排出ガスの測定において重要な役割を果たす走行抵抗の値を意図的に改ざんしていたことが20日に発覚した。
走行抵抗とは、クルマが走るときに発生する空気抵抗やタイヤ、車軸の摩擦抵抗などを合算した車体全体の抵抗のことだ。車は常にそれに抗いながら走っている。かりに空気抵抗ゼロの真空中を他の物質に接触することなく動くとしたら、いったん動き出した物体は慣性の法則によって、追加の運動エネルギーを与えなくても延々と同じスピードで動き続ける。
そこに加わる抵抗値が大きければ大きいほど、追加の運動エネルギーをエンジンや電気モーターでより多く発生させ続ける必要がある。
走行抵抗を減らせば、燃費を大きく向上させることができる。そのために自動車メーカーはエンジンや変速機の効率だけでなく、車体を少しでも空気抵抗の少ない形にしたり、転がり抵抗の少ないタイヤを使ったり、車軸がよりスムーズに回るような技術を開発したりといった努力をしている。
走行抵抗に関する技術は、ここ10年ほど、エンジンの熱効率の改善と並んで、世界の自動車業界においては最大の競争領域となっていた。
今回の三菱自の不正は、まさにその部分をターゲットとしたものだった。国交省の燃費、排出ガスの計測は実走行ではなく、クルマをローラーの上に置き、ゴロゴロとローラーを転がすというやり方で行われるのだが、それだと空気抵抗がかからず、正しい数値が得られない。
そこで、あらかじめ変速機をニュートラルにした状態でクルマを走らせ、どのくらいスピードが落ちるかを測ることで車体の空気抵抗値を割り出しておき、そのぶんローラーの抵抗を増やして、走っている時と同じような状態を仮想的に作り出す。
その前提となる値にごまかしがあれば、燃費は当然正しい数値にならない。記者会見での三菱自の説明によれば、数値をごまかしたことによる燃費改善率は車種によって5~10%、平均で7%ほどであったという。これは赤信号などで停止した時にエンジンを止めて燃料を節約するアイドリングストップ機構をつけるのに近いくらいの大差だ。
会見で明らかになった
燃費不正以外の驚くべき事実
開発担当副社長の中尾龍吾氏は「何回も繰り返す試験のなかでデータの中央値を取るべきところを下限に近い数値を使っていた」としながらも、計測値の範囲内ではあったと主張したが、燃費が平均7%違ってくるということを考えると、測定したデータの範囲内だったということ自体、とても鵜呑みにすることはできない。
三菱自は1997年、反社会勢力である総会屋の鄭照謨氏に対して利益供与を行った、いわゆる「海の家事件」を発端に、セクハラ、2度の欠陥隠蔽、欠陥改修の不徹底など、20年近くにわたってまさに不正だらけの体質を自ら正せないまま来てしまった。その報いを今後、行政罰や顧客への損害保障などにとどまらず、限りなく残酷な形で受けることになるのは避けられないだろう。
しかし、この問題は三菱自だけにとどまらない。会見では不正以外にも驚くべきことが明らかになった。
それは、クルマの許認可に関する権限を持つ国土交通省の審査があまりにもずさんだったということだ。前述のように、クルマの走行抵抗は燃費を大きく左右する、極めて重要な要素だ。その数値を国交省は、なんと自ら審査することなく、自動車メーカーからの自己申告に任せていたというのである。
「明らかになった」という言い方は、実は正しくない。
これまでも、燃費・排出ガス審査のためのフォーマットであるJC08モードのやり方について細かく取材していれば、走行抵抗が自己申告であることを知ることはできたであろう。だが、筆者はじめ多くの記者は、クルマのハードウェアを持ち込んだら、後の燃費審査は走行抵抗の計測を含め、すべて国交省が厳格に管理しているものだと思い込んでいた。
まさか燃費を左右する重要なファクターをメーカー任せにしているとは思いもよらなかったのだ。
国交省はこの問題を受け、三菱自だけでなく他社に対しても同様の不正がないか、5月18日までに調査を行うよう指示したという。また、立ち入り検査も行っている。
今回の三菱自の問題は、軽自動車のビジネスを行う子会社、MNKV社に折半出資している日産自動車が次世代モデルを開発するにあたって、不正のあった「デイズ(日産)」「ekワゴン(三菱自)」などのテストを行い、結果がおかしいことに気づいたため発覚したものだ。分厚い機密の奥にある開発現場での不正は、もともと表沙汰になりにくい。
スポーツタイヤとエコタイヤでも
まったく同じカタログ燃費値という不自然さ
メーカーに検証を求めたり、立ち入り検査を行ったりせずとも、国交省が意を決して各メーカーの市販車について走行抵抗を実際に測ってみればいいのだ。工業製品である以上、個体差もあることだろうから、審査を担当する人がラインから3車種ほどランダムに選び、それで計測すれば、メーカーが提出した走行抵抗の数値がおおむね正しいかどうかは一発で判明するはずだ。
実は、燃費や排出ガスの計測に関する不正が問題になっているのは日本ばかりではない。昨年秋、フォルクスワーゲンがディーゼルエンジンの排出ガスをごまかしていたことが一大スキャンダルとして取り上げられたが、その頃、ある国内メーカーの技術系役員は「フォルクスワーゲンのようなあからさまなものばかりではない。欧州では市販車と重量その他、走行抵抗に関係するスペックが異なる計測用のクルマを堂々と審査にかけるといったことが横行している」と、いまいましそうに語っていた。
燃費、排出ガスの性能を左右する重要な項目を“性善説”で取り扱うことに、そもそも無理があるのだ。
日本でもグレーな部分は少なからず見られる。クルマの走行抵抗に大きく関わる部品のひとつにタイヤがある。以前、ブリヂストンがタイヤの転がり性能について公開デモを行うのを見る機会があり、下り坂の同じ位置からブレーキを離して転がり、平地に移行してからどこまで到達するかというデモだったが、同じサイズのタイヤであっても到達距離にかなりの差が出た。
タイヤによって、同じ燃料でも走れる距離に違いが出るのである。実際、かつては装着タイヤによって燃費が異なるのが普通だったのだが、最近はスポーツタイヤとエコタイヤでまったく同じカタログ燃費値というモデルを見かける機会が多くなった。
走行抵抗値がまったく同じであればそうなるのだが、物理法則からみれば、不自然である。認証制度が変わってタイヤの違いが問われなくなったのだとすれば、それは国交省が走行抵抗に関する扱いについて、いい加減だということの証左だ。
幾度も不祥事を起こし、何度も更生を図りながら体質を改められなかった三菱自の信用失墜は免れない。また、いくらバレにくいといっても、クルマを作る技術がしっかりしており、かつ精神的にもフェアであるということを前提にクルマの型式認定を取得できるという立場を得ている以上、その信義を破った責任は重大である。
その一方で、メーカーがその気になれば横紙破りをできてしまうというシステムであることが露呈してしまった以上、信頼感の低下は三菱自1社にとどまるまい。
少なくとも燃費、排出ガスをはじめ、各種の審査においては、クルマそのものの性能を審査の段階で完全に測定できるように改め、不正が入り込む余地を積極的に排除する必要がある。
走行モードを限って測定した燃費が実際の燃費と大きく乖離していることをはじめ、そもそもクルマに関する行政は、「グレーゾーンが多すぎてフェアではない」という印象を持たれている。三菱自の一件を機に、自動車業界と行政が協力して新しいフェアなシステムの確立に動くべきだろう。
公益財団法人 日本自動車輸送技術協会が責任のある国交省の外郭団体とHPの情報で判断したけど、NALTEC 独立行政法人 自動車技術総合機構であった。
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案について(国土交通省)
道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律案について(国土交通省)
開けない人はここをクリック
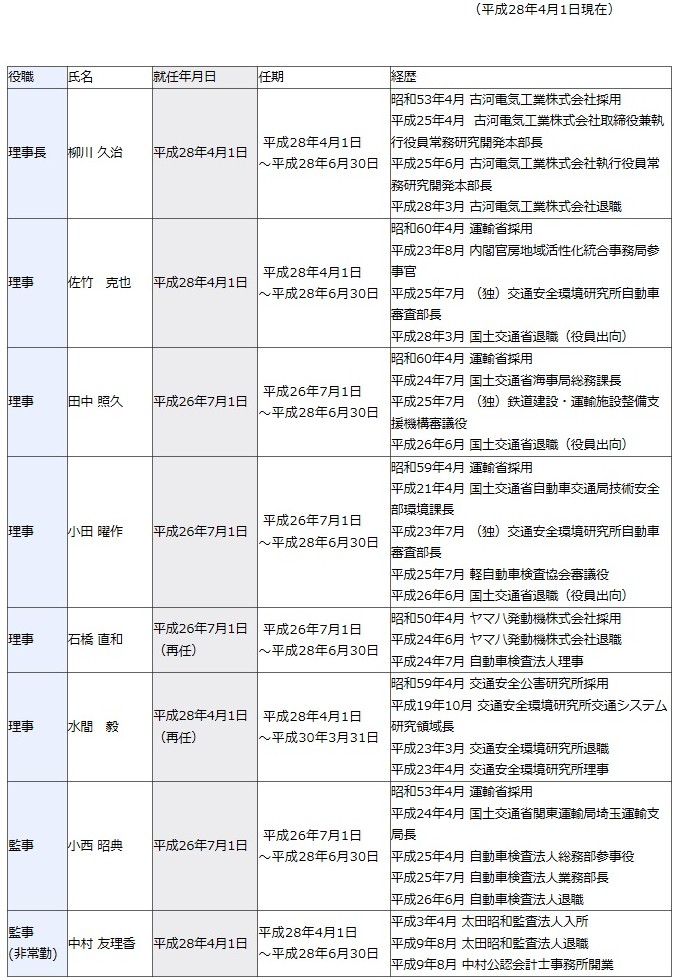
「型式認証制度に基づき、国交省は2年に1度ほどメーカーを監査している。ただ工場での品質調査が中心で、今回不正のあった設計開発部門までは通常は調べない。また、国が直接、走行抵抗値を測るには手間が掛かりすぎて現実的ではないという。担当者は『検査を迅速に行いつつ、データの信頼性を確保することが必要』と話す。」
言い訳としか聞こえない。手間が掛かりすぎるのなら、5年、一度、抜打ちで車を選んで調べるとかでも良い。抜け穴を用意しておいたとも誤解も出来る。
三菱自動車の燃費偽装問題で、国土交通省は22日、燃費算出の元となるデータをメーカー任せにしていた検査方法を見直すと明らかにした。実際の燃費が悪かった場合、エコカー減税の額にも影響が出るが、政府は購入者に負担させない方針を打ち出した。
自動車メーカーが新しい車を発売する前には、国交省の「型式認証制度」に基づき、国交省の外郭団体「自動車技術総合機構」が安全性や環境性能を審査する。燃費性能も試験し、カタログに記される値が確定する。
燃費試験では、回転するローラー台の上で車を走らせる。実際の路上を走らせると、タイヤと路面の摩擦や空気の抵抗による「走行抵抗」がかかるため、ローラーにはその分の抵抗を加えて燃費を算出する。この走行抵抗の値はメーカーが測定し、機構に自己申告する仕組みだ。
三菱自はこの仕組みを悪用し、軽自動車4車種の走行抵抗値を意図的に小さく偽装して申告した。カタログ上の燃費は、実際よりも5~10%良くなっていた可能性がある。
三菱自が出したデータを審査する側がチェックする仕組みがなく、石井啓一国交相は22日の記者会見で「不正が二度と行われないよう検査方法の見直しを検討していく」と表明した。具体的には、メーカーが走行抵抗値を測る試験に国の検査員が抜き打ちで立ち会ったり、測定試験の細かなデータを提出させたりする案が浮上している。
型式認証制度に基づき、国交省は2年に1度ほどメーカーを監査している。ただ工場での品質調査が中心で、今回不正のあった設計開発部門までは通常は調べない。また、国が直接、走行抵抗値を測るには手間が掛かりすぎて現実的ではないという。担当者は「検査を迅速に行いつつ、データの信頼性を確保することが必要」と話す。(中田絢子)
■三菱自「税金、差額お返しする」
三菱自動車がデータを偽装した軽自動車4車種では、環境性能が良い車の税金を優遇する「エコカー減税」が過剰に適用された可能性がある。国や自治体にとっては、税金を「取り損ねた」ことになるが、政府は、減税の恩恵を受けた消費者には負担を求めず、三菱側に負担させる方向で検討に入った。
「自動車各社は新車発売前、燃費などを調べる国交省の外郭団体の審査を受けている。燃費は、施設内の測定装置に車を固定し、エンジンを動かしたり、タイヤを回転させたりして算出する。」
自動車各社は新車発売前、燃費などを調べる国交省の外郭団体とは
公益財団法人 日本自動車輸送技術協会のことなのか??
日産自動車が問題に気付くのに、なぜ公益財団法人 日本自動車輸送技術協会は
10年以上も問題に気付かなかったのか????役員には自動車メーカーの役員が存在する。
三菱自動車が軽自動車の燃費データを偽装していた問題で、国土交通省が、新車を市場で発売する前に審査する際の燃費試験の方法を見直す検討を始めたことがわかった。
自動車メーカーが国交省に提出するデータについて、無作為に抽出した燃費データが正しいかを実際に道路で走行試験をして確認し、裏付け資料をそろえることを求めることが軸となる見通しだ。
また、国交省は、問題となった三菱自の計4車種の検証を検討している。他社についてもすでに売り出している車種の一部を抽出して調べる方向だ。確認には時間がかかるため、すべての車種を対象とすることは見送るとみられる。
自動車各社は新車発売前、燃費などを調べる国交省の外郭団体の審査を受けている。燃費は、施設内の測定装置に車を固定し、エンジンを動かしたり、タイヤを回転させたりして算出する。
三菱自動車の燃費試験データ不正問題で、新たに1車種でも法令とは違う方法で燃費試験用データが測定されていたことが21日、分かった。ほかに4車種でも同じ方法だった可能性が高い。三菱自が現在、国内で生産・販売している全車種のうち半数以上が法令と違う方法で測定されていた可能性が出てきた。
関係者によると、20日に国土交通省に報告した4車種のほかに、電気自動車(EV)「i-MiEV(アイ・ミーブ)」」でも道路運送車両法で定める方法とは異なる方法で燃費試験用データが測定されていた。「RVR」「アウトランダー」「パジェロ」「ミニキャブ・ミーブ」の4車種も同じ方法だった可能性が高いという。この方法について、国交省は「法令に沿っていない」と指摘している。
先に国交省に報告した4車種のうち2車種は日産自動車が販売していることから、三菱自が国内で生産・販売する約10車種のうち、不適正な方法で測定されている車種は少なくとも3車種となった。いずれについても、同法が定める方法で測定した上でデータを再提出。燃費試験を再度実施する。
一方、三菱自は、多数の問い合わせが予想されるため、現時点で判明している不正の内容を販売店に説明するなど顧客対応を本格化させた。外部有識者による委員会も設置し、誰が関与したのかなどを調査する。
国交省は21日、同法に基づき、三菱自の名古屋製作所・技術センター(愛知県岡崎市)に立ち入り検査を実施。燃費試験用データを意図的に操作した動機や方法などの解明を進める。
菅義偉官房長官は同日の記者会見で、三菱自の不正に関し「極めて深刻な事案だ」と強い表現で批判した上で「厳正に対応する」と述べた。
三菱自動車は、燃費データの不正が発覚した軽自動車4車種以外の約10車種で、少なくとも2002年から法令で定められた方法とは異なるやり方で燃費測定を行っていた。
この方法で測定しても、燃費が大きく改善するわけではないため、データ不正があったかどうかはっきりしない。ただ、不正な方法でデータを取っていたことは会社側が認めており、影響の広がりが注目される。
燃費測定の基になるのは、タイヤにかかる抵抗の強さなどを示す「走行抵抗」だ。道路運送車両法では「惰行法」と呼ばれる方法で測るよう定めている。走行中にギアをニュートラルに入れ、一定速度に減速するまで何秒かかるかを測る。これは日本や欧州で採用されている方法だ。
「Qなぜ不正ができたのか
A国交省によると、抵抗値はメーカーが申請書に記入して報告する。走行試験に国の担当者が立ち会うなどのチェックはなく、虚偽を見抜くことは不可能だという。今回は軽の開発で提携する日産自動車が抵抗値を測り、認証された数値との差を発見。問い合わせを受けた三菱自が社内調査を行って判明した。国交省は「制度の根幹を揺るがす問題だ」としており、試験方法が変わる可能性もある。」
つまり、国の規則や国交省が姿勢が不正を想定していないざる法であったと言うこと。
「国交省は『制度の根幹を揺るがす問題だ』としており、試験方法が変わる可能性もある。」と言っているが、試験方法が変っても国交省が虚偽を見抜く事は不可能と考えられる。裸の王様は変れないと言う事!
VWが不正が出来たから不正を行ったケースと環境は似ていると言う事。
三菱自動車が主力軽自動車「eKワゴン」などで燃費を良く見せる不正をしていたことが発覚した。燃費試験の信頼性を揺るがす重大な不正は、どのような手口で行われたのか。Q&Aでまとめた。
Qどんな不正があったのか
A国土交通省の燃費試験は、検査場の「シャシダイナモメーター」という装置を使い、回転する筒の上を走る車の排ガスを分析して燃費を算出する。空気抵抗やタイヤが転がる際の抵抗が少ない検査場と実際の路上の差を縮めるため、試験ではメーカーが報告した、各車種が受ける抵抗値を基に筒の回転に負荷をかけるが、三菱自は偽った数値を提出した。
Q手口は
A抵抗値は屋外の試験コースを走行して測り、複数のデータの中央値を取るべきだが、三菱自は低い数値を提出して試験時の負荷を軽くした。走行方法も国内で規定されたものではなく米国の方式を使った。
Qなぜ不正ができたのか
A国交省によると、抵抗値はメーカーが申請書に記入して報告する。走行試験に国の担当者が立ち会うなどのチェックはなく、虚偽を見抜くことは不可能だという。今回は軽の開発で提携する日産自動車が抵抗値を測り、認証された数値との差を発見。問い合わせを受けた三菱自が社内調査を行って判明した。国交省は「制度の根幹を揺るがす問題だ」としており、試験方法が変わる可能性もある。
再び経営危機に陥る可能性
三菱自動車は20日、同社製軽自動車4車種で燃費を実際よりもよく見せるためにデータを改ざんしていたと発表した。テスト時にタイヤなどの抵抗の数値を意図的に不正に操作することで、実際の燃費よりも10~15%程度に上乗せしていたという。同社の相川哲郎社長が国土交通省で記者会見し、謝罪した。当面、相川社長は原因究明に注力する考えだが、いずれ社長をはじめとするトップの経営責任は免れないだろう。
対象車種は三菱「ekワゴン」「ekスペース」と、同社が日産自動車に提供している「デイズ」「デイズルークス」の4車種で、計約62万5000台。三菱と日産は合弁で軽自動車の企画会社を運営している。現在の車種は三菱が中心となって開発したものだが、次モデルでは日産が主に開発を担う。
日産が次モデル開発に当たり、現行車種の燃費を測定したところ、国土交通省への届出の値とかい離があったため、日産側からの指摘を受け、三菱が社内調査したところデータ改ざんが発覚したという。
三菱自動車の不正行為は、昨年発覚した独フォルクスワーゲン(VW)の排ガス不正問題と構造が似ている。VWの場合は「ディフィート・デバイス」(無効化機能)と呼ばれる、排ガス試験時のみ有害物質である窒素酸化物(NOx)の排出が抑制される違法な制御ソフトを使い、通常走行では最大で基準値の40倍も排出していた。三菱もテストで不正を行うことで目標値をクリアして虚偽の燃費データを届けていた。
三菱自動車は過去に2回、大規模なリコール隠しを行ったことでブランドイメージは地におち、経営危機に陥った。三菱東京UFJ銀行、三菱重工業、三菱商事の3社が財務的な支援を行うことで、危機を乗り越え、危機の際に発行した優先株の処理もやっと終わったところだった。
三菱自動車は今回の不正によって、「業績への影響はどのくらい広がるのか分からない」としているが、ただでさえ不振の国内販売に追い打ちをかけ、再び経営危機に陥る可能性もある。頼みの綱である三菱重工業と三菱商事も、造船事業や資源エネルギー事業の不振などによって、以前のように自動車を支援する余力はないと見られる。
大手メーカーエンジニアの告白
三菱自動車は名門意識が強いからか、危機感に乏しく改革のスピードも遅く、トップ同士の不協和音や、生え抜き社員と専門性を買われて中途採用されたプロ社員との確執などが外部に漏れてきていた。
また、昨年は、適切な報告を怠ったため新車開発が遅れたとして社員2人を諭旨解雇したため、「開発遅れで懲戒処分とは異例」といった声も業界内では出ていた。社内は暗く、いつもぎすぎすした雰囲気だったという。一向に改善されないこうした組織風土も不正続発の遠因ではないか。
ただ、VW、三菱自動車と排ガスや燃費のテストの不正が続いたことは、単に企業風土の問題だけの問題では片づけられないのではないか、と筆者は感じ始めている。VWの不正について取材していた際に、ある大手メーカーのエンジニアが筆者にこう語った。
「試験で高い評価を受けた自動ブレーキが搭載されている他社の車を調べたら、試験時だけ効き目がよくなる特別な制御ソフトを利用していることが分かりました」
これも構造的にはVWや三菱自動車のやったことと近いが、現状では違法行為とはならず、「メーカーのモラルの問題」とそのエンジニアは語っていた。しかし、燃費の不正と違って自動ブレーキの場合は、人命にかかわる問題である。いずれ不正を摘発する法律が今後必要になるのではないか。
VW問題の時に取材した別のエンジニアは「2008年にVWの新型セダン『ジェッタ』が米国で発売された時に、エンジン制御のシステムを解析したが、不自然な点があった。学会でほとんど新しい発表がないVWの新型エンジンがおかしいというのはエンジン屋の中では公然の秘密だった」と語った。
日本でも5年前、東京都の調査によって、いすゞ自動車がトラックのディーゼルエンジンで「ディフィート・デバイス」を使用していたことが発覚した。これを受けて3年前から国土交通省はトラックとバスについては不正ソフトの利用を禁じているが、乗用車への利用禁止は見送った。
穿った見方かもしれないが、エンジニアの中には「どこもやっているので、ばれなければいい」といった感覚を持つ人も出てくる可能性があると、筆者はその時感じた。
お客様目線の欠如
こうした不正が起こる理由には、エンジニアの「お客様目線の欠如」もある。燃費の良さや排ガスのクリーンさといった環境技術が商品力として「武器」になり、環境技術が優れていれば税制も優遇される時代だ。
しかし、その尺度は市中を走る実走行でのデータではなく、あくまで実験時のデータであり、いわゆる「カタログ燃費」と言われるものだ。メーカーもエンジニアもカタログに載せる数値をよく見せるために、よい実験データを得ようと躍起になる。ここに不正に走る誘惑があるのではないだろうか。
ところがハイブリッドカーでも、高速道路を走るのか、渋滞道路を走るのかで実燃費は大きく違ってくる。自分が車をどのような用途で使うのか、どのような場所を走るのかをよく吟味せずに「カタログ燃費」を評価して購入している消費者もいることだろう。
そして、購入した後になって、「販売店が言っていた燃費よりも悪い」と気づく人もいるはずだ。結局、この構図はエンジニアやメーカーの自己満足や販売増のために消費者を犠牲にしているということだ。詐欺的行為と取られても仕方ないだろう。
米国では、実験と実走行のデータにかい離があるのは当然のこととして、カタログには実験データをそのまま記載できない規制がある。一定の係数をかけて実燃費に近い数値を書かなければならない。消費者の力が強い米国ならではの規制だと思うが、日本も見習っていいはずだ。
また米国の国土交通省に該当する役所では、自動車メーカーのエンジニア顔負けの博士号を持つような専門家がいて、エンジンの構造などにも精通しているため、盲目的にメーカーから提出された資料を通すことはないそうだ。自動車産業は日本の主力産業なのだから、国土交通省にもこうした専門職員がいてもいいが、日本には存在していない。
VW、三菱自動車と試験のデータ改ざんが発覚したことで、今後、カタログと実走行の数値のかい離の解消を促進するために、試験方法の見直しや世界での共通化が進む可能性がある。自動車はグローバル商品だからだ。さらに不正の取り締まりが法的に強化されるかもしれない。
これによってメーカーの環境技術への開発投資はさらに増え、世界規模で自動車メーカーの合従連衡を誘発させる引き金にもなるだろう。
不正を行い、不正が発覚すればどのように消費者が反応するのかは想像できたはずだ!しかし、不正を止められなかった!
消費者の対応と三菱グループの支援次第であるが、三菱自が三菱グループでなければ、今回の不正が公になった時点で三菱自は存続できないと思う。
三菱自動車が20日に燃費試験データを不正に操作していたことを発表し、再びブランドが失墜する事態になった。影響は対象車両の購入者をはじめ、車両を供給している日産自動車などにも及ぶ。過去の度重なるリコール(回収・無償修理)隠しでは、破綻寸前に追い込まれた。「お客様第一の組織」(幹部)に生まれ変わるため、組織改革を進め、業績も持ち直していたが、今回の不正で全てを失いかねない。
変わらぬ体質
「一つずつ石垣を積み重ねるように改善してきたが、全社員にコンプライアンス(法令順守)を徹底する難しさを感じている。無念で忸怩(じくじ)たる思い」
記者会見で相川哲郎社長は声を詰まらせた。2000、04年と相次いだリコール隠しでは、幹部社員の関与など構造的な隠蔽(いんぺい)体質が発覚した。このため、社内横断の品質担当の部署の設置や内部通報制度の整備など、品質問題に力を入れてきた。
だが今回、不正を防げず、発覚も日産の指摘がきっかけ。自浄作用がはたらかない、変わらぬ企業体質を浮き彫りにした。現時点では「当時の実験部長が『私が指示した』と言っている」(幹部)としており、「経営陣からの圧力はない」(同)という。ただ、昨年には新型車の開発状況を正確に報告しなかった担当者を処分したケースもあり、目標達成を強いるプレッシャーが組織にあった可能性もある。
一方、業績の悪化も無視できない。相川社長は「問題がどこまで広がるか全貌が見えない。かなりダメージは大きい」と述べた。日産向けを含めて約60万台の対象車のオーナーに加え、日産への補償なども必要。対象車の販売休止で岡山県の工場のラインも休止するため、地域の雇用や部品メーカーにも影響が及ぶ。ブランドイメージは悪化し、苦戦する国内販売のさらなる減少が想定される。
不正行為の発覚を受けて、既に20日の東京株式市場では三菱自の株価が急落。前日比131円(15.2%)安の733円まで売られ、年初来安値を更新した。売り注文は主要な株主にも広がり、三菱重工業は2.5%安、三菱商事は0.5%安で取引を終えた。リコール隠しで経営危機に陥った三菱自は、三菱商事など三菱グループの支援を受け、海外販売の強化や商品ラインアップの見直しなどを加速。15年4~12月期に営業利益が過去最高になるなど、回復軌道に戻ったかのようにみえていた。
自動車業界では、昨年秋に独フォルクスワーゲン(VW)が米国で排ガス規制を逃れるためディーゼル車に違法ソフトウエアを搭載していたことが発覚。トップが引責辞任し、販売減なども起きている。
業界全体に危機感
ディーゼル車については日系メーカーで同様の不正はみられなかったが、今回、三菱自が燃費試験データで不正をはたらいていたことが発覚し、業界全体の信頼を失う可能性もある。記者会見で相川社長は、自身の進退について明言を避けたが、益子修会長を含め、経営責任の問題は避けられない。失ったものはあまりに大きい。(田村龍彦)
「三菱自は記者会見で『焦りでやったものではない』と弁明したが、同社の軽自動車の燃費性能は競合他社よりやや見劣りするだけに『現場の焦りがあったのでは』(他社)との指摘もある。 」
処分は理由ではなく、事実で判断されるので、処分されるはず??そして社会的な制裁、消費者離れや中古車の価値の下落は避けれないだろう。
三菱自動車が実際より燃費を良く見せる不正行為は自社にとどまらず、供給先の日産自動車ブランドを含む計62万5000台に及んだ。今後の調査で台数はさらに増える可能性もある。三菱自は2000年代前半の「リコール隠し」で経営危機に直面して以降、信頼回復に取り組んだ。しかし提携先の日産に指摘されるまで不正をただせず、かつての「隠蔽(いんぺい)体質」を払拭(ふっしょく)できていないことを露呈した。
不正の手口は「走行抵抗値」と呼ばれる燃費を算出するための基礎データの改ざん。走行抵抗値とはタイヤの路面抵抗や空気抵抗などを数値化したもの。カタログに載せる燃費性能は国土交通省の審査で決まるが、その基になる走行抵抗値はメーカーの届け出数値が採用される。
国は国の施設で行う走行試験データに、メーカーから提出された走行抵抗値を掛け合わせるなどして燃費を算出。三菱自はメーカーの言い値が採用されるこの仕組みを悪用した。走行抵抗値は通常、自社の複数回の走行実験の中央値を採用するが、燃費を良く見せられるようデータを改ざん。この結果、カタログの燃費性能は実際より5〜10%高まったという。
近年の軽自動車は維持費の安さのほか、燃費性能が魅力で自動車各社は激しい開発競争をしている。今回の不正の背景にも「良い燃費に見せようという意図があったのは確か」(相川哲郎社長)だ。三菱自は記者会見で「焦りでやったものではない」と弁明したが、同社の軽自動車の燃費性能は競合他社よりやや見劣りするだけに「現場の焦りがあったのでは」(他社)との指摘もある。
一方、不正発覚の端緒は、軽自動車開発などで三菱自と提携する日産だった。次期車種は日産が主導で開発することが決まっており、開発の参考にと三菱自から提供を受けた車の燃費性能を計測し、カタログ上の性能に達しないことが分かった。
日産は「自主的に該当車種の販売を中断する旨を販売会社に通知し、ユーザーへのサポートの検討を始めた」とのコメントを出した。【宮島寛】
自業自得?
燃費試験で不正、ダメージコントロールに失敗
三菱自動車の20日の不正発表会見は、ダメージコントロールに失敗したお粗末会見となってしまった。
組織性が高いのかどうかなど不正実行の実態解明の説明が不十分。実態を隠しているような印象を強くした。失敗会見だ。
会見で明らかにした三菱自動車の不正は、燃費試験データを捏造したというもの。自社販売の「eK ワゴン」など2車種、15万7000台と、日産自動車に供給している「デイズ」など2車種、46万8000台の計62万5000台に及ぶ。
ことの発覚は日産自動車が次期共同開発車を開発しようとして試験したところ、公表していた数値との乖離がみつかったという。他社に指摘されるまで不正を見つけられなかったことだけでもお粗末というほかないが、会見では社内調査の中途半端さが目立った。不正が組織的なものに発展する可能性が濃厚との印象はぬぐえない。
不正実行の実態については、検査にあたった第一性能検査部長(2013年当時)が「(不正を)指示した」と自白していることを明らかにした。しかし、その上司や他の関連部署の関与については当人に対し「ヒアリングしていない」という常識では考えられない説明に終始した。
客観的で徹底的な調査を行うためとして「外部有識者の調査委員会を設置しそこに任せる」と発表した。原因、関与した人数は委員会の調査にゆだねるとも説明した。しかし、あまりにも基本的な事実関係もわかっていないと繰り返し、会見では外部委員会の設置を「隠れ蓑」として使っている印象すら与えた。
情報を出し惜しんだのは、なぜか。組織的な不正であるイメージを薄め、できるだけ関係者を限定したかったからだろうか。だとすれば、ダメージコントロールを狙って、かえってダメージを大きくした悪しき会見の典型ということになる。
三菱自動車は過去に2度の大規模なリコール隠しが発覚している。この日の会見の失敗もあって、存続を問われるほどの信用の失墜につながるだろう。
なぜ、不正を働いたのか。単純な疑問にも答えない。外部委員会にゆだねると繰り返した。しかし、不正しなかった場合の本当の燃費では、「(当時の)エコカー減税を受けられなかった可能性が高い」(中尾龍吾副社長)と認めざるえなかった。
つまり減税対象とするための不正操作だった可能性が高い。もちろん燃費のよさで販売を促進しようともしたのだろう。販売・開発戦略にかかわる不正であり、検査部署だけの判断で実行する内容ではないだろう。今後、不透明な部分に関する取材と報道合戦が繰り広げられるのは確実だ。連日のように会社の「悪行ぶり」が報じられていくことになりかねず、会社の信用失墜にこれほど効果的な道筋もあまりない。
財務の面でも深刻な影響がある。60万台に及ぶ対象車の購入者への補償は必須だが、単に損をさせたガソリン代の試算と慰謝料だけで済むのか。「正直さ」に疑いが強まったいま、賠償請求訴訟の提訴が十分に想定される。また、不正に減税を得ていたとなると、その返済もすべて三菱自動車の負担になる。
不正そのものも常識外の内容だが、ダメージコントロールに失敗したツケは、あまりにも大きいというほかはない。
土屋 直也 (ニュースソクラ編集長)
三菱自動車は、自動車の燃費試験で不正行為があったとして、20日午後5時から記者会見した。会見には相川哲郎社長らが出席して詳細について説明した。
相川:本日は当社製車両の燃費試験における不正行為につきまして、ご報告いたします。当社製軽自動車の型式認証取得において、当社が国土交通省へ提出した燃費試験データについて、燃費を実際よりも良く見せるために不正な操作が行われていたことが判明しました。また、国内法規で定められたものと異なる試験方法が取られていたことも判明しました。お客さまはじめ、全てのステークホルダーの皆さまに深くおわび申し上げます。申し訳ございませんでした。
該当車は2013年6月から当社で生産しているekワゴン、ekスペースと、日産自動車向けに供給しているデイズ、デイズ ルークスの計4車種でございます。これまでに当社は計15万7000台を販売し、日産自動車向けには計46万8000台を生産しております。2016年3月末現在でございます。
燃費試験については、該当車のいずれについても開発を担当し、認証、届出責任を持つ当社が実施していました。次期車の開発に当たり、日産自動車が該当車の燃費を参考に測定したところ、届出値とのかい離があり、当社が試験で設定した走行抵抗値について確認を求められました。これを受けた社内調査の結果、実際より燃費に有利な走行抵抗値を使用した不正を把握するに至ったものです。該当車にお乗りいただいているお客さまに対しては、今後、誠実に対応させていただきます。
なお、走行抵抗とは、車両走行時の転がり抵抗、主にタイヤによるものと、空気抵抗を合わせた抵抗のことでございます。また、該当車については生産、販売を停止することといたしました。日産自動車でも販売を停止していただいており、補償についても今後、協議いたします。
その他の国内市場向け車両についても、社内調査の過程で国内法規で定められたものと異なる試験方法が取られていたことが判明しました。また、状況の重大性を鑑み、海外市場向け車両についても調査を行います。これら問題につき、さらに客観的で徹底的な調査を行うため、独立性のある外部有識者のみによる、調査のための委員会を設置し、調査結果がまとまり次第、公表させていただく予定です。以上でございます。
不正な燃費値は実際のものとどのくらいかい離があるのか
朝日新聞:それじゃあ、引き続きよろしいですか。
相川:はい。
朝日新聞:幹事社、朝日新聞です。今、出てるものについて、燃費をどういう基準で、本来どうあるべきものがどうだったのかなどは、現時点では分からない?
相川:では、中尾のほうから。
中尾:それにつきましては、私のほうからご説明させていただきます。先ほど、相川のほうから申し上げましたように、走行抵抗の(※判別できず)。
男性:すいません、聞こえないです。
女性:聞こえない。
男性:聞こえない。
男性:すいません。
中尾:それでは私のほうからご説明します。先ほど、のほうからご説明しましたとおり、走行抵抗を低く出してる。
男性:マイク使ってしゃべってください。
男性:聞こえない。
男性:広報さん、どのマイクですか。
男性:黒いやつです。細い黒いやつ。
男性:細い黒いやつですね。
男性:社長の前にある、細い黒い。
中尾:あ、これですね。
男性:はい、ありがとうございます。
中尾:申し訳ございません。では、私のほうからご説明いたします。先ほど、相川が申し上げましたとおり、走行抵抗を低く設定していたということで、現在正規の走行抵抗値を取り直して、もう1回、試験を実施いたしております。その結果に基づきまして、実際のこの燃費値が、どれだけかい離するのかということは、結果をまた別途、発表させていただきたいというふうに思っております。
朝日新聞:では各社、質問は。どうぞ。
試験はどのように行われているのか?
記者:(※判別できず)どのような試験で(※判別できず)。
横幕:今のご質問に対しまして、私のほうからお答えしたします。まず、今回走行抵抗を測っておりますのは、自社の中で測ってございます。実際に燃費、排ガスの測定をする前段階といたしまして、ルールに、規定に定められました惰行法というものがございます。惰性の「惰」に「行く」という惰行でございます。これは、実際にはある一定の車速で走っていて、ギアをニュートラルにいたします。その際に、スピードの変化を見るわけですが、惰行法自体、国が定めております惰行法は、時速90キロからプラマイ5キロの範ちゅう内の10キロを、減速するのに何秒かかるかということを測定するというものでございます。それに対しまして今回、われわが行った試験と言いますのは、高速惰行法と呼ばれるものでございまして、これはある車速からスピードごとではなく、一気にスピードを下げてまいります。
考え方といたしましては、10キロ下がるのに何秒かかるかが定められたルール。われわれがやっておりましたのは、1秒間の間に何キロスピードが減速するかというものを測っていたものでございました。いずれの場合も、ご質問にあります、われわれの社内での試験でございます。その走行抵抗を測定したものから、二乗平均という形で、各車速の平均を取ります。その平均を取った値を基に、シャシダイナモという台上試験に車をセットいたしまして、その走行抵抗負荷を、そのシャシダイナモにインプットしまして、実際の燃費、排ガスを測るというものでございます。
今、申し上げたところはいずれも自社内で実施している試験でございます。
記者:燃費って、(※判別できず)どのぐらいでしょうか。
横幕:今のカタログ値といいますか、数字でございますか。少々お待ちください。
記者:JC08で(※判別できず)自社へ持っていって、その結果を、要はデータを不正したという。
横幕:はい。今、先ほど申し上げました、走行抵抗データというのが近似線で示されます。通常ですと測ったデータの中央値を取るわけでございますが、ここに走行抵抗を意図的に小さいものっていう形にして、燃費、排ガスの計測を行ったということでございます。
記者:すいません、JC08(※判別できず)。
横幕:はい。申し訳ございません。
記者:かい離の、まだ質問に答えてないんで。
横幕:現在、届出しております、一番新しい16型のekワゴンでございますが、2WD車におきまして、ちょっと仕様、類別がございますが、訴求車で燃費値は30.4、標準車でおきますと、2WDが26.0。また標準車の4WDは、26.6キロ、ターボチャージャーの二駆につきましては、26.2キロ、ターボチャージャーの四駆につきましては25.0キロ、いずれもパーリッターの値が届け出の燃費値ということになってございます。
記者:それに関しては、日産の(※判別できず)。
横幕:はい。基本的には走行抵抗は同じものという形でやってございます。
記者:記者:すいません。その、JC08のデータに対して、今回のかい離というのは、どれくらいの割合だったんでしょうか。何%とか、数値があるのと、かい離の割合ですね。
中尾:それにつきましては、現在正しい走行抵抗値で再試験をやってる最中でございます。今の状況からいきますと、5%から10%ぐらいのかい離があるであろうというふうにみておりますが、これはいずれにしましても最新の数値を国土交通省のほうに提示する予定にいたしております。
記者:それは5%から10%、実際は悪くなっているという、そういうことですか。
中尾:そうです。
意図的な操作によって行われたものなのか
記者:すいません、確認なんですけど、これは意図的な操作によって行われたものなのか、そうであるならば、なぜそういった意図的な不正が行われたのか。それで社長はそれに対して責任をどう受け止めていらっしゃるのか、お答えください。
相川:まず、この操作は意図的なものであると考えております。その理由は、現在、まさに詳細は調査中でございますが、数字を良く、いい燃費に見せるという意図があったのは確かでございますが、なぜ不正までしてやろうとしたか。ここまでは現在調べておりまして、分かっておりません。
私としましては、この件につきましては、把握しておりませんでした。これについては経営として責任を感じております。
記者:実際にご自身の進退も含めて、今後の責任の取り方としてはどのようにお考えですか。
相川:まずはこの問題を解決する。そして次の再発防止に向けて道筋を付けるということが、私の責任を果たすことだろうと思っております。それ以上のことは、今は考えておりません。
記者:すいません、海外だったのか(※判別できず)、社長が知ったのはいつなのか。日産から問い合わせがあったのがいつなのか。国が、たぶん検査をしなきゃいけないと思うんですけども、それをどのようにスルーしたのか。その辺も具体的に教えていただけますか。
中尾:それは私のほうから回答させていただきます。この数値を、不正を行った部署は、当社の性能実験部というところです。その中で、どのレベルまでが関与していたのかという点につきましては、今現在調査中であり、これは社内だけの調査では透明性がないというふうに考えておりますので、外部の独立した有識者による調査も含めまして、その全貌を解明していきたいというふうに思っています。
で、日産自動車のほうからその指摘がございましたのは、これは昨年の8月に当社と日産自動車が協業で造っております、現在の軽自動車の次期車を今後、日産自動車のほうで開発をお願いするということが決まりまして、そこで日産自動車側の開発がスタートいたしました。そのあと、11月ごろに次期車の軽自動車の燃費の試験を始めるために、現行車の、15型のデイズの燃費を日産自動車のほうで測定したところ、届出値との乖離があるということで、昨年の12月に本件について合同で調査をしたいという申し入れがございました。
それを受けまして、今年の2月に当社と日産自動車さんと一緒になって、実際の車の燃費を調査しまして、で、3月にそれを分析した結果、走行抵抗に差があるということが判明いたしました。それに基づきまして、4月から当社内でなんでこんなに差があるのかといったところを調査を始めまして、で、最終的に不正が行われていたということが判明し、社長に報告したのは4月13日でございます。
相川:あと、この件を日産自動車さまにご報告したのは、4月18日でございます。
記者:国の検査をどうやってスルーしたのか、答えてないですよね。
中尾:国の検査につきましては、われわれのほうから走行抵抗値というものを出しております。で、これは先ほど横幕のほうがご説明しましたとおり、走行抵抗値を、シャシダイナモ、国の燃費試験をする、台上で燃費試験をするシャシダイナモというのがございます。そこにその数値をインプットして、JC08のモード運転をするものですから、その結果、走行抵抗値がインプットされると、必然的にその値で出てくるものですから、ですから、これは国のほうとしては、走行抵抗値が正しいと思って、それをインプットした結果としては、これは分からないということになりますので、その走行抵抗値に不正があったということですので、国のほうとしては分からない状態であったというふうに判断いたします。
企業体質は簡単には変らない!これが現実なのでしょうか?
三菱自動車工業は、車両の燃費試験での不正行為について、20日午後5時から相川哲郎社長が記者会見すると発表しました。
発表によりますと、三菱自動車は自社の車両の燃費試験での不正行為について、20日午後5時から相川哲郎社長が都内で記者会見するということです。
関係者によりますと、三菱自動車が販売した、いずれも軽自動車の「ekワゴン」と「ekスペース」のほか、日産自動車向けに生産した「デイズ」と「デイズルークス」で、実際よりも燃費をよく見せる不正を行っていたということです。
対象となる台数は60万台規模に上る可能性があるということです。
会社側では具体的な内容について、このあとの記者会見で明らかにすることにしています。
「東京空港交通」(本社・東京)のマニュアルに国際線航空機が国内空港に代替着陸したケースの対応が記載されていないのではないのか?
もし、マニュアルに対応が記載されているのなら配車係がマニュアルを理解していない事になる。
東京入国管理局は空港や「東京空港交通」のマニュアルや対応に関してチェックする権限があるのであろうか?あるとすれば、東京入国管理局が見落とした可能性もある。
「東京空港交通」(本社・東京)及び東京入国管理局は事実関係を把握して公表するべきだと思う。
格安航空会社(LCC)のバニラ・エアは18日、台北発104便で17日夜に到着した乗客159人(日本人126人、外国人33人)が成田空港で入国手続きをせずに入国したと発表した。乗客を運ぶリムジンバスが誤って国内線到着口に誘導したのが原因。18日午前9時現在、47人(日本人41人、外国人6人)が入国手続きを済ませておらず、連絡が取れていない人もいるという。東京入国管理局が事実確認を進めている。
同社によると、同便は17日午後5時に成田着の予定だったが、強風の影響で着陸できず、いったん中部国際空港に代替着陸した後、午後9時45分に成田に着いた。そのため、リムジンバスを運航する「東京空港交通」(本社・東京)の配車係が国内線と勘違いし、バスに国内線到着口に行くよう指示した可能性があるという。
不審に思った乗客が午後10時ごろバニラ・エア側に指摘してミスが判明。空港内でアナウンスをしたが、既に約50人がその場にいなかった。
バニラエアは「多くの方にご迷惑をおかけしおわびします」とコメント。東京空港交通は「事実関係を確認中」としている。
【北川仁士】
「4月の電力小売り全面自由化で価格競争が激しくなれば、経営基盤の脆弱な新電力の淘汰が加速する懸念もある。」
これは誰でも想像できる事。しかし、自前の発電施設を持たないのに負債総額163億円と言うことは少なくとも誰かが得をしたと言う事!
新電力(新規参入事業者)大手の日本ロジテック協同組合(東京都中央区)が15日、東京地裁に自己破産を申請し、同日手続き開始決定を受けた。帝国データバンクによると、負債総額は約163億円と今年最大で、新電力の倒産としては過去最大規模。電気の供給は大手電力が肩代わりするため、契約者が停電することはない。
日本ロジテックは平成19年の設立。22年に電力を一括購入し仕入れ価格を下げた上で、組合員に安価な電力を販売する「電力共同購買事業」を開始し、27年3月期の売上高は約555億円だった。しかし収益性が低く、資金繰りが急速に悪化していた。
4月の電力小売り全面自由化で価格競争が激しくなれば、経営基盤の脆弱な新電力の淘汰が加速する懸念もある。
カレーチェーン「CoCo壱番屋」を運営する壱番屋(愛知県一宮市)は9日、同社が社員食堂廃棄物を一般廃棄物処理の許可を持たないダイコー(稲沢市)に委託したと掲載された中日新聞朝刊の記事について、内容の一部訂正と、その事実関係について発表した。
この記事には、同社の本社社員食堂の生ごみを、一般廃棄物処理の許可をもたない産業廃棄物処理業者ダイコーに委託し、また委託にあたって無理強いをしていた旨が記載されていた。同社はダイコーにごみの処理を委託していたことは事実だが、無理強いした事実は一切なかったとし、この経緯を下記のように説明した。
同社は、2001年より、工場で排出される産業廃棄物などの処理をダイコーに委託していたが、2010年3月からは、電子マニフェストの対応のため、他の産廃業者に委託していたパン粉および、同社員食堂の生ごみもあわせて委託するようになった。同社員食堂の規模は、1日あたりの利用者数約140人、生ごみの量は平均約5キロ。
-
なお、同社は、ダイコーが一般廃棄物処理の許可をもたないことを未確認のまま、当時契約に至った理由は下記のとおり。
01.ダイコーは食品リサイクル対応(堆肥化)をしており、環境対策上より望ましいと判断した。
-
02.当社の担当者と、ダイコーの担当者の間で、「工場に隣接する同食堂から出る生ごみも合わせてリサイクル処理が可能か」「可能である」とのやりとりが行われた。
-
03.同社担当者も、この業務が別の産廃業者から移管するということで、次に引き継ぐダイコーが一般廃棄物処理の資格を有すると思い込んだ。
今回の事件は、今年1月にダイコーが同社の廃棄ビーフカツを不正転売したことから発覚したが、廃棄物処理事業者も発注事業者も、担当者レベルまで廃棄物管理について把握し、現状を見直すことが必要だ。
環境ビジネス編集企画部が、この不正転売事件をうけ、2月に実施したアンケートでも「社内の廃棄物管理の教育」について見直しが必要と答えたのは、全体の64%にのぼった。「廃棄物業者の選定を再度行う必要がある」は56%、「廃棄物の管理体制を見直す必要がある」は52%に達した。
「それにしてもフザケているのはURの対応だ。13日の“緊急会見”で幹部5人が謝罪したのに、『これはレクです』と完全な上から目線。カメラマンを閉め出し、写真撮影は完全NG。職員が一色氏からどんな接待を受けたかについては、『回数や金額を本日は申し上げることができない』『第三者委員会の調査に任せる』とお茶を濁して説明を拒んだ。
都市再生機構(UR)は一旦、解体が必要。
URは国会などで追及を受けても『(一色氏から)複数の職員がファミレスで数百円のドリンクを提供された』と、ぬるい内部調査を公表してきた。」

甘利前経済再生相の“口利きワイロ疑惑”が新たな局面を迎えた。
東京地検特捜部が関係先に強制捜査に入ったのは今月8日。これまで千葉県の建設会社「薩摩興業」と甘利事務所の関係だけがクローズアップされてきたが、13日、都市再生機構(UR)が「職員に重大なコンプライアンス違反があった」と急きょ発表した。職員が薩摩興業側から飲食接待を受けていたことを認めたのである。しかも、100万円以上の金額だったという。
急転直下の発表は、14日発売の「週刊文春」が〈URの内部情報が甘利事務所に流れていた〉と暴いたからだ。
URから薩摩興業側に払われた補償金は、当初の2000万円から約2億2000万円に跳ね上がった。これは薩摩興業の元総務担当者、一色武氏(62)から計800万円以上の現金を受け取った見返りに、甘利氏の元秘書が“口利き”した結果だ。実は、中立的立場とみられてきたURも噛んでいたというのだ。
URの内部情報を漏らしていたのは幹部職員2人。「文春」によると、その1人は神奈川県のフィリピンパブなどで総額100万円の接待を受けた見返りとして、上積みできる補償金額などの情報を一色氏に漏らしていたらしい。甘利事務所はこの内部情報をもとにして、国交省に“プレッシャー”をかけていたようだ。これが事実とすれば、甘利氏の元秘書も、UR職員も、一色氏も“同じ穴のムジナ”ということだ。すでに職員2人は特捜部に任意聴取もされている。
「UR職員は『みなし公務員』で、刑法の収賄罪の対象です。過去に飲食接待で立件された事例もあり、特捜部は今後、贈収賄罪を適用できるか探ることになるでしょう。もし、接待を受けていたUR職員が甘利氏側が優位になると事前に分かっていたり、打ち合わせしたりしていたとすれば、甘利氏側も罪に問われることになるかもしれません。国会議員や秘書に適用したことのないあっせん利得処罰法違反で甘利氏の立件を目指すより、グッとハードルが低くなると思います」(「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士)
果たして、一色氏と甘利サイドとUR職員はグルだったのか。一色氏のカネが、甘利前大臣とUR職員に渡っていたことだけは間違いない。
それにしてもフザケているのはURの対応だ。13日の“緊急会見”で幹部5人が謝罪したのに、「これはレクです」と完全な上から目線。カメラマンを閉め出し、写真撮影は完全NG。職員が一色氏からどんな接待を受けたかについては、「回数や金額を本日は申し上げることができない」「第三者委員会の調査に任せる」とお茶を濁して説明を拒んだ。
URは国会などで追及を受けても「(一色氏から)複数の職員がファミレスで数百円のドリンクを提供された」と、ぬるい内部調査を公表してきた。
この複雑怪奇な事件の全容解明には、やはり甘利前大臣を証人喚問するしかないのではないか。
「URは『交渉への影響はなかったと考えている。今後捜査で明らかにされると思う』と説明した。」
証拠が残らないように対応してきたと言う自信なのか、それとも、既に証拠を処分したのか?
まあ、理由もなしに接待などする人はいない。URの職員が騙されたふりをして、相手に驕らせたと言うのであれば信用できるかもしれないが。
しかし、人間としてはろくでもない人だ。
「URによると、2人は2014年10月から15年10月までの1年間に、居酒屋などでそれぞれ複数回、一色氏から接待を受けた。飲食代などは今年1月中旬までに返金したという。」
どう見ても、やばいと思ったから返金したとしか考えられない。都市再生機構(UR)は組織としては腐っているかもしれない???
東京地検特捜部、2職員から任意聴取
甘利明前経済再生担当相(66)の現金授受問題を巡り、都市再生機構(UR)は13日、男性職員2人が、道路事業の移転補償でトラブルとなっていた千葉県の建設会社「薩摩興業」の元総務担当者、一色武氏(62)から飲食接待を受けていたと発表した。2人は当時、UR千葉業務部で道路事業の補償と工事を担当していた。関係者によると、東京地検特捜部の任意聴取も既に受けており、接待総額は100万円近くに上るとみられる。
URによると、2人は2014年10月から15年10月までの1年間に、居酒屋などでそれぞれ複数回、一色氏から接待を受けた。飲食代などは今年1月中旬までに返金したという。
URは「極めて不適切で誠に遺憾」として第三者による調査を実施する方針を発表。その上で「接待が補償に影響したとは把握していないが、捜査中で個別の情報は申し上げられない」として詳細な説明を拒んだ。
一色氏によると、道路事業の計画地にあった薩摩興業事務所の移転に伴うURとの補償交渉を11年9月から開始。難航していたため13年5月に甘利事務所に「口利き」を依頼した。甘利事務所側がUR側と接触すると交渉が進展し、同8月に約2億2000万円の契約を締結した。一色氏はその後も同じ工事を巡りURと別の補償交渉を進めていた。
関係者によると、2人はそれぞれ道路事業の工事と補償の責任者。一色氏は交渉の過程で2人と顔見知りとなり、URの内部情報を得ていた疑いがある。
URによると、今月10日に1人から申告があり改めて内部調査を実施した。2人のうち1人は、これまでの調査に対して一色氏から接待を受けていたことを否定していた。もう1人は1回分の接待を認めていたが、他にも接待を受けていたことを新たに認めた。URは「調査が不十分だった」としている。
この問題を巡り、特捜部はUR本社や一色氏の自宅をあっせん利得処罰法違反容疑で家宅捜索し、補償交渉の経緯を詳しく調べている。UR職員は公務員と同様に刑法の収賄罪が適用される「みなし公務員」にあたることから、2人の職務権限や補償交渉で果たした役割なども捜査し、全容解明を進めるとみられる。【石山絵歩、近松仁太郎】
甘利明前経済再生担当相の金銭授受問題で、都市再生機構(UR)は13日、男性職員2人が2014年10月から約1年間、千葉県の建設会社の元総務担当者から飲食の接待を複数回受けていたと明らかにした。
うち1人は同社との補償交渉を担当していたが、URは「交渉への影響はなかったと考えている。今後捜査で明らかにされると思う」と説明した。
マンションのエレベーター事故は新聞記事から判断して減っているように思えるが、業務用エレベーターの事故は増えているように思える。 食品加工会社は厳しそうだから十分なメンテナンスに費用をかけられないのかも?
13日午前8時半頃、北海道富良野市花園町の食品加工会社「西川食品」で、同市東麻町の社員前田美由紀さん(37)がエレベーターと床に挟まれた。
前田さんは搬送先の病院で死亡が確認された。
道警富良野署によると、前田さんは惣菜の調理工程を担当していた。惣菜の容器が入った段ボール箱を載せた業務用エレベーターが1階から2階へ上昇する途中で停止した。前田さんが2階からエレベーターに体を乗り入れたところ、エレベーターが落下し、エレベーターの天井と2階の床に体を挟まれたという。同署で事故の原因を調べている。
2200万円もの金額を懲戒免職を受けた元職員は全額弁済できるのか?
愛知県一宮市の障害者就労支援施設「コスモス」で、男性職員(既に解雇)が、障害者が働いて得た2008〜11年の収益計約2200万円を着服していたことが13日、分かった。この間、障害者が本来受け取るべき賃金が一時的に減っており、問題発覚後に施設運営法人「コスモス福祉会」(山田祥男理事長)が肩代わりして障害者に支払った。
同施設によると、11年秋ごろ、この職員が自ら着服した事実を打ち明けて問題が発覚した。施設側は職員を解雇し、同年12月に愛知県警に相談した。
同施設は、空き缶やペットボトルなどのごみを回収、圧縮のうえ、リサイクル業者に売却する事業を中心的に行っている。約40人が通所で働いている。売却益の十数%が賃金になっている。
この職員は業者に空き缶などを売却する担当で、受け取った売却益の一部を08年8月〜11年10月の間に約130回着服していた。1回当たりの着服額は平均20万円弱だったという。
障害者が受け取る賃金はコスモス福祉会がいったん立て替え、着服した元職員が施設側に全額弁済している途中という。【河部修志】
「運行管理の担当者が業務中に携帯電話を使うことは禁止されていた。」
携帯電話でのゲームも禁止と明確に記載するべきだったと思う。
【ベルリン=井口馨】独南部バイエルン州で2月に列車同士が正面衝突し、11人が死亡、85人が負傷した事故で、地元検察当局は12日、運行管理を担当していた男を過失致死容疑などで逮捕したと発表した。
独DPA通信などが伝えた。男は事故直前まで、携帯電話のゲームで遊んでいたという。
検察当局は、男が勤務開始後、携帯電話のオンラインゲームで長時間遊んでいて注意が散漫となり、誤った信号を表示させたことなどが事故の原因とみて調べている。運行管理の担当者が業務中に携帯電話を使うことは禁止されていた。男はゲームをしていたことは認めたが、「注意はそらしていない」と話しているという。
「馳浩文科相は12日の閣議後の記者会見で、「各教委や教科書会社から『不正(採択への影響)はなかった』と報告を受けているが、私は懐疑的な思いで見ている」と述べ、公取委の調査で教科書会社に排除措置命令が出た場合、教科書無償措置法に基づく発行者の指定取り消しも含む厳しい対応を検討する考えを表明した。」
当然のコメントだが、当然のコメントが出来ないケースが多い。それがこれまでの日本。
教科書会社が検定中の教科書を教員らに見せ、現金などの謝礼を渡していた問題で12日、公正取引委員会が、謝礼を渡すなどの行為で公正な取引がゆがめられた恐れがあるとして、独占禁止法違反(不公正な取引方法)の疑いで、小中学校の教科書を発行する全22社を対象に調査を始めることが分かった。
独占禁止法は、競争相手の顧客に現金などの利益を提供して取引するよう仕向ける行為を「不当な利益による顧客誘引」として禁じている。関係者によると公取委は、教科書会社が現金などの謝礼を渡したことが、こうした行為に当たるかどうか調査する。各社から事情を聴くとともに資料の提出を求め、再発防止を求める排除措置命令や警告を出すか検討する。
公取委の杉本和行委員長は、3月の参院予算委員会で「教科書発行者が、教科書の採択に関与する者に経済上の利益を不当に供与し、これにより教科書発行者間の公正な競争が阻害される恐れがある場合、独禁法上問題になる」と答弁していた。
一連の問題の出発点は三省堂で昨年10月、小中学校の校長らを集めて検定中の教科書を見せ、意見を求めた謝礼として現金5万円の提供が発覚したこと。その後、小中学校の教科書を発行する22社のうち、業界最大手の東京書籍など12社が検定中の教科書を教員らに見せ、そのうち10社が現金を渡していたことが明らかになった。
文部科学省によると、教科書会社が検定中の教科書を見せたうえで謝礼まで支払っていた教員らは約3500人。このうち約800人はその後、市町村教委が教科書を採択(選定)する際の参考資料を作ることが多い調査員を務めるなど、採択に関わった。
都道府県教委が教員らに聞き取り調査し、会議の議事録などを精査した結果、特定の教科書を推すなどの不正は確認されなかったとして、文科省は「採択に影響はなかった」と結論づけた。だが、採択の公正性に疑念を生じさせたとして文科省は3月31日、採択の公正確保の徹底を求める通知を各教委に出した。
馳浩文科相は12日の閣議後の記者会見で、「各教委や教科書会社から『不正(採択への影響)はなかった』と報告を受けているが、私は懐疑的な思いで見ている」と述べ、公取委の調査で教科書会社に排除措置命令が出た場合、教科書無償措置法に基づく発行者の指定取り消しも含む厳しい対応を検討する考えを表明した。【樋岡徹也、佐々木洋】
「違法賭博 桃田選手ら、闇スロットも NTT東公表せず」
NTT東の対応を考えると企業体質にも問題があったのかもしれない。膿を出し切ろうとする姿勢ではない。
バドミントン男子日本代表のエース、桃田賢斗選手(21)=NTT東日本、2012年ロンドン五輪代表の田児賢一選手(26)=11日付で解雇=らが違法カジノ店で賭博をした問題で、NTT東日本は12日、2人に加えて同社のバドミントン部員5人(元部員1人を含む)ら計7人が東京都墨田区の違法なスロット店でも賭博していたことを明らかにした。同社は11日に懲戒処分を発表したが、新たな賭博の事実は明らかにしていなかった。
同社の調査によれば、違法スロット店に出入りしたのは墨田区のカジノ店で賭博していたのと同じ時期。田児選手は20回程度で約50万円、桃田選手は5回程度で十数万円負けたという。懲戒処分を受けた他の6人中5人も違法スロットで賭博していた。
また、8日の記者会見で同社は桃田選手の賭博行為は全て田児選手に誘われて6回程度参加したと説明していたが、うち1回は一般女性に誘われて2人で行ったとした。違法スロット店についても、桃田選手は田児選手以外の部員と一緒に訪れたこともあった。
日本バドミントン協会の銭谷欽治専務理事は「NTT東日本から詳細な報告はなく確認したい。現時点で新たな処分を科すことは考えていない」と話した。【田原和宏】
「東京電力が福島第1原発事故時、核燃料が溶け落ちる炉心溶融(メルトダウン)を判断する社内マニュアルの基準に気付いていなかったとする問題で、東電原子力・立地本部の岡村祐一本部長代理は11日、事故前から基準を知っていたことを明らかにした。東電が「気付いていなかった」とこの問題を公表したのは今年2月。2カ月もたち、一転して幹部が把握を認めた東電の体質に批判の声も上がりそうだ。」
理論的に考えられる人達は、東電の公表を信用していないはず。だから個人的に福島の物は食べない。どうしても福島の物を食べたいと思わない限り、リスクを取って食べる理由がない。
「基準の有無が社内などで問題視されていることに気づいたのは『記者会見担当になった昨年8月以降』と説明。『今年2月まで5年間、誰も基準に気付かなかった』とする東電の公表と食い違っている。」
原発が安全かどうかと議論する前に、事実が公表されているのか、中立な立場で専門家が議論しているのか、確信が持てない限り、適切な判断は下せないと思う。嘘が真実として扱われる以上、原発が安全との結論も疑問??????
東京電力が福島第1原発事故時、核燃料が溶け落ちる炉心溶融(メルトダウン)を判断する社内マニュアルの基準に気付いていなかったとする問題で、東電原子力・立地本部の岡村祐一本部長代理は11日、事故前から基準を知っていたことを明らかにした。東電が「気付いていなかった」とこの問題を公表したのは今年2月。2カ月もたち、一転して幹部が把握を認めた東電の体質に批判の声も上がりそうだ。
基準では「炉心損傷割合が5%超」で炉心溶融と定義。岡村氏は11日の定例記者会見で「基準は社内で20年ほど業務をしている中で知った」という。事故当時は水処理関連施設などの復旧業務に就き、「(炉心溶融を)判断する立場ではなかった」と話した。
基準の有無が社内などで問題視されていることに気づいたのは「記者会見担当になった昨年8月以降」と説明。「今年2月まで5年間、誰も基準に気付かなかった」とする東電の公表と食い違っている。
この基準に従えば、事故から3日後には炉心溶融を判断できたが、東電がシミュレーションした結果、認めたのは2カ月後だった。東電は第三者検証委員会を設置して経緯を調べている。事故時のマニュアルの扱いや「発見」の経緯が焦点となっている。【渡辺諒】
東京電力福島第1原発事故で、東電が社内マニュアルに記載されている炉心溶融(メルトダウン)の判断基準を「把握していなかった」ためにメルトダウンの発表が遅れたとされる問題で、東電の広報を担当する岡村祐一・原子力・立地本部長代理が2016年4月11日の定例会見で、事故当時にメルトダウンの判断基準を「個人的な知識として」把握していたことを明らかにした。
岡本氏は
“「私は(メルトダウンの判断基準を)把握していたが、(事故当時は)直接状況をコントロールする、あるいはその場で物事を立場ではなかった」
などと釈明した。
東電は「炉心溶融(メルトダウン)だと判定する根拠がなかった」などとして11年5月までメルトダウンを認めなかったが、16年2月24日になって判断基準を記したマニュアルを「発見」したことを発表していた。この基準に従うと、事故から3日後の11年3月14日にはメルトダウンが起きたと判断できていた。
パフォーマンスの捜索なのかは、結局、最終的にどうなるかだ!
甘利明・前経済再生相(66)を巡る現金授受問題で、都市再生機構(UR)が、道路建設を巡ってトラブルになっていた建設会社「薩摩興業」(千葉県白井市)に対し、建築ができない土地への移転・建築費用として2億2000万円の補償契約を結んでいたことがわかった。
東京地検特捜部は、この補償に関するUR側の説明に不審点があることからURなどの捜索に着手したとみられる。
甘利氏と元秘書は、薩摩興業側の依頼で、補償交渉に関してURに口利きをした見返りに現金を受け取ったとして、あっせん利得処罰法違反容疑で弁護士団体から告発されている。
この補償交渉は、1960年代に計画された「千葉ニュータウン」事業に伴う千葉県道北環状線(全長12・4キロ)の建設により、近接する土地への建物移転が必要になるとして、薩摩興業がURに補償金を要求したのが発端だった。
ドラマのような展開!
勤め先の信用組合から1千万円を横領したとして愛知県警は11日、同県豊川市御津町、三河信組職員の鈴木宗行容疑者(53)を業務上横領の疑いで逮捕し、発表した。「借金支払いや生活費にあてた」と話しているという。
蒲郡署によると、鈴木容疑者は同信組の営業部次長として現金の管理を統括する立場だった2011年10月から14年9月にかけ、同信組の現金1千万円を横領した疑いがある。
3月下旬に同信組が金庫を確かめたところ、1千万円分と思われた束のうち上下の2枚だけ本物の1万円札で、ほかは白紙だった。帯封に鈴木容疑者の印鑑が押されていたため電話で問い合わせると、「今から説明に行く」と言ったきり行方不明になっていた。
鈴木容疑者は北海道に渡っており、今月10日に帯広署の駅前交番に出頭。容疑を認めたという。
「田児選手も桃田選手も海外遠征でカジノを知った。海外で大丈夫なら、日本でも……。そんな思いから、のめり込んでいったという。」
強引な言い訳。海外で死刑制度が廃止されていれば、日本も死刑制度はなくなっていない。日本ではマリファナは違法であるが、国によっては合法である。それで許されるのか?違うだろ。
スポーツしかしてこなかったので知らなかったのであれば、運が悪いが仕方がない。勉強よりもスポーツを優先した自己責任。
日本バドミントン界の異端児は、黒髪・黒いスーツで現れた
絶え間ないフラッシュにさらされる瞳に、涙が浮かぶ。記者からの質問に絶句し、声を震わせる。堕ちたスターへの追求は厳しい。派手な外見と言動が注目を集めた日本バドミントン界の若きホープ桃田賢斗、田児賢一両選手の謝罪会見は、あまりにも残酷だった。【BuzzFeed Japan/ 石戸諭】
違法カジノに出入りしていると報じられた両選手は、同じNTT東日本バドミントン部に所属している。4月8日、2人は会見を開いた。
桃田選手は世界ランク2位、リオデジャネイロオリンピックの出場が確実視されていた。愛らしいルックス、笑顔で知られる人気選手。髪の色も明るい茶色に染め上げ、ストリート系のブランドを颯爽と着こなす。男子バドミントン界に現れた若い「アイドル」として、今後の活躍が期待されていた。
会見場に現れた桃田選手の髪の色は黒く、身を包んでいたのは黒の2つボタンのスーツだった。合わせたのは白いシャツ、ネクタイもスーツと同じ色調だった。
田児選手は部内でも借金
NTT東日本の調査で明らかになった事実関係から整理する。
田児選手は2014年10月から2015年3月にかけて、報道されている東京都墨田区の闇カジノ店に月10回ほど通っていた。発端は飲んだ帰りにキャッチセールスのように声をかけられたことだ。この闇カジノ店が警察に摘発されると、同じ経営者による別の闇カジノ店に通うようになる。横浜にあるその店には、2015年5月から2016年1月にかけて月数回通っていた。その姿は「常連」そのものだ。
カジノでは1回に数万~数十万円賭けていた。負けた金額は総額約1000万円。NTT東日本のバドミントン部内でも借金を重ね、社内調査によると、借金の総額は1150万円に達する。すでに約650万円分は返済したというが、まだ500万円残っている。
桃田選手を誘ったのは田児選手だった。田児選手は桃田選手にとって、憧れの選手で
あり、先輩だ。田児選手は「カジノ賭博に対しての認識が薄かった。遊び感覚で誘った」と話す。桃田選手は2014年10月~2015年1月、同じ墨田区のカジノに計6回通った。桃田選手の負けた額は50万円だった。
田児選手も桃田選手も海外遠征でカジノを知った。海外で大丈夫なら、日本でも……。そんな思いから、のめり込んでいったという。
闇カジノの雰囲気は「自分の印象では穏やかだった」(田児選手)。桃田選手はこう語った。「いけないことだとは分かっていたけど、入ってはいけないところに入る好奇心だったり、少し楽しんでいる自分もいた」「自分もスポーツマン、勝負の世界で生きているので、ギャンブルの世界に興味があった。やめることができなかった」。
口調は冷静で、落ち着いていた。表情も変えずに質問者のほうを向き、声も荒げない。
「派手な生活をしたい。いい服を買いたい。それに“ガキんちょ”があこがれてバドミントンを頑張ってもらえたら」「プロ野球と張るような収入が欲しい」(サンケイスポーツ)。そんな発言をしていた選手とは別人のようだ。
「自分を止められない弱さがあった」
止める人はいなかったのか?
会見中盤に出た、この質問に、田児選手は言葉をつまらせた。「(10秒の沈黙)本来なら、自分が止めないといけない……」。ここで声が震える。さらに4秒間、言葉がつまる。「立場で、そういった責任があったと思うんですけど…」。右手でマイクを持っているが、その手はかすかに震えているように見えた。
言葉を継ぐのに、さらに15秒かかった。「桃田や…後輩のことを巻き込んでしまったのは全部僕なので……自分が賭博をしていて、言うのもあれなんですけど、本当に申し訳なく思いますし…」。ここで一息、吸い込む。「桃田が行こうとしていた時点で止められなかった。彼に対して、申し訳なく思います」。桃田選手はこの間、ずっと下を向いていた。
司会を務めた広報室長が「では、桃田のほうからも」とマイクを持つように促す。
利き手の左手でマイクを持ち、14秒の沈黙。
「えっとこんなに…」、言葉を詰まらせる桃田選手にカメラマンがシャッターを切る。顔をあげる。「周りの人には、あんまり言わなかったので……(15秒の沈黙)。社会人として、自分で気づいて、正しい行動をしないといけないはずなのに…自分を止められない弱さがあった」
続けて質問が飛ぶ。「一番の目標は東京オリンピックの金メダルだと聞きます。4年後の自分にかけたい言葉はありますか?」
言葉がでるのに18秒かかった。「正直、いまはこの先どうなるかわからなくて…正直、4年後なんかまったく見えない」
田児選手は時折、白いハンカチで涙を拭うが、桃田選手の口調にはあまり変化はないように思えた。しかし、質問に答えるとき以外は伏し目がちで、顔をあげると目は潤んでいるように見える。言葉を継ぐのに時間がかかるようになっていた。
3月25日、桃田選手は野球賭博問題で揺れる巨人の今シーズン開幕戦で、始球式を務めた。この始球式も、発覚の恐怖とともに臨んでいたことが明らかになる。
ジャイアンツのようにファンの皆さまから愛され、応援し続けて頂ける選手を目指し頑張っていきます。そして、リオデジャネイロ、さらには東京五輪で頂点を掴みとりたいと思います。(巨人のホームページより、桃田選手のコメントを抜粋)
「自分も野球賭博の報道をみたときは…」。言葉を切る。マイクを持つ左手の指が少し、緩んだように見えた。19秒間、言葉が途切れる。左手に力が入った。
「……他人事ではないな、というのが正直な感想で、解雇されたという報道をみたときは、怖くて、誰にも言えませんでした」。
予定された1時間を超えても、挙手は続く。
今後について問われた田児選手は、声を震わせながらいう。「自分の立場でいうのもおかしいですけど…」、ここで一度、言葉を切って呼吸を整える。「もう一度、桃田にチャンスを与えてほしい」
終始、自分をかばいつづける田児選手の言葉を聞きながら、桃田選手は下を向き、ぐっとくちびるを噛んでいた。
手元の時計で16時11分、2人は席を立ち、ドアの前で一礼し、会見場を後にした。集まった報道陣は100人超。ドアが閉まっても、シャッター音は鳴り続けていた。
「壱番屋によると、ダイコーに残飯の処理を委託するようになったのは2010年3月。それまでは別の業者に委託していたが、ダイコーの方が単価が安く、廃棄物を堆肥や飼料などにリサイクル処理していたことや、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の電子化に対応していたことなどから委託先を変更したという。」
これだけ問題が大きくなると壱番屋のチェック機能に問題があったのではと疑問を持ってしまう。
廃棄された冷凍カツの不正転売事件で、カレーチェーンを展開する「壱番屋」(愛知県一宮市)の廃棄カツを横流ししていた産業廃棄物処理会社「ダイコー」(同県稲沢市)が、無許可で壱番屋から社員食堂の残飯の処理を請け負っていたことが9日、わかった。
残飯は、ダイコーが処理許可を持たない一般廃棄物に該当し、愛知県などは廃棄物処理法違反の可能性があるとみて調べている。
一般廃棄物の収集・処理には、管轄する市町村の許可が必要だが、ダイコーは許可を受けていなかった。
壱番屋によると、ダイコーに残飯の処理を委託するようになったのは2010年3月。それまでは別の業者に委託していたが、ダイコーの方が単価が安く、廃棄物を堆肥や飼料などにリサイクル処理していたことや、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の電子化に対応していたことなどから委託先を変更したという。
「壱番屋の担当者は9日、『委託契約した際、資格があると思い込み、確認していなかった』と釈明した。」
資格があると思い込んだ根拠はなに?虚偽の資格がサイト又は会社のパンフレットに書いてあったのか?
従業員が1000人以上いる会社でも、不都合な事は記録が残らないように口頭のみの対応をしえいる会社が存在する。
問題が起きたときでも、「言った」「言わない」でグレーゾーンに持っていけるからだと思っている。
こんな会社が存在するのだから、問題は簡単にはなくならないと思う。
担当者の苦しい言い訳?資格の事なんか気にしなかったが、ここまで問題が大きくなると事実を言えないとか??
「カレーハウスCoCo壱番屋」の冷凍カツなどが不正に横流しされた事件にからみ、「壱番屋」(愛知県一宮市)が、社員食堂から出た残飯(一般廃棄物)の処理を産廃処理の許可しか持たない「ダイコー」(愛知県稲沢市)に委託していたことが分かった。廃棄物処理法に抵触する可能性がある。壱番屋の担当者は9日、「委託契約した際、資格があると思い込み、確認していなかった」と釈明した。
事業所の社員食堂から出た残飯は、廃棄物処理法で一般廃棄物に区分される。
壱番屋によると、2010年3月、ダイコーに産廃に当たる廃棄食品の処理を委託した際、社員食堂の残飯の処理も頼んだ。担当者は「廃棄食品や残飯を堆肥(たいひ)化するという話だったので、環境保護の観点から好ましいと考えた」と説明している。ダイコーから「残飯処理も可能」との説明を受けたが、資格の有無を確認しなかったという。
冷凍カツなどの横流し問題を調査していた愛知県から今年1月、指摘を受け、ダイコーが産廃処理の資格しかないことを知ったという。壱番屋は「慎重に確認していれば防げた事態で反省している」としている。
ダイコーを巡っては、壱番屋が産廃として処理を委託した冷凍カツを食品関連会社「みのりフーズ」(岐阜県羽島市)に横流しした疑いがあるとして、愛知、岐阜両県警の合同捜査本部が捜査している。【駒木智一】
廃棄食品を横流ししていた産業廃棄物処理会社ダイコー(愛知県稲沢市)が、カレー店を展開する壱番屋(同県一宮市)から社員食堂の残飯の処理を引き受けていたことが9日、分かった。
ダイコーが許可を持たない一般廃棄物に当たるため、廃棄物処理法に抵触する恐れがある。壱番屋は「産業廃棄物と区別するという認識がなかった」と釈明している。
ダイコーの大西一幸会長(75)や元従業員の説明では、ダイコーは週5日、壱番屋本社の食堂から残飯を回収。量は1回数十キロで、飼料として加工したという。
大西会長は「引き受けなければ他の仕事を回さないと言われ、受け入れざるを得なかった」と主張。これに対し、壱番屋経営企画室は「担当者に確認したが事実ではない。残飯も微々たる量で、愛知県から『問題にはならない』と聞いている」と反論した。
化学及(および)血清療法研究所(化血研、熊本市)は事業を譲渡してその後はどうするのか?
役員や幹部を高待遇で残す交渉を行っているのか?腐った人々は変らないし、変れない。長年の間に染み付いた価値観や考え方は変らない。
何かあると「昔は・・・」「うちの会社では・・・」を繰り返す。
アステラス製薬は2005年4月1日に山之内製薬と藤沢薬品工業が合併し発足したようだ。
国の承認とは異なる方法で血液製剤を製造し業務停止処分を受けている、熊本市にある血液製剤などのメーカー「化血研」は、大手製薬会社の「アステラス製薬」と事業譲渡に向けた交渉をしていることを明らかにしました。
熊本市にある化血研=化学及血清療法研究所は、およそ40年にわたって国の承認とは異なる方法で血液製剤を製造し、不正を隠すために組織的に隠蔽を図っていたとして、厚生労働省が来月6日までの110日間の業務停止処分を出し、組織の抜本的な見直しを求めています。
これを受けて化血研は8日、大手製薬会社のアステラス製薬と事業譲渡に向けた交渉をしていることを明らかにしました。アステラス製薬側も交渉していることを認めたうえで、現時点で決定していることはないとしています。
関係者によりますと、化血研は、血液製剤とワクチン、それに動物用ワクチンのすべての事業をまとめて譲渡したい意向なのに対し、アステラス製薬は動物用ワクチン事業の引き受けなどに難色を示しているということです。
また、化血研は、アステラス以外の大手製薬会社とも交渉を行っているということです
血液製剤を不正製造していたとして、厚生労働省から110日間の業務停止処分を受けている化学及(および)血清療法研究所(化血研、熊本市)が、製薬大手のアステラス製薬(東京)にワクチンや血液製剤の製造部門を事業譲渡する方向で交渉に入っていることが関係者への取材で7日、分かった。
現在、売却の条件などをめぐり調整が続いている。業務停止期間が終わる5月上旬ごろまでに合意を目指したいという。アステラスは現在、化血研が製造するワクチンと血液製剤の多くの販売を担当している。
化血研は血液製剤やワクチンの国内有力メーカー。血液製剤の不正製造で1月から業務停止となっている。塩崎恭久厚労相は、化血研について「本来は医薬品製造販売業の許可の取り消し処分とすべき事案」とし、事業譲渡も含めた組織の見直しを求めていた。
カジノが好きなら海外遠征の時に合法なカジノに行く機会ならいくらでもあったであろう。シンガポール、マカオ、韓国などカジノならたくさんある。アメリカのラスベガスにもある。
なぜ日本の闇カジノ店に行くのか?そこまでのリスクを負ってまでカジノをしたいほどカジノ中毒だったのか?
NTT東日本の社員としての自覚がなかったのか?NTT東日本の社員教育に問題があったのか?NTT東日本広報部は適当な調査でなく、しっかりとした調査を行い事実を公表してほしい。だめな企業は体裁だけのために適当なことばかりを言う。それで良いと思っているのか知らないが、騙されない人達は企業の体質に疑念を抱いていると思う。
リオデジャネイロ五輪のバドミントン男子で日本代表入りが確実視される世界ランク4位の桃田賢斗選手(21)と、2012年のロンドン五輪で日本代表だった田児(たご)賢一選手(26)=ともにNTT東日本所属=が東京都墨田区の違法な闇カジノ店=平成27年3月に警視庁が摘発、閉店=に出入りしていたことが6日、分かった。この店の元経営幹部や常連客らが、産経新聞の取材に「大金で賭博をしていた」と証言。NTT東日本広報部は「両選手に確認した結果、ともに『闇カジノ店に行ったことがある』と認めた」と回答した。
闇カジノ店は暴力団の資金源になっているとされており、今後、リオ五輪の代表選考に影響を及ぼす可能性がある。
闇カジノ店の元経営幹部の男性(47)によると、田児選手は26年12月ごろ、客引きの紹介で、違法なバカラ賭博を行っていたJR錦糸町駅に近い同店を訪問。約1週間後、田児選手の紹介で桃田選手が訪れた。この男性は「2人とも頻繁に来ていた。田児選手は多いときは100万円単位、桃田選手は数万~数十万円単位で賭けていた。最終的に2人で計1千万円以上は負けていた。ラケットを持った十数人の後輩らしき男女を連れてきたこともあった」と証言した。
常連客だった男性(45)は「ディーラーからバドミントンの有名選手だと聞かされ、驚いた。2人は顔をマスクで隠したりせず、『明日から海外遠征ですので、来なくても心配しないでください』などと話していた」と語った。
この闇カジノ店は昨年3月に警視庁の摘発を受け、賭博開帳図利などの容疑で元経営幹部の男性や暴力団関係者らが逮捕され、閉店した。
日本バドミントン協会によると、両選手は現在、インドとマレーシア、シンガポールで順次開催されている国際大会に派遣・出場するなどしている。NTT東日本によると、2人は緊急調査を受けるため早ければ7日にも帰国するという。
2人は2014年5月の世界国別団体戦「トマス杯」で、日本男子が初めて世界一に輝いたときの中心選手。桃田選手は昨年の世界選手権3位で、3日に閉幕したインド・オープンで優勝するなどエース級の存在。田児選手は平成25年に全日本総合選手権6連覇を果たしている。
NTT東日本は取材に「現在は海外遠征中で詳細な事実確認が困難なため、帰国次第、他の関係者らを含めて事情を聴き、対応を検討する」と回答。日本バドミントン協会は「本人と関係機関に確認し、事実が確認できれば処分を科すことを視野に入れて検討する」としている。
◇
【用語解説】賭博罪
社会秩序維持の観点から、結果が不確定な事象に金銭などを賭けて取り合う行為を罰する罪。競馬や競輪といった公営ギャンブルには適用されない。闇カジノでの賭博や野球賭博をした場合は、行為の頻度などによって単純賭博罪、またはより罰則の重い常習賭博罪が成立する。賭博を主催した側に対しては賭博開帳図利罪が成立する。それぞれ刑法に規定されている。
「無料通信アプリ大手『LINE(ライン)』(東京都渋谷区)が運営するスマートフォン用ゲームで使う一部のアイテム(道具)が資金決済法で規制されるゲーム上の「通貨」に当たると社内で指摘があったのに、同社は仕様を変更し規制対象と見なされないよう内部処理していたことが分かった。同法を所管する関東財務局は必要な届け出をせず法令に抵触する疑いがあるとして、同社に立ち入り検査するとともに役員らから事情聴取し、金融庁と対応を協議している。」
「関東財務局は今年1月、同法に基づく検査を開始。金融庁のガイドラインなどで定められた社内の管理体制などが不十分だった疑いもあるとみて、他のゲームも含めて資料を提出させ分析を進めている。」
法や規則改正が必要ならば、改正するべきだと思う。
◇ゲームの「鍵」、通貨の疑い
無料通信アプリ大手「LINE(ライン)」(東京都渋谷区)が運営するスマートフォン用ゲームで使う一部のアイテム(道具)が資金決済法で規制されるゲーム上の「通貨」に当たると社内で指摘があったのに、同社は仕様を変更し規制対象と見なされないよう内部処理していたことが分かった。同法を所管する関東財務局は必要な届け出をせず法令に抵触する疑いがあるとして、同社に立ち入り検査するとともに役員らから事情聴取し、金融庁と対応を協議している。
◇供託金数十億円必要か
検査対象は、2012年に公開され14年にダウンロードが4000万件を超えたヒット作として知られる同社のパズルゲーム「LINE POP(ラインポップ)」など。
資金決済法では、あらかじめ代金を支払い、商品やサービスの決済に使うものを「前払式支払手段」と規定。商品券やプリペイドカードのほか、オンラインゲームで「通貨」として使われるアイテムなども該当する。発行会社の破産で商品券やアイテムが使えなくなるなど万一の際に備え、未使用残高が1000万円を超える場合は半額を「発行保証金」として法務局などに供託し、利用者保護を図る義務がある。
複数の関係者によると、昨年5月、ゲーム内のアイテム「宝箱の鍵」が前払式支払手段に当たる可能性があると内部で指摘された。「宝箱を開ける」用途以外に、使用数に応じてゲームを先に進めたり、使えるキャラクターを増やしたりできる仕様だった。鍵1本当たり約110円相当で、当時の未使用残高は約230億円。長期間使っていない利用者分を除いても数十億円の供託を求められる可能性があったという。
同社の担当者が昨年5月に社員らに送ったメールには「未使用残高が約230億円という莫大(ばくだい)な額で、とても供託できる額ではありません」「1年近く前から通貨に該当する状況であったのに、届け出ずにいたことになりますので、処分を受けるリスクもあります」などと記載していた。
アイテムが「通貨」であれば資金決済法に基づき財務局への届け出が必要だが、その後、同社はアイテムの用途を制限するなど仕様を変えることで「通貨に該当しないという説明が可能」と判断。7月に仕様を変更し、財務局には届け出なかった。7月24日付で役員に提出された内部の報告書には「仕様変更をもって通貨に該当しないという立場を取る」と記載。同社の関係者は「多額の供託金を逃れるため、仕様変更で疑惑を覆い隠した」と証言する。
関東財務局は今年1月、同法に基づく検査を開始。金融庁のガイドラインなどで定められた社内の管理体制などが不十分だった疑いもあるとみて、他のゲームも含めて資料を提出させ分析を進めている。
LINEの担当者は取材に対し「検査を受けていることは事実。昨年5月にアイテムが前払式支払手段(通貨)に該当するのではないかという相談が社内であったが、問題ないと判断した。それをより明確にするために仕様変更し、それ以降は厳格な運用をしている」と説明した。【藤田剛】
◇◇資金決済法◇
ITの進展による新たな決済サービスを規制するため2010年に施行。旧来の法では商品券やICカードなどが対象だったが、電子マネーなどの普及に伴い法整備された。発行会社は年2回、発行額や未使用残高を財務局に報告する義務がある。報告を怠ったり無登録で発行したりした場合には罰則があり、財務局が業務改善を命じる場合もある。
法とは別に日本の社会が下した処分の結果とも言えるだろう。
実際は、既存のシンドラーエレベータの対応や整備がもっとずさんになるだろう。ビルやマンションは長く使われるもの。変更や交換が簡単に出来ないものに関しての
選択は重要と言う事であろう。
関係ない話であるが、今後、東芝の白物家電は売上げが落ちるのでは?やはりアフターサービスに不安がある製品を選ばない人達はいると思うので!
シンドラーエレベータ(東京都)は5日、エレベーターやエスカレーターのサービス事業を日本オーチス・エレベータ(同)に売却すると発表した。
シンドラー(スイス)は日本での事業から事実上撤退する。
シンドラーは、日本での点検や修理などの事業と、社員約390人を、日本オーチスと設立した新会社に移す。年内にも新会社の全株式は日本オーチスに売却する。金額は非公表。
シンドラーエレベータを巡っては、2006年に東京都港区で高校生が同社製エレベーターに挟まれ死亡する事故があった。その後、日本での販売は停止していた。日本法人自体は存続し、事故に関わる捜査や訴訟に引き続き対応する。
天下のトヨタと言えども、トヨタ創業家一族には甘かったと言う事か?既に元幹部を退社させたところは他の企業よりも対応は早いし、良いと言うことか?
トヨタ自動車系の有力部品メーカー「アイシン・エィ・ダブリュ(AW)」(愛知県安城市)への入社を志望していた県内の20代の元女子学生が、同社の40代の元幹部から採用の見返りに不適切な関係を迫られたなどとして、男性と同社を相手取り、慰謝料計600万円の支払いを求めた損害賠償訴訟を名古屋地裁に起こしたことがわかった。3月25日付。
訴状などによると、元幹部はトヨタ創業家一族で、元製造本部副本部長。県内の大学に在学していた女性は同社を第一志望に就職活動をしており、昨年7月下旬、アルバイト先で元幹部と知り合った。元幹部は8月、「筆記試験通ったね。ちょっと合格ラインに達していなかったが、僕の一言で、受からせたよ」と食事に誘い、その後、何度もメールやLINEで関係を迫ったという。
女性が断ると、最終面接間近の同月30日、「うちの会社の内定は絶対にさせないので、どこか他をあたって下さい」とメールが届き、9月に不採用になった。
元幹部は、自動織機の発明で知られるトヨタグループ創始者、故豊田佐吉氏の兄弟の孫。アイシンAWは昨年11月、この問題に関連して元幹部を処分し、会社を退いたという。
代理人弁護士は「立場を利用し、男女関係を迫っており社会的に許されない。試験の成績を知っていることから会社の関与もあった」と話し、同社の管理責任についても問題視している。同社広報は「訴状が届いていないのでコメントは差し控えたい」とした。
モラルとか倫理は理想。現実は違う!これが良い例では?
外に出さない「職員の備忘録」が一転、開示すべき「組織文書」に−−。甘利明前経済再生担当相の現金授受問題で、都市再生機構(UR)が公開した当時の秘書らとの面談記録は当初、職員の個人的文書とされ、情報公開制度の対象外だった。説明義務を果たすため例外的に公開したとUR側は説明しているが、組織防衛の意図ものぞく。【日下部聡】
この問題では国土交通省と環境省の職員が甘利氏の秘書らと面談していたが、国家公務員制度改革基本法の定める政官接触記録を作っていなかった。URは公的資金を受ける独立行政法人で、職員は公務員に準じた扱いを受ける。2月に記者会見で公開した面談記録は、いわばUR版「政官接触記録」だ。
記録について、URコンプライアンス・法務室の丹圭一チームリーダーは取材に、「国会担当の職員が個人的に備忘録としてつけていたものだ」と説明。週刊文春の報道後、秘書らとのやり取りを確認するため職員から事情を聴いたところ、記録の存在が分かったという。この職員は同僚や上司に記録を見せたことはないという。だが、記録はA4判の用紙に印字され、面談を依頼してきた議員や秘書の名前、依頼を受けた職員名、日時、内容などを書く欄があり、一定の書式で作成されている。
URには、独立行政法人情報公開法に基づき情報を開示する義務があり、開示の対象は「職員が組織的に用いる」文書とされる。URによると、面談記録は職員個人の文書で開示対象外だったが、公開した時点で「組織的に用いる」文書となったため、現在は情報公開請求で誰でも入手できる。
面談記録によると、甘利氏の秘書らは千葉県の建設会社とURの補償交渉を巡り「結局カネの話か」「少しイロを付けて」など補償増額を働きかけるような発言をした。一方で記録には、UR側が秘書らに「これ以上(交渉に)関与されない方がよろしいように思う」と示唆するなど、URの「正当性」を示す内容も含まれていた。
公開した理由について、丹氏は「URとして説明義務を果たすため」と述べた。だが、国会に参考人として呼ばれた上西郁夫UR理事長は、公開の狙いを「社会的な疑念が持たれることを考慮し、当機構への疑念を払拭(ふっしょく)する上で重要だ」と説明し、組織防衛の意図をにじませた。
重要な記録であるにもかかわらず、公的機関の裁量で開示、非開示が決まっている。政治家との面談記録作成を内部で義務づけ、最初から「組織的に用いる」文書として管理するよう内規を変えられないのか。URは「国や他の組織の動向も見なければならない」(林田桂・広報室主査)と述べ、UR単独で変えることは今のところないとした。
身の安全考えたか
元外務官僚で作家の佐藤優氏の話 URは「個人的な備忘録」と言うが、自分だけのためなら汚い字で他人に読めないように残せばいいわけで、あの記録は組織内で共有する文書だろう。省庁と比べ権限がないため身の安全を守ることを考えたのだろうが、よくこれだけ細かく取っていたと感心した。国の官僚は国会議員とのやり取りで、内容が外に出るとまずい場合には口頭で上司に報告し記録に残さない。後日、経緯を知りたくとも分からなくなるのは問題だ。
解説 政官接触、常に開示を
「備忘録」という言葉は政府の内閣人事局の幹部からも聞いた。国家公務員制度改革基本法は、国会議員の省庁への不当な介入を防ぐ目的で、国家公務員が政官接触の記録を作るよう定める。ところが、同法を所管する人事局は、情報公開請求に「記録はない」と回答しながら、国会議員との面談記録を保存していた。「職員が備忘録的に作った」との説明だった。
実際には記録があるのに、なるべく公開せずに済ます方便として「備忘録」と言う−−そんな疑念がぬぐえない。ある元官僚はこう明かした。「機微に触れるやり取りは(情報公開の対象にならないよう)『個人メモ』にしていた。上司に見せたこともあった」。上司に見せたのなら「組織的に用いた」ことになり、本来は公開の対象だ。こんな恣意(しい)的な運用が許されるなら、情報公開制度は空洞化するだけだろう。
官庁が政官接触記録の作成や公開に及び腰なのは、「後で面倒なことになる」という心理的な要因が大きいためとみられる。だが、URの例でも分かるように、それは自身を守る手段ともなる。
業者から口利きを頼まれた政治家や秘書が、公務員らに圧力をかける。汚職の温床となるこうした事例は枚挙にいとまがないが、今回ほど詳細な実態が明らかになるのは珍しい。URは「政官接触記録」の価値を世に知らしめたとも言える。
一方、政策決定過程を後で検証できるよう記録することを定めた公文書管理法は、個人のメモでも重要性に応じて公文書として扱うべきだとガイドラインでうたう。官庁は「情報を国民と共有する」という感覚を持ってほしい。同時に、国民の主権者意識も問われている。【日下部聡】
「 第三者委は王将フードと反社会勢力との関係は確認されなかった、と結論づけている。これを受け、同社も『当社が反社会勢力と関係ないことが十分ご理解いただけた。これにより、投資家やお客さまに安心して当社とお付き合いいただけるものと確信している』というコメントを発表した。・・・
お役人の調査と同じ。建前の調査は、信用できない。
そもそも、第三者委の報告書は、反社会勢力調査の対象にA氏の関係会社が含まれているかどうかを明記していない。調査したかどうかが分からないのである。また、A氏との取引を主導した元専務は、第三者委のヒアリングに応じていない。報告書ではいまだに分からないことだらけである。」
「餃子の王将」を展開する王将フードサービスの前社長が2013年12月、京都市の本社前で射殺された事件を覚えているだろうか。事件から2年3カ月たった3月29日、同社は、事件に関連し、反社会勢力(暴力団)との関係を調べた第三者委員会の調査報告書を公表した。そこには、社長銃撃の背後に潜む衝撃の事実が描かれていた。【毎日新聞経済プレミア】
全93ページの報告書では、王将フードが過去十数年間、創業家と関係が深い会社経営者「A氏」とその関係企業との間で、総額約260億円にのぼる不透明な取引を繰り返し、約170億円が未回収になっていることなど、驚くべき事実が明らかにされた。
報告書によると、A氏との不透明な取引を主導したのは創業者の次男だった。次男は02年まで専務を務めていた。そして、前社長が03年に不適切取引の清算を宣言した。そして13年11月、取引に関する社内調査の報告書が完成し、その1カ月後に前社長が射殺された。王将内部で何が起きていたのか。
◇第三者委員会が反社会勢力と王将の関係を調査
射殺現場近くで見つかった遺留物から、福岡県内の暴力団組員のDNA型が検出されたことが分かり、反社会勢力(暴力団)との関わりを示唆する報道が相次いだ。このため、王将フードは昨年12月、第三者委を設置し、反社会勢力との関係について調査を依頼すると発表した。
報告書には、1993年から06年まで、王将フードがA氏と繰り返した「経済合理性が明らかでない取引」計14項目の詳細が記されている。
「餃子の王将」は、射殺された大東(おおひがし)隆行前社長の義理の兄で、福岡県飯塚市出身の故加藤朝雄氏が67年、京都市中京区に1号店を出店したのが始まりだ。第三者委報告書によると、加藤氏は77年ごろにA氏と知り合い、交流が始まったとされる。トラブル処理の仲介や事業の相談に乗ってもらっていたようだ。
加藤氏は93年に亡くなったが、A氏と創業家の付き合いはその後も続いた。A氏との一連の多額取引や資金流出はすべて、加藤氏の長男が王将フード社長を、次男が専務を務めた時代に起きている。創業家とA氏との間に「深い関係」があったことが分かる。
取引の多くは、A氏側に土地や建物の買収を依頼したり、A氏側の不動産を買い取ったりするものだった。直接融資もあった。
◇不適切な取引で200億円が社外に流出
例えば、王将フードは95年4月、A氏が経営する会社からハワイの高級住宅地に建つ邸宅と土地を18億2900万円で購入した。購入に関する取締役会の議決はあるものの、購入理由は記載されず、経緯や経済合理性は明らかにされなかった。
98年4~9月にかけては、王将フードが子会社を通じて、A氏関係会社に計185億円を貸し付けた。約95億円は返済されたが、05年には貸金残高約40億円を債権放棄した。
さらに、00年8月には、同じくA氏の関係会社から、福岡市中央区の9階建てオフィスビルを12億3700万円で購入。02年3月、A氏関係の別の会社に5億2000万円で売却している。
結局、A氏の複数の関係会社との取引総額は、分かっているだけで約260億円に達し、うち200億円が流出して、今も170億円あまりが回収できていないという。
第三者委報告書は「創業者の長男と次男が代表権を持った期間に取引が行われていた。創業家の独断専行を戒める体制がなく、取締役会は機能不全だった」と指摘し、当時の経営体制を強く批判している。
◇不適切取引を清算した大東前社長が撃たれた理由は?
亡くなった大東氏が社長に就任したのは00年4月。しかし、次男はその後03年4月ごろまで、取締役会の議決を経ないでA氏の複数の関係会社との不動産取引を続けた。こうした取引の結果、01年3月期に会社は452億円の有利子負債を抱え、一時は倒産の危機に見舞われたという。
大東前社長は状況を変えようと、03年ごろから直接A氏と関係を清算する交渉をするようになった。購入不動産を売却したり、貸付金の債権を放棄して、06年までに関係を清算したとされる。
しかし、A氏との不透明な関係は完全には解消されず、金融機関や証券会社が不安視したことで、東証1部上場が遅れる事態になった。王将フードは12年11月、不適切取引を検証する「再発防止委員会」を作り、翌13年11月13日に社外非公表の調査報告書を完成させている。大東前社長が本社ビル前で何者かに撃たれ、亡くなったのはその1カ月後のことだ。
銃撃直後、王将フードは「社長への脅迫など思い当たる節はない」とコメントしていた。しかし、第三者委報告書を読む限り、経営陣は銃撃の一報を聞いて、会社とA氏との「深い関係」を思い浮かべたのではないか。
◇反社会勢力との関係は本当になかったのか
第三者委は王将フードと反社会勢力との関係は確認されなかった、と結論づけている。これを受け、同社も「当社が反社会勢力と関係ないことが十分ご理解いただけた。これにより、投資家やお客さまに安心して当社とお付き合いいただけるものと確信している」というコメントを発表した。
しかし、報告書によって、A氏が経営する関係会社と王将フードが電話設備保守の委託契約を結んでいたことが判明。不適切な関係が続いていたことが分かり、王将フードは3月30日、契約を即時解除し、「以後A氏とその関係会社とは一切取引しないことを確約します」と宣言しなければならなくなった。同日の東京株式市場では王将株の売り注文が殺到し、ストップ安となった。
そもそも、第三者委の報告書は、反社会勢力調査の対象にA氏の関係会社が含まれているかどうかを明記していない。調査したかどうかが分からないのである。また、A氏との取引を主導した元専務は、第三者委のヒアリングに応じていない。報告書ではいまだに分からないことだらけである。
前社長銃撃犯がいまだに逮捕されないなか、第三者委の調査で過去との決別を図ろうとした王将フード。しかし市場や株主は今も、その経営体制に不安を感じているようだ。
「山梨県都留市の診療所「東桂(ひがしかつら)メディカルクリニック」(浜本敏明院長)が、前立腺がんの検査で用いる使い捨ての生検針を、複数の患者に洗浄したのち使い回し、県の指導後も使い回しの事実を多くの患者に伝えていないことがわかった。」
理由は?診療所が赤字で存続できない?儲けを増やすため?他の診療所が同じ事をやっているが指摘を受けていない?
「山梨県は2013年7月の立ち入り調査で生検針の使い回しの実態を把握。診療所に対して、再使用を行ったすべての患者や家族に説明と謝罪をし、血液検査するよう指導した。診療所は同年12月、指摘のすべてを実施したという内容の改善報告書を、県に提出。」
山梨県は提出された改善報告書の通り、改善されたのか確認したのか?悪質であれば、改善報告書にやる気もない事項を記載する事もある。山梨県は改善されなかった場合、さらなる行政処分について説明したのか、とれとも、形だけの対応なのか?
「製品の説明書で「再使用不可」とされている単回使用器材で、使い回しは禁止されている。厚生労働省の通知でも不適切とされている。」
最後に疑問がある。製品の説明書では「使いまわしは禁止」しかし、厚生労働省の通知は「不適切」。製品のメーカーは安全のために禁止としているが、厚生労働省は通知で「禁止」ではなく「不適切」としている。つまり、不適切ではあるが、使用は禁止していないとも解釈できる。厚労省は曖昧な指導は出すべきではない。もしかすると、逃げの言い訳のために「不適切」として現場に判断させて、現場に対しては自己責任で使用を認めるという事にも解釈できる。
実際はどうなのか?????
風間直樹、榊原織和
山梨県都留市の診療所「東桂(ひがしかつら)メディカルクリニック」(浜本敏明院長)が、前立腺がんの検査で用いる使い捨ての生検針を、複数の患者に洗浄したのち使い回し、県の指導後も使い回しの事実を多くの患者に伝えていないことがわかった。生検針の使い回しには、ウイルスや細菌などの病原体が身体に入り引き起こされる、様々な感染症のリスクがある。県は再調査を検討している。
生検針は先端が2重の筒状で、くぼみがある。肛門(こうもん)から挿入し前立腺の組織を切り取るため出血することもある。製品の説明書で「再使用不可」とされている単回使用器材で、使い回しは禁止されている。厚生労働省の通知でも不適切とされている。
山梨県は2013年7月の立ち入り調査で生検針の使い回しの実態を把握。診療所に対して、再使用を行ったすべての患者や家族に説明と謝罪をし、血液検査するよう指導した。診療所は同年12月、指摘のすべてを実施したという内容の改善報告書を、県に提出。再使用は診療所を開設した04年から13年3月まで行われ、163人が対象とされている。
だが、生検針による検査を受けた患者のうち、今年2月時点で朝日新聞が接触できた28人は、使い回しに関する説明や謝罪はこれまで一切受けていないと話している。県内在住の男性患者(64)は、「検査後も何度も院長の診察を受けているのに、一切そんな話は出ていない。裏切られた気持ちでいっぱいだ」と憤る。
テレビでいろいろな取り組みが放映されるが、利益度外視でやる、何かのついでとして協力する、信念や理想のためにボランティアとして活動しないと
継続的な活動は出来ないだろうと思うことがある。
「元会長や領収書に記載された人から聞き取りを行った結果、事業に関わっていないのに名前を使ったり、家を無償で借りているのに賃借料が発生したかのように報告したりしていた。複数の名義の領収書の筆跡が似通っており、元会長の一人は『自分や事務員が書いた領収書もある』と述べた。」
今回はそんなケースかもしれない。大体、日本は人件費が高い。善意で安くまわそうと思っても、最低賃金とか、いろいろな点で問題となる。形にこだわらなければ、
見てくれは悪くなる。
空き家の賃借料が低ければ、ボランティアで働いてくれる、暇だから協力してくれる、大工だったから安くリフォームできる、余りものの建材や廃棄される建材の再利用でコストダウンできるなどがなければ、ビジネスとして成り立たないと思う。市の職員達がそのような質問したり、興味を持って事業を理解しないと、このような事はおきるであろう。
大分県宇佐市は30日、空き家を活用した移住対策事業を委託していた「NPO法人院内町活性化協議会」(2月解散)が、市の補助金約478万円を不正流用していたと発表した。
元会長2人に全額の返還を求めている。
市によると、法人は2009~14年、市の委託で空き家の掘り起こしや移住相談、空き家見学ツアーなどの移住支援を行った。昨年12月の市議会で、事業報告書に添付されていた賃金や空き家の賃借料の領収書などに不審な点があるとの指摘を受け、市が幹部職員らでつくる調査委員会を設置していた。
元会長や領収書に記載された人から聞き取りを行った結果、事業に関わっていないのに名前を使ったり、家を無償で借りているのに賃借料が発生したかのように報告したりしていた。複数の名義の領収書の筆跡が似通っており、元会長の一人は「自分や事務員が書いた領収書もある」と述べた。
法人は09年以降、121世帯、247人の転入を受け入れた。是永修治市長は記者会見で「実績はあったが、我田引水的な考えで不正を制度化しており、遺憾。厳正に対処する」と述べた。
法人の初代会長は、読売新聞の取材に「補助金は空き家対策の関連事業に使った。私的流用はなく、不正ではない。裁判で争いたい」と返還に応じない考えを示した。
一代で成り上がる人はそれなりの理由がある。甘いことなど言ってたら、簡単に大きくなれない。
それを考えれば、人のお金で相撲を取る機構の方があるかに甘いはずである。額が少なくても、条件が悪くても、引き締めは緩いはずに違いない。
それを読めなかった、又は、考慮できなかったシャープ本社の全取締役は甘かったと言う事であろう。甘いから、シャープはこのようになったとも考えられる。
台湾の鴻海ホンハイ精密工業によるシャープ買収の条件見直し交渉は、終始、鴻海のペースで進んだ。
シャープ社内の不信感は再燃しており、日台連合の船出に向けて不安を残した形となった。
「そこまで言われるがままになるなら、鴻海を断って(かつて支援策を提示していた政府系ファンドの)産業革新機構に頼むと言えばいいじゃないか」
3月25日午後、大阪市阿倍野区のシャープ本社などで開かれた13人の全取締役の非公式協議の場。鴻海の示した買収条件の修正案が報告されると、ある取締役が怒りを爆発させた。
買収額が減額されるだけでなく、シャープが経営破綻した場合に、液晶事業を鴻海が優先的に取得できると読み取れる条文が盛り込まれていたためだ。
「機構の名前を出せば、鴻海の怒りを買い、まとまらなくなる」と交渉を担ってきた取締役らが必死に制止し、その場は収まったが、シャープには、再び機構に救いを求める選択肢は残されていなかった。
仏の世界でも、仁王や阿修羅のような存在も必要。しかし、深く闇に踏込めば簡単には抜けれないだろう。誰にも知られる事なく闇との決別は困難だと思われるからである。嘘と同じである。一度、大きな嘘を付くと、嘘を隠すために、さらなる嘘を付かなければならない。そして、最後には嘘を付いたことを話せば、多くの物を失う事となり、嘘がばれるまで嘘を突き通さなければならなくなる。
「餃子ギョーザの王将」を展開する王将フードサービスが、特定の人物と総額約260億円に上る不適切取引を行っていた問題で、王将が東証1部上場を目指していた2010年、上場を支援する証券会社に対し、この人物と関係を断ったとの虚偽説明をしていたことがわかった。
実際は金銭提供などを続けており、上場目前の12年に両者の関係が東証や証券会社に発覚し、王将は上場断念に追い込まれていた。
王将が29日に公表した第三者委員会の調査報告書などによると、この人物は福岡市のゴルフ場運営会社の役員(72)。王将は1995~2005年頃、社内手続きなどを経ずに役員側と不動産取引などを繰り返し、約170億円が回収不能になった。取引は、王将創業者の次男である元専務(62)が主導したとされている。
「餃子ギョーザの王将」を展開する王将フードサービスの前社長が2013年12月に射殺された事件を受け、暴力団など反社会的勢力との関係の有無を調べていた同社の第三者委員会は29日、同社が05年頃までの約10年間、特定の人物と総額約260億円に上る不適切な不動産取引などを繰り返していたことを明らかにした。
王将が事件の1か月前、これらの取引についてまとめた報告書を作成していたことも明らかになった。
第三者委の調査報告書などによると、この人物は福岡市のゴルフ場運営会社の役員(72)で、創業者の加藤朝雄氏(故人)の知人。王将は1995年頃から役員側が所有する不動産などを、取締役会の承認を経ない不適切な形で購入。取引は総額約260億円に上り、代物弁済された分を除く約200億円が流出。うち約170億円が回収不能になったとしている。
この段階ではなるようにしかならない。まあ、出来るだけ証拠を誰が抹消したのかわからないようにしたのかどうかだけ!
免震ゴムのデータ改ざんを巡り大阪府警の家宅捜索を受けた東洋ゴム工業は30日、大阪市西区の本社で定例株主総会を開催した。清水隆史社長は出席した株主約110人に陳謝したが、厳しく責任を問う声が上がりそうだ。
総会は午前10時に、報道陣などには非公開で始まった。冒頭で、清水社長は家宅捜索について「真摯(しんし)に受け止め、誠実に全面協力を行っている。多大なご心配とご迷惑をおかけしていることを心より深くおわび申し上げる」と述べた。【小坂剛志】
運営費が2000億円もアップ!!採算は合うのか?韓国のようにスポンサーが集まらなかったら誰が責任を取るのか?
2020年東京五輪・パラリンピックを巡り、大会組織委員会の森喜朗会長は29日、当初約3000億円としていた大会運営費が約5000億円に膨らむ可能性を明らかにした。
BSフジの報道番組に出演して述べた。大会招致活動を主導した招致委員会(会長=猪瀬直樹前東京都知事)は13年9月、運営費を約3000億円と見積もっていた。
この試算に対し、森会長は「いかにでたらめだったかわかってきた。(14年1月の組織委設立後)2年間かけて全部手直ししてきた」と批判した。
その上で、当初目標よりも多くのスポンサーを集めることで約5000億円の予算確保を目指しているとし、「それ以上の収入は組織委にはないから、その中でやらないといけない」と述べた。
一般人でも、国税局元職員でも罪が同じであれば、裏やトリックを知っている国税局元職員の方が違反逃れを上手く出来るので捕まりにくいかも?
脱税を指南したとして法人税法違反に問われた東京国税局元職員・植田茅ちかや被告(70)ら3被告の初公判が29日、東京地裁(前田巌裁判長)であり、3被告とも「間違いありません」と起訴事実を認めた。
ほかに起訴されたのは、植田被告が実質経営する会計事務所の税理士だった同国税局元職員・松本剛(55)、帳簿作成代行会社代表・木下洋介(42)両被告。
起訴状によると、3被告は、出会い系サイト運営会社「システムソリューションズ」(東京都府中市)や医療法人社団「秀真会」(調布市)など4法人に対し、植田被告が実質経営する会社に架空経費を計上させる手口で、2009年9月~13年11月頃、4法人の法人所得約16億円を隠し、法人税計約4億8000万円を脱税させたとしている。
新しいスタートが良いかは個人次第と結果次第。時が経って見ないとわからない。自分なりに理解できても、その後が上手く行かなければ、いろいろと考える事があるだろう。悪いなりにも良い結果となれば、新しいスタートもポジティブに受け入れられるだろう。
大手の社員だと、大手でしか使えない人材となっている人、大手での経験を生かせる人、大きく分けると2つに分かれると思う。使えない人材は、過去がどうであれ、
望むような給料では必要ないと判断されるであろう。プライドも生活も打ち砕かれるかもしれない。
リストラの嵐の中で(7)
東芝の早期退職募集は、あくまで社員の応募を前提としている。応募しない社員が退職を強要されることはない。ただ、そうはいっても、部門ごとに50人、150人、1000人という、減らさなければならない人数が掲げられ、その人数が退職することを前提とした再建計画が立てられている。おのずと、しわ寄せは弱者に向かう。
東京・浜松町の東芝本社ビルに勤務するある50代の女性は、気持ちに整理がつけられないまま、早期退職優遇制度の「適用申請書」に署名し、印を押すことになってしまった。退職募集をめぐる、上司とのやりとりに、自分を否定されたような感情を抱いたのだ。
退職の募集条件を示された、上司との面談。「あなたのやっている業務はなくなります」。そんな言い方をされた。管理部門に勤務していて、職場がなくなるわけではない。なぜそんなふうに言われなければならないのか。
ずっと勤めてきた会社で、自分なりの貢献をしてきたつもりだ。退職者を募集しなければならなかった会社の状況もよくわかっている。でも、「仕事がなくなる」と言われたとき味わった、袋小路に追い詰められたような感情が今も消えない。
定年まであと何年か。ずっとここで働けると思っていた。はっきり考えたことはなかったが、定年後も、再雇用でしばらくは働けるはずだった。
早期退職が決まった後も、「3月末で退職」という現実に気持ちが追いつかず、再就職先を探す気が起きなかった。退職した後に考えてみようとも思った。ただ、退職日が近づく今、気持ちが少しだけ動いた。一度、再就職サービスの担当者の話を聞いてみようかと思っている。
田舎に帰ることを考える人、割り切った人
別の女性は、再就職先と転居先の二つを探している。勤務していた職場はリストラ対象になった。グループ会社への転籍を希望したが、受け入れられなかった。もう、どうしようもない。応募したかったわけではないが、退職を選ばざるをえなかった。
これまで通りの給料がもらえる転職先はなかなか見つからないのはわかっている。今の都内の住まいは家賃が高く、もっと安いところに移らなくてはならない。親のいる田舎に帰ろうか、でも……。
割り切った人もいる。「今まで上司に振り回される仕事を続けてきて、いいかげんうんざりしていた。これから先辞めるにしても、退職金の優遇がどこまであるかわからない。それなら今」と、早期退職に応じた。
定年まであと1、2年という男性社員も早期退職を決めた。今回の早期退職は、40歳から45歳までは「会社都合退職」の扱いとなり、46歳以上は「定年退職」の扱いになる。
東芝の定年退職者は、福利厚生制度で、「定年退職者招待旅行券」と「定年退職者招待旅行休暇」がもらえる。グループ企業の旅行会社を通じて申し込めば、国内旅行でも海外旅行でも、一人でも家族一緒でも、退職記念旅行を楽しむことができる。
この男性社員は、この制度を活用して旅行に出かけた。もちろん退職者として当然の権利を使っただけだが、職場の一部からは「お気楽ね」との声も出たようだ。
早期退職を説明する上司にも深い苦しみが
役職者の悩みも深い。早期退職募集の対象者一人一人と面談し、退職金の上積み額などの条件を説明して、納得してもらわなければならない。そうした役職者向けに面談講習も行われた。職場に示された早期退職募集の数。それはどう考えても「ノルマ」だ。
ある役職者は、「対象者の人生を考えると本当に心が痛む」と訴える。あるイベントで有名人とともに笑顔を見せるトップの写真を見たときに、「経営者はリストラされる社員の気持ちをわかっていない」との思いが、ふつふつと湧いてきたのだ。
1年前には考えてもいなかった早期退職募集。その選択を突きつけられ、退職を選んだ多くの人たち。今も気持ちの迷路から抜け出そうともがき続けている。
アメリカが正しくて、日本は間違いと言うわけではないが、アメリカだとこれぐらいの懲役では終わらないと思う。
「福岡地裁は28日、元妻が経営していた認可外保育所で女児14人にわいせつな行為をしたとして強制わいせつなどの罪に問われた無職、田村明晴被告(67)に『被害者の人格を無視し、玩具として扱った悪質な犯行』として懲役11年の判決(求刑は懲役15年)を言い渡した。」
認可外保育所は行政の関与が少ない分だけ、思うように出来るが、悪用されると底がなくなる。結局、利便性や規則とは言うものの、優先順位を付けて対応するしかない。利便性を優先するのであれば、今回のような問題のリスクは容認するしかない。
わいせつ行為を受けた女児に精神的又は発達障害が起きているのか知らないが、起きた事は元に戻せない。今後は、加害者に対する罰則を重くするだけだと思う。
罰則を重くしても、防止策となるかは個々の判断である。しかし罪を償わせ、被害者に悪いと思うかは別として、辛い思いをさせて後悔させると言う意味では、思い罰則は良いと思う。
福岡地裁は28日、元妻が経営していた認可外保育所で女児14人にわいせつな行為をしたとして強制わいせつなどの罪に問われた無職、田村明晴被告(67)に「被害者の人格を無視し、玩具として扱った悪質な犯行」として懲役11年の判決(求刑は懲役15年)を言い渡した。
海瀬弘章裁判官は判決理由で「保育所の『先生』の立場を利用し、わいせつ行為を理解していない未成熟さに乗じて性欲のはけ口にした」と指摘。被告が犯行を「ままごとやお医者さんごっこの延長」と表現した点などを踏まえ「犯罪性向は根深く、常習性は他に類を見ない」と非難した。
判決によると、2008年9月~14年12月、福岡県内の保育所で預かった当時1~6歳の女児計14人の下着やおむつを脱がせてわいせつな行為を計105回繰り返したり、ビデオでその様子を撮影したりした。
オリンピックなんか日本で開かなくても良かった。確実にしわ寄せは国民に増税か、サービスの低下の形で押し付けられる。日本でオリンピックを見るためだけのコストとしては大きすぎる。
「屋根は鉄と木のハイブリッド構造なので、聖火台の上部に鉄を用いることでも、木に不燃処理を施すことでも対応可能です」
聖火台上部だけでなく、火を扱う以上、安全のために周辺にも不燃処理を施す必要があるのでは?コストアップになるので忘れてください。最悪な事が起きれば、
会場に行った人が不運だと言うだけです。
4年後に開催の東京五輪・パラリンピック。昨年、立て続けに起こった混乱は小康を得て、いわゆる瘡蓋(かさぶた)ができつつあった。にも拘わらず、それを剥がし、化膿させるかのような問題が噴出したのだ。今さら聖火台がないという「新・国立競技場」。当事者の責任を問う。
***
問題が持ち上がった経緯を関係者が証言する。
「聖火台を忘れるわけがないでしょ。19年ラグビーW杯前の完成を目指していたザハ案の時から、これは『オーバーレイ工事』、ざっくり言うと、競技場が出来たあとに必要な付属施設を作るということで進めてきたんです」
こんな風に打ち明けるのは、文科省関係者のひとり。ときにわれわれは、トラックで躍動する競技者を臨場感あふれる映像で楽しむことが出来る。これは設置されたレーンに沿って走るカメラを通じてのものなのだが、こういった設備はオーバーレイ工事の範疇となる。
「ザハ案がご破算になってから、改めて新国立の仕様を指示した『要求水準書』を作りました」
と、これは組織委員会関係者の話である。
「その時も、内閣官房の新国立競技場の整備計画再検討推進室、日本スポーツ振興センター(JSC)、そして組織委員会の3者は、聖火台の『後付け』を了解済み。したがって、水準書も聖火台については触れていません」
事実、JSCに聞くと、
「聖火台の敷設は、『セレモニー関係機器の設置工事および機材検証』という項目に含まれており、時期としては20年3月以降を予定しています」
煎じ詰めれば、聖火台のことは新国立のデザインと切り離して考えて、秘中の秘である開閉会式の演出と絡め、開催の4カ月くらい前から詰めようというスタンスだった。そのことの是非はともかく、関係各所が押しなべて「異存なし」とする案件だったのだ。
■“負担増かつ批判増”
しかるに、どうして今回の混乱に至ったのか。
状況が変わったのは年末から。五輪予算が当初の6倍近い1兆8000億円規模に膨らみそうだと取り沙汰されたせいだ。今度は、JSCの関係者が言葉を継ぐ。
「面白くなかったのが、森会長をはじめ、武藤さん(敏郎事務総長)、河野さん(一郎副会長)ら、組織委員会の面々でした。負担が増えた分、批判も浴びるわけですから。特に森さんはザハ案が頓挫した際に、“国がたった2500億円も出せなかったのか。組織委員会が出すカネはその比じゃない”とこぼしていたこともあったから、“負担増かつ批判増”は、より神経を逆撫でしたことでしょう」
そればかりか、
「JSC側からは、“聖火台は五輪にかかわる問題なので、費用は組織委員会の負担でお願いしたい”という提案があった。森さんらは、“これ以上の負担は看過しがたい。聖火台の責任の所在をはっきりさせたい”などと言い始めた。2週間くらい前からです」(前出・文科省関係者)
■首相の任命責任を問う声も
ザハ案の時からなかった聖火台の存在をたきつけ、その予算負担を擦(なす)り付け合う組織委員会とJSCの面々。どことなく滑稽なやりとりを重ねる当事者の一人であるJSCの大東和美理事長(67)を直撃すると、
「聖火台のことは忘れてはいないよ。何も大きな問題じゃないと思いますし、スケジュール通りにやっています」
その一方で、
「安倍首相の任命責任は避けられない」
と指摘するのは、さる閣僚経験者である。
「例えば五輪担当相っていったい何のために作ったのか。予算は文科省が握っているし、権限もない。きっと遠藤本人もどういうことが出来るのかわかってないんじゃないかな。それに、隈案を推薦した審査委員会も悪い。屋根と聖火台との両立に少しでも言及していれば混乱はなかったはず」
そこで隈氏に尋ねると、
「屋根は鉄と木のハイブリッド構造なので、聖火台の上部に鉄を用いることでも、木に不燃処理を施すことでも対応可能です」
と説明する。
■森会長の回答
審査委員会の後には関係閣僚会議が開かれているが、
「遠藤利明五輪担当相や馳浩文科相、安倍さんに麻生財務相、舛添要一都知事ら16人が一堂に会した。それなのにわずか10分で終わっている。事なかれの典型だよ」(前出・閣僚経験者)
と断じるのだった。
わけても論難の声が強い森会長に聞くと、代理人を通じ、こう回答を寄せた。
「聖火台の件は、組織委員会には直接関係がないため、一切お答えできません」
とは言うものの、東京五輪・パラリンピック推進議員連盟幹事長代理で民主党の笠浩史代議士によると、
「これは運営を任されている組織委員会の問題でもあります。だから、馳大臣や遠藤大臣だけではなく、森さんにも責任があるんですよ。今後、文科委員会などで追及したいと思います」
■猪瀬直樹氏も“森喜朗に責任アリ”
招致を勝ち取った当時の都知事で作家の猪瀬直樹氏も同様に、
「今回の責任は、五輪の運営を担当する組織委員会のトップである森喜朗にある。だって、聖火台っていうのはオリンピック最大の象徴なんですから。14年に発足した時点で、組織委員会は聖火台やセレモニーの演出などソフト面の議論を始めるべきだった。ところが、それを蔑(ないがし)ろにしてしまったんです」
そして都知事時代に接した「聖火台プラン」に言及し、こう続ける。
「13年に招致が決まった直後から、非公式にいくつかあがっていました。特に印象に残っているのは、『空中に浮かぶ聖火台』。超伝導なのでしょうか、日本の技術力を誇るものだと思いました。それが今になって“聖火の話が抜けていた”というのは通らない」
返す刀で、遠藤五輪相と番組で共演した際のエピソードを披露し、こう一蹴する。
「ザハ案で予算を圧縮すべく、クーラー設置を取りやめることになりましたよね。そんなことをしたら熱中症で観客がばたばた倒れるのではと指摘を受けた遠藤さんは、“大丈夫”って涼しい顔で答えた。番組終了後に“やっぱりクーラーつけた方がいいですよ”と僕が言ったら彼は、“私も気にしているんですよ”と。こういった無責任体質が改まっていないのは今回よくわかった。だから、また何か起こるんじゃないかと不安です」
最後に、2年前に物故した、1964年東京五輪の聖火ランナー・坂井義則さんに代わり、補欠だった落合三泰さんが、
「一番考えなければいけないのは新国立で競技する選手のことであり、トップアスリートを見守る観客たちのこと。批判やいがみ合い抜きに、みんなで成功させるんだという空気になればいいなと思います」
と、“権力のほてい腹”をつねるように話す。
「特集 今さら聖火台がない『新・国立競技場』大悪小悪の実名リスト」より
「週刊新潮」2016年3月17日号 掲載
自動車部品大手タカタの欠陥エアバッグ問題をめぐり、怒り心頭の米当局が対決姿勢を強めている。タカタがリコール(回収・無償修理)や調査に消極的だとして、運輸省トップが同社を「性悪」呼ばわりするほど非難。議会では、内部告発の奨励など自動車関連業界を追い込む法案作成の動きが相次ぐ。危機感を強めた自動車メーカーも業を煮やし、なんと宇宙・防衛産業の協力まで仰いで原因究明に躍起となるなど騒動は広がるばかりだ。
■内部告発も奨励
「大目に見るわけにはいかない。タカタのようなbad actorのために車の安全に関する文化を変える法律が必要だ」
怒髪天をつくというべきか。米運輸省道路交通安全局(NHTSA)の声明文を読むだけで、フォックス運輸長官の怒りのほどが伝わる。英語の「bad actor」とは、文字通りの「大根役者」から転じて、「性悪」「悪者」といった意味で使われる。「トラブルメーカー」という響きも含んだ侮蔑表現だ。
NHTSAは2月20日、タカタに1日あたり約1万4千ドル(約170万円)の罰金を科すと発表した。タカタがエアバッグ問題の調査に全面的に協力しなかったというのが理由で、「安全性を確保するために十分な情報が得られるまで」罰金を取り続けるという。さらに、フォックス長官はタカタの姿勢は「容認できない」とするだけでなく、法改正にも言及した。
NHTSAはタカタに、回収したエアバッグ部品をすべて保全するよう命令。当局の調査や民事訴訟に備えるためで、原因調査も強化すると表明した。タカタが得たエアバッグについてのデータをすべて閲覧できるようにするとし、「欠陥エアバッグが搭載された経緯を徹底調査する」(フォックス長官)構えだ。
米上院商業科学運輸委員会のスーン委員長も「人々の生命が危険にさらされているなかで、協力の遅れは許されない」とタカタを批判。当局を助けるために「出来うる限りのすべてのことを直ちに実行すべきだ」と注文をつけた。
議会としての対応も加速しており、3月2日、リコール車の迅速な修理を促す法案が上院に提出された。修理が済んでいないと自動車登録の更新が難しくなる内容で、提出したのは民主党のマーキー議員とブルーメンソル議員。やはりリコール問題を起こした米ゼネラル・モーターズ(GM)も厳しく追及するなど、米自動車業界にとっては「機嫌を損ねたら厄介」(関係者)な実力者たちだ。
さらに、上院商業科学運輸委は2月26日、より強硬な法案を全会一致で可決する。自動車の製造上の欠陥などに関する「内部告発」に報奨金を出そうというもので、告発者には企業に科される罰金の最大3割が与えられる。自動車メーカーや部品・販売会社の従業員だけでなく、取引先も含まれるなど、網の目を広げて業界への監視を強めようという狙いがうかがえる。
■調査打開へ切り札?
これに青くなっているのが、タカタ製エアバッグを搭載して“痛い目”にあった自動車メーカーだ。
難航している欠陥エアバッグの原因調査を急ぎ、一刻も早く事態の沈静化を図らねば、自動車業界への規制や監視がさらにエスカレートしかねない。
日米欧の自動車メーカー10社は2月26日、原因解明のための共同調査を、人工衛星の打ち上げなどを手がける米航空宇宙・防衛企業オービタルATKに依頼すると発表した。
エアバッグは中で火薬を点火してガスを発生させて膨らませる仕組み。その点火技術は「防衛や航空宇宙分野で発達したもので、ロケット推進剤がもとになっている」(米紙ウォールストリート・ジャーナル)とされる。その分野で高い技術力をもつとされるオービタルに調査の陣頭指揮をとってもらうことで、長期化している調査の局面をなんとか打開したい考えで、調査の責任者にはNHTSAの元幹部をあてた。
■硬軟両様の戦術
ただ、タカタが事態をどれだけ深刻に受け止めているかは疑問だ。
たとえば、タカタが米当局から科された罰金。米国ではNHTSAがリコール問題の調査などでしばしば非協力的なメーカーに“警告”を発するための処分でもあり、タカタが特殊なケースというわけではない。
また1日あたり1万4千ドルの罰金を仮に1年間科され続けたとして、為替の大きな変動がなければ6億円前後と見積もられる。タカタは2014年10~12月期までに500億円超のリコール関連費用を計上しており、罰金が追い打ちをかけるというほどではない。
だからというわけではないだろうが、タカタは当局の処分に対し、「失望している」と不快感さえ示し、当局との溝の深さを世間に印象づけてしまった。NHTSAが求めている全米規模でのリコールにも、データの裏付けがないとして応じず、部品の供給による支援にとどまっている。
とはいえ、タカタも“硬軟両様”の戦術を模索している感がある。リコールが行われているエアバッグ部品の不足が深刻化するなか、部品の生産能力を9月までに倍増させると先日発表。当局の欠陥調査についても「全面的に協力する」との方針は変わらず、自動車メーカーが進めていく調査にもタカタはデータ提供などで協力する姿勢だ。
米国だけでも少なくとも6件の死亡事故が発生し、全世界で2600万台がリコール対象となったタカタの欠陥エアバッグ問題。当局とタカタ、そして自動車メーカーのせめぎ合いがまだまだ続きそうだ。
東日本大震災を食い物にしている!
東日本大震災で増税となり、多くの税金が投入された!助け合いと言いながらこのような現実もある。これが世の中と言うものなのか?
東日本大震災で被災した高速道路を巡る談合疑惑で、東日本高速道路(NEXCO東日本)関東支社発注の工事で談合をしていたとされる道路舗装業者8社の一部が、公正取引委員会の調べに「暑気払いで集まり、話し合った」などと話していることが関係者の話で分かった。
公取委は、今回の談合は幹事社はおらず、全社が集まる飲み会などの場で行われていたとみている。
公取委は24日、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで、NIPPO(東京都中央区)、前田道路(品川区)、大成ロテック(新宿区)、大林道路(千代田区)、鹿島道路(文京区)、日本道路(港区)、東亜道路工業(同)、世紀東急工業(同)に立ち入り検査を実施した。
関係者によると、8社は、NEXCO東日本関東支社が2011年7~9月に公告した常磐自動車道、北関東自動車道、東関東自動車道、東北自動車道の舗装復旧工事計8件について、話し合いで受注予定業者を決めた疑いが持たれている。入札は同年9~11月に行われた。
東京地検特捜部副部長、東京地検特捜部長、名古屋高検検事長を経て、2012年から現在に至るまで相撲協会の外部理事を務めている宗像紀夫氏(74)が、八角理事長による“協会私物化”の懸念を明かす。今年1月に行われた評議員会では、退任する山響親方の後任に、八角親方が自らの息のかかった年寄OBを押し込もうとした。元年寄が評議員になるには年寄総会での承認が必要、とのルールを無視した行動で、貴乃花親方が「おかしいじゃないですか」と詰め寄る騒ぎにもなった。
***
この事実が本誌(「週刊新潮」)の報道によって明らかになり、1月28日に行われた年寄総会は紛糾。「変じゃないか」「理事長おかしいぞ」という怒号が飛び交い、説明を求める声が相次いだが、当の八角親方は「記憶がない」などと言うのみ。それを受け、年寄たちからは「辞任しろ!」との厳しい声も上がった。
しかし、年寄総会でさんざん糾弾された八角親方はそれでも懲りなかったようである。同日、年寄総会に続いて行われた理事会で、次のような挙に出ていたのである。
「八角さんは急に“顧問弁護士をこういう方にお願いしたい”と言い出したのです。そんな話は事前に通告された議題には入っていませんでしたが、それよりも問題なのは、この時点ですでにその弁護士との契約を済ませていたことです。つまり、理事会に諮る前に勝手に契約していたのです」(相撲協会関係者)
■「誰の知り合いですか?」「いや、私です」
「八角さんが勝手に決めた事案を理事会に押し付けるような格好になっており、由々しき事態だと思います。
そもそも、相撲協会では、反社会勢力の問題に強い弁護士事務所に顧問をお願いしており、そこには弁護士が10人以上もいる。だから、新しい弁護士と顧問契約を交わす必要などないはずなのです。
新たに協会で弁護士を必要とする事態が生じたのであれば、その必要性を理事会で説明しなければなりません。今の弁護士事務所だけでは手が足らない、とか、専門分野の違う弁護士が必要になった、とか。そうした説明があれば納得できるのですが、一切それがなくて、いきなり、『この方にお願いしたい』と言ってきたわけです。
『何が専門なんですか、その人は?』
貴乃花さんがそう質問していましたが、本来、理事たるものは皆がそうやって確認すべきです。しかし、他の理事からは説明を求める声が上がらないので、私が質問しました。
『誰の知り合いですか?』
すると八角さんは、
『いや、私です』
と、“自白”したというか、認めていました。
こんなことが罷り通るようであれば、自分の知り合い、一族郎党全部連れてきていいということになってしまう。そうなればまさしく協会の私物化で、公益財団法人の運営方法として極めて不適切です」(宗像氏)
■独断で決まった高報酬の契約
この理事会では、別の事実も明らかにされた。八角親方は弁護士だけではなく、新たに女性公認会計士とも業務委託契約を交わしていたのだ。この契約も事前に理事会に諮られることなく、八角親方の独断で行われた。
「理事会で、八角さんは“決算を手伝ってもらうため、3月末まで仕事をしてもらう”と言っていましたが、実際には、その会計士とは今年1月からの1年契約になっているそうです。八角さんは理事会で嘘をついたことになります」(先の協会関係者)
「公認会計士についても、顧問弁護士の問題と同様で、そもそも、協会には、何かあればいつでも手伝ってくれる公認会計士が3人もいるのです。新しい会計士を雇わなければいけない理由があるとは思えません」(宗像氏)
理事会に諮ることなく勝手に弁護士、公認会計士と契約した八角親方。実は、問題はそれに留まらない。契約の内容に対しても不審の声が上がっているのだ。
「八角さんの独断で新たに顧問になった弁護士に対しては、月額10万円の顧問料の他、時給3万円の給料が支払われる契約になっている。公認会計士は時給2万円。で、報酬があまりに高すぎる、という声が協会内部で上がっているのです」
と、先の協会関係者。
「しかも、協会の資産について、北の湖さんの時代には、メガバンクの社債などで手堅く運用することになっていたのに、八角さんはそれを変更し、銀行預金として預けている。つまり、資金を外に流しやすい状況にある、ということです」
また、女性公認会計士については別の問題も。
「彼女、3年前に日本公認会計士協会から、1カ月の会員権停止という重い処分を受けているのです。なぜそのような問題会計士と契約を結んだのでしょうか」(同)
新たに契約した顧問弁護士と公認会計士について相撲協会に取材を申し込んだが、期日までに回答はなかった。
■北の湖さんの時代には……
「今回の相撲協会のケースがそれにあたるかどうかは分かりませんが、もし、雇う必要もないのに自分の知り合いを雇い、そこに協会が損害を被るような形で資金が流れていれば、これは『背任的行為』になります。しかも、相撲協会は民間企業ではなく、公益財団法人。尚更財産はきちんと管理されなければなりません。
私はこれまで4年間、相撲協会を見てきましたが、八角さんが理事長になってからの協会運営の乱暴さは目に余るものがある。八角さんは、未だに相撲界の古いしきたりの中での考えのままなのです。しかし、公益性を持った、開かれた協会においてそれは通用しない。北の湖さんの時代には、こんなことは絶対にあり得なかった。あの人は本当に高潔な人でしたから……」(宗像氏)
「特集 殺害予告の電話があった『相撲協会』理事長選挙の大暗闘 『八角理事長に告ぐ 相撲協会の私物化を止めよ』――宗像紀夫(日本相撲協会外部理事)」より
「週刊新潮」2016年3月17日号 掲載
運が悪いとは言え、自業自得!
東洋ゴム工業(大阪市西区)による免震ゴムの性能偽装事件で、大阪府警が23日に同社や子会社の東洋ゴム化工品(東京都新宿区)各本社など4か所を捜索したことがわかった。
大阪府枚方市の枚方寝屋川消防組合新庁舎に納入された免震ゴムのデータ偽装に関する不正競争防止法違反(虚偽表示)容疑で、府警は今後、性能不足の製品が製造、出荷された経緯などを詳しく調べる。
府警によると、他に捜索したのは、免震ゴムを製造している東洋ゴム化工品兵庫事業所明石工場(兵庫県稲美町)と同社大阪支店(大阪市北区)。関係書類など数百点を押収した。
同組合の議会議員だった枚方市議が、新庁舎用の免震ゴム19基を製造・販売した東洋ゴム化工品と氏名不詳の個人について2月以降、大阪地検特捜部と府警に同法違反容疑で告発。府警は特捜部とも連携し、不正に関わった社員の特定を進め、経営陣の関与の程度や会社の刑事責任を問えるかを慎重に捜査するとみられる。
東洋ゴム工業(大阪市西区)による免震ゴムの性能偽装事件で、大阪府警が23日に同社と子会社の東洋ゴム化工品(東京都新宿区)両本社など4か所を不正競争防止法違反(虚偽表示)容疑で捜索したことがわかった。
府警によると、他に捜索したのは、免震ゴムを製造している東洋ゴム化工品の明石工場(兵庫県稲美町)と同社大阪支店(大阪市北区)で、関係書類など数百点を押収した。
捜索容疑は大阪府枚方市の枚方寝屋川消防組合新庁舎に関する内容。東洋ゴム化工品は2014年9月頃、同組合の新庁舎用に製造、販売した免震ゴム19基を納入し、国の認定基準に合格したとする虚偽のデータを「性能検査成績書」に表示したなどの疑いがある。
東洋ゴム工業の社外調査チームによる最終報告書などによると、当時の社長らが出席した14年9月16日の会議で、国の基準に適合していないとして出荷停止が決まったが、「別の計算方法では基準に収まる」と同日中に一転、出荷継続になった。枚方市によると、同組合新庁舎に性能不足の免震ゴムが納入されたのは方針撤回から2日後だった。
東洋ゴム工業による免震ゴムの性能データ改ざん問題で、大阪府警生活経済課が不正競争防止法違反(虚偽表示)容疑で、東洋ゴム本社(大阪市西区)や子会社の東洋ゴム化工品(東京都新宿区)などを家宅捜索したことが24日、分かった。
同課によると、東洋ゴム化工品は2014年9月、大阪府枚方市の枚方寝屋川消防組合新庁舎に設置する免震ゴム19基の出荷時に、性能が国の認定基準を満たしているとする虚偽の品質を建設会社に示した疑いが持たれている。
「ただ、その調査をさらに読むと、『返還義務をいつ知ったか』という調査項目がある。それによると、延滞者のうち、奨学金を借りる前に返済義務を知っていた人の割合はわずか56.1%。これは無延滞者の92.5%と比較して、著しく低い。」
上記が事実すれば日本学生支援機構は生徒や保護者に誠実に対応していないのではないかと思う。そして、借り手に奨学金の返済義務を説明していないのであれば部分的に日本学生支援機構にも現状の問題に関して責任があると思う。借り手を増やすための手法だったのか、メディアは調査して公表してほしい。
「確かに、海外の奨学金制度は、『scholarships(給付奨学金)』と呼ばれ、返済義務はない。一方、日本の奨学金は『student loans(貸与奨学金)』だ。」
返せる当てが無いのに大きなstudent loans(貸与奨学金)に手を出すのは愚かだと思う。教育は投資だと考え、メリットのない教育にはお金をかけるべきではないと思う。student loans(貸与奨学金)も普通のloansもお金を借りる事では同じ。返す当てもないお金を借りる事は愚かである。
アメリカでは、scholarships(給付奨学金)とstudent loans(貸与奨学金)の両方ある。成績優秀者で財政的な問題があれば、scholarships(給付奨学金)を受け取れる可能性はあるが、財政的な問題だけではscholarships(給付奨学金)は無理なのでstudent loans(貸与奨学金)で大学に進学する生徒は多い。多くの生徒はstudent loans(貸与奨学金)のリスクは知っている。将来返済する額を考慮するので、将来、高収入の仕事に付けない心配がある人は、私立などは避け、授業料の安い州立やコミュニティーカレッジに進む。そこで成績が良ければ、3年生から授業料は高いが学部が充実した大きな州立大学に編入する事が多い。お金を優先させればそうなる。
返済義務を知らなかった!?
返済に苦しむ人が急増しているとして、奨学金制度の見直しを求める声が高まっている。
2月29日に公表された労働者福祉中央協議会のアンケート調査によると、奨学金の借入総額は平均312・9万円で、月の返還額の平均は約1万7000円。30代前半までの人のうち、およそ4割が「返済が苦しい」と感じているという。
確かに、月々1万7000円の返済は負担かもしれない。だが、標準的なサラリーマンの年収を鑑みれば、生活が困窮するほどの額ではないはず。なぜ、これほど返済に苦しんでいる人が多いのか。
まず、現状を確認しておこう。
返済の延滞率について、日本学生支援機構の「3月(みつき)以上延滞債権額」の割合をみると、4.6%(2013年度末)。この数字は、借入者に学生が含まれていることを考慮しても、民間金融機関の1.2%(2014年度末)に比してかなり高い。
同機構の「平成25年度奨学金の延滞者に関する属性調査結果」によれば、返還できず延滞せざるを得なくなった理由は、「家計の収入が減った」ことがきっかけとされている。延滞が継続しているのは、本人の低所得とともに延滞額が増加していったためだ。
ただ、その調査をさらに読むと、「返還義務をいつ知ったか」という調査項目がある。それによると、延滞者のうち、奨学金を借りる前に返済義務を知っていた人の割合はわずか56.1%。これは無延滞者の92.5%と比較して、著しく低い。
奨学金を借りるに当たり、本人が返さなければいけないことを知らなかったという、かなり驚きの調査結果だ。実際、延滞督促を受けてから返還義務があることを知ったという人も9・4%もいた。
奨学金制度についていろいろと問題が指摘されているが、返さなければいけないことを知らないというのが、一番大きな問題である。借りた本人に借金という自覚がなければ、返済に支障が生じるのは当然だ。
マイナス金利というチャンス
しばしば、奨学金の返済問題が議論になると、日本のように返済義務があるのはおかしいという識者が多くいる。
確かに、海外の奨学金制度は、「scholarships(給付奨学金)」と呼ばれ、返済義務はない。一方、日本の奨学金は「student loans(貸与奨学金)」だ。
「奨学金」という言葉のイメージによって、混乱を生じているのは確かだろう。ただし、だからといって返済義務があることを知らなかった人を正当化することはできない。
奨学金制度に関する問題を解決するには、まず、日本の奨学金は「借金」であると本人に自覚させる、当たり前を徹底すべきだ。
もっとも、今の経済環境では、奨学金返済に苦労している人にも朗報がある。マイナス金利政策が導入され、奨学金を低利借り換えする絶好のチャンスなのだ。
もともと、奨学金金利は低めに設定されており、固定金利で3%を上回ることはない。しかし今なら、2%を下回るものも民間金融機関から出ている。民間金融機関から借り受けて、過去に借りた奨学金を繰り上げ返済すれば、利払い費を減少させることができる。
この絶好の機会を生かして、奨学金地獄から抜け出てほしい。
『週刊現代』2016年3月26日・4月2日号より
処分を厳しくしても、問題を見つけなければ、結果は同じ。
15人が死亡した長野県軽井沢町のスキーバス事故を受け、国土交通省は、重大な事故を起こすなどして許可を取り消された事業者が、再び許可を取得する際の要件を厳格化する方針を決めた。
15人が死亡した長野県軽井沢町のスキーバス事故を受け、国土交通省は、重大な事故を起こすなどして許可を取り消された事業者が、再び許可を取得する際の要件を厳格化する方針を決めた。
国土交通省は先月、事故を起こしたバスを運行していた「イーエスピー」の事業許可を取り消すとともに、運行管理者の男性社員の資格を失効処分とした。
しかし、現行の制度では2年たてば許可や資格の再取得が可能で、悪質な事業者の排除には不十分との指摘があることから、国土交通省は、この期間を延ばすなど、再取得の要件を厳格化する方針を決めた。
また、国交省は、新規参入を許可する要件を厳しくするほか、現在は、一度取得すれば無期限で有効となっている事業許可について、一定期間ごとに体制などをチェックする更新制とすることを検討している。
運が悪いとは言え、自業自得!
乗客13人・乗員2人が死亡した長野県軽井沢町のスキーツアーバス事故で、東京都は18日、ツアーを企画した旅行会社「キースツアー」(渋谷区)に対し、契約書類を保管していなかったなどとして旅行業法に基づき旅行業登録を取り消した。
バスにツアー客を同乗させていた「フジメイトトラベル」(杉並区)と「トップトラベルサービス」(渋谷区)についても、都と観光庁がそれぞれ54日間の業務停止処分とした。【飯山太郎、内橋寿明】
ショーンKに学歴詐称疑惑について記事だで読むと、もしかして間違いかもと思うが、下記のサイトを見ると間違いのレベルではない。
アメリカでは履歴書の嘘は許されない。経歴に記載されている資格や経験について要求されれば証明/確認できる資料を添付しなければならない。
テレビ関係者はショーンKについて悪く言っていないようだが、それは、テレビや報道で学歴や事実は重要でないと認識されているからではないのか?
良いか悪いかは別としてこれが日本メディア関係者の常識なのかもしれない。
How to write References on a CV (CV PLAZA)
ショーンK、週刊文春が報じた経歴詐称とは?【ホラッチョ川上】03/16/16(The Huffington Post)
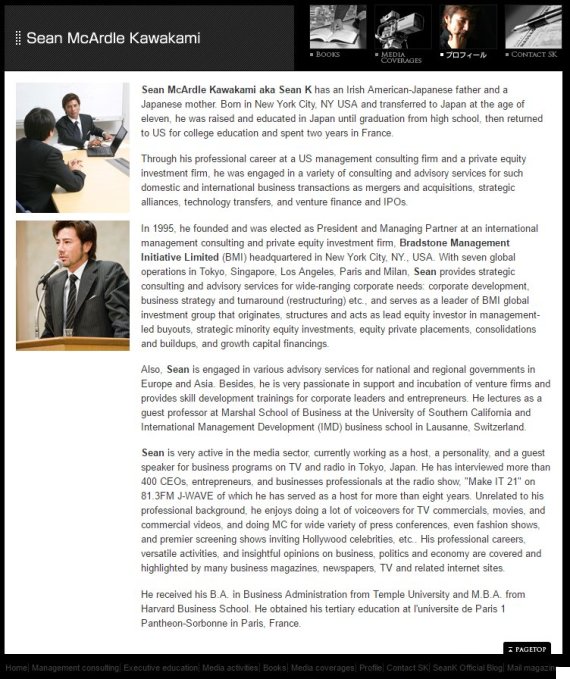
テレビ朝日系「報道ステーション」と経営コンサルタントのショーン・マクアードル川上の件であまりにも滑稽で朝の晩踏みを見て笑わせてもらった。
嘘でも何でも視聴率や印象が良ければ良いと思っているのか、嘘など記載しないと一般常識で考えているため、ダブルチェックなど行っていないがテレビの実情なのか?
大学を出なくても下記の本は書けるのか?それともゴーストライターが書いたのか?
『プロフェッショナルの5条件』朝日新聞出版 2009年 ISBN 978-4-02-330432-1
学生時代に聞いたオーディオブックで一流の営業になるためには、一流の営業のふりからはじめろと書いてあるアメリカで出版された本があった。つまり、自分が一流であるかではなく、他の人達が一流であると信じれば良いと言うことであった。お金がなくても、借金をしても、一流の服を着て、一流の時計をはめ、一流の遊びをすれば、一流の人達と付き合え、一流の仕事が最終的には出来ると書いてあった。これって詐欺と紙一重と思ったが、日本で成功する例もあるのだと思った。
茂木健一郎 公式ブログとコメントは興味深いです。茂木健一郎氏に対しては上記のアドバイスは有効であることはわかった。
『MBA講義生中継 経営戦略』 TAC出版 2007年 ISBN 4-81-321854-7
『自分力を鍛える』あさ出版 ISBN 978-4-86063-242-7
『ショーンKの即聴⇔即答ビジネス英語トレーニング』 2004年 ISBN 978-4-7574-0820-3
『成功前夜 21の起業ストーリー』 ソフトバンククリエイティブ 2005年 ISBN 4-79-733007-4
オリエンタルラジオの中田敦彦(33)が16日、TBS系「白熱ライブビビット」で、週刊文春の報道により学歴詐称が明らかになった経営コンサルタントのショーン・マクアードル川上氏について、「謝り方、謝罪の仕方がよくない。間違えたではなく、意図的なものにしかとらえられない」と、コメントした。
番組では、川上氏の経歴、学歴詐称問題について特集。川上氏と共演経験のあるテリー伊藤が「素顔は気さくで気のいいお兄ちゃん。テレビでは簡単なことを難しいったりするんでおかしかった」と、川上氏の素顔を紹介。一方、中田は、前夜に川上氏のHPに掲載された謝罪文にかみつき「意図的なものにしかとらえられない」と、経歴詐称は“間違い”ではなく、故意だったのではないかと突っ込み、テリー伊藤が「そこは弁護士と練ってね」とコメント。中田も「そういう文面ですよね」と同意した。
中田は更に、外部の人間が誰でも出られるセミナーなどに出席していたことについても「ハーバードセミナー3日間コースに出たのも、そういう経歴を作りたくって参加したという計画的なものも出てきましたよね」とコメント。MCの真矢ミキも「(経)歴っていうのが、事務所から出すじゃないですか。だから間違えるってことないと思うんですけど」と、自身の経験と照らし合わせて、川上氏のHP上の謝罪コメントについて疑問を呈していた。
「ショーンK」の愛称でテレビのコメンテーターなどとして活動する経営コンサルタントのショーン・マクアードル川上さんが15日、所属事務所のホームページを通じ、今後の活動を自粛する意向を表明した。
自らのホームページ上の「英文」履歴書の内容に間違いがあったことを認め、「責任を重く受け止める」としている。今週発売の週刊誌に学歴詐称を指摘する記事が掲載される。川上さんはテレビ朝日系「報道ステーション」などに出演。4月からはフジテレビ系の報道番組「ユアタイム」へのレギュラー出演も決まっていた。
フジテレビで4月4日にスタートする夜の報道&スポーツ番組「ユアタイム~あなたの時間~」(月~木曜後11・30、金曜後11・58)の司会に決まっていた、経営コンサルタントのショーン・マクアードル川上氏(47)が15日、公式サイトで同番組への出演を自粛すると公表した。
16日発売の「週刊文春」が学歴などの詐称疑惑があると報道。それを受けての措置で、学歴詐称を認めた上で、同番組を含め現在出演中のテレビ、ラジオ番組、来月開局するテレビ朝日系のインターネット放送の計6番組に辞退を申し入れた。
学歴詐称をしていたのは、公式サイトの英文プロフィル(現在削除)。「テンプル大学で学位、ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得。パリ第一大学に留学した」と掲載していた。週刊文春の取材に川上氏は「テンプル大の学位はない」「パリ第一大はオープンキャンパスで経済・経営だけ聴講した」と説明。同誌によると、ハーバードMBA取得者名簿にも名前はないという。
川上氏はサイトで「大変な誤解とご迷惑をおかけしました」と謝罪。発端となったプロフィルについて「急ごしらえのベータ版のまま、長い期間、誤りが存在するまま放置されてしまった」と釈明した。
会社の経歴にも詐称疑惑が浮上した。会社ホームページでビジネスパートナーとして外国人2人と日本人1人が紹介されているが、同誌は外国人2人の顔写真が別人であると指摘。川上氏は2人とも実在する人物と主張した上で、顔写真は別人であることを認めたという。
眉間にしわを寄せて話すダンディーな風貌と低音ボイス。超イケメンのインテリとしてお茶の間で人気があった。名前にもインパクトがあったが、同誌は本名が「川上伸一郎」ということも明かしている。
視聴率が低迷するフジテレビにとっては「ユアタイム」は社運をかけた春の大改編の目玉。同局広報担当者は「辞退の申し入れがあったのは事実」と説明した。
水曜コメンテーターだったテレビ朝日「報道ステーション」も降板。16日の同番組にも出演しない。同局系のインターネット放送局のニュース番組にも出演が内定していたが、同局は「本人から出演を辞退したいという申し出があり、承知したと聞いている」とした。
4月4日スタートのフジテレビ系深夜の新大型報道情報番組「ユアタイム~あなたの時間~」のメーンキャスターに就任した“ショーンK”こと経営コンサルタントのショーン・マクアードル川上氏(47)が経歴詐称を認めて、番組出演を取りやめることが15日、分かった。16日発売の週刊文春が「フジテレビ“新ニュースの顔”の正体 ショーンKの嘘」と題した特集を掲載。これを受けて15日夜に公式HPで他番組も含めての出演自粛を発表した。
フジの平日夜に放送予定だった大型報道番組の「顔」が、降板決定的となった。
川上氏は、公式HPに「お知らせ」とする文面を掲載して英文の履歴書の一部に間違いがあったことを認め、「皆様にご心配をおかけして大変申し訳ありません」と謝罪。その上で「責任を重く受け止め、番組を自粛したい」と他番組も含めての出演自粛を発表した。
週刊文春の3月24日号によると、川上氏は公式HPの英文プロフィルに、「テンプル大学で学位」「ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得」などと記載。これに対して川上氏は「学位、また修了書が発行される類のプログラムへの参加は一切ございません」と虚偽を認め、HP作成の過程で、「急ごしらえのβ版のまま、誤りが存在するまま放置されてしまいました」と釈明した。
川上氏は水曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に3月末まで出演予定だったが、同局は「自粛の申し出を了承した」と降板を決定。4月から予定されていたインターネットテレビ局「Abema TV」のニュース番組キャスターも同様に取りやめとなる。
川上氏はフジの「とくダネ!」にも出演しており、同局は本人からの申し出があったことを認めた上で「対応している」と説明。16日にも正式に両番組の出演取りやめが発表される。「ユア-」は夜の人気枠「すぽると!」を含めた時間帯の後番組として鳴り物入りでスタートする予定だったが、予期せぬ事態に見舞われた。
選挙は公平性を求められる状況で、しかもメディアの人間が関わるとは??
関与した職員8人を処分した。
13日に投開票が行われた長野県の松本市長選に出馬し、落選した元NHK解説委員の臥雲(がうん)義尚氏(52)が、送別会用に作成された私的な動画を選挙活動に利用していた問題で、NHKは、動画制作に関与した職員8人を処分した。
NHKは、私的な動画を選挙活動に利用したとして、臥雲氏側に抗議した一方、14日付で、業務目的以外で編集機材を使うなどして、動画を作成した職員4人に訓告、この動画に出演していた職員4人に、厳重注意の処分を行ったという。
ショーンKに学歴詐称疑惑については「報道ステーション」(テレビ朝日)が一番良く知っているはずだ。
「報道ステーション」(テレビ朝日)のコメンテーターとして契約する時に、履歴書に目を通しているはずだ。
「川上氏は『週刊文春』の取材に対して、『学位は取っていない』『パンテオンソルボンヌ(パリ第1大学)には入っていない。オープンキャンパスの中で聴講した』『ハーバード・ビジネス・スクールには、オープンコースの3日くらいのコースに1回行った』などと回答。」
これぐらいレベルでは履歴書に書けない。「報道ステーション」は報道番組である以上、事実を公表するべきだと思う。もしショーンKの履歴書にホームページに記載されたような学歴が記載されていなかったのであれば、なぜ誰も指摘しなかったのだろうか?「報道ステーション」は報道番組である以上、情報に関して裏が取れない、疑わしい情報に関しては注意を事前にするべきだし、間違っていれば訂正するべきである。
フジテレビが社運を賭けて4月4日からスタートさせる平日深夜の大型報道情報番組「ユアタイム~あなたの時間~」のメインキャスター、ショーン・マクアードル川上氏(47)に学歴詐称疑惑が浮上した。
川上氏は現在、「とくダネ!」(フジテレビ)、「報道ステーション」(テレビ朝日)のコメンテーターとしても人気を集める国際派経営コンサルタント。
「『ユアタイム』キャスター就任にあわせて『報ステ』は降板しますが、テレ朝とサイバーエージェントが共同で4月に開局するインターネットテレビ局『Abema TV』の看板ニュース番組の金曜MCにも内定しています」(スポーツ紙デスク)
川上氏の公式ホームページ「SEAN K」の英文プロフィールには長年にわたり、下記の記述があった。
<高校卒業まで日本で教育を受け、大学で米国に戻り、フランスで2年間を過ごした。(中略)テンプル大学でBA(学位)、ハーバード・ビジネス・スクールでMBAを取得。パリ第1大学に留学をした>(編集部訳)
川上氏は「週刊文春」の取材に対して、「学位は取っていない」「パンテオンソルボンヌ(パリ第1大学)には入っていない。オープンキャンパスの中で聴講した」「ハーバード・ビジネス・スクールには、オープンコースの3日くらいのコースに1回行った」などと回答。「ホームページは知らないうちに間違った文章が載っていた」などと釈明した。現在ホームページのプロフィールは削除されている。
<週刊文春2016年3月24日号『スクープ速報』より>
そのうち白物家電はほとんどが中国メーカーになるかもしれない。東芝は赤字だし、現金がほしいのだろうけど、中国が白物家電を全てを手に入れれば、安い人件費や安い経営コストで日本のメーカーに劣るかもしれないが、安く物を生産し、販売すれば、中国は日本製品など買わなくなるし、一部の日本の消費者でも昔の中国製品と違うと言う事で安さに負けて購入するようになるだろう。
問題を避け、きれいごとの世界で育っている子供達が傾いた日本でたくましく生きていけるだろうか?たぶん、多くは無理であろう。政府や大人は問題や財政負担を将来の世代に押し付けているが、若い世代がたくましく問題を克服すると思うのか?結果が出ない不甲斐ない教育システムに税金を無駄に使い、理想と詭弁でのらりくらりとやっていく学校や教育委員会。
東芝の問題は日本の問題と重なると思う。10年後はどのような日本になっているのだろう。
日本の白物家電は衰退し、何十年後には中国メーカーの家電しか買えなくなるかもしれない。そして将来、低学歴の日本人労働者が余り、行き場を失うかもしれない。アメリカと同じになるとは言わないが、アメリカでは金持ち層と貧困層、日本では理解できないほど違いがある。一部のエリートが世界の最先端を引っ張っているが、同じ国で読み書きもまともに出来ない人達がいる。就職支援と言っても、学校で出来なかった事が、短期間の技能習得訓練で身に付くわけが無い。アメリカで製造業を再生させる事も不可能な状況。収入がほとんどあがらないサービス業で小さな幸せや生きがいを見つけて生きていくしかない人達もいる。日本もそれで良いのだろうか?
東芝が、赤字が続く冷蔵庫や洗濯機などの白物家電事業について、中国家電大手の美的集団(広東省)に売却する方向で最終調整していることが15日わかった。不正会計問題を受けたリストラの一環。台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業に買収されるシャープに続いて、日本の家電業界をリードした東芝の白物家電事業もアジアメーカーの傘下に入ることになる。
東芝は今夏までに、家電事業子会社の東芝ライフスタイルについて株式の大半を手放す方針。売却額は100億円を超える規模とみられ、「従業員やブランドは引き継ぐ方向」(幹部)で協議しているという。
東芝の白物家電は、大半を中国やタイなど海外で生産しており、円安の影響で採算が悪化。テレビやパソコンを加えた家電事業は2016年3月期も赤字の見通しで、国内外で従業員6800人を減らす方針をすでに発表していた。
「自前の発電所を持たなかったことから利幅は小さく、予定していた発電設備の建設資金も負担となり資金繰りが悪化した。」
新規参入の難しさはあると思うが、自前の発電機を持たないからリスクが低いし、先行投資も必要ないと思う。違う角度で見れば、自前の発電機を持たないから
儲けられる時に儲けが少ないとは思うが、全てパーフェクトな条件はない。破産と言うことは、地方自治体や売電代金を回収できないと言う事になる。
新電力「日本ロジテック」が買電と売電の差額をかなり抜かない限り、実際は新電力「日本ロジテック」から電力を買っていた所が得をしたと思う。
新電力「日本ロジテック」が破産しても電気が止まるわけではないので、得をした契約者をいたのではと推測する。しかし、下記のサイトの情報を見ると??
企業や自治体向けに電力を販売する新電力大手「日本ロジテック協同組合」(東京)が、破産を申請する方向で調整していることが14日、わかった。
東京商工リサーチによると、負債総額は71億円以上とみられる。
事後処理を一任された弁護士の一人は「財務状態はかなり悪い」としている。同組合は今月いっぱいで電力事業から撤退する意向だ。
同組合は東日本大震災後、企業や自治体が発電した電力を調達して売り上げを伸ばした。東京商工リサーチによると、2012年3月期に約4億円だった売上高は、15年3月期には約555億円まで拡大した。
しかし、自前の発電所を持たなかったことから利幅は小さく、予定していた発電設備の建設資金も負担となり資金繰りが悪化した。
自治体などと電力を売買している新電力大手の日本ロジテック協同組合(東京)が、東京地裁に破産を申請する準備に入ったことが分かった。ロジテックの財産を売却するなどして換金し、債権者に弁済する裁判手続きをとる見通し。自治体などがロジテックから回収できていない資金は少なくとも四十億円にのぼっており、どれだけ回収できるかは未知数だ。
ロジテックの代理人弁護士の一人は、本紙の取材に「資金繰りが悪化して返済するめどが立っていないのは事実なので、破産の手続きをとることになるだろう」と話した。民間信用調査会社によると、負債総額は二〇一五年三月期時点で七十一億六千万円。さらに膨らんでいる可能性がある。
ロジテックは自前の発電所を持たず、ごみ焼却場の廃熱による発電など自治体や広域事業組合が管理する発電所などから電力を調達して販売し、中部地方では自治体や企業など五百以上の顧客を抱えていた。しかし販売価格を抑える戦略が裏目に出て資金繰りが行き詰まり、自治体に電力の購入代を支払えない事態が相次いだ。ロジテックが破産しても電力は中電が代理で補給するので、停電する心配はない。
各自治体は回収できていない額を公表しており、横浜市は六億九千七百万円、名古屋市は四億二千四百七十万円などとなっている。経済産業省のまとめでは、未回収額は自治体と広域事業組合の二十七団体で約四十億円にのぼる。国も再生可能エネルギーの促進費(賦課金)二億円超を徴収できておらず、東京電力など大手電力も送電網の利用料(託送料)を回収できていないという。
名古屋市は回収への選択肢に訴訟を見据える一方、ロジテックから既に購入した電気料金(一カ月二千万円程度)を支払わないことで一部を相殺して穴埋めに充てる考え。
◆甘いチェック、国民にツケ
日本ロジテック協同組合の破産がほぼ確実になった背景には、電力自由化による国の規制緩和で、新規参入の電力事業者の経営体質にチェックが行き届いていない実態がある。失敗のツケは、将来の電気料金に上乗せされ、国民が負担する可能性がある。
電力自由化は工場など大口向けから二〇〇〇年に始まったが、参入に必要なのは経済産業省に提出するA4の申請用紙一枚だけ。法人登記簿も決算書も印鑑証明書も不要で、審査も無い。届け出は約八百社に上るが、小売りの実績があるのは百社強しかなく、事業実態がない業者が大半だ。
四月以降は、一カ月以上の審査を伴う「登録制」に移行するが、財務体質は審査対象外となっているなど「許認可制」に比べてハードルは低い。経産省の担当者は「ベンチャーなども参入できるように間口を広くしている」というが、「行政の責任放棄ではないか」と指摘する識者もいる。
ロジテックは、自治体や余剰電力が売買される日本卸電力取引所から調達した電力を、東京電力や中部電力に送配電線の使用料「託送料金」を支払って顧客に届けていた。
しかし関係者によると、東電に対して二月下旬時点で託送料金など十八億円を滞納。中電にも同様の滞納金があった。ロジテックが破産すれば、東電や中電はいったん損失を負うが、国はこうした損失を託送料金の算出コストに転嫁することを認めている。託送料金が値上がりすれば大手電力と、送配電線を使う新電力それぞれの電気料金の値上がり要因となり、国民がロジテックの負債を肩代わりする形になる。
(太田鉄弥)
日本野球機構(NPB)が「声出しは『敗退行為にはつながらない』として野球協約に抵触しないと判断」であれば問題ない。
問題がない以上、「声出し」を継続しても問題はない。
賭博問題について日本野球機構(NPB)は処分を重くしたほうが良い。
プロ野球巨人の選手が自軍の公式戦の勝敗を対象に「声出し」と呼ばれる現金のやり取りをしていた問題で、巨人が声出しを日本野球機構(NPB)の調査で把握しながら公表を控えていたことが14日、巨人への取材で分かった。NPBが野球協約に抵触しないと判断したことなどが理由だという。また一連の声出しには1軍選手の大半が参加していたことも判明した。
巨人の森田清司総務本部長によると、声出しは平成24年春、成績が低迷したことを機に始まった。
試合前に投手陣と野手陣が別々に組む円陣で激励の声出しをする係に対し、巨人が勝つと1人5千円を渡し、負けると声出し係が全員に1千円を渡していた。1回当たりのやり取りの総額は投手陣が6万円、野手陣が8万円の計14万円で、一部を除いて大半の選手が参加していたという。
産経新聞の取材に笠原将生元投手(25)は「連勝していくごとに(渡す金額が)跳ね上がる」と説明したが、巨人は金額は一定だったと主張し、当時主力選手だった高橋由伸現監督の関与については「まだ分かっていない」とした。
NPBは昨秋、声出しは「敗退行為にはつながらない」として野球協約に抵触しないと判断。巨人は「少額で験担ぎの意味合いもあり、賭け事とは異質」として公表しなかった。
巨人は14日、賭博問題の再発防止に向けて設立された紀律委員会を開催。声出しについても報告された。
自業自得か?
CoCo壱番屋のビーフカツを不正転売 ダイコーは在日企業!?負債9億 不渡り、銀行取引停止処分 03/15/16(NAVER まとめ)
東京商工リサーチ名古屋支社は14日、冷凍カツなど廃棄食品の横流しが発覚した産業廃棄物処理業ダイコー(愛知県稲沢市)が手形で2度目の不渡りを出し、銀行取引停止になったことを明らかにした。取引先などへの支払いも滞っており、現時点での負債総額は約9億円とみられるという。
東京商工リサーチによると、ダイコーは横流しが発覚した1月以降、食品業者との取引が相次いで停止。代金の決済などに使う手形が、2月と3月初旬に相次いで不渡りになったという。
東京商工リサーチ名古屋支社は14日、廃棄食品の横流し事件で、食品を不正に横流ししていた愛知県の産業廃棄物処理業者「ダイコー」が2回目の不渡りを出し、銀行取引停止処分になったと明らかにした。
同支社によると、負債総額は9億円とみられる。事件発覚後に資金繰りが悪化し、2月以降、不渡りを2回出した。
東電は良い思いばかりする。結局、強いものが勝つ。正義や常識は理想。
東京電力福島第一原子力発電所の事故対応を目的とした費用について、東北6県が東電の損害賠償を見込んで支出し、東電に請求した531億円のうち、201億円の負担について合意に至っていないことが分かった。
県側は裁判外紛争解決手続き(ADR)を申し立てるなどして東電に支払いを求めているが、最終的に税金からの支出となる可能性も出ている。
原発事故の損害賠償について、国の原子力損害賠償紛争審査会は2011年8月、東電が自治体に賠償すべき対象を、放射性物質に汚染された上下水道事業への損害や、東電の代わりに行われた被害者支援の費用などとする中間指針をまとめた。ただ、指針には、「それ以外の損害も事情に応じて賠償すべき損害と認められることがあり得る」との記載もあり、原発のある福島県やそれ以外の県で、事故対応目的だった費用の負担を東電に求める動きが広がった。
下記のような事実を知った上でどれだけの人達が彼女に投票するのだろうか?
白いスーツでの登場は、清廉さのアピールか、あるいは、覆い隠したい“何か”があったからなのか。参院選に出馬を決めた「SPEED」の今井絵理子氏(32)。早くも当選確実と言われるが、薄皮一枚捲ってみると、交際相手の“過去”が重くのしかかっていて――。
***
「これは彼女が彼を更生させようとしている話でしょ。美しい話じゃないですか」
当選前から早くも出た、参院選“目玉候補”の初スキャンダル。それを事前に知らされた自民党の茂木敏充・選対委員長はそう語気を強めたという――。
さる2月9日、7月の参院選への出馬を表明した今井絵理子氏。上下白のスーツで記者会見に現れた彼女が“売り”である手話を交えながら立候補の弁を述べたのは記憶に新しい。
会見に出席した政治部記者も言う。
「芸能人だからチャラチャラしているんだろ、と思っていたのですが、立居振舞いも、質問への応対もテキパキしていて驚きました」
今井氏が夫と離婚し、聴覚障害児である息子を女手ひとつで育ててきた「シングルマザー」であることはよく知られている。それに加えて、元国民的アイドルとして持つ圧倒的な知名度。そして、まだ30代前半という“若さ”も相まって、一躍「既に当選は確実」(先の記者)の自民党のスター候補者となったのである。
ところが――。
「シングルマザーのはずの今井さんには、実は『週末婚』とも言うべき状態にある交際相手がいます。しかも、その男性にはかつて児童福祉法違反容疑での逮捕歴がある。つまり、今井さんの世間で思われているイメージと、実際の間にはかなりの差があるワケです」
と言うのは、今井氏の知人である。
■“本番行為”ありのピンサロ経営
一部では既に報じられているが、自民党にとって「極上の玉」であったはずの彼女の、最初の躓きの石となりそうな「交際相手」。仮に黒川康太氏としておくが、彼は一体、何者なのか。
「国会議員になりたいんだったら、今井さんはあいつなんかと付き合ってて大丈夫かな、と思いますよ」
そう語るのは、那覇市一の歓楽街・松山で風俗店に勤務する人物だ。
「もともと、黒川と今井さんは小中学校の同級生。学校を出た後、黒川はいろんな商売に手を出していましたが、一昨年のはじめ、松山でピンサロの経営に乗り出しました。場所は通称“時計台ビル”という建物の7階。ボックスは7つ、ピンサロと言っても1万円くらいで“本番行為”をやらせていました。月の売り上げは150万~200万円。そういう店なので、店名も謳わず隠れ営業のような形でやっていたんです」
2人が再会したのは、彼がそんな稼業に勤しんでいた最中の一昨年秋。東京で暮らす今井氏が、地元で行われた同窓会に参加。お互いバツイチという共通項もあってか、すぐに“デキて”しまったという。
「どちらかと言うと、今井さんが惚れ込んでいる感じでしたね。黒川がカラオケでSPEEDの曲を歌うでしょ。その時に東京とテレビ電話で繋ぎ、今井さんがダンスを踊ったりもしていたそうです。お互いに東京に行ったり、沖縄に帰ったりしてデートをし、親にも紹介していた。黒川がパクられたのは、そんな矢先でした」(同)
■逮捕に駆けつけた今井氏
黒川氏がお縄になったのは昨年3月のことである。
当時、地元紙の「沖縄タイムス」はこう報じている。
〈風俗店に少女 男2人逮捕〉
〈容疑者は、那覇市松山のテナントビルの一室で、14歳の女子中学生と16歳と17歳の無職少女2人を雇い、男性客相手にみだらな行為をさせた〉
要はこの店は、年端の行かない少女たちをどこかで“調達”し、客を取らせていたというワケだ。通常なら、こんな一件がわかれば、女性なら尚更、袂を分かつハズなのだが――。
“彼女”は違った。
「知らせを受けた今井さんは、着の身着のままで那覇に飛んできて警察署で面会し、彼を諭したそうです。その後、黒川は幸い、不起訴処分となり、表に出てきました。実は彼はそれ以前から金融の仕事をやると言い出し、“いいお客さんがいるから投資しない?”などと、金を集めていたんです。もちろん貸金の免許なんて持っているわけがありませんから“闇金”。私も含めて、100万円や200万円を出した者は結構います」(同)
しかし、いつまで経っても、「商売」は始まらない。金を出した仲間たちも騒ぎ始めた。すると、黒川氏は逃げるように東京へ。程なく、今井氏の自宅近くに家を借り、児童デイサービスの施設に勤務しながら、週末は彼女の自宅で過ごすようになったというのだ。
■黒川氏の父は……
事実なら、今井氏は、少女を“商品”にした風俗店に携わっていた人物に理解を示し、また、結果的に踏み倒しに手を貸していたことになる。これでは、仮に当選したとして、議員会館に借金取りが押し寄せても無理はないのだ。
東京にいる黒川氏にその辺りの事情を伺おうとしたが、取材拒否。代わりに、沖縄在住の黒川氏の父に話を聞いたところ、
「息子が“店”をやっていたのは事実ですが、実際はすぐにそれを別の人に譲ったんです。暴力団系? そう、そっち系の人に譲渡した。でも、名義が息子のままになっていたので、一度は逮捕されたけど、結局は不起訴になったんです。金融や借金の件は聞いたことがありませんが、今井さんを面会に呼んだのは私。仕事が仕事だから、向こうは縁を切るのが当たり前なんだけどね。空港まで迎えに行った時、今井さんに“帰った方が良いよ。足引っ張られるよ”と言っても、彼女は迷うことなく“面会に行きたい”と言うので連れていったんです」
いずれにせよ、黒川氏が公職に就く者の近くにいる人物として、好ましからざる存在なのは間違いない。政治家が問われる能力の一つに「人を見る目」があるが、この点から鑑みると、早くも彼女の資質には、疑問を感じざるをえないのである。
「特集 交際相手が児童福祉法違反で逮捕歴! それを美談に仕立てる自民党! 『今井絵理子』の『参院選』当確に違和感がある!」より
「週刊新潮」2016年3月3日号 掲載
まあ、なるようにしかならない。
診療報酬詐欺の疑いで逮捕されたタレントで女医の脇坂英理子容疑者(37)は、「私は騙されたので、むしろ被害者」と周囲に語っていた。
テレビ出演などでは派手なメイクをしていたが、逮捕されたときは、すっぴんのままだった。その変貌ぶりに、ネット上では、「美人女医」の肩書に騙されたと驚きの声も上がった。
■「こんな女医を出演させたテレビ局もおかしい」
なぜか女医のタレントがもてはやされる時代になったが、「『本業はしっかりしてますか』って感じる」「こんな女医を出演させたテレビ局もおかしい」と疑問も相次いでいる。
各種報道で浮き彫りになったのは、テレビでのイメージとは異質の姿だ。脇坂容疑者は、警視庁が2015年11月に着手した暴力団絡みの巨額詐欺に関与したとされ、12年11月から14年9月までに自らのクリニックで治療したように装い、各自治体から患者14人分の診療報酬155万円を騙し取った疑いが持たれている。
脇坂容疑者は、すでに逮捕されている歯科医やコンサルタント会社役員から誘われて、12年6月にまず千葉でクリニックを開業した。会社役員がニセ患者を紹介する指南役となり、2か月後には不正に手を染めたとされている。その後、東京・中目黒に移転し、14年11月までに総額約7000万円の診療報酬を得ていたともいう。「いつもガラガラだった」という客の証言もあり、正規の診察はごく一部だったらしい。
その傍ら、バラエティ番組の出演を続け、「ホストクラブに通って一晩で900万円を使った」などと派手な生活を自慢していた。ところが、14年11月になって、ネット上で詐欺行為が告発される事態になった。15年5月末にはクリニックも閉院して、患者からの返金騒ぎが報じられ、所属事務所から契約を解除されていた。
「見栄を張っているだけ」と関係者
脇坂英理子容疑者は、見かけは派手だが、お嬢さま育ちだったらしい。
生い立ちを報じるスポーツ紙などによると、戦国武将を祖先に持つ家柄に生まれ、お嬢さま学校として知られる女子中・高を経て、東京女子医大に進んだ。卒業後は同じ大学病院に勤め、結婚もして順風満帆に見えた。しかし、4年後に離婚し、別居中にホストクラブにはまってから、借金生活が始まった。
クリニックを開業して詐欺行為に手を染めたのは、それがきっかけだという。コンサルタント会社役員からも600万円以上の借金をしていたといい、脇坂容疑者の取り分は半分ほどだったと報じられている。
クリニックの事情に詳しいある関係者は、取材に対し、次のように話す。
「会社役員がクリニックの事務局になり、運営を仕切っていました。脇坂さんは、診療報酬請求には関わっておらず、しばらく不正は知りませんでした。借金をしたりして暴力団関係者に狙われる医者は多く、彼女は、不正をするための道具として使われたんだと思います。不正で得た金は、ほとんど搾り取られていたということでした。エリート意識が強くて一般常識に疎い人は多く、脇が甘かったということです」
脇坂容疑者も周囲に「私は騙されたので、むしろ被害者」などと語っているという。
「彼女は気づいたときに警察に訴えるべきでした。私は、『行って罪を認めて来なさい』と言いましたが、彼女は『弁護士がいれば勝てる』と高をくくっていました。お金はすっからかんでしたので、今もホストクラブに行っているように見えても見栄を張っているだけだと思います」
とはいえ、ガラガラの病院にニセ患者が来れば、不正に気づかないとは考えられない。脇坂容疑者は、「弁護士が来るまで話しません」と供述しているという。
調べればどちらが事実を言っているのかわかるであるだろう。
「賤ケ岳の七本槍」で知られる戦国武将・脇坂安治の子孫が10日、詐欺の疑いで逮捕された医師の脇坂英理子容疑者(37)との縁戚関係を否定した。
龍野藩脇坂家16代当主の脇坂安知氏(58)が、経営する会社のホームページを通じて「脇坂英里子容疑者と、弊社社長・脇坂とは一切関係ございません」と声明を発表した。安知氏は龍野歴史文化資料館の名誉館長も務めている。8日に診療報酬を搾取した疑いで逮捕された英里子容疑者は、15年1月の日刊スポーツの取材に脇坂安治の子孫だと説明、ツイッターなどでも公表していた。
3月9日、詐欺の疑いで逮捕されたタレント女医・脇坂英理子容疑者(37歳)。
彼女が経営する美容クリニック「Ricoクリニック」で、患者を何度も診察したように装い、診療報酬を詐取した容疑です。これは指定暴力団住吉会系組長がからんだ一連の診療報酬詐欺事件のひとつで、単なる“ずさん経営”とは別次元の犯罪です。
ちなみに、同クリニックは2014年12月に貼り紙1枚で突然休業。脱毛コースなどを契約していた患者への返金もなく、苦情が相次いで、昨年5月には閉院しています。
そのトラブルの最中にも、脇坂容疑者はキャバ嬢ばりのハデメイクでバラエティ番組に出ては、「年収5000万」「ホストクラブで一晩900万豪遊」「男性経験800人」などと吹聴していたわけです。逮捕時のスッピンの老け込み具合に、ビックリした人も多いのでは。
有名な大名で、戦前は子爵だった「脇坂家」
実は、彼女が初著書を出した昨年、女子SPA!にもインタビューしてほしいと打診があったのですが、あまりのウサン臭さに迷っているうちに立ち消えになりました。
その時にいろいろ調べたのですが、実は、脇坂容疑者は大変な名家のお嬢様。父方の先祖は豊臣秀吉の家臣として活躍した武将の脇坂安治で、徳川幕府では脇坂家はたびたび老中を努めています。明治維新のあとは「子爵」に叙された華族なのです。
本人も「祖父の代まではお城に住んでいたそうです」「両親からは厳しくしつけられた」「そのせいか割と保守的な性格で、ピアスを開けるのに10年ほど悩みました」と話しています(※1)。
小学校から高校まで名門・東洋英和女学院、大学は東京女子医大と、お嬢様らしい経歴の脇坂容疑者。いったいどこで踏み外してしまったのでしょうか?
離婚後のホスト遊びが転落の始まりか?
本人のインタビューや著書から見るに、お嬢さまにありがちな“ワルに憧れる”面はあった模様。「映画『極妻』シリーズに憧れ、銀座のホステスさんになって極妻になろうと思っていた」(※1)とか、「若い頃から悪い人が好き」で大好きだった“不良”との結婚を、親の反対で諦めたと語っています(※2)。
本格的におかしくなったのは、どうやら離婚後のようです。
彼女は26歳のとき、「見た目も家柄も性格も良い、周りからみると完璧な」(※2)外科医と結婚しましたが、別居1年を経て31歳で離婚。
別居中にホストクラブにハマッって、総額数千万円のカード払いができず、親に泣きついたそうです(※1)。離婚後の2012年に、問題の「Ricoクリニック」を開業しています。
その後もホストクラブ通いは続いていたようで、2014年にはホストをめぐるトラブルか、風俗店の女にネットで脅迫されたりしています(その女は逮捕されました)。このホスト遊び期間に、暴力団ともつながりができたのでしょうか…。
著書『あざといGirl -教えてRicoにゃん先生! ラブマナー73』(2015年1月)では、「子宮がうずいたらやっとけ」「ナチュラルメイクでザコにモテても意味がない」など、お下品なノウハウを伝授していた脇坂容疑者。
そもそも「経験人数800人」なんて、週1で新しい男性を見つけても15年かかるわけで、ビッチ偽装としか思えません。
お嬢さまが何かのきっかけで乱心してしまうのは、珍しくないパターン。かつて『極妻』に憧れた令嬢は、ガチ極道の世界に足を踏み入れてしまいました。女子SPA!でインタビューしておかなかったのが残念です。
(※1)「週刊ポスト」2013.9.13号
(※2)Webサイト「ウートピ」2015.2.23
<TEXT/女子SPA!編集部>
栄枯盛衰!
医師としては終わりか?
歯科医院の元院長や暴力団組長らによる診療報酬詐欺事件で、警視庁は9日、タレントで医師の女らを逮捕した。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、タレントで医師の脇坂英理子容疑者(37)とコンサルタント会社役員の早川和男容疑者(39)ら男女4人。
警視庁によると、脇坂容疑者らは2012年から2014年にかけて、脇坂容疑者が院長を務める東京・目黒区などのクリニックで、架空の診療や診療回数の水増しを繰り返し、診療報酬約155万円をだまし取った疑いがもたれている。
脇坂容疑者は調べに対し、「弁護士が来るまで話しません」と供述しているという。
去年4月、脇坂容疑者は取材に以下のように答えていた。
脇坂容疑者「(Q診療報酬で不正なことはしていませんか?)うちは全然。来ます、取材とか問い合わせが。関係ないんで。(Q不正なことはない?)ないです。当然です。そんなことやったら大変なことになっちゃうので」
脇坂容疑者らは多数の患者を勧誘し、クリニックで診療をしてカルテを作成し、診療回数を水増しするなどして不正請求を繰り返していたとみられている。
警視庁は、約2年半で7000万円ほどをだまし取ったとみて調べている。
投資したほとんどのお金は返ってこないのだろう。
個人的な意見であるが、人を信用するにはその人の能力と人格を見る必要があると思う。いくら人間的に良い人でも、能力が劣って入れは良い結果はだせない。いくら能力があっても人格に問題があれば、不正、詐欺、不誠実な行為など起こすリスクがある。人生は難しい。
民間信用調査機関の帝国データバンクによると、ワイン投資ファンドの組成・運営会社ヴァンネット(東京)が7日、東京地裁に自己破産を申請、破産手続き開始の決定を受けた。債権者は530人以上、負債額は40億円を超える見込み。
ヴァンネットは2000年7月の設立。フランス産の高級ワインなどを買い付けて保管すれば、将来の値上がりで利益が得られるとの触れ込みで、01年4月から14年6月までに計25のワイン投資ファンドを組成。延べ1989人の投資家から約77億4600万円の出資金を集めた。
しかし15年12月、高橋淳代表がワインの買い付けや売却に関し虚偽の報告をしていた事実が判明。財務省関東財務局から第二種金融商品取引業の登録取り消し処分と業務改善命令を受けた。
その後の弁護士による調査では、投資対象のワイン商品在庫が激減していたことが明らかになった。帝国データによると、現在は計14ファンドで未償還の出資金が36億7372万円に上っている。未償還出資者は523人いるといい、一人平均700万円強が未償還になっている計算だ。
ワインファンドを運用していた株式会社ヴァンネット(VIN-NET)が金融商品取引業者の登録取消処分を受けた。
関東財務局の発表資料によれば、ヴァンネットが過去に償還を迎えたファンドにおいて、別のファンドの資金を流用することにより、実際の運用実績とは異なる高い運用利回りで償還金等を支払っていたとのこと。
ヴァンネットは匿名組合契約のワインファンドを複数運用してきた。匿名組合契約のファンドは、通常の投資信託と比べて運用者の不正流用リスクや倒産リスクの回避策が不十分である。
また、匿名組合契約は1つのファンドが小規模化せざる得ないスキームであるため、会社の経営を安定化させるためには、毎年新しいファンドを設定し続けなければならず、ファンドの運用成績が一次的に悪化すると経営悪化になりやすく、不正を招きやすいスキームでもある。
一般投資家は、資産運用においてこのような不正流用リスクや倒産リスクを負うべきではないし、資産運用アドバイスのプロが一般投資家に推奨するべき投資スキームではない。
しかし、2013年頃から内藤忍氏はヴァンネットのワインファンドを推奨するようになり、内藤忍氏はヴァンネットの広告塔になっていた。結果、ワインファンドの投資家は運用者の不正流用という、本来は負わなくても良いリスクを負うことになってしまった。内藤忍氏は資産運用アドバイスのプロとして完全に失格である。
今のところ、内藤忍氏からは何の反省も弁明も表明されていない。事件が明らかになった翌日(12月26日)の記事「努力しなくても「恵み」が得られる方法」は、何やら意味深だが、抽象的すぎて一般読者には何の話か分からないし、27日の記事はプライベートな話だ。
なぜ一般投資家にワインファンドを推奨するに至ったのか。推奨したファンドが登録取消処分を受けて資産運用アドバイスのプロとしてどう思っているのか。きちんと事件に向き合って欲しいものだ。
四谷学院CMの確実に誤解させるCM。営業や商売と言えばそれまでかもしれないが、良心的な予備校とは思えない。
偏差値29の学生でも、北海道大学医学部に合格できる――。大学受験予備校の四谷学院のCMで、低偏差値からの「大逆転劇」のような切り口で紹介されている生徒が、実は全国屈指の名門進学高校「東大寺学園」の出身だった。こんな指摘がツイッターに登場し、「偏差値詐欺みたい」などと炎上状態になっている。
「家庭教師のトライ」で知られるトライグループの公式サイトによると、東大寺学園の偏差値は「74」だ。
■「灘」に次ぐ関西有数の進学校
難関大学に合格した実在の予備校生が登場し、受験にまつわるエピソードを語る四谷学院のテレビCM。10年以上前から同じ形式を続ける「定番CM」の1つだが、2016年2月初旬から放送されている新しいバージョンにネットで批判が集まることになった。
問題のCMでは、15年4月に北海道大学の医学部に合格したという生徒が「偏差値29からのスタートだったんです......」と語り始める。続けて、四谷学院ならば基礎から1つずつ積みあげて勉強できると語り、「偏差値29」でも効率的に学べるとアピール。最終的には、「(四谷学院が)人生のターニングポイントになりました」とまで語っている。
全く勉強のできない学生でも、四谷学院に通うことで成績が急上昇、難関大の医学部に合格を果たした――。そんな「大逆転劇」のように受け取れるこのCMは、これまでも「四谷学院すごすぎ」「ビリギャルより凄い」などとネット上で話題を集めていた。
だが、あるネットユーザーが2016年3月4日、このCMに対して鋭い指摘を寄せた。CMの中で偏差値29と紹介されていた生徒が、実は全国屈指の進学校「東大寺学園」出身だったことを発見。その内容をツイッターへ投稿したことで、翌5日には5000回以上のリツイートを記録するなど大きな注目を集めた。
東大寺学園は偏差値70を超える奈良の名門高校で、15年の進学実績によると卒業生の合わせて3割近くが東大か京大に進学している。関西では「灘」に次ぐといわれる進学校だ。ちなみに、北大医学部の偏差値は大手予備校4校(東進、河合塾、駿台、代ゼミ)の平均で67.3だった。
「嘘は言ってないけどなんか騙された感あるわ」
四谷学院のCMでは彼の「偏差値29」という部分だけが取り上げられ、そうした進学校に在籍していたことには一切触れていない。そのため、ネット上では、
「嘘は言ってないけどなんか騙された感あるわ」
「四谷学院めっちゃ凄いと思ったけど嘘だったんか」
「偏差値72の高校で校内偏差値29の落ちこぼれでもしっかり合格させます!って正直に言えば良かったのに」
といった批判的な声が相次いで上がった。なかには、「偏差値詐欺みたい」「詐欺感ハンパない」と強い語調で非難するユーザーも少なくない。
四谷学院を運営するブレーンバンクはJ-CASTニュースの取材に対し、該当する生徒が東大寺学園出身であることを認めた上で、「偏差値については本人からの聞き取りの中で出てきた数字であり、事実と認識しております」と答えた。
また、今回の騒動から、13年に発売されたノンフィクション小説「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話」(著・坪田信貴、KADOKAWA)を思い出した人も多いようだ。
この作品は、偏差値30の女子高生が1年半で劇的に学力を上げ慶應義塾大学に合格する様を描いたもので、100万部を超えるベストセラーとなった。だが、実際のところ主人公は「偏差値60を超える県内有数の進学校のなかで、一時的に落ちこぼれていただけであって、元々は優秀な生徒だった」とされ、こうしたことが分かると、ネット上では「題名詐欺」「誇大広告やめろ」などと批判が殺到、いわゆる「炎上状態」になっていた。
ネット上では「ビリギャルと同じオチ」「これで騙される奴はビリギャルが流行った時から何も学んでない」などといった声が上がっている。
「外国人技能実習制度は、外国の若者が日本で先端技術を学び、母国の発展に生かしてもらうことを目的」が実際の制度とかけ離れている。
多くの外国人が自国よりも高賃金である事に魅力を感じて日本に来日している。
実際に制度がどのように使われているかを把握すれば、制度を変える、又は、廃止する必要があるのではないのか?
日本で失踪した外国人技能実習生が昨年5803人に上り、過去最多だった前年を大幅に上回ったことが法務省の調べで分かった。
実習先での劣悪な労働環境が失踪につながるケースも多く、政府は実習先の監視を強化する法整備を進め、失踪増加に歯止めをかけたい考えだ。
外国人技能実習制度は、外国の若者が日本で先端技術を学び、母国の発展に生かしてもらうことを目的としており、昨年6月末時点で約18万人が実習を受けている。実習生の失踪は2012年は2005人だったが、13年に3566人、14年には4847人と千人規模の増加が続いている。
昨年の失踪者は中国人が3116人で最も多く、ベトナム人1705人、ミャンマー人336人と続く。制度を悪用して、実習生に別の仕事を紹介し、失踪を助長するブローカーの存在が指摘されている。失踪後、就労目的の難民申請を行うケースもある。
日本ロジテック協同組合は倒産、又は、破産するしかないのでは?
電力会社以外でも電気の売買ができる「電力の完全自由化」を前に不安な出来事です。自治体などから電気を購入して販売する事業に参入していた大手の会社が先月末に突然、事業から撤退。この会社に電気を販売していた15の自治体で33億円以上の代金が回収ができなくなっています。動画でご覧ください。
安いから人気がある。
「北海学園大の川村雅則教授(労働経済)は『適正な運賃を得るためにも、貸し切りバス事業の規制緩和を見直し、一定程度経営基盤のある事業者を育てなければならない」と指摘。その上で「バス会社だけで安全を確保することは難しいので、(運転手の過労運転防止条件を定めた)厚生労働省の改善基準告示に罰則を設けるなどして労働環境を改善するとともに、運行経路や運賃を決める旅行業者の責任を問う仕組みを作ることが必要だ』と語った。
料金が上がれば現在のような高い需要が続くとは限らない。仮定や条件が間違っていれば、心配するような事は起きない。
旅行会社やバス運行会社に対する罰則を重くし、検査を厳しくすれば良い。コスト的に合わなければ、旅行会社も企画しないし、企画しても
十分な参加者は集められない。
急増する外国人観光客らによる特需でわく九州のバス業界が、深刻な運転手不足に直面している。約6割の会社が運転手の不足を訴えており、しわ寄せは休日出勤などで現場に向かう。長野県軽井沢町のスキーツアーバス転落事故を受け、国も旅行業者やバス会社への規制を強化する方針を示しているが、専門家は「早急に労働環境の改善に取り組まなければ新たな事故を招きかねない」と警鐘を鳴らしている。
「右も左も分からない土地で正直不安です」。福岡市博多区の博多港。3月2日朝、中国人ら約2700人を乗せた大型クルーズ船の寄港を待つ貸し切りバスの男性運転手(57)が打ち明けた。男性は関東地方に本社を置くバス会社の新潟県の営業所で勤務していたが、運転手不足のため、1月に急きょ福岡への1年間の単身赴任を命じられたという。
貸し切りバス事業は2000年2月の規制緩和で免許制から許可制になり、参入事業者が増加。九州でも事業所数が00年3月の221から15年3月には469まで倍増した。それでも昨今の外国人客の急増でバスが不足。自治体の要請に基づき九州運輸局から許可を受けた隣県などの事業者が臨時に営業区域を拡大し、しのいでいるのが現状だ。博多港には鹿児島や宮崎など南九州を朝早く出発して来たバスも並ぶ。
特需のしわ寄せを受ける現場の運転手からは「OBや70歳過ぎの人が運転することもある」(42歳男性)、「休みの日に呼び出されることもある」(64歳男性)などの悲鳴が聞こえてくる。運転手を増やしたくてもバス会社間の競争も激しく、佐賀県のあるバス会社は「最近はなかなか希望者が集まらない。新規参入会社に取られている」と嘆く。
九州運輸局の昨年10~11月のアンケートでは、回答した190事業者のうち63%が「運転手不足」に悩まされていた。回答企業で働く約9300人の運転手の半数は51歳以上で、30歳以下はわずか3%。一方で賃金水準は低く、年収が300万円未満の事業者(回答は115事業者)が半数以上を占めた。
貸し切りバス業界は、旅行業者から安価で受注したバス会社が利益を出すために安全コストを軽視する実態が指摘され、国は12年の関越道ツアーバス事故後、運賃基準を引き上げた。
だが、あるバス会社の労組幹部は「その後も、バス会社によっては、旅行業者から継続して仕事を取るために値引きに応じたり、大きなバス会社に仲介料を払ったりして仕事の融通を受けている。運賃基準が見直されても運転手の待遇は改善されず、休みもなく緊張しっぱなし」と話す。
北海学園大の川村雅則教授(労働経済)は「適正な運賃を得るためにも、貸し切りバス事業の規制緩和を見直し、一定程度経営基盤のある事業者を育てなければならない」と指摘。その上で「バス会社だけで安全を確保することは難しいので、(運転手の過労運転防止条件を定めた)厚生労働省の改善基準告示に罰則を設けるなどして労働環境を改善するとともに、運行経路や運賃を決める旅行業者の責任を問う仕組みを作ることが必要だ」と語った。【下原知広、尾垣和幸】
行政の管理監督に問題があったのではないのか?
民間は発想力、柔軟な対応、新しい試みなどが出来る可能性を秘めているが、資本主義社会の悪しき部分も持ち合わせている。お金儲けを優先させる、
違法行為に躊躇しない、社会の利益を考えない等である。
国の就学支援金を不正に受給していた疑いがある株式会社立ウィッツ青山学園高校でこのような問題が起きたと言うことは、この学校にさらなる
問題がある可能性と行政の怠慢(文科省と伊賀市)の可能性が強いと言う事。
これ以上の問題を発見するとさらなる批判を受けるのを避けるために行政がチェックの手を緩めるのか、それとも今後の防止策の1つとして徹底的に
調査するのか、結果を待つしかない。
冷凍カツの横流し事件で、保管している廃棄食品を撤去するよう愛知県から改善命令を受けた産業廃棄物処理会社「ダイコー」(同県稲沢市)が、経営が悪化して休業状態になっていることを理由に、自力での撤去は困難と県に回答していたことが4日、分かった。
県は、ダイコーに処理を委託した排出元の業者に自主回収を働き掛けている。
関係者によると、不正転売を愛知県警などが捜査中のため、ダイコーの銀行口座が凍結され、出金できない状態だという。
行政の管理監督に問題があったのではないのか?
民間は発想力、柔軟な対応、新しい試みなどが出来る可能性を秘めているが、資本主義社会の悪しき部分も持ち合わせている。お金儲けを優先させる、
違法行為に躊躇しない、社会の利益を考えない等である。
国の就学支援金を不正に受給していた疑いがある株式会社立ウィッツ青山学園高校でこのような問題が起きたと言うことは、この学校にさらなる
問題がある可能性と行政の怠慢(文科省と伊賀市)の可能性が強いと言う事。
これ以上の問題を発見するとさらなる批判を受けるのを避けるために行政がチェックの手を緩めるのか、それとも今後の防止策の1つとして徹底的に
調査するのか、結果を待つしかない。
高浜行人、燧正典
国の就学支援金を不正に受給していた疑いがある株式会社立ウィッツ青山学園高校(三重県伊賀市)について、文部科学省は2日にも、監督する三重県伊賀市に対し、生徒の新規募集を見直させるよう求める通知を出す。登校中のバス内で映画を鑑賞しただけで英語と国語の授業を受けたことにするなど、不適切な教育内容があったという。
同校には通信制課程があり、生徒は一定時間本校に通って対面の授業を受けることが、学習指導要領で定められている。
伊賀市と文科省によると、同校は昨年、全国各地から生徒をバスなどを使って本校に登校させた。その際にユニバーサル・スタジオ・ジャパン(大阪)に寄り、使ったお金の釣り銭を計算させ、これを数学の授業としたという。ほかにも、神戸で美しい夜景を観賞して芸術の授業。レストランでご飯を食べて家庭科。伊賀市の最寄りの駅から本校まで2キロほど歩いて体育など。
文科省は対面授業を受けたことにならないとしている。
伊賀市は通知を受け、同校に対し、約1200人の在籍生徒の一部に授業のやり直しをすることも併せて求める方針だ。(高浜行人、燧正典)
子供でも信用しないような事!しかし誰も追及できないし、通報者がいない限り口裏合わせを組織的にすればどうしようもない。
原発が安全であるのかは知らない。しかし、もし福島のような事故が起きれば、同じような結果となる可能性は高い。
「マニュアルは隠蔽されたのか。作成前の1997〜00年に福島第1原発所長を務めた二見常夫・東京工業大特任教授は『社内でまとめたものの、溶融はあり得ないとの思い込みで共有されず、次第に忘れたのではないか』と指摘する。 」
社内で関与した人の全てが覚えていないと言う事はありえない。口に出来ないし、よほどの覚悟かいるし、全ての人達を黙らせる力が働いている以上、
事実を述べたとしても、同じ力又は、それ以上の力で歪められる可能性もある。所詮、この世の中は正義とか、正直は事があまりにも大きくなると
存在しないと言う事。社会の秩序や安定のために、正義とか正直が利用される。人間はどのような価値観を持って生きるべきなのか?哲学の世界?
何かを考えようが、何も考えなくても、いずれ人は死ぬ。何も考えず、楽しく生きるほうが楽とは思う。事実や安全など東電の社員達の生き方を考えたら幻想とも思える。
東電第三者委調査へ 隠蔽なかったか焦点
東京電力が福島第1原発事故以降、核燃料が溶け落ちる炉心溶融(メルトダウン)を判断する社内マニュアルの存在に気付かず、今月になって「発見」したとされる問題で、東電は第三者委員会を設置して経緯を調べる方針を示している。問題の背景には、安全神話に陥っていた意識の甘さに加え、「炉心溶融」との言葉に神経質だった当時の政権の顔色をうかがう東電の萎縮ぶりが見える。第三者委の調査は「なぜ5年も見つからなかったか」「隠蔽(いんぺい)はなかったのか」が焦点になる。
「溶融の判断が(あったか)どうかは分からない」。震災当時、東電フェローとして事故対応に当たった日本原子力産業協会の高橋明男理事長は25日の定例記者会見で、マニュアル問題への明言を避けた。当時の社内テレビ会議では炉心溶融を前提に議論していた記録が残るが「記憶にない」と言葉を濁した。
「発見」されたのは、2003年に作られた原子力災害対策マニュアル。溶融は「炉心損傷割合が5%超」と定義され、これに従えば事故3日後に判定ができたはずだが、認めたのは2カ月以上後だった。
マニュアルは隠蔽されたのか。作成前の1997〜00年に福島第1原発所長を務めた二見常夫・東京工業大特任教授は「社内でまとめたものの、溶融はあり得ないとの思い込みで共有されず、次第に忘れたのではないか」と指摘する。
だが、作成に関与した社員は必ずいる。事故時に存在を明かさなかった理由として考えられる一つは、政府の意向への配慮だ。1号機が水素爆発した11年3月12日の記者会見で、当時の原子力安全・保安院審議官が「炉心溶融」を明言したが、壊滅的印象を与えかねない言葉による混乱を恐れた官邸が保安院に注意し、審議官は更迭された。以後、東電も「損傷」などの表現を使うようになった。官邸を意識した東電が、マニュアル確認という基本動作をせずに放置した可能性もある。
一方、社内の事故調査報告書(12年)は、マニュアルには一切触れておらず、調査のずさんさも浮かぶ。今回の第三者委もこうした「お手盛り」に終われば、さらに批判を浴びる恐れもあり、柏崎刈羽原発(新潟県)の再稼働を控えた東電は追い詰められた格好だ。【鳥井真平、中西拓司】
「炉心溶融/東電の体質お粗末すぎる」
東電の体質がお粗末すぎるではなく、東電の力が恐ろしすぎるの間違いでは?
つまり、人脈、政治力、お金を使って5年間もの間、マニュアルの存在を隠してきたという事だと思う。東電はエリート集団。誰一人として、マニュアルの事を覚えていない事はないだろう。
新聞社やメディアが直接、東電を批判したり、検証した人達を非難できない事自体がそれを証明しているのでは?
東京電力の体質が疑われる出来事だ。福島第1原発事故に真面目に向き合ってきたのか。国民を甘く見ているのではないか。そんな腹立たしさすら感じさせる不祥事である。
事故で第1原発の3基が炉心溶融した。当時の社内マニュアルに炉心溶融を判定する基準が明記されていた。ところが、その存在に5年間、気付かなかったというのだ。
東電が炉心溶融を認めたのは事故から2カ月後の2011年5月。マニュアルに気付いていれば、事故3日後の3月14日には1、3号機を炉心溶融と判定できたという。
原子力事業者として失格だ。
いまごろなぜ、それが分かったのか。その理由を知って、またあぜんとなる。原発事故の検証を続けている新潟県の技術委員会から求められ、当時の経緯を調べ直す中で、今月になって基準が記載されていることに社員が気付いたという。
東電は独自に事故検証を行い、報告書も出している。どんな検証をしてきたのか。中身の妥当性を疑わざるを得ない。
いうまでもなく、炉心溶融か否かの判定は、事故対策や避難対策にも関わる重要なものだ。
第1原発事故は、炉心溶融後の水素爆発で大量の放射能がまき散らされた。一方で、運が味方した面もある。4号機の使用済み燃料プールの水が漏出していれば、もっと深刻な事故になっていた可能性がある。
正確な状況を把握できなければ対策の取りようがない。非常時の動向を決める判定基準に気付かないというのは、そもそもどういうことか。マニュアルが社内で共有されていないなら、それも問題だ。はなから過酷事故を想定していないということなのか。いずれにせよ、東電は経緯を説明すべきだ。
仮にも国内最大の電力事業者である。所有する原発はまだ1基も再稼働していないが、新潟県の柏崎刈羽原発の再稼働を経営再建の柱に据える。しかし、東電の事故検証が不十分として泉田裕彦知事は厳しい姿勢を取り続けている。
そうした県側の懸念を裏書きした不祥事といえる。事故に真摯(しんし)に向き合う姿勢、再発防止を真面目に考える意識を東電は欠いていないか。
最悪の事故を起こしてなお、この状態では再建は多難だろう。いっそ原発から手を引いたらどうか。
「炉心溶融/東電の体質お粗末すぎる」
東電の体質がお粗末すぎるではなく、東電の力が恐ろしすぎるの間違いでは?
つまり、人脈、政治力、お金を使って5年間もの間、マニュアルの存在を隠してきたという事だと思う。東電はエリート集団。誰一人として、マニュアルの事を覚えていない事はないだろう。
新聞社やメディアが直接、東電を批判したり、検証した人達を非難できない事自体がそれを証明しているのでは?
東京電力は、2011年の福島第1原子力発電所事故の際に、マニュアルに記載された「炉心溶融」の判定基準を見過ごしていたと発表した。基準に従っていれば、事故発生の3日後には「炉心溶融」と判定できたが、東電が炉心溶融を公式に認めたのは事故からおよそ2カ月たってからだった。
東電によると、基準の見過ごしがわかったのは今年の2月だという。なぜ約5年間も気がつかなかったのか。経緯などに関する東電の説明には不可解な点がある。第三者を入れて早急に原因や経緯を調査し明らかにすべきだ。
判定基準は緊急時の通報について定めた「原子力災害対策マニュアル」に記載されていた。まさに福島事故のような事態に備えてつくられたマニュアルである。活用されていなかったのは驚きだ。東電の事故対応がずさんだったと言わざるを得ない。
マニュアルは事故の前年の10年4月に改訂されていた。改訂作業に関わった社員が基準の存在を知らなかったとは思えない。指摘しなかったのだろうか。また12年6月に東電は事故調査報告を公表した。調査の過程で基準があることに気がつかなかったのだろうか。
基準は「炉心損傷割合が5%を超えたら炉心溶融」としていた。事故発生から3日目以降、東電は炉心損傷割合を1号機で55%、3号機では30%と推測し、核燃料が溶けていると認識していた。
にもかかわらず「炉心溶融」という言葉を避け「炉心損傷」で押し通したのはなぜか。判定基準を知らなかったことだけが理由なのか。事故発生の翌日の記者会見で「炉心溶融」に言及した原子力安全・保安院(当時)の広報担当者が交代した。「炉心溶融」を封印し事態を楽観的に見せようとした政治的な圧力はなかったのか。
こうした一連の疑問は東電の信頼にかかわる問題だ。また原発事故時に迅速、正確に情報を国民に伝えるのは、政府も含めた通報体制の課題でもある。関係者は決して軽視すべきではない。
東京電力は、福島第一原子力発電所の事故発生から2か月たって、核燃料が溶け落ちる、メルトダウンが起きたことをようやく認め大きな批判を浴びましたが、当時の社内のマニュアルでは事故発生から3日後にはメルトダウンと判断できたことを明らかにし、事故時の広報の在り方が改めて問われそうです。
福島第一原発の事故では1号機から3号機までの3基で原子炉の核燃料が溶け落ちるメルトダウン=炉心溶融が起きましたが、東京電力はメルトダウンとは明言せず、正式に認めたのは発生から2か月後の5月でした。
これについて東京電力はこれまで、「メルトダウンを判断する根拠がなかった」と説明していましたが、事故を検証している新潟県の技術委員会の申し入れを受けて調査した結果、社内のマニュアルには炉心損傷割合が5%を超えていれば炉心溶融と判定すると明記されていたことが分かりました。
実際、事故発生から3日後の3月14日の朝にはセンサーが回復した結果、1号機で燃料損傷の割合が55%、3号機では30%にそれぞれ達していたことが分かっていて、この時点でメルトダウンが起きたと判断できたことになります。
東京電力は事故後にマニュアルを見直し、現在は核燃料の損傷が5%に達する前でもメルトダウンが起きたと判断すれば直ちに公表するとしていますが、事故から5年近くたって新たな問題点が明らかになったことで、当時の広報の在り方が改めて問われそうです。
メルトダウン認めるまでの経緯
今回の発表や政府の事故調査・検証委員会の報告書などによりますと、東京電力は福島第一原発の事故発生から3日後の3月14日に核燃料の損傷の割合が1号機で55%、3号機が30%に達していることを把握しました。さらに翌日の15日には損傷の割合について1号機で70%、2号機で30%、3号機で25%と公表しますが、原子炉の核燃料が溶けているのではないかという報道陣の質問に対して「炉心溶融」や「メルトダウン」とは明言せず、「炉心損傷」という表現を使います。
一方、当時の原子力安全・保安院は、事故発生の翌日の12日の午後の記者会見で、「炉心溶融の可能性がある。炉心溶融がほぼ進んでいるのではないだろうか」と発言していました。ところが、その日の夜の会見では担当者が代わり、「炉心が破損しているということはかなり高い確率だと思いますが状況がどういうふうになっているかということは現状では正確にはわからない」と内容が大きく変わります。
さらに翌月の4月には、当時の海江田経済産業大臣の指示でことばの定義付けを行ったうえで、1号機から3号機の原子炉の状態について「燃料ペレットの溶融」とふたたび表現を変えます。
その後、事故から2か月たった5月になって、東京電力は解析の結果として1号機から3号機まででメルトダウンが起きていたことを正式に認めました。
社員「炉心溶融 なるべく使わないようにしていた」
メルトダウン=炉心溶融を巡っては、東京電力の社員が、政府の事故調査・検証委員会の聞き取りに対し、「炉心溶融」ということばを使うことに消極的だった当時の状況を証言しています。公開された証言の記録によりますと、事故当時、東京電力の本店で原子炉内の状態の解析を担当していた社員は、事故から1か月近くたった4月上旬の時点の認識として、「1号機については水位は燃料の半分ほどしか無かったため、上半分は完全に溶けているであろうと考えていた」と述べ、核燃料の一部が溶け落ちていたと見ていたことを明らかにしています。そのうえで、「この頃の当社としては、広報などの場面で炉心溶融ということばをなるべく使わないようにしていたと記憶している」「炉心溶融ということばは正確な定義があるわけではないので、誤解を与えるおそれがあるから使わないと言った考えを聞いた覚えがある」と証言しています。
福島・楢葉町の住民「憤りを感じる」
原発事故の避難指示が去年9月に解除され、住民の帰還が始まっている福島県楢葉町の住民が暮らすいわき市にある仮設住宅では、東京電力に対する憤りや不安の声が聞かれました。
今も仮設住宅で避難生活を続けている83歳の男性は、「東京電力はきちんと謝罪をしたのか。憤りを感じます」と話していました。また、72歳の女性は「メルトダウンしたと、本当に分からなかったのか、それとも隠していたのか。今ごろ言われても気分がよくない」と話していました。仮設住宅の自治会長を務める箱崎豊さんは、「楢葉町民が、安全だというお墨付きのもとに帰ろうとしているときに今さらという感じで腹立たしく思う。残念極まりない。企業体質が改めて問われる事態だ」と話していました。
福島・大熊町長「発表が遅れた真意は」
メルトダウンを巡る東京電力の対応について、福島第一原発が立地し、現在も全町民が避難を続ける大熊町の渡辺利綱町長は、「なぜ発表が遅れたのか、率直に考えて疑問に思う。単純なミスとは考えられないし発表までにだいぶ時間がかかっているので、そのあたりの真意も知りたい。最初からメルトダウンと発表されていれば、町民などの反応も違ったと思う。信頼を築く上でも、正確な情報を迅速に伝えてもらうのが大事なので、引き続き対応を求めていきたい」と話していました。
福島県知事「極めて遺憾」
東京電力の、メルトダウンを巡る通報などの対応について、福島県の内堀知事は「3月14日の時点で『炉心溶融』という重要な事象が通報されなかったことは極めて遺憾だ。今後、迅速で正確な通報や連絡が徹底されるよう、改めて強く求めたい」というコメントを出しました。
新潟県知事「隠蔽の背景など明らかに」
新潟県の泉田裕彦知事は、「事故後、5年もの間、このような重要な事実を公表せず、原発の安全対策の検証を続けている県の技術委員会に対しても真摯(しんし)に対応して来なかったことは極めて遺憾。メルトダウンを隠蔽した背景などについて今後の調査で、真実を明らかにしてほしい」というコメントを発表しました。
行政の管理・監督の甘さが利用されたケースである事に間違いない。
「環境省所管の公益財団法人が運営する産業廃棄物の電子管理システムを強化する。」
ごまかすつもりがあれば、数字などいくらでもごまかせる。何でもかんでも電子管理システムを強化すれば良いと考えているから
問題は起こる。まあ、焼け太りで予算を取って仕事が増えるのだから、実際は感謝、感謝かもしれない。
産業廃棄物処理業ダイコー(愛知県稲沢市)による廃棄食品の横流し問題で、愛知県は29日にも同社に対し、廃棄物処理法に基づき、超過保管する廃棄食品の早期撤去を求める改善命令を出す。無届け倉庫からも廃棄食品が見つかり、同法で定められている保管量を超えていると判断した。
ダイコーは食品の産業廃棄物を主に堆肥(たいひ)化する中間処理業者。保管施設も届け出が必要で、保管できる産廃量は1日の処理能力の14日分までだ。だが、愛知県の調査で、県内の本社工場と無届け倉庫の計4施設で見つかった廃棄食品は、各施設で規定の保管量を大幅に超えていたとみられる。
1月中旬に廃棄冷凍カツの横流しが発覚後、同社は休業状態で、倉庫や付近に放置された廃棄食品による悪臭や飛散が懸念されている。愛知県は廃棄を委託した食品メーカーにすでに自主回収を促しており、同社には行政処分としての改善命令で対応を強く求める。
同社が横流しした複数の廃棄食品は市場に流通し、冷凍カツでは産廃の適正な処理を報告する管理票を偽造していた。愛知県は、産廃業者としての資質を欠く同社の行為が社会に与えた影響を重く見て、さらに厳しい対応を検討する。
廃棄食品の横流し問題を受け、環境省は16日、再発防止の対策案をまとめた。食品を廃棄する際に、そのまま転売できないように印をつけたり、他のごみと混ぜたりするなどの対応を業者に求めるほか、廃棄物管理のシステム上でチェックする仕組みをつくる。有識者を集めた会議で議論し、年度内に決定する方針。
丸川珠代環境相が閣議後の記者会見で明らかにした。また、問題となっているダイコー(愛知県稲沢市)に対して環境省は、食品リサイクル法に基づく登録再生利用事業者としての登録を取り消す方針を固めた。丸川環境相は「手続きを速やかに進めていく」と述べた。
案では、環境省所管の公益財団法人が運営する産業廃棄物の電子管理システムを強化する。排出、運搬、処理などの段階で提出することになっているデータについて、食品業者が処理を委託した量と、廃棄物処理業者が処分した量が違う場合などの不審な点を検知できるようにする。
食品廃棄物処理業者への抜き打ちの立ち入り検査も強化。処理業者には処理状況の情報公開の徹底を、食品関連業者には食品廃棄物の一層の削減も要請する。
まあ、形だけで不正調査を選択するのだろうから、知名度とか知名度がある人が在籍する会社で選択しているのだろう。不正を発見する事を期待して いなけば、外部から指摘を受けなければ適切な対応は取らないであろう。まあ、NHKだから批判したい人は批判すれば良いだろう。
NHKが関連団体の不正を調べるため、外部の弁護士による調査委員会を設置した2014年の同時期に、別の監査法人にも約5000万円で関連団体の不正を調べさせていたことが24日分かった。両調査合わせて約1億円超を支出したが、後に発覚した子会社の社員2人による約2億円の着服などの問題には気づけなかった。
NHKの関連団体をめぐっては14年3月、子会社2社で架空発注などの不正が明らかになった。同月、籾井勝人(もみい・かつと)会長直轄のNHK関連団体ガバナンス調査委員会(委員長・小林英明弁護士)を設置して原因などを調べた。調査委には約5600万円を支払っていたことは分かっていた。
NHK関係者によると、調査委の調査開始と同時期に「アドバイザリー業務」の名目で東京都内の監査法人と随意契約し、不正の有無について調査を依頼。監査法人には約5000万円が支払われた。
調査委が同年8月に公表した調査結果によると、新たに見つかったのは、最初に不祥事が発覚した子会社の売り上げ800万円の水増しだけだった。
NHK広報局は「短期間で調査するには作業量が膨大となるため、監査法人に一部業務を委託し、サポートを受けた」としている。【丸山進、望月麻紀】
「日常の点検はメーカーや保守点検業者ごとに、内容や方法が異なっていて、部品の劣化や動作の不良などが日常の点検で見過ごされて事故につながるケースが、各地で毎年発生し、中には死亡事故も起きています。このため国は、エレベーターの所有者に、保守点検業者を選ぶ際には、価格だけでなく技術者の能力や実績などを考慮することや、点検結果を文書で報告させて、不具合の情報などが確実に引き継がれるよう求める指針を新たに作りました。
」
検査を通す事前提、又は、見積もり通りの範囲で検査を通す事が前提となれば、事故が起きても仕方がない。詳細な見積もりは人件費やコストがかかる。
素人やコスト重視の人間が決定権を持っていれば、良心的であろうが、経験と技術があろうが関係ない。法で規定されている検査を受けて、保守点検業者が検査を通すのだから、法的に何も問題がない。
国土交通省が問題のある保守点検業者に対して、営業停止又は解散などの重い罰則を規則で定めなければ、競争の中でブレーキを掛けるのは難しい。問題のある点検を行っても、事故又は死亡事故が起きるまで問題が公表される、又は、多くの人達が知る事はない。
「指針では必要な点検項目や、所有者や保守点検業者の責任を記した契約文書のひな形も示しています。
国土交通省建築指導課は『エレベーターの日常の点検や保守作業について、これまで具体的な管理方法を示せていなかった。契約を更新する際などに安全な利用のために指針を参考にしてもらいたい』と話しています。」
技術的にレベルが低いが向上したいと思っている保守点検業者には有効であるが、点検の仕事を取って、最低限又は会社が指示した事以上はしない方針の点検業者には意味のないもの。国交省が抜き打ち検査を行うか、問題を起こした点検業者を営業停止にする以外、問題は解決しないだろう。国交省が抜き打ち検査を行うのは、技術的に、そして、人材の問題で無理であろう。
「エレベーターの所有者に、保守点検業者を選ぶ際には、価格だけでなく技術者の能力や実績などを考慮することや、点検結果を文書で報告させて、不具合の情報などが確実に引き継がれるよう求める指針を新たに作りました。」
エレベーターの所有者や点検業者の選定に対して権限を持つ者が技術者の能力を評価できるのか?実績は参考になるが、実績の数だけでどのような
保守点検を行ってきたのかは別問題。国土交通省建築指導課がこれぐらいの対応しか出来ないのであれば、今後も事故は起こるであろう。
エレベーターの点検の際に部品の劣化などが見過ごされ、事故につながるケースが各地で起きていることを受けて、国土交通省は、所有者に対して適切な知識や技術を持った保守点検業者を選定することなどを盛りこんだ指針を作り、安全対策の徹底を求めていくことになりました。
エレベーターの点検は、建物の所有者に、年に1度保守点検業者に依頼して定期点検を行うことなどが法律で義務づけられているほか、10年前の平成18年に起きた東京・港区のエレベーター事故を受けて、定期点検を行う業者にも、ブレーキの摩耗状況を報告したり、不具合の写真を添付して報告したりすることなどが義務づけられています。
しかし、それ以外の日常の点検はメーカーや保守点検業者ごとに、内容や方法が異なっていて、部品の劣化や動作の不良などが日常の点検で見過ごされて事故につながるケースが、各地で毎年発生し、中には死亡事故も起きています。
このため国は、エレベーターの所有者に、保守点検業者を選ぶ際には、価格だけでなく技術者の能力や実績などを考慮することや、点検結果を文書で報告させて、不具合の情報などが確実に引き継がれるよう求める指針を新たに作りました。
また、指針では必要な点検項目や、所有者や保守点検業者の責任を記した契約文書のひな形も示しています。
国土交通省建築指導課は「エレベーターの日常の点検や保守作業について、これまで具体的な管理方法を示せていなかった。契約を更新する際などに安全な利用のために指針を参考にしてもらいたい」と話しています。
「長野県軽井沢町で15人が死亡したバス事故を受け、日本旅行業協会などの業界団体は、違法な運賃でのバス運行を防ぐため、法令違反に関する通報を受け付ける新組織を設立する。」
これって単なる利用者に対するパフォーマンスなのでしょうか?業界団体が設立すると言う事は、法的な罰則は適用できないし、通報の内容に対する
確認作業に関しても限度がある。
「また同庁は、どの会社のバスに乗るかを利用者が旅行の申し込み時に分かるようにするため、旅行業者が作成するパンフレットなどにバス会社名を明記するよう求める方針だ。」
問題は嘘を記載した場合の罰則及び過去の事故を消すために会社名を変えたり、新たに会社を設立する可能があると言う事。船の業界のように
船主と管理会社が簡単に社名を変えて逃げにくいように、会社に番号を付けて、国土交通省に登録するべきだろう。会社の番号で検索すれば
登録申請された住所などが誰でもチェックできる。このような環境でも実際は違反は出来るのであるが、ないよりはましである。
実現は難しいのではないのか?旅行のパンフレットには申込者が少なければツアー自体がキャンセルになる注意書きがある場合が多い。バスだけをブッキングしておくのは難しいのでは?それよりは利用するバス会社をリストアップさせて、リストアップしたバス会社の中で選択するとしたほうがまだ良心的で、実現可能だと思う。リストアップしたバス会社の過去の事故を添付資料で観閲出来る事を強制とすれば、ひどい会社が候補の中に挙がっていれば申請者が他の会社のツアーに決定する事も可能になる。バス会社もまともであれば事故履歴を無視できなくなるので、何らかの対応を取るであろう。
長野県軽井沢町で15人が死亡したバス事故を受け、日本旅行業協会などの業界団体は、違法な運賃でのバス運行を防ぐため、法令違反に関する通報を受け付ける新組織を設立する。
18日に国土交通省で開かれた事故対策検討委員会で報告された。
今回のバス事故では、バス運行会社「イーエスピー」(東京都)が旅行会社「キースツアー」(同)の要請を受け、国の基準額約26万円を大幅に下回る約19万円で運行していたことが発覚した。業界では、基準内の運賃を受け取ったバス会社から手数料として旅行会社にバックさせる方法で、事実上の基準割れが横行していることも判明。対策として、観光庁などが業界団体に新組織設立を要請していた。
新組織は通報内容を調査し、問題があれば同庁などに通報する。メンバーは業界団体の関係者や弁護士など10人程度を想定しているという。設立時期は未定。また同庁は、どの会社のバスに乗るかを利用者が旅行の申し込み時に分かるようにするため、旅行業者が作成するパンフレットなどにバス会社名を明記するよう求める方針だ。
「同省は処分を厳格化する方針だが、規模が小さい業者ほど違反が多いことから、参入基準の見直しにも着手する。」
結果に驚いて参入基準の見直しに着手する必要はないと思う。まあ、参入を厳しくするか、取締りと処分を重くするかの選択しか
違反を減らす事は出来ない。行政として簡単なのは参入基準を厳しくする事。
長野県軽井沢町のスキーバス事故を受け、国土交通省が行った貸し切りバス165台の街頭監査で、4割の66台で違反が見つかったことが15日までに、同省への取材で分かった。
同省は処分を厳格化する方針だが、規模が小さい業者ほど違反が多いことから、参入基準の見直しにも着手する。
国交省は1月21日以降、全国28カ所で抜き打ちの街頭監査を実施。運行指示書の記載漏れや車内表示などの違反が見つかったが、バス保有台数が20台以下の小規模業者では違反率は5割を超えていた。
自業自得。まだ成りの果てまで到達していないが、険しい道であろう。
東洋ゴム工業が、免震ゴムの性能偽装問題で追加の損失処理をすることで、2015年12月期連結決算の税引き後利益が赤字となる見通しとなった。
赤字転落は3月期決算だったリーマン・ショック直後の08年度以来となる。製品の交換や補償金の支払いなどに充てる資金を確保するため、自動車部品事業や本社ビル(大阪市西区)を売却する検討に入った。
東洋ゴムは昨年3月に免震ゴムの不正が発覚して以降、交換や補償費用の支払いがかさんでいる。損失の増加により、昨年11月時点で50億円の黒字を見込んでいた税引き後利益は赤字になる見通しだ。自動車向け部品事業や本社ビルの土地・建物は今春以降、売却に向けた手続きに入る。
監視委員会は、刑事告発するのだろうか?
教科書会社による謝礼問題で、教科書を発行する「新興出版社啓林館」(大阪市)が2014~15年、北海道の公立中学校長ら延べ10人に検定中の教科書を見せ、それぞれ5000円の謝礼を渡していたことが新たにわかった。
現金が渡されたのは放課後の校内だった。文部科学省が各教科書会社に求めた緊急調査の結果には含まれておらず、同社は今月5日、同省に追加報告した。これで各社から謝礼を渡された教員らは計4000人を超えた。
啓林館によると、同社の営業社員が14年12月、北海道苫小牧市の市立中学校を訪問。放課後に同校の校長と他校を含む教員3人の計4人に、検定中の中学数学の教科書などを見せ、意見を聞いた。その際、交通費名目で4人に現金5000円ずつ渡したという。
「元社長とともに拘束された建築士が建築申請の段階で設計担当者とされたが、名義を借りた別人が実際には設計していた。」
台湾では名義貸しに対する罰則はあるのだろうか?もしあるとすればどのような罰則なのであろうか?罰則がない、又は、罰則が軽いから
名義貸しが行われたのでは?
【台南(台湾南部)林哲平】台湾南部を襲った地震で倒壊した台南市の16階建てビルについて、検察当局は一部の鉄筋が必要量の半分しか使われていなかったと明らかにした。10日付の台湾各紙が伝えた。検察は耐震強度の不足が倒壊につながったとみて、拘束した建設会社の元社長らを調べている。
検察によると、ビルの1階から5階のはりや柱に入った補強用の鉄筋が構造計算書に記された量の半分に減らされていた。また、元社長とともに拘束された建築士が建築申請の段階で設計担当者とされたが、名義を借りた別人が実際には設計していた。元社長は「覚えていない」と供述しているという。
複数の不動産業者によると、1989年に設立された建設会社は戸建て民家など小規模な住宅を建設し、「地元でもあまり知られていなかった」という。90年代に市内3カ所で相次いでマンション建設を始め、94年にそろって完工させた。倒壊したビルが最後の工事となり、99年に事業停止を申請、倒産した。ある不動産業者は「能力を超える事業拡大の中でずさんな工事や設計が行われたのではないか」と話した。
倒壊したビルは小学校に近く、買い物にも便利な立地で、子供を持つ若い夫婦らに人気だった。ただ標準的な部屋の中古価格は約300万台湾ドル(約1040万円)と「付近の相場の半分」(不動産業者)という。住民の一人は「水漏れが頻繁に起きるなどトラブルが多かった」と話し、施工の不備をうかがわせた。一方で同時期に完成した2カ所のマンションは地震による被害は出ていない。
住民に若い家族が多かったことで、犠牲者には子供が目立つ。台湾当局によると、ビルの死者45人のうち12歳以下の子供は14人で3割を超える。また、閉じ込められているとみられる約90人のうち20人が子供という。
一方、台南市政府は、地震の影響で倒壊の危険性が高まり、撤去の必要がある建物が31棟に上ることを明らかにした。建物に被害が出たり、住民が不安を訴えたりしたことを受け、9日までに97棟を調べた。このうち31棟で解体、17棟では耐震補強の必要があった。
監視委員会は、刑事告発するのだろうか?
レセプト債の発行元ファンドの破綻問題で、債券を販売していたアーツ証券(東京)の社長が、ファンドを管理するオプティファクター(同)の社長に対し、ファンドが債務超過に陥っていることに関してやり取りしたメールを削除するよう依頼していたことが、関係者の話でわかった。
証券取引等監視委員会は9日、債務超過を隠して顧客を勧誘したなどとして、金融商品取引法違反(虚偽告知)容疑でアーツ証券とオプティ社を強制調査。両社が証拠の隠滅を図った可能性もあるとみて調べている。
レセプト債は、医療機関が健康保険組合などから受け取る「診療報酬」を配当などの原資とする金融商品。監視委によると、ファンドは2004年6月から債券を発行する一方、顧客から集めた資金を外部に流出させるなどして債務超過に陥り、昨年11月に破綻した。
似たような傾向はいろいろな業界であると思う。
◇中間報告公表 「調べる機会あったのに」と陳謝
旭化成建材のくい打ち工事施工データ不正問題で、親会社の旭化成は9日、不正の原因を巡る社内調査の中間報告を公表した。一連の不正が発覚した昨秋以前にも他に3件のデータ不正があり、社が把握しながら対処していなかったことを明らかにした。柿沢信行・旭化成執行役員は「他は大丈夫かという疑問を持って調べる機会はあったのに、今に至ってしまった」と陳謝した。
旭化成建材がくい工事をした横浜市都筑区のマンションで昨年10月、データ改ざんが判明。同社は過去10年の工事を調べ、360件の工事でデータ不正があったことが発覚した。しかし、今回の問題発覚より前に3件の不正が社内で表面化していたという。
調査報告によると、約10年前、ある施設のくい工事のデータに不正があることが元請け建設会社の指摘で判明。当時の小林宏史社長にも報告したが、原因究明せずに、トラブルとして処理しただけで終わった。小林氏は「報告を受けたかどうか、記憶が定かではない」と話しているという。
その後も、集合住宅など2件のくい工事でデータ不正が判明したが、担当部長や課長が特異例と判断して役員に報告せず、調査もしなかった。
問題を把握しながら改善しなかった形で、柿沢執行役員は「管理責任は大きい」と述べた。計3件の安全性に問題はないとしている。
一連の不正について調査報告は、旭化成建材はデータの管理手順やデータ取得失敗時のルールを整備しておらず、データの扱いに注意を払っていなかったと指摘。現場責任者の不正を助長し、データ軽視の風潮を生んだと分析した。【坂口雄亮】
医療機関の診療報酬請求権を債券化した金融商品=「レセプト債」を、発行元の会社が債務超過なのを隠して販売したとして、証券取引等監視委員会は、東京の証券会社などの強制調査に乗り出しました。
金融商品取引法違反の虚偽告知の疑いで強制調査を受けているのは、今月倒産した東京・中央区の「アーツ証券」や、破産した資産運用会社「オプティファクター」の関係先、数か所です。
監視委員会の調べによりますと、アーツ証券は、2013年10月ごろには『オプティ社』が債務超過状態だと把握したにもかかわらず、『オプティ社』発行の「レセプト債」を、「運用は安定している」などと説明し販売していたということです。
『オプティ社』は去年、破産し、投資家には総額227億円分が払い戻されておらず、監視委員会は、刑事告発を視野に調査を進めるものとみられます。
日本社会で断る事は難しい。飲み会があれば参加するだろう。飲むのが好きであればなおさら参加したいであろう。飲むのが好きだが車の代行サービスが割高、交通機関の不便さのためにタクシーを使うと総額が高くなる等の理由で飲酒運転をするのだろう。飲む費用に加えて、車通勤の人達は更なる追加が発生する。この追加が人件費の高い日本ではかなりの負担となるだろう。
飲食店経営に影響を与えるから飲酒運転の可能性を認識している市に飲み会自粛の解除を求めるのは自分勝手な判断と思える。
公務員に対する法令順守の期待や自己管理の要求が下がる事はないだろう。交通機関、飲食店による安い送迎サービスの提供、利便性の良い街づくり、
コストを低く抑えながらの町のコンパクト化など考えるべきであろう。まあ、どれも長いスパンの話なので本当に経営に行き詰っていれば変化が
感じられるまでに店はなくなっているだろう。環境の変化に対応できないのであれば閉店になっても仕方がないのではないのか?
歴史を見れば、地域、産業、商店の浮き沈みはある。流れに流されるのか、流れに逆らうのか、流れを変えるのか、結果でしか判断できない。
飲み会の自粛解除の陳情は部外者から見れば間違っている。
本当は個々が責任を持って判断すれば良いが、それが日本では難しいと判断したから石巻市が飲み会を自粛を決定したのだろう。飲酒運転が発覚すれば処分すれば良いだけの事だが、その前に、飲酒運転の原因を取り除けば良いと判断したのだから仕方がない。
職員の飲酒運転が相次いだことを受け、宮城県石巻市が職場関係の飲み会を自粛したことをめぐり、市内の飲食業者でつくる団体などが、自粛を解除するよう市に陳情することが分かった。
年明け以降、予約のキャンセルが相次ぐなど商売に影響が出ているという。
陳情するのは、石巻商工会議所、みやぎ寿司海道石巻地域協議会、石巻料理店組合など約10団体。8日に亀山紘市長に対し、震災の影響で飲食店経営が苦しいなか、市の自粛が追い打ちをかけていると訴える予定だ。陳情団代表の伏見不二雄さん(72)は「自粛が続けば、地域経済が大変なことになる。送別会がある年度末に向けて解除してほしい」と話している。
市では職員が昨年6月に飲酒運転で物損事故を起こしたほか、12月には2人が酒気帯び運転で相次いで逮捕された。
「同庁は重松容疑者らが2011年以降、総額1億円以上の診療報酬を詐取したとみている。」
1億円は大きな額だ!
住吉会系暴力団組長らが接骨院と共謀し、自治体などから療養費をだまし取っていた事件で、警視庁は6日、千葉県船橋市の「重松歯科医院」(閉院)を経営していた歯科医の重松武容疑者(58)(東京都渋谷区)ら3人を詐欺容疑で新たに逮捕し、同組長の三戸慶太郎被告(50)(詐欺罪で起訴)ら8人を同容疑で再逮捕した。
重松容疑者は三戸被告らの指示で、診療報酬の不正請求を繰り返していたという。一連の事件で、歯科医院での不正請求が立件されるのは初めて。同庁は重松容疑者らが2011年以降、総額1億円以上の診療報酬を詐取したとみている。
同庁幹部によると、重松容疑者らは11年7月~13年1月、重松歯科医院で患者12人分の治療回数を水増しした虚偽のレセプト(診療報酬明細書)を作成し、都内などの10自治体から診療報酬計約366万円をだまし取った疑い。
自分の会社で雇っているように装って飲食店で働くネパール人の在留資格を不正に更新させたとして、警視庁組織犯罪対策1課は4日、出入国管理法違反(資格外活動)幇助(ほうじょ)容疑で、東京都小金井市の会社役員、石堂行夫容疑者(79)を逮捕した。
石堂容疑者は、昨年イスラム教スンニ派過激組織「イスラム国」(IS)が殺害を公表したフリージャーナリストの後藤健二さん=当時(47)=の義父。同課によると容疑を認めている。
石堂容疑者は、同市の通信情報処理サービス会社の役員とされる。「就学」の在留資格で入国した30代のネパール人男女を、この会社で通訳などとして雇ったように装い、平成23年から「技術・人文知識・国際業務」の資格を取得させていたとみられる。
男女は実際は都内の飲食店で働いており、これまでに男は90万円、女は190万円を石堂さんに払ったと話している。
逮捕容疑は、報酬を得る目的で昨年4月と9月、ネパール人2人に関する偽の在留許可申請書などを東京入国管理局に提出し、在留資格を不正に更新させたとしている。
「この前、ささやかに四十九日法要をやりました。簡単ですけど供養をしまして。お世話になった方に集まっていただいて、お経をあげました」
本誌にそう打ち明けたのは、ジャーナリスト・後藤健二さん(享年47)の義父・石堂行夫さん(78)。
両親の嘆願もむなしく、1月30日、健二さんがイスラム国の凶刃に倒れてから50日あまり。行夫さんは、健二さんの母親・石堂順子さん(78)の夫で、健二さんとは義理の親子として、生前から親しく交流していた。
自宅に行くと、白い布がかけられた祭壇の真ん中には、精悍な顔つきの健二さんの遺影が掲げられていた。しかし、肝心の遺骨はないまま。順子さんが供えたという花と一緒に、全国から届いた約300通の手紙も供えられていた。
人質事件の最中には、マスコミの取材に、健二さんが結婚していたことも知らず、孫が生まれていたことも知らなかったと語っていた、石堂さん夫妻。後藤さんの死から50日が過ぎ、現在は嫁や孫との交流があるのだろうか。
「いや、会ってません。(殺害後に)私らのほうで訪ねて行ったんですよ。それでもドアも開けてもらえず、居留守を使われて全然出てきませんしね。孫にも会ってません。だいたい、1月23日に家内が外国人記者クラブで会見したでしょ。あの日の朝早くに、『健二の妻です。会見なんかやめてください』と電話がかかってきたんですよ。それ以来、連絡すら一回もないですね。だから、もう私らは会う気もないです。本来なら、あちらからウチに来てもおかしくないんですけどね」
語気を強めた行夫さんの表情に悲憤の色が……。嫁と姑の悲しき断絶は、今も続いていた。後藤さんはいま天国から、残された「家族の苦悶」をどんな思いで見つめているのだろう――。
日本は性善説が基本になっているから、悪い事は簡単に出来るようだ!
堺市社会福祉協議会の男性職員(55)が、同市の民生委員・児童委員の団体の銀行預金約1055万円を着服していた問題で、市社協は3日、美原区事務所長を務めるこの職員を懲戒解雇処分とした。
近く、堺署に業務上横領容疑で告訴する方針。
発表によると、職員は福祉事業課長として市民生委員児童委員連合会の事務局長を兼務していた2010年12月~15年3月、金庫で保管せず、勝手に手元に置いていた預金通帳を悪用。市内の委員約1100人が積み立てた約1055万円を29回にわたって引き出して着服し、私的に流用していた。市社協は、着服の隠蔽のためとは知らずに、この職員の指示で決算書を書き換えていた経理担当の男性職員(52)も、停職1か月の懲戒処分とした。
架空人物で保険証不正取得の件や今回の件を考えると、 セキュリティーやチェック機能に問題があると判断できる。
医師が交通反則切符に患者の名前を記入したとされる事件で、患者名義のパスポートを不正取得したとして、中京署などは3日、有印私文書偽造・同行使と旅券法違反の疑いで、京都市上京区、精神科医(42)=別の有印私文書偽造・同行使の罪で起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は、2014年11月13日、下京区の京都府旅券事務所で、患者を装ってパスポートを申請し、同20日、他人名義のパスポートを不正に受け取った疑い。
同署によると、精神科医(42)は申請の際、事前に不正取得した疑いがある患者名義の住民基本台帳カードを本人証明として提示し、自身の顔写真を提出していた。このパスポートでタイや韓国へ複数回渡航した形跡があるといい、府警は動機などを調べる。
失ったお金は返ってこない。金融庁は問題がお起きるなる前に何とかできなかったのか?
医療機関の診療報酬請求権を買い取り「レセプト債」と呼ばれる債券を発行していたファンドなどが破綻した問題で、証券取引等監視委員会が、債務超過の事実を隠して販売していたアーツ証券(東京都中央区)の経営陣について、金融商品取引法違反(虚偽告知)罪で検察当局に刑事告発する方針を固めたことが1日、関係者への取材で分かった。監視委は近く、同証券など関係先の強制調査に乗り出す方針。
同債をめぐってはファンド3社と運用会社「オプティファクター」(東京都品川区)が昨年11月に約291億円の負債を抱え破綻。約2470人の投資家に発行された約227億円分の債券が償還されなくなっていた。監視委によるとアーツ証券は平成16年6月以降、同債を約60億円分販売。川崎正社長ら経営陣は遅くとも25年10月ごろまでにオプティ社の社長から、資金がオプティ社の関連会社に流用されるなどしてファンドが債務超過状態にあることを知らされながら、事実を隠して販売を継続した疑いが持たれている。
川崎社長らは「安全性の高い商品」と記載した勧誘資料などを継続使用。オプティ社社長とともに、同債を扱うほかの証券6社にも虚偽の決算書などを示して販売を継続させていた。
監視委は、こうした行為が金商法が禁じる「虚偽告知」に当たるほか、投資家に錯誤を生じさせる詐欺的行為の「偽計」にあたる可能性もあるとみている。オプティ社の経営陣についても共犯に問えるとみて慎重に調査している。レセプト債問題をめぐっては、金融庁が1月29日に、監視委の勧告を受け、同証券に金融商品取引業の登録取り消しなどの行政処分を出した。
◇
アーツ証券は1日、東京地裁に自己破産を申請し、保全管理命令を受けた。帝国データバンクによると、負債総額は約59億円。
IHIは2日、2016年3月期連結決算の業績予想について、税引き後利益を300億円の赤字に下方修正すると発表した。
税引き後利益の業績予想は昨年11月時点では、180億円の黒字を見込んでいた。商品のボイラーで溶接の不良が見つかるなどして、約470億円の特別損失を計上したためで、税引き後赤字になるのは、7年ぶり。
不良溶接は昨年8月、製品の出荷前に、ボイラーの管に漏れがないかを確認する試験の過程で見つかった。本来とは異なる材料で溶接をしており、補修作業に費用がかかったという。期末に予定していた配当は無配の見通しになり、役員は責任を取って報酬の一部を返上する。
NHK 土曜ドラマ 「限界集落株式会社」 みたいな事を簡単に考えていたのでは ないのか?
山梨県南アルプス市の観光農園「南アルプス完熟農園」の営業停止に反対し、農産物を搬入してきた生産者団体が29日、同市内で記者会見を開き、営業の再開を求めた。
会見を開いたのは、農家約270軒で組織する「南アルプス完熟農園生産者協議会」。野沢益雄会長(66)は「出荷してきた農家は突然、売り場を失ってしまった。事業を早急に再開してほしい」と訴え、来月3日、営業停止の撤回を求め、金丸一元市長に直接要望するという。また、会見では斉藤幸博副会長(66)が「完熟農園の目的は農家の収入増を図るものだった」と説明。完熟農園のオープンに伴い、農家の収入は増えていたと主張した。
野沢会長は、営業停止を決めた後の市側の対応も批判。「営業停止が伝えられたのは、(営業停止した)25日の朝。今年は出荷量を増やそうと意気込んでいたのに、市の対応はあまりにもひどい」と憤った。
◆南アルプス市 外部監査へ
経営難に陥っている南アルプス市の観光農園「南アルプス完熟農園」の運営会社が、コンサルティング料などとしてこれまでに約8400万円をコンサルティング会社に支払っていることが18日、明らかになった。市が運営会社に5000万円を貸し付ける議案を審議するこの日の市議会総務常任委員会の直前、金丸一元市長が市議に報告。市議からは批判が相次ぎ、金丸市長は今後、運営会社の資金繰り悪化の原因を調べるため、外部監査を実施するとし、9月議会に追加の補正予算案を提出する考えを示した。
金丸市長の市議への説明によると、運営会社「南アルプスプロデュース」側から今月に入り、甲府市のコンサル会社への出金があるとの報告を受けた。金額は約8400万円。金丸市長は「コンサル会社にこれほどの出金があるのは異常。早急に監査を入れる必要がある」と話し、外部の会計士による監査を行う考えを示した。また、運営会社側は今後3年間、農園の経営状況にかかわらず、コンサル会社がブランド管理する商品の売り上げの4%をコンサル会社に支払う契約になっていることも報告した。
これに対し、市議からは「売上に対し、契約が高額すぎる」などと批判する声が聞かれた。
「南アルプスプロデュース」はこの日、取材に対し、「契約内容は経営のほか、デザインや基本概念など事業全般であり、売り上げ見込みも我々を含め相談して決めた」と説明。「契約の金額も高額なものではない。経営難の原因はこれまでの説明通り、天候不順で品薄となってしまったこと」としている。
一方、この日の同委員会では、5000万円を貸し付ける議案が審議され、賛成多数で可決された。
バス業界ではないが、共通した部分がある業界の会社の人と話した事がある。日本の企業ではないし、日本人でもない。個人的には結構しっかりした会社であるとの印象を受けた。コスト競争があるので全ての労働者に同じ待遇をオファー出来ないが、要になる人材は重要なので、引き止めるために手厚い待遇を提供していると言っていた。
現場の経験がある、又は、現場を良く知っていて、管理者としての能力が高い人材、又は、良い管理者になると推測できる人材は貴重と言っていた。管理能力が高い、
又は、管理できるという事は、その他の人々や現場に問題がある場合、問題を発見し、対応できるという事。良い労働者を採用しても、その現場でしか結果を出せない。
良い管理者は、複数の現場を管理できるし、普通の労働者で良い労働者を採用したと同じような結果を出せる事もあると言っていた.
問題のある企業には良い人材は一般的に来ない。破格の報酬を提示すれば人によっては来るかもしれないが、それだけの報酬を出せないケースが多いだろう。問題のある企業に例え騙されるような形で入社したとしても、問題の大きさに気付いた時点で会社を辞めるであろう。
新規参入で資金的に問題があるが改善して会社を成長させたいとか、経営者の子供達が事業を引き継ぎで改革したいと思っている等の例外を除けば、会社が大きく変わることはない。会社の規模が大きくても、管理や安全を重視していない企業は小さくても堅実な管理を行っている企業よりも安全を軽視する傾向もある。
問題のある会社、ある一定の期間で変われない会社は、市場から撤退してもらい、新規参入の可能性があるのであれば、新規参入者にチャンスを与え、活性化を期待する
ことが望ましいと思う。ただ、最低限の規制と問題のある企業をチェックし、排除する行政の存在がなくては成り立たないと思う。
確かに、コストの制限があれば良い結果を出す方法の1つだと思った。この方法はこのケースでは有効だと思うが、全ての業界やケースで有効ではない。良い管理者でも
悪い、そして、経験不足の労働者に対しては良い結果が出せないかもしれない。組み合わせも重要。それぞれの企業が考える事だと思う。
結局、似たような人材が集まるのである。問題のある企業でしか就職できない人、経験がない人、良い企業で選ばれない問題がある人、高齢の人、問題のある企業で働いた事のある人達が集まる。違法行為を会社が要求しても、前の会社でも同じような環境であれば抵抗などないであろう。仕事に就きたいけれど、仕事が見つからない人であれば、やっと見つけた仕事を失いたくないので、会社の不適切な要求に従いたくなくても、従うだろう。会社の待遇が悪くても、前者の待遇が悪ければ、違和感を抱く確立は低いであろう。待遇に不満があり、他のましな会社での就職を望み、それが可能であると思う人は、同じ失敗をしないために問題のある会社には行かない。
中田絢子
長野県軽井沢町のスキーバス事故で、国土交通省は29日、バスを運行していた「イーエスピー」(東京都羽村市)に対し、貸し切りバス事業許可の取り消し処分を出す方針を固めた。
同省による事故後の監査では、運転手に詳細な行程を示す「運行指示書」を適切に作成せず、国に届け出た基準運賃を下回る安値での契約が複数あったことが分かった。点呼記録の虚偽記載などもあり、道路運送法に違反する事例が相次いで確認された。
同省は29日、同社に追加の立ち入りを実施。道路運送法違反による行政処分は、違反ごとに決まった点数を合算して軽重を決めるが、違反の累積が行政処分としては最も重い許可取り消しに相当したという。
同省は、行政手続法に基づき、2月中にも同社に聴聞の機会を与えて、その内容を踏まえた上で正式に処分する。同社はバス事業から撤退する意向を示していたが、国交省は安全管理体制が極めてずさんだったとして厳しい処分に乗り出すことにした。(中田絢子)
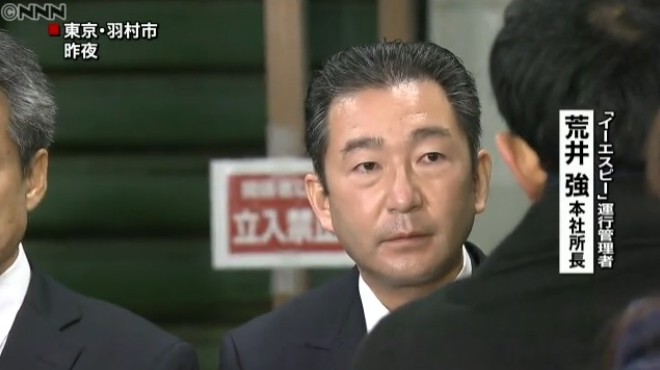
15人が死亡した長野県軽井沢町のスキーバス転落事故で、29日、バス会社の運行管理者が会見し、過去に勤めていた別のバス会社でも似たような事故が起きていたと認めた。
29日に会見したのは、東京・羽村市のバス会社「イーエスピー」で、バスの運行管理者を務める荒井強本社所長。荒井氏は、2003年には別のバス会社で運行管理者を務めていたが、その時にも大型バスの乗車経験が浅いドライバーに観光バスを運転させ、そのバスが静岡県熱海市で道路から転落し、乗客46人がケガをしていたことを認めた。
荒井所長「(Q:以前の事故から学ぶなら防げた事故では?)本当にその通りでございます。防げたと思います。仕事の内容や量が多くなって、研修もさせず、土屋ドライバーを当てこんじゃったということです」
また、荒井所長は、今回の軽井沢の事故で亡くなったドライバーの土屋廣さんには、大型バスの乗車研修を一度しか行っていなかったと明らかにした。
「イーエスピー」はすでにバス事業からの全面撤退を表明している。
これだけの横流しを「ダイコー」(愛知県稲沢市)の会長が従業員が不審を持たずに行えるのだろうか? 見て見ぬふりが現実では?
岐阜県は28日、「ダイコー」(愛知県稲沢市)が「みのりフーズ」(岐阜県羽島市)に横流しした5品目を新たに確認した。
みのりフーズで見つかった壱番屋以外の108品目のうち、横流しが判明したのは30品目となった。
新たに確認されたのは、「キリン協和フーズ(現・MCフードスペシャリティーズ)」(東京都)が輸入・販売した「グルエース」など調味料3品目と、「ニッカプランニング」(愛知県)が輸入した「水煮筍たけのこ」、それに「栗木食品」(名古屋市)が輸入した「糸切りごぼう」で、これらは2013年1月~昨年3月にダイコーが廃棄を請け負った。みのりフーズの実質的経営者の岡田正男氏(78)は県の調査に「転売はしていない」と説明したという。
また、既に判明している別の製品と同じ箱に入っていたセブン―イレブンの自主企画商品(PB)のケーキなどでも、横流しが確認された。
廃棄された冷凍ビーフカツの不正転売事件を受け、県は25日、食品製造時に出た廃棄物を扱う産業廃棄物処理業者の立ち入り検査を始めた。県の検査対象は県内の6社。秋田市も26~28日、3社に対し、立ち入り検査を実施する。
環境省は事件を受け、各都道府県や政令市などに対し、食品廃棄物を扱う産廃処理業者の立ち入り検査を実施した上で、29日までに不正の有無など検査結果を回答するよう通知を出している。
25日は午後から、大館保健所の担当者が「エコシステム秋田」(大館市)に立ち入り、食品廃棄物の処理や保管の状況などを確認した。同日の検査では、不正や特段の問題は見当たらなかったという。県は残りの5業者についても、28日までに検査を実施する。
県環境整備課は「悪質な場合は営業許可の取り消し処分を科すなど、厳しく対応する」としている。
廃棄された冷凍ビーフカツの不正転売事件で、横流しされたカツを転売していた製麺業「みのりフーズ」(岐阜県羽島市)の実質的経営者(78)が、転売先に出した領収書の控えを、事件発覚後に一部廃棄していたことが23日わかった。
転売先との取引では、産業廃棄物処理会社「ダイコー」(愛知県稲沢市)の会長(75)の指示で「伝票類は残さなかった」としてきたが、新たな証拠隠滅行為が明らかになった。
経営者が23日、読売新聞の取材に明らかにした。経営者によると、主な転売先だった名古屋市内の食品卸業者との間では伝票類は残さなかったが、それ以外の転売先との取引では、領収書や納品書を取り交わしていたという。カレーチェーン「CoCo壱番屋」を展開する壱番屋(同県一宮市)が廃棄した冷凍ビーフカツの不正転売が明らかになったのは今月13日で、経営者はその直後、転売した際の領収書の控えを「ゴミ箱に捨てた」としている。
「孝子さんは「今回も多くの大学生に同じことが起こり、胸が痛い」と話す。弘喜さんは『国の取り組みがいいかげんだから、ずさんな会社がなくならない。今度こそ有効な規制や監査に取り組むべきだ』と憤りの思いを語った。」
完璧なものはないでしょうが「有効な規制や監査」は可能だと思います。ただ、国、監督官庁、そして職員がそのような有効な監査を行うのかは疑問です。
簡単に有効な規則や法と言っても、実際にそ関係者の人達が適切に運用するか次第です。完成度の高い法律が存在するとします。逮捕する警察、そして、起訴する検察に問題があれば法の下で判決が出ても期待されたような結果になりません。もし、警察が捜査段階で賄賂を貰い、証拠を廃棄したり、調書に嘘の記述をしたりしたらどうなるでしょうか。検察が容疑者が不起訴になるように対応したらどうなるでしょうか。法に不備がなくても、被害者が期待したような判決は出ないでしょう。有効な監査も
同じ事が言えます。監査を行うのは人間です。公務員であっても人間だから手を抜きたい、早く仕事を終えて帰りたい、面倒な仕事をしなくないと思う人達も存在するのです。実際に、個人的に警察の捜査に不満があったので公安委員会に書類を提出する過程でそのような事を言われました。公務員や元公務員にそのような事を言われたのです。これが全てではないでしょうが、現実の一部です。
犠牲になった人達は運が悪かった。そして、完全でない行政が判断したコストの中に犠牲者が含まれていると思います。行政や公務員はそんな事は口が裂けても言わないでしょうが、態度や対応から判断すればそういう事だと思います。現実は厳しい。だからこそ、被害に巻き込まれないように注意するべきだと思います。次に思う事は
被害者や犠牲者になる前に、気が付いた問題について批判するべきです。批判しても多くの場合、何も変わりません。ただ、知らなかった、そのような問題を聞いたことがないと幹部、責任者、そして担当者に言わせないように行動を起こす事が重要だと思います。公務員の幹部やキャリアは詭弁家が多い。被害者や犠牲者、またはその家族になってから気付いても遅い。
31年前に起きたスキーバス転落 事故と同じであるのなら何年経っても、何十人もの人が死亡しても、大きな変化はないと言うことでしょう。
危ないし、死亡するリスクがあっても登山家は山を目指します。本人の判断です。
今回はツアーに参加した人達がリスクを認識して判断したのか?行政にどこまで期待し、行政はどのような結果を期待して対応してきたのか?について考えるべきかもしれない。行政(国交省)はたぶん逃げるから事実や本音は出てこないと思う。
労運転、過密な勤務実態や安全管理の甘さが疑われるのなら、山道や凍結などの追加のリスクを負ってまでスキーに行かない事でしょう。普通のバス以上に
危険な要素が多い。しかし、登山家のようにリスクを認識してもそれでもやりたい事があるのなら個人の判断だと思います。
乗員・乗客15人が死亡した長野県軽井沢町のスキーツアーバス転落事故と同様の悲劇が31年前にも長野市のダム湖で起きていた。日本福祉大学(愛知県美浜町)の大学生を乗せた夜行のスキーバスが転落し、学生ら25人が死亡した事故。日本福祉大学構内と現地では今も毎年1月、追悼集会と法要が続けられている。遺族は「悲しい思いは自分たちが最後だったはず。国は今度こそ抜本的対策を」と訴えている。【尾崎修二】
事故は1985年1月28日午前5時45分ごろ起きた。日本福祉大1年生ら21人が自力脱出したが、学生22人と引率教員1人、運転手2人が死亡した。「スキーバス転落」「同級生声詰まらせ」。当時の新聞記事には今回の軽井沢町でのバス事故と同じような見出しが並ぶ。
しんしんと雪が降る朝だった。事故の連絡を受けてダム湖に近い遺体安置所へ長野県下諏訪町の山形弘喜さん(75)、孝子さん(75)夫婦が駆けつけると、長女結可(ゆか)さん(当時19歳)がベニヤ板のひつぎに納められていた。遺体は冷え切っていた。「顔がきれいだったのが救いだったかもしれない」。孝子さんは振り返る。
弘喜さんは診療放射線技師、孝子さんは看護師の共働きだったため、家族でレジャーに行くことも少なく、結可さんは初めてのスキーを楽しみにしていたという。養護学校の教諭になる夢を抱いて進学したが、短い生涯を終えた。現場の慰霊碑にはこう刻まれている。「湖底に沈める若き命たちの尊さを思い 悲しみを二度とあらしめぬために」
今年も命日の法要が近づいた1月15日未明、同じ長野県で夜行スキーツアーバスが崖下に転落し、大学生ら15人の命が失われた。「またか」と夫婦はショックだった。
日本福祉大バスの事故でも、過労運転、過密な勤務実態や安全管理の甘さを指摘する声も上がった。今回の事故で一部業者のずさんな運行管理実態を伝えるニュースを見る度に不信感がよみがえる。
孝子さんは「今回も多くの大学生に同じことが起こり、胸が痛い」と話す。弘喜さんは「国の取り組みがいいかげんだから、ずさんな会社がなくならない。今度こそ有効な規制や監査に取り組むべきだ」と憤りの思いを語った。
【ことば】日本福祉大スキーバス事故
1985年1月28日午前5時45分ごろ、長野市信更(しんこう)町の犀川(さいがわ)に架かる大安寺橋付近の国道19号で、貸し切りバスが、ダム湖に転落。25人が死亡した。長野県警は、バスを運行していた三重交通と運行管理者を道交法違反(過労運転指示)容疑で書類送検したが、地検が容疑不十分で不起訴処分にした。
「制度順守の監査が最重要」と簡単に行っても現実は複雑。バス業界だけではないはずだ。北日本のある企業の社員が違法行為を行っている企業の仕事を行うと言った事を今でも覚えている。その企業のホームページには立派な事ばかり書かれている。その社員が言うには、「自分達がその仕事を受けなくても仕事を受ける企業はたくさん ある。遠慮したら仕事を取れないし、他の企業が仕事を取るだけ。」だと。まだ、若い頃だったし、お前は世間を知らないと言われたように感じたのでよく覚えている。 これが現実だと思う。その企業のホームページだけを見ると社員が恥ずかしげもなくそのような発言をするとは想像できないだろう。事実を知るのは大事故を起こした時だけだろう。その企業の運が良ければ、事故は起きず、関わりを持たない人々は事実を知る事はないであろう。今回の事故は問題の氷山の一角だと思う。
小佐野 景寿 :東洋経済 記者
「旅行会社からいただく仕事は、大半が基準額を下回っていたのではないかと思う」。バス運行会社、イーエスピーの山本崇人営業部長は1月19日、報道陣の前でこう漏らした。
その4日前の15日未明、長野県軽井沢町の国道で起きた、スキーツアー・バスの転落事故。ツアーに参加していた学生ら、乗客・乗員15人が死亡する大惨事となった。
今回の事故では、定められた基準を下回る運賃での契約や不十分な運行指示書など、バス会社の安全意識の低さが次々と発覚。冒頭の山本部長のコメントは、法令順守の意識が薄かったことを裏付けるものだ。
安全管理の不備が次々と明るみに
同社は、法令で定められた運賃の下限(約27万円)を下回る、約19万円で旅行会社と契約。昨シーズンはさらに低い、13万~14万円で契約していたことを明らかにした。
また、事故時にハンドルを握っていた運転手は、2015年12月の採用面接の際、大型バスの運転に慣れていないと伝えていたにもかかわらず、2回の研修を受けただけでスキーバスの乗務に就いていたこともわかった。
さらに事故の2日前には、前年の監査で乗務員の健康状態把握義務や点呼の実施義務などに違反したとして、国土交通省関東運輸局から行政処分を受けるなど、安全管理の不備が次々と明るみに出ている。
運賃について山本部長は「(上げてもらう交渉は)しづらい。仕事を出す側のほうが立場は強い」と弁明。「基準額を下回っているかどうかの確認を怠っていた」というずさんさと同時に、値下げの常態化もうかがわせた。
都内の中堅バス会社で、新人の指導なども担当するベテラン運転手は、貸し切りバスの運転について「初めての場所を走ることが多いため、ルートの決まった路線バスと比べて、知識と腕と判断力が必要。大型バスに慣れていないドライバーに、それも夜間の運転をさせるなんてありえない」と憤る。その一方で、安全管理がずさんなバス会社の例は「残念ながら、特に新規参入した業者の内情として、業界ではよく見聞きするのが事実」とも漏らす。
後手に回る国や業界の対策
貸し切りバスは規制緩和によって2000年に免許制から許可制に変わり、新規参入が増加。1999年度に2336社だった事業者は、2013年度には4512社まで増えた。
だが事業者拡大の一方で、重大な事故も相次いだ。2007年2月には、大阪府吹田市でスキーツアーの貸し切りバスがモノレールの橋脚に衝突。1人が死亡、26人がケガを負った。2012年4月には、群馬県の関越自動車道で高速ツアーバスが防音壁にぶつかり、7人が死亡する事故が起きた。いずれも運転手の居眠りが原因で、バス会社の安全管理体制が問われることとなった。
前出のベテラン運転手は、新規参入業者から転職したドライバーの指導を担当したことがある。「彼らの運転の技量は低く、教育に苦労するレベルだった。運転技術も磨けず、無理のあるスケジュールで過労運転が続けば、事故が起こるのも無理はない」と打ち明ける。
むろん、業界や行政も対策をしてこなかったわけではない。
2011年度には、業界団体である日本バス協会が貸し切りバス会社の安全に対する取り組みなどを審査し3段階で評価・認定する、「貸切バス事業者安全性評価認定制度」がスタート。2013年8月には、運転手1人で運行できる距離を原則として夜間は400キロメートルまで、などとする基準の改正が行われた。
さらに、相次ぐ事故の背景にあった、無理な低運賃に歯止めをかけるため、安全コストなどを反映し、国が定めた基準をベースに運賃を決める、新しい運賃・料金制度も2014年度に導入された。
こうした安全性確保に向けた模索が続く中で、再び惨事は起きた。
国土交通省は1月22日、再発防止策として、新たにバス事業に参入する際の安全確保に関するチェックの強化や、参入後の監査の実効性の向上などを検討する方針を打ち出した。これまでの施策で事故が防げなかった以上、国によるさらなる対策は不可欠だろう。
業界による自主的な取り組みも重要になってくる。日本バス協会に加盟しているバス事業者の数は2260社。4500社超ある貸し切りバス業者の半分に満たない。今回事故を起こしたイーエスピーも未加盟だ。新規参入の中小事業者を加入させるような取り組みが求められる。
制度順守の監査が最重要
ただし、制度の厳格化だけで問題が解決するわけではない。
訪日外国人観光客の増加など、貸し切りバスの需要は拡大傾向にあるものの、労働環境は厳しい。バス運転手の労働時間はほかの産業と比べて長いにもかかわらず、民営バス運転手の平均所得は全産業の男子平均を下回る。若者のなり手が少ないことから、平均年齢も48.4歳と高い。
今回の事故を受けて国交省が設置した「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」の委員を務める、名古屋大学大学院の加藤博和准教授は「リスクの低い若い人を増やせるよう、待遇を改善していくことが不可欠だ」と訴える。
常々激しい価格競争が指摘されるバス業界だが、加藤准教授によると、運転手不足に伴い、正規の運賃を取れる環境になりつつあるという。また、現在の運賃制度でも、安全性を確保したうえで運行できることを証明できれば、国が定めた下限を下回る運賃を届け出て、合法的に低運賃を提供することは可能だ。
「まともな運賃を取れていない会社には、何らかの問題があるとみられる。制度を厳しくするのではなく、現行制度をきちんと守らせるために、こうした業者を重点的・効率的に監査することが重要」と、加藤准教授は指摘する。
若者だけでなく、外国人観光客や国内のアクティブシニアにとっても重要な移動手段となった、貸し切りバス。「観光立国」を標榜するのなら、バスの安全性・信頼性確保は避けて通れない課題だ。
(「週刊東洋経済」2016年1月30日号<25日発売>「核心リポート01」に加筆)
「今回の事故を受け、国土交通省関東運輸局と警視庁が21日夜に東京都新宿区の路上で行ったツアーバスの街頭監査でも、客を乗せる前のバス計6台のうち5台で運行指示書の記載漏れなど計8件の違反が見つかった。繰り返されるツアーバスの事故。バス業界全体に安全意識が徹底される日はくるのだろうか。」
「バス業界全体に安全意識が徹底される日」と限定すればそのような日はこないだろう。新聞記事だから大げさに書いているのだろう。
今回の事故が大々的に取上げられているが、事故が結果として15人死亡となっただけ。単にガードレールを突き破りバスが大破したら死亡者なしであれば、
バス運行会社の問題は同じでもここまで記事として取上げなかったし、国交省もここまでバス運行会社が特別に悪いとのコメントをしなかったであろう。
「国交省自動車局幹部は「運行指示書の模範様式を埋めていくことで、自然に安全確認に必要な手順を踏むことができるようになっている。制度の理解が不十分なのではないか」と首をかしげる。事故車両は、行程表と異なるルートを走っていたが、運転手から運行管理者への変更連絡もなかった。」
制度を理解していなくても国交省の監査に通る事が問題。「運行指示書の模範様式を埋めていくことで、自然に安全確認に必要な手順を踏むことができるようになっている。」は現状をほとんど理解していない幹部の発言。規則を守る気はないが、形だけ運行指示書を埋めているだけ、形だけ書類を満足していれば、運次第であるが
時間の問題で事故は起こるだろう。問題を多く抱え、改善する態度を結果として見せていないバス運行会社を監査を通して市場から排除できない国交省は問題。
極端に冷たい言い方をすれば、多くのバスビジネス、バス事業の活性化、バス関連ビジネスの活性化のために事故の可能性が軽視された。そのコストが
乗客15人の死亡となっただけ。メディアや新聞の記事では頓珍漢なコメントや発言もある。命とか、安全とか言うが、事故が起きる前に批判するべきでは
なかったのか?結局、大事故や多くの被害者なしでは一般的に社会は動かないと言う事を証明している。
関係者は幕引きを必死で考えているだろう。基本的に現状が変わらなければ運次第で事故は起こると思うけど、利用者や一般人がどう感じるのかが重要と考えているはずだ。
長野県軽井沢町のスキーバス転落事故で、バス運行会社「イーエスピー」(東京都羽村市)の法令違反が次々と明らかになっている。同社は“アウトサイダー”と呼ばれる業界団体に未加入の業者だった。事故車両は道路運送法が義務付けた出発前の点呼すら行わずに出発していた。高橋美作社長(54)は事故翌日の16日に開いた会見で土下座して涙ながらに謝罪したが、事故による死者は15人。長野県警や東京労働局に家宅捜索を受け、大型バス事業からの撤退に追い込まれるなど、ずさんな運行管理の代償はあまりに大きかった。
社長が点呼に遅刻…相次ぐ違反に国交省も絶句
「本当にこの度は大変な迷惑をおかけしまして、申し訳ありませんでした。心よりおわび申し上げます」
約1時間40分に及んだ16日の会見の終了間際、高橋社長は涙ながらに土下座し、同社社員に抱きかかえられるようにして会見場を後にした。
国土交通省から書類の不備を指摘されていたが、高橋社長は会見で“新事実”を明かした。
「当日は点呼をせずに出掛けてしまいました」「私がする予定でしたが、少し時間が早く(事故で死亡した運転手2人が)出発したもので、私が遅れてしまい、立ち会うことができませんでした」
点呼に遅れた理由は「時間を思い違いしていた」。遅れた時間は当初「5分くらい」としていたが、その後、「移動も含めると10分ぐらい」と修正した。
それまで同社で行っていた点呼の場所を昨年12月から市内の別の場所に変更して以降、点呼をしないケースが「少しずつ増えていった」という。
点呼の書類にはあらかじめ社長の印鑑が押されていた。会見に同席した運行管理者は、自身が事前に押印したことを認めた上で、これまでも「正直なところ、何回かはあった」と明かした。
同社のずさんな対応は点呼だけにとどまらない。
事故を起こした運転手の法定の健康診断や適性検査を実施していなかっただけでなく、過重労働の運転手がいたことを示す資料も出てきている。国交省幹部も「かなりひどい状態」「ここまでひどいのはない」と絶句した。
下限下回る額で受注 半数は業界団体未加入
説明内容も二転三転した。
高橋社長は16日の会見で、ツアーを法定の基準額の下限を下回る額で受注していたことを明かし「利益率の高い仕事だなと思って請け負った」と説明した。だが、翌17日午前には同社幹部が「基準以下という認識はなかった。確認を怠っていた」と修正。ところが同日夕方には社長が「昨年12月には基準額を認識していた」と再び説明を変遷させた。
事故が起きたツアーでは、会社側が運転手に対して作成する「運行指示書」にルートの記載がなく、出発地と到着地しか書かれていなかった。
当初、同社幹部は「通常のツアーは、指示書に旅行会社が作った行程表や地図などを添付し、運転手に渡していた。運輸局には指示書に『別表』という記載があればいい、という指導を受けていた」として、書式に問題がないとの認識を繰り返し示していた。
だが、3日間に及んだ国土交通省の特別監査の最終日の17日になって、高橋社長が「運行指示書が正しく作られていなかった」と不備を認めた。
国交省自動車局幹部は「運行指示書の模範様式を埋めていくことで、自然に安全確認に必要な手順を踏むことができるようになっている。制度の理解が不十分なのではないか」と首をかしげる。事故車両は、行程表と異なるルートを走っていたが、運転手から運行管理者への変更連絡もなかった。
バス業界団体の公益社団法人「日本バス協会」によると、全国で約4500あるバス業者のうち、約半分にあたる会員には、新しい通達を周知したり、委員会などで教育の場を設けるなどしている。一方、協会幹部は「残る半分の未加入事業者は“アウトサイダー”と呼ばれ、知らないうちに違法行為をやっていてもおかしくない」と指摘。バス業界の“風評被害”の拡大を恐れる。
今回の事故を受け、国土交通省関東運輸局と警視庁が21日夜に東京都新宿区の路上で行ったツアーバスの街頭監査でも、客を乗せる前のバス計6台のうち5台で運行指示書の記載漏れなど計8件の違反が見つかった。繰り返されるツアーバスの事故。バス業界全体に安全意識が徹底される日はくるのだろうか。
「規制緩和の対象となるべきなのは、参入障壁などの経済規制であって、安全規制は緩和すべきではない。新規参入が増えたことによって、事実上、行政のチェックが甘くなることも考えられたが、今回の件では、それもなかったと思われる。バスの運行会社は、事故2日前に行政処分を受けており、行政チェックはある程度働いていたといえる。」
規制緩和後に以前と比べて行政のチェックが甘くなったのか、変わらないかは知らないが、今回の事故の記事を読んでいると、基本的には監査は甘いのではないかと思う。
筆者の旧大蔵省(現財務省)勤務時代の事は知らないが、現場を知らずにデータや資料だけで判断し記事を書く事は正確さを欠くとの印象を得た。
「国交省としても、この事故を契機に一斉点検をやるが、大切なことは日頃から悪徳業者を処分することである。」
「どのようなことをいわれても、行政の基本として悪徳業者の排除を躊躇(ちゅうちょ)してはいけない。」
一斉点検を行う意味があるのか疑問だ!形だけの点検は行えるだろうが、点検が本来の目的を達成する可能性は低いと思う。点検する職員の人数の問題もあるし、
実際に結果を出せるような点検を行える職員は実際に点検を行う職員よりもかなり少ないはずである。旧大蔵省(現財務省)職員は優秀な人間ばかりなのであろうか?
金融庁を批判する記事もある。
言うのは簡単であるが、自分が知っている分野に関して権限を持ち指示を出すキャリアや幹部が現場を理解して的確な指示を出し、実際に仕事をする現場の職員が
目や手となって効果的に仕事をこなし、現場の問題をフィードバックしているとは思えない。この記事を読んで、筆者に対して多くの人はどのような考えを抱くのだろうか?
長野県軽井沢町でスキーツアーの大型バスが転落し、多数の死者を出す痛ましい事故があった。
事故をめぐって、マスコミの中には、規制緩和の弊害を指摘する声もあるようだ。だが、実際には規制緩和によって貸し切りバスの新規参入は増えたが、事故率が大きく増えたとはいえない。これは国交省の統計でも確認できる。いつもながら、統計データを見ないで断定するマスコミには困ったものだ。
規制緩和の対象となるべきなのは、参入障壁などの経済規制であって、安全規制は緩和すべきではない。新規参入が増えたことによって、事実上、行政のチェックが甘くなることも考えられたが、今回の件では、それもなかったと思われる。バスの運行会社は、事故2日前に行政処分を受けており、行政チェックはある程度働いていたといえる。
もっとも、今回の事故を起こした運転手は、大型バスの運転経験がほとんどなかったとも報じられている。それが事実ならば運行会社の責任は重大であり、事前に営業停止となっていても不思議ではなかった。
スキー客は、ツアー会社の名前を知っていても、バス運行会社がどこなのか知らないケースがほとんどだ。この意味でツアー会社の責任もある。
ツアー会社は旅行業法の監督を受けている。今回の事故のツアー会社が、バス運行会社に対する行政処分を知っていたのかどうかは、大きなポイントである。旅行業法に基づく立ち入り検査で十分に調べてもらいたい。
今回の事故で教訓になるのは、次の点である。
第1に、バス運行会社や旅行業者の法令違反に対して営業停止のような処分も必要だということだ。4000社以上のバス運行会社について、国土交通省で公表している行政処分は大半が文書警告にとどまっている。許可取り消し処分は年に1件あるかどうかである。1万社程度の旅行業者について国交省は、ここ1年半で3件の警告と2件の厳重注意しかネガティブ情報を出していない。
第2に、ツアー会社に対して、どこのバス運行会社を使うのか、旅行者に対して開示する義務を負わせるべきだ。こうしたことは、今やネットの時代であり、簡単に行える。
筆者は旧大蔵省(現財務省)勤務時代に、投資顧問業者の登録制を担当していたが、数百の業者数に対して、年間で10件近くの登録取り消しを行ったこともある。その時、業界団体に天下っていた先輩から「もっと手加減をしてくれ」と懇願されたこともある。
ただし、どのようなことをいわれても、行政の基本として悪徳業者の排除を躊躇(ちゅうちょ)してはいけない。国交省としても、この事故を契機に一斉点検をやるが、大切なことは日頃から悪徳業者を処分することである。
こうした安全規制は、「安全の価格」を旅行者に正々堂々と示すためにも必要である。安全はただではない。 (元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一)
下記は興味深い記事だ!
「バスが事故ったらどうなるの?」結構気になる方も多いのではないでしょうか?
乗用車を運転している感覚で行くと「保険屋さんに電話して…」となるのですが、実は求人情報誌には決して書かれない『闇の部分』があるので今回は知られざる事故処理の実態について書いていこうと思います。
さて、みなさんはバスが事故起こす確立ってどれくらいだと思いますか??
恐らく、バスに関する事故はニュースなどで報道されますから報道数から行くとそこまで多くない気がしますよね。しかし、答は逆にかなりの頻度で発生しているのです。
さすがに人身事故は少ない(発生すればそれこそニュースになります)のですが、「ミラーが標識や電柱に接触した」「ガードレールと車体が接触した」「大型車同士のすれ違いでミラーをぶつけた」と言うような物損事故はかなりの頻度で発生しています。正直、バスなどの大型車は乗用車より面積が広いので接触リスクだけを考えれば不思議ではありません。
運転士の処分はどうなるの?
物損事故と言えども、実車であれば乗客に迷惑が掛かりますし、会社も修理代など負担が発生することから、運転士は何らかの処分を受けるわけですが、どのような処遇が待っているのでしょう?
まず、事故報告書(始末書)の提出です。これはバス業界に限らず、どの業界でも行なわれている当然のことですよね。
次に下車勤務です。下車勤務とは乗務させない勤務のことなのですが、運転士が運転に関わらない業務と言うと「洗車」「車庫の清掃」など雑用しかないのが現実です。結果、反省を促すと言いつつ「見せしめ」のイメージが強くなります。
そして、問題は修理代です。
恐らく、「自動車保険のように保険で対応するから運転士は免責分(自己負担金)だけ支払えばいいのでは?」と思っている方が多いでしょうが現実は甘くありません。
よくネットで「運転士が物損事故を起こして全額自腹で払った」と言うような記事を見かけたことがあるかもしれませんが、これは“事実”です。
もちろん、事業者ごとに「10万円までは運転士負担、それ以上は保険や会社経費で適応」など事故発生時の対応を設けているのが通常ですから、すべてのケースに当てはまるわけではありません。
しかし、運転士の金銭的負担がゼロというのは考えにくいのがこの業界で大手も例外ではありません。
特に大手の場合、営業所ごとの事故件数が管理者の評価対象になることから、運転士に高額な修理代を請求して事故件数として計上しないと言うケースもあるそうです。(同業他社、運転士談)
もちろん、事故を起こした運転士に反省を求めるため「本人に修理代を負担させるのは当然」との意見を持たれる方もいるでしょう。
しかし、「翌日までの休息時間は法定で定められた8時間ギリギリの繰り返し」「給料水準は全産業の平均以下」「扉挟みや車内事故が起きれば乗客に過失があっても運転士が処分される」「周囲の交通から保護されてはいない」など、過酷な労働環境や理不尽とも思えるリスクの中で運転士はバスを走らせているわけです。
このような状況に万一の事故に対する不安要素が加われば、離職者が多くなるのも理解できる話で、「バス運転士が不足している!」と騒がれているのは言わば”当然のこと”と言えるでしょう。
実際、家庭が支えで仕事をしている私ですが、転職して3年目、将来に不安を感じながら乗務しているのが本音です。
会社は最終的にどうなるのだろう?
壱番屋(愛知県一宮市)から廃棄委託を受けた冷凍ビーフカツを横流ししていた産業廃棄物処理会社「ダイコー」(同県稲沢市)の工場では、悪臭騒動が繰り返し起きていた。
愛知県や稲沢市には周辺住民から苦情が寄せられ、県は廃棄物処理法に基づく立ち入り検査を2014年度に複数回にわたり行っていた。
ダイコーは1996年6~8月(当時の社名はダイキン)、県から産業廃棄物の収集運搬業と中間処理業の許可を取得。廃棄処分となった食品などをリサイクルして、豚の飼料や堆肥を製造していた。稲沢市には11~15年度に、処理工場から悪臭が発生していると9件の苦情が寄せられ、同市内の別の場所にある配送センターについても14件の苦情があった。
県にも悪臭や排水漏れといった苦情が伝えられ、尾張県民事務所は同社に5回にわたり立ち入り、改善指導を行った。
県への届け出によると、ダイコーの施設は動植物性残さを1日に約125トン処理できる。同社は壱番屋から廃棄委託を受けたビーフカツ約4万枚は全て処分したと県に報告していたが、実際は約7000枚を堆肥化しただけだった。県は同社の全許可を取り消す行政処分を視野に、事実関係を調査している。
裕福や家庭の留学生や国が援助する形の留学生以外、発展途上国の留学生が日本で日本語を勉強するには金銭的に無理なケースが多いと思う。
採算が合うだけの留学生を集めようとすると逮捕された経営者と理事長のような違法行為に行き着くのだろう。
15人が死亡したバス事故の運営会社や旅行代理店が特別ではなく、違法行為を行っている会社は存在する。組織的に違法行為を管理してたのであれば、
違法行為が出来なくなった時点で、この日本語学校は終わりであろう。
全国の国立大学病院が昨年初めて公表した民間企業などからの資金提供の状況(2014年度分)を毎日新聞が集計したところ、総額は約692億円に上り、このうち提供元が明示されているのは24%にとどまることが分かった。提供元が分かるのは主要な製薬企業だけで、医療機器メーカーや研究資金を助成している財団法人などは全て「その他」の扱いで名前が伏せられている。そうした企業や団体の中には、自主的に支出先と金額を公開しているケースもあり、大学病院側の情報開示に対する消極姿勢が目立つ。
開示したのは医学部を持つ国立42大学の45病院。降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験疑惑を巡って研究者と企業との不透明な資金関係が問題になったことなどを受け、国立大病院長会議が14年6月に定めたガイドラインに沿って、ホームページなどで公表した。公立大や私立大の病院は対象外。
受領した資金は、契約に基づく受託研究などの研究開発費▽研究振興などを目的とした奨学寄付金▽研究者個人に支払う講師謝金や原稿執筆料、コンサルティング料▽接遇費−−などに分類され、総額は692億7700万円。このうち76%の525億5000万円は、提供元の名前が出ていなかった。
大学病院側が名前を開示したのは、業界団体「日本製薬工業協会(製薬協)」の加盟社からの提供分のみ。製薬協は病院側より早い12年度分から、奨学寄付金や原稿料などを渡した研究室や個人名を公表するガイドラインを設けており、受け取る側もそれに対応した形だ。一方、製薬協非加盟の製薬企業や医療機器メーカーの一部も同水準の情報開示を始めているが、病院側は公開していない。
医療や生命科学の研究では近年、公正さを担保するために、利害関係のある企業との金銭面などの関連の有無を透明化する動きが強まっている。バルサルタン問題が出てからはさらに加速し、政府は資金提供の情報開示を製薬企業に義務付ける新法の今国会提出を検討している。
国立大病院長会議代表の山本修一・千葉大病院長は「資金提供に関する情報開示は社会の要請だと認識している。今は公表に同意した製薬企業に限っているが、将来的には開示の範囲を広げられるよう検討したい」と話す。【河内敏康】
解説 率先し情報開示を
国立大病院が民間から受け取った資金のうち、主要な製薬企業以外の提供元を非開示としたのは「提供先を公開していない企業・団体から開示の同意を一つずつ取り付けるのは、手間を考えると現状では難しい」(山本修一・千葉大病院長)からだという。
だが、医療機器メーカーの業界団体「日本医療機器産業連合会」は製薬企業の団体と同様のルールを作り、全てではないものの、2014年度には約250社が公開を始めている。公募で選んだ研究者への助成額を公表している財団もある。「同意取り付けが困難」との主張は説得力を欠く。
バルサルタン事件などを受け、研究者と企業との関係に厳しい目が向けられている現状を考えれば、そもそも病院側が率先して開示すべきだが、それでも「提供元の同意が必要」というなら、全ての資金提供を目的が明確な契約の形にしたり、公開を前提としなければ受けないという条件にしたりすれば透明性は高まる。信頼回復に向け、公立・私立大病院も含めた意識改革が望まれる。【河内敏康】
【ことば】バルサルタン臨床試験疑惑
ノバルティスファーマの主力商品だった降圧剤バルサルタンに脳卒中予防などの効果があるかを確かめるため5大学が実施した臨床試験に、ノ社の社員が関わり、ノ社が奨学寄付金を出していたことが発覚。京都府立医大などでは試験データが操作されていたことも判明し、医学界と製薬業界を揺るがすスキャンダルに発展した。データを操作したとされた元社員は14年7月、薬事法違反(虚偽広告)で起訴され、法人としてのノ社とともに東京地裁で公判中。
裕福や家庭の留学生や国が援助する形の留学生以外、発展途上国の留学生が日本で日本語を勉強するには金銭的に無理なケースが多いと思う。
採算が合うだけの留学生を集めようとすると逮捕された経営者と理事長のような違法行為に行き着くのだろう。
15人が死亡したバス事故の運営会社や旅行代理店が特別ではなく、違法行為を行っている会社は存在する。組織的に違法行為を管理してたのであれば、
違法行為が出来なくなった時点で、この日本語学校は終わりであろう。
外国人留学生に法で定められた制限時間(週28時間)を超えて働かせた疑いが強まり、福岡県警は23日、日本語学校「JAPAN国際教育学院」(福岡県直方市)を実質的に経営する50代の男と理事長の有村ひとみ容疑者(52)らを出入国管理法違反(不法就労助長)容疑で逮捕した。男の妻も逮捕する方針。捜査関係者によると、男らは個々の就労先では労働時間を制限時間以内に抑えつつ、複数の場所で働かせることで違法な長時間労働を繰り返しており、県警は巧妙な手口の解明を進める。【吉住遊、菅野蘭】
県警は容疑を裏付けるため23日午前から、学校を家宅捜索した。
捜査関係者によると、男らは2015年4〜11月ごろ、学校に通うベトナム人留学生4人に複数のアルバイト先を紹介し、週28時間を超えて就労させた疑いが持たれている。県警は留学生4人も同法違反(資格外活動)容疑で逮捕した。
留学生の就労は原則として学業に専念させるため禁止されているが、学費などをまかなう目的のアルバイトは例外的に認められている。入管当局によると、各地の入国管理局事務所で在留許可証を提示し、申請書を出して許可を得れば、風俗店などを除き週28時間まで働くことができる。
捜査関係者によると、JAPAN国際教育学院の留学生もこうした手続きを経て許可を取り、地元の食品加工工場などで働いていた。個々の就労先でのアルバイトの時間は週28時間以内だが、複数のアルバイトを掛け持ちし、総労働時間が上限を超えているという。
一方、学校側は、誰がどの会社で何時間働き、どれだけの報酬を得たか、一覧表を作成して管理していた。県警はこうした情報から学校側が違法性を認識していたとみている。
学校側は留学生に就労先を次々とあっせんし、アルバイト代を得た留学生から授業料(月約5万円)や寮費などを受領していた。県警は経営の安定化を図るために考案した巧妙な仕組みとみて男らを追及する。
学校は10年4月に開校。現在はベトナム人やネパール人ら200人弱が在籍している。ホームページによると、1年半〜2年の3コースがあり、日本の大学や専門学校などへの進学を目指す留学生を指導している。
留学生の不法就労を巡っては大阪府警が15年12月、総合免税店「ラオックス」(東京都港区)社長らを同法違反(不法就労助長)容疑などで書類送検した事件がある。1990年代には、日本語学校の摘発も相次いだ。
この手の会社は生命力が強いので生き残るかもしれないが、当分は冬眠か休眠だろう。
「カレーハウスCoCo壱番屋」が廃棄した冷凍カツの横流し事件で、岐阜県羽島市の食品関連会社「みのりフーズ」が、産廃業者「ダイコー」(愛知県稲沢市)から仕入れたカツなどの食材を、羽島市の弁当店に1年半前から30回以上、転売していたことが岐阜県の調査で22日分かった。伝票類で裏付けられたという。みのりの実質的経営者の男性(78)はこれまでの調査に、社内で見つかった食材は「全てダイコーから仕入れた」と回答しており、県は転売品目の調査を進める。
また県は同日、新たにコンビニ系のヨーグルト1品目がダイコーに廃棄を委託された食材だったと発表した。横流しは計22品目となった。
一方、ダイコーの代理人弁護士は、同社会長が「乳製品や冷凍食品も、みのりに引き渡した可能性がある」と説明していることを明らかにした。【道永竜命、山口朋辰、金寿英】
「 監査官は『事故を人ごとだと思っているのか、気が緩んでいるとしか思えない。安全への意識を高めてほしい』と話している。」
自爆発言だな!でたらめや違法行為に慣れているから事故が起きても何も変わらない。変わらないほどでたらめな運行が常態化していたと考えたほうが良い。
問題のあるバス運行会社を監査してたのは誰?国土交通省職員の監査官。監査を実施していて問題に気付いていなかったのであれば大問題。
監査が形骸化していたのか、監査官の平均的な能力が低すぎたという事。15人もの死亡事故が起きるまで対応を放置していた国土交通省に部分的に責任は
あると思う。残念だが多くの被害者が出るまで対応が放置されるのは普通の事となっている。運命とか、運で人生が影響されるのなら、
形が変わるだけで本人の努力や判断で変えられる部分と運命と変えられない部分の運命が存在するのかもしれない。
一度、業界で不正や違反を行っても大丈夫との認識が広がり、非常識が常識になると元に戻すのは難しい。不正や違反が普通になっているからこれらを見つけ
指摘するまで直さない。指摘しても一時的な取締りが終わればチェックされないとの認識が広がれば、直す事もない。現状は知らないが、バス業界が
このような状態になっていれば、当分は事故が起きるかは運次第だろう。
廃棄された冷凍ビーフカツの不正転売事件で、産業廃棄物処理会社「ダイコー」(愛知県稲沢市)の男性会長(75)が、カレーチェーン「CoCo壱番屋」を展開する壱番屋(同県一宮市)から処分を委託された廃棄カツについて、製麺業「みのりフーズ」(岐阜県羽島市)に「80万円で売った」とする報告書を愛知県に提出したことが22日、ダイコー関係者への取材で分かった。
乳製品や冷凍食品など他の廃棄品の横流しも認めているという。
県の調査によると、ダイコーは昨年10月、処分を委託されたカツ約4万枚のうち約7000枚を堆肥にするなどし、残りを転売したとされる。会長は代理人の弁護士に「処理費用をかけずに利益が得られるので、魔が差した。違法と分かっていた」と説明。東日本大震災後の風評被害で売れ残ったじゃこの横流しでは「まだ食べられると思って売った」と話したという。
「 バス会社がツアー会社から足元を見られてしまう背景には、規制緩和による受注競争の激化があります。」
規制緩和が悪いと多くのメディアが批判しています。規制緩和が悪いとは思いません。ただ、規制緩和により一時的に競争が加速し、新規参入業者により監督するのが難しくなったと思います。競争が過熱すれば淘汰の力が働いて儲けられない業者や違法行為を行う業者に勝てない業者が市場から撤退するまで赤字の業者が増える。新規参入業者の中にはこれまでの業界の常識に従わない、又は、成長するためなら違法行為をためらわない業者もいるでしょう。規制緩和を決めた行政がこれらの業者の対応できない状況であれば、問題は発生するだろう。単純に考えても参入業者の数に比例して、又は、承認作業が甘ければ、もっと悪い数値で問題が発生するだろう。行政が適切に対応すれば問題は規制緩和を行っても極端に増えないだろう。環境を変えれば、結果も変わる。仕方がないこと。環境が良い方向へ進めば、デメリットよりもメリットの効果が出るだろう。
「国土交通省は今回の事故を受けて、全国の貸切バスや過去に処分を受けた事業者を対象に、緊急の監査を始めました。しかし、およそ4500社に上るすべての事業者を常にチェックするのは難しく、安全管理をどう徹底していくのかも課題です。」
バスの監査ではないが監査の仕事をした事がある。問題のある業者は脅迫までやります。問題を指摘されなくなると違法行為が継続できるので利益が上がるのは想像できるでしょう。夜の一人歩きは気を付けろとか、家族がどうなっても良いのかと言われれば、はったりかもしれませんがそこまでしてやる価値があるのかと考えてしまいます。張ったりでない場合、事後でしか確認する方法はありません。
「遺族のことばを私たち一人一人が胸に刻み、二度とこのような事故が起きることがないよう、社会全体で行動を起こすときが来ていると思います。」
違法行為を行う運営会社、それを利用する旅行業者、それらのツアーを安さから選ぶお客、全て社会の一員です。社会全体で行動を起こすのは無理。
関係のない人達は、毎日起こる事件や事故の1つとしか認識しません。この事を理解した上で対応策を考えないと全く違う事故が違う場所で起きるだけです。
綺麗ごとを繰り返すだけでは、被害者や被害者の家族になるまで問題を理解する機会はないでしょう。被害者や被害者の家族となってもいろいろな事を理解する
だけの能力がなければ苦しみ、悲しみ、怒り、失望など経験するだけで時間が過ぎるだけと思います。普段から問題を見つけ、批判する事を学ぶべきだと思います。
多くの人々が批判すれば行政も無視出来ないでしょう。
多くの犠牲者が出ると人と命とか綺麗ごとを多くのメディアが繰り返すが、違法行為を行う会社がかなり悪質な場合、どの程度までの介入を想定しているのか?
警察の介入を想定しているのか?警察は逮捕などの権限を行使できるが、力であって、知性は期待できない。警察官の不祥事を考えてたら想像する事は難しくない。
脅迫の方法と取らなくても、賄賂、接待、贈り物、その他の方法もある。公務員が逮捕されるケースを考えれば、相手の公務員次第では有効な方法と言う事です。
今月15日未明、長野県軽井沢町の国道で、スキーツアーのバスが道路下に転落。乗客と乗員、合わせて15人が死亡しました。 過去30年間で最も多くの犠牲者を出したバス事故から、22日で1週間。なぜバス事故は繰り返されるのか、そして事故の原因と背景に何があるのか、社会部の久米兵衛記者が解説します。 夜行スキーバスの悲劇 事故は、18歳から38歳までの乗客39人を乗せて長野県の斑尾高原に向かっていたスキーツアーのバスで起きました。警察などによりますと、バスは前夜に東京・原宿を出発し、午前2時ごろ群馬県と長野県の県境を走る国道18号の「碓氷バイパス」を走行中、反対車線を越えてガードレールを突き破り、そのままおよそ3メートル下の道路脇に転落しました。

バスは、天井部分から激しく樹木に衝突して大きく破損、多くの乗客は就寝中でとっさに対応できなかったとみられ、頭や全身を強く打ったほか、シートベルトを着用していなかったみられる複数の乗客も車外に投げ出されました。
この事故で、これまでに乗客13人と運転手2人が死亡。乗客26人全員も重軽傷を負いました。
奪われた若い命
今回の事故で犠牲になった乗客は、全員が大学生でした。この時期、大学入試センター試験の準備で休みになった大学も少なくなく、亡くなった学生たちの多くは休みを利用してスキーツアーに参加し、事故に巻き込まれたとみられています。 就職などを控え、夢や期待に胸を膨らませていたさなかに、突然奪われた13人の若い命。家族や友人たちは、かけがえのない人を失った悲しみに打ちひしがれています。
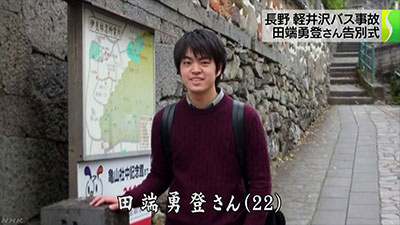
亡くなった早稲田大学国際教養学部4年生の田端勇登さん(22)は、イギリスの大学に留学して国際関係などを学び、この春から希望していた政府系の金融機関で働くことが決まっていました。母親の直美さんは、勇登さんについて「本当に努力家で、苦手だった英語も一生懸命勉強し、奨学金をもらってイギリスに留学してからは1日3時間の睡眠で頑張っていました。『日本のため、世界のために公共性の高い仕事がしたい』というのが口癖で、就職が決まったときも本当にうれしそうで、ようやくこれからというところでした。親思いで、高校の卒業式のときは涙を浮かべながら、『ここまで来られたのはお母さんのおかげです。ありがとう』と言ってくれたのが忘れられません。息が出来ないほど悲しくて苦しくて涙が止まりません」と胸の内を語ってくれました。

また、早稲田大学国際教養学部4年生の阿部真理絵さん(22)も、将来、交通インフラの分野で日本の技術を世界に広めたいという夢に向け、大手重工メーカーへの就職を目前にしていました。父親の知和さんは、「本当に明るく、誰とでも仲よくできる自慢の娘でした。1月15日は、私たち家族やほかの遺族にとっては命日になりますが、旅行業者や報道の関係者などは、このような事故が起こらないように毎年、何らかの発信、行動をなすようにしていただけければ、事故の犠牲者が皆さんの心の中に生き続け、安全に対する心のたがが緩むことを防げる一助になるのではないかと思っております」と話しています。
なぜ事故は起きたのか?
13人もの若い命を奪った事故は、なぜ起きたのか。
現場はS字カーブが連続する峠道の下り坂でした。バスは事故の直前、かなりのスピードが出ていたことが分かってきました。警察が、速度を自動的に記録する「運行記録計」を調べたところ、バスのスピードは事故当時、法定速度の時速50キロを大きく上回る80キロ前後に達していたことが分かりました。さらに、事故現場から数百メートル手前の下り坂の直線ではバスは時速100キロ前後で走行していたとみられることが、警察への取材で分かりました。
現場のおよそ250メートル手前に設置されていた国土交通省の監視カメラの映像にも、バスが下り坂のカーブを曲がる際、センターラインをはみ出し、車体が外側に傾いた状態で走る様子が映っていました。
ブレーキは効いていたのか
警察が事故のあとバスを検証したところ、どこにもギヤがかかっていないニュートラルの状態になっていたことが分かりました。

事故の衝撃やその後の車体の移動などで、ニュートラルに切り替わった可能性もあります。しかし、仮に走行中にニュートラルになっていたら、エンジンブレーキや補助ブレーキは効きません。減速するには、足元にあるフットブレーキを使うしかありません。事故の直前を捉えた監視カメラの映像で、ブレーキランプが点灯しているように見えることから、運転手はフットブレーキを踏み込んで速度を落とそうとしていた可能性があります。
しかし、映像から減速している様子は確認できないことから、現地で解析を行った日本大学生産工学部の景山一郎教授は、フットブレーキが十分に効いていなかった可能性を指摘しています。景山教授は「仮に走行中にギヤがニュートラルになっていたとしたら、バスは重量があるので、下り坂でブレーキが効かないまま速度がどんどん上がってしまった可能性がある」と分析しています。
警察の検証では今のところブレーキに異常は確認されず、死亡した運転手にも心臓発作などの症状やアルコールなどの摂取は確認されていないということです。警察は運転手がギヤなどの操作を誤って十分に減速できなかったか、何らかのトラブルがあって制御を失った疑いがあるとみています。今後は事故の直前にギヤやブレーキがどういう状態になっていたのかが、原因究明に向けた大きなポイントになります。
ずさんな安全管理も
一方で、バス会社のずさんな安全管理の実態も分かってきました。
バスの出発前には担当者が点呼を行って、運転手の健康状態や運行ルートなどを確認することが法令で義務づけられています。しかし、今回バスを運行した東京・羽村市の「イーエスピー」では、点呼を行うはずだった社長が予定の時間に遅れ、点呼が行われないまま運転手が営業所を出発していました。
ほかにも、この会社では運行状況を記録する機器に記録用紙を入れないまま運行させたり、決められた時間を超えて運転手を働かせたりしていたほか、死亡した運転手の健康状態などを記した台帳を作成していなかったりするなど、運行に関わる多くの法令違反が見つかりました。
技量不足の運転手
乗客の命を預かる運転手の経験が不足していたことも明らかになりました。
事故当時、バスを運転していた土屋廣運転手(65)は、先月、イーエスピーに採用されたばかりで、会社などによりますと、以前の勤務先では比較的小型のバスの運転が中心でした。面接でも「大型バスの運転は苦手だ」と打ち明けていましたが、会社側は「スキーツアーを任せたい」と説明し、契約社員として採用したということです。その後、土屋運転手に対して2回の研修を行ったうえで、「大丈夫だ」と判断して業務を任せるようになり、今回は4回目の業務でした。

土屋運転手について、事故の数日前にも一緒にバスに乗務したという同僚の男性は、「大型バスもある程度は運転できたが、ハンドルさばきに疑問があったり、進路変更が少し遅れたりすることがあった。吹雪で路面が凍っていたり、夜間に狭い峠道を走ったりするときは運転させなかった」と証言しています。
不足する大型バスの運転手
なぜ、会社は経験不足の運転手を採用したのか。背景には、大型バスの運転手が不足していることがあります。
平成24年に群馬県藤岡市の関越自動車道で乗客7人が死亡した事故を受けて、夜間、距離が400キロを超える場合は、原則、交代の運転手と2人で乗務することが義務づけられました。さらに、最近は外国人観光客が大幅に増え、ツアーバスの需要が増したことで、大型バスの運転手の確保は一層難しくなっています。イーエスピーの山本崇人営業部長は、大型バスの運転に不慣れな土屋運転手を採用した背景に人手不足があったと認めたうえで、「大型バスの運転も大丈夫だという現場の担当者の判断に任せてしまった。会社のミスで申し訳ない」と話しています。
激化する受注競争
ツアーバスの需要が増加する一方、バス会社の経営は、必ずしも楽にはなっていません。
イーエスピーは、今回、ツアーを企画した東京・渋谷区のツアー会社「キースツアー」から、国が適正と定めた価格の最低基準のおよそ26万円を大幅に下回る19万円で受注していたことが明らかになりました。イーエスピーによりますと、昨シーズンは、さらに低い13万円から14万円で受注していたということで、高橋美作社長は「昨シーズンより金額が上がったので、よしとしてしまった」と釈明しています。
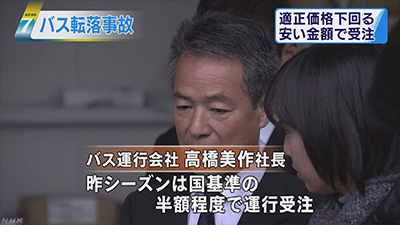
このように、バス会社がツアー会社から足元を見られてしまう背景には、規制緩和による受注競争の激化があります。スキーツアーなどに利用される貸切バスは、16年前に免許制から許可制に規制が緩和されました。これに伴い、多くの業者が参入し、貸切バスの事業者は規制緩和の前の2倍近くのおよそ4500社にまで増加しています。この結果、受注競争に勝とうと、国が定めた適正な価格の範囲を不法に下回る安い料金で受注する事業者が相次ぐようになっているのです。
受注競争が激しさを増すことで受注価格の過度なたたき合いになれば、バス会社は車両の整備や更新、運転手の健康管理などの費用を惜しみ、安全管理に支障が出るおそれもあります。交通政策に詳しい早稲田大学の戸崎肇教授は今回の事故について、「バス業界が抱える課題が一気に噴出した」と指摘しています。そのうえで、「規制緩和をする際には、きちんとルールを守って競争しなければならないが、生き残るため現実にはルールを守らないバス会社は多い。その結果、安全に対するコストまで削減して仕事を取ろうとする事業者が増え、そこが事故につながってくる大きな背景になっている」と安い運賃での受注を改善しなければ安全は確保できないと指摘します。そして、今後の対策としては「現在は強い立場にある旅行業界との関係を見直し、適正な運賃にしていくことが大切だ。ルール違反の会社は市場から追い出すなど公正な競争をさせなければいけない。われわれ消費者も安いツアーはありがたいが、『こんな価格で本当にできるのだろうか』と疑問を持つことも必要ではないか」と話しています。
“社会のひずみ” 教訓を行動に
国土交通省は今回の事故を受けて、全国の貸切バスや過去に処分を受けた事業者を対象に、緊急の監査を始めました。しかし、およそ4500社に上るすべての事業者を常にチェックするのは難しく、安全管理をどう徹底していくのかも課題です。
今回の事故のあとも、東京・大田区や兵庫県淡路市などで大型バスの事故やトラブルが相次いでいます。今回の事故で亡くなった阿部真理絵さんの父親の知和さんは、「今回の事故については憤りを禁じえませんが、報道を見ていると、今の日本が抱える偏った労働力の不足や過度な利益の追求、安全の軽視など、社会問題によって生じた、ひずみによって発生したように思えてなりません」と話しています。
遺族のことばを私たち一人一人が胸に刻み、二度とこのような事故が起きることがないよう、社会全体で行動を起こすときが来ていると思います。
結局はバランス。
「この手数料について国交省は、『商慣習としてやりとりされているもののため、規制はできない』としている。」
違法なバス運行会社を取締り、運営できない処分を出せば、バス運行会社は減るであろう。その状態で旅行会社の需要が減っていなければ、バスの取り合いに
なるから料金を上げてもバスを手配する事となる。そのような状態になれば、条件の良い旅行会社をバス運行会社は選ぶから、手数料も下げざるを得なくなるだろう。
バランスで状況は変化する。行政である国土交通省は適切な監査を行い問題のあるバス会社の運営を止める事をしっかりとすれば良い。影響を受けて廃業や閉鎖する
会社もあるだろう。安全と適切なバランスを優先するのであれば仕方のないことである。
軽井沢でバスが転落した事故に関連して、旅行会社がバス会社に対し法外な手数料を要求するケースがあることが分かった。
国土交通省の特別監査などの結果、転落事故を起こしたバスを運行していた「イーエスピー」は、旅行会社「キースツアー」から国の基準を下回る違法に安い料金で運行を受注していたことが分かっている。
旅行会社からバス会社に支払われる料金を巡っては、安すぎると安全な運行が確保できないとして、2014年に国が料金の基準を引き上げた。しかし、バスの業界団体「日本バス協会」によると、料金基準が引き上げられた後、旅行会社がバス会社に対し20%から40%の法外な手数料を要求するケースが出てきたという。
日本バス協会は「バス会社は旅行会社よりも弱い立場だ」とした上で、「安全性を担保するために、料金基準が引き上げられたにもかかわらず、旅行会社が高い手数料を吸い上げることで、バス会社に入る料金は実質的に上がっておらず、制度自体が骨抜きになってしまっている」と指摘している。
この手数料について国交省は、「商慣習としてやりとりされているもののため、規制はできない」としている。
「 監査官は『事故を人ごとだと思っているのか、気が緩んでいるとしか思えない。安全への意識を高めてほしい』と話している。」
自爆発言だな!でたらめや違法行為に慣れているから事故が起きても何も変わらない。変わらないほどでたらめな運行が常態化していたと考えたほうが良い。
問題のあるバス運行会社を監査してたのは誰?国土交通省職員の監査官。監査を実施していて問題に気付いていなかったのであれば大問題。
監査が形骸化していたのか、監査官の平均的な能力が低すぎたという事。15人もの死亡事故が起きるまで対応を放置していた国土交通省に部分的に責任は
あると思う。残念だが多くの被害者が出るまで対応が放置されるのは普通の事となっている。運命とか、運で人生が影響されるのなら、
形が変わるだけで本人の努力や判断で変えられる部分と運命と変えられない部分の運命が存在するのかもしれない。
一度、業界で不正や違反を行っても大丈夫との認識が広がり、非常識が常識になると元に戻すのは難しい。不正や違反が普通になっているからこれらを見つけ
指摘するまで直さない。指摘しても一時的な取締りが終わればチェックされないとの認識が広がれば、直す事もない。現状は知らないが、バス業界が
このような状態になっていれば、当分は事故が起きるかは運次第だろう。
長野・軽井沢町で15人が死亡したバス転落事故を受け、国土交通省が、出発前のツアーバスを緊急監査した結果、5台で安全対策に不備が見つかった。
国交省と警視庁は21日夜、東京・新宿で、スキーツアーなどに出発する前の貸し切りバスに対し、監査官が立ち入って安全対策を確認する、抜き打ちの緊急監査を実施した。
その結果、6台のうち5台で、運転者の休憩時間と場所が記載されていない、運行指示書の不備などが見つかった。
監査官は「事故を人ごとだと思っているのか、気が緩んでいるとしか思えない。安全への意識を高めてほしい」と話している。
「今回の事故では、バス運行会社で多数の法令違反が発覚しているが、規制緩和で増加する事業者に対し、監査体制が追いついていないのが実情。実効性を高めるために民間の力を借りる必要性があると判断した。」
バス事業者の監査の一部を民間委託するのは良いが、委託する会社に対する監査や処分を明確にしないと効果は期待できない事を理解しておくべき。
実際に民間と会社と言っても、ある程度、モラルのある会社やモラルのある管理者が存在する会社であれば機能するが、残念ながら、お金のためだけで仕事を
取って、パフォーマンスは処分されるか、認定を取り消されるか、チェックされるのかを見極めながら対応する会社が存在する。
耐震補強工事に使われた部品の溶接部分の検査を検査会社が故意に見逃した例や
構造計算書偽造 民間の指定確認検査機関のずさんな検査の例
を考えると民間に委託しても、仕事やお金儲けを優先して適切な検査を怠るケースがある事を認識して民間委託と不正が起きることを想定した罰則を含む委託するシステムを考えなければならない。悪質な業者が存在する事も想定して警察との協力体制、又は、警察に協力を求める手順なども考えておくべきだと思う。性善説を
基本にする事はやめたほうがよい。
旅行会社に対する法や規則も改善する事を検討するべきであろう。仕事を発注する旅行業者に問題があれば、バス事業者を適切に管理するだけでは問題は解決できない。
結局、発注者である旅行業者の圧力に屈して、一部のバス事業者からはじまって法令順守の秩序は乱れるであろう。
長野県軽井沢町で15人が死亡したスキーツアーバス転落事故を受け、国土交通省がバス事業者への監査を強化するため、監査業務の一部を民間委託する方向で検討に入ったことがわかった。
今回の事故では、バス運行会社で多数の法令違反が発覚しているが、規制緩和で増加する事業者に対し、監査体制が追いついていないのが実情。実効性を高めるために民間の力を借りる必要性があると判断した。
同省は、バス運行会社「イーエスピー」(東京都羽村市)に対し、事故の2日前、運転手の健康管理に問題があったなどとして道路運送法に基づき行政処分したが、事故後の特別監査で、これ以外にも多数の法令違反が見つかった。
貸し切りバス事業者は2000年からの規制緩和で、2倍近い約4500業者にまで膨らんだ。監査員は360人程度で、1年間に抜き打ち監査を受ける事業者数は1~2割にとどまる。
「登録再生利用事業者制度では、食品廃棄物を適正に肥料や飼料としてリサイクルする廃棄物処理業者について、環境、農林水産両省などが実績や経営基盤を審査。登録されると「優良業者」と判断され、食品関連業者から委託を受けやすくなるという。」
環境省の「優良業者」の認定及び登録するシステムに問題があったという事。一度、認定し、登録すると定期的な検証作業がない、又は、ずさんである事を意味している。
もし、認定の定期的な検証が適切に行われているとすれば、このような大胆で大規模な廃棄食品の横流しは起きなかった。行政が適切な対応を取らないと盲点を突かれる
教訓とするべきだろう。
廃棄された冷凍ビーフカツの不正転売事件で、産業廃棄物処理会社「ダイコー」(愛知県稲沢市)が、食品リサイクル法に基づいて優良業者を認定する「登録再生利用事業者」の立場を悪用し、取引先の食品関連業者らを信用させて横流しを繰り返していた疑いが強いことが、環境省などへの取材で分かった。
同省は、同社の登録取り消しを検討するとともに、登録されている全181業者に立ち入り検査を行う方針だ。
登録再生利用事業者制度では、食品廃棄物を適正に肥料や飼料としてリサイクルする廃棄物処理業者について、環境、農林水産両省などが実績や経営基盤を審査。登録されると「優良業者」と判断され、食品関連業者から委託を受けやすくなるという。
早く最終的な報告を出してほしい。坂道でニュートラルにすることは普通のでもいない。直線であれば燃料費を抑えるためにニュートラルにすると傾斜次第であるが、加速する。ドライブに入れている時よりも加速する。しかし、曲がりくねった山道でやるメリットはないと思う。加速するからブレーキに負担がかかる。距離と傾斜次第だが麓までブレーキが持たない可能性もある。エンジンブレーキを使おうとして一旦ニュートラルにしたらどのギヤにも入らなくなった以外は考えられない。ギアチェンジに不慣れな場合や、ギアに問題があればスムーズにシフトできない。推測はどこまでも推測。早く最終的な結果を公表してほしい。
15人が死亡した長野県軽井沢町のスキーツアーバス転落事故で、バスは事故直前、ギアがニュートラルの状態か4速以上の高速ギアに入っていた可能性があることが、捜査関係者などへの取材でわかった。
バスの製造会社も同様の指摘をしている。県警は、バスはフットブレーキが利かず、エンジンブレーキも利かせていない状態で制御不能に陥った可能性もあるとみて事故当時のバスの状態を調べる。
製造会社によると、事故を起こしたバスは後輪駆動で6速のマニュアル車。ブレーキはドラム式で、下り坂を走行中にフットブレーキを使いすぎると、利きが低下する「フェード現象」や「べーパーロック現象」が起きる可能性がある。このため、下り坂ではギアを3速以下に落とし、エンジン回転の抵抗で速度を落とす「エンジンブレーキ」を利かせて走るのが普通だ。
インターネットを使えば簡単に顧客を探せるメリットがあるが、同時に多くの人々に見られる。注目を受けすぎた結果であろう。
注目を受けない範囲で活動していれば今回のような処分にはならなかったかもしれない。自業自得である部分があると思う。
愛知県内のベテラン社会保険労務士の男性がブログに「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章を載せた問題で、厚生労働省は、この社労士を懲戒処分する方針を固めた。ブログの内容には批判が相次いでおり、厚労省に社労士を処分するよう求める声が出ていた。
社労士は企業からの労務相談にのる、労働や社会保険の専門家。社労士法は、信用を失墜する行為を禁じており、重大な非行などがあった場合には業務停止などの懲戒処分にできると定めている。所管する厚労省は、2月に男性から意見を聞いた上で最終的な処分を決める方針だ。
問題の文章は昨年11月に掲載。「すご腕社労士の首切りブログ」と題し、社員を「うつ病にして会社から追放したい」という質問に答える形で、「失敗や他人へ迷惑をかけたと思っていること」などを社員に繰り返しノートに書かせるよう勧める内容だった。
これに対しネットなどで批判が殺到。文章は削除されたが、愛知県社労士会は社労士の会員資格を停止した。厚労省にも、日本労働弁護団などから「若者使い捨てが疑われる企業に違法行為を教唆する極めて悪質なもの」として対応を求める声が出ていた。(斉藤太郎、北川慧一)
「労基法に違反して残業させた場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科す罰則規定がある。」
処分される確立が低く、見つかっても30万円以下の罰金であれば、体裁を気にしない会社であれば違反のほうがお得!これが現実。
まあ、違反する会社でしか就職できない人達にも部分的に責任はあるかもしれない。行政が適切に介入しなければこのバランスは変わらない。
間接的な事まで言えば、学校で就職や人生計画について教えたり、単なる勉強ではなくどのように知識や資格が収入に影響していくのか
教えれば将来の問題の発生を軽減できるかもしれない。子供が夢を持てないと反論する人もいるかもしれないが、大人になって心の準備もなく
夢もなく流されるだけの人生を送る人達がいる。残酷でも予備的な知識を教え、嫌な事でも今やろうと思う子供を増やしたほうが良いのか、
子供の頃は、自由にさせるほうが良いのか、人によって意見が違う。どのような選択を取ろうとも、結果は絶対についてくる。
最後に規則を守り採算性を出すためには能力や経験が基準以下の人達は採用されないでこともある。働いて能力を向上し、経験を得る
機会がなければ運が悪いとずっと無職の人もいるだろう。この問題の解決策は難しい。資本主義である以上、双方が妥協できる点に到達できなければ
その先はない。立ち位置が違えば考えや判断も異なる。バランスを取る事はとても難しい。
「イーエスピー」 労働基準法違反容疑などで
長野県軽井沢町のスキーツアーバス転落事故で、東京労働局青梅労働基準監督署は21日、バスを運行した「イーエスピー」(東京都羽村市)を労働基準法違反などの疑いで捜索した。
イ社を巡っては、従業員に残業させる際に労基法に基づいて従業員代表らと締結しなければならない労使協定を締結していなかったことが東京労働局などの調べで判明している。協定が結ばれていない場合、1日8時間など労働時間規制を超える労働は違法残業になり、同署は労務管理や残業の実態について詳しく調べる方針。
労基法に違反して残業させた場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科す罰則規定がある。
壱番屋(愛知県)が廃棄した冷凍カツを産業廃棄物処理会社「ダイコー」を横流しした事件は、廃棄物処理業者に大きな影響を与えるだろう。 最終的にはどこまで行政と警察が踏込んでいくか次第!
◆焼津の業者「理解せず委託受けた」
「カレーハウスCoCo壱番屋」を展開する壱番屋(愛知県)が廃棄した冷凍カツを産業廃棄物処理会社「ダイコー」(同)が横流ししていた不正転売事件に絡み、焼津市の調味料製造業者が取引先からマグロ切り身の廃棄を請け負った問題で、この業者が廃棄物処理に関する許可を受けていないことが20日、県の調べで分かった。
廃棄物処理業に参入するには、家庭ごみなどの一般廃棄物は市町村長、産業廃棄物は都道府県知事か政令市長の許可が必要だ。無許可で営業した場合は、廃棄物処理法違反となり、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方が科される。
しかし、焼津の業者はいずれの許可も受けておらず、県は同法に抵触する可能性が高いとみて、県警に情報提供するとしている。
この問題について、県警生活保安課の担当者は「社会的関心も高いので、県から情報提供があり次第、捜査していく」と話している。
県は同日、この業者に2度目の立ち入り検査を行った。調味料製造業者は検査終了後、記者団の取材に応じ、許可がないことを認めたうえで、「許可が必要だと理解していなかった。(東京の輸入業者とは)昔から取引があり、(廃棄についても)そのまま受けてしまった」と話した。
◇
県や岐阜県によると、カツを購入した「みのりフーズ」(岐阜県)に保管されていた製品のうち、「びんちょうまぐろスライス」については、焼津市の業者が昨年4月、東京都の輸入業者から約2トン分の廃棄を依頼された。その後、県内の倉庫に保管してあったマグロ切り身を、静岡市の廃棄物運搬業者に、ダイコーまで運んでもらったといい、輸入業者から処理費用を受け取っていた。
この約2トン分のうち、みのりフーズでは約0・5トン分しか見つかっておらず、残り約1・5トンの所在は不明で、市場に流通した可能性があるという。
調味料製造業者は輸入業者から、約2年前から2~3か月に1回、廃棄物の処理の委託を受けていたという。
処分は運が悪いとは言え、自業自得!
東芝の不適切会計問題を受け、日本公認会計士協会が東芝の決算を監査した新日本監査法人と担当した会計士7人に対し、協会会則に基づく懲戒処分を行う方針を固めたことが20日、わかった。
月内にも、処分手続きの開始を発表する。
処分内容は今後、同協会の規律調査会と綱紀審査会を開いて検討する。新日本には戒告など、会計士には戒告や会員権停止、退会勧告などの処分が想定されるという。会員権停止や退会処分となった場合、公認会計士の業務は行えなくなる。
同協会の調査で、新日本が協会の指針に沿った十分な監査を、東芝に対して行っていなかったことが判明した。
金融庁は昨年12月22日、公認会計士法に基づき新日本に3か月の一部業務停止命令など、会計士7人には最長6か月の業務停止命令の行政処分を行っている。
事実はひとつであっても、どのように調査するか次第で調査報告に違いが出てくるかも?
教科書を発行する「三省堂」(東京)の謝礼問題で、謝礼を受け取った校長ら6人が関与した2011年度の大阪市や岡山市など6地区の教科書選定(採択)では、中学の英語教科書が他社から三省堂に切り替わっていたことが、文部科学省の調査や読売新聞の取材でわかった。
6地区の教育委員会はいずれも「選定への影響はなかった」と説明しているが、一部の教委は「疑念を抱かせかねない事案」として、さらに調査を行うという。
教科書選定は自治体や近隣地区ごとに行われており、他社から三省堂に切り替わったのは、群馬県高崎市・安中市地区、千葉県市川市・浦安市地区、三重県四日市市など1市3町の地区、大阪市内の8地区のうち1地区、岡山市、福岡県糸島市の計6地区。11年度の選定の結果、翌12年度から使用される中学校の英語教科書が、それまで使われていた他社の教科書から三省堂に変更された。この6地区の校長ら6人は、教科書の内容を調べ、報告書を作成する「調査員」などとして選定にかかわっていた。
業界最大手も教員に現金を渡していた。
三省堂、数研出版に続いて判明した「東京書籍」(東京)の謝礼問題。同社の会議に出席した中学校の英語教員は読売新聞の取材に、「選定を期待しているとしか思えなかった」と振り返る。
この教員は中学校の教科書検定が行われていた2010年9月、名古屋市内で開かれた会議に出席した。最初に同社の担当者が中学英語の教科書の編集方針を説明し、その後、参加教員らが「白表紙」と呼ばれる検定中の教科書を閲覧して意見を述べたという。会議が終わると、懇親会が開かれ、交通費と謝礼を受け取った。日帰りだったため、宿泊代は出なかったという。
教員は「西日本の教員が多く、かなり大規模に集められていると感じた。翌年度の選定を期待した行為だったと思う」と指摘。「こうした会議は何度か開催されていたようだ」と話す。
「加藤博和・名古屋大大学院准教授(交通政策)は『待遇が悪いと若いドライバーが確保できない。不規則な生活から、どうしても健康問題が生じる。運行管理者がチェックを強化し、社として安全運行への投資も増やすべきだ』と指摘する。」
きれいごとを言うのは止めよう!そんな事を言うから会社の企業努力で何とかなると勘違いする人が増える。長野県軽井沢町のスキーバス転落事故に関してバス運行会社「イーエスピー」の記事を読みましたか?こんなバス運行会社相手にどのようにコスト競争で生き残るのでしょうか?赤字を出して銀行やその他の金融機関から融資を止められたら終わりです。安全運行よりも見積もり費用が安いほうが良いと思う旅行会社が多ければそのような環境で安全運行への投資を継続できるのでしょうか?
うわさである特定のバス運行会社が違法行為をおこなっているとします。確実な証拠がなければうわさだけでは行政は動きません。例え運良く証拠を得たとしても
1つの証拠だけでは行政が動く保障はありません。下手をすると恨まれたり、特定の旅行会社から仕事がなくなるかもしれません。違法行為を行っていても特定の
旅行会社にとってメリットがあれば違法行為を行っていても安いバス運行会社を使う可能性もあります。
違法行為やずるをするほうが儲かるのです。法律や行政による監督そして良心的な会社や経営者の存在で社会の秩序が程度の違いはあれ保たれていると思います。これらのバランスが悪いほうに崩れると悪いほうに進むと考えています。大学の教授や研究者ではないので、大規模な調査やアンケートを実施したデータなどの根拠はない。自分の読んだ情報、人から聞いた情報、そして実際に経験した情報からの判断。
今回は15人の死者が出る大惨事なり、問題のあるバス運行会社を利用した旅行会社も検査を受けています。このような結果にならなければ、後悔する旅行会社は少ないはずです。
信念、損をしてでもやりたい、選択の余地がないなどの理由がなければ、不利な条件でビジネスを継続する理由は何ですか?従業員の雇用を守る必要はないと思います。
需要があれば他の会社が雇うでしょう。労働者も選択の余地があれば、良い企業での就職を望むはずです。残念ながら良い企業がほしい人材でなければ、お互いの
意思で成り立つので就職はかなわないでしょう。良い企業がほしい人材でない、又は、資格や経験がないのは部分的には個人の責任。
優秀な学生は中小企業を敬遠する。優秀でない学生でも大企業を好み、出来れば大企業で就職しようとする。優秀でない学生は望んでいても大企業で就職出来る確立は引く。なぜでしょう?簡単に解決できる問題でしょうか。需要、供給、選択の有無等のバランスで成り立っています。いろいろな要素でバランスは変化します。外的要素で環境やバランスが変わらなければ、基本的にはかわりません。現場の情報をもっと収集して実現可能な提案を考えてください。
運転手の待遇、改善の進まず
長野県軽井沢町で15人が死亡したスキーツアーバスの転落事故で、同様の貸し切り夜行バスの運転手からは「十分な休憩がとれない」「低賃金」などと、過酷な労働環境の改善を求める声が上がる。一方、過当競争状態のバス業界は経営の苦しい会社も多く、運転手の待遇改善が進む兆しは見えていない。【野田樹、中里顕、安藤いく子】
20日午前0時半、関越道高坂サービスエリア(SA、埼玉県東松山市)。100台近い大型車用の駐車場が休憩するスキーツアーバスなどで次々埋まる。
「仮眠できるけど疲れはとれないね」。事故のあったツアーと同じく、東京から長野県・斑尾高原に向かうバスの男性運転手(63)は、まぶたが重そうな様子で話した。到着してから次の運転まで仮眠時間は8時間確保されている。しかし昼夜逆転の不規則さのため、仮眠スペースでは熟睡できないことも多く、帰り道はいつも睡魔との闘いになる。
別のバス運転手(54)は嘆く。「20年やってるが競争が激しく運賃が相当下がった。しわ寄せは運転手さ」
業界は2000〜02年の規制緩和で、免許制から事業許可制になった。国土交通省などによると、1999年度に2336社だった貸し切りバスの事業者数は11年度に4533社へ倍増。長野県内の中堅バス会社の運転手(62)は「一定規模以上の会社なら運転手は制服を着ているが、高坂SAでは10年くらい前から私服姿をよく見かける」と話す。
一方、この間の年間輸送人員は2億5161万人から2億9605万人と1・2倍にしか増えていない。民間バス運転手の所得はかつて全産業平均より上だったが、12年は平均を90万円ほど下回る約440万円。高齢化も深刻で12年段階で6人に1人が60歳以上だ。
加藤博和・名古屋大大学院准教授(交通政策)は「待遇が悪いと若いドライバーが確保できない。不規則な生活から、どうしても健康問題が生じる。運行管理者がチェックを強化し、社として安全運行への投資も増やすべきだ」と指摘する。
バス運行会社「イーエスピー」のような営業方法を取る会社はいろんな業界で存在する。損を覚悟で競争するのか、撤退や廃業、又は、他の分野に資本や人材を集中するのか、比較的に紳士的な業界へ参入するのか、相手が違法すれすれ、又は、違法行為を行っているのなら、採算が合うように同じ方法をとるのか、それともとにかく
行き着く所までがんばってみる等のいろいろな選択を考えている、又は、既に決断した企業もあるだろう。
このようなケースでは行政が動かないと問題は解決されないであろう。テレビでは規制緩和と行政の介入は全く違うように説明している番組がある。個人的な考えでは、
規則を緩和しても、最低限度の規則を守らない企業の取締りや重い処分を課する事は出来る。規制緩和で取締りや処分まで甘くする必要ない。「企業の自由度を増やすこと=違法行為の容認」ではないと思う。
バス運行会社「イーエスピー」は大型バス事業の撤退を発表したが、全てのサイズのバス事業を継続させるべきではないと思う。行政が全ての権限を持っているのだから、
行政が責任を持って判断すれば良い。どんなシステムを導入しようとも、どのような選択をしても、違法行為をする企業はなくならない。違法行為をする企業が減るような選択は可能だ。再発防止策ではどのような違法行為が可能かを想定して、対応策を考えるべきだと思う。
長野県軽井沢町のスキーバス転落事故で、バス運行会社「イーエスピー」(東京都羽村市)に法定基準額の下限を下回る額で発注した都内の旅行会社2社が、「(イ社から)下限割れの額を提案された」と話していることが19日、分かった。旅行業界で違法行為が蔓延(まんえん)している可能性が高まった。
国土交通省などによると、この2社はトラベックスツアーズ(新宿区)とJクレスト(千代田区)。ト社は志賀高原へのスキーツアー(昨年12月)、J社は山梨県への温泉ツアー(同月)をイ社に下限割れで発注していた。
都などの立ち入り検査に対し、この2社はいずれも「(イ社が)方面や距離に関係なく『今月はこの額で』と定額で受注すると提案してきた。長距離ツアーでは下限割れになった」といった趣旨の説明をしているという。法律で定める運賃計算はしておらず、違法行為であることを認識していたという。
一方、長野県警は19日、事故車両の検証を始めた。死亡した土屋広運転手(65)は昨年12月にイ社に採用されたが、面接の際、「大型バスは慣れておらず苦手だ」との趣旨の発言をしていたこともイ社の話で判明。大型バスの運転技術が未熟だった可能性も視野に原因究明を急ぐ。
事故を受け、国交省は19日、運行直前の貸し切りバスを対象とした街頭監査を今週から強化すると公表。監査官がバスターミナルなどで停車中のバスに抜き打ちで乗り込んで運行指示書の有無や飲酒していないかなどを確認する。また、処分歴のあるバス運行会社を中心に全国約100社を3月半ばまでに集中的に監査する。今月中に有識者による委員会を立ち上げ、再発防止策を話し合うことも明らかにした。
旅行業界については、観光庁や都道府県が近く、下限割れ運賃への関与などを確認する立ち入り検査を行う。厚生労働省は運転手の過重労働などの違反がないか全国のツアーバス会社に対し、労働基準法に基づく緊急の集中監督を始めることを明らかにした。
命に関わらなければ、安かろう、悪かろうもOKかもしれない。はたして今回のスキーバス転落事故は何らかの影響を与えるのか?それとも 関係者及び間接的に関わった人達以外は、時の経過と共に忘れて終わりとなるのだろうか?
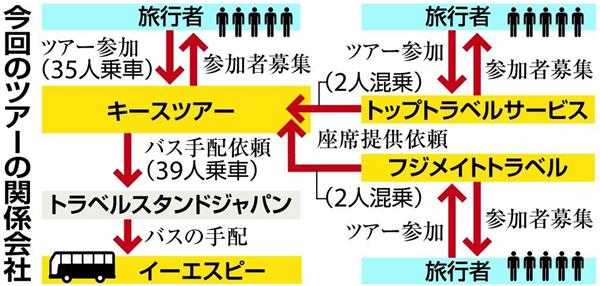
長野県軽井沢町のスキーバス転落事故で、現場の約250メートル手前に設置された監視カメラに、事故を起こしたとみられるバスが蛇行しながら走る様子が写っていることが19日、国土交通省への取材で分かった。
関係者によると、カメラに写ったバスは下り坂の右カーブでセンターラインをはみ出して走行、車体後方のブレーキランプはついていたように見えるという。現場の約1キロ手前にもカメラが設置されており、同じバスとみられる車両が走る様子が写っていたが、異常は確認されなかった。
転落現場のガードレールの破損状況や路面のタイヤ痕から、事故直前の下り坂を制限速度の時速50キロを超え、最高80キロ近い速度で走行していたとみられる。
また、今回の旅行を主催した旅行会社「キースツアー」(東京都渋谷区)に、ツアー客計4人(1人死亡、3人けが)の同乗を依頼したトップトラベルサービス(渋谷区)とフジメイトトラベル(杉並区)の旅行会社2社が、バス運行会社が「イーエスピー」(羽村市)であることを事前に把握していなかったことも、観光庁と都の立ち入り検査結果で判明した。
観光庁は所管するト社が旅行業法に基づく安全確認を怠ったとみて行政指導する方針。フ社を所管する都も同様の判断をするとみられる。フ社は取材に「主な主催者が把握していれば問題ないと思っていた」、ト社は「(キ社に)責任があると思っていた」とした。
日本もだいぶチャイナ スタンダードに近くなってきた。お金を節約する人達がいるから成り立つ。 一方で、日本政府やお役人は無駄使いばかり!
カレーチェーン店「CoCo壱番屋」が廃棄した冷凍カツが横流しされた事件で、カツを購入した岐阜県の製麺業者「みのりフーズ」から見つかった製品108品目のうち、69品目には販売元や製造元が明記されていたことが19日、分かった。
108品目は生協のマグロの切り身や焼き鳥、野菜の煮物、ケーキ、味噌など。冷凍だけでなく、常温保存の製品もあった。多くが賞味期限切れで、最も古い賞味期限は2007年9月20日。みのりフーズは、廃棄カツを横流ししていた産業廃棄物処理業者「ダイコー」(愛知県稲沢市)から入手したと説明している。
「『かなりひどい状態。この業者については徹底的にやるしかない』。事故後、特別監査を実施した国土交通省の担当者はそう漏らした。」
一生後遺症が残る被害者や死亡者が出る前に国土交通省職員は監査で徹底的にやるべきだった。昨年2月の監査の担当者ではないから言えること。
個人的な経験から言えば、問題のある会社はいろいろな点から問題がある事を確認できる。なぜなら問題がありすぎてまともな対応が出来ていない。記録簿、教育、
維持管理計画、運行マニュアル、引継ぎの際の手順、責任者の名前及び連絡先の伝達などいろいろな点で問題がある。不備を指摘すると言い訳や嘘と思える回答など
問題ありと言っているような感じである。「かなりひどい状態」の会社の問題を認識する事は業務の定期監査では難しいのか?そうであれば、今後も問題のある会社が重大事故を起こすまで待つしかないかもしれない。個人的には「かなりひどい状態」の会社が多くの不備を抱えていると判断することは困難だとは思わない。
今回の事故を起こした運転手との面接に関する社長の発言でも問題がある事がすぐにわかる。面接者の言葉だけで、履歴書を見ていない。履歴書に嘘の記載がないか確認する必要がある。履歴書の記載事項について質問する意思さえもないと言うことだ。それさえもしないと言うことはその他の書類、マニュアル、そして記録簿に関してもルーズな可能性が疑われる。チェックすれば多くの点で問題がある事が明らかになるだろう。
個人的な感想だが、問題のある会社又は悪意のある会社は担当者や当事者と連絡を取らない。個人的な推測だが、問題が起きた時に報告がないので、知らなかった、又は、対応が遅くなったと言い訳できる環境を作っていると思う。頻繁に連絡すると問題を知っていたのに対応しなかったと責任を追及される可能性がある。悪意のある労務士が非難されていたが、悪意のある弁護士も存在すると思うので、問題が起きた時の責任の回避の仕方とかアドバイスしている可能性も考えられると思う。
国土交通省職員の何には問題のある会社の社員のように言い訳ばかりする人間が存在する。監督する側の人間がこの有様ではドラマのような良い結果など期待できない。
国土交通省を批判しても何も変わらないかもしれない。しかし、批判しないと絶対に何も変わらないので批判する。国土交通大臣、現状の監査体制をどう評価しますか?
国土交通省による監査の目的に事故に繋がるような問題や不備を指摘して重大事故を防ぐ事は含まれて入ないのか?重大事故の防止が監査の目的に
含まれて入ないのであれば、事故に対して責任がある会社を潰して終わりと言うのもありかもしれない。
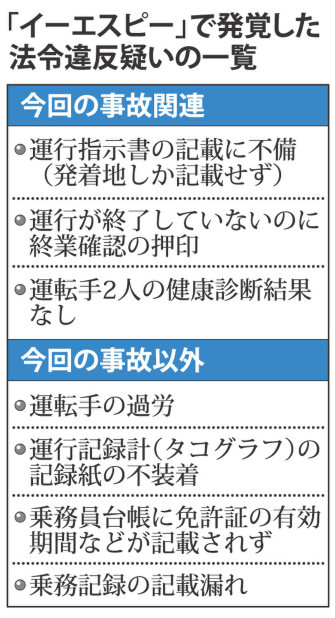
15人が死亡した長野県軽井沢町のスキーツアーバス転落事故で、道路運送法上の不備が相次いで発覚しているバス運行会社「イーエスピー」(東京都羽村市)。事故を受け、イ社は大型バス事業からの撤退を表明したが、日常の運行管理は極めてずさんなものだった。
「かなりひどい状態。この業者については徹底的にやるしかない」。事故後、特別監査を実施した国土交通省の担当者はそう漏らした。
道路運送法は、バスの運行管理者が運転手に対面し、運行前に健康状態や酒気帯びの有無を確認する「運行前点呼」を義務付けている。イ社の運行管理者は1人で、運行管理者がバスに乗っている時は、「代務者」が運行管理を代行していた。
高橋美作(みさく)社長も代務者で、事故車両に乗務する土屋広運転手(65)と勝原恵造運転手(57)の点呼を担当するはずだった。
しかし、高橋社長は集合時間に5分ほど遅刻し、点呼場所の車庫に着くと、両運転手は出発した後だった。しかも2人から出発の連絡もなかった。点呼ができていないのに、点呼の書類には、点呼を終えたことを示す欄に社員があらかじめ社長の印を押していた。社員は「社長の負担を減らしたかった」と話しているという。
高橋社長は「申し訳ない。何か問題があったとしても、2人が(出発時に)バスを引き継ぐ際、別の運転手が確認すると思った」と釈明した。
点呼漏れは今回だけではない。高橋社長は「何回かあったと思う」と述べ、常態化していたことを示唆した。
国交省の特別監査は15~17日の3日間と異例の長さとなったが、その間、さまざまな問題点が浮上した。
その一つが健康診断。2014年度の業務に対する昨年2月の国交省の一般監査で、13人中10人の運転手の定期健康診断を実施していなかったことが発覚した。更に、土屋運転手を昨年12月に採用した際、法令上必要な雇い入れ時の健康診断も怠っていた。
安全教育もずさんだった。国交省は、運転手に対し定期的に運転上の注意点などを教育するようバス事業者に求めているが、イ社は昨年1月以降、全運転手に教育していなかった。
複数の運転手の過労運転も確認されている。終業から始業までに8時間の休息が必要と定められているが、5時間しか休んでいないケースがあった。
バスにも法令上の不備や違反の疑いが次々に見つかっている。無理な運転がないかを走行後に検証する運行記録計が装着されていない車両があったほか、3カ月に1回実施することが義務付けられた定期点検整備の実施が確認できない車両もあった。【坂口雄亮、内橋寿明】
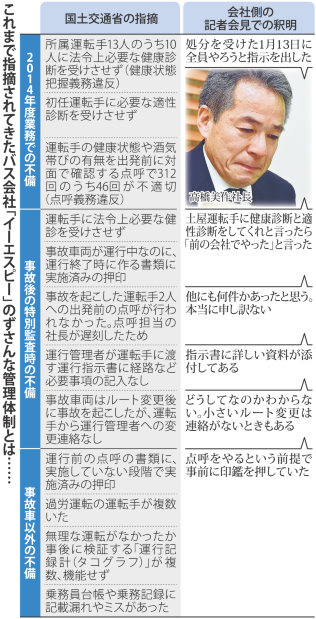
スキー客を乗せたツアーバスが道路脇に転落し、大学生ら10〜20代の若者と乗務員を合わせ14人が死亡、27人が重軽傷を負う惨事となった。現場は長野県軽井沢町の国道で、急カーブが続く峠を越えた後の緩やかな下り坂。大型バスは反対側のガードレールを突き破り横転、乗客はバスから車外に投げ出された。
当時は真夜中だったが、降雪や路面の凍結はなかった。警察は自動車運転処罰法違反(過失致死傷)容疑でバス運行会社などを家宅捜索。国土交通省も原因解明を進めている。
その中で運行会社は運転手の健康状態などを記録する「乗務員台帳」を作成しておらず、適切な運行指示書がないままバスを走らせるなどずさんな運行管理が明らかになってきた。
現に同社は事故2日前、運転手に健康診断を受けさせていなかったとして行政処分を受けていた。また道路運送法に基づく本来の指示書は発着地やルート、休憩時間などを明記して運転手に渡すべきものだが、今回は発着地だけ記した行程表があっただけ。
今季は暖冬でツアー客が少なかった影響もあった。旅行企画会社からの要請もあり、国が定めた基準を下回る運賃で受注していたともいわれる。
事故原因の徹底的な究明と関係者の厳正な処分とともに、安全確保に落ち度がないか業界全体を対象に、より踏み込んだ再発防止の対策も不可欠だろう。
いま「格安バスツアー」という言葉があふれているように、各事業者は過当競争や人手不足に直面している。事故の多くに「過労運転」の疑いが付きまとうのも、安全対策が強化されても順守されない業界事情が見え隠れする。
2002年に乗り合いバス事業が規制緩和され、事業者や車両の数が大幅に増加、実勢価格の低下を招いたという。こうした中で長距離や深夜バスの事故が目に付くようになった。
12年4月の大型連休、群馬県の関越自動車道で高速ツアーバスが鋼板製の防音壁に激突。7人が亡くなり38人が重軽傷を負った。無理な運行を強いられた運転手の居眠りが原因だった。
これを契機に国は過労運転防止策として、夜行貸し切りバスの運転手の上限距離を1日670キロから原則400キロに引き下げ。運転時間の制限や交代者の配置基準も改めたほか、運行会社の健康管理や車両整備にも目を光らせた。
しかしバス同士に限らず鉄道や飛行機との競争も激しく、事業者は生き残りにしのぎを削る。いきおい安全最優先の教訓は後回しにされがちだという。あまりに痛ましい事故が起きてしまったが、今こそ公共交通の使命を認識すべきだ。
行政が適切に介入しないと規制緩和は事故や惨事が起きるまでチキンレースを助長する。
長野県軽井沢町で15人が死亡したスキーツアーの大型バス事故で、同業のバス運転手から「業界の構造的な問題が一因だ」との指摘が相次いでいる。過当な価格競争、運転手の過酷な負担、高齢化――。規制緩和による業者の急増で、運転手を取り巻く環境は厳しさが増しているという。
「格安ツアーはとにかく経費削減。路上駐車で客を乗せ、駐車代を省く。高速道路の料金もルートに応じて上限があり、想定以上に高速を利用して上限を超えると自己負担させられる」
複数の運行会社でバス運転手を務めてきた50代の男性は話す。今回のスキーツアーを主催した「キースツアー」(東京)のツアーバスでもハンドルを握った経験があるという。……
監督官庁は法律の改正を考えたほうが良い。大胆にそして巧妙に不正をやりすぎ!
廃棄カツ横流し事件で、岐阜県は18日、羽島市の製麺業者「みのりフーズ」(羽島市)の冷凍庫に保管された加工製品「びんちょうまぐろスライス」約532キロについて、販売元の日本生活協同組合連合会(東京)が廃棄処分した一部だったと発表した。
みのりフーズは、産廃業者「ダイコー」から入手したと説明し、「製品は売っていない」と県に話している。
みのりフーズの冷凍庫で確認されたのは製品の入った段ボール96箱。いずれも賞味期限は切れていた。
県などによると、昨年4月末に販売終了した在庫で、東京都の輸入業者から静岡県の仲介業者を経て、昨年4、5月にダイコーに約2トン搬入された。残りの約1・5トンがダイコーからみのりフーズに搬入されたかは不明という。
正規販売された製品は賞味期限の表記があるものの、廃棄された製品にはないという。県は「市場に出回っている可能性がある。賞味期限の印字がないものは絶対に食べないように」と注意を呼び掛けている。
カレーチェーン店「CoCo壱番屋」が廃棄した冷凍カツが横流しされた事件で、産廃業者「ダイコー」(愛知県稲沢市)からカツを購入した製麺業者「みのりフーズ」(岐阜県羽島市)が、大手食品メーカー「ニチレイフーズ」(東京都)が廃棄処分した肉加工品も転売していたことが18日、分かった。既に消費者に流通した可能性がある。
みのりフーズの実質的経営者岡田正男氏(78)は本紙の取材に「(転売したニチレイの商品も)全てダイコーから仕入れた。賞味期限が切れた物もあったと思う」と証言した。販売を任せていた知人男性の主導で段ボール箱を詰め替え、みのりフーズの名前が入ったシールを貼り、出荷していたという。一部はみのりフーズに残っていた。
ニチレイによると、年に数回、ダイコーに廃棄処分となった食品の処理を依頼。「廃棄証明書やマニフェスト(産廃管理票)では処理が完了したことになっていた」といい、事実確認を急いでいる。県によると、みのりフーズの冷凍庫内には壱番屋の製品以外にも108品目あった。県は製造元や販売元の表示がある69品目について10都道県と保健所政令市の11市に調査を依頼している。
みのりフーズが、みそメーカー「マルコメ」(長野市)の賞味期限切れのみそを保管していることも分かった。岡田氏が明らかにした。「ダイコーから買った」と話している。マルコメによると、不良品などの廃棄をダイコーに委託していた。
これまでの通常の監査では問題や不備を見つけられない事を認めていると言う事なのでしょうか?
パフォーマンス的な監査だし、適切な監査を行える職員が不足しているので、抜き打ち検査を言う事なのでしょうか?
結果を求めるのであれば、緊急監査よりも、適切な監査を行える体制に力を要れ、継続的に実施する事が重要だと思います。結局、
時が流れ、次の犠牲者が出るまで小休憩と言う事?
遺族や被害者は、生きている限り、忘れる事の出来ない、そして、これまでの生活を継続できない事実と選択の余地なしに向き合っていくしかない。
自分も含め、直接、関係のない人々は時が経てば忙しい日常でいろいろな出来事を忘れていく。そして、同じような事故は繰り返される。
石井国土交通大臣は閣議のあとの会見で、長野県軽井沢町でスキーツアーのバスが道路下に転落し乗客と乗員合わせて15人が死亡した事故を受け、国土交通省として、貸し切りバスを対象とした緊急監査を実施する考えを明らかにしました。
長野県軽井沢町で起きたバスの転落事故について、石井国土交通大臣は閣議のあとの会見で「速やかに事実確認と原因究明を進める。その一環として、貸し切りバスを対象とした緊急の監査を実施し、法令順守の状況を確認する」と述べました。
具体的には、貸し切りバスに対し国土交通省の監査官が出発前に立ち入り、交代の運転手がいるかや走行ルートを示した運行指示書があるかなどを確認する「街頭監査」を今週から抜き打ちで実施します。
また、過去に処分歴があるなど優先的に監査すべきバス事業者を選んで、健康診断の受診状況や適正な運賃を受け取っているかなどを抜き打ちで確認する「集中的な監査」も近く行います。
また、石井大臣は旅行業者に対しても、抜き打ちの立ち入り検査を実施する考えを示し、「国の基準を下回る安い運賃で貸し切りバスを運行することへの関与など、貸し切りバスの安全な運行を妨げている違法行為がないか確認していく」と述べました。
さらに、今回の事故を踏まえた対策について検討を進めるため、今月中にも有識者による検討委員会を設置する考えを示しました。
「 今回、協会が高齢者のお金を預かったのは、成年後見制度のように家庭裁判所など公的機関が関与しない、いわば民間同士の契約だ。そのうえ高齢者は認知症などで判断能力が衰えていく恐れがあるため第三者の「目」がなければ不正が起きても発覚しない可能性がある。 」
身寄りのない高齢者はだましやすいだろう。思考能力も鈍ってくるし、認知症になれば、支援する身内はいないので、お金を取上げ、ひどい扱いをして死ぬのを待つだけで良い。献金を貰っている政治家達がいるのか国の対応も遅い。規制が強化される前に荒稼ぎする人々もいるに違いない。
「高齢者の後見問題に詳しい公益社団法人『成年後見センター・リーガルサポート』の川口純一副理事長は『普通ならあり得ない。組織的流用はおそらく初めてで、公益法人ですら問題が起きたことに非常に驚いた。高齢者に警鐘を鳴らす必要がある』と強調する。 」
お金を稼ぐためなら手段を選ばない人達が存在する限り、どの分野でも問題は起きると思う。
高齢者からの多額の預託金流用が発覚した公益財団法人「日本ライフ協会」(東京都、浜田健士代表理事)は、超高齢社会や核家族化などを背景に、急速に契約者数を伸ばしてきた。協会と同様の高齢者支援事業者も増える一方、こうした事業の監督官庁はない。信頼性が高いはずの公益財団法人で流用が発覚しただけに、専門家からは「国は一刻も早く実態調査をすべきだ」との声が上がる。【銭場裕司、田口雅士】
高齢者支援、落とし穴
「高齢者がお墓に入るまで家族がやってきたようなことを代行する事業者は増えている。一方、行政の監督は手つかずでチェック体制は何もない」。高齢者支援に詳しい専門家は、流用問題が起きた背景をこう語る。
別の専門家は「高齢者ビジネスとして産業になっている」と指摘。事業者側が契約者の預託金以外に遺贈(遺言による遺産の処分)などを受けている現状もあり、「透明性がなく、不正に取り扱われている可能性もある」と懸念する声は以前から上がっていた。
ライフ協会の会員は約2300人。最近は「1年間に約600人が新規入会し、約140人が亡くなる」(浜田代表)ペースで会員を伸ばしてきた。同様に数千人規模の会員がいるとみられる複数のNPO法人と並び、協会は大手の一角として知られていた。
今回、協会が高齢者のお金を預かったのは、成年後見制度のように家庭裁判所など公的機関が関与しない、いわば民間同士の契約だ。そのうえ高齢者は認知症などで判断能力が衰えていく恐れがあるため第三者の「目」がなければ不正が起きても発覚しない可能性がある。
協会では当初、第三者である弁護士などの「共助事務所」が預託金を管理する「3者契約」を行うとして2010年7月に公益認定された。申請書では「共助事務所が預託金を管理することで透明性を確保できます」とうたい、認定の判断ポイントとなる「事業の質を確保するための方策」があることを強調していた。
しかし、認定のわずか3カ月後、自身がお金を管理する「2者契約」の実施を無断で決定し、新規契約のほとんどは2者契約となった。契約者ごとに預託金口座を作る3者契約のような管理はなく、誰の預託金を流用したかすら分からない事態に陥っている。
高齢者の後見問題に詳しい公益社団法人「成年後見センター・リーガルサポート」の川口純一副理事長は「普通ならあり得ない。組織的流用はおそらく初めてで、公益法人ですら問題が起きたことに非常に驚いた。高齢者に警鐘を鳴らす必要がある」と強調する。
一方、問題の背景には、病院や施設などが、入院や入所時に慣習的に身元保証人を求める現状もある。
こうした身元保証について、ある司法書士は、契約の多くが未払い時の費用保証、身柄の引き取り、退去後の原状回復など広範囲なものになっていることを指摘。「法的根拠もなく、内容も理解しないまま『決まりだから』といって保証人を求められることは多い」と問題点を挙げる。
「保証被害対策全国会議」事務局長の辰巳裕規弁護士は「医療や福祉サービスについては、保証人を立てられない人が排除されたり、高額の保証会社・団体に頼まないといけなくなったりすること自体がおかしい」と指摘している。
「学術やスポーツ、慈善その他の公益事業を行う法人を対象に、内閣府の公益認定等委員会などが公益認定法に基づき審査し、行政庁が認定する。登記のみで設立できる一般法人と違い、税制上の優遇措置がある。2014年12月1日時点で9300法人(社団4089、財団5211)。主な公益法人は日本相撲協会など。 」
公益財団法人「日本ライフ協会」を存続させる必要はない。需要があり、ビジネスとして成立すると思うのであれば、一般法人としてやらせてみれば良い。
偽善の上にしか成り立たない組織に税制上の優遇措置など必要ない。
偽善者達が身寄りのない高齢者の支援と言いながら、食い物にしている組織が日本に存在すると言う事。そしてこのような組織を公益認定する裸の王様に近い行政が存在する。
全理事が19日に引責辞任へ
身寄りのない高齢者の支援をうたう公益財団法人「日本ライフ協会」(東京都港区、浜田健士代表理事)が、公益認定法の定める手続きを経ずに高齢者から将来の葬儀代などとして預託金を集め、このうち約2億7400万円を流用し、全理事が19日に引責辞任することが分かった。公益法人を監督する内閣府の公益認定等委員会は是正を勧告したものの、穴埋めの見通しは立っておらず、協会は存続の危機に陥っている。
高齢者から多額の預託金を集める同種の事業は全国で急速に拡大しており、協会は大手の一つで公益法人だが、他にもNPO法人や民間企業など業態はさまざまで、国は事業者数すら把握していない。同種事業で初とみられる組織的流用が発覚したことで、実態把握が急務となりそうだ。
協会は2002年に設立されNPO法人や一般財団法人を経て10年7月に公益認定を受けた。1人暮らしの高齢者がアパートなどに入居する際の身元保証や通院の付き添い、銀行手続きの代行から死亡後の葬儀・納骨までを一括契約する事業を全国17事業所で展開。代表的な契約プランでは、利用者が支払う総額約165万円のうち身元保証料など約106万円は協会に入り、残りの約58万円は将来の葬儀費などに充てるための預託金とされる。
毎日新聞が入手した協会の内部資料などによると、協会は当初、預託金について弁護士などの第三者が預かる「3者契約」を行うとして公益認定を得ていたが、認定の3カ月後、弁護士などを関与させず、協会がお金を管理する「2者契約」を勝手に始めていた。事業内容の変更には委員会の認定が必要だが、協会は委員会に申請しておらず、公益認定法違反の疑いが強い。
この結果、契約者約2300人のうち、2者契約の約1600人分の預託金約9億円から2億7412万2941円が引き出され、職員の賞与や事務所開設費などに流用された。このうち約1億5000万円は15年3月までに使われ、その後も、委員会の事前了解を得ずに約1億2500万円を「運転資金準備金」に充て、多くを使っていた。
協会は今月19日の評議員会で全理事8人の辞任を正式決定する。浜田代表は「預託金への認識が甘く収入と同じような感覚があった。(流用分は)契約件数が順調に推移すれば回復できると思っていた」と話している。【銭場裕司、田口雅士】
公益法人
学術やスポーツ、慈善その他の公益事業を行う法人を対象に、内閣府の公益認定等委員会などが公益認定法に基づき審査し、行政庁が認定する。登記のみで設立できる一般法人と違い、税制上の優遇措置がある。2014年12月1日時点で9300法人(社団4089、財団5211)。主な公益法人は日本相撲協会など。
「特別監査では、違法行為が相当数見つかっていて、国交省は『ここまでひどいケースはそうない。今後、徹底的に調べる』としている。」
それほどひどいバス運行会社であっても昨年2月にイーエスピーへの監査を実施した時には、多くの不備を指摘していない。どう言う事なのか?
適切な監査ではなかったのか?もし適切な監査が行われたのであれば、適切な監査と徹底的な監査の違いは何なのか?
監査を実施しても、存在する不備を指摘出来なければ、監査の本来の目的は達成できていないと思う。国土交通大臣、監査する側も改善するべき点があると
思いませんか?表に出ていないだけで監査をする者の中に不適切な関係を持った職員達が監査の結果に影響を及ぼすほど存在すると言う事ですか?
2015年、羽田空港のビジネスジェット向け格納庫をめぐる汚職事件で、国土交通省航空局運航安全課係長が収賄容疑で逮捕されたケースがありました。
長野県軽井沢町でスキーバスが転落し、14人が死亡した事故で、事故を起こしたバス会社が、今回の他に少なくとも2回、国の基準を下回る料金でツアーバスの運行を受注していたことが分かった。
国土交通省は3日連続となる特別監査を行い、バス会社イーエスピーが、今回のキースツアーの他にも、先月と今月の少なくとも2回、別の2社から国の基準の下限を下回る違法な安い料金で、ツアーバスの運行を受注していたと明らかにした。イーエスピーは、「下限の金額を認識せず、相場感で契約してしまった」と話しているという。
特別監査では、違法行為が相当数見つかっていて、国交省は「ここまでひどいケースはそうない。今後、徹底的に調べる」としている。
一方、イーエスピーは、「大型バス事業から撤退する」と発表した。
「また、イーエスピーがこれまでにも同様の低価格で運行を受注したことを示す資料数件を、国交省が入手していることも分かった。国交省は昨年2月にイーエスピーへの監査を実施しており、基準額違反は指摘していなかった。 高橋社長は取材に『今季はもっと(金額を)上げてもらう話をした』と話した。キースツアーの福田万吉社長は『最終日までの平均で下限を満たせばいいと考えている』と話したが、国交省は、こうした手法は認められないとの考えを示している。」
規則が存在すれば、権限を持つ行政の解釈が最終的なもの。バス運行会社や旅行会社が間違って営業している事は大問題。どれほどの企業が法や規則を適切に理解した
上で営業しているのが不安になるほどの問題だと思う。監査で法や規則を理解していない会社が指摘を受けない事実は衝撃的だ。
法定の基準額の下限を下回る額で受注していない事を確認するために書類、又は、まとめ(表)を見せてほしいと監査で要求すればバス運行会社や旅行会社に言い訳する
機会は与えなかったはずである。運転手を含む、運行関係者への教育についても、教育訓練実施記録、又は教育訓練計画表を監査中に見たいと言えば、事故が起きる前に
問題を把握できたはずだ。一般財団法人・化学及および血清療法研究所(化血研、熊本市)が行ったような巧妙な
隠蔽工作のように教育訓練記録の偽造や受注金額の修正が行われていれば、一般の監査では問題は確認出来ないかも知れない。会社の運行マニュアルが存在すれば、それを読み、運転手が会社にいれば、マニュアルを理解しているか簡単な質問をすれば、十分な教育が実施されいるのか確認も出来る。嘘が上手い運転手でなければ
回答に矛盾点やまともな回答が出来ないはずである。バス運行会社の監査を行った事はないが、常識の範囲でこれぐらいは考えられる。これらを追加で実施しても会社がまともであれば30分ほどで終わると思う。会社が実際に行っていなければ、探してくると言ってその場で作成したり、いろいろと言い訳するから、2時間経っても十分な資料は提出されないだろう。
旅行業法に基づき立ち入り検査出来る観光庁と東京都の責任について明確な説明が必要。今回の事故ではっきりさせないと、近い将来、似たような惨事が起きるかもしれない。
長野県軽井沢町のスキーバス転落事故で、法定の基準額の下限を下回る額でバスの運行を受注した「イーエスピー」(東京都羽村市)が、昨シーズンも下限よりも安い金額でツアーを受注していたことが17日、分かった。同社の高橋美作社長(54)が明らかにした。国土交通省はこれ以外にも数件のツアーの受注額が下限を下回っていたことや事故を起こした運転手らが必要な教育を受けていなかったことなどを新たに確認しており、さらに厳しく調査を進める。
■国交省の監査で指摘なし
イーエスピーは同日、「国交省の監査を受け、運行上の管理の未熟さ、ずさんさを実感した」として、大型バス事業から撤退する方針を明らかにした。
国交省によると、イーエスピーは今回のツアーを、安全確保のため道路運送法で定められている基準額の下限(約26万円)より安い約19万円で、主催した旅行会社「キースツアー」から受注していた。高橋社長らによると、昨シーズンは同様のツアーを13万~14万円程度で受注。今シーズンは基準額を調べ、適正価格にするために23万~24万円程度を検討したが、雪不足による集客不振などから今回のツアーは約19万円になったという。最終的な価格を提示したのは、仲介した旅行会社のトラベルスタンドジャパンだったと説明している。
また、イーエスピーがこれまでにも同様の低価格で運行を受注したことを示す資料数件を、国交省が入手していることも分かった。国交省は昨年2月にイーエスピーへの監査を実施しており、基準額違反は指摘していなかった。
高橋社長は取材に「今季はもっと(金額を)上げてもらう話をした」と話した。キースツアーの福田万吉社長は「最終日までの平均で下限を満たせばいいと考えている」と話したが、国交省は、こうした手法は認められないとの考えを示している。
今回の事故に関連する違反として、キースツアーとイーエスピーで運行申込書・引受書がない▽事故発生当時に運転していた運転手らの乗務員台帳を作成していなかった▽事故を起こした運転手2人を含む全員への必要な教育がなかった-などが確認された。
国交省は17日も、イーエスピーを特別監査し、今回の事故以外の法令違反について調査。観光庁と東京都は同日、キースツアー以外の旅行会社で、募集したツアー客が事故車に同乗していた2社を旅行業法に基づき立ち入り検査した。
今回の事件は氷山の一角であろう。
斎藤健一郎、三上元
1パック5枚入り、透明の袋に赤字で「ビーフカツ」。消費者が手にするはずのない食材だった。
カレーチェーン「CoCo(ココ)壱番屋」を全国展開する壱番屋(愛知県一宮市)の店舗用冷凍ビーフカツが、愛知県内のスーパーに並んでいた。壱番屋製と紹介するポップまであった。
津島市の「Aマートアブヤス」神守店。11日の買い物中に変だなと気づいたのは、「ココイチ」のある店にパートで勤める女性だった。ふだん厨房(ちゅうぼう)で調理するだけの食材が、なぜ――。壱番屋本社に伝わり、今回の問題が発覚した。
壱番屋が「異物混入の疑いがある」として産業廃棄物処理業ダイコー(愛知県稲沢市)に処理を委託した冷凍ビーフカツが、横流しされていた。東海3県の自治体などの17日までの発表によると、3県の34店で2万7千枚が店頭で売られたり、商品の弁当の材料に使われたりした。
全容はまだ見えない。ダイコーから横流しを受けたみのりフーズ(岐阜県羽島市)には17日も岐阜県の調査が入った。同社の実質的経営者(78)は、壱番屋の段ボール箱に入れたままにしないようダイコーから言われ、箱を詰め替えて転売したと話している。
壱番屋製であることを隠すはずだった。だが、みのりフーズから別の業者を経て仕入れた名古屋市の仲卸は、壱番屋製というポップを作って冷凍ビーフカツにつけ、Aマートアブヤスに売った。それが、神守店で「ココイチ」のパート女性が目にしたものだった。
下記の記事を読むと事故後に考えたいい訳とも思える。仮に事実だとしても国土交通省は下記の項目をチェックする必要があると思う。
「バス運行会社「イーエスピー」が国の定める最低基準額を下回る運賃で受注していた問題で、ツアーを企画した旅行会社『キースツアー』(東京都渋谷区)が『平均で下限額を下回らなければいい』との認識でいたことがわかった。道路運送法は1回の運行でも下限額未満となることを禁じており、旅行会社側にも同法への認識が不足していたことが浮き彫りとなった。」
「出勤してきた30歳代の男性職員は「国が決めたことなので仕方がない。これから110日間を何とか乗り切るしかない」と不安そうな表情を見せた。」
会社が長年行ってきた隠ぺい行為の結果だろ!「国が決めたことなので仕方がない。」と反省のない考えの社員がいるようでは、また、将来、不祥事を
起こすかもしれない。処分されたから、会社の体制や従業員の意識が変わるわけでもない。少なくとも会社や従業員が変わろうとする意思がなければ変わらないと思う。
一般財団法人・化学及および血清療法研究所(化血研、熊本市)が国の承認を受けない方法で血液製剤などを製造していた問題で、18日から化血研に対する業務停止処分が始まった。
停止期間は5月6日までの110日間で、過去最長となる。血液製剤の一部や破傷風の予防薬など8製品の製造・販売や営業活動などが禁じられる。
18日朝、厚生労働省の担当者が熊本市の化血研本所に入り、処分対象となる製品の製造ラインや保管庫、事務スペースなどが使用できないよう「封かんの証」と書かれた紙を貼り付け、封鎖していった。
出勤してきた30歳代の男性職員は「国が決めたことなので仕方がない。これから110日間を何とか乗り切るしかない」と不安そうな表情を見せた。
ワクチンや血液製剤など35製品のうち、他社が代替できない27製品は引き続き、製造・出荷が認められる。
化学及血清療法研究所(化血研)に対し、厚生労働省は8日、過去最長の110日間の業務停止処分に踏み切った。
ただ、今回の処分では、血液製剤が14製品のうち8製品、ワクチンは11製品すべてが業務停止の対象から外れた。処分期間中も化血研は多額の収入が見込まれる。「薬害オンブズパースン会議」事務局長の水口真寿美弁護士は、「40年間の不正に対する処分としては、十分とはいえない」と語気を強める。
特にワクチンでは、大きな利益を生む季節性インフルエンザの出荷継続が認められたほか、出荷を自粛しているB型肝炎と日本脳炎、A型肝炎も停止処分から除外され、事実上、出荷に「ゴーサイン」が出た。
背景には、化血研のシェア(市場占有率)の高さがある。今年10月にも予防接種法の定期接種の対象となるB型肝炎ワクチンのシェアは80%。定期接種で需要は2倍近くになる見通しで、厚労省の担当者は「化血研製は供給に不可欠」と話す。
下記の記事を読むと事故後に考えたいい訳とも思える。仮に事実だとしても国土交通省は下記の項目をチェックする必要があると思う。
「バス運行会社「イーエスピー」が国の定める最低基準額を下回る運賃で受注していた問題で、ツアーを企画した旅行会社『キースツアー』(東京都渋谷区)が『平均で下限額を下回らなければいい』との認識でいたことがわかった。道路運送法は1回の運行でも下限額未満となることを禁じており、旅行会社側にも同法への認識が不足していたことが浮き彫りとなった。」
「国交省は昨年2月、道路運送法に基づき、イーエスピーに対し2014年度中の業務の定期監査を実施。13人の運転手のうち10人について、年1回(深夜業務従事者の場合は2回)実施すべき健康診断を受けさせていなかったことが判明した。初任運転手への適性検査も怠っていた。国交省は今月13日付でイーエスピーが所有するバス7台(大型5台、中型・小型各1台)のうち、中型バス1台の使用を20日間禁じる処分を出した。」(01/15/16 毎日新聞)
キース社の福田万吉社長(38)は17日、読売新聞の取材に「暖冬でスキー客も少なかったので、トラベル社に『安くしてほしい』と話した。下限額より低いとの認識もあった」と説明。「『客が増えれば料金を上げる』とも言った。シーズン平均で下回らなければいいとの認識だった」と語った。
キース社の福田万吉社長が誤認していたのであれば、キース社から仕事を受注した他のバス運行会社にも問題がある可能性が非常に高い。国土交通省はキース社の仕事を
受注した全てのバス運行会社に対して特別監査を行い、他のバス運行会社もバス運行会社「イーエスピー」と同じ問題を抱えているのか確認し、それ以外の問題を抱えているのか再チェックする必要があると思う。誤認が言い訳でなければ、バス運行会社「イーエスピー」と同様に他のバス運行会社も程度の違いはあれど問題を抱えている可能性が非常に高い。
国交省はバス運行会社「イーエスピー」及びキース社から受注したバス運行会社を定期監査を行った職員の情報を確認し、適切な監査が行われていたのか確認する必要があると思う。そしてが国の定める最低基準額を下回る運賃で受注していた問題をチェックしたのか確認する必要がある。もし確認されていなければ、なぜ確認されなかったのか理由を聞き、癒着や監査の怠慢があったのか検証する必要があると思う。
「バス運行会社「イーエスピー」及びキース社が「道路運送法は1回の運行でも下限額未満となることを禁じている規則」について誤認し、誤認した状態で
定期監査を受けてなぜ国交省職員から問題を指摘されなかったのか?監査の手順、方法、職員に対する教育に問題がなかったのか?
国土交通省は監査の手順、方法、職員に対する教育に関して改善する必要があると思う。さらに規則を厳しくしたとしても、問題のある会社や規則を守らない会社を見つけ、処分しないと比較的まともな会社に負担が増え、業界から去っていくだけである。交通大臣は部下の机上の空論や形だけの報告を鵜呑みにせず、常識も持って対応してほしい。
バス運行会社「イーエスピー」が国の定める最低基準額を下回る運賃で受注していた問題で、ツアーを企画した旅行会社「キースツアー」(東京都渋谷区)が「平均で下限額を下回らなければいい」との認識でいたことがわかった。
道路運送法は1回の運行でも下限額未満となることを禁じており、旅行会社側にも同法への認識が不足していたことが浮き彫りとなった。
今回のツアーでは、旅行会社「キースツアー」が同業の「トラベルスタンドジャパン」(千代田区)にバス手配を依頼し、同社がイー社を手配。国土交通省によると、バス運行会社に支払われる下限額は約26万4000円だったが、イー社は約19万円で受注していた。
キース社の福田万吉社長(38)は17日、読売新聞の取材に「暖冬でスキー客も少なかったので、トラベル社に『安くしてほしい』と話した。下限額より低いとの認識もあった」と説明。「『客が増えれば料金を上げる』とも言った。シーズン平均で下回らなければいいとの認識だった」と語った。
イー社の高橋美作社長(54)も「トラベル社から約19万円で依頼されたが、2月にかけて24万~25万円に上がればいいと考えた」と話した。昨シーズンは13万~14万円で受注したこともあったといい、「赤字にならなければいいという認識だった」と述べた。
観光庁によると、旅行会社がバス運行会社に値引きを強制するなど同法に違反する運賃を設定した場合、国交省から通報を受けた都道府県などが旅行業法に基づき、旅行会社を行政処分することになる。
完全に行為が悪質だ。法律や規則による罰則がどうなっているのか知らないが、厳しい処分を検討する必要がある。
カレー店「CoCo壱番屋」を展開する壱番屋(愛知県一宮市)が廃棄した冷凍カツなどが横流しされた事件で、産業廃棄物処理会社「ダイコー」(同県稲沢市)からカツを買い入れた製麺業者「みのりフーズ」(岐阜県羽島市)が、食品を詰め替えた段ボール箱に自分の屋号と記号が印字されたラベルを張っていたことが18日、岐阜県の調査で分かった。
記号は製造所固有記号とみられ、同県などは、仕入れ先を隠すため、自ら製造したと偽装していた可能性があるとみて調べている。
みのりフーズは、壱番屋と印刷された段ボール箱に入ったビーフカツを、ダイコーから購入。別の箱に詰め替え、愛知県の業者などに販売したことが分かっている。
長野県軽井沢町でツアーバス転落事故が起きてから初めて迎えた週末、都市部の主要駅からは、スキー場や全国の都市に向かう夜行バスが次々と出発した。事故の原因はまだ不明だが、運転手らは取材に対し、夜間に長距離を走る危険性を口々に証言した。
人ごとではない
JR新大阪駅の南側にある駐車場は16日夜、多くの若者らで混雑した。相次ぐ事故を受けた規制強化=別表=で、長距離を走るバスはどれも運転手が2人ペアになっている。
「2人態勢で負担は格段に減った。それでも、眠気で危ないと思う時は少なくない」とバス歴10年の運転手(51)が打ち明ける。
15日夜、長野県白馬村のスキー場を出発。16日朝、大阪に到着し、ホテルで仮眠を取った。相方の運転手と2時間おきに交代しながら、再び白馬に向かう。
以前はトラック運転手。バスでは音楽をかけたり雑談したりできず、一人で耐えるしかない。「日中の仮眠では熟睡できない。正直、眠気は変わらないよ」
40歳代の運転手も「眠気で意識が飛びそうになったことがある」と言う。
いつもコンビニで買う濃いコーヒーとガムが頼りだ。休憩時には体操もするが、どうしても眠気に勝てず、仮眠中の相方をたたき起こした時もある。
「今回の事故原因は、居眠り、運転ミス、スリップなど、いろいろ考えられる。どれも人ごととは思えない」。そう真顔で話した。
高齢化と二極化
今回の事故の運転手は、65歳と57歳だった。国土交通省によると、バス運転手の平均年齢は48・3歳と、全産業の平均(42・0歳)を大きく上回る。
「安値競争が激しく、賃金が低くならざるを得ないことが原因」と関西の中堅バス会社の担当者は言う。同社の運転手約50人の平均年齢は50歳代。「体力的にきつい仕事なのに、年収は良くて450万円。とても若い人は就きたがらない」
一方、1回の運行に2人の運転手が必要で、訪日観光客の急増も加わり、運転手不足は深刻化している。この担当者は「経営に余裕のない中小の会社では、過重労働させるケースもあるだろう。安全面で、大手と中小の二極化が進んでいる印象だ」と指摘する。
別の会社の担当者は「中小の会社がスキーバスを運行するケースが目立つ」と話す。利用する若者らは安さを重視するうえ、路面の凍結など危険性が高く、大手は敬遠するためだ。
多くの運転手が「会社に無断でルート変更するなんて考えられない。乗客の命を預かっているという責任感を持っている」と口をそろえた。冒頭の運転手は、こう強調した。「労務管理がむちゃくちゃな会社もある。そういう会社は、業界から消えてほしい」
2012年(平成24年)4月29日、7人の死者が出た関越自動車道高速バス居眠り運転事故と今回の事故から考えると、バス業界の基準や意識が低いと思う。
そしてそれを許す行政の結果だと思う。
規制緩和すると行政が適切にコントロールしないと悪い方向へ向かう。業界に嫌気が差して離れた業者や関係者は帰ってこない。人材不足を無視できない状況
まで放置すればよほど努力しないと問題は改善されないであろう。多くの消費者が望めば、二極化するかもしれない。高いが安全、そしてただ安い。しかし、
安心は出来ない。安全を偽装して、お客を呼び込もうとする人達も現れるから、積上げた信頼が再評価されるかもしれない。
LCCも同じような問題を抱えていると個人的に思う。だから、LCCには乗らない。飛行機が落ちてからでは遅い。結局、個々が判断する事だと思う。
長野県軽井沢町でスキーツアーの大型バスが転落し14人が死亡した事故で、バス運行会社が事故時にハンドルを握っていたとみられる運転手について、経験不足を不安視し一般道を走らないよう指示していたことが16日、分かった。入社後の大型バスの運転経験が乏しく、技量不足のまま運転していた可能性がある。運行会社社長は同日、運行管理の不備を認め謝罪した。
運行会社「イーエスピー」(東京都羽村市)によると、事故時に運転していたとみられ、死亡した土屋広運転手(65)=東京都青梅市=は昨年12月に入社。研修を含め大型バスを運転したのは4回程度だったという。
土屋運転手は同社の採用面談時に「大型も何回も乗ったことがあるから大丈夫」と話したというが、同社は過去の勤務先に運転歴などを確認しておらず、慣れさせるため高速を運転させた方がよいと判断。16日に記者会見した同社の運行管理者の荒井強所長(47)は「一般道の運転はさせず、高速道路をやってもらおうと指示していた」と、経験を不安視していたことを明らかにした。
同運転手は和菓子製造や砕石販売などの会社を経て、バス運転経験は通算10年以上あった。ただ土屋運転手の過去の勤務先などによると、中型やマイクロバスの運転が多かったという。
観光会社で大型バスを15年運転した経験があるという運転手によると、大型バスは車体の重さなどから、ブレーキの使い方などで一定程度の経験が必要という。「経験が浅いと、ブレーキをかけても重さでバスが減速せず、パニックになることもある」と指摘。「大型バスの運転経験が4回程度だったとすれば、実務に就くにはあまりに少ない」と話す。
また、事故現場について「峠の下りの最後の緩いカーブなので、熟練した運転手なら事故を起こす場所ではない」とも指摘した。
「運行会社が『運行指示書』にルートを記載しないなど、ずさんな実態が次々と明らかになり、同業者からは『業界全体がいいかげんだと思われかねない』と憤りの声が上がる。『これはあり得ない』。運行指示書にツアーの出発地と到着地しか書いていなかったことに、あるバス会社の幹部はため息を漏らす。別のバス会社の代表も『運行指示書にルートを書かないのは、よほどルーズな会社だろう。そんな大変な作業ではないのに』と首をかしげる。」
上記のコメントが同業者の多く意見なのかは知らないが、上記の問題は昨年2月に国交省が行った定期監査では指摘されていないようだ。よほどルーズな会社であれば
監査でもっと多くの不備が指摘されてもおかしくないのでは???
それとも一般財団法人・化学及および血清療法研究所(化血研、熊本市)が行ったような巧妙な
隠蔽工作でもあったのか?
「国交省は昨年2月、道路運送法に基づき、イーエスピーに対し2014年度中の業務の定期監査を実施。13人の運転手のうち10人について、年1回(深夜業務従事者の場合は2回)実施すべき健康診断を受けさせていなかったことが判明した。初任運転手への適性検査も怠っていた。国交省は今月13日付でイーエスピーが所有するバス7台(大型5台、中型・小型各1台)のうち、中型バス1台の使用を20日間禁じる処分を出した。」(01/15/16 毎日新聞)
今回の事故に関与した会社が存続できるのか知らないが、行政処分で可能であるなら存続させないほうが良いのではないのか?不正な行為を継続し、大きな事故を
起こせば存続できなくなることを周知させるために前例を作るべきだと思う。被害者に対する補償が出来ない問題が残ると思うが、会社が存続しても顧客は
離れるだろうから結局十分な補償は出来ないと思う。
関係の方や規則について知らないが法改正で最低の補償額を決めて保険の加入を強制にするべきだ。また、行政は他の業界のようにバスの安全運航に関して運転手は
安全を優先し、会社は運転手に圧力をかけない事を文章にて記載させる事を要請するべきである。法が改正されたとしても、コストに関して会社からの運転手に対する圧力はなくならないだろうが少しは状況は改善するであろう。規則を守らない会社はいろいろな抜け道や方法を考える。問題の解決は期待できないが、問題の環境を改善する事は出来る。行政次第だと思う。
軽井沢バス転落事故
運行会社が「運行指示書」にルートを記載しないなど、ずさんな実態が次々と明らかになり、同業者からは「業界全体がいいかげんだと思われかねない」と憤りの声が上がる。「これはあり得ない」。運行指示書にツアーの出発地と到着地しか書いていなかったことに、あるバス会社の幹部はため息を漏らす。別のバス会社の代表も「運行指示書にルートを書かないのは、よほどルーズな会社だろう。そんな大変な作業ではないのに」と首をかしげる。
関西大の安部誠治教授(公益事業論)は、2000年の規制緩和で「参入する零細事業者が増えた。今回のような運行状況は特異なケースではないだろう」と指摘。さらに「法令通りに徹底するのは当然だが、社員が少なければおろそかになってしまう。事業参入の条件を見直しでもいいのではないか」と話した。
軽井沢バス転落事故
バスを運転していた土屋広運転手(65)は、昨年末まで約5年間働いていた都内の観光会社では本人の希望で小型バスに特化し深夜運転はしていなかった。観光会社社長は「(事故現場を)うちにいる間は通ったことはないはずだ」と指摘。イーエスピー幹部も「高速だけで一般道はやらせないようにしていた」と一般道を走ることに不安を持っていたと明かした。
また、イーエスピーによると、キースツアー側は、埼玉県にある関越自動車道の高坂サービスエリア(SA)を休憩場所として指示。しかし、土屋運転手は混んでいることを理由に、降りるべきインターチェンジを通過し、同県の上里SAで休憩した可能性がある。その結果、定められた高速道路料金内に収めるため、国道18号碓氷バイパスの峠道を通らざるを得なかったとの見方も。乗務していた勝原恵造運転手(57)は過去に同様の変更をしていた。
長野県軽井沢町で14人が死亡し、過去30年で最多の犠牲者を出した事故で、バスの運行会社「イーエスピー」(東京)の高橋美作社長(54)が遅刻して、事故を起こしたバスの出発前に、運転手2人の健康チェックができなかったことが16日、分かった。道路運送法で義務付けられた書類の不備なども明らかになり、同社のずさん管理の疑いが浮上。国土交通省は、運行停止や業務停止などの行政処分を検討する。
高橋社長は16日、東京都羽村市の同社で記者会見。黒のスーツ姿で「重大な事故を起こしてしまい、おわび申し上げます」と頭を下げた。自身が遅刻したため、法令で義務付けられた出発前の点呼ができず、事故で死去した運転手2人の健康状態の確認を怠っていたことを明らかにした。集合時間を間違えて5分遅く着いたという。ずさんな運行管理が事故の引き金になったのではないかと問われると、「もしかしたら、心の緩みがあったかもしれない」と叫ぶように答え、再び頭を下げた。
運転手が無断で走行ルートを変更するケースが以前にもあり、今回の変更も「連絡がなかった」と説明。バスツアーを国が定める基準を下回る金額で引き受けたことや、バスを運転していた土屋広運転手(65)の昨年12月の雇用時に健康診断を受けさせていなかったことも明かし、会見の最後に額を床に付け数分間にわたって土下座した。
今回のバスツアーは、旅行会社「キースツアー」から約19万円で引き受けていた。国交省によると、国が定めた距離や時間による単価の下限額を基にした最低価格を8万円下回っていた。
国交省の特別監査では、会社側が運転手に対して作成する「運行指示書」はツアーの出発地と到着地のほか、経由地などのルートを記載しなければならないが、今回のツアーの指示書には出発地と到着地しかなく、ルートの記載はなかった。また、同様に発着地しか記載のない指示書がほかのツアーでも確認された。
運転手の業務実態を把握するための「点呼簿」という書類でも虚偽記載が判明。通常、運転手は目的地到着後に会社に連絡し、運行管理者が終業の印を押すが、今回は事故があったのに業務終了の押印があったという。
また、運転手の労働時間が基準を超えていたケースや、いつ誰が乗務したかを示す乗務記録や免許証情報の乗務員台帳への記載漏れもあった。運行状況をバス車内で自動的に記録する運行記録計(タコグラフ)に用紙を装着していない車両も見つかった。
「倉庫のような部屋で仮眠するだけ」「夜行や日帰りが多く、道路も危ない」。事故を受けて、各種ツアーの中でもスキーツアーのバス運転手が過酷な勤務を強いられる実態を、同業者たちが証言した。国は事故のたびに規制を強めてきたが、スキーツアーの価格競争は激しく、安全対策がおろそかになっている可能性が浮かんだ。
事故を起こしたバスは14日午後11時に東京都内を出発し、15日午前7時半、長野県内のスキー場に到着。運転手は仮眠を取り、同日午後3時半に別の乗客を乗せ午後9時半に東京に戻る予定だった。東京を出て戻るまでの計22時間半に2人態勢で14時間半運転する。日中の運転しない時間は8時間だ。
40代の元スキーツアーバス運転手は、仮眠の場所を「倉庫」と表現。「熟睡できず、疲れが取れないまま運転する」と打ち明けた。別のバス会社の幹部は「冬の峠道は本当に危ない。うちは1泊じゃないと受けない」と話す。事故を起こしたバス会社の指定する仮眠の場所や時間は不明だが、死亡した運転手は健康診断も受けていない65歳と57歳だった。
スキーツアーでは十数年前からこうした運行が増えたという。2000年以降の規制緩和で貸し切りバス事業が免許制から許可制となり、新規参入が相次ぐ一方、スキー・スノーボード人口は14年時点で最盛期の1993年の約4割に減った。競争相手が増え、パイは縮む構図で、「もともと格安ツアーが多い上に旅行会社はさらに値切ってくる」(東京都内の観光バス業者)と、コストカットの圧力は高まる一方だ。
運転手の高齢化も懸念されている。都内のバス会社社員は「仕事が危険で、休みは固定されず、給料も安い。若い運転手が増えないのは当たり前だ」と指摘。「高齢ドライバーはつぶし(転職)もきかず、低賃金に甘んじざるを得ないので、バス会社にとって都合がいい」と声を落とす。20年以上バスガイドを務める女性(42)は「夜行バスを60歳前後の2人で運行するなど信じられない」と話す。
埼玉県内のバス会社幹部は「運行管理の専従社員の人件費など安全にはコストがかかる。経費節減で安全が犠牲になっていたのでは」と疑問を呈した。
こうした格安ツアーがアルバイトや仕送り頼みの大学生を引きつけている。事故を起こしたバスの乗客39人のうち学生は8割で、死亡した12人も全員が19~22歳の学生だった。【関谷俊介、飯山太郎、藤田剛】
国交省監査
14人が死亡した長野県軽井沢町のスキーツアーバス転落事故で、運行会社の「イーエスピー」(東京都羽村市)では、昨年2月に国土交通省の一般監査を受けた後も、違法な運行管理が常態化していた疑いがあることが同省への取材で分かった。事故後の特別監査では、今回の事故車両に乗務していた運転手以外に、過労運転の疑いがある乗務員が複数確認された。国交省は16日も特別監査を継続し、安全確保のために重要視されるべき運転手の勤務管理が不十分だったとみて実態を詳しく調べる。
イ社は昨年2月、2014年度の業務について国交省の一般監査を受けた。この際、運転手に定期健康診断や適性診断を受けさせなかったことが発覚。同省は道路運送法違反で一部車両の使用停止を命じる行政処分を今月13日付で出した。
だが、15日の特別監査で、バス会社の運行の責任者である運行管理者が、事故車両の2人の運転手に経路を指示するために作成した「運行指示書」に、経路の記載がない不備があったことが確認され、監査後もずさんな管理が続いていた疑いが浮上した。
イ社側は、ツアーを企画した「キースツアー」(東京都渋谷区)側が作成し、簡単な経路が記された行程表と地図を指示書とともに渡し、運転手に経路を指示したとしているが、行程表には2人の運転手が交代する時間や場所などが記されておらず、安全対策が不十分だった。ツアー終了後の点呼では、運転手同士の引き継ぎ状況を確認することになっているが、イ社は往路の途中で事故が起きたにもかかわらず「終業点呼簿」に運行終了を認める印鑑を押していた。
さらに、今回の事故以外の運行で、国の基準を超えて長時間運転していた社員がいる疑いも浮上。国交省は、どのくらい基準を超えていたかや、何人の運転手が過労運転状態だったかなど、詳細を確認している。
走行距離や速度などを記録するためにバスに設置されている「運行記録計」に用紙が装着されておらず、運行状況が記録できていなかったケースも見つかった。分析すれば速度超過や無理な長時間運転の有無が分かるため、道路運送法に基づく規定で記録紙を1年間保存することが義務付けられているが、運行状況を分析できないケースがあるという。運転手の免許証の記載事項や有効期限を転記する乗務員台帳にも、複数の不備が見つかっている。
特別監査で新たに判明したこれらの問題点は、昨年の一般監査で指摘を受けた後の運行を調査して発覚したとされる。国交省は監査を受けても社内で管理体制の改善が進んでいなかったとみて、運行管理者らからも詳しく事情を聴く方針。【内橋寿明、坂口雄亮】
「ツアーバスを巡っては、旅行会社側がバス会社に安価で発注し、バス会社が利益を出すために安全にかかるコストを軽視する実態が指摘されてきた。このため国は45人が死傷した2012年の関越道ツアーバス事故後、貸し切りバスの運賃基準を引き上げた経緯がある。国交省の担当者は『今も下限を下回る運賃が設定されたのは残念。安全を軽視している』と指摘した。」
規制緩和は悪い事ではない。業界の古い慣習に捕らわれず、新しい発想や他の業界では実施されている方法を導入して活性したり成長する可能性もある。ただし、
行政が最低限度の基準をしっかり守らせる、最低限度の規則を守らない業者を処分したり、業界から追放しなければ、無秩序の拡大、そして、比較的まともな
業者が違法行為を含む競争に巻き込まれ、廃業や業界に見切りをつけて閉鎖する可能性もある。
行政である国交省は業者の責任だと責任転嫁せずに、行政としての適切に機能するべきだ。
14人が死亡した長野県軽井沢町のスキーツアーバス転落事故で、バス運行会社の「イーエスピー」(東京都羽村市)が、ツアーを企画した旅行会社「キースツアー」(東京都渋谷区)から、道路運送法が定める貸し切りバスの基準運賃を下回る19万円でバス運行を受注していたことが、国土交通省の特別監査で分かった。イ社を巡ってはずさんな運行管理が相次いで発覚しているが、国交省は利益率の低い受注がイ社の安全運行体制に影響した可能性もあるとみて調べる方針。
ツアー区間は東京から長野県・斑尾高原で往復約680キロ。国の基準運賃は27万円が下限になる。基準に反する運賃は道路運送法違反で、イ社は行政処分(一定期間の車両使用停止)の対象になる。発注したキ社も旅行業法に抵触し、18日間の営業停止処分となる可能性がある。
観光庁などは16日、バスを手配した「トラベルスタンドジャパン」(東京都千代田区)に事情を聴いた。ト社側は「キ社から運賃提案があった。最初から基準を下回っていた」と説明。「キ社から『今冬は雪が少なく客も少ない。当面は低い値段でやってほしい』という要望があった」と明かしたという。料金についてはイ社も「キ社と設定した」と話している。
キ社の福田万吉社長は16日、報道陣の取材に「基準以下の契約とは思っていないが確認する」と話した。
ツアーバスを巡っては、旅行会社側がバス会社に安価で発注し、バス会社が利益を出すために安全にかかるコストを軽視する実態が指摘されてきた。このため国は45人が死傷した2012年の関越道ツアーバス事故後、貸し切りバスの運賃基準を引き上げた経緯がある。国交省の担当者は「今も下限を下回る運賃が設定されたのは残念。安全を軽視している」と指摘した。
一方、イ社の高橋美作(みさく)社長は16日、都内で記者会見し、事故車の運転手2人が出発する前に健康状態などを確認する「点呼」をしていなかったことを明らかにした。点呼は道路運送法に基づいてバス事業者に義務付けられた業務で、高橋社長が担う予定だったが、遅刻してできなかったという。
ツアーバスはその後、運行計画と異なるルートをたどり、国道18号バイパスで事故を起こした。高橋社長は高速道路料金を節約する目的だった可能性について「経費節減で下を走れと指示することはない」と否定した。【内橋寿明、坂口雄亮】
「ずさんな管理が次々と明らかになる中、イーエスピーの高橋社長は、事故の原因についても、『もしかしたら、そういう心のゆるみがあると思っています』と述べた。」
管理が甘い会社は問題が起きるまで人事。問題が起きるとは考えていない。検査や監査が終われば全て終わりと考える。問題に対して言い訳が多い。
いろいろな不備があっても指摘された箇所を修正したから問題が解決したと考えている。
事故が起きる要素が存在しても、必ずしも事故が起きるわけではない。運が良ければ事故は起きない。事故の確率が高くなるだけ。チェックする担当が甘い、チェックする担当が経験不足、又は、チェックする担当が癒着とまでは言えなくても不適切な関係がある場合、問題を抱えている他の企業が問題の指摘を受けない。公平性を考えると矛盾を感じる。公務員であればこのような問題は起きないと上の人間が勘違いしている。これらの点が厄介だと個人的に思う。
大学生など14人が死亡した長野・軽井沢町のスキーバス事故から一夜が明け、バスの運行会社・イーエスピーのずさんな運行管理の実態が、次々と明らかになっている。
たとえば、事故のバスが無事に目的地に到着したとする運行記録を作成していた。
経由地などのルートを示す指示書には、出発地と到着地しか書かれていなかった。
ほかにも、運転手に健康診断を受けさせていなかった。
出発前の点呼を確認する書類に、あらかじめ点呼が済んだことを示す印鑑が押されていたことを会社の関係者が認めるなど、安全対策を軽視していたのではないかとの疑いが高まる中、16日午後、バスの運行会社の社長が、事故後、初めて会見を行った。
イーエスピーの高橋美作社長は、「重大な事故を起こしてしまい、あらためておわび申し上げます」、「(点呼について?)当日は点呼をせずに出かけてしまいました」、「(点呼をしなかった理由について)わたしが遅れてしまい、立ち会うことができませんでした。申し訳ありませんでした」、「(点呼簿の押印について)関わるものには、はんこが押してありました」などと話した。
イーエスピーの荒井 強本社所長は「(押印した理由について)正直なところ、数値とチェックだけで、なるべく社長に負担をかけないようにということで。わたしがはんこを押していた」などと話した。
高橋美作社長は、「(健康診断について)(土屋さんは)入社の際に、前の会社で12月10日前後に健康診断をしたということを、きのう確認しました」、「大変な迷惑をおかけしまして、申し訳ありませんでした」などと話した。
バス会社・イーエスピーでは、16日午後、1時間30分にわたり会見が行われ、冒頭、謝罪のため、社長らが6回にわたり、頭を下げた。
会見では、事故を起こしたバスの運行記録について、出発前の点呼や、目的地に到着したことを確認しないまま、運行管理責任者が印鑑を事前に押していたことを明らかにした。
また、同じようなことは、これまでに4~5回やっていたとしていて、理由については、「高橋社長の手間を省くためにやった」などと話している。
また、土屋さんが2015年12月、会社で働いてから、これまでに健康診断を受けていなかったことについては、前の会社で受けたとの話を聞いていたためとしたが、診断書を確認するなどはしていなかった。
また、ほかのドライバーに対しても、必要な期間に健康診断を行っていないことについても、「個人個人で医者に行っているので、健康状態がどうなのかを把握していた」と説明した。
ずさんな管理が次々と明らかになる中、イーエスピーの高橋社長は、事故の原因についても、「もしかしたら、そういう心のゆるみがあると思っています」と述べた。
今後、国交省などが調べを進めることで、バスの運行の安全に対し、いかに規制をしていくのかが課題となるとみられる。
「調査では、廃棄されたビーフカツを横流しした産業廃棄物処理会社「ダイコー」(稲沢市)からスーパーなど小売店への流れを追っているが、現金取引が大半で、伝票類を保管していない業者もある。ダイコーの転売先の『みのりフーズ』(岐阜県羽島市)の法的な調査権を持つ岐阜県との情報共有など、緊密な連携も不可欠となる。」
確信犯的な対応が見られる。早急な法改正又は規則の改正が必要。すみやかな対応を行わないと同じような不正が繰り返される。
「カレーハウスCoCo壱番屋」を展開する壱番屋(愛知県一宮市)が廃棄した冷凍ビーフカツの不正転売事件で食の安全への不安が広がる中、県などの調査が続いている。
複雑な流通経路が調査を難しくしているが、県幹部は「不安を払拭するため、全力で取り組む」と話している。
「廃棄された加工食品が商品になって流通する異例の事態。食の安全を確保するため、職員が総出で対応しているが、流通経路は複雑で終わりは見えない」。15日午後、県保健医療局の幹部はこう語った。
県に壱番屋から情報が入ったのは12日夕。以降、生活衛生課と県内の保健所、廃棄物監視指導室などが連携し、問題のビーフカツ約4万枚の流通経路を調べている。
これまでに立ち入り調査し、ビーフカツの販売や使用、流通が確認されたのは35施設(名古屋、豊田、岡崎市分を含む)。食品指導を担当する保健所の職員や拠点となる保健所に設けられた食品広域機動グループの職員が手分けして各業者を回り、ビーフカツを入手した経緯や販売実績、保管状況などを確認している。
調査では、廃棄されたビーフカツを横流しした産業廃棄物処理会社「ダイコー」(稲沢市)からスーパーなど小売店への流れを追っているが、現金取引が大半で、伝票類を保管していない業者もある。ダイコーの転売先の「みのりフーズ」(岐阜県羽島市)の法的な調査権を持つ岐阜県との情報共有など、緊密な連携も不可欠となる。
15日までの県の調査では転売された約4万枚のうち、約2万5000枚の流通経路が判明したが、ダイコーが堆肥処理したとしている7000枚を除く8000枚は依然不明だ。
不正転売が発覚した後、県の相談窓口には「商品を買ったが大丈夫か」などの相談が多数寄せられており、この間、製造日の異なる別のビーフカツの転売も明らかになったほか、チキンカツなど別のカツが出回った可能性も出ている。県幹部は「県民の不安を取り除くため、出来るだけの調査をしていく」としている。(小山内晃)
「もう一つは12年4月、群馬県藤岡市の関越自動車道で起きた事故。ツアーバスが壁に衝突して45人が死傷。運転手が眠気を感じながら運転を続けたとされる。国交省は12~13年、1日の距離の上限を昼間は原則500キロ、夜間は400キロに引き下げ、運行記録計を使った運行管理を義務付けた。運賃制度も改定し、基準運賃の下限と上限をともに引き上げた。
これによって『コストをかけられない零細業者はかなり淘汰(とうた)された』(都内の旅行会社)という。」
淘汰と言うよりは、厳しい規則を守りながら存続するメリットがないと判断した零細業者、又は、発注者の要求する条件や料金を受け入れ、事故が起きれば責任を負う環境での存続
によりマーケットから離れた零細業者がいたと言う事ではないのか?
「 都内のバス会社94社が加盟する東京バス協会は、運転手の睡眠時無呼吸症候群の検査費用や車両の安全装置について補助を設けるなど『ハード、ソフト両面から対策を進めてきた』(市橋千秋常務理事)。だが、安全対策を周知するのは会員企業に対してだけ。今回事故を起こしたイーエスピーは非会員で、こうした対策も業界全体に浸透しているかは不透明だ。【関谷俊介、福島祥、黒川晋史】 」
国土交通省はこのような状況を把握しているのか知らないが、規則を守らない業者は存続できると言う事の裏返しである。
「低賃金で人手不足の状況では運転手への負担は増す。」
このジレンマが解消されなければ、今後、さらなる運転手不足が深刻になるであろう。低賃金だから魅力がなく若い世代が入ってこない。既に運転手で経験があれば、
多くの運転手は転職も難しいので年金が貰えるまで我慢するのであろう。その後は外国人運転手でも使うのだろうか?負のサイクルの加速だ!
このような状況を無視して、オリンピックを理由に税金を溝に捨てるように注ぎ込む日本。もっと考える事があると思う。
似たような問題はバス事業だけではないと思う。日本政府は時給を単純に上げることを考えるのではなく、将来を考えながら対応しないと日本の崩壊は加速する。
長野県軽井沢町で起きたスキーツアーバスの転落事故は、運転手2人と多数の乗客が死傷した。バス業界は国の規制緩和を受けて事業参入が相次いだが、過当競争を背景にしたツアーバスの事故が続き、国の安全対策が後手に回ってきた経緯がある。今回の事故は、規制強化で業界の安全意識に変化も見え始めた中で起こった。
多くの高速バスが発着する東京・新宿駅西口。15日午後、路肩にバスを止めて乗客を待っていた40代の運転手は「事故は人ごとではない。会社からも安全運転を徹底するよう通知があった」と心配顔で語った。
バス業界が様変わりしたのは2000~02年の規制緩和だ。需給調整の観点から国の免許制だったのが、一定の要件を満たした事業者であれば誰でも参入できる事業許可制へと切り替えられ、貸し切りバス事業の新規参入が相次いだ。今回の事故を起こしたバス運行会社「イーエスピー」も08年の設立当初は警備業務が中心で、バス事業は14年5月の後発組だ。
ツアー会社が企画し、貸し切りバス会社が運行するツアーバスは、乗り合いバスと違って運行計画を事前に国土交通省に届け出るなどの規制が少ない。過当競争の一方、安全性の問題が指摘されていた。二つの事故がそんな中で起きた。
一つは07年2月、大阪府吹田市でツアーバスがモノレールの橋脚に衝突し、27人が死傷した事故。運転手の居眠りが原因だった。国交省は08年6月、1人が運転できる1日の最大運転距離を670キロとする指針を定め、超える場合は交代運転手の配置を求めた。
もう一つは12年4月、群馬県藤岡市の関越自動車道で起きた事故。ツアーバスが壁に衝突して45人が死傷。運転手が眠気を感じながら運転を続けたとされる。国交省は12~13年、1日の距離の上限を昼間は原則500キロ、夜間は400キロに引き下げ、運行記録計を使った運行管理を義務付けた。運賃制度も改定し、基準運賃の下限と上限をともに引き上げた。
これによって「コストをかけられない零細業者はかなり淘汰(とうた)された」(都内の旅行会社)という。
旅行会社「ビッグホリデー」(東京都文京区)によると、バス会社の安全対策コストが上昇。旅行会社がバス会社に支払う額も1・5倍ほどに膨らんだ。
今回ツアーを企画した旅行会社「キースツアー」のツアー料金は1、2泊の宿泊費やリフト代を含めて1万3000~2万円程度。別の旅行会社は「バス業界全体では安全意識が改善されており以前のような価格では商品を提供できなくなった。うちのツアーは東京−上高地間の場合、バス料金だけで往復1万4000円以上する。キ社のツアー料金は非常に安い。かなりコストをカットしていたのではないか」と指摘した。
これに対し、キ社の福田万吉社長は報道陣の取材に「安全面を削ることは絶対ない」と話している。
都内のバス会社94社が加盟する東京バス協会は、運転手の睡眠時無呼吸症候群の検査費用や車両の安全装置について補助を設けるなど「ハード、ソフト両面から対策を進めてきた」(市橋千秋常務理事)。だが、安全対策を周知するのは会員企業に対してだけ。今回事故を起こしたイーエスピーは非会員で、こうした対策も業界全体に浸透しているかは不透明だ。【関谷俊介、福島祥、黒川晋史】
運転手不足・高齢化も
バス運転手不足や高齢化といった業界の課題や、事故の原因の変化を物語る統計がある。
一つは14年7月にまとめた国交省検討会の報告書。運転手は10年間にわたってほぼ横ばいの約13万人で推移しているものの、報告書は長期的には路線バスの運転手は減少傾向にあり、1人あたりの走行距離も増加傾向にあると分析した。
運転手の平均年齢は、10年前と比べて45・9歳から48・3歳へと上昇し、6人に1人が60歳以上と高齢化が目立った。一方、運転手の年間所得は440万円で、全産業の平均469万円を下回った。
検討会が実施したバス事業者に対するアンケートでは回答した35社の97%が「運転手不足による影響を実感している」と回答した。
もう一つは、国交省の「自動車運送事業用自動車事故統計年報」。バス運転手の健康状態に起因した事故は03年に18件だったのが12年は58件で、9年間で3倍以上にも増えていた。病名別では消化器系疾患が7件と最多で、くも膜下出血などの脳疾患6件、失神とめまいの4件が続いた。
低賃金で人手不足の状況では運転手への負担は増す。全国交通運輸労働組合総連合の担当者は言った。「少しぐらい体調が悪くてもバスに乗れば金になる。『体調は大丈夫か』と問われれば、少し無理をしても『大丈夫』と答える悪循環になる」【内橋寿明、東海林智】
お互いが言い争い始めたら、黙って会話を録音しておくとかして証拠を残しておかないと裁判になると長期化するだろう。
仕事を取る為には相手の間違いや問題を指摘せずに、「はい」とか「わかりました」とか、口頭だけで説明したほうが良い事も多い。
なぜなのか?文書や証拠として残る形で伝えると、万一、事故や問題が発生すると責任が明確になる。仕事を発注する側としてはそのような
リスクをチラつかす下請けよりも、問題が起きれば責任を転嫁しやすい下請けを選ぶはずである。多くの人が見積もりが同じである場合、
問題が起きれば責任を転嫁しやすい下請けを選ぶはずである。力関係の悲しい事実。
杭打ちデータの流用問題にしても似たような状況であると思う。
その他の情報:
長野県軽井沢町のバイパスでスキーバス事故
国土交通省や警察が真実を見るける事が出来るのか、事実や報告書を国土交通省がどのように生かすのかが残された問題。亡くなった被害者や後遺症が残る
怪我を負った人が事故前の状態に戻る事はない。
今回事故を起こしたバスが、“なぜ、行程表に記載されていないルートを通ったか”という点について、ツアーを企画した旅行会社側と、バスの運行会社側との間で、言い分の食い違いが出てきています。
「座席表も渡しているし、人数表も渡しているので、下車場所の地図も一緒に添付して(バス運行会社に)渡してあるので」(キースツアー 福田万吉 代表取締役)
今回の事故をめぐっては、“なぜ、バスが行程表に記載されていないルートを選択したか”という疑問が残っています。
これについて旅行会社側は、事故発生後、一貫して「運転手が判断したとしか考えられない」としていましたが、バス運行会社側は「旅行会社の担当者には事前に伝えていた」ことを明らかにしました。
「あの行程表のパーキングエリアだと、止められなかったことが多かったみたい。キースツアーには報告していたが、あくまでも担当者のレベルの話。社長の耳には入っていなかったようだ」(イーエスピー 山本崇人 営業部長)
バス運行会社側は、「ルートの変更は混雑を回避するための運転手なりに工夫だった」と説明しています。
国土交通省は16日午前、バス運行会社に監査に入り、社長らから事情を聴く方針ですが、こうした双方の言い分の食い違いや、運行自体に問題がなかったかなどについて詳しく調べる方針です。
スキーツアーなどに利用される貸し切りバスを巡っては、16年前の規制緩和に伴って参入する業者が大幅に増えた一方で、乗客が犠牲になるバス事故が相次ぎ、そのたびに規制が強化されてきました。
スキーツアーや修学旅行などに利用される貸し切りバスは、平成12年に免許制から許可制に規制が緩和されました。これに伴って多くの業者が参入し、現在は貸切バスの事業者は、規制緩和の前の2倍近くのおよそ4500社にまで増え、競争が一気に激化しました。こうしたなかで夜行の貸し切りバスの事故が相次ぎました。
平成19年2月には大阪・吹田市で、スキーツアーの貸し切りバスが道路脇の橋脚に衝突し、誘導員の男性1人が死亡し、乗客など26人が重軽傷を負いました。
平成24年4月には群馬県藤岡市の関越自動車道で、石川県から東京ディズニーランドに向かっていた貸し切りバスが道路脇の壁に衝突し、乗客7人が死亡、38人がけがをしました。いずれも運転手の居眠りが事故の原因とみられています。
これらの事故を受けて、国土交通省では安全基準を見直し、夜間、運転手が1人で乗務できる距離の上限を原則400キロまで短縮し、それを超える場合は交代の運転手と2人で乗務することが義務づけられました。
また、安全管理の責任を明確にするためツアーの企画会社にも、バスを運行する場合は国の許可を取らせるなど、規制を大幅に強化しました。
さらに、国が定めた適正な価格の範囲を不法に下回るような安い料金を掲げる事業者も現れたことから、おととし、バス会社が適正な運賃を得られるよう制度を変更し、行政指導を強化しました。
しかし、業者の数が大幅に増えたため監査など国のチェックが追いついておらず、バス会社の中には無理な運行計画を立てたり、乗務員の健康管理を行っていなかったりするなど、安全管理が不十分な業者もあると指摘する専門家もいます。
営業部長、入社時の健康診断をしていなかったことを謝罪
長野県軽井沢町の国道18号碓氷バイパスのスキーツアーバス事故で、事故を起こしたバスを運行していた「イーエスピー」(東京都羽村市)には15日午後、国土交通省の特別監査や長野県警の家宅捜索が相次いで入った。取材に応じた山本崇人営業部長は、「分からないことがたくさんある」と硬い表情で語った。
山本部長は事故当時バスを運転していたとみられる土屋広運転手(65)の入社時に健康診断や適性検査をしていなかったことを謝罪。本人の申告から、健康上の問題や過去の事故歴はないと確認したという。健康診断を実施しなかったことに「特に理由はない」としたうえで、「(土屋運転手は)繁忙期など(人手が)足りない時に助けていただくことを主とした運転手だった。2月には行う予定だった」と釈明した。
土屋運転手は2000年からドライバーとして働いていた。ただ、昨年12月にイーエスピーに入社するまで約5年間勤務していた会社では主にマイクロバスを運転し、大型バスには乗務していなかったとされる。
これに対し、山本部長は「入社以前も大型バスの運転はあったと聞いている」と説明。同社のドライバーが同乗し、研修として3回大型バスを運転してもらった後、乗務を任せるようになったという。事故当時は大型バスの4回目の乗務だったが、長野県北部方面へのツアーを担当したのが初めてだったかどうかは「確認できていない」と述べた。
交代要員として乗車していた勝原恵造運転手(57)は02年からドライバーをしており、「共にバスの素人ということはない」と話した。
一方、バスが行程表で定められたルートを変更した理由については「分からない」とし、ルート変更時に必要となる運行管理者への連絡はなかったと説明した。【山田麻未】
雇い入れ時 65歳以上の適性検査も実施せず
長野県軽井沢町の国道18号碓氷バイパスのスキーツアーバス事故で、バスを運行していた東京都羽村市の「イーエスピー」は15日夜、事故があったバスを運転していた土屋広運転手(65)を昨年12月に採用した際、労働安全衛生法で義務付けられた雇い入れ時の健康診断を実施していなかったと明らかにした。65歳以上のバス運転手に求められる適性検査も実施していなかった。同社は運転手への健康診断を怠っていたとして、今月13日付で国土交通省から道路運送法違反で行政処分(車両使用停止処分)を受けたばかりで、同省は特別監査を実施して詳しい経緯を調べている。
国交省は昨年2月、道路運送法に基づき、イーエスピーに対し2014年度中の業務の定期監査を実施。13人の運転手のうち10人について、年1回(深夜業務従事者の場合は2回)実施すべき健康診断を受けさせていなかったことが判明した。初任運転手への適性検査も怠っていた。国交省は今月13日付でイーエスピーが所有するバス7台(大型5台、中型・小型各1台)のうち、中型バス1台の使用を20日間禁じる処分を出した。
また、イーエスピーによると、バスは予定していた高速道路を利用するルートを通らず、一般道を走行中に事故を起こしたが、バス側から会社側への変更の連絡は確認されていないという。運行管理者の許可なくルートを変更した場合は道路運送法に違反する可能性があり、国交省はこの点についても会社側の態勢に問題がなかったか調べている。【山田麻未、坂口雄亮】
「県によると、新たに見つかった壱番屋の商品は、チキンカツ162枚、メンチカツ82枚、ロースカツ139枚。いずれも賞味期限が切れていたり、期限が不明だった。
冷凍庫には壱番屋の商品以外にも、骨付きフライドチキンなど200箱以上が保管してあり、大半は賞味期限切れだった。」
製麺業者「みのりフーズ」の実質経営者岡田正男氏はこの手の商売をおこなっていた可能性は高いと思う。
問題が発覚しなければ、両者とも儲けたと思う。世の中、問題が発覚しない、又は、公表されないだけで、おかしな事はたくさんある。
カレーチェーン店「CoCo壱番屋」を展開する壱番屋の廃棄した冷凍ビーフカツが横流しされた問題で、岐阜県は15日、羽島市の製麺業者「みのりフーズ」の冷凍庫から新たに壱番屋のメンチカツとロースカツが見つかったと発表した。
壱番屋から処分を依頼された産廃業者「ダイコー」(愛知県稲沢市)の横流しが発覚したビーフカツなどと同様に、いずれも一般に流通することはなく、不正な転売が常態化していた疑いがある。
県によると、新たに見つかった壱番屋の商品は、チキンカツ162枚、メンチカツ82枚、ロースカツ139枚。いずれも賞味期限が切れていたり、期限が不明だった。
冷凍庫には壱番屋の商品以外にも、骨付きフライドチキンなど200箱以上が保管してあり、大半は賞味期限切れだった。みのりフーズの実質経営者岡田正男氏(78)は県に「ダイコーから入手した」と説明した。
多治見市光ケ丘のスーパー「ヒバリヤ多治見店」で、問題のビーフカツ計885枚が販売されていたことも判明。県によると、ヒバリヤはみのりフーズから複数の業者を経て2300枚購入、昨年9月から今月まで総菜として店頭販売した。壱番屋の商品という認識はなかったという。
また、スーパーを展開する山彦(愛知県稲沢市)は同日、海津市の生鮮館やまひこ海津店で壱番屋のビーフカツ100枚を総菜として販売したと発表した。在庫はないという。
「1回に200箱ほど購入し、多くを販売を任せていた知人男性が箱を詰め替えて売ったという。岡田氏も付き合いのある羽島市内の弁当店などに販売。伝票や領収書を残さず、現金で取引していたことに関してもダイコー側からの指示だったとした。」
おかしなビジネスには手を出すなという教訓になるケース?常識があれば、おかしな指示を受けた時点で疑わなければならない。「伝票や領収書を残さず、現金で取引していた」=証拠を残さない対策と考えられる。
製麺業者「みのりフーズ」の実質経営者岡田正男氏は不審に思わなかったのか?
問題が発覚しなければ、両者とも儲けたと思う。世の中、問題が発覚しない、又は、公表されないだけで、おかしな事はたくさんある。
カレーチェーン店「CoCo壱番屋」が廃棄した冷凍カツが横流しされた問題で、岐阜県羽島市の製麺業者「みのりフーズ」の実質経営者岡田正男氏(78)は15日、メンチカツやロースカツなど新たに別の商品の転売を認めた。その上で「3~4日前に事態が明るみに出て(ダイコー側から)分かっていないことまでは話すな」と指示されたと明かし、「本当にばかなことをしたと思っている」と後悔の念を口にした。
岡田氏によると、取引はチキンカツ10箱ほどを無償で受け取ったことがきっかけ。次第に物量が多くなり、「売り先はないか」と転売へと発展した。廃棄物との認識はなかったという。
1回に200箱ほど購入し、多くを販売を任せていた知人男性が箱を詰め替えて売ったという。岡田氏も付き合いのある羽島市内の弁当店などに販売。伝票や領収書を残さず、現金で取引していたことに関してもダイコー側からの指示だったとした。岡田氏は「弁当屋さんに喜んでもらえるのではとやっていたが、今になってみれば申し訳ないことをした」と話した。
「廃棄物だという認識はなかった」。岐阜県羽島市の製麺業者「みのりフーズ」の実質経営者、岡田正男氏(78)は14日、愛知県内で報道陣の取材に応じ、意図的な偽装ではなかったことを強調した。その上で「(結果として)悪いことをしたと思うが、流れてしまったものは仕方がない」と開き直った。
岡田氏によると、産廃業者「ダイコー」の大西一幸社長とは4年ほど前に知り合った。
「いい食材があるが、販売先はないか」と持ち掛けられ、冷凍カツは過去に2回、300箱ずつ仕入れたという。仕入れ値は1箱(30枚入り)約1000円。サンプルを食べ、品質に問題がないと判断し、知人男性が交渉した販売先に2~3割増しで転売したという。
壱番屋のロゴが入った段ボール箱に入っていた冷凍カツを転売する際、別の箱に詰め替えていたことについては「ダイコーから別の箱に変えてくれと頼まれたから」と説明。
また「なぜ安いかは考えもしなかった」とした上で「産廃業者だと知っていたが、ごみだとは普通思わない。商品自体を信用していた」と語気を強めた。
壱番屋チキンカツも販売 羽島市の業者
壱番屋の冷凍ビーフカツを産廃業者「ダイコー」から購入した岐阜県羽島市の製麺業者「みのりフーズ」が、壱番屋の冷凍チキンカツを市内の取引先の弁当店に販売していたことが15日、分かった。岐阜県が14日、みのりフーズと弁当店に立ち入り調査し、2カ所の冷凍庫から計15枚のチキンカツが見つかった。壱番屋はチキンカツを一般販売していない。
県によると、チキンカツは5枚入り1袋で、みのりフーズの冷凍庫に1袋保管。弁当店の冷凍庫には2袋のほか、空の袋が見つかった。いずれも賞味期限は切れていた。
実質経営者の岡田正男氏は「ダイコーから譲り受けた」と説明。伝票などの記録はなく入手時期については「記憶がない」と話している。
弁当店は、みのりフーズから過去にもチキンカツを購入したが「壱番屋の商品という認識はなかった」と説明。壱番屋は県に「チキンカツは自主廃棄するためダイコーに処分を依頼した」と説明しているという。
壱番屋の冷凍ビーフカツを産廃業者「ダイコー」から購入した岐阜県羽島市の製麺業者「みのりフーズ」が、壱番屋の冷凍チキンカツを市内の取引先の弁当店に販売していたことが15日、分かった。岐阜県が14日、みのりフーズと弁当店に立ち入り調査し、2カ所の冷凍庫から計15枚のチキンカツが見つかった。壱番屋はチキンカツを一般販売していない。
県によると、チキンカツは5枚入り1袋で、みのりフーズの冷凍庫に1袋保管。弁当店の冷凍庫には2袋のほか、空の袋が見つかった。いずれも賞味期限は切れていた。
実質経営者の岡田正男氏は「ダイコーから譲り受けた」と説明。伝票などの記録はなく入手時期については「記憶がない」と話している。
弁当店は、みのりフーズから過去にもチキンカツを購入したが「壱番屋の商品という認識はなかった」と説明。壱番屋は県に「チキンカツは自主廃棄するためダイコーに処分を依頼した」と説明しているという。
壱番屋が廃棄したビーフカツが流通していた問題で、岐阜県は13日、羽島市上中町長間、麺類製造業「みのりフーズ」が「ダイコー」からビーフカツを購入し、愛知県内の個人業者と企業2社に転売していた、と発表した。立ち入り調査で壱番屋の名前が印刷された空の段ボール箱約800箱が見つかった。
愛知県の調査依頼を受けて、同日午後にみのりフーズへ立ち入り調査した。ダイコーとの具体的な取引を示す伝票は見つからなかったが、空の段ボール箱がたたんだ状態で残っていたという。
食品衛生責任者となっている男性従業員は県の聞き取りに対し、▽ダイコーの依頼を受けて、独断でビーフカツの取引を行ったこと▽ビーフカツを他の箱に詰め替えて愛知県内の個人業者と企業2社に全量を販売した―などと説明したという。取引の数量や時期は「記憶にない」と話しているという。県は取引の詳細を調査している。
「ザハ氏側には、昨年7月に契約解除を通告しており、それまでの期間のデザイン監修料の一部として、すでに13億円を支払っている。」
使えもしない物に13億円ものお金を使った。挙句の果てに問題は解決されていない。日本スポーツ振興センター(JSC)は責任を取るべきだ。
日本的にしか物事を考えられない日本スポーツ振興センター(JSC)がオリンピック開催に関して権限を持っている事自体が間違い。
キャンセルできるのなら、オリンピックはキャンセルで良い。東京オリンピックの時代と現在は違う。
2020年の東京五輪・パラリンピックのメインスタジアムとなる新国立競技場で事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)が、白紙撤回となった旧計画のデザインを手掛けたザハ・ハディド氏の建築事務所へデザインの未納代金を全額支払うのと引き換えに、著作権を譲るよう書面で要請していたことが13日、分かった。
ザハ氏側は、声明で要請を拒否したことを明かした上で、支払いと引き換えに事業についてのコメントを封じる追加の契約条項への署名をJSCが求め、これも拒んだと説明。ザハ氏らは昨年12月、新たに採用された大成建設、梓設計と建築家の隈研吾氏の計画案について、自らのデザインと「驚くほど似ている」とし、調査を開始したことを発表していた。
JSCは「ザハ氏の事務所側と、契約解除後の監修料の清算について、協議をしていることは事実です」と答えたが「内容については、具体的には答えられません」。ザハ氏側には、昨年7月に契約解除を通告しており、それまでの期間のデザイン監修料の一部として、すでに13億円を支払っている。
事務所は、JSCが競技場のデザインに関する「知的財産権の問題を認めた」と主張。英紙デーリー・テレグラフ(電子版)によると、デザインの著作権を得ようとするJSCに対して怒りの反応を示しているとし、満足のいく対応がなされない場合は法的措置を取る方針と報じている。
大手でこのような事故が起きるなんて!小さいと所で古いクレーンになると腐食して穴が開くまで手入れをせずに歩くのが不安に感じる事もある。
しかし、検査で指摘されないのだから仕方がないと思っていた。今回の死亡事故でクレーンに関する検査が厳しくなるだろう。
場所によってはタッチアップペイントや塗装が難しいところもあるが、こまめに手入れをする事が重要だと思う。腐食がひどくなった後では手遅れ。
13日午前、川崎市にあるJFEスチールの工場にある高さおよそ20メートルの大型クレーンの操縦室近くの床が抜け、作業員の男性が転落して死亡しました。
事故が起きたのは、川崎区扇島にあるJFEスチールの工場です。警察によりますと、13日午前10時前、作業員の男性が大型クレーンの点検作業を行うために高さおよそ20メートルの位置にある操縦室に入ろうとしたところ、突然、床が抜けたということです。転落した男性は頭を強く打ち、その場で死亡が確認されました。
死亡したのはJFEスチールの社員・鈴木健太さん(39)で、午前9時過ぎから2人で大型クレーンの点検作業をしていたということです。
警察は業務上過失致死の疑いもあるとして、床が抜けた原因を調べています。
「同会の経理などの事務は事務局長を含む職員2人が担っている。旧厚生省OBの事務局長は毎日新聞の取材に『私どものやり方にお粗末なところがあった。なかなか(修正を)やっている時間がないことがあり、段々遅れた』と話している。」
旧厚生省OBであれば規則は規則として対応しなければならない事ぐらい理解しているはず。公務員が国民に対して、強要し実行してきた事。天下り先としか考えてないし、OBとして手心を加えてもらえる考えているのだろうか?
「元会計検査院局長の有川博・日本大教授(公共政策)は『適正な決算書を提出できず、仮に監査報告書も虚偽ということになれば、公益法人として不適切なことは明らか』と指摘する。」
どこが担当でチェックしているのか?問題があれば公益法人の認定を取り消せば良い。
「1971年3月の設立で、2011年12月に公益法人に認定された。」
くい打ちデータ改ざん問題で、国土交通省は13日、傾斜した横浜市のマンションを施工した元請けの三井住友建設(東京)と1次下請けの日立ハイテクノロジーズ(同)、2次下請けの旭化成建材(同)の計3社を建設業法に基づき処分した。
三井住友建設には業務改善命令を出し、内規に基づき国交省発注工事の指名停止1カ月とした。日立ハイテクノロジーズと旭化成建材は業務改善命令と15日間の営業停止とした。
国交省によると、下請け2社は専従の現場責任者を置かず、建設業法が禁じる「工事の丸投げ」を行った。三井住友建設は事情を知りながら指導を怠っていた。
国交省の石川雄一関東地方整備局長が13日午後、3社の社長らに処分書などを手渡した。
時代の流れと運の悪さが重なったケースかも?てんかん発作を抱えている人達は教訓にして事故の再発防止に努め、医者や行政はてんかん発作のリスクを抱える人達の 運転を禁止できるようにするべきだと思う。
京都・祇園で2012年4月、軽ワゴン車が暴走し、通行人ら19人が死傷した事故で、車を運転していた男(当時30歳、死亡)が勤務していた呉服店「藍香房あいこうぼう」(京都市下京区)が8日付で事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったと、帝国データバンク京都支店が12日、発表した。
同支店によると、負債総額は5億7000万円に上るとみられる。和装離れによる需要の低迷に加え、事故の影響で来店者数が急減。15年1月期の売上高は約2億円と、02年1月期のピーク時から3分の1以下に減少していた。
同社の中西良子社長は、代理人の弁護士を通じ、「事故の影響による経営難に対処してきたが、業績回復の見通しが立たず、今回の判断に至った」とのコメントを出した。
「同会の経理などの事務は事務局長を含む職員2人が担っている。旧厚生省OBの事務局長は毎日新聞の取材に『私どものやり方にお粗末なところがあった。なかなか(修正を)やっている時間がないことがあり、段々遅れた』と話している。」
旧厚生省OBであれば規則は規則として対応しなければならない事ぐらい理解しているはず。公務員が国民に対して、強要し実行してきた事。天下り先としか考えてないし、OBとして手心を加えてもらえる考えているのだろうか?
「元会計検査院局長の有川博・日本大教授(公共政策)は『適正な決算書を提出できず、仮に監査報告書も虚偽ということになれば、公益法人として不適切なことは明らか』と指摘する。」
どこが担当でチェックしているのか?問題があれば公益法人の認定を取り消せば良い。
「1971年3月の設立で、2011年12月に公益法人に認定された。」
里親制度の普及啓発や調査研究を行っている公益財団法人「全国里親会」(東京都港区)が、2012年度以降の決算書を適正に作成していないとして、内閣府が修正を求めていることが分かった。監査報告書の一部では担当した税理士の署名が別人の筆跡とみられるケースもあり、内閣府は決算書作成の経緯を調べる方針。【武本光政】
◇監査報告書、署名偽造か
同会の事業には厚生労働省の補助金も充てられており、使い道に問題があれば調査するとみられる。ずさんな経理処理が行われていた形で、専門家は「公益法人として不適切」と指摘する。
公益法人は、公共性が高いなどとして内閣府(一つの都道府県内で活動する法人は所在地の都道府県)の認定を受けると、税制上の優遇措置を受けられる。この場合、年度終了後3カ月以内に決算書などを作成し、内閣府などに提出することが法令で義務づけられている。
ところが、内閣府や同会によると、12年度の決算書に計算ミスがあったほか、財産の増減の詳細を記した書類が添付されていないなどした。内閣府が決算書を出し直すよう求めているものの、15年末時点で最終的に修正した決算書は提出されていない。同会は13、14両年度の決算書を既に内閣府に提出しているが、12年度の修正内容を反映させる必要があるため、内閣府は13年度以降についても順次修正を求める。
さらに、14年度決算を「適正」と認定した15年5月19日付の監査報告書について、作成者の一人で同会の役員(監事)を務めていた税理士の署名が、過去の報告書の筆跡と異なる疑いが強まった。決算の妥当性などを記す監査報告書は、監事による作成が法令で義務づけられている。
同会の経理などの事務は事務局長を含む職員2人が担っている。旧厚生省OBの事務局長は毎日新聞の取材に「私どものやり方にお粗末なところがあった。なかなか(修正を)やっている時間がないことがあり、段々遅れた」と話している。
また、問題の監査報告書の筆跡について、事務局長は「(税理士と)違う」と認め、「税理士が入退院を繰り返していたので、税理士の弟に(署名を)頼んだかもしれない。詳しいことは覚えていない」と説明した。
事務局長によると、税理士は15年夏に死去したが、登記上は監事のままになっている。
全国里親会が現時点で公表している14年度決算書によると、一般会計と特別会計を合わせた収入総額は約9000万円。内閣府の担当者は取材に「事実関係を確認する」と語った。
◇厚労省から補助金
里親制度は、虐待などが原因で親元で暮らせない子どもたちを、都道府県などの委託を受けた一般家庭で育てるもの。子どもは施設より家庭的な環境で養育する方が望ましいとして、厚生労働省は近年、制度拡充を図る方針を打ち出している。
2012年度には、里親支援に向けた調査研究事業のための補助金を設け、全国里親会に対し、別の団体を経由して年間1400万円程度を随意契約で支払っている。
一方、全国里親会を巡っては、12~13年度に同事業の研究員として働いていた女性が、職場でパワーハラスメントを受けたとして同会などに約300万円の賠償を求めて14年に提訴している。全国里親会側は反論し、さいたま地裁で係争中。
元会計検査院局長の有川博・日本大教授(公共政策)は「適正な決算書を提出できず、仮に監査報告書も虚偽ということになれば、公益法人として不適切なことは明らか」と指摘する。
【ことば】全国里親会
1971年3月の設立で、2011年12月に公益法人に認定された。各地の里親らが入会する都道府県・政令指定都市単位の地方里親会の代表者らが役員を務め、運営費は地方里親会などからの会費や民間団体からの助成金などで賄われている。15年度の収入総額は予算ベースで約8600万円。
「売買の仲介契約時に、住宅診断を行うかどうかを売り主や買い主に確認するよう不動産仲介業者に義務付ける。」
中古住宅診断を行う個人、又は、企業の資格や罰則を明確して、抜き打ち検査の実施などで最低基準を維持しないと骨抜きになる。
国の基準に基いて資格を持つ検査会社の不正を考えると、中古住宅診断の報告書で素人を騙す事はもっと簡単だ。現実を考えて対応しないと購入後のトラブルは思ったほど減らないと思う。
トラブル後の言い訳も簡単だ。中古だからとか、新築と違って診断が難しいとか、中古で十分な資料が保管されていないとか、いい訳などいくらでも考えられる。
裁判に持ち込んだとしても、白黒つけるのは難しいのではないかと個人的に思う。
国交省は素人の立場で考えないと法改正しても良い結果にはならない。
中古住宅診断書を受ければ良いだけなら、所有者や売り手に有利な診断書を作成する業者を選べば良い。診断書の適正を判断するのは素人には無理。
国土交通省は10日、中古住宅を安心して売買できるよう、専門家が家屋の傷み具合を調べる住宅診断を促進する方針を決めた。
売買の仲介契約時に、住宅診断を行うかどうかを売り主や買い主に確認するよう不動産仲介業者に義務付ける。今国会に宅地建物取引業法の改正案を提出、2018年の施行を目指す。
質が担保された中古住宅が増えれば、選択の幅が広がり、若年層がマイホームを取得しやすくなるほか、リフォーム市場の活性化にもつながる。中古住宅の売買が住宅取引全体に占める割合は、日本では約1割だが、住宅診断が普及している欧米では7~9割を占める。
そこで同省は、住宅診断の普及を進め、中古住宅の流通を促す。改正案は、仲介契約時の契約書などに住宅診断の有無を記載する項目を設けることを不動産業者に義務付けることが柱。診断する場合は、不動産業者があっせんする業者が実施する。診断結果は、契約前に不動産業者が買い主に行う重要事項説明に盛り込むこととした。
また、最終的に売買契約を結ぶ際には、家屋の基礎や外壁などの状態を売り主と買い主の双方が確認し、確認事項を契約書に明記するようにする。購入後のトラブル回避が狙いだ。
「『薬害オンブズパースン会議』事務局長の水口真寿美弁護士は、『40年間の不正に対する処分としては、十分とはいえない』と語気を強める。」
供給を優先させれば仕方のない事。ずる賢い人々はこの事実を悪用する可能性が高い。よって、化学及血清療法研究所(化血研)のような悪質な行為に対する
罰則に関する法改正が必要だ。実行不可能な法律や罰則は意味がない。
厚生労働省の権限を持つ人達が化学及血清療法研究所(化血研)が親しい関係又は不適切な関係で繋がっていれば、法改正は期待できない。これで幕引き。
化学及血清療法研究所(化血研)に対し、厚生労働省は8日、過去最長の110日間の業務停止処分に踏み切った。
ただ、今回の処分では、血液製剤が14製品のうち8製品、ワクチンは11製品すべてが業務停止の対象から外れた。処分期間中も化血研は多額の収入が見込まれる。「薬害オンブズパースン会議」事務局長の水口真寿美弁護士は、「40年間の不正に対する処分としては、十分とはいえない」と語気を強める。
特にワクチンでは、大きな利益を生む季節性インフルエンザの出荷継続が認められたほか、出荷を自粛しているB型肝炎と日本脳炎、A型肝炎も停止処分から除外され、事実上、出荷に「ゴーサイン」が出た。
背景には、化血研のシェア(市場占有率)の高さがある。今年10月にも予防接種法の定期接種の対象となるB型肝炎ワクチンのシェアは80%。定期接種で需要は2倍近くになる見通しで、厚労省の担当者は「化血研製は供給に不可欠」と話す。
「旭化成は8日、子会社の旭化成建材(東京)のくい打ち工事のデータ改ざん問題で、弁護士3人で構成する外部調査委員会の中間報告書を公表した。データ流用に関し、現場担当者が多忙で、1棟が傾いた横浜市都筑区のマンションを担当する前から『データを流用する習慣が身に付いていた』と指摘。その上で、データの記録・保管の重要性への意識の低さなどを原因として挙げた。」
行政によるチェック、又は、第三者によるチェックが甘いと、旭化成グループの企業であっても身内に甘くなり、適切に機能しない組織になってしまうという事だろう。
「現場担当者がくいの不具合を隠す目的でデータを改ざんしたことを否定しており、くいが十分に打ち込まれたかどうかと、改ざんの関係性には『さらなる調査が必要』との見解を示した。」
旭化成だけでなく、業界でデータ流用が慣習になっていたので、不具合を隠す目的でデータを改ざんした事に対して罪悪感を感じていなかったかもしれない。
しかし、損害賠償の額などで認めづらくなっているのではないのか?何らかの証拠がなければ、10年も前のことなので否認されれば、行き詰ると思う。
一般的な刑事事件でも証拠がなければ、自白意外、有罪にする事は難しいと思う。同じ事であろう。
旭化成は8日、子会社の旭化成建材(東京)のくい打ち工事のデータ改ざん問題で、弁護士3人で構成する外部調査委員会の中間報告書を公表した。データ流用に関し、現場担当者が多忙で、1棟が傾いた横浜市都筑区のマンションを担当する前から「データを流用する習慣が身に付いていた」と指摘。その上で、データの記録・保管の重要性への意識の低さなどを原因として挙げた。
旭化成の浅野敏雄社長は外部調査委の中間報告を受け、「早急に再発防止体制の構築に取り組む」とのコメントを発表した。
外部調査委は旭化成建材を「建設の安全性確保を重大な責務とする事業者として、責務を十分に果たしていなかった」と厳しく批判。報告のルール化など再発防止策を講じるよう提言した。
マンション用地に以前にあった建物のくいの長さなどの情報について、旭化成建材は元請けの三井住友建設から「提供を受けていなかった」と明らかにした。くいを打ち込む場所に関しては、設計時から変更した箇所が「比較的多く見受けられる」とする一方、くいが固い地盤に到達しているかどうかは「現時点で断じることは困難」として言及を避けた。
現場担当者がくいの不具合を隠す目的でデータを改ざんしたことを否定しており、くいが十分に打ち込まれたかどうかと、改ざんの関係性には「さらなる調査が必要」との見解を示した。
自業自得!
一般財団法人・化学及血清療法研究所(化血研、熊本市)が血液製剤などを国の承認を受けていない方法で製造していた問題で、塩崎厚生労働相は8日午前の閣議後記者会見で、医薬品医療機器法に基づく110日間の業務停止命令を同日午後に出すと表明した。
「今後は化血研という組織のままで製造・販売することはない」との見方も示し、組織体制の見直しを強く求めた。
この日は、化血研の宮本誠二理事長が厚労省を訪れ、午後3時に同省幹部が処分の命令書を宮本理事長に手渡す。
会見で塩崎厚労相は、「医薬行政の根幹を揺るがす行為で、本来なら製造販売業の許可を取り消すべき事案だ」と改めて述べた。ただ、「化血研は国民の健康確保や医療に不可欠な製剤やワクチンを製造している」とし、「ただちに取り消し処分を行わず、とりあえず業務停止とする」と説明した。
方針としては良い!虚偽の報告があったとして、どのようにして虚偽を見つけ出すのだろう!
教科書を発行する「三省堂」や「数研出版」の謝礼問題で、文部科学省の義家弘介副大臣は8日、東京都内で開かれた業界団体「教科書協会」の臨時会合に出席し、同省が各教科書会社を対象に実施中の緊急調査で虚偽の報告などがあった場合、発行者の指定取り消しを含めた厳しい措置を取る方針を伝えた。
同省は各社に対し20日までに、校長らへの謝礼の提供や接待の有無などについて報告を求めている。
会合には各社の社長らが出席。義家副大臣は「過去の悪弊を断ち切る意味でも、徹底的な調査を行っていただきたい」と発言した。同協会の佐々木秀樹会長が各社を代表し、「つぶさに見直し、詳細な報告書を提出したい」と述べた。
自業自得!
教科書を発行する「三省堂」や「数研出版」の謝礼問題で、文部科学省は、各教科書会社を対象に行っている緊急調査で虚偽の報告などがあった場合、教科書無償措置法に基づき、発行者の指定取り消しを含め、厳しい措置を検討する方針を決めた。
業界団体「教科書協会」が8日に開く臨時会合に義家弘介副大臣が出席し、教科書会社側に、こうした方針を説明する。
最初に発覚した三省堂の問題を受け、同省が実施中の緊急調査では、他の教科書会社21社に同様の金銭授受や接待を行っていないか、1月20日までに報告するよう求めている。
三省堂に続き、数研出版でも検定中の教科書を見せたり、図書カードを渡したりしていたことが判明したため、同省は各社に改めて徹底した調査を求めるとともに、今回の調査後、悪質な虚偽報告などが発覚すれば発行者の指定取り消しなども検討することにした。過去に、営業活動などでの「著しい不公正」を理由に指定を取り消された事例はないという。
自業自得!
国土交通省は7日、傾きが見つかった横浜市のマンション工事に関与した三井住友建設など3社を、来週にも建設業法に基づき行政処分する方針を固めた。
1次下請けの日立ハイテクノロジーズ(東京都港区)は実質的に工事を丸投げしたとして、2次下請けの旭化成建材(千代田区)とともに営業停止処分にする方針だ。元請けの三井住友建設については、下請けの2社に対する指導を怠ったとして、業務改善命令を出す方向で調整している。
国交省によると、建設業法は丸投げ(一括下請け)を禁じており、違反すると15日以上の営業停止処分となる。横浜市の工事で、日立ハイテク社は、旭化成建材に杭くい工事に関する施工計画書を作成させ、ほぼそのまま元請けに提出していた。国交省は日立ハイテク社が「施工に実質的に携わっていない」と判断した。
杭打ちデータの流用問題で、国土交通省の有識者対策委員会は25日、再発防止策などを盛り込んだ中間報告書を公表した。
傾きが見つかった横浜市のマンションの工事では、1次下請けの日立ハイテクノロジーズ(東京都港区)と2次下請けの旭化成建材(千代田区)が、建設業法で義務づけられた主任技術者の専任配置をせず、元請けの三井住友建設(中央区)もこれを知りながら指導しなかったと指摘。同省は同法に基づき3社を行政処分する方針を固めた。
同法では、マンションなど一定規模以上の工事では、実務経験や国家資格を持つ専任の主任技術者を常駐させる必要があると定めている。しかし、報告書によると、日立ハイテク社の技術者は横浜市のマンションを含む計5工事を掛け持ちし、3か月の工期中、現場にいたのは14日以下だった。旭化成建材の技術者も計3工事を兼任し、12日しかいなかった。三井住友建設は専任でないことを知りながら是正指導や行政への通報をしなかった。同省は処分について、業務改善命令などを検討している。
自業自得!
一般財団法人・化学及および血清療法研究所(化血研、熊本市)が血液製剤やワクチンを国の承認を受けていない方法で製造していた問題で、厚生労働省は化血研に対し、医薬品医療機器法に基づき、110日間の業務停止命令を8日に出すことを決めた。
停止期間は過去最長で、製薬企業への行政処分としては最も重い。処分は今月中旬からとなる。
業務停止期間中は、医薬品の製造・販売のほか、営業や広告活動ができない。通常の処分では、化血研が製造する血液製剤とワクチン、抗毒素の計約30製品全てが対象となるが、他社の代替品がない20製品以上については患者への影響を考慮し、同省は出荷を認める方針。
厚労省は昨年5~12月に化血研を立ち入り検査し、内部資料の確認や関係者への聴取を行った。その結果、化血研が約40年前から、国の承認書と異なる方法で血液製剤を作り、約20年前からは国側の検査の際、虚偽の製造記録を提示していたことが判明した。
昨年9月には、化血研はワクチンの製造工程も国の承認書と異なっていることに気づいたにもかかわらず、国へ報告しなかった。
同省は、化血研のこうした行為が、承認書と異なる方法で作った医薬品の販売や国への虚偽報告を禁じた医薬品医療機器法に違反すると判断した。長年にわたって国の検査を欺いてきたことを問題視し、過去最長の業務停止処分にすることにした。昨年末に化血研へ処分案を示し、化血研側も受け入れたという。
厚労省によると、製薬企業への業務停止処分でこれまで最も長かったのは、1994年、抗ウイルス剤「ソリブジン」の副作用による死亡事例を報告しなかった製薬企業に対する105日間。同法には、業務停止より重い製造販売業の許可取り消し処分もあるが、過去に執行例はない。
一般財団法人・化学及および血清療法研究所(化血研、熊本市)が血液製剤などを国の承認を受けていない方法で製造していた問題で、厚生労働省の血液事業に関する専門家委員会が6日開かれ、新たに血液製剤の1製品の出荷再開が了承された。
今後、厚労省の決定を経て、出荷が再開される。
了承されたのは、出荷自粛中の化血研製の血液製剤7製品のうち、髄膜炎などの治療に使用されるグロブリン製剤。化血研では長年にわたり、国の承認を受けずに抗凝固剤「ヘパリン」を添加していたが、製剤の安全性に問題はないと判断された。他社の代替品がないため、現行の製法のまま出荷が再開される。
厚労省は近く、医薬品医療機器法に基づき、業務停止の行政処分を行うが、供給不足になり得る製品については、継続して出荷を認める方針。
自業自得!
【ワシントン清水憲司】独フォルクスワーゲン(VW)の排ガス不正問題で、米司法省は4日、違法行為の差し止めと民事制裁金の支払いを求め、米中西部ミシガン州の連邦地裁に民事訴訟を起こした。民事制裁金は数兆円規模に上る可能性もあり、VWにはさらなる痛手になりそうだ。
訴状によると、VWや傘下のアウディ、ポルシェはディーゼルエンジン車計約60万台について、停車試験中だけ排ガスの浄化装置を作動させる不正ソフトウエアを搭載。通常走行時には米規制値の最大40倍の窒素酸化物(NOx)排出があった。訴状は米当局の調査開始後もVWが不正ソフトウエアの存在を隠していたことも糾弾。不正ソフトウエア搭載車の販売や当局への報告を怠るなど、四つの違法行為があったと指摘した。
民事制裁金は、違法行為ごとに1台あたり最大3万7500ドル(約450万円)が科されるため、総額10兆円規模に膨らむ可能性もある。最高額が科されるケースは少ないものの、数兆円規模に上る可能性がある。
米環境保護局(EPA)とVWは不正車のリコールについて協議中。ソフトウエアの書き換えでなく、新たな浄化装置の取り付けや不正車の買い戻しを求められれば、VWの負担は一段と膨らむ。
車だって半ドアの警報ランプが装備されている。グレードがかなり低いボーイング737には半ドア警報ランプや音による警報装置(ブザー)は装備されていないのか?
船だっていろいろな警報ランプや音による警報装置(ブザー)は装備されている。しかし、故障を放置したり、作動テストを行っていない船は存在する。故障して、
運航に影響した時に考えるスタンスであると思っている。客船でなければ、何か起きたら船員や持ち主の自己責任で処理されるのであろう。
フィリピン・セブ発釜山行きの韓国の格安航空会社(LCC)、ジンエアー機が3日、完全にドアが閉まっていなかったとみられる状態で飛行、セブに引き返した。韓国のLCCでは昨年12月にも済州航空機が装置の不具合で急降下するトラブルがあったばかりで、韓国国土交通省は4日までに国内LCC6社の安全点検に乗り出した。
ジンエアー機は離陸の約30分後、高度約1万フィート(約3048メートル)でトラブルが判明。聯合ニューステレビが伝えた機内の映像によると、前方左側のドアの開閉部分に手の指が入るほどの隙間が開いていた。乗客は「風が入ってきた。気圧の影響で頭痛がした」などと語った。
聯合ニュースなどによるとジンエアー側は「ドア自体に問題はなかった」としており、国交省が詳しい原因を調べる。機種はボーイング737。(共同)
車だって半ドアの警報ランプが装備されているのに、飛び立ったらドアを閉められない飛行機には搭載されていないのか?
韓国の格安航空会社「ジンエアー」の旅客機はどこのメーカーの飛行機を使用しているのか?グレードがかなり低い飛行機を使用しているのか?
韓国の格安航空会社「ジンエアー」の旅客機が3日、フィリピンのセブ島を離陸後にドアが完全に閉まっていないことが分かり、引き返した。風が流れ込む音がしたことから判明し、乗客163人のうち一部が頭痛などを訴えた。
ジンエアーは、ドアに何かが挟まり隙間ができたとみており、当局が機体の整備状況などを調べている。
公共事業が減り人員整理が終了した後に復興で仕事が増えても、急には人は増やせないし、人は育たない。たぶん、人材不足とャスダック上場の測量会社、川崎地質(東京)の
企業倫理に問題があってこのような結果となったのであろう。
「国土交通省の外郭団体、土木研究センターの了戒公利部長は『素人の設計で、作業員にも危険が及ぶ』と問題視した。」
事実であれば測量会社、川崎地質(東京)を一定期間、入札への参加を禁止すれべ良い。
東日本大震災の復興事業で、異なる工事への同じ図面の流用や安全面での欠陥など、不適切な設計が横行していることが31日、分かった。設計会社などがずさんな設計をしても、発注主体の被災自治体が人手不足でチェックをできず、県、国も見抜けなかった。ことしは震災から5年となるが、巨額の国家予算を投じた復興事業で、作業員の安全が脅かされた上、追加工事で無駄な費用もかかる実態が浮かび上がった。
工事に携わった複数の関係者によると、問題があったのは震災の津波被害を受けた宮城県南三陸町の漁港復旧工事や、仙台市の河川工事、同県沿岸自治体の土木工事。関係者は「氷山の一角で、ほかにもずさんな設計は多くあった」と明かした。「税金の無駄遣い」として会計検査院にも報告されたもようだ。
南三陸町は2011年10月、被災した寄木漁港と韮浜漁港の設計をジャスダック上場の測量会社、川崎地質(東京)に約4800万円で委託し、13年11月、地元の建設会社を中心とするJV(企業共同体)が落札した。
だが設計を精査したJV側が、漁港の海水をせき止める工事で土のうの数が極めて少ないなど安全面の問題を指摘。寄木漁港の図面に、被災状況が異なる韮浜漁港と同じ図面が使われていることも判明した。JV側は設計通りに工事できず、工法変更で予定より約2千万円余分にかかった。
国土交通省の外郭団体、土木研究センターの了戒公利部長は「素人の設計で、作業員にも危険が及ぶ」と問題視した。
川崎地質は「町の委託業務で、コメントできない」としている。工事主体の南三陸町の担当者は取材に対し、図面流用があったことを認め「(設計は)あくまで工事の参考資料としての位置付け」と釈明。「より安全な設計方法はあったと思う」と話した。
宮城県が発注した仙台市の河川工事では、土手の斜面崩壊や増水の可能性など、安全面の検討が設計段階で考慮されていなかった。作業員の安全を守るため、業者側は想定外の工事を余儀なくされた上、数百万円の追加費用がかかった。県沿岸のある自治体の土木工事では、実際の工事範囲が設計上の面積より数倍広いことも判明。工事場所の地質についての事前説明もなく、工事変更で費用は予定より膨れ上がったという。
罰則を強化するしかないと思う。違反が発覚すれば、教科書を2年間、検定しないなどすれば良い。もっと違反が巧妙になる可能性は高いが、違反が発覚した時の リスクを考えて思いとどまる会社もあるかもしれない。また、校長や教員に対しても降格など厳しい処分が必要。
検定中の教科書を校長らに見せたり、意見を聞いた謝礼に金品を渡したりする行為が、三省堂以外でも行われていた。
数研出版が作成した内部資料では、検定中の教科書を白い表紙にちなんで「WB(ホワイト・ブック)」と表現し、校長らに見せる場合は、他の教員に気付かれないよう、隠れて行うなどの「留意点」が書かれていた。同社がルール違反を認識したうえで、組織的に営業攻勢をかけていた実態が浮かんだ。
◆別室で
同社の営業担当部署が作成した内部資料には、中学校長や教員から教科書への意見を聞く「編集準備会議」の開催日程や参加する教員の名前、同行する同社の営業担当者名などが記入されている。コメント欄もあり、教員の反応や同社への評価などが記されている。
資料の冒頭には、留意点などとして、「WB開示校の選出においては、部署長と相談の上、行うこと」「開示に当たっては、絶対に口外しないことを必ず伝える」「別室、放課後、学校外など、他の先生の目が届かないところで実施する」などと記載されていた。検定中の教科書は通常の表紙がないことから、業界では「白表紙」と呼ばれている。
賄賂、不適切な接待、汚職、民間会社との不適切な関係の結果として出来上がったシステム、問題があってもおかしくない。 プラグラムに誤りがあったケースの対応についても、業者に有利な契約になっているかもしれない。
マイナンバー制度の運用が始まる中、カード発行を担う地方公共団体情報システム機構のプログラムに誤りがあったことが31日、分かった。システム不備が確認されたのは初めて。関係者が明らかにした。東京都葛飾区のマイナンバー通知カード約5千世帯分が未作成だったにもかかわらず、機構のシステム上では正常終了と認識されていた。機構は誤りを修正したが、区に対し具体的なミス原因の情報開示を拒否。総務省は本体カード配布で同じミスが発生することを危惧してシステムの再点検を指示したが、機構の隠蔽(いんぺい)体質が早くも浮き彫りになった。
関係者によると、機構が平成27年10月、葛飾区から持ち込まれた住民データを「継続サーバー」から「管理サーバー」に移行した時にシステムが一時停止した。その際、実際にデータ処理が行われていなかったにもかかわらず、機構のコンピューター端末上では「終了」と表示されていた。葛飾区分のデータ移行を表すメモリー容量の変化もモニター上で確認済みで、システム上は正常に作動したことになっていた。結果、データのない通知カードは印刷されず、住民に郵送されなかった。
ただ、機構は「手順通りに業務を行った」(関係者)とも証言。職員の動向を捉えた監視カメラの録画を秘密裏に確認したところ、不正はなかったという。
一方で葛飾区にはプログラム上、「終了」を受け機構から専用線で送信されるはずだったデータ移行完了を示す「登録」通知が届かず、実際の状況を正常に反映していた。
機構は産経新聞の取材に対し、システムの不具合の具体的な原因について「特定したが、セキュリティー上の理由から言えない」としている。被害を受けた葛飾区も機構に説明を求めたが、拒否された。
高市早苗総務相は同年12月8日の記者会見で、システム上の原因について「解析を行っている」と述べるにとどめていた。機構のネットワークシステム構築を担ったのは情報通信関連企業5社。うち3社が関与を否定し、2社が「言えない」としている。
機構は26年、マイナンバー業務など公的個人認証業務を専門に行う「地方共同法人」として発足したが、秘匿性の高い個人情報を取り扱うため、省庁や地方自治体のように情報公開制度の対象になっていない。
情報、情報と厚労省は簡単に考えている。マイナンバー制度は良い事ばかりと言うが、情報の流出の危険がある事を理解していない、又は、十分な説明をしていない。
「健康保険証の番号など個人情報を含む、全国約10万3000人分のリストが流出、名簿業者が一部を転売していたことが分かった。情報セキュリティーに詳しい専門家は『複数の医療機関から漏れた可能性が高い。
これほど大量の医療関連の情報漏れは過去に例がない』と指摘。」
複数の医療機関の多くは、システム、そのプログラム、情報のバックアップ、システムやプログラムの更新に関して外部に委託しているはずである。委託している企業は
人件費の削減のために、下請け、派遣、又は契約社員を利用している可能が高い。その辺から情報が漏れたと考えて良いと思う。ベネッセで起きた事は他では起きないと
考えるほうがおかしい。
「名簿業者は『ブローカーから買った。危ないデータだと驚いたが、一部は顧客に売った』と話した。」
名簿業者に関する規則や登録が必要ではないのか?それても必要悪として今後も認めるのか?情報の売買は今後もなくならないだろう。そして、闇取引に変わるかもしれない。
それでも対応するべきであろう。
「情報セキュリティ大学院大の湯浅墾道(はるみち)教授(情報法)の話 医療情報は電子化される流れにあり、複数の医療機関から漏れた可能性がある。電子化すれば利便性が高まる一方で情報流出のリスクも高まる。医療情報はプライバシーの度合いが高い。徹底した管理が求められる。」
これぐらいは理解するのに難しくない。厚労省はどのような対応をするのか?問題を見て見ぬふりをして、自分達のしたいことをするのか?
◇リストの記載は沖縄除く46都道府県
健康保険証の番号など個人情報を含む、全国約10万3000人分のリストが流出、名簿業者が一部を転売していたことが分かった。情報セキュリティーに詳しい専門家は「複数の医療機関から漏れた可能性が高い。これほど大量の医療関連の情報漏れは過去に例がない」と指摘。成り済ましや詐欺などに悪用される恐れがあり、厚生労働省が調査を始めた。今後、リストを警察当局に提出する方針。
リストの記載は沖縄を除く46都道府県に及び、近畿や四国に集中。取材に応じた全27世帯で実在の氏名や住所などと一致した。一部は現在の保険証番号が記載されていた。
厚労省担当者は「医療機関や薬局が業務で作ったリストが流出した可能性がある」として、調査を開始した。
国内に住む人全員に12桁の番号を割り当て、将来的には年金などの個人情報を結びつけ管理するマイナンバー制度の運用が1月から始まるのを前に、情報管理の在り方をめぐり議論を呼びそうだ。
名簿業者は「ブローカーから買った。危ないデータだと驚いたが、一部は顧客に売った」と話した。
共同通信が入手したリストによると、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号のほか、保険種別や保険者番号などが並ぶ。医療費の自己負担額の算定に必要な老人保健(当時)の区分や、生活保護などの公費負担を示すとみられる欄も三つ付いていた。記載されていたのは05年3月以前に生まれた人だった。
最も多かったのは大阪府で約3万7000人。取材の結果、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号は27世帯44人全員が一致。保険証番号も一致したのは6世帯11人だった。
保険証番号とともに氏名や住所などが分かると保険証が再発行できる場合があり、本人に成り済まして借金するなどの悪用が可能になるという。
◇情報管理の徹底を
情報セキュリティ大学院大の湯浅墾道(はるみち)教授(情報法)の話 医療情報は電子化される流れにあり、複数の医療機関から漏れた可能性がある。電子化すれば利便性が高まる一方で情報流出のリスクも高まる。医療情報はプライバシーの度合いが高い。徹底した管理が求められる。
社労士として働けなくても、彼のような人材を求めるような企業が存在すれば、コンサルタントとして仕事はあるだろう。結果が全てを語るであろう。
愛知県社会保険労務士会(鬼頭統治会長)所属の男性社労士が個人のブログで「モンスター社員解雇のノウハウをご紹介」などと題する不適切な文章を掲載したとして、同会がこの社労士を3年間の会員権停止処分にし、退会を勧告していたことがわかった。
会員権が停止されると、会の事業への参加や施設の使用ができなくなる。
同会によると、この社労士は今年11月、「社員をうつ病に罹患りかんさせる方法」とのタイトルの文章を掲載。社員をうつ病にして会社から追放する方法を指南するとして「強烈な合法パワハラを与える」とし、上司に文句を言うことを就業規則で禁じ、違反した場合は降格や減給などでダメージを与えるとした。さらに「本人が自殺したとしても、うつの原因と死亡の因果関係を否定する証拠を作っておくこと」「モンスター社員に精神的打撃を与えることが楽しくなりますよ」などとも記載していた。
気をつけるしかない!
小中高生向け学習教材を販売する東京都町田市の会社が、保護者らに「代金は返金する」と言って教材を販売しながら、11月末から連絡が取れないことがわかった。
保護者は支払いのためにクレジット契約を結ばされており、信販会社から今後請求される可能性がある。首都圏など150人以上に数億円の被害が生じるとみられ、東京と神奈川、北海道の各地で被害対策弁護団が結成された。
問題の会社は、「エフォートカンパニー」。学習塾を運営し、塾への生徒の勧誘のほか、電話勧誘などで教材も販売している。
弁護団などによると、同社は、教材を購入した保護者らに「お試しのモニター契約」とうたって別教材を宣伝。保護者は信販会社と契約して別教材の代金をクレジット払いするが、サービスの一環として「当社が返金する形で全額負担する」などと説明していたという。しかし、返金が10月頃から滞り始め、エフォート社は11月末、事務所のドアに「事情によりしばらく休業します。後日必ず連絡いたします」と貼り出した後、連絡が取れない状態だという。
舌の根も乾かぬうちに、「誓い」はないがしろにされていた。血液製剤やワクチンの国内メーカー「化学及血清療法研究所」(化血研、熊本市)が国の承認と異なる方法で血液製剤などを製造していた問題。同社は薬害HIV訴訟の被告でありながら不正に手を染め、訴訟の和解と同時期に隠蔽工作を本格化させていた。一方、監督する立場の厚生労働省は、安定供給の観点から厳罰処分も打ち出しにくいというジレンマに陥っている。
■「問題ない」…希望的観測
第三者委員会の調査報告書などによると、化血研による血液製剤の不正製造が始まったのは昭和49年ごろ。ある血液製剤の製造過程でタンパク質の浮遊物が生じることを避けるため、加温工程の一部を承認と異なる方法で行ったのが最初とされる。
さらに複数の血液製剤が「非承認」の状態になったのは平成元~3年、開発中の血液製剤の臨床試験で、止血効果がなくなる問題が発生したことが発端だった。この際、血液を固まりにくくする「ヘパリン」を添加すると問題が解消できることが判明。本来、ヘパリン添加を含めた工程で承認申請をすべきだったが、臨床試験のやり直しで販売が遅れる可能性があった。このため化血研は、ヘパリン添加を隠したまま、承認申請を行ったという。
このヘパリン添加は、他の血液製剤にも関わる製造過程の「上流」で行われていたため、結果として計11製品での未承認の工法につながった。ほかの工程も含め、承認と異なるものは計12製品、31工程に上った。
ヘパリン添加に関しては当時、化血研内で積極的に安全性が議論されたことはなかった。ほかの海外メーカーで添加例があり「問題ないであろうという希望的観測」(三者委報告書)が端緒となったという。
■「最大の努力」…誓いは反故に
ヘパリンの添加そのものは、国に申請さえすれば一定期間後に承認されていたとされる。にも関わらず、なぜそこまで急いだのか。背景には薬害エイズ問題の社会問題化がある。
血液製剤は主に海外の売血を原料とした製品が使われてきた。だが、80年代に輸入血液を使用して製造された血液製剤のHIVウイルス汚染が相次ぎ判明し、平成元年には化血研を含む5製薬会社が提訴された。
こうした状況下で国は2年、原則、国内の献血を用いた血液製剤にシフトする方針を決定。この時期と、化血研がヘパリン添加を始めた時期とはほぼ重なっており「可能な限り新製品を早く承認されることが、シェア争いで有利に働くとのもくろみがあったのではないか」(厚労省関係者)とみられている。
実際、平成20年までは化血研の中で、血液製剤の売り上げが占める割合は5割を超え、人事上も血液製剤製造部門の出身者が優遇され続けた。
さらに、化血研が国による定期調査の強化を見据え、隠蔽工作を始めたのは7年ごろ。同社では調査に備え、虚偽記録をゴシック体、実際の記録を明朝体と使い分ける▽記録に紫外線を当てて変色させ、作成時期を古く見せかける▽不正な製造記録部分のページ数を「2・5」などと小数で記載し、国の調査ではページを抜く-といった周到な準備を行っていた。
8年に行われた常勤理事会では、血液製剤の製造部門担当者が、虚偽の製造記録の提示を示唆したのに対し、当時の理事長や、12月2日付で辞任した宮本誠二理事長ら幹部から反対意見は出なかったという。この会議で事実上、不正の「お墨付き」を得ていた。
一方、化血研は同じ8年、薬害エイズ訴訟の原告らと和解した際、こんな「確認書」を交わしていた。
「製薬会社は安全な医薬品を消費者に供給する義務があることを改めて深く自覚し、最大の努力を重ねることを確約する」-。
「誓い」は守られることなかった。10年には新たに就任した製造部門の課長に対し、部長が「このままでは(国の調査で)見せられん。しばらくは見せられる帳簿で対応しよう」と指示。今年5月まで不正は継続された。
三者委の調査報告書では「代替が困難なものが多いことから『つぶれない』という思いがあるとすれば、『おごり』以外の何者でもない」と厳しい口調で非難した。患者を裏切り続けてきた化血研の「罪」は重い。
■性悪説に基づいた調査を
厚生労働省は今年5~12月、計3回にわたり化血研に対する立ち入り検査を実施。行政処分のほか、刑事告発も検討している。
医薬品医療機器法(旧薬事法)上の行政処分は、主に(1)製造販売許可の取り消し(2)業務停止命令(3)業務改善命令-などがある。また同法では、非承認の医薬品の製造・販売には3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)、国の調査に対する虚偽説明には個人・法人ともに50万円以下の罰金という罰則もある。
このうち行政処分は(2)の業務停止命令とする方針だが、隠蔽工作により欺かれ続けてきた厚労省は、化血研の「罪」に対しては難しい判断を迫られる。「現在も血液製剤7種とワクチン3種の出荷が止まっており、処分によっては供給に影響が出かねない」(厚労省担当者)ためだ。
塩崎恭久厚労相は25日の閣議後会見で「薬事制度の根幹を揺るがす事態で、製造販売許可の取り消し処分相当の悪質行為と認識している」とする一方、製品の中には国民の健康確保に不可欠なものも含まれるとし「品質・安全性を確保したうえで、製造事業自体は適切に継続実施できることを同時に考えないといけない」と“苦渋の選択”であることを強調した。
近年、血液を原料としない外国製の遺伝子組み換え製剤がシェアを伸ばし「国内自給」が困難な状況が続いている。国は事業の効率化を目指して統合を促進した結果、血液製剤の主要メーカーは化血研を含め現在、国内に3社のみ。原料となる血液が限られているため利益につながりにくく、「排除しているわけではないが、民間の新規参入は高いハードルがある」(同)という。
寡占状態の問題点を議論するため、厚労省は近くタスクフォース(作業部会)を設置し、業界全体のあり方や生産体制を検討する方針だ。しかし、血友病患者で大阪HIV訴訟原告団の花井十伍代表は「そもそも安全監視と供給の調整を同じ厚労省がやっていることが疑問」と指摘する。国の調査方法についても「事前通知した上で行ってきた国の調査は形式的。今後は性善説ではなく、性悪性に基づいて行われるべきだ」と話している。
最近の不祥事を見ると、不祥事は企業の問題体質として長期的な原因の結果であるケースが多いように思える。
新宅あゆみ
東洋ゴム工業(大阪市)は25日、船舶や電車に使う防振ゴムの性能データの偽装問題で、当時の取締役や執行役員ら複数の幹部が2年前には不正を認識していたと発表した。これまでは今年8月に内部通報で把握したとしていた。再調査で幹部が不正を知りながら対策をとらず、放置していたことが明らかになった。
不正に関わった社員は4人で、その上司ら十数人にも監督責任があるとして処分を検討する。旧経営陣への法的措置は、現時点では考えていないという。不正を上司に伝えていた社員もいて、法務担当の滝脇将雄執行役員は「組織ぐるみという言葉を用いざるを得ない」と述べた。
調査報告書によると1995年以降、子会社「東洋ゴム化工品」で品質保証担当の歴代社員4人が、性能試験で過去のデータを流用するなど、不正行為を繰り返していた。出荷された不正品は記録がある99年以降で、19社向けに83種類4万7330個に上る。東洋ゴムは定期的な点検をすれば安全性に問題はないと主張している。
自業自得!給料が安いのか?身の丈にあった生活が出来なかったのか?
東京メトロの男性駅員が回数券を二重に払い戻したり、忘れ物のかばんから現金を抜き取るなどして17万円余りを着服していたことが分かりました。
東京メトロによりますと、東西線南砂町駅の男性駅員(25)は去年10月ごろから、払い戻された回数券を再び払い戻したり、忘れ物のかばんから現金やICカードを抜き取るなどして総額約17万円を着服していたということです。払い戻しの処理をしたはずの乗車券が券売機付近に落ちていたことから、男性駅員の不正が発覚しました。着服は1年2カ月で約340件に上ります。男性駅員は東京メトロの調査に対し、「貯金したかった」と話しているということです。東京メトロは男性駅員を懲戒解雇する方針で、刑事告訴も検討しています。
「化学及および血清療法研究所の動物用ワクチンの不正製造問題を受けて、農林水産省は25日、研究開発に功績があったとして11月に化血研の研究グループに贈った賞を取り消した。」
農水省はなぜ贈った省を取り消したのか?省内で情報共有が出来ていなかったから賞を贈ったのであればそのままで良いのでは?農水省では情報の共有が出来ていないとの事実の戒めとなる。
残念な事に賞をキャンセルして、トカゲの尻尾きりで終わるのであろう。本当は農水省内で情報の共有出来ていない原因究明と改善に力を入れると公表するべきであろう。
たぶん、やる気は無いのであろう。情報を共有すると問題が起きたときに知らなかったと言い訳できなくなる。
化学及および血清療法研究所の動物用ワクチンの不正製造問題を受けて、農林水産省は25日、研究開発に功績があったとして11月に化血研の研究グループに贈った賞を取り消した。
化血研から同日、「社会に迷惑をかけた」として賞を返納するとの申し出があった。
「塩崎厚生労働相は25日の閣議後記者会見で、『医薬品の製造販売の許可取り消し処分に相当する悪質な行為だ』と厳しく批判した。
ただ、化血研は他社の代替品のない血液製剤やワクチンを供給しているため、厚労省は、年明けにも化血研を医薬品医療機器法に基づき、製造販売の許可取り消し処分に次いで重い、業務停止処分とする方針を固めている。」
化血研は他社の代替品のない血液製剤やワクチンに限り、製造販売の許可を認める、又は、法的に他の製薬会社が他社の代替品のない血液製剤やワクチンを他社でも
製造できるように改正して、その交換条件として、製造販売を認めれば良いのではないのか。次に不正が発覚すれば製造販売の許可を取り消せば良い。
これにより次回は「化血研は他社の代替品のない血液製剤やワクチンを供給出来る」との理由で製造販売の許可取り消しをためらう事もない。そして
化血研は甘えや驕りを捨てて真剣に再出発をしなければならなくなる。
国内の血液製剤の約3割を製造する一般財団法人・化学及および血清療法研究所(化血研、熊本市)が、血液製剤やワクチンを国の承認を受けていない方法で製造していた問題で、塩崎厚生労働相は25日の閣議後記者会見で、「医薬品の製造販売の許可取り消し処分に相当する悪質な行為だ」と厳しく批判した。
ただ、化血研は他社の代替品のない血液製剤やワクチンを供給しているため、厚労省は、年明けにも化血研を医薬品医療機器法に基づき、製造販売の許可取り消し処分に次いで重い、業務停止処分とする方針を固めている。
会見で塩崎厚労相は、「長期間にわたって周到で組織的な隠蔽行為が行われた。薬事制度の根幹を揺るがす事態で、医薬品に対する国民の信頼を失墜させた」と厳しい処分が必要との認識を示した。
処分は、数週間以内に化血研側の弁明を聞いた上で行われる。停止期間は数十日~数か月となる見通し。
国内の血液製剤の約3割を製造する一般財団法人・化学及および血清療法研究所(化血研、熊本市)が、血液製剤やワクチンを国の承認を受けていない方法で製造していた問題で、厚生労働省が、化血研への業務停止処分の期間を過去最長規模の100日以上とする方向で検討していることがわかった。
同省はすでに化血研側に処分方針を伝えており、数週間以内に弁明を聞いたうえで年明けに最終決定する。
厚労省によると、これまでの製薬企業に対する業務停止処分で最も長かったのは、抗ウイルス剤の副作用による死亡事例の報告を怠った製薬企業に対し、1994年に出した105日間。化血研の不正では健康被害は確認されていないが、同省は、長年にわたって国側の検査に虚偽の製造記録を見せるなどの隠蔽工作を重ねたことを重くみて、長期間の停止が妥当と判断したとみられる。
「傾きが見つかった横浜市のマンションの工事では、1次下請けの日立ハイテクノロジーズ(東京都港区)と2次下請けの旭化成建材(千代田区)が、建設業法で義務づけられた主任技術者の専任配置をせず、元請けの三井住友建設(中央区)もこれを知りながら指導しなかったと指摘。同省は同法に基づき3社を行政処分する方針を固めた。」
推測であるが、これが業界のスタンダードなのでは?主任技術者の専任配置の状態でも知識や経験がなければ、問題の防止にはならない。法を満足するためだけのコストになってしまう。
それにコストや工期の短縮を優先させれば、主任技術者の専任配置の状態でも同じ事が起きたと思う。言い訳のストーリーだと思う。本当に問題の発生を防止したかったのであれば
ここまで似たような問題や手法が業界で蔓延しなかったと思う。データの使いまわしに気付けば、理由を下請けに聞いたはずである。その時点で、下請け又は下請けの社員による
偽造が継続されたら、もっと巧妙で見つからないようにしたと思う。
一般財団法人・化学及血清療法研究所(化血研、熊本市)の偽装工作のように巧妙になるはずである。
問題が発覚した時、行政は法律や適用されているシステムの範囲内でしか処分できない。法律や適用されているシステムそして行政によるチェック体制に問題があれば
企業や企業の社員が不正を実行したければ可能である事を行政は考えて改善策を考えるべきだ。杭打ちや建設業界だけでなく、全ての業界に言えることである。
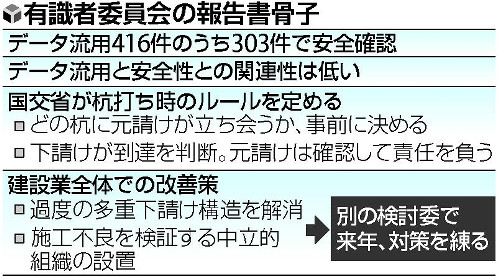
杭打ちデータの流用問題で、国土交通省の有識者対策委員会は25日、再発防止策などを盛り込んだ中間報告書を公表した。
傾きが見つかった横浜市のマンションの工事では、1次下請けの日立ハイテクノロジーズ(東京都港区)と2次下請けの旭化成建材(千代田区)が、建設業法で義務づけられた主任技術者の専任配置をせず、元請けの三井住友建設(中央区)もこれを知りながら指導しなかったと指摘。同省は同法に基づき3社を行政処分する方針を固めた。
同法では、マンションなど一定規模以上の工事では、実務経験や国家資格を持つ専任の主任技術者を常駐させる必要があると定めている。しかし、報告書によると、日立ハイテク社の技術者は横浜市のマンションを含む計5工事を掛け持ちし、3か月の工期中、現場にいたのは14日以下だった。旭化成建材の技術者も計3工事を兼任し、12日しかいなかった。三井住友建設は専任でないことを知りながら是正指導や行政への通報をしなかった。同省は処分について、業務改善命令などを検討している。
大阪大の50歳代の男性教授が、研究費を業者に預ける方法で不適切な経理処理を行っていた疑いがあることが25日、わかった。
大学は調査委員会を設けて調べており、教授の処分などを検討している。
疑いを持たれているのは、大学院情報科学研究科の男性教授。大学関係者によると、教授は約10年前から、物品を架空発注し、公的な研究費から支払われた代金を出入り業者に「預け金」としてプールさせ、定められた使途以外にも使っていたという。
業者側に預けていた総額は、1億5000万円以上になるとみられる。
学内の監査室に情報が寄せられたことから、大学は学外の有識者も含めた調査委員会を設置し、教授を含めて複数の関係者から聞き取りを行うなど調査を進めている。
補修工事を行った会社に問題があったのか、補修工事の方法に問題があったのか、原因を突き止めなければ同じ問題は起きるだろう。
「昨年6月から行われている老朽化対策の補修工事では、モルタルを岩盤に吹き付けた後、コンクリートのパネルをモルタルに沿って貼り付け、補強する予定だった。」
素人考えだが、岩盤にモルタルを吹き付ける時の密着状態はどうだったのか?岩盤から水が垂れているとか、岩盤の表面が湿っていたら、上手く密着しないのでは?
千葉県君津市の国道410号トンネル「松丘隧道ずいどう」の天井のモルタル約23・5トンが剥がれ落ちた事故で、補修工事で吹き付けられたモルタルの厚さが、設計上は10センチだったのに一部で20センチ近くあったことが24日、関係者への取材でわかった。
モルタルの重さを下部で支える施工も不十分で、国土交通省などの専門家は同日の現地調査で、モルタルが自重で剥落したとの見方を強めた。
国交省国土技術政策総合研究所と国立研究開発法人土木研究所の専門家4人が24日午後、県と合同で現地調査を行った。関係者によると、モルタルの厚さが設計の倍の20センチ近くある箇所が確認され、設計より荷重が大きかった可能性が高まっている。
昨年6月から行われている老朽化対策の補修工事では、モルタルを岩盤に吹き付けた後、コンクリートのパネルをモルタルに沿って貼り付け、補強する予定だった。今回の現場では23日にパネルを下部で支えるコンクリート基礎(高さ約1メートル50)の工事が行われ、直後にモルタルが長さ約20メートル、幅約5メートルにわたって剥落した。
一般財団法人・化学及および血清療法研究所の役員クラスがいなくならないと組織の体質は変わらないと思う。今度は、もっと巧妙に問題を隠ぺいするのだろう。
「1995年頃からは、承認通りに製造したと見せかけるために虚偽の記録を作成し、国の検査に虚偽の説明をしていた。」
組織や人間は簡単には変わらないし、変われない。
国内の血液製剤の約3割を製造する一般財団法人・化学及および血清療法研究所(化血研、熊本市)が、血液製剤やワクチンを国の承認を受けていない方法で製造していた問題で、厚生労働省は年明けにも化血研を医薬品医療機器法に基づく業務停止処分とする方針を固めた。
数週間以内に化血研側の弁明を聞いた上で処分を行う。停止期間は数十日~数か月の間で決める見通し。
厚労省は5~12月、化血研に3回にわたって立ち入り検査を行った。この結果、化血研では40年前から、国の承認書とは異なる方法で血液製剤を製造していたことが判明。1995年頃からは、承認通りに製造したと見せかけるために虚偽の記録を作成し、国の検査に虚偽の説明をしていた。
頭を使えば、現状の内部監査と外部監査でも逃げ切れる事が証明されたケースだと思う。外部監査がどこがやったのか?
新潟県阿賀野市の「さくらの街信用組合」で約2億8000万円が着服された問題で、組合は、問題を起こした総務部の男性係長(42)を懲戒解雇にした。
処分は18日付。組合の調査で、同じ現金を複数回数えさせる手口で監査を逃れていた実態が明らかになった。組合は民事訴訟の準備に加え、刑事告訴も検討している。
組合によると、係長が着服を行った期間中、内部監査と外部監査がそれぞれ2回ずつ行われた。外部監査で、係長が監査担当者の対応にあたった。担当者が組合の2階と3階を移動する間に現金をすり替え、同じ現金を複数回数えさせることで帳面と現金の差をごまかしたという。内部監査では、担当者が現金を数えることなく「現金と計算に相違ありません」という報告を出していた。このほか係長が帳面を偽装し「本部に現金が残っていない」と伝えたため、外部監査が入らなかったこともあった。
組合は、常勤5人と非常勤9人の全役員を減給にしている。
A案でもB案でも安くて構造的に強く、維持管理であればどちらでも良い。
ハディド氏がデザインの知的財産権は同氏の事務所に帰属していることも強調した事が事実であれば、A案で契約する前に法的にハディド氏と問題は起こりえない事を
日本スポーツ振興センター(JSC)を確認するべきだ。これ以上、無駄な税金を使わないでほしい。
個人的には可能であればオリンピックの東京での開催をキャンセルしてほしい。開催費用がオリンピック招致時点での試算額の6倍と公表されている。多くの税金が投入されるのは反対だ。
【ロンドン=風間徹也】建設コストの高騰を理由に白紙撤回された新国立競技場の旧デザイン案を担当した英国在住の建築家ザハ・ハディド氏は22日、新デザイン案決定を受け、「今日発表されたデザイン案の競技場の設計や観客席の配置は、我々のものと驚くほど似ている」などとする声明を発表した。
採用されたA案との類似性が「我々がこの2年間で提案してきたデザインやコスト削減が正しかったことを証明している」と指摘。デザインの知的財産権は同氏の事務所に帰属していることも強調した。
記者の書き方が悪いのか、建築家、伊東豊雄氏の発信能力に問題があるのかわからないが、負け惜しみに聞こえる。
「伊東氏はA案について『表層部分は違うが、(骨格を)はぐと中身はザハさんの案とかなり近い。訴えられるかもしれないですよ』と懸念を表明。」
「日本スポーツ振興センター(JSC)は訴えられても法的に問題ない事まで確認しているのか?確認しているのであれば仕方がない。」ぐらい言ってほしい。
新国立競技場のデザイン案が、建築家の隈研吾氏らによるA案に決定した。敗れたB案の建築家、伊東豊雄氏が都内の事務所で会見。A案が、見直し前のデザインを手掛けた英国の女性建築家ザハ・ハディド氏に近いことを指摘し「訴えられるかもしれないですよ」と話した。
伊東氏はA案について「表層部分は違うが、(骨格を)はぐと中身はザハさんの案とかなり近い。訴えられるかもしれないですよ」と懸念を表明。国産木材を多用する骨格を取り除くと、客席の構造などが物議を醸したザハ案とそっくりだと指摘した。
自身はザハ案との決別を明確に意図して、建築の構造から相違を意識してきたという。デザインやコンセプトなどではA案と同等もしくは上回る評価を得た。ただ、審査の最重要ポイントとされた「工期短縮」で大きく点数をあけられた。「事前着工ができれば確実に19年11月に間に合う、できなくても何とか完成させたい、と誠意を込めたつもりが、工期に間に合わない可能性があると受け取られてしまった」と悔やんだ。
「ある程度A案ありきだった部分もあるのかも」と恨み節も出た。両案が提示された直後、森会長が報道陣の質問に、B案支持を表明。この発言を受け、世論までもがA案シンパとなり、「反発も大きかったみたいですね」とため息をついた。「割と直感的な意見で、あの立場の方が言うのはまずいな、と内心思っていました」と、森発言が選考に与えた影響の大きさを悔やんだ。(スポニチ)
「一広によると、11月に組合が実施した品質抜き打ち検査で、関連会社が今治タオルとして出荷した1枚が吸水性などの基準を満たさなかった。さらに調査したところ、認定を受けないまま計20種類の製品を今治タオルとして出荷していたことも判明した。担当者が多忙を理由に検査に出さなかったという。」
理由としてもっとましな理由を考えられなかったのか?
「周辺のメーカーでつくる「四国タオル工業組合」(今治市)は、「水につけると5秒以内に沈む」などを条件とする独自の品質基準を設けている。」
サンプルを水につけて長くても数分待つだけでチェックできるでは?それ以外の品質基準が設けられているのか?
「四国タオル工業組合」は「ロゴマークを付けて販売」するタオルの販売会社及び製品番号(又は製品ブランド、管理番号)をどのように管理しているのだろうか?
「四国タオル工業組合」が適切に管理していれば、初歩的な段階で「今治タオル」の品質基準の認定を受けていない生地や製品をもっと簡単に絞り込めるのでは?
中国で偽ロゴマークの製造もその気になれば簡単だと思う。管理を適切にするべきだと思う。
愛媛県今治市のタオルメーカー「一広(いちひろ)」は22日、同社の関連会社が高級タオル「今治タオル」の品質基準の認定を受けていないのに、少なくとも35万枚を正規認定品として全国に出荷していたと発表した。すでに店頭から回収を終えたとしている。
周辺のメーカーでつくる「四国タオル工業組合」(今治市)は、「水につけると5秒以内に沈む」などを条件とする独自の品質基準を設けている。組合の認定検査で基準を満たせば今治タオルを名乗り、ロゴマークを付けて販売できる。
一広によると、11月に組合が実施した品質抜き打ち検査で、関連会社が今治タオルとして出荷した1枚が吸水性などの基準を満たさなかった。さらに調査したところ、認定を受けないまま計20種類の製品を今治タオルとして出荷していたことも判明した。担当者が多忙を理由に検査に出さなかったという。
一広の越智逸宏社長は「管理ミスで消費者のみなさまに多大なご迷惑をかけた」と謝罪した。(直井政夫)
「125社のうち12社で溶接の工程を省く不正が行われていたほか、製品を検査する段階で、複数の検査会社が溶接の不良を意図的に見逃すなど、不正に関わっていたことも報告されました。
インテリの机上の対策。「国など工事の発注者に対しても、抜き打ち検査を行う」は現実を理解していない。「抜き打ち検査」で問題を見つけるだけの能力と経験を持つ国土交通省職員はどれほどいるのか?
「抜き打ち検査」は能力と経験を持つものが行ってこそ効果が現れる。「抜き打ち検査」を行う事によるプレッシャーを与える事は出来る。しかし、問題を見つけられないと検査される側が
思うと張子の虎と一緒で効果がなくなる。
「再発防止策を検討する国の専門家による委員会は、部品を作る会社だけでなく検査会社も不正に関わっていたことを重く見て、元請け会社に対して、今後検査を行う場合には、取引に直接関与しない第三者の検査会社を選ぶよう求めています。」
少なくとも「求める」だけでなく強制にするべき。ただ、これでも問題は解決出来ない。元請会社が不正に関与する、又は、検査の不正を行う、検査が甘い会社を意図的に選択すれば
「取引に直接関与しない第三者の検査会社」の選択が契約条件に記載されていても、意図する効果は現れない。
検査会社に対する不正の罰則の強化で多少問題は改善されるだろう。しかし、不正の隠蔽工作が巧妙になる可能性もある。最終的には発注者のチェック能力向上が最善の
防止対策だろう。
これを受けて委員会では、工事の元請け会社に対して、すべての製品の検査を行うよう求めていくことや、国など工事の発注者に対しても、抜き打ち検査を行うよう求めていくなどの再発防止策を盛り込んだ報告書をまとめました。」
全国の500を超える橋で、耐震補強工事に使われた部品に溶接の不十分なものが見つかった問題で、その後の国土交通省の調査で、橋の数はさらに増えて690に上ることが分かりました。これを受けて国の専門家の委員会は工事を発注する国などにも製品の抜き打ち検査を行うことなどを求める再発防止策をまとめました。
この問題はことし8月、京都市の国道の橋で行われた耐震補強工事で、福井市の久富産業が製造した橋の落下を防止する装置の部品に溶接が不十分なものが見つかったもので、これまでの国土交通省の調査で、124の会社の製品で溶接が不十分な製品が確認され、使われていた橋の数は全国の556の橋に上っています。
22日開かれた再発防止策を検討する専門家による委員会では、その後の調査で、溶接が不十分な製品を作っていた会社は1社増えて125社に、橋の数は100余り増えて、香川県と長崎県を除く全国45の都道府県の690の橋に上ることが報告されました。
また、125社のうち12社で溶接の工程を省く不正が行われていたほか、製品を検査する段階で、複数の検査会社が溶接の不良を意図的に見逃すなど、不正に関わっていたことも報告されました。
これを受けて委員会では、工事の元請け会社に対して、すべての製品の検査を行うよう求めていくことや、国など工事の発注者に対しても、抜き打ち検査を行うよう求めていくなどの再発防止策を盛り込んだ報告書をまとめました。
国土交通省は今回の報告省に基づいて、今後、発注する工事の検査の在り方などを見直すとともに、自治体などに対しても、同様の対策を進めるよう求めていくことにしています。
複数の検査会社で不正
橋の耐震補強に使われる部品については、国の基準に基づいて、資格を持つ検査会社や製造会社が製品の検査を行って性能の確認をすることになっています。
この問題では、これまでに福井市にある検査会社の「北陸溶接検査事務所」の検査員が必要な調査をせずに検査報告書を作成し結果を元請けの会社に報告するなど、不正に関わっていたことが分かっています。
国土交通省によりますと、その後の調査で、札幌市の「北海道マテック」、千葉県横芝光町の「トーカン工業」、そして北九州市の「東亜非破壊検査」も同様の不正を行っていたことが明らかになったということです。
再発防止策を検討する国の専門家による委員会は、部品を作る会社だけでなく検査会社も不正に関わっていたことを重く見て、元請け会社に対して、今後検査を行う場合には、取引に直接関与しない第三者の検査会社を選ぶよう求めています。
大手商社「住友商事」が業績見通しを大幅に下方修正するという情報を知ったOBの元顧問ら2人が、この情報が発表される前に保有していた株を売却し、損失を免れるインサイダー取引をしたとして、証券取引等監視委員会は合わせて940万円の課徴金の納付を命じるよう金融庁に勧告しました。
勧告の対象となったのは住友商事のOBで、元顧問の60代の男性と、元役員の80代の男性です。
住友商事は去年9月、アメリカで進めていたシェールオイルの開発事業を巡り、およそ1700億円の損失が見込まれるとして、業績見通しを大幅に下方修正するとの発表を行い、株価が大きく下がりました。
証券取引等監視委員会によりますと、元顧問ら2人は、事前にこの情報を子会社の役員から電話やメールを通じて入手し、保有していた住友商事の株の一部を売却し、損失を免れていたということです。
監視委員会は、金融商品取引法に違反するインサイダー取引に当たるとして、元顧問に890万円余りの、元役員に50万円の課徴金の納付を命じるよう金融庁に勧告しました。
住友商事は「誠に遺憾で、株主や投資家をはじめとするすべての皆様に深くおわび申し上げます」とコメントしています。
辞任の理由は?新国立競技場及びエンブレム問題そして2020年東京五輪・パラリンピックに必要な会場整備及び大会運営が立候補の試算の6倍となるなど いろいろな問題が起きている。国民を騙すような過少の試算に胸を痛めての辞任であるのなら理解できる。映像からでしか判断できないが、豊田氏はまじめそうなので 森喜朗会長のようには振舞えないと思う。まじめであればあるほど詐欺してきなプロジェクトや茶番に付き合えないかもしれない。
2020年東京五輪・パラリンピック組織委員会は21日、東京都内で記者会見を開き、トヨタ自動車の豊田章男社長(59)が組織委副会長を辞任したと発表した。本人から18日の理事会後に申し出があり、同日付で了承された。後任にはパナソニックの津賀一宏社長(59)が就任予定で、本人から内諾を得ている。
豊田氏は大会公式エンブレムの白紙撤回問題を受けて発足した組織委の改革チームの座長を務め、組織の体質改善に取り組んできただけに突然の辞任となった。
経団連の五輪・パラリンピック等推進委員会の委員長などを務める豊田氏は、辞任理由について「経済界としての大会支援に専念する」との談話を出した。組織委の武藤敏郎事務総長は「これから経済界にさまざまな物的協力をお願いすることが想定される。お願いする立場とお願いされる立場をともにやることがいいのか、整理しなければいけないと思われていたようだ」と説明した。
トヨタ自動車は3月に国際オリンピック委員会(IOC)と最高位スポンサーである「TOPプログラム」の契約を24年まで締結し、東京五輪の運営面でのサポートも期待されている。組織委は森喜朗会長の下に5人の副会長が名を連ねていた。
ウィッツ青山学園高校(三重県伊賀市)の通信制を巡る国の就学支援金不正受給事件で、同校の運営会社の親会社「東理ホールディングス」(東京都中央区)は21日、不正受給の疑いのある会社役員3人が所属する「四谷キャンパス」(同千代田区)を今月31日で廃止すると発表した。
同キャンパスでは、会社役員3人を含む生徒計5人が、計約91万円を不正受給していたという。
同校によると、同校の通信制には今年2月末現在で1158人が在籍。同校は、通信制生徒の学習の場として「キャンパス」と呼ばれる拠点を全国約50か所に設置し、運営を外部に委託している。
キャンパスの中でも最大規模の四谷キャンパスには、11月末で151人の生徒が所属していたが、東京地検特捜部は今月8日、会社役員3人に不正受給の疑いがあるとして、詐欺容疑で東理や子会社で同校の運営会社のウィッツなどを捜索していた。
東理は、ほかに五つのキャンパスも廃止するが、四谷キャンパス以外では不正受給は見つかっていないという。同校は、廃止後の同キャンパスの生徒について「周辺のキャンパスに所属を変えてもらうなどして対応したい」としている。
「船津氏はヘパリン添加が始まった1991年頃に担当の第3製造部長を務め、92年、理事に昇格。2004~12年に理事長を務めた。」
組織的に不正が蔓延していたので、判断能力が麻痺していたのか、出世するためには黙認するしかなかったのか?関係者だけが事実を知っている。
一般財団法人・化学及血清療法研究所(化血研、熊本市)による血液製剤などの不正製造問題で、船津昭信・元理事長(70)は20日、読売新聞の取材に応じ、国の承認を受けずに抗凝固剤「ヘパリン」を添加したことについて「始めた時には不正という認識は薄かった。一時的な措置で、製造プロセスが整えば解消されると思っていた」と釈明した。
国に変更の申請をしなかった理由について「当時は血液製剤が大きなウェートを占めており、製造が止まれば影響が大きかった。開発を進めるにつれ、ヘパリンをなかなか除くことができないことがわかり、薬事法が厳しくなる中で、それをしてこなかったことが今につながっている」と語った。
船津氏はヘパリン添加が始まった1991年頃に担当の第3製造部長を務め、92年、理事に昇格。2004~12年に理事長を務めた。
一般財団法人・化学及および血清療法研究所(化血研)が無届けでボツリヌス毒素を運搬していた問題で、厚生労働省は21日午前、感染症法に基づき熊本市の化血研本所に立ち入り検査に入った。
同省は毒素の保管や運搬の実情を調べ、再発防止を求める。
同法は、生物兵器になり得るボツリヌス毒素を0・1ミリ・グラムを超えて外部に運搬する際に都道府県公安委員会に届け出るよう義務付けているが、化血研は今年10月と2007年10~12月の計4回、この毒素の試料を県内の事業所間で運搬する際に届け出をしなかった。
化血研は、血液製剤の問題でも厚労省の立ち入り検査を受けている。
血液製剤などを不正に製造していたことが問題になっている製薬メーカー「化血研」が、必要な届け出をせずに致死率の高い毒素を運んでいたとして、厚生労働省が立ち入り検査を行っています。
立ち入り検査は感染症法に基づき行われ、午前9時前、熊本市にある化血研の本社に厚生労働省の職員が入りました。
この問題は、化血研が2007年と今年10月のあわせて4回にわたり、必要な届け出をせずに強い毒性を持つボツリヌス毒素を運んでいたものです。ボツリヌス毒素は致死率が高く、生物兵器テロに使われる恐れがあるとして、運搬には都道府県公安委員会への届け出が義務付けられています。厚労省は「前例がなく、大変遺憾だ」としています。
化血研をめぐっては長年にわたり、血液製剤やワクチンなどを不正に製造するなど問題が相次いでいて、今月3日にも立ち入り検査が入ったばかりです。厚労省は近く、行政処分を行う方針です。
弁護士の数が多くなり、弁護士間の格差が広がっていると新聞の記事に書いてあった。結局、弁護には倫理とかモラルが要求されると綺麗ごとを言っても、
お金に困れば、犯罪や反社会的な行動に手を染めるという事なのだろうか?
「着服金を返済しないケースも多く、日本弁護士連合会は弁護士への信頼が崩れかねないとして、被害者に一定額を給付する救済制度の検討を始めた。」
救済制度を充実させても弁護士による不祥事が増加しているのであれば、弁護士への信頼は崩れるであろう。弁護士であるから、自分達の首を絞めるような
システムを導入しないだろうが、弁護士の経歴がチェックできるサイトなどの導入などした方が良いと思う。問題を過去に起こした弁護士達は猛反対するだろう。
仕事がなくなるリスクは高くなる、また依頼者を簡単に騙せなくなる可能性が高くなるからだ。弁護士の評価をマクロそれともマイクロ的に考えて、
どちらの方向へ進みたいか次第で、将来を考えていくべきであろう。あと、弁護士を利用するメリットが多くの国民に受け入れなければ、大きな変化はないような
気がする。
依頼者らの財産を着服したり、だまし取ったりした弁護士が過去3年間で23人起訴され、被害総額は20億円超に上ることが、読売新聞の調査でわかった。
背景には弁護士数の拡大や、成年後見人として高齢者の財産を預かる弁護士の増加があり、23人のうち9人は後見人だった。着服金を返済しないケースも多く、日本弁護士連合会は弁護士への信頼が崩れかねないとして、被害者に一定額を給付する救済制度の検討を始めた。
読売新聞は、2013年1月~先月の約3年間に、代理人や成年後見人として扱った金を着服するなどして起訴された弁護士について調べた。その結果、東京、大阪、兵庫など13都道府県の弁護士会に所属していた23人が業務上横領罪や詐欺罪で起訴され、事件数では103件。一部は有罪が確定している。
法律、規則、そして制度を変えないと改善されない問題。
悪法でも法は法である。弁護士は正義の味方ではなく、法の専門家として弁護をするのである。法律の知識と経験を使い、悪にも、善にもなれる。
法を犯さない限り、相手にとってはろくでなしであっても、何でも許される。
モラルとか、人間性の問題と非難し、懲戒請求しても、法律、規則、そして制度を変えない限り根本的な問題は解決できないし、同じような人物は出てくる。
今度はもっと上手く立ち振る舞うだけである。
ブログに公開 弁護士らが厚労相に懲戒請求
日本労働弁護団や全国過労死を考える家族の会など6団体は18日、愛知県社会保険労務士会に所属する社労士が「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題した文章をブログに公開したとして、管轄する厚生労働省に監督責任を果たすよう求めた。弁護士と社労士計9人は、塩崎恭久厚労相にブログを執筆した社労士の懲戒を請求した。
この社労士は11月24日付のブログに質問に答える形で「上司に逆らう社員をうつ病にして追放する方法」を書いた。就業規則を変更して上司に文句を言うことの禁止などを盛り込むことを提案するなどし、「万が一自殺したとしても、うつの原因と死亡の因果関係を否定する証拠を作っておくこと」とした。ブログは批判を浴び、現在は公開されていない。
過労死家族の会のメンバー、中原のり子さんは「ブログの内容は殺人を勧めるようなもの」と批判した。この社労士は「モンスター社員を真人間にするためとの思いで書いたが、誤解を与え、申し訳ない」と話している。【東海林智】
東京都知事を辞めた件では反省していると思うし、根は真面目そうだが、特別顧問としては少し疑問である。
注目を受けるし、それなりの経験は積んでいるので、上手く行けば良い効果は出るかもしれないが、東京のやり方と
大阪のやり方は違うし、発想や価値観が違う。やはり疑問。チャンスを与えれば、感謝してがんばる人もいるのは事実であるが、
やはり注目を得るために要請のような気がする。
前東京都知事で作家の猪瀬直樹氏(69)が、大阪府市特別顧問に就任することが固まった。
大阪府の松井一郎知事が要請したもので、猪瀬氏は18日、受諾する意向を府幹部に伝えた。近く特別顧問に就任し、28日に行われる府と大阪市の共同組織「副首都推進本部」の初会合に出席する見通し。
都知事経験者の立場から、副首都に必要な機能などについて助言を得たいとして、松井氏が11日に就任を依頼していた。
オリンピックの誘致には反対だった。これは明らかに詐欺のやり方だ。
「12年ロンドン大会でも大会運営費が当初見込みを大幅に上回る約2兆1千億円となり、多額の公的資金が投入されている。」
ロンドンオリンピックも想定よりも大幅に上回る約2兆1千億円で多額の公的資金が投入されたから、東京オリンピックも仕方がないと納得させるつもりか?
ばかげている。ロンドンオリンピックのデータを参考に費用の見積もりは出来たはずだ。オリンピック反対派やどちらでも良い派を欺くために、あえて
費用と小さく見積もったと思える。
「費用の大幅な増加は人件費や資材の高騰などを要因とするが、選手らを輸送する首都高速道路に専用レーンを設置するための補償費や、会場周辺の土地賃貸料など当初は見込んでいなかった負担によるものもある。」
費用を小さくするために意図的に除外したものもあると思う。新国立競技場と同じだ。騙して決めてしまえば良い、納期の問題にして逃げ切ろうとしているのではないのか?
オリンピックはスポーツ選手だけが騒げば良い。しかし、スポーツ選手のためだけにしては贅沢すぎる祭りである。この調子では、もっと多くの税金が使われる事になるのだろう。
出来るのであれば東京オリンピックをキャンセルしてほしい。
「東京五輪費用1.8兆円 組織委試算 当初の6倍、公的資金投入は必至」は本当に「オリンピック反対派やどちらでも良い派」をばかにしている。
東京五輪費はもっと圧縮できるはずだ。ただ、あれもこれもしたい、利害関係のある企業や人達の意見を聞いたら、試算の6倍になったのであろう。
当初の試算よりも多くなる事は関係者は知っていた、又は、想定していたのではないのか?
2020年東京五輪・パラリンピックに必要な会場整備や大会運営費が約1兆8千億円に上ることが18日、大会組織委員会の試算で分かった。大会への立候補段階では約3千億円と見込んでおり、費用は当初の6倍に膨らむことになる。
組織委では費用削減に向けて東京都や国との協議を急ぐが、最終的に大幅な公的資金の投入は避けられない見通し。組織委は今後、都民や国民が納得する説明を求められる。
関係者によると、組織委がスポンサーやチケット収入などで集められる資金は約4500億円と想定。しかし、仮設競技会場の整備費や施設の賃借料、テロ対策の強化といった警備費などが当初の見込みを大幅に上回ることが判明した。
費用の大幅な増加は人件費や資材の高騰などを要因とするが、選手らを輸送する首都高速道路に専用レーンを設置するための補償費や、会場周辺の土地賃貸料など当初は見込んでいなかった負担によるものもある。これに国や都の会場整備費を加えると運営費は2兆円以上に上る。
東京五輪の開催計画を記した「立候補ファイル」では、組織委の運営費は3013億円、東京都が会場の新設などで支出する額は1538億円の予定だった。
五輪の経費をめぐっては、組織委の森喜朗会長が7月、日本記者クラブでの記者会見で「(大会経費が)2兆円を超すことになるかもしれない」と述べていた。
12年ロンドン大会でも大会運営費が当初見込みを大幅に上回る約2兆1千億円となり、多額の公的資金が投入されている。
5年後のオリンピック・パラリンピックに向けて組織委員会が準備や運営に必要な費用を試算したところ、およそ1兆8000億円と当初の見込みの6倍に上り、組織委員会の財源だけでは大幅に不足することが分かりました。不足分は東京都や国が補填(ほてん)することになっていて、今後、公的な財政負担がどこまで膨らむのかが焦点になります。
組織委員会が5年後の大会の準備や運営を行うのに必要な費用は立候補段階では3000億円程度と見込まれていましたが、関係者によりますと組織委員会が先月新たに試算したところ、当初の見込みの6倍にあたるおよそ1兆8000億円に上ることが分かりました。
内訳は、仮設の競技会場の整備費などが3000億円、会場に利用する施設の賃借料などが2700億円、警備会社への委託費などセキュリティー関連の費用が2000億円、首都高速道路に専用レーンを設けるための営業補償費など選手や大会関係者の輸送に関する経費が1800億円などとなっています。費用の大幅な増加は、首都高の営業補償など当初、想定していなかった経費が加わったことや、資材や人件費の高騰なども要因だということですが、立候補段階での見通しの甘さが浮き彫りになった形です。
一方、組織委員会がチケット収入やスポンサー企業などから集められる資金は4500億円程度と見込まれ、このままでは1兆円以上が不足します。組織委員会は経費の削減とともに東京都や国の事業として実施できるものがないか検討を進めることにしていて、最終的に不足分を補填することになる都や国の財政負担が、今後どこまで膨らむのかが焦点になります。
費用は組織委・東京都・国が分担
5年後のオリンピック・パラリンピックに必要な費用は、主に、組織委員会や、東京都、それに国が分担して負担することになっています。このうち競技会場については国がメインスタジアムの新しい国立競技場を整備しますが、総工費に設計費など関連費用を含めた1581億円のうち、国がほぼ半分の791億円程度を負担し、東京都も4分の1の395億円程度を負担する方針を決めています。また東京都は大会後も施設を残す競技会場の整備などを担当し、これだけで合わせて2241億円を支出する予定です。そして、組織委員会は、大会後に取り壊す仮設の競技会場の整備をはじめ、会場の警備や、選手の輸送などといった大会の準備・運営を担当することになっていて、立候補段階ではその費用は3000億円程度と見込まれていました。
しかし、組織委員会が試算したところその費用は1兆8000億円に上ることが分かり、国や東京都が競技会場の整備で負担する費用を合わせると2兆1000億円以上に上ることになります。
財政負担の拡大避けられず
組織委員会は今後、費用を削減できないか検討を進めるとともに東京都や国の予算で実施できるものがないか役割分担の見直しを進めることにしています。都や国の事業の対象になる可能性があるのは、会場やインフラなど大会後も残され、都民、国民が利用できるもの、また、交通インフラの整備など大会開催による都民活動への影響を抑えることにつながるものなどが考えられています。組織委員会は来年5月にIOCに予算の計画を提出するため都や国との協議を急ぐことにしていますが、最終的に都や国が不足分を補填することになっているため公的な財政負担の拡大は避けられない情勢で、都民、国民が納得できる説明がこれまで以上に求められます。
前回大会でも巨額の公的資金
前回、2012年に開催されたロンドン大会でも、準備や運営、それに競技会場の整備などにかかる費用が当初の見込みの3倍近くにあたる2兆1000億円余りに膨らみ、組織委員会が財源不足に陥り、巨額の公的資金が投入されました。ロンドン大会では組織委員会が大会の準備や運営を担当し、宝くじの売り上げやロンドン市などが拠出する公的資金で競技会場やインフラの整備を行う計画でした。しかし、組織委員会がチケット収入やスポンサー企業からの収入などで集めた資金は4300億円余りにとどまりました。このため当初、組織委員会が負担することになっていた競技会場などの警備や、開会式や閉会式などを開催するための費用は公的資金でまかなわれ、競技会場などの整備費と合わせて最終的に投入された公的資金は、1兆6700億円余りに上りました。
専門家「賛同得るには説明責任を」
オリンピックなどスポーツイベントの運営に詳しい早稲田大学スポーツ科学学術院の原田宗彦教授は運営費などが大幅に増加したことについて「オリンピックの招致の段階では国内の支持、IOCの支持を取り付けなければならず、非常に小さめの数字でまとめることが多く、今回の東京も当初、小さくまとめたことがこの結果につながったと思う」と指摘しています。そのうえで、前回のロンドン大会でも開催費用が当初の3倍に増えたことを例に挙げ、「東京も予算額が増えてもしかたない面はあるが、6倍というのはかなりの膨らみ方で、若干見通しが甘かったと思う」と話しています。また、資金の不足分については東京都と国が補填することになっていることから、原田教授は「組織委員会の財務状況が破綻することはないと思うが、都民、国民の賛同を得るために組織委員会は納得できる計画を立て具体的な数字について十分な説明責任を果たしていかなければならない」と指摘しています。
人生、いろいろ!
今野晴貴 | NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者
先日、ワタミでの長時間労働によって26歳の娘を過労自死に追い込まれた両親が会社を訴えていた事案で、和解が成立した。ワタミおよび創業者の渡邉美樹氏は全面的に責任を認め、再発防止策などを含んだ和解条項に合意した。
そんな中、ある社会保険労務士が行ったブログへの書き込みが注目を集めている。
「モンスター社員を解雇せよ! すご腕社労士の首切りブログ」と題されたブログでは、「社員をうつ病に罹患させる方法」として、「適切にして強烈な合法パワハラ与え」るために、「失敗や他人へ迷惑をかけたと思っていること、不快に感じたこと、悲しかったことなどを思い出せるだけ・・・自分に非があるように関連付けて考えて書いていくことを繰り返」えさせることで、うつ病に追い込むよう指南している。さらに、「万が一本人が自殺したとしても、うつの原因と死亡の結果の相当因果関係を否定する証拠を作っておくこと」とまでアドバイスしている(ブログはすでに削除されている)。
社員の自殺までも「想定」してパワハラを推奨している点で、悪質性が極めて高いといえよう。
私は年間に3000件ほどの労働相談に関わっているが、この手の社労士、弁護士、労務コンサルが絡んだ悪質な事件は後を絶たない。拙著『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』(文藝春秋、2012年)では、「ブラック士業」の手口として指摘したものである。また、その後出版した『ブラック企業ビジネス』(朝日新聞出版、2013年)では、ブラック士業に特化し、その問題を全面的に告発してきた(尚、私は2013年にユニクロ、ワタミの弁護士たちから「脅し」ともとれる書面を送り付けられており、その経緯についても同書で紹介した)。
この社労士のブログは、私が問題にしてきたブラック士業の手口を、自ら告白する内容になっている。社員をうつ病に追い込み自ら辞めるように仕向けるというブラック企業の典型的な手口に、「専門家」である社労士が加担していると認めたのである。
ブラック企業の「共犯者」としてのブラック士業
ブラック士業は、違法な労務管理の技術を経営者に手ほどきすることで、ブラック企業を支えている。このような「専門家」は、「ブラック企業」とともに発展してきた。その背景には、違法なことでもまかり通らせたいという「ブラック企業」の経営者の思惑がある。
ブラック企業は社員を「いつでも辞めさせられる」状態に置き、過酷な選別競争を強いる。そして、「使えない」と決めつけた社員を「自己都合退職」に追い込むために、パワハラなどの違法行為を戦略的に行う。その際に、ブラック士業はこの「自己都合退職」を選択させるために、労働者をうつ病に追い込むようなパワハラ行為を積極的に推奨するのである。
それだけではない。一方では、「まだ使える」と判断した労働者を辞めさせないために、辞めると損害賠償を請求するという脅しの文書を送付することや、違法な労働組合つぶしにも加担する。
事実、京都のあるIT企業は、弁護士を立てて、過労死ラインを超える長時間労働とパワハラによって不眠症になりやむなく退職を申し出た労働者に対して、2000万円の損害賠償を請求する訴訟を提起した。
また、残業代を請求するために組合が申し入れた団体交渉に対して、「なにゆえに貴団体が当社に対し団体交渉申入れができるのか」法的根拠を示せ、という支離滅裂な主張を展開する文書を弁護士名で送付し、労使交渉を妨げようとするブラック士業もいた。こうした行為も「不当労働行為」という明白な違法行為である。
最近では新卒や、アルバイトを辞めようとした学生の親に「損害賠償を請求する」と社労士が送り付けてくる事件もたびたび生じている。違法な労務管理を行う「ブラック企業」が蔓延するなか、ブラック士業もそれに合わせて増殖してきたのである。
「脅し」で成果を上げる
このような行為は後述するように裁判になれば、ほとんどの場合、会社側が敗訴する。いわば、「違法だとわかっていて、あえて違法行為を推奨している」というわけだ。では、これらをアドバイスするブラック士業の戦略とはなにか。
それは、一言で言えば、「労働者に権利主張を諦めさせること」である。労働者が権利主張しなければ、違法状態は継続し放置される。事実、ほとんどの労働者は会社の行為が違法だとわかっても諦めてしまう。彼らはそれを狙っているのだ。労働者に諦めさせるために、「弁護士」や「社労士」といった肩書を利用し、あたかも脅迫行為に正当性があるような装いを振る舞う。
しかし、このような脅しに屈することなく、労働者が権利主張すれば、会社に責任を認めさせることができる。被害に遭っている労働者が裁判を起こせば、ブラック士業はほとんどの場合、負けるのである。
例えば、先のIT企業の事例では、裁判の結果、会社が請求した2000万円は1円も認められなかった。むしろ、実際に未払いになっていた残業代1000万円以上を会社は支払うよう命じられた。さらに、大手牛丼チェーンすき家を運営するゼンショーは、残業代請求をされた際に、アルバイトとは労働契約ではなく「業務委託契約」を締結しているのだから未払いは存在せず労使交渉も不要と当初主張していたが、裁判では敗訴を続け最高裁まで争った挙句、最終的には自ら主張を取り下げて非を認めざるを得なかった。つまり、何年もむだに争った挙句に会社は「全面降伏」したわけだ。
だが、繰り返しになるが、ほとんどの労働者は「脅し」にあらがって何年間も裁判を行うことはできない。このように企業と労働者の「係争費用の負担力」の差につけ込むことが、ブラック士業のやり口なのである。
「社長の味方」ではないブラック士業
さらに、ブラック士業の収益戦略を見ていくと、実は、ブラック士業は、社長の味方ですらないということが見えてくる。というのも、彼らは、ブラック企業と労働者の間の紛争を一つのビジネスチャンスとして考えているだけだからだ。
ブラック士業は、会社が勝とうが負けようが、事件を受任さえすれば顧問料及び訴訟費用などで儲けることができる。弁護士の場合、通常、訴訟を提起する際は、着手金として請求額の数パーセントを弁護士に支払うことが多い。仮に10パーセントだとすれば、2000万円の請求を行うだけで、200万円を手に入れることができる。裁判で、違法で支離滅裂な主張を展開するはめになったとしても、争いが起こりさえすれば必ず儲かる。
社労士の場合にも、係争中の「顧問料」のほか、社員を脅す際の「面談料」、パワハラのやり方を教える「相談料」、書面を送る際の「書面送付料金(一枚単位で取引されている)」などが膨大に発生するのだ。
だから、彼らは社長を炊きつけて、負けるような無茶な主張を展開するよう指南するのだ。アルバイトを雇っておらず、彼らを「業務委託契約」などという無茶の主張にも、うなずけるというものだろう。
なぜ負けるのに経営者は雇うのか?
もしこのような「脅し」を行っていることが明らかになれば、企業のイメージは相当悪化することは火を見るより明らかである。さらに、当然、彼らに支払う顧問料も安くはない。顧問料や裁判費用は、すぐに残業代の支払いに応じれば、負担する必要がなかった費用である。
それにも関わらず、なぜ経営者はブラック士業を雇うのか。それは、すでに述べたように、ブラック士業を活用して労働者を黙らせることができれば、「勝ち」だからである。社労士や弁護士に「訴える」と脅された労働者が請求権を放棄すれば、会社は残業代の支払いから免れることができる。
これに加え、経営者側には合法的に労働者を扱いたくない事情もある。すき家の場合、労働者が諦めず争った結果、最終的に全国の社員1万人以上に対して、過去2年分の残業代を支払うこととなった。これには、億単位の金額がかかっていると思われる。しかし、ブラック士業を雇い、その脅しに労働者が屈服したとしたら、支払いは数百万もしくは数千万円で済む。それゆえ、すき家はブラック士業に頼ったのである。労働者が「黙れば」経済的にも得だったわけである。
同様に、解雇の場合にも合法的に行う場合には退職金の上乗せなどが必要になる。この場合にも、「安く解雇がしたい企業」がその経費を削ろうとして、ブラック士業を頼るのだ。
このように、経営者は解雇の費用が発生したり、残業代請求などが労働者からあったばあい、(1)合法に支払う、(2)ブラック士業に頼って労働者を黙らせて払わない、(3)(2)を選択したが労働者が黙らなかったので結局合法に全額支払う(この場合、ブラック士業の報酬に加え、会社の汚名など膨大なコストが発生する)、の三択を迫られているということになる。
合法な支払いを拒んだ結果、一か八か、大きなリスクを背負って労働者を脅す路線に乗り出していくというわけだ。この社長の「決断」を積極的に後押しし、ビジネスチャンスを広げているのが、今回問題になった社労士のように、ブログ等で「残業代を支払わなくてよい」などと宣伝しているブラック士業たちなのである。
解決策
さらに、弁護士や社労士などがブラックな労務管理に加担する原因として、士業の数が急速に増加していることがあげられる。
特に社労士は急激に合格者数が増えている一方で、通常の保険管理の業務などは増えていない。そこで、社労士界全体として、「労使紛争」への介入を新たなビジネスチャンスにしていこうとしているのだ。もちろん、まともに新しいビジネスを行っている社労士もいる一方で、上に見たような「紛争で設ける」いかがわしいビジネスモデルを構築する新手も増えてきた。
では、このブラック士業問題の解決法はどこにあるのか。まず、業界団体である日本弁護士連合会(日弁連)や全国社会保険労務士会連合会は、違法行為を指南する会員を厳しく処分すべきである。違法行為に専門家が積極的に加担する行為は、真っ当に職務を遂行している弁護士や社労士の業務に支障をきたすことになり、かつこのような行為を容認もしくは黙認するのであれば、業界団体自体がブラック企業に加担していると思われても仕方がないだろう。まずは業界団体自身で、違法行為に対処すべきである。
そして、労働者自身がこのような「脅し」を受けた場合は、すぐに私たちNPO法人POSSEの無料窓口や、ブラック企業被害対策弁護団、日本労働弁護団所属の弁護士に相談していただきたい。ブラック士業の唯一の勝ち目は諦めさせることであり、彼らの主張には一切の法的根拠が存在しないので、適切に対処すれば、その請求から逃れることができるのはもちろん、むしろ会社に対して適切な責任を取らせることが可能にもなるのだ。
業界のトップ法人がこの有様である
年の瀬も押し詰まった12月15日、公認会計士の世界に衝撃のニュースが走った。東芝を監査した「新日本監査法人」について、金融庁の公認会計士・監査審査会が「運営が著しく不当だった」と厳しく断じる検査結果を公表したのだ。審査会は15日、同法人を行政処分するよう金融庁に勧告した。
新日本監査法人は、公認会計士約3500人を擁する国内最大手の監査法人。大元の法人は1967年に日本で最初に設立された。その後、他の法人と合併・合流を繰り返し、今では資本金約9億円、監査をする企業4000社超という、日本3大監査法人の一角を占めるまでになった巨大法人だ。
社員の多くが、司法試験と同レベルの難関国家試験に合格した公認会計士という専門家集団である。だからこそ、不正会計の発覚当初から「いったい東芝の何を監査してきたのか」と強い批判を浴びた。「著しく不当」という今回の表現は、監査法人失格の烙印(らくいん)を押されたに等しい言葉だ。法人内部でいったい何があったのか。
「社員や監査補助者が責任と役割を自覚していない」
審査会の公表文を見てみよう。A4判2枚に、新日本監査法人に対する厳しい指摘が並んでいる。
公認会計士・監査審査会が12月15日に公表した書面「新日本有限責任監査法人に対する検査結果に基づく勧告について」
審査会はこれまで2年に1度、新日本監査法人の定期検査を行ってきた。そうした過去の検査で、企業に対する監査計画の立案や手続きの不備を繰り返し指摘してきたという。
ところが、東芝不正会計を受けた今回の検査で、過去に指摘された改善策を周知徹底しておらず、改善状況を検証する態勢も構築していなかった、と指摘されたのだ。さらに「社員や監査補助者には、監査で果たすべき責任や役割を十分に自覚していない者がいる」「一部の業務執行社員は、深度ある査閲を実施しておらず、監査補助者に対する監督、指導を十分に行っていない」とも書かれた。
「業務執行社員」は、企業の監査を行い、最後に「監査証明」を出すときに監査法人を代表してサインをする幹部社員のこと。幹部社員全員ではないが、その一部は監督、指導を十分にしていないという。当然のことながら、能力のある社員が業務執行社員となるはずだ。仕事を適当にやったり、怠けたりしている幹部社員がいるということなのだろうか。
審査会は結局、「新日本監査法人の品質管理態勢は著しく不十分である」と結論づけた。つまり、新日本監査法人に企業の監査はきちんとできない、ということだ。
東芝の見積もりや事業見通しをうのみに
公表文は続いて、東芝に対する監査のどこに問題があったかを具体的に挙げている。
まず、重要な勘定で「多額の異常値」を把握していたにもかかわらず、やらなければならない実証手続きをしていなかったこと。そして、東芝が行った「見積もり方法の変更」と「事業計画の合理性」をうのみにし、批判的に検討しなかったことを指摘した。
11月27日に東芝が開示したウェスチングハウス社の減損テストに関する資料。15年間で46基の原発建設受注を前提にしており、「バラ色予測」ともいえる
この簡潔な公表文には、とても重要なことが書かれている。東芝は5月に不正会計が発覚した後、決算発表と有価証券報告書提出を延期。修正して、9月7日に財務局に提出し、公表した。その修正版もこれまでどおり新日本監査法人が監査した。ところが審査会は、まさにその9月に新日本監査法人に検査に入り、公表文に書かれた結論を出したのだ。
ということは、改めて「適正」の太鼓判を押したはずの修正版有価証券報告書も、「著しく不十分な品質管理態勢」のなかで監査されたことにならないだろうか。「多額の異常値」はさすがに直されただろう。だが、「事業計画の合理性」はどうなのだろうか。
損失隠しオリンパスに続く不正見逃し
東芝は11月、ウェスチングハウスを含めた原子力事業の2029年度までの事業計画を初めて公表した。世界で400基以上の原発建設計画があり、ウェスチングハウスが64基の受注を目指すというものだ。そして、資産評価では「保守的に見て46基受注を前提とした」と説明した。筆者は一連のリポートで、46基受注という前提は本当に保守的に見たものなのか、バラ色の予測で見通しが甘すぎるのではないか、と疑問を示した。
この原子力事業計画を、新日本監査法人は批判的に検討したのだろうか。審査会は、新日本監査法人の運営体制の不備を現在形で指摘しているのである。
新日本監査法人は、11年に損失隠しが発覚したオリンパスの監査も担当していた。このとき、金融庁から業務改善命令を受けた。同法人のサイトには今も「これら改善策を着実に推し進め、より一層の監査品質の向上に努めてまいります」(12年7月)という言葉が掲載されている。
業界のトップ法人が、こうした行政処分を繰り返し受けるのは異常である。新日本監査法人の英公一理事長は「今後は全構成員一丸となって信頼回復に取り組む」とのコメントを出したが、東芝と同じく、信頼回復への道のりはかなり険しいのではないか。
[東京 18日 ロイター] - 金融庁は、東芝<6502.T>の監査を担当してきた新日本監査法人に対し、課徴金納付命令と新規契約に関する業務の停止命令を同時に課す方針であることがわかった。課徴金額や業務停止の期間を詰めたうえで、来週に金融庁が処分を発表する。監査法人への課徴金命令は、2008年の制度導入以降、初めてとなる。
関係者が明らかにした。新日本監査法人に対しては、金融庁が同庁傘下の公認会計士・監査審査会と調査を進めてきた。金融庁は、同監査法人による東芝の監査に焦点を当てて調査してきたが、長期にわたって不適切な監査証明を出したことに加え、今回の不正会計問題の社会的な影響力の大きさを重くみているもようだ。
同法人は、2011年に発覚したオリンパス<7733.T>事件で業務改善命令を受けており、より重い処分を課す判断材料になったとみられている。東芝の監査に関わった業務執行社員の一部も、業務停止処分を受けるもようだ。業務停止処分が出ると、停止期間中は公認会計士を名乗っての業務が一切できなくなる。
金融庁、新日本監査法人ともに、コメントは差し控えるとした。
監査審査会は15日、金融庁に行政処分を課すよう勧告。東芝の監査に限らず、監査業務体制全般を検査した結果、審査会などが過去に繰り返し指摘してきた監査手続きの問題点が組織全体で改善するには至っておらず、業務運営が著しく不当だと指摘した。
新日本監査法人は日本最大手の監査法人。所属公認会計士は3500人超、監査を受ける会社は4000社を上回る。
*内容を追加します。
(和田崇彦)
迂回の賄賂か、買収のような思えるが、単なるモラルの問題に留まるようだ。法にも規則にも触れないのであれば、今後もある一定の期間が過ぎればこのような行為は続けられるのだろう。
教科書を発行する「三省堂」(東京)が検定中の教科書を校長らに見せて謝礼を払っていた問題で、謝礼を受け取った26都府県の校長ら計53人のうち、16都府県の21人がその後、教科書の選定に関与していたことが、文部科学省の調査でわかった。
選定にかかわった校長が同社の教科書を推薦し、実際に採択されたケースがあったことも判明している。文科省は、教科書選定への影響や、他の教科書会社の金銭授受の有無などをさらに調べている。
調査は、2009~14年に計7回開かれた三省堂の「編集会議」に参加し、謝礼を受け取った校長ら53人の地元教育委員会などを対象に行った。
それによると、編集会議の翌年に教科書の選定に関与した校長らは16都府県の21人。いずれも市町村教委の「調査員」として選定する教科書の参考資料を作成したり、市町村に助言する都道府県の「教科書選定審議会」のメンバーに就任したりしていた。内訳は、09年に2回開かれた小学国語の編集会議の参加者が計3人、10年の中学国語(2回)が計5人、10年の中学英語(同)が計8人、昨年の中学英語が5人だった。
出版社の三省堂(東京都)が、公立校教員に検定中の自社の教科書を見せる会議を開き、謝礼金を払った問題で、同社が文部科学省に提出した調査報告から、会議が組織ぐるみで開かれていた実態が浮かんだ。文科省は他社にも問題がないか、調査を徹底する。参加教員が処分される例も出ており、波紋が広がっている。
NHKの職員なのに大胆!
NHKの子会社「NHKアイテック」は、社員2人が放送関連施設の工事などを実態のない会社に発注するなどの方法で、およそ2億円を着服していた疑いがあることが、東京国税局の税務調査の過程で明らかになったと発表しました。NHKアイテックは引き続き、国税局の調査に協力するとともに社内調査をNHKとともに進め、刑事告訴を検討するとしています。
これは17日夕方、NHKの子会社の「NHKアイテック」が記者会見を開いて明らかにしたものです。
それによりますと、NHKアイテックの本社と千葉事業所に所属するいずれも40代の男性社員2人は、平成21年からこれまでに、放送関連施設の工事や業務を実態のない会社に発注するなどの方法で会社の金およそ2億円を着服していた疑いがあるということです。
これらの工事は、テレビの地上デジタル化に伴い、アナログ放送の受信施設を撤去したり、国の補助金の対象となる難視地域の共聴施設を設置したりするものなどで、合わせて500数十件、総額およそ4億円が発注され、このうちおよそ2億円を不正に受け取った疑いがあるということです。
これは東京国税局による税務調査の過程で明らかになったもので、社内調査に対し、2人は不正を認めているということです。
NHKアイテックは引き続き、国税局の調査に協力するとともに社内調査を進め、2人を厳正に処分し刑事告訴を検討するとしています。
今回の問題を受けて、NHKは緊急調査チームを設けて、NHKアイテックと連携して事実関係の解明を進めるとともに、NHKアイテックに対して、ほかの取引先についても実態のある会社なのか確認することや、実際に取引が行われたかチェックする体制を整備することなどを緊急に指示しました。
17日夜、記者会見したNHKの今井純理事は「関連団体のNHKアイテックの社員によって不正な行為が行われていたことは極めて遺憾です。皆様の信頼を損なう許し難い行為であり、NHKとしても大変重く受け止めています。今後、原因の究明を徹底的に行い、厳正に対処するとともに、再発防止に向けて指導監督の在り方についても点検・強化して参ります」としています。
子会社社長「おわび申し上げる」
「NHKアイテック」の久保田啓一社長は記者会見で、「2人の処分や刑事告訴を視野に入れて、事実関係の確認に努めています。社員の不正行為が明らかになったことは大変申し訳なく、おわび申し上げます」と謝罪しました。
「報告書は同時に、『2次審査以降は適切に審査が行われた』とし、審査で1位になった佐野研二郎氏を含む入選作品の決定に影響を与えた事実はないと結論づけた。」
適切な審査でなかったとしても、処分されたり、影響を受ける人がいれば、報告書には記載されないかもしれない。1次審査で不適切な行為があったのだから、
報告書の作成に関して何らかの圧力があってもおかしくはない。
2020年東京五輪・パラリンピック組織委員会は18日、9月に白紙撤回した旧エンブレムの選考過程について、「1次審査において、事前に参加を要請した8人中2人に対して、不適切な投票があった」とする外部有識者の調査結果を公表した。8人は結果的に全員が1次審査を通過した。
報告書によると、審査委員代表だった永井一正氏が槙英俊・マーケティング局長と、高崎卓馬・企画財務局クリエイティブディレクターの2人(いずれも当時)に、8人全員を自動的に2次審査に進めるよう事前に要望していた。1次審査は審査委員が104作品に対して1人1票、最大20作品を選び、2票以上を得た作品が2次審査に進む仕組みだったが、8人の作品番号を事前に知っていた槙氏と高崎氏が投票締め切り直前、8人中2人の作品は1票しか入っていないことに気づき、永井氏に該当作品の番号作品を伝えた。票を使い切っていなかった永井氏がこの2作品に投票したため、8人の1次通過が確定したという。
報告書は同時に、「2次審査以降は適切に審査が行われた」とし、審査で1位になった佐野研二郎氏を含む入選作品の決定に影響を与えた事実はないと結論づけた。
結局、客船やフェリーは建造できても、クルーズ船は無理な状態に陥っていたという事であろう。
三菱重工業が、大型客船事業を縮小する方向で調整に入った。
長崎造船所で建造中の豪華客船の納入が大幅に遅れ、巨額の損失を出しているためだ。当初は付加価値が高い客船で造船事業の収益力を上げる戦略だったが、大幅な転換を迫られる。
長崎造船所で建造しているのは、2011年に米クルーズ大手「カーニバル社」から受注した2隻。いずれも約12万5000総トン、3250人乗りの豪華客船だ。富裕層向けのクルーズ船で、豪華な内装から「海上ホテル」とも言われる。
だが、内装の仕上がりなどがカーニバル側の求める水準に至らず、1隻目の納期はこれまでに2度延期され、12月の納入も難しい見通しとなっている。2隻目も、納期の16年3月には間に合わない公算が大きい。
「同社は11月、資金繰りに行き詰まって秋田地裁に民事再生手続きを申し立て、手続きが始まっている。」
このような状態だと支援会社が現れない限り、自己破産に移行するかもしれない。
「全農は肥料を使って損害を受けた農家へ今年度中に補償をする方針。補償額は10億円を超える見通しで、全額同社に請求する。」
被害の回収は無理かも?
肥料メーカー「太平物産」(秋田市)が製造した肥料の成分表示に偽装があった問題で、秋田県警は18日、肥料取締法違反の疑いで本社や工場など複数の関係先に家宅捜索に入った。秋田市の本社には午前8時半すぎ、県警の捜査員約20人が入った。県警は、不正競争防止法違反や詐欺の疑いでの立件も視野に捜査を続けている。
販売元の全国農業協同組合連合会(全農)によると、成分偽装は少なくとも1994年から続いていた。全農は肥料を使って損害を受けた農家へ今年度中に補償をする方針。補償額は10億円を超える見通しで、全額同社に請求する。
同社は11月、資金繰りに行き詰まって秋田地裁に民事再生手続きを申し立て、手続きが始まっている。
信頼が重要な業種でこんな事が起きるとは?人間性の評価や過去が重要視される仕事はやはりあると思う。
警備大手の綜合警備保障(ALSOK)グループの警備員が巡回警備先で現金を盗んだなどとして、秋田中央署に窃盗と窃盗未遂の疑いで逮捕されていたことが分かった。警備員は懲戒解雇された。
逮捕されたのは、潟上市天王持谷地、鈴木保容疑者(28)。逮捕容疑は10月上旬、巡回警備していた県中央部の高校から現金約22万円を盗んだほか、11月19日午後10時ごろには秋田市内の事業所の金庫に鍵を差し、現金を盗もうとしたとしている。
10月の事件については「やっていない」と容疑を否認。11月の事件については認めているという。
財産を守るべき警備員が窃盗容疑で逮捕されたことについて、綜合警備保障の藤島洋広報第1課長とALSOK秋田の中村和義管理部長はいずれも「警察が捜査中なのでコメントできない」と話している。
金融庁の公認会計士・監査審査会は15日、不正会計があった東芝を監査した新日本監査法人に行政処分を行うよう金融庁に勧告した。東芝の不正の可能性に気付いたのに深く追及せず、他の企業の監査についても、審査会が繰り返し不十分だと指摘しても改善されなかったという。
勧告を受けて金融庁は、監査法人では初となる課徴金処分や、業務改善命令を年内にも科す方向で検討している。2年に1度行ってきた立ち入り検査の回数を増やすことも検討する。
審査会によると、新日本は東芝を含む複数の監査で、企業が過去に示した推計値と実績が大きくずれるなど不自然な会計処理を認識しながら、企業側の説明をうのみにして不正がないか踏み込んで調査しなかった。原因については「大企業だから大丈夫だという思い込みから、漫然と前年と同じ監査を繰り返していた」とし、意図的な不正の見逃しは確認されなかったとしている。
新日本監査法人を終わりにしても良いのでは?不適切な監査を行うと存続できなくなる事を強調するべきでは?
新日本監査法人が消滅しても、他の監査法人に人材が流れたり、他の監査法人が仕事を受け継ぐので問題ないであろう。健全な企業は不便を感じるが、
不適切な関係を維持してきた企業はしがらみのない監査法人にチェックされるので、問題のある企業のあぶり出しにもなる。
金融庁の考え次第。金融庁の人間達がどれほど監査法人や企業の役員達と親しいか次第かもしれない。発覚していない不正が公表され、
景気に影響する事を金融庁や政府がどのように判断する次第かも?
東芝の不正会計を見抜けなかった新日本監査法人が、ほかの企業の監査も不十分だったことが金融庁の公認会計士・監査審査会の調べで明らかになった。審査会は15日にも「運営が著しく不当だった」として、金融庁に行政処分を勧告する方針だ。
審査会は、立ち入り調査や関係者への聴取で、東芝を含む数社に対する新日本の監査内容を調べてきた。東芝の監査では、必要な注意を怠って不正を見抜けなかったことがわかった。また、東芝以外の企業の監査でも日本公認会計士協会が定めた監査手続きなどを満たしていない例が見つかったという。
審査会の勧告を受け、金融庁は月内にも具体的な処分内容を公表する。東芝の不正額と社会的影響が大きかったことや、ほかの企業でも不十分な監査がみつかったことから、監査法人では初となる課徴金に加え、業務改善命令も科す方向で検討している。
監査法人への課徴金処分は、2008年の公認会計士法改正で導入された。だが、11年に発覚したオリンパスの損失隠しなど、過去の不正会計問題では適用されていない。(上栗崇)
[東京 15日 ロイター] - 金融庁傘下の公認会計士・監査審査会は15日、東芝(6502.T)の監査を担当してきた新日本監査法人に対して行政処分を科すよう金融庁に勧告した。過去の検査で再三指摘してきた監査手続き上の問題点が十分に改善できておらず、自力での改善は難しいと判断した。
監査審査会は9月に同監査法人への定期検査を始めた。不正会計問題が発覚した東芝に対する監査体制のみならず、監査業務全般にわたって検証した。
検査の結果、審査会が最も重くみたのは、これまで同監査法人が繰り返し指摘されてきた問題点がいまだに改善されていなかったことだ。新日本監査法人は、リスクのある項目を重点的に監査する「リスク・アプローチ」に基づく監査計画の立案、会計上の見積もりの監査、分析的実証手続などについて審査会や公認会計士協会から是正を求められていたが、組織全体として十分な改善には至らなかった。
個別の監査業務では、重要な勘定で多額の異常値を把握しているにもかかわらず、監査の基準で求められている実証手続が未実施だったり、内部統制の無効化リスクに対応して実施する「仕訳テスト」で抽出した仕訳が未検討のままにされるなど、リスクの高い項目の監査で重要な不備も見つかった。 監査業務の審査を担当する社員も十分に機能しておらず、監査チームの重要な判断を客観的に評価できていなかった。
審査会は、新日本監査法人が自力で監査の品質管理体制の構築に取り組むのは難しいと判断。行政処分の勧告に踏み切った。15日に開かれた審査会では、委員から、今度こそ諸問題が改善されるようフォローアップしていくことについて、高い関心が寄せられたという。
監査審査会は、新日本監査法人による東芝の監査についても検査。東芝の監査にあたり、職業的専門家として求められる「懐疑心」が十分に発揮できていなかったと認定した。しかし、東芝による隠ぺい工作や東芝側から不当な圧力を受けて監査法人としての業務が行えなかったといった事情は認められなかったという。 審査会の勧告を踏まえ、金融庁は月内をめどに新日本監査法人への行政処分を出す方針。業務停止命令のほか、業務改善命令と課徴金納付命令を同時に出すといった案が有力視されているもようだ。課徴金納付命令が出れば、2008年の導入以来、初めての適用事例になる。
*写真を差し替えました。
(和田崇彦)
理想だけでは学校運営は成り立たないのだろうけど、ここまでやらないと運営が成り立たない学校に助成金やその他の税金を注ぎ込む必要はあるのか?
学校認可の厳しい基準は問題であるが、行政は不正を行わせない対策や存続できない学校の延命をしないなどしっかりしてほしい。
ウィッツ青山学園高校(三重県伊賀市)の通信制を巡る国の就学支援金不正受給事件で、受給申請に必要な「課税証明書」が虚偽申告に基づき自治体から発行されていたことが、関係者の話でわかった。
不正受給の疑いがある会社役員3人のうち1人が、別の受給者を自社の従業員であるように装って発行させていた。詐欺容疑を裏付ける手口だといえ、東京地検特捜部が調べている。
課税証明書は、1年間の所得状況を示す公的書類。会社員であれば、勤務先が作成した「給与支払報告書」に基づき、自治体から発行される。就学支援金には所得要件(保護者らの年収910万円未満)があり、受給申請で必要となる。
関係者によると、会社役員3人のうち1人は、同校が通信制生徒の学習の場と位置づける「四谷キャンパス」の関係者の女性。結婚相談所運営会社を経営しており、2013年11月~14年1月頃、当時は個人事業主だった男性に入学を持ちかけ、「お願いだから、うちの従業員ということにして」と頼んだという。
「下町ロケット2 ガウディ計画」のようにお役人と企業の癒着があるのかもしれない。
そうでなければ1年も問題は放置されないだろう。今、化血研の不正製造がメディアに取り上げられたから「化学及血清療法研究所(化血研、熊本市)が、血液製剤と人体用、動物用ワクチンについて、国の承認書と異なる方法で製造していた問題で、化血研が昨年10~12月の時点で、国の承認書と製造記録との違いを農林水産省と厚生労働省へ報告していたことが10日までに明らかになった。」
事が問題として取り上げられているだけ。メディアに取り上げられなかったら、この事実は新聞の記事となる事はなかったであろう。
事実はどうなのであろうか??
お役人の判断で国民が事実を知ることなく、葬り去られていた。一旦、癒着関係になれば終わりが来るまで癒着関係は続くであろう。なぜなら、お互いが納得して
癒着関係を解消しない限り、過去の癒着を公表される、又は、暴露されるリスクが常に存在する。癒着関係により相互メリットが存在するなら、癒着関係が発覚するリスクを
認識しない限り癒着関係を解消する理由もない。
化学及血清療法研究所(化血研、熊本市)が、血液製剤と人体用、動物用ワクチンについて、国の承認書と異なる方法で製造していた問題で、化血研が昨年10~12月の時点で、国の承認書と製造記録との違いを農林水産省と厚生労働省へ報告していたことが10日までに明らかになった。
一連の問題は今年5月、血液製剤の不正製造・隠蔽[いんぺい]に関する厚生労働省への内部告発で発覚したとされるが、厚労省や農水省はそれ以前に不正の端緒をつかんでいたことになる。両省でどの程度、情報の交換や共有が進んでいたのか、対応を疑問視する声もある。
化血研と農水省によると、化血研は昨年10月の内部定期検査で、国の承認書と異なる方法で動物用ワクチン・診断薬を製造していたことを把握。同省に報告した。
化血研は今年2月までに48製品のうち34製品で承認書との違いを確認。農水省は同月から当該製品の出荷自粛を指示した。8製品については依然、出荷が止まったままだ。
農水省は、化血研の内部告発によって血液製剤の不正製造・隠蔽が明るみに出た後の今月9日になって、立ち入り検査に入ったが、それまで1年以上にわたりその事実を公表していなかった。農水省畜水産安全管理課は「製品の種類が多く、工程も複雑だったため(公表までに)時間を要した」と釈明した。
また、この間の11月には、同省が牛に流産や死産などを起こすアカバネ病のワクチンを開発した化血研のグループを「農林水産研究開発功労者」として表彰していた。担当の農林水産技術会議事務局は「何も把握していなかった」としており、省内で化血研に関する情報の共有はなされていなかった。
一方、化血研は厚労省に対しても昨年12月、血液製剤と人体用ワクチンの製造記録に国の承認書との齟齬[そご]や誤記があるとし、承認書の一部変更を申し出た。
しかし、同省は重大違反ではないと判断。その半年後の5月の化血研の内部告発を受けて、化血研に詳細な調査報告と血液製剤や人体用ワクチンの出荷自粛を求めた。厚労省審査管理課は「承認書の一部変更を相談されたが、その根拠について化血研とやりとりしているうちに、内部告発があった」などと説明している。(山口尚久、高宗亮輔)
秋田市の肥料メーカーが成分を偽った肥料を製造していた問題で、JA全農=全国農業協同組合連合会は問題の肥料を使ったために損害を受けた農家に対する補償金が少なくとも10億円にのぼることを明らかにしました。
この問題は秋田市の肥料メーカー「太平物産」がJA全農向けに製造した肥料の大半で成分を偽装していたもので、JA全農は東日本の11の県でおよそ4万トンを販売しました。
これについてJA全農は11日、会見を開き、問題の肥料を使ったために損害を受けた農家などに対して補償金を支払うことを明らかにしました。
具体的には、本来なら高値で売ることができた「有機農産物」や「特別栽培農産物」を生産した農家が問題の肥料を使ったことで一般の農産物としてしか販売できなくなったことによる価格差を補償するということです。
また、化学肥料の割合を減らし有機農業に取り組む農家に対して国が交付金を支払う制度の対象から外れる場合にも本来受け取ることができる交付金の額を補償するということです。
JA全農は補償金の規模は少なくとも10億円に上るとみていて、その全額を「太平物産」に請求することにしています。
JA全農の山崎周二常務理事は「今回の問題で多大なご迷惑をおかけしおわびしたい」と謝罪しました。
建物のくいの工事でデータの流用などが相次いで明らかになっている問題で、業界団体は新たに2社でデータの流用が確認され、流用が行われていた物件の数も旭化成建材が関わったもの以外で56件に上ることを明らかにしました。これまでのところ横浜市のマンション以外に建物が傾くなどの異常は報告されていないということです。
この問題を巡っては旭化成建材が過去10年余りに請け負った360の物件でデータの流用や改ざんが行われていたほか、業界大手など6社の22の物件でも流用が明らかになっています。
業界団体の「コンクリートパイル建設技術協会」は、先月末に続いて、各社が自主的に行った点検のこれまでの結果を11日、国土交通省に報告し、その内容を公表しました。
それによりますと、新たにマナックと日本高圧コンクリートの2社でデータの流用が確認され、流用が行われた物件の数も旭化成建材以外で34件増えて56件に上るということです。
これまでのところ、横浜市のマンション以外に建物が傾くなどの異常は報告されていないということです。
業界団体では引き続き各社に自主的な点検の結果が分かりしだい報告を求めるとともに、年内にも業界としての再発防止策をまとめたいとしています。
一方、国土交通省は、流用が確認された物件の安全性を速やかに確認するよう、各社に指示するともに、専門家による委員会の議論を踏まえて、今月中に再発防止策を取りまとめることにしています。
地域別・種類別の物件数
「コンクリートパイル建設技術協会」によりますと、旭化成建材以外にデータの流用が確認されたのは新たに34件増えて56件に上ります。
このうち、都道府県別では、東京都11件、愛知県が10件、三重県で6件、愛媛県が5件、千葉・福井の各県がそれぞれ4件、福島県で3件、、茨城県で2件、北海道、青森、秋田、神奈川、京都、大阪、兵庫、徳島、高知、佐賀、熊本の各道府県でそれぞれ1件となっています。
また、建物の種類別では、公共施設が20件、学校が11件、医療・福祉施設と集合住宅がそれぞれ5件、流通・倉庫が3件、事務所や店舗、工場がそれぞれ2件、そのほかの物件が8件となっています。
会社別ではジャパンパイルが22件、三谷セキサンが13件、日本コンクリート工業とマナックがそれぞれ6件、前田製管と中部高圧コンクリートがそれぞれ3件、NC貝原コンクリートが2件、日本高圧コンクリートが1件となっていて、「マナック」と「日本高圧コンクリート」は今回新たにデータの流用が明らかになりました。
当然の処分じゃないの?金融庁が甘すぎた!
上栗崇
金融庁が、不正があった東芝の会計を監査していた新日本監査法人に対し、課徴金と業務改善命令の行政処分を同時に行う方向で検討していることが9日、わかった。監査法人への課徴金処分は初めて。証券取引等監視委員会が東芝について過去最高額の課徴金勧告を出しており、不正を見逃した新日本の責任も重いとみている。
金融庁の公認会計士・監査審査会は新日本への立ち入り検査や関係者の聴取を進めており、来週にも処分を公表する。課徴金は、東芝から受け取った監査報酬2年分にあたる約20億円を軸に検討している。6カ月前後の新規契約禁止も命じる可能性がある。意図的な不正の見逃しは見つからなかったが、必要な注意を怠ったために不正を見抜けなかったと判断した。
監査法人への課徴金処分は2008年の公認会計士法改正で導入された。その後発覚したオリンパスの損失隠しなど過去の不正会計問題では適用されなかったが、東芝は不正の規模が大きく、社会的影響も大きいことから、初の課徴金処分を科す方針を固めたとみられる。
不正会計問題を起こした東芝の監査を担当した新日本監査法人に対し、金融庁が業務改善命令だけでなく、課徴金の行政処分も検討していることが10日、分かった。適用されれば監査法人では初めて。会計不正を見抜けなかった責任は重いとみている。
新日本に対し、立ち入り検査を進めてきた公認会計士・監査審査会の処分勧告を受けて、早ければ年内に処分を判断する。課徴金は新日本の場合、東芝からの2年間の監査報酬に当たる20億円程度が想定される。6カ月前後にわたり新規顧客との契約を禁じる一部業務停止命令を出す可能性もある。(共同)
「同省などが主催する2015年度の『民間部門農林水産研究開発功績者表彰』では、有識者らでつくる選考委員会が9月、応募のあった22件について審査。牛に流産や死産などを引き起こす感染症『アカバネ病』のワクチンを開発した化血研の研究者3人に、賞を贈ることを決めた。」
牛に流産や死産などを引き起こす感染症「アカバネ病」のワクチンを開発した化血研の研究者3人は不正製造について知っていたのだろうか?知らないのであれば、自分の会社がモラルに反する行為や隠ぺい対策を
長年、続けていた事を知らず盲目的に研究だけに没頭していたのであろう。知っていたのなら、能力的にすばらしいが研究者のしてもモラルが欠如している。
「民間部門農林水産研究開発功績者表彰」が人物評価を評価せず、単に結果に対する表彰であれば問題ないと思う。表彰する基準に人物評価が除外されているのであれば、
農林水産省の基準に疑問を感じるが、それが農林水産省の姿勢であるなら仕方がない。
一般財団法人・化学及および血清療法研究所(化血研、熊本市)が動物用ワクチン約30種類を未承認の方法で製造していた問題で、農林水産省が11月、動物用ワクチンの研究開発に功績があったとして化血研の研究グループを表彰していたことがわかった。
同省は2月に化血研から動物用ワクチンの不正製造の報告を受けており、選考のあり方に疑問の声が上がっている。
同省などが主催する2015年度の「民間部門農林水産研究開発功績者表彰」では、有識者らでつくる選考委員会が9月、応募のあった22件について審査。牛に流産や死産などを引き起こす感染症「アカバネ病」のワクチンを開発した化血研の研究者3人に、賞を贈ることを決めた。
ところが、農水省が不正製造を把握していた約30種類のワクチンには、豚や牛などの家畜に下痢や流産などを引き起こす感染症を防ぐためのワクチンや診断薬などが含まれていた。化血研によると、表彰されたワクチン自体では不正製造はなかったという。
東京地検特捜部の強制捜査を受けた株式会社立ウィッツ青山学園高校(三重県伊賀市)が、受給資格のない3人の生徒の就学支援金を申請し、計約90万円を国から受け取っていたことが、関係者の話で分かった。特捜部はこの3人についての詐欺容疑で調べている模様だ。
関係者によると、3人はいずれも20~40代の会社役員。2014年4月に同校通信課程に入学し、四谷LETSキャンパス(東京都千代田区)に所属していた。入学願書の学歴には「中学校卒業」と虚偽の記載をしていたが、実際には高校を卒業しており、受給資格がなかった。授業や試験の添削指導などを受けたこともなかったという。
国は同年5月~今年7月に3人分にあたる計約90万円の就学支援金を同校に支給した。3人の支援金は、四谷キャンパスの代表者と3人が交わした同意書をもとに、キャンパス側に渡っていたという。
高校授業料の実質無償化に合わせて導入された国の「就学支援金」を不正に受給していた疑いがあるとして、東京地検特捜部は8日、株式会社立ウィッツ青山学園高校(三重県伊賀市)や、運営する株式会社「ウィッツ」(同市)、その親会社の「東理ホールディングス」(東京都中央区)など関連先を詐欺容疑で捜索した。
関係者によると、同校では別の高校を卒業するなどして受給資格のない複数の生徒を通信制課程に入学させ、受給資格があるように装って就学支援金を国に申請し、受給した疑いがあるという。
同校では同日午後5時半すぎ、東京地検の係官とみられる男性らが段ボール箱をワンボックス車に運びこんだ。
同校は国が進める構造改革特区制度の「教育特区」を利用し、ウィッツが株式会社立の高校として2005年に開校。今年2月時点で全日制の生徒は29人、通信制は1158人だった。
就学支援金とは、年収約910万円未満の世帯に対し国が高校の授業料を肩代わりする制度。公立高は約12万円、私立高は約12万~30万円が支給される。株式会社立高は私立高の額が適用される。高校を卒業したり、在籍期間が3年を超えたりすると支給対象から外れる。三重県によると、同校には昨年度、約1億5700万円の支援金が支給されたという。
ウィッツ社の福村康広社長は同日、「就学支援金を受け取っていたことは知っているが、詐欺は知らない。現場にはタッチしていない」と話した。
「化学及血清療法研究所」は不正や偽装が染み付いている組織であると言っているのと同じだと思う。
ここまで不正や偽装を行わないといけないようであれば、一般財団法人として存続は難しいのではないのか?普通であれば問題が公になる前に
止めると思うが、止められない理由は何か?
血液製剤を40年以上不正に製造していた「化学及血清療法研究所」(化血研、熊本市)が、家畜に使う動物用ワクチンと診断薬も国が承認していない方法でつくっていたことが、農林水産省の調査で明らかになった。農水省は9日、医薬品医療機器法違反の疑いで、化血研への立ち入り調査を始めた。
不正があったのは化血研が製造する動物用ワクチンなど約50種類のうち約30種類。豚の下痢や牛の流産を防ぐワクチンなどで、細菌の混入を調べる際、承認された手順通りに検査していなかった。今年2月に化血研から「承認された手順通りにつくっていない製品が見つかった」と報告を受けた農水省が調べ、不正を確認した。出荷済み製品は品質を調べる国家検定を通過しており、安全性に問題はないという。
製造記録の偽造といった隠蔽(いんぺい)は確認されていないが、農水省は資料の提出などを求め、さらに調査する。
化血研は、動物用ワクチン8種類の出荷を自粛しているという。担当者は取材に対し、「農水省の指導のもと適切な対応をしたい」と話している。
「発覚のきっかけの一つは内部告発だった」
どのような背景なのか知りたい。
山口利昭
すでに報じられているように、血液製剤の分野で国内シェアのおよそ3割を占める熊本市の製薬会社「化血研」さん(化学及血清療法研究所)が、国の承認を受けずに「ヘパリン」という血液を固まりにくくする成分を添加するなど、12種類の血液製剤について、国が認めた内容とは異なる方法で製造していたことが判明しました。しかも第三者委員会報告書によると、不正は40年間も続いていたそうです。ところで、化血研さんのHPはずっと閲覧不可の状態になっています。
「心が痛む」として社員から厚労省に対して内部告発があったことが不正発覚の端緒だそうで(朝日新聞ニュースはこちらです)、厚労省もいろいろと内部告発の放置問題で揺れておりましたので(?)、今回は「抜き打ち調査」などによって、かなり積極的に真剣に対応されたのかもしれません。驚くのは、「もうそろそろ内部告発があるかもしれない」ということで、化血研さんの内部では告発がなされたことを想定した対策をとっていた、とのこと(毎日新聞ニュースはこちらです)。東洋ゴムさんの免震ゴム偽装のときもそうでしたが、最近は内部告発リスクへの対策をとる企業も出てきました(もちろん、決して許されるものではありませんが・・・)。
さて、内部告発ネタとしても本件は参考になりますが、私がもっとも気になったのが、どうして厚労省のルールを無視して血液製剤を作り続けてきたのか、といった不正の動機の部分です。12月2日のNHK午後7時のニュースでは、
(化血研の)第三者委員会は、「問題の根幹は『自分たちは専門家だ』とか『製造方法を改善しているのだから当局を少々ごまかしても大きな問題ではない』という、研究者のおごりだ」と厳しく指摘している
と報じられています。もうすでに過去のエントリーでも紹介していますが、私が過去に性能偽装事件の危機対応に関与した案件でも、技術者の方々の同じような言い訳を聞きました。A社は当局の外郭団体(安全技術協会)に「チャンピョン品」と隠語で呼ばれる「テストを一発で通すためだけに作られて製品」を持ち込んで試験をクリアしていたというものですが、A社技術担当社員には社長から厳しいミッション(販売時期を遅らせないように、かならずテストは一発で通せ)が課せられていたため、工場ぐるみで偽装を行っていました。A社で長年性能偽装が続いていた理由としては、「我々はトップメーカーであり、お客様のために、最終出荷時の安全基準は世界一である。たとえレベルの低い当局の性能テストを偽装したとしても、最終出荷のテストをクリアすれば何ら問題はない」というものでした。またA社と監督官庁との長年の「持ちつもたれつ」の関係からか、安全協会の検査ルールについては、安全協会側にも落ち度があり、A社としては「お互いさま」といった感覚もあったようです。
たしかに頭の冷えている平時の感覚であれば「そんなのは技術者の驕りであり、不正を正当化できる理由にはならない」と誰でもわかります。しかし、経営者からのミッションや同業他社とのし烈な販売競争、行政との長年の(悪い意味での)信頼関係の醸成といったことが重なりますと、技術者の有事感覚としては、化血研のような発想になっても不思議ではないかもしれません。たしかに国から承認を受けている方法とは異なる方法で血液製剤を製造していたとしても、それは「国の承認しているものよりも、さらに安全性を高めるための改善の結果であり、また製造効率を高めて少しでも多くの患者さんに喜んでもらえるのであれば、偽装などたいした問題ではない」と考えることも(有事の感覚としては)十分ありえるように思います。
誠実な企業であればあるほど、技術者の方々は自社技術に誇りを持つのが当然でありますが、その誇りが、社内・社外の経営環境の中でいつしか「驕り」に変わっていくというのが真実ではないかと。しかも客観的にみても、化血研さんのワクチンがどうしても必要なので、「客観的にみて、この程度のことで我々の仕事はなくなるわけではない、とりあえず医療の場を混乱させたことは謝罪するが、再発防止に取り組んでまいります、といえば済む問題だ」といった認識が社内でも社外でも通用するのではないでしょうか。40年間も不正を続けていたのはけしからん!と批判するのは正道ですが、しかしただ批判しただけでは不正の芽を摘むことはできないと考えます。さて、この業界におけるコンプライアンス問題の捉え方を理解するには、化血研さんに対する今後の厚労省さんの対応が非常に興味深いところです。
厚生労働省自体が問題のある人達で構成されているわけだから大きな期待は出来ない。中国や韓国よりましと 思うしかない。こんな国なのでそれほどの愛国心は持たなくても良いかも?まあ、国家による洗脳やメディア操作により不適切ではあっても愛国心は根付かせることは 出来る。中国や韓国を見ればよくわかる。踊らされていても、生きていけるし、幸せと感じる事も出来る。踊らされている事を知った後でも同じように生きて行けるかについては 疑問であるが、100%正しい事などないので、個人次第。
化血研が製造する血液製剤とインフルエンザワクチンについてはニュースでも報道されたように、2015年6月に血液製剤、9月にインフルエンザワクチンの出荷自粛がありました。
ただ、不足が予想されたことから、厚生労働省は「安全性に大きな問題はない」として出荷自粛を解除した経緯があります。
さて、厚生労働省がいう安全性に大きな問題がないという根拠はどこにあったのでしょうか。足りないから出荷を許可するというスタンスでは国の機能としては意味がありません。
国が安全性に問題が無いと判断した根拠も明確にしてほしいと一個人としては思いますし、厚生労働省の安全性や品質を調べる国家検定にも大きな問題がありそうです。
一般財団法人・化学及血清療法研究所(化血研、熊本市)はある意味とてもすばらしい企業だ。ここまで規則や行政を馬鹿にした対応のために研究チームまで
あったとは!
「国の検査(査察)態勢の厳格化が見込まれた95年頃から、虚偽の製造記録を検査で提示する隠蔽工作が始まったが、こうした不正を長く続ければ、発覚を免れるのは難しいとの危機感が所内で高まった。このため、血液製剤の各製造部門では、製造実態に合わせて承認内容の変更を申請することを目指した研究を開始し、『プロジェクトチーム』も発足させた。」
この研究チームの人間達は仕事とためとは言え、隠ぺいや偽造の仕事に専念していたわけだ。つまり、人間的にモラルのない人間、不正に関わりたくないが
会社を辞めて他の会社に行くだけの決断が出来なかった意志の弱い人間、自分の仕事について「批判的思考」が出来ない企業の歯車になるための教育制度で作り出されたエリート
なのかもしれない?
行政はこのような企業や人間が存在する事を認識し、理解して、性善説による規則や法律を部分的に改正する必要があると思う。
一般財団法人・化学及血清療法研究所(化血研、熊本市)が血液製剤などを国の未承認の方法で製造していた問題で、化血研が約20年前から、不正を隠したまま承認を得るための研究を血液製剤の製造部門で進めていたことが関係者の話でわかった。
研究を踏まえて承認申請する際、虚偽の製造記録を国の検査で提示してきたことが露見しないよう、別の虚偽を記載して承認を得たケースもあった。厚生労働省は、ウソにウソを重ねた化血研の行為の悪質性は高いとみて、隠蔽工作の全容を調べている。
化血研の第三者委員会の調査報告や関係者の話によると、化血研では1974年以降、承認書と異なる製法で多くの血液製剤が作られるようになった。
国の検査(査察)態勢の厳格化が見込まれた95年頃から、虚偽の製造記録を検査で提示する隠蔽工作が始まったが、こうした不正を長く続ければ、発覚を免れるのは難しいとの危機感が所内で高まった。このため、血液製剤の各製造部門では、製造実態に合わせて承認内容の変更を申請することを目指した研究を開始し、「プロジェクトチーム」も発足させた。
血液製剤不正をこの時には既に知っていたのか?
一般財団法人・化学及血清療法研究所(熊本市北区大窪)の宮本誠二理事長は、7月3日同研究所で「今年3月期の売上高は408億3500万円で、初めて400億円を超えた」と語った。
これは「くまもと経済」8月号のインタビューに応えて語ったもの。まず今年3月期決算について、「売上高が408億3500万円、経常利益が71億8900万円で増収増益だった。売上高が400億円を超えたのは初めて。特に4種混合ワクチン、A型・B型肝炎ワクチンの売り上げ増が増収増益に貢献した」と語った。また今年3月に完成した細胞培養型ワクチン原液製造棟(FC棟)については、「現在バリデ―ション=試運転=に入っており、来年3月には本格的な生産を始める予定」と。ワクチンを取り巻く環境については、「ここ数年で環境が大きく変わった。私たちは4000万人分のインフルエンザワクチンを供給することになっており、ワクチンメーカーとして国家的な防疫事業を担う思いで取り組んでいる。責任も重いが誇りでもある」と語った。
常勤理事会のメンバーはどのようなバックグラウンドを持っているのか?
「城野洋一郎(きの・よういちろう)理事は1953(昭和28年4月生まれの59歳。島根大学大学院農学研究科修了後、80年入所。第二研究部第一研究室長、第二研究部次長などを経て、2008年第二研究部長。09年同6月評議員就任、10年3月評議員退任。
なお、同所の常勤役員は以下の通り。」
ESP細胞の小保方氏の時に思った事だが、今回の不正もそうであるが大学では倫理規定(Code of Ethics)を教えていないのかもしれない。
NHKの土曜ドラマで
ダーク・スーツ (DARK SUIT)(NHK)があった。ハシバに勤務する主人公のサラリーマンが経営再建に加わり、悪事に関わる取締役達が不正を知り、黙認する事で
役員の席を手に入れた事を知る。同じようなパターンなのか?不正を黙認し、いろいろなポジションを与えら得る?
「宮本誠二(みやもと・せいじ)理事長は熊本県出身。1950(昭和25)年8月生まれの61歳。京都大学薬学部卒業 75年入所。97年血液製剤研究部長、2001年5月理事、07年7月常務理事、08年12月副所長、10年4月副理事長就任。」
熊本市北区大窪1丁目の一般財団法人化学及血清療法研究所の理事長・所長に、6月20日付で宮本誠二副理事長・副所長が昇任した。船津昭信理事長は名誉理事長・名誉所長となった。トップ交代は8年振り。また理事に城野洋一郎第二研究部長が昇任した。
宮本誠二(みやもと・せいじ)理事長は熊本県出身。1950(昭和25)年8月生まれの61歳。京都大学薬学部卒業。75年入所。97年血液製剤研究部長、2001年5月理事、07年7月常務理事、08年12月副所長、10年4月副理事長就任。
城野洋一郎(きの・よういちろう)理事は1953(昭和28年4月生まれの59歳。島根大学大学院農学研究科修了後、80年入所。第二研究部第一研究室長、第二研究部次長などを経て、2008年第二研究部長。09年同6月評議員就任、10年3月評議員退任。
なお、同所の常勤役員は以下の通り。
▼理事長・所長 系列担当 宮本誠二▼常務理事・副所長 菊池研究所統括 溝上寛▼副理事長 営業部門担当、総務部門担当、企画部門担当、環境担当、系列副担当 水野弘道▼常務理事 研究部門担当、LCプロジェクト担当 横井公一
▼同・第一生産部門担当 千北一興▼理事・信頼性保証部門担当 佐藤哲朗▼同・営業部門副担当 中川孝▼同・総務部門副担当、企画部門副担当 松田啓二▼同・第一生産部門副担当 本田隆▼同・研究部門副担当 城野洋一郎▼監事 中垣智弘 (櫻木)
銀杏学園・熊本保健科学大学(熊本市和泉町)の理事長に、このほど船津昭信・化学及血清療法研究所理事長・所長が就任した。内野矜自理事長は常任理事に就いた。
船津昭信(ふなつ・あきのぶ)理事長は熊本県山鹿市出身、1945(昭和20)年5月1日生まれ、59歳。熊本大学理学部化学科卒。69年化学及血清療法研究所入所、88年第3製造部長、92年理事、97年常務理事、2000年副所長、03年銀杏学園理事・評議員に就任、04年7月化学及血清療法研究所理事長・所長に就任。
同学園は1959年4月化血研衛生検査技師養成所として創設、60年4月熊本医学技術専門学校に名称変更。68年2月銀杏学園短期大学設立、83年4月看護科設置。2003年4月1日熊本保健科学大学へ改組転換し、今年3月15日に銀杏学園短期大学は、最後の卒業式を行った。同学園の主な役員は次の通り。
▼理事長 船津昭信▼理事・評議員 船津昭信、内倉重人・化血研副所長、田代昭・同常務理事、杉本紘一・同、岡徹也・同、野中實男・銀杏学園短期大学名誉教授、酒匂光郎・元同短期大学学長、内野矜自・熊本保健科学大学常勤理事、岡嶋透・熊本保健科学大学学長、山田進二・同大学副学長、赤池紀生・同大学学部長、南田悠一郎・銀杏学園法人職員 (石井)
化学及血清療法研究所(熊本市大窪1丁目)の理事長・所長に、船津昭信常務理事・副所長が昇格した。7月27日付。内野矜自理事長・所長(68歳)は非常勤理事・名誉所長に退いた。
そのほかの役員人事では、副所長に内倉重人常務理事が就任。常務理事に岡徹也理事が昇格、理事に水野弘道経理部長が新任した。
船津昭信(ふなつ・あきのぶ)理事長は熊本県出身、1945(昭和20)年5月1日生まれ、59歳。69年3月に熊本大学理学部化学科を卒業し同所入所。88年第3製造部長、92年理事、97年常務理事、2000年から副所長。
同社は1945(昭和20)年設立、基本金は21億円、従業員数は1420人。出先は菊池研究所、阿蘇支所、東京事務所、東京・大坂・福岡営業所、長崎出張所がある。現在菊池研究所(菊池郡旭志村)内に約100億円をかけ遺伝子組み換えアルブミンの製剤工場を建設中。同社の常勤役員は次の通り。
▼理事長・所長 船津昭信▼常務理事・副所長 内倉重人▼常務理事 田代昭、杉本紘一、岡徹也▼理事 藤川英雄、宮本誠二、溝上寛、水野弘道
血液製剤やワクチンを未承認の方法で製造してきた化学及血清療法研究所(化血研、熊本市)に対し、2日公表された第三者委員会報告は、「組織ぐるみ」「利益優先」などと厳しい指摘を連ねた。薬害エイズ問題で激しい批判にさらされた化血研は、なぜ患者軽視の不正を重ね、悪質な隠蔽を続けたのか。
化血研問題、ワクチン供給に影響も
◆発端◆
「弁解になるが、献血を扱うメーカーとして製剤を早く出したいという思いがあった」。化血研の宮本誠二理事長は2日夜、記者会見で苦渋の表情で語った。
報告が不正製造の大きなきっかけとして言及したのは、1980年代後半から90年代前半の薬害エイズ問題だ。輸入された非加熱製剤が原因で多くの感染者が出たため、政府は血液製剤を国内生産に切り替える方針を打ち出し、化血研もこの波に乗ろうとした。
血液製剤は感染リスクをなくすため、国が認めた承認書通りに製造することが厳格に求められている。しかし、化血研は89年以降、新薬の製造工程で止血効果がなくなるなどの問題が生じた際、発売の遅れを恐れた担当理事の指示で製造工程を変更。承認書にはない方法で添加物を投入することで問題を解決した。その後も、工程の省略などを重ねた。
「不正は、早期の製品化や安定供給を最優先したことに起因している」。報告はそう指摘した。
◆隠蔽◆
組織ぐるみの隠蔽に事実上の「ゴーサイン」を出したのは、96年9月の常勤理事会だった。血液製剤の製造部門の担当者が、承認書と実際の製法が異なることを説明。国の査察では虚偽の製造記録を提示することも示唆し、出席した理事から疑義は出なかった。
同じ時期に医薬品業界では、国際化の流れに合わせ、国による査察の厳格化の動きが強まっていた。製造部門の幹部は98年、部下からの相談に、「このままでは(国に)見せられん。製品供給継続を第一に、しばらくは見せられる記録で対応しよう」と応じた。
製造部門では、過去の記録も査察で示す必要が生じたため、古く見えるように紫外線を紙に浴びせて変色させたり、筆跡を過去の関係者に似せたりした。査察に見せる虚偽の記録は字体を変えて取り違えを防ぐ念の入れようだった。
不正はその後も放置され、昨年に新薬の承認を受ける際も、添加物を不正に投入することを隠した。
◆特殊な組織◆
化血研の売り上げの半分以上を占めていた血液製剤部門の特殊な組織体質も、不正の背景にあった。元々はワクチンの売り上げが多かったが、70年代から血液製剤重視に転換。同部門の発言力は増し、一連の不正は同部門出身の前理事長が主導した。部門内に新入職員を集めたため外から異動してくる職員はほとんどおらず、内部での不正の一斉点検にも「自前で対応する」として加わらなかった。
不正が安全性に影響した事実は確認されていないが、小柳仁・東京女子医大名誉教授(心臓血管外科)は「承認と違う製法で作れば、人体に影響が出る可能性は少なからずある。人の命に密接に関わる組織として信じられない」と批判した上で、「日本の医療が世界でも信頼性が高いのは、医薬品類が徹底的に品質管理されている大前提があるからだが、今回で信頼が崩れかねない」と指摘している。(読売新聞社会部 小田克朗、医療部 赤津良太)
「この問題はことし8月、京都市の国道の「勧進橋」で行われた耐震補強工事で、福井市の久富産業が製造した橋の落下を防止する装置の部品に、溶接が不十分なものが見つかったものです。」
と書かれているから杭打ちデータ偽装で業界や業者のモラルに対する不信感により国土交通省が調べたわけではないようだ。
「検査する立場の北陸溶接検査事務所の検査員も、適切な溶接を行った部品だけを検査して、問題ないとする報告書を作成していました。」
「北陸溶接検査事務所はホームページで、『担当者は、久富産業は顧客であるとの認識でいたため、要請を拒絶することに強い心理的抵抗を感じていた。検査で溶接不良を指摘すると大幅な納期の遅延が生じることを懸念した模様だ』などとしたうえで、信頼回復に努めたいというコメントを掲載しています。」
不正を行う業者も悪いが不正を見逃す行政にも問題があると思う。
軽い癒着関係があったかもしれない。そうでなければ仕事をサボる習慣が組織的に定着していたとしか考えられない。
(株)北陸溶接検査事務所は、時代と共に進歩する技術及び技術製品の安全を厳正に検査する事で、皆様の安心な暮らしの支えであり続けたいと願っております。((株)北陸溶接検査事務所のサイト)
は薄っぺらい言葉なのか?民間企業である限り、モラルが欠如すればいつでも起き得る問題だ。
各地の国道の橋で耐震補強工事に使われた部品に溶接の不十分なものが見つかっている問題で、国土交通省のその後の調査で、合わせて45都道府県の556の橋で性能を満たしていない製品が使われていたことが分かりました。12の会社で必要な工程を省くなどの不正が行われていたということで、国土交通省は元請けに対して、補修や取り替えを行うよう求めました。
この問題はことし8月、京都市の国道の「勧進橋」で行われた耐震補強工事で、福井市の久富産業が製造した橋の落下を防止する装置の部品に、溶接が不十分なものが見つかったものです。
国土交通省は、久富産業の製品を使用した橋の調査を行うとともに、ほかの会社の製品についても抜き取り調査を行い、4日、その結果を再発防止策を検討する専門家による委員会で報告しました。
それによりますと、久富産業を含めて124の会社の製品で溶接の不十分なものが見つかり、香川県と長崎県を除く45都道府県の556の橋で性能を満たしていない製品が使われていたことが分かりました。
このうち、久富産業を含む12社で必要な工程を省くなどの不正が行われたということで、関わった橋の数はこれまでに400に上るということです。
不正が行われていた製品では、溶接部分に隙間ができるため、国が行った試験ではその面積が全体の半分を超えると大地震の際に部品が壊れ、橋の落下を防げないおそれがあるということです。
これまでのところ、会社側への聞き取りではそうした部品は見つかっていないということですが、国土交通省は元請けの建設会社に対し、順次、補修や取り替えを行うよう求めています。
委員会では今後、元請け会社が溶接の状況を記録に残すことや、国などの発注者が抜き打ち検査を行うなどの再発防止策を、さらに検討していくことにしています。
委員長を務める法政大学の森猛教授は「製造した会社には倫理観の欠如や勉強不足があったと言わざるをえないが、元請け会社にも責任がある。品質管理の在り方など必要な再発防止策を検討していきたい」と話しています。
溶接が不十分な部品とは
溶接が不十分な耐震補強の部品が見つかった落橋防止装置と呼ばれる装置は、橋桁と橋脚を鎖などでつなぐものです。主に災害時の緊急輸送道路など重要な道路の耐震補強で取り付けられています。通常、鎖は緩んだ状態ですが、大地震の際には激しい揺れで橋脚の上にのった橋桁がずれ動こうとすると、鎖が張って落ちるのを防ぎます。
今回は、この鎖を橋桁と橋脚に固定する部品で溶接が不十分なものが見つかったほか、別のタイプの装置でも溶接が不十分なものが見つかりました。
溶接が著しく不十分な場合には、いずれも大地震による激しい揺れで部品が壊れ、橋桁の落下を防げないおそれがあるとしています。
溶接不十分で なぜ出荷
溶接が不十分な部品はなぜ出荷されていたのでしょうか。国土交通省によりますと、最初に問題が明らかになった福井市の久富産業では、溶接が不十分なものを意図的に作ったうえ、製品を検査する立場の民間の検査員も検査を適切に行わず、不正に関わっていたとみられています。
国土交通省などによりますと、福井市の久富産業では、製品のうち20%から30%だけを溶接を適切に行って検査に回し、残りについては工程の一部を省き、設計どおりの溶接を行っていませんでした。
さらに検査する立場の北陸溶接検査事務所の検査員も、適切な溶接を行った部品だけを検査して、問題ないとする報告書を作成していました。
また、部品の製作を依頼した元請けの建設会社の担当者が立ち会った検査では、超音波を使った検査機器の操作をごまかして、溶接が不十分な部品が見つからないようにしていたということです。
検査員は1人で、久富産業に常駐しているような状態だったということで、国土交通省は、過去およそ5年間にわたって溶接が不十分なデータを隠蔽していた疑いがあるとしています。
これについて北陸溶接検査事務所はホームページで、「担当者は、久富産業は顧客であるとの認識でいたため、要請を拒絶することに強い心理的抵抗を感じていた。検査で溶接不良を指摘すると大幅な納期の遅延が生じることを懸念した模様だ」などとしたうえで、信頼回復に努めたいというコメントを掲載しています。
久富産業以外の11社は
各地の国道の橋で耐震補強工事に使われた部品に溶接の不十分なものが見つかった問題で、福井市の久富産業以外に、必要な工程を省くなどの不正を行っていたのは以下の11の会社です。
札幌市北区のマルエヌ野村工業、千葉県横芝光町のトーカン工業、愛知県刈谷市のエスイー鉄建、静岡市清水区の八十八工業と篠田工業、三重県玉城町のフジタ建設工業、大阪府堺市堺区の有元プラント工業、鳥取市のキシマ製作所、岡山市東区のサンベルコ、広島市中区の太陽工業、大分市の大分東明工業。
国土交通省によりますと、いずれも聞き取り調査に対して不正を行っていたことを認めているということで、国土交通省はこれらの会社が関わったほかの橋についても、さらに調査することにしています。
平成27年8月28日
○京都府内の国道24号勧進橋(国土交通省管理)において、耐震補修・補強工事の完了後に落橋防止装置※等の溶接部における不良が確認され、平成27年8月12日に近畿地方整備局京都国道事務所が記者発表を行ったところです。
※落橋防止装置とは、兵庫県南部地震程度の地震を越えるような大きな地震動により、これらの地震にもある程度耐えるよう設計されている支承などが万一破壊した場合でも、上部構造が落下するような致命的な状態とならないためにフェイルセーフとして設置しているものです。
○本件に関して、元請会社であるショーボンド建設(株)から近畿地方整備局への報告により、以下の事実を把握しました。
・溶接不良は、落橋防止装置等の部材の製作者である久富産業(株)が、工場内の溶接作業工程の一部を意図的に怠っていたことが原因である可能性が高いこと
・元請会社への納品の際に求めている超音波探傷試験に際し、溶接検査会社である(株)北陸溶接検査事務所の職員が、過去約5年間にわたって不良データの隠蔽を行っていた可能性があること
○このため、各地方整備局等及び高速道路会社において、当面、以下の対応を実施することとしましたので、お知らせいたします。
・久富産業(株)が製作した製品を使用した過去5年間の耐震補修・補強工事について、同社製の部材の溶接部の健全性の検査を実施する
・上記検査の結果、不良と判明した部材については、速やかに補修を行うよう、所定の手続きを行う
○今後、原因究明、再発防止策を検討していく中で、橋梁の溶接部に対する非破壊検査の活用を含めた定期点検の充実について検討してまいります。
○併せて、橋梁関連メーカーに対して、久富産業(株)が製作した製品を使用した耐震補修・補強工事について各発注者にご報告いただくよう、今後、業団体等を通じて協力要請などの対応を行ってまいります。
○また、地方公共団体に対しては、全ての都道府県に設置している道路メンテナンス会議(地方整備局、高速道路会社、都道府県、市町村等により構成)を活用し、国及び高速道路会社の対応について情報提供するとともに、技術的助言を行ってまいります。
国土交通省は4日、地震発生時に橋の落下を防ぐ「落橋防止装置」を製造した11社が装置の溶接工程の一部を不正に省略していたことを明らかにした。この装置を巡っては、久富産業(福井市)が意図的に溶接工程の一部を省いていたことが判明し、国交省が調査していた。11社と久富産業の不良品を使った橋は31都道府県で計400橋に上る。国交省は日常の使用に影響はないとしている。
国交省によると、国や高速道路会社が管理する橋のうち約5400橋に落橋防止装置がある。久富産業の不正を受け、国交省は耐震補強工事などに携わった元請け建設会社約1700社に部品の確認を要請し、調査を進めた。
その結果、11社の装置が使われた144橋のうち、11月末時点で43橋の落橋防止装置に溶接不良を確認。国交省が11社に事情を聴いたところ、故意に溶接工程を省いたことを認めたという。調査は続いており、不正の件数は増える可能性がある。
国交省は「一定の溶接がされているので、落橋防止装置としての機能が低下している可能性は低いが、将来を考えると補修が必要」としており、元請けに補修を求める。
これとは別に、全国の156橋の落橋防止装置に溶接の不具合などが見つかった。故意に工程を省略したのではなく、作業上のミスだったという。
不正行為があった他の11社は以下の通り。
マルエヌ野村工業(北海道)▽トーカン工業(千葉県)▽エスイー鉄建(愛知県)▽八十八工業(静岡市)▽篠田工業(静岡市)▽フジタ建設工業(三重県)▽有元プラント工業(堺市)▽キシマ製作所(鳥取市)▽サンベルコ(岡山市)▽太陽工業(広島市)▽大分東明工業(大分市)【坂口雄亮】
近畿地方整備局は28日、鴨川にかかる国道24号の勧進橋(京都市南区、伏見区)の補修・補強工事で、58個の部材に溶接不良が見つかったと発表した。他の耐震工事が施してあり、すぐに倒壊、落橋する恐れはないが、不良箇所は全て取り換える。
同局によると、工事は平成25~26年度発注。落橋防止と橋桁の支えを補強する部材で溶接不良が見つかった。部材を製作した久富産業(福井市)が鋼板と鋼板を溶接する際、工程を省いたため、溶接不良が発生した。
また納品の際、超音波で傷などを探る試験を担当した民間の北陸溶接検査事務所(福井市)の従業員が、不良を示したデータを隠していた。
7月末、京都市が近畿地方整備局に連絡して発覚。同局が調査を進めた。
人の命を軽視する重大な裏切り行為だ。血液製剤やワクチンの有力メーカーが国の承認を得ていない方法で製品をつくり、組織ぐるみで隠蔽(いんぺい)していた。長年、不正を見逃してきた国の責任も重い。
厚生労働省は三日、熊本市の一般財団法人「化学及(および)血清療法研究所」(化血研)へ立ち入り検査に入った。行政処分する方針だ。
「常軌を逸した隠蔽体質が根付いていた」
専門家による第三者委員会が公表した報告書はこう言い切った。不正は四十年以上前から始まり、血液製剤十二製品すべてで行われていたという。
歴代理事長らは不正の事実を認識し、しかも隠蔽にも関与していた。国の定期査察の際には、過去の記録に見せ掛けるために紙に紫外線を浴びせて変色させたり、偽の出納記録を作成するなどしており「極めて悪質な方法で隠し通した」と報告は指摘。安全性よりも、企業の利益を優先させる姿勢があったと断じた。
不正製造は今年五月、厚労省に内部告発が寄せられ、発覚した。同省は血液製剤とワクチンの出荷差し止めや自粛を要請した。化血研はインフルエンザワクチンの三割を供給し、流行期を前にワクチン不足が懸念された。国民の不安を招いた罪は重い。
第三者委は、重大な副作用は報告されておらず、安全性に大きな問題はない、としている。だが、血液製剤は感染リスクをなくすため、国の承認通りに製造することが厳しく求められている。未承認の方法でつくった製品を使った患者への健康被害はなかったのだろうか。疑問があれば、検証すべきだろう。
また、巧妙に隠されていたとはいえ、長年にわたり不正を見抜けなかった厚労省にも猛省を求めたい。定期査察は医薬品医療機器総合機構(PMDA)に委託し、二年に一回程度のペースで各社に行われている。しかし、日時や内容などを事前に通告していた。化血研は査察前に偽造した製造記録を準備し、不正発覚を免れていた。犯罪にも等しい。
同省は今後、一部抜き打ち検査をする方針を示したが、当然だ。検査は実効性がなければならない。官民もたれ合いのような体質を排除するべきだ。
国民の命や健康に直結する医薬品の世界では、厳しい法令順守が求められる。失墜した信頼は大きい。再発防止策を国民に示してほしい。
40年間も騙される検査を行ってきた厚生労働省だから、厚労相がリップサービスで言っているだけで、実行できるかは疑問? 検査担当の厚生労働省職員の経験と能力次第。命令、やる気そして根性だけでは結果は出せない。
東芝の利益水増し問題で、田中久雄前社長ら歴代3社長がパソコン事業の不正取引を認識しながら虚偽の利益を計上させた疑いがあるとして、証券取引等監視委員会が金融商品取引法違反容疑での刑事告発を視野に調査していることが3日、市場関係者への取材で分かった。
また、監視委は週明けにも、有価証券報告書に虚偽記載があったとして、東芝に過去最高額となる70億円超の課徴金を納付させる行政処分を科すよう、金融庁に勧告する方針だ。
東芝の利益水増し額は税引き前損益で計2248億円。インフラや半導体のほか不採算部門のパソコン事業でも行われていた。監視委は当初、刑事告発に消極的だったが、社会に与えた影響のほか、歴代経営陣が長年、不正の仕組みを理解しながら利益の計上を求め続けた点を重くみて、刑事告発の可否を検討することとした。
東芝が公表した調査委員会の報告書は、海外の生産委託先に部品を納入し、完成したパソコンを買い取る「Buy-Sell取引」で各期末に利益のかさ上げが行われたと指摘。
その上で、この取引に関して田中前社長や西田厚聡、佐々木則夫両元社長は通常の取引では実現不可能な目標を「チャレンジ」と称し、予算達成を強く指示するなど、利益水増しを余儀なくするような状況に部下を追い込み、20年度第2四半期から26年度第3四半期の間、各期末に利益をかさ上げさせたとしている。
40年間も騙される検査を行ってきた厚生労働省だから、厚労相がリップサービスで言っているだけで、実行できるかは疑問? 検査担当の厚生労働省職員の経験と能力次第。命令、やる気そして根性だけでは結果は出せない。
血液製剤やワクチンの有力メーカー「化学及(および)血清療法研究所」(化血研、熊本市)が40年以上にわたって不正製造を続けていた問題で、塩崎恭久厚生労働相は4日の閣議後会見で「厳正に対処していきたい」と、化血研に行政処分をする方針を明らかにした。製薬会社に対する国の立ち入り検査についても、抜き打ちを増やすなど検査のあり方を見直す考えを示した。
化血研は1997年ごろから、立ち入り検査時に、承認通りに製造したように偽造した記録を示すなどして発覚を免れていた。塩崎厚労相は「前代未聞の内部統制の欠落。意図的、組織的で極めて残念だ」と語った。検査のあり方について「事前に言わずに行く抜き打ち検査、査察を含め、全て見直すことが大事だ。不正をどう発見するか、しっかり検討しないといけない」と述べた。
厚労省は3日に続き4日も熊本市の化血研に立ち入り検査をしている。
偽善者という事?
「赤沢容疑者は金の使い道について『車のローンの支払いやバンドの活動費用に使った』と供述しています。」
「『血液サラサラ音頭』など6枚のCDの売り上げを骨髄移植支援団体に寄付するなどして、メディアにもよくとりあげられていた。」
出来る範囲でバンド活動を行えば良いし、バンド活動の維持に寄付などがあったのかは知らないが、収賄を正当化する理由はない。
CDの売り上げを骨髄移植支援団体に寄付する行為は、見栄っ張り、それとも、注目を引くためのパフォーマンス?
「歌うドクター」として知られる名古屋・名城病院の医師、赤沢貴洋(41)が、人工透析の患者を紹介した見返りに賄賂を受け取っていたとして、きのう3日(2015年12月)に愛知県警に逮捕・送検された。名城病院は国家公務員共済組合連合会の運営で、勤務する医師は公務員とみなされる。
警察によると、赤沢容疑者は人工透析が必要な患者8人を医療法人「光寿会」が運営する病院や診療所に転院させ、見返りに約60万円を受け取っていた。光寿会の実質的経営者の多和田英夫医師(64)も贈賄容疑で逮捕された。双方とも容疑を認めているという。
白衣姿にギターをかかえて病院・老人ホーム慰問「血液サラサラ音頭」
赤沢は看護師などとバンドを組んで、白衣姿にギターをかかえて病院や老人ホームを慰問する「歌うスーパードクター」として知られる。「血液サラサラ音頭」など6枚のCDの売り上げを骨髄移植支援団体に寄付するなどして、メディアにもよくとりあげられていた。診察を受けていた患者たちはびっくりだ。「優しく丁寧に説明して下さって、いい先生ですよ」「びっくりしてます。惜しいです」と口々に言う。赤沢は車のローンの支払いやバンドの活動で金が必要だったと供述しているという。
名古屋市の病院の医師が患者を別の病院に紹介する見返りに賄賂を受け取ったとして逮捕されました。医師はバンド活動で患者を慰問するなどしていました。
逮捕されたのは、国家公務員共済組合連合会「名城病院」の医師・赤沢貴洋容疑者(41)です。警察の調べによりますと、赤沢容疑者は、人工透析が必要な患者8人を医療法人「光寿会」が経営する病院や診療所に転院させ、光寿会の実質的経営者・多和田英夫容疑者(64)から約60万円の賄賂を受け取った疑いです。赤沢容疑者は仲間とバンドを結成し、慰問の演奏などを頻繁に行っていました。調べに対して、2人は容疑を認め、赤沢容疑者は金の使い道について「車のローンの支払いやバンドの活動費用に使った」と供述しています。
人工透析患者の転院をめぐる贈収賄事件で、収賄容疑で逮捕された名城病院(名古屋市中区)の腎・糖尿病内科医長、赤沢貴洋容疑者(41)が、自分の患者を贈賄側に紹介するごとに定額の謝礼を受け取っていたことが3日、愛知県警への取材で分かった。
謝礼は、アルバイト勤務の給料に患者1人当たり10万円を上乗せする形で支払われていた。
県警捜査2課によると、赤沢容疑者は贈賄側の医療法人「光寿会」(同市西区)の診療所で、非常勤で透析治療を担当。紹介の謝礼は月ごとの給料と一緒に振り込まれ、人数によって増減があった上、勤務しなかった月も支払いがあった。
赤沢容疑者は2~10月、名城病院で治療した8人を光寿会の病院や診療所に入院、通院させた見返りに、同会前理事長の多和田英夫容疑者(64)から約60万円を受け取った疑いで逮捕された。給料を装って税金分を天引きしており、実際の振込額は患者1人で約8万円だった。
「発覚のきっかけの一つは内部告発だった」
どのような背景なのか知りたい。
血液製剤やワクチンの国内メーカー「化学及(および)血清療法研究所」(化血研、熊本市)による不正製造問題で、発覚のきっかけの一つは内部告発だったことが、厚生労働省への取材でわかった。この情報をもとに今年5月に抜き打ちで調査をし、40年以上にわたる不正が明らかになっていったという。
厚労省によると…
「宮本誠二理事長は『今回の報告で初めて知った』『危険があるという認識はなかった』『安全性に問題はない』などと答えたが、『なぜ安全だといえるのか』と聞かれると、長い沈黙のあと、『申し訳ありません。十分なお答えができません』」
ここに問題が存在すると思う。
血液製剤やワクチンの有力メーカーの一般財団法人「化学及血清療法研究所」(化血研・熊本市)が、国の承認と異なる方法で製品を作っていた問題で、化血研はきのう2日(2015年12月)、第三者委委員会の報告書を公表した。不正は40年も前から行われていて、ニセの製造記録まで作って隠蔽していた。ただ、製品による重大な副作用の報告はないという。
薬害エイズでも汚染血液製剤
化血研はワクチンのシェアでインフルエンザ29%、ポリオ64.2%、日本脳炎36.2%、B型肝炎79.9%という有力メーカーだ。インフルは他のメーカーが3社あるが、そのほかのワクチンはライバルはそれぞれ1社しかない。血液製剤によるエイズ薬害訴訟(1996年に和解)の当事者の1つでもあった。
信用できない
問題が明るみに出たのは5月にあった内部告発だった。国が承認していない方法で製造を始めたのは74年からで、製造記録を2通作り、紙を古く見せるために紫外線を当てることまでしていた。第三者委は「常軌を逸した隠蔽」としている。
宮本誠二理事長は「今回の報告で初めて知った」「危険があるという認識はなかった」「安全性に問題はない」などと答えたが、「なぜ安全だといえるのか」と聞かれると、長い沈黙のあと、「申し訳ありません。十分なお答えができません」
化血研は宮本理事長以下理事9人全員の辞任・辞職を発表した。
「国内の血液製剤の約3割を製造する一般財団法人・化学及および血清療法研究所(化血研、熊本市)が40年前から国の未承認の方法で製造していた問題を受け、厚生労働省は、血液製剤とワクチンのメーカーに対し、製造工程の検査(査察)の一部を抜き打ちで行う方針を固めた。」
厚生労働省のパフォーマンスかどうかは、抜き打ち検査のメンバーの経験や知識、そして抜き打ち検査の情報が流れないか次第であろう。
マイナンバー制度関連事業をめぐる汚職事件では業者との癒着があった。今回の件でも、
厚生労働省の職員で全く深い関係がないと言い切れるのだろうか?厚生労働省内部の情報なしで40年間も上手く検査を逃れる事が出来るのだろうか?
国内の血液製剤の約3割を製造する一般財団法人・化学及血清療法研究所(化血研、熊本市)が40年前から国の未承認の方法で製造していた問題を受け、厚生労働省は、血液製剤とワクチンのメーカーに対し、製造工程の検査(査察)の一部を抜き打ちで行う方針を固めた。
これまでの定期的な検査は、日時や内容などをメーカー側に事前に通告していた。今後、処方箋が必要な医薬品を製造する全企業(約280社)も、抜き打ちの対象とする方向で検討する。
検査は医薬品医療機器法に基づき、国が医薬品医療機器総合機構(PMDA)に委託して実施している。各社は約2年に1回のペースで検査を受けてきたが、国側は数日間で効率的に検査を進めるために事前通告し、企業側に必要な書類を用意させてきた。
しかし、2日公表された化血研の第三者委員会の調査報告によると、化血研は国の検査前に、実際の製造記録から不正に関するページを抜き取り、国の承認内容に沿って製造したように装ったほか、想定問答集を作成して予行演習を行うなどの隠蔽工作も行った。翌日の検査の連絡を受け、所内で対応を協議した事実も認定された。
「血液製剤やワクチンの国内有数のメーカーである一般財団法人「化学及血清療法研究所」(化血研、熊本市)が、国が承認していない方法で血液製剤を製造した問題で、化血研は2日、製造記録を偽造するなど隠蔽(いんぺい)工作をしながら、40年以上にわたり国の承認書と異なる不正製造を続けていたとの調査結果を明らかにした。・・・
医薬品メーカーは法令に基づき、国の承認書に従って製造し、記録を残す義務がある。国は定期的に記録を確認しているが、化血研は95年ごろから承認書通りに製造したと虚偽の記録を作り、検査をクリアしていた。記録用紙に紫外線を浴びせて変色させ、古い書類だと見せかける工作もしていた。」
これで厚生労働省が悪質性がないと判断すれば、厚生労働省の人間と化学及血清療法研究所の人間が癒着していると考えてもおかしくない。
一般財団法人・化学及および血清療法研究所(化血研)が血液製剤などを不正な方法で製造していた問題で、厚生労働省は3日午後、医薬品医療機器法に基づき、熊本市にある化血研の本所に立ち入り検査に入った。
同省は検査結果をもとに悪質性を見極め、行政処分する。
化血研の第三者委員会が2日に公表した調査報告書によると、化血研は1974年以降、血液製剤の一部の製造工程で、国から承認された手順と異なる製法を採用。厚労相の承認を受けずに製造した医薬品の販売は同法で禁じられており、第三者委は「極めて悪質、重大な違法行為」と指摘している。
今回の問題で、厚労省が化血研に立ち入り検査に入るのは3回目となる。
血液製剤やワクチンの国内有力メーカー「化学及(および)血清療法研究所」(化血研、熊本市)が国の承認と異なる方法で製品をつくっていた問題があり、化血研は2日、第三者委員会の報告書を公表した。報告書は、不正は40年以上前から始まり、血液製剤12製品すべてで行われ、虚偽の製造記録を作成するなどして組織的に発覚を免れていたと認定。「常軌を逸した隠蔽(いんぺい)体質」と批判した。
第三者委は、重大な副作用は報告されておらず、安全性には大きな問題はないとしている。
厚生労働省は近く化血研を行政処分する方針。化血研は2日、宮本誠二理事長はじめ理事9人全員の辞任・辞職を発表した。
化血研が設置した第三者委は、元東京高裁長官の吉戒(よしかい)修一氏を委員長に元検事や専門家ら計6人で構成。
報告書によると、不正製造は、血液製剤12製品の31工程であった。製造効率を高める目的で、承認書にはない添加剤を入れたり、添加剤の量や加熱方法を勝手に変更したりしていた。本来は製造方法の一部変更の承認を得る必要があったが、その手続きをとっていなかった。不正製造は、遅くとも1974年ごろから始まり、多くは80年代から90年代前半に実施するようになった。
不正が起きた背景として、薬害エイズ問題によって国内での加熱製剤の生産増強が要請され、早期の製品化や安定供給を最優先に開発・製造を急いでいたことを挙げた。さらに、「自分たちは専門家であり、当局よりもよく知っている」「製造方法を改善しているのだから、当局を少々ごまかしても、大きな問題はない」という研究者のおごりがあったと指摘した。
前理事長や現理事長らは、不正な製造や隠蔽を認識していながら放置してきた。品質管理部門や品質保証部門の一部管理職は、不正な製造や隠蔽を認識しながら、故意にその事実を明らかにしなかったとした。
報告書では、製薬会社としてはあってはならない重大な違法行為と認定。化血研の役員たちは「先人たちの違法行為に呪縛されて、自らも違法行為を行うという悪循環に陥っていた」と指摘した。
また、薬害HIV訴訟の和解のころに経営陣が不正製造の報告を受けていたとし、「和解における誓約がうわべだけのものに過ぎなかったと非難されてもやむを得ない」と批判した。
一方、ワクチンについては、重大な不正や隠蔽を認める証拠は存在しないとした。
宮本理事長は2日夜、厚労省で会見し、「患者の皆さま、医療関係の皆さま、国民の皆さまにご迷惑をおかけしておりますことを、深くおわび申し上げます」と頭を下げた。隠蔽工作を続けたことについては「コンプライアンス意識が低かった。研究者意識で技術的な面が先行し、対応が遅れていった」と語った。
薬害HIV訴訟の原告団らに対しても「大変申し訳ないことをした」と謝罪した。
■悪質な隠蔽工作
国の調査・査察で不正製造が発覚しないように、化血研は計画的に隠蔽工作を繰り返していた。
報告書によると、隠蔽工作が本格化したのは97年ごろ。ある製造チームでは、査察で見せるための偽の製造記録はゴシック体で、実際の製造記録は明朝体で書類を二重に作成し、区別できるようにしていた。別のチームでは、不正製造による記録のページ数には「2・5」などと小数を加え、査察の時にはそのページを抜き取っていた。当時の部長は「このままでは見せられん。査察対応のものをもう一つ作らざるを得ない」と指示していた。
偽の製造記録などは過去の分も書き直し、かつての上司の承認欄には筆跡が似ている社員にサインをさせたり、紙に紫外線をあてて変色させ古くみせかけたりもしていた。
調査に備え、国の承認書に沿った想定問答集をつくり予行演習もしていたという。
◇
〈化学及血清療法研究所(化血研)〉 旧熊本医科大(熊本大医学部)の研究所が母体で1945年12月に設立された。薬害HIV訴訟の被告の一つで96年に和解が成立した。ワクチンや血液製剤の老舗で、抗がん剤や動物用の薬も製造している。ワクチンではインフルエンザは国内の約3割、百日ぜきやポリオなどを予防する子ども向けの4種混合は約6割のシェアを持つ。A型肝炎や狂犬病などは100%のシェアを占める。
◇厚労省、処分へ
血液製剤やワクチンの国内有数のメーカーである一般財団法人「化学及血清療法研究所」(化血研、熊本市)が、国が承認していない方法で血液製剤を製造した問題で、化血研は2日、製造記録を偽造するなど隠蔽(いんぺい)工作をしながら、40年以上にわたり国の承認書と異なる不正製造を続けていたとの調査結果を明らかにした。厚生労働省は化血研を行政処分する方針。【古関俊樹】
◇「常軌を逸した隠蔽体質」
化血研は、宮本誠二理事長が2日付で辞任したと発表した。他の全理事も同日付で辞任や降格などの処分とした。
化血研が2日にあった厚労省の専門家委員会に第三者委の調査結果を報告した。報告書によると、化血研は遅くとも1974年には一部の製剤について加温工程を変更し、国の承認書と異なる方法で製造していた。90年ごろには幹部の指示によって、血液製剤を作る際に血液を固まりにくくする添加物を使用する不正製造を始めた。製造効率を上げるためだったという。ワクチンでは同様の不正行為は確認されなかった。
医薬品メーカーは法令に基づき、国の承認書に従って製造し、記録を残す義務がある。国は定期的に記録を確認しているが、化血研は95年ごろから承認書通りに製造したと虚偽の記録を作り、検査をクリアしていた。記録用紙に紫外線を浴びせて変色させ、古い書類だと見せかける工作もしていた。
こうした不正行為はトップである理事長も認識しており、第三者委は「常軌を逸した隠蔽体質が根付いていた」「研究者としてのおごりが不整合(不正)や隠蔽の原因となった」と指摘した。
厚労省は今年5月に化血研を立ち入り調査し、血液製剤の製造で不正を確認。6月に血液製剤の出荷を差し止め、他のワクチンなどについても調査。化血研も9月に第三者委員会を設置し、調査を進めていた。これまでに健康被害は確認されていないという。
化血研は旧熊本医科大が前身で、45年の設立。薬害エイズ訴訟の被告企業の一つ。
◇「風土として対応できず」…理事長謝罪
化血研の宮本誠二理事長は2日夜、厚生労働省で記者会見し、「深くおわびします」と謝罪した。自身も長年にわたり不正を認識していたことを明らかにし、「化血研の風土として積極的に対応できなかった。私もその一人だ」と苦渋の表情で語った。「理事長に就任した時になぜ改善しなかったのか」と記者から問われると、宮本理事長は「改革すると血液製剤の供給がストップしてしまうことを懸念した」と明かした。
会見に先立ち、薬害エイズ訴訟原告団の代表らが「和解した私たちに対する裏切りだ」とする抗議書を宮本理事長に手渡した。【内橋寿明】
◇接種予約、中止の動き
厚生労働省は化血研に対し、血液製剤の出荷差し止めに続き、ワクチンの出荷自粛を要請している。化血研のシェアが高く代替品の確保が難しい日本脳炎とA型肝炎、B型肝炎のワクチンが不足し、東京や千葉など各地で接種の予約を中止する病院が出始めている。ワクチンを販売しているアステラス製薬によると、出荷が再開されなければ、日本脳炎は来年1月下旬、B型肝炎は来年1月中旬~下旬に市場の在庫がなくなる可能性がある(11月27日現在)という。
厚労省によると、日本脳炎ワクチンは2013年度に延べ429万2409人が接種。A型肝炎、B型肝炎は任意接種のため接種人数の統計がないという。厚労省は「製剤ごとに優先順位を付けて調査しており、終了後に出荷自粛の要請を解除する」と説明するが、解除の時期は未定。
化血研が未承認製法で血液製剤を出荷していたことで、厚労省は他の製剤についても製法の実態調査を化血研に指示した。化血研は報告したが、厚労省は報告に不備があるとして、9月までに29製品の出荷自粛を要請。安全性が確認できたり、緊急性が高かったりする製剤は出荷できるようになったが、現在もワクチン3種類、血液製剤7種類は出荷できない。【古関俊樹】
マイナンバーを使ったら簡単だとか安易に使用していると悪用された場合、誰が責任を取るのか?自治体や自治体職員から情報がリークしたらどうするのか? なりすましの人間が職員だと言って、老人からマイナンバーを聞き出して悪用したらどうするのか?火事場泥棒がいるし、避難場所での泥棒がいる環境で、 老人が騙される事はないのか?タブレット型端末が盗まれる事もあるかもしれない。どう対応するのか?
来年1月から本格利用が始まる共通番号制度のマイナンバーを使って、災害時に安否確認を行うシステムを、東大生産技術研究所(東京都目黒区)が開発した。
自治体の避難所に来た住民のマイナンバーをタブレット型端末に入力すると、避難した住民の情報を一元的に管理できる。未入力者をリストアップし、安否不明者も絞り込めるため、同研究所は内閣府の支援を受け、全国の自治体へのシステム導入を目指している。
個人情報保護法23条は、生命や身体などの保護を理由に、本人の同意なしに個人情報を第三者に提供できるとしている。ただ、内閣府によると、マイナンバーの利用に関する法律で、マイナンバーを活用できると定められているのは、年金の確認、児童手当や介護保険の申請などに限られる。災害時の活用は、被災者生活再建支援金の支給や被災者台帳の作成で認められているが、安否確認は対象外で、自治体ごとに条例を定める必要がある。
下記の記事が事実であれば、ディーゼル車の開発はかなり技術的に厳しく、コストの点から将来性がないと言うことかもしれない?
車の排ガス規制逃れ問題を追及するドイツの環境団体「ドイツ環境支援」は24日、フランス自動車大手ルノーのディーゼルエンジン車「エスパス1・6dCi」の排ガス試験を行った結果、欧州の排出基準値の最大25倍に当たる窒素酸化物(NOx)を検出したと発表した。
排ガス試験はスイス・ベルンの大学に委託し、今月上旬に実施。エンジンが冷えた状態など特定の条件下で試験をした場合にのみ基準値を満たし、温まった状態では基準の13~25倍の値が検出された。(共同)
[ベルリン 24日 ロイター] - 非政府組織のドイツ環境支援協会(DUH)は、仏ルノー(RENA.PA)のディーゼル車「エスパス1.6dCi」について、最大で現在の欧州基準(ユーロ6)の25倍の窒素酸化物の排出が明らかになったと発表した。
試験はスイスの応用科学大学により新方式で5回実施された。
ルノーのコメントは得られていない。
欧州では、試験をめぐり当局とメーカーの関係が近すぎるとの批判があり、DUHは改革を求めている。
DUHの発表文の中で国際クリーン交通委員会(ICCT)の共同創設者のアクセル・フリードリヒ氏は「このようなかたちでわれわれが呼吸する空気を損っているディーゼル車が走行しているとは信じられない。承認手続きのシステムを根本的に変更する必要がある」と主張している。
国に代わって全国の検査場で車検を行う「自動車検査独立行政法人」(東京都新宿区)が一番悪いわけだが、国土交通省は行政としてしっかり管理及び監督しなければならない。
国に代わって全国の検査場で車検を行う「自動車検査独立行政法人」(東京都新宿区)が、転倒防止のためにトラックなどを対象に実施する抜き取り検査を、東北、関東両地区で5年近く取りやめたまま放置していたことがわかった。
取りやめは東日本大震災を受けた措置で、全国93の車検場のうち、3割以上で再開されていなかった。所管する国土交通省は読売新聞の指摘を受け、今月、同法人に再開を求めた。
問題となったのは最大安定傾斜角度の検査。トラックなどがカーブ走行時に転倒するのを防ぐため、車体を一定角度に傾けて安定性を調べる。トラックは、車台をメーカーが販売し、荷台部分は専門の架装メーカーが製造、装着して車検を取得するが、架装メーカーが安全性を証明する書面を提出した場合は、検査を受ける必要はない。
「石井啓一国交相は『これほど多くのデータ流用が行われていたことは極めて遺憾』とコメントした。」
国土交通省は行政として、規則の改正を含め、どのように対応していくつもりなのか?
◇現場責任者3割の61人が関与
旭化成建材のくい打ち施工データ改ざん問題で、旭化成建材と親会社の旭化成は24日、過去に実施したくい工事3052件のうち、12%にあたる360件でデータの不正が見つかったことを国土交通省に報告し、公表した。3052件の工事に関わった現場責任者196人中、約3割の61人がデータ不正に関与していた。旭化成側は今後、不正があった360件の安全確認を始める。
くいを打ち込んだ際の地盤の強度を示す電流計のデータと、くいを補強する凝固剤の流量計データに、他のくいのデータ転用や加筆があった。旭化成の山崎真人広報室長は「3割もの現場責任者が不正に関与していたことになり、驚いている。重ねておわびしたい」と陳謝した。
360件のくい総本数は2万6351本で9%の2382本のデータに不正があった。電流計の不正は266件、流量計の不正は144件で一部で重複していた。61人の現場責任者の大半は下請けからの出向社員だった。
360件の内訳は、マンションなど集合住宅102件▽オフィスビルなど事務所20件▽商業施設12件▽工場・倉庫91件▽医療・福祉施設37件▽学校37件▽公共施設21件▽土木9件▽ホテルなど「その他」31件。都道府県別では東京が最多の73件で以下、北海道53件▽神奈川36件▽埼玉31件▽愛知23件−−と続いた。個別物件ごとの詳細は公表しなかった。
3052件中35件は既に建物が取り壊され、153件は元請け建設会社の廃業などで不正の有無を確認できなかった。旭化成側は不正の有無が判明しなかった物件の安全確認も対応を検討する。
旭化成建材がくい打ち工事を担当した横浜市都筑区のマンションで一部のくいが強固な地盤(支持層)に届かず、データが改ざんされていたことから、2004年以降に実施した3040件の調査を始めた。途中で判明した12件も調査対象に加えた。
これらとは別に、自治体などの調査で地盤とくいの凸凹の摩擦力で支える「摩擦ぐい」についてもデータ不正があったことが判明した。旭化成は「個別に対応したい」としている。また、旭化成建材は都筑区のマンションのデータ不正に関与した現場責任者が担当した工事41件中19件で不正があったと説明していたが、同社は「不正は43件中20件」と修正した。
石井啓一国交相は「これほど多くのデータ流用が行われていたことは極めて遺憾」とコメントした。
国交省は11月13日までに結果を報告するよう指示したが間に合わず、旭化成側は13日時点で266件の不正があったと報告するにとどまり、最終的な報告は24日にずれ込んだ。【坂口雄亮、内橋寿明】
全てを任せてチェックしないほうが楽であるが、時々はチェックするほうが良いであろう。チェックされないと思うと、不正に走る人達がいる。 総額約11億7800万円を着服するぐらいだから、お金のほとんどは返ってこないと思ったほうが良い。
新潟県南魚沼市のリゾートマンション「ツインタワー石打」(549戸)の管理組合前理事長(68)が、マンションの管理費など総額約11億7800万円を着服していたことが22日、組合関係者らへの取材で分かった。
組合関係者らによると、前理事長は公認会計士で、1999年11月に就任。着服は副理事長だった98年ごろから昨年10月までの約16年間にわたり、月額約2万〜12万円の管理費や入居者が積み立てた修繕費などを自らの銀行口座に移したり、引き出したりしていた。昨年11月、決算書を不審に思った組合理事らが確認したところ、着服を認めたため、前理事長を解任。今年1月、時効前の約4億円について、業務上横領容疑で警視庁に告訴状を出した。
前理事長は、会計報告の際に架空経費の計上などで発覚を免れたといい、「一時的に借りて投資で増やし、返すつもりだったが、失敗して返せなかった」と話しているという。
約10年前に同マンションを購入し、週末を利用して横浜市から訪れた男性医師(57)は「信じていたのに、裏切られた気持ちでいっぱいだ」と憤っていた。
マンションは90年に建てられ、19階建てと12階建ての2棟。上越新幹線・越後湯沢駅からは約3.5キロで、スキー場に隣接している。【柳沢亮、板鼻幸雄】
「運転手は『特定の2団体の旅行で、10回くらい不正をした』と打ち明け、『酒を勧められ、断り切れなかった。』」
たぶん、単なる言い訳。社内の規定で飲めないとか、安全運転を心がけているからと言えば良い事。どうしてもと言われれば、コップいっぱいぐらいで終えるべきだったと
思う。
伊予鉄道(本社・松山市湊町)は20日、松山室町営業所(同市室町)の男性バス運転手(48)ら4人が乗務前の飲酒検査で不正を行っていたと発表した。
愛媛県庁で記者会見した清水一郎社長は、「不祥事を起こして申し訳ない」と陳謝した。四国運輸局は道路運送法に基づき、同営業所に特別監査を行った。
同社の発表などによると、運転手は2011年3月から宿泊を伴う貸し切りバスの運行目的地で、同社の内規に反して飲酒していた。
朝の飲酒検査では本来、検知器に通したストローから呼気を吹き込み、検査の様子とデータを携帯端末で撮影して会社へ送る決まりになっている。しかし運転手は、検知器に電動ポンプをつけて空気を入れてデータをごまかしていた。
同営業所の社員の女性バスガイド(38)と、派遣の女性バスガイド2人も同様の手口で不正を行っていたという。
ドライバーへの飲酒検査は、安全確保のために法律で定められた規則。同社の内規では、宿泊を伴う勤務の時にはバスガイドを含めて飲酒を禁じていた。
内部通報をもとに同社が調査し、今月11日に確認した。運転手は「特定の2団体の旅行で、10回くらい不正をした」と打ち明け、「酒を勧められ、断り切れなかった。万一、アルコールが出ると、運転できないので困ると思った」などと釈明したという。
関西のある自動車輸入業者は取材に「神奈川事務所の車検の甘さは業界では有名。他で車検が通らない車を『神奈川』に持ち込む業者もいた」と証言した。
神奈川事務所の車検の甘さが業界でも有名であっても、国土交通省や国土交通省所管の「自動車検査独立行政法人」は何も知らなかったのか?????
そうであれば「自動車検査独立行政法人」の存続を検討する必要がある。そして、国土交通省はなぜこのような状態を放置しておいたのか、調査する必要がある。
◇虚偽有印公文書作成容疑 輸入車のサイドアンダーミラー巡り
日本の安全基準を満たしていないのに国内で販売できるよう、輸入車の自動車検査票を捏造(ねつぞう)したとして、大阪府警は21日、国土交通省所管の「自動車検査独立行政法人」神奈川事務所(横浜市都筑区)の主席自動車検査官3人を虚偽有印公文書作成の疑いで逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。府警は他に複数の捏造を確認しており、輸入業者と癒着し不正が常態化していた可能性があるとみて全容解明を進める方針。
府警は20日、同法人本部(東京都新宿区)と神奈川事務所を捜索した。3人は柏谷章(44)=神奈川県厚木市▽山本能功(よしのり)(42)=相模原市▽母ヶ野(ほがの)賢一(42)=東京都江戸川区−−の各容疑者。
捜査関係者によると、捏造の対象は、正規代理店やメーカー日本法人以外の業者が独自に海外で買い付けて販売する並行輸入車。3人は今年8〜9月、横浜市内の自動車輸入業者が仕入れたピックアップトラック3台の車検を担当。車高が高く死角がある車の前部に装着が義務付けられた「サイドアンダーミラー」などがないのに、国の基準に合格したとする検査票を作成した疑いが持たれている。
業者はこの検査票を運輸支局に提出し、自動車登録時の車検が不要になる予備検査証を取得、トラックを販売していた。
府警は10月、別の並行輸入車に車検時だけサイドアンダーミラーを付け予備検査証を運輸支局から不正取得したとして、この輸入業者の社長(61)ら2人を道路運送車両法違反容疑で逮捕。押収資料などから、自動車検査官の不正が浮上した。
正規輸入車の場合、メーカー側があらかじめ日本の基準に合った仕様で製造しており、国が書面だけで審査していることが多い。一方、並行輸入車は、同法人など第三者のチェックが必要だ。関西のある自動車輸入業者は取材に「神奈川事務所の車検の甘さは業界では有名。他で車検が通らない車を『神奈川』に持ち込む業者もいた」と証言した。
◇自動車検査独立行政法人
政府の行政改革で2002年、当時の陸運支局(現・運輸支局)の検査業務の一部を引き継ぐ形で設立された。自動車検査官は法律で「みなし公務員」と規定されている。法人傘下の検査事務所などは全国に約90カ所あり、神奈川事務所は検査官や検査レーンの数が全国で最多。
業界団体のコンクリートパイル建設技術協会の会員や役員は業界の会社の役員や社長なので動きは遅いであろう。外部の専門家や大学教授が役員としていたとしても、 「YES MAN」か何も言わない人達がなっていると思うから、たぶん、形だけかも?
熊本県は17日、旅行業法で定められた旅行業務取扱管理者を常駐させずに旅行契約を結んでいたとして、熊本大生活協同組合に対する聴聞を開いた。
生協側は事実関係を認めた。県は生協の旅行業務に関して77日間の営業停止処分にする方針。
同法は、旅行契約を行う際には、管理者が常駐することを義務付けている。生協が2012年9月から3年間、管理者として届け出ていた70歳代の男性は病気療養中で、出勤していなかった。
生協は13年12月と14年8月に旅行業登録の更新や変更をした際、いずれも男性の名前を管理者として書類に記載していたという。外部からの指摘を受けた県が今年9月に実施した立ち入り検査で違反を確認した。
契約済みの旅行は、予定通り実施できるという。
生協の深見隆久専務理事は県庁での聴聞終了後、「契約できないとは分かっていたが、うやむやにしていた。新たな管理者を雇って再発防止を図っている」と話した。
旭化成グループでなければ旭化成建材は終わりかもしれない?
旭化成建材によるくい打ちデータ偽装問題で、これまで偽装が見つかっていたくいとは別の種類の「摩擦くい」でもデータ偽装があったことが20日、分かった。さいたま市が独自調査で発見、公表した。同社が偽装の有無を調査している「既製コンクリートくい」以外で偽装が判明するのは初めて。同社は摩擦くい約6千件を施工しており、今後、調査対象を拡大するかどうか検討する。国土交通省は同社から事情を聴き始めている。
さいたま市によると、摩擦くいの施工でデータ偽装があったのは、緑消防署美園出張所のくい45本中10本と、動物愛護ふれあいセンターの38本中2本。地盤の強度を測る「電流計」とセメント利用量を量る「流量計」のデータが流用された。いずれも建物の安全性に問題はないという。
同社によると、この2件では、地中に穴を掘りながらセメントを流し込んだ上で鋼管を差し込む「摩擦くい」を使用。マンションだけでなく、工場や学校、鉄塔、耐震補強など幅広い工事を対象に、強固な地盤である「支持層」がないような軟らかい地盤で採用されている。
同社は平成14年7月以降、全国で約6千件の同種の摩擦くいの施工実績があり、同様の調査をすれば、全容解明にさらに時間がかかることになる。同社は2件の流用を認め、「理由は調査中。既製コンクリートくいの調査結果を国交省に報告する24日以降に、摩擦くいの調査をするかどうかを検討する」とした。
業界団体のコンクリートパイル建設技術協会の会員や役員は業界の会社の役員や社長なので動きは遅いであろう。外部の専門家や大学教授が役員としていたとしても、 「YES MAN」か何も言わない人達がなっていると思うから、たぶん、形だけかも?
杭(くい)打ち工事の業界団体は、会員各社がおよそ2400件について自主点検を終えたと発表しましたが、業界団体としてデータの改ざんがあったのかどうかは調査していないと説明しました。
杭打ちの業界団体である「コンクリートパイル建設技術協会」は会見を開き、データの改ざんについて会員である39社がおよそ2400件の自主点検を終えたと発表しました。
ただ、データ改ざんがあったのかどうかは明らかにせず、協会の会長を務めるジャパンパイルの黒瀬社長は「データの不正については個別の企業に対応してもらうしかなく、協会が踏み込んで尋ねるのは難しい」と説明しました。
一方、国土交通省はコンクリートパイル建設技術協会に対して、27日時点での会員による自主点検の結果を報告するよう指示しました。
また、杭打ち業界大手の「ジャパンパイル」は、既に発表していた6件のデータ改ざんに加えて、新たに1件、徳島県の病院でもデータ改ざんがあったことを認め、ジャパンパイルによる改ざんは合わせて7件になったと明らかにしました。改ざんに関与した現場の施工管理者などは7件それぞれ別で、現時点で7人が関与していたということです。
杭(くい)打ちデータの改ざんが広がっている問題で、業界団体のコンクリートパイル建設技術協会は19日、正会員約40社が自主点検した工事データの集計結果を国土交通省に報告した。元請け会社などから調査依頼があったうちの約2割にあたる約2400件を点検したとするが、協会としてはデータ流用の有無は把握していないと説明した。
協会の黒瀬晃会長(ジャパンパイル社長)は都内で開いた記者会見で「信頼を損ね、安心への願いを踏みにじる行為で心からおわび申し上げる」と陳謝した。
加盟社は手がけた案件のうち、元請け会社から調査の要請があった杭打ち工事のデータの流用の有無を調べているとみられる。ただ黒瀬会長は「協会は情報を集める立場になく踏み込んだ調査は難しい。各社や当局に対応いただくしかない」と述べ、協会としてデータ流用の有無の全容を把握していないと説明した。
自主点検の予定件数が約1万件と最も多いジャパンパイルは、約1千件の点検を済ませた。黒瀬氏はジャパンパイルが杭を打った徳島県の病院でも流用が新たに判明したと説明。データ流用は1件増え計7件になった。それぞれ別の人物が担当していた。他社でも流用があるかとの質問に黒瀬氏は「あるだろうが断定できない」と答えた。
逮捕されても、有罪になるの?処分保留とか、不起訴とかになりそう。
発売前の日本のマンガ作品が海外向け海賊版サイトに不正公開された事件で、京都府警は18日、新たに中国人2人を著作権法違反容疑で逮捕した。
捜査関係者への取材でわかった。この2人が不正公開していたとされるのは、すでに逮捕された中国人3人とは別の海外向け海賊版サイトで、府警は、こうした中国人グループが国内に複数ある可能性があるとみて解明を急ぐ。
捜査関係者によると、中国人2人は先月、「週刊少年マガジン」(講談社)に連載中の人気作「七つの大罪」の最新話を、発売前に海賊版サイトに無断で公開し、著作権を侵害した疑い。
府警は、2人が、人気マンガ「ONE PIECE(ワンピース)」を無断公開したとされる中国人3人(今月12~13日に著作権法違反容疑で逮捕)と同様に、埼玉県の配送会社社員・日高武久容疑者(69)(13日に同容疑で逮捕)から掲載雑誌を入手したとみている。
公共事業が減り人員整理が終了した後に復興で仕事が増えても、急には人は増やせないし、人は育たない。たぶん、人材不足とャスダック上場の測量会社、川崎地質(東京)の
企業倫理に問題があってこのような結果となったのであろう。
「国土交通省の外郭団体、土木研究センターの了戒公利部長は『素人の設計で、作業員にも危険が及ぶ』と問題視した。」
事実であれば測量会社、川崎地質(東京)を一定期間、入札への参加を禁止すれべ良い。
福島県楢葉町の除染作業をめぐる違法派遣事件では、3次下請けの泉友(青森県大間町)が、自社の従業員2人と下北地方などの7建設業者の従業員16人を2次下請けのジェイテック(東京)に派遣していた。
職業安定法は、自社と雇用関係のない労働者を第三者の指揮命令の下で働かせる労働者供給事業を禁止しているが、捜査関係者によると、泉友はジェイテックに人集めを依頼されていたという。
青森県内では東日本大震災以降、原発関連の工事が凍結され、受注数が減少。青森県建設業協会は「下請けの小規模業者が仕事を求めて除染作業に行かざるを得なくなったのでは」と推測する。
福島労働局の調査では、除染作業に携わる342業者のうち7割近い233業者で賃金不払いなどの法令違反が計364件見つかるなど、ずさんな雇用実態が明らかになっている。
同労働局は元請け業者18社を対象に今月、福島市で説明会を開き、違法派遣に関して楢葉町の事件を示し、派遣と請負の違いを解説し注意を呼び掛けた。
また、法令順守のためのチェックリストを初めて作成。賃金や労働時間、放射線量管理などを下請け、元請け業者の2重チェックで確認する。同労働局の担当者は「法令を守り労働者が安全に働けるよう、元請け業者を通じて下請け業者に周知徹底を図っている」と話す。
適切に対応しないと行政は面目を失うであろう。
杭打ちデータの流用問題の拡大を受け、国土交通省の有識者委員会は16日、旭化成建材以外の業者にも調査を広げる必要性を確認した。
データ流用を報告した「ジャパンパイル」(東京都中央区)以外の杭打ち大手も独自に調査を始めた。業界には中小の杭打ち業者も多く、国交省は対応に苦慮している。
ジャパンパイルは16日、過去5年間の全工事についてデータ流用の有無を調べると発表した。ジャパンパイルは建物などで使われるコンクリート杭の出荷量でシェア(占有率)2位を占め、黒瀬晃社長は業界団体の会長も務めるだけに衝撃が大きい。対象は約1万件に上り、調査には半年程度かかる見通しという。
ジャパンパイルの流用は、元請けのゼネコン各社が旭化成建材の問題を受けて自主的に始めた調査により明らかになった。業界首位の三谷セキサン(福井市)や3位の日本コンクリート工業(東京都港区)も元請けから同じ調査を求められている。日本コンクリートは「今週中にもメドをつけたい」という。
取引先に架空発注を繰り返したとして、警視庁は16日、「服部栄養専門学校」を運営する学校法人服部学園(東京都渋谷区)の元総務部長染谷吉彦容疑者(43)(新宿区西新宿)を背任容疑で逮捕した。
同庁は、染谷容疑者が今年3月までの約3年間に総額数千万円の架空発注を繰り返し、取引先からバックさせた現金を使い込んでいたとみている。
発表によると、染谷容疑者は2012年4月~15年3月、計十数回にわたり、都内の広告関連会社2社に架空の広告・宣伝業務を発注し、同学園に計約1100万円の損害を与えた疑い。バックさせた現金は、宝くじの購入などに充てていたという。調べに対し「間違いない」と容疑を認めている。
染谷容疑者は、テレビなどで活躍する同学園理事長の服部幸應ゆきおさん(69)の長男。
問題がパンドラの箱だったと言う事だろう。だから、一旦、箱が空いてしまうと収拾が付かないほどの問題が明らかになってしまう。
杭打ちデータの流用問題の広がりを受け、石井国土交通相は15日、旭化成建材以外の杭打ち工事を行う企業を対象に、調査拡大を検討していく考えを示した。
傾きが見つかった横浜市のマンションに関わった旭化成建材に加え、杭打ち大手「ジャパンパイル」(東京都中央区)でも流用が発覚した。石井氏は記者団に対し「(旭化成建材の)事案を調査して、再発防止策を講じる。その中で他の業者にもどう対応するかを検討する」と述べた。
有識者らをメンバーに設置した「基礎ぐい工事問題に関する対策委員会」は16日に第2回会合を開催する。国交省はジャパンパイルから同日中にデータ流用した18件の詳細な報告を受けた上で委員会の中で対応策を協議する予定だ。
運が悪い。杭打ちデータ改善問題が多くメディアに取り上げられていなければ、建築確認取り消しはなかったかもしれない。
規則を満足していなくとも建築確認を受けるケースがあるからだ。
「民間の指定検査会社、都市居住評価センター(東京都港区)から2012年7月に建築確認を受け、さらに14年3月に変更した計画について改めて確認を受けた。」
損失や損害に関してNIPPO(東京都中央区)、神鋼不動産(神戸市)及び民間の指定検査会社、都市居住評価センター(東京都港区)で話し合うのだろうか、
それとも裁判で争うのだろうか?
東京都文京区小石川2丁目に建設中の分譲マンション(地上8階・地下2階、総戸数107戸)について、都建築審査会が避難設備の不備を理由に建築確認を取り消す裁決をした。建築主が不備を改めて建築確認を受け直す場合、区が新たに高さ制限を設けたため、2階分の減築を迫られる可能性がある。建物はほぼ完成し販売も終了している。
建築主は、NIPPO(東京都中央区)と神鋼不動産(神戸市)。民間の指定検査会社、都市居住評価センター(東京都港区)から2012年7月に建築確認を受け、さらに14年3月に変更した計画について改めて確認を受けた。これに対して、周辺住民9人が街の景観に合わないことや安全基準を満たしてない恐れがあるとして、建築確認の取り消しを求めて審査を請求していた。
裁決書の送付は12日付。法令上、マンションでは火災や災害時に屋外に出られる避難階を設ける必要があり、審査では1階の大型駐車場が避難階と認められるかが争われた。建築審査会は、駐車場と地上との高低差が2・5メートルもあり、直接の通路が車用のスロープしかないことなどから、「避難時に有効に機能するとは認められない」と指摘。避難階段などの設置を求めた都建築安全条例違反と判断した。
旭化成建材や杭打ち大手「ジャパンパイル」がこのありさまでは小規模の会社で経営者が儲けが少なくても手抜きをしない方針の会社以外では、同じような
問題を抱えているのでは?
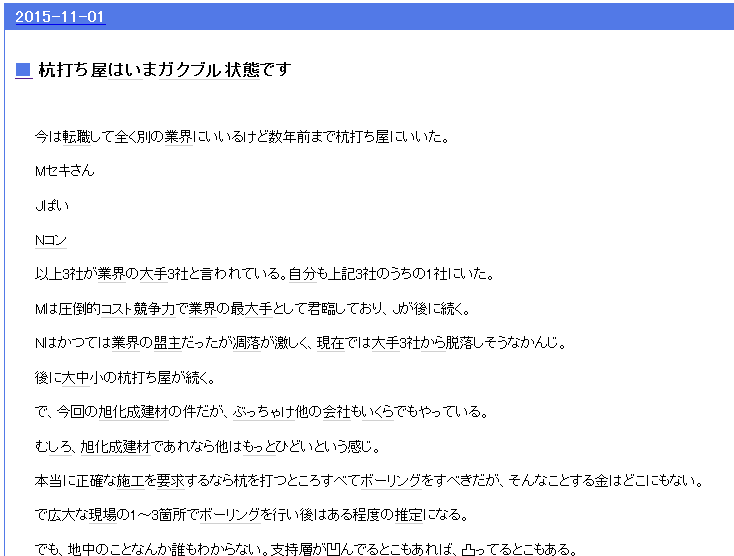
マンション傾斜問題から学ぶ建設業の限界。 11/13/15(実験スピリッツ)
BSフジLIVEプライムニュース. 「データ改ざん全容判明マンション不正の実態くい打ち現場で何が? を見たけどゲストの人達は上記についてもっと知っておくべきでは?
旭化成建材で杭(くい)のデータ改ざんや流用が相次いで発覚しているが、データ流用が別の会社でも行われていたことが日本テレビの取材で初めて明らかになった。
データの流用を行っていたのは、東京・中央区の杭打ち会社大手のジャパンパイル株式会社で、過去5年余りの少なくとも18件の工事で流用が見つかった。日本テレビが入手したそのうち1件の施工報告書では、異なる2本の杭の電流値の波形が完全に一致していて、データが流用されていたことがわかる。
ジャパンパイルは取材に対し、流用した18件のうち2件は資料作成時のミスだったが、16件は機器の不具合などでデータが取れず、故意にデータを流用したと認めた上で、「再発防止策を検討する」としている。
一方、報告を受けた国土交通省はジャパンパイルに対し、流用の詳細や理由などさらに詳しい報告を求めた。旭化成建材以外の会社でもデータ流用が発覚したことで、問題は業界全体に拡大する見通し。
横浜市のマンションに端を発したくい打ちデータ偽装問題は13日、旭化成建材の施工分だけで、50人以上の現場管理者が不正に関わり、少なくとも266件で偽装が行われていたことが判明した。すでに各地の自治体では旭化成側の公表前に独自調査を実施。いずれも安全性に問題ないとしているが、確認するデータ自体が偽装されているだけに、「暫定的な判断だ」との指摘も。自治体からは「詳細な情報が足りない」と不満の声が上がった。
データ偽装が全国最多の51件に及んだ東京都。旭化成建材が都内で手がけた354件のうち、今回判明した分だけでも約15%の物件で偽装が行われたことになる。都の担当者は「かなりの数は出るだろうと覚悟はしていたが、これほどとは」と驚きを隠さない。その一方で、これまでの都の独自調査で偽装が確認された都立学校や都営住宅など都有7施設では、建物の傾きなど不具合は見つかっていないことから、「提出書類に手を加えただけで、工事自体には手抜きのないケースも十分あり得る」との見方も示す。
都では、民間の物件で偽装が見つかった場合は元請け業者と連絡を取り合いながら安全性の確認を進める手順となっているが、「現時点では物件名や元請け業者が分からない以上、対応のしようがない」(担当者)。国土交通省が物件リストをまとめるのを待って対応する方針だ。
26件の偽装が判明した北海道は担当者が急遽(きゅうきょ)、記者会見を開き「これまで道が確認した結果とかけ離れている」と不満を漏らした。
道によると、この日の旭化成建材の発表直後、担当者にリストがメールで送られてきた。これまでの道の独自調査に対して同社側は道発注の工事で7件の偽装があったことを認めていたが、今回のリストにはそのうちの2件しか含まれていなかった。同社札幌支店は道の問い合わせに「本社に(7件全てについて)報告していた」と説明し、同社のコンピューター上のトラブルで集計漏れになった可能性を示したという。
30件の偽装が確認された神奈川県建築安全課の担当者は「医療・福祉施設もあるので早く詳細が知りたい」と訴えた。一方、都道府県別の件数発表だったため、市町村は自分の自治体で何件の偽装があったかを把握できない状況になった。発端となったマンションがある横浜市の担当者も発表直後、「何の情報もない。詳しい情報がどこから来るかも分からないので待機しているしかない」とお手上げ状態だった。
2日の会見で偽装が確認されたと発表された19件のうち、14件を占めていた愛知県では、今回7件が上積みされて計21件に。担当者は「前回多かったので、ある程度は覚悟していた」と冷静に受け止めたが、旭化成建材の調査が終わっていないことについては「遅すぎる」と批判した。
旭化成建材による杭工事データ偽装問題で、同社が過去10年間で杭を打った工事3040件のうちデータ偽装がさらに数十件増え、計三百数十件に上ることが関係者への取材で分かった。同社は13日午後、国土交通省に調査結果を報告し、記者会見して発表する。
関係者によると、社内調査により約300件でデータ偽装を確認した。その後、同様に偽装の有無について調べている元請けのゼネコンと調査結果を突き合わせたところ、件数が増えたという。これまでに、横浜市都筑区の大型マンション以外には傾くなど不具合の報告はないという。
同社は調査している3040件について、報告期限の13日までに数百件で元請けとの照合が間に合わず、さらに約180件は元請けの倒産などで連絡が付かず調査に着手できていない。
学校や病院など公共性の高い施設は、優先的に調査し、13日より前に国交省に報告するよう指示を受けていたが出来ず、ほかの物件と一緒の公表になった。石井啓一国交相は13日の閣議後会見で、「遺憾である」と述べた。
「違反した場合、国などは指示や営業停止などの監督処分、罰金100万円を科すことができる。」
罰金が100万円で済むのであればその方がお徳であろう。今回のように問題が大きくなる確立は非常に低いと思われる。
横浜市都筑区のマンションが傾いている問題で、くい打ち施工の1次下請けだった日立ハイテクノロジーズが、建設業法で定める専任の主任技術者を配置していなかった疑いがあることが11日、分かった。元請けの三井住友建設の永本芳生副社長が「(日立ハイテクの人物は)現場にいなかった」と明かした。国土交通省は日立ハイテクによる施工管理の実態を調査している。
問題のくい打ち施工では、施工不良やデータ偽装を行った旭化成建材が2次下請けとなっていた。
永本副社長は11日の決算説明会で、三井住友建設が施工当時、日立ハイテクを介さず「旭化成建材の工事内容を直接管理した」と説明。「日立ハイテクは現場にいたか」と問われ「いなかったと思う」と答えた。
建設業法は、建設業者が工事を請け負う際、現場に有資格の主任技術者を専任で置くことを義務づけている。違反した場合、国などは指示や営業停止などの監督処分、罰金100万円を科すことができる。
国交省は日立ハイテクについて「工程やデータの管理をすべき立場」とみて、当時の業務内容について報告を求めている。同社はこれまでの産経新聞の取材に、「(勤務実態などは)調査中」としていた。
杭(くい)打ち工事のデータ改ざんについて旭化成と子会社の旭化成建材(東京・千代田)は13日、都内で記者会見した。一問一答は以下の通り。
――担当者への聞き取りの結果は。
旭化成の柿沢信行執行役員「流用の理由として『データを紛失』『スイッチを入れ忘れた』『報告書の体裁を整えるため』と述べている」
――50人以上がそれぞれ個人で思いつきデータを流用したのですか。誰かが指南したのですか。
柿沢執行役員「考えついたという発言はない。1、2件だけ流用していたという人が大半。誰かが教えたということについては調査の重点としてやっている」
――元請けからのプレッシャーは。
柿沢執行役員「聞き取りの中で特に工期やプレッシャーについての発言は出ていない」
――経営責任についてはどう考えますか。
旭化成の平居正仁副社長「原因分析調査をきちんとして、何が起きたのかをはっきりさせて厳正に対処する。経営責任はいずれかの形ではっきりさせる」
――横浜の傾斜マンションでの杭の調査は。
平居副社長「担当者は支持層に届いたと証言している。三井住友建設に是非、調べさせてほしいと言っている。粘り強くお願いするとともに、杭の調査について元請けが壁になるとすれば、マンションの管理組合に働きかけることも検討しないといけない」
――1次下請けの日立ハイテクノロジーズに責任はなかったのですか。
平居副社長「三井住友建設に現場の監督責任があり、日立ハイテクは旭化成建材の管理責任を負っている。旭化成建材は自社の下請けの管理責任は負っているが、(日立ハイテクの)管理の実態についてコメントする立場にはない」
――杭打ち事業から撤退する可能性は。
平居副社長「現在は全く検討していない。旭化成建材の杭が信用できないなら結果として考えなければならないが今は議論をしていない」
――旭化成の他の事業やブランドへの影響は。
平居副社長「ブランドに大きく傷がついたが数値化できるものではない。回復のため信頼を積み上げていく」
東芝は冬の時代に突入?
東芝は12日、子会社の米原子力発電会社ウェスチングハウス(WH)で原発建設などが思うように進まず、2012、13年度の2年間に計約13億ドル(現在のレートで約1600億円)の巨額損失を計上していたことを初めて明らかにした。
その結果、WH単体は両年度とも税引き後利益が赤字になっていた。これまで具体的な情報を開示しておらず、むしろ事業が順調に進んでいるように説明してきた。投資家にとって重要な情報を開示してこなかった東芝の姿勢が改めて問われそうだ。
東芝は、約7年間で2000億円を超える不適切な会計処理が発覚し、歴代3社長らが辞任に追い込まれた。複数の関係者によると、一連の問題を調べた弁護士らで作る第三者委員会でも、WHの損失の存在を把握し、問題視する声もあった。しかし、東芝がWHの損失を調査の対象外としたことから、第三者委の報告書に盛り込まれなかった。
WHは11年の東日本大震災の影響で、原発の新規建設や受注が滞り、業績が悪化していたという。こうした場合、WHの原発建設事業などの価値が大きく下がるため、その分を損失(減損)として計上する必要がある。東芝は、WHが12年度に約9億ドル(約1100億円)、13年度に約4億ドル(約490億円)の減損処理をしたが、連結決算では減損を計上していなかった。
自業自得か?
インターネットを通じた向精神薬の密売事件で、兵庫県警は12日、奈良市法華寺町、薬剤師、河原康平容疑者(40)を麻薬取締法違反(営利目的譲渡)の疑いで逮捕した。県警は、河原容疑者が薬剤師の立場を悪用し、向精神薬をネットで大量に横流ししていたとみて追及する。
捜査関係者によると、河原容疑者は今年1月、東京都世田谷区のマンション経営、小岩井由香被告(55)=麻薬特例法違反罪などで起訴=に、向精神薬数十錠を計数千円で売り渡した疑いが持たれている。
小岩井被告はネットを通じて向精神薬を全国の約120人に転売し、計約2200万円の利益を得ていたとされ、河原容疑者が主な仕入れ元だったという。
県警が6月に小岩井被告を麻薬取締法違反容疑で逮捕し、口座やネットの記録から河原容疑者が浮かんだ。
河原容疑者はネットを通じて知り合った小岩井被告に向精神薬の転売を繰り返し、計数百万円を得ていたとみられる。河原容疑者宅の家宅捜索で、睡眠導入剤や抗うつ剤など約1万錠が見つかったという。
河原容疑者は奈良市内の調剤薬局に勤めていたが、英国から危険ドラッグの原料となる粉末を輸入するなどしたとして、今年2〜4月に医薬品医療機器法違反罪などで逮捕・起訴された。現在は別の薬局で働いているという。【宮嶋梓帆、五十嵐朋子】
元最高検総務部長で横浜弁護士会所属の中津川彰弁護士(80)が、弁護を担当した刑事事件の容疑者の妻を連れて検察トップの検事総長らと面会していたことが分かった。
同弁護士会は、刑事処分の公正さに疑惑を抱かせたなどとして、中津川弁護士を戒告の懲戒処分とした。処分は7月8日付。
同弁護士会などによると、中津川弁護士は2013年6月、強制わいせつ容疑で逮捕された男性の弁護を担当。男性の勾留期間中、男性の妻とともに、当時の捜査担当検察官やその上司、検事総長らと面会した。同弁護士会は、中津川弁護士が検察当局に対し、何らかの働きかけをしたかどうかは明らかにしていないが、「元検察官としてのキャリアや人脈などを強く印象付け、刑事処分の公正さに疑惑を抱かせた」と判断した。
医療機関の診療報酬請求権を債券化した金融商品(レセプト債)の発行元ファンドが破綻した問題で、証券取引等監視委員会が債券を販売した全国7証券の検査に乗り出したことが、関係者の話でわかった。
監視委はすでにアーツ証券(東京)など3社の検査を始めており、残り4社の検査にも近く着手。証券各社が、債務が超過していたファンドの状況を顧客にどう説明していたのか詳しく調べる。
ファンドを管理していた「オプティファクター」(同)などによると、レセプト債の発行残高は約227億円。延べ3000の個人・法人に販売されたとみられ、ジャスダック上場の商品先物取引会社「フジトミ」(同)は10日、1億円分保有していることを明かし、「償還不能になる恐れが生じた」と発表した。
今回のコメントで会社のスタンスが明らかになった。顧客がどのようにメッセージを受け取り、判断するか次第。
下請けとして仕事をする以上、このようなサイクルから抜け出す事は難しい。良い発注者から仕事をもらえるように努力するのか、
運を天に任せるのか、流れに任せて流されるままなのか、判断は難しい。
横浜市のマンションが傾いている問題で、建設を担当した三井住友建設が記者会見を行いました。
「協力業者の施工において行われた杭工事の不具合、およびデータの流用・転用を元請けとして見抜けなかったことは、誠に慚愧の至りであります」
三井住友建設は杭の不具合やデータの流用が見抜けなかったことに元請けとしての責任はあるとしながらも、「日々の管理体制に落ち度が無かった」と述べました。
また、監督者として現場に立ち会うべきだったのではとの質問に、旭化成建材を信頼していたと述べ、立ち会う必要はなかったとの認識を示しました。
一方で、三井住友建設が設計した杭が、固い地盤に届くには2メートルほど短かったことについて記者から設計ミスだったのではないかとの指摘については・・・
「設計ミスと言われるのはちょっと・・・、私どもと施工業者の間では杭を打ち込んでくださいという契約」
杭打ち工事の段階で、旭化成建材が固い地盤に届いていないことを伝えてくれれば、問題はおきなかったと話しました。
やはり体質の問題?人間でも同じだけど、考え方や価値観など変えるのは簡単ではない。
約5500件の医薬品の副作用情報を国に報告するのが遅れたとして、厚生労働省が製薬会社「ノバルティスファーマ」(東京都港区)に対し、医薬品医療機器法(旧薬事法)に基づいて業務改善命令を出す方針を固めたことが分かった。同社が副作用の報告遅れで行政処分を受けるのは3回目。
製薬会社が製造・販売する医薬品で副作用があった場合は、期限内に国に届け出なければならない。関係者によると、今年1月に国に副作用情報を報告する社内システムに障害が起き、情報が送れなくなったという。報告遅れによる新たな健康被害は出ていない。
同社広報部は「現時点でコメントは差し控えたい」としている。【古関俊樹】
公務員の検査に問題があるのは知っている。上手くやったほうが得なのだ!
秋田県の肥料メーカー「太平物産」が成分表示を偽装していた問題で、森山農林水産大臣は、太平物産が農水省の検査対象から問題の肥料を外していたことを明らかにしました。
森山農水大臣:「問題のあった有機肥料については(調査の)リストから外されていた」
農水省は通常、肥料メーカーに対して通告なしで検査を行っていますが、大平物産は2009年以降、8回の検査で提出リストに偽装が発覚した有機肥料を記載していなかったということです。このため、森山大臣は今後、通常検査の在り方も検討する考えを示しました。また、大平物産に対しては現在も農水省が立ち入り検査を行っていて、来週中には結論を出す方針です。
日本オリンピック委員会(JOC)関係者まで闇社会と繋がっているのか?表ではオリンピックは国民に勇気を与えるとか言ってお金をじゃんじゃん使い、国民に負担をさせ、 いい思いは自分達と闇社会の関係者か?
日本大学の男性名誉教授(77)が指定暴力団山口組系元組幹部の男性から2000万円を借り入れていた問題で、名誉教授が2008年5月に元幹部らと会食した場に、日本オリンピック委員会(JOC)関係者の男性が同席していた疑いが浮上した。元幹部は13年に埼玉県内の男性を相手に借金返済を求める訴訟をさいたま地裁越谷支部に起こしており、証人として出廷した名誉教授が裁判所に提出した手書きのメモにJOC関係者と元幹部が面会していたことを示す記述があった。【和田浩幸】
裁判記録のメモによると、名誉教授が当時現役の組長だった元幹部と会食した際、JOC関係者の男性も別件で元幹部と面会。投資の相談をするために集まった名誉教授ら7人とJOC関係者ら2人が合流して料理店やクラブで飲食したことが書かれていた。JOCは事実関係について情報収集している。
名誉教授は約10年前に元幹部から2000万円を借り入れたといい、日本大学は10日に調査委員会を開き、名誉教授から改めて事情を聴く。
名誉教授は08年に退職後、非常勤講師として講義を受け持っていた。大学側が6日に事情を聴いたところ、名誉教授は元幹部について「二十数年前に知人の紹介で知り合った。たまに会うくらい」と説明。名誉教授は民事裁判で昨年8月に証人として出廷し、元幹部から海外での事業資金名目で2000万円を借りていることを明らかにしていた。大学によると、名誉教授は今も返済していないという。
大学は名誉教授が担当している大学院の授業を休講にした。
◇
暴力団関係者など反社会勢力との交際は、過去にもスポーツ界や芸能界など幅広い分野でしばしば問題になってきた。
スポーツ界では2013年、日本プロゴルフ協会の副会長や理事が指定暴力団の会長とゴルフや会食をしていたことが発覚し、協会の会長を含む代議員全員が辞職した。09年には、同年7月の名古屋場所で土俵下の維持員席で暴力団関係者が観戦していたことが毎日新聞の報道で表面化した。日本相撲協会は10年、入場整理券の手配に関与した親方2人を処分した。
芸能界では11年、人気タレントの島田紳助さんが暴力団関係者との親密な交際関係があったとして、芸能活動から引退することを表明した。政界では12年、当時の田中慶秋法相が、かつて暴力団関係者の宴会に出席したことなどを指摘され、体調不良を理由に法相を辞任している。
教育関係では14年、指定暴力団山口組弘道会の関係者と過去に交際していたとして、進学塾大手「名進研」を運営する「教育企画」(名古屋市)の代表が辞任した。元代表は弘道会の資金源とされる風俗店グループの実質的経営者に約3億円を融資したという。【太田誠一】
懲戒免職?
日本郵便四国支社は9日、香川県観音寺市の観音寺郵便局の女性社員(23)が、担当した高瀬郵便局(同県三豊市)の郵便物約2万9千通を配達せず自宅などに隠していたと発表した。隠していたのは2013年12月から15年11月7日までで、捨てた郵便物はないという。四国支社によると女性社員は「仕事のやる気がなくなって隠匿した」と話しているという。
大企業の社員なのだからリスクを考えたほうが良いと思う。まあ、個々の判断なので個人の自由。
中学3年の少女を買春したとして、警視庁石神井署は9日、三菱東京UFJ銀行員の新倉達也容疑者(26)=東京都品川区荏原6丁目=を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕し、発表した。「お金を払ってセックスはしたが18歳未満とは気づかなかった」と容疑を否認しているという。
署によると、新倉容疑者は2月22日ごろ、東京都北区内のマンションの一室で、18歳未満と知りながら、当時15歳の少女に現金8千円を渡し、性交した疑いがある。2人は出会い系アプリを通じて2月上旬に知り合ったといい、少女が友人に頼んで部屋を借りていたという。
どう繋がったのだろう。日本大学の名誉教授と指定暴力団山口組の元幹部の接点はいつ、どこから始まったのか?2000万円のお金を正規のルートで借りる事が 出来なかったのか?それとも、2000万円を貰ったが、認めるわけにはいかないので、借りている事にしたのだろうか?
日本大学の名誉教授が指定暴力団山口組の元幹部から海外での投資に充てる資金として2000万円を借り、今も返済していないことが、NHKの取材で分かりました。日本大学は「教育に携わる立場にもかかわらず極めて遺憾だ」として、名誉教授が担当している大学院の授業を休講にするとともに内部調査を進めています。
これは、金銭トラブルを巡って山口組のナンバー3だった元暴力団組長がさいたま地裁越谷支部に起こした民事裁判の中で明らかになったものです。
NHKが入手した裁判記録によりますと、日本大学の77歳の名誉教授は、去年8月、この裁判に元組長側の証人として出廷し、10年ほど前、海外での投資に充てる資金として、当時、現役だった元組長から2000万円を借りたと証言していました。
名誉教授は取材に対し、金を借りた相手が山口組の幹部だと認識していたとしたうえで、「日頃からつきあいがあり、軽い気持ちで借りた。これまで返済を求められていないので借りたままだが、そのうち返すつもりだ。反社会的勢力だからすべてが悪いというのはおかしいと思う」と説明しています。
名誉教授は現在、大学院法学研究科で英米法などの授業を担当しているほか、総務省の委託を受けて国の機関に対する国民の苦情や相談に応じる行政相談委員の東京の協議会会長も務めています。
日本大学は、本人への聞き取りで元組長からの借金が確認できたとして、9日までに大学院で担当している授業を休講にする措置を取りました。そのうえで、内部調査を進めることにしていて、「大学で教育に携わる立場にもかかわらず暴力団関係者と交際していたことは極めて遺憾だ。さらに詳細に事実関係を確認し、厳格に対応していきたい」としています。
山口組元幹部とは
日本大学の名誉教授に2000万円を貸していたのは西日本に本部を置く山口組系暴力団の初代の組長で、現在82歳です。関係者によりますと、現役当時は資金力が強く、企業経営者などを集めて不動産取引や投資話の会合を頻繁に開く「経済ヤクザ」として知られた存在だということです。また、警察関係者によりますと、山口組の組織内では、5代目組長の時代に「中四国・九州ブロック長」を、平成17年に6代目組長の体制になって以降は「組長」「若頭」に次ぐナンバー3の「顧問」を務め、3年前、高齢を理由に引退しました。
NHKが入手した裁判記録には
NHKが入手した裁判記録には、日本大学の名誉教授が山口組の幹部だった元暴力団組長から2000万円を借りた経緯などが詳しく書かれています。
去年8月に行われた証人尋問で、名誉教授は『元組長からお金を借りたことはありますか』と弁護士から質問され、『あります。2000万円』と答えたうえで、「海外の案件なんです。お借りしてその経費として使わせていただいた」と述べ、投資目的の借金だったとしています。
また、借りた時期について、裁判官から『10年以上前ですか』と尋ねられると、『そのくらいになります』と答え、返済については『まだ具体的に始まっているわけではない』と述べて、全く返済しないまま借り続けていることを明らかにしました。
さらに、借用書について、『私から進んでお金を借りる以上、いくら友人の間でもきちんとしておきたいと申し上げ、みずから書きました』と説明していました。
裁判記録では、元組長が裁判の原因になった別の投資話を知人に持ちかけられた場に名誉教授が同席していたとされ、この理由について、元組長は法廷で『私より知識が高いと思っているから。名誉教授の肩書きから言ってもそうなので立ち会ってもらった』と証言していました。
「佐々木社長は『全農の調査で発覚するまで、知らなかった。会社として偽装の指示はなかった』と釈明し、偽装は各工場の歴代の工場長の判断だったとの見方を示した。動機については『原料原価の低減のためと推測される』と説明した。」
上記が事実であればすごい。どう教育すれば、全ての工場長が個人の判断と責任で偽装を行うようになるのだろう。人事の選択や方針、又は、組織の環境でそのようになるのだろうか?
偽装自体が、マニュアルがない状態で口頭で引き継がれたと言う事か?どの工場長も偽装をやめようとは思わなかったし、将来、工場長となる部下も疑問や葛藤を経験せずに
工場長となり、偽装を引き継いだのだろうか?
農水省は調査により、原因、工場長や将来の工場長候補がどのように判断し、関与したのか、解明して公表してほしい。心理学的にも興味深い。
秋田市の肥料メーカー「太平物産」の肥料の成分表示に偽装があった問題で、同社の佐々木勝美社長が9日、記者会見し「偽装は10年以上前から続いていた」と明らかにし、辞任する意向を示した。同社の肥料を使った場合、特別栽培米や有機米として販売できなくなる恐れがあるという。
肥料の成分表示、秋田のメーカーが偽装
佐々木社長によると、有機成分が5割と表示しているのに、2割しか入っていなかった肥料もあった。佐々木社長は「全農の調査で発覚するまで、知らなかった。会社として偽装の指示はなかった」と釈明し、偽装は各工場の歴代の工場長の判断だったとの見方を示した。動機については「原料原価の低減のためと推測される」と説明した。
この問題では、同社の青森、秋田、茨城、群馬県の4工場で製造されていた大半の678銘柄で、肥料袋の記載内容と実際の中身が異なっており、同社の全商品が出荷停止になっている。
社長が辞めるだけで収拾できるのか?
秋田市の肥料メーカー「太平物産」が有機肥料の成分表示を偽装していた問題で、同社の佐々木勝美社長が9日、市内で記者会見した。「信頼を裏切り深くおわびする」と謝罪し、少なくとも10年以上前から偽装があった可能性があることを明らかにした。
問題発覚後、佐々木社長が公式の場で発言するのは初めて。成分表示の偽装が盛り込まれた「製造指示書」が各工場で代々引き継がれ、10年以上前の指示書を使っていた工場もあったといい、佐々木社長は「組織ぐるみと思われても仕方がない」と述べた。
ただ、「偽装は本社の指示に基づいたものではない。自分も知らなかった」とし、本社の関与は否定。偽装の背景について「原価を低減させるためと考えられる」と話した。
農林水産省が9日までに国内4工場の立ち入り検査を行ったことも明らかにし、農水省の調査に一定の区切りがつけば社長を退く考えも示した。
販売元の全国農業協同組合連合会(JA全農)によると、同社が製造する有機肥料など783銘柄の約9割は、有機原料の配合の割合の偽装や記載以外の原料の使用などがあった。JA全農は、東日本の11県で販売した肥料約1万トンを回収するとしている。【池田一生、松本紫帆】
中国はやはりあぶないと考えたほうが良いと言うことか?
中国のバイドゥ(百度)が提供するAndroid用アプリに重大なセキュリティ上の問題が発覚。その影響範囲の広さから衝撃が走っている。この問題への対処は可能だが、感染経路などを考えると、今後の影響は広範囲に及ぶ可能性がある。
問題が見つかったのはバイドゥが提供しているAndroidアプリ開発キット(アプリ開発を容易にする部品集)の「Moplus」だ。Moplusは、特に中国で開発されているAndroid用アプリに多数採用されている。影響範囲が広い理由の一つは、開発キット自身がセキュリティ問題を抱えているため、それを使って作成されたアプリにも同様の問題が存在している可能性を否定できないためだ。
■ バイドゥには前科
バイドゥがセキュリティ問題を引き起こしたのは今回が初めてではない。日本語かな漢字変換ソフト「simeji」に、入力した文字列をバイドゥのサーバーにアップロードする機能が備わっていることが発覚。自治体などが業務に使用していた例もあって大きな問題となった。
しかし今回の衝撃はもっと大きい。Moplusには”バックドア”と呼ばれる、侵入口を勝手に開いてしまう機能が備わっていたのだ。Moplusを使ったアプリを使うと、使用している端末にバックドアが仕掛けられてしまう。さらに、仕掛けたバックドアを使って簡単に端末を遠隔操作する機能まで有している。
そのような機能を備えた開発キットを、中国を代表するネット企業と言えるバイドゥが作り大々的に配布。数多くのアプリ開発業者が利用していたからこそ”衝撃”が走ったのだ。
Moplusに深刻な脆弱性があると指摘されたのは、10月21日のこと。Moplusを使ったアプリケーションを動かすと、Android端末に”ワームホール”と呼ばれる外部コンピュータから容易に侵入できる穴(一種のバックドア)を作るというものだった。
ところが、11月6日のトレンドマイクロによる報告によると、事情がどうやら違うことがわかってきた。特定機能を実現する上での設計ミスなどに起因した脆弱性ではなく、Moplus自身の機能としてワームホールを作る機能が提供されていたようである。つまり、意図的なものだった可能性が高まっている。 トレンドマイクロがMoplusを使ったふたつのAndroidアプリで確認したところ、いずれのアプリも起動後に自動的にWebサーバーを起動する。このWebサーバーはネットからのアクセスを検出し、外部コンピュータから不正な処理を実行可能にしてしまうのだという。
一度、起動されるとシステムに登録されるため、次回からは端末を起動するだけでワームホールが出現し、いつでも端末に侵入可能な状態になる。
■ 1万4112本のAndroidアプリが使用
悪意を持った者は、このワームホールを使って実に多彩な操作を行うことができる。トレンドマイクロでは、「フィッシングサイトへの誘導」「任意の連絡先の追加」「偽のショート・メッセージ・サービス(SMS)送信」「リモートサーバへのローカルファイルのアップロード」「任意アプリのAndroid端末へのインストール」の5つの例を挙げている。
なお、トレンドマイクロによると1万4112本のアプリがMoplusを用いて開発されており、それらのアプリを実行すると、上記のワームホールが出現する可能性がある。
もうひとつこの問題を深刻なものにしているのは、出口が見えないことだ。
バイドゥは問題の指摘を受け、10月30日の段階でMoplusを更新。新しいMoplusを使って開発されたアプリは、前述のWebサーバが自動起動することはない。しかし、「Moplusを使ったアプリが新しいMoplusを使った新版に更新され、端末上のアプリも更新される」まで、ユーザーの端末上に問題のアプリが残る。
このことと、1万4112本のアプリに疑いがかかっていることを考え合わせると、最新版Moplusを修正しただけでは充分な速度で浄化が進まない事態も想定される。
さらに旧版Moplusを用い、悪意をもって開発された「定期的に見たこともないアプリを何種類も勝手にインストールする」アプリの活動も確認されているというから、さまざまな亜種のワームが次々に降ってくる可能性もある。
中国系デベロッパーが開発するAndroidに手を出さない……と思っても、エンドユーザーが区別することは容易ではない。まして、「Moplusのどのバージョンが・・・」と言われても大多数のユーザーは理解できない。手元の端末を確認したいのであれば、まずはAndroid対応のウィルススキャナーで端末を調査するほかない。グーグルが積極的にアプリストアから、問題のあるMoplusを利用したアプリを削除しなければ、完全な終息までにかなりの時間を要するだろう。
■ グーグルのエコシステム戦略にも影響
今回の問題は、あるいはグーグル自身の戦略にも影響するかもしれない。
グーグルはアプリ流通のエコシステムを健全化させるために、バージョンや端末スペックの細分化問題や、アプリストアの検索性や”おすすめ”機能を中心とした、必要なアプリとの出会いをきちんと作り込む開発に取り組んできた。
一方でAndroid本来が持つ自由なカルチャーが、スマートフォンを用いて自由にアイディアを実現したい開発者にとって魅力的という側面もあり、自由さとのバランスを取りながらAndroidアプリのエコシステム改善が進んできたといえる。
しかし、今回の件はAndroidアプリのエコシステムに小さくない影響を及ぼすだろう。アプリ流通への統制が強いiOSでは、同様の問題はまず起きないと考えられるからだ。もちろん、問題の開発キットを開発したのはバイドゥだが、それを用いた1万4112本のバックドアを作るアプリを流通に載せてしまっているのは、プラットフォーマーであるグーグルなのである。
プラットフォーム・ホルダーとして、どのような対策を講じるのか。グーグルによるプラットフォーム運営の真価が問われる時が来ている。
「関係者によると、メディカル社などは、病院や薬局が健康保険組合側に請求できる診療報酬の権利を買い取り、元利金の支払いに充てる債券を発行。」
破綻したファンド3社と運用会社1社が悪質でないとすれば、実際は診療報酬を受け取る事が出来ない病院や薬局が存在し、その額が少なくとも227億円以上であることに
なる。レセプト債4社が破綻するほど、厚労省を含め、問題が深刻で理解されていない事になる。
レセプト債4社が悪質でない限り、破綻のリスクがあるのにビジネスに関与する事はありえない。まあ、債券を買った投資家達が一番の被害者であろう。
厚労省が問題を理解し、早急に対応する必要があれば行動に移さないと将来、大きな問題となると思う。
病院や薬局が泣くのか、税金で埋め合わせるのか、システムを改善するのか、状況を把握して対応するべきだ。
診療報酬の流動化サービスなど 株式会社オプティファクターなど2社 自己破産を申請 負債105億7900万円 11/07/15(帝国データバンク)
TDB企業コード:981414543
「東京」 (株)オプティファクター(資本金2000万円、東京都品川区西五反田1-1-8、登記面=東京都渋谷区東1-10-9、代表児泉一氏)と関係会社の(株)メディカル・リレーションズ・リミテッド(資本金9800万円、東京都新宿区西新宿6-6-3、同代表、2005年7月設立、診療報酬債権等の売買)は、11月6日に東京地裁へ自己破産を申請したことを明らかにした(メディカル・リレーションズ・リミテッドは同日付で破産手続き開始決定を受けている)。
(株)オプティファクターは、2000年(平成12年)9月に設立され、医療機関向けに診療報酬債権の流動化サービス(資金調達支援)や資産運用に関するコンサルティングなどを展開して事業を拡大。しかし、2013年に創業者が死去したのち、決算書に実態が不明又は実在性の確認できない債権や売り上げが多額に計上されていること、関係会社の3ファンド(メディカル・リレーションズ・リミテッド、メディカル・トレンド・リミテッド、オプティ・メディックス・リミテッド)が有するべき現預金や医療報酬債権等のうち、実在性のあることが確認できた資産の合計額が明らかに僅少であることが判明。現代表は、ファンドの財務状態を改善するため、診療報酬債権等の取得に向けた積極的な営業、社債の利率や手数料の減額等による経費圧縮等、財務状態の健全化に努めたものの、負債の規模が過大であったため(2015年10月現在の3ファンドの発行済債権残高は約227億円)、財務状態を大幅に改善することができない状況が続いていた。
そうしたなか、10月29日に証券取引等監視委員会の調査を受ける事態となり、これ以上社債の新規発行を行うことは困難と判断。起債を行わなければ、その後に償還期限を迎える社債の償還・利払いを継続的に行うことが困難であること、また、3ファンドの譲受債権の対象医療機関に対する安定的な資金供給ができなくなる状況となり、グループの事業継続を断念した。
負債は(株)オプティファクターが約61億3200万円(2014年8月期末時点)、(株)メディカル・リレーションズ・リミテッドが約44億4700万円(2015年4月期末時点)で、2社合計で約105億7900万円。
なお、関係会社の(株)エム・アイ・ファシリティズ(資本金1500万円、東京都品川区東五反田1-20-7、同代表、負債調査中)、海外関係会社であるメディカル・トレンド・リミテッド〈英領バージン諸島、診療報酬債権等の売買、負債約56億6700万円(2015年3月期末時点)〉、オプティ・メディックス・リミテッド〈英領バージン諸島、診療報酬債権等の売買、負債約129億3100万円(2014年12月期末時点)〉については、11月6日付で東京地裁より破産手続き開始決定を受けているとしている。
問題のレセプト債を販売していた証券各社には、ファンドの破綻を知った投資家から問い合わせが相次いでいる。
債券を他の証券会社にも紹介していたというアーツ証券。8日に都内で顧客向けの説明会を開いたところ、100人弱が出席したという。同証券は取材に対し、「私たちも被害者。寝耳に水で困っている」と話した。
金沢市の竹松証券ではこれまで、286の個人・法人に計29億6600万円分の債券を販売した。不正請求でない限り、健康保険組合側からほぼ確実に支払われる診療報酬を基にしたレセプト債は、一般的に安全性が高いとされる。ファンドの破綻を知った購入者からは、「安全だと思って買ったのに」などの苦情が寄せられているという。
医療機関の診療報酬請求権を債券化した金融商品(レセプト債)の発行元ファンドが破綻した問題で、債券を販売する証券会社が今年に入り、顧客に対して「過去に金利や償還の未払いは一度もない。運用状況は改善している」と強調していたことが、関係者の話でわかった。
ファンドの運用成績の低迷を受け、顧客の不安を払拭するためだったが、結果的に事実と異なる説明をしていたことになる。
問題の債券は、東京都品川区の資産運用会社「オプティファクター」が組成したファンド3社が発行。中央区のアーツ証券が紹介役となって、国内の計7社の中小証券会社が販売していた。発行残高は約227億円に上る。
関係者によると、証券各社はアーツ証券の要請を受け、今年8月頃から、ファンドの運用報告書を顧客に配布するようになった。報告書では、ファンド3社のうち英領バージン諸島に本店を置く2社が債務超過状態にあることが示されていたという。
医療サービスに対して支払われる診療報酬を基にした金融商品(レセプト債)を全国に広めていた資産運用会社「オプティファクター」(東京都品川区)が、破綻していたことがわかった。
債券を取り扱う証券会社も寝耳に水の事態だといい、ある証券マンは「顧客の資金が焦げ付く可能性がある」と話している。
診療報酬は通常、患者を診療した医療機関が、健康保険組合側に請求して約2か月後に支払いを受ける。すぐに現金が必要な医療機関はこの請求権を、同社が運用するファンド3社に売却。ファンドは後から手に入る診療報酬を裏付けとして債券を発行し、全国七つの証券会社を通じて投資家に販売していた。
診療報酬は不正請求でなければ、健康保険組合側からほぼ確実に支払いが行われるため、これを基にしたレセプト債は一般的に安全性が高いとされている。
医療機関の診療報酬請求権を基に、資産運用のための債券(レセプト債)を発行しているファンド3社と運用会社1社が破綻し、顧客への配当が止まったことがわかった。
3社の発行債券の残高は約227億円に上るが、数千人の顧客が償還を受けられない可能性がある。ファンドの決算内容に不審な点があることから、証券取引等監視委員会が調査を始めた。
6日に東京地裁に破産手続きの開始を申し立てたのは、「メディカル・リレーションズ・リミテッド」(東京都新宿区)などファンド3社と、関係する運用会社「オプティファクター」(品川区)。メディカル社は同日付で破産手続き開始決定を受けた。4社の負債総額は約290億円。
関係者によると、メディカル社などは、病院や薬局が健康保険組合側に請求できる診療報酬の権利を買い取り、元利金の支払いに充てる債券を発行。年利は3%で、国内の七つの中小証券会社が延べ数千人の投資家に販売していたという。
警視庁が2015年11月に着手した大掛かりな診療報酬詐欺事件に、バラエティ番組に出演したこともある元タレントの女医が関与している疑いがあると、複数のメディアが報じ、大きな関心を集めている。
女医の関係者は、J-CASTニュースの取材に対し、女医は関与を否定した、としている。
■クリニックを突然休業して返金騒ぎに
東京都内でクリニックを経営していたこの女医は、既に2014年11月にネット上で診療報酬詐欺に関与している疑惑が指摘された。
その翌月にクリニックは突然、休業し、ネット上では、患者とみられる人から、「お金を支払ったのに返ってこない」という書き込みが相次ぐようになった。そして、クリニックのホームページでは、諸般の事情から2015年5月末で閉院したとのお知らせが出た。
その後、週刊誌が6月に入ってこの騒ぎを取り上げ、クリニックの資金繰りが苦しくなっていたことが分かった。警察の捜査も入っていると一部で報じられた。これに対し、女医側は、患者に対しては、返金や他院での振り替えで対応すると説明するとともに、スポンサーが見つかってクリニック再開のメドが立ったとも明らかにしていた
ところが、その後もクリニックは閉院したままで、10月末から、週刊誌系のネットニュースや夕刊紙が次々に女医の疑惑を報じた。
事実関係ははっきりしていないが、報道によると、あっせん業者を通じて学生らに2万円ほどの日当で診察を受けてもらい、月に3~7回の架空診療による請求を数か月間も続けていたとも指摘されている。暴力団系金融からお金を借り、返金を迫られて不正請求をしたとの報道もある。
警視庁が11月6日に着手した詐欺事件は、東京都内の接骨院などが暴力団関係者から患者のあっせんを受けて、自治体に診療報酬の架空請求を繰り返していた疑いが持たれている。この事件で、都内の有名医師らも関与していたと改めて報道され、それが女医ではないかとネット上で噂が広がっている。
所属事務所は6月に契約を解除
報道によると、不正請求は、数億円にも膨れ上がるのではないかともみられている。警視庁は、容疑者十数人を次々に逮捕しているともされているが、11月6日夕時点で、前出の女医が対象になっているのかは不明だ。
女医の関係者によると、週刊誌報道が2015年6月にあった後、クリニックが再開するメドが立たなくなったため、女医は、所属事務所から契約を解除された。女医は当時、診療報酬詐欺の疑いがかけられたことについて、「私はだまされたので、むしろ被害者です」と周囲に漏らしていたという。知り合いには、暴力団関係者をスタッフとして紹介され、裏切られたと訴えていたともいう。
もっとも、事実関係がどこまで本当かは、捜査の進展を待つしかなさそうだ。
女医は、クリニック閉院後は、都内のほかの複数のクリニックでアルバイトの医師として働いていたという。このうちのあるクリニックに取材すると、女医はもう来ていないとのことだった。
ネット上では、女医からはまだ返金対応を受けていないと、患者とみられる人からの書き込みが続いている。
女医は、11月6日もブログやツイッターを更新しているが、事件についての言及はなかった。
「関係者は『傷病名に対する治療内容が合っていれば、不正に気付けない』と打ち明ける。厚労省医療指導監査室も『患者側が結託すると発覚は難しい』とさじを投げる。」
考えるのがお前達の仕事だろ、厚労省医療指導監査室。
マイナンバー汚職では「室長補佐が在籍する情報政策担当参事官室では庶務担当が職員約40人分の印鑑を預かり、休暇届などがなければ職場に来なくても押印していた。」
などでたらめがまかり通る厚労省組織。言い訳を考える前に、対策を考えろ!
暴力団関係者らによる診療報酬や療養費の架空請求事件では、暴力団組員やお笑い芸人ら数百人が保険証を提供しており、少額の報酬目当てに「アルバイト感覚」で詐欺に加担していた格好だ。全国で絶えない診療報酬の架空請求。捜査幹部は「ずさんな審査が不正請求の元凶だ」と分析している。
◆報酬は数千円
「なんのことだか、分かりません」
10月中旬、架空請求に名前を使われていたお笑い芸人の男は産経新聞の取材に悪びれる様子もなく答え、お笑いのライブ会場を後にした。
警視庁組織犯罪対策4課が入手した保険証を提供したとみられる名義人には、数百人の名前がずらりと並ぶ。その中には、暴力団組員、お笑い芸人の名前もあった。捜査幹部は「保険証提供者の報酬はせいぜい数千円。アルバイト感覚でやっていたとしか思えない」と指摘する。
提供を受けた保険証を悪用して診療報酬や療養費を架空請求していたのは病院や接骨院、歯科医院。テレビ番組に出演して豪遊体験を話していた女医が勤務するクリニックも含まれていた。
医療機関側からは、三戸慶太郎容疑者側に詐取金の一部が上納されていた。三戸容疑者らは経営の苦しい医療機関に目を付けては犯行グループへ勧誘していたとみられる。
◆不正額146億円
診療報酬や療養費は、医療機関側が国民健康保険団体連合会などを通じて自治体や健康保険組合に請求して受け取る仕組みだ。
厚生労働省によると、昨年度の国民の医療費は概算で約40兆円。財政赤字に苦しむ政府にとって医療費抑制は主要課題の一つだ。
だが、厚労省によると、不正が発覚して保険医療機関の指定を取り消されたりした医院などは平成25年度だけで59機関、不正請求額は計146億円に上る。
申請の審査を担当する国民健康保険中央会によると、各都道府県で審査する請求は毎月数十万~数百万件。関係者は「傷病名に対する治療内容が合っていれば、不正に気付けない」と打ち明ける。厚労省医療指導監査室も「患者側が結託すると発覚は難しい」とさじを投げる。
ただ、捜査関係者は「摘発だけでは歯止めをかけられない。審査自体に問題がある」と指摘。「同じような治療を短期間に繰り返すなど、全体を見れば不審な動きは見つかる。不正な入出金を自動的に監視している銀行のようなシステムの導入が必要だ」と主張している。
小保方さん、弁護士を通して反論するとは思いますが、コメントをお願いします。STAP細胞はやはりありますか?
STAP細胞の騒ぎでこれだけのお金をかけた理化学研究所は救いようのない組織ですか?
◇11〜14年度の4年間 会計検査院の調べ
理化学研究所の小保方晴子元研究員によるSTAP細胞論文の不正問題を巡り、研究にかかった人件費や不正論文の調査費など一連の経費が2011〜14年度の4年間で、総額約1億4500万円に上ったことが会計検査院の調べで分かった。STAP細胞の研究や不正の調査に要した経費の総額が明らかになったのは初めて。
検査院によると、STAP細胞の研究経費は11〜13年度の3年間で計約5320万円。また、不正論文の調査・検証費には13〜14年度の2年間で、計約9170万円が使われていた。理研によると、調査・検証費には小保方氏に支払った14年度分の給与など人件費約800万円も含まれているという。
理研は今年3月、小保方氏の14年度分の人件費を除き、不正論文の調査や検証にかけた一連の経費が総額8360万円に上ったと公表。小保方氏は7月、理研の求めに応じて英科学誌ネイチャーの論文掲載費約60万円を返還した。調査経費が高額過ぎるとの批判もあったが、理研の担当者は「いずれも必要な経費だった。これ以上の返還を求めることはない」と述べた。
一方、検査院は、他の研究員が遺伝子研究に使う物品の契約方法についても調査。その結果、研究員が内規に違反して業者に直接発注したり、現金を前払いしてポイントと交換し物品を購入したりしていたケースが3910件あったことが判明し、理研に改善を求めた。理研は契約課を通じて物品を発注するなど改善策を講じているとしている。
◇STAP細胞研究の主な経費
(2011〜13年度)
・研究費 約2410万円
・小保方氏の客員研究員時代の
給与などの人件費 約1630万円
・研究室内装工事費 約1140万円
・小保方氏の旅費 約130万円
◇不正論文調査の主な経費
(13〜14年度)
・法律の専門家への相談や
職員のメンタルケアなど 約3820万円
・調査委員会の費用や
保存試料の分析 約2350万円
・検証実験や立会人旅費など 約1730万円
・研究不正再発防止のための
改革委員会や広報経費など 約1250万円
責任者及び関係者を処分する必要がある。このような状態だから税金が無駄に使われた。
契約書に理事長の記名押印を受けて契約が確定する前に着工させたり、業者への支払いをしたりしたとして、会計検査院から不適切な処理を指摘された日本スポーツ振興センター(JSC)は6日夕に記者会見を開き、2012年4月~14年12月の47件、計約49億4千万円の契約での誤りを認めた。今後責任を明らかにし、必要に応じて処分するという。10月に就任した大東和美理事長は「業務の進め方に甘さがあった。あってはならないことで厳粛に受け止めている」と陳謝した。
JSCによると、47件のうちの18件(計約3億9千万に)は、業務が終了した後に理事長の記名押印がなされていた。このうちの1件(約9千800万円)は工事内容を変更する契約だったため、建築業法に違反しているという。
こうした「さかのぼり決済」が常態化した理由について、JSCの今里譲理事は「不適切な会計と知りながら実施しており、順法精神が欠けていた。業務遂行を優先する意識、風土があった」と説明。JSCが事業主体を務める新国立競技場建設関連の契約も含まれており、「建設を早く進めなければ、というのがあった」と語った。
損害の補償は、JA全農、太平物産、それとも両方がするの?
全国農業協同組合連合会(JA全農)は5日、秋田市の業者から仕入れ、青森、岩手など東日本の11県で販売した肥料約1万トンを回収すると発表した。有機原料の配合割合などの表示を偽装していたことが判明したため。この肥料を使用して栽培した農産物の安全性に問題はないという。
業者は秋田市の「太平物産」。茨城など同社の国内4工場で製造する783銘柄全ての肥料の出荷を停止し、回収を始めた。4工場の工場長が遅くても昨年4月から、肥料を製造しやすくするといった理由で、チラシや肥料袋の記載とは異なる製造を指示していた。
太平物産の肥料を使用して栽培した農産物を「有機農産物」などと表示して販売した場合は、国のガイドラインや規格に適合しない恐れがある。このため、JA全農は通常の農産物として出荷、販売するよう生産者らに呼び掛けている。太平物産の約9割の銘柄で、有機原料の配合割合の偽装や記載以外の原料の使用などがあることが分かった。
全国農業協同組合連合会(JA全農)は5日、秋田市の肥料製造会社「太平物産」が製造した肥料の成分表示に偽装があったと発表した。
JA全農が青森や茨城、千葉など11県で販売しており、計約1万トンを回収する。農産物の安全性に問題はないという。
JA全農によると、同社の4工場が製造した783銘柄のうち、726銘柄を調査。その結果、678銘柄で肥料袋に明示された内容と異なり、肥料の成分が不足していたり、記載のない原料を使っていたりしたという。
全国農業協同組合連合会(JA全農)は5日、秋田市の業者から仕入れ、青森、岩手など東日本の11県で販売した肥料約1万トンを回収すると発表した。有機原料の配合割合などの表示を偽装していたことが判明したため。この肥料を使用して栽培した農産物の安全性に問題はないという。
業者は秋田市の「太平物産」。茨城など同社の国内4工場で製造する783銘柄全ての肥料の出荷を停止し、回収を始めた。4工場の工場長が遅くても昨年4月から、肥料を製造しやすくするといった理由で、チラシや肥料袋の記載とは異なる製造を指示していた。
太平物産の肥料を使用して栽培した農産物を「有機農産物」などと表示して販売した場合は、国のガイドラインや規格に適合しない恐れがある。このため、JA全農は通常の農産物として出荷、販売するよう生産者らに呼び掛けている。太平物産の約9割の銘柄で、有機原料の配合割合の偽装や記載以外の原料の使用などがあることが分かった。
コストの問題で「分かっていても直せず」と言う事なのか?
JA全農=全国農業協同組合連合会が東日本の11の県で販売した有機肥料の成分が偽装されていた問題で、問題の肥料を製造していた秋田市のメーカーの幹部が報道陣の取材に応じ、「偽装が分かっていても、なかなか直せなかった」と話しました。偽装を始めた時期については、少なくとも3年前からあったとしていますが、調査中だとして明言を避けました。
秋田市の肥料メーカー「太平物産」は、大半の有機肥料の製品で、表示よりも有機質の原料の割合を減らしたり表示していない原料を加えたりして、成分を偽装していたことが分かり、製造を中止しました。
この問題で、太平物産の伊藤茂美常務が、6日午前、秋田市の本社で報道陣の取材に応じ、「消費者の皆さんやJA全農などにご迷惑をおかけして申し訳ありません」と謝罪しました。そのうえで伊藤常務は、「偽装は社長の指示ではないと思う。全国に4つあるすべての工場で大なり小なり偽装はあった。自分が秋田の工場長を務めていた3年前からあった。偽装だと分かっていても、なかなか直せなかった」と話しました。
一方、偽装を始めた時期については、調査中だとして明言を避けました。
農相「有機栽培の評価に水さす行為」
森山農林水産大臣は、6日の閣議のあとの記者会見で、「消費者は有機栽培の農産物を評価しており、これに水をさすような行為で、極めて遺憾だ」と述べました。そのうえで森山大臣は、「食品の安全性に関わることではないと聞いているが、現在問題になっている肥料の成分や生産工程などを関係者から聞き取りをしている。事実関係の確認をしたうえで、法律にのっとって指導などを検討したい」と述べました。そのうえで森山大臣は、都道府県や関係機関と連携しながら、国として再発防止策を検討する考えを示しました。
太平物産とは
太平物産は、昭和23年創業の肥料メーカーです。有機配合肥料や有機化成肥料の製造・販売のほか、農業資材や工業用品の販売なども手がけています。
秋田市と東京に本社があるほか、工場が秋田市と青森市、茨城県阿見町、それに群馬県渋川市の4か所にあります。
民間の信用調査会社によりますと、主な販売先は、JA全農や大手商社、総合化学メーカーなどで、ことし3月期の決算では売り上げは65億7600万円に上っています。
一般財団法人 化学及血清療法研究所は従業員が1,927人もいるのに、
20年間も記録を偽装して国の定期調査に対応してきた。すごい。20年間も記録を偽装し、内部告発もなく、問題の発覚をコントロールしてきた事実はすごい。
騙したほうも悪いが、騙された厚労省も間抜けだ。これでも、性善説をベースにして今後も対応していくのだろうか?
関与した従業員は、会社のため、又は、仕事を失うリスク回避のために、長年、偽装工作のための規則を作成してきたわけだ。
血液製剤やワクチンを製造する「化学及血清療法研究所」(化血研・熊本市)が、20年以上前から国に承認された内容と異なる方法で血液製剤をつくっていたことが明らかになり、厚生労働省は処分を検討している。化血研は発覚を免れるため、製造記録の偽造もしていた。
化血研は原因調査などをする第三者委員会を設置しており、近く報告書をまとめる。厚労省は報告書をみたうえで、処分を決める。
化血研によると、1990年ごろから、工程を安定化させるため、血液を固まりにくくするヘパリンを承認されていないのに添加。また実際の製造記録のほかに、国の承認通りに製造したとするにせの記録もつくり、国の定期調査に対応していた。製造法の変更による健康被害は報告されていないという。
厚労省は6月に血液製剤12製品の出荷を差し止めた。ワクチンでも同様の問題がないか調べ、安全性が確認されるまで出荷の自粛を要請している。
インフルエンザワクチンでは製造書類に誤記などが見つかり、出荷が遅れた。百日ぜきや破傷風などの四種混合ワクチンは現在も出荷が止まっており、今月中旬には化血研製の在庫はなくなる見込み。
化血研は「長年にわたる法令軽視の姿勢があり申し訳ない。第三者委の報告を踏まえて品質保証体制の再構築に努める」としいる。
傾きマンション、検査に限界 市「偽造見抜くのは無理」 10/20/15(朝日新聞)で
「横浜市都筑区の大型マンションが傾いた問題で、偽装された杭のデータは、建築時の検査をすり抜けていた。国も自治体も『見抜くのは無理』と口をそろえる中、消費者は安心してついのすみかを買えるのか。国土交通省はチェックを強化する検討を始めた。
『杭打ち工事のデータを偽装されると、見抜くのは事実上、無理だ』。横浜市の幹部はそう漏らす。今回、旭化成建材の工事担当者による偽装の対象となったデータは法令上、提出の義務がない。
と書かれている。しかし、今では「旭化成建材データ偽装 『自分たちが見破る』自治体職員ら懸命」との記事が存在する。
巧妙な偽装でなければ見つけることが可能なのに、仕事をしたくない横浜市などは言い訳を付けていた事が証明された。「旭化成建材の工事担当者による偽装の対象となったデータは法令上、提出の義務がない。』この点を改正する必要が
あると思う。まあ、行政次第であるが!
旭化成建材が杭工事の施工データを偽装した問題で、複数の現場責任者が「他社の工事でもデータを偽装した」と同社に話していることが、関係者への取材で分かった。データ偽装は大手ゼネコンの清水建設が元請けとして施工した物件でも行われていたことも分かった。
関係者によると、旭化成建材の杭工事では、過去10年間の3040件のうち約300件にデータ偽装の疑いがある。現場責任者50人近くが関わっているとみられるが、同社の聞き取りに対し、複数の現場責任者が旭化成建材の工事以外でもデータ偽装をしたと証言したという。
現場責任者は杭打ちの専門業者からの一時的な出向社員が多く、他社に出向した際に偽装していた。他社の物件についても「機器の不具合でデータがうまく取れなかった」などと説明し、「杭は強固な地盤に届いていると思っている」と話しているという。
また、横浜市の傾いた大型マンションの現場責任者がデータ偽装をした19件の物件のうち、神戸製鋼所の大安(だいあん)工場(三重県いなべ市)と特別養護老人ホーム松寿園(石川県小松市)は、大手ゼネコンの清水建設が元請けとして施工したことが分かった。
横浜のマンションの元請けは三井住友建設だったが、大手ゼネコンにも影響が広がっている。清水建設広報は「安全性の検証については行政と協議を行い、元請けとして責任をもって対応する」とコメントした。
各地の杭工事をめぐっては、4日も自治体などの調査で新たな偽装が判明した。埼玉県の県営団地で1件分かったほか、北海道で2件、長野県で1件、山口県で1件などが明らかになった。
国土交通省は4日、再発防止策を検討する有識者委員会の初会合を開いた。元請けの建設業者による監督や建築基準法に基づく建築確認のあり方について、年内に中間報告をまとめる。(峯俊一平、下山祐治)
自業自得!おごりがあったのだろう。
欠陥エアバッグのリコール(回収・無償修理)報告の遅れをめぐり、自動車部品大手のタカタは米当局と約242億円の制裁金支払いで合意した。だが、今後もリコール関連費用や訴訟費用などが経営に重くのしかかる。ホンダがタカタ製エアバッグ部品の調達中止を表明したように、自動車メーカーの“タカタ離れ”が進む恐れもあり、経営への打撃は計り知れない。(田村龍彦)
「経営へのインパクトはあるが現在、資金繰りのリスクにはいたっていない」
高田重久会長兼社長は4日の会見で、今後の経営に対する懸念を打ち消すと同時に、エアバッグ事業からの撤退を否定した。また、経営責任についても「部品交換を継続し、安全の供給に注力するのが最大の責務だ」と強調した。
だが、同社の先行きに対し、市場は厳しい視線を送っている。この日の東京株式市場でタカタ株は急落し、終値は休日前の2日終値比184円安の1189円となり、下落率は13%を超えた。背景には制裁金に加え、リコール関連費用が膨らむとの懸念がある。
メーカーの自主的な回収を含め、リコール対象車は世界で約5千万台ともされる。だが、タカタが平成24年度以降で費用計上したのは約1千万台分の約800億円にとどまる。残る車両分は、現時点で自動車メーカーが負担している。
メーカー側は、原因が究明された段階で「お互いの責任割合を決める話し合いをして、費用を請求する」(ホンダ幹部)方針。費用は全体で数千億円規模になる恐れもあり、タカタが「債務超過に陥る事態も否定できない」(アナリスト)という。米国ではタカタに対する集団訴訟も起きており、多額の罰金や和解金の支払いも懸念される。
ホンダがタカタ製のガス発生装置の使用中止を表明した衝撃も大きい。エアバッグ以外の製品も含めたホンダ向けの取引は、タカタの売上高の1割以上を占める。他メーカーもホンダに追随する可能性が高い。
タカタは他社製のガス発生装置を使ったエアバッグの供給や、ガス発生剤の変更を打ち出した。しかし、ガス発生装置はエアバッグの利益の大半を占めるとされており、利益率の悪化やコスト増も想定される。問題の長期化や不十分な対応に、消費者の不信感も高まる。タカタは今回、ガス発生装置に使う硝酸アンモニウムの段階的な製造・販売中止を決めた。しかし、現在市販されている車両に搭載されたガス発生装置は交換しない。「リコールの対象になっていないものは安全だ」(幹部)としているためだ。国内でも異常破裂が原因とみられる負傷者が出る中で、消費者の不安を払拭できるかは不透明だ。
タカタは一連の問題をめぐる隠蔽(いんぺい)や改竄(かいざん)を否定した。一方、ホンダはタカタの情報提供に不適切なものがあったことを明らかにした。業界では、1・2%を出資するホンダなどによるタカタ救済も現実味を帯びている。
◇米運輸省 タカタに240億円の民事制裁金
【ワシントン清水憲司】ホンダは3日、自動車部品大手タカタの欠陥エアバッグ問題をめぐり、今後発売する新モデル車にはタカタ製の主要部品を採用したエアバッグは使用しないと発表した。また、米運輸省は同日、この問題でタカタに過去最高額となる最大2億ドル(約240億円)の民事制裁金を科すほか、事故原因の可能性が指摘される硝酸アンモニウムを使ったエアバッグの生産・販売を段階的に止めるよう命じたと発表。タカタは主要取引先と主要製品を失ったことになり、今後の経営に大きな打撃となりそうだ。
タカタ製エアバッグは、作動時に異常に大きな爆発が起こり、エアバッグ内の金属片が飛び散る欠陥が判明。米国で7人が死亡し、100人近くが負傷しており、米運輸省や自動車メーカー、タカタが原因究明と、リコール(回収・無償修理)を進めている。
ホンダは「インフレーター」と呼ばれるエアバッグの起動装置について、全世界で今後市場投入する新モデル車へのタカタ製品の使用を取りやめる。現在生産中の車についても、2016年末までに他社製に順次切り替えていく方針だ。
ホンダによると、エアバッグの欠陥問題を調査する過程でタカタから提出された資料を調べたところ、一部のデータで虚偽の報告が見つかったという。使用停止の理由について、「タカタ製品が危険と判断したわけではないが、リスクを減らす必要がある」としている。
ホンダはエアバッグ起動装置の約4分の1をタカタから調達している。主要取引先のホンダが使用打ち切りを決めたことで、他の自動車メーカーも追随する可能性がある。
一方、米運輸省道路交通安全局(NHTSA)は3日、2億ドルの民事制裁金を科し、同時に硝酸アンモニウムを起動装置に使用するエアバッグの米国内での販売を、19年以降は原則として認めないと発表した。同省によると、タカタは「欠陥に気付いていたものの、適時のリコールを怠った」ことを認め、制裁金の支払いに合意した。まず7000万ドルを支払い、十分な対応ができなかったり、新たな違法行為があったりした場合には、残り1億3000万ドルの支払いが求められる。
タカタは命令を受けて、問題のエアバッグの生産を段階的に減らし、米国内で18年末までに供給を停止すると表明した。硝酸アンモニウムを別の薬品に切り替えて、製品供給を続ける方針。高田重久会長兼社長は4日、東京都内で記者会見し、「エアバッグ不具合で亡くなった方のご冥福をお祈りするとともに、関係者にもおわびしたい」と陳謝した。
企業が大きければ大きいほど、組織の体質問題を抱えれば、簡単には自浄能力は働かないという事か?
ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン(VW)は3日、同社の排ガス不正問題についての内部調査の結果、さらに80万台の車両で二酸化炭素(CO2)排出量に関する「不整合性」が見つかったと発表した。対象車には、今回のスキャンダルで初のガソリンエンジン車も含まれる。同社の大規模な排ガス不正スキャンダルは、ますます泥沼化の様相を見せている。
排ガス不正「3リットルエンジンでも」 米当局発表、VWは否定
同社広報担当者によると、新たに問題が発覚したのはVW、アウディ(Audi)、シュコダ(Skoda)、セアト(SEAT)の各ブランドの排気量1.4、1.6、2リットルエンジン。これらの車両が示したCO2排出量が、実際の排出量よりも低かったという。
これまで問題が発覚していたのはディーゼルエンジン車だったが、同社は今回の問題に少なくとも1種のガソリンエンジン車が含まれることを認めた。
同社は今のところ、新たな問題発覚により発生する費用を20億ユーロ(約2650億円)と見込んでいるが、「これらの不正の規模を正確に見極めるのはまだ不可能」だとしている。【翻訳編集】 AFPBB News
一般的に考えれば、このような状況で手を抜くとは思えない。逆に、ばか丁寧に工事をしてくれると思う。ただ、担当チームに過去にデータ改ざんに関与したものがいたら、
いつ発覚するのかと心配して仕事に集中できなくてミスを犯す可能性もある。しかし、ミスが起きても他の者が気付いて、対応してくれると思うが?
注目されている最中に、手抜き工事をしたら旭化成建材は国土交通省の処分を受けて終わりだと思う。
旭化成建材(東京)による杭くい打ちデータ流用問題で、北海道内では2日、新たに2件の流用が発覚し、不正は計6件になった。
釧路市では、同社がこの日始めた市営住宅の杭打ち作業が急きょ中断されるなど、騒ぎは拡大する一方だ。ただ、これまでに道内で建物の傾きなどが確認されたケースはない。
「え? そんな報告は受けていない」。2日の定例記者会見中、釧路市の蝦名大也市長は気色ばんだ。同席した担当者から、市営住宅の耐震工事で、旭化成建材がこの日から杭打ちを始めたことを知らされたからだ。
同市内では10月28、29日、道営住宅で相次いで流用が明らかになった。道が1日に開いた入居者対象の説明会でも、「本当に安全性に問題はないのか」などの声が上がっていた。
「多くの住民を不安にさせている業者に、工事を任せていいのだろうか」。蝦名市長は語気を強め、杭打ちを一時中断させるよう、その場で職員に指示した。
その釧路市では同日、市の独自調査で、市営海光団地A棟(鉄筋コンクリート造5階建て、25戸)の新築工事でデータ流用が発覚。国土交通省北海道開発局も、稚内市にある東浦漁港の屋根施設の工事で不正があったと発表した。同社はこの2件についてもデータ流用を認めた。
この問題で、旭化成側はデータ改ざんに関わった複数の施工管理者に対し、聞き取り調査を行っていますが、その中の1人の担当者が、機械の不調などでデータがとれなかった際に、「元請けの建設会社から『データが足りないなら適当に作ってでも出せ。全部そろえろ』と言われた」などと証言していることが関係者への取材で新たに分かりました。
上記の証言は公表しても問題ないと判断されたのだろう。問題ないが「機械の不調などでデータがとれなかった」だけのケース。問題がある時に、元請けの建設会社に「適当に作ってでも出せ。」と
言われた事があるかが焦点だろう。実際にそのような事を言われたとしても、公に公表するのか疑問。公表すれば、元請の建設会社が悪いにしても、元請の信頼はなくなるし、
今後の仕事に影響してくる可能性がある。
良い方に解釈するとして、機械の不調などでデータが取れない事がある事を旭化成建材の管理職や役人は知っていたのか。知っていれば、どのような対応を指示していたのか?
知らなければ、知らないで管理及び監督に関して問題だと思う。
今後、どのような情報が公表されるのだろうか?
旭化成建材が杭(くい)打ちを担当した工事で、データの改ざんが相次いでいる問題です。JNNの取材で、データを改ざんした担当者の1人が旭化成側の調査に対し、「元請けの建設会社から『データが足りないなら適当に作ってでも出せ』と言われた」などと証言していることが新たに分かりました。
旭化成建材の杭打ち工事のデータ改ざんをめぐっては、JNNの取材で改ざんの疑いがある物件が全国で300件ほどに上り、少なくとも30人以上の担当者が関与していることが分かっています。
この問題で、旭化成側はデータ改ざんに関わった複数の施工管理者に対し、聞き取り調査を行っていますが、その中の1人の担当者が、機械の不調などでデータがとれなかった際に、「元請けの建設会社から『データが足りないなら適当に作ってでも出せ。全部そろえろ』と言われた」などと証言していることが関係者への取材で新たに分かりました。
国土交通省は2日、「旭化成建材」に立ち入り検査を実施し、原因を究明する考えですが、「旭化成建材」のデータの管理体制に加えて、こうした元請けとの関係についても引き続き、調査を行う方針です。
やはり旭化成建材の対応を間違えると親会社に影響を与えるという事か?
旭化成建材による杭くい打ち工事のデータ流用問題で、親会社である旭化成の株価は問題発覚前に比べ、約2割も下落し、旭化成ブランドの危機に直面している。
業績への影響も見通せず、厳しい状況に追い込まれている。
旭化成の平居正仁副社長は2日の記者会見で、「経営責任は強く感じている。原因の究明が終わり、メドが立った段階で、厳正に処分を検討する」と表明した。
旭化成の株価は問題が明らかになった10月14日以前は900円を超えていたが、大幅に下落し、その後も低迷が続いている。2日の終値は先週末終値より20円安い726・5円だった。旭化成建材の複数の社員による不正が横行していたことが分かり、グループの管理体制のずさんさが浮き彫りになっているためだ。
旭化成建材が関わった3040件のうち、1割前後で工事データ流用の疑いが出てきている。旭化成側はいまのところ、傾きなどの不具合は見つかっていないと説明しているが、新たに発覚すれば補修や建て替えなどに膨大な費用負担が発生することになる。
企業に体質の問題があれば問題は一部に留まらないと言うことか?
【ニューヨーク=越前谷知子】独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)によるディーゼル車の排ガス不正で、米環境保護局(EPA)など米当局は2日、VW傘下のポルシェなど高級車ブランドを含む7車種でも不正があったと発表した。
発表によると、米国でこれまで不正が見つかっていた排気量2リットルのエンジンのほか、2014~16年式で3リットルのエンジンでも不正が行われていたという。これに対しフォルクスワーゲンは「3リットルのエンジンに不正ソフトウェアは搭載していない」と否定するコメントを発表した。
米当局が不正を指摘したのは、ポルシェの2015年式「カイエン」のほか、フォルクスワーゲンの2014年式「トゥアレグ」、アウディの2016年式「A6クワトロ」「A7クワトロ」「A8」「A8L」「Q5」。米国では約1万台がすでに販売された。2016年式モデルの台数については当局は把握していないという。
今年9月、VWのディーゼル車の一部で、試験時と走行時で有害物質の排出量が異なるように作動する不正なソフトウェアを搭載していることが発覚。米当局は全自動車メーカーに対し、同様の不正がないか調査を開始し、2015~16年式モデルについても試験を行っていた。
同日の記者会見で、EPA幹部は「VWは再び法を犯した。予測不可能な試験を実施した結果分かったことで、今後も調査は続けていく」と述べた。
米下院エネルギー商業委員会は「偽りはいつ終わるのか、なぜ長期間発覚しなかったのか。フォルクスワーゲンは白状すべきだ」と批判する声明を発表した。
このような展開にならないとくい打ちデータに改ざんや手抜き工事の問題はパンドラの箱となっていたのではないかと思う。この問題は、下請けや少なくとも一部の
業界の人達は知っていたと思う。問題を指摘しても行政が適切に動かなければ、仕事が減る、又は、仕事がなくなるだけである。
今回は、建設業界だけの問題として扱われているが、程度の違いはあれ、いろいろな業界や企業に似たような問題は存在すると思う。
親会社の旭化成のグループ会社にはISOの認定を受けているのに企業がある。ISOの認定を受けていないにしても、ISOの要求を部分的に用いて改善しようと
することを思いつく人達はいなかったのだろうか?不正を行うのであればISOのトレーサビリティーが問題になる。いろいろな莫大な資料をメーキングしないと
誤魔化し切れなくなる。ごまかせば個人の判断で対応できるレベルでない。少なくとも部分的に組織的な隠ぺいを認めなくてはならなくなると思う。
国土交通省が立ち入り検査を行っているが、国土交通省がどこまで踏込んで調査し、対応するか次第で将来どれぐらい問題が改善されるかが決まるであろう。
問題が改善=建設コストアップは避けられないであろう。なぜなら、一般的に行政はチェックを厳しくするよりも、規則を厳しくする傾向があるからだ。
比較的に良心的に規則を守ろうとする企業は利益が減る、又は、コストアップに直面すると推測される。手を抜く人や企業は規則が厳しくなろうが、手抜きを止める事は
ないだろう。
臨床改ざん疑惑、厚労省が告発者名を漏洩 研究責任者に 01/18/14 (朝日新聞)や
手術後9人死亡の千葉県がんセンター 放置された内部告発 05/21/14(北陸中日新聞 朝刊)
が良い例だろう。
旭化成建材による建物のくい打ち施工データ改ざん問題が、拡大の一途をたどっている。親会社の旭化成は2日の記者会見で、横浜市都筑区のマンション工事のデータ改ざんに関わった現場責任者以外の担当者がデータ転用などに関与したことも認めており、旭化成建材の社内で不正が常態化していた疑いが強まった格好だ。今後は問題の実態解明に加え、経営陣の管理責任も厳しく問われることになりそうだ。【種市房子、山口知】
◇組織的か、明言避ける
「調査の過程なので、会社ぐるみ(の不正)という表現がふさわしいか、もう少し時間をいただきたい」
同日会見した旭化成の平居正仁副社長はこう語り、組織的な不正の有無について明言を避けた。ただ、くい打ち工事のデータ転用などは北海道や東京でも次々に判明。管理体制がずさんだったことは否定しがたく、建設業界でも「問題がどこまで拡大するか、先が見えなくなった」(大手ゼネコン)との懸念が広がっている。
今回の問題を巡っては、旭化成側の対応の鈍さも目立つ。同社は10月14日、横浜市のマンションでくい打ちデータに改ざんがあったと発表。その後、くい打ちを補強するセメント量のデータでも改ざんがあったことを認めたが、同社の浅野敏雄社長が初めて記者会見したのは20日になってから。調査の進捗(しんちょく)状況を公表するとしていた30日には、「問い合わせが殺到し、発表内容をまとめられなかった」として公表を断念する不手際もあった。
旭化成が実態調査と情報公開に手間取る中、関係自治体が次々にデータ転用があった建物を発表。2日には旭化成建材がかかわった全国のくい打ち工事3040件のうち、約1割で不正が行われていた疑いがあることも判明した。国土交通省幹部は「事実であれば、組織、監督の在り方が問われる事態であり、経営陣の責任は大きい」と批判。法令順守問題に詳しい山口利昭弁護士は「これだけデータ不正が横行していたのであれば、旭化成建材の幹部も認識していた可能性がある」と指摘する。
旭化成の平居副社長は2日の会見で「関係者に迷惑をかけた経営責任は強く感じている」と語り、実態解明と再発防止にめどがついた段階で関係者の処分を行う意向も表明した。不正がなぜ見逃され、対応のどこに問題があったのか。旭化成は重い説明責任を負うことになる。
「石井啓一国交相は10月30日の閣議後会見で『会社全体の施工管理に何らかの問題がある』と述べ、旭化成建材のコンプライアンス体制なども含め、徹底的に調べる方針を示していた。」
「旭化成建材のコンプライアンス体制なども含め、徹底的に調べる」と言っても、違反行為を疑う根拠があってはじめて行政は動き出す。コンプリアンス体制に
問題があっても、違法行為を疑う根拠や証拠がなければ現状ではどうにもならないのでは?
会社の体制が問題としてメディアや行政から指摘されない範囲では「みざる、きかざる、いわざる」のようなスタンスであれば問題が表面化するまで一部の人達以外は
問題を認識できないと思う。法令順守は企業のイメージやブランド力と関係があるだけで、利益やコストが優先であれば、法令順守は障害でしかない。社会秩序を守るために、
違反した企業や人達は罰せられる。しかし、違法行為が発覚しなければ、違法行為をした事実だけでは処分されない。だから企業や人々は利益やコストのためにリスクを取るのだと思う。
投資にしても、企業にしても、違法行為でなくてもリスクは存在する。リスクと見返りのバランスや個々の判断基準でリスクは取られる。旭化成建材の件にしても、
三井不動産グループが販売した大型マンション「パークシティLaLa横浜」(横浜市都筑区)の傾斜問題が公にならなければ、これまで取ってきたリスクに
関して後悔する事もなかったかもしれない。
旭化成建材が杭工事の施工データを偽装していた問題で、国土交通省は2日、建設業法に基づき、旭化成建材の本社(東京都千代田区)に立ち入り検査を始めた。
国交省は今後、同社幹部の聞き取りや資料の分析を通し、同社のすざんな施工管理について実態解明を進める。石井啓一国交相は10月30日の閣議後会見で「会社全体の施工管理に何らかの問題がある」と述べ、旭化成建材のコンプライアンス体制なども含め、徹底的に調べる方針を示していた。
旭化成関係者によると、旭化成建材が過去10年で杭を打った工事のうち約300件で杭のデータ偽装の疑いがあり、50人近くの現場責任者が関与しているという。
収拾が付かない状態!
横浜市のマンションに端を発したくい打ちデータ偽装問題で、不正が確認された北海道釧路市の道営住宅工事を行った建設業者が、くい打ち施工を担当した旭化成建材(東京)に偽装の有無を照会したところ、当初、旭化成建材が「(データ偽装などはなく)問題ない」と回答していたことが30日、関係者への取材で分かった。この住宅はその後の北海道の調査でデータが偽装されていたことが判明しており、旭化成側の社内調査が不十分な可能性がある。
問題の物件は釧路市の道営住宅2件で、北海道が28日と29日に独自調査の結果として、施工データが別工区のものから流用されるなど、偽装されていたと発表している。
2つの工事に中請けとして関わった札幌市内の建設業者によると、全国3040件を調査している旭化成建材に対し、北海道が発表する前に、自社が関与した道内物件について偽装の有無を問い合わせたところ、「問題ないので大丈夫」と回答を受けたという。
この建設業者は過去5年間に、旭化成建材にくい打ち工事を発注した物件が道内に数十件あり、業者側は「大丈夫と言われて安心していた」と話す。
建設業者によると、2件の現場では、この建設業者と元請けの建設会社が1人ずつ現場責任者を派遣して、旭化成建材の下請け業者が行っていたくい打ち作業を1本ずつチェックしていた。さらに、建設会社は施工後、旭化成建材からくい打ちのデータを受け取っていたという。
建設会社の現場責任者は「(施工当時に)強固な地盤に届いたことは1本ずつ確認した」と話し、建物の安全性に問題ないとしている。同社は「報告書は細かくチェックしていなかった」とした上で、「(旭化成建材の下請けの)施工業者がデータ記録紙を汚損するか紛失するかして、それを隠すために偽装したのではないか」と推測している。
組織的な判断だったとは!北口克彦社長は会見を開き、経緯を説明するべきでは?
理事長 北口 克彦(株式会社三省堂 代表取締役社長)(ELPA(エルパ)【英語運用能力評価協会】)
英語運用能力協会とは
英語運用能力評価協会(ELPA)は、「わが国の学校における英語教育の成果を客観的に調査・評価するテストを実施し、実戦的で効率的な学習指導の提言を行う」ため、2003年4月15日に東京都知事の認証を得て設立された特定非営利活動法人(NPO)です。
英語教育の成果を客観的に調査・評価するテストは必要ないと思う。英語教師の能力問題の解決や生徒の能力別に授業を行う事が優先だと思う。英語は、読めればよい人、単純な英語を話すだけでよい人、
専門的、又は、学術的なレベルの英語が必要な人などニーズが様々である。そして、全ての日本人が英語を話す必要はない。これも金儲けの1つか?テストである以上、傾向と対策を知っていれば
実際の能力以上に点が取れるはず。点で判断される以上、良い点を取りたい生徒は多いはず。
教科書を発行する「三省堂」(東京)が検定中の中学英語の教科書を校長ら11人に見せ、謝礼金を渡した問題で、同社は昨年10月、文部科学省の調査に、検定中の教科書を教育関係者に見せる編集会議を過去にも6回開いていたことや、毎回謝礼を支払っていたことを隠していたことがわかった。
同社の北口克彦社長が隠蔽を決め、幹部らに指示していた。
同社は30日午前、記者会見を開き、瀧本多加志・取締役出版局長が「深く反省している」と謝罪。文科省は同日、北口社長を呼び、文書で厳重注意した。
同社によると、編集会議は昨年8月のほか、2009~10年にも小学校の国語と中学校の国語、英語の教科書編集に際して計6回開かれた。いずれも参加者に謝礼を支払っており、瀧本局長は「謝礼は毎回5万円だったと思う」と説明する。
教科書を発行する「三省堂」(東京)が検定中の中学英語の教科書を校長らに見せた問題で、5万円の謝礼を受け取った校長ら11人のうち5人はその後、各市町村教委などの「調査員」などに選ばれ、教科書の採択に関与していたことが、文部科学省への取材でわかった。
同社は2009~10年にも教育関係者から意見を聞く会議を計6回開き、毎回謝礼を支払っていた。文科省は30日、同社の北口克彦社長を呼び、文書で厳重注意した。同社は30日午前、記者会見を開き、瀧本多加志・取締役出版局長が「間違った行為で、深く反省している」と謝罪した。
文科省によると、同社は昨年8月23日、英語教育に詳しい青森、埼玉、大阪、京都、福岡など11府県の公立小中学校の校長や教頭ら11人を都内のホテルに集め、意見を聞く「編集会議」を開催。その際、文科省が検定中の英語の教科書を見せ、改善点などの指摘を受けた。
仕事を取るため、生き残るためにはグレーン・ゾーンやブラック・ゾーンにまで立入って活動しないといけないのか?それとも三省堂がずるいのか?
来年度から中学校で使われる教科書を巡り、教科書会社「三省堂」(東京都千代田区)が昨年8月、公立の小中学校の校長ら11人に対し、検定中の教科書を閲覧させ、意見を聞かせてもらった謝礼名目で現金5万円を渡していたことが分かった。文部科学省は検定中に外部に見せることを禁じている。11人のうち5人はその後の教科書採択にもかかわっていた。同社は前回2010年度の検定時にも同様な行為をしていたと認め、文科省は「教科書採択の公正性に疑念を生じさせる不適切な行為」として30日、同社を厳重注意し、事実報告を求めた。
三省堂は30日午前に本社で記者会見して謝罪したうえで、同社は2009年11月から10年12月にかけても同様の「編集会議」を6回開き、小中学校の関係者に検定中の教科書を示し、現金を支払ったことを明らかにした。金額などの詳細や他に問題がある行為がなかったかを調査する。
滝本多加志取締役出版局長は「採択を期待した行為だと疑惑を持たれても仕方ない。教科書や発行者への信頼を揺るがしかねない大変誤った行動だったと深く反省している」と話した。【高木香奈】
コスト削減したらこうなる?
国土交通省は30日、航空会社のアイベックスエアラインズ(東京都江東区)が、整備記録を改ざんして運航していたなどとして、同社に事業改善命令を出した。
国交省によると、同社は2013年1月、伊丹空港で、航空機の前脚にある左右のタイヤ交換が必要にもかかわらず、誤って片方だけを交換した。その後、ミスに気付いたが、両方のタイヤ交換は必要なかったと記録を修正し、運航を続けた。同年10月には、乗降用ドアの整備点検時期が過ぎていることに気付きながら、期限内に実施済みと記録を改ざんして運航を継続した。
今年9月に国交省に情報提供があり、調べたところ、改ざんなどの不正が16件明らかになった。同社の整備部長が整備員に指示するなど、組織的だったという。
まあ、今回のように注目を受けないと変われないのだろう。まともにやっているところはあると思うが、まともにやっていないところよりも仕事は来ないし、儲からないから
大きくはならない、現状維持、又は、衰退しているかもしれない。
かつて旭化成建材の下請け会社に勤務していた元くい打ち職人の記事が事実であるなら、業界的にデータ改竄が常態化している可能性は高い。安全値を高めに取っていれば
一本や2本のデータ改竄は影響しない、又は、表に出るような問題として現れなかったのかもしれない。
行政が問題を認識してどのように対応するか次第であろう。下請けは発注者の指示は無視できない立場。仕事を失うリスクを抱える。データ改竄はなくならないと思うが
行政が対応しないと、現状の問題は変わらないであろう。
しかし、もう一本ぐらいとか、前も問題がなかったとかで、データ改竄の箇所を増やして行った人や下請けはあるかもしれない。発注者の指示で言われたとおりに行うことも
あるかもしれない。
やはり「氷山の一角」だったのか。建築物のくい打ち施工データ偽装が広がりをみせ、建設業界への不信感が一気に高まっている。こうした中、かつて旭化成建材の下請け会社に勤務していた元くい打ち職人の70代の男性が産経新聞の取材に応じ、「記録ミスをすればごまかすしかなかった」とデータの改竄(かいざん)が常態化していた実態を語った。
「データ記録を取ることは、くい打ち工にとって『絶対』。でも、毎回きちんとデータが取れる保証はない」
平成元年ごろまで約30年間、くい打ち工事で重機操作のオペレーターとして働いていた男性は、こう話す。くい打ち職人にとってデータ記録は“仕事の証し”。かつてはデータ記録の枚数に応じて給料が支払われたという。
ただ、現場で問題が生じると禁断のデータ改竄に手を染めた。具体的には、くいの長さが強固な地盤に届かなかった▽記録開始スイッチの押し忘れや記録紙のセット忘れなど人為ミスがあった▽データを記録する機械の不良があった▽大きな石があるなど地中障害が見つかった▽波形が弱いなど理想的な記録が取れなかった-などの事態が起きたときだ。
男性は「注意深くやれば問題の発生は減らせるが、それでも1つの現場で1回くらいはミスが起こっていた」と明かす。改竄の際には、波形を記録する機材で使われるものと同じ特殊インクを使ったペンを使用。ペンは事前に購入しておいた。別の記録紙の上から新たな記録紙をかぶせて手書きで波形を写し取ったり、修正液で消して加筆したりした。「元請け会社には原本でなくコピーを提出するため、ぱっと見ただけでは簡単には見破られない」。他にも、波形が似た別の記録をそのまま流用することもあったという。
元請けの建設会社などから、「もっといいもの(データ)を出せ」「何とかしろ」と要求されたことも。「いわれなくても、あうんの呼吸で加筆修正するものだった。あの手この手で必死にごまかす方法を考えた」
一方、複数のくいで長さが不足した場合は、元請けに相談して本数を増やしたり、継ぎ足して長くしたりしていた。男性は「1、2本届かなくても全体で設計時の耐久度を満たせばいい」と説明した上で、横浜市都筑区のマンションで施工不良のくいが8本あったことについては、「多過ぎる」といぶかる。
「確かにいいかげんな部分があった。これを機に見直してほしい」。男性は過去を反省しつつ、「ゼネコンなども下請けだけに押しつけないで責任を負うべきだ」と、業界全体で体質改善に取り組む覚悟を求めた。
担当者も旭化成建材も関わりたくないかも?
北海道が発注した釧路市の道営住宅の工事で、旭化成建材が工事データを流用していたことがわかった。横浜市のマンション工事の担当者とは別の人物だという。
北海道建設部・長浜光弘建築局長「我々がデータを見比べたときに、切り貼りしている状況が見受けられた。旭化成建材に確認したところ、転用したと認めざるを得ないと」
データ流用がわかったのは、2010年から11年にかけて増築した釧路市の道営住宅。北海道は、旭化成建材が杭(くい)打ち工事を施工した北海道の発注物件について、独自の調査を進めていたが、その結果、28日夜、杭31本のうち1本について、隣接する工事のデータを流用していた事実が新たにわかった。また、今回のデータを流用した担当者は、横浜市でのデータ改ざんを認めた男性とは別の担当者であることもわかった。
長浜建築局長「旭化成建材の発表では、横浜の担当者が関わった物件は北海道にはない。普通に考えれば、横浜の人じゃない別の人が北海道でやっているということ」
北海道によると、今回の道営住宅の杭打ちに関わった旭化成建材の担当者はすでに退職していて、直接、流用の経緯について聞き取りができなかったという。
旭化成建材の信頼が傷つくだけで済むのか知らないが、個人的に意見であるが親会社の旭化成次第かもしれないが、親会社の支援なくして存続できるのか?
横浜市都筑区の大型分譲マンションに傾きが見つかった問題で、横浜市は29日、旭化成建材が請け負った市管理の公共施設1件の杭くい打ち工事で、新たに施工データの流用が判明したと発表した。
市職員による目視の調査では、建物に異常は確認されていないという。同社の工事でデータ改ざんが見つかったのは、都筑区、北海道釧路市に続き3例目。
横浜市によると、新たに流用が分かったのは、地中に打ち込む杭の先端部分と固い地盤を固定するためのセメント量に関するデータ。29日午前、施設建設の元請け業者から市に対し、杭210本のうち15本でデータ流用が確認されたと連絡があった。市は「まずは施設関係者に説明する」として、施設名を公表していない。
この工事には、都筑区のマンションでデータ改ざんをした同社の現場責任者は関わっておらず、別の人物がデータを流用したとみられる。
組対4課が動いた
月に数百万円をホストクラブで使うと公言する美人女医、千葉県船橋市、市川市、千葉市などで幅広く医院を展開していた著名歯科医、プロスポーツ選手なども利用していたという接骨院……。
こうした医師や柔道整復師などが行っていた診療報酬不正請求事件が、近く、警視庁組織犯罪対策4課によって摘発される。
暴力団担当の組対4課が担当するのはなぜか。
事件の構図を描き、仲介者を利用。経営不振に喘ぐ医師や柔道整復師を集め、患者を用意し、内容虚偽の診療報酬明細書(レセプト)を作成させ、医院が受け取る療養給付費を“山分け”するシステムを作ったのが、広域暴力団だったためである。
診療報酬をいい加減なレセプトで受け取る事件は枚挙にいとまない。厚生労働省は、今年1月末、診療報酬の不正または不当請求として返還される金額が約146億円にのぼったことを明らかにした。過去5年で最高。前年度から約16億円の増加だが、それでも氷山の一角である。
地域の信頼される知識層である医師は、不正を働かないという「性善説」によって成り立つ申告制度なので、不正があることを前提としていない。
ところが不正請求は、日常的に行われている。架空患者のでっち上げ、生活保護受給者を囲い込んでのたらい回し、診察と投薬内容の水増しなど、摘発されれば全て悪質な詐欺。
ただ、最大の被害者は国であり、健康保険料を支払っている国民だが、目の前でカネが詐取されるわけではないので、被害の実感がなく、不良医師の側の罪悪感も薄い。
そこに住吉会系暴力団が目をつけた。
組長がトップ。売れない芸人も関与
トップに位置するのは4次団体の組長である。その下に配下がいて、それぞれが医師・柔道整復師をかかえる。暴力団構成員と医師・柔道整体師をつなぐのは金融ブローカーなどの仲介者。高利金融を営む彼らの耳には、窮乏した医院のニュースが入ってくる。
医師・柔道整復師を囲い込むと、今度は患者を用意しなければならず、そこに登場するのは、暴力団構成員の妻や愛人、友人知人、仲間の半グレなどの仲介役であり、彼らがアルバイト感覚の被保険者を見つけ、医師・柔道整復師につなぐ。
組長以下の暴力団構成員は10名を超え、医師の数も同程度、仲介役を経てアルバイト感覚で詐欺に加担した被保険者の数は、延べ人数で数百名に達する。被保険者には、多数の「食えないお笑い芸人」が含まれていた。
関係者の数が多いだけに、組対4課は粘り強く捜査している。事件は一度の逮捕だけでは終わらず、何度も繰り返しながら暴力団と医師・柔道整復師が組んだ新種の診療報酬詐欺事件を立件する。
今回、詐取した給付金額が医師とほぼ同額になるのが柔道整復師。彼らは、都内の商業地や住宅地で接骨院を営んでいるが、医師と同様、健康保険の適用を受けている。戦前からの既得権益で、今のように医療機関が発達していない時、骨折、脱臼などを接骨院で対処していた歴史からだ。
今は、そうした大きなケガは整形外科で対応する。接骨院では肩こりや腰痛などの慣習化した症状の患者が多いが、それでは健康保険の対象にならないと、捻挫や肉離れに変えて治療している。それも診療報酬不正請求だが、今回は、患者に仕立て上げるというもっと悪質な不正請求だった。
レセプトを不正請求して診療給付金をだまし取る今回の手口は、振り込め詐欺や野球賭博の犯罪構図に似る。
振り込め詐欺の場合、活動資金を用意、元締めとなるのは暴力団幹部で、その配下が幾つもの会社を使って、パンフレットなどを作成、電話で勧誘する「掛け子」と呼ばれる人間を雇い、引っかかった老人がいれば、末端の「受け子」がカネの受け取り役になる。
犯罪最前線にいるのは、「掛け子」であり「受け子」だが、こうした末端は、元締めの正体を知らされておらず、摘発しても暴力団に行き着けないことが多い。元締めが暴力団ではなく半グレの場合も、ケツ持ちという形で必ず暴力団が関与しているのだが、犯罪収益の解明までには至らない。
いち早く警鐘を鳴らす
野球賭博も同じである。ハンデ師を雇い、カネを用意、野球賭博の胴元を務めるのは暴力団幹部であることが多い。構成員でなかったとしても、その背後に回収役として暴力団幹部が控えており、野球賭博はおおむね、いずれかの広域暴力団の影響下にある。
ここでも末端の勧誘役は、クラブの黒服や飲食店経営者、あるいは野球賭博で話題になった巨人軍選手の窓口となっている「税理士法人に勤務するA氏」のような遊び人である。巨人軍の選手はもとより、A氏から胴元に遡るのも容易ではない。
ピラミッドの頂点に暴力団幹部がいて、振り込め詐欺や野球賭博と同様、末端の「被保険者」を囲い込んで医療費を詐取するというシステムは、新しさと目の付け所の“良さ”に驚嘆する。もちろん感心するのではなく、その芽を潰していくのが捜査当局とマスコミの役割だろう。
医療と介護を合せて56兆円にも達する日本の現状を考えれば、この巨額予算に目を付け、その収奪に工夫を凝らす反社会的勢力がますます増える。今回の事件は、その構図を暴き、いち早く警鐘を鳴らす。幸い、マスコミ受けする美人女医の存在もあって、大きく報じられよう。
組対4課が摘発する意味と意義がある捜査となりそうだ。
簡単には幕引きできない状況になっていくのでは?
北海道は29日、釧路市の道営住宅新築工事で、旭化成建材によるデータ流用が新たに判明したと発表した。打ち込まれた杭22本のうち2本のデータが同じだったという。
旭化成建材は「客観的に見てデータの転用があったと認めざるを得ない」と道にコメントしている。
同社の杭打ちデータ偽装をめぐっては28日、釧路市の別の道営住宅改良工事で発覚したばかり。
「この工事には、問題のマンション工事でデータ改ざんをした同社の現場責任者は関わっておらず、別の人物がデータ流用をしたとみられる。」
これで少なくとも程度の違いはあれどデータ改ざんは旭化成建材では行われていた可能性が高くなった。業界でもデータ改ざんが行われている可能性が高くなった。
「北海道が調べたところ、目視では傾斜などは見当たらず、同社も『安全性に問題はない』としているという。」
データ改ざんしても運良く傾斜しなかったり、「安全性に問題はない」となればデータ改ざんや手抜きは許されるのか?もし、傾斜なし、安全性に問題がなければ
データ改ざんはOKであるとの認識が旭化成建材の社員や下請けそして業界関係者にあれば、問題は氷山の一角である可能性もある。
行政は新たな規則や法律を作成する必要があると思う。傾斜の角度、亀裂の程度により販売業者及び施工業者に賠償責任を負わせるべきだと思う。
傾斜なし、安全性に問題がなければデータ改ざんはOKであるのはおかしい。消費者の立場から考えると絶対に許されるべきではない。
横浜市都筑区の大型分譲マンションに傾きが見つかった問題で、北海道は28日夜、旭化成建材が関わった北海道釧路市内にある道営住宅の工事1件で、杭くい打ちデータの流用が見つかったと発表した。
この工事には、問題のマンション工事でデータ改ざんをした同社の現場責任者は関わっておらず、別の人物がデータ流用をしたとみられる。北海道が調べたところ、目視では傾斜などは見当たらず、同社も「安全性に問題はない」としているという。
問題の工事は、釧路市東部にある鉄筋コンクリート造5階建て住宅(38世帯入居)の改良工事で、2010年7月から11年8月にかけて行われた。工期を2期にわけてエレベーターをつけるなどバリアフリー化したが、2期目の際に、1期目の杭打ち工事のデータを転用したという。
下記のYahoo!不動産の質問とその回答が事実だとすると、メディアがそこまで調査や質問しないのか、それとも、業界の人がメディアに対してはコメントしないと言う事なのでしょうか。
メディアがコメントした人の保護のためと言っても、コメントした人を企業や業界は探そうとするだろう。被害総額や被害の拡大のリスクもある。業界も狭いので調べようと
思えば、ある程度まで絞れるような気がする。
少なくとも旭化成建材は下記のような事は認識しているのではないのか?親会社の旭化成がどこまで旭化成建材の調査に関与しているのか知らないが、時間稼ぎや
中途半端な説明が続くと、旭化成のブランドが傷つくような気もする。ただ、東洋ゴムのように問題は1つだけではない場合、とにかく幕引きをしたいとの思いが
あるかもしれない。
マンションは都市部の問題。田舎にマンションを建てるメリットなどない。田舎よりも都市部のほうが生活しやすいのかもしれないが、運が悪ければリスクを背負い込む事になる
事があきらかになった。まあ、一戸建て住宅でも欠陥住宅があるから、マンションだからリスクと言う訳ではない。やはり、信頼と実績、そして最近のパフォーマンスの評価と
言う事なのだろうか。
ある中国製品についてだが安いと言うだけで非常に注文が殺到した事があった。しかし、品質や耐久性の問題で、完成後、2,3年経っても問題が発覚しないもの方が
新品よりも高くなるおかしな状態になったと聞く。検査を合格しても、品質や耐久性を保証するものでないと証明されると、このようなおかしな事もおきるのであろう。
横浜マンション杭の打ち込み不足問題について 10/15-21/15(Yahoo!不動産)
個人の責任追及するわけじゃなくって、建築業界の仕事の流れ的なことを聞きたいんですが、今は、二次下請けの旭化成建材が杭打ちを担当し、データも改ざんということになってますが、実際、現場で杭を打つ機械もレンタルだろうし、オペレーターも三次・四次下請けだったりするんじゃないでしょうか?
普通に考えて、当時、現場でオペレーターは支持層まで達していないって気づいてたんじゃないでしょうか?監督的立場だった建材の社員も、なんらかの経緯でそのことを知ってたから、データ改ざんしたんですよね。
早い話が、一部の人は気づいてたけど納期の問題もあれば、いまさら手のうちようの無いところでまで工事が進んでいたから、闇に葬ろうとしたんですよね。
普通に考えて支持層にまで達していないってことはその場で分からないものなんですか?
でも、わかってたからデータ改ざんしたんですよね。
どのタイミングで気づいてたと考えられますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
回答した人: sikoku20062000さん
回答日時: 2015/10/16 23:56:32
.掘って居て
支持層に当たると固くて掘れないから手ごたえありい!!
掘る前にボーリングして大よその深さを確認して在る筈なのですが、どーしちゃったんでしょうね。
掘った土は穴から出して
ダンプに積まねばならん。
この時に掘った土砂を見れば、解る筈。
解って居たからデータの改ざんを何時ものように何気なく。
かも知れませんね。
だから3000棟も調べ直す気がする。
直下型地震が来たら、ピサの斜塔みたいのが、あちこちに出現して
斜塔めぐりバスツアーなんてできるんですかね。
機械の能力不足で掘れない現場が在ったので設計士が判断して設計変更、太くして本数を増やした現場も在りました。
掘れない場合は現場サイドの判断では無く、設計士の判断の筈。
問題は技術的に掘れなかったのか、面倒だから掘らなかったのか?
5階建て位までの中層建築物でもボーリングして地盤の調査をして強度不足なら地質改良工事、あるいは杭を打つ時代。
木造だって杭を打つ場合も在りますけど。
回答した人: saigonodokenyaさん
回答日時: 2015/10/17 01:43:02
.普通の業者なら支持層が出るまで掘削やめません。支持層が出てから杭を建込みます。
支持層が、急に谷の様に下がってるところなんて沢山あるので元請の施工管理として、実際に揚がってきた土質を照合したり、電流計みたり、オペにヒアリングしたり、いろんな形で1本1本づつ支持層を確認します。
大臣認定工法なので、杭打機には掘削時の抵抗値を確認できる機械がついてますので普通のオペならばそれを見ながら施工してるはずです。
普通のオペなら杭屋監督か、元請の監督員に連絡するし、
杭屋の普通の監督ならば支持層に達してないなら、元請に黙って施工はしない。
そして、普通の元請担当者であれば現場所長に、普通の所長であれば、会社内と 設計監理 と 売主 と 建築主 に報告する。
普通の現場の人間ならば、基礎工事の重要さ(建物的にも、お金的にも、後からやり直しなんて…ありえない)は分かってるし、基礎に万が一不具合があったときは、個人では責任取れる訳など無いということは自覚してるはずだから、どこの会社でも担当者個人は、絶対に会社に報告していると思います。
また、報道だと担当者の悪意が原因なんて話ですが、ありえないとおもいます。特に杭屋の番頭担当者なんて、端から見てて、休みの日もあるのか無いのかわからないくらい感覚麻痺してて、社畜となって、次から次へと現場を全国隅々まで転々と、川の上だって、海の上だって、10代の人から60代の人までセメントミルクに腰まで浸かりながらクソメソになって仕事してるんですよ。悪意のある人は杭屋さんなんて出来ないし、やらないと思います。
杭の施工中の変更は、間違いなく金と時間が掛かってしまいます。下手すれば完成が遅れます。
もう買い手も決まっていたんですかね。
契約解除とか、違約金とか、保障とか、そのときはそれを考えたら…やるしかなかったのか、とりあえず確信犯的にお金の流れを作ったのか…
いずれにしても、どこかが普通じゃなくておかしな対応をしてしまったみたいですね。
違法、不法行為にあたる施工なので、現場サイドは現場止めてしまえばよいだけですので、どこからか天の声が聞こえて現場は進んで行ったのだと思いますが。
多分皆知ってて、買った人だけが知らなかったんのよ。
でも倒壊はしないだろうけど
杭の検査が厳しくなるんだろうなきっと
■別の日の記録コピー、深さ書き込み…
横浜市都筑区のマンションが傾いている問題で、くい打ち施工後に男性の現場管理者が地盤強度データを改竄(かいざん)した具体的な手口が26日、旭化成などへの取材で分かった。旭化成は社内に調査委員会を設置し、改竄の動機や詳しい状況などを調べている。
くい打ち施工を請け負った旭化成建材や親会社の旭化成によると、くい打ち施工は重機のオペレーターや現場管理者など7人が1チームとなって行う。
くい打ち機のドリルで地中に穴を掘るが、強固な地盤の「支持層」に到達すると、「電流計」と呼ばれる計器で記録している波形の波が大きく揺れ、同時にオペレーターにショックが伝わる。これを受け、ドリルが支持層に到達したかどうかをチームで確認する。
現場管理者は電流計を管理するだけでなく、専用の用紙にプリントアウトされる波形記録を保管。施工日ごとにコピーを報告書に添えて、元請けの三井住友建設に提出することになっていた。
旭化成建材の聞き取り調査に対し、現場管理者は「(機器の)スイッチを押し忘れたり、雨でぬれて波形が見えなくなったりしたので、データを転用・加筆した」と説明。データは工事の最後にまとめて提出したという。
旭化成などによると、データ改竄は別の日に実施した波形記録をそのままコピーしたり、2つの波形を継ぎはぎしてコピーするなどの手口。波形を書き足したほか、日にちや深さを書き込んで、くいが支持層に到達したように偽装していたという。
一方、事業主の三井不動産レジデンシャルは、傾いた棟の基礎に打たれたくいのうち、強固な地盤に届いているか未確認だった24本に関する地盤調査を27日に終了すると横浜市に伝えた。傾いた棟のくいは計52本。調査済みの28本のうち6本が強固な地盤に未到達、2本は届いていたものの深さ不足が判明している。
「英経済紙フィナンシャル・タイムズ(Financial Times)は25日、独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)の排ガス規制逃れ問題に関連し、欧州連合(EU)の内閣にあたる欧州委員会(European Commission)の環境担当委員が2013年に、自動車メーカーが欧州で排ガス試験の不正に及んでいると警鐘を鳴らす書簡を、他の委員に対し送っていたと報じた。」
これってあり?
ヨーロッパは日本で思われているよりも実態の経済は悪いのか?だめな物はだめと言うべきだろ。
【AFP=時事】英経済紙フィナンシャル・タイムズ(Financial Times)は25日、独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)の排ガス規制逃れ問題に関連し、欧州連合(EU)の内閣にあたる欧州委員会(European Commission)の環境担当委員が2013年に、自動車メーカーが欧州で排ガス試験の不正に及んでいると警鐘を鳴らす書簡を、他の委員に対し送っていたと報じた。
自動車業界における史上最大級のスキャンダルとなったVWの排ガス不正問題は、今年9月に発覚。VWは、製造した約1100万台に当局の排ガス試験を不正に通過させるソフトウエアが搭載されていたことを認めている。
フィナンシャル・タイムズは、この2年前に欧州委員会の委員が自動車メーカーの規制逃れを認識していながら、この抜け穴を放置していたことが、委員の間でかわされた書簡から明らかになったと報じている。
同紙によると、欧州委員会のヤネス・ポトチュニク(Janez Potocnik)環境担当委員(当時)は2013年2月にアントニオ・タヤーニ(Antonio Tajani)産業・企業担当委員に宛てた書簡のなかで、「排ガス試験サイクルの狭い範囲の外で排ガス量が著しく増加することを無視する形で、試験サイクルに合格するよう性能が厳密に調整されているとの懸念が広がっている」と指摘していた。
米当局は9月、排ガス試験下であることを検出すると排出量を調整する一方で、実際の走行時には基準値を超える有害物質の排出を可能にする装置を、VWが車両に搭載していたと公表していた。【翻訳編集】 AFPBB News
横浜市都筑区のマンションが施工不良で傾いた問題は、建設業への信頼を揺るがせている。基礎のくい打ち工事を担当した旭化成建材によると、同社の現場責任者がくい70本の施工データを改ざんし、虚偽の施工報告書が十分にチェックされないまま元請けの三井住友建設に渡っていた。「当たり前の確認作業がなされていない」。同業他社からはそんな指摘が出ている。
【写真】2センチの段差ができた棟と棟の接続部分の廊下の手すり
◇元請け側の責任、指摘も
「データを紛失したり紙が雨にぬれて使えなくなったりして、自分のミスを隠すためにやった」。現場責任者は改ざんの動機をそう話しているという。
くい打ちには8人ずつの2チームが携わり、この現場責任者は一方のチームのリーダーだった。ドリルで地盤を掘削し、電気を流して強固な地盤(支持層)を確認する。支持層に届けば電流の波形データの振幅が大きくなる。データはプリンターから紙に印字されて出てくる。
現場責任者をした経験がある別の男性によると、データの紙が雨水でぐちゃぐちゃになることはあるという。くい工事の中堅業者も「紙詰まりや紙切れもよくある」と話す。
しかし、この中堅業者は「記録を取れなければ、現場にいるゼネコンの担当者を呼び、掘削機のモーター音を聞かせるなどして確認してきた」と説明する。ドリルが支持層に当たれば、モーターの音が明らかに変わるからだ。
一方、工期に追われる下請け業者の事情を指摘する関係者もいる。くい打ち工事が実施されたのは2005年12月~06年2月。不動産価格が上昇し「ミニバブル」とも言われた07年の少し前で、建設需要は高かった。ある建設関係者は「多くの下請け業者が感じている工期厳守のプレッシャーもあったのではないか」と話す。
地盤に詳しい高橋学・立命館大教授(災害リスクマネジメント)によると、マンション周辺は鶴見川の後背湿地。6000~7000年前の縄文時代の海底に堆積(たいせき)した軟らかく湿った地層の下に約2万年前にできた谷があり、複雑な構造で基礎工事は難しいという。
慎重さが求められる現場で、ずさんな施工管理が横行していた。高橋教授は「地下は平らでない。基礎工事はより丁寧な作業が必要だ」と警鐘を鳴らす。【福島祥、岸達也】
消費者や取引相手の評価や商品の品質により、ブラントが確立される。品質が良くなくとも、CMなどのマーケティングでブランドイメージが確立される場合もあるので
良い品質=ブランドは成り立たないが、あまりにも品質が悪い、又は、あまりにも品質が悪いイメージが定着するとブランドの効果はなくなる。
ブランドを根拠に品質を良いと思うのではなく、時には自分なりの評価をするべきだと思う。そうすることによってブランドの会社は手を抜きにくいし、過去と同じ品質を
維持できない企業が改善できないと顧客は離れてしまうメッセージを送れると思う。
今回の問題は過去のブランドのイメージにとらわれず、最新の情報を収集する必要性もある事を被害者の可能性のある顧客に教えたと思う。
横浜市都筑区のマンションが傾いている問題に絡み、22日に旭化成建材が公表した過去約10年間のくい打ち施工のリストは計45都道府県で3040件にわたる膨大なものだった。うち、データを改竄(かいざん)したとされる男性の現場管理者が関わっていたのは1都8県で41件。会見した同社の幹部は「不安を与えて申し訳ない」と謝罪したものの、具体的な物件名が明らかにされることはなかった。「どう対応すればいいのだろう」。数字のみの公表に、自治体の担当者の間には困惑が広がった。
◆増幅する不信感
旭化成建材が公表した都道府県別のリストで、傾いているマンションのデータを改竄した男性の現場管理者が関わった41件の物件が所在する9都県には衝撃が走った。「うちの市なのか」「いつ旭化成から連絡が入るのか」。業者への指導監督などを行う自治体の関係者は頭を抱え、中途半端な情報開示に不信感を増幅させている。
41件のうち半数以上の23件が確認された愛知県。集合住宅に絞ると、全国13件のうち9件を占める。しかし、県内のどの自治体かは分からず、名古屋市の担当者は「なんでこういった報告になったのか」と不満を口にした。
名古屋市の人口は愛知県の約3割の約230万人に上る。集合住宅に住む名古屋市民に不安が広がることも想定されるが、担当者は「もっと詳細なリストを出してもらわないと手の打ちようがない。国や旭化成建材が出さないのであれば、市に関する部分だけでも出すよう申し入れせざるをえない」と語った。
県建築指導課の担当者も「県内の建物が含まれていると発表されただけでは対処のしようがない。書類改竄の有無など調査結果を速やかに出すべきだ」と指摘した。
◆どこが監督権限
現場管理者の手がけた物件が2件ある東京都。旭化成側の発表では「事務所」「工場・倉庫」としか分からず、担当者は「規模や場所が分からない以上、都か区か市か、どこが管理・監督権限を持つのか分からない」。
千葉県でも「用途不明」の1件が確認された。担当者はこの日、「旭化成建材側に詳細を問い合わせている。国や、建築に関する権限を持つ県内12市と情報共有しながら確認する」と説明した。
公共施設1件がある茨城県によると、リスト公表直後に問い合わせたが、同社は個人情報などを理由に公表を強く拒否したという。県建築指導課の担当者は「公の施設であり、行政として知らなければ対応できない」とした上で、「不特定多数の人が出入りするような施設かどうかも分からない。どうすれば把握できるのか、そのやり方から検討しなければならない」と憤った。
◆「ゼロ」でも不安
現場管理者が関わった物件はゼロの自治体でも不安感は残る。福島県内で旭化成建材がくい打ちで携わった物件は87件。うち学校は13件あり、県教委の担当者は「旭化成建材については全て工事の状況を確認しないといけない」とした上で、「旭化成建材は速やかに関係自治体に情報開示すべきだ」と求めた。
元請け業者も困惑する。東京都内の設備工事請負業者は3年ほど前から、全国で展開する太陽光発電パネル設置のくい打ち作業を旭化成建材に任せており、その件数は数十件に上る。
今回の発表内容に含まれているかも分からない状況といい、担当者は「『旭化成』ブランドだからこそ信用したのに、今回のようなことになった。何を基準に下請け業者を選んだらいいのか」と首を振った。
建設業界だけの問題ではないと思う。下請けが多い構造の産業は同じ問題を抱えているはず。問題が注目されていないだけと思う。
下請けが多くても、元請けや一次下請けがしっかりしていれば問題は少ないと思う。やり方はいろいろだろうが、多重下請けだから問題と言うのはおかしい。
元請けや一次下請けの監督がしっかりしていなくとも、コストを優先せずに信頼のある下請けを選ぶ、下請けが良心的であれば長期的に仕事を任せる等で
上手く回るケースもある。元請けや一次下請けの監督がかなりしっかりしていれば、コスト優先で下請けを選び、問題があれば下請けを変える、問題を直ちに
直させる事も可能である。ただし、すぐに良い下請けが見つかる、問題が簡単に修正できるかなどはその時の状況により変わる可能性がある。元請けや一次下請けの監督が
適切な監督や評価が出来ない状況で、問題のある下請けが多く入っている場合、結果は運次第。多少の問題で済むのか、問題だらけなのか、問題が発見されるのか、
問題が素人でもわかるような形で出てくるのか、ケースバイケースでしょう。
会社や監督の能力、判断基準、コスト、どのような下請けを使っているのか等のいろいろな要素が違うので、何が良いのかはコンビネーションと運次第。
全てを満たすようにすると確実にコスト高になる。上手くやればコストを抑えて、そこそこに良い物も出来る。問題は素人だけでなく、業界の人でも簡単には
判断できない事。例え、現場が変更を要求しても、その要求が妥当であるのか判断できる人達が上にいなければ、却下されるかもしれない。現場を知っていれば
何が無理なのか判断できるが、権限を持っているだけで背景や状況を理解できない人が無理なコスト削減を要求すると問題が起きる可能性は高くなる。
結局、素人にとっては運が強い事が一番の要素なのかもしれない。
工藤隆治、小林恵士
横浜市都筑区の大型マンションが傾いた問題で、杭のデータを偽装した現場責任者は、2次下請けの旭化成建材の社員だった。マンション建設には通常、何層もの下請け業者がかかわっている。業界関係者からは、元請けから工期を守るよう求められ、偽装が誘発されるとの指摘もある。
「工期が強いプレッシャーになったかどうか、ヒアリングしていきたい」
旭化成建材の親会社、旭化成の20日の記者会見。杭のデータ偽装や、杭が固い地盤(支持層)に十分届かなかった施工不良の背景に、工期やコストのプレッシャーがあったのではと問われ、平居正仁副社長はこう答えた。施工不良の杭8本は、3カ月の工期の終盤の2006年2月23~24日に施工されていた。
マンション建設は工程が細分化され、専門業者が多くかかわる。日本建設業連合会によると、工事を受注する元請けのゼネコンは全体の管理を担い、施工はしないのが一般的。杭打ちや基礎工事、柱や床を造る軀体(くたい)工事、内装工事など分野ごとに下請けに回す。内装なら下地や壁、クロス貼りに分けてさらに下請けに出される。今回の元請けの三井住友建設によると、少なくとも100社以上がかかわったという。
「現場は工期が最優先。下請けへのプレッシャーは常にある」。東海地方で大手業者のマンション建設や公共工事に長年携わる基礎工事技術者の50代の男性は明かす。
横浜市都筑区の大型分譲マンションに傾きが見つかった問題で、検査データの改ざんを行ったとされる旭化成建材(東京都千代田区)の現場責任者が作業に関わったのは30件程度に上ることが22日、わかった。
同社が過去10年間に手がけた全国の約3000件について、旭化成は都道府県別や建物種類別などの概要を同日午後、国土交通省に報告する。マンションや病院、学校などの名称は公表しないとしている。
旭化成はこの現場責任者が担当した30件程度について、杭くい打ち時の検査データの複写や加筆といった改ざんがなかったか、最優先で調査する。仮に改ざんが確認されたり、杭が固い地盤に届いていない疑いが出てきたりした場合には、現場で地盤調査や構造計算などを行って杭の状況と、建物の安全性を確認する。
国税局OBであれば、国税局がどのようなチェックするか、どのような事はチェックしないのか、国税局職員達が見落とす、又は、見逃しやすい点などについて詳しいであろう。 上手く振舞う姑息な人が得をして正直者がばかを見る事も知っていたのではないのか?まあ、国税局が脱税の方法が少なくなるほど良く働けば問題ないが、実際は、そうではないという事なのだろう。
システム開発会社に脱税を指南し、法人税3億4500万円を脱税させたとして、東京地検特捜部は国税局OBの税理士ら4人を逮捕しました。
法人税法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも国税局の元職員で元税理士の植田茅容疑者(70)と税理士の松本剛容疑者(54)、それに東京・府中市のシステム開発会社「システムソリューションズ」の実質的経営者2人のあわせて4人です。
特捜部などによりますと、システム社は3年前に法人税およそ3億4500万円を脱税した疑いが持たれていますが、その際、植田容疑者と松本容疑者は、脱税の手口を指南し、架空の外注先となる業者を紹介するなどしていたということです。
「『脱税指南』に乗っかってはいけません。」
「脱税もいけません。」(植田容疑者のブログ)
植田容疑者は国税局を退職後、税理士資格を取得。国税OBの経歴を売りに、税金に関する書籍やブログなどで顧客を集めていました。特捜部は、植田容疑者らが、他にも複数の会社に脱税を指南していた疑いもあるとみて、実態解明を進めるものとみられます。
国税局OBの元税理士らが出会い系サイトの運営会社に脱税の方法を指南し、およそ3億4500万円を脱税したとして、東京地検特捜部は、元税理士や税理士ら4人を法人税法違反の疑いで逮捕しました。
逮捕されたのは、いずれも国税局のOBで、元税理士の植田茅容疑者(70)と税理士の松本剛容疑者(54)、それに東京・府中市の出会い系サイト運営会社「システムソリューションズ」の実質的経営者、山邉英人容疑者(35)ら合わせて4人です。
東京地検特捜部の調べによりますと、植田元税理士らは、山邉容疑者らに架空の外注費を計上させるなどの脱税の方法を指南し、3年前、11億5000万円余りの所得を隠し、およそ3億4500万円を脱税したとして、法人税法違反の疑いが持たれています。
関係者によりますと、植田元税理士は国税局を退職したあと、会計事務所を実質的に経営し、「税のスペシャル大辞典」などと題したブログで節税の方法などを紹介していたということです。松本税理士は当時、植田元税理士の事務所に所属し、山邉容疑者らの会社の確定申告の手続きに関わっていたということです。
特捜部は、国税局OBの税理士らによる脱税指南の実態解明を進めています。
データを偽造した担当者が有罪であっても、何百億円の損害賠償は無理。補償の事を考えれば、偽計業務妨害罪が適用されようが関係ない。推測だが偽計業務妨害罪で 告発し、警察が受理すれば、加害者が特定出来なくとも警察は捜査を開始するであろう。
三井不動産グループが販売した大型マンション「パークシティLaLa横浜」(横浜市都筑区)の傾斜問題。700世帯を超える住民を怒りと悲しみのどん底に突き落としたのは、偽装データでデタラメな基礎工事を行った旭化成建材とその担当者だ。罪深き所業にどんな鉄槌が下されるのか。
マンションは全4棟で形成され、傾きが見つかったのは「西棟」。基礎に打たれた計52本のうち、南側の28本を調査したところ、6本が強固な地盤に未到達で、2本は届いていたものの深さが不足していた。19日から残り24本を調べており、工事の元請けで担当・管理した三井住友建設は、他の3棟についても調査を進めたい意向だ。
三井住友建設の2次下請けで、問題の基礎工事を行った旭化成建材の担当者は、社内調査に「データを記録する機械のスイッチを入れ忘れた」などと話しているという。
旭化成建材の前田富弘社長は、この担当者と当時の作業について「悪意を持って意図的に何らかの操作がされたことが推測される」とコメント。同社は、杭打ち工事に関わった約3000棟を調査中だが、再び不正が見つかれば、事態は新たな局面に入ることになる。
太平洋法律事務所の国府泰道弁護士は「データを偽造した担当者は、旭化成建材の業務を妨害した偽計業務妨害罪にあたる可能性がある」とし、続ける。
「偽計業務妨害罪は、3年以下の懲役か50万円以下の罰金に処せられる。この担当者が他にも不正行為を行っていた場合は併合罪が適応され、5割増しを上限として刑が確定する。つまり、4年半以下の懲役に処せられる」と話す。
元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏は「旭化成建材の人間と共謀して、1次下請け(日立ハイテクノロジーズ)をだまして報酬を得ていたのであれば、詐欺罪にあたる」と分析。ただ、担当者は自分のミスを隠すために改竄を行った可能性もあり、「報告書に嘘の内容を記載したとしても、自分の名前さえ正しく記載していれば、私文書偽造の罪にもならない」(若狭氏)という。
関わった会社の責任はどうか。若狭氏は「売り主と工事の元請け、1次下請け、旭化成建材の4社が、欠陥があると知りながら共謀してマンションを販売していたのなら、詐欺罪にあたる。担当者らには懲役10年以下の刑が下される」と解説する。
現在、国土交通省は三井住友建設、旭化成建材などに対し、建設業法に基づく行政処分を視野に調査を始めた。
「今回は、国交省が行政として調査に入っているため、改善指示などの行政処分が下ることになる。今後、警察が調査に乗り出し『会社としてすべき講習を行っていなかった』『主任技術者を置いていなかった』といった違反が明らかになった場合は、50万~100万円の罰金刑が下ることになる」(若狭氏)
多くの人々が泣かされている今回の問題。逃げ得は許されない。
日本政府が総合的に環太平洋パートナーシップ協定(TPP)にメリットを感じたのであろう。それとも、農産及び畜産組織よりも、工業関係組織の方が
政府に対してより強い影響力を持つのであろう。
合意した以上、なるようにしかならない。それ以外のことは個々の努力と選択次第。日本でも改善できる点もあるが、改善=たぶん、効率化のために仕事がなくなる
人々が出る(彼らは抵抗するので思うように改善できない可能性もある。)
TPPに反対しても合意した以上、関係者は出来るだけ影響の少ないソフトランディングを考えるか、いつ止めるか、それとも譲渡するか等を考えるべきであろう。
想定以上に世界の人口が増えたり、日本に必要な食料が入らなくなった時に、TPPは間違いだったと言う人はいるかもしれない。まあ、生産者の高齢化の問題もあるし、
TPPに合意しなくても問題はあると思う。
政府が環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の合意内容の全容を明らかにした20日、九州の消費者から輸入食品の値下げを期待する声が上がった。ただ2017年には再度の消費増税が予定されており、価格の下落に疑問を抱く人も。一方、生産者側からは「約束が違う」と強い批判の声が上がった。【青木絵美、野呂賢治、小原擁】
【消費者サイドからみたTPPのイメージ】
20日夕、福岡市中央区のスーパーで、同市早良区の荒木成子さん(59)と娘の利美さん(26)が280グラムで1980円の「アメリカ産」と書かれた牛タンをカゴに入れた。
3人家族で、夫と利美さんが大の牛タン好き。現在は12・8%の関税がかかっているが、TPPが発効すれば初年度に6・4%になり、以降は毎年半減し、11年目に撤廃される。荒木さんは「買いやすくなりそう」と歓迎する一方、「国産が売れず生産者が疲弊してしまう」と複雑な表情も浮かべた。
価格下落に懐疑的な見方もある。輸入パスタをよく購入するという熊本市中央区の主婦、篠(じょう)邦子さん(63)は「食料品全般の値段が下がれば家計は助かるが、消費増税もあるから、購入価格が本当に下がるだろうか」と話す。
スーパー側も影響を見通せない。西鉄ストア(福岡県筑紫野市)の広報担当者は「スーパーは末端で、間には商社やメーカーなどが介在する。お客様の価格への期待感に応え切れるかどうか分からない部分が多い」と語った。
一方、福岡県内の農林水産関連団体など計66団体でつくるTPP反対福岡ネット(福岡市)は20日、「国益にそぐわないTPPに断固反対」する特別決議を採択した。委員長の倉重博文・JA福岡中央会会長は記者会見し「政府は『農業を守った』というが守っていない。コメなど『重要5品目』は守るとした国会決議はどうなったのか。国会議員と意見交換して確かめたい」と述べた。
「会見の説明では、杭打ち作業を行った現場代理人は社内調査に対し『杭が固い地盤に届いていない、と思って作業したことはない。故意にデータの改ざんは行っていない』と説明している、ということです。ただ、現場代理人がなぜデータを改ざんしたのかについては明確な回答はありませんでした。」
「杭が固い地盤に届いていない、と思って作業したことはない。」が日本語の問題なのか、苦しい言い訳なのかトリッキー。「杭が固い地盤に届いた事を確認して作業をしてきた。」
ではないと言うことだ。例えば、死亡事故(殺人事件?)で容疑者が「刺したが殺そうと思って刺していない。」と言えば、事実は「殺そうと思って刺した。」であったら
どのように判断するのか?自白以外に間違いなく判断できるのか?
まあ、嘘であっても納得のいく説明が出来ない限り、簡単には幕引きできそうにもないようだ。
横浜市のマンションが傾いている問題で旭化成建材と親会社の旭化成の社長らが会見し、杭打ち作業を行った現場代理人は「故意にデータの改ざんは行っていない」と説明していることを明らかにしました。
「(現場代理人は)故意に不具合を隠すためにデータ転用は私は行っていないと言い続けています」(旭化成・平居正仁副社長)
会見の説明では、杭打ち作業を行った現場代理人は社内調査に対し「杭が固い地盤に届いていない、と思って作業したことはない。故意にデータの改ざんは行っていない」と説明している、ということです。ただ、現場代理人がなぜデータを改ざんしたのかについては明確な回答はありませんでした。
また、「旭化成」はマンションの改修工事にかかる費用については「全額負担する」としてきましたが、建て替える場合の費用負担については、販売した「三井不動産レジデンシャル」や元請けの「三井住友建設」と協議するという方針を明らかにしました。
また、国交省の指示を受け、旭化成建材が過去10年間に杭打ちを請け負った全国のおよそ3000件について都道府県ごとの内訳を22日までに国交省に報告する方針も明らかにしていますが、旭化成建材の前田社長は、この3000件について「データの改ざんがないとは言い切れない」と述べています。
横浜市都筑区の大型分譲マンションが傾いている問題で、工程確認や現場の安全管理などを担当した1次下請けの日立ハイテクノロジーズは、「事実確認をしている。まだ回答は差し控えたい」と答えた。
前身の日製産業の頃から、旭化成建材からくいなどの建材を調達し、元請けの建設会社に販売していた。現在は、今回のような大規模な工事からは撤退しているが、「過去の件は他も確認している。業績への影響は不明だ」とした。
親会社の日立製作所は、「状況を注意深く見守っている」とコメントした。
「横浜市のマンションでは建物を支える70本の杭のデータが改ざんされ、このうち8本は、固い地盤に届いていなかったり、十分に刺さっていませんでした。そして、この8本の杭は、いずれも3か月の工事期間のうち、最後の2週間に打ち込まれていたことが国土交通省などへの取材でわかりました。
杭の長さが足りなかった場合には、杭を追加で発注する必要がありますが、工事関係者によりますと、この時期に追加発注すると工事期間は1か月以上長くなってしまうということです。」
上記が事実であれば、原因や理由が絞れるのでは?後は関係者達がどう言うかだけのような気がする。しかし、工期の問題だと言えば、旭化成建材だけでなく他の業者も同じような事をやっていないかと疑念が
飛び火するのは確実だろう。
横浜市のマンションが傾いている問題で、固い地盤に十分に届かなかった8本の杭(くい)は、いずれも基礎工事の終了直前の時期に打たれたものであることがJNNの取材で分かりました。工事期間の大幅な遅れにつながる事態がデータ改ざんの背景となっていないか、国土交通省は調査する方針です。
横浜市のマンションでは建物を支える70本の杭のデータが改ざんされ、このうち8本は、固い地盤に届いていなかったり、十分に刺さっていませんでした。そして、この8本の杭は、いずれも3か月の工事期間のうち、最後の2週間に打ち込まれていたことが国土交通省などへの取材でわかりました。
杭の長さが足りなかった場合には、杭を追加で発注する必要がありますが、工事関係者によりますと、この時期に追加発注すると工事期間は1か月以上長くなってしまうということです。
国土交通省は、「工期を延長させられない」とのプレッシャーが杭の工事を行った旭化成建材にかかっていなかったかなどデータ改ざんの経緯を調査する方針です。
********************************************************************************************************************************************************************
平居正仁副社長「そこが本当に大事なところでございます。本人は『伝導計はあるんだ。支持層にきちんと到達したと言っている』。ですから本人の言い分についてもきちんと
調べて、なぜ発生したのか、彼が途中で十分でないまま仕事を辞めてしまったのか誤解があったのか、そこをきっちり調べない限り、一人が故意にやったのか組織的な問題なのか
、単に誤認したのか、すいません。まだ分かりません。そこを調べないと、今のご質問には答えられません」
誰も追及はしていないが、個人的な経験から言うと嘘を付く人達が存在すると言う事である。確実な証拠がなくても、いろいろな事実と言い分に食い違いある、ある部分について
嘘をついているケースでは、どこまで嘘を付いているのかまでは正確に把握できなくとも、嘘を付いていると判断できる。諦めて嘘を付いていた事を言うケース、いろいろな
根拠を提示しても、屁理屈や辻褄の合わない事を繰り返すケースなど個々のケースで全く違う。
「彼らがやってきた3千件の中で沈んだ物件はない。そういったことを考えると、そのような不具合を隠したなんてことを考えたとは思えない。」
不正を行っても、手を抜いても、すぐに形として現れないケースもある。飲酒運転を繰り返しても、捕まらないケースがあるのと同じ。あまりに手抜きがひどい、
地震、地形、建物の重量バランス分布など運良く、良い具合になっているケースもあると思う。建物の重量バランス分布が水平を保てるようになっており、固い地盤の
形状が傾斜しないような形になっていれば、建物の重量バランス分布が偏っていて、固い地盤が傾いている、又は、歪になっているケースと比べれば、傾斜も地盤沈下も
同じように手を抜いても全く違ってくると思う。
専門家でないので、あくまでも推測の話。建築業界の事ではないが手を抜いても、規則を満足しなくても、問題として認識されない程度のままのケースがあることを知っている。
だから問題があるケースは理由がある。理由があるから問題として認識される。しかし、「原因がある=問題となる」とならない。または、かなり長期のスパンでしか
問題にならないケースもある。
世の中、矛盾やおかしな事がたくさんある。そのような経験をしない人は幸せであると思う。
--少なくとも現場代理人は隠蔽の意図は持っていた
平居副社長「違います。持っている可能性があるのが一人ということです。彼らがやってきた3千件の中で沈んだ物件はない。そういったことを考えると、そのような不具合を
隠したなんてことを考えたとは思えない。ただ、その人に関しては事実と違うことを言っているかもしれないな。可能性の問題ではあるが、とにかく実態を調べたい。彼らが証言
していることが正しいのか嘘なのか、そこに嘘があったとするならば個人だったのか、組織ぐるみだったのか、そこをはっきりさせなければ、間違った方へ進む可能性はあるので
丁寧にやっていきたい」
********************************************************************************************************************************************************************
引用
--スケジュールの圧力はあったのか
前田富弘社長「そのような認識はない。当時は確かに忙しかったが、それはこれから調査していきたい」
--現場代理人の最初にヒアリングしたのはいつか。のべ何時間か。今回の原因は現場代理人一人の問題なのか、組織的な問題か
前田社長「一番最初にヒアリングをしたのは、三井住友建設さんから正式に改ざんということを伝えていただいたのは9月24日。直後の24日か25日からヒアリングを行っ
ている。私の記憶しているところでは22時間。その後さらにヒアリングをしているので22時間以上ヒアリングをしている。すべて弁護士さんではございません。私ども社員も
含めて、現場代理人には22時間行いました」
--原因は現場代理人か
平居正仁副社長「そこが本当に大事なところでございます。本人は『伝導計はあるんだ。支持層にきちんと到達したと言っている』。ですから本人の言い分についてもきちんと
調べて、なぜ発生したのか、彼が途中で十分でないまま仕事を辞めてしまったのか誤解があったのか、そこをきっちり調べない限り、一人が故意にやったのか組織的な問題なのか
、単に誤認したのか、すいません。まだ分かりません。そこを調べないと、今のご質問には答えられません」
--少なくとも現場代理人は隠蔽の意図は持っていた
平居副社長「違います。持っている可能性があるのが一人ということです。彼らがやってきた3千件の中で沈んだ物件はない。そういったことを考えると、そのような不具合を
隠したなんてことを考えたとは思えない。ただ、その人に関しては事実と違うことを言っているかもしれないな。可能性の問題ではあるが、とにかく実態を調べたい。彼らが証言
していることが正しいのか嘘なのか、そこに嘘があったとするならば個人だったのか、組織ぐるみだったのか、そこをはっきりさせなければ、間違った方へ進む可能性はあるので
丁寧にやっていきたい」
「(ほかに)傾いている物件はありません。傾いている物件は1件ですから、この物件の中にそれが起こっているのならば、その人しか可能性のある人はいないということな
んです」
--当該代理人の方は何日から何日まで工事をやっていたのか。病気で休んだときは別の人がいたのか、オペレータだけでやったのか
平居副社長「代理人がいなくて施工したということはありません。必ず代わりの代理人が来ている。ペーパーをもらうなど引き継ぎがうまくいかなくて、紛失したということは
あった」
--引き継ぎのペーパーをもらうのがうまくいかなかったというのは、どういう想定が?
平居副社長「想定でいうといろんな想定が立つんですけど…」
--何日くらい出てきていたのか
平居副社長「今は詳しい話は控えさせていただきます。ほとんど現場にはいた」
--工期にずれはあったか
平居副社長「もともとの予定通りの工期で終わったとのことです」
--3カ月間でこれだけのくいを打つのは、一般的なことなのか。70本というのは時期的にデータ改ざんの偏りはあるか
前田社長「工期が予定より長引いたということではない。工期が3カ月かかるという私たちにとっては非常に大きな物件であったと認識してください。8本については最後の工
事。70本については、ある時期に集中しているわけではない。430本で3カ月というのは普通の工期だと思う」
--支持層なのに未到達なのに、現場代理人以外で「辞める」ということは何人くらいが決めないといけないのか
平居副社長「チームの全員ですから。全員でないとできない。現場の人はあり得ないという。到達したと誤認することはある。チーム全員がそろって、『未到達だからやめた』
ということは、とても想像しておりません。それについては改めてご報告させていただきたい」
前田社長「補足させていただきますが、本当に一人の判断でできるかというと、できることではないだろう。支持層が非常に急峻(きゅうしゅん)な地形であることは間違い
ない。誤認ということも考えられないことではない。いずれにしても断定はできない。支持層に未達だったというのは8本なり6本が現在なっておりますので、それを基にすると
未達だった理由が、音だとか4つの判断材料がある中で、説明がつかない。断定はできないけれども、そこについては何らかの意図があってやった可能性はあると。ただ、ここに
ついてはもう一度正確に調査をさせていただかないといけない。今まで頂いている資料、地盤に関する調査資料はすべて元請けさまから頂いたものなので、今度は私どもも一緒に
入って調査し分析していく」
--ボーリングの人などもヒアリングしていると思うが。オペレーターなどのヒアリングの状況は
平居副社長「支持層に到達しなかった記憶はないと言っていますから、みんな支持層に当たったと言っている。信憑(しんぴょう)性についてはまだ何とも言えない」
--現場代理人一人ではできないと言っていた。チームがおかしかったということもあり得るのか
平居副社長「あり得るかもしれない。それも含めて考えたい」
--記録されたデータを転用したことを彼(現場代理人)は認めているんですよね
平居副社長「それは微妙なんですよね。やったことについて一部認めている。個別にこのくい、このくいとは認めていない」
--転用した理由は
平居副社長「理由については『紛失した。最後にまとめてやったから、どっかにいっちゃった。休みの日のデータはなかった』というようなことは言っている」
--休んだのはどのくらい?
平居副社長「3日間。(工期の)真ん中あたり」
今回の集団送還を受け、インターネット上では「運賃を着払いにして税金を節約しましょう」という“提案”まで現れた。しかし、法務省幹部は「『勝手に国を出て不法行為を犯した人間が帰ってくる費用を出す必要はない』と帰国を拒否しようとする国もある」と話し、国際社会との付き合いが一筋縄ではいかない実情を指摘した。
(6に続く)
藤尾 明彦 :ニュース編集部 記者
三井不動産レジデンシャルが販売した横浜市の大型マンション(2007年竣工)が傾いた問題で、10月20日、杭打ち工事を手掛けた旭化成建材とその親会社である旭化成が、初めて記者会見を開催した。出席者は、旭化成の浅野敏雄社長、平居正仁副社長、旭化成建材の前田富弘社長、前嶋匡・商品開発部長の4人だ。途中で旭化成の浅野社長が涙を流す場面もあった。報道陣との主なやり取りは以下の通り。会社側は調査委員会の委員長である、旭化成の平居副社長を中心に回答した。
――杭打ち工事のデータを改ざんし、支持層まで杭を打たなかった施工チームの現場代理人は、ヒアリングに対してどう答えているのか。
データ紙の紛失やデータ取得の失敗により、データを転用したことは認めているが、「不正を隠すために故意でやったことではない。杭も支持層に達したと思っている」と主張している。だが、主張には整合性が取れない部分もある。工事を手掛けた10年前の記憶と記録をもとに調査しているので、本当のことを言っているのか、ウソをついているのか、現時点で判断することは難しい。今後の調査で、杭の状態を実際見ることによって、多くのことがわかるはずだ。
現場1人の判断とは言い切れない
――杭が支持層に届いてなくても、届いたと誤認することはあるのか。届いたとの判断は、現場代理人1人が行うものなのか
今回の物件は、支持層の一部のエリアが深く沈んでいる、特殊な形状ではある。ただ、杭が支持層に届けば、必ず反動はあり、オペレーターは気付く。通常は現場管理人によるデータのチェックや、オペレーターの感覚など、すべて合わせて判断するもの。施工にかかわったチームの8人は、杭が支持層に届いたと認識しているが、10年前の記憶であり、さらなる調査が必要だ。
――現場管理人はどういう立場だったのか。杭の長さが足りなかった場合、杭を再度用意して打つことで、コストや工期を守れない、というプレッシャーがあったのではないか。
現場管理人は当時、旭化成建材の子会社から出向していた。現在は旭化成建材の契約社員だ。杭を再度打ち直す場合の費用は、元請け業者の三井住友建設が負担するので、旭化成建材にとって、追加のコスト負担にはならない。工期については当時、マンションの建設ラッシュで多忙だったので、ナーバスになっていたことはあるかもしれない。
――データの破損や紛失について、紙切れや紙詰まり、雨にぬれたなど、稚拙な理由を挙げている。その程度のことで重要なデータが取れないのか。現在も紙で記録しているのか。
2008年からは電子化され、メモリーカードで保存している。
――であれば、過去10年、旭化成建材が杭打ち工事を手掛けた3000棟のデータを調べるのは、すぐではないか。なぜ調査結果の発表に時間がかかっているのか。
データは電子化されているが、報告書はPDFで打ち出し、紙で保管している。データの転用があるかないかは、電流計のチャートの形を目で見比べて、同じような形が現れていないか確認する必要があるので、時間がかかる。
「『偽装のチェックまで今の法律は行政側に要求していないと思う』。年間約200物件を確認する東京都の飯塚睦樹・建築指導課長は戸惑う。現在の仕組みでは、杭を埋めた後に書類とヒアリングでチェックするしかない。『施工者のモラルの問題だ』と話す。」
人事のようなコメントだ。法律は人により作られ、改正や修正される。法律が時代や環境に合わなくなれば、改正や修正すればよい。「施工者のモラルの問題だ」と逃げるのなら、もっと検査を簡単にして、不正や損害が証明されれば、強制的に会社の資産を押さえ、
無理であれば、自己破産させて資産を売却して、銀行やその他の投資家よりも優先して被害者の補償に売却した資産を充てる事が出来るようにした方が良いのではないか。
「無理、出来ない」と簡単に発言し、増加する責任や仕事を避けようとするは典型的な役人の体質である。まあ、マイナンバー汚職で厚生労働省情報政策担当参事官室室長補佐が逮捕された事件
のように関係が深い業界や業者サイドの立場で権限や担当の役人が動けば、業界や業者に不利になるような対応や規則の制定などはないので、「無理、出来ない」という事があるかもしれない。
将来は天下りを考えている人達もいるかもしれないし、業者に嫌われながら仕事を増えるのを嫌う公務員も多いだろ。
マンションに住む予定も、住みたいとも思わないのでどうでも良いケースと言えば、どうでも良い事なのだが、無責任なお役所仕事には不満を持っている。もし、マンションを買った立場と
すれば、業者やお役所の対応は許せない。忙しい中で対応しないといけないし、どのような選択があって、どうするべきかと家族で話し合わなくてはならない。仕事が忙しければ、精神的な負担で
精神的にゆとりがなくなる。
行政が逃げ腰だから、行政には期待できない。三井不動産レジデンシャル、旭化成建材、そして三井住友建設がどのように対応するか次第であろう。
銀行や投資かも、企業のパフォーマンスにこれまで以上に関心を持ち、抜打ちで外部の専門家に依頼して工事作業を査定させる事をはじめるかもしれない。リスクが大きくなれば
リスク回避のための行動をリスクテイカーが取るか、リスクを取らない判断をするであろう。
横浜市都筑区の大型マンションが傾いた問題で、偽装された杭のデータは、建築時の検査をすり抜けていた。国も自治体も「見抜くのは無理」と口をそろえる中、消費者は安心してついのすみかを買えるのか。国土交通省はチェックを強化する検討を始めた。
「杭打ち工事のデータを偽装されると、見抜くのは事実上、無理だ」。横浜市の幹部はそう漏らす。今回、旭化成建材の工事担当者による偽装の対象となったデータは法令上、提出の義務がない。こうした不正はないという「性善説」に立って検査をしているためだという。
マンションなどを建設する際は、建築基準法など関連の法令に適合しているかどうかをチェックする建築確認検査が行われる。横浜市の場合、全国の自治体と同様に行政や民間の指定確認検査機関が行い、問題のマンションでは民間の検査機関が実施していた。検査費用は業者の負担という。
検査は、主に3段階。「着工前審査」では、設計図が問題ないかなどをチェックする。杭打ちなどの基礎工事の終了後には「中間検査」。さらに工事が正しく終わったかを調べる「完了検査」がある。
「セメントの量や固い地盤(支持層)に達したかなど杭打ち工事のデータは検査機関や市への提出義務がない」と市の担当者。仮に工事に疑問点があった場合に現場や、きちんと記録が残っているかの確認はするが、短時間だという。今回のマンションはすべての検査に合格していた。(豊岡亮)
■国、防止策を検討
「偽装のチェックまで今の法律は行政側に要求していないと思う」。年間約200物件を確認する東京都の飯塚睦樹・建築指導課長は戸惑う。現在の仕組みでは、杭を埋めた後に書類とヒアリングでチェックするしかない。「施工者のモラルの問題だ」と話す。
大阪市の担当者も「工事途中で何か通報でもない限り、行政で不正を知りうる機会はない。もし同様のケースが大阪市であったら、何かできたか」と悩む。
「三井住友建設は私たちの取材に対し、『地盤の深さの調査に失敗した。残念だ』『ただ、下請けの旭化成建材が杭を打った段階で、固い地盤に届かなかったというデータを出してくれれば、追加で杭を打てたため、問題は起きなかった』と主張しました。」
問題が起きた時に似たような事をいうケースはある。しかし、問題が起こる前だと、「みざる、いわざる、きかざる」を望むケースもある。問題を聞きたくない、言わないでほしいと
言う事。問題を聞いてしまったら、問題が起きた時に聞いていないと言い訳が出来なくなると言う事。問題を聞いていなければ、被害者としてアピールできるし、言わない人に
責任を押し付ける事が出来る。だから、言う人よりも言わない人の方が好まれる場合がある。全ては相手や企業次第。
今回のケースでは結果から判断して言ってほしかったケースかもしれない。しかし、今回のように最悪のケースになるまでそのように思わないかもしれない。結局、結果論
なんだろう。
横浜市の大型マンションが傾いている問題で、原因となった8本の杭(くい)が固い地盤に到達するには、設計の段階で2メートル程度短かったことがJNNの取材でわかりました。
「午前10時15分です。地盤調査を行うための専用の機械がマンションの中へと運び出されていきます」(記者)
マンションの建設を行った三井住友建設などによる地盤調査が始まりました。建物を支える杭が固い地盤に届いているかを改めて調査するものです。
なぜ、問題の8本の杭は、固い地盤に届かなかったのでしょうか。工事の施工業者や住民説明会で配られた資料によりますと、最新の地盤調査では、問題の8本の杭のまわりの固い地盤は、地中の深さ16メートルほどの深さにあることがわかりました。しかし、マンションの建設を行った三井住友建設は、設計の段階で8本の杭をすべて、14メートルとしていたのです。つまり杭は「2メートル程度足りなかった」のです。
「杭のことなんて分からないじゃない。ちゃんとしてると思って買っているから」(マンションの住民)
「普通考えられないし、びっくり。感想も何もないです」(マンションの住民)
ではなぜ、杭は2メートルほど足りなかったのでしょうか。マンションを建設した三井住友建設はJNNの取材に対し、杭が2メートルほど短かったことを認めた上で、設計する際のボーリング調査にミスがあったとしました。およそ10年前の調査では、三井住友建設は、14メートルの杭でも固い地盤に刺さるはずだったと想定。しかし、実際には、固い地盤は想定より2メートル以上深かったというのです。
三井住友建設は私たちの取材に対し、「地盤の深さの調査に失敗した。残念だ」「ただ、下請けの旭化成建材が杭を打った段階で、固い地盤に届かなかったというデータを出してくれれば、追加で杭を打てたため、問題は起きなかった」と主張しました。
横浜市や国土交通省は、三井住友建設や旭化成建材への行政処分を視野に、データの改ざんや杭の長さを決める調査の適切性について聞き取る方針です。
旭化成建材に対する処分は当然だ。厳しい処分が必要。
三井住友建設に対しては国土交通省の解釈次第。「不誠実な行為」の解釈を明確にしてほしい。
横浜市のマンションで建物を支えるくいの一部のデータが偽装されていた問題で、国土交通省は、くいの工事を請け負った旭化成建材や、工事の元請けの三井住友建設について、建設業法に違反している疑いもあるとして、今後、さらに詳しく調べたうえで、行政処分なども検討することにしています。
この問題は、横浜市都筑区のマンションで、建物を支える70本のくいのデータが偽装され、一部は必要な深さまで達していなかったものです。
これまでの会社などの説明によりますと、くいの工事を請け負った旭化成建材の担当者は、ほかのくいのデータを流用したり書き換えたりしていたということですが、工事の元請けの三井住友建設もデータの改ざんや施工の不良を見過ごしていたということです。
建設業法では、契約と異なる不十分な工事が行われるなど「不誠実な行為」をしたり、建築基準法違反などが明らかになったりした場合には、国は業務改善命令や営業停止などの行政処分ができると定められています。
国土交通省は、データの偽装を行った旭化成建材や、それを見過ごしていた三井住友建設などの一連の行為が、建設業法に違反している疑いもあるとして、今後、さらに詳しい調査を行い、行政処分が必要かどうか検討することにしています。
文部科学省は19日、8月に結果が公表された今年度の全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)で、千葉県の公立中学校の生徒34人分の「数学B」について採点漏れがあったと発表した。
採点漏れは、2007年度に学力テストを再開して以降初めて。
文科省によると、委託先の「JPメディアダイレクト」が、同校から提出された解答用紙のデータを間違えて削除し、採点していなかったという。
同校が今月15日、応用力を問う数学Bの結果が成績票に記載されていないことにに気づき、発覚。解答用紙は保存されており、文科省は近く、採点結果を同校や地元教育委員会に報告する。
「建設業法は契約への不誠実な行為をしたり、建築基準法など他の法令に違反したりした場合、国などが営業停止などの処分ができると定めている。」
「不誠実な行為」の定義はあるの?建築物の安全に影響を及ぼす杭の深度の改ざん及びセメントの量の改ざんは「不誠実な行為」?それとも
故意に杭の深度及びセメントの量を変更した事が立証されなければ「不誠実な行為」と断定されないので営業停止などの処分はないのか?
建設業法次第(「不誠実な行為」の定義があるのか?)で旭化成建材の運命が決まるかも?
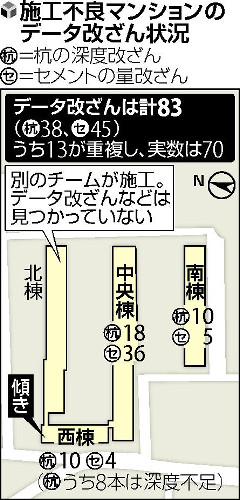
横浜市都筑区の大型分譲マンションに傾きが見つかった問題で、杭くい打ち工事を請け負った旭化成建材(東京都千代田区)の現場責任者が、掘削データを紛失するなど管理が極めてずさんだったことが、親会社の旭化成(同)の内部調査で明らかになった。
データ管理は現場任せで、元請けの三井住友建設(中央区)も報告をこまめに求めていなかった。国土交通省は、三井住友建設と旭化成建材などの行為が建設業法に違反する疑いもあるとして調査を始めた。
建設業法は契約への不誠実な行為をしたり、建築基準法など他の法令に違反したりした場合、国などが営業停止などの処分ができると定めている。
マンションは三井住友建設が施工し、三井不動産レジデンシャル(中央区)が販売した。工程管理などを担当する1次下請けは日立ハイテクノロジーズ(港区)が参加し、2次下請けで杭打ち工事を旭化成建材が担当した。
「横浜市の担当者は『不正を見つけ出す検査ではなく、性善説で運用している制度だ。くいの深さをわざわざ抜き打ちしてまで確認しない』と話す。『市内では1年間に約1万5000件の建築確認が申請されており、今回のような不正を見抜くことは不可能に近い』と苦渋の表情を浮かべる。」
「性善説で運用している」のような言い訳は他の不祥事で何度も聞いている。同じ事を繰り返すのは怠慢か、ばか。
「くい打ちなど地中の工事は終わっており、業者の施工結果報告書の記載内容を信じるしかないのが実情だ。」
性善説は機能しないし、時代遅れである。役所としては問題が起きるたびに言い訳として使いやすいが、被害者としては許されないし、損害に対して全額補償されるケースは少ない。
横浜市は本当に不正が行われるのを防ぐ、又は、減らしたいと思うのであれば、国交省にくい打ち作業の企業を認可制にする、そして/または、管理者及びオペレーターに資格を要求して
責任を明確にするべきだ。問題を起こした企業は認可を取り消す、そして/または、不正に関与した管理者及びオペレーターの資格を無効にすれば良い。不正はなくならないが
不正に関与する人々は減るし、企業も管理及び監督に注意を払うようになるであろう。
横浜市都筑区の大型マンションが施工不良で傾いている問題で、基礎のくい打ち工事で偽装データを使った旭化成建材の現場担当者が「工事のデータを記録する機械のスイッチを入れ忘れ、データを取り忘れた」と話していることが、同社への取材でわかった。傾いたマンションの基礎を支えるくいのうち、6本は強固な地盤(支持層)に達しておらず、2本も支持層に十分差し込まれていなかった。
旭化成建材は、くいが支持層に達していないことを現場担当者が知りながら、それを隠蔽(いんぺい)するためデータを偽装した可能性もあるとみており、今後は第三者も交えて調査を本格化させる方針。
マンションは4棟あり、西棟が約2センチ傾いている。施工会社は三井住友建設で、旭化成建材が2次下請けとして2005年12月~06年2月に基礎工事を実施した。2チーム(各3人)がそれぞれ掘削機を使って4棟のくい計473本を打ち込んだ。
しかし、このうちくいが支持層に届いたかを確認するデータが他のデータを転用していたり、加筆されていたりしたのが中央棟で18本、南、西両棟で各10本あった。
くいを補強するためのセメント量のデータが偽装されていたのは中央棟で36本▽南棟で5本▽西棟で4本--だった。
13本は二つの不正が重複しており、データが偽装されていたくいは計70本になる。
旭化成建材はこれまでの社内調査や関係者への聞き取りを踏まえ、データ偽装をしていたのは1チームで、その現場担当者が主に偽装していたとの見方を強めている。不十分だった西棟のくい8本について、現場担当者は「基礎のくいは支持層まで達していた」と話す一方、「データは取り忘れた」と主張。更に偽装の理由を尋ねても「覚えていない」などと不自然な説明をしているという。この点について同社は「説明がつかない。意図的な、何らかの操作があったのではないか」とみている。
施工管理に関するデータは、本来は毎日、発注者に報告しなければならないという。しかし、旭化成建材は「最初は整理できていたが、工期終盤には整理がずさんになった可能性がある」としている。データ管理とチェック体制に不備がなければ今回の問題を防げた可能性が高く、同社は「チェックや管理のあり方に不備があった」と組織上の問題も認めた。
同社によると、現場担当者は職場経験が15年程度のベテラン。同社は今後、第三者を交えて詳しい経緯を調べるとともに、この現場担当者が携わった他の建物の基礎工事に不備がなかったか調査する。【岸達也、山田奈緒、水戸健一】
◇検査では発見は困難
建築基準法施行令は、マンションなどの建築物について、構造上安全なものとするよう定めている。違反の場合、設計者や施工者に対する罰則規定もある。
問題のマンションは横浜市が2005年11月、着工を認める建築確認済証を交付し、くいを打ち込む工事は翌12月から06年2月にかけて実施された。直後の06年3~4月、東京都内の民間検査機関が建築基準法に基づく中間検査をしている。
中間検査は、建築確認の申請通りに施工され、安全に基礎が作られたかを、現地で書類や図面を見ながら調べる。しかし、くい打ちなど地中の工事は終わっており、業者の施工結果報告書の記載内容を信じるしかないのが実情だ。問題のマンションはこの報告書の記載内容の一部が虚偽だった。
横浜市の担当者は「不正を見つけ出す検査ではなく、性善説で運用している制度だ。くいの深さをわざわざ抜き打ちしてまで確認しない」と話す。「市内では1年間に約1万5000件の建築確認が申請されており、今回のような不正を見抜くことは不可能に近い」と苦渋の表情を浮かべる。【水戸健一、国本愛、内橋寿明】
「前田社長は記者団に対し、責任者がデータ記録の報告を正しく行っていなかったことなどを指摘しながら、『記録を最終的に提出する段階になって、紛失するなどしていたため、他のデータを流用したと本人は言っている』と明らかにした。」
社長が直接責任者から聞いたのだろうか。社長でなくその他の社員が責任者に聞いたのなら、よくこのような報告書を提出するものだ?とにかく提出しなければならないから
言われたとおりに記述したのだろうか。この言い訳が信用されると思うのだろうか?
責任者は故意に不正を行った事を認める事から逃げているように思える。補償する額や損害がとてつもないので認めたくないのであろうが、適切な調査が出来なければ
旭化成のブランドは大きく傷つくだろう。消費者がどのように考えるかは消費者次第なので結果を見守るしかない。
毎日整理しなくとも、記録さえ、残っていれば後になってもまとめられる。記録や計測情報があれば問題ない。ゼネコンに提出するのはわかっているはずである。
この責任者は責任者になってから、同じようなずさんな報告書を提出し続けてきたのだろうか?この責任者の報告書を旭化成建材の上司は目を通す事はなかったのだろうか?
目を通した事がなければ管理及び監督が出来ていない会社と判断しても良いのでは?
横浜市都筑区の大型マンションに傾きが生じた問題で、杭くい打ち工事を請け負った旭化成建材(東京都千代田区)の前田富弘社長は16日夜、計70本の杭の地盤データなどが改ざんされた経緯について、記者団に「(現場責任者が)施工のデータ記録を毎日整理し、ゼネコンに提出しなくてはならないのに、途中からルーズになった」と説明した。
一方、社長らが出席して16日夜に始まった住民説明会は、17日未明までの延べ7時間に及び、出席者からは怒りの声が相次いだ。
前田社長は記者団に対し、責任者がデータ記録の報告を正しく行っていなかったことなどを指摘しながら、「記録を最終的に提出する段階になって、紛失するなどしていたため、他のデータを流用したと本人は言っている」と明らかにした。データ改ざんは今のところ、この現場責任者の男性が行ったとみられるという。
「杭のデータ改ざんは70本 いずれも同じ管理者ら担当」が事実ならパズルではないがかなり繋がってきた感じがする。
ここまで来れば関係者が不正を認めるのか、なぜ不正を行ったのか、データやレポートを管理する人間は誰なのか、そしてデータに関して疑問を抱かなかったのか、
基礎工事のくいのオペレーターは
2015年第1回「ISO機械状態監視診断技術者(振動)資格認証試験」訓練コース(旭化成エンジニアリング)のような訓練コースを取った事があるのだろうか?
何かしらの訓練コースを受けたことがあるのであれば、それは役に立ったのか?今回は、隠ぺいのための単なる言い訳なのか?
開けない人はここをクリック
横浜市のマンションが傾いている問題で、データが改ざんされていた基礎工事の杭が合わせて70本に上り、いずれも同じ現場管理者とオペレーターが担当していたことが分かりました。
横浜市都筑区のマンションでは、建物を支える杭の一部が固い地盤まで届いていないにもかかわらず、届いているかのようにデータが改ざんされていました。さらに、16日の住民説明会で、杭の先端を固定するセメントの量にも改ざんがあったことが分かりました。杭打ちを請け負った旭化成建材によりますと、改ざんされた杭は70本に上るということです。
マンションの住民:「(きのうの説明会は)いたちごっこというか、あまり先には進んでない感じでした。補償は何に関しても相談して決めなきゃいけない」「もう何か心配だらけです。まだ詳細が分からないので…」
70本の工事は、いずれも同じ現場管理者と機械を扱うオペレーターが担当していたということです。旭化成建材は、この2人が関わった建物が他にどれほどあるのか調査を進めるとしています。
「基礎工事を実施した会社の親会社『旭化成』によると、データ確認を担当した現場管理者の男性は、虚偽データの使用について『覚えていない』と話したという。」
「覚えていない」との回答はとても重大な回答だ。覚えていられないほど手抜き工事を行ってきた、又は、幼稚な言い訳。現場管理者と言うことは、それなりの知識と
経験があると言う事。今回の手抜きがこのマンションだけであるなら、罪悪感なり、失敗したとの特別な感情のために覚えている可能性が高い。それが、「覚えていない」と
なれば覚えられないほど、手抜き工事を行った可能性が残る。単なる幼稚な言い訳であれば良いが、そうでなければ、この問題は、独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)の排ガス不正
と比べれば小さいが、手抜き工事の常態化を疑ったほうが良いであろう。現場管理者だけでなく、数値を計測する人間も経験や知識の違いはあれ、問題があるのでは
と考えていたかもしれない。旭化成建材の社員なのか、下請けの社員なのかは知らないが、同じ作業を繰り返していればどのような状態になれば、どのような数値が出るのかは
理論をしらなくとも、経験から推測は出来ると思う。残念ながら、下請けであれば、仕事を失うリスクがあるので何も言えないし、何も言うなと言われている可能性は高い。
事実については行政がどこまで踏み込む権限を持ち、真実をどのくらい調査したいか次第であろう。加害者側の企業や人間は必要以上に情報は出したくないはずである。
傾いていることが発覚した横浜市都筑区のマンションは、施工時にくいの一部が固い地盤(支持層)まで届いていなかった上、検査データの改ざんだけでなく、16日にはコンクリート量に関するデータの改ざんも明らかになった。建物の基礎になる重要な工事だけに、専門家は「理解しがたい」と口をそろえる。一度建ってしまえば、不具合が出るまで見抜くことは困難で「犯罪に近い」との声も上がった。
東北学院大の山口晶教授(地盤工学)は「数本であっても、くいの位置次第では建物に不具合が生じる可能性がある。基礎工事をおろそかにすると、いずれ問題になるのは明らか。その重要性を知っていれば、考えられないことだ」と疑問を呈する。
さらに「大量のくいを使う工事だったので、少しなら良いだろうという甘い考えがあったのかもしれない」と推測した。
山口教授によると、発注する側には技術者への信頼がベースにあり、通常はデータが改ざんされるという想定をしていない。完成後にくい打ち工事の不備に気付くことも難しいという。
1級建築士でNPO法人「建築Gメンの会」の田岡照良副理事長も「くいの施工中でなければ、第三者が後になって見抜くことは不可能だ」と断言した。
だからこそ、責任は重い。基礎工事を実施した会社の親会社「旭化成」によると、データ確認を担当した現場管理者の男性は、虚偽データの使用について「覚えていない」と話したという。
東海大の藤井衛教授(建築基礎工学)は「通常では考えられない。データを改ざんしたのなら、犯罪に近い」と憤りの声を上げた。
◆「見抜くの難しい」 データ虚偽で市
三井不動産グループが販売した横浜市都筑区のマンション傾斜問題で、明らかになったくいの施工不良や虚偽データの使用。市は住民説明会が終わるのを待って、週明け早々にも事業主らから内部調査の進捗(しんちょく)状況を聞き取る考えだ。市の担当者は「今回だけの特殊なケースなのか他にも波及するのかわからない。原因が特定された上で対応策を検討していく」としている。
市建築局によると、市内の建築確認申請数は年間約1万3千~1万5千件。そのうち98~99%を民間の指定確認検査機関が担っており、今回のマンションも民間の検査機関が担当した。
検査機関は、施工前に建築計画が建築基準法などに適合しているかどうか書類で確認。着工後に中間検査として1~2回工事の進捗状況を目視確認する際にはすでに工事が進んでおり、くいは見ることができない。
くいを打ち込んだ際の詳細なデータは施工記録として施工者が保管。民間検査機関や行政に提出する義務はない。検査機関が求めれば確認できるが、「今回のようなデータ転用は見抜けないのでは」と市担当者は推測する。
民間検査機関が担当した物件でも建築計画の概要書は市に提出される。しかし、建築主や住所といった項目に限られ、くいの施工状況がわかる内容ではない。市が担当した場合は独自にくいの施工報告書を中間検査前に任意提出するよう要請するが、細かいデータの添付は求めていない。担当者は「例え市が担当していたとしても虚偽を見抜くのは難しかっただろう」と話す。
林文子市長は15日の会見で「あってはならないこと。憤りを感じている。根本的な原因を追及し、再発を防ぎたい」と話した。
三井不動産グループが販売した横浜市都筑区のマンションが施工不良で傾いている問題で、マンションの基礎工事でくいの底を固めるためのコンクリート原料のセメント量のデータも改(かい)竄(ざん)されていたことが16日、分かった。3棟の計45本で行われ、うち傾いているマンションのものは4本。地盤の強度データが改竄された分と合わせ計70本分となり、うち13本で両方の改竄があった。くい打ち施工した旭化成建材の親会社である旭化成が明らかにした。
旭化成によると、くい打ち施工で地中に開けた穴に流し込むセメントの量を測る流量計のデータについて他のデータを転用・加筆。穴の底を固める作業で、量が少ない場合は強度が下がる可能性がある。地盤の強度データが改竄された3棟のくいで行われたことから、改竄は同じ担当者が実行した可能性が高い。
また、旭化成は、旭化成建材がくい打ち施工したデータがある約3千棟について、所在地などの概要を月内にも公表する方針。
マンションでは16日も説明会が開かれ、三井不動産レジデンシャルの藤林清隆社長と旭化成建材の前田富弘社長が出席。前田社長は説明会後、記者団に改竄の理由について「(強固な地盤である「支持層」への)くいの未達を隠すためにやったと推測できる」と語った。データ改竄に関わった担当者が「途中からルーズになった」とも話し、全国で他にも関わった建築物があることを明らかにした。
1棟が傾いたのはくいの一部が支持層に届いていないことが原因とみられる。通常は穴を掘るドリルに電流を流して土の抵抗を計測し、くいが支持層に届いたことを確認する。今回は4棟のくい計473本のうち3棟の38本でデータ取得に失敗し、他のくいのデータを転用するなどしていた。
神奈川・横浜市の大型マンションの施工不良問題で、16日夜、住民説明会に出席した旭化成建材の社長は、会見で、偽装は70本のくいで行われ、さらに、ミスを隠すために、意図的に行われた可能性も示唆した。
旭化成建材の前田富弘社長は「今回、マンションの住民の方に、大変なご迷惑をおかけいたしておりますことを、誠に申し訳なく思っております。まず、皆様方に安心して住んでいただけるように、誠心誠意努めてまいりたいと考えております。
申し訳ございませんでした。(住民説明会で、新たな改ざんあったというが?)電流計の改ざんが38本、それから、流量計の新たに見つかった改ざんが45本、合計すると、83本。重複しているものがあるので、70本ということになります。
実際に、くいが未到達だったという事実を考えると、何らかの事由で、くいの未到達ということを知っていた可能性がある。それを隠そうとしたということは、少なくとも8本に関しては、推測ではあるが、かなり可能性が高い」と述べた。
独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)の排ガス不正でドイツに対する良いイメージに影響を与えたのでないかと思う。そして、不正の背景やドイツ政府やドイツ人の
対応の情報はさらに良いイメージに傷を付けたのではないかと思う。
[ベルリン 15日 ロイター] - 排ガス不正問題を引き起こした独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)<VOWG_p.DE>に対し、米規制当局の厳しい姿勢とは対照的に、ドイツの政治家や当局者は慎重に接している。
「メード・イン・ジャーマニー」ブランドの代表格であるVWへのダメージを極力抑えようと、メルケル独首相は先週に行った演説の中で、同国の約7人に1人が働く自動車業界の側に立つと約束した。
VW本社のあるニーダーザクセン州のバイル州首相は13日、「ドイツ産業の真珠」である同社は共に戦う価値のある企業だと称賛した。
一方、ドイツ規制当局もこのスキャンダルについて、非常に素っ気ない声明を出すだけで、問題のある対象車をいかに修理するかに注力したいようだ。
これは、比較的規制が緩やかなドイツの慣習を踏襲している。
金融危機を受けて英米や欧州連合(EU)の規制当局は銀行に対し、何十億ドルもの制裁金などを課した。その中には独銀行最大手のドイツ銀行<DBKGn.DE>も含まれていたが、独連邦金融監督庁(BaFin)はほとんど沈黙を守っていた。
今回のVWの場合では、連邦金融監督庁は不正発表前後の状況について「いつも通りの調査」を行っているとしている。
だが、VWが米規制当局との電話会議で9月3日に不正を正式に認めてから公にするまでに2週間以上を要している。
ドイツでは、新車の承認や、新車の環境基準への適合検査はともに連邦自動車庁(KBA)の管轄となっている。一方、米国では、排ガス規制は自動車業界とは離れた環境保護局(EPA)が行う。
<不正ソフト>
KBAは15日、VWに対し、国内で対象車240万台のリコール(無償回収・修理)を強制する方針を示したが、VWが不正ソフトを搭載した対象車計1100万台のリコール計画を同庁に提出してからすでに約1週間経っていた。
KBAの報道官は、自動車メーカーの不正に対してペナルティーを科した前例はないと語った。一方、米国のEPAは、VWが最大180億ドル(約2.1兆円)の罰金を科される可能性があるとしている。
ドイツと米国の対応の違いは、米EPAが2016年のディーゼル車モデルを承認しないとVWを脅したことでも鮮明だ。この脅しが、VWに不正を告白させるに至った。
米司法省は数日のうちに刑事捜査を始め、ニューヨーク州などの州検事総長も合同捜査を開始した。
先週には米下院公聴会でVW米国法人トップが追及を受け、同英国法人社長も今週、英議会に引きずり出された。
一方ドイツでは、引責辞任したウィンターコルン前最高経営責任者(CEO)もミュラー現CEOも、今のところ議会で証言するような状況に立たされてはいない。
また、ドイツ検察当局がVW本社や関連先の家宅捜索を始めたのは、約3週間も経過した後だった。
<国民の支持>
VWのスキャンダルは米消費者の激しい怒りを買い、同社は数多くの訴訟に直面している。それに比べてドイツ国民の反応は控えめであり、自国の優れたエンジニアリングの代名詞である同社を多くの人は非難したがらない。
今年出版されたドイツ人に関する書籍「How Germans Tick」によると、ドイツと言えば何を連想するかをドイツ人に聞いたところ、63%がフォルクスワーゲンを挙げたという。
また、市場調査団体パルスが先週発表した調査では、54%が今でもVW車の購入に興味があると回答し、最も多かった。一方、もう二度と買わないと答えた人は11%、当分の間は買わないと答えた人は35%だった。
愛する自国ブランドに対する米国の取り締まりは、反米感情にも火を付けている。一部のドイツ人は米国の厳しい反応について、欧州最大の自動車メーカーであるVWを弱体化しようとする意図的な行為だと考えている。
米国への疑念はすでに、ドイツに対する米スパイ活動が報じられて以来、拡大していた。首都ベルリンでは10日、欧米間の環大西洋貿易投資連携協定(TTIP)に反対する25万人規模のデモが行われた。
フェイスブック上では、「VWは米国にとって目の上のたんこぶ」「VW、アウディ、シュコダ、セアトは今でもとても良い車。米国人は欧州の自動車メーカーをねたんでいるだけ」といった投稿も見られた。
(Caroline Copley記者、翻訳:伊藤典子 編集:下郡美紀)
「スイッチ忘れた、記録紙濡れた」は事実だろうか?もしくいが打ち込まれる地盤の強度に問題があった箇所だけ施工データを転用・加筆が行われて
いれば、判断できる人が見れば問題があることをデータで判断される事を回避するために故意に行った可能性がある。本当のデータがあれば、
後に検証された時に、問題がある事がもっと早く明らかになったはずである。問題が発覚した時に、「スイッチ忘れた、記録紙濡れた」と言えば、
グレーゾーンとして逃げ切れる可能性もある。
事実が出てくるのかは不明であるが、今後の記事に注目したい。
横浜市都筑区の大型マンションが施工不良で傾いた問題で、くい打ち施工を行った旭化成建材の工事担当者が「地盤の強度データを記録し損ねた」と、他の地盤データを転用・加筆した理由について説明していることが15日、旭化成への取材で分かった。
旭化成によると、同マンションの基盤工事では、くいが打ち込まれる地盤の強度は計器からプリンターで打ち出されることになっていたが、工事担当者は聞き取り調査に対し、「プリンターのスイッチを押し忘れたり、記録紙が泥で汚れたり、雨でぬれたりして、きちんと記録できなかった」などと話し、データが適切に記録できていなかったことを認めた。
その上で、「同じマンションの敷地内の他のくいのデータをコピーしたり、書き足したりした」などと転用や加筆の状況を説明。これらのデータは傾いたマンションだけで10本分あった。結果的に、10本のうち6本は強固な地盤である「支持層」に達しておらず、2本は支持層に到達してはいたが、打ち込みが不十分だった。
旭化成などによると、同マンションでは建設中の平成17年12月から18年2月の間に、4棟で473本のくいが打たれた。うち傾いた建物を含む3棟で計38本分のデータに転用や加筆があったとしている。いずれも傾いた建物のケースと同様に、データの取得に失敗したのが転用などの理由という。旭化成はデータ取得に失敗した状況について、さらに詳しく調査する。
この問題について、施工主の三井住友建設も「下請け業者が施工データを転用・加筆して(三井住友建設に)提出した」と説明している。横浜市は、同マンションのくいが支持層に達していなかったことが、建築基準法違反にあたる可能性があるとみて調査する。
「三井不動産グループが販売した横浜市都筑区のマンションで、くいの施工不良による傾きが見つかった問題で、打ち込んだくいが固い地盤に届いたことを記すデータは、建築確認を行う市や、その代理の民間検査機関に提出する仕組みになっていないことが、市などへの取材で分かった。専門家は『建設中にデータを確認していれば転用を見抜けた可能性がある』と指摘している。
市によると、業者は建設前、地盤の大まかな状況を調べ、想定されるくい打ちの深さを検査機関に報告するが、着工後に行ったくい打ちのデータの報告は求められていない。ただ、検査機関は工事中にも現場を確認するため、くい打ちの深さに疑問があれば、データの提出を業者に求めることがあるという。」
「業者は自治体にデータを提出する法的義務はなく、検査機関や市は虚偽だと見抜けなかった。国土交通省によると、自治体や検査機関によって『対応はまちまち』という。市の担当者は『現場で疑問がなければ、必ずしもデータと照合する必要はない』と説明。首都圏のある自治体の建築部局職員は『くいの他にも膨大な書類があり、全て点検していたらきりがない』と話す。」
今回の件で明らかな事は、業者や施工者が悪意や不適切なコスト削減の理由で手を抜く事は法的に可能である事。今回のように、不正が証拠などにより証明されない限り、
購入者が手抜きや欠陥を証明する事は難しい。「首都圏のある自治体の建築部局職員は『くいの他にも膨大な書類があり、全て点検していたらきりがない』と話す。」のが
事実であれば、システムや規則に詳しければ、それを利用して手を抜く方法もあると言う事。「業者は自治体にデータを提出する法的義務」はないについては法的義務を
負わせるべきであろう。例え、全てをチェックできないとしてもデータを提出する事が義務となれば偽造するケースも減るだろうし、裁判となっても証拠を自治体が保管していれば
はやく裁判は終わるであろう。
このまま、現状と同じように、業者は自治体にデータを提出する法的義務はないとするのか、改正するのかは、国土交通省及び地方自治体次第。
業者、市へ検査甘さ指摘も
三井不動産グループが販売した横浜市都筑区のマンションで、くいの施工不良による傾きが見つかった問題で、打ち込んだくいが固い地盤に届いたことを記すデータは、建築確認を行う市や、その代理の民間検査機関に提出する仕組みになっていないことが、市などへの取材で分かった。専門家は「建設中にデータを確認していれば転用を見抜けた可能性がある」と指摘している。
市によると、業者は建設前、地盤の大まかな状況を調べ、想定されるくい打ちの深さを検査機関に報告するが、着工後に行ったくい打ちのデータの報告は求められていない。ただ、検査機関は工事中にも現場を確認するため、くい打ちの深さに疑問があれば、データの提出を業者に求めることがあるという。
今回のケースでは、くいを打った旭化成建材はデータを計測し忘れたり、紙に印字された数値がかすれたり、雨でデータが読み取れなかったことがあったため、別のくいで計測されたデータを転用したり加筆したりして、元請けに提出する報告書に記載していた。
業者は自治体にデータを提出する法的義務はなく、検査機関や市は虚偽だと見抜けなかった。国土交通省によると、自治体や検査機関によって「対応はまちまち」という。市の担当者は「現場で疑問がなければ、必ずしもデータと照合する必要はない」と説明。首都圏のある自治体の建築部局職員は「くいの他にも膨大な書類があり、全て点検していたらきりがない」と話す。
二〇〇五年に発覚した耐震強度偽装事件の解決に取り組む高橋宏弁護士=横浜市中区=は、データを手で書き換えていることなどから「しっかり照らし合わせていれば、施工不良に気づけたのでは」とチェックの甘さを批判。「検査機関や市が施工状況を点検する際、どこまでのデータを調べるのかルールを作っておく必要がある」と指摘する。
旭化成建材の親会社の旭化成によると、くいを打つ時はくいに圧力センサーを付け、固い地盤までの距離を確認する。固い地盤に届けば圧力のデータが高い値を示すので分かる。計測ミスがあれば、元請けに報告して判断を仰ぐことになっているが、今回は相談しなかった。
問題のマンションの四棟で打たれたくい計四百七十三本のうち、転用・加筆された虚偽データのくいは三十八本。傾いた一棟では、このうち八本が固い地盤まで届かないなどの施工不良があった。
全棟建て替え方針三井不動産
旭化成3000棟調査へ
横浜市都筑区のマンションが傾いている問題で、旭化成は十五日、基礎のくい打ち工事をした子会社「旭化成建材」(東京都千代田区)が過去に施工したマンションや大型商業施設などについて、保有している約十年分のデータを早急に調査する方針を明らかにした。
対象は約三千棟に上る。そのうち問題のマンションと同じタイプのくいを打った物件は、あらためて詳細に調査するという。
旭化成は、旭化成建材がくいを打つ際のデータを一部転用・加筆した事実を認めており、社内に調査委員会を設けて原因の究明と再発防止を図る。調査や建物の補強、改修に要する費用は旭化成建材が全額負担する。
◇
事業主の三井不動産レジデンシャルは十五日、傾いている一棟だけでなくマンションを構成する他の三棟も含めた全四棟の建て替えを前提に住民と協議する方針を明らかにした。住民説明会で藤林清隆社長名の文書を示した。
部屋の買い取りなどの補償や建て替え完了までの仮住まいの費用負担にも対応する。
「今回のマンションの工事では、建築基準法に基づく建築確認や安全性の検査は、民間の検査機関が担当していました。」
「検査機関は提出された書類をもとに検査の合否を判定し、市に結果を報告しますが、市には詳細な検査内容や図面などは提出されないため、今回のような偽装をチェックするのは難しいということです。」
実際は、構造計算書偽造と同じで、厳しい検査を行えば、仕事が減る、仕事が取れないなどの
問題があると思う。しかし、料金を貰って仕事を受けたい上、検査機関の名前を出すべきではないのか?建築基準法に抜け穴があるのか、
民間の検査機関にも部分的に問題があったのかも明確にしたほうが良い。
横浜市のマンションで建物を支えるくいの一部でデータが偽装されていた問題で、横浜市の林市長は記者会見で「事業主に対して安全性の検証や原因究明の結果報告を求め、市として建築基準法に適合しているか検証する」と述べ、市として徹底して調査を行う考えを示しました。
この問題は、横浜市都筑区の11階建てのマンションが傾き、建物を支える52本のくいのうち8本が、強固な地盤に届いていなかったことなどがわかったもので、横浜市は建築基準法に違反している疑いがあるとして調査を始めています。
この問題について横浜市の林市長は記者会見で「市としてマンションの事業主には、安全性の検証や原因究明の結果報告を求めるとともに、建築基準法に適合しているか検証していく」と述べ、市として徹底して調査を行う考えを示しました。
また、工事の報告書の作成でデータの偽装が行われていたことについて、林市長は、「想像を絶する、考えられない非常な不正だ。工事を請け負った会社側がしっかりと調査するということなのでそれを待ちたいが、非常に憤りを感じる」と述べ、強く非難しました。
さらに林市長は「行政側がデータの偽造をチェックできないのか」という指摘に対して、「検討は必要だが、すべてが性悪説で信用できないというのは違うのではないか。まずは今回の原因追及を完ぺきにやるべきだ」と述べました。
「旭化成建材」が偽装していたデータについて、横浜市はくいの施工記録は市側に提出する義務がないためチェックできなかったとしています。
今回のマンションの工事では、建築基準法に基づく建築確認や安全性の検査は、民間の検査機関が担当していました。
「旭化成建材」は、偽装したくいの施工データを工事を請け負った建設会社に報告し、建設会社は、当初の設計図面と照らし合わせるなどして問題がないか確認した上で、検査機関に書類を提出します。
検査機関は提出された書類をもとに検査の合否を判定し、市に結果を報告しますが、市には詳細な検査内容や図面などは提出されないため、今回のような偽装をチェックするのは難しいということです。
横浜市の担当者は「建設計画の段階から民間の検査機関が何度も確認しているが、意図的なデータの流用があった場合は見抜くのが難しいだろうし、行政がすべてをチェックするのは対象となる物件が多いので難しい」と話しています。
問題のマンションを販売した会社が、住民を対象に開いた説明会で配付した資料によりますと、建物が傾いている11階建てのマンションの構造の安全性について、第三者機関による検証結果を11月中旬までにまとめ、対応策とあわせて住民に説明したいとしています。
これじゃピサの斜塔だ。三井不動産グループが販売した横浜市都筑区の大型マンションで、建物を支えるくいの一部が強固な地盤に達しておらず、建物が傾き始めていることが発覚。中世ヨーロッパならいざ知らず、現代の日本でこんなことが起きた理由は、基礎工事に虚偽のデータが使われたからというから開いた口がふさがらない。消費者は何に気をつけて物件を選べばいいのだろうか。(夕刊フジ)
問題となっているマンションは、神奈川県最大級の大型商業施設「ららぽーと横浜」に隣接する「パークシティLaLa横浜」。横浜市によると、マンションは2007年に完成、705世帯が入る4棟があり、傾いているのはうち11階建ての1棟。廊下の手すりが、渡り廊下でつながる別の棟の手すりに比べ約2センチ低くなっていた。
住民からの指摘により、三井不動産グループが調べたところ、建物を支える52本のくいのうち、8本が地盤の強い「支持層」に達していないか、深さが不十分だったと判明。基礎工事を行う際、別の地盤のデータが使用されていたことが原因だ。
基礎工事を担当したのは三井住友建設から請け負った旭化成の子会社、旭化成建材。「建物の補強、回収にかかる費用を全額補償する」としているが、同社が施工に関わったマンションなど他の物件にも疑惑は広がる。
三井不動産グループが販売した横浜市のマンションでの施工不良問題で、旭化成は15日、子会社「旭化成建材」(東京)がくい打ちを施工した全国のマンションや商業施設などについて、過去のデータを調査する方針を明らかにした。対象は最大で約3000棟に上る。
欠陥住宅の検査などを手がける日本建築検査研究所の岩山健一代表の話 旭化成建材は、くい打ちのデータが虚偽のデータだったとしているが、子どものうそレベルの言い訳だ。旭化成はヘーベルハウスを抱えているが、寄せられる相談は多い。施工主の三井住友建設についても相談が少なくない。
大手だから、というだけで信用はできない。名前で商売をしている大手より、仕事の中身で信用を勝ち取らなければいけない中小の企業の方が、むしろ信用できる。傾いたマンションは資産価値が落ちる。買い替えは負担が大きい。住民は、補修や補償金を求めていくことになると思うが、適切な補修かどうかも、しっかり見定める必要がある。
◆施行不良問題対処は 今回のような問題が判明した場合、対処方法は不透明だ。「補強工事として建物を持ち上げ、くいを打ち直すことは考えられる」と話すのは、「全国基礎工業協同組合連合会」の担当者。東京都豊島区役所では免震工事のため97年から3年近くかけ、ジャッキアップで本庁舎を持ち上げて新たなくいを組み込んだ。ただ、中林一樹明治大危機管理研究センター特任教授(都市防災)は「今回のような大規模マンションでは、ジャッキアップをしても建物が沈んでしまうのでは」と推測。「実際の強度を第三者機関などに早急に判断してもらい、住民に住み続けるかどうかを考えてもらうべきだ」と注文をつける。
ドイツ発の世界恐慌はないだろう。他のEUの国々も影響を受けるのでその前に何らかの対策が実施されるはず。それが出来ないようなら、EUとしての体力が ないと言うことなので、世界恐慌は避けられないし、もし起これば簡単には収束できないと思う。
ドイツの存在なくして欧州共同体もユーロ通貨も誕生していないであろう。しかし、今そのドイツが深刻な金融危機に陥る可能性があるという。
ドイツ最大の銀行であるドイツ銀行(Deutsche Bank)の行方に強い懸念がもたれているのだ。
スペインのWebメディア「mil21」によれば、ドイツ銀行の〈金融取引総額は67兆ユーロ(8710兆円)〉と言われている。それは〈ドイツGDPの20倍に匹敵する〉という。仮に、同銀行が破綻すると、ドイツだけではその負債を賄うことは出来ない膨大な負債となる。2008年に破綻したリーマン・ブラザーズが及ぼした世界金融・経済危機を遥かに上回る事態になることは間違いない。
ドイツ銀行の経営難が表面化したのは昨年からである。この1年半の間に〈株価は45ユーロ(5850円)から26ユーロ(3380円)に下落〉している。同銀行グループで〈23,000人の人員削減が実施〉された。そして、10月8日のスペイン紙『El Pais』は〈今年の第3四半期は62億ユーロ(8060億円)の赤字が見込まれ、また来年の株主への配当金が廃止される〉と報じた。
◆囁かれる数々の「不安要素」
さらに、ドイツ銀行の行方に不安を撒く種として次の4つの要因があるとスペイン電子紙『Credit y Rapidos』は挙げている。
*フォルクスワーゲン(VW)の不正ディーゼルエンジンがもたらす問題と、それがドイツの他社自動車メーカーに及ぼす影響。
*中東や中央アフリカから流入して来る難民の問題。
*ドイツの輸出が後退している。
*ドイツの重要な貿易取引相手国である中国の景気後退。
また、フォルクスワーゲンの不正問題への賠償などから、取引銀行のドイツ銀行は当面〈100億ユーロ(1兆3000億円)をVW社に融通することになっている〉ということも報じられており、この不安要素をさらに深刻なものにしている。(参照:「mil21」)
他にも、スペイン語圏ではドイツ銀行の経営に関わる不安の種は大小さまざまなWebニュース、ブログなどで取り上げられている。
同銀行が経営難にあるという噂から、〈ロシアは同銀行から50億ユーロ(6500億円)を引き出した〉という話や、〈最近3年間に違法行為があったとして80億ユーロ(1兆400億円)とその弁護料などで70億ユーロ(9100億円)を支払っている〉ということが取り沙汰されていること(参照:「mil21」)。
昨年5月に〈最高30%の値引きをしてまで流動資金だとして80億ユーロ(1兆400億円)の同銀行株を売却〉しているほか、今年3月に〈ストレステストを受けて不合格〉となっり、英国と米国とのLIBOR取引で不正があったとして米国法務省に21億ドル(2520億円)の罰金を支払う〉羽目になったことや、スタンダード&プアーズは今年6月に〈BBB+に降格〉させたこと、昨年と今年で〈二人の頭取が辞任を表明〉したことなど不安要素は数多く指摘されていること。(参照「El Robot Prescador」
などなどだ。
ギリシャの財政危機では、ギリシャはユーロ圏に残留することを決めたが、仮にユーロから離脱ということになっていれば、ドイツ銀行がギリシャに融資した資金は不良債券となってしまう。それをドイツ政府は嫌って、ギリシャをユーロ圏に留まらせたという意見もあるという。
いま、ユーロ圏では「ドイツ銀行は健全な銀行とは言えない」という認識が高まりつつある。これは、もはや一触即発、爆弾を抱えているような状況だ。何かが要因となって爆発すると、ヨーロッパそして世界を危機に陥れることになるのは明白だ。リーマン・ブラザーズの比ではない。
<文/白石和幸 photo by Gizmo23(CC BY-SA 3.0)>
しらいしかずゆき●スペイン在住の貿易コンサルタント。1973年にスペイン・バレンシアに留学以来、長くスペインで会社経営する生活。バレンシアには領事館がないため、緊時などはバルセロナの日本総領事館の代理業務もこなす。
これからもミスを繰り返すのだろう。年金番号を変更する際にミスの対応でまた必要ない費用が無駄に使われる事となる。
年金情報が流出した問題で、日本年金機構が年金番号を変更する際にミスがあり、およそ400人に本来支給すべき額とは違う金額を誤って支給していたことがわかりました。
誤った年金額を支給されたのは、個人情報が流出し、年金番号が変更された人のうち、働きながら年金を受け取っているおよそ400人です。年金機構によりますと、年金番号を変更する際、手続きにミスがあり、本来支給すべき額より多すぎたり少なすぎたりする金額を15日に支給してしまったということです。
年金機構は今後、誤って支給されたおよそ400人に対し謝罪したうえで、少なく支給した人に対しては、来月、不足分を振り込み、多く支給した人については12月の支給の際に過剰分を天引きするとしています。
信頼回復を誓ったばかりの大手企業の不正が、三たび明らかになった。鉄道や船舶などに使われる「防振ゴム」について、14日に性能データの改ざんなどを公表した東洋ゴム工業(大阪市)。同社では8年前に断熱パネルの性能偽装が発覚し、今年に入り免震ゴムのデータ改ざん問題で揺れていた。「3度目の不祥事を起こしたら会社の存続は危うい」との社外調査チームの警告は生かされなかった。【三上健太郎、岡田功】
「大変重く、かつ真摯(しんし)に受け止めている。ご心配、ご迷惑をかけて申し訳ありません」
東洋ゴムが大阪市北区で開いた謝罪会見。高木康史常務執行役員らは深々と頭を下げた。同社は8月10日に免震ゴム問題を受けた緊急品質監査の結果として、製品の“安全宣言”を出したばかりだ。
不正があった部品は、国内の18社に販売されているという。報道陣から再三にわたって18社の名前を公表するよう質問が飛んだが、会見で高木氏らは守秘義務を理由に拒んだ。8月に出した安全宣言について高木氏は「拙速に出してしまったと言われても仕方がない」。
同社によると、不正があったのは免震ゴム問題の時と同じ子会社の「東洋ゴム化工品」明石工場だった。複数が不正に関与した疑いがあり、現在、OBを含め20人から聞き取り調査をしているという。
発覚の端緒は今年8月20日。東洋ゴム子会社の明石工場の従業員が「防振ゴム製品の検査成績証明書に不実記載がある。2008年以降、検査が行われていないものがある」と報告した。報告は、同工場従業員に対し不祥事再発防止のためのコンプライアンス(法令順守)研修が実施された翌日だった。
免震ゴム問題の社外調査チームから今年6月、「不祥事を生む企業風土がある」と厳しく指摘された同社の不正の根は深い。
免震ゴム問題で厳しく批判されていたにもかかわらず、防振ゴムの不正は、疑惑の報告前日の8月19日まで行われていた。その直前の8月10日には“安全宣言”を出していた。
報告体制の遅れも目立った。8月20日の報告から、東洋ゴム本社の事業本部長に報告が上がり、出荷停止したのは13日後の9月2日。約70人体制の社内対策本部を設置したのは週末を挟んで6日後の8日で、国土交通省などへの報告は20日後の9月28日だった。
同社は1995年以降に明石工場で製造された全品を調査し、そのうち防振ゴムについては今月中に結果を発表する方針だ。
このため不正はさらに拡大する可能性がある。
◇納入先、国にも明かさず
全社的な緊急品質監査の結果、8月10日に他の製品に不正はなかったと公表していた東洋ゴム。国土交通省は記者会見で「不正はないという説明はすべて覆った。監査は意味がなかった」と批判した。
鉄道の場合、問題の製品を使っている車両は1000両程度に上る可能性がある。しかし東洋ゴムは国交省にも納入先を明らかにしていない。このため国交省は使っている可能性がある会社や団体に片っ端から注意喚起している。
国交省担当者は「東洋ゴムに納入先を明らかにするよう求めたが、事業者の了解がないと出せないと言われた」と釈明した。
その鉄道会社。問題の部品が列車の振動の緩衝材などに使用されるゴム製品のため、いずれも運行の安全にただちに影響しないと判断している。使用状況の確認を急ぎ、交換を含めた今後の対応を検討している。
JR東日本によると、ビルの免震装置の不正が発覚した2日後の今年3月15日、東洋ゴムの担当者から、ゴム製品を製造する子会社の社長名で「鉄道車両用の部品は問題がない」などと説明する書面を手渡された。
ところが、半年以上たった今月8日、国交省から問題のある部品が納入された可能性を知らされたという。東洋ゴムの緩衝材は新幹線約240両、在来線約280両で使用されており、確認を急いでいる。JR東海、西日本、九州各社も東洋ゴム製緩衝材を使用。私鉄では、京浜急行が東洋ゴム製の緩衝材を使っていた。
造船大手各社も確認作業に追われる。三井造船は「取引はあるようだが、(問題の製品の)品番が分からず、担当に問い合わせている」。三菱重工業は「自社製の船舶エンジンには使っていないが、ほかに購入した品目に使用されていないか調査中」とした。【坂口雄亮、本多健、片平知宏】
施工会社の三井住友建設は旭化成建材の不正(データの改ざん)を知らなかったのか?知らなかったのなら旭化成建材はとんでもない会社だ!
三井不動産グループが販売した横浜市都筑区の大型マンションで、基礎部分の杭の一部が強固な地盤(支持層)に届いておらず、建物の傾斜が確認された問題で、杭の打ち込み工事を請け負った旭化成建材は14日、施工の不具合と、工事に活用する地盤データに転用・加筆などの改ざんがあったことを明らかにした。
同社は補強・改修費用を全額負担する。親会社の旭化成は同日、副社長をトップとする調査委員会を設置した。
横浜市建築局によると、マンションは2006年に分譲を開始し、07年に完成。4棟計705戸で、敷地面積は約3万平方メートル。14年11月に、西棟と隣の中央棟をつなぐ渡り廊下で、手すりの高さが2センチほどずれ、西棟側が低くなっていることに住民が気づき、売り主の三井不動産レジデンシャルに連絡した。
同社と施工会社の三井住友建設が調べたところ、西棟の杭52本のうち28本を調べた時点で、6本が支持層に届いておらず、他の2本も打ち込みの深さが不十分だった。
三井不動産グループが販売した横浜市都筑区の大型マンションで、基礎部分の杭の打ち込み不足や工事データの転用が見つかった問題で、打ち込み工事を請け負った旭化成建材の親会社の旭化成は、調査委員会を設置してデータ転用の経緯を調べるとともに、旭化成建材が過去10年ほどの間に手がけた物件でも不正がなかったかを調査する方針を明らかにした。
物件数は全国で最大3000件に上り、マンションだけでなく、商業ビルや工場なども含まれるという。旭化成建材は、工事データの一部改ざんを認め、「作業の不手際でデータの一部が欠損したり、うまく取得できなかったりしたため、正常なデータで取り繕おうとした」などと説明している。
問題のマンションは4棟計705戸で2007年に完成した。14年11月、西棟(11階建て)と隣の中央棟(12階建て)をつなぐ渡り廊下で、本来は同じ高さの手すりに2センチほどのずれがあると住民が指摘。三井側の調査で、西棟が傾いており、西棟の地中に打ち込まれた杭52本のうち、少なくとも8本が強固な地盤(支持層)に届いていないなど、深さが不十分だったことが分かった。
日本年金機構が全国に所有する土地や建物のうち、3年以上も入居者がいない職員宿舎が7棟あるなど、帳簿上の価格で約15億円相当の不動産が有効に活用されていないことが、会計検査院の調べでわかった。
機構の不動産はもともと国有財産だったが、遊休化しても国に納付するための法令がなく放置されていた。検査院は機構を所管する厚生労働省に対し、国庫返納の制度を整備するよう求める。
機構は今年3月末現在、全国各地の年金事務所や職員宿舎など、簿価で約1034億円相当の土地や建物を所有する。検査院がその利用状況を調べたところ、北海道と東京都、千葉、沖縄両県にある職員宿舎計7棟(計170戸)では、少なくとも2014年度までの3年間、入居者が一人もいなかったことが判明した。
結局、会社の体質と言う事か?
東洋ゴム工業は14日、船や電車などに使う防振ゴム製品の一部で、性能について不正な結果を記載していたと発表した。過去10年分の製品を調べた結果、18社に納入した8万7804個で問題があったという。東洋ゴムは建物の免震ゴムでも性能の偽装が発覚していた。
東洋ゴム工業は14日、船舶のエンジンや電車などの振動を抑制するために使われる防振ゴム製品8万7804個について、品質試験のデータを改ざんするなどの不正があったと発表した。同社製品の性能データ改ざんなどの不正が明らかになったのは、2007年の断熱パネル、今春の免震ゴムに続いて3件目。
同社によると、過去10年間に製造した防振ゴム製品約2500万個のうち、8万7804個で、品質試験で規格値に満たなかった数値を改ざんして規格を満たしたように記載したり、試験をしていないのに過去の試験データを転記するなどしたりして、計18社に出荷していた。いずれも同社子会社「東洋ゴム化工品」の明石工場で生産されていた。同工場では、不正が判明した免震ゴムも製造していた。今年8月20日に社内から情報提供があり調査したところ、改ざんなどが発覚した。不正による具体的な被害は確認されていないという。同社は14日夕、大阪市内で記者会見を開き、詳細を説明する。
同社は免震ゴムのデータ改ざんを受けて緊急品質監査を行い、8月10日に「正規品が出荷されていたことを確認した」と発表していた。9月には、11月に引責辞任する山本卓司社長の後任に、清水隆史・常務執行役員を新社長にする人事を発表し、信頼回復と再発防止を目指す姿勢を打ち出していた。【吉永康朗】
ブランドに対する信頼性と品質はイコール(=)ではない?
三井不動産グループが販売した横浜市都筑区の大型マンションで、建物を支える杭の一部が強固な地盤に届いておらず、建物がわずかに傾斜していることがわかった。杭工事をめぐり、虚偽のデータが記録されていたことも判明。横浜市などは建築基準法違反の疑いがあるとみて調査を始めた。
問題のマンションは三井住友建設が施工し、三井不動産レジデンシャルが2006年に販売を始めた。最高12階建てで、住居棟4棟に700世帯以上が入る。
横浜市によると、住民側が昨年11月、二つの棟をつなぐ廊下の手すりが上下にずれていることに気づき、三井側に調査を要求。詳しく調べると、4棟のうち1棟で建物の片側が2・4センチ低くなっていた。
横浜市都筑区の大型マンションで、施工不良から建物が傾き、国土交通省や横浜市が建築基準法違反の疑いもあるとみて本格的な調査に乗り出した問題について、14日、マンション管理組合の理事という男性が、事業主の三井不動産レジデンシャルに対し「昨年から指摘しているのに、ずっと無視され続けた」と批判した。
男性は昨年9月ごろ、傾いた11階建てのマンションの棟の廊下の手すりが、渡り廊下でつながる別棟の手すりより約2センチ、床が約1・5センチ低くなっていることを知った。「昨年からずっと指摘していたが、初めは『東日本大震災の影響だ』とはね付けられ、施行記録も見せてもらえなかった」と三井不動産側の対応を明らかにした。何度も訴えたところ、今年2月になって、同社はようやくボーリング調査を開始。基礎工事で打ち込むくい8本が、地盤の強固な支持層に約3メートル達していなかったことが判明した。
男性は「個人的には、昨年の時点でマスコミにすべて話したかった。誠意ある回答がないことに憤りを感じる」と厳しい表情。「震度7にも耐えられるというが、本当に安全なのか」と疑いは消えない様子だった。
一方、傾いた棟の1階に住む男性(81)は、約1か月前から玄関の扉が閉まりにくくなった。「部屋を貸して生計を立てている人もいる。他の3つの棟への風評被害が心配。ちゃんと補償してくれるのか」と不安そうに話した。男性が参加した13日の住民説明会には、約80人の住民が集まった。出席した三井不動産側の常務取締役が「元に戻すためには、1、2年かかる」と説明すると、住民からは「全力あげて直せ」と怒号にも似た声が飛び交ったという。
JR鴨居駅から徒歩10分。男性は「ららぽーと横浜」に隣接したマンションの利便性を考えて新築で購入したという。「8年後にこんなことが発覚すると思わなかった」と残念そうに話した。
三井不動産側は「お客さまに対しては誠意を持って対応する」(広報担当者)としている。
「国交省は『小型機の機長が管制官の指示を勘違いした可能性がある』と説明。これに対し、小型機の機長は『許可は受けた』と話しており、運輸安全委員会は12、13の両日、交信記録の確認や関係者への聞き取りなどを行って経緯を調べている。」
交信記録が録音されているのであれば、確認すれば事実が判明するのでは?言い分が全く違う以上、どちらかが嘘を付いている、又は、能力に問題がある。
鹿児島空港付近の上空で10日夕、日本航空機と新日本航空(鹿児島県霧島市)の小型プロペラ機が同時に着陸しようとして異常接近(ニアミス)したトラブルで、国土交通省は12日、同空港の管制官は小型機に着陸許可を出していなかったことを明らかにした。
国交省は「小型機の機長が管制官の指示を勘違いした可能性がある」と説明。これに対し、小型機の機長は「許可は受けた」と話しており、運輸安全委員会は12、13の両日、交信記録の確認や関係者への聞き取りなどを行って経緯を調べている。
トラブルは、10日午後4時50分過ぎ、鹿児島空港に着陸しようとした日航のボーイング767型機(乗客乗員250人)の進路の左前方から小型機(乗員2人)が接近し、両機が着陸をやり直した。2機が最接近した距離は分かっていない。
気に入らない行動を取ったからユネスコの分担金を減らすとの発言は避難を受けるであろう。批判せずに分担金を減らせばよかった。 簡単に分担金と言うが、税金か、国債発行による財源である。今回の事は関係なしに、分担金を減らしてほしい。
自民党の二階総務会長は11日、徳島市で講演し、国連教育・科学・文化機関(ユネスコ)が世界記憶遺産に「南京大虐殺の文書」を登録したことについて、「ユネスコが『(南京事件で)日本は悪い』というなら、ユネスコの資金はもう日本は協力しないと言えないとしょうがない」と述べた。
ユネスコ予算の約1割(年間約37億円)に当たる日本の分担金を見直すべきだとの考えを示したものだ。
南京大虐殺の文書を巡っては、外務省が「完全性や真正性」に疑問を呈し、ユネスコについて「中立・公平であるべき国際機関として問題」と批判した。
着服の不祥事はお金を預かる人とお金を渡す人が違う銀行員になるまで永遠になくならないのだろう。着服金を、ほかの着服で生じた顧客の損失の穴埋めに充てる行為を繰り返すことで 発覚は遅らせる事が出来る。人間が人間である限り、防ぎようがない。人間は完璧ではない。学歴と信頼性は正比例ではあるが、イコール(=)ではない。 無駄を理解した上でシステムを変えるしかない。それでも、確率は低いがお金を預かる人とお金を渡す人が共犯すれば着服の発覚は遅れる。
茨城県にある常陽銀行は8日、下妻支店の元男性係長(46)が、顧客の融資の返済金など計約1億4000万円を着服していた疑いがあると発表した。
着服金は個人で行っていた外国為替証拠金取引(FX取引)に使用していたとみられる。元係長は9月22日から行方不明になっているという。
同行によると、元係長は、知手、下妻両支店に勤務していた2010年4月~今年8月、29回にわたり、計14の法人や個人から事前に預かった融資返済や定期預金作成用の小切手、普通預金の払い戻し請求書を使い、行内から現金を引き出させ、客に渡したように装って着服する行為を繰り返した疑いがあるという。
元係長は着服金を、ほかの着服で生じた顧客の損失の穴埋めに充てる行為を繰り返し、長期間発覚を免れていた。着服額は知手支店で約1600万円、下妻支店で約1億2400万円で、既に穴埋めされた分を除いた実損額は約5900万円になる見込みという。
元係長は9月22日、「客の金に手をつけ、返せなくなってしまった。私のことは忘れてください」などと書いた妻宛ての手紙を自宅に残し、行方不明になった。
元係長は10年2月からFX取引を始めており、損失を補充するために着服した可能性があるという。同行は計14の顧客のうち、計約3000万円の被害を確認し、告訴などを視野に下妻署に相談している。
同行は10月7日付で元係長を懲戒解職処分とした。県庁で記者会見した寺門一義頭取は「お客様や関係者の皆様に心からおわびを申し上げる」と謝罪した。
厳しい言い訳のように思えるけど、真実は?もし、「VW米国法人のマイケル・ホルン社長は証言で、不正は一部の技術者によるもので『会社としての判断ではない』」が 事実出なかったら、現時点以上に独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)は信頼を失うだろう。
【ワシントン=越前谷知子】独自動車大手フォルクスワーゲンの排ガス不正問題を巡る米下院の公聴会が8日(日本時間8日深夜)、開かれた。
VW米国法人のマイケル・ホルン社長は証言で、不正は一部の技術者によるもので「会社としての判断ではない」と述べ、組織ぐるみの行為を否定した。対象車の修理を始めるのは、早くとも来年初めになり、終了するまでには数年かかるとの見通しを示した。
冒頭で「心から謝罪する」と述べた。
パフォーマンスの捜索?それとも本当の捜索?
韓国客船 Sewol沈没の時は、検察や海洋警察から情報が漏れていた!
【ベルリン=井口馨】独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)の排ガス不正問題で、ドイツの検察当局は8日、北部ウォルフスブルクにある同社本社など関係先の捜索を行ったと発表した。
VWは排ガス基準を満たすため、不正なソフトウェアを市販車に使用しており、検察当局は社内文書などを押収したとみられる。
今回の捜索は詐欺容疑での告発を受けて検察当局が進めている「予備捜査」で、今後、関係者を特定するなど容疑が固まれば本格捜査に移行する。
VWの一部ディーゼル車は、不正ソフトを使って米環境保護局(EPA)の排ガス規制に合格していたことが発覚。このソフトは走行中に浄化装置の機能を低下させる機能があり、最大で基準の40倍の窒素酸化物(NOx)を排出していたケースも見つかっている。
【フランクフルト時事】独紙ウェルト(電子版)は7日、自動車大手フォルクスワーゲン(VW)によるディーゼル車排ガス不正問題について、ドイツ政府が遅くとも2011年には認識していた可能性があると報じた。
ただし政府は強く否定している。
同紙によると、NGOの「ドイツ環境支援協会」が11年2月に独運輸省の担当者と面会し、不正を伝えた。同協会の記録には「問題は省内で認識されていた」との記述があるほか、問題対応のため、同省の担当者が国連欧州経済委員会(UNECE)や省内の作業チームに参加したことが記載されているという。
運輸省は面会の事実は認めたものの、不正は認識していなかったと主張。UNECEとは排ガス試験などの手法を世界的に統一する構想について11年から協議してきたが、VWの問題に絡む作業チームは存在しないと反論した。
「決算は内部・外部監査を通過し、文部科学省も承認していたという。」
新国立競技場の見積もりもずさんだったが、決算を文部科学省も承認していたのであれば、文部科学省はざるのようなチェックが普通なのかもしれない。
秋田大(秋田市)は7日、2014年度の決算で、研究などに使うべき寄付金7億2243万円の使途を無断で変更し、経常損失の穴埋めに使う不適切な会計処理をしていたと発表した。
同大は関与した財務担当理事ら7人を戒告などの処分としたり、異動させたりした。
同大によると、寄付金は特定の教授の研究に使うなどの目的で数百人から集められたもので、目的外使用には寄付者の同意が必要だが、同大は承諾を得ずに転用していた。
財務担当理事が「大学の財政が立ち行かなくなる」として学長らの同意を得た上で、赤字の穴埋めに回していた。決算は内部・外部監査を通過し、文部科学省も承認していたという。
規則による要求がなく、メーカーも要求しないのであれば、墜落に影響する問題が起きるまで整備しなしが主流となるであろう。
規則で要求されない以上、法的に問題がないのだから仕方がない。航空会社が整備士による点検をプロモーションとしてアピールし、顧客が
航空会社を選択する時に整備士による点検を考慮するか次第。
航空機が空港から出発する前に実施する「飛行間点検」について、整備士を配置せず、機長だけの業務とする動きが航空業界で広がっている。毎日新聞が国内の航空会社11社に取材したところ、5社は機長だけで実施し、残りの6社のうち3社は整備士を外す検討を始めていることが分かった。航空機の性能が向上したことなどが背景にあるが、点検の質の低下を懸念する声も出ている。
飛行間点検は、航空会社が、空港に到着した航空機に対して次の出発までの間に実施する作業。機体の周りを歩き、異常がないかを目視でチェックするなどの作業を行う。機長による実施が航空法で義務づけられているが、整備士の配置は義務とされていない。国土交通省は通達で、原則として整備士も点検にあたるよう求めているが、判断は航空会社の裁量に委ねられている。
毎日新聞が、大型航空機による定期便運航を行っている国内の11社に飛行間点検の実施状況を取材したところ、スカイマーク▽ピーチ・アビエーション▽ジェットスター・ジャパン▽バニラ・エア▽春秋航空日本--の5社が整備士を配置せず、機長のみで行っていると答えた。
整備士を配置していると回答したのは日本航空▽全日空▽日本トランスオーシャン航空▽エア・ドゥ▽スカイネットアジア航空▽スターフライヤー--の6社。このうち全日空、エア・ドゥ、スカイネットアジア航空の3社は今後、整備士の配置をやめることを検討しているという。
整備士を配置しない理由について複数の社が、整備士による点検が機体メーカーのマニュアルで求められていないことを挙げている。スカイマークは「機長が厳重に点検しており、何らかの異常を発見すれば、各空港にいる整備士を呼んで確認させることになっている」と回答した。
全日空は「各航空機の持つ性能や整備プログラムなどを鑑みながら、安全を確保できる最適な体制を整えている。適切な運航体制に適応していくための社内議論を進めている」としている。
日航は、2011年に一部の機種で整備士を外すことを検討したが、不具合を見つけた際の整備士の呼び出しに時間がかかり、出発が遅れる事態が起きることを懸念して見送った経緯がある。
ある現役機長は「飛行間点検でいつも整備士が一緒にいるのと、気になることがあった時だけ来てもらうのとでは、安心感に大きな違いがある。わざわざ整備士を呼び出すことにためらいを感じるようにならないかが心配だ」と話す。
国交省は「メーカーがマニュアルで認めている以上、結果的に安全が確保されているなら問題ない。各航空会社の判断になる」としている。【松本惇】
国土交通省はパイロット不足解消対策としてパイロットの年齢上限を67歳に引き上げる方針を固めた。(02/24/15) 産経新聞
いくら健康チェックや体調チェックをしても、年齢上限を引き上げればフライト中の急死の確立は上がる。フライト中の急死は絶対に
ないとは言い切れない。運が悪ければ、日本でも同じような問題は起きるだろう。
機長が死亡しても、副操縦士が能力的そして経験的に問題なければ危険は低いと言えるが、どれぐらい安全を優先させるかであろう。
【AFP=時事】米アリゾナ(Arizona)州フェニックス(Phoenix)からマサチューセッツ(Massachusetts)州ボストン(Boston)に向かっていたアメリカン航空(American Airlines)550便で5日、機長が飛行中に体調を崩して急死し、副操縦士が無事に同機を緊急着陸させる出来事があった。同航空が発表した。
乗客147人と乗務員5人を乗せ、フェニックスを現地時間の4日午後11時55分に離陸したエアバス(Airbus)A320型機は、行き先を急きょ変更してニューヨーク(New York)州シラキュース・ハンコック国際空港(Syracuse Hancock International Airport)に現地時間の翌5日午前7時13分に着陸した。
アメリカン航空は、機長の死因は明らかにしていない。【翻訳編集】 AFPBB News
香港航空はLCCなのか知らないが、料金が安いのなら仕方がないとも思う。LCCであれば理解した上で利用するべきだし、 LCCでなければ注意して利用するか、他の航空会社を使うほうが良いかもしれない。
北海道の新千歳空港で3日に香港航空の香港行き693便が機材の故障で欠航となり、空港内で一夜を明かすことになった乗客の一部がホテルの手配などを求め、同社に強く抗議するなどの騒ぎがあったことがわかった。
同社などによると、693便は油圧系統の故障で3日夕のフライトを取りやめた。同社は乗客が宿泊するホテルを探したが、一部の部屋しか確保できず、搭乗手続きを終えて制限区域内に入っていた約190人が搭乗待合室で1泊した。
乗客は大半が香港から訪れており、ホテルの手配や食事の提供を求め、手製の横断幕を掲げて抗議する人もいたという。一夜を明かした乗客は4日、代わりの宿泊施設に移り、5日朝の便で香港へ向かった。乗客の一人は、「航空会社の対応に不満を感じた人が多かった」と話していた。
「『組織的』不正認める」となるのは当然だろう!個人又は一部門の人間だけでは不可能な事。VWはISOの認定を受けていると思うが、トレーサビリティーに 関してどのようなトリックをしているのだろうか?
【フランクフルト時事】4日付の独紙フランクフルター・アルゲマイネ(日曜版)は、自動車大手フォルクスワーゲン(VW)がディーゼル車の排ガス不正問題について、社内調査で「組織的に顧客や当局を欺いた」と分析していると報じた。監査役会筋の話として伝えた。
同紙によると、監査役会は「一部エンジニアによる不正との当初の想定を維持するのは困難」と判断している。関与が疑われる人物が広範囲に及ぶため、外部調査の委託先を、決定済みの米法律事務所以外にも拡大する方針。
同日付の独紙ビルト(日曜版)も、複数のエンジニアが内部調査に対し、VW傘下アウディのハッケンベルク開発担当取締役が不正を知っていたなどと証言したと報じた。証言によると、排ガス浄化装置を不正に操作するソフトを車両に初搭載したのは2008年。ハッケンベルク氏は07~13年にグループの主力乗用車部門「VW」の開発担当取締役を務め、不正発覚後に停職となっている。
ソフトは、05年に開発が始まったディーゼルエンジン「EA189」を使用する車両に搭載。ビルトによれば、排ガス規制の順守とコスト抑制を両立させる手段が他になく、開発が中止になる恐れがあった。このため同エンジン量産開始直前の08年にソフト搭載が決まった。ソフト供給元は、独自動車部品大手のボッシュとコンチネンタル。
ビルトによると、独連邦自動車局はVW以外に同様の不正がなかったか調査を始めた。独メーカーのほか、トヨタ自動車や三菱自動車、米フォード・モーターなどが対象に含まれている。
セキュリティーの点から考えれば浅はかな対応だ!原子力規制委のレベルの低さがわかる。
「資料の内容は、4段階ある機密性の区分のうち、2番目に低い「機密性2」で、核物質防護上の秘密情報は含まれていないという。」
機密性が低くとも流さない対応を取っていない事実は問題。
原子力規制委員会が新人職員の研修で使った資料などが大量に外部流出したことが3日、分かった。
規制委は今年3月、研修資料の一部の流出を確認したが、今回の判明分を合わせると、資料のほとんどが流出していたことになる。
規制委によると、流出したとみられるのは、原子力発電所の設備の概要や原子炉を起動させる手順を記した文書や図面など、計約3800ページ分。さらに、研修風景を撮影した動画約74時間分の大半も流出した可能性がある。資料の内容は、4段階ある機密性の区分のうち、2番目に低い「機密性2」で、核物質防護上の秘密情報は含まれていないという。
規制委は昨年4~5月に研修を実施した。資料は海外の原子力規制当局の研修でも活用できるよう、都内の翻訳会社に英訳を委託。同社はインターネットを通じ第三者に翻訳作業を依頼した。今年3月の流出は同社を通じたものだった。
慌てる必要はないと思う。中国が失敗するのを待つ事も大事。失敗を世界中が知れば、安さだけが全てでないと思う国は考え方を変えるであろう。 「家宝は寝て待て」と言うことわざもある。成功をどのタイムフレームで判断するか次第では、成功の意味が変わってくる場合もある。
2020年東京五輪・パラリンピックの大会エンブレムが白紙撤回された問題で、大会組織委員会は2日、エンブレム作成の責任者を務めていたマーケティング局の槙英俊局長と、企画財務局の高崎卓馬・クリエイティブディレクターが同日付で退任したと発表した。
2人は大手広告会社の電通から出向していたが、「業務遂行の見直し」を理由に2人の出向協定が解除され、事実上の更迭となった。マーケティング局長は当面、布村幸彦・副事務総長が兼任する。
組織委によると、槙局長は、マーケティング局がインターネット上の他人のサイトから写真を無断で使用した問題で戒告処分を受けていた。高崎ディレクターは、旧エンブレムを作成したアートディレクターの佐野研二郎氏の原案修正に関与した。
湯前郵便局(熊本県湯前町)の前局長の男性(41)が保管していた現金を着服した疑いがあるとする問題で、日本郵便九州支社(熊本市中央区)は、前局長を懲戒解雇にしていたことが、わかった。
処分は8月7日付。ほかにも、「(前局長の行為に)適切な対処をしなかった」として関係者3人を同日付で解雇処分とした。
同支社によると、前局長は2007年に就任し、貯金や保険、郵便など郵便局業務全般を管理・監督していた。約1年前から郵便局の金庫に保管されていた現金計1億数千万円を持ち出し、着服した疑いが持たれている。
同支社は今後、刑事告発も検討しているという。同支社は「郵便局に対する信頼を失墜させ、深くおわびする。今後、このような事案が発生しないよう体制づくりに努めていきたい」とのコメントを出した。
慌てる必要はないと思う。中国が失敗するのを待つ事も大事。失敗を世界中が知れば、安さだけが全てでないと思う国は考え方を変えるであろう。 「家宝は寝て待て」と言うことわざもある。成功をどのタイムフレームで判断するか次第では、成功の意味が変わってくる場合もある。
【ジャカルタ=池田慶太】日本と中国が争ったインドネシアの高速鉄道計画では、中国案が採用された。
日本は戦後長らく開発援助を続けてきた親日国で受注競争に敗れた。その裏には中国側の動きを読み切れなかった日本の誤算があった。
◆見通しの甘さ
「中国案で本当に大丈夫なのか」。日本の和泉洋人首相補佐官は9月29日、ジョコ大統領の特使として来日し、「中国案採用」を説明するソフヤン・ジャリル国家開発企画庁長官に懸念を伝えた。
ソフヤン氏は、政府支出も政府保証も出さないというインドネシア政府の条件を中国が受け入れたと繰り返した。日本は、3年で完工させるという中国案を「実現性を度外視した売り込み」と見ていただけに、採用の決定に衝撃は大きかった。「日本はインドネシアでインフラ(社会整備)整備の実績を積んでいた。選んでくれると甘く見ていた」と日本政府関係者は悔やむ。
改正する権限を持つのは公務員。公務員に有利になるのは当然。
信用調査会社の東京商工リサーチが30日、今年1~8月の介護事業者の倒産が55件に上り、過去最多だった昨年の年間倒産件数(54件)を上回ったと発表した。
4月から介護報酬が2・27%引き下げられたことや、景気回復による人手不足で人件費が上がっていることなどが影響しているとみられる。
従業員が5人未満の小規模事業者が37件で、前年同期比で倍増。また、2010年以降に設立された比較的新しい事業者が29件に上り、全体の半数を超えた。介護事業は、高齢化の進展で産業として成長が見込まれており、異業種などから安易に参入したものの、経営に行き詰まるケースが目立つという。
同社では「介護報酬の引き下げの影響が本格的に表れるのは秋以降とみられ、今後、さらに倒産が増える可能性がある」としている。
新潟県阿賀野市の「さくらの街信用組合」(長谷川信一理事長)は30日、本部総務部の男性係長(42)が2009年6月から今年9月にかけ、組合の金庫から持ち出すなどして約2億8000万円を着服していたと発表した。
発表によると、係長は09年6月以降、友人や親戚らの名義で組合の消費者ローンから不正に借り入れるなどして2055万円を着服。13年2月頃からは、組合の金庫から複数回にわたって計2億6019万円を持ち出した。係長は「競馬にのめり込んで給料では足りなくなった」と着服を認めているという。今後、係長を懲戒解雇し、刑事告訴と損害賠償請求を行う方針。
改正する権限を持つのは公務員。公務員に有利になるのは当然。
公務員や私学の教職員が加入する共済年金が10月に廃止され、会社員の厚生年金に一元化される。給付などが手厚い「官民格差」の是正が狙いだが、会社員の4割しか受け取っていない上乗せ給付が残るなど不公平感は完全には解消されていない。
公的年金には、全国民共通の基礎年金部分(1階)と、払った保険料に応じた報酬比例部分(2階)がある。1、2階部分の給付水準は厚生・共済両年金とも同じだが、保険料率は共済の方が低い。さらに、独自の上乗せ給付「職域加算」があり、「官優遇」の象徴として長く批判されてきた。
格差解消のため2012年に被用者年金一元化法が成立。10月から施行され、国家公務員・地方公務員・私学の3共済年金を廃止し、すべて厚生年金に切り替わる。これにより、保険料率は18年(私学は27年)に厚生年金と同じ18.3%(労使折半)になる。もともとの引き上げ上限は17%台だった。
公務員の職域加算は月約1万8000円に減額したうえで、「年金払い退職給付」という新制度に衣替えして残す。民間の退職金に相当する「退職手当」も約15%減額する。ただし、厚生労働省によると、職域加算に相当する上乗せがある会社員は4割弱(月約7000〜7万5000円)にとどまっている。
遺族年金を受け取れる対象も厚生年金に合わせて狭められる。夫の遺族年金を受けていた妻が亡くなると父母や孫が受給権を引き継げる「転給」という共済年金独自の制度は廃止する。
計約50兆円の共済年金の積立金は約半分を厚生年金に移す。残りは、一元化前に支給を約束している職域加算部分の支給などに充てる。
一方、一元化は公務員共済の財政を厚生年金が支える面もある。厚労省によると、昨年12月時点で、国家公務員は現役1.52人、地方公務員は1.43人で1人の受給者を支えている。2.32人で1人の厚生年金と「財布」が一つになることで、共済年金の負担をカバーする格好になる。【堀井恵里子】
公道での走行実験はあまり意味がないと思う。独フォルクスワーゲン(VW)のように不正に検査を通すつもりであれば、検査後にソフトは入れ替えれば 問題ない。実際に走っている車を抜き打ち検査しなければ、巧妙な不正は見抜けないだろう。
独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)の排ガス規制をめぐる不正問題で、歴代経営陣が関与していた疑いが強まっている。VWは30日に監査役会を開き、どう原因究明するかなどについて協議を始めた。欧州連合(EU)も以前から問題をつかんでいたとされ、対応を批判する声が出ている。
VWは、ディーゼル車に不正ソフトを積み、規制を逃れていた。不正が疑われる販売車両は世界で最大約1100万台にのぼる。焦点の一つは、いつ不正ソフトの搭載を決めたかだ。
独DPA通信は関係者の話として、VWの開発部門が2005~06年に導入を決めたと伝えた。苦戦していた米国で、コストを抑えながら厳しい環境規制に対応できる方法として検討されたという。米国では、不正ソフトが08年以降に販売したディーゼル車に搭載されていた。
今年9月に不正問題で引責辞任したマルティン・ウィンターコルン氏が会長に就いたのは07年1月。導入を決めたとされる時期は、前任のベルント・ピシェツリーダー氏が経営トップだった。独検察当局はウィンターコルン氏への捜査を始めたが、独メディアは前の経営陣も不正を知っていた可能性があると報じている。不正に関わった疑いがある幹部ら十数人が停職処分になったとの報道もある。また、検察当局はVWグループで高級車を展開するアウディも捜査する検討を始めたという。
さくらの街信用組合(新潟県阿賀野市)は30日、総務部の男性係長(42)が顧客の資金や金庫に保管されていた現金約2億8000万円を着服したと発表した。
着服金の一部は家族が弁済したが、同信組は告訴する方針。
同信組によると、係長は2009年~今年9月、顧客22人分の名義を無断で使用して融資を受けるなどの手口で、計約2100万円を着服。13年からは金庫に保管されていた現金約2億6000万円を複数回にわたり持ち出していた。係長は「競馬に使った」と話しているという。
係長が9月14日、「金庫の金を銀行に預ける」と職場を出たまま一時行方が分からなくなったことから、同信組が内部調査を行い、発覚した。
同信組の長谷川信一理事長は記者会見で「信用を第一とする地域金融機関として誠に申し訳ない。信頼回復に向け全力で取り組む」と話した。
公道での走行実験はあまり意味がないと思う。独フォルクスワーゲン(VW)のように不正に検査を通すつもりであれば、検査後にソフトは入れ替えれば 問題ない。実際に走っている車を抜き打ち検査しなければ、巧妙な不正は見抜けないだろう。
独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)の排ガス規制をめぐる不正問題で、歴代経営陣が関与していた疑いが強まっている。VWは30日に監査役会を開き、どう原因究明するかなどについて協議を始めた。欧州連合(EU)も以前から問題をつかんでいたとされ、対応を批判する声が出ている。
VWは、ディーゼル車に不正ソフトを積み、規制を逃れていた。不正が疑われる販売車両は世界で最大約1100万台にのぼる。焦点の一つは、いつ不正ソフトの搭載を決めたかだ。
独DPA通信は関係者の話として、VWの開発部門が2005~06年に導入を決めたと伝えた。苦戦していた米国で、コストを抑えながら厳しい環境規制に対応できる方法として検討されたという。米国では、不正ソフトが08年以降に販売したディーゼル車に搭載されていた。
今年9月に不正問題で引責辞任したマルティン・ウィンターコルン氏が会長に就いたのは07年1月。導入を決めたとされる時期は、前任のベルント・ピシェツリーダー氏が経営トップだった。独検察当局はウィンターコルン氏への捜査を始めたが、独メディアは前の経営陣も不正を知っていた可能性があると報じている。不正に関わった疑いがある幹部ら十数人が停職処分になったとの報道もある。また、検察当局はVWグループで高級車を展開するアウディも捜査する検討を始めたという。
力と権力があれば問題を放置又は、見逃す事が出来る。現実の世界ではある事を経験しているが、EUが放置していたのなら非常に残念だ。
独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)がディーゼル車の排ガス規制を不正に逃れていた問題で、欧州メディアはVWや欧州連合(EU)が早くから不正を把握しながら、対処しなかったと報じた。
VWと規制当局がそろって不正を放置していた可能性を示すもので、問題は一段と深刻になってきた。
◆放置
欧州メディアによると、VWやEUの規制当局は少なくとも3回、不正に対処する機会があった。
独大衆紙ビルトによると、問題となったソフトウェアを作った独部品大手ボッシュは2007年、ソフトウェアはあくまで自動車の開発用に限って使用し、販売車両には搭載しないようVWに警告していた。
独紙フランクフルター・アルゲマイネなどによると、11年頃には、社内の技術者がディーゼル車の一部で排ガス基準を満たしていないと指摘していた。
公道での走行実験はあまり意味がないと思う。独フォルクスワーゲン(VW)のように不正に検査を通すつもりであれば、検査後にソフトは入れ替えれば 問題ない。実際に走っている車を抜き打ち検査しなければ、巧妙な不正は見抜けないだろう。
【ニューヨーク=越前谷知子】独フォルクスワーゲン(VW)の排ガス不正問題を受け、米環境保護局(EPA)は25日、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンを問わず、すべての自動車を対象に排ガス検査を強化すると発表した。
同日から実際の走行時と同じ条件下での試験を追加する。日本勢を含め、各メーカーは対応を迫られる。
VWのディーゼル車は、違法なソフトウェアを使って試験の時だけ有害物質を減らす機能をフル稼働させていた。車体を固定して調べるこれまでの方式だけでは、不正を見逃す恐れがあると判断し、試験過程を長期化し、試験走行の距離も長くする。
公道での走行実験などが想定され、基準を満たせなければ、各メーカーは北米で販売できない。メーカーにとっては費用増大につながる可能性がある。
羽田空港のビジネスジェット向け格納庫をめぐる汚職事件で、国土交通省航空局運航安全課係長の川村竜也容疑者(39)=収賄容疑で逮捕=が、贈賄側の航空関連会社「ウイングズオブライフ」に売り上げを水増しして国交省に格納庫の土地使用許可を申請するよう助言していた疑いがあることが25日、捜査関係者への取材で分かった。警視庁捜査2課は、ウイングズ社が川村容疑者の助言で虚偽の報告をし、使用許可を更新していたとみている。
クレバーと言えば、クレバーだけど、言い方を変えればずる賢い。倫理観又は倫理規定は完全に欠落している。
利益のために倫理規定 ( Code of Ethics )を完全に無視した企業活動に対して独フォルクスワーゲン(VW)はどのような説明をするのだろうか?
独フォルクスワーゲン(VW)の排ガス不正について、米環境保護局(EPA)は同社のディーゼル車に搭載されたソフトウェアに、「ディフィート・デバイス(無効化機能)」と呼ばれる違法なプログラムが組み込まれていたと指摘した。
[ワシントン 25日 ロイター] - 米環境保護庁(EPA)は、独フォルクスワーゲン(VW)<VOWG_p.DE>による排出ガス規制逃れ問題を受け、車両の検査を強化する方針を固め、各自動車メーカーに文書で通知した。
[ワシントン/デトロイト 24日 ロイター] - 自動車業界史上、最大のスキャンダルの1つに身を置くことになった独フォルクスワーゲン(VW)<VOWG.DE>。世界最大の販売台数を誇る自動車メーカーが排ガス規制を不正に回避したと告白したのは、奇しくも米カリフォルニア州での低公害輸送に関する会議の直前だった。
国家ぐるみ?フォルクスワーゲン(Volkswagen、VW)のどこまでが今回の不正に関わったのだろうか?
ドイツは慎重に対応しないとドイツの信頼を失ってしまう可能性がある。
【AFP=時事】排ガス規制逃れの不正が発覚した自動車大手フォルクスワーゲン(Volkswagen、VW)の母国ドイツの外交官らが、重大な抜け穴が指摘されている従来の排ガス試験の継続を裏で働きかけていたことが24日、AFPの入手した流出文書から明らかになった。
パンドラの箱が開いてしまった。どのように幕引きされるのだろうか?
独自動車大手フォルクスワーゲン(VW)が米国でディーゼルエンジン車の排ガス規制を不正に逃れていた問題が広がりを見せています。VWは欧州でも同様の不正を行っていたとドイツの運輸相が明かしました。
独フォルクスワーゲン(VW)の米排ガス規制逃れの事件はパンドラの箱のように思える。原因調査を行えばいろいろな問題や矛盾に行き着くだろう。
問題や矛盾を解明しようとするとなぜ米排ガス規制逃れが可能になった環境やシステムを明らかにする必要があると思う。
何が公表されるかは調査する関係者やメディア次第なので今後を見守るしかない。
(ブルームバーグ):自動車メーカーは欧州では、試験場での排ガス検査の結果をごまかすために違法なソフトウエアを使う必要すらなかった。検査結果を調整する合法的な方法があるからだ。
「クリーン・ディーゼル」の嘘
整備不良と知りながら代車を貸し出し、排ガスの充満で顧客を死亡させたとして、広島県警は24日、広島市東区の自動車販売・整備会社の専務(63)ら5人を業務上過失致死容疑で広島地検に書類送検した。
1年前、広島市東区の自動車整備などを行う会社から貸し出された代車に乗っていた、当時30歳の男性が一酸化炭素中毒により死亡したのは、代車が整備不良の状態にあることを知りながら貸し出したことが原因だとして、警察は会社の専務や販売部長らを業務上過失致死の疑いで書類送検しました。
東洋ゴムや東芝のように墓穴を掘るのでは?
少数の人間で排ガス不正を行うのは不可能と思う。個人的な意見であるがエンジンの開発者チーム、排ガスのデータ担当チーム、検査の担当チーム、特別なプログラムを指示して発注した部署などは
知らなかったとは言えないと思う。排ガスのデータでは検査に通らないと認識したから特別なプログラムを指示して発注したと思うからだ。エンジンの開発者チームは簡単に排ガス規制を
満足できるのであれば、規制を満足するエンジンを開発していたはずである。ここに品質保証部門が関与していたのかは会社の組織系統次第だと思うので
何とも言えない。ただ、関与していてもおかしくはない。大きな組織で不正が簡単に出来ないシステムの会社であれば、多くの部署が関与しないと不正が発覚しないような隠蔽工作は難しいと思う。
【ロンドン坂井隆之、ベルリン中西啓介】ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン(VW)が米国でディーゼルエンジン車の排ガス規制を不正に逃れていた問題で、同社は23日、ウィンターコルン会長兼最高経営責任者(68)が辞任したと発表した。不正に関連する車両が世界で約1100万台に達する大規模なスキャンダルに発展する中で、経営責任を早期に明確化する必要があると判断した。
STAPスタップ細胞の論文不正問題に関してお金を無駄に使ってしまったと思う。小保方晴子・元理研研究員は今でもSTAPスタップ細胞はあるというのだろうか?
STAPスタップ細胞の論文不正問題で、理化学研究所などは、STAP細胞由来とされる試料はすべて、以前から理研に存在していたES細胞(胚性幹細胞)由来だったとする調査結果を24日付の英科学誌ネイチャーに発表する。
WOLで検索したら下記のサイトを見つけた。
とにかくめまぐるしい40日でした 投稿日: 2015年3月2日 マトリックス法律事務所
投稿日: 2015年3月2日だから川村航空局首都圏空港課係長が現金50万円を受け取った前になるのか、後になるのだろうか?金元社長はいつの時点での社長なのか?
弁護士が立上に関与しいるのであれば、捜査もスムーズになる?それとも逆?
「捜査2課によると、川村容疑者は航空局首都圏空港課の係長だった2013年12月、整備会社が国から得ている羽田空港(東京都大田区)の格納庫の使用許可を更新できるよう便宜を図った見返りに、伊集院容疑者から現金50万円を受け取った疑いがある。整備会社は、格納庫の使用料の滞納を繰り返していたという。」
2013年12月からの格納庫の使用料が現金50万円であれば凄く良い投資かもしれない。年間の使用料およそ1億円-現金50万円=9950万円のお徳。これが国民の負担になるのであれば、9950万円の
負担が国民に負わされた事になる。
逮捕で公務員は懲戒免職になるのだろうか?有罪が確定すれば懲戒免職になるのだろうか?
国土交通省航空局の係長が、羽田空港にある航空機の格納庫の土地の使用許可を巡り便宜を図った見返りに航空関連会社の元社長から現金およそ50万円を受け取っていた疑いが強まったとして、警視庁は係長と元社長を贈収賄の疑いで逮捕しました。
ビジネスジェットなどの格納庫の使用契約をめぐり、航空関連会社に便宜を図った見返りに現金数十万円を受け取っていた疑いが強まったとして、警視庁捜査2課は23日、贈収賄容疑で、同省航空局の係長と、航空関連会社の元社長の取り調べを始めた。容疑が固まり次第、逮捕する方針。
羽田空港にある格納庫の使用許可に絡み、便宜を図った見返りに業者から現金を授受したとして、警視庁は23日、国土交通省航空局運航安全課の係長川村竜也容疑者(39)=千葉市稲毛区小仲台5丁目=を収賄容疑で、航空機整備会社元役員の伊集院実容疑者(61)=金沢市高尾=を贈賄容疑で逮捕した、と発表した。ともに容疑をおおむね認めているという。
CEO解任が事実であろうが、推測であろうが、独フォルクスワーゲン(VW)が排ガス不正が事実である事を認めている以上、誰の責任であるのか
に関係なく、独フォルクスワーゲン(VW)の責任である事に変わりはない。
[ベルリン 22日 ロイター] - 独フォルクスワーゲン(VW)の米排ガス規制逃れの影響が拡大している。米国に続き欧州やアジアでも調査の動きが広がっているほか、ウィンターコーン最高経営責任者(CEO)を解任するとの報道も伝わり、創業78年のVWの歴史上、最大のスキャンダルに発展した。
独自動車大手フォルクスワーゲンはなぜ不正にGOサインを出したのか?不正が発覚すれば信用を失い、莫大さ損失が出るのが想像できるはず?
どのような理由で判断したのか知りたい。原因究明は企業の不正と人間が不正を認識しながら決断するプロセスの解明に貢献すると思う。
【ロンドン=五十棲忠史】22日のフランクフルト株式市場で、独自動車大手フォルクスワーゲン株は一時、約23%下落した。
8月下旬、複数の経済誌や週刊誌が東芝の利益水増し問題で引責辞任したはずの西田厚聡氏や佐々木則夫氏、田中久雄氏の歴代3社長が社用車で浜松町の本社に出勤していると報じた。実際、3氏が社内を闊歩する様子も複数の社員に目撃されている。ある週刊誌は西田氏が自宅から社用車に乗り込む姿も掲載。各誌とも問題を引き起こした歴代3社長に、いまだ役員室や社用車を与えていることを批判した。
[フランクフルト/ハンブルク 20日 ロイター] - ドイツ自動車大手フォルクスワーゲン(VW)(VOWG_p.DE)は20日、米環境保護局(EPA)から排ガス規制の不正回避を指摘されたことを受け、米国内の販売店に対し、同社のディーゼル車の一部の販売停止を指示した。
ドイツの企業も組織的な不正を行うのか?制裁金2.1兆円は高いのか、妥当なのか?
(ブルームバーグ):ドイツの自動車メーカー、フォルクスワーゲン(VW)は、米国の排気ガス規制に関する検査での不正行為を認めた。巨額の制裁金に加え、刑事訴追を受ける可能性も出てきた。
産業創出は出来たのか知らないが、お金の創出で出来たようだ。第3セクター「産業創出機構」でそこまでやる必要があったのだろうか?
大分県の補助金をだまし取ったとして国東市の第3セクター「産業創出機構」の社長らが詐欺容疑で逮捕された事件で、機構が実際の事業費に約1000万円を上乗せして補助金を申請していたことが11日、関係者への取材で分かった。
テレビで英語もあまりしゃべれない日本人の女の子達がインドネシアか、マレーシアで日本では住めないような綺麗なアパートに住んでコールセンターで
働きながら現地での生活をエンジョイしている番組を見た。日本の労働法が適用されない国で、日本人を現地採用扱いでコストダウンがここまで来ているのかと
思ったが、思った以上にポピュラーになっているのかもしれない。フィリピンでは違法なので逮捕となったのだろう。
こんな状況までコストカットしている企業が存在するのに、日本ではオリンピックと言って大盤振る舞い。海外でこのような形態で働いている日本人は年金を払っていないと思うから
将来、問題となる若者が増えているのだろう。
フィリピン国家捜査局(NBI)は11日、必要な労働許可を得ずに就労していたとして、同国中部セブの「ジャパン・インタートレード・コールセンター(JICC)」社で勤務していた日本人約60人を、不法就労の疑いで逮捕した。
「明治大学は11日、司法試験の問題の一部を漏洩(ろうえい)したとして国家公務員法(守秘義務)違反の疑いで告発された同大法科大学院の青柳幸一教授(67)について、12日付で懲戒免職にすると発表した。同大は『司法試験制度の根幹を揺るがしかねない重大な事態で、厳しい姿勢で臨むことにした』としている。」
「司法試験制度の根幹を揺るがしかねない重大な事態」であるとは思うが、制度上、不正は可能である事を明らかにした。教授と教え子がもっと巧妙に連携して対応すれば
今回のように簡単に司法試験問題漏洩は発覚しなかったと思う。恋愛感情とか、女性に好意がある程度のレベルで問題を漏洩したから発覚できたのではないか。
これがお金を貰い、簡単に不正が出来ないように打ち合わせが行われていれば、問題漏洩を疑うような明らかな点は発見できなかったと思う。
この点においては法務省が甘いと思われる。
明治大学は11日、司法試験の問題の一部を漏洩(ろうえい)したとして国家公務員法(守秘義務)違反の疑いで告発された同大法科大学院の青柳幸一教授(67)について、12日付で懲戒免職にすると発表した。同大は「司法試験制度の根幹を揺るがしかねない重大な事態で、厳しい姿勢で臨むことにした」としている。
なけなしの給料から長年、掛け金を出し老後のためにと備えてきた。その年金を「すいません、金額、間違ってました」と言われる人が続出している。あなたにも明日、その連絡が来るかもしれない。
一般の人間の男性であれば、女性に好意を抱いたり、好みの女性と知り合いになりたいと思う事はあるだろう。しかし、役職、立場、そして規則などのために
感情を自制しなければらなないこともある。感情に任せれば、単なる動物と同じレベルになってしまう。だから葛藤もストレスを感じると思う。もし、
感情を優先したいと思うのであれば、ある物を失う選択もある。
司法試験問題の漏えい事件で、国家公務員法(守秘義務)違反容疑で告発された明治大法科大学院の青柳幸一教授(67)が、法務省の調査に「女性に好意があり、合格させてあげたかった」と説明していることがわかった。
「女性への恋愛感情あった」が本当であれば年をとっても恋愛感情はあるし、昔の教育を受けた大学教授であっても、感情をコントロール出来ないこともある事を
証明した事になる。結果として昔の教育を受けても倫理と感情のジレンマが存在する状況では、感情を優先させた。
性善説は成り立たない事を前提としないと防止策は形だけのものとなるであろう。これは公務員に対する処分や罰則規定に対しても同じ事が言えると思う。
明治大学法科大学院の教授が、司法試験の問題を教え子だった女性に漏えいした事件で、教授が「女性への恋愛感情があり教えた」という趣旨の供述をしていることがわかった。
司法試験問題の漏えい事件で、東京地検特捜部の聴取を受けている明治大法科大学院の青柳あおやぎ幸一教授(67)が、考査委員として作成に関与した問題を教え子の女性に解かせ、質の高い解答を書けるまで繰り返し添削していたことが、関係者の話でわかった。
「同省案では、全国の小売店や飲食店に設置するマイナンバー(共通番号)カード読み取り端末への補助や、国民の買い物の膨大なデータを処理するコンピューター『軽減ポイント蓄積センター(仮称)』の整備などに計3000億円程度かかるとされる。」
実際はもっと掛かると思う。小売店や飲食店に設置するマイナンバー(共通番号)カード読み取り端末は税金の無駄使いだし、販売店の負担でしかない。マイナンバー(共通番号)カード読み取り端末の
維持及び管理費も継続的な負担になる。
マイナンバー(共通番号)カード読み取り端末を製造する企業、ソフトを作成する企業、コンピューター『軽減ポイント蓄積センター(仮称)』の建設に関わる企業及びセキュリティーや維持管理に
関わる企業はお金を落とす裸の王様の財務省として手厚く扱ってくれるし、財務省からの天下り先の確保も出来る。財務省にとっては良い事ばかりであるが、
税金の無駄使いである。これで財政的にゆとりがないから何年後にはまた増税とか言うのだろう。いい加減にしてほしい。
自民党が財務省の暴走を止められないのなら自民党の1人勝ちも来年で終わるかもしれない。民主党がどのようになったのか考えたらわかるのではないか。方向転換する
機会は何度もあった。しかし、国民の期待を裏切り、失望と怒りが選挙の結果として現れるまで民主党は理解できなかったと思う。
「『財務省版』キールアーチだ。第2の国立競技場問題になるのではないか」
「消費者の買い物の履歴を、政府が新設するデータセンターに保存する」事に反対だ。個人情報保護法と逆である。
年金情報流出を考えるとリスクが大きい。
「政府は、国民の買い物記録を一元管理することになる。外部からのサイバー攻撃で、個人名と購入記録が結びついた情報が流出するリスクを抱える。」
セキュリティーの維持及び監視費用、システムの構築費用、システムの維持管理費用などを考えても税金の無駄。また、政府が国民の買い物記録を一元管理するする事は
横暴であり、プライバシーの侵害である。
俺達、官僚が、日本を動かしていると思っているからこのような事を実行しようと思うのだろう。
消費税率10%時に財務省が検討している負担緩和策で、消費者の買い物の履歴を、政府が新設するデータセンターに保存する方向になった。
大学院の教授であろうが、頭が良かろうか、人間的に成熟していない、又は、倫理観が欠如していると、不正に関与する事があることを証明したケース。
司法試験の問題作成を担っていた明治大学法科大学院教授が8日、法務省から刑事告発された。教え子に問題そのものを漏らしていた疑いだ。国内有数の難関国家試験である司法試験の公正さを揺るがす事態に、法学者は「本当ならとんでもないスキャンダル」と口にした。東京地検特捜部が捜査に乗り出している。
車体ナンバーから以前の車検証の走行距離をチェックできるようなシステムにしないと安心してインターネットのオークションで車は買えないね!
中古車の走行距離を改ざんしてオークションで販売したとして、静岡県警は7日、中古車販売会社社長ら男3人を詐欺と不正競争防止法違反の両容疑で再逮捕した。
なぜ、このような事がこの時期に記事になるのでしょうか?猪瀬氏が告白すると決めたからなのか?そうでなければ理解できない。
13年9月7日(日本時間8日)、招致委員会「チーム・ニッポン」を率いた猪瀬直樹前東京都知事(68)は、ブエノスアイレスのIOC(国際オリンピック委員会)総会で、歓喜の輪の中心にいた。あれから2年、表面化した新国立競技場建設費問題で、総工費が2520億円に膨れ上がり、一時「都の負担額は500億円」とされ紛糾したが、その根拠は建設計画が白紙撤回された今も判然としない。国と都が真っ向から対立するまでに発展した「500億円」騒動について、このほど、スポーツ報知の取材に応じた猪瀬氏が「真相」を明かした。
車両検査の期限を約2時間超過したぐらいで運休し、乗客をタクシーで運ぶのはおかしい。規則は規則かもしれないが、臨機応変に出来ないのか?
検査期限を数時間超過したぐらいでトラブルが起きるほど、使用している部品の材質や品質をケチっているのか?
急遽、運休させるほど重要な事項であればエクセルで検査スケジュールを作成し、アナログ職員のために打ち出して壁に掲載しておけばよい事。
それでも見逃すようであれば、検査期限をペンでマークする。検査終了すれば、Xを付けるなどすれば良い。
これぐらいの事さえも出来ない、又は、考える事が出来ないのであれば、運次第だけどJR北海道はまた事故を起こすかもしれない。
JR北海道は5日、旭川発北見行き「特別快速きたみ」(2両編成)の1両が、同社内で定められている車両検査の期限を約2時間超過して運行していたことがわかり、運休にしたと発表した。
これって政治絡みの事件?
捜索するのであれば徹底的にやってほしい。中途半端が一番良くない。
在日本朝鮮人総連合会北海道本部(札幌市中央区)の関係会社と取引のある会社が、国の雇用対策制度を悪用して助成金をだまし取った疑いがあるとして、北海道警は6日、関係先として同本部や傘下団体などを詐欺容疑で捜索した。
武藤事務総長(元財務事務次官)の経歴を検索してみました。組織委の森喜朗会長とは「森喜朗政権下で、事務次官を務めた。」の時からの知り合いでしょうか?
武藤敏郎事務総長の経歴が超エリート!!出身大学•職歴•父の職業が気になる!? 09/01/15(謝罪会見どっとこむ)
新国立競技場に続き、公式エンブレムも白紙撤回された問題を受け、政府・与党内では、組織委の森喜朗会長や武藤事務総長(元財務事務次官)の責任を問う声が広がっている。
「東京五輪エンブレム取り下げは「ネット大勝利」ではないと思う件」
に「組織委員会の記者会見の説明(時事ドットコム詳報を参照)によれば、永井一正審査委員長による『オリジナルだと認識でき、専門家の間では分かり合えるが、一般国民には分かりにくい』という答えを得て、組織委員会としては『専門家ではないから判断する立場にはない』とした上で永井氏の意見に追従し、『デザインは模倣ではないが、五輪のイメージに悪影響があるため、原作者として提案を取り下げたい』と佐野氏の側から取り下げの申し出があり、三者で見解が一致したのだという。
ここでの流れを読む限り、組織委員会は「判断する立場」でないので判断せず、審査委員会は『一般国民にわかりにくい』と取り下げの根拠の理由を"国民”に求めた。つまり責任は"国民”にあると読め、こちらもデザインに関する判断や評価を明らかにしてない。そのために『本来は正しいものなのに理解が得られないために取り下げる』という図式が、落とし所になってしまっているわけだ。」
上記の理由であれば、エンブレムを最終的に3つに絞り、流用や類似性がない事を確認した上で、アンケートやインターネットで国民に選ばせればよい。サクラや不正行為を想定して
1位と2位の差が20%以上でなければライブのルーレットやダーツで決めれば良いのではないのか。
専門家の価値観や評価はあまり重要ではなく、国民の評価が優先されると審査委員会が言っている以上、流用や類似性がない事のチェック、及びインターネットにエンブレムの最終候補を
公開してネットでチェックさせる等のマルチ・チェックもありだろう。
下記のNHKのニュースでは「組織委員会は、今回の問題について、組織委員会、佐野氏、審査委員会の三者にそれぞれ責任がある」と書かれている。
損害賠償や税金の無駄使いに関して誰が責任を取るのか?審査委員会は選考基準及び何をチェックして上で佐野氏のエンブレムを選んだ理由を公表するべきだ。
二〇二〇年東京五輪の公式エンブレムについて、大会組織委員会は一日、使用を撤回し、新デザインを選び直すことを明らかにした。新たに別の作品との類似性を指摘する意見が上がり、デザイナーの佐野研二郎氏(43)が撤回を申し出た。主会場である新国立競技場建設案に続き、大会の顔であるエンブレムも白紙撤回される異例の事態。すでにエンブレムを使用しているスポンサーなど各方面に影響が出そうだ。
2020年東京オリンピックのエンブレムを巡る問題で、大会の組織委員会は記者会見しました。
国民やメディアが納得できる説明もなく、逃げるような対応をしているから家族やスタッフまで波紋が広がっているとは考えられないのだろうか?
「原案も最終案も、模倣や盗作は断じてないと改めて疑惑を否定した。 一方で、自身のメールアドレスに中傷のメールが送られ、家族や親族の写真もインターネットにさらされるなどのプライバシー侵害を受け、『これ以上今の状況を続けることは難しいと判断し、取り下げに関して私自身も決断致しました』と説明した。
「原案も最終案も、模倣や盗作は断じてない」が事実であれば戦うべきであると思うが、他の件では流用を認め、他人の作品を修正したり、どこまでが事実なのか疑問。
2020年東京五輪の公式エンブレムの使用中止を受け、佐野研二郎氏は1日夜、自身のホームページで「もうこれ以上は、人間として耐えられない限界状況」などとするコメントを発表した。
「 県などによると、事務所が2013年までの13年間に設計を手掛けた建物は、北上市に130件、花巻市に7件の計137件あり、北上市が12件を抽出して調べたところ、11件で設計が誤っていた。ほとんどは民間の住宅や車庫だった。
・・・ 読売新聞の取材に対し、設計を担当した2級建築士の男性(58)は『この程度(の構造)で大丈夫だろうと経験則で判断し、構造計算をしなかった。意識が欠けていた』と説明した。」
2005から2006年ごろに姉歯やイーホームズの問題で、国や自治体のチェックの甘さや制度の不備が注目を浴びた。
あれから約10年がたった。
小さな建築物でも構造計算書を提出させるべきなのでは?専門ではないので下記のサイトの情報を参考にすると「一般住宅として広く普及している木造2階建ての専用住宅では、建築士の設計に限り構造関係法規が、確認申請時にチェックされません。・・・そのため、2階建て木造住宅では、構造的な検討をしないまま建築されてしまうケースが少なからずあります。」
と書かれている。つまり、建築基準法又は制度を変えない限り、このような問題はなくならないという事がはっきりしています。確認申請をスムーズにすることを優先にするために問題のある建築物が見逃されやすい法律になっていると言う事です。
建築基準法が改正されるまでリスクを覚悟すればごまかしが可能である環境が存在すると言う事です。姉歯やイーホームズの問題は何だったのでしょうか?行政は業者よりの立ち位置にいると
言う事なのでしょうか?
岩手県北上市は28日、同市和賀町藤根の「小松組建築設計事務所」が設計した市内の木造住宅で設計の誤りが11件見つかったと発表した。
ドラマ「半沢直樹」や「花咲舞が黙ってない」の世界です。現実にも似たような問題があると考えても間違いないようです。
広島県信用組合が元支店長による不祥事を2年以上隠ぺいしていた問題で、当時、対応を協議した会議では創立60周年の式典が間近に控えていたことなどを考慮し、当局への届け出や公表を行わないよう決めたということで金融機関としての公正さよりも組合の行事を重視した経営陣の姿勢が問われます。
広島県信用組合は、
広島県信用組合の元支店長が、5年間にわたって顧客から預かった預金3400万円あまりを着服していたことがわかり信用組合では27日付けで懲戒解雇の処分にしました。
なぜ今更指摘されるの?
愛知、岐阜、三重、静岡の東海4県の郵便局の保険外交員ら数百人が2013年までの3年間で経費を過大計上し、名古屋国税局から約17億円の所得の申告漏れを指摘されていたことが分かった。
以前と同じようにエコキャップが集まるのだろうか?
ペットボトルキャップのリサイクルを通じ、ワクチン代の寄付活動をしていたNPO法人「エコキャップ推進協会(エコ推)」(横浜市)が2013年9月以降、実際は寄付を中断していた問題で、エコ推は24日、寄付を再開し、ブータンに医療支援として500万円を送ると発表した。
「同行によると、元行員は畝傍支店(橿原市)と南支店(奈良市)に勤務していた平成22年1月~27年4月、計13の個人と法人の顧客から定期預金への預け入れ名目で小切手などを預かり、計約2110万円を着服した。」
約5年の長期間に問題が発覚しない事が、南都銀行の問題だと思う。
南都銀行(奈良市)は21日、顧客から預かった小切手や現金など計約2110万円を着服したとして、男性行員(37)を懲戒解雇としたと発表した。処分は13日付。
レノボPCは価格で魅力的だが、信頼出来ないので様子見状態。以前も個人流失問題があったのに、またかと言った感じだ。
個人的にはもうレノボPCの選択はありえないと思う。
中国レノボ・グループのパソコン製品で、出荷時にパソコンに組み入れたソフトウェアに、個人情報が流出する可能性がある欠陥が見つかった。
元自民党の武藤貴也衆院議員(36)の経歴詐欺の疑いもあるようです。
アニメ銀河英雄伝説では多くの政治家は嘘つきで、自己中心的で、国民を欺く人達として描かれていた。
登場人物の国防委員長ヨブ・トリューニヒトは「愛国心や戦争を賛美して他人には死を強要しながら、自分は安全な場所に隠れている輩」。
武藤貴也衆院議員はどのような人物であろうか?
武藤貴也衆議院議員の経歴について、計算が合わないと前回のブログに記載しました。
武藤貴也衆院議員の経歴について記載した途端にこのブログのアクセスが10倍以上になって(元が少ないww)、結構驚いている管理人です。
「政府のサイバーセキュリティ戦略本部も20日、調査結果を公表。機構の水島理事長は記者会見で改めて謝罪し、自身は『問題の処理に全力であたる』として続投する意向を示した。」
「問題の処理に全力であたる」とはどう言う事なのか?いつもの形式だけの偽りの言葉なのか?税金や年金を使ってセキュリティーの専門家に仕事を任せ、セキュリティーは
万全とでも言うつもりなのか?
だめな幹部に判断する権限や指揮の権限を与えると幹部の給料だけでなく無駄な活動をすることによる他の職員やパートそして間接費用が無駄に使われる。日本年金機構から
出て行ってもらう、又は、昇格させて給料を落とす必要があると思う。実際は、そんな事など出来ないから、将来、年金は破綻、又は、支給額が大幅に削減されるであろう。
日本年金機構の個人情報流出問題で、機構の内部調査委員会(委員長=水島藤一郎理事長)は20日、流出原因などに関する調査報告書を公表した。
人件費やその他のコストを含め更なる税金の無駄遣い。
ずる賢く、人間的に尊敬できない日本年金機構又は厚労省の管理職をなんとかしなければならない。問題は日本年金機構又は厚労省が癒着して抜本的な改革を
行う意思がなければ、同じようなミスを繰り返し、自分達には甘い状態を続けるという事。
年金への信頼は今後もなくなって行くであろう。
日本年金機構が、厚生年金に加入する会社員などの個人情報をディスクに入れ勤め先に送る際、読み取るためのパスワード(PW)を同封し、普通郵便で送っていたことがわかった。封筒ごと他人の手に渡れば個人情報が流出しかねず、機構は問題だったと認め見直しを進めている。
白紙撤回となった新国立競技場の旧計画を検証する文部科学省の第三者委員会が19日に開いた第2回会合で、所管の文科省や事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)が総工費を抑える機会を逃してきた経緯が明らかになった。新たな整備計画はこうした反省を踏まえて策定されるが、旧計画の責任の所在は依然として見えてこない。
「日本スポーツ振興センター(JSC)はその2か月後、半額で収まるとの試算を出しており、検証委は妥当性を調べる。」
日本スポーツ振興センター(JSC)の責任について明確にするべきだ。調査結果次第では今回の税金の無駄遣いとなった責任は日本スポーツ振興センター(JSC)と
なる可能性が高い。誰が何を根拠に半額で収まると判断したのか、根拠についての妥当性は議論されたのか?
2020年東京五輪・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の整備計画を巡る文部科学省の検証委員会が19日開かれ、五輪開催決定前の13年7月に、設計会社が総工費3462億円との試算を出していたことが分かった。
中国・天津市で起きた大規模爆発で、国営中央テレビは19日までに、事故現場の空気中から猛毒の神経ガスが検出されたと伝えた。一定濃度で吸い込むと、死に至る場合もある。市民の不満や不信感が拡大するなか、習近平指導部は、元副市長の規律違反などの調査を始めるとともに、企業幹部ら10人と経済開発区の幹部を拘束した。責任を地方政府に押し付ける狙いがあるとみられる。
下記の記事の内容が事実であれば、他にもいつ爆発するかわからない爆弾が中国にはたくさんあるという事。
【8月19日 AFP】中国国営・新華社(Xinhua)通信は19日、中国・天津(Tianjin)で起きた大規模な爆発事故の中心となった危険物などを保管していた倉庫の所有会社の株式が、元警察幹部を父に持つ経営幹部らによって、知人などを介して密かに所有されていたと報じた。
大会組織委がベルギー人デザイナーを強く非難しているのは前例を作らないようにしていると思える。
佐野研二郎氏は2020年東京オリンピックのエンブレムの仕事を受けるべきでなかったと思う。仕事を受けなければ注目を受けないので、他のデザインをコピーしても
問題にならなかったと思う。結局、問題のある議員を大臣に任命したケースと似ている。大臣にならなければ問題も公になる確率は低い。
佐野研二郎さんがデザインした2020年東京オリンピックのエンブレムに対し、ベルギー人デザイナーが自身の制作した劇場のロゴマークと似ているとして提訴している問題で、東京オリンピックの大会組織委員会は8月17日、提訴したデザイナー側を非難する声明を発表した。「われわれの詳細な説明に耳を傾けようとせず、提訴するという道を選んだ」としている。47NEWSなどが報じた。
とにかく人命なのか?コストと人命のコンビネーションなのか?
綺麗ごとだけでなく、若い世代の負担も考えないと問題は解決できない。お金がない人達には妥協をお願いするのか、汚いかもしれないが財政にゆとりがなければ
負担を先送りにしているだけ。少子化の傾向が明かなと言うことは、将来、住宅が余ると言う事。現在の問題を解決するために単純に施設を増やせば、将来、
使われない施設が増えるという事。オリンピックのお祭りに大金をつぎ込むのを止めてこのような問題にもお金を回すべきである。オリンピックのために
彼らを見捨てるのであれば仕方のない事。オリンピックのため、アスリートのためともったいぶった言い方を遠藤利明東京五輪・パラリンピック担当相を繰り返して
いるが、あえてアスリートのためと言っているところがインチキくさい。アスリート達は自分達のためだけに新国立競技場があると本当に思わず日本の財政の
事も考えてほしい。なぜなら、遠藤利明東京五輪・パラリンピック担当相はアスリート達が要望しているからとの理由で出来るだけ予算を取ろうとしていると
思えるからだ。アスリート達が要望しているのだから国民は妥協してくれると思っている、または、強行にアスリート達に責任を負わせると疑ってしまう。
川崎市川崎区で10人が死亡した簡易宿泊所(簡宿)の火災から17日で3か月がたつ。
「両親はいま『抜き打ちで調査していれば、事件は防げたのではないか』と主張する。適切な指導を怠ったとして、昨年9月以降、市と施設に損害賠償を求める訴訟を起こし、元施設長らスタッフを複数回にわたり刑事告訴・告発した。」
法律の事には詳しくないが市に対する損害賠償は無理だと思う。認可外の保育施設なのだから、認定されない理由がある。認定保育施設であれば安心というわけではないが
多少のインチキをしてでも認定されるレベルであると言う事。認可外の保育施設であっても良心的であればよいが、急に子供を預ける必要がある人に施設の管理者が良心的であるかの判断は出来ない。
サイト(ホームページ)がよく見えても、事実を記載しているとは限らないし、最初から不審を持たれるようなサイトは作らないと思う。
小規模の施設であれば管理者が直接保育に関与する事もあると思われるが、大きくなると雇う人への指導能力、採用する人を適切に判断できる能力、信頼できる人達を
探す事できるネットワークを持っている等の問題を抱えた場合、管理者の意思だけではコントロール出来ない場合もある。
「抜き打ちで調査」と簡単に思うかもしれないが、テレビのようには行かない。問題を見つけるための抜き打ち検査が出来る人材がいるのかも重要。機転が回る人でも
経験や知識が無いと、すぐには対応できないと思う。法的な知識が無いと検査される側と問題を起こす場合がある。抜き打ち検査を行っても、担当者次第で問題を発見出来ない可能性もある。
実際の話、問題を見つけたら最後まで対応する必要がある。警察官が事件の証拠や捜査を放置しているケースがあるように、面倒な事になる。
大事な子供が死亡した遺族にとっては納得いかないであろうが、法改正や規則の改正も必要になると思う。もし認可外保育施設が悪質であれば、いろいろな隠蔽工作や
嘘を付くであろう。確実な証拠がなければ、動けない場合もある。また、動きたくない場合もある。どちらのケースに当たるのかはケース・バイ・ケース。
認可外保育施設に要求される項目を増やすとコスト高になる。また、地下にもぐる場合もある。(こっそりと子供を預かる施設が出てくるかもしれない。)
需要と供給、そして行政による取締りのバランス次第。とにかくお金であれば、訴訟。他の子供が同じ目にあわないためであれば、法改正や条例などによる規制も
ありかもしれない。世の中は被害にあわないと気付かない問題がたくさんある。
岩佐友
「『タトゥーOK』浴場増加…外国人旅行者に配慮」はお金儲けのために妥協したとしか思えない。
なぜタトゥーはためなのか説明するだけです。運悪く自分の意思でタトゥーを入れたのであれば、断られても仕方がない。日本の浴場に行くためにタトゥーを
諦めるのかと聞けばたぶん答えは「NO」。外国人は自分の価値観で判断する人が多い。他国の常識や文化などどうでも良いと考えている人が多い。
そんな人達に配慮するのはお金儲けのためとしか思えない。実際は、そうであると思う。
全国の温浴施設やリゾート施設の浴場で、入れ墨・タトゥーを理由とした入浴・入館制限を緩和する動きが出ている。
「東京都八王子市が発行したプレミアム付き商品券の販売を委託されていた多摩信用金庫(立川市)の支店職員が商品券を事前購入していた問題で、新たに昭島市発行の商品券でも96万円分が正規には販売されず、職員らが事前に購入していたことが明らかになった。」
多摩信金の体質だと思う。1支店の問題でない以上、同じような考え方をする職員がいるし、不正を制止出来ない雰囲気があるという事。空気読めの悪いバージョン。
東京都八王子市が発行したプレミアム付き商品券の販売を委託されていた多摩信用金庫(立川市)の支店職員が商品券を事前購入していた問題で、新たに昭島市発行の商品券でも96万円分が正規には販売されず、職員らが事前に購入していたことが明らかになった。
シンドラー社の体質の問題なのか、従業員の問題なのか、事実は知らない。しかし、シンドラーエレベーターのトラブルを考えるとシンドラー社に問題がないとは考えにくい。
確実にシンドラーエレベーターの信頼は下がるであろう。信頼が下がる→利益の減少→社員やパートへの給料や報酬の削減→保守作業員の不満又は保守の手抜きや言われた事意外は気付いても対応しない、報告しない等の
負のサイクルに繋がるかもしれない。
検査とか、規則とか言っても、チェックする側の経験や知識が乏しい、検査の合格を前提としていれば、期待された安全性は確保できないかもしれない。チェックする行政
及び検査する組織次第。
シンドラーエレベータの元社員は保守作業員で、点検のため外からエレベーターの扉を開ける鍵を悪用し意図的にエレベーターを止めていたという。同社とトラブルになり「腹いせのため」と動機を話したという元社員。エレベーターを止められたマンションの住民からは「本当に怖い」と驚きと憤りの声が聞かれた。
シンドラーエレベータ製のエレベーターをめぐっては、近年トラブルが相次ぎ、過去には死亡事故も発生している。国土交通省は「今回の件は犯罪行為であり信じられない。社としても監督責任がある」と厳しい姿勢を見せている。
シンドラー社の元社員が、エレベーターを人為的に操作し、利用者が閉じ込められていた事案が、複数回にわたり発生していたことがわかった。
国土交通省は12日、シンドラーエレベータ(東京都江東区)の男性社員(36)が、東京都と千葉県の都市再生機構(UR)のマンションで故意にエレベーターを止め、住民が閉じ込められるケースが7件あったと発表した。中には閉じ込められて気分が悪くなり、病院に搬送された住民もいた。シンドラー社は5日付で社員を懲戒解雇し、同社やURは刑事告訴を検討している。
シンドラー社の元社員が、エレベーターを人為的に操作し、利用者が閉じ込められていた事案が、複数回にわたり発生していたことがわかった。
運が良ければ儲けとなり、運が悪いとこうなる。本当にお金がなければ費用約2億5000万円の支払いの無理。お金を払う気がなければ自己破産か?
横浜市緑区で昨年10月、台風18号に伴う崖崩れで男性1人が死亡した事故で、崖崩れ後に市が出した是正命令に従わなかったとして、神奈川県警は12日、同市都筑区の不動産会社と社長(71)を、宅地造成等規制法違反の疑いで横浜地検に書類送検した。
氷山の一角だろう。ルールを守っていては報われない事もある。運悪く逮捕されたのだから地獄の一部を見て当然。
【法廷から】
理論と実際の計測に違いがあった。新たな発見。福島の人達はどう思うのか?
福島第一原子力発電所で事故対応にあたった東京電力の作業員が体内に吸い込んだ放射性セシウムは、当初の予測より、体外への排出が遅いという追跡調査結果を、放射線医学総合研究所の谷幸太郎研究員らが発表した。
パンドラの箱は開かれた!多くの国民が騙されている事に気付き始めた!
2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた各種競技場建設に関する問題で、先日国立競技場の建設に関する建設費が想定を上回る金額になりました。結局白紙になった一件を見て、東京オリンピックははたして成功するのか、不安に思った人も少なくないでしょう。
ごまかしか、詐欺かのレベルと思える。少なくとも国民を馬鹿にしていると思える。
2020年東京五輪・パラリンピックのメーン会場となる新国立競技場の建設をめぐり、計画が白紙撤回に至った経緯を検証する文部科学省の第三者委員会の議論が7日、始まった。テーマはデザインの選定過程、総工費の膨張や見込み額の変遷、関係者の責任の所在など多岐にわたる。主な論点を整理した。
技量を維持するための「慣熟飛行」と届けて「遊覧飛行」として飛んでいた人達の話は聞いた事がないのだろうか?
「飛ばさなければ操縦技術落ちる」と言うのであれば、費用や移動時間はかかるが他の飛行場に飛行機を移動させるか、操縦技量が落ち、飛行機の痛みも激しく、危険であると思えば、
それでもリスクを負って飛ぶのか、飛ぶのを諦めるしかないと思う。
飛行機を飛ばす側と飛行機とは関係ない人達側では判断基準や利害関係が全くことなる。一般市民を巻き込んだ事故が起きた以上仕方がない。
調布飛行場では事故後、自家用機の運航制限が続いている。
でたらめでずさん。もうオリンピックは必要ないんじゃないのか?アスリートの祭典?アスリートのためだけにそこまで税金と投入する必要があるのか?
白紙撤回に追い込まれた新国立競技場の整備計画の問題点を洗い出し、責任の明確化を図る-。7日に始った第三者委員会への国民の期待は高いが、報告書提出までわずか1カ月半しかなく、徹底した調査に基づく責任追及は困難との見方が強まっている。
白紙に戻った新国立競技場の整備計画の策定経緯などを検証する第三者委員会の初会合が7日、文部科学省で開かれた。委員からは責任の所在の不透明さや乱高下した総工費の不可解さを追及すべきだとの声が相次いだ。来週以降、下村博文文科相を含め関係者のヒアリングを開始し、3回程度会合を開いて9月中旬に報告書を取りまとめる。
日本スポーツ振興センター(JSC)の能力に問題があることはもちろんだが、悪意に満ちた組織である事が問題の根本だ。
「計画白紙」となった2020年東京五輪・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の整備計画を検証するため、文部科学省に設置された「新国立競技場整備計画経緯検証委員会」の初会合が7日、同省内で開かれた。
「JSCは「国家プロジェクトだから予算は後で何とかなる」と取り合わなかった。」
日本スポーツ振興センター(JSC)の関係者は強制的に辞任させるべきだ。
2020年東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場の建設問題で、事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)が昨年5月、基本設計の概算工事費を過少に見積もって公表していたことが、関係者の証言で分かった。設計会社側が約3000億円と提示したのに対し、JSCは資材の調達法や単価を操作するなどして1625億円と概算していた。
新国立競技場のデザインを検討した有識者会議での発言について、会議を設けた日本スポーツ振興センター(JSC)が、情報公開請求に対し議事録から一部を削除して開示したことが分かった。議事録で個人を特定する部分などは黒塗りとなっているにもかかわらず、発言そのものがなくされていた形で、情報操作とも言える手法に批判が出そうだ。
62億円ものお金を無駄にした事は本当にもったいないが、デザインを変更する事により新国立競技場が1000億以下で建設できるなら仕方がない。
日本スポーツ振興センター(JSC)の問題体質の問題も明らかになった。そのコストを思うしかない。
2020年東京五輪・パラリンピックの主会場である新国立競技場の建設計画の白紙撤回に伴う無駄な支出が新たに3億7100万円増えて、合わせて約62億円となることが分かった。4日、参院文教科学委員会で下村博文・文部科学相が松沢成文議員(次世代)の質問に答えた。
合理的でない規則を作ったほうが悪いのか、守らないほうが悪いのか?規則が優先であれば守らないほうが悪い。
聖マリアンナ医科大病院(川崎市)の精神科医による「精神保健指定医」資格の不正取得問題で、同大は6日、神経精神科部長の山口登教授を諭旨退職に、不正に関与した医師15人を休職や戒告などにする懲戒処分(7日付)を発表した。
理容店の名前を公表するべき。
名古屋市は6日、市内269か所で1日に販売した1冊1万円で1万2000円の買い物ができる「プレミアム付き商品券」について、市内の理容店が50冊を売り控えし、アルバイトや従業員、常連客の計12人に優先販売していたと発表した。
「判決は『遊興接待が常態化していた』と指摘したが、金額が多額とは言えないとして執行猶予とした。」
運が悪ければ金額が少なければ執行猶予。見つからなければ大儲け。
JR貨物の発注工事を巡る汚職事件で、東京地裁は6日、JR会社法の収賄罪に問われた同社元幹部社員・富永英之被告(46)に対して、懲役1年2月、執行猶予3年、追徴金約43万円(求刑・懲役1年2月、追徴金約43万円)の判決を言い渡した。
この損失、誰の責任?
東洋ゴム工業の免震ゴムの性能偽装問題で、同社が、製品の交換費用などとして、2015年6月中間決算に100億円程度の追加損失を計上する方向となった。
東京五輪・パラリンピック組織委員会会長の森喜朗・元首相、文科省そして日本スポーツ振興センター(JSC)、この記事読んだ?
財政制度等審議会(財務相の諮問機関)は5日、6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)を踏まえ、2016年度予算編成に向けて意見を交わした。
誰が尻拭いをするの?国民?仕事を貰う業者や企業だけ「にっこり」だね!
東京五輪・パラリンピック組織委員会会長の森喜朗・元首相は5日、BS日テレの「深層NEWS」に出演し、7月22日の記者会見で五輪全体の費用が2兆円を超えると発言したことについて、「一番心配しているのはサイバーテロ、セキュリティー。そのためにはお金を惜しんではいけない」などと話し、施設の建設以外にも様々な分野で費用がかかることについての理解を求めた。
事故が起きるには理由がある。
東京都調布市で小型プロペラ機が墜落し、小型機の2人と住民1人が死亡した事故で、事故機はエンジンを回し続ける点火プラグにトラブルが起きた可能性があることが、航空関係者への取材でわかった。
法整備が整っていないと同じような事件は起きるだろう。
仮想通貨ビットコイン(BTC)の取引サイトを運営していた「マウントゴックス」(東京都渋谷区、破産手続き中)の巨額BTC消失事件で、同社が破綻を発表する半年前の2013年8月時点で債務超過に陥っていたことが、捜査関係者への取材でわかった。
「遊覧飛行」であることがかなり高くなった。「慣熟飛行」の根拠や証拠がほとんどない。
東京都調布市の住宅街に小型飛行機が墜落し8人が死傷した事故で、小型機は死亡した川村泰史さん(36)=横浜市港北区=が1人で操縦していたとみられることが、捜査関係者への取材で分かった。搭乗していた生存者の一部が警視庁調布署捜査本部に説明したという。捜査本部は他の生存者からも事情を聴いて裏付けを進める。
「墜落した小型機を川村機長に貸していた日本エアロテックは『事業として遊覧飛行を行ったことはない』としている」
日本エアロテックの悪質性が露呈したのでは?国土交通省の調査はどのようになっているのか?
東京・調布市で小型飛行機が墜落した事故から2日で1週間となった。事故原因はいまだ明らかになっていないが、墜落した小型機に乗ったことのある人物が「お金を払って遊覧飛行したことがある」と証言した。
墜落した小型機を管理していた「日本エアロテック」の小山純二社長が27日、東京都調布市の同社で記者会見した。小型機の運航目的がパイロットの技量維持のための「慣熟飛行」で、同乗者が4人いたことについて、小山社長は「慣熟飛行のついでに同乗させてほしいと(同乗者が)頼んでいたと思う」と説明した。
民主党 山花郁夫衆議院議員との写真を会えてパイロットと判る服装で取っている。いかにも政治家との繋がりと、
パイロットであることをアピールしている。よく詐欺師や見栄っ張りな人がやる。
どちらのオーダーで燃料を入れたのか知らないが、整備・管理する日本エアロテックが燃料を入れたのであれば米パイパー社製のマニュアルに精通していなければならないと思うが??
東京都調布市の住宅街に小型飛行機が墜落し8人が死傷した事故で、この小型機が離陸可能な最大重量で離陸する場合、当時の気象条件では約960メートルの滑走距離が必要とされていることが分かった。メーカーが出している操縦マニュアルで明示されていた。小型機は上限に近い重量で飛行したとみられるが、調布飛行場の滑走路は全長約800メートルしかなかった。同飛行場での離陸が極めて危険だったことがうかがえる。【内橋寿明】
まあ、自業自得!
東洋ゴム工業(大阪市)の免震ゴムの性能が偽装されていた問題で、国土交通省は建築材料の認定制度の改善策をまとめた。
「中国の航空会社統括機関・中国民用航空局(民航局)が国内の民間航空会社パイロットを対象に調査を行ったところ、200人以上が飛行時間などの経歴を詐称していることがわかった。 」09/07/10(レコードチャイナ)
「事故機の管理を委託されていた日本エアロテックによると、川村機長の総飛行時間は『600~700時間』というが、本人は国交省に『1500時間』と申告していたという。」
日本でも経歴の詐称があり、簡単には発覚しないという事かもしれない。
8人が死傷した東京・調布市の小型機墜落事故で、警視庁は28日、関係先をガサ入れしたが、残された“謎”は多い。事故機の「総重量」にしたってそうだ。
いろいろと問題があるところは、たくさん問題を抱えていると言うことだろう!今まで行政は何をやってきたのかも問題と一緒に明らかになる。
東京・調布市で住宅に小型機が墜落し、8人が死傷した事故で、この小型機のエンジンが2004年の事故で損傷し、修理した後、交換せずに使われていたことがわかりました。警視庁は29日、現場からエンジンなどを回収し、事故の原因を調べる方針です。
東京都調布市の住宅街に小型プロペラ機が墜落し8人が死傷した事故で、同機が2004年に札幌市内で着陸失敗の事故を起こした際、エンジンを損傷していたことが29日、国土交通省への取材で分かった。交換せず修理して使い続けていたといい、運輸安全委員会は今回の事故との関係について慎重に調べる。
「小型機は事故の翌年、国の検査に合格していましたが、エンジンは交換されず、修理されたものが使われ続けていたといいます。」
国の検査に合格しているのであれば、検査ミスか、その時点では問題がなかったのかのどちらかしかない。
東京都調布市の民家に小型機が墜落し、3人が死亡した事故で、小型機が離陸前、指定場所でエンジンを最大出力に近い状態にする試運転をしていなかったことが飛行場関係者らへの取材でわかった。警視庁や運輸安全委員会は、機長による離陸前の安全確認が十分だったか調べる。
東京都調布市の住宅街に小型飛行機が墜落し8人が死傷した事故で、この小型機が2004年に北海道の空港で事故を起こした際、エンジンを支える土台のエンジンマウントやプロペラなど複数の部品を損傷していたことがわかった。損傷した部品は交換したが、エンジンは交換せず、補修して使用を続けていたという。国の運輸安全委員会は機体の整備状況などを精査し、墜落事故との関係性を調査する。
東京都調布市の住宅街に小型プロペラ機が墜落し8人が死傷した事故をめぐり、事故機を所有、管理していた会社の不透明な経営実態が明らかになってきた。同社関係者は、事故機について「『絶対乗ってはいけない機体』といわれていた」と証言。経営不振などを背景に、機体の整備が不十分だったという指摘も出ている。警視庁は28日に管理会社など3カ所を家宅捜索したが、航空業界の闇は暴かれるのか。
日本スポーツ振興センター(JSC)及び文部科学省は反論する、又は、コメントするべき!
【エアー(英)=風間徹也】新国立競技場の建設計画が白紙撤回されたことを受け、デザインを担当した英国在住の女性建築家、ザハ・ハディド氏の事務所が28日、「デザインが予算増加の最大の理由とする間違った主張をする(事業主体の)日本スポーツ振興センター(JSC)に対し、異議を唱えた」などとする声明を発表した。
ザハ氏事務所がJSC批判をしている。文部科学省が損害賠償の訴訟を起こされると強調していたが、一番恐れていたのはザハ氏事務所
日本スポーツ振興センター(JSC)や文部科学省の問題や責任がメディアに流れる事では??
損害賠償の訴訟を起こされても「十分な競争がない中で建設会社を選ぶことは過大な見積もりを招くと警告していた」事とは関係なく
建築家ザハ・ハディド氏の事務所の主張のように建設コストが下がらない事を証明できれば賠償額は低い、又は、賠償責任はないかもしれない。
訴訟での避難合戦は国民が知らなかった事まで暴露されるので、文部科学省の検証チームのレポートの妥当性にも影響すると思う。
工費高騰を理由に白紙撤回された新国立競技場の建設計画について、旧計画のデザインを担当した建築家ザハ・ハディド氏の事務所は28日、「コスト高は東京の資材や人件費高騰によるもので、デザインが原因ではない」との声明を発表した。費用がかかりすぎるとされたアーチは230億円ででき、総工費の10%未満だったとしている。
NPO法人=善と思わないほうが良いと思う。個人的に思うが、スポンサーや支援する企業がなければ本当の意味でのボランティアでなければ運営は難しいと思う。
患者数が少なく、公的支援が行き届かない「希少難病」の患者をつなぐ活動をしてきたNPO法人「希少難病患者支援事務局(ソルド)」(京都市南区)が3月末に解散し、約500人が登録していた患者向け会員制交流サイト(SNS)を突然閉鎖していたことがわかった。
日本取引所グループの清田瞭・最高経営責任者(CEO)は28日の記者会見で、東芝の不適切会計問題に対し、「コーポレートガバナンス(企業統治)の先駆的な企業という評価を完全に裏切った」と批判した。
死亡したとみられる機長の川村泰史さんは、事故機を整備・管理する日本エアロテックによると、総飛行時間は600~700時間で、航空評論家の青木謙(よし)知(とも)氏によると、操縦士の資格を取るだけでも半分程度の時間を要するため、「キャリアを積み始めた駆け出しだ」という。ただ、青木氏は「資格を取得しているので技術に問題はない」としている。
「国土交通省によりますと、航空法の規定では、パイロット養成事業を経営するためには国土交通大臣から『航空機使用事業』の許可を受けることが必要となっています。」
どうどうとホームページで事実を書いているのに処分されなかったのだから行政にも責任があるのでは??
東京・調布市の住宅に小型飛行機が墜落し3人が死亡、5人が重軽傷を負った事故で、パイロットを養成する会社を経営していた機長が、養成事業に必要な国の許可を受けていなかったことが国土交通省への取材でわかりました。
東京・調布市の住宅に小型飛行機が墜落し、3人が死亡、5人が重軽傷を負った事故で、今回の飛行の実態は、調布飛行場では禁止されている遊覧飛行だった可能性のあることが、関係者の話でわかりました。
調布飛行場を離陸直後、東京都調布市の住宅街に墜落した小型プロペラ機を操縦していた川村泰史機長(36)=死亡=は自身が経営する会社のホームページでパイロット養成をうたう一方、養成事業に必要な国の許可を受けていなかった。
墜落した小型機の機体の整備や管理を行っている「日本エアロテック」が会見し、今回のフライトの目的は、操縦者の技能を維持するための「慣熟飛行」だったとしたうえで、「機長との契約で機体を貸しただけで目的地での予定や同行者については把握していない」と話しました。
「府内の協力病院を被害者が受診した場合、警察には届けない意思を本人が示していても、同意を得て体液や毛髪を採取し、阪南中央病院(大阪府松原市)にあるNPO法人「性暴力救援センター・大阪」(通称SACHICO)が一括保管する。後で被害者が告訴などを希望した時、証拠物として警察に提出できる。
アイデアとしては大変よいが、「証拠物の採取と保管には金銭負担は発生しない。」は疑問。将来、優良になる可能性もある。ただ、普及のために無料としているような
気がする。あと、性暴力なのだから機密性が求められる。情報のセキュリティー及び情報の漏洩対策など考えると無料と簡単に言えるほど簡単に扱えない。
情報が漏れて被害者から訴えられ場合、善意で無料で対応しているのだからと逃げれないと思う。
がん患者の冷凍保存された精子が病院による管理のミスで使用不可能になったケースもある。制度の普及も重要だが無理のない制度でなければ将来、
問題を起こす事になる。また、例え、採取された体液や毛髪が保管されていても警察に届けず、調書などその他の証拠がなければ起訴や訴訟は難しいのでは?
性暴力を受けた女性から採取した加害者の体液などを、将来、被害届を出す時に備えて支援団体に保存してもらう制度を、大阪府が今月から始めた。
テレビとかドラマではいのち、いのちと医師が強調しているケースが多い。個人的には単純に生かすだけでなく個人にも選択する余地があってもよいのではと思う。
一方で病院の利益又は経営優先のために下記のようなことも起きている。これが現実であり、人間の行動。性善説を基準にしての対応は税金の無駄になる。
久永隆一、福宮智代
最近、弁護士や法律事務所の不祥事の記事を頻繁に見るようになったが、お金や生活に困るとモラルや倫理などは関係ない次元に
簡単に行ってしまうのか?
破産申し立てに関する裁判所の決定書を偽造して依頼者らに渡したとして、青森県弁護士会は23日、県内の法律事務所の元事務職員を有印公文書偽造・同行使の疑いで県警に告発したと発表した。
人文社会科学廃止について文部科学省が通知することについては視野が狭いと思う。ただ、人文社会科学を卒業しても就職に有利にならないと
子供、その両親そして高校が認識すれば何も言わなくても入学志願者や学校の判断による廃止は将来あると思う。
高校の中には生徒の進学資料で有名私立や国立の合格者の人数を記載する。その資料を参考に進学する高校を選ぶケースが多い。
日本では卒業学部以上に、卒業大学が就職に大きな影響を与えることが多い。特定の大学を入学するために興味のないが偏差値の低い学部で試験を
受ける生徒も少なくない。この点にも問題があると思う。
日本では理系を除けば大学に入れば勉強しなくても良いとの考え方が強いし、実際にそのような傾向が高い。さまざまな点を改善していかないと
問題は解決しない。少子化で若い労働者が減っていく中で人文社会科学廃止は生産性の高い学生を生み出す目的のための結果だと思う。
そうであるのなら、小学校とかもっと早い段階で子供に仕事や将来について考えさせる機会を与えるべき。また、受験勉強のためだけの勉強は
努力するわりには現実社会では応用出来ない事を教えるべきだ。
人文社会科学系と教員養成系学部・大学院の廃止や他分野への転換を国立大に求める文部科学省通知について、日本学術会議は23日、「大きな疑問がある」と批判する声明を公表した。
千葉県松戸市秋山の学校法人松山学園・松山福祉専門学校が、東京都から認可を受けず新宿区に留学生向けの教室を設置していたことが22日、わかった。
「ハディド氏から損害賠償を求められる可能性もあり、JSCの鬼沢佳弘理事は『契約破棄について、近くハディド氏側と面談して交渉したい』と話した。」
ロンドンのアクアティクス・センターが当初建設予算の3倍の結果となった事を例に挙げて、もし損害賠償を求められたら、カウンター訴訟を起こすべきだ。
もし、日本スポーツ振興センター(JSC)とザハ・ハディド氏側と日本国民に知られてはならない隠し事があれば、JSCはカウンター訴訟は
しないであろう。相手も勝つため、又は、出来るだけ良い条件で示談にするために、いろいろな事を裁判で言う可能性はある。
日本スポーツ振興センター(JSC)が損害賠償を想定しない契約書を準備していたのであれば、日本スポーツ振興センター(JSC)にも責任はある。
責任を追及するべきだ。
「白紙」に戻った新国立競技場の建設計画を巡り、事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)は21日、これまでに国内外の設計事務所やゼネコンと計約59億円の契約を結んでいたことを明らかにした。
ここまで問題が大きくなると簡単には認められないのだろう。
事実は今後明らかになるだろう!
東芝の田中久雄社長(64)と、前社長の佐々木則夫副会長(66)が21日、同日付で引責辞任した。過去の決算で利益を水増ししていた問題で、第三者委員会が「経営判断として行われた」との報告書をまとめたことを受けた。東芝の不正会計問題は、歴代3社長の辞任という異例の事態に発展した。ただ、記者会見した田中社長は報告書の指摘のうち、不正指示などについて否定した。
契約したのに白紙撤回したのだから仕方のない事。ただ、1300億円で提示したコンペがコスト圧縮の修正案でも2520億円になった責任は明確に
しなければならない。安藤氏及びザハ・ハディド氏は予算を知っているのだから責任はあるはずだ。賠償「最大100億円」試算とも新聞記事に
書かれているが、カウンター訴訟を起こしたほうが良い。1300億円がコスト圧縮の修正案でも2520億円になったのだから責任はあるはず。
安藤氏はコンペの参加者に伝えてあると断言しているのだからカウンター訴訟は可能と思う。また、あえてコストが高くなる事が推測できる
デザインを選んだ安藤氏には責任があると思う。常識で考えても、曲線が多い建造物のほうが割高になる事は予測できる事。
新国立競技場の59億円契約済みの全てが戻らなくとも、1000億円以下で建設できる国立競技場であれば白紙撤回したメリットは必ずある。
本当はもっと安く出来たはずであるが、文科省、日本スポーツ振興センター(JSC)、安藤氏そして有識者達の責任のために税金の無駄遣いの
結果となった。1000億円以下で建設できる国立競技場にするべきだ。デザインさえ限定すれば絶対に出来るはずだ!
新国立競技場建設の事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)は21日、ザハ・ハディド氏のデザインに基づく旧計画で、デザインや設計などで計約59億円の契約を結んでいると明らかにした。計画は白紙になったが、これらの業務は出来高払いのため、相当部分が戻らない見込みだ。
「文科省は無能力」について同じである。たぶん、無能ではなく仕事をしないキャリア達。そして自分達が勉強してきた以外については
何も知らない税金泥棒。プライドだけはあるが勉強しかしてこなかったキャリアは、彼らが知らない世界や分野に関して素人。
1800億円の予算も多すぎ。IOC会長は「デザイン重要でない」と言っているのから平凡なデザインでも良いから、メンテナンスや維持に
お金がかからない構造にして内装の機能に少しお金をかけたら良いと思う。文科省は何にもわからないから検討を付ける事さえ出来ない思う。
ある程度の方針を決めないと予算など推測する事も出来ないはずだ。デザインに重視すると簡単な構造にならない場合が多い。建設し易い構造で
あればコストはかなり削減できるはずである。建設しやすい=コスト及び納期に有利になる。
メンテナンスや維持に関与する仕事をしている以外の人達には理解し難いかもしれないが、メンテナンスや維持が簡単な仕様で建設や建造されていれば
建設後の維持及び管理コストが安くなる。インターネットで検索すればいろいろな情報が得られると思うが、デザインと設計のコンペにすれば
決められた予算で実現可能なデザインに絞られるはずである。デザインだけのコンペを行い、予算だけを決めた時点で文科省が無能者の集団である、
または、追加が発生しても国民に負担させようと考えいたと推測できる。どちらであっても許せない事だ。
最後に建設額が大きければ、大きいほど儲けを出しやすい。建設費の何パーセントをごまかして誰かにあげるとか、迂回させて献金するとか、
プールするとか、いろいろ出来る。天下りの受け入れの予算も確保できる。悪いほうに取れば、文科省の人間は天下りの確保を考えていたのかもしれない。
東京都の舛添要一知事は20日、2020年東京五輪・パラリンピックのメーン会場となる新国立競技場建設計画の見直しに対する提言をブログで公表した。これまでの失策について責任の所在を明らかにし、関係閣僚による組織を立ち上げ、情報公開を進めることなどを求めた。
【セントアンドルーズ(英)=風間徹也】国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長は18日、ゴルフの全英オープンを開催中の英セントアンドルーズで記者会見し、2020年東京五輪・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の建設計画が白紙撤回されたことについて、「問題を先延ばしにせず決断したのは良かった」と評価した。
三月期決算企業の定時株主総会が二十六日、ピークを迎えた。総会では、経営に外部の視点を取り入れようと、社外取締役の選任を提案する企業が増加。東京証券取引所第一部上場企業では、過去最高となる九割超の企業が社外取締役を迎え入れる見通しだ。だが、東芝など社外取締役の設置に前向きだった企業でも不祥事が起きた。今後は、社外取締役がどう役割を果たすかが問われることになる。 (大森準)
社外取締役が増えれば迅速な判断は出来なくなるだろう。しかし、適切な人材が選ばれれば極端に間違った方向に進んでいる場合にはブレーキに
なるだろう。どちらが良いかは企業次第であると思う。メリットとデメリットが存在する限り、どちらが良いかは決めれないと思う。ただ、
東芝の場合は自浄能力が明らかに欠けており、再発防止が社外取締役なしに機能する可能性は低いであろう。
東芝の利益水増し問題で、同社経営陣の大幅刷新が避けられない見通しとなった。インフラ関連など主要事業で利益水増しの疑いが強まっているためで、田中久雄社長と前社長の佐々木則夫副会長が引責辞任する方向。関係者によると田中社長は周辺に辞意を伝えた。業務執行が適切かを監視する久保誠監査委員長らの責任も問われそうだ。2代前の社長の西田厚聡(あつとし)相談役の辞任論も出ている。
新国立競技場の建設計画の総工費が膨れあがった背景には、コストについての責任の所在があいまいな「無責任の連鎖」があった。国民負担が真剣に議論された様子は見られない。
西日本高速道路(ネクスコ西日本)の廃棄物処分業務を巡る汚職事件で、大阪府警に逮捕された贈賄業者が産業廃棄物処理に関する大阪府の許可を得ずに業務を受注していたことが捜査関係者への取材で分かった。廃棄物処理法は無許可業者への業務委託を禁じており、ネクスコ側も同法に抵触する疑いが強いという。
文科省幹部は「首相や大臣が『国際的に信頼を失う可能性がある』と答弁してきただけに、覆した政府の判断は信じがたい」とぼう然としていた。
大体、文科省、お前達にも責任があるだろ!「国際的に信用を失う」だと?だったら鳩山元総理のCO2 25%削減の国際公約で既に信頼を失って
いるから問題ない!お前達の勝手な解釈を勿体付けるな。
文科省が無能者達の集団である事を世界に発信したことははずかしくないのか?ザハ・ハディド氏デザインのロンドンオリンピックのために建設された
アクアティクス・センターが当初建設予算の3倍の結果となった事は知っているのか?お前らを見ていると腹が立ってくる。
もしかすると文科省は建設コストが予算オーバーになることをうすうす知っていたのではないのか?それを納期とか、国際的信用とか言いながら
天下り先の確保に動いていたのではないのか?責任者が明確でないのも確信犯的にしたのではないのか?エリートが揃っていながら考えられないわけがない。
岩手の中2自殺では学校がいじめゼロにするためにいろいろな抜け道を考えていた。そう考えると
文科省そしてそれに乗った安藤にかなり責任がある。安藤は建築士の資格も持っているそうだ。デザインだけのコンペ。しかし1300億円の予算は伝えたと
無責任な対応。何かが隠されていたのでは?
2020年東京五輪・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の建設計画が17日、土壇場で白紙に戻った。
「文科省はハディド氏側にデザイン監修料の一部として昨年度までに13億円を支払い済みで、契約解除時に違約金を支払う条項は設けていないと説明。ただ、政府の調査では、過去の判例から違約金や賠償金として『10億円から最大100億円』を支出せざるを得ないとの数字も出た。
巨額の賠償金を支払うことになれば、新たな批判を呼び起こすのは確実だ。」
文科省、ばかじゃないの!契約書の時に建設費用が例えば30%以上アップした時には損害賠償とか、解約の時には例えば10%とか決めておくのは常識。
その契約書に同意しなければ契約しなくても良いし、事前に納得した企業や建築家だけでコンペをすればよかった。
なんか日本人であることがはずかしくなるし、嫌になる。こんなにお金をどぶに捨てるような使い方をする公務員のために税金を払うのは空しい。
■「私は現行計画見直す」
大手でも、窮地に立たされればモラルや倫理を無視する企業はあるという事だろう!
3代の社長が不正会計が関与してきた事実は企業体質の一部となっていると考えて間違いないと思う。オリンパス事件は氷山の一角なのかもしれない。
「不適切会計」に揺れる「東芝」を蝕む歴代トップの「財界総理病」 06/10/15( 新潮社 Foresight(フォーサイト))
利益の水増し問題が発覚した東芝は17日、同問題の実態解明を進めている第三者委員会(委員長・上田広一元東京高検検事長)の報告書の要約版を20日夜に公開すると発表した。翌21日午後に報告書の全文を公開したうえで、田中久雄社長らが記者会見を行う。東芝ではインフラ関連工事などの主要事業で利益を不正に水増しした会計処理をしていた疑いが強まっており、東芝幹部は17日夜、一連の問題が不正な会計処理だったことを認めた。
BBCニュースとtheguardianが取り上げている新国立競技場デザイン変更など計画見直しについての記事を読んだ。
イギリスはサッカーよりもラグビーが人気があるので、オリンピックの事よりもラグビーW杯の事で失望しているようだ。
ザハ・ハディド氏(British architect Zaha Hadid)のデザインは初期の予算よりも高額になった事(ロンドンオリンピック)が過去にもあった事が書かれている。
経験したイギリスとしては驚く事ではないのであろう。安藤は建築家であるのに、そのような情報や推測は出来なかったのだろうか?素人ではあるまい。
theguardianの記事に「Jim Heverin, project director at Zaha Hadid Architects, said the rising cost of the stadium was not a result of the design, instead blaming the increasing cost of materials.
“Our teams in Japan and the UK have been working hard with the Japan Sports Council to design a new national stadium that would be ready to host the Rugby World Cup in 2019,
the Tokyo 2020 Games and meet the need for a new home for Japanese sport for the next 50 to 100 years,” he said. 」
ザハ・ハディドアーキテクツのプロジェクトディレクター、Jim Heverinは建設費の高騰はデザインの結果ではないといっている。
ロンドンオリンピックで建設費高騰に一切触れていないし、根拠がない。外国人と仕事をしていて思うのが、彼らの言葉をそのまま信用してはいけない。
信用できる根拠が提示されている、経験から彼らの言い分に妥当性があると判断できる、又は、信用していないが拒否する選択肢がない場合以外は、
言葉をそのまま鵜呑みにすると、被害を被る、又は後悔する事になる。
プロジェクトディレクター、Jim Heverinは日本スポーツ振興センター(JSC)とかなり親密なコミュニケーションを取ってきたような表現をしている。
事実すれば日本スポーツ振興センター(JSC)は批判されていないが、かなりの責任があるのではないのか?
最後に、
森元総理「国がたった2500億円出せなかったのかね」( 07/17/15 (テレ朝ニュース)
は日本の財政問題に関心がない証拠だろうね。たった2500億円と言うのであれば、税金で年金受給額を上げればよいし、大学や高校の授業料の
無料化も良いだろう。ガソリン税も下げればよい。財政問題があるから出来ないのだろ!企業の非正規社員の増加はコストカットの結果。
ギリシャを見ていると政治も国民も人事だった。無視できない状況になって気がついた。港も売れ、空港も売れと言われる状況が日本のも着た時に
必要以上の税金を投入した新国立競技場はどれほどの価値が付くのか?
森元総理「国がたった2500億円出せなかったのかね」( 07/17/15 (テレ朝ニュース)
新国立競技場の建設計画見直しを受け、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の会長・森元総理大臣がコメントしました。
The Japanese government has decided to scrap its controversial design for the stadium for the 2020 Tokyo Olympics and Paralympics.
Rugby authorities disappointed as they lose World Cup final venue due to decision to ‘start over from zero’ on Tokyo Games showpiece
結局、これが現実。校長も人間だから失敗はある。隠す事自体、教育者としては問題ではないのか?違反すれば処分される事を身を持って子供達に
教えるべきだろう。
名城大付属高校(名古屋市中村区)の高須勝行校長が、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで、今月8日に愛知県警西尾署から交通切符(赤切符)の交付を受けていたことがわかった。高須校長は16日夜、取材に対し、「飲み会で酒を飲み、車を運転した」と事実関係を認めたが、学校には報告していなかったという。
実際の本音は別として、「見直した方がいい。もともとあのデザインは嫌だった」と森喜朗元首相はよく言った。
これで安く建設できるデザインを導入すればよい。違約金がいくらか知らないが、公表するべきだ。そして違約金の額を考えて
他のデザインしたほうがトータル的にかなり安くなるのか考えたほうが良い。
安藤よ、これでザハ・ハディド氏(64)の案に固執する必要は無い。選択した責任は安藤だ!
◇「もともとあのデザインは嫌だった」
政府は17日、2020年の東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場の建設計画を抜本的に見直す方向で検討に入った。世論の強い反対を受け、総工費2520億円を削減し、現行計画の大幅な修正が必要だと判断した。同日午後、安倍晋三首相が見直しを表明する。東京五輪・パラリンピック組織委員会会長の森喜朗元首相も同日、見直しを容認する考えを示した。
「僕は専門家じゃないけどキールアーチが問題なのは分かる。」
安藤、森喜朗元首相でもキールアーチが問題(コストアップ)になることぐらいわかるようだ。安藤は問題(コストアップ)はわからなかったのか?
わかっていたけど、選択したのか?
「それでも東京都が3000億円、組織委員会もトータルで7000億~8000億円はかかる。でも国は2520億円しか出さない。おかしいと思いませんか。3対8対2だよ。」
僕は専門家じゃないけどキールアーチが問題なのは分かる。でもそれを前提にして基礎設計をやってるんですよ。キールアーチをやめるとなると全部やり直しだ。そうすると実施設計まで1年半かかり、プレ五輪に間に合わない。
「現行案を撤回した場合のリスクは3点あった。まずザハ氏への違約金。『裁判になったら確実に負ける』(政府関係者)という懸念がつきまとった。」
心配する違約金はいくらだ?契約書の記載されているはずだろう。公表するべきだ!
建築家と呼ばれている安藤は1300億円の予算を全員に伝えていると言ったが、建設費用の1300億円の何パーセント以上の差が出た場合の損害金とか
契約に記載されいるのか?記載されていない、予算に関する責任の免除が記載されていないのであれば、デザインだけで決める無責任は誰の責任なのか、
安藤!曲線のアーチとアーチなしのデザインではどちらがコストがかからないか常識だ考えてもわかるよな!建築家でなくとも理論的な考えが出来る
人であれば理解できる。それをあえて、安藤が選んだ!基本設計前のステージまでと逃げているが、70歳にもなった建築家としてはお粗末。
メディアよ、誰が契約書を作成したのか?記事にしてほしい。
急浮上した2020年東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場の計画見直し論議は16日、新たな局面に入った。総工費2520億円に膨らんだ現行案に国民が猛反発する事態に、政府は現行案の抜本的見直しに踏み込む。現行案を維持して工期の調整などによる経費削減にとどめる慎重意見も残っているが、安全保障関連法案審議とともに、新国立競技場への対応が来夏に参院選を控えた政権の打撃となりかねない事態に安倍晋三首相の「政治決断」の段階となった。
大きな借金を日本国民に負わせて何を言っているのか?安藤がはやく引退しないから、莫大な借金が追加されるリスクに曝されている。
経験がないのならもっと謙虚になれ。はずかしいほどの混乱の渦中にいる多くのギリシャ人に聞くと、こうなるのがわかっていたら
絶対にオリンピック招致に反対していた。そんな事をギリシャ経済が最悪になってから言ってももう遅い。年金を削減され
退職後の人生設計が狂った、無理して大学院まで行かせたのに子供が職を失い、援助しなければならない等の話を聞く。日本の
債務残高(対GDP比)はギリシャより悪い。ギリシャの国債の多くは外資や外国人により購入されているから違うといっても、
日本が大きな借金をしていることにはかわりない。そして、港や空港などは資産として考えられるとしても現在の評価額と
日本が危なくなってからの評価額では大きな違いが出てくるはずだ。結局、新国立競技場のように国民に負担を負わせようと考えて
多くのプロジェクトを企画し、姑息に国民が気付かないように負担を増やしている。
日本が、国際的信頼とか言うが、財政的に日本が行き詰るほうが将来的に日本の国際的な信頼を失うことになるとは考えないのか?
建築家としての小さい世界の話だろ!安藤は70歳まで生きてきて今回のような大きなプロジェクトは経験したこと無いのだろ?
自分の経験や価値観がいかに小さいのか、今回の経験を通してもまだわからないのか?
どれほどの人が困るのかは知らないが、安藤が引退しても困らないから、すみやかに引退してくれ!しかし、人生の最後で苦しい言い訳!
これまでの発言を帳消しにしてしまう!
建築家・安藤忠雄氏「80年以降に生まれた若者はダメ」「70、80の老人が引退したら日本は困る」 12/29/10(Quumu)
「有識者会議に出なかったから『すべて安藤の責任や』というのはちょっと、私はわからない。有識者は何十人もいる」
しかし、下記のリストで専門家は安藤だけではないのでしょうか?安藤は詳しく説明したのでしょうか?安藤は基本設計の前の段階で
建設費用は1300億円では納まらない可能性がある。基本設計前ではチェックのしようがない事を説明したのでしょうか?もし怠っていれば
責任はあります。安藤が建築家ではなく、文系の大学教授であれば言い分に妥当性はあるでしょう。しかし、安藤は建築家。他の有識者は
素人の集団。
逃げの言い訳をする事で人間性がわかる。テレ朝のやじうまプラスで萩谷順が安藤の説明についてコメントしていたが、この人間も何を言っているのか
わからない。安藤は必要ないので今後、一切出てくるな!責任があるのはデザイン選定までと言うのなら必要ない。
責任があるのはデザイン選定まで――。
「安藤氏はグレーのジャケット姿で現れた。用意されたパネルを示しながら、2012年11月のデザイン選定以降は、調整に関わっていないと何度も述べた。総工費が2520億円に膨らんだことについて『もうからなくても国のためだ。それが日本のゼネコンのプライドではないか』と、建設会社との金額調整を求めた。」
「技術とコストについてはハディド氏と日本の設計チームによる次の設計段階でできるんじゃないかと思った」のは根拠のない安藤の勝手な判断。
その部分に関して責任がある。何も出来ないのなら、さっさと引退しろ!根拠のない勝手な判断で多くの金額が国民の負担となる。オリンピックなんて
必要ない。中止してもいいぞ、安藤!
「選んだ責任は感じるが、とりまとめはここまで。私は総理大臣ではない」。新国立競技場の基本デザインを選ぶ審査委員会で委員長を務めた建築家の安藤忠雄氏(73)が16日、東京都内で記者会見した。政府が計画見直しの検討を始める中、安藤氏はキールアーチと呼ばれる巨大な2本の弓状構造物が特徴のデザイン維持を求めつつ、批判が高まる総工費については自らの責任でないと強調した。
「安藤氏は当時の審査について、『デザインの選定までが仕事だった。アイデアのコンペなのでコストについて徹底的に議論することはなかった。オリンピック招致に向け斬新でシンボリックなデザインということで選んだと思う。デザインを選んだ責任はあるが、技術とコストについてはハディド氏と日本の設計チームによる次の設計段階でできるんじゃないかと思った』と説明しました。」
デザインの部分だけで、コストについては議論していないと逃げるのであれば、安藤よ、お前は黙っていろ!それとも自費で足りない部分をだすのか?
新しい国立競技場の建設費が2520億円に膨らみ、政府内で設計自体の見直しなどを模索する動きが出るなか、最初のデザインを決めた審査委員会の委員長で建築家の安藤忠雄氏が初めて記者会見を開き、「デザインの選定までが仕事で、コストの徹底議論はしなかった」と説明しました。
「安藤氏は『選んだ責任はある。ただ2520億円になり、もっと下がるところがないのか私も聞きたい。一人の国民として何とかならんのかなと思った』と述べ、見直しを求めた。
その一方で『国際協約としてザハ氏を外すわけにはいかない。そうでないと国際的信用を失う』と強調した。」
安藤、お前は、引っ込め!国際的信用を失うとカッコつけるな!あんたの顔がつぶれるだけ。外国だって、自分の利害関係に関わることならあれこれと
言い訳を付けて覆す。日本がカッコを付けたがるのは知っているが、多額の費用が絡んでいるんだ。お前に何がわかるのか?選んだ責任があるのなら、差額をポケットマネーで何とかしろ!
日本国民はこんなコメントの安藤を許すのか?1200億円ものお金を他の分野に使ったらもっと良いことが出来る。学費で苦労している子供に未来を
与えられる。学費を下げるための助成金に使えば多くの人の将来をポジティブな方向へ導ける。国際的信用はこれからの子供達が築けばよい。
安藤は自分の面子のために、多くの可能性を犠牲にしようとしている。お金がないことはどう言う事なのか。ギリシャが良い例だ。
安藤よ、お前は70歳にもなって、自分の事しか考えられない人間なのか?子供の将来や教育の事などどうでもよいのか?人間的に最低な建築家として
残りの人生を過ごしたいのか?
総工費が2520億円に膨らみ、見直しを求める意見が高まっている2020年東京五輪・パラリンピックの主会場の新国立競技場の建設で、デザインを選定した建築家の安藤忠雄氏(73)が16日、東京都内で記者会見した。安藤氏は現行案を残しながら経費削減に向けた見直しは必要との認識を示したが、巨大な構造物を備えたデザインを選んだことが経費高騰を招いた関連性は否定した。
安藤忠雄氏が記者会見場で配布した文書は次の通り(原文まま)
悪いけど安藤忠雄と呼び捨てさせてもらう。安藤忠雄は建築家であっても、プロジェクトを考えられる人間ではない事が明確になった。
能力がないのであれば僕には決められないと言うべきであった。
「選考時に『1300億円』の予算が示されていたと強調。」
これでは日本はギリシャを笑う資格はない。無能者ばかりだ!謝罪ぐらいしろ!まあ、謝っただけで何百億もの税金を突っ込む事が許されるわけはないけど。
悪いと思うなら建築家を引退しろ!いい歳なんだから建築家だけで工事費予算1300億円で収まるのかチェックできないとはっきりと言うべきだった。
2020年東京五輪・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の総工費が2520億円に膨らんだことについて、デザイン選考時の審査委員長を務めた建築家の安藤忠雄氏(73)が16日、東京都内で記者会見し、「選んだ責任はあるが、なぜ2520億円になったのか私も聞きたい」と述べ、政府がさらなる見直しの検討を始めたことに「(現行案は)残してほしいと思うが、値段が合わないのなら、徹底的に討論してほしい」と述べた。
東芝の仕事を失うリスクとプロフェッショナリズムを考えたけど、利益が最優先となったのでは??
金融庁の公認会計士・監査審査会は、東芝の決算を監査した新日本監査法人に対し、公認会計士法に基づく立ち入り検査を行う。
「ギリシャ政府の借金総額は国内総生産(GDP)の約1・8倍もあり、「財政は持ちこたえられない」と指摘した。」
そうだったら日本も破滅だね!
【ワシントン=安江邦彦】ギリシャの金融支援を巡り、ルー米財務長官は10日のニューヨークでの講演で、「ギリシャ政府が抱える債務を整理する必要がある」と述べ、ギリシャを支援している欧州連合(EU)に対して返済条件の見直しを改めて求めた。
事実を全て話してほしい。73歳になって汚点を作らないような会見を望む!
2020年東京五輪・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の総工費が2520億円に膨らんだことを受け、デザインを採用した審査委員会で委員長を務めた建築家、安藤忠雄氏(73)が近く、東京都内で記者会見を開く方針であることが、日本スポーツ振興センター(JSC)への取材で分かった。
民主党の責任といいながら建設を止めなかった自民党の無駄の象徴を今後70年間、東京に残せばよい。何かあるたびに自民党が時間がないと言い訳を
作って強引に建設させた負の象徴と言われれば良い。ギリシャ人と話す機会が多いが、多くのギリシャ人は財政のごまかしてまでオリンピックは必要なかった
と言っている。必要とされていないものにお金をかけ、挙句の果てに年金カット、社会福祉の予算削減を強引に行った。こんな結末を知っていたら
デモを起こしてでもオリンピック招致運動を阻止するべきであったと言っていた人もいた。今、日本の日本国民から姑息に負担を押し付けているのに、
新国立競技場は別会計なのか?公務員の姑息な手段であるが、計画や決定の時のデータを一番良いシナリオだけを選択し、その後に見通しが甘かったと
言い訳する。たぶん、今回の同じやり方だと思う。詐欺的な方法。着工して完成させるための姑息な方法。東京オリンピックの後には、強引に国民に
つけを回すだけ。
自民党の総務会で、新しい国立競技場を当初よりおよそ900億円多い2520億円をかけて建設する計画について、「ずさんな計画で看過できない」などといった批判が相次ぎました。
コラムの時代の愛?。変なタイトル、と思われる方も少なくないはずだ。いや、何も「今こそコラムが物を言う時代だ」と主張したいのではないし、愛を唱えたいのでもない。西武新宿線の通勤電車で思いつき、「おっ」としっくりする感じがあったのだ。
民主党の責任といいながら建設を止めなかった自民党の無駄の象徴を今後70年間、東京に残せばよい。何かあるたびに自民党が時間がないと言い訳を
作って強引に建設させた負の象徴と言われれば良い。ギリシャ人と話す機会が多いが、多くのギリシャ人は財政のごまかしてまでオリンピックは必要なかった
と言っている。必要とされていないものにお金をかけ、挙句の果てに年金カット、社会福祉の予算削減を強引に行った。こんな結末を知っていたら
デモを起こしてでもオリンピック招致運動を阻止するべきであったと言っていた人もいた。今、日本の日本国民から姑息に負担を押し付けているのに、
新国立競技場は別会計なのか?公務員の姑息な手段であるが、計画や決定の時のデータを一番良いシナリオだけを選択し、その後に見通しが甘かったと
言い訳する。たぶん、今回の同じやり方だと思う。詐欺的な方法。着工して完成させるための姑息な方法。東京オリンピックの後には、強引に国民に
つけを回すだけ。
自民党の総務会で、新しい国立競技場を当初よりおよそ900億円多い2520億円をかけて建設する計画について、「ずさんな計画で看過できない」などといった批判が相次ぎました。
「「安藤忠雄建築研究所」の名前で、番組の司会を務めるキャスターの辛坊治郎さん(59)宛に出されたファクスでは『コンペの与条件としての予算は1300億円であり、応募者も認識しています。提出物には建築コストについても示すように求められていました。それは当然評価の一つの指標となりました』と明記。」
総工費の高騰が問題となっている新国立競技場のデザイン選考について、審査委員長を務めた建築家の安藤忠雄氏(73)が11日放送の日本テレビ系(読売テレビ制作)「ウェークアップ! ぷらす」(土曜・前8時)にコメントを寄せた。安藤氏がコメントするのは問題が浮上して以来、初めてとなる。
「渋谷駅同様、使えない競技場を設計したザハ・ハディド氏には『デザイン監修料』として十三億円が支払われる。」
仕方がないから十三億円をどぶに捨てたと思い、ザハ・ハディド氏に支払い、普通の競技場を500億円以下でで建設しよう。
国民の負担はその方がはるかに軽い。
東京五輪・パラリンピックのメイン競技場となる新国立競技場の建設計画。抑制されたはずの建設コスト見積もりにも、建設完了後の収支計画の説明にも、明らかなごまかしがある。
二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、メインスタジアムとなる新国立競技場の工事費がようやく決まった――、というか、不可解だらけの疑惑を残し、二五二〇億円というべらぼうな工事費が有識者会議で了承された。
下村博文文部科学相は10日の閣議後会見で、新国立競技場建設をめぐる7日の有識者会議を欠席した建築家の安藤忠雄氏について、新国立のデザイン案を選んだ理由などに関し「何らかの形で発言してほしい」と述べ、説明責任を果たすべきだとの考えを示した。
文部科学省のキャリアは高学歴でも使い物にならない人材ばかりか?インターネットで検索したらいろいろな情報は得られるだろう。何もしなかったのか?
こんなキャリアは必要なし!
専門家ではないが、建築家は構造や力学を考慮せずにデザインを優先させる、それを現実の建物にするのはエンジニアと理解している。
「下村博文・文部科学相は10日、閣議後の記者会見で、新国立競技場の計画について『(当初予定した総工費の)1300億円がデザインする人に伝わっていたか。値段は値段、デザインはデザインということならば、ずさんだったことになる』」
こんな事、デザインを決定する前、又は、決定した後でも確認できただろ。確信犯的に時間稼ぎをしたとしか思えない。
文科相、いまさら、「ずさんだったことになる」とか言うなよ。もっと前に解決できる話だろ!
仕事柄、いろいろなギリシャ人と話す機会がある。ギリシャの財政問題について聞くと、お金がないと政府が公表していたらオリンピックなんかギリシャで
開催する必要など無かった。絶対に反対していたと質問をしたギリシャ人のほとんどが答えた。新国立競技場建設の巨額な費用を考えると
ギリシャと同じように「国立競技場将来構想有識者会議に参加した人々、日本スポーツ振興センター(JSC)及び文部科学省など
のマフィアに騙された!」と回答する日本人が将来増えるかもしれない。
◇ほかの閣僚から「デザイン決まったのは民主党政権時代」
歴代3人の社長が不適切会計に関与している疑いがある。もし事実なら歴代3人の社長の在任期間中、不適切会計に関与した東芝社員達がいると言うこと。
本人達の意思に反して仕方がなく従ったのか、それほど罪悪感を持たすに行った次第で、東芝の組織がどのような組織なのかがわかる。感覚が麻痺した
社員は窮地に陥ると不正に関与する可能性が高いと思う。これは社長だって不適切会計を指示した。自分達の不正など小さい事だから許されると自己肯定しやすい
からだ。歴代3人の社長が黒であれば、傾向としては高いと部分的に証明されたことになると思う。
東芝の不適切な会計処理を巡る問題で、西田厚聡(あつとし)相談役(71)が社長を務めていた2009年3月期の段階から営業利益のかさ上げが行われていた疑いのあることが11日、関係者の話で分かった。第三者委員会もこうした実態を把握している模様で、当時の状況などについて西田氏から複数回、事情を聴いているという。一連の問題を巡っては、前社長の佐々木則夫副会長(66)に加え、田中久雄社長(64)も現場に過剰な業績改善を迫っていたことが判明。両氏とも引責辞任する方向だが、西田社長時代まで波及すれば東芝の企業風土が一段と厳しく問われそうだ。
証拠があるのなら諦めるしかない!
東芝の不適切な会計処理を巡る問題で、田中久雄社長が同社幹部などに対し、業績改善を強く促すメールや電話をしていたことが10日、分かった。不適切処理による営業利益のかさ上げ額は累計2000億円規模に上る可能性が出ている。5月に設置された第三者委員会(委員長・上田広一元東京高検検事長)は、こうした圧力が不適切会計につながった可能性があるとして、経営トップの責任を厳しく追及している模様で、田中社長の進退が問われそうだ。
日本は性善説を基本にしているのかもしれないが、横領を公にするようになったのか、横領を行う人が増えたのか知らないが、日本の企業は甘いと
言うことになる。
宮城県警大和署などは8日、自動車部品製造会社「アイシン高丘東北」(大衡村)から約1000万円をだまし取ったとして、元社員の大和町吉岡、無職尾形早紀容疑者(35)を詐欺の疑いで逮捕した。
動かぬ証拠があるのなら自業自得!
東芝は不適切会計問題を受け、前社長の佐々木則夫副会長(66)が9月に開く予定の臨時株主総会で取締役を退く方向で調整していることが9日、分かった。佐々木氏は不適切な会計処理があった平成21年から25年まで社長を務めており、続投は難しい情勢で事実上の引責辞任となる。
岩手県紫波郡矢巾町がどのような所か知らない。
「父親によると、生徒は4月上旬頃から『(別の生徒に)ちょっかいを出されてうざい。学校に行きたくない』などと話すようになったという。」
この時点で生徒に録音できるMP3プレーヤーを持たせ、録音させておけば良かった。自殺を防止できたかもしれないし、自殺しても、
担任や校長そしていじめた生徒の両親に対して損害賠償を要求できた。そして裁判になっても勝訴する可能性も高い。
いじめた生徒に対しては傷害等で警察に被害報告を出せたかもしれない。証拠は大事。事実であろうが、正しかろうが、証拠がなければ裁判では勝てない。
このような問題は簡単には解決できない。全てが同じ方法で解決できないが証拠集めを早い段階で準備する事は良いと思う。必要なければ消去すれば良い。
最悪の事態になれば、証拠を使えばよい。
岩手県矢巾やはば町で、同県紫波しわ郡の中学2年の男子生徒(13)が電車に飛び込んで死亡した事故で、男子生徒が4月からクラスの担任と交わしていた「生活記録ノート」の全容が8日、明らかになった。
千葉市中央区の精神科病院「石郷岡病院」で2012年1月、男性入院患者に暴行し、その際の負傷によって2年後に男性が死亡したとして、千葉県警は8日、当時、同病院に勤務していた准看護師2人を傷害致死容疑で逮捕した。
東京地検の「悪質性低い」と判断には賛成できない。悪質性は高いだろう。ただ、転売や利益目的の輸入ではないからとの判断と容疑者が辞職した結果を
考慮し、弁護士やトヨタからの働きかけもあって「悪質性低い」として不起訴(起訴猶予)としたと推測する。
東京地検の「悪質性低い」との判断には個人的に納得は出来ない。まあ、法とか公平とか言っても、力を持っているものが全て。これが現実。
トヨタ自動車前常務役員のジュリー・ハンプ容疑者(55)が麻薬取締法違反(輸入)容疑で逮捕された事件で、東京地検は7日、同容疑者を勾留期限の8日までに釈放する方針を固めた。
特別養護老人ホームの実態を県は抜き打ち検査で把握する必要があると思う。現状の給料体制や人件費で満足なサービスが提供できないのなら
システムを再検討するべき。老人ホームや送迎車が良すぎる。景気対策の一部として補助金で購入できるのだろうけど、補助金は税金。
もっと効率的に運用でき、中古の建物を安くリフォーム出来るような方法も検討するべきだと思う。これで問題は解決しないと思うけど
改善しなければ税金をもっと投入するか、サービス低下しかないと思う。
埼玉県熊谷市の特別養護老人ホーム「いずみ熊谷」で昨年、入所者に別の入所者の薬を誤って与えるなどのミスがあり、2人が死亡していたことがわかった。同施設ではこれを含めて県への報告が必要な事故が計8件起きていたが、いずれも報告していなかった。県は遺族の通報で今年1月に立ち入り調査を行い、行政指導した。
「東芝過大計上1500億円超」はひどい!証券取引等監視委員会はどうしてこのような事が出来たのか調査し、同じことが出来ないようにシステムに反映させるべき。
東芝の不適切な会計問題で、過去の営業利益の過大計上額が1500億円超になる見込みになったことが分かった。
「捜査関係者によると、丸井容疑者は「准教授にふさわしい物を持つべきだと思い、バッグなどを要求するようになった」と供述しているという。」
京都大の医療機器導入を巡る汚職事件で、京都地検は3日、京大病院臨床研究総合センター元准教授・丸井晃容疑者(47)を収賄罪で起訴した。
多くの横領は既に時効の可能性が高いのでは??
勤めていた会社から、総額6億円以上を横領していたとみられる元経理担当の女。
熊本県湯前町の前の郵便局長が郵便局内の現金1億数千万円を横領した疑いがあることがわかりました。
発覚しなければ良い思いをして終わり!運が悪かった!
オリンパスの粉飾決算事件で、旧経営陣による損失隠しを指南したとして、金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)などの罪に問われた元大手証券社員、横尾宣政被告(61)の判決が1日、東京地裁であった。芦沢政治裁判長は「犯行への関与の程度は大きく、極めて多額の報酬を得た」として懲役4年、罰金1千万円(求刑・懲役6年、罰金1200万円)を言い渡した。
「調査委員会には報酬として約5600万円を支払っている。」
カラ出張やカラ接待などの計約240万円の不適切な会計処理の調査のために約5600万円。
筋は通っているが、費用対効果に関しては疑問。
マスコミでも取り上げられた千葉大学発の農業ベンチャー・(株)みらい(TSR企業コード:332071278、中央区日本橋本石町4-4-20、設立平成16年9月17日、資本金3億5142万5000円、嶋村茂治会長)は6月29日、東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。申請代理人は松田耕治弁護士ほか3名(シティユーワ法律事務所、千代田区丸の内2-2-2、電話03-6212-5715)。監督委員には降籏俊秀弁護士(新霞が関綜合法律事務所、千代田区霞が関1-4-1、電話03-6205-7830)が選任された。
「調査委員会には報酬として約5600万円を支払っている。」
カラ出張やカラ接待などの計約240万円の不適切な会計処理の調査のために約5600万円。
筋は通っているが、費用対効果に関しては疑問。
NHKの子会社「NHKアイテック」の50代の男性部長が、カラ出張やカラ接待などで計約240万円の不適切な会計処理をしていたとして、4月に諭旨退職になっていたことが30日わかった。すでに全額を弁済しているという。NHKでは昨年調査委員会を設けて全ての子会社を調査したが、この問題は見つかっていなかった。
フジテレビもこのような失敗をするほど時間とお金がないのか?
フジテレビは29日、5日放送の「池上彰緊急スペシャル! 」で韓国人をインタビューした場面で、映像と異なる吹き替えを使用したとして番組ホームページにおわびを掲載した。
今後は今回のように否認するケースが増えるのだろうな。法律を改正しないと証拠が少ない場合、逃げ得かも知れない!
北海道小樽市で昨年7月、海水浴帰りの女性3人が死亡した飲酒ひき逃げ事件で、自動車運転死傷処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた元飲食店従業員海津雅英被告(32)の裁判員裁判の初公判が29日、札幌地裁(佐伯恒治裁判長)であった。海津被告は「アルコールによって正常な運転が困難な状況ではなかった。その他の事実は間違いない」と述べ、危険運転致死傷罪については否認した。
組織的に問題がある場合、注目されている問題は氷山の一角であるケースが多い。
群馬大学病院(前橋市)で、腹腔鏡ふくくうきょうを使う高難度の肝臓手術を受けた患者8人が死亡した問題で、保険適用外の手術に診療報酬を不正請求した疑いがあるとして、厚生労働省が今月、病院への監査に本格的に着手したことがわかった。
福岡県警は26日、元本を保証するとうその説明をして外国為替証拠金取引(FX)などへの投資を募ったとして、金融商品取引法違反(虚偽告知)容疑で資産運用会社「日本ヴェリータ」福岡支店(福岡市博多区)と関連会社のJBSホールディングス(東京都中央区)を家宅捜索した。福岡や熊本などの計210人から約10億円を集めた疑いがあり、県警は運用実態があったかなど解明を進める。
トヨタ自動車常務役員、ジュリー・ハンプの麻薬密輸容疑は明らかに疑問を抱かせるケースだ。ジュリー・ハンプの弁護士と警察及び検察の
どちらが優秀なのかが結果に影響するだろう。弁護士は麻薬密輸の認識がない事を主張し無罪にしようとするだろう。警察や検察がどれだけ
客観的な証拠を集められるか次第であろう。例えトヨタ自動車常務役員、ジュリー・ハンプが無罪となっても、天下のトヨタが無罪になった
から処分しないとはならないと思う。モラルや企業イメージを考えれば処分が必要だと思う。入手の仕方が明らかに不自然。
米国から麻薬成分「オキシコドン」を含む錠剤を小包で密輸したとして、トヨタ自動車常務役員、ジュリー・ハンプ容疑者(55)=米国籍=が麻薬取締法違反(輸入)容疑で警視庁に逮捕された事件で、ハンプ容疑者が「過去にも送ってもらったことがある」という趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材でわかった。同庁は、ハンプ容疑者がオキシコドンを服用していた実態や入手の経路について詳しく調べている。
以前から書いているが技能実習のシステム自体に問題がある。中国の仲介組織そして監理団体を通して最終的に外国人技能実習生に支払う額が安くは無い。
外国人技能実習生として来日した中国人女性(29)が、「実習先の農家でセクハラを受け、適切な賃金の支払いもなかった」として、茨城県の実習先農家の親子や、実習生の受け入れ監理団体(茨城県守谷市)に対して、慰謝料300万円と未払い賃金183万円の支払いなどを求める訴訟を水戸地裁に起こした。女性は6月26日、東京・霞が関の厚生労働省で弁護士らと記者会見を開いた。
仕方がない。
確かに子供に影響を与えたり、トラウマ的な記憶になる生徒もいるかもしれない。先生が該当する生徒と話し合っただけで生徒の負担が軽減するとは限らないし、
教師の対応の仕方や周りの環境で結果も違っている。一部の人々は上記の理由で猛反発するだろう。しかし、現実から目を背けても問題が解決するわけではない。
生徒の親の問題が努力しての結果なのか、能力の問題ないのか、ギャンブルや浪費癖、又は努力や苦痛から逃げる選択を取る傾向のためなのか、いくつかの理由が
コンビネーションかもしれない。簡単には解決できない問題の場合もある。該当する全ての生徒は助けれらないが、生徒が親と同じようになりたくないと思っているのであれば、
どのような将来を想像しているのか、将来について考えているのか、どのような職業に就きたいのか、生徒の希望や考えが実現可能なのか等を聞いて
指導やサポート出来るように対応するべきだと思う。これにより、割合はわからないが堅実な方向に生徒が向かえば親子で同じサイクルは繰り返さないと思う。
昔の話だが、社会心理学か、心理学の授業を取った時に、アメリカの調査で親子の貧困や問題のある生活パターンは繰り返される確立が高いとの結果が
あると書いてあった。離婚を経験した子供は、辛い思いをしたにもかかわらず離婚していない子供に比べれば離婚する確率が高い。しかしながら、
既に夫婦関係が破綻し、子供に悪影響を与えるような険悪な状況では、離婚したほうが子供にとって精神的に良い結果をもたらす調査結果もある。あくまでもデータと
調査結果。数学の公式のようには同じ答えは出ない。
個人的に思うのは、問題から目を背けても、問題は解決しない。100%の完全な対応は現実社会では難しい。何を優先して問題を解決するかで、
答えは違う。
川崎卓哉、西堀岳路
見てはいけないものは見ない!厚労省の十八番!そして正直者は馬鹿を見る!
小泉浩樹
見つからなければ良い副収入だったのだろうけどこうなれば自業自得!
愛知県岡崎市の美容外科「マリークリニック岡崎院」元実質的経営者鈴木みなえ被告(46)が無資格で医療脱毛をしたとして医師法違反で起訴された事件で、独立行政法人地域医療機能推進機構(東京都)が運営する中京病院(名古屋市南区)の50歳代の形成外科部長が、マリークリニック岡崎院の開設届に名義を貸す医師を鈴木被告に紹介していたことが、愛知県警の捜査関係者への取材で分かった。
山口利昭
「有識者委は国の認定制度見直しを含めた再発防止策を7月中に取りまとめる予定。」
認定制度の見直し、及び再発防止に関してどうようにするのか?結局、性善説ではなく悪意があることを前提に対応するとして、
何をするのだろうか?罰則強化?罰金及び懲役刑?長期間の入札停止?
隠蔽工作やごまかしが巧妙になることは想定して対応することを忘れないように!
国土交通省は22日、東洋ゴム工業による免震ゴムの性能改ざん問題を受けて再発防止策を検討する国交省の有識者委員会(委員長・深尾精一首都大学東京名誉教授)に対し、過去に不正を行った企業への監視を強化する案を示し、大筋で了承された。
東洋ゴムが調査を頼んだ社外調査チームは本当にまともに仕事をしているようだ!
日本は形だけの調査が多い思われるケースが普通。品質保証部はごますり、隠蔽工作部と思える会社もある。
まあ、これが日本だし、品質は外国よりもましと言えば、そうかもしれない。コンプライアンスは建前の話である会社もある。
新宅あゆみ、山村哲史
「一方、関係者によるとハンプ容疑者は来日以前から、右膝の痛みを抑えるために鎮痛剤を服用していたとの情報もある。」
どこからの情報なのか知らないが、苦しい言い訳としか思えない。彼女はトヨタ自動車常務役員。本当に右膝の痛みを抑えるため「オキシコドン」が
必要であり、医者の処方箋があるのなら正規のルートで入手できる。お金を気にする身分ではない。しかし、事実は「輸入に伴う書類では錠剤が見つかった小包の内容は『ネックレス』と記載され、
中には玩具のようなネックレスやペンダントが入っていた。錠剤は小包の底にあったほか、ペンダントが入っていたケース内に敷かれた紙の下からも一部が見つかった。」
米国から麻薬を密輸したとして、トヨタ自動車役員、ジュリー・ハンプ容疑者(55)=米国籍=が麻薬取締法違反(輸入)容疑で警視庁組織犯罪対策5課に逮捕された事件で、麻薬成分「オキシコドン」が含まれていた錠剤57錠は、複数に小分けされて装飾品のケースの底などに入れられていたことが19日、捜査関係者への取材で分かった。同課は、錠剤が見つからないように分散させて隠そうとした意図があるとみている。
ジュリー・ハンプ氏はFerris State Universityを卒業している。
「State University」と書かれているからミシガンの州立大学なのだろう。名前を聞いたことが無いのでそれほど有名でないのか、
小規模の大学なのかもしれない。しかし、彼女の経歴を見るとりっぱなので現場で結果を出してきたタイプなのだろう。
現場で結果を出すために必要以上にがんばってきたので、麻薬であるオキシコドンに依存したのかもしれない。
「キシコドンはアヘンを原料とする医療用麻薬」と言う事は中毒性が高いのでは?中国のアヘン戦争時代には、多くの中国人がアヘン
中毒であった。
「麻薬輸入とは思っていない」のが事実なら堂々と日本に入国する時に持って帰ればよいと思う。また、小包の底に麻薬であるオキシコドンを詰める必要も無い。
アメリカでは今回の事件をどう捉えるのであろうか?
米国から麻薬を密輸したとして、警視庁は18日、トヨタ自動車常務役員で、米国籍のジュリー・ハンプ容疑者(55)(東京都港区六本木)を麻薬取締法違反(輸入)容疑で逮捕した。
アメリカなら傷害や不審な行動を取らない限り逮捕されないと思うけど、日本はアメリカと違う。ALT(外国語指導助手)の中には麻薬や大麻を
輸入して逮捕された人はいる。たぶん、氷山の一角だろうね!
トヨタ自動車常務役員なのだからどうしても我慢できないのならもっと上手くやればよかったと思う。それとも、トヨタに来るべきではなかったのかも
しれない。キャリアに汚点がついてしまった。
麻薬を米国から違法に輸入したとして、警視庁は18日、トヨタ自動車常務役員のジュリー・ハンプ容疑者(55)を麻薬取締法違反(輸入)の疑いで逮捕した。警視庁への取材でわかった。「麻薬を輸入したとは思っていません」と容疑を否認しているという。
愛知県警蒲郡署は17日、愛知銀行蒲郡支店(蒲郡市元町)の元支店次長で同県豊橋市牟呂町、無職青山誓吾容疑者(53)を業務上横領容疑で逮捕した。
以前、似たような事をした会社が倒産した。まだ同じような事をする会社がいるのか?
「新潟県産コシヒカリ」と偽ってブレンド米を販売したとして、新潟県警は17日、大阪府東大阪市の米穀販売会社「東友精米」の元社員の男3人を不正競争防止法違反(誤認惹起じゃっき行為)容疑で逮捕した。
韓国と日本の共通点は初期対応の甘さと、隠蔽体質。
最近の隠蔽体質の例は、年金情報流出の事実を17日間、係長の独断であるが隠蔽したこと。
韓国で感染が広がっている、MERSコロナウイルスで、自宅隔離の対象となる前に帰国していた日本人の親子について、その行動と日本政府の対応が、徐々に明らかになっている。>
日本も対応が甘い。デング熱の時も、遅い対応で被害が広がった。蚊の行動範囲が限られているとか知ったかぶりの推測で被害者が増えた。
感染者は移動するし、蚊だって車やその他の移動手段に紛れ込んで一緒に長距離を移動できる。自称、専門家の話は当てにならない。
韓国の遅い対応で、経済的に損失を出している。韓国国民だって直接的、及び間接的な被害を受けている。
韓国で感染が広がっている「MERSコロナウイルス」で、患者がいた医療機関を訪れていたなどとして症状は出ていないものの、自宅での隔離の対象となっていた日本人2人が、すでに日本に帰国していることが関係者への取材で分かりました。厚生労働省も韓国で患者がいる医療機関を訪れ、帰国した複数の人について健康状態を確認していますが、いずれも患者との接触歴はなく、発熱などの症状はないということです。
【ソウル=加藤宏一】韓国で中東呼吸器症候群(MERS=マーズ)の感染拡大の影響が一段と広がっている。韓国政府は15日、感染者が死者16人を含む150人になったと発表。感染者と接触し、自宅などで経過観察措置がとられる隔離対象者の中には日本人ら外国人も含まれることが明らかになった。韓国旅行を中止した外国人観光客は10万人を超え、旅行業界が打撃を受けている。
韓国保健福祉省の権●(=俊のにんべんを土に)郁公共保健政策官は15日、記者会見で、中東呼吸器症候群(MERS)の自宅隔離対象者に、これまで外国籍の人が20~30人おり、その中に日本人が含まれると明らかにした。症状がある人はなく、全員がウイルス検査で陰性という。日韓関係筋によると、自宅隔離対象の日本人は2人で、いずれも15日までに日本へ帰国していた。 しかし、韓国政府は隔離対象者には出国禁止措置をとっており、2人がなぜ日本へ出国できたのか不明。隔離対象者との通告を受ける前に2人が出国した可能性もある。日本政府が2人の経過を観察している。 韓国での15日までの感染者は計150人。14日に男性2人が死亡し、死者は16人になった。
中国に事実上の「拒否権」は中国のための「アジアインフラ投資銀行」AIIBと言っているようなものだ。
アジア諸国の政治家達と中国の癒着により将来の不利益になる事でも決まっていくのだろう。結局、投資を受け入れる国の国民、又は、
他の国が無駄な投資の尻拭いをしなくてはならなくなるであろう。日本もAIIBから融資を受け財政的に行き詰った国から円借款の一部又は全額の放棄を要求されるなどの影響を将来受けるであろう。
【北京=鎌田秀男】中国が主導する国際金融機関「アジアインフラ投資銀行」(AIIB)の設立協定の全容が16日、明らかになった。
医療機器会社も製薬会社もコンプライアンスを徹底したら、抜駆けがいなくならない限り、利益が減るだろう!
データ改ざん、大手製薬会社「ノバルティスファーマ」と臨床研究を行った病院の関係
を考えれば業界のずぶずぶの関係が推測できる。病院側がそのような体質なのだから、臨床研究だけに限らず、他の分野でも同じような
癒着体質があってもおかしくない。無いほうが不自然と思うほうが普通。
医療機器購入を巡る汚職事件で、京都大医学部付属病院(京都市左京区)には15日午前10時すぎ、段ボールを抱えた京都府警の捜査員約10人が訪れ、時間外出入り口から家宅捜索に入った。一方、医療機器販売会社「西村器械」(同市中京区)にも同日午前10時ごろ、捜査員4人が訪れて家宅捜索。同社の広野拓治専務は「世間を騒がせてご迷惑をおかけしました。コンプライアンスを徹底し、社員教育をやり直したい」と話した。【宮川佐知子、花澤葵】
アメリカ製とドイツ製の高級キャリーバッグ3個(計約30万円相当)で人生の一部は終わった。
医療機器の営業は多少のお金を使うことによって、継続、上手く行くと、他の契約も取れる可能性を得られるメリットがあったのだろう。
営業は不正が発覚しなれば、どんな手を使おうと仕事を取ったものが勝ち。クリーンな営業で仕事が取れなければ、給料と営業費の無駄。
会社が不適切な営業をあるかもしれないと思っていても問題があれば会社として本人が勝手に不適切な営業をしたとして切り捨てればよい。
会社が証拠が残るような形で不正な営業を指示していなければ、証拠不十分で罪に問われることはないだろう。
年金情報流出で担当係長の席が課長や課長補佐の近くなのに、隣の人間を含め、誰一人、
年金情報流出に関して知らないと答弁しているのと同じ。不都合な事は知らないふり。
元准教授が人生の階段を踏み外した事を見た人々が、業者の誘惑を断るようになれば、小さなステップだが良い方向に向かうだろう。
京都大病院(京都市左京区)臨床研究総合センターの元准教授(47)が在職中、医療機器発注で業者に便宜を図った見返りに賄賂を受け取ったとされる疑惑で、京都府警は14日午前、元准教授を収賄容疑で、業者側の医療機器販売会社(同市中京区)社員を贈賄容疑で、それぞれ取り調べを始めた。
武田薬品工業(大阪市)が高血圧治療薬「ブロプレス」を巡り不適切な広告を行った問題で、厚生労働省は12日、医薬品医療機器法(旧薬事法)に基づき、同社に業務改善命令を出した。
お坊さんも人間と言う事。厳しい修行に耐えても、内面がわからない人は存在する。これは仕方の無い事。
出来る限りよい僧侶を増やすことが課題であろう。
カラ出張を繰り返して交通費などをだまし取ったとして、京都府警下京署は10日、浄土真宗本願寺派(本山・西本願寺)の僧侶で元幹部職員の男(46)(京都市下京区)を詐欺の疑いで逮捕した。
高知県は8日、消費者物価指数などの基礎データとなる商品やサービスの価格を調べる県の小売物価統計調査員の女性が架空のデータを作成し、国に報告していたと発表した。
警視庁公安部の能力の問題なのか、民間の専門家でも無理なのか知らないが、日本のセキュリティー体制がこんな状態であれば
マイナンバー導入は先送りしなければならないと言うことだ。
いろいろな情報をリンクさせてしまうと大量の情報が抜き取られる可能性が考えられる。防御も出来ない、捜査も困難であれば利便性よりも
大量の情報流出のリスクを回避するほうが重要。厚労省及び年金機構には情報の保護する能力はない事が明らかになった。
■複数サーバー経由…相手国の協力不可欠
自業自得と運が悪かった!不正に関与しても捕まらない人々もいる!
JR貨物の発注工事を巡る汚職事件で、JR貨物は8日、石田忠正会長ら幹部5人を報酬返上などの処分とし、JR会社法の収賄罪で起訴された富永英之被告(45)を懲戒解雇した。
強度や工作を無視したアート的なデザインを選択した時点である程度、予測出来ること。
概観を妥協するほうが良い。日本はそれほどアートにこだわらない国。将来の維持管理費を考えて概観や設計を変更するべきだ。
建設費は当初1300億円を見込んでいたが、その後の試算により、最大で約3000億円。
「昨年5月に事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)が公表した計画では、『建設費は1625億円、工期は42か月』で、19年3月の完成予定だった。」
人件費の高騰があるとは言え、試算に問題があったのではないのか?国立競技場将来構想有識者会議に参加した人々と
日本スポーツ振興センター(JSC)に責任は無いのか?あるだろう。
初期投資と維持管理費を考えて変更するべきだ。建設が始まってからでは遅い。曲線は美しいが、維持補修を考えれば高額になることは
考えただけでもわかる。
今年10月の着工を控える新国立競技場(東京都新宿区)の建設計画が揺らいでいる。
昔、アメリカに住んでいた時にソーシャルセキュリティーナンバーを使われ被害を受けたことがある。あの頃はアナログの世界だった。
それでもソーシャルセキュリティーナンバーを使って名前と生年月日だけで本人確認を要求しないシステムのケースで被害を受けた。
あれを経験したから出来るだけクレジットカードは使わないし、クレジットカードでの支払いのみの通販はほとんど使用しない。
便利であるかよりも、被害にあわない事を優先している。コンビニでの支払いや、小額の口座から降り込むようにして乗っ取られても小額の被害でなるように努力している。
厚労省及び年金機構の無責任な対応の甘さには頭に来る。こんな体制でマイナンバーとは笑わせないでほしい。
セキュリティー対策よりも日本国民を騙すほうが簡単だから年金機構から次の呼び名の組織へ移行する準備でもはじめるのか?
日本年金機構のパソコンがウイルスに感染し、年金の個人情報が大量に流出した。
昔、「私は元○○銀行員です。信用してください。」と言われたことがある。「元○○銀行員だから信用できると判断できる根拠がない。
他の説明をしてほしい。」と言ったら、「皆、『元○○銀行員だったら安心。』と言われる。」と言った。本当かどうかはわからないが、
彼が言ったことが事実なら、日本は甘い国だなと思ったことがある。学校では学ばなかったが、人生経験を通して、公務員も信用できないと
学んだ。逮捕されたみずほ銀元行員は似たような事を言っていたのだろうか?
偽造書類を使って以前務めていた銀行の支店から融資をだまし取ったなどとして、警視庁捜査2課は3日、詐欺などの疑いで、みずほ銀元行員で測量会社「協立測量」(破産)元役員、丸峰順市(57)=さいたま市桜区神田=と同社の実質経営者、阿部善宏(55)=東京都練馬区豊玉中=の両容疑者ら男5人を逮捕した。捜査2課によると、丸峰容疑者ら2人は容疑を否認し、阿部容疑者ら3人は認めている。
自業自得だと思う。日本はチェック体制は甘い国。その体制を中国でも続け、チェックも行ってこなかった。
生まれた以上、いつかは終わりが来る。始まりと終わりは歴史を見ればわかる。中国に頼らなければならなかった状況が
既に衰退していた事を意味していたと思う。
東証1部上場だった化学薬品商社「江守グループホールディングス」(福井市)が4月末、民事再生法適用の申請を発表し、破綻した。同社は昨年3月期決算までは好業績を続けていたが、その後、中国の取引先から代金が回収できないなど、傾注していた中国事業での失敗が表面化。債務超過に陥り、明治の創業以来109年続いた創業家の歴史に幕を下ろした。福井の名門企業である同社の倒産劇は改めてチャイナリスクの大きさをクローズアップさせた。
125万件の個人情報流出だけでも問題。しかし、マイナンバーで多くの情報が流出したら誰が責任を取るのか?
日本年金機構は1日、職員の端末がサイバー攻撃を受け、個人情報約125万件が外部に流出したと発表した。いずれも加入者の氏名と基礎年金番号が含まれ、うち約5万2000件には住所や生年月日も含まれていた。同機構は警察に通報し、捜査を依頼した。
千葉大の韓国人女性助教は盗用がばれないと思ったのか?
千葉大は29日、同大環境健康フィールド科学センターの韓国人の女性助教が、同大の元大学院生が作ったスライド資料を盗用し、学会で発表していたと発表した。
恐ろしいな!
熊本大医学部付属病院(熊本市中央区)は、切迫早産で入院中の女性患者(20歳代)に点滴をするため、静脈内に細い管(カテーテル)を挿入した際、管内の金属製ワイヤ(長さ約40センチ)を抜き忘れたと発表した。
マニュアルやシステムが立派でもそれを運用する会社の体質や人材に問題があれば、約15年間も不正は発覚しない典型的な例だ。
約15年間に計24億7600万円。基本的にチェックがずさんであるのか、形だけのチェックが常態化していたのだろう。
少なくとも事なかれ主義と責任を問われなければ他人や同僚のことなどどうでも良い考え方があるのでは??
それとも社内的に風通しの悪い企業体質?
製紙大手の北越紀州製紙は28日、自動車教習所などを営む子会社「北越トレイディング」(新潟県長岡市)の50代の総務部長が2000年以降、不正に小切手を振り出すなどして約15年で24億7600万円を着服していたと発表した。
お金は遊興費などに使っていたという。同社は総務部長を同日付で懲戒解雇し、刑事告発する。この責任を問い、北越紀州の岸本晢夫(せきお)社長ら取締役9人が月額報酬の1~2割を2カ月間、自主返納する。
北越紀州製紙は28日、子会社の男性従業員が不正に小切手を振り出して現金に換金することなどで、2000年4月から約15年間に計24億7600万円を着服していたと発表した。同日付で懲戒解雇し、今後刑事告訴する予定だ。
高齢化問題もある。しかし、仕事として魅力が無かったり、昔からの体質で新規参入が難しいこともあるのではないのか?
多くの日本国籍漁船でも外国人船員を使っている。なぜ、外国人なのか、後継者や知識や経験の引継ぎの問題をどうするのかも考える時期であると思う。
そして、残念ながら役人が国際情勢や現状を理解していないし、現場の人間は魚を取るだけで、それ以外について知らないし、知るだけの能力がないのではないのか?
まあ、あまり魚は好きではないので個人的には関係ない。日本は物づくりには定評があっても、それ以外では外国に劣っているとも感じることがある。
世界のかつお・まぐろ類の消費量の伸びは著しい。漁獲量も1982年の190.1万トンから2012年には488.9万トンと、約2.6倍にも拡大している。とりわけ、かつお類の漁獲量の伸びは大きく、世界のかつお・まぐろ類の漁獲量の57%を占めて279.5万トン。30年間で約3.5倍の伸びになる。
中国は妥協しないと思うから、不便になるが現金自動預け払い機(ATM)を中国から撤去すればよい。
儲けを優先させれば中国の意向を無視することなど出来ない。中国に進出した日本企業はリスクを含めて進出しているのだから仕方がない。
少ないとは思うがこれから中国進出を考える日本企業は良く考えたほうが良いと思う。
経済産業省は27日、2015年版の「不公正貿易報告書」を発表した。中国政府が同国に進出した邦銀などに、現金自動預け払い機(ATM)やコンピューターシステムの技術を中国で特許登録し、事実上、情報開示するように要求していたことがわかった。
株価をつり上げるため発電機の仲介取引で約10億円を売り上げたとする虚偽の業績予想を発表したとして、東京地検特捜部は27日、金融商品取引法違反(偽計)容疑などでジャスダック上場の発電事業会社「石山ゲートウェイホールディングス」(東京都港区)社長、三木隆一容疑者(68)と同社元常務、深井憲晃容疑者(45)を逮捕した。また、同社の発電機取引に関係し、国の補助金5億円をだまし取ったとして、詐欺容疑で発電会社「テクノ・ラボ」(茨城県牛久市)社長、岡登(おかと)和得(かずのり)容疑者(55)も逮捕した。
顧客の銀行口座から現金を引き出し、着服したとして、警視庁は27日、三菱東京UFJ銀行の元行員、奈良田寿(ひとし)容疑者(52)=埼玉県川口市本町4丁目=を業務上横領の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
自業自得!
ミサイルなどの兵器製造に転用可能な炭素繊維を中国に不正輸出したとして、兵庫県警外事課は26日、同県芦屋市の貿易会社「ポリケミカルズリミテッド」会長・近藤正二容疑者(75)ら3人を外為法違反(無許可輸出)容疑で逮捕した。
事実や背景については知らないが、がんばってほしい。なかなか戦おうとする人はいない。時間やコストそしてその後の問題ないと考えると行動する人は
少ないと思う。
意に反して退職を勧められるなどパワーハラスメントを受けたとして、三重大医学部付属病院(津市)臨床麻酔部の30歳代の男性助教が25日、同大を相手取り、慰謝料などを求める訴訟を津地裁に起こした。
経理担当の不正は、規則ではいけないことでも任せる傾向があるから経理担当者が頻繁に変わらないことが原因のように思う。経理担当が頻繁に変われば不正を
長期間行えないが、理事や役員達が不適切な事を秘密に出来ないデメリットもある。
山形県鶴岡市体育協会は25日、経理担当の女性職員(55)が、協会の口座から少なくとも約1100万円を着服した疑いがあると発表した。
群馬県嬬恋村農業協同組合(松本義正・代表理事組合長)は25日、同農協の40歳代の男性職員が2572万円を横領していたと発表した。
子会社の調剤薬局で薬剤服用歴(薬歴)を記載せずに患者に薬を出し、診療報酬を請求していた問題で、ドラッグストア大手ツルハホールディングス(HD、札幌市)は25日、最終報告を厚生労働省に提出し、新たに約24万件の不適切な診療報酬請求があったと発表した。判明した不適切請求は計約41万件となった。
ドラッグストアチェーンの「くすりの福太郎」(千葉県鎌ヶ谷市)で薬剤師が薬剤服用歴(薬歴)を記載していなかった問題で、親会社の「ツルハホールディングス」(HD・札幌市)は25日、薬歴管理の不備が約41万件あり、診療報酬約1億7100万円を患者らに返還すると発表した。
国際通貨基金(IMF)やEUはどう対応するのだろうか?
甘い対応で許せば、たぶん、同じことが繰り返されるだろう。厳しい対応を取れば、EUを巻き込んで泥沼への道となるだろう。
EU統合のよる大問題は、ある国がギリシャのような財政問題を抱えた場合、放置するわけにはいかないことだろう。
個人的な意見だが、誰も苦しむことなく問題の解決策はないだろう。ラテン文化の国々が深刻な財政問題を抱えると似たような状況になると思う。
[アテネ 24日 ロイター] - ギリシャのブーチス内相は24日、債権者との間で合意に至らなければ、6月の国際通貨基金(IMF)への融資返済はできないとの考えを示した。
簡易宿泊所は定期検査報告の対象外となっているのであれば仕方がない。対象外とする判断を下した人達に責任の一部があると思うが、ほとんど又は
全ての職員達が退職しているに違いない。もしそうだとするとCase Closedだろう。
個人的な推測であるが、簡易宿泊所は定期検査報告の対象外としないと多くの簡易宿泊所が影響を受け、安く簡易宿泊所を使いたい人々にも影響が出ることを考慮
したのではないかと思う。結果から考えれば、違法建築の建物であっても火事が起きないと問題ない。過去に同様の火災による死亡事故がないので
見直す必要性に直面しなかったのだろう。ただ、実際、死亡事故につながる可能性は残っていたので、今回の結果となった。
命か、コストか、どちらが優先されるのかは難しいところである。綺麗ごとで言えば、当然、命に変わるものはない。しかし、実際は・・・なのである。
川崎市川崎区の簡易宿泊所(簡宿)の火災で、同市が建築基準法でホテルなどに義務付けられた定期的な検査報告の対象から簡宿を除外していたことが分かった。
「国際協力銀行(JBIC)も、これまでよりも積極的にリスクを取った融資を行い、資金支援を倍増させる。」
一般的にリスクを取るメリットはハイリターン。なぜハイリターンが必要なのか?ハイリターン期待の投資は損失の可能性が高い。
損失は誰が被るのか?日本国民じゃないのか?
ある国でリゾート開発が盛んになり、多くのホテルが出来た。結果、飽和状態。不動産の価値が上がっているときは良いが、実質的な
需要よりも期待だけが先行した場合、誰かが損をする。
安倍首相は21日、東京都内で演説し、アジア地域の良質なインフラ(社会基盤)整備を支援するため、2020年までの5年間に約1100億ドル(約13兆円)を投じる方針を表明した。
武田薬品工業が高血圧治療薬「ブロプレス」を巡って不適切な広告を行っていた問題で、厚生労働省は医薬品医療機器法(旧薬事法)に基づき、同社に業務改善命令を出す方針を固めた。
大型豪華客船に損害がなくて良かったと思っているのだろうか?損傷したら納期が延び、さらなる損失につながる可能性がある。
21日午前2時40分ごろ、長崎市の三菱重工長崎造船所香焼(こうやぎ)工場で、大型豪華客船を建造中の高さ約15メートル、約120トンのクレーンが倒れた。けが人はいなかった。造船所によると、倒れたクレーンは稼働しておらず、当時、作業中の別のクレーン(高さ約26メートル)が接触し倒れた。コンテナ4箱が下敷きになりつぶれたという。長崎労基署が原因を調べている。
テレビで顔出しでこの件について出ていた。会話も録音していた。よほど病院の対応に憤慨したのだろう。
病院は人命とか、患者のためとか言っても、困ると弱いものを見下した対応を取るのであろう。
藤田遼 西村圭史
藤田遼 西村圭史
アメリカは車社会だし、車の車検費用は安いし、検査基準も厳しくない。車自体もぼろぼろだが安い。そのような環境で鉄道は
物流の目的以外では難しいと思う。また、アメリカ人の気質も影響している。まあ、JR北海道の問題があるから、日本人が優れているとは
言い切れない。やはり、コストの問題は大きい。
【ニューヨーク=広瀬英治】全米鉄道旅客公社「アムトラック」の急行列車が米フィラデルフィアで脱線し、8人が死亡した事故から、19日で1週間となる。
なぜこの時期に警察当局の情報が流れるのか知らないが、興味深い記事ではある。
イスラム過激派組織「イスラム国」による日本人人質事件で、殺害されたとされるジャーナリストの後藤健二さんが、誘拐保険に加入していなかったことが政府関係者への取材でわかった。
また、形だけのパフォーマンスか?日頃からしっかりチェックしていれば良いこと。数の問題で全ては調べられないのだろうが、検査に入ったら
しっかりと調べるべきだと思う。まあ、手を抜こうが、甘い検査だろうが、それをチェックしたり指摘する機関はないから自己満足のチェックになるのだろう。
ある項目をばかみたいに調べたり、もっと問題がある施設を見逃し、おとなしい相手には規則遵守を強気に要求する。
川崎市川崎区で簡易宿泊所2棟が全焼し、多数の死傷者が出た火災で、総務省消防庁は18日、全国の消防本部に対し、管内の簡易宿泊所に防火設備や避難路などの不備がないか立ち入り検査するなどして確認し、不備があれば早急に改善を求めるよう通知した。
橋下徹大阪市長が100%正しいとは思わない。60から70%ぐらいだと思う。
まあ、接戦ではあったが「大阪都」反対の結果となった。大阪市民でも大阪府民でもないので結果に対する責任は大阪市民や大阪府民が取る事となる。
「大阪都」反対が決定した後、自民や民主の会見を見たが勝った側の会見とは思えなかった。また、自民党の会見の時、大借金を作った参議院議員太田ふさえ元大阪府知事が
バックに映っていたことに違和感を感じた。他の人々がどう思うのか知らないが意味があっての位置だと思う。
橋下徹大阪市長が大阪府知事時代に公務員衝突した事実と大阪市長になってから公務員と衝突した事実を考えると、大阪都になったから
府と市の二重行政の無駄がすぐになるなるわけではないが、システムとして無駄を無くしやすい環境を整えるという意味では良かったと思う。
システムと人々(システムを動かす人間)が同じ方向を向いていないと期待するほうどの効果は得られない。自民、公明、民主、共産、そしてその他が
反対している以上、橋下徹大阪市長が言っている様な結果にはならなかったと思う。その意味では、自民、公明、民主、共産、そしてその他が
抵抗勢力になるから財政効果は余りないと言った反対派勢力は正しかったのかもしれない。
全体としてメリットがあっても、メリットを失う人々は反対する。当然のことである。ギリシャのように地獄に行き着くまで公務員を増やし、
公務員を優遇する政策もありだと思う。だから、ギリシャやギリシャ国民に同情しない。結果として悲惨な目になっているが、ギリシャ国民が選択した結果なのだ。
政治家が悪いとか、公務員が悪いとか言っているが、それを許したのはギリシャ国民。大阪がどのようになるのか何年後、何十年後にわかるであろう。
大胆な改革に対する市民の将来不安を払拭できなかった。橋下徹大阪市長の政治生命に直結する結果となった。
福山のホテル火災と同じ。違法建築であっても厳しい指導を受けない。これが現実。コストや値段を優先させれば仕方のないこと。
5人死亡を被害が大きいのか、それとも小さいのかと判断するだけのこと。
「一般的に、60年代に建てられた木造建物が耐火建築物だった可能性は低く、市によると両施設とも建築基準法に違反する可能性が高いという。」
火災の後に詳細に判断しても遅い。まあ、安いから仕方がない。安い宿泊所に泊まる人は値段優先(1泊2千円)で選んでいるし、安全でないことは
うすうす感じていると思う。行政は問題を放置しているのだから、偽善者ぶって必要以上に規則を厳しくするべきではないと思う。
川崎エリアのまともな宿泊所で1泊2千円はないと思う。(東京には1泊2千円の宿泊施設はあるようです。)
川崎市川崎区の簡易宿泊所「吉田屋」と「よしの」の2棟が全焼して5人が死亡、19人が重軽傷を負った火災で、川崎市は18日記者会見を行い、両宿泊所が違法建築だった疑いが強いとの見方を示した。建築基準法では、宿泊施設などは鉄筋コンクリート造りなどの耐火建築物でなければ3階建て以上にはできないと定められているが、両宿泊所はいずれも木造で、実質的に3階建てだった。同市建築指導課は「こうした構造を要因として火の回りが早くなり、被害が拡大した」とみている。
川崎市などによると、全焼した「吉田屋」と「よしの」の両簡易宿泊所はいずれも木造3階建てで、各階の中央部分を通る廊下の両側に、1人用個室が並ぶ構造になっている。
「中国に次ぐ出資比率は、インド、ロシア、韓国の順となる見通しだ。」
日本はアジアインフラ投資銀行(AIIB)に参加しなくて正解だ。出資比率が高い中国、インド、ロシア、韓国を相手に日本はまともな
交渉は出来ない。どの国も「私が優先」と主張する国々だ。中国がでしゃばらないとどの国も簡単に譲歩しそうにない。迅速な投資決定は
無理そうな気がする。
中国が主導して設立準備を進めているアジアインフラ投資銀行(AIIB)の設立協定の概要が明らかになった。
過去に証明書、学位記、卒業証書そして教員免状などが偽造されている。スキャン、編集そして印刷技術も向上し、個人レベルでも安く偽造できる
時代だ。しかし、採用に関してチェックや確認を怠った責任は西九州大にある。騙すほうも悪いが、騙されないような対応を取らなかった大学も悪い。
騙せるから、騙す輩が存在する。今回の件で小城市に開設を予定する4年制「地域看護学部」(仮称)の17年の認可が延びれば、他の大学も
真剣に対応するだろう。
西九州大(佐賀県神埼市)の専任講師が学位を詐称していたことが14日、同大などへの取材でわかった。
東洋ゴムの免震不足ゴムと似ているように思える。問題を隠蔽して問題を放置してきたが、問題を放置したことにより損失がとんでもない規模に膨れ上がった。
上手くいけばそれで良いが、最悪の結果となると会社の損失は桁違い。まあ、どちらのケースでも目先の利益を優先する選択をしたのだから仕方がない。
タカタ製エアバッグのリコール(回収・無償修理)が拡大している。14日にはホンダやダイハツ工業が、前日のトヨタ自動車や日産自動車に続いて、リコールを国土交通省に届け出た。原因不明の異常が見つかるたび、自動車メーカーがリコールを行う状況が続いており、収束の兆しは見えないままだ。
(金融庁)は動くのだろうか?
準大手証券会社の岡三証券仙台支店(仙台市青葉区)が、海外株を買った仙台市泉区の無職男性(68)に実際より高いうその株価を約1年間教え続け、損失を膨らませていた疑いがあることが13日、分かった。金融商品取引法に違反する可能性が高いとして、男性は証券・金融商品あっせん相談センター(ADR、東京)に和解の仲介を申し立てている。
「今年2月には、保健所が無資格調剤の情報を得て立ち入り調査したが確認できなかったという。」
立ち入り検査ではどのような調査を行ったのだろうか?店の従業員に質問する?口裏を合わせていたり、事前に指示を受けていれば、問題は発覚しない。
調査に入られた時のために不都合な記録はしないようにしていれば現行犯で見つけるしかない。しかし、現行犯で見つけることは出来るのか?保健所と
名乗ったら現場は作業を止めるであろう。証拠を得ることは出来ない。こっそりと調剤室に入れば上手くいけば現場を押さえられる。しかし、
無資格調剤が常態化していないければ証拠を得ることは出来ない。もしかすると不法侵入とか、不適切な行為と批判されるリスクがある。保健所の
権限については全く知らないのであくまでも推測。
無資格を知っていながら調剤させた場合、薬剤師に対して資格剥奪等の罰則はあるのか?そのような罰則がなければ今後もこのような事は起きるだろう。
ちょっと検索したら、懲役や罰金だけで薬剤師の資格剥奪とは書いていない。下記の質問は2008年。つまり氷山の一角である可能性が非常に高い。
無資格で調剤したら罰則は? 2008-11-20 07:22:23(OKWave)
薬剤師法違反 --- 薬剤師法
第29条 第19条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、 3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(法庫)
あなたが飲むそのクスリ! 薬剤師でなく事務職員が「調剤」している!? 03/02/15(水島宏明 | 法政大学教授・元日本テレビ「NNNドキュメント」ディレクター)
沢伸也、月舘彩子
沢伸也、月舘彩子
愛媛県伊予市立北山崎小学校(伊予市中村)に設置されている北山崎児童クラブの運営委員会は、女性の元指導員(54)が2010年4月から約4年間にわたって、運営費約520万円を着服していたと発表した。
飲酒運転による事故で今後がどうなるのか考えると恐ろしくなったのであろう。
山梨放送(甲府市)は8日、同社営業企画部の男性部長(46)が7日午後10時頃、飲酒運転をして山梨市万力の国道140号で追突事故を起こし、男性の首や腰などに軽傷を負わせ、逃走したと発表した。
しかし日本政府はお金をじゃんじゃん使っているよ!増税すれば問題ないと思っているのだろう。
財務省は8日、国債と借入金、政府短期証券を合計した「国の借金」が2014年度末時点で1053兆3572億円になったと発表した。13年度末から28兆4003億円増え、過去最大を更新した。高齢化に伴い膨らんでいる社会保障費の財源不足を、借金で賄い続けていることが主因だ。
財務省は8日、2014年度末の「国の借金」が前年度末より約28兆円増えて1053兆3572億円となったと発表した。高齢化による医療や年金といった社会保障費の伸びなどを背景に、過去最大を更新。今年4月1日時点の人口推計(1億2691万人)で割ると、国民1人当たりの借金は約830万円となる。
東洋ゴム工業(大阪市)の免震ゴム性能偽装問題で、衆院国土交通委員会は8日、山本卓司社長(58)ら同社幹部と、偽装を見過ごした民間の性能評価機関の専務理事ら計6人を参考人として招致した。
処分が厳しいから犯罪に手を染める人が少ない場合もある。全てを知っていてインドネシアで麻薬などの犯罪に関わるのだから自業自得。
麻薬のために殺されたり、人生が崩壊する人達も存在するのだから悪いことばかりではない。死刑になっても誰かが麻薬ビジネスに参入する。
問題解決にはならないが、問題の悪化にはならないので厳しい処分の国があっても良いと思う。
【ジャカルタ=池田慶太】インドネシアで、麻薬などの違法薬物犯罪で死刑判決を受けた外国人に対する刑執行が相次いでいる。刑が執行された外国人はこの3か月間だけで12人に上る。恩赦を求める出身国側の求めを受け入れず執行に踏み切ったケースもあり、国連の潘基文パンギムン事務総長も「麻薬犯罪は死刑にするほどの重罪ではない」とする声明を出した。死刑囚の出身国との間では感情的な対立も生まれており、外交問題の火種となっている。
法に抜け穴があるのだから利用する人々が存在しても仕方がない。政府や行政に責任の一部がある。
大阪府内の男性(57)が2008年以降、三つの投資会社の設立と破産を繰り返し、全国の少なくとも約100人の出資金計約2億5000万円が返還されない状態であることが、関係者への取材でわかった。
日本はAIIBに参加しなくても良い。あの中国が日本に参加を要請するのはおかしい。本当に中国が利益を独占できるのなら嫌いな日本に
参加を要請するはずがない。問題があるから参加を要請していると考えられる。そんなAIIBに日本が参加するメリットはない。デメリットの
方が大きいに違いない。
北京=小野甲太郎、池尻和生
バクー=都留悦史
政治団体「日本歯科医師連盟」(日歯連)は今後どのような説明をするのだろうか?
政治団体「日本歯科医師連盟」(日歯連)の政治資金規正法違反事件で、日歯連が民主党議員を支援するために設立した「西村まさみ中央後援会」が、2011年以降は活動実態がないことが複数の日歯連関係者の話で分かった。
朝のテレビで見たが、明確なチェックと管理マニュアル及び罰則のある規則がなければ安全、コスト及び採算の関係でコスト優先となるだろう。
適切な維持管理をある一定期間のスパンで放置すると補修及び維持コストがすごく掛かる。また、古い施設だとお金をかけて維持管理をおこなっても
いつまで使うのかが判断が難しい、そして使用を止めて時点でごみとなる。移設にも多額の費用が発生するため転売や無料による譲渡も難しいと思う。
人件費が高く、安全を求める社会では難しい問題だ。最近、維持管理に興味を持っているのでいろいろな物を維持及び管理を考えながら見る。収益及び
維持管理の両面から見ないとだめだと思う。儲かっているところは撤去及び新設又は交換や大規模修理も可能だろうが、そうでない所は上手くお金が
掛からないようにしながら最低限度の維持や補修を考えるべきだろう。人材の問題もあるし、現実は厳しいだろう。
千葉県立蓮沼海浜公園「こどものひろば」(山武市蓮沼ホ)で2日に起きたゴンドラ型遊具「スカイパイレーツ」の落下事故で、運営する県レクリエーション都市開発は3日、遊具の安全点検が終わらなかったとして、同ひろば内にある全ての遊具の使用を4日以降も休止することを決めた。
電子部品などを扱う商社、江守グループホールディングス(福井市)は30日、民事再生法の適用を東京地裁に申請した、と発表した。負債総額は約711億円。同社は東証1部に上場しているが、5月31日に上場廃止となる。帝国データバンクによると、今年の上場企業の倒産は、スカイマークに続いて2社目。
北海道大(札幌市北区)は1日、研究費1550万円を不正受給したとして、大学院農学研究院の有賀早苗教授(57)と、夫で大学院薬学研究院の寛芳ひろよし特任教授(64)を、ともに停職10か月の懲戒処分にしたと発表した。
総合印刷会社「佐川印刷」(京都府向日市)で財務や経理を担当していた元男性役員が、グループ会社の資金約80億円を取締役会の決議を経ずに、不正に流用した疑いのあることが1日、複数の関係者への取材で分かった。佐川側は資金流用の関係先となった土地や建物など資産の仮差し押さえを京都地裁に申請、4月までに相次いで認められた。元役員は疑惑発覚後の今年1月に辞任。捜査当局も同様の疑惑を把握しており、巨額資金流用事件に発展する可能性もある。
佐川印刷グループで元役員の巨額資金流用疑惑が1日、浮上した。佐川側が仮差し押さえに乗り出した資産には、国内最高峰の自動車レース、全日本選手権フォーミュラ・ニッポン(FN)のシンガポール大会の主催者に名乗りを上げた知人男性(55)側の不動産も含まれている。元役員は内部調査で、大会の舞台となるサーキットの運営など男性側の事業に約54億円を不正流用したことを認めたが、レース自体はサーキットの未完成などを理由に中止された。
生活保護についてよく知らないが目的に関係なく収入は収入となっていれば仕方がない。制度の改正を求めていくしかない。
それてとも奨学金の支給を学費の免除、又は、一部免除として対応できるように民間団体に働きかける方法も考えるべきであろう。
制度のおいて特例とか、例外の記載がなければ無理だと思う。基準は基準。基準が間違っていても、現状に対応していなくとも
基準が変えられるまでは基準である。
福島県立高校に通う長女の奨学金を収入と認定し、生活保護費を減額したのは不当だとして、福島市の30歳代の母親と長女が30日、同市に認定処分取り消しと100万円の精神的損害賠償を求め、福島地裁に提訴した。
子供に関わる人は仕事を変えるか、行動に関しては慎重になるべきだと思う。建前だけで考えたら良くない。
女子中学生にわいせつな行為をしたとして、京都府警は30日、大津市の認定こども園園長・熊本真季雄容疑者(37)(京都市西京区)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕した。
しっかり捜査してほしい。
政治団体「日本歯科医師連盟」(日歯連)の東京都内の本部事務所に、東京地検特捜部が30日、家宅捜索に入った。日歯連をめぐっては、複数の参院議員の後援会に対して、別の政治団体を経由する「迂回(うかい)寄付」をすることで、政治資金規正法が定めた上限を超える寄付をした疑いが指摘されている。
県の主導が事実であるのなら責任の明確にするべきだ!しかしうやむやにする可能性もある。
大北森林組合(長野県大町市)の補助金不正受給問題で、組合が設置した第三者委員会(委員長=竹内永浩弁護士)は28日、県が組合に対し、予算消化のために架空申請を働きかけたととれるメールを送っていたことを明らかにした。
東洋ゴムの免震不足ゴムのように調べれば調べるほどいろいろな問題が出てくる可能性があるかもしれない。
群馬大学病院の患者死亡問題で、開腹による膵臓すいぞうの切除手術を同じ執刀医から受け、手術後まもなく死亡した患者がいたことが関係者への取材でわかった。
文部科学省は28日、昨年開設を不認可とした「幸福の科学大学」(千葉県長生村)の申請者である学校法人「幸福の科学学園」に対し、大学や短大などの設置を5年間認めないと通知した。
個人的な意見だけど、アメリカに住んだほうが幸せだと思う。記事に「親しい自分と同じハーフの友人が自ら命を絶ったこと」や
「学校ではゴミを投げ付けられたり、差別的な言葉を吐かれたりした。肌の色や髪の毛をからかわれ、クラスメートに同じプールで泳がないでと言われたこともある」
が書かれている。彼女は少しでも日本を変えたい、又は、変化を起こしたいと思っているように感じる。ただ、もし彼女が佐世保ではなく、横須賀
で育ったら、また、白人のハーフであったら状況は違っていたと思う。彼女の経験した辛さや痛みが彼女の原動力となっているように思えるので
彼女が経験した事が良かったのかは後になるまで分からない。
2015年の「ミス・ユニバース」日本代表に選ばれた宮本エリアナさん(20)は、日本人の母とアフリカ系米国人の父を持つ。幼少時には肌の色をからかわれ、ひどいいじめにも遭ったという宮本さん。日本代表に選ばれたことは日本以上に欧米のメディアから「日本人のアイデンティティー意識の変化か」と注目され、相次ぐ取材を受ける日々だ。「ハーフでも日本を代表できることを世界中に知らせたい」と胸を張る宮本さんは、来年1月に開かれるミス・ユニバース世界大会に臨む。
TBSも朝日新聞のように企業体質に問題があると言う事なのであろう。まあ、メディアがこのような体質では真実は語れない。
韓国軍がベトナム戦争中に慰安所を開設していたことを週刊文春でスクープしたTBSの山口敬之ワシントン支局長が、この記事をきっかけに懲戒処分を受け、営業局に異動させられていたことが分かった。
本当はお金が理由でしょう。資格を持った人を雇うと経費に影響するから。
放射線技師の免許を持たない事務員らにレントゲン写真を撮らせていたとして、警視庁は24日、東京都西東京市のペインクリニック院長の男(38)(東京都練馬区)と同院の事務員ら計9人を診療放射線技師法違反容疑で書類送検した。
かなりの人間が処分されるだろう。処分によって被害が縮小するわけではないのでどうなるのだろうか?少なくとも部分的に組織の体質であり、
問題であると思われる。
東洋ゴム工業が基準に満たない免震ゴムを製造・販売していた問題で、外部調査の結果、製品の出荷停止方針を決めながらデータを補正するなどして出荷を続けていたことが分かった。
山村哲史、笠井哲也
東洋ゴム工業の子会社による免震ゴムの性能偽装問題で、東洋ゴムが昨年9月に出荷停止と国への報告をいったん決定しながら、直後に方針を撤回していたことが24日分かった。方針撤回の根拠が技術的裏付けに乏しいことが今年1月に判明し、2月に入ってようやく出荷を止めており、同社の危機管理体制が厳しく問われそうだ。
東洋ゴム工業は、国の認定を不正に取得した免震装置を製造販売した問題について、弁護士による外部調査の中間報告を公表しました。性能のデータの問題が、おととしの夏ごろの段階で社内で報告されていたことや、去年9月に製品の出荷を停止する方針がいったん決まりながら、すぐに撤回されていたことが明らかになりました。
さすが日本年金機構(東京)だ。安ければ違法でも何でも良い姿勢がよくわかる。
日本年金機構(東京)が外部委託していた福島、和歌山、大分3県の年金データ入力業務を巡り、業務を請け負った会社が昨年10月以降、労働者派遣法に基づく許可・届け出のない別会社から社員派遣を受け、働かせていたことが、同機構などへの取材でわかった。
請求額:1人当たり100万ユーロ(約1億2800万円)は安いのか、高いのか?
【ベルリン=工藤武人】ドイツの格安航空会社ジャーマンウィングスの旅客機墜落から24日で1か月がたつ。
結局、リスクやコストを考えると違法なことをしないと儲からないのではないのか?
5年間働くことを条件にベトナム人に仕事を紹介し、中途退職できないよう保証金を支払わせていたとして、大阪労働局は23日、職業安定法に基づき、職業紹介業「大阪グローバル」(大阪府和泉市久井町)に2カ月間の事業停止を命じた。
横浜市のNPO法人「エコキャップ推進協会」は存続の危機かも?まあ、前から思うがNPO法人だから信頼・信用できるとは思っていないので今回の件も
氷山の一角だと思う。大きく注目を受けて、メディアも取り上げ、多くの人々に考える機会を与えてくれたと思う。
嶋田圭一郎、影山遼
たぶん、犯人が挑戦状とか、犯行声明を出さない限り、所有者を特定できないのではないかと思う。
小型無人飛行機(ドローン)を使えばいろいろな事が出来るぐらい想像力を使えば簡単なこと。今回の件まで対応しなかったこと事態、
危機管理意識が低いと思う。
いつ、誰が、何のために飛ばしたのか。国の中枢である首相官邸の屋上で22日、小型無人飛行機(ドローン)が見つかった。鳥のような視点で、人が立ち入れない災害現場や観光地を自由に撮影できる便利さ、新鮮さもあり、ドローンは人気が急上昇。政府は飛行ルールなどの規制を検討している。
捜査関係者によると、ウイングズ社は平成25年4月以降、主要事業である格納庫賃貸事業の売り上げはほぼなく、赤字経営が続いていた。
ウイングズ社は土地使用料を毎年滞納しており、川村容疑者は使用許可の更新に必要な釈明の方法などを助言していた。
格納庫の土地使用の申請には、経営状況に関する資料が求められるが、ウイングズ社は売り上げを水増しして報告し、事業が順調なように見せかけていたという。26年には受け入れ機数も104機と報告したが、すべて無償で受け入れていた航空機で、利益は実際には発生していなかった。
川村容疑者は助言の見返りとして、ウイングズ社元社長の金沢星(キム・テクソン)容疑者(61)=贈賄容疑で逮捕=からウイングズ社の関連会社に転職するための支度金名目などとして、現金を受領。26年に米国ラスベガスへ家族旅行した際の渡航費も負担させたうえ、頻繁に飲食の接待も受けていた。
このプログラムによって、排ガス試験が行われていることを検知し、有害物質を取り除く浄化装置をフル稼働させるという悪質な手口だった。
EPAなどによると、排ガス試験では車体を固定し、通常走行のように加速や減速を繰り返し、排ガスに含まれる窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)などの有害物質の量を調べる。日本の検査もほぼ同じ方式という。
エンジンの回転数を調整するなどシステムを制御するソフトウェアは、どの車にも搭載されている。VWはこうしたソフトウェアの中に、違法なプログラムを組み込んでいた。このプログラムの働きで、ハンドルの動きやホイールの位置、アクセルの踏み込み具合などから、試験が行われていることを検知していた。
ガソリンエンジン車を含め、米国とカナダで販売の全乗用車および軽トラックを対象に違法な機器が取り付けられていないか検査する。さらに通常の道路状況下で排出基準を満たしているかを調べるため、追加検査を求める可能性もある。追加検査では、スモッグや酸性雨に関連する窒素酸化物に加え、温室効果ガスである二酸化炭素の排出量も測定する。
EPA交通・大気汚染管理局のクリス・グランドラー局長は記者団に対し「検査の内容を各メーカーに通知することはしない」と語った。
検査強化に伴い、自動車メーカーによってはリコール(回収・無償修理)や製造変更などを余儀なくされ、負担が増す恐れもある。
1年以上も調査官をかわした末、VWは米環境保護局(EPA)とカリフォルニア州当局の幹部2人に不正を認めた。
それは、経緯に詳しい人物2人によれば8月21日の出来事で、VWは事件が公になるほぼ1カ月前に規制当局の圧力に屈していたことになる。それまでの約1年間、VWは自社のディーゼル車が一般道路での走行時に排気ガス中の有害物質の水準が急上昇するのはエラーだと主張し続けた。
米当局は9月18日に問題を公表。試験走行時に排ガス規制に適合するようにモードを切り替えるソフトウエアが、世界中で販売された自社製ディーゼル車の約1100万台に搭載されていたことをVWは認めた。実際に問題が発覚してから米規制当局がそれを公にするまでに1カ月程度かかったのは、当局が対応の準備に時間を要したからだ。
EPAはVWに対し、最大180億ドル(約2.17兆円)の罰金を科すとしている。同社はまた、集団訴訟などでさらに何十億ドルもの費用がかかる可能性もある上、刑事捜査にも直面。ウィンターコルン最高経営責任者(CEO)が引責辞任し、経営陣は混乱した状態にある。関係筋によると、米国法人の社長を含む複数の幹部も処分される。
一貫して否定し続けるというVWの姿勢に直面しながら、調査官は同社の体系的な不正をどのように暴いていったのか──。今後同社に科されるであろう制裁や、より厳しい調査を受けることになる自動車業界にとって、現在に至るまでの経緯はさまざまな意味合いを持つかもしれない。非協力的な同社の態度は、米政府による罰則措置に影響を与える可能性もある。
規制当局者たちは当初、VWが不正行為について冒頭の会議場で認めたことに驚いたという。EPA交通・大気汚染管理局のクリストファー・グランドラー局長は会議でスピーチをする数分前、VWの代表者から不正について聞かされた。事情に詳しい複数の関係筋によれば、カリフォルニア州大気資源局(CARB)の参加者らも口頭で伝えられたという。
この経緯について、VWはロイターに対しコメントを差し控えた。
2009年までVW米国法人で環境対策の責任者を務め、2011年に退職したノルベルト・クラウス氏は、米国法人でディーゼル車の開発に関わった人は1人もいないとし、「ソフトウエアの変更について何も知らない」とロイターの電話取材に答えた。
<1年以上の疑惑に終止符>
正式にVWが不正を認めたのは9月3日、同社幹部とEPA、カリフォルニア州当局者らとの電話会議でのことだった。
それ以前に、VWとアウディが来年発売予定のディーゼル車の承認を保留するとEPAが警告していたことが、同社米国法人のエンジニアリングと環境対策の責任者であるスチュワート・ジョンソン氏と同社の弁護士に送った書簡で明らかになった。書簡にはEPAの行動スケジュールの一部が詳細に記述されていた。
このようにしてVWと米当局側との15カ月間に及ぶやり取りは終止符が打たれたと、複数の関係筋は明かす。EPAなど米規制当局側は、VWのディーゼル車が通常走行中に基準を超える有害物質の窒素酸化物(NOX)を排出していると疑うようになっていた。
VWは2008年、いわゆる「クリーンディーゼル」エンジン搭載の「ジェッタTDI」(2009年モデル)を大々的に宣伝した。2008年に開催されたロサンゼルス自動車ショーでは「グリーンカー・オブ・ザ・イヤー」に選ばれたそのエンジンは、ディーゼル乗用車が全体の半数を占める欧州と比べ、僅かなシェアしかない米国販売を拡大する突破口と見られた。
<祖父のディーゼル車>
クラウス氏は2008年当時、米規制当局へのプレゼンテーションで「これは祖父のディーゼル車とは違う」と語っていた。同氏らVW側はカリフォルニア州を含むすべての州の汚染基準に適合すると主張していた。
その約10年前から、VWやマツダ<7261.T>など他の自動車メーカーは業界団体「ディーゼル・テクノロジー・フォーラム」を設立し、ディーゼル車に対する規制緩和を求めロビー活動を行っていた。2005年にはディーゼル車に対する税控除も実施された。2009年にVWのジェッタが発売されると、米国の販売代理店では完売が相次いだ。
一方ほぼ同時期に、欧州の規制当局は各社が主張するディーゼル車の排ガス水準に懐疑的になっていた。2013年に発表された欧州委員会(EC)の調査は、欧州の自動車メーカーが試験の抜け穴を利用していると結論付けた。ECの別の調査結果でも、欧州メーカーが販売するディーゼル車は試験走行と一般走行で結果に相違があることが示された。
CARBのスタンリー・ヤング氏によると、EC規制当局が米国での路上走行時のデータを求めているのを受け、カリフォルニア州は調査を開始したという。
データ作成は2013年2月、輸送車両の環境適合性などを調査する非営利団体の国際クリーン交通委員会(ICCT)に委託され、ウエストバージニア大学(WVU)の研究者たちが行った。
WVUの研究チームによると、2013年春に7週間にわたってVWのジェッタ(2012年モデル)と同パサート(2013年モデル)を、ディーゼルエンジン搭載のBMWのX5と一般道で比較走行した。その結果、BMW車の排ガス水準は試験走行時の範囲内に収まっていたが、ジェッタは法定基準の15─35倍、パサートは10─20倍も上回っていた。
その後間もなくしてWVUがテストした同じ2台を、CARBの施設で試験走行したところ、排ガス基準内に収まる結果となった。
それから1年間かけてWVUの研究チームはデータを分析。その結果をカリフォルニア州サンディエゴで昨年3月31日に開催された会議で発表した。
<警戒強めた米当局>
この調査結果について「米国とカリフォルニア州にとって明らかに問題だと、幹部たちは警戒を強めた」とCARBのヤング氏は話す。
ヤング氏によると、昨夏に始まったカリフォルニア州当局者らとVWとの話し合いで、VWのエンジニアは調査データとその手法に異議を唱え、結果の信ぴょう性を損なおうとしたという。「断固反対する態度だった」と同氏は振り返る。
EPAによると、VWは昨年12月2日に独自の調査結果を持ち出し、基準を超えていたのは「さまざまな技術的問題と予期せぬ走行中のコンディション」のせいだと主張した。その後、VWはエンジン制御ソフトを修正するためのリコール(回収・無償修理)に同意した。
CARBのエンジニアたちはテストを続け、VWによるソフト修正でも排ガスが大きく減少しないことを明らかにした。事態の打開につながったのは、車のコンピューターシステムに保存されていた診断データを調べたときだった。
ヤング氏は「いくつか非常に不思議な異常を発見した」と言う。
「例えば、通常とは逆に、車は温まった状態よりも冷えた状態での方がクリーンに作動していた。普通は温まったときに汚染制御システムも最善に働く。だが、この車は違った。明らかに何か違うことが起きていた。われわれは時間をかけて、彼らが合理的な説明ができないほどに十分な証拠と疑問を集めた」と同氏は説明する。
CARBは今年7月8日、その結果をVWに提示したが、同社の立場に変わりは見られなかった。一部の当局者は、VWが試験走行時に排ガス規制モードに切り替わる「無効化機能(defeat device)」ソフトを自社の車に搭載して意図的に法を犯しているのではないかとひそかに疑問に思っていたと、関係者の1人は明らかにした。
同ソフトは通常走行時には排ガス低減装置を無効化し、有害物質を基準値の最大40倍排出する。
「こんなふうにだまして逃げ切れると思うなんて、想像をはるかに超えている」と、1999年から2004年までCARBを率いたアラン・ロイド氏は驚きを隠せない様子で語った。
(原文:Timothy Gardner、Paul Lienert、David Morgan、翻訳:伊藤典子、編集:下郡美紀)
この文書はドイツの政策方針書で、欧州連合(EU)の規制機関に対し、最新の車両試験でも重大な抜け穴を残し、実際の二酸化炭素(CO2)排出量が公式結果として発表される排出量より多くなるよう要請している。
この文書について最初に報じた英紙ガーディアン(Guardian)は、同様の要求を記した政策方針書がフランスや英国にも存在すると伝えている。
流出した技術文書の日付は今年5月で、内容はフォルクスワーゲンの不正問題で焦点となっている窒素酸化物(NOx)ではなく、CO2排出量の測定検査に関するものだ。従来の試験NEDCから厳密な新試験WLTPへの変更点に、制限を加える方策を具体的に論じている。
ドイツはこの文書内で、相関試験の際にEUがこれまでに提案してきた以上の例外を認めるよう求めており、下り坂で試験を行うことも例外対象に含まれている。
市民団体「交通と環境(Transport & Environment)」のグレッグ・アーチャー(Greg Archer)氏は、EU主要国がフォルクスワーゲンの不正を批判する傍ら、秘密裏に試験の緩和を実現しようと工作していたと指摘。「VWの不正に対しEUの捜査を要求しながら、同時に新検査を甘くするためのロビー活動を裏でやっているとは、まったくの偽善だ」と批判している。【翻訳編集】 AFPBB News
また、独BMWのディーゼル車の排ガスから基準値超の窒素酸化物(NOx)が検出されたと報じられたほか、欧米の報道によると、米環境保護局(EPA)は、BMWや独ダイムラー、米ゼネラル・モーターズ(GM)などについても調査する方針を固めたといい、自動車業界全体に波及する可能性が出てきました。
今回のVWの不正問題は、どのような手法で行なわれたのか。また、この問題はどこまで波及し、日本メーカーにとっては追い風となり得るのか。モータージャーナリストの池田直渡氏に寄稿してもらいました。
■身代わり受験
フォルクスワーゲンは不正を行った。それは間違いない。ただし、その糾弾は漠然とし過ぎており、却って本質が見えなくなっている感じがする。
ひとまずは、フォルクスワーゲンがやったことの何が悪くて、何が悪いとは言えないのか、そのあたりを整理してみたい。ただし、現在も刻々と状況が変わり、続々と新たな情報が寄せられる状況なので、残念ながら現時点で分かっている情報をベースに順当な考察をしたものにならざるを得ないことはご理解いただきたい。
不正が発覚したのはフォルクスワーゲンのEA189型のディーゼル・エンジンで、欧州のひとつ前の排ガス規制「ユーロ5」の適合エンジンだ。フォルクスワーゲンのアナウンスが「一部車種」を強調するのは最新の「ユーロ6」対応のエンジンでは不正をやっていないとしているからだ。
フォルクスワーゲンがやったことを一言で言えば「身代わり受験」だ。現在世界各国の排ガステストでは、予め運転パターンが決められている。フォルクスワーゲンは米環境保護庁(EPA)が行う排ガス試験の際、その運転パターンを検出すると、即座に試験対策用の専用プログラムに制御を切り替え、動力性能を犠牲にして優良な試験結果を示すようにセットされている。つまり、普通の運転モードでは使わない特殊なテスト専用プログラムに身代わり受験させて不正な結果を出していたのである。明らかな反社会行為で許されるべきものではない。
一方で「テストモード以外では毒ガスを出し放題だったのがけしからん」という論調を多数見かけるが、これは的外れだ。例えるなら「受験科目以外の勉強をちゃんとしないとはけしからん」という話である。普通の大学を受験するのに、受験を控えてわざわざ受験科目以外の美術や音楽を勉強をする受験生がいないように、各国が定めた試験モード以外の運転モードにまで完璧を期している自動車メーカーは世界中に一社もない。
例えば最高速で延々巡行するような時まで排ガスをキレイにしようと思えば、コストが高騰して、競争に勝てなくなる。ここを誤ると全ての自動車メーカーがクロになってしまう。要は、路上走行時に試験と同じ制御が行われているならそれは不正ではないということだ。
こうした「非受験科目」の運転で有害ガスの排出数値が悪化するのは、30年以上前から当たり前に行われてきたことだ。もちろんモラルとしてどうかと言われれば正しいとは言えないが、そのために価格や動力性能で他社に負けるクルマを作っても、誰も買ってくれないのだから構造的に仕方がない。だからこそ各国政府は、排気ガスの基準を徐々に引き上げ、試験問題を難しくしてきたのだ。現在の規制値が十分かどうかについては議論の余地があるだろうが、それは今回の件とまた別の話である。
■欧州と北米の規制の差
さて、フォルクスワーゲンは何故このような反社会行動に及んだのだろうか?
先に触れた様に、世界各国では、それぞれ独自の排気ガス規制がある。米国と日本はその規制値が近い。そもそも米国の規制を参考にして作られたから当然だ。両国で最も重視してきたのは光化学スモッグの原因となる窒素酸化物(NOx)だ。次に炭化水素(HC)と一酸化炭素(CO)で、二酸化炭素(CO2)と粒状物質(PM)について顧みられるようになったのはこの十年少々のことである。
翻って、欧州ではこうした毒性ガスの問題より、環境課税がかけられるCO2排出量とPMが主題となっていた。毒性ガスについては日米と比較すれば相当に緩く、欧州のそれが日米と同等レベルの規制になったのは2014年のユーロ6規制が始まってからだ。
このユーロ6規制は2014年9月以降の発売モデルに課せられたが、すでに販売されているモデルについては2015年の9月まで移行措置がとられたのである。クルマのエンジンはそう簡単に新型に積み替えられないから、モデルチェンジが済んでいないクルマはひとつ前のユーロ5規制適合のまま売らなくてはならない。
この新規制は事前にアナウンスされていたので、間も無く新型に変わることがわかっていてわざわざ現行モデルを買う消費者はいない。しかしフォルクスワーゲンはトヨタとの販売台数一騎打ちの最中だ。「端境期だから仕方ない」と販売の鈍化を眺めていられる状況ではない。当然この間の販売をどうするのかが重大な問題になった。
そこでフォルクスワーゲンは北米に白羽の矢を立てることになる。北米は速度規制が厳しく、ゆっくり定速で巡行する使い方が多いので、本来ディーゼルに向いているマーケットだ。なのに、ディーゼルが普及していない。売り込み先として大きな期待ができるのだ。
■ごまかしの手口
そこで問題になるのが前述の米EPAの規制「Tier2 Bin5」だ。緩いユーロ5規制適合のエンジンではこの規制を通らない。Tier2 Bin5のテストモードを詳細に見ると、特に苦しいのは市街地でのんびり走っている時の急加速を想定したテストだ。ディーゼルの排気ガス温度は低く、ターボでエネルギーを吸収されるとこの温度はさらに下がる。市街地を高いギヤで巡行している時は燃料をあまり燃やさないので排気ガス温度は低い。
具合の悪いことに触媒は化学反応を促進する装置なので、温度依存性が高い性質がある。そのため巡行から急加速する際には、触媒の温度が下がってしまっているため十分に作動しない。その結果NOxがどっと出て規制に抵触してしまうのだ。だからこの時にエンジン制御を特別なプログラムに変える。燃料の噴射量や噴射タイミングを変え、併せて後処理浄化装置をフル稼働させる。
この後処理装置には2種類あり、ひとつは近年普及しだした排気ガスに尿素を噴霧する尿素SCR方式だ。尿素とNOxの化学反応により、NOxを無害な窒素と酸素と二酸化炭素に還元する。温度依存性はあるが、そういう条件だけなら尿素を余分に吹くことである程度の効果が見込める。
しかし旧来型のもうひとつのタイプ、NOx吸蔵還元触媒方式が問題で、こちらは温度依存性がより高い。触媒を十分に働かせるためには、生の燃料をわざと排気管に流して燃焼させ、触媒を加温しなくてはならない。ところが、触媒の加熱は加速の瞬間に一気に行うのは難しい。フォルクスワーゲンの場合この2種の後処理装置を車種によって単独で、あるいは両方備えていた。
詳細は未発表なので、ここからは想像だが、EPAのテストモードではいつ急加速するか予めタイムチャートでわかっているのだから、加速前の巡行中から余分に燃料を吹く制御を行って触媒を加熱していたのではないかと筆者は考えている。もしそうだとすれば、急加速をいつ行うかがわからない現実の路上では不可能な制御だ。テストのタイムチャートを仕込んだ特殊プログラムに頼らなければならない理由の説明がつく。
■VWだけの問題なのか
さて、気になるのがこの問題がどこまで拡大するかだ。北米とカナダは完全にアウトだ。しかし欧州ではユーロ5の規制には準拠しているので、常識的に考えると問題にはならないだろう。問題の本質は欧州と北米の排ガス規制のギャップを無理やり乗り越えようとしたことにあるのだ。
と、ここまで書いたところで信じられない続報が入った。報道によれば、フォルクスワーゲンがドイツでも同様の不正を行っていたことをドイツの運輸相が明らかにしたのだ。言葉を失う。まだニュースは速報レベルなので、詳細はわからない。
しかしこれが事実なら話は変わってくる。ドイツで不正を働かなければならないとすれば、ユーロ6規制だろう。いくらなんでも緩いユーロ5をクリアできなかったとは考えにくい。ということはユーロ5規制適合車で北米のTier2 Bin5をごまかすために使った手口を、欧州内でも行って、ユーロ6適合を不正に取得していたことになる。
前述の様にユーロ6規制の施行は昨年からで、とりあえず新型車のみが対象。継続販売車に関しては2015年9月まで許されているため北米より対象となる期間は限られるはずだが、いかんせん母数が多い。欧州ではディーゼルは非常にポピュラーなのだ。
地域的には、カナダを含む北米と日本。欧州と欧州基準に準拠した中国。南米やロシア、インド、ASEAN、アフリカの基準までは分からないが、限りなくどこでもアウトになるだろう。事実上の「全世界リコール」だが、最新の排ガス規制の適合は部品の交換や後付けで簡単にできるものではない。各国省庁から緩和措置が得られず、厳格な処分を下されたらクルマを丸ごと新車に交換する以外に手がなくなるはずだ。しかもそのために本当にユーロ6に適合するエンジンを作らなくてはならない。もはやブランド・イメージの失墜がどうのという話ではなく、債務超過の危機だ。
さて、この問題は果たしてフォルクスワーゲン固有の問題なのだろうか? フォルクスワーゲンの制御プログラムを作っているのはドイツのメガサプライヤー、ボッシュだ。もちろんボッシュが単独でできることではない。フォルクスワーゲンのオーダーか、協議があってこうした不正プログラムを作成したはずで、その共犯責任がどうなのかは司法の範疇で、誰の何の証言も聞いていない筆者が書くと完全な予断になってしまう。これについては推移を見守りたい。
フォルクスワーゲンとボッシュがそういう“抜け穴”を使っていたことは、ボッシュをサプライヤーとして使う他メーカーも知っていた可能性は高い。「何故フォルクスワーゲンはユーロ5規制のクルマを北米で売れるのか?」「何故フォルクスワーゲンのクルマはユーロ6をクリアしながらあれだけの出力が出ているのか?」と問い詰められれば、言い訳のしようはないからだ。
そこで他メーカーが、裏プログラムのカラクリを聞いた時に、どういう判断を下したのかが重大な問題だ。すでに外紙の一部はBMWも欧州規制に対して同様の不正があった可能性について記事にし始めている。いまのところBMWはこれを否定しているが、今後どうなるのかはまだ分からない。一歩間違えば、ボッシュにシステムを発注している欧州メーカー各社が芋づる式に連座する可能性があるのだ。
もうひとつ日本のメーカーは大丈夫なのだろうか? 実はディーゼルエンジンに関しては諸般の事情で日本のメーカーは出遅れた。結果的に近年の国産ディーゼルは規制強化後のユーロ6と日本の厳しい規制を視野に入れて開発されている。特に日本では国交省や都による抜き取り検査が行われているため、不正をすれば早期に摘発される。過去にいすゞが摘発されたことがあり、リスクが高いことはよくわかっているはずなのだ。
最新の排ガス規制に準拠するためには従来の高圧縮比のディーゼルでは難しいため、低圧縮にする手法が取られている。圧縮比を下げるとNOxの発生は抑制されるからだ。一例として、最近ディーゼルに力を入れているマツダなどは、圧縮比をディーゼルの常識では考えられないほど下げている。当然、欧州勢に比べてパワーでは不利になるが、それでも圧縮比を落としたのだ。
もはや何を信じたらいいのかは分からないので絶対とは言わないが、順当に考えられる限り、ここまでやって規制に引っかかるとは考えにくい。マツダのディーゼルシステムは日本のデンソー製だ。長年にわたって日米の厳しい排ガス規制を潜り抜けてきた会社だけに、正攻法でクリアできていると考えていいと思う。ちなみにデンソーのシステムを使うのは他に、トヨタやボルボ、ジャガー・ランドローバーなどだ。
■ディーゼルはもうダメなのか
そもそも論で言うと、ディーゼルエンジンはガソリンエンジンと比べて排ガスのクリーンさにおいて10年は遅れている。それでも将来的な石油不足などに鑑みれば、燃料の雑食性が高く、燃えるものなら何でも燃料にできるディーゼルは将来的な選択肢のひとつとして大事な内燃機関だ。エタノールなどの植物由来燃料などにも対応できるからだ。直近にそれが実用化される可能性は高いとは言えないが、将来技術としては重要なシステムなのだ。
さて、最後に世界経済に及ぼす影響について、可能性を付記しておく。欧州経済の大黒柱であるフォルクスワーゲンの今回の事件は、EUの金融センターたるドイツの足元を確実に揺るがすだろう。ましてやドイツの他メーカー数社がボッシュもろとも連座したら、EU経済全体に多大な混乱をもたらすことが懸念される。
特にここ数年、フォルクスワーゲンは中国マーケットで多くの利益を稼ぎ出してきたが、もはやカウントダウン状態にある中国バブル崩壊でも打撃を受けるのは必至だ。そのショックだけでも甚大だと思われてきたところに今回のディーゼルショックである。もはや何が起こっても不思議はない。
世界経済の枢軸プレイヤーである中国とEUが揃って大やけどをするようなことがあれば、世界恐慌につながりかねない。上手くハンドリングしないと大変なことになる。反面、経済的混乱が限定的に済み、かつ状況を日米が上手く捌けば、両国の経済にとって大きなジャンプアップのチャンスでもある。どちらに転ぶかはまだわからないが、世界経済にとって大きな転機となるだろうことはほぼ間違いない。
(池田直渡・モータージャーナル)
ドイツのフォルクスワーゲン(VW)がソフトウエアを使って米国での排ガス検査をごまかしていたことが発覚したことで、欧州の規制当局と政治家は域内の甘い検査プログラムの見直しを考えている。
自動車メーカーから検査を請け負うドイツの会社、テュエフ・ズートによれば、エアコンを取り除くなどして車の重量を減らし検査結果を調整することを欧州連合(EU)の欧州委員会は認めている。こうした小細工のおかげで、検査の結果とディーゼル車が路上で実際に排出する排ガスの量には開きが生じて拡大したと、欧州委のルシア・カウデ報道官が明らかにした。
同報道官は「何も不正をしなくても、ディーゼルエンジン車の路上での窒素酸化物排出量が検査での量よりはるかに多いということは可能だ」と電子メールで指摘した。
欧州では現在、排ガス検査は試験場でしか行われていない。より厳格な路上走行検査が来年導入される予定だが、そこでの要件を満たす必要が生じるのは2017年半ばになってからで、ドイツのヘンドリクス環境・建設・原子力安全相はこのプロセスの前倒しを望むと述べた。また、バス・アイクハウト欧州議員(オランダ)は結果操作が容易な排ガス検査について、「このような人をばかにしたごまかし」に終止符を打たなければならないと声明で訴えた。
欧州で検査を受ける車は「ゴールデンサンプル」と呼ばれ、実際に販売される車とは大きく異なると、テュエフ・ズートの広報担当、ビンセンツォ・ルカ氏が述べた。さまざまな搭載部分を外した後の車は通常、実際に販売される車よりも100-150キロ軽くなるという。
「合法的に排ガス量を減らす手段が可能な限り利用される」と同氏は述べた。
重さを軽くするほか、メーカーは検査用の車のために検査時と同じスピードと気温が設定された際に排ガスを少なめに抑える排気システムを設計していると、サンフォード・C・バーンスティーンのアナリスト、マックス・ウォーバートン氏が22日のリポートに記述した。
原題:No Cheating Needed. Europe’s Lax Laws Make Diesel
Tests a Snap(抜粋)
記事に関する記者への問い合わせ先:ベルリン Naomi Kresge ;ベルリン Brian Parkin ;ブリュッセル Jonathan Stearns ,nkresge@bloomberg.net,bparkin@bloomberg.net,jstearns2@bloomberg.net
9月19日、フランクフルトのモーターショーの宴もたけなわな頃、フォルクスワーゲン(VW)社の排ガス試験の不正が報道され、以来、ドイツでは爆弾が落ちたような騒ぎになっている。
問題となっているのはVW社のディーゼルエンジン車で、アメリカの環境保護局が不正を摘発した。
このニュースが巷に流されたのが土曜日であったことは、おそらく偶然ではない。株式市場の大混乱を防ぐ目的があったはずだ。
とはいえ21日の月曜日、混乱は十分に起こった。フランクフルトの株式市場が開いた途端、VW社の株価は下がり続け、その日の終値は17%のマイナス。そして、翌22日はさらにまた17%下がった。しかも、株価が転がり落ちたのはVWだけでなく、メルセデスやアウディ、そしてコンチネンタルといった関連会社も同様だ。
VW社が自ら認めた不正の中身というのは、ものすごくハイテクだ。なんと、排ガスの検査の時だけ、窒素化合物などが少なくなるソフトウェアが埋め込んであったらしい。
アメリカの環境保護局によれば、普通の走行時は、基準値の10倍から40倍もの有毒物質が排出されるという。よりによってVWは「クリーン・ディーゼル」と銘打って、これらの車種を大々的に宣伝していた。
このソフトが埋め込んであるのは、2009年から15年までにアメリカで販売されたゴルフなど48万2000台のディーゼル車で、制裁金は1台につき37,500ドルとして、単純計算で、合計約180億ドル。
しかし、火曜日のニュースでは、不正ソフト搭載の車が販売されたのはアメリカだけでなく、全世界で1100万台に上ると報道された。そういえばドイツの環境保護団体もすでに長い間、排ガス成分の公表値と実際の測量値が一致しないケースを訴えていた。
なお今回の不正は、単なる数値の粉飾とは違い、環境、ひいては人の健康に害を及ぼすことを承知の上での犯罪だと見なされる可能性が大で、そうなればアメリカでの刑事訴追も免れない。もちろん、すべての車がリコールされ、無償で改善されなければならないので、その経費も莫大だ。
しかし、何といっても一番の出費は、これから始まるであろう集団訴訟。最悪の場合、VWは国に救済してもらわなければならなくなるかもしれない。
偶然のことながら、つい最近、日本で自動車関係の本の編集者と会ったとき、VWが良いという話になった。よく走るし、コンパクトだが高級感もある。比較的、値段も安い。これぞドイツの底力。日本の自動車メーカーも頑張らなければ、というような話だった。
ドイツの私の友人が、今、問題になっているディーゼルのゴルフに乗っていて、数年前まではこの車でよく遠出をした。運転するのはいつも私。ドイツを縦断してバルト海へも行ったし、アルプスを超えてイタリアにも行った。
だから私は、この車のことは十分に知っているつもりだ。フロント操作のわかり易さ、運転のしやすさ、馬力、燃費、座り心地の良さ、静かさ、そして、小ぶりなのにゆったりとしていて、何時間運転しても疲れない……etc。
ただ、前述の編集者の話では、売り上げはトヨタに匹敵するのに(2014年はトヨタが売り上げ世界一、わずかの差でVWが2位)、利益率がトヨタよりずっと低いそうだ。利益はいったいどこへ消えているのか?
自動車界の帝王と社長との権力闘争劇
実はVW社では、今年の4月、不思議なことが起こっていた。VWを世界の冠たる企業の一つに育て上げた天才、フェルディナント・ピエヒ氏が泥沼のような権力闘争に敗れ、監査役会会長という役職を電光石火のごとく辞任したのだ。
ピエヒ氏をこの座から追い落とすために尽力したのが、マーティン・ヴィンターコーン社長。ピエヒ氏は、ヴィンターコーン社長の任期延長に反対を表明、それを知ったヴィンターコーン氏が反撃し、あっという間に一騎打ちとなったのだった。
今年78歳のピエヒ氏の過去は光り輝いている。ポルシェ社の創業者、フェルディナント・ポルシェの孫で、生まれた時から血の中に自動車が走っていたらしく、車のエンジニアとしても、企業の経営者としても、めくるめく成功を収め続けた。
ピエヒ氏は70年代、ポルシェからアウディに移籍し、アウディを大躍進させ、90年代にはVWの会長に就任して、ベントレー、ランボルギーニ、ブガッティ など高級スポーツカーメーカーを次々と買収、労働者の車VWのイメージを一新させた。今では、チェコのシュコダも、スペインのセアトも、そしてポルシェも、すべてVW社の傘下だ。
2002年からは監査役会会長となっていたピエヒ氏だが、いずれにしても、VWはもちろん、ドイツの自動車界では帝王のような存在だった。その帝王が権力闘争に巻き込まれ、週刊誌を賑わした挙句、無残に追い落とされた。
ただ、不思議だったのは、闘争の本当の原因が最後まで分からなかったことだ。アメリカ市場での失敗、配当の減少、ヴィンターコーン氏の経営手腕に疑問を呈する意見もあれば、ピエヒ氏の独裁が問題ではないかという記事もあった。
しかし、どの記事を読んでも核心は書かれておらず、結局、何も分からないまま、私たちはそんな話は忘れてしまった。9月5日になって、後任が決まったという小さな記事が出ていたとき、「そんなことがあったっけ」と、ちょっと思い出した程度だった。
ヴィンターコーン社長の苦しいコメント
いずれにしても、その権力闘争に打ち勝ったヴィンターコーン氏は、今、VW社始まって以来の危機に際し、その代表者として対処しなければならなくなった。ところがまず20日の氏のコメントは、まことにお粗末なものだった。
そもそもVW社は、不正を認めているのだ。なのにヴィンターコーン氏は、「我が社はいかなる法規や法律の違反も許さない!」と言ったので、私は耳を疑った。「顧客の信用を取り戻すため、一刻も早く真相を究明したい」とか。
氏が不正を追及する側だとすると、では、いったい誰がやったのか? 法規の目をくぐり抜けるためのソフトウェアをこっそりと車に仕込むような重大、かつ危険な決定が、下の方のエンジニアだけの独断でなされた? ヴィンターコーン氏が何も知らなかったとは、とても考えにくい。
ひょっとすると、4月の権力闘争は、本当はこの不正を巡ってのものだったのかもしれないと私は考える。情報はすでにあったのではないか。どうにかして対処しなくてはならないが、社外に漏らすことは許されない。そして、それは実際に漏れなかった。そう考えれば、どの記事を読んでも訳が分からなかった謎は解ける。
さて、その後、案の定、おかしなコメントを出したヴィンターコーン氏への批判は強まり、22日には、彼が全面謝罪するビデオが流された。ドイツ人が、このように早い時期、しかも真相究明で責任者が明らかになる前に全面謝罪をするというのは、非常に珍しいことだ。
たとえば、今年3月のジャーマンウィングスの事故でも、150人もの死者が出たにもかかわらず、当時も今も誰も謝ってはいない。 このような不幸なことが起こったことを遺憾に思っ たり、 遺族とともに深い悲しみに包まれ たりしただけだ。つまり、謝罪ビデオが作られたという事実が、VW社が非常に追い詰められている証拠でもある。
VW社は、ドイツ北部のニーダーザクセン州に本社を持つ大コンツェルンだ。フォルクスワーゲンのフォルクは民衆、ワーゲンは車。ヒトラー政権下で立ち上げられた。
戦後は、あやうくソ連に接収されそうになったが、イギリス軍の管理を経て、49年、ドイツの手に戻る。以後、VWは経済復興を果たしたドイツ人の国民車となったばかりか、全世界で大成功を収めた。
有名な「カブトムシ」は、戦前から2003年まで生産が続き、2153万という生産台数を誇る。今でも、オールドタイマーとしては貴重品。その設計者が、前述のピエヒ氏の祖父、フェルディナント・ポルシェ氏だ。
VW社は、中国への進出も早かった。84年に上海汽車との合弁会社を作り、中国市場で大成功を収めている。最近では、販売台数の3分の1以上が中国向けなので、中国の景気減退の影響を受けるリスクも非常に高い。
それだけに、アメリカ市場に力を入れ始めていたのだが、しかし、VWはこれまでもアメリカで成功した試しがなく、今回、その悪夢がさらに増幅されたというしかない。
VWの醜聞は、ドイツ人自身の醜聞
いずれにしてもこの事件は、株式市場を見てもわかる通り、問題が一企業に留まらず、ドイツ全体に波及する恐れがある。だから、ドイツ人が戦々恐々としているのはわかるが、一つ気になったのは、22日のZDF(第二テレビ)のニュースに出てきた経済専門家という人の話。
「我々の車が世界中で認められていたのは、安いからではなく、その高品質のせいであった。今回の事件でその品質に傷がつけば、他国のメーカーが力を増す」
そこまではわかる。問題はそのあとだ。
「そうなれば、 ワンダフル! と言いながら、他のメーカーがその隙間に入り込む。たとえば、トヨタ!」
と、トヨタを名指しで、しかも憎々しげに語ったのだった。
これは非常に示唆的だ。すでに日本企業は、人の災いを喜ぶ悪者にされている。しかし、言っておくが、日本車も安いから売れているわけではない。安くて、しかも品質がよいから売れているのである! 私はドイツでも日本車に乗っている。
ドイツ人は、おそらく私が日本車を誇りに思うのと同じく、ドイツ車に対してアイデンティティーを感じている。特に国民車VWはドイツの技術であり、ドイツ人の誇りであった。VWの醜聞を、ドイツ人は自分自身の醜聞と感じている。
だから私の勘では、ドイツ人はこの危機を抜け出すため、ドイツの成功を妬んでドイツを陥れようとする国(←アメリカ)や、ドイツの不幸を利用する姑息な国(←日本)といった敵を見出し、久々に一致団結するような気がする。
ドイツの雇用の7分の1は、自動車とその関連産業で支えられている。23日、ヴィンターコーン社長は早くも辞任。この事件が、これからまだまだ深刻な問題に発展していくことは間違いない。
著者: 川口マーン惠美
県警は、エンジン警告灯が点灯していたのに、うち1人が黒いビニールテープを貼って故障を隠したとしている。
専務以外の4人は、常務(50)と販売部長(60)、30歳と56歳の自動車整備士2人。販売部長は「代車を交換するのが面倒だった」と容疑を認め、他の4人は「覚えていない」と否認しているという。
発表では、5人は、新車の納車を待っていた社会福祉士の男性(当時30歳)に対し、整備不良と伝えないまま昨年8月23日頃に代車を提供。同9月24日早朝、男性が広島市の中国自動車道サービスエリアでエンジンをかけて休憩中に排ガスが車内に充満し、一酸化炭素中毒で死亡させた疑い。
代車は排ガス浄化装置の一部の「O2センサー」が故障していたうえ、マフラーが劣化して断裂しており、高濃度の一酸化炭素を含む排ガスが漏れていた。
1年前の9月24日、広島市安佐北区の中国自動車道のサービスエリアで、当時30歳の男性が軽乗用車の車内で休憩中一酸化炭素中毒により死亡しました。
警察によりますと男性は、広島市東区の自動車整備などを行う会社からこの軽乗用車を代車として貸し出されていたということで警察が原因を捜査していました。
その結果、この会社の専務や当時の店長、それに販売部長の3人が、エンジンの不具合を知らせるランプが点灯する整備不良の状態にあることを知りながら、ランプの上にテープをはり男性に告げずに貸し出していたことがわかったということです。
警察は24日、3人を業務上過失致死の疑いで、また部下の2人を業務上過失致死に加えて、別の部品の故障を知りながら車検を合格させていた虚偽公文書作成などの疑いで書類送検しました。
テープをはったのは貸し出した当日だということで調べに対し販売部長は、「正常な車に交換してほしいと言われると面倒なのでやった」と供述しているということです。
ウィンターコルン氏は23日に開かれた臨時監査役会(取締役会に相当)で辞任を表明し、承認された。臨時監査役会後に記者会見したフーバー監査役会長は、「ウィンターコルン氏から辞職の申し出があり、その意思を尊重した」と説明。「不正についてウィンターコルン氏は関知していなかったと認識している」とした上で、規制逃れに関わった社員を地元検察当局に刑事告発することを明らかにした。
ウィンターコルン氏は声明で「不正問題についてまったく関知していなかったが、VW社の利益のために辞職する。VWには人事を含めた新たなスタートが必要だ」と辞任の理由を説明した。後任人事は25日に監査役会を開いて協議する。独メディアではグループ会社ポルシェのミュラー会長の名前が挙がっている。
この問題では、米環境保護局(EPA)が18日、VWが一部のディーゼル車に、当局の検査の時だけ排ガス低減機能が作動する違法なソフトウエアを搭載し、規制を逃れていたとして、最大180億ドル(約2兆1600億円)の制裁金を科す可能性があると発表。米司法省も刑事捜査を開始したほか、ドイツやカナダ、イタリア、韓国など世界各国の当局が調査の意向を表明している。ウィンターコルン氏は当初トップにとどまる意向を示唆していたが、監査役会で退陣論が大勢を占めたことで、辞任を決断した模様だ。
ウィンターコルン氏は技術者出身で、2007年に会長に就任。VWの売り上げの急拡大をけん引し、15年には新車販売でトヨタ自動車を抜いて世界首位に立つことが確実視されていた。今年4月には、創業者一族で実力者のピエヒ監査役会長(当時)と対立したが、監査役会からの支持でピエヒ氏を辞任に追い込み、自らの任期を2年延長して18年末まで続投することを内定させたばかりだった。
小保方晴子・元理研研究員の研究室に残っていた試料の遺伝子を解析した。理研の外部調査委員会が昨年12月、同様の結論を出しているが、国際的な科学誌に発表されるのは初めて。
また、米ハーバード大など米、中、イスラエルの7研究室がSTAP細胞の再現に計133回取り組み、いずれも失敗に終わったとの報告も掲載される。小保方氏らが昨年7月にSTAP論文を撤回した際は、複数の画像の不正が理由だったが、これで、STAP細胞の存在根拠は国際的、科学的に完全に失われた。
このような癒着関係が成立するにはかなり関係が深かったのか、国交省係長がお金に困っていたのだろう。お金に困っていたのであれば、他の違法行為にも関与している可能性はあると思う。
収賄の疑いで逮捕されたのは、国土交通省航空局運航安全課の係長、川村竜也容疑者(39)で、金沢市にある航空関連会社、「Wings of Life」の元社長で韓国籍の、金澤星容疑者(61)が贈賄の疑いで逮捕されました。
警視庁の調べによりますと、川村係長は、おととし12月、羽田空港にある航空機の格納庫の土地を巡り、金元社長の会社が国との間で結ぶ使用許可などが延長できるよう便宜を図った見返りに現金およそ50万円を受け取ったとして収賄の疑いが持たれています。
これまでの調べで、金元社長の会社は、国土交通省から国有地の使用許可を得て、格納庫を使った航空機の整備事業を行っていますが、年間およそ1億円の使用料の支払いを滞納し、許可の更新が問題になっていたということです。
これについて許可に関する業務を担当していた川村係長は、上司などに更新に問題は無いという説明を繰り返していたということです。
警視庁によりますと、調べに対し2人は、いずれも容疑を認めているということです。警視庁は、現金が渡った詳しいいきさつや使いみちなどを捜査する方針です。
川村係長が逮捕されたことについて国土交通省航空局は「職員が収賄の疑いで逮捕されたことは極めて遺憾です。今後、具体的な事実関係が明らかになり次第、厳正に対処してまいります」とコメントしています。
捜査関係者によると、国が発注したビジネスジェットなどを格納する格納庫の使用契約をめぐって平成25年、航空関連会社が受注できるように便宜を図った見返りに、現金数十万円を受け取った疑いが持たれている。
捜査2課によると、川村容疑者は航空局首都圏空港課の係長だった2013年12月、整備会社が国から得ている羽田空港(東京都大田区)の格納庫の使用許可を更新できるよう便宜を図った見返りに、伊集院容疑者から現金50万円を受け取った疑いがある。整備会社は、格納庫の使用料の滞納を繰り返していたという。
VWは対象車両が世界で1100万台販売されていると発表。
今回の問題に絡み、2015年の連結業績目標を下方修正するとともに、対処費用として第3・四半期に約65億ユーロ(72億7000万ドル)の引当金を計上するとした。
ただ問題のディーゼルエンジン「EA189」は、試験時と実際の排ガス量に大きな開きがあり、引当金は今後膨らむ可能性があるとしている。
VWの危機はドイツ国内でもショックが広がっており、メルケル独首相は「徹底した透明性」を求めた。
欧州株式市場では、前日20%近く急落したVWがこの日も約20%値下がりし4年ぶり安値に沈んだ。安値時点で、最大300億ドルの時価総額が吹き飛んだ。
VWの売りは他の自動車メーカーにも波及。フランスのプジョーシトロエングループ(PSA)は8.8%、ドイツのダイムラーは7.0%、欧米自動車大手フィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCA)は6.2%それぞれ連れ安となった。
独紙ターゲスシュピーゲルは、VWが不正発覚を受けて、ウィンターコーンCEOを解任すると報道。VWは「事実無根」として否定した。
VWが23日に予定していた監査役会を22日夕に前倒しするとの一部報道もあったが、関係筋によると、排ガス規制試験の問題について話し合う監査役会は23日しか予定されていない。全体の取締役会は25日開催の見込み。
排ガス不正問題で21日も大きく値を下げており、2日間で約34%も値下がりした。
株安は、欧州の自動車各社にも波及した。前日の終値と比べ、仏プジョー・シトロエン・グループは約7・9%安、仏ルノーが約6・8%安、独ダイムラーが約6・7%安と、いずれも大きく値下がりした。
フランクフルト市場のドイツ株式指数(DAX)は3・8%安、ロンドン市場のフィナンシャル・タイムズ(FT)100種平均株価指数は2・8%安となった。
この報道について東芝の社員は「3氏に誰もモノが言えず、世間ズレした会社と思われても仕方がない」と嘆く。3氏は問題の責任をとって7月21日付で辞任しており、役職のない身。この“厚待遇”に対して、この社員だけでなく、現役社員やOBからも異論が噴出しているという。
東芝の広報は3氏の待遇について、「監査法人のヒアリングや、引き継ぎ業務があるため、出勤している」と弁明するが、世間の常識からすれば、理解し難い待遇だ。だが、それよりも大きな問題は、歴代のトップに対し、誰も引導を渡せていないという点だ。
◇
一連の利益水増し問題では、歴代3社長が「社長月例」と呼ばれる会議で「チャレンジ」と呼ばれる高い目標を示し、部下に圧力をかけ、組織ぐるみで不正会計を行っていたことが分かっている。
外部識者らによる第三者委員会(委員長・上田広一元東京高検検事長)は、部下が上司に意見をいえない体質が会社全体に根づき、問題が広がったと調査報告書で結論付けた。
こうした社内体質を改めることこそが再生の第一歩のはずだが、東芝はかつてのトップに遠慮しているのか、「役員室を出て電車で通ってください」と誰もいえないようだ。それだけ東芝はこれまでのトップが強い権力を持ち、絶対的な存在だったのかもしれない。
室町正志会長兼社長は8月31日に開いた2015年3月期の連結決算の延期会見で「内部通報が増え、企業風土の改善につながる意識が社員に出てきた」と語ったが、歴代3社長がいまだ社内を闊歩する話を聞く限り、会社が大きく変わったとは言い難い。
◇
一方、東芝社内では8月に発表した新たな経営体制についても、本当にこれで再生できるのかとの声が上がっているようだ。経営刷新委員会の議論を踏まえ、東芝は社外取締役の数を従来の4人から7人に増やして、経営監視の強化を再発防止の柱に据えた。
これらの人事は有力OBで日本郵政社長を務める西室泰三相談役の意向が色濃く反映されている。社長に就任する室町氏は責任を取って辞任する意向だったが、西室氏が強く慰留したため、残留を決めた。
社外取締役に就任する経済同友会の小林喜光代表幹事(三菱ケミカルホールディングス会長)や、池田弘一アサヒホールディングス相談役、取締役会議長に就く予定の前田新造資生堂相談役も、西室氏の強い要請があったとされる。
新たな経営陣は、室町氏をはじめ西室氏の意向が通りやすい人物で固められており、「有力OBの関与が強まり、今までと全く変わらない」(東芝元幹部)との指摘もある。
その西室氏だが、東芝社長のほかに東証社長や日本郵政社長を歴任。今夏も戦後70年談話に関する有識者会議「21世紀構想懇談会」の座長を務めるなど、政財界に顔が利き、東芝社内では「スーパートップ」と呼ばれている。
西田氏、佐々木氏、田中氏の社長人事も西室氏の了承の上で就任しており、東芝の経営に強い影響力を持っている。今回の問題について、直接関与していないが、「歴代3社長の就任を了承し、創業140年で最大の危機を招いた」(前述の元幹部)と西室氏の責任を問う声も一部に出ている。
過去のしがらみを抱えたまま、再生を進めても、同じことをまた繰り返すとみている社員やOBも少なくないようだ。
◇
9月7日、東芝は2度延期した15年3月期の連結決算を発表した。この日は浜松町の本社で夕方から決算説明会を開催したが、地下の駐車場には、西田氏や佐々木氏、田中氏が使う社用車の姿はなくなっていた。
東芝広報によれば、3氏は38階にあった役員室をすでに退去し、本社への出勤も減っているという。8月下旬の報道による批判を受けて、自ら退去したのか、それとも誰かが忠告したのか真相はわからない。いずれにしろ、再生に向けて、東芝本社も少し変化の芽が出てきたと信じたい。
ただ、付け加えておくと、7日夕、本社地下の駐車場には、西室氏の社用車だけがひと際目立つ位置に止まっていた。(黄金崎元)
同社のウィンターコルン社長は「顧客の信頼を裏切ったことを深くおわびする」との声明を出し、この問題に関して外部調査を依頼したことを明らかにした。
EPAは18日、同社の一部車が排ガス規制を不正に回避するためのソフトウエアを搭載していたと指摘。同社に科される制裁金は、最大180億ドルに達する可能性もあるという。
VW社の広報担当は、該当車の一部販売停止を認めたが、具体的な台数については明らかにしなかった。
ウィンターコルン社長は「内規や法律に対する違反を容認するようなことはしない」と強調し、関係当局に全面的に協力する姿勢を示した。ただ、外部調査の委託先に関しては、具体的に言及しなかった。
EPAによると、問題とされたソフトウエアは、排ガス低減機能の作動を通常運転時は停止させる一方、排ガス検査が行われている間は作動させていたという。通常走行時の排ガス量は規制値の40倍に達していた。 同社の広報担当は、EPAの指摘を事実と認めるとともに、当局の調査に積極的に協力するとした。
VWとアウディ部門のディーゼルエンジン車は、当局による検査の時だけ排気ガスをコントロールする機能がフル稼働するソフトウエアを搭載して販売されていた。米環境保護局(EPA)によると、通常走行時の排気ガスは基準の10-40倍に達する。
EPAは、米国の大気浄化法への違反に対して司法省による刑事訴追につながり得ると説明。EPAのシンシア・ジャイルズ氏によると、同局は1台当たり3万7500ドルの制裁金を科す可能性がある。対象車は48万2000台で、その場合、最大180億ドル(約2兆1600億円)となる。2009-15年型が対象。
ジャイルズ氏は「こうした仕掛けを車に搭載し大気浄化規制を逃れることは違法であり、国民の健康を脅かすものだ」と指摘した。
VWは発表文で調査に協力しているとした上で、それ以上コメントはできないとした。
EPAはVWへの18日の書簡で、VWが規制逃れに向けたソフトウエアの搭載について認めたと指摘していた。
原題:Volkswagen Admits to Cheating U.S. Emissions Tests for
Years (4)(抜粋)
事業費の2分の1以内となっている補助金で、実際の事業費のほぼ全額を賄おうとしていたとみられる。県警は動機などを調べている。
関係者によると、機構は県に全体の事業費を2144万3000円として申請し、税抜き後の半額に当たる992万7000円の補助金を交付された。事業費は主に事務所の内装に関するもので、見積書で壁、床の貼り替え工事費や備品の購入費などを高く設定していた。見積書は施工業者を含む2社が作成し、いずれも同額程度だったという。県警は、見積書の作成の経緯についても調べている。
県警の発表によると、機構の社長(43)と、社長が経営し機構に出資した東京のIT企業の社員(27)は共謀。2月上旬から4月17日頃にかけ、国東市国東町の機構事務所の内装工事費について虚偽の見積書や補助金交付申請書などを県に提出し、補助金をだまし取った疑い。
◇
社長は6月から1年間の任期で、別府市の「総合政策アドバイザー」を務めている。社長を委嘱した同市の長野恭紘市長は11日、市議会全員協議会で「任命責任は私にあり、重く受け止めている」と述べ、謝罪した。市は社長のアドバイザー委嘱を解く方針。
NBIなどによると、JICC社は外資系企業などが集まるセブ中心部の「ITパーク」地区に事務所を構え、電話対応代行業務などをしている。関係者によると、同社で働いていた日本人は半年間の実務研修中のため、就業許可は不要だと主張しているという。
JICC社のフィリピン人従業員は12日、取材に対し、日本人従業員が逮捕されたことを確認したが、容疑などの詳細についてはコメントを避けた。(共同)
法務省は、青柳教授が教え子だった20代の受験生の女性に対し、自身が作成を担当した憲法に関する論文式の問題を漏らした疑いがあるとして、同法違反容疑で東京地検特捜部に告発した。特捜部は青柳教授の自宅や同大学院の研究室を家宅捜索。任意で事情聴取をするなどして関与を調べている。青柳教授は法務省の調査に漏洩を認めたという。
10日にあった参院法務委員会では、上川陽子法相が、青柳教授が今年2~4月に複数回にわたり、研究室で女性に問題を教えていたと説明。マークシート方式の短答式試験でも問題を漏らした疑いがあることを明かしている。
自分たちのミスを棚に上げ
失敗や過失も、二度までなら仏さまが許してくれると言うが、不祥事を繰り返すこの組織を、はたして許せる人がいるだろうか。
私たちの生活に直結する年金を取り扱う日本年金機構で、またまた業務の杜撰さが明らかになった。8月24日、朝日新聞が1面トップで報じたところによると、年金機構では発足から5年で、事務処理のミスが1万件を超えたという。
「ミス」と呼べば軽く聞こえるが、事態は深刻だ。同紙の集計によると、このミスによって、年金の「未払い」や「過払い」など、私たちが受け取る年金額に間違いがあったというミスの合計金額は、あわせて約89億円分。
さらには、2014年度だけで、年金額が100万円以上間違っていた事例が、656件もあったというのだ。
職員の中には、「年金制度が複雑で覚えられない」などとミスの責任を制度の煩雑さに転嫁する声もあるようだが、年金機構と同じく、多数の顧客を抱え、複雑な業務をこなしている銀行や郵便貯金の窓口で、「すみません、手続きミスで100万円以上、間違えました」などと、あなたは言われたことがあるだろうか?
さらに異様な事態が、前出の記事に紹介されている。埼玉県在住の70歳の男性。その妻が、昨年11月、自身の年金の金額を確かめようと年金事務所を訪れた。
すると年金機構側に、「これまで支払った年金には、過払いがあった」、「本来は男性が届け出をして、受け取りを止めるべきものだった」と責められた上、過去5年分の過払い金、約197万円の返納を求められた。
男性と妻は、さぞ仰天したことだろう。何の悪気もなく、振り込まれる年金額が正しいものと信じて家計をやりくりしてきたのだ。5年で197万円ということは、月々にならせば3万3000円弱。この年金が、夏場のクーラーにかかる電気代や、高騰する食費などに充てられ、夫婦の生活全般の質を高めていたことは想像に難くない。
ところが、事態は一転。200万円近いカネの返納を求められ、男性は今後10年間、毎年20万円を返していかなければならないのだという。月々に直せば約1万6000円の支払いだ。
毎月、プラス3万3000円だったものが、今度はマイナス1万6000円に。月々の家計のやりくりで考えれば、一気に支出を5万円近くも切り詰めなければいけない。
本当に、自分が手続きを怠ったがために、こんな間違いが起こったのか? 疑問を感じた男性は、機構側に調査を求めた。
その結果、発覚から半年以上経った今年7月になって、年金機構は「本来は機構がチェックできていなければならなかった」と認め、謝罪したという。だがもちろん、謝られても男性の支払いが免除されたわけではない。
なぜ、こんなとんでもないミスを乱発するのか。
年金機構の前身である旧社会保険庁時代から、その異様さを指摘し続けてきたジャーナリストの岩瀬達哉氏は、こう話す。
「年金機構の業務マニュアルでは、『年金の支払いに関する職員の事務処理については管理者がチェックすること』となっているのですが、そのチェックがなされていないことが最大の原因です。
機構側は『人手不足』を理由に上げますが、実際は管理者や職員の能力不足、使命感・責任感の欠如が原因だと思います」
「法律上、決まっています」
責任感が薄れる一因は、旧社保庁時代から清算しきれていない、人事の歪みだと岩瀬氏は指摘する。
「たとえば、年金機構では、旧社保庁の怠慢な業務に対する反省から、管理職に就くには全国異動の経験を必要とする、と定めました。
社保庁時代、職員は採用された土地から基本的には異動しなかった。職員は、そこで組合活動を続け、発言力を高めないと、人事の上でも偉くなれなかった。要するに、組合が組織を牛耳ってきたわけです。
それを防ぐため全国異動という条件がつけられたわけですが、年金機構はこれを骨抜きにした。『同じブロック内でも都府県をまたげば全国異動』と定義したのです。
たとえば南関東ブロックの職員なら、東京から神奈川に異動しただけで全国異動となる。当然、組織風土の改革は進まず、風通しの悪さは一向に改善されないままです」
いずれにしても、たまらないのはわれわれ、一般の年金受給者の側だ。
他人事ではない年金機構の「過払い」や「未払い」。あなたにも、ある日突然、年金機構から「あなたの年金額に疑問があるので、年金事務所までお越しください」などと電話があるかもしれない。
「振り込め詐欺か?」と疑いながらも、年金事務所の窓口に行くと、「200万円は過払いでしたので、返してください」などと言われるのだ。
もし、私たちが、手続きミスの被害者となったら、一体何が起きるのか。
まずは「過払い」、つまり知らぬ間に年金を多くもらってしまっていた場合だ。本誌の質問に対し、日本年金機構経営企画部広報室はこう回答した。
「過払いについては、本来、受け取れない部分ですので、不手際があったにせよ、十分にご理解をいただいて、お返しをいただくよう手続きを進めているところです。
過払いがあった場合は、会計法では過去5年分についてはご返金をいただくことが、法律上、決まっており、返納をお願いしています。
本来は一括で即返納をいただくものですが、経済的にどうしても困難だという方には、分割によってご返納いただくようお願いをしています。
ただ、それぞれのご生活もあり、経済的なご事情もおありでしょうから、たとえば返納期間を5年間延長して、月々いくらという形で返納していただくとか、さらに期間を延長して、分割での返納をお願いする可能性もゼロではありません」
「未払い」のケースでは…
もし返納は無理だとか、そもそも機構のミスなのだから納得などできないと、受給者が支払いを拒否したら、どうなるのか。
「返納を拒否された方に機構側が裁判を起こすことは考えておりません。また、税金の不払いなら、国税庁が資産を差し押さえることもありますが、年金の過払い分の返納について、基本的に差し押さえをすることはありません」(同広報室)
しかしそれでは、実際には回収の困難が予想されるのではないか、と重ねて問うと、こんな答えが返ってきた。
「そうですね。ただ、これは不当利得ということになります。本来、受け取るべきでないものを受け取ったのですから。懇切丁寧に説明を尽くして、お返しいただくことになります」(同広報室)
いまはこう話す年金機構。だが、年金財政も逼迫する現在、年金の行く末に不安を持つ人々からは、「過払いでもらい過ぎた人から、キッチリ回収するべきだ」という意見も出るかもしれない。
たしかに、年金財源のパイは縮むばかりなのだ。結果、年金機構が裁判も辞さないと方向転換する可能性もゼロではない。そうなれば、もともとは機構側の手続きミスにもかかわらず、過払いを受けた人は社会的に責められ、裁判所に訴えられることになる。
そして、その裁判費用のために、また国民の貴重な税金が浪費されていくのだ。
行政訴訟などに詳しい梅本・栗原・上田法律事務所の上田啓子弁護士によると、裁判になれば過払い分を受け取っていた受給者のほうが、やはり立場は弱いという。
「年金機構のミスにより発生した過払いであっても、受給者はその年金をもらう法的根拠がないので、機構側からの返還要請には応じざるを得ません。残念ながら法的には返還を拒否できません」
では、一方の「未払い」、つまり本来もらえるはずの年金がもらえていなかった場合はどうか。急に思いがけない未払い金を受け取れるとなれば、少しは溜飲も下がるかもしれないが、問題となるのは、未払いのあった人が、すでに亡くなっていた場合だ。
「年金は、相続の対象ではありません。一身専属の権利、つまりご本人さまに対して給付させていただくものです。ですから、お亡くなりになった方には支払えません。
ただし、個人と生計を共にされていた配偶者や子供には死去された方への未払い金をお支払いしています。
転勤や病気療養で、故人とは別居されていた方でも、故人から仕送りや援助を受けていたことを示す書類などを提出いただければ、支給させていただきます」(前出・年金機構広報室)
未納が増えるのも当然
自分の年金にミスはないのか。「ねんきん特別便」など各種の資料はあるが、複雑すぎて個人で理解するには限界がある。確認するためには、現状では年金機構の窓口である年金事務所で問い合わせるしかない。
不祥事を繰り返した旧社保庁と決別し、生まれ変わったはずの年金機構。だが、ここにきてハッカーによる年金情報流出など、再びトラブルが相次ぐ。
「手違いがあるのは仕方ないにしても、報道によればミスが増加傾向にある。それが問題だ」(元年金業務監視委員会委員長・郷原信郎弁護士)。
その裏事情を、旧社保庁の年金問題を追及し、「ミスター年金」の異名をとった民主党代表代行の長妻昭元厚労相は、こう明かす。
「厚労省は、旧社保庁で『消えた年金』問題が注目されて以降、エース級の人材を機構に出向させて、年金機構プロパーの人材育成とガバナンスの確立を目指してきました。ところが、安倍政権になってから、年金問題への関心が薄れ、厚労省は優秀な人材を引き上げてしまった。
そもそも、年金機構のように、政策立案ができず、現場で事務をする部隊を、キャリア官僚は一段、格下に見る傾向がある。その意識を変えないといけません。旧社保庁時代と比べれば、窓口の対応など格段に改善された部分もあるのですが、こう、年中行事のようにミスを繰り返されては、国民はたまりません」
官僚の傲慢、職員の怠慢。そのツケを、なけなしの年金で生活する私たちが払う。
何よりも足りないのは、当事者である年金機構の、職員の想像力だろう。
長寿社会になったいま、年金は国民にとって、老後の短くない人生を、不安なく暮らすための「頼みの綱」だ。
そう信じてきたからこそ、ときには生活が苦しくとも、どうにかやりくりをして掛け金を支払い続けてきたのではなかったか。それがはたして、どれだけの労苦だったのか。それを想う想像力が感じられないのである。
職員にとっては、ただの書類上の数字に過ぎないだろう。だが、100万単位のカネを動かすことは、私たち一般国民には容易なことではない。
こうした事態が繰り返されれば、「年金は信用できない」という不安が一層広がり、現役世代の未納も増加。結局は年金崩壊を、それを司る組織が自ら招くことにもなりかねない。本当に、フザけるな、年金機構である。
「週刊現代」2015年9月12日号より
司法試験の問題を作成する考査委員であるがゆえに、教え子に有益な情報を与える事が出来た、もし、考査委員でなければ教え子との関係は違ったものになって
いたかもしれない。これは教え子と教え子が何を求めていたのか次第。お金持ちの人に仕事を貰おうとする者、人脈を作ろうと近づく者、何かを買ってもらおうと思う者達
が近寄ってくるのは程度の違いはあると思うが、何かを期待しているからだ。お金持ちが貧乏になっても近寄ってくるこれらの人達はほとんどいないであろう。
今回がそのようなケースなのか、教え子に好意を抱いた青柳幸一教授の一方的な押し付けだったのか、事実はわからない。中間の状態だったのかもしれない。
ギブ・アンド・テイクはお互いが理解していれば良い場合もある。しかし、それを禁止する、又は、公平性を優先するための決まりがあるケースもある。
明治大法科大学院の青柳幸一教授は理論的には全てを理解していると思うし、知識に関しては一般人の上のレベルであろう。知性や倫理よりも感情が行動を
支配した今回のケースを徹底的に調べる事により、機密漏えい、公務員の汚職、政治家の汚職、公務員の罰則に関して改善に繋がる何かが見つかるかもしれない。
これまでのように教授を処分して終わりにするのであれば、形だけの調査で終わるのも良いかもしれない。何年後に、誰かが同じ過ちを繰り返し、再度、
騒ぐのも愚かであるが良いかもしれない。
司法試験の順守事項に反し、教え子だった20歳代女性と学内外で頻繁に会っていたことも判明。女性への私的な感情が問題漏えいにつながった可能性があり、東京地検特捜部は動機などを調べている。
関係者によると、青柳教授は、大学院入学当初に自身の講義を受講した女性と知り合った。法務省の司法試験委員会が定める順守事項では、司法試験の問題を作成する考査委員が、法科大学院の修了生や修了予定者に指導することを禁止している。
司法試験の問題を作成した、明治大学法科大学院・青柳幸一教授(67)は、教え子だった20代の女性に論文の問題を教えたとして、東京地検特捜部が、国家公務員法の守秘義務違反の疑いで、強制捜査に乗り出している。
関係者によると、青柳教授は、明治大学法科大学院の合格実績を上げるためではなく、「女性に対して恋愛感情があり、問題を教えた」という趣旨の供述をしていることが、新たにわかった。
また青柳教授は、論文問題だけではなく、その模範解答も女性に漏えいし、複数回にわたって、個別に指導していたという。
特捜部は、論文問題以外にマークシート方式の問題でも漏えいがないか、調べを進めている。
本番の試験で、女性はこの問題でほぼ満点だったという。法務省は8日、教授を国家公務員法(守秘義務)違反容疑で告発し、考査委員を解任した。
特捜部は既に青柳教授の自宅などを捜索しており、漏えいの時期などを調べている。
青柳教授が今年5月の試験前に同大学院修了の20歳代女性に漏えいした疑いがあるのは、考査委員として自分で作成に関わった論文式試験の「公法」に関する1問。
関係者によると、青柳教授はまず女性に問題を解かせ、出題内容に照らして論じるべきポイントを説明。女性が解答を書き直す度に添削もしていたという。
消費増税時の負担緩和策とされる財務省案に対して、公明党内からそんな声が漏れ始めた。
同省案では、全国の小売店や飲食店に設置するマイナンバー(共通番号)カード読み取り端末への補助や、国民の買い物の膨大なデータを処理するコンピューター「軽減ポイント蓄積センター(仮称)」の整備などに計3000億円程度かかるとされる。白紙撤回された国立競技場整備計画の2520億円をも上回る額だ。
競技場は、巨大な2本のキールアーチで屋根を支える斬新なデザインが建設費高騰につながった。財務省案も情報技術(IT)を駆使した斬新なものだが、「実現性などが何ら検証されていない」点がそっくりというわけだ。
公明党からは、「早めに財務省案を白紙撤回しないと、政権にダメージを与えかねない」と懸念する声も出ている。
財務省は購入データを暗号化するとしているが、サイバー攻撃などで外部に流出する懸念もある。
財務省原案では、消費者は共通番号制度のマイナンバーカードを店頭で示し、情報端末で本人確認を行う。「酒類を除く飲食料品」を購入すると、税率2%分の金額がデータセンターに送信され、蓄積される。
政府は、国民の買い物記録を一元管理することになる。外部からのサイバー攻撃で、個人名と購入記録が結びついた情報が流出するリスクを抱える。日本年金機構がサイバー被害で約125万件(約101万人分)という過去最大規模の情報を流出させたのは記憶に新しい。個人の消費行動を政府が把握することに、国民の心理的な抵抗感が強まる可能性もある。
「司法試験の公正性に対する信頼を、根底から損なうものだ」。8日午前、法務省で報道機関の取材に応じた小山太士・人事課長は厳しい表情で話した。
同省によると、明治大法科大学院の青柳幸一教授(67)は、考査委員の中でも「主査」として憲法分野の問題作成のとりまとめ役を務めていた。同教授は同大学院を修了した教え子の女性に、自分が作問に関わった憲法についての論文式試験の内容だけでなく、解答する上で必要な論述のポイントまで、事前に教えていたという。
論文試験は800点満点で憲法には100点が配分されていた。解答用紙は憲法だけでA4判で8ページ分だったという。6~8月に論文式試験の採点が始まると、この女性の答案だけが「情報漏洩(ろうえい)がなければ作成困難」な内容だったという。疑問に感じた別の考査委員が情報提供し、法務省が調査に乗り出した。
青柳教授とこの女性は調査に対し、漏洩があったことを認めたという。高得点だったほかの受験生の答案を見ても女性のような論述はなかったことから、同省は「ほかに漏洩はなかったと考えられる」としている。
司法試験をめぐっては、2007年にも慶応大法科大学院の教授が試験問題に関する「勉強会」を開いて指導していたことが問題になった。今回は、法務省が青柳教授を刑事告発する事態となった。刑事告発に至った理由について小山課長は「一番の違いは、漏洩の事実を認めていることだ」と説明。一方、漏洩の動機などについては「刑事事件として捜査中で、それ以上は答えられない」と繰り返した。
インターネットのオークションサイトで複数のアカウントで出品し、巧妙に高評価を維持して、販売を繰り返していたとみられる。県警は2013年頃から100台以上、5000万円以上を売り上げていたとみて、余罪を追及している。
◇良い評価多く
県警の調べによると、中古車販売会社社長(39)(静岡市葵区)らは、中古の軽自動車のデジタル式走行距離計を機械を使って約19万キロから約3万キロに改ざんし、走行距離が事実であるように装ってネットオークションに出品、埼玉県の男性(45)に落札させ、今年6月下旬、約40万円をだまし取った疑いが持たれている。
「とても丁寧な対応をして頂き、安心してお取引させて頂くことが出来ました」。3人が登録していたアカウントの一つには、落札者の良い評価が多く記録されていた。
ネットオークションでは、出品者のアカウントに、落札者がスムーズに取引ができたかどうかを評価する欄がある。別の落札希望者が、出品者の信用性を判断する際の目安にするためだ。
県警幹部によると、3人は、走行距離の改ざんに気付いた落札者が低評価を付けると、アカウントを消去し、別のアカウントで出品する手口を取っていた。県警は「高評価の出品者であるように装い、安心感を持たせていた」とみている。
◇見えない相手
「走行距離はメーター表示距離」「トラブル防止のため全てメーター交換または改ざん・走行距離不明扱いとさせて頂きます」――。
商品の注意事項には、最初から免責を狙ったとみられる記載もあった。国民生活センターは「ネットによる中古車取引の場合、相手方の顔が見えず、直接交渉もできないことが多いため、問題が生じても被害回復は難しい」と指摘する。
中古車業界の信頼を高めようと、一般社団法人「日本オートオークション協議会」は、中古車の走行距離を一括してデータ管理する取り組みも行っている。
日本自動車査定協会静岡県支所(静岡市)に、このオートオークションを経由した中古車を持ち込めば、手数料1500円で走行距離の記録を調べてもらえる。
ただ、対象は特定のオークション会場の出品車に限られ、個人間の直接取引や店頭に並ぶ商品までは目が届いていないのが実情だ。
自動車査定協会の担当者は「車の購入は大きな買い物なので、十分に情報を集め、慎重に取引すべきだ」と話している。(村上藍、笹村直也)
◆アカウント=インターネット上で、オークションなどの特定のサービスを使用するための権利のこと。メールアドレスやパスワードなどを登録すれば取得できる。一部のオークションの場合、クレジットカードや決済用の銀行口座が異なれば、1人が複数のアカウントを持つことができる。
今年5月、下村博文文部科学相(61)が、13年12月に猪瀬知事(当時)から「内諾を得ている」などとして、都に新国立建設費の一部負担金500億円を要請した。だが、猪瀬氏は、この下村氏の発言を否定する。
「当時は(新国立の)周辺整備費について『372億円を負担してほしい』ということだった。都議会でも、私は新国立競技場の本体工事部分を負担しないと明言している」
猪瀬氏は、372億円が適正な価格か検証するための専門委員会を設置を検討していたという。だが直後に、徳洲会から都知事選の資金5000万円を借用した問題が発覚し、招致決定からわずか3か月後に辞任を余儀なくされた。
では、「500億円」はどこから出てきた話なのか。猪瀬氏は続ける。
「2016年の東京招致に向けて、都知事だった石原(慎太郎)さんが活動を熱心に行っていたが、国は消極的だった。当時は晴海に都立スタジアムを作るといって、建設予算1000億のうち、折半で500億を都が負担すると言っていた。でも今回の新国立競技場は、別問題。国立ですから、都が建てるものではない。なのに、森(喜朗)さんは記憶違いして、『国立に都が500億出す』と下村氏にも伝えていたようだ」
今回の猪瀬氏の“証言”は、石原氏(82)がこれまで話してきた「東京都が新国立の半分のお金を出すなんて一切言ってない。約束もしていない」などといった内容と一致している。猪瀬氏、石原氏の発言が正しいのであれば、現大会組織委員会の森会長(78)の「記憶違い」が、騒動の大きな要因になったといえそうだ。
都の費用負担「500億円」について、下村氏は、五輪招致が決定した翌々月の13年11月、猪瀬知事(当時)と負担割合を初協議し、同12月に「都議会と直接話して『500億円は都で出す』と内々に了承をもらっている」と発言していた。しかし、新知事となった舛添要一氏(66)は、下村氏の負担要請に対して「根拠がない話では受け入れられない」などと拒否する構えを見せていた。
同社によると、列車は同日午後3時5分に旭川を出発し、午後4時40分頃、下白滝駅(遠軽町下白滝)で停車していたところ、指令センターから「車両の点検期限が切れている可能性がある」と連絡があった。
車両を点検した結果、ブレーキ装置の点検などのため、3日以内に1度実施する「仕業検査」を行わないまま、旭川運転所―下白滝の約103キロを走行していたことが判明した。乗客34人はタクシー11台に分乗し、降車予定の駅に移動した。
同社は「十分に注意を払い、同種事案の再発防止に努めたい」としている。
捜査関係者によると、札幌市にある複数の飲食店経営会社は、失業者らを雇用した際に助成金を支給する厚生労働省の制度を悪用。実際には雇用していない人を雇用したと装うなどし、多額の助成金をだまし取った疑いが持たれている。
雇用されたとされる従業員の中には、北海道朝鮮初中高級学校(札幌市清田区)の教員の名前もあったという。道警は押収資料を分析するなどして実態の解明を進める。
自民党幹部や政府関係者によると、同党幹部や五輪関係者らが、佐野氏の“盗用”疑惑が浮上して以降、エンブレムを差し替えるよう組織委に再三にわたって警告していた。
五輪関係団体幹部らは、独自にデザインアートに詳しい識者から意見を聴取。「今後のエンブレム使用は厳しい」との判断に傾き、組織委にも水面下で使用をやめるよう説得をしてきた。だが、森氏と近い関係にある武藤氏らが「1回決めたものを撤回すると、国際的な信用問題になる」と聞く耳を持たず、事態は悪化した。
森氏は五輪・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の総工費膨張問題でも、全面見直しに向けた「最大の障壁だった」(自民党幹部)。自身が関与してきたラグビーW杯日本大会も運営や事務手続き上の不手際から、南アフリカなどから返上論が出ている。「新国立とエンブレム問題のダブルパンチ。組織の一新が必要だ」との声が強まっている。
エンブレムは佐野氏がデザインし、七月に発表。その後ベルギーの劇場のロゴとの類似性を指摘され、八月に劇場側が使用差し止めを求めて提訴した。組織委は同月二十八日、デザイン原案を公表し、盗用疑惑を否定した。
しかし二十九日以降、エンブレムを空港などで活用する事例の説明に使われた写真がインターネット画像の流用であるとする指摘が上がった。問題なしとされた原案についても、二〇一三年に東京・銀座で開かれた、活字デザインの巨匠ヤン・チヒョルト(一九〇二~七四年)を紹介する展覧会のポスターの一部に似ているとの指摘が出た。
事態を重く見た組織委は九月一日午前、佐野氏と、デザインを選んだ審査委員代表の永井一正氏を呼んで対応を協議した。佐野氏は、エンブレム活用例をめぐる写真の無断流用を「不注意だった」と認める一方、原案はオリジナルであると重ねて主張した。
永井氏は「専門家の間では分かり合えるが、国民には分かりにくい」と指摘。佐野氏は「模倣ではないが、五輪のイメージに悪影響を与えてしまう」として提案取り下げを申し出、組織委が了承した。佐野氏への賞金百万円の支払いも取りやめる。
都内で会見した組織委の武藤敏郎事務総長は「国民にご心配をおかけし、都や政府、国際オリンピック委員会(IOC)などの関係者に申し訳ない。スポンサー各社にもご迷惑をおかけした」と陳謝した。今後、公募により新エンブレムの選定作業に着手するという。
佐野氏をめぐっては、手掛けたサントリービールのキャンペーン賞品のデザインが他の作品との類似性を指摘され、佐野氏側が一部を取り下げていた。武藤氏は「関知するところではない」と述べ、今回の決定との関連性を否定している。
佐野氏は同日夜、デザイン事務所のホームページでコメントを公表。「模倣や盗作は断じてしていない」とあらためて盗作疑惑を否定した上で、関係者に謝罪。取り下げの理由には、ネット上などでの批判やバッシングが続いていることを挙げ「もうこれ以上今の状況を続けることは難しいと判断した」と説明した。
◆事例画像 無断流用認める
組織委員会の武藤敏郎事務総長は、公式エンブレムの発表記者会見などで示した活用例のイメージ画像について、佐野研二郎氏がインターネット上の他人のサイトから無断流用したことを認めたと明らかにした。
空港ロビーの天井からエンブレムをつり下げた画像と、ビルの壁面などにエンブレムが掲示されている画像の二点について流用が指摘されていた。
流用された二点はそれぞれ羽田空港、東京・渋谷の写真で、別々の英語サイトで公開中。またネットでは、別の英語サイトにある音楽フェスティバルの写真が、渋谷の写真と合成する素材として流用されたとの指摘も出ている。
◆新国立に続き…指摘耳貸さず
東京五輪のエンブレムが発表から一カ月余りで撤回に追い込まれた。混乱の責任について、組織委員会の武藤敏郎事務総長は一日の記者会見で、組織委、デザインの審査委員会、佐野研二郎氏を念頭に「三者三様」と述べた。だが、佐野氏が撤回を申し出るまで、自ら判断しなかった組織委の責任は極めて重い。
問題としては公開性の低さがある。審査委が佐野氏のデザインを選定したのは昨年十一月。国際商標調査で似たデザインが見つかり、佐野氏が二度の修正を行った上で、エンブレムは今年七月下旬に発表された。一方で、佐野氏の原案を公表し、経緯の詳細な説明があったのは、八月二十八日になってからだ。
佐野氏の原案と修正後のデザインについて、あるグラフィックデザイナーは「あまりに違っている。ここまで修正するなら、ほかの作品から選考する選択肢もあったはずだ」と、選考過程の不透明さを指摘する。
佐野氏のさまざまな作品をめぐっては一カ月余りにわたり、「似ている」との指摘が相次いだ。佐野氏側は一部の模倣も認めた。組織委はこの間、一貫して「問題ない」と説明。少ない専門家で決め、外部の指摘があっても押し通そうとする姿勢は、白紙撤回された新国立競技場の建設計画にも通じる。
武藤事務総長は今後、再公募する方針を示すが、このままでは次も「同じ問題が起こる可能性はある」と認める。「できるだけ多くの意見を聞く、オープンなやり方で懸念を払拭(ふっしょく)できないか。より開かれた選考過程を何とか工夫したい」と話す。
それにはまず経緯を検証し、反省を生かす必要がある。国立競技場の問題と違って期限が迫っているわけではないから、急ぐ必要はない。みながいいねと納得する大会にするため、責任の所在を含め、国民への丁寧な説明を求めたい。(北爪三記)
組織委員会は、今回の問題について、組織委員会、佐野氏、審査委員会の三者にそれぞれ責任があるとしたうえで、「組織委員会は事態の状況を見極めたうえで、新しいエンブレムをつくっていくのが責任だと思っている。佐野氏は、『盗作、模倣をしたことはない』と明言しており、デザイナーとしての立場は理解する。
そのうえで、取り下げるという決断をしたことで、責任を果たしたのではないか。審査委員会は、佐野氏のデザインを一番優れたものとして推奨したが、それを取り下げることをやむを得ないと決断したということが責任の取り方ではないかと思う」と述べました。
そのうえで、国際的な信用が失墜したのではないかという質問に対して、「このエンブレムを長く続けていくことのほうが、もはや適切でないと判断した。新たなエンブレムをつくることで信用を確立していきたい」と述べました。
結局、家族やスタッフを言い訳に利用して早く舞台から降りたかっただけのように思える。狼少年のようなケースとも思える。嘘ばっかり言っていると
本当の事を言っても信用してもらえない。今回の佐野氏のコメントが事実であるのかも疑問。
佐野研二郎氏はデザイナーを職業として生きている以上、著作権とか、コピーライトに関してルーズなのはおかしいと思う。新人であれば、そのような事もあるかもしれない。
分野は違うが元理研の小保方氏のように感じる。コピペが悪い事として研究者として知らなかった。佐野氏はデザイナーとして著作権とか、コピーライトを知らなかったのか。
しかもオリンピックのエンブレムである。注目を受けない小さい仕事ではない。この件についてはっきりしてほしい。
佐野氏は、エンブレムを「伝統的かつ新しい日本、東京を表現すべく大胆に、そして丁寧にデザイン致しました」と説明。原案も最終案も、模倣や盗作は断じてないと改めて疑惑を否定した。
一方で、自身のメールアドレスに中傷のメールが送られ、家族や親族の写真もインターネットにさらされるなどのプライバシー侵害を受け、「これ以上今の状況を続けることは難しいと判断し、取り下げに関して私自身も決断致しました」と説明した。
佐野氏のコメント全文は以下の通り。
◇
エンブレムにつきまして
私は、東京オリンピック・パラリンピックの大会の成功を願う純粋な思いからエンブレムのコンペティションに参加致しました。エンブレムがフラッグに掲げられ、世界中の人に仰ぎ見られている光景や、金メダルに刻まれたエンブレムを強くイメージしながら伝統的かつ新しい日本、東京を表現すべく大胆に、そして丁寧にデザイン致しました。
このような国をあげての大切なイベントのシンボルとなるエンブレムのデザイン選考への参加は、デザイナーにとっては大舞台であって、疑いをかけられているような模倣や盗作は、原案に関しても、最終案に関しても、あってはならないし、絶対に許されないことと今でも思っております。模倣や盗作は断じてしていないことを、誓って申し上げます。
しかしながら、エンブレムのデザイン以外の私の仕事において不手際があり、謝罪致しました。この件については、一切の責任は自分にあります。改めて御迷惑をかけてしまったアーティストや皆様に深くお詫びいたします。
その後は、残念ながら一部のメディアで悪しきイメージが増幅され、私の他の作品についても、あたかも全てが何かの模倣だと報じられ、話題となりさらには作ったこともないデザインにまで、佐野研二郎の盗作作品となって世に紹介されてしまう程の騒動に発展してしまいました。
自宅や実家、事務所にメディアの取材が昼夜、休日問わず来ています。事実関係の確認がなされないまま断片的に、報道されることもしばしばありました。
また、私個人の会社のメールアドレスがネット上で話題にされ、様々なオンラインアカウントに無断で登録され、毎日、誹謗中傷のメールが送られ、記憶にないショッピングサイトやSNSから入会確認のメールが届きます。自分のみならず、家族や無関係の親族の写真もネット上にさらされるなどのプライバシー侵害もあり、異常な状況が今も続いています。
今の状況はコンペに参加した当時の自分の思いとは、全く別の方向に向かってしまいました。もうこれ以上は、人間として耐えられない限界状況だと思うに至りました。
組織委員会の皆様、審査委員会、制作者である私自身とで協議をする中、オリンピック・パラリンピックを成功させたいとひとえに祈念する気持ちに変わりがない旨を再度皆様にお伝えいたしました。またこのような騒動や私自身や作品への疑義に対して繰り返される批判やバッシングから、家族やスタッフを守る為にも、もうこれ以上今の状況を続けることは難しいと判断し、今回の取り下げに関して私自身も決断致しました。
今後につきましては、私の作品や仕事を通じて少しでも皆様の信頼を取り戻すべく日々の仕事に専念するしかないと思っております。
図らずもご迷惑をおかけしてしまった多くの方々、そして組織委員会の皆様、審査委員会の皆様、関係各所の皆様には深くお詫び申し上げる次第です。上記事情のゆえ今回の判断に関しましてはどうか御理解くださいますようお願い申し上げます。
2015年9月1日 佐野研二郎
「構造設計をしなかった。」としても経験則が正しければ、問題なし。しかし言い訳だけでコスト削減のためであれば「小松組建築設計事務所」及び設計を担当した2級建築士の男性(58)に対して戒めとして厳しい処分が必要。
「小松組建築設計事務所」が担当した民間の住宅や車庫は建築確認は行われていたのか?もし建築確認が行われていたのであれば、部分的に行政にも責任があるのでは??
地震や風圧に耐えるための筋交いや壁の強度が不足していた。
県などによると、事務所が2013年までの13年間に設計を手掛けた建物は、北上市に130件、花巻市に7件の計137件あり、北上市が12件を抽出して調べたところ、11件で設計が誤っていた。ほとんどは民間の住宅や車庫だった。
両市は残りの建物についても図面などの提出を求め、設計に誤りが見つかれば、事務所や施工業者に改修工事を指導する。14、15年に手掛けた建物も調査する。県は、建築士法に基づく建築士の処分を検討している。
昨年7月、車庫兼倉庫の設計を事務所に依頼していた北上市民から「筋交いが足りないのでは」と、市に相談が寄せられた。市が調べたところ、設計に誤りが見つかった。
読売新聞の取材に対し、設計を担当した2級建築士の男性(58)は「この程度(の構造)で大丈夫だろうと経験則で判断し、構造計算をしなかった。意識が欠けていた」と説明した。
この問題は、広島県信用組合の54歳の元支店長が、平成20年から5年間にわたって顧客の預金あわせて3473万円を着服していたにもかかわらず、組合が2年以上にわたって当局への届け出を行わず隠ぺいしていたものです。
組合では問題が発覚したおととし4月、当時の吉田貞之理事長ら4人の理事が出席する会議で対応を協議し、この中では問題を公表するべきだという意見もでたということです。
しかし、▼組合の創立60周年を記念する式典が翌月に予定されていたことや▼過去にも職員による着服が相次いでいたことなどから公表に消極的な雰囲気が強まり最終的に当時の吉田理事長が隠ぺいを判断したということです。
広島県信用組合では、28日、弁護士などで作る第三者委員会を設置し、原因などを検証することにしていますが、金融機関としての公正さより組合の行事を重視した経営陣の姿勢が問われます。
支店長だった男性職員が、
客の預金およそ3500万円を
着服した事実を把握しながら、
2年以上も届け出をしていなかったと
発表しました。
「組織的な隠蔽」を認めています。
県信用組合の会見)
「誠に申し訳ありませんでした」
県信用組合の発表によりますと、
因島支店や尾道支店の支店長だった54歳の男性職員が、
2008年5月からおよそ5年間に渡って、
客から預かった定期積金の掛け金や、
普通預金の払い戻し金の
着服や流用を繰り返していました。
客18人分の
1億5200万円あまりに手を着け
最終的に3473万円を着服していたということです。
県信用組合は、客からの問い合わせで
内部調査を実施しこの事実を把握していましたが、
金融庁への届け出をせず、
27日付で懲戒解雇処分にするまで、
職員を民間企業に出向させていたといいます。
不祥事を発表しないことは、
組織のトップ4人で構成する
常勤理事会で決めたと明らかにしました。
県信用組合・西川和彦理事長)
「届け出なかったということは、隠蔽になるというふうに認識しております」
県信用組合は、
弁護士らによる「第三者委員会」に再発防止策の検討を依頼。
トップの吉田貞之会長は、
辞任する意向を示しています。
広島県信用組合はこの問題を2年以上にわたって公表しておらず、当時の理事長が隠ぺいの判断を行っていたということで金融機関としてのあり方が厳しく問われそうです。
これは28日午後、広島県信用組合の西川和彦理事長らが記者会見して明らかにしました。
それによりますと広島県信用組合の因島支店と因島北支店、それに尾道支店の支店長だった54歳の男性職員が、平成20年から平成25年にかけて顧客18人から預かった預金あわせて3473万円を着服していたということです。
元支店長は着服した金を飲食費やギャンブル、それに借金の返済などに使っていたということで着服した預金の穴埋めなどのために流用を繰り返し、その総額は1億5000万円あまりにのぼるということです。
顧客から「通帳の残高が合わない」と問い合わせがあり調べたところ、おととし4月に元支店長が着服を認めたということです。
ところが、広島県信用組合ではその後も2年以上にわたって法令で義務づけられている金融庁への届け出を行わず、元支店長の処分も行わないまま事実を隠ぺいしていました。
ことし6月になって匿名の通報があり、信用組合は中国財務局に届け出て27日付けで元支店長を懲戒解雇の処分にしました。
西川理事長は、「当時的確な対応ができず深く反省している。多大なご迷惑をおかけし心よりおわびします」と話しています。
当時の理事長で隠ぺいの判断を行った吉田貞之会長は、問題の責任をとって辞任する意向を示しているということですが、重大な不祥事を組織ぐるみで隠し続けたことで金融機関としてのあり方が厳しく問われることになりそうです。
これについて中国財務局は、「金融機関に対し、法令の順守を指導してきた中でこのような事案が発生したことは誠に遺憾です」とコメントしています。
過少申告加算税を含めた追徴税額は約2億数千万円とみられる。
日本郵便(東京都)などによると、郵便局の保険外交員は、給与収入と別に営業成績に応じた事業収入があり、経費を除いた事業所得が20万円を超えると確定申告が必要だが、保険外交員らは業務と無関係のマイカーのガソリン代や同僚との飲食代、携帯電話の利用料を経費として計上し、所得を圧縮していたという。
同社によると、業務用の携帯電話の利用料や交通費は日本郵便が負担しているため、経費はほとんどかからないのが実態だという。同社は「保険外交員に対し指導を徹底し、適正な確定申告をさせたい」としている。
31日に、在東京ブータン王国名誉総領事館を通じて、医薬品やワクチン購入などに運用されている同国の基金に寄付する。東京都内の日本外国特派員協会で記者会見した矢部信司理事長は、「今後も支援を必要とする国や地域の求めに応じ、寄付をしたい」と述べた。
エコ推は07年設立。全国にキャップ回収を呼びかけ、売却益の一部をワクチン代として寄付する活動を続けてきたが、13年9月以降は寄付を中断していたことが判明。「(中断期間中は)障害者支援事業に収益金を使用したが、説明不足だった」と謝罪していた。
同行によると、元行員は畝傍支店(橿原市)と南支店(奈良市)に勤務していた平成22年1月~27年4月、計13の個人と法人の顧客から定期預金への預け入れ名目で小切手などを預かり、計約2110万円を着服した。
7月中旬に個人客から問い合わせがあり発覚。元行員は車やゴルフなどで消費者金融に借金があり、返済などに充てていたという。
被害額は8月上旬、親族が全額を弁済。同行は今後刑事告発について検討するとし、「内部管理体制の問題点を洗い出し、再発防止と信頼回復に向け全力で取り組む」とした。
国内では、2014年10月~15年6月に製造・販売されたノートパソコン「YOGA3」の一部製品など16製品。同社はソフトを消すプログラムの無償配布を始めた。
レノボ日本法人によると、このソフトは購入後、最初に起動した時のみ作動し、パソコンの基本性能をレノボ社に自動的に送信する機能がある。しかし、海外の専門家が今年3月、このソフトが原因で、ウイルスに感染したり、パソコンを遠隔操作されたりする可能性があると指摘していた。
ポイントは5年間のアルバイト生活後に東京外語大学に入学したという記事と2007年に嘉田由紀子元滋賀県知事の地域政党スタッフになったというものです。
どちらも正しいとなると、これは由々しき問題です。
どちらも正しければ、2007年当時、かれは東京外語大生か社会人でなければなりません。
京都大学院生時代に地域政党スタッフになったという経歴は詐称と言うことになります。
同時に、2009年時点では京都大学院生であり、修了は落選後と言うことになります。
落選した2009年衆議院選挙で経歴を詐称していたということにも繋がります。
ということで、まずは嘉田由紀子氏にFacebookを通じてメッセージを送りました。

そもそも公人たる衆議院議員が自身の経歴を詳らかにしない(この表現方法が正しいんですよ、安倍君。「詳らかに読んでいない」ってやっぱ変よ?)から国民は疑問に思うのです。
個人で調べる限界、個人への連絡はなかなか来ないという現状の中、調べられるだけ調べてみました。
嘉田元滋賀県知事からは未連絡。
日刊ゲンダイからも未連絡という状況です。
まず、1998年に高校卒業後の自称アルバイト生活(実質5浪?)の事実についてです。
日刊ゲンダイさんは教えてくれませんでしたが、どうやら事実のようです。
朝日新聞が2009年時点で初立候補した武藤貴也氏の記事を掲載していました。
そこに5年のアルバイト生活について記載がありましたし、まだ立候補者の一人ですから貶める必要もない時期です。
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?id=A0001311&type=article
計約125万件(約101万人分)の流出はすべて、5月20日に機構本部(東京)の職員が標的型メールを開封したことが原因で、同21~23日の3日間で一気に流出したことが判明。その約2週間も前から断続的な攻撃が続いていたが、機構が有効な対策を講じなかったことで、甚大な流出被害を招いた。
政府のサイバーセキュリティ戦略本部も20日、調査結果を公表。機構の水島理事長は記者会見で改めて謝罪し、自身は「問題の処理に全力であたる」として続投する意向を示した。
報告書によると、機構は5月8~20日に全国各地の部署で、特定の企業や団体の情報流出などを狙う「標的型メール」を計124通受信。このうち5通が5人の職員によって開封され、計31台のパソコン端末がウイルスに感染した。
機構は、事業主と従業員で折半する厚生年金保険料の額を算定するため、毎年1回7月に、全国約170万の加入事業所に従業員の給与データの提出を要請。希望する約10万事業所に、従業員ごとの氏名と前年度分のおよその月給額などを記録したディスクを事前に郵送している。昇給などがあればデータを上書きのうえ、返送してもらう。
機構のホームページから誰でも無料でダウンロードできるプログラムを使ってPWを入力すれば、ディスクからデータを引き出せる。このため、PWの管理は特に重要になる。
ところが機構によると、事業所を管理するためにつけた5ケタの番号をPWに転用。ディスクとともに、事業所番号を記した紙や、PWは事業所番号だと説明する紙も同封し、書留などではなく普通郵便で送っていた。封筒が誤配されたり盗まれたりすればPWが簡単にわかり、個人情報が大量に漏れかねなかった。
昨年度末に機構内で疑問視する声があがり、今年度から説明の紙でPWに関する記載をやめた。来年度からPWを事業所番号から変える方針だ。ディスクをPWと別の郵便で送ることや、提供自体の中止も検討している。(山田史比古)
JSCが同日の会合に提出した資料によると、東京五輪開催決定前の2013年7月時点で、設計会社は総工費が3462億円に膨らむと試算していた。
公認会計士の 国井隆委員は五輪招致でアピールできるインパクトの強いデザインを採用した背景には一定の理解を示しつつ、公共事業はある程度決まった予算を前提として進めるものとし「(コスト軽視の)流れを逆にするタイミング、潮目はあったのかなと感じる」と指摘。同9月に五輪の東京開催が決まった後も「夢物語を引きずった」と、早期にコスト削減のための抜本的な見直しに着手しなかったJSCなどの姿勢を問題視した。
総工費はその後、規模縮小によって一時は1625億円まで圧縮したが、難工事が容易に想定できたデザインの見直しまでは踏み込まなかったため、資材価格の高騰などで再び膨らみ、最終的に2520億円となった。元陸上五輪選手の 為末大委員は「予算の優先順位をもうちょっと高いところに置いておけば(早期に)この方向ではいけそうにないという判断もあったと思う」と語った。
野放図に工事費が膨らんだ要因の一つに、デザイン公募段階でJSCが示した総工費1300億円が、明確な上限ではなかった点がある。新たな計画では「公募段階から価格の上限をピン留めする」とJSC担当者は言う。旧計画では、大会組織委員会の森喜朗会長や東京都の舛添要一知事ら五輪に関わる主要機関のトップらで構成された有識者会議が機能しなかった反省も残る。新計画では建築や景観の専門家で固めた審査委員会がコストや技術面の実現可能性をチェックする。
一方、破綻した巨大プロジェクトの責任の所在はいまだ不明確なままだ。関係機関が複雑に絡み合い、為末委員は「正直なところ分かりにくい」と認める。第三者委は9月中旬までに報告をまとめる予定。 柏木昇委員長はこれまで文科省やJSCの担当者ら十数人を対象にヒアリングを実施したと説明するが「主要な方にはもう一度ヒアリングすることになるのではないか」と述べた。
日本スポーツ振興センター(JSC)はその2か月後、半額で収まるとの試算を出しており、検証委は妥当性を調べる。
JSCが検証委に提出した資料によると、12年7月の国際コンペに1300億円の条件で公募されたデザイン案は、設計会社が忠実に再現し、各競技団体の要望を盛り込んだ結果、約2・6倍に膨れあがった。
文科省から削減指示を受けたJSCは、床面積を減らすなどして13年9月には1785億円に削減し、さらに14年5月、1625億円とする基本設計案を公表した。
しかし今年1~2月に、建設業者が3088億円の工事見積もりを提示すると、設計会社は2112億円と試算。JSCは7月、総工費2520億円でまとめており、検証委は今後、極端に増減した根拠を調べる。柏木昇委員長は、文科省やJSC関係者12~13人から聞き取り調査を行ったとして、今後、下村文科相らトップも調べるとの考えを示した。
中央テレビは、現場に出動した消防幹部の話として、爆発の起きた付近の大気から化学兵器の1つ、神経ガスの成分が検出されたと伝えた。検出された神経ガスの詳細は明らかでない。
北京化工大学の化学専門家の話として、神経性ガスを一定濃度で吸い込むと、呼吸困難や心臓停止が起こり、死に至る場合もあるとも伝えた。
現場の倉庫には、爆弾の材料などに使われる硝酸カリウムや硝酸アンモニウムなど、40種類を超える危険な化学物質が少なくとも約3000トン保管されていた。これらの物質が神経ガスを発生させた可能性がある。
こうしたなか、共産党中央規律検査委員会は18日、元副市長で国家安全生産監督管理総局の楊棟梁局長(閣僚級)に重大な規律違反と違法行為があり調査していると発表した。
中国メディアによると、楊氏は天津市副市長を10年以上務めた地元の名士で、爆発があった倉庫を所有する中国企業「瑞海国際物流公司」と関係が深い化学工場で1990年代に副社長を務めていた。2012年に国家安全生産監督管理総局長に就任後、化学物質など危険物を扱う業者に対する許認可を緩めたとされる。
また、瑞海国際物流公司の于学偉会長ら10人と、同市の経済開発区「浜海新区」の臨港経済区管理委員会の幹部ら2人が拘束されたという。
中国人記者の間では、この企業の後ろ盾は地元出身の李瑞環・元政治局常務委員で、親族も経営に関与しているとささやかれている。事実とすれば、楊氏への調査は突破口にすぎず、捜査の手は元最高指導部メンバーに及ぶ可能性もある。
巨大な火の玉が発生し少なくとも114人が死亡した爆発を受け、警察当局は倉庫を所有していた企業「瑞海国際物流公司(Rui Hai International Logistics)」の会長ら10人の身柄を拘束した。
共産党の一党独裁政権に対する批判が広がるのを防ごうと、中国当局が地元の当局者や個人に責任を負わせようとしている中、新華社通信は拘束された人物の一部との面会を許可され、その発言内容を大々的に報じた。
新華社によると、天津港の元警察当局責任者を父に持つ瑞海国際物流の董社軒(Dong Shexuan)副会長(34)は同窓生を介して瑞海国際物流の株式の45%を所有していたという。残りの株式は、同社の于学偉(Yu Xuewei)会長が知人の名義で保有していた。于会長は国営化学企業「中化集団(Sinochem)」の元重役。
董副会長は新華社に対し「父親の問題があったので同窓生に株式を保有してもらっていた」と述べ、「もし私が事業に投資していることが明るみに出れば悪影響を及ぼす恐れがあった」と語った。新華社によると董副会長は警察や消防当局に持っていた人脈を使って、検査を回避したり許認可を得たりしていたという。
また新華社によると、瑞海国際物流は今年6月までの9か月間、必要な免許が切れた状態だった。于会長は新華社に対し「最初の免許が失効した後でわれわれは延長を申請した」「だが多くの企業が免許なしに操業しており、問題だとは考えなかったので操業は続けた」と語ったという。
実際は、大会組織委がどれだけの情報を現状でもっているのか知らないが、うんざりしているかもしれない。
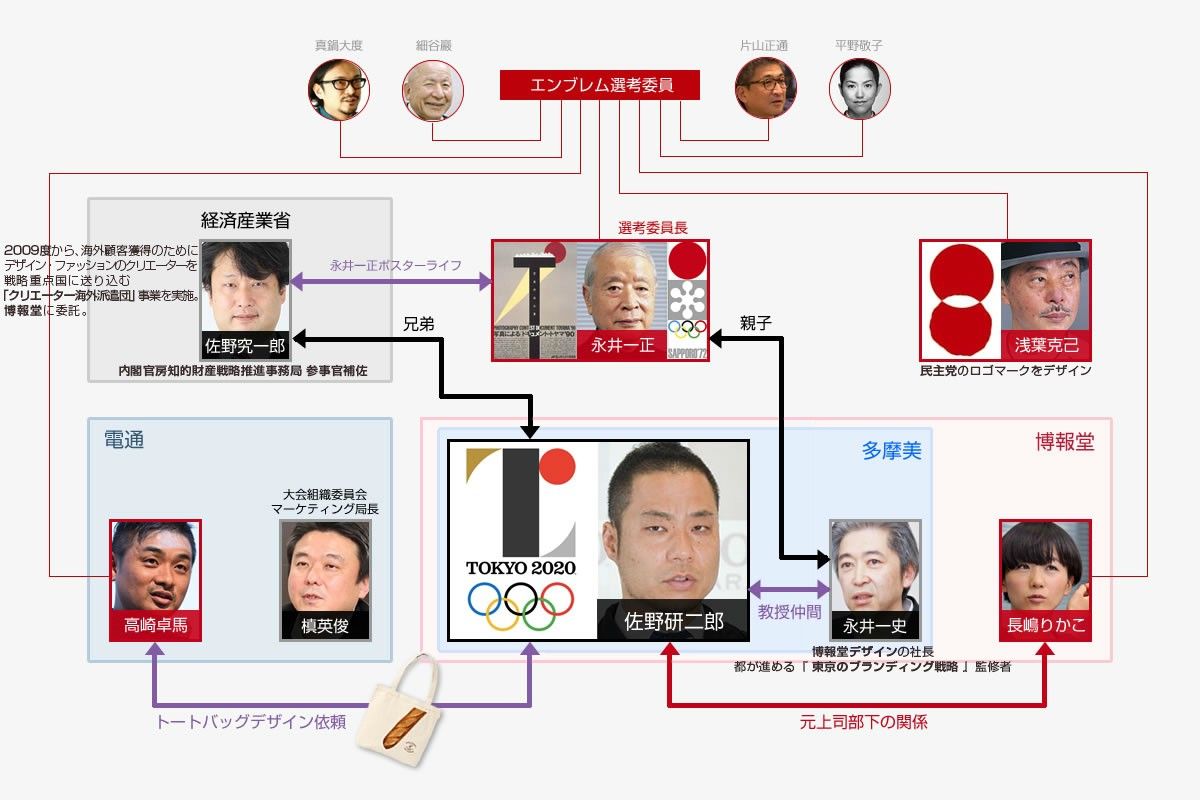
東京五輪エンブレムデザイン選考委員相関図
東京オリンピックのエンブレムを巡っては、ベルギーのデザイナー、オリビエ・ドビ氏とベルギー・リエージュ劇場側の代理人が14日、著作権を侵害されたとして、国際オリンピック委員会(IOC)に対し使用の差し止めなどを求める訴訟をリエージュの民事裁判所に起こしていた。ロゴの使用を続けた場合、IOCや公的機関、ロゴを使った企業などに、賠償金各5万ユーロ(約690万円)を支払わせると、求めていたとされる。
これに対し、大会組織委員会は14日、「訴状を見て対応を協議したい」とコメントしていたが、内容を確認したうえで、デザイナー側に書面で回答を行ったとしている。組織委はドビ氏らに対して、「自らの主張を対外発信し続けたうえ、提訴する道を選んだ態度は公共団体としての振る舞いとしては受け入れがたい」と、強く非難した。
IOCや日本オリンピック委員会(JOC)、大会組織委員会は佐野氏デザインのエンブレムについて、「独自の創造過程に基づく完全にオリジナルな作品であり、大会の価値やメッセージを内包し、1964年(大会)のエンブレムとの結び付きも示した作品であることを強調した」とドビ氏に伝えていた。
現場周辺の簡宿街では、市に構造や防火対策の問題を指摘されるなど、経営環境が大きく変わったことで、廃業する宿も出始めた。市は居住者に民間アパートへの転居を促しているが、受け入れ先探しは難航している。
「みんなには悪いけど、良い時期にやめたのかな」。8月上旬、市に廃止届を提出した簡宿で、管理人だった女性(79)は後片づけをしながらつぶやいた。
火災後、市は火元と同じように2、3階部分が吹き抜け構造になっている簡宿など24棟を建築基準法違反で是正指導し、3階以上の使用を禁止した。部屋数が減れば簡宿の経営は圧迫され、防火対策にも多額の費用がかかる。
宇都宮市の認可外保育施設で保育中の生後9カ月の女児が熱中症で死亡する事件があった。当時の施設長が保護責任者遺棄致死容疑で逮捕され、同罪で起訴された。待機児童の受け皿ともなっている認可外施設の問題を浮き彫りにした悲劇。防ぐことはできなかったのか。
事件が起きたのは昨年7月。共働きの夫婦がともに出張のため、女児を施設に預けたが、3日後に熱中症で死亡した。起訴状などによると、女児は高熱と下痢が続いていたのに、元施設長は医師の診察を受けさせずに放置して死亡させたとされる。冷房はついていなかったとみられ、顔には打撲痕があった。これまでの調べに対し、元施設長は「適切な保育を行っていた」と否認しているという。
「子どもの爪がはがされている」「毛布でぐるぐる巻きにし、ひもで縛っている」。女児が死亡する約2カ月前に保護者たちから市に苦情が寄せられていたことも、事件後にわかった。
市は苦情を受けた数日後、施設に事前連絡した上で立ち入り調査を実施したが、異常は確認できず、施設はその後「病院で医師が治療のために爪をはがしたと解釈する」などと文書で回答したという。
両親はいま「抜き打ちで調査していれば、事件は防げたのではないか」と主張する。適切な指導を怠ったとして、昨年9月以降、市と施設に損害賠償を求める訴訟を起こし、元施設長らスタッフを複数回にわたり刑事告訴・告発した。
増え続ける外国人旅行者がファッション感覚でタトゥーを入れていることが多いためで、暴力団関係者と区別しようと、「シールで隠せる大きさ」を限度に容認するケースが目立つ。2020年の東京五輪・パラリンピックに向け、施設側からは「海外との文化の違いを理解すべきだ」との声が上がる。
年間約25万人が利用するさいたま市北区の温浴施設「おふろcafe utatane」は、専用のシール(12・8センチ×18・2センチ)で隠せる大きさのタトゥーについて入浴制限の対象外とすることを決めた。8月1日から1か月間試行し、トラブルがなければ本格実施に踏み切る。
同施設の経営者で、浴場などの若手経営者団体「一般社団法人ニッポンおふろ元気プロジェクト」代表理事の山崎寿樹さん(32)は「外国人旅行者が増え、文化としてタトゥーを認める必要があると感じた」と説明する。
同市の商品券は1冊1万円で20%分のプレミアムが付き、7月に3万冊を完売した。同信金は4750冊の販売を委託され、職員らが96冊を事前に購入した。
八王子市の商品券でも、新たに61冊(1冊5000円、30万5000円分)の事前購入が判明。同市分で正規に販売されなかったのは計363冊になった。
同信金によると、職員が顧客らの依頼を受けて取り置いたり、自分で使うために事前購入したりし、支店長や副支店長ら支店幹部も関わっていた。同信金では会長や理事長の報酬全額返上(1か月)などの処分を決め、関わった職員らを今後処分する。
しかし、コストを優先する発注者はさほど考慮しないかもしれない。もしかすると値引率が上がれば今以上にシンドラーエレベーターを選択するかもしれない。
エレベーターの使用者が選択するのではないのでこればかりは予測出来ない。
同社によると、元社員は平成20年9月に入社。保守作業員として1人でメンテナンス作業ができる社内資格を持った「中堅レベル」だったという。自身の降格人事をめぐるトラブルもあったが、同社は「率先して物事に取り組み、リーダーシップがあった」と話す。
しかし、そうした立場を悪用し、夏の暑い時期に利用者をエレベーターに閉じ込める行為を繰り返したとされる。
閉じ込め事案7件のうち3件が起きた千葉市稲毛区のマンション。住民によると、国土交通省が発表した事案以外にも最近、たびたびエレベーターにトラブルがあったという。住民の主婦(39)は7月初旬、降下中にエレベーターが急停止し、10秒ほど閉じ込められたという。「エレベーターは不安だが、使わないと生活できない。私の件も故意なのだとしたら怖い」と話した。
2件の閉じ込め事案があった東京都杉並区のマンションでは、7階に住む主婦(34)が「安全点検を行うべき社員がやっていたなんて…。悪意ある人が堂々と操作できていたと思うと本当に怖い」と驚いていた。
同社製エレベーターをめぐっては、東京都港区のマンションで平成18年、エレベーターの扉が開いたまま上昇し、高校2年の男子生徒=当時(16)=が、かごの床と外枠に挟まれて死亡した事故があった。業務上過失致死罪で点検責任者ら4人が起訴され、今年9月に判決が出る予定だ。
24年には金沢市でも、同様の挟まれ方をした女性=当時(63)=が死亡する事故が起こり、石川県警が業務上過失致死容疑で捜査している。
同社は「お客さまをはじめ関係各位には、大変なご心配をお掛けしましたことを心からおわび申し上げます」と謝罪した。
シンドラー社によると、保守点検業務を行っている住宅のエレベーターで、2015年6月下旬以降、原因が特定できない閉じ込め事案が、複数発生した。
このうち、8月2日に茨城県内のホテルのエレベーターで発生した事案では、閉じ込められた男性が、直接、フロントに「シンドラーを呼ばないのか」などと電話するなど、対応に不自然な点があったことから、調査を行ったところ、この男性がシンドラー社の元社員で、自ら閉じ込められていたことがわかったという。
元社員はこれまでに、この自作自演のほか、緊急用の鍵を使って、エレベーターの外にある安全装置を操作し、エレベーターを停止させるなどして、利用者を閉じ込める同様の事案を7件、起こしていたことを認めたという。
元社員は、「動機は腹いせ」と言っているという。
この社員が関与した可能性がある物件については、緊急点検をするよう国土交通省も指示を出している。
関係者によると、元社員は平成25年7月に支店長に就任したが、今年6月15日付で平社員に降格となり、同社側とトラブルになっていた。元社員は「腹いせでやった」と話しているという。
国交省や同社などによると、元社員は同社に勤務していた6月28日~8月1日の間、URのマンション計5カ所で、保守点検用の鍵で乗り場にある扉を開け、本来はトラブル時に作動する安全装置を意図的に作動させるなどの手口で、最長約45分間にわたってエレベーターを停止させていた。
マンションの住民計7人が被害に遭った。エアコンが付いておらず、うち30代の女性1人が気分が悪くなって病院に搬送された。いずれもけがはなかった。
茨城県内のホテルで今月2日に元社員自身が「エレベーターに閉じ込められた」と通報。しかし、元社員は自力で脱出し、その場を立ち去っていた。安全装置を作動させた際に内側から自力で扉を開けるには専門的な操作が必要なことなど不審点があったため、同社が調査したところ元社員による自作自演が発覚。6月末から原因不明の故障が相次いでいたことから、同社が元社員への聞き取りを進めたところ、ほか7件に関わったことも認めた。
国交省は同社からの報告を受け、元社員が保守点検に関与した全てのエレベーターの安全性について緊急点検するよう指示した。
シンドラー社によると、保守点検業務を行っている住宅のエレベーターで、2015年6月下旬以降、原因が特定できない閉じ込め事案が、複数発生した。
このうち、8月2日に茨城県内のホテルのエレベーターで発生した事案では、閉じ込められた男性が、直接、フロントに「シンドラーを呼ばないのか」などと電話するなど、対応に不自然な点があったことから、調査を行ったところ、この男性がシンドラー社の元社員で、自ら閉じ込められていたことがわかったという。
元社員はこれまでに、この自作自演のほか、緊急用の鍵を使って、エレベーターの外にある安全装置を操作し、エレベーターを停止させるなどして、利用者を閉じ込める同様の事案を7件、起こしていたことを認めたという。
元社員は、「動機は腹いせ」と言っているという。
この社員が関与した可能性がある物件については、緊急点検をするよう国土交通省も指示を出している。
発表によると、同社は2009年1月23日~10年3月9日頃、崖崩れが発生した山林内で市の許可を受けずに盛り土をし、事故後の14年10月10日、市から同法に基づく是正命令を受けたが、対応しなかった疑い。社長は「(工事をする)お金がなかった」と容疑を認めている。
市は今年7月までに、行政代執行で斜面を保護する工事を実施。費用約2億5000万円の支払いを同社に求めるという。
ソープランドでの接待はいったい何の目的のためだったのか。接待を受けた被告は「友情からだ」と語り、接待をした別の被告は「会社のためだった」と主張した。JR貨物の発注工事をめぐる贈収賄事件で、JR会社法違反(収賄)罪に問われた同社元幹部男性(46)と、同法の贈賄罪に問われた電気設備会社「カナデン」元営業担当男性課長(47)の両被告の判決公判が8月6日に東京地裁(戸苅左近裁判官)で開かれ、いずれも有罪判決が言い渡された。公判では、立場が違えば思いが異なることが鮮明となった。(太田明広)
■ソープ店の会員を上司の名前で登録
元幹部は、JR貨物が発注した照明設備の改修工事などで、カナデンが照明機器などを納入できるよう便宜を図った見返りとして、元課長からソープランドで7回にわたり、計約42万円相当の接待を受けたとして起訴された。
JR貨物の役員や従業員はJR会社法という法律で、公務員と同じように賄賂を受け取ったりすることが禁じられている。
「ストレスたまった。行かない?」。元課長の公判での証言によると、元幹部がこう持ちかけてくると、ソープ接待を要求する隠語だったという。元幹部は指定する店があるほど、ソープ接待にのめり込んでいた実態が明らかになった。
今回起訴された7件の接待のほとんどは川崎市内の同じ店で、指名女性も同じだった。店への会員登録もして、当時の上司の名前を使っていた。「自分の名前が表に出るのが何となく嫌だった」と、元幹部は証言した。「上司の名前を使う許可は取っていたのか」と検察側から問われると、公判で唯一気恥ずかしさからか表情を崩し否定する場面もあった。
接待をする側の元課長は、ソープ店での支払いだけを先に済ませると、元幹部がサービスを終えるまで近くの居酒屋などで時間を潰して待った。
「自分はそういうのがもともと好きではなかった」と元課長。「ソープでの接待費はさすがに経費では落ちないと思い自腹を切った」と振り返った。
そもそもソープ接待をするようになったのは、紹介者を通じて元課長が元幹部と出会った際、ソープ店の名前を出されて「あそこは面白い。行きたいね」と要求されたからだったという。
一方の元幹部は、「(ストレスたまったという)隠語を使った記憶がないし、食事をした際にその流れで行く感じで暗黙の了解だった」と積極的な関与を否定し、2人の証言が食い違った。
■「赤信号みんなで渡れば怖くない」
なぜ、元幹部にソープ接待までする必要があったのか。
「会社にとって良かれと思ってやった。まさか会社に迷惑をかけると思わなかった」
元課長によると、カナデンでの所属部署のターゲット層は従来の固定客が中心だった。ただ、固定客が先細りし始めており、当時の社長の指示もあり新規開拓が求められていた。
元幹部に接待を始めたのが平成20年ごろだった。当時建設業者など他社がこぞって元幹部に飲食やゴルフ、ソープ接待をしていた実態があったと、元課長は証言した。
「新規で食い込むには接待が欠かせなかった」と他社と同様に接待を始めた。
検察側の冒頭陳述によると、元幹部には「業者選定の大きな影響があった」と明かした。選定には上司や役員の承認が必要だが、信頼を得ていた元幹部の意見がほぼそのまま反映されたという。17年ごろから業者からの接待を受けるようになっていた。
別の業者によると、元幹部は発言を否定するが、「接待をしない業者は使わない」「営業で汗をかくところは引き合う」などと述べていたという。
元課長は「JR貨物社員が公務員に準じるとは知らなかった。接待が贈賄になる認識もなかった」と悔やんだ。
「たくさんの会社が元幹部を接待していた。ソープ以外の接待費は会社に経費として認められており、問題はないと勝手に解釈していた」と振り返った。検察からは「赤信号みんなで渡れば怖くないということか」と皮肉られた。
接待の結果、カナデンと結びつきを強めた元幹部。ライバル社は調書のなかで「商売敵だったカナデンは今まで一度もJR貨物から受注したことがなかった。扱う製品もこちらの方がよかったのに、カナデンに発注すると聞かされたときは腑に落ちなかった」と当時を振り返った。
■友人なのに一銭も払わず
「仕事上の関係を超えて、友人としての認識だった」と元幹部は元課長を評した。日頃から細やかに営業活動をし、対応も迅速だった元課長に信頼感を抱いていたという。
この証言に、検察側が厳しく追及した。
検事「元課長と友人のような感覚があったということか」
元幹部「はい」
検事「接待の1回あたりは約10万円かかっている。今までに計20回ほど接待を受けているが、カネを払ったことはあるのか」
元幹部「ない」
検事「本当に友人のようだと思っていたのか」
元幹部「はい」
検事「かなり接待を受けているが、まあ賄賂だけど。ソープ以外にも飲食やタクシー代まで支払ってもらい、1円も払っていないよね」
元幹部「はい」
検事「1円も払わないのに友人ということがあり得るのか」
元幹部「当時はそのように思っていた」
検事「友人で好意でやってくれるということか。毎回10万円ぐらい出してもらっている。普通は友人ではないよね」
元幹部「はい」
一方、元課長も「会社のためだと思ってやった」という証言を追及された。
検事「受注ができれば会社内での評価はあがるよね。ボーナス上がったのでは。100万円以上も上がっているが」
元課長「はい」
検事「それって会社のためではなく、あなた自身のためだったのでは」
元課長「評価が上がると思った」
検事「ソープ接待は禁じ手では。次元が違うことは」
元課長「そう言われればそうだ」
検察の鋭い追及に両被告とも疲れた表情を浮かべた。
両被告とも公判ではいずれも起訴内容を認め、反省の弁を述べていた。
元幹部は懲役1年2月、執行猶予3年、追徴金約42万円(求刑懲役1年2月、追徴金約42万円)、元課長は懲役10月、執行猶予3年(同懲役10月)の判決が言い渡された。戸苅裁判官は「遊興接待が常態化し、両被告の規範意識は相当鈍っていた」と批判した。
公判中、両被告は隣に座りながらも目を合わせることはなかった。ともに事件後に会社を懲戒解雇された両被告が、この後も“友情”が続くとはどうしても見えなかった。
谷研究員らは、セシウムの一部が水に溶けにくい化合物になり、肺に長くとどまるためではないかと推定している。被曝ひばく線量を見積もる計算モデルの見直しにつながる可能性があるという。
同研究所では、事故直後に原子炉の中央制御室で監視業務などにあたり、被曝線量が特に高かった作業員7人について、年に数回、検査を受けてもらい、体内のセシウム137などの量を測っている。
作業員のセシウム量は、事故後、約2年間は、「肺から血液へ溶け込み、尿などを通じた排出により、70~100日ごとに半減していく」という予測通りに減少していた。しかし、2013年の半ば頃から減り方が鈍くなった。
今回の東京オリンピック・パラリンピックは、約60年ぶりの夏季開催。今回の新国立の騒動の背景に、前東京オリンピック当時の日本の行動経済成長期に想いを重ね、景気回復の足掛かりにと期待を寄せている人が多いことがうかがえます。
しかし、今回東京オリンピック・パラリンピックに向けて建設を予定していたのは新国立競技場だけではありません。オリンピック以後も取り壊さず、恒久利用される施設が全12施設予定されていますが、国立競技場以外にも、建設計画が見直されている施設が他にもあります。
今後どんな施設の建設が予定されているのか。
調べてみました。(金額は2015年7月時点)
国立競技場以外にも、雲行きの怪しい会場が…
オリンピックアクアティクスセンター
総工費:683億円予定
現状:競泳・飛込・シンクロナイズドスイミングのメイン会場。オリンピック終了後は、収容可能人数を5000人縮小し、民間運用する。オリンピック後の施設運営計画が策定されるのは8月中旬予定。なお、競技会場の見直しによって、水球の会場は整備中止。
海の森水上競技場
総工費:491億円
現状:そもそも69億円の総工費が見込まれていたが、その後1038億円に。再検討の後、570億円になり、予算面を見ても計画が定まっていなかったが、護岸工事規模見直しやレイアウトの見直しで整備費を491億円まで圧縮予定。
オリンピック選手村
総工費:1057億円
現状:東京都晴海に建設予定。ただし、セーリングなど一部競技開催場所が遠方になることも予想されており、移動面も考慮し分村の可能性も出てきている。
大井ホッケー競技場
総工費:46億円
現状:大井ふ頭中央海浜公園内に2会場新設される予定。
有明アリーナ
総工費:404億円
現状:バレーボールのメイン会場であり、恒久施設。
葛西臨海公園
総工費:32~73億円
現状:当初予定していた葛西臨海公園の隣都有地に移転案が出ている。当初建設設備費は32億円。
有明ベロドローム
総工費:65億円
現状:そもそも東京都・有明に仮説のベロドームを建設予定だったが、計画の見直しによって建設中止に。その後、静岡県伊豆市への変更が検討されるも、国際自転車競技連合は東京都での実施を求めており、7月28日の国際オリンピック委員会理事会にて再協議予定。
夢の島ユース・プラザ・アリーナ(A・B)
総工費:73億円
現状:再検討の結果建設中止に。開催予定だったバドミントンは武蔵野森総合スポーツ施設(東京都・調布市)で、バスケットボールはさいたまスーパーアリーナ(埼玉県・さいたま市)に変更となったが、バドミントンの開催会場は選手村からの移動距離が問題視されいまだ合意には至っていない。
若洲オリンピックマリーナ
総工費:100億円
現状:再検討の結果建設中止に。その後、既存施設の若洲海浜公園ヨット訓練所を改修・拡張活用することになったが、羽田空港の航空管制に空撮が制限される問題が浮上。都外での代替地として千葉県美浜区の稲毛ヨットハーバーの他、神奈川県藤沢市の江の島ヨットハーバーなどが候補に挙がっている。
オリンピックを前に知っておくべき、オリンピック負債
せっかく60年ぶりの夏季五輪国内開催。綺麗で安全な日本を対外的にアピールするためにも、お金をかけても新しい施設でやるべきでは、という考えもあるでしょう。
しかし、オリンピックの開催による開催国の経済的負担は予想以上に大きく、2004年にギリシャで開催されたアテナ大会では施設建設費を国債でまかない、これがギリシャ危機の一因になったとも言われているのです。
また、カナダは1976年に開催したモントリオール大会の負債を、2006年11月に30年かけて返済完了しています。
オリンピックに向けて景況感は良くなっているように感じるかもしれませんが、問題は開催後。その後、アテネやカナダのようなことにはならないにしても、日本の景気がその後傾くということも予想されます。施設の建設は、計画から遅れれば遅れるほど費用がかさむのも事実。日本は現在建設業における現場とび職の担い手も少なく、オリンピック実現を前に前途多難な状況です。
今回の競技場の一件を楽観的に見ていた人は多面的な見方が必要かもしれません。
(書いた人:考務店)
【デザイン選定】
建築家ザハ・ハディド氏によるデザインは12年、日本スポーツ振興センター(JSC)の国際公募で選ばれた。最終的に残った3候補の評価は分かれたが、審査委員長の 安藤忠雄 (あんどう・ただお) 氏が推し、委員は賛同。安藤氏は「スポーツの躍動感を思わせるような斬新なデザイン」と理由を説明している。
第三者委の初会合では、元五輪陸上選手の為末大氏が「五輪招致を勝ち取るためのデザインだったのでは」と疑問を呈した。 柏木昇委員長は、設計とデザインを一体で公募する手法を採用すれば、総工費を抑えられた可能性があると指摘した。
屋根を支える巨大な2本のアーチ構造の工事は、技術的に困難とされる。当初の想定額1300億円で建設が可能かどうかの議論の有無に加え、応募期間や審査期間、情報公開の在り方が適切だったのかも焦点となる。
【見直しタイミング】
総工費の見通しは、資材費や人件費の高騰だけでなく、デザインもネックとなり二転三転した。文科省やJSCはその都度、計画の一部見直しを図ったが、デザイン変更など抜本策には踏み込まず、最終的には当初想定を1千億円以上超える2520億円に膨らんだ。結果的に時間が浪費され、決断が遅れたことによる無駄な支出も生じた。
また、文科省が会合に提出した資料で、JSCが競技場の建設業者から「3千億円を超える」と伝えられていたのに、文科省には2月時点で「2100億円程度になる」と900億円も低い独自試算を報告していたことも判明した。
3千億円という試算の表面化や、建築家槙文彦氏らによる代替案提示、下村博文文部科学相が最終的な総工費と完成時期を発表したタイミングなど、計画を見直す機会は何度もあったとみられ、検証が求められそうだ。
【責任の所在】
デザインの採用や総工費の膨張、白紙撤回に至るまでの混乱を招いた責任はどこにあるのか。
初会合ではJSCや文科省への批判が相次いだ。経済同友会専務理事で、みずほ証券常任顧問の 横尾敬介氏は、事業主体のJSCについて「総工費が大きく変動するなんて民間では考えられない。事業を差配する能力はあったのか」と述べた。
為末氏は「一度決めたことだから、あとは現場で工夫して、ということだったのでは」と述べ、計画を監督すべき立場だった下村氏ら文科省関係者の責任を問う考えを示した。
スポーツ行政の在り方や組織、執行体制にまで踏み込むのかも注目される。
(共同通信)
もし聞いた事があれば通報するべきであったと思う。これまで大きな事故がないから、今後も起こらないとは限らない。事故が起これば、
調布飛行場の存続、又はさらなる規制は想像できるだろう。
同飛行場では、周辺住民への配慮のため、1992年から自家用機の新規登録を認めていない。92年当時は35機だった自家用機は現在、今回の事故機を含めて23機に減少。離着陸回数も、この5年間で4割以上減っている。今回の事故を受け、舛添要一都知事は「(将来的には)自家用機の運航停止も視野に入れて検討する」と述べたが、今後の運用は未定だ。
多くの住民は飛行に不安を抱く一方で、同飛行場で自家用機を操縦している男性は「飛ばなければ操縦の腕が落ち、飛行機も動かさなければ傷む。今の状況では、別の飛行場に移動させることもできない」と頭を痛めている。
税金はどんぶり勘定で投入され、問題が発覚すると言い訳ばかりで誰も責任を取らない。責任を取れない人々に多額のお金を支払う必要もない。肩書きだけで
仕事が出来ない人を任命するよりも、真剣に仕事をする人達にチャンスを与えるべきでは?日本ではそのような環境はないと思うが、少なくとも責任を明確にして
責任を取らすべきだ。組織や役職が作られた時に権限や責任を明確にしていないからこうなるのだ。たぶん、問題が発生した時に責任から逃れるという意図で、
明確にしていないと思う。オリンピックに選ばれたから仕方がないが、最低限度の投資でよい。オリンピックを大義名分にしてオリンピックだからお金を使いたい、
使ってほしい人達が多くいるからこうなるのであろう。
下村博文文部科学相が示した検証項目は(1)当初の総工費1300億円の積算根拠や、膨張の経緯(2)建築家のザハ・ハディド氏のデザイン案の選考過程(3)計画を見直すべきだったタイミング(4)文科省と事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)の役割-など多岐にわたる。提出期限を9月中旬に設定したのも、今秋作成予定の新整備計画に“失敗の教訓”を反映させたいとの狙いからだ。
ただ、柏木昇委員長が会合終了後、記者団に「9月半ばの提出は不可能。普通なら半年は頂かないと…」と本音を漏らしたように、短すぎる期間が障害となりかねない。さらに文科省が関与者としてリストアップした同省とJSCの幹部だけで40人以上に及び、設計会社やゼネコン関係者を含めれば聴取対象はさらに膨らみ、証言の収集と分析だけで時間が奪われる。会合では関係者間の口裏合わせを警戒して、議事録公開のタイミングに配慮を求める意見があがったほどだ。
“犯人捜し”に終始すれば全体像を見失うが、責任の明確化には一定レベルでの事実認定は不可避だ。厳しい条件と重圧のもと、第三者委には核心に迫る調査を求めたい。(花房壮)
下村氏は会合の冒頭で「国民の関心が極めて高い。責任について、私へのヒアリングも含め、厳しく検討してほしい」と話した。関与した文科省や事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)の幹部らには証拠を保全するよう指示したことを明らかにした。国際取引法などが専門の柏木昇東大名誉教授が委員長に就任。元陸上五輪選手の為末大氏や、経済同友会専務理事の横尾敬介みずほ証券常任顧問ら5人が委員を務める。
会合では、厳しい意見が相次いだ。柏木委員長は「工事全体をマネジメントするシステムに欠陥があったのではないか」と指摘。横尾委員は乱高下した総工費について「民間ではあり得ない」と切り捨てた。
柏木委員長は会合終了後、記者団に対し「この規模の案件の調査は半年程度かかる」と調査期間の短さに不満を漏らす一方、来週以降に文科省幹部らのヒアリングに着手し、下村氏からも総工費が膨張した経緯などを聞き取る方針を明言。ほかに、デザインコンペで委員長を務めた建築家の安藤忠雄氏や新国立の将来構想有識者会議メンバーだった森喜朗元首相らも対象になる可能性がある。
総工費が乱高下した経緯などに批判が続出し、委員長に選出された柏木昇・東京大名誉教授は会議後、下村文科相やデザイン選定時の審査委員長を務めた建築家の安藤忠雄氏らのヒアリングも必要との考えを示した。
計画白紙に至った責任の所在などについて議論し、9月中旬までに報告書を取りまとめる。約1時間半にわたった会合で、委員からは「(当初予算の)1300億円は実現可能性があったのか」などと総工費算定根拠に対する疑問が示され、事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)について「これだけの事業をまとめる能力があったのか」などと批判が相次いだ。
正確な額が公表されていれば、計画見直しが早まった可能性がある。1625億円の根拠は7日に始まる文部科学省の検証委員会でも議題となる。
JSCは昨年5月、基本設計を発表した。8万人収容で開閉式屋根を持つ新競技場は地上6階、地下2階の鉄骨造りで延べ床面積は約21万平方メートル。概算工事費は1625億円とした。
関係者によると、昨年1月から本格化した基本設計の作業で、設計会社側は概算工事費を約3000億円と試算した。
しかし、JSCは「国家プロジェクトだから予算は後で何とかなる」と取り合わなかった。
JSCは1625億円を「13年7月時点の単価。消費税5%」の条件で試算した。さらに実際には調達できないような資材単価を用いるなどして概算工事費を過少に見積もったという。
基本設計発表の半年前の13年末、財務省と文科省は総工費を1625億円とすることで合意しており、JSCはこの「上限」に合わせた可能性がある。ある文科省幹部は「文科省の担当者が上限内で収まるよう指示したのではないか」と指摘している。
今年2月、施工するゼネコンが総工費3000億円との見通しを示したことでJSCと文科省は総工費縮減の検討を重ね、下村博文文科相が6月29日、総工費2520億円と公表した。しかし、膨大な総工費に批判が集まり、政府は7月17日に計画を白紙撤回した。
JSCは「政府部内の調整を経た結果、13年12月27日に示された概算工事費を超えないよう基本設計を進めた。基本設計に記載した1625億円は、設計JV(共同企業体)側とも確認のうえ算出した」と文書で回答した。【山本浩資、三木陽介】
問題の議事録は2012年11月15日に開かれた第3回有識者会議のもので、毎日新聞は情報公開請求で入手した。会議は非公開で、新国立競技場のデザイン審査について、イラク出身で英国在住のザハ・ハディド氏の作品を1位に選んだことが報告された。
開示された文書では、審査委員長を務めた建築家の安藤忠雄氏が次点の作品を論評している部分や出席者名などが黒塗りになっていた。一方、新国立競技場計画の検証を進める自民党行政改革推進本部(河野太郎本部長)が4日、非公開部分を明らかにした文書を報道陣に公開した。
二つを比較すると、情報公開請求で開示された文書では、森喜朗元首相がデザインについて「神宮のところに宇宙から何かがおりてきた感じだ。ほんとうにマッチするのかな。次の入選作も、神宮の森にカキフライのフライのないカキか、生ガキがいるっていう感じ」と論評した部分が削除されていた。
安藤氏が次点の作品の方が実現性が高いと認めつつ「可能性に挑戦する、日本の技術者が向かっていく意味でいい」とザハ案を選んだ理由について述べた部分が黒塗りされていたことも分かった。
NPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は「二つの議事録は削除だけでなく、言い回しが異なる部分もあり別物。複数の議事録の存在は、当初開示された方が改変されていた可能性が高く、その行為は違法の疑いがある。何らかの意図で発言を削除したと考えざるを得ない」と指摘した。【山本浩資】
文科省によれば、増加分は建設主体である日本スポーツ振興センター(JSC)が建設や工事など専門知識を必要とする業務の助言などを受けるため、山下設計など3社の共同体と結んだ発注者支援業務。13年度から15年度の3年間で計5億6200万円の契約を結び、うち今年度の前払い金8200万円を含む3億7100万円が支払い済みで大部分が無駄になるが、JSCは「この知見は生かされる」としている。
JSCは先月21日、民主党の「東京オリンピック・パラリンピックに係る公共事業再検討本部」でデザインや設計などで結んだ契約が約59億円で、その大部分が無駄な支出となるとの見解を示した。今回指摘された契約分を含めなかった理由について、下村氏は「民主党からの資料要求がデザイン、設計、施工に関わるものであったため」と話した。
松沢氏は「62億円もの金を捨て金にした。あなたが責任を取らない限り、この大失態のけじめはつかない」と下村氏に辞任を迫った。これに対して下村氏は「責任について(の指摘は)謙虚に受け止めるが、意見は相いれない。最終的に安倍晋三首相がゼロから見直しするのは大英断」と強調。自らの責任については7日に初会合を開く有識者による検証委員会の判断に委ねる考えを示した。【田原和宏】
同病院では、医師11人が、実際には治療に関わっていない患者を診察したと偽るなどして資格を不正に取得。指導医を含む医師23人が資格を取り消され、申請中だった医師3人も不正を指摘された。関与した26人のうち、既に退職した11人を除く15人が懲戒処分の対象で、資格申請者を指導した准教授2人が休職3か月、指導医だった講師や資格を不正取得した助教ら計9人が休職2か月など。山口教授は直接関与しなかったが、監督責任を問われた。
販売は先着順で、従業員自身が働く店での購入は禁じられていた。市は同様のケースがないか調査する。
市によると、匿名の情報提供で発覚。同店は1500冊の販売を委託されており、午前10時の販売開始から約50分後、1450冊を売った時点で「完売」とした。並んでいた約20人が購入できなかった。市は店側に未使用の37冊を返還させ、一部使うなどした13冊のプレミアム相当額の2万6000円の返還を求める。
同法の贈賄罪に問われた電気設備会社「カナデン」元課長・三枝裕祐被告(47)は、懲役10月、執行猶予3年(同・懲役10月)とした。戸苅左近裁判官は「JR貨物の職務の公正と信頼が大きく損なわれた」と述べた。
判決によると、富永被告は、JR貨物発注の照明設備改修工事などでカナデンが照明機器などを納入できるよう便宜を図った見返りに、2012~14年に7回にわたり、三枝被告から風俗店で計約43万円相当の接待を受けた。判決は「遊興接待が常態化していた」と指摘したが、金額が多額とは言えないとして執行猶予とした。
同社は5月に発表した1~3月期決算で140億円を損失計上していたが、建物の所有者への補償や代替品の生産費用が膨らむ見通しとなった。近く、業績予想を下方修正する。最終的な費用は500億円規模に膨らむ可能性もある。
東洋ゴムは、問題の免震ゴムが使われている全国154棟のすべてを交換するとしている。5月時点では、交換作業だけで少なくとも140億円かかると見込んでいた。
内閣府が7月に公表した試算は、景気回復に伴う税収増を見込み、2020年度の基礎的財政収支の赤字が従来の9・4兆円から6・2兆円に縮小した。これについて、ある委員は「景気が良くなれば(財政が)改善するという楽観論が広がる恐れがある」と指摘し、経済成長だけで財政再建を進められるという考え方に警鐘を鳴らした。
また、「ギリシャは、市場から強制される形で歳出改革を行う。最悪の事態になる前に、財政再建の手を打たなければならない」という意見も出た。
整備計画再検討中の新国立競技場については、「五輪で終わるものではない。50年、70年残る物にしたい。(建設費については)2000億円を超えないというのもあるし、当初の1300億円というのもある」と述べた。
プラグの異常時に発生する破裂音が離陸後に聞こえたとの情報が複数ある。事故機が飛行場の指定場所でエンジンの点検を行っていなかったことも判明。運輸安全委員会などは、離陸前の点検不備が事故につながった可能性もあるとみて調べている。
調布飛行場には、離陸前の航空機がエンジンの作動を確認するための指定場所が、滑走開始ポイントのすぐ手前にある。
事故が起きた7月26日に事故機より先に滑走路に向かった別の小型機の乗員(66)によると、事故機から飛行場側に「エンジンチェックは終わった。駐機場から滑走開始ポイントに直接行かせて」と無線通信があり、小型機を追い抜いて離陸したという。この乗員は、「通常、エンジンチェックは駐機場ではやらない」と指摘する。
警視庁は、同社が同月以降、顧客から集めた現金を別の顧客への返金に回さざるを得ない「自転車操業」状態に陥っていたとみている。
捜査関係者によると、同社社長のマルク・カルプレス容疑者(30)(私電磁的記録不正作出・同供用容疑で逮捕)は11年3月に取引サイトの運営を開始し、顧客から現金を集め、BTC取引を仲介することで手数料収入を得ていた。
運営開始以来、同社の事業は拡大し、民間信用調査会社によると、流動資産は、13年3月には約38億円に達していた。ところが、同庁がマウント社の会計書類や銀行の取引記録などを調べたところ、13年8月には債務超過に陥り、全顧客から預託金の返金を求められた場合、返金に充てる資産が足りない状態になっていたことがわかった。
捜査関係者によると、小型機には座席が3列あった。操縦席のある最前列には、機長の川村さんが1人で座り操縦していたとみられる。操縦席は最前列に二つあり、川村さんはメインの操縦席とされる左側に座っていた可能性が高いという。
一方、同乗者4人は向かい合わせとなっている2、3列目に2人ずつ座っていたとみられる。現場の状況などから、死亡した全日空社員、早川充さん(36)=東京都練馬区=は2列目に座っていた可能性が高く、逃げ遅れて焼死したらしい。
小型機は左翼側から墜落し、左の燃料タンクから火が出て住宅に燃え広がった可能性があるという。【山崎征克、神保圭作】
墜落した小型機の川村泰史機長は飛行目的について、技量を維持するための「慣熟飛行」と届けていたが、同乗者の4人は操縦免許を持っておらず、実質的には「遊覧飛行」だったとの指摘もある。
墜落した小型機を川村機長に貸していた日本エアロテックは「事業として遊覧飛行を行ったことはない」としているが、墜落した小型機に乗った人物が取材に応じ、「日本エアロテックに料金を支払い、遊覧飛行をしたことがある」と証言した。
墜落機に乗った人「平成19年ですから、8年くらい前の1月に(埼玉・桶川市のホンダエアポートから)中部国際空港へ、同じ年の4月に(ホンダエアポートから)仙台空港に遊覧をお願いしました。事故の起きた飛行機に乗って、(今回の)ニュースをみてびっくりした」
記者「パイロットはどういう方?」
墜落機に乗った人「普通に運航して遊覧目的のチャーターをしているふうに感じました」
記者「金額はいくらくらい?」
墜落機に乗った人「請求書の金額が、日本エアロテック社の運航部門の方へ、口座の方へ私が24万5830円を(振り込んだ)。(日本エアロテックは)遊覧飛行はしてないというコメントをテレビで私も聞いていましたが、(今回も)遊覧だったのではないかと思った」
川村機長は日本エアロテックの元社員で、独立後も日本エアロテックの小型機を頻繁に利用していた。警視庁などは、今回の飛行目的や同乗者4人の搭乗の経緯なども調べている。
市街地にある調布飛行場は、騒音を軽減するため管理者の東京都と調布市など周辺自治体が遊覧や訓練飛行を禁止する覚書を交わしている。このため自家用機の飛行は公目的の飛行や整備・慣熟飛行などに限られている。
小山社長は「遊覧飛行は調布ではできない。そういう話は一切ない」と話した。
小山社長によると、同乗していた4人のうち、重傷を負った男性(51)が川村泰史機長(36)と知り合いで、他の同乗者3人はいずれもこの男性の知人という。男性は小山社長に「慣熟飛行の時に一緒に飛べる」と話していたという。
川村機長は小型機をエ社から借りて飛行していた。【宮崎隆】
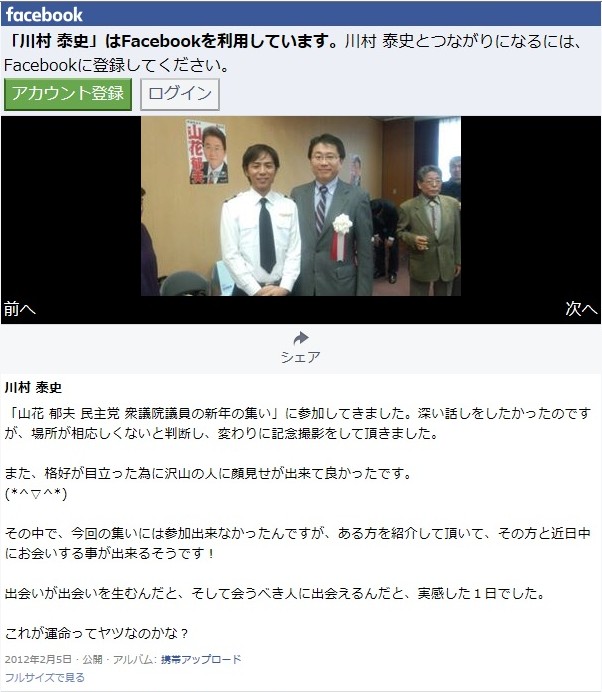
「川村 泰史」(Facebook)
小型機は米パイパー社製の単発プロペラ機「PA−46−350P型(マリブ・ミラージュ)」。同社が同型機の操縦者や所有者向けに発行している操縦マニュアルによると、離陸可能な最大重量は機体を含め1950キロ。標準装備の機体は1245キロであることから、搭載が可能な人や荷物、燃料の総量は計算上、705キロとなる。
一方、マニュアルによると、最大重量に達している同型機が適切な速度で滑走した場合、気象条件が「無風」で「気温34度」なら、安全な飛行のために約960メートルの滑走が必要とされている。調布飛行場の滑走路の全長は約800メートルで約160メートル短い。事故当時の飛行場周辺はほぼ無風で、気温は34度だった。
マニュアルは、機体性能や操作の方法などを詳細に記載しており、米連邦航空局(FAA)が承認している。国内での同型機の飛行もこのマニュアルに基づいて認められている。
マニュアルなどによると、満タンにした時の同型機の燃料は約360キロで、約6時間20分の飛行が可能とされている。小型機を管理していた日本エアロテックによると、小型機は事故4日前に約40分間飛行したが、この飛行前に燃料を満タンにしており、大部分は残っていたとみられる。小型機の定員は6人で、事故時は5人の成人男性が搭乗していた。こうしたことから、事故当時はほぼ最大重量に近い状態だったと推定される。
元日本航空機長で航空評論家の小林宏之さんによると、操縦マニュアルで必要だと指示されている滑走距離は、実際に必要な滑走距離より15%程度長いのが通常という。それを当てはめた場合でも最大重量で離陸するには835メートルが必要で、調布飛行場の滑走路では足りないことになる。小林さんは「事故は重量が一因になったとみられる。離陸前に重量を計算したのか疑問だ。調布飛行場の短い滑走路や当時の気象条件を考慮して、重量を減らすべきだった」と指摘している。
免震ゴムの認定審査や製品の出荷時に、国が指定する性能評価機関が、工場への立ち入り検査や抜き打ちのサンプル調査を行うことが柱。従来の書面審査では性能データの改ざんを見抜けなかったためで、29日に開かれる有識者委員会の意見を踏まえて正式に決定する。
また、不正を行ったメーカーに対しては、立ち入り検査回数を増やし、同省も重点的にチェックする。
同社は、154棟に納入した約2900基の交換に応じるとするが、同省はこのうち約2000基の高機能型について「性能値が著しく低かった」として、同社には交換用製品の製造を認めない方針で、他社製品への交換となる。残る約900基は、他社製品だと工事が長期化する恐れもあるため、同社による製造の可否を慎重に検討している。
事故機は、調布飛行場から伊豆大島まで約1時間の飛行を予定していたが、亡くなった川村泰史機長(36)は飛行計画書に「5時間分の燃料を積載」と記していた。
「事故機そのものの重量は1200キロで、片道分の5倍量、300キロ近い燃料を積み、さらに川村機長を含む成人男性5人と荷物が乗っていた。総重量は、離陸可能な1950キロギリギリだったとみられています」(国交省関係者)
それでなくても、単発機のエンジンは、気温が35度前後になると出力が下がるとされる。事故発生時は34度。加えて、当時は風も弱かった。事故機は調布飛行場の滑走路(800メートル)を目いっぱい使い、何とか離陸していたという。重量の影響で高度を上げられず、失速、墜落した可能性は否定できない。
「パイロットの技量にもよりますが、上限ギリギリの重量で飛ぶこと自体は、珍しい話ではありません。ただ、一般的には少しでも機体を軽くしようと考えますし、往復で2時間のフライトなら、3時間分の燃料で十分でしょう。なぜ、5時間分だったのか。往復する以外の“目的”があったのかもしれませんが、機長の判断ですから、何とも言えません」(航空評論家・青木謙知氏)
都営の調布飛行場は経費削減で06年から管制官がおらず、安全確認はパイロット任せだった。
事故機の管理を委託されていた日本エアロテックによると、川村機長の総飛行時間は「600~700時間」というが、本人は国交省に「1500時間」と申告していたという。それも謎だ。
「600~700時間なら“ひよっこ”、1500時間でようやく中堅です。いずれにせよ、ベテランとは言い難い。技量に問題はなくても、経験で判断力に差が出ることは確かです」(青木謙知氏)
川村機長は事故当日、予定していた小型機から訓練用の小型機に機体を変更していたが、それも理由は不明。飛行目的もパイロットが技能を維持するための「慣熟飛行」と届け出ていたが、調布飛行場では禁じられている「遊覧飛行」だった疑惑も残っている。エアロ社の小山純二社長は遊覧目的を否定していたが、搭乗者4人のうち1人は川村機長とも小山社長とも面識があった。
「“黙認”していた可能性はあるし、4人が搭乗した経緯も、はっきりしないところがある。小山社長は『機体のトラブルはない』と言いますが、それは今後の調査次第でしょう。舛添要一都知事は『調査をみて、安全対策を徹底したい』などと他人事のように語っていましたが、どうも寄ってたかって川村機長ひとりを悪者にしようとしているフシがあります」(前出の国交省関係者)
事故機には、フライトレコーダーが搭載されていなかった。事故の全容解明のカギを握るのは、負傷した3人の搭乗者の“証言”だ。早期回復が待たれる。
「墜落した小型飛行機の回収作業が行われています。いくつかに分けてトラックに運び出そうとしています」(記者)
クレーン車でつり上げられる事故機のエンジン。
今月26日、調布市の住宅に小型の飛行機が墜落、機長の川村泰史さん(36)と同乗していた全日空社員・早川充さん(36)、鈴木希望さん(34)とみられる3人が死亡し、5人が重軽傷を負いました。
29日、現場から事故機のエンジンや尾翼などが回収されましたが、新たな事実が明らかに。2004年、札幌市の丘珠空港で小型機は着陸に失敗する事故を起こしていましたが、この時、エンジンが損傷し、修理に出されていたことが分かりました。小型機は事故の翌年、国の検査に合格していましたが、エンジンは交換されず、修理されたものが使われ続けていたといいます。国の運輸安全委員会はこの損傷と今回の事故との関連を調べる方針です。
一方、自宅の二階にいて、事故に巻き込まれた鈴木さん。去年の秋まで東京都内のペットショップに店長として勤務していました。
「犬が幸せであればいいと、そういう人だった。鈴木さんはとにかく、この子(犬)らは逃がしてやらないと死ぬだろうということで必死になったんだろう、精いっぱいだったんだろうと思う」(元勤務先の同僚)
警視庁などは回収したエンジンなどを分析し、事故の原因について詳しく調べる方針です。
一方、警視庁は同日、墜落現場からエンジンや尾翼部分などを回収。エンジンの状況について詳しく分析する。
国交省によると、小型機は04年10月27日に札幌で着陸に失敗。エンジンを搭載する機首部分を損傷した。
小型機を管理している日本エアロテック(調布市)は、このときのエンジンへの対応について「メーカーなどが経緯や損傷状況を綿密に精査して修理点検を完了した。日米の監督官庁も承認した」と説明している。
自動車の車検にあたる耐空証明検査にも毎年合格しているといい、同省航空機安全課は「問題がないことを確認している」と話している。
小型機は今回の事故前、離陸のための滑走距離が通常より長かったほか、離陸後に機体を揺らしながら本来のルートから左に大きく外れたとされる。業務上過失致死傷容疑で調べている警視庁調布署捜査本部は、何らかの理由でエンジンの出力が低下し、十分な速度が出ていなかった可能性があるとみている。
国土交通省などによると、事故機のような小型機は、離陸前にエンジンを最大出力に近い状態にし、エンジンの調子を点検する試運転「エンジン・ランナップ」をすることが、メーカーのマニュアルで定められている。
飛行場関係者の説明では、小型機を操縦していたとみられる機長の川村泰史さん(36)=川崎市=は、駐機場から試運転の指定場所を通って滑走路に行く間に、調布飛行場職員との交信で「エンジン・ランナップ・コンプリート(試運転完了)」と伝えた。だが、指定場所では試運転することなく素通りし、そのまま滑走路に進んで離陸したのを飛行場関係者が目撃した。小型機が指定場所以外で試運転をしたかはわかっていない。
事故機は定員6人の小型機「PA46−350P型」。04年10月、別の機長の操縦で札幌市の丘珠(おかだま)空港に着陸する際、いったん接地したあと、バランスを崩したため着陸をやり直そうとして失敗し、滑走路脇の草地に前のめりになる形で止まった。
プロペラが大きく変形したほかエンジン部分に近いエンジンマウントや防火壁も破損、変形した。今回の墜落事故後、国土交通省が事故機の管理会社「日本エアロテック」に確認すると、破損、変形した部品は交換していたが、エンジンそのものは交換せず修理したことが判明。修理後の05年6月、車検に相当する国の年1回の「耐空証明検査」に合格して飛行を再開。その後も毎年、検査に合格していた。
国交省によると、事故機が積んでいた種類のエンジンは使用時間が2000時間に達すると、分解して整備しなければならない。事故機は今年5月1日に耐空証明検査を受けたが、その際のエンジン使用時間は983時間で、比較的余裕がある状態だったという。
事故機はフライトレコーダーなどを搭載していないため、運輸安全委は今後日本エアロテックの担当者から整備状況を聞き取り、整備記録を精査して、機体に不備はなかったかを調べる。【松本惇、坂口雄亮】
◇機体の大半押収
警視庁調布署捜査本部は29日、墜落現場から小型飛行機の尾翼やエンジンなど、機体の大部分を押収した。今後、国の運輸安全委員会とともに分析し、墜落原因の解明につながる痕跡が残っていないか調べる。【山崎征克】
◇運航停止を要請 小金井市
小型機墜落事故で東京都小金井市の稲葉孝彦市長は29日、都庁を訪れ、自家用機の運航停止を視野に入れた対応などを求める要請書を提出した。同市は調布飛行場の北側に位置している。これまでに調布、三鷹、府中の地元3市が都に要請書を出している。【青木英一】
◇「点検問題ない」エアロテック社
日本エアロテックの小山純二社長は04年の事故後の保守点検について「航空機製造会社の定める点検方式に従って、整備作業を実施し、当社の整備士資格保有者がその作業の実効性を確認し、問題点はなかった」とのコメントを出した。
事故機は、単発プロペラ機「PA46-350P型」(通称マリブ・ミラージュ)で、1989年に製造された。2004年10月、札幌市の丘珠(おかだま)空港で着陸に失敗して機首部分から接地する事故を起こし、修理後の05年には、自衛隊機に異常接近するトラブルが問題となった。
いわくつきの機体だったわけだが、さらに不透明なのは、事故機をめぐる複数の会社だ。機体を所有するのは、不動産関連会社「ベル・ハンド・クラブ」(東京都福生市)で、整備・管理するのは「日本エアロテック」(調布市)。そして、事故機を操縦し、死亡した川村泰史(たいし)機長(36)のパイロット養成会社「シップ・アビエーション」(同)にリースしていたという。3社は28日に家宅捜索を受けた。
ベル社を知る関係者は「3つの会社は一体。ベル社の創業者と、エアロ社の小山純二社長は親族関係にあるようで、川村機長も、エアロ社の社員のようなもの。ベル社をトップとするグループ会社だ」と明かす。
民間調査機関などによると、ベル社は会員制レジャークラブとして1983年に設立された。富裕層向けに航空機、小型船舶、ロールス・ロイスなどの高級外車をリースし、バブルの最盛期には1000人以上の会員を獲得。個人会員600万円、法人会員1200万円と高額な入会金で数億円規模の年商を誇ったが、業績は次第に悪化し、2009年に東京地裁で民事再生計画が許可された。
ベル社の経営状態を知る関係者は、「数年前には、格納庫の地代を滞納したり、燃料代金の未払いもあったようだ。エアロ社の前社長時代は整備もしっかりやっていたが、前社長が約5年前に亡くなると、資金難もあり、整備がずさんになった。とくに事故機は、仲間内では『絶対に乗ってはいけない機体』といわれていた」と話す。
そんな中、調布飛行場で禁止されている「遊覧飛行」が常態化していた疑いも浮上している。利用客の一人は「8年ほど前に、ベル社所有の6人乗りの機体で伊豆大島に向かったが、そのときのフライトでは7万円を支払った。会員か、会員勧誘のために乗せるケースもあったようだが、いずれにせよ営業目的だったはずだ」と語る。
警視庁は、機体に何らかのトラブルが起きた疑いがあるとみて、業務上過失致死傷容疑で捜査を進めている。「起きるべくして起きた」(前出の関係者)という今回の事故。原因究明が待たれる。
声明によると、建設費高騰の原因は円安などに伴う資材価格の上昇や施工業者の選定プロセスにあるとし、「十分な競争がなく業者を選ぶことで見積もりが増えた」などと主張。1000億円近い費用がかかるとされた屋根を支える巨大アーチについては、標準的な橋の建設技術で230億円で完成できるとし、「デザイン変更を含めたコスト削減を提言したが認められなかった」と言及した。
また、安倍首相に対し、計画見直しをサポートする準備があることを表明した書簡を送ったことも明らかにした。
事務所は、事業主体である日本スポーツ振興センター(JSC)の姿勢を批判。「低価格な競技場を提案する用意もあったが、JSCから要請はなかった。十分な競争がない中で建設会社を選ぶことは過大な見積もりを招くと警告していたが、聞き入れられなかった」とした。
計画見直しで新しいデザインを選べば、質が悪くなるうえ、建設費も高くなるリスクがあるとし、安倍晋三首相に対し、有効な提案をする準備があると書簡を送ったことも明かした。(ロンドン=河野正樹、渡辺志帆)
京都府が、ソルドに支給した事業委託費のうち約500万円について、使途が不適切として返還請求していることも判明した。
ソルドは2009年、孤立しがちな希少難病患者の支援を目的に発足。元学習塾経営の男性(45)が代表となり、全身の筋力が衰える難病「遠位型ミオパチー」の患者女性(38)が副代表を務めた。
11年7月には、難病患者をつなぐSNS「Re:me(リミィ)」を開設。今年3月時点で、約200疾患の患者約500人が登録していた。治療などに関する情報を交換し、研究者に患者を紹介する役割も果たしていたという。
東証1部上場の東芝株については、上場を維持した上で、管理体制に問題があることを投資家に知らせる「特設注意市場銘柄」に指定する見通しも示した。
東芝は2003年に「委員会等設置会社」(現在は指名委員会等設置会社)に移行し、社外取締役が過半数を占める「監査委員会」などを設置した。清田氏は「形式は整っていたが、社外取締役に十分な情報を流さなかった」と指摘した。
一方、今年初めに国土交通省に提出した資料では自己申告で1500時間としていた。国交省は「中堅だ」とみている。
川村さんは小型機の操縦士を養成するスクールを経営。平成25年には関西空港で子供を対象にしたセミナーで講師も務めていた。
その際のプロフィルによると、両親ともに航空会社に勤務し、幼いころから航空機に親しみを持っていたという。米国や日本での訓練を受け操縦士の資格を取得。日本エアロテックに入社した後、独立し25年4月にスクールを設立した。独立後も日本エアロテックの整備機体を扱うなどかかわりがあった。調布飛行場を拠点とし操縦技術の普及などに力を入れていたとされる。
日本エアロテックの小山純二社長によると、操縦技術を他人に教えることができる国の資格試験を一回で合格するなど、努力家だったという。
小山社長は「一度乗せてもらったが、安心して任せられる技術があった」とする。この日の飛行前もいつもと変わりはなく、「気をつけて」と声をかけた小山社長に「いってきます」と話していたという。
「川村機長は会社のホームページで『関連役所等の理解が得られず、許可を受けるに至っておりません』としたうえで、訓練は航空機使用事業ではなく、『クラブ運営方式』だと主張しています。」
国土交通省によりますと、航空法の規定では、パイロット養成事業を経営するためには国土交通大臣から「航空機使用事業」の許可を受けることが必要となっています。
この事故で死亡したとみられる川村泰史機長(36)は「シップ・アビエーション」というパイロットを養成する会社を経営していましたが、その後の国交省への取材で川村機長が訓練の指導に必要な「操縦教育証明」の免許は取得していたものの、「航空機使用事業」の許可を国から受けていなかったことがわかりました。
川村機長は会社のホームページで「関連役所等の理解が得られず、許可を受けるに至っておりません」としたうえで、訓練は航空機使用事業ではなく、「クラブ運営方式」だと主張しています。
東京都に提出された飛行計画では、操縦士の技能の維持が目的の「慣熟飛行」と記されていました。しかし、専門家はこう指摘します。
「(慣熟飛行に5人も乗っていたことは)ちょっと疑問を感じる。慣れるためだったらパイロットだけで慣熟飛行すべき」(航空評論家 小林宏之さん)
死亡したとみられる機長の川村さんの関係者は、今回のフライトは、けがをした一部の搭乗者が希望したもので、関係者と共に東京の伊豆大島を日帰りで往復する事実上の遊覧飛行だった可能性があると話しています。フライトを希望した搭乗者は、機長の川村さんや機体の管理・整備を請け負う日本エアロテックの小山純二社長と以前から仕事上の付き合いがあり、川村さんの関係者の説明では、フライトの打診を受けた川村さんは、当初、「都合が悪い」と一旦断りましたが、小山社長からも依頼されたため、断り切れず、飛行目的は「慣熟飛行」と記載をして飛行することになったということです。
これに対し、日本エアロテックは・・・
「遊覧飛行ではございません。慣熟飛行と認識しています」(日本エアロテック 小山純二社長)
今回の飛行が遊覧飛行であることを否定、「慣熟飛行」であると強調しました。しかし、国交省の幹部はこんな疑問を示しています。
「慣熟飛行にライセンスを持っていない人が搭乗している理由がよくわからない。飛行場の管理事務所は本当に遊覧飛行だと思わなかったのか」(国土交通省 航空局幹部)
さらに、調布飛行場を管理する東京都の舛添知事も、実態を調べる必要があると述べました。
「実際に訓練のための慣熟飛行という届け出でありながら、そうじゃない遊覧飛行であったとするならば、届け出様式などさまざまな問題が出てくるので、それは改善しないといけない」(東京都 舛添要一知事)
調布飛行場では遊覧飛行は禁止されていて、国の運輸安全委員会は搭乗者の関係や飛行目的などを詳しく調べることにしています。
国土交通省への取材で判明。事故時の飛行目的はパイロット免許を持つ人が技能を維持するための「慣熟飛行」だったが、川村さんのほかに4人が同乗していた理由は分かっていない。
都によると、慣熟飛行ではパイロットを目指す人の同乗も許される。運輸安全委員会が飛行目的などと併せ、経緯の調査を進めている。
航空法の規定では、パイロット養成事業を経営するには、国交相から「航空機使用事業」の許可を受けることが必要。
国交省によると、川村機長は訓練の指導に必要な「操縦教育証明」の免許は取得済。自身が社長を務めるシップ・アビエーション(調布市)のホームページで、自家用操縦士コースの場合、訓練期間は約5カ月で費用は約324万円などと紹介している。
その一方で「関連役所等の理解が得られず、許可を受けるに至っておりません」とし、訓練はパイロットを養成する航空機使用事業ではないとも主張。燃料代などの必要経費だけを負担する会員制の「クラブ運営方式」だと主張している。
国交省は同社の事業の実情について「詳細は不明」としている。航空法は、許可なく航空機使用事業を営んだ場合、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、または両方を科すとする罰則を定めている。関係者は「過去には許可なく航空機使用事業をしていたことによる行政指導をしたこともあるが、最近、会社組織で行っているケースは聞いたことがない」と話している。
同省や都によると、調布飛行場では離着陸の回数は制限されている。遊覧飛行は許されていない。川村機長の飛行時間は約1500時間だった。
会見は東京・調布市にある「日本エアロテック」の本社で行われ、冒頭に小山純二社長は「いろいろな方にご迷惑をかけ、深くおわび申し上げます」と謝罪のことばを述べました。そのうえで、今回のフライトの目的について、「パイロットが技能を維持するための『慣熟飛行』だった。重要なのは着陸を経験することで、目的地だった伊豆大島で着陸すれば往復で2回経験できる」と述べました。
一方で、小山社長は、調布飛行場で禁止されている遊覧飛行だったのではないかという質問に対し「あくまで川村泰史機長との契約で機体を貸しただけなので、目的地での予定は把握していない。ただ、現地に着いてお昼になれば食事もするし、いい景色があれば写真を撮ることもあると思う」としています。
「慣熟飛行」では料金を取って乗客を乗せることはできませんが、ほかの人を同乗させることは禁止されていないということです。
しかし、会社は会見で今回の同乗者について「1人は仕事上の関係で知っている人だが、同乗者がどういう目的で参加したのかは特に聞いていない」などと話しています。
「慣熟飛行」とは
「慣熟飛行」は、航空法上定められたものではなく、操縦技能の維持や、新しい路線に慣れるための飛行で、慣習的に使われていることばです。
東京都によりますと、「慣熟飛行」とはパイロットの操縦技能を維持するために行われるもので、パイロット資格の取得を目指す人が操縦を見学するために同乗することも含まれるとしています。
一方、国土交通省は「慣熟飛行」は、航空法で定められたことばではないとしています。そのうえで、一般論として旅客機を運航する航空会社で、新しい路線を開いた際にパイロットが訓練したり、パイロットが経験したことのない路線を操縦する際に訓練したりすることに「慣熟飛行」ということばが使われることがあるとしています。
慣熟飛行 都は書面のみで確認
東京都が管理する調布飛行場は、主に伊豆諸島を結ぶ定期便や測量や撮影などのための航空機に利用されています。住宅地に近いことなどから地元の自治体と安全対策を協議した結果、遊覧飛行や体験飛行などは禁止されていて今回、事故を起こした小型機のような自家用機については、パイロットの操縦技能を維持するための「慣熟飛行」しか認められていません。
飛行場にある管理事務所では、自家用機が飛行場を利用する際は、その目的を確認するため、機長から事前に飛行目的や搭乗者の氏名などを記した「空港使用届出書」の提出を受け、書面上で確認を行っています。都によりますと今回、事故を起こした小型機も管理事務所に対し、慣熟飛行が目的だとする届出書を提出していたということです。
一方、都によりますと慣熟飛行は、機長以外にも操縦免許の取得を目指す人が同乗して見学することも可能になっていますが、実際に同乗者に目的を確認することはないということです。
保管方法は大阪府警と協議してマニュアル化した。現在、4病院が協力しており、府はさらに増やす方針。証拠物の採取と保管には金銭負担は発生しない。」
被害に遭った直後は警察への相談をためらう人が多い実情を踏まえた試み。証拠物を警察以外で管理する制度を整えた自治体は全国初。
府内の協力病院を被害者が受診した場合、警察には届けない意思を本人が示していても、同意を得て体液や毛髪を採取し、阪南中央病院(大阪府松原市)にあるNPO法人「性暴力救援センター・大阪」(通称SACHICO)が一括保管する。後で被害者が告訴などを希望した時、証拠物として警察に提出できる。
保管方法は大阪府警と協議してマニュアル化した。現在、4病院が協力しており、府はさらに増やす方針。証拠物の採取と保管には金銭負担は発生しない。
精神疾患の疑いがある生活保護受給者に受診を促す自治体の事業で、東京都内の医療グループによる患者の不当な「囲い込み」があったとして、支援団体が24日、厚生労働省に監査を求めた。生活保護の支援員を務める精神科医院のスタッフが自分の勤務先への通院を勧めていたと指摘。通院が生活保護費受給の条件という虚偽の説明をしていた例もあったとしている。
監査を求めたのは弁護士らでつくる「医療扶助・人権ネットワーク」。自治体によっては、生活保護の窓口に精神保健福祉士や看護師らを支援員として置き、精神疾患の疑いがあれば自立に向けて受診を促す。東京都によると、23区のうち21区が支援員を配置している。
24日に記者会見した同ネットワークによると、大田区と江戸川区は都内に4医院を持つ医療グループと委託契約を結び、計7人のスタッフを支援員として配置。スタッフが自分の勤務先への通院が生活保護費受給の条件だと誤解を招く説明をしていた例があったという。医療グループ側の紹介で劣悪な環境の部屋に住み、同意の手続きが不透明なまま生活保護費を管理される患者もあったとする。
告発は7日付。事務所の内部調査では、2件の文書偽造容疑のほか、複数の案件が放置されていたことも明らかになったというが、同会は事務所の所在地や元職員の性別、年代などについて、「捜査への支障の可能性」を理由に明らかにしなかった。
同会が所属弁護士や職員の違法行為について告発するのは初めてという。記者会見した同会の竹本真紀まさき会長らの説明によると、元職員は2007年1月と09年3月に事務所が受任した破産手続きについて、裁判所に申し立てをしていなかったことを隠すため、それぞれ13年1月頃と14年2月頃、本来は裁判所が作成する「免責許可決定書」を偽造して依頼者らに渡した疑いが持たれている。別の依頼者への決定書の名前欄に今回の依頼者の名前を記載した紙を貼ってコピーするなどし、真正な決定書を装ったという。
文書偽造の疑いが発覚したのは今年3月中旬。この2件とは別の破産手続きについて、債権者側から事務所に問い合わせがあり、所属弁護士が元職員に確認したところ、2件の文書偽造のほか、複数の案件を放置していたことを認めたという。その後、事務所から同会に報告があり、同会でも元職員に事情を聞くなどして調査を進めていた。
元職員は6月に事務所を退職し、同会には事実関係を認めた上で、「依頼者から問い合わせを受けるたび、『まだ手続き中』と回答していた」などとする陳述書を提出したという。同会から裁判所側に事実関係を説明したほか、事務所からも各依頼者らに謝罪したとしている。
竹本会長は会見で、「二度とあってはならないこと。各会員に注意喚起し、再発防止に努めたい」とコメントした。ただ、「捜査を依頼している立場として、説明は謙抑的にならざるを得ない」とも述べた。事務所の弁護士に対する弁護士会としての懲戒処分の有無については明言を避けた。
「人文社会科学には、独自の役割に加えて、自然科学との連携によって課題解決に向かうという役割が託されている」と主張している。
18歳人口の減少などを見据え、文科省は6月8日、「組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に取り組むよう努める」などとする通知を各大学に出した。これに対し同会議は、人材育成には、文化歴史の知識や批判的思考力が欠かせないとし、人文社会科学の軽視は、「大学教育全体を底の浅いものにしかねない」と危惧を示した。
大西隆会長(豊橋技術科学大学長)は記者会見で、「根拠がはっきりしないまま人文社会科学系や教員養成系のみを再編対象として名指しするのは理不尽だ」と、文科省通知を批判した。
教室は6月に閉鎖されたが、同法人を所管する県は、学校教育法違反の疑いもあるとみて、23日に学園に事情を聞く方針だ。
県学事課によると、学園は1990年1月に同校の設置認可を得た。認可されたのは1学年80人定員の介護福祉科(2年制)のみで、設置場所は松戸市秋山の1か所となっている。
しかし、学園によると、同科の学生も思うように集まらず、2013年4月、留学生向けの「国際ビジネス経営コース」を開設した。同コースは松戸市の本校のほかに、新宿区のビルに無認可で教室を構えた。
2014年末で契約期間を終えたものは支払いが確定しており、今年分についても業務内容に応じて多くが支払われる見込みという。
JSCが民主党の会合に提出した資料によると、英国在住の女性建築家、ザハ・ハディド氏の事務所に対してはデザイン監修料として約14億7000万円の契約を締結。このうち15年度の1億7000万円分の支払いについては今後、調整する。ハディド氏から損害賠償を求められる可能性もあり、JSCの鬼沢佳弘理事は「契約破棄について、近くハディド氏側と面談して交渉したい」と話した。
第三者委の報告書によると、東芝は2008年4月から14年12月までにわたって、社内の全事業で税引き前利益で総額1518億円の利益水増しをしていた。経営トップの判断が影響したとも認定した。
東芝の歴代トップ辞任は、これを受けて決まった。不正が始まった当時の社長で、事業の「選択と集中」を進めて名経営者と呼ばれた西田厚聡氏(71)も相談役を退いた。
不正に関わったとして辞任した取締役は社長や4人の副社長を含む8人となり、全取締役16人の半数に達した。暫定的に室町正志会長(65)が社長を兼ね、新経営陣は8月中旬までに決めて9月の臨時株主総会に諮る。
問題を調べた第三者委の報告書全文も、同日公表された。佐々木氏、田中氏らが事業部門に予算通りの利益を実現するよう強く求めたことが税引き前利益で総額1518億円の水増しという不正のきっかけになり、担当取締役らも一部を認識していたとした。
第三者委の上田広一委員長(元東京高検検事長)も同日会見し、一連の会計処理について「違法という意識がないまま行われたものもかなりあるが、会計用語としては不正会計だった」と指摘した。
今後、東京証券取引所は東芝株について、上場を維持しながら内部管理体制の改善を求める「特設注意市場銘柄」に指定する見通し。改善が見込めないと上場廃止となる。不正会計で株主や投資家の信頼を損なったとして、約9千万円の「上場契約違約金」も請求する方針だ。
また、日本公認会計士協会は、東芝の会計監査が適切だったかどうか調査を始めた。今後、担当した新日本監査法人への聞き取りをして、処分なども検討する方針だ。
■10秒以上深く頭下げる
東京・芝浦の東芝本社。会見場には報道記者や証券アナリストら約400人が詰めかけた。田中社長、室町会長、前田恵造専務が現れると、カメラのフラッシュが激しく浴びせられた。冒頭、田中社長が「かかる事態を起こしたことを厳粛に受け止め、すべての関係者に心よりおわび申し上げます」と述べ、壇上の3人は立ち上がって10秒以上深く頭を下げた。
一方、記者らの質問が不正を起こした背景に迫ると、田中社長はその度に「第三者委員会の報告書をご覧いただきたい」と繰り返した。
自身が不正を指示したかどうかについては「直接的な指示をしたという認識はない」と明確に否定。「部下にうそやごまかしを命じたか」という質問に、「ございません」と語気を強めた。西田相談役ら当時の経営トップから「圧力を受けていたか」という問いにも、斜め上を見上げながら一呼吸置き、「特にございません」とつぶやくように答えた。
■第三者委の指摘と東芝の説明は食い違う
【第三者委の報告書】 【東芝・田中社長】
「利益水増しは経営判断だった」→「指示した認識はない」
「利益目標は実現不可能だった」→「努力で可能なレベルだ」
「社長は問題を知り容認」 →(回答を避ける)
「社長の圧力が水増しの原因に」→「適正な会計処理が大前提だった」
JSCがこの日、民主党の「東京オリンピック・パラリンピックに係る公共事業再検討本部」に提出した資料によると、ハディド氏のデザイン監修が約14億7千万円。日建設計、梓設計、日本設計、アラップ設計共同体の設計業務が36億5千万円。施工予定業者で設計にも携わった大成建設、竹中工務店の技術協力が約7億9千万円。
ハディド氏との契約は17日の同本部の会合では17億円と説明していたが、21日は、13億円を支払い済みで、さらに今年度分1億7千万円のうち契約解除前の業務の報酬が必要なうえ、業務中止のための追加費用が発生すると説明。損害賠償を請求される可能性もあるとした。また設計業務については「若干残っている部分があれば返還をお願いする」、技術協力は「一部削る余地があるかも」としており、関係各社と協議する。
新国立競技場をめぐっては、文部科学省が当初想定の2倍近い2520億円で建設する計画を6月29日に発表。JSC有識者会議も今月7日に了承した。しかし建設費が膨らんだことに批判が集中したため、安倍晋三首相が17日に計画を白紙に戻すと表明した。デザインや設計業務の約59億円とは別に、有識者会議の了承を受けて9日に大成建設と契約したスタンド部分の工事約33億円分については、JSC幹部は「資材調達していなければキャンセルできるはず」としている。(阿久津篤史)
提言では「文部科学省は無能力・無責任で、これが最大の失敗の原因」と指摘。安倍晋三首相をトップに関係閣僚らによる「新国立競技場建設本部」を組織し、政治家のほか、中央官庁やゼネコンなど民間企業、アスリートらの作業委員会を立ち上げるべきだ、としている。
また、「失敗の第二の原因は、一部の政治家や関係者やゼネコンなどが密室で議論したことにある」とし、議論を公開して、国民を巻き込んでの合意形成が必要とした。
バッハ会長は五輪の競技場に求める条件について、「唯一の関心は選手と観客が使いやすい、最先端のスタジアムであること。デザインはあまり重要ではない」と語った。また、撤回の理由が建設費の高騰だったことについては「日本は妥当な金額で素晴らしい競技場を造ると確信している」と語り、5年後の五輪開催に問題はないという認識を示した。
東証の集計では、社外取締役を置く一部上場企業は六月末には前年同期より17・7ポイント上昇し92・0%に達する見通し。これまで社外取締役を置いていなかった企業でも、住友不動産が前経団連会長の米倉弘昌氏ら二人、鹿島はコマツ元社長の坂根正弘氏ら三人を社外取締役に選んだ。
企業が社外取締役を増やしているのは、法改正などへの対応を迫られたためだ。五月に施行された改正会社法は、資本金が五億円以上の大企業に対し社外取締役を置かない場合、株主総会などでその理由を説明するよう義務付けた。
さらに東証と金融庁は、六月から適用を始めた企業統治原則(コーポレートガバナンス・コード)で、企業と利害関係を持たない独立性が高い社外取締役を「少なくとも二名以上選任すべき」と定めた。経営の透明性を高め、企業の成長力を向上させるのが狙いだ。外国人投資家の間でも、社外取締役を選任しているかどうかを、企業を評価する基準の一つとする傾向が強まっている。
こうした動きを受け、今年の株主総会では三菱UFJフィナンシャル・グループや三菱ケミカルホールディングスなど、社外取締役による監督機能が強い「指名委員会等設置会社」に移行する企業も増えた。指名委員会等設置会社には、役員人事などを審議する「指名委員会」や役員報酬を決める「報酬委員会」など三つの委員会を設置し、委員の過半数を社外取締役が占めるようにすることも義務付けられている。
だが企業統治に詳しい専門家の間では「社外取締役を入れただけで企業価値が上がるとは誰も思わない」(野村証券の西山賢吾氏)との指摘も根強い。不適切な会計処理が見つかった東芝は指名委員会等設置会社。社外取締役も四人いるが、不祥事を防げなかった。大和総研の吉川英徳(ひでのり)氏は「社外取締役には株主の代理人としての期待が大きく、株主の利益につながる助言をすることが求められる」と話す。
同社幹部は「今回の問題が『意図的』と認定されるのは仕方がない。『粉飾』と批判されるのではないか」と不正会計を事実上認めており、経営責任は極めて重いとの認識が広がっている。
この問題を巡っては、田中社長が同社幹部らに対し、電話やメールで「何で予算を達成できないんだ」などと強く迫っていたことが判明。佐々木副会長も社長時代、過剰な業績改善要求を行っていた。こうした経営トップの姿勢が各事業部門での損失先送りや売り上げの前倒し計上などにつながったとみられ、両氏の辞任は避けられない情勢だ。
一方、取締役で監査委員長の久保氏は利益水増しを見過ごす形となった。久保氏は2014年6月まで財務担当の副社長を務めており、社内から「出身の財務部門は問題を知っていたはず」(関係者)との批判が上がっている。
利益水増しはインフラ関連に加え、半導体、パソコン、テレビの主要事業で行われていた疑いが強まっており、各部門を担当した歴代役員の責任も問われそう。西田相談役が社長だった09年3月期にもパソコン部品の取引で利益水増しなどの疑いが浮上。西田氏が会長時代、社長だった佐々木氏の経営手腕を批判したことで「利益至上主義」に拍車がかかったとの見方もあり、同社内では「相談役辞任はやむを得ない」「西田氏だけ無事とはならない」との指摘が出ている。
東芝では取締役16人のうち、社外は元外交官2人、企業経営者、大学教授の計4人。社外によるチェック機能も十分に働かなかったことから、新たに公認会計士など企業会計や法令順守の専門家を社外取締役に迎えることを検討している。
【岡大介、片平知宏】
「私も1300億円、どうかなと思っていた」
見直しが決まった英国在住の女性建築家ザハ・ハディド氏のデザインについて、国際デザインコンクール(コンペ)審査委員長だった建築家の安藤忠雄氏は16日の記者会見でそう話した。選考当時はデザイン重視でコスト面への意識が低かったことを認めたが、「私たちが任されたのはデザイン選定まで」と強調、責任はないとの主張に終始した。
デザインの決定を受けて計画の策定を進めてきたのは、文部科学省所管の独立行政法人「日本スポーツ振興センター(JSC)」だ。JSCの河野一郎理事長は今月7日、読売新聞の取材に対し、「文科省からハディド氏のデザインをもとに建設計画を進めるよう指示されていた」とし、JSCには計画を変更する権限がないと主張した。
政府内には「JSCが大規模施設の建設にかかわった経験は少なく、ゼネコンとの交渉など無理だ」という声もあった。特殊構造の「キールアーチ」に巨額の費用がかかるなどの理由で、今年春になって総工費は当初の1300億円から、3000億円を超えるまで膨れあがることが判明した。
下村文科相は、東京都と費用負担をめぐる協議に乗り出したが、舛添要一都知事は強く反発。5月18日に下村氏と会談後、記者団に「都が負担する根拠がない。誰が責任者で、誰に責任を問えばいいのか」といらだちをあらわにした。
舛添氏と論争を繰り広げた下村氏は6月9日の記者会見で、責任の所在について、「第一義的にJSCにある」としつつ、「明確な責任者がどこなのかわからないまま来てしまった」と反省の弁を口にした。与党内には「文科省の対応がずさんすぎた」(自民党中堅)との批判が強い。
一方、高速道路株式会社法違反(収賄)の疑いで逮捕された大阪高速道路事務所の総務課長、平野浩治容疑者(54)は「カードローンを複数抱え、多額の借金があった」と供述していることも分かった。府警は18日朝、大阪府茨木市の同事務所の捜索を始めた。
捜査関係者によると、平野容疑者は2013年9〜11月、閉鎖された管理事務所の廃棄物処分業務の随意契約に絡み、土木工事会社「近畿施設サービス」(大阪府箕面市)社長、室屋伯(はく)容疑者(56)が受注できるよう便宜を図り、現金30万円を受け取った疑いがある。府警は平野容疑者が無許可業者と知りながら業務契約を結んだとみている。
府警は18日午後、両容疑者を大阪地検に送検する。
文科省、お前らは基本設計もない段階で予算の1300億円を超えない事をただの絵だけでどうやって確認したのか?お前達が無能だから
こうなったとは思わない事が信じられない。申しわけと思わない、国民に負担を押し付ける事に関しても悪いとは思わないのだろう。

最初の建設予算の3倍をかけて建造する価値を見つけられない。だから多くのイギリス人達からも批判を受けたのであろう。
計画を批判し、撤回を求めてきた建築家らはこの日の安倍首相の決断を歓迎した。一方、一部契約が済み、走り始めた計画の突然の撤回に、驚きや困惑を隠せない関係者もいた。
首相官邸での会議を終えた下村文部科学相は「多くの国民の皆さん、アスリートから、ご心配や問題視する意見が出ていたので、約1か月前から(計画の)見直しをしていた」と切り出した。決断が17日になった理由については「ラグビー・ワールドカップには間に合わないが、五輪には間に合うことが今日確信できた」と説明した。ただ、責任問題を問われると「検証する中で適切に判断する」と言葉を濁した。
下村文科相に設計のやり直しを求める提言書を出した、東大名誉教授で建築家の大野秀敏さんは、安倍首相が白紙撤回を明言する映像を見ながら「これ以上、決断が遅れたら完成が間に合わない時期で、ラストチャンスだった。我々の主張が社会に浸透したという意味では良かった」とうなずいた。
今後の課題については「時間がないので、国は早急に、どのような施設にするのか方針を打ち出さなくてはならない」とし、「透明性を確保した上で案を決定し、東京の品格を上げるような施設にしてほしい」と注文を付けた。
同じく現行のデザインに反対していた1級建築士の森山高至さんも、「巨大な『キールアーチ』で屋根を支える特殊構造を続ける限り、非常に高額になることを首相は理解してくれたのだろう。問題が大きくなったことで、多くの人が計画に詳しくなり、疑問を持つようになった結果でもある」と話した。
その上で、「今からコンペになっても、間に合わせるためのアイデアは色々ある。多くの建築家が応募すればコンペが盛り上がり、再び五輪へのムードも高まるだろう」と期待を寄せた。
一方、白紙撤回に驚きの声も上がった。文科省幹部は「首相や大臣が『国際的に信頼を失う可能性がある』と答弁してきただけに、覆した政府の判断は信じがたい」とぼう然としていた。
現行案を捨ててやり直すことについて「要項作成や業者選定など、全てゼロからやり直しをする。本当に間に合うのか」と不安をにじませた。
「2019年ラグビー・ワールドカップ(W杯)日本大会には間に合いませんが、お許しいただきたい」
安倍晋三首相は17日午後、首相官邸5階の執務室で、2020年東京五輪・パラリンピック組織委員会会長の森喜朗元首相にこう頭を下げた。
それでも不満そうな表情の森氏に首相が示したのが、建設計画を見直した場合の工期などを示した1枚の紙だった。
「ギリギリ間に合うと希望的なことを言ってできないとかえってまずいでしょう」
森氏は、内容を確かめると小さな声で応じた。
「それじゃ、やむをえませんね」
首相が示したA4の文書は、国土交通省などが作成したものだった。もう一度、コンペをやり直して半年以内に設計を決定し、20年春に完成させ、五輪には間に合わせるという計画見通しが示されていた。
首相が工期などの計画見直しを文部科学省に指示したのは6月2日頃だった。総工費や工期など現状計画の変更が可能かどうか検討するよう伝えた。
「計画の見直しを再検討してみてほしい」
これに対し、文科省の回答はかたくなだった。
「できません」
文科省は、国際オリンピック委員会(IOC)での首相演説などを根拠に、建築家ザハ・ハディド氏のデザインは「国際公約」と見なしていた。下村博文文科相も公の場で「既存計画を進める以外ない」と表明していた。
ただ、12年にデザインを国際公募した際に「1300億円程度」という条件の総工費はふくれ上がり、6月29日の文科省の正式発表では2520億円になっていた。ロンドンなどの過去の開催地に比べても高すぎるとの批判は強まった。
政府高官は「安全保障関連法案と違い、国立競技場問題では全部のマスコミが批判的だ」と警戒。首相も周辺に「アーチが無駄遣いの象徴のようになっている。世論が持たないかもしれない」と懸念を口にするようになっていた。
また、安保関連法案の審議を通じ、内閣支持率はじりじり下がっていた。さらに五輪にも建設が間に合わないかもしれないとの情報に、首相が下村氏を呼んでただしたが、下村氏は「努力する」と繰り返すのみ。しびれを切らした首相はついに文科省だけでなく、国交省にもこう指示した。
「では、私は現行計画を『見直す』。それを前提に検討してほしい」
■首相、最後まで悩み抜き…賠償「最大100億円」試算
安倍晋三首相が新国立競技場の計画見直しで、国土交通省や文部科学省に念入りに検討させたのは、2020年東京五輪・パラリンピックまでに建設が間に合うのかという工期と、現行計画より総工費を抑えられる見通しが立つのかというコストの問題だった。
加えて大きな問題となったのは、現行計画を白紙にした場合には、デザインしたザハ・ハディド氏側に支払うべき損害賠償などが発生する可能性があることだった。文科省はハディド氏側にデザイン監修料の一部として昨年度までに13億円を支払い済みで、契約解除時に違約金を支払う条項は設けていないと説明。ただ、政府の調査では、過去の判例から違約金や賠償金として「10億円から最大100億円」を支出せざるを得ないとの数字も出た。巨額の賠償金を支払うことになれば、新たな批判を呼び起こすのは確実だ。
このため首相も最終決断に踏み切るまで悩み抜いていたようだ。首相は9日夜の会食で、次世代の党の松沢成文幹事長に「下村(博文文科相)さんは『絶対大丈夫』と言っている」と話し、松沢氏が「見直さないと世論が持たなくなる」と指摘すると、首相は苦り切った表情を浮かべた。
また、計画変更の難関の一つは、五輪大会組織委員会会長の森喜朗元首相の説得だった。14日には自民党幹部から首相周辺に「森氏は変更に慎重だ」という情報が入った。今月末にクアラルンプールで開かれる国際オリンピック委員会(IOC)総会で森氏自身がメーン会場の説明をする予定になっているためだった。
森氏には自分が説明し、説得するしかない-。審議中の安全保障関連法案の衆院通過後に森氏と会談する日程も前から入っていた。
17日の首相と森氏の会談が終わり、下村氏や遠藤利明五輪相が執務室に招き入れられると、森氏はラグビーの合言葉を引用して言った。「首相が決めたことだ。みんなで団結してやろう。ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン(一人はみんなのために、みんなは一人のために)」 (水内茂幸)
◇第三者委、20日に報告書要約版
東芝幹部は「今回の問題が『意図的』と認定されるのは仕方がない状況だ」と、利益の水増しが不正会計だったことを事実上認めた上で「第三者委の報告書が発表されたら『粉飾』と批判されるのではないか」と危機感をあらわにした。
第三者委の関係者は「社長の発言には『頑張って業績を上げろ』という以上に、(損失先送りなどを促すような)踏み込んだ内容があった」と指摘。さらに「現場に会計操作をしなければいけないと思わせてしまったことが問題」と強調する。利益水増し問題を巡っては、田中社長が幹部らに早朝の電話やメールで「何で予算を達成できないんだ」「売上高、利益をもう少し上げろ」などと要請していたことが判明。佐々木則夫副会長も社長時代に業績改善を現場に強く迫っていたことが明らかになっている。
経営トップからの強い業績改善圧力に応えるため、各事業部門が不正な会計処理に踏み出す構図になっていた模様だ。
また、関係者によると、西田厚聡(あつとし)相談役が社長を務めていた2009年3月期にもパソコンの部品取引を巡って利益水増しをしていた疑いがあり、第三者委は西田氏からも聴取を行った。調査報告書で歴代経営トップの責任や関与をどう認定するかが焦点となる。
一方、東芝の会計監査を担当している新日本監査法人も、長期間にわたってなぜ利益水増しを見抜けなかったかが問われている。ただ、新日本が東芝から虚偽の説明を受けていた可能性もあり、第三者委は報告書で新日本の責任や対応をどう認定するか慎重に検討している。【片平知宏、岡大介】
森喜朗元総理大臣:「ああいう、でかいものやったことないんだよ。スーパーゼネコンと話し合うような行為をしたことないわけですよ。
JSCだけじゃないですよ、文科省もそうですよ。国がたった2500億円も出せなかったのかねっていう、そういう不満はある。何を基準に『高い』と言うんだね。皆、『高い、高い』と言うけれど」
Prime Minister Shinzo Abe said his government would "start over from zero".
The original design, by British architect Zaha Hadid, had come under criticism as estimated building costs almost doubled, reaching $2bn (£1.3bn)
Mr Abe says the new stadium will still be completed in time for the games.
However, the delay means that the stadium will no longer be ready in time for the 2019 Rugby World Cup, which Japan is also hosting.
World Rugby said it was "extremely disappointed" and was "urgently seeking further detailed clarification".
Japanese officials say the contract with Zaha Hadid's architecture firm will be cancelled, and a new design chosen within six months.
Zaha Hadid Architects said that the stadium the firm had designed could be built cost-effectively.
"It is not the case that the recently reported cost increases are due to the design," the firm said in a statement.
The real challenges were "increases in construction costs in Tokyo and a fixed deadline", it said, adding that building costs in Tokyo were higher than many other places as the risk of earthquakes meant that strict safety standards were needed.
Under the original plans, Tokyo's stadium would have been bigger and more expensive than any of its recent predecessors.
It drew increasing criticism as estimated costs spiralled from $1bn to $2bn.
The futuristic design of the stadium also drew attention, with architects likening it to a turtle or a bicycle helmet.
Announcing the cancellation on Friday, Mr Abe said: "I have been listening to the voices of the people and the athletes for about a month now, thinking about the possibility of a review."
"We must go back to the drawing board," he added. "The cost has just ballooned too much."
He said that he had made the decision after being assured that it was still possible to complete construction of a new design in time for the Olympics.
Dame Zaha Hadid has won several architectural awards, including the 2004 Pritzker Architecture Prize and the 2010 and 2011 Stirling Prizes.
She designed the London Aquatics Centre for the London 2012 Olympics and Paralympics, as well as Qatar's Al-Wakrah stadium for the 2022 football World Cup.
Commentators have described her projects as exuberant, extravagant and striking.
However, it is not the first time one of her designs exceeded the initial budget - the London Aquatics Centre's budget more than tripled from its initial budget of $116m (£75m).
The Japanese government has scrapped controversial plans for a dramatic Zaha Hadid-designed $2bn (£1.3bn) stadium envisioned as the focal point of the 2020 Tokyo Olympics, amid concern about rising costs and a growing public backlash.
The move sparked an immediate response from world rugby’s governing body, which was scheduled to host the 2019 World Cup final in the stadium and will now no longer be able to do so. It said it was “very disappointed” at the decision and would need to consider its options.
“We have decided to go back to the start on the Tokyo Olympics-Paralympics stadium plan, and start over from zero,” said the prime minister, Shinzō Abe, after a meeting at his office with Yoshirō Mori, chairman of the Tokyo 2020 organising committee. Organisers had already decided to scale back the original designs but they will now be scrapped altogether.
“I have been listening to the voices of the people and the athletes for about a month now, thinking about the possibility of a review,” he added. “We must go back to the drawing board. The cost has just ballooned too much.”
He said he had taken the decision after being reassured that there was still time to draw up new plans and complete the new stadium, on the site of the existing national stadium, before the 2020 Olympics. London began building its Olympic stadium in 2007, five years before the Games.
The ambitious design by the award-winning Iraqi-British architect Hadid, likened to a bike helmet, was due to not only host the opening game and final of the 2019 Rugby World Cup but also the 2020 Olympics and then become the new national stadium.
It was a key part of the bid that triumphed over Istanbul and Madrid in 2013 to win the right to host the 2020 Games. But the government has faced growing criticism as the estimated cost for the stadium almost doubled from original estimates to 252bn yen (£1.3bn).
Abe said he had obtained the consent of Mori, a former prime minister, and instructed the sports and Olympics ministers to conduct a review and draw up a new plan.
World rugby’s governing body immediately hit out at the decision and said it would seek urgent clarification of the plans for the 2019 World Cup, awarded as part of a push to grow the sport in new markets.
“World Rugby is extremely disappointed by today’s announcement that the new national stadium will not be ready to host Rugby World Cup 2019 matches, despite repeated assurances to the contrary from the Japan Rugby 2019 organising committee and Japan Sports Council,” said a spokesman.
Hadid, who has designed a similarly divisive stadium for the 2022 Football World Cup in Qatar, won the design contest for the Tokyo stadium in 2012, but faced a barrage of criticism over its appearance.
And amid growing international scrutiny of the costs and benefits of hosting a Games – something that the recently elected International Olympic Committee president, Thomas Bach, has promised to focus on – and domestic public pressure, organisers will now be forced to look for a more cost-effective solution.
Jim Heverin, project director at Zaha Hadid Architects, said the rising cost of the stadium was not a result of the design, instead blaming the increasing cost of materials.
“Our teams in Japan and the UK have been working hard with the Japan Sports Council to design a new national stadium that would be ready to host the Rugby World Cup in 2019, the Tokyo 2020 Games and meet the need for a new home for Japanese sport for the next 50 to 100 years,” he said.
“It is not the case that the recently reported cost increases are due to the design, which uses standard materials and techniques well within the capability of Japanese contractors, and meets the budget set by the Japan Sports Council. The real challenge for the stadium has been agreeing an acceptable construction cost against the backdrop of steep annual increases in construction costs in Tokyo and a fixed deadline.”
One Japanese architect, Arata Isozaki, described the design as “like a turtle waiting for Japan to sink so that it can swim away”. The Pritzker prize-winning architect Fumihiko Maki, 86, organised a symposium to protest against the scheme, and was joined by fellow leading Japanese architects Toyo Ito, Kengo Kuma and Sou Fujimoto. A petition was launched calling for the project to be scrapped.
Last year Hadid hit back at her peers’ complaints, telling Dezeen magazine: “I think it’s embarrassing for them. Many of them were friends of mine, actually the ones which I supported before like Toyo Ito, who I worked with on a project in London. I’ve known him for a long time.
“I understand it’s their town. But they’re hypocrites because if they are against the idea of doing a stadium on that site, I don’t think they should have entered the competition. The fact that they lost is their problem.
“They don’t want a foreigner to build in Tokyo for a national stadium. On the other hand, they all have work abroad. Whether it’s Sejima, Toyo Ito, or Maki or Isozaki or Kengo Kuma.”
The affair has echoes of the controversy that surrounded Hadid’s Aquatics Centre in London, where costs soared threefold to £269m as a result of the ambitious design, and certain elements had to be pared back.
The history of Olympic stadiums is chequered, due to the difficulties in planning for a future beyond the Games. The Beijing National Stadium, also known as the Bird’s Nest, is rarely used, although it will be pressed into action for the World Athletics Championships this summer, while the legacy issues with the venues built for the 2004 Games in Athens have become a symbol for the subsequent wider malaise in the country.
The the future of London’s Olympic Stadium, where total costs have now soared to £701m thanks to an ambitious plan to convert it into a multi-use venue that will become West Ham United’s home ground, has also proved controversial.
IOC vice-president John Coates, who is chair of the coordination commission that liaises with the host organising committee, said it had been reassured that the review would not affect the delivery of the stadium in time for the Games.
“The national stadium is a national project, which will serve the people of Japan for many years to come. This is why the Japanese government is best placed to decide on what is appropriate for this venue,” he said.
本人や関係者によると、高須校長は8日午後10時ごろ、愛知県西尾市内で、酒気を帯びているにもかかわらず、乗用車を運転した疑いがある。パトロール中の西尾署員が停止を求め、呼気検査をした結果、アルコールが検出されたという。
高須校長は取材に対し、飲み会の出席者や酒量などについて明らかにしていない。学校に報告しなかった理由については「8月中旬に出頭を命じられている。その時点で報告し、進退をはっきりさせるつもりだった」と説明した。
高須校長は県教委高校教育課長や学習教育部長などを歴任し、2013年3月まで県立岡崎高校校長。現在は名城大学常勤理事で、付属高校校長を兼務している。
同校は17日、終業式だったが高須校長は欠席した。
森喜朗元首相は「見直した方がいい。もともとあのデザインは嫌だった」とBS番組で言ったそうだ。
政府が2020年東京五輪・パラリンピックの主会場となる新国立競技場の建設計画を見直す方針を固めたことについて、大会組織委員会会長の森喜朗元首相は17日、BS番組の収録で「見直した方がいい。もともとあのデザインは嫌だった」と述べ、デザインの変更など計画の見直しを容認した。【浅妻博之】
政府は、競技場を19年のラグビーワールドカップ(W杯)で使う計画は断念して競技場が完成するまでの工期をのばし、デザインや工法などを大きく修正することで、総工費を圧縮する考えだ。
安倍首相は17日午後、森元首相と会談し、計画見直しへの協力を求める。森氏は17日、BS朝日の番組収録で、計画の見直しについて「した方がいい」と発言。「僕は元々、あのスタジアムは嫌だった。生ガキみたいだ。(現行案の2本の巨大アーチは)合わないじゃない、東京に」と語った。下村博文文部科学相は17日午前の記者会見で、安倍首相が下村氏とも会談し、記者会見するとの見通しを示した。
こういう考え方が日本の借金を増やしている。日本の借金を考え、将来に負担を減らすことを考えないから、日本の借金が増えていく。
格差が子供の教育に影響していると頻繁に記事になっているが、たいした問題でないのならなぜ取り上げるのか?自己責任で放置しておけばよい。
日本の財政がさらに苦しくなれば、良い仕事に就けない人達も含めて、増税して負担させればよい。蓄えのない老人は古い簡易宿泊所に押し込めておけば良い。
東京オリンピックのため、ラグビーW杯のために自慢できる新国立競技場を建設する方が優先されると言うことなのだろう!
それにキールの部材は7月中に発注しないと間に合わないそうだ。あまりに巨大だから全体を作って競技場に運べないから切断したのを運んで現場で接合するしかない。だから仮設工場もいるんですよ。
問題は総事業費だけど、そこは腹をくくって国家的事業だからということで納得してもらうしかないんです。大事なことは、五輪は国と東京都と組織委員会が協力してやることなんです。そして経費を徹底的に精査すること。僕が組織委員会にきて2000億円くらいはすでに圧縮したよ。
それでも東京都が3000億円、組織委員会もトータルで7000億~8000億円はかかる。でも国は2520億円しか出さない。おかしいと思いませんか。3対8対2だよ。
16日朝、東京都内で開かれた自民党の議員有志でつくる新国立競技場勉強会。国民の猛反発に危機感を抱いた約70人が集まった会場は熱気に満ちていた。議論を主導した後藤田正純衆院議員は「文部科学省に聞くと、できません、間に合いません、国際公約ですという三つの答えが返ってきた。今までの進め方はいかがなものか」と口火を切ると、河野太郎衆院議員は「キールアーチをやめないと、この問題は解決しない。官邸はそれを外していいという議論をしていると理解している」と気勢を上げる。懸案だった安保法案が衆院通過したその日、政府は次なる懸案の打開に動いた。
キールアーチはイラク出身の建築家、ザハ・ハディド氏(64)による現行案の象徴でもある開閉式屋根を支える2本の弓状の巨大な構造物だ。それを外すことはデザインの抜本的な変更を意味する。その場合はザハ氏に新たなデザインを求めるのか−−。政府の判断は五輪招致の象徴と位置付けられながら、総工費高騰の代名詞となってしまった「キールアーチ」の撤回を辞さないものだった。
現行案を撤回した場合のリスクは3点あった。まずザハ氏への違約金。「裁判になったら確実に負ける」(政府関係者)という懸念がつきまとった。
続いて、文科省が設計のやり直しは完成まで61カ月を要すると試算した日程。それでは19年9月開幕のラグビー・ワールドカップ(W杯)に間に合わなくなる。横浜市の日産スタジアムの代替案も取りざたされたが、五輪組織委員会の森喜朗会長がW杯招致も尽力してきたこともあり「納得してもらえるか」(文科省幹部)と様子をうかがってきた。
また、現行案は安倍首相が東京五輪の開催が決まった13年9月の国際オリンピック委員会(IOC)総会でイメージ図を示したうえで建設を約束した。「総理が約束したことを撤回できない」(政府関係者)と、国際公約が独り歩きした理由だ。ただし、IOCはデザイン変更を「政府の判断次第」(ジョン・コーツ副会長)と公約とも思っていない。そこは安倍首相の判断次第だった。
しかし、現行案を推進した側は戸惑いを隠せない。事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)の関係者は見直しとなっても「そうですか。じゃあそうしましょうという話ではない」と話す。設計の全面見直しは見送り、キールアーチを備えた現行案のままで工期を延ばす選択肢もある。予定されている19年5月の完成時期を遅らせれば、資材や人材の確保に余裕ができ、総工費削減につながるという目算だ。政府内ではさまざまなシミュレーションが飛び交っている。
安保法案の審議で報道各社の世論調査では、安倍内閣の不支持が支持を上回っている。新国立への対応で選択を間違えば、さらに逆風が吹きかねない。今月末にはクアラルンプールでIOC理事会・総会が開かれ、新国立の状況を報告しなければならない。残された時間は少ない。【三木陽介、藤野智成、田原和宏、熊田明裕】
新国立競技場の総工費が膨張している問題について、選考時の審査委員長を務めた安藤忠雄氏(73)が16日、初めて口を開いた。「2520億円と聞いて、『えー』と思った」と驚いたことを明かし、自身の責任は「デザイン選定まで」にとどまると繰り返し強調した。
■批判集中に不満
東京都内のホテルで午前11時過ぎから開かれた記者会見。安藤氏は、笑みを浮かべ、約250人の報道陣の前に姿を見せた。冒頭、「有識者会議に出なかったから『すべて安藤の責任や』というのはちょっと、私はわからない。有識者は何十人もいる」と自身に批判の矛先が向かっていることに不満を述べた。
安藤氏はさらに、デザイン選定から設計までの過程を記したパネルを示した。「私たちが任されたのは、デザイン選定まで」と強調し、「安藤に責任をなすりつけたらええんじゃないかと思うかもしれないが」とその後の費用高騰については責任がないとの認識を示した。
会見場の東京都千代田区のホテルには、200人を超える報道陣が詰めかけた。午前11時15分、安藤氏はグレーのジャケット姿で現れた。用意されたパネルを示しながら、2012年11月のデザイン選定以降は、調整に関わっていないと何度も述べた。総工費が2520億円に膨らんだことについて「もうからなくても国のためだ。それが日本のゼネコンのプライドではないか」と、建設会社との金額調整を求めた。
デザインが審査条件の1300億円で建設可能か検討したかについては「アイデアのコンペで、徹底的なコストの議論にはなっていない」と語った。今月7日の日本スポーツ振興センター(JSC)の有識者会議を欠席したことに関し「欠席しただけで全て私の責任と言われるのは分からない」と話した。
イラク出身で英国在住の建築家、ザハ・ハディド氏の作品が選ばれた経緯をたどると、審査の過程で安藤氏が強く推していた様子が浮かび上がる。
「日本の技術力のチャレンジという精神から17番がいいと思います」。12年11月7日。JSCが基本構想のデザインを募った国際コンクールの審査委員会で安藤氏は発言した。委員の一人であるJSCの河野一郎理事長が「いかがでしょうか」と尋ねると「賛成」の声が上がった。17番はハディド氏の作品だ。
情報公開請求で開示された議事録によると、2次審査に残った11点のうち、委員長を含む委員10人による投票では、ハディド氏の作品を含む3点が同点。だが、他の委員から「委員長の1票は2票か3票の重みがあると判断すべきかと思う」などと促され、安藤氏がハディド氏の作品を選んだ。審査委員会も、募集要項などを了承したJSCの国立競技場将来構想有識者会議も原則、非公開だった。
安藤氏はハディド氏の提案を「宇宙から舞い降りたような斬新な案に心を動かされた」と講評していた。【山本浩資、飯山太郎、武本光政】
新国立競技場の最初のデザインは2012年11月に安藤氏が委員長を務めた審査委員会で、1300億円の建設費の設定のもと、イラク人女性建築家、ザハ・ハディド氏の作品を最優秀賞として選びました。
安藤氏は、建設費が2520億円に膨らんだ改築計画を了承した今月7日の有識者会議を欠席しましたが、16日午前、都内のホテルで記者会見を開き、一連の経緯について初めて説明しました。安藤氏は当時の審査について、「デザインの選定までが仕事だった。
アイデアのコンペなのでコストについて徹底的に議論することはなかった。オリンピック招致に向け斬新でシンボリックなデザインということで選んだと思う。デザインを選んだ責任はあるが、技術とコストについてはハディド氏と日本の設計チームによる次の設計段階でできるんじゃないかと思った」と説明しました。
そのうえで、政府内で設計自体の見直しなどを模索する動きが出ていることについて、「ハディド氏のデザインは外す訳にはいかないと思うが、2520億円は高すぎ、もっと下がらないかなと思うので徹底的に議論して調整してほしい」と話しました。
デザイン変えないことが望ましい
安藤忠雄氏の記者会見のあと取材に応じたJSC=日本スポーツ振興センターの鬼澤佳弘理事は、政府内で設計自体の見直しなどを模索する動きが出ていることについて、「報道では理解しているが、正式に伝達や指示は受けていない」と述べました。
そのうえでザハ・ハディド氏のデザインを変更する可能性については、「これまでの決定の経緯や条件、それに約束などから国際的にも『変更は難しい』という判断があったので、変更しないことを前提に議論を進めていくのではないかと思う。
こうした判断に関係なく議論するということならば、変更という判断もありえないわけでない。ただ、安藤氏が言うように、基本的にはハディド氏のデザインで進まなければ日本の信頼や信用にも関わるという認識を持っている」と述べ、今後、何らかの見直しがあったとしてもデザインは変えないことが望ましいという見解を示しました。
建設主体の日本スポーツ振興センター(JSC)が国際デザインコンクールを実施して12年11月、イラク出身の女性建築家、ザハ・ハディド氏のデザインに決めた際の審査委員会の委員長。安藤氏は「選んだ責任はある。ただ2520億円になり、もっと下がるところがないのか私も聞きたい。一人の国民として何とかならんのかなと思った」と述べ、見直しを求めた。その一方で「国際協約としてザハ氏を外すわけにはいかない。そうでないと国際的信用を失う」と強調した。
巨大な2本の弓状のキール構造で開閉式屋根を支えるデザインが経費高騰の要因となったが、五輪招致が決まった13年9月の時点で審査委員会と設計の関わりが終了しており、その後の総工費高騰には「消費税増税と物価上昇に伴う工事費の上昇分は理解できるが、それ以外の大幅なコストアップにつながった項目の詳細、基本設計以降の設計プロセスについて承知していない」と関与を否定した。
選定時は1300億円の予算を前提に決定。技術的に困難な構造である上、資材や人件費の高騰を受け、総工費は昨年5月の基本設計時の1625億円から2520億円に増えた。デザイン選定の理由について安藤氏は「アイデアがダイナミックで斬新でシンボリックだった。16年五輪招致に敗れ、20年は勝ってほしい思いがあった」と述べ、斬新なデザインが五輪を勝ち取る上で重要な役割を果たしたとの認識を示した。
安藤氏は実施設計を了承した7日のJSCの有識者会議を欠席しており、新国立競技場のデザインに対する批判が高まってから初めて見解を述べた。
菅義偉官房長官は16日午前の記者会見で、新国立競技場建設計画に関し「整備額が大きく膨らんだ理由について国民の皆さんに説明が足りなかった」と述べた。「国民負担ができるだけ生じないように(競技場運営の)民間委託など、いろいろな工夫を考える必要がある」とも指摘した。建設計画の見直しについては「現時点では決定していない」とした。【藤野智成】
◇
新国立競技場改築について、国際デザイン競技審査委員長として、ザハ・ハディド氏の提案を選んだ審査の経緯をここに記します。
老朽化した国立競技場の改築計画は、国家プロジェクトとしてスタートしました。「1300億円の予算」、「神宮外苑の敷地」、オリンピック開催に求められる「80000人の収容規模」、スポーツに加えコンサートなどの文化イベントを可能とする「可動屋根」といった、これまでのオリンピックスタジアムにはない複雑な要求が前提条件としてありました。さらに2019年ラグビーワールドカップを見据えたタイトなスケジュールが求められました。
その基本デザインのアイディア選定は、2020年オリンピック・パラリンピックの招致のためのアピールになるよう、世界に開かれた日本のイメージを発信する国際デザイン競技として行うことが、2012年7月に決まりました。
2013年1月のオリンピック招致ファイル提出に間に合わせるため、短い準備期間での国際デザイン競技開催となり、参加資格は国家プロジェクトを遂行可能な実績のある建築家になりましたが、世界から46作品が集まりました。
デザイン競技の審査は、10名の審査委員による審査委員会を組織して行われ、歴史・都市計画・建築計画・設備計画・構造計画といった建築の専門分野の方々と、スポーツ利用、文化利用に係る方々、国際デザイン競技の主催者である日本スポーツ振興センターの代表者が参加し、私が審査委員長を務めました。グローバルな視点の審査委員として、世界的に著名で実績がある海外の建築家2名も参加しました。
まず始めに、審査委員会の下に設けられた10名の建築分野の専門家からなる技術調査委員会で、機能性、環境配慮、構造計画、事業費等について、実現可能性を検証しました。その後、二段階の審査で、デザイン競技の要件であった未来を示すデザイン性、技術的なチャレンジ、スポーツ・イベントの際の機能性、施設建設の実現性等の観点から詳細にわたり議論を行いました。2012年11月の二次審査では、審査員による投票を行いました。上位作品については票が分かれ、最後まで激しい議論が交わされました。その結果、委員会の総意として、ザハ・ハディド氏の案が選ばれました。
審査で選ばれたザハ・ハディド氏の提案は、スポーツの躍動感を思わせる、流線型の斬新なデザインでした。極めてインパクトのある形態ですが、背後には構造と内部の空間表現の見事な一致があり、都市空間とのつながりにおいても、シンプルで力強いアイディアが示されていました。とりわけ大胆な建築構造がそのまま表れたアリーナ空間の高揚感、臨場感、一体感は際だったものがありました。
一方で、ザハ・ハディド氏の案にはいくつかの課題がありました。技術的な難しさについては、日本の技術力を結集することにより実現できるものと考えられました。コストについては、ザハ・ハディド氏と日本の設計チームによる次の設計段階で、調整が可能なものと考えられました。
最終的に、世界に日本の先進性を発信し、優れた日本の技術をアピールできるデザインを高く評価し、ザハ・ハディド案を最優秀賞にする結論に達しました。実際、その力強いデザインは、2020年オリンピック・パラリンピック招致において原動力の一つとなりました。
国際デザイン競技審査委員会の実質的な関わりはここで終了し、設計チームによる作業に移行しました。
発注者である日本スポーツ振興センターのもと、技術提案プロポーザルによって日建設計・日本設計・梓設計・アラップが設計チームとして選ばれました。2013年6月に設計作業が始まり、あらゆる課題について検討が行われ、2014年5月に基本設計まで完了しました。この時点で、当初のデザイン競技時の予算1300億円に対し、基本設計に基づく概算工事費は1625億円と発表されました。この額ならばさらに実施設計段階でコストを抑える調整を行っていくことで実現可能だと認識しました。
基本設計により1625億円で実現可能だとの工事費が提出され、事業者による確認がなされた後、消費税増税と物価上昇にともなう工事費の上昇分は理解できますが、それ以外の大幅なコストアップにつながった項目の詳細について、また、基本設計以降の実施設計における設計プロセスについては承知しておりません。更なる説明が求められていると思います。
そして発注者である日本スポーツ振興センターの強いリーダーシップのもと、設計チーム、建設チームが、さらなる知恵を可能な限り出し合い一丸となって取り組むことで、最善の結果が導かれ、未来に受け継がれるべき新国立競技場が完成することを切に願っています。
2015年7月16日
新国立競技場基本構想国際デザイン競技
審査委員長 安藤忠雄
専門家に見積もりの妥当性や根拠に伺いを立てる発想はなかったのか?相手の言い分をチェックもせずに鵜呑みにするのはばかだ。70歳にも
なってもそんな事もわからないのか?肩書きだけの人間は使えない良い例だ。
費用高騰などが問題化して以降、安藤氏が公の場で発言するのは初めて。安藤氏は今月7日、2520億円を承認した日本スポーツ振興センターの有識者会議を欠席。これに関し、「欠席したから責任があるというのはわからない」と自身に批判が集まっていることに疑問を呈した。
デザインが費用高騰を招いたとの批判には、選考時に「1300億円」の予算が示されていたと強調。その上で「デザインを決める場で、コストについて徹底的な議論にはなっていなかった」と釈明した。
安藤氏を巡っては、下村文部科学相が10日、「選んだ理由を堂々と発言してほしい」と述べるなど、その発言が注目されていた。
構造的な問題が見つかれば、業務改善命令などの行政処分も検討する。
関係者によると、新日本監査法人は金融庁に対し、「監査は適正な手続きで行ったが、東芝から実態と異なる説明を受けた」と説明しているという。
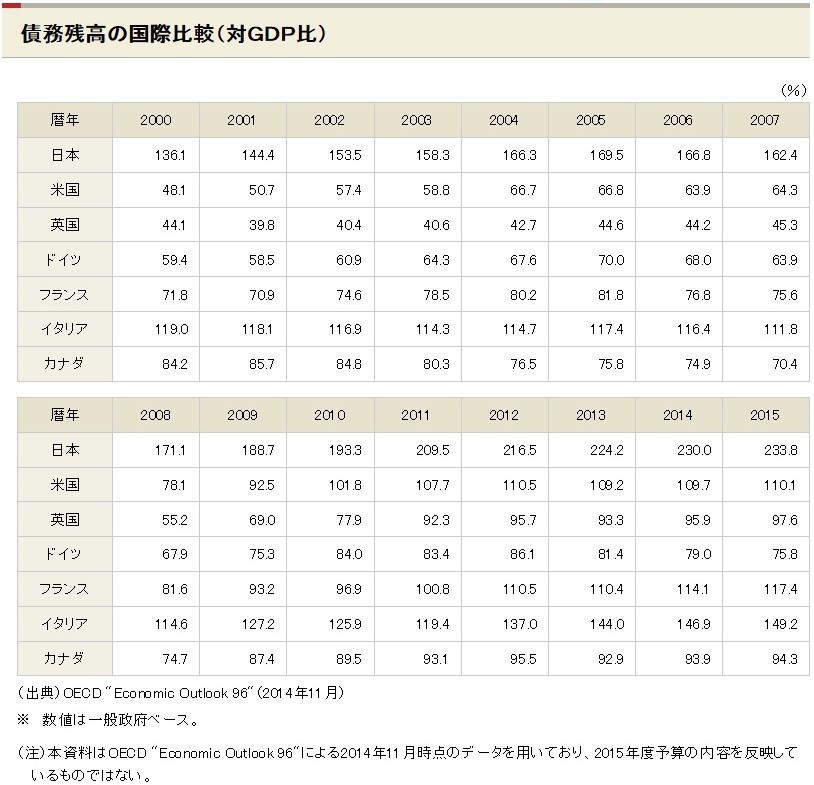
債務残高の国際比較(対GDP比)(財務省)
ギリシャ政府の借金総額は国内総生産(GDP)の約1・8倍もあり、「財政は持ちこたえられない」と指摘した。
ギリシャ政府に対しても「持続可能な経済へ立て直すため、困難な手段を講じる必要がある」と強調し、改めて財政の緊縮策の導入など厳しい改革を求めた。
ギリシャ政府が、付加価値税(日本の消費税に相当)の増税や年金支給額の削減などを柱とする新改革案をEU側に提案したことについては「必要な構造改革を反映している。(交渉するギリシャとEUの)両者は近づいているように見える」と歓迎した。
安藤氏は、下村文部科学相から「選んだ理由を堂々と発言してほしい」と指摘されていた。
2020年の東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムとなる新しい国立競技場について、国は、デザインの大幅な見直しをせず、当初よりおよそ900億円多い2520億円をかけて建設する計画です。これについて、14日開かれた自民党の総務会で出席者から、「国民の納得は得られておらず、しっかりと議論しなければ将来に禍根を残す」といった指摘や、「ずさんな計画に基づいて、高額な改築を行おうとするもので看過できない」といった批判が相次ぎました。
このあとの記者会見で二階総務会長は、「各種の世論調査の結果を見ても、国民の大半が計画に対して疑問を持っており、われわれとしても重要な関心を示さざるをえない。国民がひとしく関心のある問題であり、しかるべく説明ができる人から話を聞きたい」と述べ、計画の内容や経緯などについて文部科学省などに説明を求める考えを示しました。
細野氏「必要あれば計画変更しきちんとしたものを」
新国立競技場について、民主党の細野政策調査会長は、記者会見で、「計画の変更は、必要に応じて行うべきだったし、これからもやるべきだ。オリンピックを、みんなから喜ばれるようにしていくことは当然の責務であり、それをやれるのは政権の側だ。必要があれば、計画をしっかり変更して、きちんとしたものを造るべきだ」と述べました。
なんで「コラムの時代の愛」なんだ、と言われれば、あれです、あれ、ガルシア=マルケスです。南米コロンビアのノーベル賞作家に「コレラの時代の愛」という映画化もされた長編小説があり、その語呂合わせです。
というのも、20代のころ読んだ作家、橋本治氏のコラム集のタイトルに感心したことがあったからだ。一冊は「ロバート本」で、もう一冊は「デビッド100(ヒャッ)コラム」という題。
1960年代の米国のスパイドラマで、日本でも人気を博した「0011ナポレオン・ソロ」の主演俳優、ロバート・ボーンと、デビッド・マッカラムを文字った題で、深い意味はない。本コラムもそれに習い、語呂になじんでもらえればという願いを込め、始めたいと思います。
いい加減な統計や無謀な借金は、ギリシアの近代文化
ギリシャ危機が始まって、かれこれ5年半になる。危機というのは「機」と書くくらいだから、本来、瞬間かせいぜい短期間、一過性のものだが、これだけ長く続くと、もはや日常で、「危機慣れ」とでも言うのか、ギリシャでは「ずっと危機なんだから、危機も何もないじゃないか」という声も聞かれる。
危機の始まりは2009年10月。就任したばかりのパパンドレウ首相が、前の政権の赤字隠しをばらし、「大丈夫か、ギリシャ」「デタラメじゃないか」と一気に信用を落とし、ギリシャ国債が暴落した。
このパパンドレウ氏、日本で言えば安倍首相か鳩山元首相のような政界のボンボン、サラブレッドだ。祖父も父も首相を経験した3代目で、特に父親は左派の貧困層へのばらまきで人気を博し、右派中心だったギリシャ政界に初めて「左派の中間層」を生み出した人物である。
その息子、アメリカで高等教育を受けたパパンドレウ氏が何を思ったのか、「前の右派政権が借金を重ね、粉飾決算をしていた」と世界に公表してしまった。
正直なことだが、もともといい加減な統計や無謀な借金は、自分の父親が広めた体質、ギリシャの近代文化であり、「何を今更」「わざわざばらしちゃって」というのが政界のみならず、大方のギリシャ人の見方だった。欧州連合(EU)には「3%ルール」がある。国の借金、財政赤字は国内総生産の3%以内に収めよという、いわば会則だ。
ギリシャは01年にEU入りする前はもちろん、会員になってもなし崩し的に3%を超える借金を続けてきたがなんとなく許されてきた。「あの国の統計は当てにならないと最初からわかっていた」(ルクセンブルクの元中央銀行総裁)が、ユーロが上り調子のころはさほど問題にはならなかった。
たとえば、01年は4・5%、02年は4・8%と控えめだが、無理してアテネ五輪を開いた04年にギリシャの財政赤字は7・5%に膨らみ、危機を招いた09年の決算ではあれこれ帳簿を誤魔化し「せいぜい6%程度」と発表しながら、調べてみたら13・6%に上っていた。やることが大胆なのだ。
通常、政権交代後、国庫からお金が持ち逃げされても、「まあ、そこは」となあなあで済ましてきたのに、パパンドレウ氏は「前の政権が悪い!」と勇ましく発表してしまったわけだ。
それからこの方、欧州中央銀行などは、とにかく財政を立て直し、何とか返済できる体力をと、借金の棒引きや付け替えで支援金を注ぎ込んできたが、ギリシャは一向に回復せず、ずるずるとここまで来た。国際通貨基金(IMF)の借金の一部が返済期限を迎えた6月末、「返せません」となり、今回のデフォルト(債務不履行)となった。従来の「事実上のデフォルト」が「正式のデフォルト」になりそうな事態となった。
危機の初期、アテネの町で「国勢調査員」のように一軒一軒話を聞いて回ったときのギリシャ人の言葉が忘れられない。
「大体、ギリシャ国債なんか買う方が悪い。俺たちは政府の連中をよく知ってるから、利子が高くたって絶対に買わない」「ドイツの大企業とか、ギリシャに借金させて資金を集め、もうけた連中がいるだろ。そいつらが返せばいいんだ」「なんで俺たちが増税や年金減らしでツケを払わされるんだ」「国の、政治家の失敗だろ、なんでそれを国民が払わなきゃならないんだ」
商人や勤め人、年金生活者、観光ガイド、ミュージシャンといろいろだが、実に多くの人からこんな話を聞いた。
それから5年あまり。パパンドレウ氏は去り、首相はサマラスというやはり世襲政治家の右派を経て、今のチプラス首相となった。日本で言えば、といってもそんな事態は考えられないが、政権が民主党から自民党に戻り、それでもだめで、ついに「庶民の味方」といい続けてきた左翼政党から首相が躍り出てきた。ちょっと想像はつかないが、社民党の福島瑞穂さんが突如人気を博し、「この際、最後の切り札に」となんとなく選ばれたようなものだ。
「瀬戸際」といい続けてはや5年 ギリシャの危機状態はずるずるとつづいていく
チプラス首相は、新たな増税や年金削減策を盛り込んだ、EUなどが作成した構造改革案を受け入れるかどうかを国民投票で問い、投票者の6割超から「反対」という答が出た。
「緊縮に耐え、我慢します」と言っては欧州中央から金を引き出し、危機の渦中も借金を積み上げてきたギリシャ。依然、被害者意識の強い国民たちが「とにかく俺たちはもう払わない」と、ようやく本音を公式にぶちまけた記念日、とも言える。
それで、即、ユーロを離脱し、現地通貨ドラクマも戻るかといえば、そんなことない。「国民が反対って言ってますから」と、チプラス首相はあれこれ言い訳しながら欧州中央などから、新たな支援金を引き出す策を練るはずだ。「瀬戸際」といい続けてはや5年、ギリシャの危機状態は、ずるずると続きそうだ。
藤原章生 (毎日新聞記者)
2020年の東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムとなる新しい国立競技場について、国は、デザインの大幅な見直しをせず、当初よりおよそ900億円多い2520億円をかけて建設する計画です。これについて、14日開かれた自民党の総務会で出席者から、「国民の納得は得られておらず、しっかりと議論しなければ将来に禍根を残す」といった指摘や、「ずさんな計画に基づいて、高額な改築を行おうとするもので看過できない」といった批判が相次ぎました。
このあとの記者会見で二階総務会長は、「各種の世論調査の結果を見ても、国民の大半が計画に対して疑問を持っており、われわれとしても重要な関心を示さざるをえない。国民がひとしく関心のある問題であり、しかるべく説明ができる人から話を聞きたい」と述べ、計画の内容や経緯などについて文部科学省などに説明を求める考えを示しました。
細野氏「必要あれば計画変更しきちんとしたものを」
新国立競技場について、民主党の細野政策調査会長は、記者会見で、「計画の変更は、必要に応じて行うべきだったし、これからもやるべきだ。オリンピックを、みんなから喜ばれるようにしていくことは当然の責務であり、それをやれるのは政権の側だ。必要があれば、計画をしっかり変更して、きちんとしたものを造るべきだ」と述べました。

日刊スポーツ
上記がが事実ならデザイン決定後の基本設計や実施設計の責任なのか、コンペの与条件としての予算は1300億円であることを認識していたハディド氏の責任なのか、はっきりする。
ハディド氏の見積もりに問題があれば損害賠償を請求する事が契約書次第であるが可能ではないのか?早く検証して答えを出そう。
お高いの見積もりを比べるだけで結果を出せると思う。
「安藤忠雄建築研究所」の名前で、番組の司会を務めるキャスターの辛坊治郎さん(59)宛に出されたファクスでは「コンペの与条件としての予算は1300億円であり、応募者も認識しています。提出物には建築コストについても示すように求められていました。それは当然評価の一つの指標となりました」と明記。下村博文文部科学相が10日の閣議後の会見で発言した「値段(総工費)とデザインを別々にしていたとしたら、ずさんだと思う」との言葉に反発した。
また、辛坊さんによると、安藤氏は「デザイン決定後の基本設計や実施設計には、審査委員会はかかわっていない」と話していたといい、最終的な計画概要の2520億円という金額に関しては「辛坊ちゃん、何でこんなに増えてるのか、分からへんねん!」と驚いていたという。安藤氏が7日の有識者会議を欠席した点に関して辛坊さんは「しゃべりたい気持ちは満々らしいが、周囲から止められているらしい」と聞いているとした。
2520億円に膨れ上がった総工費に対し財源確保の見通しはいまだに立っていない。1000兆円という空前絶後の負債を抱える国家でありながら、財政再建に取り組むどころか、不必要な巨額赤字をなお積み上げようとするのは世界中のもの笑い以外の何物でもない。
しかし見直しを求める世論を無視するように、事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)有識者会議が建設計画を了承したことに、各方面から批判が渦巻いている。
主な批判の論点は当初予算の倍近い金額に膨れ上がったこと。確かに当初の想定が大甘だったことは間違いない。
審議委員だった安藤忠雄氏は「コンペの条件としての予算は1300億円であり、応募者も認識しています」とコメントしており、当時の審議委員の1人であった建築家は「委員にはコスト見積もりを精査するようには求められなかった」とインタビューで述べていた。
つまり、建設コストの根拠がいい加減なままデザインを決め、基本設計や実施計画を詰めてみたら倍に膨れ上がったということだ。プロセス自体に問題があるとしか言いようがない。
これはまさに東京五輪向け整備に関し、小生が従来から指摘してきた懸念が現実化している事態だ。
無策のまま最悪の事態に至ることを避けるため、この問題に関し4つほど関係者の「ごまかし」を指摘しておきたい。
(1)最新の建設コスト見積もりに潜むごまかし
当初見積もりとの食い違いに関するJSCの今回の説明にはごまかしを感じる。建設計画の了承を発表した際にJSCは、当初予算から倍増した理由を次のように説明した。資材や人件費の上昇で350億円、消費増税分で40億円増、さらにアーチ2本で建物を支える「キールアーチ」というデザインの特殊性によって765億円増、と。
まるで途中から「キールアーチ」になったような説明である。しかし途中から環境条件が変わってしまった資材・人件費の上昇や消費増税と違い、「キールアーチ」のデザインは五輪が決定する前から分かっていた条件である。
もし「このデザインでは予算1300億円に収まるのは初めから無理なんです」と言いたいのなら、何としてもデザインを変えるべきだったという肝心の結論も伝えるべきだろう。
もしくは「このデザインでは建設経験が世の中にほとんどなく、正しいコストの見積もりが限りなく難しいんです」と言いたいのなら(建築家の幾多のコメントを拝見する限り、こちらが真実に近いだろう)、今回示されている「2520億円」という総額もまた信頼に値しないと言わざるを得ない。
しかも、この金額には五輪・パラリンピック後に設置を先送りした開閉式屋根の整備費や1万5千席の仮設スタンド設置分に加え、200億円超と見積もりされていた周辺整備費も含まれていない。これらを加えると結局、総額は3000億円前後になるのではないか。
しかしそれでは改めて批判が高まるため、今回は先送りした分の建設費などを除外して、一見コストが減額された印象を与えようとしたのではないか。実に姑息なやり方である。
(2)運営後の収益計画におけるごまかし
今回JSCが発表した収支目論見では、開閉式屋根を設置した場合という条件付きで、収入40億8100万円、支出が40億4300万円、締めて3800万円の黒字と試算している。この微妙な黒字額からは、いかにも無理矢理に黒字にした印象が強い。弊社が時々頼まれる事業見直し時に、担当部門がこんな事業計画案を出そうものなら、真っ先に疑って精査の対象となる。
既に各方面から、これらの収入の見積もりの甘さと支出の過小さを指摘されている。つまり、これは楽観シナリオに基づく見積もりだということである。
通常、事業計画の策定には悲観シナリオと(2つの中間に位置する)妥当シナリオも並行して検討し、その上で妥当シナリオの計画値を正式に上申する(楽観シナリオと悲観シナリオの予測数値は添付資料に回されることが多い)。楽観シナリオに基づく数値だけを提示するJSCのやり方は、ごまかし以外の何物でもない。
ちなみに、この収支計画には完成後にかかる修繕費が以前より多少増額して約1046億円と計上されているものの、50年間に必要な大規模改修費は別枠扱いとして、収支計画に組み込んでいない。これもまた「ごまかし」である。
しかもその年平均21億円という修繕費はまだまだ随分と過小だと言わざるを得ない。専門家の指摘によると、JSCが収支計画の前提としている開閉式の屋根というものは非常に故障しやすいものらしい。
実際、大分銀行ドームは前年の故障に応じて2011年に大規模な改修工事を終えたものの、2年後の2013年に再度、故障によって屋根が開いたままになり、大分県は予算措置に往生したそうである。また、豊田スタジアムは多額の改修費と維持費を理由に今年度から屋根を開けっ放しにしている(開き直った措置だが、問題が判明した時点で現実的な対処をしたといえる)。
これらのスタジアムでの改修工事費は5~15億円掛かっている。建築費がこれらの10倍以上掛かる上に、特殊構造となる「キールアーチ」に対応した新国立競技場の開閉屋根の改修工事となれば、100億円前後に上るのではないか。新しいうちはともかく、稼働後20~30年経てくれば故障が頻発することは避けられない。
ここで今ある情報に基づき妥当シナリオを想定してみよう。
建設当初の数年間は可動式の屋根ができていないため赤字になるとJSCはいう。毎年数~10億円程度の赤字としよう。
数年後に300億円ほどの追加費用を掛けて可動式屋根を追加設置、その後仮に20年ほど幸運にも故障なしに運用できたとして、既に見た通り楽観シナリオの下でギリギリの収支である。実際には1~2億円程度の赤字は避けられないのではないか。
その後は数年に一度の(しかも頻度は段々高まる)改修工事のたびに100億円ずつ吐き出すばかりか、故障期間は雨天時に使えない、工事期間は全く使えない、となれば収入はガクンと落ち込む。平均して毎年20億円近くの赤字を積み重ねることになるだろう。
こんな収支計画の事業をGOさせる経営者がいたら、お目に掛かりたいものだ。間違いなく負の遺産になろう。
(3)納期に関するごまかし
見直しをしない理由として、関係者は「今から国際コンペをやり直して設計を詰めてから建設するとなると、2020年の五輪に間に合わない」という。安倍首相もこのため変更を断念したという。本当にそうだろうか。
まず、国際コンペをやり直す必要はない。デザインコンペは既に実施されており、ザハ・ハディド氏のデザインがどうしても予算内に収まらないということで失格するとしたら、次点とされた作品を選ぶのが筋だ(もちろん予算内に収まるという条件の下ですが)。
これから基本設計そして詳細設計、さらに実施計画を詰めると五輪に間に合わないというのは本当だろうか。まだ5年あるのだ。
ザハ・ハディド氏のデザインに基づく特殊な構造の場合にはそうかも知れないが、もっとまともな構造であれば、日本の建設業界の設計力・実行力をもってすれば十分可能ではないか(ただし、工事ピーク時前後には周辺のあちこちに臨時の資材置き場を設ける、などの工夫も必要となるかも知れない)。
JSCのいう「間に合わない」対象は本当に東京五輪なのか、かなり疑わしい。本当は政界・スポーツ界に隠然たる影響力を持つ森喜朗・元首相がかねてご執心の、2019年9月からのラグビー・ワールドカップ日本開催に間に合わない、ということなのではないか。安倍首相と菅官房長官は関係者を問い詰めるべきだ。
(4)責任の所在に関するごまかし
下村文科相はデザインの審査委員長を務めた安藤忠雄氏に(先日の有識者会議を欠席したことに絡めて)「説明を求めたい」と批判している。当初見積もりが甘かったことに全ての責任を負いかぶせようという意図が透けて見えるものだ。確かに安藤氏に非がないとも思えないが、「第一級戦犯」ではなかろう。
本当に責任を取るべきは、過去に何度もあった見直しの機会に、当初のデザイン案をあきらめて基本設計を見直すという決断を先送りしてきた文科省とJSTの幹部である。とりわけ、最後のチャンスでありながら今また、見直しをせずに他に責任をなすりつけようとしている最高幹部の下村文科相の責任こそが重大ではないか。
改めて感じるのは、これほど「ごまかし」を重ねてでも関係者が基本設計の見直しに踏み切らないのには、よほどの理由があるのだろうということだ。
関係者や事情通は「国際的信用」や「無責任の構造」、先に触れた森・元総理への遠慮、などをいろいろと挙げる。しかしそれにしてもここまで政治問題化しながらも文科省とJSCが強引に世論に抗するのは、今一つ腑に落ちない。もしかすると我々の知らない巨悪の構造が隠れているのかも知れない。ジャーナリストの活躍を待つ所以である。(日沖博道)
二五二〇億の内訳は、竹中工務店が担当する「屋根工区」が九五〇億、大成建設が担当する「スタンド工区」が一五七〇億になる。驚きなのは、昨年五月発表の建設費が一六二五億円(解体費用を除く)で、これだけでも額は膨大と言われていたのに、蓋を開けてみれば当初の予定より九〇〇億円も上乗せした二五二〇億に及んだことだ。
さらにアンビリーバボーなことに、現在、建設費に確保されている財源が六二六億円しかないと言われている(国が三九二億を負担、スポーツ振興基金が一二五億円、totoの売り上げ金から一〇九億円を供出)。
これに、新国立競技場のネーミングライツ(命名権)で二〇〇億、totoの売り上げから六六〇億を供出する予定だが、それでもぜんぜん足らず、文部科学省は東京都に五〇〇億を負担するよう言い出した。舛添要一都知事は寝耳に水だったようだが、おカネがなければ税金があるじゃん、とお役人さんが得意とする身勝手作戦がオリンピックでも展開されようとしている。
それでも、まだ五三四億円もの建設費が不足しているのだ。
何故、こんなことになったのか――? 文部科学省の役人たちが無能だからか。それとも、文科省傘下の独立行政法人『スポーツ振興センター(JSC)』の職員はほとんどが文科省からの出向者で占められているから母体が無能なら傘下団体もやっぱり無能になってしまうのか。JSCには文科省で使えないやつが放り出されているのだろうか? でも本当に使えないのだ、こいつら。
「JSCも文科省の官僚も最悪だ。都市計画の変更などは難しいと思っていたが、まさか本体をつくる能力もないとは」
政府関係者は呆れているそうだ。国民も呆れています。舛添さんも呆れている。
「文科相に任せていたらアウトです。一〇億や二〇億で学校をつくったことはあっても、一〇〇〇億以上の建物をつくった経験もない。責任能力がない」
二五二〇億という額に落ち着いたとき、JSC幹部はこんなことを言った。
「国が主導でやることで、JSCがやることではなかった」
文科省に劣らずJSCもぼんくら揃いな団体だが、しかし、彼らはぼんくらなりに計画は立てていた。それが、石原慎太郎都知事時代に行なわれた、二〇一六年の五輪招致活動である。当時を知る関係者が言う。
「二〇一六年の招致では、『世界一コンパクトな五輪』を掲げ、一九六四年の東京五輪のレガシー(遺産)である旧国立競技場とベイエリアを結ぶ晴海に新スタジアムをつくるというプランでした。旧国立競技場を残し、二つのスタジアムを併用する理想的なプランでしたが、招致失敗でこの案は消えた。二〇二〇年招致に向けて再始動する過程で、新国立競技場を建設するプランが浮上してきたのです」
当時のプランをスポーツ紙の記者が語る。
「JSCは、旧国立競技場に耐震補強を施し、改修して継続利用する“改修案”を検討していました。JSCは設計会社に依頼して、改修案が作成された。この案では、収容人員は約七万人(中略)予算は七七七億円でした」
オリンピックのメインスタジアム建設費は、アテネが約三〇〇億円、北京が約六五〇億円、ロンドンが約七〇〇億円と言われているから、七七七億は妥当な数字ではあった。バブルでもあるまいに、二五二〇億という額が異常すぎるのだ。
だから、二〇一六年の招致に成功していたか、当時のプランを踏襲していれば、予算は今回の三分の一以下で済んだのだが、それはいまさら言ってもしょうがない。滝川雅美ちゃん……、もとい、滝川クリステルさんの、お・も・て・な・し、が功を奏したかどうかはさておき、日本は二〇二〇年のオリンピック・パラリンピック開催国になった。
そして、二〇一二年三月、各分野十四人のメンバーからなる『国立競技場将来構想有識者会議』が設立された。発足当時は「八万人収容」「開閉式の屋根」「可動式観客席の導入」等々の方針が決められた。問題となる国際デザインコンクール――、いわゆるコンペの実施を発表したのがその年の七月だ。審査委員長には建築家の安藤忠雄氏が就任するが、このときから新国立競技場建設をめぐる迷走が始まるのである。
コンペの発表が七月。応募の締め切りが九月二五日という異例のスケジュールが組まれた。オリンピックのメインスタジアムにして日本の国立競技場を決めるコンペなのに、応募期間がわずかに二ヵ月しかないというのは、実に不可解と言わざるを得ない。
不可解なこのコンペには、応募資格まで設けられた。首を傾げたのは東京電機大学の今川憲英教授だ。
「コンペの応募資格が、収容人数一万五〇〇〇人以上のスタジアム設計経験者と、国際的な建築賞を受賞したことのある人物に限定されており、そのこと自体かなり異例です」
応募は、海外から三十四点、国内から十二点の計四十六点があった。これをブラインドで一次審査にかけ、二次審査には十一点(海外七・国内四)が残った。二次審査は、各委員(日本人八・海外二)が良いものから順に三点を選ぶ方式が取り入れられたが、不可解なのは、この後の審査過程だ。
「ザハ案(今回採用された女性建築家)以外、豪州と日本の設計事務所の案が残りました。ここから安藤さんの意向で日本案が外され、最後は二案になる“決選投票”となったのです」(スポーツ紙デスク)
今回の審査委員には外国人建築家が二人、名を連ねていたが、何とも不可解なことに、彼らは一度も来日せず、一次審査にも投票しなかった。ではどうしたかというと、二次審査に残った作品をJSC職員が現地まで持参し、順位とコメントを聞き取り、審査に反映させたという。だから、外国人審査員の最終決選においての発言はない。
「決選投票は四対四で割れてしまい、その後もめいめいが意見を述べましたが、いったん休憩しようということになった。で、皆が席を離れた後、ひとりの委員が安藤さんに『こういうときは委員長が決めるべきでしょう』と話しかけたのです。実際、それ以上繰り返しても結果は変わりそうになく、安藤さんも『わかりました』と応じていました」
安藤忠雄氏は、さきの有識者会議のメンバーでもある。
「だから他の委員が詳しく知り得ない“上の意向”にも通じていたのでしょう。一時間ほどの休憩をはさみ、再び委員が席に着くと、安藤さんは『日本はいま、たいへんな困難の中にある。非常につらいムードを払拭し、未来の日本人全体の希望になるような建物にしたい』という趣旨のことを口にし、ザハ案を推したのです。そこで安藤さんは全員に向かって『全会一致ということでよろしいですか』と念を押し、誰も異論がなかったので、そのまま決まりました」
皆さんもザハ・ハディド氏がデザインした新国立競技場のイメージ像はご存じだろう。安藤氏曰く、あれが『未来の日本人全体の希望』だそうだ。呵々大笑。どーでもいいけど、安藤忠雄という建築家は、ぜんぜん使えない東急東横みなとみらい線の渋谷駅を設計した人です。乗り換えるのに五分も十分も歩かされる不便駅です。
「専門家が見れば、予算の範囲でつくれないのは審査段階でわかります。だいいち、建物の一部が敷地外に飛び出しており、本来ならば失格の作品を最優秀賞に選んでしまった。せめて招致が決まった段階で、ザハ案が違反であると公表し、十分な条件によるコンペを開いて仕切り直すべきでした。それをしなかったのは、安藤さんの責任でしょう」(今回、二次審査まで残った建築家の渡辺邦夫氏)
ザハ氏の作品は、昆虫の触角のように伸びたスロープがJR線をまたぎ、施設の高さも制限をオーバーしていた。応募条件から大きく逸脱していたにもかかわらず、安藤忠雄氏はコンペの優勝者としたのである。ホワイ?
ついでながら言えば、ザハ案は床面積を四分の三に縮小、高さも低く抑えるなど修正が必要だったのだが、どーいうわけか安藤さんはザハ案を選んだ理由のいっさいを説明しようとはせず、メディアにも口をつぐんだままだ。ホワイ? ただ、
〈コンセプトが強ければ後で修正できる〉
〈つくりあげるのはたいへん難しいが、日本の土木、建築技術は世界最高レベルにあり、乗り越えていける〉
とは言ってるみたいですけど。渋谷駅同様、使えない競技場を設計したザハ・ハディド氏には『デザイン監修料』として十三億円が支払われる。
「たしかに有識者会議でデザインは決めたけど、ぼくらは何の権限もなく、契約はJSCがやるわけだから、どうなっていくのかわかりません。五輪までに間に合ってほしいとは思いますけどね」
こんな無責任発言をしたのは、有識者会議・佐藤禎一委員長(元文部事務次官)だ。
未来の日本人全体の希望(安藤氏の発言)は、ぎりぎりの工夫をこらし、何とか一六二五億円で建設できるとの見通しを立てたが、やはり、使えない文科省とJSCだけあって甘かった。消費増税に加え、資材や人件費の高騰で、〈未来の日本人全体の希望(安藤氏の発言)〉には二五二〇億もの予算がかかることになったのである。
さらに言えば、本来なら昨年七月に始まるはずだった解体工事の入札で官製談合の疑いが浮上し、昨年十二月、三回目の入札でようやく業者が決まるなど、JSCがいかにお粗末な組織であるかも判明した。
また、東京オリンピック・パラリンピックに先んじて、二〇一九年にはラグビーのワールドカップが日本で開催される。このメインスタジアムも新国立競技場だから、JSCは工事を急がなければならないのだが、ザハ案のままでいくとW杯までに競技場の完成が間に合わず、開閉式の屋根工事は先送りすることになった(開閉式屋根の工事費一六八億円は今回の二五二〇億円に含まれず)。
屋根工区を担当するのは竹中工務店だが、同社はテレビのニュースを見て、初めて開閉式屋根工事が先送りになったことを知ったのだという。つまり、JSCから知らされていなかったということだ。JSCの担当者は文科省の出向者ばかりだから、民間のルールとか取引先との信頼関係というのがわからないのだろう。元文部事務次官も有識者会議の委員長だってえのに、あんな無責任な発言をするし。
私は思う。いったい誰がこんな滅茶苦茶なプランをゴリ押ししたのかと。
テレビ東京の『午後のロードショー』は今年二〇年目を迎えるが、今月の特集は「サメ」だ。残念なことだが、日本には「サメの脳みそ」と揶揄された元総理がいる。森喜朗氏だ。東京オリンピック・パラリンピックの実現には、ITを「イット」と読んで笑われたサメ頭の暗躍があるとも言われているのだ。
〈当初、五輪招致への再挑戦に消極的だった石原氏を口説き落としたのが森氏だった。スポーツジャーナリストの谷口源太郎氏は、「そこには森氏のしたたかな計算があった」と指摘する〉
「森氏は日本ラグビー協会の会長を長く務め、二〇一九年に日本で開催されるラグビーW杯招致に尽力していました。彼の狙いはまさにラグビーW杯の会場として新国立競技場を建設することでした。ラグビーW杯は準決勝と決勝の会場は集客人数八万人以上が望ましいとされているのですが、ラグビーW杯のために新国立を主張しても世論は動かせない。そこで、東京五輪のメインスタジアムにすることを口実にしたのです」
そして、こんなバックグラウンドも。
「石原氏が再立候補の狼煙を上げた日本体育協会とJOCの一〇〇周年事業のレセプションは、森氏自ら実行委員長を務めていました」
新国立競技場建設を既定路線としたのは、JSCが新体制になってからのことだ。
「新理事長に就いたのはラグビー協会の理事・河野一郎氏でした。彼は筑波大の教授で、五輪やラグビー代表のチームドクターでもあったドーピングの専門家。英語が堪能で弁も立つことから、森氏の強い意向で二〇一六年の五輪招致委員会の事務総長に選ばれた」(スポーツ紙記者)
が、彼が力を入れたのはラグビーW杯招致のほうで、二〇一六年の五輪招致には失敗する。
「ラグビーW杯招致にばかり熱心で、IOC委員にアタックできるチャンスをみすみす逃していたと招致委員会内部からも批判の声があがっていました。それなのに招致失敗の責任をとるどころか、スポーツ行政の鍵を握るJSCのトップに就任したので、周囲も驚いていました」
森喜朗氏の狙いがラグビーW杯の開催にあり、そのためにまずオリンピック・パラリンピックの東京開催を実現させ、JSCの理事長に息のかかったラグビー協会の理事をスライド就任させる。そして、W杯の準決勝・決勝戦を行なうため、八万人を収容できるよう国立競技場新しく建て替えさせた――、とすれば、森氏はたいしたマキャベリストではないか。
その森喜朗氏は、建設予算が二五二〇億と決まった直後、「これはあくまで国家プロジェクト」と言い放った。すごいぞ森喜朗! オリンピックをラグビーワールドカップの出汁にするなんて。
だから、もしかしたら、多くの人が森喜朗氏に踊らされていたのかもしれない。
週刊新潮の記者さんが、ザハ案を採用した安藤忠雄氏を自宅近くで直撃している。
「いや、ちょっと、私わからない。またね」
食い下がる記者さんに、安藤氏はキレたそうだ。
「いいから、来んといてくれや。はい、さいなら……、ええ加減にせえや! もう帰れよ! 」
紳士の振る舞いからは程遠い安藤氏だが、この人も、踊らされているのだろう。
ラグビー好きなひとりの思惑と文科省、その文科省から出向したJSCとが、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックのメインスタジアム建設予算をアンビリーバボーな二五二〇億円にまで押し上げた。実にぼんくらな仕事ぶりである。
新国立競技場の工費は二五二〇億だが、ここには一万五〇〇〇席の仮設スタンド、開閉式屋根の工費(一六八億円)は含まれていない。べらぼうな費用がかかる新国立競技場は、しかし、完成した後も問題をはらんでいる。
競技場の維持管理費に、五〇年間で一〇四六億円が必要になるというのだ。年間収支の黒字見込みは約三八〇〇万円ほどで、すると、新国立競技場は、毎年二〇億円前後が赤字になる。文科省やJSCは、その赤字ぶんの補填すらも、私たちの税金で補う心づもりでいるのだろう。
ザハ氏のデザインは「キールアーチ構造」と言い、二本のアーチで建物を支える特殊な構造になっているらしい。安藤忠雄氏は、日本の技術ならキールアーチを完成できると言っている。
私も、そうであることを願っている。文科省とJSCの仕事ぶりはお粗末きわまりなく、計画が二転三転してきた。工事だけはしっかりと、見事な新国立競技場をつくってほしい。
ぼんくらなお役人のぼんくら仕事を民間企業がカバーする。それが、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックである。
参考記事:朝日新聞・東京新聞・毎日新聞7月8日他
週刊文春6月4日号 週刊新潮6月18日号
降旗 学
安藤氏は新国立のデザインとして英国の女性建築家、ザハ・ハディド氏の案の採用を決めた平成24年11月の審査委員会の委員長を務め、日本スポーツ振興センター(JSC)が整備事業案を報告した今月7日の有識者会議での発言が注目されていたが、自己都合により欠席していた。
下村氏はこの日の会見で「(安藤氏は)堂々と自信を持ってなぜザハ氏の案を選んだのか。21世紀において、国内外にその重要性を何らかの形で発言してほしい」と述べた。
また、新国立のデザイン選考について、「(当初の総工費)1300億円がどの程度、公募の中で伝わっていたのか。値段とデザインを別々にしていたとしたら、ずさんだ」として検証する考えを示した。
 国立競技場将来構想有識者会議に参加した人々、日本スポーツ振興センター(JSC)及び文部科学省の関係者は理解できないことがあれば建築家の安藤忠雄氏
に質問しなかったのか?また、1300億円は計画の予算だったのか、それとも決まったデザインの見積もりだったのか?この点を明確にするだけで
部分的な責任は誰にあるのか判るのではないのか?
国立競技場将来構想有識者会議に参加した人々、日本スポーツ振興センター(JSC)及び文部科学省の関係者は理解できないことがあれば建築家の安藤忠雄氏
に質問しなかったのか?また、1300億円は計画の予算だったのか、それとも決まったデザインの見積もりだったのか?この点を明確にするだけで
部分的な責任は誰にあるのか判るのではないのか?
下村博文・文部科学相は10日、閣議後の記者会見で、新国立競技場の計画について「(当初予定した総工費の)1300億円がデザインする人に伝わっていたか。値段は値段、デザインはデザインということならば、ずさんだったことになる」と述べ、2012年の国際公募や選考の過程を検証する考えを示した。ほかの閣僚からも「デザインが決まったのは民主党政権時代」と、総工費膨張の原因を民主党に責任転嫁するような発言が相次いだ。
実施計画で了承された建築家ザハ・ハディド氏の案は開閉式屋根を支える2本の巨大な弓状の構造物(キールアーチ)が特徴で、総工費をつり上げた。下村氏はハディド氏がデザインする際、当初予定していた総工費を「どの程度認識していたのか」と疑問を呈した。
安倍晋三首相は10日の衆院平和安全法制特別委員会で「民主党政権時にザハ案でいくと決まったが、その後、検討を重ねる中で費用がかさんだ」と答弁。麻生太郎副総理兼財務相は会見で「建設費用が決まった経緯がよく分からない。(12年当時の)野田内閣に聞いてください。政権交代のときに渡されただけで、我々は額も知らされていなかった」と述べた。【田原和宏】
西田社長時代に不適切な対応が疑われているのはパソコン事業の部品取引を巡る会計処理。東芝は低価格で一括購入したパソコン部品を、購入時より高い価格でパソコンの製造委託先に販売していた。この部品取引に伴う利益計上の時期などが不適切だった疑いが浮上している。東芝関係者は部品取引について「パソコン関連で09年3月期に、それなりに大きな金額で不適切処理が行われていた疑いがある」と指摘した。
東芝は09年3月期、リーマン・ショックに端を発した世界的な金融・経済危機の影響で2000億円台の営業赤字に転落。業績を下支えするため、パソコン事業で利益の先取りをするなど不適切処理を行っていた可能性が指摘されている。西田氏は14年6月に相談役に退いているものの、第三者委の調査結果次第で、責任を問われることもある。
一方、田中社長は同社幹部らにメールなどで「何で予算を達成できないんだ」「売上高、利益をもう少し上げろ」などと強く求め、損失先送りなどを事実上、促していた疑いがある。また、社長就任前には部品などの調達担当役員を長く務め、パソコン部品の不適切処理などで責任を問われる可能性も浮上している。
一連の問題で14年3月期までの利益かさ上げ額は2000億円規模に拡大する可能性がある。田中社長だけでなく、佐々木副会長も社長時代に現場に強く業績改善を迫っていたことが明らかになっており、両氏の引責辞任は避けられない情勢だ。第三者委は20日前後にこの問題の調査報告書をまとめる予定。これを受け、東芝は経営責任の明確化を図る方針だ。【片平知宏】
【ことば】東芝の不適切会計問題
証券取引等監視委員会が今年2月、東芝に対して報告命令と検査を行い、問題が発覚した。東芝は4月に室町正志会長をトップとする特別調査委員会を、5月に上田広一元東京高検検事長が委員長の第三者委員会を設け、実態解明を進めている。これまでに次世代電力計などインフラ関連工事を中心に21件の不適切な会計処理が明らかになったほか、2014年3月期までの5年間で累計548億円の営業利益かさ上げが判明。第三者委は半導体、パソコン、テレビの主要事業でも不適切処理があったと見て調査し、金額はさらに膨らむ見通し。東芝は15年3月期決算を発表できず、期末配当を無配にする異例の事態に陥っている。
同社の関係者によると、田中社長は各事業を取り仕切る幹部などに対し、早朝に電話をかけて「何で予算を達成できないんだ」と迫ったり、メールで「売上高をもう少し上げろ」「利益を早く上げろ」などと要求したりすることがあったという。前社長の佐々木則夫副会長も同社関係者に業績改善を強く求めていたことが明らかになっており、既に取締役を退任する方向で最終調整している。
東芝はインフラ関連工事を中心に計21件の不適切処理があり、2014年3月期まで累計548億円の利益かさ上げがあったと説明。第三者委はインフラ関連に加え、半導体、パソコン、テレビの主要事業でも不適切処理があったと見て調べ、7月中旬をめどに調査報告書をまとめる方針だ。
東芝は第三者委の報告を受けて、経営責任の明確化を図る。【片平知宏】
発表によると、尾形容疑者は同社で経理担当を務めていた2012年8月28日頃、インターネットバンキングで取引先の2社に送金する際、水増しした偽の金額を担当者に伝えたうえ、水増しした分を自己名義の口座に振り込ませ、同社から約1000万円をだまし取った疑い。「ブランド品や家の購入資金が欲しかった」と話しているという。
同署は6月、尾形容疑者に12年7月から13年8月にかけ、約40回にわたって計約2億1000万円をだまし取られたとする同社の告訴状を受理しており、関連を調べている。尾形容疑者は2月に懲戒解雇された。
佐々木氏は最初の問題が発覚したインフラ部門出身で、現在は、経団連の副会長を務めている。
会計問題では、東芝幹部が業績を良く見せようとした「動かぬ証拠」(東芝関係者)が見つかっているもようで、弁護士などで構成する第三者委員会が意図的な会計操作と認定する可能性があるという。
今回の会計問題は佐々木氏が経営トップだった時代に集中しており、東芝は、辞任は避けられないと判断したようだ。東芝は第三者委員会の調査結果が出た段階で、経営責任を明確にし、新たな役員を選任する方針だ。
別の生徒からの暴力や、体調不良を繰り返し訴え、助けを求める「叫び」が記録されている。SOSはなぜ届かなかったのか。学校側は死亡にいたった経緯などの調査を始めた。
クラス替えが終わり、2年生としてのスタートを切った4月。ノートの書き出しは7日で、「学年がスタートした1日。この今日を大切に、でだしよく、終わりよくしたい」と意欲的な記述で始まっていた。異変が起きたのは、4月中旬だった。
〈最近、「いかれてる」とかいわれ、けっこうかちんときます。やめろといってもやめない。学校がまたつまんなくなってきた〉(4月17日)
父親によると、生徒は4月上旬頃から「(別の生徒に)ちょっかいを出されてうざい。学校に行きたくない」などと話すようになったという。
その後、生徒は「イライラする」「だるい」「つかれました」と徐々に体調不良を訴えるようになる。具体的ないじめの記述と共に、心理的不安も書くようになる。暗闇の中で人が迷っているイラストを添え、孤立感を訴える記述も出てきた。
別の生徒からの仕打ちについて「しつこい」との記述が続き、6月3日には「けんかしました。ボクはついに、げんかいになりました」とつづった。
そして担任に直接助けを求める記述が現れる。 〈次やってきたら殴るつもりでいきます。そうなるまえに、ボクを助け……〉(6月5日)
〈実はボクさんざんいままで苦しんでたんスよ?なぐられたり、けられたり、首しめられたり、悪口言われたり!〉(6月8日)
6月中旬には、担任が「きのう話しができてよかったです」と記載し、生徒と話をした形跡もある。
しかしその後、テストに関する記述が続くが、約2週間後に突然自殺をほのめかす。
〈生きるのにつかれてきた。氏(死)んでいいですか?〉(6月28日)
最後の記述は死の6日前だった。
〈ボクがいつ消えるかはわかりません。もう市(死)ぬ場所はきまってるんですけどね〉(6月29日)
これに対し、担任は学校行事についてのコメントしか書いていない。
この日を最後に、記述は途絶える。7月5日、生徒は祖父に「買い物に行ってくる」と言って外出したまま、帰らぬ人になった。
校長は7日の記者会見で、「ノートの内容について担任から報告がなかった」と述べた。担任は体調不良だとして7日から休んでおり、生徒が記載した後にどう対応したかや、生徒との間でどんなやりとりがあったかなどについて、学校側は把握できていない。(盛岡支局 福元洋平、安田英樹)
逮捕されたのは、同病院に勤務する菅原巧容疑者(62)(千葉市若葉区加曽利町)と、現在は退職している田中清容疑者(66)(千葉県市川市真間)。発表によると、両容疑者は12年1月1日、同病院の保護室で、入院中の男性(当時33歳)の着替えを介助する際、顔をひざで押さえたり、顔を蹴ったりして首の骨を折るなどの重傷を負わせ、14年4月28日、肺炎のため呼吸できなくなったことが原因で死亡させた疑い。
調べに対し、菅原容疑者は黙秘し、田中容疑者は「業務上の行為で、けがをさせようとしたわけではない」と供述しているという。
不起訴(起訴猶予)とする見通し。地検は、同容疑者が輸入したオキシコドンは膝の痛みを止める目的で家族から送ってもらったものだったことなどから、悪質性は低いと判断したとみられる。
関係者によると、ハンプ容疑者は「日本で規制されている薬だと知っていた」とは供述しているものの、「麻薬とは考えていなかった」と一貫して容疑を否定しているという。
ハンプ容疑者は、先月11日に麻薬であるオキシコドンを含む錠剤57錠を米国から国際郵便で成田空港に密輸したとして、同18日に警視庁に逮捕された。錠剤が入った宅配便は「ネックレス」と申告され、中にはプラスチック製のネックレスなどが入っていた。錠剤は一見してわからないよう箱の底などに敷き詰められていたという。
◇県が行政指導
いずみ熊谷の岡部陽子施設長らが4日に記者会見して明らかにした。事故を隠すために報告しなかったと認めたうえで、謝罪した。
岡部施設長らによると、昨年12月19日、女性入所者(88)に、別の入所者が服用するパーキンソン病の薬を介護職員が渡した。女性は薬を飲み、副作用による嘔吐(おうと)が原因とみられる誤嚥(ごえん)性肺炎で3日後に死亡した。介護職員は薬を置いた別の入所者の食膳を誤って女性に渡したという。県警が業務上過失致死容疑で捜査している。
同3月21日には、いなりずしを食べた男性入所者(84)が喉につまらせ、1カ月後に誤嚥性肺炎で死亡した。男性には食べやすいちらしずしを提供することになっていたが、調理を担当する職員らのミスが原因で、他の入所者と同じいなりずしを提供してしまったという。
いずみ熊谷ではこの他に、昨年4〜12月の間、入所者が転倒して腰の骨を折る▽入所者が入浴中に意識を失い救急搬送される▽職員が入所者に誤った量の薬を飲ませる▽入所者が喉に食事を詰まらせて肺炎になる−−など厚生労働省令に基づく県への報告が必要な事故が6件起きていたが、死亡事例2件をあわせた計8件を報告していなかった。
いずみ熊谷は2012年4月に開所。
入所者90人とショートステイ10人の計100人が利用し、職員は約70人。社会福祉法人「和泉の会」が運営している。
岡部施設長は会見で「利用者を心配させる事態を招き、心からおわび申し上げます」と話した。【安藤いく子、和田浩幸】
2010年3月期~14年3月期の5年間について、すでに公表したインフラ関連事業の548億円に加え、パソコン事業を中心にテレビ、半導体事業でも業績を良く見せる会計処理が行われたとみられる。田中久雄社長ら経営陣の進退が問われる事態が避けられなくなってきた。
外部の専門家による第三者委員会が17日にも調査結果を発表する。東芝の利益の過大計上額は、この間の営業利益の1割以上に相当することになる。
東芝は今年2月、証券取引等監視委員会による検査を受け、過去の会計処理について社内調査を開始した。その結果、ノンストップ自動料金収受システム(ETC)や、次世代電力計「スマートメーター」などインフラ事業を中心に、営業利益ベースで548億円の過大計上があったことが判明した。
その後、弁護士や公認会計士などで構成する第三者委員会が、他の事業についても調査を開始。新たに1000億円規模で不適切な会計処理が発覚した。パソコンについては、製造委託先に部品を販売する際、その利益を実態よりも多く計上した疑いがある。テレビは、広告宣伝費などの費用の計上を先送りしていたとみられる。半導体については、価格下落などに伴う在庫の評価損を適切に計上しなかった可能性がある。
受注業者の医療機器販売会社「西村器械」社員・西村幸造容疑者(39)は贈賄罪で略式起訴し、京都簡裁が同日、罰金60万円の略式命令を出した。罰金は即日納付された。
起訴状では、丸井容疑者は研究で使う医療機器を購入する際、西村容疑者に便宜を図った見返りに、2010年12月~13年9月、計5回にわたりバッグなど計17点(計約100万円相当)を受け取ったとされる。西村容疑者を略式起訴にした理由を「バッグなどは丸井容疑者が要求したため」としている。
捜査関係者によると、丸井容疑者は「准教授にふさわしい物を持つべきだと思い、バッグなどを要求するようになった」と供述しているという。
被害に遭ったのは、この会社だけではなかった。
当時の勤務先の社長は「(横領は)2,500万~2,600万円くらいあったと思う、今考えたら、恐ろしい女やな」と話した。
6月、兵庫・伊丹市の運送会社から、1,000万円余りを横領した疑いで逮捕された、元経理担当の岸田蓉子容疑者(66)。
運送会社の社員は、「バッグ等は、エルメスとかなんか、指輪とかは高級な指輪」と話した。
事件当時、岸田容疑者は、運送会社で経理を1人で担当し、13年間で、総額6億円以上を横領したとみられている。
そして、その金で、北海道・ニセコに一軒家を建てたり、総額3億円相当の美術品を買いあさっていたこともわかっている。
この横領が原因で、当時の社長は、自殺する事態になっていた。
自殺した社長の弟は「(自殺した兄は)資金を調達するために、日々走り回る状況。(岸田容疑者は)『足らんかったら、アンタ給料払われへんで』、『どうにかしろ』と。人間じゃないですよね、やっていることが」と話した。
実は、岸田容疑者が横領していたのは、この会社からだけではなかった。
当時の勤務先の社長は、「おそらくあの時に、(警察に被害届を)出していたら、今こんなことがなかったかもしれない」と話した。
伊丹市の運送会社に勤務する以前、大阪・豊中市の電機メーカーで経理を担当していた岸田容疑者。
実は、この会社でも、巨額の横領をしていたことが、FNNの取材でわかった。
岸田容疑者は、宅配便などの支払いに、会社の小切手を使うところを、自分の現金で支払い、余った小切手に好きな金額を水増しして記入し、銀行で現金化していた。
その横領額は、3年間で、およそ2,500万円にものぼる。
当時の勤務先の社長は「帳簿を全部ひっくり返して調べたら、(横領が)出るわ出るわで。(岸田容疑者に)『これ、お前がやったのだろう?』 と。(岸田容疑者は)『そうです』と」と話した。
また、当時の勤務先の社長は「(岸田容疑者の)娘さんの顔にちょっとしたあざがある、あざを取るために、金が欲しかったみたい。(岸田容疑者は)100%お金がなかったと思う。派手っぽいところは、この会社にいる時はなかった。警察ざたに十分なるが、(岸田容疑には)『ボチボチでも返せよ』と」と話した。
会社側は、岸田容疑者を刑事告訴せず、解雇。
そして、その翌年、岸田容疑者は、伊丹市の運送会社に就職し、のちに自殺者も出る、巨額横領事件に手を染めたとみられている。
当時の勤務先の社長は「どういうかたちで、そういうこと(横領)を覚えたのか、びっくりします。今考えたら、恐ろしい女やな」と話した。
7月1日、運送会社から、およそ1,500万円を横領していた疑いで再逮捕された岸田容疑者。
警察は、引き続き余罪について、捜査している。
日本郵便が業務上横領の疑いで調査しているのは、熊本県湯前町の40歳の前の局長です。
この問題は湯前郵便局内で不適切な処理業務の疑いが発生したため、日本郵便九州支社がこの前の局長から事情を聴いていたものです。
日本郵便によりますと、前の局長はおよそ1年前から郵便局内の金庫にあった現金1億数千万円を横領していたと見られています。今後、日本郵便は前の局長を刑事告訴する予定です。
日本郵便は「誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます」とコメントしています。
ともに同罪などに問われた元証券社員、羽田拓被告(52)は懲役3年、罰金600万円(同懲役5年、罰金800万円)▽小野裕史被告(53)は懲役2年執行猶予4年、罰金400万円(同懲役3年、同600万円)とした。そのうえで、3人から約8億8400万円を追徴するとした。
公判で横尾被告ら3人は、無罪を主張していた。
判決によると、横尾被告らはオリンパスの元社長=同罪などで有罪が確定=ら旧経営陣らとともに、2007、08年の3月期決算について、純資産額をそれぞれ1100億円余り水増ししたうその有価証券報告書を作成し、財務局に提出。その報酬で得た計約22億円を複数の外国銀行の口座を経由させて隠すなどした。
債権者説明会を7月1日(水)13時30分よりAP東京八重洲通りA会議室(中央区京橋1-10-7KPP八重洲ビル13F)で開催予定。
負債総額は10億9251万円(平成27年5月31日時点)。
大学発ベンチャーとして、人工的に温度や光等の環境を制御した水耕栽培作物の装置研究開発を手掛けていた。マスコミによる紹介で知名度を高め、水耕栽培装置およびその装置で生産された自社ブランド野菜「みらい畑野菜」の販売量を増やすなど業容を拡大、平成26年2月には千葉県柏市と宮城県多賀城市の工場が完成して稼働し始めた。
しかし、工場で安定した野菜の生産ができず、27年3月期は大幅な営業赤字を計上した。また、工場への設備投資に要した資金の返済期限がせまり、6月末の決済資金の目途が立たないことから、今回の措置となった。
スポンサーは現状未定だが、9月末までに決定して事業譲渡する予定。
NHKアイテックによると、部長は2013年度から14年度にかけ、実際には行っていない出張の経費を受け取ったり、1人で飲食した代金を接待費として精算したりするなどしていたという。14年度末のチェックで明らかになった。上司3人も訓戒や厳重注意の処分を受けた。
NHKでは昨年3月、二つの子会社で売り上げの水増しや不正流用が相次いで発覚。籾井勝人会長が社長を務めていた日本ユニシスの顧問弁護士を委員長とする調査委員会を設置して、8月に「NHKの監督強化や事業の整理」などの提言を受けていた。調査ではNHKに関連する子会社や公益法人など計26団体を対象にしていたが、新たな問題は発見できなかった。調査委員会には報酬として約5600万円を支払っている。(滝沢卓、星賀亨弘)
「同局は、編集ミスに加え、最終チェックが不十分だったと説明。」
お金と時間があれば最終チェックが不十分になることはないと思う。お金があれば人を増やせば問題なし。時間が無くても人を増やせば問題なし。
よってお金と時間の問題と思う。
同局によると、女性が「(韓国は)文化がたくさんあります」などと答えている映像に「(日本は)嫌いですよ。だって韓国を苦しめたじゃないですか」と日本語で吹き替えした。また、男性が「過去の歴史を反省しない」と言っている映像には「日本人にはいい人もいますが、国として嫌い」とかぶせた。2人とも別の場面ではナレーション通りの発言があったという。
同局は、編集ミスに加え、最終チェックが不十分だったと説明。「今後はこのようなことがないよう再発防止に努める」とコメントした。
起訴状によると、海津被告は昨年7月13日午後4時半ごろ、小樽市の市道で、飲酒の影響で前方を注意するのが困難な状態で乗用車を時速50~60キロで運転。北海道岩見沢市の会社員原野沙耶佳さん(当時29)ら4人をはね、原野さんら3人を死なせ、1人に重傷を負わせたなどとされる。
札幌地検は昨年8月、同法違反(過失運転致死傷)などの罪で起訴。だが、厳罰を求める遺族から7万人分を超す署名が提出されたのを受け、同10月、より罰則の重い危険運転致死傷罪に訴因変更している。一方で、地検は今月、過失運転致死傷罪などを予備的訴因として追加しており、合わせて審理される。
不正請求を確認すれば返還を求める。組織的な不正など悪質性が高いと判断された場合、保険医療機関の指定を取り消す行政処分が行われる可能性もある。
群馬大病院によると、問題の起きた旧第二外科では、2010年12月~14年6月に保険適用外とみられる腹腔鏡手術が計58例行われ、うち35例で診療報酬が請求されていた。具体的には、本来は保険適用外とみられる腹腔鏡手術を、保険適用された腹腔鏡手術や開腹手術として請求していた。
県警によると、捜索容疑は九州の60代女性に「必ず全額を返す」とうそを言って投資させたとしている。証券取引等監視委員会が3月、無登録でファンドを販売したなどとして、同社と同社社長、グループ会社の「ギフタージャパン」に業務禁止を命じるよう東京地裁に申し立てていた。【吉川雄策】
捜査関係者によると、錠剤が見つかった小包はミシガン州から発送され、ケンタッキー州の空港を経由、6月11日に成田空港に空輸された。ハンプ容疑者はこの小包について「父親から送ってもらった」との趣旨の供述をし、目的については「膝の痛みを和らげるために輸入した」と説明している。
オキシコドンを海外から郵送で輸入することは禁じられており、携帯して持ち込む場合は医師の証明書などが必要とされる。ハンプ容疑者は4月にトヨタ役員に就任した後、いったん米国に帰り、今月再び日本に入国していた。警視庁は、こうした機会がありながら宅配便で取り寄せた経緯を調べている。【斎川瞳】
借金をしてまで技能実習生になるメリットが存在する事自体おかしい。生活するだけの最低限度の支払い、そして/又は、衣食住の提供と経験だけで
十分である。そのかわり実習生のなのだから残業や長時間労働は禁止するべき。しかし、実際、外国人は稼げないと日本には来ないと思う。
実習生がほしい日本企業が増えれば、供給不足の問題も発生する。結局、システム自体が本音と建前を考慮していないから問題となる。
実習生の女性は「セクハラは辛くて、耐えられませんでした。監理団体に訴えたけれども、対応してくれませんでした。農家と監理団体に責任を取ってもらいたい。日本の司法は公正だと信じています」と話した。
会見には、この実習生女性から相談を受け、女性を支援している監理団体職員の男性(42)も同席。男性は「良心が耐えられないと女性を支援したら、監理団体に脅され、解雇された」として、女性と一緒に、解雇無効や賃金支払いを求めて監理団体を訴えている。
●「セクハラが次第にエスカレート」
訴状などによると、女性は2013年9月に来日。同年10月に茨城県の大葉生産農家と雇用契約を結んで働き始めたが、この農家経営者の父から、身体を触られるなどのセクハラを受けるようになった。
女性は来日する際、借金をして出国費用や保証金など約120万円を本国の送り出し機関に支払っており、借金の保証人となった親に迷惑がかけられないと思って、当初はしぶしぶセクハラを我慢していたという。
セクハラが次第にエスカレートしたため、女性は2014年8月に実習生受け入れ監理団体に相談。ところが、セクハラを隠蔽しようとした監理団体側から、黙っておくよう恫喝を受けたという。
女性は2015年1月18日以降、仕事を与えられずに放置されたため、現在は労働組合の支援を受けて、労組が用意してくれた住まい(シェルター)で暮らしているという。
●朝8時~深夜までの「作業」が連日
訴状などによると、女性が2013年に結んだ雇用契約では、女性が提示された時給は713円で、平日の労働時間は朝8時から夕方5時までという条件だった。
しかし、実際には朝8時~夕方16時に大葉を摘み取る作業があり、夕食と入浴後の17時からは、大葉を10枚ごとにゴムで束ねる作業に従事させられ、月によっては連日午前2時~3時まで続いたという。
この「大葉巻き」の作業について、雇用先の農家は「これは(労働ではなく)内職だ」として、1束当たり2円しか支払わなかったという。大葉巻きは、慣れた人でも1時間に150束程度しかできず、時給に換算すると300円程度だったという。
女性の代理人を務める指宿昭一弁護士は「大葉巻きの作業は労働で、残業代の支払いが必要だ」と指摘した。
●外国人技能実習制度は「人権侵害の温床」
技能実習制度は、途上国の労働者を受け入れて人材育成する「国際貢献」を目的とする制度だが、昨今では「低賃金労働者を雇用する手段」としての悪用が指摘され、見直しの議論も起きている。
指宿弁護士は「実習生は、劣悪な実習先に当たってしまったとき、他で働くという選択肢がありません。日本に来るために多額の投資や借金をしているため、途中で逃げ出しにくいこともあり、人権侵害の温床となっています」と制度の問題点を指摘していた。
学校給食費を「払えるのに払わない」とみられる未納が相次ぎ、埼玉県北本市立の中学校4校は、3カ月未納が続いた場合は給食を提供しないことを決めた。実施は7月から。未納額が膨らんだことによる苦肉の策だが、各家庭に通知したところ、該当する保護者43人のうち、納付の意思を示さない保護者は3人に激減した。
市教委によると、生徒1人あたりの給食費は月4500円で、全額が材料費。今年4月から6月まで3カ月分の未納が続く家庭の未納額は計58万500円。担任教諭が家庭訪問などで納付を求めてきたが、一部未納を含む全体額は約180万円に上っており、7月分の食材購入が危ぶまれる状況だった、と説明する。
そこで、4校の校長会は3カ月未納が続く家庭の保護者43人に、生徒に弁当を持たせるよう求めることにして、学校だよりなどで通知。「『有料』なものを手に入れる時は、それ相当額の支払いをするというのは社会のルール」などと書いた。すると、40人が実際に納付するか、「納付する」との意思を示したという。
該当する家庭に、生活保護を受給しているなど給食費を負担しなくてよい例はなく、家庭から学校に相談もなかったため、市教委は「いずれも支払うだけの資力があると考えられる」とみている。だが、「実際に弁当を持参させることは、他の生徒から好奇の目で見られるなど生徒へのマイナス面が大きい」として、細心の注意を払うよう校長会に指導。残る3家庭についても「今月中に一部でも納付してもらうよう努力する」と説明している。
大手薬局チェーンの調剤薬局で薬剤服用歴(薬歴)が大量に未記載だったことが相次ぎ発覚した問題で、2014年中に全国の調剤薬局1220カ所で81万件を超える未記載があったことが判明した。全調剤薬局の約2%に上る。業界団体が自主点検したもので、厚生労働省が24日、中央社会保険医療協議会(厚労相の諮問機関)で公表した。
薬歴は、患者ごとに薬剤師が記録。記載されていないと、副作用などの健康被害が起きる可能性がある。
調査は厚労省の要請を受け、日本薬剤師会、日本保険薬局協会、日本チェーンドラッグストア協会の3団体が実施。昨年中に薬歴を管理指導したとして診療報酬を申請したうち、1220カ所で薬歴の未記載があった。申請件数は2052万9703件で、このうち3・96%の81万2144件に記載がなかった。
名義貸しには医療コンサルタントの男も関与しており、県警は、形成外科部長と医療コンサルの男、鈴木被告の3人が、同院に常勤医師がいないことを隠し、無許可で診療所を開設した医療法違反の疑いが強まったとして、23日に逮捕する。
捜査関係者によると、部長は2012~13年頃、鈴木被告が同県岡崎市保健所に同院の開設届を出す際、知り合いの男性医師を開設者として鈴木被告に紹介した疑いがもたれている。部長は医療コンサルタントを介して名義を貸す医師を紹介し、報酬を受け取っていたとみられる。
本日(6月22日)、東洋ゴム工業さんは免震ゴム性能偽装事件に関する外部調査委員会報告書の全文を公表しました。300頁を超える大部であり、私は前半の「問題行為」についてはもっとも代表的な「G0.39」に関する問題行為の説明部分だけしか読んでおりませんが、240頁以降の「問題行為の発覚状況並びにTR及びCIの対応状況」「原因、背景」「再発防止策」等は精読いたしました。4月27日のエントリー「空白の3カ月に何が起きたのか」で投げかけた私の疑問は、やはり重大なポイントだったようでして、東洋ゴム工業社のトップの不正関与の有無を評価すべき根拠事実は、昨年10月23日から今年1月末までの事実関係から判断されることになります。
ただし、(法律専門職という立場上)東洋ゴム工業さんの役員の方々の不正関与を詳細に論じることは控えさせていただきまして、本日は私にとって関心の高い内部告発・内部通報に関連する事実関係のみ取り上げたいと思います。東芝さんの不適切会計問題が内部告発によって明るみになったことがご承知のとおりですが、私はこの東洋ゴム工業さんの免震偽装事件についても内部告発や内部通報の有無について関心を抱いておりました。ちなみに、このたびの不正事件に先行する2007年の断熱パネルの偽装事件でも、やはり内部告発がきっかけとなって発覚したことがあったそうです。
本日公表された外部調査委員会報告書によりますと、免震性能計算を引き継いだ社員が、前任者の改ざん疑惑に気付いたわけですが、この疑惑については内部通報も内部告発もされなかったそうです。つまり疑惑に気付いた社員は「前任者の計算がどうもおかしい」といった相談を上司に持ちかけ、その上司が調べたところ、やはり偽装疑惑が高まることになるわけですが、(内部通報が窓口に届く、ということはなかったために)最初に社員が気づいてから親会社のトップに疑惑が知らされるまでに1年を要したことになります。また、きちんとした社内調査部隊が構成されなかったことも問題とされています。
東洋ゴム工業さんには内部通報制度があり、それなりに通報の件数も多かったようですが、ではなぜこの疑惑に気付いた社員が通報制度を活用しなかったかというと「乙B(偽装の実行者)が行っていた補正に技術的根拠がないことが明確とはいえなかったため」だそうです(同報告書276頁注参照)。この理由は内部通報制度の活用において非常に重要なポイントであり、ヘルプライン規程等に通報対象事実として「不正事実」とある場合には、通報者はとても悩むわけです。自身が通報したい事実は、果たして「不正事実」に該当するのだろうか、もし該当しない場合は私自身が処分されるのではないだろうか、と逡巡し、最終的には通報をあきらめることがあります。もしヘルプライン規程の文言を「不正、もしくは不正のおそれ」として、できるだけ通報対象事実を広くとらえ、さらに社員研修等で「不正のおそれ」の概念を周知させていれば、上記のような社員の理由で通報を断念するケースは少なくなるものと思われます。本事件でも、仮に疑惑に気付いた社員が内部通報制度を積極的に活用できていたとすれば、親会社のトップが偽装疑惑をもっと速やかに知ることができたのではないでしょうか。
そしてもうひとつ、上記報告書には内部通報制度の活用を阻害するような重要な事実が記載されています。昨年10月23日、つまり東洋ゴム工業さんのトップが出荷済の免震ゴムを回収すべきか悩んでいたときに、「回収もせず、公表もしない場合のデメリット」が取締役間で議論されています。そのデメリットの第一として「公表しないままでいると、内部通報されてしまうデメリット」が挙げられています。同社の取締役らは、これを懸念して内部通報を行うおそれのある関係者リストを作成し、「事前説明」を行うことが提案されました(同報告書260頁参照)。この「事前説明」とはどのようなものか、外部調査委員会は不明としていますが、おそらく通報するおそれのある者を呼んで、もし通報した場合には社員等の身分がどうなるのか、あらかじめ説明をしておく、という意味ではないかと推測されます(これは私自身の推測です)。つまり内部通報・内部告発のリスクを同社は認識したうえで、このリスクをつぶしておこうと考えていたようです。
報告書のこの記述には少々驚きました。取締役が内部通報(内部告発)しそうな社員のリストを作成すること自体、尋常ではありませんが、その対象者に事前説明を行うというのも前代未聞です。会社の経営陣というのは、追い詰められてしまうとこのような対策まで真剣に考えてしまうのだろうか・・・と驚愕いたします。このような事実を知ると「やはり公益通報への不利益処分に対しては、なんらかのペナルティが必要ではないか」との思いを抱かざるをえません。
本事件が経営者関与、組織ぐるみの不正といえるかどうかは、昨年10月23日前後の同社役員の行動の評価次第であり、あまり明確にはされていません。また、監査役監査や内部監査等がなぜ機能しなかったのか、そのあたりも「情報が届かなかったから」で済ませてよいのかどうかは不明であり、このあたりは読む方にとって意見が分かれるかもしれません。ただ、公益通報者保護制度の改正を考えるうえで(なぜ内部通報制度は機能しないのか等)、本事件の事実経過が参考になることは間違いないものと感じました。
東洋ゴムが2007年に発覚した断熱パネルの耐火性能の改ざん問題で再発防止策を策定したにもかかわらず、免震ゴムで改ざんを繰り返した点を重視した。有識者委は国の認定制度見直しを含めた再発防止策を7月中に取りまとめる予定
東洋ゴム工業が免震ゴムの性能データを偽装していた問題で、製品を開発する部門の担当者に加え、上司や同僚が問題行為を指示したり、不正を知りながら出荷を黙認したりしていた疑いがあることがわかった。開発部門が測定したデータをチェックする品質保証部も、データを書き換えていたことが判明。個人的な不正にとどまらない内容で、会社としての責任が厳しく問われそうだ。
東洋ゴムが調査を頼んだ社外調査チームが22日午後、調査報告書を公表する。
報告書によると、品質保証部の担当者は、顧客からのクレームを避けるためや、事前に用意した資料に合うようにするためにデータを書き換えていた。「上司に相談したと思うが、記憶は定かではない」と証言しているという。
さらに、複数の社員が問題を認識していたことを示唆するメールなどもあるという。開発部門以外にも「(開発担当者に)心理的圧力をかけていたことが疑われる」社員がいるとも記している。
関与を否定する社員もいるため断定は避けたが、報告書は「関与が真実であるとした場合を想定した上で、十分な再発防止策にすべきだ」と提言。関係者の再調査も検討すべきだと指摘している。
4月の中間報告では、現在は子会社に移された開発部門の担当者と後任らが改ざんに関与。上司の監督が適正でなかったことや、担当者が納期に間に合わせるプレッシャーを受けたことが挙げられていた。
性能偽装があったのは、東洋ゴムが1996年以降に出荷した免震ゴム。全国の公共施設やマンションなど154棟に使われており、東洋ゴムがすべての交換を計画している。(新宅あゆみ、山村哲史)
弁護士と相談してどのようなコメントを出すのだろうか?
◇「膝痛で鎮痛剤使用」情報も
捜査関係者によると、錠剤は小袋やケースなどに分けられていたという。輸入に伴う書類では錠剤が見つかった小包の内容は「ネックレス」と記載され、中には玩具のようなネックレスやペンダントが入っていた。錠剤は小包の底にあったほか、ペンダントが入っていたケース内に敷かれた紙の下からも一部が見つかった。ハンプ容疑者は「麻薬を輸入したとは思っていない」と否認している。
一方、関係者によるとハンプ容疑者は来日以前から、右膝の痛みを抑えるために鎮痛剤を服用していたとの情報もある。オキシコドンは鎮痛剤として医療機関などで使用されており、処方箋があれば入手は可能。ただ、国外から日本に持ち込む場合は、手続きをしたうえで本人が携行しなければならず、郵送で取り寄せることは禁じられている。
同課は19日午前、ハンプ容疑者を東京地検に送検した。【斎川瞳、宮崎隆】
同庁幹部によると、ハンプ容疑者は今月11日、麻薬であるオキシコドンの錠剤57錠を米・ケンタッキー州から国際郵便で成田空港に密輸した疑い。小包の底に詰められていた錠剤入りの小袋を東京税関が発見、警視庁に通報した。
厚生労働省によると、オキシコドンはアヘンを原料とする医療用麻薬。がんの痛みの緩和などに使われるが、日本でも米国でも、医師の処方がないと使用できない。日本では、国の許可を得れば、個人が携帯して海外から持ち込むことができるが、郵送での輸入は認められていない。
警視庁の調べに対し、ハンプ容疑者は「麻薬を輸入したとは思っていない」と容疑を否認している。
ハンプ容疑者は米ゼネラル・モーターズ(GM)、米ペプシコなどを経て、2012年に北米トヨタに入社。今年4月、トヨタ初の女性役員に就任し、渉外・広報を担当している。
トヨタ自動車広報部は「逮捕については承知しているが、それ以上は把握していない。捜査には全面的に協力していく。今後の捜査を通じて、法を犯す意図はなかったということが明らかにされると信じている」とのコメントを出した。
ハンプ容疑者は米国出身で、今年4月に女性としてはトヨタ自動車で初の常務役員に就任。広報部門を担当している。
組織犯罪対策5課によると、ハンプ容疑者は今月11日、米国から日本に麻薬成分を含む錠剤57錠を輸入した疑いがある。空輸された宅配便を東京税関が調べたところ、麻薬を見つけたという。警視庁は、ハンプ容疑者が麻薬を個人的に利用するために輸入した可能性があるとみて、経緯を調べている。
ハンプ容疑者は米国自動車最大手のゼネラル・モーターズ社(GM)を経て、2012年には北米トヨタ副社長に就任した。
発表によると、青山容疑者は同支店次長だった昨年3月3日、前任の浜松支店の顧客だった浜松市内の60歳代の女性の口座から298万円を勝手に引き出し、着服した疑い。青山容疑者は、同じ女性の口座から2012年3月~昨年7月、9回にわたり計3078万円を引き出したほか、別の顧客3人の預金計1579万円を横領したとして、昨年9月に懲戒解雇され、10月に刑事告訴された。被害額は計4955万円に上る。
青山容疑者は、払い戻し請求書を偽造して1回に数百万円を引き出し、クラブでの飲食代などに充てていたという。
逮捕されたのは、大阪市旭区新森、無職重久公伯きみのり(49)、同市城東区成育、無職中島俊彦(42)、奈良県生駒市俵口町、会社員宇田悠作(35)の3容疑者。
発表によると、3人は同社に勤めていた昨年9月中旬から10月上旬にかけて、コシヒカリではない複数の品種が混ざった米を「新潟県産のコシヒカリ」と表示した袋に入れ、東京都内の取引先に3袋(計9キロ)を計3790円で販売した疑い。3人はいずれも「故意に偽装表示をしたことはない」などと容疑を否認しているという。
同社の出荷米を県が抽出検査したところ、コシヒカリではない6品種が15~85%混ざっていることが判明し、県が昨年11月に県警に刑事告発していた。
いまだ終息の兆しの見えない、MERSコロナウイルス。
こうした中、自宅隔離の対象となった日本人の母と子の2人が、すでに日本へ帰国していたことについて、16日朝、閣僚へ質問が相次いだ。>
岸田外相は「韓国政府とは連絡を取り合い、意思疎通を図っております。ただ、詳細につきましては、個人情報に通ずる部分もありますので、私からは控えさせていただきたいと思います」と述べた。>
菅官房長官は「適切な感染防止策を講じており、全く問題ないということであります」と述べた。>
詳細について、一様に口を閉ざしたが、FNNの取材で、2人の行動が徐々に明らかになってきた。>
MERS感染者に接触した疑いが持たれたのは、2歳の女の子。
韓国政府が事実を把握し、自宅隔離に指定したが、連絡が間に合わず、母と子は6月10日、すでに日本へ帰国していた。>
2人は、特段の自覚症状もなかったため、韓国国内で検査を受けていないとみられている。>
日韓政府関係者によると、日本政府がこうした事実を把握したのは、先週中のことだった。>
帰国した母と子は、まだ潜伏期間中だという。
現在、1日2回の体温報告をする健康観察の対象としていて、発熱などの症状は出ていない。
また、厚労省によると、この母と子とは別に、感染者と接触した疑いが持たれた日本人が、隔離対象となる前に、すでに日本に帰国したことは、6月に入り、数件あったという。>
一連の事実を、なぜ日本政府が公表しなかったのか。
塩崎厚労相は「無用な混乱を避けるという観点から、検体検査を実施して、その結果が陽性の場合に公表をする」と述べた。>
MERSは、発症するまで感染しないとみられるが、日本政府は、濃厚接触者は、外出自粛などの措置を取るとしている。>
一方の韓国は、幅広く自宅隔離の対象としており、状況が異なる両国で、対応の違いも際立っている。>
6月12日から、一時隔離対象となった韓国人の男性は、「わたしは働いていたが、すぐに家に帰れと言われた。公共の交通機関を利用するなと言われて、(当局が)救急車を職場に送ってきて、救急車の中で、通知書とマスクを渡されました」と話した。>
韓国では、16日、新たに3人が死亡し、死者19人、感染者154人となっている。
こうした事態に、WHO(世界保健機関)は、日本時間の16日夜、緊急に専門家会合を開き、渡航制限措置などについて協議している。
厳重な水際対策、そして、いざというときの冷静な対応が求められる。
韓国で150人の感染者が出ている「MERSコロナウイルス」で、韓国政府は15日、感染の拡大を防ぐため、医療機関や自宅での隔離の対象としている5200人の中に、日本人が含まれていることを明らかにしました。
韓国政府によりますと、日本人はいずれも症状が出ていないため、自宅での隔離の対象となっていましたが、関係者は隔離の対象となった日本人2人が、すでに日本に帰国していることを明らかにしました。
関係者によりますと、2人は患者がいた医療機関を訪れたため、念のため、自宅での隔離の対象者になったということで、症状なども出ていないということです。
厚生労働省によりますと、韓国で患者がいる医療機関を訪れ、日本に帰国した複数の人について、検疫所などが健康状態を確認しているということです。いずれも現地で患者と接触しておらず、発熱などの症状はないということです。
これについて国の専門家会議のメンバーで東北大学の賀来満夫教授は、「患者との接触歴がなければ、感染している可能性は低いし、仮に感染していても症状がなければ、ほかの人に感染を広げることも考えにくい。冷静に対応すべきで、行政は本人や家族に話を聞くなどして情報の把握を徹底してほしい」と話しています。
検疫所などは14日間、1日2回、発熱がないかなどを電話やメールで確認し、症状が出た場合はMERSコロナウイルスに感染していないかどうか検査を行うことにしています。
保健福祉省は同日の記者会見で、5200人超の隔離対象者のうち、日本人ら20~30人の外国人が含まれていると明かした。いずれも自宅での隔離対象者で、ウイルス検査の結果は陰性という。在韓日本大使館の関係者によると、隔離対象者の日本人はすでに日本に帰国し、日本政府が経過観察している。この日本人がなぜ出国できたかは不明だが、隔離対象者との通告を受ける前に出国した可能性もある。
大使館関係者は「(隔離対象者の)日本人が感染した、感染の疑いがあるという情報は伝わっていない」としている。
隔離対象者は感染が確認された人と同じ時間帯に病院に滞在したことなどを理由に自宅にとどまるよう求められた人が大半を占める。MERSコロナウイルスの潜伏期間は最大2週間で、すでに隔離が解かれた人もいる。韓国の政府関係者は「地域社会にMERSの感染は広がっておらず、統制可能な状況にある」と強調した。
文化体育観光省はMERSの感染拡大を受け、13日までに約10万8千人の外国人観光客が韓国旅行を中止したと発表した。中国や香港、台湾など中華圏が8万人超と全体の75%を占めており、日本が13%の1万4千人超でこれに続く。1~11日の外国人旅行客は前年同期比24.6%減った。
同省の当局者によると、外国人観光客が韓国滞在時にMERSに感染した場合、治療費を補償する保険商品を開発する方針を示した。観光業界を支援するため、総額720億ウォン(約80億円)規模の運転資金の融資制度も設ける予定だ。
世界保健機関(WHO)は感染終息の兆しが見えないことを受け、専門家による緊急委員会を16日に開き、対応を検討する。 (共同)
資本金1000億ドル(約12兆3000億円)のうち中国の出資額は最終的に297億ドルと最大になり、出資比率などに基づき算定する「議決権」も25%を超えて、最重要事項を決定する際に事実上の「拒否権」を持つことが確定した。運営の中心となる理事会では、出資額が上位の中国、インド、ロシアの3か国が常にポストを握る。
創設メンバー57か国の代表は29日、北京の釣魚台国賓館で設立協定に署名し、年内の業務開始をめざす。
設立協定によると、資本金の75%をアジアや中東の「域内国」が、25%を欧州などの「域外国」が、それぞれ負担。国内総生産(GDP)など経済力を基に算出した各国の出資額は、中国に続いて、インド83億ドル、ロシア65億ドル、ドイツ44億ドル、韓国37億ドルの順となった。
たぶん、これは氷山の一角だから運が悪かったのだろう。真面目な人が現場を目撃したのか、臨床研究総合センターの元准教授に対して良くない思いを
抱いていた所に不正を利用した、元准教授の失脚を望んでいた、不適切な随意契約を知っていた他の業者による通報等のいろいろな原因が推測できる。
どのような理由にしろ、脇が甘かったからこのような結果となった。
捜査関係者への取材でわかった。
捜査関係者によると、元准教授は同センターで血管再生医療の研究チームに所属していた当時、研究用の医療機器を随意契約で発注した際、同社が受注できるよう取りはからった謝礼として、2012年10月と13年9月の2回、同社社員からアメリカ製とドイツ製の高級キャリーバッグ3個(計約30万円相当)を受領した疑いがある。
問題の広告が、同法が禁じる誇大広告にあたると、厚労省は判断した。製薬会社が誇大広告で業務改善命令を受けるのは初めて。
京都大などによるブロプレスと他の薬を比べる臨床研究で、効果に明確な差がなかったにもかかわらず、同社は広告で、グラフに矢印を付けるなどして差を強調しようとした。このグラフは、ブロプレスが有効に見えるよう線がずらされていた。厚労省の聞き取りに同社側は、グラフの強調を認めたが、線の書き換えは否定したという。
厚労省は同社に対し、外部有識者を交えた広告審査実施や、法令に関する社員教育の徹底を求めた。同社は「心配をかけおわびする。必要な改善策を実施する」とのコメントを出した。
東日本大震災当日に運休したはずの新幹線を使ったと申告し、不正が発覚したという。男は容疑を否認している。
発表では、男は信者の勧誘活動などを行う本願寺宗務首都圏センター(東京)の総合庶務部長などだった2010年7~9月、打ち合わせで西本願寺に行ったなどと偽り、東京―京都間の新幹線代や宿泊費など9回分の出張経費計約44万円を詐取した疑い。
男は内部監査で不正が表面化した後の11年9月に依願退職したが、同派が14年1月、同署に告訴していた。同署は逮捕容疑以外にも計18回、約90万円分を不正請求した疑いがあるとみて調べる。
架空の報告は少なくとも過去10年間にわたって行われていた可能性があり、県は4日付で調査員を解任した。
県の発表によると、女性は1993年から県内で調査員を務め、月3回程度、食料品や家電製品の価格のほか、家賃などの調査を担当していた。
女性は今年5月に入院。県などが後任の調査員を選ぶ過程で、調査対象の一部の店舗がすでに廃業していたことが判明。調査資格のない実母に調査をさせていたことや、家賃調査で架空の家賃を報告していたこともわかった。県などは、過去の統計データへの影響を調査しているが、大きな影響はない見通しという。県統計課の担当者は「統計への信頼を失墜させ、申し訳ない」としている。
日本年金機構の年金個人情報流出事件は、8日で機構の公表から1週間。これまでにウイルスに感染した端末や乗っ取られた国内のサーバーは特定されつつあるが、サイバー攻撃の発信元は分かっていない。警視庁公安部は通信記録の解析を進めているが、サイバー攻撃では発信元を隠蔽(いんぺい)するソフトウエアを駆使することが多く、全容解明のハードルは高い。
◆日本しか狙わず
関係者などによると、職員に届いたウイルスメールはフリーメールサービスを使って送られていた。フリーメールサービスのアドレスは偽名でも取得でき、IDとパスワードさえ用意すれば複数、用意できる。
また、流出した個人情報の一部は、機構や攻撃者と関係ない都内の海運会社のサーバーに残っていた。何らかの脆弱(ぜいじゃく)性を突かれて乗っ取られ、遠隔操作の踏み台にされたとみられる。
今回の攻撃は「標的型攻撃」とされ、狙った組織の弱点をあらかじめ調査したうえで実行される。端末が感染したウイルスは「バックドア」型と呼ばれ、外部からコンピューターに侵入する「裏口」を用意する機能を持っていた。
攻撃者はこのウイルスに感染した端末を遠隔操作することで、端末内に保存されている情報や、端末が接続されているシステムに勝手にアクセスし、情報を盗み取る。
ウイルスの型やサーバーを乗っ取る手段などの特徴が合致することから、攻撃者は昨秋に衆院議員や大手企業にウイルスメールを送った攻撃者と同一グループか、その協力者ではないかとの見方もある。セキュリティー会社によると、このグループは「日本の組織しか狙わない」という特徴も持っているという。
◆途中から追跡不能
警視庁公安部は関係するサーバーや端末の捜査を進めているが、攻撃者の特定は困難を極めそうだ。
端緒となるのはそれぞれの通信履歴。機構や海運会社のサーバー、メールに表記されていたリンク先のサーバー、フリーメールサービスを利用したときのIPアドレスの記録が手掛かりになる。ウイルスのプログラムには、盗んだ情報のあて先が書かれている場合もあり、情報が流れた経路を把握するのにも役立つ。
しかし標的型攻撃を含むサイバー攻撃は、複数のサーバーを経由させて仕掛けられ、発信元を匿名化するソフトウエアが使われていることが多く、解析は容易ではない。
海外からの攻撃であれば、通信経路をある程度たどれたとしても、途中から追跡できなくなることがほとんどだ。海外のサーバーの記録を見るには管轄の捜査当局に照会する必要があるが、相手国によっては数カ月かかり「記録の保存期限が終わった」として回答が得られない場合も少なくないからだ。
今回のウイルスは中国語の書式が採用されており、「中国語圏の人物が関与した可能性があるが、だとすれば攻撃者の特定は極めて難しい」との声は多い。捜査関係者は「何らかのミスで余計な記録を残していないかなど相手の『綻(ほころ)び』を探しながらの捜査になる。時間がかかることは間違いないだろう」と話した。
発表によると、石田会長と田村修二社長は月額報酬20%を1か月返上。富永被告が所属した事業開発本部の本部長ら2人は月額報酬10%を1か月返上する。被告の直属の上司の開発部担当部長は5日間出勤停止の懲戒処分とした。いずれも管理監督責任を問われた。
同社は「今後二度と起こさぬよう、速やかな信頼回復に努める」とのコメントを出した。
 「文科省は安価な外国産への変更などを求めている」けど文科省の人間は品質や耐久性などを理解しての判断したのか?
デメリットを理解した上での判断であれば良いが、材質をケチると耐久性や維持管理が莫大な金額になることがある。
よく役人は自分達がその部署にいなくなれば関係ない、責任を問われないのだから目先だけの判断でよいと考えているような対応を取ることが
あるが、実際はどうなのか?
「文科省は安価な外国産への変更などを求めている」けど文科省の人間は品質や耐久性などを理解しての判断したのか?
デメリットを理解した上での判断であれば良いが、材質をケチると耐久性や維持管理が莫大な金額になることがある。
よく役人は自分達がその部署にいなくなれば関係ない、責任を問われないのだから目先だけの判断でよいと考えているような対応を取ることが
あるが、実際はどうなのか?
建設費が2500億円にも膨らむ可能性が浮上し、2019年9月開幕のラグビー・ワールドカップ(W杯)に間に合うか微妙な情勢だ。建築専門家はデザインの抜本的見直しを提言。費用負担を巡り、舛添要一・東京都知事と下村文部科学相との対立も深まっており、先行きは見えない。
◇衝撃
「建設費3000億円超、工期は50か月程度」。技術提案を基に施工業者に内定した大手ゼネコンの大成建設と竹中工務店が、この春提出したという見積もりに、文部科学省の担当者らは目を疑った。
昨年5月に事業主体の日本スポーツ振興センター(JSC)が公表した計画では、「建設費は1625億円、工期は42か月」で、19年3月の完成予定だった。
工期が「50か月」となれば、ラグビーW杯に間に合わない。見積もりの途中段階では、完成が翌20年の東京五輪・パラリンピック後になるとの説明すらあったという。
文科省などは、高い技術が必要なフィールド上の開閉式屋根の設置を五輪後に先送りすることなどで、費用を少なくして工期も縮めるプランの検討に入った。
騒音を防ぎ、雨もしのぐ開閉式屋根は、五輪後にコンサートなどの利用を増やすために計画された。屋根がなければ、今度は五輪後の収入が伸びないという問題を抱えることになる。
◇ツケ
相次ぐ見込み違いは、12年に採用が決定した斬新なデザインに起因するとの見方が強い。
採用されたデザインは、競技場の屋根にかかる2本の巨大アーチが特徴的。ただ、ゼネコンの見積もりでは、この「キールアーチ」と呼ばれる部分だけで、品質が高く高価な鉄が2万トン近く必要になるという。
文科省は安価な外国産への変更などを求めているが、ゼネコンとの意見の隔たりは埋まらず、政府関係者は「奇抜なデザインを選んだツケが今になって回ってきた」と皮肉る。
建築界のノーベル賞と呼ばれる「プリツカー賞」を受賞している建築家の槙文彦さん(86)らで作るグループは、巨大アーチがコスト高や工期の長期化を招いているとして、巨大アーチを取りやめるよう提言する。
グループは、現行のままだと建設費は2700億円を超えると試算。アーチを取りやめれば、最大1500億円程度に圧縮でき、工期も42か月程度に収まるとしている。槙さんは「今が計画を見直す最後のチャンスだ」と訴えている。
機構の業務体制に問題はないのか。マイナンバー制度の開始を控え、政府や公的機関の個人情報管理は大丈夫か。3氏に聞いた。
侵入後の対策も必要に…満永拓邦氏
一般社団法人JPCERT/CC
早期警戒グループマネージャ
サイバー攻撃を受けた企業を支援する業務の中で痛感しているのが、昨年からの標的型攻撃の急増だ。今回の日本年金機構へのサイバー攻撃は、このうち「クラウディオメガ」と呼ばれる海外グループの手口と類似しており、一連の攻撃である可能性が高い。
感染端末に命令を出したり、情報を送信させたりする指令用サーバーは以前は海外に置かれることが多かったが、このグループは国内に置くのが特徴だ。海外との通信が頻繁に発生すると被害者が異常に気づくため、発覚を遅らせる狙いがあるのだろう。
私が被害対応した企業では、システムに侵入されて平均1年は気づいていなかった。つまり、気づいた時には既に様々な情報が根こそぎ取られている場合が多いのだ。
標的は政府機関から企業、研究機関など幅広い。技術情報や研究成果など、日本経済の原動力となってきた貴重な知的財産が日々、奪われていくことに脅威を感じる。
海外からの攻撃であれば、通信経路をある程度たどれたとしても、途中から追跡できなくなることがほとんどだ。海外のサーバーの記録を見るには管轄の捜査当局に照会する必要があるが、相手国によっては数カ月かかり「記録の保存期限が終わった」として回答が得られない場合も少なくないからだ。
一方で、手口はどんどん高度化している。攻撃者はまず、標的企業と取引のある中小企業などに侵入し、メールのやり取りを盗み見してから、業務内容に沿った内容のメールを潜り込ませる。昨年、対応した案件では、見積もりを依頼した正規のメールに対して「見積もりができました」とウイルス付きメールを返信していた。私でも迷わず開けてしまうだろうと思った。今回の機構への攻撃では、添付ファイルを開けた職員を責める声もあるが、これほどメールの文面が巧妙になる中で、100%守るのは不可能だ。
ウイルス対策ソフトを入れていれば安心という時代も終わった。かつてのように、大量のウイルス付きメールを無差別に送る「バラマキ型」なら、ウイルス対策会社に集まるウイルス情報によって検知の精度を上げることができたが、標的型攻撃では標的企業にだけ反応するウイルスが使われるため検知が難しい。
だから、今後は「入り口対策」だけでなく、内部に侵入されてしまうことを前提とした、その後の対策が重要になる。今回は重要な個人情報が作業端末に置かれていたが、内部に入られても重要情報にはなかなかたどり着けないようにする工夫が必要だ。システム内部の異常や外部への不審な通信の監視、組織内に緊急対応チームを作ることも有効だろう。
欠かせないのが情報共有。我々の組織は被害対応によって得た情報を重要インフラ企業などに提供する枠組みをもっている。一方、内閣サイバーセキュリティセンターも政府機関への攻撃情報を、また総務省や警察庁などもそれぞれ管轄企業の被害情報を共有する仕組みを持つ。省庁ごとにバラバラに情報を持っていては勿体もったいない。業界をまたぐ共有も一部始まっているが、まだコミュニケーションが密でない面もあり改善が必要だ。
もう一つ、一般の人に対する情報提供も重要だろう。日本ではサイバー被害は隠される傾向にあるが、その結果、本当の脅威が社会に伝わっていないと感じる。知識としては理解しているが、どこか人ごとで、被害にあって初めて「まさか自分が狙われるなんて」と慌てる。攻撃の実態を正しく理解し備えるためにも、今後、被害情報の扱い方について検討が必要だろう。(編集委員 若江雅子)
みつなが・たくほう
セキュリティー会社を経て2011年から現職。サイバー攻撃を受けた企業などに対し、対応を技術的に支援したり手口の分析などを行ったりする。36歳。
旧社保庁の体質残る…東田親司氏
大東文化大教授
日本年金機構は、前身の旧社会保険庁が様々な不祥事を起こして解体されたことを受け、2010年に発足した。
年金記録問題が07年に表面化した際、私は総務省に設置された年金記録問題検証委員会の委員として、原因究明に参加した。そのときに驚いたのは、旧社保庁の特異な組織体質だ。
旧社保庁の職員は、3種類に分かれていた。厚生労働省から来る上層部のキャリア職員と、社保庁の本庁採用組。そして圧倒的多数を占めていたのが、各地域ごとに採用される、ノンキャリアの現場職員だ。人事などでの交流が乏しく、組織としての一体感がなかった。キャリア職員は、組織全体を統率できていなかった。
現場職員は、多くが自治労傘下の労働組合に加入しており、労組が職場を牛耳っていた。オンラインシステムの導入など、加入者や受給者の利便性を向上させるような業務の改善も、組合が「仕事が増える」と反対したため、なかなか進まなかった。
ガバナンス(統治)の欠如した組織体質が、コンピューターで管理する年金記録の中に、基礎年金番号と結びつかず誰のものかわからない記録が約5000万件も生じる背景になった。職員が端末装置を使い、有名人の年金記録を勝手にのぞき見していた問題など、多くの不祥事が起きた。
この反省を受けて発足した日本年金機構は、組織体質の改善を目標に掲げた。日本年金機構法には、年金に対する国民の信頼確保が目的として明記されている。そのためには本来、業務の隅々まで見直さなければならなかったはずだ。
ところが今回、機構では個人情報とつながるパソコンを使って、職員がメールのやりとりをしていた。届いたメールでパソコンがウイルスに感染し、情報が流出した。個人情報を扱う作業は本来、インターネットと接続しない環境で行うべきだと指摘されている。
個人情報が保存されたファイルには、パスワードを設定するよう内規で定められていたが、流出したファイルには設定されていないものも多く、簡単に見られる「内規違反」の状態だったという。機構の職員は、大半が旧社保庁からの移籍組だ。看板は「日本年金機構」に変わっても、仕事が増える面倒なことはしたくないという、旧社保庁の悪あしき組織体質が、まだ残っているように見える。
今回流出した情報は、基礎年金番号、氏名、生年月日、住所の4種類とされている。機構はこのほかにも給与など、よりプライバシーに関わる情報を大量に保有しており、4種類の情報はその確認に使われる。個人情報保護の重要性を、組織全体できちんと認識していたかは疑問だ。機構は、漏れた情報だけで第三者に年金を取られる可能性は低いと説明しているが、年金制度への信頼に与えたダメージは計り知れない。
政府は組織体質の問題点まで掘り下げて原因を究明し、個人情報の管理に万全を期す必要がある。(編集委員 石崎浩)
ひがしだ・しんじ
旧総務庁行政監察局長を経て2000年から現職。専門は公共政策論。総務省の「年金記録問題検証委員会」委員を務めた。69歳。
情報管理 投資惜しむな…上原哲太郎氏
立命館大情報理工学部教授
マイナンバーを用いた公的機関の情報交換は専用の回線を使う。インターネットとは切り離されており、マイナンバー制度が情報漏えいのリスクを高めることはない。
年金情報の流出事件は、基幹システムから取り出した基礎年金番号を業務端末にコピーして放置するという情報管理の初歩的なミスが原因で、マイナンバーとは無関係だ。また、マイナンバー制度実施後も、年金の受給額や所得額などの最も守るべき情報は公的機関ごとに分散管理される。本人の情報がまとめて芋づる式に流出する事態にはならないよう設計されている。
一方、従業員のマイナンバーを管理する民間企業は、厳しいアクセス制限を求められるが、情報流出の可能性がゼロではない。もし、民間企業が情報流出に気づかなかったり、放置したままにしたりすると、悪意のある個人や組織がマイナンバーを使い、本人の様々な情報を何らかの方法で寄せ集め、商売の道具にしてしまう危険性がある。万が一、情報が流出した場合はすぐに公表し、番号を変えるなどの対策を講じる必要がある。それが、今回の事件から学ぶべき教訓だ。
職員による不正の可能性も指摘されるが、マイナンバー法では情報の故意の提供に対して、最高で懲役4年の罰則が設けられた。端末で検索する際に履歴が残るなどの技術的な仕組みもあり、十分に抑止力はあると思う。とはいえ、最後は職員のモラルが頼りで、情報管理の徹底には必要な投資を惜しむべきではない。(編集委員 阿部文彦)
うえはら・てつたろう
京大工学部卒。総務省・経済産業省の暗号技術検討会委員。NPO法人「情報セキュリティ研究所」理事。47歳。
阿部容疑者らは平成19年以降、丸峰容疑者が以前勤務していた同行荻窪支店などに対し、巨額の業務を請け負ったとする偽造の契約書を示して業績を粉飾。計20億円以上の融資をだまし取っていたとみられる。
阿部容疑者らは4億円しか返済しておらず、残りの融資金は別の借入金の返済や会社の運転資金に充てていた。同社は24年12月に破産手続きを開始。25年10月に同行が阿部容疑者を刑事告訴していた。
逮捕容疑は21年10月、同行荻窪支店に対し、約2600万円で請け負った高速道路測量業務の受注金額を5億3500万円に偽造した契約書を示し、計約4億5千万円の融資を受けたとしている。
落胆の社長
「じくじたるところは109年に及ぶ歴史に幕を下ろすことで、強く責任を感じている」
福井市内で4月30日に行った記者会見で、社長の江守清隆氏(54)はこう悔やんだ。負債総額は4月末時点で約711億円。帝国データバンクによると、2000年以降に経営破綻した福井県に本社を置く企業の中で最大規模だ。
江守グループホールディングスは5月29日付で、中核企業の江守商事を含む主要8社の全株式をスポンサー企業などが出資する特定目的会社に譲渡。創業家の江守氏は江守商事の社長を退任した。
中国に傾注
同社は明治39年に江守薬店として創業。昭和33年に江守商店となり、45年に江守商事に改称。染料、工業薬品、化学薬品などで業容を拡大し、平成18年に東証1部に上場。26年4月に持ち株会社に移行した。
一方、6年の上海事務所設置のころから中国への進出を強め、化学品や電子部品などの販売で業績を伸ばした。26年3月期決算の連結最終利益は4期連続で過去最高を更新し、売上高は2千億円を突破した。
ところが好調な業績とは裏腹に、中国の大口取引先からの代金回収が滞ったほか、中国子会社の不正取引などによる特別損失計上で、26年12月末時点で234億円の債務超過となっていた。
同社の売上高のうち中国市場は7割を占め、過大な中国依存度が屋台骨に大きな衝撃を与える結果につながった。
チャイナリスク
複数の民間信用調査会社の関係者は「中国での取引でだまされたという印象もあるが、放漫経営の側面も否定できない」と厳しい見方を示す。
ビジネスでの現金の流れを示す営業キャッシュフローは26年3月期まで5期連続でマイナス。一方、金融機関からの借り入れなどを反映する財務キャッシュフローは膨らんでおり、ツケを回収できないまま、借り入れでまかなっていた財務状況は明白だった。
中国での不正を見抜けなかった
中国子会社の不正を見抜けなかったことに対する風当たりも強い。江守は3月、中国子会社の経営トップだった元総経理が、親族が経営する会社と取引を行っていたと発表。元総経理が内部規則に違反し、江守の承諾を得ずに親族の会社と取引を行い、最終的な販売先が仕入れ先と同一の「売り戻し取引」が見つかったという。本来は手数料収入だけとするはずの利益を商品売買の売り上げがあったように計上していた。
同社は8社の事業と社員の雇用は維持するとしているが、経営は創業家の手を離れた。江守氏は「苦渋の決断だった」と落胆を隠せない。中国傾注の代償はあまりにも大きかった。
サイバー攻撃の防衛対策は公務員では無理だろう。外部委託になると、外部委託先からの情報漏えいのリスクや膨大な管理費を支払わなければならない
可能性もある。費用対効果を考えると実際はどうなのか?
同機構によると、電子メールの添付ファイルを開封したことで端末がウイルスに感染し、不正アクセスを受けた。情報流出は5月28日に判明。基幹システムである社会保険オンラインシステムへの不正アクセスは今のところ確認されていないが、さらに調査を進めている。
流出したのは約125万件の基礎年金番号など。うち約116万7000件には生年月日が、約5万2000件には住所と生年月日が含まれていた。
同機構は2日から、情報が流出した加入者から年金の手続きがあった場合には、本人確認をした上で手続きを行う。今後、基礎年金番号を変更して対処する方針。
流出した加入者には個別に通知して謝罪するとともに、不審な連絡があった場合の専用電話窓口を設置した。電話番号はフリーダイヤル(0120)818211。
千葉大によると、助教は2013年5月に発行された韓国の学会誌で、同じ研究グループの元大学院生作成の資料を韓国語に翻訳し、出典を明記せずに掲載した。同月に行われた学会で助教が講演した際も、スライドで使用していたという。
ワイヤは静脈を破って左肺付近に達し、2日後に摘出された。患者はその後、出産し、退院したという。
病院の発表によると、昨年4月、産科の男性医師がカテーテルを患者の右肘の静脈から挿入した際、管内のワイヤを抜かず、そのまま留置した。患者が翌日、肩や左上半身の痛みを訴えたためエコー検査などを行い、抜き忘れが発覚。上半身を3か所切開してワイヤを摘出した。
ワイヤはカテーテルをスムーズに挿入するために管内にあり、挿入後は抜き取る必要があるが、医師は知らなかったという。病院が設置した医療安全調査専門委員会は、医師に十分な知識がなかったと結論づけた。
岸本哲夫社長をはじめ全取締役が月額報酬10~20%を2カ月間自主返上する。
元従業員は着服した金をギャンブルなどに充てていた。北越紀州製紙は長期間発覚しなかったことについて「長年同じ業務に携わり、他者によるチェックが難しかった」(総務部)と説明している。
その一方で、かつては世界一の漁業国であった日本の地位が低下している。総漁業量は1982年時には1282万トンだったが、2012年には484万トンと3分の1に激減。中国などに後れをとり、いまは世界第8位に甘んじている。かつお・まぐろ類の漁獲量に関しても、日本は45.8万トンで世界第2位を維持しているものの、第1位のインドネシアの66.6万トンに大きく引き離されている状態だ。
このように苦戦する日本の漁業だが、その理由は何なのだろうか。
■ 深刻な高齢化問題
自民党本部で5 月26日、かつお・まぐろ漁業推進議員連盟第7回総会が開かれた。総会には新代表に就任した鈴木俊一元環境相や副会長の小野寺五典元防衛相など議連のメンバーの他、「日本かつお・まぐろ漁業協同組合」、「一般社団法人全国遠洋かつお・まぐろ漁業者協会」と「一般社団全国近海かつお・まぐろ漁業協会」が参加した。
さらに管轄官庁である水産庁に加え、国土交通省や厚生労働省、さらに外務省や法務省、財務省からも関係法規の担当者が出席し、日本のかつお・まぐろ漁業が直面する諸問題について話し合った。
今直面している課題・・・そのひとつは高齢化問題だ。
「全国遠洋かつお・まぐろ漁業者協会」によると、2012年時の同会所属船の年齢構成は平均56歳で、60歳以上が37%を占める。さらに新規就業者は5名にすぎず、同協会は船員確保と育成が喫緊の課題だと訴えた。
実際に高齢化問題は深刻で、水産庁のデータでは漁業就業者は約18万人で、過去10年間で3割減少した。遠洋まぐろはえ縄漁では60歳以上の就業者が42%を占めており、50代をも含めると、全体の83.3%にも上る。
政府は漁業の存続のため、毎年度2000人の新規就業者を確保すべく、「新規漁業就業者総合対策支援事業」として本年度予算に6億1400万円を計上した。また「沿岸漁業リーダー・女性育成支援事業」に3300万円、「安全な漁業労働環境保全確保事業」に1900万円を充てている。
しかし根本的な問題を解決せずして、漁業の問題は解消されない。日本の漁業にとって乗り越えなくてはいけないのは、コストの増大と年々厳しくなる国際環境だ。
■ 高騰する入漁料
コストに関しては昨今の急激な円安による燃料費の高騰もあるが、より深刻に関係者を悩ませているのは高騰する入漁料など国際環境の変化に基づくものだろう。
2014年6月にナウル協定加盟国(PNA:パプアニューギニア、ソロモン諸島、パラオ、ミクロネシア、キリバス、ナウル、ツバル、マーシャル諸島で構成)が2015年1月から1日あたりの入漁料(VDS)を8000ドルに引き上げたことは、日本の遠洋漁業に大きな衝撃を与えた。PNAのEEZ(排他的経済水域)は日本にとって海外まき網漁獲量の9割を占めているからだ。
そもそもPNAがVDSを導入した2005年以前では、南洋海域での入漁料は漁船1隻あたり年間約2000万円で、操業日数に制限はなかったのだ。さらに2012年に最低価格制度が導入されてから、入漁料はいっそう高騰。水産庁は日本が払うべきこうした入漁料は2015年には55億5600万円に達すると見込んでおり、漁船1隻あたり必要とされる入漁経費は年間1億7000万円を超えると予想されている。
「VDSが導入されて、外国は1日あたりの漁獲量が増えるように漁船を大型化した。一方で日本は国内の利害調整ができなくて、水産庁が漁船の大型化を許さなかった」
日本漁船の建造が法律で制限を受けていた間に外国に引き離されたと述べるのは、かつお・まぐろ議連で事務局長を務める自民党の井林辰憲衆院議員だ。井林氏の地元は焼津港を擁する静岡2区。焼津港は全国トップクラスの水揚げ量や水揚げ金額を誇り、かつお漁やまぐろ漁の大拠点地でもある。
実際に日本のまき網漁船ほとんどは1000トン型で、中国や台湾、韓国などが標準とする1800トン型と比べて漁倉容積や速力などで遅れをとっている上、魚群探査用ヘリコプターの搭載もない状態だ。
外国漁船の脅威は大型化だけではない。「全国遠洋かつお・まぐろ漁業者協会」は、台湾系の小型漁船が南太平洋島嶼国に船籍を移して増隻していることに危機感を募らせている。
そもそも小型漁船は十分な冷凍設備を持たないためにOPRT(責任あるまぐろ漁業推進機構)の管理枠外とされていたが、これら新規の小型船はマイナス50度の超低温設備を備えており、規制の目をくぐりぬけているからだ。
■ 政府の積極的な研究調査も必要
また「全国近海かつお・まぐろ漁業協会」は、パラオ共和国で外国漁船商船漁業禁止法案、ミクロネシア連邦でサメ法案が出されており、日本漁船が海域から締め出される危険性について政府の対処を求めている。
こうした問題について井林氏は、「政府を通じて適切な国際ルールを作っていくこと、また島嶼国にはODAの水産無償資金協力を行っているが、これを国内漁業者の入漁確保に資するように活用していくことが重要だ。外務省は『ODAは紐付きであってはならない』と原則にこだわりがちだが、漁業を守ることこそ国益にかなうことだ」と述べる。
さらに水産資源について、政府の積極的な研究調査も必要だと井林氏は主張する。たとえば昨年はかつおが歴史的な不漁で、外国漁船による南洋での乱獲が原因ではないかと言われたが、真相はまだ解明されていない。
「実はかつおの生態はよくわかっていないところがあり、南洋で成魚に発信器を付けても、日本海域で発見されなかった。おそらくは北緯20度あたりで一度産卵し、それが成魚となり北上するのだろうと推定されているが、詳細は不明だ」。
水産庁はこの「ミッシングリンク」の早急な解明に務めることを言明。原因がわかれば対策を打つことも可能だが、それを後押しするのは政治の役割だと井林氏は述べる。「日本の漁業は伝統産業であり、食文化を担う重要な役割も果たしている。我々はこれをしっかりと守っていかなければならない」。
安積 明子
中国は欧米の銀行にも同様の要求をしている模様だ。
経産省などによると、中国は14年末、国内に設置するATMなどには、中国で登録されている特許技術を使うように求めるガイドライン(指針)を示した。事実上、ATMなどで現在使われている技術を中国で特許登録することを義務付ける内容だ。
特許を登録すれば、公開が原則なので、第三者でも閲覧できる。日本企業からは「ATMなどに使われる技術は、企業秘密であるだけでなく、防犯上の問題もあり、到底開示できない」との声が広がっている。
三木、深井両容疑者の逮捕容疑は、株価をつり上げる目的で、実際は取引実態がないのに中国から仕入れた発電機25台を転売したとして、平成25年11月、26年6月期の連結業績を上方修正する虚偽の予想を発表したとしている。
岡登容疑者の逮捕容疑は、実際には発電機25台を280万ドル(27日午後2時半時点の日本円で約3億4千万円)で購入したのに、26年5月、購入費約10億円を支出したなどと虚偽を記載した報告書を提出し、資源エネルギー庁所管の補助金5億円を不正に受給した疑いが持たれている。
石山ゲート社をめぐっては証券取引等監視委員会が26年10月、有価証券報告書に虚偽の記載をしたとして金商法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑で強制調査。特捜部も同容疑などで捜査を進めていたが、捜査の過程でテクノ社による補助金詐欺の容疑も浮上していた。
石山ゲート社が設置した第三者委員会は26年12月、発電機の売買契約は中国企業とテクノ社との間で直接結ばれ、仲介取引は存在しないと指摘していた。
三木容疑者は産経新聞の19日の取材に「(第三者委の指摘を受けて)上場廃止を避けるために決算を訂正した。取引の存在が認められなかったのは残念だ」と話していた。
一方、岡登容疑者は22日、産経新聞の取材に「補助金を不正に受給した認識は全くない」と書面で回答していた。
補助金は東日本大震災後の電力不足を機に新設された自家発電補助制度。当初、石山ゲート社が主体となって申請されたが、最終的には事業主体がテクノ社に変更され、同社に補助上限の5億円が支給されていた。
捜査2課によると、奈良田容疑者は同行横浜支店の支店長代理だった2011年4月~13年5月、顧客4人に金融商品の購入を勧め、払い戻し請求書と通帳を預かって顧客の口座から現金計約1870万円を払い戻して横領した疑いがある。同課の説明では、逮捕容疑を含め、顧客計33人の口座から02年5月以降、現金約1億1千万円が引き出された疑いがあるという。奈良田容疑者は「ぜいたくな暮らしをしたかった。飲食費に使った」などと述べ、関与を認める供述をしているという。
昨年4月、顧客の1人から同行に「買ったはずの社債がない」と相談があり、被害が判明。同行は昨年9月、奈良田容疑者を懲戒解雇とし、警視庁に告発していた。
三菱東京UFJ銀行広報部は「元行員が逮捕されたことは誠に申し訳なく、深くおわび申し上げる」とのコメントを出した。
兵器転用の恐れがある機器や技術は、国際的な取り決めで貿易が制限されている。一定以上の強度がある炭素繊維は経済産業相の許可が必要な「リスト規制」の対象となっており、炭素繊維の不正輸出を巡る逮捕は初めてという。
県警によると、近藤容疑者ら3人は、強度が高い国内メーカー製の炭素繊維数千キロを韓国・光州市の企業に販売すると偽って申請し、許可を不正に取得。2010年1月、大阪・南港から韓国・釜山経由で、中国に輸出した疑い。
炭素繊維は中国・人民解放軍の関連先に渡った可能性があるといい、県警は、軍需物資の製造に転用された疑いもあるとみて調べる。
請求額は明らかにしていない。
訴状などによると、助教は2012年1月、同大の男性教授から「違う場所を探しなさい。大学での臨床はしなくていいから」と言われ、手術室などがある手術場への出入りを禁じられた。また、同年5月には、同大の女性講師が助教に退職届の書類を送るよう秘書に指示し、助教は書類を受け取ったという。
助教はこれらのことを病院長に伝えたが、大学側が適切な対応を取らなかったとして、「技術の習得や研さんの機会が不当に奪われた」と主張している。同大は「個人情報に関わることでもあり、コメントできない」としている。
職員は協会に対し、「借金の返済や生活費に使った。申し訳ないことをした」などと話し、うち300万円を弁済。残りも弁済する意思を示しているという。協会は職員を21日付で自宅謹慎処分とした。被害金額は現在も調査中で、月内にも県警へ被害届を提出する方針。
発表によると、21日に協会の監事が2014年度決算の監査をした際、職員が通帳の提出を拒んだことから、協会が調査した。
その結果、協会の基金を管理する定期預金の通帳と定期預金の証書、協会の関連団体「鶴岡市スポーツ強化後援会」の寄付金などを管理する通帳の計3通の残高が、決算額よりも計約1100万円少ないことが判明した。
職員は1994年に同協会に採用され、20年間経理を担当。業務で金融機関を訪れる際、協会の通帳と印鑑を使って無断で現金を引き出していたという。職員は「約10年前から使い込んだ」とも話しているという。
協会の稲泉真彦会長は25日夜に開いた記者会見で「指導・管理が不十分で不正が発生した。市民の皆様に深くおわびしたい」と謝罪した。
今後、刑事告訴を検討する。
発表によると、男性職員は2010年3月から15年5月までの間、89回にわたり、農家に支払う金額などを記入する経理伝票を架空に作成。振り込み先を家族名義の口座にして金を横領していた。伝票作成には上司の印鑑が必要だが、男性職員は上司が不在の時に印鑑を無断使用した。
今年2~4月分の仮決算で、農家への支払額が前年に比べて多額だったため発覚。男性職員は同農協の調査に対して、「住宅ローンや教育資金、生活資金に使った」と話しているという。親族から全額が返納されており、男性職員は出勤停止になっている。今後処分を決める。
問題を受け、同農協は印鑑を施錠できる場所に保管するなどの対策を取る。
ツルハHDは、子会社「くすりの福太郎」(千葉県鎌ケ谷市)の小川久哉社長が辞任して取締役に降格、後任に阿部光伸ツルハHD常務(61)を充てる人事を決めた。いずれも31日付
発表では、調剤薬局がある85店舗を調査したところ、2013年2月末時点で薬歴19万8073件が管理システムに入力されていなかった。ほかに今年1月までの1年間で、1か月以上の入力遅れが18万5111件、未入力が3万9494件あった。同社はこのうち、計41万7125件で不適切な診療報酬請求があったと判断、厚生労働省と協議した上で自主返還するとした。
また、同社は5月31日付で、くすりの福太郎の小川久哉社長が取締役に降格、ツルハHD取締役兼専務執行役員を辞任すると発表した。
内相はメガテレビで、6月のIMFへ返済総額は16億ユーロだが「返済する資金はない」と述べた。
債務不履行(デフォルト)によるクレジットイベントについての質問には「模索しておらず、望んでもいない。われわれの戦略ではない」指摘。その上で「(債権団との)強力な合意に向け協議を続けている」と述べた。ただ債権団が求める極端な財政緊縮策には反対するとした。
またラファザニス・エネルギー相は24日、「いわゆる(国際)機関は過去4カ月の間、ギリシャ国民に苦痛を点滴注入してきた」と非難。向こう数日間で約束に沿う形での合意に至らない可能性に備え、政府は準備する必要があるとの考えを示した。
検査では建築士らのチェックを受けることになるため、違法建築の疑いを把握し、改善指導ができた可能性がある。政令市で除外しているのは川崎市のみ。同市は、市建築基準法施行細則を改正し、簡宿も対象とする方針だ。
同法では、不特定多数が利用する宿泊施設などの所有者・管理者に対し、定期的に専門家の検査を受け、建物の構造や防火設備などを各自治体に報告するよう定めている。対象施設の種類や規模は各自治体の裁量に任され、それぞれ施行細則で規定している。
川崎市の施行細則では、床面積の合計が300平方メートル超のホテルと旅館に年1回の報告を求める一方、簡宿は対象外としていた。
読売新聞の取材に対し、川崎を除く全国の19政令市と東京都はいずれも、一般のホテルや旅館などと同様に簡宿にも1~3年に1回の報告を義務付けていると説明している。
川崎市建築指導課は「かつては簡宿も定期報告の対象だったという話があり、何らかの理由で外されたとみられるが、経緯は調査中。今後、実態把握できるような制度を検討する」とする。
今回の火災で、出火元の「吉田屋」は延べ床面積が545平方メートル、延焼で全焼した隣の「よしの」は463平方メートルで、除外規定がなければ、ともに定期報告が義務付けられる宿だった。
直近5年間の支援規模(約850億ドル)よりも3割増やす。政府資金を呼び水にして民間資金を取り込み、成長著しいアジアを官民一体で支援する。
安倍首相は、「アジアにおいて、いかなる国の恣意しい的な思惑によっても左右されないフェアで持続可能なマーケットを作り上げよう」と述べた。中国が主導するアジアインフラ投資銀行(AIIB)に対抗し、日本独自の取り組みをアジア諸国にアピールする狙いがある。
具体的には、国際協力機構(JICA)が、低金利で長期間融資する円借款や投融資などで支援する資金を従来より25%増やす。JICAは、国際金融機関であるアジア開発銀行(ADB)と連携し、民間事業に出融資を行う新たな仕組みを作る。
国際協力銀行(JBIC)も、これまでよりも積極的にリスクを取った融資を行い、資金支援を倍増させる。
同法が禁じる「誇大広告」に当たると判断した。同省によると、製薬会社が誇大広告で業務改善命令を受けるのは初めて。
同社は、ブロプレスと他の薬の効果を比べる臨床研究で、明確な差はないとする結果が出たにもかかわらず、ブロプレスが有利に見えるグラフを広告に使っていた。同法は医薬品に関して、虚偽や誇大な広告を行うことを禁じている。
研究は京都大などが2001~05年に実施。同社が昨年6月に公表した第三者機関の調査報告書では、ブロプレスの売り上げを伸ばすため、研究段階で社員が一定の関与をしたことは認めたが、虚偽広告や誇大広告には当たらないとしていた。
長崎造船所の別の工場にある「ジャイアント・カンチレバークレーン」など4施設は「明治日本の産業革命遺産」として、国際記念物遺跡会議(イコモス)が今月4日、「世界文化遺産への登録が適当」と勧告した。【竹内麻子】
不妊治療を手がけていた大阪市立総合医療センターで、患者の知らないうちに精子の凍結保存が打ち切られていた。「絶対に子どもがほしい」。そう願っていた妻は、夫からその事実を知らされて、泣き崩れた。
大阪府池田市の会社員、北村哲也さん(30)は2003年、同病院で血液の病気の骨髄異形成症候群と診断された。当時は18歳。治療のために放射線治療を受け、抗がん剤を服用することになった。副作用で精子のもとになる細胞がなくなる恐れがあったため、両親や医師の勧めで03年12月に精子を凍結保存した。保管費用は無償だった。
9年後の12年12月、交際していた現在の妻(28)と同病院を訪れた。北村さんは「子どもが自分と同じ病気になるかもしれない」と子どもについては消極的だったが、「女性に生まれた以上、絶対に子どもが欲しい」と説得され、「父親になりたい」と考えるようになっていた。
診察室では、産科部長から「凍結精子は保管されています」と説明を受けた。ただ、「専門の医師が異動したので、病院としては不妊治療ができなくなりました。できるだけ早く、別の病院に移管してほしい」と告げられたという。
「すぐに移管先を見つけるのは無理かもしれないので、それまで管理してもらえますか」と尋ねると、産科部長は「勝手に破棄することは100%ない」と言ったという。この点について病院側は否定している。産科部長によると、13年3月末までに移すよう求めた上で、「期限が来たらピタッとやめるわけじゃない、とは言った」という。
「結婚するまで、置かせてもらおう」。そう話した2人は、今年1月に結婚した。凍結精子を移せるクリニックを見つけ、4月に同病院に問い合わせた。翌日、職員から電話があった。「移管をお願いしていたが返事がなく、管理が行き届かない状況になった。使用に関して医学的には担保できません」
「あかんて」。北村さんが事情を伝えると、妻は泣き崩れた。「あかんてどういう意味? 何でなん?」
4月25日、北村さんは副院長をはじめ医師4人と職員1人に面会した。電子カルテには「12年度中(13年3月末まで)の移管をお願いした」と書かれていた。ただ、期限を過ぎれば廃棄するとの記載はなく、書面による説明や同意書の作成記録もなかった。
医師たちは「連絡がなかった。病院に責任はない」と謝罪にも応じなかった。北村さんは「大きな病院でちゃんと管理してもらえると信じていた」と話し、病院側の謝罪を求めている。
凍結精子を移す予定だったクリニックの診断で、北村さんの今の精子は動いていないことがわかっている。今後、手術で精巣を開き、精子のもとになる細胞が残っているかを確かめる予定だ。精子が見つかる可能性は30%前後だという。(藤田遼)
大阪市立総合医療センター(大阪市都島区)が、患者2人の了承を得ずに精子の凍結保存を中止していたことが朝日新聞の調べでわかった。不妊治療で精子を使おうとした患者の問い合わせで発覚した。病院側は1人に謝罪したが、別の1人には別病院に精子を移すよう求めていたとして、問題ないとの見解を示した。
保存を打ち切られたのは大阪府と奈良県の30代の男性2人。大阪の男性によると、精子をつくる機能に悪影響が懸念される放射線治療などのため、2003年12月にあらかじめ精子を凍結保存した。奈良の男性は04年11月に凍結保存した。
同病院によると、12年4月に責任者の婦人科副部長が別病院に異動。その時点で計13人分の精子を無償で凍結保存していたが、昨年9月ごろ、元副部長の指示で凍結保存のための液体窒素の補充が打ち切られた。
元副部長によると、12年4月の異動時に「1年をめどに患者の意向を確認してほしい」と口頭で看護師に依頼していたため、保管期限が13年3月末までということが患者にも伝わっていると思い込んだという。液体窒素の補充をしていた医師も、患者の了承が得られているか確認しなかった。
今年4月、精子を使おうとした大阪の男性が同病院に問い合わせて凍結保存の中止が発覚。病院側が調べたところ、13人中6人については元副部長が事前に了承を得ており、3人は死亡していた。別の2人には「1年ごとに意思表示をしなければ廃棄する」と書いた文書を渡していた記録が見つかった。
しかし、大阪と奈良の2人には了承を得ていなかった。奈良の男性には今月15日に電話で謝罪したという。大阪の男性については、13年3月末までに別病院に精子を移すよう、12年の受診時に依頼していたとして、問題ないとの見解を示している。男性は「勝手に廃棄することはないと説明された」と主張しているが病院側は否定している。
保存容器は現在も病院内にあるが、内部の精子の機能は失われているという。(藤田遼、西村圭史)
■説明不十分だった
〈大阪市立総合医療センターの瀧藤伸英病院長の話〉 大阪の男性については、凍結保存継続の意思表明がなかったので保管をやめた。他の病院に移管するよう伝えていたので対応に問題はない。言葉がなくても、移管をお願いした期限より先は保証できないという意思があった。その意味を患者が受け取れたかは何とも言えない。説明が不十分だったことは否めず、文書も示して説明すべきだった。奈良の男性には謝罪した。結果的に男性は精子を使う予定がなかったが、そうでなければ取り返しのつかないことになっていたと思う。
列車が事故直前に急加速した原因について謎が深まる一方、人為ミスを補う安全システムの不備が明らかとなり、米交通の大動脈が抱える根深い問題が浮き彫りとなっている。
◆赤字体質
長距離鉄道の安全対策を所管する連邦鉄道局(FRA)は16日、アムトラックに対し、今回の事故路線に、制限速度に達するとブレーキがかかる安全装置の導入を急ぐよう指示した。
アムトラックは今年末までにこの安全装置を全路線で導入する予定だったが、全米で最も利用客の多い「北東回廊」と呼ばれるワシントン―ニューヨーク―ボストン間では、事故現場を含む北行きの路線で未整備の区間が目立っていた。
安全対策が遅れた背景には、日本の旧国鉄のような公営企業であるアムトラックの恒常的な赤字体質があるとの見方が出ている。国家予算から年間十数億ドルの補助を受けなければならず、設備投資の資金も限られるためだ。
アムトラックに対する2015年度の補助金は13日、運営に批判的な共和党が多数の下院歳出委員会で、前年より約2億6000万ドル少ない11億4000万ドル(約1359億7000万円)で可決された。
民主党のペロシ下院院内総務は14日の記者会見で、削減された支出に安全装置設置費用も含まれていたと述べ、「不幸なことだ」と嘆いた。共和党のベイナー下院議長は同日の記者会見で、今回の事故原因と補助金不足を結びつける質問に「本当にそんなくだらないことを聞くのか」と声を荒らげた。共和党内では、アムトラックの運営が非効率だとの見方が大勢を占め、民営化を求める声も根強い。
「後藤さんは、シリアで拘束される前の昨年10月8日に民放のテレビ番組に出演した際、1日あたり約10万円の掛け金で、英国の会社の保険に入っていると話していた。」
この発言はテレビのためだけのものだったという事か?実際、誘拐された時に当事者や家族が困るだけ。それで保険会社が交渉に動かなかったのか?
誘拐保険に加入していないことは妻や知人には伝えていたのだろうか?殺害された今となってはどうでも良いことか?
警察当局が保険会社などに確認した結果、判明したという。
後藤さんは、シリアで拘束される前の昨年10月8日に民放のテレビ番組に出演した際、1日あたり約10万円の掛け金で、英国の会社の保険に入っていると話していた。
後藤さんが殺害されたとみられる映像が公開されたことを受け、警視庁などは、人質強要処罰法違反容疑などで捜査を開始。保険会社に加入状況を確認するとともに、後藤さんの口座を調べるなどした結果、一般的な海外旅行保険にしか加入していなかったことが判明した。この海外旅行保険は病気や事故などは補償されるが、テロは対象外で、今回の事件でも保険金は支払われていないという。
夜間に多数の逃げ遅れが出たことを重視し、夜間を想定した避難訓練の実施なども指導するよう求めている。
この火災では、17日未明に出火し、多数の宿泊客が建物に取り残され、一部は2階から飛び降りるなどして避難した。出火元の「吉田屋」が、無届けで「3階建て」となっていた疑いも持たれている。このため、総務省消防庁は、防火対策が脆弱ぜいじゃくな施設が多い簡易宿泊所の実態を早急に把握する必要があると判断した。
地域政党・大阪維新の会代表の橋下氏が推進してきた「大阪都」構想の賛否を問う住民投票は、反対が僅差で賛成を上回った。投票率は66・83%に上り、市民の関心の高さを示した。
これに伴い、政令指定都市の大阪市を廃止して5特別区に分割し、広域行政を大阪府に移管する制度案は廃案となり、大阪市が存続することが決まった。
橋下氏は記者会見で、「都構想を説明し切れなかった私自身の力不足」と敗戦の弁を語った。
橋下氏らは、「府と市の二重行政の無駄を省き、生み出した金で豊かな大阪を作る」と強調した。行政改革分を含め、財政効果は年155億円に上るとも訴えた。
都構想に反対する自民、公明両党などは、財政効果は年1億円にすぎないと反論した。「大阪市を分割すると、住民サービスが低下する」とも主張した。
読売新聞の世論調査では、2011年以降、賛成が多数だったが、先月27日の告示前には賛否が拮抗きっこうし、告示後は反対の方が多くなった。財政効果が不透明な中、身近な行政サービス低下への懸念を感じる人が増えたためだろう。
橋下氏は、維新だけで制度案を作成し、市議会の十分な議論がないまま住民投票に持ち込んだ。この強引な手法も批判を招いた。
大阪市は、企業の本社機能の流出が続き、「商都」としての地盤沈下が指摘されて久しい。生活保護受給者の割合も格段に高い。
今後も、大阪市の活性化に向けた議論は継続する必要がある。
道府県と政令市の二重行政は、大阪だけの問題ではない。
昨年の地方自治法改正で、16年度から知事と政令市長の「調整会議」の設置が義務づけられる。人口減時代に道府県と政令市がどう連携するか、議論を深めたい。
維新の党にとって、都構想の頓挫は大きな打撃である。最高顧問の橋下氏は、12月の市長任期満了後の政界引退を改めて表明した。江田代表も辞任する意向を明らかにした。党全体の影響力の低下は免れまい。
安倍政権との関係にも変化が生じよう。橋下氏は、安全保障政策や憲法改正で首相と考えが近く、政権との協力を重視してきた。
維新の党が今後、どんな路線を取るにせよ、「責任野党」として建設的な政策論争を政権に仕掛ける姿勢を忘れるべきではない。
東京の安宿を探してみると山谷では三畳一間の個室に2000円台で宿泊可能でした 2014年11月11日(Gigazine)
火元とみられる吉田屋は1961年、よしのは62年に築造された。床面積などの要件から、2階建てと見なされているが、部屋は3階まである。一般的に、60年代に建てられた木造建物が耐火建築物だった可能性は低く、市によると両施設とも建築基準法に違反する可能性が高いという。同市は、新築当時から3階建てだったのか、あるいは後に無断で増築されたのかを市消防局などと共同で調べている。
同市には、類似した構造の簡易宿泊所が多数ある。同市は再発防止を目的に「市の関係部署や国と協力し、これらの施設の実態調査を実施することも検討する」(同課)と話している。【太田圭介】
◇市など現場検証
川崎市川崎区の簡易宿泊所2棟(ともに木造3階建て)が全焼して5人が死亡、19人が重軽傷を負った火災で、神奈川県警川崎署と川崎市消防局は18日午前、連絡の取れない宿泊者ら行方不明者の捜索を再開し、現場検証を行った。失火と放火の両方の可能性があるとみて原因を調べている。
この火災では火元とみられる吉田屋の焼け跡から5人の遺体が見つかり、うち1人は吉田屋に宿泊していた市川実さん(48)と判明。川崎署によると、吉田屋の宿泊者名簿には44人、隣接する「よしの」の名簿には30人の名前があった。そのうち吉田屋の男性8人前後と連絡が取れておらず、身元が分かっていない4人の死者はこの中に含まれるとみられる。ただ出火当時、何人の宿泊者がいたかは判明していない。
吉田屋の火災現場では午前9時半過ぎ、マスクやゴーグルを付けた警察官や消防隊員ら約60人が集まり、焼け跡で作業を始めた。わずかに焼け残った壁や柱などの一部を見て回ったり、がれきを掘り起こしたりした。現場の周囲はブルーシートで覆われ、通りを挟んだ公園では、避難した宿泊者や住民ら数十人が集まり、作業を見守っていた。【村上尊一、福永方人、国本愛】
宿泊客らの話では、1部屋が3畳程度の広さで1泊2000円前後。同市などによると、吉田屋は1961年、よしのは翌62年に建てられており、高度経済成長期には、港湾などで働く日雇い労働者の利用が多かったが、最近は、長期宿泊する高齢の生活保護受給者が目立っていたという。
17日時点で、吉田屋を居住地として生活保護を受給している人は38人で、よしのを居住地として受給している人も35人いる。持病で欠勤が続いて解雇され、簡易宿泊所で生活しているという50歳代男性は「自分は若い方。10年、20年と住んでいる70歳代、80歳代の人も多い」と話している。
創設メンバーが57か国まで増えたため、資本金は当初予定した500億ドルより大幅に増やす。出資比率の算定方法も固まり、中国は20%台後半でトップとなる。創設メンバー国は節目となる設立会合を6月下旬に開く方向で調整している。
資本金は1000億ドル(約12兆円)には達しないが、近い規模とする方向で詰めている。中国は最大で50%出資する意向も示していたが、3割を切る水準に落ち着く見通しだ。中国の発言権を落とし、信頼性の高い国際金融機関として運営する狙いがあるとみられる。中国に次ぐ出資比率は、インド、ロシア、韓国の順となる見通しだ。
講師は同大の就業規定に基づく処分を受けて辞職した(いずれも4月20日付)。同大は「講師の個人情報に関わること」として、処分内容のほか、講師の性別や年齢なども公表していない。
同大や文部科学省によると、講師は佐賀大大学院の医学博士号の学位取得を証明する「学位記」を偽造し、2013年4月に西九州大に採用された。13~14年度に学生を指導したが、3月下旬に匿名で文科省に「学位は詐称ではないか」との情報提供があり、同大が調査を開始。4月27日に学位記が偽造されていたことが文科省に報告された。
博士号の取得は採用の条件ではなかったという。講師の指導により学生が取得した単位は取り消さない。
報道陣の取材に対し、同大の向井常博学長は「(詐称を)見抜くことができなかった責任は重い。深く反省している」と話した。同大は在籍する教員の学歴を出身大学などに確認しており、採用時の確認も徹底するという。
同大は小城市に開設を予定する4年制「地域看護学部」(仮称)の17年の認可を目指している。文科省は学部などの認可基準で、申請内容に教員の経歴などの虚偽や不正があった場合、最長5年は認可しないと定めており、今回の詐称が認可に影響する可能性もある。文科省は「大学側から受けた報告内容を精査し、認可基準を適用するか検討したい」としている。
ホンダは同日、今回のリコールが日本を含む世界で約490万台に上ることを明らかにした。2008年以来、タカタ製エアバッグにからむ同社のリコールは自主回収なども含めて約1960万台に膨らんだ。
新たなリコールに踏み切ったのは、調査を目的に国内で無作為に回収したエアバッグのガス発生装置でガス発生剤の異常が見つかったためだ。仮に異常破裂が起きれば乗員を傷付ける恐れがある。原因は特定できないものの、昨年12月のリコール同様、「被害を防ぐための予防的措置」(広報部)を取った。当初のリコールは、タカタが00年代前半に海外工場で生産したエアバッグが対象で、発生剤の成形時の圧力不足や湿度管理など製造上の不備が主な原因だった。だが、その後も、米国などで原因不明の異常破裂が相次いだ。
タカタや自動車メーカーは回収したエアバッグの調査を進めている。タカタがガス発生剤に使用する硝酸アンモニウムは気温や湿度によって不安定化しやすく、過酷な環境での経年劣化や設計上の問題なども指摘されているが、特定には至っていない。今回、国内各社が届け出たリコールの対象車は主に04~08年ごろのモデルで、これまでの中心だった00~03年ごろのモデルより新しい。
関係者によると、男性は2013年9月、同支店の勧誘を受け、グーグルやツイッターなど海外6社の株式を1000万円分購入。営業担当者が毎日、電話で男性に虚偽の終値を報告していた。
男性の妻が14年11月、運用状況を聞いたところ、担当者は損失額を56万円と説明。態度などを不審に思った妻が上司に釈明を求めると、実際は6倍近い約310万円に上り、担当者の電話報告がうそだったことが判明した。
男性側は「証券取引に対する信頼を根底から失いかねない行為で、極めて悪質だ」と批判。虚偽報告の詳しい説明と賠償を求め、ことし4月、和解の仲介を申し立てた。結論次第で訴訟を提起するという。
金融商品取引法は契約に関して虚偽内容を顧客に告げた場合、企業に2億円以下の罰金、担当者にも1年以下の懲役や300万円以下の罰金を科すと規定している。
岡三証券グループは「個別事案につき、回答できない」(グループ広報部)と話している。
チェーン薬局で薬剤師資格のない事務員が患者の薬を作っていた実態が明らかになった。薬を処方される患者への背信行為ともいえる無資格調剤。発覚することはほとんどないが、この薬局にとどまることではないようだ。
今回問題となったファーマライズ社の首都圏の薬局は、総合病院から道路を挟んだ徒歩1分の住宅街にある。店に入ると、正面に処方箋(せん)の受付があり、右側に薬を受け取るカウンター、その奥にガラス張りの調剤室がある。関係者によると、薬剤師4人、事務員2、3人が働いていた。
朝日新聞が入手した録音記録には、薬剤師と事務員の生々しいやりとりが残されていた。
昨年12月5日、薬剤師から塗り薬を混ぜて作るよう指示された事務員。戸惑いながら薬剤師に相談する。
「私、これ混ぜられる自信ないんですけど」
「硬いほうに、軟らかいのをちょっとずつ混ぜて」
「ちょっと見ていただいていいですか」
朝日新聞は、薬剤師法が禁じる無資格調剤の様子が録音された音声記録を入手した。薬剤師資格のない事務員が飲み薬を作るなどしている記録は、昨年11月から今年3月まで続き、調剤の様子だけでなく、患者とのやりとりも含まれている。 「硬いほうに、軟らかいのをちょっとずつ混ぜて」
患者の症状に応じて薬を混ぜる行為は分量などを間違えると意識障害など患者の健康に影響を及ぼす危険もある。厚生労働省医薬食品局は「薬そのものを配合する行為は薬剤師自身が行うべき業務で、医薬品の安全性確保の観点からも問題だ」としている。
今回、無資格調剤が判明したのは調剤薬局チェーンの「ファーマライズホールディングス」(本社・東京、東証1部上場)傘下の首都圏の薬局の一つ。今年2月には、保健所が無資格調剤の情報を得て立ち入り調査したが確認できなかったという。朝日新聞の取材に対して同社がこの薬局での無資格調剤の事実を認め、厚労省も同社から事情を聴いている。
元指導員は4月に全額を返還しており、運営委員会は刑事告訴しない方針。
運営委員会と市の発表によると、元指導員は経理を担当していた10年4月~14年5月、領収書を偽造するなどして児童クラブの口座から金を引き出していた。元指導員が退職した後、経理を引き継いだ別の指導員が不審な領収書に気づいて発覚。市が14年8月から調査を始めていた。
元指導員は着服を認め、「住宅ローンや子どもの学費に充てた」と話しているという。運営委員会の二神和徳会長は「児童や保護者に申し訳ない。会計の体制を強化するなどし、再発防止に努めたい」としている。
山梨県警は道路交通法違反(酒気帯び運転、事故不申告)などの疑いで調べている。
同社広報室によると、男性部長は7日夜に同僚4人と甲府市内の飲食店2店でビール中ジョッキ3杯やワインなどを飲んだ後、同社から車で山梨市内の自宅に帰る途中に事故を起こした。男性部長は同社に対し飲酒運転を認め、「気が動転して逃げてしまった」と話しているという。
県警や同社によると、車のナンバーの目撃情報から男性部長の車が浮上し、日下部署員が自宅を訪れて事情を聞いたという。同社は「高い倫理観と重い社会的責任が求められる報道機関の社員としてあってはならない行為」とした。一方、同社は男性部長の実名について「警察の捜査が任意取り調べの段階」として明らかにしていない。
総務省推計の4月1日時点の総人口1億2691万人で割ると、国民1人当たり約830万円の借金を抱えている計算となる。
借金の内訳は、国債が881兆4847億円。13年度から27兆7211億円も増え、借金依存の体質をあらためて浮き彫りにした。
山本社長は「ご迷惑をおかけした皆様におわびいたします」と謝罪する一方、同社がいったん決めた出荷停止をすぐに撤回したことについて、「許容される方法で算出したデータが基準を満たしているという報告があった。隠蔽とは考えていない」と釈明した。
4月に公表された社外調査チームによる中間報告書では、明石工場の元課長代理に加え、2013年1月に元課長代理から業務を引き継いだ社員ら2人も性能のデータを改ざんしており、うち1人が同年夏頃には上司に改ざんを報告していたことが明らかになっている。
◆大使館に「白い粉」
「インドネシアの法的な主権は尊重されなければならない」。ジョコ大統領は4月29日、外国人7人を含む麻薬犯8人の死刑執行後、反発を強める死刑囚の出身国政府に対してこう語り、死刑に反発する声に対して、強くけん制してみせた。
刑を執行された外国人の国籍は、豪州が2人、ブラジル1人など。このうち豪州の2人は「バリ・ナイン」と呼ばれる密売グループの主犯格。8・3キロの麻薬密輸に関与したとして2005年に逮捕された。
うち1人は男性らに損害賠償を求めて提訴し、説明義務違反を認定した判決がすでに確定。こうした事態に至った背景には、設立と破産が繰り返されていた経緯を出資者が知らなかったこともあるとみられ、専門家は、法的整備の必要性を指摘している。
関係者によると、男性は先物取引会社で約30年勤めた後の08年3月、大阪市内で石油などの海外先物取引を手がける投資会社を設立。09年2月、原油や金の取引を行う2社目、11年2月には二酸化炭素排出権の取引を扱う3社目をいずれも同市内に設立するなどした。
北京を訪問中の高村正彦・自民党副総裁ら超党派の日中友好議員連盟の議員団は5日、中国共産党序列3位の張徳江(チャントーチアン)・全国人民代表大会常務委員長と約1時間半、会談した。
会談後に記者会見した高村氏によると、張氏は中国が設立を主導するアジアインフラ投資銀行(AIIB)について「いい銀行にする努力をしたい。日本も協力してほしい」と呼びかけ、高村氏は「透明性などの懸念がある程度払拭(ふっしょく)されれば、日本が入ることを検討することもありうべしだ」と伝えた。
また、張氏は「日本の戦後70年の平和国家としての歩みを評価する」と繰り返し言及。「70年という重要な時期に中国国民や世界の人たちが納得できるものにしてほしい」とも語り、安倍首相が今年夏にも出す戦後70年談話について注視していく姿勢も見せた。
アジア開発銀行(ADB)は4日、アジアでのインフラ整備に民間企業がお金を投じやすくするための信託基金を設立した、と発表した。日本は4千万ドル(約48億円)を拠出。カナダ、オーストラリアの各政府とADBからの拠出分を足して計7400万ドル(約90億円)を集めた。
財源が限られるアジア諸国は、インフラ整備への投融資を民間企業にも求めてきた。だが、採算性が不透明ではお金は入れられず、民間資金の活用はうまく進んでいないのが現状だ。
ADBは日英仏などの8銀行と協力。当事国政府に代わって事業調査や事業者の選定、契約書の作成などにお金を出し、民間企業の投資判断を手助けする。基金には欧州も関心を示しており、規模は将来的に最大1億5千万ドルまで拡大する見通しだ。ADBの中尾武彦総裁は中国主導のアジアインフラ投資銀行(AIIB)との協力を明言しており、新基金がAIIBの投融資先の発掘にも活用される可能性がある。(バクー=都留悦史)
西村後援会の資金は事実上、日歯連が管理していたことも判明。東京地検特捜部は、日歯連が自民党議員を支援する団体に法定上限額を上回る寄付を行うため、実態のない西村後援会を利用した迂回うかい寄付を行ったとみて、政治資金収支報告書の虚偽記入の疑いで解明を進めている。
西村後援会は、西村正美参院議員(51)(民主、比例)が初当選した参院選の4か月前の10年3月に設立。事務所所在地は東京都千代田区の日本歯科医師会館で、日歯連や、石井みどり参院議員(65)(自民、比例)を支援する「石井みどり中央後援会」と同じ。会館入り口付近には現在も両後援会の看板が置かれている。
しかし、複数の日歯連関係者によると、西村後援会は10年の選挙時だけ会館4階にある日歯連の部屋の一角に机やいすを設置したが、現在は何も置いていないという。関係者の一人は「選挙用に作った団体なので、選挙が終わればやることがない」と説明する。
収支報告書によると、西村後援会は10年、「ハガキ郵送代」などで計約1億円を支出したが、11年と12年は、繰越金以外の収入と支出は数千円しかなかった。
ところが、石井議員が参院選で再選を目指した13年、西村後援会は1月23日に日歯連から5000万円の寄付を受け、同じ日に石井後援会に同額を寄付。日歯連はその2か月後、石井後援会にも4500万円を寄付した。これにより、規正法の定める年間5000万円の上限を超える計9500万円の資金が日歯連から石井後援会に移動した。この年、西村後援会で他の収支はほぼゼロだった。
両後援会の代表はいずれも日歯連の高木幹正会長が務め、別の日歯連関係者は「両後援会の資金は事実上、日歯連が管理し、使途も決めていた」と明かす。問題の5000万円は、実際に西村後援会の口座に入金された上で、石井後援会に移されていたが、この資金移動を考案し、実行したのは日歯連だったという。
日歯連はこれまでの取材に「日歯連と両後援会はそれぞれ独立した団体で目的も異なり、個々の寄付も独立したもので迂回献金ではない」と説明している。
同社と県は、事故原因を究明し、全遊具の安全が確認されるまで運転は再開しないとしている。同社は、大型連休中の運転再開は困難とみている。
3日の事故現場の調査には、国土交通省の職員や専門家も立ち会った。
事業の譲渡先は、興和紡(名古屋市)と投資ファンド「ジェイ・ウィル・パートナーズ」(東京都)が出資する新会社「江守コーポレーション」(同)。江守グループは5月に8子会社の全株式を譲渡する予定で、金額は約100億円。
処分は3月16日付。
発表によると、2人はパーキンソン病の創薬などに関する研究について、同じ研究内容にもかかわらず、2人で別々に日本学術振興会に研究費補助金を申請。早苗教授は2006年度に800万円、07年度に750万円を受給し、寛芳特任教授は06年度に750万円、07年度に740万円を受給した。寛芳特任教授には申請通りの研究実態があったが、早苗教授には研究実態がなかったという。
14年4月、同振興会から「補助金申請に同一の研究内容のものがある」といった問い合わせがあり、同大が調査委員会を設置して調べていた。早苗教授は、補助金を別の研究の備品購入などに使っていたといい、調査委に「研究費を確保して環境を整備したかった」と話したという。私的流用は確認されていないという。同大は、早苗教授が寛芳特任教授と同じ内容の研究成果報告書を作っていたことから共謀関係にあるとして、2人とも処分した。
佐川側の内部資料によると、判明した流出先は、元役員の知人男性が主体的に実施したシンガポールのサーキット運営などの資金(約54億円)▽元役員が代表取締役だった別会社の資金(約15億5700万円)▽京都府南丹市のゴルフ場の買収資金(7億2千万円)▽モンゴルの金融機関の増資に関する資金(4億円)。元役員は1月に佐川印刷の取締役を辞任する直前、独断でグループ会社の資金を不正に流用した概要を記した報告書を佐川側に提出していた。
関係者などによると、佐川印刷のグループ会社「エスピータック」(京都府亀岡市)の口座から第三者に対し、不透明な形で多額の資金が移されていることが昨年秋、外部の指摘で発覚。佐川側が調査を進めたところ、元役員による不正流用の疑いが浮上した。
佐川側は今年に入り資金回収を本格化。元役員の知人の経営コンサルタント会社が十数億円で買収した南丹市のゴルフ場運営会社の株式や、知人男性側が京都市内で所有する複数の事務所やマンションについて、仮差し押さえを京都地裁に申し立て、4月までに順次認められた。
元役員は報告書で「銀行印をひそかに押印することができたので、他の役員らに発覚することなく出金した」と手口を説明。「多大なる迷惑をかけた」と謝罪している。産経新聞は元役員に対し、家族を通じて直接取材を申し込んだが応じていない。
佐川印刷は「捜査機関に被害を相談している。調査中の事案のため詳細は答えられない」としている。
FNの運営主体の日本レースプロモーション(JRP)は平成23年3月、翌24年にシンガポールでレースを開催すると発表。記者会見では大会の主催者としてこの男性が出席し「日本の素晴らしいレースを海外にも見てもらいたい」と開催への意気込みを語っていた。
JRP関係者によると、男性側の会社が期間内にサーキット場を完成させることができないなど支障が生じたため、開催は中止になったという。FNは25年からスーパーフォーミュラに名称変更されている。
佐川印刷の元関係者の話や登記簿によると、元役員は十数年前、男性が経営に関与した京都市内の建設会社が佐川関連の工事を請け負ったことなどで男性と知り合い、同市内で不動産関連会社を共同経営するなどして親密な関係を築いた。
約10年前には男性の関係者が自動車レースに関わり、男性自身もレースへの興味を深めたという。
元役員は流用疑惑発覚直後の今年1月、佐川側に提出した報告書で「男性が主体となって実施した寺の建築・墓地建築資金、シンガポールのサーキットの運営資金で約54億円を佐川印刷グループから流出させた」と説明。佐川側は男性側の経営会社が所有していたマンションや事務所の仮差し押さえを京都地裁に申請し、4月までに認められている。
産経新聞は男性に対し、男性の会社やメールを通じて取材を申し込んだが、応じなかった。
母娘の代理人弁護士によると、長女は同市内の県立高校2年で、母親と二人暮らし。一家は生活保護費の受給世帯で、長女は民間団体などから奨学金も給付されていた。しかし、同市は奨学金を収入と認定。長女が奨学金として受け取った9万円を昨年7月までに保護費から差し引いたという。
母親は「奨学金は生活費に充てるために支給されるのではない。前例を作れば、ほかの奨学金制度にも影響を及ぼしかねない」とコメントを出した。同市は「訴状を見ていないのでコメントできない」と話している。
「18歳以上だと思っていた」と容疑を否認している。
発表では、熊本容疑者は今年1月、京都市伏見区のホテルで、当時中学3年の少女(15)に現金を支払う約束をしてわいせつな行為をした疑い。2万円を渡していた。
少女を派遣していた売春クラブを府警が摘発して発覚した。府警によると、熊本容疑者は、幼い女子の紹介を求める趣旨のメールをクラブ経営者に送っていたという。
日歯連は、全国の歯科医師で組織する公益社団法人の日本歯科医師会(日歯)を母体とする政治団体。
日歯連をめぐっては今年2月、2013年参院選で当選した石井みどり議員(自民)に対して同年、同法の上限5千万円を超える計9500万円の寄付をしていた疑いが、朝日新聞の報道で発覚した。さらに、10年参院選に当選した西村正美議員(民主)についても、同様の疑惑が指摘されている。石井議員、西村議員とも、献金当時、日歯連が選挙などで支援していた。
政治資金収支報告書によると、日歯連は13年1月23日、西村氏を支援する「西村まさみ中央後援会」に5千万円を寄付。西村後援会は同日、石井氏を支援する「石井みどり中央後援会」に同額である5千万円を寄付した。その後、日歯連は同年3月15日に、石井後援会にも直接4500万円を寄付した。結果的に、日歯連から計9500万円が石井後援会に渡った形だ。
第三者委は2009~13年度に不適切な受給額が7億2124万円に上るとした。県が今年1月に不正受給額として公表した2億2189万円を大幅に上回っている。
第三者委はこの日、県北安曇地方事務所林務課の職員から組合の担当者に届いたメールを公開。11年3月10日付のメールには、「作業道で補助金額が33万3000円くらい(単価2540円で187メートル)の申請を1件作っていただけたらありがたい」とあった。文面に近い金額が交付されたことを確認したという。
竹内委員長は「架空申請による予算消化が、県の主導で行われてきた疑いがある」との見方を示した。
第三者委によると、当時の県の担当職員から聞き取り調査をしようとしたが、県は、県独自の検証委員会の調査を優先させるとして応じていない。このため、第三者委は県に対し、メールの情報公開を請求する方針を明らかにした。
不適切な手続きによる受給額の7億2124万円は、09~13年度の5か年に組合へ交付された補助金13億2635万円の半分以上を占める。保存書類や現地視察などを行って第三者委が算出した。
県林務部は、問題のメールについて「5月1日の検証委で議題に上げ、説明したい」としている。
病院は膵臓手術の死亡例についても調べるとみられる。
関係者によると、膵臓手術の死亡例は、病院側が肝臓手術の死亡状況を調査している過程で判明した。今後、病院側から依頼された外部の専門医が、カルテなどの記録をもとに、診療上の問題がなかったかどうか調査するという。病院は当初、開腹手術の調査結果を5月にも公表するとしてきたが、ずれ込む見通し。同病院は30日、前橋市内で記者会見し、調査の進捗しんちょく状況などについて発表する。
同省では、大川隆法氏(宗教法人「幸福の科学」総裁)の著作物のなかに、文科省に対する脅しととらえられる表現があるなど不正な行為があったとし、不認可とした昨年10月から2019年10月までの5年間、設置を認めないこととした。幸福の科学学園は「学問の自由、信教の自由を侵害する不当な処分と考える」とのコメントを発表した。
「宮本さんはデイリー・メールに『もちろん、日本を選ぶわ。自分では、私はとことん日本人だと思っている。そう、100%日本人よ。肌の色の違いは、その人となりとは全く関係ないはず』と言い切った。」
ほんとうに100%日本人であればそのように考える可能性は低いと思う。戦う姿勢を見せること自体、日本人的ではない。父がアメリカ人で
アメリカの高校を卒業したバックグラウンドを持つ時点で典型的な日本人でいられるわけがない。長い間、海外で過ごした帰国子女の多くが、
典型的な日本人でないのと同じ。東京で生まれ育った日本人が田舎で目立つことなく存在できるか?特別な例を除いては難しいと思う。
アメリカでも同じ。田舎育ちのアメリカ人と都会育ちのアメリカ人は違う。北部で生まれ育ったアメリカ人と南部で生まれ育ったアメリカ人は違う。
しかしそのような違いを知らない日本人にとってはアメリカ人はアメリカ人だ。彼女のケースも同じだと思う。彼女が日本の都会で受け入れられたら、
田舎でも受け入れられるかといえば、まったく違うと思う。議論しても結論は出ないが、彼女の人生なのだから思うように生きれば良いと思う。
振り返れるほど時が経たないと何も言えないと思う。彼女がどのような人と出会い、どのような経験をするかで彼女の考えや価値観も変わっていくと思う。
ミス・ユニバースは「ミス・ワールド」「ミス・インターナショナル」とともに世界3大ミスコンテストの1つで、世界大会には80以上の国・地域から代表が出場し、美と知性、感性、人間性などを競う。最近では、2007年に日本代表の森理世さん(28)が優勝している。
■「自分らしく頑張る」
長崎県佐世保市出身の宮本さんは先月、東京で開催された日本代表を決める最終審査に長崎県代表として出場。地方大会(応募者は全国で約5000人)を勝ち上がったファイナリスト44人の中から、見事、日本代表の座を射止め、「ハーフの私でいいのかなという不安もあるが、世界大会は自分を信じ、自分らしく頑張りたい」と喜びを語った。一方で、日本人らしい白い肌が美の象徴というイメージからは離れた宮本さんの選出は、異例の出来事として海外で話題を呼んだ。
宮本さんは、米海軍佐世保基地に勤務していた父(43)と地元出身の母との間に生まれ、佐世保市内の小中学校を卒業。高校時代は、父の出身地である米アーカンソー州ジャクソンビルで学び、帰国後は日本でバーテンダーやモデルをしてきた。
■自殺した友人のため
米CNNなどの取材に対し、宮本さんは子供時代を振り返り、「学校ではゴミを投げ付けられたり、差別的な言葉を吐かれたりした。肌の色や髪の毛をからかわれ、クラスメートに同じプールで泳がないでと言われたこともある」と語った。ロイター通信には、コンテストに応募した動機について、親しい自分と同じハーフの友人が自ら命を絶ったことをあげ、「『日本人に受け入れられていない気がする』と話していた友人のためにも、日本の世の中をちょっと変えたいと思った。ハーフに対する世間の見方を変えてもらいたい」と述べた。
■ネット批判にも冷静
ネット上では、宮本さんが日本代表に選ばれると「日本代表にハーフを選んではダメだ」「日本人らしくない」などといった心ない書き込みがされた。だが、宮本さんは冷静だ。米ブルームバーグとのインタビューで「批判がなかったら、逆に私が出る意味がなかったんじゃないかと思う。批判は無視せず、その人たちの考えを変えられるような活動をしたい」と力を込めた。
宮本さんの父は、米国で英紙デイリー・メールの取材を受け、「私自身は日本で人種差別を受けた覚えはないが、子供だったエリアナは相当いじめられたに違いない。よく耐えたと思うし、常に前向きな娘を誇りに思う」と述べた。
現在、日米二重国籍の宮本さんは、22歳までにどちらかを選ばなければならない。宮本さんはデイリー・メールに「もちろん、日本を選ぶわ。自分では、私はとことん日本人だと思っている。そう、100%日本人よ。肌の色の違いは、その人となりとは全く関係ないはず」と言い切った。
「歴史的スクープ 韓国軍にベトナム人慰安婦がいた!」。週刊文春の2015年4月2日号は、こんなタイトルで7ページにわたる大特集を組んだ。
懲戒処分を受け、営業局に異動を命じられる
その記事は、山口敬之支局長名で書かれており、アメリカの機密公文書まで調べた文字通りの調査報道だった。この記事は大きな反響を呼び、ネット上では、なぜTBSでは報じなかったのかも話題になった。
記事によると、山口氏はアメリカに赴任する直前の2013年、ある外交関係者から、慰安所の未確認情報があり、米政府の資料などで裏付けられるかもしれないと耳打ちされた。山口氏は、韓国に加害者の側面があることが分かれば、慰安婦問題の突破口になるはずだとの考えに共感し、この年9月から公文書を探す取材が始まった。
そして、14年7月になって、米軍司令部が「韓国軍による韓国兵専用慰安所」と断定する書簡を見つけた。今度は、当時をよく知る人物がいないかをリサーチし、米海兵隊の歩兵部隊長だった米国人男性(71)から決定的な証言を得た。サイゴン(現ホーチミン市)にその慰安所があり、市内の別の場所には、1区画20人前後のベトナム人女性が働かされていたもっと大きな慰安所もあったというのだ。韓国兵のレイプや性病蔓延などを防ぐのが理由だったというが、二十歳未満の少女も多かったともいう。
記事が載った文春は3月26日に発売されたが、4月24日になって、一部のネットメディアやブログで、山口氏が前日付で懲戒処分を受け、左遷・更迭させられたとの情報が出回った。また、山口氏は、自らの取材結果を報道するよう何度もTBSに求めたが、結局報道しない方向になったとの根拠不明の情報も流れた。
山口氏「寄稿に至る手続きが問題とされた」
夕刊フジが4月26日になって、この情報を大きく取り上げ、ネット上でも騒ぎが大きくなった。
その記事によると、山口敬之氏は、TBSから15日間の出勤停止処分を受け、営業局のローカルタイム営業部への異動を内示された。その理由について、「関係者の間では、取材の成果を他社の媒体に発表したため左遷されたという見方も広がっている」と伝えた。
これに対し、山口氏はフェイスブックで、報道で問い合わせが多かったとして自ら説明した。そこでは、4月23日付でワシントン支局長の任を解かれ、営業局への異動を命じられたのは事実だと認めた。また、懲戒処分もあったとした。その理由としては、「週刊文春への寄稿内容ではなく、寄稿に至る手続きが問題とされました」と明かした。そして、「見解の相違はありますが、今回の懲戒処分がTBSの報道姿勢に直接リンクするものではない」と言っている。
フェイスブックでは、そもそもなぜTBSが報じなかったのかとさらに質問があったが、山口氏は、「会社が私の取材成果を報道しなかった真意は、私にはわからない」と繰り返した。ただ、「事実は揺るぎなく、世に知らしむべきニュースと考えて公表に踏み切りました」と説明している。
韓国の主要メディアはほとんど記事を取り上げていないが、日刊紙「ハンギョレ新聞」だけは、「腹立たしいが、反論は困難...」だとして政府次元の解決努力を促している。山口さんは、その報道を取り上げ、専門家などからも「裏付けが必要」との指摘は出ていないとしており、自らの取材に自信を持っているようだ。
ネット上では、山口氏について、賞賛や激励が相次ぎ、フェイスブックには1日足らずで1100を越える「いいね」が付いたほどだ。TBSに対しては、「この処分自体は当然のこと」と理解する向きも一部であるものの、「報道しない自由っていうやつか」「政府の圧力は散々批判してるのに、自分等がやってる矛盾」といった批判や疑問が続出している。
TBSの広報部では、J-CASTニュースの取材に対し、「人事の詳細については、お答えしておりません」とだけコメントした。
発表によると、院長は昨年9月までの1年間に、放射線技師ではない事務員や柔道整復師らに指示し、患者18人の腰や胸などのレントゲン写真を撮らせた疑い。事務員らは、資格がないのに撮影した疑い。
同院に放射線技師はおらず、医師である院長以外は撮影ができなかった。調べに対し、院長は「診療時間を短縮するためだった」と容疑を認めている。
外部調査チームの中間報告によると、東洋ゴム工業は去年9月の社内会議で、問題となった製品の出荷停止方針を決定したが、別のデータを使えば大臣認定基準に収まるとの社内報告があったため、出荷を続けていたという。しかし、このデータには技術的根拠がなく、製品はその後、半年にわたって出荷が続けられた。
また、報告書では2013年夏頃に免震ゴムの性能不足が発覚していたことや、担当技術者と後任2人のあわせて3人がデータ改ざんに関わっていたことなども示されている。
問題の背景として経営陣の意識や判断の甘さなども指摘されていて、調査チームは5月中旬以降に最終報告を行う見込み。
マンションなど建物に使う免震ゴムの性能を偽っていた問題で、東洋ゴム工業(大阪市)の経営陣が、昨年5月に検査データの「偽装」を知りながら、製品の出荷を止めるまでに9カ月かかっていたことがわかった。同社が24日に公表した弁護士による社内調査の中間報告書で明らかになった。経営陣は判断の甘さが指摘されており、最終報告書を待って責任をとることになる。
この報告書は、3月13日に免震ゴムの性能が国土交通相の認定基準に合っていなかったと発表した55棟分が対象。弁護士が延べ69人に聞き取ってまとめた。
問題が社内で発覚したのは、2013年夏。子会社で免震ゴムの性能検査を担当していた社員が異動し、後任の社員が「検査のデータが実測値と合わない」と上司に報告した。
外部の法律事務所による中間調査報告書に明記された。東洋ゴムが公表した報告書概要によると、昨年9月に信木明社長(現会長)と山本卓司専務執行役員(現社長)が出席した1回目の会議で、出荷停止の準備を進めることと国土交通省に不正の疑いを報告する方針が決まった。
ところが同じ日に開いた2回目の会議で、「別の試験データを採用することで国の基準をクリアできる」とする報告が上がり、撤回された。しかし今年1月、この試験データには技術的根拠がないことが山本氏らに報告され、2月にようやく出荷停止と国への報告が実現した。
また、データ改竄(かいざん)を始めた前任者から平成25年1月に業務を引き継いだ技術者が、同年夏ごろに試験データの矛盾を上司に報告していたことも判明。東洋ゴムはこれまで、会社が不正の疑いを認識したのは「26年2月」と説明していた。
大阪市内で会見した瀧脇將雄CSR統括センター長は「中間報告は厳粛に受け止めている。方針撤回された経緯は社内で検証中」と述べた。
東洋ゴム工業は、先月公表した全国55棟の建物に使われた免震装置の問題について、ことし2月に10人の弁護士による社外調査チームに依頼して関係者への聴き取りなどによる調査を進めてきました。
会社が24日に公表した調査チームの中間報告によりますと、免震装置の担当者が根拠のない数値を書類に記載するなどして、平成14年から23年まで5回にわたって国の認定を受けていたほか、業務を引き継いだ後任の担当者2人も、平成22年からことし2月にかけて、同様の手法でデータを補正するなどして製品の出荷を続けさせていたとしています。
また、会社はこれまで、問題を認識した時期を去年2月と説明してきましたが、今回の報告では、その半年ほど前のおととし夏ごろに、後任の担当者の1人がデータの不整合を上司に報告していたことを明らかにしました。
さらに、去年9月16日の午前に役員が出席して開かれた会議で、製品の出荷停止を準備したり、国土交通省に報告したりする方針がいったん決まったものの、午後になって製品の試験のやり方によっては求められる性能を満たすことができるという報告があったため、方針が撤回されたとしています。
そのうえで中間報告は、会社の問題点を12項目にわたって指摘し、安全を守る技術を扱う企業として保持すべき規範意識に欠け、管理・監督や監査態勢の不備、経営陣の認識の甘さがあったなどとしています。
会社によりますと、社外調査チームは別の免震装置の問題も調査し、来月中に最終報告をまとめるということです。
東洋ゴム工業「真摯に受け止める」
大阪市で記者会見した東洋ゴム工業の瀧脇將雄CSR統括センター長は、「中間報告の内容を厳粛かつ真摯(しんし)に受け止めている」と述べました。
今回の中間報告では、会社で過去に起きた建材を巡る不正の教訓が生かされなかったと指摘されています。
これについて瀧脇センター長は、「社内教育などは熱心にやってきたつもりだが、具体的にどういう点が不十分と言われているのか確認し、再発防止に向けて検討したい」と述べました。
東洋ゴム工業は、問題の免震装置を原則としてすべて交換する方針を示していますが、24日の会見では、別の免震装置の問題への対応や認定の取り直しなどに時間がかかるため「2年、3年で、とは決められない」と説明し、少なくとも数年はかかるという見通しを示しました。
同機構は今年3月になって事態を把握し、委託契約を解除したが、個人情報を扱う公的な業務が、違法状態の派遣労働によって担われていた。
同機構などによると、委託した業務は、厚生年金への加入や脱退に関する届け出のデータ入力などの作業。データには氏名や住所、生年月日などの個人情報が含まれている。同機構は昨年10月、3県の事務センターでの1年間の業務を福井市の情報処理会社に委託した。
個人的な意見だが中国の飛行機が墜落したらこれほどの額はでないと思う。
機体を意図的に墜落させた疑いがある副操縦士、アンドレアス・ルビッツ容疑者(27)の明確な動機は不明のままだ。
独デュッセルドルフの検察当局は本紙に、動機について「新たに発表する情報はない」と述べた。これまでの捜査では、同容疑者は、精神的な問題を理由に、機体の操縦を認められなくなるとの不安から犯行に及んだとの見方が出ている。
ドイツ運輸省は、再発を防ぐため、航空当局や精神科医ら有識者を交えた作業部会を設置し、今月8日に初会合を開いた。パイロットの飛行適性の厳格化などが協議されたとみられる。
DPA通信によると、乗客約20人の家族が代理人の弁護士を通じてルフトハンザと賠償金を交渉中。請求額は1人当たり100万ユーロ(約1億2800万円)が浮上しているという。
同労働局によると平成23年5月~26年4月、同社と関係のあったベトナムの現地機関が、日本での就労を希望する27人のベトナム人から1人約30万円の保証金を徴収。5年間の雇用期間を満了できなかった場合は同社が保証金を使用するという誓約書にサインさせていた。
さらに、現地機関はそれぞれの家族にも同社への違約金支払いを誓わせ、府内の製造業者などで働かせていたという。労働局は保証金や誓約書でベトナム人を支配下に置き、そのうえで企業で働かせていたことが職業安定法違反(労働者供給事業の禁止)に当たると判断した。
横浜市のNPO法人「エコキャップ推進協会」(エコ推)がペットボトルのふたの売却益をワクチン代に寄付していない問題を受け、主な協力団体の「全日本プラスチックリサイクル工業会」は23日、東京都墨田区の本部で関係者会議を開き、エコ推には売却益を渡さない方針を決めた。
工業会では、全国の会員企業の有志約20社が「世界の子どもたちにワクチンを贈る活動」に協力する業務契約をエコ推と締結。学校などで集めたふたを受け取ってリサイクルし、ふた1キロ当たり20円をエコ推に支払ってきた。今後は、会員企業ごとの判断で、別のNPO法人を通じて「世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)」(東京都港区)に寄付するか、直接JCVに寄付をする。
大塚一郎会長は「キャップを集めている方々は、エコ推に渡すことを許さないだろう。今後はしっかりワクチンになるところに贈りたい」と話す。
ドローンは、首相官邸の屋上にあるヘリポート近くで見つかった。22日午前11時半ごろ、官邸3階のエントランスには、記者やカメラマンが慌ただしく出入りし始め、半透明のガラス天井越しには、警視庁の捜査員らが動く影が透けて見えた。上空では報道各社のヘリが旋回。捜査員がブルーシートでドローンを覆った。「確認中としか答えられない」。官邸事務所のスタッフは正午前、朝日新聞の電話取材にこう答えた。政府高官は記者団にテロの可能性を問われ、「まだ分かりません」と答えた。
東京・新宿の大手家電量販店には、カメラ付きのドローンが10種類ほど並ぶ。1週間前、カメラコーナーの目立つ一角に、専門コーナーが急きょ設けられた。
価格は約1万~15万6千円。一番大きい商品でも全長30~40センチ、重さ1・2キロほどで、最軽量の商品は約55グラムだ。売り場の男性店員によると、1日10人前後が購入するといい、「勢いのある商品です」。主力は2万円台の機種だが、より高性能な10万円以上のものを選ぶ客も少なくないという。
販売は1年前からしていたが、全地球測位システム(GPS)付きの本格的なものが中心で、目立たない場所に数台並んでいただけだった。しかし、ラジコンヘリのように手動で手軽に扱える低価格の商品が出回り始め、ネット上で評判が広まってここ1カ月で問い合わせが急増。急きょ種類を増やした。
売り場で説明書を読んでいた東京都板橋区の男性会社員(42)は、2台目の購入を考えているという。元々ラジコンヘリの愛好家で、1台目は3万円台を購入した。公衆無線LAN(WiFi)を使い、動画をスマートフォンにリアルタイムで送信できるタイプ。「川や田んぼを、空から見られる。もっと性能が良い商品を買うつもりです」
記者は、一番売れ行きが良いというドローン「GALAXY VISITOR6」(中国製、2万7864円)を購入し、飛ばしてみた。全長約24センチ重さ115グラム。コントローラーのレバーを上昇方向に上げると、四つのプロペラが勢いよく回り始め、音を立てて浮上した。操縦しながら撮影された映像をリアルタイムに手元のスマートフォンに送ることができる。レバー操作で上昇、下降を繰り返してみる。思いのほか簡単だ。もう一つのレバーで右旋回、左旋回を試みると、右に倒しすぎたのか、勢いよく右に旋回。慌てて方向を変えたが、木の枝にひっかかり墜落。プロペラの一つが破損し、飛べなくなってしまった。
ドローンはこれまで海外製品が主力だったが、国産機の製造も始まっている。精密部品大手の菊池製作所(東京都八王子市)が製造した量産機は、直径102センチ、重さ3キロ。秒速4メートルの速さで飛び、GPSを使いながら自動操縦で10~30分ほど飛べる。価格は約200万~300万円。これまでに約50機がインフラを点検する空撮用などに販売された。開発した自律制御システム研究所(千葉市)の野波健蔵社長(千葉大特別教授)は、「悪質な行為で、開発に水を差された思いだ。正しく使えばこれほど便利なものはない」と話した。
■警備・宅配…広がる用途
ドローンは様々な分野で注目されている。
問題の影響が拡大しているようだ。
東洋ゴム工業(大阪市)による免震ゴムの性能偽装問題で、同社が21日に性能不足のゴムが使用されていたと公表した90棟の中に、東京都文京区立本郷小学校(同区本郷、全校児童500人)の校舎が含まれていたことが分かった。
同社が公表した90棟のうち5棟が学校(私立、公立)だが、同社も国土交通省も校名は明らかにしていない。
文京区によると、21日に同社担当者が区を訪問し、2002年の校舎改築工事の際に使用した免震ゴムが性能不足だったと伝えられた。区は、一連の問題が3月に発覚した後、同小に使われたゴムの性能を問い合わせたが、同社は「問題ない」と答えていたという。
同小は今後も授業を通常通り行う。
首相官邸の屋上に落下しているのが見つかった小型無人飛行機「ドローン」の件で、早急に規則作成に取り掛かるであろう。

首相官邸の屋上に落下しているのが見つかった小型無人飛行機「ドローン」。国内でも普及が進む一方、空港周辺などを除けば、地上から250メートルまでの高さであれば飛行に規制はない。誰が何の目的で飛ばしたのか。不安が広がった。
ドローンは元々、敵地の偵察など軍事目的で開発され、米軍などはイスラム過激派に対する攻撃などにも使用している。しかし、近年は研究・商業目的での利用や開発の機運が高まっており、ネット通販大手「アマゾン」は無人機を使った商品の宅配をテストしているほか、IT大手のグーグルも開発を進めている。
日本では自衛隊のほか、長野県警がテロ対策と警備目的で利用するために導入。総務省は遠隔操作する電波の混信トラブルを防ぐため、用途に応じて無人機用の周波数を割り当てることを検討している。
現行の航空法ではドローンは用途に関係なく「模型飛行機」に該当し、航空機の運航に危険を及ぼす空域でのみ飛行が禁止されている。空港周辺などを除けば地上250メートル、航空路内でも地上150メートルまでの高度であれば、届け出なしに飛ばすことが可能だ。しかし、安価な小型ドローンの急速な普及で、民間企業によるドローンを活用した事業参入が増加しており、トラブルの多発が予想されることから、国土交通省は航空法改正によるドローン運用を規制するためのルール作りを進めている。【佐藤賢二郎、斎藤良太】
東洋ゴムだけでなく、他の会社に対しても良い教訓となるだろう。しかし、同じような問題を防止できない企業はこれからも存在するだろう。
東洋ゴム工業の性能不足の免震ゴムが使用された建物が新たに90棟確認されたことで、同社は業績への影響が避けられなくなった。株価も低迷が続いており、信頼は失われたまま。焦点は5月上旬をめどに公表される経営陣の進退に移る。
同社は平成27年12月期の連結最終利益を280億円と予想しているが、免震ゴムの交換などに要する費用は100億円単位に膨らむ可能性がある。久世哲也専務執行役員は「単純にかけ算して出るものではない」と語り、現時点では損失額は不明としたが、赤字に転落する恐れもある。
さらに、株主ら利害関係者からの信頼は失われたままだ。東洋ゴム株の21日の終値は、最初に問題を発表した3月13日の終値と比べて15%低下。3月末の株主総会では、山本卓司社長らに引責辞任を求める声もあがった。
経営責任について、久世氏は「外部による調査結果が5月上旬をめどに出る。処分や再発防止策とセットで公表したい」と述べた。
組織ぐるみだからこうなったのであろう。
東洋ゴム工業の子会社が製造した免震ゴムの試験データが改竄(かいざん)され、性能が偽装されていた問題で、東洋ゴムは21日、新たに90棟で性能不足の製品を使用していることが分かったと発表した。データがなく性能が判定できない物件も9棟あり99棟で製品を交換する。3月に公表した55棟も含め、耐震性調査や交換が必要な物件は、30都道府県計154棟の免震ゴム計2907基に上ることになった。
同社によると、今回新たに性能不足が判明した製品は、平成8年4月から27年1月まで20年近くに渡って出荷された。試験データの改竄に関わった技術者について、当初は1人と発表していたが、4人が不正に関与していた可能性があることが判明。同社は外部の法律事務所に調査を委託しており、5月上旬に調査結果や再発防止策を公表する。
同社が、改竄前のデータで性能を検証した結果、25都府県90棟に使われていた免震ゴム678基が国の基準に不適合となった。また9棟のうち177基はデータが十分でなく、判定できなかった。
国土交通省によると、90棟のなかには、滋賀県近江八幡市の市立総合医療センターや大阪市の市中央公会堂などが含まれている。判定不能の9棟の1棟は、盛岡市の中央消防署新庁舎だった。国交省は同社に対し、震度6強~7程度の地震に対する安全性調査を行い、4月中に結果を報告するよう指示した。
大阪市で記者会見した同社の久世哲也代表取締役専務執行役員は「事態を大変重く受け止めている。大変申し訳ない思いで、全社を挙げて問題の対応に当たる」と謝罪した。
東洋ゴムは3月25日、18都府県55棟の2052基以外に、性能不足の製品を出荷した可能性があると発表。195棟の調査を始め、重複があったことから154棟を対象に調べた。
基本的に日本の医療業界の体質はこのようなものではないのか?一部のすばらしい医師や良心的な個人経営の病院が良いだけで、基本的に 体質の問題があるからこのような問題が起きるのでは?個々の医師の意思では改革できるような単純なものではないと推測する。長いものには巻かれろ! 上手く振舞わないと生きていけない世界なのかもしれない。

医療に携わる者としての倫理観の欠如に、あきれるばかりだ。
不適切な診察や治療が行われていなかったのか、徹底した調査が必要である。
川崎市の聖マリアンナ医科大病院で、11人の医師が「精神保健指定医」の資格を虚偽申請により不正に取得していた。厚生労働省は、指導した上司を含め、計20人の資格を取り消した。
不正取得による大量処分は、過去に例がないという。
精神保健指定医は、全国で1万4630人に上る。自分や他人を傷つける恐れがある患者を、知事などの権限で強制的に入院させる「措置入院」の判定に関わる。家族などの同意で入院させる「医療保護入院」の適否も判断する。
患者の行動を制限する強い権限を持つため、精神保健福祉法に基づき、厚生労働相が十分な知識と経験を持つ医師を指定する仕組みになっている。
虚偽申請は、資格制度の趣旨を蔑ないがしろにする行為である。
指定医の申請には、精神科医として3年以上の実務経験と、診断した8症例以上のリポートを提出することが必要だ。11人は先輩医師のリポートの一部を書き換え、自らが診断したように見せかけて申請していた。極めて悪質だ。
看過できないのは、リポートの使い回しが常態化していたことだ。病院側は、医師間でデータの受け渡しが行われていたと認めた。指導医のチェック機能も働かなかった。深刻な事態である。
今回、厚労省から酷似したリポートの存在を指摘され、病院側は初めて不正に気付いたという。
資格を不正取得した医師は、4人の措置入院の判定に関わった。医療保護入院の判定は約100人に達する。誤った判定で患者が措置入院などになっていれば、人権上、大きな問題だ。川崎市と病院には詳細な検証が求められる。
指定医は診療報酬の優遇を受けられる。資格の不正取得の結果、外来診療で上乗せされた約170万円について、病院側が返還する方針を示したのは当然だ。
指定医の取り消しにより、聖マリアンナ医科大病院は神経精神科の体制を縮小した。地域医療に影響が及んでいる。
厚労省は再発防止策として、リポートのデータベース化を急ぐ。類似のリポートを判別できるようにするためだ。他の病院でも同様の不正がなかったかどうかについても調査する。
精神科医療の信頼回復には、指定医の厳格な審査が不可欠だ。
コストが高そうだが、コストさえ下がれば実用化はありえそう。 特に太陽光発電の効率が良い島や田舎ではメリットが特にありそう。ただ、故障や管理維持の問題も解決されなければならないだろう。 ほぼメンテナンスフリーで故障が少なければ需要も増えるだろう。
東芝は、災害時の利用を想定した水素で発電する燃料電池システムを開発し、川崎市との共同で、実証実験を20日に始めた。
装置は、太陽光発電の電気で水道水から水素を抽出し、タンクに貯蔵して、燃料電池で発電する。水と太陽光だけで発電できるのが特徴で、川崎市に設置した装置を使えば、300人が約1週間生活するのに使う電力と温水を供給できるという。自治体からの受注を目指す。
「聖マリアンナ医大病院(川崎市宮前区)の医師が精神保健指定医資格を不正取得し取り消し処分を受けた問題をめぐり、重度の精神障害がある患者に向き合う関係者らに波紋が広がっている。『社会の信頼を裏切る行為で、精神科医療全体への不信や不安を生みかねない』-。
専門家は同病院のずさんな体制を非難するとともに、病棟勤務医の減少も背景にあるとの見方を示す。患者の保護を担う関係者も、深刻な指定医不足に目を向けるべきと強調している。」
深刻な指定医不足の問題と資格の不正取得は別問題。需要があれば資格の不正取得が許されるのか?資格取得基準に問題があるのなら、厚生労働省に
報告するべき。報告されながら問題を放置するのであれば厚生労働省の問題と思う。
下記の記事を読むと現状と指定医不足をアピールして寛大な処置を訴えているように感じる。個人的にはおかしいと思う。現状と指定医不足は今回とは
関係ない問題。問題解決のために仕方がなく資格を不正に取得させたとも極端に解釈すれば取れる。同じような問題はこの件だけでなく多くあると思う。
仕方がなく諦める人、不正に手を染める人、コストの影響で事業を断念する人などたくさんのケースと選択がある。この件だけを特別扱いするのはおかしい。
【ワシントン時事】19日付の米紙ワシントン・ポストは、連邦捜査局(FBI)の毛髪鑑定部門の鑑定官28人のうち26人が1999年まで20年以上にわたり、検察側に有利になるよう誇張した鑑定結果を証拠として公判に提出し続けていたと報じた。鑑定結果が被告に不利な証拠として用いられた裁判268件中、95%以上に当たる257件で証拠に不備があった。
弁護士団体などによる調査結果として伝えた。鑑定官らは、不完全な統計データに基づき証言していたという。不備のある証拠が採用された裁判で死刑を言い渡された被告は32人おり、うち14人が執行を受けるか獄中で死亡するかした。
FBIと司法省は誤りを認め、46州とワシントンの検察当局に、新たな裁判が必要かどうか判断するよう求める通達を出す手続きに入った。
「聖マリアンナ医大病院(川崎市宮前区)の医師が精神保健指定医資格を不正取得し取り消し処分を受けた問題をめぐり、重度の精神障害がある患者に向き合う関係者らに波紋が広がっている。『社会の信頼を裏切る行為で、精神科医療全体への不信や不安を生みかねない』-。
専門家は同病院のずさんな体制を非難するとともに、病棟勤務医の減少も背景にあるとの見方を示す。患者の保護を担う関係者も、深刻な指定医不足に目を向けるべきと強調している。」
深刻な指定医不足の問題と資格の不正取得は別問題。需要があれば資格の不正取得が許されるのか?資格取得基準に問題があるのなら、厚生労働省に
報告するべき。報告されながら問題を放置するのであれば厚生労働省の問題と思う。
下記の記事を読むと現状と指定医不足をアピールして寛大な処置を訴えているように感じる。個人的にはおかしいと思う。現状と指定医不足は今回とは
関係ない問題。問題解決のために仕方がなく資格を不正に取得させたとも極端に解釈すれば取れる。同じような問題はこの件だけでなく多くあると思う。
仕方がなく諦める人、不正に手を染める人、コストの影響で事業を断念する人などたくさんのケースと選択がある。この件だけを特別扱いするのはおかしい。
聖マリアンナ医大病院(川崎市宮前区)の医師が精神保健指定医資格を不正取得し取り消し処分を受けた問題をめぐり、重度の精神障害がある患者に向き合う関係者らに波紋が広がっている。「社会の信頼を裏切る行為で、精神科医療全体への不信や不安を生みかねない」-。専門家は同病院のずさんな体制を非難するとともに、病棟勤務医の減少も背景にあるとの見方を示す。患者の保護を担う関係者も、深刻な指定医不足に目を向けるべきと強調している。
同病院の精神科受診者数は1日平均約130人(2013年度)で、県全域で進めている精神科救急医療体制にも協力している。今年4月1日時点で常勤の指定医は12人おり、このうち7人の資格取り消しが決定。当面は残る5人で診療体制の維持を図るとしているが、「入院診療は縮小せざるを得ない」(尾崎承一病院長)のが現状という。
厚生労働省関東信越厚生局によると、県内在住の指定医は882人(14年度)で、11年度に比べ58人増えた。ただ、自身も指定医で医療法制度に詳しい東洋大の白石弘巳教授は「病棟の指定医は、むしろ少なくなっている」とみる。「暴れてしまうような重症患者を担当したり、患者に怒鳴られたりする病院勤務を敬遠する医師は多い」とし、比較的症状が軽い通院患者を診察するクリニックでの勤務を希望するケースが増えているのが実情という。
実際、重い精神障害がある患者に向き合う現場では、受け入れ先をめぐる困惑が続いている。
「自傷他害の恐れ」があり精神保健指定医の診断が必要とされるケースの多くは、警察に保護される。県警幹部によると、ほぼ毎日数人を保護する警察署もある中、指定医や入院先は慢性的に不足しており、署内で長時間の保護を余儀なくされるケースも少なくないという。
本人の同意なしで強制的に入院させる「措置入院」には2人以上の指定医の判定が必要だが、医師がなかなか見つからず「署内で一晩を明かすことも珍しくない。指定医はそれだけ足りていない」と元県警幹部は強調する。「入院先も見つからず、警察官が県東部から西部の病院に送り届けることもしばしばある」と打ち明けた。
別の県警幹部は「保護室がない署は他署を頼ったりしている。(自傷他害行為を防ぐため)署員はつきっきりで対応し、警察の負担は大きい」とし、「指定医不足という運用上の課題こそ深刻だ」と指摘する。
韓国の借金による株式投資が日本の株にも影響していたら、損する時は損失が大きくなる。
投資家たちが株を買うため証券会社から借りた金が過去最高額に達した。15日の証券会社信用融資額は7兆759億ウォン(約7756億円)で、それまで最も多かった2007年6月26日の7兆105億ウォン(約7684億円)を上回った。今年初めの5兆ウォン(約5480億円)台から4カ月にして2兆ウォン(約2192億円)近く増えたというわけだ。これは、株式市場が強い回復傾向を示しているのを受け、個人投資家たちが借金をしてでも「買い」に走っているためだ。KOSPI(韓国総合株価指数)は17日、過去最高の2228まであと85ポイントと迫る2143で引け、コスダック指数は7年ぶりに700台を突破した。
経済展望が好転して株式市場に長期投資金が流入、それにより株式市場が活況を呈するのは望ましいことだ。各企業は投資資金の調達が容易になり、投資家の消費余力も増える。
しかし、最近の株式市場回復傾向は、景気回復の兆しではなく「金の力」によるものだ、というのが専門家らの見方だ。欧州が先月から金を追加で増やしており、韓国も史上初めて基準金利を年1%台に引き下げたことから、株式市場に資金が流入している。だがその一方で、実物経済は消費も輸出も不振を免れられず、今年の成長率は2%台に低下するとの見通しもある。
今後、株価が下落に転じれば信用融資を返済するため株は売られ、株価がさらに暴落し、経済に大きな不安要因を与える可能性がある。個人投資家たちは株価が下がって金を失うだけでなく、借りた金の返済まで重なり二重苦にさいなまれる。2008年の世界金融危機前には信用融資額が過去最高を記録したが、危機後は株価指数が急落、元金を失う「担保不足口座」が続出した。
政策担当者らは、現在の株式市場上昇に浸って不安要因に目をつぶってはならない。07年には大統領や首相までが「借金投資」の危険性の警告に立ち上がった。信用融資が再び増えた11年には、金融監督院長が信用融資を自粛するよう証券各社に要請した。景気回復の後押しがない株価上昇は「蜃気楼(しんきろう)」に終わる可能性がある。政府は経済再生に全力を注ぐと同時に、借金投資の危険性も事前に警告して株式市場に健全な投資ムードを広めなければならない。
もし日本がAIIBに参加していたら結構な額を出資させられていたに違いない。
「創設メンバー間の覚書で、アジア域外国の出資比率を25~30%とすることが決まった」
ここがヨーロッパの国々が参加した理由だろう。デメリットよりもメリットが大きい可能性が大。
【ワシントン=栗原守】中国の朱光耀・財務次官は17日、ワシントンで講演し、アジアインフラ投資銀行(AIIB)への出資比率について、創設メンバー間の覚書で、アジア域外国の出資比率を25~30%とすることが決まったと明らかにした。
中国を始めとするアジア域内の出資比率は、残る70~75%となる。中国は、最大50%を出資する可能性がある。
AIIBの創設メンバーは、アジアのほか、中東、欧州など世界57か国からなる。
作業に関わっていた人に誰も大学で機械や土木を専攻した者はいなかったのでろう。もしいたのならこのような時に理系である強みを発揮しなければならない。 それとも皆、「YES」マンだから何も言えなかったのか?
JR山手線で12日朝に架線の支柱が倒れ、同線など一部区間が9時間以上にわたり運転を見合わせた問題で、JR東日本は17日、今回倒れた支柱から先月に鉄製の「はり」を撤去する際、撤去後の支柱の強度を事前に計算しないまま工事を行っていたと発表した。
社内規定違反にあたり、強度計算をしていれば、倒壊を防ぐ措置が取られた可能性がある。同社は強度計算が行われなかった経緯を調べている。
同社によると、倒れた支柱は元々、別の支柱と「はり」で結ぶ門型の構造になっており、山手線(内回り)と京浜東北線(北行き)の2本の線路をまたぐ形で設置されていた。門型の構造により、支線(ワイヤ)の引っ張る力(約5トン)に十分耐えられるようになっていたという。
山手線では数年前から、メンテナンスがしやすい支柱への交換作業が行われており、今回倒れた支柱については先月25日、まず反対側の支柱とをつなぐ「はり」が撤去された。この撤去により、支柱の強度が弱まった可能性がある。
同社の内規では、今回のような設備の構造を変更する工事を行う際、設計段階で工事後の設備の強度計算を実施するよう定めている。この計算で強度不足が生じることが判明すれば、補強するなど設計を変更して安全を確保するという。
「厚労省は『あってはならない倫理観に欠けた行為』と批判。過去に出された申請と新たな申請を付き合わせて使い回しがないかなどを確認できるシステムを構築し、再発を防ぐという。」
厚労省は何を言っているんだ!いろいろな問題を放置しているのは厚労省だろ!不正が出来るからやるんだよ。馬鹿じゃないんだから不正がすぐ見つかるようだったら
誰もしない。前から言っているが性善説を前提にしてはだめだ。
聖マリアンナ医大(川崎市宮前区)の調査委員会は15日、精神保健指定医の資格を取り消された20人のうち、指導医を除く11人全員が担当ではない患者の症例リポートで資格を申請していたことを明らかにした。申請には8例のリポートが必要だが、1症例を複数の医師が使用する「重複症例」も9医師に計26例確認されるなど、ずさんな申請体制が常態化していた。病院側は同日夜に会見し、「国民の信頼を裏切り、弁解の余地がない」と謝罪した。
◇
調査委の青木治人委員長(同大副理事長)によると、神経精神科内では資格取得の参考にするため、先輩医師の資料を譲り受けることが慣例化。紙ベースだった資料が2011年ごろからデジタルデータとなり、「治療経過などの文書をわずかに書き換えて提出する例が見られた」という。
提出する8症例についても、自身が担当した1人の症例以外は別の医師の症例を採用していた悪質なケースもあった。青木委員長は「病棟内のカンファレンスで共有したものを、症例として拡大解釈して使っていた」などと説明した。
一方、申請書類をチェックする立場にあった9人の指導医も、リポートの症例を診療録と照合せずに署名していた。「その場でサインしたケースもあった」(青木委員長)といい、調査委は指導医としての責任を十分に果たしていなかったと結論付けた。
同病院によると、2011年から13年までの3年間で、計12人の医師が同資格を取得。このうち、他病院に出張中だった1人を除く11人が不正を行っていた。
また今回資格が取り消された医師の中で、重い精神障害がある患者を強制入院させる「措置入院」の判断に関わったケースはなく、家族などの同意で強制入院させる「医療保護入院」が100例あったという。
病院側は指定医が外来診療した件数をさかのぼり、診療報酬を自主返納することも検討中とした。
今年4月1日現在で神経精神科の常勤医師は15人で、うち12人が指定医の資格を取得していた。今回、7人が資格を取り消され、17日以降の有資格者は5人になる。
聖マリアンナ医科大病院(川崎市宮前区)の神経精神科の医師が「精神保健指定医」の資格を不正取得したとされる問題で、厚生労働省は15日、平成22年6月から26年7月までに資格を取得した医師11人と指導医9人の計20人(うち11人が退職)の資格を取り消すと発表した。処分は17日付。
厚労省によると、確認できる14年以降で、不適正なケースリポート提出にからむ指定医資格取り消しは4例目だが、複数の処分は異例という。
厚労省によると、精神保健指定医は精神保健福祉法に基づき、自分や他人を傷つける恐れのある精神疾患の患者を強制的に入院させる「措置入院」や、身体拘束などの行動制限の必要性を判断する。資格取得には病院での一定期間の実務経験証明書や、患者8人以上を診察したケースリポートの提出が必要となる。
しかし、処分を受けた20人のうち11人は、自身が診察していない患者のリポートを提出。カルテが残る過去5年分を調べたところ、24症例が複数のリポートで使い回されていた。「先輩に過去のリポートをもらった」「患者の情報を医局で共有していたので作成したが、認識が甘かった」などと釈明したという。残る9人は、11人の指導医として指導や確認を怠ったとして処分を受けた。
厚労省は「あってはならない倫理観に欠けた行為」と批判。過去に出された申請と新たな申請を付き合わせて使い回しがないかなどを確認できるシステムを構築し、再発を防ぐという。
下記の記事が事実なのか知らないが、事実だとしても日本はAIIBに参加する必要はない。金づるにされるだけ。
何人かの外国人に「日本は金だけを出せばよい、こちらが上手くお金を使う。」とか、「日本がお金を出すのを当然。」と言われた経験がある。
不愉快だった。日本政府が出すお金は税金である。
ドイツがAIIBに参加が正しいと思えば、ドイツの勝手。日本に参加要請などせずに儲ければ良い。ギリシャ問題のように問題が発生しても
日本がAIIBに参加していなければ真剣に悩む必要もない。日本も影響は受けるだろうが、参加した場合と影響は格段に違うだろう。
中国主導で設立準備が進むアジアインフラ投資銀行(AIIB)を巡り、安倍首相が今月1日、ドイツのメルケル首相と電話で会談し、メルケル氏から日本もAIIBに参加するよう求められていたことがわかった。
首相は、公正な運営体制が確保出来るかどうか見極めたいとする従来の立場を説明したという。政府関係者が明らかにした。
メルケル氏としては、日本を組織の枠組み作りの議論に加えて、中国に運営体制の見直しを迫りたいという思惑があったとみられる。
政府は、電話会談を行ったことを公表していない。
「雲や霧の状況は秒単位で変わるため、管制官が着陸許可を出した時点では問題がなかったとしても、瞬間的に視界が悪い状態になった可能性は考えられる。」
管制官が広島空港で何年勤務しているか知らない。しかし、十分な勤務期間があるのであれば「管制官が着陸許可を出した時点では問題がなかったとしても、瞬間的に視界が悪い状態」
になることを考慮して反対側からアプローチをアドバイスをアドバイスするべきではないのか?風向きの影響で東側からアプローチしたのであれば、
風の影響と視界悪化の可能性の考慮を比べればどちらが経験上、優先順位が高かったのか?
パイロット経験者の専門家がいろいろとコメントしているが、あくまでも彼らの経験で広島空港に着陸した経験があると言っている専門家はいない。
そうだとすれば一般的な意見であって、広島空港についてのより正確なコメントが出来る人はいないと言うこと。
パイロットの性格次第であるが、自己中心的であれば嘘も含めて責任回避の発言をするであろう。嘘を付いても証明されなければ人的責任だけとの判断を
されないはず。警察官だって、ぼまかし、不祥事、犯罪そして殺人をする時代なのだから
パイロットが人間的にすばらしいと言う事でもないだろう。パイロットの精神的及び適正問題がリアルタイムにチェックされていれば、ジャーマンウィングスの墜落事故
は起きていない。ベトナム航空の韓国人副操縦士が偽造ライセンスで乗務していた事件もある。
嘘を付くような人間を採用しないのであればなぜ彼は副操縦士として勤務できたのか?
広島空港(広島県三原市)で韓国・仁川(インチョン)発広島行きアシアナ航空162便(エアバスA320)が着陸に失敗した事故で、事故機が通常よりも約30メートル低い高度で滑走路に進入した可能性が高いことが15日、わかった。着陸直前は気象の影響で急激に視界不良になっていたとみられ、運輸安全委員会などは異常な高度低下との関係を調べている。また、国交省は同日、負傷者数を乗客25人、乗員2人の計27人と発表した。
広島空港で調査に当たっている運輸安全委員会の調査官は「可能性として下降気流もあったかもしれない」と話し、下降気流の発生の有無も調査対象になることを示した。
事故機は滑走路に進入する際、滑走路の東端から325メートル離れた位置にある高さ約6.4メートルの「ローカライザーアンテナ(着陸誘導用アンテナ)」に接触して破損させた。国土交通省の調べで、この地点で航空機は通常、アンテナより約30メートル高いところを飛行していることが判明した。
国交省によると、広島空港の管制官が事故機に対して着陸許可を出したのは14日午後8時ごろ。同空港で東側から着陸する際の条件となる視界は1600メートルで、天候に問題はなかったとみられる。広島空港に観測所がある関西航空地方気象台によると、この時点で滑走路付近の視界は1800メートル以上あった。しかし、その後視界は急に悪くなり、事故が起きた8時5分ごろには300〜500メートルにまで悪化していたという。午後8時ごろの空港周辺は弱い雨が降り、一部に霧がかかっていた。
事故直前の管制官との交信では、パイロットが何らかの異常を伝えるやりとりはなかったという。
山間地にある広島空港は、霧が発生しやすく、最も精度の高い「カテゴリー3」と呼ばれる計器着陸装置(ILS)で着陸機を誘導している。ILSは西側からの進入だけに対応し、東側からの着陸には対応していない。事故機は東側から進入し、滑走路の照明を見ながら着陸していた。
滑走路には事故機が接触した際にできたとみられる傷があり、周辺には部品が散乱。事故機は左右の主翼や胴体後方の下部などを損傷していた。着陸後に地面に接触して左旋回し、滑走路を外れて停止したとみられる。【佐藤賢二郎、狩野智彦、斎川瞳】
◇航空ジャーナリストの坪田敦史さんの話
雲や霧の状況は秒単位で変わるため、管制官が着陸許可を出した時点では問題がなかったとしても、瞬間的に視界が悪い状態になった可能性は考えられる。パイロットは滑走路がよく見えていない状況で進入を続けたのではないか。パイロットはいかなる状況にも適切に対処できなければならず、視界不良などの問題が起きたのならゴーアラウンド(着陸やり直し)の判断をすべきだった。

アシアナ機あわや斜面転落、フェンスまで十数m(読売新聞)
広島空港が開港して20年以上
が経っている。今更、「 山あいにある広島空港は霧や雲が発生しやすいため、着陸機を滑走路まで誘導する計器着陸装置は国内空港でも最高水準のものが運用されているが、アシアナ航空162便は風向きの影響でこの装置が利用できない東側から進入した。」
との理由で事故を起こすのか?
出発前に最低限のシナリオと対応ぐらいブリーフィングでアシアナ航空は確認させないのか?それぞれの空港の特徴や問題点、そして対応策のまとめなどを
作成していないのか?もし、作成していなくて、優秀なパイロットを雇用していなければ事故は運次第かも?
着陸機を滑走路まで誘導する計器着陸装置なしで着陸できないパイロットを使うな!
パイロットの資格を持っていれば規則的には飛行できるが、安全とは別次元。
山あいにある広島空港は霧や雲が発生しやすいため、着陸機を滑走路まで誘導する計器着陸装置は国内空港でも最高水準のものが運用されているが、アシアナ航空162便は風向きの影響でこの装置が利用できない東側から進入した。
この際、通常よりもかなり低い高度で滑走路に入ったとみられているが、どんな原因が考えられるのか。
元日航機長で航空評論家の小林宏之さんは「当時、空港周辺の低いところに雲があったようだ。パイロットが滑走路を確かめようと高度を下げ過ぎたか、滑走路までの距離と維持すべき高度を見誤ったのではないか」と推測。「機材故障もありえるが、ヒューマンエラーで起きた可能性がある」と指摘する。
元日航機長で航空評論家の諸星広夫さんによると、破損した着陸誘導用の無線アンテナがある滑走路の手前約300メートルの地点では通常、機体の高度は50~60メートルはあるはずだという。「高さ約6メートルの無線アンテナに接触したのは、滑走路前での高度が低すぎたということ。計器着陸装置が使えなかった場合、手動の着陸になり、もし慣れないパイロットなら緊張するかもしれない」とみる。
サンフランシスコ空港のアシアナ航空214便着陸失敗事故を知っている人達はすごく慌てたであろう。状況が判断できない状態では、早く機体から
離れないと火災に巻き込まれる可能性もある。アシアナ航空はLCCじゃないけど結構事故を起こす。

アシアナ航空214便着陸失敗事故 (平和と繁栄の回廊)
着陸に失敗して乗員乗客計27人が負傷した14日夜の広島空港(広島県三原市)のアシアナ航空機事故。雨の中、緊急脱出装置で機外に逃れた複数の乗客が撮影した動画には「赤ちゃん大丈夫か」と叫ぶ人や、乗務員に食ってかかる乗客らしい人の声など、生々しい音声が収録されていた。多くの乗客が「死を意識した」と話す混乱の様子が伝わってくる。
動画の一つは、韓国で家族旅行をした帰りに事故に遭った広島県安芸高田市の男性会社員(29)が機内から脱出した直後、家族を連れて走って逃げながら撮影したもの。消防車のサイレンが鳴り響き、遠くに機体が見える。暗闇の中、女性が「逃げて! 赤ちゃん大丈夫ですか」などと叫んでいる。
 男性によると、着陸の5分ほど前、高度を下げる機体が大きく揺れた。着陸と同時に「バーン」という大きな音がして上下に揺れ、乗客の女性らの「キャー」という悲鳴が機内に響いた。両側の窓の外に火柱が見え、床から出る焦げ臭い煙で視界が悪くなり、機内は一気にパニック状態になった。
男性によると、着陸の5分ほど前、高度を下げる機体が大きく揺れた。着陸と同時に「バーン」という大きな音がして上下に揺れ、乗客の女性らの「キャー」という悲鳴が機内に響いた。両側の窓の外に火柱が見え、床から出る焦げ臭い煙で視界が悪くなり、機内は一気にパニック状態になった。
機体が停止すると、客室乗務員が機体中央の両側の非常口を開けようとしたが、開かない。乗務員までが冷静さを失っている様子を見て、男性は「もうだめかもしれない。外に出られない」と思ったが、後方から「逃げてください」と乗務員の声が響き、何とか機外へ逃れた。
男性は「機体が爆発するかもしれないと恐怖でいっぱいだった。家族を守ろうと、急いで逃げた。とにかく焦っていた」と話す。
もう一つの動画は、別の男性(58)が、機体から脱出した直後にデジタルカメラで撮影した。撮影時間は約20秒。傾いた機体や消防車、逃げる人影のほか、女性が甲高い声で乗務員をののしるような声が収められている。
事故から一夜明けた15日、広島空港は滑走路の閉鎖が続く影響で航空便の欠航が相次いだ。2階出発ロビーでは、搭乗予定客らがキャンセルや別便への振り替えの手続きをしていた。
事故機に搭乗していた広島市中区の女性(29)は、事故後に三原市内の病院で治療を受けた後、空港に隣接するホテルに宿泊。事故直前の状況について「硬い物同士がぶつかるような『ドン』という衝撃が2回あり、1回目の衝撃の前に急降下があった」と振り返った。その後機内に煙が充満し、「ギャー」「人殺し」などの叫び声などにパニックになって過呼吸を起こしたという。女性は「怖くて飛行機にもう乗れない。真相を早く知りたい」と語った。【宮嶋梓帆、矢澤秀範、瀬谷健介、菅沼舞】
テレビで見たがフェンス側にあともう少し滑っていたら機体は折れていたかもしれない。機体が折れていたら燃料タンクが破損し、火災の可能性もあるし、
死者も出ていたかもしれない。不幸中の幸い!
運輸安全委員会は最近事故ばかりで大忙しだろう。
雨に煙る夜の空港に、けたたましい救急車のサイレンが鳴り響いた。広島県三原市の広島空港で、14日午後8時5分ごろ、韓国・仁川(インチョン)発のアシアナ航空162便(エアバスA320)が着陸時に滑走路をそれて停止した滑走路逸脱事故。着陸寸前に尾翼が誘導装置の無線アンテナに接触、機体は衝撃とともに滑走路にたたきつけられた。一時はエンジンからも煙が出たといい、脱出した乗客は心配そうにけが人を気遣った。
事故機のエアバスA320には乗客74人が搭乗、客席は半分ほどが埋まっていた。友人3人で2泊3日の韓国旅行を終えて帰国した広島市の会社員、岡崎みどりさん(52)は「着陸前、窓越しに右の主翼付近に炎のようなものが見えた。機内でも煙の焦げ臭いにおいがして、死ぬかと思った」と恐怖を語った。3人ともけがはなかったが、頭から血を流して救急車で搬送された乗客もおり、「腰が抜けそうだった」と話した。
ロシア人の男性乗客も「何が起きたのか分からなかった。エンジン部分に火を見た。自分も信じられなかったが、みんなもそうだったろう。ロケットに乗っているような気分だった」と不安そう。
3歳の娘と搭乗していた広島県福山市の保育士、那仁(ならん)真紀さん(46)は到着10分前から機体がかなり揺れるのを感じていた。着陸時に「バーン」という音がして、衝撃で前の座席で頭を打ち、額を切った。
隣の娘の体をとっさに手で押さえたが、機内には悲鳴が上がった。客室乗務員が「早く降りてください」と叫び、ドアから脱出した。「機体前方のドア付近から白い煙が入ってきて、爆発すると思った」と緊張した様子。
幼い子供を連れた日本人の女性(34)は着陸時に「ドーン」という音が聞こえて、機体が止まって窓の外を見ると炎と煙に気づいたという。「到着前から、窓から濃い霧が見えて、着陸できるのか心配していた」と話した。
インドネシア旅行の帰りに仁川経由で広島に戻ってきた広島県庄原市の農業、新宅道和さん(58)は脱出する際に首をひねるけがをした。広島に到着する手前から気流の影響で機体が上下に揺れるのを感じた。着陸直前には乗客から「キャー」と悲鳴が上がった。着陸後に機体が停止すると、客室内には煙が充満。「冷静に脱出できたが、こんな事故に遭うなんて現実感がない」と振り返った。
日本人男性(29)は「衝撃の後、機内は電気が消えて、煙が充満した。顔から血を流している人もいた。乗員のアナウンスは韓国語だけだった」と振り返り、「飛行機にはもう乗りたくない」と話した。婚約者と2泊3日の韓国旅行帰りだった広島市中区の男性会社員(29)は「着陸前に大きな衝撃があった後に、もう一度衝撃があった。かがむこともできず、頭をぶつけて出血する乗客もいた」と興奮した様子だった。【高田房二郎、目野創、石川将来、菅沼舞】
志村福子麻酔医は本当に強い。なかなか出来ないことだ。
厚生労働省は群馬大学病院腹腔鏡手術8人死亡の問題もあって無視できなくなったのだろう。
権力と権限を持つ厚生労働省を相手にここまでやったとは本当にすごいと思う。
厚生労働省は14日、腹腔(ふくくう)鏡手術後に患者が相次いで死亡した千葉県がんセンター(千葉市)について、質の高いがん治療を提供する「がん診療連携拠点病院」の指定を更新しないと発表した。診療報酬の優遇のほか、がん専門医らへの研修や患者の相談支援事業などの補助金が受けられなくなる。
千葉県がんセンター(千葉市中央区)で腹腔(ふくくう)鏡手術を受けたがん患者が相次いで死亡した問題で、県の第三者検証委員会は、検証対象とした11例の大半で術式の選択や術中、術後の対応に複数の問題があったなどとする最終報告書案をまとめ、30日、県側へ提出した。指摘を受けたセンターは、院内の体質改善を含めた再発防止策を迫られる。
医師や弁護士などで構成する第三者委が検証対象としたのは、2008年6月〜14年2月に腹腔鏡を使った術式で膵臓(すいぞう)や肝臓、胃などの切除手術を受けた後に死亡した57〜86歳の男女11人。うち8人は、消化器外科の50代の男性医師が執刀した。各事例については高度な専門知識が求められるため、第三者委が依頼した日本外科学会が分析を進めていた。
報告書案は、肝臓部分切除を受け4日後に死亡した男性(59)のケースを「出血量を予測する検査が遅れた」と分析。胆管合流部付近を切除し、約3カ月後に死亡した男性(74)については「難度の高い手術を腹腔鏡で行った判断に問題があり、がんの進行が判明した段階で開腹手術に切り替える必要があった」などと問題点を指摘した。
さらに、11件全てのケースで、高度な医療技術や新たな術式の実施前に開く院内倫理審査委員会に諮っておらず、家族らへの事前説明に関する記録も不十分などとして、センターの管理体制の改善を求めた。【岡崎大輔、円谷美晶】
橋本佳子(m3.com編集長)
「医療の良心を守る市民の会」の7月12日のシンポジウムで、前千葉県がんセンター麻酔科医の志村福子氏は、同センターに在籍していた2011年に、医療事故と歯科医師の医科麻酔科研修について、厚生労働省への内部告発に至った経緯を「それ以外に言うところがなかった」と説明、それでも厚労省は対応せず、「内部告発しても、どこも対応できない構図」と語り、内部告発の苦労と限界、さらには医療機関が自浄作用を失った場合の対応の難しさを吐露した。
結局、事故が相次いだ千葉県がんセンター消化器外科の腹腔鏡下手術の問題は、今年に入り、マスコミに大きく取り上げられるに至った。同センターは一部の事例について事故調査を実施していたものの、この4月以降、腹腔鏡下手術を中止し、本格的な調査や対応にようやく乗り出した(同センターのホームページを参照)。歯科医師の医科麻酔科研修については、千葉県警が医師法違反(無資格医業)の疑いで捜査、千葉地検は2012年3月に手術管理部長らを起訴猶予処分としている。
「私が経験したのは、多くの病院で日常的に行われているものではなく、千葉県がんセンターが特殊なのだと思う。しかし、その解決に当たって、内部告発は役に立たなかった」。こう語る志村氏は、「本来は内部告発に至る前に、自らが問題提起して、解決するのが組織の在り方」と指摘するとともに、内部告発が必ずしも有効に機能しない現状を踏まえ、手術成績を公開するシステムなどを構築すれば、外部チェック機能が働き、全体成績の向上が期待できるとした。
志村氏自身は、内部告発を理由にパワーハラスメントを受け、千葉県がんセンターを退職、今は長野県の病院に勤務している。千葉県を相手に提訴した国家賠償請求訴訟では、2013年12月の千葉地裁判決、2014年5月の東京高裁判決ともに、志村氏が勝訴している(東京高裁判決は慰謝料30万円の支払いを千葉県に求める判決。6月に県が最高裁に上告)。
シンポジウムでは、同じく内部告発者の立場から、前金沢大学付属病院産婦人科講師の打出喜善氏が自らの経験を語った。志村氏と共通していたのは、内部告発は組織自体のために行うものであり、本来なら内部告発をしなくても済む組織にすべきという点だ。また2006年4月から施行された公益通報者保護法も、内部告発を機能させる仕組みとしては不十分ということも、両者とも身をもって経験している。
打出氏がかかわったのは、自身が所属する金沢大産婦人科の医師が、1998年に患者の同意を得ずに実施した臨床試験で、その後に一人の患者が死亡した事件。遺族が1999年に民事訴訟に訴え、打出氏は遺族の側に立って証拠をそろえるなどして支援、2006年3月に上告棄却という形で、遺族側の勝訴が確定した。さらに裁判の過程で発覚した事実を無視できなかった打出氏は、臨床試験の症例登録票を改ざんした同産婦人科の担当医を公文書偽造罪、同科教授を裁判での偽証罪で告発したものの、不起訴になった。
「内部告発」は、英語では、「whistle blower」、つまり「警笛を鳴らす人」。しかし、日本語の「内部告発」には、「whistle blower」よりも負のイメージが強いと打出氏は指摘。「内部告発の目的は、非倫理的行動の是正であり、それが達成できるなら内部告発という手段を取らなくて済む」(打出氏)。
打出氏は、1998年以降も、金沢大学に勤務していた。「自分の母校であり、いい病院、いい大学であってほしいと思っており、外から批判するのは、嫌だと思っていた。けれども、やはり不幸だったことは事実」と打出氏は語り、大学内で厳しい立場に置かれたことを明かした。「失えば、得るものがある」(打出氏)。「失うもの」とは、大学内での立場、「得るもの」とは、打出氏の行動の支援者だ。2006年に公益通報者保護法が施行された。しかし、(1)「労働者」に対する解雇等の不利益な取り扱いを禁止する法律であるため、管理者になったら、保護の対象から外れる可能性がある、(2)通報の対象となる法律が定められている――という問題があるとした。(2)の点は、改善に向けて検討が進められている。
シンポジウムのテーマは、「患者と医療者が手をつなぐためにすべきこと 事故調査は?何故、内部告発を?」。志村氏と打出氏のほか、夫を医療事故で亡くした伊藤典子氏が、自らの裁判の経験を語った。
「医療の良心を守る市民の会」は、“医療事故調”の設置を長年求めてきたこともあり、今国会で法案可決し、2015年10月から創設予定の “医療事故調”に議論は発展。新制度では、医療事故調査を行う第三者機関として医療事故調査・支援センターの設置などが予定されている。
志村氏は、新制度が、「院内調査が第一」である点に触れ、「千葉県がんセンターは、院内調査を実施する気配がなかったので、事故に遭った当事者や第三者が、医療事故調査・支援センターに訴えるシステムがないと成り立たないのではないか」と発言。
「医療の良心を守る市民の会」代表の永井裕之氏も、「医療界の自律性がないと、本当の事故調査はできないという危惧を抱いている」と指摘。その上で、今後、議論が本格化する“医療事故調”のガイドラインが重要であり、遺族や病院職員などが直接、医療事故調査・支援センターに訴える仕組みが必要だとした。法律では、同センターによる事故調査は、医療機関による報告事例に限られる。「医療機関の管理者による意図的な事故隠しなどを少なくするために、医療事故調査・支援センターが遺族の訴えを検討し、『これは調査した方がいい』と医療機関に助言する仕組みをぜひ作ってもらいたい」(永井氏)。
フロアからは、「内部告発の矢がどこに飛んでいくかを考えていかなければいけない」との発言も出た。「矢」の先は、事故の被害者、厚労省、マスコミなどが想定され、被害者に飛び、時に大学の内部紛争に巻き込まれ、被害者が内部告発に振り回されることもあるため、発言者は、「“医療事故調”で内部告発をどう扱うかを検討しないと、変なところに矢が飛んでいきかねない」と釘を刺した。
内部告発の対象は、歯科の麻酔研修と医療事故
志村氏が約30分にわたり語った体験は、以下のようなものだ。千葉県がんセンターには、2007年から非常勤医として、2010年4月から常勤医になったものの、半年後の2010年9月末に退職した。
内部告発の対象は、2つの問題。一つが、歯科医師の医科麻酔科研修、もう一つが、消化器外科の手術だ。
歯科医師の医科麻酔科研修については、厚労省がガイドラインで、「歯科医師が研修の目的で麻酔行為に参加する場合は、患者の同意を得なければならない」などと定めている。麻酔の種類別に研修方法も規定され、硬膜外麻酔や脊椎麻酔については、「研修指導医または研修指導補助医の行為を補助するもの」とされている。
「2007年から勤務を始めたが、厚労省のガイドラインが守られていなかった。患者に対して説明もせず、硬膜外麻酔や脊椎麻酔も、(指導医等がいない状態で)歯科医師がやっていた。非常勤医だったため、あまり言える立場ではなかったが、問題を感じていた」と志村氏は話す。
消化器外科の手術について、志村氏は、「腹腔鏡下手術に限らず、一般の手術でも術後早期の再手術が多かった。千葉県がんセンターに勤めている人にとっては、特定の科で、再手術が多いのは、共通の認識だったと思う」と語る。特に問題視されたのは、腹腔鏡下の膵頭十二指腸切除術。「保険診療でできる手術ではない。(先進的な医療に取り組むことで、名声を高める目的があったのではないか。違う術式で保険請求していたとも報道されている」(志村氏)。
消化器外科の手術を問題視する直接的なきっかけとなったのが、2008年11月に手術、その5カ月後に死亡した事例だという。同手術の麻酔にも、歯科医師がかかわっていた。「術前から状態が悪い患者で、腹腔鏡下手術後の翌日に、再手術をした。その麻酔担当が歯科医師で、術中に心停止した。蘇生に時間がかかって、植物状態になった。歯科医師は、『急変したので、手術管理部長を呼んだが、なかなか部長が来てくれなかった』と言っている。重症な症例なのに、現場を離れて、研修という立場の歯科医師に任せきりになっていたことが問題。他の職員から、事故調査委員会を開くべきとの声が上がったが、病院側は開かなかった。その後も、歯科医師の医科麻酔科研修もそのまま続いた」(志村氏)。
厚労省、内部告発に対応せず
志村氏は、「2008年から2010年までの間、私一人で内部告発していたかと言えば、半分はイエスで、半分はノー。このままではいけないという問題認識を一部の医師も持っており、今も問題解決に向けてがんばっている」と語る。
2010年4月に千葉県がんセンターの常勤医となったのは、非常勤医の立場では意見は言えず、また現場をきちんと把握するためだという。しかしながら、その時点でも、歯科医師の医科麻酔科研修は、患者の同意取得方法をはじめ、ガイドラインを遵守しているとは言えない状況だった。そもそも、当時、手術管理部の常勤麻酔科医は、部長と志村氏の2人のみで、残り4人が全て歯科医師だった上、初期研修がローテーションしてくる状況では、麻酔科医の数が圧倒的に不足していた。
こうした中で、2件の医療事故が起きた。志村氏は、「このままでは患者の安全にかかわる、と懸念した。手術管理部長に言っても無駄だろうと思い、センター長に訴えた。センター長は歯科医師がどんな勤務をしているのか、また事故の状況も把握していなかった。かなりしつこく言ったが、改善はなかった」と当時を振り返る。その結果、志村氏は2010年8月から、手術室に出入り禁止の状態になり、仕事がなくなり、センター長に訴えたところ、千葉県内の他の病院への異動を提示されたという。遠距離で通勤には難しい病院であったことから、2010年9月末、志村氏は退職した。
次の段階として、志村氏が訴えた先は、千葉県病院局長。歯科医師の医科麻酔科研修、消化器外科の腹腔鏡下手術などに関する問題点を記し、病院局長宛てにメールを送った。しかし、調査をしたり、志村氏に直接話を聞きに来ることはなかったという。
埒が明かないため、千葉県病院局長宛てと同様の内容のメールを厚労省に送ったのは、2011年2月のことだ。しかし、その返事は、(1)2010年9月末に退職し、千葉県がんセンターの「労働者」ではないので、公益通報者保護法に基づく「公益通報」の要件にはあてはまらない、(2)千葉県がんセンターの事例なので、千葉県に相談すべき――という内容だ。「メールには、既に千葉県病院局に相談していることも書いていた。これで、内部告発しても、どこも対応してくれないという構図ができ上った」(志村氏)。
志村氏は今、知り合いを通じて探した長野県の病院に勤務している。「実名で裁判をしていることもあり、千葉県内では職が見つからなかった。正直、病院にとっては、『うるさい医師』と映るのだろう。しかし、今の病院の院長は『信念を持ってやっていることだったら、気にしない』と言ってくれた。内部告発すると、同業者からは『反体制側』『受け入れられない存在』になる上、その後の就職にも影響する。なぜ内部告発をした側が、ネガティブに取られるのか。本来なら、内部告発をせずに済む体制、さらに内部告発をしたら、その人の人権が守られる体制が必要」。志村氏はこう語り、講演を締めくくった。

志村さんの告発に対する厚労省の回答メール。千葉県に相談するよう勧めている=一部画像処理
10年夏、センター長に問題指摘
"腹腔鏡下手術後の死亡例が相次いでいることが発覚した千葉県がんセンター=千葉市中央区仁戸名町で、本社ヘリ「あさづる」から
千葉県がんセンター(千葉市)で、腹腔(ふくくう)鏡下手術を受けた患者9人が、手術後に相次いで死亡していた。うち7人は同じ執刀医によるもので、手術ミスの疑いもある。センターに勤務していた麻酔医が県や厚生労働省などに告発していたが、放置されていた。麻酔医は「告発が受け付けられていれば、死亡事例が相次ぐことは防げたのでは」と話す。 (荒井六貴)
「父は初期のがんと言われ、すぐに治ると思っていた。でも、手術の後、1日もたたないうちに再手術をすることになって、意識が戻らずそのまま亡くなった」
千葉県がんセンターで2008年11月、胃がんの腹腔鏡下手術を受け、5カ月後に死亡した男性=当時(58)=の長男(39)は、不信感を募らせる。
一部報道で、死亡例が相次いでいることが発覚したのは今年4月。県病院局などによると、08年6月から14年2月にかけ、この男性を含め、胃や膵臓(すいぞう)の一部などを摘出するため、腹腔鏡で手術を受けた9人の患者が、手術後に死亡していた。うち7人は、消化器外科部の指導的立場にあるベテランの男性A医師が担当していた。
腹腔鏡下手術は、患者の体に数カ所の小さな穴を開け、カメラや器具を入れて行う。開腹手術に比べ、体を傷つける範囲が少なく、患者の負担は小さい。一方で、モニター画面を見ながらの高度な技術が必要で、危険性も高まる。
実は、12年9月に女性(76)、13年1月に男性(57)の2人が死亡した段階で、センターは外部有識者を招いた事故調査委員会を設置していた。昨年8月にまとまった報告書では、電子カルテの記載不備などを指摘。「腹腔鏡下手術のメリットやデメリットについて患者への説明が十分でなく、センターの倫理審査委員会の合意もなかった」「肝胆膵外科に、経験の深い外科医が手術に参加していれば、重要なアドバイスが得られた可能性が高い」などとした。ただ、この報告書は遺族には示されなかった。
その後、センター長は、膵臓がんの腹腔鏡下手術を見合わせるよう指示した。だが、今年2月に胆のうと胆管を摘出する手術で患者がまた死亡した。
膵臓などを摘出する膵頭十二指腸切除術で腹腔鏡を使うのは保険適用外だが、保険請求していた疑惑も浮上している。
冒頭の08年11月に手術を受けた男性の長男らは、センターが事故調査委員会を設ける前の11年9月、センターの説明に納得できないとして、外部で検証することなどを求める質問状を提出していた。
センターが12年2月に出した回答は「原因の特定は不可能。胃の手術での死亡例は、現在までありません」と説明。わざわざ「胃」に限定して「死亡例なし」と伝えていた。
長男は「死亡例を隠したように感じ、誠意に欠けている。父の死はいったい、何だったのか。真相をはっきりさせてほしい」と話す。
県病院局は「短期間で死亡が相次いだ事態を重く受け止める」として、あらためて外部の有識者による検証委員会を設置することを表明。手術ミスの有無や、手術方法の選択の妥当性、保険の不正請求疑惑などについて詳しく調べるとしている。
退職後は告発できない!? 県も厚労省も動かず
センターや県は、遺族が訴えるもっと前から問題を把握していた疑いがある。
センターの麻酔科医として勤務していた志村福子医師(42)が10年夏から11月にかけ、当時のセンター長や県病院局長らに、口頭やメールで告発していたからだ。
志村さんは、腹腔鏡下手術で死亡事例が相次いでいることや、歯科医師が無資格で麻酔をかけている実態を伝えていた。志村さんとは別の医師もセンターに改善を訴えていたという。
県病院局長宛てのメールでは「消化器外科は再手術が頻回で、他の病院に比べ、異常に再手術が多い。中には死亡例もある」「私の統計では1年間に10例以上は再手術です」などと指摘。「センター長は、全く動こうとしない。外圧で変化を生じさせるしかないと考えた」と強調していた。
告発理由について、志村さんは「大きな事故があったのに、第三者を入れて、検証さえしていなかった。そのまま放置したら、不幸になるのは患者だ」と考えたという。「問題の医師らは、他の選択肢があっても、腹腔鏡にこだわる印象があった。腹腔鏡下手術ができない病院は、患者が集まらないという現実もあった」と話す。
病院局長からは「今後、私の方で調査する」という返信があったが、具体的に動いた様子はなかった。それどころか、志村さんは、仕事を完全に外される嫌がらせも受け、10年9月に退職に追い込まれたという。
志村さんは今度は、11年2月、厚労省の公益通報窓口に、実名で告発した。
郵送とメールで、死亡事例を詳しく説明し「センター長や県病院局長にも申し入れているが、黙殺され改善されない。患者に質の高い適切な治療を提供する理念から、大きくかけ離れている」と対応を求めた。
しかし、厚労省はそっけなかった。告発の手順を定める公益通報者保護法の要件に該当せず、所管する県に相談してほしいと返信された。保護法で保護の対象となるのは、「労働者」と定められている。志村さんはその時点では退職しており、その「労働者」には当たらないという論法だった。
現在は長野県安曇野市の病院に勤務する志村さんは、「県が対応しないから、厚労省に告発したのに。厚労省も相手にしてくれず、なえてしまった。あの時、すぐに調査を開始していれば、これほど死亡事例が増えることはなかったのではないか」と残念がる。
告発を放置したことについて、県病院局経営管理課の海宝伸夫副課長は「告発の有無を含めて調査している。検証委の報告を待つ」とだけコメントした。厚労省医政局総務課は「もっと丁寧に対応できたと考えている。公益通報のルールに縛られすぎず、より柔軟に対応できるよう検討を始めている」と、反省の弁を述べる。
告発者を守るための公益通報者保護法をめぐっては、数々の欠陥が指摘されている。公益通報制度に詳しい中村雅人弁護士は「通報の適格要件が厳しすぎたり、守らない場合の罰則がないなどの問題がある」と話す。「官僚は、できるだけ仕事をしなくて済むように解釈する傾向がある。告発の受け手の教育や、法改正などを検討すべきだ」
どの世界にも似たような問題が存在するのか? 皆、同じ人間。結局は似たように行動を取っても不思議ではない。
聖マリアンナ医科大学病院(川崎市)で医師11人が、厚生労働省が定める「精神保健指定医」の資格を不正に取得していた疑いがあり、大学が調査委員会を設置して事実関係を調べていることが14日、わかった。
厚労省は、同病院医師らの指定医の資格取り消しについて近く協議する。同病院では資格申請中の医師3人についても不正の疑いが浮上しているという。
同大学によると、今年2月、厚労省から、大学病院の神経精神科に所属していた医師について、同省に提出した診療記録などに問題があり、「不正に資格を得た疑いがある」との指摘があった。精神保健指定医の指定を受けるためには、一定数の診療経験などが必要となる。
同大は弁護士など外部委員も交えた8人による調査委員会を設置し、指定医資格を取得した経緯などを調べたところ、「複数の医師が同じ患者の症例を提出した」などの違反が見つかった。厚労省からは「自分が診ていない症例を提出した疑いがある」との指摘もあった。
現時点では、既に資格を取得した医師11人と資格を申請中の3人について不正が疑われているが、指導医9人についても、監督責任があるとして、厚労省から調査を求められているという。
厚労省も調査を行っており、同大学病院の医師らの指定医を取り消すかどうか検討を進める。
ドラマのような展開だ!
韓国船籍旅客船「セウォル号」(M/V"SEWOL", IMO9105205)の大惨事から
推測すると真実はわからないままだろう!検察や警官から情報がリークしたようにいろいろなところで情報漏えいや情報の消去の
可能性がある。権力が集中する構造では公平な捜査は無理であろう。
【ソウル=豊浦潤一】韓国の李明博イミョンバク政権下での資源外交に絡む横領疑惑で検察の取り調べを受けていた建設会社の前会長が、朴槿恵パククネ大統領の元秘書室長らに多額の現金を渡したと暴露して自殺したことで、政界が大揺れとなっている。
前政権の暗部である横領疑惑にメスが入ることで、朴政権の浮揚につながると見られていたが、暴露により窮地に立たされる展開となった。
検察は12日、特別捜査チームを設置した。
疑惑を暴露したのは、与党セヌリ党の元国会議員で「京南企業」の成完鍾・前会長(63)。海外での資源開発に絡み公社と政府系金融機関から借りた資金を横領したなどの疑いで検察の取り調べを受けていたが、9日、ソウルの山中で自殺した。
韓国紙・京郷新聞は10日、自殺直前の成氏との電話インタビューを特報。成氏は2006年9月、金淇春前秘書室長に10万ドル(約1200万円)、07年に許泰烈元秘書室長に7億ウォン(約7700万円)を渡したと語った。当時、許氏は大統領選の党内予備選に出馬した朴氏の選対幹部を務めていた。
さらに自殺した成氏の上着から発見されたメモには、金、許の両元秘書室長のほか、李丙●・現秘書室長、李完九首相ら朴大統領に近い実力者を含む計8人の名前や職位と、そのうち6人に渡した金額が記されていた。8人のうちほとんどは疑惑を否定している。(●は王ヘンに「其」)
最大野党・新政治民主連合は「憲政史上最悪の醜聞」と批判を強めており、朴大統領は12日、「聖域なき厳正な対処」を検察に求めるコメントを発表した。
兵庫県警高砂署員が姫路市内のホテルで団体職員の女性(61)に任意同行を求めた際、女性がトイレ内で自殺を図り死亡した問題で、女性が勤務していた伊保漁業協同組合(高砂市)で約2000万円の使途不明金があることがわかった。
3月上旬に行われた県の監査で見つかり、発覚後、女性が行方不明になっていた。
同漁協によると、女性は漁協で会計を担当。県の監査の日に女性は出勤せず、その後連絡が取れなくなっていた。
同署によると、4月10日午後0時頃、女性から同僚に「源泉徴収票のコピーをファクスしてほしい」とメールがあり、送り先になっていた姫路市内のホテルに同署員2人が出向いた。同2時40分頃に女性がロビーに現れ、任意同行を求めたという。
営業として働いたことはない。営業は仕事とってなんぼと聞いたことがある。営業的なことをした事はあるがどこまで汚いことをするのか、
そこまでごまかすのか、完全に赤字であるのを分かっていて仕事を取るのかなど、嫌な部分を見るとそこまでしなくとも良いと思い、結果、仕事が取れなかった。
今回のような記事を読むと悪い気はしない。神様を信じないけど、神様の天罰だと思いたい。当事者達は「神様、なぜ俺達だけが」と思っているかもしれない。
JR貨物の倉庫工事を巡る汚職事件で、JR会社法の贈賄容疑で逮捕された電気設備会社「カナデン」(東京都港区)課長の三枝裕祐容疑者(47)が、事件4年前の2008年頃から、収賄側のJR貨物幹部富永英之容疑者(45)と交流を深め、富永容疑者が転勤先から本社に戻ったのを機に本格的な接待攻勢を始めていたことが分かった。
警視庁は、三枝容疑者が計画的に口利きを持ちかけたとみている。
捜査関係者などによると、富永容疑者は1992年にJR貨物に入社し、主に事業開発本部で工事の発注を担当。仕事を通じて複数の業者と付き合いがあり、富永容疑者を中心にした会合やゴルフコンペも開かれていたという。
カナデンで空調や照明機器の営業を担当していた三枝容疑者は08年頃、同業者の知人を介して富永容疑者と知り合い、交流を始めた。
富永容疑者が10年4月に九州の支店に転勤した後も連絡を取り合い、富永容疑者が12年3月に本社に戻って倉庫工事の発注権限を持つ事業開発本部開発部のグループリーダーに就任すると、その3か月後から風俗店での接待を始めたという。
富永容疑者は12年6月~14年8月、カナデンが倉庫工事を下請けとして受注できるよう便宜を図った見返りに、風俗店で計約43万円相当の接待を受けた疑いが持たれている。
東洋ゴム工業が免震ゴムの性能を偽装した問題が発覚して13日で1か月を迎える。
4月中にも公表される不正の経緯に関する調査結果が今後の焦点だ。2007年に発生した防火用建材の性能偽装問題を受け、再発防止に取り組みながら同様の問題が発生し、山本卓司社長ら経営陣の責任を追及する声も強まっている。
不正を行った明石工場の50歳代の元課長代理は13年1月まで、10年以上も品質管理を担当していた。東洋ゴムは、個人による不正の可能性が高いと説明するが、管理体制の不備を指摘する声は強い。
東洋ゴムは07年の防火用建材の問題発覚後、再発防止策として〈1〉全製品の品質検査〈2〉部門間の人事異動の徹底――などを打ち出した。この時期には既に免震ゴムの不正が行われていたが、同年11月の品質検査をすり抜けた。
元課長代理も全社的な異動の始まった08年4月以降、5年近く担当を替わらなかった。国土交通省は「対策が一つでも確実に実施されていれば今回の事案は起きていない」と指摘する。
不正を行ったらとんでもない損害を被ることを経験しないと止められないのであろう。そうでなければ不正を行ったほうが得だ。不正を行っても
何十年と問題にならないケースを知っている。まあ、だからと言ってこのままなのか、もうそろそろ問題になるのか見当が付かない。
関与していないのどのようになっても関係ないが、時々、不正を行っているほうが得だと思う。ある人にある問題についてどう思うのかと尋ねられた
ことがある。不正であることは知っているが、自分達が取締る立場ではないし、問題になった時は全てを受け入れる覚悟があれば、同じようにすればよいし、
最悪の状況を受け入れたくなければ、問題にならないからと言ってまねをするべきでないと言ったことがある。
免震ゴム問題が最悪の状況なのか知らないが、このようにならないと不正をした人達や会社が得ばかりとなる。
東洋ゴム工業は当初、性能偽装があったのは2004年以降に納品された製品で、これらが18都府県の55棟の建物で使われたとしていた。
しかし、その後、製品の開発や性能テストを担当していた元課長代理が、「55棟以外に使われている別の製品でも性能を表す数値を改ざんした」と認めたため、同社は、1996年以降に納品され、計約200の建物に使用された別の免震ゴムについても、性能が国の基準を満たしているかどうか調査を開始した。
同社はこれまで、このうち約130の建物に使われている約1600の免震ゴムの性能などを確認し、その結果、約10%が国の基準を満たしていないのに納品されていたことが新たに判明。問題はさらに拡大する可能性が高い。
同社は近く、約200棟に使用された製品全体についての調査結果を公表し、国交省に報告する。また、今月中にも、社内で偽装が行われ、見過ごされた経緯や背景、再発防止策などを公表する方針。
お人好しや偽善者を安く利用する外務省の判断が裏目に出ただけ。どれぐらいの人達が実際にボランティアに参加しているのか知らないが (メディアの情報はNPOなどに利用されている場合があるので信頼しない。また、政治家への準備段階としての活動している人達もいるかもしれない。) 交通費や滞在費まで自己負担でいろいろな被災地に行く人達の行動が理解できない。被災地が近くであれば、近いからちょっと助けてあげようかと 思うことは理解できる。しかし、遠くまで旅費の自己負担で出かけているのは個人的に理解できない。結果、安く又は無料で労働力を使えるので地方自治体や 政府機関としては嬉しい事に違いない。給料を貰っていながら対応の悪い公務員達は辞めさしてほしい。給料を貰って悪いサービスを提供。 ボランティアなら妥協出来るかもしれないが、税金が投入されて悪いサービスや税金の無駄遣いの企画の実行は止めてほしい。
外務省の「領事シニアボランティア」として中国・上海の日本総領事館で活動中に負傷した京都府内の60歳代女性が、労働基準法に基づき治療費などの支払い義務が国にあることの確認を求めた訴訟で、京都地裁(神山隆一裁判長)は10日、女性の請求を認める判決を言い渡した。
外務省によると、同ボランティアは領事館業務を向上させるため2003年に導入され、海外勤務の経験などがある40~69歳の民間人に委嘱。14年に終了するまで延べ37人が派遣された。
判決によると、女性は犯罪行為で中国当局に拘束された邦人への対応などを担当。09年4月、同館内の階段で転倒し、左足の甲骨折などのけがを負った。
国は「女性の活動は領事業務の補助や助言」などと主張したが、判決は、女性と領事館員の業務に大きな差はなく、「領事らの指揮、監督下にあった」と認定。使用者として治療費の支払い義務があると認めた。
同省は「厳しい判決。関係省庁と協議し、対応を検討する」とし、原告代理人の渡辺輝人弁護士は「国がボランティア名目で労働者を酷使していた実態を踏まえた判決」と評価した。
NHKの報道番組「クローズアップ現代」でのやらせ疑惑で、放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会(川端和治委員長)は10日、問題視される放送回の取り扱いについて討議。
委員から「放送倫理上、問題がある」との意見が数多く出された。NHKが今月中にもまとめる調査報告書を待って、今後の具体的な対応を決める。
問題となっているのは、昨年5月14日に放送された「追跡“出家詐欺”~狙われる宗教法人~」。多重債務者がブローカーを介し、出家して名前を変えることで融資などをだまし取る手口を紹介した。
同番組でブローカーとされた男性は、NHKに訂正報道を申し入れ、期限内に明確な回答がない場合、BPOの放送人権委員会に人権侵害を申し立てる意向を示している。検証委はこれとは別に、放送倫理の観点から討議を続ける。
◇すでに「同級生の男子生徒に飲ませた」供述
名古屋市昭和区のアパートで昨年12月、同市千種区の森外茂子さん(当時77歳)が殺害された事件で、愛知県警が殺人容疑で逮捕した名古屋大学の女子学生(19)=鑑定留置中=が宮城県の私立高校在学時、猛毒のタリウムの中毒とみられる症状で視力が低下した同級生の男子生徒とは別に「もう1人にも毒を飲ませた」という趣旨の話をしていることが、捜査関係者への取材で分かった。愛知、宮城両県警は立件の可否を慎重に検討している。【三上剛輝】
捜査関係者へのこれまでの取材で、女子学生が同じクラスの男子生徒に対し「毒を飲ませた」と話していることが分かっている。高校などによると、男子生徒は2012年6月ごろから体調を崩し、同10月には視力が低下するなどして入院。タリウム中毒とみられ、両県警は傷害容疑での立件を視野に、女子学生の関与について調べている。
捜査関係者によると、女子学生は毒を飲ませた相手として、男子生徒とは別人の名前も挙げているという。この人物も心身の不調を訴えたとされる。ただ、男子生徒の事件と違い、裏付ける証拠が少ないことから、両県警は慎重に捜査を続けている。
女子学生は1月27日、森さんを殺害したとして、殺人容疑で逮捕された。「人を殺してみたかった」と容疑を認めており、自宅アパートからはタリウムとみられる薬物が押収された。名古屋地検は2月12日、責任能力の有無を調べるための鑑定留置を開始した。期限は5月12日。
◇13年9月から 「主に障害者自立支援事業に使用」
「ペットボトルのキャップを集めて世界の子供にワクチンを届けよう」と呼び掛け、キャップの売却益をワクチン代として寄付してきたNPO法人「エコキャップ推進協会(エコ推)」(横浜市中区)が、2013年9月から寄付をしていなかったことが分かった。矢部信司理事長が10日、記者会見して明らかにした。売却益は主に障害者自立支援事業に使っていたという。
エコ推は2007年12月から、国連児童基金(ユニセフ)を通じて途上国にワクチンを届けるNPO法人「世界の子どもにワクチンを日本委員会(JCV)」に売却益の寄付を開始。総額は13年8月までに約1億2000万円に上った。
矢部理事長によると、JCVとの間で寄付の方針を巡り見解の相違があったことや障害者支援を活動の中心にするようになったため、寄付を見送っているという。エコ推の定款では、売却益はワクチン代や障害者支援など7事業に充てるとしている。
矢部理事長は「ワクチンの寄贈が、子供たちがキャップのリサイクルを進めるモチベーションになっていた事実もあり、申し訳ない」と謝罪した。【水戸健一】
43万円の風俗接待で2億円の仕事を受注。違法でなければすごく安上がり!
JR貨物の倉庫工事を巡る汚職事件で、電気設備会社「カナデン」(東京都港区、東証1部)側が、JR会社法の収賄容疑で警視庁に逮捕されたJR貨物幹部社員・富永英之容疑者(45)への接待を開始した半年後に、初めて倉庫の下請け工事を受注していたことが、捜査関係者への取材でわかった。
カナデンは接待開始から1年半で計3件、総額約2億円の工事を受注していた。
同庁は11日午前、JR貨物本社(渋谷区)を捜索。接待を機に富永容疑者がカナデン側との関係を急速に深め、カナデンが下請けに入れるよう便宜を図ったとみて調べている。
捜査関係者によると、富永容疑者は2012年3月、東京貨物ターミナル駅(品川区)の倉庫工事の発注権限を持つ「グループリーダー」に就任。同法の贈賄容疑で逮捕されたカナデン課長・三枝裕祐容疑者(47)は、その3か月後の6月から富永容疑者への風俗店での接待を始めた。カナデンは同年12月、駅倉庫の照明・空調工事の下請け受注に初めて成功し、13年11月までに他に2件の工事を受注したという。
徹底的に調査すればよい!自業自得!43万円を自腹で支払っていなければ会社から資金は出ているはず。 ところで株式会社カナデンは大きい会社なの??三菱電機系の会社らしい。 ISO9001を取得しているらしいから、全て記録に残しているのかな??不都合な記録や打ち合わせ記録は消去しているのかな? ISO9001を取得するとトレーサビリティーを要求されるから面倒だと思う。まあ、ごまかしかが前提であれば形だけでよいので なんでもありだと思う。審査は内部と外部審査員次第!
東京・品川にある国内最大の貨物駅「東京貨物ターミナル駅」の倉庫新築工事や改修工事を巡り、下請け業者から接待を受けたとして、警視庁は10日、JR貨物(東京都)幹部社員の富永英之容疑者(45)(品川区勝島)をJR会社法の収賄容疑で、電気設備会社「カナデン」(港区)課長の三枝裕祐容疑者(47)(大田区池上)を同法の贈賄容疑で、それぞれ逮捕した。
同庁幹部によると、富永容疑者は2012年6月~14年8月、JR貨物が発注した東京貨物ターミナル駅の倉庫新築工事や改修工事で、カナデンが下請けとして照明工事や空調工事を受注できるよう便宜を図った見返りに、三枝容疑者から7回にわたり、川崎市などの風俗店で計約43万円相当の接待を受けた疑い。2人とも容疑を認めている。
富永容疑者はJR貨物事業開発本部開発部の「グループリーダー」で、工事の発注を担当。カナデンを下請けに入れるよう元請け企業側に要請したとみられる。
物流施設の設備工事で便宜を図った見返りに業者から接待を受けたとして、警視庁は10日、JR貨物(東京都渋谷区)の事業開発本部開発部グループリーダー富永英之容疑者(45)=東京都品川区勝島1丁目=をJR会社法の収賄容疑で逮捕した。電気設備会社「カナデン」(東京都港区)の課長三枝裕祐(ゆうすけ)容疑者(47)=東京都大田区池上4丁目=も同法の贈賄容疑で逮捕した。2人は容疑を認めているという。
捜査2課によると、富永容疑者は、東京貨物ターミナル駅(品川区)の敷地内にある物流施設「エフ・プラザ東京」の計4棟の設備改修工事や建築工事で、カナデンが照明器具工事などに下請けとして参入できるよう取り計らった謝礼などとして、2012年6月中旬~14年8月上旬ごろ、三枝容疑者から7回にわたり風俗店で計約43万円分の接待を受けた疑いがある。富永容疑者は課長級の社員で、工事の発注や設計、管理を担当。三枝容疑者は空調機器の販売に携わっていた。
JR貨物によると、「エフ・プラザ」は物流業者が貨物の保管や荷さばき、積み替えなどができる大規模複合施設。全国6カ所の貨物駅構内にある。JR貨物は「深くおわび申し上げます。捜査に全面的に協力し、真相を究明してまいります」とのコメントを出した。カナデンは「事実関係を確認中」と説明している。
JR貨物の役職員は、JR会社法で「みなし公務員」とされており、職務に関して賄賂を受け取ったり要求したりした場合、懲役3~5年以下とする罰則がある。
JRのグループ企業の1つ、「JR貨物」の幹部社員が、東京・品川区の貨物ターミナルにある物流施設の工事を巡り、都内の電気設備会社から繰り返し接待を受けた見返りに工事に参入できるよう便宜を図った疑いが強まったとして、警視庁は、JRのグループ企業の社員が賄賂を受け取ることを禁じたJR会社法違反の疑いでこの幹部社員らを逮捕しました。
逮捕されたのは、東京・渋谷区にある「JR貨物」の本社で「グループリーダー」という役職についていた幹部社員の富永英之容疑者(45)と、東京・港区にある電気設備会社「カナデン」の課長の三枝裕祐容疑者(47)です。
警視庁の調べによりますと、富永容疑者は、JR貨物が発注した東京・品川区の貨物ターミナルにある大型の物流施設の建て替えなどの工事を巡り、43万円相当の接待を受けた見返りに、「カナデン」が工事に参入できるよう便宜を図った疑いが持たれています。調べに対し、2人とも容疑を認めているということです。
旧国鉄から発足したJRのグループ企業のうち、JR北海道・四国・九州、それにJR貨物の4社は、現在も国が経営を監督し、役員や社員が賄賂を受け取った場合は、JR会社法で、懲役3年以下、または5年以下の罰則の対象となります。警視庁は「カナデン」を捜索するとともに、2人を本格的に取り調べ、接待が繰り返された詳しいいきさつを捜査する方針です。
JRのグループ企業の一つ、JR貨物の幹部社員が、東京・品川区の貨物ターミナルにある物流施設の工事を巡り、都内の電気設備会社から繰り返し接待を受けた見返りに工事に参入できるよう便宜を図った疑いが強まったとして、警視庁はJRのグループ企業の社員が賄賂を受け取ることを禁じたJR会社法違反の疑いで取り調べを始めました。容疑が固まりしだい逮捕する方針です。
取り調べを受けているのは、東京・渋谷区にあるJR貨物の本社で、グループリーダーという役職に就いていた40代の幹部社員と、東京・港区にある電気設備会社「カナデン」の40代の課長です。警視庁の調べによりますと、この幹部社員は、JR貨物が発注した東京・品川区の貨物ターミナルにある大型の物流施設の建て替えなどの工事を巡り、数十万円相当の接待を受けた見返りに「カナデン」が工事に参入できるよう便宜を図った疑いが持たれています。
旧国鉄から発足したJRのグループ企業のうち、JR北海道・四国・九州、それにJR貨物の4社は、現在も国が経営を監督し、役員や社員が賄賂を受け取った場合は、JR会社法で懲役3年以下、または5年以下の罰則の対象となります。警視庁は、カナデンを捜索するとともに、容疑が固まりしだい、JR会社法違反の疑いで幹部社員らを逮捕し、詳しいいきさつを捜査する方針です。
ドラマのような展開だ!
韓国船籍旅客船「セウォル号」(M/V"SEWOL", IMO9105205)の大惨事から
推測すると真実はわからないままだろう!検察や警官から情報がリークしたようにいろいろなところで情報漏えいや情報の消去の
可能性がある。権力が集中する構造では公平な捜査は無理であろう。
【ソウル聯合ニュース】国益に損失を与えたと指摘されている韓国の李明博(イ・ミョンバク)前政権の海外資源開発事業に絡み、横領などの疑いで検察の捜査を受けていた建設・開発会社「京南企業」の前会長、成完鍾(ソン・ワンジョン)氏(63)が自殺した事件で、成氏が有力政治家らへの贈賄に関するメモを残していたことが10日、分かった。
ソウル中央地検によると、9日にソウル北部の北漢山で首をつって自殺した成氏の遺体を検視した際、ズボンのポケットから名前と金額が書かれたメモが見つかった。メモには朴槿恵(パク・クネ)大統領の前秘書室長の金淇春(キム・ギチュン)氏や朴政権の初代秘書室長の許泰烈(ホ・テヨル)氏、現秘書室長の李丙ギ(イ・ビョンギ)氏、李完九(イ・ワング)首相らの名前があり、政権の実力者らに対する検察の捜査が始まるとの見方も出ている。
これと関連し、韓国紙の京郷新聞は10日、金淇春氏や許泰烈氏に金銭を渡したと語る成氏の肉声ファイルを公開した。成氏は自殺の直前、同紙の電話取材に応じていた。
成氏はその中で、ハンナラ党(現在の与党セヌリ党)の大統領選候補を選ぶ党内選挙の前後に当たる2006~07年に金淇春氏に10万ドル(約1200万円)を、許泰烈氏に7億ウォン(約7700万円)を渡したことを明かした。この発言は成氏のメモの内容とも一致するとされる。
メモについて、李完九首相の秘書室長は聯合ニュースの取材に対し、「二人は特に縁がない」として、金品を受け取ったことを否定した。また、李丙ギ秘書室長は「成氏が自分は無実だから助けてほしいと、検察の捜査に影響力を行使するよう要請してきた」とした上で、「要請を断ったことを恨みに思ったようだ」とのコメントを出した。金淇春氏は聯合ニュースの取材に対し、「(成氏と)面識はあったが、親交はなかった」と主張。金品の授受については「決してそういうことはない。作り話だ」と否定した。
地獄の沙汰は金次第。全ての判定基準は規則次第!
フランス南東部のアルプスに墜落した独格安航空ジャーマンウィングスのアンドレアス・ルビッツ副操縦士(27)は機長のコーヒーに薬物を入れ、機長がトイレに行くように仕向けた可能性が出てきた。副操縦士は機長を操縦室から閉め出した状態でエアバスA320型機を墜落させたとみられている。
英タブロイド紙デイリー・メールの9日付電子版に掲載された記事によると、ドイツの検察当局は副操縦士が機長のコーヒーに化学薬品を加えた可能性があるとみている。
捜査当局は薬物混入の手がかりを見つけるため、ルビッツ副操縦士のパソコンを調べている。当局によると、副操縦士はパソコンを使って自殺の方法や操縦室のドアの安全性を調べていた。
副操縦士は離陸後、機長にトイレに行くよう促したと伝えられている。
副操縦士は2009年に数カ月間、パイロット訓練を中断したことが報じられている。訓練再開の際に副操縦士は、ジャーマンウィングスの親会社であるルフトハンザ航空のパイロット養成学校に、重いうつ症状の時期を乗り越えたと話したという。
ルフトハンザによると、訓練再開の際に、副操縦士はすべての健康診断や適性検査に合格した。
ロイター通信によると、ドイツ連邦航空局(LBA)は9日、適正な手続きを経て副操縦士がパイロット免許を取得したと述べた。
LBAは先週末、副操縦士のうつ症状については認識していなかったと話した。ルフトハンザによると、2013年まで有効だった規制の下ではこうした情報はLBAに報告する義務はなかったという。
副操縦士が機長の飲み物に薬物を入れた疑いがあるとの報道は米紙ニューヨークポストが先に報じた。
ジャーマンウィングスの墜落事故では乗員乗客150人が全員死亡した。
原文(英語):Germanwings co-pilot may have spiked captain’s drink
By Yaron Steinbuch
大学の推薦は絶対ありえない。運が悪ければ退学。試合は出場自体。
本庄第一高等学校(厳選!韓国情報)と書き込みがあります。
【ソウル聯合ニュース】韓国・ソウル中部警察署は10日、ソウル市内のショッピングモールで盗みを働いたとして日本の高校生22人を検挙したと発表した。
検挙された生徒たちは先月27日午前10時半ごろ、ソウル・東大門のショッピングモール「ミリオレ」で、店員が出勤していない開店前の店が多いことに目を付け、9店舗を回りながらベルトや財布など70点余り、合計252万ウォン(約28万円)相当を盗んだ疑いがもたれている。
全員3年生でサッカー部に所属しており、韓国の高校との親善試合のため訪韓していた。帰国前の自由時間に犯行を行ったことが明らかになった。
被害届を受けた警察は現場の防犯カメラに映っていた生徒が着ていたユニホームを確認し、学校関係者に連絡を取った。22人は日本に帰っていたため再訪韓を要請し、検挙した。
サッカー部監督から犯行が発覚した事実を知らされた生徒たちは容疑を認め、再訪韓し警察で取り調べを受け帰国した。盗んだ品は全て返した。
警察は、偶発的だったとはいえ被害者と被害品の数が多く、大人数による犯行であるため罪質が軽微でないと判断し、起訴相当の意見を付けて送検する予定だ。
大企業のように選べないが、上手く人材を育てるとか、人材の秘められた才能を見極め適材適所で配属できれば、中小企業にもチャンスはあると思う。
優秀すぎる学生は高待遇を期待し、プライドも高い。中小企業に必要とは思えない、上手く使えなければ費用対効果は期待できない。
中小企業と言っても、大企業と比べて個々の違いが大きい。将来性にしても運もあるし、偶然に技術やノウハウが時代に合う場合もあれば、
経営者や従業員の能力ややる気とのコンビネーションもある。優秀な学生はリスクを冒して中小に選ぶ必要もない。また、転職を考えるのであれば
大手企業からの方がブランドを使えるから優位であろう。本人に実力があってもそれを見抜く中小企業の人事部はほとんどいないと思う。だから
大手企業であれば大きなはずれはないだろうと判断して採用する可能性が高い。
勝てば、成長すれば理由などいくらでも付けられる。結果を出すことが出来るかどうか!それだけ!
経済産業省中小企業庁が月内の閣議決定を目指す2015年版「中小企業白書」の概要が9日、分かった。安倍晋三政権の経済政策「アベノミクス」の恩恵が十分に及んでいない中小企業が質・量両面で人材不足に直面している課題を指摘。インターネットを有効活用するなど、「人材確保の方策を多様化していくことが必要」と呼びかけている。
白書では中小企業の景況感について消費税増税後の悪化から「足元では持ち直しの動きも見られる」と分析した。ただ、円安で原材料の仕入れ単価が上昇して採算が厳しくなっており、「販売価格に転嫁できる対策が重要」と説明する。
また、大企業の海外進出が加速したことで相互依存関係が希薄化し、中小企業でも自ら需要を開拓する必要性に迫られている。なかでも優秀な人材の確保や技術開発の拡大に成功した企業の収益率は「大企業をしのいでいる」と強調した。
ただ、アンケートでは、「人材を確保できている」と答えた中小企業は4割強にとどまり、全国的に人手不足が広がっている。「応募はあってもよい人材がいない」という声が多く、質と量両面で人材確保が壁にぶつかっている。
そうしたなか、採用ではハローワークや知人・友人の紹介など従来の「顔が見える手段」が重視されており、「方法や供給源が極めて限られている」と分析。自社ホームページを活用したりインターンシップを実施したりする企業は少なく、「さまざまな採用手段の底上げ」を要請している。
一方、小規模企業(製造業なら従業員20人以下)の白書を今回初めて策定した。事業所数がピーク時から小売業で50%減、製造業で46%減とほぼ半減していることなど、日頃焦点が当たることが少ない小規模企業の実態把握に努めている。
テレビ朝日の「報道ステーション」でアベノミクスを取り上げた報道に対し、自民党が「特殊な事例をいたずらに強調した」と批判し、「公平中立な」番組作りを要請していたことが分かった。自民党は要請を認め「圧力はなかった」と説明するが、編集権への介入との指摘も出ている。
要請書は衆院解散後の昨年11月26日、自民党衆院議員の福井照報道局長名で出された。同月24日放送の「報道ステーション」について「アベノミクスの効果が、大企業や富裕層のみに及び、それ以外の国民には及んでいないかのごとく、特定の富裕層のライフスタイルを強調して紹介する内容」だと批判。「意見が対立している問題は、できるだけ多くの角度から論点を明らかにしなければならないとされている放送法4条4号の規定に照らし、特殊な事例をいたずらに強調した編集及び解説は十分な意を尽くしているとは言えない」として「公平中立な番組作成に取り組むよう、特段の配慮を」求めている。
◇自民「圧力」否定
自民党は同月20日にも、在京テレビ局各社に選挙報道の公平中立などを求める要請書を渡していた。自民党報道局は毎日新聞の取材に「(要請書を)送ったことは間違いない」と認めたうえで「報道に対する圧力ではないかと言われるが、文面を見ればそういうものではないと理解してもらえると思う」と話した。
テレビ朝日広報部は「文書を受領したことは事実。番組では日ごろから公平公正を旨としており、特定の個人・団体からの意見に左右されることはありません」とコメントした。【青島顕、須藤唯哉】
貸したお金を返してもらえないのならODAと同じ。ODAは効率よく税金が使われていないので個人的にあまり支持できないが、日本の税金を使って日本の企業に仕事を出すODAの方がまし。
中国がこれまで通りの発展を続けるとは思えないので、どこかが資金を出す羽目になる。ヨーロッパは経済的に問題を抱えているのでメリットがあれば
資金の協力をするだろうが、メリットがなくなった時点で引くと思う。日本は外交が下手なのでヨーロッパの国々のように上手く立ち回れないと
思うのでAIIBに参加しなくて正解。
ヨーロッパは経済的な問題を抱えている。悪いほうに転がるとアジアの事などかまってられなくなる。ロシアやギリシャそして財政問題を抱える国々。
同時に問題が起こればかなり深刻になると思う。
麻生太郎財務相は9日の記者会見で、中国が主導するアジアインフラ投資銀行(AIIB)に関し、現段階での参加を見送った理由を約10分間にわたって説明した。日露戦争の際に戦時公債を発行したことに触れ、「(日本は)1日も遅れず、1銭たりとも約定を違えず全額を返済した。しかし、今は世界で借りたお金を約定通り返さない方が多い」とも語り、AIIBによる不透明な融資審査基準や過剰融資に懸念を示した。詳細は以下の通り。
--日本が参加した場合、AIIB設立当初の出資金は最低でも1000億円と試算されている
「AIIB参加国は最終的にいくつになるのか知らないが、出資額の総額も中身もわからないので、今の段階で考えているわけではない。何回も同じことを言っているので、もう飽きてきたけど、やることは1つなんですよ。お金を貸すというのは、返ってこないお金は貸せない。返ってこないお金はやるっていうんだからね」
「(インフラ整備の)ニーズがあるというのはわかる。米国が世界銀行、日本がアジア開発銀行(ADB)、ヨーロッパが国際通貨基金(IMF)は責任を持ってやっている。ところが、日本は1905年、日露戦争をやるにあたって戦時公債を発行した。1000万ポンド。日本は1日も遅れず、1銭たりとも約定を違えず全額を返済した。名も知れぬ東洋の小さな黄色人種にお金を貸した英国もすごかったんだろうが、1銭たりとも、1日も約定を違えずきちんと払った。今日、世界で他国の外貨でカネを借りて返済が滞ったことが1回もない国が日本以外にあるならば教えてくれ。ぜひ俺はそれを知りたい。他の国の中央銀行総裁も知らない」
「だから、お金というのは貸したら返ってくるもんだと日本の人は思っているんだ。子供の時からしつけられてきたんだから。しかし、今、借りたお金を返さないのは多いんじゃないの? 世界で借りたお金を約定通り返さない国の方が多い。何が言いたいかというと、もう1個(国際金融機関を)増やすんだぜ。きちんと審査をして(既存の国際金融機関の)3行で足しても400億円か500億円かといっているときに、いきなり後ろから来て、みんな貸さないの? じゃあ俺(AIIB)が貸してやるよと、300億円、400億円を貸しますと言ってなったとするよ」
「その時、この後からきた300億円は前から貸している3行の400億円に乗っかった。返済が始まり、400億円のお金は計画通りに返ってくるんだけど、後からきた300億円は全然、融資計画ができていないから、その分は返せませんでしたと。そうなったとき、まずは3行の400億円は優先的に返してくれるかと。国内だったら、まだやれるだろう。しかし、海外相手にそれができるか。700億円が全部焦げ付き、お返しできるお金は300億円だけです、といわれたら、間違いなく被害が出る。こっちは税金を預かっているわけだから」
「ちゃんと審査やら、何やらは参加する国で決めましょうねと。どういう理事会の構成ですか、審査はどこで、誰がやるんですかと。最初から俺たちはこれしか言っていない。だから(中国側は)返事を下さいと。3月31日というのは、こっちが出した提案を聞かない限りは俺たちは答えようがない。何の返事もないなら、こっちもしようがないと言っているだけだ。AIIBの話というのは、次は(参加判断の期限が)6月だとか報道されているが、どうして6月なのかさっぱり知らない。日本はなぜ参加しないのかと色々な人が言ってくるが、面倒くさくていちいち説明しないといけないので、飽きるくらい同じ話をしている」
中国福建省の高級法院(高裁)は、二つのグループが病死した豚2000トン余りを加工して売りさばいていたと公表した。これらの肉はひき肉やハムとして市場に流通したという。地元裁判所はグループの12人に懲役16年〜同2年6月の判決を言い渡した。9日付の中国各紙が伝えた。
報道によると、グループは同省竜岩市で病死した豚を安く買い上げ、加工して同省アモイや江蘇省無錫、広東省深センなどで売りさばいた。販売額は計5500万元(約10億7000万円)余りに達した。
中国ではネズミの肉を羊肉に偽装して販売するなど、食の安全に関わる事件が後を絶たない。(共同)
日本もアメリカみたいに訴訟が増えるのなら公共施設は地方自治体などが保険に加入したりするべきだと思う。悪質なケースを除けば、 改善策を考えるべきだと思う。最悪のケースを考えると何も出来なくなる。
学校の校庭から転がり出たサッカーボールをよけようとして転倒し、約1年半後に死亡した80代の男性の遺族が、ボールを蹴った小学生(当時11歳)の両親に損害賠償を求めた裁判で、最高裁は4月9日、遺族側の請求を棄却する判決を下した。1審と2審では、子どもの「監督義務」を怠っていたとして、両親に1000万円以上の賠償を命じる判決が出ていたが、最高裁はそれを覆す判断を示した。
今回の最高裁判決を受けて、少年の父親は、代理人を通してコメントを公開した。その全文は次のとおり。
●児童の父親のコメント
私たち夫婦、息子にとって苦悩の10年でした。
被害者の方にケガを負わせ、結果的に死亡したという事実を厳粛に受け止め、親としての道義的責任を痛切に感じています。
息子は自分の蹴ったサッカーボールが原因で人が一人亡くなったということで、ずっと罪の意識を持ちながら、思春期、青年期を歩んできました。
ただ親として子供を守ってやりたいと思ったのも事実です。
息子は当日の放課後、学校のグラウンドで、友人とフリーキックの練習をしていたに過ぎません。もともとあったゴールにむかってボールをける、法律のことはよくわかりませんが、このことが法的に責められるくらい悪いことなのかという疑問がずっと拭えませんでした。
また、親として、少なくとも世間様と同じ程度に厳しくしつけ、教育をしてきたつもりでした。この裁判を通じて、「息子に過失がある」、「違法行為だ」、「親のしつけ、教育がなっていない」と断じられたことは、我々親子にとって大変なショックであり、自暴自棄になりかけたこともありました。
本日、最高裁で判決が出たとお聞きしました。正直、まだ気持ちの整理もできておりませんが、我々の主張が認められたということでひとまず安堵しています。
ただ、被害者の方のことを考えると、我々の苦悩が終わることはありません。
(判決内容や弁護士の記者会見についての記事)
<最高裁・逆転判決>小学生が蹴ったボールで転倒し死亡――親の「賠償責任」認めず
福島県は7日、空間放射線量を計測するモニタリングポスト約30台で異常を示したと発表した。周辺の複数のモニタリングポストの数値に異常がなく、県は、測定データを伝送する際に不具合が起きたとみている。修理か交換かを検討する。
県によると、異常を示したのは、県が3月末に設置し、4月から試験運用を開始した簡易型モニタリングポスト77台のうちの約30台。南相馬市や伊達市など7市町村に及び、南相馬市と葛尾村の計2台では通常値の約1000倍に上昇した。
県によると、3日に南相馬市の2カ所で異常に高い測定値が出たため、業者に確認するよう依頼していた。県放射線監視室は「公表は原因究明してからと考えた。異常を認識した時点で公表すべきだった」としている。【岡田英】
大阪桐蔭中学・高校の裏金問題で、解明のカギを握る教員用パソコンについて学校側が発覚直前に突然壊れたと主張して、物議を醸している。
この問題では、20年以上前から5億円以上の裏金が作られ、学習塾経営者への接待のほか、ブランド品購入、ゴルフ代などにも使われたことが分かっている。
■「なぜ都合良く壊れるのか」「証拠隠滅か」
塾接待は、学校の進学実績を上げるため、優秀な子供に学校に来てもらうのが目的だった。受験先は塾の意向に左右される傾向があるからだ。とはいえ、裏金は学校のためばかりではなく、私的な目的のために使われていた疑惑も浮上している。
100万円のブランドバッグ、数十万円のアクセサリー、エルメスのスカーフ...。デパートでのブランド品購入だけで、なんと1億円近くも注ぎ込んでいた。こうした支出が公私混同ではないかという疑いの目を向けられているのだ。
隠し口座も複数あったとされ、学校を運営する大阪産業大学が調査を依頼した第3者委員会でも、その証拠探しに追われた。
ところが、3月25日に発表された第3者委の報告書によると、前進路指導部主事は、ヒアリング調査に対し、裏金管理に使っていた教員用パソコンが14年9月ごろに突然壊れてしまったと主張した。これは、教職員組合と大学との翌月の団体交渉で裏金が発覚する直前のことだ。この主事は、すぐに業者に壊れた原因の調査やデータの回復を依頼したというが、業者からは、原因は不明であり、データ回復もできないと言われたと、第3者委に説明した。
こうした学校側の説明に対し、ネット上では、疑問や異論の声が噴出している。
「なぜ都合良く壊れるのか」「証拠隠滅か」「小学生みたいな言い訳するなw」...
警察の捜査で初めて真相の解明が進む?
裏金問題の解明に向けて、証言や証拠を集めるためのネックになっていることがまだある。
隠し口座などを知っているとみられる大阪桐蔭の前事務長が、体調不良を理由にして、第3者委員会のヒアリング調査に応じていないのだ。第3者委では、ヒアリングは難しいとみて、書面での回答を求めたが反応はなかったという。
25年以上も務めた前校長は、裏金作りのキーマンとされているが、ヒアリング調査には応じたものの、報道によると、学校が本人に連絡を取れない状態になっているという。
第3者委の委員長だった畠田健治弁護士は、パソコンが壊れた原因について、「ドリルで穴を開けたとか、水をかけたとかいった痕跡は見つからず、結局なぜかは分からなかった」と話す。データの修復もできなかったといい、バックアップを取っていたかと聞くと、前進路指導部主事は、「取っていない」と答えたという。
ヒアリングに応じない前事務長については、「診断書はもらえませんでした。どこまで本当かは分かりませんが、体調不良で書面も見られるような状態ではないとは聞いています」と話した。
第3者委の報告書では、大阪産業大は前校長らの刑事告訴を検討すべきだとしている。もし個人的な目的で裏金を使ったとしたら、業務上横領罪に当たるというのだ。証言や証拠がなかなか集まらない以上、警察の捜査によって初めて真相の解明が進むのかもしれない。
大阪産業大の学園広報課では、今後について、前校長らの刑事告訴を含めて検討する考えを取材に明かした。大学理事長らで作る対応委員会が4月末までに告訴などの対策を盛り込んだ報告書をまとめるとしている。
徳島県松茂町の徳島空港で5日、滑走路上に作業車両があるのに海上自衛隊の管制官が着陸許可を出し、日航機が着陸をやり直したトラブルで、日航機がいったん接地した地点から車までは1000メートル前後しかなかったことがわかった。
そのまま着陸していれば、車まで十数秒で達する距離で、運輸安全委員会は詳しい状況を調べる。
管制を担当する海自徳島教育航空群などによると、羽田発の日本航空455便(ボーイング767―300型機、乗客乗員計67人)のパイロットが、同空港の滑走路(2500メートル)東端付近の上空を飛行していた5日午前11時前、滑走路の中央付近に作業用の乗用車があるのを発見した。
着陸態勢に入っていたが、着陸のやり直しを決め、滑走路にいったん着地した後、すぐに離陸した。着陸時の速度は一般的に時速250キロ程度で、着陸していれば止まりきれずに衝突する可能性があったという。
作業車両は、トラブルの20~30分前に管制官の許可を得て滑走路に入り、電球の交換作業中だったが、管制官が、車が滑走路上にいることを失念して着陸許可を出した。
「3日夜に大阪市内で橋下市長と一緒に行った会見で“疑惑”の詳細について自ら語ったが、文書でもあらためて細かい経緯などを説明した。衆院本会議を病欠した先月13日の『週の初めから嘔吐(おうと)、下痢、高熱、悪寒等が続き、本当に苦しんでおり』、
前日の12日に診断書を発行してもらったものの『(12日の)夕刻にはだいぶ回復した』と主張。その夜、ショーパブなど3軒をはしごし『翌朝(13日)、体調が急変し、嘔吐下痢症が続き、とても本会議に耐えられる状況ではなくなった』と本会議は欠席し、大阪に移動したとした。」
上記が事実としよう。週の初めから嘔吐(おうと)、下痢、高熱、悪寒等が続きていたのならだいぶ回復したぐらいでショーパブなど3軒をはしごするのは
非常識。安静にするべきだ。初めての当選ではないのだから自覚がない。また、嘔吐下痢症が続いていたのなら大阪への移動も大変だ。横になっているべき。
「問題となった会食は医師でもある自民党議員と行い、これは『医者と患者』として会食したと主張。続くショーパブなどへはその代議士から『上西さんと親しいと言ったら、店の経営者が会いたいと希望しているのでついてきてほしい』と懇願されたからと弁明した。」
「週の初めから嘔吐(おうと)、下痢、高熱、悪寒等が続きていた」のが事実であれば断ればよい。自民党の
赤枝恒雄(Yahoo!みんなの政治)衆院議員は71歳にもなっても
強引なのか?医師であれば配慮ぐらいしてあげるべきなのでは?それとも口実なのだから何もいえないのだろうか?
国会を病欠し、その前後の対応が問題視され、維新の党と傘下の政治団体・大阪維新の会から除名処分を受けた上西小百合衆院議員(31、比例近畿ブロック)が5日、報道各社に文書を送付し、“恨み節”をにじませながらあらためて議員辞職しないことを宣言した。
除名処分から一夜明けた5日も、4日に引き続き大阪府吹田市のビル2階にある上西議員の事務所にはテレビ局が取材に訪れるなどしたがシャッターは閉まったまま。電話の呼び出し音が時折鳴るだけだったが、文書送付で“抗戦”の意思を示した。
文書は400字詰め原稿用紙にして4枚余り、約1700字にも上る内容。その中には「処分の大きな理由に挙げられている事例につきましては若干事実が伝わっておりません」と、報道を基にして処分した大阪維新、党などへの“恨み節”とも取れる表現も。冒頭で「衷心(心の底)よりお詫(わ)び申し上げます」としながら「まだまだ国政で微力を尽くしたいので」と議員辞職はせず、無所属で議員活動を続ける決意もにじませた。
3日夜に大阪市内で橋下市長と一緒に行った会見で“疑惑”の詳細について自ら語ったが、文書でもあらためて細かい経緯などを説明した。衆院本会議を病欠した先月13日の「週の初めから嘔吐(おうと)、下痢、高熱、悪寒等が続き、本当に苦しんでおり」、前日の12日に診断書を発行してもらったものの「(12日の)夕刻にはだいぶ回復した」と主張。その夜、ショーパブなど3軒をはしごし「翌朝(13日)、体調が急変し、嘔吐下痢症が続き、とても本会議に耐えられる状況ではなくなった」と本会議は欠席し、大阪に移動したとした。
問題となった会食は医師でもある自民党議員と行い、これは「医者と患者」として会食したと主張。続くショーパブなどへはその代議士から「上西さんと親しいと言ったら、店の経営者が会いたいと希望しているのでついてきてほしい」と懇願されたからと弁明した。
また、週刊誌などが報じた14、15日の旅行に関しては「14日は静養した」とあらためて否定。15日に男性秘書と京都府北部へ行ったことは認めたが一部で“不倫旅行”とされた件については「当該秘書は独身なので、いかに今回の報道が不誠実かつ不正確か」と最後まで抵抗した。
国会病欠前後の対応を問題視されて維新の党と、傘下の大阪維新の会から除籍(除名)処分を受けた上西小百合衆院議員(比例近畿)は5日、「議員辞職はせず無所属で国政に邁進(まいしん)する」との談話を発表した。また、処分理由について「若干事実が伝わっていない」と反論した。
談話によると、上西氏は衆院本会議を病気で欠席した3月13日の前日に病院で診断書を書いてもらったものの、夕方には「だいぶ回復した」と主張。その夜にともに都内の料理店に出かけた医師でもある自民党の赤枝恒雄衆院議員(比例東京)とは、持病の相談のため「医者と患者」として面会したという。
料理店を出た後、上西氏は都内のショーパブに行ったが、これについては赤枝氏に「『上西さんと親しいと言ったら、店の経営者が会いたいと希望しているのでついてきてほしい』と懇願されたから」と弁明した。13日朝には「体調が急変し、嘔吐(おうと)、下痢症が続き、とても本会議に耐えられる状況ではなくなった」として本会議を欠席し、大阪に新幹線で移動した。
週刊誌などが報じた14、15日の旅行に関しては、14日は静養していたと重ねて強調。15日に男性秘書と京都府を訪ねたのは認めたが、「政務遂行のため」と重ねて「デート」報道を否定した。上西氏は一連の騒動に謝罪した上で、「初心に帰って無所属議員として一から出直す覚悟だ」としている。
上西氏は3日夜に大阪維新の会代表の橋下徹大阪市長とともに大阪市内で記者会見を行い、「デート旅行」を否定したが、橋下氏は病欠前後の行動を問題視し、4日に除名を発表。維新の党も同日中に除名処分を決めた。
東洋ゴム工業(大阪市)の免震ゴムの性能が偽装されていた問題で、18都府県55棟に使われた2052基のうち、約89%が国が求める性能を満たしていなかったことが3日、わかった。
この問題を受けた、国土交通省の有識者委員会の初会合が3日開かれ、個々の製品の性能データなどが提出された。委員長を務める首都大学東京の深尾精一名誉教授が終了後に記者会見し、「55棟は大地震でも倒壊の恐れはないが、当初想定された高い免震性能を回復するため、免震ゴムを交換すべきというのが委員共通の意見だ」と述べた。
委員会では今後、原因究明とともに、国がお墨付きを与える「性能評価」のあり方を含めて再発防止策を検討し、夏頃までに提言をまとめる方針。
福井県勝山市で3月、東邦大大学院生・菅原みわさん(25)が絞殺された事件で、福井地検は3日、元福井大教職大学院特命准教授・前園泰徳容疑者(42)を殺人罪で起訴した。
起訴状などでは、前園容疑者は3月12日、同市の市道に止めた軽乗用車内で、菅原さんの首を腕で絞めつけて殺害したとしている。
捜査関係者によると、前園容疑者の携帯電話を調べたところ、事件直前に菅原さんと交わされたメールなど複数の通信記録が削除されていたという。前園容疑者は県警の調べに対し、当初は殺害への関与を認めたが、その後黙秘している。県警や地検は詳細な殺害場所などを特定していない。
前園容疑者は3月31日、勾留理由を開示する法廷で「菅原さんから殺してと頼まれた」と述べ、弁護人は嘱託殺人罪を主張していた。
特命准教授の任期は同日までだったが、福井大は「在任中の事件なので処分を検討中」としている。
日本郵便信越支社は3日、事務委託先の長野県小諸市諸の諸簡易郵便局の局長だった60歳代の女性が利用者から現金100万円をだまし取った疑いがあると発表した。
支社によると、女性は2月下旬、窓口に来た利用者に「現金100万円を私に預ければ、約1割の利息を払う」などと言って詐取した疑い。支社はほかにも被害に遭った人がいるとみて調査中で、詐欺容疑での告発も検討している。
女性は1991年から業務を受託していた。「自家用車の購入代金が必要だった」と話しているという。諸簡易郵便局は3月4日に閉鎖されている。
学校が適切に教育できれば塾など必要ない。また、本人が望めば高度の教育を受ける制度又は成績優秀者には学費無料の制度を作ればよい。
塾は試験に受かるために特化した教育形態なので塾に行くことが望ましいとは思わない。ただ、大学進学又は有名な大学進学を目的にすると
試験で受からなければならないので塾に行くほうが有利になる。人間として、総合的な能力を身につけるためにはあまり塾に時間を費やすことが
良いとは思わない。スポーツと通して精神的な強さがないと良い結果が出せないとか、素質の不足を努力や自分に強みを生かすとか、弱点を
克服する方法もあることを知ること、いくらがんばっても報われないこともあり、挫折から立ち直ることによる成長などいろいろな良い点がある。
残念なことに、最終学歴でほぼ出世や社会的な評価が決まることもあるので、その点を変えていくほうに力を入れたほうが良いのではないのか。
セカンド・チャンスで再起できる社会にするべきではないのか?最終学歴で貧困から二度と抜け出せない社会を何とかするべきでないのか?
個人的にはこんな愚かなことには賛成しない。
貧しい家庭になった理由や両親の学歴、仕事、人生観や生活習慣など調査し、分析してから効率的な対策を検討するべきだ。個人及び両親の人生観、価値観そして
生活習慣が間接的に貧しい家庭になる原因と関連があると思う。塾が原因と安易に考えている時点で税金と時間の無駄遣い。
政府は2日、官民一体で貧困家庭の子供を支援する「子供の未来応援国民運動」の発起人集会を首相官邸で開き、企業や個人に寄付を呼びかけて基金を創設することを確認した。
金銭的な理由で塾に通えなかったり、スポーツ・芸術分野の活動が続けられなかったりする子供を支援するのが目的だ。
基金事業のほか、各種の支援情報を検索、閲覧できるポータルサイトの開設、優れた支援事業を行った団体に対し、総理大臣表彰などを実施することも申し合わせた。今夏をメドに事務局を設置し、準備を本格化させる。
この日は、安倍首相、日本経済団体連合会審議員会の伊藤一郎副議長(旭化成会長)、日本新聞協会の白石興二郎会長(読売新聞グループ本社社長)ら幅広い分野の代表者が発起人として出席した。首相は「子供たちの未来が家庭の経済事情によって左右されることがないように社会をあげて取り組んでいきたい」と強調。また、今夏をメドに政府の支援策を取りまとめる考えも示した。
やらせの問題もあるし、NHKはしっかりしないとだめだ!
NHKの籾井勝人(もみい・かつと)会長が関連会社2社の不正を契機に自ら設置した「NHK関連団体ガバナンス調査委員会」(委員長・小林英明弁護士)の調査費が約5500万円だったことが分かった。通常より数倍高額だと指摘する専門家もおり、籾井会長への批判がさらに高まりそうだ。
委員会は昨年3月末に設置され、調査期間は8月までの5カ月間。委員会は小林弁護士ら3人で構成。補助者として加わった5人の弁護士を含め、いずれも小林弁護士と同じ事務所に所属している。
毎日新聞が入手した調査報告書によると、委員会は2件の不正についての内部調査を、資料などを基に再評価した。また関連会社・団体を含む全役職員に呼びかけ提供された27件の不正の疑いについて、約150時間かけて関係者や資料を調べた。その結果はA4判49ページの報告書と、同15ページの提言にまとめられた。NHKの国会などでの説明によると、弁護士に対する支払いは時間制で計算されており、総額契約ではなかったという。
第三者機関による調査のあり方に詳しい弁護士は、報告書を確認した上で「資料を基にした表面的な調査が多い。その割に支払われた額は法外に高いのではないか」と指摘する。【須藤唯哉、望月麻紀】
厚労省は調査できる人間を任命し、徹底的に調査するべきだろ!
群馬大学病院(前橋市)で腹腔鏡ふくくうきょうを使う高難度の肝臓手術を受け、患者8人が死亡した問題で、病院側は記者会見で、執刀医が3月31日付で退職したことを発表した。
退職金は支払われていないという。
また、病院側が3月に公表した調査報告書に対し、執刀医から反論の上申書が寄せられたことも明らかにした。患者への説明が不十分とされた点について、「時間をかけて説明した」と反論。「全例で過失があった」とされたことには「納得いかない」などとしている。
反論に対し、病院側は「診療記録がないため判断できない」と認めなかった。
ドイツの格安航空会社ジャーマンウィングスそして/又はルフトハンザに恨みでもあったのだろうか? 計画的に機体の墜落を準備していたのであれば、注目を受けたい、又は会社に恨みがなければこれだけの人々を巻き込もうと思わないだろう。 注目を受けることにより会社が批判され、会社が損害を被り、会社に調査が入ることは予測できるだろう。まあ、事実が明らかになるかは???
フランス南東部に墜落した旅客機の副操縦士が、前日までインターネットで自殺の方法や操縦室のドアの安全規則について検索していたことがわかった。計画的に機体を墜落させた疑いが強まっている。
ドイツの検察当局は2日、副操縦士の自宅から押収したタブレット端末を調べた結果、先月16日から墜落前日までのインターネットの検索履歴が残っていたことを明らかにした。
検察会見「副操縦士は、病気の治療方法を調べていたほか、自殺の方法と実現の可能性について情報を得ていた」
副操縦士は、操縦室のドアの安全規則についても検索しており、自殺のために計画的に機体を墜落させようとした可能性が高まっている。
一方、フランスの検察当局は飛行のデータを記録したフライトレコーダーを現場から回収したと発表した。解析は可能だとみている。また、現場で収容された遺体から乗客・乗員の全員分にあたる150人分のDNAを検出したことも明らかにし、来週から身元の確認作業を行うという。
担当医だけの問題ではなく、群大病院の組織体質にも問題があるような対応だ!
群馬大学病院(前橋市)で腹腔鏡ふくくうきょうを使う高難度の肝臓手術を受け、患者8人が死亡した問題で、病院側は2日夜、前橋市内で記者会見を開き、開腹手術の死亡問題を含め総合的に検証する委員会を新たに設置することを発表した。
患者が死亡しているのに高難度手術が続いた理由などについて再調査し、真相究明を目指す。
この日、東京都内で開かれた調査委員会で外部委員から調査の見直しを提案されたのを受け、決定した。今回の調査委は、病院側が先月公表した最終報告書を巡り、調査手続きや内容を巡る不備が指摘されていたため開かれた。
調査委では問題点として、〈1〉外部委員が報告書の内容を承認した後に「過失があった」などと無断で加筆していた〈2〉執刀医ら当事者の聴取内容の詳細を外部委員に知らせなかった〈3〉検証もなく高難度手術が続けられた背景が解明しきれていない――といったことが挙げられた。
ドイツの格安航空会社ジャーマンウィングス機墜落事故が影響したのか?
いつの時代になっても、多くの犠牲と屍によって規則の改正や問題の指摘の結果となる。
工藤隆治
桜美林大学(本部・東京都)の航空パイロット養成コースが、訓練の管理のずさんさを国土交通省から指摘され、国の養成施設としての指定を3月末に返上していたことがわかった。大学による国のライセンスの技能審査に疑念が生じたため、国交省は、パイロットのライセンスを取得した学生の技量テストをやり直す異例の措置をとった。
日本航空元機長で、養成コース長の宮崎邦夫教授は取材に、「就職対策に力を入れすぎ、組織運営や安全管理がおろそかだった。反省している」と話した。
格安航空会社(LCC)の急増でパイロットは世界的に不足し、日本でも昨年、LCCで大量欠航が相次いだ。15年後には国内だけで2千人以上足りなくなるとの試算がある。国交省の審議会は昨年7月、私立大を日本のパイロット養成の柱の一つに位置づけた。安全運航と事故防止に向け、養成機関の質の確保が緊急の課題となりそうだ。
NHKの報道番組「クローズアップ現代」で「やらせ」があったとされる問題で、番組内で「出家詐欺ブローカー」とされた大阪府内の男性(50)が1日、「自分はブローカーではない」として、訂正放送を求める申し入れ書をNHKに提出した。ブローカーと多重債務者の交渉現場とされる映像について、男性は「記者の指示でブローカーを演じた」と述べ、当時は再現映像の撮影だと思っていたと説明した。
男性はこの日、NHKの聞き取り調査に応じて撮影時の様子などを説明。その後、大阪市内で取材に応じた。代理人の弁護士によると、今後、意に沿う回答が得られない場合は、放送倫理・番組向上機構(BPO)への人権侵害の申し立てを検討するという。
問題の番組は、昨年5月14日放送の「クローズアップ現代」。多重債務者がブローカーを介して出家し、名前を変えて融資などをだまし取る手口を紹介した。「やらせ」疑惑は今年3月発売の週刊文春が報道した。
NHK広報局は「男性とそれ以外の関係者の話などに食い違いがあり、引き続き確認作業を行っている。事実関係がまとまった時点で報告したい」とコメントした。【棚部秀行】
月舘彩子、沢木香織
病気ごとの推奨薬が示された「診療指針」の作成医が、多額の「講師謝金」などを製薬会社から受けていることが朝日新聞の集計でわかった。医師向けに専門医が話す講演会は「専門的情報を提供する学術的なもの」(日本製薬工業協会の自主基準)とされているが、製薬会社にとっては営業の手段になっている場合がある。指針の公正さを保つ上で、作成医が金銭を受け取ることに懸念の声が医学界からあがっている(本文はこちら)。
病気ごとの推奨薬が示された「診療指針」の作成医が、多額の「講師謝金」などを製薬会社から受けていることが朝日新聞の集計でわかった。医師向けに専門医が話す講演会は「専門的情報を提供する学術的なもの」(日本製薬工業協会の自主基準)とされているが、製薬会社にとっては営業の手段になっている場合がある。指針の公正さを保つ上で、作成医が金銭を受け取ることに懸念の声が医学界からあがっている。
■競合薬多いと高額傾向
製薬会社が医師向けの講演会を開く狙いを、ある営業担当者はこう打ち明ける。「直接医師に薬を売り込むよりは、影響力のある先生に講演会などを通じてPRしてもらった方が営業効果がある。講演会後の情報交換会は接待にあたらないので、医師と接触できるいいチャンスだ」
営業社員の過剰な接待が医師の処方に影響を与えているという疑念を持たれないよう、製薬業界は2012年から医師への接待に上限金額を設けるなど、自主ルールを強化した。そこで、講演会が営業の場になってきているという。
「影響力のある医師」として複数の営業担当者が挙げるのが、診療指針を作成した医師だ。推奨薬を決めた当事者に講演してもらうと宣伝効果が高いという。
「殺してください」と言われて殺すには余程の愛情がないと殺せない。その前に、生きていくこと、又は、休んでも良いから自分のペースで 生きていくように説得するべきだろう。殺害されることを切望していたことが事実として、なぜこの女性は死にたがっていたのか? 自殺の選択もあったはず。殺害を要求すると言う事は、上手く殺害しないと相手に迷惑(逮捕される)をかけることを意味している。 大学院生の女性がそのような事を考えられなかったのか?辻褄が合わない。
福井県勝山市で3月中旬、東邦大大学院生・菅原みわさん(25)が軽乗用車内で絞殺された事件で、殺人容疑で逮捕された福井大教職大学院の特命准教授・前園泰徳容疑者(42)の勾留理由を開示する法廷が31日、福井簡裁であった。
意見陳述で、前園容疑者は「菅原さんから『もう無理です。殺してください』と頼まれて首を絞めた」と述べた。
法廷で、前園容疑者は「遺族の方には心よりおわび申し上げます」と謝罪。同容疑者の弁護人は嘱託殺人罪の成立を主張した。
一方、立川忠裁判官は「犯行後の態度などから逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断した」と、勾留を許可した理由を説明した。
アジア投銀見送りで問題ない。日本のODAはアジアの国々を支援をしているが、日本の企業に仕事を与える役目も担っていると思う。
もし日本が参加すれば国連のように多額の支援を求められる割には日本にメリットがない以上に利用されるだけになるであろう。
ヨーロッパの国(経済的に良くない国々)の人達と話すとヨーロッパでは労働力の安い中国へ工場が移転されたり、発注先がヨーロッパから中国へ
シフトして仕事がなくなった人々で困っていると言っていた。仕事を失った人々が再就職できる可能性は低く、富裕層だけがより富を増やしたり、
影響を受けないと言っていた。一度、閉鎖された工場や競争力を失った業界は再出発できないほど空洞化が進み、将来への展望はないそうである。
そんなヨーロッパでアジアインフラ投資銀行(AIIB)への参加によりメリットがあれば参加するのは当然。しかし、将来、ギリシャのように
なる国が出た場合、誰か、又は、多くの出資をした国が泣くはめになる。だからアジア投銀見送りで良い。
日本政府がアジアインフラ投資銀行(AIIB)への参加表明を見送ったことについて、経済界からは、企業の海外展開にマイナスにならないよう今後の参加を期待する声が出た。
ただ、参加を見送っても事業への影響は限定的だとして、おおむね冷静に受け止めている。
経済同友会の長谷川閑史やすちか代表幹事は31日の記者会見で、政府の判断を待つ姿勢を示したうえで、「(日本企業の)インフラビジネスが、不利になるようなことだけはないようにしてほしい」と注文をつけた。化学や繊維を取り扱う中堅商社・蝶理の先浜一夫社長も記者会見で、「ビジネスにおいてハンデのないようにまずはしてほしい」と述べた。
経済界には、中国が自国の利益ばかりを優先した運営はしないとの見方が出ている。ある経済界首脳は「英独仏といった先進国が入り、中国は変なことができないだろう」と語った。ある大手ゼネコンは「AIIBの案件は中国の影響が強く、日本が参加しても事業を取れるわけではない」と指摘した。
渡辺周
医師が製薬会社から講演料として受け取っていた高額の謝礼。どのような講演会なのか。多額の副収入を得ているのはどんな医師なのか。
東京都新宿区の高級ホテルで2月、胃の病気についての研究会が2日間にわたって開かれた。大手製薬2社と医師との共催。2日目の講演会では、司会役の医師が講師役の私立大教授の医師を紹介するとき、スポンサー名をあげながら、こう続けた。「多少はPRが入ってくるかと思います」
講師は共催2社が発売する薬の商品名を繰り返しつつ「この薬の時代がやってきた」と語った。会場にはイチゴのショートケーキとコーヒーが用意され、参加者は食べながら聴講。約40分の講演が終わっても会場から質問はなく、参加した約80人の医師らはすぐに部屋を後にした。
製薬会社主催の講演会は全国の病院や医師会館でも開かれる。製薬関係者によると講師役の医師への謝金は、教授クラスで15万~20万円、准教授は10万円。講師クラスだと5千円の場合もあるという。
一方で製薬会社主催の講演会は「主催企業の商品を批判しにくい」として、避ける医師も出てきている。
内閣府障害者政策委員会の委員で精神科医の上野秀樹さんは、2年ほど前までは製薬会社が関わる講演会を引き受けていた。3万円以上のタクシー代をもらったこともある。だが営業担当者から、講演で商品名を言うよう頼まれ、嫌気が差したという。いまは製薬会社がスポンサーの講演会は断っている。
上野さんは「製薬会社が営利企業である限り、講演会の建前が啓発であっても、利益に結びつけようとする。医師も、企業からボールペン1本をもらうのから始まり、徐々に感覚を鈍らされ、心を支配される。医師にその自覚がないことが問題だ」と指摘する。
英製薬大手のグラクソ・スミスクラインは2016年1月から、全世界で医師への講演料の支払いを中止する。同社の担当者は「専門医が薬の情報を正しく伝える講演の役割を否定するわけではないが、一般社会からみたら製薬会社主催の会はひょっとしてバイアスがかかっているのではという疑念を払拭(ふっしょく)したい」と説明。医師との癒着を疑われる余地をなくすためとしている。自社製品の情報を医師に伝える手段としては、インターネットの利用に力を入れていくという。
■「連呼・宣伝してない」「研究評価の表れ」
製薬会社から1千万円以上を得ていた184人は大学教授が多く、半数は糖尿病や高血圧など生活習慣病の専門医だった。
最も多かったのは順天堂大学特任教授で糖尿病医の河盛隆造氏。240件の講演などで4747万円を得た。河盛氏は取材に「糖尿病の治療のしかたを教えている。薬の名前を連呼して宣伝したことはない」。一方で「市民公開講座や各地の医師会の講演に呼ばれて行ってみたら、メーカーから講演料が支払われていたということもよくある。手元に残るのは納税をして半分」などと話した。
2番目に多かった糖尿病医の小田原雅人・東京医大教授は201件の講演などで3971万円を得た。「講演会等は適切な情報提供に寄与する機会。大学病院の業務に支障を来さないように留意している」と説明した。
糖尿病医の加来浩平・川崎医大特任教授は116件の講演などで3719万円。「講演活動を地道にやってきて、治療レベルは相当に上がっている。依頼が来る人ほど見識があってメッセージ発信能力が高い」
194件の講演などで3596万円を得た山岸昌一・久留米大教授も糖尿病が専門。「これまでの研究が広く評価された一つの表れ。講演会の半分程度は土、日曜日。平日の場合は夕方からで、日帰りか翌朝に戻るので、業務に全く差し支えはない」
感染症を専門とする三鴨(みかも)広繁・愛知医科大教授は、152件の講演などで3381万円を得た。「医師の報酬額は、1講演200万円以上のこともあるアナウンサーや著名人に比べると低い。しかもパワーポイントを100枚程度作成しなければならない。体力的に厳しい生活をし時間を捻出している。平均睡眠時間も4時間程度」と説明した。循環器が専門の山下武志・心臓血管研究所長は168件の講演などで3267万円。朝日新聞の取材に「応じるつもりはない」と回答した。
◇
製薬会社が2013年度に医師らに支払った金銭情報を、自社のウェブサイトなどで公表している。朝日新聞は、それらの情報を集計した。留意点は以下の通り。
●医師の氏名が同姓同名で所属機関名が異なれば、所属機関ごとに1人として数えた。そのため、製薬会社が支払った医師の総人数は「のべ人数」にした。受取額が1千万円超の184人に同姓同名はなかった。
●公表された医師への支払い情報の対象期間を各社は決算期に合わせている。「13年4月~14年3月」としている社が多いが、「13年1月~12月」「13年7月~14年6月」「12年12月~13年11月」という社もある。
●日本製薬工業協会加盟72社のほか、支払い情報を公表した関連会社(武田バイオ開発センター、興和創薬、大正富山医薬品、帝人在宅医療、ガンブロ)5社も集計した。
●消費税を含めていない社もあり、公表された金額で集計した。
●大半の社が1円単位の金額を公表したが、1千円単位~100万円単位で公表した会社が17社あり、公表された金額で集計した。(渡辺周)
渡辺周、沢木香織 月舘彩子
国内の製薬会社72社が、2013年度に医師へ支払った講演料や原稿料を公表した。朝日新聞が集計したところ、のべ約10万人の医師に計35万件の講演などで総額約300億円が支払われていた。1千万円を超えたのは184人で、最高額は240件の講演料などで4700万円だった。医師個人が製薬業界から受け取った金銭の全容が明らかになるのは初めて。医学系の各学会が病気ごとに定める「診療指針」の作成医も多額を受け取っていた。
医師が製薬会社から受けた金銭情報を公開する欧米での動きを受け、大手製薬会社が加盟する業界団体の日本製薬工業協会(製薬協)は11年1月に「透明性ガイドライン」を策定。日本医学会は翌2月に製薬会社との利害関係について指針を作り「多額の金銭が提供されると研究成果の解釈や発表でバイアスがかかる可能性がある」として情報公開の動きに同調した。
製薬協加盟72社と関連会社は、13年から医師や医療機関に支払った金銭情報をそれぞれ公表し始めた。医師個人への支払額の公表は1年遅れ、14年8月から順次公開。今年2月末に全社が出そろい、朝日新聞が集計した。
コメンテーターの暴走か、権力による圧力か――。テレビ朝日の「報道ステーション」の生放送中、元経済産業省官僚の古賀茂明氏が、官邸などを批判した問題が波紋を広げている。安倍政権は「放送法」を持ち出し、テレビ局を牽制(けんせい)。関係者は放送への影響を懸念する。
テレビ朝日は31日、年度末の定例社長会見に出席した早河洋会長が「ニュースの解説・伝達が役割の番組で、出演を巡るやり取りが番組内であり、あってはならない件だった。皆さまにおわびをしたい」と陳謝した。
古賀氏は27日の「報ステ」に出演中、古舘伊知郎キャスターから中東情勢への意見を求められた際に突然話題を変え、早河会長らの意向で降板に至った、と発言。続けて「菅(義偉)官房長官をはじめ官邸のみなさんにはものすごいバッシングを受けてきました」と述べた。
聞いた話だが「深刻なうつ」になった人は回復しても極度のストレスやプレッシャー、長時間のストレスやプレッシャーを経験すると うつが発生するらしい。昨日まで普通に行動していても、極度のストレスを経験するとうつが発生し普通に行動できなくなるケースもあるらしい。 多くの人命を左右する仕事は、個人の意思や自由もあるかもしれないが、制限を設けるべきだと思う。
【ベルリン=工藤武人】フランス南東部で起きたドイツの格安航空会社ジャーマンウィングス機墜落で、親会社のルフトハンザ航空は3月31日、同機を意図的に墜落させた疑いのある副操縦士、アンドレアス・ルビッツ容疑者(27)が、2009年の時点で「深刻なうつ症状だった」とする報告を受けていたと発表した。
同容疑者は08年にパイロット育成施設で訓練を受け始めたが、翌年になって訓練施設に「深刻なうつ症状だったが回復した」と電子メールで報告していたという。
同社は3月26日の記者会見で、同容疑者がパイロット育成施設で訓練を受け始めた後、長期間にわたって訓練を中断していたと発表したが、中断していた理由については明らかにしていなかった。同容疑者は墜落前も精神面の問題を抱えて通院していたことが、これまでの独捜査当局の調べで判明しており、パイロットとしての適性判断や健康管理などの対策が十分だったかも問われることになる。
【ベルリン時事】フランス南東部で3月24日起きたドイツ格安航空会社ジャーマンウィングスの旅客機墜落で、親会社ルフトハンザ航空は31日、意図的に墜落させた疑いのあるアンドレアス・ルビッツ副操縦士(27)から2009年に、「深刻なうつ症状」を患っていたとの報告を受けていたと発表した。
ルフトハンザは墜落後の記者会見で、副操縦士が6年前に数カ月間訓練を中断していたことを明らかにしたが、理由には言及していなかった。会社が副操縦士の心理面の病気を把握していたと判明したことで、採用後の健康管理が適切に行われていたかが改めて問われそうだ。
(ブルームバーグ):ジャーマンウイングスの旅客機が副操縦士の意図的な急降下によって墜落したことで、親会社のルフトハンザ航空は犠牲者の遺族に対し無限の賠償責任を負う可能性があると、弁護士らが指摘した。
スウォンジー大学で航空法を講じるジョージ・レルダス氏は、「犠牲者に対する賠償責任は無限だ。航空会社から見れば厳しいことだが、有効な反論の手段はない。不合理なことだが、保険というものがあるのはこのためだ」と語った。
乗客乗員150人全員が死亡した事故について調査しているフランスの当局は26日、アンドレアス・ルビッツ副操縦士(27)が故意に墜落させたものだとの見解を発表した。ドイツ当局は27日にルビッツ副操縦士が墜落当日「勤務に適さない」状態だったことを示す診断書を、破られた状態で発見した。
墜落した旅客機はスペインのバルセロナからドイツのデュッセルドルフへ向かう国際便だったため、1999年のモントリオール条約が適用される。同条約によって遺族は犠牲者1人当たり最低でも13万9000ドル(約1700万円)相当の賠償金を自ずと保証される。
しかし「条約は賠償額を制限していない」と指摘するのは、シカゴの法律事務所クリフォード・ロー・オフィシズで航空機事故の損害賠償訴訟を手掛けるケビン・P・ダーキン弁護士。同氏は26日の電話インタビューで、航空会社は自社以外の何かが墜落の唯一の原因だと証明しない限り、遺族からの請求を拒否できないと述べた。
原題:Co-Pilot Suicide Leaves Lufthansa Facing Unlimited
Liability(抜粋)
記事に関する記者への問い合わせ先:ルクセンブルク Stephanie Bodoni
;ロンドン Jeremy Hodges ;
federal court in Chicago Andrew Harris
,sbodoni@bloomberg.net,jhodges17@bloomberg.net,aharris16@bloomberg.net
記事についてのエディターへの問い合わせ先:
Anthony Aarons
Peter Chapman, Angela Cullen ,aaarons@bloomberg.net
本当は誰の責任なのか知らないが、一人だけの問題ではないと思う。ここまで問題が大きくなればけじめとか、責任を明確にしなければいけないのであろう。
東洋ゴム工業は30日、国の基準に満たない免震ゴムを製造した全額出資子会社の東洋ゴム化工品(東京)の藤巻勝己社長(59)が、代表権のない取締役に降格する27日付の人事を発表した。
東洋ゴムは免震ゴムの交換や顧客対応などに専念させるとしている。
藤巻氏の後任には、東洋ゴム化工品の前社長、岡崎俊明・非常勤取締役(56)が社長に復帰した。岡崎氏は東洋ゴム本体で免震ゴムなどを所管する部門の執行役員を兼務している。親会社との連携を強化する狙いもあるとみられる。
東洋ゴム化工品は、東洋ゴム本体が手がけていた免震ゴムの製造部門を切り離し、別の販売子会社と統合させて2013年1月に発足し、岡崎氏が社長を務めた。藤巻氏は14年1月、社長に就任した。
認識があるのか、ないのかはとてもトリッキー。認識がなかったと嘘をつかれればどうやって有罪にするのか?
ベネッセコーポレーションの顧客情報流出事件で、警視庁は30日、不正競争防止法違反で公判中の元システムエンジニア(SE)松崎正臣被告(40)から買い取った顧客情報を流出させたとして、東京都江東区の名簿業者「セフティー」と、同社社長(45)を同法違反(営業秘密の開示)容疑で書類送検した。
同庁によると、別の名簿業者のルートも含め、学習塾など全国の500社以上に子供や保護者の個人情報が流出していたという。
発表によると、セフティーは昨年5月21日、松崎被告がベネッセ社の顧客データベースから不正に持ち出した顧客情報約900万件を購入。7月1、2日の2回にわたり、このうち1万6317件を熊本県内の教育関連会社に転売し、営業秘密にあたる顧客情報を流出させた疑い。
同庁は昨年10月、セフティーを捜索。同社が、松崎被告から買い取った顧客情報のうち約474万件を、学習塾や呉服店、写真店など50社以上に総額約1600万円で転売したことを突き止めた。調べに対し、セフティーの社長は「営業秘密だとの認識はなかった」と容疑を否認している。
東日本大震災の経験から防災意識が高まる中で発覚した東洋ゴム工業による免震装置の性能偽装。震度5強程度なら十分な耐震性があるとの検証結果を発表したが、さらに別の建物で使われた装置でも基準を満たしていない可能性があると判明した。病巣は深く、広い。
事態は収束に向かうどころか、深刻さを増すばかりである。
東洋ゴム工業は3月25日、免震装置のゴムの性能を改ざんしていた問題で、震度5強程度の揺れでも倒壊や崩壊はしないという検証結果を発表した。
ところが同じ25日、国土交通省は国の性能基準を満たしていない同社製品が設置された建築物の棟数は、さらに拡大する可能性があることを明らかにした。
問題が初めて公表された13日時点では、不良品が使われた物件は全国の自治体の庁舎や消防署、警察署、病院や民間マンションなど55棟だった。その後の調査で、同じタイプのゴムを使った他の建物でも基準に満たない疑いが判明。異なるタイプのゴムを含め計195棟を調査することになった。
免震ゴムは上図のように、建物の底に設置される。地震が起きるとゴムが動き、地面から建物に伝わる地震の力を低減して揺れを小さくする。これによって建物の損傷や、室内の家具などが倒れるのを防ぐ。
国交相が認定する基準では、ゴムの性能のばらつきは10%までは許容されているが、問題の製品は最大50%に達する。日本免震構造協会の沢田研自専務理事によると、50%のばらつきがある場合、建物の揺れ幅は想定より3割程度大きくなる。
では、それが実際にどれほど危険なのか。大手ゼネコンの技術者によると、家具などの転倒を防ぐ免震機能それ自体が失われることはない。ただ想定以上に建物が動くため、配管などの設備に異常が出る可能性はある。
東日本大震災で震度6弱~強の揺れに見舞われた仙台市の問題の建物3棟では、損傷などは報告されていない。
ただ安全性に大きな問題はないとはいえ、問題の製品はすでに国交相の認定を取り消されており、不良品であることに変わりはない。民間マンションであれば資産価値が下がるし、自治体庁舎は災害時に拠点となるため、住民の不安は残る。
こうした心理を考慮してか、太田昭宏国交相は24日の記者会見で「(安全性に問題がなくても)交換を行う方向で厳しく指導する」と語った。
免震ゴムはもともと経年劣化に応じて交換はできる。しかし、前出の大手ゼネコン技術者は「全国で55棟に設置された2052基を一斉に交換するのは厳しい」と頭を抱える。
専門の工事業者は少なく、工期は1棟につき準備も含めて2年はかかる。交換する新たなゴムの確保も必要だ。対象が55棟からさらに拡大すれば、一層難航すること必至である。
それにしても東洋ゴムの一連の対応は、ずさんの一言に尽きる。
同社の説明では、子会社である東洋ゴム加工品の担当者が10年間、1人で免震ゴムの試験データを管理しており、昨年2月に交代した後任の担当者が「なぜ思い通りの性能が出ないのか」と疑問に思ったのが、不正が明らかになる発端だった。
社内調査を経て、最終的に不適合の可能性を国交省に連絡したのは今年2月9日。1年も経過している。同社は「前任の担当者しか詳細を知らず、上司も何人か交代しており、調査に時間がかかった」と弁解するが、不正の可能性を認識した昨年2月以降、12棟に欠陥品が出荷されていた。
● 過去にも偽装 コンプラ掲げた中計のむなしさ
国交省は17日に兵庫県の同社明石工場を立ち入り調査し、子会社の前任担当者によってデータが改ざんされたことを確認した。改ざんや社内調査の経緯については東洋ゴムが現在、外部の弁護士に依頼して調べており、4月以降に結果を公表する。
立ち入り調査をした田中敬三・国交省建築安全調査室長は本誌の取材に対し、「営業部からのプレッシャーがあったのではないか、という説明を東洋ゴム側から受けた」と話す。
同社の2014年12月期決算は、売上高3937億円、営業利益475億円、当期純利益312億円。いずれも過去最高だ。売り上げや利益の多くは北米を中心とした自動車向けタイヤによるもので、それ以外の事業は増収減益。そのマイナス要因として決算説明資料にわざわざ「建築免震ゴムの販売低迷等により」と載せるぐらいだから、営業担当者に焦りがあったことは想像に難くない。
同社は07年にも建築用断熱パネルで耐火性能の偽装が発覚した。昨年から始まった中期経営計画では「コンプライアンスの徹底」をうたってみせたが、実態は正反対だ。トカゲのしっぽ切りで担当者個人に責任を押し付けて片付けられる問題ではない。
(週刊ダイヤモンド編集部 岡田 悟)
妻を刃物で刺して殺害しようとしたとして、福岡県警早良署は30日、福岡市城南区七隈6、福岡大助教塩井誠次郎容疑者(37)を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。同署は詳しい動機などを調べている。
発表によると、塩井容疑者は30日午前5時36分頃、自宅で、同大助教の妻(33)の胸や背中を刃物で数回刺して殺害しようとした疑い。塩井容疑者は「間違いない」と供述しているという。
塩井容疑者が直後に「夫婦げんかで妻を刺した」と119番。駆けつけた同署員らが、室内の階段付近で血を流して座り込んでいる妻を見つけた。妻は病院に運ばれ、重傷。階段付近で包丁が見つかっており、同署は凶器とみて調べている。
同大によると、塩井容疑者は2007年4月から放射線などを用いて研究を行うRIセンターで勤務。勤務態度は真面目だった。衛藤卓也学長は「世間をお騒がせして誠に申し訳ない。事実関係を確認し、適切に対処する」とのコメントを出した。
「金銭的な事情から、塾に通う余裕のない家庭の子供の学習を支援する団体や、スポーツ・芸術分野で能力があっても活動を続けることが難しい子供を支援する狙いがある。」
学校が適切に教育できれば塾など必要ない。また、本人が望めば高度の教育を受ける制度又は成績優秀者には学費無料の制度を作ればよい。
塾は試験に受かるために特化した教育形態なので塾に行くことが望ましいとは思わない。ただ、大学進学又は有名な大学進学を目的にすると
試験で受からなければならないので塾に行くほうが有利になる。人間として、総合的な能力を身につけるためにはあまり塾に時間を費やすことが
良いとは思わない。スポーツと通して精神的な強さがないと良い結果が出せないとか、素質の不足を努力や自分に強みを生かすとか、弱点を
克服する方法もあることを知ること、いくらがんばっても報われないこともあり、挫折から立ち直ることによる成長などいろいろな良い点がある。
残念なことに、最終学歴でほぼ出世や社会的な評価が決まることもあるので、その点を変えていくほうに力を入れたほうが良いのではないのか。
セカンド・チャンスで再起できる社会にするべきではないのか?最終学歴で貧困から二度と抜け出せない社会を何とかするべきでないのか?
おろかな厚生労働省が考えそうなことだ!個人的にはこんな愚かなことには賛成しない。
「官民一体で貧しい家庭の子供を支える「子供の未来応援国民運動」(仮称)の発起人集会を開く」
貧しい家庭になった理由や両親の学歴、仕事、人生観や生活習慣など調査し、分析してから効率的な対策を検討するべきだ。個人及び両親の人生観、価値観そして
生活習慣が間接的に貧しい家庭になる原因と関連があると思う。塾が原因と安易に考えている時点で税金と時間の無駄遣い。
政府は、貧困家庭の子供を支援するため、自治体や財界などと連携して企業や個人に寄付を呼びかけ、基金を新設する。
厚生労働省が昨年7月に発表した子供の貧困率は16・3%(2012年)と過去最悪の状態で、金銭的な事情から、塾に通う余裕のない家庭の子供の学習を支援する団体や、スポーツ・芸術分野で能力があっても活動を続けることが難しい子供を支援する狙いがある。
安倍首相が4月2日、自治体や財界、マスコミなど幅広い分野の代表を首相官邸に招き、官民一体で貧しい家庭の子供を支える「子供の未来応援国民運動」(仮称)の発起人集会を開く。基金を設置することも申し合わせる。
新基金については、今夏をメドに事務局を発足させ、寄付の呼びかけを本格化させる方針だ。政府は基金の設置や運営面で関与していく。
今回の事故で、飛行機のリスクが明らかにされたと思う。パイロットの問題がこれほど注目された最近の事故はないと思う。
150人が乗ったドイツのジャーマンウイングス機の墜落。ボイスレコーダーの記録からアンドレアス・ルビッツ副操縦士(27)が、意図的に墜落させたとみられることがわかりましたが、さらに新たな事実が明らかとなりました。
「デュッセルドルフにある副操縦士の自宅アパートからは、体調を悪化させているという医師が書いた証明書が見つかったということです」(記者)
「(副操縦士は)疾患を抱えていて治療中だったことを示す資料を押収した」(ドイツの検察当局)
27日に会見したドイツの検察によりますと、診断書には「体調悪化」を理由に「仕事を休むべきだ」とする医師の診断が書かれていて、墜落当日についても、仕事を休むよう、アドバイスする内容でした。しかし、これらの診断書はいずれも破り捨てられていたといいます。
「事故当日も休むよう指示した診断書が破かれた状態で見つかったことは、副操縦士が会社や関係者に自分の疾患を隠していたという推測を裏付けるものだ」(ドイツ検察当局)
また、関係先の捜索では、遺書のようなものは見つかっておらず、政治的、宗教的な背景を示すものも確認されていないといいます。押収した医療関係の証拠の分析には、数日かかるということです。
10代でグライダーの免許を取り、憧れのパイロットになる夢も叶えたルビッツ副操縦士。実は、ジャーマンウイングスの親会社ルフトハンザは、パイロット養成期間中の6年前、数か月間に渡って訓練を中断していたことを明らかにしていました。ただ、その理由については・・・
「(訓練中断の)理由については言えません。ドイツでは医学的理由があった場合、明かしてはならず、それは死後も同じです」(ルフトハンザ航空CEO)
副操縦士が抱えていた疾患について、ドイツのメディアは「うつ病だった」と報じています。大衆紙「ビルト」は、「訓練を中断している間、客室乗務員として働かなくてはならなかったため、同僚からばかにされるなど、本人は色々と悩んでいた」と伝えています。
パイロットも、うつ病とは無縁ではありません。パイロットのカウンセリング経験がある精神科医は「自分がうつ病だと言いだしにくい職業だ」と話します。
「(パイロットは)ストレスが非常に高い、緊張度が高い仕事のために、そのことが原因で不安感・緊張感がいつまでもとれない。パイロットの仕事は社会的にもある程度、地位の高いものだから、そこから外されることの恐怖感もあるし、自分に結構自信があって今までやってきたのに『こんなはずではなかった』と、最終的にかなりのうつ状態になるまで頑張り続ける(ケースもある)」(成城墨岡クリニック 墨岡孝院長〔精神科医〕)
談合が止めれない構造になっていたことを証明しているようなもの!
「機構は受注会社との間で、『談合した場合は請負代金額の10%の違約金を支払わせる』との契約を結んでおり」は建前だけの
パフォーマンスで談合が発覚し、違約金が請求されることを想定していない。談合が発覚しなければ談合に関与したほうが良いのは当然、
談合が発覚する可能性があると思えば違約金を支払うことまで想定しているので提訴して問題にしないと思う。
北陸新幹線の雪害対策工事を巡る談合事件で、有罪が確定した設備工事会社3社が27日、発注元の独立行政法人「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に対し、計約9億5000万円の違約金の返還を求める訴訟を東京地裁に起こした。
談合に関与した機構幹部も有罪が確定しており、3社は「機構が組織ぐるみで談合の損害を発生、拡大させており、違約金の請求は無効だ」としている。
訴えたのは、三建設備工業(東京)と東洋熱工業(同)、三晃空調(大阪)。この3社を含む8社の担当者は昨年、2011~12年に談合して総額約174億円の工事を落札したとして、独占禁止法違反(不当な取引制限)の有罪が確定した。
機構は受注会社との間で、「談合した場合は請負代金額の10%の違約金を支払わせる」との契約を結んでおり、工事を完了した7社に追加工事分も含めて計約20億4600万円を請求。2社は違約金を支払い、5社には違約金分を減額して工事代金が支払われた。
ルフトハンザはうつ病の経歴を考慮しない方針なのだろう。しかし、うつ病を発症した人は重圧、継続的なストレスを受ける、又は、集中的にストレスを
受ける可能性がある仕事には向かないと思う。特に多くの人命に影響を与える仕事は本人には悪いが従事させないほうが良いと思う。
ルフトハンザは過去に「深刻なうつ病」で精神療法を受けた人にもチャンスを与える寛大な会社なのだろうが、このような事故が起きてしまったら、
会社に対する信頼性や補償を含めて大変だと思う。個人的には同じ料金ならルフトハンザの飛行機には乗りたいとは思わない。
[ベルリン 27日 ロイター] - 独ビルト紙は27日、乗客乗員150人全員が犠牲となった格安航空会社ジャーマンウィングスの旅客機事故で、故意に機体を墜落させたとみられている副操縦士が、6年前に「深刻なうつ病」を患い、精神療法を受けていたと報じた。
フランスの検察当局は、墜落機から回収されたボイスレコーダーを解析した結果、アンドレアス・ルビッツ副操縦士(27)が機長をコックピットから締め出し、同機を故意に降下させ墜落させた可能性があると発表したが、その動機は明らかにされていない。
ビルト紙は内部資料やジャーマンウィングスの親会社であるルフトハンザ<LHAG.DE>の関係筋から、副操縦士が計1年半、精神療法を受けた経験があると報道。これら関係資料は、ドイツ当局が調べた後でフランスの捜査当局に渡されるという。
ルフトハンザのカールステン・シュポア最高経営責任者(CEO)は26日、記者会見で副操縦士は6年前に数カ月間訓練を休んだが、飛行に必要なすべての検査に合格したと明らかにした。
同社の広報担当者は27日、副操縦士の健康状態についてコメントを差し控えた。
[ベルリン/パリ/セーヌレザルプ 27日 ロイター] - 乗客乗員150人全員が犠牲となった格安航空会社ジャーマンウィングスの旅客機事故で、故意に機体を墜落させたとみられている副操縦士が、6年前に「深刻なうつ病」を患い、精神療法を受けていたと独ビルト紙が27日報じた。
フランスの検察当局は、墜落機から回収されたボイスレコーダーを解析した結果、アンドレアス・ルビッツ副操縦士(27)が機長をコックピットから閉め出し、同機を故意に降下させ墜落させた可能性があると26日発表したが、その動機は明らかにされていない。ドイツの捜査当局は同日、モンタバウアにある副操縦士の実家を家宅捜索。証拠として、コンピューターなどを押収し、動機の解明に向けた捜査を開始した。
ビルト紙は内部資料やジャーマンウィングスの親会社であるルフトハンザ(LHAG.DE: 株価, 企業情報, レポート)の関係筋から、副操縦士が計1年半、精神療法を受けた経験があると報道。これら関係資料は、ドイツ当局が調べた後でフランスの捜査当局に渡されるという。
仏マルセイユ検察当局者は会見で、副操縦士の行動の動機を推測することはできないとした上で、「故意に航空機を破壊しようとしたようだ」と語った。また、「機長がコックピットのドアを壊そうとした音が聞こえる」とし、機長は恐らくトイレに行くためにコックピットを離れたとの見方を示した。
この会見に先立ち、ドイツの州検察当局は、墜落時にコックピットにいたのは操縦士1人だけだったと発表。独仏の検察当局は、副操縦士はテロリストのリストには載っておらず、「テロ行為」だったと考える根拠はないとしている。
<副操縦士の地元に衝撃>
ルビッツ副操縦士の地元モンタバウアには、今回知らせを受けて衝撃が走った。副操縦士が免許を取得した飛行クラブのメンバーは「言葉が出ない。彼を知っているだけに想像すらできない」と動揺を隠せない様子だった。
副操縦士の性格についてこの知人は、「楽しい男だった。時に物静かな一面を見せていたかもしれないが、他の青年と変わらなかった」と話した。親しみやすく、悪意を持っていたようには見受けられなかったとの声も聞かれた。
副操縦士のフェイスブックのページからは、ハーフマラソンに参加したり、ポップ音楽やクラブに興味があったり、米サンフランシスコのゴールデンゲート・ブリッジを訪れたりと、活動的なライフスタイルを送っていたことが伺える。
ルフトハンザによると副操縦士は2013年9月、ジャーマンウィングスに入社、操縦時間は630時間だった。一方、機長の操縦時間は6000時間超で、親会社のルフトハンザに10年間勤務していた。
また、副操縦士は6年前、数カ月間訓練を休んだが、飛行に必要なすべての検査に合格したと明らかにした。
カールステン・シュポア最高経営責任者(CEO)は、訓練を休むことは特異でないと説明し、乗員の採用は非常に慎重に進めており、心理面の審査を受けさせていると強調。「どのような安全規制であれ、条件をいくら高く設定しても、実際にわれわれの基準は信じられないほど高水準だが、こうした事故が発生する可能性を排除する方法はない」と語った。
ルフトハンザなどによると、コックピットのドアは暗証コードを使って開けることができるが、コックピット内からブロックすることも可能という。
同検察当局は音声記録では「最後の瞬間になって叫び声が聞こえた」と説明し、乗客の大半は機体が地面に衝突する直前まで墜落の危険性に気付かなかった可能性も指摘した。
飛行経路を捕捉するウェブサービス「フライトレーダー24」は、墜落機の自動操縦装置を、設定可能な最低高度である100フィートに何者かが突然変更したことを明らかにした。衛星データの解析によると、高度が設定された9秒後、機体の降下が始まったという。同機は約6000フィートの高度で墜落している。
今回機長がコックピットを離れた際に事故が起きた可能性が強まっていることを受け、航空各社では、乗員2人が常に操縦室内にいることを義務付ける動きが相次いでいる。米国以外の多くの国では、トイレに行く際など片方の離席は認められているのが現状だ。
エア・カナダ(AC.TO: 株価, 企業情報, レポート)、格安航空会社(LCC)のノルウェー・エアシャトル(NWC.OL: 株価, 企業情報, レポート)、英イージージェット(EZJ.L: 株価, 企業情報, レポート)、独エア・ベルリン(AB1.DE: 株価, 企業情報, レポート)は直ちに、2人の操縦士が常にコックピット内にいるよう定めたと明らかにした。エア・ベルリンによると「顧客から懸念の声が多く寄せられた」という。アイルランドのLCC、ライアンエア(RYA.I: 株価, 企業情報, レポート)は既に義務化していた。
一方、ルフトハンザは義務付けの必要はないと表明。カールステン・シュポア最高経営責任者(CEO)は記者らに対し「今回は特殊な事例であり、規定変更の必要があるとは考えていない。ただ、専門家らと検討はする」と述べた。ツイッターではこれを批判し、義務化を求める意見が挙がっている。
「ルビッツ副操縦士は2008年にルフトハンザ社の育成施設でパイロットとして訓練を受け始めたものの、一時中断。その後、
改めて健康診断や適性検査を受け直したという。客室乗務員などを務めた後、パイロットになった。シュポア氏は
『どれほど洗練された育成システムを持っていても、悪意のある個人を排除することはできない』と述べた。」
そんなコメントをしたら全てにおいて改善する意味はなくなる。つまり事故に遭うかは運次第と言っているのと同じ。パイロット不足が影響しているのか?
安全を優先すれば基準の緩和は良いことなどない。これはパイロットの基準を緩和した国土交通省にも言えること。安全優先か、コスト優先か、どちらを優先するかで
結果に影響する可能性はある。利用者にもっと情報を提供して自己責任で安全優先の飛行機か、コスト優先の飛行機かを選択させるべきだと思う。
【パリ=本間圭一、三好益史】フランス南東部のアルプス山中で24日に墜落したドイツの格安航空会社ジャーマンウィングスの旅客機を巡り、仏検察当局のブリス・ロバン検察官は26日、仏南部マルセイユで記者会見し、機長がコックピットの外に出た後、副操縦士が意図的に機体を降下させたとの見方を明らかにした。
検察官は、副操縦士を殺人容疑で捜査する考えを示した。
ロバン氏は、機体を降下させたのはドイツ国籍のアンドレアス・ルビッツ副操縦士(27)だったとした上で、「テロリストとしてリストアップされていない」「墜落をテロとみなす根拠はない」などと述べた。
ドイツ誌フォルクス(電子版)は26日、捜査当局が同日、独西部モンタバウアーのルビッツ副操縦士の実家と、同デュッセルドルフの住居への家宅捜索を開始したと報じた。
ロバン氏によると、回収されたボイスレコーダーから、墜落前30分間の会話が判明した。機長がルビッツ副操縦士に操縦を任せ、コックピットを出た後、同副操縦士は扉を開けるのを拒否し、機長を閉め出した。ジャーマンウィングスの親会社ルフトハンザ航空によると、墜落機のコックピットのドアは、外側からコードを入力すれば開けられる仕組みだったが、内部から阻止することもできたという。
ルビッツ副操縦士は管制官の問いかけに応じず、墜落直前までの10分間は、同副操縦士の呼吸音だけが聞こえた。機長がコックピットを出る前に同副操縦士と交わした会話は、着陸についての説明で、異変はなかった。
ロバン氏は、ボイスレコーダーの分析から「最後の瞬間になって乗客の叫び声が聞こえた」と述べ、墜落の直前まで乗客が墜落の危険性に気付かなかった可能性を指摘した。
ルフトハンザ航空のカーステン・シュポア最高経営責任者(CEO)は、この後、独西部ケルンの同社本社で記者会見した。シュポア氏は、ルビッツ副操縦士が意図的に機体を降下させたとする仏当局の発表について、「我々全員にとって、非常にショックなことだ」と語った。
ルビッツ副操縦士は2008年にルフトハンザ社の育成施設でパイロットとして訓練を受け始めたものの、一時中断。その後、改めて健康診断や適性検査を受け直したという。客室乗務員などを務めた後、パイロットになった。シュポア氏は「どれほど洗練された育成システムを持っていても、悪意のある個人を排除することはできない」と述べた。
シュポア氏によると、同社やジャーマンウィングス社のパイロットは、定期的に飛行試験や身体検査を受けることになっているが、精神面の検査は行っていないという。
東京大学分子細胞生物学研究所の論文不正問題で、東大は27日、不正に関与した当時の大学院生ら3人の博士号を、学内の規定に基づいて取り消したと発表した。
東大の博士号取り消しは2010年と11年にあったが、一度に3人の取り消しは初めて。
東大の科学研究行動規範委員会は昨年12月、同研究所の加藤茂明元教授(12年辞職)の研究室が1999~2010年に発表した論文33本で、画像の捏造ねつぞうや改ざんが見つかったと公表。加藤元教授ら計11人が不正に関与したと結論づけた。
東大は、11人のうち、05~07年に博士号を得た元大学院生ら3人は、不正と認定された画像を自分の博士論文でも使っていたことから、学位の取り消しに該当すると判断した。うち1人は一時、東大の助教(13年辞職)を務めていた。
東大は、加藤元教授らについて、懲戒規定に基づく処分と研究費返還請求を引き続き検討する。
根本的に理研と同じレベル。STAP細胞がないと結論に至るまで結構な時間とお金がかかった。
「免震ゴム」を巡る問題で立ち入り調査です。
17日午後4時、国土交通省の担当者らが兵庫県にある東洋ゴム工業の明石工場に立ち入り調査に入りました。この工場は、性能基準を満たしていないゴムを含む免震装置を製造した工場です。調査では、保存されているデータの確認や従業員への聞き取りなどが進められています。また、担当者が交代したことがきっかけで、東洋ゴム社内で問題が発覚した後も納入が続けられ、12の建物に使われていたことも新たに分かりました。東洋ゴム工業は「データが偽装されているとの確証が持てず、納入を続けてしまった」としています。
東洋ゴム工業(本社・大阪市)による免震ゴムの性能偽装問題で、国土交通省は25日、全国の55棟以外にも、新たな不良品の免震ゴムが納入されていた可能性がある、と同社から連絡を受けたと発表した。設置場所や基数は同社が調査中で、判明し次第、報告するよう求めた。
国交省によると、新たに不良品の可能性がでてきたのは、すでに国交大臣認定が取り消された3製品以外のタイプ。試験データの数値を改ざんした同じ元課長代理が関わった疑いがあるという。同社は55棟のほかに、全国195棟に免震ゴムを設置しているという。
「墜落事故を受けて24日、他の乗員らがデュッセルドルフ空港などで業務を拒否。その結果、欧州全体で約30便が欠航となったという。同社報道担当者は、業務拒否について「乗員たちの個人的な理由」と説明している。」
根本的な問題がない限り、乗員が業務を拒否する理由は考えられない。何か公表できない問題があったのか?
フランス南東部の山中に、乗客乗員計150人を乗せたドイツの格安航空会社ジャーマンウィングスの旅客機が墜落した事故で、日本外務省は25日、搭乗者リストに掲載された邦人2人について、いずれも独西部デュッセルドルフ在住の男性で、永田敏(ながたさとし)さん(60代)、佐藤淳一(さとうじゅんいち)さん(40代)と発表した。一方、AFP通信などによると、現場で飛行記録を収めたブラックボックス1個が発見された。
外務省は、実際に搭乗していたのかなどを含め安否確認を急いでいる。
発電設備などの販売を手がける西華産業(東京)によると、佐藤さんは同社の現地法人社員だという。同社の広報担当者は「搭乗していたのは弊社社員です」と話した。詳細を現在確認中という。デュッセルドルフの現地法人社員も「佐藤はうちの社員です。仕事でこの航空機を使っていたが、詳細は確認中」と対応に追われた様子だった。
一方、AFP通信によると、カズヌーブ仏内相は24日、墜落現場でブラックボックスを回収したことを明らかにすると共に、「数時間以内に分析にまわされる。事故調査が進む」と説明した。
スペインのバルセロナ発、ドイツ西部デュッセルドルフ行きのジャーマンウィングスの9525便(エアバスA320型機)は、24日午前11時(日本時間同日午後7時)ごろ、フランス南東部の山岳地帯に墜落した。旅客機には乗客144人と乗員6人の計150人が搭乗。赤ちゃん2人も含まれているという。仏メディアによると、オランド大統領は24日、「状況から見て、生存者はおそらくいないとみられる」との見方を示した。
墜落現場での捜索活動は難航している。仏政府は捜索に、救助隊員300人、軍警察300人、ヘリコプター10機、飛行機1機などを投入。だが現場は標高2千メートル級の山岳地帯。岩山が連なり、車両での接近は困難なため、ヘリなどで上空からの捜索に頼らざるを得ない。AP通信は24日、仏政府高官の話として、現場近くにヘリコプターが着陸したものの、生存者は発見できなかったと報じた。仏テレビは同日、墜落現場の上空を飛ぶヘリコプターから、黒ずんだ岩肌に事故機の残骸らしきものが大量に散乱している様子を伝えた。
仏メディアによると、仏当局者は同日夜、「安全のためヘリでの捜索はいったん打ち切り、明朝夜明けに再開する」と語った。
現場に近く、現地対策本部が置かれているセーヌレザルプの当局者の一人は朝日新聞の取材に対し、「現場は山が険しく、救助も捜索も困難だ」と語った。
ジャーマンウィングスの最高経営責任者は24日夜に再び記者会見し、航空事故の調査当局者や同社の技術者が現場に入ったと発表した。しかし、搭乗者の詳しい国籍については「確認中」としたままだった。
事故機が向かっていたデュッセルドルフ近郊のギムナジウム(日本の中高に相当)は24日、同校の生徒16人と教師2人が搭乗していた可能性があると明らかにした。スペイン語学級の10年生で、バルセロナで1週間弱の交換留学を終えて帰国する途中だったという。
25日には、ドイツのメルケル首相が墜落現場を訪れ、オランド仏大統領やスペインのラホイ首相と対応を協議する予定だ。
一方、独誌シュピーゲル(電子版)は24日、ジャーマンウィングスの事故機が墜落前日に、デュッセルドルフ空港で機体不良のため数時間、離陸できなかったと報じた。系列会社ルフトハンザの報道担当者は、同誌の取材に「機体前方の車輪の開閉扉に技術的な問題があったが、その後、完全に解決した」と説明した。
ジャーマンウィングス内部にも動揺が広がる。墜落事故を受けて24日、他の乗員らがデュッセルドルフ空港などで業務を拒否。その結果、欧州全体で約30便が欠航となったという。同社報道担当者は、業務拒否について「乗員たちの個人的な理由」と説明している。(ベルリン=玉川透、パリ=吉田美智子、仏南東部セーヌレザルプ=青田秀樹)
コメントで過去にLCCについて書いた。個人的にはLCCには乗らない。健全なLCCもあるとは思うが、自分では内部的なことまでわからないので 避ける。LCCでない航空会社が安全なのかはわからないが、それで事故に遭えば運が悪いと諦めている。 コストカットや人件費のカットが歪を引き起こさないように出来ればよいが、規則無視や 問題を指摘されなければ問題ないと考える企業が事故を起こさなければ事故が起きるまで追従するか、倒産の危機に直面する可能性もある。 今回の事故まで日本ではLCCについてネガティブなコメントをするメディアは少なかったと思う。個人的にはいまさらと思う。 戦争に行っても生きて帰ってくる強運の人もいるし、通勤や通学で事故に遭う人もいるのだから心配しても仕方がないのかもしれない。 結局は個人の判断。
【デュッセルドルフ時事】フランス南東部で墜落したドイツ格安航空(LCC)ジャーマンウィングスの旅客機が向かっていたドイツ・デュッセルドルフは、日本企業が集中し、欧州最大級の日本人街がある都市だ。搭乗者名簿には2人の日本人とみられる名前があり、地元の日本人社会にも衝撃が走った。
デュッセルドルフ中心部でラーメン店などを経営する佐伯春彦さん(46)は「自分もよく仕事でジャーマンウィングスを利用する。まったく人ごとではない」とこわばった表情。「ここは日本人が集まる場所。みなテロではなかったのかと不安がっている」とも語った。
デュッセルドルフに出張で訪れたという大手日本企業のロンドン駐在員男性は「出張でLCCをよく使うが、不安になった」と顔を曇らせた。デュッセルドルフ近郊に住む50代の会社員女性は「ニュースを聞いた時は、絶対に日本人がいると思った」と話した。
デュッセルドルフには約5000人の日本人が在住。中心部の「インマーマン通り」には日本食材店や日本の漫画を取り扱う書店などが立ち並び、地元では「日本通り」とも呼ばれる。(
欧州の販売基盤と技術を買うのであれば中国化工集団の判断次第。しかし、日本では「ピレリ」のブランド力は落ちるであろう。 ボルボと同じ。日本で中国の「ピレリ」との認識が広がればもっとブランド力は落ちるであろう。
【北京=栗原守】中国国有企業の「中国化工集団」は、イタリアのタイヤ大手「ピレリ」を買収すると発表した。
買収総額は71億ユーロ(約9200億円)にのぼるとみられる。
買収は中国化工の子会社を通じて進められる。中国化工は、世界5位のタイヤメーカーのピレリを買収することで、欧州などの販売基盤を手に入れる。高級タイヤ事業に強いピレリのブランド力を生かす狙いもある模様だ。
一方、ピレリは、世界最大規模の自動車市場の中国での事業拡大などを図る方向だ。
半沢の世界だな!
みずほ銀行の元行員の男が、東京都内の男性医師から1億円以上をだまし取ったとして、逮捕されたことが分かりました。警視庁は、被害が数十億円に上るとみて調べています。
逮捕されたのは、みずほ銀行の元行員で審査役だった及川幹雄容疑者(51)です。及川容疑者は、2011年5月からの約1年間に、世田谷区に住む男性医師に「特別な顧客にだけ紹介している商品です」などと嘘の投資話を持ち掛けて、1億円以上をだまし取った疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、及川容疑者は当時、千代田区内幸町にあったみずほ銀行本店の応接室を使って元本保証や高配当をうたい、自分の話を信じ込ませていたということです。警視庁は、及川容疑者が他にも数十人から合わせて数十億円をだまし取ったとみて調べています。.
「政府の経済政策である「観光立国」の推進に合わせ、入国審査時の“水際対策”や治安対策の重要性が改めて浮き彫りになった格好だ。」
データは事実かもしれないが、データの数値を間接的に操作は出来る。単純にデータを鵜呑みにしないほうがよいと思う。
観光立国の推進のために行ったビザ免除の後遺症。政府やメディアはほとんど触れていないがこれはビザ免除になった時点で想定できたこと。
観光産業や外国人観光客による直接又は間接的に恩恵を受けない人達にとっては負担が増しただけ。
法務省は4月から、外国人が日本で会社経営をしやすくするために、在留資格を取得するための条件を大幅に緩和する。
現在は、日本で法人登記をしたことを条件に、外国人経営者に「投資・経営」という在留資格を与え、長期の滞在を認めている。だが、海外に住む外国人が法人登記を行うには、日本での住民票が必要となるため、日本人の協力者に代行してもらわない限りは、事前の登記は難しかった。
同省は4月から、事前登記がなくても、設立しようとしている会社の定款や事業計画書などの資料から、起業が目的であることを確認できれば、4か月限定で「投資・経営」の在留資格を与えることにした。この期間で法人登記が完了すれば、長期間の滞在に切り替えることができるようにする。同省は、入管難民法の施行規則の見直しで対応する。
「政府の経済政策である「観光立国」の推進に合わせ、入国審査時の“水際対策”や治安対策の重要性が改めて浮き彫りになった格好だ。」
データは事実かもしれないが、データの数値を間接的に操作は出来る。単純にデータを鵜呑みにしないほうがよいと思う。
観光立国の推進のために行ったビザ免除の後遺症。政府やメディアはほとんど触れていないがこれはビザ免除になった時点で想定できたこと。
観光産業や外国人観光客による直接又は間接的に恩恵を受けない人達にとっては負担が増しただけ。
タイ人の入国拒否者数が昨年、約20年ぶりに1000人を超え、国籍・地域別で最多となったことが法務省への取材で分かった。平成25年7月に始まった査証(ビザ)免除の影響とみられ、不法残留や不法就労も後を絶たない。彼らはどのようにして日本に入国し、住居と仕事を得るのか-。ビザ免除を悪用し、不法就労していたタイ人の行方を追った。(池田証志、加藤園子)
■「やはり『サメン』だ」
今年2月のある日。夜明け前の午前5時半ごろ、東京入国管理局の入国警備官らは複数の自動車に分乗し、茨城県内で不法就労するタイ人の住居に到着した。「不法滞在している外国人がいる」との情報提供を基に約3カ月間の内偵をへて着手にこぎつけた。
摘発対象は、農作業に従事するタイ人男女だ。入国警備官らは、産業廃棄物が山のように積まれた敷地内に建つ平屋を取り囲んだ。目隠しのためか、全ての窓にベニヤ板が打ち付けられている。
日の出とともに、タイ人男性が玄関から出てきた。青いジャンパーを着た入国警備官が近寄り「東京入管ですが…」と声をかけると、男性は素直に応じ、入国警備官らを家に入れた。
玄関で靴を脱ぎ、廊下に上がる。狭い通路の両脇に合計3つの部屋があった。畳やふすま、はりが傷んだまま放置されている。一度は人が住まない廃屋になっていたようだ。入国警備官が確認すると、屋内にはさらにタイ人の男女2人がいた。
布団が敷かれたままの部屋に3人を集め、旅券(パスポート)を出させると、旅券番号や名前を携帯電話で東京入管に連絡。データ照合の結果、3人が昨年11月に15日間の短期滞在の資格で入国したまま消息を絶っていたことが判明した。
「やはりサメン(査証免除)だ」。入国警備官の一人がつぶやいた。3人は不法残留と不法就労の事実を認め、スーツケースを取り出して荷造りを始めた。
「追い詰められて逃げ出したり、抵抗したりする外国人もいますが、タイ人はたいていおとなしいです」。入国警備官たちはいつも、防刀(ぼうじん)ジャケットをジャンパーの下に着用している。
■「日本が好き、でももう来られないね」
「バンコクから名古屋の空港に着いて、新幹線で東京に行った。それから、ここ(茨城県)に来た」。東京入管へ護送されるバスの中で、摘発されたタイ人女性(39)は流暢(りゅうちょう)な日本語で話した。バスの窓に張られた鉄格子越しに冬の畑の景色が流れて見える。
女性の来日は3度目。不法就労も初めてではないという。今回は、タイ東部サケオで借金してブローカーに80万円を払い、航空券や日本国内での職業斡旋(あっせん)を依頼した。
仕事は野菜の収穫などの農作業。ブローカーに指示された畑へ行く毎日だ。一日の給料は5000円だったという。滞在日数から考えると、日本で稼いだ額は借金返済に遠く及ばない。
「借金は返せない…」。タイに帰れば、子供2人がいるという女性。「日本が好き。でも、もう来られないね」
中堅の入国警備官は「2、3年働ければ、タイに鉄筋3階建ての家が建つ。でも、途中で摘発されれば、借金しに来たようなもの」と肩をすくめた。
入管幹部によると、タイの貧困地域から不法入国を試みる者が目立つという。一般のツアーに紛れたり、別の国の観光地を経由してきたりと入国の仕方も手が込んできている。ただ、無事入国できたとしても、必ず働けるとはかぎらない。「空港で待つように」とブローカーに言われたが、いつまでたっても迎えが来なかった…という事例もある。
■「取り締まり強化するしかない」
都会ではマッサージ店などで不法就労し、摘発されるタイ人が増えている。警察庁によると、昨年、不法残留などの入管難民法違反で摘発されたタイ人は139人に上り、前年比で36%増えた。窃盗など刑法犯で摘発されるケースもあり、捜査当局は危機感を強めている。
警視庁は昨年10月、不法残留をしながら東京都や千葉県内のマッサージ店で働いていたとして、タイ国籍の女10人を入管難民法違反(不法残留)容疑で、店を経営していたタイ国籍の姉妹を犯人蔵匿容疑で逮捕した。従業員の女らはビザ免除で入国し、約2カ月間不法残留していた。経営者の姉妹がビザ免除を悪用して従業員を来日させ、働かせたとみられている。
法務省によると、昨年1年間に日本への入国を拒否されたタイ人は、前年(489人)の2倍以上に増加。その他の上位国は前年までと同様の傾向となっており、国籍・地域別で前年に最も多かった韓国を抜いて最多になった。政府の経済政策である「観光立国」の推進に合わせ、入国審査時の“水際対策”や治安対策の重要性が改めて浮き彫りになった格好だ。
警視庁幹部は「ビザ免除をチャンスと考え、そのまま不法残留する外国人も増えるだろう。入国の間口を広げれば、罪を犯す外国人の流入も避けられない。治安悪化につながらないよう、取り締まりを強化していくしかない」と話した。
STAP細胞論文問題で、理化学研究所が論文不正の調査や検証にかけた一連の経費が総額8360万円に上ったことが分かった。降圧剤バルサルタン(商品名ディオバン)の臨床試験疑惑など他の研究不正と比べても、単独の組織がかけた費用としては突出した額となっていた。STAP論文不正は、研究への信頼を揺るがしただけではなく、金銭的にも大きな代償を払う結果となった。
理研によると、疑惑が発覚してから約1年間にかかった主な経費の内訳は、STAP細胞の有無を調べる検証実験1560万円▽研究室に残った試料の分析1410万円▽二つの調査委員会940万円▽記者会見場費など広報経費770万円など。弁護士経費など2820万円、精神科医の来所など関係者のメンタルケアに200万円を支出していた。
毎日新聞が過去3年の主な研究不正調査に携わった大学や学会に取材したところ、バルサルタン疑惑の舞台となった京都府立医大の調査費は約1200万円だった。期間は約4カ月で、費用の大半がカルテや患者データなどの解析を第三者機関に業務委託した分という。東京慈恵会医大は約1500万円で、やはりカルテなどの解析を業務委託した費用が大半だった。
東京大分子細胞生物学研究所で起きた33本の論文不正では、東大は調査費に約230万円をかけた。元東邦大准教授の麻酔科医による172本の論文不正を認定した日本麻酔科学会は、事務局の人件費を含めて524万円を支払ったという。人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使い世界初の臨床応用に成功したとの虚偽発表に伴う東大の論文調査費は約26万円だった。
理研の規定では、今回かかった費用は不正認定された研究者には請求できないため、理研が国からの運営費交付金の一部から支出したという。【八田浩輔】
◇調査経費の膨張 背景に理研の対応の迷走
STAP不正問題の調査などの経費が膨らんだ背景には、理研の対応の迷走がある。不要論が根強かった小保方(おぼかた)晴子氏が参加した検証実験では、監視カメラを付けた特別の部屋を用意し、立会人を付けて実施したが、小保方氏の参加時には論文は撤回されていた。もし「胚性幹細胞(ES細胞)混入」について、残された試料の解析を当初から始めていれば「決着」はより早まったはずだ。検証実験の立会人の旅費だけで180万円かかっている。
また、1回目の調査委員会が昨年3月末に結論を出したものの、残された疑義を調べるため再び調査委を設置した。この二つの調査委の経費だけで1000万円近い。
今回、理研の調査経費と比べた研究不正も、科学界に与えた影響はSTAP論文同様に大きい。バルサルタン疑惑は世界的な製薬企業を巻き込んだ刑事事件に発展。東大分子細胞生物学研究所の問題では研究室の組織的な不正が指摘された。元東邦大准教授の不正論文本数は「世界記録」とすらいわれる。
研究不正の調査費はこれまでほとんど明らかにされてこなかった。不正のコストを明らかにすることは、不正の抑止効果のみならず、公正で均質な調査の実現にもつながるはずだ。【八田浩輔】
◇STAP細胞論文の理研の不正調査に関連してかかった経費
▽二つの調査委員会(外部委員への謝金・交通費、会場費など)940万円
▽保存試料の分析 1410万円
▽検証実験(技術スタッフ人件費、研究消耗品、実験室整備費)
1560万円
▽検証実験の立会人旅費 180万円
▽発生・再生科学総合研究センター(CDB、当時)「自己点検検証委員会」
(外部委員の謝金・交通費、会場費など) 80万円
▽改革委員会(同) 400万円
▽メンタルケア(ポストベンション=自殺で残された人たちへのケア=、精
神科医など来所謝金) 200万円
▽広報経費(記者会見会場費など) 770万円
▽法律事項など専門家への相談(弁護士経費など) 2820万円
国内最大級のインターネット上の仮想商店街「楽天市場」で、店舗の口コミ評価をつり上げる架空の投稿をされて損害を被ったとして、運営する楽天(本社・東京)が大阪市北区のコンピューターシステム会社を相手取り、約1億9000万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。20日に第1回口頭弁論があり、システム会社側は争う姿勢を示した。
楽天市場には昨年末現在で約4万1000店舗が出店する。客はネット上で商品を注文でき、電子決済も可能。商品や店の対応を客が5段階評価で投稿する「みんなのレビュー」と呼ばれる仕組みがあり、商品ごとに扱う店の投稿を読める。
訴状によると、システム会社は150件当たり8万円の対価で、客を装う投稿を請け負っていた。楽天が昨年1月以降に調査した結果、121店舗の11万件以上の投稿が同社による架空投稿だったとしている。
楽天は店舗側に投稿の削除を求め、応じない店舗とは契約を解除した。訴状では「適切なレビューを掲載できず、他の出店者や消費者に公正なサービスを提供できなかった」と主張し、得られたはずの広告料収入などの賠償を求めている。
楽天は「コメントできない」、システム会社は「一切答えられない」としている。【堀江拓哉】
東洋ゴムように担当者の交代で問題が発覚したケースが他にもあれば隠蔽している、又は、偽装した担当者が正直に名乗り出るだろうか? 組織ぐるみの偽装であれば今名乗り出なければ後で発覚した場合厳しい行政処分で会社はなくなると判断すると思うが、個人又は少人数による 偽装であれば正直に名乗り出ても地獄、今後も偽装を隠蔽する地獄であろう。どのみち地獄に行くのであれば、運がよければ偽装が見つからない可能性も ある後の選択ではないだろうか?このようなケースが本当に存在すれば、国交省のパフォーマンスは空振りに終わるであろう。
東洋ゴム工業(本社・大阪市)の免震ゴム性能偽装問題を受け、国土交通省は20日、免震ゴムを製造する他の26社に対し、同様の問題がないかの調査を指示した、と発表した。国交大臣認定の不正取得や認定基準に満たない不良品の有無などを4月20日までに文書で回答するよう求めている。
国交省によると、調査対象は26社が2000年以降に取得した免震ゴムの大臣認定167件。指定性能評価機関に出した試験データなどの調査や担当者への聴取をしたうえで回答し、問題があれば同省が追加調査とヒアリングを実施する。
構造計算書偽造問題及び民間の指定確認検査機関のずさんな検査の問題
は国会の証人喚問に呼ばれるほど注目を浴びたが個人的にはうやむやに幕引きとなった気がする。
問題を認めて地獄を見るよりは、問題を先延ばしにして上手くソフトランディング出来る事を望むのが日本的な選択。問題を認めると現在のような状態になることが
想像できるのなら問題を先延ばしにするしかない。福島の原発問題はあいまいに上手くやっていると思う。(上手くやっているからこそ、まったく信用しない。)
提出された予定よりも遅れ、対応策も失敗や問題ばかり。事実を言ったらとんでもないことになると思う。
「今回で言えば、日本免震構造協会である。評価した評価機関、認定した国交省も、無罪放免とは言えまい。
日本免震構造協会の幹部は『基本的には技術者の倫理観があるという前提。書類全体でうまく整合性をとり、偽装されると、見抜くのは難しい』と打ち明ける。
また国交省の住宅局建築指導課は『うちはきちんとやっている。ただ免震ゴムに関しては、サンプル調査までしたことはない』と説明する。」
茶番だ。きちんとやっているが偽装は見抜けない。形だけのチェックはきちんとやっていると言う事だろう!
PSC(外国船舶監督官)の検査も同じことが言える。検査をしても明らかな不備が見逃される。
まじめな人が馬鹿を見る社会であることは間違いない。
「(皆さまとの信頼を)自ら崩壊させるような事態に直面し、痛恨の思いを抱いております」――。
3月13日。大阪市で開かれた、東洋ゴム工業の記者会見。山本卓司社長は苦渋の表情で語った。だが、過去の教訓は、生かされていなかった。
東洋ゴムの子会社、東洋ゴム化工品が2004年7月から2015年2月に製造・出荷した免震ゴム(高減衰ゴム)について、計55棟・2052基が、国土交通省の認定する性能評価基準を満たしていない”不適合な製品”だったことが判明した。取得した大臣認定のうち3製品は、技術的根拠がないのに認定を取得するため、”データを改ざん”した書類を国交省に提出していたという悪質さだ。後者については、自主的に認定の取り下げを申請し、国交省から取り消された。
免震ゴムは建築物の基礎部分として使われ、地震の揺れを吸収するために使われる。該当する東洋ゴム化工品製の免震ゴムを採用した建築物は、建築基準法第37条に違反した「違法建築物」の扱いになる。本来なら基準値に対して10%の誤差しか許されないが、今回不適合となった中には、最大で50%も異なる製品があった。
一人の担当者に10年も任せ切り
波紋は大きかった。東洋ゴムは当初、子会社製の免震ゴムが採用された建物について、「所有者の承認がない」ことを理由に、個別名を一切明かしていなかった。が、マスメディアによる報道が先行、長野市第一庁舎や舞鶴医療センター(京都府)などで、実際に使われていることが明らかになった。
消防庁舎に不適合品18基が設置された静岡県御前崎市によると、会見のあった13日夜に初めて知り、自主的に東洋ゴムに連絡したという。16日には東洋ゴム側の関係者が来たが、「具体的な対策を示してほしかったが、あまり内容のあるものではなかった」(御前崎市)。
業を煮やしたのか、3月17日には国交省が55棟のうち、「公共性が高い」と判断した15棟について、名称と所在地を公表した。
なぜこうした不正が起こったのか。浮き彫りになってくるのは、組織としての品質管理体制のずさんさだ。免震ゴムの評価については、10年間以上もたった1人の担当者(製品開発部課長)が担っていたとする。会社側は、専門性の高い仕事のため、担当できる人間が1人しかいなかったと説明。担当者の上司は複数交代したが、内容が専門的で、「この製品を知っている上司ではなく、担当者が恣意的に改ざんしても、非常にわかりづらい体制だった」(山本社長)。
しかも、この問題が発覚したのは、その担当者が交代した2014年2月。新担当者が業務を引き継ぎ、「何かがおかしい」と感じ取った。が、それから2015年2月まで、丸1年間も不適合な製品が納入されていたのだ。これに対して会社側は「過去のデータを追跡したりして、何が問題かを突きとめるのに、1年かかった」と弁明している。
東洋ゴムだけではなく、認定した行政などの責任も重い。
免震ゴムのように建築物に使われる部材は、国交省の大臣認定を受ける必要がある。メーカーが認定を受けるには、国交省の決めた指定性能評価機関による、性能評価書を発行してもらわなければならない。今回で言えば、日本免震構造協会である。評価した評価機関、認定した国交省も、無罪放免とは言えまい。
日本免震構造協会の幹部は「基本的には技術者の倫理観があるという前提。書類全体でうまく整合性をとり、偽装されると、見抜くのは難しい」と打ち明ける。また国交省の住宅局建築指導課は「うちはきちんとやっている。ただ免震ゴムに関しては、サンプル調査までしたことはない」と説明する。
安全性に懸念ある場合のみ、交換する
今回の場合、大臣認定を受けた後でも、製品出荷前の検査の段階で、本来であれば不適合で基準値から外れていたバラつきの値をデータ上で修正し、出荷にこぎ着けたという。認定取得のための意図的なデータ改ざんについても、「推定だが、担当者は、予定通り出荷することを優先させたのではないか」(山本社長)と、納期の遅れを恐れたことからくる行動だった可能性が高い。
耐震・免震構造に詳しい、北村春幸・東京理科大教授は次のように指摘する。
「免震ゴムは加硫部分(圧力・温度・時間)のコントロールが非常に難しい。どうしても製造でバラつきは出てしまうようだ。問題なのは、不良品を出荷しないという品質管理を、メーカーが怠っていたこと」
現状で東洋ゴムとしては「対象物件の損害、事故が発生したという事実は、把握していない」という。今後の対応については、安全性を確認すべく、建設会社や設計会社に構造計算を依頼。確認できれば認定を取り直す。そして「万が一」、安全性に懸念が生じた場合、「他社製代替品も含め、交換などの対応を可及的速やかに進める」としている。
ちなみに免震ゴムは、小さいものでも1基100万円以上。ジャッキアップして取り替えるため、建物自体を取り壊す必要はないが、それでも数トンの重さがあるため、相応の時間と費用、労力がかかる。
2007年にも耐火性能を”偽装”
振り返ると、東洋ゴムは2007年、学校などで使う断熱パネルでも、耐火性能を”偽装”し、大臣認定を不正取得。基準よりも総発熱量が約3倍だったことが発覚した。この時には当時の片岡善雄社長が辞任する事態にまで発展している。
今回、経営責任について山本社長は、「今はすべての物件に対してお詫びし、ご説明することを最優先に進めていくことが責任」と、述べるにとどめた。自身や担当者の社内処分についても公表していない。
一方、国交省は3月17日午後、東洋ゴム化工品の明石工場(兵庫県)に立ち入り調査。会社から任意での残存データ提供を受けている。太田昭宏国交相は「日本の免震技術に対する信頼を失わせるもので許しがたい」と厳しく非難した。
東日本大震災以降、建築物の安全・安心について、消費者の見る目は格段に厳しくなった。当然ながら、現在居住し利用している被害者に与える、心理的影響も大きい。東洋ゴムはいったいどんな形で責任を取るのか。信用回復への道は、とてつもなく険しい。
東洋ゴム工業の山本卓司社長は18日、不良品の免震ゴムの疑惑が発覚した後、1年間も出荷を続けていた問題で、「上層部は社内で(製品には)『問題ない』と報告を受けていた」と釈明した。国土交通省で改善指示を受けた後、報道陣の質問に答えた。
山本社長によると、昨年2月に子会社で疑惑が発覚し、数カ月後に本社での本格調査を開始。その数カ月後に「問題ない」との報告があり、出荷を継続したとしている。不良品が使われた全国55棟のうち12棟は、問題発覚以降に使われていた。山本社長は「報告が虚偽だったのか、さらに詳しく調べている」と話した。
55棟のうち、所有者に問題の説明を終えたのは半数程度にとどまるという。不良品の免震ゴムは1年以内を目標に「原則すべてを交換する」とも述べた。
国交省は18日、東洋ゴム工業に対し、マンション住民らへの丁寧な説明、2007年に耐火偽装問題があったにもかかわらず今回の問題が起きた原因の究明など6項目を指示した。
福島原発がある町民は被害者として扱われていると感じる。しかし、玄海原発廃炉の記事を読むと安易に受け入れてきた地方自治体と住民にも
責任があると思う。原発の事故による影響の恐怖と原発廃炉による関連交付金減額の恐怖。どちらの選択にしてもメリットとデメリットが
存在する。原発廃炉となれば廃炉関係の仕事はあるだろう。簡単に廃炉作業は終了しないので廃炉作業の仕事でも良いのであれば仕事に関して
心配しなくても良い。しかし、仕事を探して引越しする人達も出てくるだろう。福島原発のように放射能汚染により移住するのか、仕事を
求めて移住するのかだけである。簡単に原発への依存度を下げていくことなど出来ない。出来るのであれば、原発を受け入れる必要などなかった
はずだ。表現は悪いが、アルコール中毒やニコチン中毒と同じだ。一度、常習性が普通になると簡単には止められない。
福島原発の地元の人達は人事とは思わず、運が悪かっただけで原発を受け入れた時点でパンドラの箱は開いたと思ったほうが良い。
個々の人々の生活に焦点を当てれば残酷にも見えるが、リスクから目を背けてきたが、事故によりリスクと向き合わされ地獄から逃げれなくなったとも
思える。下記の記事を読むと人間は自分勝手だと思う。それともメディアの操作でそう感じるのだろうか?
九州電力が18日、玄海原発1号機(佐賀県玄海町)の廃炉を正式決定した。原発関連の交付金などに頼ってきた地元住民は「時代の流れ」などと受け止めつつ、地域経済への影響や廃炉に伴う廃棄物の処分などへの不安を抱いている。九電は廃炉表明の一方で、他の原発の早期再稼働を目指す考えも改めて明確にした。
「設備の有効利用の観点から何とか運転延長を考えたが、かなわなかった」。午後7時から佐賀市の九電佐賀支社で開いた記者会見。九電の瓜生(うりう)道明社長は苦渋の表情を浮かべながら廃炉決定に至った理由を説明した。2013年に施行された原発の新規制基準の下では大規模な追加対策工事が必要となり、運転開始から40年になり規模も小さな玄海1号機は投資額が回収できないと判断したという。
ただ地元には廃炉による財政や地域経済への影響を懸念する声が根強い。山口祥義(よしのり)知事は記者団に「原発への依存度を下げていく方向を私も考えている。よく判断してもらった」と評価した上で、「今回の決定によって間違いなくマイナスになる部分が出てくると思う」と語った。
玄海町が国や県から受けた原発関連交付金は昨年度までの39年間で総額331億円余り。今年度当初予算約100億円のうち約67億円が原発関係の歳入だ。1号機関連の交付金減額は再来年度からで、町は約4億円と試算する。
佐賀市内での会見に先立ち、玄海町役場を訪れた瓜生社長に対し、岸本英雄町長は廃炉後の地域経済への不安をのぞかせ「速やかな再稼働と、地域振興についても考えてほしい」と注文。瓜生社長も、13年7月に再稼働に向けた安全審査を原子力規制委員会に申請している玄海3、4号機について「一日も早い再稼働を目指したい」と応じた。
岸本町長はその後の取材に対し「廃炉作業で人がやって来るが、一過性のものでしかない。財政は厳しくなる。行政サービスの質を下げない方法を考えたい」と話した。
玄海町の自営業男性(59)は「廃炉は時代の流れ。ただ原発の仕事に携わる人はたくさんおり、せめて稼働時と変わらぬ雇用が確保できるようにしてほしい」と要望する。
一方、同町の水産加工会社代表、野崎哲雄さん(65)は廃炉に伴う放射性廃棄物の処分や使用済み核燃料の保管などの課題を挙げ「国策で始めた原発なんだから最後の処分まで国がきちんと責任を持ってほしい」と言う。その上で「原発に頼らない産業を考えていかねばならない」と話し、廃炉決定を機に原発依存体質からの脱却を目指すよう訴えた。【鈴木一生、原田哲郎、松尾雅也】
さすが大阪の商売人。ドラマのようだ。
夫の遺産の一部を隠し、相続税約2億3400万円を脱税したとして、大阪国税局が、金属くず運搬会社の嶋袋君枝・取締役(73)(大阪市西淀川区)を相続税法違反容疑で地検に告発したことがわかった。
重加算税を含めた追徴税額は約3億1700万円とみられ、既に修正申告したという。
関係者によると、嶋袋取締役は、金属くず卸売業を営み、2012年2月に亡くなった夫(当時74歳)の遺産を息子2人と相続する際、対象の遺産が計約15億3800万円あったのに、3億円超の現金を自宅の収納庫に隠すなどして、計約4億8400万円を除外して過少に申告した疑い。
立入り検査はパフォーマンスのような気がする。今回の国交相認定のための性能偽装問題は氷山の一角だと思う。 大きな地震がなければこのままでも問題ないと思う。大きな地震がなければ役に立たない装置。 ただ、免震や安全のために免震使用に追加の費用を払った点については補償や対応をするべきだ。
東洋ゴム工業(本社・大阪市)の免震ゴム性能偽装問題で、国土交通省は17日、不良品が使われた全国55棟のうち、庁舎や病院などの公的施設計15棟の名前を公表した。同日午後には兵庫県稲美町にある同社明石工場を立ち入り調査。データ改ざんを確認した。
これまで国交省は、「不安をあおる」などと名前は公表してこなかったが、工事中断などで納入先に動揺が広がったため、方針を転換。15棟については「不特定多数の出入りがある」「東洋ゴム工業が16日までに納入先への説明を終えた」として公表に踏み切った。同社に対しては、今月中に安全性の調査を終えるよう指示したという。
民間の病院4棟も所有者の同意を得られ次第、公表する。ただ、共同住宅など他の36棟は「財産価値が下がる」などの理由から、調査で危険と判断されなければ公表しない方針だ。
17日の立ち入り調査は、国交相認定の基準に満たない、不正に設置された免震ゴムの試験データを得るのが目的。国交省は同日、担当幹部18人による「連絡会議」を省内に設置。調査結果などをふまえ実態解明を急ぐ考えだが、今回の問題での刑事告発は難しいとみており、国交相認定のあり方を含め、再発防止に向けた建築基準法など法令改正などの検討を始めた。
東洋ゴム工業の電話窓口(0120・880・328)には、17日午後6時までにマンション住民らから2755件の問い合わせが集中しているという。(小林誠一)



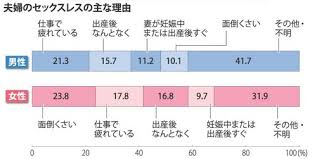





















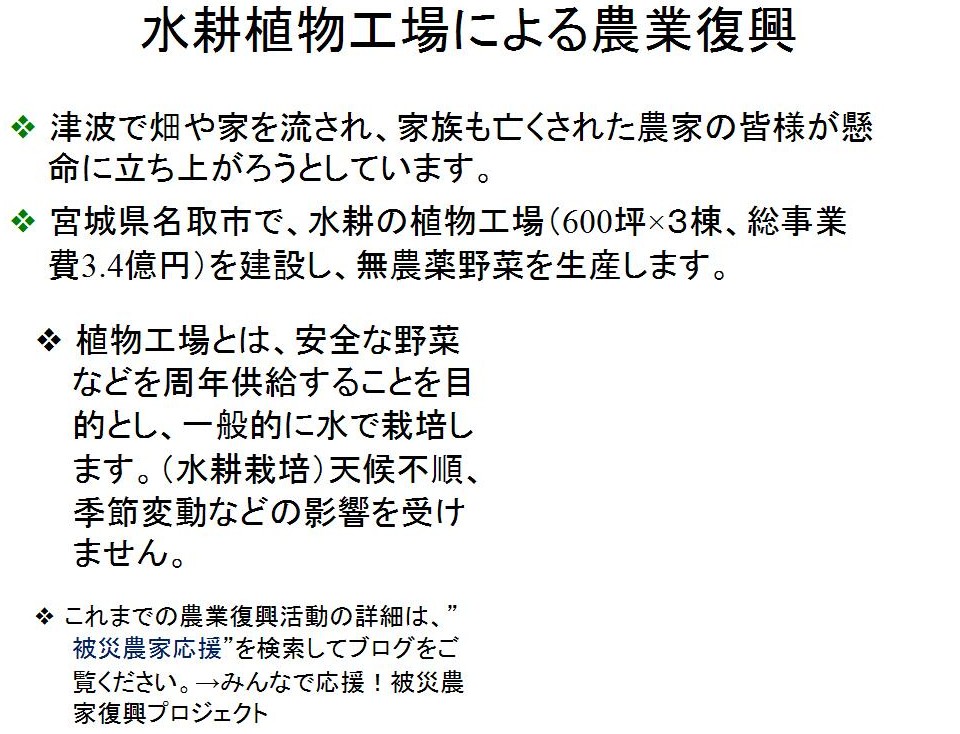

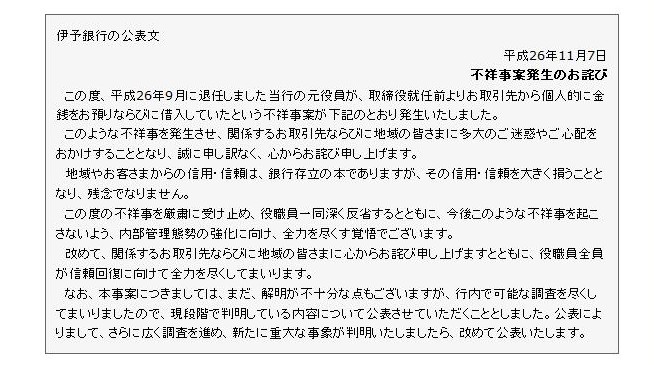

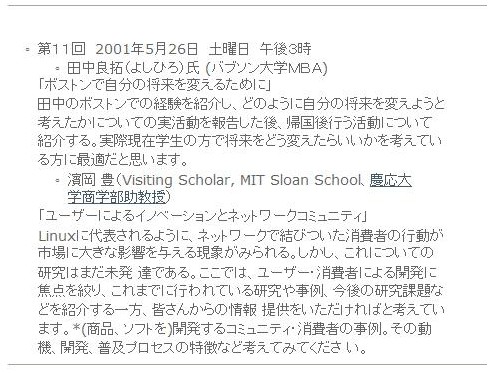
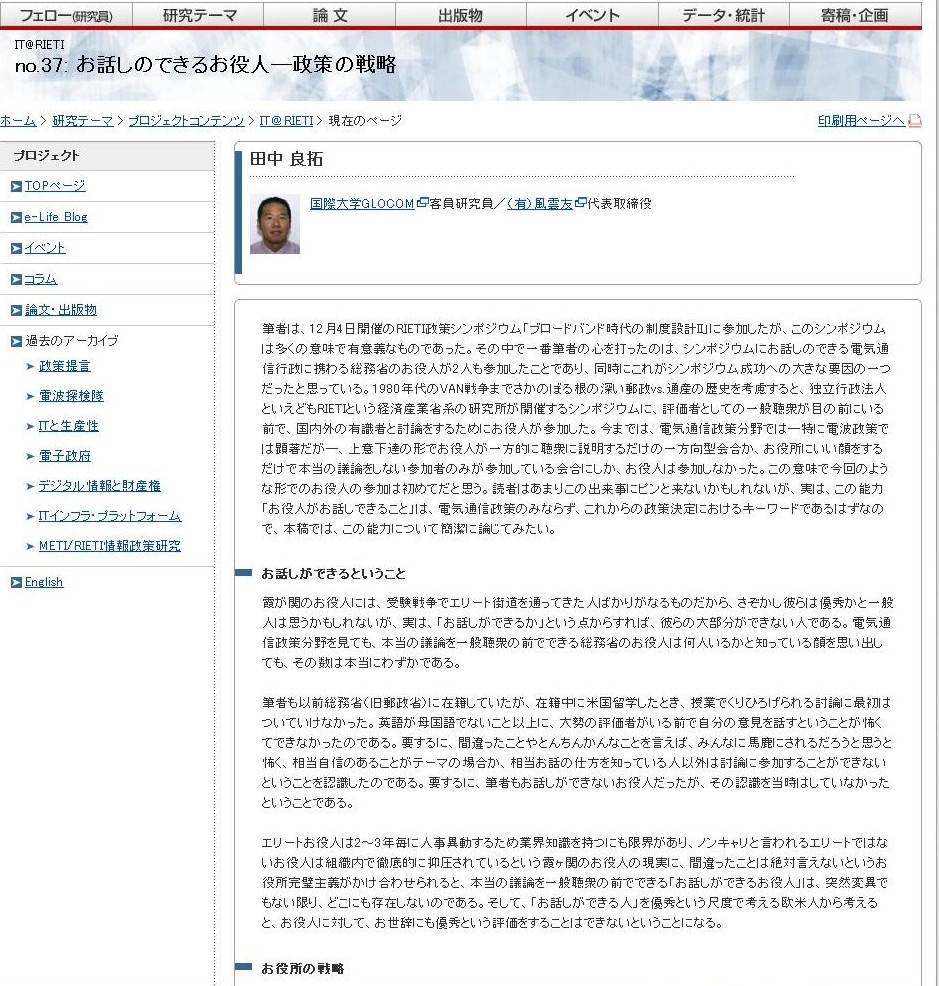
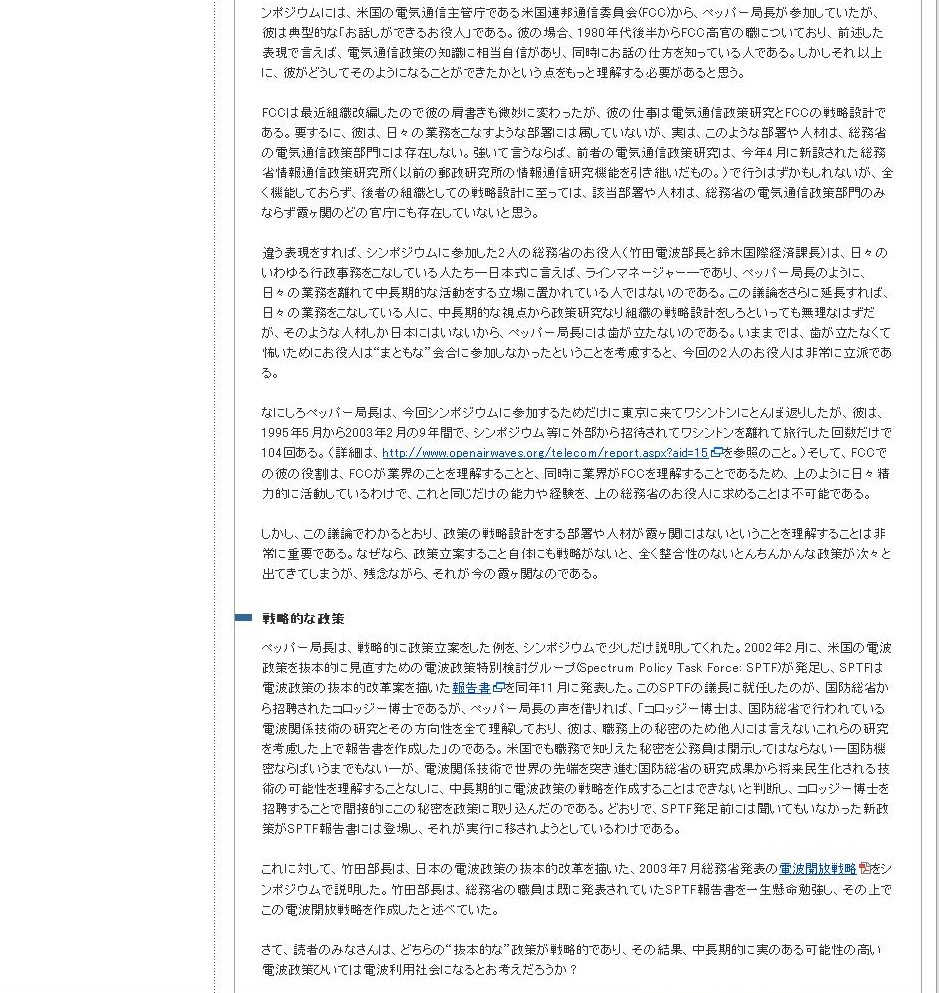
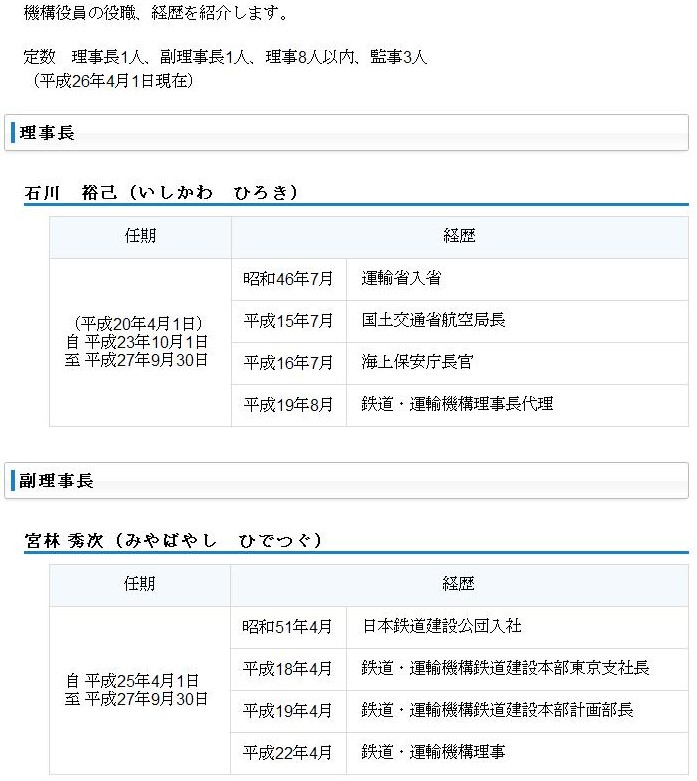





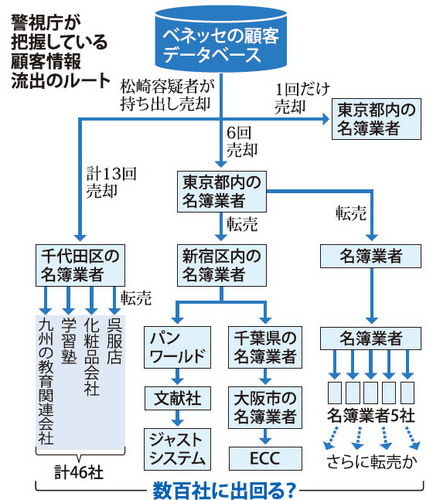
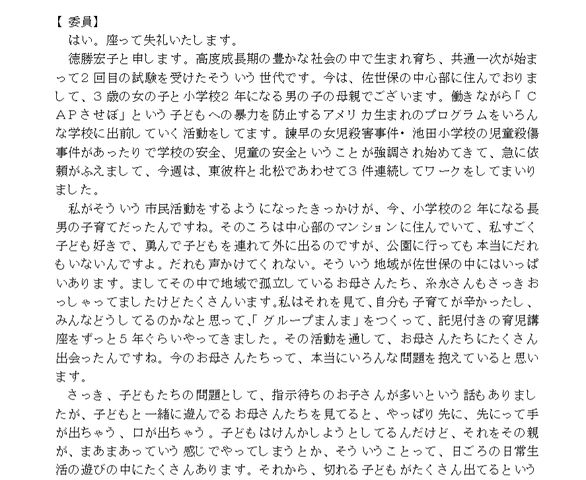






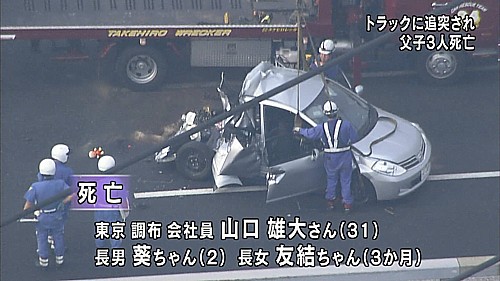
 東京都柔道連盟 福田二朗会長 (astjt_koikeのジオログ)
東京都柔道連盟 福田二朗会長 (astjt_koikeのジオログ)