海運&造船ニュース!
UNDER-PERFORMING SHIPS (1年間に3回以上出港停止を受けた船舶) TOKYO MOUのHP
最近、造船所がニュースで注目を受けているが、注目を浴びると悪い事もニュースになるので諸刃の剣かもしれない。
日本でLNG船の建造は復活するのか?――3500億円の投資と「現場の壁」【IME#4】 01/12/26(Yuto Ito / 船舶・海洋の技術士)
国立造船所構想の全貌:日本造船業の再興に向けた国家戦略】 06/24/25(Yuto Ito / 船舶・海洋の技術士)
上記の記事を読むとLNG船の建造は復活は難しいと思った。既に韓国がマーケットを独占し、中国が後釜を狙っているので、LNG船の船価が良いと言っても難しいと思う。仮に可能だとしても、規模的には、今治造船か、大島造船以外の造船所では難しいと思う。サイズ的には他の造船所でも可能だと思うが、効率を考えるとこの二社しかない。しかし、大島造船はバルクキャリア専門なので、タンカーには手を出さないだろう。
日本の船は高いと言われるが、一部では、品質は良いとか、品質が良い時代のイメージを持っている外国人は多い。なので、付加価値ではなく、効率と競争力を考えて、効果が出そうな造船所を選んで協力、統合、そして投資していくべきだと思う。たぶん、これが最後のチャンスだと思うので、しがらみとか、公平を無視して、効率と競争力を考えて投資を選択するべきだと思う。山のような砂も満遍なく使うと、すぐになくなってしまう。選別は選ばれなかった造船所はかわいそうだと思うけど、人材が減っているので、集約して雇用は保証する場良いと思う。同じような規模で似たような船を作っている造船所は共有部分を増やして効率を上げるしかないと思う。建造能力よりも、効率を上げるべきだと思う。建造能力は景気に左右されるので、効率が良くなければ、不景気な時に生き残れないと思う。世界の造船所を相手に、船価値引きの競争に巻き込まれる。建造能力が上がれば、発注が減っているのに、仕事量は確保しなければならなくなる。この部分がダメージとなると思う。
広島県三原市の造船工場で15日、作業中の男性に金属製パイプが衝突する事故がありました。男性は病院に搬送されましたが、死亡しました。
【写真を見る】重さ200キロのパイプが衝突か 造船工場から「左足付近がえぐれて意識がもうろうとしている」と通報 加圧検査中の男性(54)が死亡
事故があったのは、三原市幸崎能地にある今治造船の広島工場です。
警察と消防によりますと、15日午後5時ごろ「左足付近がえぐれていて意識がもうろうとしている」と、119番通報がありました。呉市の協力会社役員の男性(48)が、市内の病院に運ばれましたが、約1時間後に死亡が確認されました。
工場では当時、溶接したパイプの接続部分に漏れがないか確認する作業がおこなわれていました。その際何らかの原因でパイプが外れ、男性に衝突したということです。パイプは、金属製で長さ約2.3メートル、重さは約200キロでした。
事故当時、近くにほかの作業員もいましたが、他に巻き込まれた人はいないということです。
警察は事故が起きた原因などについて詳しく調べています。
中国放送
自分が気を付けても、他の人がミスしたら終わりの場合はある。中小に比べれば、大手はまだまともに思える。ただ、建造している船が大きいので、ブロックが大きかったり、構造物が大きくなるので高さが高くなる傾向はある。
動いているハッチカバーの乗っている船員を見ると、凄いなと思う。急に揺れたり、強風が吹いて、カーゴホールドに落ちたら終わりだなと思うので。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
ほんまに造船上での死亡事故、重大事故は多すぎる。
製鉄会社なんかより全然多い気がするぞ最近。
年末はJMUで感電事故死があり、年始は今治の造船所で鋼材の下敷きになり重体に、、、
「ご安全に」は造船会社でこそ必要な挨拶ではないだろうか
某造船所勤務してましたが割と自分は大丈夫?と思うのか安全帯していない人良く見かけた!
未だ腰ベルトだけの造船所にも疑問残るが?
長崎労働基準監督署は13日、西海市の「株式会社大島造船所」と係長を、労働安全衛生法違反の疑いで長崎地方検察庁に書類送検しました。
【画像を見る】高さ4m、手すりなしだった疑い
■高さ4メートル超の作業場 墜落防止措置を怠った疑い
書類送検されたのは、西海市大島町にある造船業の「株式会社大島造船所」と係長です。
長崎労基署によりますと2025年3月15日、大島造船所大島工場内で、「計測用マーカー」を船体ブロックに取り付ける作業を行っていた40代の男性社員が、地上から高さ4.25メートルのブロックの端から墜落し、翌日死亡したということです。
■法令で定められた「手すり」など設置せず
労働安全衛生規則では、高さ2メートル以上の場所で作業を行う場合、
手すりや囲いなどの墜落防止設備を設けることが義務付けられています。
しかし、当時現場では墜落防止措置が講じられていなかった疑いが持たれています。
さらに、現場には安全帯をかける綱が設置されていましたが、墜落した社員はその綱に安全帯をかけていなかったとみられるということです。
■「重く受け止めている」会社コメント
大島造船所は、社員が亡くなった事実を重く受け止めているとしており、
安全パトロールにつとめながら再発防止策の検討を進めているとしています。
■後を絶たない墜落事故 労基署は厳正対処の方針
長崎労働基準監督署の管内では、2025年の1年間(1月〜12月末)に休業4日以上の労働災害が592件発生(うち6件が死亡災害)、このうち墜落・転落による災害は98件(うち死亡3件)に上っています。
労基署は「墜落災害は重篤な結果となりやすい」として、今後も法違反により死亡や重傷などの労働災害を発生させた事業者に対しては、司法処分を含め厳正に対処していくとしています。
長崎放送
国内の造船トップで、丸亀市などに事業所がある今治造船(愛媛)は、国内2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU・横浜市)の子会社化の手続きが完了したと発表しました。
2025年6月に子会社化の方針を明らかにし、公正取引委員会も2025年11月に、市場競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断し、今治造船に対して排除措置命令を行わない旨の通知を行い、子会社化を承認していました。
今治造船は鉄鋼大手のJFEホールディングスと、機械メーカーのIHIからJMUの株式を追加取得し、出資比率を60%に引き上げました。
◆今治造船はJMUとすでに資本業務提携など行う
今治造船はJMUと2021年に資本業務提携などを行い、商船事業の国際競争力を高めていました。今後さらに激化すると予想される世界的な競争環境を見据え、さらなる関係強化が必要と判断したということです。
政府支援なども受けながら、国内での生産能力増強や、増産体制を整えていくとしています。
アメリカの海軍の船の建造問題を切っ掛けに造船が注目を浴びている。建造量を増やす事だけを国やメディアは取り上げているが、建造量を増やすと言う事は、世界経済や海運市場に大きく影響を受けやすいと言う事を指摘する記事はほとんどない。
海運や造船関連株価が高騰し、政府が投資すると言うのであれば、将来的に競争力が残り、効率をアップする事を優先に考えるべきだと思う。
これまでの下請け会社との関係は、安く建造するには造船所にとっては理想的だったと思うが、それは造船が花形で多くの優秀な人材と多くの人々が業界に入ってきたから、その影響で人が足りていた、又は、転職するよりは同じ業界で働く方が良いと思っていた人がそれなりにいたと言う事だと思う。今、少子化と今後の就職先を考えた場合、造船や海運が選ばれるのかを考えて、環境を変えたり、協力出来る事や改善できる事を設備投資だけではなく実行する必要があると思う。
「デジタル化などで効率を高める」などメディアは簡単に書いているが、船の設計基本方針や艤装などは経験を積んだ人がいなければ決まらない。素人よりはAIに頼った方が良いと思うが、マーケティングや顧客が違えば、素人から見れば、船は船だろうが、全く同じではない。
船をどこの造船所に発注するにしても海運会社の財務が強いのか、技術が強いのかでも、変わってくる。また、いつ発注するかで、選択肢があるのかも変わってくる。発注する船の種類の違いで、受注してもらえるのか、敬遠されるなどの判断に影響する。
船を長期間、使用すると考えると、選択する時にいろいろと考える事は増える。建造で使用されるメーカーの選択が影響するからだ。将来、修理、部品調達、中古部品にしても、倒産する確率が低いメーカーを選ばないと安いからと言うだけで選ぶと将来、船の運航に影響を与える原因となる。
上記のような事を考えていない海運会社は存在する。しかし、技術部門がしっかりしている海運会社であれば、上記のような事を考える。小型の外航近海船を安いので多くの韓国の会社が中国に発注したが、修理や予備品の手配で大きな問題が発生する事が運航後に判明して、判断基準を変更した例がある。
船は建造契約後から引き渡しまで時間がかかる。そして、金融と同じように、儲かるからと多くの船主や投資会社が似たような船を発注すると、需要と供給で儲けが下がる、又は赤字になるリスクがある。そして世界経済や特定の理由で需要と供給が変化する。単純に建造量を増やすとまともに影響を受ける事になる。
数値目標だけに拘ると失敗すると思う。お金をばらまけば直ぐに蒸発する。お金を投資する前に方針や基準を決めてどこにどのように投資するのか、決める必要はあると思う。合弁や吸収合併した方が良いケースではそうした方が良いし、体質的に合弁や吸収合併すれば混乱する場合は、効率が良い方を選ぶなどメリハリは必要だと思う。
三井造船は日本から消滅した。この理由をしっかりと理解して、今回の注目と投資で日本の造船業界が長く生き残れるような選択をするべきだと思う。造船業は3Kと言われてきた。この部分から身を背けずに改革していく必要があると思う。
日本経済にとって本格的な好循環の実現に向けた正念場の年が明けた。昨年は株価や賃金が上昇し、日銀が政策金利を引き上げる環境も整った。その勢いを産業の成長に結び付けることが重要だ。地域経済としては国の政策を地元産業の発展に生かしたい。
昨秋発足した高市早苗政権は「強い経済」を掲げ、日本成長戦略本部を設けた。官民の連携で重点投資する17の戦略分野を定めた。「人工知能(AI)・半導体」に次ぐ2番目に挙げたのが造船だ。
世界有数の集積
瀬戸内は天然の良港が多く、海運業が盛んだったことから造船業が発展した。部品の製造を含め、その産業集積は今も世界有数といわれる。
造船業の盛衰は国の政策に左右されやすい。1990年代まで日本の建造量は世界一だったが、国が支援を強めた中国と韓国に抜かれた。受注が激減する中、瀬戸内では造船所の撤退と再編が相次いだ。国内最大手の今治造船(愛媛県今治市)や常石グループ(福山市)を中心に、厳しい時代を乗り越えてきた。
国が今回策定した「造船業再生ロードマップ」は、現在約900万総トンの年間建造量を2035年に1800万総トンへと倍増させる目標を掲げる。世界シェアを2割程度に引き上げる構想で、反転攻勢を期するものだ。
35年までに官民で1兆円規模の投資を想定する。具体的な国の支援内容は、造船会社の資金調達を後押しする金融支援に加え、先進的な機器の導入や先端技術の開発、環境対応などが挙がっている。
地場銀行も支援
政府の方針の背景には、造船業が衰退した米国からの要請がある。中国に対抗するため協力を強めたい考えだろう。国策となったことは、地域の事業者にとって追い風に違いない。できる限り活用し、各社の事業基盤を強化したい。地域の競争力を高める機会とするべきだ。
近年、広島銀行(広島市中区)や山口銀行(下関市)など地場銀行も造船・海運分野の支援を強めている。金融、保険、港湾、商社、研究機関などが連携して技術革新を生み出す海事クラスター(集積)として、瀬戸内の存在感が高まるといい。
瀬戸内のもう一つの中核産業である自動車は試練が続く。昨年はトランプ米大統領の関税政策に振り回された。先行きの不透明感が増し、為替の変動も激しかった。政治に自由貿易が妨げられる恐れは今年も変わりそうにない。さまざまな展開を想定しつつ、電動化や自動運転など新たな技術に対応することが求められる。
課題は人手不足
化学や鉄鋼業を含め、瀬戸内工業地域は重厚長大型で知られる。最大の課題は人手不足だ。現場の作業者に加え、次の成長を切り開く人材をいかに確保、育成していくかが問われる。デジタル化などで効率を高めることが重要だ。同時に事業の発展と賃金上昇のサイクルを確立し、地域に人材が集まるようにしたい。
バブル経済の崩壊から約35年。「日本はもはや先進国ではない」との声も聞かれる。「失われた30年」を40年にしてはならない。世界中が競争を繰り広げる中、国民の生活水準を維持するためには一定の経済成長は欠かせない。
ただ「強い経済」の目的は、あくまで国民の幸福であるべきだ。政府は、成長を追求する中で広がる格差を直視し、経済弱者への配慮を忘れないようにしてほしい。
日本の造船業の復権に向け、建造能力の増強が計画されている。四方を海に囲まれ、貿易量の99%超を海運が担う日本にとって、造船業は経済安全保障の観点から極めて重要な産業である。瀬戸内エリアの関連企業が培ってきた技術力や人材の基盤を生かし、地域経済の活性化にもつなげたい。
日本の造船業は1990年代まで世界シェアの4割前後を占め、トップの座にあった。しかし、2000年代以降は中国・韓国勢が政府支援の下で設備投資を進め、建造能力で日本を大きく上回るようになった。価格面でも太刀打ちするのが難しく、日本の24年の受注量シェアは、わずか8%にまで落ち込んだ。競争力強化のため、分社化や資本提携といった業界再編を余儀なくされている。
政府は先月、35年をめどに年間建造量を現在のおよそ2倍となる約1800万総トンに引き上げる目標を打ち出した。世界シェアは2割程度を目指す。これに呼応する形で造船メーカー各社も、総額3500億円の設備投資を計画している。大型クレーンの整備やロボットの導入などで生産効率を高めるという。反転攻勢に向けた転機としたい。
造船業の復権が求められる理由の一つは、経済安保にある。海運は企業活動や市民生活を支える重要なインフラであり、緊急時には救援物資などの輸送を担う生命線となる。造船業が衰退した米国も中国メーカーへの過度な依存に危機感を強め、28日には日米両政府が造船能力拡大に向けた協力覚書を交わした。国際物流網を安定的に維持するためには、造船業の強化は欠かせない。
国際的な気候変動対策も造船業再生の後押しとなる。国連の国際海事機関(IMO)は50年までに海運分野で温室効果ガスの排出をゼロにする目標を掲げており、水素やアンモニアを燃料とする次世代船の需要拡大が見込まれる。日本メーカーはこうした分野で技術的な優位性を発揮できる。世界的に船舶の入れ替え需要が集中するこの好機を逃すべきでない。
瀬戸内エリアには、三井E&Sやツネイシホールディングス、今治造船といった造船関連の拠点が多数立地しており、部品産業の裾野も広い。玉野市では製造品出荷額の約6割を造船などの輸送用機械が占めており、尾道、三原、丸亀市も3割前後に上る。高度な技術を蓄積してきたこれらの地域こそ、造船業の復権をけん引する中核拠点になり得るだろう。
政府は各社による設備投資や研究開発の支援に力を入れてほしい。製造現場の人手不足への対応や、先進的な船舶設計を担う人材育成も求められる。日本には大手海運会社があり、現場の声を次世代船の開発に反映できる強みがある。官民が結束して「造船立国」の再生を目指してもらいたい。
HD現代重工業「AI造船所」の記事に影響されているのか知らないが、宇宙戦艦ヤマトの自動戦艦工場のようにはいかないと思う。
大型船で同型船の建造に特化した造船所はメリットがあるかもしれないが、該当しない造船所にはメリットがあまりないと思う。
アナログ設備が多い造船所は該当しないと思うし、規模の小さい造船所も該当しないと思う。
設計からブロックの溶接までをグループで共有できる造船所は将来を考えて投資は出来ると思うが、該当しない造船所はお金を捨てるだけのように思う。
本当にAIロボットを使う造船所が出てきたら、日本の造船所は二極化すると思う。ハイテク設備の造船所とアナログと部分的にデジタルの造船所。
一部の造船所を除いて、投資に見合う結果は期待出来ないと思う。発想は素晴らしいけど、結局は、結果が全て。
船と言っても、ヨーロッパスタイルの船、日本スタイルの船、韓国スタイルの船、そして中国スタイルの船があるし、船主や顧客のニーズも違う。どのようなマーケティングをするのか、どのような設計をするのか、方針次第で違いは存在する。
政府は2026年から国内造船業の省人化に必要なロボット開発の支援を始める。鋼板の曲げ加工や溶接、塗装といった熟練技術者の「技」を人工知能(AI)に学習させる。民間事業者に研究費を委託する形で開発を後押しする。
1月中に具体案をまとめ、2月にも事業者を公募する。1年ほどで造船業の現場での実用化を目指す。内閣府と国土交通省が海上技術安全研究所を介して事業者に研究委託費を提…
* この記事はAIによって翻訳されました。
Park Seungju
HD現代は造船所自体の運営方式を高度化する段階へと戦略の中心を移している。鍵となるのは「未来先端造船所(FOS)」の構築だ。単に自動化設備を増やすだけでなく、設計・生産・運営の全過程をデータと人工知能(AI)でつなぎ、造船所の運営構造そのものを再編する構想である。
FOSは三つの段階で構成される。すでに構築を終えた第1段階は、工程や設備、作業状況をデータでリアルタイムに把握できる「見える造船所」だ。生産計画や作業指示、設備稼働、安全管理まで主要情報が一つのシステムに統合され、現場の流れを即座に把握できる。
第2段階では工程間のデータを連携し、予測する。AIや機械学習を通じて人員・資材・設備配置に関する意思決定をシステムが支援する構造となり、造船所運営の変動性や不確実性を低減することに焦点が置かれている。HD現代は2030年までに最終段階である第3段階「知能型自律運営造船所」を完成させ、生産性30%向上、工期30%短縮を目指している。
造船は最も伝統的な製造業であると同時に、産業への波及効果が大きい基幹産業だ。工程が長く複雑なだけに、生産性や品質、納期を同時に管理する運営体制の重要性も高い。HD現代重工業の関係者は「造船所の競争力は、どれだけ予測可能かつ安定的に運営できるかにかかっている」とし、「FOSは生産性と納期、品質を同時に管理するための造船所運営体制を構築する過程だ」と説明した。
AIはすでに現場に浸透している。鋼板切断工程には資材ロスを最小化するためのAIベースの最適化技術が適用されている。熟練工の作業パターンを学習し、切断配置を自動で提案する仕組みだ。液化天然ガス(LNG)・液化石油ガス(LPG)貨物タンクの製作や設計レビュー工程でも、繰り返し計算や検証作業にAIが投入され、業務負担の軽減に貢献している。船舶契約段階で発生する数百~数千件の船主要望への対応も、データベースや言語モデルを活用し処理速度を高めている。
デジタル造船所の範囲はソフトウェアにとどまらない。HD現代は長期的に溶接・組立・搬送など物理的作業を担う「フィジカルAI」の導入まで視野に入れている。現在は一部工程でロボットや自動化設備が導入されている段階だが、今後は造船所環境に適した次世代ロボット技術へと拡大していく計画だ。
造船所全体を仮想空間に再現するデジタルツイン技術も高度化している。仮想環境で工程を検証した後、実際の生産に反映することで、大規模プロジェクトの試行錯誤やリスクを低減することが目的だ。
脱炭素・ゼロエミッション船もHD現代が先行を狙うもう一つの軸だ。その代わりにアンモニア、メタノール、電気推進、水素、小型モジュール原発(SMR)など特定の解決策に集中するのではなく、多様な選択肢を並行する戦略を取っている。まだ市場の方向性が定まっていない中、造船会社は船主の選択変化に即応できる必要があるとの判断からだ。アンモニア燃料船はすでに実際の建造と検証段階に入り、メタノール燃料船や電気推進技術も実証段階へと進んでいる。水素とSMRは中長期課題として技術的な準備を進めている。
30日午後、呉市の造船会社で
漏電の検査をしていた作業員の男性(38)が感電し、死亡しました。
警察によりますと30日午後6時10分ごろ、
呉市昭和町の造船会社「ジャパンマリンユナイテッド」で、
呉市広白石の会社員・下花直貴さん(38)が、感電する事故がありました。
ドックポンプ所で、漏電の検査中に何らかの理由で変圧器の回路に接触して、
感電したとみられています。
下花さんは、病院に搬送されましたが、約2時間半後に死亡が確認されました。
警察は、感電した瞬間を見ていた作業員などに話を聞くなどして
事故の原因を詳しく調べています。
広島ニュースTSS
今治造船グループは規模が大きくなったから、グループ内でやれば良いと思うし、規模が大きくなったから可能だろう。
ロボットとか、機械とか言うけど、基本設計から、データーを共有して行わないと効率よく生産まで持って行けないと思う。データーの共有となると下請けを使わないようにしないと情報が漏れる。しかし下請けを使わないとコストがアップする。この板挟みをどう解決するか考えないとダメだと思う。
データーの共有が可能になったとしても、ソフトの購入、アップグレードの費用、そして人材がソフトを使いこなせるようになるまでのコストや時間を考えると下請けにメリットはない。今治造船グループの専属下請けであれば違うのかもしれないが、仕事が切れないように仕事があるのか疑問。同型船建造になったら、自動化の部分が増えると言う事は、連続建造が終わるまでは、仕事がない可能性はあるわけだ。それなりの能力があるのなら、別の会社で働く方が良いと思える。
いろいろな造船所が設計で違うソフトを使えば、下請けの負担は増える。それに見合った報酬があれば良いが、ないのなら造船に関わるメリットはあまりないと思う。大学では造船や設計についてあまり教えていないし、教えられる人はほとんどいないと思う。船の事を理解し、ソフトを使いこなし、船の仕様の事まで理解できるのであれば、造船よりも海運会社で働く方が高給で将来が安定していると思う。
これまでのやり方を変えて、給料や支払金額を上げないと人は来ないと思う。規模が小さい造船所で船台のキャパが似ていれば、設計部門を統合し、設計や工作基準をどちらかの造船所に合わせるとかしないとこれから人材を育てるのでは遅いと思う。
造船所の経営方針や組織の体質があまりにも違えば、協力するメリットは理解できても、実際に協力する段階でいろいろな問題が起きて生産性は一時的に落ちるように思える。韓国や中国と競いながら、改善や改革は出来るのだろうか?
関係ないからどうでも良いけど、造船関連株の高騰は驚いた。まあ、造船で苦労した人達は子供に造船関連に行けとは言わないと思う。メディアの記者は何も知らないのだろうが、いろいろあったし、技術者不足は今始まった事ではないと思う。
アメリカやイギリスの造船所が自国の海軍の船を建造できないほど競争力や能力が低下しているから、造船は重要と考え始めたのではないかと思う。韓国も以前に比べれば造船は衰退していると思う。そして、不況の時代に、韓国人も日本人も中国に行って造船技術を教えすぎた結果、中国の造船の成長を助けたと思う。韓国のメディアは韓国人が中国に行って、建造技術を教えすぎたと記事として書いていた。外国人の監督の中には、韓国建造の船の質が落ちたと言う人が増えているので、日本のメディアが言うほど、韓国造船業界の競争力が高くない可能性はあると思う。日本に比べたら、船価が安いと言うだけだと思う。船は引き取って、運航してみないと、評価できない。船を運航して問題があると、船価が安くても選択が失敗だったと判断する監督や海運会社は存在する。
中国建造の大型船の溶接は良くなったように感じる。聞いたら、機械で溶接するからだと言っていた。中国の造船所で機械による溶接が増えた。日本の造船所だと拡張できないから、大型のブロックと機械溶接は難しいのではないのか?比較的新しい造船所は大きなブロックを搬送できるようになっているが、古い造船所はそんな事は出来ないだろう。レイアウトが悪すぎる。造船所を選んで投資するしかないように思える。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
デフレが長引き人と企業が資産を溜め込みすぎた。誰かがリスクをとってお金を使わないと、このままだと人と企業が育たず、消費すればするほど中国の技術者が育つという構造の中で日本が没落してしまう。団塊の世代が抜け現場は外国人技能実習生依存。ここからどう巻き返すか。一時的に政府債務が増えるのはしょうがない。今リスクをとって技術を継承していくことが、未来の子供たちへの責任を果たすことになる。国内の設備投資が活発になれば建設や運輸などにもお金が回るようになる。これらの仕事も儲かる仕事になれば、サービス業が縮小し若者が農業や建設、ものづくりを仕事として選ぶようになる。そしたら自然と少子化も改善する。お金は血液と同じ。全身を巡らせないと健康体を保てない。国力はGDPではなく、自分でコントロールできる範囲が広いかどうかで決まる。単に消費を増やすだけでは中国の成長を促すだけだ。脱中国、脱中抜き、脱中学受験が大事
造船業の復活とか言ってるけど、今の日本の造船企業の注文残高は3年先まで埋まっている状況で、新規のオーダーも断らざるを得ない。
じゃあ造船所をもっと増やせばいいと言う話になるけど、人材が確保できないんだよね。
今でも中国人やフィリピン人などの外国人の技能労働者に頼ってる部分もあるからね。
遅い遅すぎる。そもそも国家が主導して業界を再編しそれに伴って人減らしを進めた。造船って造船会社本体よりも協力会社や下請けが主に担っているがその協力会社や下請けが廃業や縮小している。低賃金で働いてきた職人や1人親方も殆ど引退している。外国人労働者も腕が上がったら中国や韓国、アメリカに引き抜かれるに決まってる。ラピタスの半導体も国家主導だが失敗する。
何故衰退したのかを考えなければ意味はない。1兆あろうともね。金の問題にするから発展しない。高市は死の商人で何とかするとかほざくが、戦争あっての死の商人。日本愚民は戦争を望んでいると攻撃されても反論できないだろうさ。勿論裏社会も関わってくるしな。武器関係はよ。
日本造船工業会(造工会)の檜垣幸人会長(今治造船〈愛媛県今治市〉社長、写真)は18日の会見で、政府が国内造船業の再興に向け官民で1兆円規模の投資を呼び込む基金創設を決めたことなどを念頭に「最後のチャンスだ」と強調した。2025年を「造船業界として追い風となる動きが強くなった1年だった」と総括。政府支援を活用しつつ大規模な設備投資を行い「大幅な生産性向上を図り、35年の建造量倍増に積極的に取り組んでいく」とした。
川重が8年ぶり新造船受注、高速水中翼船の性能
政府支援を活用した設備投資の対象は、人手不足などへの対応と建造量の拡大に並行して取り組むため「優先順位としてはロボットや機械になると思う」との見方を示した。
また、国際海事機関(IMO)の温室効果ガス(GHG)排出量規制の正式採択が1年延期されたことにも言及。50年ごろまでのGHG排出ゼロの目標は変わっていないことを踏まえ「新燃料などの開発・普及に継続して取り組む」と語った。
海上自衛隊の潜水艦のエンジンの燃費性能に関する検査データを改ざんしていたとして、防衛省は近く、川崎重工業を指名停止処分にする方向で調整していることが関係者への取材でわかった。停止期間は数カ月間で検討している。
【写真】川崎重工業の神戸工場=神戸市中央区
川重は昨年8月、船舶用エンジンの燃費データを改ざんしていたと発表。川重などによると、外部の弁護士でつくる特別調査委員会が関連した不正がないか調べたところ、2021年までに製造された潜水艦エンジンの一部型式でも、燃費性能に関わる検査データの改ざんをしていた疑いが判明した。安全性や運用面での影響はないとしている。
関係者によると、不正は少なくとも20年ほど前から続いていた疑いがある。防衛省は悪質性が高いと判断し、所管する防衛関連の入札などへの参加をできなくする指名停止とする方向で調整。川重側の特別調査委も年内に、不正の全容について最終報告をまとめる方向で調整中という。
海自は現在、潜水艦を25隻保有し、川重と三菱重工業がほぼ半分ずつ建造している。川重はほかにも哨戒機や輸送ヘリなどを製造。防衛装備庁の24年度中央調達実績では、契約額は全体2位の6383億円にのぼる。
川重をめぐっては、潜水艦の修理に関し、防衛予算を使って多額の裏金を捻出していた問題が発覚し、防衛省は特別防衛監察を実施した。中谷元・前防衛相は8月の閣議後会見で「(川重の)不祥事が相次いでおり、たいへん遺憾に思う」と述べていた。(矢島大輔、佐藤瑞季)
海上自衛隊の潜水艦用ディーゼルエンジンの燃費性能データを改ざんしたとして、防衛省は、製造元の川崎重工業を「指名停止」処分とする方向で最終調整に入った。関係者への取材で判明した。契約不履行が横行していたとの判断とみられ、指名停止期間は2・5カ月を軸に検討し、違約金の算出も進めている模様だ。
【表でわかる】川崎重工の不正を巡る経過
この問題は、川重が商船用エンジンの検査でデータを書き換えていた不正を調査する過程で発覚し、「潜水艦でも不正が疑われる」と防衛省に申告した。川重は外部の弁護士らの特別調査委員会で実態解明を進めており、年内にも最終報告を公表する見通しとなっている。
防衛省によると、海自は25隻の潜水艦を保有し、川重と三菱重工業がほぼ半数ずつを建造。動力源となる蓄電池の充電などに使うディーゼルエンジンについては三菱重工製の潜水艦も含めて川重が製造し、「おやしお型」「そうりゅう型」「たいげい型」といった現役艦に搭載されている。
エンジンは組み立て後、陸上で燃料消費量などの各種データを計測する。関係者によると、川重は防衛省側の求める基準に適合するように装ったり、計測値のばらつきを小さく見せたりするため虚偽の数値を報告。遅くとも2002年ごろから約20年間、改ざんを繰り返したという。
防衛省は、海洋での試運転では基準を満たしているとの報告を川重から受け確認したといい、「潜水艦の安全性や性能に影響を及ぼすものではない」(中谷元・前防衛相)としている。
潜水艦や航空機、艦艇、ミサイルなどの主要装備品を取得する防衛装備庁の中央調達で川重の契約実績は長年上位に位置し、24年度は6383億円と三菱重工に次ぐ2位だった。防衛省が指名停止処分とした場合には通常、入札や公募などに参加させないため、政府が掲げる「防衛力の抜本的強化」に影響が生じるのか注目される。
川重を巡っては、防衛省は海自潜水艦の修理契約に絡んで約17億円の裏金を捻出し乗組員らに不適切な物品提供をしていた問題で、24年12月以降、2度の「厳重注意」とした。ただ、この処分に際し省内には「甘過ぎるのでは」と疑問視する声もあった。また、川重は13年にも陸上自衛隊のヘリコプター開発を巡る官製談合事件で、防衛省から2カ月の指名停止処分を受けた。【松浦吉剛、竹内望】
【シドニー時事】オーストラリア政府は12日、韓国造船大手ハンファが豪同業大手オースタルに対する出資比率を約2割に引き上げることを条件付きで承認した。
オースタルは、日本の海上自衛隊護衛艦「もがみ」の改良型が選定された次期海軍フリゲート艦の建造を受注する可能性があり、その場合、機密情報の保護が課題となる。
ハンファはオースタルへの出資比率を従来の9.9%から19.9%に引き上げることが認められた。豪政府は条件として、(1)19.9%を超える出資は不可(2)機密情報へのアクセスや保存を制限(3)ハンファがオースタルの取締役に指名する人物に関する厳格な基準の設定―を挙げた。
11隻を導入するフリゲート艦計画では、最初の3隻を日本で、残り8隻を豪国内でそれぞれ建造する予定。オースタルは地元建造分の受注先として有力視される。機密情報の制限などの条件は同計画をにらんだものとみられ、チャーマーズ財務相は「安全保障上の課題を全て考慮して判断した」と説明した。
【シドニー共同】オーストラリア政府は、韓国造船大手がオーストラリア造船大手オースタルへの出資比率を引き上げることを認めると発表。オースタルは、日本と共同開発・生産を目指す豪海軍の新型艦建造を担う有力候補。
韓国の造船所が目先の利益のためなのか、それとも、今、金になるのなら将来、自分達の首を絞める事になるかもしれないけど、情報や技術をお金にしたいのか知らないが、韓国がいろいろな国の造船産業の支援に動いている。将来、中国、韓国、日本だけでなく、インドやベトナムの復活などリスクが存在する。日本政府は建造能力を増やすよりも生き残れる投資に注力するべきだと思う。
Paul Bartlett, Correspondent
HD Hyundai plans to invest up to $2bn in the development of a new shipyard in India, according to reports, as the company signed a partnership with local government on shipyard development and operation.
The South Korean chaebol’s partnership with Tamil Nadu state to build a new shipyard is a major step forward in the country’s drive to become a top-10 shipbuilding nation by 2030, and to reach the top five by 2047.
The Indian Government’s Maritime Amrit Kaal Vision 2047 requires not only expansion of existing facilities such as Cochin Shipyard, which has just won a four-ship order from Svitzer for electric tugs, but also entirely new shipyards built from scratch.
However, the investment is also part of a much broader South Korean strategy to expand across a range of industrial sectors in what is now the world’s most populous country. Major Korean companies including Hyundai Motor and Samsung Electronics have already established major facilities in the Thoothukudi region of Tamil Nadu.
The state is one of five regions that have been shortlisted for new shipyard construction. They include Gujarat and Andhra Pradesh. But HD Hyundai’s commitment to Tamil Nadu state could prove to be a key strategic winner. The company has highlighted the Thoothukudi region’s climatic conditions, similar to its Ulsan headquarters in Korea, and its proximity to other maritime developments nearby.
The shipbuilding deal follows the signing of a Memorandum of Understanding by HD Hyundai and Indian state enterprise, Bharat Earth Movers Limited, earlier this month. The companies plan to break what is seen as the monopoly held by China’s ZMPC group in the provision of heavy cranes for Indian port facilities, industrial sectors, and shipyards.
Earlier this year, HD Hyundai signed another MoU with Cochin Shipyard. The two parties plan to collaborate on ship design, supply chain management, labour resources and manufacturing efficiency.
Nevertheless, for India to break into the top ten of shipbuilding nations within four years presents a huge challenge. Different sources currently pitch the country at between sixteenth and twenty-second in the global shipbuilding league, holding a world share of well below 1%.
Yet analysts point to the surging scale of international investment in Indian infrastructure. Examples include Maersk’s $2bn commitment to expand APM Terminals in Pipavav; DP World’s $5bn to develop sustainable coastal shipping, shipbuilding and ship repair facilities; and MSC’s plans to transfer 12 ships to the Indian registry.
News provided by HD Hyundai
Signed an exclusive business agreement with the Tamil Nadu state government to promote the establishment of a new shipyard
Tamil Nadu state assessed as the most optimal site with climate and rainfall similar to Ulsan, and is expected to have additional large-scale investments in port facilities
Will also be partnering with an Indian state-owned enterprise for port crane business to deliver goliath and jib cranes to local shipyards
"India is a market with strong growth potential, and we hope to expand cooperation and develop it into a new growth engine"
SEOUL, South Korea, Dec. 7, 2025 /PRNewswire/ -- HD Hyundai has initiated a review on the establishment of a new shipyard in India.
HD Hyundai announced on Sunday, December 7, that it signed a strategic and comprehensive partnership with the Tamil Nadu state government regarding the establishment of a new shipyard in India. The ceremony was held recently in Madurai, southern India, with the attendance of Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, State Industries Minister T.R.B. Rajaa, and Head of Corporate Planning at HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, Choi Hannae.
The Indian government is strategically pursuing the "Maritime Amrit Kaal Vision 2047" in an effort to become one of the world's top five shipbuilding and shipping nations. To achieve this goal, the government is actively reviewing not only the expansion of existing shipyards but also the establishment of new facilities.
In practice, the Indian government has shortlisted five states—including Tamil Nadu, Gujarat, and Andhra Pradesh—as candidate sites for the construction of a new shipyard and is currently in the process of identifying the most suitable location. Seeking to revitalize the local economy, the Tamil Nadu state government has made the establishment of a shipyard its top priority and has expanded efforts to provide incentives and subsidies, enhance infrastructure, and secure skilled talent. As a result, the state has ultimately selected HD Hyundai as its project partner for the establishment of the new shipyard.
In particular, the Thoothukudi region of Tamil Nadu—cited as one of the candidate sites for the new shipyard—is regarded as an optimal location, with temperature and rainfall conditions similar to those of Ulsan, Korea, where HD Hyundai Heavy Industries is located. It already hosts major Korean companies such as Hyundai Motor Company and Samsung Electronics, and large-scale investments are planned for nearby port facilities, further strengthening expectations for future business expansion.
Earlier this month, HD Hyundai also signed a Memorandum of Understanding on the collaboration for maritime & port crane development in India with BEML (Bharat Earth Movers Limited), a state-owned enterprise under the Indian Ministry of Defence, in Bengaluru, southern India. Headquartered in Bengaluru, BEML operates in various sectors including defense and aerospace equipment, mining and construction equipment, and railway and metro vehicles. The company also has multiple manufacturing bases in southern India, including Bengaluru and Kolar.
Through this agreement, HD Hyundai plans to strengthen collaboration with BEML across the entire crane manufacturing process—including design, production, and quality assurance—aiming to gradually build port crane manufacturing capabilities within India. Looking ahead, the company also plans to expand its business by supplying goliath and jib cranes to local shipyards in India.
In relation to this, HD Hyundai Samho, a shipbuilding affiliate of HD Hyundai, successfully delivered a 600-ton Goliath crane to Cochin Shipyard, India's largest state-owned shipbuilder, in February of this year. In addition, in August, HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, the intermediary holding company for the shipbuilding division, announced it would acquire HD Hyundai Eco Vina from Doosan Enerbility to further reinforce HD Hyundai's ongoing expansion in the crane business.
An HD Hyundai official said, "India is a market with strong growth potential, backed by the government's robust commitment to fostering the shipbuilding industry," adding, "We will continue to expand cooperation with India in the shipbuilding and offshore sectors and develop it into a new growth engine."
Earlier in July this year, HD Hyundai signed an MOU with Cochin Shipyard to promote cooperation in a wide range of areas, including design and procurement support, productivity enhancement, and human capital development. More recently, the scope of this partnership has been expanded to include naval vessel projects, further strengthening HD Hyundai's presence in India.
SOURCE HD Hyundai
造船と言っても、儲かるような造船所、又は、儲かるような産業に考えないと税金を溝に捨てるようになると言う事が、韓国の例を見ればわかる。
下手をすればどこかの造船所が倒産するまで低船価競争に巻き込まれるリスクがある。日本が建造能力を増やせば、低船価競争の影響を受けるリスクが高まる。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
「組織縮小と統合で赤字減らす…韓国造船大手3社」
幾ら受注を誇っても結局は「儲かってなんぼ」。受注が増えるだけ、資材高騰の煽りを受け、赤字は膨らむ。
米国に投資する余裕は本当にあるのだろうか。
>組織縮小と統合で赤字減らす…
これが、まさかの赤字だったようです。
過去の記事では韓国の造船業は…好調でシェアを伸ばしつつ、拡大路線だったような。
韓国の造船業界が収益性中心に体質改善にスピードを出している。HD現代重工業、サムスン重工業、ハンファオーシャンの韓国造船ビッグスリーは最近、海洋プラント、風力、陸上設備など非主力部門を整備し組織を縮小再編中だ。コロナ禍後の受注回復傾向にもかかわらず、収益性の裏付けがなく本格的な構造調整で選択と集中に向かう様相だ。
造船業界によると、ハンファオーシャンは先月海洋設備と陸上プラント組織を統合してエネルギープラント事業部門(EPU)を新設した。既存の海洋事業部門(OBU)とエネルギー・インフラ事業部門(E&I)をまとめたものだ。海洋事業部門は浮体式石油生産・貯蔵・積出設備(FPSO)と海上風力設置船(WTIV)、E&I部門は陸上プラントと風力団地を担ってきた。
2つの組織とも今年400億ウォン台の赤字を記録し、受注もほとんどない状況だ。造船業界関係者は「統合は人材重複を減らし、工程・設計部門の効率を上げようとする措置。これまでは似た業務が二元化して運営効率が落ちていた」と説明した。
サムスン重工業も事情は似ている。核心収益源である液化天然ガス(LNG)船とコンテナ船の受注は続いているが、海洋プラント部門は厳しい状況だ。今年の海洋プラント受注目標は約20億ドルだったが、実際の受注額は約5億ドルで4分の1水準にとどまった。ロシアからの受注取り消し、ブラジルの海洋プラント遅延など大型プロジェクトへの支障が相次ぎ収益性にも悪影響を与えている。
これに伴い、サムスン重工業は海洋部門の新規受注よりは既存の契約でリスクを減らし、収益性確保に集中している。内部的には海洋事業組織をスリム化し、構造を設計・調達中心に改編して固定費負担を減らす作業も進行中だ。また、LNG運搬船を中心に商船受注競争力を育て、親環境・自動運航船舶を開発するなど未来成長分野に焦点を合わせている。
HD現代尾浦造船と合併したHD現代重工業は大型化を通じて効率性最大化に出た。海洋プラントや未来エネルギー設備事業よりは船舶中心のポートフォリオ強化に集中している。一部ではHD現代重工業が親環境推進船舶と自動運航技術など未来型船舶分野の中心に投資し収益性が低い部門を整理するという見通しも出ている。
造船業界のこうした流れは「選択と集中」戦略の延長線とみることができる。LNG運搬船、超大型コンテナ船など高付加価値船舶の需要は回復傾向にあるが海洋設備や風力プラントなどは発注元の予算縮小やプロジェクト遅延などで変動性が大きい。これに対し造船3社も手持ち工事量の確保より収益中心の選別受注と組織運営効率化に焦点を合わせる戦略に旋回している。
ただ今後の課題も少なくない。非主力部門を整理すれば一時的にコストは減らすことができるが、今後の新成長動力確保の機会を逃しかねないとの懸念が出ている。海洋プラント・海上風力などは長期的には成長可能性が高い分野で、内外の発注環境変化により再び重要性が大きくなるかもしれないためだ。
韓国輸出入銀行のヤン・ジョンソ首席研究員は「統合と構造調整が短期的な業績防衛には役立つが、長期的には技術力維持と市場対応能力を並行しなければならない。収益性中心の戦略と未来成長戦略のバランスが重要だ」と強調した。
上記に関してだが、日本からも中国のブロック工場や造船所に艤装やいろいろな知識を教えた日本人達がいた。上記が事実なら、中国に造船業界に力を付けさせたのは、今、苦しんでいる日本と韓国であると言っているようなものだ。
上記が正しいと言うのであれば、日本と韓国は中国人労働者を造船業界から減らす努力をするべきだと思う。
上記が事実なら矛盾の中で解決方法を探すしかない。つまり、若年層を取り込もうとするとコストアップを容認するしかない。しかひ、若年層を増やせば、コストアップにより競争力を失う。コスト優先も良いが、自国の国籍を持つ労働者の造船技術は避けられないし、継承の問題は絶対に起きる。
国内の造船所間の競争も良いが、協力して外国の造船所との争いに勝てるように、共通化と効率を最優先に考えながら、上記の問題のバランスを取るしかないだろう。
中国の覇権主義的膨張により、極東の軍事情勢は極めて深刻な局⾯に突⼊した。
中国が新型空母「福建」の就役を目前に控え、露骨に台湾海峡を威嚇している。西側専門家までもが「真の脅威の始まり」と警告を発し、日本の安全保障にとっても看過できない緊張状態が周辺海域に拡大している。中国は既に「遼寧」と「山東」で運用準備を完了させているが、今回の「福建」は電磁カタパルトを搭載した初の実戦配備級空母である点が、これまでの中国製兵器への評価を一変させる重大な懸念である。しかし、軍事メディアが分析した内部構造には予想外の根本的欠陥が満ちており、中国政府が意図的に情報をリークしたのではないかという疑念も浮上している。
実際に公開されたスペックは、ロシア・ウクライナ戦争の教訓を巧みに模倣し、技術を吸収したレベルとされている。中国が西側の技術に追いついたという分析が相次いだ背景だ。だが、衝撃的なのは別の点にある。中国の空母開発速度が米国を上回る真の理由が、「長年にわたる他国技術の盗用」と「強引な産業基盤の利用」にあるという事実だ。電磁カタパルト技術については、米国が数十年の試行錯誤を経ても不安定なのに対し、中国や一部東アジア諸国がはるかに容易に実現できるとの見方がある。その背景には、高速鉄道や磁気浮上技術といった産業基盤を、中国が国策として強力に推進し、軍事転用している実態がある。技術開発の土壌がない米国との構造的な差が、この速度差を生んでいる。
日米同盟の足枷となる「友好国」からの技術流出
さらに深刻な問題は、友好国であるはずの韓国の造船技術が、致命的な失策により大量に中国へ流出した点である。2000年代以降、韓国の技術者が造船不況を背景に大量に中国へ渡り、中核的な艤装・エンジン・溶接技術までもが中国の造船所に事実上無償で伝授された。STX大連造船所の運営事例も重なり、中国の造船産業は躍進し、ついには空母までも商船のように量産するレベルに達した。一方、米国では、高水準の賃金構造により「3K業種」への若年層の参入が停滞し、造船技術は2000年代の一部東アジア諸国のレベルにも達していないとの指摘があり、同盟国の技術基盤の弱体化が懸念される。
「福建」の欠陥が示す危機
問題は「福建」の決定的欠陥である。中国の軍事メディア「海事先鋒」は、着陸滑走路と電磁カタパルトラインが重なり、艦載機の同時離着陸が事実上不可能だと指摘した。中型戦闘機J-15の着陸衝撃は滑走路の端まで及ぶため、2号・3号カタパルトは着陸中には使用できない。さらに1号ラインまで重なり、整備移動中にも干渉が発生するという分析が登場した。中国政府への批判が禁忌の国で、このような欠陥をメディアが報じたことは、軍事専門家の間で「意図的漏洩」という解釈に繋がっている。
中国のこのような無謀な開発強行は、過去から続く戦略的常套手段だ。ロシアの駆逐艦を導入し、欠陥だらけの複製艦を建造し、毎回一隻二隻ずつ廃棄するような手法で技術を強制的に蓄積する方式である。まず「遼寧」を運用した後、「山東」を建造し、続いて電磁カタパルトの巨大な壁を「福建」で突破する形だ。米国が11年かかる空母を中国は6年で進水させ、建造費は半分の水準だ。この速度で進めば、西側の分析のように25年以内に米国の空母戦力に追いつくことも非現実的な話ではない。
この危機的状況に対し、米国と日本をはじめとする同盟国の連携強化こそが唯一の解決策となる。米国の造船所が自ら中国の追撃を振り払う可能性は事実上ない。そのため米国は、空母・潜水艦に役割を集中させ、日本や韓国などの信頼できる同盟国に対し、水上艦の建造・整備の主要部分を委ねる構造を事実上既成路線としている。
韓国の造船技術を米国で活用する「MASGAプログラム」がその中核であり、これは中国の低価格攻勢に晒される日本と東アジア諸国の造船業にとっても、技術力を維持する上で極めて重要な機会となる。「福建」の欠陥が示すものは、単なる技術的な未熟さではない。東アジアの軍拡競争が既に次の段階に入り、日本はこれに「一刻の猶予もない」対応を迫られているという、極めて重大な警告である。
この間、国内では事業の撤退や縮小が相次いだ。特に目立ったのが総合重工メーカーの動きだ。かつて業界の盟主と言われた三菱重工業は、12年に神戸造船所での商船建造から撤退し、長崎造船所と下関造船所に集約。日本の近代造船発祥の地であり、同社創業の地でもある長崎でも22年、LNG船などの大型船に対応したドックを備える香焼工場を大島造船所に売却、建造量は大幅に減った。
また、三井E&Sも、商船事業を手掛ける三井E&S造船について、21年に株式の49%を専業の常石造船へ売却。常石は持ち株比率を66%まで高めた後、25年6月には残りの株式も取得し完全子会社化した。三井E&Sは艦船事業も三菱重工に売却済みで、今回の売却で造船事業から完全撤退したことになる。同社は今後、船舶用や港湾用のクレーンや、船舶用エンジンに活路を見いだす構えだ。
一方、業界は深刻な人手不足にも直面している。国土交通省海事局によると、造船業の就労者数は16年に約9万1千人だったが、25年には約7万7千人まで減少した。特に、設計やエンジニアリングに携わる「高度人材」の不足はより深刻だ。少子高齢化や人口減が根本理由とはいえ、未来への希望がなければフレッシュで有能な人材も集まらないだけにシェア回復は急務だ。
<三菱重工>造船リストラ 発祥の地・長崎43万人の大悲鳴 11/14/16(毎日新聞)の記事には次のように書かれている。
受注したのは「プロトタイプ」と呼ばれる1番船。内装や設計をゼロから行わなければならず、米カーニバルの厳しい要求が予想されたことから、「無謀な受注」(地元信用調査マン)だった。
三菱重工は04年に大型客船「ダイヤモンド・プリンセス」を引き渡して以降、大型客船の受注が途絶えている。「10年以上受注空白が続くと、技術継承ができなくなる」(三菱重工幹部)との判断から、受注を強行した。
◇3件の火災、特別損失2540億円
建造は、長崎造船所の香焼(こうやぎ)工場(長崎市)で進められているが、苦戦続きだ。1番船の「アイーダ・プリマ」では、今年1月には不審火とみられる3件の火災が船内で発生。1年遅れた2016年3月にようやく引き渡した。建造中の2隻目も含めた特別損失は累計2540億円となり、2隻で1000億円とみられる受注額を大きく上回っている。
上記の例が良い例だろう。建造能力があれば儲かるわけではない。若い設計やエンジニアリングに携わる「高度人材」を調達できたとしても、特定の船に関して経験や知識がないと三菱重工のような悲劇や損失は発生する可能性がある。日本の海運関連の記事を書く記者達は韓国は上手くやっていると書いている記事が多いが、下記のような問題は韓国にはある。
韓経:韓国LNG運搬船受注ジャックポット歓呼の裏に…仏から「1兆ウォンの請求書」舞い込む 06/04/20(中央日報日本語版)
10年間かけて開発した韓国産LNGタンク技術…197億ウォンかけて補修も同じ欠陥 12/02/19(中央日報日本語版)
韓国の造船所はLNG船建造で建造するたびにフランスの設計会社にライセンス料を支払わなければならない。ライセンス料を支払いたくないので10年を設計に費やして建造されたLNG船は欠陥を改修する事が出来ず、建造から5年以上経っても荷物を運べず、LNG燃料船のバンカー船として動いていたが、事故を起こした。
South Korea: Ship Collision 02/02/24(Crew Club)

On February 21, 2024, the Sm Jeju Lng1 collided with a ferry 6 kilometers off Yoseo Island in South Korea. The gas carrier received severe damage to its side. The ferry suffered damage to the bow, it is not known to what extent. At the time of the LNG accident, the carrier was without cargo. 77 crew members of both ships were rescued. The vessels are not in danger of sinking. No casualties were reported.
日本の造船業界が、異例の大規模投資を打ち出した。今治造船など17社からなる日本造船工業会が、計3500億円の設備投資に踏み切る方針を表明。政府・自民党も3500億円に政府支出を上乗せした「1兆円基金」の創設を検討中だ。造船王国再興に官民一体で邁進する。文=ジャーナリスト/井田通人(雑誌『経済界』2026年1月号より)
国が造船所を新設 民間に貸与する仕組み
3500億円の投資は、自民党が10月23日に開いた経済安全保障推進本部などの合同会議で造工会の檜垣幸人会長(今治造船社長)が表明した。各社の投資額が多くても年間70億~80億円にとどまるとされる中、かなり思い切った額といえる。
投入資金は、建造・修理施設であるドック内に設置するつり上げクレーンの導入などに充てる。つり上げクレーンは、鉄板でできた船体ブロックを溶接し、1つの船として組み上げるのに使う。クレーンが大型であればあるほどブロックを大きくでき、ドックの生産効率も高まる。大型クレーンは1基当たり100億円弱もすることから、大手といえどもおいそれと導入できる代物ではないが、成長のための必要経費とみなした。
また、液化天然ガス(LNG)運搬船の建造に充てることも検討していく。LNG運搬船はエネルギーシフトで需要が増加しているが、中韓との競争に敗れ、19年を最後に国内での建造が途絶えている。建造再開にあたっては、業界各社が設計を共通化することも念頭に置いている。
自民党は今年6月、国の主導で1兆円超の投資を可能とする基金の創設を提言したばかり。そこでは国が造船所の新設や再建、既存設備の更新を手掛け、民間に貸与する「政府所有・民間運営(GOCO)」方式の導入が想定されている。GOCOは、22年に成立した経済安全保障推進法に基づき、「特定重要物質」の安定供給を確保するために政府が活用できるとされているものだ。
業界側が大規模投資を打ち出した背景には、自らの努力を世間にアピールすることで、支援への理解を得やすくする狙いがあるとみられる。今後は支援額などについて政府との話し合いを進めたい考えだ。
高市早苗首相が10月21日に策定を指示した総合経済対策では、官民連携による危機管理投資の例として造船が挙げられている。早ければ総合経済対策の関連予算に1兆円基金の一部が盛り込まれる可能性もある。会議では、自民党の小林鷹之政調会長が「産業界としても最大限のリスクをとっていただき、官民での取り組みを進めていく必要がある」と、「オールジャパン」での取り組みに意欲を示した。
官民連携が進む背景には、国内造船業の置かれた厳しい現状への危機感がある。日本は戦後間もない1950年代後半に英国を抜いて建造量で世界トップとなり、70~80年代には世界シェアの半分近くを握っていた。しかしその後は人件費が安く、手厚い公的支援も受ける中韓に押されるようになり、2000年に韓国、00年代後半には中国に抜かれた。
かつての世界シェア50% 今では5%にまで下落
三つ巴とはいうものの、現在は世界シェアの約半分を中国が握っており、30%近い韓国の背中も遠い。両国に抜かれてからもしばらくは2割程度のシェアを死守していたが、直近は10%以下にまで落ち込んでいる。受注量ベースではさらに少なく、もはや5%程度にすぎないともいわれる。
この間、国内では事業の撤退や縮小が相次いだ。特に目立ったのが総合重工メーカーの動きだ。かつて業界の盟主と言われた三菱重工業は、12年に神戸造船所での商船建造から撤退し、長崎造船所と下関造船所に集約。日本の近代造船発祥の地であり、同社創業の地でもある長崎でも22年、LNG船などの大型船に対応したドックを備える香焼工場を大島造船所に売却、建造量は大幅に減った。
また、三井E&Sも、商船事業を手掛ける三井E&S造船について、21年に株式の49%を専業の常石造船へ売却。常石は持ち株比率を66%まで高めた後、25年6月には残りの株式も取得し完全子会社化した。三井E&Sは艦船事業も三菱重工に売却済みで、今回の売却で造船事業から完全撤退したことになる。同社は今後、船舶用や港湾用のクレーンや、船舶用エンジンに活路を見いだす構えだ。
一方、業界は深刻な人手不足にも直面している。国土交通省海事局によると、造船業の就労者数は16年に約9万1千人だったが、25年には約7万7千人まで減少した。特に、設計やエンジニアリングに携わる「高度人材」の不足はより深刻だ。少子高齢化や人口減が根本理由とはいえ、未来への希望がなければフレッシュで有能な人材も集まらないだけにシェア回復は急務だ。
政府は国内建造量を、35年をめどに現在の約2倍となる年間約1800万総トンに引き上げる方針。24年の国内建造量は908万総トンだった。目標通り1800万総トンまで倍増できれば、シェアはさしあたり20%まで回復する。
幸い、足元の造船各社の業績は好調に推移している。手持ち工事量(受注残)は多く、各社のドックは3年以上先まで埋まっている。船価も高いため収益性も悪くない。余力のあるうちに投資を実行し、将来に備えたいところだ。
そんな業界にとって追い風になると期待されているのが、米国の動向だ。トランプ氏が大統領に返り咲いてからの米国は、自国の経済安全保障を脅かす中国との対決姿勢を一層強めてきた。中でも中国で造られた船舶に追加の入港手数料を課すと表明したことは、海運会社による中国への船舶発注を抑制し、発注先を中国以外に切り替える効果をもたらし始めた。入港規制は結局、米中合意で1年間停止されることになったものの、米国による中国の排除で日本が「漁夫の利」を得られると期待する向きは多い。
その米国との間では、造船分野での協力に関する話も進む。日米両国は、米国の建造能力拡大に向け10月下旬に覚書を締結。造船作業部会を設けることや、米国の造船・海事産業への投資促進などが盛り込まれた。造船分野への投資は、7月の関税合意で日本が米国に投資を約束した5500億ドル(約85兆円)にも含まれている。
もっとも、米国への協力では韓国の方がより踏み込んだ対応をとっていると言わざるを得ない。傘下に造船大手のハンファオーシャンを抱える韓国財閥のハンファグループは24年6月、米造船大手のフィリー造船所を1億ドル(約154億円)で買収すると発表。今年6月には最大手のHD現代重工業が米造船所のエジソン・シュエスト・オフショア(ECO)と提携し、28年までにLNG燃料対応のコンテナ船を共同で建造すると発表している。軍需の取り込みも狙い積極的な米国シフトをとる韓国に対し、日本メーカーは自国への投資で精一杯で動きが鈍い。人手不足で人材育成での支援も行いづらく、支援したくても打つ手は限られているのが実情だ。
1兆円基金などの政府支援についても、「前進ではあるが、遅きに失した」(造船大手幹部)といった、やや冷めた受け止めが目立つ。
中韓の主要な造船所が巨大で、大量の大型船を集中生産できる体制を整えているのに対し、日本は各地に分散しており、スケールメリットを発揮しにくい。中韓に対抗するには、大型クレーン導入などによる造船所単位の能力増強だけでなく、メーカー同士の統合を促し、造船所の大胆な統廃合を進める必要があるが、造船所の閉鎖は地域雇用に大きく影響することもあり、なかなかそこまで踏み切れないのが実情だ。
近年は、日本の強みとされる技術力にも疑問符が付き始めている。環境規制に対応したアンモニアや水素、メタノールなどの次世代燃料船は技術的な難易度が高いだけに利益率が高く、日本の技術力を生かしやすいとされるが、この分野の覇権獲得を目指しているのは中韓も同様だ。日本がその緒戦ともいえるLNG運搬船で世界をリードすると豪語したにもかかわらず惨敗したのは前述の通り。厳しい競争を勝ち抜くには、資金だけでなく、開発・設計などにおける業界横断的な協力も欠かせない。
これらの課題は業界の自助努力だけでは解決するのが困難なだけに、高市政権がどこまで関与するのか、その「本気度」が試されることになる。 造船業界は多くの雇用を生み出している上に産業のすそ野が広い。業界が地盤沈下すれば、海運などの隣接業界も含め、甚大な影響が出かねない。しかも日本は四方を海に囲まれ、貿易の99・6%を海上輸送に頼っているだけに、経済全体にとって致命傷となる恐れすらある。
自民党の提言には、基金創設以外にもデジタル技術の導入促進などによる開発・設計・建造の効率化や、人材育成の拠点整備、ゼロエミッション船の開発・実証と建造体制の整備などが盛り込まれている。オールジャパンの機運が高まっているうちに、二の矢、三の矢を矢継ぎ早に繰り出す必要がある。
ちょっと前まで、造船は先が無いと思う人が多かったから、大学でも造船学科はなくなり、海洋〇〇とか、工学部の中に残っていたりする程度。
かなり前から、設計がないと言われていたけど、給料を上げられないし、将来に不安があるから、船舶設計したいと思う人は少ないと思う。
急に、造船が注目されて、株価が急上昇したから、造船や設計の仕事をしたい人が増えるわけでもないし、新卒を採用しても教育しなければならないから戦力にはならないと思う。
造船所によって、建造のスタイルがちがうし、クレーンのキャパも違うから、図面を使いまわすような高効率は無理だろう。それでも一から設計するよりは効率が良いと言った感じだろうか?
たぶん、造船業界では設計はかなり減っていると思うけど、儲かりそうな外航の大型船はお金を投入しようと言うことなのだろう。
現場は重要だけど、規則が頻繁に変わるので、昔に建造された船の図面を使って検査に通る船は建造できない。だから設計も必要。ただ、船価で負けると仕事がない。仕事が取れても現場の人間がいなければ建造は無理。バランスが必要。
海運大手と造船や設計を手がける企業計7社は1日、次世代の燃料船といった先端船舶の設計を効率化するため覚書を結んだと発表した。中国、韓国メーカーに押される日本の造船業の再生に向け業界を超えて連携する。船の設計会社に海運大手3社などが出資し、国内での増産体制構築を目指す。
今治造船(愛媛県今治市)と三菱重工業が共同で設立した設計会社マイルズ(東京)に、日本郵船、商船三井、川崎汽船の海運3社と、造船大手ジャパンマリンユナイテッド(横浜市)、設計会社の日本シップヤード(東京)の計5社が出資する。今治造船が保有するマイルズの株式49%分を、5社が買い取る方向で調整する。
By Associate Editor
Vietnam’s state-owned shipbuilding company, SBIC, is facing imminent bankruptcy, prompting government intervention aimed at restructuring the corporation. This decision follows a resolution approved by the Politburo, which has sanctioned the bankruptcy of SBIC and its seven subsidiaries.
Leading this initiative is Deputy Minister of Transport Nguyen Xuan Sang, who has asserted that the bankruptcy has become unavoidable after failed restructuring attempts. SBIC is burdened by substantial debt that far exceeds its total assets, making it financially unsustainable. The bankruptcy process aims to facilitate a transfer of ownership, allowing the company and its subsidiaries to operate free from old debts, thereby enabling profitable units to escape the financial liabilities associated with SBIC’s past.
The challenges faced by Vietnam’s state-run shipbuilding sector can be traced back over the past decade, characterized by mismanagement and unmanageable cost overruns. The situation worsened following the collapse of the former state shipbuilder, Vinashin, in 2010, which was subsequently restructured as SBIC in 2013, inheriting $4 billion in debts from Vinashin.
Despite its historical prominence, positioned as the fifth-largest shipbuilder globally during its peak from 1999 to 2007, SBIC’s operations have struggled to achieve profitability. Recently, the Transport Ministry reported that SBIC has been unable to meet its financial obligations owing to its inherited debts from Vinashin.
In response to the crisis, Minister Sang has conducted a comprehensive review of SBIC’s operations nationwide and has begun drafting a bankruptcy roadmap focused on maximizing asset recovery and capital. Following the filing for bankruptcy, the process will progress through a legal framework that includes asset liquidation and debt repayments, with operational units continuing their work under existing contracts during the transition.
Despite the current turmoil, Sang maintains that this is an opportune moment for rejuvenating the maritime industry. With global trends shifting towards sustainable shipping solutions, there is potential for Vietnamese shipyards to reinvent themselves by producing a new generation of vessels that utilize alternative fuels. The completion of the bankruptcy process could, therefore, herald a fresh start, allowing shipyards to adapt to evolving market demands and seize new development opportunities.
運輸省の代表者は1月10日午後、 VTCニュースに対しこの情報を確認した。
運輸省は、ベトナム造船総公司(SBIC、旧ビナシン)の2024年第1四半期の破産は避けられず、これにより同社の子会社は効率的に事業を運営できるようになり、旧債務の責任を免れることになると述べた。
「実際、SBIC傘下の造船会社の中には非常に順調に事業を展開し、毎年利益を上げているところもあるが、稼いだお金は借入金の利息を支払い、ビナシン時代からの古い負債を返済するには十分ではない」と運輸省は明らかにした。
運輸省は現在、ベトナム造船総公社(SBIC、旧ビナシン)の破産手続きを進めている。(イメージ画像:ハノイ・セキュリティ・ニュース)
破産後、会社の清算により得られた資金とその資産は、破産法の規定に従って、負債の支払い、給与、ビナシン時代からの未払い拠出金がある従業員の社会保険などに使用されることになります。
グエン・スアン・サン副大臣は、2024年初頭に親会社であるSBICとその加盟企業との会合で、運輸省はSBICの破産手続きにおける運輸省傘下の機関および部署のロードマップと具体的な責任を決定する実施計画を最終調整していると述べた。
「決議220の目的は、資本と資産を最大限に回収し、国家予算の使用を最小限に抑えることです。国家予算を使用する必要がある場合は、法令を遵守し、国、関係組織、個人、そして造船・船舶修理業界の金銭と資産の損失を最小限に抑える必要があります」とサン副大臣は強調した。
運輸副大臣は、SBIC加盟企業と協力し、SBICの破産は実質的に事業を新たな所有者に売却することを意味すると分析した。破産手続きの完了により、SBIC加盟造船企業は新たな段階に入り、発展の機会を掴むことができる。破産後、新たな事業主は既存の債務を負う必要がなくなり、生産と事業運営に対するコントロールを強化し、より高い効率性を確保できる。
ロードマップによると、SBICは近々人員体制を再編し、困難や障害を精査し、運輸省企業管理局と連携して解決に努め、会員企業が破産手続きを完了するための最良の条件を整える予定です。このプロセスにおいて、SBIC会員企業は、法的規制と市場原理を遵守し、国庫資金と資産の損失を最小限に抑え、関係組織および個人の透明性と説明責任を確保し、従業員の正当な権利と利益を最優先し、実施プロセス全体を通じて厳格な検査・監督メカニズムを確保する必要があります。
ハロン造船会社 - SBICの7つの子会社の1つ。(写真:SBIC)
サン副大臣は、人材に関して、SBICの破産は同社の再生と再編のための条件を整えることを目的としていると述べた。したがって、誰が所有権を取得するかに関わらず、現在同社の各部門で雇用されている経験豊富な経営陣と従業員は依然として非常に必要とされるだろう。
手続きに従い、加盟ユニットとSBICは裁判所に破産を申請します。裁判所が破産手続きを開始し、破産宣告を行うと、裁判所の判決に従って資産、債務、支払い優先順位の清算が行われます。この手続き中も、既存の契約を締結している事業ユニットは通常通り事業を継続します。
運輸省の決議第220号に基づく研修を最初に受けた2社は、Pha Rung Shipbuilding Company LimitedとBach Dang Shipbuilding Company Limitedであった。
計画によると、運輸省は、破産が予定されている残りの5社の従業員に対し決議220号を周知・説明するための代表団を組織し続ける予定であり、対象となるのは、ハロン造船会社( クアンニン省)、ティンロン造船会社(ナムディン省)、カムラン造船会社(カインホア省)、サイゴン造船業会社およびサイゴン造船・海事産業会社(ホーチミン市)である。
運輸省は既にSBICに対し、各企業の現状を徹底的に調査・評価し、関連文書を収集し、各企業に応じた具体的な解決策を策定するよう求める文書を送付している。影響を受けると予想される企業は、親会社であるSBIC、その子会社(7社)、そして未だ再編が完了していない旧Vinashin加盟企業147社である。
政府は、親会社である造船業総公社(SBIC)と7つの子会社(ハロン、ファルン、バクダン、ティンロン、カムランで船舶を建造している有限責任会社(1人有限責任会社)5社、サイゴン造船業株式会社、サイゴン造船海事産業株式会社)の破産に向けた対応に関する決議第220号を発行した。
同時に、親会社である SBIC の Song Cam Shipbuilding Joint Stock Company における資本持分を回収し、SBIC の子会社に関する事項の処理を継続し、親会社である SBIC とこれらの企業における 7 つの子会社の資産と財産権を回収します。
要件は、資本と資産を最大限に回収し、国家予算の使用を最小限に抑え、国家予算を使用する必要がある場合は法律に従って行う必要があり、国、関連組織、個人、造船および船舶修理業界の金銭と資産の損失を最小限に抑えることです。
タイムラインに関しては、決議では親会社であるSBICとその子会社7社に対し、2024年第1四半期に破産手続きの申請を提出できるよう、法律に従って必要な手続きを早急に検討し完了するよう求めている。
2010年、政府検査機関はベトナム造船総公社(Vinashin)に対する検査結果を発表し、一連の違反、欠陥、損失を指摘しました。その後、Vinashinは組織再編を行いました。
2013年、ベトナム造船業総公司(SBIC)が親子会社方式で設立されました。親会社であるSBICは、企業法に基づき運営される国有完全所有の有限責任会社です。
SBIC には、Pha Rung Shipbuilding Company Limited、Bach Dang Shipbuilding Company Limited、Ha Long Shipbuilding Company Limited、Thinh Long Shipbuilding Company Limited、Cam Ranh Shipbuilding Company Limited、Saigon Shipbuilding Industry Company Limited、Saigon Shipbuilding and Maritime Industry Company Limited、および Song Cam Shipbuilding Joint Stock Company の 8 つの子会社があります。
特に、ソンカム造船株式会社は効率的に事業を運営しており、不良債権もないため、決議220号に基づき破産政策の対象とはなりません。
タン・ラム
政府はこのほど、造船工業総公社(ShipBuilding Industry Corporation=SBIC、旧ビナシン=Vinashin)および子会社7社の破産手続きの実施に関する決議を発表した。
破産する子会社は、◇ハロン造船(Ha Long Shipyard)、◇ファーズン造船(Pha Rung Shipyard)、◇バクダン造船(Bach Dang Shipyard)、◇ティンロン造船(Thinh Long Shipyard)、◇カムラン造船(Cam Ranh Shipyard)、◇サイゴン造船工業(SSIC)、◇サイゴンシップマリン(Saigon Shipmarin)の7社。
SBICと子会社7社は2024年1~3月期に破産する。
SBICは2014年の設立で、資本金は9兆5200億VND(約560億円)となっている。非効率な経営により損失や多額の負債を抱えている。2021年は▲3兆8000億VND(約▲220億円)の赤字となった。
「国内の年間建造量を現在の約910万総トンから35年をめどに倍増させる目標」は愚かだ。絶対に、税金を溝に捨てるようになるのでやめるべきだ。他の産業の事はわからないが、北海道の半導体工場建設は疑問。ジャパンディスプレイの失敗を考えると、「国内の年間建造量を現在の約910万総トンから35年をめどに倍増させる目標」と考えるような愚かな人間達が権力を持っている、又は、上にいると言う事ではないのだろうか?
一部の企業や人達はこの愚かな目標で潤うだろうが、お金を無駄にするような事はやめるべき。日本は、中国や韓国と争う必要はない。もう一部の分野では勝てない。中国は公平性を無視して、敵国を痛めつけるために税金をつぎ込む。確認は出来ないが、中国で船を建造すれば、中国政府系金融や中国系企業が有利な条件で融資したり、傭船してくれると言う話は聞いた。船価だけの話ではない競争は、おかしい。
大型の外国船は、日本国内の造船所で争うのではなく、外国の造船所がライバルとの認識で、国内造船所で共通化の部分を増やし、効率を上げるべきだ。個々の造船所の強みや個性を失う事になる可能性があるが、工作基準の共有化部分を増やし、効率を上げ、設計に関しても同じサイズであれば、新設計に関しては共有出来るようにするべきだと思う。また、クレーンの新設をして、他の造船所と同じキャパが可能であれば設計を変更なしで利用できる可能性が高くなる。設計の共有化のために工作基準の共有化を進めるべきだと思う。
造船所に投資するにしても公平ではなく、将来性がある造船所を優先するべきだと思う。
「政府は35年をめどに、年間建造量を現在の約910万総トンから、約1800万総トンに倍増させたい考え。」は愚かすぎる。建造能力を増やしても、儲かる船価で発注してくれる船主を見つけられるのか?船台が足りないから、船価が高くても日本に発注してくれる外国の船主がいるのではないのか?建造能力が増えれば、競争が激化して、国際的に船価を下げる競争に巻き込まれ、誰も得しない状況になるのではないのか?建造能力を2倍に増やすと言う事は、現場の人間も2倍とはならないかもしれないが、外国人労働者が増える事になる。造船不況になったらどうするのか?外国人労働者を国外へ叩き出すのか?個人的な経験から言えば、造船不況で多くの同級生と家族が転校していった。日本人であれば、転校だが、外国人達をどうするのか?
造船不況で転職、転勤、そして低賃金で妥協など負のサイクルを見てきたので、無謀、又は、闇雲な投資には反対だ。失敗するだけだ。最初に書いたように、国内造船所で共通化の部分を増やし、国内の造船所が協力し合って、効率を上げていく事を考えるべきだ。建造量を増やすと言っても、建造する船の種類にはいろいろある。効率を考えれば、住み分けを考えるべきだと思う。世界的に見た建造のサイクルやマーケットの需要などで船と言っても、建造サイクルや発注のパターンが違う。オーバーキャパシティになれば、船価の下落、作り慣れていない種類の船の受注など効率や儲けに影響する。安易な造船の建造能力を増やすのは素人の考えだと思う。
国内の造船所をライバルと思わずに、協力出来るところは協力して、外国の造船所と戦うための協力を共有化を考えるべき。ただ、日本の造船所といっても、同じ種類の船を建造していても、経営者の方針や船主の層によっては船の設計や仕様が違う。だから、全く同じ設計で建造うするのは難しいかもしれない。効率化アップのため妥協できる事、そして、共有化できる部分を増やす事は建造能力に関係なくやるべきだと思う。
アメリカのために建造能力を増やすと言うのであれば、軍の船になるので、防衛産業に関わっている造船所だけで対応するべきだと思う。補給艦に関しては他の造船所でも建造できるかもしれないが、効率を考えれば防衛産業に関わっている造船所で対応するべきだと思う。
インドが商船の建造拡大を考えているようだ。韓国の造船所と関係を強めている。ベトナムの造船所は無茶苦茶して、勢いはなくなった。しかし、発展途上国が造船を産業にしようとする傾向はある。急激な建造能力アップはリスクでしかない。繰返すようだが、建造能力の倍増はやめるべき。お金をどぶに捨てる結果となる。
なぜ日本の造船業界が韓国や中国に負けたのか考えるべき。アメリカのための建造能力アップであれば、防衛産業に関わっている造船所だけで対応するべき。それ以外の造船所は効率アップと共通化部分を増やす事で対応するべき。
HD現代重工、インドの艦艇建造に参加…韓国造船業界のインド進出加速 11/12/25(ハンギョレ新聞)には「サムスン重工業も9月にインド西部のグジャラート州にあるスワン造船所とMOUを締結しており、商船建造および重工業プロジェクトを共同で推進することにしている。サムスン重工は、インド最大規模のドライドック(排水設備を備えた造船施設)と超大型タンカーおよび海洋設備の建造能力を備えたスワン造船所と船舶設計や海洋プロジェクトの分野で協力を模索しつつ、インド市場への足場を確保するという計画を明らかにしている。」と書かれている。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
「造船、生産拡大へ基金1200億円」
それで業界再生の目途は有るのかな。
本気なら1200億円では、少なすぎると思うけど。
造船市場は中国と韓国による寡占状態だそうな。
日本が負けた原因は判って居て、対策は出来ているのだろうか。
「日米関税交渉では建造能力拡大に向けた覚書」を交わしいるそうだけと、
その為のアリバイ作りに税金を投入するんじゃ無いのかな。
其れとも、米艦艇の修理の為のドック整備だとか。
だったらムダ金に終わるだけだから、止めた方が良いと思う。
日本は衰退する斜陽国。
造船分野でも中国の投資規模に追いつける見込みはなく、中国の背中は遠のくばかり。
日本は韓国にさえ勝てない。
日本の造船業はミャンマー人などが支えているが、優秀な外国人材は中国や韓国の会社に容易く引き抜かれる。
外国人の選り好みをしていては日本の造船業は維持できない。
文化やマナーの違いごときでガタガタ騒いで外国人を排斥していられる余裕は今の日本には無い。
多文化共生の住みやすさをアピールして中国や韓国との差別化を図り、外国人材を積極的に受け入れていくことだけが日本の唯一の生き残り策。
それができないなら、造船業は捨てるしかない。
採算が取れず衰退した業界に
日の丸を掲げても、再生の道はあるのだろうか?
しかも3年間でだ!
戦艦や潜水艦製造に、注力しても一度終えた、業界復活への道のりは、平坦なものとは言えない!^_^
造船は、人手不足、外国人頼り
そう簡単にはいかんよ
2025年度補正予算案には、国内造船業の再生に向けた基金の創設など1204億円の関連予算が計上された。
このうち基金が26年からの3年分で1200億円を占める。各社の設備投資のほか、人工知能(AI)やロボットを活用した先端技術の開発・実証などを支援し、生産能力の拡大につなげる。
政府は35年をめどに、年間建造量を現在の約910万総トンから、約1800万総トンに倍増させたい考え。総合経済対策では1兆円規模の官民投資の実現を掲げ、基金には今後10年間で総額3500億円を拠出する計画だ。業界団体の日本造船工業会も同額を投資する方針。
また、日米関税交渉では建造能力拡大に向けた覚書を交わしており、米国造船業の現状把握に向けた調査事業費として1億5000万円を盛り込んだ。
東京都港区に本拠を置く船舶貸出・販売の「株式会社YONE MARIN」は、11月5日付で東京地方裁判所より破産手続の開始決定を受け倒産したことが明らかになりました。
2023年に設立の同社は、クルーザー・ボートの販売や会員制シェアサービスによる船舶の貸出を主力に事業を展開するほか、リゾート型会員制ガレージハウスの運営も手掛けるなど事業を拡大しました。
しかし、借入先とのトラブルが発生したことで資金調達に支障を来すと、資金繰りの行き詰まりから2025年初に事業を停止し今回の措置に至ったようです。
負債総額は約11億7000万円の見通しです。
HD現代重工業は11日、インド最大の造船所であるコーチン造船所と「インド海軍揚陸艦事業の推進のための戦略的協力了解覚書(MOU)」を締結したことを明らかにした。
HD現代重工は今回の協力事業で、揚陸艦の設計・技術支援を推進することで、インドの特殊船市場への進出の足掛かりとする計画であることを明かした。続けて「フィリピンやペルーなどの様々な国の海軍艦艇の建造および技術協力の経験を土台」に事業を推進するとして、「HD現代重工業はインド海軍の現代化の最適のパートナー」だと述べた。同社は今月3日にはペルーの国営造船所と「ペルー潜水艦共同開発および建造意向表明書(LOI)」を締結しており、3月にはフィリピンから受注した哨戒艦(しょうかいかん)を引き渡している。HD現代重工は最近、米国最大の防衛産業造船会社であるハンチントン・インガルスとともに、米海軍の次世代軍需支援艦の建造事業への参加も推進することを決めている。
HD現代重工はインド南部ケーララ州にある国営コーチン造船所について、商船から空母に至るまで様々な船種の設計、建造、修理能力を備えていると説明した。HD現代重工の中間持株会社であるHD韓国造船海洋は、7月にコーチン造船所と設計・購入支援、生産性向上、マンパワー強化などで協力するとするMOUを結んでいる。
相次ぐMOUの締結は、インド政府が海軍力の強化などを内容とする15年間の軍の現代化計画を最近発表した中で実現した。またインド政府は、20位前後にとどまる造船の世界市場シェアの順位を、2030年に10位に引き上げる計画を立てている。独立100周年となる2047年までに5位圏内に入るなど、造船業を戦略産業へと育成していくというのがインド政府の構想だ。そのためには外国の造船会社との提携が必要となるが、中国とは国と国との関係が敵対的なため難しいことから、韓国企業がその相手として取りあげられている。
サムスン重工業も9月にインド西部のグジャラート州にあるスワン造船所とMOUを締結しており、商船建造および重工業プロジェクトを共同で推進することにしている。サムスン重工は、インド最大規模のドライドック(排水設備を備えた造船施設)と超大型タンカーおよび海洋設備の建造能力を備えたスワン造船所と船舶設計や海洋プロジェクトの分野で協力を模索しつつ、インド市場への足場を確保するという計画を明らかにしている。
イ・ボニョン記者
基金を通じて生産基盤の強化に加え、人工知能(AI)やロボットを活用した先端技術の開発・実証などを資金面で後押しする。国内の年間建造量を現在の約910万総トンから35年をめどに倍増させる目標だ。
「国内の年間建造量を現在の約910万総トンから35年をめどに倍増させる目標」は愚かだ。絶対に、税金を溝に捨てるようになるのでやめるべきだ。他の産業の事はわからないが、北海道の半導体工場建設は疑問。ジャパンディスプレイの失敗を考えると、「国内の年間建造量を現在の約910万総トンから35年をめどに倍増させる目標」と考えるような愚かな人間達が権力を持っている、又は、上にいると言う事ではないのだろうか?
一部の企業や人達はこの愚かな目標で潤うだろうが、お金を無駄にするような事はやめるべき。日本は、中国や韓国と争う必要はない。もう一部の分野では勝てない。中国は公平性を無視して、敵国を痛めつけるために税金をつぎ込む。確認は出来ないが、中国で船を建造すれば、中国政府系金融や中国系企業が有利な条件で融資したり、傭船してくれると言う話は聞いた。船価だけの話ではない競争は、おかしい。
大型の外国船は、日本国内の造船所で争うのではなく、外国の造船所がライバルとの認識で、国内造船所で共通化の部分を増やし、効率を上げるべきだ。個々の造船所の強みや個性を失う事になる可能性があるが、工作基準の共有化部分を増やし、効率を上げ、設計に関しても同じサイズであれば、新設計に関しては共有出来るようにするべきだと思う。また、クレーンの新設をして、他の造船所と同じキャパが可能であれば設計を変更なしで利用できる可能性が高くなる。設計の共有化のために工作基準の共有化を進めるべきだと思う。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
アメリカ海軍を維持するために必要な造船力がないことを懸念したトランプから日本が、その肩代わりする様に指示されているからです。アメリカの造船力にある程度のめどがついたら、今度は日本が競争相手となるから造船業界を縮小しろと言ってくる。日本の全ては、アメリカ意向次第なのです。
造船業はかつて労働集約型産業と言われてたくさんの雇用を生むことがよいことなんですが、建造量がだいぶ減った今ですら多くの外国人労働者に頼っています。建造量を増やすとなると外国人が激増になりそうなことが心配ですね
造船復活も大事ですが
造船内・造船関係で使う機械を日本製にする事も大事だと思います
使う機械が中国製に押される現状も考えなければと思います。
悪質な持ち込み業者には運輸支局での持ち込み受検を2年間させるとかの罰則有ったら不正車輌は激減すると思う。
通うだけでもかなりのコストなのでかなりキツい罰ですね。
タンカー等のデカさと量が物を言う船は中国の独擅場。
高価な巨大豪華客船は欧州の独擅場。
高圧ガスタンクなどの高付加価値船は独擅場とまではいかなくとも韓国が非常に強い。
……今更、日本の造船業が入り込む余地がどこにあるんです?
船舶関係の雑誌を軽く読んでも、日本の造船所の新造船なんて小さな内航船や、国内海運会社がお情けで発注している中規模貨物船がぽつぽつある程度ですよ。
造船業というのは典型的な労働集約型産業であって、欧州のように高付加価値への転換が出来なかった時点で日本の造船業は終わっているんです。
政府は27日、国内造船業の再生に向け、2025年度補正予算案に基金の創設などで1200億円を計上する方針を固めた。
基金を通じて生産基盤の強化に加え、人工知能(AI)やロボットを活用した先端技術の開発・実証などを資金面で後押しする。国内の年間建造量を現在の約910万総トンから35年をめどに倍増させる目標だ。
造船業支援を巡り、政府は総合経済対策に官民合わせて1兆円規模の投資を目指す方針を明記。基金に今後10年間で総額3500億円を拠出する。業界団体の日本造船工業会も同額を投資すると表明している。
造船会社が出資する船の設計会社に海運大手の日本郵船、商船三井、川崎汽船の3社が資本参加することが26日分かった。中国、韓国メーカーに押される日本の造船業の再生に向け海運業界も連携し、次世代運搬船の開発に取り組む。生産能力の拡大については日米両政府が協力を推進する覚書を結んでおり、こうした投資が今後、拡大するかどうかが注目される。
3社が資本参加するのは、今治造船と三菱重工業が共同で設立したマイルズ。造船プロセスの合理化を目指し、船の設計を標準化して量産体制を整える狙いもある。脱炭素の動きは海運業界でも重要視されており、環境負荷の低い次世代燃料船の需要増加を見据え、開発を進める。
足場ごと転落したのならどうしようもない。
長崎県西海市の造船所で28日、30代の作業員の男性が高所作業中に足場ごと転落し、死亡する事故がありました。
事故があったのは西海市大島町の大島造船所で、警察によりますと、28日午前11時50分ごろ、高さ数メートルの高さで船体の溶接部分の確認作業をしていた30代の男性作業員が、足場ごと転落しました。
男性は頭から出血し意識不明の重体で西海市内の病院に運ばれましたが、間もなく死亡が確認されました。
警察が、事故の詳しい原因を調べています。
海外の方が安く解体できるし、大型の船は外航船なので、外国の解体ヤードまで自航できる。だから日本での解体は、上手く行くとは個人的に思えない。この意味の上手く行くとは、儲からないと言う意味。
船の修繕やドックを考えたら良い。ほとんどの大型の船は海外で修繕やドックをする。シップリサイクルで儲けが出るなら、同じように日本でも修繕やドックで儲ける事が出来るはずである。
全国銀行協会のイベントが23日、都内で開かれ、地方創生の取り組みとして愛媛県松山市の「オオノ開發」が進めている国内初の「シップリサイクル事業」が紹介されました。
【写真】愛知の事業所で行われる船の解体・再資源化
「海外マネーの日本への呼び込み」などをテーマに開かれた全国銀行協会のイベントでは、愛媛銀行の向井常務が海運、造船が盛んな愛媛ならではの地方創生の取り組みを紹介しました。
(愛媛銀行・向井正知 常務)
「弊行はシップファイナンスの歴史が古く、かつて海運銀行と呼ばれるほど地場の海運、造船業と親密な関係を築き海事産業を金融面から支えてまいりました」
愛媛銀行が紹介したのは、オオノ開發が国内第1号の認可を受け準備を進めている国内初の「シップリサイクル事業」で、船舶を解体し鉄の再資源化を進める計画について説明しました。
(オオノ開發・山下裕二 社長)
「金融関係機関の皆さまから支援を受けながら、愛知県・知多事業所で2028年4月の開業を目指しております」
鉄鋼業界では、世界的に鉄スクラップの需要が高まっているものの、船舶の解体は主に海外で行なわれていて、愛媛銀行の向井常務は「需要を国内に取り込んでいく」と事業の意義を語っていました。

23日、福山市の工場で屋根から男性が転落し死亡する事故がありました。警察は労災事故として、事故の原因を調べています。 事故があったのは、福山市沼隈町の常石造船の第2工場です。警察と消防によりますと、23日午前10時半ごろ、「20mの高さの屋根から人が落ちた」と119番通報がありました。 大分市に住む塗装工の小野貴勝さん(31)が、工場の屋根で防水補強の溶剤を吹き付ける準備などをしていたところ、屋根が抜け落ちて約20m下に転落。病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。 小野さんは当時、スレート屋根で1人で作業していたとみられていて、警察が事故の詳しい原因を調べています。









愛媛県今治市の造船下請業者が、破産手続き開始の決定を裁判所から受けたことが9日に分かりました。負債は約1500万円と見られています。
破産手続き開始の決定を受けたのは、今治市小泉の造船下請業「高春工業」です。
東京商工リサーチ今治支店によりますと「高春工業」は2018年4月に設立。地元の造船所の下請けとして作業を行い、2022年12月期の売上げは2600万円。しかし受注単価が厳しく従業員の退職などもあり、事業を続けることが困難になったとしています。
破産手続きの開始の決定は松山地裁今治支部から10月1日に受けました。負債は約1500万円と見られています。
By Lisa Baertlein
LOS ANGELES (Reuters) -The U.S. is one week away from imposing port fees on certain vessels with links to China, a move expected to cost the top 10 carriers $3.2 billion next year as President Donald Trump seeks to address China's growing dominance on the high seas.
"While some observers believe the October 14 deadline may be extended — or even scrapped — as part of broader negotiations, the uncertainty has already unsettled carriers, adding another layer of geopolitical risk to fleet deployment strategies," S&P said in a report this week.
Trump's administration said fees imposed on ships built, owned or operated by Chinese entities will help pay to revive U.S. shipbuilding. A law to direct that long-term funding is making its way through the U.S. Congress with strong bipartisan support.
In an update late last week, the U.S. Trade Representative put ship owners on notice that they, not the agency, are responsible for establishing if the fees apply.
"The burden for determining if a vessel owes the fee is on the operator, NOT CBP," USTR said.
It also said fees must be paid through the Department of the Treasury's Pay.gov website, not at the port of entry.
Vessels owned or operated by a Chinese entity will face a flat fee of $80 per net tonnage per voyage to the U.S. Non-Chinese operators of Chinese-built ships will be charged the higher amount of either $23 per net tonnage or $154 per 20-foot equivalent unit capacity. Both fees are imposed on a ship no more than five times a year, maritime technology and data provider Alphaliner said.
Following intense industry push back, USTR significantly eased fees from initial proposals, exempted many U.S.-based operators and extended the timeline for fees on liquefied natural gas (LNG) carriers.
On the other hand, it expanded fees to include any non-U.S. built roll-on/roll-off auto carriers - with exceptions for U.S.-flagged ships.
Alphaliner estimated that Chinese carrier COSCO, including its OOCL fleet, is most exposed to the fees.
COSCO's fees could be as much as $1.53 billion next year - nearly half of the $3.2 billion projected for the top 10 cargo carriers, it said.
Many other carriers, including France's CMA CGM, said they re-deployed Chinese-built ships to avoid the fees.
Meanwhile, Beijing has responded. Premier Li Qiang signed a decree pledging countermeasures against any discriminatory measures on Chinese ships or crews.
Trump and Chinese President Xi Jinping are slated to meet at the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit scheduled for late October through November 1 in South Korea.
Last year, U.S. shipyards built fewer than 10 commercial ships. China shipyards, many of which build both commercial and military vessels, turned out well over 1,000.
(Reporting by Lisa Baertlein in Los Angeles, additional reporting by Gus Trompiz in Paris; Editing by David Gregorio)
Pölös Zsófia
Journalist Trans.info
Starting 14 October 2025, ships owned, operated or built in China will face new U.S. port fees of up to $50 per net ton, part of Washington’s latest trade measures designed to curb Chinese dominance in global shipping and shipbuilding. Vessels that fail to pay the fees in advance risk being denied unloading at U.S. ports, the U.S. Customs and Border Protection has warned.
“Vessels without proof of payment will be subject to denial of lading or unlading operations, or clearance withheld, until payment can be verified,” CBP said, as quoted by The Maritime Executive.The requirement effectively means ships that have not paid the tariff will not be permitted to unload cargo, a policy Washington hopes will pressure shipowners and charterers to comply before reaching U.S. waters.
アメリカだけでなく、イギリスも自国の海軍の船を建造する事が出来ず、スペインで建造するそうだ。商船で競争力がなくなると、建造量が減るわけだから、軍の船を建造するとなっても、造船の関係する技術者や職人がいるとは限らないと言う事だろう。セキュリティー的に言えば、かなりダメージだと思う。情報の守秘義務、修理、そして改造となっても、イギリス国内で出来ない可能性は高くなる。ハイテクではなくても、生産がストップすれば
Mike McBrideBBC News NI
A UK warship will now be largely built in Spain because the Harland & Wolff (H&W) shipyard in Belfast is "not ready", a Spanish shipbuilding firm has said.
Navantia, Spain's state-owned shipbuilder, leading the £1.6 billion Fleet Solid Support (FSS) programme, confirmed that most of the construction of the first of three Royal Navy vessels will now take place in Spain.
Originally the midsection of the first ship was to be built in Belfast, but that has now moved to Cádiz in Spain.
Donato Martínez, chief executive of Navantia UK said the move was because H&W's facilities were still "undergoing upgrades" after the yard was rescued after it fell into administration last year.
Navantia is the major partner in the FSS programme to build three naval logistics vessels with Harland and Wolff as subcontractor.
Harland and Wolff's main site is the historic Titanic shipyard in Belfast and it also has yards at Appledore in Devon and at Methil and Arnish in Scotland.
Navantia, which is owned by Spain's government, has its main shipyard in Cádiz, southern Spain, where the majority of its 4,000 employees are based.
'Shuffled a little bit of things'
"The facilities were not ready in Belfast," Donato Martínez said in an interview with the Financial Times.
"We shuffled a little bit things for ship one into Spain, and we moved from Spain things for ships two and three."
Under the original plan, the ship's midsection was to be built at H&W's Belfast yard, with the bow constructed at H&W's Appledore facility in Devon and other sections in Spain, before final assembly in Belfast.
But under the revised plan, the bow will be built in Devon, while the midsection and the remainder of the first ship will now be constructed in Cádiz.
All three vessels are still to be assembled in Belfast.
'Ensure timely delivery of the vessels'
In a statement to BBC News NI, Navantia said that following their acquisition of Harland & Wolff, "some adjustments are being made to the programme to ensure timely delivery of the vessels".
They said this is to "allow the planned recapitalisation investment in the Belfast shipyard to be completed".
"It will be necessary to increase the proportion of FSS ship one build in Spain which will be offset by greater UK content for ships two and three, supporting our vision to enhance UK sovereign shipbuilding capability now and into the future."
"For all three ships, the Appledore scope (in Devon) is unchanged," they added.
A Ministry of Defence (MoD) spokesperson said that the "overall build strategy for the FSS programme remains unchanged" and that all three ships will still be assembled in the UK.
■中小型船は免除、初期提案から緩和も影響大
昔、アメリカの海運会社のアメリカ人と話す機会があったが、アメリカはアメリカ人労働者を守る規則と弁護士の影響で、アメリカ人を使いにくいので、アメリカに登録されている会社なのに、アメリカ生まれの人間がほとんどいないと笑っていた。
労働者を守る規則が充実しているのは良いが、ちょっとした事で弁護士を立ててくるから、他の選択があればアメリカ人を雇わなくなるのは仕方が無いように思える。
危険が伴う製造業はアメリカではコスト高か、難しいとなるのは自然だと思う。ただ、移民や不法移民がいるから、総合的にはグレーだと思う。
東京商工リサーチ北九州支店によると、福岡県水巻町の内航海運業や不動産賃貸業を営んでいた上野海運と、グループ会社で石油製品販売業の菱栄石油は、3日付で福岡地裁小倉支部から特別清算開始決定を受けた。負債総額は現在調査中。
現代自動車グループとLGエナジーソリューションが米ジョージア州に10兆ウォンを投じて作ったバッテリー工場で300人以上の韓国人が米移民当局に逮捕・拘禁され、現地人材だけでは工場建設だけでなく運営も厳しい韓国企業の現実があらわれたとの評価が出ている。第1次トランプ政権以降に韓国企業が米国に製造業の工場を大挙作ったが、現地人材の熟練度不足などで少なくない困難を経験してきたためだ。
韓国企業が米国に工場を作る際に体験する最初の障壁は許認可問題だ。環境・安全規制の場合、連邦政府と州政府からそれぞれ許認可を受けなくてはならないが、週ごとに規制基準が異なる。これをどうにか合わせたとしても建設現場で必須の溶接工からして現地で確保するのが容易でない。米国が輩出する溶接工があまりに少ない上に、韓国企業の要求に見合う人材はさらに足りないためだ。韓国産業研究院のチョ・チョル選任研究委員は「米国は工場設計・施工・管理などがとても細かく分けられており、竣工まで韓国より長い期間がかかるが人材不足も深刻だ」と指摘した。
工場を作っても難関は続く。まず現地で熟練人材を得るのが難しい。現代自動車グループの場合、2005年にアラバマ州の現代自動車工場竣工から20年にわたる試行錯誤の末に製造人材を養成し、現地化にも成功した。だが進出初期には組み立て・溶接技術者を確保するのが容易でなく困りきったという。現在は自動化工程が導入されたが最終組み立てと品質検査には熟練人材が必須だ。
業界関係者は「テスラだけでも、米国製は中国製テスラより段差などが激しく組み立て完成度が落ちるという評価を受ける。それだけ米国には繊細な組み立て技術を持っている人材が足りないという意味」と話した。その上雇用後の労働の質も落ちる。業界関係者は「訓練させたのに数カ月で工場を辞めるケースが米国ではとても多い」と話した。一部工場では雇用した現地人のうち麻薬問題などで仕事をまともにできなかったケースもあったという。
韓国企業がこの10年で米国に作ったバッテリー、自動車、半導体などの最新工場では熟練技術職がより重要だ。米国内で製造業の雇用は手が油まみれになる単純労働とみなされるが、最近の先端設備を備えた工場は違う。単純労働は自動化が進んでいる方で、工場の生産性を左右するのは複雑な機械操作と維持保守を引き受ける技術人材だ。バッテリー業界関係者は「バッテリー工場は先端技術と伝統製造業の労働集約的生産方式が結びついている所。現地の人材を教育し歩留まりを一定程度引き上げるには相当な時間と努力が必要なので、序盤には韓国で工場を運営した人材の参加が避けられない」と話した。
トランプ米大統領が再建を推進する造船業も人材不足が深刻だ。米国には造船熟練工がいないばかりか、船舶設計エンジニアを養成する大学もミシガン大学造船海洋工学科1カ所だけだ。これに対しフィリー造船所を買収したハンファオーシャンは韓国から50人を派遣して現地人材を教育中だ。ソウル大学造船海洋工学科のイ・シンヒョン教授は「良質の人材が十分に供給されなければMASGAプロジェクトも順調に進まなくなるだろう」と懸念する。
トランプ政権の関税政策により現地直接投資が増え米国で製造業従事者需要は急増しているが、実際に米国内では既存の製造業雇用を満たすのも困難なことが明らかになった。外国人材に対する開放がなくては製造業の再建は難しいという指摘が出る。
米公営放送NPRの5月の報道によると、現在米国内製造業雇用のうち約50万件は人材不足により埋まらない状態だ。デロイトが昨年米国の製造業200社を対象にアンケート調査した結果、回答企業の65%以上は「人材採用と維持」を最大の課題に挙げた。デロイトは「2033年まで追加で380万人の製造業労働者が必要な見通しだが、人材問題が解決されなければ最大190万件が埋まらないだろう」と分析した。トランプ政権の関税施行で現地工場需要が増えた点を考慮すれば米国内の製造業人材不足はさらに深刻化する。
結局米国政府が「米国に工場を作れ」と要求だけするのではなく、内部で製造業人材を育て外国専門人材をしっかり活用しなければならないという指摘が出る。米労働統計局によると、昨年の米国の民間労働力の19.2%は外国人が占め、前年の18.6%から0.6ポイント拡大した。世宗(セジョン)大学経営学部のキム・テジョン教授は「トランプ政権は大規模生産施設を積極的に誘致しながら人材養成は疎かにしている。結局韓国人が現地人材を教育しなければならない状況だが、両国の労働者が一緒に働けるよう助けるべきで、これをかえって妨げてはならないだろう」と話した。
見た感じ、技術的には大した船ではないと思うけど、外国仕様の船を知らない小型の造船所には理解できないレベルだろう。また、全く同じように設計、そして建造する必要もないと思うけど、小型で英語も読めない造船所の人達には無理だろう。商船三井にしても大型船であれば、専門家や経験豊富な船員達はいると思うけど、小型船に関しては知識がないのではないかと思う。
ヨーロッパで設計された船はコンセプトが全く違う。怖くて変更や改良できないだろうな!もう日本の造船所で直ぐに理解できるような人材はいないと思う。英語の問題もあるし。特殊船に関してほぼ全てが日本の船舶設計とは思想が違う。
結局、アルミの船体だけ作って、それ以外は、システムとして丸ごと買うようになるのだろう。それなりの隻数を建造すれば、何かを学ぶかもしれないけど、メンテも外国からのサービスエンジニアを呼ぶようになるから割高だろう。日本人を教育するとしても英語が出来る人間が必要だから割高になると思う。システムが複雑だから故障すると稼働率も落ちるし、直ぐに対応できないと思う。船価が大きいから小型造船所は興味を持っているのだろうけど、外国のメーカーは日本のように扱えないよ。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
CTVのシートは、本来は船酔い防止ではなく、作業者の腰を守るためのシート。
波浪中の高速船での移動は、腰への衝撃が凄まじい。移動中に労災防止のため、CTVはダンパー付きシートを導入している。
最近は安くはなったけれど、価格はCrew用で70万円前後、操舵手用のHelm seatは150万円くらいする。
インペラとバケットを含むウォータージェット一式、エンジン、シート、全て輸入品で、国産はドンガラくらい?
高品質のアルミ溶接ができる造船所も、日本で何社もない。また、岩手の小鯖造船さんあたりに頼るんじゃないの?
そもそもJR九州のクイーンビートルすら、誰も修理の名乗りを上げないくらいだから。
風力発電は、気候的要因が重要なものです。
日本は台風がたくさん来る地域で、欧州は全くというレベルで来ません
そういう地域を真似て電力をつくるのは馬鹿です
これを推進した政治家を次の選挙で堕とす
それが国民の義務でしょう
洋上風力発電の設置やメンテナンスに欠かせない交通船「CTV(クルー・トランスファー・ベッセル)」。揺れに強く、高速で技術者を風車まで運ぶこの船の国産化に、長崎の造船所が挑戦しています。世界で需要が拡大する新市場で、ヨーロッパ勢に追いつけるか注目されています。
【写真を見る】【洋上風力】世界需要拡大のCTV船 国産化プロジェクト始動 欧州勢に迫れるか
■洋上風力発電を支える 時速46キロの高速船「CTV」
波静かな長崎港に、見慣れない船が姿を現しました。商船三井が保有する「KAZEHAYA(かぜはや)」。揺れが少ない双胴船で長さ26.3メートル。最大速力は24.9ノット=時速46.1キロメートルと高速です。
洋上風力発電の設置やメンテナンスに不可欠な船で「CTV」と呼ばれています。洋上の風車まで拠点となる港からメンテナンスなどを行う技術者を輸送するための交通船です。
■幅10メートルの巨大フェンダー 風車への安全な乗り移りを実現
双胴船「KAZEHAYA」はアルミ製で軽く、短時間で風車まで作業員を運べるよう高速化が図られています。
大きな特徴は船首に取り付けられた幅、約10メートルあるフェンダーです。このフェンダーを風車の付け根にある梯子に押し当てて船体を安定させ、技師が乗り移ります。
■揺れを吸収する特別シート「快適!」と驚きの声
今回の入港の目的は、商船三井が長崎の造船・海事産業と連携を深めるためのいわば『顔合わせ』です。作業員用の客室には12名分の椅子があります。
KAZEHAYA 早川昇司船長:
「座ってみてください。揺れを吸収できるので」
「…快適!すごい!」
風車への乗り移りや高所作業を行う作業員が、移動中に船酔いしないよう配慮されています。
客室の上が操縦席です。操縦席は広い視界を確保し、作業員が船首から風車に乗り移る様子を直接確認できます。洋上での風車への接続は風や波の影響を受けやすいため手元で細かい操船を行います。
■製造はオランダ「できれば日本で」
「KAZEHAYA」はオランダの造船会社「Damen Shipyard(ダーメン・シップヤード)社」が設計・製造した船です。機器の表示はすべて英語。エンジンも外国製です。このため、国内での運用で苦労することもあります。
商船三井 沼田紗奈さん:
「メンテナンスをするときに部品を取り寄せるとか、技師の方を呼ぶのに時間もお金もかかってしまう点は困っています。できれば日本のメーカーの皆さんと一緒に頑張っていけたらなと思います」
商船三井 琴賀岡 健太さん:
「一番大事なのは、地元の企業の皆様への雇用が促進をされること、洋上風力発電産業に対する理解を深めていただくことだと考えておりまして、そのきっかけになればいいなと考えております」
長崎県産業振興財団では、長崎の造船業が担う役割に期待を寄せています。
長崎県産業振興財団 川口晋治さん:
「国内でも洋上風力プロジェクトが、いろいろ立ち上がってきてますし、政府におかれましても今後どんどん推進しようとしております。そういう中でCTVの需要も今後どんどん拡大されると思われますので、国内で建造する場合は長崎県の造船業の皆様が連携して建造に携わっていただければと思っております」
■アルミ船パイオニア企業の挑戦
オランダのDamen Shipyard社の設計に基づき、CTVの建造に動き出している造船所があります。
創業1967年の佐世保市の沖新船舶工業は、FRPやアルミ船など、軽量素材の船舶を手掛ける県内のパイオニアです。
沖新船舶工業 津志田正和設計部長:
「今までのお客さんとは違う別の市場ということで、新しい仕事が呼び込めるかなとは思っています」
沖新船舶工業では、離島フェリーのほか水産庁や国交省の業務艇など、高速性や安全性が求められるアルミ船を数多く手掛けてきました。アルミニウムは曲げや溶接などの加工が他の金属と比べて難しいとされています。
津志田さんは初めてCTVを見たとき“黒船”に感じたといいます。
沖新船舶工業 津志田正和 設計部長:
「正直、カルチャーショックを受けました。船体(建造)はアルミで溶接だとか、あまり(日本も)劣ってはいないと思います。ただ電子機器・機械類、(デザイン性)というところではやっぱりヨーロッパが進んでるなっていうのは感じましたね」
記者:
Q、今まで、作業員をどこかに送る船で、ああいう思想・発想って日本にあったんですか?
「ないと思います。客船であってもあそこまでのグレードはないですし…そうですね、もう、かなりの高レベル・ハイスペックな客室だと思いますね」
世界4位への再浮上
■国内需要は約100隻、アジア市場も視野
沖新船舶工業は、円安の影響は大きいものの、建造の速さとその後のメンテナンスで国産のメリットは出せると話します。
沖新船舶工業 津志田正和設計部長:
「国内の需要は国土交通省が発表しているので100隻ぐらいいると思うんすよね。国外も今、韓国もどんどんどんどん洋上風力発電やってますし、もう台湾、インドに関してはもう日本より既に先に進んでる状態なんで、これから日本がどう太刀打ちできるかというのは考えてますけど。ヨーロッパの技術に追いついて、さらにいいものを作っていければ。国産化っていうのも、国外に輸出っていうことももちろん考えてます」
ヨーロッパやアジアが先行する「洋上風力発電」。世界の技術に追いつき、追い越そうと国際的な「新市場」へ参入する挑戦が始まっています。
■国産CTV実現への課題 価格競争力と国際規格への対応
現在、国内では洋上風力発電の設置が進んでいますが、風車はほとんどがヨーロッパ製で先行するヨーロッパの風車メーカーが「CTV」の仕様や安全基準などについて厳しい標準規格を定めています。
今後、国産の「CTV」を国際市場で展開していくためには、これらの標準規格をクリアした上で価格競争でも負けない船をつくる必要があります。
課題は山積みですが、長崎が培ってきた造船の技術力を生かして、新たな産業の柱に成長させてほしいところです。
長崎放送
発電船に関してトルコは何十年も前から建造し輸出している。そう言う意味ではかなりの経験があると思う。マレーシアか、インドネシアでもトルコ製の発電船が使われていたと思う。バージタイプが座礁し、使えなくなった記事を見た事がある。アフリカで適切に管理できるのだろうか?
18年間を封じ込めたインドネシア発電船 PLTD Apung 1(じゃかるたインドネシア語レッスン)
ここにもインドネシアの国旗が。重さ2600トン、電力公社のディーゼル発電船(じゃかるたインドネシア語レッスン)
巨大津波に流されたアチェの発電船 Kapal PLTD Apung Tsunami Aceh(インドネシア文化宮(GBI-Tokyo))
PLNとPT PALは、インドネシア東部地域向けの2船舶発電所を追加(VOI)
PT PAL Indonesia Dukung Pemberdayaan Daerah Lewat Pembangkit Listrik Terapung(Good News From Indonesia)
商船三井が8月20日、パシフィコ横浜で開催された第9回アフリカ開発会議(TICAD9)の併催イベント「TICAD Business Expo & Conference」に登壇し、アフリカでの発電船事業について紹介した。
「発電船」とは聞き慣れない言葉かもしれないが、文字通り発電する機能を持つ船舶のこと。海に浮かぶ発電所だ。もともと重油を燃料とする発電船事業を展開していたトルコの発電船事業者カルパワーシップ社と商船三井が協業。商船三井がアジアの海運会社で唯一手がける、LNG(液化天然ガス)の貯蔵・再ガス化機能を有する“FSRU”(Floating Storage and Regasification Unit、浮体式LNG貯蔵再ガス化設備)を発電船と共に設置することで、発電船の燃料を環境負荷の低いLNGに転換する取り組みを進めている。
LNG船(最下部の船)で運ばれてきたLNGを隣のFSRUに移し、貯蔵。電力需要に応じてLNGをガス化(気化)させ、発電船(上部にある3隻)に送り、ガスでつくった電力を陸上の電力網に送電する。
伝統的な海運事業に加え、船舶を活用した多様な社会インフラ事業を展開する商船三井。現在アフリカでは、モザンビークとセネガルの2カ国で発電船事業を開始している。
同社の小林潤氏は、アフリカの電力事情について、アクセス格差の是正とグリーンエネルギーへの移行という二つの緊急の課題があるとする。「大陸全体で、約6億人が依然として電気へのアクセスがない状態で生活しています。サハラ以南のアフリカには、電気が使えない人々の約80%が集中しており、多くの国ではアクセス率が30%未満です。単に不便なだけでなく、医療、教育、産業の成長が制限されている状態です。同時に、世界は脱炭素化へと進んでいます。発展の途上にあるアフリカ経済では、電力供給を実現しつつ、エネルギー転換に貢献する解決策を必要としていますが、ここに当社のLNG発電ソリューションの意味があると考えています」という。「私たちの事業の主な利点は三つあります。第1に速度。陸上の発電所は、土地の取得や許可取得などに通常5年から7年かかりますが、発電船は数カ月で電力供給を開始できます。第2に柔軟性。需要の変化に応じて船舶の場所を移すことができます。第3にクリーンな燃料であること。LNG発電は重油と比較してCO2排出量を約2~3割減らすことができます」とアピールする。
同社の渡邉達郎常務執行役員は「LNG発電船事業をはじめとするさまざまな事業でパートナーと協力し、アフリカの持続可能な未来を支えるインフラ、物流、エネルギーソリューションを構築したい」としている。
関税措置をめぐる日米交渉で経済安全保障の観点から両国が協力を深める分野に「造船」が含まれたことを踏まえ、国土交通省は来年度予算案の概算要求の重要項目として造船業の強化を掲げる方針です。造船設備の拡張などを進めるほか、協力内容の具体化にあわせて柔軟に予算措置を講じることも検討しています。
中国が国主導で造船の世界シェアを大きく伸ばす中、関税措置をめぐる日米交渉で経済安全保障の観点から両国が協力を深めることで合意した分野には造船が含まれました。
これを踏まえ、国土交通省は、8月末に締め切られる来年度予算案の概算要求で、造船についての強じんなサプライチェーンの構築が必要だとして、造船業の強化を重要項目として掲げる方針です。
要求段階では金額を示さない「事項要求」としますが、当面は、船の建造量を引き上げるための国内の造船所の拡張や、老朽化した設備を自動化や省力化の機能を持つ設備に更新するための支援を想定しています。
また、日米協力の内容の具体化にあわせて新たな支援策が必要になる可能性もあるため、柔軟に予算措置を講じることも検討しています。
国土交通省は今後、関係省庁と連携して造船業の強化に向けたロードマップの策定にも取り組むことにしていて、政府全体での中長期的な支援につなげたい考えです。
ヨーロッパの造船所の中には倒産、又は、消滅する前に、ナックル部分の多い船を建造していた造船所がある。個人的な推測だが、コストカットのためだったと思う。
ライバルが存在する限り、コストカット戦争はなくならない。一部の船を除いて、コストカットの試行錯誤はなくならないだろう。「撓鉄」技術工は今後も減っていくだろう。
防衛産業はあまりコストを気にしないので防衛産業か、一部の造船所に集約されていく可能性はあると思う。
戦後の復興や高度経済成長の原動力となった日本の造船業。世界に冠たる造船大国への発展を支えてきたのは、分厚い鋼板を火と水で自在に曲げる「撓鉄(ぎょうてつ)」に代表される高い技術力だった。この匠の技を今も磨き続けているのが、兵庫県相生市の造船所「JMUアムテック」だ。建造量では中韓両国の後塵(こうじん)を拝する今、熟練工たちがともすバーナーの炎は「造船ニッポン」復活の光にもみえる。
■ガスバーナーで
相生湾に面して立ち並ぶ工場棟の一角で、ガスバーナーと冷却水のノズルを手に厚さ4センチの鋼板に向かう撓鉄工の北川哲也さん(52)。平成3年入社の熟練職人が、鋼板をバーナーで熱したり、放水して冷やしたりしていくと、平面の分厚い板が徐々に丸みを帯びてくる。
木型を合わせて曲がり具合を確認しながら、その作業を繰り返す。鋼板の表面を高温で熱すると膨張し、その部分を急激に冷やすと加熱前より収縮して曲げが生じる-という仕組みを利用した撓鉄加工。プレスやローラーなどと比べて繊細な曲げ加工が可能なため、船首や船尾など複雑な曲面を持つ船舶の製造にはもってこいの技術だ。
「個々の鋼板やその日の気象条件によって曲がり方が違う。いかに同じような仕上がりに持っていくか、今も考えながら作業に当たっているんです」と話し、青白い炎と水しぶきを分厚い鉄の板に放っていた。
■建造量世界一に
JMUアムテックは、明治40年創業の「播磨船渠(せんきょ)」がその前身。「播磨造船」などと改称したのち、大正5年には日本を代表する商社・鈴木商店が買収、「播磨造船所」として再出発したが、7年に帝国汽船の造船部となり規模を拡大。しかし第一次大戦後の恐慌の影響を受けて10年、神戸製鋼所の播磨造船工場になったが、昭和4年に「播磨造船所」の名で分離独立。国内屈指の造船所に成長していった。
第二次大戦をはさんで昭和35年、戦後最大(当時)となる石川島重工業との合併で「石川島播磨重工業(IHI)」の相生事業所に。37~39年は世界一の建造量を誇った。
だが、造船不況のあおりを受けてIHIは相生事業所の新造船撤退を決定。平成2年にこれらの部門を引き継ぎ「アイ・エイチ・アイ・アムテック」が誕生。親会社の統合によって25年に現社名となった。さらに今年6月、今治造船がJMUの子会社化を発表。アムテックの社名がどうなるか現時点では不明だ。
■次代へ技術継承
「大切にしてきたのは、技術を絶やさず次代に伝えること」。水野昌芳取締役(65)が強調する。
創業から120年近く、常に時代の波に翻弄されつつ生き残ったアムテック。継承してきた撓鉄などの技術力に着目し、船首や船尾などに特化したブロックの製造を事業の大きな柱の一つに掲げた。
造波抵抗を減らすために設ける「バルバスバウ」と呼ばれる船首下部の丸い突起部分は、複雑な3次元曲面で構成され、撓鉄技術が大いに活躍する。各社とも熟練工が減少していく中、バルバスバウなどのブロック製造を請け負い、これまでに製造した船首は約700個にのぼる。世界的にみても突出した数だという。
技術継承のため、ベテランから若手に技を継承する技能マスター制度を平成17年に制定。20年には全国で6カ所目となる技能研修センターを開設した。自社だけでなく地元企業の若手従業員を受け入れ、地域ぐるみでレベル向上を図る取り組みだ。
「ただ、バルバスバウについては順風ではない」と水野さん。船種や運行速度によってはバルバスバウがないほうが燃費向上につながるとされるためだ。
それでも撓鉄の必要性に変わりはなく、技術工を確保するため毎年、若手の採用を続ける。さらに新造船でも、海面の清掃や油の回収などができる「海洋環境整備船」を連続で建造するなど、着実に受注を伸ばしている。撓鉄は造船技術の象徴。バーナーの炎は絶やさずともし続けてほしい。(小林宏之)
内海造船は瀬戸田工場(広島県尾道市)の新造船建造設備を増強する。総額27億円を投じて160トン吊りの塔型クレーン2基を導入する。液化天然ガス(LNG)燃料船をはじめ、従来より重量が増す新燃料船やゼロエミッション船の船体ブロックを効率よく搭載できるようにする。フェリーやRORO船など、自社が得意とする船種の競争力を一段と高める。
【写真】160トン吊りクレーンを導入する瀬戸田工場
現在、瀬戸田工場の船台には130トン吊り2基、60トン吊り2基の塔型クレーンを備えている。このうち60トン吊り2基を160トン吊りに更新する。2028年3月までに工事を完了する見通しだ。
内海造船はフェリーやRORO船で国内トップクラスの建造実績を持つ。二酸化炭素(CO2)の排出量削減を目的として陸上輸送から海上輸送に切り替えるモーダルシフトの一環で需要が期待できる。
現状、フェリーや4万重量トン型バラ積み運搬船(40GC)、RORO船、輸送艦、自動車運搬船などで3年分の手持ち工事を抱えている。
国際海事機関(IMO)が50年ごろまでの国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出ゼロを掲げており、今後は重油燃料船からアンモニアや水素などを燃料とするゼロエミッション船への切り替えが加速する見込み。これらは燃料タンクをはじめ追加設備が必要になる。これに伴い船体ブロックも高重量化する。
内海造船はこの5年間は10数億円の設備投資を継続してきたが、需要の変化に対応して設備投資を積み増す。
July 29 (SeeNews) - The Zagreb Stock Exchange said it will delist shares of shipyard 3. Maj Brodogradiliste on August 28 at the company's request amid ongoing bankruptcy proceedings.
The last trading day for [ZSE:3MAJ] shares is August 27, the bourse said in a press release.
The shipyard has 1,462,140 shares listed on the exchange.
In May, the commercial court in Rijeka opened bankruptcy proceedings against the shipyard after the company’s bank accounts had been blocked for at least 50 days.
The company's shipbuilding business had earlier been transferred to its subsidiary 3. Maj Rijeka 1905, which became state-owned following a 10.3 million euro ($11.9 million) debt-for-equity swap.
The Zagreb bourse placed 3. Maj Brodogradiliste’s stock under its monitoring segment on Monday following the announcement of the delisting.
The shipyard's shares last traded on the Zagreb bourse on June 26, ending flat at 1.98 euro.
($ = 0.863 euro)
By Romania Journal

日本の大学には造船学科は存在せず、工学部や海洋開発の一部として残っているだけ。専門で大学を卒業しても、何も知らない工学部の学生よりはまし程度でしかないと思う。入社してから設計の事を学ぶのは非効率だし、時間もかかる。統合して、同型船で建造するのが一番効率的だと思う。サイズのメリットと効率のメリットに焦点を絞って頑張るしかないと思う。造船所で違いはあるが価格優先で質、信頼性、そして耐久性のコンビネーションで選択が決まると思うので、日本の造船所と言う考え方で統合による効率化は良い選択だと思う。造船所による多少の違いはあった方が、発注者の希望を取り込むには良いかもしれない。ターゲットをどこにおいて設計するかも重要な部分ではあると思う。船やタイプが同じでも、船のスペック次第で、日本を避ける発注者はいる。価格が一番重要であるが、スペックも発注者によっては重要な事はある。ただ、効率の部分はあるので、全てを取り込もうとしない事も重要だし、ターゲットと設計も重要な事もある。
今治造船が成功したには理由があるので、当分の間は、今治造船のやり方が有利かも知れない。全ての発注者を取り込もうする事は無理だと思うので、設計する前にターゲットを考える事が重要だと思う。技術がと言っても、発注者や運航者が評価する事なので、評価されない部分を頑張っても無駄な結果になると思う。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
>日本の造船業は、長年にわたり高い技術力と信頼性で世界に名を馳せてきた
まず、この間違った認識から改める必要があります。
安価なバルクやタンカーでシェアを伸ばしたに過ぎないから
韓国や中国に抜かれた。
北欧の造船所はなぜ生き残っているのか?
本当の「高い技術」があるからです。
日本は技術者の給料を3倍にしないと技術でも韓国中国に抜かれる。
技術者がプライドを持てる待遇をして欲しい。
学生が造船なんて・・・・と思わないような待遇を
日本造船業の反転攻勢
日本の造船業は、長年にわたり高い技術力と信頼性で世界に名を馳せてきた。しかし1990年代以降、中国や韓国の巨大造船所が台頭し、受注競争が激化。建造量シェアで日本は第3位に後退した。
【画像】「なんとぉぉぉぉ!」 これが大手海運の「平均年収」です! グラフで見る(10枚)
こうしたなか、国内最大手の今治造船と第2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU)が、統合に向けて大きく動いた。両社は2025年6月26日、今治造船がJMUの株式を追加取得し、議決権比率を30%から60%へ引き上げたことで、JMUは実質的に子会社となった。
かつて日本は、世界の造船業をリードしていた。1956(昭和31)年には世界一の建造量シェアを記録し、1970~1980年代にはその割合が約5割に達した。技術と生産効率の高さで、日本の造船業は圧倒的な存在感を示していた。
しかし1980年代以降、韓国が新たな大型造船所を相次いで建設。さらに2000年代には中国が急速にシェアを伸ばし、日本は徐々に後退。特に2000年代後半からは両国の物量と価格競争に押され、日本の建造量シェアは現在10%台にとどまっている。
今回の子会社化は、日本の造船業が再び世界市場に挑むための転換点となる可能性を秘めている。
今治造船とJMUの統合戦略
今治造船は愛媛県今治市に本社を置く、日本最大の造船会社である。1901(明治34)年の創業以来、3000隻以上の船舶を建造してきた老舗企業だ。ばら積み船、コンテナ船、タンカーなど多様な船種の建造に強みを持つ。
今治造船グループは国内に複数の工場や造船所を有し、設計から建造、修繕まで一貫したサービスを提供可能だ。高い品質と技術力は国内外の海運会社から高く評価されている。
一方、ジャパンマリンユナイテッド(JMU)は、ユニバーサル造船とアイ・エイチ・アイ マリンユナイテッドの統合により2013(平成25)年に誕生した造船会社だ。両社は日本の重工業を牽引してきたユニバーサル造船(旧日本鋼管造船部門)と石川島播磨重工業(現IHI)造船部門にルーツを持ち、長年にわたる技術蓄積がある。ばら積み貨物船やタンカーに加え、
・液化天然ガス(LNG)船やLPG船といった高付加価値のガス運搬船
・護衛艦などの特殊船
の建造に強みを持つ。国内第2位の規模を誇り、今治造船とともに日本の造船業を支える柱だった。
今治造船とJMUは長らく国内二大造船メーカーとして競争を続けてきた。同時に日本の造船業を支える両輪でもあった。しかし、両社は国際競争力を高めるため、2021年に合弁会社「日本シップヤード」(NSY)を共同出資で設立した。同社はLNG運搬船を除く商船の開発、基本設計、販売を共同で手がける体制を整えている。これにより、日本造船業の競争力強化と効率化が進むことが期待される。
世界4位への再浮上
この統合により、今治造船グループの国内竣工量シェアは5割を超える規模となる。続いて
・大島造船所
・名村造船所
・新来島どっく
がそれぞれ10%前後のシェアを占めており、今治造船グループの圧倒的な影響力が明らかだ。
世界市場に目を向けると、両社の年間建造量合計は約500万総トンに達すると予想される。これはハンファオーシャンを上回り、
「世界4位」
の建造能力となる。さらに、韓国の現代重工業やサムスン重工業に匹敵する競争力を持つことになる。かつて世界シェアの半数以上を占めていた日本造船業が、再び
「世界のトップグループに返り咲く可能性」
が高い。この動きは業界に大きな影響を与えると予想される。まず国内では競争環境が激変し、寡占化が加速するだろう。従来、複数の造船所が受注を巡って競争してきたが、統合により今治造船グループが国内建造量の約半分を占めることで、実質的な寡占状態が形成される。これにより中堅・中小の造船所は、
・ニッチ分野への特化
・今治造船グループとの連携強化
を模索する必要に迫られる。国内競争の縮小は業界効率化を促す一方で、多様なプレイヤーの育成を難しくする可能性もある。
また、国際的には中国・韓国の巨大造船グループとの直接対決が避けられない。特に高付加価値船や特殊専門船種の分野で、これまで以上に激しい受注競争が繰り広げられるだろう。日本造船業の今後は、この競争の中で技術力と効率性をどう磨くかにかかっている。
造船業の再編と規制
今治造船関係者は、
「今までは助走期間だった。子会社化で本当の一枚岩になる」
と語っている(『日本経済新聞』2025年6月27日付け)。NSYとしての共同活動を経て、今後はシナジー効果をさらに高めることが期待される。
・生産効率の向上
・技術力の強化
・調達コストの削減
・マーケティング統合
などがこれまで以上に進む見込みだ。また、NSYの共同出資とは異なり、子会社化により意思決定が迅速化され、スピード感を持った市場展開が可能になる。
造船業界では今回の今治造船によるJMU子会社化のように、過去にも多くの再編や統合が繰り返されてきた。近年では、中国の中国船舶工業集団(CSSC)が吸収合併を重ね、中国最大手として業界を牽引している。一方で、失敗に終わった買収事例も存在する。代表例が
「韓国・大宇造船の買収計画」
だ。2019年に現代重工業グループは大宇造船買収を試みたが、欧州委員会が欧州連合(EU)の合併規則に基づき、LNG運搬船市場での競争低下を懸念して拒否した。このため計画は2022年に白紙撤回されている。
この事例は、造船業における大規模統合が法規制上の複雑な問題をともなうことを示している。本件でも日本国内の競争力低下の懸念が指摘されており、今後の動向には業界全体の注目が集まっている。
日本モデル再評価の兆し
今治造船によるJMUの子会社化は、日本の造船業にとって再生の起爆剤となる一手だ。「日本モデル」と呼ばれる高品質・高信頼の造船技術が、再び世界の舞台で評価される可能性を帯びている。
今回の統合で、国内シェアは大きく拡大し、世界でも第4位の地位へと浮上する見通しだ。技術力、建造規模、そして受注力の三拍子が揃う体制が整いつつある。
だが、規模の追求で終わるなら、この再編は本質的な変革にはつながらない。カギとなるのは、
・低炭素化
・高付加価値化
への確かな取り組みだ。環境規制の強化が進むなかで、持続可能な技術革新をどれだけ具体化できるかが、次の競争軸となる。
今後の成果と行動次第で、日本の造船業は再び世界の主役としての存在感を取り戻すことができる。その意味で今回の子会社化は、企業統合を超えた「構造転換」の起点といえる。
岩城寿也(海事ライター)
【07月23日 KOREA WAVE】韓国の大手造船企業「ハンファオーシャン」がアメリカの子会社ハンファ・フィラデルフィア造船所と手を組み、輸出型LNG運搬船の共同建造に乗り出す。
ハンファオーシャンはこのほど、ハンファ・フィラデルフィア造船所から3480億ウォン規模のLNG運搬船1隻の建造契約を締結し、さらに1隻のオプション契約も同時に確保した。
今回の契約は、ハンファオーシャンの系列会社であるハンファ海運が発注するLNG運搬船の建造について、ハンファ・フィラデルフィア造船所が契約を結んだ後、ハンファオーシャンが下請けとして建造契約を結ぶという構造だ。
このプロジェクトは、1970年代後半以来約50年ぶりにアメリカの造船所に発注された輸出型LNG運搬船。アメリカの造船・海運産業の再建およびエネルギー安全保障強化戦略の一環として推進される。特に米政府が2029年から段階的に施行を予定している「アメリカ産LNG運搬船を活用したアメリカ産LNG輸出輸送の義務化政策」への先制的な対応という点で、その戦略的価値は大きい。
ハンファオーシャンは今回の受注を通じて、北米LNG運搬船市場で独自の技術力と供給主導権を確保することとなった。また、世界で唯一、韓国とアメリカに生産拠点を持つハンファオーシャンは、ハンファ・フィラデルフィア造船所と協力建造体制を構築し、実質的にアメリカでLNG運搬船を建造できる能力を拡充していく。
今回の共同建造を通じて、ハンファオーシャンは韓国の高度な造船技術を段階的にハンファ・フィラデルフィア造船所に移転し、ハンファ・フィラデルフィア造船所は高付加価値船舶分野への事業領域の拡大を図る。特に今回の発注は、ハンファ海運の戦略的判断のもと、ハンファオーシャンは仕事の確保、ハンファ・フィラデルフィア造船所は技術力の獲得という「二兎」を得て、アメリカ市場進出に一歩近づいたとの評価を受けている。
LNG運搬船の建造の大部分はハンファオーシャンの巨済事業場を中心に進められる。ハンファ・フィラデルフィア造船所はアメリカ沿岸警備隊(USCG)やアメリカの法令および海上安全基準を満たすための認証作業などを支援する。アメリカ船籍として登録する必要がある場合、USCG基準の満足と認証作業は必須で、実際にアメリカでの船舶建造経験が豊富なハンファ・フィラデルフィア造船所がこれを主導する。今回のプロジェクトは、両造船所による共同建造モデルとして運営される。
ハンファオーシャン関係者は「ハンファ・フィラデルフィア造船所はアメリカでジョーンズ法の対象となる大型商業船の半数以上を建造してきた中核的な造船所。今回のプロジェクトは、LNG運搬船という難易度の高い船舶分野への拡張を通じてハンファ・フィラデルフィア造船所の技術的力量を一段と引き上げると同時に、ハンファオーシャンのグローバル技術力をアメリカ造船業に融合させる契機になる」と強調した。
急に、アメリカでLNG船の建造なんか出来るわけないと思ったけど、コメントの情報を含めて、体裁だけと言った感じなんだろうね。
韓国の造船所が成功するのかどうか、個人的には全く予想できない。昔、アメリカの映画で日本の自動車メーカーがアメリカの工場で四苦八苦するコメディー映画があったが、車の生産と比べて造船は自動化の部分が少ないから大変だと思う。苦労しても、連続建造が可能なだけの発注があるとも思えない。アメリカの無茶苦茶な要求や発言がなければ、絶対にありえない事。
アメリカ留学した経験があるから言えるが、やはり文化や国の価値観の違いは大きいと思う。アメリカの労働階級は人種も多様だし、韓国や日本の様なやり方は通用しないと思う。後、アメリカ政府がどれほど造船が軌道に乗る事を重要視しているのかわからない。造船と言うか、海軍の維持のために必要と言う事は理解しているとは思うが、それがどのくらい重要なのか、優先順位としてはどの位置なのかでも違ってくると思う。韓国にしても、日本にしても、造船産業は衰えているので同じ事をアメリカが言ってきたとしても、10年後であればもっと衰退していると思う。そうなれば、中国には太刀打ちできないのは確実だし、韓国も余力はなかったと思える。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
ほぼ韓国製造してアメリカ製で登録させたいって、艤装はアメリカでやるのかな?
アメリカの造船技術ってなんとなく大雑把そう。
ハンファオーシャンが所有する米フィリー造船所の実績をつくるために、同じハンファグループの海運系列会社が頼まれて発注しただけ。
よくわからん記事内容。自己満足で結構だが。
ハンファオーシャンが所有する米フィリー造船所がハンファグループの海運系列会社ハンファ海運から液化天然ガス(LNG)運搬船を受注した。フィリー造船所がLNG運搬船を受注したのは初めてだ。
ハンファオーシャンは22日、フィリー造船所(法人名・ハンファフィリーシップヤード)と3480億ウォン(約369億円)規模のLNG運搬船1隻に対する建造契約を締結し追加の1隻に対するオプション契約も確保したと明らかにした。今回の契約はハンファ海運がフィリー造船所にLNG運搬船を発注し、フィリー造船所は親会社であるハンファオーシャンに船舶建造の下請けを任せる形態だ。
契約によると、LNG運搬船建造の相当部分はハンファオーシャン巨済(コジェ)造船所で行われる。まだフィリー造船所はLNG運搬船舶を建造できる資材供給網と人材をそろえられていないためだ。代わりにフィリー造船所はこの船を米国船舶として登録するための現地認証作業を引き受ける。建造が韓国で行われても進水と完成が米国で行われれば米国商船として登録できるというのがハンファオーシャンの見通しだ。
ハンファオーシャン関係者は「LNG運搬船の共同建造を通じハンファオーシャンの技術力がフィリー造船所に移転されるだろう」と期待した。
マリンレジャーで人気のダイビング船で事故が相次ぎ、国土交通省などが安全対策に乗り出す。様々な業者が入り組む「玉石混交」の状態で、国も実態を把握し切れていなかったが、使用の有無を申請させて、実態に合った検査につなげる。安全管理などをまとめたガイドラインも近く公表し、業者やダイビング客に注意を呼び掛ける。
【写真】「乱立」するダイビング船、危険性と注意点は
国交省などによると、ダイビング船は海上運送法の「人の運送をする事業」にあたらず、事業としての国への届け出が不要。遊漁船やプレジャーボートを転用する場合や、ダイビングツアーを行う業者と、船を運航する業者が別々のケースもあり、全国で誰が、何隻を運航しているかも把握できていなかった。
そうしたなか、国に代わって小型船を検査する特別民間法人「日本小型船舶検査機構(JCI)」が近く、船の所有者に対して、船舶安全法に基づいて検査時に申告する項目に「ダイビング目的での船の使用の有無」を追加する。「使う」と答えた場合、ダイビングに使う器材などを考慮して検査する。所管する国交省が近く認可する方針だ。
ダイビング船は空気ボンベなど重い潜水器材を多く積むため、同じ規模でも釣り船などと比べて、乗船可能な定員は少ない。今後はさらに注意を促すが、現状は知識に乏しい業者もいて、転覆事故につながるケースもあった。
祖業の地は今、三菱重工系です。
親会社の常石造船が決断
常石造船(広島県福山市)は2025年6月26日、グループ会社の株式会社三保造船所、神田ドック株式会社、三井E&S造船株式会社、由良ドック株式会社、株式会社三井造船昭島研究所の5社について社名を変更するとともに、造船セグメント全社の企業ロゴを常石グループのグループロゴへ統一すると発表しました。
実施日は6月30日。旧社名と新社名は以下の通りです。
・株式会社三保造船所→常石三保造船株式会社
・神田ドック株式会社→常石呉ドック株式会社
・三井E&S造船株式会社→常石ソリューションズ東京ベイ株式会社
・由良ドック株式会社→常石由良ドック株式会社
・株式会社三井造船昭島研究所→常石造船昭島研究所株式会社
これに伴い、80年以上の歴史を持つ「三井造船」の名称は消滅することになります。
なお、今回の社名変更は、造船セグメントにおける資本構成の見直しに伴うものであり、急速に変化する海事産業の事業環境に対応し、今後も持続的な成長を実現するための取り組みの一環と説明しています。
三井造船は1917(大正6)年11月、三井物産の造船部として岡山県児島郡日比町玉(現在の玉野市)で創業すると、玉造船所として独立したのち、1942(昭和17)年1月に三井造船へと商号変更しています。
その後、1978(昭和53)年6月に昭島研究所(のちの三井造船昭島研究所)を開設。2018年に純粋持株会社化し、三井E&Sホールディングスが誕生するとともに三井E&S造船が生まれています。
しかし、厳しさを増す造船事業に見切りをつけた三井E&Sホールディングスは、2021年に三井E&S造船の艦艇事業を会社分割し、新会社株式を三菱重工業に譲渡するとともに、商船事業を主な事業とする同社株式の49%を常石造船へ譲渡。翌2022年には、常石造船へ三井E&S造船の発行済株式の17%を追加で譲渡していました。
四国は造船所も多いし、船主も多い。最終的に、四国、中国地方、そして九州の造船所が最後まで残るような気がする。日本最大の海事エリアは間違っていないかな。
「日本最大の海事都市を目で見て確かめよう」と、愛媛県今治市にある今治明徳短大の1年生39人が26日、国内最大手の「今治造船」今治工場(同市小浦町)を訪ね、海事都市の現況と製造現場を学んだ。
参加したのは、ライフデザイン学科に学ぶ39人。内訳はミャンマー人28人、日本人8人、中国人3人と留学生が多い。この日は「地域活性化論」講座の一環で訪れ、ほとんどの学生にとって造船所の見学は初めてだった。
まず、映像で造船の概要について学び、今治造船グループの建造量シェアは国内で36%、世界で4・7%に及ぶことや、2月には建造船が3000隻に達したことなどを聞いた。また、今治には造船、海運、金融、保険、教育などの海事関連機関が集まり、日本最大の海事都市を形成していると説明を受けた。
造船現場では、重さ400トンほどのブロックごとに鋼鉄の素材がドックに運び込まれ、つなぎ合わされる場面などを見学した。ミャンマーから留学している男性のアウンチョーナインさん(25)は「大きさにもつくり方にもびっくりしました。ミャンマーの家族にも話して聞かせたい」と興味深そうに語った。
地域活性化論の講座では今後、和船による水軍レースに学生らが参加するほか、特産のタオル工場などを見学して今治の特性を学ぶことにしている。【松倉展人】
中国の造船所の存在がある限り、今治造船のやり方でないと戦えないと思う。船の質は別にして船価で大きく差があれば船主は中国に流れる。しかも中国の場合、中国政府が融資や傭船で中国で船を建造すれば有利な特典を保証しているとの話を聞く。
トランプ大統領が中国建造船に対して負担を課すと言っている時に、行動するのが勝負としてはベストに思える。
日本の他の造船所は合併やグループ化しないと生き残れなくなる可能性が高くなったと思う。(中型及び大型船建造の造船所)効率化で引き離されたら、赤字覚悟で受注するか、他の造船所と設計や工作基準を共有化しか選択肢はないと思う。それでもかなり厳しいと思う。規則やいろいろな規制が厳しくなりすぎだと思う。
日本の大学には造船課はほとんどない。海洋とか、工学部の一部で造船を教えているが、基本的な理論であって、建造とかの専門的な事は教えていない。日本の大学は実戦に関しては欧米に比べてかなり遅れている。造船に関する参考書や専門書にしてもいつの時代の情報やサンプル化と思うほど古い。人材に関してもかなり厳しいだろうね。そういう意味では、効率化と共有化しかないと思う。同じ図面で連続建造すれば、コストは下がるし、効率は上がる。設計の人材がいなくても同じ図面を使うので問題はない。ただ、変わった船や特殊船の建造になれば、昔の船価が参考にならないほどコストアップになると思う。海運会社が持つ船のタイプ次第では代替船の建造が難しく、倒産になるパターンが出てくるかもしれない。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
今治造船はかつての中堅造船会社、一方のJMUは石川島播磨、住友、JFE、日立といった大手が集結してできた会社。それでも縮小均衡には逆らえず今治造船の傘下に。
昔の人が聞いたらひっくり返りそうな結果になりましたね
今治造船はJMUが抱える防衛省案件を欲しがっている、重工2社は造船なんて切り離したい。
両社の利害が一致した結果か?しかしJMUの経営に一族経営の会社が口を出す状態はJMUにとってもまた国防のとっても不幸な結果になりそうですな。
造船最大手の今治造船(愛媛県今治市)は26日、2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU)への出資比率を6割に引き上げ、子会社化すると発表した。JMUへの出資比率は今治造船が30%、JFEホールディングス(HD)とIHIが35%ずつで、JFEとIHIから株式を取得する。
【写真】ドック内ではコンテナ船の建造が進んでいた(2024年3月、JMU津事業所で)
取得額は非公表。JMUとの連携を強化することで、中国・韓国勢に対抗する。
効率だけを考えれば、ベストに近い選択だと思う。今後、建造や設計などの全ての基準を今治造船の基準に合わせると思う。同じ設計や仕様で建造した方が効率は良いし、メーカーとの価格交渉にも有利であろう。ただ、船の質を下げる方向へ向かう造船所は残念に思うかもしれないが、昔を知っている人達はそんなに多くないので、今治造船の事しか知らない人達が増えるだろう。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
運搬船とか中国、韓国と国際価格で勝負する分野はスケールメリットでコストカットやるしかないからね
一方自衛隊向けの艦艇は、三菱重工やIHIがやるのだろうな
今後も商船を造る所は吸収合併が行われるだろう
JMUには日本鋼管も加わってますね。大きい会社でしたが合併で
名前が消えて知ってる人も少なくなりました。
国内造船首位の今治造船(愛媛県今治市)は26日、2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市)への出資比率を現状の30%から60%に引き上げ、子会社化すると発表した。
糸魚川市のタンカー船を運行する会社が、新潟地裁高田支部から破産開始の決定を受けたことがわかりました。
民間の信用調査会社「帝国データバンク」によりますと、糸魚川市の「山弘海運」は2017年3月に設立され、糸魚川市の姫川港に停泊するタンカー船を中心に運行業務を請け負い、2024年2月期には年収入高約1億6500万円を計上していました。しかし、以前から厳しい収益環境が続いていたなかで前代表が死去。その後、現代表が代表に就任するも先行きの見通しが立たず、今回の措置となったということです。負債は、約2600万円とみられています。
軍とか、海上自衛隊の船の修理や建造は国家保安やセキュリティーの問題があるから簡単ではないと思うよ。中央日報の記者はどこまで理解しているのか知らないけど、日本だって外国人労働者がいる。中国人の労働者も結構、日本の造船所で働いている。アメリカ軍の仕事を貰えば、中国人労働者を排除する必要があるかもしれない。誰がスパイなのか、スパイでなくても、誰が情報を売るかわからない。いろいろな管理やセキュリティーの事を考えると、それなりの仕事が貰えないのなら関わらない方が良いかもしれない。
アメリカに中国建造商船にかんして高い入港税なり、高額な追加費用を長期間、継続するように頼んだ方が一般商船の仕事は増えると思う。
米国海軍艦艇維持・整備・補修(MRO)市場に中型造船会社まで飛び込んでいる。受注量の減少で新しい事業が必要であるうえ、MRO市場が米艦艇建造市場まで拡張する可能性があるという期待のためだ。
造船業界によると、HJ重工業とSKオーシャンプラントがMRO事業進出を宣言した中、大韓造船とケイ造船も進出を検討している。昨年、中型造船会社の業績は悪くなかった。大韓造船とケイ造船、HJ重工業など中型造船3社は造船業「スーパーサイクル」を迎え、昨年は黒字を出した。大韓造船は昨年、営業利益が1581億ウォンで、営業利益率は14.7%と過去最高だった。ケイ造船とHJ重工業(造船部門)は営業損失から抜け出した。
しかし楽観はできない。昨年の受注量が前年比で減少したからだ。韓国輸出入銀行海外経済研究所が発表した報告書「2024年中型造船産業動向および示唆点」によると、国内中型造船会社の昨年の受注量はタンカー25万CGT(標準貨物船換算トン数)と、前年比で40.8%減少した。年末基準の受注残高も前年比4.6%減少した。報告書は「建造量を大きく超過する受注を達成できなかった」と指摘した。
こうした状況でMROは中型造船所の新たな事業として注目されている。米海軍MRO事業は現在のところ特定「免許」が必要ない。大型造船所を除いて米MRO事業への公式進出を宣言した造船会社はHJ重工業とSKオーシャンプラントだ。両社は韓国防衛産業企業の免許は持つが、米海軍艦艇整備協約(MSRA)は取得前だ。
今年1月、米国は非戦闘艦MRO事業にMSRAがなくても入札できるよう規定を変えた。16日の企業説明会で米海軍MRO事業進出を発表したSKオーシャンプラントの関係者は「規模が小さい韓国護衛艦と警備艦の建造・修理経験が豊富であり、米海軍MRO事業も十分に可能」と説明した。ケイ造船と大韓造船はMRO事業への進出を検討している。ケイ造船の関係者は「MRO事業には防衛産業免許が必要でなく、過去に特殊船建造経験があり、進出を計画中」と話した。
ある造船業界の関係者は「MROをカーセンターの概念でみると、バンパーだけを交換する修理もあり、全体的な修理もある」とし「参加会社が多様化し、今後MRO物量も増えれば、大手は大手、中堅は中堅で各規模に合う事業を引き受けることができるだろう」と述べた。
Sam Chambers
The Japanese government will issue a major new shipbuilding directive next month, aimed to revive an industry it used to lead the world in, as well as using the nation’s yards as a bargaining chip in trade talks with the Donald Trump administration in the US.
Using the 2022-promulgated Economic Security Promotion Act, Tokyo will aim to revive dormant shipbuilding and repair docks and support the construction of new shipbuilding facilties both at home and overseas.
Tokyo and Washington are also close to establishing a Japan-US Shipbuilding Revitalization Fund, with Japanese yards pitching to build car carriers and LNG vessels, as well as investing in yards in the US.
The two nations are also discussing naval ships and icebreakers, as well as ways to build a maritime supply chain between Japan and the US that is not dependent on China.
China currently holds 70% of global shipbuilding capacity and nearly 90% of repair capacity. Japan’s share of shipbuilding volume was about 50% in the early 1990s, but has now fallen to around 10%.
Both Japan and South Korea have been holding many meetings with US officials in recent months to try and pivot away from China’s maritime dominance. In October, the Trump administration is set to enact increased port fees on Chinese-linked tonnage calling in the US, one of a host of measures the US government is taking to try and curb China’s growing maritime power.
OHKが週末に配信した主なニュースから、関心の高かったものを紹介します。
【1位】飲食店の「ふ~太」など運営…F管理(旧:風来坊)など2社破産開始 負債約5億7000万円か【岡山】(5/9)
【2位】三井E&S 造船から撤退 造船会社全株式を常石造船に譲渡 造船は玉野で創業100年以上の歴史【岡山】(5/7)
【3位】JR西日本グループのホテル会社 ホテルグランヴィア岡山の運営会社など4社吸収合併へ【岡山】 (5/7)
【4位】母親と男児2人が車にはねられ、母親死亡 過失運転致傷の現行犯で20歳の女逮捕【香川】(5/7)
【5位】JFEホールディングスが中期経営計画公表 西日本製鉄所では福山地区の第4高炉完全休止へ(5/8)
<OHKWEB調べ>
岡山放送
アメリカのように軍の船を建造できないようになっては困るので大規模な投資をするのだろう。軍事力を考えると無駄でも投資が必要と言う事だろう。
船は直ぐに建造できるものではないから、そう言う意味では防衛のためのコストを言う考えなのだろう。商船的に考えると無駄とは思えるけど。
記事にはなっていないけど、大型船を建造する日本の造船所には問い合わせが来ているのでは?
工期を短く出来れば、儲かるかも?トランプ大統領の任期が終わるまでの話なのか?それともその後も継続するのか?
日本は世界の船隊に占める保有船のシェアが12%で、保有船腹量ランキング(重量トンベース)は中国、ギリシャに次ぐ世界3位となっている。国際海運団体BIMCO(ボルチック国際海運協議会)の統計によると、日本の足元の船腹量は約2億8800万重量トンになる計算。このうち半分弱を大手邦船オペレーター(運航船社)が拠点を置く東京が占め、約3分の1を専業船主が集積する今治(愛媛県)が占める。BIMCOは日本の船主と造船所について、「米国による中国保有船・建造船への入港料導入で利益がもたらされる可能性がある」と分析する。
BIMCOによると、世界全体の足元の船腹量は24億重量トン。これを178カ国・1万6622社の船主が保有しており、このうち日本船主は船隊規模115重量トンから2860万重量トンまでの604社になる。
世界の船隊に占める日本船主の船種別のシェアはグラフの通り。
地域別では、邦船大手3社など複数の有力オーナーオペレーター(船主兼運航船社)が拠点を構える東京の船主が、日本の船腹量の48%を保有。東京は保有船腹量で国内1位であるほか、世界4位の都市となっている。船種別では、邦船大手3社が保有する世界最大のガス船隊が目立つ。
国内2位は、112社の専業船主が集積する今治地区。今治は保有船腹量で世界6位であり、5位のシンガポールに僅差で迫っているという。
BIMCOは今治を拠点とする船主として、日鮮海運、今治造船グループの正栄汽船、瑞穂産業を挙げた上で、「今治船主はバルカーとコンテナ船で世界でも大きなシェアを持つが、タンカー部門への関与はあまり大きくない」としている。
世界の保有船腹量ランキングでは2023年、中国が10年間首位だったギリシャを抜いて初めて1位に浮上し、世界最大の船舶保有国となった。
ギリシャ船主はリーマン・ショック後の海運不況時、強力な資金力を生かして市況循環とは逆に船舶投資を拡大。13年に日本船主の保有船腹量を上回って以来、22年まで保有船腹量世界トップを維持してきた。
中国船主は15年以降、船舶投資を加速し、18年に日本船主の保有船腹量を超えて以来、ギリシャ船主を上回るペースで船隊を拡大した。
日本海事新聞
アメリカに自動車工場を作るか、アメリカの造船所に自動車運搬船を発注するかしかないだろう。
韓国の造船所がアメリカの造船所を買収したから、韓国から多くの技術者と現場の生え抜きを連れて、建造を始めたら船は造れるんじゃないのかな?
ほとんどの買い物は海外製になるし、韓国で建造されている船の多くの偽装品は中国から輸入されていたから、建造出来てもかなり高い船価になるだろう。韓国製品だけでなんとかなるのか?
Lisa Baertlein
[ニューオーリンズ 25日 ロイター] - 米通商代表部(USTR)が外国で建造された全ての自動車運搬船に入港料を課す計画を公表したことを受け、海運会社が救済措置を求めていることが複数の関係者の話で分かった。
この措置はUSTRが17日、米国の造船業を復活させ、海運業界における中国の支配力を低下させるため中国に関連する一部船舶に入港料を課す取り組みの一環として発表した。2月の当初案では言及されていなかった。
具体的には、外国で建造された自動車船を対象に、積載できる車両1台当たり150ドルを10月14日から徴収する計画。6000台を輸送できる船舶の場合、入港料は90万ドルとなる。
中国で建造された船舶や中国が所有する船舶にとどまらない内容となったため、業界に衝撃が広がった。自動車船を利用する顧客の大きな費用増につながる可能性もある。
世界海運評議会はほぼ全ての自動車船が入港料の対象になるとし、意図しない影響をもたらすと警告している。
弁護士や業界団体関係者は、懸念について協議するためUSTRに会合を要請したと述べた。USTRは業界代表と面会するかコメントしていない。
アルファライナーによると、現在運航されている自動車船1466隻のうち、米国で建造されたのは39隻にとどまる。
(ブルームバーグ): トランプ政権は今月、米国の港湾に入港する中国船籍の船舶への課税案をさらに推し進め、建造された国を問わず外国の自動車輸送船も入港料賦課の対象とする計画を打ち出した。
ノルウェーの首都オスロに本社を置く自動車輸送会社ホーグ・オートライナーズは米国の入港料賦課計画により、同社に最大7000万ドル(約100億円)のコストが発生する恐れがあると明らかにした。同社によれば、米国に寄港する船舶1隻当たり最大100万ドルのコストが見込まれるという。
アンドレアス・エンガー最高経営責任者(CEO)は決算説明会で、入港料の補償を求める可能性に言及。コスト抑制に向け、運航のスケジュールやパターンを調整する公算が大きいと述べた。
原題:Auto Carrier Sees Worst-Case $70 Million Hit From US Port Fees(抜粋)
米通商代表部(USTR)が先週発表した中国関係船などに対する入港料徴収について、米国以外で建造された自動車船に入港料を課すことが唐突に盛り込まれたことで、海運関係者の間に困惑が広がっている。米国の港湾に寄港するほぼ全ての自動車船に手数料の支払いが求められることになる。
非米国建造自動車船に対する入港料は、当該船舶の輸送能力に応じて徴収される。入港料は1CEU(標準車換算積載量)当たり150ドルで、大型船の6000―7000台積みの場合は90万―105万ドル(約1・3億―1・5億円)。
USTRは米国造船所での自動車船建造を促すことが狙いとしている。入港料は寄港地ごとではなく、1航海ごとに課される模様だ。180日後から徴収が始まる。
米国の造船所に自動車船を発注し建造すれば、最大3年間、入港料が免除されるとの規定もある。ただ、「免除の条件は現実的ではない」(自動車船関係者)。
自動車船の世界の船腹量は約840隻。そのうち米国船籍の自動車船は一定数あるものの、新たな入港料の対象から除外される米国建造船は皆無とみられる。
半年後からは、邦船大手を含む自動車船オペレーター(運航会社)が米国向けの輸送サービスを提供するたびに入港料が発生することになる。
自動車船オペの入港料負担は大きくなりそうだ。米国の自動車販売市場が大きい上、海上輸送を利用した輸入台数も多い。邦船勢は日本からのほか、欧州や中南米から配船している自動車船もある。
米国が導入する中国関係船などに対する入港料は、中国が海運・物流・造船分野で支配的な地位を占めることに対する措置になる。USTRは2月に入港料案を公表した。
2月に公表した案には、中国関係船ではない自動車船に入港料を課す案はなかった。そのため、中国建造船比率が低い邦船社の自動車船事業への影響は軽微にとどまるとみられていた。
USTRは今回、自動車船に関してのみ中国関係船だけでなく、日本や韓国などの造船所で建造されたものにも入港料を課す方針を打ち出した。「米国向けサービスを提供する限り、入港料徴収から逃れられなくなった」(海運関係者)
世界海運評議会(WSC)は18日、USTRが導入する入港料に対し深刻な懸念を表明。自動車船に対する新たな措置に関しては、「今回の恣意(しい)的な行動は全ての海外建造船を対象とするもので、米国の消費者にとって自動車価格の上昇につながる一方で、米国の海事関連投資を促進する効果は乏しい」と非難した。
米通商代表部(USTR)は17日、中国籍の船舶や中国製の船舶に対する入港料の課徴を含む措置を発表した。これには、外国製の自動車運搬船や将来的にはLNG船に対する追加措置も含まれる。
USTRは通商法301条(外国の不公正な貿易慣行に対して米国が制裁措置を講じる条項)について1年間にわたり基づく調査を行い、米国の通商を圧迫していると判断。その根拠を報告書として公表し、これに基づく措置として入港料を課すこととした。
USTRの提案では入港料は2段階に分けて課され、第1段階として180日後に中国の船舶所有者や運航者、中国製船舶に対する料金は純トン数に基づき、今後数年間にわたって段階的に増加する。さらに米国建造の自動車運搬船を奨励するため、中国以外の外国で建造された自動車運搬船に対しても、積載能力に基づく料金を課すとした。
第2段階として3年後に、米国製液化天然ガス(LNG)船の優遇措置として、3年後から、米国製のLNG船の使用を促進するため、外国船によるLNG輸送に対する制限を導入し、22年間かけて段階的に強化するとした。

問題が長期化すれば、韓国や日本の造船業にとってはメリットになるだろう。コンテナ船に関しては今治造船に大きなメリットがあると思う。他の日本の造船所はそれなりのメリットがあるだろう。中国に合弁造船所がある三井や川崎はデメリットが大きいだろう。

これで日本と韓国に見積もりの問い合わせがたくさん来るだろう。そして、中古の韓国及び日本建造船の価値が上がるだろう。
日本が出来る事はお互いの造船所で図面を融通し合って、出来るだけ効率良く同型船を建造し、納期を短くする事で利益を出す事だろう。日本の建造能力は少ない。多くの発注が来ても能力的に無理だろう。連続建造で効率を上げるしかないだろう。大型船を建造する造船所はかなり恩恵を受けるけど、小型船を建造する造船所にはあまりメリットがないだろう。中型船を建造する造船所はメリットはあるけど、大型船を建造する造船所のようなメリットはないだろう。
韓国の造船所は儲けたお金でアメリカの造船所を購入して、海軍の代替船を建造できるように準備するのかな?この部分が「”中国船” アメリカ寄港に手数料徴収へ」に含まれているのなら、ある一定の期間はこの政策は続きそうな気がする。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
中国が保有・運航する船や中国で建造された船が、アメリカに寄港する場合に手数料を徴収する方針を発表しました。だけどこれアメリカ国民が輸入しているものだからその分価格が上がりアメリカ国民の負担が増えるiPhoneだって慌てて免除した。
>アメリカの造船業を再生するためとしていますが
もはやアメリカの造船業は設備も技術も人材も金もノウハウもない。
自国の海軍艦船のメンテナンスすらろくにできず老朽化一方のアメリカ海軍。
「再生」とのお題目だけじゃなく、いつ、誰が、どうやってまでを発表しない(できない)のがポピュリズム政権の虚勢。
それに踊らされるのが勇ましげな言葉だけで感情論に走る無知性。
アメリカを「再生」するなら、まずは教育の復活からだろうが、教育が復活すればトランプのようなポピュリストは消えるだろう。
少数与党さん、もう、米中戦争は、始まっているにです
中国詣ですることのリスクを考えてください
選挙に行かない国民の半数よ、もう、無知、無関心、無責任で 無投票を続けるのを止めてください 金持ち喧嘩せずの時代は終わりました
今の売国イミン政策による金儲け大好きの少数与党と、外国人参政権を狙う最大野党が、日本人の生命と財産を本気で守る気があると思いますか?
日本人の生命と財産を本気で守る気概のあある政党に投票してください それが、あなたやあなたの子供の命を守ることに繋がります
政治への無知、無関心、無責任、無投票は、あなたや家族の生命と財産を危険にさらします
最近の外国人犯罪、トラブル、異常だと思いませんか? 再エネ賦課金で苦しんでいるのは誰ですか、儲かっているのはどこの国ですか
トランプ政権が中国に新たな圧力です。
USTR=アメリカ通商代表部は海運や造船の分野で中国が独占的支配を強めているとして、中国が保有・運航する船や中国で建造された船が、アメリカに寄港する場合に手数料を徴収する方針を発表しました。
不公正な貿易相手国に対抗する通商法301条に基づいた措置で、180日後から徴収するということです。
アメリカの造船業を再生するためとしていますが、関税政策で対立する両国の新たな火種となりそうです。
テレビ朝日報道局
出入国在留管理庁は25日、造船大手の今治造船(愛媛県今治市)について、技能実習生を受け入れるための実習計画の認定を取り消したと発表した。労働安全衛生法違反に問われて罰金刑が確定したことが、実習計画の取り消し事由にあたると判断した。取り消された計画は2134件で、1事業者あたりの取り消し件数としては過去最多という。
【イラスト】25年後、日本は外国人が1割? 地方で進む「開国」と「争奪戦」
同社は25日から5年間、技能実習生の受け入れができなくなる。技能実習制度に代わって2027年までに始まる育成就労制度の労働者も受け入れられない。入管庁は、同社が罰金刑を受けた違反の具体的な内容については明らかにしていない。
技能実習生を受け入れるには、実習生ごとに実習計画を作成し、外国人技能実習機構の認定を受ける必要がある。技能実習法は、認定した計画の通りに実習が実施されていない場合や、出入国や労働に関する法令違反があった場合などに、計画の認定を取り消すことができると規定している。
同法に基づいて、事業者の実習計画が取り消された件数は18年度以降で計9346件ある。主要企業では、19年に三菱自動車やパナソニックが認定の取り消しを受けている。(久保田一道)
「船の検査」と書かれているけどどんな検査していたのだろうか?それなりの大きさの造船所の従業員は装備としてはやっていると思う。ただ、いつ、どのように使う基準になっているのかは知らない。下請けで危険な作業をしない人達はフックなんてしていない。階段を使う時は、多くの人達がいる場合は、一緒に行かず、上がり切ったのを見てから上がる。仮設の通路や階段がどのくらいの重さまで持つのか知らないし、錆びている場所だってある。計算されていたとしても、腐食していない時と腐食後では強度だって違うはずだと思う。
数分、待って安全率が高くなるのなら待つ方が良いと思う。船は大きかったら、落ちたらもう終わりだと思う。古い船に行くと溶接部に亀裂があったり、腐食して強度がなかったり、損傷して溶接部が外れていたりするから、少し力を入れたぐらいで動かない事を確認しながらはしごとか、手すりを使わなければならない。確認しないで普通に使う人がいるけど、運が悪いと終わりだと個人的には思っている。書類で事故の責任を一切問わないとサインを要求される事はある。日本ではそんな事を要求しないから、危険を感じないのだろうけど、外国は結構、うるさい。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
安全器具を装着していたなら、亡くなられた方の使い方が悪かったとしか言えない。例えばフックを掛け忘れていたとか。40代なら小さな子供がいるかも知れないし、遺族の方に配慮されてください。
運が悪けりゃ1メートルの脚立から
落ちても死亡事故になるし。
西海市大島町の大島造船所の工場で15日午前、40代の男性作業員が倒れているのが発見されました。男性は意識不明の状態で病院に搬送されましたが、警察によりますと16日午前3時半ごろに死亡が確認されました。
男性は建造された船の検査をしていたところ、高さ約4mの場所から転落したとみられていて、安全器具は身に着けていたということです。
テレビ長崎
新造船と既存船の整備では要求される能力、経験、そして知識が違うと個人的には思う。整備、修理、そして維持管理だと馬鹿なければ経験の方が重要だと思う。慣れていないとどこが問題なのか感や経験で推測できない。いろいろな船やメーカーに精通していないと分解の仕方、整備の仕方、問題などの情報が違うので時間をかければ同じ結果とはならない可能性が高い。鉄板の部分の切り替えや修復ならコストが安い造船所や国での整備でも良いが、稼働する機器になると整備しようとして壊す事がある。実際にそのような話は過去の中国でドック(整備を受けた)した船から結構聞いた。ドックのコストが安いし、会社が決めるから仕方が無いと言う船員達は多かった。最近は、そのような話はあまり聞かなくなったので、多少は、経験を積んだり、同じ作業を繰返す事で良くなったのだろうと思う。
昔は韓国でドックすると言う話は聞いたが、大型船に関してはそのような話は聞かない。もう韓国でドックするという話は、小型から中型の船しかないのだろう。
そのような状況なので、韓国で米軍の船を整備しても期待できるような結果は得られないと思う。
日本では特定のエリアでは米軍の船の整備や修理を行っているので、ドックに関しては、値段を無視すれば日本の方が安定した整備をするだろうと思う。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
ラーム・エマニュエル駐日米大使は19日、米海軍艦船の大規模修理を日本の民間会社に委託するために、日米で作業部会を発足させたことを明らかにした。対象は、米海軍横須賀基地(神奈川県)に司令部を置く第7艦隊所属の艦船。最初の修理は佐世保基地(長崎県)に配備されている揚陸艦「ニューオーリンズ」(満載排水量2万5000トン)で、1月末までに開始するという。
まぁこれの延長だろう
試しに非戦闘艦でやらせてみて結果を見てみようと言うことだと思うし、韓国では戦闘艦の整備はやらせないと思う
米海軍軍需支援艦「ウォリー・シラー号」は、退役まじかの老朽艦です。
戦闘艦艇と云うよりも、後方支援の補給艦(貨物船)です。
機密情報もない船なので、コスパを考えて韓国に補修整備を発注したのでしょう。
>「米海軍側が『日本の造船会社はこのようにしないのに韓国は違う』と驚いた」
→それは、そうでしょう。日本の造船会社なら最初から損傷箇所の修理も織り込んで金額提示するでしょうね。いい加減な見積で安い、早いと言って契約取って、後から増額、工期延長するような事は致しませんから。
米海軍に嫌味を言われた事にもしかしてお気づきでは無い???
古い輸送艦一隻の整備改修に50億か。
要するに三ヶ月の予定の整備が半年かかったってことですね。
韓国は北朝鮮と戦争中の国です。
もし、停戦が破られた場合、ドッグで修理中の軍艦はすぐに出航という訳にはいきません。
予定が三ヶ月伸びればリスクもそれだけ増えます・・・
「艦艇整備中にも作戦にすぐ投入できる韓国の地政学的位置も受注可能性を高めるだろう」
この軍事学科の教授ってのは馬鹿なんですかね?
まあ、米海軍軍需支援艦みたいな非戦闘艦ならともかく高度な技術と機密がある戦闘艦を紛争地帯で中国と通じているような国に任せることはないでしょうね。
ハンファオーシャンが韓国造船会社の中で初めて米国海軍艦艇維持・補修・整備(MRO)事業を完了した。米国が海軍力強化のため、老朽化した軍艦の整備に拍車をかけており、韓国造船会社の追加受注への期待感が高まっている。
ハンファオーシャンは13日、米海軍軍需支援艦「ウォリー・シラー(Wally Schirra)号」が整備を終え、この日慶尚南道巨済(キョンサンナムド・コジェ)造船所から出港したと明らかにした。ウォリー・シラー号が昨年9月2日に入港して193日、約6カ月ぶりのことだ。ウォリー・シラー号は貨物・弾薬・燃料などを戦闘艦に供給する非戦闘艦で、排水量約4万トン(t)級、全長・全幅がそれぞれ210メートル、32.3メートルに達する大型艦艇だ。
ハンファオーシャンは今回の「窓整備(創整備)」で船体などの外観を整備し、フレームなどの内部構造物を分解して整備した後、再度組み立てした。当初約3カ月がかかると予想したが、整備の途中に船体内の損傷部位を発見し、今年初めに米海軍に知らせ、追加契約で整備を3カ月延長した。ハンファオーシャンの関係者は「米海軍側が『日本の造船会社はこのようにしないのに韓国は違う』と驚いた」と伝えた。業界ではハンファオーシャンが従来の契約(約200億ウォン)に追加整備契約(約300億ウォン)まで計500億ウォン(約50億7000万円)以上を稼いだとみられる。
米軍事海上輸送司令部のパトリック・ムーア韓国派遣隊長はこの日の出港式で「今後も協力関係を強化する多くの機会があるだろう」と述べた。大慶(テギョン)大学軍事学科のキム・ギウォン教授は「艦艇整備中にも作戦にすぐ投入できる韓国の地政学的位置も受注可能性を高めるだろう」と説明した。ハンファオーシャンは今年5~6件、HD現代は2~3件のMRO事業受注を目指す。
かなり昔の話だが、IHIと呼ばれる造船所に大型タンカーを何隻も発注した、発展途上国の船主が自国で造船所を作って船を作ろうと考えた。大型クレーン、建屋のあるブロック工場、油圧でブロックを流れ作業で移動できるシステム、そして船に載せる一万馬力を超える主機がバージの載せられて到着した。準備が出来たと建造しようとしたが、誰も船の建造の経験がないので建造できないと言う話になった。その場所に一度連れて行ってもらった。一万馬力を超える主機がバージに10年以上の乗ったままだった。そのうちに建造できるだろうとおもっていたらしいが、10年経っても建造できず、他の造船所から発注されるブロックだけは細々と作っていた。
造船学科を卒業した学生が多く雇用されたが、理論だけで経験がないので大型船を建造する自信がなかったそうだ。学歴は大切かも知れないが、業種や業界、そして特定の仕事については経験や実勢が重要である事を理解できないかったと言う例だろう。
アメリカの造船所に関しても同じ事は言えると思う。新造船を経験していないアメリカ人労働者を採用して米軍の船を建造するのはかなり難しいと思う。また、アメリはメートルやキログラムのSI単位ではなく、フィートやパウンドの単位が使われる事が多い。
モノづくりでは新しいやり方や新しい技術を導入し、生産性を上げる事が必要とは思うが、新しいやり方は問題が起きるリスクがあるので時間的にゆとりがあるとか、リスクが発生しても対応できる環境がないと難しいデメリットがある。同じ事を繰返していれば、過去の経験や情報に蓄積から問題を予測できるし、問題が起きても対応の仕方がわかっているので問題が起きても大きな問題にならない可能性は高い。デメリットは同じ事を繰返していると、新しいやり方で成功した国や企業に負けるリスクが存在する事。そして効率は上がらない。
アメリカだけの問題ではなく、将来、日本でも同じ事は起きると思う。アメリカでは造船だけでなく、海運でも同じ事が言える。アメリカ人船員はほとんどいない。かなり高齢のアメリカ人監督と話した時には、2つの問題があると言っていた。アメリカ人船員の待遇向上が結果的に首を絞めた。アメリカ人船員の労働条件を向上させたことはアメリカ船員達には歓迎されたが、結局は、コスト高につながり、コストや国際競争を考えるとアメリカ船員は使わない海運会社が増えた。アメリカ人船員が少なくなると監督も少なくなる。人材が減ると教育しなくても仕事が出来る外国人を採用するようになる会社が増えた。アメリカで登記された会社なのに従業員の8割以上がアメリカ生まれではない、グリーンカードやアメリカ国籍を取得した人達になり、本当にアメリカの会社なのかと思うようになったと言っていた。第二次世界大戦後は海軍から除隊した経験豊富な船員がたくさんいた。その状況を当然のように思い、アメリカ人船員達の減少が明らかになっても有効な対策を得られなかった。聞いた話の全てが問題の原因なのかは知らないが、アメリカの海運は弱っているのは事実のようだ。
アメリカで内航船を見ると船齢が高い船や設計やデザインが古臭い船が多い。過保護と言うか、守られ過ぎると競争力がガラパゴス的になり競争力を完全に失う結果になる傾向が高いと言う事だろう。
物事の判断は判断基準、マイクロ的、マクロ的、将来的な部分、また、競争相手など様々な条件次第で正解は変わってくると思う。日本の海運や造船が衰退に向かっているのは事実だと思うが、それでも、必要と思えば、効率や統合、そして効率のための協力や共通部分の拡大など対応は取るべきだと思う。
イギリスのタイタニックを建造した造船所が再び、倒産したそうだ。国際競争力はないらしいが、自国での建造能力維持のために政府が救済するらしい。イギリスで建造した小型空母は故障が多く、ドックにいる方が長いらしい。ウクライナとロシアの戦闘で軍事力はなくてはならない意識が高まったと思うし、老朽化した軍事装備のリプレイスには生産及び製造能力なくしては不可能であると言う事を理解した国々が増えたと言う事だろう。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
まあ造船業の世界シェアはが中国が5割超、新規受注にいたっては7割強という話もあるので、それに対抗するためにこういう話が出てくるのは自然の流れでしょう。
選ばれるのが韓国かはともかく、米国内の造船に投資していては中国との競争に間に合わないのは間違いないと思います。
本来はこういう時に日本が手をあげたいところではあるんですが、人手不足や技術流出リスクやらで応えられなさそうなのが残念なところですね。
太平洋戦争時はアメリカ各地の造船所で空母、駆逐艦が多く作られ、
「月刊正規空母」「週刊護衛空母」「日刊駆逐艦」と言われるくらいのペースで建造されていったけれども、現在はアメリカの造船所は太平洋戦争時に比べて大幅に減ったうえに、軍艦自体も大きくなったので当然建造のペースも遅くなるのは当たり前でしょう。
軍用を造船できるのは日本では2社で自衛隊の予定が埋まっているからアメリカから受注は不可能。
では造船所増やす、改修工事で場所を確保しても造船作業員がいないから無理です。熟練した技術を要する為準備が必要となる。
造船所を増やせば継続的に受注がないと赤字と失業者を出す。
韓国にはこの考えがないから必死に受注したがっている。
最初にアメリカの憲法か法律で軍艦は他国での建造を禁止している。
工業を捨てた国の末路だな。
アメリカの国際収支は
・サービス収支、所得収支、投資収支が黒字
・貿易赤字が飛び抜けて赤字
という構造。
アメリカは、IT等で金を稼ぎ、外国での投資で利益を稼ぎ、さらに外国から自国に米国債等にたくさんお金が流入しているのに、それらの金を全て外国からの物の輸入に使っている状態。
しかも今は低失業率。つまり自国の生産力を限界まで使ってこの状態。戦争という莫大な物の消費に耐えられる経済構造ではない。1980年代の日米貿易摩擦の頃とは構造が全然違う。
ここの議論で、商船と艦艇の違いが全く抜け落ちている。
ある程度の性能で良ければ建造にはそれほどの日数はかからないが、艦艇は別物です。米戦略国際問題研究所(CSIS)がそんなに韓国の艦艇が優れていると評価していることに疑問を感じるのですが、世界的にはそんな評価なのですかね。
韓国の造船に関する内情はひどいようですよ。
大字が経営が傾き、現代が造船業に進出したようですが、技術の継承もなく未経験者を使って製造した為に、2015年製造の船舶はトラブルが多く、それ以降も大型船の船体基部を中国に外注しているのもバレましたし。2015年生のトラブルで有名なのは操船不能になった上に、全電源喪失を起こして其の儘の状態で大型の橋の橋脚などに激突しています。
日本の佐世保でも造船しないのかな?
調べてみたら、補修と修理だけとか。
韓国は釜山の左下になんかそういう島あるよね。
日韓で造るべき。トランプのことだから、費用負担しろとか言ってきそうだけど
米国の専門家の間で「韓日など同盟国の船舶建造能力を強化し、これらが米海軍の艦艇を作るようにしなければならない」という分析が出てきた。トランプ米大統領の主張通りに米国の造船業を育成するだけでは中国との軍備競争で勝つのは難しいという危機意識が反映されたとみられる。
【写真】艦艇整備に向け韓国に入港した米海軍の補給艦「ウォリー・シラー」
米戦略国際問題研究所(CSIS)は11日に発刊した「船舶戦争」という報告書で、米軍艦の確保に向けた「フレンドショアリング」案を提示した。フレンドショアリングは友達(フレンド)と企業の生産施設(ショアリング)の合成語で、信頼できる同盟国と細かな供給網を構築することを意味する。報告書は「投資共助と政策的インセンティブを通じて日本、韓国、欧州などの船舶建造能力を強化しなければならない」と強調した。特に韓日を「核心国」としてこれらが米国の造船業に投資するよう積極的に奨励すべきともした。
米議会調査局(CRS)の海軍専門家ロナルド・オルーク氏もこの日、下院軍事委員会海軍力小委員会の公聴会に出した報告書で同様の提言を出した。彼は「軍艦艇や艦艇の一部を日本や韓国、欧州など同盟国の造船所で建造しなければならない。米国の法律でこれを禁止しているが、解決しなければならない」とした。
米連邦の規定によると、大統領が国家安全保障次元で例外を許容しない限り海外の造船所での軍艦建造は禁止されている。技術流出の懸念のためだ。しかし現在は軍艦建造能力で中国を牽制するどころか追いつくこともできておらず、米政府次元で規制に手を加えなければならない必要性があるということだ。
現在米国の造船会社は長期にわたる政府の保護と予算にだけ依存して競争力を失っており、艦艇の建造・修理能力が大きく退歩したという評価を受けている。ブレット・サイドル米海軍研究開発調達担当次官補代行は公聴会で「米国の造船業は戦闘力を恒久的かつ持続的に増強するのに必要な速度で船舶を生産できずにいる」と診断した。この日の公聴会では「20年前に6年かかった軍艦建造がいまは9年に増えた」という指摘も出た。
逆に韓国の船舶設計技法を学ぶべきという提言も出てきた。オルーク氏は報告書で「米国の造船業が韓国のように労働投入量を減らす船舶設計を開発するなど生産性向上の慣行と技法を導入しなければならない」と指摘した。
林 光一郎
米国で第2期トランプ政権が始まりました。就任後まだ1ヶ月も経っていないのに様々なニュースが飛び込んできて、調査を仕事にしている身としては圧倒される毎日です。
そういったニュースの中にはもちろん海運に関するものも含まれます。それらは現時点ではまだ初期段階であり、状況も流動的なため、解説記事を書く状況にはありませんが、米国で海運への政治的な関心が高まっていることは間違いなく、かつ海運は貿易や安全保障、中国との競争などさまざまな要素に関わるため、最終的には大きなニュースになっていくと思います。
今回の記事では、今後米国から出てくるであろう海運関係のニュースを読み解くための基礎知識として、米国の海運業の現状と歴史について解説します。世界最大の経済大国であり、世界最大の海軍を持つ米国の海運業は必ずしも大きくはありません。このような状況はなぜ生じたのでしょうか?
米国の海運業の現状は?
最初に現在の米国海運業がどのような規模にあるのかを見てみましょう。全体としての規模感をUNCTADが集計した国別の支配船隊シェア(自国籍船だけではなく自国船社がコントロールする海外籍船も含む)で見ると、米国のシェアは2.1%で、首位の中国(香港含む)のほぼ1割に過ぎず、日本の5分の1、ドイツや台湾よりも小さくトップ10にも入らない(12位)状況になっています。
船種別の内訳では、タンカーと一部のバルカーには一定のプレゼンスが残っています。これは米国にはエネルギーや鉱石、穀物などを扱う巨大コモディティ企業(資源メジャーや穀物メジャーと呼ばれる)が存在し、それら企業が自社輸送部門として保有・コントロールしている船隊が存在するからです。
一方でそういった自社輸送が存在しない船種、例えばコンテナ輸送などでは米国の外航海運でのプレゼンスはほぼ消滅しました。かつてコンテナ革命を先導したSea-LandやAPLといった外航コンテナ船社は現在は外国資本に買収・統合されてしまったのです(Sea-LandはMaerskの、APLはCMA CGMの一部になっています)。
なお、米国政府は緊急時に利用できる船隊を維持することを目的とし、米軍の補給物資などの政府貨物の一定割合を米国籍船で運ぶルールを設定しています。このため、上記のMaerskやCMA CGMは一部のコンテナ船を米国船籍にして、それら貨物の輸送を行っています。
一方で、米国では内航海運は一定の規模を維持しています。これは、米国は国土が広く、ハワイやプエルトリコなど本土から離れた領土も保有しているため、国内の島嶼部や遠隔地間の輸送にはそれに見合った規模の船が必要だからです。例えば米国の内航コンテナ船社であるMatsonは、米国本土とハワイを結ぶ航路を中心に、アラスカ航路やグアム、ミクロネシアなどの航路を運営しています(米国と中国本土を結ぶシャトルサービスなど小規模な外航航路も手掛けるが事業に占める割合は低い)。これら航路は内航ではあるものの長距離航路であり、Matsonの船隊規模は基幹航路を手掛けるトップテン規模のコンテナ船社にはまったく及びませんが、内航コンテナ船社としては高い30位前後の順位を維持しています。
このような内航の現状の背景には米国の内航保護法である「ジョーンズ・アクト(Jones Act)」があります。ジョーンズ・アクトでは、米国国内航路に就航できる船は、米国籍船であり、米国船員を乗り組ませ、米国造船所で建造されたことが義務付けられています。これら要件のうち船籍や船員国籍は他の多くの国の内航保護法にも存在しますが、自国建造という条件は現在の主要海運国の間ではほとんどみられません。
近年の米国造船業は衰退傾向にあり、建造する船の価格が国際価格より大幅に高く、納期も長い状況になっています。このことが一因となり米国内航船隊の利用が進みません。そして、そもそも技術的に高度な貨物船(LNG輸送船など)は米国造船所で建造することすらできない状況です。そのため、ハワイやプエルトリコ向けのLNG海上輸送に支障が生じる、つまり内航規制のためLNGを米国本土から送れず、結果的に外国から購入せざるを得ないという事態まで起きているのです。
米国の海運業の歴史
続いて、米国の海運業がこのような状態に至るまでの歴史を見ていきましょう。
20世紀初頭までの世界の外航海運業はイギリスが世界の商船隊の半分近くを占める圧倒的な存在感を示しており、米国の海運業は「イギリス以外」の国の一つ、という存在でしかありませんでした。ですが、二度の世界大戦がこの状況を変えます、
第一次世界大戦が勃発すると戦場となったヨーロッパでは物資を米国やアジアから輸入しなければならなくなりました。一方でヨーロッパ諸国の商船隊は軍用に徴発されます。貿易量が増えて船が減った結果、世界規模で空前の海運ブームが発生しました。既に巨大な工業力を持っていた米国は大量の商船を建造し、自国の海運業の船隊規模も拡大しました。これにより、第一次世界大戦終了後には米国が世界第二位の海運国に成長します(ちなみにこの時期の世界第三位の海運国は日本でした)。
そして第二次世界大戦では、戦場は世界規模に広がり物資輸送の規模は第一次世界大戦よりも拡大する一方、商船は第一次世界大戦以上に徹底した攻撃の対象となり戦前に存在していた商船は次々と失われていきました。そのなかで世界の商船建造を一手に担ったのが米国でした。以前の記事(バルカー(ばら積み貨物船)のことをもっと知ってもらいたい(基本・歴史編))で少し解説したように米国で主に建造されたのはリバティ船などの戦時標準船で、ブロック工法や溶接結合などの当時の最新技術を導入し、18か所の造船所を用いピーク時には1日に1隻以上と言われる驚異的なペースでの建造が進められました。戦後に米国の海運業がその受け皿となり、米国は世界最大の海運国となったのです。
第二次世界大戦が終了し、日本やヨーロッパ各国が造船業や海運業の再建を進めるなかで、全体としての米国商船隊のシェアは低下していきますが、米国海運業はなおさまざまな分野で世界をリードする存在でした。その代表がコンテナ革命であり、マルコム・マクレーン氏が創業したSea-Land社などの米国コンテナ船社が海上輸送のイノベーションを牽引しました。
この状況が変わったのは1970年代です。この時期に外航海運ではパナマやマルタ、マーシャル諸島など税金や手数料が安い国(便宜置籍国)に船籍を置き、人件費の安い発展途上国の船員を乗せて運航するビジネスモデルが登場し、1980年頃からコストの高い先進国の船と本格的に競合しはじめました。
これに対する対応は先進国の中でも国ごとに分かれ、それが国ごとの現在の状況の違いに繋がっています。
ヨーロッパ各国はEU統合を控えていたこともあり、得意分野やコスト構造が異なる国々が船舶保有・運航・海事サービスなどの海事機能を分担し、結果としてヨーロッパ全体として海運業を維持・成長させる道を選ぶこととなりました。
プラザ合意による急速な円高を経てこの競合に直面した日本は、海運各社が血の出るような構造改革を行い、長期輸送契約を必要としていた産業界の理解も得て、日本単独での海事クラスタの再編に成功し、国際競争力を保ちました。
ですが米国では、このような改革が行われないまま停滞し、Sea-LandやAPLといった外航コンテナ船社が外国企業に買収されるなどして、冒頭に述べたような状況にまで縮小していきます。
米国の海運がこのような状況になったのは、一つには内航海運が造船と一蓮托生になって高コスト構造のまま政府の強い保護のもとにあり、かつ外航海運と内航海運の類似性が日欧よりも強かった(内航でも外航と同様の長距離航路、大型船が使われていた)ために、外航海運業界が単独で身を切るような構造改革を行うことが難しかったことがあります。
そしてもう一つ、冷戦が終わり、自由貿易が拡大する中で、外国船社が米国市場で激しい競争を展開してサービスの改善が進み、そこに米国船社が含まれていなくても政治的な問題にはなりにくい構図が続いてきたため、世界で戦える外航海運を維持する政治的な必要性が高くなかった、というのも大きな理由でした。
米国での海運への関心の再浮上
では、そうした状況にあった米国の海運が、なぜいま再び政治的関心を集めているのでしょうか。大きく二つの要因があります。
一つめは自由貿易に対する米国国内の見方の変化です。かつては「自由貿易は米国に富をもたらす」という見方が主流だった米国で、いまや「自由貿易は米国から富を奪っている」という懸念が広がっています。コロナ禍におけるコンテナ運賃の急騰や輸送の混乱(過去記事「コンテナ運賃決定メカニズム・フーシ派攻撃直後の運賃上昇要因(スエズ運河迂回とコンテナ運賃)」でも触れました)なども国民の間の不信を掻き立てました。そのような状況下で、かつて大きな問題にされなかった「米国の国際海運を担うのは外国船社ばかり」という状況が、米国民や政治家の不信や懸念の対象となりはじめたのです。
二つめは中国の台頭です。従来、海運や造船、海事サービス業の世界は日本やヨーロッパ、韓国など、米国と友好関係にある国々が圧倒的シェアを占めていました。ところが近年、中国が海運分野でのシェアを急激に高めてきました。上でグラフをお見せした国別の支配船隊シェアでは中国(香港含む)は2022年にギリシャを抜いて世界最大になり、その後もシェアを高めて20パーセントに迫ろうとしています。造船分野ではさらに中国のシェアは高く、2024年の新造船受注量では、中国は実に世界の77パーセントを占めているのです(載貨重量トン基準, Clarksons調べ)。
中国は現状、海運分野では西側諸国が作ってきた海運秩序を揺るがす行動を取っているわけではありません。ですが米国では、米国支配船のシェアがますます低下している状況と対比され、安全保障の観点から中国の海運分野での存在感が警戒される対象になったのです。
こうした二つの要因が複合して、米国国内では海運業や造船業をどのように保護・育成すべきかの議論が活発化しつつあります。但し、現状では議論の論点はあまり整理されていません。広く括ればアメリカ・ファーストと言える考え方の中でも、「米国の国内産業として海運・造船を守るという観点」「外航海運力を含む総合的なシーパワーを中国と争うという観点」「外国の海運会社が米国の富を収奪するのを防ぐという観点」など論者ごとに複数の異なる観点が存在しているのです。本来ならその議論の受け皿となるはずの外航海運業界が事実上存在しないという状況が、米国での海運に関する議論を複雑なものにしています。これらの議論の具体的な内容や、誰がどのような意見を述べているかについては、今後の解説記事の中で触れていきたいと思います。
まとめ
この記事では現在の米国の海運業の規模の小ささ、かつて世界最大を誇った米国商船隊が縮小してきた歴史的な経緯、商船隊縮小を許してきた外部環境が変化したことでの米国での海運への関心の再浮上についてご説明しました。冒頭に書いた通り、これらの関心や議論の高まりの中でいくつもの施策が検討されています。それらの議論が具体化した段階で、解説記事を書いていきます。

Non-core operations are being wound down, the firm said
Greg Torode Jonathan Saul
[香港/ロンドン 6日 ロイター] - 海運業界では国際的な海上輸送のハブである香港から業務を移し、船籍登録を他の地域に変更する動きが静かに進んでいる。香港船籍の船舶を巡り、非常時に中国当局に徴用されたり、米中関係の緊迫に伴い米国の制裁対象になったりするのではないかといった懸念が高まっているためだ。
中国が自国の安全保障における香港の役割を強調している一方、米国は、台湾などを巡る軍事衝突の発生時における中国商船の重要性の分析に力を入れている。海運業界の幹部らは、こうしたことが業界全体に不安を広げていると話した。
香港は100年以上にわたり船主やブローカー、金融業者、保険業者、弁護士といった海運関連業者が集中する拠点となってきた。公式統計によると2022年に海運・港湾業が域内総生産(GDP)に占める比率は4.2%。英情報会社ベッセルズバリューによると船籍登録数は世界で8番目に多い。
しかしロイターが香港の事情に詳しい24人に取材したところ多くの関係者は、安全保障目標を重視する中国の姿勢や貿易摩擦の激化、さらに中国に忠実な香港行政長官が緊急時に海運業務を掌握できる広範な権限を持つといった要因を挙げて、商業海運業界が米中間の軍事衝突に巻き込まれるリスクを懸念する声が高まっていると証言した。
ある業界幹部は「中国がわれわれの船を求めて接触してくる一方で米国がわれわれを標的にするような事態は避けたい」と述べた。
<潮流の変化>
商業船舶は安全・環境規則順守のために、特定の国または管轄区域に船籍登録する義務を負う。調査会社ベッセルズバリューの分析によると、中国系企業が運航する船舶の香港での船籍登録は増えているが、外航船(外国航路を運航する大型船舶)の香港での登録数は4年前の2580隻から24年1月には2366隻へと8%余り減少した。
香港から船籍を移した船舶の移籍先を見ると、2023年と24年には74隻がシンガポールとマーシャル諸島で再登録された。これらの船は主に石炭、鉄鉱石、穀物などの貨物を輸送するばら積み貨物船だった。さらにタンカー15隻とコンテナ船7隻も別個に香港からこうした国に移籍した。公式統計からは、香港の船籍登録数は1997年以降の20年間に400%増加したものの、21年を境に減少に転じたことが分かる。
香港政府の報道官は、地政学や貿易環境の変化を踏まえて海運企業が業務を見直すのは自然なことで、船籍登録数が短期間で変動するのもよくあることだと説明。引き続き有力な国際海運センターとして卓越した地位を維持すると述べた。また船籍登録を規定する法律や非常事態関連の規定により、香港の行政長官には中国の商船隊に船舶を徴用する権限はないとも述べた。
しかし植民地時代の非常事態権限が米中紛争時どのように適用され得るかについての質問には詳細な説明を避けた。非常事態条項は行政長官に「いかなる規則でも制定できる」権限を与えており、対象には船舶や資産の掌握も含まれる。
弁護士や業界関係者によると、船舶の船籍変更は売却、チャーター、航路の変更など、さまざまな理由で行われる。海運コンサルタントである米カラツァス・マリン・アドバイザーズのバジル・カラツァス氏は、シンガポールが中国の海運および貨物貿易への依存度が低い企業にとって好まれる拠点になっていると指摘。その理由としてシンガポールは法制度などを含めて使い勝手の良い環境を提供しつつ、香港に比べてリスクが低い点を挙げた。
<商船隊>
香港の船籍登録は安全性と規制基準の高さで広く知られ、外国の港をスムーズに通過できると関係者は指摘する。一方、安全保障アナリスト4人や中国人民解放軍(PLA)の軍事研究によると、紛争発生時にこうした船舶は人民解放軍を支援する商船隊の中核を成し、中国向けの石油や食料、産業資源の供給を担うことになる。
中国が多数の商船を抱えるのと対照的に米国は商船建造業の規模が小さく、米国船籍の商船数ははるかに少ない。中国の国有船は軍事衝突の際には米国の標的になる見通しで、中国は国内の莫大な需要を満たすため、また国際海上輸送に大きく依存しているゆえに、その場合には他の船舶が必要になりそうだと3人のアナリストが指摘した。
海上戦略にはトランプ米大統領も着目しており、1月の大統領就任演説で「中国の支配下に置かれた」パナマ運河を「取り戻す」と発言。香港の複合企業、CKハチソン・ホールディングス(長江和記実業)は最近、パナマ運河周辺2港を含む港湾の運営権を米国などの投資家連合に売却する方針を打ち出した。トランプ氏は今月4日の議会演説で、ホワイトハウス内に造船局を新設するとも発表している。
過去10年間、中国の政府や軍の文書および研究は中国の商船が持つ民政・軍事両用の「デュアルユース(二重用途)」の価値を強調してきた。2015年に制定された規則では、タンカー、コンテナ船、ばら積み貨物船を含む5種類の商船について軍事用途に適応できるよう設計することが義務付けられたと国営メディアが報じている。その後、国有企業の中国遠洋海運集団(COSCO)の事業は大幅に拡大。同社の公開文書によると、中国政府は政治将校を商船に配置している。米国は今年1月、中国軍と関連があるとしてCOSCO子会社をブラックリストに追加した。
<真のリスク軽減>
地政学的な課題にもかかわらず香港は依然として船主にとって重要な拠点であり続けているが、それでも一部の企業は密かにリスクヘッジを進めている。
2014年に香港で設立され、現在はロンドン市場に上場しているテイラー・マリタイムは近年、香港での事業を縮小している。21年以降、船籍登録をマーシャル諸島とシンガポールに移し、事業拠点をロンドン、ガーンジー、シンガポール、香港、ダーバンに分散させた。事情に詳しい関係者は「テイラー・マリタイムは香港で真のリスク軽減を図った」と話した。
香港上場のパシフィック・ベイスン・シッピングは、以前は110隻のばら積み貨物船を香港に登録していたが、潜在的なリスクを見極めつつ、船籍の登録変更を視野に入れた緊急対応計画を策定中だと関係者2名が明かした。
香港船主協会のアンガド・バンガ会長は、複雑な地政学的環境の中で海運企業はリスク評価に基づいて緊急時対応計画を調整しているが、船舶の徴用についての懸念は聞いたことがないと述べた。
しかし一部の業界関係者は、香港に対する漠然とした不安が経営判断に影響を及ぼしていると指摘する。弁護士3人によると、近年まで中国で建造され、中国の銀行が融資した船舶の契約では香港での船籍登録が義務付けられるのが一般的だった。ただ過去2年間で船主の要求により香港以外での登録も選択肢として明記される契約が出てきたという。ロイターはこの変更を独自に確認することはできなかった。
中国は軍事の近代化を進め、台湾への武力行使を否定せず、香港の国家安全保障上の重要性を強調している。ロイターが取材した業界幹部3人と弁護士2人によると、2020年7月に施行された香港国家安全維持法が海運業界のリスクを高める要因になっている。
弁護士らは、仮に香港政府が緊急時に船舶を徴用しようとしても、香港船籍の船の多くは香港から遠く離れた海域を航行しているため、実際には困難かもしれないと指摘する。しかし長年存在してきた非常時の統制権限を、「国家安全保障」というレンズを通して見なければならなくなったという。
ある弁護士は、一部の船主は愛国心から、または危機による見返りを期待して、政府からの要請を拒否しないだろうと話した。一方で別の弁護士は「そもそも要請を受ける可能性がある状況に身を置かない方がいい。国家安全保障の地図は明確に塗り替えられ、ほんの数年前には問題ではなかったことが問題になっている」と述べた。
米国のトランプ政権は中国の海洋、物流、造船部門の支配力拡張に対抗するため、中国製船舶を使用あるいは発注した海運会社には入港手数料を課す案を推進すると明らかにした。その影響で、韓国証券市場では海運株が反射利益を得て急騰している。
24日午前11時現在、韓国の有価証券市場で韓国最大の海運会社であるHMMは、取引中に52週最高値(2万1650ウォン)に達し、前取引日より12%以上上昇している。興亜海運も6%以上上昇し、大韓海運などの銘柄も2%以上上昇している。韓国国内の海運会社の株価急騰は、米国の中国に課す手数料措置に対する反射的な恩恵への期待感のためとみられる。
ただし、市場の専門家らは、韓国の船会社もこのような手数料の措置から完全に自由な立場ではないと指摘する。NH投資証券のチョン・ヨンスン研究員は「中国製船舶の割合が少ないHMMが恩恵を受けると予想されるが、今回の措置は中国の海運会社や中国製船舶および中国に引き渡される予定の船舶を保有したグローバル船会社に包括的に適用されることから、(諸企業は)手数料は避けがたいと判断する」との見通しを述べた。
21日(現地時間)、米通商代表部(USTR)は中国海運会社に対する手数料賦課計画を発表した。来月24日には公聴会を開催する予定だ。今回の措置には、中国の海運会社が米国の港に入る際、最大で手数料100万ドルを払わせるか、船舶トン当たり1000ドルを課す案が含まれている。また、中国の造船所で建造した船舶が米国の港に入港する際、最大で150万ドルを課し、海運会社の船団(複数の船舶を束ねる言葉)で中国製船舶が一定の割合を超える場合、差等的に少なくとも50万ドルから最大100万ドルの手数料を払わなければならない。中国の造船所に船舶を発注した海運会社が入港する際にも同様に手数料を課す。
これに先立ってバイデン政権は、中国の海上・物流・造船産業の慣行に対する調査を進め、トランプ大統領が就任する直前に関連の結果報告書を発表した。米政府は中国が不当に船舶業界を支配しており、問題解決のための「緊急措置」が必要だと判断した。ただし、手数料が実際に賦課される場合、追加の費用の負担が米国の消費者に転嫁される可能性が高いとの懸念も出ている。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
米国、中国をやっつけるために、選べられる手段、もはや尽きようとしているのか、一艘150万ドルの過料がどれくらい、米国の優位性に寄与するかわからんが、米中デカップリングにもう一つドライブフォースを追加したことに間違いない。ますます自由貿易の推進に力を入れる中国と、関税や手数料等、他国との貿易を税収の源泉とする米国との並行世界が出来上がった暁には、米国再び偉大になり、世界もより平和になることを期待したい。
半世紀前に米国で働いていたが、まだまだ余裕があってよい国であった。今は大変そうですね。いいがかりをつけるのに苦労してるより、自国民をしっかり働かせることを考えたらどうですか。将来につながりますよ。
中国船舶に対する米国の牽制(けんせい)が本格化する中で韓国造船所が中国に奪われた大型商船市場の覇権を取り戻せるかどうか注目される。
米国通商代表部(USTR)は21日(現地時間)、中国海運会社と中国製船舶に関連した海上輸送サービスに手数料賦課を推進すると明らかにした。米国港に入ってくる船舶が中国海運会社の船舶の場合、最大100万ドル(約1億4900万円)、中国製船舶の場合は最大150万ドルの手数料を賦課する内容だ。USTRのキャサリン・タイ代表は先月16日にもすでに中国船舶・海運会社に対する規制を予告した。中国が造船・海洋市場を掌握するために不公正な手段を使ってきたとし、これを防ぐための緊急措置が必要だと明らかにした。タイ氏は「米国は毎年5隻未満の船舶を建造しているが中国は1700隻以上を建造している。このような中国の優位は公正な競争を毀損し、(米国の)経済的安保リスクを高めさせる」と述べた。
今回の措置に対してブルームバーグ通信は「中国船舶の輸送コストが上昇すれば韓国と日本造船業界に機会が生まれる可能性がある」と分析した。現在、中国はコンテナ船やタンカーなど大型商船分野で韓国・日本造船所を抜いてグローバル覇権を握った状態だ。2021年の時点で韓国は1万2000~1万7000TEU(1TEU=20フィートコンテナ1台分)規模の大型コンテナ船の新規受注をめぐって中国と互角に競争したが、その後、中国に重心が傾いた。造船・海運市況分析企業のクラークソンズ・リサーチによると、昨年全世界の大型コンテナ船新規受注シェアは韓国と中国がそれぞれ22%、78%だった。1万7000TEU以上の超大型は2023年から中国が新規受注を一気に奪い、韓国はたった1隻も受注できなかった。
大型タンカー分野も同じだ。スエズ運河を通過できる12万5000~20万DWT(載貨重量トン数)級タンカー市場で韓国は2022年に初めて中国に新規受注1位を許し、20万DWT以上の級大型タンカー(VLCC)で昨年韓国の新規受注シェアは22%にとどまった。韓国輸出入銀行のヤン・ジョンソ首席研究員は「米国の規制で中国船舶の輸送コストが増えればグローバル船主は韓国製コンテナ船やタンカーの発注を再び増やす可能性がある」と分析した。
商船と共に米国が中国の「海洋崛起」を牽制するために軍艦規模を拡大することも韓国にとっては機会だ。米国防総省は先月、中国最大国営造船会社の中国船舶工業集団(CSSC)をブラックリストにいれるなど軍事的牽制を強化すると同時に米海軍艦隊規模を拡大している。米海軍の「2025建造計画」によると30年間で軍艦364隻を購入する計画だ。
これって下っ端になるためのコース。これぐらいでは船の設計は出来ないと思うよ。船は基本は同じかもしれないけど、船の大きさや種類が違えば知るべきことがかなり違ってくる。また、どの立場から船を見るかで船を建造すると言っても理想とする船は違ってくると思う。
給料優先なら造船よりは海運の方が良いと思うよ。大手なら年収1000万円超えだし、造船よりも年収は高い。もちろん、外航船の話。内航船は違う。しかし、大きさや船の種類によっては学校の偏差値から考えれば高収入かも?
造船業界の下請けの従業員がかなり減っているから下っ端が必要と言う事なのだろう。将来がないと思うから人が減っている、又は、魅力がないから減っていると思わないのだろうか?世界の船舶建造量が2倍に増えても、日本の仕事が増えるとは限らない。丁度、今、アメリカが中国建造の船になんらかの税金をアメリカに入港した時に課すとか言っているから、実現したら、多少は、日本の建造量は増えるだろうと思う。そしてこれが実施され、長期的に継続されれば、日本で建造される船は確実に増えるだろう。ただ、現場の人達はかなり減っているからどうなのかなと思うところがある。やはり技術の継承は一度、絶えるとダメだと思う。
日本の造船に関する本を見てもわかる。いつの時代の船が本に載っているのかと思うし、基本的なこと以外、大したことは書かれていない。これじゃ、誰かに教えてもらわないと会社が教育しない限り、使えないと思う。
広島県福山市の福山大学は、県の東部地域で盛んな造船など海事産業を担う人材を育てる新たなコースを、4月に開設することを決めました。
【写真を見る】海事産業担う人材育成に地元の期待 福山大学に造船学ぶコース開設へ 4月 工学部内に 広島県福山市
福山大学が新たに設けるのは「海洋機械コース」です。工学部にある4つの学科の一つ、「機械システム工学科」に開設します。
背景を工学部長の梅国章教授に聞きました。
工学部長・梅国章教授
「海事産業から福山大学に、人材の供給ということで非常に要望があった」
決断には、造船業界の今後の見通しも関係していました。
工学部長・梅国章教授
「今から2040年代に向けて、世界の船舶建造量も2倍に増えるという風な環境があって、それでなくても人が足りないんですが、さらに足りなくなる」
海洋機械コースは4月の入学生からが対象で、1年間、工学の基礎を学び2年生から希望者がコースを選びます。定員は現在の機械システム工学科の50人枠を変えず、その半分が海洋コースへ進む想定でいます。
コースで学ぶ内容の一部を紹介してもらいました。こちらは「高速光造形機」と呼ばれる機械です。3次元CADで造った形がプラスチックで造形されます。この装置を使えば、こんな船も作れます…。授業では、このような部品の模型をつくる予定です。
記者
「学生がこの取り組み、こういう学びをするのはどういうメリットがあるのでしょうか」
工学部・中東潤准教授
「まずコンピューターの中で物を造るということができる。コンピューターの中でシミュレーションもできるわけです。わざわざ実物を造って、そして試験をしてという、そういう手間は大きく省けてまいりますので、今日、こういったデジタル技術を活用した技術者が求められている」
海洋機械コースの学生は、3年生になると船に使われる部品を形造り、構造について学びを深めるということです。さきほどの模型を造る前段のCADも学びます。このように、造船に必要な機械の知識を学んでいきます…。
そして4年生になると、造船会社などへ長期のインターンシップが予定されており、船ができあがる過程を肌で感じながら、学びを深めていきます。
福山大学が造船業界の水先案内人になれるのか注目が集まり始めています。
中国放送
はやく「中国製船舶への関税や港湾使用料の賦課」を発表し、実施してほしい。アメリカの造船所で建造された商船はほとんどないので、中国が同じ事をしても効果はないだろう。中国建造の船を持っている船主は発表前に船を売るべきか、状況を分析してから判断するグループに分かれるだろうね。まあ、口だけの場合もあるから何とも言えない。ただ、アメリカ海軍の船の修理や新造能力を考えると中国に対してダメージを与えないと状況は悪化するだけだから何かやるのではないかと個人的には思う。
Andrea Shalal
[ワシントン 13日 ロイター] - バイデン米政権は、中国が不公正な政策や慣行を用いて世界の海運、物流、造船セクターを支配していると結論づけた。関係者が明らかにした。
米通商代表部(USTR)は、全米鉄鋼労組を含む5労組の要請を受けて2024年4月に通商法301条に基づく調査を開始。中国が自国の造船・海運業界を優位に立たせるために、資金援助、外国企業への障壁、技術移転の強制、知的財産の窃盗、調達政策などを駆使したと結論づけた。報告書は中国が「海事、造船、物流部門で人件費を深刻かつ人為的に抑制している」と指摘した。
報告書は、1500億ドル規模の世界造船業界における中国のシェアが2000年の約5%から23年には50%以上に拡大したのは、主に政府補助金が寄与したことを示すデータを示した。
USTRは今週中に報告書を発表する予定という。米労組が求める、中国製船舶への関税や港湾使用料の賦課に道が開かれる可能性がある。
1980年代初頭、米国には300以上の造船所があったが現在は20しかない。専門家によれば、民生用、軍用ともに造船需要は旺盛で増加傾向にあるという。
松山・小倉フェリー(松山市)は27日、松山―小倉(北九州市)航路の運航を2025年6月30日で終了すると発表した。新型コロナウイルス禍で乗客やトラックなど車両の利用が大幅に落ち込み、燃料価格の高騰や船の老朽化が追い打ちとなった。松山と九州を結ぶ唯一の航路が半世紀以上の歴史に幕を下ろす。
同社によると、新型コロナ禍前の18年度は利用客が約10万人、車両が約4万5千台だったが、23年度は利用客約4万6千人、車両約2万5千台にまで激減し、コロナ禍以降赤字が続いていた。今年7月から、それまでの毎日上下1便を隔日運航(松山観光港、小倉港とも午後9時55分発)に変更するなどして収支改善を図ったが、燃料油価格がコロナ禍前の2倍以上となり、経営を圧迫した。運航する「フェリーくるしま」が就航から36年たち、修繕費も負担になっていた。
カナデビア(旧日立造船)と川崎重工業は25日、船舶用エンジンの燃費データ改ざんに関する報告書を国土交通省に提出したと発表した。
いずれも9月の中間報告提出以降に明らかになった内容を追加。再発防止策などを盛り込んだ。
カナデビアでは、子会社2社が1999年以降に出荷したエンジン1375台のほぼ全てで改ざんが判明。燃料消費率や窒素酸化物(NOx)排出量が正しい数値になっていなかった。25日の報告書では、再発防止策として「不適切行為を認めない企業風土の醸成に取り組む」などと明記。子会社2社では、社長と各部門長の面談の開始、品質保証部門で監視の強化などに取り組んでいるとした。
船舶用エンジン673台でデータ改ざんをしていた川崎重工も同日、社内調査の結果を発表。大半のエンジンのNOx放出量が規制値内に収まっていた一方、8台は確認できなかった。
カナデビア(旧日立造船)は25日、子会社による船舶用エンジンの燃費データ改ざん問題で、海洋汚染防止法などが規制値を定めている窒素酸化物の排出量を再計算した結果、21台で不適合の懸念があると発表した。
アメリカが韓国や日本にアメリカの造船所を買収して軍関係の船を建造してほしいと打診したのだから、ヤフーのコメントにはネガティブなコメントが多いが仕事は取れるであろう。ただ、最初は補給艦とか軍事関連で特殊性の低い物からはじめるのではないかと思う。
日本よりも韓国系アメリカ人との関係が強い韓国の方が個人的な意見だが有利だと思う。アメリカ人労働者を使わなければならないので、日本であろうが、韓国であろうが、あまり関係ないと思う。
関係ないが1986年の映画「ガン・ホー」はアメリカの一地方に日本の自動車メーカーを誘致しようとする話。日本の自動車メーカーは既にアメリカに工場があり経験があると思うけど、常石造船以外は海外での造船事業で失敗しているので、日本の大手造船所による買収及び進出は難しいと思う。
海外進出は現地と上手くやる必要があるので、自国のシステムを輸出すれば成功すると言うわけではないと個人的には思う。現地の人達との関係や上手く使う経験などがいるので、日本で成功しているとか、日本の製品が良いからとの理由だけでは難しいと思う。どのような人材がその会社にいるかも重要だと思う。
あれこれ言っても、時間が経てば結果は分かる。成功しようが、失敗しようが関係ないので韓国の問題。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
韓国型戦闘機の開発で米国は主要技術移転を拒否、韓国はやむなく、イスラエルなどの協力でレーダーなどを開発しました。軍事技術の移転を拒否されているうちは、軍船の建造受注は不可能でしょう。
北朝鮮のハッキングによる機密漏洩が続き、中国製IP監視カメラを軍施設で使用するようなセキュリティの国には、米軍は技術移転を認めないでしょう。
軍事機密や技術の秘匿性の無い、「軍でも使用する」一般船舶の受注なら、可能かもしれません。
韓国政治が混乱中の最中、景気の良さそうな報道をし続けるが、
所詮「安かろう、悪かろう」で終わり何時の間にか別の業種の賞賛報道をするだろう…
しかし、何処にでも「情報」を御漏らしし、未払いしている所も有ると思うのに、何処から買収出来る資金が有るのかが疑問だし、買収した元が回収出来るのかも疑問
トランプ政権に変わると「白紙」になっていたりして…
韓国のハンファグループが米国現地の造船所の買収を終えた。韓国の造船会社としては初めて米軍の艦艇を維持・補修する役割を越えて、軍艦の建造受注まで進むための橋頭堡を備えることになった。
ハンファグループは20日、米フィラデルフィアにあるフィリ造船所の買収と関連した諸般の手続きを最終的に終えたと発表した。同グループは6カ月前の今年6月、フィリ造船所の親会社であるノルウェーのアーカー社と買収本契約を締結した。
今回の買収は、ハンファ・オーシャンとハンファ・システムが共同で行った。両社がそれぞれ設立した米国現地法人を通じて、それぞれフィリ造船所の持分40%と60%を買い入れた。買収金額は計1億ドル。
フィリ造船所は、米東部沿岸の海軍基地3カ所に隣接した民営造船所だ。建造ドックが米国内最大水準であり、相対的に最新設備を備えているというのがハンファグループ側の説明だ。実際、米国内の相当数の造船所は1970年代に建てられたが、フィリ造船所は1997年に建てられた。ここは米海軍の国営造船所の敷地内に設立され、主に「ジョーンズ法」によって米国内や沿岸で使われるコンテナ船など大型商船を製造してきた。ジョーンズ法は、米国沿岸と本土内の船舶輸送に使われる船舶は、必ず米国内の造船所で建造されなければならないと規定している。2000年以降、同法の適用を受ける米国沿岸用大型商船の約50%が同造船所で建造された。
ハンファグループは、同造船所を北米市場での拠点にする構想だ。まず、既存のドックとハンファ・オーシャンが保有するエコ船舶生産技術を結合し、高付加価値船舶分野で北米市場の立地を強化する計画だ。ハンファ・システムも自動運航技術が適用された次世代船舶の開発などを支援する。
米軍艦艇の受注も狙っている。米国の国家安保と関連した海軍艦艇の建造は、バーンズ-トリプソン修正法によって海外造船所で建造することが禁止されている。米国の軍艦建造を受注するためには、まず米国現地の造船所を買収しなければならないわけだ。ハンファグループは、ここで軍艦の建造も可能になるよう、今後追加の設備投資も進める計画だ。
中国の台湾侵攻の可能性などに備えるために米海軍が推算した軍艦の必要隻数は、2042年までに381隻。現在、利用可能な軍艦は296隻のみ。中国の強大な海軍力を牽制するための米海軍の建艦需要は急増する見通しだ。米海軍が今年3月に発表した「30年艦艇建造計画」によると、米海軍は来年の6隻を皮切りに、今後2030年までに70隻の軍艦を建造する計画だ。このような米海軍の需要に米国造船産業の生産力量が追いつかないため、韓国の造船会社にも機会が開かれる可能性がある。
ハンファグループの関係者は「フィリ造船所は米海軍の艦艇建造およびメンテナンス(MRO)事業の重要拠点として活用される見通し」だとし「今回の買収はハンファグループがグローバル海洋防衛産業での立ち位置を強化する重要な転換点になるだろう」と期待を示した。
ナム・ジヒョン記者
18日午後、八戸市で、貨物船を建造する作業にあたっていた55歳の男性がおよそ7メートルの高さから落下して死亡しました。
18日午後2時すぎ、八戸市豊洲で、建造中の貨物船の船倉にあたる部分で高所作業中だった八戸市の建設作業員、若松直樹さん(55)が、クレーンで荷物を搬入するための穴から、およそ7メートル下に落下しました。
若松さんは頭などを強く打ち、病院に搬送されましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。
警察によりますと、当時は6人で作業にあたっていたということで、一緒にいた作業員に話を聞くなどして、安全対策が適切に講じられていたか確認するとともに、事故の詳しい原因を調べることにしています。
海運大手の商船三井は31日、ロシアの液化天然ガス(LNG)開発事業に貸し出す予定だった大型船4隻について、現地の関係企業などと契約内容の変更に向けて協議を始めたと発表した。同事業に対する欧米の制裁強化を受け、当初の計画通り貸し出すのは難しいと判断した。
同社はロシアの北極圏で進められる「アークティックLNG2」と呼ばれる事業にLNG船3隻、タンカー1隻を貸し出す契約を、2022年2月までに結んだ。その後に始まったロシアによるウクライナ侵攻を受け、同事業は、ロシア産LNGの輸出拡大を防ごうとする米政府などの経済制裁の対象に加えられていた。
商船三井は、同事業に関わらない形で4隻を貸し出すといった契約に変更できない場合、第三者に売却することを検討するとしている。ただ、いずれも砕氷機能を持つ特殊な船で、積極的に買い手がつくかは不透明なため、十分な売却価格を見込めない恐れもあるという。
この4隻はロシア事業のために建造を決めた船で、同社は計1056億円を投じている。投資額の回収が見込めなければ損失を計上する可能性があるとしている。(中村建太)
【AFP=時事】タイで処理するために数百トンの廃棄物を積載して今年7月にアルバニアを出航した船舶が、貨物に有害廃棄物が含まれている可能性があるとの内部告発を受けてタイに受け入れを拒まれ、アルバニア最大の港湾都市ドゥラス(Durres)に29日、帰港した。
【写真】有害廃棄物とみられる数百トンの貨物を積載してアルバニアに帰ってきた船舶
トルコ船籍の「モリーバ(Moliva)」は7月初旬にアルバニアを出港。アルバニア税関当局の当時の書類によると、貨物は「酸化鉄」などの産業廃棄物で、輸出は許可されていた。
しかし、途上国への有害廃棄物の輸出根絶に取り組むNGO、バーゼル・アクション・ネットワーク(BAN)に寄せられた内部告発によれば、貨物には、保管および輸送に厳格な条件を要する有害廃棄物の電炉ダスト(EAFD)が含まれているとみられている。
同船はタイ側に受け入れを拒否され、スペイン、ポルトガル、イタリア、トルコに寄港した後、数か月かけてアルバニアに帰港した。
BANのジム・パケット(Jim Puckett)代表は「われわれの主張が事実であれば、これは国際法で定められた有害廃棄物」だとし、輸出は「犯罪行為」だと主張した。
ドゥラスの検察は、コンテナに有害廃棄物が含まれているかどうかを判断するため、サンプルを分析するとしている。【翻訳編集】 AFPBB News
安全ばかりを気にしていたら効率は悪くなるが、自己責任で安全を確認する必要はあると思う。
階段とか、垂直はしごの溶接部分にクラックがあったり、手すりや階段の足場が腐食している事がある。実際に仕事の時に結構、気にしない利用する人達はいるが、個人的には怪我したり、死にたくはないので、ゆっくりと確認しながら移動する。
この前、船員にクラックや腐食している部分があるから利用する時には気を付けた方が良いと言ったら、「は?」みたいな顔をされた。気になったからアドバイスしたけどアドバイスを無視するかどうかは彼らが判断すれば良い。どこまでが安全で、どこまでがぎりぎり安全なのか判断するのは難しい。
ハンドレール(手すり)とかも状態の悪い船だと力をかけないように触れないようにする。落ちたら死ぬか、大けがだろうなと思うから、凄く慎重に移動する。でも最終的には運だと思う。個々が考えて判断し、行動するしかないと思う。造船所と言っても、規模や会社が違えば対応は違うと個人的に思う。
5から10年ほど前の話だが、中国の造船所の中にはタンクに入る時に計測しない造船所があると船員が言っていた。鳥をタンクに入れて音がしなくなったら酸素がない証拠だと言っていたらしい。今はどうかしらないが、中国の田舎の造船所は足場は竹の材料で作るとか言っていた。今は違うとは思うけど、人の命は国によって価値が違うと思う。
会社のマニュアルが存在しても、存在しているだけで読んでいない、理解していない事はある。パフォーマンス的に良い事ばかりをマニュアルに入れると仕事の効率がかなり悪くなるのではないかと思う。話は変わるが、海上風力発電のメンテに関わる人は、造船所で働く人よりも危険度は上がるのではないかと思う。強風の影響や海水や潮風で腐食したはしごや階段はとても危険だと思う。風力発電が設置されたばかりの時は安全かも知れないが、腐食が始まるとメンテのための設備のメンテにもお金がかかると思う。手入れの悪い船のはしごや階段は本当にボロボロで穴が開いていたり、強度がない。検査に通るのが不思議だが、まともな検査を行わない検査会社は存在するので理想と現実は違う。
昔と比べると造船所では外国人作業員が増えたので、コミュニケーションや詳細の説明などはどうなるのかなと個人的に思う。管理会社や士官クラスの船員次第だけど、誤解を最小限にするような英語の質問や説明、そして言い回しをする船や船員達は存在する。そのような対応をしていない船や船員達も存在する。だから直ぐに事故やけが人が発生するわけではない。運次第だし、いろいろな要素が重なって結果が出る。
10月26日、高松市の造船会社で、作業中だった20代の男性作業員3人が18メートルの高さから落下し死亡した事故で、警察と労働基準監督署が28日、会社に立ち入り検査に入りました。
(中村香月記者)
「午前10時過ぎです。警察官たちが、労災事故があった現場に立ち入り検査に入っていきます」
事故があったのは、高松市朝日町の造船会社、四国ドックです。この事故は、26日午後1時半ごろ、男性作業員3人が18メートルの高さで手すりを取り付ける作業をしていたところ、作業場が崩れて落下したものです。
この事故で、作業をしていた高木優行さん(27)、小野光さん(21)、高橋功太さん(21)の3人が病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。警察と高松労働基準監督署の職員は28日、事故の原因究明へ立ち入り検査に入り、現場を確認したほか、関係者への聞き取りを行いました。
警察によりますと、3人が乗っていた甲板部分の作業場と船の本体をつないでいた金属製の部品が折れていたということで、事故の状況を詳しく調べています。
岡山放送
上記のコメントは間違っていると思う。韓国が付加価値の高い船(船価の高い船)を受注したが、慣れていない設計と建造で大赤字を出して、方向を転換して慣れている増えだけの建造に専念している。日本は、これまでの経験の蓄積で安定した船をリスクを避けて建造している。三菱重工がクルーズ船を2隻受注して1000億円近くの赤字を出してクルーズ船建造から撤退し、クルーズ船を建造した造船所を大島造船に売却した。
高橋豪
海洋国家日本が世界に誇ってきた造船業は、中国・韓国勢に押されてシェアが落ちた。脱炭素や経済安全保障を掲げ、国は手厚い支援に乗り出す。「造船ニッポン」復権の夢を、どこまで追い求めるべきなのか。
この春、一隻の希少な船が完成した。「関鯨丸(かんげいまる)」(9299トン)。船団による商業捕鯨を束ねる世界唯一の「捕鯨母船」で、国内では実に73年ぶりの新造となる。
手がけたのは業界中堅の旭洋造船(山口県下関市)。社長の越智勝彦は「カーボンニュートラルを意識した」という。電気モーターで動き、そのために4基の発電機を積む。今は発電のため硫黄分の少ない重油を燃やすが、水素・アンモニアを燃やすエンジンや燃料電池が使いやすくなれば、それに取りかえるのだという。
「市況の良いコンテナ船など汎用船の生産性を上げるだけでなく、特殊で付加価値の高い船を設計、製造できる力を維持し、欧米から注文があっても造れるようにする。そこに日本の中小造船所の生きる道があると思う」
世界のおおむね9割の船は日中韓の3カ国で造られている。ただ、日本は1990年代まで世界シェアで40%前後を誇る「お家芸」だったものの、23年には16%まで下がった。
26日午後1時25分ごろ、高松市朝日町1丁目の造船会社「四国ドック」の敷地内で、「3人が高所から転落した」と119番通報があった。3人は男性で病院に搬送されたが、いずれも死亡した。
【グラフ】中韓に離された造船業 「巨額補助金とは戦えぬ」
死亡したのは、いずれも造船工の小野光さん(21)=高松市高松町=、高橋功太さん(21)=香川県坂出市大屋冨町=、高木優行さん(27)=高松市檀紙町。
高松北署によると、3人は当時、1万トン級の貨物船(全長約190メートル、幅約31メートル)の造船作業中で、18メートルの高さに設けられた足場ごと転落したとみられるという。(土居恭子)
ブロックは多くて4点、少ないとブロック2点とか、3点で吊るのに良くブロックの上に乗るな!
愛媛県今治市の造船工場で22日午後、ク吊り上げられた船の構造物から作業員2人が転落し鎖骨を折るケガをしました。
今治海上保安部によりますと、事故は今治造船の今治工場で22日午後3時半頃に発生。海上の台船からクレーンで吊り上げられた船体のブロックから作業員の男性2人が約3メートル下の台船に転落しました。2人は病院に運ばれ、ともに鎖骨を折っていました。
原因は船体ブロックが揺れたためと見られ、海上保安部が当時の詳しい状況を調べています。
船を建造しているからどんなタイプやサイズの船が建造できるとは限らない。建造は出来るかもしれないが、品質や利益は期待できない状況だと、リスクを負って将来の投資として始めるか、リスクには手を出すべきではないと言う事だろう。
三菱だって大型客船を2隻受注し、建造して1000億円の損を出した。そんな巨額な損を出すリスクがあるのなら、無理して豪華客船を建造する必要はないと思う。
モノづくりには経験の蓄積が重要な分野があると思う。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
>「メイド・イン・コリア」のクルーズ船の割合は0%に近い
受注経験がほぼない、造船技術も未知数の国の造船会社に対して、海の上で数千人レベルの人命を預ける大型船の発注をするチャレンジャーな企業なんてない。「造船先進国」とか言ってるが、そのプライドこそ悪。
船だけでなく、ペトロナスツインタワーは建設途中で韓国側の棟が傾き始めたから、日本建設の別棟と無理矢理繋いで、日本側に追加負担を強いたり、ロッテタワーは完成した途端に不具合が多数報告されているのに素知らぬ顔で営業を続けていたり、KTXはフランスのTGVの技術を丸々倣ったはずが、車両事故率はTGVの4倍もあったり。造船、建設技術以上に、そのベースにあるそもそもの「物を安全に造って運用するマインド」が根本的に外から信用されないレベルなんだから「メイド・イン・コリア」のクルーズ船を増やすなんて絵空事でしかない。「泥舟」に乗りたい人は普通いない。
12日午前7時、7万5000トン規模のクルーズ船「ノルウェージャン・スピリット」が仁川(インチョン)港に入った。世界のクルーズ運航会社トップ5に挙げられるノルウェージャン・クルーズラインが運航するこの船は、乗客規模が1972人、長さは268メートルに達する。航海する際に船が水に浸る部分が37メートルだ。
ノルウェージャン・スピリットは今月初めに横浜を出発し日本国内の港湾を経て11日に済州(チェジュ)、この日仁川に着いた。コロナ禍収束と多国旅行のトレンドが「韓国→中国」から「韓国→日本」に変わってこうした路線が増加しているという。富裕層の旅行とされるだけに旅行者の支出も相当なものだ。昨年BCカードはクルーズ船入港日になると地域商圏の売り上げが最大30%増加するという分析を出したりもした。国際クルーズ船協会(CLIA)によると、世界のクルーズ観光客は昨年3170万人で、コロナ禍前の最高値だった2019年の2970万人を超えた。CLIAは今年3470万人、2027年には3970万人がクルーズ船に搭乗するものと予想した。
このように韓国の港湾に出入りするクルーズ船が増え、観光・港湾業界の表情が明るくなるが、これを見つめる造船業界は複雑なだけだ。「メイド・イン・コリア」のクルーズ船の割合は0%に近いためだ。クルーズ船は一隻の価格が7000億~1兆ウォンに達する高付加価値事業だが、韓国の主要造船会社が建造したことはほとんどない状況だ。
◇欧州4カ国の造船会社が89%掌握
クルーズ船建造はイタリアの造船会社フィンカンティエリがトップだ。市場シェアは45.7%で半分に近い。次いでドイツ、フランス、フィンランドの企業が43%を分け合っている。韓国の造船業界は一隻2000億~3000億ウォンのコンテナ船や液化天然ガス(LNG)運搬船分野では受注が好況だが、世界で年間20隻ずつ新規発注されるクルーズ船建造には手を出せずにいる。
韓国造船業界が話す最も高い障壁は事業経験だ。韓国クルーズフォーラムのシム・サンジン副会長は「いまもし他の新生企業が『サムスン電子のように半導体を作る』と宣言して仕事を得られるだろうか。経験がなければ市場に参入しにくいように、クルーズ船建造も同じこと」と話した。2000年代に現代峨山(アサン)の金剛山事業所総所長を務め旅客船運航業務を経験したシム副会長は、「クルーズ船は『海の上のホテル』の快適さを維持するために運航中の振動を最小化し、柱の間隔を広くして公演を観覧しやすくするなど技術難度がある。韓国が造船先進国だからとすぐに作れるものではない」と付け加えた。現代峨山が金剛山観光事業当時に現代重工業(現・HD現代)にクルーズ船建造を任せずノルウェー製を使ったのもこうした理由だ。
三井住友海上火災保険は10日、遊漁船事業者向けに新たな保険商品の提供を始めると明らかにした。デジタル化支援サービスと組み合わせることで、リスクを的確に把握し、通常の保険よりも保険料を大幅に抑える。北海道・知床半島沖の観光船沈没事故を受けた遊漁船業法改正で、安全運航のための業務負担が増えた事業者をデジタル技術で後押しし、釣り客が安心して船を利用できる環境を整える。
新保険はB.Creation(ビークリエーション、兵庫県芦屋市)が遊漁船事業者向けに開発し、約1千社が導入済みのオンラインサービスの機能の一つとなる。26人が死亡・行方不明となった知床事故を受け、今年4月に施行された改正遊漁船業法が、遊漁船事業者や乗務主任者に新たに義務付けた船舶・設備の点検や乗務記録の作成に関するデータをオンライン上で記録・保管できる。
三井住友海上にとっては、サービス利用者の法令順守状況を容易に確認できる。保険加入手続きをオンラインで完結させ、事務コストも抑える。従来に比べて、保険料を最大4割抑えられるという。
全国約1万3000社の遊漁船事業者の大半は小規模・零細事業者で、事故が起きた場合の損害賠償リスクを抱えながら、安全管理業務の負担増に直面する。三井住友海上などは経営基盤の弱い遊漁船事業者に対し、新保険による割安な補償とデジタル化による業務効率化を売り込み拡販を図る。今後は釣り客専用の保険などの開発も検討する方針だ。(永田岳彦)

Non-core operations are being wound down, the firm said

The GMB union said the yards were needed for "future capabilities"

Non-core operations are being wound down, the firm said
官報によると、広島県呉市に本拠を置いていた元造船業の「株式会社クレサービス」(旧商号:株式会社神田造船所)は、8月5日付で東京地方裁判所より特別清算の開始決定を受けたことが明らかになりました。
1937年に創業の同社は、本社のある呉市・川尻工場にて大型船舶を中心とする新造船を手掛けていたものの、中国・韓国メーカーをはじめとする競合との競争激化で受注が減少したほか、資材価格の高騰も重なり採算が悪化したため、2022年には主力の造船事業から撤退しました。
その後は、新会社の「神田ドック株式会社」を設立し、採算が見込める船の修繕事業を引き継いだ一方、自らは清算目的会社として現商号に改称し事後処理を進めていました。
負債総額は約109億円の見通しです。
広島県呉市に拠点を置き、2022年に新造船事業から撤退した旧神田造船所(現クレサービス)が4月末で解散を決議し、今月5日付で東京地裁から特別清算の開始命令を受けたことが19日、分かった。代表清算人や帝国データバンク広島支店によると、負債総額は約109億4700万円。
同支店などによると、同社は22年1月、中韓メーカーとの競争の激化や資材価格の高騰を受け、新造船事業から撤退。同4月に修繕事業を常石造船(福山市)に引き継いだ。今年4月30日に株主総会で解散を決議。5月に本社を呉市から東京に移した。
旧神田造船所は1937年創業。2011年3月期の売上高は約361億円だったが、事業環境の悪化で15年3月期は債務超過になった。22年3月期の売上高は約66億円だった。
中国新聞社
造船業を手がけていたクレサービス(旧神田造船所、広島県呉市)が東京地裁から特別清算開始命令を受けたことが19日わかった。命令は5日付で、帝国データバンクなどによると負債総額はおよそ109億円。人件費の安い中国や韓国勢との価格競争に耐えきれず債務超過に陥っていた。
クレサービスは株主総会の決議により4月末に解散している。帝国データなどによると2000年代に生産設備を増強し、11年3月期には売上高361億円を計上した。中韓勢との競争や海運市況の低迷で経営が悪化し、22年3月期は66億円に落ち込んだ。新造船からは既に撤退し、修繕事業は神田ドック(呉市)が引き継いだ。
「厳しく対応したらトヨタ自動車をはじめ日本を支えている自動車、造船関係会社は皆、中国や韓国の企業に吸収されてしまうのではないか?」とのコメントがあったが、日本は外国相手や外国人にはめっぽう弱い。
PSC(ポート・ステート・コントロール)と呼ばれる人は日本では国土交通省職員だ。サブスタンダード船と呼ばれる船はインチキな検査を行う検査会社の副産物であるケースが多い。それをPSCによる検査で見逃しているケースが多いのが現状だと思う。見逃しているのか、それとも、能力不足なのかの判断についてはコンビネーションだと思っている。つまり、仕事が面倒だから見逃しているケースと能力、知識、そして経験不足から不備を見つけられないケースがあるのでコンビネーションだと思う。
燃費の偽装を見抜くのは簡単ではないと思う。そして大型船だと公開試験では1日以上かかるのでほとんどは日本海事協会の検査官が対応しているケースがおおいのではないかと思う。日本国籍の船であってもJG船の内航船でなければ、国交省職員が検査に立ち会うケースはかなり少ないと思う。スピード試験と燃費計測の両方が行われるから、上手くごまかさないといけないだろうと思う。契約で最低スピードが記載されていれば、そのスピードが出なければ補償問題や引き取り拒否の可能性がある。
サブスタンダード船と思われる船を検査して不備を見つける方がはるかに簡単だと思うが、それほど不備を見つけられレないのか不備を書いていないケースは多いと思う。違うレベルや違う次元だが、外国人が逮捕されても、不起訴処分となるケースに似ていると思う。対応が甘いし、法、規則そしてシステムに問題があれが改正すれば良い。サブスタンダード船に関していれば出来る事でも出来ないと言う。検査会社のインチキ検査に対して検査会社に対して何も出来ないのなら少なくともサブスタンダード船の不備を見つけて検査に問題がある事を積み重ねで指摘すれば良いと思うが、そのような考えはないようだ。
検査会社のインチキ検査を取り締まらないのかと指摘した事はあるけど、外国政府がとか、外国の会社だからみたいな事を言ってやる気はなさそうに思えた。こんな状態で外国人労働者を増やして管理や治安維持が出来るはずがないと個人的には思っている。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
出荷台数のほぼ全てが外航船向けでしょうから、MARPOL条約に基づき2023年1月から適用開始されたEEXI規制に多少影響すると思われる。
特に、2000年代に出荷された高出力で燃料消費量が多い機械式制御の主機だと最大回転数にさらなる制限をかける必要があり、運航速度の低下が懸念される。
しかし、環境規制もあいまって燃費重視の商船がほとんどで、最高出力ギリギリの回転数で航行を続ける船はほぼ存在しないので、海運業界に与える経済的損失は少ないだろう。
不正は各企業の問題だが、日本の政府は産業のアクセルは踏まないで、ブレーキばかり踏んでいる印象。たまに踏むアクセルは半導体やら液晶やら、トップダウン型で空ぶかしして失敗する。
韓国のエンタメ、台湾の半導体みたいに国を上げて世界シェアを取りに行く様な大胆に支援をしつつの規制のブレーキを踏むべきでしょう。
自動車会社も造船会社も概ね皆同じ・・・
不正自体は良くないが、ここまで広がるとそもそも厳しすぎる国の旧態依然とした時代にそぐわない時間のかかる検査の仕組み自体にも問題があるのではないか? おそらく監督官庁の関係者も知っていたはず・・・
厳しく対応したらトヨタ自動車をはじめ日本を支えている自動車、造船関係会社は皆、中国や韓国の企業に吸収されてしまうのではないか?
おそらく中国や韓国はもっとゆるいと思いますよ。
マスコミもそのことも調査して取り上げて欲しい。
大型船舶のエンジンてほとんどがライセンス生産なんですよね。
特に有名なのがドイツのMAN B&W。なので基本はどの会社も同じ。
日立もアイメックスも他社もMANのライセンシーでそれに独自の技術を入れ込みながら生産している。
MANライセンシーである他社にも波及しないか心配。
国交省は急にどうしたのでしょうか?長年目溢しあるいは調査していないことを、非難すべきは国交省の不手際では!車そして船と日本の成長の基幹となった産業で、公明党・斎藤国交大臣は現在、中韓に押されて立て直しが必要な産業をどうしたいのでしょうか?官僚の天下りが出来なくなって来ている効果なのでしょうか。
日立造船の子会社2社による船舶用エンジンの燃費データ改ざん問題で、国土交通省は10日、子会社の「アイメックス」本社(広島県尾道市)に対し、海洋汚染防止法に基づく立ち入り調査を始めた。
【写真】「アイメックス」に立ち入り調査に入る国土交通省の担当者ら
10日午前9時過ぎ、国交省の担当者5人がアイメックス本社を訪れ、調査に着手した。関係書類の確認や担当者からの聞き取りを通じ、25年に及ぶ不正の経緯を詳しく調べる。
国交省と日立造船によると、アイメックスは1999年9月以降に出荷した窒素酸化物(NOx)規制対象の船舶用エンジン414台で、一定の出力に必要な燃料消費量を示す「燃料消費率」のデータを改ざんしていた。うち95%が外国籍船向けだった。
国交省は今月5日、改ざんについて日立造船側から報告を受け、不正の全容解明と再発防止策の策定を進め、8月末をめどに報告するよう指示。8日には、もう1社の子会社「日立造船マリンエンジン」有明工場(熊本県長洲町)に立ち入り調査を行った。
日立造船は2024年7月5日、同社グループで舶用エンジン事業を行う連結子会社の日立造船マリンエンジンとアイメックスにおいて、舶用エンジンの陸上運転記録に不適切な書き換えが行われていたことが発覚したと発表した。
調査対象エンジンとデータ書き換え台数[クリックで拡大] 出所:日立造船
発覚の流れは以下の通りだ。2024年4月24日に国土交通省海事局から舶用エンジンメーカーに対し、環境と安全に関する規制順守の徹底と適切な業務運営に関する注意喚起があり、日立造船マリンエンジンとアイメックスでは社内調査を開始。その結果、顧客立ち合いの陸上運転(陸上公試運転)に関して提出した「陸上運転記録(TEST RESULTS OF SHOP TRIAL)」の「燃料消費率」に関するデータの不適切な書き換えがあったことが確認された。具体的には、燃料消費量が実際と違う値が表示される装置を使用しており、NOx放出量の算出に影響を及ぼしている可能性があることが分かったという。
調査対象の舶用エンジンの台数は日立造船マリンエンジン(1999年11月以降)が950台、アイメックス(1999年9月以降)が416台で、その内、データ書き換えが行われていなかったのはアイメックスの2台のみで、その他の全てでデータの書き換えが行われていた。
関係者へのヒアリングでは、陸上公試運転時に燃料消費率を顧客仕様の許容値内におさめたり、データのバラツキを抑えたりするために書き換えをしていたとしている。現在は適正なデータを使用した陸上公試運転を行うように対応しており、現時点で調査対象エンジンで安全性に疑義があるような事案は確認されていないという。法令や規格などへの抵触については現在確認中だとしている。
日立造船の子会社2社による船舶用エンジンの燃費性能データ改ざん問題で、国土交通省は8日午前、「日立造船マリンエンジン」有明工場(熊本県長洲町)に対し、海洋汚染防止法に基づく立ち入り調査を始めた。もう1社の「アイメックス」も週内に調査する。
スーツ姿の国交省職員5人は同日午前9時15分頃、同工場を訪れ、調査に着手した。関係書類の確認や担当者からの聞き取りを行い、不正の事実関係を調べる。
国交省や日立造船の発表によると、日立造船マリンエンジンは、1999年11月以降に出荷した窒素酸化物(NOx)規制対象の船舶用エンジン950台で、一定の出力に必要な燃料消費量を示す「燃料消費率」のデータを改ざんしていた。うち903台が外国籍船向けだった。
同様の問題は重工大手IHIの子会社でも発覚しており、国交省は他の船舶用エンジンメーカー19社に対し、不正の有無を社内調査し、9月末までに報告するよう指示している。
日立造船の子会社が船に使われるエンジンのデータを改ざんして出荷していたことが分かり、国土交通省が立ち入り調査を行いました。
国交省によりますと、今月5日、日立造船から子会社の「日立造船マリンエンジン」と「アイメックス」が、船に使われるエンジンの燃料消費率のデータを改ざんし、出荷していたと報告がありました。
これを受け国交省は熊本県長洲町にある「日立造船マリンエンジン」の工場に立ち入り調査を行いました。
これまでに改ざんが確認され出荷されたエンジンは、1999年9月以降、1364台に上るということです。
国交省は「アイメックス」の工場についても10日にも立ち入り調査を行う予定です。
テレビ朝日
中国では燃料消費量の計測でごまかしが頻繁に起きていると聞いた事はあるが、日本でも程度の違いはあれどやっていたんだね!しかし、中国建造の船の燃料消費量があまりにも酷いと日本に発注する外国船主がいるぐらいだから、日本が燃料消費料をごまかしてもまだメリットがあるぐらい燃料消費は良いんだろうね。
中国建造船の建造仕様書の燃料消費量は嘘だと外国人監督はよく言っていたからね。あと防音試験もインチキがあるのでは?少なくとも中国ではあると思った。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
IHI子会社に続き、日立子会社もですか。
自動車メーカーもですが、1社が公表すると、同じ様な不祥事が立て続けに報告されますね。
別件で渦中の重工さんとか大丈夫なんでしょうか?
日立造船は5日、船舶用エンジンを製造する子会社が燃費性能のデータを改ざんしていたと発表した。日立造船マリンエンジン(熊本県)とアイメックス(広島県)の2社で、改ざんは1999年9月以降に出荷した計1364台に上った。
一定の出力に必要な燃料の消費量を示す「燃料消費率」を顧客が求める仕様の範囲内に収めたり、データのばらつきを抑えたりするため、消費量が実際と違う数値が表示される装置を使用して性能試験を行っていたという。
日立造船は外部の有識者で構成する特別調査委員会を設置し、原因究明にあたる。同社は「多大なる迷惑と心配をかける事態となり、深くおわびを申し上げる」とのコメントを出した。
日立造船は5日、子会社が船舶用エンジンの燃費に関する測定データを改ざんしていたと発表した。20年以上にわたって不正が横行し、1364台での改ざんが確認された。
【写真】日立造船本社=大阪市住之江区
不正があったのは船舶エンジン製造の子会社「日立造船マリンエンジン」と「アイメックス」。
社内調査によると、1999年以降に出荷された計1364台の船舶のエンジンで「燃料消費率」に関するデータの書き換えをおこなっていた。燃費に関する測定データを許容値の範囲内におさめるためや、データのばらつきを抑えるために書き換えをしていたという。
燃料消費率は、完成したエンジンを出荷する前に、納入先に報告するために試運転して測定する。(福岡龍一郎)
日立造船は5日、船舶用エンジン事業を手掛ける子会社の日立造船マリンエンジン(熊本県長洲町)とアイメックス(広島県尾道市)が製造する船舶用エンジンで、燃料消費率のデータを改ざんしていたことが社内調査で判明したと発表した。
改ざんは1999年以降に両社が出荷した計1364台に上り、調査対象のほぼ全てでデータの書き換えが見つかった。
日立造船は「信頼を大きく損ねる結果となり、深くおわび申し上げる」とのコメントを出した。外部有識者による特別調査委員会を設置し、事実関係や原因の究明に当たるとともに、業務運営体制の見直しなど再発防止策を講じる。
顧客に提出した陸上での試運転の記録に、実際のデータとは違う値を表示していた。環境規制の対象となる窒素酸化物(NOx)の放出量の算出にも影響が出ている可能性があり、整合性を調査している。
瀬戸内海汽船(広島市南区)が私的整理の手法を用いた経営再建を計画していることが27日、分かった。
【画像】瀬戸内海汽船が年内で運航を終えるクルーズ船「銀河」
新型コロナウイルス禍による乗客の減少や、燃料価格の高騰などが響き、2023年度決算時で7億5600万円の債務超過に陥っている。金融機関の支援やスポンサー企業の出資受け入れなどを通じ、事業継続を目指している。
瀬戸内海汽船は1945年の設立。フェリー会社や飲食業などグループ7社があり、広島市から宮島や江田島に向かう航路などがある。
業務効率化などにつながる図面の共通化について既に遅すぎるとは思うけど、やらないよりはましだと思う。
図面の共通化と言っても、建造工程や建造方法についても共通化を考えないと図面の話だけではダメだと思う。ただ、これまでのやり方を変える現場は大変だろう。軌道に乗るまでは問題が発生したり、慣れないことによる時間が短縮できない問題があるのではないかと思う。
日本中小型造船工業会は20日、東京都内で総会開催後に会見を開き、田中敬二新会長(福岡造船会長)が抱負を述べた。田中会長は「資機材価格や人件費などを含めたコスト増、人手不足、環境規制対応など課題が山積している」点を強調。「これらは1社で解決できるものではない」と語り、業界内、舶用機器メーカーなどと連携して対応する必要性を指摘した。
業務効率化などにつながる図面の共通化について、田中会長は「やりたいとは思うが、なかなか難しい」と説明。自身の福岡造船では、傘下に臼杵造船所などを抱えるものの「各工場でクレーンをはじめ設備能力などが異なり、造り方も違うため、当社でさえ時間がかかっている」ことを紹介した。
設計に関して中小造工では、日本財団の助成事業として「DX(デジタルトランスフォーメーション)化に伴う設計業務プロセスの刷新手法の提言」を2カ年で推進。2024年度には、将来のDX設計システム導入・運用のための設計業務プロセスの提言とその活動ロードマップ作成を進める。
中小造工は、日本財団基金事業として、「海外向け巡視船艇の設計支援事業」も実施している。岩本泉専務理事は、日本でもODA(政府開発援助)などにより巡視船艇を輸出している一方、「海外の造船では、巡視船艇がデザイン性に富んでいるほか、引き渡し後のメンテナンス業務をパッケージで提供している」点を指摘。売り込み方などを真剣に議論し、今年11月から同事業ではフェーズ2に入り、具体的な設計作業などに入ることを明らかにした。
中小造工は、日本財団の助成事業としてさらに、「洋上風力発電関係船舶の国内修繕・建造の推進」も行っている。
アメリカ軍やアメリカ沿岸警備隊の船舶では利益が出ると思うが、それだけで利益が出るのだろうか?
日系アメリカ人よりは歴史が浅い韓国系アメリカ人が多いからコミュニケーションの点では有利かも知れない。ただ、労働者があまり働かないアメリカ人や移民のルールを持つアメリカ人になるような気がするからアジアの造船所と同じ事を考えていると痛い目を見ると思う。
韓国は既にいくらかの国の軍に補給艦を建造して引き渡しているから日本よりは購入する理由は多いと思う。アメリカは古い海軍の船や沿岸で使われている船舶が多い。上手くやればしばらくの間は利益は出るかもしれない。ただ、お金がないし、まだ使えるから必要ないと考える民間会社が多いのならたいへん。そしてアメリカは結構、単位でフィートとかポンドを使うからSIユニットを韓国には面倒かもしれない。
韓国のハンファグループが米国のフィリー(Philly)造船所を1億ドルで買収した。米国の商船をはじめ防衛産業市場にも本格的に進出する計画だ。
ハンファグループは21日、フィリー造船所の持株100%を1億ドルで買収する契約を前日に結んだことを明らかにした。買収にはハンファシステムとハンファオーシャンが参加した。ハンファグループは「韓国企業としては初めて米国造船業に進出することになった」と話した。
ハンファグループは、今回の買収で米国の商船・防衛産業市場に進出する踏み台を設けたとみている。フィリー造船所はノルウェー企業の米国所在の子会社で、米国本土の沿岸で運航する商船を建造してきた。米国で建造された石油化学製品運搬船(PC船)やコンテナ船など大型商船の約50%を供給している。米運輸省海事庁(MARAD)の大型多目的訓練艦や海洋風力設置船、官公船など、多様な分野の建造実績もある。
韓国の防衛産業企業であるハンファシステムは、商船と特殊船の両方でシナジー効果を期待している。ハンファシステムが持つ海洋無人システム技術を活用し、自動運航が可能な民間商船を開発するなどの協力が可能だということだ。フィリー造船所を足場に、米国の無人水上艇・艦艇などの特殊船市場に進出することも期待できる。
ハンファオーシャンは今回確保した海外生産拠点を通じて売上の多角化を推進する計画だ。フィリー造船所が強みを持つ中型級タンカーとコンテナ船分野に受注を拡大するという期待もある。さらに、ハンファオーシャンのスマート工程技術などを活用して、フィリー造船所の原価競争力を改善するとも語った。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
なぜ負債4,000万円でニュースになるのか不思議です。
愛媛県今治市で船舶溶接を手がける「雅工業」が松山地裁今治支部から12日に破産手統きの開始決定を受けたことがわかりました。
帝国データバンクによりますと雅工業は、船舶向けの溶接業者として2008年に設立され造船会社の協力業者として、主に船体の溶接などを手掛けていました。
負債額はおよそ4000万円と見られています。
一時的だろうと思うし、中国で安くコンテナを製造しているのだから、製造すれば良いだけの事。
中国の輸出産業が、製品出荷用のコンテナの入手難に悩んでいる。
「5月以降、輸出貨物の急増とともに、海運会社からの空きコンテナの供給が追いつかなくなった。出荷を急いでいる輸出業者は、40フィートコンテナ1本あたり1000ドル(約15万6800円)を超えるリース料で探さなければならない状況だ」
【写真】国際海運大手A.P. モラー・マースクの発注で建造中の大型コンテナ船(同社ウェブサイトより)
財新記者の取材に応じた複数の国際物流業者は、そう口をそろえた。上述のリース料は1年前の3倍を超える水準だ。
不足しているのはコンテナだけではない。中国と海外を結ぶコンテナ船の輸送力も逼迫しており、一部では投機的な動きも現れ始めた。例えば、ある物流業者は輸出用コンテナのワンウェイ(片道)リース料として、顧客に対して2000ドル(約31万3600円)以上を提示しているという。
■需給バランスの脆さが露呈
輸出大国である中国は、貨物を詰めて海外に送り出すコンテナの数が、海外から入ってくる数よりもはるかに多い。そんな中、物流業界は大量の空きコンテナを海外から中国に回送すると同時に、中国で新たに製造したコンテナも調達することで、需給バランスを維持している。
だが、需給バランス調整の手段が限られているため、何らかのきっかけで不均衡が生じると、修正するのは容易ではない。今回のコンテナ不足に関しては、発端は2023年10月に始まった「ガザ危機」だった。
中東情勢の緊迫により、中国とヨーロッパを結ぶコンテナ船のほとんどが(スエズ運河経由から)喜望峰回りへの航路変更を余儀なくされ、輸送にかかる日数が伸びた。その影響で、コンテナ船に積まれて“海上を漂う”コンテナが増加したタイミングに、中国の輸出回復が重なり、空きコンテナがにわかに足りなくなったのだ。
需給バランスの乱れによるコンテナ不足は、新型コロナウイルスの世界的大流行の最中にも生じた。今回は当時のような大混乱の再来になるのだろうか。
「目下の空きコンテナの不足は、コロナ禍の時とは様相が異なる」。そう指摘するのは、国際物流のワンストップサービスを手がける涅浦頓供応鏈科技の幹部の陸春栄氏だ。
陸氏の解説によれば、コロナ禍の時期には世界各地のコンテナ港で荷さばきが遅延し、大量のコンテナがヤードに滞留。空きコンテナを中国に戻すこと自体が困難だった。それに比べて、現在はコンテナ港の稼働に問題はなく、空きコンテナの中国への回送に支障はないという。
「今回のコンテナ不足は(一時的な需給のミスマッチによるもので)、9月頃には改善の兆しが見えてくるだろう」。陸氏はそう予想する。
■コンテナの総量は余り気味
コンテナの供給サイドの視点で見ると、全世界に存在するコンテナの総量は、国際貿易の規模に対して余り気味だ。
業界団体の中国集装箱行業協会のデータによれば、世界のコンテナ保有量はコロナ禍が始まる前は約4000万TEU(20フィートコンテナ換算)だったが、2023年末時点では5100万TEUと3割近く増加した。
ガザ危機の半年前の2023年春には、中国各地の港湾に空きコンテナの山が積み上がっていたことは記憶に新しい。(訳注:詳しくは『【ルポ】中国「空きコンテナ山積み」の現場を歩く』を参照)
コンテナ船の輸送力の増強も、需給バランスの改善にプラスに働く。イギリスの海事情報会社クラークソンズ・リサーチによれば、2024年は新造コンテナ船の(海運会社への)引き渡しが集中することから、全世界の輸送力が9%増える見通しだという。
さらに、中国のコンテナ製造会社も(コンテナ不足を受けて)生産ペースを引き上げている。こうした状況を背景に、業界関係者の間では「コンテナ不足は長続きしない」との見方が多数派になっている。
(財新記者:李蓉茜)
※原文の配信は5月24日
財新 Biz&Tech
韓国の造船3社が相次ぐ契約解除で頭を悩ませている。かつて船舶を発注したロシア海運会社などが契約を撤回してからだ。
13日、造船業界によると、サムスン重工業は前日、ロシアのズヴェズダ(ZVEZDA)造船所から4兆8500億ウォン(約5500億円)規模の受注契約の解除を通知された。ロシア船主が一方的に契約解除を通知すると、同時に納付した手付金8億ドル(約1257億円)と遅延利子支給を要求しており、今回の契約解除は国際訴訟戦につながる見通しだ。
サムスン重工業はズヴェズダ造船所と2020年11月から船舶ブロック(船舶用鉄構造物)と資機材供給契約を結んだ。サムスン重工業が船舶ブロックなどを製作して造船所に送れば、現地で最終組み立てして建造する契約だった。ズヴェズダは手付金として8億ドルを支給したが、ロシアがウクライナに侵攻した2022年2月から西側制裁が始まり、契約に赤信号が灯った。サムスン重工業関係者は「ズヴェズダと契約維持の可否をめぐり交渉を続けてきたが、今月11日ズヴェズダ側が契約不履行を主張し、17隻に対する契約解除を通知した」として「国際訴訟につながるだけに結論まで相当な時間がかかるものと予想される」と話した。
これに先立ち、ハンファオーシャンは2022年、ロシア海運会社のソブコムフロットと締結した液化天然ガス(LNG)運搬船3隻の供給契約を解除した。ウクライナ侵攻による制裁規定を守る必要があったためだ。ハンファオーシャンは2020年、ソブコムフロットから砕氷LNG船3隻を計8億7100万ドルで受注した。現代三湖(ヒョンデ・サムホ)重工業も同年、ソブコムフロットから5億5000万ドルで受注したLNG運搬船3隻に対する契約を解除した後、辛うじて新しい船主に再販売した。
ILO(国際労働機関)の船内船員設備に関する条約(第92号)ぐらい批准すればと思うが、小型船とかで影響が多いのかもしれない。批准すれば問題を放置するわけにはいかなくなるから、批准を避けているのかもしれない。
ILO(国際労働機関)の船内船員設備に関する条約(第92号)が批准されていても、違反やインチキは存在するからそんなに神経質になる必要はないと思うが、規則の要求になると、注目されている車の認定不正のように不正は不正になるから慎重になるのかもしれない。
安いスプリングマットレスは長期間使いたいとは個人的には思わない。狭い内航船では厚みがあるし、建造途中の搬入は大型船に比べると大変になると思う。マットレスが使えるベットの寸法にするので小型船では居住区の設計変更や配置を変更する必要が出てくるだろう。内航船の船員で喜ぶ人達がいるのなら良い事だと思う。ところで国内建造船とは内航船のこと?日本ではILO(国際労働機関)の船内船員設備に関する条約(第92号)が要求される外航船は多く建造されている。
【関西】海運各社が船員のウェルビーイング(心身の健康や幸福)実現に向けて取り組む中、寝具を改善し船舶の安全運航にもつなげる動きが出てきた。従来、船員用船室にはウレタン製マットレスが用いられてきたが、より快適な高密度連続スプリングの製品の採用が始まった。関係者によると、2024年に入り新来島どっく(愛媛県今治市)が建造する船舶で、フランスベッド(東京都新宿区)製の高密度連続スプリングマットレスの採用が決まった。
25年度引き渡し船からの採用となる。国内建造船では、船員用寝具にウレタンマットレスを用いるのが主流。こうした中、国内メーカーのフランスベッドが製造した「WGSマットレス」が、日本造船所の建造船で初採用された。
ILO(国際労働機関)の船内船員設備に関する条約(第92号)には、船員の寝台にバネ材の使用が明記されている。ただ、同条約を日本は批准しておらず、長らくウレタン材が用いられてきた。
ウレタン製のマットレスは比較的安価で手軽な半面、スプリングを用いたマットレスよりも硬さや柔らかさといった品質面で劣る。また、製品劣化が早いことや、臭いの面でも難点があった。
採用が決まった製品は高密度連続スプリングを用いたホテル仕様で、適度な硬さや内部に湿気をためない通気性の良さが特徴。スプリングを覆うクッション部分は抗菌・防臭・防ダニ機能、マットレスを覆う生地は除菌機能を持つ。
高品質なスプリングマットレス導入を通じ船員の「睡眠の質」向上が見込まれ、長い洋上生活での快適性改善が期待できる。また、船員交代で船室の利用者が替わることを踏まえ、抗菌・防臭・防ダニといった機能を通じ、より衛生的な空間の提供が可能となる。
一日のうち3分の1が睡眠時間ともいわれる中、心身の健康と睡眠は密接な関係にある。特に生活リズムが不規則となる船員生活で、睡眠の質の低下は安全運航の妨げにもなりかねない。
こうした中、快適性が高く製品劣化も少ないスプリングマットレスは、船主が造船所へ要望している居住環境改善にも合致すると業界関係者はみる。高品質な寝具の採用は、船員生活向上の象徴的な事例となりそうだ。
一般的にスプリングを用いたマットレスは10年以上使用可能という。また、船員の福利厚生の観点から、新造船だけでなく、既存船での入れ替えニーズが広がる可能性も期待できる。
日本海事新聞社
2023年ぐらいからAMSAは長期の入港禁止にする事が多くなったと思う。

Peace was banned for three months due to maintenance issues (AMSA photo)
Bucarest/Costanza
In recent days, the Dutch shipbuilding group Damen has filed with the Court of Constance for bankruptcy in the the Romanian shipyard Damen Shipyards Mangalia, of in which it owns 49% of the capital. The remaining 51% of the company's share capital The company has been held by the Romanian government since 2018 through Santierul Naval 2 Mai, a wholly-owned company controlled by the Ministry of Economy, while the management of the of the plant is entrusted to Damen ( of 23 March and 28 July 2018). Last summer, Damen demonstrated the intention to leave the Mangalia company, also appealing to the International Arbitration Centre of the Chamber Austrian Economic Association of Vienna in order to obtain the resolution of the of the 2018 agreement with the Bucharest government ( of 7 August 2023).
Meanwhile, more than a thousand of the 1,500 workers at the shipyard in Mangalia have been placed on technical unemployment since Monday due to the absence of work in the plant.

支綱切断された船が初めて海へと動き出す瞬間、青空に風船と紙テープが舞い、歓声が上がった。
韓国は敵に塩を送るような支援をするメリットはあったのだろうか?韓国はLNGタンカーの建造でライセンス料をフランスの設計会社に支払うので儲けがほとんどないと多くの記事で書かれている。
ライセンス料を払いたくないので韓国で設計し建造したLNGタンカーは建造から10年経ってもまともに運航できないらしい。今年に入って、RO-RO船に衝突されて船体に大きな穴が空いた。
中国の国有造船最大手の中国船舶集団(CSSC)は4月29日、カタールの国営エネルギー企業のカタールエナジーから、タンク総容量27万1000立方メートルの大型LNG(液化天然ガス)タンカー18隻の建造を受注した。
【写真】北京で開催されたCSSCとカタールエナジーの契約調印式(CSSCのウェブサイトより)
財新の取材によれば、これらのLNGタンカーの受注価格は1隻当たり約3億800万ドル(約482億5343万円)。18隻の総額は約55億ドル(約8617億円)に上り、一度の受注額としては世界の造船業界で過去最大だ。
■タンク容量を6割拡大
今回受注した大型LNGタンカーの設計と建造は、CSSC傘下の滬東中華造船が担当する。その船体は長さ344メートル、幅53.6メートルと世界最大級で、輸送能力は現在の大型LNGタンカーの主流(タンク総容量17万4000立方メートル)を6割近くも上回る。
滬東中華造船は、韓国造船大手STXグループの子会社のSTXヨーロッパ(旧アーカーヤーズ)から技術支援を受け、中国で初めてLNGタンカー建造に参入した造船会社だ。これまでに34隻の大型LNGタンカーを顧客に引き渡した実績を持ち、現在建造中および建造待ちの大型LNGタンカーは今回受注した18隻を含めて合計58隻となった。
近年、二酸化炭素(CO2
)の排出削減に向けた世界的なエネルギー・シフトが続く中、(2022年2月に始まった)ロシアのウクライナ侵攻に伴う世界のエネルギー貿易の再編が重なり、LNGの需要が拡大。造船業界はLNGタンカーの建造ブームに沸いている。
イギリスの海事情報会社クラークソンズ・リサーチのデータによれば、世界の造船会社が2023年に受注したLNGタンカーは合計66隻。2024年は1月から4月までに47隻を受注しており、過去10年の平均受注数である年間41隻を早くも上回った。
大型LNGタンカーの建造は、これまでは韓国の造船会社の独壇場だった。サムスン重工業、HD現代重工業、ハンファオーシャン(旧大宇造船海洋)の3社で、世界の受注数の7割超を占める時代が長年続いていた。
だが、今回の建造ブームでは中国の造船会社が続々と参入。現時点で建造中または受注済みのLNGタンカーは合計89隻と、世界市場の4分の1を占めるまでになった。
■LNG長期調達契約が追い風
カタールは天然ガスの埋蔵量が世界第3位、LNGの生産・輸出量でも世界有数の規模を持ち、さらなる輸出拡大を目指している。
CSSCがカタールエナジーから過去最大の受注を獲得した背景には、中国とカタールが結んだLNGの長期調達契約があると見られている。中国の国有エネルギー大手の中国石油化工(シノペック)は2021年以降、カタールエナジーと3本の長期調達契約を締結しており、年間合計900万トンのLNGを中国に輸入することになっている。
さらに両社は2023年5月、カタールエナジーが開発中のノースフィールド・ガス田の東部拡張(NFE)プロジェクトに、シノペックが資本参加することにも合意した。
(財新記者:李蓉茜)
※原文の配信は4月30日
財新 Biz&Tech

SKセレニティ号 [マリントラフィック ホームページ キャプチャー]

正常運航中のSM JEJU LNG1号船 [マリントラフィック ホームページ キャプチャー]
Evelyn Macairan

東京商工リサーチによりますと、愛媛県西条市に本社を置く坂本工業が8日、松山地裁より破産開始決定を受けたということです。負債総額は債権者約20人に対し約7400万円です。
同社は2009年に設立、造船部門と人材派遣部門があり、地元の造船会社などからの一定の受注基盤を築き、ピークとなる19年8月期には4200万円の売り上げを計上していました。ところが同業他社との競合が厳しく、21年8月期には3300万円まで落ち込んでいました。そのような中、先行きに見通しが立たないことから事業継続を断念、今回の措置を取ったとみられるということです。
A chief engineer and a second engineer both working aboard a Greek-owned and registered product tanker pleaded guilty today, May 7, to a series of MARPOL violations while their vessel was near a petroleum terminal located in Sewaren, New Jersey. Sentencing for the two engineers is scheduled for October with the U.S. Attorney’s Office in New Jersey reporting the charges carry a maximum penalty of six years in prison and a fine of $250,000.
The U.S. Coast Guard and the U.S. Attorney’s office did not provide details on when the offense took place, but it reported the two engineers were working on a chemical tanker named Kriti Ruby (48,000 dwt). Built in 2008, the vessel is managed from Greece.
In court, Konstantinos Atsalis, who was employed as the chief engineer on the vessel admitted that the vessel’s crew had knowingly bypassed required pollution prevention equipment by discharging oily waste from the vessel’s engine room through its sewage system into the sea. Atsalis further admitted that he directed crew members to hide equipment used to conduct transfers of oily waste from the engine room bilge wells to the sewage tank before the Coast Guard boarded the vessel.
The chief engineer also admitted to concealing the actions by falsifying the vessel’s oil record book. The falsified log was presented to the U.S. Coast Guard during its routine inspection.
Second engineer Sonny Bosito also pleaded guilty to violating the Act to Prevent Pollution from Ships. He admitted in his plea to concealing the discharge of oily waste into the sea through the vessel’s sewage system by causing a false record book to be presented to the U.S. Coast Guard during its inspection of the vessel. Bosito further admitted to directing crew members to hide equipment used to conduct transfers from the bilge wells to the sewage tank before the Coast Guard’s inspection.
For the vessel, it was not the first time it has had issues with the U.S. Coast Guard. During a 2022 expanded examination in New York, the U.S. Coast Guard cited the vessel for deficiencies including blockages in the oil discharge monitoring and control system and the oil filtering equipment. This resulted in a seven-day detention.
Last month, the USCG released its annual report on inspections highlighting a significant increase year-over-year in detentions during Port State inspections. They, however, noted it might have been an aftereffect of the pandemic’s impact on inspection regimes. During 2023, they said Fire Safety and Safety Management accounted for the majority of the detention orders followed by Life Saving Systems. Over 8,000 inspections were performed in 2023 with 101 vessels issued detentions.
船は自然や天候との戦いや休日や土日が忙しいケースがあるから何らかの魅力がないと選択しないかもしれない。長男だから地元に残るとの考えがなければ、能力があったり、新しい事に興味があれば、都会や都市部に出て行くと思うから、仕方が無く選択する傾向は低くなると思う。
問題には早く手を打つべき問題と急がなくても良い問題があると思うが、それを適切に理解して対応しないと時間切れで非効率な対応や選択になると思う。まあ、分かっていても出来ない状況やしがらみや人間関係の影響で対応が不適切になる事はあると思うので、なるようにしかならないし、運よく問題解決が出来る人がいればラッキーだと思う。
折田汽船(鹿児島市)は鹿児島-屋久島の「フェリー屋久島2」を12日から7月末までの間に計20日間運休する。乗組員が離職し人員不足となったため。採用活動を進めており、6月以降の運休が回避できないか探っている。
【写真】フェリー屋久島2から降りる乗客=10日、鹿児島市本港新町
同社によると、3、4月で10人が所属していた部署から3人が離職し、欠員分をカバーする乗組員の休養日を設けるための措置。主な運休日は水、日曜日で、5月は12、15、19、22、26、29日の計6日間。6、7月は計14日間予定しており、ホームページで確認できる。
県旅客船協会が2023年に実施した調査によると、定期航路を運航する16事業者のうち、12事業者が「人手が不足している」と回答している。
新型コロナウイルス下では乗組員の感染や濃厚接触者の自宅待機で人繰りがつかず、臨時運休した事業者が相次いだ。折田汽船も22年に同様のケースがあった。
折田新吾常務は「お客さまに迷惑をかけて申し訳ない。できるだけ早く運休日を減らせるようにしたい」と話した。
南日本新聞 | 鹿児島
人それぞれで合う、合わない、又は、好き嫌いはあると思う。どこの記事なのかは忘れたが、小学生でなりたい職業のトップに警察官が上位にあるが、年齢が上がるとランキングからはずれるようだ。つまり、イメージだけでは職業としては選択しない、そして、いろいろな選択を考えるので、魅力ある労働環境、給料、そしてその他の優先順位のコンビネーションで判断するのだと思う。
つまり、体験乗船をやらないよりはましだと思うが、効果は期待できないと個人的には思う。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
船員不足の原因となる労働環境をどうにかしないとすぐ辞めるよ
一人でも船員目指してくれたらなぁ…
香川県の小豆島で地元の小学生たちが新人船乗りを養成する練習船に体験乗船しました。
新人船乗りを養成する海技教育機構の練習船、「大成丸」に体験乗船したのは、香川県小豆島町にある星城小学校の6年生24人です。
児童たちは船員に案内してもらいながら船の中を見学したり、実際にハンドルを握って操縦を模擬体験するなど、興味深々の様子で船について学んでいました。
(児童は…)
「操縦は簡単だと思っていたが意外と難しかった」
「リアルですごく楽しかった」
「すごいなと思ったところもあるし、こういう風にできていたのかと気づいたところもあった」
この体験乗船は深刻化する船員不足の解消につなげようと小豆島町などが企画したもので2018年度から行われています。新型コロナの影響で対面での交流は4年ぶりとなりました。
岡山放送
新造船から撤退/大型ドック 設備生かす
住友重機械工業グループの住友重機械マリンエンジニアリング(東京都品川区、宮島康一社長)は、横須賀造船所(神奈川県横須賀市)の新造船事業から撤退する。1897年に浦賀船渠として創業以来、別子銅山の工作方と並ぶ祖業の一つとして120余年にわたり事業を営んできた。今後は洋上風力発電事業にシフトし、再起を図る。(八家宏太)
【写真】新造船事業からの撤退が決まった横須賀造船所のドック
2021年12月28日、横須賀造船所の役員会議室。窓外の夕日を望み、宮島社長は住友重機械マリンエンジニアリングのかじ取りを託された。実はこの時点で新造船撤退のシナリオは動き出していたという。新造船事業の幕引き含みでの打診に「社長就任を告げられた時、いすから転げ落ちそうになった」(宮島社長)。数年がかりで周到に撤退準備を進めてきたのは協力会社を含めた雇用に加え、設備の活用方法を検討するためだ。
時を同じくして盛り上がっていたのが洋上風力発電。洋上風力発電は大量導入やコスト低減が可能であるとともに経済波及効果が期待され、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた切り札とされる。政府のグリーンイノベーション基金事業の後押しを受け、大量の鉄鋼構造物の需要が生まれる公算が大きい。
東京湾最大級のドックを持つ横須賀造船所の設備を生かせる道が開けたことから、幹部社員を手始めに少しずつ社内で情報を開示し、24年2月14日開催の住友重機械の取締役会で正式に新造船事業からの撤退が決まった。
撤退を知った国内外の顧客からは、驚きとともに「あと1隻でもいいから造ってほしい」という声が複数寄せられたという。新造船事業について「個人的には続けられるなら続けたい」と宮島社長は悔しさをにじませつつも、「新造船事業だけを見れば赤字。右肩上がりの絵を描けない。慈善事業ではないのでどこかで決断をしなければならなかった」と語る。
決定的だったのは08年のリーマン・ショックだ。ピーク時には横須賀造船所で年9隻の新造船を竣工した実績があるが、リーマン・ショックを機に引き合いは一気に枯れ、12年には受注ゼロを味わった。「こんなに長く暗黒の時代が続くとは思わなかった」(同)。
建造船種を10万重量トン級の中型タンカー(アフラマックスタンカー)1本に絞り、量産による習熟効果やトヨタ生産方式の導入などで生きながらえてきたが、年3隻程度で固定費を賄うには限界がある。ライバルの韓国、中国造船所が市場を席巻し、経営危機に陥っても政府支援を受けて何度でも蘇る。皮肉にも足元ではタンカーの需要が急激に広がり、船価は高水準に張り付いているが、当初計画通り26年1月の引き渡しをもって横須賀造船所の新造船事業は収束する運びだ。
今後は浮体式洋上風力発電設備の大型構造物に活路を見いだす。造船受注が活況の今、洋上風力関連の工事を手がけられる大型ドックの価値は高い。横須賀造船所は300トン吊りゴライアスクレーン2基を備えるが、需要動向次第で1200トン吊りの導入も見据える。宮島社長は「まずは実証機の受注を取る。将来的にも受注実績が重要だ」と力を込める。住友重機械マリンエンジニアリングの新たな“船出”が始まる。
手持ち工事高水準/新造船市場、環境が一変 新燃料船ブーム到来
リーマン・ショック以降の韓国、中国造船所との競争激化、新型コロナウイルス感染拡大による商談の停滞、鋼材・資機材高、海運市況低迷など、新造船市場を取り巻く環境は近年目まぐるしく変化してきた。20年10月にはおよそ2年が安全圏内とされる日本の輸出船手持ち工事量が1年を切るほどに落ち込み、複数の造船所が赤字受注に走るか、商船事業から撤退するかを迫られた。
三菱重工業は国内最大級の長崎造船所香焼工場(長崎市)の新造船エリアを大島造船所(長崎県西海市)に譲渡。ジャパンマリンユナイテッド(JMU)は舞鶴事業所(京都府舞鶴市)での商船建造から撤退した。三井E&Sも新造船事業から手を引いた。
一方、ロシアによるウクライナ侵攻などにより国際エネルギー事情やサプライチェーン(供給網)が変化。カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)の潮流も強まり、液化天然ガス(LNG)やアンモニア、メタノール、水素など新燃料への切り替えブームが到来。30年代早々には1億総トンを超え、「その後も新造船需要は高原状態が継続する」(日本造船工業会)との見立てがある。
日本船舶輸出組合によると、3月末時点の輸出船の手持ち工事量は2762万総トンで、日本の造船所は3年分を超える高水準を確保している計算。鋼材高は厳しいが、為替の円安という追い風もある。余力が生まれたこの好機を生かし、投資を十分に行い、ゼロエミッション船の開発やスマートファクトリー化、新事業へのシフトなどを進めることで造船所の価値が一層高まる見込みだ。
By Admin
Saint Kitts and Nevis-flagged oil and chemical tanker Green Land was arrested in Singapore waters on Wednesday (17 April).
The 46,136 DWT vessel was added to the list of vessels under Sheriff’s arrest in Singapore’s court system.
According to the list, the vessel was arrested at 3.30pm and the arresting solicitor listed was law firm PDLegal LLC. The ship is currently held at Global OM (Offshore & Marine) – Grid 3816C.
No further details regarding the reason behind the arrest were provided in the list.
China-flagged container ship Xin Xin Shan was also placed under Sheriff’s arrest at 12.10pm on 20 April. The ship is currently held at Eastern Anchorage and the arresting solicitor listed was law firm DennisMathiew.
時代の流れと環境の変化の結果だろう。コンテナ船の大型化は逆行しないと思うし、アメリカまでの距離を考えると将来がない事は明らかだと思う。
米西岸オレゴン州ポートランド港は、ターミナル6でのコンテナ貨物取り扱いを10月1日で終了する。ポートランド港湾局の貿易・経済発展担当責任者、キース・リーヴィット氏が顧客向けの書簡で明らかにした。寄港船社減少による損失拡大が要因。同港湾局によると、コンテナターミナル運営では過去3年間で3000万ドル以上の損失を計上しており、州政府の財政支援などを求めていた。今後は、完成車などの取り扱いに集中する。
ポートランド港はオレゴン州唯一のコンテナ港で、オレゴン州や近接するアイダホ州などの荷主を中心に、ニッチポートとして利用されてきた。コロンビア川沿いの河川港で喫水が13メートル強と浅く、コンテナ船の大型化が進む中で徐々に存在感が低下。主要顧客だった韓国船社韓進海運の経営破綻などで、2016年以降定期寄港が激減。17年には、ターミナル6を運営してきたフィリピン港湾運営大手ICTSIが、労使紛争の激化を敬遠し、10年から25年契約だった賃貸契約を破棄し撤退。その後、港湾局は新たな借り手を探してきたが進展せず、ターミナル6を自営していた。22年にはターミナル6とシアトル・タコマ間の鉄道輸送を提供してきた米鉄道大手BNSFが、物量減少を理由にサービスを停止した。
現在は韓国船社SMライン、スイス船社MSCが定期寄港している。
コンテナ取扱量は22年が前年比6割増の17・1万TEUと、コロナ禍を背景に拡大したが、過去最高だった03年(33・9万TEU)からは、ほぼ半減している。




韓国だって造船は衰退している。日本は韓国よりも衰退が早い。
アメリカの状況を考えると能力ではなく、やはり高くても建造して実績や経験のある労働者を維持できなければ、ある製品を製造できなくなると言う事だと思う。
同じ事や似た事を繰返す事は難しくないが、一旦、休止して経験を持っている人がいなくなったり、経験が次の世代に受け継がれなくなったら終わりと言う事だろう。人材の層が薄くなり、経験を持つ人達がいなくなってしまうと言う事だろう。
10年以上も前にアメリカに行った時に、多くの船が高齢で新しい船がほとんど建造されていない事実に驚いた。そんな状況だと船を建造しようと思っても建造コストが高くなり、効率が悪く、コストパフォーマンスが悪くなる。
日本だって同じ流れ。今や造船は縮小へ向かう運命。20年経てばもっと状況は悪くなっていると思う。造船に関与する人材だって、昔は優秀な人が入っていたが、今では優秀な人は造船を避ける。当然と言えば当然。衰退する産業で就職したいと考えるエリートがいるはずがない。
日本は英語の問題があるし、現在でも技術的な事がわかり、英語が出来る人はほとんどいないから少なくとも日本がアメリカに進出する事はないと思う。英語の問題だけでなく、アメリカ人を理解した上で進出しないと痛い目に遭うと思う。日本の下請けしか知らない造船所の人達だと無理だと思う。言葉の問題があるから考えるだけ無駄。アメリカの艦艇を日本で修理や改造する事は可能だと思う。しかし、最近は中国人労働者が日本の造船所でも多いから、機密保持という意味では今後、難しくなると思う。
アメリカの大学を卒業して造船とか海運とかの経験がある人は少ないだろう。そう言う意味では自分みたいな存在はお宝として評価されるかもね!通訳だって、造船や海運の事を知らないと出来ないと思うよ。まあ、日本がアメリカに進出する事はないからどうでも良い事。
韓国の方が、海外でいろいろな事をやっているし、経験がある人達が日本と比べれば若いので、有利だと思う。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
アメリカの造船業が廃れたのは日本、韓国の造船業の圧倒的な価格競争力に敗れたからだが、日本、韓国の造船業も中国にシェアーを奪われている。アメリカでは、このところのインフレで賃金も上昇を続けているためコスト競争力は
さらに低下している。産業構造が高度化したアメリカでいまさら重工長大産業を復活させることは現実的ではないのかもしれない。
>向こうは何を求めているんだろうか?
アメリカに投資をしろ!って事だから、日本や韓国の造船メーカーがアメリカで製造設備を作りアメリカ人を高い賃金で雇い最新技術を提供せよ!って事だ。
米軍向けは国防費で買ってやるが、商船については日韓メーカーの営業努力次第だって事になる。
まあ、アメリカの下請けをやれって事だよ。
日本や韓国の造船メーカーに、アメリカ国内の廃工場を買収して再建させアメリカ人を雇用してほしい……ということ?
いや日本の造船メーカーも経営は厳しいし。さらに言えばUSスチール買収問題についての報道を見てると、本当にそれは十分な利益が見込める話なのかちょっとばかり疑問にも感じられるが。
太平洋戦争の最中に、世界最大の戦艦を建造する技術を持っていた日本。作戦負けによって壊滅した空母群も、今の空母建設に重要なデーターを残す程の機能やシステムを持っていたらしい。だからこそアメリカの原爆投下地点の決定には、造船所の有る広島と長崎に決定したと聞く。日本の造船技術は素晴らしいと思う。ただ今になってそれが生かされてないのは日本政府の販売努力が無いので残念。国家としてのプロジェクトであるとしての認識が足りないような気がする。恐らくだけど、韓国や中国に比べて、ロビー活動はかなり劣っている事だろうと思う。
自国の造船業へたれてしまって同盟国に連携してと頭下げる。USsteelもこのまま放置なら国内同業他社に安く買われて寡占進めば米国鉄鋼業はさらに競争力無くして造船業と同じく衰退の一途。組合の反対とまだ残ってる「鉄は国家なり」の自尊心から日鉄に吸収されるの拒んでるが、日米連携ゆうなら鉄鋼業もその方向で再編したほうが将来的に良さそう。
造船業界は好不況の波が激しく、不況期には各社が数年間大赤字をタレ流す状況となってしまう。
モノ言う株主の力が強い米国で、赤字を数年間続けたら、経営者は突き上げを食らうだろう。日本企業が米国で造船業を手掛けるなら、そうならないよう米国政府の手厚い支援が必須だろう。
米国の造船業への投資はかなり難しい。ドル高で人件費が高くなり、労組などの縛りも多いのに労働者の質は日韓の方が高い、それでいて税金も高く環境規制もうるさいとなれば、日韓の造船所からすると投資する理由が見つからない。当然のことながら、こんな高コストの米国で製造した船に、国際市場での競争力はまず期待できない。米国で作ってペイするのは軍艦ぐらいだろうが、日韓のような同盟国とはいえ外国資本の入った造船所で軍艦を製造するほど、米軍は間抜けではない。おまけにUSスチールの話が示すように、政府による介入が増えてきた米国である。トランプ当選の有無にかかわらず、この傾向は強まる一方である。よほどの優遇措置を与えなければ、誰も米国の造船業になど見向きもしないだろう。
継承、経験が途絶えると再度その産業を立ち上げるのは厳しい。特に製造業はちょっとしたノウハウなど、単純にマニュアル化すれば済む訳ではない。
米国本土での作業立ち上げとなるが、日本企業だと海外勤務、出張を嫌う社員が多く、また現地で安定して経験のある職人を確保するのも難しいからあまり積極的に進出しないかなと思います。三菱だと客船建造中の火災など起こしているからどうなのかな。おまけに大統領選挙もあるから、動くとしたら選挙後にどうなるかかな。
鋼材価格の高騰や半導体不足は米海軍にも大きく影響
アメリカ海軍のカルロス・デル・トロ長官が2024年2月、日本と韓国を訪問し、船舶の新造や修繕などを手掛けている造船所幹部と相次いで会談を行いました。デル・トロ長官は米国の造船業の現状に危機感を抱いており、日本や韓国の企業から投資を呼び込むことで国内の造船所を復活させ、艦艇と商船両方の建造能力を強化させる考えを示しています。
【長官きちゃったよ!】三菱・横浜で修理中の米軍艦を視察する様子(写真)
デル・トロ長官が日韓の造船会社に支援を求めた背景には、中国の新造ヤードが商船建造で圧倒的なシェアを占め、その生産設備を生かして海軍力の増強を行っていることがあげられます。
実際、中国の造船所における2023年の年間建造量は4232万重量トンで、世界シェアは50%。受注量では7120万重量トンもあり、こちらのシェア率は67%にものぼっています。特にバラ積み運搬船は世界全体の8割を占め、原油タンカーも7割、コンテナ船も5割といずれも高いシェアを握っています。
こうした状況に関してデル・トロ長官は、2023年9月にハーバード・ケネディ・スクールで行った講演のなかで「中国は世界の海上物流の大部分を支配している。このことは、危機や紛争が発生した場合、アメリカ経済にとって実質的な運航リスクと経済リスクをもたらす」と指摘。同時に「過去30年間、中国の総合的な海洋力が飛躍的に成長する一方で、我が国は急激に衰退した」と述べています。
近年では、新型コロナウイルスのパンデミックで物流が大きく混乱したのに続き、鋼材をはじめとした資機材価格の高騰、世界的な半導体不足など造船業全体を取り巻く環境が大きく悪化したことで、アメリカ海軍が整備を進めるコロンビア級原子力潜水艦やコンステレーション級ミサイル・フリゲートの建造計画にも影響が出ていました。
日本に来る前に韓国へ
デル・トロ長官は、「海事産業は、我が国の経済および国家安全保障にとって極めて重要な戦略的産業」と位置付けており、2023年11月には造船業の課題に対処するため政府造船評議会(GSC)を立ち上げています。
加えて「日本や韓国を含む海外の最も親密な同盟国と提携する機運が高まっている。世界でトップクラスの造船会社を誘致して米国内に子会社を設立させ、民間造船所に投資することで、造船業の能力を近代化と拡大を図り、より健全で競争力のある雇用を創出しなければならない」としています。
最初に訪問した韓国でデル・トロ長官は、ハンファオーシャン(旧大宇造船海洋)を傘下に持つハンファグループの金東官(キム・ドングァン)副会長や、HD現代重工業などを傘下に持つHD現代の鄭基宣(チョン・キスン)副会長と個別に会談しました。その後、現代重工の蔚山造船所やハンファオーシャンの巨済事業所の視察も行っています。
両社は韓国海軍向けの世宗大王(セジョンデワン)級駆逐艦や島山安昌浩(トサンアンチャンホ)級潜水艦の建造経験があるほか、ハンファは大宇時代にイギリス海軍のタイド型給油艦を、現代重工はニュージーランド海軍の補給艦「アオテアロア」を建造するなど海外向け艦艇でも実績を持っています。
なお、商船分野についても、需要が高まっているLNG(液化天然ガス)船や海上輸送で必須のメガコンテナ船の受注を安定して確保しているうえ、新船型の開発も積極的に行っています。
視察を終えたデル・トロ長官は「ハンファと現代は業界のグローバル・スタンダードを確立している」と高く評価。アメリカ進出について強い関心を得られたとして、「両社の高い技術とノウハウ、そして最先端のベスト・プラクティスがアメリカの地で実現することを考えると、これほど楽しみなことはない」と述べています。
横浜で修理中の米軍艦も視察
続いて訪問した日本では、東京・赤坂のアメリカ大使館で三菱重工業の江口雅之執行役員(防衛・宇宙セグメント長)、ジャパンマリンユナイテッド(JMU)の江藤淳常務執行役員(艦船事業本部横浜事業所長)、名村造船所の名村健介社長(佐世保重工業社長)と会談。ここでもアメリカ国内の造船所への投資について議論が行われました。
また、デル・トロ長官はLNG船や艦艇、フェリーなどの修繕を行っている三菱重工横浜製作所を視察し、入渠中のアメリカ海軍給油艦「ビッグホーン」の艦長とも懇談しています。
デル・トロ長官は「現在稼働中の造船所に加え、米国内には数多くの造船所跡地があり、それらはほとんど手つかずの状態で眠っている。これらは、イージス駆逐艦のような艦艇だけでなく、化石燃料から水素のようなグリーン・エネルギーへの転換を容易にするアンモニア輸送船のような高付加価値船の建造施設として再整備することができる」と話していることから、商船建造にも力を入れる方針のようです。
なお、アメリカにはすでにオースタル(豪州)やフィンカンティエリ(イタリア)といった外国資本の造船会社が進出しているため、今後、日本や韓国の資本が入った造船所が誕生する可能性は十分にあるといえるでしょう。
深水千翔(海事ライター)
新来島どっく(愛媛県今治市、森克司社長)は13日、同社グループで内製化した液化天然ガス(LNG)燃料タンク搭載の1番船となる自動車運搬船「CERULEAN ACE(セルリアン エース)」を今治市大西町新町の大西工場で商船三井に引き渡した。
LNG燃料は、多くの船で使われている重油燃料と比べ二酸化炭素や硫黄酸化物などの排出が少なく、環境負荷が低いとされる。同タンクは新来島どっくが2021年にグループ化した新来島サノヤス造船(岡山県倉敷市)で研究、製造を進めていた。タンク製造にはマイナス160度以下の低温に耐える高い加工技術が求められ、中国製のシェアが高い。今後、世界的に需要が高まるとみられる。
「CERULEAN―」は全長199・95メートル、幅38メートル。乗用車7050台を積載でき、LNG燃料のほか重油燃料にも対応している。
愛媛新聞社
常石造船などで構成する常石グループの2023年商船受注隻数が62隻に達した。22年の35隻から大幅に隻数を伸ばした。同社開発のヒット商品となる8万2000重量トン型(82型)カムサマックスバルカーを軸に成約を積み上げた。カムサでは、従来の重油焚(だ)きのほか、メタノール燃料型も20隻成約。メタノール燃料船としては、カムサのほか66型バルカー、さらにコンテナ船でも同社建造船として最大船型となる5900TEU型を開発し、3船型で計約30隻を受注した。昨年1年の成約拡大を受け、足元では27年末までの手持ち工事確保にほぼめどを付けた。
関係者が23年受注実績を明らかにした。受注隻数には、常石造船のほか、中国の常石集団〈舟山〉造船(TZS)、フィリピンのツネイシ・ヘビー・インダストリーズ〈セブ〉(THI)分も入る。関係者は「23年の受注隻数目標は40隻としていたが、実績は大幅にこれを上回った。62隻のほか、24隻分を受注内定した」と語る。
常石造船は昨年、メタノール燃料船の成約で存在感を示した。23年1月に世界初のメタノール燃料バルカーとして、米穀物メジャーのカーギルを用船先とするカムサ2隻を三井物産から受注することで基本合意したと発表。それ以降成約を積み重ね、メタノール燃料船としてカムサ20隻のほか、66型バルカー3隻、5900TEU型コンテナ船4隻の計27隻を受注した。
船舶の新・代替燃料化に関連する動きとして、今年1月に5000立方メートル型LPG(液化石油ガス)船の第1船を引き渡した。常石造船としてLPG船の建造は初めてで、LPG貨物タンクも自社で製造した。曲げ加工、溶接などを含むこのノウハウをLNG(液化天然ガス)、アンモニアなどの燃料タンク製造に生かす。
常石造船は、内航船分野でも新・代替燃料化に対する取り組みを進める。
現在、NSユナイテッド内航海運向けにLNG専焼エンジンとリチウムイオンバッテリーを組み合わせたハイブリッド推進システム適用の5560重量トン型石灰石船を建造中で、3月に引き渡す予定。
このほか、常石グループの神原汽船、ツネイシクラフト&ファシリティーズの2社が、ベルギー海運大手CMBと共同で出資するジャパンハイドロが計画している「水素混焼エンジン搭載型タグボート」も常石造船が建造する。今年に建造を開始し、来年に引き渡す。
常石造船は、船舶の新・代替燃料について、候補となる対象全てに対応する方針。「全方位でやっている。バイオ燃料や原子力推進なども勉強する予定。『これが来そうだ(需要が増えそうだ)』となったとき、すぐに動けるようにしたい」(関係者)
By GNNLiberia
BY REUTERS |
Dozens of oil tankers used by Russia have ceased sailing under flags of Liberia and the Marshall Islands in recent weeks after the U.S. increased sanctions enforcement on ships linked to those registries, according to shipping data and interviews with industry and government officials.
The shift reflects the close relationship between the U.S. and the flag administration companies of Liberia and the Marshall Islands, which are headquartered not in their home countries but in Virginia, just miles from Washington D.C. and within the jurisdiction of U.S. sanctions enforcement.
The heavy past use of those flags also represents a potentially lasting vulnerability for Russia’s oil fleet. According to energy and sanctions specialists, tankers will remain liable for sanctions violations even after they switch to a new flag outside of U.S. reach.
“They’ve created an enduring liability and enduring risk,” said Craig Kennedy, a center associate at Harvard University’s Davis Center for Russian and Eurasian Studies.
Commercial ships must be registered or flagged with a particular country to ensure they comply with internationally recognized safety and environmental rules.
Reuters analyzed LSEG and Lloyd’s List Intelligence shipping data and interviewed government officials, flag registry representatives and shipping analysts to provide previously unpublished details on the role of flag registries in the recent wave of U.S. sanctions announcements targeting Russia’s oil fleet, and the vulnerabilities they pose to Russian oil shipping.
The G-7, the European Union and Australia imposed a $60 a barrel price cap on Russian oil exports in December 2022 as part of wider economic sanctions aimed at cutting Moscow’s revenues without disrupting global energy supplies, following Russia’s invasion of Ukraine.
The cap bans the use of Western maritime services when tankers carry Russian oil priced at or above the cap. A U.S. official, who requested anonymity when speaking about the sanctions, confirmed that the Liberian and Marshall Islands flag registries qualify as Western services.
三光汽船(本社・東京都港区、田端仁一社長)が海運業の歴史に幕を下ろす。年内に最後の保有船「Sanko Hawking」(8万2500重量トン、2021年に常石造船で竣工)を売却する。同社は14年に2回目となる更生手続きを終了し、通常会社として復帰していた。近年は黒字転換していたが、社長の後任人事が難航。後継者不足や新規投資が難しくなり事業の継続が困難になった。「海運業界の風雲児」として波乱の歴史をたどった三光汽船は創業から90年で海運業から撤退する。
三光汽船は1934年に大阪で創業。ほどなく元衆議院議員の故河本敏夫氏が社長に就任すると、戦後の復興に合わせ船隊規模を増加させた。
同社は63年の海運集約に参加せず、「一匹狼」「自主独立」を標榜(ひょうぼう)する。
71年に時価発行増資と第三者割当増資で資金調達を拡大。これを新造船の大量発注の資金に回すと同時に72年にはジャパンライン(当時)株を買い占め、「三光商法」ともいわれた。
一方、石油ショックで不況に直面すると大量の新造船が不採算船となり85年に当時として戦後最大の5200億円の負債を抱え倒産、1回目の会社更生法適用を申請した。
98年に1回目の更生手続きの終結に伴い、00年には同社生え抜きの松井毅氏が社長に就任した。
リーマン・ショック前の07―08年には売上高2293億円、経常利益797億円の過去最高の業績を記録。売上高経常利益率は35%と当時の日本の海運業界でもトップの利益率を誇った。
三光汽船はリーマン・ショック前の好景気に大量の中型バルカーを発注。保有船35隻に対し用船150隻という「過度なレバレッジ経営」(他人資本=船主に頼る経営)に傾注していく。
くしくも85年の倒産と同様に、過度な投資後の不況が同社を直撃する。
中型バルカーだけでなく、オフショア支援船を数十隻規模で発注したことも経営悪化に拍車を掛けた。
12年7月に負債1558億円、用船料の支払い債務4056億円を抱え東京地裁に2回目となる会社更生法適用を申請、13年10月に更生計画の認可を受けた。
再建に向けスポンサー探しに難航するが、13年に米投資金融のエリオットが投融資枠の設定を含め50億円の支援でスポンサー契約を締結。
同社から田端氏が管財人兼社長として就任すると更生計画時点で44隻だった船隊を28隻までスリム化した。海運市況の上昇もあり、わずか1年後の14年12月に更生手続きを終結させ通常会社に戻った。
更生手続き終了後、バルカー、LPG(液化石油ガス)船、アフラマックス、オフショア船、ケミカル(石油化学製品)船などを運航していたが、15―16年にかけ円高で業績が不振に陥る。
段階的に保有船を縮小してきたが、ここにきて11年間、社長を務めた田端氏の健康問題に伴う後継者不足、新造船への投資が難しくなった。
現在、最後の保有船1隻について売却先の選定に入っている。数々の時代の荒波を乗り越えた三光汽船の海運業の歴史に幕が下りることになる。
【解説】見えた再建...にじむ無念
11年前、管財人兼社長に就任した当時の田端氏は再建の意欲に燃え、目つきが鋭かった。「体質の改善と意識改革を進める」とインタビューで再三語っていた。
田端氏はシティ銀行、米投資銀行エリオット出身の経歴を持つ。
大胆なリストラをするのかと思っていたが、人減らしより船隊規模の縮小を優先させた。神戸商船大学(現神戸大学)卒、反田産業汽船での勤務経験を考えると、どこか「潮の香り」がする経営者という印象もあった。
今回、最後の保有船を売却するに当たり、無念の言葉もにじむ。
最後の保有船は21年竣工の新鋭船。カーギルの用船保証がつき、「稼働率は98%、一流の荷主と堅実な運航をすれば黒字化するノウハウを確立できた」と語る。
実際、円安の効果もあるが、10億円規模の黒字を計上している。
今回、三光汽船が海運業から撤退する最大の理由は田端氏の健康問題、さらに今後の投資に対する懸念である。
社長就任時54歳だった田端氏も今年で65歳になる。昨年入院し、経営のバトンタッチを検討した。
しかし、日本の大半の船主同様に適任者がおらず、事業の売却も考えたが、「田端さんとセットでなければ無理だ」と言われたという。
新燃料が定まらない現状で新造船に投資するにはリスクもある。三徳船舶の故多賀征志氏にも相談したが、多賀さん自身が昨年亡くなってしまった。
社員やスタッフ10人の面倒は最後まで見るという。
近年は記者も三光汽船の取材から遠ざかっていた。
10年前、経営者と記者という立場から鋭く対立した時もあった。経営の一線から退く田端氏の姿に共感する部分が多いことに、記者も三光汽船の歴史、時の経過を感じざるを得なかった。
(山本裕史)
日本海事新聞社
事業再生ADR(裁判以外の紛争解決)で経営再建をめざしていた三光汽船(東京・千代田)は2日午前、東京地裁に会社更生法の適用を申請した。主力船が船主から差し押さえられるなど顧客離れが深刻化。ばら積み船の運賃も低迷し、再生計画づくりが行き詰まった。負債総額は1558億円。同社は1985年にも会社更生法の適用を申請しており、2度目の経営破綻となる。営業は継続する。
ばら積み船の運賃低迷で運航船の船主に払う賃料とのギャップが広がり、資金繰りが悪化した。3月に事業再生ADRを申請し再建をめざしていたが、運賃はその後も悪化。外国船主による北米沖での船舶の差し押さえも発生し、貨物を輸送できない事態に陥り、荷主離れが加速した。
用船料の支払い延期要請などが発端となって運航船の船主が用船契約を解約する動きも広がった。ただ支払いの繰り延べ交渉は難航し、燃料費の支払いなども負担となって資金繰りに行き詰まった。
同社は短期の輸送契約が主流。長期契約が主体の大手に比べて好況時は高い収益を見込めるが、不況になると経営が苦しくなる。12年3月期は995億円の売上高に対し、1103億円の最終赤字に陥った。
3月時点では15年3月期にばら積み船の最大船型「ケープサイズ」の運賃が1日あたり3万ドルという前提で黒字転換する再生計画を描いていたが、足元では4千ドル未満で低迷。再生計画のメドが立たなくなった。
三光汽船は新生銀行や三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行など金融機関10行に対して290億円の負債を抱えている。
同社は85年に当時戦後最大となる約6650億円の負債を抱えて会社更生法の適用を申請した。98年には更生手続きを終え、一時は上場もめざしていたが海運不況に耐えきれずに再び経営危機に陥った。
2026年で新造船から撤退する「住友横須賀」
東京湾からまた一つ、新造船ヤードが消えます。住友重機械工業は2024年2月14日、住友重機械マリンエンジニアリングの横須賀造船所で行っている商船の新造船事業から撤退すると発表しました。2024年に入ってから新規受注は中止しており、2026年1月の引き渡しが建造最終船となります。
横須賀造船所のドックは引き続き船舶修繕で使用するほか、需要増が見込まれる洋上風力発電の浮体式構造物などの製造に活用する予定です。
【住友が持ってました】世界に4つしかない横須賀の“風格がスゴイ造船所”(写真)
住友重機械工業は11万重量トン級の石油を運ぶアフラマックスタンカーに特化する戦略を取っていたことで知られています。同船種を日本で建造しているのは横須賀造船所だけで、国内外から高い評価を得ていました。近年では国際海運で大きな課題となっているGHG(温室効果ガス)排出を削減する新船型として、LNG(液化天然ガス)燃料船やメタノール燃料船の開発にも取り組んでいました。
それではなぜ一般商船の建造を取り止めることを決めたのでしょうか。
決算会見で渡部敏朗取締役専務執行役員CFO(最高財務責任者)は「2012~2013年以降はかなり船価も低迷して受注も苦しい状況だった」と背景を説明します。
「新造船はかなり採算的に苦しい状況で、実質赤字できていた。実際に事業をやっている住友重機械マリンエンジニアリングは、修理船などもやっており、これらの収益で新造船事業をカバーしてきた。しかし近年はそれでもカバーしきれず、赤字が継続していた」(渡部CFO)
住友重機械工業は1969(昭和44)年に住友機械工業と浦賀重工業が合併して誕生した会社です。浦賀重工は1897(明治30)年に創業した浦賀船渠(浦賀ドック)を前身としており、住重グループは120年以上にわたって造船業を営んできたことになります。
浦賀では青函連絡船の「翔鳳丸」や「津軽丸」といった鉄道史に残る車載客船や、戦後の引き揚げ輸送で活躍した日本海汽船の「白山丸」、瀬戸内海の女王として知られる関西汽船の「むらさき丸」、旧日本海軍の軽巡洋艦「五十鈴」、駆逐艦「時雨」、海上自衛隊の護衛艦「はつゆき」、試験艦「あすか」など官民問わず多種多様な船を送り出しています。その数1300隻以上。1980年代に海技教育機構の練習帆船「日本丸」と「海王丸」を建造したのも浦賀の造船所でした。
浦賀と追浜、2つの造船所の「その後」
住友重機械工業は浦賀だけでなく、1959(昭和34)年に旧横須賀海軍工廠の第2船台などを取得して設置した横須賀工場や1971年に船舶の大型化に伴って開設した追浜造船所(現・横須賀造船所)が稼働しており、東京湾内における大型商船ヤードの一翼を担っていました。
しかしオイルショック後の造船不況に突入すると、主力製品である大型タンカーを中心に新造船需要が激減し、大量キャンセルが続出。生産設備の整理が求められるようになります。手狭となっていた横須賀工場は閉鎖売却され、浦賀造船所は規模を縮小し艦艇・官公庁船にシフト。商船の建造は追浜造船所が中心となります。
ただ日本経済そのものが低迷する時代を迎え、造船業も生産設備の増強とコスト競争力で優位に立つ中国や韓国に抜かれていきました。2000年代に起きた造船所再編の流れの中で、住友重機械工業は浦賀艦船工場を艦艇部門と共にIHI子会社のIHIMU(アイ・エイチ・アイマリンユナイテッド)横浜工場へ統合することを決め、護衛艦「たかなみ」の引き渡しをもって住重グループは浦賀での新造船建造から撤退しました。
2003年に住友重機械マリンエンジニアリングが発足すると「中型タンカーNo.1」を掲げ、追浜の横須賀造船所で建造するアフラマックスタンカーへの差別化集中戦略を取りました。余分な在庫を抱えず、顧客からの要望に応じた効率的なモノづくりを行うトヨタ生産方式を導入してコスト削減を図り、建造船種を絞ることでより高品質な船を提供していくという方針は当たり、2007年に業績は好転します。
しかし、2008年のリーマンショックが起きると、新造船を取り巻く事業環境は急速に悪化。受注隻数を制限し建造隻数も年3隻まで絞って体制の見直しを試みていたものの、船価の変動、鋼材や資機材価格の高騰、さらには中国や韓国の造船所もアフラマックスタンカーに参入して競争環境が悪化する中で、将来的に事業を継続することは困難な状況に追い込まれました。
こうして住友重機械工業は長年にわたる横須賀での商船建造から撤退することになったのです。受注残は7隻で2026年1月まで順次引き渡しを行います。
広~いヤードはまだまだ活用 新ステージへ
かつて31万重量トン型VLCC(大型原油タンカー)を建造した三井E&S造船の千葉工場も2021年3月で造船事業から完全に撤退しており、住友横須賀が新造船から手を引くと、東京湾内で大型商船が建造できるヤードはJMU(ジャパンマリンユナイテッド)横浜事業所磯子工場だけとなります。
横須賀造船所の今後について住友重機械工業の下村真司社長は「ドックの一部は既に修理船で使用している。また、これから洋上風力発電をやっていく中で、浮体式構造物を建造する上でドックが非常に重要になってくると考えている」と話します。
住友重機械マリンエンジニアリングは、東京湾近海の官公庁船と在日米軍向けの艦船修理に注力しており、アメリカ海軍の原子力空母からアメリカ陸軍の揚陸艇まで、幅広い船種で修理・改造サービスを提供しています。若干ではあるものの、商船の修繕も行っており、長さ580m、幅80mの大型ドックを活用し、大型船入渠工事や中小型船の同時入渠工事も可能。大型のゴライアスクレーンを使っての吊り入渠ができるのも特長の一つです。修理船事業は継続するため、東京湾内の修繕拠点はこれまで通り維持できる見通しです。
もう一つは、脱炭素エネルギー領域として展開していく洋上風力用構造物や関連船舶、風力推進コンポーネントの製造です。浮体式洋上風発の中でも、例えばバージ型は造船所のドックで製造し、そのまま海へ引っ張り出すことができるというメリットを持っています。
「我々のドックは、非常に幅が広いこともあって、対応できる浮体式構造物も多い。ドックを有効活用しながら脱炭素エネルギーの分野に今後向けて活用していきたい」(下村社長)
新造船事業撤退に伴って空いた場所は、グループの住友建機が大型油圧ショベルの新工場を建設し、これまでの千葉製造所を中・小型のショベルの生産に特化させて油圧ショベルの増産に対応する方針です。また、港湾クレーンのような大型クレーンの製造も横須賀製造所で行っていきます。
横須賀造船所を象徴する巨大なゴライアスクレーンの下で新しい船が建造され、最終船が引き渡されるまで2年を切りました。横須賀における大型商船建造の歴史が幕を下ろそうとしています。
深水千翔(海事ライター)
日本の造船メーカー、住友重機械工業は14日、子会社の住友重機械マリンエンジニアリングによる一般商船の新造船事業から撤退すると発表した。東京湾の神奈川県横須賀市に位置する住友重機械工業は、韓国や中国との激しい競争で造船事業が困難に直面していた。
造船業界によると、中・大型タンカーを主力とする住友重機械工業の昨年の受注規模は169億6000万円にとどまり、受注残は11万5000DWT(載貨重量トン数)のアフラマックス級タンカー6隻だけだ。
住友重機械工業の横須賀造船所は日本で最も古い造船会社の一つで、1897年創業の浦賀船渠がルーツだ。同造船所は長年、数多くの軍艦、商船、旅客船などを建造した。超大型原油タンカー(ULCC)、世界初の二重船体構造タンカー、世界初の砕氷タンカーを建造したこともある。
日本の造船業は韓国と中国に押され、急激に衰退した。受注残ベースで日本のシェアは2019年の16%から21年に11%、23年に10%へと低下した。
韓国造船業界はこれまで液化天然ガス(LNG)タンカー、超大型コンテナ船の受注で持ちこたえてきたが、大口受注分の建造が大詰めを迎えており、タンカーの受注競争に乗り出す必要がある。タンカー市場は新造注文が増えているが、中国が低価格で受注している。先週、中国はギリシャの船会社が発注した18億ドル規模の大型原油タンカー(VLCC、30万DWT規模)を14隻を受注した。 同じ期間、韓国によるタンカー受注は現代三湖重工業のスエズマックス級(12万~20万DWT)2隻、DH造船のシャトルタンカー3隻にとどまった。タンカーはLNGタンカーに比べ高い技術力が必要なく、価格競争力が重要なので、中国と厳しい競争関係にある。
最近の経営陣交代後、初めてタンカー市場の受注競争を迎えるハンファオーシャンは市場参入戦略の検討を続けている。ハンファオーシャンは対外的には低価格で受注するぐらいならばドックを空けておく方針だ。しかし、造船業は受注がなくても固定費用が発生するため、低価格受注でも赤字縮小にはつながる。
パク・チョンヨプ記者
Republic of Liberia has issued a Marine Advisory, to draw the attention of shipowners, operators, masters and Liberia’s Recognized Organizations (RO) to AMSA’s policy on remote surveys.
AMSA has reported recent instances where an RO undertook a remote survey to sight rectification of a deficiency for a ship detained in Australia, whereupon AMSA’s re-attendance of the ship, it was found that the deficiencies were still outstanding.
As a result, AMSA will no longer accept any remote survey from an RO for a ship detained in Australia and cited the following two recent examples:
A bulk carrier was surveyed remotely after being detained for defective auxiliary generators. The RO declared that both the required generators were operating satisfactorily. This remote survey was not accepted by AMSA. When the RO boarded the ship, none of the generators could sustain their rated power.
Another bulk carrier was detained with a large number of maintenance related defects. The RO undertook a remote survey and attested that all defects had been rectified. When AMSA boarded the ship, a significant number of defects remained outstanding.
Remote surveys are not equivalent to a physical survey. As a result, we will no longer accept any remote survey from an RO for a ship detained in Australia.
..AMSA stated.
As such, the Republic of Liberia recommends that Owners, Operators, Masters and RO’s to ensure that physical attendance of an RO Surveyor is arranged whenever verification of the rectification of any deficiency on a vessel detained in Australia by the vessel’s RO is required.
住友重機械工業は14日、新規の造船受注からの撤退を決めたと明らかにした。鋼材価格の上昇や海外企業との競争が激しい状態が続いていることなどから、「将来的に事業を継続することは困難」と判断した。これに伴い、2023年12月期決算に8億4千万円の特別損失を計上した。
新規の造船に関わる従業員は今後、洋上風力発電関連などグループの別の事業に再配置していく。船の修理やアフターサービスは続ける方針で、現時点で人員削減は予定していないという。
住友重機械工業が新造船事業からの撤退を決めた。14日に造船事業の再構築を発表し、一般商船の建造については2024年度以降の新規受注を停止し、受注残の引き渡しをもって終了することを明らかにした。建造拠点のある横須賀製造所(神奈川県横須賀市)では撤退後、洋上風力発電用の浮体建造などを手掛ける。1897年設立の浦賀船渠からスタートした住重の造船業は大きな転換点を迎える。(2面に関連記事)
新造船事業からの撤退後は26年をめどに、洋上風力用構造物および関連船舶を建造。修理船事業や風力推進関連などのエンジニアリングサービスも手掛ける。これに加えて横須賀製造所は24年から、大型港湾クレーンなどグループ内企業との生産協業を開始。ショベル工場も新設し、26年から生産を開始する。
住重はアフラマックスタンカーに特化する戦略を取り、近年も国内外の船主から高い評価を得て一定のペースで受注。同船種の日本唯一の建造ヤードとして横須賀造船所で連続建造してきた。
住重グループの住友重機械マリンエンジニアリングの宮島康一社長は22年の就任時、本紙の取材に「横須賀の地で造船事業を継続していくためにも、船以外にプラスアルファとして例えば鉄構造物などの製造も検討しなければならない」と語っていた。
日本海事新聞社
Vietnam’s state-owned shipbuilding company SBIC is facing bankruptcy, and the government has initiated plans to overhaul the corporation. This follows a resolution passed last month by Vietnam’s Political Bureau (Politburo), which gave a green light to declare SBIC and its seven subsidiaries bankrupt.
The Deputy Minister of Transport Nguyen Xuan Sang is leading the working group tasked with implementing the resolution. During a meeting with SBIC’s managers on January 3, Xuan Sang emphasized that the bankruptcy was inevitable after sustained efforts to restructure the company proved unsuccessful. SBIC’s debt balance remains large compared to total assets.
The bankruptcy process includes a transfer of ownership, he said, which will enable the company and its subsidiaries to operate without the burden of old debts. The profitable subsidiaries will also be freed from their parent company’s debt burden.
For almost a decade, Vietnam’s state-run shipbuilding has been in the doldrums because of alleged mismanagement and cost overruns. This began with the crash of former state shipbuilder Vinashin in 2010, which was later restructured into SBIC in 2013. At the time, SBIC was saddled with debts totaling $4 billion left by Vinashin.
However, a recent report by the Transport Ministry claimed that SBIC’s shipbuilding operations have been unable to make any profit, hence the difficulty in meeting financial obligations inherited from Vinashin.
In the last two weeks, Sang has led the working group to conduct a full evaluation of SBIC’s operations across the country, and initiated drafting of a bankruptcy roadmap to maximize capital and asset recovery.
This will be followed by SBIC and its subsidiaries filing for bankruptcy. Once the case is resolved, liquidation of assets and debt payment will be carried out in accordance with a court ruling. During the process, actively operating units with existing contracts will continue with their normal operations.
At its prime, Vietnamese shipbuilding climbed up the ranks to become the fifth largest in the world, fueled by a boom between 1999 and 2007. Despite the current collapse of the sector in Vietnam, Sang said this is a good time for a comeback as the maritime industry is gradually replacing old ship with a new generation of vessels running on alternative fuels.
“The completion of bankruptcy will be an opportunity for shipyards to enter a new phase and seize the moment for development,” said Sang.
A process has been started to allow the Vietnam Shipbuilding Industry Corporation (SBIC) to declare bankruptcy, according to the deputy minister of transport Nguyễn Xuân Sang.
HÀ NỘI — A process has begun to allow the Việt Nam Shipbuilding Industry Corporation (SBIC) to declare bankruptcy, according to Deputy Minister of Transport Nguyễn Xuân Sang.
The Ministry of Transport (MoT) says the bankruptcy was, at this point, an inevitable conclusion and the ministry is now aiming for an overhaul of the corporation's core businesses while trying to retain as many experienced managers and workers as possible.
Established in 2013, SBIC was formed through the reorganisation and restructuring of the Vinashin Group. At that time, its charter capital was over VNĐ9.5 trillion (US$390 million). However, SBIC had to bear the debt burden left by Vinashin, totalling over $4 billion.
Meanwhile, the bankruptcy will allow profitable subsidiaries to thrive by freeing them from their parent corporation's old and existing debt. A recent report by the ministry said while the corporation's ship-building businesses have consistently been able to turn a profit in the last few years, they were not sufficient to meet financial obligations inherited from the Vinashin era.
Vinashin, officially known as the Vietnam Shipbuilding Industry Group, is a State-owned enterprise in Việt Nam involved in shipbuilding, ship repair, and maritime industries. Between the years 2000 and 2010, Vinashin faced financial difficulties and a significant debt crisis due to mismanagement, cost overruns, and a lack of transparency.
Funds obtained from the liquidation of the company and assets will be utilised according to bankruptcy laws, including debt repayment, salary payment, and social insurance for workers, remaining from the Vinashin period, according to the MoT.
Earlier this week, the MoT conducted a full evaluation and review of SBIC's businesses and subsidiaries across the country. The ministry has started building a detailed roadmap aimed at maximising capital and asset recovery while minimising the use of additional State budgets.
In a meeting with SBIC's managers, the deputy minister said the bankruptcy includes the transfer of ownership of the corporation. Once completed, it will allow SBIC's member shipbuilding companies to enter a new phase, free from the burden of old debts, so they can have more proactive control in their production and business activities, ensuring greater efficiency.
SBIC was asked to complete the personnel reorganisation, address difficulties, and coordinate with the Business Management Department under the Ministry of Transport to facilitate the bankruptcy procedures for its member companies.
Regarding the corporation's existing workers, Sang said that the bankruptcy is aimed at creating conditions for business revival and restructuring activities. Therefore, regardless of the owner, there is still a significant need for an experienced management team and labour force within the existing businesses.
Following the process, member units and SBIC will submit bankruptcy procedures to the court. Once the court opens the case and declares bankruptcy, the liquidation of assets, obligations, and payment priorities will be carried out according to the court's ruling. During this process, actively operating units with existing contracts will continue their normal operations.
In an earlier development, the MoT sent a document to SBIC requesting a thorough assessment of the situation of each business, compiling documents, and developing specific plans for each enterprise. The affected units include the parent company SBIC, its subsidiaries (seven companies), and 147 former Vinashin member businesses that have not completed restructuring. — VNS
by Naida Hakirevic Prevljak
The United Arab Emirates (UAE) has banned vessels flying the flag of the Republic of Cameroon from calling UAE waters and ports.
On Januaury 2, 2024, the UAE Federal Maritime Administration (FMA), represented by the Ministry of Energy and Infrastructure, published a new circular.
In the circular, the FMA said it decided to include the vessels registered under the flag state of Cameroon to the existing list of restricted flag state vessels.
As informed, the Cameroon-flagged ships have no longer access to UAE ports and waters unless they are classed by a member of the International Association of Classification Societies (IACS) or by the Emirates Classification Society – Tasneef.
“Accordingly, all the maritime companies and ship agents in UAE are hereby requested not to provide the services to those vessels that are not complying with this circular to avoid legal accountability,” the FMA noted.
Apart from Cameroon, the concerned flag states countries list includes Albania, Belize, the Democratic People’s Republic of Korea, Sao Tome and Principe, Tonga, Congo, Equatorial Guinea, and the United Republic of Tanzania.
The administration, which is responsible for regulating foreign ships’ operations in the UAE waters and ports, has not provided further information explaining the reason behind this decision. However, reports indicate that the ban may be linked to Cameroon’s reputation as a ‘heaven’ for Russia’s so-called ghost fleet.
There is a growing number of law-abiding ships in the world which have no insurance protection. Having no insurance becomes a problem when accidents involving these ghost ships occur, especially for countries controlling the waters where accidents take place.
Therefore, the UAE’s recent move can be seen as an attempt to distance itself from unfortunate and risky situations involving ghost ships.
Since the introduction of the G7 oil price cap for Russia’s crude oil and refined products there have been speculations on Russia’s so-called shadow fleet being used to evade sanctions. Last year, S&P Global Market Intelligence whitepaper estimated that 443 tanker vessels (with a deadweight greater than 10,000) are currently operating within the Russian shadow or ghost fleet. Cameroon is among the flag states linked to vessels’ illegal activities, according to the report.
It is worth noting that the Paris MOU has identified Cameroon as a flag state with a ‘very high risk’, placing it on its Black List of ships. Vessels Haksa, Skymoon King, Gelibolu 2, Sefora, Sheksna, Bella are currently banned from the Paris Mou region, data provided by the Paris MoU shows.
政府はこのほど、造船工業総公社(ShipBuilding Industry Corporation=SBIC、旧ビナシン=Vinashin)および子会社7社の破産手続きの実施に関する決議を発表した。
破産する子会社は、◇ハロン造船(Ha Long Shipyard)、◇ファーズン造船(Pha Rung Shipyard)、◇バクダン造船(Bach Dang Shipyard)、◇ティンロン造船(Thinh Long Shipyard)、◇カムラン造船(Cam Ranh Shipyard)、◇サイゴン造船工業(SSIC)、◇サイゴンシップマリン(Saigon Shipmarin)の7社。
SBICと子会社7社は2024年1~3月期に破産する。
SBICは2014年の設立で、資本金は9兆5200億VND(約560億円)となっている。非効率な経営により損失や多額の負債を抱えている。2021年は▲3兆8000億VND(約▲220億円)の赤字となった。
人それぞれで合う、合わない、又は、好き嫌いはあると思う。どこの記事なのかは忘れたが、小学生でなりたい職業のトップに警察官が上位にあるが、年齢が上がるとランキングからはずれるようだ。つまり、イメージだけでは職業としては選択しない、そして、いろいろな選択を考えるので、魅力ある労働環境、給料、そしてその他の優先順位のコンビネーションで判断するのだと思う。
つまり、体験乗船をやらないよりはましだと思うが、効果は期待できないと個人的には思う。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
船員不足の原因となる労働環境をどうにかしないとすぐ辞めるよ
一人でも船員目指してくれたらなぁ…
香川県の小豆島で地元の小学生たちが新人船乗りを養成する練習船に体験乗船しました。
新人船乗りを養成する海技教育機構の練習船、「大成丸」に体験乗船したのは、香川県小豆島町にある星城小学校の6年生24人です。
児童たちは船員に案内してもらいながら船の中を見学したり、実際にハンドルを握って操縦を模擬体験するなど、興味深々の様子で船について学んでいました。
(児童は…)
「操縦は簡単だと思っていたが意外と難しかった」
「リアルですごく楽しかった」
「すごいなと思ったところもあるし、こういう風にできていたのかと気づいたところもあった」
この体験乗船は深刻化する船員不足の解消につなげようと小豆島町などが企画したもので2018年度から行われています。新型コロナの影響で対面での交流は4年ぶりとなりました。
岡山放送
2023年12月18日、韓国の造船最大手の一つ『サムスン重工業』が興味深い公示を出しました。
韓国型と誇った「KC-1」を用いたLNG運搬船が欠陥船と認定され、裁判の結果、賠償金2.9億ドルを支払うことになった――というものです。まず以下をご覧ください。

原告(申請人):SHIKC1 SHIPHOLDING SA/SHIKC2 SHIPHOLDING SA
韓国の技術レベルは安い船価の造船所だと中国と大してかわらないと外国人の監督が言っていた。コストを安くしても労働力の質があまりにも下がれが、安かろう、悪かろうの評価を受けるようになるリスクがあると思った。
韓国造船業は政府との関係が親密なようなのでそこが大きく日本と違うように思える。日本は技術者が不足していると思うが、韓国も同じように思える。下請け業者などは作業着も着ないで、私服で港までやってきてメンテナンスをしているのを見ると、結構、給料をカットされているのかなと思ったりする。
作業着やその他の物を持って外国の港まで行くのは大変なのはわかるけど、最小限に絞って移動するはどうなのかなとも思う。何が正しいのかはわからないので、生き残ったところが勝ちなのかもしれない。
10年以上続いた長期低迷から抜け出し、好況を迎えた韓国の造船業界が最近、海外生産拠点の構築を再検討している。2000年代初めから半ばにかけての好況では、人件費を節減するためフィリピン、中国などに大規模造船所を建設した。その後不況で安値で売却した例もあるが、当時の失敗を教訓に国内の熟練工を派遣し、生産効率を上げたベトナム合弁造船所など成功例もある。4~5年分の受注を蓄積する中、韓国国内での慢性的な人材不足を打開し、最近事業を拡大している軍艦など防衛産業分野では海外にも生産拠点を設け、競争力も高める狙いだ。
■米国法人設立、サウジ合弁造船所試験稼働
ハンファオーシャンは今年9月の理事会(取締役会)で米国法人の設立を決議した さらに、先ごろには増資で調達した1兆4971億ウォン(約1,710億円)のうち約4200億ウォンを海外への防衛産業拡張に向けた生産拠点構築と艦船の整備・修理・分解点検(MRO)企業の株式取得に充てる計画を明らかにした。60兆ウォンに達するカナダ潜水艦事業の受注など海外事業を拡大するために北米に生産拠点を確保する動きとみられる。米ペンシルベニア州フィラデルフィアにある「フィリー造船所」の買収説も浮上した。
HD韓国造船海洋の子会社、HD現代重工業がアラムコなどサウジアラビアの国営企業と合弁で現地に建設した造船所IMIも今月から試験稼働に入った。大型ドック3個、巨大クレーン4基、岸壁7つなどを備え、年間40隻以上を建造可能だ。来年下半期に本格稼働に入り、造船所の株式20%を保有しているHD現代重工業は近隣に追加で船舶エンジン工場も建設している。
■韓国国内で人材難、納期遅延懸念で海外生産検討
韓国造船企業の海外生産拠点設置検討は人材難が最大の理由とみられている。国内造船所のドックが数年先まで埋まっている状況で、作業員が不足するなど好況と人手不足が重なり、納期遅延の危険性が高まったことから、再び海外進出を検討し始めた格好だ。韓国造船海洋プラント協会によると、受注増加に対応するため、2027年までに約4万3000人の増員が必要と試算されている。造船業界関係者は「韓国の造船所の最も優れた競争力は建造能力と納期順守だったが、慢性的な人材不足で中小造船会社だけでなく、大型造船会社もスケジュールに支障が出ている」と話した。
HD現代重工業はフィリピンのスービック造船所の設備を借用し、これまでにフィリピンに輸出した軍艦の修理を行う計画だ。メンテナンス事業への進出だが、今後の新造船事業拡大、さらにはスービック造船所の買収説まで取り沙汰されている。ただ、大宇造船海洋の中国・山東造船所、STX造船海洋の中国・大連造船所、韓進重工業のフィリピン・スービック造船所など数千億~数兆ウォン規模の海外投資失敗を繰り返すべきではないとの懸念もある。2000年代初めに好況を迎え、韓国造船各社は現地の安価な労働力で人件費を節減するため、海外造船所に大規模投資を行ったが、生産性は国内の造船所に比べ半分程度にとどまった。熟練工が極度に不足していた。
■ベトナムで合弁成功例…現地技術者の教育強化
中国・フィリピンでの失敗例とは異なり、HD現代重工業の系列企業である現代ベトナム造船は成功例として挙げられる。1996年、現代尾浦造船とベトナム国営の合弁会社として設立された現代ベトナム造船は修理・改造事業を行い、2000年代後半に新造船事業に転換した。他の海外造船所が生産性低下で廃業に向かう中、現代尾浦造船から派遣されたエンジニア60人余りが常駐し、生産工程全般に韓国国内と同じ品質管理体系を採用した。その結果、ベトナムは造船業界で世界5位の国に成長し、現代ベトナム造船がこのうちシェア約74%を握る。業績は好調で、昨年700トンの巨大クレーンを新設し、今年の売上目標は約5億4380万ドル(約800億円)だ。
フィリピンのスービック造船所で軍艦の保守・補修事業を検討しているHD現代重工業は、フィリピンの技術者60人余りを韓国・蔚山に招き、一緒に働くことで技術ノウハウを共有する。一部は既に投入されており、年末までに人員を増やす計画だ。同社関係者は「海外生産拠点が国内と同様の水準の技術力を維持することがカギだ」と話した。サウジ合弁造船所IMIにも今年末、エンジニア100人余りが派遣される予定だ。
李貞九(イ・ジョング)記者
消防によりますと、16日午前10時半ごろ、洲本市由良町にある造船所でクレーンが倒れ、 解体作業をしていた30代くらいの中国国籍とみられる男性2人が意識不明の重体だということです。
このうち1人は両足を切断しているということです。 警察と消防が事故の詳しい状況を調べています。
警察や消防によりますと、きょう午前10時半ごろ、兵庫県洲本市の造船所で30代くらいの男性2人が倒れているのが見つかりました。
2人とも病院に運ばれましたが意識不明の重体だということです。
2人のうち1人はクレーンを解体するため、高さ十数メートルの位置で作業していたところ、クレーンごと崩れて落下。地上にいたもう1人が巻き込まれたとみられます。
また、消防によりますと、午前10時半ごろに「左太ももが切断されている」と119番通報があったということで、消防が駆け付けて、がれきの下敷きになった男性2人を午前11時すぎまでに救出したということです。
警察は、事故が起きた原因を調べています。
海運業に従事する人で作る労働組合「全日本海員組合」の前の組合長が、関連団体の基金からおよそ3億円を私的に流用した疑いがあるとして、組合員らが業務上横領や脱税などの疑いで東京地検に告発状を提出しました。
告発状によりますと、森田保己 前組合長は、2015年から2020年にかけて、外国人船員の研修などに充てる基金からおよそ3億円を私的に流用し、高級腕時計などの購入に充てた、業務上横領の疑いや、流用した金について税務申告しなかった脱税の疑いがあるということです。
森田前組合長をめぐっては、基金の私的流用や、海外の業者からリベートを受け取って得た合わせておよそ6億円の所得を税務申告していなかったとして、東京国税局が申告漏れを指摘し、追徴課税していました。
会見した組合の元幹部や組合員によりますと、私的流用された基金のうち、前組合長から返還されたのは一部にとどまっているということです。
全日本海員組合の元組合長、井出本榮さんは、「組合長による横領を許しては、基金の信頼が失われかねない。組合が動かないため、私たちが動いた」と話していました。
「ポルトガル海軍『画期的な無人機空母』を発注」との記事だが、ポルトガル軍はあまり有名だと言うイメージはない。何でも無人にすれば良いというものではないと思う。無人機の開発だって高額になるだろうし、メンテナンスだって簡単ではないと思う。ウクライナとロシアの戦闘で安価な無人ドローンが思った以上に良い戦果を出したからと言って無人機が万能と言うわけではないと思う。
安価な無人機でなければ、回収できなかったり、行方不明になると結構な痛手だと思う。技術的なブレークスルーが必要なケースはあるが、発想の転換で既存の技術を融合させたり、既存の技術や新しい部品の使用による改良でコストパフォーマンスの良い結果を出せるケースはあると思う。まあ、成功しても失敗してもポルトガル軍の問題だからどうでも良い。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
日本は海洋国家なのに半導体と全く同じで政府の対応のまずさで?衰退産業に位置付けられています。優秀な学生が集まらない。東大はひどくて、保健学科と並び船舶海洋工学科には落ちこぼれ学生しか集まらない。昔ながらの職人造船では日本の造船は衰退の一途です。
中韓へ追い上げられた昭和の造船不況時に新造船を建造出来るドックを国の方針で絞り込んだ上に、平成になっても吸収合併を繰り返してますからね?
海運が持ち直して造船所が長いバックオーダーを抱えていればワンオフの洋上風力発電に関する作業船なんて…
無人機や医療コンテナを収容できる艦艇
オランダの造船会社であるダーメン・グループは2023年11月24日、ポルトガル海軍と革新的な、多目的艦を提供する契約を結んだと発表しました。
【色々と役立ちそう】多機能海軍プラットフォームと呼ばれる無人機空母の完成予想図です(写真)
ダーメンが建造するのは、全長107mで空母のような飛行甲板を持つ多目的艦とのことで、無人偵察機やヘリコプターを配備する計画となっています。
ほかにも、UUV(無人潜水艇)やUSV(無人水上艇)用の格納庫も備え、海軍での通常任務のほか、海洋調査、捜索救助、緊急救援なども担うことが計画されており、甲板上には、コンテナ型の病院施設や高気圧室を設置することも想定されています。ポルトガル海軍では同艦の分類を「多機能海軍プラットフォーム(PNM)」と呼称しています。
なお、このプロジェクトは、新型コロナウイルスによるパンデミックの影響を受けたEU加盟国を支援する経済復興パッケージ「NextGenerationEU(ネクストジェネレーションEU)」の一部である「復興・回復ファシリティ」と呼ばれる復興策から資金援助を受けています。
乗りものニュース編集部
松山市に本社を置く船舶管理会社は、先月、資金繰りが悪化したとして、東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請しました。
負債総額は80億円余りに上るということで県内では2010年以降で最大になるとみられます。
民事再生法の適用を申請したのは松山市に本社を置く船舶管理会社「オリエントライン」です。
この会社は、特別清算した海運会社の業務を引き継ぐために2016年に設立され、船舶の管理を行っていましたが赤字決算が続いていたということです。
しかし、業績が回復しないまま融資を受けていた金融機関への利払いなどの負担が続く中で資金繰りが悪化し、先月26日に民事再生法の適用を申請しました。
民間の信用調査会社「帝国データバンク」によりますと、負債総額はおよそ87億円にのぼり、県内では2010年以降で最大になるとみられます。
帝国データバンクによりますと、県内では、ことし1月からきょうまでの間に民事再生法の申請は33件、負債総額はあわせて110億円余りに上り、件数はすでに去年1年間の申請数と並んでいます。
帝国データバンクでは新型コロナ関連の支援策が終わったことやエネルギー価格の高騰などによって企業の資金繰りが厳しくなっているとしています。
株式会社オリエントライン
船舶管理
民事再生法の適用を申請
TDB企業コード:443017661
負債87億円
「愛媛」 (株)オリエントライン(資本金100万円、松山市三番町6-3-4、代表久金光氏)は、東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、9月26日に同地裁より監督命令を受けていたことが判明した。
申請代理人は、柴原多弁護士(東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、電話03-6250-6200)。監督委員には、三森仁弁護士(東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内マイプラザ、あさひ法律事務所、電話03-5219-0002)が選任されている。
当社は、2016年(平成28年)3月に設立された船舶管理業者。旧・(株)オリエントライン(TDB企業コード:740161622、現・日本船舶実業(株)、2017年10月特別清算開始)の再建過程の一環で、同社の事業を譲受する受け皿会社として設立された経緯を有し、パナマに所在する子会社が保有する船舶の船舶管理業務を手がけるとともに、子会社に対する貸付金(取引金融機関からの借入金)を実質的に譲受する形でスタートした。
しかし、金利負担を吸収できるだけの採算性を確保できず、毎期赤字決算を余儀なくされていた。そのため、取引金融機関と調整を行うなかで、出口戦略として今回の措置をとるに至った。
負債は約87億円。
ばら積み貨物輸送を中核とする海運会社のマレーシア・バルク・キャリアーズ(メイバルク)は5日、総合リース大手の東京センチュリーに、ばら積み貨物船「アラム・ケカル」を売却すると発表した。売却額は44億3,000万円。
メイバルクの間接子会社ケカル・シッピングが、東京センチュリーと合意覚書を締結した。11月15日までの取引完了を予定している。
メイバルクの2023年上半期(1~6月)の売上高は前年同期比13.5%減の6,805万リンギ(約21億5,000万円)、純利益は94.5%減の382万リンギだった。

Photo courtesy Netherlands Coastguard
愛媛労働局は15日、愛媛県今治市高部の造船業「三宅工業三宅大我」が新型コロナ対策の雇用調整助成金1170万円余りを不正受給していたと発表しました。
愛媛労働局によりますと「三宅工業三宅大我」は従業員に対し休業手当を全く支給していないにも関わらず、新型コロナの影響で従業員を休ませ、休業手当を支給したなどとする嘘の申請書類を作り、雇用調整助成金1170万円余りを受け取ったということです。愛媛労働局は7月12日付で支給の取り消しを行い、一部は返還されたということです。
愛媛労働局は「申請に誤りがある場合は速やかに申告を行い返還してほしい」と呼びかけています。
下記の記事を書いた記者はあまり造船の事をわかっていないと思う。中国で建造されているのは、中国の人件費が安かったり、儲けなしに近い価格で多くのヨーロッパスタイルの船をヨーロッパ船主のために建造したから経験や実績があるだけのこと。技術の問題ではない。
韓国でも韓国が得意としている船のタイプやサイズ以外では、設計が出来ないから受注したいけど受注できない話を聞く。
日本は人件費が高く、効率を重視するから変わった船は建造しない、建造隻数が少ないと建造しない方針であった事に加えて、人材不足と人材の高齢化が状況を更に悪化させたと思う。
日本の造船所の設計は、変わった船を設計して建造する人材がほとんどいないし、特殊な船、又は、変わった船を建造しても赤字になる可能性が高いので手を出さないと思う。船がどのように使われるかを理解して、新しい規則や規則改正を満足する船を設計し、建造するのは効率重視で同型船や過去に建造した船だけしか建造しない造船所には難しいと思う。ヨーロッパスタイルの船やヨーロッパスタイルの中国建造の船を真似て建造しようと思っても、日本スタイルの船と違うからかなり設計変更をしなければならない。設計変更すると新しい規則や規則改正を満足しているかチェックしなければならない。同型船を建造する場合、設計のチェックは必要ないし、設計の部分は必要ない。現場も前回と同じように建造するだけなので楽に感じるはずである。
造船所があまり建造経験のない船を建造した場合、行き当たりばったりの船を建造したと思われる印象を受ける。検査に通るだけでいっぱいいっぱいだと思う。下記のコメントで東大の学生の事を書いているが、社員の高学歴は良い事だが、高学歴だけでは船は建造できない。経験が必要になる。また、インターネットにも、本にも特殊な船の情報を見つける事は出来ない。優秀な東大の学生であっても経験や特殊な知識なしには、特殊な船の設計と建造は無理だと思う。頭が良ければ問題ない世界ではない。学歴がある基準以上で経験があれば、そちらの方が良いと思う。造船は、構造、機関、電気、そして艤装などの分野があり全てを深いレベルまで理解するのは無理だと思う。例え、スーパーマンのような人材がいても、同型船を建造するのなら必要ない。会社によっては何でも出来る社員が必要な会社と特定の事が出来る社員が必要な会社があるように、いろいろなパターンがある。分散タイプの会社経営や特定の分野に特化する会社経営があるが、ケースバイケースでどちらが良いかはわからないと思う。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
日本は海洋国家なのに半導体と全く同じで政府の対応のまずさで?衰退産業に位置付けられています。優秀な学生が集まらない。東大はひどくて、保健学科と並び船舶海洋工学科には落ちこぼれ学生しか集まらない。昔ながらの職人造船では日本の造船は衰退の一途です。
中韓へ追い上げられた昭和の造船不況時に新造船を建造出来るドックを国の方針で絞り込んだ上に、平成になっても吸収合併を繰り返してますからね?
海運が持ち直して造船所が長いバックオーダーを抱えていればワンオフの洋上風力発電に関する作業船なんて…
あんな船もこんな船も必要な「洋上風力発電」
アフターコロナの経済活動再開にともなう世界的な外航海運市況の好調を受けて、停滞していた国内の造船業にも追い風が吹いています。外航だけでなく、国内で運航される内航の分野で、造船の新たなマーケットとして注目されているもの――そのひとつが「洋上風力発電」です。発電所の建設や維持管理に、多種多様な船が必要と見込まれています。
【バケモンか!?】これが世界最大級の「クレーン船」です…何のため?(写真)
洋上風力発電は2050年カーボンニュートラル実現に向け、「今後、拡大が期待されているエネルギー源」(資源エネルギー庁)とされています。国のグリーン成長戦略では2040年までに洋上風発の発電量を30~45GWまで拡大する目標も掲げています。一方で、その建設や維持管理に使われる特殊な船舶の設計・建造で、日本は欧州勢に後れを取っており、国内で新造や修繕を行える体制の確立が急務となっています。
必要になる船の種類は実に様々です。海底地盤調査に使用するCPT調査船をはじめ、洋上風車のナセルや基礎部、ブレードなどを運ぶ重量物船、発電設備の建設を行うSEP船(自己昇降式作業台船)、電力ケーブルや情報通信ケーブルを敷設するCLV(ケーブル敷設船)、建設後の保守作業を支援するSOV(洋上風発作業母船)、そして建設や保守作業に従事する人員や物資を運ぶCTV(作業員輸送船)などがあります。
日本では洋上風発の建設需要の高まりを受けて、清水建設が最大揚重能力(吊り上げ能力)で2500トンを誇る世界最大級の自航式SEP船「BLUE WIND」(2万8000総トン)をジャパンマリンユナイテッド(JMU)で建造し、2023年から稼働を開始しました。
川崎汽船グループのケイライン・ウインド・サービス(KWS)も、2016年にJMUで竣工したアンカーハンドリング・タグ・サプライ船(AHTS)「あかつき」と、2021年にアイ・エス・ビーで竣工したオフショア支援船「かいゆう」を中心に洋上風発関連の支援船事業を行っています。CTVの分野では、いち早く洋上風発に目を付けていた東京汽船が2015年に国産初のCTV「PORTCAT ONE」(19総トン)をツネイシクラフト&ファシリティーズで建造しました。
ただ、いずれの船種も国内造船所での建造実績は少なく、中小造船所での建造に最適な中型サイズのSOV(長さ84m程度)やCLV、大型CTV(長さ35m程度)は国産化が進んでいません。重量物船は日本で建造できるものの、例えばNYKバルク・プロジェクトの新型重量物船「KATORI」「KIFUNE」(1万2470重量トン)は中国の招商局南京金陵船舶で建造されています。
国産船だけで洋上風力発電をつくるには?
日本中小型造船工業会の会長を務める旭洋造船(山口県下関市)の越智勝彦社長は、「対中国、韓国を念頭に置いて新たな分野に挑戦し市場を拡大していくことが必要だ。洋上風力分野などの新たな市場に参入する準備をしていきたい」と意気込みます。
同工業会は、これまで各社が建造経験のないSOVや大型CTVの国内建造・修繕の実現を目指しています。日本財団の助成を受け、欧州設計会社から設計に関する情報を入手するとともに、洋上風発の開発会社や船社などの協力も得ながら課題解決に向けたとりまとめを行い、コンセプト設計を作成する予定です。
特に陸上と洋上風発サイトの間で技術者を運ぶCTVは、建設の始まりから保守維持、解体まで多くの段階で活用できる上、比較的小型の船舶であるため中小規模の造船所でも建造が可能です。現在(2023年3月末時点)、国内では9隻が稼働中ですが、国土交通省海事局は2030年には約50隻、2040年には約200隻が必要になると想定しており、こうした点からも造船・舶用各社はCTVへの期待を寄せています。
一方で洋上風発は欧州で先行して導入が拡大した経緯から、従来のCTVは欧州の海域に合わせた設計で建造されており、うねりの影響が大きい日本周辺海域では、欧州に比べて出航できない日が多くなる可能性あると指摘されています。そのため日本で洋上風発の建設と効率的に進め、維持していくには、日本の海域に合わせたCTVを建造することが必要です。
こうした背景から国土交通省は2023年3月、CTVの国内建造を促進するため安全設計ガイドラインを策定。安全性を担保しつつ、風車メーカーのニーズを取り入れるなど国内造船所がCTVを建造するにあたって留意する事項をまとめました。
国産SOVに関してはKWSがアイ・エス・ビーやヤンマー、川崎重工業と共同で水素燃料などに対応した船型の研究を進めているほか、東京汽船とイーストブリッジリニューアブルの開発したSOVとCLVが日本海事協会から基本設計承認(AiP)を取得しています。
洋上風発の建設と維持には、おのずと船が関わることになります。カーボンニュートラル実現に向けた再生可能エネルギーの一つとして注目されている洋上風発。それを取り巻く船舶の課題と将来の可能性についてもぜひ注目してみてください。
深水千翔(海事ライター)
造船所も昔に比べれば減ったし、昔は優秀な人が造船所に入社していたが、現在は優秀な人は船が好きでなければ造船所では働かない。
造船は徐々に衰退していくだろうと思う。外航海運は造船で働いているほど人は必要としないし、物流と関係が深いので海運は残っていくだろうと思う。
造船は古い産業なので考え方は古い。変なところで妥協せずに昔のスタイルと下請けに強要する。変えてはいけない部分はあると思うので、理由があればこだわるべきだと思うが、惰力的な感じで続けるのは間違っていると思う。まあ、それが気付かない人達は我慢したり、他の人達を泣かせたりして行きつくところに行くまで続けるのだろう。
変化すれば生き残れる場合と努力しても簡単には生き残れない場合がある。良く知らない人は判断できないケースはあるし、全体的に状況を捉えないと解決策が見えない事はある。そして理論や理想とは別に現状の状況や環境を理解した上で解決策を考えられないと良い結果を出せるとは限らないと思う。また、失ってから、又は、後悔する状況にならないと問題を理解できない事はある。
好調の造船 2つの追い風
新型コロナウイルス感染症の影響で停滞していた経済活動が再開し、海運市況が上昇。これに伴って新造船価も上がり、新造船マーケットは2021年3月を底として徐々に回復傾向に向かっています。年間海上荷動量は、2000年段階で約64億トンだったのに対し、2022年は119億トンまで成長しており、今後も船舶の需要が増えると予想されています。そのためか、2023年6月に相次いで開催された造船・舶用事業者の団体による総会と懇親会では明るい声も聞かれました。
【何このデカさ!!??】6月竣工 もう日本に戻って来れない「世界最大級のコンテナ船」(写真)
日本船舶輸出組合によると、2022年度の輸出船契約実績は280隻約1174万総トンと、2021年度の313隻約1430万総トンよりは減ったものの、2015年度に389隻約2018万総トンを記録して以降では2番目の水準となっています。一時期は危険水域に突入していた手持ち工事量も回復し、2.7年分まで確保できています。
日本中小型造船工業会の会長を務める旭洋造船(山口県下関市)の越智勝彦社長は、「外航海運市況の好転や円安の恩恵で受注の回復が顕著だ。特にバルクキャリアー(ばら積み貨物船)では2年から3年先までの受注をしている造船所も多々ある」と話します。実際、バルクキャリアーで最小船型となるハンディサイズの発注が進んでおり、鋼材価格の上昇に苦しむ日本の造船所も同船型を軸に受注活動を行っているようです。
これに加えて世界的な環境規制の影響もチャンスとなりそうです。
IMO(国際海事機関)は2018年にGHG(温室効果ガス)削減戦略を採択。2050年までにGHG排出量を2008年比で50%以上削減し、今世紀中のなるべく早い時期にゼロエミッションを達成するとした目標を掲げましたが、日本郵船や商船三井、川崎汽船といった大手船社が揃って2050年までのネットゼロ・エミッション化を目標として打ち出し、新燃料船の開発を積極的に行っています。
鉄鋼大手の日本製鉄や石油大手の出光興産も2050年カーボンニュートラルを掲げ、サプライチェーン全体のGHG排出量を大幅に削減する方向に舵を切りました。日本は2050年までに国際海運からの温室効果ガス(GHG)の排出を全体としてゼロにすることを目指しており、IMO(国際海事機関)にも、これを世界共通の目標として掲げることをアメリカやイギリスなどとともに提案しています。
見えている「建造量年1億総トン」の世界
日本造船工業会によると、全世界の新造船建造量は年間約5500万総トン(2022年)。既存のディーゼル船を置き換え、GHGの排出量を抑えられるLNG(液化天然ガス)やLPG(液化石油ガス)、水素、アンモニア、メタノールなどを使用する新燃料船へ切り替えるには、2030年以降で年間1億総トンレベルの建造が必要とされています。
同会の金花芳則会長(川崎重工業会長)は「環境規制により各船社は2050年までに現存船を総取り換えする方向に動いており、新造船の建造量は大幅に増加するものと見ている」と話していました。
「この需要拡大をうまく捉えることにより、造船・舶用工業ともに安定した経営が可能になる。船舶のゼロエミッション化というゲームチェンジに応えていくために、舶用工業とはエンジンの開発や新燃料に関する規格化、サプライチェーンの準備などの連携強化が必要になってくる」(金花会長)
ただ、それでも日本造船が厳しい状況を脱したとは言い切れません。2022年の竣工量は世界3位となる950万総トンですが、2位の韓国は1630万総トン、1位の中国は2570万総トンと水をあけられています。新造船のシェア率は中国が47%、韓国が30%、そして日本が17%と上位3か国で9割以上を占めており、今後も造船大国の地位を守っていくためには、造船所の安定的な操業を確保しつつ、他国に負けない性能とコスト競争力を持つ船を開発していく必要があります。
とはいえ世界的に需要が高まっているLNG船の建造や貨物船とは違う能力が要求される大型客船の建造から日本は事実上撤退しており、それ以外の船種で戦うしかないのが現状です。
このままでは指をくわえて見てるだけ?
さらに、活況を呈する外航船とは裏腹に、国内の海上物流を支える内航船の受注もまだまだ厳しい状況です。背景には用船料が鋼材価格や資機材価格などの高騰を反映したコストと船価に対応できるレベルに上がらず、船主などが発注に踏み切れないという事情があります。
また、造船業界では現場と設計の双方で高齢化が進んでいるだけでなく、若手の採用が難しくなっており、人材確保が最重要課題として掲げられています。当然、船舶の航行を支えるエンジンや配電盤、計器などを製造する舶用企業にとっては、日本の造船所が安定的に受注していくことが非常に重要です。
日本舶用工業会の木下茂樹会長(ダイハツディーゼル会長)は「2030年以降、年間1億総トンレベルの建造になった場合、人材の確保、新燃料技術の対応、そして我々が製造する機器の供給の確保など、たくさんの課題が出てくる」と述べた上で、目指すべき船舶産業の姿を明確化するため国土交通省が設置した「船舶産業の変革実現のための検討会」に期待感を込めました。
2023年6月にはジャパンマリンユナイテッド(JMU)呉事業所で世界最大級となる2万4000TEU型コンテナ船「ONE INNOVATION」が引き渡されました。同船は政府系海外向けインフラファンド、海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)が建造費用の一部を出資しており、国をあげて日本の海事産業を強化しようという動きの一環です。今後、日本の造船業が復活していくのか、2023年は大きく動き始めた年となったのかもしれません。
深水千翔(海事ライター)
たぶん、問題なく検査に合格は出来るだろう。問題は、ヨーロッパで建造された船のような快適性が提供できるか、大きな故障なく運航できるのか、耐久性の問題だと思う。
後は、海が荒れた時、火災が発生した時など、通常の状態でない事が起きた時に、問題なくいろいろな設備が稼働するかだと思う。検査は検査を通そうとする前提の場合、検査の本来の意味はなさないと思う。
【動画】嵐で破壊されたクルーズ船内が浸水する様子と、船の周辺で荒れ狂う高波...乗客が撮影 06/04/23(Newsweek)

【6月4日 CGTN Japanese】中国初の国産大型クルーズ船「愛達・魔都(Adora Magic City、アドラ・マジックシティー)」が運用側への引き渡しの段階に入りました。数日後には、ドックから出されることになります。
出渠の準備期間は6日間です。ドックでは6月1日未明に注水作業が始まりました。今後はドック内での浮上、施設内での移動、施設外への移動が行われます。この間、クルーズ船の移動と共に傾斜試験、舷門放水試験、救命ボートの海面投下、巡航試験など、船全体の重量や救命ボート、舷門の機能について次の段階の検証が進められます。船は6月6日には、正式にドックから出る予定です。
船名に「魔都」の語が使われたのは、上海が「魔都」と呼ばれていることから、「上海で設計」と「上海で建造」の2点を際立たせる狙いがあります。船長は323.6メートル、総トン数は13.55万トン、高さは24階建てのビルに相当する70メートルです。定員数は6500人余りで、年末に引き渡される予定です。なお、中国国産の2隻目の大型クルーズ船の建造が去年8月8日にはじまっています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News
CGTN Japanese
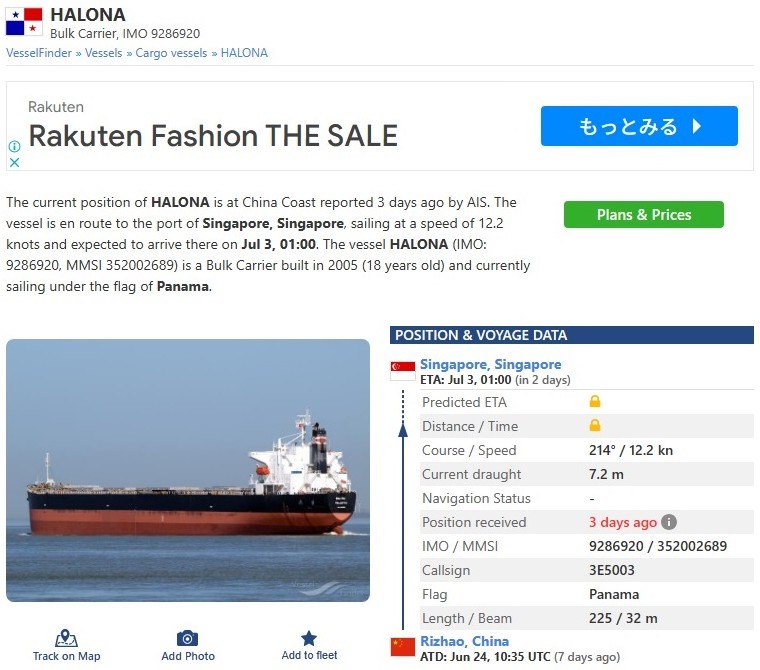
By Gary Dixon
France has banned a Chinese bulk carrier that failed to get a number of deficiencies fixed in its home country.
The 76,000-dwt panamax Xin Feng (built 2005) has been refused access to the Paris Memorandum of Understanding on Port State Control region.
The Paris MOU said the ship was detained in Nantes on 6 January after safety inspectors found seven deficiencies.
All were grounds for detention and included invalid certificates for construction safety, load lines and safety equipment.
Life-saving equipment was not properly maintained and two unspecified faults were identified with structural condition.
This was its first ever detention. The vessel was released but failed to call at the repair yard in China as agreed.
AIS data shows the bulker left Vlissingen in the Netherlands on 23 January bound for Zhoushan in China, with an arrival date of 20 March.
But the last update was from 13 February with the vessel in the Bay of Biscay.
The Liberia-flagged ship is classed by Nippon Kaiji Kyokai in Japan.
The operator is listed as South Ocean Marine Group of Fujian. The company could not be contacted for comment.
Cargo ship banned after three strikes
The Paris MOU also said the 3,000-dwt general cargo ship NS Sprinter (built 1992) has been banned for three months after failing three checks in two years.
The Belize-flagged vessel was held in Licata, Italy, for five days in February with 13 deficiencies.
Inspectors found expired life boats in a broken container, problems with fire-fighting equipment, improperly maintained sanitary facilities and damaged catwalk railings.
The NS Sprinter was also detained in Italy and Spain last year.
Oslo Shipholding of Tirana, Albania, is listed as the operator.
個人的な経験から言っても、同じ事を繰り返す、同じ環境で同じ事を繰り返す方が楽だし、効率的だと思う。しかし、それが出来ないのなら意識して多少の変化には対応できるように慣れるしかない。対応できるようになれば、順応能力が身についたと言う事だから、住む場所にこだわりがなければ、別の会社で評価してくれる会社を探した方が良いと思う。変わらない、又は、変われない会社にいても、意味がない。
造船所と言っても、ピンキリだと思う。ひどい造船所に言ったら、良い造船所の非常識が常識。つまり事故がいつ起きても不思議ではないと思う。
塗装をしていたのなら換気するぐらいは常識なので、原因があると思うが、次ニュースを待つしかない。
ヤフーコメントに下記のようなコメントがあった。
派遣法による派遣社員がどこの企業も多くなり、職人さんと同じように何年もかけて育てる技能者や技術者がいなくなった結果、不注意な倒壊、爆発などの無責任な事故が多発している。
早く、日本人の気風にあった雇用制度に変更して下さい。
それと周囲の人たちが判るほど怠惰な公務員や正規社員を解雇できる仕組みを創る事が先で、彼らの仕事を補うためにパートや派遣を募集するなんて・・本末転倒もいいとこ・・!!!!
安全管理とか雇用云々と、正規か非正規は、安全衛生とは直接は関係無いかと。。
正規か非正規かに関わらず、安全衛生を守るのは事業者の義務であり責任です。
働かない公務員や従業員をクビに出来ないとか、非正規がその犠牲になってるとかは、
別な問題、雇用制度の問題、派遣法、企業側の雇用モラル(人件費を経費にしたいとか)、企業と下請との問題では無いですか?
かつて客船アイーダや古くはダイヤモンドプリンセス他、長崎造船所では毎年のように災害が発生してますね。
水の浦門の出口ではバイク通勤者の傍若無人の振る舞いにより近隣からの苦情が絶えず、挙句に歩車分離式の信号に変えられたりと、そもそもが各作業員の「安全」に対する意識が低いのが根底にあるからだと思われます。
逆に、某工場では無災害記録を優先するあまり労災隠しもあったりと、内部事情を知る人間からしたら、体質的に問題だらけの企業のように感じます。
三菱というグループが全てにおいて時代遅れなんだと思います。
グループ全て何て書くと色々と批判があるのでしょうが。
顧客に対し人命を無視したデータ改ざんしたり、
社員は自殺に追い込まれ、事故により作業員が死亡。
飛行機作れば途中で頓挫、客船作れば火事、自動車作ればタイヤが外れる。
仕事で三菱グループの何社かと絡みがありますが、総じて風通しが悪い組織で、決定が極めて遅く、責任は取らない組織。
時間の概念が基本的に希薄。
下請けや業者は中途半端な話で先に進めれば途中で梯子を外し、PJに関わる社員達は梯子を外した意識も無いから当然謝罪も無い。
親方日の丸で潰れないと言う意識、三菱という特権意識でプライドだけは宇宙まで高い。
トヨタのように自身の身を削りと言う意識もない。
スペースジェットやロケットで悪いニュースか特に最近目立つが、そもそも時代遅れのメーカーの集まりグループなんだと思う。
親戚が長崎の三菱重工に勤めていたが会社の不満や愚痴が多かった
とにかく風通しの悪い組織風土で上にモノを言えないので日々黙って仕事をこなすしかなかったそうだ
名門の大企業というブランドが悪い方向にしか向かってなく現場と経営陣との意思疎通が疎か
経営陣が現場ファーストにならないと今後事故や不正が出てくると言っていたことをこの事故のニュースを見て思い出しました
今日午前11時過ぎ、長崎県長崎市の三菱重工業長崎造船所の敷地内の工場で、爆発音がしました。
【写真を見る】三菱長崎造船所で爆発 50代男性が死亡 護衛艦を建造中の現場か【長崎】
警察と消防によりますと、午前11時24分に、三菱重工業 長崎造船所 立神工場から「工場内で爆発があり、一人ケガをしている」と通報があったということです。
消防が救助活動を行い、従業員とみられる50代の男性を救助しましたが、意識不明の重体で、長崎市内の病院に搬送されましたが、午後1時前に死亡が確認されたということです。
近隣の住民は「何か大砲がドーンってするようなすごい音だった。滅多に聞かないから、そんな音は。
だからおかしいね、何の音だったんだろうと思って覗いたけど、煙も何も出てないし。1回で終わった」と話しています。
三菱重工業の広報は「爆発があったのは午前11時10分頃で、“艦艇エリア”のガス設備が、何らかの原因で爆発したとみられる」と話しています。
また、爆発原因について造船所の元幹部は「驚いている。場所的に自衛隊の護衛艦の新造ブロック。塗料のなどが周りの溶接の火などに引火して爆発したのではないか?
爆発するのは、塗料として使うシンナーと溶接用のガスボンベしかない。
通常はそうならないように換気をしている」と話しています。
関係者によりますと、このエリアで建造していたのは、『もがみ型護衛艦』と見られています。
■造船所「男性従業員が倒れている」連絡で救助要請した
きょう午後1時過ぎ、長崎造船所の玄関前で、西本 憲司 総務部 総務第六第グループ長が事故について説明しました。
長崎造船所の説明によりますと、「午前11時10分頃、建造中の船の一部である“ブロック”の総合組み立て場で『男性1人が倒れている』との連絡があり、消防に救急要請をした。
倒れていたのはパートナー会社の男性従業員で、近くにいる作業員がAEDを使って対応をした。
男性従業員がどのような作業をしていたのかなどは、現在 確認中。
どんな船を作っていたのかは、お客様のこともあり言えない」としています。
また、西本憲司 総務 第六グループ長は「被害に遭われた方の早い回復を祈っている。周辺地域にも迷惑をかけ申し訳ない」と話しています。
長崎放送
22日午前11時25分ごろ、長崎市東立神町の三菱重工長崎造船所立神工場の従業員から消防に「シンナーのガスが爆発した。同僚の意識と呼吸がない」と119番があった。長崎市消防局によると、男性作業員1人が意識不明で救急搬送された。心肺停止状態という。
【爆発の通報があった三菱重工長崎造船所】
長崎県警長崎署には同11時半ごろ、消防から「立神工場で気化した塗料に引火して爆発した」と連絡があった。同署によると、現場は工場の第1ドック。負傷したのは50代の男性で、船の組み立て現場で作業していたという。
三菱重工広報部は取材に、負傷者は協力会社の社員と説明。担当者は「爆発があったことは確認した。正確な情報収集に努めている」と話した。【松本美緒、長岡健太郎】
日韓ビジネスコンサルタント
劉 明鎬 氏
韓国造船業が抱えている懸念材料は
受注が増加することは嬉しいニュースだが、中国の追い上げだけでなく、水面下で韓国の造船業が抱えているいくつかの課題もある。まず、韓国造船3社が競合しており、とくに中国企業の低価格攻勢をかわすため、韓国企業も受注価格を下げざるを得ないという現状がある。黒字を計上しているのは3社のうち韓国造船海洋(現代重工業グループ)だけで、大宇造船海洋やサムスン重工業は赤字状態である。長期不況による低価受注がまだ尾を引いている。
2つ目は中国の追い上げが尋常ではない点である。昨年韓国は世界のLNGタンカー発注170隻のうち、69%に当たる118隻を受注した。問題は数年前まで一桁であった中国の市場占有率が30%近くなったことだ。2021年には7.8%に過ぎなかった市場占有率は1年で4倍近く跳ね上がった。その反面韓国のシェアは92.2%から67.9%に落としている。
LNGタンカーは受注から引き渡しまでだいたい3年程度かかるが、韓国のドックは26年の建造分まで予約が入っていて、納期を優先するバイヤーは、中国の造船会社に発注し、このような現象が起きていると分析する専門家もいる。しかし、中国造船業は中国政府の主導でLNGタンカーの研究開発に力を入れており、建造経験をベースに中国も技術を蓄積していく可能性がある。中国企業は中国政府の金融支援をバックに低価格攻勢にも積極的である。
最後に韓国造船業界が抱えている構造的な問題である。造船産業は元受け(大手造船会社)、下請会社、孫請け会社などのように垂直構造をしている。契約、設計、監督などの仕事は、大手造船会社でやるが、その他の仕事はほとんど低賃金で雇われている下請会社が請け負うことになる。
船舶の寿命は10年くらいで、造船産業には、どうしても好況と不況のサイクルがある。不況が訪れると、不況を乗り越えるため、大手造船会社は固定費を削減するため、自分で抱えている人員は減らし、下請会社などを活用する。それで現在のような垂直構造が出来上がった。ところが、造船不況が長期化したため、下請会社も耐え切れず、倒産したり、人員を減らしていて、その結果、現在は仕事があっても労働者を確保するのも難しくなっている。
一方ではサプライチェーンの崩壊で原材料価格が高騰し、造船会社の利益を圧迫している。大宇造船海洋の場合、21年に売上高は4兆4,866億ウォンであったが、当期赤字額は1兆7,000億ウォンであった。累積赤字は7兆7,000億ウォンに上り、収益構造が脆弱である。
今後造船産業が目指すべき方法は
国際海事機関(IMO)は対08年比で、30年までに平均燃費を40%低減し、温室ガスの総排出量は50年までに50%削減するという目標を掲げている。このような流れを受けて、韓国の造船会社も今後は、環境に優しいスマート船舶の技術開発に積極的に投資し、LNGタンカーの次の船舶といわれている水素燃料や電気で航行する船舶を開発する必要があるだろう。韓国政府も30年までに炭素排出ゼロの船舶を商用化しようとしている。これに先立ち26年までに、乗組員なしで遠隔制御で航行が可能な自律航行船舶の商用化を急いでいる。
韓国の造船産業は中国にこのまま市場を奪われていくのか、それとも技術格差を広げてシェアを維持していくのか、激しい攻防戦が繰り広げられることが予想される。
(了)
日韓ビジネスコンサルタント
劉 明鎬 氏
一時は韓国輸出産業の稼ぎ頭であった造船業
近代の造船業はイギリスでスタートし、1970年代には日本で花を咲かせ、当時日本は造船業で世界をリードしていた。その後日本から造船技術を教えてもらった韓国造船業界は、日本の造船会社が不況で設計人材をリストラしていた間に、新しい工法の開発などに注力し、2003年以降、新規受注量、建造量、受注残量の3指標において、世界シェア1位を占めるようになった。07年5月を基準にすると、当時韓国の自動車輸出額は33億ドル、半導体の輸出額は30億ドルであったのに対して、造船業の輸出額は何と49億ドルを記録していた。世界で建造されている10隻のうち、4隻は韓国で建造された船舶であった。
しかし、世界金融危機(07~10年)が発生することによって、造船業は深刻な不況に見舞われることになる。この不況を乗り越えるため、韓国の造船会社が選んだ道は、海洋プラント事業であった。ところが、経験不足、低価受注、納期遅延などが原因で、この決定は韓国の造船業にとっては最悪の選択となり、造船会社は奈落の底に落ちることとなった。韓国の造船業は暗いトンネルからなかなか抜け出ることができず、四苦八苦していた。政府の支援やリストラなどで何とか踏ん張っていたが、20年下半期からようやく新規受注増加という光が造船業に差し始めた。
だが、韓国の造船業は近年、急激に台頭してきた中国勢に価格面で太刀打ちできなくなりつつある。そこで韓国はコンテナ船やバルク船よりも、LNGタンカーなどに力を入れた。韓国はLNGタンカー以外にも超大型コンテナ船や超大型原油タンカーの建造ではまだしばらくは中国や日本をリードしていた。なかでもLNGタンカーは付加価値の高い船舶で、氷点下163度で液化した天然ガス(LNG)を運搬するので、運搬の途中で液化ガスが気化して消失することを最小化する高い技術力が求められ、今までは韓国企業の独壇場であった。韓国企業が市場全体の9割以上を受注していたのである。そのような状況下、エネルギー価格の高騰とウクライナ戦争の影響などにより、LNGタンカーの需要は増加し、韓国企業は26年の年末まで受注予約が入っている。
韓国でしか建造できないと信じていたLNGタンカー市場にも異変が起きている。2年連続世界1位の座を中国に明け渡した韓国造船業界は、今まで韓国企業の独壇場であったLNGタンカーの分野でも中国に急浮上を許していて、韓国造船業の地位は揺らいでいる。
世界の環境規制の強化、ウクライナ戦争の長期化などによるヨーロッパでのLNG需要の増加などにより、LNGタンカーの需要は当面の間堅調が予想される。水素燃料や蓄電池を活用した大型船舶などの選択肢もあるが、まだ価格が高く、LNG時代がしばらく続くことが予見される。
(つづく)
【1月21日 CGTN Japanese】昨年、中国の造船業の国際市場におけるシェアは引き続き1位を維持しました。載貨重量トン数で見た世界シェアは、竣工量では47.3%、新規受注量では55.2%、受注残(手持ち工事量)では49.8%を占めています。
世界中で新規に発注された船舶の内で、環境にやさしいデュアルフューエルエンジン船舶が占める割合は前年より24ポイント上昇して49%を超えており、いずれも中国が建造を請け負っているものです。クリーンで低炭素への転換は中国の造船業が力を入れている点の一つでもあります。
中国南部の広州市のある造船所では、昨年、メタノールも燃料とするデュアルフューエルエンジンの船を4隻引き渡しており、現在も新たに2隻を建造中です。この造船所が以前に開発したデュアルフューエルエンジン船で使用される液化天然ガスに比べ、メタノールは入手しやすく、製造プロセスもよりクリーンだということです。
中国船舶工業協会の統計によれば、昨年は船舶用代替燃料として石油の代わりにメタノールを使う傾向が顕著で、新規に建造されたメタノール燃料船は通年で43隻に上りました。クリーンエネルギー燃料船の市場シェアだけを見ても、世界中で新規に発注されたクリーンエネルギー船は2021年の30%から昨年12月時点では51%に上昇しているということです。
P ManojETInfra
MUMBAI: The government is set to ban 25-year-old oil tankers, bulk carriers, and general cargo vessels, both Indian registered and foreign flagged, from calling Indian ports to load and unload cargo as it looks to encourage a younger fleet to improve safety, meet global rules on ship emissions and protect the marine environment from pollution during mishaps.
In the case of gas carriers, fully cellular container vessels, harbour tugs (those operating within ports), specialised vessels such as diving support, geo-technical, pipe laying, seismic survey, well simulation etc, dredgers and offshore fleet, the age limit for operating into and within India will be set at 30 years.
For anchor handling tugs and tugs involved in long tow, non-self-propelled ocean-going cargo carrying barges and any other vessels, the age cap will be 25 years, according to a draft order written by the Directorate General of Shipping (D G Shipping) seen by ET Infra.
The ‘Age Norms and other Qualitative Parameters for Registration/operation of Vessels under Indian Flag and requirement for foreign flag vessels calling at Indian ports for carrying Indian cargo or providing services in Indian Exclusive Economic Zones/offshore area’ is expected to be announced in the next few days.
Second hand ships, across categories, of 20 years and above cannot be acquired by Indian entities and registered under the Indian flag. The age limit for acquiring and registering second hand dredgers will be 15 years.
Ships will be automatically deregistered/deleted from the Indian registry on reaching the stipulated age limit for operations for the respective segments.
The D G Shipping will also prescribe various compliance checks on quality and safety of new ships, second hand purchases and existing vessels based on age slabs.
The age and other qualitative parameters will apply to foreign flag vessels calling Indian ports for carrying Indian export-import (EXIM) and coastal cargo whether on free-on-board (FOB) or cost-insurance and freight (CIF) or delivered basis or providing services within the Exclusive Economic Zones of India/offshore area, whether chartered by an Indian entity or otherwise. In such cases, the maximum age of the vessel will be calculated on the date of commencement of service or carriage of cargo.
Further, if a foreign entity is competing for an Indian cargo (on FOB or CIF or delivered basis), a ship owned by that entity must not be older than 20 years.
The age and other qualitative parameters will also be applicable to vessels acquired under the ‘Indian controlled tonnage’ regime carrying Indian EXIM/coastal cargo whether on FOB or CIF or delivered basis or providing services within the Exclusive Economic Zones of India/offshore area.
The age of the vessel will be computed from the ‘Date of Build’ as mentioned in the Certificate of Registry.
Passenger vessels will be excluded from the age norms.
“Quality tonnage is paramount for safe and secure expansion of the maritime sector and to achieve sustainability in ocean governance. The safety of life at sea and ships depends on the quality of tonnage registered under the flag of a country,” according to D G Shipping, India’s maritime regulator.
The International Maritime Organisation or IMO, the U N body that regulates global shipping, has adopted an initial strategy for reduction of GreenHouse Gas emissions. To achieve the targets defined by the IMO, vessels need to be transformed to run on alternate fuels and age norms will assist in ensuring gradual phasing out of fossil fuel ships and entry of alternate/low carbon energy efficient ships, it said.
Prior technical clearance is not required for acquisition of vessels below 25 years of age, according to the existing guidelines on registering ships under the Indian flag. Such clearances, though, are mandated for vessels of 25 years and above.
The age norms are being introduced to improve the quality of Indian tonnage and supplements a government plan to promote flagging of ships in India.
In 2021, the government unveiled a subsidy scheme for Indian flag ships for moving state-owned cargo.
Under the subsidy scheme, Indian fleet owners get a 5-15 percent extra on charter rates, depending on age slabs, on ships registered in India after February 1, 2021.
The government has budgeted a corpus of Rs1,624 crore to be disbursed as subsidy for moving crude oil, LPG, coal, and fertiliser cargo for state-run firms, over five years, to boost Indian tonnage.
The absence of age norms has allowed Indian charterers (those hiring ships) to go for older ships and benefit from “better rates” as older tonnage is available at “lower freight rates” as compared to younger vessels, resulting in lower transportation costs.
Charterers have also stayed clear of putting age norms in tenders in the absence of stipulation by the maritime regulator.
“There is a need for review and to specify certain requirements to enable registration/operation of quality tonnage under the Indian flag. There is also a need to create a level playing field for Indian ships by applying the requirements for quality tonnage to foreign flagged vessels calling Indian ports or Indian offshore facilities, for carrying Indian cargo or for providing services in Indian EEZ/Offshore area,” the D G Shipping added.
韓国は溶接工、人材不足と材料の高騰で苦しいらしいから、中国に発注と言うことになるのだろう。しかし品質は大丈夫なのだろうか?設計は韓国のようにヨーロッパから買うのだろうか?韓国は設計のライセンスコストで苦しいので、自国で設計した船を建造したが未だにまともに運航できていないそうだ。
【1月18日 CGTN Japanese】今年に入って、中国製の液化天然ガス(LNG)を輸送する船の新規受注は前年比約4倍増となり、世界シェアの3分の1を占めていることがわかりました。
欧州のエネルギー危機を背景に、2022年からLNG船への需要が急増し、世界的に不足している状態が続いています。そんな中、中国はLNG船の生産能力を強化するため、いくつかの造船所は増資に踏み切りました。現時点で、外国からの予約注文が2028年まで入っている造船所もあるということです。
中国船舶工業業界協会によると、2022年の中国製LNG船の新規受注は、前年比3.8倍増の481万トンで、過去最高を記録しました。また、世界市場における中国のシェアは2021年の12%から2022年には30%以上に拡大しており、なかでも容量17万4000立方メートルの大型船は55隻を受注しており、大きな躍進を遂げています。
Abby Williams

人件費の高い、又は、賃金アップを要求する韓国人を切り捨てて、外国人労働者を使っているような事を書いていた記事を読んだけど、結局、安い船価の国際競争の先は、チキンレースと行きつくとこまで行く将来のない結末だと思う。
韓国国内の造船会社が、船を作る人材を確保できず、気をもんでいる。低い賃金と画一的な週52時間制などの理由で、仕事場を離れた国内技能人材の現場復帰は非常に遅い。その代わり、外国人労働者を増やそうとしても容易ではない。政府の入国審査を経て配置される速度は遅く、数字も非常に不足している。造船会社各社は、膨大な注文を受けていながらも、納期遅れによるクレームを心配している。
昨年、韓国造船海洋や三星(サムスン)重工業、大宇(テウ)造船海洋の造船業界「ビッグ3」は、2年連続で受注目標を超過達成した。3〜4年分年分の仕事をあらかじめ確保したのだ。特に、ウクライナ戦争によるエネルギー供給の支障で、世界各国で韓国造船会社が圧倒的競争力を持つ高価な液化天然ガス(LNG)輸送船舶の需要が急増した。問題は、船を作る人材を探すのがとても難しいとことだ。
実際、2014年には20万人を超えていた造船業の従事者は、昨年は半分以下の9万人余りに減った。減少した人材は、そのほとんどが溶接工などの現場人材だ。その間、造船業の景気が悪かったうえに、週52時間制の拡大で延長労働手当てまで受け取れなくなり、多くの労働者が他の働き口を探して去った。当面は、外国人労働者をもっと使うこと以外に代案がない。
昨年4月、政府もこのような理由で造船業関連の特定活動ビザの人員制限を撤廃したが、年末までに新たに採用された外国人溶接工は90人余りに過ぎなかった。産業通商資源部や法務部などの関連省庁が書類を審査する過程で、ボトルネック現象が生じたため、長くは5ヵ月以上入国が遅れたためだ。外国人労働者の技能検証機関が変わったことや、担当公務員数の不足などが理由に挙げられる。
造船業界は、今年第3四半期に生産人員が1万3000人も不足すると予想している。人材を補充できなければ、船を適時に作って引き渡すことができず、発注会社に巨額の補償金を払わなければならない。納期に追われた一部の造船業者は、力を入れて受注した仕事を中国業者に下請けし始めている。
政府は今年、韓国の輸出は昨年より4.5%減少するだろうという見通しを示し、輸出拡大を促している。造船業界の人手不足のように、一刻を争う現場の問題から一つ一つ解決することが、百の言葉より輸出拡大にもっと重要だ。
The Australian Federal Court is preparing to auction off the livestock carrier Yangtze Fortune which it believes has been abandoned by its owners while the International Transport Workers’ Federation is highlighting the ship as the latest example of owners mistreating their crews. The ITF is saying that it believes the livestock sector is in trouble with an increasing number of complaints and insolvencies.
Built in 2005 in China as a containership, the vessel has a checkered history having at least five different names and a long list of managers and registered owners. The 4,800 dwt ship operated carrying livestock between Australia and China with a crew of approximately 30. During its most recent trip, it was expected to load 5,200 head of cattle for transport to China.
The vessel has a long list of deficiencies identified during port state inspections dating back to 2013. However, it avoided detentions for the most part except in Australia briefly in 2020 and that was regarding its operating plan as opposed to structural issues. In July 2022, an initial inspection in Ningbo, China however found issues with the stowage of rescue boats and the launching arrangements for survival craft.
The Australian Maritime Safety Authority reports the vessel arrived at Portland near Melbourne in southern Australia on September 28 and remained at anchor. AMSA reports it has been monitoring the situation with the vessel which is registered in Liberia paying attention to the crew welfare and is now working with the Admiralty Marshall to ensure the crew welfare and entitlements are maintained now that the vessel is in the hands of the court.
The courts became involved when Australasian Global Exports Pty issued a writ against the ship in Western Australia with claims of damages of US$2.3 million plus A$1 million for breach of a September booking. Dan-Bunkering moved to have the ship arrested for non-payment of bills and subsequently Singapore ship chandlers also filed against the ship.
The court reports that the vessel is deteriorating while no maintenance and it has not received a reply from the owners. The Marshall ordered the ship moved to the dock and later paid for the purchase of fuel because the owners had not supplied fuel. Further, the Marshal reports that the vessel undertook a temporary repair for the crack in its hull, which appears to be holding at this time.
Saying that the vessel is all but abandoned by the registered owners Soar Harmony Shipping of China, the judge concluded in a December 20 hearing, “Clearly, the vultures are circling. I see little to no prospect that the judicial sale of the vessel can be avoided.” He noted that neither the shipowner nor any bareboat charterer or mortgagee has intervened to maintain the vessel. The court highlights that the clock is ticking as the Marshall reports from documentation provided by the master that it appears that the vessel’s marine hull and machinery insurance is set to expire on December 31, 2022. If that occurs, the judge said all claimants’ security will be imperiled.
The International Labor Organization reports that it has also received an abandonment notice for the crew. The court reports that there are 36 crewmembers aboard but that it could be reduced to 16. The crew however is unwilling to leave the ship until they are paid their back wages.
According to inspectors from the ITF that boarded the ship and interviewed the crew who are Philippine nationals, shipboard documentation shows the crew received only one-third of its wages in October. Several of the crew members have been aboard the ship for eight or nine months. The ITF reports it is providing support for the crew as their provisions run low but it is concerned because collectively the crew is owed a quarter of a million dollars in unpaid wages. The crew can not leave the ship because they would forfeit their claims but faces few prospects of recovering all of their back pay.
The ITF reports that AMSA and the court are working together for the crew. The judge concluded after the December 20 hearing that “In the circumstances, I am satisfied that there should be orders for the sale of the vessel. I see no other available course,” but ITF is concerned that the monies raised are unlikely to cover all the owner’s debt meaning the crew might still not get paid. They are also involving the flag state for its obligations to the crew and to provide for reparation if necessary.
The ITF Australian Inspectorate Coordinator, Ian Bray, however, said that he sees a broader problem in the livestock shipping industry. “We believe there is an epidemic of borderline insolvency amongst the operators of these livestock ships as they repeatedly feature among the worst cases in our inspections around Australia and internationally,” said Bray. The sector is the frequent target of activists that want the livestock trade ended and the maritime unions who also highlight the working conditions aboard the ships.
For now, the crew of the Yangtze Fortune remains in limbo. The court has directed the Marshall to proceed with the sale once the plaintiffs file the necessary paperwork.
日本クルーズ客船(本社・大阪市)が運航するクルーズ船「ぱしふぃっくびいなす」(2万6594トン)は27日、神戸港を出発するクルーズで営業運航を終了する。20日からは出入港時に催しが開かれ、引退を惜しむ人々が集まっている。
1998年に就航した。旅客定員476人。豪華な客室や劇場、プールを備え、「飛鳥Ⅱ」や「にっぽん丸」と並び、日本を代表するクルーズ船とされた。神戸港を主に発着地とし、入港数はクルーズ船として最多の計約680回に及ぶ。
新型コロナウイルスの感染拡大で2年間休止し、2022年3月に運航を本格再開したものの、客足が戻らなかった。同社は「事業継続が困難と判断し、やむなく引退を決めた」としている。
20日夜の出港時には甲南大ジャズ研究会の演奏があり、日本クルーズ客船の社員らがペンライトを手に乗客を見送った。花火が打ち上がり、歓声が広がった。
セレモニーは続き、24日の出港時には神戸学院大の吹奏楽部が演奏する予定。27日の最終航海では出港時に神戸市消防音楽隊が演奏して送り出す。2023年1月4日の入港時には、須磨翔風高和太鼓部の演奏で歓迎する。
神戸港最後の出港となる1月6日には市消防音楽隊の演奏で見送られながら、相生市のドッグへ向かう。神戸市は「神戸港を盛り上げてくれた。市民にも親しまれた船だった」と惜しむ。
神戸港発着の遊覧船で海上からの見送りクルーズも計画されている。
神戸ポートターミナル(同市中央区)の3階では「ぱしふぃっくびいなす」を中心にクルーズ船の航跡をたどるパネル展示が1月末まで開かれている。【大野航太郎】
クルーズビジネス業界はまだまだ冬の時代だと思う。
国際クルーズ船大手のコスタクルーズが、中国を含むアジア市場から全面撤退することがわかった。財新記者が複数の関係者から入手した情報によれば、同社は中国、香港、台湾、シンガポール、日本、韓国などの社員に対して、業務停止の決定をすでに通知した。
この記事の写真を見る
コスタクルーズのアジア撤退の背景は、最大の市場である中国で新型コロナウイルスの流行を封じ込めるための厳しい行動制限が続き、クルーズ船の運航再開が見通せないことだ。同社が東アジアに配置する4隻の大型クルーズ船は、新型コロナ発生前の2019年には中国の港から発着するツアーが航海期間の3分の2を占め、大勢の中国人乗船客で賑わっていた。
同社が中国市場から撤退する兆しは、すでに昨年から現れていた。2021年10月、コスタクルーズは中国市場向けに情報発信していたSNSの公式アカウントの更新を停止。業界情報に詳しい中国の旅行サイトの関係者によれば、コスタクルーズの中国地区責任者を務めていた葉蓬氏は昨年のうちに退社し、多くの従業員が後に続いたという。
■カーニバル系の食い合い回避も
コスタクルーズは1860年にイタリアのコスタ家が創業した老舗企業だ。同社は1996年、クルーズ船世界最大手のカーニバルの傘下に入った。カーニバルは現在、国際クルーズ船の市場全体の4割を握っている。
新型コロナの世界的大流行が始まるまで、国際クルーズ船の市場ではアジア太平洋地区の乗船客数が世界全体の6割近くを占めていた。なかでも中国の伸びが目覚ましく、2018年の乗船客数は延べ219万人とアジア全体の半分に上った。
業界関係者の一部は、コスタクルーズの中国撤退の裏には新型コロナの影響以外の理由もあると見ている。それは、カーニバルの傘下企業同士による需要の食い合いを避けることだ。
カーニバルは2018年、中国の国有造船大手の中国船舶集団(CSSC)と手を組み、合弁会社CSSCカーニバル・クルーズ・シッピングを発足させた。その狙いは、同社を中国のクルーズ船業界の旗艦企業に育てることにあると見られている。
(財新記者:李蓉茜)
※原文の配信は10月24日
財新 Biz&Tech
下記の記事の内容が事実なら日本も影響を受けているのでは?
韓国の造船業界はビッグ3企業が全部赤字だというのによくもっています。
値段の叩き合いだというのに中国企業と張り合っていられるのは大したもの――という見方もできます。
イギリスの造船・海運市況調査会社『クラークソンリサーチ』によれば、韓国と中国の造船受注チキンレースは継続中で、10月の実績は以下のようになっています。
2022年10月
中国:180万CGT(34隻:シェア53%)
韓国:143万CGT(22隻:シェア42%)
※CGTは「Compensated gross tonnage」の略で「標準貨物船換算トン数」と訳されます。船舶の建造工事量を表す指標です。
2022年度の累計で見ると以下のようになります。
2022年01~10月累計
中国:1,581万CGT(570隻:シェア46%)
韓国:1,465万CGT(261隻:シェア42%)
世界一の座を巡って中国とのチキンレースを戦っているわけですが、月次で見ると韓国は10月に首位の座から転落し、累計ではいまだ中国に届いておりません。
韓国メディア『韓国経済』には、中国に押されたことについて以下のように報じています。
『韓国造船海洋』『サムスン重工業』『大宇造船海洋』など、韓国造船業界が世界船舶受注首位の座を1カ月ぶりに中国に明け渡した。
中国の低価格受注攻勢に押された結果だ。
韓国企業は「造船業界世界最強」の地位を巡って中国と激しい競争を続けている。
(中略)
中国造船業界が自国政府の資金など支援を背景に低価格受注に乗り出し、韓国造船業界を脅かしているという分析が出ている。
(後略)
⇒参照・引用元:『韓国経済』「『中国の低価格攻勢にあった』…K造船、中国に1位を渡す」
「中国造船業界が自国政府の資金など支援を背景に低価格受注に乗り出し、韓国造船業界を脅かしている」なんて書いていますが、じゃあ韓国はどうなんだ?という話です。
すでに事実上破綻していた『大宇造船海洋』に国策銀行の資金を入れて延命させ、安値受注を繰り返した挙げ句にいまだ赤字という事態となっていますが――これを国の補助金によるものといわずしてなんというのでしょうか。
韓国に中国の行っていることを非難などできません。似たりよったりなのです。
両国ともWTOに加盟しているのですから呆れる他ありませんが、中国・韓国の造船産業におけるどつき合いは、結局「国によるドーピング競争」みたいなものです。
※中国はWTOに加盟する際に「国営企業は減らす」と約束したのに、事態は全く正反対の「国営企業ばかりになる」方向へ動いています。
ですから韓国はよく戦っているともいえます。図体がでかく、いざとなれば韓国よりもずっと大きな金額を投入できるだろう中国を相手に回し、善戦(?)しているのですから。
「それは、血を吐きながら続ける、悲しいマラソンですよ」に等しく、褒められたものではありませんが。
(吉田ハンチング@dcp)
「人がいません。もう数年になりました。入ってきても数カ月もたたずにみんな出て行きます。資格要件は最初から確認もしません。外国人労働者も行こうとしないのが地方にある造船所です」(地方造船所関係者)。
96.6%。現在の造船業界で生産職の人材が不足していると答えた企業の割合だ。最近韓国の造船業界は類例がない好況にも船を建造する人材が不足し地団駄を踏んでいる。求人難が続くと韓国政府は外国人人材の造船所勤務要件を緩和する対策を出したが、これさえもあちこちで穴があいている。現場では「長期間続いた不況で熟練者が流出し、すでに人材プールがすべて崩壊した状況」と口をそろえた。
造船産業だけでなく今後の韓国経済を率いていく半導体、未来自動車業種の企業の半分ほどが人材不足を訴えているというアンケート調査結果が出た。景気低迷と就職難の中にも現場に必要な人材が適材適所につながらずにいるという指摘が出る。
韓国経営者総協会が実施した「未来新主力産業(半導体、未来自動車、造船、バイオヘルス)の人材需給状況体感調査」(回答企業415社)によると、造船業界事業者の52.2%が現在人材が不足していると答えた。次いで半導体が45.0%、未来自動車が43.0%、バイオヘルスが29.0%の順で働き手がいないと答えた。
これら企業は共通して現場の生産職人材が足りないと口をそろえた。特に造船業の場合、生産職人材が足りないと答えた割合は全体の96.6%に達した。未来自動車も95.4%でやはり絶対多数の企業が生産職の人材が不足している状態だと答え、半導体(64.5%)とバイオヘルス(55.2%)業界も半分以上が生産職の労働力難に苦しめられていると明らかにした。
半導体と造船、未来自動車の人材不足企業の相当数は5年後にも生産職の人材不足は変わらないだろうと予想した。
造船(46.7%)と半導体(38.3%)企業は人材不足の理由として、頻繁な離職・退職を挙げた。バイオヘルス(55.2%)、未来自動車(44.2%)企業は該当分野の経歴職志願者不足で労働力難を体験していると答えた。特に造船業界では現場仕事そのものを敬遠する雰囲気を労働力難の原因のひとつに挙げたりもした。
生産職以外の核心職務(▽研究開発・設計・デザイン▽品質管理・整備▽販売・購入・営業)の5年後の人材需給見通しに対しては「現時点で判断できない」という回答が最も多かった。これは世界市場の環境変化速度が予測しにくいほど速く、多くの企業が未来の市場状況に対する不確実性から人材需給計画を立てられなかったためと推定される。
これら企業は労働力難を解消する政策でとして「人材採用費用支援」が必要だと答えた。半導体企業は「契約学科など産学連係を通じた企業に合わせた人材育成」(25%)、「特性化高校人材養成システム強化」(23%)など学齢期の優秀人材をあらかじめ育てなければならないと答えた。未来自動車業種の場合、企業に合わせた訓練プログラム運営に向けた支援拡大を解決策に挙げた。
韓国経営者総協会のイム・ヨンテ雇用政策チーム長は「短期的には現場に合わせた職業訓練強化と雇用規制緩和で現場人材ミスマッチを解消しなければならない。人材を供給する教育機関と人材を必要とする企業間の敏捷な協力が何より重要だ」と話した。
韓国造船業界は、超大型船や大型LNG船を欧州や中東から大量受注、一方で、造船労働者は文前政権の労働政策である週52時間規制により、手取りが少なくなり、相当数が転職、特に造船作業の70%に当たる溶接工の不足が顕著になっているという。
(韓国は文在寅政権時代に最低賃金を3割以上上昇させたことから、発展途上国からの労働者派遣が急増している)
すでに造船業界は大企業、中小企業に限らず、多くの外国人労働者を雇用しているが、今回は9月から1150人の溶接工が入国するようになっていたベトナム人の溶接工の入国が予定より大幅に遅れているという。
仲介業者がベトナムの審査機関に提出する書類を偽装していたことが発覚、ベトナム当局が再審査にかけており、大幅に遅れているという。
それでも韓国へ来るのは早くて12月とされ、すでに造船工事が遅れ、業界として納期遅れの違約金支払いも現実なものになってきているという。
外国人溶接工の導入は、
昨年約600人、今年の外国人溶接工の需要は急増し約2800人とされ、うち1150人がベトナム人だという。ベトナムの仲介業者を介して予定していたベトナム人溶接工たちだが、ベトナムの審査で、受入条件の2年以上の実務経験や学歴などが審査書類で詐称されていたことが発覚、現地で技量テストを受けても、12月にベトナムから1150人が来るとも限らなくなっている。
韓国の造船業界の外国人溶接工は、現地仲介業者を通してベトナム、タイ、インドネシア、ミャンマー、ウズベキスタンなどから受け入れている。
納期遅延問題も、英国、カタール船主などから受注した液化天然ガス(LNG)運搬船と大型コンテナ船の引き渡しが遅れる可能性があるという。
造船地の巨済一帯にある中小造船業者代表は「大宇造船海洋とサムスン重工業は、2ヶ月ほど、現代三湖重工業、現代尾浦造船などは1ヶ月ほど船舶工程が遅れている」とし、「造船業界全体が4000億~5000億ウォン(約400億~500億円)規模の遅延損害金を払わなければならない」見込みだといる。協力業者による納期遅れは、元請から遅延損害金が請求されることになる。
こうした事態は、韓国自体が外国人労働者への依存度が高まり、質の悪い仲介業者も多くなり、問題発生や事故などに企業が振り回される事例が大幅に増えており、予期されたことと見られている。
韓国の週労働時間52時間厳守の労働規制も、今では全企業に執行されている。また、大手造船会社と中小造船会社の賃金格差は2倍に達するといい、大手が大型や超大型船・LNG船の受注に奔走、中・小型船を主力とする中小造船会社の人材難はさらに深刻だという。それぞれに協力会社も多数。
そうした人手難に、外国人労働者も上記国以外にアフリカ人を提案する仲介業者も現れてきているという。
ある外国人労働者は、派遣費用とは別に、斡旋手数料で1200万ウォンを派遣国の仲介業者に支払う契約となっており、仲介業者に貸付金の返済として月々元利金を支払っているという。(韓国への旅費なども高利で貸付、紹介手数料とともに月々元利金を支払っている。長期に滞在しなければ実質稼げない)
こうしたことは日本へ来る技能実習生も同じこと。日本の政治家はとぼけばかり。
韓国では外国人労働者については5回まで転職が可能とされており、過労や不平不満から転職する外国人労働者も多いとされ、業界では5回を3回までに修正すべきだとしている。しかし、こうした労働者たちの一定数は、不法滞在労働者にも化けている。
外国人労働者の受け入れは、
海外人材仲介業者が韓国の仲介業者からの派遣要請書類を検証した後、人材募集し現地で技量テストを終えればよい。ベトナムの例では、労働省と法務省などの審査も受ける。以後、韓国造船海洋プラント協会の予備推薦書発給、産業通商資源部の推薦書発給、法務部審査を経て入国ビザが交付され、勤労者が入国することになるという。
このように、中小企業の外国人依存度が高まったのは、国内で働く人材を求めることができないためだ。
(韓国の造船会社は、リーマンショック後、安値で商船や海上石油プラントを取り捲り、納品時期となった2015年の決算では3社とも大赤字になり、3大造船とも銀行管理下に入った。2017年に文在寅政権になり、失業者問題から造船会社を金融機関から開放させ、造船会社は再び受注しまくっている。2021年は3大造船会社とも造船事業では大赤字を露呈していた。今年はどうだろうか・・・)
韓国の造船海洋プラント協会によると、造船業の柱である溶接、塗装、電気など生産機能職不足人材は来年6月1万1000人に達する見通しで、さらに2027年には3万6000人が不足する見通しだという。
人材難を深化させた原因としては、大企業に適用された週52時間労働制、おって中小企業にも適用されたことによるもの。
労働者の7割が、残業ができず手取りが減り、造船業界からも相当数が離れたという。
韓国の造船大手3社は、世界中から受注しまくっており、韓国の造船海洋プラント協会によると、造船業の柱である溶接、塗装、電気など生産機能職不足人材は、来年6月までに1万1099人に達する見通しで、さらに2027年までには3万6000人が必要と推算されているという。
以上、韓国紙など参照
英国の造船海運市況分析機関のクラークソンリサーチ社によると、
2022年4月の韓国造船会社の手持ち工事高は、前月比34%と急増して3268万CGT(688隻)となり、2016年(692隻)以来の高水準になっているという。
世界の手持ち工事量は9595万CGTで、韓国は中国(4044万CGT)の次に多かった。
韓国の1隻当たりの受注単価は1億4300万ドルで、中国(8600万ドル)より66%高い。高付加価値のLNG船の受注が、中国の安保問題もあり、韓国は欧州・中東からは独占的になっている。
露制裁により、今後、カタールや米国から大量に欧州へ液化した天然ガス(LNG)が輸出され、そのため、欧州超大手の商船会社やカタール政府が韓国へLNGを大量発注している。
米国では現在、超大型のLNGプラントが建設されており、2025年には完成し、欧州はじめ全世界へ輸出するという。
天然ガスも原油も世界最大の生産国は米国。ただ、シェールオイル・ガス軍団は共和党でありトランプと仲良し、バイデンの増産要請に見向きもせず今日に至っている。
日本では、自民党の歴代の国交省大臣たちは利権絡みが多すぎたため、時の首相が2001年にしがらみのない女性を大臣にし、2005年からほぼそうかの人の定席となっている。学会のことは別にして世界の造船業界の動向など知る良しもない時代が今に続き、日本の造船業界はほとんど死滅している。かつて世界一だった。
日本の政治をよりよくするためには自民党を分裂させるしかない。小泉の強度の党議拘束の乱発から異常な自民党の状態が今に続いている。ぶっ壊すどころかおかしくしてしまった。
自民党を分裂させることにより、ほかの政党もひっくるめて政界を再編させ、凌ぎあわせてこそ日本の成長と未来がある。
韓国は、もともと監視国家で政治家の不正犯罪以外、表立った犯罪は限られているが、不法滞在者は・・・。
「人がいません。もう数年になりました。入ってきても数カ月もたたずにみんな出て行きます。資格要件は最初から確認もしません。外国人労働者も行こうとしないのが地方にある造船所です」(地方造船所関係者)。
96.6%。現在の造船業界で生産職の人材が不足していると答えた企業の割合だ。最近韓国の造船業界は類例がない好況にも船を建造する人材が不足し地団駄を踏んでいる。求人難が続くと韓国政府は外国人人材の造船所勤務要件を緩和する対策を出したが、これさえもあちこちで穴があいている。現場では「長期間続いた不況で熟練者が流出し、すでに人材プールがすべて崩壊した状況」と口をそろえた。
造船産業だけでなく今後の韓国経済を率いていく半導体、未来自動車業種の企業の半分ほどが人材不足を訴えているというアンケート調査結果が出た。景気低迷と就職難の中にも現場に必要な人材が適材適所につながらずにいるという指摘が出る。
韓国経営者総協会が実施した「未来新主力産業(半導体、未来自動車、造船、バイオヘルス)の人材需給状況体感調査」(回答企業415社)によると、造船業界事業者の52.2%が現在人材が不足していると答えた。次いで半導体が45.0%、未来自動車が43.0%、バイオヘルスが29.0%の順で働き手がいないと答えた。
これら企業は共通して現場の生産職人材が足りないと口をそろえた。特に造船業の場合、生産職人材が足りないと答えた割合は全体の96.6%に達した。未来自動車も95.4%でやはり絶対多数の企業が生産職の人材が不足している状態だと答え、半導体(64.5%)とバイオヘルス(55.2%)業界も半分以上が生産職の労働力難に苦しめられていると明らかにした。
半導体と造船、未来自動車の人材不足企業の相当数は5年後にも生産職の人材不足は変わらないだろうと予想した。
造船(46.7%)と半導体(38.3%)企業は人材不足の理由として、頻繁な離職・退職を挙げた。バイオヘルス(55.2%)、未来自動車(44.2%)企業は該当分野の経歴職志願者不足で労働力難を体験していると答えた。特に造船業界では現場仕事そのものを敬遠する雰囲気を労働力難の原因のひとつに挙げたりもした。
生産職以外の核心職務(▽研究開発・設計・デザイン▽品質管理・整備▽販売・購入・営業)の5年後の人材需給見通しに対しては「現時点で判断できない」という回答が最も多かった。これは世界市場の環境変化速度が予測しにくいほど速く、多くの企業が未来の市場状況に対する不確実性から人材需給計画を立てられなかったためと推定される。
これら企業は労働力難を解消する政策でとして「人材採用費用支援」が必要だと答えた。半導体企業は「契約学科など産学連係を通じた企業に合わせた人材育成」(25%)、「特性化高校人材養成システム強化」(23%)など学齢期の優秀人材をあらかじめ育てなければならないと答えた。未来自動車業種の場合、企業に合わせた訓練プログラム運営に向けた支援拡大を解決策に挙げた。
韓国経営者総協会のイム・ヨンテ雇用政策チーム長は「短期的には現場に合わせた職業訓練強化と雇用規制緩和で現場人材ミスマッチを解消しなければならない。人材を供給する教育機関と人材を必要とする企業間の敏捷な協力が何より重要だ」と話した。
2022年9月6日、韓国・マネートゥデイは「受注の朗報が相次ぐ韓国造船業界だが人手不足が深刻化しており、専門家は造船が没落した日本の二の舞いになりかねないと警告している」と伝えた。
韓国造船海洋プラント協会によると、14年末には20万3441人に達した韓国造船業界の従事者数が、昨年末には9万2687人まで落ち込んだ。受注不況による新規採用の縮小に加え、定年退職者の離脱、転職者の増加などが指摘された。現場技能職だけでなく技術・研究・管理職の離脱も深刻化しており、これがより大きな問題だと専門家は指摘しているという。次世代船舶技術の研究・開発(R&D)を担う人材が不足すれば、韓国造船産業の競争力後退は避けられず、記事は「かつて世界の造船産業を牛耳っていたが、韓国に追撃を許したのち急速に衰退した日本の轍(てつ)を踏む形だ」と懸念を示している。
記事は「日本の造船は韓国、中国などに追い越され、1980年代後半~90年序盤に韓国に造船の覇権を明け渡した」「収益性を理由に造船会社の採用規模が縮小化された結果が業界の衰退へとつながった。さらに大学での人材支援が途絶え、続々と学科が消え、日本造船業界の悪循環が固着化された」などと説明。
その上で「韓国造船業界の現状もさほど変わらない」と指摘。「大学生の就職希望企業ランキングで上位を守り続けた造船会社は2008年の世界金融危機以降は圏外となり、関連専攻の人気も低迷している。また最近、サムスン重工業や大宇造船海洋など4社が公正取引委員会に『現代重工業グループが不当な人材の引き抜きを行っている』と訴える問題もあった」としている。
専門家は、造船業界の極度の人材難について「液化天然ガス(LNG)運搬船など高付加価値船舶の受注量と二重燃料動力のエコ船舶需要が急増したため」だと指摘している。さらに、人材流出は継続すると思われるが、技術・研究・管理職を必要とする船種の受注が大きく増えることで、造船業界の余力も消耗されていくとの見方を示している。新たな人材確保が難しい中では在職中の経験者が現代重工業グループに転職しサムスンや大宇の反発が強まることになりかねず、「構造的悪循環という根本原因の打開策を業界だけでなく政府、産業銀行などが講じる必要がある」と助言している。
この記事に、韓国のネットユーザーからは「昔は働いた分だけ稼げたけど、今は下請けの下請けになって10年以上働いてる人も最低賃金しかもらえない。それでは人手も減って当然だ」「人がいないんじゃなく、上の人ばかりもうけて働きアリは賃金が上がらないから現場を去っていってるんだ」「安くこき使おうとするから働きたがる人がいないだけ」「正しくは『奴隷がいない』でしょ」「賃上げを求めたらクビ、デモをしたら訴訟。そんなことをしておいて人材不足だ何だと言うなんて、恥ずかしくないのか」「記者は大企業の立場でばかり記事を書くな。企業は自分たち優先で大規模リストラを行い、下請けに孫請けで現場の人たちを奴隷扱いしてきたというのに」「汗水流して働いている労働者を軽んじるなら滅びるだけだ」など、厳しいコメントが多数寄せられている。(翻訳・編集/麻江)
※記事中の中国をはじめとする海外メディアの報道部分、およびネットユーザーの投稿部分は、各現地メディアあるいは投稿者個人の見解であり、RecordChinaの立場を代表するものではありません。
造船業のリストラを契機に、多くの労働者が造船所を去った。一部は京畿道の半導体工場、蔚山・麗水・大山の石油化学産業団地、発電所といったプラント建設現場に向かった。それらが建設現場に向かった第一の理由は賃金だ。賃金が下げられた造船所に比べて、賃金水準が高いからだ。もう一つ重要な問題がある。安全管理だ。造船所からプラントに移って来た作業者たちも話をする。大多数が造船所に較べて、プラントで働く方が相対的に安全だと言う。賃金も賃金だが、怪我せずに、安全に働けるプラント現場の方がもう少し良いということだ。造船業や建設業の特性上、労災事故の規模と被害は極めて深刻だ。労災で作業が中止されれば金は稼げない。酷いときは、障害を負ったり、命を失うことまである。このため、安全な事業場を選ばざるを得ない。
造船所は製造業の事業場だ。しかし、産業の特性のため、建設業の安全基準を参考にすることが多い。船舶1隻の大きさが、普通の建築物よりも遙かに大きいからだ。しかし、法律上、造船業に対する明確な基準がない。最も基本的な安全管理費の計上基準だけでも、建設業のように、プロジェクトや進捗率に応じた計上の基準を提示することは難しい。造船業は、事業場の中で同時多発的に船舶の製作をするからだ。このため、建設業のような細かい規定がない。造船所の安全管理は建設業に較べて杜撰にならざるを得ない。
「重大災害処罰等に関する法律」(重大災害処罰法)が今年の1月27日から施行され、すべての造船所に安全管理を求めている。ある造船所は下請け労働者の連続労災死亡事故で、雇用労働部から作業中止まで受けた。このため、数千億ウォンの安全費用を投資するというマスコミ報道まで出た。しかし、現場で変わったことはないという声が出ている。安全教育は直営(元請け職員)と一部の一次下請けに辛うじて適用されるレベルだ。実際に仕事をする下請け労働者に対する教育は、形式的にしか行われていない。
火器・足場の下部・密閉空間の監視員、クレーン信号手といった安全補助人員の配置から正しく行われていない。それさえ、固定式クレーン設備にはクレーンの使用に関する教育を受けた人が配置されるが、その他の領域では、監視員に対する基本的な安全教育すらまともに行われていない。石油化学・半導体プラントの場合、火器・足場の下部・密閉空間の監視員、クレーン信号手に対して特別の安全教育を履修し、教育内容と関連した試験を通過してから現場に配置されている点と比較すると、深刻なレベルだ。
建設と造船所の最大の災害である墜落事故への対応も同じだ。足場作業時に足場が正しく設置されているかを検査し、使用許可のタグを付けていなけらば、作業ができないようにするべきである。しかし、造船所の現場では、きちんと守られていない。甚だしくは、余りにも多くの下請け業者が足場を設置するので、どの業者で設置したのかが把握しにくいといった状況も、たまに生じている。元請け会社が専門の安全監視要員を雇用し、足場の検査などの安全管理をしなかったり、表面に現れている部分だけを管理することによって生じる問題だ。
造船所も化学物質を扱う産業だ。船舶の塗装作業の時に有害な化学物質を使用する。保温(配管、設備等の温度を一定に維持させるため断熱材を付ける)の過程では、空気中の保温材のくずを吸入する問題がある。それでも物質安全保健資料(MSDS)についての教育は、きちんと行われていないケースが多い。当然、作業者は何かの化学物質にばく露していて、事故が発生した時の初期対応・職業病・有害性に対する情報が不足している状態で働かざるを得ない。
プラント産業群のように専門の安全管理者を雇用するよりも、他の部署で働いていた人を安全部署に配置する事例もある。いくら正規職が安全管理を引き受けているとしても、専門知識を備えていなければ無駄だ。当然、体系的な安全管理もうまくいっていない。
労災に対応する文化も後進的だ。例えば、某造船所でLPG切断機の使用中の爆発事故で作業者が死亡することがあった。事故が起きてから非常通路を設置したり、火気監視者を追加で配置したり、ガス類の保管方法が改善された。泥縄式のレベルだ。
造船所内の安全管理オンブズマン・システムも形式的だ。現場の作業者が危険な要素を見付けた時に、会社が作ったアプリに情報を提供しても、危険要素の情報を提供する写真を削除しろと言い、むしろ情報提供した下請け労働者に圧力をかけた事例がある。情報の提供を受ければ措置を執らなければならない。しかし形式的な安全管理だけをしていて、実際の人員の投入やフィードバックは全くない。こんなことでは、どんな労働者がもう少しでも造船所に居ようとするだろうか。
建設業にも再下請けの問題があるにはある。しかし、元請け会社は安全計画の樹立と管理・監督を行い、下請け業者が実務を引き受ける枠組みが整っている。また、各工程によって専門業者に下請けする基本的な形は整っている。しかし、造船所の下請けは人材供給しかしないのがほとんどだ。このため、いくら元請けが管理・監督を強化すると言っても、多段階下請け構造では安全教育と責任の所在が曖昧にならざるを得ない。マルチ商法の下請けに対する改善策も考えるべき領域だ。
造船所の低賃金問題が水面上に浮上した。しかし、賃金だけが上がってもダメだ。『死なずに働ける権利』が保障された現場であるべきだ。そうしなければ、造船所に労働者は戻ってこないだろう。
2022年8月5日 毎日労働ニュース ハ・イネ(安全管理労働者)
クルーズ客船「ぱしふぃっくびいなす」(約2.6万トン)を運航する日本クルーズ客船は、2023年1月に客船事業を終了すると発表した。12月27日~2023年1月4日の日程で沖縄や奄美を巡る「びいなすニューイヤークルーズ」が最終運航となる。その後、同社は解散手続きに入る。 ※画像は日本クルーズ客船のホームページより
日本クルーズ客船は、トラベルボイスの取材に対して事業を終了する理由を「コロナ禍の影響による厳しい事業環境」と説明。コロナ禍で2020年2月に運休後、2022年3月までの本格再開までの2年間はほぼ運休となり、売り上げが立たなかった。具体的には、2021年夏季にいったん運航を再開したものの、感染状況を踏まえて運休となり、本格再開までの2年間で運航できたのは、わずか計8コース(19泊分)だった。
また、2022年3月の本格再開後も、感染対策で乗客数の制限を余儀なくされた。集客状況もコロナ以前の半分以下で、需要回復は厳しかった。日本のクルーズ客船はシニア層の顧客の強い需要に支えられていたが、コロナ禍においては「雰囲気からすると、コロナが収束するまで我慢しようというお客様が多い印象。慎重でまじめな方が多かったのでは」(同社広報担当)という。
「ぱしふぃっくびいなす」は最終クルーズの運航後、ドックに入る。その後は以前から、クルーズスケジュールを出していなかった。
日本クルーズ客船は、新日本海フェリー等のSHKグループが1989年4月に設立。1990年にクルーズ客船「おりえんとびいなす」を就航し、1998年に「ぱしふぃっくびいなす」を就航したが、2001年10月以降は「ぱしふぃっくびいなす」のみで運航していた。
同社の事業終了後は、日本企業で外航クルーズ(日本から海外へ行く国際クルーズ)を運航する客船会社は、郵船クルーズ(飛鳥II:総トン数・約5万トン)と商船三井客船(にっぽん丸:総トン数・約2.2万トン)の2社・2船のみとなる。
トラベルボイス編集部
個人的な意見だけど韓国建造の船の質は以前よりも落ちていると思う。そして、艤装品に関しては以前よりも、韓国製よりも中国製の割合が多くなっているように思える。
日本も似たような問題を抱えているけど、価格を抑えるために外国人労働者を増やすのはやめた方が良いと思う。それよりはどのようにすれば効率よく船を建造できるかを考えた方が良いと思う。品質を落とせば、タイムラグで影響は出る。無駄や改善が必要な工程は見直した方が良い。
日本や韓国に言える事だが、同形船で効率よく建造するしか中国には対応出来ないと思う。副作用は変わった船やあまり建造されないタイプの船を建造する時には割高になる可能性がある。
全ての産業に言える事ではないが、単純労働しか出来ない人達は危険、又は、きつい仕事でも選ばずに働かないと、必要とされない人達となってしまう。そして、危険、又は、きつい仕事は外国人労働者で埋められるので、一生、仕事がない状態の可能性がある。例え、仕事があったとしても低賃金の仕事しかない環境になるだろう。
政府はこのような状況は解決されない事を理解して、初等教育のカリキュラム、進学や就職を考えて改善する必要があると思う。これまでの教育は外国人労働者を増やす事で通用しないだけでなく、生涯にわたって無職の大人を作り出してしまう可能性がある。
韓国政府が人材難に苦しむ製造業などの労働力難を解消するため外国人労働者を大挙投じることにした。造船業、基礎産業、タクシー・バス業、飲食店・小売業、農業の5部門では労働力難が特に深刻なことが明らかになり、これら業種に対する外国人労働者投入が集中的に行われる。
韓国政府は8日に非常経済閣僚会議を開き、求人難解消支援案を確定した。政府が把握した6月基準の求人数は造船業が4800人、基礎産業が2万7000人、飲食店と小売業が1万4200人、タクシー・バス業が2300人などだ。職の空きは23万4000件程度だ。職の空きとは1カ月以内に仕事を始められる雇用数を意味する。
政府はまず基礎産業など製造業で新規外国人導入を6000人増やすことにした。求人難が深刻な造船業に優先配分する。E-9(非専門人材)のビザ割り当てを拡大する方式を活用する。
特に造船業には溶接と塗装工のような専門人材の場合、クオータを廃止する内容のE-7(特定活動)ビザを改善する。このようになれば専門人材3000人が追加で投入できると推定される。
農業部門では求人数がどれだけになるのか正確に把握されていない。ただ小規模農場を中心に労働力難が深化していることを確認した。これに伴い、農業部門に外国人クオータ600人を拡大配分し2224人に増やすことにした。
韓国政府はまた、下半期に配分することにした雇用許可人員を繰り上げ配分することにし、7-9月期と10-12月期に分けて発行した雇用許可書を今月中に発行することにした。入国を待機している人員など6万3000人も早期に入国させる方針だ。このようになれば上半期の入国者を含め8万4000人の外国人材が今年入国することになる。
10月中に来年のクオータを確定し雇用許可書を年内に発行する案も推進する。来年1月から必要な人材が入国できるようにするためだ。業種区分を設けない弾力配分クオータも1万人以上配分する。
政府はこれとともに求人難が深刻な地域と業種は特別管理することにした。慢性的に人材が不足している造船業と基礎産業が密集した地域の雇用センター17カ所に迅速就業支援タスクフォースを設置して全方向で支援する方針だ。
造船業の場合、緊急な作業量が増加すれば特別延長労働を活用できるよう速やかに認可することにした。特別延長労働は災害や一時的業務増加のような特別な事情がある場合、雇用労働部長官の認可を受け週52時間に加えて8時間の特別延長労働ができる制度だ。
雇用労働部の李正植(イ・ジョンシク)長官は「最近の求人難は新型コロナウイルスによる外国人労働者の入国遅延と対面サービス業況の回復により人材需要が急増して発生した一時的な要因とともに、これまで累積してきた劣悪な労働環境など構造的要因が複合的に作用した結果。外国人と新規人材参入を助ける一方、中長期的に労働市場の二重構造改善を持続推進したい」と話した。
からである。当然、乗船中は家に帰れないなどという問題はなくなる。
加えて、遠隔操船であれば、運航状況に応じて業務に従事する船員数を柔軟に変更できる。
「入出港時や荒天時は船員を増やす」
「外洋を通常運航中は船員を減らす」
といった運用が可能となれば、船員の総労働時間を減らせるはずだ。
内航コンテナ船なら可能かもしれないが他の種類の船だと難しいと思うよ。船の事を知らない人の発想だと思う。なぜ近代化船がなくなり、グレードの低い船に外国人船員を使うようになったのかを考えたらヒントがあると思うよ。船は天候やその他の要因でスケジュールが変わるから対応できる船員の数にも問題が出ると思う。緊急事態やトラブルが発生した場合、今まで以上に対応が難しくなる。まあ、個人的に思う事はあるが直接的に関係がある人達が考える事だと思う。
人手不足はトラックだけではない
物流現場の人手不足というと、トラックドライバーをイメージする人が多いのではないだろうか。確かに、トラックドライバーは1995(平成7)年頃をピークに減少しており、このまま放置すると2030年には約3割のモノが運べなくなるとの予測もある。
【画像】「えっ…!」 これがトラック運転手の「年収」です(15枚)
今まで猶予されていた時間外労働の上限規制がトラックドライバーにも適用されるという「2024年問題」も存在する。昨今の物価高の一因に、トラックの運賃上昇があることを考えても、最も身近な人手不足の例といってよいだろう。
実のところ、物流現場には人手不足が顕著な仕事がもうひとつある。それは
「船員」
である。
日本国内の港と港を結ぶ内航海運の船員は、原則「日本人」に限定されていることもあって、トラックドライバーと同様、人手不足は深刻だ。トラックドライバーは50歳以上の割合が5割近くになりつつあるが、内航海運のそれは既に5割を超えている。近年、若年層の雇用を強化しているとはいえ、トラックより先にモノが運べなくなる可能性もある。
「物流といえばトラック」というイメージを持っている人もいるだろう。だが、海運は日本国内での輸送量の40%を占める。55%を占めるトラックに比べれば相対的に小さいが、人手不足により船を動かせなくなったとすれば、日本経済に多大な影響を及ぼすはずである。
日本と世界をつなぐ外航海運の船員は日本人に限定されていない。実際、外国籍の船員が9割以上を占める。それゆえ、日本国内での人手不足の影響は受けないが、今後日本の経済力が低下したとき、果たして外国籍の船員を確保し続けられるだろうか。
島国である日本は、輸出入の
「99%超」
を海運に頼っている。つまり、外航海運の船員を確保できなくなった瞬間、社会生活を継続するためのライフラインを失するのである。
給与水準の問題ではない
なぜ、トラックドライバーが不足しているのか。
それは、他の仕事と比べて給与水準が低いからである。さればこそ、トラックドライバーの給与を増やすべきだとの議論がある。
では、船員はというと、この議論は基本的に当てはまらない。他の仕事よりも給与水準が高いからである。それでもなお人手不足になる最大の理由は、「乗船中は家に帰れない」という海運独特の働き方にある。
外航海運であれば半年以上、内航海運であっても3か月程度は乗船する。その間は家に帰れないが、下船後にまとまった休暇が与えられる。内航海運であれば、
「3か月乗船/1か月休暇」
が基本のサイクルだ。毎日家に帰ることよりも、給与水準や長期休暇の取得を重視する人にとっては魅力的な職場といえよう。
ただ、そのような職場を好んで選ぶ人は減少傾向にある。結果として、船員になりたい人、船員を続けたい人と、海運を維持するために必要な人数との間でギャップが生じているのである。
自動運航船の実用化は抜本的な解決策
自動運航船の実用化は、この船員不足の問題を根本から解決してくれる。もちろん、最終的には完全に無人での運航を期待したいところだが、その手前にある遠隔操船であっても十分に有効だ。なぜなら、船員は
「家にいながらにして船を操れるようになる」
からである。当然、乗船中は家に帰れないなどという問題はなくなる。
加えて、遠隔操船であれば、運航状況に応じて業務に従事する船員数を柔軟に変更できる。
「入出港時や荒天時は船員を増やす」
「外洋を通常運航中は船員を減らす」
といった運用が可能となれば、船員の総労働時間を減らせるはずだ。
船員のための居住スペースが不要になることも大きい。長期の航行を想定した外航船であれば、ジム、バスケットボールコート、カラオケルームなどの娯楽スペースも設けられている。その分を積載スペースに回せば、より多くの貨物を運べるようになる。ひとつの貨物あたりの輸送費やCO2排出量を削減できるわけだ。
世界にはいまだに海賊が存在しており、外航船が襲われることもあるが、船員が乗っていなければ人命を失う心配はない。現代の海賊は、船員を拉致しての身代金目的での襲撃が多いことを考えると、被害に遭いにくくなる可能性もある。
つまるところ、自動運航船の実用化は船員の労働環境を改善するだけではない。海運の効率性や生産性を広く高める価値があるといってよいだろう。
自動運航の実現は夢物語ではない
海洋船舶の支援を主とする日本財団は、海運会社、通信会社、保険会社、ITベンチャーなどとともに、自動運航船の実用化に向けた取り組みを進めている。
その主体となるコンソーシアムのひとつであるDFFAS(Designing the Future of Full Autonomous Ship)は、2021年9月に陸上からの遠隔操船を可能とするフリートオペレーションセンターを千葉市に開設した。そして、2022年2月には、東京港と津松阪港(三重県松阪市)の間での実証実験を実施し、船が多数行き交う海域での自動運航に世界で初めて成功したのである。
日本財団は、2025年までに自動運航船を実用化するとの目標を掲げている。その期限内での達成が困難であったとしても、遠からず実用化を成し遂げられるのではないか。さすれば、徐々に自動運航船が増えていくことで、船員不足の問題は解消し、日本の物流はよりサステナブルになる。
世界に先駆けて自動運航船を実用化できれば、新たな輸出産業とすることも夢ではない。海運立国復活への道は、自動運航の実現に託されているといっても過言ではないのである。
小野塚征志(戦略コンサルタント)
諏訪和仁
招集された役員たち 突きつけられた資料には・・・
会社を起こした創業者が、最初に手がけた事業、それが祖業だ。会社の数だけ祖業はある。その歴史は会社の歩みと重なる。
上田孝(70)が、祖業を売ると決めたのは、2年前の夏だった。
2020年8月17日、中堅造船会社サノヤスホールディングス(HD)社長だった上田は、大阪・中之島にある本社の会議室に、造船事業の子会社の役員を集めた。
役員らに示した資料には、
「造船以外の事業の売却」
「造船の売却」
「現状のままでの他社傘下入り」と、三つの選択肢が並んでいた。さらに、
「法的再生 会社更生法または民事再生法適用申請」
その横には「今何もしなければ、いずれ法的整理に追い込まれる可能性大」とも書かれていた。
上田は言った。
「造船と、造船以外の両方の事業が生き続けるには、どうすればいいか。私の意見は、造船を体力がある新来島(しんくるしま)どっくの傘下に入れれば、造船も生き続けられるし、残った事業も生き続けることができる」
上田の発言は、造船事業を同業他社に売却する、という意味だ。新来島どっくは、愛媛県今治市にある中堅造船会社で、瀬戸内海や愛知県、高知県の造船会社を買収してグループを拡大してきた。
役員たちは、言葉が出なかった。
渡辺義則(65)のショックも大きかった。海運会社や船主から船の注文を取ってくる営業の責任者だった。
「造船は非常に厳しかった。だから、この事業をどうするんだっていうことは冷静に考えなきゃいけないんだけれども、それでも心中穏やかではないですよ」
造船は、サノヤスHDの売上高約500億円の6割を占める大黒柱の事業だ。
100年以上も前、船大工の修業を積んだ佐野川谷(さのがわや)安太郎が大阪の木津川べりで始めた祖業である。水島の造船所(岡山県倉敷市)には、全長200メートル以上ある貨物船を年に最大12隻造る設備を持つまでに至った。
しかし、建造量で首位の中国や、台頭する韓国勢に対抗すると安値受注になり、造るほど赤字が膨らんだ。20年度は、前年度に続いて大幅な赤字が避けられない状況だった。
役員たちから反対する声は出…
船員に義務付けられている特別健康検査の書類を偽造し提出したとして、宇部海上保安署は9日、宇部市中村町の昭栄海運の会社役員を務める親子を有印私
見た目でヨーロッパのデザインをパクっていると思える。これで海洋資源をバンバンとるのだろう。

韓国の大宇(デウ)造船海洋が倒産危機に直面しているようだ!
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering may face a court-ordered rehabilitation process unless action is taken on a monthlong strike there, the company’s main creditor Korea Development Bank said.
“It would be more difficult for DSME to repay its debts as the strike drags on … we’re not going to help the builder unless it gets back to work,” an executive at the state-run bank said, suggesting that the country’s third-largest shipbuilder would have no choice but to ask the court for help if the strike results in a poorer liquidity.
The strike, which started last month as subcontractors occupied the shipyard’s main dock demanding a 30 percent pay raise, is projected to cause losses amounting to 816.5 billion won ($622.1 million) by July and 1.3 trillion won by August, according to the bank.
But neither the company nor striking workers seem ready to compromise anytime soon. Mediation efforts by the labor minister as well as President Yoon Suk-yeol, who himself called the sit-in “illegal,” have instead rallied the workers and proved ineffective.
Analysts said the builder would find it hard to stay afloat without extra loans from KDB — the main creditor that had injected 2.6 trillion won into the company since 2016, contributing to more than half the 4.2 trillion won the creditors had chipped in to save the firm.
KDB had backed merging DSME and its crosstown rival Hyundai Heavy Industries, a tie-up that would have resulted in the world’s largest shipbuilder, but in January European Union antitrust regulators blocked the proposal, saying the two Korean builders’ market dominance could lead to reduced competition.
DSME had already undergone rounds of restructuring so it has few assets to sell or enough collateral to pull loans, analysts said, noting the court could take steps to liquidate the firm altogether if it files for receivership again.
Source: The Korea Herald.
South Korean government and state lender are floating the idea of letting deficit-stricken Daewoo Shipbuilding Engineering & Marine Engineering (DSME) go bankrupt if shipyard contract workers do not end the months-long strike that has been amplifying losses for the shipbuilder currently under state management.
DSME’s subcontract workers staging a sit-down strike for over 50 days and facing an unofficial ultimatum have offered to end the strike if DSME drops the plans to file civil and criminal lawsuits against protesters and demand compensation for losses from dockyard disruption from illegal striking.
On Friday, DSME shares fell 1.46 percent to 20,250 won, as of 11:56 a.m. in Seoul.
The two parties reached an agreement on the wage issue on Wednesday, with workers yielding their demand for a 30 percent hike in base wage to accept a 4.5 percent raise offered by the management.
The union has significantly retreated from its hard-line stance after the government threatened to use force and flagged the possibility of bankruptcy. DSME`s management also vowed to take legal actions as the sit-down strike is estimated to have caused losses of 32 billion won ($24 million) a day, or 784.5 billion won so far.
The management fears it could be held responsible for breach of duty as it is more or less a public entity due to tax-financed bailouts of 11.8 trillion won.
“The company had repeatedly accepted all the demands in the past even after contract workers illegally occupied dockyards, but we cannot go on complying with their demands every time,” said a DSME official, who asked to remain unnamed.
An official from the labor ministry said the government cannot dissuade an employer from pursuing a damage suit when losses are too large.
The metal union to which the subcontract workers belong reportedly has a budget of 59.4 billion won for this year, which comes to 196 million won per day. The court fining of 3 million won so far has worked as little threat to end the strike.
Authorities, in turn, have begun to play hardball. State-lender Korea Development Bank is said to have floated the idea of letting DSME go bankrupt.
DSME’s debt ratio hit 546.5 percent as of March 31, 2022, jumping from 390.7 percent at the end of 2021. If not for rollover or additional rescue from the state lender, the shipbuilder would go bankrupt as its debt ratio exceeds 400 percent.
The shipbuilder reported an operating loss of 470.1 billion won in the first quarter after incurring 1.75 trillion won in operating loss and 1.7 trillion won in net loss for the full year of 2021. Cumulative net loss over the last 10 years amounted to 7.7 trillion won.
DSEM has been under state management since 2000, receiving bailouts of 11.8 trillion won amid a lengthy slump in the shipbuilding industry.
The Korean government planned to merge the nationalized shipbuilder with Hyundai Heavy Industries but it flopped due to the opposition from the antitrust authority of the European Union.
By Choi Seung-gyoon, Kim Hee-rae, Moon Gwang-min and Cho Jeehyun
「造船業好況期に大宇(デウ)造船海洋は最悪の状況を迎えた」。
19日慶尚南道巨済(キョンサンナムド・コジェ)の大宇造船海洋玉浦(オクポ)造船所。船舶建造に必要な足場を設置・解体する下請け企業A社所属の労働者のイさんがした話だ。イさんは「会社が来月に廃業することになった」と虚しい表情だった。造船所で20年にわたり働いてきた彼は「造船不況期をどうにか耐えてきたが突然のストのせいで…」と言葉を続けることができなかった。
A社は造船業労働者が働けるよう作業場に踏み台を設置・解体する仕事を請けおっており、造船所内のほぼすべての工程に投入される。ところが先月2日に大宇造船海洋下請け企業労組である民主労総金属労組巨済(コジェ)・統営(トンヨン)・固城(コソン)造船下請け支会がストに入ってから元請けである大宇造船海洋から受注する作業量が急減した。A社は仕事が減ると、10人がすべき仕事を13人~15人で分け勤務時間も減らした。だが廃業が予告された8月からは仕事が最初からゼロになったという。
今回のスト過程で造船下請け支会の組合員7人が船舶4隻を同時に建造できる世界最大規模の作業場である1番ドックを不法占拠し、この日まで座り込みをしながら48日にわたり造船所のドック稼動率が半分に落ちた。このため船舶の先行・後行工程に支障が生じ造船所が事実上まひした。
当初A社は造船業不況の余波で経営難に陥っていた。それでも昨年から造船業受注が回復して今年下半期からは会社の事情もそれなりに良くなると期待した。だがスト後にこれ以上会社を維持しにくい状況に直面した。会社代表が今月の賃金支払いのため私費で7000万ウォンを使ったが赤字が7億ウォンほど貯まり廃業手続きを踏むことになった。
A社社員のヤンさんは「これまで持ちこたえただけにそろそろ回復するかと思った。8月には作業量が増えると期待した。週末に日雇い仕事までしながら耐えてきたが、結局ストが長引き職場まで失うことになった。くやしい」と話す。
A社の代表は「現場職・事務職140人の雇用継承のため八方手を尽くしているが、会社の売却先が見つからない」と話す。
今回のストがさらに長引けば110社以上ある大宇造船海洋の下請け企業が相次ぎ倒産するという懸念も出ている。これら下請け企業従事者は1万1000人に上る。中央日報の取材を総合すると、現在まで廃業したり廃業を予告した下請け企業は7社だ。スト後の先月30日に3社が廃業し、7月末と8月初めに4社が廃業する予定だ。
こうした状況から造船下請け支会に加入していない他の下請け労働者からはストを支持するより恨む声が出ている。
廃業を前にしてA社従業員のヤンさんは「150人余りがストに参加した造船下請け支会が1万人を超える大宇造船下請け労働者を代表することはできない。自分たちが生きようと他の下請け労働者の命を人質にして交渉するな」と話した。
地域商圏でも今回のスト長期化を懸念する声が出ている。大宇造船海洋に近い玉浦市場には「長期間のストで地域経済が破綻する!」などスト解決を促す地域商人会の垂れ幕が掲げられている。大宇造船海洋は19日基準でスト長期化により発生した売り上げ損失5700億ウォンを含め7100億ウォンを超える損害をこうむったと明らかにした。
大宇造船海洋下請け労組のストが18日で47日目に入った。裁判所が座り込む組合員に対し退去命令を下し、協力業者労使と元請けである大宇造船海洋労使などが交渉テーブルに就いたが、事態は依然として解決の糸口を見いだせずにいる。
昌原(チャンウォン)地裁統営(トンヨン)支院は最近大宇造船海洋側が民主労総金属労組巨済・統営・固城造船下請け支会のユ・チェアン副支会長を相手取り起こした集会とデモ禁止仮処分申請の一部を認めた。裁判所はユ副支会長が退去しなければ使用側に1日300万ウォンずつ支払わなくてはならないという命令も下した。
ユ副支会長は先月22日から建造中である原油運搬船(VLCC)船舶の1立方メートルほどの構造物に入って出入口を溶接した後に座り込んでいる。また別の組合員6人は船内の高さ15メートルの欄干に上がって座り込みを続けている。
15日に下請け労組が賃金・賞与金折衷案を提示したが、使用者側と大宇造船側は先に座り込みを終えるべきとの立場だ。大宇造船関係者は「まだ進展した内容はない」と伝えた。
下請け組合員は先月2日から賃金30%引き上げと労組専従者の活動保障などを要求して座り込んでいる。昨年の賃金実受領額が2014年より31.7%減ったという実態調査が根拠だ。
スト長期化で損失は雪だるま式に大きくなった状態だ。産業資源部によると15日基準でストにともなう累積損害額は5700億ウォンに達する。産業通商資源部の李昌洋(イ・チャンヤン)長官は最近記者らと会い「現在船舶3隻の進水・建造作業が中断されている。大宇造船は毎日259億ウォンの売り上げ損失と57億ウォンの固定費損失が発生していると推測される」と話した。
この日大宇造船海洋は18~19日に570人ほどが休業に入ると明らかにした。ドック占拠の余波で工程が止まり休業するほかない状況だと説明する。
ここに労組内での対立の兆しまで見られ状況はさらに混乱している。元請け労組である金属労組大宇造船支会所属の組合員の一部が上級団体である「金属労組脱退」を案件として総会招集を要請した状態だ。大宇造船支会関係者は「協力会社労組(下請け支会)ストが長期化し直営労組まで大きな被害を受けている。こうなれば共倒れになりかねないという内部の雰囲気が大きくなり総会招集要求が寄せられたもの」と話した。
韓悳洙(ハン・ドクス)首相が14日に厳正対応の方針を明らかにしたのに続き、経営界も下請け労組を圧迫し始めた。韓国経営者総協会はこの日声明を通じ「(下請け労組は)業務に先に復帰した後に対話を通じて問題を解決しよう」と促した。続けて政府には「公権力執行に出なければならない」という立場を明らかにした。
現場の専門家らは、大宇造船の状況が7年余りにわたる造船業構造調整の結果であり、債権団の管理を受ける赤字企業の宿命だと診断する。造船業界関係者は「いまの手持ち工事量はほとんど1年半前に受注したもの。当時は船体価格がいまより30~40%低かった」と話した。続けて「昨年末から厚板など原材料価格が大幅に引き上げられ、工事代金を引き上げられる状況ではない」と付け加えた。元請け業者でも有給休暇、残業手当の支給がほとんど消えたとも伝えた。
工事代金を協力業者が望む通りに引き上げることもできない状況だ。大宇造船は昨年売り上げ4兆4800億ウォン、営業赤字1兆7500億ウォンを記録した。1-3月期にも4700億ウォンの営業赤字を出した。その上債権団の管理を受ける大宇造船は資金管理が他の会社より厳格だ。
造船業は人材不足でも苦しんでいる。韓国造船海洋プラント協会によると造船所勤務人材は2014年末の約20万3000人から今年5月には9万2000人まで急減した。生活苦に陥った溶接工や塗装工の多くが首都圏の建設現場に移ったという。
Nearly eight years after all work stopped at the Dalian shipyard, one of the last pieces in the long-running bankruptcy of STX has been sold. Chinese officials reported that they completed the auction of the remaining assets of STX Dalian Shipbuilding, which had been the largest foreign investment in the Chinese shipbuilding industry.
Hengli Heavy Industry Group Co., a subsidiary of Hengli Group, was the successful bidder for the shipyard with reports indicating that they paid $257 million for the assets. Hengli is said to be the second-largest private enterprise in China with diversified interests including large operations in the refining and chemical industries. The company is reported to have shipbuilding and marine heavy tool manufacturing interests but it was unclear if they planned to open a commercial shipyard on the site at Changxing Island. Chinese media reports said the company plans to establish a “high-end port equipment manufacturing base.”
The STX shipyard opened in 2006 and was widely promoted as part of the industrial development of Changxing and Dalian. At its peak, it employed 30,000 people before beginning to experience financial troubles in 2012. The downturn in the global shipbuilding industry led to financial problems for all of the South Korean company’s operations and by 2013 there were reports that the company was exploring the sale of assets possibly in Finland, France, and China. Chinese tried to raise additional capital for the Dalian shipyard.
Bankruptcy proceedings for the Dalian shipyard were initiated in 2014, a year before STX collapsed. The Chinese yard sought court permission to restructure and reorganize, laying off 10,000 people while losing several shipbuilding orders. In March 2015, however, the yard was declared bankrupt with reports saying China was selling off the company in pieces. The company was said to have debt of $3.2 billion.
Dalian Shipbuilding Industry Company was interested in acquiring the main shipyard facility but the deal was blocked by its parent company. After that, China attempted to auction off the STX Dalian facility with as many as 10 auctions failing to find a buyer for the facility. The shipyard has remained idle since 2015.
The sale of the shipyard in China comes a year after South Korea's state-owned bank completed the sale of the company's South Korean operations. Two South Korean investment firms acquired the company for just over $200 million and relaunched the shipyard as K Shipbuilding. The company's other assets, including the yards in France and Finland, had been sold several years earlier. At its peak, STX, which was started in 1967, had been the world's fourth largest shipbuilder and the first to have an extensive network of yards ranging from Europe to Asia.
中国船社がフィリピン人船員の起用を積極化しているようだ。中国人船員の賃金上昇が顕著なためとみられ、フィリピンなど他国の船員に切り替えることで、船舶管理費用を抑制する狙いだ。中国船社によるフィリピン人船員の起用に拍車がかかれば、同国人船員の採用競争が激化する可能性もあるため、日本の海運関係者も中国船社の動向を注視している。
フィリピンに駐在する海運関係者によると、中国の船舶管理会社などがフィリピン人船員を採用する動きを活発化させている。
国際海運会議所(ICS)によると、中国はフィリピン、インドネシア、ロシア、ウクライナと並ぶ船員の5大供給国の一つ。船舶職員に限れば中国は世界最大の供給国で、部員の供給もフィリピンに次いで多い。
ただ、経済発展に伴う陸上の賃金上昇につられる形で、中国人船員の賃金も上昇基調で推移。「中国人から他の国籍の船員への配乗替えは加速している」(船舶管理関係者)
別の船舶管理関係者は「今のところフィリピン人船員の確保が難しくなるなどといった影響は出ていない」と述べた上で、将来的にフィリピン人船員の採用競争激化に懸念を示した。
一方、ロシアによるウクライナ侵攻を巡り、ウクライナ人船員の代替供給国としてフィリピンも挙げられているが、フィリピン人船員への切り替えの動きは一部にとどまっているようだ。
A district court judge in Delaware imposed a $3 million fine and five-year probation on Greek tanker company Liquimar Tanker Management and its vessel the Evridiki during the sentencing hearing on a MARPOL case dating from 2019. The company and the chief engineer were convicted in December 2019 on charges of deliberating concealing pollution, but during the sentencing hearing on Thursday, government prosecutors provided new evidence implicating at least three senior shoreside employees in the efforts to deceive U.S. Coast Guard inspectors.
“Ocean outlaws and polluters such as these will continue to be vigorously prosecuted to the full extent of the law,” said Assistant Attorney General Todd Kim for the Justice Department’s Environment and Natural Resources Division after the sentencing hearing.
The case stems from a March 2019 inspection of the Liberian-flag crude oil tanker Evridiki (167,294 dwt) conducted by the U.S. Coast Guard while the vessel was anchored in Delaware Bay. During the inspection of the tanker that was built in South Korea in 2007, the ship’s Chief Engineer, Nikolaos Vastardis, tried to deceive Coast Guard inspectors regarding the use of the ship’s oily water separator and oil content meter. The jury found Vastardis had used a hidden valve to trap fresh water inside the sample line so that the OCM sensor registered zero parts per million concentration of oil instead of what was really being discharged overboard. When the Coast Guard opened the OWS, they found it was inoperable and fouled with copious amounts of oil and soot.
During the 2019 trial, the Coast Guard showed evidence taken from analyzing historic data recovered from the machine’s memory chip to prove that the meter was being tricked. Vastardis appealed the conviction challenging U.S. jurisdiction over foreign vessels but the conviction was upheld in December 2021.
Government prosecutors provided new evidence on Thursday showing that shoreside staff assisted by creating fake certificates and fake seals sent to the vessel by email on documents attesting to the calibration of the meter and proper testing of pressure relief valves for the cargo. A fake certificate was used during the inspection and the Coast Guard said that Vastardis was specifically asked about the validity of the certificate.
Referring to the forged documents as the “elephant in the room” that the defendants asked the judge to ignore, federal prosecutors told the court that the companies' “failure to address, let alone mention this willful misconduct, demonstrates that these defendants are willfully blind if not completely unrepentant.”
They demonstrated to the court that the documents had been faked based on data found on the device. They showed that the meter was not energized on the date that the fake certificate claimed the meter was calibrated. Similarly, the certificate for the testing of the pressure relief valves was dated on a day when the cargo tanks are full. The USCG said it is impossible to test the value when the vessel is loaded with cargo.
The U.S. Department of Justice continues to prosecute MARPOL violations. Over a 20-year period since the 1990s, it was reported that they won convictions against more than 140 shipping firms.
ロシアに対する金融制裁で建造代金が支払えず
大宇造船海洋は、ロシアに対する西側諸国の金融制裁により、建造代金の受け取りが困難になった1隻の液化天然ガス(LNG)運搬船についての契約を取り消した。
大宇造船海洋は18日、LNG運搬船1隻の建造の中間前払金が期限内に入ってこないため、その船舶を発注した欧州の船主に解約を通知したと公示した。造船業界の説明によると、大宇造船海洋が述べた欧州の船主はロシア国籍。ロシアとウクライナの戦争に伴う金融制裁のせいで、建造代金を契約どおりにやり取りすることが難しくなったのだ。
大宇造船海洋はその船主と、同じ仕様の3隻のLNG運搬船の建造契約を結んでいた。契約金の総額は1兆137億ウォン(約1030億円)で、今回の取り消しで契約金額は6758億ウォン(約689億円)に減った。
業界によると、今回契約が取り消された1号船は、すでに鋼材の切断(Steel Cutting)作業を終えてブロック製作段階に入っていた。船舶は鉄板を切って船の形につなぎ合わせてブロックを作り、次にそのブロックをつないで完成する。残りの2~3号船も1~2カ月の時差で工程が進んでいた。
大宇造船海洋は現在、船主側に解約を通知しただけで、作業の進んでいるLNG運搬船の建造を中止するかどうかはまだ決めていないという。造船業界の関係者は本紙の電話取材に対し「造船会社側には金を受け取る適当な方法がない。ロシアに対する金融制裁が続けば、残る2隻の契約も取り消される可能性が高い」と話した。
韓国の造船所はどのくらいロシアからの受注船を持っているのか知らないが、受注した船の数次第では苦しいかもしれない。
Brodosplit the Croatian shipbuilder has filed for provisional bankruptcy as the company looks for a solution to a financial crisis brought on by the EU's financial and banking sanctions against Russian institutions. The largest industrial employer in Croatia, the shipyard and its parent company DIV Group explain that it is not an operational problem but instead a loss of construction financing and an inability to complete a financial bridge solution with the government.
The problem began for Brodosplit early in April as the EU moved to tighten the financial sanctions on Russia and included VTB, a Russian bank and lending network, majority state-owned, in the restrictions. Brodosplit is building two commercial projects for which it required €150 million ($159 million). DIV committed to supplying €30 million and the shipyard took loans from VTB for a total of €120 million. As of March, the shipyard has drawn €82 million from the Russians when the loans were blocked as part of the sanctions. The restrictions imposed on VTB due to the war in Ukraine prevented the payment of the remaining €38 million.
Initially, DIV stepped in to provide additional financial support but they turned to the government proposing a bridge loan to the shipyard to finance the completion of the two ships. DIV says it also became financially overextended supporting the shipyard. Brodosplit reports that work on one of the two projects is nearly finished and they estimate it could be completed with an additional €500,000, while the second project requires approximately €8 million to complete the ship due for delivery at the end of the year.
DIV reports that it has been in intensive talks with the Croatian Bank for Reconstruction and Development (HBOR) to secure a loan for Brodosplit, but that it has not received a response from the government to its proposal. It emphasizes that it is not asking for a subsidy, but instead a loan.
“I hope they didn't give up on us,” a director of Brodosplit told Croatian media over the weekend. “We will survive with or without the government,” he said while saying that the company however would be “crippled,” without the government loan. He emphasized that some workers have not been paid in weeks and while there had been promises of assistance from the Agency for the Protection of Workers, nothing had been received. About 600 employees were continuing as of last week to work at the shipyard, mostly on coastal patrol boats for the Ministry of Defense and another new building, but most of the 1,500 employees have been furloughed since production ceased in April.
There had been a rumor that a solution had been found with the government, but last week the finance minister said that the situation was still being analyzed for the technical, legal, and financial implications of guarantying the shipyard’s request. The shipyard notes that it was profitable in 2021, but that its financial situation is complicated by EU restrictions. The yard was privatized by the government to meet EU restrictions when the country entered the EU in 2013 and the government is now unsure as to the level or form of support it is permitted to provide.
In April, suppliers to the company that had not been paid asked the court about the terms of filing a bankruptcy claim. The shipyard and its parent company however filed a pre-bankruptcy petition seeking to delay any actions by the creditors as they cited claims against Croatia and the ongoing discussions with the government. Last week the company was forced to refile due to an omission on the first filing while the minister said the court filing was complicating an already complex situation.
Brodosplit is not the only maritime company that found itself caught in the impact of the sanctions. In Norway, Havila Kystruten had arranged to lease its cruise ships from the Russian finance company GTLK, which was also included in the April sanctions by the EU. Havila’s first cruise ship, Havila Capella, was temporarily laid up because of issues related to its insurance and ownership by the Russian company, while the shipyard provided a bridge loan so Havila could take delivery of its second cruise ship. The company is working on refinancing while also seeking exemptions from the Norwegian government.
A Russian shipyard is now unable to continue building ships or repair vessels as they do not have enough money to do so, according to the Ukrainian Intelligence Directorate (GUR). The shipyard in question, Vostochnaya Verf JSC, located in Vladivostok, is also experiencing supply chain interruptions of foreign components due to economic sanctions imposed on them in the west, which leaves these yards highly useless.
The Ukrainian Intelligence Directorate allegedly obtained a Russian Defense Ministry report outlining the hardships Russian shipyards were experiencing. One particular shipyard in Vladivostok could not complete a government order of two tankers and two missile boats worth 35 billion rubles due to hardships brought upon by the sanctions. They also could no longer maintain and repair Russian ships.
Furthermore, the lack of foreign components severely hampered the construction of new vessels. Such components include steering columns, navigation systems, naval warfare systems, charges for naval artillery shells, and radio stations.
“In particular, the AT “Vostočnâ Verfʹ” (Vladivostok/Vostochnaya Verf ) has to fulfill state orders for a total amount of 35 billion rubles. Including the construction and supply of two marine tankers, two small rocket ships, two moving maritime docks, repair and service of ships and boats of various types,” the Ukrainian intelligence agency claimed on Facebook.
According to them, all work has been “suspended” in the shipyard since the start of April 2022. Additionally, the majority of the staff have been “dismissed,” and the execution of contracts for orders has been canceled. The Russian shipyard has reportedly begun the bankruptcy procedures. These claims were not independently verified; however, they did post the documents that supposedly put some legitimacy to the claim. The authenticity of the documents could also not be verified as of writing.
The documents posted online supposedly indicates all the shortages of foreign components the shipyard is experiencing and that they cannot find Russian or Asian substitutes for the imported components. The production of powder charges for marine artillery was also stopped due to the shortage of parts and foreign components.
“The Russian military-industrial complex remains dependent on imported high technologies. Without the supply of which, Russia is unable to continue the production of modern weapons,” the Facebook post read.
Vostochnaya Verf JSC is the main supplier of ships for the maritime border forces of the Russian Navy. Specifically, according to their website, they supply to the Far East Fleet and Pacific Fleet of the Russian Navy through Rosoboronexport.
This development comes after Russia’s flagship of the Russian Black Sea Fleet, the Moskva, was allegedly sunk by the Ukrainians with two Neptune anti-ship missiles. However, the Russians claim that a fire broke out on board, and the fire had made ammunition explode, which led to its sinking. While they also claimed that the ship was still buoyant, Turkish and Romanian authorities reported that the cruiser had sunk around 0248 hours.
Along with the loss of the Moskva are the loss of its crew and captain. It was reported that Captain 1st Rank Kuprin Anton Valerievich had died during the explosion. The fate of the Moskva’s crew remains shrouded in mystery, with some intel suggesting that the majority of the sailors died with their captain and with the Russians claiming that there are many survivors.
The Russian government released a video allegedly showing survivors of the Moskva incident. It was shown that the Commander-in-Chief of the Russian Navy, Admiral Nikolay Yevmenov met up with the crew of the Moskva in Sevastopol. The video appears to be carefully scripted and edited.
SOFREP believes that the video might be fake as there is no way of knowing whether those shown in the video are the actual crew of the Moskva. The Russians could easily round up sailors(on a naval base) and have them stand-in for the lost crew. The video also purports to show Captain Kuprin(who is not identified in the video by Russian media), who is widely believed to be dead. However, SOFREP Editor-in-chief Sean Spoonts pointed out that the facial features of Kuprin, such as a mole on his left jaw, could be easily reproduced with a makeup pencil and should not be considered certain proof. Russians have a history of using political decoys, and could certainly use one for Captain Kuprin for whom there are few photos to use in comparison.
With all of these being mentioned, it is also important to emphasize that the Russians have been experiencing difficulty in supplying military equipment to replace losses in the field. For example, SOFREP was one of the media outlets that was first to report on Uralvagonzavod (Russia’s primary tank manufacturer) halting production due to the lack of foreign-made components. This makes it highly probable that its shipbuilding capabilities had also suffered the same problem.
It is not only the equipment production that has been hampered by the sanctions. Reports that the entire Russian defense industry has been taking a hit due to the sheer amount of Western sanctions. It was reported by the Ukrainian intelligence agency that the Zircon hypersonic cruise missile’s production was delayed due to a backlog of production demands and the loss of foreign components, as well as the rising cost of raw materials.
Due to these production stoppages, the Russians have allegedly been restoring old military vehicles to replace losses in the invasion. Furthermore, corruption within the factories and industries has hobbled the refurbishment because unknown individuals have stolen parts and entire engines. Below is a screen cap of Ukrainian troops inspecting captured Russian military explosives to discover that they are just woodblocks inside the packaging. This is what is being delivered to Russian troops in the field.
“Optical devices and electronics containing precious metals were stolen from the combat vehicles,” the GUR reported. The 4th Tank Division‘s backup tanks, the division that was obliterated in Ukraine, were reportedly completely dismantled, and no engines were found in the tanks.
With these developments, it is reasonable to question whether Russia can still sustain its offensive in the Donbas region, which was said to be launched earlier today. With thousands of their troops killed, hundreds of their military aircraft and vehicles destroyed, and their production chain halted, the Russians may be risking all they have on the supposed “liberation” of Donbas.
ウクライナ戦争でロシア産原材料の需給が厳しくなった上、新コロナ19による中国地域の封鎖まで重なり原材料の大混乱が続いている。原材料の需給難に加え価格まで急騰し輸出採算性まで急悪化している。
鉄鋼価格の急騰は造船にも影響
造船協会の関係者は「今年4月、厚板価格が史上最高値を更新し国内造船所の収益が大幅に悪化した」とし、「厚板価格の引き上げ分に対して積み立てなければならない損失充当金が増える場合、会計上の営業損失は4兆4000ウォン(円貨約0.1円)に達する」と述べている。
隣国造船海洋事業の報告書によると厚板価格は2020年1トン当たり66万7000ウォンから2021年1トン当たり112万1000ウォンへと2倍近く急騰している。
現代重工業傘下の造船3社は昨年、造船事業で鋼材購入だけで2兆6454億ウォン。売上原価のうち鋼材購入費が占める割合は14%程度と推算されている。
問題は造船会社が船舶を受注してから実際に建造に至るまで2年半ほどかかるという点。昨年、建造を終えた船舶は主に2019年の不況期の受注であるため相対的に規模が小さい。以後、受注活況を勘案すれば今後、建造される船舶が増え、このため厚板価格の上昇による負担がさらに大きくなる。
現代重工業系の船舶の受注残高は2019年末の23兆3481億ウォンから昨年末32兆9688億ウォンへと41%も増加している。
ポスコなど鉄鋼会社と国内造船会社は今年、厚板価格の交渉を進めている。
鉄鋼会社は鉄鉱石や有煙炭価格の高騰によるコスト上昇を考慮し厚板供給価格を前年比10%水準まで引き上げるべきだという立場だ。一方、造船会社各社は2%以内の引き上げを要求し平行線をたどっている。
以上、
<世界から取り捲る隣国造船業界、世界一の受注量>
隣国の造船会社が今年第1四半期、全世界の船舶発注量の半分ほどを独占する受注を爆発させた。
2021年期の3大造船Gは軒並み造船部門で大赤字を計上しているが、今後、船価上昇による業績改善も続くと見ている。
今年、第1四半期に隣国の造船会社が「驚きの受注」を申告し期待感も高まっている。造船会社は年初に提示した受注目標の40.9%を第1四半期にすでに達成している。
企業別では現代重工業が26%、現代尾浦造船が42%、現代三湖重工業が90%(以上3社は現代重工業G)、サムスン重工業が25%、政府系銀行傘下の大宇造船海洋が47%などの達成率を記録している。
これら造船会社の第1四半期の受注規模は152億ドルに達する。世界の新規発注量の49%を隣国造船会社が占め2015年以降7年ぶりに第1四半期の受注で中国を抜いた。
専門家たちは受注実績とともに先価格の上昇に注目すべきだと指摘。
収益性の面でも国内造船会社が有利な位置についたとみている。国内造船所の今年第1四半期の新規受注総トン数は昨年第1四半期比減少したが、受注金額は同水準を維持している。
業界では造船会社が受注残高のおかげで攻撃的な受注に乗り出す代わり船価の引き上げに集中しているという分析が出ている。実際、コンテナ船が40%、LNG船の新造船価格が22%上昇したという。
英クラークソン・リサーチが発表する新造船指数も昨年、第1四半期130から今年第1四半期158まで上昇している。
クラークソンによると韓国は今年1~3月、全世界の船舶発注量920万CGT(259隻)の49.7%にあたる457万CGT(97隻)受注して世界一。
全世界の受注残量は3月末基準で9,471万CGT、うち隣国は3,238万CGTで、2019年下半期から2021年までに受注した2,826万CGTが受注残として残っている。
こうした船舶の建造に厚板価格や機械類、諸材の高騰により、2,019年上半期までに受注した分で前期は大赤字となり、それ以降2020年までに受注した船舶が今年完成してくることから今期も大赤字が予想される。
大損しなくて良かったと思っているだろう。ウクライナとロシアの戦闘前に受注した船舶の資材高騰が今後の心配となる可能性は高い。
サムスン重工業が、原油ボーリング船(ドリルシップ)4隻を韓国内の私募ファンド(PEF)運用会社キュリアスパートナーズに1兆400億ウォン(約1040億円)に売却する。悪性在庫を処分して財務構造を改善し、自律走行船舶など未来型船舶に投資する財源を調達したとみられる。キュリアスは最近、原油高で取引が再開され始めたドリルシップに先制投資した後、適時に売却して収益を上げる計画だ。造船業界では、今回の取引が資本市場主導型の構造調整の成功モデルとして定着するかどうかに関心が集まっている。
韓国の造船業界によると、サムスン重工業は21日、取締役会を開き、ドリル14隻をキュリアスに売却する案件を承認した。 契約は1兆400億ウォン(約1040億円)で、このうちサムスン重工業がPEFに再出資する5900億ウォン(約590億円)を除けば会社に流入する現金は、4500億ウォン(約450億円)だ。
サムスン重工業「厄介者」ドリルシップ売却で未来船舶投資へ
ドリルシップは、深海で原油·ガスボーリング作業ができる船舶形態の設備だ。1隻当たりの建造費用が少なくとも5億ドルに達する大型プロジェクトだが、サムスン重工業にとっては、これまで悩みの種だった。2014年初め、1バレル=100ドルを上回っていた国際原油価格が同年下半期から40ドル台に暴落し、船主らが相次いでドリルシップの引き渡しを拒否した。
数千億ウォンを投入して乾燥したドリルシップを造船所に凍結したことで生じた損害は、財務諸表に貸倒れ充当金として反映された。 メンテナンス費としても毎年、数百億ウォン(数十億円)を投入しなければならなかった。サムスン重工業は2020年に,、昨年1兆3120億ウォン(約1312億円)の営業損失(連結基準)を記録したが、引き渡していないドリルシップが大規模損失の原因の一つとして挙げられた。
雰囲気が反転したのは、最近、国際原油価格が100ドル台に上昇したためだ。原油ボーリング市場が蘇り、ドリルシップの取引が再開されるだろうという期待が高まっている。サムスン重工業にエネルギー企業の買収に関する問い合わせが入り始めた。問題は、船舶引渡しが再開されても財務諸表に反映されるまで時差があるという点だった。世界的な造船会社各社が、未来先端船舶の開発に我先にと乗り出している状況下で、研究開発(R&D)財源の確保も急務だった。 船舶を直ちに流動化する案を悩んだ理由だ。
キュリアスは、原油価格が最低70ドルラインを維持するものと予想し、取引に積極的に乗り出したという。主要エネルギー会社が、深海油田探査開発を再開し、高仕様ドリルシップの需要が増えているだけに、すでに乾燥している三星重工業のドリルシップに「ラブコール」が続くものと予想した。
キュリアスは、企業の構造調整を専門とするPEF運用会社だ。2020年には、破産の危機に陥ったHSG城東朝鮮に1500億ウォン(約150億円)を投資して正常化した後、今年3月に投資金を回収した。
徳島県鳴門市の造船会社「神例造船株式会社」が自己破産申請の準備に入ったことが明らかになりました。
神例造船株式会社 概要
概要を表示
神例造船株式会社について
神例造船株式会社は1872年創業。同社は、タンカーや貨物船、海底ケーブルの敷設船など中型船の製造事業を主力に展開していたほか、橋梁や水門等の鋼構造物を手掛けていました。
しかし、海外との競争激化に加え、2020年の新型コロナウイルス感染拡大による影響で、受注が減少し業績が悪化。回復の見通しが立たず、資金繰りが限界に達したため、事業を停止し、今回の措置となりました。
負債総額は約15億円の見通しです。
負債総額推定15億円
帝国データバンク徳島支店は、県内造船大手の「 神例かんれい 造船」(鳴門市里浦町、神例哲也社長)が事業を停止したと発表した。事後処理を弁護士に一任しており、徳島地裁に自己破産を申請するとみられる。負債総額は推定約15億円。
徳島支店によると、神例造船は明治初期の創業。タンカーや貨物船、海底ケーブル敷設船などの製造を手掛けてきた。
2011年12月期には約95億円の売り上げがあったが、リーマン・ショックの影響で受注が減り、海外勢との競争激化により業績が低迷。18年12月期から3期連続で赤字に転落していた。
徳島県内造船大手で明治期創業の老舗・神例造船(鳴門市)が事業を停止し、近く破産申し立てを行う予定であることが11日、分かった。負債総額は、東京商工リサーチ徳島支店は調査中とし、帝国データバンク徳島支店は15億円規模とみている。
神例造船は1872年ごろに創業し、1961年に法人化した。東京商工リサーチ徳島支店によると、従業員は73人。3千~5千トンクラスの中型船を中心に最大1万5千トンまで建造可能な設備を有し…
状況の変化や時間の経過で、何が良いか悪いのか変わってしまうと言う例だと思う。
国際社会のロシアに対する金融制裁が本格化し、10兆ウォン(約952億円)にのぼるロシアの受注物量を保有する韓国の造船会社が、非常事態に直面している。特に船舶を発注したロシア船社およびエネルギー会社が、取引制限対象の「ブラックリスト」に載ってから引き渡し遅延などのリスクが現実のものとなっている。
13日、韓国の造船業界によると、サムスン重工業は当初、3月に引き渡す予定だったアフラマックス級(中型)砕氷原油運搬船2隻の引き渡し時期を延期するという。発注会社のロシア国営船会社ソブコムフロートが、制裁対象企業リストに上がった上、同日からロシアの主要金融会社が、国際決済網(SWIFT)から排除され、代金を決済する道が閉ざされたためだ。
2019年11月に受注した両船舶の建造代金は1億6000万ドル(約1875億ウォン)だ。このうち、まだ受け取っていない代金が全体の約50%と推定される。船舶建造契約は、全体代金の20%を受け取り、その後の建造段階によって30%を分け与え、完成した船舶を引き渡す際に50%の残金を受け取る「ヘビーテール」方式が一般的だ。サムスン重工業の関係者は「まだ規制初期で契約に及ぼす影響を判断するのは難しい状況」とし「規制の進行状況を見ながらリスクを最小化する案を模索中」と述べた。
引渡しの遅れが現実のものとなり、業界ではロシア受注物量に対するリスクが浮き彫りになっている。サムスン重工業をはじめ、大宇(テウ)造船海洋、韓国造船海洋など韓国の主要造船会社が、ロシア船主から受注した船舶および海洋プラント規模は80億5000万ドル(約9兆7000億ウォン)に達する。企業別では、サムスン重工業が50億ドル、大宇(テウ)造船海洋が25億ドル、韓国造船海洋が5億5000万ドルの順だ。
韓国の造船業界では、すでに本格的な建造に入り、引き渡し時期が1年以内に迫っている船舶がもたらす潜在的なリスクに注目している。証券業界の分析によると、ロシア全体の受注物量のうち、建造が始まった船舶は最高60%レベルと試算される。資材購買費、人件費などに相当な費用が投入されている船舶だ。
ロシアで受注した船舶の大半は、再販売が不可能な特殊船舶という点も造船業界の悩みの種だ。受注船舶の大半は、北極海の凍った海を航海できる機能を備えた液化天然ガス(LNG)運搬船と海洋プラントが占めている。北極海周辺に位置している鉱区から天然ガスを生産したり、移す目的で発注が行われたためだ。
韓国の造船業界関係者は「最近、LNG船市場は超好況だが、砕氷船の需要先は、北極航路を保有するロシアだけ」とし「船舶を他の所に販売するのも難しく、制裁が長期化すれば、造船会社の損失は避けられない状況」と述べた。また別の関係者は「造船業界のロシア受注は、政府の新北方政策に歩調を合わせて行われた部分も大きい」とし「多くの協力業者も絡んだ問題であるだけに、精巧な政策的支援策作りが必要だ」と指摘した。
ファン·ジョンファン
By Shahid FaridiExpress News Service
NEW DELHI: India’s largest drydock Pipavav Shipyard is likely to be sold by March 10 this year at a price that would require the lenders to take a 90-95% haircut. Reliance Naval and Engineering Ltd (RNEL), the present owner of Pipavav Shipyard, has been undergoing Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) since January 2020.
The lenders are currently voting on bids by Hazel Mercantile-Swan Energy consortium and Navin Jindal-owned JSPL. The voting on proposals of these two companies started on February 25, 2022 and is likely to end around March 10, 2022.
Sources said the net present value of Hazel-Swan plan is estimated around Rs 1,200 crore and that of JSPL is around Rs 700 crore. RNEL owes Rs 12,400 crore to lenders. Hence, total recovery for the lenders under the Hazel- Swan plan would be 9.8% and under JSPL plan 5.6%, resulting in a haircut of 90% to 95% for lenders. Sources said some lenders had raised the issue of eligibility of one of the bidders -- Hazel-Swan consortium.
Swan Energy, owned by Mumbai-based businessman Nikhil Merchant, holds 74% stake in the special purpose vehicle set up with Hazel Mercantile to bid for RNEL. According to reports, Nikhil Merchant was a director on the board of the Navi Mumbai Smart City Infrastructure Ltd, which has defaulted on bank loans and those loans have been classified as a non performing asset (NPA) by the banks.
Merchant was on the board of this company from 2015 to till December 2021, and he resigned much after submitting the resolution plan for Pipavav Shipyard. Similarly, the question of eligibility of Minesh Shah, a director on the Board of Hazel Mercantile Limited, was also raised by some lenders. Shah reportedly continues on the board of various companies of HDIL Limited, another wilful defaulter.
US-based private equity firm Cerberus is set to buy the Philippines’ insolvent Hanjin Subic Bay shipyard in a $300m deal, reported Reuters.
The shipyard is located at a former US navy base near to the South China Sea.
Its strategic location is said to make it appealing to Chinese state-run companies, which caused national security concerns for defence chiefs in the Philippines.
Around eight foreign firms, including two anonymous Chinese entities, previously showed interest in purchasing the shipyard in 2019.
The Subic Bay shipyard provides access to the disputed South China Sea, where China has been increasing its military actions to control trade routes.
Prior to defaulting on $1.3bn of loans in 2019, the shipyard was operated by Hanjin Philippines. It owes $412m in debts to various Filipino banks.
Some parts of the shipyard will be leased to locators, reported Reuters, citing facility administrator Rosario Bernaldo.
The Philippines’ Navy is also planning to lease a third of the 300ha shipyard from Cerberus for its own base, according to a source familiar with the matter.
According to another source, the deal is anticipated to be completed by 15 April, and the shipbuilding facility is scheduled to restart operations later in the year.
Written by Francesca Webster
The Bremerhaven Lloyd Werft Shipyard sold over the course of this weekend to Bremen contractor Kurt Zech and the Bremerhaven steelwork contractor Thorsten Rönner. German media Butenunbinnen reported that the contract was signed late on 4th March and Dr Christoph Morgen, Insolvency Administrator of MV Werften Holdings Limited and Owner of Lloyd Investitions- und Verwaltung GmbH (holding company), commented on the 5th; "For two days we conducted intensive negotiations with different bidders," it said. "Both concepts were presented to us in detail. In the end, the Rönner-Zech Group was awarded the contract."
The other major bidder for the shipyard was yacht builder Al Seer Marine from the United Arab Emirates. Butenunbinnen reported that this had initially been the favoured investor, while the Bremerhaven Lord Mayor Melf Grantz had spoken out in favour of the Rönner-Zech Group.
At the time of its bankruptcy, the Lloyd Werft shipyard employed 300 employees and the future of those jobs under the new ownership is currently unknown. The shipyard filed for bankruptcy on 10th January and cited financial complications with the Genting Group that owned both MV Werften and Lloyd Werft. It was reported at the time of the announcement that Rönner had already expressed an interest in the shipyard.
By ファン·ジョンファン
ウクライナ危機を受けた対露金融制裁が本格化し、ロシアからの受注を増やしてきた韓国造船会社の悩みが深まっている。長期化する場合、10兆ウォン(約9700億円)に達するロシア受注物量に対する引渡しの支障や、契約の取り消しにつながりかねないためだ。
関連業界によると、韓国造船海洋、大宇造船海洋、サムスン重工業など韓国の主要造船会社が、ロシアの船主から受注した船舶·海洋プラントは、80億5000万ドル(約9兆7000億ウォン)に上る。1月末現在で、3社が積み上げた仕事(受注残高)978億ドルの約8%だ。
企業別では、サムスン重工業(50億ドル)、大宇(テウ)造船海洋(25億ドル)、韓国造船海洋(5億5000万ドル)の順だ。 3社が受注した船舶の大半は、北極海の凍った海を航海できる機能を備えた液化天然ガス(LNG)運搬船だ。2010年代初期から推進されたロシアの北極航路開拓事業によって、ロシアのエネルギー会社ノバテックや大手海運会社ソブコンフロートなどが発注した物量だ。
造船業界は、ロシア金融会社が国際銀行間通信協会(SWIFT)からの締め出され、国際社会の金融制裁が長期化する場合、発注取り消し、引渡し拒否などリスクが現実化すると見ている。ノバテックなどエネルギー会社に資金を提供する現地の金融会社が制裁対象になり、ロシア産の原料の輸出も制裁を受け、これらの会社が推進していた大規模なLNGプロジェクト自体が揺れているからだ。
サムスン重工業が建造した耐氷原油運搬船
受注した船舶の多くが、北極海という特殊な環境に合わせた船舶であることもリスク要因だ。契約が取り消され、該当船舶が在庫として残る場合、他の船社に売らなければならないが、一般航路を運航する船社には、耐氷·砕氷などの特殊機能は必要ない。
全体の船舶代金の50%以上を引渡しの時点で受け取る契約構造も、韓国の造船会社としては心配の種だ。造船業界関係者は「まだ制裁の影響が現実化していないが、最悪の場合も念頭に置いて動向を注視している」と述べた。
一方、最近、LNG船を中心に船価上昇傾向が目立つ状況で、建造に入っていない契約物量の取り消しはむしろ「好材料」になる可能性があるという分析も出ている。KTB投資証券の分析によると、3社の全体ロシア受注残高のうち半分ほどが建造に入っていない24年以降の引渡し分だ。
英国の造船・海運市況専門会社のクラークソン・リサーチによると、2月末現在、17万4000㎥級LNG船の平均価格は2億1800万ドルで、ロシア発の受注が活発だった2020年に比べ20%以上上昇した。 契約が取り消され、残される建造空間(スロット)を高めた船価を反映した新たな契約で満たし、受注残高全般の「質」を高めることができるという。KTB投資証券のチェ·グァンシク研究員は「24-25年は短納期スロットとなり、好材料と悪材料が入り混じっている」と分析した。
名村造船所は18日、子会社の佐世保重工業(長崎県佐世保市)が名村造船所を割当先とする債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)を3月29日に実施すると発表した。経営再建中の佐世保重工業は債務105億円を圧縮し、業績回復を急ぐ。
佐世保重工業は旧日本海軍の設備を継承して1946年に創業した名門だ。2014年に名村造船所の傘下に入りタンカーなどを製造してきたが、中国・韓国メーカーとの競争激化で経営が悪化。17年3月期から赤字が続き、21年3月期に債務超過に陥った。
佐世保重工業は効率化のため21年に約250人の希望退職を募ったほか、22年1月、ギリシャの船会社から受注したバラ積み船の引き渡しを最後に新造船事業を休止した。今後は船舶修繕事業に軸足を移し、客船など幅広く受注する。
造船業界を取り巻く経営環境は厳しい。名村造船所は22年3月期の最終損益が80億円の赤字見通し。最終赤字は3期連続となる。20年にはサノヤスホールディングスが造船事業から撤退を決めている。
安く受注して終わるのか、仕事がなくて終わるのか、チキンレースのように思える。生き残った方が競争が緩和した状況で受注できると言う事か?
現代(ヒョンデ)重工業グループが主力である造船事業で昨年期待以下の実績を収めた。来月の業績発表を控えた大宇(デウ)造船海洋もやはり1兆ウォン台の赤字が予想される。ただ高付加価値船舶の受注が続き、遅くても来年からは業績反転が可能だろうと期待される。現代重工業グループの造船部門中間持ち株会社である韓国造船海洋は7日、昨年売り上げ15兆4934億ウォン、営業赤字1兆3848億ウォンを記録したと公示した。売り上げは前年より4%増えたが、営業損失から抜け出すことはできなかった。現代重工業が8006億ウォン、現代三湖(サムホ)重工業が3072億ウォン、現代尾浦(ミポ)造船が2266億ウォンと子会社が一斉に営業赤字を出した。
他の造船会社も事情は同じだ。これに先立ち先月27日にサムスン重工業は昨年1兆3120億ウォンの営業赤字を記録したと明らかにした。売り上げは6兆6220億ウォンで前年より3.5%減った。業界では大宇造船海洋やはり昨年売り上げ4兆3650億ウォン、営業赤字1兆3011億ウォンを記録したとみている。
不振の原因は明らかだ。新型コロナウイルスによる2020年の受注の崖と原材料価格上昇が悪材料だった。特に昨年は船舶用鉄鋼材の厚板価格上昇が足を引っ張った。昨年上半期に1トン当たり約80万ウォンだった造船用厚板価格は昨年下半期には110万ウォン台まで急騰した。厚板は船舶建造原価の20%ほどを占める。
株価も振るわない。この日の韓国取引所によると、年初から造船3社の株価は平均10.9%下落した。同じ期間の韓国総合株価指数(KOSPI)の下げ幅8.1%より大きい。だが早ければ今年末、遅くとも来年には業界が赤字のトンネルから抜け出すと予想する。何より受注実績が右上がりとなっている。
造船3社は昨年457億ドル相当を受注し、目標額の317億ドルを超過達成した。今年に入ってもこの日基準で韓国造船海洋が34隻、大宇造船海洋が12隻の46隻の建造契約を確保しており受注ラッシュを継続している。
韓国造船海洋の場合、1月の1カ月だけで34隻(37億ドル)を受注し、年間目標の21%を達成した。ただサムスン重工業は現在まで受注実績がない。両社が受注した船舶のうち9隻が親環境・高効率船舶と呼ばれる液化天然ガス(LNG)運搬船だ。こうした受注の朗報が業績改善につながるには最小1年ほどかかる。新たに受注しても1年前後の設計期間がかかり、ヤードで作業を始めてから業績に反映されるためだ。昨年の受注成績が今年の業績に反映されると点も肯定的だ。
NH投資証券のチェ・ジンミョン研究員は「厚板価格上昇による引当金を設定した上に、鉄鉱石価格は昨年の高値に比べ下落した。昨年受注した船舶単価が上昇し造船業種の収益性は今年を基点に改善されるだろう」と予想した。
一方、現代重工業グループの持ち株会社である現代重工業ホールディングスは昨年売り上げ28兆1587億ウォン、営業利益1兆854億ウォンで会社設立以来最大の実績を達成した。特に売り上げは前年の18兆9110億ウォンと比較して48.9%増加した。現代オイルバンクと現代建設機械、現代エレクトリックなど主要子会社好実績を出したおかげだ。
売上高は1兆4800億円で4%増えたが 「通常賃金判決と鉄鋼材価格上昇の影響」 現代重持株は持株会社への転換後、最大の業績 製油業の好業績のおかげで、営業利益1040億円
韓国造船海洋が昨年、1兆3848億ウォン(約1330億円)の営業損失を記録し、前年に比べて赤字に転じた。鉄鋼材価格の上昇と通常賃金敗訴判決による大規模な引当金が設定され、1兆ウォン台の営業損失を記録した。一方、現代重工業持株は精油部門(現代オイルバンク)の好業績のおかげで2018年に持株会社への転換を完了して以来、最大の実績を記録した。
韓国造船海洋は昨年の売上が15兆4934億ウォン(約1兆4800億円)で、前年より4%増加したと発表した。エコ船舶の発注が増加するなど、造船市況が回復に転じたおかげだ。現代重工業の売上げは8兆3113億ウォン(約8千億円)、現代サムホ重工業は4兆2410億ウォン(約4千億円)、現代尾浦造船は2兆8872億ウォン(約2800億円)に達した。3社共に韓国造船海洋の造船業子会社である。
営業利益は1兆3848億ウォンの赤字を記録した。同社は「通常賃金判決および昨年上半期の鋼材価格急騰による引当金の設定」を赤字転換の原因に挙げた。昨年12月、最高裁は現代重工業が定期ボーナスと祝日ボーナスを賃金遡及分に含めるべきだという趣旨の判決を下した。コロナ禍で昨年上半期のグローバルサプライチェーンがまひし、船舶製造の主な材料である鉄鋼材価格も急騰した。
韓国造船海洋はこの日、公示を通じて「最高裁の判決敗訴によって支払うべき賃金総額を推定し、引当金約8400億ウォン(約800億円)を設定した」と明らかにした。昨年第2四半期には原材料価格の引き上げによる工事損失引当金8900億ウォン(約850億円)を策定している。
一方、現代重工業持株は精油業子会社の現代オイルバンクの好業績に支えられ、持株会社への転換後最大の業績を記録した。現代重工業持株は2021年の連結基準で売上高28兆1587億ウォン(約2兆7千億円)、営業利益1兆854億ウォン(約1千億円)を記録した。このうち、現代オイルバンクが売上高20兆6065億ウォン(約1兆9800億円)、営業利益1兆1424億ウォン(約1100億円)を記録し、持株会社の業績を牽引した。原油価格の上昇による在庫効果が拡大し、石油製品に対する需要が回復したことで収益が増えた。
建設機械部門の現代建設機械は、売上高3兆5520億ウォン(約3400億円)と営業利益1818億ウォン(約170億円)を、現代斗山インフラコアは昨年8月のグループ編入後、売上高1兆6782億ウォン(約1600億円)と営業利益373億ウォン(約35億円)を記録した。
現代重工業持株の関係者は「昨年の一回性の費用の反映を通じて不確実性を解消した上、造船や精油、建設機械など主力事業の市況改善が続いており、今年も好業績が予想される」とし、「収益性中心の営業戦略と市場を先導するエコ技術開発などを通じて、安定的な実績を維持できるよう最善を尽くす」と述べた。
コンテナ船の用船料は高騰しているのにタンカーはだめらしい。
中国のエネルギー海運大手の中遠海運能源運輸(コスコ・シッピング・エナジー・トランスポーテーション、漢字の略称は中遠海能)は1月22日、2021年の通期純損益が過去最大の49億2000万~51億2000万元(約882億~917億円)の赤字になるとの業績予想を発表した。
この記事の写真を見る
上海証券取引所に上場する同社の株式は、発表後の最初の営業日となった1月24日の取引開始と同時に売りが殺到。株価はストップ安となり、取引が再開された後場の終値は前営業日比9.91%安の5.09元(約91.2円)で引けた。
注目すべきなのは、赤字の原因は本業ではなく、保有するタンカーの資産価値を一括して減損処理するためであることだ。中遠海能は国有海運最大手の中国遠洋海運集団(コスコ・グループ)の傘下にあり、現時点で141隻を保有する世界最大のタンカー船主である。今回の発表によれば、同社はそのうち94隻について、総額約49億6000万元(約889億円)の減損引当金を2021年決算に計上する。
なお、減損処理の影響を除いた本業の業績も好調とは言えず、辛うじて収支均衡を保っている状況だ。その理由について同社は、「新型コロナウイルス流行の長期化によりグローバルな経済活動が停滞し、石油の需要が抑制された」ためだと説明している。
■巨額減損の根拠に疑問の声も
「2021年は過去約30年間で最も厳しい1年だった。(荷主から受け取る)用船料がタンカーの運航コストを下回る状態が年間の半分以上に達し、VLCC(超大型タンカー)では1日当たりの赤字額が2万ドル(約227万円)を超えた」。財新記者の取材の応じた関係者は、石油タンカー業界の苦況をそう証言した。
タンカー運賃の大幅な下落は、中遠海能が巨額の減損処理に踏み切るにあたり最も重要な根拠となった。
イギリスの海事コンサルティング会社のドゥルーリーは、石油タンカーのスポット運賃の収益レベルを予測し、海運会社にデータを提供している。中遠海能はそのデータを船舶資産の減損テストのパラメーターとして採用しており、ドゥルーリーが将来の予測値を大きく引き下げたことを理由に、今回の減損処理が必要になったと説明している。
だが、減損処理の大きさやタイミングについては、投資家から疑問の声も上がっている。上海証券取引所は、減損額の算定の具体的なプロセスやパラメーターの選択根拠をより詳しく(投資家に対して)説明し、巨額減損の合理性を論証するよう中遠海能に求めた。
同取引所はさらに、過去の減損処理が同業他者に比べて不十分だったり、遅れたりしてはいなかったか、実態を説明することも求めている。
(財新記者:賈天琼)
※原文の配信は1月24日
財新 Biz&Tech
ベルギーで唯一の造船所が倒産したらしい。この前、デンマークのODENSE STEEL SHIPYARDで建造された船に訪船する機会があった。2006年には世界で最大級のコンテナ船を建造したが、2012年に最後の新造船を引き渡し、今は、跡形もないそうだ。栄枯盛衰!時代が変われば、いろいろな物も変わると言う事だろう。
The books have been laid down at the Meuse et Sambre shipyard. On Friday, the
Namur company court declared bankruptcy. The CSC, a French-speaking labor union,
confirms this.
In 1906, Meuse and Sambre was established. It is the last shipbuilding and ship
repair firm in Belgium. It does so in Seilles, Namur, Liège, and Charleroi,
among other places.
The management proposed that the operations be continued, but the company court
denied it. She named a trustee to search for potential buyers.
The company’s low liquidity condition, according to CEO Eric Lallemand, played
games on it. However, he claims that the shipyard’s order book still contains
orders worth roughly 10 million euros.
Bee Meuse and Sambre employs 70 workers at the moment. Their employment are at
peril, but they will continue to work as usual for the time being.
(ブルームバーグ): クルーズ船運航のゲンティン香港(雲頂香港)が会社清算を申請した。ドイツの造船子会社破産後、資金繰りが行き詰まった。
ゲンティン香港は19日、債権者や利害関係者との交渉に向けた「あらゆる合理的な努力が尽き」、法人登記先であるバミューダの最高裁判所に会社清算の申し立てを行ったと香港取引所への届け出で説明。同社は18日、「信頼に足る」再編案が示されなければ、バミューダの裁判所で現地時間18日に暫定的な会社清算手続きの申請を進める方針を示していた。
2020年に始まった新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)で旅行需要は激減。クルーズ船の運航は停止され、旅行業界では再編や破綻が相次いだ。ゲンティン香港は昨年5月、17億ドル(現行レートで約1950億円)という記録的な赤字を計上していた。
ゲンティン香港が間接所有するMVウェルフテンは先週、ドイツの裁判所に破産を申請。独当局との救済協議が不調に終わっていた。ゲンティン香港は投資家に27億8000万ドルに上るクロスデフォルトの可能性を警告していた。
原題:Cruise Operator Genting Hong Kong Files to Wind Up Company(抜粋)
新造船、それとも修繕船?
24日朝、今治市の造船所の岸壁で造船中の船から火が出て、作業員1人が病院に搬送されましたが、24日夕方、死亡しました。
24日午前8時前、今治市小浦町の造船所西側の岸壁で、係留していた船から火が出ました。
警察によりますと造船中の貨物船・294トンの機関室から火が出たということで、消火作業にあたっていた松山市の作業員、木村勇介(38)さんが病院に搬送されました。
木村さんは全身にやけどを負い、病院で手当をうけていましたが、24日夕方、死亡しました。
現場は来島海峡大橋から西に1キロほど離れた造船所が建ち並ぶ地域で、警察や消防が火事の原因を詳しく調べています。
(ブルームバーグ): クルーズ船の運航を手掛けるゲンティン香港(雲頂香港)の株価が13日の香港市場で上場来最大の値下がりを記録した。同社のドイツ造船子会社が独裁判所に破産を申請したことを受け、ゲンティン香港は27億8000万ドル(約3185億円)に上るクロスデフォルトが生じる可能性があると投資家に警告していた。
ゲンティン香港株は過去1週間、売買が停止。取引が再開された13日、同社株は一時60%下落し、56%安で引けた。マレーシアの富豪、林国泰氏が率いるゲンティンはカジノやホテルなど展開するコングロマリット。
ゲンティン香港は香港取引所への13日の届け出で、10日に破産申請したMVウェルフテン絡みの融資枠(8800万ドル)に関係する法的手続きは独裁判所が17日に出す判断次第だと説明した。
ゲンティン香港は2020年8月、債権者向けの支払い計34億ドルを停止している。MVウェルフテンは地元政府に救済を求めたが合意に至らず、破産申請を行った。
原題:Genting Hong Kong Plunges Record 56% on Default Fears (1) (抜粋)
自動航行の定義は?
動画は船員が接岸のために係船機の近くで作業してるけど?
北九州市で17日、自動航行できる大型フェリーの世界初となる実証実験が行われました。
17日午後、北九州市門司区の新門司港に入港したのは、大型フェリーの『それいゆ』です。
■山木記者
「ゆっくり船が近づいてきますが、実は人の手は使わず、自動で着港しています。」
船体に取り付けられたセンサーが障害物を検知し、AIが分析して、ほかの船との衝突を避けるほか、操船が難しい船の離着岸も自動で行います。
実証実験では、港への離着岸と、新門司と伊予灘の間の往復240キロを最高時速50キロの高速で、自動航行すること、ともに大型フェリーとして世界で初めて成功したということです。
国内では、船員の高齢化や人的ミスによる海難事故などが課題となっていて、開発を進める日本財団などは、2025年の実用化を目指しています。
クルーズ船には冬の時代であるのは明らかだと思う。そのうち、クルーズ船を専門に建造してきた造船所が倒産する可能性はあると思う。
米クルーズ会社ノルウェージャン・クルーズラインが運行するカリブ海への10日間の旅が、新型コロナウイルスにより突如、途中でキャンセルされ、乗客たちは海上で足止めを食らっている。
ノルウェージャン・ジェム号は1月9日にニューヨークを出港し、さまざまな島を訪れる予定だった。しかし、クルーズ業界メディア・CruiseHiveによると、このツアーが始まってすぐに、まず2つの寄港先への立ち寄りがキャンセルとなり、その数日後には残り全ての訪問を取りやめることになったという。
乗客のエイミー・フォカラシオさんは「航海中に島や港に寄って休憩もできないなんて、悪夢のようです。何もやることがないのにあと4日も海上にいるなんて、想像できません」とUSA Today紙に話し、このクルーズを「地獄のクルーズ」と呼んだ。
ノルウェージャン・クルーズラインの広報担当者はこのキャンセルについて「新型コロナ関連の事情」によるもので、「難しい決断だった」と述べた。「客船はシント・マールテンのフィリップスブルフで一泊し、まもなくニューヨークへ戻る予定です。ニューヨークの到着予定時刻はまだ確定していません」と1月16日、ハフポストUS版に語った。
CruiseHiveによると、シント・マールテンでの停泊は、ノルウェージャン・ジェム号唯一の寄港地であったという。また、乗客には旅費が全額返金されたほか、今後の旅行も割引されると報じている。
ノルウェージャン・クルーズラインは今月初め、公衆衛生の状況の変化による渡航規制の継続を理由に、8つの旅行をキャンセルした。今回の突然の予定変更は、それに続くものとなった。
12月末、CDC(米疫病対策センター)は、船内でのウイルス感染率が高いことから、ワクチン接種の有無に関わらず、クルーズを避けるように呼びかけていた。
ハフポストUS版の記事を翻訳・編集・加筆しました。
Nina Golgowski
造船所に行って昔と確実に違う事は外国人労働者が増えた事。今は経験のある日本人が上で指示やチェックをしているが、若い日本人達が少ない。何年後、何十年後には外国人達にお任せコースか、縮小しかないと思う。継続しないと技術ややりながら学ぶしかない経験は途絶える。
時代の流れとして終わらすのか、改善する事によって寿命を延ばすのか、やり方次第のケースがあるので、個々が頑張るのか、業界で頑張るのかを含めて考える必要はあると思う。
佐世保重工業(SSK)の最後の新造船となる中型ばら積み船が13日、船主に引き渡される。「これで最後だと思うと残念だし、寂しい」。同社のOB会で会長を務める久野哲(さとし)さん(74)=長崎県佐世保市権常寺町=は、造船業が盛んだったころを振り返り、主力事業を休止した会社の将来を憂えた。
終戦翌年の1946年、SSKは旧海軍工廠(こうしょう)の施設を借り受け、佐世保船舶工業として設立した。62年には当時世界最大の13万トン級タンカー「日章丸」を完成させるなど、世界に誇る技術力で地域経済をけん引。久野さんは「世界一の船を造った会社だということはみんな知っていた。SSKのバッジを付けた大人は憧れの存在だった」と振り返る。
68年に入社。造船部に配属され、大型タンカーなどの建造に携わった。現在、社員数は千人に満たないが、入社当時は社員だけで7千人近く、下請け企業の従業員も含めると構内で1万人以上が働いていたという。「当時は経営状況も非常によかった。入社して4、5年目の夏のボーナスが、国鉄で30年ぐらい働いている父と同じくらいだった」
仕事は過酷だった。夏場は鉄板が熱くなり、タンクの中で切断や溶接の作業をすると汗が噴き出した。職場の風呂に入ってから帰るのが日課。風呂場は従業員でごった返し「毎日芋を洗うようだった」。そんな忙しい日々も、自分たちが造った船が世界の海で活躍すると思えば、乗り越えることができた。
経営は時代の波に翻弄(ほんろう)され、浮き沈みを繰り返した。特に印象に残っているのは73年の第1次オイルショック。石油輸送需要が低迷して経営危機に陥り、賃金カットなどの合理化策を提示する会社と労働組合が激しく対立した。その後も数々の困難に直面したが「それでも今と比べれば、いい時代だった」。
造船は裾野が広く、これまで雇用創出などに貢献してきた。その一方で、今回の事業休止が地域経済に与えるダメージは計り知れず「下請け企業にどれだけ影響が広がるか」と懸念。中国・韓国の台頭で国内の造船業界が苦戦している現状を憂い「国にもっと支援をしてほしい」と願う。
「この難局を乗り越えて、いつかまた、SSKで船を造れるようにならないだろうか」。難しいとは分かっているけどね、と久野さんは寂しそうに語った。
長崎県佐世保市の佐世保重工業(SSK)で12日、同社にとって最後の新造船となる中型ばら積み船(8万2千トン)の命名式が行われた。1953年に初めて進水した「永邦丸」から数えて510隻目。世界に先駆けて大型タンカーを建造するなど、地域経済を支えてきた中核事業からの事実上の撤退となる。今後は修繕船事業を主力に、経営再建を目指す。
船はギリシャの海運会社が発注した。全長約225メートル、幅約32メートル。穀物を積載する。13日に船主へ引き渡され、韓国に向けて出航する。
命名式では、船名が「TOLMI」(トゥルミ)と発表された。支綱の切断後、くす玉が割れ、関係者が拍手を送った。
SSKは昨年2月、新型コロナウイルス禍に伴う受注の急減などを理由に新造船事業の休止を発表した。これに伴い、子会社を含む全従業員の3割近くに上る250人規模の希望退職者を募集。応募した248人が5月までに順次退職する。
今後は海上自衛隊や米海軍佐世保基地が近くにある強みを生かし、修繕船事業に注力。新造船用の第4ドックは修繕船兼用に改修する。改修工事は9月末に完了予定。
名村建介社長は「当社の生き残りと事業継続のための苦渋の決断となった。修繕船事業は地の利に加え、設備面でも明らかに優位性がある」と述べた。
◎「日本一の修繕ヤード目指す」 名村社長
佐世保重工業(SSK)の名村建介社長は12日の式典後、報道陣の取材に応じた。今後、新造船に代わって修繕船を主力事業に成長させる考えを改めて示し「日本一の修繕ヤードを目指す。新生SSKとして、しっかり羽ばたいていく」と意気込みを語った。
新造船用の第4ドック(長さ400メートル)は修繕船兼用に改修する。名村社長は、第3ドック(長さ370メートル)と合わせて「国内最大級の大型修繕用ドックを2基有することになる」と強調。修繕で重要な岸壁が総延長約1200メートルあることも強みとし「日本でも希有(けう)な修繕ヤードで、優位性があると自負している」と自信を見せた。
これまで修繕の主力だった自衛隊艦艇に加え、海上保安庁の巡視船、米艦船、客船、液化天然ガス(LNG)運搬船などの修繕工事に積極的に取り組む方針を掲げ「しっかり競争していけると確信している」と述べた。
第4ドックを新造と修繕の兼用とし、新造の機能を残すが、「少なくとも当面は修繕船事業に集中して取り組んでいく」と説明。親会社の名村造船所(大阪市)伊万里事業所での新造船について、今後SSKで工事を補完する可能性を示し「佐世保の艤装(ぎそう)関係の機能は、グループの大きな力になり得ると考えている」と話した。
人材的には厳しいと思う。優秀な人材はこないと思う。将来に不安がある業界には来ないだろう。
古い産業や会社には必要な部分と不必要な部分が混在する。ただ、不必要な部分を切り取るのは簡単ではない。変化を嫌う古株が存在する。造船は頭が良い若者を採用したら問題解決できる業種ではない。経験が重要な比率が高いと思う。
経験があれば優秀でなくても何をどうすれば良いのかわかる。経験があれば、答えを推測できる。日本は見て覚えろと考える現場が多いので、本を読んで理解する事は不可能。造船関連の専門書を見ればわかるが、時が止まっているような本ばかりだ。このような本を読んでも基本が理解できるぐらい程度。
日本の大学は実戦で必要な知識や技術を教えるところではない。結局、採用後に会社が育てるか、経験を積みながら成長するしかない。だから人材不足になれば、育てる人達も不足していると考えた方が良いと思う。
船の基本は同じかもしれないが、船の大きさや種類が違えば、現場や仕事を通して学習するか、経験を得ない限り、即戦力にはならないと思う。その意味では、他の業界と比べると大型船のように、舵を切ってもタイムラグのために結果はすぐに出ないと思う。
船や海運は知れば知るほど奥が深いと思う。まあ、いろいろ問題があっても運が良ければ問題は直ぐには起きない。運が悪いと大きな失敗、そして、大きな損失として結果に現れる。まあ、なるようにしかならないし、個人的な考えが当たっていようが、間違っていようが、結果は時間が経てばわかる事。
国が改革を後押し
国が後押しする造船改革が動きだした。国土交通省が造船と海運を支援するスキームを設けて、今治造船(愛媛県今治市)グループやジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市西区)など造船大手が相次いで認定を受けた。海運の活況に伴って新造船の需要が回復しているものの、資機材価格の上昇が各社の収益を圧迫する可能性がある。中国や韓国勢が市場を席巻する構図も続く。日本勢が挽回するには大胆なテコ入れが必要で、今回が最後のチャンスだ。
【写真】国内初の自航式、世界最大級の「洋上風力」作業船
「制度を最大限活用し、現場での生産力を持続的に高めつつ、世の中を先取りした船舶の開発が必要だ」―。日本造船工業会(造工会)の宮永俊一会長(三菱重工業会長)は、国交省の支援スキームを生かした各社の取り組みに期待を寄せる。
「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(海事産業強化法)」の施行に伴って、造船と海運を支援するスキームが整った。船舶の供給側と利用者側の両面での施策により、好循環を生み出すことを狙う。造船会社は生産性向上や事業再編などの方針をまとめた計画を策定し、認定されることで日本政策金融公庫などによる金融支援を受けられる。税制の特例措置も利点だ。一方で海運会社も、環境負荷を低減する船舶などを導入する計画を造船会社と策定し、認定されることで同様の支援を受けられる。
公的支援や経営統合により巨大化した中韓勢に苦戦を強いられてきた日本勢にとって、今回のスキームの活用が巻き返しへの第一歩だ。大規模ロットに対応する設計や建造体制の構築、造船所の抜本的な運営の見直し、次世代技術の開発など課題の解消が進む可能性がある。今治造船や川崎重工業、名村造船所グループ、三菱造船(横浜市西区)などがそろって同計画の認定を受けた。川重の橋本康彦社長は「我々の大きなミッションが水素分野だ。(液化水素を運搬する)船により造船の新たな可能性を示す」と意気込む。
造船業界では国の方針に先行する形で、再編がここ数年進んできた。今治造船とJMUが資本業務提携に伴って、商船の設計や営業を統合した共同出資会社は発足から1年を迎えた。船舶の燃料転換を追い風に、日本郵船や商船三井から液化天然ガス(LNG)を燃料に使う自動車船を相次いで受注し、滑り出しは上々だ。JMUの株主であるIHIの井手博社長は「営業力の強化などでシナジーを生み出せており心強い」と期待する。今治造船とJMUの提携は、“造船ニッポン”の先行きを占う試金石だ。
一方、三井E&Sホールディングス(HD)は艦艇と官公庁船事業を三菱重工業に譲渡し、造船子会社は常石造船(広島県福山市)から出資を受け入れた。一連の構造改革により国内の新造船から事実上撤退し、船舶のエンジニアリングに専念する。
再編で中韓勢に対抗
こうした造船所の再編は地域経済への影響が大きいものの、各社は向き合わざるを得ない。JMUは舞鶴事業所(京都府舞鶴市)での商船の建造を終了した。三菱重工は長崎造船所香焼工場(長崎市)の新造船エリアを大島造船所(長崎県西海市)に譲渡する契約を結び、2022年度に完了する予定。中韓勢との厳しい競争が続く中、造船所の合理化に向けた動きが今後も広がりそうだ。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴って低迷していた受注環境は改善している。日本船舶輸出組合(JSEA)によると、11月末の輸出船手持ち工事量は約1850万総トン。安定操業の目安とされる2年分の工事量には満たないものの、20年を底に緩やかな回復が続く。
背景にあるのが好調な海運市況だ。バラ積み船やコンテナ船を中心に新造船の需要も底堅く推移している。造工会の宮永会長は「新型コロナの感染が収束すれば世界経済も回復し、海上の荷動き量も成長トレンドを取り戻す」と指摘する。
ようやく活気が戻りつつある造船業界だが、今度は資機材の高騰に直面している。船価の3割を占めるのが鋼材で、造工会によると鋼材の値上がりに船価の上昇が追い付いていないという。船価に高騰分を反映しきれずに、コストが増えれば造船会社の収益を圧迫する。川重は21年4―9月期連結決算で、中国の船舶事業の業績が悪化し、受注工事損失引当金を計上した。
造工会の宮永会長は「鋼材を大量に使う造船業では安定供給が最優先事項であり、鋼材メーカーにはその点のご配慮をお願いしたい」と話す。経営努力では対処しきれない課題で、各社は厳しいやりくりを迫られる。しかも高騰により、建造が内定しているものの、正式な契約に至らない案件が急増しているという。
また中長期では新造船市場の活況が見込まれている。10年前後に大量に竣工した船舶の代替建造が必要なためだ。造工会では40年までの新造船の需要量を年平均約7000万総トンと予測する。競争を左右しそうなのが、温室効果ガスを排出しない船舶(ゼロエミッション船)だ。
海運業界が国際海運からの温室効果ガスの排出総量を50年までにゼロにする方針を表明しており、造船業界も「海事クラスターと連携して研究開発に着手する」(宮永造工会会長)方針。外航船では燃焼時に二酸化炭素(CO2)を排出しないアンモニアや水素を燃料として活用し、内航船向けには燃料電池を搭載した船舶の実用化が進む見込みだ。
LNG運搬船などの受注を中韓勢に奪われた日本勢にとって、ゼロエミッション船により再び競争力を高められる可能性がある。そのためには造船や海運、商社など「オールジャパン」の体制で開発を加速させることが必要だ。世界的なカーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)の動向を先取りすることが、造船ニッポンが復権するカギとなる。
日刊工業新聞・孝志勇輔
韓国で設計できないのは今分かった問題ではない。対応出来ないのだからロイヤルティーを払って建造するのか、他のタイプの船を建造するのか判断するだけだと思う。
韓国造船業界は昨年初めから12月22日までに液化天然ガス(LNG)タンカー68隻を受注した。LNGタンカーは1隻当たりの受注価格が2億ドル(約228億円)に達する代表的な高付加価値船舶で、全世界で発注された74隻のうち92%を韓国企業が受注したことになる。企業別では現代重工業グループが32隻、サムスン重工業が21隻、大宇造船海洋が15隻をそれぞれ受注した。
【グラフ】LNGタンカーの受注実績と韓国造船企業がGTTに支払うロイヤルティーの規模
しかし、韓国の造船会社の素晴らしいLNGタンカー受注実績の背後で収益を上げている企業がある。LNGタンカーの設計技術を保有するフランス企業ガストランスポート・アンド・テクニガス(GTT)が受注価格の5%をロイヤルティーとして持っていくからだ。合計すると少なくとも8000億ウォン(約768億円)に達する。韓国造船業界幹部は「能力では韓国が上回っているが、カネは仏GTTがもうけている」と漏らした。
■LNGタンカーの営業利益率1-2%、ロイヤルティーは5%
LNGタンカーは超低温で液化した天然ガスを輸送する船舶だ。燃料にもLNGを使用するため、環境にやさしい船舶とされている。LNGタンカーで最も重要な設備はマイナス163度で液化された天然ガスを運ぶLNGタンクだ。内部の温度が少しでも上昇すれば、LNGが急激に膨張して爆発しかねず、精巧な設計技術が求められる。夏には190度を超える外部との温度差に耐えなければならない。
韓国造船3社が競争力を持つのは四角形のメンブレンタンクだ。1990年代まで世界のLNGタンカー市場を席巻した日本が採用していた球形のモスタンクを淘汰し、韓国造船業界がLNGタンカー市場を支配する足掛かりとなった。メンブレンタンクはモスタンクよりも積載量が40%も多いからだ。
しかし、韓国造船各社は独自技術を持たない。仏GTTがメンブレンタンク設計の独自技術を持っているため、韓国造船各社はLNGタンカーを建造するたびに船体価格の約5%の1000万ドルをロイヤルティーとして支払っているとされる。昨年68隻のLNGタンカーを受注した造船3社がロイヤルティーだけで8000億ウォン以上を支払わなければならない計算になる。通常LNGタンカー建造時の韓国造船各社の営業利益率はようやく1-2%であることからみて、巨額がロイヤルティーとして持っていかれる計算だ。匿名の造船業界関係者は「一時2億5000万ドルまで高騰したLNGタンカーの価格が徐々に下落する一方、人件費や厚板など原材料コストが上昇し、造船会社のLNGタンカーの営業利益率はだんだん低下している」とした上で、「ようやく船を建造しても、GTTをもうけさせているのではないかという情けなさを感じる」と漏らした。海外の船会社は安全性が立証されていない技術の採用を嫌うため、今後もGTTの独走がしばらく続くのは確実な状況だ。
■独自技術確保への遠い道のり
韓国造船各社は独自技術の確保に向けて努力しているが、まだ目に見える成果を上げられずにいる。韓国造船3社と韓国ガス公社は2014年、韓国型LNGタンク設計技術「KC-1」を共同開発した。しかし、この技術を採用して18年に建造した2隻のLNGタンカーではタンク外壁の結氷問題が起き、修理しても問題解決には至らず、いまだに運航できないままだ。韓国政府と造船3社は「KC-1」に続く新技術「KC-2」の開発に着手し、今年末までに技術を開発する計画だが、世界市場で認められるためにはまだ道のりが遠いとみられている。
大型コンテナ船のエンジンも独自技術がなく、高額のロイヤルティーを支払っている。現代重工業は世界シェア30%以上を占める首位だが、独自技術はドイツ企業MAN、中国船舶工業集団(CSSC)系のヴィンタートゥール・ガス&ディーゼル(WinGD)が保有している。造船業界によると、現代重工業は大型エンジンを建造する際、エンジン価格の5-10%をこれら企業にロイヤルティーとして支払っているという。
辛殷珍(シン・ウンジン)記者
マレーシアの会社が親会社になるらしいドイツの「Genting’s German Shipyards」が倒産したようだ。グループ会社が多数のクルーズ船を所有し、2016年にドイツの3つの造船所を買収したがコロナの流行で大きな影響を受けた結果らしい。
多数のクルーズ船を所有しているだけで大きな痛手だろうが、クルーズ船を主に建造している造船所を買収した事で痛手が拡大した形となったのだろう。
将来はわからないが、短期間の栄枯盛衰の例のようだ!大型コンテナ船を持っている海運会社は儲かっているのに!
The German shipyard operations of Genting Hong Kong filed for bankruptcy on January 10 after last-minute talks between the Malaysian parent company and the German state officials failed to reach an agreement on the terms of a government loan to keep the operations going. The filings known as insolvency under German law included the MV Werften group in the east as well as Lloyd-Weft in Bremerhaven.
Discussions are ongoing to determine the short-term situation. At the end of last week, MV Werften said that it was in danger of violating convents on its loan that was forcing the company to delay payment of wages to its nearly 2,000 employees. After being informed of the bankruptcy filing, representatives of the union said that employees were willing to show up for work tomorrow at the yard while officials from the state and federal government both addressed the situation calling for a long-term restructuring of the operations.
An internal announcement circulated to the unions and their members at the end of the day on Monday called it a bitter day while executives from Genting were quoted in the German media as saying the government had lost sight of the number of jobs and important financial contribution from the shipyards. "Without the coronavirus, we would never have asked the government for a single euro," Genting Hong Kong President Colin Au said in statements reported in the German press.
The impasse came about over the financial contributions and guarantees the federal government was insisting on from Genting. The state of Mecklenburg-Western Pomerania, where MV Werften is located, initially had provided bridge loans in the fall of 2020 to restart operations at the shipyard after it closed during the pandemic. Those loans were used to complete an expedition cruise ship for Genting’s Crystal Cruises and in June 2021 it was announced that the federal and state governments had developed a new package to restructure the shipyard operations to complete construction on the first of two giant 208,000 gross ton Global Dream cruise ships.
The package was restructured several times and last week reports said the government was offering €600 million (approximately $675 million) to continue the operations. Under the federal government Economic Stabilization Fund, Genting was required to invest 20 percent of the value of the loan. The Global Dream cruise ship would also have served as collateral for the loan.
"The government did everything possible to avoid insolvency and save jobs. However, the owners rejected our offer of help and the consequence is insolvency," Economy Minister Robert Habeck said Monday.
The government reportedly offered to lower Genting’s participation to €60 million. Genting said that it had provided $30 million which was sufficient to access a portion of the loan that they tried to draw down in December. Genting reportedly offered to increase its participation to $45 million. Au said Genting had submitted four different offers to the government during the negotiations.
Management of MV Werften filed for insolvency at the Schwerin District Court. Under German law, insolvency administrators must now be appointed to begin working on restructuring. A government will provide unemployment payments to the workers.
Germany’s minister and finance officials for the state addressed the situation late on Monday saying the focus needed to be on maintaining the jobs and completing construction of the Global Dream cruise ship. The ship is reported to be 75 percent complete with delivery expected later this year. They are also calling for a long-term restructuring of the company, possibly splitting the three yards in the east into independent operations and possibly refocusing on the offshore industry. They said it was clear the yards could not continue to function in their current structure.
Lloyd-Werft, also owned by Genting, filed for bankruptcy as well on Monday. The shipyard, which had been a major repair and overhaul facility for the cruise industry, has also increasingly focused on the luxury yacht business. Last year, Genting said it would close Lloyd-Werft, but recently it was reported that they were negotiating for the sale of the yard. A company from the United Arab Emirates has reportedly signed a letter of intent to acquire 50 percent of the yard, which employed approximately 300 people in Bremerhaven.
Genting Hong Kong says it is still looking for new sources of funding to help navigate the COVID-19 pandemic after falling to another US$238.3 million loss for the six months to 30 June 2021.
The loss, while narrowed from a 1H20 loss of US$742.6 million, reflects ongoing headwinds for the company’s core cruise ship business – one of the hardest hit industries globally form the pandemic.
Despite finalizing agreements with creditors in June that will see the company granted new loans and extensions to maturities around its US$2.6 billion of debt, Genting Hong Kong said in its H1 results release overnight that it continues to search out further funding opportunities.
“The Company’s financial results remain heavily impacted by the COVID-19 pandemic and the extent of the losses will depend on many factors including the timing of full return to service of its cruise fleet,” it said.
“The Company continues to seek new sources of funding in view of the uncertainties in the recovery.”
Genting Hong Kong reported a decline in revenue in 1H21 to US$182.3 million, down from US$226.2 million in 1H20 due to the suspension of Crystal Cruises and Star Cruises operation since early 2020.
However, the resumption of cruising in Taiwan and Singapore at various times helped reduce the group’s EBITDA loss to US$171.2 million.
Staying positive, Genting Hong Kong cited a Cruise Ships in Service Report issued by Cruise Industry News which said around 50% of the global cruise fleet is expected to be back in service by the end of August 2021.
The company, which has recently resumed sailings from Singapore and Hong Kong, is planning to relaunch Explorer Dream in Taiwan from September, having suspended operations for a second time in May.
造船中堅の常石造船(福山市沼隈町常石)は、来年4月1日付で同業の神田造船所(呉市)から修繕事業を譲り受ける。
神田造船所が完全子会社を新設して呉市内の全2工場を承継させた後、常石造船が新会社の全株式を取得する見込み。現在百数十人いる従業員は新会社へ移る予定だが、人員や役員体制、譲渡額などは今後詰める。修繕事業の年間売上高は30億円前後とみられる。
神田造船所は1948年設立、資本金6500万円。フェリーなど内航船の建造が主力だったが赤字が続き、新造船事業からは来春までに撤退する方針。修繕事業は収益が安定しており、規模の大きい常石造船グループの傘下で事業や雇用の継続を目指す。
常石造船は「当社の本社工場と距離が近く、両社の修繕ドックを効率的に運用して業容拡大につなげたい」としている。
基本的には日本籍で建造すると国土交通の承認された物しか搭載できない。全く同じものを製造しても承認費用で総額が違ってくる。単純にパナマ船籍は税金が安いと言うわけではない。そして、船員に関しても外国籍の船員は使えない。総額で大きな違いとなってくる。
船の修理や維持で造船所に入っても外国船籍船でないので部品にも関税がかかる。外国籍であれば保税地域に部品をおいて関税がかからないように出来るが、日本籍になればそのような対応は出来ない。
結果としてコストはかかるが高額な船を遊ばせるよりも良いとの判断だと思う。
日韓航路の高速船 コロナ禍で本格稼働できず
JR九州高速船は2021年12月16日(木)、新型高速船「クイーンビートル」をパナマ船籍から日本船籍に変更する手続きを開始したと発表しました。
【広い!】クイーンビートルの内部を写真で見る
クイーンビートルは福岡と韓国・釜山を結ぶ航路の新型船として2020年10月に博多港へ入りましたが、新型コロナの影響で国際運航ができない状態が続いています。
2021年3月からは、国土交通省から特例を受け、福岡県の沿岸で遊覧運航を行うなどしているものの、「国内での臨時運航などの事業可能性を広げるため、日本籍に転籍することが望ましいとの判断に至りました」ということです。
クイーンビートルは「トリマラン」、日本語で「三胴船」と呼ばれる珍しい形状が特徴。水に沈む部分が少ないため水の抵抗が減り、高速性能と安定性を発揮します。もともとは日韓を結ぶLCCとの競合を意図して導入されました。
コスト面などで有利なパナマ船籍とすることは、外航船においては一般的な手法ですが、自国内の物資や旅客の輸送は自国籍船に限るという規制があるため、国内航路への就航も難しい状況でした。
JR九州によると、日韓関係の悪化もあり、「コロナが落ち着いたとしても日韓航路へ就航できるかは未知数」だといいます。今後は船籍登記のほか船舶検査、無線局検査などを経て、2022年3月中の日本船籍化を予定しているとのこと。その後どこに就航させるかは決まっていないものの、これにより国内各港間の運行が可能になるといいます。
乗りものニュース編集部
JR九州高速船(福岡市博多区、水野正幸社長)は、運用する高速船「クイーンビートル」の船籍をパナマから日本へ変更する。日本船籍とすることで国内港同士を結んで運航できるなど活用の可能性が広がる。2022年3月の変更を予定する。
【写真】高速船「クイーンビートル」
同社はJR九州の全額出資による船舶事業子会社。クイーンビートルは新型の新造船として、20年に博多―韓国・釜山航路へ就航予定だったがコロナ禍により国際航路で運用できていない。
外国船籍のため国内運航に制限があることから、現在は国の「沿岸輸送特許」を得て国内で遊覧運航を実施している。
プレスリリース配信元:TDB
国内造船業界の経営動向調査
造船業界が苦境にあえいでいる。リーマン・ショック前における新造船の大量建造に加え、2013年前後の需要回復を見込んだ投機的な新造船の建造により、現時点においても世界の船腹供給量は需要を上回る状況にある。一般社団法人日本造船工業会がまとめた『造船関係資料』によると、2020年末における世界の新造船手持工事量は1億2099万総トンと、2008年(3億6807万総トン)のおよそ3分の1にまで減少し、「造船不況」と呼ばれる状況に陥っている。この間、中国や韓国の造船業者との価格競争により船価も低迷。中小造船所では操業維持のための赤字受注を余儀なくされるケースも散見され、業界中堅・大手では再編や撤退の動きが活発化している。
<調査結果(要旨)>
2020年度の売上高合計は1兆9782億7400万円で前年度比3.0%減
2020年度の当期利益が「赤字」の割合は27.9%、このうち約半数が2期連続赤字
地域別の社数は『九州』が116社(構成比24.4%)で最多、西日本が328社(同69.1%)
倒産は2000年以降で58件発生、最大の倒産は昭和ナミレイ(株)(堺市西区、負債374億円)
地域別の分布:社数は『九州』が最多、売上高合計は『四国』が最多
抽出した488社のうち、2020年度(2020年4月期~2021年3月期)決算数値が判明した475社について、本社所在地別に集計したところ、社数は『九州』が116社(構成比24.4%)で最多となった。以下、『中国』が94社(同19.8%)、『関東』が62社(同13.1%)で続き、西日本(近畿以西)が全体の約7割を占めた。
売上高合計をみると、業界大手を擁する『四国』が6573億8000万円(構成比33.1%)でおよそ3分の1を占めて最多。『関東』が3909億5900万円(同19.7%)、『中国』が3472億5900万円(同17.5%)で続き、西日本が全体の73.8%を占めた。
他方、従業員数合計は『関東』が8942名(構成比30.9%)で最多となり、『九州』が5149名(同17.8%)、『中国』が4964名(同17.1%)で続いた。西日本は全体の約6割にとどまった。
売上高の動向:2020年度は前期比3.0%減、約6割が減収
抽出した488社のうち、3期連続で売上高が判明した462社 [1] の売上高合計をみると、2020年度は1兆9782億7400万円と、前年度(2兆396億2200万円)に比べて3.0%減少した。減少傾向の推移となるなか、2兆円の大台を割り込んだ。
2020年度は「増収」企業が120社(構成比26.0%)と3割を下回ったのに対し、「減収」企業が272社(同58.9%)と約6割にのぼった。このうち、「2期連続減収」となったのは90社で全体の19.5%を占める。他方、「2期連続増収」となったのは39社(全体の8.4%)にとどまり、国内造船業者が厳しい受注環境に置かれていることが分かる。
2020年度の「増収」「減収」企業の割合を地域別にみると、「増収」の割合が最も高かったのは『東北』で36.0%だった。他方、「減収」の割合は『北海道』(76.5%)と『四国』(76.1%)の2地域が7割を上回った。なお、全体に占める「2期連続減収」の割合が最も高かったのは『関東』(24.2%)だった。
また、売上高規模別にみると、「増収」の割合が最も高かったのは「10~100億円未満」で47.4%だった。他方、「減収」の割合は「1億円未満」(67.5%)と「100億円以上」(63.6%)が6割を上回り、「10~100億円未満」(48.7%)では「2期連続減収」が半数を超えた。なお、全体に占める「2期連続減収」の割合が最も高かったのは「100億円以上」(30.3%)だった。
利益の動向:4割超の企業で利益が減少
抽出した488社のうち、3期連続で当期利益が判明した企業(2019年度:236社、2020年度:226社)の収益状況を分析すると、2020年度は163社(構成比72.1%)が「黒字」となったものの、構成比は2019年度(72.5%)から0.4ポイント低下した。「黒字」企業のうち「増益」となったのは104社で全体の46.0%を占めた。「黒字転換」は27社だった。
他方、「赤字」となったのは63社(同27.9%)で、このうち「2期連続赤字」となったのは30社で、構成比は「赤字」企業の47.6%、全体の13.3%に達した。この30社のうち14社は赤字が拡大した。「赤字転落」は28社だった。
「減益」のほか、「赤字転落」「赤字拡大」を合わせた『利益が減った企業』は合計で99社にのぼり、全体の43.8%を占めた。
2020年度の利益を地域別にみると、「黒字」の割合が最も高かったのは『東北』で83.3%だった。他方、「赤字」の割合が最も高かったのは『北陸』で60.0%にのぼり、『四国』も40.0%に達した。なお、『利益が減った企業』の割合は『中部』(61.5%)が最も高かった。
また、売上高規模別にみると、「黒字」の割合が最も高かったのは「1~10億円未満」で79.2%だった。他方、「赤字」の割合が最も高かったのは「100億円以上」で半数にのぼり、「1億円未満」も4割を超えた。『利益が減った企業』の割合は売上高規模が大きくなるごとに上昇する傾向がみられた。
「倒産」「休廃業・解散」の状況:再建型倒産が目立つ
造船業における2000年以降の企業倒産(法的整理のみ、負債1000万円以上)の発生状況をみると、2021年10月末時点までに計58件が確認された。年別の件数は2013年が7件で最多となり、2008年以降の新造船受注急減のあおりを受けた形の倒産が多かった。
他方、2016年以降に確認された「休廃業・解散」については、2018年の13件が最多で、2019年も11件と2年連続で2桁を数えた。2020年は2件にとどまったものの、2021年は1~10月(10カ月間)で既に6件に達している。もっとも、「休廃業・解散」に至る造船業者は、修繕事業を主体とする小規模事業者が大半を占めている。
2000年以降の全倒産を態様別にみると、「破産」が32件(構成比55.2%)で最も多いものの、一般の倒産に比べて「民事再生法」(同29.3%)や「会社更生法」(同3.4%)という再建型倒産の割合が高いのが特徴だ。造船業は各地域の雇用面で重要な役割を担っており、スポンサーなどによる支援を受けて再生を果たすケースが多い。例えば、昭和ナミレイ(株)が所有していた因島工場(広島県尾道市)は、内海造船(株)(東証2部)が買収のうえ、従業員も再雇用された。清算型の「特別清算」においても、マーレ(株)のように別途設立した新会社に事業を承継させ、抜本的な事業再生を図るパターンも多く見られている。また、地域別にみると『近畿』が13件(構成比22.4%)で最も多く、『関東』が12件(同20.7%)、『中国』が10件(同17.2%)で続いた。
まとめ・今後の見通し:さらなる業界再編が進む可能性も
冒頭にも触れた日本造船工業会の『造船関係資料』によると、2021年6月末時点における世界の新造船手持工事量は1億4860万総トンと、2020年末時点(1億2099万総トン)から増加している。背景には船腹需給バランスの改善と、世界経済の回復に伴うコンテナ荷動きの活発化、LNG燃料船の発注増があり、久々の受注増加に湧いている。しかし、この増加した受注の多くを中韓両国の造船業者が獲得。日本国内の新造船手持ち工事量は1981万総トンと、2020年末に比べて約1割しか増えていないのが実情で、相対的に日本の立ち位置は後退している。
本調査でも、造船業者の2020年度の売上高合計は前年度に比べて3.0%減少し、2兆円の大台を割り込んだことが分かった。「減収」企業が約6割にのぼり、その3分の1(全体の約2割)が2期連続で減収を余儀なくされていた。これが「造船不況」と言われる所以だ。
中韓造船業者との受注競争により採算が悪化し疲弊した中小造船業者は、足元の鋼材価格急騰で受注済み新造船の採算がさらに悪化。新造船事業から撤退して修繕事業に特化する中堅造船業者も出てきている。さらに、海運業界全体がゼロ・エミッションへと舵を切るなか、造船業者は次世代燃料船の開発・建造へのシフトが不可欠となり、産学が連携した技術開発にも取り組む必要が生じる。造船業者にはこれまで以上に強大な資本力が求められる状況になりつつあり、中小・中堅業者も巻き込んだ再編が一層進む可能性がある。
日本の造船業界は環境テクノロジーにおいて世界でもトップクラスの技術を有しており、潮流は追い風であると評される。次世代燃料船の開発・建造を進めるなかで国際競争力を有する“造船大国ニッポン”の復権を果たすためには、事業再編や環境対応技術開発を促進する補助金や低利融資を盛り込んだ現行の海事産業強化法による支援を含め、“官”からの機動的で柔軟な財政支援が重要となるだろう。
日本の中古フェリーで採算が取れていたのなら、新造フェリーで採算性は大丈夫なのだろうか?助成金があるのでは?



済州と仁川を結ぶ旅客船「Beyond Trust」入港 12/11/21(chosun Online)
旅客船「セウォル号」が仁川(インチョン)から済州島(チェジュド)へ向かう途中、南西部の珍島(チンド)沖で沈没した事故を受けて、およそ7年間途絶えていた仁川と済州島を結ぶ旅客船の運航が10日から、再開されました。
現代重工業グループの現代尾浦(ヒョンデミポ)造船によりますと、韓国のフェリー会社「ハイデックス・ストレージ」の2万7000トン級カーフェリー「ビヨンド・トラスト号」が就航し、10日夜に仁川港を出航する第一便から、済州島を結ぶ航路での本格的な運航を始めるということです。
現代尾浦造船がおととし受注し、建造した「ビヨンド・トラスト号」 は、全長170メートル、幅26メートル、高さ28メートルで、850人の乗客と487台の乗用車、65個のコンテナを載せて最大23.2ノート(時速43キロ)で運航できます。
「ビヨンド・トラスト号」は、現代重工業が独自開発した、窒素酸化物の排出を抑える最適燃料噴射技術を採用した、1万3000馬力級の「船舶推進用強力エンジン」2機や硫黄酸化物低減装置などを搭載し、さまざまな環境規制に対応します。
また乗客の安全を考え、低重量、低重心に設計し、運航時の復元性を最大化したと説明しています。
さらに浸水や火災など緊急時に備えて、海上脱出設備(MES)、衛星航法装置、自動火災報知設備、スプリンクラーなど多様な安全設備を備えています。
内部には90あまりの船室をはじめ、レストラン、ビジネスラウンジ、サンセットテラス、マッサージラウンジ、コンビニ、キッズゾーン、ペットゾーンなどをそろえています。
仁川港からは毎週月、水、金曜日の午後7時に出発し、済州港からは毎週火、木曜日の午後8時30分と土曜日午後7時30分にそれぞれ出発します。
到着までの所要時間は14時間ほどということです。
現代尾浦造船の社長は就航式で、「大きな苦痛の上に誕生した旅客船であるだけに、誰もが安心して旅行を楽しめられる船を建造するため、全力を尽くした。世界トップレベルの造船技術を持つ韓国で、国民が安全なフェリーに乗って、海上旅行を楽しめることを望む」と話しました。
仁川と済州島を結ぶ航路は、2014年4月のセウォル号沈没事故を受けて、セウォル号とオハマナ号を運航していた清海鎮(チョンへジン)海運が同じ年5月に免許を取り消されて以降、運航が途絶えていました。
SHIN WATANABE, Nikkei staff writer
DALIAN, China -- China State Shipbuilding Corp. has set sail on efforts to streamline operations and develop new technologies, starting with the bankruptcy of a Tianjin shipyard that has long struggled with debt.
The move is unusual for a state-owned Chinese company, which typically is expected to maintain and even expand employment. But China's leading shipbuilder looks to trim the fat so it can focus more resources on ammonia-fueled vessels and other emerging areas.
Tianjin Xingang Shipbuilding Heavy Industry, a group subsidiary that builds cargo ships and other vessels, went bankrupt in October with 13 billion yuan ($2.04 billion) in total debts. The company, which employed about 1,700 people as of August, will terminate contracts with workers by the end of 2023, local media report.
Another group company, Dalian Shipbuilding Industry, will take over some of Tianjin Xingang's production and employees. But many workers likely will be let go.
"The Chinese government essentially made the decision for Tianjin Xingang to go bankrupt," an industry insider in Shanghai said, noting that CSSC is state-owned. "It's part of a push to streamline the group."
CSSC agreed in October 2019 to merge with China Shipbuilding Industry, then the country's No. 2 shipbuilder. The process concluded late this October after CSSC acquired stakes in two units from the State-owned Assets Supervision and Administration Commission -- an agency under China's State Council cabinet -- and the sprawling group is beginning to streamline operations.
But CSSC is expected to bolster research and development.
"The group is making Shanghai Merchant Ship Design and Research Institute and other ship design units compete, instead of streamlining them," an industry insider said.
The state-owned shipbuilder also is working to improve coordination within the group.
"To avoid cannibalizing clients, each shipyard is screening orders based on their strengths, like liquefied natural gas carriers or bulk carriers," the insider said.
Excess staff are being diverted to new business areas. Dalian Shipbuilding is developing a carbon-neutral vessel that runs on ammonia, a field drawing attention from overseas rivals like Japan's Imabari Shipbuilding.
CSSC plans to move its headquarters to Shanghai, where many of its clients are based, from Beijing in December, according to local reports. It is investing 18 billion yuan to build a cutting-edge shipyard in Shanghai by the end of 2023, which will replace an older facility in the city.
CSSC said it received 18.38 million tons in new shipbuilding orders during the January-June half, up nearly triple from a year earlier. Revenue increased 9% and net profit by 26% on the year for the January-September period.
The shipbuilding industry is booming globally as demand for maritime shipments rises. South Korean builders received 51% of new orders for civilian ships worldwide in the January-June period, while Chinese players captured 38%. Japanese companies accounted for 8% as they continue to struggle to expand market share.
常石造船(広島県福山市)は26日、神田造船所(同県呉市)の修繕事業を2022年4月1日付で取得すると発表した。取得額は非公表。両社の修繕ドックで船舶の受け入れを融通し合うことで事業の柔軟性を高め、技術力の向上も狙う。
神田造船所はすでに、22年1月に建造する分をもって主力の新造船から撤退する方針を発表している。残る修繕事業を新たに設立する子会社に承継させた上で、その会社の全株式を常石造船に譲渡する。神田造船所の21年3月期の売上高は約150億円で、修繕事業は2割を占める。
修繕事業では、神田造船所は内航船に強く、常石造船はばら積み船や外航船を得意分野とする。互いの技術を学び、高め合うことを狙う。国内の新造船は中国などとの価格競争で厳しい環境にあるが、修繕は定期点検などで安定した需要がある。
債権の取立不能または取立遅延のおそれに関するお知らせ:ひろぎんホールディングス
東証1部上場の金融持株会社「ひろぎんホールディングス」は、保有する債権について取立不能または取立遅延のおそれが生じたことを明らかにしました。
これは、子会社の「広島銀行」および「ひろぎんリース」の取引先となる造船業「株式会社神田造船所」(広島県呉市)が、主力の造船事業から撤退し、修繕事業に特化する事業再編計画を策定中で、取引金融機関に対して債権放棄などの金融支援を要請する可能性が高まったための措置です。
債権額は、広島銀行の貸出金が101億7800万円、ひろぎんリースのリース投資資産などが300万円の見込みで、当該債権については担保・引当金などで全額が保全されているため、業績予想への影響はありません。
Jehan Ashmore
Irish Ferries announced today the addition of a second ro-ro cruise ferry Isle of Innisfree to its Dover-Calais route joining Isle of Inishmore, which was launched just months ago onto the premier UK-France link, writes Jehan Ashmore.
Under the terms of the purchase agreement, title to the 28,833 tonne ship Calais Seaways transferred to Irish Continental Group (ICG) upon delivery yesterday. Following drydocking and rebranding into Irish Ferries livery, the 1,140 passenger/83 freight vehicles or 600 cars capacity ferry is expected to enter service within the first week of December.
The debut of the renamed ferry, Isle of Innisfree (the third to take the name) will double frequency on the short-sea link between Britain and mainland continental Europe, thus providing customers a complete UK landbridge service with their Irish Sea routes. In addition the two-ship service will enable Irish Ferries to be closer to rival DFDS three-ship operation, though P&O Ferries have four ferries plying on the Strait of Dover.
Isle of Innisfree, originally launched as Prins Filip was built in 1991 by the Boelwerf shipyard in Belgium, however did not enter service until the following year for RMT, a Belgium state operator that also linked the UK from Dover to Oostende. Despite several change of ownerships and under various renamings, the ferry has spent for the most part of a career plying between south east England and northern France.
The introduction of Isle of Innisfree offers a host of quality facilities for freight drivers/passengers such as a self-service restaurant, café/bar, Club Class lounge, onboard duty-free shop, children’s play area and spacious outdoor decks.
Commenting on the acquisition of secondhand tonnage, Andrew Sheen, Irish Ferries Managing Director, said: “We are delighted be able to add a second ship to our Dover / Calais route, with the ship doubling our frequency with a departure every 2 ½ hours rather than the current 5 hours between sailings. The ship underlines our commitment to this route and facilitates trade for both exporters and importers as well as ensuring capacity for essential passenger movements and greater choice for tourism”.
Afloat also adds the name of ferry chosen, Isle of Innisfree revives that of a previous vessel of the same name when ICG ordered their first custom-built newbuild which entered service on the Dublin-Holyhead in 1995. The order for Isle of Innisfree (II) on the Ireland-Wales route was much needed to modernise, as predecessor B&I Line (acquired in 1991 by ICG) was an ailing Irish state-owned company operating ageing smaller tonnage.
As for the first ever ferry named Isle of Innisfree, this took place in the early 1990's under the brand of B&I (when chartered-in by ICG). Despite the change of ownership, ICG retained the line's famous trading name until consigned to history at the start of 1995.
The second Isle of Innisfree built in the Netherlands served the Ireland-north Wales link until replaced by Isle of Inishmore in 1997 and which in turn was replaced by Ulysses in 2001. The cruiseferry continues to operate the Irish Sea service.
As referred above, the Isle of Innisfree, ICG eventually sold the renamed Kaitaki following years on charter in New Zealand as Afloat reported over the years. The ship continues to operate in the southern hemisphere for operator, KiwiRail. Their InterIander service links the north and south islands across the Cook Strait on the Wellington-Picton route.
A pair of larger passenger, freight train-enabled ferries have been ordered to replace Kaitaki along with two other fleetmates. The first of the newbuilds is due to enter service in 2025 and the second in the following year.
Both ro-pax ferries are to be built by South Korean shipyard Hyundai Mipo Dockyard which is currently building the Isle of Man Steam-Packet's newbuild ro-pax which is to be named Manxman and delivered in 2023.
The newbuild will replace Ben-My-Chree which was built by Van der Giessen de Nord that was also responsible for the construction of the Innisfree/Kaitaki and the Isle of Inishmore.
In addition the Dutch shipyard also built Blue Star 1 which is on charter to ICG following the transfer of Isle of Inishmore from the Rosslare-Pembroke route.
欧州の独占禁止当局が、現代重工業による大宇造船海洋の買収を許可しないことが明らかになった。
12日のロイターの報道によると、欧州連合の欧州委員会(EC)は現代重工業による大宇造船海洋の買収に対して企業結合禁止命令を下す見込みだという。ロイターは「(現代重工業と大宇造船海洋が)競争制限に対する懸念を払拭できる是正案を提示するのを拒否し、EUの『拒否権』行使を目前にしている」と報道した。
現代重工業は、締め切り期限である7日になっても、欧州委に是正案を提出しなかった。欧州委の企業結合審査制度は、企業が自ら提出した是正案をもとに運営される。会社が是正案を提示しない場合、当局は一方的に是正措置を課すことはできない。これに対して欧州委は、提出された是正案を検討した後、条件付き承認などを下す形で進めていく。ただし、企業が是正案を出さなかったり、提出した是正案が競争制限性を解消するのには不十分であると判断される場合、EUが禁止命令を下すこともできる。
欧州を含む全世界の主な独占禁止当局は、特にLNG運搬船市場の独占・寡占の深化を懸念してきた。今回の企業結合が行われるとなると、既存の3強体制が2強体制に再編されることになる。この懸念を根本的に解消するためには、株式の売却など構造的な措置が含まれていなければならないが、現代重工業は構造的な措置は選択肢ではないという判断により、是正案を提出しないものと伝えられた。
現代重工業グループは2019年3月、大宇造船海洋の最大株主である産業銀行から大宇造船海洋を買収する契約を結んだ。欧州委は同年末、審査を始めたが、コロナ禍などの要因のため、数回延期した経緯がある。今回、最終的に禁止命令が下されるとなると、これは、2019年以後では欧州委による初の禁止命令となる。欧州委は2019年、企業結合3件に禁止命令を下したが、いずれも企業が是正案を提出したが欧州委が不十分だと判断したケースだ。現代重工業による大宇造船海洋の買収は、韓国の公正取引委員会でも審査が進行中だ。
現代重工業側は「造船市場は単にシェアだけで支配力を評価するのは不可能であり、特定の企業による独占が難しい構造であるため承認が妥当だと判断され、このために最善を尽くす」と明らかにした。
この記事を書いた記者は船の事をほとんど知らないのであろう。韓国の造船所が建造するLNG船はフランスの技術。船を建造するたびにロイヤリティを支払わなければならない。
ロイヤリティを支払いたくないので韓国国内で開発に10年をかけたが問題が解決でない状態で、船の修理が問題となっている。また、図面があった方が良いが、図面があるから良い船が直ぐに建造できるわけではない。経験や人材がなければ無理だと言う事を理解する必要があると思う。船価が高くてもかかった費用が大きければ利益は少ないし、損が発生する可能性もある。三菱重工がクルーズ船を二隻で1000億円で受注したが、2000億円以上の損を出したのが良い例。
韓経:韓国LNG運搬船受注ジャックポット歓呼の裏に…仏から「1兆ウォンの請求書」舞い込む 06/04/20(中央日報日本語版)
10年間かけて開発した韓国産LNGタンク技術…197億ウォンかけて補修も同じ欠陥 12/02/19(中央日報日本語版)
2021年10月15日、韓国・ヘラルド経済によると、韓国の造船会社に最近、世界の造船市場で韓国とライバル関係にある日本と中国からの発注が相次いでいる。記事は「日中は自国発注率がほぼ100%で、ライバル国への発注は非常に異例のこと」と伝えている。
記事によると、今年1〜9月に韓国は日本国籍の船会社から計56万2833CGT(11隻)を受注した(英造船海運分析機構「クラークソンズ・リサーチ」社調べ)。受注した船種はLGN船が5隻で最も多かったという。業界関係者は「かつて造船世界トップだった日本は最近、自国の造船トップ2(今治造船とジャパンマリンユナイテッド)の合弁会社を設立するなどして中韓に追いつこうとしているが、建造に高い技術力を要するLNG船に関しては、この分野をリードする韓国に発注せざるを得なかったのだろう」と説明したという。
また、昨年は韓国への発注がなかった中国の船会社も最近、韓国にコンテナ船10隻(10万1990CGT)を発注した。これについて業界関係者は「高付加価値船舶に力を入れる韓国と違い中国は低価格受注がほとんどで、自国発注率が100%に近い。中国が自国の造船所より高い値段を払って韓国に発注するのは非常に異例のこと」と述べたという。
この記事に韓国のネットユーザーからは「わが国が誇らしい」「ついに韓国が独歩的な船舶製造国になった。素晴らしい」「死にかけていた造船を立て直してくれた文在寅(ムン・ジェイン)大統領に感謝」など喜びの声が寄せられている。
一方で「先端技術を盗もうという魂胆では?」「分解して研究するためだ」「喜ぶことではない。また技術が盗まれる」と“裏”を疑う声も多く、「価格をもっと上げるか、売らないか、どちらかにしてほしい」と求める声も上がっている。(翻訳・編集/堂本)
創業102年を迎える熊本県宇城市三角町の篠崎造船鉄工所が初めて、医療船を手掛けている。政府開発援助(ODA)事業で、太平洋にあるマーシャル諸島共和国の医療支援を担う。10月末に完成予定で、新型コロナウイルス禍が沈静し次第、約100年にわたり三角で培われた技術が世界に向けて出航する。
8月26日、医療船「リワトゥーン・モア(船なくして島民の健康なし)」は社員や地域住民らに見守られながら、宇土半島と造船所のある戸馳島の海峡「モタレノ瀬戸」へゆっくり進水した。篠崎鉄蔵社長(84)は、海に浮かんだ船を満足そうに見つめた。
外務省所管の一般財団法人・日本国際協力システムによる業者選定を経て、篠崎造船鉄工所が受注。技術コンサルタントの日本造船技術センターと打ち合わせを重ねながら、約1年かけて進水式までたどり着いた。
船は長さ30メートル、幅6メートル、総トン数は140トン。診察室のほか、歯や妊婦の状態を診る設備、移動式のレントゲン装置などを備え、主に島民らの健康診断のために運航される。建造費は約4億2千万円で、現在は内装工事が進んでいる。
アメリカ南部テキサス州を7日に出発し、カリブ海一周クルーズをしていた「カーニバル・ビスタ号」で11日、乗員26人、乗客1人の合計27人から新型コロナの陽性が確認されていたことが分かりました。
造船所は1919年創業。貨物船を主体に100隻以上を造ってきた。これまで手掛けた最大の船は積載量約3千トンの貨物船。石油タンカーのほか、化学薬品を運ぶケミカルタンカーを造る技術も持つ。
4代目の篠崎社長によると戦後、県内の造船業組合には48社が加盟したが、木造から鋼船へと切り替わっていった昭和30年代に次々と廃業。天草、八代地区などで地場数社が操業するが、今も組合に所属するのは篠崎造船鉄工所だけとなった。「瀬戸内などの造船業者は変化に対応して成長したが、熊本は木造にこだわり時代の流れに乗れなかった。『肥後の引き倒し』といった協調性に欠ける県民性も影響したのでは」
造船所の社員40人に加え、内装や配管など「協力会社」から40人の派遣社員と事業を展開。新入社員には大分地域造船技術センター(大分県)での約3カ月間の研修を通じ、造船業に必要な数種類の免許を取得させるなど技術者の育成にも力を入れてきた。
社のモットーは「いい船を造れば必ず引き合いがある」。「真面目に仕事に取り組み、職人を育ててきた」と篠崎社長。最もうれしいのは、船が無事に進水した瞬間だという。計算を重ね、技術と経験を精いっぱいつぎ込むが、「船は浮かべてみないと分からない。最後まで心配ですよ」と打ち明ける。
同社は造船のほか、船のメンテナンスや樋門[ひもん]の造設も担う。2020年5月期の売り上げは新型コロナの影響で、例年に比べて半分以下の約6億円にとどまったが、黒字を確保した。(飛松佐和子)
チーフオフィサーがローディングコンピューターの使い方を理解していなくてバラストが十分でなく転覆とは情けない。原因究明でチーフオフィサーは被害が大きくてなかなか事実を認める事が出来なかったからこんなにも時間がかかったのかな?
US likely to release report on cargo ship accident next year 10/19/19(The Korea Herald)




【杭州共同】中国浙江省寧波市にある韓国系企業、サムスン重工業の造船所で9日、造船所閉鎖を知った中国人従業員数千人が抗議活動を行い、補償などを要求した。台湾の中央通信が12日までに伝えた。
従業員は7月に閉鎖を知ったが、会社側から十分な説明がなく、9日は造船所内で「仕事が欲しい。家族を養わなければならない」などと書いた横断幕を掲げて会社側に説明や補償を求めた。
造船所は1995年に設立、約4500人の従業員がいるという。
佐渡汽船(新潟県佐渡市)は16日、2021年6月中間連結決算を発表し、6月末時点の債務超過額が26億8800万円に拡大したことを明らかにした。長引く新型コロナウイルス禍で旅客需要が低迷。高速カーフェリー「あかね」の売却に伴う佐渡、上越両市への補助金返還も響き、今年3月末からの3カ月間で債務超過額は10億円余りも膨らんだ。
県内小学校の修学旅行が予定通り実施され、今年1~6月の旅客輸送は約29万5千人。キャンセルが相次いだ前年同期を8・7%上回ったが、ウイルス禍前の19年同期に比べると54%減った。
同社は今年6月、あかねをスペインの海運会社に30億5千万円で売却することを決め、7月に引き渡しを行った。あかねの建造の際に佐渡、上越両市から総額10億円余りの補助金を受けており、売却に伴って両市への補助金返還額計約6億7千万円を特別損失として計上した。
同社の債務超過額は昨年12月末時点で8億7600万円だったが、今年3月末時点で16億4400万円に拡大した。
21年12月末での債務超過解消を目指し、あかねに代わってジェットフォイルを就航した小木-直江津航路で年間約4億円の赤字圧縮を図るなど経営改善を進めるが、ウイルス禍で輸送需要回復のめどは立っていない。観光の最盛期である夏場も、7月の旅客輸送が19年比で6割の水準にとどまっている。
筆頭株主である県は佐渡汽船に対し、既に約8億6千万円の支援を実施している。債務超過の拡大を受けて県交通政策課は「利用者が増える夏の結果がまだ出ていない。経営改善の状況を厳しくチェックする」と強調。佐渡市交通政策課は「債務超過額が3月末から10億円増加したことを踏まえると、経営改善計画の見直しも含めて検討する必要があるのではないか」としている。
同社は今後、ジェットフォイルなどの旅客運賃割引や自動車航送運賃割引の廃止など、さらに踏み込んだ改善策を検討する。三富丈堂(たけあき)総務部長は「経営改善策を確実に実施するとともに、資本増強に向けた方策も検討したい」としている。
中間決算は売上高34億5200万円(前年同期29億9600万円)、営業損失15億3900万円(同営業損失17億1300万円)、経常損失16億1500万円(同経常損失17億4600万円)、純損失21億6500万円(同純損失17億4100万円)だった。21年12月期通期の業績予想は、大都市圏を中心に感染の「第5波」が続いており、影響を見通すことが困難として引き続き未定とした。
旅行関係やクルーズ関係はコロナ前の状態に戻れないかもしれない。戻れたとしてもかなりの時間がかかると思う。
原則、ワクチン接種を乗客に義務付けていた運航中のクルーズ船から27人の新型コロナ陽性者が確認されましたが、全員、ワクチンを接種済みでした。
アメリカ南部テキサス州を7日に出発し、カリブ海一周クルーズをしていた「カーニバル・ビスタ号」で11日、乗員26人、乗客1人の合計27人から新型コロナの陽性が確認されていたことが分かりました。
陽性者は全員、ワクチンを接種していて、無症状または軽い症状だということです。
このクルーズは子どもや疾患を持つ人を例外として、原則、乗員乗客にワクチン接種を義務付けていて、船に乗った約4300人の98%近くがワクチンを接種済みでした。
陽性者は隔離されたうえで乗客にはその事実が伝えられ、クルーズは再開されているということです。
テレビ朝日
もし船員の国籍が中国ではなく、他の国籍であれば、人種差別とか、日国際的だと非難されると思うが、中国人船員に対して中国が判断しているのであれば問題ないと思う。
小さな犠牲よりも、大きくなるリスクの原因を絶つと言う判断だと思う。目先の感情よりも、感染が広まった時のリスクに優先順位を置いたと言う事。
日本は東京オリンピックのために将来のリスクを見逃し、感染が拡大すると国民を見捨てる判断をした。日本だって小中国と考える事は出来ると思う。まあ、完全な解決方法がない場合には、基準や価値観で判断しないと、日本のようにぐちゃぐちゃになる。東京オリンピックに関する判断基準や説明が無茶苦茶になっている。
中国はコロナの怖さを知っているから対応が厳しいと思う。国が違えば法律や価値観が違う。だからこそ愛国心ではなく、その国が良い国であれば、国民はその国に留まりたいと思うと思う。中国はこのような対応が出来るから、欧米の国々と比べて感染者が医療レベルが充実していないにも関わらず少ないと思う。少なくとも北京オリンピックが終わるまでは厳しい対応を取り続けると思う。
船主がコストを問題視しなければ、小型船に修理の人間と医療従事者を乗せて船に接岸できると思う。十分なお金を払えば、韓国で手配できると思う。
9日付の香港紙・明報によると、乗組員から発熱者が出た貨物船が中国江蘇省の港に入ろうとしたところ、新型コロナウイルス対策を理由に入港を拒否され、インターネットで助けを求める事態に陥った。
報道や乗組員が投稿したとみられる映像によると、フィリピンを出発した船には中国人20人が乗り込んでいる。8日時点で13人が発熱しており、乗組員は呼吸困難者がいると涙ながらに訴えた。
船は3日、入港申請を拒否され、浙江省の地元政府に医療支援を求めた。地元政府は8日になって支援の手続きに入ったという。船はエンジンの故障で浙江省沖に停泊している。
江蘇、浙江両省では、この1か月弱で500人以上の感染者が確認され、当局が警戒を強めていた。(香港支局 吉岡みゆき)
だめな船長や士官を使うととんでもない事が起きるリスクがあると言う教訓になると思う。
インド洋の島国モーリシャス沖で大型貨物船が座礁し、油が流出し始めてから8月6日で1年になる。沿岸部のマングローブ林などの油の除去は今年1月に終わったものの、今春をめどに解体予定だった船体後部は天候不順のため作業が中断しており、完了のめどはいまだ立っていない。
【写真】モーリシャス沖で2020年8月17日、座礁した貨物船を視察する日本の国際緊急援助隊=国際協力機構(JICA)提供
長鋪(ながしき)汽船(岡山県)の子会社が所有する貨物船「WAKASHIO」(全長約300メートル)が同国南東部の海岸から約2キロの浅瀬で座礁したのは昨年7月25日だった。座礁時にサンゴ礁が破壊されたほか、8月6日になって燃料油約1千トンが流出。油は約30キロにわたって海岸線に漂着し、マングローブ林などを汚染した。一帯では今年3月まで半年以上にわたって漁業ができなくなるなど、現地の人々の生活にも影響が出た。
船体は座礁後に真っ二つに割れた。前部は昨年8月中に沖合に曳航(えいこう)されて深海に沈められたが、残る後部の撤去が問題になっていた。長鋪汽船は中国企業と契約し、昨年12月に解体を始める予定だったが、実際に始まったのは今年2月。3月中旬以降は悪天候により作業ができていない。天候が安定する9月下旬の再開を見込んでいるが、完了時期は未定だという。
長鋪汽船などによると、船長らは携帯電話の電波の届く範囲に入ろうと浅瀬に近づいて座礁。正確な沿岸からの距離や水深が把握できない縮尺の海図を利用していたことや、レーダーや目視での見張りを怠っていたことが指摘されている。モーリシャス当局はインド人船長ら2人を航海の安全を脅かした容疑などで逮捕。現在も裁判が続いている。同社は今月2日の報道発表で「事故原因究明、環境保護そして船骸撤去に全力を尽くします」とした。
高知県で新たに10人が新型コロナウイルスに感染していることが分かりました。
感染が確認されたのは20代から50代までの男女10人です。全員が軽症で2人の感染経路が分かっていません。
中央西管内で発生していた共同生活を送る船員たちのクラスターで新たに20代と30代の男性合わせて3人の感染が分かりました。
3人はすでに感染が分かっている別の船の6人と7月10日から21日まで同じ場所で共同生活をしていました。これで合わせて9人のクラスターとなりました。
また県内の90代男性がファイザー製のワクチンを打った3日後の7月9日に死亡していたことが分かりました。男性は医療機関に入院していて死因は肺炎ということです。
また高知市は高校生などが夏休み中に1回目のワクチン接種を受けられるように16歳から19歳までを対象とした接種券をあさって(4日)から発送すると発表しました。
対象者はおよそ1万2000人で医療機関での個別接種か市役所南別館での集団接種を選ぶことができます。接種券は8月10日までに到着する予定です。
高知さんさんテレビ
船は引き取ってからの運航及び維持コスト、故障や修理などのコストや頻度、マーケットでの価格など総合的に評価する必要があると思う。
また、船主や監督の評価の仕方で総合評価は変わってくると思う。酷い船だなと思っても監督がまあまあの船だと言っているのを聞くと、基準が違えば評価が大きく変わってくると納得する。何年ぐらい運航するのかによっても評価が違ってくると思う。政界経済の影響を受けるマーケットの動向の予測が難しい。正しいと思っても、悪い結果になったり、間違ったかなと思ってもとても良い結果になったりする。
日本の造船業に関していえば、人材だけは確実に減っていているし、直ぐに経験のある人達を調達できないので、予測を誤ると需要があっても対応出来ない状況がくるかもしれない。
長く構造不況に苦しんできた日本の造船業界に、ようやく薄明かりが差してきた。
「中国や韓国の造船所の船台(ドック)が埋まっている。船価アップを図りながら受注を伸ばしたい」
7月12日、都内で会見した業界最大手・今治造船の檜垣幸人社長はほおを緩ませた。
今治造船の手持ち工事量は7月時点で、適正水準とされる2年分を超え、2.5年分近くに積み上げている。業界2位のジャパン マリンユナイテッド(JMU)も同様に受注量を増やしており、業界にとっては久しぶりに明るい話題が続いている。
■一時は業界存続の「崖っぷち」に
足元の業績も回復している。今治造船の2021年3月期の売上高は3712億円と微減ながら、営業黒字を確保した模様だ(営業損益は未公表。前期は207億円の営業赤字)。JMUなども赤字を縮小させている。
背景には、巣ごもり需要の増加に伴う海運市況の改善がある。足元のコンテナ運賃は上昇し、日本郵船などの海運企業は業績を上方修正している。好業績を背景に、これまで抑制していた新造船の発注を活発化させているのだ。今後、ますます厳しくなる排ガスなどの環境規制への対応もあり、排ガス対応の進んだ新造船への需要が増していくのは間違いない。
ここ10年ほど、日本の造船会社は新造船をなかなか受注できなかった。政府の支援を受けた中国や韓国勢が、シェア獲得のために赤字受注に邁進してきたからだ。中国、韓国とも国家主導で造船業界の再編が進み、複数の船を一括受注する「連続建造」が主流になりつつある。個社の造船能力が比較的小さい日本勢は多数隻の一括受注が難しく、苦しい立場に立ち続けてきた。
造船事業は設計から完成まで数年程度の工期を要し、手持ち工事量を2年程度持っていないと「工場を稼働できない空白の時期ができてしまう」(檜垣社長)。造船会社などでつくる日本船舶輸出組合によると、手持ち工事量は2020年6月末に1.05年分にまで減少し、業界存続の「崖っぷち」に立たされていた。
ただ、ここに来て、遅ればせながら進めてきた業界再編の動きがようやく実を結び始めている。
国内1、2位の今治造船とJMUは資本提携を結び、2021年1月に営業・設計を行う合弁会社「日本シップヤード」を設立。両社は日本シップヤードの設立前からすでに共同受注に取り組んでおり、2020年12月には「オーシャンネットワークエクスプレス(ONE。川崎汽船と商船三井、日本郵船のコンテナ船事業統合会社)」が傭船予定の世界最大級の超大型コンテナ船6隻を共同受注した。
2021年6月には、日本郵船が発注したLNG自動車運搬船12隻を日本シップヤードと新来島どっくがそれぞれ6隻ずつ受注した。
今後は海外の受注獲得にも期待がかかる。日本シップヤードの檜垣清志副社長(今治造船専務)は「それぞれの強みを生かした営業活動ができている。忙しすぎて設計部門が新技術の仕込みをできないほどだ」と話す。
■過剰な生産能力は手つかず
ただ、先行きには懸念もある。1つが船の材料となる鋼材価格の高騰だ。原料である鉄鉱石価格の上昇や需給逼迫を背景に、日本製鉄やJFEスチールなど国内の製鉄会社も値上げに動いている。コスト上昇分は船の販売価格に上乗せせざるをえないが、船価はこれまで低迷続きだっただけに、値上げが認められるか不透明だ。
それ以上に問題なのは、日本の造船業界の生産能力が過剰なことだ。1980年代に国の主導により人員整理が進んで以来、造船業に従事する人の数はほぼ横ばいで推移している。「持続可能な水準からは明らかに過剰」(造船大手幹部)だが、地方に散在する造船所の地元にとって雇用問題は一大事だ。
近年は造船不況に耐えきれず、造船事業そのものを外部に売却する動きが相次いだ。経営危機に陥った三井E&Sホールディングス(旧三井造船)は、岡山県玉野市の造船所で行っていた艦艇事業を三菱重工に譲渡する。同社は商船事業の生産からも手を引き、100年以上の歴史を持つ名門・三井造船の祖業がついに幕を下ろす。
JMUの舞鶴事業所(京都府)や名村造船所傘下の佐世保重工(長崎県)も新造船をやめ、修繕事業に特化することを決めた。三菱重工も香焼工場(長崎県)を大島造船所に売却する。いずれの造船所も、地域雇用の中心を担っており、地元経済への衝撃は計り知れない。
溶接など多くの工程が手作業で行われる造船は、典型的な労働集約型産業だ。労働力人口の減少が見込まれる中、縮小もやむなしとの声も上がる一方、製鉄から造船、海運までの「海事クラスター」という観点から産業を保護すべきとの意見も根強い。日本の産業界全体に関わる困難な課題に向き合う必要がある。
高橋 玲央 :東洋経済 記者
個人的には単純に船価とかで利益が出るかは言えないと思う。造りなれていない船種だと効率は悪いと思う。韓国とひとまとめにするのは少し違うと思う。韓国建造の船の中には中国建造かと思うほど質の悪い船がある。ただ、スペック的に標準以上の船が欲しければ日本ではなく、韓国か、中国になると思う。船の品質ではなく、建造仕様書のスペックが高いと言う事。日本だと多分、かなりの高船価か、シリーズでの発注でないと受けないと思う。設計も現場も普段しない事に対しては時間がかかると思う。
韓国造船海洋、第2四半期の営業損失860億円 厚板価格の引き上げによる費用増加を繰り上げ反映 鉄鋼業界は「低価格受注が原因」と指摘
「(第2四半期の実績に)いくつか問題がありますので、予め申し上げます」
韓国造船海洋のソン・ギジョン常務(IR担当)は21日午後開かれた自社のオンライン実績発表会で、重い口を開いた。現代重工業グループの造船3社を支配する中間持株会社の韓国造船海洋が、今年第2四半期だけで9千億ウォン台の営業赤字を出したと、投資家らに電撃公開した直後のことだ。
造船業界は造船に使う鉄板価格の高騰で赤字は避けられないと訴えているが、鉄鋼業界は赤字受注が原因なのに鉄板価格のせいにしていると主張している。
同日、韓国造船海洋が公開した今年第2四半期の営業損失は8973億ウォン(約860億円)で、昨年第2四半期に比べて大幅な赤字に転じた。現代重工業や現代三湖重工業、現代尾浦造船など子会社が4~6月の3カ月間、一斉に数千億ウォン台の赤字を記録した影響だ。
これは市場の予想をはるかに上回る規模だ。当初、証券業界は、韓国造船海洋の第2四半期の営業赤字が400億ウォン(約38億円)程度にとどまるだろうと見込んでいた。ソン常務は「商船部門の収益性が良くなっていたのに、鋼材価格が急に引き上げられ、こうした事態が発生した」と強調した。
韓国造船海洋は最近、船舶建造に使う厚板(厚い鉄板)の価格が高騰し、今後の予想費用の増加分である8960億ウォンを、第2四半期に繰り上げて反映したと説明した。第2四半期の赤字のほとんどが鉄板原価上昇のために発生したという意味だ。
船舶受注から建造まで2~3年を要する造船会社は、船舶の建造進行状況に合わせて売上高などの実績を一定期間に分けて会計に反映する。もしも最初の受注当時推定した工事原価が途中で増えれば、これを追加費用として上乗せしなければならない。
韓国造船海洋は、ポスコなど主要鉄鋼メーカーと厚板の価格を交渉中だが、供給価格が現在の1トン当たり70万ウォン(約6万7千円)台から100万~115万ウォン(約9万5千~約11万円)ウォンまで上がると見て、今後の原価増加額を前もって費用として会計処理した。
大宇造船海洋やサムスン重工業など、まだ第2四半期の実績を発表していない他の造船会社も同じ悩みを抱えている。最近、世界的な景気回復の影響を受け、コンテナ船などの船舶発注が大幅に増えて受注好況を迎えているが、当の造船会社は急激なコスト上昇で、大規模な赤字を懸念している。大宇造船海洋やサムスン重工業は、今年第1四半期もそれぞれ2129億ウォン(約200億円)と5068億ウォン(約480億円)の営業赤字を記録した。
一方、鉄鋼業界は造船業界のこのような説明に反発している。ある大手鉄鋼メーカーの関係者は「そもそも造船会社が原材料価格の変動可能性を考慮せず、低価格で受注したのが原因なのに、今になって鉄鋼会社のせいにしている」と指摘した。
鉄鋼メーカーは2008年の世界金融危機以降、造船業が長期不況に陥っている間、供給価格の引き上げを控えるなど、苦しみを分かち合ってきたと説明した。今も造船業界には他の業界に比べて厚板を1トン当たり50万ウォン(約4万8千円)以上安く供給しているが、鉄鉱石など原料価格が急騰したため、今は値上げが避けられないという立場だ。
鉄鋼業界の関係者は「最近、厚板事業部の社員らはほかの事業部に比べ収益が高くないため、成果給を受け取れないとして、不満を抱いている」とし、「過去、韓国の鉄鋼業界が日本や中国産の輸入などで困難に直面していた時は主導権を握って価格を抑えた造船各社が、いざ立場が逆転すると私たちを悪者にするのは納得がいかない」と述べた。
同日、韓国造船海洋の株価は前営業日より4.49%(5500ウォン)高の1株=12万8千ウォン(約1万2千円)で取引を終えた。大信証券のイ・ドンホン研究委員は本紙との電話インタビューで「厚板の価格引き上げによる損失はすでに予告された悪材料だったため、投資家は不確実性が解消されたと判断したようだ」とし、「ただ、厚板以外の船舶原材料価格も上昇する傾向にあり、下半期にも大きな利益を期待するのは難しいだろう」と見通した。
三井E&S造船玉野艦船工場(玉野市玉)で21日、最後の船の引き渡し式が行われた。1917年の創業以来、この地で888隻の商船を造った。海外勢の台頭で採算が見込めなくなり、104年間続けてきた商船建造はこれで終了。10月からは、三菱重工業(東京)が玉野での官公庁船の建造を引き継ぐ。
最後の船は、パナマ船籍のばら積み貨物船「JAL KALPATARU」。全長199・99メートル、幅36メートル、載貨重量約6万6千トン、定員25人。4月に進水し、岸壁に係留して船内の設備工事などを施していた。
岸壁であった式典には社員ら約300人が出席し、それぞれ船を背に記念撮影。タグボートに引かれてゆっくり出航していくと、皆で社旗や手を振って遠ざかる船尾を見送った。
三井E&S造船は今後、工場を持たず、付加価値の高い新型商船や運航システムの開発に特化。資本業務提携する常石造船(福山市)など国内外の造船所からの設計受託を柱に据える。玉野で造船に携わってきた社員約700人のうち、約300人はグループの三井造船特機エンジニアリング(玉野市玉)に、約400人は三菱重工グループに移る予定。
ハイテク船は、イニシャルと維持管理コストの問題がある。結局、維持管理をしっかりしないと期待したように機能しない。維持管理コストと人件費の問題のバランスが大事だと思う。単純な仕様の船は問題が起きにくいが、ハイテクになると問題が起きると修理するまで使えない。船が古くなると修理するのか、新造船にするのかの判断が難しくなる。内航船ではないく、外航船だが、自動化仕様で建造されても、古くなると自動化を止めて船員を増やして対応している船は存在する。リモコン、又は、遠隔操作が壊れたら修理せずにそのまま使う船は存在する。便利さを諦めれば、船としては問題なく使える。ハイテク化を追求すれば、船が古くなると多くの基盤を交換しないと運航すら難しくなる。船のデジタル化は費用対効果を考えないと新造船の時が良いがその後を考える必要があると思う。
内航船は船の維持管理作業は造船所が行うケースが多し、外国には行かないので、メンテナンスの点では問題は小さいと思う。後はコストだけだと思う。
「内航船」、国内の貨物輸送を担う船舶のことだ。陸上を走るトラック運送と違ってふだん目にする機会は少ないかもしれないが、国内の貨物輸送のおよそ4割はこの内航船が担っている。まさに日本の“血流”そのものと言えるが、慢性的な船員の人手不足と高齢化に業界は悩まされている。この長年の課題解決に向けて瀬戸内の企業がある取り組みを加速させている。(松山放送局記者 武田智成)
「確保が困難」深刻な高齢化と人手不足
貨物輸送を行う内航船は国内に5000隻余り、船員はおよそ2万8000人いる。(2019年、国土交通省調べ)
船員の年齢構成を見ると、60歳以上が全体の24%、50歳以上だとほぼ半数の47%を占め、高齢化が進んでいる。
労働の実態はどうか。
平成29年度に国が行った調査では内航船員1人当たり1か月の平均労働時間は238時間となっている。これは一般労働者の170時間や建設業の180時間と比べて圧倒的に長い。しかも1か月(31日)の平均労働日数は29.86日と、ほとんど休日を取得できていないことになる。
貨物船では3か月乗船してその後に1か月休暇を取るのが一般的だという。長期にわたって陸を離れる業務上、船員法という法律でこうした働き方が認められているというが、労働現場の厳しさが想像できる。
実際、働き始めてすぐに辞めてしまう若者も少なくなく、国が内航船の事業者を対象に行った調査で40%近くが「船員の確保が困難」と答え、人手不足が深刻だ。
課題克服に向け動き出したプロジェクト
こうした中、環境改善につながるのではと業界が期待しているプロジェクトがある。ことし5月、広島県の「本瓦造船」と山口県の「冨士汽船」、愛媛県の「SKウインチ」が共同で発表した「次世代型デジタル内航船」だ。
畝河内代表
「これまでも課題解決に向けた動きはあったがなかなか実現しなかった。今回の取り組みは、荷主、船主、造船所、そして内航海運業界が一つになって長年の課題を克服する大きな一歩となる」
どんな船なのか。6月にしゅんこうしたデジタル内航船「りゅうと」は全長40メートル、幅8メートル、総トン数は199トンのケミカルタンカーだ。
最大の特長はデジタル技術によって作業の負担を大幅に少なくできることにある。
甲板での作業から解放される!?
内航船は安全管理のため、船員法などによって4人以上の乗船が義務づけられている。
船員の仕事の中でもっとも時間をとられるのが、荷役つまり荷物の積み降ろし作業だ。
手動で作業する従来のタンカー
例えばケミカルタンカーで液体の積み降ろしをするさい、船員は総出で船体とパイプをつないだり、量を調整するためバルブを回したり長時間労働を強いられる。計量器を見ながら手動で行っている。
バルブの操作がすべて手動の場合、いちばん時間がかかる作業で早くても1時間、大きい船だと3時間かかることもあるという。
一方、新たなデジタル船では、パイプをつないだあとは操縦室で1人での作業が可能になる。
ディスプレー画面の「荷役開始」ボタンに触れるだけで液体が流れ始め、タンクの容量の確認やバルブの調整も遠隔で行うことができる。甲板での作業から解放されるのだ。
世界初!の技術を搭載し 安全性も向上
また、船が接岸する際、いかりやロープを巻き上げるための装置、ウインチの操作も課題となっていた。これまでの一般的なウインチは、油圧式のモーターで動き、複数の船員が岸壁との距離などを測りながら手動で操作する。
ここに電動化の技術を搭載した。愛媛県の企業が開発した新しいウインチは電気自動車のモーターを応用した世界初のものだという。
操作も操縦室のモニターを見ながら行える。
搭載するセンサーとウインチが連動して動くことで接岸作業の精度がより高くなっただけでなく、そばで目視する必要もなくなったため、船員がロープに巻き込まれるといった事故のリスクもなくなるという。
開発した会社によると、こうしたデジタル技術の導入で船員の労働時間は従来の船と比べて2割程度、削減できるとしている。
その分仕事に余裕が生まれ、安全性が高まることも期待される。
本瓦社長
「デジタル技術の力で何とかして乗組員の負担を減らして、より仕事をしやすい環境を作りたい。ほかのさまざまな船舶に導入するのはまだ時間がかかると思うが、長年の課題の克服に向けて期待を持てる取り組みだ」
海事産業の集積地 四国に寄せられる期待
こうした取り組みに業界団体も大きな期待を寄せている。
安藤専務理事
「業界としてもデジタル化に注目しています。海外に荷物を運び運航距離が長い外航船は運転の自動化が求められますし、内航船は負担が重い荷物の積み降ろしの作業の省力化が必要です。デジタル化による業務の削減と若い人への魅力の発信という2つの課題を同時に解決できる船の開発は、内航海運業界全体にとっても大事な1歩になることは間違いないと思います」
今治を中心に海事産業の取材を始めてほぼ1年になる。造船会社からは中韓のライバル会社との激しい価格競争やコロナで商談ができないという窮状を聞いてきた。また、内航船の会社ではとにかく人が足りないという現実も目の当たりにした。
デジタル船は人手不足を解決する一助になるだろうが、貨物船と一口にいってもケミカルタンカーやコンテナ船、ばら積み船など用途によって形状はさまざまだ。最も時間がかかる荷役作業を軽減するには、それぞれに対応した技術が必要になるだろう。
四国ではほかにも、香川県と徳島県の造船会社が重油を使わずリチウムイオン電池で動く世界初の「電動タンカー」を建造することが決まっている。世界でも有数の海事産業の集積地で最新の動きを伝えていきたい。
捜索救助船「GEO BARENTS」(IMO9252503)は特殊な船なので難民や移民を乗せた船を救助するには向いているように思える。
本音がどうであろうがPSC(外国船舶監督官)による外国船籍船の検査は合法だし、問題を見つければ詳細な検査を行う事が出来るので問題ない。
出港停止命令や不備の是正を避けたいのであれば、誰が検査に来ても不備を発見できないように維持管理をしっかりするしかない。
個人的には経験豊富なPSC(外国船舶監督官)が不備を見つけようと思えば、よほどしっかりと維持管理されていない船であれば不備を見るける事は難しい事ではない。PSCによる検査の現状を理解すれば、不備が見つけられなかったから、不備がないわけではない。
(CNN) フランスの医療支援団体「国境なき医師団(MSF)」は、地中海で難民や移民400人以上を救助してきた捜索救助船がイタリア当局に差し押さえられたと発表した。人命が危険にさらされかねないとして早期解放を訴えている。
MSFの4日の発表によると、捜索救助船の「ジオバレンツ」は今月2日、シチリア島のアウグスタ港で当局に差し押さえられた。
イタリア沿岸警備隊は、同国の港に入港する外国船に対して行っている「定期点検」の結果、「乗員や乗客の安全を脅かしかねない技術的な不備」が見つかったと説明する。
同船はゴムボートや救命胴衣といった救命具の装備が不十分だったと沿岸警備隊は説明。14時間に及んだ点検で計22件の問題が見つかり、そのうち10件を理由に同船を差し押さえたとしている。
MSFは、「必要な調整は全て行う用意がある」としながらも、イタリア港湾当局が人命救助を目的とした同船の出航を阻むため、異常を発見する狙いで長時間に及ぶ徹底検査を行ったと主張。「人道支援団体の船が差し押さえられ、その間にも地中海では人命が不必要に失われ続けている」とした。
イタリアには欧州を目指す移民や難民が押し寄せている。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は5月の時点で、今年に入って少なくとも500人が、地中海を渡る危険な航海の途中で命を落としたと発表した。死者は前年同時期の150人に比べて3倍以上に増えている。
韓国でフェリーが建造されているが大丈夫なのだろうか?
例えば、台湾では沿海区域でも波が高いので、日本の瀬戸内海を想定したフェリーでは運航が難しいと聞いたことがある。
ニュージーランドがどのような規則なのか知らないが、規則が厳しければ、中国と韓国で運航されている韓国建造のフェリー(NEW GOLDEN BRIDGE Vll)を参考に出来ない場合もあると思う。この船、NEW GOLDEN BRIDGE V(RAINBOW LOVE)に似ていると思うは自分だけだろうか?

KiwiRail has signed an agreement with Hyundai Mipo Dockyard to deliver two ships, for a price $150 million above funds set aside in the Budget.
The contract for the two new Cook Strait ferries has been awarded to South Korean shipyard Hyundai Mipo Dockyard.


Mikhail Voytenko
One of the containers on cargo deck of Chinese cargo/passenger ferry NEW GOLDEN BRIDGE VII caught fire in the evening May 27 at Incheon, Korea, when the ship was about to set sail, bound for Weihai, China. All 420 passengers left the ship, fire was extinguished in less than an hour, the ship left Incheon at night same day. Cargo deck reportedly, sustained some non-detainable damages, several containers near the one on fire were also damaged.
Passenger ro-ro cargo ship NEW GOLDEN BRIDGE VII, IMO 9813254, GT 30322, built 2018, flag Panama, manager WEIDONG FERRY CO LTD, China.
この手の問題は新しい問題ではない。中国が苦しむのなら韓国だって同じ。後は、単純に大型船を建造している造船所が一番影響を受ける事になる。最後に、効率の良い仕事を受注しているのか、儲からない契約を仕方がなく取っているかで、さらに影響の違いがあるであろう。
鋼材価格の上昇が続くなか、中国の造船業界は厳しいコスト環境にさらされている。5月18日、国有造船大手の中国船舶集団(CSSC)は決算説明会で「新造船の受注価格は多少上がったものの、造船に用いる鋼材の値上がり幅のほうが大きく、利益率に悪影響を及ぼしている」と説明した。
ある国有造船所の関係者は財新記者の取材に対し「2万4000TEU(20フィートコンテナ換算)級のコンテナ船を例にとると、船体価格は約1億5000万ドル(約163億5000万円)になる。それに対して建造に必要な鋼材の値段は近年2000万ドル(約21億8000万円)以上も跳ね上がり、船体価格に占める鋼板価格の割合が昨年末の25%から40%近くまで上昇した」と語った。
造船業界はもともと利益が薄く、鋼板などのコスト上昇は利益を大きく圧迫する。「今年は利益を出すのが難しい。赤字にならなければラッキーだが、今受注している仕事の大部分は、鋼板価格の上昇により赤字回避は難しそうだ。だからと言って受注しなければ、ドックの確保もできず、生産も止まってもっと赤字になる。造船所は仕方なく受注している状況だ」。前出の国有造船所の関係者は、そう溜息をつく。
鋼材メーカーと船主の板挟み
また造船業は国際競争が激しく、生産能力も過剰気味になっている。「船主は世界各地の多数の造船所から見積もりを取って価格を比較する。なかでも韓国の造船所は強力なライバルだ」(前出の国有造船所の関係者)。
一般的に造船契約は変更がきかず、契約時に船主と造船所の間で価格、支払い条件、引き渡し時期を決めてしまえば、契約期間中の原材料価格の上昇、為替変動などのリスクはすべて造船所が引き受ける。そのため、造船市場が好調なときは、船の価格と支払い条件は造船所にとって有利に働くが、市場が低調なときは船主に有利となる。
造船業界における鋼板の仕入れに詳しい別の関係者は、「現在中国の鋼材市場は供給不足の状況にある。造船所は鋼材価格の値下げ要求に聞く耳を持ってもらえなくなった」と語る。
そのうえで、この関係者は「造船所は厄介な立場に置かれている。船の値段は船主の言いなりで、鋼材価格も鉄鋼メーカーの要求を受け入れるしかない。造船所は間に挟まれて耐えがたい状況に追い込まれている」と漏らした。
(財新記者:賈天琼)
海運業の好況で船の発注が急増 受注-売上の時差で造船会社の業績は後退 現場では鉄板価格が上がり、収益悪化を懸念
「造船業が没落の危機から圧倒的な世界1位として復活しました」
文在寅(ムン・ジェイン)大統領は今月10日、就任4周年演説でこのように強調した。一時は受注の崖に直面した韓国の造船会社が再び蘇ったという話だ。
しかし、数字に表われる企業業績や業界の雰囲気は全く異なる。現場でもまだ追い風を体感していないという声があがっている。
受注だけを見れば、造船業の復活を語れそうにみえる。11日、業界によると、今年第1四半期(1~3月)の国内造船会社の受注量は532万CGT(船舶建造量指標である「標準貨物船換算トン数」)で、昨年第1四半期に比べ868%増加した。同期間の新規受注額も119億ドルと、753%伸びた。各造船所のドック(船を作る作業場)は一杯になり、各造船会社は2年分の仕事(受注残高)を積んだ。
これは前方産業である海運業の好況のおかげだ。新型コロナ流行以降、物流が増加して海運運賃も跳ね上がり、海運会社がこれまで見合わせてきたコンテナ船の発注を大幅に増やしたからだ。実際、サムスン重工業は今年3月、台湾の海運会社エバーグリーンから単一契約では過去最大規模のコンテナ船20隻を一度に受注した。
船舶価格も跳ね上がっている。英国の造船・海運市況分析会社のクラックソンリサーチの資料によると、世界市場で新しく生産された船舶価格を指数に換算した新造船価格指数は今月134で、2015年2月以来6年ぶりの最高値を記録した。造船所ドックの空きがなくなり、造船会社の交渉力が大きくなったことが影響した。
営業実績はこのような流れとははっきり異なる。年初に大量の受注を受けたサムスン重工業は、今年第1四半期だけで5千億ウォン台の営業赤字を出した。悪性在庫として抱えている海洋掘削船(ドリルシップ)の評価損失2100億ウォン(約204億円)と、新規受注物量の追加損失予想額(工事損失充当金)1200億ウォン(約117億円)などが反映された。信用格付け会社のある関係者は「受注直後に予想工事原価が大幅に増えたというのは、昨年、受注の崖に直面した際にドックをまず一杯にするために低価格で受注したことを意味する」と述べた。会社側は、再来年になれば営業黒字へと転換できると予想している。サムスン重工業の株価は、第1四半期の業績発表(5月4日)後、19%も急落した。
世界1、2位の造船会社である韓国造船海洋と大宇造船海洋も状況はそれほど変わらない。韓国造船海洋の今年第1四半期の営業利益は675億ウォン(約66億円)と、昨年第1四半期に比べて45%減少した。市場ではまだ実績を公開していない大宇造船も、第1四半期にやっと営業黒字を出したと推算している。
このように受注と業績との乖離が生じるのは、受注産業である造船業の特徴のためだ。船舶の場合、受注から設計、建造、引渡しまで1~2年かかるため、現在の造船会社の売り上げと利益とされるのはほとんどが受注不足に陥っていた過去の契約の物量だ。当時受注した船舶価格も高くなかったため、当面は利益率の改善も期待しがたい状況だ。
造船会社は船舶建造期間中に発注先から請負費を分けて支給され、会計も工事の進行率によって売上と利益を分けて反映する。
最近、船舶製造に入る厚板(厚い鉄板)の価格が鉄鉱石の品薄の影響で大幅に値上がりしている状況も、造船会社としては好ましくない流れだ。収益性に否定的な影響を与えるためだ。今年に入って受注したマージンの良い工事収益は1~2年後から本格的に反映されるが、原材料価格の上昇は直ちに実績に悪影響を及ぼしうるということだ。実際、サムスン重工業と韓国造船海洋が今年第1四半期に船舶製造に使う鋼材価格の引き上げの影響により追加で反映した費用は、それぞれ1千億ウォンを超える。
ある大手造船会社の関係者は、「内部的には、現在の受注好況が少なくとも今年下半期まで続けば、来年以降の売上と利益の改善につながるとみている」と語った。SK証券のユ・スンウ研究員も「昨年コロナの影響で遅延した船舶発注物量が年初に一気に殺到し、造船業況がV字に反騰するような錯視効果が生じた」とし「2004~2008年のような造船業の好況が再び訪れるのは、少なくとも以前の好況期に発注した船舶が大量に交替時期を迎える2024年以降になるとみられる」と述べた。
パク・ジョンオ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
「特にこの3隻のうち2隻は当初韓国所有だったことから、これら船会社が制裁を違反していなかったか調査を受ける可能性もある。販売する船舶の所有権が最終的に北朝鮮に渡るかもしれないことを事前に認知していたとすれば、韓国船会社や仲介人も制裁を違反していた可能性がある。」
まあ、よほどの証拠がない限り無理だろう。売り手は転売されるのかどうかを知る必要はない。お金さえ、支払われれば問題ない。北朝鮮に転売した会社は、売り手に北朝鮮に売ると言う必要はない。
例えば、北朝鮮に売られると知っていれば、証拠が残らないように動くから内通者がいなければ事実確認は無理だと思う。おとり捜査が可能で、おとり捜査をしない限り無理だと思う。
北朝鮮が国連安全保障理事会の制裁を避けて一昨年からタンカー3隻を購入していたという研究報告書が公表された。3隻はともに中国仲介業者を経て引き渡されたが、このうち2隻はかつて韓国企業の所有だったことが確認され、制裁違反の懸念が提起されている。
米戦略国際問題研究所(CSIS)傘下のアジア海洋透明性イニシアチブ(AMTI)は1日(現地時間)、「北朝鮮は制裁にもかかわらずタンカーを調達している」と題する報告書を公開した。
報告書や国際海事機関(IMO)ホームページによると、昨年10月「シンピョン5号(Sin Phyong 5)」というタンカーが北朝鮮船舶として登録された。この船舶はかつて釜山(プサン)に位置した韓国船会社の所有だったが、2019年7月27日に韓国から中国北東沿岸の王家湾に移動した。
シンピョン5号は、現在平壌(ピョンヤン)にあるミョンリュ貿易(Myongryu Trading)の所有になっている。米財務省と国連安保理北朝鮮制裁委員会の専門家パネルは、ミョンリュ貿易が所有している別の船舶である「ミョンリュ1号(Myong Ru 1)」が油類の密貿易に加担していた情況を確認した。ミョンリュ貿易がシンピョン5号を購入したのもやはり同じ目的で使おうとしているかもしれないという指摘が出ている理由だ。
2019年11月に北朝鮮所有となった「クァンチョン2号(Kwang Chon 2)」もかつて韓国船会社が所有する船舶だった。「クァンチョン2号」は、北朝鮮南浦港(ナムポハン)で10回にわたって油類を積み出していたことが確認されている。
昨年北朝鮮が追加で購入した「ウォルボンサン(Wol Bong San)」はかつて香港にある企業が所有する船舶だった。「ウォルボンサン」もまた、国連安保理専門家パネルの調査の結果、南浦港に移されていることが確認された。また、2017年から2020年まで北朝鮮の船舶間の瀬取り場所としてしばしば使われてきた中国舟山湾の東側地域を何度も行き来していた記録も確認された。
これに先立ち2017年12月、国連安保理決議2397号は北朝鮮が搬入できる精製油を年間合計50万バレルに制限した。また国連加盟国が北朝鮮に精製油を提供する場合、量を報告するようにしている。
また、2016年11月に採択された国連安保理2321号は北朝鮮に新規船舶を販売あるいは供給・移転する行為そのものを禁止している。北朝鮮はタンカー3隻を調達することができたこと自体が制裁回避行為ということだ。
特にこの3隻のうち2隻は当初韓国所有だったことから、これら船会社が制裁を違反していなかったか調査を受ける可能性もある。販売する船舶の所有権が最終的に北朝鮮に渡るかもしれないことを事前に認知していたとすれば、韓国船会社や仲介人も制裁を違反していた可能性がある。報告書を作成したレオ・バン研究員は「中国で活動する船舶購入者は明らかに国連制裁を違反しており、(彼らに船を売った)韓国の仲介業者などもあわせて制裁を違反したとみるかどうかは、業者が中国側に対する実態調査作業をどのように進めたかにかかっている」と分析した。
一方、ボイス・オブ・アメリカ(VOA)放送は2日の報道で、北朝鮮が南浦港に新たな油類荷役施設を建設しているが、既存の施設に出入りするタンカーは今年に入って2隻にとどまるなど、事実上タンカーの往来はほぼ途絶えていると分析した。新型コロナウイルス感染症(新型肺炎)事態による外貨枯渇と国際社会の制裁で油類の搬入が難しくなった状況でも、北朝鮮が中国を通じてタンカーを調達するなどでして制裁を避けているという懸念が出ている。
【ソウル聯合ニュース】米シンクタンク、戦略国際問題研究所(CSIS)傘下のアジア海洋透明性イニシアチブ(AMTI)は3日までに、韓国企業が一時所有していたタンカー2隻を北朝鮮が中国を通じて購入したとする報告書を公開した。
国連安全保障理事会の対北朝鮮制裁決議は北朝鮮に対する直接的・間接的な船舶の供給を禁じており、状況によっては韓国企業が制裁違反に問われる可能性も提起されている。
報告書は、北朝鮮が2019~20年に中国からタンカー3隻を購入したが、そのうち2隻は過去に韓国企業が所有していたものであり、中国を経由して北朝鮮に入ったと説明した。
国連安保理は16年に対北朝鮮制裁決議で加盟国が新品の船舶を北朝鮮に直接的・間接的に供給、販売、移転することを禁じており、17年にはこの条項を中古船舶にも拡大した。
船舶が中国を経て北朝鮮に入ったとしても、韓国企業や仲介業者が船舶の最終所有主が北朝鮮であることを知っていたとすれば間接販売に当たり、制裁違反と見なされる余地がある。
報告書を作成した研究員は、米政府系放送ボイス・オブ・アメリカ(VOA)のインタビューで「国連安保理決議は船舶をはじめ、物資を直接的・間接的に北に流入させることを禁止している」とし、「韓国政府がこれを厳格に適用すれば、韓国の仲介業者が注意義務を怠ったかどうかを確認する可能性もある」と説明した。
また、取引に介入した韓国の仲介業者が制裁に違反したと見なすかどうかは、韓国政府がどのように解釈するかにかかっていると述べた。
報告書は、「この船舶は韓国の仲介業者を通じて中国の企業や個人に渡った」として、関係者は機密を理由に口を閉ざしていると指摘。昨年タンカー2隻を購入したように、今年も新たな船舶を容易に購入できるだろうとの見方を示した。
韓国外交部の当局者は「政府は国際社会との緊密な協力と国連安保理決議下で(制裁順守の)努力を傾けている」とし、「北の安保理制裁回避の動向を注視しており、現在確認中だ」と述べた。
報告書は、北朝鮮が購入したタンカーは国連の制裁で搬入量が制限されている石油精製品を秘密裏に運ぶために使われたと推定している。
国連安保理は17年に採択した北朝鮮に対する制裁決議で、北朝鮮が1年に搬入できる石油精製品の上限を計50万バレルに制限し、国連加盟国に毎月北朝鮮への石油精製品の供給量を報告させることを決めた。
だが、北朝鮮は海上で船舶間の積み荷を移し替えて密輸する「瀬取り」などの方法を用いて制裁の網をかいくぐっているとされる。
松田史朗
【広島】造船中堅の神田造船所(呉市)が来年1月、主力の造船事業から撤退する。資材高騰による中国や韓国メーカーとの価格競争激化が主因だ。呉市では2023年に日本製鉄瀬戸内製鉄所呉地区が閉鎖の予定で、地域のさらなる雇用悪化を懸念する声もある。
撤退するのは売り上げ約150億円(20年度)の約8割を占める主力の造船事業。同社の造船技術は業界での評価が高かったが、来年1月の建造船の出荷を最後に事業を終える。5年ほど前から中韓メーカーとの競争激化で赤字が続き、5月下旬の役員会で事業からの撤退を決断した。
事業撤退後の主な売り上げは修繕や検査事業で、同社は年30億円程度とみる。ただ、同分野は民間からの受注が好調で黒字が続く。事業を特化することで営業拡大につなげる考えだ。
一方、従業員320人のうち造船事業に携わる人員が約3分の2を占め、雇用悪化への不安は拭えない。今後の配置転換や再就職先支援については労働組合と協議中で「結論を得るまで数カ月かかる」(役員)という。
呉市産業部商工振興課の担当者は「雇用への影響は当然出ると思う。メインバンクの広島銀行と話し合って経営を進めると聞いているが、市としても何らかの対策を考えたい」としている。(松田史朗)
【カイロ時事】エジプトのスエズ運河で3月に正栄汽船(愛媛県今治市)所有の大型コンテナ船「エバーギブン」が座礁した事故で、運河を管理するスエズ運河庁が船主らに求めている損害賠償額について、当初の9億1600万ドル(約996億円)から約6億ドル(約652億円)への減額を提示したことが10日、明らかになった。
【写真】スエズ運河での所有船の座礁を受け、記者会見で謝罪する「正栄汽船」の桧垣幸人社長
ただ、コンテナ船の船主責任保険を引き受けている事業者「英国クラブ」は時事通信の取材に「依然として法外な請求で、根拠も示されていない」と回答し、解決の見通しは立っていない。
運河庁はこれまで、コンテナ船離礁作業などの費用や「(運河の)評判を損ねた」とする名目で賠償を要求していたが、反発する船主や事業者との交渉は難航。エジプト側は賠償金が支払われるまで船の航行を認めない決定を下し、船主側による異議申し立てもエジプトの裁判所に退けられた。
どこの設計会社が設計したのだろうか?旅客船を設計した経験が少なかったのだろうか?それとも安い見積もりを出した設計会社を選んだのだろうか?安い見積もりで設計を受注すれば、似たような船を設計した経験がなければ、重量を計算せずに例えば、萩海運の所有している三菱重工で建造された船の係数で推測したのかもしれない。このような問題はないわけではない。船を軽くするために船の一部をアルミにした変更した宮島のフェリーのケースだってある。巡視船発注したら…重すぎて速度出ず 納品断念 川崎 01/28/18(朝日新聞)のケースもある。
船の建造や船の設計はかなり能力があるか、経験がないと失敗する可能性が高い。中国で建造される船の多くは酷い船が多いが安いと言う事で実績を積み上げてきた。経験と日本が技術支援したりして、船の品質は確実に良くなっている。経験によって学ぶ、又は、学べる事は業界や会社の業務内容によっては重要な要素だと思う。
それは日本でも同じ。建造実勢があまりなければ能力がある設計会社を選択する事で問題を解する事は出来る。しかし、経験があまりない造船所だとチェックする項目が増える可能性が高く、外注する複数の設計会社の図面や情報に間違いがないかチェックする無駄な項目が増えたりするので、競合する設計会社が安い見積もりを出すからと言う事でチキンレースに参戦すると損をしたり、今回のような事に巻きまれる可能性はある。造船所が損をすれば、絶対とは言えないが、設計費用は支払わないだろうし、正式な契約書がなくても損失が大きいので損害賠償を造船所の経営者次第では要求されるかもしれない。仕事をして費用が回収できないのであれば、仕事を取らない方が結果論であるが良かったかもしれない。
昔に比べて規則の変更が多く、複雑になってきている。絶対数で設計の経験者が減ってきているので通勤できる範囲で探すのが難しかったり、知識がない新卒を育てるだけのゆとりもないと思うので、今後、同じような問題はこれまで以上に起きる可能性はあると思う。海運と造船はある一定程度の人材は必要とは思うが、今後も減って行くと思う。アメリカやオーストラリアのように競争力がなくなり、造船所が激減して、船齢30年とか40年の船を修理しながら使うようになるかもしれない。まあ、日本はそこまでなるとは思わないが、ビートルのような船でなくても、これまでのようには建造できなくなると考えた方が良いと思う。
中川壮
山口県萩市の離島と本土を結ぶ旅客定期航路を運営する第三セクター「萩海運」(社長=田中文夫市長)は23日、建造中の新船の船体重量が計画より大幅に超過する建造ミスがあったと発表した。このままだと人や荷物を計画通りに運べないため、造船会社との建造契約を解除し、改めて別の会社と契約を結び直す方針という。
新船は相島と萩港を結ぶ相島航路で、6月に就航予定だった。現行の船を6月以降も使用するため、航路の運航に支障はないと萩海運は説明している。
萩海運などによると、新船の建造は2020年7月、萩海運と鉄道建設・運輸施設整備支援機構が共同で、鈴木造船(三重県)に8億7527万円で発注した。今月9日にあった進水式で船が沈みすぎたため確認したところ、船体の重さが計画の約154トンより約49トン超過していた。装備品などの重量確認が不十分だったとみられる。鈴木造船が22日、契約解除を申し出た。新船引き渡し期限は5月末だった。
萩海運は市が95・5%出資する有限会社。田中市長は「一日も早く新船が就航されるよう市としても支援していく」とのコメントを出した。(中川壮)

萩市の離島、相島と本土を結ぶ航路に就航予定だった新造船「あいしま」の重量が設計より約50トンオーバーしていることが判明し、運航する第三セクター萩海運などが発注先の鈴木造船(三重県)と請負契約を解除する手続きを進めていることが分かった。改めて別の業者に発注し直すため、老朽化が進む定期船「つばき2」を引き続き使用することになる。
萩海運によると、1990年に就航したつばき2の老朽化に伴い、後継となる新船を発注した。新船建造は公募型プロポーザルを実施し、唯一応募があった鈴木造船に決まった。萩海運と横浜市の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道・運輸機構)が共同で昨年7月、鈴木造船に8億7527万円(税込み)で新船建造の請負契約を結んだ。6月1日に就航予定だった。
ところが、9日に三重県で行われた進水式で海に浮かんだ新船を見た関係者が「沈みすぎなのでは」と指摘。鈴木造船が詳細を確認したところ、何も積んでいない状態の重量が計画では約154トンだったのに、実際は約203トンと約50トン超過していることが判明した。船内の各種装備の重量を十分に計算していなかったことが主な要因という。
別の業者に発注へ
船体が重量オーバーだと、計画より速度が出にくくなる上、燃費が悪くなるなど性能面でもさまざまな問題が生じる可能性がある。萩海運と鉄道・運輸機構は鈴木造船と契約破棄の合意を正式に結んだ後、改めて別の業者に新船建造を発注するという。
萩海運の社長を務める田中文夫市長は「計画と大きく乖離(かいり)する問題が発生したため契約を解除せざるを得ず、非常に残念。新船の就航を待ち望んでいた相島地区の皆さんには、誠に申し訳なく感じている。一日も早く新船が就航されるよう市としても支援していく」との談話を出した。
(木島優輔)
萩海運(山口県萩市)は23日、萩市の離島・相島と本土を結ぶ新しい定期船の重量が計画より大幅に超過し、建造した鈴木造船(三重県四日市市)との契約を解除すると発表した。6月に予定されていた就航は白紙になった。
萩海運によると、4月9日に四日市市であった進水式に出席した社員が、船体が大きく水面下に沈んでいることを不審に思い、同社と共同で建造を発注した独立行政法人の鉄道建設・運輸施設整備支援機構(横浜市)に相談。機構が調査したところ、重量が当初の計画の約154トンより約49トン重くなっていると判明した。船体が重いと船底が海底に接触するなどして運航できないため、機構と鈴木造船が協議。船体の改良では対応できないため、鈴木造船は22日、機構側へ契約解除の意向を伝えた。。
船舶用プロペラ大手のナカシマプロペラ(岡山市東区上道北方)がドイツの大手船舶用機器メーカーを買収したことが12日、分かった。大型船のかじやプロペラの前に取り付ける省エネ装置で世界トップ級のシェアを持つ「ベッカーマリンシステムズ」。主力のプロペラを含め、船舶の推進力や燃費を左右する船尾周辺設備の一貫製造で相乗効果を発揮し、業容拡大を目指す。
関係者によると、ベッカー社の株式の51%を3月31日、完全子会社ナカシマヨーロッパ(オランダ)が取得。経営トップは引き続きドイツ人に任せるが、役員を選任する経営委員会を新たに設け、定員5人のうち3人を中島崇喜社長らナカシマプロペラ幹部が占める。買収額は不詳ながら、同社にとって過去最大の投資という。
ベッカー社は1946年設立、売上高80億円(2020年12月期)、従業員115人。祖業のかじと、プロペラ周辺の水流を整えて燃費を改善する船尾ダクトで世界的大手。ナカシマプロペラとは1978年から日本国内の独占代理店契約を結んでおり、協業をより深めるため2019年末から交渉していた。
ナカシマプロペラは近年、独自に船尾ダクトを開発、製造。ベッカー社を子会社化したことで競合を解消し、設計や営業部門などを統合して効率化する。加えて、ダクトからプロペラ、かじに至る推進設備をグループで統合的に開発できる体制を築き、顧客の造船所や船主に売り込む。
海運業界では、環境規制の強化で燃費改善へのニーズが高まっている。ベッカー社は新造船に加え、就航中の船舶へのダクト追設も得意。プロペラは新造船向けが主だが、今後は就航船に対しても交換などをダクトとセットで提案し、収益の底上げを狙う。
ナカシマプロペラは1926年創業、資本金1億円。売上高216億円(2020年11月期)。従業員422人。プロペラの国内シェアはほぼ100%、世界シェアは約30%。ナカシマヨーロッパは2月、海外事業の強化のため設立した。
LNG船を建造しているのだから修理は可能だと思うが、LNG船の建造や修理の経験がない造船所だった、利益度外視で修理をやっても上手く行くかは?だと思う。
韓国ガス公社は、現在保有しているLNG船舶についての定期修理を国内造船所に委託することにしたと、5日に明らかにした。
定期修理は、安定的なLNG輸送のために運航中の船舶を5年に2回、定期的に陸上で検査・修理することを指す。韓国ガス公社は、これまで人件費が抑えられるシンガポールやマレーシアなどの海外造船会社に修理を委託してきたが、最近の新型コロナウイルスの長期化により海外での修理が難しくなり、昨年に約84億ウォン(約8億2300万円)をかけて韓国国内の造船所で船舶7隻の修理を成功的に進めた。韓国ガス公社は今回、キョンサンナムド(慶尚南道)と国内造船所などと緊密に協力して、修理設備の補強、関連技術の伝授など、これまで設備・経験不足で困難を経験してきた国内LNG船舶の修理分野を支援するための多様な方案を推進することにした。今回の修理をきっかけに、造船業界の雇用創出はもちろん、修理費の外貨流出を防止することにつながり、新型コロナウイルスで低迷した国内景気の活性化に向けた役割を果たすものと期待している。
韓国ガス公社関係者は「今年に国内の造船所で修理予定のLNG船舶は計12隻である」とし「今後も国内造船業の育成のために修理需要を持続的に確保するために努力していく」と述べた。
外国の要求をそのまま受け入れるのは良くないと思うが、最終的には、関係者の考え、どのような選択があるのか、どのような人脈があるのか次第で結果の出し方が違うので関係者次第だと思う。
エジプト当局がスエズ運河を塞いだ大型コンテナ船「エバー・ギブン」の座礁事故に対して、10億ドル(約1106億円)以上の損害賠償を請求する予定だと、米国経済メディアCNBCが2日報道した。
【写真】もっと大きな写真を見る
スエズ運河管理庁(CSA)のオサマ・ラビ局長は先月31日、エジプト放送「サダエル・バラード」とのインタビューで、「われわれは10億ドル以上の賠償金を受け取る」と述べた。
ラビ庁長は、「賠償金額は運河の収入損失を始め、引き上げ装備や船舶引き上げに投入された救助隊員800人の人件費を根拠にしたものだ」と説明した。
ラビ庁長は「2~3日内に補償合意がなされることを願う」とし「、もしそうでなければ、現在整備点検を受けているエバーギブン号はグレートビター湖で抑留されるだろう」と述べた。
続いて「われわれはいかなる補償にも合意することができ、そうでなければ法廷に立つこともできる」と警告した。ただ、ラビ庁長は、どこに賠償金を請求するかは明らかにしなかったとCNBCは伝えた。
2018年に建造されたパナマ船籍のエバーグリーン号は日本の正栄汽船がオーナーで、台湾のエバー・グリーンが傭船社となっている。
CNBCによると、台湾のエバー・グリーンは「運送中だった貨物遅延の責任を負わない」とし、所有者の正栄汽船は「CSAと補償問題を話し合うが、今のところ、詳しい内容は公開しない」と明らかにした。
三菱重工業は30日、主力の長崎造船所香焼(こうやぎ)工場(長崎市)の新造船エリアを、国内造船大手の大島造船所(西海市)に売却する契約を締結したと発表した。4月から段階的に譲渡を始め、2022年度内に完了する。売却額は非公表。中国や韓国勢の台頭で収益力が悪化しており、液化天然ガス(LNG)運搬船など大型船事業の建造から事実上撤退する。
香焼工場のうち修繕を手掛けるドックなどは残す。約600人の従業員は、社内の配置転換や大島造船への転籍などを検討している。三菱重工の造船所は長崎市内に二つあり、祖業の地とする本工場は維持する。今後は防衛省向けの艦艇事業やフェリーなどの民間用船舶事業に注力する。
香焼工場は大型タンカーの量産のため1972年に建設され、同社最大規模の1000メートルのドックを持つ。国内造船業界は再編が相次いでおり、首位の今治造船(愛媛県今治市)と2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市)が資本提携している。
◇「県内造船業の振興に寄与」 中村知事
三菱重工業長崎造船所香焼工場の新造船エリアが大島造船所に売却されることが正式に決まったことを受け、関係者からはさまざまな声が上がった。
中村法道知事は「県内経済への影響も考慮いただいたと受け止めている。日本を代表する造船所の香焼工場が、世界トップクラスのバルク船の建造量を誇る大島造船所に活用されることは、県の造船業の振興に寄与するものと期待している」とコメントを出した。
三菱重工業は香焼工場の従業員の処遇については「検討中」としており、工場で働く30代の男性従業員は「社員の今後に真摯(しんし)に向き合ってほしい」と要望した。【田中韻】
経営再建中の三井E&Sホールディングス(HD、東京)は29日、防衛省向け艦艇事業を三菱重工業(東京)に譲渡する契約を結んだと発表した。商船事業は常石造船(福山市)との資本提携で大筋合意し、完全子会社・三井E&S造船の株式の49%を売却する方向で詰めている。それぞれ10月1日に新体制に移行する予定。中核拠点の玉野事業所(玉野市玉)の造船事業は大幅に縮小し、船舶用エンジンなどで生き残りを図る。
【図表】三井E&Sの造船事業
三菱重工に譲渡するのは、防衛省の艦艇や海上保安庁の巡視船といった官公庁船。玉野の生産設備の一部を移管し、三菱重工が玉野で建造や修繕を続ける。譲渡額は非公表。三井E&SHDは財務の改善などに充てる。玉野では主に「補助艦」と呼ばれる補給艦や輸送艦を手掛けており、護衛艦や潜水艦が中心の三菱重工は船種の拡大を図る。
ばら積み貨物船などの商船事業は、常石造船と主要な条件で合意した。さらに細部を協議し、4月下旬の最終契約を目指す。10月以降も船舶の設計などは続けるが、建造は常石造船がフィリピンや中国に持つ工場か、中国大手・揚子江船業との合弁工場に委託する方針。
10月以降、玉野に勤める三井E&S造船の従業員約700人のうち、約300人は三井E&Sグループ内で異動。約400人が三菱重工グループへ転籍となり、いずれも玉野で勤務する見込み。
3回のPCR検査はすべて陰性で4回目で陽性になるケースがある限り、クルーズビジネスの将来は厳しい。多くのお客が乗り込むので、1人でも感染者がPCR検査をすり抜けてしまうと、他の人達に感染させるリスクがあり、閉鎖された環境なので感染が広がるリスクが高い。フェリーでも単に移動手段として利用であれば、個室を増やせばリスクは減らすことが出来るが、クルーズ船は楽しむことがメインなのでこれまでのような環境は期待するのは難しいし、自由度を上げるとリスクが高くなるジレンマが存在すると思う。
郵船クルーズは18日、横浜港大さん橋国際客船ターミナルに着岸中のクルーズ船「飛鳥Ⅱ」(5万444トン)で、外国籍の乗組員1人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同船は1月4日からクルーズを休止しており、船内に乗客はいなかった。
同社によると、感染した乗組員は居住国出国前(3月1日)、日本入国時(同月3日)、飛鳥Ⅱ乗船時(同)に実施した3回のPCR検査はすべて陰性だった。3日以降は船内で勤務し、せきの症状があったため検査したところ、16日に感染が判明、現在は船外で療養中という。船内に濃厚接触者はいなかったが、接点のある乗組員47人を検査し全員の陰性が確認された。今後、全乗組員約400人を検査する。
同社は19日からクルーズを再開する予定だったが、23日までに出発予定の三つのクルーズは中止とした。
【釜山聯合ニュース】韓国南部・釜山と日本を結ぶ国際旅客船を運営する韓国の船舶会社が日本旅行のボイコットに続く新型コロナウイルス感染拡大の影響で倒産の危機に立たされているとして、支援を訴えている。
釜山港国際旅客船協議会によると、日本による対韓輸出規制強化への反発から日本旅行のボイコットが始まった2019年7月から同年末までの期間、釜山と日本を結ぶ旅客船の乗客は前年同期比で約8割減少し、20年は新型コロナウイルスの影響で客足がほぼ途絶えた。
釜山港国際旅客ターミナルから対馬や福岡、大阪、下関を訪れた乗客は18年の約142万6000人から19年は約93万2000人、20年は約6万人と急減した。新型コロナウイルスが拡大した20年4月以降は乗客が一人もいないため、高速旅客船はいずれも運航を停止し、カーフェリーは貨物を輸送している。
この間、高速旅客船会社6社のうち2社が廃業した。残りの船舶会社も従業員の大多数が無給休職に入るなど、深刻な資金難に陥っている。協議会の関係者は「船舶会社は資産売却、構造調整など生き残りに必死になっているが、流動性不足によりもう耐えられない限界状況に到達した」と述べた。
協議会側は船舶会社の存続のためには実質的な支援が必要として、海洋振興公社が船舶会社から船舶を買い取った後、貸し出す方式の支援などを求めている。
県は27日、新たに今治市の1人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。今治造船で発生したクラスター(感染者集団)の関係者で、県内の感染確認は計1062人となった。重症者は現在1人。
県によると、新たに感染が判明したのは仕事以外の関係者で、これまでの感染者の濃厚接触者として検査した。国外居住者を含む同クラスターの感染者は累計14人となった。年代や症状などの詳細は感染者数が5~10人程度に達した段階で後日、統計的に公表する。
この事例では26日時点で仕事関係者の調査や検査を完了していた。県は「囲い込みをしている中での陽性確認で、今治市で感染が拡大しているわけではない。気を緩めることなく感染回避行動を取ってほしい」としている。
県は県内で新たに1人が新型コロナウイルスに感染したと発表しました。
新たに感染が確認されたのは今治市の1人で、今治造船のクラスターの関係者です。
別の陽性者と生活上の接触があった濃厚接触者として、2月23日に検査を行った際は陰性でしたが、その後症状が現れたため再検査したところ26日陽性が判明しました。
濃厚接触者が少なくとも1人いて、現在県が確認を進めています。
今治造船関連のクラスターはこれで14人となりました。
また、県内のこれまでの感染者は1062人となり、現在1人が重症です。
今治造船の仕事関係のクラスターの関連で、新たに3人の感染者が判明しました。
また、愛媛県は2月28日、ワクチンの集団接種の訓練を伊予市で行います。
今治造船によりますと、新たな感染者は既存の事例の3人です。
この事例は、今治造船に仕事で訪れていたバングラデシュ人の船員関係のクラスターで、今治市内の2人の仕事関係者と外国人の監督の感染が判明しました。
今治造船・渡部健司常務:
「乗組員の補助・手助けで接触の機会が多い3人だと思います」
今回の3人は陽性者と接触があったと思われる60人を検査し、感染が判明したとしています。
今治造船は濃厚接触者が多いため、業務への影響が大きいことを明かしました。
また、愛媛県は2月28日、ワクチンの集団接種に向けて、午前中の2時間に伊予市保健センターで訓練に取り組みます。
竣工した船に関連して新型コロナウイルスの集団感染・クラスターが発生した「今治造船」は、22日、今治市の本社で会見を開きました。
この中で担当者は、今回のクラスターでこれまでに感染が確認されたのは竣工したコンテナ船を海外へ運航するために今治市内に滞在していたバングラデシュ人の船員あわせて9人と、船員を指導していた外国籍の監督1人、それに船員の入国手続きや船に消耗品などを届けていた日本人の取引先の2人のあわせて12人だと説明しました。
県はこのクラスターでの感染確認は11人だとしていて、この理由について、今治造船は、取引先の2人のうち1人は、22日午後、検査の結果が判明したためだとしています。
今治造船の渡部健司人事総務本部長は「保健所や県と連携をとりながら感染拡大防止にむけて全力をあげていきます」と述べました。
今治造船(愛媛県今治市)は19日、バングラデシュから派遣された同国籍の船員7人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。新造船の出港準備のため今治市内に滞在し、船内作業に従事していた。接触した可能性のある他の船員や従業員ら約30人は、在宅勤務や自宅待機している。
今治造船によると、出港後に中国に入国するために必要なPCR検査で陽性を確認した。同社は「保健所や関係機関と連携しながら、感染拡大防止に最大限努力したい」とコメントしている。
佐世保重工業は組合が強かったので従業員の中にはそのDNAが残っていると何かの記事で読んだことがあるが本当だろうか?
佐世保重工業(SSK、佐世保市)は12日、2022年1月で中核の新造船事業を休止すると発表した。これに伴い今年5月から、希望退職者250人を募る方針。新造船需要と船価の低迷が長期化する中、収益改善に向け大規模な事業改革と人員整理を進める。
同社は14年10月に造船中堅の名村造船所(大阪市)の子会社となり、コスト競争力を強化。しかし、中国・韓国との価格競争にさらされ、20年3月期連結決算で4期連続の赤字を計上。新型コロナ禍で新造船需要が落ち込む中、競争力を短期的に改善させることは困難と判断し、同日の取締役会で休止を決定した。
既に受注している5隻の引き渡しが終わる来年1月以降、SSKで新造船はしない。今後、海上自衛隊の艦艇修繕船事業を売り上げの柱に据え、フェリーや一般商船の修繕にも取り組む方針。
同社の従業員数は現在約740人。子会社2社を含めると計約900人。新造船部門の従業員は、修繕船部門への配置転換や名村造船所への出向、転籍を進める。ただ、全員の配置先確保は困難な状況で、かつ人件費削減により収益性を高める必要もあるため5月6~21日の期間、希望退職者250人を募る。社としても転職を支援する。
同日、佐世保市内で開かれた記者会見で名村建介社長は「新造船事業の休止はSSKが生き残るための苦渋の決断。取引先をはじめ、地元のみなさまには多大なご心配とご迷惑をおかけする。艦艇修繕を柱に、収益基盤の強化、安定した事業の再構築を加速させる」と述べた。
◆需要低迷 抜本的な再構築へ
本県第二の都市の経済を長年支えてきたが、全社の3割近くの人員削減に踏み切らざるを得ないほど苦境にある。
造船業界は2010年ごろから供給過剰が常態化し価格が低迷。中韓メーカーによる安値攻勢が拍車を掛けた。さらに新型コロナウイルス禍で世界的に海上輸送需要が落ち込み、日本の20年受注量は前年に比べ、ほぼ半減した。
この間、SSKは名村造船所の傘下に入り、老朽設備の更新や伊万里事業所との一体運営など支援を受けてきた。だが主力の中型ばら積み船は中国との競合分野。コスト競争力の改善が見込めず、中核事業の抜本的な再構築を迫られた。配置転換や出向・転籍だけでは足りず、約250人の希望退職を募る。
今後は修繕事業と舶用機械事業を両輪に収益改善を急ぐ。新造ドックを修繕兼用に改修し、これまで取りこぼしていた修繕ニーズに応えるとともに「将来、伊万里の新造船事業を補完できる機能は残しておく」(名村建介社長)という。とはいえ、自衛隊や海上保安庁の南西警備に対応できる佐世保の「地政学的優位性」(同社長)がSSKのよりどころとなる。
佐世保重工業(SSK)の新造船事業休止が発表された12日、地元佐世保に衝撃と動揺が走った。250人規模の希望退職者も募る方針で、従業員は将来の生活を不安視。新型コロナ禍で地域経済は疲弊しており、経済界も「大きなダメージを受けるのではないか」と危惧する。
SSKは同日午後4時からの記者会見と前後し、従業員らに方針を説明した。従業員の30代男性は「やっぱりかという感じ。(事業休止は)何となく予想はしていた」と落胆。新規受注がなく、社内には先行きを案じる声が出ていた。会社存続のため「仕方ない」と理解を示す一方で「今後は本当に大丈夫なのか…」と不安を漏らした。
SSKは5月に250人の希望退職者を募る。「職場には若い世代が多いので心配。残っても地獄、辞めても地獄にならないか」。設計担当の40代男性は表情を曇らせる。SSK労組の大田保則執行委員長は「経営陣は(人員整理の前に)他にできることがあったのではないか」と疑問視。「SSKの中心にある新造船事業が消えてしまうのは悔しく、残念でならない」と肩を落とした。
佐世保商工会議所の金子卓也会頭は「事業運営体制の見直し・強化により、真の再建が実現されることを期待する」とコメント。ただ、地元経済への影響は非常に大きいとし「今後も雇用維持と、取引企業への配慮は引き続きお願いしたい」と注文した。
ある地元経営者は「新型コロナの影響でどの企業も疲弊している。地元企業だけで退職者の受け皿を用意するのも容易ではないだろう」と懸念を口にした。
造船中堅の名村造船所(大阪市)傘下の佐世保重工業(SSK、長崎県佐世保市)は12日、新造船事業を2022年1月で休止すると発表した。今年5月に250人の希望退職者を募集する。中国、韓国企業の台頭で競争力が低下し、新型コロナウイルスの感染拡大が受注減に拍車を掛けた。自衛隊の艦艇修繕と機械事業に経営の軸足を移す。
「日章丸」の進水式、今も語り草に=1962年7月(佐世保重工業提供)
佐世保市で記者会見した名村建介社長は「生き残るための苦渋の決断」と説明した。佐世保市に隣接する佐賀県伊万里市に名村の主力造船所があることから、SSKの造船設備はそのまま補完的に活用を続け、将来の新造船事業再開の余地を残す。
SSKは中韓勢の台頭や世界的な船舶の過剰供給による船価低迷などを背景に、14年に名村造船所の完全子会社となり、経営効率化やコスト削減に取り組んだが、新型コロナで新造船の需要が急減。設備の老朽化などもあり、競争力を短期間で改善するのは困難と判断した。
20年3月期決算では、新造船事業は売上高320億円のうち253億円を占める。従業員は今年1月時点で739人。うち新造船事業は359人で、他に管理部門などについても希望退職の対象とする。
SSKは1946年、旧海軍佐世保工廠(こうしょう)の設備を使い、佐世保船舶工業として創業。50~60年代はタンカー建造で活況を呈したが、70年代後半の造船不況以降は何度も経営不振に陥った。新造船売上高のピークは83年度の762億円。(宮崎省三)
「韓国人船長と船員は滞っている賃金の支払いを要求して航路を無断離脱したと船会社側はみている。ケイトンサン関係者は『船長や船員など4人の賃金が1月31日に入金されなければならなかったが入金できなかった』とし『すると4日、操業を中断して航路を無断で離脱した』と話した。韓国人船長や船員ら4人の月給は合計1250万ウォン(約118万円)だ。」
釜山(プサン)に本社を置く(株)ケイトンサンやこの船長について全く知らない。個人的な推測だが、この韓国人船長に重大に人格問題がないのであれば指示を無視する前にいろいろと会社の資金繰りが厳しい事を疑わせる事があったのではないのか?
例えば、船に運航に必要な部品、備品や食料が届かなくなった、又は、必要な物が要求しても支給されなくなった。現地の業者がばかでなければ、支払いが遅くなった、又は、支払いが期限内に支払われないなどを経験すると対応が悪くなる。韓国人船長が感が良い、又は、過去にも経営に問題を抱えた会社の対応を経験していれば強く出なければ給料が支払われないし、待っても会社が倒産すれば支払われない給料の額が増えるだけと判断したのかもしれない。
「釜山(プサン)に本社を置く(株)ケイトンサン関係者は9日、中央日報の電話取材に対して「今月5日、セネガル・ダカール港に入港するはずの漁船が入港を拒否してシエラレオネ側に逃走中」としながら「韓国人船長と船員が結託して船舶を奪取し、外国人船員を拉致した」と主張した。」
船員が会社と連絡を取れる状態ではないと思うので、船員は何も知らずに船長の命令を聞いている可能性は高いと思う。多くの日本人は船員に対する給料未払いは少ない、又は、このような問題を知らないと思う。ゴーン被告の逃亡先レバノンで今度は大火災…迫る「包囲網」に覇気を失う 09/15/20(日刊ゲンダイDIGITAL)の原因の原料は船主が放置した船の貨物だったそうだ。
韓国人船長・船員4人が船会社の入港指示を無視してシエラレオネ海域に逃走していることが確認された。漁船には韓国人船長と船員の他に外国人船員33人が乗船している。
釜山(プサン)に本社を置く(株)ケイトンサン関係者は9日、中央日報の電話取材に対して「今月5日、セネガル・ダカール港に入港するはずの漁船が入港を拒否してシエラレオネ側に逃走中」としながら「韓国人船長と船員が結託して船舶を奪取し、外国人船員を拉致した」と主張した。
航路を無断で離脱した漁船は、韓国の会社であるケイトンサンとアフリカに本社を置くSKトレーディングカンパニーの合作会社の所属で、規模は139トンだ。
船会社側はギニアビサウ港で操業中だった漁船が船会社の入港指示を無視して航路を離脱すると、5日ギニアビサウ当局に緊急手配を要請した。また、8日には在セネガル韓国大使館と外交部にも申告した。ケイトンサン関係者は「ギニアビサウ当局でインターポールに協力を要請した状態」とし「漁船の移動経路を追跡中」と話した。
韓国人船長と船員は滞っている賃金の支払いを要求して航路を無断離脱したと船会社側はみている。ケイトンサン関係者は「船長や船員など4人の賃金が1月31日に入金されなければならなかったが入金できなかった」とし「すると4日、操業を中断して航路を無断で離脱した」と話した。韓国人船長や船員ら4人の月給は合計1250万ウォン(約118万円)だ。
この関係者は「賃金の支払い遅延から4日で操業を中断し、航路を離脱したとみている」とし「SKトレーディングカンパニー側が船長と船員に入港を呼びかけているが、まだ交渉がうまく進んでいない」と話した。
漁船に乗船している外国人船員はインドネシア8人、ベトナム1人、ギニアビサウ10人、ギニア7人、シエラレオネ6人、ガーナ1人などとなっている。韓国外交部が9日、船会社を通じて外国人船員と韓国人船員の身辺の安全を確認した。外交部関係者は「大使館や関係当局などを通して事実関係を確認している」とし「事項を鋭意注視し、必要な措置を取る方針」と話した。
平行線のままだと船は動けないね!
イランで革命防衛隊に拿捕された韓国船舶が海洋汚染行為を賠償しなければならないという主張が出てきた。
【写真】イラン革命守備隊の監視を受けて移動する韓国タンカー
韓国の聯合ニュースによると、イラン海運協会長は5日(現地時間)、イラン半官営「メフル通信」とのインタビューで「韓国の船(韓国ケミ)は反復的な環境法違反容疑で拿捕された」とし「必ず環境汚染に対する賠償金を支払わなければならない」と主張した。だが具体的な環境汚染の事例や賠償金の金額に言及することはなかった。
韓国ケミが所属するDMシッピングは海洋汚染容疑を全面的に否定している。DMシッピング関係者は「海洋汚染をする理由は全くない」としながら「周辺に船が非常に多く、もし海洋汚染をしていたとすればすでに申告があったはず」と明らかにした。
あわせて「毎年1回検査を受けていて、外部衝撃がなければ(汚染の可能性は)ほとんどない」としながら「3カ月前に精密検査を受け、バラスト水を捨てるときも微生物を除去して捨てている」と付け加えた。
これに先立ち、イラン革命防衛隊は前日午前10時ごろにガルフ海域(ペルシャ湾)で韓国国籍船舶「韓国ケミ」を拿捕した。その後声明を通じて、革命防衛隊側は「該当船舶は海洋環境規制を繰り返し違反した」とし「今回の事件は司法当局が扱うことになるだろう」と明らかにしていた。
イラン半官営「タスニム通信」は「韓国ケミが大トンブ島から11マイル(17.6キロメートル)離れた海域で、大規模な海洋汚染を起こした」と報じた。
一方、韓国外交部は拿捕事件に関連し、イラン大使を呼んで抗議し、船舶と船員の早期抑留解除を要求した。
韓国国防部もオマーンのマスカット港南側海域で作戦を遂行していた清海部隊の駆逐艦「崔瑩(チェ・ヨン)」を緊急出動させ、同艦はこの日午前、ホルムズ海峡近隣の海域に到着した。
イランの軍隊である革命防衛隊が今月4日、ペルシャ湾(アラビア湾)で韓国船籍の化学運搬船「韓国ケミ」号を拿捕したことに関連し、イラン政府報道官が5日「韓国政府が70億ドル(約7186億円)を人質に取っている」と話し、その意図が注目されている。アリ・ラビエイ報道官はこの日、オンライン記者会見で「韓国船舶拿捕が人質劇に該当する」という主張に反論して「もし人質劇が存在するなら、それはわれわれの資金70億ドルを根拠なく凍結した韓国政府だろう」と話したとロイター通信が報じた。韓国のウリィ銀行とIBK企業銀行は米国の対イラン経済制裁で、イラン産石油の輸入代金約70億ドルを支払うことができず凍結している。
【写真】韓国外交部のエレベーターに乗るイラン大使
今回の事件に対し、外交界では「イランが米国との衝突の可能性に備え、韓国船舶を事実上『人質』に取った」と分析している。韓国が対立中の米国とイランの間に挟まれた状態だという説明だ。米CNNも韓国が両国対立の「無関係の被害者(neutral victim)」になったと評価した。
イランが韓国船舶を拿捕したことは米国の現在と次期政府の両方にそれぞれ「警告」と「圧迫」のメッセージを同時に送るためのものとみられる。任期最後までイランに対して軍事行動の可能性を繰り返し示唆しているドナルド・トランプ米大統領に対しては「攻撃は容認しない」という「警告」メッセージになりえる。今月20日の就任を控えたジョー・バイデン時期大統領には、イラン核合意(JCPOA)再協議の可能性を念頭に置いて交渉力を高めるための「圧迫」だとみることができる。
イランは、昨年11月の核科学者暗殺と今月3日のガセム・ソレイマニ司令官の死亡1周忌を契機に対米報復の意思も固めてきた。4日、ウラン濃縮濃度を20%に高め始めたまさにその日に韓国船舶を突然拿捕したのは、米国を直接挑発するのではなく同盟国の一つを選んで迂迴的な警告を送ったと解釈することができる。
ただし米国とイランはどちらも戦争拡大は自制して対応程度を調節している。イランは今回の事件に対して「完全に技術的な事案」としながら「政治的目的ではなく、環境汚染のため」と主張している。米国も国務省次元の原則的立場だけを出している。米国務省報道官は4日、「イランに抑留されている韓国船籍タンカーを直ちに釈放することを要求する」とし「(拿捕は)国際社会の制裁圧力を緩和しようとする試み」と批判した。
米国とイランがトランプ任期末に「強対強」の衝突は避けても、イランは韓国船舶拿捕によって、今後、所期の成果を期待することができる。現在イランには次期バイデン政府を相手に核交渉と制裁緩和議論を行うときに備えた「テコ」が必要だ。バイデン氏はイランが核合意に復帰してこそ米国も復帰するという立場を繰り返し明らかにしてきた。イランは「弾道ミサイルを議題に追加する交渉は不可」という主張を繰り返しているが、内心は今年6月に行われる自国の大統領選前に対米交渉を決着させたい雰囲気だ。このような状況で、拿捕した韓国船舶を利用してイラン政府が米国の制裁緩和を狙う場合、抑留者の釈放交渉に悪影響を与える可能性がある。
韓国外交部は高ギョン錫(コ・ギョンソク)アフリカ・中東局長をはじめとする代表団をイランに派遣し、拿捕船舶に関連した交渉を進める予定だ。崔鍾建(チェ・ジョンゴン)外交部第1次官も事前に予定された10日のイラン訪問を変更なく推進する。
イランが韓国船籍の「韓国ケミ号」を拿捕(だほ)した背景に挙げられている韓国国内の「イラン資金」は、イランが過去およそ2年間、韓国から回収できずにいた8兆ウォン(現在のレートで約7560億円。以下同じ)前後の資金のことだ。イランが保有する海外資産の中では最大規模といわれている。この資金は、2018年に米国のドナルド・トランプ政権がイランとの核合意から脱退して対イラン制裁を強化した際、韓国国内の銀行で凍結された状態にある。
■「アジア・パワー指数」1位は米国、韓国7位…日本は?
■大部分がイランの原油輸出代金
韓国・イラン両政府は2010年、米国がイランに対する金融制裁に乗り出してドル送金ルートがふさがれると、ウリ銀行および企業銀行にウォン決済口座を作り、輸出入代金用として使うことで合意した。例えば、イランが韓国に原油を輸出したら、韓国側は代金をドルではなくウォンで支払ってこの口座に振り込み、イランが韓国企業から商品を輸入する際には、この口座から資金を引き出して韓国企業に支払う-という方式だ。
こうした相殺方式で貿易を行うと、イランに直接ドルが流れ込まない。当時は、韓国が支払う原油代金がイランの核兵器開発の資金に転用されないという確信を米国政府に植え付けることが重要だったため、この方式は「神の一手」と考えられた。韓国はイランに自動車部品や化学製品を主に輸出し、イランから原油を輸入した。韓国のイラン産原油依存度は10%前後で、2013年までの時点でも両国の貿易額は100億ドル(約1兆270億円)に達していた。
しかしトランプ政権が、イランとの貿易自体できないように制裁を強化したことで状況が変わった。ウリ銀行・企業銀行のイラン中央銀行名義の口座は凍結され、イランのメラト銀行ソウル支店は営業停止となった後、資金を一時的に韓国銀行へ預けなければならなかった。この3銀行にあるイラン資金は8兆ウォン前後、ドルに換算して70億ドルほどだと韓国政府関係者は説明している。資金が凍結された後、制裁を受けない人道的次元の医療品輸出が間欠的に行われたが、極めて小規模だった。8兆ウォンという巨額の資金をイランが回収したり処理したりする方法がなかったのだ。
■「韓国船を拿捕して担保にする可能性」
これまでイランは、この凍結資金を解除するよう韓国政府に強く要求してきた。韓国政府は最近、コロナ被害が大きいイランに韓国製の医薬品や防疫装備などを輸出し、返済に代えるという方式を提案した。しかし一部のイラン側関係者が「途方もなく金額が小さい」という理由で公然と不満を示していたという。また昨年には、イラン国内のコロナの状況が悪化すると、強硬派の政治家らが「韓国が原油代金を支払わないのでワクチンが買えず、こうなった」「韓国と米国は主従関係」と、反韓感情をあおることもあった。
そこで代案として浮上したのが、コバックス・ファシリティー(COVAX facility)を通してコロナワクチンを確保し、この代金を韓国国内の凍結資金で納付するという案だ。韓国外交部(省に相当)の関係者は「コバックス代納用として活用できるようにする案を話し合っているところだった」とし「米財務省から特別承認ももらった状態だった」と語った。コバックス・ファシリティーは、世界保健機関(WHO)が主導するコロナワクチンの共同購入および配分事業だ。人道的金融取引なので制裁事案ではなく、8兆ウォンのうち1000億ウォン(約94億円)未満の資金をコバックスに前金として支払うことで米国の同意も得られていたという。
ところがイランは、この資金がドルに換金されて米国の大手銀行に送金される過程で米国がこの資金を凍結する可能性を懸念した、といわれている。ある外交消息筋は「イランは米国を信用できないので、資金を確実に引き出すための“担保”として韓国船を拿捕した可能性がある」と語った。韓米はワクチン代金の代納に合意したが、イランは米国を信用できず、はねつけたのだ。イランが拿捕の名分として掲げた「海洋汚染行為」は口実にすぎないというわけだ。イランがこの日、自国メディアを総動員して韓国船の拿捕場面を動画や写真などで公開したのも、その効果を最大化するための手段とみられる。イラン革命防衛隊がツイッターで公開した動画によると、拿捕の過程で高速艇や小型ボートなど少なくとも5隻の中小の艦艇と、ヘリまで動員されていた。ただし韓国政府は、船舶の拿捕とコバックス代納問題を公式に連結することには慎重な構えを見せている。外交部関係者は「イラン側に、今回の船舶抑留とウォン代金を連携して交渉しようという意図があるのかと尋ねてみたが、『それは絶対にない』と1次的な返答があった」と語った。
ハードよりもソフト(船員)の管理の失敗だと思う。航海機器や装置の性能が上がっても、それを使う船員のレベルが向上しない、又は、本来の目的を果たさないような使い方をされていては意味がない。会社の方針、船のタイプや船の大きさなどで要求される船員の能力が違う。ソフト(船員)の評価や管理などは重要な場合がある事を理解する必要はあると思う。陸上から支援すれば良いと考えると間違いの場合もあると思う。
商船三井は21日、船舶の座礁リスクを監視するシステムの開発を始めたと発表した。2021年春の実用化を目指す。インド洋の島国モーリシャス沖で今夏、チャーターしていた貨物船が座礁し、大量の燃料油を流出させた事故を受けて、再発防止策の一環として取り組む。人工衛星を使った位置情報を元に、危険な海域に進もうとする船の船員などに自動で警告を出す機能などを盛り込む計画だ。
監視システムは運航支援システム開発のナパ(フィンランド)、船舶の安全審査などを担う日本海事協会(東京・千代田)と共同で開発する。商船三井がナパに運航データを提供し、海事協会が安全面などで必要な助言をする。警告機能の他、陸上からの支援がしやすいよう、複数の船舶情報を1画面でまとめて表示できる機能も開発する。
商船三井は、モーリシャスでの座礁は船員が携帯の電波を拾うために危険な航路をとった可能性があるとみている。法的責任の発生しないチャーター船も含め再発の防止に活用したい考えだ。
ギリシャの船主は会社さえ選べば問題はないように思える。ただ、良いギリシャ船主を他の造船所が手放さないと思うのでその点ではどうなのだろうか?
情報筋によると、大島造船所がギリシャ船主から8万2000重量トン型(カムサマックス)バルカー1隻を受注した模様だ。ギリシャ向けの成約は約45年ぶり。大島造船は1970年代に、ギリシャ向け受注船のクレーム対応による建造工程の混乱を経験。こうした経緯などを踏まえ、強みの源泉である「バルカーの多数隻高速建造」の安定化を徹底するため、ギリシャ向けの営業を行わない方針を長らく堅持してきた。だが、新造発注が
21日、、西海市の大島造船所で、ガス溶接機を使って金属を切断するなどしていた男性作業員が、火の粉を浴びるなどしてやけどを負い、23日に亡くなりました。
21日午後2時半ごろ、西海市の大島造船所の建造中の船内で、長崎市畝刈町の溶接工、山口正信さん(68)の作業服に火がついているのを同僚が見つけ、火を消し止めました。
山口さんは全身の半分にやけどを負い、大村市内の病院に運ばれましたが、23日、亡くなったということです。
警察によりますと、山口さんは当時、ガス溶接機を使って頭上の鉄骨の溶接などをしている際、火の粉が散って作業服に火がついたと見られ、警察が詳しいいきさつを調べています。
小出大貴
経済インサイド
「まるで月と地球だな」
7月2日、東京・霞が関の国土交通省が入るビルの11階。午前10時から始まった会議の参加者のひとりは配られた資料を見て心のなかでつぶやいた。
目線の先、国交省による「日本造船所の規模面での弱さ」と題したグラフは、タンカーやコンテナ船といった「商船」の分野で、日本と、ライバルの中国と韓国の造船会社の造船所を比べていた。
生産量を表す大小の円が並ぶ。縦軸は従業員数、横軸は造船所の面積。最も大きな円は韓国の造船大手「大宇造船海洋」の造船所。そして他の韓国勢、中国勢が続く。国内勢は人が少なくせまいことを示すグラフ左下に小さな円が密集するので、拡大した別欄に示された。比較できないほどの差に、宇宙の星の大きさを比べる図を思い起こした。韓国が大きな「地球」なら、日本は小さな「月」というわけだ。
赤羽一嘉国交相が「(造船)業界は存続の危機にさらされている」と5月に呼びかけた国交省の政策審議会での一幕だ。造船会社や船員の業界団体のトップや大学教授ら計17人が集まり、税金での支援策や新たな法律の案を話し合った。
造船はスケールメリットがものを言う。大きい造船所ほど多くの受注ができ、費用を抑えて安く売れる。日本は、中韓との建造能力と価格の差に苦しんでいる。戦後の50年代以降は世界首位の建造量を誇り、「世界の造船所」の役割を担っていた。
しかし、2000年、後発ながら巨額の投資をてこに急成長した韓国に首位を奪われた。09年には国営企業を中心とする中国にも抜かれた。中国は、経済成長によって物流のニーズが増えたため、巨大造船所の育成を「国策」に掲げていた。
中韓の国を挙げた造船への投資は、雇用対策の側面もあった。投資競争は海上物流量の伸びを超えて過熱。08年のリーマン・ショックやその後の中国経済の減速などによって船の需要が落ち込むと、10年以降は「船余り」が定着し、不況が続く。韓国政府は15年、経営危機に陥った大宇造船海洋に1.2兆円を公金支援した。
安値競争、国内勢はジリ貧
19年の商船建造量の世界シェアは中国35%、韓国32%、日本24%。各国企業が仕事をとることを優先して赤字でも受注するような「安値競争」に挑んだ。規模が小さく価格競争力に劣る国内勢は競り負け、ジリ貧なのが実情だ。中韓も苦しいが、世界の物流量は長期的には増えて船余りは解消されるとみられ、いまの苦しみは「過渡期」との見方が業界では一般的だ。
足元では新型コロナウイルスの影響で商談が止まり、国内造船業の受注残は危険とされる2年を切り「1.03年」という「極めて危機的な状況」(斎藤保・日本造船工業会長・IHI取締役)にある。船は一般的に受注から2年かけて設計を詰め、1年で組み立てる。いま受注しても設計に2年かかれば、つくる船がなくなる「1.03」年後から約1年間は造船所は仕事がなくなってしまうことになる。国交省の審議会は、こうした事態の打開を期待された。
12月11日に、7月以降4回の会議を経て国交省の審議会が出した支援案は、業界再編や協業を後押しするための10億円を21年度の政府予算に盛り込むにとどまった。「ありがたいが、ゆがめられた今の市場で何の足しになるのか」。国内の大手造船首脳は額の少なさに肩を落とす。
複数の関係者が、19年末ごろには政府系金融機関を使い造船業向けに「5千億円」の融資枠を確保する動きがあったと明かす。しかし、回収の見込みが立たないとして銀行側が断り、見込みがある場合にのみ融資することに決まったという。
別の大手造船幹部は話す。「リスクマネーは出せず、日本政府にはこれが限界ということだろう。経営が持たなくなってなりふり構わなくなる会社が出てくる。いや、すでに出てきている」
戦後のものづくりを代表した造船業がたそがれの時を迎えている。この20年間、韓国、中国に追い上げられ、抜き去られた。港からは造船所が消えつつある中、デジタル化と環境規制の波が襲う。ニッポンの造船業はどこに向かうのか。
相次ぐリストラ
京都府の舞鶴市役所3階「特…
ラムス・インヴェストメント・パナマ・エス・エイ(DUNS:853736457、パナマ共和国パナマ市コスタ・デル・エステ、パセオ・デル・マール通り、設立1995(平成7)年12月、資本金1000米ドル)は11月11日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には相羽利昭弁護士(三宅・今井・池田法律事務所、新宿区新宿1-8-5、電話03-3356-5251)が選任された。
負債総額は債権者27名に対して139億7920万円(1億3235万3738.54米ドル、10月7日のレート:105.62円換算)。
2015(平成27)年11月に債権者より会社更生を申し立てられ同日、保全管理命令を受けたラムスコーポレーション(株)(TSR企業コード゛:293357102、東京都)の元社長であるヴィパン・クマール・シャルマ氏の個人資産会社。
ラムスコーポレーションはシンガポール、パナマで船舶保有SPC(特別目的会社)を束ねる外航船保有大手ユナイテッドオーシャン・グループの1社として、船舶運航管理を手掛けていた。日本では造船手配などの各種交渉や大手海運会社の船舶代理業務なども手掛け、2015年3月期には売上高1億1148万円をあげていた。しかし、景気減速など海運市況悪化による収益低迷から資金繰りが悪化。借入金の返済が進まず、シンガポール、パナマに拠点を置くグループの船舶会社38社とともに債権者から2015年11月、東京地裁に会社更生を申し立てられ同年12月、更生開始決定を受け、その後、2017年1月に更生計画認可決定を受けた。
ラムス・インヴェストメント・パナマ・エス・エイに経営実態はほとんどなかったが、シャルマ氏に債権を保有する会社から破産を申し立てられ、今回の措置となった。
広栄運輸(株)(TSR企業コード:352451653、法人番号:8020001017240、横浜市鶴見区平安町1-46-1、設立1977(昭和52)年4月)は11月2日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し同日、監督命令を受けた。申請代理人は長屋憲一弁護士(NeOパートナーズ法律事務所、東京都千代田区平河町2-4-13、電話03-5226-1116)。監督委員には内藤平弁護士(みずき総合法律事務所、東京都新宿区市谷八幡町13、電話03-6265-0151)が選任された。
負債総額は約10億円。
(株)日新(TSR企業コード:350104140、法人番号:2020001028235、横浜市中区、東証1部上場)の持分法適用会社である新栄運輸(株)(TSR企業コード:350067171、法人番号:7020001017563、横浜市鶴見区)の関係会社。新栄運輸の下請けとして、一般貨物自動車運送を主体に自動車運送取扱、倉庫業、梱包業などを手掛け、2012年3月期に売上高2億7197万円を計上した。
しかし、2015年3月期には売上高が1億6878万円に落ち込み、775万円の赤字を計上。その後も低迷を抜け出せないなか、新栄運輸で不正経理が発覚し、2020年10月1日付で同社は代表取締役専務を解任した。これに前後して、当社の代表取締役も務めていた同氏を当社は9月30日付で解任。新栄運輸は、手形決済期日までに資金手当てができないことから10月19日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、当社は連鎖する形で今回の措置となった。
カリブ海で運航再開したクルーズ船で乗客1人が新型コロナ検査で陽性の仮判定を受けた/SeaDream Yacht Club
(CNN) 新型コロナウイルス感染拡大後にカリブ海で運航を再開した初のクルーズ船上で、乗客1人が検査で陽性の仮判定を受けたことが分かった。
世界各地で小型豪華客船を運航する米シードリーム・ヨットクラブの「シードリーム1」(乗客定員112人、乗組員定員95人)は、今月7日にカリブ海の島国バルバドスを出発。カリブ海クルーズ再開の第1号として、「セントビンセント及びグレナディーン諸島」とグレナダを回る旅を予定していた。出航地と寄港予定地はいずれも米国人の立ち入りを禁止していない。
このクルーズに参加している旅行サイト「ザ・ポインツ・ガイ」のレポーター、ジーン・スローン氏によると、11日の昼食前に船長からの船内アナウンスで、乗客1人が仮陽性の判定を受けたとの知らせがあった。乗客は全員客室に戻り、隔離態勢に入るよう指示があった。
船はグレナディーン諸島のユニオン島に停泊していたが、すぐにバルバドスへ引き返し始めたという。
スローン氏はCNNトラベルへのメールで、クルーズ業界への影響は今後数時間から数日で事態がどう動くか次第だと指摘した。
シードリーム1では船内での感染の可能性を排除するため、徹底した検査体制が設けられた。検査は乗客が出航地へ向かう前と乗船直前、さらに出発から4日後に実施された。
シードリーム・ヨットクラブはこの夏、他社に先駆けてノルウェーでの運航を再開し、1人も感染者を出さずにシーズンを終えていた。
同社の幹部は9月にカリブ海での再開を発表した場で、「運航を再開した最初の豪華クルーズラインとして多くの教訓を得てきた。豪華さを損なわずに安全な環境を提供できることを確信している」と述べていた。
たった100万円で譲渡か!しかし、今が決断の時期かもしれない。造船で勝負する会社にとっては撤退を考えている造船所と交渉するチャンス。そうでなければなかなか撤退を決める造船所は少ない。生き残りをかける造船所としては、設計が出来る人材を確保できるし、同じ図面で船を建造できるメリットがある。もう船の設計が出来る人材を見つける事は難しいし、育てるだけの時間や余力はないと思う。撤退する造船所には必要のない人材だが、造船で生き残りをかける造船所には必要な人材。ただ、造船所が違えば、設計、工程、その他の詳細や人材の質まで違うので統一して動き出すまでには時間がかかりそうに思える。本当は効率が良く、質の良い方法を選ぶのが良いと思うが現場が対応できなければ力のある方に合わせるしかないであろう。中途半端に両方を残すと中途半端になるし間違いが起きると思う。
サノヤス造船は結構良い船を建造していたと思うが、効率に特化したバルクキャリアだけではだめだったのかもしれない。中国はやはり安かろう、悪かろうだと思うが、中国建造の船は良くないと経験を通して理解しなければ理解するのが難しい船主は少なくないと思う。また、中国建造の船は良くないと理解するのに数年から10年ほどかかる場合がある。船が古くならないと大きな問題にならない事がある。
監督や管理会社の能力が低ければ、問題がある船でも気付かなかったり、良くないと思わない事がある。良い船だから発注が来るわけでもないようだ。日本は良いものであれば売れると思っているが、評価される良い部分が売りに出来なければ、良いものであっても売れるとは限らないと個人的には思う。また、買い手が何を望んでいるのか理解して効率よく設計しないと生産側が良いと思っていても売れるとは限らないと思う。
結果が全てなので新来島どっくには頑張ってもらいたい。
造船中堅のサノヤスホールディングス(HD、大阪)は9日、倉敷市に主力工場を持つ中核子会社・サノヤス造船(大阪)の全株式を、同業中堅の新来島どっく(東京)に譲渡する契約を結んだと発表した。中国、韓国勢との競合で業績が悪化していた上、新型コロナウイルスによる市況の悪化が追い打ちをかけた。同HDは造船事業から撤退する。
来年1月15日の臨時株主総会を経て正式決定する。サノヤス造船は同3月1日から「新来島サノヤス造船」に社名が変わる。本社の所在地は今後詰める。譲渡額は100万円。
主力の水島製造所(倉敷市児島塩生)の従業員は社員約480人、協力会社約350人。同HDは「雇用は原則維持される。協力会社への発注も現状維持を要望している」と説明。水島では採算性の良いガスタンク製造や船舶の修繕事業に乗り出す準備を進めており、その方向性も維持される見通しという。
同HDは遊園地施設関連などの事業を継続する。大阪市内で記者会見した上田孝社長は「回復の兆しが全く見えない事業をこれ以上継続することは当社の財務体力上、困難だ。価格競争が非常に熾烈(しれつ)で、利益が出ない体質になっている」と述べた。
新来島どっくは「水島は同じ瀬戸内地域で生産協力しやすく、技術や設計の面で見習うべき点もある。スケールメリットを生かし、今回の不況を乗り越えたい」としている。
1911年創業のサノヤス造船は、ばら積み貨物船が主力。2工場のうち水島製造所で建造、大阪製造所(大阪)で修繕を主に手掛ける。造船事業の2020年3月期の売上高は299億円、本業のもうけを示す営業損益は27億円の赤字(前年は3億円の黒字)だった。
水島製造所は74年操業。ピークの06~13年は年12隻ペースで商船を建造していたが、中韓メーカーとの競合で船価が低迷し、近年は7、8隻。受注残は目標の2年半分に対し、20年3月期は1年半分ほどにとどまる。さらに新型コロナウイルスの影響で海運市況が悪化して商談がストップ。今夏には全社員を対象に初の一時帰休を行い、建造ペースを緩めていた。
新来島どっくは1902年創業、連結売上高974億円(20年3月期)、単体従業員840人。造船所は主力の愛媛県今治市や東広島市など国内5カ所。自動車運搬船や化学製品タンカーを得意とする。
サノヤスホールディングス(HD)は9日、造船事業から撤退すると発表した。子会社のサノヤス造船(大阪市)の全株式を2021年2月末に新来島どっく(東京・千代田)に売却する。譲渡額は100万円だが、新来島どっくはサノヤス造船の借入金40億円を引き継ぐ。中韓勢との競争激化や新型コロナウイルスの感染拡大による海運市況の悪化で需要が低迷。事業継続が困難と判断した。
サノヤス造船は、新造船や船舶の修復、船舶用のガスタンクなどを手掛ける主力の水島製造所(岡山県倉敷市)と、ガスタンクなどを生産する大阪製造所(大阪市)の2拠点を構える。従業員約600人の雇用は新来島どっくが引き継ぐ。
サノヤスHDの造船事業は20年3月期の売上高は299億円、27億円の営業赤字だった。近年は安値受注で攻勢をかける中韓勢を前に新造船の受注が低迷した。足元では新型コロナウイルスの影響で海外との商談が進まず、受注残は安定操業に必要とされる2年分を下回る。駐車場向け装置など「非造船事業」も赤字に陥り、祖業の造船売却を決めた。
サノヤス造船の主力であるバラ積み船を手掛ける新来島どっくに売却する。同社は自動車運搬船やタンカーも製造する。従業員は約850人で、20年3月期の売上高は974億円だった。
サノヤスHDの上田孝社長は9日、大阪市での記者会見で「(環境配慮型の)技術開発のスピードが上がり、コストも増えるなか、サノヤスの規模では限界がある」と説明した。
サノヤスHDは同日、21年3月期の連結最終損益が63億円の赤字(前期は22億円の赤字)になりそうだと発表した。売上高は10%減の450億円を見込む。いずれも従来予想は未定だった。
大阪府に本社を置くサノヤスホールディングスは、倉敷市などで行ってきた造船事業から撤退すると発表しました。
子会社のサノヤス造船の水島製造所で働く従業員およそ500人の雇用は、維持される見通しだということです。
サノヤスホールディングスによりますと、9日に開かれた取締役会で造船事業から撤退し、子会社のサノヤス造船のすべての株式を、東京の造船会社「新来島どっく」に譲渡することを決めました。
譲渡額は100万円だということです。
倉敷市にあるサノヤス造船の水島製造所では、中型の貨物船や石炭を運ぶ専用の船などを製造してきましたが、中国や韓国の企業などとの受注競争や、新型コロナウイルスの感染拡大によって業績が悪化し、サノヤス造船は昨年度の決算で、本業のもうけを示す営業利益は29億円の赤字でした。
サノヤスホールディングスによりますと、水島製造所で働くおよそ500人の従業員については「新来島どっく」にすべての株式を譲渡したあとも、雇用が維持される見通しだということです。
造船中堅のサノヤスホールディングス(HD、大阪)は9日、倉敷市に主力工場を持つ中核子会社・サノヤス造船(大阪)の全株式を、同業中堅の新来島どっく(東京)に譲渡する契約を結んだと発表した。中国、韓国勢との競合で業績が悪化していた上、新型コロナウイルスによる市況の悪化が追い打ちをかけた。同HDは造船事業から撤退する。
来年1月15日の臨時株主総会を経て正式決定する。サノヤス造船は同3月1日から「新来島サノヤス造船」に社名が変わる。本社の所在地は今後詰める。譲渡額は100万円。
主力の水島製造所(倉敷市児島塩生)の従業員は社員約480人、協力会社約350人。同HDは「雇用は原則維持される。協力会社への発注も現状維持を要望している」と説明。水島では採算性の良いガスタンク製造や船舶の修繕事業に乗り出す準備を進めており、その方向性も維持される見通しという。
同HDは遊園地施設関連などの事業を継続する。大阪市内で記者会見した上田孝社長は「回復の兆しが全く見えない事業をこれ以上継続することは当社の財務体力上、困難だ。価格競争が非常に熾烈(しれつ)で、利益が出ない体質になっている」と述べた。
新来島どっくは「水島は同じ瀬戸内地域で生産協力しやすく、技術や設計の面で見習うべき点もある。スケールメリットを生かし、今回の不況を乗り越えたい」としている。
1911年創業のサノヤス造船は、ばら積み貨物船が主力。2工場のうち水島製造所で建造、大阪製造所(大阪)で修繕を主に手掛ける。造船事業の2020年3月期の売上高は299億円、本業のもうけを示す営業損益は27億円の赤字(前年は3億円の黒字)だった。
水島製造所は74年操業。ピークの06~13年は年12隻ペースで商船を建造していたが、中韓メーカーとの競合で船価が低迷し、近年は7、8隻。受注残は目標の2年半分に対し、20年3月期は1年半分ほどにとどまる。さらに新型コロナウイルスの影響で海運市況が悪化して商談がストップ。今夏には全社員を対象に初の一時帰休を行い、建造ペースを緩めていた。
新来島どっくは1902年創業、連結売上高974億円(20年3月期)、単体従業員840人。造船所は主力の愛媛県今治市や東広島市など国内5カ所。自動車運搬船や化学製品タンカーを得意とする。
個人的な意見だが韓国建造の船は依然と比べると品質が落ちているように思える。中国の船価に対応して船価と品質を落としているのかな?
造船業受注の崖が続いている。今月初めまでの韓国造船業の船舶受注額は昨年の半分にも満たなかった。受注の崖による波及効果は翌年から現れるだけに、来年の造船所の雇用減少などが予想される。
現代重工業グループ、大宇造船海洋、サムスン重工業の3社によると今月初めまでの3社の受注額は96億ドルで昨年の270億ドルの半分に満たなかった。造船大手3社すべてで受注が落ち込んでいる。現代重工業グループは今月初めまでに52億ドルを受注したが昨年の130億ドルの40%水準にとどまっている。大宇造船海洋は33億ドルで昨年の68億ドルの半分、サムスン重工業は11億ドルで昨年の71億ドルの15%水準にとどまった。
実際の受注額は3社が掲げた目標受注額313億ドルの3分の1水準だ。年末までの受注を考慮しても目標を大きく下回るものとみられる。
新型コロナウイルスにより世界の造船需要が振るわないのが最大の要因だ。また、3社は6月にカタール国営石油会社のカタール・ペトロリアムとLNG運搬船100隻に対するスロット契約(本契約前のドック予約)を結んだが本契約は先送りされている。
産業研究院のイ・ウンチャン副研究委員は「カタールを含め大型プロジェクトが新型コロナウイルスで遅れている。主要海運会社が今年から施行される船舶環境規制を考慮し、LNG推進船の発注が続くと期待したが、同じ理由で延期された」と話した。
国際海事機関(IMO)は船舶用燃料の硫黄酸化物含有率を3.5%から0.5%に下げる「IMO2020」を今年から適用した。IMO2020が施行されればLNG運搬船で技術優位を持つ韓国が恩恵を得られると予想したが、現実はそうでなかった。
NH投資証券のチェ・ジンミョン研究員は「カタールなど大型LNGプロジェクトに対する妥当性が悪化したものではないが、世界的海運会社の財政難がばら積み船やタンカーだけでなくLNG運搬船の発注まで全方向に悪影響を及ぼした」とした。
カタールプロジェクトに対する期待が過度だったとの指摘も出る。ある業界関係者は「カタールプロジェクトは2024年に始まるためLNG運搬船の発注は2022年からだが、あたかも受注したかのように話した側面がある」と話した。また、当初新造船100隻でなく老朽船舶の置き換え分がさらにあるとみていたが、これ以上の発注はないというのが業界の支配的な見方だ。
◇底を打って反騰?
受注は急減したが、7-9月期の造船業の業績は悪くなかった。現代重工業グループの中間持ち株会社である韓国造船海洋の営業利益は昨年7-9月期より34.3%増加した407億ウォンを記録し、サムスン重工業は昨年より赤字幅を大きく減らした。理由は2018年から昨年まで受注量が着実に増えたためだ。発注から引き渡しまで3年がかかる大型船舶プロジェクトは通常翌年から売り上げに反映される。
世界の造船発注は3~4年周期で上下を繰り返している。2016年に最悪の受注減を体験し、今年再び急減した。専門家らは今年が底で来年下半期以降に反騰すると予想した。
ハナ金融投資のパク・ムヒョン研究委員は「今後各国の環境規制が硫黄酸化物だけでなく二酸化炭素排出制限などに拡大する。LNGを燃料に使うLNG推進船に対する需要は増加するほかない。中国・日本はLNG推進船に対する技術がなく、需要は増えながら競争者は減った局面」と話した。
カタールプロジェクトの本契約は来年4-6月期ころと予想した。チェ・ジンミョン研究員は「4-6月期に40~60隻の発注が予想される。来年4-6月期にLNG運搬船をはじめ7-9月期にはばら積み船とタンカーなども正常化軌道に入るものとみられる」と話した。
ただし、今年の受注急減による来年の手持ち工事量減少にともなう備えが必要という見方もある。イ・ウンチャン副研究委員は「造船3社よりは協力企業の雇用減少が予想される。大型造船所は協力企業従業員の現場離脱防止に向けた努力が必要だ」と付け加えた。
会社更生手続き中の東北最大の造船会社「ヤマニシ」(石巻市)は30日、更生計画案を東京地裁に提出した。関係者によると金融機関や取引企業に総額120億~130億円の債権放棄を求める内容。今後、書面投票による債権者の議決を経て、年内に裁判所の認可決定を目指す。
ヤマニシや関係者によると、負債総額は140億円以上で、無担保部分の9割以上のカットを要請する。担保がある債権者には原則、全額を弁済する方針。今後、石巻地方の取引先や有力企業から出資を受ける。認可決定後、防衛装備品メーカー「JMUディフェンスシステムズ」(京都府舞鶴市)出身の出本政徳氏がいったん社長に就く。
今後の事業は船舶修繕と鉄構造物の製造を柱とし、主力だった新造船建造は当面、停止する。希望退職を募るなどし、従業員を約150人から70人に半減させた。2022年3月期に黒字転換を見込む。
管財人の松嶋英機弁護士(東京弁護士会)は「地元関係者の総力を挙げた支援に深く感謝したい。今後、全力を挙げて更生計画案の認可と遂行に努める」との談話を出した。
ヤマニシは1月31日、123億円の負債を抱え会社更生法の適用を申請。2月17日に更生手続き開始の決定を受けた。新型コロナウイルス感染拡大で事業環境が悪化し、スポンサー企業の選定を一時断念。自主再建に方針を変え、更生計画案の策定を進めていた。
会社更生手続き中の東北最大の造船会社「ヤマニシ」(石巻市)が、金融機関や取引企業に総額120億~130億円の債権放棄を求める更生計画案をまとめたことが29日、関係者への取材で分かった。計画案は30日に東京地裁に提出される見通し。
関係者によると、負債総額は140億円以上に上り、無担保部分の9割以上のカットを要請する。担保がある債権者には原則、全額を弁済するという。
今後の事業は船舶修繕と鉄構造物の製造を中心とし、主力だった新造船建造は凍結する。希望退職を募るなどし、従業員を約150人から約70人に半減させた。営業利益は2022年3月期から黒字転換を見込む。
ヤマニシは1920年に創業。東日本大震災の津波で被災し、東日本大震災事業者再生支援機構による出資やグループ化補助金の交付を受けたが、減価償却費などで約42億円の債務超過に陥った。1月31日に会社更生法の適用を申請し、2月17日に更生手続き開始の決定を受けた。
新型コロナウイルス感染拡大で事業環境が悪化し、スポンサー企業の選定を一時断念。自主再建に方針を変え、更生計画案の策定を進めてきた。
会社更生手続き中の東北最大の造船会社「ヤマニシ」(宮城県石巻市)は3日、募集した希望退職の応募者が60人だったと発表した。予定した63人は下回ったが、応募期間延長はしない方針。
ヤマニシと子会社「ヤマニシテクノサービス」(同)の内訳は明らかにしていないが、60人のほとんどがヤマニシの従業員。退職日は今月30日。早期退職を希望し、自己都合退職となる従業員も他に2人いるという。
定年後に再雇用された従業員十数人も30日に退職する。両社の従業員は10月以降、現在の約150人から半数以下の約70人になる見通し。
人員削減は主力の新造船事業を当面停止し、事業を船舶修繕と鉄構造物の製造に絞るため決定。8月17~28日に希望退職者を募った。
ヤマニシは1月31日、123億円の負債を抱え会社更生法の適用を申請。2月17日に更生手続き開始の決定を受けた。新型コロナウイルス感染拡大で事業環境が悪化し、スポンサー企業の選定を一時断念。自主再建に方針を変えた。更生計画案の策定を進め、10月30日までに東京地裁に提出する予定。
【AFP=時事】英イングランド南岸沖で25日、タンカー「ネイブ・アンドロメダ(Nave Andromeda)」の乗組員らが密航者に脅されて船内の安全な場所に隠れざるを得ない事態となり、英軍の兵士が同船に乗り込み、容疑者7人を拘束した。国防省が明らかにした。
動画:乳がん治療を受けた米女性スイマー、54時間ノンストップで英国海峡横断に成功
英国防省は、ツイッター(Twitter)で、「警察の要請に応じ、国防相と内相は、軍の要員がイギリス海峡(English Channel)で乗っ取られた疑いのある船舶に乗り込むことを許可した」「軍は同船を掌握し、7人を拘束した」と明らかにし、乗組員は無事だと付け加えた。
これに先立ち、イングランド南部ハンプシャー(Hampshire)州の警察は、密航者が乗組員を言葉で脅迫したが、負傷者は報告されておらず、タンカーの周囲3マイル(約5キロ)への立ち入りを禁じたと発表していた。
タンカーの所有者を代理する法律事務所、テータム・アンド・コー(Tatham & Co)はBBCに対し、この事案は「100%乗っ取りではない」として、発見された密航者らが船室に閉じ込められるのに抵抗したのだと説明した。
このタンカーの船会社に近い筋もBBCに語ったところによると、乗組員はしばらく前から密航者の存在に気付いていた。船が英国に近づくと密航者が興奮したため、乗組員らは船内の安全な避難所に退避した。
同船は原油4万2000トンを積んで先週ナイジェリアを出航。25日にイングランド南部のサウサンプトン(Southampton)に入港する予定だった。
鹿児島-奄美-沖縄航路に定期貨客船を運航しているマリックスラインの代替船を内海造船が建造するそうだが、これと関係しているのだろうか。
三菱重工業の子会社、三菱造船(横浜市)は21日、船舶の建造に関する特許権を侵害されたとして、東証2部上場の内海造船を相手取り、損害賠償を求める訴訟を東京地裁に提起したと発表した。
提訴は9月30日付。請求額は12億4000万円。三菱側は、船舶の損傷時の復原性に関する特許権を侵害されたと主張している。これに対し、内海造船は「特許権は無効で、当社の建造船は特許権を侵害していない」と反論している。
三菱重工業 <7011> の子会社、三菱造船(横浜市)は21日、船舶の建造に関する特許権を侵害されたとして、東証2部上場の内海造船 <7018> を相手取り、損害賠償を求める訴訟を東京地裁に提起したと発表した。
鹿児島-奄美-沖縄航路に定期貨客船を運航しているマリックスライン(本社鹿児島市、岩男直哉社長)は19日、クイーンコーラル8(4945トン、1999年就航)の代替船として、新造船を建造すると発表した。2021年12月に就航予定。船名は、一般公募する。
【写真】新造船のイメージイラスト
新船は全長145メートル、幅24メートル、総トン数約8000トン。現行船より大型化し、貨物と車両の積載能力を強化する。旅客定員は100人以上少ない655人。プライバシーを重視して個室や寝台を増やし、2等和室には仕切りを設置し個人エリアを確保する。キッズルームやシャワー室も備える。バリアフリーに配慮し、エスカレーターとエレベーターは各2基備える。
鉄道建設・運輸施設整備支援機構の融資を受け、広島県の内海造船で建造する。
船名募集は、11月16日(必着)まで。住所、氏名、年齢、電話番号、船名、理由を明記し、はがきかメールで申し込む。同社ホームページに詳細を掲載している。21年6月下旬の命名進水当日に発表する。採用者には往復乗船券など贈る。
【深層リポート】
新潟県佐渡市と新潟市などを結ぶ離島航路を運営する佐渡汽船(本社・佐渡市)が経営危機に直面している。令和2年6月中間連結決算(1~6月)で17億4100万円の最終赤字を計上して債務超過に陥り、決算短信に「継続企業の前提に関する注記」を記載した。県は支援に乗り出す方針だが、改善への先行きは視界不良だ。
企業は、将来にわたり事業を継続していくことを前提にしている。しかし、深刻な業績悪化により、事業の継続に重大なリスクが生じた場合、決算短信などに「継続企業の前提に関する注記」としてリスク内容を記載し、投資家などに注意を促す。
最近では、アパレル大手レナウンの元年12月期連結決算短信に注記が記載され、同社は5月、東京地裁から民事再生手続き開始の決定を受けた。注記を記載した佐渡汽船の経営改善は待ったなしとなっている。
コロナが追い打ち
同社の経営悪化の大きな要因の一つは、旅客輸送人員の減少だ。平成26年に年間158万人だったものが、令和元年には147万人と10万人以上減っている。これは、佐渡を訪れる観光客の減少が影響しているとみられる。
県の観光入込客統計では、平成26年に佐渡を訪れた観光客は年間延べ153万人。これが令和元年には同123万人と30万人も減っている。この間、同社の連結最終損益も赤字が目立つ。
国土交通省OBの花角(はなずみ)英世知事は、佐渡の観光客減少について「旅行の形態が団体中心から個人や少人数グループに変わってきている中、旅行の目的も食だったり体験型の観光だったりと多様化している。そうした観光ニーズに十分にこたえられなかったことが背景にあるとみている」という。
窮状に追い打ちをかけたのが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う移動や外出の自粛である。同社の旅客輸送は4月が前年同月比79%減、5月が同86%減、6月が同64%減と、壊滅的な状況に陥った。その結果、8月12日発表の6月中間連結決算で5680万円の債務超過に陥った。
当面の経営改善策
佐渡汽船は7月7日、県や関係市、県内の交通・観光事業者などからなる佐渡航路確保維持改善協議会(会長=田中昌直・県交通政策局長)に経営改善案を提示。目玉は、赤字が続く小木(佐渡市)-直江津(上越市)航路で使用している高速カーフェリーを売却し、新たにジェットフォイル(高速旅客船)を導入するというものだ。
「この航路の赤字額は年間10億円ほど。ジェットフォイルにすることで整備費用などが軽減され、赤字額を4億円ほど圧縮できるとみている」と同社の尾崎弘明社長は説明する。しかし、抜本的な改善策とは言い難く、赤字体質からの脱却は難しい状況だ。
地域の重要交通インフラとして何としても維持しなくてはいけないが、肝心の輸送量はじり貧状態が続く。地元の第四銀行は7月下旬、新型コロナの影響で大きなダメージを受けた佐渡汽船に運転資金として10億円、さらに8月末には取引金融機関3行が14億円を融資し、オール新潟で支えている格好だ。
抜本的な経営改善策を見いだせない中、花角知事は「国に離島航路である佐渡航路へのさらなる支援を求めていきたい」としている。
【佐渡汽船】 佐渡-新潟本土間の離島航路を運営する海運会社。本社は新潟県佐渡市。ジャスダック上場。筆頭株主は同県(保有比率約38%)。昭和7年、佐渡航路で競合していた商船会社3社を経営統合し、県も資本参加して誕生。両津(佐渡市)-新潟(新潟市)、小木(佐渡市)-直江津(上越市)の2つの定期航路を持つ。グループ会社は昨年末時点で11社あり、一般貨物・自動車運送、旅行・観光業などを営む。
【記者の独り言】 佐渡汽船の経営問題は、日本の課題の縮図でもある。佐渡市の人口は昭和40年に10万人超だったが、今年7月1日現在は約半分の約5万2000人と推計される。佐渡を訪れる観光客も、平成26年の年間延べ153万人から令和元年には同123万人に減少。過疎化とともに「島内の産業の衰退も進んでいる」(信用調査機関)うえ、新型コロナウイルス対策とも向き合わなくてはならず、経営改善は一筋縄ではいかない。(本田賢一)
「A ship is required to have a Safe Manning Certificate on board. This would have specified that a crew of 24 would be needed for a 13 year old Capesize Bulk Carrier, like the Wakashio.
The only way to travel in breach of this Safe Manning Certificate, is with a ‘Certificate of Emergency Exception.’
Captain John Konrad explains what this means. He is licensed to captain the world’s largest ships, including Capesize Bulk Carriers, and now runs leading maritime news site, gCaptain. “If the crew number goes below that required by the minimum safe manning certificate then the ship owner can ask class for an ‘Emergency Exemption.’ Otherwise the ship is unable to leave Port unless this has been granted.”
So the only way for the Wakashio to have been allowed to leave the Port of Singapore (its last port of call), would have been if an ‘Emergency Exemption’ had been granted by the ship’s inspectors. As the Wakashio is registered in Panama, the ship inspectors would have been Class NK, based in Japan.」
「a crew of 24 would be needed for a 13 year old Capesize Bulk Carrier」はどの国際条約に記載されているのだろうか?無知なので知らないのかもしれないがはっきりと記載するべきだ。自分の知識ではどこの旗国も船の船齢が高くなってもSafe Manning Certificate (最小安全配員証書)で要求される船員の数は変わらない。国際総トン数、船のタイプ、エンジンの馬力、エンジンのタイプでほぼ決まり、船が船級が認定する自動化があるかどうかで違いが出るくらいだ。
確かに船の船齢が高くなると維持管理で船員が多くいた方が良いが、建造された船の品質や船主や管理会社がどのような維持管理を行ってきたのかで船の状態に大きな違いが出てくるので、船齢だけで判断するのは間違っていると思う。
下記の記事では、Safe Manning Certificate (最小安全配員証書)を強調しているがCertificate of Emergency Exceptionの問題どころではない問題を知っている。
次のケースを見てください。繰り返しますが、パナマ・ビューローは、パナマ国海運局に一部ではありません。最低乗員証書は、パナマ国海運局から発行されるものです。
パナマ国海運局(ニューヨーク事務所)からFAXされてきたものを勝手に書き直してパナマ・ビューローのスタンプを押しています。そして、その裏には、本物のコピーで
あるとM. OKAMOTO氏がサインをしています。これも、おかしな行為だと思います。
FAXで送られてきたものであれば、修正してFAXしてもらうだけでよいと考えられます。
間違いであるのであれば、その間違いであることが書かれた手紙を添付すべきでしょう。本物は、FAXが送られてきた前の日付が発効日になっており、パナマ・ビューローのM. OKAMOTO氏が書き換えたようになっていませんでした。現在、M. OKAMOTO氏はマーシャルアイランドで働いているようです。
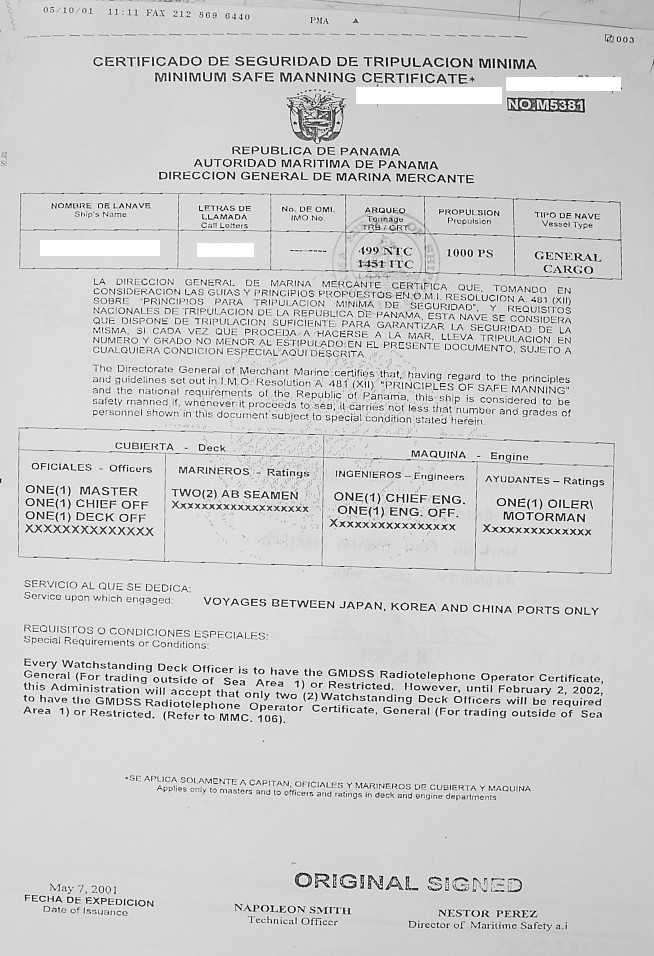
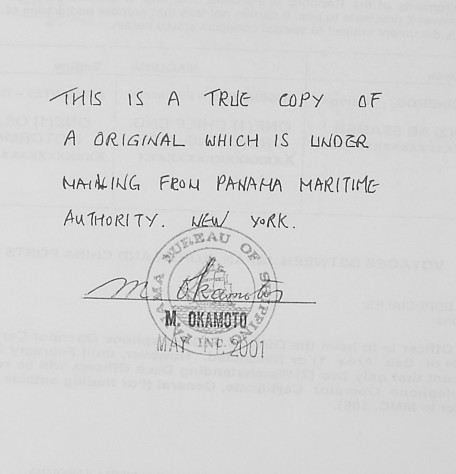
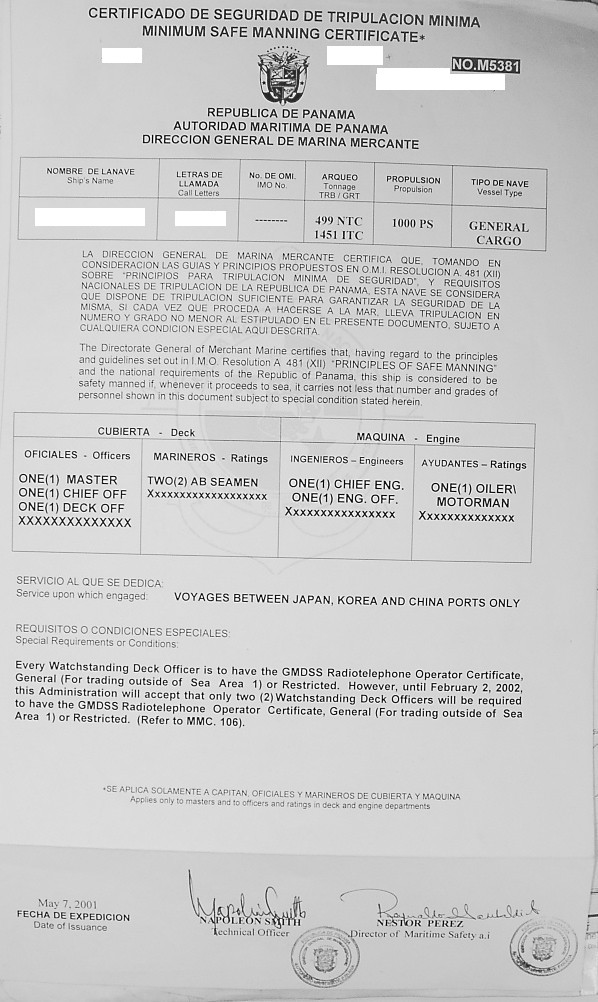

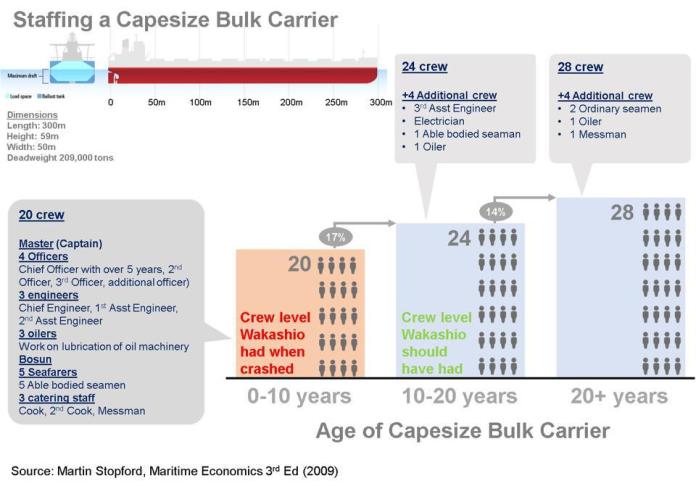
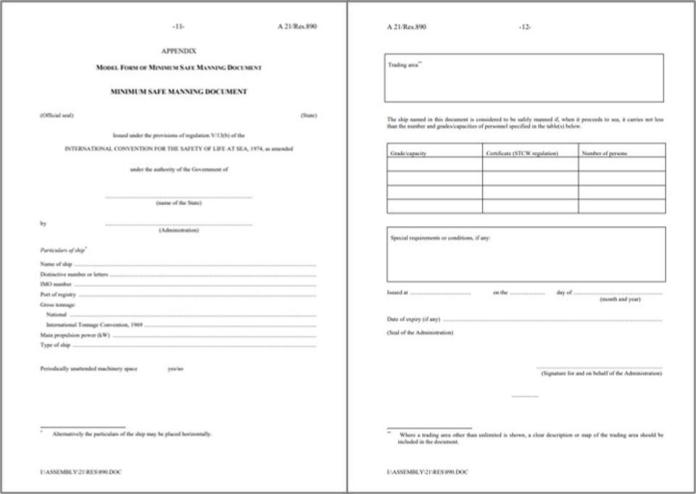
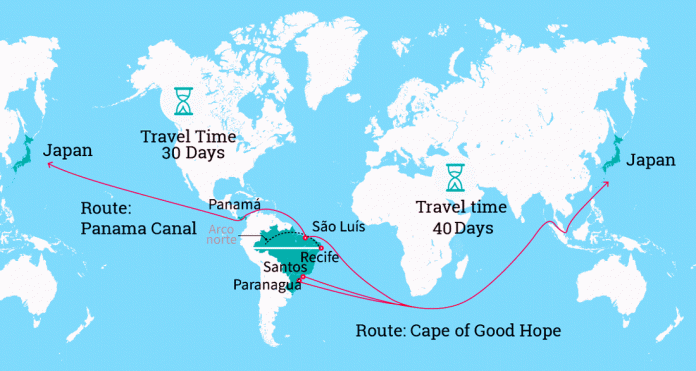
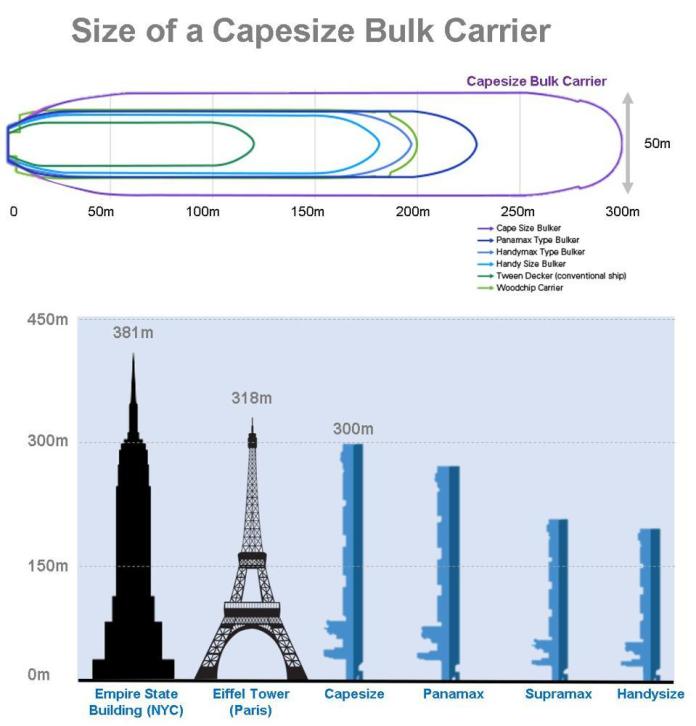

By Inga Neilsen Associate Producer
A cargo ship riddled with coronavirus cases off the coast of Western Australia has sailed from its anchorage at Port Headland last night.
The Vega Dream, an iron ore bulk carrier, arrived from Manila in the Philippines via Shanghai.
While docked off the WA coast, the ship returned seven positive tests out of the 20 crew members on board
The outbreak started from one crew member who returned a "weak positive" test on Monday after being hospitalised the day before, WA authorities said.
The vessel is now en-route to the Philippines after given clearance by the Australia Maritime Safety Authority last night.
"In line with its commitment to humanitarian care, the Western Australian Department of Health offered assistance to the COVID-19 positive crew," the WA Department of Health said in a statement.
"However as medical intervention is not currently required, this was declined."
WA Health noted that it had provided advice to the vessel around infection prevention and control, as well as access to the Department's vessel deep-cleaning plans.
WA Health said the same methods were used for successfuly containing COVID-19 outbreaks on other plagued ships off the states' coast - the Artania, Al Kuwait and Patricia Oldendorff.
検疫とPCR検査の陰性判定を受けるなどフィリピンの規則を守って感染が広がった事実は東京オリンピックを強引に開催するとしても外国人の入国をかなり減らして厳格にしないとオリンピック後に日本が大変なことになる事を意味すると思う。
検査の制度の問題もあるし、感染者が検査で陽性が出るタイミングでなければ結果に表れないなどを考えるとリスクは絶対に存在すると理解して対応するしかない。つまり人の移動や接触が増えれば、検査で陰性となっているが実際は新型コロナに感染している人との接触機会が増える、そして、接触より感染した人がさらに感染していない人達に感染させると言う事。
感染している人達が少ない環境であれば人の移動や接触が増えても感染は急速に広がらないが、感染者が増えれば、同じ環境や時間でも感染者は急激に増えると思う。
感染者が多い国では感染者が多いので人の移動や接触が増えればすぐに感染が加速して二次関数的な増加で広がると思う。まあ、個々が判断する自由があれば、自己責任で選択すれば良いと思う。
商船三井は12日、同社の保有する貨物船「ベガ ドリーム」のフィリピン人船員20人のうち、7人に新型コロナウイルス肺炎の陽性判定が出たと発表した。同船はオーストラリア西岸の港に3日到着し、現在は同港沖に停泊している、1人は地元病院で治療を受けており、命に別条はないという。残る6人に症状はなく、船内で自主隔離している。感染経路は不明。
陽性の7人は8~9月にフィリピンで乗船した。いずれも検疫とPCR検査の陰性判定を受けるなどフィリピンの規則を守っていたという。陰性の13人は船内で待機している。商船三井は今後の対応を検討する。
引き渡し後に運航して実際に、トラブルなどの経験を通して改良点や電動タンカーのメリットやデメリットが分かってくるのだろう。
内航船は外航船と違い大がかりなメンテナンスは基本的にドックで行う。この船はハイブリッドなのか、純粋な電動タンカーなのだろうか?非常用の発電機が
なければバッテリーに問題があったり、バッテリーの容量の表示に問題があり、実際の容量とバッテリーの表示と違えば航海中に推進力を失う可能性がある。
船が運航される港や施設が決まっていれば問題ないが、充電できる設備がない港には行けないとか、制限などがあるかもしれない。船員はこの船のために訓練は
必要だと思う。従来の船とは違うので教育なしで船に乗る事は出来ないと思う。まあ、それぐらいの事は考えていると思うので問題ないのかもしれない。
世界的に環境規制が厳しくなる中、温室効果ガスを出さずに電池だけで動く世界初の「電動タンカー」が日本で建造されることになりました。重油を燃料とする現在のタンカーに比べて運航管理の負担が小さく、人手不足が深刻な船員の負担を軽減する効果も期待されています。
この「電動タンカー」は、大手機械メーカーの「川崎重工業」が開発した電動システムを使って、四国の造船会社2社が合わせて2隻を建造します。
全長およそ60メートル、総トン数は499トンで、電気自動車およそ100台分の容量があるリチウムイオン電池で、温室効果ガスを排出せずに動くということです。
完成予定は再来年の3月で、タンカーを発注した東京の海運会社「旭タンカー」によりますと、電気だけで動くタンカーは世界で初めてだということです。
重油を燃料とする従来のタンカーに比べて建造の費用はかかりますが、運航を管理する作業の負担が小さく、人手不足が深刻な船員の負担を軽減する効果も期待されています。
建造されたタンカーは東京湾で重油を運搬する計画で、災害時には沿岸の施設に電気を供給することも検討するということです。
世界的に環境規制が厳しくなる中、自動車業界に続いて海運業界にも電動化の流れが本格的に広がるきっかけになるか注目されます。
由良町の造船所できのう(25日)午後、船の甲板の一部が落下し、下敷きになった作業員が死亡しました。
きのう(25日)午後4時ごろ、由良町の船舶工事会社「MES(エムイーエス)―KHI(ケイエイチアイ)由良ドック」の造船所で、船の甲板の一部が落下し、およそ2・5メートル下にいた別会社の作業員で大阪市の65歳の男性が下敷きになり、病院に運ばれましたが、間もなく死亡が確認されました。
御坊警察署によりますと、落下したのは重さおよそ7トン、最大部分の長さおよそ8メートル、幅およそ4メートルの鉄製甲板の一部で、死亡した男性は他の作業員4人と甲板の溶接作業をしていました。警察が、事故原因などを詳しく調べています。
ポートエンタープライズ(株)(兵庫県神戸市灘区篠原本町5-2-5、 資本金・7,187万4,000円、 設立・昭和43年8月、 代表清算人・黒澤 隆氏)は、神戸地方裁判所より特別清算開始命令を受けた。
当社は、昭和43年8月設立の船舶用機器卸売業者である。 貨物船を筆頭に各種船舶向けのエンジンや油圧機器・発電機などを主力に販売する他、ロープ類や帆布も取り扱ってきた。
インドネシアやマレーシアなど東南アジア圏が営業エリアの8割を占め、海運業者への納入で平成27年6月期では年商42億円内外をあげてきた。
しかし、堅調な受注基盤を確保してきたものの近年代表者の体調不良から経営環境に陰りが見え始め、取引行からの信用不安が高まっていた。
このような中、売上の水増しなど粉飾決算が発覚し、過年度の修正申告で28億円もの特別損失を計上すると22億円の債務超過に転落していた。

7日午後、愛媛県今治市の造船工場でクレーンから積荷が落下し34歳の作業員の男性が死亡しました。
警察によりますと、7日午後2時ごろ、今治市小浦町にある今治造船今治工場で白石英樹さん34歳が血を流して倒れているのを同僚が見つけました。白石さんは、市内の病院に運ばれましたが、まもなく死亡しました。警察によりますと、クレーンに釣られていた積荷の一部が落下し白石さんに当たったとみられ、警察は当時の状況を詳しく調べています。
愛媛県内の造船工場では、作業中の死亡事故などが相次ぎ、愛媛労働局は先月、造船の業界団体に対し、設備の緊急点検などを要請しました。しかし、その後も事故が続き、今年7月からの2か月余りの間に県内の造船工場で発生した死亡事故はこれで4件になりました。
5日午後、八幡浜市の造船工場にある建造中の船の中で作業をしていた56歳の男性が、二酸化炭素ボンベ8本が入った台の下敷きになって死亡しました。
5日午後3時すぎ、八幡浜市栗野浦の「栗之浦ドック」の第二工場で、建造中のケミカルタンカーの船内で作業をしていた男性が二酸化炭素ボンベが入った台の下敷きになって倒れているのを別の作業員が見つけて消防に通報しました。
男性は病院に運ばれましたが死亡しました。
警察によりますと死亡したのは八幡浜市五反田の会社員、都築真治さん(56)です。
都築さんは船尾にある部屋で1人で溶接などの作業を行うことになっていましたが、休憩時間になっても戻らなかったため作業員が船内を捜していたところボンベが入った台の下敷きになっているのを見つけたということです。
ボンベは1本当たり、縦1メートル60センチ、直径26センチの大きさで、重さは50キロあり、台には8本が入っていたということです。
警察は何らかの原因でボンベが入った台が倒れて下敷きになったとみて、事故の詳しい状況を調べています。
海運の働き方で変更できる部分と出来ない部分がある。外航海運と内航海運だけでも大きな違いがある。良く理解して改革方針を考えないと時間と努力の無駄になると思う。
船員の働き方改革をめぐり、政府は健康対策や労働時間の管理を強化することになった。海上運輸は日本の経済を支える上で大きな役割を果たす一方で、船の仕事には長時間勤務や重労働がつきものだ。早ければ来年の通常国会に船員法など関連法改正案を提出するが、既に労働環境改善の取り組みを始めた企業もある。
「このままだと船員を殺してしまう」。重油を運ぶタンカーを運航する白石海運(大阪市港区)の白石紗苗取締役(35)が8年前に社内の改革に乗り出したのは、強烈な危機感がきっかけだ。
出港した船が次の港に着くまで緊張感が続く。積み込みや積み降ろしの荷役作業も過酷で、真夏の体感温度は50度を超えることも。
船員を増やして1人当たりの乗船回数や日数を削減。会社の事務態勢も強化し、労働時間の記録管理や健康証明書となる船員手帳の更新手続きを一括した。健診後は船員が結果を会社に報告するようルール化し、既往症や服薬状況も把握した。
いずれも陸では一般的だが、船では徹底されていなかった。「昔の船員は一匹おおかみみたいな働き方だったからそれでもよかったが、今は働き手が定着しない」と白石さん。ベテランが「体が楽になった」と喜ぶ姿に、自身も「うれしい」と話す。
国土交通省のデータでは、国内の港を行き来する船の高齢化が最も高い。船員約2万8000人(2019年10月現在)のうち、46.4%が50代以上。持病を抱えながら働く人も少なくない。
豊国海運(東京都港区)は今年からタブレット端末を使ったオンライン診療の試みを始めた。急病やけがの際、端末経由で陸上の医師に診てもらえるだけでなく、血圧やアルコール呼気など日常的な健康チェックの結果も本社と共有できる。
先月27日、サムソン重工業・巨済造船所のタンカー建造現場で爆発と推定される事故が起き、下請け業者の職員が死亡した。労組は6人の命を奪った2017年のクレーン惨事当時に指摘した問題が、全く解決されていないために起きた事故だと見ている。
金属労組の巨済統営古城下請け支会は「サムソン重工業の5万トン級のタンカーの浄水タンクで、爆発と推定される事故が発生し、1時間捜索した後、タンク内部の密閉空間でペインティング作業をしていた労働者が死体で発見された」と、31日に明らかにした。タンクの外部でペインティング作業をしていた労働者は、身体に火が点いたまま辛うじて事故現場から脱出して、病院に移送された。
労働部統営支庁労災予防課の関係者は「労働者1人は死亡し、1人は全身の52%に、2度の火傷をして治療中」とし、「火災の原因が爆発であったかどうかは、鑑識結果が出なければ確実には判らない」と説明した。この日、国立科学捜査研究院と統営海洋警察署、労働部統営支庁は事故現場に鑑識を行った。
死亡事故の根本原因について労組は、爆発・火災事故が起り得る環境が全く改善されなかったせいだと見ている。「2017年のクレーン惨事当時、労働部の特別監督結果報告書で指摘された問題点に対する後続措置が、キチンとなされていなかった」ということだ。
労組が言う『クレーン惨事』は、2017年5月1日にサムソン重工業巨済造船所で、巨人クレーンとタワークレーンが衝突し、下請け労働者6人が亡くなり、25人が大怪我をした事件をいう。メーデーのこの日、造船所に出勤した労働者の大部分は下請け労働者だった。
当時、労働部はサムソン重工業巨済造船所に対する特別監督を行い、866件の産業安全保健法違反事項を摘発したが、この中には爆発事故に関する内容が含まれていた。『密閉区域での爆発の危険のない換気ファン・照明灯・電気設備設置』『密閉区域の有機溶剤除去、引火性蒸気の排出換気設置』『密閉区域作業の開始の前・中に、酸素濃度を測定』『密閉空間と外部の見張り役との間に常時連絡設備を設置し緊急状況に対応』『密閉空間への関係者以外の立入禁止』などだ。労組は「当時、労働部は既に爆発事故の危険要素を把握して改善を要求していた。それでも爆発事故が発生したということは、特別監督に対する後続措置が行われていないことを傍証する」と主張した。
労組はまた、サムソン重工業は他の造船会社と違う、危険性の高い塗料を使わせたと主張する。労組は「大宇造船は(今回の事故が起きた洗浄タンク関連の作業現場に)爆発・窒息の危険が少ない無溶剤の塗料を使ったが、サムソン重工業は有機溶剤の塗料を使った」とし、「有機溶剤の塗料は付着力を強める。すなわち労働者の安全より品質が優先とするサムソン重工業では、いつ爆発事故が起きてもおかしくない構造」と明らかにした。
また、死亡事故直後に『作業中止』がされた領域も問題だ。労組は密閉空間作業の全体あるいは密閉空間でのペインティング作業全体を中止するべきだとするが、労働部は事故が起きた作業場のスプレー作業に対してにだけ、中止命令を出した。現行の産業安全保健法は『事故が発生した作業と同じ作業』に限って、中止命令が出せるとしている。労組は「労働部が同じ作業の意味を縮小解釈し、塗装作業中でも、スプレー作業に対してのみ中止命令を出した」と主張した。
労組は「当初、文在寅大統領は重大災害の発生時には、全作業場の作業を中断し、原因糾明、再発防止策を用意すると約束した。」「ところが、2018年に産業安全保健法を改悪して、『事故発生作業と同じ作業』にだけ、作業中止がされるように縮小し、今では、同一作業の意味まで縮小して解釈するような結果に繋がっている」と話した。
2020年9月1日 京鄕新聞 ソン・ユンギョン記者
生きた船、又は、スクラップそして売りに出ていた59,400-ton 自動車運搬船 Sincerity Aceを購入して修理して運航させようとしたのは韓国の船会社。
まあ、詳細は知らないが、船の国籍がパナマ船籍から韓国国籍に変わったのであれば、国籍変更の書類やプロセスで韓国の行政機関が問題を見落としたのだから仕方がない。
実際、船の登録に関して詳細に調べる国は少ない。だから問題のある船や犯罪に使われた船でも特定の船籍であれば、登録が可能なのである。また、韓国の通関で提出する時に提出書類に不備があったのか、提出書類に不備があったが許可が下りてしまった事等も問題があると思う。
日本でもある事だが担当者が違えば意見や判断が違う事はある。まあ、癒着や袖の下が有効なのか次第で違ってくる場合もあると思う。

2020年8月21日、韓国・KBSが「米国に向かっていた日本車3800台が韓国で廃車になる」としてその実態を報じ、韓国のネット上で注目を集めている。
横浜から米国に向かっていた自動車運搬船「シンセリティー・エース」(パナマ船籍、約5万9000トン)で18年12月31日、大規模な火災が発生した。船には日本車約3800台が積まれており、この事故による財産被害は100億円を超えたとされている。
記事は「問題は、パナマ船籍の日本の船会社が運営していたこの船が韓国国籍に変わったことにより発生した」としている。事故後、船は国際中古船舶市場に売り出され、韓国の船会社が約35億ウォン(約3億円)で購入。昨年2月には船舶の臨時国籍を取得し、船は韓国の領海を運航し始めたという。
その後、船は紆余曲折の末に慶尚南統営市の安定国家産業団地に入港することになったが、韓国政府や関税庁は積まれていた約3800台の自動車の処理に悩んだ。燃えてしまった自動車は、国と国の間の移動が厳しく制限された廃棄物(両国政府の承認が必要)に分類されるためだ。船を購入した船主は統営港で船を修理して使用する計画だったが、自動車の輸入許可が下りないために数十億ウォンの損害を被ったという。
韓国政府は苦心の末、先月になってようやく輸入許可を出した。一方、日本政府は「燃えた自動車は日本から輸出した廃棄物でない」として「廃棄物の搬入は政府が関与する問題でない」との立場を貫いているという。韓国政府関係者は「今回のような、公海上で発生した船舶火災事故の廃棄物の国内への搬入は非常に珍しいケース」と話したという。
自動車は最近、荷役作業が始まり、今後2カ月で全て廃棄されるとみられている。記事は「日本の自動車約3800台が韓国で屑鉄として廃棄される異例の作業が始まったということだ」と説明している。
また、統営地域の住民らは、長期間放置された船による「2次被害」を心配している。統営付近の海は米食品医薬品局(FDA)から認定を受けた清浄海域で、カキやホタテなどの養殖場が密集している。そのため今回のことで「清浄海域地」のイメージが崩れたり、汚染被害が発生したりしないかと懸念が高まっているという。
韓国政府は、廃棄物の国と国の間の移動やその処理に関する法律を見直し、今回の事例のように廃棄物が船舶で長期間放置されることがないように改善案を講じる考えを示している。
最後に記事は「数奇な運命をたどったこの船の次の航海地は分からないが、今回の事例は廃棄物の輸入と処理に関する重要な事例として残ることは明らかだ」と伝えている。
これに韓国のネットユーザーからは「日本の廃棄物を買うなんてどうかしている」「業者は一体どんなつもりで購入した?損したとしても入港許可を出すべきでない。日本に送り返してほしい」「利益を追求するとしても、ある程度は環境や他人への配慮が必要だ。船主にとっては1つのビジネスだけど、それ以外のほとんどの韓国人に被害を与えている」「なぜ環境団体や反日団体はこういう問題に抗議しない?」「中古船舶市場で買ったならまた同じように売ることもできる。韓国が輸出した車でもないのに…。いくらお金になるといっても法律の穴を利用して廃棄物を輸入する行為は許せない」など、船の購入者への批判の声が続出している。
韓国政府に対しても「環境部関係者を調査してほしい。なぜこんな廃棄物の輸入を許可した?これは親日行為では?」「最初に領海への進入を禁止するべきだった。法的根拠もあるのに」など不満げな声が寄せられている。(翻訳・編集/堂本)
福岡泰雄
 長崎県松浦市の岸壁に17日、自動車運搬船「シンセリティー・エース」(パナマ船籍、約5万9千トン)が接岸した。昨年末に3千台超の車を積んで横浜からハワイに航行中、太平洋上で火災を起こした船だ。
長崎県松浦市の岸壁に17日、自動車運搬船「シンセリティー・エース」(パナマ船籍、約5万9千トン)が接岸した。昨年末に3千台超の車を積んで横浜からハワイに航行中、太平洋上で火災を起こした船だ。
引航してきた日本サルヴェージ(本社・東京)によると、船には鎮火後の状態のままで車が積まれている。同市今福町の民間企業の敷地の岸壁を一時「間借り」し、その間に船の管理会社が韓国に船を移動させる調整をするという。
地元の漁協は「10日間ほど接岸させてほしい」とサルヴェージ社から打診された。その間に、韓国側との協議が整わなかった場合は、被害のなかった一部の車を今福で下ろしたいとの意向も示されたという。
船は火災後、処理の決まらぬまま九州各地の港を経て持ち込まれた。この日は正午前、岸壁との間にクレーン船を1隻はさむ形で接岸。船体は少し右舷側に傾き、さびが目立った。見物に来ていた住民らは、船体に残る火災の爪痕に驚いていた。(福岡泰雄))
クルーズ船運航会社の倒産となるのだろうか?
(ブルームバーグ): マレーシアの富豪、林国泰氏が率いる東南アジア最大級のコングロマリット、ゲンティンの株価が21日のクアラルンプール株式市場で大きく下げている。クルーズ船運航会社のゲンティン香港(雲頂香港)が債権者へ全ての支払いを停止すると前日発表した。
ゲンティン株は前営業日比で一時5.8%安となった。20日のマレーシア市場は祝日のため休場だった。
雲頂香港への協調融資に加わったマレーシアのマラヤン・バンキングやRHB銀行の株価も下落。クアラルンプール郊外でカジノとリゾートを運営するゲンティン・マレーシアの株価は一時6.1%下げた。新型コロナウイルス感染拡大でクルーズ旅行需要が減退したほか、移動制限でカジノやリゾートを訪れる人も減っている。
林氏は雲頂香港の持ち株ほぼ全てを融資の担保として差し出している。ブルームバーグ・ビリオネア指数によれば、林氏の資産は担保の株式を除いて約7億ドル(約740億円)と、年初の15億ドルから大きく減った。林家の持ち株会社にコメントを求めたが返答はなかった。
原題:Lim’s Genting Empire Under Pressure After Cruise Firm Debt Woes、Chairman of Ailing Cruise Firm Pledged Almost All His Shares (3)(抜粋)
クルーズ船運航会社の倒産となるのだろうか?
流通科学大の森隆行教授は17日夕、東京都内で開かれた海事振興連盟の「年齢制限のない若手勉強会」で、「外国人労働者『船員内航船への導入問題』(日本社会への影響)」をテーマに講演した。森氏は「船員不足が内航海運の最大の課題」と指摘し、「日本人船員確保・育成は当然必要。一方で内航海運への外国人船員導入を求める主張ではないが、カボタージュ規制(国内海上輸送の自国籍船限定)を堅持した上で、外国人船員導入に関する議論の必要性はある」と述べた。
森氏は「外国人船員を配乗させた場合は、受け入れ人数の枠組みを構築すべきだ」と主張。労使に政府が加わり、雇用や賃金を含めた労働条件について、きちんとした枠組みをつくることも前提とした。
さらに「船員不足が特に深刻な一部中小船主の間で、外国人船員の導入を望む声が聞かれるようになってきて、非公式の場で外国人船員の問題が議論される場面も見られるようになった」と内航業界の現状を語った。
日本の内航船で外国人船員の配乗が認められていない理由については、「カボタージュ規制によるものではなく、1966年の外国人労働の受け入れに関する閣議決定によるもの」と説明した。
内航海運業界で外国人船員を受け入れられないとする理由にも言及。
内航船の場合、外航船と違い外国人船員は日本に住むためコストは安くならない▽内航船員に英語でのコミュニケーションは困難▽瀬戸内海など複雑な海域の航行は外国人には難しく任せられない―といった点を紹介した。
これに対し、「内航での外国人船員導入の話はコストの問題ではなく、外国人船員は必ずしも日本に居住するわけではない。船内のコミュニケーションも日本語で行うことを前提にすべきだ。日本人の経験の浅い船員でも複雑な海域の航行は難しいのでは」と発言した。
外国人船員を内航海運に導入することによる日本社会への影響も考察。雇用・賃金面については、「供給が需要を上回らないように外国人船員雇用数をコントロールし、給料を含めた労働条件のルール作りを行うといった前提があれば、影響はない」と主張。治安・生活環境といった面でも大きな影響はないとした。
同勉強会は海洋立国懇話会と共同で開催しているもので、今回は新型コロナウイルス感染予防対応として、人数を絞って行った。
「In a press conference, the centre’s communicable disease branch head, Dr Chuang Shuk-kwan, said that as of Sunday, 55 people working at the container terminal were confirmed to have contracted the virus. Among them, 41 are staff of Wang Kee Port Operation Services.」
コンテナの荷役は半自動だからコンテナ船に行くのが怖くなる。
負のスパイラルのはじまりか、もう、既に始まっていると思う。
外航船は日本で建造する必要はない。ただ、外国の造船所は日本の造船所よりもごまかしがひどいと聞く。船の事が良く知っていなければならないし、外国人との
交渉を英語が出来る日本人の監督はそれほど多くないと思う。外国人に任せすぎるとインド洋モーリシャス沖で座礁した日本の貨物船「わかしお」
のように問題が起きた後では遅いと言う事になる可能性はある。
ポーランドは一時は造船が盛んであった。ポーランドの人件費でも造船は成り立たなくなった。最後のステージでは、北朝鮮からの出稼ぎ溶接職人がたくさんいたそうだ。
能力が高い人達はEU圏内の給料の良い造船所や造船又は海運関連会社に移ったそうだ。造船が終わった後に、雇用にために再び造船を復活させたいとの動きはあったそうであるが、人が戻ってこない、クレーンや作業機械の維持管理がひどく、稼働するには
かなりのお金がかかるとの事でほぼ不可能であることがわかったそうだ。
残すにしても、終わらすにしても、正解は存在しないし、安い給料でも仕事があった方が良いのか、別の仕事を探すほうが良いのか、人の生き方や価値観で違ってくるので
同じ選択はないだろう。アメリカでも生産が強い時代には地元の大きな工場で働くのが普通の時代があったそうだ。上手く乗り越える事が出来なかった自治体は
職なし、高給の仕事なし、若者の流出、低賃金や貧困家族の増加でみすぼらしい町になっていったようだ。衰退した町は昔はお金にゆとりがあったのかなと思われる
古い建物があったり、お金にゆとりがなくなって維持管理できなくなり放置された建物が目立つので分かりやすい。日本の自治体でもおなじようになって行くケースが
増えるのだろうか?
三井E&S HD、旧三井造船が玉野市の主力工場で船舶の建造から事実上、撤退することが分かりました。造船の町はどうなるのか。地元からも不安の声が上がっています。
玉野市の玉地区にある商店街は平日ということもあり人もまばらで静か。それでもすぐ近くにあるある企業の話題が、地元の人たちを騒がせていました。
(まちの人は…)
「びっくりしましたけど、大変。下請けの人たちが」
「造船が無くなるのは寂しいなと。これからが心配」
三井E&S HD、旧三井造船は8月5日、玉野市の工場で船舶の建造から撤退する方針を明らかにしました。
商船の建造は広島の会社、防衛省向けの艦艇事業は東京の三菱重工業にそれぞれ委託、譲渡を検討するとしています。
旧三井造船の始まりは100年以上前、創業の地は、今の玉野市でした。
工場の見学や進水式の公開なども行い地域にとって欠かせない存在に。市内の事業所で働く人はHDの関係だけで、2000人を超えています。しかし造船事業は中国や韓国との競合で赤字が続き、事業規模縮小の対象になりました。
玉野市内には関連会社も多く、地域経済への影響も懸念されるもののHDは「艦艇事業は、三菱重工業に譲渡しても市内で建造を続ける方向で協議している」としています。
(玉野市 黒田晋市長)
「ものづくりの工場として今後展開をしていくための仕組み作りだと(以前から)お聞きしておりますし、モノづくりの集団、造船業というものをきちんと残していくべく、全力を挙げて取り組みたい」
長年、まちを支えてきた基幹産業はどうなるのか。
市もホールディングスも、地域にとって大切な灯を絶やさないよう力を尽くしたいと話しています。
岡山放送
三井E&Sホールディングス(東京)が、造船子会社・三井E&S造船玉野艦船工場(玉野市玉)での商船の建造を終え、提携先に生産委託していく方針を発表してから一夜明けた6日、地元の玉野市で波紋が広がった。船舶建造の大幅縮小が見込まれる中、関係者らからは雇用や地域経済はどうなるのかといった不安の声が聞かれた。
黒田晋市長は「三井側から、(常石造船や三菱重工業など)他社との協議は玉野の製造拠点を残すためで、仕事や雇用が失われることはないと聞いている。協議の進展を見ながら、仮に『話が違う』ということになれば、維持してもらえるよう厳然と申し入れする」と述べた。
玉野商工会議所の実井準専務理事は「創業の地として発展してきた企業城下町が、岐路に立たされている。三井の撤退で雇用が減り、人口減少につながらないよう、できる対策は全て打ちたい」と話す。
昼休み、工場の外で休憩していた協力企業の40代の男性従業員は「会社から正式な話がないので何とも言えないが、以前から縮小傾向にあるとは耳にしていた。自分たちの仕事がこれからどうなるのか」と表情を曇らせた。
工場は1917年に三井物産造船部として創業して以来、地域にとって欠かせない存在。近くの菓子店「やまもと製菓」は、進水式にちなんだもなか「進水 久寿玉」が看板商品。4代目店主の山本一樹さん(58)は「造船のまちで生まれ育ったのがわれわれの誇り。どのような形でも船造りの灯はつないでほしい」と訴えた。
経営再建中の三井E&Sホールディングス(HD、東京)は5日、2020~22年度の中期経営計画を発表し、造船子会社・三井E&S造船玉野艦船工場(岡山県玉野市玉)で手掛けるばら積み貨物船などの商船建造を終え、提携先に生産を委託する方針を明らかにした。玉野で造船に携わる従業員は提携先に転籍となる可能性がある。
同日発表した第1四半期決算で、今年4~6月の商船受注がゼロに、受注残が5隻になったことを開示。同HDの岡良一社長=玉野市出身=は商船事業について「受注はかなり厳しく、工場を持たない方向で検討している。受注残は玉野で造るが、以降は協業先と決定していきたい。主に(協業先の)揚子江船業、常石造船への建造委託を考えている」と述べた。
計画期間中、グループ従業員1万3千人を事業売却による他社への転籍などで2千人程度減らすことも表明。玉野の造船部門の約850人については一定人数がグループ外に転籍する方向ながら、今後の詳細は未定という。同HDは商船について「国内建造を希望する船主もおり、船価が改善すれば再び玉野で造る可能性はある」としている。
造船・重機大手の同HDは、インドネシアの火力発電所建設工事で巨額損失を出し、昨年5月に経営再生計画を策定。中国や韓国勢との競合で営業赤字が続く造船部門では、商船に特化した千葉工場(千葉県)を来年3月で閉鎖することを決めた一方、中国大手・揚子江船業との合弁で商船建造の子会社を稼働させた。
玉野の事業については来年10月をめどに、商船事業で常石造船(福山市沼隈町常石)と資本提携し、防衛省向け艦艇事業は三菱重工業(東京)に売却する計画を進めている。
玉野に勤務する従業員は「まだ詳しい説明がなく、何とも言えない」。玉野市内の協力会社幹部は「今年に入って下請けの仕事が減っており、嫌な予感が当たってしまった。造船に携わる市民は多く、非常に心配。何とか地域の雇用を維持してほしい」と話した。
玉野は三井E&Sグループ創業の地。艦船工場のほか、国内トップシェアの船舶用エンジンや産業機械を主力とする三井E&Sマシナリー玉野機械工場ががあり、協力会社を含め約4千人が勤務している。マシナリー社は業績が堅調で、中期経営計画では今後の中核領域と位置付けており、玉野の主力事業となる見通し。
◇
同HDの2020年4~6月期連結決算は、純損益が84億円の赤字に転落した。前年同期は23億円の黒字だった。新型コロナウイルスの影響で、海洋油田の生産設備を手掛ける子会社の収支が悪化した。売上高は前年同期比0・4%増の1607億円。
ツネイシホールディングス(HD、広島県福山市)傘下の常石造船(同)は同じ瀬戸内地方に工場を持つ三井E&S造船(東京・中央)に出資する協議に入った。2018年から部品の共同調達などで業務提携していた。中国や韓国の造船大手との受注競争が激しくなる中、連携を強化し、経営体質の改善を狙う。
両社はこれまでも設計技術の供与、研究開発などで提携していたが、資本を入れることで協力の範囲を広げてスピードを早めることを狙う。中・小型のばら積み船などの共同受注も検討する。20年12月をメドに最終契約を結び、21年10月の出資完了を目指す。
ツネイシHDの造船事業は常石造船が柱で、19年12月期の売上高は前年比8%増の1646億円。従来ばら積み船を得意としていたが、近年はタンカーやコンテナ船など船種を広げてきた。いち早く海外生産に注力、1994年からフィリピン、03年から中国で造船所を運営する。現在の生産能力は常石工場(福山市)が2割、海外の2工場がそれぞれ4割だ。
海外に工場を持つ常石は国内の相場に比べて安い船価で受注できるが、それでも中国勢と同等の価格競争力を持つには至らないという。強化される環境規制を背景に、燃費の良さなど性能を売りにして生き残りを図っている。
三井E&Sホールディングスは1917年、岡山県児島郡日比町(現・玉野市)に旧三井物産造船部として創業したのがルーツ。現在も同市内に造船子会社、三井E&S造船の工場を置く。
2年前の業務提携では三井側が受注した船を常石の海外工場で建造する構想もあったが、まだ実現していない。今回の資本提携を機に生産能力の共用も一段と進める可能性がある。
国内の造船大手は安い船価を武器にする中韓勢との受注競争で収益が悪化している。厳しい船価でも造船所の稼働を維持し地域の経済を守るため、受注せざるを得ない局面もある。
「いずれは資本提携に発展すると想像していた。驚きはない」。冷静に受け止めるのは、愛媛の中堅造船会社の幹部だ。コロナ下で受注環境が厳しいだけに「大きな会社ほどダメージも大きい。提携拡大のスケジュールが早まったのではないか」と指摘する。
大阪市に本社を置くサノヤス造船の上田孝社長は「グローバル競争が激しくなる中で、造船各社は戦略を見直す時期に差しかかった。当社も人ごとではない」としている。
瀬戸内など西日本は国内の造船業の中心地。愛媛県には建造量で国内首位の今治造船の本社があるほか、2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU)も広島県呉市に主力事業所を置く。
造船は自動車や家電に比べて部品点数が多く裾野の広い産業だ。船舶用エンジンではヤンマーグループ、ボイラーの三浦工業、船舶用塗料の中国塗料など、関連産業がこれほどそろうのは世界でも北欧くらいだ。
一方、労働集約型で地域の雇用を支えてきた。JMUが2021年での新造船からの撤退を決めた舞鶴市では、地元の商工会議所が「市経済にとって最悪の事態」との声明を出した。
新造船の受注環境が厳しい中、業界の合従連衡は加速する見通しだ。西日本でも造船所の再編が進む可能性がある。関連企業も地域の経済界も、各社の動きを注視している。
このケースを考えるとクルーズ船関連会社の倒産が年末までには起きそうだ!
[オスロ 3日 ロイター] - ノルウェー政府は3日、今後出航する100人以上が乗るクルーズ船を対象に、国内の港への下船をすべて禁止した。期間は2週間。すでに出航している船からの下船は可能という。
先週末に同国のトロムソ港で一部の乗員・乗客を下ろしたクルーズ船で新型コロナウイルス集団感染が分かったことを受けたもの。
この船はノルウェーのフッティルーテンが運航する「ロアール・アムンセン」で、保健当局によると、乗客・乗員の少なくとも41人が新型コロナの検査で陽性反応を示している。他の乗客・乗員、数百人には10日間の自主隔離措置が言い渡された。
当局者によると、ノルウェーは乗員・乗客の出身国であるドイツ、デンマーク、オーストリア、フィリピン、ラトビアの当局と連絡を取っている。
人口540万人のノルウェーは、新型コロナ流行を制御できているとして、数週間前に大半の経済活動を再開させた。3日時点で、同国での感染者は9268人、感染による死者は256人。
フッティルーテンは6月半ば、新型コロナの感染拡大を受けて停止していた外航クルーズ船の運航を、人数制限や厳格な感染予防対策を講じた上で、世界に先駆けて再開していた。
集団感染を受け、同社は当面、クルーズ客船の運航を中止する。
同社のシェルダン最高経営責任者(CEO)は会見で謝罪した。
ノルウェー警察はロイターに対し、今回の問題で違法行為がなかったか調べる方針を明らかにした。
「フッティルーテンは6月半ば、新型コロナの感染拡大を受けて停止していた外航クルーズ船の運航を、人数制限や厳格な感染予防対策を講じた上で3カ月ぶりに再開した。」
人数制限や厳格な感染予防対策を講じた上で新型コロナに40人が感染していたのでは、クルーズ船ビジネスは当分厳しいと思う。クルーズビジネスは新型コロナの終息なしには
無理な状態だと思う。
[オスロ 2日 ロイター] - ノルウェーの保健当局は2日、7月半ば以降に運航された2本のクルーズの乗員・乗客の間で少なくとも40人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。
感染者が確認されたのはフッティルーテンが運航するクルーズ船「ロアール・アムンセン」。7月31日にトロムソの港に到着した際に乗員4人が病院に搬送され、その後新型コロナへの感染が確認された。検査の結果、乗員158人のうち、この4人のほかにさらに32人が感染していることも判明した。
乗員は船上で隔離されているが、31日に到着した便の乗客178人は、乗員の感染が確認される前にすでに下船しており、追跡作業が行われている。
保健当局とトロムソの自治体によると、7月17日以降に運航されたロアール・アムンセンの2本のクルーズに参加した計387人の乗客のうち、これまでに4人の感染が判明している。
保健当局幹部は、このクルーズ船に関連した感染者の増加が予想されると述べた。
フッティルーテンは6月半ば、新型コロナの感染拡大を受けて停止していた外航クルーズ船の運航を、人数制限や厳格な感染予防対策を講じた上で3カ月ぶりに再開した。
フィリピンで新型コロナウイルスの感染者が10万人を超え、首都マニラなどでは4日から再び移動制限などの規制が強化されることになりました。
フィリピンでは2日に新たに5032人の感染者が確認され、国内の累計感染者は10万人を超えました。これを受け、ドゥテルテ大統領は4日から18日までマニラ首都圏やその周辺の州で鉄道やバスなどの公共交通機関を休止するなど、規制を再び強めることを明らかにしました。フィリピンでは3月に都市封鎖が実施されて以降、一部の地域で規制の緩和が順次、進められていましたが、医療体制が逼迫(ひっぱく)していることを受けて医療団体は再度、規制の強化を求めていました。
フィリピン船員次第であるが休暇で家族に会いに帰ったのは良いが感染していないのかを確認する作業がたいへんだろう。船員交代で他の船員に感染させるリスクを 考えた対応する必要がある。
フィリピンの新型コロナの1日の感染者が1日だけで5000人に迫り、「ここが第2のニューヨークになる」という切迫した意見がフィリピン医療界から出ている。ドゥテルテ政府が緩和した封鎖令を再び強化するよう求めた。
ロイター通信によると、フィリピン保健省は同日、史上最大の4963人の新規感染者が出たと報告した。 一日の感染者だけ見れば、メキシコやロシアに続き、世界で3番目だ。 感染者は9万8232人で、死者は17人増の2039人となっている。
フィリピンの医療団体は政府に公開書簡を送り、「われわれは国家に遭難信号を送る。 医療システムが手に負えなくなっている」と訴えた。
また「我々はコロナとの戦いで負けている。 団結して最終行動計画を立てなければならない」と求めた。 ある保健団体関係者は「今回の事態でフィリピンは第2のニューヨークになるだろう」とし「患者たちが家や担架の上で死ぬ瀬戸際状況に追い込まれるだろう」と述べている。
医師たちは、ドゥテルテ大統領に対し、今月15日まで首都マニラとその周辺を「厳重隔離地域」の状態に置き、新たな戦略作りの時間を設けるよう求めた.
三井E&Sホールディングスは31日、ツネイシホールディングス(広島県福山市)と、造船子会社同士が資本提携する方向で協議入りすると発表した。三井E&Sが子会社の三井E&S造船について、保有株の一部をツネイシ傘下の常石造船に譲渡する。価格競争が激化し、中国勢や韓国勢に押される中で、一体的な事業運営を進めて生き残りを図る。
出資比率などは今後詰めるが、常石の資本参加後も三井E&Sは親会社の地位を維持する。年末をめどに最終契約書を交わし、来年10月に手続きを完了したい考えだ。
三井E&S造船と常石は2年前に業務提携。互いの強みを生かしつつ費用削減や人材交流を進め、資本提携への発展を探っていた。
三井E&Sは造船事業の不振などで、本業のもうけを示す連結営業損益が令和2年3月期まで3年連続で赤字となっている。このため造船事業の構造改革を打ち出し、他にも千葉工場(千葉県市原市)での商船建造から撤退することを決めたほか、艦船事業を三菱重工業に譲渡する方向で協議している。
国内の造船業界をめぐっては、首位の今治造船が2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市西区)に3割を出資することを決めており、生き残りに向けた再編の動きが加速している。(井田通人)
三井E&Sホールディングス <7003> とツネイシホールディングス(広島県福山市)が造船事業で資本提携に向けた協議を始めることが31日、分かった。傘下の三井E&S造船と常石造船は、2018年に商船分野で業務提携し、設計、調達、製造などで協力を進めている。さらに資本提携に向けた協議に踏み込み、造船事業での生き残りを目指す。
造船大手のジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市)は30日、有明事業所(熊本県長洲町)の従業員の50人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。これを受け、同社はもともと土日出勤の職場も含めて、同事業所で7月30日~8月2日の4日間を休業とする。本社には「有明クラスター対策チーム」を設置した。
有明事業所では大型タンカーなどを製造している。同社によると、25日に同事業所の社員2人の感染が判明。その後PCR検査を実施し、同じ職場にいた濃厚接触者など対象者247人のうち、29日午後6時までに同社や協力会社社員の合計50人の感染が判明した。同事業所には正社員と協力会社の合計で約2400人がおり、その約2%に相当する。残り92人も検査の結果待ちの状況だ。
同事業所は感染発覚以降一部の生産を中止し、濃厚接触者にPCR検査や2週間の自宅待機措置を命じたが、さらに拡大防止を徹底するため休業に踏み切った。現状「業績への大きな影響はないと見ている」という。JMUではこれまで他事業所含め数人規模の感染はあったが、数十人規模の感染は今回が初めてだ。
同社は現場から事務所に戻った際など「一部でマスクの着用など徹底が不十分だった」としており、日本造船工業会(東京・港)が5月に策定した造船所向けの感染対策ガイドラインを守るよう「周知を徹底し、原因究明に努める」としている。
造船大手ジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市)は27日、熊本県内初のクラスター(感染者集団)とみられる新型コロナウイルスの集団感染が、長洲町の有明事業所で発生したと自社ホームページで公表した。4月に有明保健所管内(玉名郡市、荒尾市)で感染確認された男性が、協力会社の社員だったことも明らかにした。
同社広報グループによると、有明事業所の従業員は約1200人。協力会社を含めると約2400人が働く。3月末以降、事業所にはマスク着用や時差出勤、食堂など共用設備の使用中止など対策を指示したという。ただ、4月に協力会社社員の感染が確認されたにもかかわらず、感染者が相次いだフロアでは、普段から大半がマスク未着用だったことが有明保健所の聞き取りで判明している。
同社は「地域に心配をかけて申し訳ない。保健所の指導も受けながら、適切な感染予防対策を改めて徹底したい」としている。
地域最大の企業での感染拡大に住民らには戸惑いが広がった。長洲町の自営業の男性(71)は「長洲のような小さな町で起きるとは。自粛ムードが高まり、店の売り上げに今後響いてこないだろうか」と懸念した。
中逸博光長洲町長は「感染が広がらないよう町民や企業に予防策の徹底を呼び掛けたい」と強調。「スピード感を持って対応するには保健所と自治体、企業が情報を共有する場が必要だ」と、町への情報提供が少ないことに不満も示した。
有明保健所管内では、家族が有明事業所に通う人が出勤を見合わせるケースも。玉名市は集団検診を急きょ中止した。県玉名地域振興局も、管内首長や警察署長らを対象に31日に開く予定だった主要事業説明会を取りやめた。(樋口琢郎、長濱星悟、松本敦)
日本政府が自国の造船業と海運業を支援するため1件当たり数百億円規模の大規模金融支援を実施する。
27日の読売新聞によると、日本政府は世界の造船市場のシェアを拡大する韓国と中国に対抗するため、自国の造船業界に大規模金融支援を実施する方針を確定した。1件当たり数百億円規模と予想される金融支援を年内に実施して産業基盤を維持し、自前の海上輸送力を確保するという計画だ。
このため船舶を専門的に購入する特定目的会社(SPC)を海外に設立し、政策金融会社を動員してSPCに資金を支援する。日本国際協力銀行(JBIC)はSPCに直接資金を融資し、日本政策投資銀行(DBJ)はSPCに資金を融資する民間銀行に公的保証を付与するなど可能な手段をすべて動員する計画だ。
政策金融会社から支援された資金でSPCが日本の造船会社の船舶を購入すれば日本の海運会社はこのPCを通じて運用船舶を買い取ったり用船する。政策金融会社を通じて低利で資金を借りたSPCは低価格で用船が可能になり、日本の海運会社が日本の造船会社から船舶を調達する割合も増えるという計算だ。
日本の造船業シェアは受注量基準で2015年の32%から2019年には16%とわずか4年で半減した。韓国と中国の攻勢に押されたためだ。自国の造船会社の競争力が落ちて日本の海運会社が運用船舶を日本の造船会社に発注する割合も2014~2018年に75%まで落ちた。1996~2000年だけでもこの割合は94%に達していた。
日本はこれまで他国政府が自国の造船業を支援するのに反対してきた。2018年に現代重工業と大宇造船海洋の合併が発表されると、韓国政府が1兆円を超える公的資金を支援して市場競争を害したとして世界貿易機関(WTO)に2度にわたり提訴した。
これに対し日本政府高官は「このままでは日本の造船業が消滅しかねず、WTO協定に違反しない範囲内で政府が手を差し伸べるしかない」と説明した。
公取委、9億7千万ウォンの課徴金…下請の技術奪取では史上最高額
現代重工業が下請け会社の核となる技術を強制的に奪った末、約15年間続いてきた取引まで一方的に打ち切ったことに関し、技術資料の奪取で過去最高額の課徴金が課されることになった。
公正取引委員会(公取委)は26日、現代重工業が主要部品の供給を受けていたグローバル強小企業(小規模で一般的な知名度は低いが、特定分野で国際的に優れた実績のある企業)S社から強圧的に技術資料を奪ってライバル会社に渡し、その後、取引も打ち切っていたことを確認し、是正を命ずるとともに課徴金9億7千万ウォン(約8580万円)を課すことを決めたと発表した。公取委が技術資料の奪取と流用行為に対して課した課徴金としては、過去最高額だ。
公取委によると、現代重工業は2000年に船舶用ディーゼルエンジンを開発したが、核となる付属品であるピストンは国外メーカーから輸入して使用していた。これを改善するために現代重工業は2003年、当時韓国最高の技術を持っていたS社にピストンの国産化を要請し、研究開発の末、国外製品に代わるピストンの開発に成功した。両社の関係は2012年夏ごろ、現代重工業がS社の企業秘密であるピストン製造技術に関する情報を強制的に奪ったことで亀裂が生じた。現代重工業はS社からピストンの独占供給を受けていたが、数年が経つとコスト削減のために供給の二元化を望むようになった。結局、発注元の地位を利用してS社からピストン製作に必要な材料、部品、製造工程ごとの設備、管理項目などが記載された最重要技術資料を事実上強制的に奪った。続いてS社の技術を別のピストン開発企業B社に密かに渡し、製品を生産させた。
技術情報を渡さなければ量産承認が取り消される可能性があると、現代重工業がS社に圧力をかけていたことも明らかになっている。また、企業秘密の開示を求めつつも、何の書面資料もS社に渡していなかった。結局、現代重工業は秘密裏に進められていたB社の製品開発が終わると、両社に競争をさせた。その後わずか3カ月でS社製品の単価は11%も引き下げられた。これに止まらず、現代重工業は1年後にS社との取引を完全に打ち切った。遂にS社は2017年1月に現代重工業を警察に告発し、続いて公取委も昨年10月に検察総長の要請を受けて現代重工業と主な社員および幹部を告発している。
公取委は今回の調査で、大企業がコスト削減のため、下請企業から技術資料を奪い、これを他の企業に提供した末、遂には取引すら打ち切ったことを確認した。現代重工業は「欠陥発生対策のために資料を要求した」と主張したが、公取委は「欠陥発生に関する要求は最小限の範囲を超えており、欠陥が発生していない製品に関する情報も要求事項に含まれていた」として、これを認めなかった。昨年、国会の産業通商資源中小ベンチャー企業委員会の国政監査でもこの問題が取り上げられると、共に民主党のソン・ガプソク議員は「S社は現代重工業に技術が奪われて発注が急減し、2018年からは受注が完全に途絶えている」とし「協力企業の核となる技術を奪い、弊履のごとく捨てる行動が、果たして世界造船1位の企業にふさわしい行いなのかを考えなければならない」と非難している。ただし、公取委は昨年すでに検察に告発しているため、今回更なる告発はしないこととしている。
1975年に設立されたS社は、鉄道の機関車、発電所、エンジンの技術でコルベンシュミットなどのドイツの2つの企業と並び、ピストン分野で世界3大企業として認められてきた。昨年、日本が韓国を相手に報復的輸出規制を始めた際も、中小企業ベンチャー部が選定した「素材・部品・装備(素部装)強小企業100社」の一つに挙げられるなど、先進技術を持つ企業として評価されている。
公取委は「下請会社に対し技術資料を要求したり流用行為を行ったりしてはならず、正当な理由があっても必ず書面方式を取らなければならない」とし「技術力を持つ強小企業が正当な対価を受け取って、新たな成長基盤を整備できるよう、技術流用行為の監視を強化する」と述べた。
ホン・ソクチェ記者
造船大手のジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市)は27日、有明事業所(熊本県長洲町)の従業員23人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。同事業所の消毒を実施し、感染者に2週間の自宅待機を命じるなどの措置をとった。濃厚接触者96人についても順次検査を受けており、感染があった職場に関連する一部の生産を停止している。
有明事業所では大型タンカーなどを生産している。同社によれば25日に同事業所の社員2人の感染が判明。その後検査を実施し、27日午前10時までに社員22人、グループ会社社員1人の合計23人の感染が判明した。同事業所の正社員数約1200人の2%程度にあたる。
同じ職場にいるなどした濃厚接触者96人も、順次検査を受けている。すでに一部の生産を中止しており、「陽性者数による生産への影響を見極めている」(JMU)。同社ではすでに横浜事業所磯子工場(横浜市)や今回の有明事業所で協力会社など関係者の感染が確認されていたが、数十人規模の感染が確認されたのは初めて。
これまでマスクの利用や手洗い、時差出勤などをしてきたが感染が拡大したため「適切な感染防止対策に努める」としている。日本造船工業会(東京・港)は5月、造船各社について事業所の感染対策についてガイドラインを通達している。
国内造船首位のジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市)は27日、大型の原油タンカーなどを建造している有明事業所(熊本県長洲町)で、従業員の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。
25日に従業員2人の感染を確認。濃厚接触者96人が順次検査を受けており、27日午前10時までに、このうち21人の感染が判明したという。
「造船業が急激に悪化した2016年と同じ状況だ。あのときは工団(工業団地)の社員1000人が巨済を離れた。今年もすでに工場が何か所空っぽになったか分からない」
1994年から慶尚南道巨済市のソンネ工業団地で造船向け機資材を扱う企業を営むAさんは最近、全く眠れない日々を過ごしている。今年初めに仕事が入ってこなくなり3万坪規模の資材置き場が空っぽになった。「崖っぷちに追い込まれたというのはこういう感じなのか」。Aさんは1日に何十回もめまいを感じる。他の造船協力会社も状況は同じだ。工場の平均稼働率は15%以下まで落ち込んだ。一緒に働いていた工業団地の社員数百人はいつの間にか新たな仕事を見つけて巨済を離れた。
巨済は、大宇造船海洋とサムスン重工業という国内3大造船会社のうちの2社が拠点を置く韓国造船業のメッカだ。機資材を製造する協力会社数百社も、この2社と共に国内の船舶市場をけん引してきた。しかし現在は状況が異なる。格下と考えていた中国や東南アジアが韓国の造船業界と巨済を脅かし、2016年から造船海洋部門の受注が徐々に減少し始めたところに、今年に入って追い打ちをかけるように新型コロナウイルスと原油価格下落という直撃弾を受けた。国内造船3社の今年上半期の受注実績は目標額の半分にも満たないという。
一部では「カタールから液化天然ガス(LNG)船を100隻も受注したのになぜ苦境なのか」といぶかしがる声もある。しかしカタールは「スロット」(船舶建造スペース)を予約しただけで、実際に何隻発注するのかは契約書にハンコが押される直前まで分からない。契約締結後の設計、原資材の購入を経て本格的に建造に着手するのは早くて2022年だ。現在の受注低迷を解消してくれるわけではないのだ。
造船業界が最も懸念する部分は、今回の苦境を脱することができずに熟練工たちが巨済を去ることだ。ともすれば世界最高レベルの造船産業の生態系が崩壊する恐れがある。船舶と海洋プラント建造に投入される人材の80-90%は協力会社の労働者たちだが、不況の冷たい風は最も弱い存在である労働者たちに真っ先に吹き付けるのだ。巨済市は今年下半期までに最大8000人の協力会社社員が職を失うと推定している。
特に造船業界は、日本の前轍を踏むのではないかと懸念している。一時期、世界の造船市場を席巻していた日本は、1980年代半ばの不況期に入ると政府次元で造船業を斜陽産業と判断し、大規模な構造調整を実施した。その過程で熟練工たちが造船所を去り、他の産業へと散らばっていった。その後2000年代に造船産業が再び好況に転じると、日本は増加した需要をさばくことができず、韓国に世界1位の座を明け渡してしまった。
このままでは韓国も、日本の造船業が崩壊したのと同じ過程をたどるかもしれない。好況と不況の浮き沈みが繰り返される造船業の特性上、今後受注があったときに、これを処理する人員が必要だ。最近巨済市が雇用創出よりも現在の雇用を守ることに総力を挙げている理由がこれだ。それさえも政府の支援がなくては容易ではない。
巨済市は最低でも160億ウォン(約14億3000万円)が追加で必要だとみている。政府の次元で来年度の普通交付税(地方交付税)支援を拡大するとともに、産業危機対応特別地域への指定期間を延長するなどの支援が迅速に行われなければならない。一方で崩壊した産業生態系を再構築するためには、さらに高額の請求書が伴うものだ。国の基幹産業である造船産業の生態系を守るために、政府の関心と決断が必要だ。今後はカタールからの大規模受注の幻想から離れ、現実を見つめるべきだ。
キム・ウヨン産業部記者
建造した商船の写真などが飾られる神船の展示ホール=いずれも神戸市兵庫区和田崎町1
三菱重工業が2010年7月、神戸造船所(神船、神戸市兵庫区)で商船の建造から撤退すると表明して10年となる。12年6月末に最終船を引き渡した後は、防衛省向けの潜水艦などに特化。現在6千人超の従業員が在籍し、原子力や航空・宇宙の関連機器を中心に年間4千億円台規模で生産する。今も「造船所」の名をとどめる同社主力拠点の現状などを取材した。(長尾亮太)
「商船の建造を終えるまでに約1600隻の船を送り出しました」。開所からの歴史をたどる構内の展示ホールで、担当者が力を込めた。ここで産声を上げた数々の船の写真や、進水式で船体をつなぎ留めるロープなどが飾られ、往時の活況を今に伝える。
神船は1968年に国内で初めて建造したコンテナ船をはじめ、タンカーやばら積み船などを手掛けた。だが、中韓勢との激しい価格競争に巻き込まれた上、08年のリーマン・ショックで需要が一気に縮小。受注の見通しが立たなくなり、長崎、下関の両造船所に商船建造を集約する方針を10年7月に打ち出した。
■新たな培地
商船撤退で神船には5・4ヘクタールの敷地が生まれ、三菱重工の新たな事業や生産再編の受け皿となった。
同社は14年、国産初のジェット旅客機スペースジェット(当時はMRJ)の量産に向け、旧造船エリアなどを主翼の一貫生産ラインとして活用する構想を打ち出した。すでに外板の曲げ加工や切削、主翼の骨組みを削り出す設備を導入。同ジェットの開発が大幅に遅れる中、17年度からは米ボーイングの新型旅客機777Xの外板をつくる。
生産再編では、高砂製作所の大型冷凍機と、岩塚工場(名古屋市)の食品包装機械の各生産機能を、それぞれ17年と18年に神船に移管した。
■屋台骨
神船は、造船で培った溶接技術をもとに火力発電のボイラーを生産し、蒸気発生器などの原子力発電プラントに進出した。11年の東日本大震災で東京電力福島第1原発事故が起きると、安全性が問われる原発の事業環境は一変した。
それでも、同事故後に国内で再稼働した9基の原発は全て製造元の三菱重工がサポート。不測事態に備えたバックアップ機能など、新たな規制に対応した工事も手掛ける。また、同原発の汚染処理水を保管するタンク千基のうち、神船が192基を納入した。神船の生産額4千億円台のうち最大シェアを占め、屋台骨を支える存在だ。
【三菱重工業神戸造船所】同社発祥の長崎造船所に次いで古い事業所。船の修理拠点として1905(明治38)年に開設、2年後に建造を始めた。「次男坊」と位置づけられ、自由闊達(かったつ)な気風から、新たな事業が次々と生まれた。17(大正6)年に自動車を試作し、のちの三菱自動車に。19年(大正6)に分離した電機製作所は三菱電機の前身に当たる。2012年に商船建造から撤退した後、16年に民間航空機の部品工場を設けた。
■食品機械事業を移管「新たな製品を」三菱重工機械システム池田直昭社長■
商船撤退後の神船を舞台にした生産再編で、受け皿会社となったのが三菱重工機械システムだ。多彩な機械を製造する同社の経営戦略などを池田直昭社長(59)に聞いた。
-事業概要は。
「飲料の高速充填(じゅうてん)装置が食品包装機械の一例。缶ビール向けは国内でシェア50%を上回り、近年はチューハイ向けも増えてきた。もともと生産機能があった名古屋市内の工場は、新たな使い道を探ることになり、商船撤退で場所に余裕ができた神船に移した」
-地域とつながりは生まれたか。
「食品包装機械は多くの部品を使う。商船建造を支えてもらった地元の協力会社に、包装機械用の部品を供給してもらう事例もでてきた」
-強みと課題は。
「交通管理システム、風洞設備などの試験装置、輪転機をはじめ多彩な機械を一つの会社が手掛けることにより、『かけ算』で製品を生み出せる。新しい製品を送り出してきた神船の文化を体現するため、組織や拠点の枠を超えて力を合わせたい」
【いけだ・なおあき】阪大院修了。85年三菱重工業。神戸造船所の原発プラント部門を経験し、三菱重工機械システム設備インフラ事業本部長などを経て、20年4月から現職。神戸市東灘区出身。
山口県
2018年10月の大島大橋貨物船衝突事故で、被害を受けた周防大島町の住民や事業者が船主責任制限法に基づいて届け出た損害の調査期日(破産事件での債権者集会に相当)が20日、広島地裁であった。管理人弁護士は「島に架かる唯一の陸路が著しく損傷したことで、断水や通行止めが生じることは予見可能だった」として、断水などで被害を受けた住民に上限10万円の慰謝料を支払う意向を示した。貨物船を所有する海運会社側は異議を申し立てた。次回期日は9月16日の予定。
調査期日は非公開で、関係者によると、管理人弁護士は、東日本大震災の東京電力福島第1原発事故による避難者の裁判での損害賠償額などを参考に、慰謝料の上限を決めたと説明。断水に伴う町外への一時避難や水運びによる骨折や体調不良は、事故との因果関係が認められないとしながらも、避難費用や通院・入院の医療費を慰謝料の一部と見なして、上限10万円の範囲内で認めるとした。
イエメン沖で放置の貯蔵施設は英語の記事では2年前に既に問題として取り上げられている。
結局、無秩序状態の国をどうにかしないとこのような事は起きる。国連が騒いでいるのなら買い取って油を他の船に移送してスクラップにするか、深い海に沈めれば良いと思う。
多くの船主が反対すると思うが、タンカーを建造する時に、保険のような形で登録する前にリサイクル料金みたいな形で船の総トン数で請求して今回のような場合に基金で
スクラップにすれば良いと思う。
Esso Japan - (1976-1996) (現在のイエメン西部ホデイダ(Hodeida)港沖に係留されている浮体式海洋石油貯蔵積出設備「セイファー(Safer)」)
【AFP=時事】国連(UN)は15日、イエメン沖に放置され、腐食が進んでいる石油貯蔵施設について異例の会合を開き、もしも内部の原油110万バレルが紅海(Red Sea)に流出すれば「大惨事」になると懸念を示した。
【写真】太平洋の「核のひつぎ」から汚染物漏出の恐れ、国連総長が懸念
イエメン西部ホデイダ(Hodeida)港沖に係留されている浮体式海洋石油貯蔵積出設備「セイファー(Safer)」が建造されたのは45年前。破損すれば、海洋資源や数万人の貧しい漁民にとって壊滅的な結果をもたらす恐れがある。
国連環境計画(UNEP)のインガー・アンダーセン(Inger Andersen)事務局長は国連安全保障理事会(UN Security Council)に対し、同施設の「状態は日々劣化しており、原油流出の可能性が高まっている」と説明。「迫り来る環境的、経済的、人道的大惨事を阻止するために協調して動ける時間は残りわずかだ」と訴えた。
安保理によるとすでに14日、ホデイダを掌握しているイエメンの反政府武装勢力フーシ派(Huthi)に対し、同施設の簡単な修理と次の段取りを見極めるための視察チームを送る計画の詳細を送付したという。
国連は視察チーム派遣について、12日の時点でフーシ派はおおむね合意していると明かしていた。だがフーシ派は昨年夏にも同様の合意をしていながら、直前になってジブチからの国連視察団の訪問を中止させていた。
イエメン内戦によって同国北部のほぼ全域をフーシ派が掌握して以降、セイファーは過去5年間、事実上整備なしで放置されている。貯蔵施設には倒壊や爆発の可能性があり、そうした事態が起きれば、周辺地域の生態系の回復に最長30年かかるような惨事になるだろうと専門家らは指摘している。
同貯蔵施設の問題は、経済や人道支援などイエメンの他の問題と同様、フーシ派側の交渉の切り札になっている。フーシ派は、重油の売却額をめぐる支配権を確保するためにこの危機を利用しているとして非難されている。【翻訳編集】 AFPBB News

SAマリン(有)は聞いたことはないけどミャンマーで仕事をしていた事はいろいろなサイトに書かれている。
平成25年度外務省政府開発援助海外経済協力事業
(本邦技術活用等途上国支援推進事業)委託費 「案件化調査」
ファイナル・レポート
ミャンマー国イラワジ川流域における低吃水軽量
台船を活用した農産物及び関連資材輸送システムの案件化調査
平成 26 年 3 月 (2014 年)
SAマリン有限会社・株式会社野村総合研究所共同企業体
(外務省)
ミャンマー国
イラワジ川における低吃水軽量台船の普及・実証事業報 告 書
平成28年9月(2016年)
独立行政法人国際協力機構 (JICA) SAマリン有限会社
(独立行政法人国際協力機構 (JICA))
既報。海運業のSAマリン(有)(所在地:広島県福山市沖野上町3丁目*** )は7月10日、広島地裁福山支部において破産手続きの開始決定を受けました。
停止時の負債額は約4億円。
同社は昭和37年創業の海運会社。同社はタグボートやバージ船を所有し、船体ブロックなどの海上輸送により以前は5億円以上の収入高を計上していた。しかし、船体プロック輸送の受注は不安定で最近は低迷、船体購入の借入金も大きく、資金繰りに給するようになっていた。
破産管財人には、堂前圭佑弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年10月16日午前10時。
事件番号は令和2年(フ)第51号となっています。
海運業のSAマリン(有)(広島県福山市沖野上町3-9-31、代表:宮本判司)は1月31日事業停止、事後処理を成田学弁護士(電話084-922-7510)に一任して、自己破産申請の準備に入った。
負債額は約4億円。
同社は昭和37年創業の海運会社。同社はタグボートやバージ船を所有し、船体ブロックなどの海上輸送により以前は5億円以上の収入高を計上していた。しかし、船体プロック輸送の受注は不安定で最近は低迷、船体購入の借入金も大きく、資金繰りに給するようになっていた。
かつて世界の船舶の6分の1を建造していた瀬戸内地方の造船業。
長年その隆盛を支えてきた中小企業が、今、ミャンマーの大河を舞台に、初のコンテナ輸送を根付かせるべく奮闘している。同社の挑戦を支えているのは、「輸送の効率を改善し、この国の人々に恩返ししたい」という、親子3代にわたる熱い思いだ。
コンテナ輸送で"バラ荷"のリスクを軽減
工業化や海外からの投資が急速に進むミャンマー。その国土を南北に縦断するように流れる3本の大河には、砕石や材木、穀物などを積んだ小舟が多く行き交う。道路が舗装されていない地域も多いこの国で、重量があってかさばる物資を大量に輸送するために川が果たす役割は大きく、現在、年間約700万トンに上る物資が水運で運ばれているといわれている。特に、全長2150キロメートル、流域面積43万平方キロメートルに達する国内最大のエーヤワディー川は、物流の要だ。
とはいえ、その効率は決していいとは言えない。諸外国から同国最大の国際輸出入港であるヤンゴン港にコンテナで届いた物資も、陸揚げ後、コンテナから出され、「バラ荷」の状態にして小舟に積み替えているため、時間的にも労力的にもロスが大きいのだ。さらに、バラ荷の積み下ろしの際に荷の一部が落下して強い衝撃を受けたり、川の上で雨風にさらされて痛んだり、盗難にあったりするといったリスクも高い。
それでもわざわざこうした方法が採られているのは、エーヤワディー川の水深が浅いためだ。雨期と乾期の水深差が10メートル以上あるエーヤワディー川では、乾期には水位が1メートル以下の浅瀬も多く出現するため、船体の一番下から水面までの垂直距離(吃水)が深い大型船舶は物理的に航行できない。そこで、コンテナから物資をヤンゴン港でいったん取り出し、浅瀬でも航行可能な小舟に積み替えているというわけだ。
そんなこの国で、浅瀬でも航行できるタイプの台船を導入してコンテナのまま運べるようにすることで、今後ますます増える物流に対応したいという思いを胸に、この国にコンテナ水運輸送を根付かせるべく奮闘している日本企業がある。SAマリン有限会社だ。
3代にわたり受け継ぐ ミャンマーへの思い
同社は、1962年の創業以来、瀬戸内海の造船会社向けに船舶ブロックを運搬してきた広島県の中小企業だ。当時、この地域は世界の船舶の6分の1を建造していたほど造船業が盛んだったが、2000年代に入って衰退の一途をたどり、廃業を迫られる企業も相次いだ。そんな中、同社がミャンマーで新規事業に乗り出すことを決断したのは、代表取締役の宮本判司さんが初めてエーヤワディー川を訪れた際、造船業が活況だったころの瀬戸内地方に似ているのを見て「これはいける」と直感したためだ。かつて第二次世界大戦に従軍した判司さんの父、藤井武夫さんが、この国の人々に助けられて帰国を果たしたことも聞いており、その恩返しをしたいという理由もあった。
おりしも、日本政府として国内の中小企業の海外展開を支援する気運が高まりつつあったことが、同社の挑戦を後押しした。まず2013〜14年に外務省の助成を受け、浅瀬でも航行できる軽量の台船を使った水運事業の可能性を調査。翌年には、JICAの普及・実証事業の一環として、ヤンゴン市内の造船所で水面から60センチメートル程度しか沈まない台船を7カ月かけて製造した。これは、コンテナだけでなく、重量物や大型の積み荷も運搬できる上、将来的にはコンテナを吊り上げるクレーンも搭載できるように設計された自信作だ。昨年は、乾期と雨期の2度、この台船にコンテナを載せて輸送試験を実施した。
こうした積み重ねが実を結び、同社は今年の5月、日本とミャンマー両国が官民を挙げて開発を進めるティラワ経済特区(SEZ)に隣接するティラワ港と北部のシュエメ港の間で、現地の内陸水運公社(IWT)と共に輸送サービスを開始した。怒涛の挑戦を現地で率いているのは、判司さんの長男でミャンマー支社長を務める宮本武司さんだ。いかにも水辺の男らしい真っ黒に日焼けした顔をほころばせながら、「これまでなかったサービスを新たに立ち上げることで物流改善の一翼を担い、この国の発展に貢献したい」と話す武司さんの胸には、祖父と父から脈々と受け継いだミャンマーへの熱い思いが溢れている。
この国の発展と人々の幸せを願う瀬戸内の企業魂が、大河の水面にきらきらと輝いている。
水深差10メートル
6月中旬のイラワジ川の上は、息苦しいほど密度の濃い空気が辺りいっぱいに立ち込めていた。川岸に停泊しているのは、バージ船と呼ばれる台船だ。
長さ60メートル、幅15メートル、深さ3メートルで総重量は約300トン。20フィート大の貨物コンテナを約60個は積める大きさだが、平たく言えば“いかだ”だ。
等間隔に並んだコンテナの1つのトビラが開かれると、2000箱はあるだろうか、隙間なく積み重ねられた白いダンボール箱が中から現れた。表に「国連世界食糧計画(WFP)」「日本基金(Japan Fund)」と印された栄養強化ビスケットだ。
と、左右に一人ずつ男性が立ち、白い壁を少しずつ切り崩すかのように2箱ずつ取り出しては、一列に並んだ男たちの肩に載せていく。
受け取った段ボールを首と肩で挟むように支え、落とさないように両手を添えた不安定な姿勢のまま、器用に細い板をつたって甲板から岸に降りていく荷役夫たち。そのまま川辺に停まっているトラックの荷台に運び込むと、再びコンテナまで戻ってくる。
この暑さの中、決して楽ではない作業のはずだが、コンテナの前でカメラを構える筆者の前を通るたびにレンズの向こうでおどけてみせる若者もいて、そのたびに辺りの空気がふっと和む。2つ目のコンテナのトビラが開かれると、今度はコメが詰まった麻袋の山が現れた。
ここは、国土の中央部に位置する古都マンダレーから、イラワジ川を約100キロ南西に下ったパコック港だ。約3000もの仏塔が天にそびえる幻想的な風景で知られるバガン遺跡から車で約1時間ほどのところに位置する。
バージ船の向こう側には、ザガイン橋と呼ばれるトラス橋が左右に伸びる。三角形を組み合わせたデザインが美しい。
広大な国土とデルタ地帯を有するこの国において、内陸水運は重要な輸送手段の一つである。水辺に立つと、砕石や材木、穀物などを積んでゆっくりと川の上を進む小舟をよく見掛ける。水運によって運ばれている物資は、年間約700万トンに上るという。
しかし、それらの貨物は現在、ほとんどが「バラ荷」の状態で運ばれている。諸外国からヤンゴン港に陸揚げされた貨物でさえ、すべてコンテナから搬出され、バラバラに小舟に積み替えられて内陸部へと運ばれているのだ。
そのため、荷積みや荷下ろしは、冒頭のような荷役夫たちの存在なしには成り立たない。
最大の原因は、水深の浅さだ。国土を南北に流れる全長2150キロ、流域面積43万平方キロのイラワジ川は、交通や物流の大動脈となるポテンシャルを有している。その一方で、雨期と乾期の水深差が10メートル以上あり、乾期には水位が1メートル以下の浅瀬も多く出現する。
船体の一番下から水面までの垂直距離(吃水)が深い大きな船舶は物理的に航行できないため、浅瀬でも航行可能な船舶への積み替えを余儀なくされているというわけだ。
バラ荷の課題
しかし、こうしたバラ荷輸送には問題がある。まず、時間的あるいはコスト的なロスの大きさだ。また、バラ荷を人力で積み下ろしする過程で、荷の一部が落下して強い衝撃を受けたり、雨風にあたったりして損傷を受ける可能性もある。さらに、盗難リスクも高い。
しかし、海外からの投資や工業化の進展によって増加の一途をたどるミャンマーの物流需要の今後を考える時、重量物を大量に輸送できる内陸水運を本格活用する必要があるのは明らかだ。
国際協力機構(JICA)が2014年に策定した全国運輸交通マスタープランでも、内陸水運の活用は鉄道や道路の整備とともに3本柱の1つに位置づけられている。
「浅瀬でも航行できる台船をこの国に導入し、荷痛みが少なく、施錠できて盗難リスクも少ないコンテナ輸送を根づかせ輸送効率を向上したい」
そんな願いをかかげ、4年前に始まったある日本企業の挑戦が、佳境を迎えている。その先頭に立つ宮本武司さんは、かつては世界中の船舶の6分の1を建造していた瀬戸内地方のSAマリン(有)(本社・広島県福山市)の後継ぎだ。
昨年8月には、SAマリンミャンマーの社長に就任した。がっしりとした体格と真っ黒に日焼けした風貌だが、ふと見せる笑顔は驚くほど親しみやすく、おっとりした広島弁も耳に優しい。
1962年の創業以来、瀬戸内海の造船会社向けに船舶ブロックを運搬していたSAマリンが、国内市場の行き詰まりを受けてミャンマーでの事業展開に乗り出すに至ったのは、めぐり合わせの賜物だ。
2008年に発生したリーマンショックと、その後の民主党政権下の円高によって倒産や赤字が相次ぎ、2014年までに受注残高がなくなると言われていた国内の造船市場。これを受け、武司氏の父でSAマリン代表取締役の宮本判司氏は、海外のコンテナビジネスの状況を視察するために、まず中国・上海港を訪れた。
しかし、同国のコンテナビジネスは思っていた以上に盛えており、同社が参入する余地はなかった。
その後、同じ広島にある企業から紹介されてミャンマー・イラワジ川を訪れた判司氏が、「ここならできそう」だと直感したのは、造船業が右肩上がりに伸びた1960年代後半から70年代の日本によく似ていたことに加え、判司氏自身、第2次世界大戦に従軍したミャンマー(当時のビルマ)から奇跡的に生還した父・武雄氏(武司氏の祖父)から、いかに現地の人々に助けられたか聞かされて育ったことも無関係ではなかった。
「父は、どこでも良かったのではなく、ミャンマーだから挑戦を決意したんだと思います」と、武司氏は判司氏を思いやる。
おりしも、日本政府として国内の中小企業の海外展開を後押しする気運が高まりつつあったことから、同社は2013年~14年3月、新たに外務省で始まったばかりの案件化調査事業を受注し、イラワジ川で吃水の低い軽量の台船を活用した内陸水運の事業化に向けた調査を実施した。
さらに2015年2月からは、JICAの普及・実証事業の一環として、ヤンゴン市内にある国営の造船所において、水深が1~2メートル程度の浅い河川でも運航可能な吃水60センチ程度の台船を7カ月かけて建造。さらに、実際にコンテナを搭載し、乾期と雨期の2度にわたりヤンゴンからマンダレーまでイラワジ川を航行して成功を収めた。
冒頭の荷役作業は、ヤンゴンでWFPから請け負った食糧やオイルをマンダレー経由でパコック港まで運んだ後の、荷下ろし作業の1コマだ。
「公務員」転じて「海の男」へ
実は、パコック港に到着する2日前、ちょっとした、いや、かなり大きなハプニングがあった。
ヤンゴンの飲料水メーカーから預かったペットボトル2000本をマンダレー港で午前中に下ろし、夕方にはパコック港に向けて出航する予定だったにもかかわらず、荷主のトラックが受け取りに現れなかったのだ。
スタッフが慌てて運転手に電話をした結果、トラック会社の調整不足であることが判明。結局、その日は荷を下ろせず、出航を1日遅らさざるを得なかった。
実は、3月の乾期の時にも似たようなことがあった。午前中に来るはずのトラックが現れたのは、夕方になってからだったという。
約束の日時に荷物を受け取らないと、航行の全体スケジュールがずれる。出航が1日遅れると、ヤンゴンに戻るまでに3日、4日と遅れが重なり、次の仕事にも影響が出かねない。
だが、驚いたことに、武司氏はこの日、やきもきするスタッフを前に「彼らは今回、顧客ではなく、われわれの実証試験に協力してもらっている立場。調整不足は日本でもあるし、1日遅れても水は腐らない」とまったく動じなかった。
むしろ「事前に何度も確認しておけばよかった」「これがこの国の輸送業の現実。今日はいい勉強になった」と笑顔すら見せる。
「ミャンマーの人はのんびり屋なんですね」。そう言って笑う同氏は、一風変わった経歴の持ち主だ。
もともと家業を継ぐつもりはなく、地元の市役所に勤務していた。堅実な公務員生活の傍ら、福山市の町おこしに情熱を注いでいたが、外務省の案件化調査が決定したのを機に、退職。ミャンマー事業に専念するため、SAマリンに入社した。
水運業という未知の世界に飛び込むにあたっては、相当の葛藤と覚悟を迫られたに違いないが、「70歳を超えた父1人では、現地との往復も書類の作成も限界がありますから」「素人だったのがかえって良かったのでしょう」と、どこまでも爽やかだ。
かくして始まった武司氏の挑戦は、さぞ、人との縁に満ちていたはずだ。
マンダレー港のハプニングがあった後でさえ、武司氏と笑顔でその後の段取りについて打ち合わせるミャンマー人スタッフたちからは、営業や通訳、ドライバーといった役割を超えた「同志」としての連帯感と、「物流の改善を通じて祖国の発展に貢献したい」という誇りが伝わってくる。
何か問題が起きても、怒ったり衝突したりせず、相手にきちんと伝えることを重視する武司氏の自然体で鷹揚な人柄があったからこそ、こんなチームが結成されたに違いない――。笑い合う彼らを見ながら、ふとそんなことを考えた。
水面に輝く挑戦
7月下旬、武司氏は判司氏とともに、ヤンゴン市内のホテルで日緬両国の企業関係者ら約140人を対象にセミナーを開き、2回にわたる実証実験の結果を報告した。
さらに、「コンテナ輸送の事業化に向けて今後もこの国で挑戦し続けたい」との決意も明らかにした。
もちろん、課題はある。第1に、ライバル企業の存在だ。内陸水運の会社は国内に400~500社あり、棲み分けが必要なのだ。そこで重要になるのが、価格競争に陥らないこと。
「例えて言うなら、ただサーカスを見せるのではなく、シルクドソレイユのように、舞台性やテーマ性、ストーリー性を持たせることで、コストが高くても他が追随できない新たな価値を提供し、同じ市場で競わなくてもすむ存在になる」というのが、武司氏の戦略だ。
水運に関わる企業は多くても、コンテナを載せて航行できるバージ船は、今回、この国で建造した台船ただ1隻だ。さらに、この台船は、コンテナ専用船としても、重量物専用船としても活用できる上、将来的にはコンテナを吊り上げるクレーンも搭載できるよう、設計段階から考えられている。
「自分たちで価格を設定し、新しい市場を開拓していけるだけの付加価値は十分出せる」と武司氏は強気だ。
第2に、規制のハードルも高い。よく知られているように、日本をはじめ、多くの国が「内陸水運は自国船に限る」という「カボタージュ規制」を設けている。ここミャンマーも、例外ではない。
内陸水運公社(IWT)との合弁企業であればその限りではないとはいえ、新規参入は決して容易ではない中、「どうすればビジネスになるのか」、模索が続く。
第3に、人材育成の必要性だ。
マンダレー港でのハプニングからも、「人の意識を変えないと行動は変わらない」ことを痛感している武司氏。今後は、日本の水運業のやり方を導入することで賃金が上昇し、労働条件も良くなることを伝えた上で、「日本の企業人と意思疎通でき、同じ目標に向かって進んでいける人材」を育成しようとしている。
ただ船を作ってコンテナを運ぶだけでなく、数々の課題の解決に挑む宮本さん親子。その挑戦は、今、ようやく曙光が見えてきた段階だが、彼らの背中を見ていると、近い将来、イラワジ川の岸辺にバージ船が停泊し、クレーンでコンテナが積み下ろしされている景色があちこちで見られるようになるかもしれないと思えてくる。
「ゼロから一を作る協力こそがこの国の発展につながり、われわれの勉強にもなる」――。果敢に挑み続ける瀬戸内の企業魂が、大河の水面に輝いている。
(つづく)
筆者:玉懸 光枝
船舶輸送のSAマリン(広島県福山市)はミャンマーで河川物流事業に進出する。経済発展に伴い物流の需要は急増している。陸運はインフラ整備の遅れや輸送量の制約を抱えているため、河川物流に注目が集まっている。専門の河川航行用運搬船(バージ)を建造。年明けにも運航を始める。川のつながりを生かし中国展開も視野に入れる。

経済発展著しいミャンマーで河川物流に進出(ヤンゴン市内、建造したバージ船)
「河川から物流を開拓する」(宮本武司専務)。ミャンマーではガタガタな道路で荷物を運ぶ陸路が主流。海路は木造船を使った交通手段で、物流は利用客が運ぶ物資・食物が多かった。決して効率が高い輸送手段ではなかった。
今春、国際協力機構(JICA)とミャンマー河川物流の普及に向けた契約を結んだ。対象は最大都市ヤンゴン、マンダレーなど主要都市をつなぐエーヤワディー川(旧イラワジ川)。「陸運に比べれば、河川輸送でのメリットは歴然としていた」(宮本専務)
問題は山積していた。一つが水位。上流、中流域の水位差は季節によって約10メートルに達する。特に乾期は深さが数メートル程度にまで干上がる。
小さな船なら意味がない。大きすぎたら使えない。最適な船舶を造り出すため試行錯誤を繰り返した。船舶は地元企業がJICAの資金をもとに建造。全長60メートル、幅15メートル、専用クレーン1基を備えたバージ船が10月に完成した。甲板の広さから航空母艦を思わせる風貌だ。20フィートの規制コンテナ80個を積載できる。
就航は2016年1月。運営は現地の国営企業が手掛け、SAマリンは保守管理などを担当する。現地で建設が進む発電所・プラントの機材輸送も可能だ。ミャンマーでは初の大型バージ船となる。
宮本専務はこの半年でミャンマーに25回足を運んだ。赤丸で埋め尽くされた畳2畳ほどの大きな地図は現地開拓に向けた布石を意味する。8月にミャンマーに海運・輸送のコンサルタント会社を設立した。船舶運営は現地企業が主導しているが、将来的には自社運営を見据えている。
ミャンマーには同業他社が10社進出したが、最終的にSAマリンが残った。「熱意と思い入れが強かった」と宮本専務。両国政府に提出した書類・リポートは数知れない。SAマリンがミャンマーの海上物流に採用されたことは綿密な裏打ち作業の結果とも言える。
経済・文化の発展は河川にある――。経済発展が著しいミャンマーを河川物流で支えることが今回事業の柱だ。エーヤワディー川の上流にあるのは中国。SAマリンは中国企業向けの輸送事業展開を視野に入れた検討を始めている。
(福山支局長 佐々木聖)
「日本の造船所にもリファンド・ギャランティー(RG、前渡し金返還保証)を求める時代がくるのかもしれない」■ヤマニシの破綻 16日午前、新造船の発注動向について海運ブローカーに取材中、電話口からこんなセリフが出た。船舶の建造は長期間にわたる。このため造船所が建造費の一部を発注者から前受け金として受領するケースが一般的である。具体的には、船主など発注者は 1.契約時 2.起工時 …
2020年7月20日 公開
中野汽船(有)|山口県防府市
【業種】 海運
【倒産形態】 破産手続開始決定
業種 海運
倒産形態 破産手続開始決定
所在地 山口県防府市
子供のころ、同じような事があった。親が造船所で働いている同級生の多くが転校していった。別の会社を探すか、引っ越しするしかない。
「海軍工廠以来の120年のものづくりの技術が無くなる。艦船の修理に特化すれば、造船技術が無くなるのではと心配する声がある」
理解は出来るがコスト競争で生き残る事が出来なければ、造船技術が継承されても新造船を建造する事はほぼないと思う。もし新造船の需要があった時には
その時は諦めるしかない。造船に限らず、同じ事が言える。個人的にいえば、日本の造船は信頼度や品質はまだ良いと思うが、設計や発想に関しては
時代遅れの部分がある。ただ、稀少価値とか言っても、利益が出るような環境や人材がいなければ、絵に描いた餅。効率と多少の改善を目指して
生き残りをかけるしかないと思う。下請けを泣かせるだけでは将来はないがコスト削減は可能。どこまで先を見るかで方針は変わってくると思う。
舞鶴市議会の市内造船事業調査特別委員会は15日、造船会社のジャパンマリンユナイテッド(JMU、本社・横浜市)舞鶴事業所(舞鶴市余部下)の近藤修管理部長を参考人として招致した。同事業所は新造船事業から撤退し、修繕事業に特化するため7月1日から設計部門の配置転換を始めた。近藤部長によると、6月1日現在で在籍していた設計部門の社員に意向を聞いた結果、34人中19人(55%)が「配置転換に応じられない」と回答していることを明らかにした。【塩田敏夫】
造船業は舞鶴市の基幹産業だった。1901(明治34)年、舞鶴鎮守府が、その2年後には海軍の艦船を開発、建造する海軍直営の工場として舞鶴海軍工廠(こうしょう)が設置された。戦後は海軍工廠を受け継ぐ形で民間会社となったが、これまでは海上自衛隊の艦船などの大型船を建造できる日本海側唯一の造船所だった。
JMU舞鶴事業所の1月1日現在の社員数は549人(ベトナム人の技能実習生67人を含む)。このうち、新造船部門の292人(設計部門51人、造船部門は241人)が配置転換の対象となり、既に一部は定期異動などをした。
造船部門の社員の配置転換は11月1日から始まる。地域採用社員を対象に6月に配転先を提示し、現在面談を実施中で「本人の意向を7月末に確認する予定」という。
委員会では、「海軍工廠以来の120年のものづくりの技術が無くなる。艦船の修理に特化すれば、造船技術が無くなるのではと心配する声がある」との質問が出た。
これに対し、近藤部長は「JMU全社の中で補完し合い、新造船技術を継承、発展させる考え」と答え、艦船の修繕についても「今まで以上の対応」をすると述べた。
市によると、配置転換される社員の多くが地元に残ることを希望している。市は舞鶴商工会議所などの協力を得て、求人情報を提供するなど雇用支援活動を続けるとしている。
〔丹波・丹後版〕
佐渡汽船は7日、慢性的な赤字が続く小木(新潟県佐渡市)―直江津(同上越市)航路について、2015年に就航した高速カーフェリー「あかね」(5702トン、628人乗り)を売却し、21年4月から高速船ジェットフォイルに切り替えることを決めた。船体が小さい高速船への転換で費用を削減し、収支改善を図る。【井口彩】
この日の取締役会で決定。新潟県庁であった県や地元自治体、国の運輸局などでつくる「佐渡航路確保維持改善協議会」で尾崎弘明社長が明らかにした。
あかねは豪州製の双胴型フェリーで、以前のフェリーより1時間短い1時間40分で同航路を結ぶ。北陸新幹線開業による関西・北陸からの観光客増加を見込み、佐渡・上越市などの資金支援を受けて15年4月に導入した。しかし佐渡市の人口減などで利用客が減少。あかね導入の初年度は目標に近い約18万人が利用したが、現在は約12万人と約3分の2になり、同社の経営を圧迫する要因となっていた。
このため同社は、あかねを売却し、すでに新潟航路(新潟市)―両津(佐渡市)で就航している高速船を1隻、新たに調達することを決めた。調達には、あかねの売却益のほか、自治体の補助金や国土交通省所管の独立行政法人「鉄道・運輸機構」の支援制度などを使う。あかねの売却先や、購入かリースかの調達方法は検討中。
尾崎社長は報道陣の取材に、高速船への転換で同航路の赤字額約10億円を4億円ほど圧縮できるとの試算を示した。同社によると、船体の特徴で波が高い時に揺れやすかった問題も解決できるという。「結果として5年で替えるのは申し訳ないが、(このままでは)維持がかなわなくなっている。運航形態を変えながら、航路自体は続けていきたい」と理解を求めた。
高速船の導入で所要時間は現在より短くなるが、運賃は値上がりする見込み。現行は片道3970円(大人2等)だが、同航路より短距離の、新潟両津航路の高速船運賃(6640円)よりも高くなる予定だ。
同航路は国道350号の海上区間になっている。高速船へ転換すると乗用車が運べなくなるが、県によると、国道指定に影響はない見通しだ。
佐渡市の渡辺竜五市長は「佐渡と本土を結ぶ海上国道にも指定された生活航路であり、引き続きこの航路を維持すべきだ。今後、協議会で十分な議論を交わしていくべきだ」とのコメントを発表した。
造船所と言っても、いつ建造された、又は、どのような船のサイズやタイプを想定してレイアウトが決められたかで船の建造効率が違ってくる。追加投資をするぐらいなら
我慢して建造するほうが良いとの判断で建造している造船所はあると思う。日本でも歴史がある造船所よりも新しい造船所のほうが効率を考えて建造されている傾向が高い。
建造する船のタイプやサイズで需要が違ったり、同型船(同じデザインで建造される船)が建造できる船を建造しているのか次第でも違ってくる。
また、周りに下請け業者が多いなどの条件も影響すると思う。下請け業者が少ない形態の工場や生産施設であれば周りに下請け業者が多かろうが、少なかろうが関係ないと
思う。
韓国だって一部の造船所以外は受注がない。予算を低くしたいから韓国ではなく中国で建造すると言う船主は存在する。その中国でも1年間に船を一隻も建造してない造船所がが
たくさんあると聞く。新聞の記事にはないが、そのような話は聞く。結局、過剰投資と世界景気の失速でいつかは誰かが損失を受けるのはわかっていたが、その時が来るまで
多くの人が止めなかったと言う事だろう。今、中国ではマスクを製造する小さな工場が閉鎖されたり、倒産しているそうだ。同じ理屈だと思う。
まあ、造船の将来はわからないが中国の人件費の高騰の割合と品質や耐久性や信頼性の相対的な評価で評価や発注は変わる可能性はあると思う。中国建造の船は建造して
5年しか経っていなくてもメンテが悪いとものすごく酷い船がある。まあ、その問題を理解できないほど使う側の人材不足や人材の経験不足が存在すれば問題として認識されないかもしれない。
従業員300人配転、地域にダメージ
国内造船2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市西区)が舞鶴事業所(京都府舞鶴市)での商船建造から撤退する。2021年4―6月にも建造を止め、艦船修理に特化する。海軍工廠(こうしょう)をルーツとする日本海側唯一の大型造船所で雇用への影響が懸念される。経済合理性からやむを得ない決断だが、JMUの一連の動きは造船大手の苦悩を映す。
6月3日、参議院国際経済・外交に関する調査会。議題の海事産業の基盤強化について参考人に立った舞鶴市の多々見良三市長は「突然こういう変化が起こることを疑問に思う。なぜもっと早めに分からなかったのか」と憤り、JMU舞鶴事業所での商船建造撤退に不快感を示した。
従業員約300人が配置転換となり造船所の「約7割が空き地になる」(多々見市長)。下請けを含めた地域のダメージは甚大で多々見市長は「地元の首長として心苦しい」と胸の内を明かす。8割の社員が地元に残留することを望んでいるという。
JMUでは規模の小さな舞鶴事業所をめぐり19年半ばから舶用メーカーの間で「舞鶴向け商船受注が途絶えている。手持ち工事の線表が伸びていかない」とささやかれていた。
一方でJMUは19年11月に国内造船首位の今治造船(愛媛県今治市)との提携を発表。IHIやJFEホールディングス(HD)、日立造船という日本を代表する重厚長大企業を株主とするJMUが、オーナー系の今治造船から出資を受け入れる内容は、業界で衝撃を持って受け止められた。
業績改善に向けた改革の絵を示してほしい―。赤字体質にかねて株主から改革を迫られていたJMU。大型再編をテコにした成長戦略と合理化をセットに再建構想を描いた。2月、大型再編のはざまで舞鶴縮小が正式に決まった。
さかのぼること2年前。JMUと関わりの深い造船所が閉鎖された。「100万トンドック」の異名を持ち、超大型タンカーなどの新造船を送り出してきたIHIの旧愛知工場(愛知県知多市)だ。
IHIは造船事業をJFEHDと統合する形で切り出したが、海洋事業拠点として愛知工場を本体に残していた。ところが海洋構造物工事でつまずき、多額の損失を計上。液化天然ガス(LNG)運搬船などに使われる独自アルミニウム貯蔵タンクに愛知工場の存続を託した。
14年、満を持してJMUが同タンクを搭載した大型LNG船を受注したが、長年にわたるLNG船建造の空白を埋められずに工程が混乱。業績悪化を招いた。その後、JMUがLNG船を受注する計画は途絶え、愛知工場は役割を失った。
超大型ヤード(造船所)を武器に大量受注をさらう韓国、低船価で追い上げる中国に対し、数年前には「日本の造船所は高付加価値船で差別化するべきだ」との論調が主流派だった。日本の大手造船はLNG船やブラジルでの海洋構造物事業、客船など難しい工事に手を出したが、結果は惨敗。造船所の縮小は敗戦処理の一環だ。
三菱重工業は主力の長崎造船所香焼工場(長崎市)を大島造船所(長崎県西海市)に売却する方針を固め、商船は下関造船所(山口県下関市)のフェリーなどを中心とする構造改革を断行する。
三井E&S造船(東京都中央区)は、千葉工場(千葉県市原市)での商船撤退の決定に続き、創業の地である玉野艦船工場(岡山県玉野市)の艦船事業を三菱重工に譲渡することを決め、国内の新造船事業からは実質的に撤退する方向だ。
6月、現代重工業など韓国造船大手3社が中東カタールから合計2兆円規模のLNG船を大量受注することが分かった。中国造船最大手の中国船舶集団にも3000億円規模が発注されるという。海洋事業の失敗で経営が傾いた大宇造船海洋への韓国政府の支援が問題視されるが、韓中ヤードの力は強い。19年には韓国と中国で、各1、2位企業が統合に合意。統合2社の世界シェアは約4割に達する。
翻って日本。2年分が安全水域といわれる手持ち工事は目下1・2年分程度に枯れ、操業ダウンを余儀なくされる。勝ち筋をどこに見いだせば良いのか。世界の海上荷動き量はリーマン・ショック後の09年に前年比で減少したが、基本的には世界経済成長率と連動して増加し、一定の新造船需要がある。
焦点は環境規制だ。国際海事機関(IMO)は50年までに温室効果ガスの排出量を08年水準の半分に削減する目標を掲げる。従来技術の延長線では達成できず、IoT(モノのインターネット)や人工知能(AI)を駆使した最適航路設定、新素材の採用、自動操船など勝負の土俵が変わる公算が大きい。
5月、国土交通省がまとめた「海事産業将来像検討会」の報告書。企業間連携・統合の促進やデジタル化に対応した産業構造への転換、官公庁船分野の海外展開などが示された。政府系金融機関による出融資の活用検討など踏み込んだ内容だ。
造船、海運、舶用機器などという従来の海事クラスターにとらわれず、IT企業や港湾事業者などバリューチェーンを進化させなければニューノーマル(新常態)の世界では生き残れない。造船業の国内就労者数は約8万人。大胆な改革を進めなければ雇用は失われ続ける。
JMUが舞鶴事業所での商船建造を終了するまであと1年。京都府、舞鶴市は関係機関を招集した「JMU舞鶴事業所対策連絡会議」を共催し、雇用対策などに力を注いでいる。日本海側の国防の要として約120年にわたり海洋国家を支え続けてきた港湾都市が揺れている。
2020年2月4日、舞鶴市役所。舞鶴市の多々見良三市長はJMUの千葉光太郎社長と向き合っていた。JMUによる前日の撤退発表を受け、多々見市長は「存続のために何かしたんですか」と切り出し、千葉社長は「国とも掛け合ったが解決策が得られなかった」と返したという。
人口約8万人の小都市、舞鶴市にとってJMU舞鶴事業所の存在は極めて大きい。商船では中型のバラ積み船やタンカーを建造し、建造能力は年間6隻前後。金属加工や塗装、電気、運輸など幅広い市内関連企業を束ねる基幹産業として地域産業をけん引し、ベトナム人研修生を含め550人(20年1月時点)が働いている。
舞鶴市の製造業事業所数は漸減傾向にあり、15年の115事業所から18年には102事業所に減少。一方、製品出荷額は1812億円と、バラつきがありながらも近年は増加傾向で推移してきた。JMUが商船事業から撤退すると情勢は大きく変わる恐れがある。
舞鶴商工会議所が2月に会員企業を対象に実施した緊急アンケートによると、約4割が売り上げに影響があると回答。このうち対応策がある事業所は1割に満たなかった。最も緊急を要する支援内容について「新規受注先」と回答した事業所が最も多かった。
「舞鶴のモノづくり技術が消滅する危機。撤退を撤回してほしい」「より一層の沈み込みのきっかけになる」「JMUの配転で下請け事業者が追い出され従業員への影響が出ることは避けて」など不安視する意見が出た。
舞鶴市は今後、同商工会議所やハローワークなどと連携し、市内企業と、同市内で転職を希望するJMU従業員とのマッチングイベントを開くなど、積極的に雇用対策に取り組む。さらに洋上風力発電設備の建造を誘致するほか、舞鶴港を再整備し、トランシップ(積み替え)港としての機能強化を図るといった構想を、国家事業として進めてもらうべく、今後国に要望を伝える方針だ。
多々見市長は「国土交通省や京都府などと連携した舞鶴港の機能強化やエネルギー拠点化に向けた施策を推進する」という。また、京都府北部5市2町の圏域があたかも一つの30万人都市圏として機能するための広域連携の必要性を訴える。
JMUが舞鶴事業所での商船建造を終えるまでに残された時間は少ない。地域経済活性化に向け、市長のリーダーシップが一段と求められる。
【多々見良三市長に聞く】
―JMUの商船建造撤退は地域に大きなダメージを与えます。
「どんな産業も下火になればやめざるを得ない。一定の理解はしている。ただ日本の造船業は技術力は高いが設備投資の遅れで世界と戦いづらくなっているように思う」
―事業所の7割近くが空きます。
「洋上風力発電設備を建造できる製造業の誘致を目指す。国家事業として2―3年以内に構想を示してもらえるよう働きかける。雇用を生み、造船業の技術力を生かせる産業を誘致したい。干満の差がほとんどなく、津波に強い舞鶴港は積み替え港としても格好だ」
―市としての雇用政策は。
「JMUと協力会社の従業員の雇用を確保できるよう万全を期す。商工会議所などと連携し、再就職希望のJMU従業員を対象に市内事業所説明会を開くほか近隣市町の企業にも協力を呼びかける。雇用する企業には国の労働移動支援助成金を活用してほしい」
―日立造船が建設運営を担う予定だったパーム油発電所立地計画が断念されました。
「スポンサーさえいればやってみたい。パーム油にこだわらず工業用地としてあの場所を利用できるような企業を誘致したい。まちづくりに稼ぐ場所は必要だ」
日刊工業新聞京都総局・大原佑美子)
今年上半期の世界の船舶発注量が過去最低となった。1997年の通貨危機、2008年のグローバル金融危機当時よりも少ない。造船業界では「カタール液化天然ガス(LNG)船100隻の発注がある前に枯死する」という声が出ている。
英国造船海運市況分析機関クラークソンリサーチによると、今年上半期の世界の船舶発注量は575万CGT(標準貨物船換算トン数)と、前年同期比58.3%減少した。これはクラークソンが統計を出し始めた1996年以降で最も少ない。従来の最低は通貨危機直後の1999年の658万CGTだった。好況だった2007年(4619万CGT)と比較すると8分の1にすぎない。国別受注量も韓国は118万CGTにとどまり、中国(351万CGT)との差が大きかった。
受注減少の理由は、新型コロナウイルスの感染拡大で船主が発注を先延ばししているからだ。現代重工業、大宇造船海洋、サムスン重工業の「造船ビッグ3」はまだ今年の目標受注量の15%にすぎない。先月初め造船3社がカタールとLNG船23兆6000億ウォン(約20兆円)規模のスロット契約を締結したことが伝えられたが、今回の発表でまた雰囲気は冷え込んだ。業界関係者は「覚悟はしていたが、蓋を開けてみると予想よりはるかに深刻だった」とし「最悪の雇用寒波が襲った2016年と似た雰囲気」と伝えた。
今年の受注減少の影響は2、3年後まで続くという分析だ。契約後に船舶の設計、原材料の購買などを経て実際の建造に入るのに通常2年ほどかかるため、今後の数年間は造船会社のドックが空く可能性がある。2027年までと予定されているカタールLNG船100隻発注は未来の話という説明だ。
造船3社は今年下半期にモザンビークとロシアで予定されている大規模なLNG船発注に期待している。しかし最近はLNG運賃が急落し、プロジェクトが延期されるという見方も出ている。クラークソンによると、16万立方メートル級LNG船の一日スポット運賃は3万4000ドルと、前年同期比で38.1%下落した。
業界関係者は「カタールが年末からLNG船を発注しても、現在の状況が続けばその前に流動性危機を迎えるかもしれない」とし「政府の積極的な金融支援が必要だ」と強調した。
海外の財閥系コングロマリット(複合企業)が、経営難の海運事業への関与を後退させている。今春に破綻したドイツ多目的船社ジーマリンが属するゼック・グループのほか、デンマーク多目的船社ソルコの親会社ソルニコなど有力財閥が長引く海運不況に業を煮やし、海運事業会社への資金支援打ち切りを断行。足元ではシンガポール船社パシフィック・キャリアーズ(PCL)の親会社クオック・グループなどの動向も注視される。コングロマリットの信用力をてこに規模を拡大してきたオペレーターの経営不安は、国内外の船主や金融機関に波紋を広げている。
「強固な財務基盤を持つ親会社がグループ船社を切り捨てる姿勢は、日本のビジネス文化では理解しにくい。貸船していた船主にとっては、はしごを外された格好だ」
ドライ市場関係者はそう指摘する。
欧州コングロマリットのゼック、ソルニコは海運不況をM&A(買収・合併)の好機と捉えて投資を拡大。しかし、長期不況やコロナ禍で我慢の限界に達し、海運からの退却姿勢を強めた。
ゼック傘下のジーマリンの母体であるドイツ新興船社ジーボーンは2017-18年に同業の独リックマース・リニエや船舶管理大手ERシッファーツなどを相次ぎ買収。しかし昨冬ごろからジーマリンの経営不安が顕在化し、今年2月にドイツの営業・運航拠点が裁判所の管理下に入り、3月に日本拠点も閉鎖した。
市場関係者は、ジーマリンの経営体制について「海運のアマチュアだった」と厳しく評価する。「グループ内の管理体制が急成長に追い付いていなかった。貨物ポジションなどのデータが社内で共有されておらず、混乱していたようだ」(市場関係者)
■口座に12万円
スポーツ用品ブランド「ヒュンメル」などを擁するデンマークの複合企業ソルニコは、昨年から海運事業の構造改革を断行。“アセットライト”戦略を掲げ、長期用船や自社船保有の機能を担っていた海運子会社を相次ぎ清算した。
海外紙によると、昨年10月に清算手続きに入ったソルニコ傘下のTSチャータリングは銀行口座に7800デンマーククローネ(約12万円)しか残っておらず、長期用船していた複数隻の多目的船は国内外の船主に一方的に返船された。
一方、親会社のソルニコは19年決算でヒュンメルや食品事業の好調により、税引き前利益5億1300万デンマーククローネ(約82億円)の好決算を記録。海運子会社と明暗が分かれた。
■親会社の看板
TSチャータリングのような長期貸船先が倒産した場合、その親会社に未払い用船料を求めることはできないのか。
船主関係者は「親会社とはいえ、あくまで別法人。用船契約に親会社保証が付いていたり、極めて悪質な計画倒産であったりしない限り、親会社に契約義務の承継を求めることは難しい」と話す。
「結局、親会社が超一流という看板は、安心材料にならない。逆に大きなコングロマリットであればあるほど、海運が不採算事業だと判断すれば、容赦ない切り捨ては十分にあり得る」(商社関係者)
一方、オーナーの支援継続により、経営難を脱した海運会社も存在する。
デンマーク船社ジェイ・ローリッツェンは6月、ドライ・ガス船事業の苦境に当たり100%株主のローリッツェン財団が増資を引き受けて2000万ドル(約21億円)を支援した。
ローリッツェンはもともと祖業が船であり、海運に根差しているとの見方もある。
船主関係者は「取引先の信用力を判断する上ではブランドに惑わされず、中身を見極めることが欠かせない。心配なら親会社の保証を取り付けることも必要になる」としている。
韓国造船業の今年上半期の受注量が急減した。韓国造船業は上半期に37隻を受注した。前年同期は92隻だった。2年前の同期(150隻)と比較すると「半分の半分」だ。深刻な不況だった2016年上半期は30隻だった。
英造船海運市況分析機関クラークソンリサーチによると、今年上半期の全世界の船舶発注量は259隻、575万CGT(標準貨物船換算トン)と、前年同期の42%水準にとどまった。
このうち韓国造船業は37隻、118万CGTを受注した。一方、中国は145隻、351万CGTを受注し、全世界の物量の61%(CGT基準)を占めた。日本は36隻、57万CGTだった。全世界の船舶発注量は2010年以降最も少なかった2016年上半期(766万CGT、423隻)に比べ25%減少した。
韓国造船ビッグ3の受注も急減した。現代重工業グループは33隻(推定値)を20億ドル(約2070億円)で受注し、前年同期(36億ドル)比44%減少した。大宇造船海洋は6隻・14億4000万ドルと、前年同期(27億7000万ドル)のおよそ半分だった。サムスン重工業は上半期に5隻を5億ドルで受注し、前年同期(32億ドル)比で84%減少した。個別企業が発表した受注量とクラークソンリサーチの集計に差があるのは6月分の反映のためだ。
1隻あたり単価は韓国が8200万ドルと、中国(4700万ドル)に比べ60%高かった。しかし韓国が受注した船舶価格は昨年の平均(1億100万ドル)に比べ20%低下した。高付加価値のLNG運搬船の受注がなかったからだ。
NH投資証券のチェ・ジンミョン研究員は「新型コロナのパンデミック状況で世界エネルギー企業がLNG運搬船の発注を先延ばしするなど投資決定を遅らせたため」と説明した。
一方、下半期は受注が増えるという。チェ研究員は「新型コロナにもかかわらず、カタールとモザンビークのLNGプロジェクトが始まった。新型コロナがガス運送市場に及ぼす影響が制限的ということを確認したため」とし「下半期にカタールとモザンビークの発注をはじめ、ロシアなどでもプロジェクトが始まるだろう」と伝えた。韓国造船業界は先月、カタール国営企業とLNG運搬船100隻の「スロット(本契約前のドック確保)」契約を結んでいる。
ノルウェーのKleven造船所が倒産したそうだ。この造船所については全く知らないが、写真のようにサプライボートばかり建造していれば原油価格の下落の影響を受けていると思う。
過去に建造した船を検索すると建造するのが難しそうな付加価値の船を建造している。結局、付加価値の高い船を建造していても利益が出なければ存続できない可能性がある
一例だと思う。

船員交代のリスク


まあ、一部社員を解雇しても新型コロナの状況とワクチンの流通次第では、クルーズ会社は持たないかもしれない。新型コロナはやっかいだ!
高齢者は重症化になりやすいそうなので、運が悪いと冥土の旅への始まりなるかもしれない。大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の乗客の一部は死亡しているので
推測ではなく、前例がある。外国の人々の行動をニュースで見る限り、安全とは言えないと思う。まあ、選択の自由はあるので個々が判断して決めればよい。
新型コロナウイルスの集団感染が起きた大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の運航会社の日本法人「カーニバル・ジャパン」(東京)が、一部社員に30日付での解雇を通知したことがわかった。会社側は人員削減の必要が生じたとしているが、社員側は「苦境を乗り越えるために頑張ったのに。不当解雇だ」などと反発している。
【写真】カーニバル・ジャパン社が一部の従業員に渡した退職合意書(画像の一部を加工しています)
解雇通知を受けた社員の一部が加入する連合ユニオン東京などによると、同社は6月初旬、正社員約70人のうち24人に、コロナによる業績悪化を理由に退職を求めた。渡航制限が続き、各国を回るクルーズ船の運航再開の見通しが立たない中、「必要最低限の人員で業務を維持する」などの説明があったという。
退職を求められた社員は入社直後から10年以上まで幅広く、営業や予約担当など様々な部署にまたがり、育休中の人もいた。「(会社に)残る選択肢はない」などと言われ、やむを得ず退職合意書にサインした人もいたとしている。
倒産は近いのかも?まあ、何が事実でも関係なので、事実がニュースになった時に知ればよいだけ。ただ、こんな状態だと受注できても、メーカーがすんなりと製品を 納入するのかな?
中型造船所のSTX造船海洋が再び人員削減に出る。STX造船海洋は29日、社内報を通じ「固定費削減と競争力回復に向け全社員を対象に希望退職申請を受け付ける」と明らかにした。希望退職にともなう慰労金は通常賃金の14カ月分だ。
STX造船海洋は今年船舶を1隻も受注できないなど「受注の崖」に置かれている。同社は「長期にわたる自助努力にもかかわらず、受注・損益悪化で再び生き残りに向けた高強度の自助計画をするほかない状況」と明らかにした。STX造船海洋は2018年に産業銀行と自助計画を前提とした条件付き経営正常化約定を結んだ。
生産現場は2018年から6カ月単位で無給循環休職に入るなどこれまで自助努力をしてきた。生産職500人のうち250人ずつ交代して休職する形態だ。これに対し慶尚南道(キョンサンナムド)は無給休職解消に向け政府支援に加え自治体も支援すると提案したりもした。造船業特別雇用支援制度により韓国政府が最大6カ月間にわたり月198万ウォンを限度に66%を支援し、残り35%のうち慶尚南道が5%を負担する形だ。だがSTX造船海洋は人員削減のない支援はその場しのぎにすぎないと判断したとみられる。
STX造船海洋関係者は「造船業特別雇用支援を受けてもいまの形(6カ月無給循環休職)より費用がかかる。人員を減らさなければこれ以上耐えることはできない。政府・自治体の支援は後で考慮する事案」と話した。続けて「6カ月の一時支援は来年にさらに厳しい結果を招くことになる。固定費そのものを低くしなくては競争力を確保し難い」と付け加えた。
STX造船海洋は2013年から7年間続けてきた構造調整による従業員数が3分の1に減った。造船所の売り上げと直結する受注残高は7隻、2億4500万ドルだ。追加受注がなければ来年上半期には売り上げがすべてなくなる。同社は社内報の最後に「今後も継続してベルトをきつく締めるほかない」とした。
労組は1日から無給休職中断を要求してストに入っている。2018年に労使が合意した無給休職期間は先月で終わったが、会社側は新型コロナウイルスなど経営環境悪化を受け無給休職を中断できないという立場だ。
クルーズ会社は冬の時代だろう!
佐世保市に停泊していた貨物船の交代要員として入国した中国籍船員16人について、新型コロナウイルスのPCR検査の結果が判明する前に、関西空港検疫所(大阪府)が同市への移動を許可していたことが17日、長崎県などへの取材で分かった。移動途中に1人の陽性が判明。県は厚生労働省に対し、水際対策の改善を求める文書をメールで送ったという。
同検疫所によると、16人は9日昼ごろからPCR検査を受けた後、チャーターバスで同市へ移動。途中で1人の陽性が判明したため、本県の医療機関での受け入れを求めた。連絡を受けた本県が難色を示したため、陽性者は本県入りする前に途中下車して引き返し、県外の医療機関が受け入れた。他の船員15人は11日に同市に到着。12日に佐世保港から出港した。
厚労省は制限対象地域からの入国者に対し、原則として検査結果が判明するまで検疫所などで待機を求める一方で、無症状の場合は公共交通を使わずに自宅への移動、待機を認めている。検疫所は取材に対し「チャーターバスは一般の人に接触しないので公共交通に当たらない。船は自宅と同じという判断をした」と説明した。
既報。海運業管理業務代行サービスの(株)グローウィル(所在地:大阪府大阪市淀川区西中島***)は6月9日、大阪地裁において破産手続き開始決定を受けた。
負債総額は約9億円。
資本金は5000万円。
同社は平成10年5月に設立、今回倒産の事態となった。
所在地:山口県防府市大字新田1660‐3
6月5日、同社は山口地裁より破産手続開始の決定を受けた。
破産管財人は黒川裕希弁護士(弁護士法人末永法律事務所、山口市駅通り2‐3‐18、電話:083‐922‐0415)。
無人運航船開発がオートパイロットの延長ぐらいなら可能だと思うが、「無人運航は人工知能(AI)が操船し、必要に応じて陸上から遠隔操作する。」
になると遠隔操作がメインになるか、壁にぶち当たると思う。遠隔操作をどの範囲まで考えているのか、遠隔操作のためにどれだけの設備投資をするかの問題があると思う。また、通信の問題や緊急の操作が要求される場合、どのような対応を取るのであろうか?
船が大きいと事故による影響や損害は大きくなる傾向はあると思う。
三菱重工業は12日、長崎市の長崎造船所で建造する大型高速フェリーに無人運航システムを導入すると発表した。高齢化による船員不足や人的ミスによる海難事故といった課題の解決が期待される。
子会社の三菱造船(横浜市)が昨年、新日本海フェリー(大阪市)から2隻(各1万6千トン、各定員600人程度)を受注した。長崎でフェリーを造るのは2012年に引き渡して以来。1隻目は既に起工し、無人運航システムは2隻目に搭載する。
三菱重工によると、21年6月末に引き渡し、国内航路で商業運用しながら約1年間、実証実験を行う。同社が実用船で大規模な無人運航実験に取り組むのは初めて。1990年代から有人航海や荷役を支援する自動化システムを開発してきたが、さらに高度な無人運航の実用化を目指す。
無人運航は人工知能(AI)が操船し、必要に応じて陸上から遠隔操作する。具体的には、離着岸時の操船制御や、他船舶との衝突や座礁を回避する技術を開発する。グループ会社が開発中の遠隔診断技術を機関室の監視に応用することで、燃料漏れなど故障の予知が期待できる。
日本財団の助成金を活用する。同財団は同日、海運や造船、ITなど複数の企業・団体が2021年度末までに五つの無人運航船の実証実験を行うと発表した。計約34億円を投じ、世界に先駆けて25年までの実用化を目指す。国内運航船の半数を40年までに無人化すれば、年間1兆円の経済効果を見込めるという。
【シンガポール=谷繭子】新型コロナウイルス対策の入国制限により、貨物船などから下船できずに海上で足止めされていたインド人船員87人が12日、シンガポール発ムンバイ行きのチャーター機で帰途についた。契約期間が終了しても下船できない船員は世界に約20万人いるとされ、健康状態の悪化などが懸念されている。シンガポールは国境制限の緩和を始めており、国も船員の帰国を支援する方針だ。
「やっとインドに帰って家族に会える」。石油タンカーの船長、ラビ・ナガルさん(40)はシンガポールのチャンギ空港で、チャーター機に乗り込む前にこう語った。2019年11月から南アフリカなどを回る4カ月の航海に出たものの、新型コロナ対策で外国人の入国を禁止する国が増え、交代できずに8カ月、船上で勤務を続けた。「いつ下船できるのか分からず、乗員はストレスが高かった」と振り返った。
各国の船主団体で構成する国際海運会議所(ICS)によると、こうした船員は5月時点で世界で約20万人に上るという。ICSは「人道的災害に発展している」と警鐘を鳴らしていた。
12日のチャーター便はシンガポールの船舶管理会社、エグゼクティブ・シップ・マネジメントが用意した。ムンバイから交代要員の54人をシンガポールに運び、ナガルさんら87人を乗せてムンバイへUターンした。
インドへの国際線の乗り入れは制限が厳しいが、政府間の協力で実現したという。チャンギ空港では船員向けのチャーター便が6月前半に4機、発着する予定だ。
シンガポールは新型コロナで停止していた国際的な人の往来の再開に動き出している。ビジネス渡航を中国の一部路線で解禁したほか、オーストラリアや韓国などとも交渉を進めている。
新型コロナウイルスの感染拡大で船員交代が難航する中、一部船社の間で直接インドに船を寄港し、インド人船員を交代するオペレーションが徐々に広がり始めている。寄港に伴うデビエーション(航路離脱)を最小化するため、中東などで船積みのあるタンカーなどリキッド系の船種で行われるケースが多いようだ。
船員交代のために、インドに直接寄港させると、本来の最適航路から外れることになる。
寄港するには最適航路からデビエーションさせる必要があるが、「時間もお金も余計にかかる」(邦船社の関係者)。
そのため、デビエーションを最小化する観点から、インドへの直接寄港では、中東-極東航路などに従事するタンカーなどが対象となることが多いようだ。
同関係者は「なるべくデビエーションしないで済むよう、中近東や紅海周辺の港に向かう船で行うようにしている。先般、VLCC(大型原油タンカー)より小型の船型で実施した。他社でも同様の動きがあるようだ」と語る。
インドに直接、船を寄港させて行う交代では、新たに乗り組む船員も下船する船員もインド人に限定される。
下船する船員については、直接母国に寄港することになるので、外国人よりも故郷への帰還が円滑に進みやすい。
同関係者は「国際線のフライトが停滞しているので、インド人以外を下船させても母国に帰すことが難しい」と指摘。
一方、「国内線も平時のようには動いていないので、インド人であっても数百キロの長距離を陸路で帰すこともある」と語る。
こうした船員供給国への直接寄港による船員交代は、インドだけでなくフィリピンも対象に検討が進められているという。





韓国がカタールから液化天然ガス(LNG)運搬船100隻を受注したというニュースでジャックポットを引き当てた外国企業がある。LNG貨物タンクの基本技術を持つフランスのGTTだ。LNG運搬船1隻を建造するたびにロイヤルティとして100億ウォン(約8億8470万円)を韓国の造船会社から受け取る。予定通りカタールに100隻を引き渡せば1兆ウォンが支払われる格好だ。造船業界も半導体のように「素材・部品・装備の国産化」が急がれるという指摘が出る。韓国政府はLNG貨物倉開発を国策課題に選定することにした。
◇造船会社の利益に匹敵するロイヤルティ
3日の業界によると、現代重工業、大宇造船海洋、サムスン重工業の韓国造船大手3社は17万立方メートル以上の大型LNG運搬船1隻を建造するたびに船体価格約2000億ウォンの5%に当たる100億ウォンをGTTにロイヤルティとして払っている。昨年韓国の造船業界が受注した大型LNG運搬船が51隻であることを考慮すると、ロイヤルティだけで約5100億ウォンを支払ったと推定される。造船会社がLNG運搬船1隻を建造する時に残る収益の5~7%と同水準の金額だ。
造船大手3社は1日、カタール国営石油会社のカタールペトロリアムと23兆ウォン規模で100隻以上のLNG運搬船スロット予約契約を結んだ。100隻をすべて建造すればロイヤルティだけで1兆1500億ウォンをGTTに払わなければならない。「芸は韓国が演じ、金はフランスがもらう」という指摘が出る理由だ。
貨物倉はLNG運搬船の核心技術だ。氷点下163度で液化したLNGを運送する過程で波など外部衝撃により船舶が揺れる時でも安定した状態を維持する役割をする。韓国が1990年代までLNG運搬船市場を独占していた日本を追い越すことができたのも貨物倉のおかげだ。日本が球型のモス型LNG運搬船に固執する間に韓国はボックス形のタンクを装備したメンブレン型を導入して市場を掌握した。メンブレン型はモス型より積載量を40%ほど増やせる。ただ特許をGTTが持っており費用負担問題が提起され続けてきた。
韓国を追撃している中国の造船会社がGTTの技術を使っていることも潜在的脅威要因だ。造船業界は今回のカタールからの超大型受注により韓国の技術力が中国より大きく上回っているという事実が立証されたとし、「LNG運搬船超格差」に自信を持った。だが基本技術の自立がなければいつでも中国に追撃されかねないという指摘が出る。
◇「韓国型貨物倉」後続開発始動
造船業界と韓国政府もこれに対する問題意識はある。中国との競争がますます激しくなるだけにロイヤルティ支出を減らして原価競争力を高め、利益率も改善しなければならない課題は「足下の火」だ。造船大手3社は発注元である韓国ガス公社とともに2014年に韓国型貨物倉である「KC-1」を開発してLNG運搬船4隻を建造した。だが設計ミスで貨物倉で結露する問題が発生し、このうち2隻の運航が中断された。現代重工業「ハイメックス」、大宇造船海洋の「ソリダス」など韓国の造船業界が独自に開発した貨物倉設計技術もまだLNG運搬船に採用された事例はない。造船業界関係者は「大規模な量を先物で契約するLNG取引の特性上、船主はLNG運搬船を発注する際に船舶の安全性を最も重要な基準とする。船主が検証されたGTTの技術を望むため現在としては国産技術の採用は難しい」と話す。
造船大手3社と韓国政府は後続モデル開発を推進している。産業通商資源部は次世代LNG貨物倉研究開発事業を国策課題に選定し来月公告する予定だ。KC-1の品質を改善して安全性を高めることが骨子だ。LNG気化率(蒸発率)を低くし生産単価を下げることに焦点を合わせた。産業通商資源部関係者は、「業界の意見を取りまとめて開発計画を策定する段階。これを通じて具体的な事業費用と期間を確定する方針」と話した。
今後7年間、韓国造船企業のドックが活気づく。カタールの企業と23兆ウォン(約2兆円)の液化天然ガス(LNG)運搬船建造契約をしたからだ。現代重工業グループ、大宇造船海洋、サムスン重工業の「造船ビッグ3」は1日(現地時間)、カタール国営石油企業カタール・ペトロリアム(QP)と2027年まで100隻のLNG船発注を保証する「スロット契約」を締結したと2日、明らかにした。船を建造する空間をあらかじめ確保する段階であり、受注前の契約だ。1隻あたりの価格は約1億8000万ドルで、3社の総額は192億ドル(約2兆円)。各社のスロット規模は秘密維持合意のため公開されなかったが、3社とも似た水準という。
100隻すべてが本契約につながる場合、韓国造船業界の歴代最大規模の契約となる。世界LNG船市場は韓国、中国、日本が競争している。今回の計116隻のうち100隻を韓国が契約し、3カ国間の競争で圧倒的優位となった。残りの16隻は中国滬東中華造船であり、カタールがLNG最大消費国の中国を優待した契約という点を考慮すれば、事実上、韓国の独占だ。韓国は過去3年間(2017-19年)、世界の船会社が発注したLNG船124隻のうち118隻を受注した。
産業研究院のホン・ソンイン研究委員は「新型コロナ時局で恵みの雨のようだ」とし「中国のLNG船建造経験は滬東中華造船だけが持つが、自国の海運会社が発注した物量を消化している。日本のLNG船は依然としてスチームタービンエンジンを使用しているが、効率が低いので市場で淘汰される雰囲気」と説明した。
業界はQPとの契約がその間延期されてきたLNG船発注の呼び水になると予想している。ハナ金融投資のパク・ムヒョン研究員は「今後展開されるグローバル船企業のLNG船発注の導火線になりそうだ」とし「ロシア・ヤマルLNGプロジェクトやモザンビークをはじめ、最近LNG輸出が増加しているオーストラリア・米国・カナダなどの発注が続くだろう」と予想した。
一方、LNG船だけでは韓国造船業を牽引するには力不足という声もある。ホン・ソンイン研究委員は「韓国造船はLNG船市場内ではシェアが80%にのぼるほど独歩的だが、LNGにあまりにも集中すれば建造設備やインフラに問題が生じる」とし「コンテナ船やタンカーなどが他の船種の需要がともに回復するのがカギ」と述べた。
過去3年間の造船ビッグ3の受注総額は738億ドルで、うちLNG船は240億ドルで全体の32.5%。LNG船とともに高付加価値船種の超大型タンカー(VLCC)の発注は減り、中小型タンカー船などは価格競争力がある中国造船所がほとんど受注する状況だ。
NH投資証券のチェ・ジンミョン研究員は「恵みの雨だが、十分な量ではない」とし「造船3社の売上全体でみると年間の約30%の物量を確保したということだ。ビッグ3のドックがすべて埋まるわけではないので、中小型造船会社への効果は大きくないだろう」と述べた。
2日の株式市場で造船株は大幅に値上がりした。韓国造船海洋は前日比6.4%上昇した9万8100ウォンで取引を終えた。サムスン重工業(18.27%)、大宇造船海洋(14.41%)、現代尾浦造船(3.32%)、現代重工業持株(1.07%)などの造船株も同時に値上がりした。サムスン重工業優先株はストップ高(29.91%)となった。
韓国大手海運会社のHMM(旧現代商船)のコンテナ船が相次いで世界最大船籍量の記録を打ち立てた。
HMMは2万4000TEU級(1TEUは6メートル分のコンテナ1つ)の超大型コンテナ2号船「HMMオスロ号」が今月28日にシンガポール港から出港したと31日、明らかにした。
HMMオスロ号は今月8日に欧州に向けて出発した2万4000TEU級1号船「HMMアルヘシラス号」に続く2号船だ。2万4000TEU級は世界最大規模のコンテナ船だ。
HMMは1号船HMMアルヘシラス号に1万9621TEUを積載して世界最大船籍量を記録した。オスロ号にも同じ量のコンテナをのせた。
HMMは今年9月まで大宇造船海洋から7隻、サムスン重工業から5隻など計12隻の2万4000TEU級コンテナ船の引渡しを受ける。
会社更生手続き中の東北最大の造船会社「ヤマニシ」(宮城県石巻市)は22日、経営再建を支援するスポンサー企業選定を一時断念し、自主再建に方針を転換すると発表した。新型コロナウイルス感染拡大で事業環境が不透明になり、候補企業との合意が困難と判断した。
同社によると、スポンサー選定では3月の1次入札で複数社に絞り込んだ。事業実態の調査期間などを考慮して4月末までの確定期限を5月末に延長したが、今月中旬の最終入札には応札がなかったという。
今後は収益が見込める船舶修繕と鉄構造物の製造を中心に更生計画案を策定する。6月29日の計画提出期限の延長も検討する。
主力の新造船事業は更生計画認可後5年以内に再開を目指す。スポンサー選定は経営状態が安定した時期に再開する方針。管財人の松嶋英機弁護士(東京弁護士会)は「自主再建に向けて全力を尽くす」と話す。
同社は1920年に創業。東日本大震災の津波で被災し、東日本大震災事業者再生支援機構による出資やグループ化補助金の交付を受けたが、減価償却費などで約42億円の債務超過に陥った。1月31日に会社更生法の適用を申請し、2月17日に更生手続き開始の決定を受けた。
特別清算開始決定 負債総額 約64億円
同社は5月1日、鹿児島地裁から特別清算開始決定を受けた。
負債総額は約64億円。
代表清算人:西村 賢
~円高や海運市況悪化が影響~
大東海運産業(株)(TSR企業コード:940015013、法人番号:9340001002548、鹿児島市名山町1-3、設立1960(昭和35)年12月、資本金8800万円、代表清算人:西村賢弁護士)は5月1日、鹿児島地裁より特別清算開始決定を受けた。
負債総額は約64億円(2019年5月期決算時点)。
大手海運業者との密接な取引関係を背景に、自社およびSPC(特定目的会社)で新船建造を意欲的に進め、南西諸島とアジア近海に定期航路を有するほか、大型船舶の船主業を手掛けていた。とくに、台湾企業が日本向けに出荷する鋼材の輸送が安定部門となっていたため台湾航路の鋼材海運に強く、一時期はオペレーション業務も含めて常時約20隻を運航。2012年5月期にはSPCを含む売上高は約75億円を計上していた。
しかし、2008年以降の円高、燃油価格の高止まり、為替デリバティブ取引での損失などで多額の赤字を計上して経営状態が悪化。2013年7月、東あすか氏が代表取締役に就任した頃から外部機関の協力・同意を取り付けて、経営改善に本格的に乗り出した。社有不動産を始めとした資産売却でスリム化、関係会社の整理等を図ったほか、為替相場も円安に転じるなど事業環境が好転し、2015年5月期のSPCを含む総売上高は約81億円、単独売上高は約34億円を計上していた。
しかし、その後、為替の円高傾向や海運市況の悪化によって取り巻く経営環境が悪化。2017年10月1日、会社分割によりゼネラルマリックス海運(株)(TSR企業コード:025187015、法人番号:6010401132591、東京都港区)に日本・台湾航路に関わる営業基盤と、船舶および船舶建造資金の借入残を移管。以降は事業を大型遠洋船舶の船主業に縮小したが、世界的な海運市況の悪化によって、2019年5月期の売上高は約1億7000万円に落ち込み、債務超過額は約57億円に膨らんでいた。
こうしたなか、当社は2019年12月27日、株主総会の決議により解散し、今回の措置となった。

ヤマニシ(宮城県石巻市)は、1920年3月に設立。東北で最大規模の老舗造船業者で、漁師ごとに要求が異なる小型漁船の建造で培った技術力を強みに外航貨物船、コンテナ船等を受注し業容を拡大、ピーク時の2010年3月期には年売上高約198億2100万円を計上していた。
【新型コロナ】造船各社「修繕」フル稼働、中国停滞で日本に需要
東日本大震災では津波により製造設備等が甚大な被害を受け、実質的な休業を余儀なくされたが、12年2月に企業再生支援機構(現地域経済活性化支援機構)や金融機関による支援(設備資金、運転資金の融資等)を受けて再スタートを切った。また、同年11月には東日本大震災事業者再生支援機構が約40億円を出資するなど支援を受け、地域経済復興のシンボル的な存在として再建の道を歩み出した。
しかし、競合激化を背景に新規受注を確保するため赤字受注が散発し、13年3月期から17年3月期までの5年間、新造船事業は売上総利益段階から赤字となっていた。一方で修繕事業は震災後の特需もあり、黒字を確保していたが、新造船事業の赤字をカバーするだけの規模ではなかった。
さらに黒字だった同事業も復興需要の収束に伴い受注が減少したうえ、外注業者の廃業により、収益率の高い船舶エンジンの整備にかかわる修繕を、費用が高い外注業者に新たに依頼せざるを得なくなり、18年3月期には売上総利益段階で赤字に転落。このため、災害からの復旧費用や減価償却費などの諸経費負担も重荷となり、12年3月期から18年3月期まで当期純損失計上を余儀なくされるなど、赤字経営から脱却できずにいた。
その後も、メーンバンクによるデット・デット・スワップによる追加金融支援などにより、19年3月期には約1600万円の当期純利益を計上したが、あくまでも表面上の回復に過ぎなかった。世界的な造船不況という業界環境の中で根本的な解決策が見当たらないまま自主再建を断念、会社更生法による再建の道を選ぶこととなった。
ドイツの造船所が倒産したそうだ。フェリーを2隻発注していたアリルランド・フェリーは残りの一隻を中国かどこかで建造できる可能性があるのか検討しているそうだが、中国は品質と信頼性を考えると無理だと思う。まあ、日本はヨーロッパスタイルの船は船価が合わないので損を出すだけなので取らないであろう。まあ、この倒産した造船所が損を出して倒産しているのだから、手を出す造船所はいないと思う。
船舶による砂・砂利採取、建材販売を手がける住吉海運(本社・徳島県鳴門市、昼馬正人社長、資本金1700万円)と関係会社3社はこのほど、営業を停止し自己破産の手続きに入った。民間信用調査機関の帝国データバンクによると、グループ合計の負債額は約100億万円。住吉海運は76年の設立。瀬戸内海-九州・沖縄間で採取船・プッシャーバージ船など用船も含め十数隻を運航、01年4月期の売上高は約30億8000…
特定の国籍に船を登録するのは、コスト削減、規則の緩和、船主に対する対応の早さ、法や規則からの逃避、管理やチェックの甘さなどいろいろな理由でどの船籍を良いかが選ばれる。
PSC(外国船舶監督官)による世界規模での検査が行われているのは部分的に問題のあるサブスタンダード船が野放しの状態のため。それでも個人的には一部の国を除いてはやらないよりはましと思う程度だったり、たかりの原因となっている国がある。
多くのサブスタンダード船が登録されている旗国には現実的に責任を取る事は出来ないし、取る気もない場合が多いと思う。責任を取る気がないからサブスタンダード船が簡単に登録できるし、登録の手順が確立されていても守られない。規則があるから大丈夫と思うのは日本の常識。規則があっても守る必要がない、又は、守らせる行動を起こさなければ規則がないよりもましな程度でしかない。
国際条約があっても国(旗国)の判断で解釈が違う問題が既に存在する。国際法が新しく出来ても問題がなくなる事はないと思う。そして、新しい国際法はコストに跳ね返ってくる。保険会社は対応を嫌がると思うが、集団感染が起きた場合、対応のコスト、治療費、補償や賠償を保険がカバーする事を証明する証書を要求する事でも対応は出来ると思う。かなりの保険費用が発生すると思うが保険会社からすみやかに感染者に対応する費用が寄港国や寄港の行政に支払われれば現在のような対応を取る国や港は減ると思う。
保険でカバーされる事を証明する証書がなければ寄港させない交際条約や法律が採択されれば、サブスタンダード船と思われるフェリーや客船が入港出来なくなるので、ある意味では良い事だと思う。
クルーズ船は比較的にゆとりのある人達が利用する傾向があるので、多少の価格アップよりは快適や安全を重要視すると思うので影響はあるが、現状よりは良い印象を与えられると思う。
長崎港に停泊中のイタリア船籍「コスタ・アトランチカ」で乗員48人の新型コロナウイルス感染が明らかになるなど各国のクルーズ船で集団感染が相次いでいることを受け、日本政府は国際法上、入港国、船籍国(旗国)、船会社などの対応責任が不明確な現状を打開する国際的な制度について、調査・研究を始める。
【新型コロナ 感染した?と思ったら】
2~3月に横浜港に停泊した「ダイヤモンド・プリンセス」は米国企業が運航する英国船籍のクルーズ船。約3700人(56カ国・地域)の乗員・乗客のうち700人以上が感染したが、クルーズ船での新型感染症の集団感染は「世界初」で、責任を明確に規定した既存の国際法がない。船舶は公海上では旗国の主権下にあり、運航中の船内の公衆衛生は運航会社や船長が責任を持つが、今回は入港を認めた日本政府が大規模な検疫や医療機関での治療などを負担した。
その後、感染者がいる可能性があったオランダ船籍のクルーズ船「ウエステルダム」が沖縄に接近したが、日本政府は入港を拒否。その後もタイ、米領グアムなどが同船の入港を拒否した。
こうした事態を受け、日本政府は入港国や旗国、船会社などで責任を分担できるような新たな仕組みを目指し、国際法に詳しい専門家やシンクタンクに課題整理や提言を委託する。月内にも成立する見通しの2020年度補正予算案に調査研究費6000万円を盛り込んだ。【田所柳子】
「三菱重工の子会社三菱造船は当初、3月14日以降は乗員は船内にとどまっていたと説明していたが、22日の記者会見で、船会社の判断で乗員の下船が行われていたと訂正した。担当者は「長崎市内の病院に行ったり、タクシーで行ったりしたと思うが、改めて確認する。調査中だが、乗下船もあり得る」と述べた。
県は3月に下船させないよう三菱側に要請していたが、中村法道知事は『三菱重工から出入りはないと聞いていた。大変残念』と述べた。」
三菱造船に「県は3月に下船させないよう三菱側に要請していた」事について伝わっていなかったのか?伝わっていなかったのであれば三菱重工の組織的な問題。情報が伝わらないほど組織の士気が下がっているのか?
もし、「県は3月に下船させないよう三菱側に要請していた」事実が伝わっていたのなら、三菱造船のゲートでのチェックやセキュリティに問題があると言う事だろう。一般的にゲートで身分証明書や所属を聞かれるはずである。三菱造船のゲートは下請けの会社なのか、契約している警備会社の社員なのか知らないがどのようになっていたのであろうか?
「三菱重工から出入りはないと聞いていた。」は三菱造船からの回答をそのまま伝えたのであろうか?それとも隠蔽だったのだろうか?
長崎県は22日、長崎市の三菱重工業長崎造船所香焼(こうやぎ)工場に停泊中のイタリアの客船「コスタ・アトランチカ」(8万6千トン、乗員623人)内で、新たに外国籍の乗員33人が新型コロナウイルスに感染したと明らかにした。重症者は確認されておらず、陽性者は個室で隔離しているという。乗客は乗っていない。
【写真】三菱重工業長崎造船所香焼工場に停泊するコスタ・アトランチカ(手前)などコスタ・クルーズ社の客船3隻=2020年4月21日午後3時50分、長崎市、朝日新聞社ヘリから、堀英治撮影
クラスターの発生を受け、県などは今後、残りの乗員のPCR検査をし、陽性者と陰性者に分ける方針を決めた。陰性者は早期帰国をめざし、陽性者は軽症の場合は船内で待機させ、重症者はまずは県内の医療機関で引き受けることを確認した。今後、医療・搬送支援のため自衛隊に災害派遣要請を行う予定という。
県などによると、19日に運航するコスタクルーズ社から「4人に発熱の症状がある」と長崎市保健所に連絡があり、PCR検査の結果、1人が陽性と判明。濃厚接触者53人と料理スタッフ4人を21日から検査していた。コスタ社日本支社によると、二十数人に発熱症状が出ていた。
客船は中国で修繕する予定だったが、新型コロナの影響で変更され、2月20日から3月25日まで三菱重工の工場で修繕していた。その後、海上での試運転などを経て、4月1日から香焼工場に接岸していた。
三菱重工の子会社三菱造船は当初、3月14日以降は乗員は船内にとどまっていたと説明していたが、22日の記者会見で、船会社の判断で乗員の下船が行われていたと訂正した。担当者は「長崎市内の病院に行ったり、タクシーで行ったりしたと思うが、改めて確認する。調査中だが、乗下船もあり得る」と述べた。
県は3月に下船させないよう三菱側に要請していたが、中村法道知事は「三菱重工から出入りはないと聞いていた。大変残念」と述べた。
長崎市の三菱重工香焼工場に係留されているイタリア船籍のクルーズ客船内で外国人乗組員33人の新型コロナウィルス感染が確認されました。長崎市と県は22日の会見でコスタ・アトランチカの乗組員33人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表しました。コスタ・アトランチカは今年1月下旬に長崎に入港2月から3月にかけて三菱重工香焼工場で修繕工事を行い、その後も船内に623人の乗組員を残した状態で香焼工場に係留されていました。コスタアトランチカではおととい最初の感染者1人が確認者されておりそれを受けて調査した結果今回の集団感染が明らかになりました。この船の感染確認者は合わせると34人になります香焼工場には21日の段階で厚生労働省感染症クラスター対策班が入っており、長崎県は自衛隊の派遣を要請する方針です。
長崎県と長崎市、三菱重工業は20日、同市香焼町の三菱重工業長崎造船所香焼工場に停泊しているクルーズ船コスタ・アトランチカ(8万6千トン)の船内で、外国籍の船会社社員1人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。濃厚接触者3人も検査したが陰性だった。
ほかに濃厚接触の可能性があるのは53人。21日に長崎大学病院で検査を実施する。
県庁で記者会見した中村法道知事はクラスター(感染者集団)発生への警戒感を示し、医療面での対応について「状況によっては自衛隊の協力をいただく必要があるかもしれない」と述べ、自衛隊への災害派遣要請も視野に入れていることを明らかにした。
クルーズ船の船会社は、イタリアのコスタ・クロティエーレ社。修繕などのため1月下旬から3月下旬にかけ香焼工場に停泊した。修繕を終えていったん海上に出たが、その後、物資補給などのため長崎に戻り、4月1日から香焼工場に停泊していたという。
乗組員は、外国籍の船員や船医ら計623人で、船内に居住。検査した4人は個室に隔離。濃厚接触の可能性がある53人とほかの乗組員の滞在場所は分けているという。乗客はいない。県は新型コロナの流行を受け、3月13日に船会社に乗組員の乗下船の自粛を要請し、その後、乗下船はないという。
感染した社員について、船会社は年代、性別を現時点で明らかにしていない。この社員は今月14日にせきや発熱の症状があり、19日に船会社から長崎市保健所に相談があった。20日に濃厚接触者を含む計4人の検体を採取し、PCR検査を実施した。
会見には田上富久市長と三菱重工業の子会社三菱造船の椎葉邦男常務も出席した。椎葉氏は「ご迷惑をおかけして申し訳ない。コロナ対策を最重要に掲げてやってきた。県や市と連携して感染予防に努める」と述べた。
長崎市香焼町に停泊中で、新型コロナウイルスの感染者1人が判明したクルーズ船「コスタアトランチカ」(イタリア籍)の乗組員の一人が21日、共同通信の取材に応じ「先週から船内で20人以上が発熱したと聞いた」と証言した。長崎県と市は、船内の状況確認や感染者が多数発生した場合などの対応について検討を急いだ。
証言したのはフィリピン国籍の20代乗組員。船内で食事を運ぶ同僚から、発熱した人の数を聞いたという。県の幹部は20日の記者会見で、クラスター(感染者集団)の発生について「可能性は否定できない」として、万全を期すと説明していた。
三菱重工業長崎造船所香焼工場に停泊しているイタリアのクルーズ客船内で新型コロナウイルスの感染者が確認されました。外国籍の船会社の社員です。感染が確認されたのは長崎造船所香焼工場で2月20日から3月25日まで修繕工事をしていた大型客船「コスタ・アトランティカ」に乗っている船会社「コスタ・クロティエーレ」の社員です。19日、船会社から長崎市の帰国者・接触者相談センターに相談があり、20日、船医が4人の検体を採取し長崎市保健環境試験所でPCR検査をした結果、午後4時半ごろ1人が陽性と確認されました。今月14日に発熱があり、熱と咳の症状が続いていますが重症ではなく、18日ごろまで運動もしていたということです。ほか3人は全員陰性でした。「コスタ・アトランティカ」の乗組員は623人。全員外国籍で船内に居住しています。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて長崎県は3月13日に乗員の乗下船を控えるよう要請し、翌14日以降、乗下船者はいないとしています。濃厚接触者は56人いて、21日に全員のPCR検査を実施します。
西日本新聞 長崎・佐世保版 西田 昌矢
中国での新型コロナウイルスの感染拡大を受け、イタリアのクルーズ船運航会社「コスタ・クルーズ社」は上海で予定していた修繕工事を、長崎市の三菱重工業長崎造船所・香焼工場で行うよう変更した。コスタ社はほかにも所有するクルーズ船2隻を同工場の岸壁に接岸している。理由は明らかにしていないが、運航休止に伴う緊急避難措置とみられる。
三菱重工によると、修繕をしているのはコスタ・アトランチカ(8万5619トン)。20日から今月末までの予定で船体の塗装や機材のメンテナンスをしている。
コスタ・ベネチア(13万5500トン)は21日、コスタ・セレーナ(11万4500トン)は22日から接岸。コスタ社によると乗員に感染は確認されていないが上陸はさせず、離岸時期は未定。3隻とも中国を発着する航路を運航しているという。
三菱重工は長崎を修繕事業の拠点とする計画を進めている。今回のクルーズ船は初の受注となるが、計画とは関係なく新型ウイルスの余波という側面が強い。(西田昌矢)
内航船舶貸渡業の下津海運(株)(所在地:和歌山県海南市下津町下津*** )は4月15日、和歌山地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
負債総額は約3億円。
資本金は3500万円。
同社は大正12年創業、昭和29年9月に法人化へ、今回倒産の事態となった。
破産管財人には、大谷惣一弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年7月9日午前10時25分。
事件番号は令和2年(フ)第71号となっています。
中国でのドックが元に戻れば同じ事が中国で起きるのだろうね!
(ブルームバーグ): シンガポールの石油取引会社ヒン・レオン・トレーディングの伝説的創業者リム・オン・クイン氏の一人息子リム・チー・メン氏は、先物取引で積み上がった約8億ドル(約860億円)の損失を同社が隠していたと述べた。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。同社の財務に想定よりはるかに大きな穴がある可能性がある。
燃料油取引大手のヒン・レオン(株式非公開)のトレーディング損失は、サウジアラビアとロシアの価格競争や新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)を受けた今年の原油価格急落の影響の深刻さを浮き彫りにした。
関係者によると、リム・チー・メン氏は銀行融資を確保するため担保提供していた精製品の一部を同社が売却したと説明した。その結果、保有在庫と銀行融資で担保にした在庫の差が相当開いており、多額の融資を行っていた銀行は担保不足で非常に大きな損失を被る恐れがある。関係者は債務支払いの一時停止手続き案を通知したヒン・レオンの海運企業オーシャン・タンカーズによる4月17日の電子メールを引用した。
エバン・リム氏としても知られるリム・チー・メン氏は、数年にわたり損失が発生した理由を知らなかったと述べており、父親がヒン・レオンの財務部門に損失を財務諸表から除外するよう指示していたという。リム・チー・メン氏と姉妹のリム・フエイ・チン氏の署名がある同電子メールについて事情を知る複数の関係者が明らかにした。
19日にリム親子に取材を試みたが連絡は取れなかった。ヒン・レオンやオーシャン・タンカーズに電話や電子メールでコメントを求めたが返答はない。ヒン・レオンは債務返済難でオーシャン・タンカーズと共に17日に裁判所に債権者からの保護を申請しており、ヒン・レオンの顧問法律事務所ラジャ・タンの広報担当はコメントできないと述べた。両社はリム一族が所有する。
原題:Singapore Oil Trader Said to Have Hidden $800 Million Losses (2)(抜粋)
中韓勢の安値攻勢で苦境に立たされている日本の造船会社が大型再編に動き出した。国内造船首位の今治造船(愛媛県今治市、非上場)と2位のジャパン マリンユナイテッド(JMU、横浜市、非上場)が3月末、資本業務提携した。
今治造船が10月1日付でJMUが発行する新株を譲り受け、議決権ベースで30%出資する大株主になる。現在、約46%ずつ出資しているJFEホールディングス(HD)、IHIの持ち株比率は、それぞれ約32%に低下する。今治造船が第3位の大株主になる。
提携の第1弾として10月にも大型タンカーやばら積み船など液化天然ガス(LNG)以外の商船の営業・設計会社、日本シップヤード(東京・千代田区)を設立する。資本金は1億円。今治造船が51%、JMUが49%出資し、人員は両社からの出向者で500人規模となる。社長にはJMUの前田明徳取締役執行役員、副社長には今治造船の檜垣清志専務取締役が就く。
今治造船の建造量は450万総トン、JMUのそれは236万総トン。2社を合わせれば国内シェア50%を握るメガ造船会社が誕生するが、それでも世界シェアではわずか1割にとどまる。大型合併で巨大化する中韓勢の足元にも及ばない。
今治造船の檜垣幸人社長は都内で開いた記者会見で、「日本の造船業を残すため、いい品質で最先端の船を誰よりも早く造る」と強調した。JMUの千葉光太郎社長は「今治造船の規模、販売力と我々の人材や技術を融合すれば強い会社になる」とした。
「海賊の末裔」といわれる造船一族・檜垣家
今回の提携は、「地方の独立系」の今治造船と「大手重工系」のJMUという、これまで交わることはなかった2社が手を結んだことに意味がある。造船不況を象徴する“事件”だ。
JMUの成り立ちを振り返ると、1995年、石川島播磨重工業(現・IHI)と住友重機械工業の艦艇部門が統合して設立された。2002年、石播の海洋船舶部門が統合し、アイ・エイチ・アイマリンユナイテッドに商号変更した。同年、日本鋼管(現JFEホールディングス)と日立造船の船舶部門が統合してユニバーサル造船が発足した。13年1月、ユニバーサル造船を存続会社としてアイ・エイチ・アイマリンユナイテッドを吸収合併し、現在のJMUが誕生した。
今治造船は非上場のオーナー企業ゆえに、その実態はほとんど知られていない。オーナーの檜垣家は謎の造船一族と呼ばれている。今治造船本体のほか、グループ・関連会社・取引先など檜垣一族の総数は100人になんなんとする。
愛媛県には檜垣家と並ぶオーナー企業、大王製紙の井川家があった。井川家は創業家の3代目がバカラ賭博に狂い、創業本家は経営の第一線から身を引いたが、大王製紙が井川家の一族郎党を養っている構図は変わらない。檜垣家は安土桃山時代に瀬戸内海を支配した村上水軍・来島家の家臣団がルーツといわれている。だから、「海賊の末裔」と呼ばれるのだ。
1901(明治34)年、檜垣為治が今治市内に檜垣造船所を創業したことに始まる。太平洋戦争の戦時下の国家統制で地元造船の6社が合併し、今治造船が生まれた。戦後、今治造船は仕事がなく、従業員も離散。現場総監督を務めていた為治の次男の正一は、息子(長男)の正司らとともに今治造船を飛び出し自分たちの造船所をつくった。その後、船大工の大半を失い休業に追い込まれた今治造船が支援を要請してきたため、正一は資本金30万円をかき集め、古巣に戻った。59年、正一が今治造船の社長に就任。これ以降、檜垣家がオーナーとなった。
中興の祖は檜垣俊幸・グループ社主
1980年代には、三菱重工業、三井造船、石川島播磨重工業、日立造船といった大手造船会社が競争していた。今治造船の生産能力は大手造船会社の3分の1だった。今治造船は瀬戸内海に数多くある地場の独立系の造船所の一つにすぎなかった。造船不況で大手がドックを削減し、新事業にシフトするなか、今治造船は経営不振の地場の造船会社を次々と傘下に収め規模を拡大していった。
92年、実質創業者である正一の長男、正司が会長になると、正一の三男の俊幸が跡を継いで社長の椅子に座った。俊幸が今治造船を業界トップに押し上げる礎を築き、中興の祖と呼ばれている。俊幸の現在の肩書はグループ社主である。2005年、俊幸の後任の社長の栄治(正一の五男)が亡くなり、幸人が43歳の若さで社長になった。幸人は俊幸の長男。慶應大学卒業後、三井物産に入社し、船舶部で2年間の修業を経て今治造船に入った。
今治造船が大赤字のJMUを救済
今治造船は非上場のため財務情報は開示していない。唯一、知ることができるのは官報に掲載される決算公告のみだ。
2019年3月期決算(単体)の売上高は前期比9%増の3910億円、純利益は同95%増の116億円。黒字経営を続け利益剰余金は3692億円ある。これに対してJMUは大型LNG運搬船の建造で巨額の工事損失引当金を計上、18年3月期は698億円の最終赤字に陥った。19年3月期決算(単体)の売上高は前期比11%減の2541億円、純利益は12億円の黒字に転換したものの、利益剰余金は377億円の赤字だ。
さらに、JMUの20年3月期は純損益が360億円の赤字の見込みだ。JMUの業績悪化を受けて、出資企業は20年3月期の連結決算で、JMU株の評価損を計上する。46%出資するJFEは165億円の投資損失を計上。同じく46%出資のIHIは92億円、8%出資の日立造船は26億円の評価損を計上。すでに発表している65億円と合わせて特別損失は91億円になる。日立造船の例から見てIHIは追加で減損処理をする可能性大だ。
今治造船とJMUの財務内容には雲泥の差がある。今回の提携は今治造船によるJMUの事実上の救済である。
JMUの出資企業であるIHIは脱造船を進め、航空機エンジンに経営の軸足を移している。JMUの株式を売却して、造船から完全に手を引くのではないかという観測が流れる。国内の造船業界は川崎重工業と三井造船(現三井E&Sホールディングス)の経営統合が破談になって以来、無風状態が続いたため、世界規模の競争から、完全に取り残されてしまった。今回の国内1位と2位の連合で、「造船の再編が始まる」とみる関係者は多い。重工系の代表格である三菱重工業をはじめ大手は造船事業の縮小を進めている。
造船専業は、今治造船、大島造船所(長崎県西海市)、常石造船(広島県福山市)など。いずれも独立系だ。造船専業の瀬戸内の企業も危機感を募らせており、1、2位連合に加わることになるかもしれない。そうなれば、文字通り、“オールジャパン”の造船会社が誕生する。)
元・クルーズ船運航
特別清算開始命令受ける
TDB企業コード:435002627
「長崎」 HTBクルーズ(株)(資本金4億円、佐世保市ハウステンボス町1-1、代表清算人和田光氏)は、3月23日に長崎地裁佐世保支部より特別清算開始命令を受けた。
当社は、アジアからの集客を企図するハウステンボス(株)(佐世保市、「ハウステンボス」経営)が、長崎県等の協力を得て、上海-長崎航路のフェリー運航を目的として2011年(平成23年)1月に設立。「ハウステンボス」内の運河を航行するクルーズ船、漫画ONE PIECE(ワンピース)に登場する架空船「サウザンド・サニー号」などを運航するほか、関係会社が所有する「オーシャンローズ号」(船籍パナマ、全長約193メートル、約3万トン)を使用して、長崎から上海航路を定期運航(週1便)していた。
2011年3月に発生した東日本大震災の影響でハウステンボスに来場する外国人旅行客が急減。その後は、ハウステンボス内における新規イベントなどで国内旅行者の増加によりクルーズ船の稼働率を保っていたものの、2012年に発生した尖閣諸島をめぐる、日中関係悪化による予約客のキャンセル急増と、中国旅行会社による日本向け団体旅行商品の販売自粛により2012年10月には上海航路の運休を余儀なくされていた。
その後、早期再開に努めていたものの、2013年1月に上海航路の無期運休を決断。オーシャンローズ号を海外事業法人に対し裸傭船していたが、2019年8月30日開催の株主総会の決議により解散していた。
負債は精査中。
商船三井は11日、A.P.モラー・マースク(デンマーク)、サムコシッピングホールディング(シンガポール)、オーシャンタンカーズ・シンガポール(同)、フェニックスタンカーズ(商船三井の100%出資シンガポール法人)との間で、VLCCプールに関する共同運航協定書を締結し、プール運営会社としてノバ・タンカーズをデンマークに設立することを決めた。
VLCCプールは2月初旬にプール運航を開始し、年末までに高品質で平均船齢約3年の50隻程度のVLCC船隊に拡充する計画。商船三井では「柔軟性、低船齢、信頼性を兼ね備えた船隊によって、環境に適合し、顧客ニーズにもあった高品質のサービスを提供していく」としている。
ミャンマー港湾局(MPA)は、最大都市ヤンゴンに来航する全船舶に対して、入港の72時間前までに全乗組員の健康状況の報告を義務付ける。新型コロナウイルス感染症の水際対策の一環。ミャンマー・タイムズ(電子版)が20日伝えた。
MPAは入港しようとする船舶に、申告書類を送り、船舶側は72時間前までにEメールで返送する。もし一人でも健康に問題がある乗組員がいる場合は、MPAの健康診断チームが船舶を検査後、貨物の荷揚げと荷降ろしだけを認める。通関手続きに遅延が出ないよう、検査は迅速に行う方針だ。
2020年2月のヤンゴンの港湾に入港した船舶は、前年同月を4%上回る172隻、コンテナ数は25%増の10万7,900個だった。シンガポールやマレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ、中国からの船舶が主だった。
けさ香川県多度津町の今治造船の工場で、造船中の大型貨物船のタンク内で清掃作業をしていた男性2人が倒れているのが見つかり死亡が確認されました。
きょう午前8時半頃、今治造船丸亀工場の多度津事業部で、造船中の大型貨物船のタンク内で作業員が倒れていると職員から119番通報がありました。消防が駆け付けたところ、船内清掃作業員の瀬戸宏紀さん46歳と尾崎涼さん34歳の2人が倒れているのが見つかりました。2人は午後2時半ごろに救助されましたが、死亡が確認されました。
警察によりますと、瀬戸さんと尾崎さんはきのうの朝からタンクの清掃を行っていて、このタンクは船内の廃水や油を貯留するためのもので狭いということです。船は試走のため進水していましたが、通常、進水後にこのタンクへ立ち入ることはないということで、警察では、2人の死因の特定を急ぐとともに、事故原因を詳しく調べています。
24日朝、香川県多度津町で建造中の大型貨物船の中で、清掃作業員2人が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。
午前8時半ごろ、香川県多度津町の岸壁で、今治造船が建造していた大型貨物船のタンクの中で、男性2人が倒れているのが見つかりました。
タンクは船の底の部分にあり、周辺が狭く作業が難航したため、2人は約5時間後に救出されましたが、間もなく死亡が確認されました。
死亡したのはいずれも清掃作業員で、坂出市の瀬戸宏紀さんと丸亀市の尾崎涼さんです。
警察によりますと、2人は貨物船の進水式に備え、23日朝から船内の清掃作業にあたっていましたが、夜になっても連絡が取れなかったということです。
警察では事故の原因を調べています。
神戸港と宮崎港を結ぶフェリー内で有料放送を無料で見られるよう、改造したB―CAS(ビーキャス)カードを乗員に譲渡したとして、神戸海上保安部は17日までに、不正競争防止法違反の疑いで宮崎カーフェリーの男性社員(42)を逮捕した。容疑を認めている。
逮捕容疑は昨年12月17日より前に、同社運航のフェリー「こうべエキスプレス」の乗員に、有料放送を無料視聴できる改造B―CASカードを渡した疑い。男性は同月18日に逮捕されたが後日釈放され、このカードを改造するなどした疑いでも書類送検された。
新型コロナウイルスの感染が中国に続いて米国と欧州でも広がり、輸出の尖兵の海運業界でも不安感が強まっている。中国発の物流量回復が容易でないうえ運賃も下落し、縮小する世界貿易の被害をそのまま受けている。
現代商船によると、同社の2月の中国発物流量は前年同月比で50%減少した。現代商船の関係者は「中国を出発して米国と欧州に運ぶ物流量が会社全体の50%以上を占めるが、新型コロナの影響で中国の工場が停止し、物流量が大幅に減少した」と説明した。
◆運賃下落で零細会社が倒産の危機
物流量が減少したことで運賃指数も下落している。中国発コンテナ運賃指数(CCFI)は昨年末970水準だったが、13日には898.44まで下落した。貨物船の運賃を代表するバルチック・ケープ指数(BCI)は1999年の集計開始以降、初めてマイナスとなった。
業界トップの現代商船はまだ状況が良い方だ。中国工場と共に閉鎖された港湾が再開され、生活必需品を中心に短期的ではあるが米国と欧州の需要がある。グローバル連合体「ザ・アライアンス」を通じて船舶運用調節も可能だ。
しかし多くの中小規模の船会社は厳しい財政事情の中で運賃までが大きく下落し、倒産危機に追い込まれている。業界5位の興亜海運は10日、ワークアウト(企業改善作業)を申請した。韓国海洋振興公社が1500億ウォン規模の金融支援策を出したが、融資資格に達しない零細業者が多く、業界の雰囲気は沈んでいる。
◆船は米西部に…中国から積み出せず
物流量が減少しただけでなく貨物を積み出す船もない。新型コロナのため中国の荷役が進まず、多くの船舶が米国西部にある。ところが中国の状況が回復し、中国から米国・欧州で物を移動させるべき状況を迎えたが、中国には船がない。通常、貨物船が米国から中国まで太平洋を横切るのに3週間ほどかかる。
NH投資証券のチョン・ヨンスン研究員は「グローバルサプライチェーンに問題が生じている」とし「船舶の需要増加が確実なタンカーを除いて、コンテナ・バルク部門の需要不振はしばらく続くだろう」と予想した。
◆自動車・造船など事態長期化を懸念
海運業だけでなく韓国の輸出を主導する重厚長大産業が一斉に超緊張状態を迎えている。現代車のチェコ工場、米アラバマ州工場、起亜車のスロバキア工場、米ジョージア州工場は現地で部品を調達するため、工場の稼働には現在のところ問題がない。
もちろん感染者が増えて工場を閉鎖することになれば打撃が避けられない。最大の懸念は販売が減少することだ。現代車の場合、米国市場で2月に5万313台を販売し、2月の業績では過去最高となった。こうした流れの中で新型コロナが足かせにならないか心配だ。ディーラー網を稼働できない状況を迎えることも考えられる。現代車チェコ工場の労働組合が14日間の防疫強化と生産中断を要求した点も負担だ。
◆現代車、リーマンショック以来の米アシュアランスプログラム
現代車は販売不振を防ぐことに力を注いでいる。現代車米国販売法人(HMA)は自動車を購入またはレンタルする顧客が失職する場合、最大6カ月間は分割払い・リース金額を代わりに支払う「アシュアランスプログラム」を実施する。現代車の「アシュアランスプログラム」は2009年のリーマンショック当時以来11年ぶり。
造船業の場合、原油価格の下落で海洋プラント発注が消え、一部の打撃が予想される。ただ、造船業界は原油価格が1バレルあたり50-60ドルだった当時も海洋プラントの受注が活発でなかったため、今より状況がさらに悪化することはないとみている。
造船業界の関係者は「原油安が長く続くほどタンカーの追加発注を期待できるが、その間に国際情勢がまたどう変わるのか予想しがたい」と話した。
三重県の志摩半島沖で7日、千葉港から韓国のウルサン港に向かっていたタンカーの66歳の乗員が倒れ、鳥羽海上保安部が搬送しましたが、死亡が確認されました。鳥羽海上保安部は8日、死因を調べることにしていますが、新型コロナウイルスの感染はないとみられています。
鳥羽海上保安部によりますと、7日午後8時半ごろ、千葉港から韓国のウルサン港に向けて航行中のタンカー「セヤングプライム」が三重県の志摩半島沖で「乗組員が倒れて意識がない」と搬送要請があったということです。
鳥羽海上保安部は巡視艇「しののめ」で搬送に向かい、8日午前0時半ごろ鳥羽港で乗員を待機していた消防に引き渡しましたが、その場で死亡が確認されました。
死亡が確認されたのは韓国籍のリー・ドンギョンさん(66)で、7日午後8時ごろ、船内の自分の部屋の近くで倒れているのが発見され、当初はゆっくり弱く呼吸していましたが、8時15分ごろに止まったということです。
タンカーには韓国の乗員10人とインドネシアの乗員4人がいたことから、鳥羽海上保安部では防護服に防護マスクを付けて対応しましたが、リーさんやほかの乗員にも熱はなく、新型コロナウイルスの感染ではないとみられています。
また、外傷や持病も確認されていないということで鳥羽海上保安部は、8日に検視をして死因を調べることにしています。
数年か、かなり前に北海道か、東北で逮捕された人がいたので、やっている人はいないと思ったが、やっている人はいるんだね!
中古漁船を無許可でロシアの業者などに販売したとして、警視庁公安部と北海道警が、北海道根室市の自営業の男(67)を古物営業法違反(無許可営業)容疑で釧路地検に書類送検した。送検は20日付。男は容疑を認め、「許可が必要とは知らなかった」と供述しているという。
書類送検容疑は、2017年7月~18年2月、中古漁船4隻を北海道公安委員会の許可を得ずにロシアと日本の業者に販売したとしている。
公安部によると、20トン未満の船の売買には古物営業の許可が必要だが、販売されたのはいずれも十数トンの漁船で、刺し網漁や定置網漁などに使われていたとみられる。男は00年ごろから計100隻以上をロシアの業者などに販売し、年間数百万円の利益を得ていたとみられる。【金森崇之】
三井E&Sホールディングス <7003> は27日、連結子会社の三井E&S造船が千葉工場での造船事業を終了すると発表した。事業廃止期日は2021年3月31日の予定。新造商船の建造が大半を占める千葉工場の造船事業を終了し、経営資源を再配置して収益性の向上を図る。千葉工場の従業員については、他工場やグループ各社への再配置を中心に検討するとともに希望退職も募集する。募集人員は200人で、募集期間は6月1~15日。 。
フィンランドのクヴァルネル・マサ造船所ヘルシンキ工場で建造されているので、ヨーロッパの機器が多いので、日本建造と同じような値段で受けたら赤字ではないのだろうか?
ヨーロッパの設計と日本の設計はかなり違うよ。使用している機器もヨーロッパ製だと英語のマニュアル読みながら整備しないと無理だと思う。勉強にはなるかもしれないが、次回はあるのだろうか?これが最初で最後のような気がする。
日本人は日本の常識で考えるけど、外国人相手だと日本の常識で判断したら間違い。そこのところをよく理解しないとね!
新型コロナウイルスの影響で中国での修理が中止となったイタリアのクルーズ船が三菱重工・長崎造船所で修理をうけることになりきのうから工事が始まりました。
三菱重工香焼工場で修理を受けているのはイタリア船籍のクルーズ船「コスタ・アトランチカ」ですコスタ・アトランティカはアジアを中心にクルーズを行っていますが新型コロナウイルスの影響で先月末からの予定がキャンセルになり香焼工場の岸壁に係留されていました元々この時期に中国・上海での修繕工事が予定されていましたがそれもできなくなったため以前から取引関係のあった三菱重工・長崎造船所に工事を打診。きのう、工事契約を終え塗装工事や機器のメンテナンスが始まりました。工事は今月末までのおよそ一週間の予定だということです。三菱重工によりますと長崎造船所で、大型クルーズ船を修理するのは今回が初めてです。
三井E&Sホールディングス <7003> は27日、連結子会社の三井E&S造船が千葉工場での造船事業を終了すると発表した。事業廃止期日は2021年3月31日の予定。新造商船の建造が大半を占める千葉工場の造船事業を終了し、経営資源を再配置して収益性の向上を図る。千葉工場の従業員については、他工場やグループ各社への再配置を中心に検討するとともに希望退職も募集する。募集人員は200人で、募集期間は6月1~15日。 。
「韓国と中国を結ぶ路線のコンテナ輸送率は普段の50%水準にもなりません。このまま行けば中国依存度が高い中小海運会社は破産するほかありません」。
14日、韓国最大の貿易港である釜山(プサン)新港。コンテナでぎっしり埋まっているべき甲板がガランと空いたまま「フロリダ・ベイ号」が入ってきた。インドネシアを出発し中国・寧波を経て入港したコンテナ船だった。この船は中国で荷物をまともに載せることができず、積載量の3分の1である400TEU(1TEUは6メートルコンテナ1個)だけ載せ釜山新港に到着した。中国の港が事実上まひしたためだ。
空っぽの船舶とは反対に埠頭にはコンテナが幾重にも積み重なった。釜山新港の蔵置率(港湾受け入れ能力に対する積まれたコンテナの割合)は飽和直前である80%を上回った。中国などに送り返さなければならない空のコンテナばかりあふれるためだ。
◇運賃指数4年来の最低水準
新型コロナウイルスによる肺炎が拡散し各国にコンテナ船を運航する海運業界が直撃弾を受けた。コンテナ船だけでなくばら積み船やタンカーも物流量が急減し運賃が下落したためだ。
ブルームバーグが17日に伝えたところによると、海運業況を示す指標のひとつであるバルク貨物運賃指数(BDI、1985年1月=1000ポイント)は10日411に落ち4年ぶりの低水準を記録した。以前のピークだった昨年9月より83.7%急落した。BDIが低いほど海運業況が悪いという意味だ。
13日には超大型貨物船運賃を反映するBDIケープサイズ指数が1999年集計以降初めてマイナスに落ち込んだりもした。「世界の工場」である中国が新型肺炎で動きが止まり、鉄鉱石、原油、穀物などの原材料輸送が急減した影響だ。マースク(デンマーク)、MSC(スイス)、ハパクロイド(ドイツ)の世界海運大手3社は中国路線の船舶数を減らしている。フランスの海運調査機関アルファライナーは1-3月期の欧州~アジア路線の運航回数が昨年1-3月期の半分以下に減ると予想した。
中国から韓国への貨物がなく釜山新港への接岸を取り消す船舶も増える傾向だ。現代商船のチョン・ジェホン釜山地域本部長は「春節連休が終わったが中国港湾の稼動率は20%水準にとどまっている。一部中国工場が再稼働を始めたが工場から港までコンテナを運ぶトラックがまともに運行されていない」と伝えた。
◇「全産業界をまひさせるかも」
韓国の海運企業も輸送量減少と運賃下落で崖っぷちに追いやられた。韓国最大の海運会社である現代商船の中国物流の割合は50%に達する。現代商船は今年「10年ぶりの赤字脱出」を目標に掲げたが、新型肺炎の直撃弾を受けた。ばら積み船を運営するパンオーシャン、近海コンテナ海運の高麗海運、興亜海運、長錦商船なども衝撃波を避けることはできない見通しだ。
デンマークの海運専門コンサルティング会社のシーインテリジェンスは新型肺炎以降に世界のコンテナ物流量が35万個減り、世界の海運業界が毎週3億5000万ドルほどの損失を出していると推定した。洪楠基(ホン・ナムギ)副首相兼企画財政部長官が海運業界に600億ウォン規模の緊急経営資金を支援すると発表したが、業界では実効性がないという指摘が出ている。業界関係者は「米中貿易戦争の傷がまだ癒えていない状況で新型肺炎に襲われた。中小海運会社は破産危機に置かれた」と話した。
海運業界の危機は他の産業界にも連鎖的に影響を与える可能性が大きいと分析される。韓国貿易協会によると昨年韓国が中国から輸入した素材・部品は62兆1550億ウォン規模で、素材・部品輸入額全体の30.5%を占めた。海路がふさがれば中国からの部品・素材調達が途絶え、自動車、機械、航空など韓国の主要工場もまともに稼動できなくなる。
アルファライナーは新型肺炎で1-3月期の中国港湾物流量が600万TEU以上減少するだろうと予想した。中国への輸出割合が全体の27%と高い韓国が大きな打撃を受けるほかない。韓国海洋水産開発院のチェ・ゴンウ専門研究員は「新型肺炎問題が長期化する場合、海運業界が最悪の危機に陥りかねない」と話した。
稚内沖の海上で、ゴムホースや電気ケーブルなど246キロの資材を不法に投棄した疑いで、北海道漁連と重油タンカーの乗組員らが書類送検されました。
書類送検されたのは、北海道漁連と重油タンカー「第三ぎょれん丸」の大坪進一(おおつぼ・しんいち)船長ら4人です。
おととし11月、稚内の南西およそ30キロの海上で、不要になったゴムホースや電気コード、係留ロープなど、あわせておよそ240キロの資材を不法投棄した疑いがもたれています。
内部告発で問題を把握した北海道漁連が、稚内海上保安部に通報していました。
船長らとともに書類送検された北海道漁連は、「漁業者に謝罪し、再発防止策を徹底したい」とコメントしています。
海運業管理業務代行サービスの(株)グローウィル(所在地:大阪府大阪市淀川区西中島***)は2月5日、同日までに事後処理を弁護士に一任、自己破産申請の準備に入った。
負債総額は約10億円。
資本金は5000万円。
同社は平成10年5月に設立、今回倒産の事態となった。
担当弁護士には、芝原明夫弁護士(06-6361-3208)ほかが任命されている。
時代の流れ!
造船大手のJMU(ジャパン マリンユナイテッド)は2020年2月3日(月)、同社舞鶴事業所について、新造商船の建造を終了し、今後は自衛隊の艦船修理事業に特化することを発表しました。
舞鶴事業所では現在、商船6隻の建造中ですが、2021年度第1四半期までにすべての船が完工予定です。なお自衛隊の艦船建造は、2009(平成21)年に就役した砕氷艦「しらせ」が最後になります。
これについてJMUは、新造商船市場において世界的な船腹(積載)量過剰と供給力過剰があるなか、中国および韓国の大手造船会社の再編が進み、厳しい事業環境が続いているとし、これらに対抗する建造体制の構築を図るための施策といいます。
また、これにより「現在の建造体制を見直し、リソースの集約や船種の集中により商品価値向上を図っていく」とし、舞鶴事業所を艦船修理に特化することで「収益性の向上を図っていくことを決断いたしました」とのことです。
なお新造商船事業に従事している舞鶴事業所の従業員については、「今後強化を図っていくほかの事業所への再配置を中心に検討していきます」としています。
造船大手のジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市西区)は3日、舞鶴事業所(京都府舞鶴市)での船舶建造を終了すると発表した。令和3年6月までに受注済みの船舶の建造を終え、その後は防衛省向け艦船の修理に特化する。従業員約300人の雇用は維持し、配置転換する方向で検討していく。
建造終了に伴い、2年3月期連結決算で48億円の特別損失を計上する。最終損益は360億円の赤字となる見通し。
造船業界は、世界的な「船余り」を背景にした供給過剰に苦しんでおり、中国と韓国、日本による競争が激化している。JMUによると、舞鶴事業所が手掛ける中型のばら積み船やタンカーは特に厳しい環境が続いているという。同社は今後、商船を有明事業所(熊本県長洲町)と呉事業所(広島県呉市)、津事業所(三重県津市)の3カ所で、艦船は横浜事業所(横浜市)で建造する方針だ。
JMUは昨年11月、国内首位の今治造船(愛媛県今治市)と資本提携で基本合意。今治はJMUに最大30%を出資する方向で検討している。今回の建造終了は、提携に備えた措置でもありそうだ。
JMUは、平成25年にIHIとJFEホールディングスがそれぞれ約46%、日立造船が約8%を出資して設立された。船舶建造量は今治に次ぐ国内2位。
造船業界では、ほかにも三菱重工業が長崎造船所香焼工場(長崎県長崎市)を大島造船所(同西海市)に売却する方向で検討するなど、再編の動きが加速している。
まあ、記事の内容は事実なのだろうが、知らない人が読むと誤解するかもしれない。記事の内容はセメント運搬船「UBC Cyprus」で働くようなフィリピン船員の話で、多くのフィリピン船員達がこのようではないと思う。もっと良い待遇で働いているフィリピン船員達は存在するし、もっとひどい環境の船で働いているフィリピン船員達も存在する。
フィリピン船員が世界のために劣悪な環境で働いているように書かれているように感じたが、働く環境は一般的に良いが、日本人船員だってこのような感じで働いていた。また、給料は良いが、この環境よりももっとひどい環境で働いていた日本人船員はいた。
まあまあの海運会社が所有する船で船長として働けば、メイドを雇い、フィリピンでは多いと思われる家に住むことが出来る。子供が勉強を嫌いでなければそれなりの教育を提供できる。船員の需要があるから船員としての生活を受け入れればフィリピンでは中流以上の生活が出来る。フィリピンで出稼ぎは多い事実は、島が多いフィリピンでは十分な雇用を維持するだけの産業が育たなかった事を認めている事と同じ事だと思う。船員の出身国の経済が良くなると船員が減る傾向がある。船員にならなくてもそれなりの収入が得られる仕事の需要があり、経済発展の結果として国内の給料が上がるので船員になる動機が薄れていく結果だと思う。国内で働けば給料は国内の相場で決まる。しかし、船員として働けば船員の出身国に関係なく、国際的な相場と国際条約やその他の規則で決まる。自国の経済レベルが低ければ低いほど、船員として働く魅力が強くなると思う。
先進国では船員が極端に減少するのは、先進国の給料基準ではなく国際的な船員の相場で仕事や拘束は国籍に関係なくそれなりに同じである事が影響していると思う。外国人労働力を受け入れていない国では、3Kの仕事についてもらおうと思うと給料を良くしないと人が集まらない。給料を良くしても集まらないかもしれない。外国人労働力の受け入れが可能であれば、給料と労働条件が自国で働くよりも魅力であれば外国人はやってくる。需要と供給そして規則や環境のバランスで誰が参入してくるのかが決まってくる。10年前の話であるが、医者を止めて航海士になった船員と話したことがある。医師として働いて得られる収入の10倍の給料を得られると言っていた。きっかけは船長である父親に誘われたと言っていた。父親に嫌だったら給料をためたら船員を止めたら良いと言われ、一軒家を建てられる額がたまるまでは働く事にしたと言っていた。船員の仕事が日本人に魅力的でなくても、現在の給料の10倍を貰える仕事であれば、日本人の中でも飛びつく人はいると思う。実際には、日本人の現在の給料の10倍もの給料を支払ってくれるまともな仕事はないと思う。
需要と供給のバランスが成り立たなければ、誰も働かない、又は、誰も望まない。だから、ギブアンドテイク。利用されるだけの人達は存在するだろうし、使用されながらチャンスをつかんで人生が大きく変わる人達が存在する。田舎の村に住んでいては会えない人や体験できない経験を積む事が出来る。出会いや経験を利用して大きく飛躍できる人達は少ないながらも存在すると思う。
グローバリゼーションの影響で先進国に住んでいても経済的に滑り落ちていく人達は存在する。誰かが上に行けば誰かが落ちる。バランスを考えれば理解する事は難しくない。下記の記事を読んでフィリピン人船員は単純に大変だと思うのか、グローバリゼーションの一部分だと思うのかでも感じ方は違ってくると思う。
ジュン・ラッセル・レウニール(27)は7年前、最初の航海で貨物船内の奥深くに送り込まれ、筋肉が痛くなるまでシャベルで鉄鉱石をすくった。その後もさらに12時間、彼はシャベルを振るい続けた。
「その1カ月間は、船室で3度も泣いた」とレウニールは語った。
レウニールのようなフィリピン人たちは、ここ数十年にわたり、国際貿易の90%を担うグローバルな海運業を支えてきた。
数カ月前、レウニールら計19人のフィリピン人の男性船員は日本からフィリピンまでのセメント運搬船に乗務した。
船にビジターとして乗った者を、海の旅は新鮮な気持ちにさせる。エンジンのうなりで、波の音がかき消される。嵐の後、甲板には死んだトビウオが散らかる。安い燃料の臭いに満ちた風が吹く。
だが船員たちにとっては、海のロマンはとっくに消え去っており、骨が折れる単調な作業の繰り返し以上につらいのが、仕事の後の退屈さだ。
船で料理人をしているジェイソン・グアニオ(29)はかつて、モンテネグロから中国までボーキサイトを運ぶ2カ月の航海をしたとき、海以外のモノが見えることを期待してブリッジ(操船室)へと駆け込んだことを思い出した。
だが過去30年間、その大半を貨物船に乗務してきた機関室調整員のアルヌルフォ・アバド(51)はこの仕事に感謝していると語った。「海は私に生きがいを与えてくれた」
船員になった男性は、漁民や大工や稲作農家の息子たちである。ほとんどが望むオフィサー(訳注=機関長や航海士ら海技資格を持つ乗組員)になるには、大学の学位が必要だ。そのために、なかには裏庭での養豚の稼ぎや道端でアイスキャンディー売りをして得たポケットマネーを学資にして大学を出た者もいる。
彼らは、月にせいぜい100ドルの収入しか期待できない田舎の村での暮らしを捨てた。海で働けば、その10倍か、しばしばそれ以上を稼げる。
首に太いゴールドの鎖を巻いて里帰りし、竹づくりの小屋が並ぶ地区に高いコンクリートの家を建て、両親を養い、きょうだい、めい、おいの大学資金を出してやる。結婚の申し込みも舞い込んでくる。
過酷ながら実入りのいい貨物船の乗務がフィリピンで盛んになるのは1980年代である。海での仕事にフィリピン人を訓練する組織的キャンペーンが始まったのだ。職業あっせん機関は、フィリピン人船員を国際的な海運会社に売り込む。政府の関係部局は、配置の管理に介入した。
船員志望者のための商船大学産業が台頭した。
近年、船舶各社はベトナムやミャンマー、中国からより多くの船員を雇うようになった。それでも、世界の船乗り160万人のうち約40万人がフィリピン人だ。2018年でみると、フィリピン人船員は計60億ドルを母国に送金している。
フィリピンでは、彼らの英雄的な犠牲や伝説的な偉業、放蕩(ほうとう)な暮らしぶりが歌になっている。カラオケの定番は恋人が嘆く歌。「あなたが船員だから、私は何でも耐えてきた」のに、結局は「あなたはLolokoの船乗りだった」ことがわかったと歌う。Lolokoはフィリピンの隠語で、女たらしという意味だ。
セメント運搬船「UBC Cyprus(キプロス)」の船上は、他の多くの船舶と同様、フィリピン文化の世界だ。
フィリピン人船長ロドリゴ・ソヨソは、商業漁船の見習いからスタートした。その船には35人余りが乗っており、風呂は週1回だけだった。彼は甲板に寝て、海に滑り落ちないように足首を通気口にくくりつけた。
士官へと昇進する過程で、さびたタグボートに乗り、悪臭を放つ家畜運搬船に乗り、クルーズ船にも乗った。
船長として、ソヨソは国際海事規則を順守し、他の船との衝突を避け、寒冷前線や季節風の動きを監視する。腐敗した税関職員をかわし、かわせない時のためにたばこのカートンを用意している。
(記者が乗った)この船は船員全員が男性だった。世界の商業船員に占める女性の割合は約1%だ。
土曜の夜、男性たちは食堂のカラオケで、「わたしの心は、あなたを思って、いつまで待ち続けるだろうか?」といった歌詞の、思慕の歌を歌う。
インターネットは船上暮らしのわびしさを少し和らげたが、この船の場合、無料でダウンロードできるのはわずかに50メガバイト。「フェイスブックを開くと、表示は消えてしまう」とソヨソは言う。
この航海では、インターネットはダウンしていた。
インターネットが登場する前は、船員たちは港に着くと、お互いを押しのけながら、われ先にと電話ブースに行き、わが子の(カトリック教徒としての)洗礼式は済んだかどうかを電話で知ろうとした。その間、同僚たちは(電話ブースを仕切る)プレキシガラス(訳注=透明のアクリル樹脂)をドンドンとたたくのだった。
当時、「オーバーオーバー(over―over)」と呼ばれる慣習もあった。船乗りたちは、それぞれ妻やガールフレンドに無線通信で、「愛しているよ、オーバー(どうぞ、次はそちらから何か話して)」と語りかけるのだ。
海で働くのは危険だ。過去10年間に1036隻の船が沈んだ。このなかには、スコットランドの近海で、悪天候のためセメント運搬船が転覆、生存者なしという事故もある。
係留ロープには人の首をプッツリはねとばす力がかかることもあるし、落ちてきた格子戸で指が切り落とされることもある。舷側を打ちつける大きな波のうねりで、人がパイプにたたきつけられたり、海に押し流されたりする。
感電することもあれば、やけどをしたり、盲腸炎にかかったりもする。最寄りの病院まで、救援ヘリを使って数時間、あるいは数日かかる。
しかし、船乗りにとって最大の課題は、孤立していることの精神的な緊張に耐えることであると船長のソヨソは言う。
船の上では、問題をあれこれ考える時間があり、どうすることもできないとなると、落ち込むのも簡単だ。ソヨソは、あまりにも落胆して仕事ができなくなったり、自殺したりするケースをみてきたと話していた。(抄訳)
(Aurora Almendral) The New York Times
日本の造船所でこのように多くの荷物を積載できるスーパー貨物船を建造する事が出来れば需要があるかもしれませんね!
今治との提携を機に合理化へ、艦艇事業を主力に
国内造船2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市西区)が、舞鶴事業所(京都府舞鶴市)での商船建造から撤退する方向で検討していることが明らかになった。中小型バラ積み運搬船を中心に建造を続けてきたが、中国の造船所や国内造船所との競争激化で受注環境が悪化している。JMUは国内首位の今治造船(愛媛県今治市)との資本業務提携を決めており、自社の生産合理化に踏み切る格好だ。
市場原理を無視した韓国政府、世界の造船業に多大な損失
JMUの舞鶴事業所は海軍工廠(こうしょう)を前身とし、日本海沿岸では随一の大型造船所。今後、艦艇事業を主力に運営していく。バラ積み運搬船やプロダクトタンカーなど国際的に競争の激しい商船からは手を引く方向だ。
舞鶴事業所での商船建造を打ち切る場合、筆頭株主のIHIやJFEホールディングス(HD)にも損失が発生する可能性がある。JMUは今後、超大型船を建造できる設備を持つ有明事業所(熊本県長洲町)や呉事業所(広島県呉市)、津事業所(津市)を中心に商船事業の競争力を高める。
JMUは11月末に今治造船との資本業務提携を発表。経営統合には踏み込まないが、商船の営業と設計の新会社を共同で設立するなど、広範囲での協業を進める。舞鶴事業所での商船建造からの撤退など生産合理化により、シナジーを最大化するとみられる。
造船業界では大型再編が相次ぐ。韓国では現代重工業が大宇造船海洋を買収する。中国でも中国造船首位の中国船舶工業集団と同2位の中国船舶重工集団が統合した。日本の造船所は重工系を中心に苦しい戦いを強いられ、商船事業の構造改革の必要性に迫られている。
三菱重工業は神戸造船所(神戸市兵庫区)での商船建造から撤退したのに続き、主力の長崎造船所香焼工場(長崎市)を大島造船所(長崎県西海市)に譲渡する方針。同様に商船建造を縮小する動きが広がる可能性が高い。
自動航行の信頼性が上がれば軍事及び商用に使えるので開発するメリットはあると思う。
ただ、センサーの信頼性の問題などがあり、毎日の維持管理なしで自動航行は簡単にはいかないと思う。船の運航は条件が良い時ばかりではない。波、風、海流、推進、海中の障害物、干満、その他の障害物、レーダーには映らない物体、そして行動予想できない物の移動など克服しなければならない事がたくさんあると思う。
中国初の自動航行貨物船が12月15日、同国南部広東省珠海市で自動航行試験を行った。
「筋斗雲0号」はこの日の朝9時、地元物産を積んで珠海市の東澳島を出港、港珠澳大橋の第1埠頭に向かった。
貨物船には、デジタル制御技術と電動推進システムが搭載されており、リモート監視およびアラーム機能を装備。 同じ積載量の従来の貨物船に比べ、建設と運用コストをそれぞれ20%以上節約でき、燃料消費量を15%削減できるとしている。
全長12.86メートル、幅3.8メートルの筋斗雲0号の喫水は1メートルで、設計上の航行速度は8ノット。プロジェクトチームは今後、複数の船舶が遭遇した際の衝突回避や自動停泊の試験を行うことにより、内陸河川での自動航行を実現するとしている。
(中国、珠海、12月17日、映像:CCTV/アフロ)
韓国の中型造船所は仕事が全くないらしい。利益なし、又は、赤字がわかっていながら受注するしかないようだ。中国の船価が大きく影響しているようだ。
まだまだ、中国建造船の品質は悪いと思うし、悪いと言う監督や船長は存在するが、安さで決定する会社は多いようだ。中国で建造された船を引き取った後に、問題や品質の問題などは全て管理会社や監督の負担になる傾向があるようだ。
会社が変われば優先順位が違うので会社の自己責任で判断が行われる。アジアのPSC(外国船舶監督官)はオーストラリアやアメリカに比べると経験や知識のレベルが低い。サブスタンダード船であっても出港停止命令を受けたり、たくさんの不備を書かれる可能性は低い。ただし、中国は別。結構、中国の港に入港した外国籍船が出港停止命令を受ける事が多くなっている。10人ほどのPSC(外国船舶監督官)がやってくるとの話を聞いたことがあるし、お金(賄賂)を要求するとの話を聞いた事は多くある(ただし、お金は絶対に直接受け取らずに、船舶代理店が回収するケースが多いようだ。)。純粋にサブスタンダード船の撲滅のために動いているように思えない。また、規則を理解しないまま、不備を書く事が中国では頻繁に起きている。船に適用する規則は、船のトン数、種類、建造年月日、キール日、改造された日などいろいろな項目で変わってくる。かなりの経験、又は、知識がないとどの規則が適用されるのか現場で判断するのは難しい。船級の検査官は、事前に情報や図面などにアクセスできるし、知識がなくても本部の図面承認担当の部署やその他の部署がが指示を出すので、最低限の経験や知識で検査できる。
まあ、PSC(外国船舶監督官)はランダムチェックと言う言い訳が使えるので、問題を見逃しても責任を問われる事はないと理解している。結果として、サブスタンダード船に対して不備を指摘せずに運航させていると、運の悪さと重なり、海難を起こして、油汚染、沈没、破壊、そして放置などの問題を起こして、保険が下りない、保険の支払額が低いなどで被害が補償されずに放置される事となる。
日本のPSC(外国船舶監督官)が先頭に立ってサブスタンダード船の不備を指摘し、出港停止命令を頻繁に出すようになれば、品質の悪い中国建造の船は維持管理費が高く、荷主や用船社からの信頼が低いとの理由などで、日本や韓国に発注が動く事はあるかもしれないが、現状では期待しない方が良いと思う。
受注で韓国が圧倒、再編モード熱帯びる
三菱重工業が香焼(こうやぎ)工場(長崎市)を、造船国内3位の大島造船所(長崎県西海市)に売却する方向で交渉を進めていることが明らかになった。同工場は2008年に国内最大級のゴライアスクレーンを稼働させ液化天然ガス(LNG)船受注に注力してきたが、安値受注攻勢を続ける韓国との競争を前に、先行きの見通しが立たないと判断したもようだ。造船業界は11月末に最大手の今治造船(愛媛県今治市)と2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市西区)が提携を発表したばかり。再編の動きが一気に熱を帯びてきた。
三菱重工社長は「造船撤退」否定、本当?
香焼工場は吊り能力1200トンのゴライアスクレーンとともに、全長1000メートルの巨大ドックを備える。建造能力を高めて世界規模で需要増加が期待できるLNG船の受注を増やす計画だった。実際、LNG輸出国のカタールが今後10年で100隻規模の大量調達を決めたのをはじめ、モザンビークも16隻の新造船調達を計画するなどLNG船市場は活況を呈している。
ただ、ふたを開けてみると受注できたのは圧倒的に韓国勢。日本勢は蚊帳の外に置かれた。明暗を分けたのは価格競争力だ。世界最大手の現代重工業は、スケールメリットを生かし、年間10隻以上をまとめて建造。資材調達力と連続生産による習熟度向上を合わせて、コストを引き下げていくやり方だ。韓国政府もこの動きを全面的に後押し。「韓国勢に対抗するには現在より1―2割安い値段で注文を取らなければならない」―。造船各社の首脳は口をそろえる。
国内造船会社の中では、川崎重工業と三井E&S造船(東京都中央区)もLNG船受注を狙う方針を示しているが、主体は中国の合弁会社。中国は安価な人件費でコストが安い上、中国国内のLNG船需要だけでも事業が成り立つとの読みもある。無理して受注を取る考えはない。
今治造船と提携を決めたJMUも、協業分野からはLNG船を外している。17年度にLNG船建造に伴う損失で、694億円もの当期赤字を出した経緯があり、新規の受注には及び腰だ。国内5カ所の新造船事業所の建造手法やデータなどを統一し、コスト競争力を強化する考え。今後はこれに、今治造船のコスト削減ノウハウも加わる。
国内造船は今後、今治造船とJMU連合にさらに数社が加わるとの観測もある。ただ、単純に連合を組むだけでは、小規模の造船所が乱立する過剰状態は変わらない。「環境規制の強化で世界の新造船需要が数年後に再び上向く。それまでは我慢比べの状況が続く」(国内造船)との声もある。存亡を賭けた“チキンレース”は激しさを増している。
日刊工業新聞・嶋田歩
三菱重工業が長崎造船所香焼工場(長崎市香焼町)を売却する方向で大島造船所(西海市)と交渉していることが12日、関係者への取材で分かった。主力の液化天然ガス(LNG)運搬船の受注環境が厳しく、生産体制を縮小する。
大島造船所はバルクキャリアー(ばら積み貨物船)増産に向け、香焼工場受け入れに前向きとみられる。売買する工場の範囲や金額、時期については調整している。三菱重工は近く方針を決めるもよう。同社広報は「決定した事実はない」としている。
香焼工場は1972年完成。長さ1キロの国内最大級ドックは、つり下げ能力1200トン1基、600トン2基の門型クレーンを備え、通称「100万トンドック」と呼ばれている。
これまでLNGや液化石油ガス(LPG)の運搬船を連続建造してきた。だが韓国企業の低価格攻勢を受け、LNG船は2015年12月を最後に受注が途絶え、残る1隻を今年9月に引き渡して以降、手持ち工事はなくなった。
一方、本工場(長崎市飽の浦町など)では艦艇やフェリーの建造を継続する。中小型客船建造や客船修繕の拠点化も視野に入れている。
三菱重工は17年、大島造船所など造船専業3社と商船事業で提携していた。
三菱重工業が、長崎市内に持つ2造船所のうち、主力の香焼工場の売却も視野に、造船国内3位の大島造船所(長崎県西海市)と事業再編に向けて協議していることが12日、分かった。造船分野で中国、韓国企業が世界的に台頭する中、生産体制を縮小して着実に利益を稼げる体制を構築する狙い。
国内造船を巡っては、首位の今治造船(愛媛県今治市)と2位ジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市)が資本提携で基本合意したと発表したばかりで、再編機運がさらに高まりそうだ。
香焼工場は、三菱重工の祖業とされる長崎造船所を構成する生産拠点の一つ。国内最大級のドックを誇っている。
生き残りかけ大型再編進む
11月末、造船業界でビッグニュースが飛び出した。建造量で国内首位の今治造船(愛媛県今治市)と、同2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市西区)が資本・業務提携。商船分野で営業や設計を手がける会社を共同で設立し、将来の生産効率化についても検討。具体案を2020年3月までに詰めるとしている。大手同士の提携が他社を巻き込んだ新しい再編の呼び水となるか―。
鋼材使用量はトヨタに次ぐ2位、韓国と戦う瀬戸内の造船メーカー
両社が手を組んだのは、中国や韓国の造船大手に対抗するのが狙いだ。中国は同国首位の中国船舶工業集団(CSSC)と同2位の中国船舶重工集団(CSIC)が11月に経営統合。韓国も同国最大手の現代重工が同3位の大宇造船海洋と経営統合を進める。統合後の建造力は中韓ともに、今治・JMU連合の2倍強に相当する。
規模はバラ積み貨物船などの連続建造に有利だ。商船は1隻数百億円以上する高価な買い物だけに、船主は船のコストに敏感。安値で同型船を大量受注し、建造を国内各所で振り分け、資材も一括調達すれば、低コストでシェアを奪える。
これは韓国造船業躍進の際に使われた手法だ。中国も人件費が安く資材を低コストで調達できる強みがある。高コスト体質の日本は環境規制対応や省エネルギー技術で強みを持つが中韓の追い上げで差は縮まっている。
今治造船はJMU以外にも三菱造船(横浜市西区)と液化天然ガス(LNG)船で協業する。三井E&Sホールディングス(HD)は中国揚子江船業(江蘇省)との合弁会社に軸足を移し、護衛艦などについては三菱造船と提携を模索。川崎重工業は中国合弁会社で新ドックを稼働した。
国内造船業界は今後、今治・JMUグループと海外建造グループに集約するとの見方が強い。造船所は長い歴史で地域と密接なつながりがある上、廃業や撤退で伝承が途切れたら「数十年は再起不可能」という装置産業でもある。各社が難しい選択を迫られている。
日刊工業新聞・嶋田歩
SK海運は韓国の会社であれば国内で解決すれば問題ないからそれほど深刻ではないと思う。ヨーロッパの船主だったら補償金額とかすごいと思う。
SM JEJU LNG1号船(IMO: 9830745, MMSI: 351605000)の国籍はパナマ籍のようだ。
新技術や新設計は綺麗な言葉で表現すれば生みの苦しみ。しかし、上手く行かず、将来に生かす事が出来なければ、無駄でしかないリスク。
韓国造船会社を支えているLNG船。この船には液化天然ガス(LNG)を保管するタンクがある。マイナス160度で維持されるべき超低温のLNGを保管できる技術を保有する企業がフランスのGTTしかないため、韓国造船会社はLNG船1隻に最大100億ウォン(約10億円、船舶価格の5%)のロイヤリティーをこの企業に支払わなければならなかった。
韓国ガス公社と主要造船会社が2004年から10年間の国産化作業を通じて開発したのが「KC-1」(韓国型タンク核心設計技術)だ。LNG船1隻に最大36億ウォンの費用を支払えばよい。国産技術であるため国富の流出もない。
ところが2018年4月、この技術を適用したLNG船2隻の船体の外壁に結氷が発生した。その後、197億ウォンを投入して一度補修したが、昨年5月にまたも同じ欠陥が表れた。先月、2度目の補修に入ったLNG船2隻について「修理完了後にもまた欠陥が表れるおそれがある」という指摘が出ている。
国会産業通商資源中小ベンチャー企業委員会所属のチャン・ソクチュン自由韓国党議員室が2日に韓国ガス公社から受けた資料によると、SK海運所属のSKセレニティ号、SKスピカ号は先月から来年3月の完了を目標にサムスン重工業巨済(コジェ)造船所で補修中だ。
資料によると、2次補修方法はタンク下側の空間に断熱材を設置して空間内部の対流現象を防ぐ方式だ。ガス公社は「タンクのコーナー空間内の低温気体流動を遮断し、低温発生部位を除去する」と明らかにした。
KC-1タンクはLNGと直接接するステンレススチール材質の大型タンク(メンブレイン)とこれを覆ったポリウレタン材質の断熱材部位、外側の船体との連結部位で構成されている。
問題はこの方式が検証された方式でないという点だ。このため、ガス公社がすでに検証されている補修方式を採用しなかったという主張も出ている。
サムスン重工業が建造して9月に大韓海運に引き渡したSM JEJU LNG1号船の場合、KC-1技術が適用されたが、断熱方式が異なる。大型タンク(メンブレイン)の外側の空間をすべて断熱材を覆って対流現象を防いだ。コップに例えると下面と横面にすべて布をぶせた形態だ。SM JEJU LNG1号は現在正常運行中で、今月末に2号も引き渡す予定だ。業界関係者は「全体に断熱材を覆わず空間を残す点がSKセレニティ号、SKスピカ号の2次補修の問題」と指摘した。
SK海運は2018年10月、ガス公社の子会社でKC-1技術管理会社のKC LNGテック(KLT)を相手取り250億ウォンの船舶運航損失関連の損害賠償訴訟を起こした。このためガス公社が積極的に補修せず責任を回避しているという指摘が出ている。
韓国党のチャン・ソクチュン議員は「KC-1は国民の税金157億ウォンで開発した国産技術だが、ガス公社の責任回避で死蔵される危機を迎えている」とし「責任の主体であるガス公社が失敗という結論が出た1次修理時の固執を2次修理でも見せていて、まともに修理されるかは疑問」と述べた。
KLT側の関係者は「新しい船を建造するのと従来の船を修理するのは状況が異なる」とし「SKセレニティ号、SKスピカ号のタンクに一部の空間があるのは補修の結果に全く関係ない」と述べた。
この記事、何とも言えない。仕事がないから耐氷タンカーを受注したのか、利益が出ると思ったから受注したかで、利益に大きな影響があると思う。
「今回受注した船舶は氷点下30度の極限の環境で厚さ最大70センチの氷と衝突しても安全に運航できる耐氷タンカーだ。」
タンカーはタンカーでも条件がかなり違う。構造などは普通のタンカーに近いかもしれないが、「氷点下30度の極限の環境で厚さ最大70センチの氷と衝突しても安全に運航」の条件が簡単にクリアー出来なければ損を出す可能性は高いと思う。
「高級仕様で一般タンカーより2倍高く超大型タンカーと似ている」
三菱重工が客船を受注して大損を出した事を考えれば想像できる。以前、客船を建造したら大丈夫と思ったのだろうが、受注額の倍の損失を出す結果となった。仕事が選べるのであれば同じ事を繰り返すのが一番良い。どの変更がどのような影響を与えるのか想像できないほど技術力が落ち、経験がある十分な人材がいない状態になれば、変わった事をすれば損失が発生する可能性は高くなると考えた方が良い。
サムスン重工業が石油タンカー2隻をさらに受注し、今年累積受注額71億ドル(約7800憶円)を達成した。目標受注額である78億ドルの91%水準だ。
サムスン重工業は欧州地域の船社からアフラマックス級石油タンカー2隻を計1875億ウォンで受注したと2日、伝えた。今回受注した船舶は氷点下30度の極限の環境で厚さ最大70センチの氷と衝突しても安全に運航できる耐氷タンカーだ。韓国産業研究院のイ・ウンチャン副研究委員は「高級仕様で一般タンカーより2倍高く超大型タンカーと似ている」とし「技術力を前面に出して受注に成功したとみられる」と話した。
サムスン重工業は2005年、世界最初の両方向砕氷船を受注して砕氷商船市場を切り開いたことに続き、2008年には世界最初の極地用掘削船建造契約を締結して成功的に引き渡した。
サムスン重工業がこの日まで達成した受注額71億ドルは昨年受注額(69億ウォン)を上回る金額であり、ここ5年間最高実績だ。昨年の受注額は63億ドルだった。船種別ではLNG運搬船13隻、コンテナ船6隻、石油タンカー16隻、石油化学製品運搬船2隻、特殊船1隻、FPSO1基など計39隻を受注した。
また、英国の造船・海運分析機関のクラークソンズ・リサーチによると、10月末を基準にサムスン重工業の受注残高は583万CGT(標準貨物船換算トン数)で7月以来4カ月連続で単一造船所1位を記録している。
サムスン重工業関係者は「米中間貿易葛藤の影響などで今年の世界船舶発注量が減少した中でも受注を繰り返して昨年の実績を上回った」とし、「差別化した競争力でLNG船、耐氷タンカーなど高付加価値船の市場シェアを引き続き拡大していくだろう」と話した。
韓国造船業「ビッグ3〔現代(ヒュンダイ)重工業・大宇(テウ)造船海洋・サムスン重工業〕」の今年の受注額は目標値に及ばないものとみられる。現代重工業の今年の目標額は159億ドルで、先月末まで90億ドルを受注して目標値の56%にとどまった。大宇造船海洋は83億7000万ドルの目標額の中で先月末まで54億ドルを受注して65%を達成した。
小出大貴 福山亜希
国内造船首位の今治造船(愛媛県今治市)と、2位のジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市)は29日、資本業務提携することで合意したと発表した。商船事業で協業し、設計と営業を担う新会社をつくる。世界的に造船会社の再編が進むなか、生産体制を強化して国際競争力の強化を図る。
JMUが新たに株式を発行し、今治造船が買い取る。出資比率や出資額は今後の交渉で詰めるが、今治造船は現時点で「JMUを買収して傘下におさめることは想定していない」(広報担当者)としている。来年3月までに最終契約を結ぶ予定だ。
共同でつくる新会社は、タンカーやコンテナ船、鉄鉱石や穀物を運ぶばら積み船などの設計と営業を担う。液化天然ガス(LNG)運搬船は除く。将来的に両社の物流網や工場設備を一部で共有化したり、効率の良い建造方法を共同研究したりする方針という。
資本業務提携に踏み切った背景には、ライバルの中国・韓国メーカーに価格競争で太刀打ちできていないことがある。中国の首位と2位の造船会社が今月、経営統合。韓国では、企業グループとして造船世界首位の現代重工業が大宇造船海洋との統合を模索するなど再編も加速している。中韓勢が一段と競争力を高めることへの日本勢の危機感は強く、業界再編の機運が高まっていた。
JMUは、鉄鋼大手JFEホ…
「海保は1日、貨物船を立ち入り検査した。破損の故意がなく、過失を認めたため、貨物船側は今後、保険会社を通して補償する見通し。」
本当に海保は保険で損害が補償できる事を確認したのだろうか?
青森県むつ市の川内町漁協は5日、蛎崎(かきざき)沖の漁業権海域に侵入した外国船にホタテ養殖設備を破損されたことを明らかにした。被害額は少なく見積もって数百万円。
青森海上保安部と漁協によると1日未明、しけのため陸奥湾内に避難していたトーゴ船籍の貨物船(約2000トン)が養殖海域に侵入したのを地元漁師が見つけた。貨物船はアンカーを引き上げる際、養殖の設備も引きちぎった。
ホタテの稚貝を入れた約520個の籠をつなぐロープが切れたほか、設備を固定するアンカーも壊れた。漁協はほかに被害がないかを確認した上で、6日にも破損した設備の片付けを始める。
海保は1日、貨物船を立ち入り検査した。破損の故意がなく、過失を認めたため、貨物船側は今後、保険会社を通して補償する見通し。貨物船は同日、湾外に出た。
ひとまとめに韓国と言うが韓国は大手だけが赤字覚悟で仕事を取っているが、中小造船は仕事が全くない状態。
国際規則が大きく変わり、船価に影響するので、一部の船主は様子見状態。
なんとか生き残れば、競争相手が減って多少楽になるかもしれないが、人材の維持がそれまで持つのかがカギかもしれない。
結局、仕事を継続しないと技術の維持と技術の継承は不可能。途絶えてしまうと、同じ事をしても同じコストでは出来ない可能性が高い。
仕事をやりながら学ぶ事はあるし、繰り返し同じ事を繰り返すから能力や効率が維持できると思う。
船価が良くても経験が少ない、又は、得意分野でない船であれば、効率が悪い、又は、失敗する可能性があるので、良い受注であるとは言えない。
まあ、韓国が沈んで、中国の人件費が急速に上がって競争力がなくなるのを祈るしかないと思う。
空前の液化天然ガス(LNG)船の発注ブームが到来しているというのに、日本の造船業界は現時点で全く盛り上がっていない。それどころか国内の一部造船所では、静かなる造船事業の“店じまい”ムードが高まりつつある。(ダイヤモンド編集部 新井美江子)
● 圧倒的な建造能力の差で 受注競争から脱落
「このブームに乗れないのだとすれば、さすがに厳しいですね」(LNG業界幹部)。日本の総合重工系の造船各社にとって、今年はひときわ寒い冬となりそうだ。
「LNG船向けの圧縮機の引き合いは、供給が間に合わないくらい多いですよ」。神戸製鋼所の役員がにやりと笑って語るように、世界全体で見れば今、造船業界には空前の液化天然ガス(LNG)船ブームが到来している。
世界最大のLNG輸出国である中東のカタールが、この先10年で100隻規模のLNG船を大量調達する方針を決め、発注を開始しているからだ。LNGプロジェクトは今後、アフリカのモザンビークやロシアなどでも立ち上がる予定であり、LNG船の需要は当分、増加傾向が続きそうだ。
神戸製鋼が製造するLNG船向けの圧縮機は、沸点が-約160度と超低温なだけに大気熱などで気化し続けてしまうLNGのガスを、タンクに戻したり、エンジンの燃料として活用したりするための機械だ。バラ色のLNG船市場で好調な売れ行きを確保し、まさにウハウハの状態である。
ところが、こうしたブームに乗れる国内メーカーがある一方で、日本の造船各社には冷たい風が吹く。船価が利益を取れるレベルに浮上しない中で、韓国勢がなりふり構わぬ安値受注を仕掛けているからだ。
造船も大方のものづくりと同じく、同じものを大量に生産した方が調達力も、製造における習熟度も上がって生産効率がアップする。ところが、連続建造の能力でいくと、年間10~20隻のLNG船をまとめて請け負える大規模な設備を持つ韓国勢が、年間数隻しか造れない日本勢に圧倒的に勝っている。
そもそも、造船業が雇用確保を目的とする国策となっている韓国では、新規案件の受注確保は絶対。「日本が世界貿易機関(WTO)に紛争解決を要請してもなお続いている」(重工メーカー役員)という国による造船会社に対する公的助成の後押しもあって、「日本より1~2割安い価格を提示してくる」(別の重工メーカー幹部)のが現状なのだ。
● 2~3割のシェア獲得を狙う川重も 建造のメインは中国
重工メーカー関係者は、「韓国勢も今の受注価格では黒字は出ないはずだ」と口をそろえるものの、いずれにしても、価格面では韓国勢に完敗状態だ。激しい消耗戦を前に、日本の総合重工系の造船各社は戦々恐々としている。LNG船の「国内建造事業」から撤退するのか、あるいは競合と組んで再編するのか。重大局面を迎えつつあるのだ。
JFEホールディングスとIHIを2大株主に持つジャパン マリンユナイテッド(JMU)は、「失敗の反省や確かな事業性分析が終わるまでは、LNG船の受注はしない」(JMU幹部)と明言する。LNG船の建造難航による工事費高騰を主要因とし、2017年度に694億円もの最終赤字を出したJMUとしては、無理からぬ判断ではある。
傘下の三菱造船や三菱重工海洋鉄構で造船事業を行う三菱重工業も同様だ。船台を埋めるために無理に受注した大型客船の工事の大混乱で、累計2719億円もの巨額損失を計上した負の歴史の教訓から、「無理な受注は二度としない」(三菱重工関係者)との思いは強い。
川崎重工業と三井E&Sホールディングス(旧三井造船)傘下の三井E&S造船については、LNG船の受注自体は狙っていく構えだ。ただし、この2社も建造のメインはコスト効率の高い中国だ。
「LNG船で世界シェア20~30%を取る」。10月2日、未完だった中期経営計画の詳細編をようやく出した川崎重工では、餅田義典・川崎重工業船舶海洋カンパニープレジデント(「餅」の字の食偏は正式には終端部が縦画からの撥ねに点画の形)が鼻息荒いLNG船の受注目標を述べた。だが、川崎重工が連続建造できる6隻程度のLNG船のうち、少なくとも4隻は中国の造船合弁会社である大連中遠海運川崎船舶工程(DACKS)で建造する算段なのである。
三井E&S造船も、競争が比較的緩やかな中小型のLNG船の受注に絞り込んだ上で、建造は中国の揚子江船業集団、三井物産と共に今年、中国に設立した造船合弁会社、江蘇揚子三井造船で行う考えだ。
● 再編に踏ん切りが付かず 静かに始まる“転身”策
では、総合重工系の造船会社が抱える国内の造船所はいったいどうするのか。実は、一部の造船所では、静かなる造船事業の“店じまい”ムードが高まりつつある。
すでに、9月30日には三菱重工で象徴的なことが起こった。長崎造船所香焼工場で働く従業員を、長崎市中心部の大波止から送り届けていた通勤船が廃止されたのだ。
長さ1000メートルのドックを備える三菱重工最大規模の香焼工場は、今年6月になんとオーナー系の造船専業会社である“格下”の今治造船から、原油タンカー1隻の建造受託を決めたほど受注に困っている。それでも前述したLNG船と同様に、他の船でも赤字受注は行わない方針を貫いており、人員が大幅に減っていた。
今後は、ノウハウを生かせる大型の鉄鋼構造物の受注など、必ずしも船にこだわらない事業展開を行う。「誇り高き三菱重工の造船部門が橋げたなど造れるか」と声を荒らげる向きがあったのも今は昔の話だ。
造船業からの“転身”を図っているのは三井E&S造船の千葉工場、川崎重工の坂出工場も同じだ。千葉工場は千葉という利を生かして都心のインフラ向け大型鉄鋼構造物などの建造を、坂出工場はLNG船の建造で培った知見を生かした船舶運航管理支援システムやガス燃料供給システムの拡販を図る。
造船専業のJMUは、しばらくは初心に立ち返り、タンカーとバルカー(ばら積み船)、コンテナ船の「タバコ戦略」で急場をしのぐ考えだ。今年4月には、新造船の建造を行う5つの造船事業所の建造手法などを比較して生産体制を強化し、全社視点で生産の計画・実行を推進する生産センターも新設。効率化を急ピッチで行う。
株主であるJFEの経営陣は、いまや事あるごとに事業所の統廃合の必要性を語っている。これで恒常的な黒字体制を確保できなければ、2013年にユニバーサル造船とアイ・エイチ・アイ マリンユナイテッドが統合して以来、かたくなに保持してきた事業所の再編にいよいよメスが入ることになるだろう。
造船所の積極的な統廃合を行うために、再編の道を選ぶという選択肢については、「各社とも総論賛成、各論反対」(総合重工メーカー幹部)の情勢だ。むしろ、浮上の見通しが絶望的な長い造船不況下では、造船各社には、統廃合で一時的に抱える「過剰な設備能力」を恐れる風潮さえある。かといって、各社が自助努力で描くリストラ策には限界がある。
業界内の再編圧力と、自社完結の合理化策の手詰まり感は高まるばかり。再編か撤退か――。日の丸造船メーカーによるチキンレースが始まっている。
ダイヤモンド編集部/新井美江子



現在のフェリーを運航したら良いのでは?
内航船用に建造されたフェリーはフィリピンやインドネシアに売るしかないよ。ヨーロッパでは規則の要求を満足しないので買ってくれない。
韓国がインチキして運航すれば外国でも行けるフェリーになるかも?どの選択にしても昔のように良い価格で買ってくれないと思う。
無理して新造船に拘る必要はないのでは?
新しい船の建設を目指している宮崎カーフェリーは、今年中に船を発注する方針です。造船費用が当初の見込みを上回る中、宮崎市は、必要に応じて財政支援を検討する考えを示しました。
宮崎カーフェリーは、年内にも新しい船を2隻、発注する方針です。
造船費用は資材の高騰もあって、当初の想定を40億円上回る最大で180億円になる見込みです。
宮崎カーフェリーには県や宮崎市などが出資していて、市議会一般質問で宮崎市の戸敷市長は、次のように答えました。
(宮崎市 戸敷市長の答弁)
「会社自身による自己資金の確保が第一と考えています。その上で要請があれば、将来的な収支の見通しや県による支援の内容を踏まえまして、必要に応じて何らかの支援策を検討したいと考えています。」
造船費用は、県も必要に応じて財政支援を検討する方針を示しています。
宮崎カーフェリーでは、年内の造船発注に向け、県や宮崎市に対する支援要請の必要性を含め、資金の調達方法を協議しています。
TEXT BY AARIAN MARSHALL
駆逐艦の制御にタッチスクリーンを導入していた米海軍が、昔ながらの物理的なスロットル操作に戻すことを決断した。
米海軍海洋システム司令部が8月9日に発表した今回の決定は、駆逐艦を操縦する船員らがタッチスクリーン式の統合船橋・航海システムを十分に理解していなかったという調査結果に基づいている。この調査は米艦隊総軍と国家運輸安全委員会(NTSB)によるもので、2017年に発生したミサイル駆逐艦「ジョン・S・マケイン」と貨物船との衝突事故の一因が、統合システムの欠陥と誤った使用によるものであることが示されている。
米海軍協会ニュース「USNI News」の記事によると、タッチスクリーン式のシステムを物理的なスロットルに戻すには、18〜24カ月かかるという。
指摘されていたインターフェースの欠陥
一連のタッチスクリーンに起因する問題は、設計、テスト、訓練の3つが不十分という最悪の三拍子が揃ったことで発生したとみられている。17年の駆逐艦による事故後に数カ月かけて実施された米艦隊総軍の調査によると、船の操舵システムが改良されたばかりにもかかわらず、見張りに立った船員らが使用法の訓練をきちんと受けていなかったことが明らかになっている。
さらに調査によると、タッチスクリーン上で設定される制御や配色も「安全を重視すべき制御盤に関する業界のベストプラクティスに反していた」という。実際に操舵システムを使用していた乗組員たちがタッチスクリーンを利用せず、バックアップとして用意されていたトラックボールとボタンで操作することがあったことも明らかになっている。
国家運輸安全委員会の報告書でも、同じようにインターフェースの欠陥が指摘されている。さらにシステムのバックアップ用に用意されていたマニュアルモードについても問題があったことを強調していた。司令官のなかには、ドックへの出入りの際にマニュアル操作を積極的に利用する者もいたという。また、システムがマニュアルモードでコンピューターによる支援機能も併用していた際に、ほかの持ち場の後方にいる船員らが意図せず一方的に操舵の制御を引き継ぐことができていたことも、安全調査官の調査で明らかになっている。
デジタル化によるフラストレーションが蔓延
報告書では、ジョン・S・マケインと貨物船の衝突事故や2017年に西大西洋で相次いだ別の衝突事故について、別の要因の存在も指摘している。海軍による不十分なオペレーション、船の司令官の監督不備、そして乗組員のミスを招いた疲労の蓄積などだ。
海軍の内部調査によると、明らかに複雑なデジタルシステムによるフラストレーションが、海軍全体に蔓延していたようだ。「物理的なスロットルを取り上げられてしまった、という意見が海軍から最も多く寄せられていました。現場からは『われわれが使えるスロットルが欲しい』という声が出ていたのです」と、船のプログラムを統括する海軍少将のビル・ガリニスは最近の講演で語っている。
機械工学を専門とするデューク大学の博士研究員で、米海軍の航空母艦のシステム設計に注目してきたウェストン・ロスによると、こうした不満は決して新しいものではないという。「(海軍隊員は)レヴェルの低い技術を好む人の集団になりがちです。というのも、そういった技術はどんなときでも機能するからです」と、彼は言う。
米海軍海洋システム司令部広報官のコリーン・オルークは、海軍は「水上艦のブリッジの設備の構成を共通化していく方向に向かっている」と説明している。これによって船員らによるシステムの操作だけでなく、海軍による訓練も容易になる。

<2019年8月31日号> 中国政府が、国有企業同士の統合による巨大化を進めている。7月2日、造船関連の国有企業である中国船舶工業集団(中船集団)と中国船舶重工集団(中船重工)の戦略的再編計画が明らかになった。両社はそれぞれ中国造船業の1位と2位で、統合すれば、売上高4200億元(1元=約15円)、総資産8100億元の巨大企業となる。総資産では、同じく統合が計画されている韓国の現代重工業と大宇造船海洋の合計の2倍を超える見通しだ。
[シンガポール/クアラルンプール 16日 ロイター] - リフィニティブおよびベッセルズ・バリューの船舶追跡データによると、中国企業が所有する超大型原油タンカー(VLCC)「パシフィック・ブラボー」がマラッカ海峡に向かう途中のインド洋沖合で6月5日、船舶の位置などを示すトランスポンダー(無線中継機)のスイッチが切られ、追跡できなくなっていたことが分かった。
米政府は、パシフィック・ブラボーがイラン産原油を積んでおり、米国の対イラン制裁に違反するとして、アジアの港湾都市に対し同船を寄港させないよう警告していた。VLCCは一般的に約200万バレルの石油を輸送する。[nL4N2343JL]
その後、7月18日にVLCC「ラテン・ベンチャー」のトランスポンダーがマラッカ海峡に面したマレーシアのポートディクソンで作動した。ポートディクソンはパシフィック・ブラボーが最後に位置を示した地点からおよそ1500キロメートル離れている。
ただ、船舶追跡データによれば、ラテン・ベンチャーとパシフィック・ブラボーが発信した国際海事機関(IMO)の船舶識別番号は「IMO9206035」で一致。IMOの識別番号が変更されることはないため、ラテン・ベンチャーとパシフィック・ブラボーは同一のタンカーであり、所有者が米国の対イラン制裁の回避を試みた可能性がある。
オンライン船舶サイト「イクエーシス」のデータによると、タンカーの所有者は上海を拠点とするクンルン・ホールディングスで、シンガポールにもオフィスを構えている。オフィスに電話で問い合わせたが応答はなかった。
追跡データによると、パシフィック・ブラボーとして航海中の貨物タンクは満杯だったが、42日後にラテン・ベンチャーとして現れた際には空だったという。
タンカーの石油が積み下ろされた地点は確認できていない。
マレーシア当局の発表によると、ラテン・ベンチャーは6月29日にポートディクソンに入港し、乗組員を入れ替えた後、7月18日に出港した。ただ貨物の積み下ろしはなかったという。
船舶追跡データによると、ポートディクソンを出港後、タンカーはシンガポールを通過し、マレーシアの南東海岸に寄港。7月25日のデータでは貨物タンクがほぼ満杯となり、8月14日時点では同地点に停泊中という。
By Roslan Khasawneh and A. Ananthalakshmi
SINGAPORE/KUALA LUMPUR (Reuters) - While in the Indian Ocean heading towards the Strait of Malacca, the very large crude carrier (VLCC) Pacific Bravo went dark on June 5, shutting off the transponder that signals its position and direction to other ships, ship-tracking data showed.
A U.S. government official had warned ports in Asia not to allow the ship to dock, saying it was carrying Iranian crude in violation of U.S. economic sanctions. A VLCC typically transports about 2 million barrels of oil, worth about $120 million at current prices.
On July 18, the transponder of the VLCC Latin Venture was activated offshore Port Dickson, Malaysia, in the Strait of Malacca, about 1,500 km (940 miles) from where the Pacific Bravo had last been signalling its position.
But both the Latin Venture and the Pacific Bravo transmitted the same unique identification number, IMO9206035, issued by the International Maritime Organization (IMO), according to data from information provider Refinitiv and VesselsValue, a company that tracks ships and vessel transactions. Thomson Reuters has a minority stake in Refinitiv.
Since IMO numbers remain with a ship for life, this indicated the Latin Venture and the Pacific Bravo were the same vessel and suggested the owner was trying to evade Iranian oil sanctions.
"Without speculating on any particular shipowners' actions, generally speaking for a ship to change its name abruptly after receiving accusations from the U.S., it can only be that the owner is hopeful that the market will be deceived by something as rudimentary as a name change," said Matt Stanley, an oil broker at StarFuels in Dubai.
The Latin Venture oil tanker shut off its transponder from early June to July 18 - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/7/5922/5905/LatinVentureTransponder.png
The vessel is owned by Kunlun Holdings, which, according to data from Equasis.org, a shipping transparency website set up by the European Commission and the French Maritime Administration, is based in Shanghai. The company also has an office in Singapore.
Calls to the company's offices were unanswered.
Latin Venture status and location on Refinitiv Eikon - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/ce/7/5921/5904/LatinVentureLatest.png
While operating as the Pacific Bravo, the ship's transmission data showed that its cargo tanks were full before it turned off the transponder. When it reappeared 42 days later as the Latin Venture, it was empty, according to Refinitiv and VesselsValue data.
Reuters was not able to ascertain where or if the oil onboard the Latin Venture was offloaded.
According to a statement from the Marine Department Malaysia, the Latin Venture entered Port Dickson on June 29 for a crew change and departed on July 18. The statement said that no cargo was discharged.
The United States reimposed sanctions on Iran in November after pulling out of a 2015 accord involving Tehran and six world powers that limited Iran's nuclear programme. Aiming to cut Iran's oil sales to zero, Washington in May ended sanction waivers given to some importers of Iranian oil.
Iranian officials were not immediately available for comment.
While it was not aware of this particular situation, China has always opposed unilateral sanctions and "long-armed jurisdiction", a Chinese Foreign Ministry spokesperson said in response to a Reuters request for comment.
"The global community, including China, is legally engaged in normal co-operation with Iran within the framework of international law, which deserves to be respected and protected," the spokesperson said.
Responding to a Reuters request for comment on its reaction to the name change, a U.S. State Department spokesman said on Aug. 1: "We do not preview our sanctions activities, but we will continue to look for ways to impose costs on Iran in an effort to convince the Iranian regime that its campaign of destabilising activities will entail significant costs."
After departing Port Dickson, the tanker sailed past Singapore to the southeastern coast of Malaysia and on July 25 it transmitted that its cargo tanks were nearly full. As of Aug. 14, the ship remains there, ship-tracking data shows.
The origin of the oil cargo could not be determined.
The track of the Latin Venture vessel from Iran to Malaysia - https://tmsnrt.rs/2N3eZcE
(Reporting by Roslan Khasawneh in SINGAPORE and A. Ananthalakshmi KUALA LUMPUR; additional reporting by Muyu Xu in BEIJING, SHANGHAI and BEIJING bureau, Jane Chung in SEOUL and Jonathan Saul in LONDON; editing by Christian Schmollinger)
【AFP=時事】国際社会の制裁に違反してシリアに石油を運んでいたとして英領ジブラルタルが拿捕(だほ)した後、解放を決めたイランの大型石油タンカー「グレース1(Grace 1)」に関し、米司法省は16日、同タンカーを差し押さえるための令状を取得したと発表した。
動画:ジブラルタル、イランのタンカー解放命令 米国の要請に反し
令状は、国際緊急事態経済権限法(IEEPA)と、銀行詐欺、マネーロンダリング(資金洗浄)、テロに関わる資産の没収を定めた法規への違反を根拠として、グレース1と積み荷の石油全量、現金99万5000ドル(約1億600万円)の没収を認めている。【翻訳編集】 AFPBB News
【ロンドン時事】1912年に大西洋で氷山と衝突して沈没し、1500人以上が死亡した豪華客船タイタニック号を建造した英国の造船所が5日、事実上破綻した。国際競争の激化で経営が行き詰まり、あえなく沈んだ。英メディアが一斉に報じた。
既に会計事務所を管財人に指名し、6日に裁判所に破綻を正式申請する。造船所の親会社が身売り先を探してきたが、期限の5日夕までに見つからず、自主再建を断念した。
この造船所はハーランド・アンド・ウルフ社。英領北アイルランドのベルファストで1861年に創業。最盛期には3万人以上を雇用した。第2次大戦後は船舶の保守・修理などに活路を見いだし事業を継続。現在の従業員は約130人という。
By Guest Author
Several dubious practices are employed by bunker fuel suppliers during a typical bunker stem operation. These malpractices are more prevalent in Asian ports than in those of North America or Europe. Having said that no matter which part of the world the vessel is fixed to stem bunkers, the importance of accurately measuring the barge fuel tanks before and after delivery is a crucial phase in any bunker stem operation. It is therefore very important that the vessel’s bunker operation team methodically take the barge tank measurements, applying the correct trim/list before and after bunkering, recording the actual temperature of the bunker fuel before/after delivery etc. Proper temperature measurement alone can save thousands of dollars!
Disputes can arise either by innocent mistake or deliberate short supply by the barge; like introducing air to froth up the fuel (cappuccino effect) or giving incorrect temperatures and so on. Also when bunker is being transferred from a refinery to a storage tank and to the barge and then delivered to the vessel, there is a lot of scope for errors and deliberate manipulations that will result in a difference (sometimes quite significant) between the quantity claimed to have been supplied and the quantity received by the ship. If this is due to an innocent mistake then probably with fullest co-operation of the barge company/ fuel suppliers and full disclosure of stock movement records might indicate the “missing” bunker.
However, often this is not the case and experience tells us that when disputes do arise over quantity transferred, any ‘post-delivery’ investigation on quantity shortages are often inconclusive especially if the shipboard personnel involved in bunkering operation have neglected the basic principles of safeguarding it’s owners/charterers’ rights in way of collecting and preserving evidence. Protests, legal fees, etc. all add on to costs with usually neither party actually concluding with certainty what transpired on board. A success of any bunker dispute claim will largely depend on the detailed contemporaneous written evidence by the shipboard personnel at the time the supply is made.
Considering the present bunker fuel prices we deem “bunker stem survey” absolutely necessary, in order to make sure that the quantities as mentioned on the Bunker Delivery Note (BDN) are true and correct. However, there are many ship operators who leave the above procedure to the Chief Engineer to save on survey cost with the vessel often ending up with an incorrect supplied quantity and a commercial loss of thousands of dollars for the operators.
It is important to note that when a surveyor is appointed by the charterers / owners to oversee the stemming operation, the Master/Chief Engineer is still in charge of ensuring proper steps have been taken to prevent such malpractices and that the surveyor should be assisting and working under the Chief Engineer’s supervision and not the other way around.
‘Unfortunately ‘stealing bunker fuel’ for profit due to increasing fuel prices is here to stay for a long time to come’.
Loss prevention during bunker stemming largely depends on the hands-on approach and practical experience of bunker surveyors and AVA Marine’s exclusive division “Bunker Detective” is able to offer these ‘Bunker Stem Surveys’ to ship owners and charterers globally.
The guidance mentioned in this article should not be construed as exhaustive and is aimed primarily for vessel operators and ship owners to educate their shipboard personnel for better detection and prevention of these malpractices for occurring in the first place.
What the ship owners and operators need to know:
The ship owner and the charterer both have the responsibility for the provision of bunkers – in a time charter the charterers will provide bunkers whereas in a voyage charter the owners will normally supply bunkers. Therefore it is important for both the owners and the charterers to be aware of the tricks of the
Tricks of the Trade:
1. Understanding the Fuel Density & Weight Relationship
Marine fuel is always sold by weight (mass) and delivered by volume. Hence for this reason bunker receipts must always be signed “For Volume Only” and adding the words “weight to be determined after testing of the representative sample”. Never sign for weight if uncertain about the density.
What many bunker surveyors do not realize is that the density given in the supplier’s bunker delivery note (BDN) may not be true and thus the weight determined by calculation should be considered as the ‘preliminary’ weight of the fuel transferred to the vessel. The actual weight is only determined after the density is verified by an independent fuel testing authority and then factored into the final recalculation of the actual weight of the fuel delivered onboard. That is why we always stress the importance of accurately obtaining bunker samples both onboard the vessel and the barge.
Once the samples are dispatch to the vessel’s chosen independent fuel testing laboratory we request the copy of the Fuel Test Reports so that revised bunker survey report can be sent to the client. Below is typical scenario of how density can affect the weight of fuel transferred on board.
A ship owner/charterer has a fleet of 20 vessels bunkering an average of 1000 MT each month.
table 1
Now imagine a charterer operating a fleet of 50, 70 or 100 vessels – the commercial loss would be value in millions of dollars every year!
Key Notes:
•If the density of fuel cannot be verified onboard or independently verified at the time of bunkering, the BDN should be signed only for ‘volume’ and not for weight
•Remember whenever in doubt or have concerns always issue a letter of protest
2. Understanding the Fuel Temperature & Volume Relationship
Petroleum products have a high rate of thermal expansion which must be taken into account when several thousand tons are transferred or purchased. The barge will often try to under-declare the temperature during the opening gauge and over-declare during the closing.
This malpractice is quite common in day to day bunkering and therefore we always ask the ship officers responsible for bunkering operations to be extra vigilant and check the temperatures of all bunker tanks during the opening gauge and thereafter periodically check and record the temperature of the fuel as it is pumped onboard. The temperatures should be checked both at the barge and the ship’s manifold. If temperature gauges are provided it would be prudent to take photographs where permissible.
The barge will often try to under-declare the temperature during the opening gauge and over-declare during the closing. Always verify temperatures of all bunker tanks during the opening gauge and thereafter periodically check and record the temperature of the fuel as it is pumped onboard. The temperatures should be checked both at the barge and the ship’s manifold and average of all the readings taken during final calculations. If temperature gauges are provided it would be prudent to take photographs where permissible.
Also note that the existing flow measurement systems will have a separate temperature and pressure gauges where these could easily be tempered with or gauges not being accurate like non-aqueous liquid filled gauges with glycerine and silicone oils often seen with broken sight glass. The whole purpose of a liquid filled gauge is for the liquid to absorb vibrations, thus providing a dampening effect to enable accurate readings and also to reduce wear and tear by lubricating all moving parts – in other words this affects the integrity and reliability of the gauge readings over time.
There have been cases where the glass in the mercury cup case thermometer is gently heated to create a bubble effect to prevent the correct registering of the temperature of the fuel oil. This malpractice could be illustrated by the following example:
Within a large fleet the loss could run into millions of dollars a year!
Key Notes:
• Always check and record the temperatures of the fuel tanks before and after and periodically during bunkering operation
•Carry own infra-red laser temperature gun as a part of your equipment
•Remember whenever in doubt or have concerns always issue a letter of protest
3. The Cappuccino Bunkers: (also sometimes known as the Coca Cola Effect)
This essentially may be described as frothing/bubbling effect caused by compressed air blown through the delivery hose. The aerated bunkers when sounded will give the impression that the fuel is delivered as ordered. In fact after sometime when the entrapped air in suspension settles out of the fuel oil the oil level drops and a short fall is discovered. In large bunker deliveries this could be considerable with huge financial implications. Know more about Cappuccino Bunkers here.
We have often been asked why the flow meter cannot detect the air being introduced in the system and compensate accordingly. Well, most flow meters in use today are of either the wrong type or the wrong size. In other words are not technologically advanced. All the standard flow meters will only measure the volume of throughput and not the actual mass of fuel being delivered. As a result when is air introduced into the system, which is essentially ‘small air bubbles’ – the flow meter will register it as volume.
However, there are flow meters out in the market which are capable of measuring the true quantity (mass) of the fuel delivered. One such meter is the ‘Coriolis Mass Meter’ – it has been in existence for quite some time now and only getting better. Coriolis meters take direct mass flow measurements using the Coriolis Effect (a deflection of moving objects when they are viewed in a rotating reference frame –we won’t be discussing this effect as this is beyond the scope of this article). Coriolis meters are less sensitive to pressure, temperature, viscosity, and density changes, allowing them to measure liquids, slurries and gases accurately without the need for compensation. These meters having no moving parts require little maintenance however, the initial cost and line modifications is usually a deterrent for many ship operators for not installing it.
Precautions against Cappuccino Bunkers:
Before Fuel Transfer
At the time of opening gauge fuel oil should be observed from ullage hatches for any foam on the surface of the bunkers. Foam may also be detected on the ullage tape. If there is no foam then the oil level on the tape should appear distinct with no entrained bubbles. If by observation of the tape and the surface of the fuel you suspect entrained air then obtain a sample of the fuel by lowering a weighted bottle into the tank. Pour the sample into a clean glass jar and observe carefully for signs of foam or bubbles.
If these observations show entrained air the Chief Engineer should not allow the bunkering to start and notify the owners / charterers immediately. The barge Master should be issued with a letter of protest and a copy sent to the ship’s agent. If the barge Master decides to disconnect from the ship and go to another location then the agent should immediately inform the port authority and try to establish where
the barge has gone. All relevant times and facts should be recorded in the deck log book.
During Fuel Transfer
If the Chief Engineer has not observed any entrained air during the initial barge survey it is still possible that air can be introduced to the barge tanks or the delivery line during the pumping period for example by introducing air into the system by crack opening the suction valve of an empty bunker tank while pumping from other tanks. Hence it is important for the Chief Engineers to continue gauging the ship’s receiving tanks while the bunkering is in progress as air bubbles would be readily seen on the sounding tape.The Singapore Bunkering Procedure SS 600 prohibits the use of compressed air from bottles or compressors during the pumping period or during stripping and line clearing. It should be confirmed with the barge Master that he will follow this procedure (Reference SS600 paragraphs 1.12.10/11/12/13).
Stripping of barge tanks can also introduce air and stripping should only be performed at the end of the delivery for a short period of time. The barge Master must agree to inform the Chief Engineer when he intends to start stripping and when it has been completed.
Ship’s crew and surveyor need to be alert during bunkering and check for the following signs:
•Bunker hose jerking or whipping around.
•Gurgling sound when standing in vicinity of bunker manifold.
•Fluctuations of pressure indication on manifold pressure gauge.
•Unusual noises from the bunker barge
After Fuel Transfer
It is also possible to introduce air into the delivery line during blowing through at high pressure. Therefore it is imperative that the barge informs the ship before and after blowing through is completed so that the ship crew can be extra vigilant during this period.
The ship’s bunker manifold valve should be checked shut before gauging of the vessel’s tanks.
Key Notes: (IDENTIFYING CAPPUCCINO BUNKERS)
•Signs of froth/foam on the surface of the fuel in the barge tanks during opening gauge
•Excessive bubbles on the sounding tape prior to, during and after bunkering
•Bunker hose jerking or whipping around
•Slow delivery rates then what has been agreed
•Gurgling sound in vicinity of bunker manifold
•Fluctuations of pressure on manifold pressure gauge.
•Unusual noises from the bunker barge
Note that hose jerking or evidence of sporadic bubbles superficial in nature after line blowing or stripping of tanks is fairly common and should not be construed as evidence of malpractices.
4. Fuel Delivered with High Water Content
Traces of water in bunker fuel are normally very low about 0.1-0.2% by volume. ISO 8217:2010 Fuel Standards for ‘Marine Residual Fuels’ gives the maximum allowable water content to be 0.5 % v/v.
Water can originate from number of sources like heating coil damage causing leakages and tank condensation; however deliberate injection cannot be ruled out. In case large quantity is found then a letter of protest should be issued immediately. However, the exact quantity of water can only be determined after the settlement phase where the water would have settled down at the bottom of the
Key Notes:
•High water content causes other issues like removal costs to ashore if the OWS (Oily Water Separator) onboard is not able to filter it out and also reduces the fuel’s specific energy
•Fuel samples provided by the barge may not have any traces of water as the samples may have been taken prior to bunkering and mixing of water. Always ensure that the fuel samples are collected during bunkering and not before or after. For these reasons never sign labels in advance or sign for samples of unknown origin. Samples should only be signed for those actually witnessed.
•Use of water-finding paste on the sounding tape is good for distillate fuels only and does not work with residual fuels. Even incorrect type of ‘water-detecting’ paste could be used.
•On-site testing should be done for water-in-oil test. It may be not viable for the ship operators to invest in high end equipment for such purposes but as a minimum the vessel should be able to test a bunker representative fuel sample for water, test for density and compatibility
•Remember whenever in doubt or have concerns always issue a letter of protest
05. Inter-tank Transfers (gravitating of fuel)
During opening gauge the fuel could be transferred from high level to a low level (or empty / slack tank) by gravity. For example a barge may have four tanks 1P/1S, 2P/2S, 3P/3S and 4P/4S. The opening gauge starts from say aft tanks 4P/4S. While the gauging is underway, the tank level of 4P/4S could be easily dropped under gravity to a slack or empty tank forward say 1P/1S. Thus essentially the same fuel quantity is measured twice. This method is still in use and if not detected the barge can claim that full quantity was delivered to the vessel but the vessel will have a substantial shortfall. Once the bunkering has commenced it is too late to do anything and it will be virtually impossible to trace the ‘missing’ fuel. A thorough investigation will be needed to determine the exact stock control quantity and full disclosure from the supplier which can take many months/years of legal action and still the matter may not be resolved. Read more on gravitating of fuel here.
It is imperative that the attending surveyor or vessel’s representative re-gauges the tanks in the following sequence:
If the initial gauging was forward to aft, then after gauging the last aft tank; the surveyor or vessel’s representative should re-gauge all tanks from aft to forward. The readings should be exactly the same.
As an additional precaution, at the commencement of bunker transfer, the surveyor or vessel’s representative should re-gauge the first tank(s) used to transfer oil to the vessel. The reading should match that taken during the initial gauging.
Key Notes:
•The only effective way of dealing with this dubious practice is re-sounding the tanks as above before bunkering commences
•Remember whenever in doubt or have concerns always issue a letter of protest
6. Flow meter/Pipe work Tampering
Bunker barges fitted with a flow meter should be checked for proper functioning by sighting a valid calibration certificate and ensuring the seal is intact.
There may also be unauthorised piping (by-pass lines) fitted to the flow meter running into the pump suction side and thus this unauthorised contraption will register the throughput of fuel twice through the flow meter.
Key Notes:
•Verify flow meter seal is intact
•Verify validity of the calibration certificate and that it is for the same type flow meter
•Look out for any suspicious by-pass lines running after the flow meter
•Consult the barge piping diagram if in doubt
•Remember whenever in doubt or have concerns always issue a letter of protest
7. Quantity measurements by flow meter only
The barge may claim that the soundings and ullage ports have been sealed by customs or seized or some other reasons and therefore force the vessel to go by the volumetric flow meter only.
Remember that this may be just the first sign of an unscrupulous barge Master as such we wary of other tricks of trade.
Key Notes:
•Never agree and go by the flow meter only fuel delivery
•Remember whenever in doubt or have concerns always issue a letter of protest
8. Pumping / Mixing Slops into Bunkers
Though we seldom come across this now because of tighter sampling procedures in place but introducing slops and thus contaminants into the fuel delivery will reduce the actual fuel amount and also can create engine problems down the line. Unfortunately this cannot be detected until the representative fuel samples have been tested by an independent fuel testing facility.
A typical scenario where this malpractice would be carried out is after an argument over short supply; the barge would pump in sludge / water to make up for the short supply. As the sample collection would have been completed; it is therefore imperative that if allowed a second pumping re-sampling is done both on the barge and the vessel.
Key Notes:
•Always witness and collect samples by continuous drip method i.e. the sample to be drawn continuously throughout the bunkering delivery period
•It should be a practice onboard to isolate the fuel delivered to separate tanks and not to be consumed until such time the fuel testing report gives a clean bill of health
•In case of second pumping re-sampling should be carried out both on the vessel and the barge to ensure no contaminants like sludge/water is been delivered to the vessel
•Fuel contamination amongst other things can create problems with the fuel injection system and exhaust valves with costly repairs
•Remember whenever in doubt or have concerns always issue a letter of protest
9. Questionable Tank Calibration Tables
Verify that the sounding / ullage tables are approved by the Class (Class Certified – with endorsement). Having more than one set of sounding book is not uncommon and having the tables modified to the supplier’s advantage is always a possibility. Inserted pages, corrections, different print/paper type are all indications of tampering. Sometimes the barge may have a new calibration table (with the old one being obsolete). This could be following modification of the tanks internal structure during a dry dock repair or simply because the original calibration tables would have been incorrect. Always find out the reason for new calibration table and making sure it’s Class Certified.
The same could be said for the list / trim correction tables which could be easily modified again to the supplier’s advantage.
Key Notes:
•Look for Class Approved calibration tables with endorsement
•Remember whenever in doubt or have concerns always issue a letter of protest
10. Tampering with Gauging Equipment
Always verify the condition of sounding tape. Sounding tapes could be tampered with in many ways:tampering with gauging element
1.Deliberate altering of sounding tapes and using wrong size of bobs
2.Sounding bobs from tapes that have been switched over
3.Cutting the tape and re-joining resulting in non-linear tape
Key Notes:
•Check for calibration certificate for the gauging equipment in use
•Use a ruler to ascertain the precise sounding/ullage when below the 20 cm mark
•Use own sounding / ullage tapes
•Pay particular attention to ‘millimeter’ soundings especially when the tanks are full and taking ullages as small errors will have a big impact on the total bunker quantity.
•Remember whenever in doubt or have concerns always issue a letter of protest
11. Empty Tanks -Unpumpable Fuel (Zero Dip Volume Application)
In an event of a short delivery be wary that empty tanks may not be empty even with zero dip and that substantial pumpable may exist. Verify the tanks claimed to be empty – don’t take the supplier’s word for it.
Zero dip volume application principle – The bunker surveyor or the vessel representative should notify the barge representative that the zero dip volume of the tank(s) shall be included in the bunker tanker calculations. The condition shall deemed to apply when the closing gauge would indicate no oil cut whereas the visual inspection of the bunker tanker cargo tank indicate free flowing oil at the aft of the tank. To avoid zero dip volume application, sufficient bunkers should be retained in cargo tanks such that it touches all four sides of the tank.
To apply zero dip correction – it is assumed that the tank is rectangular where the sounding is not constrained by a sounding pipe – i.e. sounding should be taken in an “open sounding” position (from the hatch) where the sounding tape bob is free to travel with the trim of the barge and not restricted by the sounding pipe. However, if the tape is used inside a sounding pipe this correction would be invalid.
Liquid cargo should only be trim and/or list corrected if the liquid is in contact with all bulkheads. When the liquid is not in contact with all bulkheads, a wedge correction should be applied.
no wedge
wedge exists
*Cut – The oil level on the tape or bob or the water level marking on a tape or bob coated with water indicating paste. “Taking a cut” is taking a measurement of the oil or water level.
Key Notes:
•Do not assume any tanks to be empty even when reaching stripping level
•Check tank calibration tables to verify the unpumpable
•Apply correct list / trim corrections during calculations
•Remember whenever in doubt or have concerns always issue a letter of protest
12. Inflated / Deflated Tank Volumes
Level of oil on the tape / bob should be clearly identifiable (same colour and viscosity as the rest of the oil in the tank).
Soundings can be inflated during opening gauging by pouring diesel oil into the sounding pipe just before gauging.
sounding
Another method of inflating the sounding is high pressure compressed air being injected directly into the sounding pipe, pressurizing the pipe and thus causing the level of oil to rise giving a higher reading without even frothing or creating bubbles. This would be done en-route to the vessel just before delivery.
The reverse is true – that is the soundings can be deflated during closing gauging by pouring copious amount of paint thinner into the sounding pipe just before gauging. The thinner washes off the oil level marking on the sounding tape to indicate less oil.
Key Notes:
•Always check the level of on the sounding tape and if in doubt re-gauge the tank
•Remember whenever in doubt or have concerns always issue a letter of protest
13. Under-Declaring actual ROB and Deliberate Short-Supplying of Fuel
Why it is important for the ship operators to ascertain the exact fuel quantity onboard prior stemming bunkers?
The malpractices during bunkering operations which we see and hear about though quite prevalent with bunker suppliers; but on many occasions we have come across situations where the receiving vessel will be as much as involved as the supplier in these dubious practices. Often we have found that the vessel would under-declare fuel quantity which is then either sold back to the barge supplier or simply kept hidden on the vessel until an opportunity comes along to profit from this.
For example: An order for 1000 metric tons of FO is placed at the next bunkering port – the vessel has an excess of 50 metric tons (un-declared). Now when the supply barge comes alongside (through prior negotiations) the vessel would deliberately short-receive (or barge will deliberately short-supply) 50 tons.
In other words the actual supplied quantity would be 950 tons but on the BDN it would be reported as 1000 tons and the operator will be invoiced based on this BDN quantity. The short-received (or short delivered bunker) profit will be shared between the supplier and the vessel. In the end it is the operator who is affected – suffering the loss twice (50 tons + 50 tons).
Contributing factors for the loss:
•Too much reliance on the vessel’s staff
•No bunker stem audits are conducted which involves elaborate detective work carried out by independent third party surveying firms
•Ignoring non-nominating (non-receiving) tanks to be included in the overall tank measurements during stem operations
•Most shipping companies will engage the services of an independent surveyor to protect their interest in case of a large discrepancy in the final figures between the barge and the vessel; however, how many companies actually give clear instructions to the attending surveyor to measure all non-nominated tanks (non-receiving tanks)? Or how many surveying firms actually carry out the measurements diligently? Failing to do so leaves the operator vulnerable as explained above.
This is further illustrated as follows:
scenario 1
The excess 53 MT of fuel oil will be in favor of the owners with a loss to the charterers
scenario 2
Key Notes:
•Carry out regular ‘bunker stem audits’ – in a large fleet this is an indispensible loss control tool
•Measure all non-nominated tanks prior to stemming operations and again after bunkering is completed
•Always engage the services of a reputable bunker stem surveying firm during stem operations.
About Bunker Detective:
Bunker Detective is an exclusive division of AVA Marine Group Inc. AVA Marine is a professional marine surveying and consultancy firm – founded and led by its principal marine surveyor Kaivan H. Chinoy. The Company provides a comprehensive range of specialist marine surveying, marine loss control & consultancy services primarily in Western Canada and the West Coast of the United States. To learn more about their marine surveying capabilities, visit the website at ava-marine.com / bunkerdetective.com
Special thanks to Kaivan H. Chinoy From Bunker Detective for giving us permission to reproduced this article.
Disclaimer: This article is based on the author’s own research, knowledge and experience in the subject matter and references used from various P&I LP bulletins and should only be used for reference rather than being taken as a legal
advice for any particular case or used for any other purpose.
Over to you..
Cecilia Müller Torbrand, Executive Director, MACN, says: “MACN’s experiences in locations including Nigeria, the Suez Canal, and Argentina show us that real change is possible when all parties are engaged. That’s why we are delighted to have the support of so many key stakeholders for this Campaign to improve the operating environment in Indian ports.”
The Ministry of Shipping, India, stated: “We are committed to ensuring that vessels calling port in India do not face unnecessary obstacles or illicit demands. Tackling these issues is good for the shipping industry, for port workers, and for India as a trade destination. We are pleased to be joining forces with MACN and other stakeholders to implement concrete actions with the potential for real impact.”
国内造船所が新造船手持ち工事量の減少に苦しんでいる。日本船舶輸出組合によると、5月末の新造船手持ち工事量は482隻約2385万総トンと、2000年以来19年ぶりの低水準だった。邦船社の発注停滞の長期化に加え、海外船主の発注意欲も鈍化。環境規制への対応と鋼材価格の上昇で船価が上がり基調にもかかわらず、用船料の低迷持続でミスマッチが広がっており、営業担当者は焦りを募らせている。「受注環境が本当…
フィリピンの海運・物流大手チェルシー・ロジスティクス(CLC)は24日、中堅造船会社の福岡造船(福岡市)と貨客船の購入契約を締結したと発表した。契約額は明らかにしていない。2021年6月に納入を受ける予定だ。
購入するのは、全長123メートルのRORO船(トラック等の車両が直接乗り入れることができる船)。乗客定員は1,085人で、乗客が増え続けているビサヤ、ミンダナオ両地方の需要に応えられるという。バスとトラックの積載台数は最大でそれぞれ24台、11台となる。
CLCのクリス・ダムイ社長は「創業70年以上の歴史を持つ、福岡造船の技術は信頼に値する」とコメント。福岡造船との長期的な協力関係を築きたい考えを示した。
福岡造船の担当者は25日、NNAに対し、受注額については公表していないと説明。今後の受注見通しについてはコメントを控えた。
「国内の港を巡るため、自宅に帰らないまま船上での生活が数カ月続くなど特有の勤務形態が敬遠されているからだ。」
確かに特有の勤務形態が理由かもしれないが、陸での生活が向上し快適になっているにも関わらず、船での生活は大きく変わらない事も理由だと思う。
ただ、改善=コストに繋がるので人材難を認識しているが、変える事が難しいと思う。
昔の船員と今の船員の体格に大きな変化があるのかわからないが、内航船は限られたスペースにいろいろを詰め込んだ感じなので身長が高い人にとっては暮らしにくいと思う。造船所の設備を含め、古いものが多いので、造船所での修理や検査による滞在は快適とは思えない。
束縛に関して問題がないの人であれば、ブラックな会社で働くよりは時間の流れが遅いので良いかもしれない。ただ、小さい会社は当たり外れが大きいと思うし、情報が出回らないので、情報を知らない人にとっては暗闇の世界かもしれない。
外国人船員を受け入れれば、確実に急速に日本船員はいなくなるであろう。それを仕方がないと思うのか、やはり日本人船員が必要と思うのか、判断する人次第であろう。外航船では英語が使用言語になっているケースが多く、英語でのコミュニケーションがほとんどであるが、内航船では現場で働いている日本人達は英語を話せないので、船員同士のコミュニケーションの問題、そして現場の作業に関わる人々とのコミュニケーションの問題があるので、外国人船員を使うようになれば、当分の間、事故が多くなるであろう。
また、単純に船と言っても種類が変われば、要求される知識や経験、そして、現場でやる仕事が違う。コンテナ船などは比較的に外国人でも可能かもしれないが、他の種類の船では難しい可能性が高い。
まあ、単身赴任の人達が多くいるのだから、家族と一緒に生活していないから船員の仕事がだめなのだと考えるのは間違っていると思う。結局は、メリットとデメリットを考えて、船員の仕事でも良いかと思えるかどうかだと思う。
原材料や工業製品などを運搬する内航海運業界が人手不足に危機感を募らせている。国内の港を巡るため、自宅に帰らないまま船上での生活が数カ月続くなど特有の勤務形態が敬遠されているからだ。規制で外国人が雇えないこともネックになっている。経済への影響も心配され、国も対策に乗り出している。
3月中旬、名古屋港に由良機船(名古屋市)の貨物船が着岸し、建築用の木材を大型クレーンで次々と降ろしていた。広島県呉市で積み込み、岡山、大阪、名古屋、静岡、千葉と回る輸送の途中だ。茨城県の鹿島港で新たに木材を積んで逆に進む。3カ月このルートを繰り返す間、船員は船で寝泊まりし、その後1カ月休む。山下真次船長(53)は「人手が足りず作業量が多くなり、20代が入社しても数年で辞めることが多い」と嘆く。
国土交通省によると、内航海運(フェリーを含む)の船員は1970年代のピーク時に7万人を超えていたが…
フィリピンの海運・物流会社チェルシー・ロジスティクス・アンド・インフラストラクチャー(CLC)は5月29日、日本船主くみあい船舶(本社・東京)と新造船建造の資金調達に関する戦略的協定を締結したと発表した。くみあい船舶の子会社がCLC子会社のスターライトフェリーの新造フェリー「S-1191」を保有、BBC(裸用船)契約でスターライトフェリーに再貸船する。BBC契約期間は20年間。くみあい船舶…
国土交通省九州運輸局は5月10日、船員法などの関係法令に違反し、累積ポイントが基準を超えた違反船舶の所有者を公表した。
今回、違反船舶所有者として公表されたのは、貨物船「第三廣良丸」を所有する(有)山本海運(鹿児島市)で、発航前の検査や適切な航海当直などに関する違反が確認されたため、3月19日付で行政指導にあたる戒告処分を受けた。
九州運輸局によると、今年3月16日、同船が鹿児島県の港で他船に衝突。海上保安庁の取り調べで同月14日に同船が座礁していたことが判明したという。同社は事故発生後、関係機関への報告を怠っていた。
船舶所有者が公表されたのは、船員法などの違反に対する累積ポイントが120ポイント以上となったため。
【東城 洋平】
「an IMO code of anti-corruption best practices」に関して「Corruption(汚職)」と処分に関して明確に記載されなければないよりまし程度にしかならない。また、「Corruption(汚職)」の定義や適用範囲が明確でなければ実際には処分される事はないと思う。例えば、賄賂を貰わなくても、仕事を取るために便宜を図る、検査を簡単にする、又は、問題に目を瞑る事が「Corruption(汚職)」に含まれなければ、穴の開いたざるの規則になる事は予測できる。
お金さえ払えば国際条約で要求される証書を発給してもらえる、規則を満足しなくても良い。PSCによる検査を受けても出港停止を受けるような結果にはなかなかならないのが現実。
極端な例で言えば、モンゴル籍船、
カンボジア籍船、
シエラレオネ籍船、
グルジア籍船、
キリバス籍船、
トーゴ籍船、そして
パラオ籍船などに承認された検査会社や旗国の監督に問題があることを考えれば、かなりしっかりやらないと大きな改善は期待できない。期待していないのなら出来るだけ規則を守ろうとする旗国や人間達がばかを見る。
現代(ヒュンダイ)重工業が大宇(テウ)造船海洋の買収を推進するなど造船業の再編の最中だが、中型造船会社は仕事不足で生存を心配せざるを得ない境遇だ。産業銀行や輸出入銀行など国策銀行が将来的窮状を憂慮し、中型造船会社の構造調整に消極的だという指摘も出る。
7日、輸出入銀行海外経済研究所によると昨年中型造船会社の受注実績(物量基準)は54万7000CGT(標準貨物船換算トン数)で前年より26.2%減った。金額でも13.6%少ない10億8000万ドル(約1063億円)に留まった。
現代重工業と大宇造船海洋、サムスン重工業の造船「ビッグ3」を含む韓国造船業界が昨年7年ぶりに中国を抜いて受注量世界1位を奪還したのと相反する。英国の造船・海運市況分析機関クラークソンリサーチの集計結果によると、昨年韓国造船会社の船舶受注実績は前年より71.8%多い1307万9767CGTに及んだ。受注額も55.3%多い269億4633万ドル(約30兆4170億ウォン)に及ぶ。船舶受注増加分の大半をビッグ3が持っていった結果という分析だ。
中型造船会社の肩身はますます狭まっている。2010年に39億5000万ドルを受注し、国内造船市場で12.6%占有率を記録した中型造船会社の昨年国内市場占有率(受注額基準)は4%水準に留まった。関連統計が作成され始めた2006年(10.0%)以降の最低値だ。
1937年に開業した韓国最古の造船業者である韓進(ハンジン)重工業は国策銀行の産業銀行に経営権が移った。釜山影島(プサンヨンド)の狭い造船所のために大型船舶受注に問題を抱えた同社はフィリピン・スービックに超大型造船所を建設したが、受注不振の余波で資本蚕食に陥った。韓進重工業が産業銀行の下へ入り、5大中型造船会社〔韓進・STX・成東(ソンドン)・大韓・大鮮(テソン)〕の経営権をすべて国策銀行が持つことになった。
中型造船会社の没落の最も大きな原因は仕事不足だ。海運業界が単位当たりの運送コスト削減と環境規制対応のために主に大型船舶を発注しており、中型造船会社の仕事自体が減っている。昨年、中型造船会社が主に建造した1万DWT(載貨重量トン数)級の船舶発注量は999万CGTで前年より15.6%減少した。昨年4分期(10~12月)さんでは受注に成功した中型造船会社は全羅南道海南(チョンラナムド・ヘナム)の対韓朝鮮と釜山(プサン)の大統領選挙造船の二つの所だけだ。
造船業界が大手企業中心に再編され、中型造船所は買収合併(M&A)市場でも冷遇される境遇だ。慶尚南道統営(キョンサンナムド・トンヨン)の成東造船海洋は昨年10月とことし2月に売却が失敗に終わった中、今月3度目の売却を控えている。受注が粘り強い大鮮造船も昨年価格の問題で売却に失敗した。一時は世界4位の造船会社だったSTX造船海洋は前受金払い戻し保証(RG)問題で受注に困窮している。造船会社が注文を受けた船を引渡すことができない場合に備え、銀行が発注処に前金を代わりに支払う保証人になるRGを受けることができなければ受注自体が不可能だ。
造船業界内外では中型造船会社の供給過剰問題から解決すべきだという声が高まっている。不渡り危機に陥ったこれらの造船会社の構造調整が遅れているということだ。造船業界関係者は「一部の中型造船会社が低価格受注など『身を削った』競争を始めたため競争力を確保している造船会社の足を引っ張っている」と指摘した。
アークテック造船所と建造契約を締結しているのなら造船所は平気で2年遅れとは言わないと思う。
三菱重工長崎が建造した欧米のクルーズ会社から受注した大型客船の納期遅れで
2000億円以上の損失を出した。
大型客船を2隻で約1000億円で受注したらしい。NGO「ピースボート」は延滞料を契約書でいくらにしているのだろか?
一般常識で考えて、契約後の納期が遅れる場合、違約金やそれなりの額を発注者に支払う。本当に建造契約を締結したのだろうか?
1983年、早稲田大学の学生だった辻元清美氏(現・衆院議員)らが設立し、世界一周旅行を手がけてきたNGO「ピースボート」。同NGOが進めていた「豪華客船」の完成が遅れ、ツアーの受付を中止していることが、「週刊文春」の取材でわかった。
【写真】問題の「エコシップクルーズ」のパンフレット
「豪華客船計画」とは、2015年にピースボートが発表した新型クルーズ船「エコシップ」(乗客定員1800人)の造船計画だ。
「『エコシップ』の一番の売りは太陽光発電などで二酸化炭素の排出を約4割軽減できる点にある。570億円という莫大な建造費は、社会問題に熱心な基金や個人の投資やクラウドファンディングで集めると説明していました」(業界関係者)
だが、1月22日、ピースボートの船旅を企画・実施する旅行会社「ジャパングレイス」の公式HPに次の文章が掲載された。
〈エコシップの造船契約を締結しているアークテック造船所より(中略)当初完成予定の2020年3月からは2年遅れとなる2022年3月完成という結論が提示され、その変更を受け入れるしかないとの判断に至りました〉
ピースボートのリピーターの一人は、「週刊文春」の取材に次のように答えた。
「2015年に初めて新造船について知り、すぐに旅行代金140万円を振り込みました。ただ、リピーターにだけ計画を公表したのが不可解でした」
海運・造船専門紙「海事プレス」を発行する海事プレス社元社長の若勢敏美氏が疑問を呈する。
「造船所すら決まっていない段階で乗客からお金を集めており、業界の常識から外れています。そもそも570億円の大金が本当に集まるのか疑問です。すでに発表した3回分の船旅で、予約金はかなりの金額になっているはず。船室のランクによって値段は異なりますが、すでに約50億円が集まっているのではないでしょうか」
ジャパングレイスは次のように回答した。
「昨年半ばから、完成時期に影響が出る可能性が造船所より指摘されましたが、最終的に造船所から間に合わないとの回答が出たため、昨年12月末からは受付をしておりません。
いただいた旅行代金は建設資金に充てる予定はありますが、既に支払ったのかなどは造船契約の守秘事項となっております。集まっている金額は、貴誌の記事で不安を覚えたお客様全員が取り消しを申し出る事態となっても、返還に応じられる程度であり、当社の財政基盤にまでは影響しません」
1月31日(木)発売の「週刊文春」では、ピースボートの「豪華客船計画」の顛末について詳報している。
「週刊文春」編集部/週刊文春 2019年2月7日号
塗装や作業を実際にやってみて思う事だが、足場は重要。ただ、安全で仕事しやすい足場であっても、作業前の準備と作業後の撤去に時間がかかる。
仕事が同じでなければ、効率化は多少可能かもしれないが、大きな効率化は無理だと思う。早くしようと思って問題が発生すると欲張らずに問題が起きなようにする選択の方が良い結果となる。ただ、これだけは結果次第。運が良ければ、効率を優先する方が良いが、何か起きると効率優先はどうかと言う事になる。
結局、いろいろなリスク、メリット、デメリットそして確率を考えて個々が判断するしかないと思う。
長崎市にある船舶塗装の工場で、船のタンク内に組んでいた足場が崩れ、作業員3人がけがをしました。この工場では去年も労災死亡事故が起きていました。
事故があったのは、長崎市深堀町にある船舶塗装の工場、ナカタマックコーポレーション長崎工場です。警察などによりますと、きょう午後1時半ごろ、建造中の船のタンク内で、高さ2メートルの足場が解体中に突然、崩れ、男性作業員3人が、下敷きになりました。3人は病院で手当を受けていてこのうち、一人は肋骨を骨折しています。3人とも命に別状はないということです。この工場では、去年9月にもタンク内で塗装をしていた作業員が、高さ17メートルのはしごから落ちて死亡する労災事故が起きていて、工場側は事故後、安全対策の徹底をはかっていたと説明しています。
中国のZhejiang Haizhou Shipyardが倒産、クロアチアの3 Maj Shipyardが倒産、そして韓国のHanjin Heavy Industries and Constructionのフィリピン工場が倒産した。造船は冬の時代なのだろうか?
A tanker operated by Singapore’s top bunker supplier has been arrested in Malaysia on suspicion of making an illegal ship-to-ship (STS) fuel transfer off Pengerang.
Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) patrol boats were conducting a joint patrol operation with the Australian Border Force when they detected oil tankers, Kantek 2 and Ramai Awana, according to local media reports.
MMEA believes Kantek 2 was transferring fuel, believed to be marine fuel oil, to Ramai Awana. This happened around noon on 27 September.
Upon inspection, both vessels could not prove they had obtained the relevant documentation from the director of Marine Malaysia in Pengerang waters for the STS operation. They were also unable to produce ship insurance documents.
Data from IHS Markit’s maritime portal indicate that 2008-built, Singapore-registered Kantek 2 is a 6,200 dwt product tanker operated by Sentek Marine & Trading. Ramai Awana, built in 1976, is registered in Cook Islands. It is a 2,120 dwt product tanker operated by Dutaryo Overseas Trading Corp.
Both operators are incorporated in Singapore. Sentek was Singapore’s largest bunker supplier by volume in 2017 and was ranked second in 2016.
At the time of the incident, there were 23 crew members on board both vessels, all of whom are Singaporeans aged between 27 and 55. Four of them were taken into custody to assist with further investigations.
MMEA is investigating the case under Malaysia’s Merchant Shipping Ordinance 1952, Section 49 1B (1) (k), which prohibits the transfer of oil without permission from the director of Marine Malaysia and Section 49 1B (1) (l).
If found guilty, vessel owners could be fined up to MYR100,000 or jailed up to two years, or both.
Pengerang is southeast of Pasir Gudang, Malaysia’s oil refining and downstream hub, and further east of Singapore. It appears to be a hotspot for such illegal transfers, as vessel operators plying the waters near the Pasir Gudang Port boundary attempt to evade tax.
Last month, two Malaysian-registered tankers were arrested on suspicion of illegal fuel transfer, one of which was transporting liquefied natural gas.
A similar case involving another Sentek tanker was reported at about the same time. MMEA detained bunkering tanker Sentek 33 and a fishing vessel, Fu Yuan Yu 677, on suspicion of carrying out illegal STS fuel transfer.
Sentek 33, is a 2014-built, Singapore-registered, 540 dwt bunkering tanker, while China-registered Fu Yuan Yu 677 is part of a fleet belonging to Fuzhou Honglong Ocean Fishing.
Both vessels were anchored about 7 km southeast of Pengerang and Fu Yuan Yu 677 was believed to be receiving marine gasoil from Sentek 33. This took place at about 4 pm in the afternoon.
Upon inspection by MMEA, both failed to produce the permits necessary for anchoring in Malaysian waters or carrying STS transfer. Five of 18 crew members on board both ships were assisting with investigations.
2019年1月3日、米華字メディアの多維新聞は、韓国紙・東亜日報がこのほど、「2018年は韓国の造船業界には意味深い1年だった」とする記事を掲載したことを紹介した。
それによると、東亜日報は「2018年は韓国の造船業界には意味深い1年だった。12年に受注量基準で世界造船トップの座を中国に明け渡して以来6年ぶりに世界トップのタイトルを取り戻したからだ。昨年の世界の船舶発注量は、ピークだった07年の30%水準だが、受注量1位を取り戻したことは大きな意味がある成果だ」とした。
一方で、東亜日報は「中国造船業は低迷している」とし、「中国は安い人件費による価格競争力を武器に00年以降、韓国を抜いて急成長した。だが、人件費が増加している上、品質や技術力で韓国に押されているためだ。造船業界によると、昨年1隻の船舶も受注できない中国造船所が約70%に上るという」とした。
東亜日報は「韓国の専門家たちはこうした状況を楽観していない」とし、韓国造船海洋資材工業協同組合のカン・ジェジョン常務の話として「高付加価値の船舶を多く受注している大手造船会社は、新年も正常化に弾みがつくだろう。しかし、中国と競争する中小造船会社は困難な状況が続くだろう。中小造船会社は財政状況が悪く、海外受注も難しいうえ、バルクなど技術力があまり必要でない船舶の場合は中国の船舶の価格の方が安いので、中国に発注が行かざるを得ない」と伝えた。(翻訳・編集/柳川)
「内外装の設計は国際的に活躍するデザイナー、佐藤オオキさんのデザイン会社「nendo」(東京)に依頼した。」
宣伝のためだと思うが、別に国際的に活躍するデザイナー、佐藤オオキさん(まったく誰だか知らない)にお金をかけるよりは
船員の食事にお金をかけてほしい。食事が美味しくないと楽しくないと思う。
まあ、勝手に判断するよりは若い船員や水産学校の生徒に船に何を期待するのかアンケートを取って判断した方が良いと思う。
押しつけの親切は当事者達には伝わらない事はある。まあ、船員の事などどうでもよく、宣伝と何かやっているとアピールしたいのであれば
思うようにやっても問題ないと思う。
あと、人間関係や教育方法も働く人達にとっては重要だと思う。
◇快適な居室、ネット利用可
重労働というイメージを一新し「人が集まる魅力ある船」をテーマにした遠洋マグロはえ縄漁船の建造が、宮城県気仙沼市で進められている。機能やデザインを重視し、職場環境の改善を図る「改革型マグロ船」として同市の漁業会社「臼福本店」が計画した。新船にはスマートフォンでソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)などが利用できる通信環境や、従来より広く快適な居室を整備する。【新井敦】
マグロ漁業は乗組員の高齢化が進み、東日本大震災後に乗船した新人船員の定着率は5割に満たないという課題を抱える。同市では年々難しくなる若手船員の確保につなげるため、船内作業にトヨタ方式の「カイゼン」を取り入れるなど、漁業関係者らによる業務の見直しが本格化している。
臼福本店は新船の導入で、労働負荷の高い作業工程の省力化や、乗組員の労働環境の改善を図るとともに、操業形態を見直して収益性の向上を目指す。
新船は486トン。内外装の設計は国際的に活躍するデザイナー、佐藤オオキさんのデザイン会社「nendo」(東京)に依頼した。船内設備では、陸上と同様に海上でもインターネットが常時利用できる通信環境を充実させる。国内のマグロ船では初といい、洋上からSNSを活用した情報発信などが可能になる。
乗組員の居室はデザインを刷新し、従来の船より1人当たりの床面積を広げ、天井を高くするほか、シャワーやトイレを増設。長期間の航海に配慮し、寝台も大きくする。ストレス軽減を目的にアロマを取り入れ、植物から抽出した新緑の香りで乗組員が気分転換を図れるようにする。
総工費は約8億円。水産庁の漁業構造改革総合対策事業の補助金を活用する。11月に同市のみらい造船吉田工場で起工式があり、完成は来年11月の予定。
臼井壮太朗社長は「担い手不足を解決するため、労働環境をよくしたい。これまでにない、乗ってみたいと思うマグロ船に一新し、未来につなげたい」と話している。
「所有船舶6隻」と書かれているが、小さな船舶?
内航船だとタンカー以外、任意でISMコードに適合する船はほとんどないので
現状はどうなっているのだろうか?
船舶の運航に必要な手続きを怠ったとして、水島海上保安部は6日、船員法違反などの疑いで海運会社(倉敷市)と同社の男性社長(76)ら乗組員20人を書類送検した。
送検容疑は4~8月、同社と男性社長が、所有船舶6隻の乗組員を雇用した際に運輸局へ届け出をせず、うち4人について医師による健康証明書を持たないまま業務に当たらせるなどし、乗組員らは運輸局での船員手帳の交付申請や航海日誌への記載を怠った疑い。
同保安部によると、7月に行った第6管区海上保安本部の一斉取り締まりで発覚。男性社長は「手続きが複雑で面倒だった」と供述、他19人も容疑を認めている。
危険や汚くなる作業がある。男女平等と言うのであればそのような仕事もしなければならないと思う。
機関は無理だけど航海士だったら貨物船よりは客船の方が汚い仕事は少ないかもしれない。これまでの想像と現実での経験でどのように
考え方がかわるのだろうか?経験しないと理解できない事、学校では教えてくれない事がある。
閉ざされた世界を女性の視点でホームページやSNSで紹介する事は良い事かもしれない。
「男社会」のイメージが根強く、50歳以上のベテランが増加していることから、今後、深刻な人員不足が予想される海運業界。女性の登用が急務とされる業界に高校卒業と同時に飛び込み、約半年間にわたる研修期間を終えた1人の女性船員がこのほど、姫路港(兵庫県姫路市)から初出航した。「立派な航海士になって、女性でも珍しくない仕事にしたい」と意気込み、業界の注目を集めている。
船舶管理・船員派遣業を行う七洋船舶管理(神戸市)姫路営業所の岡田菜々子さん(19)。鳥取県米子市で生まれ育ち、中学時代から船員に憧れた。漁船が多い日本海側の出身だが、「物流を支える貨物船に乗りたい」と同社に就職した。同社によると、高校卒業後すぐに、船員として乗船する女性は業界で初めてといい、業界紙でも取り上げられた。
岡田さんは中学卒業後、同県立境港総合技術高校の海洋科に進学。船長コースで船舶の航海技術や海上法規などについて学んだ。卒業後すぐに船員になるべく勉強を続けたが、「女性船員は採用できない」とする会社が多く、就職に苦労した。そんな時に教員から同社を紹介された。
同社は女性船員の雇用実績はなかったが、人材確保の面からも前向きだった。大橋了輔管理部長は「(岡田さんから)『船に乗りたい』という誰よりも強い思いを感じた」と話す。岡田さんは11月から、国内の港で貨物を運送する内航船員として勤務し、大阪や仙台、博多など全国各地に寄港しながら海上生活を送る。
「一番の楽しみはもつ鍋や牛タン、みそかつなど各地の名物料理」と笑顔を見せる一方で「一人前の船員になって女性がもっと入りやすい業界にしたい」と夢を語った。同社では来年も女性船員1人の入社が内定しており、佐藤清社長は「このまま女性の雇用に力を入れ、将来は女性だけの貨物船を持ちたい」と話した。(谷川直生)
もし日本の客船や貨客船が沈没したら、韓国船籍旅客船「セウォル号」(M/V"SEWOL", IMO9105205)のように救命いかだが固着していたり、浮いてこなかった可能性があると言う事?
韓国のような不幸な海難が起きなくてよかった。韓国に笑われる。
国土交通省は2日、国認定の船舶整備事業者「協栄マリンテクノロジ」(東京)の福山営業所(広島県福山市)が約16年間にわたり、旅客フェリーや貨物船、タンカーに備え付ける救命いかだなどに必要な整備を省略し、実施したように記録を改ざんしていたと発表した。国交省は同日、船舶安全法に違反するとして認定の効力を停止した。
改ざん期間は2002年8月から今年6月まで。5年ごとに法律で義務付けられている整備で、乗客や乗員らが緊急避難するための「膨張式救命いかだ」や「降下式乗り込み装置」が正常に動くかどうかといったテストを省略していた。
国土交通省は2日、東証1部上場の協栄産業の子会社が船舶に搭載されている救命いかだなどの整備記録を改ざんしていたと発表した。同省は再整備や交換などを指示した。
発表によると、船舶用救命設備の販売や整備、点検を手掛ける協栄マリンテクノロジ(東京)は、2002年8月から今年6月まで、法律に基づく救命いかだなどの整備について、必要な整備項目を省略。実際には行われていないにもかかわらず、実施したように見せかけるため、整備記録を改ざんしていた。
外国船員が日本人船員より劣っているとは思わない。ただ、外国船員と言っても不適切な学校から一流の学校まで幅広いレベルがある。
外航船であれば英語が話せれば問題ないが、内航船の日本人船員はほとんどが英語が話せないので外国船員と英語での意思疎通は無理。
外航船でも建前は使用言語は英語となっているが、英語を理解出来ていない下っ端の船員は存在する。それでも検査や審査は通っている。
外国人船員に問題がある事もあるが、検査や審査の基準が大きく、規則に通っていなくても合格の証明とされる証書が入手出来る事に
問題がある。結果として、座礁、衝突などの海難を起こす原因となる。
日本語を話す外国船員は多くない。能力や知識があってもコミュニケーションの問題があれば、緊急時な詳細な説明が必要なケースでは
適切に対応できない。
内航船は外航船と違っていろいろな国籍の船員と一緒に働く経験がないので例え規則が変わっても現場が対応できないであろう。
問題はたくさんある。
入管法改正案が注目を浴びているが、問題があろうとも規則にしてしまえば良いと思うのであれば、問題や事故が起きようとも関係ないかもしれない。
被害者達は運が悪かったと思えば心配する事は何もないかもしれない。
大島大橋に貨物船が衝突した事故は一例であろう。事故や海難が起きても、被害者達以外にとっては
関係ない事である。
多くの業界と同じく、物流の大動脈である海運業も少子高齢化と人手不足に悩まされている。深刻なのは、国内産業の基礎物資輸送の要である内航海運で事業継続が危ぶまれる事業者が増えていることだ。
海外の港を行き来する外航船と異なり、内航船は日本国内の港から港へモノや人を運ぶ海運業者だ。鉄鋼や石油製品、セメントなど国内の産業基礎物資輸送の約8割を担う。災害などで陸路が寸断された際には代替輸送を行うほか、環境負荷軽減に向けたモーダルシフトの受け入れ先としても期待されている。
内航船の船員数はバブル崩壊後の景気低迷に伴い、1990年の5万6100人から2016年には2万7639人へ半減。その一方で輸送量は2010年以降、3億6000万〜3億7000万トン程度で下げ止まっており、現状の船員規模を維持する必要がある。しかし、年齢構成をみると心もとない状況だ。
船員の過半数は50歳以上
内航船員の7割強を占める貨物船の場合、50歳以上が53%、60歳以上も28%を占める。一方、30歳未満の若手船員は16%にすぎない。いびつな年齢構成になった背景には、内航船員は日本人でなければならないというルールがあるからだ。
1899年(明治32年)の船舶法制定以来、内航船は経済安全保障上の観点から日本籍船に限定され、外国人船員も認められてこなかった。一方、運賃がドル建ての外航船は、1985年のプラザ合意後の円高をきっかけにコスト削減策として外国人船員の採用に舵を切った。
内航海運は、外航海運の外国人船員化と漁獲制限に伴って漁船からあぶれた日本人船員の受け皿となった。バブル崩壊後の輸送量減少で新造船が減ったこともあり、人手不足とは無縁でいられた。「即戦力を採用できたので、長らく船員育成に力を入れてこなかった」(内航船関係者)ため、今そのツケが回ってきた格好だ。
日本の刑事裁判では、法廷での証言よりも、取り調べ段階での供述調書が何よりも重視される。密室での長期間かつ苛酷な取り調べから解放されたいがために、事実に反する内容であっても、調書に署名してしまえば、法廷で否認に転じてもまず通らない。
航海士や機関士になるには国家資格の海技士免許が必要で、船の大きさや航行区域に応じて1〜6級に分かれている。小型の内航船であれば6級から乗ることができ、4級を持っていれば比較的大きな船の船長になれるが、免許取得には乗船履歴などの条件をクリアする必要がある。
内航船員を養成する代表的な教育機関に海技教育機構があり、中学卒業者を対象にした海上技術学校4校と、高校卒業者以上を対象とする海上技術短期大学校3校、海技大学校を擁する。技術学校では3年の修業期間終了後に6カ月の乗船実習を受けると、4級の航海士か機関士の免許を取得できる。短大も乗船実習を含め2年で同様の免許が取得可能だ。
同機構では“士官候補生”の内航船員を毎年330〜380人程度送り出している。技術学校、短大とも志願者は募集定員を上回っており、これまでのところ船員希望の若者を確保できていないわけではない。
船員1年目の手取りは月25万円
そもそも船員は高給取りだ。「船員1年目でも乗船中の月給は手当込みで手取り25万円程度」(海技教育機構の遠藤敏伸・募集就職課長)。貨物船の場合、勤務形態は3カ月乗船、1カ月陸上休暇のサイクルが基本で、乗船中は賄い付きなので食費もかからない。「海が好き、給料がいい、まとまった休みが取れる点を志望動機に挙げる生徒が多い」(同)という。
国土交通省の試算によると、60歳以上の船員が今後5年間で退職する場合には毎年1200人程度の新規就業者が必要という。海技教育機構の定員増が検討されているほか、水産系高校から内航船員希望者を募ったり、社会人経験者を対象とした6級取得養成制度を設けたりすることで、退職者の補充を急いでいる。
女性船員の育成も課題だ。内航海運の女性船員比率は2%にすぎず、貨物船ではさらにその比率は下がる。貨物の積みおろしの際には力仕事が必要な上、伝統的な男性職場のため採用する側も敬遠しがちだ。しかし、11年前から女性船員を定期的に作用してきた協同商船の福田正海専務は「結婚を機に辞めることも多いが、いずれは女性船員だけで1隻運航させたい」と採用に積極的な事業者も登場している。
荷主からコスト削減目的で外国人船員の採用を求める声が出たことがある。しかし、「日本人船員とのコミュニケーションの問題や、混雑した港を航行する技術が必要なため、外国人船員(の採用)は難しい」(内航海運大手)として、現在そうした要望は出ていない。
もっとも、内航海運業界内でも船員不足の状況は一律ではない。これには特有の契約形態が影響している。
運送事業者は「オペレーター」と呼ばれ、元請けのほかに2次、3次の下請け事業者がいる。オペレーターは自社保有船のほかに、貸渡事業者(オーナー)から船員ごと船を借り、請け負った貨物を運送する。荷主はオペレーターに運賃を、オペレーターはオーナーに用船料を支払う多重構造になっている。
貸渡事業者の6割が「一杯船主」
オペレーターは2018年3月時点で1515事業者おり、主に荷主である石油元売り会社や鉄鋼会社などの系列に属する上位60事業者が総輸送量の8割を契約している。一方、オーナーも1470事業者いるが、その6割程度が主に小型船を1隻のみ保有する「一杯船主」だ。
大型船を複数保有するなど事業規模の比較的大きいオペレーターやオーナーは、船内環境を含めた待遇の良さをアピールできるため、「船員採用ではそれほど苦労していない」(内航海運大手)。海技教育機構の卒業生も大手事業者を中心に入社していく。
船員が辞める理由として、もっとも多いのは人間関係と内航海運関係者は口をそろえる。小規模事業者は若手の船員に来て欲しいが、せいぜい5〜6人乗りで年齢が高い船員ばかりの小型船は敬遠されがち。一杯船主だと人間関係がこじれた際にほかの船に移ることもできず、待遇も見劣りがする。一方、オーナー側も“促成栽培”で経験不足の若手船員を雇うことに不安を覚えるうえ、少人数運航では育成する余裕もない。
内航海運オーナーの営業利益率は1.3%と全産業平均の約3分の1にすぎない。1隻数億円以上する船の建造費も借り入れで賄っている状況だ。後継者難、船員不足となれば事業継続は難しくなり、実際、一杯船主は2005年から10年間で39%減少した。
国交省もようやく本腰に
業界からは「一杯船主が安く請け負っているから成り立っている業界。いなくなったらどうするのか」(中堅オーナー)と先行きを危惧する声があがる。小規模事業者が主に所有する499総トン以下の小型船は内航船全体の隻数の8割弱を占める。統合や集約を進めようにも「赤字の事業者を集めてどういう経営をするのか」「長らく地縁血縁でやってきた世界なので難しい」との見方が大勢だ。
船員や海運関連の従業員らでつくる全日本海員組合の森田保己組合長は「そもそも運賃や用船料が削られてきたことが、内航海運が直面している問題の要因。用船料の適正化が不可欠だ。小型船が動かなくなればその分を外国籍船に頼むことになりかねず、事故も多発するおそれがある」と、現場の声を代弁する。
国交省でも小規模事業者の船員不足を含め、内航海運の課題解決に向けて各種検討会を設置するなど本腰を入れ始めた。荷主、オペレーター、オーナーいずれもが“三方良し”とならなければ、経済安全保障を掲げたオールジャパン体制の維持は難しくなるだろう。
著者:山本 直樹
The state-owned group said on 22 October through its Hong Kong-listed international trading company, AVIC International Holdings, that it is in preliminary negotiations with potential investors about the possible sale.
The statement confirmed that AVIC had not yet reached any formal agreement with the unidentified investors.
AVIC's shipbuilding business, which has some interests in the naval sector, is channelled through its AVIC International Maritime Holdings business. This unit owns shares in three shipyards in China: AVIC Weihai, Taizhou CATIC Shipbuilding Heavy Industry, and AVIC Dingheng Shipbuilding.
Hong Kong-listed AVIC has a 73.8% stake in Singapore-listed AVIC International Maritime Holdings, which owns the Deltamarin ship design firm and three shipyards in China –AVIC Weihai Shipyard in Zaobei Bay in northern ...
三井E&Sホールディングス傘下の三井E&S造船(東京都中央区)は2019年4月に中国の揚子江船業(江蘇省)と三井物産の3社で造船事業の合弁会社を設立。揚子江船業の低コスト建造ノウハウと三井E&Sの技術力を融合。国際分業を進め、物流やエネルギー輸送の増大が期待される中国の新造船需要を取り込む。
新造船需要は回復傾向にあるが、韓国造船所が政府支援を受けて受注攻勢を強めるなど船価低迷は続く。
このため三井E&Sは今春、常石造船(広島県福山市)とも商船事業で提携するなど構造改革を急ピッチで進めている。造船業界では川崎重工業が中国進出で先行し成功を収めているほか常石造船も中国やフィリピンで工場を運営する。生き残りをかけ国際分業が新たな潮流になりそうだ。
新会社の資本金は約112億円。揚子江船業が51%を出資し、残り49%を三井E&Sと三井物産で握る。揚子江船業の売り上げは3200億円規模でバラ積み運搬船など年50隻超を建造する中国最大の民営造船所。複数工場を持ち、そのうち一つを新会社が運営する。最大200億円超を投じて最新鋭の建造ドックも新設する。社長は揚子江船業から出し、三井E&Sから幹部クラスを派遣する。新会社は5年後に売上高700億―800億円を目指す。
三井E&Sは千葉事業所と玉野事業所で新造船を建造しており海外建造は初。日本での商船建造は継続するが、環境対応船や艦艇、官公庁船を軸に運営する。汎用的なバラ積み船などは中国の合弁会社で建造する方向。三井物産は営業面で支援する。
揚子江船業は合弁会社を通じて三井E&Sの技術力や設計力、生産性向上ノウハウを習得。難易度の高いガス運搬船など事業領域の拡大を目指すもよう。
「藤原氏は旧会社の関連会社ジィ・エス・ケーの海務課長を務めていた。」
課長から一気に社長と大出世だが、本人に覚悟がないと結構大変だと思う。普通、こんな事はなかなか起きないので人生最大のチャンスなのか、
それとも苦労の始まりなのか、結果次第だと思う。
経営破綻し離島航路を休止・廃止した五島産業汽船(長崎県新上五島町)の元従業員らが設立した同名の新会社は15日、運休中の長崎-鯛ノ浦(同町)を引き継ぎ、1日2往復する計画を発表した。旧会社が休止・廃止した全4航路について、運賃全額の払い戻しにも応じる。
新会社の社長に就任した藤原圭介氏(44)は同日、県庁で記者会見。九州運輸局の認可が下り次第、「一日も早い運航再開を目指す」と意欲を示した。
新生「五島産業汽船」には、県商工会連合会長を務める宅島壽雄氏ら県内建設会社の関係者3人が計1500万円を出資し、役員に就いた。藤原氏は旧会社の関連会社ジィ・エス・ケーの海務課長を務めていた。
解雇されるなどした元従業員計68人(関連会社を含む)のうち、藤原氏ら20人が新会社に入社。旧会社から高速船「ありかわ8号」(定員79人、58トン)と鯛ノ浦港ターミナルなどを購入した。
長崎-鯛ノ浦は、旧会社が町所有の高速船「びっぐあーす」2隻(定員300人、1号293トン、2号295トン)で1日3往復していた。新会社は航路再開を優先し当面、ありかわ8号で1日2往復する計画。新会社は「町の判断次第」とした上で、指定管理者となって、びっぐあーすの運航にも意欲を示した。
払い戻しについて、新会社は未使用回数券分も合わせて総額100万円程度と見込んでいる。運航再開と同時に払い戻す方針で、具体的な手続きは後日告知するとした。
旧会社は長崎-鯛ノ浦のほか、佐世保(鯨瀬)-上五島(有川)▽佐世保(鯨瀬)-五島(福江)▽長崎-天草(崎津)を運航していた。
タンカーが接岸する施設では携帯電話や電気機器の使用禁止となっている。
防爆及び防水仕様であればターミナルが納得すれば問題ないであろう。
投資額より効率アップによるコスト削減が大きいのであればメリットがあると思う。後は会社と取引先次第だと思う。
IT化が良い場合もあるが、悪い場合もあると思う。荷役や造船所の現場に行くと、携帯を持って隠れて遊んでいる人達を見ることが多くなった。
近くに行って画面を覗き込んでいないのでもしかすると入力作業をしているのかもしれないが、もし、ゲームとか仕事以外の事をやっているので
あれば効率アップやIT化の本来の目的は相殺又は別の次元に行ってしまうと思う。
事務の部分はITにより改善するかもしれないが、それ以外は人材の能力や人間性が重要な部分があると思う。
製造業や流通業など、現場の力が強い業種はIT化が進みにくいといわれる。しかし、全国に拠点を持つ海運会社「ハヤシ海運」では、経営企画部の活躍によって、ペーパーレスやタブレット導入といった業務のIT化を進めている。
IT導入の現場でよく語られる「使われないシステム」。せっかく多額の投資をしたのに、完成したシステムが業務現場で使われない――読者の皆さんにもそんな経験をした方はいるのではないだろうか。
特に製造業や流通業など、システムに関わる人間と業務現場に“物理的”な距離があると、この問題は起こりがちだ。情シスと現場。同じ社員であるはずなのに、どこかよそよそしくなってしまったり、コミュニケーションロスが起こったりして、現場の困りごとやニーズを満たしきれないシステムができ上がってしまう。
石油製品の港湾荷役(貨物の積卸作業全般)から、船舶代理店業や通関業などを一貫して手掛ける「ハヤシ海運」は、その事業形態から、拠点がバラバラに散らばりやすい「海運業」であるものの、経営企画部の活躍により、ペーパーレスなどITを使ったさまざまな改革を進めている。
“普通”のIT機器は使っちゃダメ! 知られざる「石油コンビナート」の世界
ハヤシ海運でITシステムを管轄しているのは、経営企画部だ。社員の多くは現場が中心で、バックオフィスの人数が少ないことから情報システム部を置いていないのだという。一般的に経営企画というと、事業企画や内部統制などが主な業務だが、同社ではIT戦略などの業務も兼ねている。
同社 経営企画部に勤めている榎春彦さんは、2年ほど前に経営企画部に来て以来、この事業はIT活用を進めにくいと感じているそうだ。今は、手書きで行っていた施設の点検業務を携帯型端末でできるようにするシステムの導入を進めている。「大したことない」と思う人もいるかもしれないが、そこには業界ならではの特殊な事情があった。
「海運というのは現場主体の業種なので、なかなかITが入り込む余地がないんですよね。その現場自体も製油所や油槽所内のため、通常の電子機器は全く持ち込めないケースがあるんです。そのため、PCを含めてITに接するのは事務方という構造になりがちで、業務も含めた電子化が進めにくい。セキュリティの必要性を説明するといったこと一つにしても、じっくり説明をしております」(榎さん)
ガソリンなどの石油製品は常温で蒸発するため(揮発性)、製油所や油槽所内の現場では、通常のPCやスマートフォンなどの電子機器は、電源を入れたり、内部のモーターが動いたりするだけで火花が出るため、火災が発生する可能性がある。スマートフォンなどの機器は持ち込めるはずもなく、明かりを照らすライトですら、決められた物しか持ち込めない。
そのため、コンビナートに持ち込む機器は、法律で決まった「防爆」基準をクリアしたものに限られる。同社では、業界で初めて防爆仕様の携帯型端末を導入する準備を進めており、この冬から稼働する予定だ。
「以前からずっと、現場での点検業務を電子化できないかという議論はありました。例えば、雨の日は点検表が破けたりしないように何かしらの工夫をするといった煩わしさがありますが、タッチでチェックできればラクになります。異常があった部分をカメラで撮影して送るといったこともできますし。感圧式にも対応しているので、手袋をしていても操作できるというのはうれしいポイントです」(榎さん)
この携帯型端末を見つけたのは榎さんだ。ウェアラブル機器の展示会に行った際に見つけ、すぐにベンダーへ連絡を取ったのだという。経営企画部に来る直前に現場研修を受けていたこともあり、現場のニーズには敏感だ。
「経営企画部に来る前は、同じ製油所内にある研究所に20年ほど勤めていました。主に潤滑油の研究開発や試験業務、車のエンジンを分解したりといった研究補助業務をやっていましたね。その前は親がやっていた運送会社にいたんですよ」(榎さん)
ペーパーレス化のカギになった「サイボウズ Garoon」
現場だけでなく、事務方でもIT活用を進めている。以前は会議の資料や議事録は紙で配っていたが、今では全てデータで配るなどペーパーレス化を成功させた。その成功の裏には、グループウェア「サイボウズ Garoon」(ガルーン)の存在があったという。会議で使う資料をGaroonのスケジュールで共有するようにしたことで印刷を止めたのだ。
「最初は、これまで通り紙で資料が欲しいと言う人もいましたが、『資料は全てGaroonの中に入っているので、必要であればご自身で印刷願えませんでしょうか』とあえて突き放しました。そのうちに皆がGaroonの使い方に慣れてきて、逆にいちいち紙に印刷するのが面倒になり、ペーパーレスが定着していきました。今では、紙の資料を渡すと『いらない』と逆に突き返されるほど。会社の雰囲気はずいぶん変わりました」(榎さん)
議事録の作成もGaroon上で行うようにしたことで、作業時間を大幅に減らすことができたそうだ。「他にも契約書や申請書など、皆が共通で使うファイルや計画書、ISO9001に基づいた手順書などをGaroon上に置いていますね。アクセス権を設定して、特定の部署だけが見えるような仕組みも取り入れています」(榎さん)
社内のメンバーとのやりとりにはメッセージ機能を使っており、ワークフローもGaroonで行っている。Garoon自体は2005年から使っていたが、オンプレミス版からクラウド版に乗り換えたことで、場所を選ばずスムーズに決裁が行えるようになったという。さらに、最近ではプロジェクト推進用の機能「スペース」も活用し始めた。
「きっかけはプロジェクトを進めていく中で、5人の情報をメールでやりとりしていたら、だんだん何が何だか分からなくなってしまったことですね。たまたまサイボウズのセミナーでスペースの使い方を学んだので、使ってみようと提案しました。
掲示板のように、縦方向のスクロールだけで情報が追えるので『意外と便利だね』という声が出てきていて、浸透し始めているのかなと思います。今はまだわれわれの拠点で試験的に使っている段階ですが、今後、複数の拠点で1つのプロジェクトを進めるようなことがあれば、有効だと考えています」(榎さん)
もちろん、スケジュール機能についても皆で使っていて、各拠点に散らばった役員や管理職同士が互いのスケジュールをひと目で確認できる。榎さん自身も各拠点に出張することが非常に多く、重宝しているそうだ。
「ITシステム全般に言えますが、現場や業務部門は『なぜこれを使わなければならないのか』が分からないことが多いんです。管理者側は良かれと思って導入するんですが。仕事のやり方を変えなくてはいけないから、うっとうしいと感じる人もいるでしょう。何も説明せずに導入したら“使われないシステム”になってしまうので、日頃から現場や業務部門と話をして、なぜこれが必要なのか? を理解してもらうようにしています」(榎さん)
“オフ”の時間に、現場のニーズが出てくる
榎さんが他の拠点に行くのは、トラブルが起こったときや、新しくシステムを立ち上げるときなど自ら出向いてサポートを行う時もある。現場に行くと、Garoonの使い方なども含めて、さまざまな質問をされるのだという。業務時間中よりも、食事をしたり、飲みに行ったりという“オフ”の時間に「こんなシステムがあったら便利だね」という話で盛り上がるそうだ。
例えば「このExcel業務が面倒だから何とかならないか」「事務所に携帯電話の電波が入りにくいんだけど何とかならないか」「添付ファイルが送れない」「PCってもっと早くならないか」など、拠点にまで行かないと知り得ないような、細かな相談も少なくない。とはいえ、拠点の人と仲良くなるまでは、こうした相談は一切出てこなかったという。
「本部から来た人間に対して警戒している雰囲気はありますよね。『余計なことを言うとヤバいぞ』みたいな。彼らからすれば、本部って何をやっているのかよく分からないところもあるのだと思います。私は多いときは月に2、3回ほど、他の拠点に行くことがあるのですが、そうすると現場の人とだんだん仲良くなるんですよ。
トラブルを解決していくうちに『あいつはITについて詳しいぞ』みたいなウワサが流れるらしく(笑)。そうなってから、ご飯にいったときに『なんか困ったことないの?』と聞くと、どんどん出てきてびっくりしました」(榎さん)
現場の気持ちを知るには「荒天の日に現場に出ろ!」
ITによる課題解決を通じ、本部と現場のパイプという役割を担うこともある経営企画部。最近では、若手のメンバーが入ってきたこともあり、現場の気持ちを理解してもらうために「荒天の日に現場に出ろ!」とアドバイスしているそうだ。
船舶が港に停泊する際は、岸壁に設置しているボラード(フック)に綱を巻き付けて固定する必要がある。その綱を船舶から受け取るのは、積卸作業全般を担っているハヤシ海運の役目だ。相手が巨大なタンカーである場合、小型のボートで近づき、海上で綱を受け取って陸まで運ぶのだという。
「タンカーの中には全長が300メートルほどあるような巨大なものもあります。天気が良くて穏やかなときはいいですが、たとえ荒天で海が荒れているときでも、やらなくてはならない時があります。
波が激しい時は、船が数メートル以上も上下します。そのなかで綱を運ぶ恐怖は、その場にいた人にしか分かりません。手すりも命綱もありませんし、ずいぶん前の話と聞いてますが、実際に海に投げ出された人もいるそうです。私も2年前に現場研修で経験しましたが、状況によっては命がけですよ。こういう経験をすると、現場との距離はぐっと縮まりますね」(榎さん)
経営企画部になる前は、もともと総務部にいたという榎さん。IT管理も含め、全社的な視点が必要なさまざまな業務を進めてきた。今後も、セキュリティ対策の啓蒙やシステムのクラウド移行など、現場の仕事を楽にする施策を企画していくという。
労を惜しまず現場に出向き、オフの時間で信頼を勝ち取り、現場のニーズに合わせたITで課題を解決していく。現場の力が強い業種はIT化が進みにくいといわれる中、地道な取り組みでIT活用を広めていく――そんな「総務系情シス」が、海運男子たちの仕事を支えているのだ。
近い将来、若い船員不足の現状では、船を運航するのに必要な資格を持つ船員の確保が問題となり、航路を維持できなくなる問題が
出てくると思う。退職が近い船員達は船員を続ける可能性が高いが、若い世代は船員として仕事を考える時、船員としての選択を
しないかもしれない。
昔は外航船の船員から内航船の船員に変わる事はあったようだが、外国船の日本人船員がほとんどいない現状では同じ事は無理。
海上自衛隊からの転職を促すとしても、同じ船だから勤務や仕事が同じであるとは限らない。公務員体質だと中小の民間海運会社は
向かないかもしれない。臨機応変が求められる事が多いように思える。
国交省はこれまでのパターンやシステムが継続できると簡単に思わないほうが良いと思う。対応を考えていないと人が育つ、又は、教育を
終えるまでには時間がかかるので、大きな問題となる可能性がある。
国交省や海保の対応を見ているとすごく遅いと思うので、かなり手遅れになるまでこの分野の対応は口先だけで実際には解決や改善には向かわないと
思う。結果は、何十年後にわかるであろう。最近、流行りの車の自動運転の船舶バージョンを期待するのであろうか?早すぎるし、コストを
考えれば現実的に近い将来はないと思う。コストを無視すれば可能な航路はあるかもしれないが、コストは無視できないと思う。
「すべては私の計画の甘さ、判断の遅さで、後手後手に回った」-。突然の運休で島民らを混乱させた五島産業汽船(新上五島町)の野口順治社長は、4日の県庁での記者会見で、憔悴(しょうすい)した表情でこう謝罪した。五島-佐世保航路を開設するなど、離島住民の期待を背負い、航路を拡大していった同社。新上五島町などに構成資産がある「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界文化遺産に登録され、交流人口拡大に追い風が吹き始めた直後の経営破綻だった。
「住民の強い要望」で2015年4月に参入した佐世保-上五島(有川)航路。他社が撤退した赤字路線で、結果的にこれが経営上のネックとなった。
設備投資なども重くのしかかり、8月中旬に1回目の不渡りを出した。「10月1日午後3時までは債権者への交渉に努めたが、かなわぬ状況になった」。「夜逃げ」との指摘があったことについては、2日以降も関係先と連絡を取るなどして事業継続を模索していたとした。人口減少などで経営環境が厳しくなる中、「30年間に渡り離島航路の運営に懸命に取り組んできた」(野口社長)が、状況は好転しなかった。
突然の運休となった2日、港では張り紙を前に戸惑う人たちの姿が見られた。窓口も閉ざした理由について、「過去に関西航路を閉鎖した際、利用者と職員とのトラブルの経験から安全面を優先した」と釈明した。
会見終了後、新上五島町に向かい夕方から町役場で江上悦生町長ら約50人に経緯を報告。「海上タクシーとして始め、ここまで育ててもらった。本当に迷惑をかけて、申し訳ない」と声を詰まらせた。
五島産業汽船(長崎県新上五島町)が離島航路を2日から突然運休、事業停止状態となっている問題で、野口順治社長(54)が4日、県庁で会見し、来週にも破産手続きに入ることを明らかにした。負債総額は関連会社を含め判明分で21億円。野口社長は島民ら利用者に「突然のことで多大な迷惑をお掛けし、本当に申し訳ない」と謝罪。公設民営で運航していた長崎-上五島(鯛ノ浦)航路の早期再開を新上五島町が目指していることには「最大限協力したい」と述べた。
代理人の石橋龍太郎弁護士によると、判明している負債総額は同社が17億3千万円、発券業務などを行う関連会社のジィ・エス・ケーが3億7千万円。関連会社を含めた従業員計68人は2日までにほぼ全員を解雇した。
野口社長によると、2015年に参入した佐世保-上五島(有川)航路が、当初から赤字で約4億円の累積損失を出すなど経営を圧迫。船の修繕費などもかさみ、8月と今月1日に不渡りを出して銀行取引が停止となった。2回目の不渡りについては「債権者に猶予を求めたが延期できなかった」と述べた。
従業員の9月分の賃金、30日前までに解雇予告をしなかったことに伴う解雇予告手当などが未払いで、国の立て替え払い制度を使う準備をしている。運賃などを支払い済みの利用者に対しては全額を払い戻す意向だが、対象人数や総額は未確定という。
今後について野口社長は同町に協力する意向を示し、「事業譲渡や港の自社ビルの使用などできる限りサポートしたい」と話した。
同社は1990年設立。18年4月期決算は売上高が11億6千万円、経常損益は1億1800万円の赤字だった。長崎-上五島、佐世保-上五島のほか、佐世保-五島(福江)を運航し、長崎-熊本県天草でも高速船を試験運航していたが、いずれも1日までに休止、廃止を九州運輸局に届け出ていた。
長崎・五島列島と長崎市などを結ぶ「五島産業汽船」(長崎県新上五島町)が2日に突然運航を休止したことを受け、野口順治社長は4日、長崎県庁で記者会見し、関連会社を含めた負債総額が21億円を上回る見通しで近く破産手続きに入ると明らかにした。野口氏は「利用者、島民、県民の皆さまに迷惑を掛けて申し訳ない」と謝罪した。
長崎・五島列島と長崎市などを結ぶ「五島産業汽船」(長崎県新上五島町)が2日、旅客船の営業を突然休止した。3日も混乱が続いており、長崎県の中村法道知事が「突然の運航休止は、住民生活や経済活動のみならず、観光交流への多大な影響が懸念される」とコメントするなど、困惑が広がる。各地の離島では人口減が進んでおり、輸送手段の確保が地域の課題として浮上した形だ。
九州運輸局や県によると、五島産業汽船は定期航路、不定期航路を合わせ全4便を運航。経営悪化が原因とみられ、1日までに、全航路を運休したり、廃止したりする届け出を九州運輸局に提出したという。
五島列島と長崎市などを結ぶ他社便は通常通り運航しているが、住民らは別の港まで移動する必要がある。長崎県の担当者は、1日に五島産業汽船に2日以降の運航休止を確認したが、2日以降は連絡が取れない状況が続いている。
新上五島町の安永佳秀観光商工課長は「島外の病院に通う住民の負担増や、観光の利便性低下は大きな痛手。何らかの形で維持してほしい」と話す。長崎市の長崎港では3日も窓口のシャッターが閉まったまま。訪れた長崎市の男性(68)は「五島産業汽船に勤める友人と連絡が取れない。何が起きているのか」と困惑の表情を浮かべた。
従業員の事を考えずに、経営者の立場だけで考えれば、倒産の一日前、又は、当日まで従業員には伏せておくのが普通であろう。
倒産するのがわかれば、債権者達が押し寄せる。保全命令が出る前であれば、会社の物を借金のかたに持っていく会社や人達がいるであろう。
納入しようとしていた物は中止、又は、納入したものを取りに来るかもしれない。従業員達は自分達の給料、雇用、そして再就職の
事だけしか考えないであろうが、売掛を回収していない会社は、回収できなければほとんど損になる。売却できるような資産や物は
銀行が抑えているので、優先順位が低い会社は取れるものはない。
五島産業が汽船が所有していた船舶を妥当な値段で地方自治体や航路を引き継ぐ会社が入手できれば、船員達の就職は早く決まる可能性がある。
船の運航や維持管理に精通した船員を雇うのが一番ベストだと思う。新しい会社のやり方が嫌で再就職しないとか、就職しても退職する
船員はいるかもしれないが、それは仕方のない事。
船員でない従業員は厳し可能性はある。航路を引き継ぐ自治体や海運会社でダブル仕事の従業員は必要ない。人材不足で、必要であれば、
採用される可能性はあるが、コストを抑えて船を運航しようとすれば、必要のない人材は取らないであろう。
「五島産業汽船は8月中旬に1回目の不渡りを出し、苦境に陥っていた。だが男性は『会社が危ないとのうわさも聞かなかったし、(運休を)まったく予想していなかった。自分以外の人も知らなかった様子だった』と話す。」
不渡りを出せば良い事など何もない。だから会社や経営者は不渡りを出さないように努力するのである。会社が危ないとのうわさがなくても多少の準備や覚悟が必要なのではと思う。
まだ、新聞の記事では「倒産」と書かれていないので倒産ではないのかもしれないが時間の問題ではと思う。結果が出た以上、なるようにしかならない。
後は、個々の運や努力で新しいスタートに決めるしかない。
五島産業汽船(長崎県新上五島町)の突然の運休に伴い、同社に解雇された従業員の男性が3日までに長崎新聞社の取材に応じた。「同僚もみんな驚いている。寝耳に水の状態」と困惑ぶりを語った。
運休前日の1日、男性は朝から普段通りに働き、乗船予約も受け付けていた。ところが夕方になり、会社側は「不渡りを2回出して経営状態が悪化した」と突然解雇を通告したという。
五島産業汽船は8月中旬に1回目の不渡りを出し、苦境に陥っていた。だが男性は「会社が危ないとのうわさも聞かなかったし、(運休を)まったく予想していなかった。自分以外の人も知らなかった様子だった」と話す。
乗船券を購入した利用者に払い戻しもできていない。「従業員は笑顔を意識し、お客さまに気持ちよく利用してもらうことを心掛けていた。どう謝罪していいか分からない」と気に病んでいる。
10月の給与が支給されるかどうかも分からない。「解雇通知が2~3週間前ならば身の振り方を考えられた。年齢によっては再就職の見通しが立たない人もいるだろう」と憤る。自身の今後については「まったく分からない」と途方に暮れた。
長崎、佐世保と五島列島を結ぶ五島産業汽船(長崎県新上五島町、野口順治社長)は2日、全航路で船の運航を停止した。資金繰りが悪化し経営破綻したとみられる。従業員は同日までに解雇された。離島の生活や経済を支える重要航路は再開の見通しが立っていない。
関係者によると、五島産業汽船は8月中旬に1回目、10月1日に2回目の不渡りを出し、銀行取引停止処分になったもようだ。
九州運輸局によると、五島産業汽船は9月25日、佐世保(鯨瀬)-上五島(有川)の廃止を届け出た。さらに10月1日、長崎-上五島(鯛ノ浦)と佐世保(鯨瀬)-五島(福江)の休止届も提出し、休止期間を31日から1年間としていた。いずれも経営上の理由としており、九州運輸局は受理した。
海上運送法に基づき休止や廃止の届け出は30日前と規定されている。九州運輸局は「休止や廃止の前例は他にもあるが、これほど急なのは聞いたことがない」と戸惑っている。
五島産業汽船は1日に長崎県に運休を伝えた。2日は朝から本社や各港の営業所が閉め切られ、窓口に「会社都合につき、しばらくの間運休いたします」と通知が張り出された。突然の運休に利用者は困惑し、長崎県や関係市町も五島産業汽船と連絡が取れない状況が続いた。
五島産業汽船は五島列島航路のほか、7~11月の週末に長崎-天草(崎津)を試験運航している。関連会社USAポートサービスが運航している上五島(有川)-小値賀-佐世保(宇久平)定期航路も2日から運休した。
五島産業汽船の昨年の利用者数は、長崎-上五島10万9500人、佐世保-上五島5万6800人。昨年5月に開設した佐世保-五島は8月までに約3万人が利用した。東京商工リサーチ長崎支店によると、五島産業汽船は船舶売買に伴う損失などにより、今年4月期決算で約2億9千万円の赤字を計上していた。
新上五島町の江上悦生町長は「運休の事態になって残念。関係機関の協力を得て、一日も早い運航再開に向け最善を尽くしたい」と話した。
五島列島と長崎、佐世保市などを結ぶ五島産業汽船(新上五島町有川郷)が全航路の営業を突然休止した2日、利用者からは「驚いた」「きちんと理由の説明を」など戸惑いの声が聞かれた。島民にとって生活の一部になっている離島航路。運航を維持する経営面の難しさが改めて浮き彫りになった。
「会社都合につき、しばらくの間運休いたします」。長崎港ターミナルビル(長崎市)にある同社のカウンターには「お知らせ」と題した1枚紙が貼り出されただけ。ブラインドは閉まったままで暗く、従業員の姿はなかった。
カウンターを訪れた長崎市の60代女性は、同社グループの旅行会社を通じて五島列島を旅するツアーを申し込んでいたが、1日夜になって「従業員不在のため2日は入金が受け付けられない」との電話連絡を受けたといい「旅行はパーになってしまったね」と苦笑い。
同社のルーツをたどると、上五島と長崎市を結ぶ航路が九州商船の奈良尾(上五島南部)発着便しかなく、不便を強いられた上五島北部の住民有志が鯛ノ浦-長崎の航路開設を目指して事業を起こした経緯がある。
同社が運航してきた旅客船のうち、2隻の高速船を所有する新上五島町の江上悦生町長は2日、県庁を訪れ、担当部局や県議らと協議。報道陣の取材に「潜伏キリシタン関連遺産を訪れる観光客が増えている中で残念だ。(航路を)再開させるための手法を国や県と詰めたい」と胸中を明かした。
同じく五島列島と長崎市などをフェリーや高速船で結ぶ九州商船がストライキのため欠航した昨年末、五島産業汽船が代替輸送した実績があり、九州商船は「自社航路で増便できないかなど柔軟な対応を検討している」という。
五島産業汽船の航路廃止と休止について、ツイッターには「非常にショック。地元のために役に立っていただけに」「年末年始やお盆時期の帰省にもかなり影響が出るだろうな」などの反応が相次いだ。
=2018/10/03付 西日本新聞朝刊=
韓国造船業界の今年1~8月の受注実績が日本と中国の受注実績を合算したものよりも多いことが明らかになった。
7日、英国の造船・海運分析機関であるクラークソンによると、韓国は1月から8月まで累積受注額156億5800万ドル(172隻、756万4977CGT)を達成して世界1位を占めた。
中国は106億1400万ドル(268隻、570万1687CGT)、日本は27億9100万ドル(85隻、203万6556CGT)をそれぞれ記録した。中国と日本の累積受注額を合わせると134億500万ドルになるが、韓国にはあと約23億ドル及ばない。
このような韓国の好実績は、LNG船のような高付加価値船舶の受注が増加しているためだという。中国はバルク船中心の受注を確保しているが、高付加価値船舶の受注は韓国におされている。また、LNG船の価格上昇も韓国の受注実績にプラスの影響を及ぼした。
愛媛県新居浜市の新居浜海上保安署は28日、新居浜港に有害物質を流したとして海洋汚染防止法違反の疑いで、広島県尾道市の三谷海運と同社が管理する菱日丸船員の鎌田雅生1等航海士(45)=東京都足立区=を書類送検した。鎌田1等航海士は「少量なら流しても影響はないと思った」と容疑を認めている。
書類送検容疑は3月3日、有害物質の過酸化水素溶液を菱日丸から新居浜港に陸揚げした後、配管に残っていた約10リットルを洗浄水で流し、海に排出した疑い。
同海保によると、鎌田1等航海士は有害液体汚染防止管理者だった。別の業務で海上にいた海上保安官が、菱日丸が排水用のホースを垂らしているのを見て発覚した。
「休暇後に生き残りに向けた闘争を準備しなければならない時間が来ます。熱帯夜で眠れないです」。
8日に全国金属労働組合現代重工業支部のホームページにある組合員がこうした書き込みをした。現代重工業とサムスン重工業、大宇造船海洋の造船大手3社造船会社は先月30日から今月10日まで1~2週間の夏休みに入った。楽しくなければならない夏休みがこのように沈鬱になったのは人材構造調整と賃金団体交渉などで労使対立が予告されたのが理由だ。
12日の造船業界によると、韓国の造船大手3社が下半期に計画している人員縮小規模は少なくとも3000人を上回る。現代重工業は2014年10月にアラブ首長国連邦から受注した海洋プラント(海洋原油ボーリング設備)を今月19日に引き渡すと、蔚山(ウルサン)造船所に残る海洋プラントの仕事はなくなることになる。中国などに押され3~4年にわたり海洋プラント工事を1件も受注できなかった。このため現代重工業の海洋プラント工場は20日から稼動が中断される。
現代重工業関係者は「すでに下半期から仕事不足により余剰人材が発生しており、循環休職・休業などを実施したほか、4月には700人ほどに対する希望退職を実施した。海洋プラント工場の稼動が中断すればここで働いていた2000人ほどに対する処理案も決めなければならないだろう」と説明した。
サムスン重工業も人材構造調整を予告した。同社は2016年に債権銀行に経営改善計画を提出して生産人材を5000人ほど縮小すると明らかにした。しかしこれまで縮小された人数は3400人ほどだ。サムスン重工業はまた、当時債権団に2016年から2018年までに160億ドル以上の受注実績を達成すると明らかにしていたが、現在の受注実績は100億ドルにすぎない。このため下半期に最小1000人、多くて2000人に達する人員縮小があると予想されている。
大宇造船海洋もやはり受注金額20億ドルに達する海洋プラント「ローズバンクプロジェクト」の入札で脱落する場合には受注目標達成に「赤信号」が灯ることになり、人員縮小を避けられなくなる。
韓国の大手造船会社は今年液化天然ガス(LNG)運搬船、超大型タンカーなど一部領域では受注が増えた。しかし現代重工業とサムスン重工業は上半期にそれぞれ2995億ウォンと1483億ウォンの営業赤字を出すと予想した。両社とも前年同期と比較すると赤字に転落することになる。
中堅造船会社の状況はさらに厳しい。STX造船海洋は社宅や鎮海(チンヘ)工場の敷地など2600億ウォン規模の非営業用資産を売却して船舶建造資金確保に乗り出しているがこれすらも難航している。債権団の新規支援が途絶えたこの会社は独自に資金を調達できなければ船舶建造の仕事を受けることができなくなり経営正常化が難しくなる。
韓国輸出入銀行海外経済研究所によると、上半期に韓進(ハンジン)重工業、STX造船海洋、城東(ソンドン)造船海洋、大韓造船、SPP、大鮮(テソン)造船、韓国ヤナセなど中規模造船会社10社が受注した船舶は合計12隻、27万3000CGT(標準貨物船換算トン数、高付加価値船舶に高い加重値を適用した重量単位)にとどまった。前年同期より23.5%減った数値だ。
専門家らは下半期の造船業危機を克服するには公共発注を増やして手持ち工事量不足に対応しなければならないと強調する。また、大手と中小の間の緊密な生態系構築により世界的な環境規制で拡大する親環境船舶への転換市場を機会にしなければならないと助言した。
産業研究院のイ・ウンチャン副研究委員は「下半期は生産の側面で最悪の時期になるだろう。官公船のLNG燃料推進船発注と、軍・海洋警察の公共発注により内需需要を活性化し、韓国の海運会社の老朽船舶の親環境船舶への置き換えを誘導して中堅造船会社の競争力を高めなければならない」と強調した。
中国でLNG燃料のバルクキャリアが建造されたそうである。実際、問題なく運航されているのだろうか?
検査に合格しても問題があるのかは別問題だと個人的に思う。


199総トン型タグボート型の消防救助艇は約14億円だそうです。破格に高い仕様だ。タグボートして使うのはもったいないな! 維持、管理費も普通の消防装置が付いたタグボートと違って高そうだ。
東京消防庁は24日、火災などに遭った船を押したり引いたりできるタグボート型の消防救助艇「おおえど」の就航式を晴海客船ターミナル(東京・中央)で開いた。国内の消防機関でタグボート型の消防艇を導入するのは初めて。都は大型クルーズ船を受け入れられる新埠頭の建設を進めており、大型船の入港増が見込まれる東京湾での消防力を高める狙いがある。

消防救助艇は火災が起きた船舶に放水したり、船客を避難させたりする。おおえどには、船を押し引きする機能があり、被災船舶を岸につけて陸上の消防隊と連携したり、出火箇所を風下に向けて延焼を防いだりできるという。
総トン数は198トンで、全長37.6メートル、全幅9.7メートル。就航式では新装備のプロペラを使ってその場で360度旋回したり、被災船舶から船客を避難させるかご(バスケット)を動かしたりと、新機能をお披露目した。導入費用は約14億円。
【福岡】福岡造船(福岡市中央区、田中敬二社長、092・751・9271)は臼杵造船所(大分県臼杵市)の発行済み株式の90%超を取得した。取得額は非公表。化学品や薬品などを運ぶケミカルタンカーの建造に強みを持つ両社のグループ化により、資材の共同購入によるコスト低減や設計開発力の強化などを図る。
福岡造船は福岡と長崎に造船所を持ち、2017年3月期の売上高は約432億円。国内外の造船所による受注競争が激化し、騒音規制や排ガス規制など世界的な環境基準に対応した設計開発力の向上が求められる中、1月には渡辺造船所(長崎市)の全株式を取得し子会社化するなど、提携強化の動きを進めている。
ギリシャのヘレニック造船所が倒産した。日本の船主や日本にとっては関係ない事だと思う。
ギリシャ人の船長や監督と話した時は、現場で働く人間は怠け者だからと言っていた。以前に倒産、又は、経営者が変わっていると言っていた。怠け者の基準は、アジアの造船所を比べての意見のようだった。
休憩が多いとか、動きが遅いとか言っていたけど、労働者側の立場から判断すると良い事。
会社が倒産すれば、現場で働いている労働者達にも影響が出る。実際、労働者達はどのように考えているのだろう。
Thomas Novelly
Jeffboat, one of the largest inland shipbuilders in the country, is closing its doors.
President and CEO Mark Knoy said in a statement it will close after it finishes construction of remaining barges by the beginning of May.
"With orders running out and no future backlog of business, the shipyard will launch its last barge sometime in the middle of April," Knoy said.
Jeffboat announced in November it would lay off 278 workers.
The closure comes in the midst of a heavy lull in the barge industry, according to the statement. At its peak, Jeffboat hired more than 1,300 employees. Currently, it has around 220 employees, the statement said.
"For me, this is heartbreaking news that the Boat Yard will be closing," said Jeff Cooper, a former worker at Jeffboat and recording secretary for the Teamsters, which represents hourly workers at the company.
"Like so many others, I started my career there as a young man working as a first-class welder and pipe-fitter. I have met so many great people over the course of time there," Cooper said in a statement released by the company Monday morning.
Jeffersonville Mayor Mike Moore said he grew up in the town in the 60s and 70s. Townspeople were familiar with the train whistles at the shipyard and life, in a way, revolved around Jeffboat's schedule. He even played on Jeffboat's little league team as a child.
"If your mom or dad didn’t work there then your neighbors did," Moore said. "It was the company that built Jeffersonville. It’s sad to think that the day will come where that company is a distant memory."
Jeffboat began operating in 1834. The company also owns American Commercial Barge Line LLC, which operates 3,600 barges and 140 boats. Knoy said ACBL would not be affected by Jeffboat's closure.
“While we’re very sorry that market conditions have left us with no choice but to close
Jeffboat,” Knoy said, “The shipyard closure will not have an impact on ACBL’s barge freight business or its customers, vendors, and teammates.”
Jeffboat has not decided what it will do with its 65 acres of riverfront property, but a statement from One Southern Indiana, the local chamber of commerce asks for a modern development of the former property.
“We implore the officials of Jeffboat to consider the community, its needs and the future of regional business and talent attraction and retention, when creating a transition plan for the 80-acre property with one mile of river front currently occupied by the shipyard.," President and CEO Wendy Dant Chesser said in a statement.
Jim Kincaid, the assistant to the President of Teamster's 89, said he was a former worker at Jeffboat and was sad to see it close.
"It's a very sad day for a lot of hard-working, ship-building craftsmen and craftswomen," Kincaid said in the statement. "I worked beside a lot of these folks for many years through the most extreme weather anybody can imagine ... Words can't express how saddened we are that this historical shipyard is closing its doors."
(Bloomberg) -- 国内最大の海運会社、日本郵船は13日夜、中国の連結子会社で不正支出事案が判明し、2018年3月期連結純利益予想を20億円程度押し下げる見込みだと発表した。
郵船の発表資料によると、不正があったのは完成車輸送事業を手掛ける中国子会社「NYKカーキャリア」(上海市)。現地採用の元幹部らによる業務上横領などの疑いが生じており、同社は5日付で内藤忠顕社長を委員長とする調査委員会を設置、調査は現在も進行中としている。
同社は2017年4-12月期業績を1月31日に発表。世界的な荷動きの増加に伴う海運事業の運賃上昇で業績は好調に推移し同期の純利益は168億円で、通期純利益は110億円を見込むとしていた。今回の問題を受けて過年度と今期業績への影響については、内容が確定次第 、速やかに開示するとしている。また金融庁への提出期限を迎える四半期報告書の提出期限は14日だが、延長申請も含め検討する方針だ。
同社広報担当者の木幡龍太氏はブルームバーグの取材に対し、昨年11月に中国の税務当局からの問い合わせがきっかけで不正事案が発覚。調査の報告書が郵船経営幹部に届いたのはことし1月末と明かした。調査では、中国人の元幹部ら約10人が関与し、完成車輸送のトレーラーの費用などの水増しや架空請求などの不正会計行為で収益を着服していたことが明らかになったという。
その上で、木幡氏は、さらに当時この子会社には日本人社員はおらず、また郵船社員の関与もないと述べ、「現在も事実関係の究明のため慎重に調査を進めている。金融庁や証券取引所への対応は今後決まり次第発表する」と語った。
日本郵船は14日、2018年3月期第3四半期報告書の提出期限を同日から3月23日までに延長するよう関東財務局に申請した。中国の連結子会社で業務上横領など不正な費用支出が行われた可能性があると判明したため。日本郵船は「連結決算の最終損益への影響は、現時点では累計で総額約20億円程度の損失が生じる可能性がある」と見込んでおり、確定次第、速やかに開示するとしている。
日本郵船は13日、中国の連結子会社に対し、業務上横領などの疑いで調査を始めたと発表した。現地採用の元幹部らが不正な支出を行った疑いがあるという。連結決算の最終損益への影響は現時点で総額20億円程度を見込む。
5日付で社内に調査委員会を設置した。14日が第3四半期報告書の提出期限で、調査の進展次第で延長申請も検討する。(共同)
川崎市は25日、老朽化した市の巡視船「つばめ」(約28トン)の後継船が完成したものの、船体が重すぎて市の求める速度が出ないため、業者との建造契約を解除すると発表した。当面、「つばめ」を使い続けるという。
市によると、「つばめ」は1974年建造。湾岸部の工場地帯を海上から巡視してきた。老朽化したため市は30トン級の船の新造を決め、入札を経て2016年春、横浜市の造船会社と契約を結んだ。建造費は約2億7200万円。就航予定は17年4月で、名称も「かもめ」と決まっていた。
同社は17年3月、市から求められた「19ノット以上」の速度が出るか試験運航をしたところ約14ノットしか出なかった。重さは30トンの計画だったが45トンあった。軽量化を試みたが昨夏の試験でも14ノット止まり。今月に入り、市に「納品断念」の連絡をしてきたという。
同社は「建造時、重量の管理をきちんとしていなかった」と説明しているという。市が建造費を負担することはないといい、賠償金のほか、運航が続く「つばめ」の使用・維持管理の費用も同社が払うという。
市の担当者は「こんな事態は聞いたことがない」と驚き、「新たな船を極力早く造る」と話している。(斎藤茂洋)
造船大手の今治造船は中堅の南日本造船(大分県臼杵市)を買収する。南日本造船の主要株主である三井造船と商船三井が12日発表した。両社の持つ南日本造船の株式を今治造船が取得し、4月1日付で事業を引き継ぐ計画で、正式契約に向け協議を進める。買収金額は明らかにしていない。
南日本造船は自動車運搬船やタンカーを手掛け、臼杵市や大分市に工場を有している。三井造船が発行済み株式の25%、商船三井が24%を持っている。今治造船は、雇用などは維持する方向で協議するもようだ。
三井造船は2017年3月期連結決算で、船舶部門の営業損益が97億円の赤字だった。事業の縮小に向け南日本造船の株式を売却するとみられる。
建造量で国内首位の今治造船は昨年、国内で17年ぶりに新設の大型ドックを完成させた。大型コンテナ船を建造し国際競争力を高めようとしている。(共同)
造船業界で国内最大手の「今治造船」は、生産能力を高めて国際競争力を強化するため、「三井造船」の傘下で大分県に本社を置く「南日本造船」の事業を買収することで合意したと発表しました。
発表によりますと、今治造船は、三井造船の傘下で大分県臼杵市に本社を置く南日本造船の事業をことし4月1日付けで買収することで、三井造船や南日本造船などと基本合意しました。各社は今後、買収額や株式の譲渡割合、それに、南日本造船の従業員を引き継ぐかどうかなど、具体的な条件について協議を進めるとしています。
南日本造船は、自動車運搬船やタンカーを中心とした船の建造や修理などを手がけ、年間の売り上げは200億円余りに上ります。
今回の買収で今治造船は、生産能力を高めて国際競争力を強化する狙いがあります。
一方、三井造船は、不振が続く造船事業の見直しを進めていて、官公庁向けの船や環境に配慮した商船などの得意分野に経営資源を集中させて事業を立て直したい考えです。
国内の造船各社は、中国や韓国企業との競争で厳しい経営環境が続いていて、コストを削減するために提携したり、事業を見直したりする動きが広がっています。
宮崎カーフェリーは、地域経済活性化支援機構が、同社に対し再生支援を決定したと発表した。会社分割で新会社に事業と船舶を移し、同社は承継・船舶譲渡対価を原資として債権者に弁済を行う。新会社は運賃の適正化、稼働率の改善などに取り組むとしている。
同社は、「現在使用している船舶も建造後約20年が経過しており、老朽化とともに時代のニーズにお応えできない状況にあり、増加している上り便のトラック需要や客室の個室化など、新船の建造が経営の喫緊の課題となっていた」としたうえで、「支援機構に加えて、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、日本政策投資銀行、宮崎県信用農業協同組合連合会、東郷メディキットなどの地元行政機関、地元金融機関、地元経済界の皆様のご支援を受け、リプレースを実現することが、これまで以上に地域の発展に貢献することができるものと確信し、今回の支援決定の運びとなった」とコメントした。
宮崎港と神戸港の間でフェリーを運航している「宮崎カーフェリー」が多額の債務を負っているとして、航路を維持するため、宮崎県や地元の経済界、それに官民ファンドの「地域経済活性化支援機構」などが新会社を設立して事業を移し、支援していくことになりました。
宮崎市に本社があるフェリー会社「宮崎カーフェリー」は、全長170メートルの2隻の船で宮崎港と神戸港の間を1日2便運航し、この航路は県産の農作物や畜産品を積んだトラックを関西圏や首都圏へ運ぶ、宮崎県にとって重要なルートになっています。
「地域経済活性化支援機構」によりますと、2隻の船は就航からおよそ20年が経過し老朽化していて、航路を維持するためには新しい船が必要ですが、「宮崎カーフェリー」は関連会社も含めると多額の債務を負っていることから費用の調達が難しく、財務状態の抜本的な改善が欠かせないということです。
このため、宮崎県や宮崎市、地元の経済界、それに「地域経済活性化支援機構」などが出資して新会社を設立し、支援していくことになりました。
今後、新しい会社に従業員や現在使っている船を移して来年3月をめどに新体制に移行し、運航を続けながら5年後の2022年ごろに新しい船の就航を目指すとしています。
また、現在の会社の債務は、債権者に対し一部を弁済したうえで、残りについては放棄を求めるということです。
県と宮崎市は、宮崎カーフェリーが運航する宮崎ー神戸航路を維持するため、民間企業とともに新会社を設立すると発表しました。県と市は、新会社にあわせて1億5000万円を出資し、新会社は、新しいフェリーの導入を目指します。
宮崎と神戸を結ぶフェリーは、宮崎市に本社のある「宮崎カーフェリー」が、毎日1往復運航しています。県などによりますと、新会社は県と宮崎市、それに民間企業が出資して来年3月1日に設立され、老朽化が進んでいるフェリー2隻を更新し、新たなフェリーについては2022年ごろの導入を目指します。
県の出資額は、目標とする資本金11億5000万円のうち1億円、宮崎市の出資額は5000万円で、県と宮崎市は、11月開会するそれぞれの議会にこの出資額を盛り込んだ補正予算案を提出する予定です。このほか、宮崎銀行や宮崎太陽銀行、それにJAグループなどの地元経済界も出資することになっています。
(河野知事)「長期にわたって航路を安定的に運航していくためにはオール宮崎での支援体制が必要ではないか、県としても出資しながらひとつの求心力となってオール宮崎で結束する体制を作っていこうと」
(宮崎カーフェリー・黒木政典社長)「新船建造にめどがつかない状況が続いていた、新船建造を実現するためには、外部の力を借りるしかないとないという結論に達した」
新会社が設立されれば、従業員は新会社に再雇用され、現在運航している宮崎カーフェリーは負債の清算後に解散する見込みです。
大消費地と距離が離れている宮崎にとって、農産物などの大規模輸送にフェリーは欠かせません。官民が一体となった新会社設立の背景にはなにがあったのでしょうか。田中記者のリポートです。
(田中記者)「現在使われているフェリーは、約130台の大型トラックを一度に運搬可能ですが、繁忙期には積み荷を断ることもあり、船体の大型化が求められていました」
トラックドライバーが船内で休憩することのできるフェリーは、関東や関西方面に出荷される農畜産物などの重要な輸送手段となっています。しかし、青果物の出荷が増える秋から春にかけては、大型トラック約30台分の荷物が積み残しとなることが課題となっていました。
(県トラック協会・牧田信良会長)「どうしても積みきらない、今も積みきれないということが発生していますし絶対にないといけない、阪神航路はないといけない宮崎の生命線だと言ってもいいような大事な船だと思います」
(JA宮崎経済連・新森雄吾会長)「輸送コストの引き下げというのが課題なので、他の産地に比べて遠くにあるため、どうしても輸送コストがかかるというのが一つのネックだった」
就航から20年以上経過した船体は、老朽化が進み燃費も悪いため、運送コストを押し上げていて、効率の優れた新たな大型フェリーの導入が急務となっています。しかし宮崎カーフェリーには、前身のマリンエキスプレスから引き継いだ多額の負債が残っていて、100億円を超える費用がかかると試算されているフェリー2隻を造船するには、資金調達が厳しい状況が続いていました。
新会社では行政や企業のほか、官民ファンドの一つである「地域経済活性化支援機構」も1億円を出資し、債権を圧縮した上で運賃の適正化を図るなどして、新しい船舶の導入を目指す方針です。
(地域経済活性化支援機構・今井信義社長)「新船をどうやって計画通り短期のうちに仕上げていくかということが最大の懸案事項、ぜひモデルとして成功させたい」
(河野知事)「本県経済にとって本当に欠くべからざる航路ということをこれからも維持のために皆さまのご理解とご協力をいただきながら取り組んでまいりたい」
宮崎と大消費地を結び、県産品の流通に不可欠なフェリー航路。路線維持に向け、官民一体となった取り組みが加速することになります。
宮崎カーフェリー(株)(TDB企業コード:880322702、資本金1000万円、宮崎県宮崎市港3-14、代表黒木政典氏、従業員96名)と、関係会社の宮崎船舶(有)(TDB企業コード:375011978、資本金300万円、同所、同代表)の2社は、11月20日、事業を新会社に譲渡したうえで解散し、特別清算を申請する方針であることを発表した。
宮崎カーフェリー(株)は、2004年(平成16年)4月に経営難に陥った(株)マリンエキスプレス(宮崎市、登記面=東京都中央区、2005年12月に特別清算開始決定)から事業を継承する目的で設立。同年6月に宮崎港-大阪南港と、宮崎港-日向細島港-大阪・貝塚港を結ぶ2航路の営業を譲り受けて事業を開始し、2006年3月期には年収入高約60億5200万円を計上していた。
しかし、(株)マリンエキスプレスから転籍した従業員の労働債務を引き継いだこともあり、当初から大幅な債務超過を余儀なくされていた。原油高を背景とする燃料費高騰のなか、2006年4月に貝塚航路から撤退する一方、燃料油価格変動調整金(バンカーサーチャージ)の導入などで立て直しを図っていたが、2009年には高速道路料金引き下げが実施されたこともあって2010年3月期の年収入高は約46億300万円にまでダウン。同期から5期連続で経常赤字を余儀なくされるなど、債務超過額が拡大していた。さらなるコストダウンを目的に2014年10月には大阪南港発着から神戸港発着に変更したが、東九州自動車道の整備進捗とともに貨物需要が大分港に流出するなど、収益改善の見通しが立ちにくくなるなか、関係会社も含めた債務償還のメドが立たないことから、メーンバンクとともに地域経済活性化支援機構(REVIC)に支援を申し込み、11月14日付で再生支援の決定を受けた。
宮崎船舶(有)は、2003年(平成15年)8月に設立。(株)マリンエキスプレスが所有していた船舶4隻を譲り受け、(株)マリンエキスプレスおよび宮崎カーフェリー(株)に裸傭船として貸し渡していた。2006年に2隻を売却したものの、多額の債務超過に陥っていた。
負債は2社合計で推定80億円。
なお、現在もフェリーの運航は継続中。2社は今後、各々の事業を地元の自治体や企業、REVICなどが出資する新会社に分割譲渡のうえで解散し、金融機関からの債務免除を受けるために特別清算を申請する見通し。
BY CASEY CONLEY
(MOBILE, Ala.) — Horizon Shipbuilding of Bayou La Batre, Ala., has filed for Chapter 11 bankruptcy protection.
The filing, on Oct. 24 in U.S. Bankruptcy Court in Mobile, came about a month after the company announced it was losing money building high-speed ferries for Hornblower's NYC Ferry service. At the time, Horizon said it could not reach agreement with Hornblower to restructure the deal.
Court filings suggest issues with a contract to build three tugboats for McAllister Towing pushed Horizon into bankruptcy. The yard delivered the 6,770-hp tug Capt. Brian A. McAllister this summer but work had stopped on two other tugs.
The shipyard blamed the work stoppage on its "financial inability to continue without a major restructuring of the (contract) terms." McAllister responded by issuing a default notice and also warning the shipyard it planned to terminate the contract for the two remaining vessels.
"The debtor has cited the impending termination of the shipbuilding agreement as the reason for its Chapter 11 filing," McAllister's attorneys said in a court filing.
Subcontractors awaiting payment have "asserted" liens on the undelivered tugboats, according to McAllister's filing.
Horizon and Metal Shark of Louisiana won contracts with Hornblower to build 19 high-speed catamaran ferries for the New York commuter service. Horizon delivered the 10 ferries scheduled for 2017, but up to three more vessels were set for arrival next year. The status of those ferries could not be confirmed.
Meanwhile, Hornblower has hired Metal Shark to build five more ferries, including four 97-foot, 350-passenger boats.
“As Horizon works through its current situation, we wish them well," Hornblower said in a prepared statement. "Should their situation change, we would welcome the opportunity to work their them again in the future.”
Horizon Shipbuilding CEO Travis Short said Thursday that the shipyard believed its bid for the Hornblower ferries was sufficient to cover their costs. However, in February, the yard realized the vessels were requiring more labor than expected.
"Shortly thereafter the substantial use of contract labor was also necessary to support the extremely aggressive delivery schedule," Short said in a prepared statement. "Hornblower was immediately notified of the financial issues and Horizon diligently attempted to find a solution. Possible price adjustments on vessels in production at the time as well as price adjustments on future vessels were consistently provided by Hornblower, through discussions with NY EDC (New York City Economic Development Corp.), until the 10th ferry was delivered in September."
Short said issues with the McAllister tug project stemmed from cost uncertainty around building one of the first Tier 4 tugboats in the U.S.
"The resulting labor and material costs for one the first Tier 4 installations in the country were much higher than anticipated for a firm fixed-price contract without price modification," Short said, noting that the shipyard expects to emerge from bankruptcy.
"With the soft shipbuilding market, Horizon anticipates a moderate recovery but recovery remains our goal," he said. "Unfortunately, Horizon is experiencing a back-to-back loss and a Chapter 11 filing that most shipyards can appreciate but, at the end of the day, we are as good as any boatbuilder out there.”
The shipyard's Chapter 11 filing aims to restructure the company's debt rather than liquidate. Horizon said it owes money to between 100 and 199 creditors. It also lists assets between $1 million and $10 million and estimates its liabilities are within the same range.
Creditors listed in the bankruptcy filing include HNY Ferry Fleet, McAllister Towing, Markey Machinery and Schottel among many others. The news publications Maritime Reporter and Waterways Journal are among the firms Horizon owes money.
McAllister Transportation declined to comment.
ギリシャのヘレニック造船所が倒産した。日本の船主や日本にとっては関係ない事だと思う。
ギリシャ人の船長や監督と話した時は、現場で働く人間は怠け者だからと言っていた。以前に倒産、又は、経営者が変わっていると言っていた。怠け者の基準は、アジアの造船所を比べての意見のようだった。
休憩が多いとか、動きが遅いとか言っていたけど、労働者側の立場から判断すると良い事。
会社が倒産すれば、現場で働いている労働者達にも影響が出る。実際、労働者達はどのように考えているのだろう。
The Greek state has filed a petition with an Athens first instance court requesting insolvency proceedings against the troubled Hellenic Shipyards S.A at Skaramangas under the newly revised bankruptcy code, which foresees the rapid sale of assets and withdrawal of old shares.
The move comes in the wake of a decision by an international arbitration tribunal in favor of the current French-Lebanese group that runs the shipyards, and with the latter pointing to a complete vindication in its lengthy legal tussle with the Greek state.
Privinvest, in fact, called on the Greek state to respect the court’s ruling and warned of further legal claims, both in Greek courts and international venues.
In terms of the latest development, Deputy Economy Minister Stergios Pitsiorlas, the previous head of Greece’s privatization agency (HRADF), said discussion over the bankruptcy petition is scheduled for mid November, assuming the court accepts the petition.
The Privinvest group last week said it was expecting compensation from the Greek state of between 150 to 200 million euros, following to a ruling in favor of the company by the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce.
The case before the international tribunal pitted the French-Lebanese Safa family, which controls Privinvest, against the Greek state. The former charged that the Greek state had failed to meet contractual agreements worth hundreds of millions of euros following Privinvest’s purchase of the Piraeus-area Hellenic Shipyards in 2010
Among others, Privinvest executive Iskandar Safa had sought arbitration in his capacity as an individual investor in the company, while the same dispute extends to a bilateral investment pact between Lebanon and Greece.
Source: Naftemporiki / By A. Tsimplakis
川崎重工は、ノルウェーのオフショア作業船の主要船社であるIsland Offshore Shipholding LPグループ(以下、アイランドオフショア社)の子会社との間で、オフショア作業船1隻の造船契約を締結しています。
現在、海洋関連企業の多くは、原油価格の低迷により厳しい経営環境に直面しています。アイランドオフショア社は通常通り事業を継続していますが、昨年11月以降、金融債務の元本償還を一時停止し、取引銀行団と債務繰延について協議中であり、本年6月末を目途に取り纏める予定と公表されています。
当社としましては、今後の動向を注視するとともに、何らかの大きな動きがあった場合には改めてお知らせします。
Two shipping companies based in Egypt and Singapore pleaded guilty today in federal court in Beaumont, Texas, to violating the Act to Prevent Pollution from Ships (APPS) and obstruction of justice for covering up the illegal dumping of oil-contaminated bilge water and garbage from one of their ships into the sea.
Acting Assistant Attorney General Jeffrey H. Wood for the Department of Justice Environment and Natural Resources Division and Acting U.S. Attorney Brit Featherston for the Eastern District of Texas, announced the plea agreement. The agreement includes a $1.9 million dollar penalty and requires marine and coastal restoration efforts at three National Wildlife Refuges located on the Gulf of Mexico in East Texas, where the offending vessel transited and made port stops.
“This case involved egregious violations of U.S. and international laws that are key to protecting the oceans from pollution, and deliberate efforts to mislead U.S. Coast Guard officials about these criminal acts,” said Acting Assistant Attorney General Wood. “The Department of Justice will continue to aggressively prosecute criminal acts that pollute the oceans.”
“Intentional acts of pollution in the Gulf of Mexico and Texas wetlands will not be tolerated, and violators such as defendants, Egyptian Tanker Company and Thome Ship Management, will be held responsible for their conduct,” said Acting U.S. Attorney Brit Featherston for the Eastern District of Texas. “Our citizens depend on clean water for their recreation and their livelihood. This kind of irresponsible conduct threatens both.”
Defendants Egyptian Tanker Company and Thome Ship Management are the owner and operator of the 57,920 gross ton, 809-foot long, ocean-going, oil tank ship called the M/T ETC MENA. Large ships like the M/T ETC MENA generate oil-contaminated bilge waste when water mixes in the bottom or bilges of the ship with oil that has leaked from the ship’s engines and other areas. This waste must be processed to separate the water from the oil and other wastes by using pollution prevention equipment, including an Oily Water Separator (OWS), before being discharged into the sea. These large ships also generate garbage, including ash from the incinerators, steel, and other non-organic wastes, which are collected in plastic bags and stored onboard until they can be disposed of properly at shore-side facilities. APPS requires that the disposal of the ship’s bilge waste and garbage be fully recorded in the ship’s Oil Record Book and Garbage Record Book.
The investigation began on April 26, 2016, when the U.S. Coast Guard’s Marine Safety Unit in Port Arthur, Texas, received information from a crew member on the M/T ETC MENA that the ship had illegally dumped bilge waste overboard into the ocean. The crewmember provided a written statement, photographs, and video of the alleged conduct. During the inspection of the ship that same day, the Coast Guard found a pump covered in oil submerged in the ship’s bilge primary tank that looked similar to the pump that the crew member said was used to pump the bilge waste overboard.
“Environmental crimes put the marine environment and our natural resources at risk,” said Rear Admiral Dave Callahan, Commander, Eighth Coast Guard District. “This case serves as another example that the United States will not tolerate these actions and violators will be held accountable. Coast Guard Marine Safety Unit Port Arthur, the Coast Guard Investigative Service, and the Department of Justice should be commended for their tireless efforts and cooperation in investigating and prosecuting this case.”
In pleading guilty, the companies admitted that its crew members bypassed the ships OWS and discharged bilge water into the ocean in March 2016 without it first passing through this pollution prevention equipment. The government’s investigation also revealed that crew members were instructed to throw plastic garbage bags filled with metal and incinerator ash into the sea in March 2016. The discharge of bilge water without using the OWS and of plastic garbage into the ocean was not entered into the ship’s Oil Record Book and Garbage Record Book in violation of APPS. The companies also pleaded guilty to obstruction of justice for presenting these false documents to the Coast Guard during the inspection in Port Arthur, Texas.
The companies will be placed on a four-year term of probation that includes a comprehensive environmental compliance plan to ensure, among other things, that all of ships operated by Thome Ship Management that come to the United States fully comply with all applicable marine environmental protection requirements established by national and international laws. The compliance plan will be implemented by an independent auditing company and supervised by a court-appointed monitor.
Assistant U.S. Attorney Joseph R. Batte of the Eastern District of Texas, Senior Trial Attorney David P. Kehoe, and Trial Attorney John D. Cashman at the Environmental Crimes Section of the Department of Justice prosecuted the case. The case was investigated by the Coast Guard’s Investigative Service.
ジェットフォイルに限らず、特殊船やあまり建造されないデザインの船の建造価格が高くなる傾向は止まらないであろう。
日本の人件費が上がり続ける限り、効率化や利益率を無視する事は出来ない。頻繁に建造されない船は、同じサイズの船であっても、
建造するとなると契約、建造、キール日などにより適用される規則が増えたり、厳しくなる傾向が高い。これが逆行する事はないと考えてよい。
技術の継承や経験の継承にも見えないコストが掛かる。次にいつ建造するかわからない船に関して引き継ぎ作業を行うと、実際に建造する時に
見えない費用が入っている場合があると思う。経営判断によっては建造の話が来た時に考えれば良いと思っている造船所もあるだろう。
結果、どちらの方法であっても、違いはあれ、コストアップになる事は避けられない。間隔があまりにも長くなると、建造は可能かもしれないが
コストを考えれば建造のメリットがあるのかと言うレベルになるかもしれない。
いろいろな事を考慮して、妥協や断念も選択肢に入っていれば、それほど騒ぐことではないと思う。船の高速化は良い事ではあるが、
コスト、要望そしてコストの受け入れのバランスだと思う。高速化よりもコストダウンを多くの利用者が望めば、それはそれで良いと思う。
少子化や人口減少が鈍化する事があっても逆行する事はないので、一般的に考えれば将来的な利用者も減ると思う。
生産が中止されているジェットフォイル
東海汽船が川崎重工に発注する超高速船ジェットフォイルの新造船建造が話題を呼んでいます。
そのおもな理由は、時速45ノット(約83km/h)を誇るジェットフォイルが、造船業の常識を超える25年ぶりの新造となること、推進システムなどが従来と同等でありながら、建造価格が51億円と25年前に比べてかなり高額になっていること(バリアフリー化など内装の刷新といった改良が行われているものの)、川重がこれを契機に高速船の量産体制に移行できるかということ、そして同船の船体デザインを2020年「東京オリンピック」のエンブレムデザイナー野老朝雄(ところあさお)さんが起用されること、です。
ジェットフォイルは、毎分180トンもの海水を取り込み、これを噴出すること推力を得て前進する高速船で、港を出ると翼走に移るという船ならぬコンセプトの「船」で、航空機メーカーのボーイングが1960年代に開発しました。
その後、1989(平成元)年からは川重が独占建造するライセンスを取得。以降、1995(平成7)年まで神戸工場で計15隻を建造しました。
川重は、「当初から多くて20隻程度」と見込んでいた分を建造したことから、「需要が一巡した」との判断で生産を中止していました。
しかし、ボーイングで建造された28隻を含めて、多くが老朽化してきたことから、運航する船会社からは建造再開を求める声も多く、数年前から代替建造の計画で造船所との交渉が進められていました。
生産中止のジェットフォイル、「修理用」を活用して新造を実現
ただ、この船の基幹推進システムであるウォータージェットの生産が「少なくとも5隻分のロットが集まらないと生産再開はできない」(川重)という状況が続き、新造船商談は実現せず、運航会社は既存航路の中古船を転配するなどでしのいできました。
実際、2015年に東海汽船が投入した「セブンアイランド大漁」は、JR九州が1994(平成6)年に建造した「ビートル5」を購入したものです。
今回の新造船は、船齢36年を迎える東海汽船のジェットフォイル「セブンアイランド虹」の代替を考えたものです。数が集まらないと生産再開が難しいウォータージェットシステムについては、就航船の修理用などで用意していたものを準用。それにより、ジェットフォイルの新造が実現しました。
ただ東海汽船では、この「虹」の代替でジェットフォイルの建造を終了するつもりはなく、さらに「セブンアイランド愛」などの後継船建造を進めたいという希望を持っています。
しかし東海汽船によると「当社だけで、川重の求める隻数を確保することはできません」といい、そのため同社は佐渡汽船、JR九州、九州郵船、鹿児島商船など、今回の新造をきっかけにジェットフォイル運航各社が足並みをそろえられないかどうか、検討を求めています。
「離島航路の高速化は(住民生活の維持のためにも)有効です。地方自治体にもジェット船を整備する必要性をご理解いただき、ご支援をいただければ」(東海汽船 山崎潤一社長)
造船事業の縮小を発表したばかりの川重ですが、これら特殊船、高速船の建造を通じた生産品目の多様化が実現できるかも、注目されています。
2020年、オリンピックで東京湾もにぎやかに?
また今回の新造船について、東海汽船では2020年のオリンピック開幕までに就航させることもあって、船体のデザインをそのエンブレムをデザインした野老朝雄さんに依頼することを決めました。
これまで東海汽船のジェットフォイルは、すべて、船好きの画家として高名な故・柳原良平さんが手掛け、その斬新さが親しまれていましたが、このたびの「虹」の代替船については、新しいコンセプトが必要になるとの考え方から、オリンピックエンブレムのデザイナーである野老さんを起用することになったものです。
東海汽船はさらに、在来型の貨客船「さるびあ」の新造も計画。同船は2020年7月就航を目指し、三菱重工下関造船所と交渉に入りました。東海汽船は、関連の小笠原海運などを含めて継続してきた新造船整備計画を、オリンピックまでに一段落させる計画。どうやら「オリンピックイヤー」の2020年は、東京港も明るい話題で包まれることになりそうです。
若勢敏美(船旅事業研究家)
5月13日午後、尾道市瀬戸田町の造船所で、湯沸かし器の水漏れを修理していた男性作業員が死亡する事故があった。13日午後3時ごろ、尾道市瀬戸田町にある「内海造船」で、60歳の男性作業員が船の中にある湯沸かし器を修理していたところ、部品が外れ男性の頭を直撃した。男性は病院に運ばれたが、まもなく死亡が確認された。「内海造船」では、一昨年も塗装中の男性作業員が転落し、死亡する事故が起きている。(TSS)

Company builds tanks used to carry LNG at the site
TOKYO -- Japan's IHI will cease production of offshore structures at its Aichi Works shipyard, after delays at the site resulted in sinking profits for the company.
The shipyard no longer takes new orders, with the facility to terminate production after completing its last SPB tank, an aluminum tank used to carry liquefied natural gas on ships. IHI will relocate the shipyard's 400 to 500 workers to other units and consider alternative uses for the site.
IHI sees promise in the SPB tank business and aims to develop it elsewhere.
The Aichi Works, established in the 1970s, boasts a dock spanning 800 meters with the capability to construct supertankers back to back.
In 2013, a slowdown in the industry led IHI to establish shipbuilder Japan Marine United with JFE Holdings. Meanwhile, IHI's marine segment shifted focus to high-value-added products, winning orders for complex structures such as offshore drilling ships.
But after continuous production delays, ballooning construction costs drove the company's net profit down to 1.5 billion yen ($13.6 million) for fiscal 2015. A year later, IHI scrapped dividends for the first time in eight years.
Japanese companies once held more than half of the world's market share for shipbuilding. But the rise of South Korean and Chinese rivals has sent that figure falling to around 20%. Kawasaki Heavy Industries is also preparing to close a site in Kagawa Prefecture.
【ソウル時事】韓国南東部・巨済島にあるサムスン重工業の造船所で1日午後、建設中の海洋プラントの上にクレーンが倒れた。
聯合ニュースによると、この事故で作業員6人が死亡、22人が重軽傷を負った。
クレーン同士が接触して倒れたとみられており、警察は、クレーンの接触を避けるための措置が適切だったかどうかなどを調べている。
韓国ではこの日、「勤労者の日(メーデー)」で休日だが、作業員は休日特別勤務中に事故に遭ったという。
South Korea’s Samsung Heavy Industries is to delay the construction a jackup rig being built at the shipyard after a rig leg was severely damaged.
26日、尾道市の造船所で意識不明の状態で見つかったタイ国籍の男性技能実習生が27日朝、死亡しました。
死亡したのは、タイ国籍の技能実習生で33歳のプラウオンアートンさんです。
プラウオンさんは、26日尾道市瀬戸田町の造船所・光洋工業で、台船内の空間の浸水確認を行っていましたが午前10時半ころ心肺停止の状態で見つかりました。
警察によりますと、意識不明だったプラウオンさんは、27日午前6時頃、病院で死亡が確認されました。
死因は低酸素脳症です。
警察は、業務上過失致死傷の疑いがあるとみて、会社の関係者に事情を聞くなどして死亡に至る経緯を調べています。
26日午前、尾道市の造船所で、タイ国籍の作業員が台船の内部で意識不明の状態で見つかりました。
救助に向かった作業員も、酸欠で一時意識不明となりました。
事故があったのは、尾道市瀬戸田町の造船所光洋工業です。
警察と消防によりますと、午前10時半頃、「男性が、船のマンホールの中3メートル下で酸欠状態で意識不明だ」と消防に通報がありました。
男性は、台船内の空間の浸水確認をしていたタイ国籍の作業員で、心肺停止の状態で病院に運ばれ、現在も意識不明の重体です。
倒れているのを発見したフィリピン国籍の男性作業員と現場監督が男性の救出にあたりましたが、フィリピン人作業員も一時意識不明となり病院に搬送。
その後、意識は回復したということです。
光洋工業によりますと、台船の内部は、長時間、蓋を閉めていると酸素濃度が低くなるため、通常は蓋を開けて、空気の入れ換えをしたりするということです。
警察が事故当時の状況や原因を詳しく調べています。
(光洋工業 出口勇樹社長)
「大変申し訳なく思っています」
「これからこういうことないよう気を付けたいです。申し訳ありませんでした」
光洋工業によりますと、作業員2人は、技能実習生です。
台船内部の空間は幅7・5メートル、長さ10メートルの広さだということです。
26日午前、広島県尾道市にある造船会社で作業員の外国籍の男性2人が酸欠と見られる症状で病院に運ばれ、このうち1人が意識不明の重体となっています。
26日午前10時半ごろ、尾道市瀬戸田町の造船会社光洋工業の瀬戸田工場で、「作業員の男性2人が酸欠になっている」と消防に通報がありました。
消防や警察によりますと、2人は病院に運ばれましたが、このうちタイ国籍の33歳の男性が意識不明の重体となっています。消防によりますと、当時、岸壁にとめた長さ45メートル、幅15メートルの台船の内部で浸水がないかを確認する作業が行われていて、中で、タイ国籍の男性が意識を失って倒れているのが見つかり、救助に向かったフィリピン国籍の25歳の男性も体調不良を訴えたということです。
現場の工場は瀬戸内海にある生口島の北部の海沿いにあり、会社のホームページによりますと、この会社は船の建造や修理のほか、船のリースを手がけているということです。警察と消防などが当時の状況を調べています。
26日午前10時半ごろ、広島県尾道市の造船会社光洋工業の工場で、作業員2人が酸欠状態になり、市内の病院に搬送された。広島県警などによると、タイ国籍の男性(33)が心肺停止の状態。もう1人のフィリピン国籍の男性(25)は、命に別条はない。
県警によると、当時、台船の中で浸水がないか確認作業をしていた。
会社は瀬戸内海の生口島にある。
大手重工3社が、事業の柱の一つだった造船・海洋事業に頭を悩ませている。受注が減ったところに工事などの失敗が重なり、各社とも大きな赤字を計上。撤退を視野に入れるなどの抜本改革案を3月中にまとめる考えだったが、足元の市況に明るさが出始めたこともあり、どこまで踏み込んだ内容になるかが注目されている。
3月中旬、三菱重工業長崎造船所(長崎市)のドックでは独企業向けの2隻目の大型客船で完成をめざした作業が進んでいた。
この大型客船を巡っては、1隻目とともに設計変更などが相次ぎ、今年3月期までの赤字額が2540億円に達した。このため、同社は昨秋、大型客船事業からの撤退を表明。今年2月には、商船事業全体を分社化して切り離し、収益の責任を明確にする方針も明らかにしている。
加えて、国内最大手の今治造船(愛媛県今治市)など3社との提携交渉にも力を入れている。
三菱重工が総合重工メーカーの技術力を生かして一部の船で設計を担い、実際の建造は、船を安く造る専業メーカーの能力に任せる「分業」が狙いだ。営業や部材の調達も共同化してさらにコスト削減を図る。
三菱重工の大倉浩治船舶・海洋事業部長は「お互いの強みを持ち寄って成長を目指す」と意気込む。
造船事業に苦しむ総合重工メーカーは、三菱重工だけではない。川崎重工業とIHIも、海外向け案件などで工期が遅れてコストが膨らみ、大きな赤字を出した。
川重は昨年10月、金花芳則社長をトップとする「構造改革会議」を設置。中国の合弁会社の造船所を積極活用し、コストを減らす方策などを中心に検討している。
資源掘削船の船体や液化天然ガス(LNG)船のタンクなどの「海洋構造物」の建造を手がけるIHIは、2015年度半ばから新規の受注を凍結。将来も事業を継続するか、慎重に判断する方針だ。
朝日新聞社
2014年に長崎市深堀町1の福岡造船(本社・福岡市)長崎工場で起きた爆発事故で、長崎労働基準監督署は1日、同社と男性工場長(64)を労働安全衛生法違反容疑で長崎区検に書類送検した。
事故は建造中のタンカー内で電気溶接中に発生。作業していた下請け会社の男性6人がやけどや骨折などのけがを負い、うち1人は下半身不随になった。前日に別の下請け会社が爆発場所で塗装作業をしており、塗料から蒸発した可燃性ガスなどが残り、溶接作業の際に引火したとみられる。送検容疑は、同社と工場長が二つの下請け会社にそれぞれの作業内容について連絡を怠ったとしている。【今野悠貴】
〔長崎版〕
21日午後2時40分ごろ、和歌山市西浜で、「波浪計が爆発した」と119番があった。和歌山県警和歌山西署によると、波浪計の内部で点検作業をしていた「日立造船」(大阪市住之江区)の社員、石田俊宏さん(31)が全身のやけどなどで死亡。もう1人の男性社員(28)も顔面にやけどを負った。
同署によると、爆発が起きた波浪計は高さ約15メートル、直径約5メートルで、日立造船が製造。衛星利用測位システム(GPS)機能が付いており、海に浮かべて波の高さを計測する。
波浪計は国土交通省が白浜沖に設置したが、昨年12月にGPSが使えなくなるトラブルがあり、修理のため同市内に移動。石田さんらが国交省の職員の立ち会いで点検作業を行っていたところ、波浪計内部のバッテリー室で爆発が起きたという。同署が詳しい原因を調べている。
The coastal region of North Jeolla is in a bad state. The home of dockyards of Hyundai Heavy Industries is in shock after the news that the Gunsan yard would be closed as a part of the shipbuilder's restructuring as the result of the protracted global slump. About 6,000 jobs could be lost when including parts suppliers. The livelihoods of many are at stake. The business community that lived off the dockyards also would be affected. The whole Gunsan community is in jeopardy.
The company and the community are struggling to adjust. On a visit to Gunsan last month, Choi Kil-seon, chairman of Hyundai Heavy Industries, said the shutting of the dock was inevitable because there was no work. He reiterated that the choice was necessary to save the company. But Gunsan is equally desperate. Representatives of residents have been rallying in front of the home of Chung Mong-joon, director of the Asan Foundation and largest shareholder in Hyundai Heavy Industries. North Jeolla province residents have submitted petitions to the Ulsan headquarters of the shipbuilder protesting the shutdown.
Neither side can back down. Hyundai Heavy Industries does not have the money to run the shipyard without any work, and Gunsan residents cannot watch their economy go to ruins. Neither side imagined they would end up this way seven years ago. The small coastal city has emerged as a shipbuilding dynamo after the company built a shipyard there in 2010. Although there is one dry dock, the yard built for $1.2 billion is one of the world's largest with an output capacity of 1.3 million tons and is equipped with 1,650-ton crane. It rolled out more than 12 large vessels a year and was responsible for 20 percent of the region's total exports and 9 percent of outbound shipments from North Jeolla.
When the seven-year-old dock closes down, about 24 percent of the workers in the community will be out of work. The facilities and crane will start to rust. It will be the second "Tears of Malmo-type" situation after a crane from a dock in South Gyeongsang province was sold off earlier this year. Malmo was a flourishing dock in Sweden. Its landmark 138-meter Kockums Crane was dismantled and sold when the Kockums shipyard went bankrupt in 2002, and it earned the nickname "Tears of Malmo" because local residents wept as they watching the crane being towed away. The term is now used to refer to the collapse of a shipbuilder. A gantry crane at the Masan shipyard of Sungdong Heay Industries, which went bankrupt four years ago in South Gyeongsang, was sold to a Romanian company in a fire sale.
South Korea's coast region is rapidly turning into a rust belt. Ulsan ? home to 10 docks belonging to Hyundai Heavy Industries ? is also shaken because of a lack of work. Other shipbuilding regions in Busan and Geoje, South Gyeongsang, are no different. The three shipbuilding majors ? Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries, and Samsung Heavy Industries ? let go 6,713 workers last year. They will lay off another 14,000 this year. There is talk of DSME going bankrupt in April. It has already used up most of the rescue fund of 4.2 trillion won ($3.67 billion) from state lender Korea Development Bank, and doesn't have enough work to run its operations.
Presidential hopefuls have rushed to Gunsan and poured out solutions. Lee Jae-myung, mayor of Seongnam, has promised to advance state procurement of warships; Moon Jae-in of the Democratic Party vowed to place government ship orders; Ahn Cheol-soo of the People's Party said the government would give the shipyard priority in government orders; and Chun Jung-bae, also of the People's Party, offered to directly negotiate with Hyundai Heavy Industries. But that's a lot of hot air.
As DSME's case underscores, there is no end to bailing out an entire industry. Otherwise, Hyundai Heavy Industries would not have attempted to close down a shipyard it spent over 2 trillion won to build. Shipbuilding has lost competitiveness because it did not preemptively prepare for an industrial downturn and the government did not play its policymaking role. Companies invest because they have confidence in the future. But investment sentiment is at rock bottom with all of the presidential candidates out to bash large companies. They vow to toughen a law that could threaten management rights even at smaller enterprises. Their credibility has been impaired by the ongoing power abuse scandal involving the president.
Korean companies will have second thoughts about doing business at home. Industry leaders like Hyundai Motor, Samsung Electronics and LG Electronics are all looking overseas for facility investment. If companies migrate overseas, jobs at home will become scarcer. We must change the business environment. Otherwise, industrial sites all across the country will weep tears.
JoongAng Ilbo, Feb. 20, Page 28
*The author is an editorial writer of the JoongAng Ilbo.
Kim Dong-ho
Evergreen Holding, the parent group of Sinopacific Shipbuilding, has had all the fixed assets of the company frozen by courts due to a series of debt disputes with creditors.
According to the group, total liabilities of Evergreen Holding amount to RMB6.97bn ($1bn) and it is currently dealing with over 50 court cases for debts amounting to around RMB2.66bn ($387m). The company has lost all court cases that have already been completed.
Zhejiang Shipbuilding, an affiliate yard of Evergreen Holding,went bankruptin April 2016 and another subsidiary yard of the group, Sinopacific Offshore & Engineering, went into liquidation process in August 2016 after CMIC terminated the acquisition of the yard.
Subsidiary yard Yangzhou Dayang Shipbuilding is in the middle of a restructuring process.
Evergreen Holding has also been involved in several bond payment defaults. The Group said it is now making its best efforts to self-rescue and protect the interests of investors and creditors.
韓国に脅威となるほど猛威を振るっていた中国造船業が急激に衰退している。世界1位の座を獲得するために無理やり規模を拡大して「受注の崖」にぶつかり、業界全体が相次ぎ倒産する危機に直面している。9日、米ウォールストリートジャーナル(WSJ)によれば、中国造船業は急激な需要不振に船社が相次いで倒産し、大量の労働者が解雇されている。数千人の造船業労働者が勤めていた中国江蘇省儀徴市でも捨てられたクレーンと作りかけた錆びのついた船だけが残っている廃墟と化した。
一時、グローバル市場のシェア30%を占めた中国の造船所はすでに75%が閉鎖されている。英国の造船・海運分析機関クラークソンリサーチによると、中国の679造船所のうち運営中の造船所は169カ所だけだ。残りの510カ所は運営していない。中国は「2015年造船業世界1位」を目指して2000年代初から産業規模を拡大してきた。しかし、それ以来グローバル景気低迷が続いて貿易規模が縮小され、コンテナ船など新規受注が減ることで深刻な供給過剰に陥った。中国政府は慌てて構造調整というカードを取り出し、造船業の量的成長を質的成長に誘導しようとしたが、対内外の景気不振により成果を出すことができなかった。
中国経済メディアの網易財経は「中国造船業は生産過剰と技術力不足で業況が悪化し、競争が激しくなり、民営企業が苦境に陥っている」と報じた。実際、大型船舶を大量に生産できる中国大型造船所は2013年から着実に減少して現在70カ所水準へと大幅に減少し、中小企業数百社が倒産したと、WSJは伝えた。
物流会社のIHS海上貿易のロバート・ウィルミントン研究員は「中国造船業が頂点に立った時は1億5000万ドル(約170億6000万円)に達したバルク船の価値が現在、わずか4500万ドルに下落した」と話した。
中国は昨年、二大海運会社である中国遠洋運輸公司(COSCO)と中国海運総公司(CSCL)傘下の造船所11カ所を一本化することにするなど、構造調整に拍車をかけている。しかし、グローバル景気回復の足取りが鈍くなり、中国内の受注を除いて事実上受注がなく、それさえも「仮注文(Phantom Order)」という疑問が提起された。英国の海運コンサルティング会社のMSIは「中国造船業の受注の3分の1が虚構である可能性がある」と疑問を提起した。MSIのアダム・ケント博士は「中国造船業界の今年の引き渡し量が1700万CGT(標準貨物換算トン数)に達するが、その中で相当数は実際に引き渡されないだろう」と話した。昨年も中国造船業界は2000万CGTを引き渡すと明らかにしたが、実際の引き渡し量は半分の1000万CGTにとどまった。ケント博士は「今年の引き渡し量のほとんどは2013年ごろに契約を結んだもので、船舶はほとんど2~3年以内に引き渡しが完了する」とし、「契約が虚構であったか、契約が取り消しとなったが公開せず実際の発注につながらない仮注文が生じたとみられる」と話した。
中国造船業の危機は、韓国造船業の機会として捉えられる。実際に、今年に入って受注実績が逆転した。クラークソンリサーチによると、1月の世界船舶発注量は韓国が33万CGT、中国は11万CGT、日本が2万CGTと、韓国が1位を占めた。教保(キョボ)証券のイ・カンロク研究員は「グローバル発注量が好況期の水準に回復することができないとしても、中国など世界の造船生産能力の50%以上が減少し、現代重工業・サムスン重工業など韓国の大型造船所にとって十分なチャンスになるだろう」と分析した。
共産主義は最大限の生産をするシステムで、減産はできないようになっている
日中韓造船業の苦戦振り
かつて日中韓が造船大国世界一の座をかけて争っていたが、この1年で様相が激変しています。
2016年9月に韓国最大のの韓進(ハンジン)海運が経営破たんし、海運業の苦境が表面化しました。
2016年にジェトロが発表した世界貿易統計では、2015年の貿易額は12.7%減の16兆ドルでした。
2016年の世界貿易はまだ出ていないものの、中国の貿易総額が6.8%減、アメリカも4%減(推定)、日本は11%減などとなっている。
世界経済の悪化を背景に貿易額が減少している上に、物の貿易が減少しサービスの割合が増えている。
石油や自動車は減少し、ソフトウェアやアニメなど輸送する必要がない商品の取引金額が増加した。
韓国の造船業はサムスン、大宇、ヒュンダイの「御三家」が安い人件費を背景に日本から受注を奪ったが、今では倒産や合併が囁かれている。
国家破綻して通貨のウォンが暴落したのを良い事に、低価格を武器に1999年から日本を受注額で上回っていました。
だが2016年末の受注残高は日本は2006万4千トン(835隻)、韓国1989万トン(473隻)で日本が上回りました。
受注残高は受注したがまだ引き渡していない数で、今後の業績を予想でき、2017年以降は日本の総受注数が韓国を上回る可能性が高い。
2016年の総受注数は中国351万3千トン、韓国157万2千トン、日本111万5千トンという順位になった。
だが世界一の順位競争より重要なのは3カ国の大手造船企業がどれも赤字経営な事で、大赤字を出して世界一を取っても意味がない。
共産主義の造船所とは
韓国は3位の大宇造船が倒産寸前、ヒュンダイは親会社の現代グループは既に存在せず、支援を受けられない。
サムスンもスマホの出火騒動などで今後の情勢が厳しくなると予想され、造船部門は赤字経営を続けています。
韓国の造船会社は経費削減のためにリストラや設備縮小、賃金の未払いなどを行っていて、韓国の雇用悪化に一役買っている。
その韓国を倒して世界一になった中国の造船業だが、他の産業と同じく過剰設備、過剰生産、過剰輸出で市場を崩壊させました。
共産主義制度では「増産」だけが評価され「減産」するとマイナスどころか犯罪行為で、工場長が共産党に無断で減産したら逮捕されます。
北朝鮮の工場を連想すると分かるが、増産は表彰され減産は処罰されるので、何でも最大限過剰生産します。
この国家体制は世界大戦の時には機能し、ソ連はドイツを物量で圧倒したが、増やしたものを減産する制度は存在しないのです。
だから中国は必ず船でも鉄鋼でも自動車でも何でも、限界まで生産して市場が崩壊し、工場が破綻するまで増産し続けます。
レアアースは今でも中国が世界の9割を生産しているのに、減産ができないので密輸品が世界に溢れて価格が暴落したままです。
中国の大手造船所は全て国営か元国営、あるいは共産党が経営に関与する準国営企業になっています。
他に小さい造船所が無数に存在し、過剰生産の原因になっていて、政府は生産調整を奨励している。
2015年のピーク時から生産能力を半減させる予定だが、実現してもまだ生産能力が余りまくっています。
日本の造船業は大再編を避けられず
韓国や中国の造船業が苦戦し日本が安泰とは行かず、三菱重工は客船で巨額赤字、川崎は撤退を模索しています。
日本の造船業の顧客は70%以上が国内向けなので、これ以上中韓に市場を奪われることは無いが、世界経済や世界貿易の縮小はどうしようもない。
三菱重工は旅客機やプラントやロケットなど造船以外の分野で過去最高益を出したが、造船部門を他社と再編成する計画を建てている。
川崎重工も造船以外で黒字にしたものの「荷物」を下ろしたいようで、事業撤退を検討していると報道されました。
今治造船、JMU(旧 IHI)、三井造船、日立造船、佐世保重工業など戦前からの造船所が乱立しているが、いかにも数が多く非効率に思えます。
日本の造船業がほぼ国内向けになった以上、こんなに多くの造船会社は必要なくなり、大手数社に収斂していくでしょう。
身の丈に合ったコンパクトな体制にしたほうが、中韓との競争にも有利だと考えられます。
Web Editor: Zhang Xu
A freighter belonging to a bankrupt shipyard has been sold for 96 million yuan (US$13.98million) in online judicial sale, thus becoming the most expensive ship ever sold at an online auction in China, Shanghai Maritime Court said on Saturday. [Photo: Shanghai Daily]
A freighter belonging to a bankrupt shipyard has been sold for 96 million yuan (US$13.98million) in online judicial sale, thus becoming the most expensive ship ever sold at an online auction in China, Shanghai Maritime Court said on Saturday.
The Nantong Minde Heavy Industry Co, based in Jiangsu Province, had made the ship for a Canadian buyer. But the shipyard went bankrupt in July 31, 2015, when the ship was just being completed. The buyer then cancelled the order, the court said.
Later, local court asked Shanghai Maritime Court to initiate its sale. The auction was started on Taobao.com on January 26, and the ship was sold to a Singaporean.
大宇造船海洋が今年に入っても資金難を解消できずにいる。毎月1000億ウォン(約100億円)以上の現金が不足していると分析されている。長い「受注の崖」の影響で運営費として出ていく費用がより多くなったからだ。
造船業界によると、大宇造船は正常な営業活動で毎月入ってくる現金が6000億ウォンであるのに対し、運営費として出ていく金額は7000億ウォンにのぼり、流動性問題に苦しんでいる。
大宇造船の流動性危機を加重するのは4月21日の4400億ウォンをはじめ、今年満期を迎える9400億ウォンの社債だ。今年の利子費用(2400億ウォン)と営業関連の現金不足(年間1兆2000億ウォン)を勘案すると、計2兆3800億ウォン(日常的な営業活動除外)が大宇造船から今年出ていく現金となる。
一方、入ってくる現金は引き渡しや売却交渉が少しでも遅滞する場合、支障が生じる可能性がある。大宇造船はアンゴラ国営石油企業ソナンゴルとの交渉を通じて引き渡し代金1兆ウォンほどを3回に分けて受けるが、今年は6000億ウォンほど入る計画だ。
また子会社と資産を売却し、今年は現金1兆3000億ウォン程を確保することにした。7000億ウォンを投入して建造しながら引き渡しが取り消しになった掘削船1隻をはじめ、大宇造船海洋建設、ルーマニアのマンガリア造船所なども売却を進めている。大宇造船は債権団の残りの支援金7000億ウォンで資金のミスマッチ(需給不一致)をかろうじて解消するほど流動性が「一触即発」状態だ。
政府と債権団は大宇造船が流動性危機を迎えることに備え、債権団共同管理(自律協約)を本格的に検討し始めた。債権団共同管理とは、最大株主の産業銀行や今まで資金を支援した輸出入銀行のほかの銀行も債権を株式に転換する方式で苦痛を分担することだ。4月から満期を迎える社債も社債権者集会を通じて満期を延長し出資転換をしてこそ大宇造船の生存が可能になる。出資転換対象の債権者はウリィ・国民・新韓・KEBハナ銀行、農協などの銀行と国民年金管理公団、証券会社、保険会社など債権投資家。
一部は「債権団主導型法定管理」も代案に提示している。2014年の大韓造船、2016年のSTX造船海洋の法定管理事例を参考にしようということだ。大韓造船は法定管理であるにもかかわらず債権団が4300億ウォンの新規資金を支援し、商取引債権もすべて返済し、協力会社の連鎖不渡りを防いだ。STX造船も法定管理中に船主との交渉を通じて受注契約取り消しを最小化した。
20日午前8時半ごろ、岡山県玉野市の三井造船玉野事業所で、同社社員の野田進さん(62)=玉野市奥玉=が作業場に向かう工事用エスカレーターに乗っていた際にプラスチック製の踏み板が破損し落下、板とフレームの間に体を挟まれた。午前11時すぎに救出されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。
県警によると、野田さんはこの日、他の作業員と共に船尾にかじを取り付ける作業をしていた。県警が事故原因を調べている。
船舶の修理・修繕業界などに"特需"という神風が吹こうとしている。国際海事機関(IMO)によって、世界の生態系を守る狙いから船舶のバラスト水(海水)の浄化を義務付ける条約が発効したためで、既存船を含めて短期間のうちに浄化装置を取り付けなければならなくなったためで、関係業界の中には大型ドックを新設する動きなども出ている。その動きを探った。
瀬戸内海のほぼ中央に位置する広島県尾道市因島。かつては人口が4万人を超え、日立造船が主力造船所を置くなど「造船の島」として栄えたことはよく知られている。最近はその造船業も衰退し、代わりに「しまなみ海道」(本四連絡橋・尾道ー今治ルート)沿いの観光資源を活かした「観光の島」として再生を図っている。
その因島の北端にほど近い重井地区に立地する三和ドックが6万3000トンクラスの新設大型ドックを完成させ、地元ではちょっとした話題になっている。ドックの大きさは全長220メートル、幅約45メートルで、付随する本社ビルなど関連施設を含めると、投資額は約120億円に達する巨大投資だ。
なぜドック新設なのか?
造船業界は海運市況低迷の直撃を受けた「船余り」(海運業界関係者)から受注が激減し、先行きに赤信号が灯っているが、なにゆえに今、ドックの新設なのだろうか。
これについて、三和ドックの寺西勇社長は「国際海事機関(IMO)によって、外航船舶のバラスト水の規制強化が採択され、バラスト水の処理装置の設置が船舶に義務付けられるため、設置工事など船舶の修繕工事が今後、急増することが予想される。このドックはそのための修繕船用なんです」と、その理由を説明する。
船舶のバラスト水は積荷を降ろした船を空荷の状態で運行する際、船体を安定させるために積み込む海水のことで、荷物を積載した後は再び海中に放出される。問題はこのバラスト水(海水)だ。海水中にはプランクトンなど多くの微生物が生存しており、バラスト水の注排水によって本来の生息地ではない場所に移動させられ、世界の生態系を崩すことになるのだ。
このためIMOでは生態系を守るため、外航船舶に積み込むバラスト水の浄化を義務付けた「船舶バラスト水規制管理条約」を採択した。この条約はフィンランドが批准し、対象船腹量の35%以上という発効要件を満たしたため、2017年9月8日から正式に発効することになった。
浄化装置の設置が義務付けられる船舶は新造船だけでなく、現在、運航されている既存船にも適用されるため、対象となる船舶は「全世界で約6万隻、国内の海運会社や船主がからむのは2000〜3000隻程度ではないか」(国土交通省関係者)とみられている。
1隻当たり5000万〜3億円
では、条約の発効によって海運会社や船主などにはどのくらいの費用負担が生ずるのだろうか。これについて関係者は「船舶の大きさなどによって異なるが、1隻当たり5000万〜3億円程度ではないか」とみられており、設置されていない船舶は「それぞれの港で入港を拒否されたり、差し押さえられたりするケースも発生する」とみられている。期間は向こう5年程度で、既存船はこの間に定期検査などでの入渠の際に設置工事を行うことになる。
しかし、海運業界にとっては新たな負担となることは間違いない。国土交通省などによると「老朽船などではこの際、スクラップに走るのではないか」(船舶産業課関係者)という見方も出ている。「スクラップが多く発生すれば、"船余り"の状態が解消されて、新たな需要が生まれ、造船不況も多少緩むのではないか」(内海造船関係者)という声も漏れる。
一方で修繕やヤードを備える造船所や水処理装置メーカーなどにとっては「ちょっとした特需の発生」(三浦工業関係者)ということになる。三和ドックが大型ドック新設という大型投資に踏み切ったのもこれを千載一遇のチャンスとしてのものだ。
特に大型ドックの完成によって「これまでは内航船中心だった修繕事業が近海船なども対象になり、売り上げも現状の約51億円から70億〜80億円レベルにアップする」(寺西社長)と期待を込める。
また三浦工業やJFEエンジニアリング、粟田工業など装置メーカーでも生産能力の強化など規制強化に合わせた体制作りを急いでいる。
中でも三浦工業では本社工場(愛媛県松山市)に約30億円を投じて組み立て専用の新工場を建設中だ。完成は2017年6月頃の予定でこれによって装置の生産能力は現在の年産300台から720台に高まる。これに合わせて海外での営業体制も強化する方針で、台湾やシンガポール、オランダなどでの体制整備を急いでいる。
不透明な米国の動向
だが、本当に“特需”は発生するのだろうか。実は不安視する向きも多いのだ。それはバラスト水対策にからむ米国の存在だ。米国は「バラスト水対策についてIMOより厳しい規制策を求めている」(杉原毅向島ドック社長)とされるが、米国の規制当局である米国沿岸警備隊(USCG)による処理装置の認定作業が遅れているためだ。
このため一船主などの間では「USCGの認定を受けた処理装置がまだ存在していないことを理由に装置の導入延期を求める動きがある」(修繕事業界関係者)ことも事実だ。こうした状況下、関係者の間からは「しばらくは様子見だ」(杉原・向島ドック社長)という声も出ているが、最近になってUSCGは機械の認定作業をはじめ、一部メーカーの機械について認定を始めているという報告も伝わっている。バラスト対策を巡る業界関係者の一喜一憂ははじまったばかりである。
19日午前9時5分ごろ、香川県多度津町西港町にある今治造船(本社愛媛県今治市)の工場敷地内で、案内看板に「爆弾をしかけた」などと書かれたと県警丸亀署に通報があった。同工場内の複数箇所でガス漏れも発生していた。同署は関連を調べるとともに業務妨害事件として捜査している。
同社などによると、19日午前7時ごろ出社した従業員が門付近の案内看板など3カ所に黒いマジックのようなもので書かれているのを発見。施設内のバルブが緩みガスが漏れているのも確認された。
同署が敷地内に不審物がないか調べている。同社は安全が確認されるまで同工場の操業を停止するとしている。
現代重工業の群山造船所閉鎖方針に全羅北道道民「強い反発」
本社への抗議訪問・鄭夢準(チョンモンジュン)元議員ソウル自宅前に立ち集会予定
全羅北道と群山経済の主軸である現代重工業が群山造船所を閉鎖することが知られると、全羅北道と群山市などが強く反発している。
本社を抗議訪問して決起大会を開くなど、集団行動も辞さないという方針だ。
19日群山市によるとソンハジン道知事、キムグァンヨン国会議員、ムンドンシン群山市長、パクチョンヒ群山市議会議長、群山商工会議所の役員、群山造船所協力会社の代表などが24日、現代重工業蔚山本社を訪れ、群山造船所の閉鎖に反対する道民29万人の署名が入った署名簿を渡す予定だ。
群山造船所の閉鎖方針に抗議する意味で、署名簿を渡すことである。
翌日には全羅北道地域の政治・経済・社会・文化界の関係者など500人余りが現代重工業の大株主である鄭夢準元議員のソウル自宅前で「汎道民決起闘争の出征式」をする計画だ。
出征式の後、参加者らはドア市場を皮切りに、閉鎖の方針が撤回されるまで1人デモを続ける予定だ。
群山市関係者は「全羅北道と群山市の200億ウォン補助金の支援、造船産業クラスター造成や進入道路の建設、大学造船学科の新設などの努力を無視したまま、経済論理だけで群山造船所のドアを閉めようとした現代重工業の仕打ちは不当だ」と話した。
一方、現代重工業チェギルソン会長は今年20日午後、群山市庁で道知事、群山市長、全北・群山商工会議所会長団などと群山造船所の閉鎖と関連した非公開面談をする予定であるため、結果に関心が集まっている。
受注残高品切れ後に暫定閉鎖
現代重工業の群山造船所が希望退職を実施している。会社側は今回、希望退職の申請を行っていない職員は1月末から順に蔚山造船所に移動する計画であることが分かった。
4日、現代重工業労働組合によると、群山造船所は、先週から3週間希望退職申請を受けることにした。希望退職者には40ヵ月分の給料と子供の学資金、旧正月ボーナスを支給することにした。対象は、正規職の全員である。現在、群山造船所で働く正規職は650人余りだ。今まで数十人が希望退職の申請を行ったという。
群山造船所職員は、「会社側は今回、希望退職申請をしないで残った人々を今月末から順に蔚山造船所・船舶事業部門に移すことを検討している」、「蔚山も職員たちがあふれて分社して構造調整をするのに行って持ち堪えることができるかどうかみんな心配」と憂慮した。
群山造船所の残りの仕事は3月に全てなくなる。受注日照りのせいに群山造船所はこれ以上建造する物量を本社から割り当てられなかった。 群山造船所が暫定閉鎖されれば、正規職の職員が職を失うことになること以外にも2次、3次協力会社まで相次ぐ倒産することになる。造船業界の関係者は「政府で中小造船会社を助けるために、規模が小さな船舶を発注するように、群山造船所も閉鎖を防ぐため、受注支援を行う必要がある」と話した。
By Aiswarya Lakshmi
South Korea‘s three majors shipbuilders are forecast to get much fewer orders next year, Yonhap reports quoting industry sources.
The three shipyards - Hyundai Heavy Industries (HHI), Samsung Heavy Industries (010140.KS) (SHI) and Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) - are struggling to set their order targets for next year due to the global vessel glut and fiercer competition from Chinese rivals.
The top three shipbuilders are expected to suffer from tough business conditions in 2017 on financial front too.
DSME is shooting for a 2017 order number that is similar to this year’s goal of $6.2 billion. At the start of the year, the troubled shipyard aimed to win orders worth $10.8 billion this year but was forced to cut the figure in June.
Daewoo Shipbuilding is doing its best to secure enough liquidity for the bond payments and is in the process of selling non-essential assets including subsidiaries and real estate.
HHI has reportedly set its 2017 order target at a level similar to this year’s US$9.5 billion. The shipyard bagged contracts worth $7.1 billion, much lower than its goal of $19.5 billion set at the start of the year.
SHI to set its 2017 order target at a level that is slightly higher than $5.3 billion for this year, as the company is likely to clinch a 3 trillion-won ($2.50 billion) order for the construction of a floating LNG unit from Italian petroleum giant Eni early next year
HHI, DSME and SHI have all posted multiple quarters of losses in the past year-and-a-half amid delivery delays and a plunge in demand for new vessels and oil platforms.
The top four Korean shipbuilders have 2.3 trillion won ($1.9 billion) in notes maturing next year, the most in Bloomberg-compiled data going back to 1997.
大学院教授の考えだが、専門外なのか、問題を理解しているのか、勘違いな意見だと思う。
世界5位だった韓国海運産業の一つの軸が崩れている。韓国を代表する外航定期船会社の韓進海運はアマチュア的な法定管理決定のため清算を控えていて、一つ残った現代商船までがまともなアライアンス(海運同盟)に加入もできず、世界的な無限競争の海に放り出された。
1980年代まで定期船海運は船会社が集まって運賃を決める海運同盟を利用し、収入が安定していた。その後、海運同盟が瓦解して船会社間の競争が激しくなり、運賃は下落した。コンテナ船が大型化し、商品を積んで運ぶ船腹量は大きく増えたが、物流量はむしろ減少し、船舶の空きが多い状態(最大30%)が続いている。大幅な廃船措置がなければ運賃はさらに下がるしかない構造だ。アライアンスを通じて経費を節約し、採算が取れるよう努力しているが、力不足だ。船腹量を調節する協力体制がないため、他の船会社が倒産して船腹量が減るのを船会社は待っている。しかし韓国の韓進海運がこうした需給不均衡の直撃弾を受けた。韓国の船会社を保護する措置が求められる。
まず、海運市況に対する認識の転換が必要だ。運賃は自由化され、需要より供給が超過する状況で、韓国の船会社はどう生き残るのか。韓進海運が第3国の貨物を運送して稼いだ5兆ウォン(約5000億円)の外貨、韓進海運の売上高8兆ウォン(大韓航空水準)が消えても、外国の船会社を利用して他の産業でそれだけの売り上げを出せるため、自国籍船会社はなくてもかまわないと自信を持って言えるのか。売上高8兆ウォンの関連産業効果は非常に大きい。国籍船会社が必要だという結論に到達すれば、政府は船会社に対する支援および育成に強い意志を見せなければいけない。船腹需給の調節が崩れた状態で各国の政府と船会社はチキンゲームをしているからだ。
2つ目、また事業の多角化が要求される。外航コンテナ船以外の不定期船市況は良いため、不定期船の運航で稼いだ収益でコンテナ船運航の赤字を埋めるシステムを築き、不況を乗り越えなければならない。これは過去に韓国の船会社がしてきた方式で、日本のNYK(陸上物流分野)とマースク(エネルギー産業分野)の戦略でもある。最近、現代商船が大型コンテナ船を発注するという当初の計画を変更し、タンカーなどの建造をするという決定は適切な選択だ。積載する貨物を集めるのも難しく、運賃が低いため、赤字が出る可能性はさらに高い。1980-90年代の黄金比率のポートフォリオを現代商船が回復するよう政府が支援してこそ、この不況を乗り越えることができる。
3つ目、韓国の貨物積取比率(海上輸出入貨物量のうち自国籍船の輸送比率)を高め、金融利子負担を下げて損失を減らす必要がある。船会社は大量荷主と長期運送契約を締結するのがよい。現在、韓国の貨物の積取比率は20%にすぎない。これを50%水準に引き上げれば安定的に営業することができる。景気の変動によって5-10%の運賃を増額または減額し、船会社と荷主が不況時に助け合う共生運賃約定を締結しよう。日本は自国船舶の利用率が70%に達する。1990年代半ば韓国の積取比率は50%に達していたため、これは再び達成できる目標だ。こうした共生の約定は船会社(船主)と金融団も締結できるはずだ。海運の景気が悪ければ金融団は貸出利子を市場金利より下げ、海運景気が良くなった時に高めれば、船会社の経営に役立つ。韓国の外航定期船海運が長期不況の波を越えて復活するよう、船会社、政府、荷主および金融界すべてが力を合わせるべきだ。
キム・インヒョン高麗大法学専門大学院教授/韓国解決法学会長
今次会合の主要な審議事項は以下のとおりです。
1.船舶燃料の硫黄分濃度規制の開始時期の検討
IMOでは、2008年に大気汚染防止対策として船舶からの硫黄酸化物(SOx)排出削減のため、その燃料油中の硫黄分濃度の規制を導入しました。この規制では、船舶の燃料油中に含まれる硫黄分を段階的に削減していくものであり、一般海域(全海域)と指定海域(北海・バルト海等)に分けて規制値を設定しています。
今次会合では、IMOが設置した専門家部会による世界の船舶燃料油の需給予測に基づき、一般海域における燃料油中硫黄分の規制値(現行3.5%以下)を0.5%以下に強化する時期を2020年か2025年のいずれが適切かを審議した結果、日本を含む多数国が支持した2020年からの開始を決定しました。2020年からは、全ての船舶がこの規制に適合する燃料油を使用するか、同等の効果のあるLNG等の代替燃料油の使用、または排気ガス洗浄装置を使用する必要があります。
2.燃料消費実績報告制度の導入
IMOでは、2013年に船舶から排出される温室効果ガス(CO2)削減対策として、新造船の温室効果ガス排出性能を段階的に強化する規制(※)を他の輸送モードに先だって導入しました。更にIMOでは、現存船を含めた燃料消費実績を「見える化」するための議論を進めてきました。
燃料消費実績報告制度は、我が国より提案したもので、総トン数5,000トン以上の国際航海に従事する全ての船舶を対象に、運航データ(燃料消費量、航海距離及び航海時間)をIMOに2019年から報告する制度(各船舶の燃料消費実績を「見える化」することで、船舶からの温室効果ガス削減を促す)で、今次会合において、同制度を導入するための条約改正案が採択されました。
(※)EEDI規制:新造船のCO2排出量を設計建造段階において「一定条件下で1トンの貨物を1マイル運ぶのに排出すると見積もられるCO2グラム数」としてインデックス化し、船舶の性能を差別化するもの
第70回海洋環境保護委員会の開催概要については別添をご覧ください。
船の排出ガス規制が決定 予想より早く、きつい?
2016年10月下旬、IMO(国際海事機関)はSOX(硫黄酸化物)排出規制の強化を決定しました。これまで欧州海域や北米近海(ECA)のみに適用されていた船舶からのSOX排出規制が、世界中の海で適用(グローバルキャップ)されるというものです。従来、船舶の排気ガスからの硫黄分排出は3.5%まで認められていたのですが、今回の決定により、一気に0.5%以下(ECAでは0.1%)にまで規制されます。
施行は2020年1月1日で、現存船、新造船問わずすべての船舶に適用される予定です。これに対し日本の造船業界は、「予想したより早いし、きつい」との戸惑いの声を上げるとともに、その情報収集と対処策の検討に追われています。
海事専門紙である海事プレスが2016年12月1日(木)付けで伝えたところによると、今回のIMOの決定に関し、対策を問われた日本郵船の内藤忠顕社長は「ルールが不安定なため、的を絞り切れない。何が最適なソリューションか現時点ではまだ見えない」と話したといいます。環境対策において日本の海運会社では最先端にあるといわれる日本郵船でさえ、この規制強化への最適解は得られていないようです。
2020年以降の地球温暖化対策を定めた「パリ協定」に代表されるように、世界的な環境規制の高まりのなかで、船舶界においてもすでにCO2の排出やNOX(窒素酸化物)の排出、バラスト水の浄化対策といった環境対策が実施されています。そして今回のSOX対策については、次の3つの方策を中心に進められると考えられます。
3つのSOX対策、いずれも一長一短あり
ひとつは、燃料油自体からSOXを削減する方法です。現在、船舶用の燃料は「C重油」が使われていますが、これには硫黄分が多く含まれているため、そこへ硫黄分の少ない「A重油」をブレンドするといった方策が挙げられます。IMOの論議では、こうしたブレンド油の十分な調達が2020年に間に合わないという見方もあったようですが、石油業界側が「間に合わせるべき」という意思を受け入れたことが、今回の規制強化の決定へつながったといわれています。
しかしこれら「低硫黄重油」は、C重油に比べ単純計算で1.3から1.5倍の価格になると見られ、またどんな状態で供給されるのか、世界中の港において供給が可能なのか、といった点で不確定な要素が大きいというのが実情です。
第二のプランは、排気ガスから硫黄分を削減する「スクラバー」と呼ばれる脱硫装置を船に取り付ける方法です。特に現存船への有効な対策と見られていますが、機器自体が大きく、重量も重く、付帯的な設備も必要になるなど、簡単には導入を決断できないようです。
そしてもっともドラスティックな3つめの対処策が、SOXだけでなくNOXの除去やCO2対策にもなる「LNG焚きエンジンの搭載」です。すでに欧州では重油とLNG(液化天然ガス)の二元燃料焚きが多く採用されており、こと新造船においては、LNG焚きの普及へと進む潮流の只中にあります。特に入港する港湾が決まっているフェリーでは、LNG燃料供給も比較的受けやすいと考えられ、普及への好材料のひとつでしょう。ほかにも、LPG(液化石油ガス)やメタノール焚き、水素燃料など未来に向けた構想があります。
一方で、LNG燃料船は、それが二元燃料(重油とLNG)エンジンであったとしても、建造コストが高くなります。またLNGは燃料としての比重が小さいため、重油と同じ量の燃料を積むためには2倍の容量の燃料タンクが必要になります。その点において、なるべくコンパクトな船体が求められるフェリーでは、やはり採用しにくいともいわれています。とりわけ、瀬戸内海では全長200m以下の船しか夜間航行ができないほか、日本特有の様々な規制があり、これらとの整合も必要になります。
対策に着手し始めた国内造船業界、しかし世界の選択は…
日本の造船や船舶用機械業界は、効率的なLNGエンジンの開発、改良や、コンパクトなエンジンルームの開発など、LNG燃料船の新設計に着手し始めてはいるようです。たとえば日本郵船は、欧州海域で運航する自動車専用船として2016年9月、LNG焚き船を就航させています。
しかし、すでに規制が現実のものになっている欧米の船会社は、フェリー、客船を皮切りに、一説によると90隻以上、建造計画中のものを含めると200隻規模で、大胆にLNG焚き船を導入する計画に着手しているといいます。
そんななか、北欧の大手フェリー会社であるバイキングライン社(フィンランド)が、2020年就航予定で6万3000総トンにおよぶLNG焚きの大型ROPAX(豪華フェリー)を、1プラス1隻オプション形式で中国の厦門重工に発注したというニュースも伝わってきました。
いま欧州の造船所は、客船建造ブームで受注余力がありません。そこで欧州のクルーズ会社は、中国の造船所を選択したのです。
このまま日本の造船所が新しい環境規制の時代へ対応できない場合、客船やフェリーの分野で「日本パッシング」が起きかねません。
若勢敏美(船旅事業研究家)
After more than 10 years of discussions, International Maritime Organization (IMO) finally set the global sulfur cap of 0.5% to be in place from 2020, during its Marine Environment Protection Committee (MEPC), meeting for its 70th session in London during 27~28 Oct. 2016. (See the press release from IMO here.)
“Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships”, MARPOL Annex VI adopted on 19 May 2005, which has been updated at later meetings. Regulation 14 of this guideline is about controlling SOx emission from marine diesel engines from 1) All ships of 400 gross tonnage, 2) Fixed or floating platforms (drilling rigs) and 3) Floating craft and submersibles.
The regulation 14 suggests the fuel is to be of ‘clean fuel’ with low sulfur contents. As an alternative to using ‘clean fuel’, MEPC allows exhaust gas cleaning systems like ‘scrubbers’ to clean the emissions before the exhaust gas is release to atmosphere.
SOx scrubber systems from STI is a result of more than 10 years of development, onboard tests, and actual installations onboard ships. STI’s SOx scrubber system has following features,
•in-line system that can replace existing silencers,
•dry/wet run without any provisions to switch the modes,
•waste water treatment to comply with discharge water requirements,
•compact design with low water consumption,
•continuous emission monitoring system (Scheme B) as standard but Scheme A configuration is available
•all-in-one control and monitoring system with independent emergency shutdown system
•various configurations of open/close/hybrid operation as per requirements.
SOx scrubber system from STI is custom made for each project. STI is ready to provide technical and commercial proposals.
For any inquiries about the SOx Scrubber system inquiries, please contact STI at scrubber@simulationtech.co.kr.
Kitack Lim was elected Secretary-General of the International Maritime Organization (IMO) by the 114th session of the IMO Council in June 2015 for a four-year period beginning 1 January 2016. The election was endorsed by the IMO's Assembly at its 29th session in November 2015. Mr. Lim (Republic of Korea) is the eighth elected Secretary-General of the International Maritime Organization and has also assumed the role of Chancellor of the World Maritime University (WMU). Mr. Lim obtained an MSc degree from WMU in 1991 with a specialization in Maritime Safety and Administration focusing on navigation.
“Mr. Kitack Lim is the first Chancellor and first IMO Secretary General, to hold an MSc degree from the University and we are honoured to have an alumnus rise to assume such an important function for the maritime community. We look forward to working with Mr. Lim as we advance the goals of IMO and its member States through WMU’s maritime and oceans capacity building mission in support of the UN 2030 Sustainable Development Goals,” stated Dr. Cleopatra Doumbia-Henry, WMU President.
A message from IMO Secretary-General Kitack Lim
"It is a great honour to have been elected as Secretary-General of this prestigious and important Organization, and as I begin my term I very much look forward to the challenges ahead.
I join an august group of people who have been chosen to lead this organization and I would like to pay tribute to them all – in particular my immediate predecessor, Mr. Koji Sekimizu, whose enthusiasm and devotion to meeting the Organization's goals has brought such positive and beneficial results.
IMO currently faces an array of issues. With the collective wisdom and insight of IMO Member States and other stakeholders, I am confident we can meet these challenges and continue to forge a future where shipping meets the needs of the world in a safe, secure and sustainable way, building on the substantial efforts and achievements of the IMO to date.
My vision is one of strengthened partnerships – between developing and developed countries, between governments and industry, between IMO Member States and regions. I will also endeavour to strengthen communication between the maritime industry and the general public, I see IMO acting as a bridge between all these stakeholders in what I have referred to as "a voyage together".
For my part, I plan to concentrate on several overarching objectives:
effective implementation of international conventions and regulations
building capacity in developing countries, particularly small island developing States and least developed countries
promoting IMO's global status
contributing to shared growth for all Member States
the efficient performance of the Secretariat.
As the servant of the Member States and on behalf of the Secretariat, I will work proactively to ensure that, through consensus and cooperation among its Member States, IMO continues to develop and deliver on its mission."
The biography for Mr. Lim can be found here.
業界や産業のすそ野が広いと言う事は間接的な強みだと思う。お互いが協力し合う、又はコミュニケーションを取ろうと思えば簡単にできる。
業界や産業が縮小すれば、海外に取引先やパートナーを探す必要が出て来る。必要のない過当競争がなくなるのでメリットに感じる、
競争相手が減る恩恵を受ける企業もある、縮小するマーケットで生き残ろうとさらなる努力をする企業もあるので必ずしも悪い事ではないとは思うが、全体的にはマイナスだと思う。
価格と品質のバランスが良く、海外との取引で生き延びる企業もあるだろう。製品の品質や将来性でなく、接待やコネで仕事を受注してきた
企業が消える可能性もある。変化は現在の環境を変えてしまう可能性が高い。変化により下剋上、強みが弱み、弱みが強みとなるなども起きる場合がある。
苦境を乗り切った企業の中には成長する企業もあるだろう。
最終的には結果が全て。韓国の造船業界はリストラの嵐が吹き荒れている。2,3年すれば結果が数字や形で現れるだろう。
今月24日午後、鉄工所が集中するソウル市永登浦区文来洞の路地では、100メートルほど歩いただけでシャッターを下ろした業者が10カ所以上あった。大きな文字で「賃貸」という表示が張られた場所も目立った。文来洞は部品、金型、熱処理メーカーが2400社集まった地域で、一時は設計図さえ渡せば、あらゆる部品を作ることができるとまで言われたが、今は閑散としている。溶接業者を経営するPさん(51)は「10年前まではボルトやナットの加工で月に数百万ウォンを稼ぐことができたが、最近は倒産するところが増えている」と話した。
韓国製造業を下支えしてきた末端中小企業30万社が今、崩壊しつつある。一般に従業員数が10人に満たない零細企業で、機械部品、金属加工、縫製、印刷など韓国製造業の下請け構造の末端に位置する。韓国の製造業全体の被雇用者数(約392万人)の4分の1を零細企業が占めるとされる。数年来の景気低迷はそうした零細企業を襲っている。現地で出会った経営者は「周辺には30年以上事業を営んできたプライドから廃業こそ思いとどまっているが、注文が全くない企業があちこちにある」と語った。
■めっき・金型…、末端中小企業の崩壊
首都圏の代表的な工業地区である半月、始華、南洞の各工業団地では最近1年間に3万人が職場を去った。3-4年続く不況に耐えられず、零細中小企業が従業員を削減したためだ。
京畿道安山市の半月工業団地では、交差点に「土地5000坪と建物一括売却」といった横断幕があちこちに見られた。同団地には従業員数10人未満、年商10億ウォン未満の零細めっき業者が約200社ある。ここで亜鉛めっき業者を15年間営むKさん(60)は「自動車部品メーカーからの受注が減少し、先月に従業員7人のうち3人を解雇した。財産を全て処分して運転資金に充て、借金しか残っていない」と話した。別のめっき業者の経営者Pさん(61)は「毎月400万ウォンの賃貸料も稼げず、工場を閉鎖するかどうか悩んでいる」と漏らした。
始華工業団地で出会った金属加工業者のYさん(59)は「5人いた従業員を2人に減らし、自宅と工場を担保に5億ウォンを超える融資を受けた。毎日が苦しい」と話した。
6000社以上の印刷業者が集中するソウル市中区の忠武路一帯も内需不況の直撃を受けている。地下鉄忠武路駅近くの印刷所通りでは、40カ所余りある印刷工場のうち20カ所以上で印刷機が止まっていた。ドンホコミュニケーッションのキム・ユンジョン代表は「以前は印刷物を運ぶバイクで歩行者が通りにくいほどだったが、今はがらんとしている」と話す。
■来年は連鎖倒産も
中小企業経営者は「資金力がない零細企業は既に限界に達している」と指摘した。中小企業中央会が中小企業300社を対象に調査した結果、28.7%が「現在の経済状況は通貨危機、金融危機に準じる危機的状況だ」と答えた。実際に仁川市の南洞工業団地に進出した従業員50人未満の中小企業の稼働率は正常水準(80%)に満たない62%にとどまっている。
問題は来年にかけ状況がさらに悪化するとみられる点だ。中小企業研究院のキム・セジョン院長は「来年は国政の混乱継続と米国の保護主義台頭、米中貿易摩擦など不安要因が山積している。大企業、中小企業問わず製造業の基盤が没落する最悪のシナリオが懸念される」と分析した。
成好哲(ソン・ホチョル)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
「エクソンバルディーズ号のアラスカでの座礁を契機に義務化された二重船殻船舶が世界の造船業の好況を導いたように、硫黄酸化物規制でも同様の効果を期待できるということだ。 」
個人的には二重船殻船舶とLNG推進船舶とは同じようには考えられないと思う。二重船殻船舶でも、シングルハル船舶でも燃料は同じ。
簡単に世界中のどこの港でもLNG燃料をLNG燃料船に提供できるようにならないと思う。特に発展途上国や後進国の港では普及しないであろう。
LNG燃料が調達しやすい港だけを定期的に運航する船、又は規制が厳しい国の港に頻繁に行く船でハイブリッド船であれば、問題がない。不定期船で
発展途上国や後進国の港にも寄港する船は最終的にはコストで判断されるであろう。
アメリカがバラスト水の規制基準を世界基準以上に厳しくした。規則を通してしまえばメーカーや業界は従うしかないと思ったのであろう。しかし、
現実は暫定措置で対応する結果となった。
電気自動車やハイブリッド車はそれほど普及していない。コストや利便性を考えると買い替えるだけのメリットがないからである。LNG燃料船も
同じ事が言えると思う。バラス水管理条約は想定以上に発効が遅れた。コストを考えれば、受け入れたくない関係者や国が多かったと言う事だと思う。
液化天然ガス(LNG)を燃料に使うLNG推進船が受注の崖の前にある造船業界を救うだろうか。
海洋水産部と産業通商資源部は16日に開かれた第18回経済関係閣僚会議で「LNG推進船舶関連産業育成案」を報告した。今後世界でLNG推進船舶の需要が増加するとみてまとめた対策だ。
国際運航船舶は国際海事機関(IMO)の協約により2020年1月から硫黄酸化物(SOx)含有率が0.5%以下の燃料を使わなければならない。現在の基準の3.5%以下からさらに強化される。新基準に合わせるために国際運航船舶は▽低硫黄燃料(ディーゼルなど)を使う▽燃焼後の排気ガスから硫黄分を除去する装置を追加で装着▽根本的に硫黄分の含まれないLNGを使う――の中からひとつを選ばなければならない。業界ではこれらの方法のうち経済性が最も高いLNG推進船舶の新規発注とLNG燃料が使えるように船舶を整備する需要が増えると期待している。
韓国政府の育成案もこれを前提とした支援策を盛り込んだ。主な内容は▽政府・自治体など公共機関からLNG推進船を試験導入し▽LNG推進船の港湾施設使用料を減免するなど税制支援策を展開し▽中長期的にLNG推進船舶関連インフラを構築する――などだ。
世界的にLNG推進船舶は多くない。技術的に設計と建造が容易ではなく、費用も多くかかるためだ。ノルウェー船級協会によると世界で77隻が運航されており、このうち3分の1ほどがカーフェリーとして使われている。国際運航船舶が6万隻を超える点を考慮するとわずかな数だ。だが規制導入によりこれからはコンテナ船などにLNG推進船舶の用途が拡大する見通しだ。
今回の支援案で政府が2025年までに韓国国内で発注される船舶のうちLNG推進船舶の割合を10%(20隻)に高めるという目標を立てた点は注目すべきだ。この場合、最悪の受注の崖を迎えている造船業界に多少なりとも道が開けるためだ。今年造船大手3社の累積船舶受注は33億ドルで年初目標の10%程度にとどまっている。船舶受注が最悪を通過し回復傾向に差し掛かったという分析だが、この3年間続いた受注減少のため状況は楽観的なばかりではない。
韓国政府がLNG推進船舶を発注して関連産業を育成する場合、造船会社は業況改善が見込まれる2018年上半期まで持ち堪える余地ができる。現在は原油価格が下がり造船会社の主要収入源のひとつである海洋プラント入札が中断され、来年9月下旬ごろにも新規入札が始まるとみられるためそれまで耐え抜ける発注量が切実だ。2020年1月から硫黄酸化物規制が始まるため、LNG推進船舶の発注から引き渡しまで2~3年ほどかかる点を考慮すると2018年以前に発注が始まるだろうというのが造船業界の希望混じりの計算だ。
造船業界はこれまで硫黄分含有量制限規制発表、船舶バラスト水処理装置(BWMS)規制発効などにより世界の老朽船舶置き換えサイクルが前倒しされると期待してきた。BWMS規制も海洋生態系破壊などを防止するために船舶バラスト水から有害水上生物と病原菌を除去した後に排出するよう規定した法案で、やはり造船業界では好材料の要因に挙げられる。2020年までにこの要件をクリアしなければならない400トン級以上の船舶は100万~500万ドルをかけて船を改修するより新規発注を選ぶ可能性が高いためだ。
ハナ大投証券アナリストのパク・ムヒョン氏は「世界の中古船舶の95%が機械式エンジンを搭載しており、硫黄酸化物規制に対応するために自然にLNG推進船舶時代が開幕するだろう」と話した。彼は「2000年代初期に5000隻に達したタンカーが8年の時間を置いてすべて二重船殻船舶に置き換えられたより多くの船舶置き換え需要をもたらすだろう」と予想する。エクソンバルディーズ号のアラスカでの座礁を契機に義務化された二重船殻船舶が世界の造船業の好況を導いたように、硫黄酸化物規制でも同様の効果を期待できるということだ。
かつて世界一の建造量を誇った日本の造船業界が苦境に陥っている。
重工各社は相次いで事業縮小や他社との提携強化を進めており、今後、業界全体を巻き込んだ再編が加速する能性もある。
■三菱重工は納期遅れで損失2400億円
「欧米向けの大型客船はコスト的に全然成り立たない。当分無理だろう」。三菱重工業の宮永俊一社長は2016年10月18日の記者会見で、苦渋の表情を浮かべて大型客船建造からの撤退を発表した。
同社が欧米のクルーズ会社から受注した大型客船2隻の建造で積み重ねた損失は約2400億円にも及ぶ。大型客船の設計や建造には特別なノウハウが必要だが、発注元が求める最新鋭の内装や設備に経験や技術が追いつかず、何度も作業をやり直すなどして納期が遅れたためだ。
ピンチに陥っているのは三菱重工だけではない。川崎重工業は9月末、造船事業の採算が悪化しているとして、存廃を含めて検討することを表明した。IHIも10月24日、コストが膨らみ業績を圧迫している資源掘削船など海洋関連事業について、抜本的な対策を検討すると明らかにした。三井造船も、船舶部門の苦戦で2016年9月中間連結決算が23億円の営業赤字に沈んだ。
1956年から半世紀近く世界首位に君臨した日本の造船業がここまで苦しんでいる原因の一つは、中国など新興国の景気減速に伴う市場の低迷だ。2000年代、中国の経済成長を見込んで大量に船が発注された反動で、足元は船余りの状態が続く。日本造船工業会によると、15年に環境規制強化前の駆け込み発注が急増した反動もあって、16年1~8月の日本の受注量は前年同期の2割程度に激減した。
「高付加価値で差別化」戦略が裏目に
日本勢の戦略ミスも大きく響いた。低コストを武器に00年代に台頭した中国・韓国勢に対抗するため、大型客船や海洋資源開発船など高付加価値の船で差別化を図ろうとしたが、技術やノウハウ面で壁に突き当たり、巨額の損失を計上する羽目になった。
窮地に追い込まれた業界に打開策はあるのか。三菱重工は、大型客船建造からの撤退に加え、今治造船(愛媛県今治市)、名村造船所(大阪市)、大島造船所(長崎県西海市)と進めている提携協議を加速させる。今後、三菱重工が技術力を生かして設計を担い、コスト競争力のある造船専業3社が建造を行うなど、協業を強化する方針だ。造船業界では「4社が本気になって連携すれば手強い」(他社幹部)と警戒する声も上がっている。
川崎重工、IHIも17年3月末までに具体的な構造改革方針を出す予定だ。川崎重工と三井造船は過去に経営統合を模索したが、13年に破談となった経緯がある。厳しい造船不況の中、再び他社との提携を模索する可能性もありそうだ。
ただ、再編して国際競争力を取り戻すには、国内の造船所の閉鎖・統合が避けられないとみられ、下請けも含めて大規模な雇用が失われる恐れがある。日本の造船業界がかつてのような輝きを取り戻す道は険しい。
三菱重工業は今、抜本的な構造改革を行っている。ついに発祥の地、長崎造船所(長崎市)で手がけている大型客船事業から撤退することを10月18日に発表した。長崎の地で今、何が起きているのか。週刊エコノミスト編集部の酒井雅浩記者が報告する。
◇「止血」を優先した大型客船事業撤退
大型客船事業は三菱重工の造船事業の中核だ。だが宮永俊一社長は10月18日の記者会見で「コスト的にも成り立たない」と撤退の理由を述べた。
宮永社長の決断をある同社幹部は「踏み込んだ対応もためらわないという内外へのメッセージ」と解説するものの、「あせりがあるのでは」(格付け会社アナリスト)とみる市場関係者も多い。「今の重工には先を見据える余裕がなく、出血を止めることを優先せざるをえなかった」との厳しい評価がある。
◇地元クラブのママはさびしげ
「長船(ながせん)の方は、ますます姿を見せなくなるのかしら……」。地元クラブのママはさみしげにつぶやく。「ながせん」とは、三菱重工業長崎造船所の地元での通称だ。長崎市内の繁華街では「このあたりの店の3分の2は長船が落とした金でできた」と長崎造船所関係者は豪語していた。かつては店が満席でも、先に入った客に出ていくように要求することすらあったという。
しかし2011年10月、客船世界最大手の米カーニバル系のアイーダ・クルーズ社(ドイツ)から大型客船2隻(12万トン)を受注してから、雲行きがあやしくなった。
受注したのは「プロトタイプ」と呼ばれる1番船。内装や設計をゼロから行わなければならず、米カーニバルの厳しい要求が予想されたことから、「無謀な受注」(地元信用調査マン)だった。
三菱重工は04年に大型客船「ダイヤモンド・プリンセス」を引き渡して以降、大型客船の受注が途絶えている。「10年以上受注空白が続くと、技術継承ができなくなる」(三菱重工幹部)との判断から、受注を強行した。
◇3件の火災、特別損失2540億円
建造は、長崎造船所の香焼(こうやぎ)工場(長崎市)で進められているが、苦戦続きだ。1番船の「アイーダ・プリマ」では、今年1月には不審火とみられる3件の火災が船内で発生。1年遅れた2016年3月にようやく引き渡した。建造中の2隻目も含めた特別損失は累計2540億円となり、2隻で1000億円とみられる受注額を大きく上回っている。
長く長崎造船所で労働組合活動に携わった男性は「昔は『こういうときこそ飲みに行け』と先輩から言われたものだが」となげく。長崎造船所にはステータスと同時に、長崎の政治、経済を動かしているという「矜持(きょうじ)」があった。
地元の「オーナー企業」のような振る舞いをする代わりに「金回りや面倒見もよかった」(長崎造船所構内で業務に携わる業者)という。それが宮永社長になってから中央集権化が強まり、地方の事業所の力が弱体化。担当者の裁量に任された調達も、本社の意向を無視できず、地元業者への優遇措置はできなくなった。
◇今治造船など3社と提携協議
長崎造船所は今、改革の真っただ中にある。三菱重工は15年10月、長崎造船所が手がける商船事業を商船建造の「三菱重工船舶海洋」と船体ブロック製造の「三菱重工船体」の100%子会社2社に分社。
また大型客船からの撤退を発表した記者会見で、今治造船(愛媛県今治市)など3社と進めている提携協議を16年度中にまとめ、3社が受注した船の設計を三菱重工が担うといった連携を図る改革方針も表明した。
しかし地元紙記者は「オーナー系の造船会社と三菱重工とは体質がまったく違う。建造を3社に委託するなら、三菱重工にはノウハウが蓄積しない無意味な連携だ」と疑問を投げかける。
◇長崎造船所が撤退したら人口は3分の1に?
ただ、中小型客船の建造は引き続き行う「含み」を見せている。長崎は、これにすがるような思いだ。三菱グループの日本郵船が運用する豪華客船「飛鳥2」(5万トン)の後継船については「思い入れがある」(宮永社長)と受注を示唆している。
これについて、市場関係者からは「客船からの全面撤退への期待が大きかった。踏み切れなかったことへの失望はぬぐえない」(証券会社アナリスト)と「中途半端」との厳しい見方がある一方で、長崎では「長崎造船所にはいつまでも、創業の地としてこれまで通りものづくりを続けてほしい」との願いが強い。
長崎市の人口は現在約43万人。長崎造船所の影響力は以前に比べ弱くなっているとはいえ、ある市議は「長崎造船所が全面撤退すれば、街の規模は15万人」と分析する。祖業での手加減のない改革の成否は、長崎の街の行方を大きく左右する。
Chinese dry bulk shipping company Zhejiang Ocean Shipping (Zosco) has been declared bankrupt by Hangzhou Intermediate People's Court, Chinese media reports.
The news comes after Zosco's principal, Zhejiang Transportation Investment Group (Zhejiang Transportation), in July applied to have the company liquidated, citing debt issues.
While the company's total assets are reported to be valued at RMB5.1 billion ($752 million), 14 major creditors are said to be claiming a total of approximately RMB10.9 billion ($1.6 billion).
Zosco, which sold two of it bulkers in July and currently has a fleet of ten, is said to have recently put a further four of its Capesize bulkers up for sale en bloc.
The court is said to be in the process of arranging an initial creditor's meeting.
Zosco's sister company, Zhejiang Shipping is also noted to be struggling financially, with its subsidiary, Wenzhou Shipping having recently been declared bankrupt.
As Ship & Bunker reported earlier this month, in the wake of the collapse of shipping major Hanjin Shipping Co Ltd (Hanjin), Hyundai Merchant Marine Co Ltd (HMM) said it is considering the submission of a preliminary bid for Hanjin's assets used on Asia-to-U.S. routes
Ship & Bunker News Team
国際的な事業環境の悪化を受け主力の定期コンテナ船事業を統合することで合意した海運大手3社は、31日来年3月期の決算見通しをそろって下方修正し、「日本郵船」と「川崎汽船」が、過去最大の最終赤字に陥ると発表しました。
海運3社は、ことし4月から来年3月までの1年間を通じた決算の見通しを発表し、「日本郵船」は、ことし7月時点の150億円の赤字の予想を過去最大となる2450億円の最終赤字に修正しました。
「川崎汽船」も455億円の赤字の予想を、過去最大の940億円の最終赤字に修正。「商船三井」も黒字ながら、最終利益の予想を150億円から70億円にそろって下方修正しました。
いずれも、船の供給過剰や世界経済の減速などによる国際的な運賃の低迷で収益が悪化し、特に「日本郵船」は、コンテナ船や貨物船の資産価値を引き下げる「減損処理」による損失も膨らみました。
こうした国際的な事業環境の悪化を受け3社は、31日主力の定期コンテナ船事業の統合に向け新会社を設立し、海運業界で加速する国際的な合併や買収など合従連衡の動きに対抗していくことで合意しました。
記者会見した日本郵船の宮本教子経営委員は、「多額の損失を出してしまい、大変、遺憾に思う。運賃の低迷は底打ちの傾向も見られるので、来年度以降、一刻も早く黒字回復を目指したい」と述べました。
三菱重工業は18日、大型客船事業から事実上撤退すると発表した。海外企業から受注した大型客船の建造が想定通り進まず、多額の損失を出したためで、今後は荷物も積める貨客船や中小型客船に集中する。また、今治造船(愛媛県今治市)などとの提携強化を通じ、液化天然ガス(LNG)運搬船などに注力していく方針を示した。
三菱重工の宮永俊一社長が同日、東京都内で記者会見し、「大型客船全体を請け負うのはコスト的にも成り立たない。当面無理」と述べた。
三菱重工は2011年、欧米系クルーズ会社から、世界最大の戦艦だった「大和」「武蔵」の2倍近い12万トン級客船2隻を受注。しかし、設計や建造に手間取り、納入が遅れた結果、16年3月期までに計2300億円超の特別損失を計上した。
この経緯について三菱重工は、一から設計する新型船だったにもかかわらず、「楽観的、拙速な判断で受注した」(幹部)と断定。西洋風内装工事のノウハウが不足していた上、客室の無線Wi-Fi装備など発注側の要求に対応できず、「再発注や調達先変更などの悪循環を誘発した」と総括した。大型客船の関連産業は欧米に集積しており、日本での建造は不利として、今後は貨客船や中小型客船に専念するとした。
同じ三菱系の日本郵船が運用する豪華客船「飛鳥2」(5万トン)の後継船については「思い入れがある」(宮永社長)として受注に含みを持たせた。
また、今治造船、大島造船所(長崎県西海市)、名村造船所(大阪市)と進めている提携協議を16年度中にまとめ、3社が受注した船の設計を三菱重工が担うといった連携を図る改革方針も表明。将来的には造船事業の分社化や3社との資本提携も視野に入れるという。【宮島寛】
◇中韓と競争激化
造船業を巡っては、川崎重工業も9月、業績が悪化している造船事業を抜本的に見直すと発表した。中国、韓国勢との競争激化や世界的な市況低迷により、国内勢は生き残りをかけた再編の波に突入しつつある。
1990年代まで造船量で世界首位だった日本は、急速に台頭する中韓勢に追い抜かれ、15年の新造船建造シェアは19%。中国の37%、韓国の34%に大きく水をあけられた。円高や人件費増でコスト競争力が下がったのが一因で、日本は三菱重工業など総合重工メーカーを中心にLNG運搬船など高付加価値船への注力で生き残りを図ってきた。
しかし、川崎重工はブラジル向け資源開発船取引の焦げ付き、三菱重工も大型客船の建造遅延で巨額損失を計上した。高付加価値化路線の「生みの苦しみ」(村山滋・日本造船工業会会長)に直面している状況だ。
さらに今年に入ると新興国景気の低迷などで世界の造船市況が悪化。日本船舶輸出組合によると、受注量に当たる1~9月の輸出船契約実績は前年同期の約2割にまで落ち込んだ。ウォン高に見舞われた韓国では現代重工業と大宇造船海洋、サムスン重工業の大手3社が大幅リストラを模索しており、中国でも大手の統合案が浮上している。
三菱重工は18日に今治造船などとの資本提携を模索する考えも示したが、合理化競争で後れを取ると中韓との差がさらに開くことにもなりかねない。【宮島寛】
◇キーワード・三菱重工業
三菱商事、三菱東京UFJ銀行と並ぶ三菱グループの中核企業。1884年に長崎造船所としてスタートし、現在では原子力や火力、水処理などのエネルギー・環境分野、自衛隊機、ロケットなどの防衛・宇宙分野、民間航空機や商船などの交通・輸送分野など多様な事業を手がける。国産初のジェット旅客機として開発が進む「MRJ」も三菱重工が2008年に事業化を決め、開発主体の三菱航空機を設立。16年3月期の連結売上高は4兆468億円。
祖業の造船部門は戦時中に戦艦「武蔵」を建造したことで知られる。今は客船やフェリー、液化天然ガス(LNG)の運搬船などを手がける。昨年10月には長崎造船所の一部事業を分社化するなど構造改革を進めている。
三菱重工業が大型客船の受注を凍結する方向で調整していることが9日、分かった。建造の遅れで巨額の損失を出した失敗を踏まえ、いったん手を引く。旅客のほかに貨物も運べる大型貨客船などに注力する。提携協議中の今治造船(愛媛県今治市)など3社とは、三菱重工の造船所の共同利用を検討する。造船で安定した収益を出せるよう構造転換を急ぐ。
三菱重工本社の船の設計などを手掛ける部門の分社化も検討する。今治造船など3社が受注した船の設計を請け負えるようにするとみられる。三菱重工の持つ高い技術力を最大限に活用する。
Posted by Gordon Smith
STX Offshore & Shipbuilding and STX France might be sold by South Korean bankruptcy court. The both assets of the bankrupted shipbuilding group may be sold as a package to unnamed British company for total value of 906 million USD. According to officials, the negotiations are in further stage and represent a change in the plan of the Seoul Central District Court, which wanted to separate the share of STX Offshore & Shipbuilding in the French yard via Samil PricewaterhouseCoopers. The sale will need approval from the French government, which owns the remaining 33.34% stake in Saint-Nazaire facility of STX France, which is expert in building cruise and passenger ships.
The Goseong Offshore & Shipbuilding, which is local unit of the shipbuilding group in South Korea, could also be included into the package deal. Seoul Central District Court is negotiation to sell the liquidated assets and start repayment of the debts to creditors. The assets of the shipbuilding group were assessed to 1.2 billion USD.
“A foreign company has shown interest in buying three STX companies together. We’re looking into such a possibility”, said judge and a spokesman for the Seoul Central District Court, Choi Ung-young.
STX, which filed for receivership in May and investment banks submitted their final due diligence report to the bankruptcy court in August. It is Korean fourth-largest shipyard and a unit of conglomerate STX Corp. STX is active in shipping, construction and energy around the world.
川崎重工業は、急激な円高などによって収益が大幅に悪化しているため、今後、造船事業からの撤退も含めて抜本的な事業の見直しを検討することになりました。
川崎重工業が30日に発表した来年3月期のグループ全体の業績見通しによりますと、売り上げは当初の予想より3.8%少ない1兆5100億円に、本業のもうけを示す営業利益も51.4%少ない340億円にそれぞれ下方修正しました。
これは、今年度、円高が想定を上回るペースで急激に進み、収益が圧迫されたことが主な要因で、特に造船事業は、新規に受注した船で、設計段階のトラブルや工期の遅れなどによる追加の費用が発生したため、大幅に収益が悪化しました。このため、川崎重工業は、造船事業について、今後も続けるかどうかも含めて抜本的な事業の見直しを検討し、来年3月までに結論を出す方針です。
川崎重工業によりますと、造船事業の売り上げは全体の6%程度だということで、事業から撤退し、航空宇宙事業などに経営資源を集中させることも含めて検討することにしています。造船業界では、中国との競合が激しくなっているため、三菱重工業もほかの造船メーカーと提携に向けた協議を進めるなど事業を見直す動きが活発になっています。
川崎重工業は30日、業績予想を下方修正するとともに、船舶海洋事業の業績が大幅に悪化したため「事業の継続性を含め今後の方針を検討する」と発表した。金花芳則社長をトップとする構造改革会議を設置し、事業撤退も視野に検討する。2016年度末をめどに結論を公表する。
16年9月中間決算の連結純損益予想を修正し、50億円の赤字に転落する見通しだと発表した。従来予想は145億円の黒字だった。
初めての船種となるノルウェー向け船舶や、建造中の液化天然ガス(LNG)船で、費用が当初の見積もりを上回る見通しになったことなどが影響した。円高の進行も響いた。
同社が30%出資しているブラジルのエンセアーダ社の資金繰りが悪化して特別損失を計上するのが主因。2016年3月通期の業績についてはまだ見直ししていないが、岩井コスモ証券は今後さらに数十億円規模の損失拡大が懸念されるとして、レーティング(株式格付け)を「B+」から「B」に、目標株価を530円から390円に引き下げた。
今回の特損計上は、13年6月に社長就任以来快進撃を続けていた村山滋社長の足を止めたかたちとなった。数年来1兆3000億円前後を徘徊していた同社の年商を、14年3月期には約1兆4000億円、15年3月期には約1兆5000億円と伸張させ、16年3月期には1兆6000億円超となる業績予想で走ってきたからだ。
航空宇宙 部門が「スター」なら、船舶海洋部門は「ドッグ」
機械の百貨店」とも称される川崎重工は、多岐にわたる事業を7つに分けて経営している。そのなかでも好調で業績に寄与しているのが、村山社長の出身母体でもある航空宇宙部門だ。同部門は16年3月期予想では営業利益を対前年比21%増となる440億円と見込んでいる。村山社長自身も年初にこう意欲を示している。
「ボーイング向けは、この3年で計1000億円を投資した。開発中の最新機「777X」向けでは、昨年、名古屋第一工場(愛知県弥富市)に生産・組み立ての新工場の建設に着手した。自社生産するロボットを導入し、自動化を進める。今後も生産技術を高めたい」(1月16日付SankeiBiz記事より)
一方、今回損失計上の原因となったブラジル事業は船舶海洋部門だ。同部門は15年9月の半期実績で、31億円の営業赤字に沈んだ。同社の7事業部のなかで唯一の赤字部門だ。今回の特損計上で部門赤字額は年度合計としてさらに大きくなる。
実は村山氏が社長に登板したのも、この船舶海洋部門の動きと関連していた。13年に前経営陣が同部門改善の究極の一手として三井造船との経営統合(全社)を図ったのだが、村山氏など他部門の取締役の反対があり解任された。
ROIC経営とはPPMの変形
村山氏は、ROIC経営という耳慣れない経営技法を引っさげてこの巨大企業を率いてきた。
川崎重工で主要事業とされるのは、他に「ガスタービン・機械」「モーターサイクル&エンジン」「車両」「プラント・環境」「精密機械」だ。「船舶海洋」と「航空宇宙」と合わせて7主要事業とされる。ROICはリターン・オン・インベステッド・キャピタルの略、つまり投下資本利益率だ。経常利益額を投下資本で割った数値で、大きいほどいい。
川崎重工の場合、Y軸に営業利益額、X軸にROIC(%)を取る。座標軸はそれぞれをゼロとすると、4象限からなるチャートが得られる。このチャートに7事業の数値をプロットし、さらにそのプロット点を中心に当該事業の年商を円として表すと、規模感も一目で掌握できる。
一企業が複数の事業にどのように経営資源を分配するのかを決定するための手法のひとつとしてPPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント、別名:BCGマトリックス)がある。ROIC経営の手法と得られるチャートは、実はPPMとよく似ているというか、PPMの応用というべき技法だ。PPMをさらに精緻に複雑にして、PPMと同じ結果を得ようとしているにすぎないともいえる。
PPMの場合は、Y軸に市場成長率、X軸にマーケット・シェアをとり、4象限の中に自社の各事業をプロットする。PPMは1980年代に発表された古い技法だということと、両基準とも相対的で主観が入るなどの批判により衰退してきたが、私に言わせればわかりやすく使いやすい技法なので、経営コンサルタント会社が顧客からフィー(報酬)を取れないのが衰退の理由だった。
川崎重工の場合、PPMによれば「船舶海洋」は「負け犬」に、「航空宇宙」は「花形」に分類される。PPMでは前者は撤退を、後者は優先事業としなさい、と示唆される。
ROIC分析を経営実践に活かし続けろ
川崎重工では、7事業部のレベルを超えて32のビジネスユニット(BU)をROICチャート分析しているという。そして、それによりBUを5つの格付けランクに分けている。それは当然のことで、PPM亜流のROICは事業の優先順位、投資順位を求めるものだからだ。多岐にというか広範な事業展開をしている同社のような大企業では、経営トップといえどすべての事業の詳細について把握できない。詳細を把握することなしにメリハリを付けた経営をしていく技法が必要なのだ。
川崎重工の場合、ROIC分析に基づいた格付けをBUレベルでは開示していないという。社員は自部門の格付けは知らないというのだ。これについて太田和男CFO(最高財務責任者)は、「『ウチはコングロマリット(複合体)経営。強い事業と弱い事業が相互に補完できる体制づくりが優先』と語り、事業の選択と集中には慎重だ」(「日経ビジネス」(日経BP社/1月18日号)と説明している。
せっかく複雑な分析技法を開発・駆使しているのに、その結果は発表しないし、使わないという。つまり、財務部門の単なるシミュレーションであり、太田氏の時間潰しということであろうか。
そんなことはないだろう。告げられない、のだ。PPM分析の場合、社員や事業リーダーへの告知は難しい。「ドッグ:負け犬」となれば「もう撤退するよ」という告知となる。アメリカなら転職準備を始めなさい、というシグナルと受け取られるだろう。「キャッシュ・カウ:金のなる木」ということでも複雑だ。「君の事業はもう成長しなくていい。投資もしない。そのままプロダクト・ライフ・サイクルの衰退期に入っていって、静かに利益貢献をしてほしい」などと明示されて、意欲を高めることができる幹部がどれだけいるだろうか。
川崎重工の現在の好調は、「航空宇宙部門」という「花形」事業のおかげだ。これが続いているうちに「船舶海洋部門」をカーブアウト(切り離し)して社外に出してしまうことだ。そして、そこで得られるキャッシュを他5部門に効果的に投資する。こんなやりくりで同社は「次の1兆円」を目指すことができる。
村山社長が航空宇宙部門出身だけに、同部門の好調に酔って事業ポートフォリオ戦略を出動しない「無策の時間」があったりすると、14~15年の成長はほどなく止まってしまうだろう。
(文=山田修/ビジネス評論家、経営コンサルタント)
山本 直樹 :東洋経済 記者
これでウミ出しとなるのか――。川崎重工業は14日、ブラジルの造船事業に関連して、2015年第3四半期(4~12月)に221億円の損失を計上すると発表した。
ブラジルの汚職問題に絡み、現地企業との合弁会社、エンセアーダが受注したドリルシップ(海洋掘削船)2隻の建造工事代金が1年以上支払われない状況が続き、同社が経営難に陥ったためだ。
ドリルシップの建造は川崎重工業が請け負っており、2015年に引き渡し予定だった1番船はほぼ完成、2番船も5割程度まで進捗していた。だが早期の入金再開が見込めないことから同年11月にエンセアーダと工事中断に合意し、損失処理を行うことになった。
保険が効かず、損失が膨らんだ
損失の内訳は、エンセアーダへの出資金、貸付金の評価損28億円とドリルシップ関連の売掛金、仕掛品の評価損192億円。NEXI(日本貿易保険)の輸出保険で一定額を賄える見通しだったが、「見解の相違があり求償できる可能性が低い」(広報)ことから損失額が膨らんだ。なお、ほぼ完成済みの1隻については50億円程度の回収可能性があるとして、その分は損失処理から差し引いた。
川崎重工業がブラジル事業に参入したのは2012年のこと。超深海の巨大油田開発を進めていたブラジル政府の協力要請を受け、現地の建設大手3社が設立したエンセアーダに3割出資した。2013年にはエンセアーダが国営石油会社、ペトロブラス向けドリルシップ6隻を受注。そのうち2隻の船体部などを川崎重工業が引き受け、坂出工場(香川県)で建造していた。
しかし、翌年にペトロブラスや建設会社などが絡む大規模な賄賂・汚職スキャンダルが発覚。この余波でエンセアーダへのドリルシップ建造工事の入金が停止し、資金繰りが悪化。川崎重工業への支払いも止まった。
三菱重工業やIHIも同様に現地造船会社に経営参画していたが、前2015年3月期にブラジル造船事業の関連損失としてそれぞれ80億円強、290億円を計上。三菱重工業は出資も引き揚げる方針だ。一方、川崎重工業はエンセアーダが現地合弁先からつなぎ融資を受けていたこともあり、事業の継続性に問題はないとしてこれまで損失処理をしていなかった。
担当の代表取締役が降格へ
その後も経営環境が改善しなかったことから、川崎重工業もついに損失処理の判断に至った。実はブラジル以外でも、ノルウェー企業から受注した海洋掘削船で仕様変更に伴う工期延期でコストが膨らみ、今期の造船事業は赤字の見通し。こうした責任を明確にする形で、今回の損失計上とともに造船事業を担当する村上彰男代表取締役常務を代表権のない取締役に降格する人事を発表した。
だが、エンセアーダに対する技術指導や研修生の受け入れなど、合弁契約に基づく協力関係は継続する。国内造船大手は韓国、中国勢が台頭してきたコンテナ船やタンカーなどから、付加価値の高い分野へシフトする動きが鮮明になっている。川崎重工業としては、今後も「新規参入した海洋掘削関連で生き残りを図る」と強気の構えだ。
こうした対応について、「ブラジルから撤退せずに造船事業のトップを更迭するのは、ちぐはぐな印象」(造船アナリスト)との声も聞かれる。
1月20日のニューヨーク原油先物市場では、1バレル=26ドル台前半と約12年8カ月ぶりの安値を付け、海洋掘削事業を取り巻く環境はきわめて厳しい。競合が縮小・撤退判断に傾く中で橋頭堡を築くことができれば、残存者利益を享受することができる。しかし、強烈な逆風に耐えてどこまで事業を継続できるか、正念場が続くことになる。
韓進海運の経営破綻が思わぬ方向に飛び火した。
同社は川崎汽船など5社で共同配船のアライアンスを構成しており、加盟各社は目下、韓進海運の経営破綻に伴う混乱の対応で手いっぱいの状況だが、すでに世界では「韓進海運の抜けた穴」をめぐって荷主獲得競争が始まっている。
こうした中、近鉄エクスプレスが昨年5月に買収した大手国際フォワーダー「APLロジスティクス」(シンガポール)がその取引先に「川崎汽船に倒産の可能性がある」という内容のメールを発信していたことがわかった。
川崎汽船は現時点で相手方の社名を伏せているが、同社によると、APLロジスティクスから配信されたというメールに基づき荷主から「倒産する可能性があるというのは本当なのか」といった問い合わせが多数寄せられている。
問い合わせが殺到したことに驚いた川崎汽船は、直ちにAPLロジにメールの撤回を強く求めて抗議。この結果、APLロジ側はメールを発信していた事実とその内容の誤りを認め、メールの撤回と訂正文書の送付を約束した。
しかし、ただでさえ韓進海運の経営破綻に伴う対応に追われている最中のできごとだけに、事態を重視した川崎汽船は「事実無根であり、非常に迷惑な話だ」と憤りを隠さず、APLロジに対する法的措置も辞さない構えだ。
実際のところ、韓進海運の経営破綻が川崎汽船に及ぼす影響はどの程度になるのか。
直接的な影響は、取引先への説明や混乱の最中にある「貨物」にどう対応するかといった業務上の対応が中心で、総合海運会社である同社にとってコンテナ船部門は一部に過ぎず、「屋台骨を揺るがすほどまでは行かないのではないか」という見方が大勢を占める。
同社も「韓進海運と同じアライアンスに属しているわけだから、同業他社との『呉越同舟』による悪影響はあるが、財務面にはさほど大きなダメージとならないのではないか」との見方を示すが、舵取りを誤れば影響が大きくなる可能性をはらんだ敏感な問題であることは間違いない。
そういう中で発覚した、APLロジによる川崎汽船倒産メールだけに、同社とその取引先が受けたショックは小さくないだろう。
23日時点でAPLロジは、このメールに関する公式声明を発していない。
親会社の近鉄エクスプレスは「そういうメールがAPLロジスティクスから発信されたという報告は受けているが、詳細を把握できていない」とコメントした。自社グループ入りしてからまだ日が浅いとはいえ、1500億円もの巨費を投じて買収したAPLロジによる行為であり、国際的な混乱が生じている韓進問題に関することだけに、知りませんで済む話しではない。
窮地にある物流企業のあらぬ噂を「あっても不思議ではないタイミング」で流したとなれば、企業姿勢やコーポレートガバナンスが機能していないのではないかという指摘も出てこよう。
子会社で発生した事態に、近鉄エクスプレスはどう対応するのか。
同社によると現在、近鉄エクスプレス品川本社のAPLロジスティクス担当役員がシンガポールに飛び、今回の事態を含めた詳細な状況把握と収拾に向け、陣頭指揮を取っているという。具体的な対応は未定だが、担当役員が帰国後、26日にも同社首脳が役員から報告を受けたうえで対応を協議する予定で、「事実関係を精査し、真摯に、スピーディーに対応していきたい」としている。
韓進海運の経営破綻が思わぬ方向に飛び火した。
同社は川崎汽船など5社で共同配船のアライアンスを構成しており、加盟各社は目下、韓進海運の経営破綻に伴う混乱の対応で手いっぱいの状況だが、すでに世界では「韓進海運の抜けた穴」をめぐって荷主獲得競争が始まっている。
こうした中、近鉄エクスプレスが昨年5月に買収した大手国際フォワーダー「APLロジスティクス」(シンガポール)がその取引先に「川崎汽船に倒産の可能性がある」という内容のメールを発信していたことがわかった。
川崎汽船は現時点で相手方の社名を伏せているが、同社によると、APLロジスティクスから配信されたというメールに基づき荷主から「倒産する可能性があるというのは本当なのか」といった問い合わせが多数寄せられている。
問い合わせが殺到したことに驚いた川崎汽船は、直ちにAPLロジにメールの撤回を強く求めて抗議。この結果、APLロジ側はメールを発信していた事実とその内容の誤りを認め、メールの撤回と訂正文書の送付を約束した。
しかし、ただでさえ韓進海運の経営破綻に伴う対応に追われている最中のできごとだけに、事態を重視した川崎汽船は「事実無根であり、非常に迷惑な話だ」と憤りを隠さず、APLロジに対する法的措置も辞さない構えだ。
実際のところ、韓進海運の経営破綻が川崎汽船に及ぼす影響はどの程度になるのか。
直接的な影響は、取引先への説明や混乱の最中にある「貨物」にどう対応するかといった業務上の対応が中心で、総合海運会社である同社にとってコンテナ船部門は一部に過ぎず、「屋台骨を揺るがすほどまでは行かないのではないか」という見方が大勢を占める。
同社も「韓進海運と同じアライアンスに属しているわけだから、同業他社との『呉越同舟』による悪影響はあるが、財務面にはさほど大きなダメージとならないのではないか」との見方を示すが、舵取りを誤れば影響が大きくなる可能性をはらんだ敏感な問題であることは間違いない。
そういう中で発覚した、APLロジによる川崎汽船倒産メールだけに、同社とその取引先が受けたショックは小さくないだろう。
23日時点でAPLロジは、このメールに関する公式声明を発していない。
親会社の近鉄エクスプレスは「そういうメールがAPLロジスティクスから発信されたという報告は受けているが、詳細を把握できていない」とコメントした。自社グループ入りしてからまだ日が浅いとはいえ、1500億円もの巨費を投じて買収したAPLロジによる行為であり、国際的な混乱が生じている韓進問題に関することだけに、知りませんで済む話しではない。
窮地にある物流企業のあらぬ噂を「あっても不思議ではないタイミング」で流したとなれば、企業姿勢やコーポレートガバナンスが機能していないのではないかという指摘も出てこよう。
子会社で発生した事態に、近鉄エクスプレスはどう対応するのか。
同社によると現在、近鉄エクスプレス品川本社のAPLロジスティクス担当役員がシンガポールに飛び、今回の事態を含めた詳細な状況把握と収拾に向け、陣頭指揮を取っているという。具体的な対応は未定だが、担当役員が帰国後、26日にも同社首脳が役員から報告を受けたうえで対応を協議する予定で、「事実関係を精査し、真摯に、スピーディーに対応していきたい」としている。
韓国の海運業界が崩壊の危機にひんしている。同国最大手の韓進海運が8月末に経営破綻したためだ。あおりで国際物流は大きく混乱し、韓国の輸出にも悪影響が及ぶ懸念は強い。韓国内では日中の船に頼らなければ「貿易立国・韓国」も立ち行かなくなりかねないとの嘆き節も聞かれ始めている。
■70隻以上が幽霊船に
9月11日現在、韓進海運が保有するコンテナ船97隻のうち70隻以上が世界各地の海上で幽霊船のように漂っている。荷役費、燃料費などが支払えず、入港を拒否されているためだ。韓国メディアは、積み荷の総額は約140億ドル(約1兆4000億円)に上り、これらの荷降ろしには計千数百億ウォンかかると伝えている。
韓進海運を抱える財閥、韓進グループの趙亮鎬会長は私費で400億ウォン(約37億円)の拠出を表明。グループ中核の大韓航空も韓進海運の資産を担保に600億ウォンを拠出する方針を示したが、社外役員から「大韓航空の株主の利益を侵害し、背任に当たる恐れがある」と指摘され、実際に拠出できるかどうかはわからない状況という。
「貨物が届かない」-。朝鮮日報によると、米ニューヨークのプラザホテルで7日に開かれた米金融大手ゴールドマン・サックスの年次会議「流通業カンファレンス」では、韓進海運の破綻による国際物流の混乱に対して参加企業からこんな悲鳴が上がった。
米国では11月の最終金曜日に最大のショッピングセール「ブラックフライデー」を控える。このままでは韓国や中国から輸送されるはずだった衣類や玩具がセールに間に合わなくなる恐れは大きい。
米電子機器メーカーのヒューレットパッカード(HP)の関係者は「韓進海運の船舶にコンテナ500個以上の貨物を積んでいるが、ロサンゼルスの港などに入れない状態だ」として「このままでは市場シェアまで急落してしまう」と嘆いたという。
昨年、韓進海運が取り扱った約460万TEU(1TEUは20フィートコンテナ1個分)のうち韓国の貨物は10.7%にすぎず、残りは中国や米国、日本など外国の貨物だ。それだけに、物流の混乱による被害は世界規模で拡大している。
中央日報は12日の社説で「緻密な善後策もないまま韓進海運を経営破綻させ、混乱を収拾できない政府の無能さを世界にさらしている」と批判した。
■オーナー家のミス
韓進海運が日本の会社更生法の適用に当たる「法定管理」をソウル中央地裁に申請したのは8月31日。ロイター通信によると、昨年末の負債額は5兆6000億ウォン(約5200億円)に上ったという。
韓進海運は4月、政府系の韓国産業銀行(KDB)などでつくる債権団による「共同管理」を申請し、経営再建を進めてきた。だが、債権団は8月30日に、共同管理を9月4日の期限から延長しない方針を決定。経営再建には1兆ウォン超の資金が必要とされるが、韓進海運が示す資金負担額が債権団の要求に満たず、これ以上の支援は困難と判断した。
フランスの調査会社の統計などでは、韓進海運はコンテナの積載能力で世界7位。その歩みは韓国海運業の歴史と重なる。
中央日報などによると、同社は1977年に韓進グループ創業者の故趙重勲氏が国内初のコンテナ専用船会社として設立した。当時、航空業を軌道に乗せた趙氏は朴正煕大統領の勧めで海運業に参入。陸・海・空にわたる総合物流企業を目指した。
韓進海運は78年に中東航路、79年に北米西岸航路を開設し、世界的な海運会社に成長。92年に売上高が1兆ウォンを超え、欧州、中国などにも航路を広げた。
だが、世界的な海運不況が直撃し、2011年12月期に最終赤字に転落。その後、保有資産の売却などで業績は一時的に持ち直したものの、新興国経済の減速で荷動きが鈍って運賃が低迷し、再び経営危機に陥った。
「オーナー家の経営判断のミス」。同社の破綻については、こんな見方も多い。
財務改善のため保有船舶を売却して用船会社からのチャーターに切り替えたが、最終的に高すぎる用船料が経営の大きな重荷となったからだ。
■釜山港の地位低下も
韓進海運の破綻で生じた海運市場の空白を突く動きが出てきている。
朝鮮日報によると、海運世界最大手のデンマーク企業、マースクは8日、中国・上海、韓国・釜山、米国・ロサンゼルスを結ぶ新路線を15日から運航すると発表。同社関係者は「(韓進海運の法定管理で)船舶確保に問題が生じ、解決を求める荷主の問い合わせが増えた」と説明した。
同2位のスイスMSCも15日、中国~釜山~カナダ路線の運航を始めた。価格競争力を備えた海外の巨大海運会社が相次いで釜山港に進出し、韓進海運の取り扱い貨物を根こそぎ持っていこうとしている形だ。
韓国内では「韓進海運だけでなく、現代商船など韓国の海運各社の存立基盤が揺らぐ。韓国海運業の崩壊懸念が現実となった」と危ぶむ声も浮上している。
海外の海運会社による攻勢は釜山港の競争力を低下させるとの見方もある。韓進海運はこれまで中国、日本、東南アジアなどから小型貨物船で運んだ積み替え貨物を釜山港に集め、大型貨物船に移して米国に運んでいた。しかし、海外の海運会社は釜山港を利用せず、上海港などをハブ港湾とする可能性が大きい。
韓進海運は2015年に韓国の貿易量の約7%を扱っており、破綻が韓国の貿易の障害となることへの警戒感も強まっている。
韓国海洋水産開発院の梁昌虎院長は中央日報のインタビューに「1年半後からは国内輸出入業者は船を外国に依存しなければいけない」とし「韓進海運が消えれば日本や中国に高い運賃を支払うことになるだろう」と指摘した。
韓進海運の破綻は世界の海運市場の勢力図を大きく塗り替えるのは間違いない。(本田誠)
コンテナ船では世界7番手、韓国では最大手の韓進(ハンジン)海運の経営破綻の影響が世界中に広がっている。
寄港や荷下ろしに関する費用の不払いを恐れ、入港を拒否されている船は約70隻。世界の海を漂流中だ。前代未聞の事態に荷主はもちろん、港を目の前に下船できない缶詰め状態の乗客や乗員が悲鳴を上げている。
■「ナッツ・リターン」の兄弟企業
発端は先月末、同社の経営再建策が手ぬるいとして銀行団に追加融資を拒まれ、韓国の裁判所に破産手続きの申請をしたこと。海運不況でコンテナ船運賃の低迷が続くうえ、オーナー家が支援に消極的なことが融資拒否の理由という。
通信社のロイターによると、各地の海をさまよう貨物船に積まれたコンテナの数は約40万個、積み荷の価値は約140億ドル(約1兆4000億円)、荷主は約8300社におよぶ。
韓進のコンテナ船の入港を拒否した中には日本の港も含まれていて、同社と取引がある日本の船会社や港への影響も避けられない。神戸港では、神戸市が韓進の空コンテナの滞留を避けるため、コンテナの移動、回収費用を補助する緊急措置を14日から開始したほど。
韓進海運の負債は約55億ドル(約5500億円)。韓国ではナッツ・リターン事件で悪名をはせた大韓航空が兄弟企業で、同じ財閥に属している。韓進海運の経営難は以前からで、韓国では大韓航空の支援の遅れに批判が高まっている。
米国の経済紙・ウォール・ストリート・ジャーナルによると、同社は債権者による自社船や積み荷の差し押さえを防ぐため、今月初め、米国ニュージャージー州の裁判所に破産手続きの申請をしたという。
日本近海をさまよう船も
荷主はもちろんだが、寄港を拒否された船に乗り合わせた不運な乗客や乗員は途方に暮れている。
英国の公共放送BBCによると、日本列島付近を航行していたハンジン・ジェネバ号に乗船中の英国の美術大学院生レベッカ・モスさん(25)は「23日を海で」というカナダ・バンクーバーの美術財団のプログラムに、800人以上の応募者から選ばれた。バンクーバーから乗船し、今月15日に上海で下船する予定だったが、今も日本近海をさまよう羽目に。
船には25人の乗員が乗り組み、食べ物や飲み物は数週間持つというが、船長もいつどこに入港できるか見当がつかない。彼女はインスタグラムによる取材を通じ、「2週間前に聞いたときは一時的なものと思っていた。今はどこかに寄港できる知らせを待ちわびているけど、先がどうなるか誰にもわかりません」と不安を隠せない。
BBCの別の取材に、2週間前からシンガポール港に停泊中のハンジン・ローマの36歳の船長は、友達からもらったシンガポールのSIMカード付きスマホが外界の情報を得る唯一の手段という。韓国・釜山に住む妻と娘は1日も早い寄港と帰国を望むが、朗報は聞けないままという。
荷主や乗員の家族は船会社に早急な対応を迫るが、金融支援のめどがつかない限り、船の「漂流」は続く。韓国紙・朝鮮日報日本語版によると、パク・クネ大統領は13日の閣議で、「韓進海運は自助努力が全く足りない」「企業が再建に努めず、政府がすべてを解決してくれるだろうと考える企業経営方式は決して黙認しない」と厳しく批判。韓国では相次ぐ財閥企業の失態やモラルハザードに、かつてないほどの不満やいらだちが高まっている。
韓国の柳一鎬(ユ・イルホ)経済副首相兼企画財政部(省に相当)長官は7日、韓国海運最大手、韓進海運の経営破綻(はたん)による物流混乱と関連し「韓進海運の船を利用するため船積み待機中の貨物についても、代替船舶の投入拡大といった対策を講じる」と明らかにした。産業競争力の強化を話し合う関係閣僚会議で述べた。
柳副首相は「構造調整の推進体系の枠内で緊急対策をまとめ、備えてきた」としながらも「現場に混乱と懸念を与えたことに対し、経済チームのトップとして大きな責任を感じている」と述べた。代替船舶の投入スケジュールについては「2日にベトナム路線に代替船舶1隻を投入し、今週から米州、欧州、東南アジア路線などに20隻以上を追加投入する計画だ」と説明した。
一方、韓進海運の法定管理(会社更生法に相当)手続きを担当するソウル中央地裁破産6部はこの日「韓進海運の(経営)正常化に向け、銀行団の助力が必要だ」とし、同社メーンバンクの政府系金融機関、韓国産業銀行に緊急資金支援を要請した。だが、同行関係者は「銀行団が支援に乗り出す可能性は低い」としている。
韓国の海運最大手、韓進(ハンジン)海運が日本の会社更生法にあたる法定管理を申請したことを受け、同社のコンテナ船が世界各国の港で受け入れを拒否されるなど混乱が生じている。韓国メーカーの北米向け輸出への影響も懸念されるなか、朴槿恵(パク・クネ)政権の準備不足も指弾された。「韓進ショック」は東京都にも及んでいる。
韓国メディアによると、韓進が保有するコンテナ船やバルク船は計141隻あるが、5日時点でこのうち79隻が23カ国44港で入国を拒否されるなど運航に支障が出た。貨物の積み卸しを委託された業者が代金が支払われないことを恐れて作業を拒否するなどの事態が起きているという。
韓国から北米向けの輸出にも影を落とす。サムスン電子は40%超、LG電子は20%超の海上物流を韓進で扱っているとされる。韓国政府は8日から一部の代替船を準備するが、感謝祭やブラックフライデーなどクリスマス商戦に向けた最も大事な時期だけに、貨物の到着遅れは深刻だ。
ハンギョレ新聞は、納期が遅れている貨物に関して最大140億ドル(約1兆4560億円)規模の訴訟に巻き込まれる懸念があると報じた。
5日に母港の釜山港に入港した船も貨物を降ろしただけで、船舶の差し押さえを避ける狙いもあって再び港を離れ、公海上で待機していると聯合ニュースは報じた。飲料水や食料も残り少なく、排泄(はいせつ)物をためる施設の容量も限界に達しつつあるなど乗組員は劣悪な環境で「海の上の難民」のような状態だという。
ハンギョレ新聞は、「韓進を存続させるかどうかに焦点が合わされ、法定管理の余波に関する政府のきめ細かい対策は不十分だった」と朴政権の対応を批判した。
日本にも余波は及ぶ。韓進の日本支店は2日、「当面の間、日本の各港への入港の見込みが立っていない」と説明した。
また、東京都が約50%の株式を保有する東京港埠頭(ふとう)によると、韓進は青海コンテナ埠頭のA3ターミナルを1994年以来、借り受けている。
また、中央防波堤外側外貿コンテナ埠頭のY2ターミナルについても昨年8月に本契約の前段階にあたる賃貸借予約契約を韓進と結び、2017年に供用開始予定となっている。東京港埠頭は「動向を見極めたい」(総務課)としている。
韓国では、韓進が今後、再建ではなく清算に向かう可能性が高いとの観測もある。仮に清算となれば、東京港の一連の契約について見直される可能性もありそうだ。
韓国の海運最大手で、保有船腹量で世界第7位の韓進(ハンジン)海運が経営破綻(はたん)し、同社が運航している貨物船68隻が、日米中など世界23カ国の44港湾で立ち往生しかねない事態に陥っている。韓国政府は4日、緊急の関係省庁次官会議を開いたが、当面必要な資金繰りに苦しんでいる。
韓進海運は8月31日、債権団との交渉決裂を受けて、法定管理(日本の会社更生法適用に相当)をソウル中央地方裁判所に申請した。債権団が同社貨物船を差し押さえたり、入港料や荷役料の支払いが滞ったりする可能性が出てきた。
同社によれば、4日現在、計68隻が荷役中か今後の荷役が予定されている。このうち、日本の横浜、名古屋、門司の3港では、タグボートや荷役などの業者が不払いを恐れて作業を拒否し、外洋で立ち往生しているという。
シンガポールで「韓進ローマ号」仮差押さえ 中国・スペイン・米国の港では入港拒否
韓進(ハンジン)海運が法定管理を申請した31日、海外では船舶の仮差押さえと入港拒否が相次いだ。
債権団の支援中断により法定管理の申請が既定の事実となった30日、シンガポールの裁判所は韓進海運所有の5308TEU(1TEUは20フィートコンテナ1個)級のコンテナ船「韓進ローマ号」をシンガポールの港で仮差押さえした。ドイツの海運企業のリクモスが、韓進海運の傭船料が未払いになっているとしてこの船の仮差押さえを申請したという。停泊地で船舶が仮差押さ処分を受ければ、差し押さえが解除されるまで埠頭への接岸や荷役作業は不可能になる。
韓進海運が傭船していた他の船舶も相次いで運航を中断していることが分かった。韓進海運が傭船したコンテナ船「韓進メキシコ号」は31日に運航を中止した。船主のPILが傭船料の未払いを理由に運航の中断を要求し、直ちに貨物輸送に支障が生じることになった。現在、韓進海運所有のコンテナ船は37隻で、61隻は海外の船主から借りて使っている。
韓進海運の船舶に対して現金での支払いを要求し、事実上の入港拒否をする所も相次いで現れている。31日こうした方針を知らせてきたところは、中国の廈門と星港、スペインのバレンシア、米国のサバンナ、カナダのプリンスルパート、シンガポールの港だ。船舶が入港すれば港湾への接岸と貨物の荷役作業を行うが、ここに入る費用を現金で払わない限り入港を許可しないと通知したのだ。
海外債権者による船舶の仮差押さえと債権回収、入港拒否は今後も続く見通しだ。法定管理を申請すれば、韓国国内では裁判所の債務保全処分により仮差押さえを避けることはできるが、外国では差し押さえ処分が続く可能性がある。その場合、韓進海運の船舶に載せられた貨物の引き渡しは不可能になるか、遅れることになるため、輸出入企業に被害を及ぼすことも予想される。
一方、この日韓国国際物流協会、釜山港湾運送労組、韓国船主協会など20以上の団体が釜山港国際旅客ターミナルで「韓進海運の再生のための汎市民決起大会」を開き、韓進海運が必要とする3000億ウォン(約278億円)の調達方案の摸索などを要求した。
【ソウル=藤本欣也】韓国海運最大手の韓進(ハンジン)海運が31日、日本の会社更生法に当たる法定管理をソウル中央地方裁判所に申請した。
債権団は、1兆ウォン(約920億円)規模の経営改善案を要求してきたが、5千億ウォンを提示する同社側と折り合わず、8月30日、追加資金支援を拒否することを決定していた。韓進海運は大韓航空などを傘下に収める韓国財閥、韓進グループの中核企業で世界7位の海運会社。長引く海運不況で経営難に陥っていた。
今後、債権者に保有船舶を差し押さえられる可能性があり、積載貨物の輸送にも支障を来しかねない。聯合ニュースによると、裁判所側は、債権者が韓進海運の資産を強制執行することを禁止する包括的禁止命令を出す方針という。
同社が基盤としていた釜山港への影響も大きく、韓国政府は海洋水産省を中心に対策に乗り出す。
経営が悪化していた韓国の財閥グループで、同国海運最大手の韓進(ハンジン)海運は31日午前、取締役会を開き、日本の会社更生法に当たる法定管理を申請することを決めた。聯合ニュースなどが報じた。前日に銀行など債権団が同社への追加金融支援を行わないと決定、再建への道が閉ざされていた。
韓進海運は、韓進グループの中核企業で、大韓航空は兄弟会社にあたる。大韓航空の客室乗務員に激怒して離陸を遅らせた「ナッツ姫」の父としても知られる創業家2代目の趙亮鎬(チョ・ヤンホ)会長がグループ総帥を務める。
その趙氏は今年5月、2018年平昌(ピョンチャン)冬季五輪の組織委員会会長を突如辞任した。その理由が、韓進海運の経営に専念するというものだった。
海運不況や船舶の調達戦略のミスもあって財務状況が悪化、船のリース料の引き下げや社債の償還延長交渉などを進めてきたが、金融支援でなんとか生き延びる「ゾンビ企業」状態となっていた。
韓国メディアによると、韓進海運の債権団は、韓進グループに7000億ウォン(約637億円)以上の資金支援を求めたが、韓進側は4000億ウォン(約364億円)以上の支援をすると、グループ全体の経営危機につながる恐れがあるとするなど、両者の隔たりは埋まらなかった。
同業の現代(ヒュンダイ)商船の合併論も再浮上したが、同社の業績も悪化していることもあり、実現しなかった。
債権団は30日、追加支援を行わないことを決定。債権団の共同管理の期限である9月4日を待たずに法定管理に追い込まれることになった。
主な取引銀行はすでに貸倒引当金を積んでいるため、韓進海運法定管理に突入した場合も損失は限定的とされるが、1兆1891億ウォン(約1082億円)規模の社債については回収される可能性は低く、農協や信用保証基金などの社債保有者が損失を被る恐れがあるという。
韓国の金融監督院がまとめた財務状況に問題のある企業32社の中にも両社は含まれている。ほかにも破綻懸念のある大企業がゴロゴロしているのが韓国の実情だ。
韓進(ハンジン)海運の法定管理(企業再生手続き)が秒読み段階に入った中で、韓国政府が海運業界と市場の衝撃を最小化するための対策準備に入った。
28日、政府関係者は「現代(ヒョンデ)商船が国内の荷主の物流量を最大限吸収できるよう規模を大きくしなければならない」として「1万3000TEU(1TEUは6メートルのコンテナ1個)以上級のコンテナ船10隻を建造できる船舶ファンドの支援を現代商船に集中する」と話した。韓進海運が法定管理に入れば船舶が債権者に抑留される可能性が高いため、荷主らは代替船舶を探さなければならない。この過程で運送費の負担が大きくなる可能性がある。
国際貨物データ専門調査機関のデータマインによれば北米航路(アジア~米国)基準で2015年の国内の主な荷主別の韓進海運依存度はサムスン56%、LG化学53.8%、ネクセンタイヤ24.9%、LGエレクトロニクス23.2%、ヒョソン20.8%、ハンファソーラーワンが12.9%だ。韓進海運の物量をそのまま現代商船が吸収するのは難しい見通しだ。韓進海運が属する海運同盟の「CKYHE」の中国のコスコ、台湾のエバーグリーンと陽明海運、日本の川崎汽船などが先にこれに代わる可能性が高いためだ。
現代商船の関係者は「8~9月はコンテナ船社にとって最大の繁忙期で韓進海運の荷主の貨物を追加で運送する余力が足りない」と話した。
債権団は韓進海運が破産を避けるのかどうか神経を尖らせている。債権団は法定管理の下でも新規の資金支援を通じて企業再生の可能性を高める「クレディターズ・トラック」(債権団主導の再生計画案の樹立)という制度を活用する案を検討した。だが韓進海運に適用するのは不可能だと知らされた。産業銀行をはじめとしてKEBハナ・農協・ウリィ・国民・輸出入・釜山(プサン)銀行など債権団の韓進海運の与信は計1兆128億ウォン(約920億円)規模だ。ほとんどが貸倒引当金を積んで法定管理にともなう被害がわずかなことが分かった。
1兆1891億ウォン(約1100億円)規模の韓進海運の会社債は投資家に大きな被害を残すものとみられる。韓進海運が破産すれば回収率が0~5%に近いというのが法定管理専門家たちの見通しだ。公募社債(4210億ウォン)はほとんどが単位農協、信協が持っている。私慕社債(7681億ウォン)は信用保証基金と産業銀行が保有している。金融監督院は近くタスクフォースを構成して被害対策を講じることにした。
韓進グループはこの日、報道資料を通じて「一部の海外銀行が船舶金融償還を猶予してくれることになった」として「政府と債権団の支援が切実だ」と明らかにした。
三菱重工業の客船建造が、事業をやめるかどうかの瀬戸際に追い込まれている。造船は創業時からの「本業」で、中でも客船は花形事業だったが、約10年ぶりに受注した超大型客船で大赤字を出したためだ。ただ、日本で豪華客船をつくれるのは三菱重工だけ。日本の造船業の将来もかかって、板挟み状態だ。
三菱重工の客船の歴史は古い。創立3年後の1887(明治20)年に1隻目を完成させて以来、130年近くで約100隻をつくった。
旅客機の旅が広がった戦後の40年以上は客船をつくらなかったが、1990年、日本郵船向けの「クリスタル・ハーモニー(現飛鳥II)」で復活。造船業界では中国や韓国が台頭し始めていたが、客室など細かく様々な作業が必要な客船は中韓勢がまだ手がけておらず、差別化の切り札にする狙いがあった。
狙い通り、英国の海運会社向けの超大型客船「ダイヤモンド・プリンセス(サファイア・プリンセスに改名)」などを受注したが、長崎造船所で建造中の2002年に同船で火災が発生するトラブルに見舞われた。三菱重工はその後10年近くの間、客船造りを控えた。
次の受注は11年。ドイツのアイーダ・クルーズに納入する大型客船2隻を受注した。ところが、客船造りを休んでいた10年近くの間に世の中はデジタル化が進み、客室すべてにネット設備を設けるのが当たり前に。ノウハウがない三菱重工は手間取り、設計遅れや建設やり直しで大赤字になった。
日本の見栄のため「シップリサイクル条約」の早期締結は良いがインパクトかなり大きいと思う。
シップリサイクル条約の国内法制化の方向性を検討します 平成29年10月27日(国土交通省)
新造船のコストアップは確実だし、造船所の負担もアップ。
多くの日本の中古船は海外に売船されている。売船されて日本の港から出向する時に日本(国交省や保安庁)はかなり目をつぶっている。
シップリサイクル条約が適用されたら、海外売船の時、どうするのか?これまで通り目を瞑るのか、それとも、出向前にチェックするのか?
目を瞑らないとかなり大きな問題となると思う。
答弁本文情報
平成二十八年八月八日受領
答弁第三〇号
内閣衆質一九一第三〇号
平成二十八年八月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出シップリサイクル条約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
伊藤 博敏
常識外れの裁判
東京地裁で普通に考えれば、よく理解できない裁判が進行している。7月12日に公判が開かれ、双方の代理人が論点を確認した。
原告はインド人社長のヴィパン・クマール・シャルマ氏で、被告は三菱東京UFJ銀行(以下三菱UFJ)。
船舶の運行管理を手がけるラムス・コーポレーション(以下ラムス)を経営していたシャルマ氏は、三菱UFJが突然行った会社更生手続申請や破産手続申請によって、事業家としての生命を絶たれ、信用を失い、精神的損害を受けたので、10億円の慰謝料を請求するというものだ。
ラムスは、船舶を保有するユナイテッド・オーシャン・グループ(UOG)とともに、会社更生法適用申請を申し立てられ、昨年12月末、更生手続開始が決定し、負債総額1400億円で倒産した。同時に自身の破産手続開始も決定され、シャルマ氏は即時抗告したものの、却下された。
この裁判が注目されるのは、『週刊文春』が7月7日発売号で「三菱東京UFJ銀行 不適切融資150億円と銀座クラブたかり接待」という記事を書いたからだ。
倒産した会社が、焦げ付かせた金融機関に“慰謝料”を請求する――。
常識ではありえない行為の裏に、三菱UFJとシャルマ氏の尋常ではない接待と、契約書無視の取引実態があることが明かされた。
とはいえ、裁判でこれまでに明らかになっているのは、ラムス側の虚偽であり不実だ。即時抗告を却下した理由として、裁判所は、「偽装ないし不実の表示をされて融資に踏み切った相手方(三菱UFJ)としては、もはや信頼関係を維持するのが困難」としており、「相手方(三菱UFJ)が原審被申立人らによる傭船契約の偽装を認識していた証拠はない」としている。
この続きは、プレミアム
某メガバンクで、経営破綻した取引先の企業から、行内の規定に反する過剰な接待を受けていたとして、調査と行員らの処分の検討がなされている旨、報道がありました。
【以下「週刊文春WEB」の記事】
昨年最大の破綻となった船舶会社の倒産事件で、メガバンクトップの三菱東京UFJ銀行の幹部を含む複数の行員が、銀座の高級クラブなどで接待を繰り返し受けていたことが、週刊文春の取材でわかった。
ユナイテッドオーシャン・グループ(UOG)は、昨年11月、三菱などの銀行団によって会社更生法適用申請を申立てられ、大晦日に更生手続き開始が決定。負債総額約1400億円の昨年最大の大型破綻となった。三菱は、UOGに10年間で約730億円を融資し、当時の小山田隆副頭取(現・頭取)が融資契約の調印式に出席するなど蜜月関係にあった。UOGの社長によれば、こうした融資の過程で、新橋支社長(当時)を含む6人の行員に対し、銀座の寿司屋や割烹、高級クラブなどで接待。さらに、社長の海外出張中には、行員は自分たちだけでクラブに飲みに行き、その飲み代をUOGにツケ回しするなどしており、単純計算でその総額は1000万円を超えるという
コチラの会社の破たんは結構大型でしたので、当時からよく話題になってましたが、これだけの接待が常態化した会社だったとは知りませんでしたね。
なんでも、銀行以外でも接待攻勢で取引先を維持・拡大してきた会社らしいですね。
ワタクシはこの会社の担当者でもなんでもないので、ただの想像ですが、多くのメガバンクの法人担当者は、「運悪く表沙汰になったな、でもこれくらいで処分されるとは。少しやり過ぎかな?」くらいの認識しかないでしょうね。
それだけ、接待は蔓延してますね。
銀行の接待というと、ほとんどがする方ではなくてされる方。
今回の問題では、単に接待を受けていたというだけでは、通常、問題になりません。
問題は、接待先が破たんしてしまい、それも大型で世間の関心が高い上に、接待の件がマスコミにバレた。ということと、行員だけで行った分までその請求をつけ回ししていた。ということですね。
これでは世間に示しがつかないので、社内処分を検討する、ということらしいです。
特に監督官庁から行政処分があるわけでもなく、逮捕者がでるわけでもなく、単なる銀行の社内処分です。
つまり、コンプライアンス違反として、行き過ぎの接待や社内ルールに基づかない接待を受けた(適切な報告などをしていない。)として処分されるワケですね。
まぁ自分たちだけで飲みに行って、その請求を全部つけ回ししてたらこれはやり過ぎですね。
取引先が入れたボトルを「来た時は好きに飲んでいいよ」、くらいのことはよくありますが・・・
多分、担当者が自分たちだけで接待を受けていれば罪悪感も多少あったんでしょうけど、支社長や役員クラスも接待を受けていた場所で、感覚がマヒしてることもあったんでしょう。
メガバンクの支社長、役員クラスになると、ほとんど毎日、接待だのパーティだのと予定が入ってまして、それをこなすのも大変なんでしょうけど、もはや接待付けそのものですね。
休みの日も接待ゴルフやパーティ招待などいろいろあります。
ワタクシも接待でクラブに連れてってもらうことはよくありましたが、自分たちだけのポケットマネーでは絶対行かないですし、所詮、連れていく甲斐性がないとホントの遊びにはならないですね。
ということでこのような接待は氷山の一角でして、社内の規定に従った接待は、日常、山のようにあるワケでして、それに溺れない自制心が求められます。
伊藤 博敏
常識外れの裁判
週刊文春の勢いが止まらない。三菱の御三家、三菱東京UFJに文春砲が撃ち放たれたようだ。その内容とは、三菱東京UFJがラムス社という船舶会社に対し、不適切融資や過剰接待の要求を行い、その親会社であるユナイテッド・オーシャングループ(UOG)を破産に追い込んだというものだ。
一般的に銀行員は規則が厳しく、取引先との接待なども制限されていると聞く。そうした常識からするとにわかに信じがたいような話だ。週刊文春では、ラムス社のシャルマ社長の告発という形で、三菱東京UFJ銀行の行員たちの、あまりに非常識で横暴な態度が見て取れる。
三菱東京UFJへの文春砲の内容は?
三菱東京UFJに関する文春砲の内容は以下のようなものだ。
三菱東京UFJはUOGという会社に対し極めて強引な手法で融資を行っていた。他の銀行が通常では融資を断るような、まだ契約が煮詰まっていない段階の造船について、資金使途をうやむやにしたまま先駆けて融資をしたり、ひどい場合には傭船契約を捏造させたというのだ。ちなみに、傭船契約というのは船を貸す契約のことだ。UOGは船を作って、それを人に貸して儲ける会社だが、貸す見込みのある船の建造資金しか普通は融資をしない。逆に言えば、傭船契約の契約書があれば、銀行は融資ができることになる。
その過程で、UOG社が、船を借りてくれる日本郵船を接待する際に、三菱東京UFJの社員が勝手についてきたり、行員だけで勝手に銀座の高級クラブで飲み食いしてUOG社にツケを回したり、海外出張先のシンガポールでもUOGの金で遊びまわったりと、悪行三昧を繰り返していたという。
最終的に、UOG社は三菱東京UFJから、問題の傭船契約の契約書が偽造されたものであることを突きつけられ、融資の返済を迫られた。そして返すことができずに会社更生法が適用されたというのだ。
週刊文春の内容を整理すると、三菱東京UFJ側が業績のためか無理矢理にUOG社に貸す過程で、契約書の偽造等をさせ、社長がいいなりになるのをいいことに過剰融資でジャブついた金があるのを知って、UOGの金で豪遊。しかし、担当者たちが変わったタイミングで過去の不適切融資がおこなわれたことを知る。関与したものは、出向や左遷で追い出した。あとは、当事者であるUOG社とシャルマ社長を葬りさらねばならない。
通常であれば、いきなりの会社更生法適用は珍しい。業績が悪くなれば、返済の猶予を行い、少しずつでも返してもらうよう働きかけるのが現在の銀行の通常の行動だ。有無を言わさず破産に追い込み、これまでの不適切融資についても闇に葬り去ろうとしたのだろう。
不適切融資と過剰接待は本当にあったのか?
しかしながら、週刊文春の記事には疑問点もある。基本的に、シャルマ社長の視点でしか物事が語られていない。シャルマ社長に対して性悪説で見れば、自分が本当に契約書を偽造し、不適切融資や過剰接待などについても、全くなかったとは言えない程度のものを大げさに言って、最後に貸し剥がされた三菱への恨みを晴らそうとしている、という見方もできる。
確かに、今のメガバンクのコンプライアンスの厳しさを考慮すれば、これほどの悪事を働く方が難しいという気もする。
おそらくは、シャルマ社長が主張する真っ黒と、三菱が主張する白の中間程度の不適切性があったのだろう。長引く不況で、銀行側は資金需要があって返済が見込める会社に融資をするために必死だ。UOG社が日本郵船と懇意にしていたことで、審査の目が緩み、なんとかしてこの会社に金を貸そうと苦心していたのだろう。
その過程で、UOG側も味をしめ、少しずつ嘘を重ねて多額の融資を銀行から引き出した。本来必要ではない金がUOG社に溜まっていく。金が口座にあると、人はおかしくなる。シャルマ社長自身も、遊び方が派手になっていく過程で、銀行員たちも一緒になって調子に乗ってしまったのだろう。
三菱東京UFJ側の反応次第ではあるが、真相はわからぬままだ。しかし、文春砲の実績を見れば、三菱の対応如何でさらなる追撃があるかもしれない。もしあれば、ぜひ見てみたいものだ。
グローバルコンサルティング企業のマッキンゼーは財政や数字の判断は出来るが、技術や船主の分析など出来るのだろうか??
船のサイズや種類など複雑な要素が多い。マーケット、世界経済、投機的な発注、造船所事情など複雑に絡み合っていると思う。
業界の人達でも簡単に出来るとは思えないが??
グローバルコンサルティング企業のマッキンゼーが14日、現代(ヒョンデ)重工業・サムスン重工業・大宇(デウ)造船海洋など造船3社に対するコンサルティングに着手した。韓国政府はこのコンサルティングの結果に基づいて造船「ビッグ3」の事業再編案を組むという計画だ。マッキンゼーは第1次のコンサルティング結果を来月末に政府に提出する予定だ。
14日、金融当局によればマッキンゼーは造船海洋プラント協会からの依頼を受けてこの日から現代重工業など造船ビッグ3に対するコンサルティング作業に着手した。造船海洋プラント協会の関係者は「造船業種の構造改編が急務でコンサルティングを急いで行うことにした」と説明した。
マッキンゼーは現代重工業とサムスン重工業、大宇造船海洋が先月主債権銀行に提出した自救計画案とは別に、会社別の受注現況・展望、グローバル造船業界の動向・展望、中国との競争力格差などを分析する予定だ。また船舶の種類を浮遊式原油生産および保存設備(FPSO)、ドリルシップ、半潜水式ボーリング船、バルク船、コンテナ船、液化天然ガス(LNG)船などに細分化した後、造船3社がどの船舶において競争力があるのかに対する分析も行う。
マッキンゼーは第1次コンサルティングの結果を来月末、政府に報告することにした。引き続き8月12日までに最終報告書を作成して提出する予定だ。これに関連して任鍾龍(イム・ジョンリョン)金融委員長は8日、産業・企業構造調整案を発表しながら「造船協会で依頼したコンサルティングの結果によって造船ビッグ3間の事業再編、設備縮小など自律的な構造調整を推進する」と明らかにした。
金融委はこの日「任委員長が造船業の構造調整会議でサムスン重工業と大宇造船海洋の合併などを検討した」という報道が出てきたことに関して「内部的にサムスン重工業と大宇造船海洋の合併を全く検討したことはない」として「政府主導の人為的な構造調整は望ましくないとの立場に変わりはない」と明らかにした。
Hamburg-based shipping trust Marenave Schiffahrts said that it received a letter of intent from its lenders stating that its entire fleet should be sold in an effort to repay the company’s ship financing loans.
The letter of intent, which was sent in the course of the ongoing discussions with the banks financing the Marenave-fleet, remains subject to approval by the banks’ respective bodies.
Furthermore, the banks said that they are willing to release the company from any liability, under certain prerequisites.
“The release from liability is an essential requirement for the entry of a potential investor,” Marenave said, adding that the company’s Management Board will now examine the proposal.
In February 2016, Marenave Schiffahrts reached an agreement with the bank consortium financing eight of its product tanker and container shipping companies to extend its restructured debt.
The initial agreement, reached in April 2013, was supposed to cover the company’s businesses until the end of 2015, but has been extended to June 30, 2016.
With this agreement, the repayment obligations of the shipping companies for the first half of 2016 were reduced by some USD 10.3 million.
日本の造船業界も韓国を笑っていられない状況だと思う。まあ、韓国の造船業界が急速に縮小すれば、努力せずとも現状の状況は良くなるであろう。
韓国の柳一鎬(ユ・イルホ)副首相兼企画財政部長官率いる構造調整号が燃料(資本拡充)をたっぷりと満たして8日に始動した。構造調整過程で起きた「コントロールタワーがない」という指摘に柳副首相が主宰する産業競争力強化関係閣僚会議も新設した。これまで構造調整の実弾調達案をめぐり真っ向から対立していた韓国政府と韓国銀行が資本拡充のために12兆ウォン(資本拡充ファンド11兆ウォン+1兆ウォン以上の直接出資)を用意することで合意した。政府の構造調整推進計画発表翌日に韓国銀行がサプライズで基準金利引き下げを発表した。基準金利は1年ぶりに0.25%低い1.25%を記録した。市場専門家は不良企業構造調整で景気活力が落ちることに備えた韓国銀行の政策共同歩調と解説する。
相当数の学界・造船業専門家は柳一鎬構造調整号に最も重要な「地図(改編方向)」がなく実効性に劣ると指摘する。韓国経済研究院の権泰信(クォン・テシン)院長は「構造調整は既存の事業や組織を変え企業の競争力を引き上げる作業だ。今回の案は財政投入で問題を先送りしたものにすぎない」と指摘する。建国(コングク)大学のオ・ジョングン特任教授も「推進計画を見れば人材と組織を減らす造船ビッグスリーの自救策だけ羅列されている。資本拡充で用意した実弾でどの会社を支援するのか、産業改編をどのようにするのかなど大きなビジョンが見られない」と話した。全体的に政府は1歩退いている姿だ。造船協会は8月にコンサルティングを通じて韓国の造船産業の適正供給能力と規模などを分析した結果を出す。ここからも政府は抜けており業界が自主的に構造調整を推進する計画だ。
◇「需要不足続けば造船業界共倒れも」
専門家らは政府が乗り出して大きな枠組みで産業改編補完策が出てこなければならないと口をそろえる。韓国海洋大学のイ・ガンギ教授は「今後世界的な需要不足で造船業の景気が急落すれば過去よりさらに大きな危機が来るだろう。政府が1日も早く構造調整を通じて産業次元の競争力を高める案を用意しなければならない」と話した。(中央SUNDAY第483号)
未来アセット大宇のソン・ギジョン研究員も「今年に入り世界の造船業は2009年の金融危機水準の受注空白が続いている。現在のようにすべての大型造船会社が構造調整せず競争体制に進むならばさらに厳しい時期が到来しかねない」と懸念する。彼は過去に日本造船業が政府主導の大規模構造調整を展開したため不況を克服できたと付け加えた。1970年初めに日本の造船市場は世界シェアが55%を超える造船大国だった。73年のオイルショック以降造船業は大きくぐらついた。日本政府は80年代に2度にわたり高強度構造調整に出た。61カ所あった造船所を26カ所に減らした。ソン研究員は「世界市場での支配力は低くなったが果敢な構造調整により現在まで世界シェア20%を維持している。韓国の造船業も買収合併(M&A)やビッグディールまで覚悟して産業競争力を高める構造調整が必要だ」と話した。
イ教授は規模の縮小は基本で、造船業の中長期ビジネスモデルを探すことも構造調整の役割だと考える。このために構造調整のコントロールタワーに造船3社の営業総括役員も入れなければならないと助言した。イ教授は「財務専門家は負債規模のような数字だけで産業を分析する。今後世界の造船景気を把握し継続して収益を出せる事業戦略を立てるには業界の現況を最もよく知っている営業担当者がコントロールタワーに参加しなければならないだろう」と話した。また、造船会社より海運会社に先に財政投入がされるべきとした。海運会社が復活すれば造船会社は仕事を確保することができ、造船会社が船舶建造に必要な機材を購入することにより造船機資材業者が活力を取り戻す好循環構造になるためだ。
◇「優れた設計能力生かし競争力格差広げなければ」
反対に今回の対策が日本式構造調整に追従しなかったという点で肯定的に見る専門家もいる。ハナ金融投資のパク・ムヒョン研究員は「ビジネスで最も大きな恩恵はライバルが消えること。韓国の造船会社を統廃合すれば最も大きな利益を得るのが中国の造船会社だ」と話す。実際に日本政府が80年代に構造調整をして商船分野の核心設計人材が韓国の造船業に大挙移動し、これが韓国が世界の造船業のトップに上り詰める決定的契機になったということだ。現在まで日本の造船所は設計人材が不足し低い技術力で建造が可能なバルク船分野に注力している。
大宇造船海洋の初代社長を務めたホン・インギKAIST経営大学招聘教授も「政府が適切なタイミングで構造調整に出たのは正しいが、企業をあまりに追い詰めて優れた設計人材や超大型タンカー(VLCC)、液化天然ガス(LNG)船など高付加価値船舶事業が中国に渡らないようにしなければならない」と話した。(中央SUNDAY第483号)
パク研究員は、韓国の造船産業は依然として世界的な競争力を備えていると分析した。彼は「今回造船3社が出した自救案は受注見通しを根拠としたもの。造船業をしっかりと評価するには受注を獲得した船舶数より建造技術を示す引き渡し実績を考えなくてはならない」と話した。造船海運分析会社の英クラークソンリサーチによると5月基準で韓国の造船業界は549万7612CGTの船舶引き渡し量を記録し、中国の459万9755CGTを抜いて1位となった。中国は韓国より受注残高が30%以上多いが建造技術力が不足し引き渡し量で後れを取ったのだ。例えば中国最大の民営造船所の熔盛重工は何回も船舶建造ができず契約を解除され2年前に破産した。パク研究員は「歴史的に受注量がなくてつぶれた造船所はなかった。むしろ建造遅延にともなう引き渡し量減少は造船所の流動性圧迫につながるのが一般的」と話した。
パク研究員は「単純な統廃合より競合企業と格差を広げられる新事業を探すのがより有効な案になるだろう」と説明した。彼は「最近親環境船舶に対する需要が増加し世界で3万隻に達する中小型船舶の置き換え需要が増加している。今後中小型船舶市場は燃費技術力が優れた韓国の造船業の新しい収益源になれる」と話した。
◇「専門性落ちる産業銀行が出てくるのは無理」
オ・ジョングン教授は産業銀行が依然として構造調整の前面に出てくるのは問題があると指摘した。産業銀行が数兆ウォンの公的資金を投じたSTX造船海洋は最近法定管理に向けた手続きを踏んでおり、大宇造船海洋は昨年5兆ウォン以上の営業損失を出した。現在産業銀行は大宇造船海洋の不良管理に対する検察捜査まで受けている。オ教授は「専門性が劣る国策銀行が10兆ウォンを超える資本拡充を受けながらも構造調整を請け負わなければならないのか疑問。米ゼネラルモーターズ(GM))のように構造調整は外部専門家に任せなければならない」と話した。
GMは2008年の金融危機で直撃弾を受け翌年破産した。当時投入された公的資金だけで500億ドルに達する。政府は資金だけ輸血し、構造調整はウォール街出身の財務専門家スティーブ・ラトナー氏が引き受けた。彼を中心に構造改革や投資など各分野の専門家で構成されたタスクフォースは素早く果敢に組織を改編した。ポンティアックなど人気のない車種の生産を中断し生産ラインを減らした。GMは構造調整を進めてから3年ぶりに世界の自動車市場1位に復帰した。(中央SUNDAY第483号)
1か月ほど前、造船業界の状況を取材するために慶尚南道・巨済島にある大宇造船海洋の玉浦造船所を訪れた。そこで「半潜水式掘削船」の詳細設計を担当したA部長と会った。「半潜水式掘削船」とは、海底の石油を探査・掘削する海洋プラントの一種だ。しかし、数兆ウォン(数千億円)の赤字を抱え、今では「韓国の造船業界でリストラの嵐を巻き起こした主犯」というレッテルを貼られている。大宇造船が2011年末に受注し、およそ3年かけて製造した「半潜水式掘削船」は、全世界で発注されたもののうち最もハイスペックな最先端の掘削船だったという。雨風や強い波にさらされる北極付近の海上に設置されるため、従来のものよりはるかに精密に各種装備を制御する必要があるからだ。「実力もないのに、『できる』と大口をたたいて受注し、結局大きな損失を被った」と話すA部長の表情は暗かった。造船業のリストラが大きな波紋を呼んでいる今、A部長が続けて口にした言葉が脳裏に焼き付いて離れない。
「足りない実力を補うため、ここ2年は週末返上で働いた。その過程で、特に入社10年未満の若手エンジニアたちは本当に過酷な経験をしたと思う。今、造船業のリストラについて話す債権団や政府関係者の目には、後輩たちが敗残兵に見えるかもしれない」
韓国国内の造船業の危機について、その根本を探ってみると、結局は人の問題に突き当たる。造船業が好況に沸いていた2000年代後半、国内の造船各社はやみくもに受注競争を繰り広げ、会社の規模を拡大していった。ハンダ付けさえできれば技術力を問わず人をかき集めた。このため釜山から路上生活者が消えたという話も聞かれた。しかし当時、海洋プラントのような産業を担当する高度な人材は育成することができなかった。そのような人材も育てずに海洋プラント事業に飛び込んだのだから、失敗は当然のことだった。ところが、われわれは同じ失敗を繰り返している。せっかく海洋プラントの技術を身に付けた人材を、自らの手で切り捨てているのだ。
人員削減を進める国内の造船各社は現在、希望退職を募っている。当初は幹部クラスのベテラン社員が対象だったが、若手社員も大挙して希望退職申請書にサインしているという。「韓国の造船業には未来がない」という認識が社会全体に広まり、能力のある若いエンジニアたちが別の業種に転職しようとしているのだ。このままでは結局、数兆ウォンに上る高い授業料を払って習得した「海洋プラント技術」も全てが無駄になってしまう。既に人材の流出は深刻だ。先日、巨済島で会ったある造船企業協力会社の社長は「今年初めから、中心的な立場だったエンジニアが次々と離職し、今では設計図面すらまともに読めずコスト削減ばかり叫ぶ人間が製造現場を監督している」と話した。
ソウル大学工学部の教授たちが昨年、韓国の産業の現状を鋭く診断した本『蓄積の時間』を出版したが、この本によると先進国の競争力の核となっているのは、結局は多くの試行錯誤を経て蓄積した「経験」の数々だ。「海洋プラントの失敗」の苦い経験をかみしめ、その経験を蓄積した人材を守るのが、リストラや造船企業の立て直し以上に重要なのだ。
李性勲(イ・ソンフン)産業1部記者
2016年6月8日、人民網によると、韓国検察庁・腐敗犯罪特別捜査団はこの日午前、粉飾会計疑惑が出ている大宇造船海洋の本社や玉浦造船所などを家宅捜査した。
同捜査団は大規模な汚職案件の解明に向けて設立されたチームで、検察総長の直接管理下にある。大宇造船海洋の数兆ウォン(1兆ウォンは約900億円)規模とも言われる粉飾会計、経営不正疑惑をめぐる捜査には150人余りが関わっており、かつてのトップ2人にはすでに出国禁止措置を取っている。(翻訳・編集/野谷)
7日午前5時、慶尚南道巨済市(キョンサンナムド・コジェシ)の古県(コヒョン)水協同マート前。トンウォン人力など10社ほどの人材派遣業者が集まっている所だ。夜が白々と明けてくると左胸に大宇(デウ)造船海洋やサムスン重工業などの名前が入った造船所の作業服姿の人たちが相次いで人材派遣事務所に入っていった。
ハンイル人力の事務所を訪れたパクさんもそうした1人だ。パクさんは3カ月前にはサムスン重工業協力企業の物量チーム(下請けから再び孫請けで働く契約職労働者)で配管の仕事をしていた。残業と休日勤務まですれば1カ月に300万ウォン(約27万円)を稼げた。しかし昨年から仕事が減り残業などができなくなり最後の月給は130万ウォンしかもらえなかった。そこで訪れたのが人材市場だ。
パクさんはほとんど毎日明け方4時ごとに家を出て人材派遣事務所で紹介された玉山洞(オクサンドン)などのマンション建設現場に行く。建設資材整理や掃除で1日10万ウォン、1カ月に170万ウォンほど稼げる。しかし住んでいるワンルームの家賃25万ウォンもまともに払えずにいる。家のコメも底をついた。
パクさんは「1日稼いで1日を暮らすが最近は雨が多くて仕事ができず生活費がなくなった。きのうの夕食は即席めんを食べ、朝食は抜いて出てきた」と話した。パクさんは「1日も早く造船景気が回復して再び造船所で働きに行けるようになれば良いだろう」と話した。
ムンさん(41)も大宇造船海洋の協力業者物量チームで配管の仕事をしていたが仕事がなくなり物量チームが解体されたため2カ月前からトンウォン人材で仕事を紹介されている。ムンさんは「私もそうだがほとんどの人に家庭があり、切られたからと家で休むことはできない状況。造船景気が良くなり他の所に働き口ができるまではこうして持ち堪えるほかはない」と話した。
現在トンウォン人力とハンイル人力がそれぞれ1日60人供給している人材の20%程度が造船所労働者出身だ。ほとんどが大宇造船海洋とサムスン重工業の協力業者物量チームで働いていて仕事がなくなり職を失った人たちだ。古県洞の50社ほどの人材派遣事務所の状況も似ている。週末と休日には造船所労働者の割合が40~50%に増える。残業が減り月給が減った造船所の労働者がアルバイト形態で働きに出ているからだ。
トンウォン人力のチョ・ムンジョン所長(50)は「4~6日の連休期間にも毎日10~20人の造船所労働者が集まった」と話した。ハンイル人力のファン・ミンホ事務長(48)は、「悲しい現実だが造船景気が悪化し人材派遣事務所には働きたいという人があふれている」と話した。
巨済(コジェ)はGS建設やポスコ建設などの大規模マンション建設現場が多いが、現代(ヒョンデ)重工業がある蔚山(ウルサン)はそうではなく仕事は見つかりにくい。蔚山市東区にある現代人力の関係者は「3月から現代重工業下請け業者の物量チームが20~30人単位で来て他の仕事を探してほしいと頼まれるが紹介できずにいる」と話した。
慶尚南道咸安(ハムアン)などに農作業に行く造船所労働者もいる。法定管理に入った昌原市(チャンウォンシ)のSTX造船海洋の協力業者であるポギョンテック出身の労働者らは先月末から10~20人ずつ咸安のスイカ農家と昌寧(チャンニョン)のタマネギ農家で働いている。1日の日当10万ウォンを稼ぐためだ。従業員80人のこの会社はこのところ仕事がなく全従業員の10~20%だけが船舶の塗装の仕事をしている。ポギョンテックのチェ・チャンシク代表(60)は「従業員が『しばらく農作業をしに行く。仕事が入ったら連絡してほしい』と言うのが申し訳なく、喉がつまって返事ができなかった」と話した。
大宇造船海洋とサムスン重工業は昨年初めに従業員数が9万5000人に達したが、現在は9万人程度だ。両社の労組は今年末まで2万人程度がさらに減るとみている。現代重工業は同じ期間に6万3500人から5万8700人に減った。労組は7000人程度がさらに構造調整されるとみている。STXは2014年から今年初めまでに8600人のうち2500人が職を失った。
大宇造船海洋労働組合のチョ・ヒョンウ政策企画室長は「6月以降に造船所労働者の大規模失職が予想されるだけに政府が雇用危機地域指定など彼らが生計を維持できる転職プログラムを導入し迅速に他の仕事を見つけられるよう助けなければならない」と話している。
「クロアチア人技能者が『日本人は英語を話す人が少ないから、通訳を介さないといけない。手間がかかってしょうがない』としていたように、これも外国人労働者をマネジメントし慣れていないことがさらに悪化させたかもしれません。やはりノウハウのなさを感じさせます。」
簡単に通訳と言いますが、船の事や客船について知識がなければ、的確には訳せません。しかも、相手の英語が流暢でないと、それぞれの国のくせのある英語に戸惑うと思いますよ。いろいろな国の人と英語でコミュニケーションを取った経験がないと間違いや誤解がないような会話は難しいかもしれません。個人的な経験からの意見です。
外国人の管理が出来ない日本の企業は今にはじまった問題ではないと思います。外国の企業で外国人を普通に使っているところは、日本企業と違うと感心するぐらいスムーズです。自社で新人を育て上げるのも良いですが、そのような環境で働いた経験のある日本人を採用して学んだほうが楽かもしれません。そのような日本人がかなり少ないと思います。
【クイズ】三菱重工が2011年に受注した大型客船「アイーダ・プリマ」は、コスタ・グループ傘下のアイーダ・クルーズが運航するクルーズ客船です。では、コスタ・グループの本社所在地はどこでしょう?
(1)アメリカ
(2)イギリス
(3)イタリア
●三菱重工の客船損失で見えた日本のものづくり崩壊
また憂鬱な話になってしまうので最初ボツにしたものの、印象に残るものでもあったのでもう一度引っ張り出してきました。
私は「ものづくり」という曖昧な言い方が嫌いなのですが、「日本のものづくりはすごい」といった幻想は一度断ち切ってしまった方が良いでしょう。
そういった例となりそうなのが、三菱重工の豪華客船の件です。2011年に受注した大型客船「アイーダ・プリマ」は大幅に遅延、3度の火災も起きて"特別損失は累計で1800億円を超え"てしまいました。
この理由についての三菱重工の説明は以下のような感じだそうです。
三菱重工の巨額特損、知られざるもう1つの理由:日経ビジネスオンライン 佐藤 浩実 2016年4月4日
三菱重工の主張は一貫している。船内のWi-Fiなど10年前にはなかった要求仕様に手間取った、客室数が多く複雑な構造だった、顧客から設計変更の要望が相次いだ…。「知見不足による設計の遅れが、後々まで響いてしまった」(鯨井洋一交通・輸送ドメイン長)という趣旨の説明が、特損を計上するたびに決算会見で繰り返された。
一方、作者の佐藤浩実さんは、別の理由があるという見方でした。これは後述します。ただ、上記の三菱重工の主張の時点で「知見不足」なのですから、日本のものづくりがちっともすごくないことがわかってしまいます。
●日本人には技能的に作れない豪華客船
では、佐藤浩実さんの見る本当の理由の方へ。ポイントとなるのは外国人労働者の多さ。この多さの理由の一つは、単純に労働者不足でした。これはまだがっくりするほどのものではないでしょう。
客船を造ることができる建設業者は震災復興や東京五輪をにらんだ再開発で忙しく、長崎に来ている余裕はない。
ところが、日本の製造業を信仰している人にとってまたショックなのが、もう一つの理由の方です。"人数と技能の両面で「日本の技能者だけではできなかった」(三菱重工の宮永俊一社長)"ということで、技能的でも日本人だけでは作れないというのです。
具体的に言うと、"内装に欧州製の調度品を多く使うなど、日本の協力企業にはノウハウがない作業"だったとのことでした。
●外国人労働者をマネジメントできない日本企業
したがって、今は外国人労働者をうまく使うことが重要であるということになります。ところが、これが日本企業が苦手とするところです。
例えば、サボる外国人技能者が出てきても、なぜか三菱重工は見て見ぬふり。結果的にまじめにやっている日本人技能者にもストレスが溜まります。どうもうまく管理できていないというようでした。
また、ポルトガル人技能者は「日本人は意思決定に時間がかかりすぎだ」と憤っていました。これは日本企業が中国・台湾に負けるのは当然 シャープもスピード不足のせい?でも指摘されていた日本の特徴です。
ただ、クロアチア人技能者が「日本人は英語を話す人が少ないから、通訳を介さないといけない。手間がかかってしょうがない」としていたように、これも外国人労働者をマネジメントし慣れていないことがさらに悪化させたかもしれません。やはりノウハウのなさを感じさせます。
なお、既に日本の人口が減ってきていることを考えると、今後外国人労働者に働いてもらう機会が増えることが予想されます。外国人労働者のマネジメントが下手だというのは、これからさらに問題となってきそうです。
●「アイーダ・プリマ」はイタリア企業から受注
「アイーダ・プリマ」を頼んだコスタ(Costa)・グループはイタリアでした。そういや、コスタクルタ(Costacurta)というイタリア代表の名DFがいました。
【クイズ】三菱重工が2011年に受注した大型客船「アイーダ・プリマ」は、コスタ・グループ傘下のアイーダ・クルーズが運航するクルーズ客船です。では、コスタ・グループの本社所在地はどこでしょう?
(1)アメリカ
(2)イギリス
(3)イタリア
【答え】(3)イタリア
ただ、こうやって納期遅れまくりだと次はないかもしれません。そうやって日本企業には頼まないという決定が増えていくと、労働力不足はあまり心配しないで良いかもしれません。とはいえ、それは全然嬉しくない流れですよね。
やっぱりこれからは外国人労働者とうまく仕事していけるよう努力するしかないのでしょう。
事業継続は「2番船」の進捗カギに。三菱自の問題も重荷に
三菱重工業が長崎造船所(長崎市)で建造中の欧アイーダ・クルーズ向け大型客船2隻に関連して、2014年3月期からの累計損失が2375億円に上る見通しとなった。受注した2隻のうち、1番船は3月14日に引き渡し済み。今後の損失リスクに対する焦点は、2番船建造の進捗(しんちょく)に移った。
宮永俊一社長は25日に記者会見し「2番船は艤装(ぎそう)工事が本格化し、現時点で予想できる損失を今回織り込んだ」と説明した。ただ、2番船の引き渡し時期については「客先とさまざまな条件を交渉中で、16年中は難しい」との考えを示した。
第4四半期に入り、引き渡しに向けた最終仕上げや本船全体の制御システムの確立、各種最終検査などの遅れが表面化し、特別損失を追加計上することとなった。宮永社長は「オイルと天然ガスの混焼エンジンを導入するなど最新鋭の設備を装備しており、これら作業に想定外の時間を要した」と分析する。
一方、2番船については「客先と1番船のスペックを踏襲するという認識で一致している」と言及。1番船で蓄積したノウハウや技術を最大限活用し、早期の完工を目指す。
2番船引き渡し後の大型客船事業に関しては「社内に客船事業の評価委員会を設けており、ここで今後の方向性を詰める」(宮永社長)とした。同委員会には化学プラントの部隊やエンジニアリング部隊が参加。大型案件のリスク管理のあり方などを検討し、16年夏から秋にかけて客船の継続を含め「ある程度の方向性を示す」と話した。
最大の懸案だった大型客船案件について「終息を迎えつつある」と宮永社長。だがここにきて、持ち分法適用会社である三菱自動車の燃費試験データの不正操作問題が浮上。筆頭株主である三菱重工の新たな懸案事項が降って湧いた。この問題について宮永社長は「内容によっては、三菱重工の持ち分法投資損益に影響が出る」とした上で、「感情的なことに流されずに、一つひとつ冷静に対応する」と強調した。
<解説>
紆余曲折を経て1番船をようやく引き渡した間に、特損は2375億円に膨らんだ。2番船も計画の年内引き渡しは難しい状況で、一層のリスク管理が求められそう。今後は大型客船の建造を続けるかが焦点となる。
その傍ら、三菱自動車の燃費試験データの不正操作問題という新たな難題が立ちふさがった。持ち分法適用会社である三菱自問題は三菱重工の業績への影響に加え、三菱ブランドの根幹を揺るがす事態に発展する可能性が大きい。この難題に宮永俊一社長はどう舵を取るのか。その決断は困難を極める。
日刊工業新聞編集局第一産業部 長塚 崇寛
三菱重工業は25日、客船世界最大手の米カーニバル傘下、アイーダ・クルーズ向け大型客船2隻で、新たに508億円の特別損失を計上すると発表した。客船をめぐる損失額は累計2300億円を超えた。三菱重工は先月、1番船を1年遅れで引き渡したが、2番船は年内引き渡しが難しい状況。度重なる損失計上でイメージ悪化は避けられそうもない。
2番船について1番船で手直しした分を反映させることから、建造工程の大幅見直しに掛かる費用を追加損失として計上した。1番船でもエンジンの不具合や顧客の要望に応じた騒音対策、1月に3回発生した火災の影響で引き渡しが遅れて費用がかさんだ。
三菱重工は同日記者会見を開き、宮永俊一社長は「大変な損失だが、ようやく収束に近づいている。一番船と同様にできれば、これ以上(の損失)は出ない」と説明した。客船事業の今後の方針については社内評価委員会で協議しており、宮永社長は「夏から秋にかけて大きな方向性を出す」と明らかにした。
三菱重工は11年、アイーダ・クルーズ向け大型客船2隻を受注した。長崎造船所(長崎市)で建造していたが、1番船は当初予定の15年3月から1年遅れての引き渡しとなった。2番船も16年3月から遅れており、「今年中に引き渡すのは難しい可能性がある」(宮永社長)という状況だ。受注額は2隻で1000億円とみられるが、大幅に上回る損失を計上する事態に陥った。
Hanjin Heavy Industries plans to reorganize its business structure toward building general-purpose merchant ships at the Philippines' Subic shipyard and special-purpose ships at Busan's Yeongdo shipyard.
This move is based the creditors’ judgment that the current structure of building merchant ships and special-purpose ships both at Yeongdo shipyard would continue to incur losses. Some industry watchers see this decision as a signal for the restructuring of the whole shipbuilding industry.
If Yeongdo shipyard's merchant ship division is liquidated, it would inevitably lead to the downsizing of workers as well, which could certainly bring about opposition from the labor union and political parties.
At present, Hanjin’s Yeongdo shipyard has three docks, with the length of each dock estimated at 200-300 meters, about a half of those at other major shipyards.
With the limited length of its docks, Yeongdo shipyard, accordingly, is unable to build ultra-large containerships, VLCCs, and LNG carriers which are emerging as new cash cows for other major Korean shipyards.
The main areas of business for the shipyard are mid-sized tankers and containerships, the areas where Chinese shipyards are growing at a rapid pace. Hanjin creditors said that considering that the shipyard's merchant ship division is lagging in cost competitiveness behind its Chinese rivals, it is difficult for the division to make profits.
South Korea’s oldest existing shipyard might relocate from its central Busan location. Founded in 1937, Hanjin Heavy Industries & Construction’s Yeongdo shipyard, has an enviable central position in South Korea’s second city. Now going through a restructuring, speculation is growing Hanjin Heavy will cash in the site, and move to another Busan facility in the nearby district of Sinseondae.
Hanjin Heavy, which also has a huge shipyard in Subic Bay in the Philippines (pictured), has long been constrained at home by the cramped nature of its shipyard. When building 8,000 teu containerships, for example, Hanjin Heavy was forced to pioneer a novel method of stitching the ship together in two parts to overcome drydock size constraints.
■矢継ぎ早に重機大手3社を襲う「トラブル禍」
三菱重工業、IHI、川崎重工業の総合重機大手3社がそろって、多額な損失を伴う相次ぐ技術的なトラブルに見舞われている。それは、日本のものづくりを支えてきた「機械の総合デパート」の屋台骨を揺るがしかねない非常事態にほかならない。
この危機的状況にIHI、川重がそれぞれ経営陣を刷新し、三菱重工は約2000億円の資産売却に踏み切るなど、ものづくり死守に背水の陣を敷く。3社を矢継ぎ早に襲う「トラブル禍」は、さながらものづくりで満身創痍に陥った各社の姿を象徴している。
最大手の三菱重工は、度重なる設計変更や3度にわたる火災事故などで建造する大型客船2隻の引き渡しが大幅に遅れ、2015年4~12月期で530億円の特別損失を計上し、累計すると特損は1872億円に脹れ上がる。当初、2015年3月を予定していた1隻目の納入は大幅に遅れ、3月14日にようやく引き渡しにこぎつけた。2隻目の納入への影響も避けられず、2隻で約1000億円とされる受注額は丸ごと吹き飛び、特損は受注額の2倍に膨らむ可能性も捨て切れない。
造船事業は同社の祖業なものの、中国・韓国勢の攻勢を前に昨年10月、商船部門などの分社化に踏み切った。しかし、客船建造に限っては「大型客船を建造できる日本唯一の企業」との自負もあり本体にとどめた。その結果は完全に裏目に出てしまった。「国産初」で期待を集める小型ジェット旅客機「MRJ(三菱リージョナルジェット)」も開発が大幅に遅れ、やっと初飛行にこぎ着けたものの、初号機の納入は17年4~6月期から18年半ばにずれ込むなどトラブル続きだ。
■復活を目指す経営変革は時間との戦い
IHIはさらに深刻な事態に襲われている。国内外工事での事故や不具合に、愛知工場(愛知県知多市)の海洋構造物事業でのトラブルなどが重なり、16年3月期は300億円の最終損失を計上し、7期ぶりの最終赤字に転落する見通しだ。同期は四半期ごとに立て続けて業績を下方修正する体たらくで、斎藤保社長兼最高経営責任者(CEO)から「ものづくりの力の低下は否めない」と自戒を込めた発言も飛び出すありさまだ。
川重もブラジルでの合弁船舶事業が原油安の影響から資金繰りに逼迫し、15年10~12月期に221億円の損失を計上しており、3社のものづくりに対する“基礎体力”の衰えは否めない。その意味で、経営変革は待ったなしで、IHI、川重はそれぞれ社長交代をてこに、製造現場の刷新に臨む。
IHIは4月1日付で、満岡次郎取締役常務執行役員が社長兼最高執行責任者(COO)に昇格し、斎藤氏は代表権付きの会長兼CEOとなり、二人三脚で経営の建て直しの陣頭指揮に当たる。満岡氏は稼ぎ頭の航空エンジン畑出身で、同社初のCOOに就くと同時に、トラブルが相次ぐ現場を自ら統括する異例の体制でものづくり力の再生を急ぐ。
川重は6月末に村山滋社長が代表権のある会長に就き、後任に金花芳則常務が昇格する。同社は13年6月に三井造船との経営統合を巡って当時の長谷川聡社長ら統合推進派の役員が解任された経緯があり、村山氏が社内の“しこり”をほぐした後を引き継ぐ金花氏には人心一新により新たな成長軌道乗せを託すと同時に、ブラジル合弁事業で甘さを露呈したリスク管理の強化が求められる。
一方、三菱重工は客船事業のトラブルを教訓にリスク管理体制を整備するほか、保有株式や遊休不動産など約2000億円の資産を18年までの2年間で売却し、毀損した財務体質を立て直す方針とされる。総合重機大手はものづくり力が生命線なだけに、その復活を目指す経営変革は時間との戦いであり、否応なしにその実行力が試される。
経済ジャーナリスト 水月仁史=文
22日、今治市の造船所で、建造中の輸送船の塗装作業をしていた男性が倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。
警察によりますと、22日午後6時半ごろ、今治市吉海町本庄の「あいえす造船」で、建造中の6,300トンの輸送船の内部で塗装作業を行っていた今治市横田町の塗装工、行本俊光さん(34歳)が、船内で倒れているのを同じ作業をしていた男性が見つけました。
通報を受けた消防が駆けつけたところ、行本さんは、すでに心肺停止の状態だったということで、搬送先の今治市内の病院で死亡が確認されました。
警察によりますと、行本さんは、もう1人の作業員の男性と2人で船内で塗装作業をしていたということです。
船内は、作業に使われた塗料に含まれているガスが充満している可能性があるということで、警察は、船内の状況を確認しながら、詳しい原因を調べることにしています。
おととし2月、西海市の造船所で下請け会社の作業員が鉄骨の下敷きになって死亡した事故で、長崎労働基準監督署は危険を防止する措置を怠っていたとして、この造船所と作業責任者を労働安全衛生法違反の疑いで書類送検しました。 書類送検されたのは西海市大島町の大島造船所と、この会社の34歳の作業責任者です。 おととし2月、大島造船所の工場で、貨物船の溶接作業をしていた当時36歳の作業員が、落下してきた重さ2トンの鉄骨の下敷きになり、死亡しました。 長崎労働基準監督署の調べで鉄骨は、固定していない状態で高さ2メートルのと...
広島・三原労働基準監督署は、労働災害防止に必要な下請との連絡調整を怠っていたとして、小池造船海運㈱(広島県豊田郡)と同社係長を労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)違反の疑いで広島地検呉支部に書類送検した。
平成28年3月、特定元方事業者の同社が船舶の修繕作業をしていたところ、下請業者の労働者が移動してきたクレーンの走行装置と手すりの間に挟まれ死亡する労働災害が発生している。同社は、法律で定められている作業間の連絡および調整をしていなかった。
大崎上島町の同じ造船所で、今月7日ときのう、相次いで労災死亡事故が発生しています。事故があったのは大崎上島町の小池造船海運です。けさから警察と三原労働基準監督署が現地入りし、事故の詳しい状況を調べています。今月7日の1件目の事故では、造船所内のドックで修理中の船の甲板から、船員の鈴木冨久亀さん(63)が約8㍍下のドックの底に転落して死亡しました。さらに、2日後のきのう、同じドックで船のプロペラを修理していた外部業者の田中和彦さん(46)がクレーンと落下防止策の間に挟まれ死亡しました。田中さんは昨日が作業の最終日で道具をしまう作業をしていたということです。小池造船海運㈱の小池英勝代表取締役は「うちのドック内で起こった事故なので、管理体制がずさんだった。遺族の方の心痛を考えますと反省しかない」と述べました。
3月7日江蘇省揚州市李典船舶工業地区にある大洋造船の前に数百人の作業員が集まり、数ヶ月滞っている給料を払えと叫びました。3月8日、作業員代表が国の信訪局に陳情しました。この会社は去年9月にも3000人の作業員の賃金支払い要求デモがありました。
大洋造船は2012年から経営不振で工員の福利厚生費が大幅削減され、2014年から給料、残業代、ボーナス、諸般福利手当のカットがあり、状況は現在も依然として変わらず、多くの人が自宅待機しています。
工業地区で仕事をする劉さんは8日に、大洋造船の前で数百人の作業員の賃金支払い要求デモを目撃しました。
劉さん
「この造船場はよく作業員に取り囲まれていると聞いています。昨日はわざわざ野次馬として見に行ったのですが、本当に数百人いました。実はこの辺りの造船所はほとんど経営不振で倒産寸前です」
記者は8日に大洋造船に電話しましたが無人でした。現地の社会保障局員は、この件は信訪局が仲裁すると言っています。
揚州信訪局職員
「今、大洋造船の作業員代表20名がここにいます。現在調整している最中ですが、どのような結果になるかについてはノーコメントです」
公開資料により大洋造船は、2003年10月に設立した外資との合弁大企業ですが、正式従業員および派遣アルバイトは一万人にも及びました。但し、現在は500人しか残っていません。
新唐人テレビがお伝えしました。
http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2016/03/08/a1256619.html (中国語)
(翻訳/碧眞 ナレーター/金丸 映像編集/李)
バルクインベストが破産申請した。下記の記事から少なくとも6つの日本の海運会社が船を傭船に出していたようだ。優良資産も売却されたのだからもう泣き寝入りしかないのか?
バルク・インベスト倒産/借船料残高625億円、日本18社から22隻。日本船主憤り「優良子会社売却直後」 03/06/16 (日本海事新聞)
ノルウェーのドライ船社バルク・インベスト(旧ウエスタンバルク)は現地時間3日、破産手続き開始を申請したと発表した。同社は日本船主18社から…
Norwegian shipping firm Bulk Invest said on Thursday it had filed for bankruptcy after failing to win backing for a financial restructuring needed to survive in difficult market conditions.
Spot rates in the dry bulk shipping market are close to all-time-lows and far below breakeven rates after years of lower demand growth and a wave of new dry bulk vessels entering the market.
Bulk Invest is the first European dry bulk shipping firm to go bankrupt this year.
Until recently known as Western Bulk, the company said in a statement that seven shipowners with outstanding hire claims against it had rejected the restructuring efforts.
Last month six of the shipowners asked for a legal injunction, requiring a reversal of the sale of subsidiary Western Bulk Chartering to Bulk Invest's majority shareholder Kistefos Equity Operations.
A lawyer for the six Japanese shipowners, Kristian Lindhartsen, said his clients believed that the bankruptcy was the result of Bulk Invest's own actions.
"The company sold Western Bulk Chartering AS below market value, and our clients are determined in pursuing this," Lindhartsen wrote in an e-mail to Reuters.
Bulk Invest said it had done nothing wrong when selling Western Bulk Chartering and that the transaction had been conducted on market terms.
Bulk Invest had total liabilities of $143.4 million at the end of 2015. The company's shares were suspended from trade in Oslo following the bankruptcy filing.
An administrator will now be appointed to decide what to do with Bulk Invest's assets.
Kistefos did not immediately respond to requests for comment. (Reporting by Stine Jacobsen and Ole Petter Skonnord; editing by Adrian Croft)
去年、下関市の造船会社の工場でクレーンから落下した鉄板の下敷きになって作業員が死亡した事故で、警察はクレーンを操縦していた21歳の会社員が作業員に事前に避難を指示しなかったことが事故につながった疑いが強まったとして3日業務上過失致死の疑いで書類送検しました。
書類送検されたのは下関市長府港町の造船会社「旭洋造船」の21歳の会社員の男です。
去年9月、旭洋造船の工場で、クレーンで運んでいた重さおよそ600キロの鉄板が突然落下し、近くで溶接作業をしていた64歳の男性作業員が下敷きになって死亡しました。
警察は、クレーンを操縦していた21歳の会社員が、作業員に事前に避難を指示しなかったことが事故につながった疑いが強まったとして3日、業務上過失致死の疑いで書類送検しました。
調べに対し、容疑を認めているということです。
旭洋造船の永冨隆総務部長は「今回の事故を重く受け止め労災事故が二度と起こらないように安全対策を徹底していく」とコメントしています。
神田造船所(呉市)は今月中に、主要株主の三井物産と主力銀行の広島銀行(広島市中区)に増資を引き受けてもらった後で資本金や利益準備金を取り崩す「増減資」を実施する。昨年3月末時点で10億8700万円あった債務超過を解消する狙いだ。
「法律の規制を無くせば、新たな自動操縦やレーダーなどの装置が開発され、水先人などすぐに不要になるだろう。船舶よりもはるかに高速で空中を飛行する飛行機でさえ管制塔の指示だけで離着陸している。低速で水に浮かんでいる船舶ならもっと容易にできそうなものだがどうか。」
現場や詳細を知らない人の意見だと思う。水先人法は改正及び見直しは必要であるが、廃止は現実的でない。
船のサイズや船及び船を管理する会社の評価で強制を判断するなど改正に盛り込む必要はあると思う。
同じ船であっても、免状を持っている船員が操船していても、会社のレベルで安全度がかなり違う。評価が難しい、評価の妥当性についても
反論する船主、用船社、および管理会社などが存在するので、PSC(外国船舶監督官)による検査結果で
船の評価がMOUのサイトで公開されているのでMOUの評価で判断するようにすれば良いと思う。
サブスタンダード船や悪質な会社が運航する船は
事故を起こす可能性が高いが、運賃が安いので使われる事が多い。そのような危険性が高い船には水先人を強制にすれば良い。事故は減るし、
荷主や用船社が減るので、サブスタンダード船や悪質な会社が運航する船は日本エリアで減るであろう。部分的に用船料の高い船を利用する事により輸送料が上がる可能性は高いが、その点については
日本国民に説明するべきだと思う。危険だが、安いのが一番と多くの国民が考えるのであれば、選択を尊重するのも良いと思う。
この世の中、メリットとデメリットが存在する。パーフェクトな選択はほとんどない。
安全で安価な輸送を国民が望んでいるのであれば、お金をかけないように船の操船を支援するような環境を整備するべきであろう。
比較的に電力に簡単にアクセスが出来る場所にはAISのシステムに似た方法でAISと連動しているレーダーや電子チャートに目印が確認でき、
航海機器上での補助的な役割を提供できるようにすれば良い。AISシステムを利用して船の動静を提供しているサイトは、協力や提携の形で
安価にサービスを提供できる体制を構築している。上手く利用すれば、船が間違ったルートやおかしな方向に走っていれば、船主や管理会社に
警報を送る事が安価なサービスとして提供できる。多くのエリアがカバー出来れば事故を未然に防いだり、事故調査が簡単になる。
最後に日本人の人件費が高騰している以上、見直しや改善を海運だけでなく、その他の業界や分野で行う必要があると思う。反発や高齢の人達からの
理解が得られない事があると思うが、放置すれば高負担を維持しなくてはならない。
水先人制度というのは法律によってのみ成り立っている制度であり、不要であると思う。
古い雑誌だが、「日経ビジネス 2004年4月5日号」に、「復権海運に“水先人の波”高し」という記事があった。ネットで調べてみると、水先人とは次のような仕事のようだ。
「港の中では多くの船が行き交っており、船の航行には細心の注意が必要です。世界中を航海し、何百という港に入出港している外航船の船長が、それぞれの港の特徴を把握することは困難です。このため、航行の案内役として乗船し、船長に助言して船を安全に効率的に導くのが『水先人』です。水先人は、それぞれの港について熟知しており、船の安全航行のための強い味方です」。
「わが国では、外航船の出入の多い港や水域は水先区として設定されている。全国で 39 の水先区が設定され、これにより不慣れな船舶であっても水先業務の提供を受けて安全かつ効率的に運航できるようになっている。このうち、特に潮流などの自然条件が厳しく、海上交通の輻輳する水域や港においては水先人を要請するか否かは船長の判断に委ねられておらず、水先法により一定基準以上の船舶に対して水先人の乗船が義務付けられている。これを「強制水先」と呼ぶ。現在、東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海の一部水域、関門海峡、佐世保港および那覇港に合計 11 の強制水先区が設定されている。清水港には強制水先区がなく、船舶側の判断で水先の有無が判断できるメリットがあるが、強制水先区については規制緩和の動きもある」。
で、日経ビジネスの記事には、「『月10日勤務で年収2200万円』が港の競争力そぐ」とある。いまどきこんな仕事があるとは...。水先人側は、乗船のための移動があるので実質20日勤務だと言っているようだが、納得できない。また移動は自宅からタクシー、新幹線や特急のグリーン車を使うという。優遇されすぎているのではないか。このような費用は全て船舶の運賃に加算される。日本の海運業が国際競争力に劣る原因がこれだ。このままでは日本の海運業が衰退してしまう。
「この水先(案内)人の料金体系が異常になったのは1964年に遡るらしい」というページもある。
水先人法が制定されたのは昭和24年(1949年)だ。当時と今とでは、船舶自体の性能や操船技術が格段に向上しているのではないのか。改正されているとはいえ50年以上前の法律に依存し、かつ常識はずれの人件費がかかる制度は廃止すべきである。
四方を海に囲まれている日本で海運業が衰退するとは笑い話にもならない。
さて、このような意見に対して批判された事がある。「『月10日勤務で年収2200万円』が高級だというが、その仕事のために必要な(操船)技術を習得するのに高い費用をかけているのだ」と。
僕に言わせれば全く反論になっていない。無用な技術を習得するのに金をかける方がおかしいのだ。そもそも金をかけた分だけ利益が返ってくるのであれば、誰も苦労しない。法律によって保護されているから言えるのだろう。
法律の規制を無くせば、新たな自動操縦やレーダーなどの装置が開発され、水先人などすぐに不要になるだろう。船舶よりもはるかに高速で空中を飛行する飛行機でさえ管制塔の指示だけで離着陸している。低速で水に浮かんでいる船舶ならもっと容易にできそうなものだがどうか。
By MarEx
Bulk Invest (formerly Western Bulk) has announced that it faces a lawsuit from creditors seeking reversal of the recent sale of its subsidiary Western Bulk Chartering to Bulk Invest's majority shareholder, Kistefos AS – and that it may have only weeks to negotiate its continued survival.
Bulk Invest faced mounting liquidity problems early this year and entered into an “accelerated process” with Kistefos for the sale of of its chartering unit in order to raise capital. To meet regulatory requirements, the sale had to be approved by shareholders at a general meeting, held February 25, and a majority voted in favor.
However, the firm said that “the Company [Bulk Invest] immediately prior to the general meeting had received an application for arrest in the shares of Western Bulk Chartering AS and a motion for injunction with a request for return of the shares.”
Bulk Invest has not specified the names of the creditors involved in the suit, and it will contest the suit. The firm “believes that the alleged claims are completely unfounded.”
Media reports suggest that six Japanese shipowners (with $170 million in charter contracts with Bulk Invest) have asked for an injunction to halt the sale, which they described as “an illegal payment of dividend,” alleging that Kistefos paid too little for Western Bulk Chartering. The shipowners reportedly see a bankruptcy proceeding as an acceptable outcome.
Even if it should win the suit and keep the capital raised from the sale, Bulk Invest faces trouble. In its Q4 2015 results released Monday, the firm says that it is locked into long-term chartering-in contracts – at charter rates well above what it can get by hiring the ships out at present spot prices.
The firm says that its future is “highly dependent” on negotiating rate reductions for its chartered-in fleet and discussions with its creditors. If “no solution is achieved, [Bulk Invest] will most likely not be able to continue its business” - and the timeline may be short. A new arrangement is needed “within a few weeks,” the firm said.
The firm raised $16 million in cash from the recent sale, but it is spending about $4 to $5 million per month on overhead, even though it has “implemented an almost full stop in payments, including charter hire for the chartered-in vessel.”
A dissolution of the company at current market values for its assets would most likely leave creditors with a loss, the firm says – especially given the bankruptcy liabilities in its charter-in contracts, which it estimates in the range of $250 million.
Holly Birkett
Western Bulk has sold its subsidiary Western Bulk Chartering to Kistefos AS, a Norwegian private investment firm led by Christen Sveaas, who is chairman of the Oslo-listed shipping group.
Western Bulk Chartering’s (WBC) enterprise value is $47m, but Western Bulk will receive just $16m as a cash consideration for the business unit.
Kistefos, which controls around 60.4% of Western Bulk shares, will assume WBC’s treasury bonds and its outstanding debt of NOK271m ($31.36m) under its NOK300m ($34.71m) senior unsecured bond.
Western Bulk said the sale was made to boost its liquidity and was in the best interests of the group and its shareholders.
“The company is exposed to an increasingly challenging market situation with dramatically low dry bulk charter rates and guarantees granted by group companies for charters for certain ship owners. This has resulted in significant strains on the company’s short-term liquidity situation,” Western Bulk said in a filing today.
WBC operates a fleet of around 160 bulk carriers, according to the company’s Q3 2015 financial report. Most of its fleet are supramaxes, all of which are chartered-in for varying periods of time from different owners including Western Bulk Shipholding. In April 2015, WBC closed its panamax chartering unit, which had been struggling.
WBC will become an independent company as soon as the transaction is completed and will continue to operate under its current management “until further notice on arm’s-length terms agreed with the purchaser”, Western Bulk said. Kistefos also intends to offer Western Bulk’s existing shareholders the opportunity to acquire a pro-rata portion of WBC.
The sell-off requires approval from the majority of Western Bulk’s bondholders to be completed, for which a extraordinary general meeting is scheduled for around February 3.
The company aims to complete the transaction within three weeks of receiving the approval and to transfer the shares and bonds “within a few days”.
「番船は当初、2015年3月に納入する予定だったが、設計変更や資材調達の難航、内装の仕様変更などで、3回納期を延期した。今月中旬にイタリア当局の最終検査を受けた後、引き渡す。」
この船の船級はどこなのか知らないが、「イタリア当局」であれば上手くやれば検査を簡単にしてもらえたのでは?RINA(イタリア船級協会)に
日本人検査官はいないと思う。イタリアでは賄賂は未だにあり。検査官に足が付かないように上手く交渉すれば、検査が簡単になるかも?ただ、
賄賂代として経費に上げられないので上手くやる必要はあるだろう。何千億円の損を考えれば賄賂の額など小さなもの。
まあ、三菱重工に臨機応変に動ける人間は少ないだろうし、リスクを冒してまで会社に尽くす人はいないだろうし、建前のコーポレートガバナンスの問題もある。巨額損失は仕方のなかったことかもしれない。
三菱重工業は世界最大のクルーズ客船運航会社、米カーニバル・コーポレーション向けに大型旅客船を2隻建造中だが、その納期が遅れている。
カーニバル傘下のアイーダ・クルーズに納入する2隻は長崎造船所で建造している。2番船の船体部分は完了したが、同時建造している1番船の引き渡しが大幅に遅れている影響で、人員を2番船に割くことができない。
1番船は当初、2015年3月に納入する予定だったが、設計変更や資材調達の難航、内装の仕様変更などで、3回納期を延期した。今月中旬にイタリア当局の最終検査を受けた後、引き渡す。
1番船は今年に入り、船内で段ボールなどが燃える火災が3度起きた。長崎県警大浦署は放火の可能性があるとみて調べている。放火というのは、たとえ被害は軽微でも、より深刻な事態だ。9年ぶりの大型客船の建造は御難続きなのである。
客船事業を造船の柱に
三菱重工は11年、カーニバルから大型客船2隻を受注した。12万4500総トン、3300人乗りという大型船である。アイーダ・クルーズが使う船で、受注額は2隻で1000億円。長崎造船所で建造し、1番船は15年3月、2番船は16年3月に引き渡す予定になっていた。
三菱重工の客船事業は02年10月に、建造中の「ダイヤモンド・プリンセス号」が火災を起こした後、注文が途絶えていた。
中国や韓国に受注を奪われ、三菱重工は10年に貨物運搬船など採算の悪い商船の建造から撤退した。その後は高い技術力を生かし、LNG(液化天然ガス)運搬船や大型客船、艦船などに経営資源を集中してきた。とりわけ客船事業を造船の柱に据え、海外での受注活動を積極的に行ってきた。
カーニバルは16年までにさらに8隻の客船を保有する計画だ。2隻の受注で三菱重工に追加注文の可能性が高まった。当時、「日本で建造できるのは当社だけ」と三菱重工の鼻息は滅法荒かった。だが納期の遅れが相次ぎ、大型客船分野のチャンピオンになる夢は消えた。
受注額を大幅に上回る特損1800億円超
長崎造船所香焼工場で13年6月、1番船を起工した。だが1年もたたない14年3月、設計変更を繰り返し費用が増加したという理由で、641億円の特別損失を計上すると発表した。同年10月には追加特損398億円、さらに15年5月にも297億円の損失が出ると公表した。
15年3月期連結決算の売上高は前期比19%増の3兆9921億円、営業利益は44%増の2961億円と過去最高を更新した。火力発電所部門を日立製作所と統合したことに伴う売り上げ増が寄与した。しかし、純利益は31%減の1104億円だった。豪華客船事業で特損が膨らんだためだ。
15年9月期中間決算でも310億円の特損を計上した。過去の特損と合わせて累計は1648億円に達した。1番船が納期を再々延期した代償がこれだ。2番船の納入遅れで、さらに損失は膨らむことが確実だ。
三菱重工は2月4日、16年3月期の業績見通しを下方修正した。連結純利益は、それまで1300億円(前期比18%増)を見込んでいたが、一転、18%減の900億円となる。大型客船部門で新たに221億円の特損が発生する。累計損失は5年間で1869億円になる。損失の累計は2隻の受注額の2倍近くに膨らむことになる。
下方修正したとはいえ、売上高は2.7%増の4兆1000億円と初の4兆円台に乗る。営業利益は1.3%増の3000億円と過去最高を更新する見込みだ。
祖業である造船事業は不振のシンボルに変わり果て、客船事業への復帰は高くついた。1、2番船の納入が済めば客船事業から撤退するとみられている。
不審火の原因を探る
三菱重工長崎造船所では、今年に入って船内で不審火が3回連続して起きた。世界から集まった数千人規模の労働者をゲートで一人ひとりチェックしているが、巨大な船に入ってしまえば、すべてのエリアをカメラで監視するのは不可能だ。「これだけ人数が多いと(火事の)原因究明もできない」との声が挙がり、現場の混乱は終息していない。
02年にも大型客船で火災が発生し、全体の4割が焼失している。その原因は溶接作業の熱だったが、今回は放火で、しかも犯人も動機もわかっていない。1番船がこのような状況で、年末にした2番船の納期も守れる保証はない。再延期すれば損失はさらに増える。
三菱重工は昨年秋、商船事業などを分社化。長崎造船所は実質6つの会社に分かれている。大型客船は三菱重工本体、今後の主力となるガス運搬船は新しくできた会社だ。さらに多数の関連・協力会社がひしめき合っている。
この分社が長崎造船所の一体感を失わせているのではないかとの懸念も生じている。宮永俊一社長の経営力・統率力(ガバナビリティ)が問われている。
特定の種類の船そして大きさの船は同じような問題となるだろう。造船業界は日本の建設業界の構造と思わずに考えるべきであろう。まあ、 造船とか海運と言っても、影響を受ける人達とさほど影響を受けない人達に分かれるから、足並みは乱れるし、将来の事など考えるゆとりがない 企業や人達にとってはどうでも良いことかもしれない。
超高層マンションよりも圧迫感が少なく、一戸建てに近い住み心地が実感できる低層マンションが近年、準都心や近郊外部で激減している。日本の建設業界の構造が理由だ。住宅ジャーナリスト櫻井幸雄さんが報告する。
◇3階建て低層マンションのメリットは
超高層マンションの対局にあるのが「低層マンション」。5階建てまでのものを低層と呼ぶことが多いのだが、本来は3階建て、妥協しても4階建てまでが低層らしい低層マンション。長所は、マンションの圧迫感が薄れ、一戸建てに近い住み心地を実感できること。さらに、一戸建てより安い分譲価格で購入できること。マンションと一戸建ての中間のような存在となるわけだ。
3階建てまでの低層であれば、一戸建て中心の住宅地にも建設が可能。土地に定められる用途地域別で最も規制が厳しいのは「第1種低層住居専用地域」。厳しいところでは、「建物の高さは10メートルまで」と規制され、一戸建て中心の住宅地となる。
「高さ10メートルまで」と定められた場所でも、3階建てマンションならば建設が可能。だから、静かな住宅エリアに暮らしたいが一戸建ては予算的に無理、でも、低層マンションなら買える、という人にとって救いの神となるわけだ。
◇静かな住宅街に落ち着いたたたずまい
3階建てでも鉄筋コンクリート造りなので、頑丈だし、断熱性、遮音性も高い。周囲には2階建ての一戸建てが多くなるため、3階部分は眺望が良好になる。
以上のメリットから、3階建ての低層マンションには、根強い人気があった。私自身、30年ほど前に購入した最初のマンションは低層3階建てだった。
見た目が派手な超高層マンションに憧れる人と同じぐらい、落ち着いた低層マンションに憧れる人も多いのである。
ところが、この低層マンションが近年激減している。超高層マンションであれば、簡単に探すことができるが、低層マンションは“絶滅危惧種”といえるくらい希少なのだ。都心や京都の超高級物件であればまれに出合うものの、準都心や近郊外部では、多くの人が購入できる価格設定の低層マンションはすっかり影を潜めている。
低層マンションファンとしては、なんとか造り続けてほしい。だが、そうしたくてもできない事情がある。それは、日本の建設業界が抱える問題でもある。
現在、日本では職人不足による建設費の高騰が続いている。工事現場で働く人が減ってしまったのだ。もともと、工事現場の仕事は3K(きつい、汚い、危険)労働のイメージがあり、若い人が減っていた。それに加えて、2007年あたりから10年までの不動産不況で仕事が減り、仕方なく離職する人が増えた。当時、不動産価格はまだまだ下がるから、買い控えしろ、という声が多かった。これは、建設工事従業者をいじめる側面もあったわけだ。
結果、サービス業などに新たな仕事を求める人が増えたのだが、その中には鉄筋工と型枠職人が多かったとされる。いずれも、鉄筋コンクリート造りのマンション工事現場には欠かせない人たちである。
◇建築費が高騰し、一戸建てより高くなる
この職人不足が現在の建築費高騰につながっている。特に、一戸建てよりも鉄筋コンクリート造りのマンションで建築費の高騰が著しい。それは、鉄筋工と型枠職人が減ってしまったことも大きな原因だと私はみている。
一戸建てと比べて、マンションのほうが建築費の上昇は大きい。その結果、低層マンションを造ると、1戸あたりの建築費が高くなりすぎ、分譲価格全体も高額になってしまう。周囲の建売住宅より、低層マンションのほうが高い……そういう現象が起きてしまった。
同じような立地条件で、同じような広さ(延べ床面積)の低層マンションと建売住宅が新築で分譲され、建売住宅のほうが安かったら、どうなるか。低層マンションの勝ち目は薄い。だから、不動産会社は準都心・近郊外エリアで、低層マンションを造らない。
マンションを造るなら、5階建て以上の建物が建設できる土地を探す。7階建てとか11階建てになれば、1戸あたりの土地代負担が抑えられ、建売住宅より安い価格でマンションを分譲できる。商売として成り立つからだ。
以上の動きから、準都心・近郊外では、広い道路に面した土地のマンション、工場エリアのマンション分譲が増え、一戸建て住宅地内の低層マンションがみつからなくなった。
低層マンションは今や“絶滅危惧種”になりつつある。それは、日本の悲しい現実なのである。
■提出資料、虚偽の疑い/金融機関が刑事告訴検討
船舶大手「日本郵船」に船舶を供給していた船主大手「ユナイテッドオーシャン・グループ」(昨年11月破綻)が複数銀行から受けた計1千億円超の融資のうち、少なくとも数十億円が回収不能の見通しとなっていることが19日、金融関係者への取材で分かった。金融機関側は「融資の際に虚偽の資料が提出された可能性がある」としており、詐欺罪などでの刑事告訴を視野に事実関係を調査している。日本郵船も社員が関与していないか内部調査に乗り出した。
日本郵船や金融関係者などによると、ユナイテッドグループは統括管理会社「ラムスコーポレーション」と、船を所有する特別目的会社(SPC)38社からなる船主グループ。日本郵船に所有船舶約40隻をリースする「用船契約」を締結していた。
一般的に船舶業界では融資を受ける際、SPC側が造船費用や完成後に発生する用船料などについての書類を金融機関に提出する。ユナイテッドグループも約10年前から、三菱東京UFJ、りそな、みずほの各行などから計1千億円超の融資を受けていた。
しかし、金融機関の調査によって昨秋、ユナイテッドグループが金融機関側に提出した資料に不審な点があることが判明。金融関係者は「用船料や期間、造船費用などが水増しされていたことが発覚した。水増しは遅くとも数年前から行われていたもようだ」としている。こうした虚偽の書類に基づくとみられる融資額は各金融機関を合わせて数百億円規模で、少なくとも数十億円が回収不能となる見込みという。
債権者である金融機関側が昨年11月、ユナイテッドグループの更生手続きの開始を東京地裁に申し立て、地裁は12月に開始を決定した。申し立ての中で金融機関側は、融資に使われた書類で「虚偽の情報が含まれていた」との趣旨の主張をしているという。
民間信用調査機関によると、ユナイテッドグループの負債は昨年倒産した企業で最大の約1400億円だった。ユナイテッドグループの代理人は産経新聞の取材に、融資について「係争中の案件についてはコメントできない」と話している。
日本郵船は「(ユナイテッドグループが)どのような融資を受けているのかについては一切関知していないが、社員が関与した可能性がないか内部調査を始めた」としている。
◇
【用語解説】用船契約
船主が船舶会社に船をリースする際に結ぶ契約。10年や20年など使用期間に応じた利用料(用船料)を定める。市況の変動に準じて用船料を変える条項を盛り込むこともある。船主が造船費用捻出などのため融資を申し込む際、金融機関側は用船契約の内容を見てから、融資が可能か判断することが多い。
◇
【用語解説】SPC
「特別目的会社」の略称。企業が資金を調達するなどの目的で設立する。企業から資産の譲渡を受けるなどして、企業本体と資産を切り離した形で資金調達を図る。船舶業界で使う場合は、基本的に船1隻ごとに設立される。損失隠しのための不良債権の譲渡先として使われるケースもある。
広島・三原労働基準監督署は、労働災害防止に必要な下請との連絡調整を怠っていたとして、小池造船海運㈱(広島県豊田郡)と同社係長を労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)違反の疑いで広島地検呉支部に書類送検した。
平成28年3月、特定元方事業者の同社が船舶の修繕作業をしていたところ、下請業者の労働者が移動してきたクレーンの走行装置と手すりの間に挟まれ死亡する労働災害が発生している。同社は、法律で定められている作業間の連絡および調整をしていなかった。
大崎上島町の同じ造船所で、3月7日と9日、相次いで労災死亡事故が発生した。事故があったのは大崎上島町の小池造船海運。3月7日の1件目の事故では、造船所内のドックで修理中の船の甲板から、船員の鈴木冨久亀さん(63)が約8メートル下のドックの底に転落して死亡した。さらに2日後、同じドックで船のプロペラを修理していた外部業者の田中和彦さん(46)がクレーンと落下防止策の間に挟まれ死亡した。田中さんは昨日が作業の最終日で道具をしまう作業をしていたという。小池造船海運㈱の小池英勝代表取締役は「うちのドック内で起こった事故なので、管理体制がずさんだった。遺族の方の心痛を考えますと反省しかない」と述べた。
「日本郵船に騙された」。取引金融機関の間ではこんな穏やかならざる囁きも交わされているという。
〝事件〟は昨年十一月十一日、ある船主会社グループの経営破綻劇で幕を開けた。統括会社で船舶関連の契約業務請負や管理業務を行っているラムスコーポレーション(東京・港区)と実際に船舶を所有している三十八社のSPC(特別目的会社)から成るユナイテッドオーシャン・グループ(UOG)―その借入金の一部に債務不履行(デフォルト)が発生し、債権者の一人だったみずほフィナンシャルグループ系のリース準大手、興銀リースから会社更生法の適用申請を申し立てられたのだ。
UOGとラムス社は新船建造費の融資を受けるに際し、金融機関との間でクロスデフォルト条項を交わしていたとされている。借入金が一つでもデフォルトを起こせば、残りの借入金が返済期限を迎えていなくても、すべてがデフォルトを起こしたとみなされ、債権者が返済を要求できる仕組み。興銀リースはその発動に踏み切ったのだ。
そして同十二月三十一日、UOGは東京地裁から会社更生法手続き開始の決定を受ける。興銀リース自体の焦げ付きは三十七億円弱に過ぎなかったものの、グループ全体での負債総額は約一千四百億円にも上った。規模としては昨年で最大級の企業倒産だった。
とはいえ、ここまでなら規模こそ大きいものの、それこそ「どこにでもある破綻劇」(金融筋)。すでに更生法の手続き開始が決まった以上、その枠組みに沿って清々粛々と法的整理を進めていけば済む。
ところが―事はこれでは終わらなかったのである。倒産と相前後する形で、UOGが偽りの契約内容をもとに金融機関から不正に融資を引き出していた疑いが浮上したうえ、日本郵船がどうやらそれに一枚嚙んでいるのでは、といった疑惑までが銀行関係者らの間でまことしやかに取り沙汰されはじめたからだ。
「クルマも女もあてがった」
実はUOGは「極めて特殊な船主会社」(海運業界筋)だとされている。シンガポールに二十四社、パナマに十四社登記されているSPCを通じて、七万トン以上のパナマックス船十三隻、四万トン以上のハンディマックス船九隻、自動車船七隻など三十八隻を保有しているが、そのすべてを日本郵船一社だけに貸し付けているためだ。
通常三十八隻もの船を所有していれば、複数の海運会社に船を貸して、リスク分散を図るのが真っ当な経営の在り方だ。海運会社が破綻すれば傭船料を取りっぱぐれる恐れもあるからだ。実際、昨年九月末には売上高で業界五位の第一中央汽船が民事再生法の適用を申請するなど、直近での破綻劇も起こっている。
一方で、船主からすれば日本郵船のような相対的に財務体質の良好な海運会社とできるだけ多くの取引関係を持ちたいと思うのも本音だろう。それだけに同社をめぐる船主間の貸し付け競争は激しい。とりわけ二〇一二年以降は、海運市況や船価が底に達したとみたファンドなど世界の投機マネーが大量に造船市場に流入、競争はさらにエスカレートしている。それなのに「なぜUOGがここまで日本郵船に食い込めたのか」。海運大手三社の一角、商船三井幹部の一人もしきりと首を捻る。
UOGはインド人のヴィパン・クマール・シャルマ社長が一代で起こした会社だ。十歳のときから日本で育った人物で、一九九一年に設立した。日本郵船との間に無論、何の資本関係もない。それが日本郵船の全傭船隻数五百十四隻(一五年九月末)の七・四%を占めるまでに取引を拡大させたのだ。
業界関係者によると、シャルマ社長による日本郵船首脳や幹部らに対する〝接待攻勢〟は「実はそのスジでは有名な話だった」という。一説では経営陣や役員候補の人材に対し、社長自身が「相当なカネを使った。クルマも女もあてがった」などと吹聴していたとか。なかでも経団連副会長をつとめ、「最高実力者」(日本郵船関係者)とされた草刈隆郎元社長・会長(現特別顧問)とは「因縁浅からぬものがあった」(周辺筋)とされている。
だが、それならばどうしてUOGは破綻しなければならなかったのか。船主会社は取引相手の海運会社が存続している限り、安定・継続的に傭船料が入ってくるストックビジネスだ。本業に専念してさえいれば「大儲けはできないにしても、借入金の返済に行き詰まるほど資金繰りに窮するようなことはほとんどない」(メガバンク筋)ともいわれている。まして傭船先は大手三社のなかでも信用格付け最高位の日本郵船だ。
一般的に船主が新船を建造しようとする場合、その資金は総工費の一割を自己資金、残り九割を金融機関からの借り入れで賄うといわれている。しかし、金融機関側からすれば建造する船の傭船先が決まっており、その傭船契約の内容が確かなものでなければ危なっかしくて多額の融資など実行できるハズもない。
そこで金融機関側は融資に際して、建造される船がどこに貸し出されて、どれくらいの傭船料が見込めるのかを確認することになる。そのうえで傭船契約から得られる傭船料が元利金の返済原資となるようスキームを設計し、ファイナンスを実施するわけだ。「傭船料債権譲渡担保」と呼ばれる仕組みで、逆に船主側からすれば、傭船先から得られる傭船料の中から金融機関に対して決められた契約の通りに借入金の返済を行っていけば自ずと完済にまでこぎつけられることになる。デフォルトを起こすリスクは極めて少ない。なのに―UOGは破綻した。
初歩的ともいえる〝融資詐欺〟
こうして浮かび上がってきたのが、前述の疑惑だ。要するにUOGが起こすハズのないデフォルトを起こしたのは「そもそもUOGが金融機関に提出した傭船契約書そのものに何らかの瑕疵があったか、意図的に細工が施されたシロモノだったのではないか」(銀行筋)というわけだ。
そんななか業界関係者らの間で駆け巡っているのが、UOGと日本郵船との間の傭船料の取り決めは「異例ともいえる内容だった」との情報だ。当初の傭船料は固定だが、数年後には変動制に移行し、「国際的な海運市況に連動させる形になっていた」というのである。
事実とすれば業界の商慣行や常識から言って「あり得ない契約」(川崎汽船関係者)だろう。運賃相場の高止まりや上昇が続くのなら、確かに船主にとって変動制は好都合だ。しかし、ひとたび下落に転じれば傭船料収入が急減、金融機関への返済が滞り、あっという間に破綻に追い込まれるのは「火を見るより明らか」(メガバンク幹部)だからだ。
第一、こうした契約内容では回収不能リスクが高過ぎて、金融機関も融資自体を行わないし、行えない。強行して損失が生じれば「背任容疑で刑事責任すら問われかねない」(同前)ためだ。しかし現実には、UOGへの融資は実行された。だとすれば考えられるのは、UOGが市況連動型傭船料という事実をひた隠しにしていたか、契約書を完全固定制に偽造していたかということくらいしかあるまい。
金融関係者によるとシップファイナンスの場合、借り入れを希望する船主が提出する契約書類は必ずしも原本である必要はなく、コピーで十分なのだという。そこでこれを悪用する形で紛い物を作成、本物に見せかけて銀行側に提出していたのではないか――。大手銀行のある幹部はこう推察する。
典型的で初歩的ともいえる“融資詐欺”だが、金融機関側からすれば提出された書類の真贋はともあれ、契約書に記載され、傭船料収入ひいては借入金返済原資の裏付けともなっている「日本郵船」の肩書と信用力は絶対的にモノを言う。「資金需要の伸び悩みに困っていただけに、一も二もなく融資に応じたのでは……」。大手地銀幹部は思いを巡らせる。
何かしらの作為とある種の不実
それにしても日本郵船は「非常識」とされている傭船料市況スライドの契約をなぜUOGに押し付けたのだろう。船主会社と海運会社の力関係を利用した、いわば優越的地位の乱用といえなくもないが、こうした契約内容ではUOGが金融機関から新船建造のための融資を引き出せないであろうことは「日本郵船側も当然、認識していたハズだ」(海運業界関係者)。
だとすれば、それでもなお融資を引き出そうとするとUOGが、何らかの不正に手を染めざるを得なくなる可能性も「当然ながら予見できたハズ」(業界筋)。にもかかわらず、日本郵船は目をつぶっていたばかりか、実際に融資が引き出されて三十八隻もの船が建造されるに至るまでひたすら沈黙を続けた。「そこに何かしらの作為とある種の不実を感じざるを得ない」。金融関係者の一人は呟く。騙された―の声が燻る所以か。
UOGが興銀リース以外のどんな金融機関とどれくらいの規模の取引があったのか、現時点ではすべてが具体的に明確になっているわけではない。しかし各大手銀行ともここ数年揃ってシップファイナンスに力を入れてきた経緯もあるだけに、その大半が今回の破綻に巻き込まれたのはほぼ確実。事情通らの間では「みずほ銀行や商工中金、さらには日本郵船本体のメーンバンクでもある三菱東京UFJ銀行なども焦げ付きを抱えたらしい」といった観測が飛び交う。また、りそなホールディングスが二〇一五年度上期(四~九月)決算で大幅な減益に転じる原因となった約三百二十二億円の個別貸倒引当金の計上も「その大部分がUOG向けだった」(市場関係者)とも取り沙汰されている。
日本郵船ではUOGの破綻後も同社との傭船契約を解除せず、現行契約の残存期間中はそのまま船を借りて傭船料を支払い続けていくことで、ひとまず金融機関側の怒りと反発を和らげたい意向とされる。だが、金融筋の一人は「破綻の真相究明と責任の所在の明確化が先」と声を荒らげる。今後の展開次第では日本郵船の経営体制を揺さぶる事態ともなりかねない。
運賃市況下落の波が追い打ち
そんな日本郵船の足元へひたひたと押し寄せているのが、ここにきて再びピッチを早めつつある運賃市況下落の波だ。昨年八月には一時一千六十六にまで回復していたバルチック海運指数(一九八五年=一千)は同十二月には五百十九に悪化。足元は四百を大きく割り込み、史上最低の水準にまで落ち込んでいる。中国をはじめとした新興国の景気減速を受けて鉄鉱石や石炭などの資源需要が低迷、それらを運ぶバラ積み船の需給バランス悪化に歯止めがかからないためだ。
日本郵船が一月二十九日に発表した一五年度第3四半期決算(十~十二月)では経常利益が前年同期の二百四十八億円から約四割も減少。営業利益七百五十億円、経常利益八百億円などとしていた通期の利益計画の下方修正にも追い込まれた。
日本郵船では一円円安が進むごとに経常利益が年約十一億円押し上げられ、船舶重油など燃料価格が一トン当たり十ドル下がれば、同様に約十三億円がかさ上げされるとされている。上期は運賃市況低迷による減益要因をこうした円安・燃料安効果でカバーして三八%強の経常増益を確保したが、下期は運賃市況の下落幅が余りに大きく、年明け以降の大幅な原油安効果も食い潰される格好だ。
海運業界関係者によると、一四年まで二年連続で減少したバラ積み船の竣工隻数は一五年には増加に転じ、一六年以降もしばらくは新造船による供給圧力が続くという。日用品などを運ぶコンテナ船も新船建造に歯止めがかかる気配はない。なかでも攻勢をかけているのが、同船舶で世界シェア一五%と圧倒的な首位に立つデンマークのAPモラー・マースクグループ傘下のマースクライン。一四年末には積載能力を日本郵船支配下の船舶より約八割も高めた超大型コンテナ船を日本に就航、今後も相次ぎ投入していく方針だとされている。
「そんなことになれば運賃市況は間違いなく底割れする」。日本郵船関係者の一人は青ざめる。
無論、日本郵船とて市況変動の波にただただ翻弄されているだけではない。一四年度からの中期計画では①短期的変動に左右されにくい中長期運搬契約の拡大②不採算船や老朽船の返船・売船はじめ船舶資産のスリム化―などを進める一方、海洋開発などのエネルギー関連分野やLNG輸送船に重点投資、新たな収益の柱として育成していく方針も打ち出した。ただ当面は日本郵船に恩恵をもたらす原油安は、海洋開発など新分野の将来性に暗く大きな影を落とす。
UOG破綻に伴う後始末の方向性が見通せないのと同様、日本郵船の行く手もまた、不透明だ。
4隻連続建造計画を撤回
三井造船はグループの新潟造船(新潟市中央区)で建造する欧州向け海洋支援船建造を全面支援する。設計変更や不具合などで工程が混乱し、今期に入り合計約110億円の損失を計上するなど連結業績に多大な影響を与えている。新潟造船での4隻連続建造計画を撤回し、三井造船の玉野事業所(岡山県玉野市)、千葉事業所(千葉県市原市)で分担建造し、多様な人材を送り込むなど、グループの総力をあげて、損失拡大をくい止める。
新潟造船は2014年3月に、カナダ・ディーケイグループ傘下のオランダ・ALPから世界最大級のえい航能力(300トン)を持つ海洋支援船4隻を受注した。200億円規模とみられる大型受注となったが、工事が難航し、予想を超える資機材の増加、現場工数の増加が発生した。
このため親会社の三井造船は2隻を千葉事業所と玉野事業所でも分担し、艤装(ぎそう)工事などを引き受ける。うち1隻は玉野事業所で引き渡す。残る2隻は当初計画通り新潟造船で建造する。16年半ばまでの契約納期に間に合わせる。
韓国造船業界が酷い状態になっているから言いたい放題書いているのだろう。
技術力と言うよりは、韓国が好きな投資の集中で失敗した結果だと個人的に思う。
つまり、韓国は大型商船の連続建造に投資と人材を集中したと言う事。結果、小型から中型を建造する造船所は大型船の建造へ移行した、又は、
消滅した。小型から中型の船が必要な韓国船主は日本の中古を売船して使う、又は、中国で建造するしか選択肢がない。日本で建造すると
コストの面で経営が成り立たないのか、日本での建造は珍しい。
韓国客船 Sewol沈没事故では韓国では客船を建造していない事を多くの日本人が知った。
大型商船建造で世界一になっても客船を建造する技術と経験は別なのである。経験の蓄積と技術を組み合わせなければ、良い船を建造する事は
難しい。日本は修繕すれば使用できても、人件費が高いので修繕コストが高くなる、客船建造で補助金が出るケースもあるのでスクラップ寸前まで
使用する事はまれである。よって、韓国よりは小型から中型船を建造する環境は日本の方が恵まれている。日本の造船業界も徐々に衰退はしてきているので、変わった内航船を建造する場合、建造コストが昔と比較して割高になる、又は建造する造船所がなくなる(非常に高い船価であれば建造する造船所は困らない)と思うので過去の傾向は変わるかもしれない。
三菱重工の大型客船巨額特損を考えれば少しは理解できるであろう。ケースバイケースであるが、建造を継続していないと、技術や経験の蓄積の
継承や建造効率が落ちる。コスト削減や利益アップのために同型船の建造に多くの日本の造船所はシフトしている。得意分野の種類やサイズ以外の
船を建造する場合、継続して建造している造船所と比べて、利益や効率で不利になる場合がある事を理解しておくべきだろう。この点では、
あまり韓国の造船所を笑ってばかりはいられないと思う。外国人労働者の比率も上がっている。経験しないと理解できない、又は、習得できない
事もある。歴史がある産業は頭の固い、又は、意味を考えずに繰り返す人々が多い。
造船業界では技術と経験の蓄積は時として同じ、又は、コンビネーションだと思う。経験によって学んだから、失敗しないように対応できるの場合がある。学校で学んでいないからとか、新しい技術を知らないから、失敗したと言う事ではない。問題にぶち当たるまで問題を想定できない、そして、
問題の対応策を準備出来ないのに納期の問題が精神的に襲い掛かる。経験からどのような問題が起きるのか想像できるのと、出来ないでは結果に影響する場合もある。単純に技術不足で説明できない事もある。外部者や記者ににとってはどうでも良いことなのだろう。韓国造船業界が今回の危機を乗り越える事が出来たとすれば、危機はチャンスと言える日も来るだろう。
なぜ韓国で建造しないのかと疑問に思う一般人は多いだろう。小型から中型船を建造する技術や経験の蓄積が競争力のある船の建造で十分でない。
品質も良くなく、価格が高い船を誰が発注するのか?結局、利益が出る大型商船に依存したという事。
日本は韓国を笑わず、韓国の失敗から失敗しないように学ぶべきであろう。まあ、なるようにしかならないから、結果が出た後に分析するのは
簡単であろう。
韓国の高度成長を半導体とともに牽引(けんいん)してきた造船業界が“沈没”寸前だ。「ビッグ3」と呼ばれる現代重工業、サムスン重工業、大宇造船海洋の韓国造船大手3社は昨年、そろって過去最大の赤字に陥ったとみられる。世界経済の減速に伴う受注減が響いたのは間違いないが、韓国内では技術力の向上をおざなりにして安値受注を繰り返してきた「未熟な競争文化」を問題視する声もあがる。製造強国を誇ってきた韓国の自信喪失は明白だ。
8兆ウォンの赤字
「これほどひどい業績になるのは初めてだ」
聯合ニュースは韓国造船業界関係者のこんな嘆きを伝える。
同ニュースによると、大宇造船海洋の昨年の営業赤字は約5兆ウォン(約4950億円)、現代重工業とサムスン重工業もそれぞれ1兆4000億~1兆5000億ウォンと造船、証券業界は推計しているという。ビッグ3がそろって兆単位の赤字を計上するのは初めてで、合計では8兆ウォンにも達する史上最悪の危機的状況だ。
大宇造船海洋に対しては大株主で債権団の中心である政府系の韓国産業銀行が昨年10月に合計4兆2000億ウォンに上る支援策を発表した。資金の手当てがなければ、経営破綻が免れないところまで追い込まれている。
大宇造船海洋は昨年8月以降、早期退職などで部長クラス以上の社員を1300人から1000人に減らし、本社役員も3割削減。不動産など一部資産も売却するなど厳しい再建計画を実施中という。リストラを余儀なくされているのは他のビッグ3も同じだ。
「最近公開された映画『オデッセイ』の原作を読んだが、火星で孤立した主人公が地球に戻るという希望を失わず生存のために死闘した結果、無事に帰還するのを見て感銘を受けた」
中央日報は同社の鄭聖立社長が再建の努力を「火星からの帰還」にたとえる悲壮な覚悟を報じている。
造船不況は韓国の地域経済にも打撃を与えている。造船所が密集する巨済市では、市場・スーパーの売上高が1年間に20~25%減少するなど、景気の冷え込みが顕著だ。
後進的な競争文化
なぜ、これほどまでの苦戦を強いられるようになったのか。
世界的な造船不況というだけでは説明しきれない。世界の造船市場は日本、中国、韓国が9割を占めるが、中でも韓国の受注の落ち込みが際立っているからだ。
韓国経済新聞などによると、韓国の造船企業は昨年、1015万CGT(標準換算トン数・建造難易度などを考慮した船舶重量)を受注した。1位の中国より10万CGT少なかった。日本は914万CGTで、3位だった。市場シェアは中国が30.3%、韓国が30%、日本が27.1%となり、中国の受注量1位は2012年から4年連続という。
問題は下期の受注動向だ。中国が692万CGTを受注したのに対し、韓国は342万CGTと中国の半分にもならなかった。日本(442万CGT)にも追い抜かれている。
受注量の差は年末に近づくほど広がっており、11~12月は中国が韓国の8倍にも上った。12月の韓国の受注量は2009年9月以来の最低水準という。
価格競争力のある中国が技術力もつけ、もともと技術力に優れる日本は円安で価格競争力を増しており、両国に韓国が挟撃される構図となっているようだ。
加えて、韓国が原価割れの安値受注も辞さずにシェアを守ろうとしたことで損失が拡大。注力してきた海洋プラント(原油などの掘削・生産装置)でも技術不足で工期が遅れたり、原油安を背景に契約のキャンセルが相次いだりしたことも傷口を広げた。
韓国内では造船業の不振の原因として「たい焼きでも作るように船を作り、いわゆる『カタログ営業』だけを続けてきたのだから技術力があるはずがない」(韓国経済新聞)、「勝利のためにはどんな変則的な方式も辞さないという後進的な競争文化が根底で作用している」(中央日報)といった“自虐的”な見方も出ている。
座礁の危機
造船業で日本が40年以上守り続けた世界一の座を韓国が奪ったのは2000年だ。それ以降、造船業は韓国経済の自慢の種だったが、近年は中国に1位を譲り渡しただけでなく、日本にも追い上げられ、焦りの色を深めている。日本のシェアは13年が16.5%、14年が21.6%、15年が27.1%と拡大傾向にある。
中央日報は「主力産業の危機は韓国経済の危機だ。このまま放置すれば成長エンジンが止まり『韓国号』は座礁するだろう」と警鐘を鳴らしている。
実際、韓国銀行(中央銀行)が発表した15年の成長率は2.6%(速報値)だった。韓国メディアによると、政府は3%台を目標としていたが、2012年以来、3年ぶりの低水準となった。輸出の伸びが鈍化し、14年の2.8%から15年は0.4%になったことが響いた。
造船業の苦境は大きな曲がり角に立った韓国経済を象徴しているといえるだろう。(本田誠)
川重・大和田常務に聞く「(ブラジル事業)赤字だからといってやめるのは賢くない」
ブラジルの造船合弁事業で221億円の損失を計上した川崎重工業。2016年3月期連結業績予想の下方修正を余儀なくされたが、売上高、営業利益、経常利益とも過去最高を更新する見通し。影を落とす船舶海洋事業。このタイミングで巨額損失を計上した背景を含め足元の状況を財務・人事部門管掌の太田和男常務に聞いた。
―坂出工場(香川県坂出市)のドリルシップ建造に関する入金が約1年停滞しているにもかかわらず、工事を継続してきました。
「一方的に工事を止めると遅延金などペナルティーが生じる。楽観せず少しずつ建造してきたが、昨年11月に生産中断で合意した。出資先のエンセアーダが昨年12月末を期限とする貸付金、売掛金を支払わない見通しになり、2回続けて入金がない場合は評価する社内ルールに従い、会計士と相談した上で損失を引き当てた」
―1番船はほぼ完成しています。扱いは。
「ブラジルでトップサイド(上部構造物)を付ければ完成する状態。坂出工場の岸壁に係船しているが、LNG(液化天然ガス)運搬船など他工事には干渉しない。2隻目はブロック建造だけ。邪魔にはならない」
―エンセアーダは2隻を含めペトロブラス向けドリルシップ計6隻を受注しています。
「5、6番船はキャンセルになった。4番船まで契約は有効だが、納期は決まっておらず、損益リスクがないことを確認しない限り工事を再開しない」
―合弁解消などブラジル事業から手を引く考えは。
「追加費用は発生しない。支援するにしてもその都度の契約となる。日本とブラジルの政府間で造船業支援の話し合いが起点で赤字だからといってやめるのは賢くない。エンセアーダの人員は当初の1000人規模から数百人に減り、固定費負担は軽く、設備投資も止めた。合弁相手のオデブレヒトによるつなぎ融資も続いている」
―神戸工場(神戸市中央区)で手がけるノルウェー向けオフショア作業船納期も1年延期しました。
「まだ設計段階。建造は16年度からだ。受注戦略には影響するが、きちんと仕上げて実績を作りたい。神戸、坂出ともに海洋事業での追加損失はないものとみている」
―船舶海洋事業における基本戦略「GOOD(ガス運搬船、海外造船所、海洋、防衛)」の見直しは。
「坂出、神戸とも2年半―3年分の手持ち工事がある。LNG船は豊富なオプション契約を抱えているが行使されず、船価も低い。半年から1年以上かかるかもしれない。ただ、何十年もLNG船で埋められるとは考えていない。付加価値が高く、量が期待できるのが海洋構造物。一方、標準商船を手がける中国の合弁2造船所は好調。第3四半期から採算の良い新造船を建造しており、持ち分法利益も相当期待できる」
【記者の目・新造船建造続く間に新戦略を】
ブラジル合弁事業の膿を出し切った。しかし油価価格の下落やブラジル汚職が続く中、船舶海洋事業のGOOD戦略は壁にぶつかっている。頼みのLNG船受注もプロジェクト遅延などで踊り場。韓国の大手造船所の商船シフトも脅威だ。当面の工事量を抱え、好採算の新造船建造が続く間に、新たな打ち手を示す必要がありそうだ。
(聞き手=鈴木真央)
三菱重工、欧向け大型客船の損失1800億円に
三菱重工業は4日、2015年10―12月期に客船事業に関連して221億円の特別損失を追加計上したと発表した。これにより長崎造船所(長崎市)で建造中の欧アイーダ・クルーズ向け大型客船2隻をめぐる損失は、1000億円と言われる受注額を大きく上回り、累計1800億円超に達した。同日会見した宮永俊一社長は「何が起こるか予断を許さず、軽々には判断できない」と追加損失の可能性を示唆した。
今回、新たに内装工事の最終仕上げの手直しや客先調整、火災影響などが生じ、1番船の納期を再延期した。1番船は月内にイタリア当局の安全確認を得る見通しで引き渡しのめどを付けたが、当初3月を予定していた2番船の納期は協議中で「16年度内に(工事が)終わると思っている」(宮永社長)と不透明感が残る。
客船事業の巨額損失の反省からCEO直轄の「事業リスク総括部」を新設。「MRJ」をはじめとする新規事業や大型受注については経営トップが主導する形で、全社検証能力を手厚くする。さらに技術監査機能を強化するためCTO直轄の「シェアードテクノロジー部門」を創設。リスクマネジメント体制を抜本的に見直す。
客船事業を預かる交通・輸送ドメイン長の鯨井洋一副社長の責任については「潜在的問題は11―12年に起きた。(プロジェクト管理の)体制刷新後は全力で対策を打ってきた。責任は会社全体で追う」(宮永社長)とし進退には触れなかった。
日刊工業新聞2016年2月5日 機械面
時代や環境が違うのに、昔と比較してどうなるのか?造船の変わらない部分と変わった部分がある。そこを理解しなければ間違いを起こして当然。
付加価値とか、技術立国とか言うのは簡単であるが、状況や環境を勘違いしていると間違いは起こる。
昔に比べれば、技術者の数が少なくなっている、経験のある人が少なくなっている、技術の継承が出来ていないところも多い、造船所の身勝手な
リストラのためにリストラされないように部下を早く育てようとしなくなっている人達がいる、いくら高学歴であっても造船の知識や経験がなければ
使い物にならない、大学で一般論しか教えていない(実際に、やりながら覚えるスタイルなので効率を考えれば無駄が多い。高い日本の人件費や大学の学費を考えると無駄のダブル又はトリプル)、造船と言っても単なる溶接ではない、船の種類やサイズによって知識や経験が必要、日本とヨーロッパではデザインやコンセプトの違いがあるが、それを理解している人達は少数、昔に比べて能力の低い人材が入るようになった(給料や将来性に関して魅力がなくなった)、外国人と同等にやり合うには英語が話せ、船の規則に精通し、英語を使う人用に開発されたソフトを使いこなす必要がある。そのような人材が集まる待遇は基本的に無理などいろいろな要因がある。さまざまな要因が複雑に絡み合っている。
三菱重工業、川崎重工業、IHIの重工3社が“船”に泣かされている。各社とも航空機事業が好調な一方、大型客船や海底油田で掘削を行うドリルシップ(資源掘削船)を建造する造船事業で特別損失を計上、業績の足を引っ張っている。日本の新造船は排ガス規制の駆け込み需要や円安を追い風に受注が好調なのに、なぜ重工3社は船に苦しめられているのか…
長崎湾に面する三菱重工長崎造船所の香焼工場(長崎市)で「洋上のホテル」と呼ばれる豪華客船が建造されている。約12万5000総トン、長さ約300メートル、幅37.6メートル、約3300人乗りで、三菱重工にとって約10年ぶりとなる大型客船の建造にあたる。同社は2011年に米カーニバル傘下の「アイーダ・クルーズ」から2隻を受注した。
三菱重工の宮永俊一社長は、2隻の豪華客船について「本当にすごい工事だ」と話す。同社はアイーダ・クルーズから度重なる設計や資材変更を求められ、建造に苦労している最中だ。すでに計1645億円の特損を計上しており、客船事業から撤退する可能性も浮上している。
昨年3月に予定されていた一番船の納入は3度も延期され、宮永社長が長崎造船所に何度も足を運び、工事の進捗状況を自分の目で確認するほど気をつかう。
その工事の難しさについて宮永社長は「1500も部屋がある点だ」と指摘する。スイートルームが多ければ、カーペットを敷くのも楽だが、1500に上る部屋数に、現場の負担は並大抵ではない。
また、ITの進化で10年前に建造した大型客船と仕様が全く異なるという。宮永社長は「勉強不足で船のスペックの読み方が不十分だった」と脇の甘さをこう認める。
だが、問題は三菱重工の技術が足りないという点だけではなさそうだ。造船業界はほかの業界と異なり、顧客の力が圧倒的に強い。「無理な要求でも応えなければ、こう発注はこないビジネスだ」(造船業界関係者)という。
このため、顧客と設計や仕様を詰めるコミュニケーション能力が極めて重要という。今回、三菱重工は「背伸びして難しい工事を受注した」との声も業界関係者の間でささやかれている。
その背景には韓国や中国勢の追い上げがある。付加価値の高い豪華客船の建造にシフトしなければ、客船事業で生き残れないという事情もあった。三菱重工にとって造船事業は「祖業」でもあり、復活を狙った新たなチャレンジだったが、それが今のところ裏目に出てしまった格好だ。
そして、災難は続き、1月11日、完成間近とみられていた1番船で火災が発生した。三菱重工は4月30日に予定されている引き渡しへの影響はないとしているが、さらに、特損が膨らむ可能性も出ている。
大型客船の受注額は1000億円程度とみられるが、三菱重工の特損の計上額はこれを大きく上回る。大型客船の市場は成長が期待されているが、桁違いの損失を出すリスクもある。今後について、宮永社長は「2隻の納入が終わってから考える」とし、“撤退”の2文字もよぎる。
一方、川崎重工とIHIはブラジルの造船事業で苦しんでいる。ブラジルでは12年に超深海の巨大油田開発が本格化し、国営石油会社ペトロブラスが開発計画を進めていたが、ドリルシップなど海洋構造物を手がける現地の造船会社が足りず、政府が日本に助けを求めてきた。
川崎重工やIHIをはじめ、三菱重工、今治造船、名村造船所なども現地に進出したが、ペトロブラスを巡る予期せぬ汚職問題が発生。現在は現地の事業が止まっており、各社とも特損の計上を強いられている。
川崎重工も14日、現地の合弁会社からの資金回収が困難となり、15年10~12月期連結で221億円の特損を計上すると発表した。16年3月期連結で最終利益が3期連続で過去最高を更新する見通しだったが、達成が難しくなった。担当役員も責任を問われ、降格が決まった。
同社の造船事業は中国で合弁会社をつくり、現地の需要を取り込み、着実に収益を上げていたが、ブラジル事業に足を引っ張られた格好だ。
IHIもすでに15年3月期連結決算でブラジルの造船所からの未回収金で290億円の特損を計上している。9月の中間決算でも、シンガポールの会社から受注した海洋の石油生産設備の設計変更などで特損を計上。同社は今年度、初めて中期経営計画の目標を達成する見通しだったが、この損失で頓挫した。
同社は02年に造船事業を分社化。現在はユニバーサル造船と合併し、「ジャパンマリンユナイテッド」として、造船事業を展開しているが、愛知工場(愛知県知多市)でドリルシップなど海洋構造物を手がけている。
生き残りを図るため、難易度の高いドリルシップの建造に注力しているが、経験不足がたたり、顧客から図面変更や製造工程の見直しを求められ、9月中間で特損計上に追い込まれた。斎藤保社長は「知見がないにもかかわらず、新分野の扱いとせず、工事を進めたのが要因」と語り、今後は運営体制を厳しくチェックし、再発防止に努める方針だ。
現在、日本の造船業は円安や排ガス規制の駆け込み需要で新造船の受注は好調で、2~3年分の受注残を確保している。だが、韓国や中国勢が力をつけており、日本勢が生き残るには技術力を高め、難易度が高い建造にチャレンジするしかない。その中で「経験を積み、大きな損失を出さない運営ができるかが重要だ」(大和証券の田井宏介チーフアナリスト)という。
三菱重工が手がける大型客船は、世界でも建造できるのは数社。ドリルシップの建造では韓国勢も苦戦しているという。壁を乗り越えれば活路が見いだせるが、リスクも大きい。3社とも経営全体の足を引っ張る造船事業をどう位置付けていくのかが改めて問われている。(黄金崎元)。
(ブルームバーグ):中国の造船業界が潮目の変化に苦しんでいる。人民元安と原材料需要減の波が押し寄せ、近い将来に閉鎖に追い込まれる造船所が増えそうな雲行きだ。
中国は世界2位の規模を持つ造船業界を抱える。だが2010年以降、140前後の造船所が廃業した。JPモルガン・チェースのアナリスト、イ・ソクジェ氏とイ・ミンソン氏は6日付のリポートで、昨年受注があった中国の造船所は69しかなく、向こう2年間で倒産する造船所はさらに増えるだろうとの見通しを示した。受注実績のある造船所は13年に147、14年は126だった。
中国船舶工業行業協会(CANSI)が昨年12月15日に発表したデータによると、業界全体の受注隻数は同年1-11月で前年同期比59%減少した。海運業界の過剰輸送能力で輸送料は下がり、顧客は船舶の発注をキャンセルしている。造船所は政府の支援を模索しているが、12月には舟山五洲船舶修造が国有企業としては10年ぶりの破綻に追い込まれた。
韓国のハナデトゥ証券でアナリストを務めるパク・ムヒョン氏は「中国造船業界で注文がキャンセルされる確率は日増しに高まっている」と指摘。「人民元安で顧客にとって船舶価格が安くなった可能性はあるが、それでも購入意欲を呼び戻すには十分ではないだろう。業界に多少の延命策を施したとしても、再生はできない」と述べた。
原題:Shipyards Vanish as China Loses Appetite for Consuming Iron Ore(抜粋)
ユン・テウ記者
国内最大の造船会社が危機のドロ沼に落ち込み、 事実上の非常経営体制に突入した中で、 長い間、地域の大黒柱になってきた中小造船会社が続々と倒産している。 一瞬にして職場を失った労働者たちと、大黒柱を失った地域の小商工人が直ちに直撃弾を受けた。 地域の大黒柱である会社がまったくなくなり、 危機を克服する機会も失った地域経済は、 自ら新しい突破口を模索すべき状況に置かれている。 政府が事実上、手をこまねいているからだ。
国内造船業の危機…受注残高の世界順位が変わる
造船産業は電子産業、自動車産業と3大主力輸出産業と言われるが、 最近では危機を迎えている。 国内造船業は2000年代後半に世界金融危機を迎え、困難を味わい続けている。 現代重工と大宇造船海洋、サムスン重工業の国内3大造船会社はもちろん、 中小の造船所も危機を避けることはできない。
危機は世界受注残高の順位で可視化される。 2008年だけでも国内造船会社は世界10位圏中に8か所が入っていた。 だが大型造船会社をはじめとする国内造船業が危機を迎え、 中国と日本の造船会社が順次成長しており、 ソンドン造船海洋とSPP造船など世界10位圏に入っていた国内の中小造船会社3か所がすべて順位外に押し出された。
中小造船会社がすべて押し出されたことで、堅固だった大型造船会社の順位も変わった。 昨年11月末、中国造船所の上海外高橋(ワイカオチャオ)が韓国大型造船会社を押し出して世界5位になった。 現代重工など国内3大造船会社と現代三湖重工業、現代尾浦造船の韓国造船会社5社は、 この10年間で1位から5位の地位を強硬に守ってきた。 だが12月29日に英国の造船・海運分析機関クラークソンが発表した資料によれば、 現代尾浦造船が6位に押し出され、中国造船会社に5位を譲った。 7位から10位はすべて中国の造船会社(2社)と日本の造船会社(2社)だ。
造船業の危機、中小造船会社直撃弾…27社から6社に減る
国内造船業種の危機は、中小造船所がまず直撃弾を受けた形だ。 国内の中小造船所は27社だったが、最近は6社に数が減るなど、連鎖倒産を避けられずにいる。 造船業種で回復不可能な「限界企業」は昨年は18.2%で、この5年間で3倍に増えた。
慶南道統営市は一時は造船所の灯り夜も暗くなかったが、最近は夜は暗い。 統営市彌勒島は一時は国内中型造船所で一杯だったが、 世界金融危機の時からソンドン造船海洋と21世紀造船、サモ造船、シナSBなどの主要造船所が続々と経営危機になり、 事実上倒産したところも多い。
最大規模のソンドン造船海洋は、2010年から債権団が管理しサムスン重工業に委託運営されている形で、 21世紀造船は2013年の破産の後、まだ工場は残っているが数年間運用されていない。 サモ造船は韓国ヤナセが買い取り韓国ヤナセ統営造船所と名前を変えた。 韓国ヤナセ統営は、政府が前受金の発給保証を拒否したものの自力で3500トン級の石油化学製品運搬船を一隻建造し、なんとか命脈を維持している。
70余年の統営シナSB、結局破産
最後に残ったシナSBは、2000年代初めに船舶受注残高基準で世界16位に上がったが、 結局昨年11月23日に昌原地方法院に破産申込書を提出し、 続いて27日に破産宣告を受けた。 シナSBは世界金融危機の余波で経営難になり、 2014年4月からは法定管理を受けている間に4回の売却を試みたが、 結局失敗した。 一時は約4000人もの労働者の職場だったシナSBには、 復職を要求して座り込みをしていた23人の労働者だけが残された。
シナSBの破産は地域で決して軽くない意味を持つ。 シナSBは1946年に設立され、1980年に市場に売り物として出されるなど、 迂余曲折を体験したが統営有志と役職員、労働者が各々資金を出して命脈を繋いだ。 従業員の持株会社としてよみがえったシナSBは、 1993年に5000万ドル輸出塔を築いたのに続き、 2009年には6億ドル輸出塔を築く快挙を成し遂げた。 だがイ・グクチョル前会長など元専任経営陣の相次ぐ腐敗に加え金融危機まで重なって、 70年の歴史のある会社が崩壊してしまったのだ。
近隣にある慶南道泗川市の造船所の事情も同じだ。 SPP造船は2010年に1兆ウォンを越える損失をこうむった後、債権団管理の下で運営された。 SPP造船は人員を半分ほど減らし、給与を削減するなどの迂余曲折を経た末に、 今年の上半期に341億ウォンの営業利益を出してタンカー8隻を新規受注したが、 結局、売却を控えている状況だ。 ウリ銀行などの債権団が前受金の発給保証を拒否したことで、新規受注は無用の物になった。
中小造船所、政府の無視の中、前途暗く
そのため慶尚南道議会と泗川市)議会も憂慮を示している。 泗川市の総人口は12万人ほどだが、SPP造船と関連社の労働者、その家族が1万3000人ほどいるからだ。 慶尚南道議会と泗川市議会は12月にそれぞれ対政府建議案を採択し、政府の中小造船所に対する構造調整に憂慮を現わした。
地域経済が危機をあじわっている中、 政府は特別な対策を出さず、むしろ再起の踏み台にするための前受金発給保証などの中小造船所の要求を無視している。 政府が12月30日に発表した造船業構造調整案は、 各会社の自救案を基礎とするSTX造船海洋支援、サムスン重工業のソンドン造船海洋経営協力、SPP造船売却などがあるだけだ。
国内4大造船会社である韓進重工業は7日、一時的な流動性危機を打開するために、主債権銀行の産業銀行など債権団に自律協約(債権団共同管理)を申請した。
韓進重工業はこの日、「景気低迷などによる一時的な流動性不足の解決として経営正常化を推進する次元で、理事会の決議を経て主債権銀行の産業銀行など債権団に自律協約を申請した」と発表した。
韓進重工業の金融業界に対する債務は昨年11月末の時点で約1兆6000億ウォンで、産業銀行(5000億ウォン)とハナ銀行(2100億ウォン)など第1金融業界に対する債務(1兆4000億ウォン)がほとんどだ。残りの2000億ウォンほどは建設共済組合など、第2金融業界に対する債務だ。韓進重工業はフィリピンのスービック造船所と釜山の影島造船所、アパートブランドの「ヘモロ」などを運営する造船・建設会社で、最近数年間の営業損失の累積で資金難を経験してきた。
産業銀行は8日までに債権団に、韓進重工業への自律協約を開始するかどうかを確認する案件を債権金融機関協議会に付議し、遅くとも15日までに自律協約を開始するかどうかを確定する方針だ。韓進重工業の自己救済計画を土台に、満期到来債権の延長などに債権団が合意するかがカギだが、韓進重工業の流動性危機が一時的であるという点から、自律協約の開始可能性に重みが加わっている。自律協約開始のためには債権団全体の同意が必要だ。
自律協約はワークアウト(企業改善作業)や法定管理(会社更生手続)よりも強度の低い構造調整手段として、主要債権銀行を中心に融資返済の猶予や追加の資金支援などの措置が行われる。
韓進重工業は7日、満期が到来する建設共済組合の債務600億ウォンの満期延長で急場をしのいだ後、8日に自律協約を申請する予定だった。建設共済組合のように第2金融業界に対する債務は、第1金融業界の債権者を対象とした自律協約を通じて満期延長や債務調整が不可能なためだ。しかし7日、自律協約申請のニュースが伝わったことからりこの日に自律協約を申請することに糸口をつかんだ。自律協約申請のニュースが知らされて、この日の韓進重工業の株価(終値基準)は前日(3775ウォン)比で22.25%(840ウォン)下がった2935ウォンを記録した。
韓進重工業は資産売却にさらに速度を加えると明らかにした。韓進重工業の関係者は、「残っている保有資産の中で売ることができるものはぜんぶ売る」と語った。
韓進重工業は最近、70万平方メートルに達する仁川北港の土地を売却した。韓進重工業側は残っている160万平方メートルの北港の土地も売却する計画だ。韓進重工業は東ソウルターミナルの建物と付属する土地、そして運営権までも売却する方針だ。仁川北港の土地と東ソウルターミナル関連資産の時価は2兆ウォンを超えるものと推定される。
韓進重工業は2~3年前から1兆9000億ウォン規模の社債を償還した。他の造船会社とは異なり社債の負債がなく、フィリピンのスービック造船所の実績が安定しているので、一時的な流動性危機だけを乗り越えればターンアラウンドが可能だという立場だ。特に「造船ビッグ3」が海洋プラント事業で巨額の損失をこうむったこととは異なり、韓進重工業はこの分野にかかわらなかったので、相対的に打撃が小さかったという点を強調した。
ソン・ギジョンKDB大宇証券研究員は、「資産売却は容易ではないが、韓進重工業が希望する価格帯での売却が行われれば、利子を負担しつつも営業で利益を出すことができるだろう」と語った。
[パク・ヨンボム記者/チョン・ソグ記者]
2011年に始まった世界的な造船産業不況で韓国大手造船企業が経営難を迎え、造船所が密集した巨済市(コジェシ)の地域経済は不況のトンネルに入っている。
1997年の国際通貨基金(IMF)危機当時も不況を知らなかった「富裕都市」(1人あたり所得約4万ドル)巨済は、新年に入って過去の栄華を取り戻すために再起の死闘をしている。
その先頭に大宇造船海洋玉浦(オクポ)造船所が立つ。「野戦司令官」イ・サンギル生産本部長(専務、55)は4カ月間、帰宅していない。生産本部所属の他の役員4人と同じく事務室にベッドを置き、会社ですべての宿泊を解決する。イ本部長は「4兆ウォン(約4000億円)以上の損失が明るみに出て多くの役員が会社を離れたが、残った役員も謝罪の気持ちで会社経営正常化まで退勤していない」と述べた。
会社はコスト削減と率先垂範レベルで社長を含む60人の役員用車両を3000cc級大型車「ジェネシス」「グレンジャー」から1000cc級軽自動車のモーニングに変えた。
職員5万人の働く雰囲気も変えた。大宇造船は商船から海洋プラントに事業を拡張し、職員が2012年の3万人から昨年は5万人へと大きく増えた。しかし会社管理システムは3万人水準にとどまっていた。したがって出退勤と昼休み、作業時間が守られていなかった。午前8時に作業が始まっても更衣室に職員が残っていたり、昼休みの前から食堂に列ができたりした。イ本部長は「一日8時間(残業除く)のうち40%が非勤務時間と把握されるほどだった」とし「工程ごとにタイムスケジュールを組み直すなど『基本秩序づくり』から始めた」と述べた。
雰囲気が変わり、職員の考え方も変わっている。「ここでなくても働けるところは多い」という態度だった職員が「ここで生き残らなければいけない」という切迫した気持ちに変わった。会社の変化した秩序に適応できなければ解雇されるという危機感も強まった。何よりも慶尚南道内の中小型造船所(10社)のうち1社が倒産し、この3カ月間で160社の協力会社のうち28社が閉鎖した影響も大きかった。
溶接服・軍手など消耗品を配給制から交換制に変え、勤倹ムードも広まった。昨年11月に会社でごみ箱に捨てられた消耗品のうちリサイクル可能な物品を社内20カ所の食堂に展示し、職員の心を動かした。年末年始の行事もなくしたり減らした。イ・ピルスン班長(50、組立3部)は「昨年、会社正常化討論会で全役職員が会社を再建しようと誓って署名した」とし「その後1万人の職員が成果給350億ウォンを集めて自社株を買うなど心を一つにして協力している」と伝えた。
大宇造船海洋の鄭聖立(チョン・ソンリプ)社長(66)は「最近公開された映画『オデッセイ』の原作を読んだが、火星で孤立した主人公(マーク・ワトニー)が地球に戻ることができるという希望を失わず生存のために死闘した結果、無事に帰還するのを見て感銘を受け、役職員にも一読を勧めた」とし「主人公のように我々も希望を捨てずに努力すれば、大株主(31.46%)である産業銀行の予想(2019年)より早い来年末ごろ経営正常化目標を達成できるはず」と覚悟を見せた。
造船所緊縮経営の影響で付近の市場・スーパーの売上高が1年間に20-25%減少し、地域民生経済が冷え込んだ巨済市も、新年に入って活路を模索している。その間、造船業好況期に相対的に観光産業発展が遅かった。巨済市は今後、観光産業の発展に集中し、造船業の不況による危機を克服するという戦略を推進中だ。
ハンファホテル&リゾート(株)の投資(1936億ウォン)を誘致し、昨年12月初めに巨済と釜山を結ぶ巨加大橋近隣の長木面農所里一帯11万2580平方メートルに「巨済海洋観光テーマパーク」を造成する事業を始めた。今年8月に国防部から譲り受ける只心島(チシムド)も開発する。2017年と2018年に巨済鶴洞ケーブルカー事業も終える予定だ。権民鎬(クォン・ミンホ)巨済市長は「造船業が不況だからといって挫折することはない。観光という新しい産業を創出し、富裕都市の名声を引き継いでいきたい」と述べた。
2016年1月2日、澎湃新聞は記事「国有造船企業に初の倒産、破産ラッシュのピークを迎える2016年造船業界」を掲載した。
浙江省海運集団は子会社にあたる五洲船舶の破産を申請した。負債総額は9億1100万元(約168億6000万円)。国有造船企業としては初の破産となった。2001年創設の五洲船舶は10万トン級以下の船舶建造を手がけ、載貨容積トン数にして年30万トンの建造能力を擁している。
問題は五洲船舶だけではない。中国造船業界に厳しい冬が訪れている。中国工業情報化部は13期5カ年計画(2016〜2020年)における世界の造船需要は年8000〜9000万トン(載貨容積トン数)と推測している。しかし中国の造船能力は8000万トンに達しており、世界中の需要すべてを受注してようやく生産能力がフル稼働になるという、深刻な生産能力過剰に直面している。
今後激しい淘汰の波が訪れ、造船企業の破産ラッシュが到来するとみられる。国有企業は軍艦の発注を受けられるなど政府の支援が見込めるが、そうした助けがない民間企業に倒産が集中する可能性が高いという。(翻訳・編集/増田聡太郎)
下記の記事で書かれている事は常識の範囲。もし、契約や見積もり担当がそれを理解できなかったのであれば、企業のコミュニケーション能力の問題。
仕事を受注する事を優先して部下の意見を聞かなかった役員達が存在するのなら、自業自得!専門家でなくとも全体的に理解できる技術者がいれば、
記事かかれたような事など想定出来たと思う。三菱重工も客船2隻で現在、約1600億円の損失を出しているので、組織が大きくなると
単純に常識で判断できない材料があるのかもしれない。
韓国の造船所が付加価値に方向転換したことが間違いだったとコメントしている人もいますが、三井造船だって過去に浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備(FPSO)の船の
改造で損失を出しました。今回は上手く行ったのでしょう。経験不足や技術の継承が行われていない等の問題があれば付加価値と言っても考えるほど簡単ではないと言うことであろう。
三井造船株式会社(社長:田中 孝雄)は、千葉事業所にて建造中でありました、三井海洋開発株式会社(社長:宮﨑 俊郎)より受注した浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備(FPSO)の船体部を引き渡し、本日、FPSO船体部は千葉事業所より出帆しました。
本FPSOは、三井海洋開発社によるトップサイド(甲板上に設置される石油・ガスの生産設備)搭載工事の後、ペトロブラス社(45%)、BGグループ(30%)、レプソル・シノペック・ブラジル社(25%)の3社によって結成されるコンソーシアムに用船される予定です。
FPSOは、海底に眠る巨大油田から取り出した原油を洋上にて処理し、貯蔵する設備です。FPSOの建造は、当社としては、2000年の引き渡し以降、本船が2基目となります。
韓国の造船大手3社である現代重工業、大宇造船海洋、サムスン重工業は昨年1-9月に合計で7兆3000億ウォン(約7525億円)もの営業赤字を出した。3社とも第4四半期(10-12月)の黒字転換は難しい状況だ。3社の2014年の営業赤字(2兆6266億ウォン)を含めると2年間で10兆ウォン前後の損失を計上することになる。
韓国造船業界が沈没直前の状態となったのは、無理なプラント受注による影響が大きい。2009年以降、商船発注が途絶した時期に集中的に受注した海洋プラントの建造が遅れ、「海洋プラントの呪い」という新語まで生まれた。
大宇造船海洋の鄭聖立(チョン・ソンニプ)社長は「適正な生産能力に比べ150%多く受注したことが足かせになった。適正生産能力は設備の量とエンジニアの数で決まるが、3社いずれも過剰受注で人材の確保ができず、人件費も大きく上昇した」と述べた。
■同じ発注元・鉱区でも異なる設計
海洋プラントの多額損失は設計や部品がプラントごとに異なる特殊性にも原因がある。外観は似ているが、同じ設計図で建造された海洋設備は一つもない。設計会社、発注元の求めに基づき、その都度異なる部品を使用するのが一般的だ。
同じ発注元が同じ鉱区に設置に設置する海洋プラントでも細部の設計、機能、規格が完全に異なる。大宇造船海洋がフランスのトタルから受注し、2012年と13年に引き渡した浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備(浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備(FPSO)の「パズフロー」「クロブ」が代表的だ。
2基はアフリカのアンゴラ西側の深海にある同一鉱区に投入され、米エンジニアリング専門企業のKBRが上部構造物(トップサイド)の設計を請け負った。しかし、2基ともサイズがやや異なり、原油の生産・貯蔵容量にも違いがある。
部品も発注元と設計会社によって千差万別だ。現代重工業が英BPに引き渡したFPSO「プルトニオ」と米エクソンモービルに引き渡したFPSO「キゾンバ」に使われたはしごや鉄製フェンスは規格が完全に異なる。プルトニオには足場の間隔24センチメートル、全長10.12メートルのはしご、キゾンバには足場の間隔30センチメートル、全長10.07メートルのはしごが設置された。作業員の転落防止用の鉄製安全フェンスの規格もプルトニオは縦横が3メートル×1.1メートルだが、キゾンバは3.3メートル×1.08メートルだ。造船業界関係者は「バルブはもちろん、ボルト、ナットまで発注元や設計会社の求めに応じ、他社の製品を使用しなければならないケースが多い。地球上に全く同じ海洋プラントは存在しないといっても間違いない」と述べた。
■海洋プラントの標準化へ協議
こうした状況は海洋プラントの建造過程の特性によるものだ。船を建造する場合、造船会社は同じ種類の船の建造を繰り返し、ノウハウを積むことで収益性を高める。すなわち、基本設計が比較的標準化されており、韓国国内で設計が可能な商船は基本的に設計図が同一で、同じ部品が使われる。このため、同じ設計図による建造を続けるほどコスト削減や建造期間の短縮が可能になる。
例えば、1万8000TEU(20フィート標準コンテナ換算)のコンテナ貨物船10隻を受注し、順次建造する場合、試行錯誤を減らすことができる。同じ船を複数建造することによる「シリーズ効果」が期待できるからだ。
しかし、一般の船舶とは異なり、海洋プラントはシリーズ効果が望めない。投入される地域は同じでも、油井による生産条件が異なるため、設計も違ってくる。生産用海洋プラントは一般に20年以上同じ油井に投入される。問題は油井が隣接していたとしても油井ごとに原油やガスに埋蔵量、成分が異なり、水深や地盤にも差があるため、それを設計に反映する必要があり。
海洋プラントが標準化されていないことによる問題点を改善するため、造船業界と石油業界は海洋プラントの国際標準化に向けた協議を最近開始した。韓国造船大手3社、世界の石油メジャー、プラント専門エンジニアリング会社は昨年10月、米国で海洋プラント標準化推進着手会議を開き、来年上半期までに海洋プラントの資材、設計、業務手続きなどの標準化を共同で推進することで一致した。
現代重工業の崔吉善(チェ・ギルソン)会長は「海洋プラントのコスト上昇と工程遅延などの問題を解消し、競争力を強化するためには標準化が必須だ。国内の機材・資材業者の参入障壁を下げることにもつながる」と指摘した。
金起弘(キム・ギホン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
造船大国として船舶受注量世界1位だった中国だが、今年に入って様子が変わってきたようだ。中国メディアの経済参考報はこのほど、「造船業の構造的な生産過剰で窮地に陥った」と題する記事を掲載し、国家戦略の一環として成長してきた中国の造船業が危機に面していると報じた。
記事はまず、海運業全体の長期低迷により世界の造船業全体が厳冬期に入ったと分析。そのため「中国の造船業は1月から10月までの受注が62.1%も下落した」と報じた。2014年12月から、中国では倒産する造船企業が出始め、15年3月からは大型の造船所も次々と倒産している。8月30日の時点で8社ある上場企業のうち4社は赤字というデータもある。
これほど厳しい状況になったのには、主に中国造船業の生産過剰が背景にあると記事では分析。中国の造船能力は受注量の2倍に達しており、「将来的に40%の造船企業が淘汰されるだろう」との業界関係者の見方を示した。
日韓と比べて中国の受注が大幅に下落したのは、韓国は高い技術力で超大型コンテナ船とタンカー船を大量受注することができ、日本は円安によってこれまで中国が多く受注してきたばら積み船の「発注を奪った」ためと主張。一方の中国は「技術力がないため造船企業が淘汰された」と分析した。中国には最近需要が増えてきたLNG船のような高い技術を要する新型省エネ船舶の製造は少なく、技術力をさほど必要とせず海運業の影響を受けやすいばら積み船の生産が主だったという。現在の造船業界は二極化が進んでいるため「17年が中国造船業の正念場だ」と今後についても厳しい見方を示した。
しかし記事では最後に、政府が製造業の今後の指針を示した「中国製造2025」で、造船業は十大重点産業の1つとなっていると紹介し、今後の中国は造船大国から造船強国へと変化していく必要があると主張。戦略技術ロードマップに沿って2020年には造船強国となり、2025年には一定の影響力を有する海洋工程装備及びハイテク船舶の製造強国になることができるか、現状を見る限りではかなり厳しい状況だ。(編集担当:村山健二)(イメージ写真提供:123RF)
韓国経済に危機警報
統営の造船会社、3社のうち2社が破産
蔚山の輸出、2011年の1000億ドルから700億ドルに急落
韓国南部の慶尚南道統営市では、2000年代後半には新亜sb、21世紀造船など中小造船会社3社の造船所で従業員数千人が夜も明かりをともして働いていた。だが新亜sbは昨年4月に最後の船を引き渡してから1年半後の今年11月に破産した。21世紀造船も13年に破産し、造船所を閉鎖した。現在、ここで建造中の船は韓国ヤナセ統営造船所(旧サムホ造船)の石油化学製品運搬船(3500トン級)が唯一だ。
造船業が破綻し、労働者が離れていったため、近隣のワンルームマンションの賃料はかつての保証金500万ウォン(現在のレートで約52万円、以下同じ)、家賃50万ウォン(約5万円)から保証金200万ウォン(約21万円)、家賃20万ウォン(約2万円)ほどに急落した。ある地元住民は「住民も造船業が持ち直すとは期待しておらず、造船所の跡地にウォーターパークのような娯楽施設ができることを望んでいる程度だ」と語った。
韓国経済の成長をけん引してきた造船、鉄鋼、石油化学などの重厚長大製造業が「成長の壁」にぶち当たり、各地で危機のシグナルがとらえられている。韓国最大企業のサムスン電子も今年の売上高が200兆ウォン(約20兆7000億円)を下回り、1990年以来25年ぶりに2年連続の減少を記録すると見込まれている。気位が高かったアウトドアメーカーやデパートが70-80%オフの破格セールや出張セールに乗り出すほど、内需不振も深刻だ。サムスン電子の幹部は「問題は来年以降の見通しがさらに暗いことだ」と語る。
■輸出製造業の不況で揺らぐ地域経済
「急売買、テギョンネクスビルマンション、79平方メートル、2億3900万ウォン(約2470万円)」
南東部・蔚山市東区田下洞一帯の不動産屋には、「急売」を知らせるチラシがびっしりと貼られている。現代重工業の本社があるこの地域は「社宅村」と呼ばれるほど同社の従業員が多いエリアだった。造船業の活況で富裕層エリアとして知られるようになったが、1年ほど前から始まった造船不況の直撃を受けた。地元のある不動産会社の経営者は「2月に売り出された物件がまだたくさん残っている」と言い、買いたい人が殺到していた2-3年前が夢のように感じられると肩を落とした。2月に1200人余りが同社を早期退職し、売買がほぼ途絶えたという。
蔚山・統営=チョ・ジェヒ記者
栄枯盛衰は世の習いと言う事か?韓国の造船業がここまで来るとは!
まあ、新聞の記事にはなっていないが、中国の造船業も受注ではなく利益で考えると良くないようだ!
3日、慶尚南道巨済市(コジェシ)玉浦(オクポ)1洞の食堂街。昼休みになったが、食堂を訪れる人はあまりいなかった。6カ月前まで大宇造船海洋の職員で混み合っていたところだ。しかし大宇造船が4-6月期に3兆399億ウォン(約3170億円)、7-9月期に1兆2171億ウォンの損失を出し、風景が変わった。
ここにある刺し身店は最近、昼の営業をしていない。昼間の客が6カ月間に比べて半分以上減り、利益が出ないからだ。やむを得ず晩だけ営業することにした。店の関係者は「ここは大宇造船の職員を迎えて商売をするところだが、最近は公務員の客がいなければ店を閉める状況」と話した。近くの韓定食店と焼き肉店はすでに閉店した。
巨済が揺れている。「通貨危機が何かも分からなかった」という巨済だった。巨済に造船所が建設された1970年代(サムスン重工業1977年竣工、大宇造船1981年竣工)以来、初めての不況という声も出ている。サムスン重工業と大宇造船が大規模な赤字を出した影響だ。両社は海洋プラント事業で兆ウォン単位の損失を出し、さらに原油安のため受注が減っている。
巨済市内の店は6月末の1万3727店から10月末には1万2116店へと4カ月間に11.7%(1611店)減った。サムスン重工業と大宇造船の周辺が大きな打撃を受けた。サムスン重工業近隣の古縣洞(コヒョンドン)と長坪洞(チャンピョンドン)の店はそれぞれ432店、219店減少した。地域別にみると1、2位だ。大宇造船近隣の玉浦1洞と玉浦2洞でもそれぞれ172店、156店が消えた。商売にならないからだ。
玉浦市場のウォン・イルシク商店繁栄会長は「昨年のセウォル号惨事と今年のMERS(中東呼吸器症候群)で雰囲気が沈み始め、大宇造船とサムスン重工業の大規模赤字の話が出ると完全に冷え込んだ」と説明した。
巨済市内のマートの売り上げも減った。ある大型マートの7-9月期の売上高は前年同期比7.4%減少した。MERSが広まった4-6月期(7.2%減少)より減少幅が大きかった。マート関係者は「造船所の大型赤字がMERSより怖い」と語った。
不動産景気も冷え込んでいる。巨済市は過去10年間、1平方メートルあたり平均公示地価が全国で最も大きく上がった地域だ。2006年から今年まで190%上昇した。地価はもちろんマンションの価格も上がった。昨年までは新規分譲マンションに数千万ウォンのプレミアムが付いて取引された。今はそうでない。マンションの価格も家賃も下落している。
不動産関係者は「2億-2億5000万ウォンほどの中型マンション(専用面積62.8-96.9平方メートル)価格が6カ月間に2000万-5000万ウォンほど落ちた」とし「1年間ほど巨済で仕事をする短期人材が好むワンルームマンションの家賃も50万ウォンから35万ウォン水準に下落した」と説明した。先月末を基準に分譲中の9カ所のマンションの一般分譲4438世帯のうち32%の1440世帯がまだ売れていない。「分譲開始と同時にプレミアムがついて売れた昨年と比較すると、隔世の感がある」と不動産関係者は話した。
韓国船級協会がミャンマー船籍船の検査を代行して行えるようになったそうだ。 韓国船級協会は韓国客船 Sewol沈没事故以来、厳しい状態が続いているようだから、活発に営業活動を していると言う事なのか?
Author: Ei Thandar Tun & Zin Thu Tun
Ship classification society Korean Register (KR) has been officially permitted to maintain and inspect local cargo ships, said an official from the Department of Marine Administration.
“No foreign companies will work with us if we can’t guarantee the safety of their cargo. When KR takes control of the maintenance and inspection of the ships, they will be able to give guarantee to clients,” said U Ye Myint, director of the Department, which is under the Ministry of Transport.
Every local cargo liners will have to be checked by KR once a year. The KR will recommend the maintenance needs of the cargo liners and the ship owners have to carry out the repairs and maintenance.
“The owners of the ships have to repair and maintain their ships when we ask them to do so. If they fail to act according to our recommendation, we will not give them compensation when the ships or cargo get damaged,” said Capt Yeong Chul Park, regional director of KR.
The Department of Marine Administration has already permitted four companies to do maintenance and safety inspections of local ships. KR is the latest inclusion.
Other four companies in the list are Lloyds, BV Company, NK Company and APS.
There are only 14 seaworthy Myanmar-owned cargo liners. All 14 ships are owned by Myanmar Five Star Shipping Corporation.
韓国の造船所は日本の造船所以上に建造設備に投資して建造納期が短いから厳しいだろう。アイドリング状態による赤字は多きはず。
オフショア関係のキャンセルが多発しているようだ。実際は、船台のスケジュールが詰まっていたから無理して取らなかったら、キャンセルで
受注しなければならない状態になったのかもしれない。個人的な推測。
人から聞いた話だが昔ほど中国建造の船は安くないらしい。中国との価格競争の影響なのか、個人的には韓国建造船の作りが荒くなったように思える。
少数であるが韓国で建造したのに思ったほど良くなかったと言っている人もいた。
中国の造船所も厳しい状態が続いている。
受注隻数が多いから、儲かっているかは別次元。三菱重工の客船問題を考えれば理解できるであろう。2隻で約1000億円の受注で、既に1300億円の赤字。
破格の値段を提示すれば跳び付く船主はいるだろう。ヨーロッパの船主は中国に発注したが、納期に問題があるので、
他の中国造船所に変更したケースもある。建造できる能力や技術がないのに受注するような造船所が存在するのが中国。数年は様子を見るしかない。
「韓国の造船・海運分析機関によると、韓国の先月の船舶受注はわずか3隻に終わった。標準貨物船換算トン数(CGT)基準では約8万CGTで、金融危機の影響で受注が減った09年9月以来の最低数値を記録した。
一方、中国の先月の受注は60隻、146万CGTで、世界の発注量の80%を占めた。日本は5万CGTだった。」
2015年12月3日、韓国・ニュース1によると、韓国の造船業界が、受注件数で世界一の座を中国に明け渡した。今年7~9月に中国に抜かれた後、10月には1位を奪還したものの11月は再び順位が逆転した。
韓国の造船・海運分析機関によると、韓国の先月の船舶受注はわずか3隻に終わった。標準貨物船換算トン数(CGT)基準では約8万CGTで、金融危機の影響で受注が減った09年9月以来の最低数値を記録した。一方、中国の先月の受注は60隻、146万CGTで、世界の発注量の80%を占めた。日本は5万CGTだった。
今年11月までの累計受注実績では、韓国が992万CGTで世界トップを維持、次いで中国(882万CGT)、日本(677万CGT)の順となっている。
この報道に、韓国のネットユーザーは次のようなコメントを寄せた。
「受注量にこだわっていたら赤字が増えるばかりだよ。価格競争で中国に勝てるわけがない」
「造船も鉄鋼も家電も海外建設も駄目。これから20年は社会人生活をしないといけないのに、国の将来は暗いなあ」
「造船も海運も下降か。せいぜい残るのは現代・起亜自動車とサムスン電子ってとこだね」
「中国に押される代表的な産業が造船業だ。その次はLCD(液晶ディスプレー)に半導体、スマートフォンなどなど。中国製は同じような品質で値段が半額なんだから、誰も韓国製を買わないよ」
「日米やドイツ、フランス、英国は、理由もなく造船をやめたわけじゃない。造船は人件費がかかり過ぎるんだ」
「造船がもう駄目だって、もうみんな分かってるよ」
「自然な流れ」
「皆さん、大企業を心配する前に、自分たちの将来を心配しよう」
「中国は周辺国の競争力を一度に制圧している。まるでブラックホールのように、すべてをのみ込みそうだ」(翻訳・編集/吉金)
LNGは余剰状態になりつつあるのか?
大宇、ヤマル向けLNG船は船殻ブロック溶接部にクラックで4ヶ月納期が遅れるようだ。コスト削減で想定外の損失が出てきる造船所があるようだ。
EU・日本"大宇造船の資金支援WTO違反"
OECD委員会で公式問題提起、異議継続時は追加支援しにくいかも
http://news1.kr/articles/?2493055
イメージ 1[ソウルミーナ]欧州連合(EU)と日本が産業銀行などの国策銀行の大宇(テウ)造船海洋資金支援対策について、公式的に抗議したものと把握された。
政府による特定企業の支援を厳しく禁止する世界貿易機関(WTO)規定を違反したというもので、過去、ハイニックス半導体に対する産業銀行の支援に米国政府が異議を提起したのと同じ幹だ。
韓国政府当局と産業銀行は政府補助金ではないという趣旨の報告書を作って対応する計画だが、実際の提訴につながる場合、膨大な訴訟の費用を含めた時間と資源が消耗するだけに状況を注視している。
19日、造船業界や産業通商資源部・金融委員会など関係当局によると、今月初めにフランス・パリで開かれた経済協力開発機構(OECD)造船の専門委員会(WP6)でドイツを中心としたEUと日本が先月末、産銀の大宇造船支援を問題視したものと確認された。
WTO規定には世界企業間の公正な競争のために、国が特定企業に政府補助金を支援する行為が制限されている。
会議に出席したある関係者は"EUと日本は事実上、韓国政府が大宇造船海洋を支援したというふうに追い込んだ"と説明した。韓国側は今回の支援が大宇造船の債権団の産業銀行など国策銀行の主導で行われた点を挙げ、政府補助金ではないと反ばくした。
OECD WP6はこの案件を来年6月に開かれる次の会議の時にもっと取り扱うことにし、産業銀行と輸出入銀行などは、韓国側の召命を盛り込んだ報告書を作る計画だ。 国内造船業界と政府などはWTO規定を違反していないだけに、実際の提訴に至っても韓国側が敗訴する確率は低いものと期待している。
今回の問題提起も世界の造船業界を主導する韓国と新興強者に浮上した中国を牽制しようとするレベルの行動と分析している。 この2000年代初頭もこれと似たような内容の造船紛争を行って勝利した経験があるということだ。 しかし、実際に提訴された場合、数十億ウォン台の訴訟費用と各機関の人員を投入、消耗戦が予想され、国内造船業界にも否定的な影響を与えるものと懸念される。
特に、ハイニックス支援当時、米国政府の強力な抗議で支援に速度調節が必要だっただけに、競争国の異議提起が続く場合、追加支援が難しいとなる可能性もある。
欧州連合(EU)と日本が産業銀行などの国策銀行の大宇(テウ)造船海洋の資金支援を置いて世界貿易機関(WTO)規定違反だと問題提起したことに対して、政府はWTO提訴する可能性が低いと見ている。
19日、産業通商資源部、金融委員会などによると、今月初めにフランス・パリで開かれた経済協力開発機構(OECD)造船の専門委員会(WP6)はEUと日本などの提案で産業銀行の大宇造船支援に対するWTO規定違反如何について論議した。
産業部の関係者は"産業銀行が大宇造船の株主として参加した時から提起された部分"とし、"WTO提訴する可能性が低いと見ている"と話した。
EUと日本が指摘したのは先月末、産銀と輸出入銀行などの国策銀行で構成された債権団が大宇造船の流動性危機の解消のために4兆2000億ウォンを支援することにした部分だ。
WTOは企業間の公正な競争のために、国が特定企業に政府補助金を支援する行為を制限している。 もし規定を破った場合、WTO提訴を通じて救済を受けることができる。
政府側は債権団の大宇造船の支援が政府補助金ではないと反ばくした。 金融委の関係者は"大株主が商業的判断によって支援したこと"とし、"政府が(債権団の大宇造船支援を)決定したのではない"と話した。
政府はこのような内容を盛り込んだ報告書を作成し、次期会議を通じて適切かどうかを伝える計画だ。 金融委の関係者は"次回の会合の時まで検討した後、問題があれば、次の会議である6ヵ月後に説明することにした"と明らかにした。
(翻訳:みそっち)
日韓ビジネスコンサルタント 劉明鎬(在日経歴20年)
韓国の造船業界は、建造量では世界トップを争うほど成長し、韓国の輸出に大きく貢献してきた業界である。しかし、近年になって、その造船業界に暗雲が立ち込めている。
その原因としては、原油価格の下落、造船・海洋プラントの受注減少、競争力の低下、収益性の悪化などが上げられ、韓国造船業界はまさに史上最悪の危機に直面している。それに、中国企業の低価格攻勢と、日本の技術力と円安を武器にした造船企業の競争力回復も大きな脅威になっている。上記のようにいろいろな要因が重なって韓国造船業界は苦戦を強いられているが、特に造船業界の大手3社を苦しめているのは、大手3社が受注した海洋プラント(原油などを掘削・生産する装置)である。海洋プラントが足を引っ張る形で造船3社は、第2四半期に次いで第3四半期も巨額損失を出し、業界が騒然としているし、今の状況を改善できるこれといった方策もないので、業界では懸念している。
世界で一番建造能力を持っている大宇造船海洋は、このような海洋プラントの損失を隠すために2兆ウォン近く粉飾決算を行なって業界を騒がせたのは数カ月前である。大宇造船海洋だけでなく、他の造船会社も巨額損失が明るみにでて、造船業界に対する不安は増幅している。
韓国造船業界に今何が起こっているのか、海洋プラントはなぜ造船業界の足を引っ張っているのかを今回は追ってみよう。
韓国の造船大手3社は近年それぞれ、海洋プラントや掘削船を集中的に受注してきた。しかし、激しい競争のなかで受注を確実にするため、低価格で受注を敢行した。低価格だけでも損失が発生するのに、技術不足による工期の遅れなども重なって損失が膨らんだ。弱り目に祟り目で、最近の原油価格の低下で石油メジャーは海洋プラントの契約キャンセルを続発させ、造船会社の収益に大打撃を与えている。大手3社は低価格受注が影響して、今年の第2四半期にもそれぞれ営業赤字を計上し、営業赤字の合計金額は何と4兆7,509億ウォンに達していた。現代重工業は第2四半期に営業損失を計上していて、その金額は1,710億ウォンであったし、大宇造船海洋も第2四半期の営業損失を3兆318億ウォン出し、サムスン重工業も創業以来最大となる1兆5,481億ウォンの営業損失を計上した。それだけでなく、大手3社は第3四半期にも大幅赤字を計上した。大手3社のなかで唯一第3四半期に黒字をキープしていたサムスン重工業は、海洋プラントがキャンセルされ、最終的に赤字に転落する結果となった。
韓国の造船業界は、2017年まで建造して引き渡すことになっている海洋プラントの受注量は75兆ウォンである。しかし、このまま原油価格の低迷が続けば、グローバル石油メジャーは、石油開発を先送りする可能性も十分あるため、海洋ブラントの受注案件は今後韓国造船会社にとっては時限爆弾になりかねない。
韓国の金融監督院によると、大手3社の第3四半期の営業損失合計は2兆1,247億ウォンであるということだ。サムスン重工業は10月には第3四半期の営業利益を846億ウォンであると開示した。しかし業績発表3にち後に米国の掘削会社であるPacific Drilling社からドリルシップの契約を一方的にキャンセルされてしまった。
これにより、サムスン重工業はこの損失を第3四半期の業績に反映し、100億ウォンの赤字になったことを修正開示した。
現代重工業もノルウェーのフレッド・オルソン社からのドリルシップのキャンセルがあり、それを反映し、第3四半期の営業損失を6,784億ウォンから8,976億ウォンに修正した。
(つづく)
日韓ビジネスコンサルタント 劉明鎬(在日経歴20年)
現在造船3社が保有している海洋プロジェクトの受注規模は662億ドル(約75兆ウォン)である。受注案件のなかで海洋プラントが占める各社の割合は現代重工業が45%で(243億ドル)、サムスン重工業67%で(220億ドル)、大宇造船海洋は46%(199億ドル)である。
受注には成功しているものの、問題は原油価格の低迷である。原油価格が60ドルを超えないと、掘削をしても採算性がないようだ。ところが、原油価格は現在40ドル台を推移していて、今後も原油価格が上昇する要因はすくない。それに、今後米国の金利引き上げが実施されると、資金調達コストが上昇し、石油採掘が減っていく確率が高くなる。なお、イランの原油が市場に供給されることになったら、原油は市場で供給過剰になる公算も高い。
このような見通しに立つと、現在のキャンセルだけでなく、今後も海洋プラントはキャンセルされるかもしれないし、計画が先送りされる可能性も十分ある。
このような状況は、現時点ですでに発生しつつある。サムスン重工業は、今年の8月から12月に引き渡すことになっていた掘削装置を2017年に延期された。大宇造船海洋が受注したトランスオーシャン社の案件も、引渡し時期が来年10月から2017日年10月に延期された。今受注した案件の引渡し時期は2017年に集中しているが、今のような状況では引渡し時期が守られるという保障はどこにもない。即ち、2017年まで造船各社の業績は非常に不透明であるといわざるを得ない。
さらに納品の先送りの問題だけでなく、国内造船会社にとって設計能力の不足も別の問題として指摘されている。設計能力もろくに備わっていないのに受注をして、工期の遅れなども発生しているようだ。工期の遅れは追加費用の発生またはペナルティを発生させ、損失額を膨らませているのが現状である。
このような状況なので、造船業界は2017年まで売上の減少が続くという見通しが大半を占めている。受注が増加してこそ将来の売上が増えていくが、受注額は現在売上高を大幅に下回っている。来年も船舶の発注が減少する可能性が高い。最近海運の世界最大手であるデンマークのマスク社は大宇造船会社と結んだオプション契約をキャンセルすると発表した。大宇造船海洋から11隻の大型コンテナ船を契約する際に、追加で6隻のコンテナ船の発注できるオプション契約をマスク社は締結しているが、それをキャンセルしたわけだ。来年に導入される環境規制に備えるために今年は駆け込み需要があっただけに、来年は需要の落ち込みも予想されると専門家は指摘する。韓国の造船会社は輸出に貢献をする存在から国民の血税を吸い込む存在に変わってしまっている。中国は最近韓国とは対照的に海洋プラントでも奮闘している。数ヶ月前までは月単位で受注世界1位に返り咲いて喜んでいた韓国の造船業界であるが、半年前から風向きが変わっている。これからは陸地よりも海洋が大事になる時代になるし、造船産業は鉄鋼事業など関連産業との波及効果も大きいので、造船産業の凋落を放置してはならない。海洋プラントの設計能力の向上、事業戦略の再構築、リストラなどを通じた構造調整をしないと、韓国の造船業界に未来はないかもしれない。
(了)
造船業界のリーダー、三菱重工の失敗
日本の造船業で「悲願」ともされた、豪華客船の建造。その灯が消えてしまうかもしれません。
来年にも4隻体制に 導入進む日本の空母、その現状と課題
三菱重工・長崎造船所が現在、ドイツの豪華客船建造において、当初予定の納期を9か月間引き延ばさざるを得なくなっています。それだけでなく、受注船価の165%増しにあたる1646億円もの損失発生が確定。これは造船の常識からすれば、けた外れの損失です。
さらに工程の再遅れも起きていると見られ、「このままでは今年12月の新しい納期も守れるかどうか」という綱渡りの操業が続いています。
業界内からも「三菱さんの、次のプロジェクトへの受注取り組みは実際上、無理だろう」という見方さえ出ています。韓国・中国の追い上げのなかで、付加価値の高い客船建造にシフトしていこうとした造船業界のリーダー、三菱重工の失敗は、日本の造船業にボディブローのように効いてくるのかもしれません。
日本で豪華客船を建造できるのは事実上、三菱のみ
三菱重工・長崎造船所の香焼工場(長崎市)。日本最大の規模を誇るこの造船所では現在、ドイツのクルーズ会社アイーダ・クルーズ向けの豪華客船「アイーダ・プリマ(12万4500総トン、3300人乗り)」を建造中です。これは三菱にとって、創業以来101隻目という記念すべき客船となります。
豪華客船は、部品・機器類が1200万点に達し、建造には高い“実力”が必要。これまで三菱重工はその“実力”を持っており、新時代の豪華客船建造を再開した1989(平成元)年以降でも、国内外から6隻を受注し建造。この間、欧州の造船所以外で、豪華客船の新造を手掛けたのは同社だけです。現在の日本で豪華客船を建造できるのは、事実上同社のみといえます。
三菱重工は、2004(平成16)年に就航させた「ダイヤモンド・プリンセス(11万総トン)」の建造中に火災事故を発生させた苦い経験もあり、一時、客船の新規受注を中断します。その後、工程管理の強化や新技術の導入、設備投資などを行い、万全の体制を組んで、アイーダ・クルーズから2隻を受注。2013年6月に第1船の「アイーダ・プリマ」を起工し、今年3月の竣工を目指していました。
しかし三菱重工は船主から大幅な設計変更を求められ、やり直しなどで大混乱に陥りました。当初の納期を過ぎた今年2015年5月8日には、第1船の納期を半年遅らせ、今年9月とすることで船主と合意。合計1336億円の損失を引き当てると公表しています。
その後も三菱重工は、並行して建造中の2隻目とあわせて、現場に工員を総動員して建造を進めたものの、1隻目の納期を今年12月まで再延期。さらに309億5300万円の追加損失が出ることが明らかになりました。
さらに第2船の引き渡し時期は公表されておらず、「合理的な損失の引き当ては完了した」(10月30日、三菱重工)としているものの、追加損失もあり得るという状態が続いています。
なぜ、三菱重工はこのような事態に追い込まれているのでしょうか。
同社では理由として、公式に「プロトタイプの建造」という船主の要求に応えられなかったことを挙げています。つまり、船主が期待した新船型の開発に応じ切れなかったということですが、設計・製造を含めた三菱重工の“現場力”の劣化を指摘する声は、社内外から出ています。
同社は今後、一種のリストラ策として、客船部門を「エンジニアリング事業」に組み込む方針です。しかし「エンジニアリング事業」の具体的な内容は明らかにされておらず、同業の造船会社も「受注リスクを負わず、製造など担う中堅の造船所や海外の造船所に協力するといったイメージかもしれないが、(三菱さんでさえ上手くいかなかった大きなリスクがある)客船建造に取り組む造船会社はあるのだろうか」と話します。
いずれにしても、このドイツ船には3隻目の建造計画があったほか、日本のクルーズ会社の客船も代替建造期に差し掛かっています。日本で唯一、豪華客船に取り組んできた三菱重工について、客船建造の継続を期待する声がないわけではありません。
当面は、今年12月に引き渡しが迫るアイーダ・クルーズの第1船と、来春に竣工予定の第2船を無事に建造することが課題です。しかしこのままでは、これらドイツ船が日本の造船業が手掛けた最後の豪華客船になる可能性もあります。
若勢敏美
韓進海運と現代商船の強制合併説
政府「未確認情報による混乱憂慮
構造調整は債権団と企業による自律協議」
部署間の異見が混乱深める要因にも
政府、業界状況展望報告書作成後
構造調整ガイドラインを活用させる
海運業の構造調整に関連して、韓進(ハンジン)海運と現代商船の強制合併説などの噂がマスコミで相次いで報道され市場が混乱すると、政府が慌てて鎮火に乗り出した。しかし産業構造改編を念頭に置き発足した構造調整汎政府協議体内ですら部署間の意見が分かれ、政府主導の構造調整に対する批判も出され、事態が政府の思惑通り鎮まることはなさそうだ。
キム・ヨンボム金融委員会事務局長(汎政府協議体実務作業班長)は10日に緊急ブリーフィングを開き、個別企業の構造調整方案と関連した“推測性”報道の自制を求めた。前日、現代商船と韓進海運の強制合併説について金融委と海洋水産部が説明資料を出して公式に否定したのに続き、直接状況の説明に出た。
キム事務局長は「個別企業の構造調整に関連した未確認の報道が相次いで市場に大きな混乱を招き、個別企業や債権団、投資家、協力業者などすべての利害関係者に損失を与えかねない」とマスコミに協力を求めた。キム事務局長は「企業の構造調整で、汎政府協議体は産業別主務部署の産業政策的判断等を通して構造調整の大きな方向を示すだけ」とし、「個別の企業の構造調整は債権団と企業の自律的な協議の下で進められる」と強調した。
先月13日に発足した構造調整汎政府協議体は金融委員長が主催し、産業通商資源部、海洋水産部、金融監督院、産業銀行などの次官および副機関長級が参加して基幹産業の競争力強化および構造調整の方向を議論している。同協議体は近い将来、海運をはじめ造船、建設、鉄鋼、石油化学など脆弱な業種に対する産業政策的判断を示す業界状況展望報告書を作成する計画だ。同協議体は現在、大企業信用評価を進行中の債権銀行が関連業種の企業を評価する際、業界状況展望報告書をガイドラインの役割にさせる方針だ。
金融委では韓進海運と現代商船の合併推進説をハプニングとみなす雰囲気が漂う。イ・ミョンスン金融委構造改善政策官は「誰が見つけてきたか知らないが、かなり前にアイディアの次元でそんな話があったようで、韓進海運が断ったことで終わったことなのに、それが遅れてマスコミに報道されたようだ」と語り、「汎政府協議体発足後は合併関連の話はまったく出ていない」と説明した。
だが協議体内での海運業構造調整をめぐる異見が大きくなり、合併説などの混乱が生じているとの指摘もある。数年間、現代グループと財務構造改善の約定を結び構造調整を進めている産業銀行や金融当局は、買収・合併方案まで考慮していたことが分かった。しかし主務部署の海洋水産部は「2大船会社は必要」として構造調整より海運業支援に重きを置いている。海洋水産部関係者は「金融委とは意見が違うこともある」とし「まずは現代グループが産業銀行に提出する再建計画を見て、関係部署と現代商船の問題を協議する」と話した。
現代商船と海運が支配株主の経営権防御のための不法・不当行為を日常的に行って業績悪化が深まり、構造調整に支障をきたしていたのを傍観してきた金融当局の対応の遅れにも批判が起きている。経済改革連帯はこの日、論評で「大株主に押され構造調整を遅延させてきた政府が、今になって幕の裏から介入するやり方で処理するのは問題解決をより困難にさせるだけ」とし「金融当局は該当企業の不良原因の把握および責任追及、特に不法行為に対する厳重な制裁など、本来の任務から始めなければならない」と指摘した。
キム・スホン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
韓国語原文入力:2015-11-10 20:02
http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/716856.html訳Y.B
Singapore’s Pioneer Marine Inc., owner and operator of drybulk handysizes, has terminated three newbuilding contracts at Chinese Yangzhou Guoyu Shipyard within the company’s efforts to cut costs in a depressed dry bulk market.
The contracts termination will be at no cost to the company, Pioneer said.
Pioneer added that the delivery schedule of its eight newbuildings has been delayed spreading over the following two years. Namely, five vessels are now scheduled to deliver before the end of 2016 and the remaining three vessels to be delivered in 2017
“Our newbuilding program continues to represent a strategic partnership between Pioneer and Yangzhou Guoyu Shipyard. We are grateful for their support through the current unprecedented downturn in the dry bulk market. We are being proactive in creating a long runway for the company and the reduction in our capital expenditure commitments strengthens our balance sheet significantly,” said the company’s CEO, Pankaj Khanna.
According to Khanna, the cancellation frees up USD 34 million of equity commitments and the delay in deliveries pushes out the capex over an extended period.
“We have now delayed our newbuilding deliveries by a total of 96 months and also proactively raised USD 25 million of equity in August,” he added.
Pioneer Marine owns thirteen Handysize and one Handymax drybulk carriers with an additional 8 Handysize newbuildings on order.
LNGは余剰状態になりつつあるのか?
大宇、ヤマル向けLNG船は船殻ブロック溶接部にクラックで4ヶ月納期が遅れるようだ。コスト削減で想定外の損失が出てきる造船所があるようだ。
Xiaolin Zeng
Malaysian carrier MISC has laid up three LNG carriers as its major shareholder, national oil company PETRONAS, was affected by the drop in gas prices.
During a briefing with analysts after announcing a net profit of USD119.4 million for 3Q15, up 19% year on year (y/y), MISC revealed the idled vessels. Higher earnings for MISC's oil and chemical tanker units were offset by lower earnings by its LNG sector.
Two Aman-class LNG vessels, Aman Bintulu and Aman Hakata, have been laid up for several months. UOB Kay Hian Securities analyst Kong Ho Meng said, "The original contract is still ongoing with the remainder tenure to span up until 2020, but we understand that the end-client had recently decided that it does not require the vessels to continue operations. The outlook of these vessels is still unknown."
Aman Hakata is chartered to PETRONAS unit Malaysia LNG to deliver LNG from the oil company's Sarawak fields to Japan's Sendai port.
Vessel-tracking data from IHS Maritime & Trade's Market Intelligence Network shows 1998-built Aman Hakata has been idled in Labuan since 18 July while 1993-built Aman Bintulu has been moored in Labuan since 13 November 2014. The latter was chartered to Malaysia LNG to deliver LNG from PETRONAS' Sarawak fields to Saibu Gas Co's Fukuoka terminal.
The third vessel, 2006-built Seri Anggun, has recently come off a charter contract to BG Group. No contracts have been secured for Seri Anggun yet and it has been anchored in Miri Anchorage, Sarawak, since 14 October.
MISC's 3Q15 LNG earnings fell 38% y/y, as three lucrative LNG shipping contracts expired in September 2014, February 2015, and August 2015. At least two more ships chartered on shorter terms were also temporarily off-hire during 2015.
Separately, South Korean shipbuilder Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering told IHS Fairplay that all 15 ships it is building for the Yamal LNG project should be profitable, following reports that delivery of the first ship would be delayed by four months to October 2016 due to welding issues.
DSME would not comment on the problem but said that while it expects losses from the first ship it would deliver to Sovcomflot, it expects an overall profit when all the ships are delivered to the Russian company, Mitsui OSK Lines, and Teekay.
KR (韓国船級協会)はセウォル(Sewol)号の沈没事故で信頼を失った。韓国政府(the Ministry of Oceans and Fisheries)は検査機関をKR (韓国船級協会)だけでなく、LR(ロイド船級協会)、
DNV・GL(ノルウェー・ドイツ船級協会)、BV(フランス船級協会)を追加の検査機関として候補に挙げているようだ。
KR (韓国船級協会)と自業自得と言えばそうかもしれない。技術的や経験の問題よりも、組織の自浄能力の欠如、そして韓国社会に根付いているネガティブな社会構造が
問題であると思う。日本と同じで、しがらみのないよそ者にしか改善できない問題だと思う。
Xiaolin Zeng
By 31 October, the Ministry of Oceans and Fisheries (MoF) will nominate either Lloyd’s Register, DNV GL, or Bureau Veritas to join KR in classifying South Korean-owned ships.
Since 3 December 1975, when KR was designated as a government agency, South Korea’s Ship Safety Act has stipulated that only KR was authorised to carry out vessel inspections, although the Korea Ship Safety Technology Authority was authorised to classify and survey Korean ships.
KR is a member of the International Association of Classification Societies, so South Korean companies running oceangoing vessels have gravitated towards it, leaving the authority to confine its focus to ships plying domestic waters.
While the agency virtually monopolised domestic classification, it also succeeded in getting foreign shipowners into its fold. Its sales since 1975 averaged KRW126 billion/year (USD110.8 million), with registered tonnage hitting 63 million gt, giving it a global market share of 5.2%.
KR, which classified Sewol, came under fire after the ferry capsized on 16 April 2014, leaving 304 of 476 passengers and crew dead or missing. Many victims were Danwon High School students who had been on an excursion to Jeju Island.
(巨済=連合ニュース)慶尚南道巨済にある大宇造船海洋のオクポ造船所で火事が発生し、作業中の労働者6人が有毒ガスを吸い込んで病院に運ばれた。
10日午前10時40分に大宇造船の第3ドックで建造中の液化天然ガス(LNG)運搬船タンク内部で火災が起こった。
消防当局は巨済消防署所属の消防車10台あまりなどを現場に派遣して1時間ぶりに火災を鎮圧した。
同日の火災で、内部で作業中の労働者6人が有毒ガスを吸い込み、近くの大宇病院に運ばれ治療を受けている。
その内1~2人は重傷であることが分かった。




【巨済聯合ニュース】10日午前10時40分ごろ、韓国南部、慶尚南道巨済市の大宇造船海洋の玉浦造船所で火災があり、従業員1人が死亡、7人が負傷した。負傷者のうち1人が重体、3人は重傷という。
火災は建造中の液化石油ガス(LPG)運搬船のタンク内で発生。火は約1時間後に消し止められた。
消防当局は、タンク内で溶接作業中に飛び散った火花が引火性の高い物質に燃え移ったとみて、詳しい出火原因を調べている。
同造船所では8月にも同様の火災が発生し、9人が死傷した。
[釜山 22日 ロイター] - 石炭や鉄鉱石、穀物など乾貨物(ドライカーゴ)を運ぶばら積み船の運賃は、商品需要の冷え込みや貨物船の大型化を背景に引き続き圧迫される見通しで、業界再編への圧力が一段と強まることが予想されている。
JPモルガンの韓国責任者、ソクジェ・リー氏は運賃の低迷が何年も続く可能性があると指摘し、特に中国造船業界にとって脅威になると述べた。中国では労働コストがこの10年で3倍に上昇し、今や韓国や日本よりも高水準となっているためだ。
リー氏は「中国では向こう2年間に大規模な業界再編が起きるだろう」との見方を示した。
業界専門家の間では、中国遠洋運輸集団(COSCO)[COSCO.UL] と中国海運集団[CNSHI.UL] の国有海運大手2社の合併が発表されるとの観測がある。COSCOは中国遠洋(チャイナCOSCO)(601919.SS) 、中国海運集団は中海発展(600026.SS)をそれぞれ傘下に持つ。これらを含む両社の傘下企業の株式は合併の可能性が浮上した2カ月前から売買停止となっている。
商品コンサルタント会社コモドア・リサーチのジェフリー・ランズバーグ氏はロイターに対し、中国の景気減速や原材料需要低下の影響に加え、世界の他の地域のばら積み船市場も低迷していると述べた。
同氏は「中国を除く世界の粗鋼生産は、中国の粗鋼生産より状況が悪化している」としたが、まだその認識は広がっていないという。
「それが認識されれば、ばら積み船市場の長期的な見通しがどれほど暗いかがわかるだろう」と話し、世界の粗鋼生産の半分は中国以外が占めていると指摘した。
一方、来年パナマ運河の拡張工事が完了することや中国の「21世紀の海のシルクロード」構想に、希望の兆しを見出そうとする業界関係者もいる。
船舶ブローカー大手、クラークソンズ・プラトーのマーティン・ロウ氏は「用船契約と需要がともに増えれば、ある時点から運賃が上昇し始めるだろう」と述べた。
世界最大級の曳航能力を持つオフショア船で、日本ではたぶん建造されていない新型設計の船。こんなタグボートを見た事がありますか?下記の写真をご覧ください。
設計は日本ではなくオフショア船の設計建造に多数の実績があるノルウェーのULSTEIN DESIGN & SOLUTIONS社の設計。設計した経験が無ければ、現場は戸惑うだろうし、
指示書や注意点は英語のはず。詳細について聞きたくても質問は英語になるはず。英語が出来ても経験が無ければ、上手く翻訳できないかもしれない。技術の専門英語は
簡単には翻訳できない。英語がさほど出来なくても、技術英語の単語を知っていればコミュニケーションが取れることが可能な事はある。
英語が出来なくてもこれまで建造してきたオフショア船に似ていればある程度は感で対応できたかもしれない。しかし、新設計となると経験と語学力が必要になるのでは?
素人なのでよく知りませんが、工期遅れで損失が拡大している支援船は、LP MARITIME SERVICES B.V 社(本社:オランダ)発注のオフショア船と推測します。

世界最大級の曳航能力を持つ作業船の進水式が19日、新潟造船(新潟市中央区)で行われた。
作業船は沖合油田に使われる巨大構造物を現場まで引っ張る作業などに使われる「オーシャンゴーイングタグ」。今後、操舵そうだ室などが造られ、来年早々に完成する予定。
作業船の標準的な曳航能力は160~170トン程度だが、同社はオランダの会社から曳航能力300トンの巨大船を4隻受注。昨年秋から建造を進めてきた1隻目の骨格がほぼ完成した。4隻はいずれも総トン数は約5700トン、全長89メートル、幅21メートル、深さ9.5メートル。完成後は世界各地の沖合油田などで活躍することになる。

2014年3月に、欧州顧客向けにオーシャン・ゴーイング・タグ4隻を受注しました。
本船は、オフショア船の設計建造に多数の実績があるノルウェーのULSTEIN DESIGN & SOLUTIONS社の設計を活用して建造します。曳航能力は、世界最大級の300トンとなります。
これら4隻は、カナダのTEEKAYグループ傘下のTEEKAY OFFSHORE PARTNERS社の子会社であるALP MARITIME SERVICES B.V 社(本社:オランダ)に、2016年夏までに順次竣工・引渡しです。
当社はこれらのタグの建造を通じて、三井造船グループが推進する海洋関係プロジェクトへの事業展開の一翼を担います。
主 要 目]
全長 88.90m
幅 21.00m
深さ 9.50m
計画満載吃水 7.00m
速力 18.40knot
曳航能力 300ton
主機関 4,500kw×4基(合計 約24,500ps)
推進装置 ノズル付き可変ピッチプロペラ
最大搭載人員 35人
ocean_going_tug_niigata_mar2014 「Daewoo keeps No. 1 shipyard position」でも大赤字なのに、『中国造船業界が不調、10年ぶりに日韓に後れを取る=「中国にとっては深刻な問題だ」「造船は日中韓が世界を席巻してる」』の記事。 事実といつのデータを使うかで、いろいろと書けるものだ。いろいろな記事を比べないと何が事実が誤解しそう。
2015年10月19日、韓国・ニュース1は、中国造船業界の受注が不調で10年ぶりに日韓に後れを取ったことを伝えた。
英国の造船・海運市況分析機関クラークソン・リサーチによると、中国の造船業界が今年9月までに受注したのは270件だ。これは昨年、中国の造船業界が受注した930件の3分の1に過ぎない。さらに船の付加価値を勘案した財貨重量トン数(DWT)に換算すると、韓国の造船業界は今年9月までに2810万トンを受注しており、日本は1900万トン、中国は1680万トン。中国が日中韓3カ国の中で最下位ということになる。
受注件数では、韓国と日本はそれぞれ212件を結んでいる。日韓は中国に比べて件数は少ないが、DWT基準受注は大きい。それだけ付加価値の高い大型船舶を受注したということになる。中国が最下位となったのは10年ぶりのことになるという。
この報道に、韓国のネットユーザーからさまざまなコメントが寄せられている。
「造船業では日中韓が世界を席巻しているということだな」
「物量で勝たねばならない中国が、物量で負けたということは深刻な問題だ」
「10年ぶりの快挙を誇りに思う」
「造船で中国に勝ったとは、すごいことだ」
「韓国も政治だけちゃんとすれば、そう大変でもなさそうだな」
「造船関係の報道は一体どうなっているのだ。つい先日は韓国の造船業界が沈むような内容だったのに」
「トン数ベースで韓国が1位か。世界の貿易量が減少すれば、造船業界が最初に打撃を受ける。今は苦しい時期だが、以前、サムスンの半導体がチキンレースをして競争相手を倒産させたように、困難な時期に耐えて生き残り、競争相手を負かすことができればいい」(翻訳・編集/三田)
SEOUL, Oct. 23 (Yonhap) -- Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. has maintained its position as the world's largest shipbuilder by order backlog for 11 straight months, industry data showed Friday.
According to the data compiled by global researcher Clarkson Research Services, the South Korean shipbuilder had the largest order backlog totaling 8.50 million compensated gross tons (CGTs) as of end-September.
Daewoo Shipbuilding was followed by its major local rivals, Hyundai Heavy Industries Co. and Samsung Heavy Industries Co., whose comparable figures were 5.13 million CGTs and 5.01 million CGTs, respectively.
Since November last year, Daewoo Shipbuilding has been the world's largest shipyard in terms of tons of ships on order.
The shipbuilder is pushing to restructure, including selling assets and reducing the number of its executives, as it is reeling from massive losses.
The shipyard suffered a record loss in the second quarter, largely due to increased costs stemming from a delay in the construction of low-priced ships and offshore facilities.
The net loss came to 2.39 trillion won (US$2.1 billion) in the April-June period, compared with a profit of 76 billion won a year earlier, the company said.
Its creditors, led by the state-run Korea Development Bank, is devising a rescue plan for the shipbuilder that will likely include an injection of additional funds from its creditors, as well as a $5 billion refund guarantee on advance payments made to Daewoo Shipbuilding.
The government has suspended a push for creditors to bail out Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering after estimated losses swelled to W5 trillion due to a canceled order and rising costs in the industry (US$1=W1,139).
The cash-strapped shipbuilder will only get another lifeline only if it comes up with a radical restructuring plan and workers undertake in writing to back the plan.
The government in a closed-door meeting led by Finance Minister Choi Kyung-hwan on Thursday decided to halt support for Daewoo. The decision came after an earlier restructuring plan by the shipbuilder, which included laying off executives and selling assets, failed to impress creditors and prompted workers to threaten industrial action.
An audit by the state-run Korea Development Bank, the main creditor, shows Daewoo facing an operating loss of W5.3 trillion and a net loss of W4.8 trillion this year.
Creditors had been mulling a W4.3 trillion cash injection.
The bankrupcy filing this week of Noryards Fosen shipyard in Trøndelag will throw another 200 people out of work, the latest casualities of the slowdown in Norway’s oil and offshore industries.
Newspaper Dagens Næringsliv (DN) reported that the yard failed to secure a contract for the construction of a new subsea vessel. The contract was worth NOK 700 million and would have provided enough work to keep the yard operating.
Around 120 of Noryards Fosen’s staff are already on furlough while 72 had hung on to their jobs. Around 80 employees have lost their jobs over the past two years. Now the roughly 200 remaining will be out of work as well.
DN reported that the yard was believed to have debt of around NOK 235 million, most of it owed to suppliers who haven’t been paid. “It’s with great regret that the board has decided to file for bankruptcy,” the yard’s chief executive, Ivar Hanson, stated. A sister yard in Bergen, however, will remain in operation. The yards are owned by a Ukrainian investor through his Luxembourg-registered company Calexco, which took over after Bergen Group’s heavy losses on new ferries built for Fjord Line.
新聞社だから兎に角書かないといけないのだろうが、短期的そして中期的な視点では評価も違ってくるように思える。
中国の受注は増えたが、品質は価格ほど上昇していない。また、安さで中国に発注したが引き取った船に満足していない船主も存在する。
時が流れれば、流れも変わる時もあると思う。確かに出て行ったものは二度と帰ってこない場合もある。付け加えて周りの環境やその時の経済が
複雑にリンクしたり、影響して予測が難しい。撤退するのか、改善の努力を継続しながら時期を待つかは企業の判断だと思う。
韓国はいろいろな事がマイナス又はダウンサイジングに向かっているので、楽天的に考えられないのだろう。ブラジルは考慮する必要はないが、
インドの造船業がどのように成長するか次第では、中国だけを考えていては失敗すると思う。まあ、なるようにしかならないから、心配しても仕方がないと
言えばそうかもしれない。
私は大学で「中国金融市場」と「グローバルエネルギー政治」を講義しながら真っ黒な暗雲が韓国の造船産業に集まる不吉な予感を抱いている。世界エネルギー市場と中国発の暗雲は大きく分けて3つだ。
最初に、2014年6月を基点に国際石油価格は1バレル=110ドルから50ドル台に急落した。専門機関は2~3年間、現在の低オイル価格が持続すると展望している。するとエクソンモービル、シェル、BP、トタル、Eniなど世界メジャー石油化学企業などは今後2年間で2000億ドル規模の設備投資を削減した。北極をはじめとするかなりの海洋鉱区のボーリングと開発を中断したり延期したりした。韓国の造船海洋産業の主な新規事業(海洋プラント受注)がそれだけ減ったことになる。その上オイル価格の下落と費用を念頭に置いた国際発注者らはどうにかして従来の発注物の引き渡しを遅らせながら設計変更を要求するなど一層難しくなるだろう。
2番目、韓国は国際市場で中国との競争を意識するほかはない。中国は最近、国内景気の停滞で大々的な経済成長モデルの変化を追求している。すなわちこれまで成長動力だった国内投資の減少を代替するために低金利の債権の発行を通じて莫大な財源をかき集め、対外投資を拡大して海外プロジェクトを積極的に受注する側に方向を切り替えたのだ。
中国はすでに2005年から世界の石油やガス、鉱山に大変な海外投資をした。その規模は約4000億ドルに達する。問題は中国共産党と国務院の一糸乱れぬ指揮のもと、海外に投資したエネルギー企業や合弁プロジェクトが船舶・海洋プラント発注をほとんど中国の造船所に集め始めたという点だ。中国の発注者に提供する長期金融条件は、韓国の企業がほとんど沿えないダンピングに近い最優待条件だ。
中国は債権発行規模が2007年の7兆ドルから2014年は28兆ドルへと4倍増加した。借金残額はGDPの280%で世界で最も負債比率が高い国になった。こうした状況でも国際超低金利を活用して対内外債権を発行し、大型私営企業に長期優待金融を支援している。
また今年7月、中国中央銀行は中国開発銀行に470億ドル、中国輸出入銀行に450億ドルを増額出資することにした。これは中国造船業者の受注を支援することが明らかだ。中国は海外発注者の投資家であり金融支援者であると同時に需要者だ。こういう多様な立場で主導権を握っている中国の競争力は、韓国の造船海洋企業をより一層難しくさせるだろう。
3番目、最近中国のNDRC(経済企画委員会)はインターネット分野と製造業分野を国家的に支援している。昨年はオイルガスのパイプライン産業、水資源保存産業などに5300億ドルの投資を支援した。今年は産業用ロボット、クリーンエネルギー用の自動車産業、医療産業などのほかに「最高水準の海洋エンジニアリングの設備製作産業」を新たに指定して支援することにした。最近、中国は半導体・自動車・スマートフォンなど各分野で韓国をぴったりと追撃するか、一部は追い越している。このような状況で海洋エンジニアリングと製造分野を集中的に支援するという中国の政策は、韓国の造船業界と海洋エンジニアリング業界にとっては大きな危機要因だ。さらに中国は自らの需要市場がぼう大かつ莫大な海外投資をした状態だ。中国政府の指揮のもと中国エネルギー企業は中国造船業者の海洋設備を使おうとするだろう。このようになれば近い将来、韓国の企業は金融条件と価格条件で中国企業に比べて途方もなく不利な状況で競争するほかはない。
韓国の造船海洋ビッグ3は、海洋プラントで途方もない赤字が発生した。その原因は造船から海洋プラント側に急変した受注市場の構造の変化から探さなければならない。かつて6対4であった造船と海洋プラントの比率は2011年以来3対7に変わった。これに比べて資源大国は国益優先主義で海洋プラントを現地企業に発注する流れが明確になっている。韓国の企業はこうした「現地化」のリスク要因を正しく理解できずに自ら足の甲をつかんだ。ここに資源の適切な配置とキャッシュフローを軽視した経営が、莫大な赤字と流動性の危機まで追い立てたのだ。
しかし過去の過ちの責任は徹底的に糾明するものの、これから生きる道を探さなければならない。国際市場で今まで1位を守ってきた造船海洋産業をそのまま死に追いやってはいけない。造船海洋産業は20万人余りの雇用と年600億ドルを輸出する「孝行息子」産業だ。これまで高い授業料を払った失敗を反面教師にして、競争力のある産業へと再び生かすために国家的な力を集めなければならない。企業はもちろん政府、国策金融機関、学界も積極的に力を加えなければならない。韓国の1等基幹産業である造船海洋を中国に全て譲り渡すことはできないではないか。造船海洋は単純な民間事業ではない。企業らに知らせて生存しろというには国家的支援を受けている中国企業に対抗して競争しなければならない条件が非常に負担だ。強い者が生き残るのではなく、生き残る者が強い者だ。
ホン・インギKAIST経営大学招へい教授・元大宇(デウ)造船代表理事
◆外部者執筆のコラムは中央日報の編集方針と異なる場合があります。
9月29日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請していた、第一中央汽船(株)(TDB企業コード:985402836、資本金289億5841万150円、東京都中央区新富2-14-4、代表藥師寺正和氏ほか1名、従業員154名)と100%子会社のSTAR BULK CARRIER CO.,S.A.(パナマ共和国)の2社は、10月5日付で再生手続き開始決定を受けた。
再生債権の届け出期間は12月7日までで、再生債権の一般調査期間は2016年1月12日から19日まで。再生計画案の提出期限は同年2月3日までとなっている。
当社は、1933年(昭和8年)9月設立の第一汽船(株)と42年(昭和17年)5月設立の中央汽船(株)が対等合併し、60年(昭和35年)10月に新設会社として発足。同年12月に東証1部上場を果たした。鉱石や石炭、ボーキサイト、ニッケル鉱石を中心に木材や穀物等の撒積貨物、鉄鋼製品、原油などを扱い、外航不定期航路部門では大手に位置づけられていた。日本と中国の外航定期航路と内航不定期航路を加えた内外航海上輸送を行い、多種多様な輸送貨物に対応。住友系企業が上位株主に名を連ね、同グループ系企業を主な顧客としていた。新興国の成長や鉄鉱石・石炭など撒積貨物の荷動きが活発だったことで好調な運航が続き、世界的に船舶量が増加するなか、2008年3月期の年収入高は約1666億2700万円を計上していた。
しかし、リーマン・ショック後の受注減少、燃料費の高騰、円高の影響等で経営状態が急速に悪化。2010年3月期の年収入高は約1007億7100万円に減少する一方、運航隻数(グループ)は161隻に増加していた。その後は円安進行による円換算での業績押し上げもあり、2013年3月期の年収入高は約1292億4600万円に持ち直すなか、所有船の売却や運航費の圧縮などを進めていたが、為替変動や燃料高に加え、保有船舶の減損損失や造船契約の解約金等の特別損失を計上したため、約323億100万円の当期純損失を計上。筆頭株主の(株)商船三井(東証1部)が増資に応じるほか、投資ファンドなど複数の支援を得て再建を進めていた。
他方、2006年12月に中国企業より傭船した船舶が座礁し、全損になった事故の損害賠償責任を巡り、2013年7月に英国高等法院より第一審判決にて1億6660万ドルの支払いを命ずる判決が出されていた(その後、2015年1月の第二審判決では賠償責任がなくなり勝訴)。そうしたなか、市況の悪化により2015年3月期は年収入高約1237億9000万円に対し、当期純損失約26億6000万円を計上。4期連続の最終赤字となるなか、運航隻数は172隻に増加するなど、過年度の設備投資負担が経営を圧迫、ここに来て民事再生法による再建を目指すこととなった。
負債は2015年6月末時点で第一中央汽船(株)が約1196億800万円、STAR BULK CARRIER CO.,S.A.が約568億5900万円で、2社合計で約1764億6700万円だが、今後の民事再生手続きにおいて増加する可能性がある。
なお、2015年の上場企業倒産は江守グループホールディングス(株)(4月民事再生法、東証1部、負債711億円)に次いで3社目で、同社を抜いて負債総額は今年最大。また、海運業者の倒産としては三光汽船(株)(1985年8月会社更生法、負債5200億円)に次いで過去2番目となる。
三菱は長崎の船舶から事業を出発させたが、今や事業主体は宇宙、航空、軍需に変わり、船舶部門の火が消え去ろうとしている。
三菱の船舶部門は超円安にもかかわらず何やっているのか、それ以前の長きデフレ、円高に造船技術さえもなくしてしまったようだ。
引渡し前の豪華客船の炎上に始まり、三井商船の大型コンテナ船2つ折れ沈没事件、今度は豪華客船の設計ミスによる巨額損失事件。
分社化は、事業を立て直すためのものである一方、立て直せなかった場合は身売りか、清算となる。行く末が心配される。
造船部門の優秀な人材が、いつしかロケットや航空、軍需などの他部門に吸い取られたり、配置されなかった結果のようにも見える。
三菱重工業は採算が悪化している造船事業を立て直すため、長崎造船所内にある2つの部門を分社化して10月、新会社を立ち上げることになり28日、会社の社長を兼務する造船所の所長らが記者会見し、来年度から黒字化を目指したいなどと抱負を語った。
三菱重工業が分社化して来月1日に立ち上げるのは、LNG=液化天然ガスなどのガス運搬船を建造する「三菱重工船舶海洋」と、船の骨格となる「ブロック」の製造・販売を行う「三菱重工船体」で、本社はいずれも長崎市香焼町の長崎造船所の香焼工場内に置く。
2つの会社は、それぞれの事業に特化し、組織のコンパクト化やコスト削減を進めることで収益の安定化を図ることにしている。
2社とも来年度からの黒字化を目指し、3年から4年後までに年間の売上額を「三菱重工船舶海洋」で1000億円、「三菱重工船体」で100億円を目標にしている。
「三菱重工船舶海洋」の社長を兼務することになる長崎造船所の横田宏所長は28日の会見で「長崎の基幹産業である造船業を守るとともにさらに発展させていきたい。やっていけると思っている」と話している。
三菱重工業の造船事業をめぐっては、ドイツから受注した大型客船で設計のやり直しが大量に発生して巨額の特別損失を計上するなど採算が悪化しているため、客船の建造は引き続き三菱重工業が担うことにしている。
中国造船業はやばい!韓国の鉄板を使うのをストップして、中国製の鉄板を使うらしい。品質は確実に悪くなるな!
Industry downturn has caused Shenzhen-listed Sainty Marine to lose large number of projects, but it has only told bourse about four of them
By staff reporter Bao Zhiming
(Shanghai) - A Shenzhen-listed shipbuilder has not told the stock market about 29 lost orders, a check of filings by a Caixin reporter on August 5 has found.
Data from industry research firms and information provided by a shipbuilding executive reveal that Sainty Marine Corp. Ltd., based in the eastern province of Jiangsu, lost 33 orders for ships that it had received from 2013 to March this year. Those lost orders were worth 6 billion yuan, information from the shipbuilder shows.
The company told the stock market in May that buyers canceled four orders, but it has not told the Shenzhen bourse about the remainder. Regulators warned the company in April that it could be delisted at the end of the year if it did not fix its financial problems.
A downturn in the shipping industry has forced some buyers to drop orders, the British shipping consulting company Clarksons Plc. said. New orders fell by half over the first six months of the year compared to the same period of 2014.
Chinese shipbuilders received nearly three-quarters fewer orders in the first half of the year, the China Association of the National Shipbuilding Industry said, and some companies are facing financial problems.
Industry research firms say Sainty Marine had lost 25 orders as of the end of June.
Sainty Marine lost another eight orders when Nantong Mingde Heavy Industry Group went bankrupt on July 31, an executive at the private shipbuilder in Jiangsu said. Sainty Marine and Nantong Mingde started cooperating in 2013, the executive said, but the partnership faltered in the second half of 2014.
Nantong Mingde could not finish ships on schedule and then could not repay Sainty Marine money it owed, said Cao Chunhua, secretary to the listed company's board of directors.
Sainty Marine has said it tried but failed to Nantong Mingde undergo a restructuring in a bid to recoup its money.
The listed company has also said it has to repay ship buyers around 800 million yuan in prepaid money and interest on the orders that were lost due to Nantong Mingde's bankruptcy and that it could lose up to 2.9 billion yuan over its dealings with Nantong Mingde.
Sainty Marine said in May and July that it was unable to repay bank loans totaling 560 million yuan and that accounts with Bank of China and Export-Import Bank had been frozen.
(Rewritten by Guo Kai)
韓国経済はやばい!
South Korean shipbuilders and steelmakers are increasingly facing risks from China’s recent restructuring in its ailing shipbuilding sector.
Beijing on Monday announced a large-scale restructuring in the industry as part of efforts to shift away from its investment-driven economic growth model and concentrate on boosting domestic consumption.
Market watchers said the escalating crisis in China could take a huge toll on local shipbuilders as well as steelmakers, should they try to push ahead with strategies like lowering costs and raising the export volume.
“How Korean shipbuilders would try to maintain profit amid China’s threat is a question. As an internal plan, the top three companies said they will undergo restructuring. It’s the external factors, such as cost reduction of materials like steel and exchange rates, that could have a ripple effect in the steel industry,” Hyundai Steel spokesman Yoo Hyun-ki said.
“Korean steelmakers already have very little margin selling thick steel plates (used for building vessels),” he said.
Chinese steel companies are the linchpin of the global industry, accounting for about 50 percent of worldwide production with prices as much as 25 percent lower than global competitors. It is estimated that thick plates produced in Korea cost between 500,000 won ($430) and 600,000 won per ton, while Chinese products are priced up to 25 percent cheaper at about 450,000 won per ton.
According to Chinese media, Beijing decided to shut down 2,700 of 3,000 shipyards. Only 51 companies were deemed worthy of support and were whitelisted by the government.
Nantong Mingde Industry, a private shipyard in Nantong, Jiangsu Province, entered bankruptcy in late July, the latest following Beijing’s decision to crack down on industrial overcapacity in the country.
Local shipbuilders, like Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering and Samsung Heavy Industries, have been hit by a double whammy of industry downturn and prolonged deficit from offshore businesses.
“I call this a crisis. The Korean shipbuilding industry has lost track and it may sink if it doesn’t find its advantage over price-competitive Chinese rivals,” a Korea Development Bank analyst said, wishing to stay anonymous.
Steel companies like POSCO and Hyundai Steel are also threatened by China’s move, as the price of Chinese thick plates has dropped even more following a string of shut downs.
“Should the leftover stock pour into Korea and other countries, it could deal a significant blow to POSCO and Hyundai’s sales,” she said.
“Chinese rivals are catching up very fast. What we can do, instead of joining their price competition, is to develop special steel products that require decades of research and experience,” Kim Sung-joo, director at Hyundai Steel’s research and development center said in a recent interview with The Korea Herald.
By Suk Gee-hyun (monicasuk@heraldcorp.com)
理由があるから倒産する。
Tongzhou District People’s Court in Nantong officially declared Nantong Mingde Heavy Industry bankrupt on July 31, ending all hopes of restructuring at this financially troubled shipbuilding subsidiary of Jiangsu Sainty Marine Corporation.
The court said that Mingde’s request to extend the period for submission of the restructuring plan was denied, after the shipbuilder missed the first deadline to submit the plan back in June.
The court accepted Mingde’s application for the bankruptcy reorganization on December 26, 2014, and the shipbuilder had until June 26 to submit the restructuring plan, seeing that China’s bankruptcy law stipulates that administrators or debtors must submit a draft reorganization plan within six months of the court’s acceptance of the restructuring plan.
After the court refused to allow additional three months to Mingde to submit the restructuring plan, the company filed for bankruptcy.
Earlier this year, Sainty Marine said that Mingde is experiencing difficulties with respect to the delivery of 32 newbuilding units due to the latter’s ongoing restructuring process.
Sainty Marine has been struggling with financial hurdles over the recent period which saw freezing of its assets by banks in addition to defaulting on its bank loans.
China’s Dalian Shipbuilding Industry Corporation (DSIC) has agreed to merge with the bankrupt Dalian Daeyang Shipyard, after which Daeyang will be dissolved and deregistered.
DSIC will be the surviving company with its registered capital of CNY 8.5 billion (USD 1.37bn) remaining unchanged. All creditor’s rights and debts of DSIC and Daeyang, with its registered capital of CNY 901.2 million, shall be assumed and borne by DSIC.
Daeyang was a subsidiary of South Korean shipping company Daeyang Shipping until January this year, when DSIC acquired 100% of equity shares in the shipyard.
The shipyard has been operational since May 2009, specializing in conversions and ship repairs at its 300,000 ton and 100,000 ton dry docks.
Located two miles away from the port of Dalian and one mile away from the Dalian anchorage, the shipyard extends over an area of 560.000 square meters.
Additionally to the dry-docking facilities, the shipyard utilises repair berths of a total of 1,310 meters in length with a minimum drought of 7.5 meters, as well as workshops and related facilities.
DSIC plans to upgrade the shipyard and use it to construct navy vessels and LNG carriers.
時代の流れは恐ろしい!
The South Korean Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering will liquidate its foreign subsidiaries, including Daewoo Mangalia Heavy Industries. The shipbuilder has serious financial problems during the last years, despite of the increased number of orders.
According to the plan for stabilization and cost reduction is closing of several unprofitable foreign plants. It is expected the sea shipbuilding division of Daewoo to have a loss of 3 trillion KRW in 2015, which means that the third-largest shipbuilder in the world will need to close or sell its foreign subsidiaries to limit additional crashes.
The biggest loses for Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering come from the collapse in the construction of vessels for the offshore industry.
Daewoo holds 51% stake in the shipyard of Mangalia, which acquired 18 years ago. Owner of the rest of the capital is the Government of Romania. According to unofficial data, the current liabilities of the shipyard exceeded its assets and the company may go in bankruptcy.
Still it is not clear if the government of Romania will try to rescue the shipbuilding plant, where are working thousand of people, but Daewoo definitely will leave it. There is also an option for financial aid from the Romanian finance ministry to the shipbuilding plant,
which might save it from benkruptcy, but such deal is not yet officially negotiated.
サプライボートは艤装中だと推測するがSPP Shipbuildingはどうするのだろう?
Genoa: A legal dispute is likely to emerge between Finarge and SPP Shipbuilding after the Italian company, owned by Rimorchiatori Riuniti Group, decided to cancel a shipbuilding contract for a new AHTS vessel.
SPP officials claimed they had not heard of the cancellation when contacted by Splash today while the Italian owner declined to comment on the subject.
However sources have confirmed to Splash that following several months of delay on the delivery, which was scheduled in the third quarter of 2014, and given the present low market cycle in the offshore segment, Rimorchiatori Riuniti prefers to exercise the right to cancel the contract.
The Genoa-based shipping company placed the order with SPP Shipbuilding in April 2013 for two (1 +1 option) AHTS vessels at $60m each and thus entering the offshore supply vessels market.
Last week Splash exclusively revealed Rimrchiatori Riuniti’s latest investment, a modern kamsarmax bulk carrier bought from Japan’s Nissin Shipping.
規模が大きくなれば大型船と同じ、舵を切ってもすぐには方向は変わらない。よい時には、利益も大きい。 まあ、世界経済や海運業界のマーケット状況もあるので努力だけで乗り切れるのかは疑問。
大宇造船に最も多くの資金を貸したもう一つの国策銀行、輸出入銀行も同じだ。輸出入銀行長の李徳勲(イ・ドクフン)は、この政権に入って勢いづいたという「西江金融人会」のメンバーだ。当初、朴大統領は彼をウリィ金融会長として考えていたという。適任者ではないと青瓦台(チョンワデ、大統領府)実務陣が反対すると、1年後の昨年3月、輸出入銀行長に指名した。国策銀行を前に出して造船産業を危機から救い出すというのは大統領の公約でもあった。ところが輸出入銀行は自らが管理中のソンドン造船海洋とデソン造船だけに集中した。不振の造船所の合併を通じた構造改革が至急だったが、「我々は知らない」だった。ついに5月、任鍾龍(イム・ジョンリョン)金融委員長が「(造船業は)個別企業でなく産業別構造改革が行われなければいけない」と強調したが、時すでに遅しだった。
その間、27社の国内中小造船会社のうち21社が消えた。残りの6社のうち韓進重工業を除いた5社がワークアウト(企業財務構造改善作業)または法定管理(企業再建手続き)中だ。昨年、5社は売上高が5兆5142億ウォン、営業損失だけで8341億ウォンだった。それでも出血競争は相変わらずだ。産業銀行・輸出入銀行が主軸の債権団は1社あたり多くて3兆ウォン以上の資金を注ぎ込んで延命中だが、底が抜けた瓶に水を注ぐようなものだ。造船業発の経済危機さえ防ぐことができればこの上なくありがたいことだ。
私はこれがすべて、金融を製造業にお金でも貸す辺境業種として、また金融機関のトップの地位を政権の戦利品くらいに考える大統領のためだと考える。李明博(イ・ミョンバク)政権は高麗大の人脈と側近を金融機関に天下りさせた。「歴代最悪」「韓国金融を20年後退させた」という評価を受けた。ところが今の政権はそれ以上だ。だからつまらないと思いながらも、また大統領のせいにすることになるのだ。
イ・ジョンジェ論説委員
大宇造船海洋の構造調整ロードマップがまとめられた。早ければ来月末までに実態調査を終えた後、大株主の産業銀行、最大債権銀行の輸出入銀行の主導でオーダーメード型支援に入る。本来3カ月ほどかかる実態調査期間を半分に減らすファーストトラック(速戦即決)を通じてだ。構造調整の長期化にともなう企業価値下落を防ごうという趣旨だ。産業銀行をはじめとする債権団は21日、金融委員会と大宇造船対策会議を開きこうした内容の構造調整推進日程を決めたと明らかにした。
債権団に与えられた最大の課題は大宇造船の負債比率維持だ。受注残高世界1位である大宇造船の対外信用度を維持するためだ。負債比率が上がれば格付け下落で受注が大幅に減りかねない。最近発生した2兆ウォン台の損失が4~6月期の業績に反映されれば大宇造船の負債比率は370%から600%台に大幅に上がる。4兆6000億ウォンだった自己資本が2兆ウォン前後に縮小するためだ。イーベスト投資証券のソン・ソヒョン研究員は、「大宇造船は昨年4月に5000億ウォンの社債を発行した際に負債比率を500%以下で維持する条件を掲げた。この条件を守れなければ社債の格付けは落ちるだろう」と話した。
負債比率上昇を防ぐには損失額を充当できる水準の支援が必要だ。産業銀行は▽有償増資▽出資転換▽新規資金支援▽貸し出し満期延長の大きく4種類の案を用意した。産業銀行関係者は、「4種類の案を組み合わせれば自律協約やワークアウトの適用を受けなくても財務構造を改善できるだろう」と話した。例えば損失規模が予想通り2兆ウォン台ならば大株主である産業銀行の有償増資と産業銀行、輸出入銀行による債務の株式化(出資転換)だけで十分だ。しかし損失額が予想を大きく上回れば都市銀行の出資転換だけでなく貸し出し満期延長、利率引き下げ措置まで動員されることができる。
もちろん具体的な支援案は実態調査結果により変わる。債権団内で支援案や負担比率をめぐる溝が広がる可能性があるからだ。双方の意見の相違は15日に任鍾竜(イム・ジョンリョン)金融委員長主宰で開かれた大宇造船対策会議ですでに表れた。当時産業銀行は「債権団が苦痛を分担しなければならない」としたのに対し、輸出入銀行をはじめとする他の債権団は「大株主である産業銀行の有償増資が優先解決策」として対抗した。結局金融委員会は「ひとまず産業銀行が主軸となり、輸出入銀行は積極的に協力せよ」と交通整理をして一段落した。
実態調査の過程で損失反映が先送りされたことに対する責任攻防も大きくなるものとみられる。産業銀行は「大宇造船の元経営陣が何度も海洋プラントに問題がないと報告したので損失の有無がわからなかった」と主張する。しかし市場では2009年から大宇造船の最高財務責任者(CFO)を産業銀行出身者が務めており、損失がわからなかったというのは常識的に納得しがたいという意見が説得力を持っている。
専門家はこの機会に大きな枠組みでの造船業構造調整案を用意しなければならないと指摘する。造船業の長期沈滞を考慮すれば大宇造船1社に対する緊急支援は弥縫策にとどまりかねないという判断からだ。建国(コングク)大学金融IT学科のオ・ジョングン教授は「STX造船海洋や城東造船海洋の経緯悪化を体験しても金融当局と銀行が大宇造船の損失を全く感知できなかったのは大きな問題。金融当局が造船業種の不良感知システム強化と経営強化に向け格別の措置を出さなければならないだろう」と話している。
Xiamen Shipbuilding Industry, recently delivered a roll-on/roll-off car shipping vessel to its European owner. The company received the order in 2013 when the shipbuilding industry was sluggish and competition was extremely fierce.
Now, the company has orders for 42 ships, which will keep its shipbuilding going to the end of 2017.
China Business News said that although the completed tonnage of domestic shipbuilding companies has shown a moderate increase, the newly received orders represent a sharp decline.
Government statistics show that in the first six months of this year, shipbuilding companies completed construction of a total of 18.53 million tons in the first six months this year, up 6.3% from the same period of last year. The newly received orders amount to a combined total of 11.19 million tons, down 72.6% from the same period of last year.
The figures conform to the current sluggish situation since the shipbuilding industry began to undergo a long winter starting in the second half of 2007.
The Baltic Day Index, an economic indicator that provides assessments of the price of moving major raw materials by sea, has slipped sharply from 11,793 on May 20, 2008 to less than 600 as of April this year.
Due to the credit crunch and delivery delays, as well as substandard quality, several shipbuilding companies in the first half of the year have been unable to survive. Among them, Jiangsu East Heavy Industry filed for bankruptcy in March this year, while the Nantong Mingde Heavy Indusry filed for bankruptcy last December.
この前、転覆した川船で自信が付き、韓国も予算で中国の会社を選んだのか?
By Lee Hong Liang from Singapore
A Chinese-led consortium has emerged as the preferred bidder to undertake the difficult task of hoisting the South Korean passenger ferry Sewol, which sank last year April with the loss of more than 300 lives, most of them school children.
South Korea’s ministry of oceans and fisheries said it will start negotiations next Monday with the Chinese consortium involving China’s state-owned Shanghai Salvage Co and a Korean firm, which beat other bidders including European and US companies. Over 20 companies are said to have entered the bidding.
The ministry added that it would talk to a second preferred bidder – a consortium led by China’s state-run China Yantai Salvage – if negotiations with Shanghai Salvage fall through.
The ministry said that Shanghai Salvage was selected due to its experience in salvaging sunken vessels. The Chinese firm offered to lift Sewol for $74m by using a frame built with metal beams on the sea floor instead of drilling holes into its side.
“We regarded Shanghai Salvage’s idea as safe… because the Sewol’s hull remains fragile,” Yeon Yeong-jin a ministry official in charge of salvage, told reporters.
The 6,825-dwt Sewol was carrying 476 people, including 325 students, when it sank off the southwest coast. Only 75 students survived.
Lee Joon-seok, captain of Sewol, was found guilty of murder and sentenced to life imprisonment in April this year.
さすがギリシャ船主。ある意味、ギリシャ船主は今後も生き残るだろう!
By Costas Paris
ATHENS- its negotiations with international creditors, this seafaring nation says now it will do what it has resisted doing for years-raise taxes on its globe-spanning shipping industry.
And that has put the sector in a spin.
“Greek owners will do what needs to be done to stay competitive,” said Michael Boudouroglou, who runs Greece-based, New York-listed Box Ships Inc. and Paragon Shipping Inc., with a combined fleet of 25 container and dry-bulk vessels.
As part of bigger talks over a possible debt financing deal with its international creditors, Greece has said it is willing to increase tonnage tax for Greece-based shipping companies, and will consider cutting other special tax advantages the industry has long enjoyed.
Those benefits include no taxes on profits from shipping operations, and no taxes on ship sales. Over the years, that has helped keep a big chunk of the global shipping industry based here.
Greek owners operate almost 20% of the global fleet of merchant ships, and more than half of the European Union’s fleet. The industry makes up 7.5% of the Greek economy and employs around 200,000 people.
But it has also been in the cross hairs amid the current crisis. Greek shipowners have already offered to voluntarily pay an additional €420 million ($468 million) in tonnage tax from 2014 to 2017. Under fresh pressure by its creditors, Athens now says that isn’t enough. It now plans not only to further increase the tonnage tax, but also gradually withdraw the special tax breaks.
Several owners said over the weekend that if the new increases come into force, they plan to set up operations in other shipping capitals such as London, Singapore and Dubai.
Over the years, countries such as the U.K., Ireland and Cyprus have tried to lure Greek owners, moving to boost their dwindling national shipping registries.
“I am in Greece because I love my country, but I won’t stay around to see my business being ruined,” said one owner of a big Greek tanker fleet.
J.P. Morgan analyst Noah Parquette wrote that any new taxes on shipping companies “would likely force many shipowners to set up outside the country, negatively impacting the economy and potentially disrupting a tradition of shipping in Greece that goes back thousands of years.”
個人的な意見だがいろいろな要素があったと思う。中国に発注した会社の監督達の多くは、「韓国も最初はろくな船しか建造できなかった。しかし、
今は問題のない船を建造している。中国も同じ。」と昔は言っていた。今は、そんな事を言う監督達はかなり減った。中国から問題のある船を引き取って
マーケットが急落したら、転売しようとする中国建造船が敬遠され、少し高くても日本が良いと言う監督が増えた。マーケットが良い時は、日本船でも
中国船でも高値で売れたそうだ。中国建造船で問題を抱えて船主が増えて、検査レポートに多くの不備が記載されている船が敬遠されたり、1、2年運航されて
問題ない船の方が船台に載っている船の方が高い場合もあるそうだ。引き取って大きな問題が見つかり修理しても良い値段で売れるのか不安なので
係船して買い手を探したが1年以上も売れずにいる船もあるらしい。
船が高値で取引され、とにかく船がほしい時期に中国の造船所が増えたような気がする。外航船は株のように世界経済に影響されながら船価や傭船料が
変動する。中国は人件費が高くなった分だけ日本や韓国と比べて不利なような気がする。さらに日本も韓国の造船所は中国の船価に対応するために
船の仕様を落としたり、小さな備品を中国から輸入したりして船価を落とした。中国建造船の品質が向上する、又は、更なる船価の値引きを高騰している
人件費で実現するのはかなり厳しいと思う。まあ、変動するのが世の中。不変な物などほとんどない。中国造船業が再起するのか、さらに沈むのかは、
中国政府及び造船所次第。
中国メディアの騰訊財経は13日、韓国の朝鮮日報の報道を引用し、2014年まで3年連続で世界一の船舶受注量を誇った中国の造船業が停滞していると伝えた。
記事は一例として、浙江省最大の造船メーカーが経営難に陥っていることを挙げた。「同社は2010年には5000人の社員を雇用し、毎年14隻の船舶を建造していた」が、受注量が減少したうえに受注単価も下落したことで経営難に陥ったという。
また、江蘇省にも破産を申請した造船メーカーがあることなどを紹介し、中国では15年に入って以来、破産申請を行う造船メーカーが相次いでいるうえ、受注量も急減していると伝えた。2010年には中国に3000社以上あった造船メーカーは今、100社ほどしか残っておらず、「受注があり、正常に経営できている造船メーカーは20社ほど」という。
中国の造船業が停滞している主な理由は、ばら積み貨物船の受注減少および円安とされる。円安により、中国の造船業は日本仕事を奪われている構図だ。記事はJPモルガン・チェースのアナリストも、「ばら積み貨物船の建造は日中両国で世界の50%以上のシェアを有しており、円安は中国造船業にとって大きな圧力となっている」との見方を示したと報じた。
また、15年における日本の受注量は中国を抜いて世界2位になる見通しだと伝え、「中国を抜くのは06年以来」と報じた。一方で、韓国の造船メーカーは好調で、15年1-5月の累計受注量は前年比15%増という。(編集担当:村山健二)
29日未明、ソウル良才洞(ヤンジェドン)のKOTRA(大韓貿易投資振興公社)の社屋に報告が入った。ギリシャ・アテネ現地から送られた「情報報告」だった。ギリシャ企業と貿易をする韓国国内企業に「非常対応」を注文した。KOTRAアテネ貿易館は「現地企業の代金未納や倒産など非常状況に備えた慎重な取引が必要だ」と強調した。
造船業界の懸念が深まっている。ギリシャに多くの船を輸出してきたからだ。韓国の対ギリシャ輸出の80%を船舶が占めるほどだ。ギリシャ危機が伝えられた直後から国内重工業企業は現地取引先の現況を問い合わせる作業に入った。造船会社の関係者は「ギリシャの船会社はほとんど税金・安全規定が有利な南米やパナマなどに船を登録する『便宜置籍』を活用しているため、現地の危機にすぐには影響を受けないだろう」としながらも「しかし危機が長引けば、輸出が減少するしかない」と心配した。
ギリシャのデフォルト(債務不履行)懸念で韓国産業界はもう一つの「時限爆弾」を抱えることになった。韓国とギリシャの貿易量は昨年14億6000万ドル(約1兆7000億ウォン)ほどだ。KOTRAアテネ貿易館は「現地企業が金融機関の貸し渋りで資金難を迎えている」とし「ギリシャ輸入企業が海外の物を購入できない状況」と伝えた。特に韓国の主力輸出品の携帯電話・家電製品・蓄電池・石油化学原料などが打撃を受けるという見方を示した。
何よりも韓国の輸出が今年に入ってユーロ安・円安で致命傷を受けているため、「ギリシャ発衝撃波」の懸念はさらに強まっている。特にギリシャがデフォルトを宣言する場合、イタリア・スペイン・ポルトガルとともに財政危機を迎える「南部欧州」に危機が伝染するという「破局的シナリオ」も浮上している。このため欧州連合(EU)全体に対する韓国の輸出まで影響を与えるという憂慮もある。韓国貿易協会によると、1-5月の対EU輸出はユーロ安などの影響で190億9600万ドルにとどまり、前年比で16.7%減少した。
韓国貿易協会国際貿易研究院が29日に発表した「輸出産業景況判断指数(EBSI)」調査で韓国国内の輸出企業755社の7-9月期の指数は98にとどまった。輸出景気の見通しが明るいという意見が多いほど指数は200に近づき、暗いという意見が多いほど0に近づく。国際貿易研究院のカン・ネヨン研究員は「輸出対象国の景気不振(16%)と為替レートの変動性拡大(14%)を懸念する声が最も多かった」と述べた。
ギリシャ危機が長期化すればMERS・干ばつ・輸出不振で冷え込んだ「経済心理」がさらに悪化する可能性が高い。全国経済人連合会が29日、売上高600大企業を対象に調査した「7月の企業景況判断指数(BSI)」は84.3となり、2012年末の欧州財政危機以来3年7カ月ぶりに最低水準となった。
適切な解決方法がないという点も悩みだ。大韓商工会議所のチョン・スボン経済調査本部長は「企業が輸出競争力を持てるよう規制改革を加速する必要がある」とし「長期的に為替レートの影響を受けないよう、製造業・輸出に偏った産業構造をサービス業・内需中心に再編しなければいけない」と述べた。
造船業の不況が続いている。下手をすると世界1位も譲り渡すかもしれないという危機意識も広まっている。時々船舶受注のニュースが聞こえるが昨年にはおよばない。円安を背にした日本と、政府支援を土台にした中国の追撃は強まっている。こうした状況で「マルメ(Malmoe、スウェーデンの都市)の涙を忘れてはいけない」という懸念まで出てきた。世界造船産業の中心が欧州から韓国に移ってきたことを象徴する「マルメの涙」が約10年ぶりに韓国で再演される恐れがあるという危機感が高まっている。
◆「マルメの涙を忘れるな」
パク・ジョンボン現代(ヒョンデ)重工業副社長(海洋プラント事業本部海洋事業代表)は4日、社員たちに送った文で「今の状況では私たちはマルメの涙エピソードを思い出さざるをえない」として「(今の)危機を克服できない限りマルメの涙は他人ごとではなく、私たちの涙になるかもしれない」と指摘した。
マルメの涙というのは現代重工業が2002年スウェーデンのコックムス造船所の大型クレーンをわずか1ドルで買収した「事件」を意味する。スウェーデンのマルメに本社を置くコックムス造船所は一時、世界の造船市場を先導していたが韓国企業の躍進に押されて結局は倒産した。造船所内にあったクレーンは解体費用を負担する会社を探せず放置され、現代重工業に売却された。スウェーデン国営放送はクレーンが船に積まれて消える姿を葬送曲と共に報道しながら「マルメが泣いた」と表現した。そのクレーンは現在、現代重工業の蔚山(ウルサン)本社にある。
パク副社長は「造船・海洋プラントは受注減少、競争力低下、収益性低下などで史上最悪の危機を迎えている」として「低価格の労働力を前面に出した中国企業などは私たちを猛烈に追撃しており、技術力と円安を土台にした日本の造船企業も大量受注に乗り出している」と診断した。彼は「弱り目にたたり目で国際石油価格まで下落しながら顧客が船舶・海洋プラントの発注を減らしている」と懸念した。
◆韓国造船業、危険な1位
パク副社長の診断のように韓国の造船業界の状況は難しい。英国造船・海運分析機関クラークソンが分析した資料を見ると今年1~5月の全世界の船舶発注量は989万9782CGT(標準換算トン数・建造難易度などを考慮した船舶の重さ)だ。昨年同期の発注量(2343万8845CGT)の半分にも至らない。
韓国企業の受注量も昨年の577万9695CGTから今年は433万2061CGTへと約25%減った。特に今年に入ってから海洋プラントの受注実績は一度もない。国際石油価格が急落しながら大手石油会社が発注を先送りしているためだ。現代重工業・サムスン重工業・大宇(デウ)造船海洋など「ビッグ3」が事業構造を海洋プラント中心に再編するやいなや海洋プラント発注が途切れた上にすでに受注した事業では一部損失が発生している。
競争国の躍進を懸念する声も出てくる。政府の支援を背景にした中国は2012年から昨年までの3年間で韓国を抜いて受注1位を占めた。円安を背にした日本は今年1月に受注量1位を記録した。国内造船会社の実績はたやすく反騰できずにいる。「ビッグ3」の中でサムスン重工業を除く2社が1-3月期の赤字を記録した。
◆不況の中での善戦…いつ反騰するか
造船業界では不況が今年の下半期までは続く可能性が高いという見方が出ている。国際原油価格が直ちに上がる可能性が高くない上に海運景気の上昇傾向を期待するのも困難だという理由からだ。ただし韓国の造船企業が中国や日本に比べて技術力優位にあるので不況の中でも善戦を継続するという観測が多い。
中国は昨年1~5月に1002万2657CGTを受注したが、今年の受注量は195万5158CGTにとどまった。日本の受注量も同期間で498万956CGTから222万6419CGTと半減した。そうするとこの期間に受注量減少幅が25%にとどまった韓国が市場占有率1位を取り戻した。
受注のニュースもずっと聞こえてきている。現代重工業は1日ノルウェーの船会社とLNG FSRU(浮遊式液化天然ガス保存・再気化設備)1隻の建造契約を結び、大宇造船海洋は2日にA.P.モラー・マースクから18億ドル(約1兆9800億ウォン)規模の大型コンテナ船11隻を受注した。サムスン重工業は4日、米国の船会社と3700億ウォン規模のシャトルタンカー3隻契約を締結した。
船価が割高になると思うけど?
[上海 18日 ロイター] - 中国の英字紙チャイナ・デーリーによると、中国政府はすべての造船会社に対し、新規に建造する船舶を緊急時に軍事目的に転用できる構造とするよう義務付ける指針を承認した。
中国船級協会が明らかにした。
「設計等を行う技術者や現場の技能者の不足へ対応すること・・・我が国造船業がこれらの需要を取り込み、成長を図っていくためには、海洋産業の技術者の育成・確保が必要となります。」
儲からない、将来の展望が無い、景気の山谷が大きい、元受の目先の帳尻合わせのコストカットの圧力や安い海外外注へのシフト、若者の3K(劣悪な環境)などで人々が
造船や海運を敬遠しているから人材不足なのである。ここに行政として気付いていないのであれば救いようがない。
造船が労働集約型とは言え、経験不足の人間を入れても底辺の部分は補えるが、指示や判断が要求される人々の代わりは短期間では出来ない。
3Dと言っても、十分に使いこなせる人材であれば、他の安定し、将来のある業界で仕事に就くのが普通。しかも、外航船建造であれば
英語も出来ないとだめだ。外国の監督が英語が通じないとぼやいている。
優秀な人材と簡単に言うが、魅力的な給料を提示すればコストアップになる。福利厚生とか、労働条件とか言っても、一部の大手だけの話。 安全教育や安全を優先にすればコストアップや納期に影響する。中小はいかに規則を潜り抜けながら安全などを犠牲にしてコストカットを達成しようとしている。下請けなど消耗品。 今、人材不足で困っているだけ。不況になれば下請けを切り捨て、その次は、自社の社員を切り捨てる。少しでも考えるタイプの 人間であれば、他の条件の良い会社や業界で働くことを考えるのが普通。悪い条件でも、地元で通勤に便利が良いだけで造船所での仕事を選ぶ若者がいる。 これは、両親と同居が出来る、幼馴染や同級生がいる地元の人間の選択。地元でなければ、同じ給料では実質的に使えるお金は少ない。
中小になると役職や管理職の人間達の判断基準が時代遅れ。ゴマすりながら仕事をして行くと運命共同体で一緒に地獄に行くリスクあり。昔の人間達で 改革的な人間は少ない。改革的であっても、役職の人間が古いタイプであれば衝突して出て行くパターンもある。
良い設計など必要ない。安くて検査に通ればよいのである。規則を満足していなくても、検査官が不備を見つけなければ検査は通る。 悪い例であるが、究極な例は、サブスタンダード船。 悪い設計かどうかは、事故や船主からクレームがなければどうでも良いこと。良い設計かどうかは、発注者の造船所でも判断できないケースもある。 発注者の船主も、経験や知識不足であれば故障があるかどうか、船主や船員のとって使い勝手が良いかだけで、それ以上のレベルでは判断できない。 問題に直面するまで、又は、良い船を使用しない限り、比較が出来ない場合もある。結局は、コスト。一時、多くの外国船主が中国に発注した。なぜなのか? コストが安いから。その後、一部の船主は中国を敬遠するようになった。品質の問題を経験し、コストパフォーマンスで判断したら中国建造の船は 良い選択肢でないと認識したから。需要側が何を求めているか次第である。コストが最優先であれば、品質やコストパフォーマンスはさほど考慮されない。
海運も同じ。船員が自分の子供を船員にしたくないと思うような環境、又は、気持ちになるのであれば、いくらアピールしても無駄。 船員が自分の子供を船員にしたいと思う環境がなければ、どのようなPRをしてもさほど増えない。造船で書いたこと同じ。魅力的であれば PRが無くても人は集まるし、PRすれば多くの人々が来るだろう。造船にしても、海運にしても、自分の子供に就職しろとは言わない。 確かに、隣の芝は青く見えると言う事もある。事実を知らないから、知らない業界が魅力的に見えることもある。魅力的な会社や 業界は造船や海運以外であるはずだ。個人的には他を探すほうが子供のとって良い選択だと思う。(確かに時代によって会社や業界の浮き沈みはある。)
人材が集まらない業界には理由があるから集まらないのである。人々も考える。何が自分にとって良い条件なのか?選択肢があるのなら、どの選択肢が 一番良いのか?騙して入社させることも出来る。運が良ければ、騙された社員の数パーセントは諦めて同じ会社や同じ業界に残るかもしれない。 しかし抜本的な解決にはならない。

Shanghai: The receiver of the bankrupt shipyard Judger Shipbuilding is publicly looking for investors in an effort to rescue the yard.
According to an announcement from the receiver, the yard is seeking investment from the shipbuilding and logistics sectors including distribution and warehousing.
Judger Shipbuilding filed for bankruptcy in April and reported debts of RMB1.924bn ($310.3m).
An official from Judger Shipbuilding’s receiver told Splash that the restructuring process of the shipyard is not optimistic amid the current recession, and the yard’s assets will go to auction if new investors are not found.
Judger Shipbuilding’s parent Judger Group, a multi sector enterprise mainly engaged in the business of clothing and real estate, has been under an ongoing restructuring process since February.
渡辺 清治 :週刊東洋経済 副編集長
IHI、三菱重工業、川崎重工業、名村造船など、日本の重工・造船業界が揺れている。震源地は日本の真裏に位置するブラジル。同国の国営石油会社、ペトロブラスを巡る大規模な賄賂・汚職スキャンダルの影響により、日本勢が出資・事業参画している現地造船所が経営危機に見舞われているからだ。
ブラジルでは近年、「プレソルト」と呼ばれる超深海の巨大油田開発が本格化し、国家プロジェクトでペトロブラスが大規模な開発計画を進めている。開発にはドリルシップ(試掘・開発用の堀削船)など膨大な数の海洋構造物を使用するが、ブラジルは産業育成や雇用・経済対策として、そうした設備を自国企業へ優先的に発注する政策をとってきた。
技術協力の要請受け、日本勢が事業参画
その主要な受け皿となったのが、現地の大手建設会社が設立した複数の新興造船会社。しかし、掘削船などを受注したはいいが、建造に必要な造船の技術がブラジルにはない。そこで、ブラジル政府や各建設会社が協力を求めた先が日本だった。
日本の重工・造船業界にとっても、協力要請は渡りに船だった。掘削船やFPSO(浮体式の原油生産貯蔵積み出し設備)などの海洋資源関連構造物は巨大な市場があるが、韓国勢が圧倒的に強く、伝統的な運搬用商船を主とする日本勢は大きく出遅れている。ブラジル企業と手を組めば、現地の合弁造船会社を通じてペトロブラスが発注する膨大な設備を優先的に受注できる。
かくして、国内の重工・造船会社は相次いで現地の新興造船会社へ出資した。2012~2013年にかけてのことだ。
日本企業が事業参画したブラジルの造船会社は3社。IHIが傘下のジャパンマリンユナイテッドなどと共同でアトランチコスル造船所に、三菱重工や名村造船所、今治造船、大島造船所などの連合がエコビックス社の経営に参画。また、川崎重工は単独でエンセアーダ社に出資し、3陣営は技術指導部隊や造船所運営に関わる人員を現地に派遣している。
ところが、こうして日本勢が事業に参画した矢先、予期せぬ大問題が起きた。ペトロブラスを巡る大規模な賄賂・汚職スキャンダルだ。
現地では昨年、製油所の建設工事などに絡んで、大手建設会社などが契約の見返りに政治家やペトロブラスの社員らに賄賂を渡していたことが発覚。ペトロブラスの関係者や大手建設会社、プラントエンジ会社の幹部らが相次ぎ逮捕・起訴され、政界にも捜査の手が及んでいる。
ブラジルの新興3造船所が受注した掘削船(3社合計で16隻)は、いずれもペトロブラスの関連会社、セッチブラジル社が発注元。しかし、セッチブラジルも賄賂・汚職の疑いで捜査対象になり、設備投資資金の面倒を見るはずだった国立社会経済開発銀行などが渦中にある同社への融資を凍結。これにより、造船会社に対する前渡し金などの支払いが2014年11月から途絶えたため、各造船所は資金繰りに窮し、深刻な経営・財政状況に陥っている。
IHI、ブラジル関連で290億円の損失計上
こうした事態を受け、事業に参画している日本の重工・造船会社は、前2015年3月期決算で多額の損失計上を強いられた。中でも大きな打撃を被ったのがIHIで、関連損失額は290億円に上った。
損失の内訳は債務保証損失が194億円、のれん代を含む出資分の全額減損で76億円、関連工事損失で21億円。IHIは出資時の株主間協定でアトランチコスル造船所の借入金の一部を債務保証していた。「実際に金融機関から履行を求められたわけではないが、そうしたリスクも高いと判断し、債務保証の全額を損失引当処理した」(財務部長の望月幹夫・常務執行役員)と言う。
また、IHIは現地造船所から請け負う形で、掘削船2隻の居住区や船体ブロックを愛知工場で建造していた。現地造船所から工事代金の入金が途絶えため、建造工事は中断しており、同工事に関わる未回収金なども合わせて損失処理した。
エコビックス社に出資する三菱重工、名村造船所も「株式価値が著しく低下し、回復の見込みが立たない状況にある」と判断し、現時点での出資分全額を15年3月期決算で損失処理した。損失額は三菱重工が80億円強、名村造船所が21億円。2社と連合を組んで出資した非上場組の今治造船、大島造船所も同様の損失を被ったことになる。
唯一、エンセアーダ社に出資(出資総額は48億円)する川崎重工だけは損失処理を見送った。エンセアーダはまだ造船所を建設中の段階。川崎重工の説明によると、「造船所の主要株主である現地のオデブレヒト社が支援しているため、現時点では事業の継続に問題はなく、損失処理の必要性はないと判断した」と言う。
ただ、同造船所もセッチブラジルからの入金が途絶えている状況は同じ。川崎重工はエンセアーダから引き受けた掘削船2隻の船体、推進プロペラ装置の製作を国内の工場で行っており、その入金も現在は途絶えている。国内工事分は大半がNEXI(日本貿易保険)の保険でリスクヘッジされているが、今のような状況が長引けば、出資金や工事代金の一部について損失処理を余儀なくされる可能性がある。
現地の3造船所は掘採船以外でもペトロブラス関連の仕事を数多く受注している。日本企業が経営参画した時点での受注残で見ると、IHIが関わるアトランチコスルはタンカー22隻、掘削船7隻。三菱重工連合のエコビックスはFPSO用の船体8隻と掘削船3隻、川崎重工のエンセアーダは掘削船6隻とFPSO用船体4隻をすでに受注済みだった。
このうち、セッチブラジルが発注元なのは掘削船のみで、FPSO関連やタンカーに関しては支払いが行われているという。ただし、掘削船は1隻700億円以上と契約金額がケタ違いに大きく、本来なら作業の進捗に合わせて支払われるはずの前払い金の入金が途絶えた影響は甚大だ。
3造船所に対するセッチブラジルの遅延前渡し金は、3月時点で総額500億円超に及ぶ模様。資金繰りに窮した現地の造船所は、当座を凌ぐために大量の人員を解雇。また、損失拡大を食い止めるため、アトランチコスルがセッチブラジルに対して掘削船7隻の受注契約破棄を通告するなど、事態は混迷を深めている。
場合によっては、法的整理の可能性も
IHIの斎藤保社長は5月初旬の決算説明会で、「アトランチコスル造船所の再建見通しやブラジル側株主との協議、現地政府による支援などの環境整備次第では、当社も何らかの支援をしていく考えはある」としつつも、「ただし、そうした条件が整わない場合には、清算や民事再生も含めた処置の可能性もある」と厳しい見解を示した。
5月中旬には、IHIの斎藤社長、川崎重工の村山滋社長がみずからブラジルへ乗り込み、三菱重工の現法トップらとともに、ルセフ大統領と直接面会。現地造船会社の窮状を訴え、政府としての救済措置を要請したが、6月3日時点ではまだ支払いは再開されていない。
「ペトロブラス関連の仕事を大量に受注していくことで、ブラジルの造船事業は大きな成長が期待できる」ーー。つい2、3年前にそうした大きな期待を持って、現地企業と手を組んだ日本の重工・造船会社。予想だにしなかったペトロプラスを巡る賄賂・汚職問題の影響に翻弄され、各社は今、“ブラジル問題”に頭を抱えている。
by Wendy Wysong
with contributing authors Kabir Singh and Shobna Chandran
Introduction
Corruption in Singapore has been characterized by high-profile cases involving public officials. For example, in 2014, two former senior public officials were prosecuted for allegedly obtaining sexual gratification in exchange for favoring certain companies; in the same year, a university professor was prosecuted for obtaining sexual gratification and other gifts from a student in exchange for better grades. These cases have raised and clarified interesting issues in relation to Singapore’s anti-corruption laws.
Most recently, however, the Singapore High Court made clear that private sector bribery was equally abhorrent, tripling the jail term (from two to six months) of a marine surveyor convicted on corruption charges relating to the receipt of bribes to omit safety breaches in his reports. Public Prosecutor v Syed Mostofa Romel [2015] SGHC 117.
This case is significant for the guidance it gives on sentencing of corruption charges. More importantly, it dispels the perceived distinction between corruption in the private and public sectors.
Summary of Facts
The accused was an associate consultant with a marine surveying firm. His job was to inspect vessels before they were allowed to be docked at port terminals in order to ensure that the documentation of incoming vessels was in order and that the vessel was seaworthy. If a vessel was classified as high-risk, it would not be allowed to dock unless and until it rectified any problems identified by the surveyor.
In the course of an inspection of an oil tanker off Singapore’s Jurong Island on March 10, 2014, the consultant informed the tanker’s captain and chief engineer of several observations he would be making that would result in a high-risk certification. The captain argued that the defects were minor ones which could be readily rectified. He asked the consultant how the situation could be resolved and the consultant informed him that money would do so.
The consultant omitted the high-risk observations when an agreement was reached as to a suitable sum, but the captain reported the incident once the tanker docked.
The District Court convicted the consultant, but the Prosecution appealed the two-month sentence imposed, as “manifestly inadequate.”
Judgment
The Singapore High Court issued a written judgment on April 28, 2015, tripling the custodial sentence of the accused to six months. In doing so, the Court explicitly rejected as a misperception that only public sector corruption was punishable by custodial sentences while private sector corruption would typically attract only a fine.
The Court noted that with public services being increasingly outsourced, there is a need to hold the private sector accountable for the public services they are responsible for delivering.
The Court stated that although “the ways in which private sector corruption can manifest its ugly head are diverse,” they could be fit into three broad (and non-exhaustive) categories:
1.Those who accept kickbacks for conferring benefits will be given a custodial sentence depending on the specific facts of the case
2.Those who solicit bribes in return for not discharging their duties can also expect custodial sentences
3.Those who solicit bribes by threatening to withhold the legitimate rights of others can expect custodial sentences
The Court pointed out the heightened culpability in the third category because the threat of harm to the paying party without a lawful basis will generally result in the paying party being deprived of his legitimate rights unless he pays a bribe. For example, a bribe may be solicited for the timely processing of applications for licences/permits or to ensure that “an applicant’s application is…not somehow inexplicably misplaced.”
Such offences should result in custodial sentences because they destroy Singapore’s reputation for transparency in the business context. Indeed, the Court observed that such acts which undermine legitimate rights “will not be tolerated and will be severely dealt with.”
Accordingly, the Court found that the conduct of the consultant fell into the third category. Further, the Court disregarded the classification of the consultant as a first-time offender and held that undue weight had been given by the trial judge to his guilty plea.
Implications
This case highlights the stringent approach of the Singapore courts toward corruption in both the public and private sector. In this regard, the Chief Justice opined, “this type of corruption is antithetical to everything Singapore stands for” and “clean and honest dealing is one of [Singapore’s] key competitive advantages and corruption compromises the predictability and openness which Singapore offers and investors have come to expect. This is a hard-won prize achieved through our collective efforts as a society and we must not allow these to be undone. ”
This case further affirms the zero-tolerance policy for corruption in Singapore, regardless of rank and seniority, both in the public and private sectors.
Similarly, in January 2015, the Prime Minister also announced a number of key developments in this area:
1.The Government is reviewing the Prevention of Corruption Act (Singapore’s principal anti-corruption law) with a view to keeping pace with international developments.
2.The Corrupt Practices Investigation Bureau (Singapore’s central agency for investigating corruption) will have its manpower increased by 20 percent from its current strength of about 120.
3.A Corruption Reporting Center will be set up in the city center so that the public can report graft incidents more discreetly and at a more publicly accessible location. This supplements the current avenues available for the public to report corruption to the Corrupt Practices Investigation Bureau.
These recent development demonstrate Singapore’s commitment to maintain the country’s leading reputation for transparency, openness and insusceptibility to corruption.
最近、韓国建造の船の質が下がってきていると感じていたがこう言う背景があったのか?中国建造船の質は上がっていないのだから
発注する船主次第。悪かろう、安かろうで良いのか?船価や傭船料も株みたいに上がったりだから、良い船を持っているから、
安全運航をしているから、儲かるとは限らない。ただ、問題がある船は初期投資が低いだけで問題だらけだと思うが、船主や傭船社が
問題として認識しない限り、状況は改善しないだろう。
中国の造船所も儲けが出ないほど安い船価をオファーして倒産している造船所もあるようだから生き残って様子見もありかもしれない。
人生、山あり、谷ありだが、ビジネスも同じ。
28日の韓国メディア・毎日経済によると、長年にわたって韓国経済を支えてきた造船業の経営が悪化、「今手術をしなければ、韓国経済のがんに」なりかねない状況となっている。
記事によると、城東造船海洋とSPP造船は、受注した船舶を建造する資金が調達できずに債権団に数千億円の資金支援を要請した。支援によって緊急事態は脱したものの、追加受注は受けられない状況だという。他の造船各社も資金不足の状況は同じで、存亡の岐路に立たされている。これまでにSTX造船や城東造船、SPP造船が、融資を返済できずに国策銀行などの傘下に入った。韓国は、国の基幹産業という理由で造船業を支えてきたが、中国による供給過剰や船舶の大型化傾向によって、この手法も限界を迎えつつある。
韓国造船業界の苦境は、中国企業との競争の中で船舶価格が下落したことや、船舶代金の最大90%が船の引き渡し時点にならないと受け取れない「ヘビーテール」方式が一般化したことなどが原因とされる。
こうした中、SPP造船の主力銀行・ウリ銀行は、年内にも同社を中国か日本の造船会社に売却することを検討している。政府や金融機関の間では「個別企業の対応では、造船業を生かすことができない」という共通認識が生まれているためだ。ほかにも城東造船海洋がサムスン重工業や韓進重工業との委託経営を通じた吸収合併を計画、当初は城東造船との統合を目指していたSTX造船は大宇造船海洋の委託経営を目指すなど、業界の構造調整の動きが本格化しつつある。
現代重工業、大宇造船海洋、サムスン重工業という韓国の「造船ビッグ3」も例外ではない。現代は大規模なリストラを実施する一方で、グループ企業が保有する株式を売却するなどして資金を調達している。大宇、サムスンも新成長事業に育てようと投資してきた風力発電事業を縮小・撤退している。
この報道に対し、韓国ネットユーザーからは様々なコメントが寄せられている。
「職員を含めて規模を小さくして、合併するしかない。国内の大手造船会社を中心に合併しないと競争は難しい」
「早く対処したほうがいい。リストラはつらいと思うが、やらないと、業界全体が落ち込むことになる」
「半導体メーカーのように合併以外は道がない」
「いつまで税金でやっていくつもり?すでに斜陽産業。大手以外は撤収しろ。そうしないと、格安で受注して損するだけ」
「頑張って働いてきた社員ではなく、オーナーの家族らをリストラすればいい」
「インドが呼んでいる時に行け。この機会に鉄鋼やらみんなインドに行って、新しい市場で闘ってほしい」
「造船業はもう終わり。中小は生き残れない」
「リストラだけでは、後発国である中国に勝てない。これからベトナムやタイなども入ってくると、韓国には今よりも不利な状況に・・・。決断が必要な時」
「造船所が多すぎる。お互いケンカばかりして受注額を下げないで、協力して上げていく努力をしなければならない。勇気と決断の時」
「これからが始まり。鉄鋼、自動車、半導体・・・次々と沈没していく」
(編集 MJ)
業 種 船舶運行管理
商 号 エスエス海運株式会社<旧・関兵海運(株)>
所在地 東京都
倒産態様 特別清算開始決定受ける
負債額 負債5億円
「東京」 エスエス海運(株)(資本金1000万円、港区南青山1-1-1、代表清算人関駿也氏)は、5月25日に東京地裁より特別清算開始決定を受けた。
当社は、1977年(昭和52年)5月に設立。バブル期に不動産・リゾート事業などを展開して成長した関兵精麦(株)(仙台市)を中核としたグループの1社で、同社や関連会社が所有する船舶の運航および管理業務を手がけていたが、バブル崩壊後に関連会社が相次いで経営難に陥るなか、2003年には関兵精麦(株)が民事再生法の適用を申請(その後、2010年に解散)。以後は同社の資本傘下から外れ、元・関係会社が所有する外国船籍のバルク船の管理、船員や修繕の手配、また他社から調達した傭船を貸船する外航海運業を手がけ、2013年8月期の年収入高は約1億4300万円を計上していた。
しかし、船舶の管理コストや減価償却、税負担も重く、慢性的な赤字決算に陥り、債務超過状態が続いていた。このため、2014年9月1日に親会社のゲートシッピング(株)〈現:関兵海運(株)、同所、同代表〉へ全事業を移管し、同日付で当社は関兵海運(株)から現商号に変更。その後、9月30日に株主総会の決議により解散して債務整理を進め、今年5月18日に特別清算を申請していた。
大型豪華客船に損害がなくて良かったと思っているのだろうか?損傷したら納期が延び、さらなる損失につながる可能性がある。
21日午前2時40分ごろ、三菱重工業長崎造船所(長崎市)の香焼工場で、豪華客船を建造中の高さ約15メートル、約120トンのクレーンが倒れた。周囲に人はおらず、けが人はいなかった。長崎労働基準監督署が原因を調べている。
長崎造船所によると、当時、この大型クレーンは作動していなかったが、近くにあった別のクレーンが、鉄くずを入れるごみ箱(重さ約500キロ)を船に積み込んでいた。このクレーンが旋回した際、ワイヤを巻き上げる部分が大型クレーンのアームに接触した。
大型クレーンは横倒しになり、コンテナ4個がつぶれたが、建造中の豪華客船には当たらなかった。船は全長約300メートルで、ドイツから受注した。造船所は納期に影響はないとしている。
21日午前2時40分ごろ、長崎市の三菱重工長崎造船所香焼(こうやぎ)工場で、大型豪華客船を建造中の高さ約15メートル、約120トンのクレーンが倒れた。けが人はいなかった。造船所によると、倒れたクレーンは稼働しておらず、当時、作業中の別のクレーン(高さ約26メートル)が接触し倒れた。コンテナ4箱が下敷きになりつぶれたという。長崎労基署が原因を調べている。
長崎造船所の別の工場にある「ジャイアント・カンチレバークレーン」など4施設は「明治日本の産業革命遺産」として、国際記念物遺跡会議(イコモス)が今月4日、「世界文化遺産への登録が適当」と勧告した。【竹内麻子】
三菱重工業がここ2年で合計1300億円強の特別損失の計上を余儀なくされた客船の引き渡しが、9月に迫っている。日本で唯一大型客船を建造できる同社の競争力の象徴と期待された客船受注だが、目先は造船事業をけん引するどころか足を引っ張っている。これ以上の遅れは許されない中、建造作業が続く長崎造船所香焼工場(長崎市)をのぞくと、一番船の引き渡しに向け仕事の見直しも含めて苦闘する現場の姿があった。
■倍増の4000人を投入 事務所からの移動時間も短縮
香焼工場の入り口から最も奥まった場所にあるドック。本来は船の修繕に使うためのものだが、現在は巨大な客船が鎮座する。外から見た印象は、巨大な横長のビルを載せた船のようだ。
人、人、人――。先月中旬に工場の高台に案内されてこの客船の中をのぞくと、作業者が所狭しと懸命に動き回る姿がみえた。同工場で客船に投入されているのは4000人弱。「現場はとにかく必死」と案内役の造船所関係者が説明した。
4月に入り、この客船の船腹に、発注元を象徴する「目」のマークが入った。「アイーダ・クルーズ」。世界最大のクルーズ客船会社であるカーニバル社からの発注だ。12万4500総トン、約3300人乗りの超大型客船となる。
現在客船建造に関わる4000人弱は、1年ほど前に比べほぼ倍増している。平常時は2000人前後が働く同工場の人員は客船だけで倍に膨らんでいる計算だ。
通勤などにも影響が出ている。工場はもともと島を埋め立てたもので、長崎市の中心市街地からの道は限られる。出勤と退勤時間帯には、通勤車で大渋滞が起きるようになった。駐車場も足りない。外部に駐車場を借り、バスを使ったピストン輸送で対応している。
さらに中心市街地と香焼工場をつなぐ通勤船を、午前中だけで3往復にするなど増発。大量の作業者の足の確保に奔走する。
働く人たちの事務所も足りない。客船のすぐそばに並ぶのは、数多くのプレハブ小屋だ。事務所が遠ければ、その分移動時間もかかる。船の近くに設置し、数分の時間も削り出す。
三菱重工の客船事業の歴史は優に100年を超える。1908年に竣工した「天洋丸」や、太平洋の女王との呼び名もあった「浅間丸」など豪華客船を相次ぎ建造してきた。
■仕様変更繰り返す一番船 受注額上回る特損計上
いま建造を進めるアイーダ向け客船は、ダイヤモンド・プリンセス以来およそ10年ぶりの大型受注だ。韓国勢などの激しい追い上げをかわし、造船事業を収益源にする狙いがあった。
「三番船だったダイヤモンド・プリンセスと違い、アイーダはプロトタイプの一番船だ」。14年3月、鯨井洋一交通・輸送ドメイン長は約640億円の特別損失を計上することについての記者会見でこう説明した。発注先の要望に応え設計変更を繰り返し、費用が増加。仕様が固まりきっていない一番船の難しさを訴えた。その後、10月に追加の特損400億円を発表した。
今月8日にはさらに297億円を特損として追加計上すると発表した。野島龍彦最高財務責任者(CFO)は同日、「設計が完了し、今後の費用発生の見極めが終わった」としてさらなる引き当て増加を否定したが、この2年で計上した累計の特損は約1300億円と、2隻で1000億円とされる受注額を上回る金額にまで膨らんだ。
■客船部門を分離 エンジニアリング主導で工程管理徹底
三菱重工も客船事業の建造現場のありかたについて、一時的な対応にとどまらず、根本から見直すことを課題と捉えている。客船事業を商船部門から分離し、エンジニアリング部門の主導に移した。
交通システムや化学プラントなどを手掛ける造船外部の人材を長崎造船所に送り込む。オーダーメード型の受注スタイルで工程管理も流動的になりがちな客船事業に、他の事業からのノウハウを移植しながら体質を強化する。
当初予定から半年遅れとなる9月の一番船納入の遅れは許されない。半年後の来年3月には二番船の引き渡しも迫る。
香焼工場から車で30分程の長崎造船所本工場。長崎の中心地にほど近い同工場では、対岸から二番船を建造する様子がうかがえる。一番船の引き渡しが終わり次第、二番船に一気に人を投入する。一息つく余裕はない。
10月には同造船所で手掛ける商船事業の建造と、ブロック製造がそれぞれ分社化される予定だ。他社との連携も模索しているようだ。日本最初の艦船修理工場として創設された現在の長崎造船所。日本の重工業を支えてきた同造船所は、今回の苦難を糧に進化できるか。大きな分岐点に立っている。
(企業報道部 岩戸寿)
ZHEJIANG ZHENG HE SHIPBUILDING CO.,LTD
が倒産した!再生は厳しいと思う!

Dexter Yan
Zhejiang Zhenghe Shipbuilding has filed for restructuring at a Chinese court because of operational difficulties resulting from financial problems.
On 31 March, the People's Court of Dinghai District, Zhoushan Municipality, put on file the restructuring application by Zhenghe Shipbuilding, a statement of the shipyard said on 12 May.
Zhenghe Shipbuilding will enter an official restructuring process in due time, it added. The shipyard predicted that a complete restructuring plan will be published in three to five months.
Currently, the shipyard is gradually resuming production, with the operations and staff stabilised, Zhenghe Shipbuilding said.
According to IHS Maritime's Sea-web.com, the yard's orderbook consisted of nine bulk carriers, which are on order by China Huarong Financial, Seatankers Management, and Zhangjiagang Wan Peng Wood. The earliest delivery is scheduled in May for the 67,000 dwt He Rong.
Zhenghe Shipbuilding is wholly owned by Qingdao Zhenghe Shipping, according to China's company registry system.
In addition, both Zhenghe Shipbuilding and Qingdao Zhenghe Shipping were sued by China CITIC Bank in November 2014 over loan disputes, according to court verdicts seen by IHS Maritime.
いくら補助金を出しても、支援しても再生できない会社や産業は消えるしかないのかもしれない。税金を投入しても
一時的な雇用の維持だけ。
個人的な意見だけど、たしかに時代の流れや技術の進化そして賃金コストのアップによる競争力の低下もある。しかし、倒産する会社の
中には倒産するような従業員だと思うこともある。例えば、良い方向に変えようとする姿勢が見られない、無駄が多いし、給料が少なくなったからと
手を抜くことを考えている、会社の取ってマイナスになることがわかっていても自分には関係ないと無視する、無視出来なくなるまで問題に
対応しない(問題が大きくなり、結果として損失も仕事も多くなる)のような点が倒産した企業の従業員に見られた。データとして比較しているわけでもないし、
個人的な経験からなので違うのかもしれないが、そう感じた。
The European Commission has found that around EUR 290 million (USD 324 million) of public support granted by Portugal to Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A. (ENVC), the former operator of shipyards located in Viana do Castelo in Portugal, was not compatible with EU state aid rules, and is to be paid back by the ENVC.
The Commission decision has taken into account that ENVC is currently in the process of being wound up and that part of its assets (including a sub-concession of the land on which ENVC operated) has been acquired by the private operator WestSea, owned by Martifer and Navalria. Since WestSea only acquired part of the assets and has acquired them at market conditions following an open and competitive tender, the Commission has concluded that WestSea is not the economic successor of ENVC. The obligation to repay the incompatible aid therefore remains with ENVC and is not passed on to WestSea.
ENVC made heavy losses since 2000. Since then, Portugal has directly and indirectly granted continuous subsidies to ENVC via numerous measures, including a capital increase in 2006, several loans granted between 2006 and 2011 to cover operating costs, comfort letters and guarantees to underwrite financing agreements between ENVC and commercial banks.
The Commission found that no private investor would have accepted to subsidise a loss-making company over 13 years. The measures were therefore not granted on market terms and constitute state aid within the meaning of the EU rules. They gave ENVC a significant economic advantage over its competitors, who had to operate without such subsidies, the Commission said.
The Commission further concluded that the measures are not compatible with common rules, in particular the applicable 2004 Guidelines on rescue and restructuring aid, on the basis of which aid to companies in difficulty may be allowed subject to certain conditions:
•ENVC, at the time, had no realistic restructuring program to ensure the company’s long-term viability without further state support; •ENVC received repeated aid, at least over the last ten years, in breach of the “one time last time” principle, which allows the grant of rescue or restructuring aid only once in a ten-year period.
2隻で約1千億円とみられる受注額よりも損失額(1336億円)が大きい。多くの管理職が処分を受けるのだろうね。
個人的な意見だが、例え三菱重工業が多くの客船やフェリーを建造していても、ヨーロッパ仕様の設計だと内装、内装の詳細、取付位置、搭載機器
などが日本仕様とは違う。ヨーロッパの人はこだわりが強いので詳細な打合せ及び末端の施工業者が指示を理解していないとやり直しとなるケースが
ある。一般の商船を見ても日本の最低グレード仕様、日本の仕様、韓国造船所のヨーロッパ船主仕様、ヨーロッパで建造された船の仕様を見ても
明らかに違うことがわかる。まして客船になると想像出来ない仕様だと思う。残念ながら日本の造船所は韓国の造船所と比べればヨーロッパ仕様に
対する経験が少ない。確かに韓国船籍旅客船「セウォル号」(M/V"SEWOL", IMO9105205)の大惨事
で韓国の造船所はフェリーを建造する技術の蓄積や経験がないことが明確となった。小型の内航船になると日本の方が明らかに進んでいる。これは韓国では
多くの日本建造内航船が使われており、韓国で新造船を建造するよりも日本の中古船を買う方が安く、品質にも問題がないため。韓国では
小型船を建造する造船所は倒産、消滅、又は、大型船の建造に切り替えたケース多いため、小型船を建造するのが難しくなった。やはり物作りは
継続して作り続けなければ進歩がないし、下手すれば技術が継承されない、そして競争力もなくなる。技術の蓄積や経験が
なければ他の種類の船を建造できるからどんな船でも簡単に建造できるわけではないことが明らかになったと思う。
韓国の造船所は経験のない海洋プラント産業を受注して大きな損失を出している。
この点では三菱重工業と同じ失敗をしていると言える。
 三菱重工業は8日、長崎造船所(長崎市)で進む2隻の大型客船の建造が難航しているため、累計1336億円の損失を計上したと発表した。設計の不具合や造り直しが相次いで損失がふくらみ、2隻で約1千億円とみられる受注額を上回る規模になった。
三菱重工業は8日、長崎造船所(長崎市)で進む2隻の大型客船の建造が難航しているため、累計1336億円の損失を計上したと発表した。設計の不具合や造り直しが相次いで損失がふくらみ、2隻で約1千億円とみられる受注額を上回る規模になった。
8日発表した2015年3月期決算で、これまでの損失額1039億円に加え、297億円の特別損失を計上した。純利益は前年比31・2%減の1104億円となった。
大型客船は、世界最大のクルーズ会社カーニバル社の子会社から11年11月に受注。長さ約300メートル、約3300人乗りで、三菱重工が11年ぶりに受注した客船だった。だが設計が難航し、大幅な造り直しも必要になったことで多くの人員を投入せざるを得なくなった。1隻目は予定より半年遅れて今年9月、2隻目は16年春に引き渡しを迎える予定だ。(南日慶子)
Shanghai: Financially troubled Sainty Marine has announced that the company currently has RMB357.3m ($57.5m) worth of loan payments in arrears, just a day after a court froze RMB300m ($48.42m) worth of assets of three major shareholders of the company due to its inability to repay loans to Bank of Jiangsu.
The banks owed the payments are Bank of Jiangsu, Bank of Nanjing and China Merchants Bank, and Sainty Marine said it is currently in talks with the financial institutions to try and solve the issue.
The shipyard is now in the process of restructuring the bankrupt Mingde Heavy Industry and might face up to RMB2.94bn ($473m) in losses if the restructuring fails. It is also facing the huge risk of not being able to collect repayments from its financing business, with several ongoing lawsuits with debtor companies.
Meanwhile, the company’s stock trading has been restricted by the stock exchange due to breach of local listing rules.
韓国で昨年4月に起きたセウォル号沈没事故で、世界最大の保険組織・英ロイズ保険組合が保険金支払いを拒否する可能性が高いと現地メディアが報じた。一方、軍の次期戦闘機の開発計画では、米国側がレーダーなどの重要な軍事技術の提供を拒否していたことが判明。セウォル号では常態化していた過積載や船長・乗員の事故後の対応が、戦闘機では機密扱いの技術の管理態勢などがそれぞれ問題視され、協力が得られなかったとみられる。さまざまな分野で「規則違反」が横行する韓国だが、そうしたツケが回ってきたといえそうだ。(岡田敏彦)
政情不安に新たな火種
朴槿恵(パク・クネ)大統領が外遊から帰国し、過労による胃けいれんといん頭炎で療養。経済面ではウォン高に見舞われ、首相は違法献金疑惑で辞職、ソウルで起きたセウォル号遺族らによる反政府デモでは、バリケードがわりの警察車両(大型バス)約70台が破壊される被害…。
こんな“弱り目にたたり目”状態の韓国で、渦中のセウォル号遺族に対する保険金が支払われない可能性が出てきたことを、韓国メディア「ネイバーニュース」が報じた。大型客船事故で保険金が支払われないとはどういうことなのか。
老舗の掟
セウォル号を運行していた清海鎮海運は、1人あたり3億5千万ウォン(約3850万円)の保険契約を韓国海運組合と締結していた。同組合はさらに三星火災とコリアンリという「再保険会社」2社の保険に加入。さらにこの2社は再保険引き受け専門の組織「ロイズ保険組合」(英国)に保険加入していた。
再保険とは、大規模な自然災害や大事故などの巨大なリスクは1社では対応し切れないため、リスクを他の会社と分担するためのもの。ロイズ保険組合は1688年、ロンドンに開店した喫茶店で保険業を始めたという老舗で、保険金はしっかり支払われると思われたが…。
重過失の連続
セウォル号事故をめぐっては、もうけ主義に走った末の過積載やバラスト水の不適切な扱い、運行の未熟さ、さらに救難措置を行わず真っ先に逃げ出した船長や船員など、とんでもない実態が次々と明らかになった。こうした点が、保険の免責理由の「重過失」にあたるのでは-と、今更ながら韓国保険業界で問題となったのだ。
このため三星火災とコリアンリの2社が、弁護士付き添いでロイズに出向いて議論すると報じられた。
清海鎮海運のオーナーは事故後遺体で発見され、韓国政府はその一族から4千億ウォン(440億円)相当の資産を差し押さえるとされているが、朴大統領が国民に約束したセウォル号引き揚げ作業の費用だけでも4千億ウォンを上回る見込み。1983年の大韓航空機撃墜事件同様、遺族への賠償額がすずめの涙となる可能性もあるとみられている。
海も空も信用不安
凪(な)いだ海でのフェリー転覆が約300人もの死亡事故に発展するのだから、保険会社も運行関係者を信用できなくて当然だが、こうした信用不安は「空」にも広がっている。韓国の次期主力戦闘機、KFX開発が“迷走”しているのだ。
開発計画が発表されたのは2001年。老朽化しつつあるF-5戦闘機やF-4ファントム戦闘機の代替戦闘機を国産で開発、生産しようという野心的なプロジェクトで、米国の戦闘機メーカーからレーダーに映らない「ステルス技術」など、最新技術を無償提供してもらおうと計画した。
あれから14年…
ところが計画は遅々として進まず。紆余(うよ)曲折を経て今年3月、米航空機メーカーのロッキード・マーチンと組んだ韓国航空宇宙産業(KAI)と、欧州航空機大手のエアバスと組んだ大韓航空の2社が開発事業に入札。結果、ロッキード・マーチンとKAIのチームが選ばれた。
ようやく開発が始動するとあって、中央日報(電子版)など現地マスコミは一斉に今後の展開も予測。中央日報は「19兆ウォン(約2兆円)投入 ステルス技術がカギ」とのタイトルで詳報。「開発に成功すれば(現在の韓国空軍主力戦闘機でアメリカ製の)F-16より優秀な戦闘機を保有することになる」と報じたが、すぐにそれが楽観的な見方だったことが分かる。現地メディア「アジア・トゥデイ」が、ステルスなどの最新技術は何一つ供与されないと報じたのだ。
ブラックボックスを積んでいく作業
現地報道を総合すると、KFX事業のキモとなる最新AESA(アクティブ電子走査アレイ)レーダーを始め、IRST(赤外線捜索追尾システム)や電子妨害装置などの最先端装置は、米ロッキード・マーチン社が生産し、韓国KAIはその「できあがった装置」を機体に組み付けるだけになるという。
中身の仕組みは公開せず、分解も不可能とした「ブラックボックス」を指示通りに本体に接続する作業だ。米国は、軍事機密の塊ともいえる装置の仕組みを韓国に教えて生産させること、つまり韓国への「技術移転」を許さないという選択をとったのだ。
この背景には韓国側の数々の疑惑がある。かつてF-15Kの目標探知センサー「タイガーアイ」を勝手に分解したなどの疑惑があった韓国軍だが、昨年にはこうした疑惑をはるかに越えるスパイ事件が明らかになっている。
風俗店で接待…
現地マスコミによると、海軍の次期新軍艦や武装ヘリコプターなどに関する軍事機密31件が7年間にわたって流出し、関わった軍事企業の役員や予備役(OB)の空軍中佐、同海軍大尉ら7人が昨年夏に逮捕、起訴された。その手口もさることながら、驚くのは軍事機密の“安さ”だ。
聯合ニュース(電子版)によると、防衛事業庁の40代の少佐は、風俗店で2度の接待を受け、武装ヘリコプターのナビゲーションシステムの開発結果リポートを、韓国防衛産業の「K社」のキム理事に提供。また同庁の40代の大佐は、訓練機購入計画のメモを同理事に渡した見返りとして、250万ウォン(約27万5千円)のギターを受け取り、さらに風俗店での接待も受けていた。
メールで機密を送信、色仕掛けも
また軍の将校らもキム理事に防衛機密を漏洩(ろうえい)。機密文書を携帯電話で撮影してメールで送信するなど、極めてお気軽に軍の情報をリークしていた。こうした機密情報のなかには、敵戦闘機の電子妨害装置を無力化するアンチジャミングシステムなど韓国では自主開発できない、つまり米軍から供与された最先端技術が含まれていたとされる。
一方でキム理事は「若い女性社員を雇って将校との夕食や登山会に参加させていた」とも報じられた。ちなみに韓国の「登山会」とは売春斡旋(あっせん)業者の隠れみのとして利用されたこともある。また登山といっても韓国は低い山ばかりで、そうした山域は「バッカスおばさん」(バッカスという商品名の滋養強壮剤を売りつつ売春をもちかける中高年女性を指す)の活動場所でもある。二重三重の色仕掛けで軍の将校を籠絡していた可能性がある。
古典的な色仕掛けで米国から供与された軍事機密が漏れたのも問題だが、信じられないのはその後の展開だ。
韓国軍と検察は、機密を得た国内の防衛業者らに対しては社屋などを捜索して原本を押収したが、海外の防衛業者に対しては「自主的な削除を勧告した」だけという。漏れたまま放置しているに等しい措置で、国内からも批判が出ている。こんな状態で米国が最新技術を韓国に与えることはありえないだろう。
他の船を検索していたら偶然に見つけた。単なる中国建造のタンカーなのだが、日本の海運会社の船のようだ。中国建造のケミカルタンカーが日本で運航される時代になったのか?もっと大きな中国建造タンカーについてバルブがすぐにだめになった、漏れがひどい、 機器がすぐ壊れる等の話は良く聞くが、この船はどうなのだろうか。バルカーの話だが中国建造の船に不満な外国船主が円安で日本に帰って来ている。 安いのだから仕方がないと思わなければ中国建造は????
Oslo-listed subsea contractor Cecon ASA has requested from a Norwegian court to declare it bankrupt having failed to present a restructuring plan.
Over the last 4 months, Cecon has been subject to compulsory composition proceedings, during which time it explored all possibilities for a debt restructuring solution which would give the creditors of the company a minimum of 25% dividend over time.
“Up until very recently, the company was working on a solution that, while being complex, was promising. However and due to recent and unforeseen events, the company’s cash balance (in Escrow against the Gdf contract ) was given to GdF against the company´s will and understanding of the Escrow terms. This has eliminated a very important building block in the restructuring solution,” Cecon said in a statement.
As a result, the company’s board of directors has decided to notify the compulsory composition committee that Cecon is unable to present a plan for a compulsory composition – whereby the committee will notify the same to the City Court of Aust-Agder and request that the company is declared bankrupt.
APRIL 24, 2015 — Norwegian construction vessel company Cecon ASA is filing for bankruptcy. The company is probably best known to Marine Log readers for the saga involving the three newbuilds that it ordered from Canada's Davie shipyard in 2007 for delivery in 2009. The first of the trio was eventually handed over in August last year and the second was launched earlier this year.
What looks to have pushed Cecon over the edge appears to be a financial crisis related to a contract secured with GdF Suez.
In an Oslo stock exchange filing today, Cecon says it "has over the last four months been subject to compulsory composition proceedings, during which time the company has explored all possibilities for a debt restructuring solution which would give the creditors of the company a minimum of 25% dividend over time.
"Up until very recently, the company was working on a solution that, while being complex, was promising. However and due to recent and unforeseen events, the company's cash balance (in escrow against the GdF contract ) was given to GdF against the company's will and understanding of the escrow terms. This has eliminated a very important building block in the restructuring solution.
"The board of directors of the company has decided to notify the compulsory composition committee that the company is unable to present a plan for a compulsory composition - whereby the compulsory composition committee will notify the same to the City Court of Aust-Agder and request that the company is declared bankrupt.
"The company is a holding company and the companies it is invested in will continue its operations as prior to this."
Posted by Eric Haun
Twenty-eight units of Brazilian engineering firm Grupo Schahin filed for bankruptcy protection on Friday as fallout from a corruption scandal at key client Petróleo Brasileiro SA hampered efforts to refinance up to 6.5 billion reais ($2.1 billion) in debt.
Schahin, which has businesses ranging from engineering and electricity to oil and gas services, made the request for creditor protection in a São Paulo state court, according to a statement. Under terms of the bankruptcy protection plan, Schahin plans to abandon its activities in engineering and construction and focus on oil and gas services.
A. Qua.
Genoa - The shipping company Energy Shipping brought its books to court yesterday. Energy Shipping is a subsidiary of the Ascheri Group that is active in the dry bulk transportation sector, the company had only one ship of its own, despite a massive programme of investment launched in recent years.
According to sources in the sector, the company’s debt is about €18 million, essentially owed to two companies from which Ascheri rented two ships in the long term. Having broken the contract prematurely, the two companies asked for early payment of rental, which shook the little Genoese company’s account books. Energy Shipping is a subsidiary of the Ascheri group, and is currently in negotiations with its creditors (and which obtained a €4-million loan from the banks yesterday).
Greg Miller
Italian owner Rizzo Bottiglieri-De Carlini Armatori (RBDA) has filed for Chapter 15 bankruptcy protection in Houston, Texas.
The mixed fleet operator, which owns 16 bulkers and tankers, sought court protection in Italy on 3 February. The US filing on 8 April is intended as an ancillary asset shield to complement primary protection under Italian bankruptcy law.
RBDA noted in its court filings that two of its bulkers - RBD Italia and Maria Cristian Rizzo - were targeted with arrest warrants after court filings by ING bank last month. Those cases were related to the OW Bunker insolvency; ING is the agent for a USD700 million OW Bunker credit facility and has targeted vessels that purchased fuel from OW Bunker.
"Although both of those cases were resolved, there are additional vessels which are or will shortly be calling in the ports of the US," said RBDA director Giuseppe Mauro Rizzo in his company's Chapter 15 bankruptcy petition.
"Over the course of the past several years, RBDA has faced significant challenges," said Rizzo. "The environment of economic distress caused by the worldwide recession has had a direct impact on RBDA's operations."
At the time of its Italian insolvency filing, RBDA had total assets of USD773.6 million and total liabilities of USD813 million, including USD785.9 million in bank debt.
中国にVLGCを発注するリスク。リスクを恐れていては儲けはない。しかし、無謀と勝負は違うような気がする。まあ、下記の記事だと 船主は損しないと言う事だけど、日本の荷主だったら許してくれないのでは??MOLが中国建造のガス船を運航している/運航する予定? 実際、問題はないのだろうか?
Shanghai: Judger Shipbuilding, a Wenzhou-based private shipyard invested by Zhejiang Judger Group, has officially filed for bankruptcy with Wenzhou Intermediate People’s Court.
The shipyard has been suffering from financial difficulties since 2012. Wenzhou local government also attempted to save yards by offering some financial support.
Judger Shipbuilding has managed to sell two 82,000 dwt bulkers abandoned by Hong Kong owner Parakou Shipping in 2013 and 2014. However, the shipyard was still unable to solve its debt crisis and decided to file for bankruptcy.
The shipyard currently has debt of around RMB1.72bn ($277m) in total. The first creditors’ meeting will be held on May 27.
朴槿恵(パク・クネ)大統領は2013年に韓半島(朝鮮半島)と欧州を鉄道でつなぐ「シルクロード・エクスプレス(SRX)」事業を推進すると明らかにした。その後、中国政府が東アジアと欧州を陸路と海路で連結する「一帯一路」政策を宣言すると、SRX事業はより一層現実的な構想になった。しかし北朝鮮が非友好的態度を見せながらSRX事業は前進できなかった。数日前、北朝鮮は5月27日にソウルで開かれる「国際鉄道協力機構(OSJD)」会議に参加しないと明らかにした。SRXの見通しがより一層暗くなったわけだ。北朝鮮経由の鉄道路線についての代案として早くから議論されていたのは西海(ソヘ)を横切る列車フェリーだ。造船と海運の専門家であるソ・サンヒョン博士に西海列車フェリーを利用したSRXの展望を聞いてみた。合わせて韓国経済において重要な役割を果たす造船・海洋プラント産業の現状と展望について考えてみる。
--SRX事業は素晴らしい構想だ。しかし事業があまりにもぼう大で国際的なだけに、さまざまな問題もある。最も決定的問題は、鉄道が北朝鮮を通り過ぎるという事情だ。北朝鮮鉄道が老朽化して実質的に新しく敷設しなければならないという事実も大きな問題だが、北朝鮮の政治的不安と敵対的態度はさらに大きな問題だ。かなり前から代案として議論されていた西海列車フェリーはどんな事業なのか。
「韓国と欧州をつなぐSRXは、窮極的にはユーラシア横断鉄道網に接続しなければならない。その鉄道網は一番東側にシベリア横断鉄道(TSR)があり、その西側に中国を通る路線3本がある。満州を通る路線(TMR)、モンゴルを通る路線(TMGR)、そして中国北部を経て中央アジアを通り過ぎる路線(TCR)だ。いつか私たちの鉄道がこの路線すべてと連結されるだろう。しかし中国の急速な発展と比重を考えれば、TCRが中心路線になることは明らかだ。シベリアを経由するほかの路線とは違ってTCRは人口が密集した中国中心部を通り過ぎるため経済的にはかなり有利だ。TCRとの接続は北朝鮮を経ればむしろ非効率的だ。新義州(シンウィジュ)をすぎて満州、西海岸(ソヘアン)に背を向けて中国中心部に再び降りて行く路線だと遠回りになる。列車フェリーを利用すればすぐに西海を渡る。距離がはるかに短く経済的だろう」
--西海列車フェリーが経済的だということは明白だが、北朝鮮の影響を受けないために安定的に運営できることがかえってより大きな長所ではないか。
「そうだ。これまで開城(ケソン)工業団地で北朝鮮の極悪非道な態度によって韓国企業と政府がどれほど大変な困難を体験しただろうか。今でも北朝鮮の一方的な賃金引き上げ要求で厳しい境遇だ。北朝鮮が何かと理由をつけて鉄道を防げれば韓国はとても困惑してしまう。SRXが西海フェリーによってTCRに連結されるならば、そんなリスクは消える」
--西海フェリーは北朝鮮を通り過ぎる路線の運営にも役立ちそうだ。西海フェリーとTCRが主交易路になれば北朝鮮が享受する地理的優勢が弱まる。万一、SRXの4路線がすべて北朝鮮を通り過ぎることになれば北朝鮮は自らの独占的地位を目いっぱい享受しようとするし、私たちは困り果ててしまう。中国政府でも西海フェリー案を歓迎しているのか。
「中国政府が韓国政府よりも積極的だ。自ら野心的に推進するTCRの成功に役立つからだろう。2002年に韓国建設交通部と中国鉄道部が列車フェリー事業を推進することで合意した。中国は2011年初めに山東省の煙台港をフェリー寄港地として選定し、韓国も数カ月後に平沢(ピョンテク)・唐津(タンジン)港を選定した。煙台地方政府はその後、この事業に高い関心を見せてきたし、韓国側は経済首席秘書官で朴正煕(パク・チョンヒ)大統領を補佐したシン・ドンシク博士がずっと中国の人々と協力してきた」
--SRXが北朝鮮を通り過ぎるとなれば北朝鮮は良い牌を手にしたと判断するようだ。ソウルで開かれるOSJD会議で韓国が加入することになったが、北朝鮮が参加しないとして韓国の加入が遅れることになった。私たちは平壌(ピョンヤン)で開かれた会議に参加したのに北朝鮮が参加しないのはそうした計算から出たのだろう。西海フェリーをTCRに結びつける案は北朝鮮の否定的態度に対する良い対策と思われる。
「そうだ。北朝鮮鉄道の実質的な再建に入る莫大な費用と長い時間が全くかからないという大きな利点まである。すでに中国から新疆省と中央アジアを経て欧州に達する路線にドイツが定期列車を就役した。今から積極的に乗り出せば2~3年以内に西海フェリーがTCRに連結できる。すべての条件が良くても北朝鮮の鉄道再建には最低5年はかかると推算されている。北朝鮮との関係が良くなっても北朝鮮を経るSRXが10年以内には建設できないという話だ。私たちの合理的選択は明らかだ」
--韓国政府が西海フェリーに消極的だったのは政治的意味合いもありそうだ。北朝鮮との関係を改善しろとの世論を考慮して、韓国政府は北朝鮮との関係改善という政治的目標をいつも念頭に置きながら具体的事業を推進する傾向がある。北朝鮮はもちろんその点を逆に利用しているし。それで具体的事業が政治的影響を受けてまともに推進されない。SRX事業も同じだ。韓国政府は初めからSRX事業を北朝鮮との関係改善の端緒としていたような印象がある。今も「北朝鮮リスク」を事業計画に反映しなければならないようだ。
「窮極的に重要なのは韓国が代替的な輸送路線を多数確保することだ。それでこそ経由国の政治的影響から自由でありうる。西海フェリーはそうした大きな戦略に応えたのものといえる」
--代替的な路線を確保しなければならないという言葉を聞くと、北極航路を思い浮かべる。北極航路は一時大きな関心を集めたが、現実性はあるのか。
「地球温暖化で北極海を経て欧州に向かる航路が有望になっている。しかしいまだ結氷期間が長く常時運行は不可能だ。苛酷な気候、短い日照時間、環境汚染のリスクのような制約要因も障害だ。実際に商船が往来するにはロシア海岸に船が立ち寄って燃料を供給して遭難時に避難できる港がいくつか必要だ。そのため北極航路はいまだ現実性がない。だが北極海で石油を開発する事業が活発になれば、韓国の造船・海洋プラント産業にとっては良い機会になるだろう。特に地理的に有利な釜山(プサン)港が大きな恩恵を受けるだろう」
--一時は韓国が世界で最も多い船を作っていたが、近年は中国に押されている。主な原因は何か。
「今回の経済危機が近づく前は世界的に多くの船が発注された。経済危機が近づいて物流量が減ると船舶が余り、船舶発注は減った。深海で石油を採掘する事業の採算性が低くなり、海洋プラントへの需要まで減った」
--韓国の造船所が海洋プラント分野に進出して大きな損失を出したことが危機の直接的原因だという話がある。
「海洋プラントは深海から石油を採掘する設備なので極限状況で運用される。自然に設計・製作・運用・整備および撤去で多くの先端技術が必要だ。韓国の造船所はこの分野に初めて進出したため経験もなく技術も不足していた。それまで造船分野で積み重ねてきた経験と技術を応用すれば良いだろうと考えていたが、実際にやってみると韓国の造船所には耐えがたいということが分かった。経験もなく設計能力が不足すると正確な原価計算さえ難しかった。韓国の造船所間の競争も激しかった。結局、韓国の造船所がとても低い値段で応札したことが明らかになったりもした」
--対策と展望は。
「このように残念な結果は韓国の造船所が海洋プラント分野に初めての進出しながら払った授業料だといえる。これからは何より設計能力を育てなければならない。韓国の造船所の強みが建造能力なのに、設計能力が不足していれば設計会社に縛られ利益を出しにくい。さらには設備の運用、整備および撤去でも能力が向上すれば高い競争力を備えることができる。研究開発に投資して技術が向上すれば状況が良くなるだろうと思われる」
--研究開発への投資はまともに成り立つのか。
「海洋プラント設計エンジニアリングセンターが今年から活動する予定だ。船舶海洋プラント研究所では釜山に深海工学水槽を2017年から運用する予定だ。最も深い部分が50メートルあるこの水槽で実験すれば、より精巧な設計が可能になる。海洋プラントの経済性は石油とガス価格の騰落に影響を受ける。それで短期的には採算性が悪化したが、長期的には有望な分野だといえる」
--韓国の造船所の建造競争力はどれほどのものか。中国の造船所が韓国を追い抜いたが。
「韓国の造船所は全般的に設計・建造が厳しいが、付加価値の大きい船舶分野で競争力があるといえる。経済が発展して所得が高まった国は労働集約的分野から退いて技術集約的分野を切り開くという一般的傾向が、造船産業においても適用されるだろう。政府の莫大な支援を受けていち早く成長した中国の造船所は一般船舶分野で当分優位を維持するだろう」
--韓国の造船所が特に強みを持つ技術は。
「建造・設計分野で競争力が高い。特にガスを利用した推進力の開発で卓越している。LNGやLPGを積み出す船がこの推進力を使えば燃料を別に載せる必要がないため競争力が高い。大型コンテナ船の技術でも世界最高レベルだ」
--クルーズ船の展望はどうか。
「クルーズ船の船体を建造するのは特別なことではない。しかしクルーズ船は海上のホテルと同じだ。重要なのは快適で優雅な生活環境のデザインだろう。その点では韓国は欧州に大きく立ち遅れている。実は造船技術で最も先んじた日本もクルーズ船分野には進出できなかった」
ソ・サンヒョン博士…1956年釜山(プサン)生まれ。ソウル大学造船工学科卒。ミシガン大学船舶海洋工学科卒(船舶制御・自動化分野の研究で工学博士取得)。海洋研究所海洋システム研究本部長、韓国水路学会副会長役。現在は船舶海洋プラント研究所長。電子海図、海洋地理情報・衛星航法システム分野で開拓的な研究を遂行した。大韓民国水域電子海図開発に対する功績で2001年大統領表彰を受ける。
<インタビュー後記>中国鉄道連結、次期政権でも推進すべき
科学者や工学者らと話すと彼らの時間軸(time-horizon)が非常に長いことを改めて悟らされる。科学的発見や技術的発明は長くかかる。そのような発見や発明の実用化はさらに長くかかることもある。新しい技術を社会基盤施設に適用することは当然長くかかる。世論に敏感な政界や言論界は時間軸が短くならざるをえない。自然に科学や技術から出る発展などは社会の関心をあまり受けない。SRXのような国際的事業は特に長い観点で推進されなければならない。問題は韓国で1つの政権の時間軸を5年以上延ばせないという事情だ。現政権で提案し、いまだ具体化されなかったからといって次の政権でその事業がまともに推進されるのかどうか誰も断言できない。長期的に韓国企業の競争力を高めるのに重要な事業であるので、いち早く事業の運動量を増やして次の政権でも活発に推進されなければいけないということでソ博士と私は意見を共にした。
IHIは6日、ブラジル造船事業の不振で2015年3月期の連結決算で53億円の損失を計上する見通しだと発表した。IHIが投資目的会社を通じて出資している造船会社、アトランチコスル(EAS)の経営悪化に伴う損失を計上する。
EASは、汚職事件の舞台となったブラジル国営石油会社ペトロブラス子会社からタンカーや石油掘削船を受注していた。汚職事件で発注元の資金繰りが悪化、一部未払いも生じており、IHIはEASへの出資金を減損処理した上で、投資目的会社がEASに対して行っていた銀行借り入れ保証も負担する。
このほか、IHIはEASに対する連結保証債務が3月末時点で194億円あるが、「現時点では保証の履行請求はない」(広報)としている。また、IHIの愛知工場(愛知県知多市)でペトロブラス向けに掘削船の居住スペースや船殻ブロックなど約200億円分を受注したが、汚職の影響で進捗(しんちょく)率約4割で建造を中断している。
世界3位の造船会社、大宇造船海洋が社長選任の遅れで危機に陥っている。同社の今年の月間受注額は1月の12億ドル(約1430億円)から2月には2億ドル(約240億円)に減り、3月は「ゼロ」になった。昨年12月、高載浩(コ・ジェホ)社長の交代がささやかれるようになって以降、大株主である韓国産業銀行が後任社長の選任を4カ月近く先送りしているため、1隻当たり数千億ウォン(数百億円)の船を発注する海外の海運会社が「誰が社長になるかも分からない状況では契約できない」と契約を拒んでいるのだ。同社のある役員は「今年の受注が少なければ、2017年には造船所が空いてしまいかねない」と危機感を募らせている。
産業銀行は来月中に社長を選任するとしているが、公示の日程などを考慮すると時間はあまり残っていない。先月29日付で社長の任期が満了した高載浩氏は、後任が決まるまで社長代行を務めている。社長の選任が遅れている理由をめぐり、業界では「政府が天下りをさせるため時間稼ぎをしている」との憶測が広がっている。会社のムードはすでに滅茶苦茶だ。続投が有力視されていた高氏が退任するかもしれないとのうわさが出て以降、社長のポストをめぐり派閥争いが盛んになり、ネガティブキャンペーンが起きたり怪文書が出回ったりした。
「注文した船はちゃんと完成するのか」という海外海運会社からの問い合わせも相次いでいる。大宇造船海洋に4隻の商船を発注した「ギリシャの船舶王」ジョン・アンジェリクシス氏は韓国に派遣した社員に対し、社長選任の行方などを毎日報告するよう指示した。また、ロシアの海運会社ソブコムフロットのセルゲイ・フランク会長は先月11日に自ら訪韓し「発注した15隻の砕氷LNG(液化天然ガス)運搬船の建造スケジュールに支障が出ないか懸念される」と述べた。
専門家らは、銀行側と政府は天下りをあきらめ、今からでも取締役会に社長の選任を任せるべきだと指摘している。同社の元社外取締役は「このままでは世界3位の造船所が3流造船所になってしまいかねず、韓国経済全体に悪影響が及ぶ」と懸念を示した。これに対し、産業銀行側は、5月に臨時株主総会を開いて新社長を選任する案を推進していると説明した。
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 金起弘(キム・ギホン)記者
Oslo: Avance Gas has said that VLGC Monsoon (83,000dwt, built 2015), delivered from Jiangnan Shipyard in January, will be dry docked at Zhoushan Changhong International Shipyard this week.
The company said that technical irregularities occurred during its current voyage from Panama to China, and the vessel will head to the repair yard upon completion of discharge.
Investigations will then get underway to look at the cause of the defects and assess the scope of the work required. While the ship is under warranty from the yard, Avance will be looking at significant lost revenue while the vessel is out of action, and the company said that based on the report from the team investigating the defects, it will assess what stress tests will need to be applied to the sister ships to ensure that no similar technical defects occur.
The series of orders seem plagued with issues. Last April, a fire broke out on board one of the newbuildings although no injuries were reported with the fire extinguished almost immediately. Later in August, another fire broke out on one of the vessels, taking two hours to be put out.
Avance has six more of the vessels set to deliver from Jiangnan through the course of this year, having ordered a total of eight.
Norwegian owner and operator of Very Large Gas Carriers (VLGC) Avance Gas will dry dock the recently delivered VLGC Monsoon after technical irregularities occurred during the vessel’s voyage from Balboa (Panama) to China.
The VLGC Monsoon, the second hull delivered from Jiangnan Shipyard in January 2015, will be dry docked at Zhoushan Changhong International Shipyard close to Ningbo around April 1.
Third party experts will perform investigations of the cause of the defects once the ship is docked.
Avance says that the scope of the rectification work and the off-hire period will be assessed as soon as the report from the experts is received, expected around mid April.
The ship is under warranties from the Jiangnan Shipyard and no major costs is expected in relation to the dry-docking, apart from possible lost revenue.
Based on the report from the experts, it will also be assessed what stress test will be applied to the sister ships to ensure that no similar technical defects occur.
VLGC Monsoon was on a 60-90 days time charter with an undisclosed charterer, started in early February.
The Monsoon was delivered on January 13, together with its sister ship VLGCs Mistral.
By GlobeNewswire
Bermuda, 28 March: Avance Gas (OSE: AVANCE) reports that VLGC Monsoon, the second hull delivered from Jiangnan Shipyard in January 2015, will be dry docked at Zhoushan Changhong International Shipyard close to Ningbo around 1 April 2015, upon completion of current discharge operations due to technical irregularities occurred during the voyage from Balboa (Panama) to China. Third party experts will perform investigations of the cause of the defects once the ship is docked. The scope of the rectification work and the off-hire period will be assessed as soon as the report from the experts is received, expected around mid April. The ship is under warranties from the Jiangnan Shipyard and no major costs is expected in relation to the dry-docking, apart from possible lost revenue. Based on the report from the experts, it will also be assessed what stress test will applied to the sister ships to ensure that no similar technical defects will occur.
For further queries, please contact:
Christian Andersen, President
Tel: +47 22 00 48 05 / Email: c.andersen@avancegas.com
Peder C. G. Simonsen, CFO
Tel: +47 22 00 48 15 / Email: p.simonsen@avancegas.com
ABOUT AVANCE GAS
Avance Gas operates in the global market for transportation of liquefied petroleum gas (LPG). The Company is one of the world's leading owners and operators of very large gas carrier (VLGC), and operates a fleet of eight modern ships and has a newbuilding program of six VLGCs. For more information about Avance Gas, please visit: www.avancegas.com.
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.
by Selina Lum The Straits Times
MARINE surveyor whose job was to inspect ships before they berthed, but asked for bribes to omit safety breaches in his report, yesterday had his jail term for corruption tripled from two months to six.
Syed Mostofa Romel, 50, was caught red-handed last May in a sting operation by the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), in which safety breaches were planted on a vessel and the dollar bills handed to Romel were marked.
The Bangladeshi was sentenced to two months' jail by a district court last month.
The prosecution appealed to the High Court, arguing that the original sentence was "unduly lenient" and did not reflect the seriousness of the danger posed by his corrupt acts.
Chief Justice Sundaresh Menon agreed. "This type of corruption is antithetical to everything Singapore stands for," he said as he upped the jail term for Romel, who was due to be released on Sunday.
Romel was an associate consultant with a marine surveying firm whose job was to inspect vessels before they were allowed to be docked at port terminals.
The checks include making sure that the documentation was in order and that the vessel was seaworthy.
A ship classified as low or medium risk would generally be allowed to dock. If a ship was classified as high-risk, the operator would have to rectify the problems identified before the ship was allowed to be docked, thus incurring delays and additional costs.
On Mar 10 last year, after inspecting the tanker Torero at a terminal off Jurong Island, Romel told the captain and chief engineer that he had made several observations which would result in a high-risk certification.
The captain disagreed, saying they were minor issues. Money could fix the problems, Romel told him.
The captain offered US$500 (S$680) but Romel demanded US$3,000. Romel then omitted the high-risk observations in his inspection report.
On May 27, CPIB launched an operation to nab Romel, using the same vessel, this time deliberately prepared with safety breaches, and with Romel assigned again to inspect it.
True to form, Romel raised the breaches to the captain, who handed him US$3,000 in marked bills. When Romel returned to shore with the cash, he was immediately arrested by CPIB officers.
Deputy Public Prosecutor Grace Lim argued that Romel should be jailed for six to eight months as his corrupt actions were detrimental to public safety and Singapore's reputation as a marine services hub.
Romel's lawyer, Mr Thong Chee Kun, argued that no actual harm was caused; neither was evidence produced to show the potential harm.
【サンパウロ時事】ブラジル国営会社ペトロブラスを舞台にした汚職事件で、三菱重工業などが出資する造船所が深刻な経営危機に陥っていることが分かった。発注企業が事件への関与を指摘され、13億レアル(約476億円)に上る未払い金が発生したためだ。日本政府はブラジル政府に対し、問題解決に向けた支援を要請した。地元紙エスタド・ジ・サンパウロが27日、報じた。
同紙などによると、ペトロブラスは石油投資会社セッチを通じ、川崎重工業と三菱重工、IHIがそれぞれ出資する3造船所に対し、開発・掘削用の大型ドリル船などを発注。だが、セッチ社の元役員による汚職事件への関与が発覚し、同社が国有銀行からの融資を受けられなくなり、資金繰りが悪化。昨年11月以降、造船所への支払いができなくなった。
これにより、各造船所は給与の未払いや従業員の解雇を余儀なくされており、地元紙ジョナル・ド・コメルシオは、未払いが続けば倒産の恐れもあると報じた。
日本政府は今週、ブラジル政府に対し文書で支援を要請。在ブラジル日本大使館は時事通信の取材に「早期の問題解決を求めているのは事実」と語った。ブラジル側も深刻に受け止め、セッチ社への特別融資などの解決策が議論されているとみられる。
ペトロブラスの汚職疑惑をめぐっては、取引先企業との間で契約金を約3%水増しし、与党議員らへの賄賂の原資としていた疑惑が浮上。国内外の企業が水増しに協力した疑いが広がっている。
KEN MORIYASU, Nikkei staff writer
DALIAN, China -- STX Dalian, the largest foreign-affiliated shipbuilder in China, has entered liquidation proceedings.
The company, which is under the umbrella of South Korea's STX group, filed for bankruptcy protection last year but could not find a sponsor. This was due to its heavy debt load, which totals 20 billion yuan ($3.2 billion).
At its peak, STX Dalian had more than 20,000 employees. Remaining staffers are to be let go.
Major industry player Dalian Shipbuilding Industry once considered buying STX Dalian. Last October, however, an executive told a local paper that Dalian Shipbuilding had no intention of striking a deal and taking on the struggling company's excessive debt and payroll.
As Communist Party chief of Liaoning Province in 2006, current Chinese Premier Li Keqiang wooed STX to build a shipyard on Changxing Island. The government supported the project as a core business for the island; investment totaled $2.9 billion.
STX Dalian halted operations last year, having found itself unable to deal with the effects of the global financial crisis and a slowdown in the shipbuilding industry.
Jung Suk-yee
STX Engine publicly announced on March 16 that its investing corporations, STX Dalian Engine and STX Dalian Metal, were declared bankrupt in the Dalian Intermediate People's Court.
Also, STX Dalian Medium Equipment, which was financed by STX Heavy Industries, was declared bankrupt by the same Chinese court.
STX Engine said, “We will counter according to the relevant statue procedure.”
Angela Yu
STX Dalian Group, the bankrupt subsidiary shipyard of South Korea's STX Corporation, failed to complete bankruptcy reorganisation and has entered bankruptcy liquidation, Chinese media reported on 13 March.
Sources from STX (Dalian) Engine recently said that the reorganisation of six affiliated companies of STX Dalian has already confirmed to be a failure, and all current employees will be laid off.
Six branches of STX (Dalian) Shipbuilding, China's largest wholly foreign-funded shipbuilding company, started bankruptcy reorganisation procedures in June 2014, according to the announcement by local court.
The court stated that due to their inability to pay off their debts before the due date, the companies had filed a bankruptcy reorganisation plan with the court.
Creditors were required to submit claims to the six companies before 26 September 2014, and the first meeting of creditors was held in the middle of last October, while the second meeting of creditors was scheduled to be held on 8 March 2015.
During the reorganisation, around 10,000 employees have been laid off, and the rest will be laid off in the near future, according to the sources.
Dalian Shipbuilding Industry Company (DSIC) was said to have secretly acquired STX Dalian, however, the rumour was denied by China Shipbuilding Industry Corporation, the parent company of DSIC, last October.
Total liabilities of STX Dalian stands at around CNY20 billion (USD3.2 billion), which is too much for any company to acquire, Wang Hai, shipping expert from Ship.sh told IHS Maritime.
STX Dalian was established in 2007, with a registered capital of USD1.125 billion, and employed over 20,000 people at its peak time. However, the STX chaebol's deterioration into financial trouble in 2013 precipitated STX Dalian's demise.
STX Offshore & Shipbuilding told IHS Maritime that the decision to liquidate STX Dalian was taken by the Chinese courts and it had no say in the matter. STX O&S added that the Dalian yard had ceased work on all ship orders since 2014.
Tom Mitchell in Beijing
Missing shipowners, a white knight reportedly detained by Beijing police and an abandoned African timber deal have all featured in recent Chinese shipping disasters, as the country痴 slowest economic growth in a quarter-century sinks Chinese shipbuilders and their clients at an alarming rate.
In an attempt to contain the damage, government officials have urged the country's two largest private shipbuilders to discuss a potential merger.
Earlier this week, Singapore-listed Yangzijiang Shipbuilding said it had been asked by Chinese government agencies to consider taking a stake in China Rongsheng Heavy Industries, a smaller rival that last year restructured debts totalling more than Rmb10bn ($1.6bn).
Rongsheng suspended trading in its Hong Kong-listed shares on Wednesday morning, pending the announcement of a "substantial disposal?.
While Rongsheng's woes have been building for years, the recent collapse in the benchmark Baltic Dry Index to 30-year lows has pushed it and many other maritime companies to the brink ? especially small, privately owned companies that build, lease or operate the bulk carriers that transport commodities such as iron ore and coal.
Short-term ship leasing is cheap, punishing those who signed long-term leases at higher day rates a year ago,? says Russell Barling, an independent transport analyst. 釘ulk shipping has been going through a long period of pain, winnowing out those with cashflow problems, and not just in China.?
Some recent failures have reverberated beyond Chinese shores.
On March 5, a Hong Kong liquidation meeting for Shagang Shipping attracted more than two dozen creditors including representatives of big global maritime players such as George Economou, the Greek shipping magnate, and Belgian bulk carrier Bocimar.
Privately owned Shagang first made waves overseas in 2013 when it asked South Korean authorities to seize a cruise ship operated by HNA Group, a Chinese conglomerate with which it has been embroiled in a dispute over $66m in alleged arrears. Shagang's action forced HNA to organise an airlift evacuation of the vessel's 1,600 stranded passengers.
Shagang's own debts could be more than 10 times the amount it is seeking from HNA, according to Chris Grieveson, a maritime lawyer who is defending HNA. Shagang痴 liquidators declined to comment.
"The massive profits that shipowners enjoyed up to 2008 were all driven by China's demand for raw materials,? Mr Grieveson says. 釘ut now there痴 excess tonnage in the market and you致e got low freight rates, so people are struggling.
"[Shagang] isn't the only big shipping bankruptcy recently,? he adds, referring to the collapses of Denmark's Copenship and Daebo Shipping of South Korea. 釘ut China is very much in the centre of it all because everyone is taking goods there.?
In Rongsheng's case, Chinese authorities intervened less than a week after a white knight investor, who had been poised to inject up to Rmb2.5bn into the company, was reportedly detained by Beijing authorities during the course of an unrelated corruption investigation.
"The company has no information as to the details of the incident and has been unable to contact [the investor],? Rongsheng told the Hong Kong stock exchange on March 4. 典he board has decided that it is not in the best interests of the company and its shareholders to proceed with the [deal].?
Four other Chinese shipbuilders have, since early February, either been hit by court orders freezing their shareholders? assets, secured government approval for restructuring or halted trading in their shares pending a reorganisation.
In the last case, Singapore-listed JES International announced the restructuring of its Chinese shipbuilding arm, which it said had been brought low by 妬nadequate internal management? and 都ustained significant financial losses?. The company also abandoned plans to purchase a forestry business in the Congo.
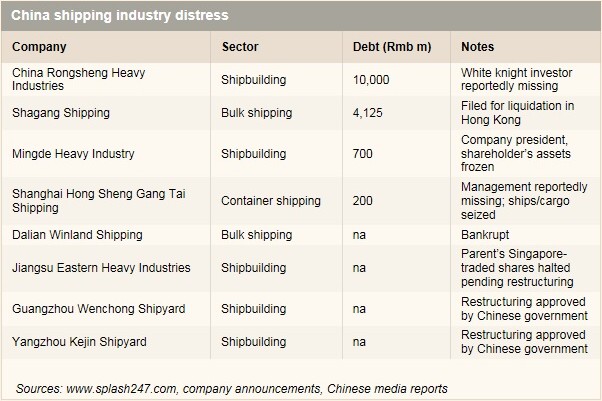
In another diversification bid, Rongsheng purchased stakes in four oilfields in Kyrgyzstan last year but remains hamstrung by the collapse of its core business. In its search for a saviour for Rongsheng, the Chinese government passed over six large state-owned groups, many of which are struggling with chronic problems of their own.
"There is massive overcapacity in Chinese shipbuilding,? says Tim Huxley, chief executive of Wah Kwong Maritime Transport, a Hong Kong shipping company. 鉄tate-owned yards are not going to rush in to save these facilities.?
In addition to China's struggling shipbuilders and Shagang, at least three other privately owned Chinese shipping companies have capsized this year.
Padded order books and delivery delays preceded the demise of Rongsheng Heavy Industries, once the country's busiest shipbuilder
By staff reporters Bao Zhiming, Wu Hongyuran and Yu Ning
(Beijing) – Piles of rusty steel bars and old ship parts are virtually all that's left of a sprawling shipyard in the eastern city of Rugao, where Jiangsu Rongsheng Heavy Industries Group Co. used to employ more than 30,000 people.
Once China's largest shipbuilder, Rongsheng is on the verge of bankruptcy. Orders have dried up and banks are refusing credit. Questions have been raised about the shipyard's business practices, including allegations of padded order books. And Rongsheng is apparently behind on repaying some of the 20.4 billion yuan in combined debt owed to 14 banks, three trusts and three leasing firms, sources told Caixin.
The few hundred shipyard workers left – survivors of what's now a three-year downsizing – are wondering whether they'll ever see their overdue paychecks. Those with an uncertain future include a worker who cuts steel from abandoned ships into pieces that can be sold for scrap. "We haven't been paid since November," the worker said.
Rongsheng is on the ropes now that it has completed a multi-year order for so-called Valemax ships for the Brazilian iron ore mining giant Companhia Vale do Rio Doce. The last of these 16 bulk carriers, the Ore Ningbo, was delivered in January.
With a carrying capacity of up to 400,000 tons, Valemaxes are the world's largest ore carriers. Vale hired Rongsheng to build the ships starting in 2008, and has tolerated the shipyard's slow pace: The Ore Ningbo was delivered three years late.
Rongsheng employees said the Ore Ningbo may have been the shipyard's last product because no new ship orders are expected and all contracts for unfinished ships have either been canceled or are in jeopardy.
A Rongsheng manager who asked not to be named said Shipping Corp. of India recently cancelled an order for a 300,000 ton bulk commodities carrier. "And work has been suspended on a 57,000 ton crude oil vessel for Shanghai Northsea Shipping Co."
Another manager said he expected "no business after the delivery of the last ship to Vale. Most workers have been dismissed. Management can stay, but their numbers are falling. Their contracts will not be extended after they expire."
Heavy Debt
Rongsheng's weak financial position was highlighted by a third-quarter 2014 financial report in which the company posted a net loss of 2.4 billion yuan. It also reported 31.3 billion yuan in liabilities, including 7.6 billion yuan worth of outstanding short-term debt.
Sources said that Rongsheng's outstanding debt includes 6 billion yuan owed the Bank of China and 2 billion yuan it borrowed from China Minsheng Bank. It's also indebted to government policy banks: Some 4 billion yuan has to be repaid to the Export-Import Bank of China, and 2 billion is owed to China Development Bank (CDB).
A source close to the company said Rongsheng's capital crunch has worsened since February 2014, when the CDB demanded more collateral after the company failed to make a scheduled payment on a 710 million yuan loan. When Rongsheng refused, the CDB called the loan. Other banks that issued loans to the shipbuilder have taken similar steps, said the source.
A few months after CDB's move, the Jiangsu Province government intervened by renegotiating overdue loans and encouraging Rongsheng to reorganize its business. Provincial officials and representatives from the Rugao government tried to help in May 2014 by sponsoring a meeting between Rongsheng and state-owned China State Shipbuilding Corp. (CSSC) officials aimed at a possible bailout.
At the meeting, officials discussed several cooperation options, said a source close to CSSC's board of directors. But the talks ended without an agreement. A CSSC source said his company decided against pursuing a tie-up due to the complexity of Rongsheng's asset structure and heavy debt.
"It would cost at least 5 billion yuan to restart operations at Rongsheng's facility, plus they have a huge amount of debt," the source said. "Buying Rongsheng would not be a good deal."
Also falling through was a proposed deal with an investment firm called Hongyi Shengli Investment Co., which offered to buy a 19 percent stake in Rongsheng.
Officials said in February the pending deal would make Hongyi Shengli the shipbuilder's largest shareholder, and that eventually Rongsheng would be overhauled and re-emerge as a company focusing on the energy sector. But just one week after the announcement, police detained Hongyi Shengli's controller, Wang Ping, on embezzlement charges.
On March 4, a Rongsheng statement said its board had dropped plans to sell a stake to Hongyi Shengli. A banking source said this meant Rongsheng's "second plan also failed."
Rongsheng's demise began in 2011, six years after company founder and former chairman Zhang Zhirong started the company with money made when he worked as a property developer in the 1990s. The new shipyard stunned the industry by clinching major vessel orders from the start, even at a time when most of the world's shipyards were slumping.
Rongsheng's success attracted investors and banks to the company's side, fueling its expansion.
In retrospect, said a Rongsheng executive, the company went too far. Financial reports for the years 2008 to 2011 show Rongsheng planned to spend between 1.5 billion yuan and 5.4 billion yuan annually on fixed-asset investments.
The executive said Zhang supported the expansion plan in hopes that greater production capacity would help accelerate shipbuilding and deliveries. In addition, a source close to Zhang said some expansion decisions were designed to improve the company's bottom line through real estate development that had nothing to do with building ships.
Nevertheless, the shipyard, a sprawling facility spread across one-third of Changqingsha Island in the middle of the Yangtze River, suffered from a lack of capacity and management problems. As a result, the company had trouble meeting its contract obligations, including delivery timetables.
"All of Rongsheng's problems are tied to difficulties with delivering ships," said a Rongsheng manager. "Many of Rongsheng's order cancellations were due to its own delivery delays."
Rongsheng built ships with a combined capacity of 8 million tons in 2010 and was preparing to begin filling US$ 3 billion in new orders the following year. But the company's 2011 orders wound up totaling only US$ 1.8 billion. That same year, according to shipping information provider Lloyd's List, Rongsheng's customers canceled contracts for 23 new vessels. A former Rongsheng engineer said the company had to significantly cut its equipment purchase spending plan because "there was no money."
In 2012, Rongsheng received orders for only two ships. Layoffs ensued, with some 20,000 workers getting the axe. The company closed the year with a net loss of 573 million yuan, down from a 1.7 billion yuan net profit in 2011 and despite 1.27 billion yuan in government subsidies. The bleeding worsened in 2013, with 8.7 billion yuan in reported losses.
Despite a recovery of the Chinese shipbuilding industry in 2014, Rongsheng saw no relief, as its clients canceled orders for 59 vessels that year.
Things were looking up for Rongsheng in May 2014, when it announced orders for six bulk carrier vessels from a European ship owner. But the contract was later dropped because Rongsheng couldn't find a bank willing to finance the project.
In years past, Rongsheng found it easy to get bank support for building orders. But according to a ship financing expert, banks changed their tune after Rongsheng started having trouble repaying loans. The repayment woes surfaced after the company apparently overstretched its order books to the point where it couldn't deliver vessels on time.
Padding the Books
Moreover, sources close to the company said Rongsheng tried to look stronger than it was by exaggerating its records with fake orders.
The problems surfaced shortly after Rongsheng's November 2010 listing on the Hong Kong Stock Exchange raised HK$ 14 billion. The company wowed investors by declaring that it received orders for 111 ships. And Zhang impressed government officials by announcing that "Rongsheng is moving toward assuming a leadership position in the global shipbuilding industry."
In fact, though, the company's troubles had been quietly mounting behind the scenes since at least July 2009, when a Greek customer, Thenamaris Ships, cancelled an order for a 15,600 ton Suezmax bulk commodity ship after the shipyard missed its delivery deadline.
The ship, later named Roxen Star, was eventually built and bought by Roxen Shipping, a company controlled by Chinese businessman Guan Xiong, for US$ 72 million. The deal helped Rongsheng retain market confidence as it prepared for the listing.
In fact, according to several sources at Rongsheng, it was Zhang who bought the Roxen Star and paid Guan Xiong and Roxen Shipping.
Since then, Guan and his companies have reportedly stepped in to rescue some US$ 2 billion worth of ship contracts that were canceled by Rongsheng's other customers. Without these orders, Rongsheng never would have maintained its status as the No. 1 shipbuilder in China from 2009 to 2013.
Rongsheng's profitable period was marked by orders from around the world. Its first big client, Norway's Golden Ocean Group Ltd., ordered six freighters in 2005. The following year it banked orders for 49 vessels worth a combined 3.2 billion yuan.
In 2008, Rongsheng clinched contracts for 16 ships worth a total US$ 1.9 billion. The biggest deal – a US$ 1.5 billion contract with Vale for 12 Valemax carriers – was the largest shipbuilding contract ever signed.
For years financiers stood behind Rongsheng. In November 2009, for example, Minsheng Bank's Minsheng Financial Leasing Co. provided 900 million yuan financing for eight ship orders.
Financing was a key ingredient in Rongsheng's formula for success. After the global financial crisis of 2008, many ship owners could no longer afford paying in advance for new vessels. So builders such as Rongsheng started arranging up-front financing with Chinese banks that got projects off the ground.
As a result, Rongsheng's borrowing from banks rose to 25.4 billion yuan in 2011 from 3.6 billion yuan in 2009.
Rongsheng also won government support. From 2010 to 2012, it received hefty tax breaks and subsidies from the Rugao government. These incentives were worth 830 million yuan in 2010, 1.25 billion yuan the following year and 1.3 billion yuan in 2012, company financial reports show.
Financiers backed off, though, when it became apparent that Rongsheng was failing to meet delivery schedules and losing customers.
An employee of Everbright Bank who asked not to be identified said the bank's assessment of Rongsheng found that its biggest problems were tied to its production operations. "But by the time the bank realized the problem," the employee said, "the company was already in financial trouble."
Rongsheng's and Zhang's dealings with the phony contract angel Guan also played into the company's loss of favor with customers and financiers.
An example of this sleight-of-hand tactic revolved around a contract signed in August 2011 for 20 crude oil carriers to be built for a Hong Kong-based ship owner called Global Union. The order was written into Rongsheng's records, but a source said that not a single ship was delivered. It wasn't until July 2014 that Rongsheng acknowledged the order had been cancelled.
Behind Global Union is a Hong Kong based company named CMG Shipping, which is controlled by Guan, company documents show. According to business registration records in Hong Kong, Guan launched 12 shipping companies in that city in 2010 and 2011. In May 2010, some of these companies ordered nine bulk freighters from Rongsheng.
Rongsheng's order books show that through the years Guan's companies have ordered at least 30 ships from the shipyard, and 17 were cancelled.
A Rongsheng employee said Guan and Zhang are friends and business partners. Another source close to Rongsheng said Zhang paid for the ships bought by Guan's companies through shady contracts. The source said Zhang pulled all the levers for an order for six bulk carriers in 2011. The company placing the order was Marshall Islands-registered Superior Gain Investment Ltd., a company that was formed and registered as a business shortly before ordering the ships.
Zhang essentially placed the orders to pad the company's order books, the source said. In this way Rongsheng could "control the timing of order cancellations," the source said. "That's why Rongsheng could have a huge number of orders in hand."
Rongsheng officials have never explained the company's order-book methodology to investors, nor responded to claims that Zhang and Guan conspired to inflate the shipyard's business. Stock investors have sold off Rongsheng, and it now trades at around 75 Hong Kong cents a share, down from a peak of HK$ 8.35 in 2011.
But a company employee who works in the office of Rongsheng President Chen Qiang said that Zhang and his business partner placed ship orders that did not have to be publicly disclosed.
And Lei Dong, director of the president's office at Rongsheng, said no listed company disclosure rules were violated because the shipbuilder can choose between two ways of reporting orders for vessels that won't be built as long as a contract remains valid.
However, an industry source said Rongsheng's true list of valid orders is much smaller than reported. "I think Rongsheng counts all intended and cancelled orders," the source said.
A source close to Zhang said 28 of the 49 orders for ships placed in 2006 and 2007 were later canceled. And although Rongsheng planned to build 33 ships in 2009, the source said, only 10 were delivered.
(Rewritten by Han Wei)
中国の造船業界は縮小していくのか?
China’s Jiangsu Eastern Heavy Industries shipyard (JEHI), a subsidiary of JES International Holdings, has filed an application for debt and liabilities restructuring at Taizhou Intermediate People’s Court.
If the application is accepted, JES claims that ”no other creditors will be able to commence a winding up application as against JEHI, and negotiations will be carried out by the management of JEHI at the oversight of a manager,” which will be appointed by the court to oversee the restructuring process.
JEHI says that it plans to implement the restructuring scheme ”to maximise the value of the company and its assets for its creditors and shareholders.”
JES said that in recent years, due to a decline in the shipbuilding industry as well as inadequate internal management, JEHI has sustained significant financial losses. Particularly, JEHI was impaired by its severe lack of liquidity and cash flow.
The group claims that ”the proposed restructuring scheme will allow JEHI to carry on its business in the ordinary course of nature during the restructuring period, without the threat and distraction of proceedings and other action which may be taken by its creditors.”
Due to JEHI’s restructuring, JES decided not to proceed with the announced placement of 183 million ordinary shares. Trading of shares in Singapore-listed group has been suspended as of today.
In July 2014, the Supreme People’s Court of China blacklisted JEHI for failing to settle its debt obligations.
World Maritime News Staff
China’s ministry of industry and information technology has reinstated the ‘white list’ status for Jiangsu New East Marine Equipment Co in a latest statement on 31 December 2014.
Jiangsu New East Marine Equipment, wholly-owned by JES International Holdings, had earlier saw its name being removed from the ‘white list’ in September last year.
The reason for earlier removing Jiangsu New East Marine Equipment from the ‘white list’ was not explained by the ministry, but the company’s sister firm Jiangsu Eastern Heavy Industry was blacklisted by the Supreme People’s Court of China in September for refusing to repay its debt obligations of around RMB15m ($2.4m) from five separate lawsuits filed by equipment suppliers.
Similarly, the reason for putting back Jiangsu New East Marine Equipment to the ‘white list’ was not given by the ministry.
The parent firm JES had defended its subsidiary by saying that the equipment suppliers actually did not fulfill their obligations as they have failed to rectify the equipment defects.
Chinese shipyards that made it to the ‘white list’ are expected to enjoy greater access to financial support from the local banks and be recognised as a better shipbuilder in China.
At present, a total of 60 state-owned and privately-owned Chinese yards are listed. There are about 300 active Chinese shipyards across the country.
Source from : www.seatrade-global.com
Eight replacement newbuildings will carry a higher price tag than the orders originally contracted by the German owner at JES
Reederei Vogemann has turned to Yangzijiang Shipbuilding for up to eight newcastlemax bulkers.
Industry sources say the eight 208,000-dwt newbuildings are for delivery from late 2016 into 2017. The deal involves four firm ships, plus four options.
TradeWinds is told that the ships will replace eight similar-size newbuildings the company signed up for early this year at JES International Holdings. But that deal did not materialise as the yard failed to secure refund guarantees.
Chinese financial institutions are tightening up on lending to shipyards as the sector is regarded as risky.
Also, JES subsidiary Jiangsu New East Marine Equipment was removed from the first batch of “white list” shipyards drawn up by China Ministry of Industry and Information Technology (MIIT).
Jiangsu Eastern Heavy Industry, another subsidiary of JES, is also blacklisted by the Supreme People’s Court of China for failing to settle debt obligations of around CNY 15m ($2.44m) covering five separate lawsuits filed by equipment suppliers.
China, faced with an excess of shipbuilding capacity, singling out in the white list shipyards considered worthy of policy support.
The Vogemann order is costing around $24m more than previously. It is said to be paying around $56m for each newcastlemax at Yangzijiang compared with a reported $53m at JES.
Vogemann is also listed with six fuel-efficient handysize bulkers on order at Samjin Shipbuilding. The 36,000-dwt units were booked last year at a reported price of around $22m each for delivery from the end of this year into 2015. However, Vogemann is not likely to take delivery of the sextet from Samjin as the yard is now under Chinese court protection and operations have stopped.
The Korean shipyard was hit with financial troubles and failed to secure refund guarantees for its newbuilidngs. It is unknown if Vogemann is looking for another shipyard to have the handysize ships built.
Vogemann has also acquired tonnage from the secondhand market. In July, it bought the Mipo-built, 36,800-dwt Voge Emma (ex-A Handy) and Voge Mia (ex-B Handy, both built 2011) for $18.5m and $18m, respectively. The duo was previously owned by Nobu Su’s Tomorrow Makes Today (TMT) and they were sold at an auction approved by the US Bankruptcy Court in Houston, Texas.
The company has also offloaded two vessels from its fleet. It sold the 700-teu feedership Johanna (built 1999) for $1.6m to Foroohari Reederei and the 71,000-dwt panamax bulker Voge West (built 1995) to an undisclosed buyer for $5.5m.
London broker Clarksons’ database lists Vogemann as currently owning three capesizes, three open-hatch handies, one panamax bulker, six handysize bulkers and two handysize products tankers.
BC, Riga
Another insolvency claim has been filed against Rigas kugu buvetava (Riga Shipyard), according to information provided by Firmas.lv.
The insolvency case was initiated by
the Riga Northern District Court on February 20, according to information
published on the Insolvency Administration's website. The claim was filed by the
foreign company Nordweg Ship Repair.
The court will review the case onMarch 5, as LETA learned from the
court.
Riga Shipyard CEO Janis Skvarnovics told LETA that the company has not received
any documents from the court, he was therefore unable to comment on the case.
Skvarnovics explained that Riga Shipyard had signed a contract with Nordweg
Ship Repair, a company which carried out various activities as a
subcontractor. "A number of these activities, in our opinion, were not accomplished, for this reason, we have filed a claim against this
company," Skvarnovics added.
The Riga Northern District Court
told LETA, however, it has not yet
received Riga Shipyard's claim against Nordweg
Ship Repair.
In the spring of 2014, several insolvency claims were filed against Riga Shipyard.
Skvarnovics blamed the claims on one of the company's minority shareholders. These insolvency claims were artificial
and intended to generate major publicity, the claimant was expecting Riga
Shipyard to go bankrupt any moment. All these attempts failed, Skvarnovics said
in an interview with LETA.
As reported, Riga Shipyard turned over EUR 12.386 million in the first nine months of 2014; net losses amounted
to EUR 1.281 million, according to the company's financial report submitted to
the "Nasdaq" Riga Stock Exchange.
Remars-Riga is the largest shareholder in Riga Shipyard with 49.86% of shares.
Riga Shipyard is a shareholder in Tosmares kugubuvetava (49.72%), and Remars Granula (partnership 49.8%). Riga
Shipyard was founded in 1995.
国籍と検査会社を選択すれば、MLC違反は問題ない。MLCの不備もPSC (外国船舶監督官) 次第で、航路や寄港する国によっては指摘されない。これが現実だから傭船社及び荷主の判断次第。MLCで大きな変化が見られるのは大型船又は 厳しいPSC (外国船舶監督官)がいる港や国に寄港する船だけ。
The International Chamber of Shipping (ICS) has warned shipowners off flying the flags of Tanzania, Mongolia, Moldova, Cambodia and Sierra Leone because they do not comply with United Nations' labour standards. According to the annual ICS flag state performance table published last week, these are examples of sub-standard ship registers, reported London's Tanker Operator. "One area on which we would like to see more progress is with respect to ratification of the ILO Maritime Labour Convention," said ICS secretary general Peter Hinchliffe. "But following the entry into force of the convention, it is now being enforced worldwide through Port State Control and the vast majority of international shipping companies are operating in compliance, with the exception of the official flag state certification," he said.
By Aiswarya Lakshmi
Korea’s dry bulk shipping company Daebo International Shipping has reportedly filed an application for rehabilitation proceedings with a court in South Korea.
Daebo is the 3rd dry bulk shipping company to file for bankruptcy protection this month following China’s Winland Ocean Shipping and Denmark’s Copenship.
Under the rehabilitation proceedings in Korea, similar to the Chapter 11 proceedings in the United States, a company is allowed to ultimately survive and continue operation, albeit in a restructured form.
It cited reasons of prolonged rout in prices for dry bulk commodities such as iron ore and coal.
Should the court grant the petition, Daebo’s further dealings will be subject to regulation by the court. A receiver would be appointed by the court and a timetable would be set for the further progress of the procedure.
In addition, Daebo would be requested to file their claims to the receiver, and should they be rejected then the claim must be brought to the court to determine.
Marine insurer Skuld said that this will have an impact on all creditors and debtors to Daebo and members should review any open position or account they may have in relation to business dealings with this company.
Daebo International’s website lists that it has a fleet of eight vessels, including four panamaxes and one handymax bulker. Daebo was established in 1974 and operates a fleet of 30 to 35 vessels, mostly involved in coal and iron ore transport.
Shippers have described the dry bulk sector's current downturn as the worst market conditions since the 1980s.
Dry-bulkers are not the only shippers in trouble. Over 10% of the global LNG tanker fleet is currently estimated to be idled after Asian LNG prices fell almost 2/3 since February 2014.
Daebo International Shipping has reportedly filed an application for rehabilitation proceedings with a court in South Korea.
This is the third dry bulk company to file for bankruptcy protection this month following in the wake of Winland Ocean Shipping and Copenship.
Daebo International is said to have made the filing on 11 February, according to a member advisory from Skuld.
“Members may have already had some experience of this procedure following a number of high profile bankruptcies and reorganisations in Korean shipping following the financial crisis in 2008,” the P&I club said.
“While this procedure has similarities to bankruptcy proceedings, it is intended to allow the company to ultimately survive and continue operation. It is therefore similar, in some ways, to the Chapter 11 proceedings in the US.”
TradeWinds reported in November that Daebo International had reduced its fleet to six ships after offloading another modern panamax bulker.
The Tsuneishi-built, 76,000-dwt Sea of Future (built 2005) was reportedly sold to an undisclosed buyer for $15.8m, according to sources.
The ship, which is due for special survey in February, was purchased by Daebo as Ikan Kerapu from Pacific Carriers for $30m in April 2009.
Daebo was established in 1974 and operates a fleet of 30 to 35 vessels, mostly involved in coal and iron ore transport.
Weaker demand from China and an oversupply of tonnage has led to the industry downturn, pushing the BDI to an all-time low this month.
In Denmark, privately owned Copenship filed for bankruptcy earlier in February after losses in the dry bulk market.
This was followed on 12 February China’s Winland Ocean Shipping Corp, which filed for Chapter 11 bankruptcy protection in the US.
Dalian - A Dalian shipowner, Winland Ocean Shipping, has filed for Chapter 11 bankruptcy protection in Texas after two of its three vessels were confiscated in China and Singapore last year. The company said it hopes to restructure and reduce its existing secured debt “to levels that are consistent with the currently depressed levels of the charter market”. The group, which at its peak had a fleet of 12 ships, property holdings plus an online trading platform, said it needs to restructure more than $48m in secured debt.
(Source: Sinoshipnews)
Winland Ocean Shipping Corp of China has filed for Chapter 11 bankruptcy protection in the US after two of its vessels were arrested.
The filing in Texas federal court last week reveals the Dalian-based company needs to restructure $48m of secured debt.
Two ships were arrested in Singapore and China over unpaid loans in September and December.
It reportedly has one vessel left trading
Winland Ocean traded on the US over-the-counter (OTC) equities market until it withdrew in early 2012.
The company, led by Sharry Xue and Li Honglin, controlled a fleet of 12 bulkers, general cargoships and small boxships at that time.
Most of the fleet has been sold or scrapped since.
TradeWinds reported in September that affiliated company Winland Shipping’s mortgage holder, China Merchants Bank (CMB), took action against one of two supramaxes that were funded under a $37m credit facility from CMB.
It prevented the sailing of the 56,900-dwt-dwt Rui Lee (built 2011), sistership of the 56,800-dwt Fon Tai (also built 2011).
Rui Lee is at anchor off Singapore, while Fon Tai is anchored off Doha in Qatar.

RUI LEE IMO 9588512(ShipSpotting.com )
By Kevin Rector
A Japanese ship operator was ordered to pay $1.8 million for illegally dumping oil residue and bilge water into the ocean last year, as part of a plea agreement Friday in federal court in Baltimore..
A crew member on board the ship who acted as a whistle-blower will receive $250,000 of that, while $450,000 will go to the National Fish and Wildlife Foundation for projects benefiting the Chesapeake Bay, according to the office of Rod J. Rosenstein, the U.S. attorney for Maryland.
The sentence, handed down by U.S. District Judge Catherine C. Blake, came after Hachiuma Steamship Co., the operator of the M/V Selene Leader, pleaded guilty to violating the Act to Prevent Pollution from Ships.
The plea agreement includes three years of probation, during which the company must develop an environmental compliance program, according to Rosenstein's office.
The shipping line could not be reached for comment.
"The Coast Guard is trying to send a message to the maritime industry that environmental compliance is not optional and that deliberate violators will be apprehended," said Coast Guard Capt. Kevin Kiefer of the port of Baltimore.
According to the plea agreement, the M/V Selene Leader arrived in Baltimore on Jan. 29, 2014, with an oil record book that did not account for oily waste that had been discharged directly into the ocean.
Law requires that such discharge must first pass through a machine that separates oil from water.
A whistle-blower among the crew came forward about the discharge, and helped investigators determine that crew members Noly Torato Vidad, 47, and Ireneo Tomo Tuale, 63, both of the Philippines, had arranged the scheme.
Vidad and Tuale have pleaded guilty in separate proceedings and are scheduled to appear in federal court in Baltimore on Feb. 20 and March 3, respectively, for sentencing, Rosenstein's office said.
A company controlled by NYK has admitted covering up the deliberate discharge of oil and has been ordered to $1.8m by a US court.
The US Department of Justice (DOJ) issued a news release stating that the Hachiuma Steamship Company pleaded guilty in federal court to violating the Act to Prevent Pollution from Ships (APPS) by failing to maintain an accurate oil record book (ORB) concerning the illegal disposal of oil residue and bilge water overboard from the vehicle carrier M/V Selene Leader.
It allegedly failed to maintain an accurate oil record book concerning the illegal disposal of oil residue and bilge water from the car carrier Selene Leader (built 2010). In addition to the fine, chief US District Judge Catherine Blake ordered Hachiuma Steamship to be placed on probation for three years during which it is to develop an environmental compliance program.
“The US Coast Guard is trying to send a message to the maritime industry that environmental compliance is not optional and that deliberate violators will be apprehended,” said US Coast Guard (USCG) captain Kevin Kiefer, captain of the Port of Baltimore.
“The sentence fits the crime because it includes a requirement that these defendants develop and implement a comprehensive environmental compliance program that will be ensured by outside auditors. Companies that get caught can expect a much closer look.”
According to the plea agreement, in January 2014, engine room crew members of the vessel under the supervision of the chief engineer Noly Torato Vidad and first engineer Ireneo Tomo Tuale transferred oily wastes between oil tanks on board the ship using rubber hoses and then illegally bypassed pollution control equipment and discharged the oily wastes overboard into the ocean. The Selene Leader arrived in Baltimore on 29 January 2014 with an oil record book that failed to include entries reflecting the discharge of oily water and oily waste directly into the ocean.
The USCG boarded the ship for inspection the next day and found that Vidad had tried to hide the illegal discharges of oil by falsifying the oil record book, destroying documents, lying to USCG investigators, and instructing subordinate crew members to lie to the USCG.
Some $250,000 of the fine was awarded to a whistleblower on board the M/V Selene Leader who alerted the USCG about the illegal activities on board the vessel, provided a video showing the illegal transfers of oily wastes and assisted in the USCG’s investigation.
Vidad, age 47, and Tuale, age 63, both of the Philippines, previously pleaded guilty to their participation in the scheme and are due to be sentenced in federal court in Baltimore on 20 February and 3 March 2015, respectively.
The company was sentenced to pay $1.8 million and to serve three years on probation, during which time it must develop and implement an environmental compliance program.
London - Privately-owned shipping company Copenship has filed for bankruptcy in Copenhagen after losses in the dry bulk market, its Chief Executive Michael Fenger told Reuters. Copenship had been operating over 50 chartered small-sized dry-bulk vessels carrying goods such as grain, iron ore and timber. “We have done what we could to raise the funds to save the company, but we have reached a point where there is not more to do,” Michael Fenger wrote in a text message to Reuters on Wednesday. The Baltic Exchange’s main sea freight index, which tracks rates for ships carrying dry bulk commodities, fell to its lowest level in nearly three decades on Tuesday, hurt by weaker rates across all four vessel segments. On Wednesday the index stood at 569, close to the historic low level of 554 set in July 1986. “First of all, we have found ourselves in an extremely bad dry cargo market. Secondly, there are several counterparties that have caused us losses, and then thirdly there are different insurance cases that could hit us,” Fenger wrote. Insolvency administrator Per Astrup Madsen from Copenhagen law firm Lett said the vessels will be handed back to owners. “Copenship expected to turn around the business in 2014 but the dry bulk freight rates continued the falling trend,” Astrup Madsen said. One of the world’s leading dry bulk shipping companies, Copenhagen-based D/S Norden, posted a net loss of $326 million for 2012 and 2013 combined, and said in December it expects a full-year 2014 EBITDA loss of between $290 million and $230 million. Shipping analyst Peter Sand at shipping organisation Bimco said 2015 looks set to be dull on the demand side, whereas the supply side is likely to provide the same amount of new capacity as in 2014. “Such a development will not improve the fundamental market balance,” he wrote in a note
全ては結果次第。総合力では日本の方が韓国より上だと思うが、造船産業に関わっている世代の構成は韓国の方が若いし、これまでの日本の造船界を支えてきた世代は退職する時期。退職者の再雇用を行ったとしてもどれくらい引っ張れるのだろうか?外国人を使えば使うほど、技術の伝承は困難となる。技術を伝承できる世代が減っていくのは確実だし、自分のものにするまでにやはりトライ・アンド・エラーの時間は必要。結果は違うが、どのような選択をしても結果は出る。出る結果が違うだけ。 今回の計画の結果は、何十年後にならないとわからない。
日本造船企業の今治造船が16年ぶりに超大型ドックを建設することになり、韓国造船業界が緊張している。今治造船は先月29日、400億円を投資し、香川県に長さ600メートル、幅80メートルに大型クレーン3つを備えた超大型ドックを建設すると明らかにした。このドックでは台湾の海運企業から受注したコンテナ船11隻を建造する予定だ。
同社は最近、自国の船会社から2万500TEU級の超大型コンテナ船6隻も受注した。ウルトラマックス級(約1万8000TEU級以上)超大型コンテナ船市場を事実上独占してきた現代重工業、サムスン重工業、大宇造船海洋など韓国造船3社もまだ2万TEU級船舶は受注していない。
業界関係者は「日本が2万TEU級船舶を先に建造すれば、韓国造船業の牙城が揺れる」とし「円安と技術力、安倍政権の支援を背に、日本造船企業が中国よりも速いスピードで韓国を追撃している」と話した。
◆円安・統廃合で日本造船業「復活」
国際造船海運市況分析機関クラークソンによると、昨年、日本造船業界の受注量は780万CGTだった。世界市場シェアは2012年の17.1%から19.7%に高まった。同じ期間、韓国造船業界の市場シェアは31.1%から29.7%に減少した。
過去10年間、韓国造船業界のライバルは中国だった。中国の世界造船市場シェアは2000年代初期まで10%にもならなかったが、政府の全面的な船舶金融支援、造船所の統廃合などで昨年38.6%まで増えた。しかし液化天然ガス(LNG)船や超大型コンテナ船など高い技術力を基盤とする高付加価値船舶分野では韓国が優位を維持してきた。高付加価値の船舶分野で競争するという点で、日本は中国よりも脅威だ。
1980年代まで世界市場を掌握していた日本造船業界は現在、LNG市場に死活をかけている。福島原発事故以降、日本国内のLNG需要が急増し、日本の船会社は新規LNG船の発注を準備しているためだ。日本の新型LNG船は、韓国造船会社が新しい成長動力としてきたLNG船と燃費および性能が似ている。
◆「1%利率」船舶金融支援が弾みに
日本造船企業は安倍政権の発足後に続いた円安の影響で受注競争力を確保したうえ、数年間にわたる構造調整を通じてコスト競争力を高めた。日本政府は2008年以降、円高で造船業が打撃を受け、大々的な統廃合に入った。昨年、アイ・エイチ・アイマリンユナイテッドとユニバーサル造船が合併して世界4位規模のジャパンマリンユナイテッド(JMC)が誕生し、今治造船と三菱重工業はLNG船舶部門を切り離してLNG専門造船所(MI LNG)を設立した。日本造船業界は現在5社体制に再編された。さらに円安効果までが本格的に表れ、昨年、円を基準に船舶の価格は約15%下落した。
超大型ドックの建設は日本造船業の復活を意味する信号と業界は受け止めている。日本政府は統廃合の後、造船業の復活に向けて船舶価格の80%まで1%の利率で船舶金融を支援する政策を始めた。今治のドック建設に続き、日本造船業界の新増設計画が後に続くという見方が出てくる理由だ。
サムスン重工業の関係者は「日本造船業の最も大きな弱点は中小型の造船所が多く、今まで建造した船舶の最大サイズが1万4000TEU級だった」とし「超大型ドックの建設で2万TEU級船舶の建造までが可能になれば、いつでも韓国に追いつく可能性がある」と話した。
BULK BRASIL IMO 9392432 Flag: Panama 02/01/15 (ShipSpotting.com)

Ainslie Drewitt-Smith and Emily Laurence
Twenty Filipino men have been found with no food, on board a vessel berthed at Port Kembla.
The Panamanian-registered vessel, the Bulk Brasil, was detained by the Australian Maritime Safety Authority on Thursday afternoon.
The ship is operated by Japanese Company Keymax and is full of Australian Cargo, bound for the UK.
International Transport Workers' Federation (ITF) National Co-ordinator Dean Summers said the seafarers haven't been paid since September.
"The shocking thing is that this company has signed agreements with our organisation to say that they will pay an international minimum standard and yet haven't bothered paying them for four months. Now this is the crisis, when the human element comes to the fore."
"Over the past 20 years the ships have improved but the quality of management and respect for seafarers is probably at an all time low," he said.
Mr Summers said the men need to be back paid and the Australian company who owns the cargo needs to be investigated.
"The Australian cargo owners, those that make profits selling their cargo to international markets, have to take responsibility for this," he said.
"You can't just put your cargo on the crappiest, cheapest ship, that doesn't feed and doesn't pay it's seafarers and say it's not your responsibility."
"So we're looking for the cargo owner and we'll be holding them up to some responsibility in this as well."
Mr Summers said Japanese company Keymax is known to have had ships breach the Maritime Labour Convention at 12 ports worldwide.
"We're trying to engage Keymax in this to get them to fix all of the problems on all of their ships," he said.
The ABC has sought comment from the Australian Maritime Safety Authority.
Mission to Seafarers Australia says the 20 unpaid Filipino workers on board the Bulk Brasil is an all too familiar story.
National Executive Officer Reverend Canon Garry Dodd said a number of companies, despite the law, are prepared to risk fines and having ships detained just to save money.
"When you think about the total value of cargo that's on a vessel versus the small amount that goes into wages it's just criminal, it really is modern day slavery," Reverend Dodd said.
He said most Australians do not appreciate the ramifications.
"If you haven't been paid for three or four months as in the case of the Brasil, it means that seafarers children haven't been going to school or they haven't been able to be fed, or entire families have gone without," Reverend Dodd said.
The men are almost guaranteed to be paid now that AMSA and the International Transport Workers Union are involved, according to Reverend Dodd.
He said it is a big decision for a seafarer to speak out.
"The captain is called the master for a very good reason, that they have absolute control over every aspect of the seafarers life, so it is very difficult for seafarers to have the courage to speak out because of fear of being abandoned, by being blacklisted," he said.
"The reality is that if seafarers do complain, it can be very difficult for them to ever get another job."
第一中央汽船<9132>が23日、06年に起きた大型ばら積み船「オーシャン・ビクトリー」号の座礁事故の損害賠償請求の第二審で、同社側に船主への損害賠償支払いを命じた第一審判決が取り消されたと発表。同社は15年3月期の業績予想(最終損益は27億円の赤字)に訴訟損失(約58億円)を引き当てているため、逆転勝訴によって戻り入れ益が発生する見込み。判決が業績に与える影響については「現在精査中」としている。
オーシャン・ビクトリー号は、06年9月に第一中汽が中国の船主から短期用船契約で借り受けていたが、同年10月に鹿島港外で悪天候により座礁、全損した。船主は第一中汽に対し、1億4200万ドルの損害賠償を求めていた。第一審では第一中汽側に、約1億3800万ドルの損害賠償と訴訟費用などを支払うよう命じたが、第一中汽はこれを不服として控訴していた。
グローバル経済は恐ろしい!強みが弱点となる。予測出来そうで予測できない事が起きる。下がれば上がる。上がれば下がる。問題はいつ!
下がったまま上がって事ケースもあるが、歴史は繰り返される。主人公や背景が変わるだけ。
By Seonjin Cha
South Korean shipbuilders, last year’s biggest stock-market losers, are the most popular target for short sellers in 2015 as falling crude hurts oil-rig demand.
Bearish wagers used borrowed stock against Hyundai Mipo Dockyard Co. (010620) rose to 7.3 percent of shares outstanding on Jan. 8, the highest level on the Kospi index and up from 4.3 percent a year ago, according to data compiled by Bloomberg and Markit Group Ltd. Short interest in Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. and Hyundai Heavy Industries Co. (009540) has more than tripled in the past 12 months.
While shipbuilding’s importance to the Korean economy has diminished since former President Park Chung Hee promoted the industry in the 1970s, the nation’s 10 biggest shipyards still provided 183,000 jobs at the end of 2013. As demand for ships to move consumer goods declined amid a global economic slowdown, Korean shipbuilders have become increasingly reliant on orders for rigs and drill ships.
“It’s hard to expect much upside for shipbuilders as long as oil prices remain low,” Lee Jin Woo, a money manager at Seoul-based KTB Asset Management Co., which oversees about $8.8 billion, said by phone. “Companies will have to delay capital investments and orders for ships and offshore projects.”
A gauge of Korean shipbuilders plunged 51 percent last year, the biggest drop among more than 100 industry groups on the nation’s benchmark stock gauge. Hyundai Heavy, the fourth-largest company by market capitalization in the benchmark Kospi at its peak in April 2011, now ranks 34th after losing about $31 billion in value.
Hyundai Mipo dropped 3 percent, the most since Dec. 26, at the close in Seoul. Daewoo Shipbuilding slid 1.2 percent, while Hyundai Heavy closed unchanged. The Kospi (KOSPI) retreated 0.2 percent. Press offices of the three companies declined to comment on stock performance.
Net Loss
Hyundai Mipo shares fell to their lowest level since 2006 this month. The company received $1.8 billion worth of new orders in 2014, the lowest in five years and almost half its annual target of $3.5 billion. The company recorded a net loss of 416 billion won ($385 million) in the third quarter, its widest in at least four years.
“The amount of short selling shows investors’ pessimism,” said Chang Keun Ho, a Seoul-based analyst at Samsung Asset Management Co., which oversees about $112 billion of assets. “New orders have dropped and earnings came in as a shock. It’ll take time for people to believe the shipbuilding business has stabilized, especially given the oil price hit.”
Short interest in Hyundai Heavy has surged to 3.5 percent, its highest since at least 2006, from 0.5 percent a year ago. Oil exploration comprised 19 percent of last year’s new orders, almost double the 11 percent recorded in 2012. The company swung to a loss of 1.18 trillion won in the third quarter from a profit of 25.4 billion won a year earlier.
New Orders
Daewoo Shipbuilding’s short interest increased to 5.3 percent from 1.7 percent a year ago. New orders for drill ships and other offshore production vessels accounted for 60 percent of the company’s total in 2013, compared with 44 percent in 2011. The stock has fallen 73 percent from its high in October 2007 through yesterday.
Oil prices slumped almost 50 percent last year as the Organization of Petroleum Exporting Countries resisted output cuts even amid a global surplus that Qatar estimates at 2 million barrels a day. West Texas Intermediate will trade at $41 a barrel in three months, down from a previous forecast of $70 for the first quarter, Goldman Sachs Group Inc. said in a report distributed yesterday.
Shares in shipbuilders will probably rebound because selling has been excessive and demand for tankers may rise as falling oil boosts crude and gas shipments, said Park Moo Hyun, an analyst at Hana Daetoo Securities Co. in Seoul. Earnings may pick up from as early as the second quarter, he said.
Chinese Demand
China’s efforts to lift reserves may increase its imports by as much as 700,000 barrels a day this year, according to London-based Energy Aspects Ltd. China boosted imports by 8.3 percent, or 460,000 barrels a day, in the first nine months of this year, the fastest pace since 2010, customs data show.
The average price-to-book ratio for the six companies in Korea’s shipbuilder index is around 0.6 times net assets, a 43 percent discount to the Kospi.
“The current valuation on the sector is ridiculous,” said Park. “Worries about shipbuilders are overdone.”
While analysts predict gains of more than 20 percent over the next 12 months for both Hyundai Mipo and Daewoo Shipbuilding, the average price targets have fallen to their lowest levels in at least four years, according to data compiled by Bloomberg. The Baltic Dry Index (BDIY), a measure of commodity shipping rates, tumbled 66 percent last year.
“People are still uncertain about shipbuilders,” said KTB’s Lee. “Any share rebound from short-covering won’t last without fundamental improvement. I don’t see a reason to overweight the sector in the short term. They may have to suffer a little more.”
LNG船建造=質の良いLNG船の建造とはならない。中国勢の技術水準の高まりを示すと言えばそうとも言えるが、船を問題や修理の必要なしである一定の期間運航できるかは別の問題。こればかりは実験と同じで船を運航させてある一定の期間が過ぎるまでわからないこと。
■中国船舶工業集団(中国国有造船大手)傘下の中船集団滬東中華造船が液化天然ガス(LNG)運搬船を建造し、借り主となる米石油大手エクソンモービルに引き渡す。中国企業が建造したLNG船を輸出するのは初めてという。
9日付の上海紙「解放日報」が伝えた。8日に上海市郊外の長江に浮かぶ長興島の埠頭で命名式典が開かれ、「パプア」と名付けられた。エクソンモービルがパプアニューギニアで生産するLNGを中国に運搬するのに使う。
韓国や日本の造船大手は高い建造技術が求められるLNG船の受注に力を入れている。ただ、今回、海外に輸出するLNG船が完成したことは中国勢の技術水準の高まりを示しており、今後の受注競争にも影響が出てきそうだ。
中国は環境負荷の低い天然ガスの利用を今後積極化する方針で、2020年に年6000万トンのLNGを輸入する見込み。その時点で必要なLNG船は50隻という。現在、中国がLNG輸入に活用している運搬船は6隻だけで、今後、中国製LNG船の調達が加速しそうだ。(上海=菅原透)
米国のシェールガス開発ブームに後押しされて昨年、LNG(天然液化ガス)船舶の新規発注件数が計60隻に達した中で、韓国の造船会社が73%である44隻を受注したことが分かった。昨年、LNG船の新規発注件数は2004年の計75隻が発注されて以降10年ぶりとなる最大規模だ。
英国の造船・海運調査機関クラークソンが最近発行した報告書によれば、韓国の造船会社は昨年全世界で発注された60隻中44隻のLNG船を受注し、約73%の占有率を記録した。大宇(デウ)造船海洋はこのうち30隻を受注し、全世界物量の半分を占めた。サムスン重工業は8隻、現代(ヒョンデ)重工業は6隻をそれぞれ受注した。日本と中国はそれぞれ11隻、5隻を受注し韓国の後に続いた。
業界は最近、船舶の大型化傾向が韓国造船会社にとって好材料だったとみている。韓国は大型LNG船舶の建造能力が日本や中国よりも大きく上回っている。特に2016年に工事が終わるパナマ運河にはパナマックス級(7万トン級)の船舶が運航でき、需要が大きく伸びた。昨年発注された60隻のLNG船のうち47隻が17万立方メートル級以上の大型船舶だった。
昨年LNG船の受注が急増した結果、全世界で運航中のLNG船10隻のうち6隻は韓国製が占めることになった。1991年に現代重工業が初めてLNG船舶市場に進出して以降これまでに韓国の造船業界は計358隻を受注した。全世界の総受注量(586隻)の61%を掌握したことになる。
Bulk: Bauxite transports, one of the biggest commodities for the global dry bulk fleet, could face a higher risk evaluation after the Bulk Jupiter shipwreck on January 1st. D/S Norden anticipates extensive investigation into the accident.
BY OLE ANDERSEN
Dry bulk vessel Bulk Jupiter's dramatic wreck around 150 nautical miles off the coast of Vietnam on January 1st, in which 18 of 19 crew members are believed to have been killed, has sent shock waves through the international dry bulk industry and among marine insurers.
The ship, from carrier Gasbulk, was loaded with 46,400 tons of bauxite, one of the biggest dry bulk commodities, used to manufacture aluminum, when the ship en-route from port city Kuantan in Malaysia emitted distress signals on January 1st at 10.54 pm UTC and subsequently sank.
Now bauxite could be upgraded to a high-risk cargo.
Insurers reacting
The direct causes behind the tragic wreck remain unknown, but at Danish carrier D/S Norden, Head of Dry Cargo Operations Jens Christensen confirms that several of the P&I clubs have reacted to the accident and are speculating that one cause could be the cargo, the bauxite, which can become liquefied and thus move around in the cargo holds if the bauxite's humidity becomes too high.
Combine this with a ship that is rolling in the water at high heel, the worst case scenario is that the ship will capsize very quickly.
"We have to await the results of the investigation into this tragic accident. In any case, we expect a very thorough investigation, and then we'll see whether this leads the IMO to reevaluate the codes used in dry bulk shipping."
The so-called IMSBC code, International Maritime Solid Bulk Cargoes, which has applied to dry bulk for years, specifically addresses the risk of liquefaction and divides dry bulk into three categories, A, B and C.
The risk of liquefaction is specifically mentioned for A cargoes, stating that carriers should always know the exact humidity level in the cargo, which the shipper is required to test.
The risks of bauxite
In accordance with the current and applicable code, bauxite is categorized as a group C cargo, which means that the code does not imply a risk of liquefaction even though accidents have been reported in recent years on board ships carrying bauxite.
"The latest wreck could result in discussions about whether bauxite should be upgraded to an A cargo. If that happens it will be a major change, because shippers will always be required to supply a TML certificate (Transportable Moisture Limit), which requires extensive lab testing and documentation stating the current humidity level," says Jens Christensen.
Norden has not transported bauxite from Malaysia and Indonesia in recent years, but the carrier's ships do load considerable volumes from three major bauxite ports in Guinea, Brazil and Ghana.
"But it's very important to secure complete clarification of the current accident, and we're following developments closely"says Jens Christensen.
At this time the industry is speculating about possible causes for the Jupiter Bulk shipwreck. The ship was built in 2006.
These speculations include cargo humidity, and observers point to the fact that Malaysia in recent months has been hit by massive monsoon rains.
Companies such as American Club, Britannia P&I and Norwegian Hull Club have been mentioned as marine insurers reacting to the accident with an appeal for increased vigilance even though the cause remains completely unknown at this time.
Carrier Gearbulk has published two statements so far concerning the tragic accident, most recently on Monday, January 5th, stating that no additional casualties or parts from the wreck had been recovered. The entire crew hails from the Philippines. The ship's cook is the only survivor at this point, while two deceased crew members have been recovered following the accident.
IMO secretary-general Koji Sekimizu says action must be taken to improve the safety standards on passenger ferries following the fatal fire on the Norman Atlantic. In a message to the industry Sekimizu said: “2014 will be remembered as another year of very serious maritime casualties involving passenger ships, with the tragedy of Sewol and the fire aboard the Norman Atlantic. IMO must take action to investigate these maritime accidents and improve safety standards of passenger ships.” “In this context, I urge IMO member governments to review the current level of safety standards of passenger ships at the Maritime Safety Committee”.
中国・南通明徳 が破産 (Nantong Mingde Heavy Industries Bankrupt)
BY Wendy Laursen
China’s Nantong Mingde Heavy Industries has been ordered to file for bankruptcy after an application by Chinese shipbuilder Sainty Marine on December 26.
The court declared the shipyard insolvent and accepted an application for its bankruptcy and reorganization by Sainty Marine.
Both yards are listed on the Chinese government’s white-list for receiving financial support, and they had been collaborating to win orders.
Nantong Mindge has built chemical tankers as well as a range of other vessels including offshore vessels. According to media reports, it currentlyl continues the construction of 14 stainless steel chemical tankers.
In a media statement Mingde president Ji Fenghua said it was a pity that his company was forced to file for bankruptcy. However, he conceded that the move should ensure the shipyard’s continued survival.
By Lee Hong Liang from Singapore
Debt-ridden Nantong Mingde Heavy Industry will enter into a restructuring process as ordered by a local court and the shipbuilder is expected to be acquired by compatriot shipbuilder Sainty Marine.
Nantong Intermediate People's Court on 26 December ordered Mingde to file for bankruptcy and its biggest debtor Sainty Marine will take control of Mingde via a debt-to-equity rescue deal.
Due to the prolonged recession of the global shipbuilding industry, particularly in China, Mingde has been making losses and failed to secure fresh loans from the banks, local reports said. Mingde, lacking cashflow, had been collaborating with Sainty Marine to jointly win newbuilding orders, eventually leaving the former in the debt of the latter over the years.
Mingde is one of China's 59 'white list' shipyards, which are expected to enjoy financial support from the local banks and gain recognition as reputable shipbuilders. Sainty Marine also made it to the 'white list'.
Sainty Marine recently announced to the stock exchange that it has cancelled four newbuildings with Corbita Maritime Investment as the shipowner could not make payments. The botched deal is expected to result in a potential loss of RMB37m ($5.9m) in 2014 for the Shenzhen-listed yard.
At present, Mingde continues its daily operations as the yard holds an order for 14 stainless steel chemical tankers due for deliveries between 2016 to 2017.
子会社の三菱航空機が開発してきた国産初のジェット旅客機「MRJ(三菱リージョナルジェット)」の試験機が平成27年春にも初飛行を控え、“ノリノリ”ムードの三菱重工業。しかし、そのムードをそぐ事態が相次いで発生している。欧州のクルーズ運航会社から受注した大型客船の建造費が当初見込みを大幅に上回り、平成26年3月期から2期連続で特別損失を出し、合計約1000億円を計上する事態に陥った。さらに26年12月に入り、三菱重工が建造した貨物船の沈没事故をめぐり、運行会社などから合計600億円の賠償請求が提訴されたことも明らかになった。明治17年、三菱財閥の創業者岩崎弥太郎が長崎造船所を国から借り受け、造船事業に乗り出したのが三菱重工の始まりだが、祖業である造船事業が全体の足を引っ張る状況に直面している。
■最高益更新も苦渋の表情
「今後一切出ないようにしたいが、可能性はゼロではない」
10月末に行われた平成26年9月中間連結決算説明会の場で、野島龍彦取締役は、これ以上の客船事業での損失があり得るかとの記者の問いに対し、苦渋の表情でこう答えた。
皮肉なことに客船以外の事業は、2月に火力発電事業を統合した「三菱日立パワーシステムズ」のシナジー効果や、積極的なM&A(企業の合併・買収)戦略などを打ち出すなど、“イケイケ”状態。9月中間連結決算は、営業利益が前年同期比56.7%増の1182億円と過去最高に達した。
しかし、客船の建造遅延の影響から27年3月期に398億円の特損を計上する。この影響で、最終利益見通しは、前回予想より300億円少ない1000億円(37.7%減)に下方修正した。
三菱重工は、23年11月にクルーズ客船運航世界最大手の米カーニバル傘下の伊クルーズ客船会社コスタ・グループから約12万5000総トン、3250人乗りの大型豪華客船2隻を受注した。受注額は公表していないが、約1000億円ともいわれる。国内で建造する客船としては過去最大級だ。
しかし、今は受注額が特損額に匹敵する状況に陥っている。
かみ合わない歯車
実は、受注直後から三菱重工とアイーダ社との歯車はかみ合っていなかったとされる。造船事業に長年のノウハウを持つ三菱重工だが、客船は得意の貨物船やLNG船と仕様が大きく異なる。いわば、船の上に“巨大なホテル”をつくるようなもので、貨物船などと比べてノウハウや蓄積も乏しい。ただし、スケジュールを守るなど、日本ならではのきめ細かさで対応できると踏んでいた。
ところがフタを開けると、アイーダ社側から、内装や空調設備などの仕様に対し、細かいオーダーが続出。しかも、イメージと異なる、といった理由で設計変更に何度も応じる場面もあったという。こうした積み重ねによるスケジュールの遅れや人件費増加が響き、大規模な特損を生み出したのだ。
そして、ここへきて、さらに頭の痛い訴訟を起こされていることが明らかになった。
ことの発端は、25年6月、インド洋を航行中の貨物船の船体が破断し、大量の積み荷とともに沈没した事故だ。
26年12月に入り、沈没した貨物船「エムオーエル コンフォート号」の事故責任は、強度に余裕を持たせる設計をしないなど三菱重工に設計ミスがあると、運航会社の商船三井や保険会社などが相継ぎ提訴し、請求額は計600億円に上ることが明らかになった。 三菱重工側は、商船三井に引き渡す際の強度検査で問題は見つからず、過失はないとして請求棄却を求めているが、事態の進展次第では、さらなる特損を積み上げてしまう可能性も出ている。まさに「一難去ってまた一難」の状況なのだ。
■不採算事業は“撤退”も選択肢
三菱重工は今後、客船事業などをどう進めていくのか。
中間決算説明会で、船舶などを担当する交通・輸送ドメイン長を務める鯨井洋一副社長は、今回の豪華客船の1、2番船建造後の事業について、「船の設計などを中心に行うシステムインテグレーターになるのか、引き続き自分たちで作り続けるかを検討する」と述べるなど構造改革を急ぐ方針を口にした。
もっとも三菱重工は、22年に戦略的な事業に資源を重点投入する「戦略的事業評価制度」を導入している。裏を返せば、不採算とされた事業には積極的な資金投入はしないこ都を意味する。巨額特損を出す客船事業が、今後評価の対象になるとの見方もある。
懸念材料はまだある。
今回の客船を受注した船会社の親会社であるカーニバルが26年10月、中国の造船大手、中国船舶工業集団(CSSC)と客船建造の合弁事業立ち上げに向けての覚書に調印したのだ。日本の高い技術力やマネジメント能力に対し、「人件費の安い中国勢が人海戦術で客船事業を攻めようとしても、実際はなかなか厳しいはず」(重電関連アナリスト)との見方があるが、脅威となる可能性は否定できない。
もっとも、「10年後を見通せば、(客船事業が)有益なアイテムになる可能性は十分ある。安易に撤退せず、やり続ける必要があるのではないか」(重電関連アナリスト)との声もある。先進技術を搭載し、燃費削減と環境負荷低減を実現する大型客船を建造できる能力は、依然、大きな強みとして差別化できるメリットがある。
貨物船の巨額訴訟という新たな火種も生まれている中、三菱重工はこの難局をどう乗り越え、“創業事業”の造船事業をどう立て直すのか。MRJの離陸とともに、今後の造船事業の行方も関心を呼びそうだ。
島根県浜田市沖で長崎県の巻き網漁船第1源福丸が沈没し、乗組員2人が死亡した事故で、漁船を所有する東洋漁業(長崎市)は27日、浜田港に停泊中の22日未明、船内で起きた同僚同士の傷害事件に船長が巻き込まれ、けがの治療のため下船し、事故が起きた24日未明は不在だったと明らかにした。
浜田海上保安部は「大型船舶の免許を他の船員が持っていたので問題ない」と話しており、同社も「1人当たりの作業量は増えたかもしれないが、事故の直接の原因とは考えていない」としている。
東洋漁業は不明者捜索と事故原因の解明のため、漁船の引き揚げに向けた調査を年明けにも始める方針も明らかにした。
傷害事件は停泊中の船内で船員が別の船員に熱湯をかけてけがを負わせ、船長もやけどをした。
一方、運輸安全委員会の船舶事故調査官3人は27日、東洋漁業本社を訪れ、漁船の安全マニュアルや運航記録など十数点を収集した。
また、行方不明になっている乗組員の家族らは27日、船で片道約1時間かかる海域に行った。午前9時ごろ、浜田港で船に乗り込んだ3家族7人は、冷たい風が吹く中、硬い表情のまま無言だった。
行方不明になっているのは、漁労長浜本満義さん(52)、機関長松口明裕さん(54)、機関員今西要一さん(60)=いずれも長崎県平戸市。浜田市に駆け付けた家族らが「現場に行きたい」と要望していた。
事故では、平戸市の甲板長横山晶一さん(59)と甲板員塚本圭司さん(56)が死亡した。市内では27日、2人の葬儀が営まれた。
島根県浜田市沖で長崎県の巻き網漁船第1源福丸が沈没し、乗組員2人が死亡した事故で、漁船を所有する東洋漁業(長崎市)は27日、浜田港に停泊中の22日未明、船内で起きた傷害事件に船長が巻き込まれて下船し、事故が起きた24日未明は不在だったと明らかにした。
浜田海上保安部は「大型船舶の免許を他の船員が持っていたので問題ない」と話しており、同社も「1人当たりの作業量は増えたかもしれないが、事故の直接の原因とは考えていない」としている。
東洋漁業は不明者捜索と事故原因の解明のため、漁船の引き揚げに向けた調査を年明けにも始める方針も明らかにした。
一方、運輸安全委員会の船舶事故調査官3人は27日、東洋漁業本社を訪れ、漁船の安全マニュアルや運航記録など十数点を収集した。
また、行方不明になっている乗組員の家族らは27日、船で片道約1時間かかる海域に行った。午前9時ごろ、浜田港で船に乗り込んだ3家族7人は、冷たい風が吹く中、硬い表情のまま無言だった。
行方不明になっているのは、漁労長の浜本満義さん(52)、機関長の松口明裕さん(54)、機関員の今西要一さん(60)=いずれも長崎県平戸市。浜田市に駆け付けた家族らが「現場に行きたい」と要望していた。
事故では、平戸市の甲板長の横山晶一さん(59)と甲板員の塚本圭司さん(56)が死亡した。市内では27日、2人の葬儀が営まれた。
島根県浜田市沖で東洋漁業(長崎市)の巻き網漁船「第1源福丸」が沈没した事故で、現場海域では浜田海上保安部などが行方不明の3人の捜索を続けた。また第1源福丸の船長が沈没の2日前に船内で起きた傷害事件の影響で船を下り、事故当時は不在だったことが分かった。
島根県警浜田署や東洋漁業によると、事件は22日未明、しけのため浜田港に停泊中だった第1源福丸の船内で発生し、機関員の桝屋家親容疑者(63)が逮捕された。逮捕容疑は、甲板員(29)を倒して、やかんの熱湯をかけ約1カ月のやけどを負わせたとしている。船長の西沢幸三さん(46)も巻き込まれてやけどし、3人は事件後、下船したという。
船長不在で欠員が出た中での操業について、東洋漁業は「法的に問題はない。1人当たりの仕事量は増えたかもしれないが、事故の直接の原因ではないと考えている」としている。【竹内麻子、野呂賢治】
三菱重工業が、造船事業の主要部分を分社化する検討に入ったことが23日、わかった。
主力の液化天然ガス(LNG)タンカー部門を分社化し、防衛関連など特殊船舶のみ本体に残すとみられる。赤字の続く大型客船部門は新規受注を凍結し、事実上撤退する方向だ。
同社の造船事業はLNGや液化石油ガス(LPG)輸送船が中心だが、中国や韓国の造船大手との価格競争が激しく、採算が悪化していた。
新分野として大型客船に力を入れていたが、不振が続き、大型客船2隻の建造トラブルで1000億円超の特別損失を出している。
このため同社は、造船事業について「分社化で構造改革を進め、自立できるようにした上で、他社との資本提携なども含めた生き残り策を探るのが合理的」(関係者)と判断した。次期中期経営計画が始まる来年度から、具体的な検討に入ると見られる。
Mercuriaが倒産したOW Bunkerの船舶燃料専門家を40人以上雇用
AsiaNet 58965 (1392)
【ジュネーブ2014年12月16日PRN=共同通信JBN】
*船舶燃料事業およびサービス提供を拡大するエネルギー大手
エネルギーおよび商品の大手グループMercuriaはデンマークを本拠に船舶燃料の供給を専門にしていた倒産企業OW Bunkerから40人以上の船舶燃料専門家を雇い入れたと発表した。
Mercuriaの取引グループの責任者であるマギッド・シェヌーダ氏は「今回の動きは活気にあふれた当社燃料油取引インフラの自然な拡大である。才能ある専門家を当社陣営に加えることで、Mercuriaは現物燃料油ビジネスにおける人材およびビジネス関係の強化、顧客に提供するサービスの拡大、さらにエネルギー分野の専門知識を必要とする機関に対してサービスおよび専門知識を提供することで国際船舶燃料市場の安定性、信頼性の増加をはかるものだ」と述べた。
Mercuriaに加入することになった数十人の専門家はバンカー重油を消費者に提供する任にあたることになるが、これによってMercuriaは現物商品とエネルギーの取引企業として扱うサービスを拡大する。今回船舶燃料の専門家が加入したことで、Mercuriaは船舶向けのエネルギー供給の品質、荷渡しを監督する独立した子会社Minervaを設立することを検討することになった。
これら新規採用の専門家はMercuriaが韓国、ギリシャ、日本に開設する事務所で勤務する予定で、規模の拡大が続くヒューストンやジュネーブではさらにスタッフを加えるなどして、同社は世界に展開する取引所および駐在員のネットワークをさらに補強する。Mercuriaは既存および新加入のスタッフを得て今後も燃料の注文通り、時間通りの納入を確約することを続ける考えである。
シェヌーダ氏は「これらの人たちは長年、船舶燃料の管理の経験を持っており、船舶燃料コストのリスクを低減し、取引相手がコストを管理する手助けをする専門スキルを持っている」として次のように述べた。「今日、Mercuriaのチームはすべての主要石油取引フォーラムで市場開発をおこなうための深い認識を持っている。当社は世界的な視野を持つ一方で、各地のリアルタイム市場ダイナミックスに対する観察眼も持っている」
Mercuriaはエネルギーとコモディティーの分野で世界大手グループの1つである。グループの主な取扱品目はエネルギーで、そのコモディティーのバリューチェーンのあらゆる段階に携わっており、2013年の売り上げは1120億米ドルに上った。コモディティー物流と戦略資産の間でバランスが取れた事業展開を行っている。市場知識、多様な出身母体や経験を持つ1000人以上の従業員が世界で勤務し、グループの幅広いリーチを支えている。最近になって、同グループはJ.P. Morgan Chase and Co.からの現物商品取引事業の買収を完了した。
By Ian Lewis London
Cremer Group among the names lending support as young company forges on with its fleet development programme
A fledgling German owner that has secured blue-chip backing is moving to acquire more vessels in the project sector.
Auerbach Schiffahrt is pushing forward its fleet development with the backing of shareholders including Cremer Group, as well as managerial support from former Bimco chairman Robert Lorenz-Meyer.
The Hamburg-based company, which was set up four years ago, is negotiating an order for two more multipurpose (MPP) vessels in the F-500 series at China’s Jiangzhou Union Shipbuilding.
If the options are exercised, Auerbach will be left with seven MPP ships, including the two already under construction at the yard.
Work on the first two F-500 vessels — so named because the ships are each equipped with two cranes capable of lifting 500 tons in total — started in October. Costing $18.5m each, they are slated for delivery in mid-2016.
Those orders followed design talks lasting almost two years with Leer-based shipping companies Briese Schiffahrts and Krey Schiffahrts. The new design is based on the E and F series comprising more than 80 MPP units.
They include the former Beluga Shipping-controlled, 12,750-dwt/ 665-teu MPP boxships Maple Lea and Maple Lotta (both built 2007), which Auerbach acquired at auction in 2011.
Auerbach was founded in 2010 by Alexander Tebbe and Lucius Bunk, who met while working with German shipping company Ernst Russ. The initial plan had been to focus on acquiring distressed assets but banks refused to sell vessels at what Auerbach considered market prices, or the available ships on the market were poorly maintained.
So a decision was taken to target newbuildings, which then cost the same as five-year-old secondhand vessels. The move was made possible with the support of shareholders who took “a clear long-term strategy”, says Bunk.
Auerbach’s largest shareholder remains the Mohrle family, former owners of a do-it-yourself (DIY) chain that they sold in order to invest in start-up companies.
Other backers include shipping names such as Hamburg-based grain trader Peter Cremer Holding. Cremer is known for chartering panamax bulkers but took to supporting Auerbach in the MPP sector as a form of diversification.
Others make up a list of around 10 shareholders.
Lorenz-Meyer is not a shareholder but serves as company chairman and is credited with giving Auerbach strong support.
“What’s very valuable about this is that these people are on our board,” said Bunk.
“We speak on a very regular basis and discuss possible new projects and strategies. They are very involved and creative on how things are developing.”
Bunk says the talks with Briese and Krey resulted in modifications to the E and F-class vessels to create a more fuel-efficient design with more flexible cargo handling.
Briese, which has 130 MPP and heavylift ships, subsequently ordered two of the same design at Jiangzhou Union. The hull design and two-stroke engine, with an ultra-long stroke, are set to mean the new designs will consume at least 25% less fuel than existing vessels.The ships have a 77-metre-long cargo hold, as well as two Liebherr deck cranes, each with a lifting capacity of 250 tons.
Separately, Auerbach also manages the 12,750-dwt/447-teu E-Ship 1 (built 2010), a prototype rotor sailship developed by Enercon.
与党セヌリ党と政府が5日、違法操業をする中国漁船に対する刑事処罰を強化し、無許可漁船は没収して廃船する案を検討することにした。政府・与党はこの日、合同政策調整会議を開き、このように決めた。領海を侵犯する中国漁船が凶暴になり、違法操業を鎮圧する過程で海洋警察の公務員が死亡する事態が発生しているだけに、これを放置すべきではないという判断からだ。
政府・与党は暴力を行使する中国船員に対しては罰金のほか、公務執行妨害容疑で刑事処罰することにした。ただ、中国当局の許可を受けていない違法漁船を没収して廃船する案は、韓中漁業協定の改定や中国政府の同意が必要であるため、実現するかどうかは不透明だ。これに関しセヌリ党の姜錫勲(カン・ソクフン)政策委副議長は「韓中漁業協定改定に先立ち、国内法の排他的経済水域(EEZ)法を改正し、中国側に圧力を加える案も検討している」と話した。
政府・与党は違法操業に対する取り締まりを強化するため、最近新設された国民安全処海洋警備安全本部の人員を補強することにした。何よりも中国漁船の違法漁労を現場で取り締まる特殊機動隊の人員を選抜することにした。 .
バルクキャリア「SEAPACE」号(IMO: 9486025)に取り付けられている中国(Wuhan Marine Machinery Plant Co Ltd)製のIHIのデッキクレーンが真っ二つに折れたそうです。
IHIのサイトに
「デッキクレーン・クレーンの中国内での授権に関するお知らせ」として
真っ二つに折れたIHIのデッキクレーンは2010年に中国で建造されたバルクキャリアに設置されたいたそうです。製造年月日は記事には掲載されていませんが2009又は2010年製だと推測されます。クレーンが折れた理由はメンテナンスに問題があったと言われていますが、TSB(カナダ運輸安全委員会)はクレーンに欠陥があったのではないかと調査しております。調査対象のIHIクレーンは2008年から2014年の間に中国で建造された約450隻の船に設置されているとの事です。折れたクレーンは武漢船用機械有限責任公司がIHIクレーンとして製造したクレーンであるとの事です。同じIHIクレーンが設置された約450隻の船にも同様の問題がある可能性が懸念されています。
「武漢船用機械有限責任公司 は、株式会社IHIから正当に受権して、IHI-WMブランドによるデッキクレーン・ウインチを中国内で独占的に製造し、また販売できる権限を有しております。中国でIHI-WMブランドのデッキクレーン・ウィンチをご要望の際は、武漢船用機械有限責任公司にお申し付け下さい。」
と書かれているのでIHIのデッキクレーンで間違いないと思います。
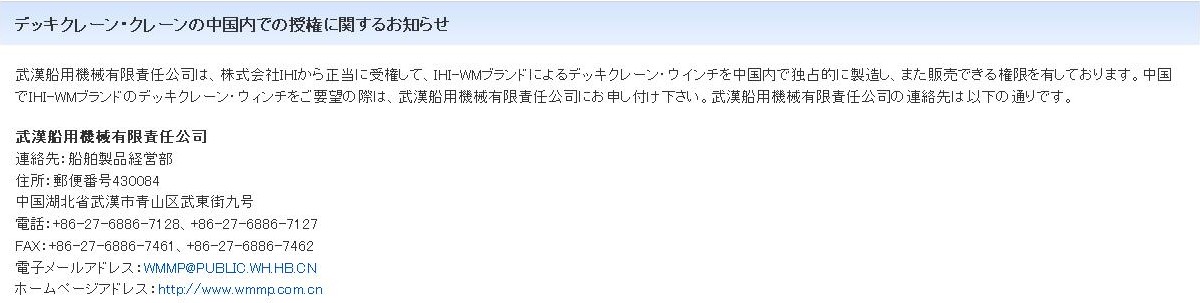
IHI crane slewing bearing changeout (Alatas)
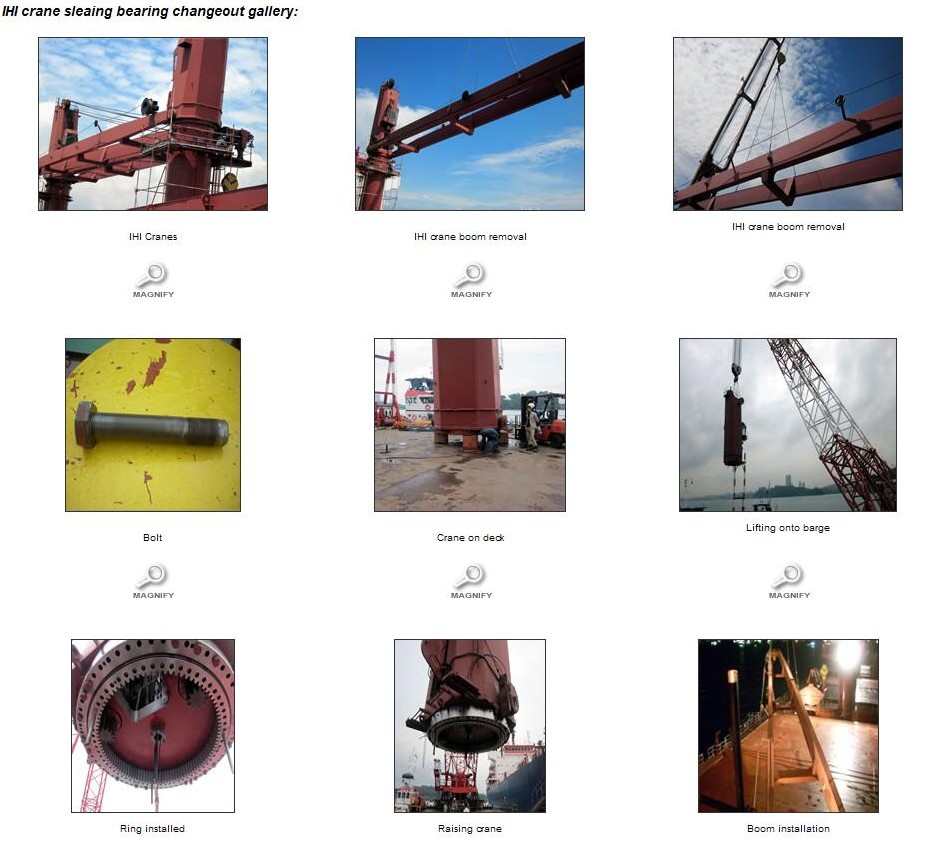

Canada has urged owners to check a certain type of Chinese-made crane after an accident on a bulker injured an operator this summer.

The damaged crane
The Transportation Safety Board of Canada (TSB) said a “catastrophic failure” of a cargo-handling crane on the 57,000–dwt Seapace (built 2010) occurred in Becancour on 13 August.
“The slewing ring bearing broke apart and the complete cabin and jib assemblies collapsed into a cargo hold, injuring the crane operator,” it added.
It has launched a joint investigation with Transport Malta, but in the meantime issued this warning: “There is a possibility that the same progressive failure of a slewing ring bearing will occur on any vessel fitted with similar cargo handling cranes.
“Vessel owners should take whatever measures considered appropriate to ensure the integrity of any similar unit in service on board vessels.”
There is no known central database of vessels with such cranes.
The bulker is one of 443 similar ships built between 2008 and 2014 by various Chinese shipyards.
The crane was built for IHI of Japan under licence by Wuhan Marine Machinery Plant (WMMP) of China.
It is an electro-hydraulic jib crane of type SS36T.
The slewing ring bearing assembly was fabricated by Dalian Metallurgical Bearing of China.

Canadian Watchdog Warns on Chinese-Made Cranes
Canada's Transportation Safety Board took the unusual step of warning about a possible defect in a widely used Chinese-made ship cargo crane after a worker was injured in Quebec.
Tests are still being done, but the federal watchdog issued the warning because it believes many similar cranes are in use. The TSB is not aware of any other incidents and does not know exactly which cranes could be vulnerable.
"We felt that we had to send this information as widely as we could and as fast as we could," TSB investigator François Dumont told Reuters.

In August, a crane on a bulk carrier in Bécancour, Quebec collapsed after a slewing ring bearing fractured. Its cab was partially crushed and the operator injured.
The crane was made for Japan's Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co Ltd, now IHI Corp, by China's Wuhan Marine Machinery Plant Co Ltd, a subsidiary of China Shipbuilding Industry Corp, one of the country's two largest state-owned shipbuilding groups.
The Canadian investigation is focused on the bearing and whether there was a fabrication failure, Dumont said. It is being examined at a lab in Ottawa. The bearing was made by China's Dalian Metallurgical Bearing Co Ltd.
IHI, Wuhan Marine Machinery and Dalian could not immediately comment.

The ship is one of 443 built at shipyards across China between 2008 and 2014 based on a single set of plans, said Dumont. Each has four cranes.

Dumont said investigators believe that all the ships may have the same bearing and the TSB is liaising with ship owners and manufacturers, who do have that information.
A Wuhan Marine Machinery representative is among several outside experts observing the Ottawa tests.

The collapse of cranes fitted on ships has been a longstanding problem, said Michael Grey, a master mariner and journalist who campaigns on ship safety issues.
"The lack of maintenance is generally to blame," said Grey, adding that cranes are exposed during voyages and difficult to access

But Canadian investigators do not believe poor maintenance was a factor in Quebec. Dumont said the crane was maintained and operated properly and inspected regularly.
A final TSB report is expected in the first half of 2015.
Comment by the Heavy Lift Specialist:
As the Slew bearing of any crane is the most critical part of a crane, utmost care must be taken to garantee that a quality product is used and verified by inspection and tracebility records.
by Canadian Manufacturing Staff

Safety regulators say a broken slewing ring bearing led to the collapse of a cargo crane aboard a ship in Quebec in August. PHOTO TSB
GATINEAU, Que.—A “catastrophic failure” aboard a cargo ship in Quebec over the summer has prompted federal safety regulators to issue a warning to vessel owners.
The Transportation Safety Board of Canada (TSB) said a bulk carrier was docked in Becancour, Que., across the St. Lawrence from Trois-Rivieres, Que., in August when one of its cargo cranes suffered a failure that sent the cabin and jib assemblies crashing down into a cargo hold, injuring the crane operator.
The safety agency traced the failure to a broken slewing ring bearing.
“There is a possibility that the same progressive failure of a slewing ring bearing will occur on any vessel fitted with similar cargo handling cranes,” the agency said in a statement, noting there is no known central database identifying ships outfitted with the cranes.
The bulk carrier involved in the incident was one of nearly 450 built at various shipyards in China between 2008 and 2014.
The cargo handling crane involved was built for Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd. (IHI) of Japan, under licence by Wuhan Marine Machinery Plant Co. Ltd. (WMMP) of China.
It was an electro-hydraulic jib crane, according to the TSB, and its slewing ring bearing assembly was manufactured by Dalian Metallurgical Bearing Co. Ltd. of China
According to the TSB, nearly 450 ships worldwide may be at risk of a similar incident.
The agency said vessel owners should take whatever measures considered appropriate to ensure the integrity of any similar unit in service aboard other ships.
IHIのデッキクレーン(IHI-WMMP)は30tonカーゴブロックの問題をニュージーランドで指摘されて2011年に資料を作成して対応をしています。
TSB(カナダ運輸安全委員会)が2015年に公表する報告書の結果次第では、同じように対応するようになるかもしれません。
Maritime NZ Safety Bulletin
Maritime NZ has issued a Safety Bulletin to draw attention to a number of recent crane block failures on IHI and IHI-WMMP deck cranes on log ships and to make available advice from the manufacturer as to the correct operation of the cranes and their recommended remedial action.
There have been a number of failures of crane blocks on 30 tonne IHI deck cranes on log ships in New Zealand over the past year. Fortunately there have been no serious injuries as a result of these failures to date, but any crane failure is potentially very serious.
The crane manufacturer IHI Corporation has proposed a modification to the blocks on this type of crane, as detailed in the attached bulletin (IHI ref. NGO-6185, 22 June 2011), to eliminate or reduce the incidence of such failures.
IHI suggests that at least some of these failures may have been attributable to slewing loads without lifting first, resulting in damage to the blocks due to side loading and subsequent failure over time.
However, no independent evidence has been presented to support this view, and there may well be other factors involved in the failures. While Maritime New Zealand (MNZ) is providing a copy of IHI's bulletin to highlight safety issues with the cranes, MNZ is not in a position to endorse IHI's views as regards the mode of failure.
Guidance
The purpose of this safety bulletin is to:
There have been a number of failures of crane blocks on 30 tonne IHI deck cranes on log ships in New Zealand over the past year. Fortunately there have been no serious injuries as a result of these failures to date, but any crane failure is potentially very serious.
The crane manufacturer IHI Corporation has proposed a modification to the blocks on this type of crane, as detailed in the attached bulletin (IHI ref. NGO-6185, 22 June 2011), to eliminate or reduce the incidence of such failures.
IHI Corporation Bulletin (IHI ref. NGO-6185, 22 June 2011) [PDF: 114Kb, 5 pages]
IHI suggests that at least some of these failures may have been attributable to slewing loads without lifting first, resulting in damage to the blocks due to side loading and subsequent failure over time. However, no independent evidence has been presented to support this view, and there may well be other factors involved in the failures. While Maritime New Zealand (MNZ) is providing a copy of IHI’s bulletin to highlight safety issues with the cranes, MNZ is not in a position to endorse IHI’s views as regards the mode of failure.
For further information please contact our Wellington office:
Phone: 0508 22 55 22 or (04) 473 0111
Fax: (04) 494 8901
Email: enquiries@maritimenz.govt.nz
渡辺 清治 :週刊東洋経済 副編集長
130年の歴史を誇る、三菱重工業の造船事業が危機に直面している。10月31日、同社は2011年に受注した大型客船をめぐり、仕様変更などで398億円の特別損失が発生することを明らかにした。前期もこの客船で巨額の特損を計上しており、前期と今期で関連特損は1000億円を超す。
問題となっているのは、クルーズ客船の世界大手、米カーニバル傘下の欧州アイーダ・クルーズ社から受注した大型客船2隻。3000人以上の収容が可能な大型クルーズ客船で、日本で建造される客船としては過去最大。三菱重工は2002年に建造中の大型客船が炎上して巨額損失を被った経緯があり、11年ぶりに受注したのがアイーダ社の客船だった。
巨額の追加費用が発生、完成も半年遅れ
しかし、客室の内装など細かな仕様を決めるに当たって、アイーダ社との間で認識の違いが顕在化。三菱重工の提案に対し、アイーダ側はより高級な仕様に変更するよう強く主張。結局、三菱重工側は先方の要求をのんで大幅な設計変更や高価な資材の使用を余儀なくされ、前期決算で641億円もの追加費用を特損計上している。
今期の特損に計上するのは、新たに発生が見込まれる追加費用分。「アイーダ社と最終的な仕様を確認していく中で、パブリックエリアやホテル部分に関して、再び設計のやり直しが大量に生じてしまった」(野島龍彦CFO)という。
すでに1隻目は長崎造船所の香焼工場で内装工事に取り掛かっている段階だが、最終設計の変更により、工事をやり直す箇所が続出。作業の遅れを取り戻すための人件費もかさみ、追加費用が400億円近くにまで膨れ上がった。完成は当初の予定より半年遅れ、1隻目の引き渡しは2015年秋にずれ込む見通しだ。
アイーダ社の客船を受注した2011年当時、造船業界はリーマンショックまで続いた海運・造船バブルの反動で新船の発注量が激減。韓国、中国勢の攻勢にもさらされ、日本の造船業は存続が危ぶまれた。
こうした中でいち早く動いたのが三菱重工だった。同社は民間船舶分野で一般汎用商船から撤退。1000人規模に及ぶ設計陣を生かして技術難易度の高い船種に集中する戦略を掲げ、得意とするLNG(液化天然ガス)運搬船に加えて、大型客船を新たな柱と位置づけた。客船に活路を求めたのは、バラ積み船やコンテナ船などの一般汎用商船とは違って、1隻あたりの金額が大きくライバルも少ないからだ。
だが、そのもくろみは完全に外れた。問題となっている客船の受注金額について三菱重工は公表していないが、2隻合計で総額1000億円前後と見られる。1000億円で受注した客船2隻を作るために1000億円以上の損が出るのだから、開いた口がふさがらない。
もともと赤字受注だったが…
そもそも今回の客船は当初から採算割れの受注だった。「最初の2隻を造れば、3隻目、4隻目、5隻目とその後も継続的に仕事が取れる。トータルで考えれば(最初の赤字分は)取り戻せる」(同社関係者)とそろばんをはじき、受注に踏み切った経緯がある。
ここで経験不足が露呈した。これまで三菱重工が手掛けてきた客船は、すでに同じ設計の船が存在し、あらかじめ仕様が決まっているものだった。今回、アイーダ社から受注したのは新型客船の「1番船」。初の船型となるため、仕様を含めて一から協議して設計を決めていく必要があった。
当然、1番船は相手側の意向で仕様が変わる可能性があり、追加費用が発生するリスクも大きい。本来なら、そうした費用負担の扱いについて契約書の中で細かく明記しておく必要があるが、三菱重工のリスク認識が甘く、契約書の中で十分なリスクヘッジが行われていなかったと見られる。
客船の巨額損失により、同社が描いた造船事業の生き残り戦略は破綻。客船の受注は事実上凍結し、民間船舶における当面の受注活動は得意とするLNG運搬船などに専念する。長崎造船所の雇用維持や収益確保のための対策として、今後は同業他社から大型商船の船体ブロック建造を引き受けるなど、下請的な仕事も検討するという。
宮永俊一社長は「(祖業なので)船に対する愛着はあるが、事業のやり方を見直し、きちんと収益を出せる事業に変えていく必要がある。これからどうすべきかを徹底的に詰めていく」と構造改革の必要性を強調した。造船事業の生き残りに向けた試練は続く。
気仙沼市で2400万円余りを団体から着服したとして逮捕されていた元事務局長が、別の団体でも定期預金1900万円余りを着服していたとして業務上横領などの疑いで再逮捕されました。
再逮捕されたのは、船員が航海士などの資格を取るための研修を運営していた「気仙沼水産振興センター運営協議会」の元事務局長、菊池利明容疑者(65)です。
警察によりますと、菊池元事務局長は、4年前の8月、管理していた団体の定期預金、およそ1920万円を解約し勝手に作った団体名義の口座に移したとして、業務上横領などの疑いが持たれています。
警察の調べに対し菊池元事務局長は「横領したのは間違いありません」と容疑を認めているということです。
菊池元事務局長は船員がけがをした際などに本人や家族に支払われる保険の手続きを代行している「宮城県北部船主協会」の元事務局長としても、船主から預かっていた保険料の中から2400万円余りを着服したとして、9月下旬に逮捕されています。
日本ではほとんど取り上げられていないが、オーストラリアでは今でも注目されているようだ。

EXCLUSIVE: A SHIPPING firm already under investigation over how two Filipino sailors were killed aboard a bulk carrier in Australian waters faces new scrutiny following allegations the ship is a "rusting hulk" in breach of Australian safety rules.
The Sage Sagittarius coal carrier was inspected in late September at the Port of Newcastle by New South Wales Deputy Coroner Sharon Freund, ship owners and the International Transport Workers' Federation that advocates on behalf of international seafarers.
RELATED: The muddy waters surrounding the 'Murder Ship'
The group visited the ship which is the subject of a looming inquest by the NSW State Coroner into how the two Filipino seafarers died on the ship in late 2012.
The death of a third sailor, Japanese superintendent Kosaku Monji will also be considered in the inquest.
He was killed on the Sagittarius just weeks after it left the Port of Newcastle.
This third fatality earned the carrier its notorious title of "Death or Murder Ship" from the ITF.
The Sagittarius is one of thousands of bulk carriers that visit regional Queensland ports including those of Gladstone and Abbot Point north of Mackay.
The inquest was ordered following a six-month award-winning investigation into the ship by APN.
ITF Australia coordinator Dean Summers said he did not believe the life rafts he saw during the September inspection were capable of saving lives.
"If your ship is sinking, you would find some solace in the fact that emergency life rafts are going to open," he said.
"Under the circumstances I saw, they would not have opened."
He said the group also saw emergency stop switches in need of repair.
These activate when someone is at risk of injury or death from machinery.
"They were rusted and frozen and completely inoperable," Mr Summers said.
Lawyers for Japanese ship managers Hachiuma Steamship would not discuss the allegations.
Speaking from Tokyo by email, Hachiuma's Naoya Miyasaka said any claims relating to safety would be "taken very seriously".
"All such matters are dealt with through the many inspections carried out on-board the vessel during the year by ourselves, but more importantly, by a number of external and competent authorities," he said.
He said the safety of Hachiuma's crew and ships was its "primary concern".
More than 1600 pages of investigative notes from the Australian Federal Police, NSW Police, the Australian Maritime Safety Authority and international authorities will be examined by the Deputy Coroner before the inquest begins in May next year.
TIMELINE OF EVENTS
AUGUST 30, 2012 (Day of first death)
● Filipino chief cook Cesar Llanto, 42, vanished overboard 800km north-west of Cairns.
● Crew members claim he was reporting abuse suffered by a fellow seafarer. Investigators found no way he could fall overboard. Ship diverted to Port Kembla for investigation.
SEPTEMBER 14, 2012 (15 days after first death)
● Filipino chief engineer Hector Collado, 57, falls more than 10m to his death while the ship was docked at the Port of Newcastle.
OCTOBER 6, 2012 (37 days after first death)
● Monji, 37, crushed to death by conveyor belt machinery in Japan
SEPTEMBER 19, 2013 (One year, 20 days after first death)
● Panama publishes confidential report into three deaths.
JUNE 16, 2014 (One year, 9 months, 17 days after first death)
● New South Wales Coroner to consider an inquest into Mr Llanto and Mr Collado's deaths in Australian waters.
Shanghai: Jiangxi Jiangzhou Union Shipbuilding, an affiliated shipyard of Hong Kong-listed China Ocean Shipbuilding Industry Group, hasn’t paid salaries to employees for almost a year, Jiangxi local media reported.
Staff at the shipyard said some 700 employees had not been paid for the past 11 months.
Wang Sanlong, general manager of Jiangzhou Union Shipbuilding, admitted that the shipyard has some salary arrears, as the shipyard is facing financial difficulties.
China Ocean Shipbuilding Industry Group announced this week that it intended to team up with Jiangxi Jianglian Heavy Industries to build LNG related infrastructure including ships, containment systems, LNG fuelling stations and LNG bunker barges, and the cooperation will be conducted through Jiangzhou Union Shipbuilding.
“We are looking for help from the local government, hopefully we can sort this out in the coming months,” Wang said.
船主協会元事務局長を横領の疑いで再逮捕 宮城 10/20/14 (産経新聞)
県北部船主協会(気仙沼市)の預金約1260万円を着服したとして、県警捜査2課と気仙沼署は、業務上横領容疑で横浜市旭区川井本町の同協会元事務局長、菊池利明被告(65)=業務上横領罪で起訴=を再逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は、同協会の事務局長として預金口座の管理と出納を行っていた平成25年2月18日、協会名義の口座から、船員の労働保険料として約1260万円を払い戻し、着服したとしている。
同署によると、同協会は菊池容疑者を同年6月に解雇。同協会などは同月、約1億7千万円を横領したとして同署に告訴していた。
県警は今年4月、菊池容疑者が約5630万円を横領したとして告訴を受理。9月24日、昨年3月26日に同協会の預金約1190万円を着服したとして、菊池容疑者を逮捕していた。
After cancelling the order for four vessels from the Samjin Shipyard earlier this year, dry cargo specialist Bocimar, a part of CMB Group, has decided to cancel a further order for six vessels due to the bankruptcy of the yard, the Belgium-based company disclosed in their third quarter results report.
The advances paid for all cancelled vessels – including interest – have already been reimbursed or are expected to be reimbursed shortly.
The CMB Group has recorded the third quarter consolidated result of US$ -12.16 million (2013: US$13.88m) bringing the consolidated result for the first nine months of 2014 to a total of US$ -14.97m (2013: US$36.67m).
Bocimar contributed US$-15.12m (2013: US$5.37m) to the third quarter consolidated result.
CMB Group says that against all expectations the markets for the transport of dry bulk did not recover. CMB sees the reasons for the still ailing dry bulk segment in the iron ore shipping increase not being able to absorb the increase of the global Capesize fleet.
The overall weakening of demand for other commodities, in particular coal, also continues to have a further negative impact on market sentiment.
The delivery of the new Stornoway ferry, MV Loch Seaforth, is in question as its shipyard faces bankruptcy after suffering financial problems.
The ownership of the £42 million ship will sail into stormy waters if the yard collapses.
The ship is being built at the Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) yard in Germany which is in danger of going under with cash flow problems.
She is almost ready but workers are still installing equipment and undertaking the final internal fitting-out.
But delays on completing construction works at the new ferry pier at Stornoway has hampered the handover plans.
If the yard goes bankrupt, administrators are likely to hold on to the vessel until the legal wrangles are sorted out.
A Norwegian company has offered to invest or buy out the Flensburger ship yard but no firm deal has yet been finalised.
No date for the ship’s handover is available, said Caledonian Maritime Assets Ltd (CMAL) – the Scottish Government company which owns the ships which provide ferry services to the Western Isles.
A CMAL spokesperson said: “Flensburger Schiffbau-Gesellschaft MBH and Co KG shipyard (FSG) is currently the subject of an acquisition that is due to complete later this month.
“However the work on the MV Loch Seaforth is nearing completion and is not expected to be impacted.
“A team from CMAL is in Germany overseeing the final elements of the build and are currently in discussions with FSG on the handover of the vessel.
“The date will be confirmed as soon as it is available later this month.”
The Loch Seaforth is designed to have a capacity for up to 700 passengers and 143 cars or 20 commercial vehicles though the actual number of vehicles which can be carried in practice is still being worked out.
これほどまでに韓国のシステムが実際は腐敗し、機能していない現実は驚いた。そして、多くの人達が簡単に虚偽、証拠隠滅、そして不正に関与したいた事実は、信用できない社会システムが存在する事を示していると思う。
韓国沈没事故 原因は船の増築・過積載 10/06/14 (聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】今年4月16日に全羅南道・珍島沖で沈没し294人の死者を出した旅客船セウォル号の沈没事故で、韓国検察は6日、船の運航会社側の無理な増築・過積載、操舵手の操舵技術の未熟さなどが直接の原因になったとする捜査結果を発表した。
事故後、検察の捜査は▼セウォル号の沈没原因と乗客救助義務違反の責任▼船舶安全管理・監督責任▼事故後の救助過程での違反行為▼同船運航会社・清海鎮海運のオーナー一家の不正▼海運業界全般の構造的問題――の五つの分野を中心に行われた。
検察はまず、船が運航会社による無理な増築・過積載で復元力(船がバランスを崩した際に元に戻ろうとする力)が著しく悪化した上に、操舵手の操舵技術の未熟さにより、船体が左に傾き復元力を失って沈没したものと結論付けた。
また、事故前後に海洋警察のずさんな対応が人命被害を拡大させたと判断。
全羅南道・珍島の管制センター(VTS)の要員らが規定通りに勤務しなかったほか、実際にセウォル号と交信したかのように虚偽の交信日誌を作成した。さらに、検察の捜査が始まると、服務監視用カメラの映像ファイルを削除したことも判明した。
事故直後、救助に向かった海洋警察艇123艇は現場で乗客に避難誘導のための措置を取らなかったにもかかわらず、実際に避難を呼びかける案内放送を行い船内への進入を試みたかのように装った艦艇日誌を作成した。
検察はセウォル号事故や救助過程の捜査とは別に、オーナー一家の不正に対する捜査を行い運航会社の実質的なオーナー、兪炳彦(ユ・ビョンオン)氏が同船の構造的な問題点を認識していたにもかかわらず、過積載運航を黙認もしくは指示していた事実を確認した。
また、オーナー一家に対する捜査の過程で、一家が系列会社や兪氏が創設したキリスト教系新興教団の資金、約1836億ウォン(188億円)を不正に受け取っていた事実も明らかにした。
さらに、この事故をきっかけに船舶収入や検査、安全点検、運航関連免許取得など海運業界全般の構造的な不正問題も捜査し、韓国海運組合と韓国船級など関連機関の不法行為を摘発した。
事故後、5カ月以上進められた検察による捜査の結果、これまでに399人が立件され、このうち154人が拘束された。
検察は事故の収拾費用をめぐり、犯罪収益を凍結する意味で兪氏一家の財産1157億ウォンについて5回にわたり追徴保全措置を取り、1222億ウォン相当を差し押さえた。
検察関係者は「今後、関連事故の公判や兪氏一家の隠し財産追跡、回収に万全を期する」と話した。
また、事故に関連し提起されているさまざまな疑惑についても捜査を続けるとした。
下記の条件で公募する企業はあるのだろうか?赤字覚悟で大手が下請け設計会社に作成させるのだろうか?造船所の船台によってはLBDも変わる。LBDの変更は一部の変更なのか?
維持及びメンテナンスコストは考慮しなくても良い。リアリスティックでないかも?
「なお、一般配置図、中央断面図、構造詳細図、機関室配置図及び機器リスト・図面については、2次元図面に加えて3D-CADデータも作成すること」
大手及び中手でも3D-CADに対応していないところがある思うが??元大手の造船所の人間か、大学の教授の発想なのか?0.5億円の上限は安すぎると思う。
【記者手帳】STX売却で遠のいたクルーズ船建造技術 09/28/14 (朝鮮日報 )
フィンランドの首都ヘルシンキの北西240キロメートルにあるラウマには、最近までSTXフィンランドのラウマ造船所があった。韓国造船大手STXグループは昨年9月、収益性の悪化、受注低迷を理由に同造船所の閉鎖を決め、今年初めにラウマ市当局に造船所の土地を売却した。造船所の入り口にある看板は「ラウマ海岸工業団地」に掛け替えられていた。
STXグループは2008年、ノルウェーの造船業者、アーカーヤーズ(現STXヨーロッパ)を買収し、造船業界は韓国が手の届かなかったクルーズ船建造技術を手中に収めたと歓呼した。アーカーヤーズはイタリアのフィンカンティエリ、ドイツのマイヤーベルフトなどとともに世界のクルーズ船市場で大手だった。そして、地理的に近いラウマ造船所は旅客船分野で優れた技術が評価されていた。
このため、韓国造船業界はSTXのアーカーヤーズ買収が大型商船の製造に偏った韓国造船業の弱点を補う絶好の機会ととらえていた。
しかし、アーカーヤーズ買収から6年。STX造船海洋は19日、STXフィンランドをフィンランド政府とドイツのマイヤーベルフト造船所のコンソーシアムに売却した。資金難でSTXグループが解体され、STXフィンランドがリストラの対象になったためだ。韓国国内に売却先がないため、フィンランド政府に再売却された格好だ。
韓国造船業界はSTXフィンランドの売却を惜しむ声が大きい。STX造船海洋関係者は「欧州連合(EU)の反独占調査まで受けて、ようやく買収した企業を虚しく手放すのは残念だ」と話した。特に韓国造船業の弱点とされてきたクルーズ船建造技術を確保できる機会を逃したことは痛恨だ。
今年4月のセウォル号沈没事故以降、韓国国内では「造船大国と言いながら、まともな旅客船も作れないのでは話にならない」との批判が巻き起こった。韓国が造船業で世界1位に立っているとはいえ、手中に収めたクルーズ船技術を活用もできないまま手放した現実がただただ悔やまれる。
HA NOI (VNS) — The Vietnamese Government will not make any preferential policies to support the Vietnam National Shipping Lines (Vinalines) during its restructuring plan.
Minister of Transport Dinh La Thang said this at a meeting attended by Vinalines’ owners in Ha Noi on August 13. Hosted by the minister, the meeting aimed to share the group’s difficulties and orient its restructuring plan, in which debt restructuring would be a key task to achieve success.
Thang emphasised that unlike the support extended to the Vietnam Shipbuilding Industry Group (Vinashin), there would be no policy support for Vinalines which would have to pay its debts itself.
“Vinalines is different with Vinashin. Vinalines is not as difficult to handle as Vinashin so that it will not receive a preferential support policy like Vinashin,” said Thang.
The minister also asked Vinalines to negotiate with banks and credit institutions responsibly, to find out the best way to resolve the debt problem as well as to try its best to fulfill its payment obligations.
At the meeting, Vinalines shared its difficulties and development plan and listened to ideas presented by representatives of the State Bank of Viet Nam, 22 credit institutions and commercial banks who are debt owners of Vinalines. They discussed methods and ways to resolve the debts of the group and its subsidiaries.
A Vinalines representative said that in such a situation and faced with the task of repaying VND11 trillion, or US$523.8 million, Vinalines would be unable to repay all principle amounts and interests on the debt to banks and credit institutions on time.
Therefore, Vinalines proposed methods that would convert the loan into contributions of capital at the group’s companies and resolve the loan through the Debt and Asset Trading Corporation (DATC).
Head of Enterprise Development Department Ho Sy Hung, representing the Ministry of Planning and Investment, said the banks could convert loans into contributions of capital. However, they need to study capital divestment properly.
However, the banks and credit institutions spoke of a number of difficulties during the co-ordination process of debt restructuring, such as a regulation which does not allow investment in other sectors and complicated procedures associated with guaranteed assets.
They also said the State Bank of Vietnam has not yet set up a mechanism that allows a number of banks to convert loans into contributions of capital in the group’s sea ports and its investment in other sectors that are under divestment or the parent company.
The Vinalines representative said the State’s holding of 75 per cent of shares in sea ports is one reason hindering Vinalines’ debt restructuring process. A number of banks said they will convert loans into contributions of capital in sea ports if the State reduces its stake to 51 per cent or below.
As for resolving the loan through the DATC, the representative of the Ministry of Finance said that he agreed with the proposed method to resolve debts through DATC. He said this is a flexible method in which DATC will buy Vinalines’ debts from banks and credit institutions with cash, not by issuing bonds as was done with Vinashin.
A number of debt owners have reportedly said that they cannot wait for Vinalines to repay its debts, so they have begun negotiating with DATC. As a first step, the two sides have reached a basic agreement.
However, the difficulty is that DATC does not have enough capital resources to buy all debts of Vinalines, but only part of them.
Apart from not receiving any government support, as confirmed by Minister of Transport Dinh La Thang, Vinalines will also have to further tighten coordination with banks to find the most suitable method to resolve its debts.
Vinalines has been focusing on three areas, namely shipping, port management and maritime services and logistics. Shipping services brought the largest share of revenue to the group earlier.
ABG Shipyard, large privately-owned shipbuilder in India, suffers from financial problems.
According to overseas press, ABG Shipyard has seen a sharp decrease in overseas newbuilding orders over the past five years and even several cancellations of contracts have got the Indian yard into a difficult situation despite of domestic lenders' financial support.
A local financial market analyst Kotak Securities explained through its current report that ABG proceeded Corporate Debt Restructuring (CDR) for its debt of around $1.82bn (including bank guarantees for cancellation of export orders) last March. Delay in orders, rising burden for shipbuilding price with delay in facility expansion investment have also severely disturbed its profit structure.
Since October last year, ABG has recorded losses three quarters in a low, reflecting that the Indian yard's ability to repay its debts has been gradually weakened.
ABG Shipyard’s current market capitalization, which is registered at the Mumbai Stock Exchange, amounts to $215m while having recorded net loss of $10m during the second quarter of this year.
Meanwhile, it is reported that the Indian yard has recently cancelled the last unit of AHTS series contracted with a compatriot state-run Shipping Corporation of India (SCI) due to delay in delivery. With this, all the six units in the AHTS series awarded at ABG ended up cancelled.
source:asiasis
船主協会で着服容疑=元事務局長を逮捕-宮城県警 09/25/14 (時事通信)
宮城県北部船主協会(同県気仙沼市)が管理する口座から1190万円を着服したとして、県警気仙沼署などは24日、業務上横領容疑で同協会の元事務局長、菊池利明容疑者(65)=横浜市旭区川井本町=を逮捕した。容疑を認めているという。協会には使途不明金などが1億7000万円あり、同署が詳しく調べている。
Norwegian investment company Maritime Opportunities (MO) has bought two supramax bulk carriers from German Banks for USD 45 million, while cancelling contracts for two 36,000 dwt bulker newbuildings at Samjin Shipping Industries (SSI), China.
国際海事機関事務局長の関水康司氏が2期目を辞退し退職するようだ。日本人として初となる国際海事機関事務局長のようだ。
一般的には2期続けるのが普通なので驚いている人もいるようだ。まあ、自分には何の影響もない。しかし利害関係やメリットがあった人達は落胆しているだろう。その一方で喜んでいる人や国もいるはず。次のIMO事務局長は誰になるのだろう。
By MarEx
Koji Sekimizu, secretary general of IMO, has announced he will step down at the end of his first term of office ending in December 2015 for personal reasons.
The International Maritime Organisation (IMO) secretary general, Koji Sekimizu, has announced that he will resign at the end of his first term in office ending in December 2015 for family reasons. Mr. Sekimizu's announcement caught many by surprise as it is usual for a newly elected secretary general to continue for a second term and it was anticipated that he would hold the post until 2019.
SEPTEMBER 19, 2014 — IMO Secretary General Koji Sekimizu will not seek reappointment when his current term concludes at the end of 2015. He gave the news yesterday at a regular informal briefing of IMO Member Governments at IMO Headquarters in London.
International Maritime Organisation (IMO) Secretary-General Koji Sekimizu has disclosed his decision not to seek reappointment at the fulfilment of the current term at the end of 2015.
STX 大連に続き、Weihai Samjin Shipbuilding (威海三進船業有限公司)も破産となった。韓国系造船は厳しい状況にいるらしい。
Dalian: Financially troubled Weihai Samjin Shipbuilding is going to be taken over by the Weihai local government.
Dalian: Weihai Intermediate People’s Court has declared the bankruptcy of Weihai Samjin Shipbuilding under the request of creditor bank ICBC. The shipyard couldn’t fulfill many shipbuilding contracts due to financial difficulties.
Moyoun Jin
The deal is said to hinge on the Norwegian company agreeing a design that is significantly more efficient than conventional car carriers at an acceptable price.
A coroner is calling for safety training standards to be improved for crews of foreign ships operating in polar waters.
函館の造船所で早朝火災 工場2棟炎上 車両6台焼く 08/22/14 (北海道新聞)
22日午前5時35分ごろ、函館市弁天町20、函館どつく(野口忠雄社長)函館造船所で、敷地内にある木造一部鉄骨造り2階建ての工具工場から出火、棟続きで同3階建ての食堂棟に延焼し、2棟の内部延べ約2600平方メートルを全焼した。けが人はいなかった。 函館市消防本部などによると、火は工場前にあった軽トラックなどにも燃え移り、6台が全焼した。火災発生当時、工場は操業しておらず、内部や付近に人はいなかった。現場はJR函館駅から西に約2キロ離れた函館港の西端にある。
トルコや韓国では徴兵制度がある。トルコでは船員であれば兵役は免除。韓国では船員として5年以上の経験があれば兵役は免除。
民間人を乗せていても、兵器ではなく、衣料品や食料物資だとしても敵やテロ集団は戦闘や戦争を支援する行為と判断すれば攻撃される危険がある。戦闘や戦争で補給路や補給物資を断つのは常識。弾薬や食料なしでは戦闘や戦争は続けられない。船員不足だと業界が認識しているのに、船員を予備自衛官にする検討は疑問を感じる。平和時の物流よりも有事の物流手段の確保を優先させるのか?
国民が有事には自衛隊の派遣が普通となると認識すれば、両親として、妻として、子供として、自衛隊員になる事や、自衛隊員のままでいる事に反対する人々が増えると思う。これに加えて少子化がネガティブ要素になるだろう。
「同省防衛政策課は、『予備自衛官になるかどうかを決めるのは船員本人で、強制できない』と強調。予備自衛官になるよう船員が強いられるおそれについては『会社側の問題で、省としては関知しない』としている。」
民間船:有事の隊員輸送 船員を予備自衛官として戦地に (1/2)
(2/2) 08/03/14 (毎日新聞)
尖閣諸島を含む南西諸島の有事の際、自衛隊員を戦闘地域まで運ぶために民間フェリーの船員を予備自衛官とし、現地まで運航させる方向で防衛省が検討を始めた。すでに先月、2社から高速のフェリー2隻を借りる契約を結んだ。太平洋戦争では軍に徴用された民間船約2500隻が沈められ、6万人以上の船員が犠牲となった歴史があり、議論を呼びそうだ。
民間船:戦時中、徴用2500隻沈没 船員6万人死亡 08/03/14 (毎日新聞)
戦時中の船員の徴用では、悲惨な歴史がある。公益財団法人「日本殉職船員顕彰会」などによると、日本は太平洋戦争前は世界第3位の海運国だった。開戦後に民間商船や船員の大半が徴用され、米潜水艦などに攻撃された結果、約2500隻を失い、6万人以上の船員が犠牲となった。船員の死亡率は推計43%とされ海軍の兵士の2倍以上に達した。年齢制限のある徴兵と異なり、14、15歳で徴用された少年船員もおり、17歳以下の死者は1万人程度とされる。
Joseph Bonney, Senior Editor
More than a year after the container ship MOL Comfort and its 4,382 containers sank in the Gulf of Aden, shippers are watching developments in a Japanese court and awaiting a classification society’s report on the sinking.
下記の条件で公募する企業はあるのだろうか?赤字覚悟で大手が下請け設計会社に作成させるのだろうか?造船所の船台によってはLBDも変わる。LBDの変更は一部の変更なのか?
維持及びメンテナンスコストは考慮しなくても良い。リアリスティックでないかも?
3.補助対象事業本事業は、上記1.の目的を達成するため、中小造船所で低コストかつ容易に建造が可能であり、比較対象船舶(0.0143 l /ton*mile)(A重油換算)から16%以上の省エネルギー効果を有した499トン一般貨物船(以下「省エネルギー内航船舶」という。)の標準的な船型の開発をするために以下に掲げる事項に係る事業を対象とします。(1)省エネルギー内航船舶の仕様検討省エネルギー内航船舶の標準的な船型を開発するにあたって、船型の仕様を検討し、決定すること。
川崎汽船、Maritime Anti-Corruption Networkに加入 (川崎汽船株式会社)
韓国客船 Sewol沈没事故に関する腐敗や汚職(Corruption and bribes)は酷かった!負のサイクルは驚くほど強くリンクして結果として多くの犠牲者を出した。実際の効果は疑問だが、Maritime Anti-Corruptionに対する運動は広がると思う。
Sub-shippingとサブスタンダード船の原因が腐敗や汚職(Corruption and bribes)と関係ある以上後退はしないだろう。Maritime Anti-Corruption Networkは基本的には港で起きる腐敗や汚職(Corruption and bribes)のようだ。船の検査や問題のある船の登録の問題についても扱ってほしい。検査をごまかしてもらわないと多くのサブスタンダード船は検査に通らない。検査に通らなければ、サブスタンダード船の運航(Sub-shipping)は無理であろう。また、サブスタンダード船は密輸や犯罪に使用される確率が非常に高い。
Bribery and corruption regulation is ever-tightening. Additionally, stakeholders expect companies to play a significant role in addressing the root causes of corruption. Are you confident that your business risks are well-managed and that you are participating in real efforts to confront systemic issues throughout your global supply chain?
Cecilia Müller, Compliance Specialist,
造船や海運の将来性、仕事に対する報酬(給料)、業界の改善(労働環境及び改善に対する姿勢)に対する姿勢、下請けに対する対応などの総合的な結果として人材が入ってこない、離れて行くのではないのか?
外国人の導入と言う一時的な対応もできる。しかし、海運や造船だけに限らないが、技術や知識を教えられる人達は不老不死ではない。次世代の新たに参入したい日本人は外国人から技術や知識を学ぶのか?そのころには技術や知識を教えられる日本人達はかなり減っているだろう。
第1回造船業・海洋産業における人材確保・育成方策に関する検討会の開催について 07/30/14 (国土交通省)
造船業は、裾野が広い産業であり、多数の関連事業者が集積し、地域の雇用と経済を支えています。現在、受注回復の局面にある造船業が成長の機会を失うことなく、地方経済の成長を支えていくためには、設計等を行う技術者や現場の技能者の不足へ対応することが喫緊の課題となっており、6月24日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2014」及び「日本再興戦略(改訂2014)」 では、造船業における外国人材の活用とともに、人材確保・育成対策を総合的に推進することが決定されております。
M/V "Ardmore Cherokee" (IMO: 9707845, 船級:ABS ?)の納期は遅れるかも?
タンカー内で6人負傷=建造作業中、6月にも死亡火災-長崎 08/02/14 (時事通信)
2日午前11時50分ごろ、長崎市深堀町の「福岡造船」(福岡市中央区)長崎工場から「建造中のタンカーから爆発音を聞いた。負傷者が出ている」と119番があった。6人の男性作業員がやけどや打撲などの重軽傷を負い、消防が市内の病院に搬送した。いずれも意識はあるという。
福岡造船長崎造船所で火災 1名死亡 07/28/14 (JC-NET)
12日午後0時50分ころ、長崎市深堀町にある造船所「福岡造船長崎工場」で、建造中のケミカルタンカーで火災が発生、船の底の部分で作業していたと見られる男性作業員1人が死亡した。
いとこは愛媛今治の造船所に塗装工で勤めていたのですが、下請けの出向で長崎の造... 06/29/14 (Yahoo!知恵袋)
いとこは愛媛今治の造船所に塗装工で勤めていたのですが、下請けの出向で長崎の造船所に配属されました。今月12日に火災事故に逢い、亡くなりました。検死も終わり、骨だけの葬儀も済ませました。
大変でしたね。
造船所で爆発、作業員1人死亡=塗装作業中シンナー引火か-東京・江東 07/28/14 (時事通信)
28日午前11時ごろ、東京都江東区潮見の造船所「墨田川造船」で爆発があり、いずれも30代で男性の作業員1人が死亡、1人が負傷した。警視庁深川署によると、2人は塗装作業中で、使用していたシンナーに引火した可能性があるという。同署などが詳しい事故原因を調べている。
リスカ、副社長に前パナマ海事庁海事局長のアルフォンソ・カスティジェーロ氏が就任で何かが変わるのか?
Alfonso Castillero, former Director-General of the Panama Registry, has joined the Liberian Registry as Vice-President.
The Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR), a member of the YCF Group of companies and exclusive administrator of the world’s largest quality ship register, has appointed Christian Mollitor to the position of vice-president.
(人手不足列島)造船所、頼みは外国人 実習生が急増、建設業と人材争奪戦 07/09/14 (朝日新聞)
建設や外食業界で目立つ人手不足が、製造業にも広がってきた。円安で受注が
増えている造船業界では、溶接や塗装などの職種で建設業と人材の奪い合いに
なっていて、人手を確保しづらくなっている。ものづくりの現場で、外国人に
頼る動きが強まっている。
横領発覚の韓国船級協会幹部、懲戒なしで子会社に再就職 07/01/14 (Korean News Zero)
韓国船級協会で、国から支給された研究費を横領した幹部が懲戒処分を受けることもなく子会社に再就職し、その後も同協会の資金を横領していたことが分かった。
管制いいかげん・防犯カメラ映像削除珍島VTS所属海上警察3人令状
検察がセウォル号沈没当時管制業務を疎かにして防犯カメラ映像まで削除した珍島海上交通管制センター(VTS)所属海洋警察官3人に対して拘束令状を請求した。
欧米から“違法国”レッテル貼られる韓国遠洋漁業の「乱獲」「横暴」…「アフリカから略奪」批判も、船内では凄まじき“セクハラ疑惑” (1/3)
(2/3)
(3/3) 07/01/14 (産経新聞)
東シナ海などで中国漁船が違法操業を繰り返し、韓国は怒りの声をあげているが、韓国の遠洋漁業も評判はすこぶる悪い。韓国の遠洋漁業をめぐり、欧州連合(EU)が「違法操業国」のレッテルを貼るかに関心が集まっている。アフリカ漁船に偽装までして行われたアフリカ沿岸などでの乱獲を咎められたためだが、現地メディアは、
「国際社会でメンツをつぶす可能性が高まっている」(朝鮮日報WEB版)と指摘。
世界5大遠洋漁業としてのプライドに大きな傷が付くとの危機感を募らせている。
中国誘致の韓国系造船STX大連、破綻手続きを開始 06/28/14 (日本経済新聞)
中国・大連(遼寧省)でアジア有数の造船所を展開していた韓国STX造船海洋の現地法人、STX大連が破綻手続きを開始した。大連市中級人民法院は26日、日本の会社更生法に当たる「破産重整」の申請を受理したと発表した。
Joseph Bonney, Senior Editor
By Bloomberg
建設はオリンピックと津波被害地域の復興がたまたま重なっただけ。人が育つには時間と経験が必要。
造船の人材難が顕在化-安価受注で人件費低水準 06/23/14 (日刊工業新聞)
建設や物流、飲食業など多くの産業で人材不足が深刻化する中、造船業界も同じ問題を抱える。造船受注が回復した今、現場作業を担うワーカーを募集しても、多くは東日本大震災の復興や東京五輪のインフラ整備に取られて、簡単に呼び戻せる状況にない。造船各社が数年先まで仕事量を確保する中で、人材不足問題はより深刻になりそうだ。(福山支局長・丸山美和)
韓国では不正検査が常態化していたと考えても良いのでは?
旅客船沈没:海警出身の海運組合幹部を緊急逮捕 兪炳彦容疑者の逃亡を手助けした男も 06/20/14 (朝鮮日報日本語版)
仁川地検の海運不正特別捜査班は19日、海洋警察の治安監(ナンバー2)を務めた韓国海運組合のK安全本部長(61)を前日に緊急逮捕した、と発表した。
また、韓国船級協会検査員が逮捕されました。
韓国海軍の艦艇の船舶検査も不正、トイレが爆発? 06/20/14 (KBS News, Youtube)
韓国海軍の艦艇の船舶検査も不正、トイレが爆発? 06/20/14 (Yahoo!知恵袋)
韓国海軍の艦艇の船舶検査も不正、トイレが爆発?
50億の船を130億ウォンと'誇大評価' 船主また、拘束 06/14/14 (minaQのつぶやき )
海運業界の慣行的な不正にはビックリ
2013.7.20
福岡造船長崎造船所で火災 1名死亡 06/13/14 (JC-NET)
12日午後0時50分ころ、長崎市深堀町にある造船所「福岡造船長崎工場」で、建造中のケミカルタンカーで火災が発生、船の底の部分で作業していたと見られる男性作業員1人が死亡した。
消防や警察が駆けつけたところ、建造中の2万5000トンのケミカルタンカーの内部にある、水を出し入れして船の浮力を調整する「バラストタンク」から煙が出ていたという。
EUが韓国を違法操業国指定
海洋水産部の対応の遅れが原因
Moyoun Jin
An inspector from the Korean Register of Shipping and a manager of Korea Shipping Association have been arrested for their alleged careless checks on the capsized ferry Sewol, the Gwangju District Court's Mokpo branch announced today. The KR inspector, known only as Jeon, was in charge of safety inspection of the Sewol when it was renovated in February 2013 at a dockyard in Yeongam, South Jeolla Province. KR had classed the Sewol, which capsized on 16 April and killed an estimated 304 of the 476 passengers and crew. The court said Jeon had failed to follow procedure correctly when he inspected the Sewol's stability such as the centre of gravity, cargo capacity and amount of ballast water. Although the additions of decks to the Sewol did not match its blueprint, Jeon allegedly failed to detect this, resulting in difficulties in the search and rescue operations and the ongoing investigations. The court is also questioning other KR staff to probe if there were other illegal acts and corruption during the inspection. The KSA manager, identified as Kim, is suspected of approving the report on Sewol's safety inspection, although the report contained inaccuracies. KSA supervises South Korea's coastal shipping industry. Also, employees of Korea Maritime Safety Service, which handled safety inspection for Sewol's life-saving appliances, and employees of Sewol owner Chonghaejin Marine will be prosecuted for professional negligence resulting in death. Twenty-nine people have been arrested over the disaster, including 15 Sewol crew members and five Chonghaejin employees.
佐世保重工業が名村造船の子会社になって思うこと 05/26/14 (whomeohのblog長崎ぶらぶら平和日記)
佐世保重工業(SSK)は経営危機で倒産の危機に陥り、来島ドックグループの坪内寿夫氏が救済に乗り出した昭和53年までは、造船大手8社に君臨していた。このためSSK従業員は名村造船や瀬戸内の今治造船や救済した来島ドックなど中小造船を見下していた。時代は変わった。
セキュリティーが仇となった!罪がどんどん重くなる。
<韓国旅客船沈没>韓国船級が書類隠し…CCTV映像を確保 05/24/14 (中央日報日本語版)
釜山地検特別捜査本部は23日、「韓国船級の職員が検察の家宅捜索前日に書類を運び出した事実を確認した」と明らかにした。
「韓国船級は今年2月、セウォル号に対する安全検査で「異常なし」という判定を下した。」と書かれているが、英語の記事(IHS Maritime 360)では「intermediary survey」と書かれているから、単なる年次検査ではない。救命いかだだけでなく、操舵機やスタビライザーの故障について船員が証言しているそうだ。見落としたのか、見逃したのかは不明であるが、捜査で明らかになるだろう。
<韓国旅客船沈没>船長に殺人罪適用を検討 05/23/14 (中央日報日本語版)
韓国旅客船セウォル号沈没事故を捜査中の検警合同捜査本部(以下、合捜本部)は22日、船長のイ・ジュンソク容疑者(69)や航海士などに「不作為による殺人」容疑を適用する方向で綿密に検討している。
名村造船、佐世保重工を子会社化 中韓勢に対抗 05/20/14 (朝鮮日報日本語版)
名村造船所は23日、佐世保重工業を株式交換により10月1日付で完全子会社化すると発表した。世界の造船業界では、コスト競争力で勝る中国・韓国勢が優勢で、日本の造船各社は苦戦している。規模の拡大によって経営基盤を強化しながら、設計・開発力を高めて生き残りを図る。造船の市況回復は道半ばで中堅メーカーも多いことから、今後も業界再編が続きそうだ。
変化への拒否反応は当然の事。人材の問題があるから、下の職員達は新しい組織に移るだけ。懲罰的な解体であるならば、幹部クラスの出世や天下りはなくなるだろう。
中国船取締は新しい組織で継続するだろう。海洋警察が警察に統合される。先輩と後輩の関係や既に警察組織で形成されているだろう派閥や出世への過程などで、公平や評価が無いと簡単に出世は出来ないし、天下りの席も当分の間、確保できないだろう。その事を嘆いている人の方が多いのでは??
しかし、日本もこれぐらい大胆にやってほしい。社会保険庁の件は、名前が変わっただけでほとんど何も変わっていない。厚労省自体が腐った組織だ。
旅客船沈没:突然の解体方針に海洋警察職員らは放心状態 05/20/14 (朝鮮日報日本語版)
過ちは認めるが、解体は行き過ぎ」
「中国船取り締まりなど、それなりに果たしてきた役割を全て否定」
朴大統領「最終責任は私」…海洋警察庁を解体 05/19/14 (読売新聞)
【ソウル=豊浦潤一】韓国の朴槿恵(パククネ)大統領は19日、304人が死亡、行方不明になった旅客船「セウォル号」沈没事故を受け、海洋警察庁など関連省庁の解体や、安全無視の船会社を放置した官僚機構の改革を柱とする国民向け談話をソウルの大統領府で発表した。
<韓国旅客船沈没>海水部の幹部、韓国船級の法人カードで会食 05/17/14 (中央日報日本語版)
海洋水産部(海水部)の幹部が旅客船「セウォル号」事故の1週間前まで、韓国船級法人のクレジットカードを世宗市の飲食店やカラオケなどで使っていたことを、検察が確認した。検察は、海水部幹部がこのカードをセウォル号事故の直後に返したという韓国船級幹部の陳述も確保した。
RO-RO船「あさかぜ」が改造されて上のフェリーになる。スタビリティーとかは問題ないのだろうか?
以前、フィリピン人の船長に質問した事がある。「残念だがフィリピンは賄賂で何とかなる国」と言われた。
そう言う事なので事故が起こっても不思議ではない。
「Investigators want to know if the renovations may have made the ferry more likely to capsize or raised the ship's center of gravity. The South Korean Ministry of Oceans and Fisheries announced in late April that it would ask lawmakers to consider legislation prohibiting modifications to ships to increase passenger capacity. The government plans to take away the company's licenses for all its routes, including the one on which the Sewol sank, according to an official at the ministry.」
韓国政府は今回の件で混乱しているようだ。重心が上がる事は改造する前に専門家でなくとも、造船を専行している学生なら想定できる事。改造による影響が韓国船級協会(KR)及び韓国の規則の許容範囲であったのかを確かめることが重量。改造による影響が規則の許容範囲であったにもかかわらず、今回の結果となったのであれば安全を優先させる規則に改正すれば良いだけだ。
旅客定員を増やすために改造を禁止する規則を考えていると言う事は、韓国船級協会(KR)を全く信用しないと言っている事同じだ。韓国船級協会(KR)の判断を信用できないのなら客船だけでなく、韓国船級協会(KR)の図面承認及び検査で新造船は建造出来ないと言っている事と同じように思える。なぜなら、図面及び図面承認に問題があれば、問題のある新造船が建造される事を意味する。「新造船=問題のない船」はなりたたない。
By Madison Park, CNN
「自虐と敗北主義に浸る」韓国、官民癒着にメス 05/16/14 (読売新聞)
【ソウル=豊浦潤一】韓国の旅客船「セウォル号」の沈没事故から16日で1か月。先進国入りを目指す韓国が、国民の安全網に致命的欠陥を抱えていた事実を浮き彫りにした。
<韓国旅客船沈没>船長「事故の瞬間、船員だけは生きなければという考え」(1)
(2) 05/16/14(中央日報日本語版)
旅客船「セウォル号」のイ・ジュンソク船長(69)を含む船員15人は、約440人の乗客を退船させる場合、自分たちが後まわしになることを知りながら、退船放送をせず先に脱出したことが分かった。イ船長は乗客救護措置を取らずに逃げた「不作為による殺人」容疑の動機について、「船員だけは何とか生きなければいけないと考えた」と述べたことが確認された。
韓国造船業、海洋プラントの呪いに陥る 05/15/14 (asiae)
アジア経済ユ・インホ記者、キム・スンミ記者]国内ビッグ3造船業者が'海洋プラント'沼に落ちてさ迷っている。
一時韓国造船業の未来と呼ばれた海洋プラント事業が'アキレス腱'で作用していることだ。 3~4年前造船業者が受注実績を上げるために、確実な技術力と安全問題、専門人材補強などの何の準備なしで海洋プラント事業を無条件拡張したためだ。
'海洋プラント フロンティア'という甘い夢にぬれていた三星重工業は、'海洋プラント悪夢'に苦しめられている。 サムスンは2010年以後造船業景気(競技)が下落されるや既存食べ物商船で海洋プラントに目を向けた。 当時、三星重工業は商船はすでに盛りが過ぎた退物で取り扱った。
会社の戦力を全部海洋プラントに注ぎ込んだ。 その結果、一日と置かずにdrill-ship、生産保存荷役設備など海洋プラント受注便りを伝えた。 4年が過ぎた今、これは全部悲劇で終わった。
実際の三星重工業は、海洋プラントの収益が悪化して、設立以来最も大きい規模の赤字を出した。 三星重工業は、1分期公示に営業損失3625億ウォンを記録した。 2012年受注したオーストラリアのイクシース海洋ガス処理設備(CPF)と2013年受注したナイジェリア エッジや富裕式液化天然ガス生産保存荷役設備(FPSO)等2件の海洋プラント工事で7600億ウォンの損失が予想されるにつれ、約5000億ウォンの工事損失引当金を実績に反映した結果だ。
オーストラリアのイクシースCPFは、三星重工業が初めて換装してみるプロジェクトで、初期設計手続きから事業が遅れたし、後続工程で辞退変更で作業物量と費用が増加した。 エッジやFPSOは現地で機資材生産拠点を万はことが困難に陥った。
採算の見込みが無い船を建造するのは常識で考えれば間違いだ。政府に財政のゆとりがあればどのように考えれば問題ない。この記事自体、造船業界の意向かもしれない。中古船を使用するのは問題ない。利益追求のために安全性を犠牲にする改造、利益追及のための違法運航、インチキの整備や検査、そして船を機能を維持するための修理などが原因なのに新造船まで話を飛躍させることに疑問を感じる。新造船の運航で採算は大丈夫なのか?フェリーだと桟橋等の接岸施設、港湾(深さの制限)また航路で予想される必要な最低乗客や貨物など条件が違う。コスト削減のために同じ同型フェリーを建造する事も不可能に近い。中古船だと、安いから仕方がないと妥協が出来るだろう。フェリー運賃を政府の補助で安くして国民の負担を軽くしても、財政にゆとりが無ければ増税や他の予算のカットしか方法が無く、結局、遠まわしで国民の負担となる。
日本も補助金や助成金などの支援がなければ新造船が無理な航路がある。造船も海運もなだらかではなるが衰退している。他人事とは言えない問題だろう。橋や道路の維持管理の問題がテレビで頻繁に流されるようになった。船も道路や橋と同様に採算が取れなければ政府支援なしに新造船は無理。
【社説】造船大国の名誉を懸けて優れた旅客船を造れ 05/15/14 (朝鮮日報日本語)
韓国政府は旅客船「セウォル号」を運航していた清海鎮海運に対し、仁川と済州島を結ぶ旅客船運航の免許を12日付で取り消した。これを受けてこの航路には今後新たな事業者が参入する見通しだが、その場合も今回の清海鎮海運と同様、海外で製造された中古のカーフェリーを使わざるを得ない状況だという。長距離を運航する旅客船を製造するには、最低でも700億-800億ウォン(約69-79億円)は必要だが、韓国国内にこれを負担できるような運航会社はない。
<韓国旅客船沈没>船員、負傷した同僚放置して脱出…「殺人罪の適用方針」 05/14/14 (中央日報日本語版)
セウォル号から最初に脱出した機関部の船員が、負傷していた同僚を見ても何の措置もせずに脱出したという陳述を検察が確保した。同僚は調理員2人で、現在も不明状態だ。
海水部公務員に接待ロビー韓国船級チーム長令状 支援金取り引き港湾庁職員・設計業者代表も令状方針 05/13/14 (韓国日報)
海洋水産部公務員たちが監督対象である韓国船級(KR)幹部から金品ともてなしを受けたことが明らかになった。
【社説】癒着が招いた事故を捜査する人たちも癒着 05/12/14 (朝鮮日報日本語版)
海運汚職について捜査中の釜山地方検察庁特別捜査チームは、船舶の安全検査を行う韓国船級協会に関する捜査情報を海洋警察の担当者に流したとして、同捜査チーム所属の捜査官C氏を在宅で立件し、またC氏から受け取った情報を韓国船級協会の法務チーム長に伝えた海洋警察のL警視の身柄を拘束した。検察は2人の逮捕状を申請したが、裁判所はL氏についてのみ逮捕状を出した。一方、韓国船級協会は家宅捜索が行われる前に、重要資料をパソコンなどから削除したことも分かった。釜山地検は海洋警察に対し、韓国船級協会の前職・現職幹部によるヨットの使用状況に関する資料を提出するよう文書で要請したが、L氏はこの文書を携帯電話で撮影し、韓国船級協会に送っていたという。
【捜査情報、検察職員が海上警察に漏洩】 05/09/14 (韓国日報)
韓国船級の押収捜索に参加
<韓国旅客船沈没>海洋警察、韓国船級に家宅捜索を事前に知らせる 05/08/14 (中央日報日本語版)
海洋警察が韓国船級に検察の家宅捜索情報を事前に知らせたことが明らかになった。
申し訳ないが、朝鮮日報の孫振碩(ソン・ジンソク)記者はあまり船の事について詳しくないのであろう。
日本で内航船が長く使われない理由はいくらかある。傭船会社が船がある一定の船齢になると傭船しない。または、新造船を要求する。外国船だと運航航路を考慮しながらドック費用が安い外国の造船所で維持及び修理工事が行える。日本の内航船は外国へ行けない場合が多いし、日本の規則による規制のため外国の造船所での維持及び修理工事よりも日本の造船所が割高になる傾向がある。日本の造船所が仕事を確保できるように景気対策的な発注がある。トン数の権利などは船の隻数のコントロールの機能がある。新造船が出来ると、それまで使用された船は外売されるのが一般的である。上記の組み合わせのために、日本で内航船は特殊船の除いては長期間使用される事はない。
韓国で老齢船=問題である関係が成り立つのであれば、検査の問題、船会社による維持管理の問題、旗国(主管庁)による監視の問題があることを証明していることだと思う。老齢船の問題よりは、貨物や乗客を増やす工事に問題が無いのか、救命及び火災設備が問題なく機能するかに焦点を絞った方が良い。船が新しくとも復原性に問題があれば船は転覆する。外板が腐食して穴が開き、沈没するのとは違うが、沈没の原因には変わりない。救命及び火災設備が問題なく機能し、避難誘導が適切に行われれば、船が故障しても、被害者が出る事はない。救命いかだの代わりに救命ボートを増やすべきであろう。救命ボートは救命いかだよりも安全だ。ただ、コストがかかり、荷物や乗客が減るデメリットがある。また、年次の検査費用も救命いかだよりもアップとなる。しかし、これらの費用は新造船建造を考えれば小さい額だ。
「海洋水産部は『国際フェリーは救命ボートを定員の125%(沿岸旅客船は100%)が乗れるよう備えなければならないなど、厳しい安全基準をクリアしているだけでなく、相手国の港湾当局から国際的な安全規則を遵守しているか監視・指導を受けているため、大きな問題はない』との見解を示している。」
下記の写真はサブスタンダード船の写真である。2008年から2009年の2年間でPSCから13回の検査を受けた。
日本のPSC(外国船舶監督官)は6回も検査したが、下記の不備を指摘しなかった。船の長さは80m未満の元日本船籍内航船。大きな船ではない。どんな検査を行えば見逃すのだろうか。
サンプル 3 2003年の10月に撮影。
(朝鮮日報日本語版) 旅客船沈没:国際フェリー船齢平均22年、深刻な老朽化 05/08/14 (朝鮮日報日本語版)
本紙が全数調査、セウォル号より古いものが半数以上
韓国船舶受注量が急減 世界3位に転落=日中を下回る 05/08/14 (聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】昨年から今年初めまで好調だった韓国造船業界の船舶受注量が急減していることが8日、分かった。
【取材日記】「独島旅客船に異常なし」と叫んだ海洋警察 05/07/14 (/中央日報日本語版)
旅客船「セウォル号」沈没事故発生から16日後、今度は独島(ドクト、日本名・竹島)沖で旅客船のエンジンが故障する事故が発生した。
396人乗せた独島行き旅客船、エンジン故障…鬱陵島に引き返す 05/03/14 (/中央日報日本語版)
旅客船「セウォル号」沈没事故発生から16日後、今度は独島(ドクト、日本名・竹島)沖で旅客船のエンジンが故障する事故が発生した。
旅客船沈没:ホワイトハウスHPに捜査中断を求める請願 05/06/14 (朝鮮日報日本語版)
「『セウォル号沈没事故』の捜査は教会の弾圧であり、株主に対する不当な圧迫」と主張し、事故捜査の中止を求める請願が、米国ホワイトハウスのホームページに登場した
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
石川のまき網漁「濱田漁業」が破産開始決定受け倒産 05/06/14 (不景気.com)
石川県珠洲市に本拠を置くまき網漁業の「濱田漁業株式会社」は、4月30日付で金沢地方裁判所輪島支部より破産手続の開始決定を受け倒産したことが明らかになりました。
Resignations and arrests mount as police leave no stone unturned in their efforts to determine criminal responsibility for the Sewol tragedy
韓国議会の沈没事故阻止法案が利権団体の圧力で頓挫。与党議員も率先して法案廃棄に協力した 05/01/14(韓国日報)
[単独]『惨事』防ぐ法案3年前失敗に終わった
韓国の保険会社が違法改造船の保険料支払いを拒否。裁判所も支払い義務はないと決定を下した 05/01/14(韓国日報)
裁判所「構造変更で船舶沈没…保険金支給義務ない」
放射線検出コンテナ、開封し原因特定…本牧ふ頭 05/01/14(読売新聞)
横浜市中区の横浜港本牧ふ頭で、国の基準値を超える放射線量が検出された国際小包を積んだ船便コンテナが4月11日から現地で保管されたままになっている問題で、日本郵便は30日、コンテナを5月1日に開封すると発表した。
これだけMOUやPSCが検査活動をおこなっても、サブスタンダード船はなくならないし、サブスタンダード船の不備を指摘出来ない現状で、どのようにそれぞれの国内客船の問題を解決するつもりなのか。人命優先は、先進国だけの話。奇麗事だけでは何も解決できないのが経済的に問題のある発展途上国や後進国。政府と癒着し、独占的な地位を利用して安全を軽視して、不当に高い料金を取っているのなら問題の改善は出来るだろう。しかし、国民の所得が低いのでそれに見合うコストで船が運行されていれば、安全な船にすれば料金に跳ね上がる事は明らか。賄賂や癒着などが蔓延している国では、規則が改正されたとしても規則が守られる保証もない。問題解決は簡単ではないだろう。
The chairman and CEO of the Korean Register of Shipping has resigned over the Sewol ferry disaster, joining a list of officials who have quit over the tragedy. Chon Young Kee, who had only been elected to head the classification society in April 2013, tendered his resignation on 25 April, a day after prosecutors investigating the Sewol disaster visited KR's Busan office to obtain documents relating to the ferry. KR had classed the Sewol, which capsized on 16 April and killing an estimated 302 of the 476 passengers and crew. A KR spokesperson said: "Dr Chon has decided to step down as chief executive of KR to ease the pain and sorrow of the Korean people and the families who lost their loved ones on board Sewol. The thoughts and prayers of all KR staff are with those who have been affected by this tragedy." The spokesman told IHS Maritime that one of KR's executive VPs will serve as an interim chairman until new elections are held. He added that Chon's resignation took effect immediately. He added: "There're no plans for an election until investigations are completed. Dr Chon, a 30-year veteran in the classification business, remains willing and available to assist with the efforts to resolve the incident. The paperwork to process Dr Chon's resignation will take about a week. "Dr Chon's decision does not suggest any wrongdoing, negligence or any other deficiency by KR associated with this very tragic accident. The actual cause behind the accident will not be known until the on-going investigation is complete, but we are confident that we have performed our duties diligently and in strict accordance with the relevant national and international regulations as well as our rules. We will do whatever is necessary to assist the authorities with the accident investigation and to provide services to our customers without interruption." Chon's appointment last year marked the first time in KR's 53-year history that its chairman was appointed internally. Prior to his appointment, Chon served executive VP of KR's technical division. The Sewol disaster saw the country's Prime Minister Chung Hong Won tendering his resignation on 27 April, citing a failure to prevent the accident and poor handling of the rescue operations.
Delegates to IMO’s Legal Committee observed a minute’s silence today (28 April 20214) to demonstrate their compassion for the victims of the tragic accident involving the ferry Sewol on 16 April 2014.
Lloyd’s List, The Globe and Mail
首相辞任とフェリー沈没で露呈した韓国海運事業のお粗末さ 04/27/14 (北の国から猫と二人で想う事)
韓国籍は便宜置籍船じゃないけどITFは韓国籍を便宜置籍船と同等と宣言した方が良いかもしれない。ITFが便宜置籍船と呼んでいる旗国の中で良い旗国は韓国政府よりもPSCから出港停止命令を受けた船舶の再検査に関しては厳しい。船級による検査に加えて韓国政府よりも旗国の検査を定期的に行っている。
旅客船沈没:海外で出港停止の韓国船、59隻中15隻が… 04/27/14 (朝鮮日報日本語版)
昨年末の監査院の監査で判明
崔慶韻(チェ・ギョンウン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
支払うのはやめてほしかった。ソマリアの海賊問題と同じで、一度味をしめると歯止めが利かなくなると思う。短絡的な判断では??
商船三井「差し押さえ長引くと顧客に迷惑」 午後にも上海出港へ 04/24/14 (産経新聞)
中国の裁判所が戦後補償をめぐる損害賠償訴訟で商船三井所有の貨物船を差し押さえた問題で、商船三井は24日、中国当局の差し押さえが解除されたことを確認し、出港の準備が整ったことを明らかにした。「24日午後にも出港の予定」(広報室)としている。
中国相手のビジネスはリスクを考えたうえで行わないと酷い目い合う。
中国の裁判所 商船三井の運搬船を差し押さえ 04/20/14 (NHK)
中国・上海の裁判所は、日中戦争の前後に中国の船会社の関係者が日本の船会社に船を貸した際の賃貸料が未払いだとして、賠償を求めていた裁判で、敗訴した日本の商船三井が賠償に応じていないとして、商船三井の大型の鉄鉱石運搬船を浙江省の港で差し押さえたと発表しました。
七つの海、不渡りの男(現在、船乗りのサイト)を読むと船員もたいへんそうです。船員不足がさらに現場の船員の労働環境を悪化させているように読み取れる。
なんちゃって航海士の航海日誌 (インターンシップを利用して、内航海運会社の船に見習い航海士として乗船してきた体験が紹介されている)
内航船の船員不足深刻 若手育成追いつかず 人材確保へ模索 04/20/14 (神戸新聞)
国内貨物を支える「内航船」の船員が不足し、有効求人倍率が上昇を続けている。定年退職後も働き続けた世代が引退し始めているが、特殊な技術を要するため人材育成には時間がかかる。国土交通省は経済成長が続けば2020年には、内航船の5分の1が動かなくなると試算。内航船の人材不足は経済に与える打撃も大きく、海運各社は今月、神戸市で合同の就職説明会を開くなど業界を挙げて船員確保を模索している。(有島弘記)
ブラックリストに載るような国籍に登録される船舶は、サブスタンダード船である可能性が高く、犯罪に使われる確率が高いと言う事。
下記の記事の参考情報
今月4日、全羅南道麗水市(チョンラナムド・ヨスシ)の巨文島(コムンド)から南東34カイリ(約63キロ)の公海上。北朝鮮船員16人が乗ったモンゴル国籍の4300トン級貨物船「グランドフォーチュン1号」が沈没した。
徳島の鋼構造物製造「新栄鉄工」が自己破産申請し倒産 04/14/14 (不景気.com)
徳島県阿南市に本拠を置く鋼構造物製造の「新栄鉄工株式会社」は、4月14日付で徳島地方裁判所へ自己破産を申請し倒産したことが明らかになりました。
横浜・本牧ふ頭のコンテナから基準超の放射線検出 04/14/14 (テレビ朝日)
横浜市の本牧ふ頭のコンテナから、国の基準を超える放射線が検出されました。
ケッペル、中国の造船所運営に参入 04/11/14 (日本経済新聞)
■ケッペル・オフショア・アンド・マリン(シンガポールの海上石油掘削装置世界大手) 経営再建中の中国の大型造船所の運営に乗り出す。福建省の造船所を改造。掘削装置の修繕・建設や需要の底堅い船舶を建造する。
Singapore is rightly proud of its squeaky clean image in a part of the world where dirty deals at high levels are unfortunately still endemic. Not surprisingly, Singapore’s bunkering industry - which serves the many thousands of vessels transiting the Malacca Straits and with 2013 sales of 42.7 million tons of fuel to 37,000 vessels – has therefore been an object of close Government scrutiny for many years.
SHANGHAI | By Pete Sweeney
机上の空論だけでは理解できない事がある。軌道に乗るまでは簡単に行かない事があることを考慮していなかったのだろう。
三菱重工、客船事業で特損600億円 業績予想は変更せず 03/24/14 (日本経済新聞)
三菱重工業は24日、2014年3月期に客船事業で約600億円の特別損失を計上すると発表した。クルーズ客船最大手の米カーニバル社から受注した大型客船2隻について、設計作業の遅れが響き、資材調達などの費用がかさんだ。14年3月期の業績予想は変更しなかった。
構造的なものや環境を変えて行かないと、海運業だけをアピールしても魅力ある仕事には思えないと思う。船員ではないのでどうでも良い事だけど、はやく改革しないと簡単には変われないし、変わらないよ。進水式に子供を招待しても船員になんかならないと思うよ。船員になりたいと思わせる魅力が無いと無理でしょう。船員になった場合の不便さをどうように改善できるのか考えるべきだと思う。船員とはこんなものとか、昔の船員は・・・などと言っても昔を知らない人にとっては関係ない事。
海運業、若者が憧れる業界にしたい 03/13/14 (NetIB-NEWS)
北陸信越地方の海運企業社長A氏は、「海運業という存在自体が、国民に知られていないのでは」と危ぶむ。A社長自身、幼い頃から「家は海運業」と言うたびに関心のない反応を示されてきた。苦笑したのは「海運業」と聞いた相手から「占い師さんですか?」と問い返されたこと。どうやら「開運」と聞き間違えたらしい。「いっそ、屋号の海運を、開運に変えたら、少なくとも人目は引くかもしれませんね」と冗談まじりで微笑むが、その目は笑っているとは言い難い。
By Craig Ryan on March 4, 2014
Japanese shipbuilder Namura Shipbuilding has won a contract for the construction of two bulk carriers.
SEOUL, Feb. 17 (Yonhap) -- Prosecutors on Monday raided the offices of STX Group and its affiliates as part of their probe into corruption allegations against the ailing group.
杉本海運が破産手続き開始、TDB調べ 02/27/14 (Logistics Today)
帝国データバンクは27日、杉本海運(徳島県阿南市)が2月14日に徳島地裁阿南支部から破産手続き開始決定を受けたと発表した。破産管財人は白川剛弁護士(徳島市徳島町)。
2014-02-11 17:48
福岡の海運業「丸二海運」が自己破産申請し倒産へ 01/22/14 (不景気.com)
福岡県福岡市に本拠を置く海運業の「丸二海運株式会社」は、1月17日までに事業を停止し事後処理を弁護士に一任、自己破産申請の準備に入ったことが明らかになりました。
丸二海運が破産申請準備、負債21億円、TDB調べ 01/21/14 (Logistics Today)
帝国データバンク(TDB)によると、福岡市博多区祗園町の丸二海運は17日までに事後処理を浦川雄基弁護士(福岡市中央区天神)ほか1人に一任、自己破産申請の準備に入った。
Japan's main private ship insurer, the Japan P&I Club, said it has resumed normal coverage for tankers carrying Iranian oil, a step in easing imports in line with U.S. and EU moves as relations with Tehran thaw.
長栄海運(岡山)が破産手続き開始、TDB調べ 12/17/13 (Logistics Today)
岡山県笠岡市の内航海運会社「長栄海運」と「笠興海運」は17日、岡山地裁倉敷支部から破産手続き開始決定を12月9日付で受けたと公告した。破産管財人には、谷和子弁護士(倉敷市、倉敷総合法律事務所)が選任されている。
DNV(ノルウェー船級協会)とGL(ドイツ船級協会)が統合した。
DNV GL launches new global brand 12/16/13(DNV GL)
D“In defining our new identity as DNV GL, our company’s vision of making a ‘global impact for a safe and sustainable future’ has never been more relevant than it is today,” says Henrik O. Madsen, President & CEO, DNV GL Group. “The new brand that we launch today reflects our broader service offering aimed at enabling our customers to make the world safer, smarter and greener.”
世界1位の韓国造船業が没落の道を辿っている 12/24/13 (平成太平記)
没落する世界1位造船業...路上に追い出される労働者たち
韓国ドラマではこの手のストーリーは良く出てくるが、現実とたいして変わらないと言う事なのか?
ある外国人監督が検査官達と造船所の癒着があると言っていたが下記の記事が事実なら本当の話である可能性は高いな?検査を簡単にしてもらう方が検査官達にわたすお金よりもコストで考えれば効率が良いはずだ。しかし、日本建造のコンテナ船は折れたが、韓国建造の船が折れたとは聞いたことがない。また、検査を簡単にしてもらってもはるかに中国建造船よりは良いと言う事なのか。賄賂を含んだ見積もりでも韓国建造船のほうがまだ競争力のある価格であると言う事であろう。
構造不況の韓国経済、頼みの造船ビッグ3もダメそう 12/15/13 (minaQのつぶやき)
わいろ額50億ウォンに40人余り起訴 、‘検察発風浪’に難しく浮かび上がった船沈むかも 大宇・サムスン・現代重工業納品不正捜査…
下請けからワイロを取って何が悪い
http://www.sisapress.com/news/articleView.html?idxno=61701
[マネーミーナ] 国内造船業界に激しい風が吹き荒れている。大宇造船海洋·三星重工業·現代重工業など‘ビッグ3’造船会社と納品業者に検察が刀を抜いたためだ。
LPG船受注急増 佐々木造船、15年秋まで確保 12/13/13 (中国新聞)
▽シェールガス副産物で生産増
小型ばら積み船建造へ サノヤス水島、省エネ売り 12/10/13 (中国新聞)
サノヤス造船水島製造所(倉敷市)は、13年ぶりに積載量6万トン級の小型ばら積み船を建造する。円安で競争力が高まり、省エネ性能などを売りに受注が見込めると判断した。建造する船の種類を広げ、受注回復を目...
立石海運(長崎)が破産手続き開始決定、TDB調べ 12/09/13 (Logistics Today)
帝国データバンク(TDB)によると、長崎県壱岐市石田町の立石海運と関連会社の泰洋汽船が11月26日、長崎地裁壱岐支部から破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人は松坂典洋弁護士(長崎県壱岐市郷ノ浦町)。
A COSCO Shipping Co Ltd (Coscol) heavylift vessel has been detained in Singapore since Monday by legal representatives from Incisive Law for "unspecified reasons", according to a document from the Singapore Supreme Court.
DA CUI YUN IMO 9451329(ShipSpotting.com)
The historically famous shipbuilding yard in Gdansk, Poland may bankrupt during the next months. This information came after failed negotiations between the management of the yard and the local government for financial aid of the shipyard. The factory is owned by the Ukrainian company ISD, which has over 58.1 million USD debts to several external external companies and public institutions. The managers of the shipyard held negotiations with some ministers and government institutions for permanent solution of the financial problems financial aid for restructuring the company. The negotiations were the last chance for reviving the Gdansk shipbuilding yard and saving the job of thousands of employees.
OSX社、会社更生申請へ=負債額は45億レとも=設備売却で再建の見込みあり? 11/13//13 (ニッケイ新聞)
エイケ・バチスタ氏率いるEBXグループの船会社OSXが11日、会社更生の手続きをリオ州裁に申請した。同グループ企業の会社更生手続き申請は石油のOGX社に続き2社目となる。12日付フォーリャ、エスタード両紙が報じた。
ブラジル大富豪バチスタ氏の造船会社OSX、破産法適用申請か 11/11//13 (モーニングスター)
ブラジルの大富豪エイキ・バチスタ氏が率いる石油・ガス生産会社OGXペトロレオに続いて、同氏がオーナーとなっている造船大手OSXブラジルは早ければ11日にも、リオデジャネイロの裁判所に対し債権者からの資産保護を求めて破産法の適用を申請する見通しとなった。地元経済紙バロール・エコノミコ(電子版)などが9日に伝えた。
Updated: 2013-11-09 07:14
三菱重工など5社、ブラジル造船大手に資本参加で合意し株式購入契約締結 10/22/13(日経プレスリリース)にどれぐらい影響を与えるのだろうか??
ブラジルの石油会社OGXが破産申請-中南米で過去最大の企業破綻に 10/31/13(WSJ.com)
By
LUCIANA MAGALHAES, ROGERIO JELMAYER AND MATTHEW COWLEY
ブラジル油・ガス大手OGX、破産法の適用を申請―負債額5千億円 10/22/13(増谷 栄一 | The US-Euro Economic File代表)
ブラジルの大富豪エイキ・バチスタ氏が率いる石油・ガス生産会社OGXペトロレオは30日午後、債務整理をめぐる数カ月にわたった債権者との協議が不調に終わったとして、リオデジャネイロの裁判所に対し債権者からの資産保護を求めて破産法の適用を申請した。国営通信アジェンシア・ブラジル(電子版)など複数のメディアが伝えた。
By Sabrina Lorenzi and Jeb Blount
三菱重工など5社、ブラジル造船大手に資本参加で合意し株式購入契約締結 10/22/13(日経プレスリリース)
ブラジル造船大手エコビックス社に日本連合5社で資本参加
ギリシャで一番大きな造船所が倒産に直面しているらしい。
Greece's largest shipyard Skaramanga has thrown down the gauntlet to the Greek government and remains closed although the right of the company to operate on a rotating basis had expired at the end of September.
神戸工場で100年超造船支え 川重第一号ドック撤去へ 09/28/12(神戸新聞)
国登録有形文化財の川崎重工業神戸工場第一号ドック(神戸市中央区、1902年完成)が撤去されることが27日、分かった。前身の川崎造船所初代社長、松方幸次郎が建設を決断し、「造船界の壮挙」とされた巨大石造施設。近代化をけん引した造船業の繁栄を今に伝えるが、「老朽化で維持管理が難しくなった」(川重)という。11月から埋め戻す工事にかかり、跡地利用を検討する。
ドックが沈没 海上に油流出 江田島 (09/29/13) 中国新聞
造船所で部品落下作業員けが 広島 08/20/12(読売新聞)
江田島市の造船所で20日、クレーンのワイヤーが切れて、およそ40トンの部品が落下し、そばにいた作業員が逃げる際に、足の骨を折る労災事故があり、労働基準監督署が21日から詳しい原因を調べています。
貨物船第二十一幸栄丸作業員死亡事件 平成14年2月14日(日本財団図書館(電子図書館) 海難審判庁裁決録(平成14年度))
性能が良く漁獲量の多い日本船に対する不満による通告が事実かどうか知らないが、ブラジルの漁獲ルールに違反するような行為を継続していた事に問題がある。
違反していたが過去に拿捕されなかったからそのままで良いと考える方にも問題があると思う。指摘されるまで、又は、重い処分を受けるまで違反を継続する対応にも問題があったと思う。
ブラジルの200カイリ水域内で操業している以上、国際ルールだけでなくブラジルのブラジルの漁獲ルールに従うのが当然。「加盟国はそれに従って国内法を整備するが、ブラジル政府は漁業者に対し、〈1〉と〈2〉を必須とする国内法を整備していた。一方、3隻は〈1〉の方法だと漁がやりにくく、おもりで船員がけがをする恐れがあるため、〈2〉と〈3〉の方法を取っていたという。」違反していないのに拿捕されたのなら問題だが、違反している以上反論は出来ない。漁業業界では常識ではないのかもしれないが、一般商船は国際条約及び寄港国の国内法を守る事は当然。国際条約が漁船に適用されないケースが多いのでこのような常識は理解できないのかもしれない。国によっては、関係者への賄賂や根回しで問題の指摘を受けないような対策が有効だと聞いた事はある。
水産庁は外国の200カイリ水域内で操業する場合、その国の規則を守るように指導すべきだった。もちろん、追加の規則を満足する事はコストアップにつながる事が多い。規則違反を指摘されて反論は出来ないと思う。飲酒運転して警察に捕まり、全ての飲酒運転者が捕まらないので納得いかないと言っても警察官が見逃す意思がなければ無理と同じ。
ブラジルでマグロ船拿捕、高性能日本船に不満か 09/26/13(読売新聞)
宮城県気仙沼市船籍の遠洋マグロはえ縄漁船・第7勝栄丸(410トン)など漁船3隻が7~8月にかけ、環境保護規定に違反したとして、ブラジル当局に拿捕(だほ)された問題で、第7勝栄丸を所有する同市の水産会社「勝倉漁業」の勝倉宏明社長が25日、現地入りし、情報収集にあたっている。
ブラジル沖で日本のマグロ漁船3隻拿捕 09/25/13(NHK)
ブラジル沖で、ことし7月から8月にかけて、日本のマグロ漁船3隻が環境保護規定違反の疑いでブラジル当局に拿捕(だほ)され、このうち、1隻の漁船の差し押さえが続けられていることなどから、日本政府では早期の解決を関係当局に働きかけています。
日本マグロ漁船3隻がブラジルで拿捕 09/25/13(nikkansports.com)
ブラジル沖で操業していた日本のマグロ漁船3隻が7~8月にかけ、ブラジルの環境保護規定に違反したとの理由で相次いで拿捕(だほ)されていたことが24日、分かった。
DNVとGLがDNV GLグループへ 09/12/13(DNV GL)
オスロ:DNVとGLの合併が関係機関より承認され、新会社DNV GLが、9月12日に誕生しましたことをお知らせ致します。これにより、船級協会、第三者認証機関、オイル&ガス分野のリスクマネジメント、風力/電力送配電分野のエキスパートを主とする世界有数のサービス・プロバイダーが誕生致します。
DNV GL merger approved by competition authorities 09/11/13(DNV GL)
DNV GL will be the world’s largest ship and offshore classification society to the maritime industry, a leading provider of technical assurance and risk management services to the oil & gas industry and a leading expert in wind and power transmission and distribution. DNV GL also takes the position as one of the top three management system certification bodies in the world.
紀南造船所が破産開始 08/28/13(WBS和歌山放送ニュース)
那智勝浦町にある株式会社起南(きなん)造船所が先月(7月)25日、和歌山地方裁判所新宮支部へ破産申請し、先月(7月)30日に破産開始決定を受けていたことが民間の信用調査機関の調べでわかりました。
瀬戸内工業(株)/自己破産申請 08/13/13(JC-NET)
舶機器や部品製造の瀬戸内工業(株)(広島県尾道市向東町9210、代表:松崎徹)は8月8日、申請処理を高岡優弁護士(電話082-221-5754)ほかに一任して、広島地裁尾道支部へ自己破産申請した。
By Rob Almeida
ドイツの造船所が設計ミスで船がキャンセルされた。結果として造船所が売りに出されている。しかし売却の交渉は破局になるかも?
Talks are underway with potential buyers, including Russians, about the bankrupt P+S Werften facility Volkswerft in Stralsund, in east Germany, and a deal could be clinched as early as September, reports Tom Todd.
Banks have tightened lending to Chinese shipyards, putting more pressure on an industry that is already suffering from sluggish demand and a supply glut, as Beijing tries to cut excess capacity across a range of sectors.
By Grant LaFleche, The Standard
The future of St. Catharines' ship industry was thrown into question Monday when Seaway Marine and Industrial Inc. filed for bankruptcy.
China Shipyards Squeezed by Low Down Payments Amid Credit Crunch
A regional court has declared the historic Gdansk shipyard bankrupt, a move which brings to a close months of speculation about the future of the site where Poland's Solidarity movement was born.
世界一の造船国・中国、今後5年間で3分の1の造船所が倒産の可能性―米メディア 07/07/13(レコードチャイナ)
2013年7月5日、ブルームバーグによると、世界最大の造船国である中国の造船業界が苦境に立たされている。業界の予測によると、今後5年以内に3分の1の造船所が倒産する可能性があるという。環球時報(電子版)が伝えた。
需要と供給の差が大きければ、供給が縮小するしかない。これまでも同じ事が繰り返されてきた。
中国熔盛重工集団(1101:HKG)が資金繰り困難に陥った 07/06/13(Market Hack)
ウォールストリート・ジャーナルによると中国第三位の造船会社、中国熔盛重工集団(China Rongsheng Heavy Industries Group、コード番号1101:HKG )が資金繰り困難に陥っています。同社株は金曜日の立ち合いで-16%の急落を演じました。
中国造船大手「影の銀行」対策で資金難 政府に支援要請 07/06/13(産経新聞)
【北京=共同】中国造船大手、中国熔盛重工集団は5日、資金繰りの悪化を受け、政府に支援を求めていることを明らかにした。景気減速のほか、ノンバンクなど「影の銀行(シャドーバンキング)」対策の金融引き締めの影響で、資金調達が困難になったとみられる。同社は民間の造船企業では中国最大規模。
By Jasmine Wang
By DINNY MCMAHONand COLUM MURPHY
A major Chinese company is experiencing a rare cash crunch, in a potential test of Beijing's willingness to sacrifice a big employer in order to streamline a bloated industry, in this case shipbuilding.
* Appeals for financial help from government, big shareholders
中国熔盛重工集団、8000人レイオフ 07/03/13(産経新聞)
【上海】中国の民間造船大手、中国熔盛重工集団(1101.HK)の幹部は2日遅く、同社がこの数カ月で約8000人の従業員をレイオフ(一時解雇)し、一部の労働者が中国東部、南通市の生産拠点外で抗議を行っていたと明らかにした。
Engineering firm Biprostal has filed a motion for the bankruptcy of Stocznia Gdańsk, Poland's best-know shipyard. The shipyard failed to pay Biprostal for delivered services.
TAIPEI -- Taiwan Marine Transportation (TMT) said Friday that it has filed for bankruptcy protection with the Federal Court in Houston in a bid to prevent its creditors from taking its vessels registered overseas into custody.
TMT said the move to seek protection under Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code is aimed at allowing the company to financially restructure itself without interruption from its creditors, while it is determined to negotiate with its creditors on how to get through its financial crisis.
Twenty-three single-ship companies associated with Taiwanese shipping group Today Makes Tomorrow (TMT) have filed for bankruptcy in U.S. court, TMT said in an emailed press release.
By RACHAEL FEINTZEIG
By Alison Leung
The recent bankruptcy filing by STX Pan Ocean is the latest blow for South Korea’s best-known self-made tycoon.
韓国のマグロ漁、国際環境団体が批判 06/10/13 (中央日報日本語版)
世界で3番目にマグロ漁獲量が多い韓国の遠洋漁船は主に南太平洋で操業している。漁船は巻き網を使用したり金属筒を海に投げておく。海のまん中に浮遊物が浮いていれば小さな魚が集まる。捕食者から自身を保護できる避難所と考えるからだ。小さな魚が集まれば、これを食べるためにマグロのような大きな魚も集まる。この時から漁船は網を設置し、本格的なマグロ漁を始める。
(朝鮮日報日本語版) STXパンオーシャン、会社更生手続きへ 06/08/13(産経新聞)
資金難で事業再編を進めているSTXグループの海運会社、STXパンオーシャンが7日、ソウル中央地裁に法定管理(会社更生法適用に相当)を申請した。
New owner was settled at the fourth court auction for Samho Shipbuilding which had gone bankrupt early last year.
聞きしに勝る!中国人のエゲツナイ「商魂」 現地進出の大阪の社長が激白 07/21/12(産経新聞)
こんなこともあった。中国産の電球は品質が悪く、すぐ点かなくなるので、今井さんが「日本の電球はこんなことはない」と不満を漏らすと、従業員がこう言った。「社長、中国人はいったい何人いてると思う。長持ちする電球だったら、作っている人たちが困るでしょ」
川崎重工業と三井造船、経営統合交渉で調整 04/22/13(News i)
実現すれば、2兆円規模の巨大企業が誕生します。重工業メーカー大手の川崎重工業と三井造船が、将来的な経営統合を視野に入れた交渉を始める方向で調整していることが明らかになりました。
The crisis enveloping the South Korean-owned shipbuilder STX deepened as the company revealed that it failed to sell its affiliate STX Pan Ocean.
(株)三保造船所/自己破産へ 03/15/13(JC-NET)
造船業の(株)三保造船所(大阪市港区築港1-3-16、代表:三保博司)は3月8日事業停止、事後処理を西念京祐弁護士(電話06-6316-8824)ほかに一任して、自己破産申請の準備に入った。
フェリー試運転中、作業員が軸に巻き込まれ死亡 03/17/13(読売新聞)
17日午前7時45分頃、広島県尾道市瀬戸田町沖の瀬戸内海で、同町の内海造船が新造フェリー(1985トン)の海上試運転中、エンジンルームの点検をしていた岡山県備前市の船舶機器メーカー作業員浜本稔さん(58)がプロペラ軸に巻き込まれ、死亡した。
大間~函館フェリーの新造船「大函丸」…広島・内海造船で進水式 12/17/12(レスポンス)
1985トンの船体が、青森県大間町や津軽海峡フェリーの関係者たちに見守られながら、ゆっくりと海へ進水。広島県尾道市の内海造船瀬戸田工場で13日、大間~函館フェリー航路の新造船・大函丸(だいかんまる)の進水式が行われた。
ツネイシHD、多度津工場の生産停止 地元は雇用懸念 02/09/13(日本経済新聞)
造船・海運大手のツネイシホールディングス(HD、広島県福山市)は8日、多度津工場(香川県多度津町)での生産から撤退する方針を固めた。多度津工場は従業員約260人を抱えるほか、パートや派遣社員ら10人が勤務。同工場の下請け企業は35社に及び、下請け企業だけで約1000人が勤務している。工場が閉鎖されれば、地元の雇用に影響が出る恐れもある。
「日本の造船業界は円高による価格競争力の低下を背景に韓国や中国に押されて受注が激減していて、作る船が無くなってしまう『2014年問題』として業界に暗雲が立ち込めています。」
これについては正しい情報とは言えないのでは??韓国でも造船所の倒産や閉鎖が起こっています。中国でも1年以上も船を建造していない造船所があります。
実際に、中国は安いが品質が悪すぎるとのことで中国で建造しないと言っている外国船主もいます。問題は、世界的な景気低迷による物流の停滞、需要と供給の
バランスが崩れ、供給過剰になっている。そして、バブル状態で発注された高船価と高いチャーター契約が需要低迷の中で海運会社を苦しめる。
船舶建造の生産性が向上しているのに、バブル状態の期間に儲かるとのことで造船所が世界中で増えた。どこかで淘汰されるしかない。自然の原理。
どの国のどの造船が終わるのかわからないけど、3,4年前からこのような事になることを言っていた人達はいた。ただ、下請けの人達は知る余地もないし、
考えてもいなかったと思う。円高や韓国や中国と言えば、はずれではないが正解でもない。
購入のメリットが一番あるのは近くに造船所のある今造であろうと思う。常石にメリットがないのだから他の造船所にはメリットはないと思う。
ただ、今造も苦しのは他の造船所と同じなので売却額が重要になってくるのでは??今造が購入したとしても経営効率化のため、下請けの雇用が維持されるとは思わない。
ただ閉鎖の状態が続くよりは良いと思われる。
造船不況 香川県にも影響 02/08/13(RNC西日本放送)
日本の造船業に不況の波が押し寄せています。
国営海運の貨物船、スクラップより安価で売却[運輸] 02/05/13(中央日報)
国営ベトナム海運総公社(ビナラインズ)傘下の海運会社の大型貨物船が、北部クアンニン省に1年以上放置された後、トン当たりの価格に換算すると鉄スクラップよりも安く売却されていたことが分かった。4日付VNエクスプレスが報じた。
北朝鮮が3度目の核実験を強行する場合、韓国政府は北朝鮮に入港した船舶の内外への進入を防ぐ事実上の海上封鎖を積極的に検討していると韓国政府当局者が2日に明らかにした。
景気沈滞の直撃弾を受ける韓国造船業界 01/28/13(中央日報)
27日午前10時、全南霊岩郡デブル産業団地にある船体ブロック製造会社のK社。 道路沿いの幅40メートルほどの正門は閉まり、出入り口の左側には「留置権行使中」という幕が設置されている。 一時は200人ほど勤務していた工場の内部には人が見えない。 入り口の警備員は「産業団地内でも軸となる会社だが、先月、不渡りを出した」と話した。 付近のJ社も鉄門が閉まっている。 3年前まで船体ブロックがあちこちに見られた野積場と工場ががらがらになっている。 産業団地周辺の道路も閑散としている。 大型トレーラーが船体ブロックを積んで頻繁に出入りする姿はもう見られない。 B社の代表は「工場を開けているが、受注量がなく、5カ月間操業していない」と話した。
工場労働者も「海外転勤」の時代 川崎重工従業員がブラジル造船会社に (Part1)
(Part2) 12/21/12(J-CASTニュース)
造船大手の川崎重工業は、国内主力拠点の坂出工場(香川県)の従業員の約2割にあたる180人を、国内の他工場のほか、ブラジルの造船会社に派遣する方針を固めた。
中国の造船参入で既に苦しんでいる日本および韓国造船業界。ベトナムの大型船建造は加速することはあっても減速することはないだろう。そして三菱が設計を提供する
インドの参入も予想される。造船不況は経済の好転による改善はあっても、競争環境の激化は避けられないであろう。韓国は法律で国の許可なしに中国への設計の販売を禁止した。
既に逮捕され刑務所にいる韓国人もいるそうだ。品質は悪くとも設計図があれば船は建造できる。日本から韓国へ造船がシフトした過去から学んだことだろう。資本主義から
考えるとおかしいが、韓国の利益を優先に考えるとそれもひとつの賢明な判断と言える。防御してもいずれ労働力の安い国へシフトする。しかし必要以上にシフトを
加速させる必要があるのか??日本および韓国の造船業界そしてそれぞれの国の下請けとして働く労働者は違う立場であろう。国として、そして自国の雇用を維持したい国として
判断の違いが出てくるのかもしれない。
Nam Trieu shipyard launches 56,200-tonne bulk carrier 12/17/12(TalkVietnam)
Nhan Dan – The Nam Trieu Shipbuilding Industry Corporation (NASICO) delivered a 56,200 tonne bulk carrier named Vosco Sunrise, on December 16 to the Vietnam Ocean Shipping Company (VOSCO).
On December 16, Nam Trieu Shipbuilding Industry Corporation, under the Vietnam Shipbuilding Industry Group, launched a 56,200 tonne cargo ship named Vosco Sunrise.
▼続報/(株)大西組造船所 ~ 再生手続廃止、破産手続開始申立準備へ 【負債総額80億円内外】 12/12/12(AreaBiz広島)
特別情報福山版No.1546号ジャッジメント 他で経営難を報じ、平成21年6月30日付東経トップニュースで民事再生手続開始申立、広島支社特別情報No.7693号(H22.10.15)で確定債権者判明を既報の当社であるが、24年11月29日、広島地裁より再生手続廃止・保全管理命令及び包括的禁止命令を受け、破産手続開始申立準備に入る見通しであることが判明した。保全管理人は、幟立 廣幸弁護士[幟立・為末法律事務所, 広島県広島市中区上八丁堀8-26 メープル八丁堀306号,TEL 082-221-1350]が選任されている。負債総額は80億円内外にのぼる見通し。事件番号 平成21年(再)第5号。
三光汽船の関係会社6社が破産申請…負債合計46億円 12/03/12(レスポンス)
東京商工リサーチによると、MERIDIAN BULKSHIP LIMITEDほか、三光汽船の関係6社が11月21日に東京地裁から破産開始決定を受けていたことが判明した。
三光汽船(株)関連会社の6社破産 12/03/12(レスポンス)
MERIDIAN BULKSHIP LIMITED(リベリア共和国モンロビア ブロードストリート80、日本事務所:東京都千代田区内幸町2-2-3、代表:朝藤久)、
受注ゼロの韓進重、復職従業員に仕事なし 11/13/12(産経新聞)
5日午前11時ごろ、兵庫県姫路市家島町の造船所で、社員の男性(52)=同町=がクレーンから落下した鉄板(重さ500キロ)に下半身などを挟まれ、搬送先の病院で死亡が確認された。
存続なるか 日の丸造船業 (1/3ページ)
(2/3ページ)
(4/3ページ)11/27/12(東洋経済オンライン)
「今までの常識が通じない、大変な時代になった」。川崎重工業の船舶海洋カンパニーを率いる神林伸光・常務取締役の偽らざる心境だ。
受注ゼロの韓進重、復職従業員に仕事なし 11/13/12(中央日報日本語版)
釜山市影島区の韓進重工業影島造船所では、北西側にある特殊船舶の作業ゾーンからクレーンの音が響いていたが、商船の作業ゾーンから聞こえるのは風が吹き抜ける音だけだった。商船作業ゾーンの機関、配管、船体の各工場、ドックなどは全て操業を停止。資材を運ぶクレーン20基は大半が止まっていた。造船所の本館ビルには「労働組合は会社と一つになり…」というスローガンが虚しく掲げられていた。
退職金に慰労金でも希望退職者がいない現代重工業(2) 11/04/12(中央日報日本語版)
浦項(ポハン)、蔚山(ウルサン)、巨済(コジェ)、統営(トンヨン)など東南圏製造業ベルトに流れる危機の不安感はそれだけではない。鉄鋼業界最大手のポスコも構造調整説があふれている。統営には仕事がない中小造船業者が数多くある。仕事がある大型造船会社も安心できる境遇ではない。知識経済部によると韓国の新規船舶受注量は2007年の3251万CGT(付加価値換算トン数)から昨年は1374万CGT、今年は9月末現在で520万CGTだ。受注残高も同じ期間に6440万CGTから3860万CGT、3003万CGTと急減した。大型造船会社は高付加価値船舶と海洋プラントに活路を見出しているが、中小企業は枯死直前だ。
退職金に慰労金でも希望退職者がいない現代重工業(1) 11/04/12(中央日報日本語版)
1日午後、蔚山(ウルサン)広域市の現代(ヒョンデ)重工業。930万平方メートルの広い工場内の道路の上を、数百トンを超える船舶構造物が大型輸送車に載せられゆっくりと動く。船を作るドックの上では超大型ガントリークレーンが休む暇もなく動いていた。現場は活気に満ちていた。だが、不安と不確実性の影がちらついた。同日午後3時。10分の休み時間。作業場のあちこちにある喫煙場所に集まった従業員が短い対話を交わす。労組幹部だったある従業員は、「1カ月後に控えた大統領選挙は格別話題にならない。現在進行中の希望退職が最大の話題だ」と話した。
By MarEx
The tragic accident happened onboard the coal carrier Sage Sagittarius. For a third time a man is dead in interval of 6 weeks.
The vicitim is Kosaku Monji 37. He was on the ship on October 6 when it was unloading a cargo of Newcastle coal in the Japanese port of Kudamatsu. Then arrives back ini Newcastle.
日本の石炭専用船船員3人死亡 10/29/12(オーストラリア生活情報サイト NICHIGO PRESS)
6週間の間に異なる死因で次々と
貨物船SAGE SAGITTARIUS作業員(工務監督)死亡 10/06/12(運輸安全委員会)
概要:
原因:
ベルトコンベヤーに上半身を挟まれた男性の死亡確認…石炭陸揚げ作業中 - 山口 10/06/12(産経新聞)
6日午前7時半ごろ、山口県下松市のJX日鉱日石エネルギー下松事業所の岸壁に
接岸していた船の上で、海運業「八馬汽船」(神戸市)社員、
門司耕作さん(37)=熊本県山鹿市=がベルトコンベヤーに上半身を挟まれているのが
見つかり、事業所が119番した。消防署員が駆け付けたが、門司さんは間もなく死亡が確認された。
“造船世界トップ”現代重工業、初めて希望退職者を募集 10/23/12(中央日報日本語版)
造船世界トップの現代(ヒョンデ)重工業が初めて希望退職者を募集する。
【取材日記】危機の韓国造船ベルトを生かそう 10/15/12(中央日報日本語版)
韓国造船産業の歴史を語る時、故鄭周永(チョン・ジュヨン)現代グループ名誉会長の「亀甲船」エピソードが欠かせない。 鄭会長は1970年、蔚山造船所を建設するために英国の銀行から融資を受ける際、亀甲船が描かれた500ウォン貨幣1枚を担保に出した。 整った造船所もないが、1500年前に鉄甲船を建造した技術力がある民族であることを主張した。 このように借りた資金で現代式船舶建造施設を備えた造船所を建設し、2隻のタンカー(26万トン級)を建造した。
仕事が急減…韓国南海岸の造船ベルト崩れる 10/11/12(中央日報日本語版)
統営(トンヨン)の信亜sb造船所で10日、船2隻の最終作業が行われている。 今年末に船が完成すれば、造船所は休業状態となる。 これまで船の部品が積まれていた野積場はがらがらに空いている。
先月20日夜、慶尚南道統営市道南洞。 例年なら“不夜城”となるこの街は閑散としていた。 ほとんどの飲食店が“開店休業”状態だ。 造船所付近のビルは1階を除いてほとんど空いていた。 出入口や窓には「賃貸問い合わせ」という文字が見える。 この地域の観光ホテルのハ・ジェグ支配人(47)は「造船所前の飲食店の経営者の中には、自分の店を閉めて、統営市内でアルバイトをしている人がかなりいる」とし「造船所の盛況で97年には通貨危機も知らなかった統営が、今では深刻な危機を迎えている」と述べた。
呉市仁方本町の造船所で火災 09/21/12(酸素カプセルは呉市の宮迫接骨鍼灸院)
9月11日午前10時20分ごろ、呉市仁方本町3の船体ブロック加工・組立「寺岡」の仁方事業所で、「造船所内に係留している船舶が燃えている」と119番があった。
中国造船企業、受注激減で相次いで倒産「将来2、3年のうちに半分が消える」 09/10/12(大紀元)
【大紀元日本9月10日】国内外の景気悪化で受注が激減し、中国造船業界は現在深刻な状況に陥っており、造船企業が相次いで倒産している。業界関係者は将来2~3年間で国内の半分の造船企業が倒産に追い込まれるだろうと予測している。
コストアップと技術力が同じペースで上昇しなかったことも原因だろう。安いけれど多くの問題がある。船を転売して儲かる間は
誰も問題として真剣に取り組まなかったが、転売して儲けられないとなれば当分船を運行しなければならない。中国建造船で問題を
抱えた監督や会社は、やはり少なくとも韓国建造船でないとだめだと言っている傾向が結果として韓国が受注1位になった理由であろう。
中国建造船でも問題ないと言っている監督や会社もあるが、やはり中国建造船はだめだと言っている人達が圧倒的に多い。
中国造船業界に冬の時代 “利益なき繁忙”過剰供給で経営行き詰まり 08/15/12(SankeiBiz)
2006年に日本、09年に韓国を一気に追い抜き、世界一の受注量を誇るに至った中国の造船業界が苦境に陥っている。
A building binge fueled by boom times has led to a glut of ships as China's economy slows down. China's expansion of the sector has only compounded the problem.
船の照明が付いていないので、電球を取り換えさせた。船を一回りして同じ場所に戻ってくるとさっき取り換えたばかりの電球がもうつかなくなっている。
機関の船員になぜこんな粗悪な中国製の電球を注文するのかと聞いた。会社が安いから注文すると言う。しかし、電球を取り換える船員の給料を考えると
本当に安いのかと理解に苦しむ。船の耐久性も同じであれば日本建造や韓国建造船と比べるとはるかに劣るであろう。個人的には明らかに劣るし、
日本製やヨーロッパ製の機器を積んでいても取付や保管管理に問題があって、外国製の機器を取り付けても同じ性能は期待できないと思う。
それでも中国で船を建造する船主はたくさん存在する。日本や韓国だって昔はそんなに良くない船を造っていたという高齢の監督がいるが、それは例えが
違うと思う。まあ、船を管理、運航した経験がなければ理解できない話かもしれない。あと、何年、その船を運航するのかも重要な判断基準になると思う。
聞きしに勝る!中国人のエゲツナイ「商魂」 現地進出の大阪の社長が激白 07/21/12(産経新聞)
こんなこともあった。中国産の電球は品質が悪く、すぐ点かなくなるので、今井さんが「日本の電球はこんなことはない」と不満を漏らすと、従業員がこう言った。「社長、中国人はいったい何人いてると思う。長持ちする電球だったら、作っている人たちが困るでしょ」
三光汽船、2度目の経営破綻 私的整理による再建断念 07/03/12(SankeiBiz)
私的整理の手法である「事業再生ADR」で再建を進めていた中堅海運会社の三光汽船は2日、東京地裁に会社更生法の適用を申請した。帝国データバンクによると負債総額は約1558億円で、2月に経営破綻した半導体大手、エルピーダメモリに次いで今年2番目の規模となる。三光汽船は1985年8月にも会社更生法の適用を申請しており、2度目の経営破綻となる。
Zhejiang Jingang Shipbuilding Co, the largest private shipbuilder in Taizhou, East China's Zhejiang Province, has filed for bankruptcy in a local court and is considering shifting to other businesses as the shipbuilding industry is facing a bleak prospect.
Many small-sized shipyards in China, plagued by a shortage of new orders, are on the brink of bankruptcy as a result of the sluggish world economy, a glut of vessels and soaring fuel prices.
Zhejiang Jingang Shipbuilding CO., LTD.が破産したそうです。
もう既に建造契約が完了しているようなので今後どうなるのだろうか。世界中から客船建造の経験を持つ退職者をリクルートしてくるのだろう。
それでも無理かもしれない。しかしタイタニックの概観が条件で現行の国際条約を満足する船の設計はかなり難しいだろう。
今、造船所は厳しい状態であるが建造契約を結んだ造船所はどこなのか。大博打の覚悟で決断したのか、それとも楽天家の経営陣なのか?
タイタニック2号に疑問=中国企業、客船建造実績なし 05/03/12(時事ドットコム)
【上海時事】オーストラリアの資産家クライブ・パーマー氏が先月30日、中国の造船会社に発注したと発表した豪華客船「タイタニック2号」に対し、中国国内で実現性を疑問視する見方が浮上している。世界一の造船大国になったとはいえ、中国の造船会社が豪華客船を建造した実績はなく、技術もないことを業界も認めているためだ。
受注で苦しい中国造船所と安いからとの理由で中国の造船所となったと思うが大丈夫なのだろうか。
中国で豪華客船を建造する能力があるのか?設計は特別仕様となるだろうし、豪華客船と言うのだろうからあちこちに不具合があることは
許されないと思う。日本や韓国でも新設計だと不具合があるのに中国で豪華客船なんてありえないと思う。張りぼての豪華客船でなく、
本物の豪華客船。完成が楽しみだ!タイタニックと同様に処女航海で沈没はないにしてもエンジントラブルぐらいはあるかも?
ところで最新の安全システムとは規則を満足すると言うこと、それとも現在の安全システムで最高の仕様で建造すること?
仕様書の打合せ、タンクテスト、内装の仕様、使用されるメーカーの選定などやることがたくさんある。2016年航海は可能??
“不沈タイタニック”建造 豪資産家、2016年航海目指す 04/30/12(産経新聞)
オーストラリアの資産家の男性が30日、100年前に大西洋で沈没した英豪華客船タイタニック号と同じ大きさの複製を建造すると発表した。現代の技術で“沈まない設計”を目指し、2016年を目標に、初代と同様、英国から米国に向けて初航海させる予定という。AP通信などが伝えた。
中国の三大造船指標が軒並み低下、船舶業が深刻な調整期に突入 04/09/12(サーチナ)
<中国証券報>2012年1-2月、世界船舶市場が低迷を続けている影響により、中国の三大造船指標が前年同期に比べともに低下し、工業生産額の増加幅も減速している。専門家は、世界経済の回復感が乏しい中、船舶の需要と価格が上昇に転じる兆しはなく、中国の船舶業は深刻な調整期に突入するだろうと見ている。9日付中国証券報が伝えた。
爆発:宮城県塩釜市の造船所で4人が負傷 04/02/12(毎日新聞)
逮捕容疑は2013年3月26日、協会名義の口座から労働保険料として3740万円を引き出し、うち2550万円は労働局に払い込んだが、残る1190万円を着服した疑い。
--------------------------------------------------------------------------------
The two 57,000 dwt bulkers Emerald Strait and Endeavour Strait, previously owned by Carsten Rehder, were delivered from Sanfu Shipbuilding.
Significant delays are stated as the reason behind cancelling the 36,000 dwt newbuildings, originally ordered by Ultrabulk of Denmark for a total sum of USD 40m, which last year sold a 50% stake to MO at cost price.
This is not the first cancellation at the troubled shipyard, with Belgium’s Bocimar recently binning the order for four handy-size bulkers at SSI.
Local court declared Weihai Samjin Shipyard bankrupt, and the local government is engaged in a restructuring plan to salvage the shipyard.
His wife has been seriously ill Sekimizu has decided to commit himself to caring for her in case she becomes unwell again.
61-year-old Sekimizu said in his blog post: “I hope she will not become unwell again, of course, but I know, that cannot be guaranteed, and it could be more so if I was honoured for another term of four years, and I cannot accept not being able to one hundred percent commit myself to the work of IMO. This is the reason for not seeking reappointment.
"As the Chinese saying goes, “the person who chases two rabbits, catches neither.”
Many expected Sekimizu to hold the post for the typical two terms which would have seen him in the post until 2019.
Sekimizu urged IMO member states continue to support him over his remaining term in office. “I would like to seek continuous support and cooperation from Member Governments and permanent representatives and the staff in the Secretariat,” he said.
Writing in his regular blog, Mr. Sekimizu said the decision was due to personal reasons related to the health of his wife and that he had given Member Governments the following statement:
"I would like to retire from IMO at the end of the current term which expires at the end of 2015. I will not seek reappointment.
"This is because of my desire to ensure my support to my wife, who has a serious health issue, and I would like to ensure that, when needed, I could give more time for her care and support for her immune system problems.
"This March and April, her problem flared up. Because of making the necessary arrangements for her care, I could not fully maintain my commitment to the work of IMO and I had to compromise my planned travel schedule in April.
"Thanks to the effort of the medical service in this country, she is recovering. She is receiving excellent medical care in this country and I am very pleased with the current status of recovery. But she needs continuous health care.
"My core reason for not seeking reappointment is that if she becomes unwell again in the future, that could affect my duty and responsibilities and I may have to compromise my work, in order to ensure her care. I hope she will not become unwell again, of course, but I know, that cannot be guaranteed, and it could be more so if I was honored for another term of four years, and I cannot accept not being able to one hundred percent commit myself to the work of IMO.
"This is the reason for not seeking reappointment.
"When I put myself forward for the position of Secretary-General in 2010, we were fairly confident that she would be OK under the treatment and that I would be able to concentrate on my work as the Secretary-General, if elected. This has been the case up until this March.
"Now, we encountered the reality and I am having to take everything into serious consideration in order to avoid the possibility of potential problems in the future.
"As the Chinese saying goes, 'the person who chases two rabbits, catches neither.'
"Therefore, I have made up my mind not to seek reappointment. I am sure that there are a number of highly-qualified people who can replace me and lead the Organization towards the future. But nobody can replace me to take care of her.
"In our life, I believe that what is the most important thing is to be honest to yourself. I was honest when I proposed to her some forty years ago. I was always honest to myself when I applied for a post at IMO and resigned from the Transport Ministry of Japan. I was honest to myself when I challenged myself to become the Secretary-General and I was always honest to my judgement when I took any initiatives as the Secretary-General in dealing with major management issues of this Organization. And again, I am honest and loyal to myself in taking this major decision in my life.
"I believe that my decision is good for her in the first instance, and good for the Organization and also good for me.
"I would therefore seek kind understanding from Member Governments. Particularly those who rigorously supported me from the beginning of the selection process in 2011.
Review and Reform is making progress and for the rest of my term as the Secretary-General, I will continue to put all my time and effort into IMO until I retire at the end of 2015."
Therefore, I would like to seek continuous support and cooperation from Member Governments and permanent representatives and the staff in the Secretariat.
I will inform the Council of this decision through a formal document soon."
--------------------------------------------------------------------------------
Secretary-General Sekimizu stated that reasons of personal nature led to the decision not to seek reappointment.
“I would like to retire from IMO at the end of the current term which expires at the end of 2015. I will not seek reappointment.
This is because of my desire to ensure my support to my wife, who has a serious health issue, and I would like to ensure that, when needed, I could give more time for her care and support for her immune system problems.
My core reason for not seeking reappointment is that if she becomes unwell again in the future, that could affect my duty and responsibilities and I may have to compromise my work, in order to ensure her care.
I hope she will not become unwell again, of course, but I know, that cannot be guaranteed, and it could be more so if I was honoured for another term of four years, and I cannot accept not being able to one hundred percent commit myself to the work of IMO.
This is the reason for not seeking reappointment,” Sekimizu said.
The Korean invested shipyard has been facing financial difficulties since last year with much of the yard’s production facilities now suspended.
Belgian owner Bocimar has cancelled orders for four 36,000 dwt bulkers at Weihai Samjin as the shipyard could not deliver the ships on time. Germaen owner Oldendorff also cancelled one ship at the shipyard.
Weihai Samjin currently has in-hand orders of 52 vessels. The government is now working on the rescue plans for the shipyard.
Samjin is the latest Korean yard in China to fail – following the likes of STX and Daehan in Korea.
The court has asked the creditors of the shipyard to report debt information. The first creditors’ meeting is scheduled in December 25.
Currently most of the work in the shipyard has been suspended. Weihai local government is trying to restructure the shipyard by bringing in new investors.
Samjin Shipbuilding Industries has confirmed to IHS Maritime that it is in discussions to sell itself due to its financial troubles.
Established in 1999, the South Korean-owned company whose shipbuilding facilities are in Weihai in China's Shandong province, found itself mired in financial woes after accepting low-priced orders in the last few years.
"It's true that we're trying to sell our company. However, we cannot disclose any more details such as who will be the buyer. The only thing we can reveal is that we aim to sell the company within the year. The sale will be confirmed in October at the earliest," said a senior executive at Samjin Shipbuilding.
Other media reports speculate that the Chinese government could acquire the yard. Samjin's troubles saw the company suspending shipbuilding activity for two months earlier this year, causing Belgian bulker owner Bocimar to cancel orders for four 35,700dwt Handysize bulkers labelled Hulls 1052 to 1055.
IHS Maritime's Sea-Web data shows the ships are CMB Laszlo, CMB Diego, CMB Louis and CMB Laurence and that the keels have been laid.
The ships, ordered in December 2011, were due to be delivered in March 2015. Bocimar, which still has seven other sister vessels on order at Samjin, had said, "An amount of $29.985M representing the advances paid - including interest - has already been reimbursed. Bocimar, however, continues to closely monitor the situation of the yard and does not rule out any future subsequent cancellations."
UK-based Siem Offshore unit Siem Car Carriers, which ordered six pure car-and-truck carriers (PCTCs) at $60M each from Samjin in 2012-13, told IHS Maritime that it has not taken any action regarding the orders.
"At the moment, we're still monitoring the yard's situation. It's still wait-and-see," said a Siem executive. IHS Maritime's Sea-Web data shows that one of Siem's PCTCs, labelled Samjin 2003, is under construction while the other five PCTCs have statuses listed as "On Order/Not Commenced".
Oslo-based Siem Car Carriers is understood to be in the process of placing its first newbuilding order.
Sources say Siem has booked a pair of 6,500-car-equivalent-unit (ceu) ships at $60m apiece for delivery in 2014 and 2015 from Samjin Shipbuilding Industries in China.
TradeWinds understands the deal hinges on Siem agreeing a design that is significantly more efficient than conventional car carriers at a acceptable price.
Siem chairman Simon CG Stevens declines to comment.
However, some market observers question the reasons for the order as Siem has been mainly operating midsize tonnage between the Far East and US West Coast (USWC). They say Siem had previously time-chartered the 6,340-ceu Ocean Challenger (built 2010) from Mitsui & Co of Japan but swapped with Hoegh Autoliners for a smaller ship as it did not have the volume of vehicles to fill the larger pure car/truck carrier (PCTC).
Players say Siem redelivered the Ocean Challenger to its owner last year.
Siem operates a car carrier and ro-ro service in the Pacific with chartered ships and two owned — the 3,900-ceu Dresden and Verona (both built 2000), bought as resales for $35m each in 2000.
Siem beginnings
Siem was set up as Partner Shipping in Grimstad in 2008 by the former management of shortsea operator United Car Carriers (UECC).
A year later, investor Kristian Siem joined as an industrial partner, taking a 50% stake. In 2011, Siem Industries bought the outstanding 50% in the company, which became Siem Car Carriers.
The price linked to the Siem order is comparable to that placed last month by Aker ASA subsidiary Ocean Yield for two 6,500-ceu ships at Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)’s Romanian plant in Mangalia, which will go on charter to Leif Hoegh & Co.
It is estimated they would have cost $65m to $67m if built in South Korea.
Samjin has recently been successful in getting orders for handysize bulkers but has built car carriers in the past.
The 6,800-ceu Dyvi Atlantic (renamed NOCC Atlantic, built 2009) was handed over to Norwegian owner Dyvi (now Norwegian Car Carriers) three years ago but the sistership Dyvi Pacific sank during sea trials at the yard and was declared a constructive total loss (CTL).
The sinking of a South-Korean fishing boat that killed 22 people in 2010 was the result of negligence by the ship's master and officers on board, a coronial inquiry has found.
The No 1 Insung sank on December 13 just off Antarctica, 2700km south-east of Bluff, inside the NZ Search and Rescue Region.
Teams from New Zealand searched for two days for the missing sailors.
The report found the crewmen were working excessive hours, with navigators and watch keepers working 16-hour shifts at the time of the sinking.
The report also says there were "no on board emergency drills, no evacuation drills and no training in any safety aspects".
The sinking and resulting loss of life was largely preventable, Richard McElrea has found, and he is calling on the Government to work with foreign countries to improve safety training on vessels operating in New Zealand waters.
"It is clearly in the interests of both countries that appropriate environmental safety standards are maintained in these important international waters," the report says.
実際に軍事行動を考えれば、物資や兵器の輸送が必要となる。物資や兵器の供給なしでは戦闘や戦争は続けられない。船員を予備自衛官とする検討は実際に戦闘や戦争に備えることを前提にしていると思う。予備自衛官として登録されれば少しの手当ては貰えるのだろうが命のリスクと対価としては安いかもしれない。
理屈ではそうかもしれないが、政府は協力的な会社には間接的に財政支援や優遇措置を考えるはずだ。そうでなければ、船員や船員の家族を心配させるリスクを取る会社は増えないであろう。そうなれば、やはり政府と防衛省は次の手を考えると思う。財政に問題を抱えているのになぜ増税しなければならない方向に進んでいくのか?
同省が隊員輸送に活用するのは、津軽海峡フェリー(北海道函館市)の「ナッチャンWorld」号と新日本海フェリー(大阪市)の「はくおう」号で、ともに1万トンを超える。同省は2隻を今年度末まで7億円で借り上げたが、来年度以降は両社や金融機関などの出資で設ける特別目的会社(SPC)が船を所有し、平時は民間、有事には防衛省が使う仕組みを目指す。
乗組員については、有事や平時の演習など年間数十日の運用で現役自衛官を専従させられないとの判断から、自衛官OBの予備自衛官や、あらかじめ予備自衛官に仕立てた民間船員を充てることを検討している。
背景には海自出身の予備自衛官不足がある。2012年度の予備自衛官約3万2000人の大半は陸自出身者で、海自出身者は682人。現役海自隊員で艦船に乗り組むのは3分の1程度で、船に乗れる予備自衛官は限られるとみられる。招集時には一刻も早く港へ行く必要もあり、居住地などを考えると条件を満たす者はさらに少なくなる。
しかも、海自出身の予備自衛官は新任を退任が上回り、毎年約50人ずつ減少。自衛隊の艦船と民間のフェリーでは操船技術が大きく異なることもあり、2隻の運航に必要な乗組員約80人を自衛隊OBでまかなうのは難しいとみられる。
同省防衛政策課は、「予備自衛官になるかどうかを決めるのは船員本人で、強制できない」と強調。予備自衛官になるよう船員が強いられるおそれについては「会社側の問題で、省としては関知しない」としている。装備政策課は「有事で民間船員の予備自衛官が乗り組めば、操船技術は格段に安定する。船を操れる者と、自衛官の感覚を持つ自衛隊OBの双方が乗るのが好ましい」としている。
防衛省の2隻借り上げに協力する船会社2社は、取材に応じていない。
◇「事実上の徴用」
全国の船員で構成する全日本海員組合の元関西地方支部長で、船員の歴史に詳しい新古勝さん(70)は、「予備自衛官になれと会社に言われたら、船員はたやすく断れない。事実上の徴用であり、太平洋戦争の悲劇を繰り返しかねず、絶対に反対だ」と批判する。【平和取材班】
「戦地で死ぬと思っていた。戦争では船員などの民間人がまず犠牲になる」。横浜市西区の久我吉男さん(88)は太平洋戦争中、乗り組んでいた商船が沈められ、奇跡的に生還した体験を語った。
16歳の時、「船員募集」の広告を見て海員養成所に入所。半年後に商船の甲板員として徴用され、南方で働くことになった。1944年9月、18歳でボーキサイトを積んだ商船に乗り組み、日本に向けてフィリピンを出航した。5隻の護衛の艦船に守られていたが、港を出た翌朝、米軍機の攻撃で沈没した。救命イカダで漂流中に、砂浜が見えた。泳いで向かったが、幻覚だった。そのまま気を失い、沈没から4日目にフィリピン人漁師に助けられた。
一緒に乗船した30人のうち、助かったのは15人。負傷した自分以外は再び商船で日本に向かったが、その船も撃沈され、全員が亡くなった。
1人帰国を果たし、待っていたのは徴兵検査だった。「今度は軍人か」。入隊直前に戦争が終わった。「1人で海を漂い、どれほど怖かったか。国は守ってくれない。民間人を巻き込む戦争の恐ろしさを、忘れてはならない」
With nominal capacity of 8,110 20-foot-equivalent units, the MOL Comfort is the largest container ship to be declared a total loss. There’s no solid estimate of losses, but they’re expected to be heavy and to be litigated for years to come.
A $66 million hull and machinery policy was held mostly by Japanese insurers. The largest losses, however, will involve the vessel’s cargo. Estimates for cargo insurance losses have ranged from $200 million to $500 million.
Many of the MOL’s containers were filled with electronics or other consumer goods when the vessel went down on the Singapore-to-Jeddah leg of its Asia-Europe route. Insurers say the containers’ contents were insured for their retail value instead of their cost.
The Tokyo District Court this year allowed cargo interests and other plaintiffs to join MOL, the ship’s owner, in its lawsuit seeking damages from Mitsubishi Heavy Industries, which built the ship. Mitsubishi insists there was no problem with the design or construction.
The Japanese court combined 12 proceedings under Japan’s Product Liability Law into one, a move that allows evidence in one case to be used in another, similar to what happens in a class-action lawsuit.
Plaintiffs along with MOL include cargo underwriters, shippers, non-vessel-operating common carriers and container owners.
The MOL Comfort split in two on June 17, 2013, during a Force-7 storm after the hull apparently cracked from the bottom. Both sections of the ship later sank. The 26 crewmembers escaped by lifeboat and were rescued.
With the ship and its containers lost, investigators are struggling to determine why a 5-year-old vessel broke in two. Speculation has centered on overweight containers, misdeclared cargo, and stowage errors, but definitive answers may remain elusive.
Weeks after the sinking, MOL withdrew the MOL Comfort’s six sister ships from service and strengthened their hulls as a precautionary measure. The carrier brought in the U.K.-based classification society Lloyd’s Register as technical adviser on other vessels with similar designs.
The Japanese classification society ClassNK, MOL and Mitsubishi Heavy Industries are cooperating with a Japanese government inquiry that is expected to issue its preliminary findings within the next several weeks.
An interim report issued last December by Japan’s Committee on Large Container Ship Safety said performed small amounts of buckling were found on the bottom hull plates of several of the MOL’s sister ships, but said further investigation was needed to determine likely causes.
The committee performed simulations of hull strengths and loads, and performed structural inspections on the MOL Comfort’s sister vessels. The interim report found no evidence of fire or explosion, although one section of the vessel caught fire while under tow before sinking; there was no grounding or collision.
The ClassNK-led investigation team’s report is being awaited by the International Association of Classification Societies, which recently formed a group to help incorporate the results of the Japanese investigation into IACS standards for large container ships.
「なお、一般配置図、中央断面図、構造詳細図、機関室配置図及び機器リスト・図面については、2次元図面に加えて3D-CADデータも作成すること」
大手及び中手でも3D-CADに対応していないところがある思うが??元大手の造船所の人間か、大学の教授の発想なのか?0.5億円の上限は安すぎると思う。
仕様の決定にあたっては、以下に留意すること。
①内航船の船主、オペレータ、荷主、中小造船所に対して、現在使用している船舶の主要目、主機出力、就航航路、積載状態等についてヒアリングを実施すること。
②ヒアリング結果を整理し、ニーズについてとりまとめたうえで、標準的な船型の仕様(載貨重量、L、B、D、d、主機馬力・型式、航海速力、ハッチ寸法等)を決定するとともに、仕様が一部変更されるケースを類型化すること。
(2)省エネルギー内航船舶の標準的な船型の開発(1)で決定した仕様に基づき、省エネルギー内航船舶の標準的な船型の開発を実施する。開発にあたっては、以下に留意すること。
①当該標準的な船型は主機としてディーゼル機関を想定すること。
②当該標準的な船型の平水中における船体抵抗、制動馬力等を、水槽試験によって求めること。
③当該標準的な船型の省エネルギー効果を、1トンの貨物を1マイル運搬する際のエネルギー消費量(原油換算)で評価すること。
④当該標準的な船型は、比較対象船舶(0.0143 l /ton*mile) (A重油換算)から16%以上の省エネルギー効果を有していること。
⑤当該標準的な船型の基本設計データ(※1)を作成すること。
⑥当該標準的な船型について、一部の仕様を変更して建造を行う場合であっても、容易に対応することが可能であること。
⑦当該標準的な船型について、一部の仕様を変更して建造を行う場合であっても、比較対象船舶(0.0143 l /ton*mile)(A重油換算)から16%以上の省エネルギー効果を有することを確認すること。
※1 基本設計データ:計画主要目、船体線図、一般配置図、中央断面図、重量計算書、総トン数計算書、乾舷計算書、排水量テーブル、諸タンクテーブル、重量重心トリム計算書、損傷時復原性計算書、諸室配置図、構造詳細図、機関室配置図、機器リスト・図面 (なお、一般配置図、中央断面図、構造詳細図、機関室配置図及び機器リスト・図面については、2次元図面に加えて3D-CADデータも作成すること。13.成果物においても同様とする。)
※2 (1)及び(2)の事項に係る事業を進めるにあたり、第三者の専門家によって構成される委員会を組織し、技術的知見を反映させることで、客観性及び信頼性を確保すること。4.補助事業実施期間交付決定日から平成27年3月31日までの間
3※ 補助事業者が行う本事業(以下「補助事業」という。)を実施途中で取りやめた場合は、補助金の交付を行わないので留意すること。
5.申請資格申請にあたっては、次の①~⑤までの全ての条件を満たすことが必要です。
①本邦法人であること。
②補助事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領(平成15・01・29会課第1号)別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
⑤「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当しないこと(誓約事項に違反した場合、交付決定の全部又は一部を取り消すことに留意すること)。
※ 共同申請について
・ 共同申請とする場合には、以下の内容が含まれている申請者間で取り決めた契約書(様式自由)の写しの提出が必要です。
➢ 申請者同士が連帯責任を負うことについて
➢ 申請者間の役割分担の明確化について
➢ 補助事業に係る財産処分制限期間終了まで連帯責任を負い続けることについて
➢ 補助事業に係る財産処分制限期間終了までの構成員の脱退禁止について
➢ 補助事業に係る財産処分制限期間終了までの構成員の破産又は解散時の分担業務完了方法について
➢ 財産の適切な管理者及び財産の管理方法を明確化することについて
6.補助金交付の要件
(1)採択予定件数:1件
(2)公募予算額:0.5億円/年
(3)補助率:補助対象経費の定額定額補助とし、0.5億円を上限とします。なお、最終的な実施内容、交付決定額は、経済産業省が関係者と調整した上で決定することとします。
(4)補助対象経費の区分
補助対象経費は、補助事業の遂行に直接必要な経費及び補助事業成果の取りまとめに必要な経費とし、具体的には以下のとおりです。
経費項目 内容
開発調査費 省エネルギー内航船舶の標準的な船舶の開発調査に必要と認めるもの。(人件費、旅費、会場費、謝金、会議費、備品費、借料及び賃料、消耗品費、外注費、印刷製本費、補助員人件費、委託費、その他調査を行うために特に必要と認められるもの)
8.審査・採択
(1)審査方法
審査は、原則として有識者で構成される審査委員会において申請書類に基づいて行いますが、必要に応じてヒアリング及び現地調査を実施するほか、追加資料の提出を求めることがあります。
(2)審査基準
以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。ただし、審査基準④、⑥、⑦及び⑧を満たしていない申請については、他項目の評価にかかわらず採択いたしません。
① 内航船の船主、オペレータ、荷主、中小造船所に対する、現在使用している船舶の主要目、主機出力、就航航路、積載状態等についてのヒアリング方法が、具体的かつ効率的に提案されているか。
② 類型化にあたり、標準的な船型の仕様がニーズにより一部変更されるケースが適切に想定されているか。
③ 標準的な船型の平水中における船体抵抗、制動馬力等を求める水槽試験(設備を含む)が具体的かつ適切に想定されているか。
④ 開発する標準的な船型は、比較対象船舶(0.0143 l /ton*mile)(A重油換算)から16%以上の省エネルギー効果を有することが見込まれるか。
⑤ 開発調査の成果として得られる標準的な船型の基本設計データについて、中小造船所が一部の仕様を変更して建造を行う場合であっても、16%以上の省エネルギー効果を有することが見込まれるか。
⑥ 開発調査の成果として得られる標準的な船型の基本設計データについて、中小造船所において一部の仕様を変更して建造を行うことによる幅広い応用が見込まれるか。
⑦ 補助事業に係る計画が妥当であるか。・ スケジュールの設定が適正かどうか。・ 必要となる経費・費目を過不足無く考慮し、適正な積算が行われているか。等
⑧ 補助事業に係る実施体制が妥当であるか。・ 補助事業を的確に遂行する組織、人員等を有しているか。・ 補助事業の関連分野に関する知見を有しているか。・ 補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有しているか。等
15.問い合わせ先
<公募に係る全般的な問い合わせ先>
【経済産業省】
〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課
担当:中村、宮坂
電話 :03-3501-9726
E-mail : logistics2@meti.go.jp
<本事業の内容に係る問い合わせ先>
【国土交通省】
海事局 海洋・環境政策課
担当:河合、上田
電話:03-5253-8614
電子メールにてお問い合わせの際は、件名(題名)を必ず『【質問】平成26年度「省エネルギー型ロジスティクス等推進事業費補助金(革新的省エネルギー型海上輸送システム実証事業省エネルギー船舶の内航船への普及支援(標準的省エネルギー船舶開発調査))」(会社名、氏名)』としてください。他の件名(題名)ではお問い合わせに回答できない場合があります。以上
The Maritime Anti-Corruption Network (MACN) is a global business network working towards its vision of a maritime industry free of corruption that enables fair trade to the benefit of society at large.
MACN Members promote good corporate practice in the maritime industry for tackling bribes, facilitation payments, and other forms of corruption by adopting the MACN Anti-Corruption Principles, communicating progress on implementation, sharing best practices, and creating awareness of industry challenges.
MACN also collaborates with key stakeholders, including governments, authorities, and international organizations, in markets where corruption is prevalent to its membership, to identify and mitigate the root causes of corruption in the maritime industry.
Why Join?
As a member of MACN you make an active contribution to the elimination of corruption in the maritime industry.
Maersk Line and Vice Chairman of
the Maritime Anti-corruption Network
The Maritime Anti-Corruption Network was established in January 2011 by shipping companies to collaborate on strategies to address corruption affecting the maritime industry. Today, MACN is a global business network working towards its vision of a maritime industry free of corruption that enables fair trade to the benefit of society at large. MACN members promote good corporate practice in the maritime industry for tackling bribes, facilitation payments, and other forms of corruption by adopting the MACN Anti-Corruption Principles, communicating progress on implementation, sharing best practices, and creating awareness of industry challenges. MACN also collaborates with key stakeholders, including governments, authorities, and international organizations, in markets where corruption is prevalent, to identify and mitigate the root causes of corruption. MACN members jointly contribute to the group’s success by serving on the member-elected steering committee, one of several working groups, and/or by attending and actively participating in the MACN annual member meeting. MACN membership is conditioned on an agreement to comply with MACN’s Operating Charter, Anti-Corruption Principles, Anti-Trust Policy and associated procedures as well as contributing financial support to MACN’s initiatives and routine operations. BSR, a global business network and consultancy focused on sustainability, acts as secretariat for MACN.
Who can join MACN?
As a member companies make an active commitment to the elimination of corruption affecting the maritime industry. Companies can join as regular or associate member:
•Regular membership is open to vessel owners and operators who commit to implementing the MACN Anti-Corruption Principles.
•Associate membership is open to other companies and associations involved in the maritime industry
What are MACN’s goals and objectives?
One of MACN’s key objectives is to tackle concrete issues as well as root causes of all forms of corruption, specific to the maritime industry. In order for MACN’s members to be able to effectively combat these issues, it is necessary to identify the scope of the challenge including potential solutions. MACN members have agreed to a two-pronged approach. Some of the actions will be designed to achieve results on a short time basis while others will have success criteria with a longer time frame:
•Address issues of facilitation payments at ports and canal transits through short-term and medium-term initiatives. In some countries these actions can be designed by MACN and its members alone while in other countries, partnering with other stakeholders is needed to achieve sustainable results.
•With the assistance of the local government(s) conduct research into the underlying root cause(s) of corruption. With the local government(s) addressing these root cause(s), the long-term goal is to eliminate corruption in the maritime sector.
What are MACN’s pilots and collaborative actions?
MACN believes that transparency and dialogue with diverse stakeholders serve as helpful means to address challenges with corruption and that these factors make the timeframe of implementing concrete improvement measures shorter. To fulfill MACN’s goals and objectives, MACN is seeking support from government bodies and relevant international organizations. MACN has therefore explored collaboration with the UN Development Program (UNDP) and the UN Office on Drugs and Crime (UNDOC) to design and implement interventions that will serve to reduce and prevent corruption at ports. The aim is to identify issues caused by corrupt practices in the administration and handling of ships at ports including customs, cargo handling, and ship operations; and will involve commercial partners relevant for the whole value chain. MACN is focused on defining country specific solutions to improve current situations as they do not believe one solution fits all.
October 2012
採算に合わないから造船や海運が終焉を終わるまで突き進むのだろうか?町工場でも同じだと思う。若手を育てるほど収入はない、苦しいだけの経営を続けるメリットが無いから、こつこつ又は運良く知識や経験を積み重ね特殊で、業界から評価される技術を持った町工場以外は廃業しているのではないのか?
そうだとすれば、業界が改善や努力なしに人材確保や育成など検討しても意味が無い。将来性や魅力がないのなら行政を巻き込んでも無駄。外国人を活用するのであれば検討するべきだろう。しかし先はそれほど長くはないと思う。将来は発展途上国出身の外国人の下で日本人は働くのか?それはないと思う。現場を全く知らずに外国人を指揮する事は無理だと思う。IT研修やコールセンター業務で無駄な助成金を出して、税金を無駄にする意味の無い短期の雇用を考えるのなら、真剣に雇用、外国人労働者、人材の育成と給料について考えるべきだと思う。良い仕事でなくとも、途絶えれば復活はかなり難しい。終わりにする産業なのか、続ける産業なのか、一定の期間までは続ける産業なのかある程度の結論は出すべきだと思う。
また、世界における海洋資源開発の推進に伴い、海洋開発施設等の海洋産業に係る建造需要は増加を続けており、我が国造船業がこれらの需要を取り込み、成長を図っていくためには、海洋産業の技術者の育成・確保が必要となります。
このため、我が国造船業・海洋産業の発展を長期的に担う日本人技能者及び技術者の雇用拡大と育成方法につき検討するため、「造船業・海洋産業における人材確保・育成方策に関する検討会」を設置することとし、以下のとおり、第1回検討会を開催しますので、お知らせ致します。
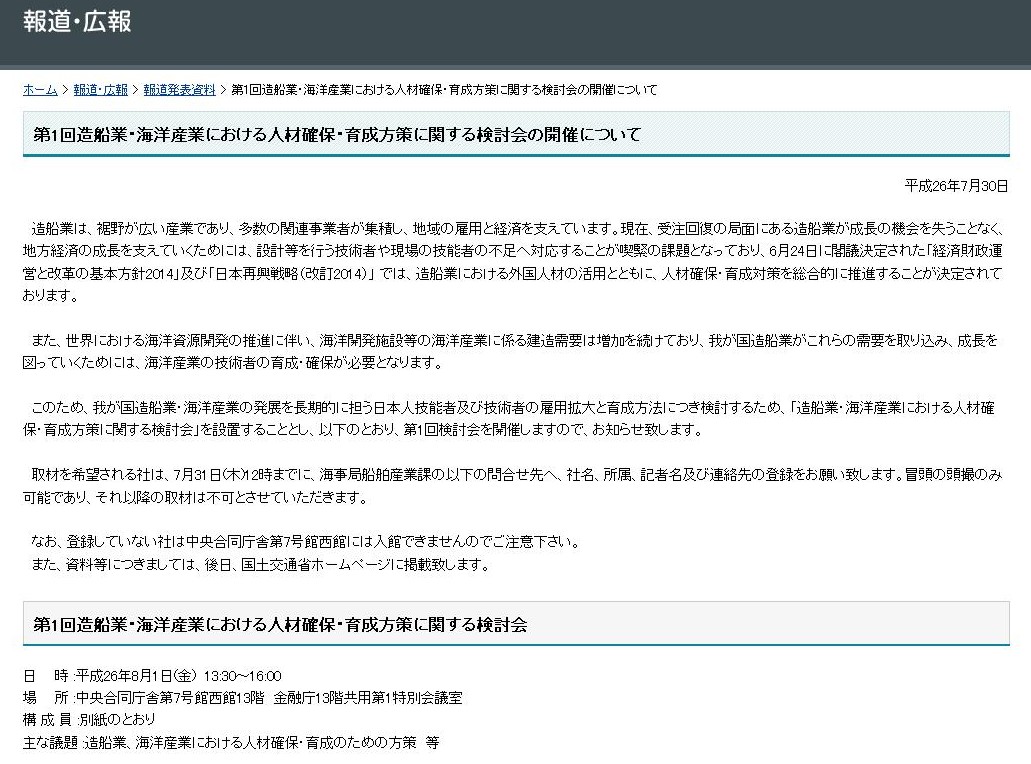
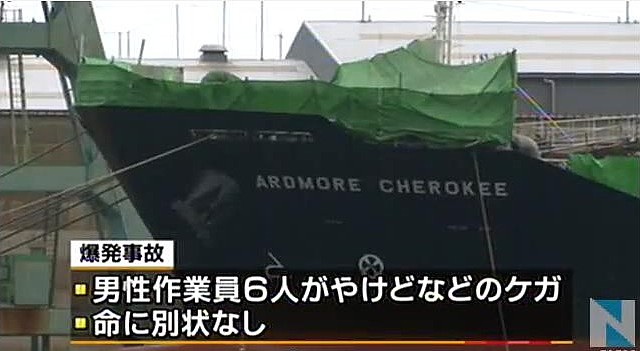

県警大浦署などによると、作業員は20~60代の男性で、同社の協力会社の従業員。爆発は船首付近で、6人は近くで溶接作業などをしていたという。
同タンカーの船内では、6月にも火災が発生。協力会社の男性社員=当時(45)=が死亡した。同署などは、爆発原因を調べるとともに、同社の安全管理などに問題がなかったかどうかも調べる。
同社によると、タンカーは排水量が2万5000トンのケミカルタンカー。約半年前に建造を開始し、今年10月に完成する予定という。
消防や警察が駆けつけたところ、建造中の2万5000トンのケミカルタンカーの内部にある、水を出し入れして船の浮力を調整する「バラストタンク」から煙が出ていたという。
消防が船内を調べたところ、船の底の部分に男性が倒れているのが見つかったが、船内には煙が充満し、有毒ガスが発生しているおそれがあったことから、男性の救出はなかなか進まず、午後7時10分ごろに運び出され死亡が確認された。
火は、火災発生から6時間半あまり後の午後7時半ごろになって消し止められた。
現場は、JR長崎駅の南西約8キロのところにある長崎港に面した造船所などが建ち並ぶ一帯。
本雇いの社長だけが、葬儀に参列しましたが、労災や補償の話がいまだにまったく出てきません。従弟45歳はひとりもので、単身長崎へ移ったものです。結婚歴もなく、彼女もいませんでした。新聞記事は名前すらなく、有毒ガスの恐れがあったため、だれも近づけず、たったひとりで死んだとの事。塗装の現場なら防毒マスクの一つくらい、備えがないのかと悔しくて。
おばたちのために慰謝料と補償を求めるつもりです。下請けの上に単身者、不利は理解しますが、どれぐらいの補償が妥当でしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
chabocobuさん
2014/6/3009:30:06
亡くなられた方のご冥福をお祈りします。
現在 私が聞いている限りでは、火災の原因が特定出来ていません。
本人さんの作業服に引火したのは、間違い有りませんが、どこから火が移ったか、どんな作業を、どの様な態勢で作業していたかが不明です。
つまり 会社側の過失と、本人さんの過失の度合いがまだ出せないのだと思います。
しかし 元請けのH造船も、直属のI塗装にしても、監督責任が有るので、必ず慰謝料と補償の話が出てきます。
あまりにも遅い時は、長崎労働局に相談して下さい。
金額については、会社側の過失と、本人さんの過失の度合いが有るので、一概には言えませんが、長崎県の造船所で発生した死亡事故の場合、2~3千万+α位が相場だと思います。
それから I塗装さんがキチンと労災保険に加入していれば、ご家族に遺族年金が支給されますので、確認してください。
同署によると、2人は下請け会社の作業員。運河に台船を浮かべ、別の船の船体を塗装していた。死亡した男性は爆発で吹き飛ばされ、即死状態。もう1人は意識があるという。
墨田川造船のホームページによると、同社は海上保安庁の巡視艇など主に官公庁向けに建造している。
Castillero worked for sixteen years in the Panamanian maritime sector, rising through the ranks to become head of the registry and director-general of the merchant marine. He says, “I am very excited to be joining the Liberian Registry, although of course I will miss my colleagues from Panama, from whom I part on extremely good terms. Over the years I have gained a thorough understanding of the strengths and weaknesses of the industry and its regulations, and indeed of all maritime registries. I would like to acknowledge the professionalism and independence of my leadership staff and of the many key individuals from the consular services and elsewhere, because without them nothing would have been possible.
“Shipping is a highly competitive – and, on occasions, political - industry. I am leaving what is currently the world’s largest ship registry to join the world’s second largest registry. But it is not necessarily about size. It is about quality. Ship registries have a vital role to play in the safe and efficient conduct of world seaborne trade, and change and renewal is part of the process of continuing improvement. Competition is fierce, and I am looking forward to using my experience to help develop still further the expertise and service offering of the Liberian Registry. Liberia’s unprecedented growth and envied reputation for safety, innovation and seafarer welfare continues to be attested to by respected independent arbiters throughout the world.”
Scott Bergeron, CEO of the Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR), the US-based manager of the Liberian Registry, says, “We welcome the appointment of Alfonso Castillero. It is not every day that the opportunity arises to appoint somebody of his experience and quality. His long involvement at the highest level of international ship registry affairs will be invaluable and will strengthen the cadre of seasoned industry professionals who help to make Liberia the flag of choice for continually increasing numbers of the world’s leading ship owners and operators.”
The Liberian Registry is one of the world’s largest and most active shipping registers, and has long been considered the world’s most technologically advanced maritime administration. It has a long-established track record of combining the highest standards of safety for vessels and crews with the highest levels of responsive service to owners. www.liscr.com
This newly created role represents a return to LISCR for Mollitor. Having formerly held the position of Assistant Department Head of Seafarer Certification & Documentation, he left the registry in 2001 to further develop his career. This included practising law in Alaska and carrying out maritime and environmental regulatory compliance roles at Royal Caribbean International and Holland America Line.
During that time, he served as the NorthWest Cruiseship Association’s representative to Washington State’s ballast water policy work group and as co-director of the joint US Coast Guard/Holland America Line cruise ship mass rescue operation exercise held in Ketchikan, Alaska.
Mollitor, a graduate of the United States Merchant Marine Academy and Tulane University Law School, also recently earned his Master of Business Administration from Western Washington University. He is a member of the Alaska Bar and the Maritime Law Association of the United States.
In his new role, Christian Mollitor will augment the registry leadership team’s marketing and business development efforts, oversee head office support of the global network of regional offices, and manage special projects. He says, “I am pleased to have the opportunity to return to LISCR. The last twelve years of my career have given me a greater perspective of the needs of the shipping industry and a specific view of how the premier maritime administrator, LISCR, can best provide regulatory compliance services.”
Scott Bergeron, CEO, says, “We are delighted to have been able to recruit Christian back to the registry. His experience and academic achievements will serve us well as the registry continues its global expansion. It is always deeply satisfying to have great employees return to the company after further developing their credentials.”
長崎造船所が実習生の受け入れを始めたのは2006年3月。当初は年10~15人
だったが、いまではフィリピン人121人、インドネシア人12人、ベトナム人
6人の計139人が働く。3年前、大型客船の受注が11年ぶりに決まって大量の
労働力が必要になり、一昨年から急に増やした。
外国人実習生を活用する動きは、他の大手重工メーカーにも広がる。三井造船は
インドネシア人など現在約30人の外国人を2年後に100人に増やす方針。
IHIも9月以降、愛知事業所(愛知県知多市)でベトナム人を150人ほど採用し、
溶接作業などを担ってもらう。LNG(液化天然ガス)運搬船に搭載するタンクの
受注が好調だが、自動車産業が集積する愛知県は人集めが難しいためだ。
韓国船級協会や海運業界に関する不正について捜査を行っている釜山地検の特別捜査本部(ペ・ソンボム本部長)は先月30日、船級協会の子会社iKRの新事業本部長L容疑者(42)に対し事前拘束令状(容疑者の身柄を確保できていない状態で捜査機関が裁判所に請求する令状)を請求した。L容疑者は昨年12月、船級協会の子会社の幹部と共謀し、成果給と称して4100万ウォン(現在のレートで約410万円、以下同じ)を受け取り、自分が関係する刑事事件の弁護士費用に充てたほか、業務推進費の1000万ウォン(約100万円)も横領した疑いが持たれている。また、L容疑者は2011年から昨年にかけ、国からの研究費を水増しして請求し、これを業者に渡した後、3000万ウォン(約300万円)を返金させ、業務用のクレジットカードで1500万ウォン(約150万円)を横領した疑いも持たれている。
一方、L容疑者はこれとは別に、船級協会の資金6000万ウォン(約600万円)を横領していたことが内部監査によって明らかになったが、船級協会はL容疑者に対する懲戒処分を行わず、辞表を受理しただけで、船級協会の子会社であるiKRは昨年9月、新事業本部長としてL容疑者を受け入れていたという。検察は、船級協会の子会社の社長や幹部についても、L容疑者と共謀し資金を横領していた証拠をつかみ、捜査を行っている。また検察は、L容疑者の子会社への再就職に、船級協会の元会長オ・ゴンギュン容疑者(62)=逮捕済み=が関与したいたか否かについても調べを進めている。
セウォル号沈没『不良対応』海上警察初めての令状 07/01/14 (デイリー韓国)
光州(クァンジュ)地検海上警察捜査専門担当チームは1日、職務遺棄、虚偽公文書作成、公用物件損傷などの疑惑で管制業務担当者2人、防犯カメラ管理者1人など珍島VTS所属海上警察3人に対して拘束令状を請求した。
セウォル号惨事初期対応と直結した海上警察に対して拘束令状が請求されたのは今回が初めてだ。家宅捜索情報を韓国船級幹部に流した副山海警情報官が先月拘束されたのだが、初期対応と関連して海上警察が拘束された事例はまだない。
捜査専門担当チームによれば管制業務担当者2人はセウォル号が沈没した去る4月16日午前、管轄海域を半々に分けて観察するようにする規定を破って1人だけでモニタリングをしてセウォル号の異常兆候を適時に把握することが出来なかった疑惑を受けている。
これらは勤務怠慢事実が摘発されることを憂慮して2人全てが正常勤務したように船舶との交信日誌も操作したと調査された。
珍島VTSは去る3月頃から2人1組管制指針を破って夜間勤務時1人で管制を引き受けたと分かった。所属管制官12人全員が服務規定を違反したのだ。
珍島VTSはこれを隠そうと防犯カメラを外側に向かうように固定し、防犯カメラ管理者は3ヶ月位撮影分を最初から削除することもした。光州(クァンジュ)地検は最高検察庁に映像復元を依頼した。
検察は救助・捜索業者選定過程で特典疑惑を受けた海上警察とウンディーネの癒着の有無に対しても調査している。
検察は複数の海上警察幹部とウンディーネのキム某代表に対して出国禁止措置をした。
キム代表は海上警察の法廷団体で昨年1月スタートした韓国海洋救助協会の副総裁だ。
このために海上警察が仕事を集めるために清海鎮(チョンヘジン)海運にウンディーネを救難業者で選定するように直・間接的な圧力を加えられるという疑惑が提起されてきた。
■業界保護のために見過ごしてきたのか
「韓国漁船の操業は非常に悪質だった」
現地メディアの朝鮮日報でさえこう表現したほどの韓国漁船の横暴ぶりに、ついにEUも業を煮やした。EUの調査団が6月初旬に韓国に入りして調査を実施したのだ。報道によると、韓国の漁船は、西アフリカ沿岸国の領海(海岸線から12カイリ=約22キロ以内)を侵犯して操業。国籍を知られないようにするためアフリカ漁船に偽装して、これが摘発されることもあったという。
1990年代後半から違法操業を取り締まるよう求める文書が国際機関から何度も送付されたが、
「業界保護のためこれまでと同じやり方の操業を続けても目をつむってきたのは事実」と語った韓国海洋水産部関係者の声が紹介された。
確かに不可解なことはある。韓国は世界有数のIT国家だが、違法操業の監視システムが導入されたのは今年に入ってから。朝鮮日報は、監督官庁にあたる韓国海洋水産部を批判。旅客線セウォル号の沈没事故をめぐり、安全対策が後手に回っていたことを引き合いに、海洋水産部の安易な対応がこういう状況を招いたと分析した。
違法操業国に指定されると、水産物の輸出禁止などの制裁が取られる可能性があり、経済的にも打撃だ。
韓国以外に、違法操業国に指定される可能性があるのは、スリランカやトーゴ、ガーナ、フィジーなどのいずれも開発途上国。先進国クラブに位置づけられる経済協力開発機構(OECD)加盟国である韓国にとって、違法国家扱いは、国際社会でのメンツを失う。
■「先進国としての責任を放棄」との辛辣な批判
韓国の遠洋漁業を批判したのは、EUだけではない。米国も同じだ。京郷新聞(WEB版)は昨年、アフリカなどで、韓国漁船が世界的な保護魚種の乱獲といった違法操業をしていると米国から指摘されたと伝えた。
韓国漁船は南極海で保護魚種の魚を制限量の4倍捕獲。南極海洋生物保存委員会所属の25カ国は、漁船を違法操業船舶に指定しようとしたが、満場一致を得られず不発に終わった。韓国が唯一反対したからだ。
米議会報告では、韓国がアフリカ沿岸国で偽造漁業権を使用、カヌーで不法操業をしていたことも
指摘されたという。
環境保護団体のグリーンピースは辛辣で、
「アフリカの人たちの食料になる水産資源を略奪している」とし、
「先進国としての責任を放棄している」と厳しく批判したという。
■「性器」擦りつけのセクハラ疑惑も
違法操業問題とは直接関係はないが、かつて韓国の遠洋漁業をめぐって、漁船内の破廉恥行為がニュージーランド政府の報告で明らかにされ、非人道的な体質の一端が浮き彫りになったことがあった。
ハンギョレ新聞(WEB)によると、2011年、韓国の遠洋漁業船からインドネシア船員32人が逃げ出し、ニュージーランド政府に衝撃の“体験”を語った。
同紙によると、韓国人船員は自分の性器を触るようにインドネシア船員に強要するセクハラ行為のほか、ステンレス製のファンで頭を殴ってけがをさせて放置するなどの暴行があったという。
韓国の国家人権委員会差別是正委員会が、ソウル公益法人センターなどからインドネシア船員に代わって訴えを受けたが、これが棄却された。人権委は、インドネシア船員の性器を触ったり、自分の性器を擦りつけたりした「可能性」は認めたが、「被害者と目撃者の陳述が一致しない」との理由で棄却を決定。その一方で、遠洋漁業という空間的特性を踏まえた「セクハラ予防と救済のための対策準備が必要」との勧告を行った。
いま韓国の遠洋漁業に求められているのは、国際ルールに乗っ取った対応と近代的なシステムを導入した漁船の運営にほかならない。韓国だけなく、中国による韓国近海や遠洋での乱獲も指摘されているが、海洋大国を自負する国家であるなら、ルールを守ることこそが国際社会からの尊敬を得る一歩になるはずだ。
STXは李克強首相が遼寧省トップの共産党委書記時代に、東北振興策の目玉として誘致。大連市北部の渤海湾に浮かぶ長興島に2007年に進出した。
遼寧省と大連市の政府は昨年来、国有造船大手の大連船舶重工集団に吸収合併させる再建案などを模索してきたが、債務が膨大で、海外にも複雑に及ぶため難航した。STXは今後、6カ月以内に再建案を裁判所に提出し、再建が不可能と判断されれば破産する。
STX大連の初期投資額は約15億ドル(約1520億円)。その後も14億ドル追加投資し、地元銀行からも多額の借り入れがあった。従業員は約2万1500人。東北振興策の重要プロジェクトである長興島再開発は中核事業を失った形だ。
Nautilus Holdings Ltd., which charters 16 container ships to ocean carriers, filed for bankruptcy protection, citing a “depressed” charter market.
The Bermuda-based company listed assets of more than $500 million and debt of more than $100 million in its Chapter 11 filing in U.S. Bankruptcy Court in White Plains, New York. James A. Mesterharm, a managing director at AlixPartners, was appointed chief restructuring officer.
Nautilus’ court filings listed 16 ships totaling 70,000 20-foot-equivalent units and ranging from 2,500 to 7,000 TEUs in capacity. The ships are chartered to carriers including Maersk Line, Hapag-Lloyd, Yang Ming, United Arab Shipping and CCNI, the company said.
Each of the ships is operated by a separate unit. In a court filing, Mesterharm said expiring long-term charters, combined with high leverage, “have left some of the debtors struggling to service their debt” and unable to comply with loan covenants and payment obligations.
“The debtors’ business has experienced significant pressure as a result of the expiration of seveal existing long-term charter contracts with rates higher than current charter rates which reflect a depressed market for container vessels,” Mesterharm said.
Mesterharm said, however, that Nautilus believes it has a good mix of vessel sizes in sectors where demand is strengthening, a number of long-term charters with favorable rates extending to 2018-2019, and “relationships with the top performing liner operators who are leading market consolidation efforts.”
By Masumi Suga
June 25 (Bloomberg) — Japanese shipbuilder Kawasaki Heavy Industries Ltd. plans to construct gas carriers abroad as it strives to lower costs and take market share from Korean rivals.
At present currency levels, the company’s Chinese ventures are more cost competitive than Korean shipyards, Akio Murakami, head of Kawasaki Heavy’s shipbuilding and offshore division, said in an interview in Tokyo.
“Our Chinese venture, Nacks, has built a variety of vessels so far, and LNG and LPG carriers are the only area that has yet to be handled,” Murakami said in the June 13 interview, referring to liquefied natural gas and petroleum gas. “Once we get the first contract and deliver a good vessel, many orders will follow.”
Kawasaki Heavy, based in the western port city of Kobe, estimates costs at its Chinese facilities are as much as 20 percent lower than at Korean yards, Murakami said.
The company gained a foothold in China in 1995 by forming a venture with China Ocean Shipping Group Co. in Nantong on the outskirts of Shanghai. While the venture builds large-sized bulkers and very large crude carriers, the company constructs liquefied natural gas carriers only at its yard in Sakaide on the southern Japanese island of Shikoku.
Shale Gas
Kawasaki’s push reflects the broader challenge facing Japanese shipbuilders to win back contracts from Korean rivals currently controlling about 80 percent of the market for LNG vessels. In the midst of Japan’s needs for cheaper energy after the 2011 Fukushima nuclear accident, Kawasaki and other domestic shipbuilders are counting on upcoming contracts for gas carriers used to ship gas from U.S. shale projects.
Japan’s four major shipbuilders including Kawasaki have together bid to build vessels that will carry LNG from the Cameron terminal in the U.S. state of Louisiana when shipments begin in 2017, Murakami said. Mitsui & Co. plans to secure 10 LNG tankers for the project, he said. More talks on orders for some other U.S. shale gas projects will start as soon as this year.
The yen has weakened 15 percent since the end of 2012, the most among Group of 10 currencies. Shipyards in Japan now have a more equal footing against Korean rivals after seeing contracts go elsewhere when the yen was stronger, Murakami said.
Kawasaki, whose origin as a shipyard dates to 1878, got six percent of its sales from its ship and ocean unit in the year ended March 31. It has diversified operations to areas including high-speed trains and fuselage parts for Boeing Co.’s 787s to Ninja motorcycles.
The company came under the spotlight a year ago when it ousted its president and said it scrapped merger talks with Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Murakami said the company won’t reject a merger that can create synergies but that growing bigger in its domestic market isn’t the only goal.
“At the moment, we intend to work with other companies on any win-win projects without leading to M&A,” he said.
個人的に思うが、コストを強調するが、ある点では改善が行われていなかったり、昔からと同じ無駄が放置されていたりする。目先のコストを優先して全体的に考えればコスト増になっている場合もある。その時は目先のコストを更に追及する。馬鹿でない限り他の選択があれば変わるでしょう。
お役人は増税すれば良いと簡単に考えているが、日本も生き残れる分野と生き残れない分野に分かれてきていると思う。国は良く考えて対応するべきだ。ターニングポイントを過ぎてからでは遅い。
「熟練工も若手も足りない」―。造船ブロックを製造する因島鉄工業団地協同組合(広島県尾道市)の片島伸一郎理事長は頭を抱える。リーマン・ショック後の受注減少を受け、約2年前、再雇用の熟練工や外国人技能実習生の受け入れをやむなく止めた。
その後、為替の円安進行などで2013年夏以降、徐々に仕事量が増えてきたが、「一度現場を離れた熟練工はもともと年齢も高く、体力の問題もあって戻ってはくれない。若手は建設業界に流れた」(片島理事長)。
若手が向かった先は、東日本大震災の復興や東京五輪のインフラ整備現場で、日当が3万円とも言われる。造船業界は低船価で受注した船の建造が続いており、「建設業ほど高い日当は出せない。単価が違いすぎて人材を集められない」(同)のが現状だ。人手不足のため、今年に入り発注を断らざるを得ないケースも出てきている。
K容疑者は船舶の発注などをめぐり、船主らから金品を受け取ったり、虚偽の出張費を計上したりした疑いが持たれており、業務上横領や背任収賄などの容疑が適用された。K容疑者は西海(黄海)地方海洋警察庁長官や東海(日本海)地方海洋警察庁長官、海洋警察装備品技術局長などを務めた後、2012年に海運組合に転職し、安全本部長を務めていた。検察はK容疑者の容疑が立証され次第、逮捕状を請求する方針だ。
一方、検察は今月17日、業務妨害や公文書偽造などの疑いで、船舶安全技術工団の検査員3人に対する逮捕状を請求したが、19日までに却下された。
仁川地裁は逮捕状の請求却下の理由について「一定の住居を持ち、証拠も全て確保しているため、証拠隠滅の恐れはない」と述べた。
検査員らは旅客船や釣り船などのエンジンを検査し安全証明書を発行する立場にありながら、エンジン検査を行わず、虚偽の証明書を発行した疑いが持たれている。
一方、沈没した旅客船「セウォル号」の実質的なオーナーとされる兪炳彦(ユ・ビョンオン)容疑者(73)=前セモ・グループ会長=一家の不正について捜査を行っている特別捜査班は19日、兪容疑者の逃亡を手助けした疑いで、B容疑者を逮捕した。B容疑者は先月、兪容疑者が全羅南道順天市の別荘に逃亡した際、手助けしたとして逮捕・起訴されたA容疑者の息子だ。
検察はこの日、B容疑者を逮捕するため、兪容疑者が率いる宗教団体「キリスト教福音浸礼会(通称:救援派)」の施設「クムスウォン」(京畿道安城市)の近くにあるレジャー施設に対し家宅捜索を行った。この施設は兪容疑者の長男・大均(テギュン)容疑者(44)=逃亡中=が所有しているとされ、そり遊びや動物とのふれ合いができる。
全洙竜(チョン・スヨン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
6/20 釜山地検、海軍艦艇の船舶検査を代行する業者から、便宜を図る見返りに賄賂を受け取った容疑で船級協会の検査員を逮捕 (韓国最新ニュースまとめ読み)
IACSのメンバーなのに結構、ずさんだ。言い方を変えれば、韓国客船沈没により常態化した検査の不正が注目を浴びただけなのかも知れない。詳細は下記のサイトで
セウォル号の沈没事故で問題になった
船舶の手抜き検査が韓国海軍でも実施さていた疑惑が浮上。
-------------------------
海軍艦艇の検査でも裏金取引...韓国船級検査員令状
(KBS 2014.06.20)
韓国海軍の安全検査を担当していた
代行業者に1000万ウォンを要求していた、
韓国船級の支部の主席検査員を逮捕。
「国の安全保障と直結する
海軍艦艇に対する船舶検査を監督する立場の検査員が
金銭を要求し受け取ったという事実が重要で
悪質なので逮捕令状を請求した」
by 特別捜査本部関係者
特別捜査本部は
韓国船級と業者の癒着はまだあると捜査を拡大し
糞尿処理装置の製造企業の経営者も逮捕。
「低価格の船舶糞尿処理装置を
安全機能が増強された高価な製品のように騙すため、
品質確認書と試験成績書を偽造または、
書き換えて関係機関の検証を通過した疑惑」
防水機能しかない船舶用の糞尿処理装置を
防爆型として偽装納品していた。
-------------------------
防爆でない
韓国海軍のトイレは爆発するのだろうか?
虚偽契約40億の追加融資…浦項アラクイーンズの船主の拘束
http://www.imaeil.com/sub_news/sub_news_view.php?news_id=27989&yy=2014#axzz34bIZxhiB
[今日のミーナ]旅客船船主たちが銀行融資金を多く受けようと慣行的に船舶価格を膨らませたという疑惑が検察捜査で相次いで事実と明らかになっている。
大邱地検の浦項(ポハン)支庁は12日、船舶価格を水増しして銀行から40億ウォンの不当な融資を受け取った容疑(貸出詐欺など)で、浦項~鬱陵客船アラクイーンズ号(3千404t級、定員855人)の実質的な船主のP(60)氏を拘束したと発表した。
鬱稜島からは小型船に乗り換えての独島観光が目玉になるはずだったが運行は白紙化されることになった。
検察によると、P氏は今年2012年アラクイーンズ号を購入した当時、50億ウォン程度の船値を130億ウォンと水増しした虚偽の売買契約書を作って銀行から計60億ウォンを融資を受けるなど実際の融資可能金額(20億ウォン)より40億ウォンをさらに融資を受けた疑いを受けている。
検察はアラクイーンズ号を販売したイタリアメーカーに問い合わせた結果、現地旅客船の価格が約30億ウォンの水準であることを確認しており、我が国に持ち込む時に課される関税などをすべて含めても50億ウォンを大きく上回ることはないと見ている。アラクイーンズ号は昨年7月に浦項~鬱陵路線に投入されたが、エンジン故障や火災など各種事故で一ヵ月で運航が中止され、結局、先月30日に定期旅客運送事業免許が取り消された。
一方、検察は先月末、船値を膨らませて銀行から10億ウォンの不当な融資を受けて、収益をわざと言及せず、税金4千万ウォンを脱税した容疑(融資詐欺に`脱税など)に鬱陵~独島旅客船独島サラン号(295t)の船主H(61)氏を逮捕したことがある。
大邱地検の浦項(ポハン)支庁チェセフン支庁長は"3月号事件以降、海運業界に関して、全方位的に強力な調査を行っている。海運業界の慣行的な不正を撲滅できるように捜査を拡大したい"とした。
(翻訳:みそっち)
浦項~鬱陵航路 アラクイーンズ号は就航2日目に火災発生
http://news.donga.com/BestClick/3/all/20130720/56565024/1
7月20日エンジン室で原因不明の火花が発生して乗組員が病院へ運ばれた。
エンジン修理代金は未納、運航は無期延期中、
http://aisddaz.kyongbuk.co.kr/main/news/news_content.php?id=627383&news_area=040
浦項海洋警察によると、アラクイーンズ号が鬱陵島道洞港から244人の乗客を乗せて出発した時刻は午後5時30分。アラクイーンズ号は出発の2時間の間29ノットの速度を維持した。
しかし、午後7時50分頃、突然速度を21ノットで降り運航、海洋警察の警備艇は、船上に問題が発生したと判断して、浦項海警状況室に知らせた。
アラクイーンズ号は浦項海警は、火災の発生を把握するまでに30分余りの間、火災の事実を申告していなかった。
浦項海警は現在、「なぜ、火災の発生申告が遅れたのか」について、船主側を相手に調査を行っている。
これに対してグァンウン高速海運側は「火災がすぐに消火になって運航に支障がなく、申告をしなかった」と釈明した。
火災発生の原因と関連してもグァンウン高速海運側は「エンジンの欠陥に起因するエンジンルームの火災ではなく、火傷を負った機関士が機関室内で4つのエンジンの油のレベルを合わせる過程で、油が少し漏れ、エンジンルームの展開のために流出した油が付着した機関士の作業服に火がついて発生した事故」と説明した。
このような解明について船の専門家たちの意見は違う。
専門家は「運航中に油のレベルを手動で操作することはほとんどなく、油が流出した場合でも、エンジンルームの熱気が原因で火災が発生したということは到底納得がいかない」とし、「火災原因の徹底的な究明が必要だ」と指摘した。
このように、運航二日だけに原因が不明確な火災が発生すると、船舶の安全点検が適切に行われているかの疑問も提起されている。特にアラクイーンズ号は、最初の出発前日翌日18日の午後遅くまで、船舶の安全点検を担当した韓国船級(KR)の安全検査済証を受けていなかった。エンジンの出力が100%稼働していなかったことが分かった。しかし、翌日の19日午前、出港決定機関である浦項地方海洋港湾庁の検査済証が受信され、この日初出港が可能だった。
出航後もアラクイーンズ号は許可速度である35ノットで運航していないことが明らかになった。35ノットの速力での運航をすれば浦項 - 鬱陵間を3時間30部品に運航することができる。アラクイーンズ号は、二日間の規定運航時間よりも30分と1時間遅れての運航が行われた。
消防が船内を調べたところ、船の底の部分に男性が倒れているのが見つかったが、船内には煙が充満し、有毒ガスが発生しているおそれがあったことから、男性の救出はなかなか進まず、午後7時10分ごろに運び出され死亡が確認された。
火は、火災発生から6時間半あまり後の午後7時半ごろになって消し止められた。
現場は、JR長崎駅の南西約8キロのところにある長崎港に面した造船所などが建ち並ぶ一帯。
韓国の遠洋漁船による漁獲量制限違反など違法操業を問題視している欧州連合(EU)が、韓国を違法操業国として指定する見通しとなり、国際社会で大きくメンツをつぶす可能性が高まっている。EUの調査団は9日に来韓し、韓国国内での違法操業監視システムについてすでに実態調査を行っているが、違法操業国への指定を阻止するのは簡単ではなさそうだ。
韓国と共に違法操業国に指定される見通しの国はスリランカ、トーゴ、ガーナ、フィジーなどで、いずれも開発途上国だ。これらの国々と同じ扱いを受けてしまえば、世界5大遠洋漁業国としてのプライドにも大きく傷が付く。
このような状況を招いたのは、海洋水産部(省に相当)の安易な対応によるものと考えられる。1966年に遠洋漁業を開始した韓国は、1980年代まで海外で特別な制約なしに魚を捕り続けた。ところが1990年代後半になると、漁業資源の枯渇に危機感を持った国連食糧農業機関(FAO)が操業方法についての勧告基準を定め、これを各国に通知したことで雰囲気が変わり始めた。
ところが海洋水産部はこの世界的な流れの深刻さに気が付かなかった。海洋水産部の関係者は「1990年代後半から違法操業を取り締まるよう求める文書が国際機関から何度も送付されていたが、業界保護のためこれまでと同じやり方の操業を続けても目をつむってきたのは事実だ」と述べた。
2008年にはEUがFAOの基準を法制化し、これに強制力を与えた。これが一種の「グローバルスタンダード」として定着したが、海洋水産部はEUから違法操業国として予備指定された昨年までの5年間、何の対応も取ってこなかったのだ。
EUが問題視している西アフリカ沿岸での韓国漁船の操業は非常に悪質だった。海洋水産部によると、沿岸国の領海(海岸線から12カイリ=約22キロ以内)を平気で侵犯して操業を続け、また国籍を知られないようにするためアフリカの漁船に偽装し、これが摘発されることもあった。西アフリカ沿岸で操業する韓国の遠洋漁船はこれまで40隻前後にとどまっていたため、海洋水産部がもう少し真剣に対応していれば、不祥事を阻止することはできたはずだった。だが海洋水産部は昨年まで、違法操業に対して2億ウォン(約2000万円)以下の課徴金を徴収する程度の処罰しか行ってこなかった。韓国は情報技術(IT)が高度に発達した国として世界から認められているが、遠洋漁船の位置を監視するシステム(VMS)が導入されたのは今年に入ってからだ。国民は旅客船「セウォル号」沈没事故の際、海洋水産部が旅客船の安全対策強化策を後追いのような形で取りまとめるなど、そのずさんな対応を目の当たりにした。「牛が逃げた後で小屋を直す(失敗してから後悔しても意味がない)」ということわざ通りの行動を繰り返す海洋水産部に対し、国民はこれ以上理解を示すことが難しくなりそうだ。
孫振碩(ソン・ジンソク)記者 朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
SSKは戦後、海軍工廠の施設を受け継いで市民が興した会社だ。佐世保市民には愛着がある。初の10万トンタンカー、日章丸を建造したことがSSK従業員のみならず佐世保市民の自慢。
昭和53年当時、従業員は8500人以上いた。(今は1200人程度か)だが、石油ショック後の造船不況で希望退職を募ったが、銀行が退職金の資金調達に応ぜず、倒産の危機に。当時の水野重雄日本商工会議所会頭ら国を挙げての救済劇で、再建に坪内氏が乗り出し、銀行も退職金を出したいきさつがある。
坪内氏がSSKの経営を引き受ける条件は①週休2日制をなくす②給料の25%カット③ボーナスなしーの三点だったと思う。
坪内氏の経営哲学は徹底していた。従業員を洗脳教育をして「サービス労働をする」というリポートを書くまで寝かせずに教育を続けた。低賃金重労働を徹底して、看板制度(トヨタと異なる)とその日の工事目標を書かせる。もちろん就労時間の8時間ではできなく、約2倍の工事量を書かせ、それをやり遂げるまで帰さなかった。もちろん残業代はなし(残業代をと言うとリポートで書いただろうと言われる)。
また技術は金で買える、と言うのが坪内氏の哲学。新聞、テレビのインタビューなどで公言。SSKには優秀な技術者が多数いたが、優秀な技術者ほど反発。多くの技術者がSSKを辞めた。この事態に九州大学の造船の教授は「もうSSKには人材を出さない」と言ったほど。
辞めた技術者が来島ドックに派遣され驚いたという。設計図などなしに船を建造していたという。例えば499トンの同型船ばかり作っているから、従業員は勘を頼りに船を作っていたという。
これら技術者は日本が造船不況のため多くが韓国の大手造船所に行って技術指導。今、日本を苦しめている。「どんがら」だけをつくるのはすぐにSSKの技術に追いついた。
SSKの施設は明治時代の古いもの。韓国は新型。韓国は価格競争でSSKに勝ち、SSKは人件費削減のためにさらに合理化をした。
これには多くの事務系の従業員も含めついていけず、次々に退職。資材も地元からの調達をやめ、安い来島どっくと同じものを使った。
これに反発した組合は大規模なストをして、組合が勝利した。
だが坪内氏は「辻一三佐世保市長、国竹七郎労愛会(SSK労組)会長、佐世保商工会議所の佐藤達郎専務理事を佐世保の三悪人」と呼び、マスコミから坪内批判も上がったのを従業員に見せないために、愛媛で坪内氏がオーナーと出している「日刊新愛媛」という日刊紙をSSKOBを配達人にして従業員の自宅に配り、坪内批判を目に触れさせないようにした。
しかし労災事故は多く発生、確か昭和57年には10人が亡くなるバラウニ号火災も起きた。
だが、この方法も長くは続かず、坪内経営は挫折。平成3年にはSSKは坪内グループを離れた。
だが新しい船出も厳しく、技術もないから昔の方式で「どんがら」を造るだけ。三菱のように自衛艦やLNG船のような高付加価値の船は建造できない。
再建が坪内でなく、技術者を大切にしていたら、LNG、LPGの高付加価値の船を造っていただろう。この研究はしていたのだから。
私が佐世保に行く前の昭和50年頃だがSSKは100万トンドックを伊万里に造る計画を発表したら、佐世保市は反発。米軍に掛け合って佐世保市の崎辺地区に造るようにSSKに払い下げをした。だが造船不況などでつくられていない。私は今でもSSKは崎辺に新しい新式のドックを造るべきだと思う。
この伊万里に名村造船所がドッグを造ったのは皮肉か。
私は名村造船所と佐世保重工業の株式交換に関する契約締結のお知らせを読んだ。どこの新聞社の記事もこのプレスリリースを参考にして書いている。
こちらへ
それによると、リーマンショックを機に船価の低迷、既存船腹量は過剰で、今後、低価格の船を建造しなければならない。SSKはこの2年間赤字で、今後も赤字が予測される。これを克服する体力がなく、どこかの子会社になるしかないということ。
それで候補に挙がったのが、佐世保の近くの伊万里にドッグがある名村造船所で一定の規模を拡大して、設計などを一緒にしてスケールメリットをだ生かそうと言うこと。
何しろここ数年、合併や技術提携が進んでいる。造船部門は石川島播磨(IHI)、住友造船、日本鋼管、日立造船が統合してジャパンマリンユナイテッドを造り建造量は日本で今治造船に次いで2位。トップの今治も三菱と業務提携している。川崎重工業と三井造船の統合はつぶれたが。
佐世保は何度も言うように基地の街で造船はなくてはならない街。もしも坪内氏が来なくて(坪内の合理化で自殺者は大勢いる)、市民が新しい造船所を造ってはじめに自衛艦と米軍の艦艇の修繕からしていていた方が、佐世保市民にとっては幸せだったかもと思っている。坪内経営は前近代的で近代的ではない。つぶれるのが当たり前だ。
検察によると、韓国船級釜山本社を家宅捜索する前日の先月23日夜に、役職員が会長室と役員室から書類を運ぶ場面が録画されたCCTV映像を確保したという。
韓国船級は釜山海洋警察のイ警査から家宅捜索が行われるという情報を事前に受けた。捜査情報を流したイ警査は17日に罷免された。
また検察はこの日、海洋水産部の幹部に数回にわたりゴルフ接待をしたり、商品券や法人クレジットカードを渡した容疑(賄賂供与など)で、韓国船級のキム本部長(59)とキム・チーム長(45)に対する拘束令状を請求した。
15人の船舶職乗務員のうち誰ひとりとして乗客救護措置をしなかったことが明るみになるにつれてのことだ。不作為とはどのような行為もしないことを意味する法律用語。
合捜本部の関係者はこの日、「彼らに対して殺人罪が適用できるかどうかを判断するために判例と法理を調べている」とし、「現在は事実関係を確定することが先だ」と話した。
合捜本部はまた、この日海洋水産部(以下、海水部)に韓国海運組合と韓国船級に対する監査資料を要請するなど、海水部にも捜査を拡大させている。
合捜本部は、セウォル号沈没事故を起こした清海鎮(チョンヘジン)海運などに対して海運組合が監督を正しく行っていたかについて調査してきた。海運組合は海運会社の会費で運営されている利益団体で、船舶の運航地図・監督に対する規制権限を政府から委任されている。
合捜本部は韓国船級の検査のやり方とあわせて、海水部の韓国船級に対する監査が適切に行われていたかについても調査を進めていく方針だ。韓国船級は今年2月、セウォル号に対する安全検査で「異常なし」という判定を下した。韓国船級にはキム・ギュソプ政府代行検査本部長など海水部出身の官僚がいる。
合捜本部はこの日、危険にさらされていた乗客を放置したまま逃げた容疑(遺棄致死)で1等航海士のK(42)とS(34)、2等航海士K(47)、機関長P(54)など4人を拘束した。この4人には全員、遺棄致死および受難救護法違反容疑が適用された。これを受けてすでに拘束されているイ・ジュンソク船長(69)など3人を含む7人に増えた。自殺を試みた機関士S(58)ら船員2人は被疑者身分で調査を受けている。
1等航海士のKは事故当時、珍島(チンド)海上交通管制センター(VTS)と交信した船員だ。合捜本部は彼ら船員を対象に、船長の退船指示の有無とあわせてブリッジ(操縦室)に集まって脱出の共謀を図ったかどうかについて調査中だ。捜査チームは、当時は船長の退船指示がなかったものと把握している。
これについて航海士Sは「船長が乗客に対して退船命令を下して無電で知らせた」とし、「船員に対する退船命令は船が90度近く傾いた時点で下りた」と主張している。航海士Kも「救命艇を操作しようとしたが、そこまで行くのが大変だった」とし、「救助を試みようとはした」と釈明した。
名村造船グループは建造量ベースで国内4位、佐世保重工は同10位。統合により、今治造船、ジャパンマリンユナイテッド(JMU)に次いで3位となる。同日、東京都内で記者会見した名村造船の名村建介社長は「厳しい競争を生き残るためには開発力・設計力を高め、市場が求める製品をいかに投入できるかがポイント。そのためには一定の規模拡大が必要」と話した。
佐世保重工の普通株式1株に対し、名村造船の株式0.128株を割り当てる。佐世保重工は9月26日付で上場廃止となる。設計力・開発力、調達力の強化を柱とし、営業での協力や管理部門の効率化なども進める。
両社の筆頭株主はいずれも新日鉄住金/dx/async/async.do/ae=P_LK_ILCORP;bg=0000801;dv=pc;sv=NX。名村造船は佐賀県伊万里市に、佐世保重工は長崎県佐世保市に造船所があり、地理的にも近い。
両社は石炭や鉄鉱石を運ぶばら積み船やタンカーなどが主力製品で、船の修繕事業も手掛けている。設計力の強化で「顧客が求める省燃費船や、需要が高まっているガスの運搬船にも挑戦したい」(名村社長)という。
世界の造船市場では規模で勝り、コスト競争力が高い中韓勢が受注で優位に立つ。両国メーカーの合算で建造量ベースで世界シェアの7割を握る。
米調査会社IHSによると、2013年(速報値)の建造量ベースで世界首位は中国の中国船舶工業集団公司(CSSC)、2位は韓国の現代重工業。日本勢では今治造船の6位が最高。CSSCの建造量は今治造船の1.7倍に及ぶ。
中韓勢に受注で先行され、1年ほど前までは、日本で建造する船がなくなるという「2014年問題」がささやかれていた。しかし、為替の円安進行に加え、韓国では対ドルでウォン高が進行するなど中韓勢の苦戦もあり、日本勢の受注が回復。懸念は払拭(ふっしょく)された。ただ、リーマン・ショック後に低価格で受注した船の建造が本格化しており、各社の収益は厳しい。
佐世保重工も低価格受注の影響で、12年度と13年度は2期連続赤字で、14年度も営業赤字を見込む。今後も為替変動などで造船不況が訪れる可能性もあることから、業況が上向いているタイミングをとらえ、傘下入りを決めた。佐世保重工の湯下善文社長は「中長期的に考えると収益は厳しく、造船専業企業が単独で事業を続けるのは難しい」と話した。
国内造船業の再編では、13年1月にユニバーサル造船とアイ・エイチ・アイマリンユナイテッドが統合してJMUが発足。川崎重工業と三井造船の経営統合も浮上したが、昨年6月に破談となっている。
海洋警察解体でも、全く新しい組織になるわけではない。組織の人材はほぼ同じ。日本でも同じであるが、韓国で公務員問題が存在する限り、大きな変化はないと思う。公務員はどこに行っても公務員。公務員が民間会社のサラリーマンになるわけではない。
朴槿恵(パク・クンヘ)大統領が19日午前、旅客船セウォル号沈没事故に関する国民向け談話を通じ、海洋警察庁の解体を表明したことを受け、海洋警察庁本庁(仁川市延寿区松島)はまるで幽霊にとりつかれたようなムードに包まれた。部外者の立ち入りは規制され、各部署の事務室はほとんどドアが閉ざされていた。庁舎の廊下を行き来する人々もあまり目につかなかった。3-4人の職員が外に出てきて、たばこを吸いながら雑談するいつもの光景も見られなかった。
職員たちは、海洋警察解体の方針について「過ちは認めるが、あまりにも行き過ぎなのではないか」との反応を示した。ある中堅幹部は「今回の事件で海洋警察は多くの非難を浴びており、事件がある程度片付いた段階で、相当な組織の再編が行われるだろうという考えはあったが、解体までいくとは思わなかった。組織がバラバラになり、自分たちがこれからどうなっていくのか分からないため、皆呆然とした様子だ」と話した。
事故発生後、全羅南道木浦市や同道珍島郡彭木港で事故の収拾に当たり、最近本庁に復帰した幹部は虚脱感を隠せない。「行方不明者の家族は当初、海洋警察を激しく非難していたが、時間がたつにつれ、われわれが懸命に取り組んでいるのを見て、陰では「ご苦労さん。ありがとう」と声を掛けてくれる人たちもかなりいた。そのため、われわれもすまない気持ちになり、より一生懸命取り組もうと決心していたが、突然こんなことになった」
不満を示す人もいた。ある職員は「事件発生当初には、われわれの対応に問題があったことは認めるが、その後は救助活動に最善を尽くしたのに、全ての責任を海洋警察だけに押し付けられたような感じだ。今は海洋警察が国民に対し罪を犯したも同然という状況で、何も言えないが、それでもこれまで海洋警察がそれなりに果たしてきた役割が、一度に忘れ去られるような気がして、とても気分が悪い」と語った。
2011年、仁川海洋警察署の李清好(イ・チョンホ)警査(日本の警部補に相当)が、違法操業の中国漁船に対する取り締まりの最中、漁船の船長に刺殺された事件を思い浮かべた職員も少なくない。当時は国民が海洋警察の置かれた状況を理解し、何か事件が起こるたび「海洋警察にもっと多くの支援が必要だ」という意見が多かったが、今回のセウォル号事件で何もかもがなかったことにされたというわけだ。
一部の職員は「同じ警察とはいえ、海と陸地で業務を分けていたものを、突然一緒にしたらどうなるのか心配だ」と話した。「国家安全処を新設するというが、結局はあちこちの官公庁の業務を寄せ集めて新たな組織を作るだけで終わるのではないか」という声もあった。ある幹部は「海洋警察をなくしたところで、海上での業務は誰に任せ、どうしていくのかが分からない」と語った。
仁川=崔在鎔(チェ・ジェヨン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
大統領は冒頭、「まともに対処できなかった最終責任は大統領である私にある」と謝罪。最後には、命をなげうって他の乗客を助けた犠牲者の名前を涙ぐみながら読み上げ、「(こうした姿に)韓国の希望を見る。真の英雄だ」とたたえた。
大統領は事故直後の海洋警察の救助活動について、「積極的に人命救助活動を行っていたら犠牲を大きく減らすことができた。事実上の失敗だった」と断定。海洋警察庁を解体し、捜査機能を警察庁へ移管することを明らかにした。「国家安全処」を新設し、海洋警察庁の救助・警備機能と、海洋水産省や安全行政省の安全機能を移すとした。
釜山地検特別捜査チーム(チーム長パク・フンジュン特捜部長)と韓国船級によると、韓国船級のAチーム長は先月7日に海水部の幹部に法人カードを渡したという。海水部の幹部はカードを受けた当日と9日、2度にわたり約90万ウォン(約9万円)を会食に使った。Aチーム長は検察で「先月18日、セウォル号汎政府事故対策本部が設置された全羅南道珍島郡庁で法人カードを返してもらった」と話した。
また検察は昨年8月に韓国船級Bチーム長が法人カードを別の海水部幹部に渡したという証拠を確保した。韓国船級チーム長らの携帯電話文字メッセージを通じてだ。「カードを返してもらったか」「まだ使っていない(海水部の) ○○○が保管している」というメッセージが交わされた。検察はこの時期の該当法人カードの使用内訳を確認している。
釜山海洋警察署はこの日、懲戒委員会を開き、先月24日に検察が家宅捜索するという情報を韓国船級にあらかじめ知らせた容疑で拘束されたイ警査(41)を罷免した。


安全がお金よりも優先される国ではない。

(Philippine Ship Spotters Society)

Ship laden with stones sinks off Pelong Rocks 07/08/13 (Borneo Bulletin Online)
悪天候で真っ二つに折れた船。構造喫水でゆとりのある強度が要求されていれば、悪天候でもこのように簡単に船は折れない。
MOL COMFORTの原因は?
(CNN) -- A month after the Sewol ferry sank, leaving 284 people dead and 20 missing, the incident set off a bout of national soul searching in South Korea over what went wrong.
Much of the blame has fallen on the ferry's crew, who scrambled to safety while the passengers were told repeatedly to stay put. Four of them have been charged with murder, prosecutors told CNN Thursday. The company's CEO has also been charged with "causing death by negligence, as well as causing the capsizing of the ship in the line of duty."
Beyond the ferry's owners and crew, the sinking has spurred a debate about governmental oversight and what preventive measures could've been taken. The South Korean president, Park Geun-hye, said in a speech on April 21: "This accident is highlighting many problems. First, the ship's introduction (how it came into the country), inspections, operational permits must be examined."
The reckoning over the accident has been a bitter one. Here is a look at some of the suspected factors behind the tragedy:
1. South Korean investigators: Sewol was overloaded
The passenger ferry was carrying more than double the ship's limit when it capsized, according to South Korean investigators.
Since Chonghaejin Marine Company started the Incheon to Jeju route in March 2013, 57% of its trips carried excess cargo (139 times out of 241 trips), according to the prosecutors. The company profited from overloading the ferry, earning an extra profit of $2.9 million since March 2013, investigators say.
Too much cargo contributed to sinking, police say
2. Prosecutors: Cargo on the ferry was not properly secured
Investigators have been probing the possibility the ship overturned because of a sharp turn that may have shifted the cargo, knocking the vessel off balance. Witnesses have described how several containers fell over and made booming sounds as they tumbled off balance.
Loosely tied goods contributed to the Sewol's sinking, because the cargo hadn't been tied properly, senior prosecutor Yang Joong-jin said earlier this month.
"The lashing devices that should have held cargo goods steady were loose, and some of the crew members did not even know" how to use them correctly, Yang said.
3. Crew insisted passengers stay put
"Please do not move from your location," the ferry's loudspeakers blared at those on board. "Absolutely do not move."
This type of warning was heard repeatedly as the Sewol began its descent into the water. Hundreds of passengers, unable to tell what was happening, complied. The instruction to remain in place, instead of getting on lifeboats, has been described as "terribly, tragically wrong," by one CNN analyst.
It's unclear why the crew made this determination, which remains one of the most haunting and perplexing questions surrounding the incident.
A transcript of the communication between Sewol and the local authority shows that the decision was made fairly early. At 9:00 a.m., the Jeju Vessel Traffic Services Center told an unidentified crew member: "Please put on the life vests and get ready as people may have to abandon ship."
The Sewol crew member immediately replied: "It is hard for people to move."
During communications with the local traffic services center that lasted until 9:38 a.m., the unidentified crew member repeatedly asserted that passengers could not reach life rafts or rescue boats because "they can't move... the vessel has listed."(From transcript)
4. The captain abandoned ship, while passengers were told not to move.
Capt. Lee Joon-seok of the Sewol has come under heavy criticism for abandoning the ship while hundreds of passengers remained on board. Pictures of the captain in what looks like his underwear hopping into the arms of the rescuer infuriated the nation.
President Park Geun-hye described the crew's actions as being "like murder." Lee is now facing murder charges. He initially defended the decision saying that he had everyone "stand by and wait for the rescue boat to arrive."
"The tidal current was strong and water temperature was cold, and there was no rescue boat," he told reporters last month. "So I had everyone stand by and wait for the rescue boat to arrive."
5. Inexperienced crew member steered the ship.
Authorities have questioned why an inexperienced third mate was guiding the ship at the time of the accident.
That third mate is also facing charges of not abiding by emergency safety law, negligence which led to the ship sinking and causing injuries leading to deaths.
The captain was not at helm at the time of the accident. There is no law requiring the captain to be on the bridge when the third mate is steering, but that an inexperienced member of the crew was navigating in one of the most treacherous stretches of the trip has raised questions.
The third mate denied making a sharp turn a few days after the accident and said, "The steering turned much more than usual. There are aspects where I made mistakes but for some reason the steering turned so much faster than usual."
6. Delays on notifying proper authorities of the accident
The first distress call came not from the ship's crew, but instead from a boy on board who used a cell phone to contact emergency services at 8:52 a.m. His call to emergency services gave rescuers a few extra minutes to get to the stricken Sewol as it is listed dangerously before capsizing.
Three minutes later, the ship's crew made a distress to authorities in Jeju -- which was the ship's destination rather than near its accident site. The miscommunication may have caused delays.
7. Ship's modifications raise questions
The Sewol had been renovated in 2013 to expand the top floor to make room for more passengers.
The 20-year-old ship was originally used in Japan, until Chonghaejin Marine Co. purchased the ferry in 2012 and refurbished it. Chonghaejin added extra passenger cabins on the third, fourth and fifth decks, raising passenger capacity and altering the weight and balance of the vessel.
Investigators want to know if the renovations may have made the ferry more likely to capsize or raised the ship's center of gravity. The South Korean Ministry of Oceans and Fisheries announced in late April that it would ask lawmakers to consider legislation prohibiting modifications to ships to increase passenger capacity. The government plans to take away the company's licenses for all its routes, including the one on which the Sewol sank, according to an official at the ministry.
支持率が急落した朴槿恵パククネ大統領は「国家改造」を掲げ、安全無視の船会社を野放しにした官僚機構の改革で求心力回復を狙う。贈収賄疑惑も浮上し、捜査を徹底する方針だ。
◆海洋マフィア
過積載が常態化し、救命艇も使い物にならず、船員らは乗客を置き去り……。「人災の連鎖」の根っこに「海洋マフィア」と呼ばれる天下り官僚の腐敗があることが、捜査で浮かび上がった。
海洋警察や、公益法人の船舶検査機関「韓国船級」が2月25日に実施したセ号の点検では、非常訓練の実施状況や救命装備は「良好」としていた。セ号は事故当時、救命いかだが塗装で固まって使えず、貨物も固定できなかったにもかかわらずだ。
韓国船級の歴代会長と理事長12人のうち8人が海洋水産省などの官僚出身で、役員には海洋警察元幹部もいる。捜査当局は、船舶を検査する過程で業者から金品を受け取った疑いがあるとして4月下旬から韓国船級などを捜索。韓国船級の職員には、海洋水産省職員に数十回、酒食やゴルフ接待を繰り返し、120万円相当の商品券を渡した容疑が浮上した。
海運会社でつくる「韓国海運組合」は、出港前に安全点検することが義務づけられているが、積載基準の倍近い貨物などを載せていたセ号を見逃していた。この組合の歴代理事長も12人中10人が同省出身だ。
◆繰り返す大事故
韓国社会はこの1か月、事故の衝撃で「自虐と敗北主義に浸った」(13日付「中央日報」)。朴大統領は4月29日の閣議で、「船舶の管理不行き届き、過積載、乗員の訓練の未実施。今回明らかになった問題は、(292人の犠牲者を出した)20年前の西海フェリー事故と同じだ」と嘆いた。
検警合同捜査本部(本部長アン・サンドン検事長)は15日、セウォル号沈没事故の当日、乗客救助の責任が最も大きいイ船長とカン・ウォンシク1等航海士(42)、キム・ヨンホ2等航海士(47)、パク・キホ機関長(58)の4人を拘束、起訴した。合同捜査本部は確認された犠牲者284人に対する殺人容疑などを適用した。生死が確認されていない行方不明者20人は被害者から除いた。
生存者152人に対する殺人未遂、業務上過失船舶埋没、水難救護法・船員法違反容疑も追加した。
また、パク・ハンギョル3等航海士(25、女)と当直のチョ・ジュンギ操舵手(55)も拘束、起訴した。2人は事故当日、復元性問題で操舵角度を5度以上回せば沈没の危険があることを知りながらも、15度以上の大角変針で船を沈没させ、救護措置を取らず脱出した疑い(逃走船舶罪)。
イ船長には最高刑が死刑の殺人罪が無罪となる場合を考慮し、最高無期懲役の逃走船舶罪も予備的罪名に追加した。検察はソン・ジテ1等機関士(58)を含め、残りの船員9人も最高懲役45年の遺棄致死・致傷罪を適用し、拘束、起訴した。
合同捜査本部の関係者はイ船長ら4人に対する殺人罪起訴に関し、「海洋警察珍島管制センター(VTS)から30分間ほど『救命リングを着用させて乗客を脱出させろ』という指示を受けたにもかかわらず、『放送・船内移動が不可能』という嘘をつき、9時37分に交信を切り、先に退船したため、殺人罪が成立する」と明らかにした。また「船員が脱出した9時38分、3階の甲板が浸水していないことも確認され、退船放送さえしていれば乗客全員が海洋警察や付近の漁船に救助される可能性があった」と話した。
検察の調査の結果、セウォル号の船長と船員8人は先月16日午前8時52分、操舵室に集まり、脱出を謀議した。船舶の2階の高さの浸水限界線まで水が上がってくると、船を捨てることにした。船員は開閉方式である船舶の扉が水に浸る場合、水圧のために開かないということを知っていた。イ船長らは当時、服や無線機を持ってくるため自分の船室を行き来する間にも、乗客にこの事実を知らせなかった。船体のあちこちに放送設備と電話機、非常ベル、無線機などがあったが、何も使用しなかった。
数回にわたり乗客の脱出を指示した珍島VTSとの交信内容もすべて無視して偽りの交信をした。一部の船員は救助艦が現れればすぐに脱出できるよう消防ホースを体にくくりつけて待機していたことも新たに確認された。
船員の大角変針も事故の原因と確認された。事故当日の午前8時48分。セウォル号のチョ・ジュンギ操舵手は操舵角度を135度から150度以上に急激に変えた。「操舵角度を140度に合わせろ」というパク・ハンギョル3等航海士の指示に基づき、さらに10度以上回した。当時運航中だった航路は潮流が速い孟骨(メンゴル)水道だったため、5度以上の変針をしてはならないところだった。急激な変針で右側に急旋回したセウォル号は左舷側に急速に傾き始めた。正常な船なら船体が復元するが、増築過程で復元性に問題が生じたこの船は結局、大きく傾いた。
適正量を大幅に超過した貨物量と船積み問題も船を沈没させた要因となった。事故当時、セウォル号にはコンテナや車両など2142トンの貨物が積載されていた。韓国船級が許可した適正積載量1077トンの倍だった。一方、船員は船のバランスを取るバラスト水は基準量の1565トンの半分にもならない761トンのみ入れていた。
無気力な救助活動をした海洋警察に対する捜査も本格化した。検察はこの日、「今後、救助関係者に対する徹底的な捜査を通じて相応の責任を問う」と述べた。
現代重工業も、海洋プラント事業拡大にともなう呪いに陥った。 今年に入り、収益性悪化と産業災害という2種類突発悪材料に処することになったのだ。 現代重工業も1分期1889億ウォンの営業損失を記録した。
昨年4分期871億ウォン損失に続き、第2四半期連続赤字だ。 しかも、現代重工業は海洋プラント部門で発生することもできる大規模損失を反映しなかった状態なので、今後も実績好転が容易ではないというのが業界の観測だ。
大宇造船海洋は、ピク3ヂュン海洋プラント事業でなかなか良い実績をおさめているけれど、潜在的な威嚇要因がある。 インペクスロブト受注した'イクシースFPSO'がそれだ。 三星重工業が同じ発注処からプロジェクトを受注して、莫大な損害をこうむった前例があるためだ。
業界関係者は"海洋プラント受注規模が商船よりはるかに大きいが、損する商売"として"技術力をより高めて、部品国産化を成し遂げなくては収益を出し難い"と話した。
http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2014051511053741926
韓国国内では66の旅客船運航会社が国内の95航路で173隻の船を運航している。しかし年間の売上総額は2012年の時点で3268億ウォン(約324億円)にとどまっており、これは1社当たりの平均にすると50億ウォン(約5億円)程度にしかならない。しかも全体の70%が資本金10億ウォン(約9900万円)以下の零細企業だ。このように小規模の運航会社が乱立する状況では、いくら安全に関する規制を強化しても、本当に安心して利用できる旅客船を確保することなどできないだろう。新しい船を建造する費用の10-20%で海外から中古の船を購入できるのだから、資金力に乏しい運航会社が新しい船を発注することなど考えられない。実際に韓国国内で運航中の1000トン以上の沿岸旅客船17隻のうち、15隻は海外から買い取った中古の船だ。
韓国国内の沿岸旅客船利用者数は年間1500万人近くに達している。そのうち75%は本土から島に向かう観光客だ。都市で運行する地下鉄や路線バスの場合、政府や自治体が財政支援を行っているため、実質的に半分は国営や市営のようなものだ。つまりこれらは「公共交通機関」であるため税金で支援が行われているわけだ。一方で沿岸旅客船を運航する会社に税金から支援を行うとなれば、何か違和感を持つ人も多いだろう。だからといって自力で経営するよう放置したままでは、海上航路全体の基盤がさらに脆弱(ぜいじゃく)になる恐れもある。沿岸旅客船の乗務員8200人のうち、41%が60歳以上と高齢化も進んでいる。若くて有能な人材をこの分野で育てることができなければ、乗客の安全確保もそれだけ難しくなるはずだ。
日本は1990年代の終わりごろ、政府と旅客船運航会社が船の建造費を一定の割合で負担し合って、完成した船の所有権を分け合う制度が導入され、これによって規模の小さい運航会社も簡単に新しい船を確保できるようになった。具体的には政府が船体価格の70-90%、会社側が10-30%を負担し、その割合に応じて利益を分け合うというものだ。日本では離島航路で運航される船の86%がこの方式によって製造されたものだ。
世界1位の造船大国などと誇ってきた韓国の造船メーカー各社は、韓国国内には実際に船の価格を支払えるだけの海運会社が存在しないため、旅客船の建造を事実上放棄している。しかし政府が船舶金融制度をうまく活用すれば、それほど高価ではなくともしっかりとした旅客船は建造できるはずだ。政府と造船業界、海運業界が知恵を出し合い、先進国レベルの旅客船を建造し沿岸航路に投入する方策を今後ぜひとも考え出さねばならない。
また旅客船を利用する際の料金が、過度に低く抑えられているとの指摘も根強い。離島で生活し旅客船を利用せざるを得ない島の住民に対しては、今と同じように料金を低く抑える一方で、観光客からは船の運航に必要な経費を賄えるだけのまともな料金を徴収する方向で検討を進めていくべきだろう。
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
13日、セウォル号沈没事件を捜査中の検察・警察合同捜査本部によれば「調理員2人が負傷して動けないのを見ながら、そのまま脱出した」という陳述を2人の機関部職員から得た。負傷していたのを見た機関部の乗務員は計4人だ。合同捜査本部は該当船員が救助された後、海洋警察に負傷者がいることを知らせなかった点を基に「不作為による殺人罪」を適用させる方針だ。不作為による殺人は、義務を履行しなかった時に人が死んでしまうかもしれないという事実を知りながら行動に移さなかったケースをいう。最高で死刑を宣告することができる。
◆海洋水産部にロビー活動=釜山(プサン)地検特別捜査チームは2012年から最近まで、海水部の公務員らに数十回にわたって商品券を配ったり酒席・ゴルフ接待をしたりしていた容疑で、韓国船級のキムチーム長(52)に対してこの日、拘束令状を請求した。また別のチーム長も海水部公務員らに数十回にわたって金品を渡したり供応をしたりしていた容疑を確認して捜査中だ。
検察はまた韓国船級のオ・ゴンギュン元会長(62)の自宅を家宅捜索して、韓国船級の幹部20人余りの名前と4300万ウォン余りの金額が書かれたメモを発見した。人事の口利きの代償として金品が行き来したものか確認中だ。検察は、韓国船級内の特定大学出身の同窓生が1人あたり100万~200万ウォンずつをオ元会長に渡していたと見ている。時期は2009年だ。検察は金品が行き来した後の2010~2011年、メモに書かれた人物のうち60%が希望の部署に異動したと把握している。
韓国船級と海運不正を捜査する釜山(プサン)地検特別捜査チーム(チーム長パク・フンジュン特捜部長)は12日、公務員に酒とゴルフを接待して商品券を与えた疑惑(賄賂供与)で韓国船級チーム長A(52)さんに対して事前拘束令状を請求したと明らかにした。
Aさんは最近3年間、海水部公務員に数十回にかけて遊興酒屋とゴルフ接待をして商品券など1千200万ウォン相当を与えた疑惑を受けている。
特別捜査チームは海水部公務員たちに数十回にかけて金品ともてなしを提供した他のチーム長クラス幹部も調査している。
検察は公務員たちが業務の関連性がある韓国船級幹部から賄賂を受けて船舶の安全、人命保護などに関連した監督機能が毀損されたと判断した。
特別捜査チームは船舶総トン数調査と関連して業者から金品を受けた疑惑(賄賂授受)で釜山(プサン)地方海洋港湾庁船舶検査担当6級公務員イ某(43)さんと賄賂を提供した疑惑(賄賂供与)で船舶設計業者H社代表B(53)さんに対しても拘束令状を請求することにした。
イ氏は2009年から2011年まで船舶の総トン数の測定検査をしてAさんから便宜を見てほしいという請託と共に15回にかけて現金と商品券などを合わせて1千10万ウォンを取り込んだ疑惑を受けている。
B代表は会社役員であるAさんに担当公務員に賄賂を送るように指示し、別にイ氏に会って数百万ウォンの金品を提供した疑惑を受けている。
韓国日報(韓国語)
http://news.hankooki.com/lpage/society/201405/h2014051310260621950.htm
韓国船級協会は政府の委託を受けて船舶の検査を行う団体だ。旅客船「セウォル号」が沈没した際、船に設置されていた46隻の救命ボートのうち1隻しか使えなかったことが問題になっているが、今年2月にこの救命ボート全てについて「良好」との判定を下していたのも同協会だった。同協会の会長にはこれまで11人が就任しているが、その中の8人は海洋水産部(省に相当)の元幹部による天下りだった。海洋水産部は退職した官僚を韓国船級協会に再就職させ、同協会は海洋水産部から監督を受ける際、彼らを前面に立てるなどして利用していた。このような実態が知られるようになると「業界とこれを監督する政府部処(省庁)による癒着が、海運業界の安全管理をずさんなものにした」「これが最終的にセウォル号沈没という悲惨な事故を招いた」などと激しい批判が巻き起こった。
しかもこの黒い癒着を解明する捜査の過程で、今度は捜査機関の担当者も被疑者と癒着していたのだ。C氏は海洋警察に勤務する親戚を通じて1年前にL氏と知り合い、それ以来ずっと親しく付き合ってきた。またL氏は海洋警察で情報を取り扱う業務を担当しながら、韓国船級協会の法務チーム長とも顔見知りになったという。その結果、C氏とL氏は個人的な関係を自らの職務よりも優先させて捜査の守秘義務を守らず、C氏はL氏を通じて検察による捜査状況を韓国船級協会にリアルタイムで知らせていたのだ。政府や検察・警察にこのような人間がいる限り、近くまた大惨事が発生するとの心配も現実味を帯びてくる。
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
機密、何度もやり取りした特別捜査チーム捜査官に令状
セウォル号沈没事件の根本原因と指摘された『黒い癒着』のゴールは、予想以上に深かった。船舶検査機関、韓国船級への検察の家宅捜索計画を密かに漏洩した海洋警察が、検察捜査官から関連情報を入手した事が判明した。韓国船級などの組織的な妨害で、捜査が困難に陥った検察は、捜査官介入の事実が発覚し、波紋を懸念し、戦々恐々としている。
海運業界の不正を捜査中の釜山(プサン)地検特別捜査チーム(チーム長パク・フンジュン特捜部長)は9日、検察の捜査情報を漏洩した疑い(公務上の秘密漏洩)で、特別捜査チーム所属チェ某捜査官(36ㆍ8級)・釜山海警イ某(41)容疑者への拘束令状を請求した事を発表した。
検察によると、イ容疑者は先月24日、釜山地検が韓国船級釜山本社・役職員事務室など9ヵ所を家宅捜査するとの情報をチェ捜査官が、韓国船級の法務チーム長原毛(42)氏に文字メッセージで知らせた容疑を受けている。調査の結果、2人は、海洋警察職員のチェ捜査官の母方の叔父の紹介で会い、1年以上親交を続けて来た事が明らかになった。これらは、家宅捜索の他、検察の捜査機密を数回、電話や文字メッセージでやり取りしたと伝えられた。
これに先立ち検察は、先月29日、韓国船級押収捜索で確保したウォン氏の携帯電話からイ容疑者が1回目の家宅捜索前日の先月23日、関連情報を知らせた文字メッセージを発見。イ容疑者は、ウォン氏の携帯電話が押収された事実を知らず、この2日にも『検察が、海警側に韓国船級のヨット利用資料を要求して来た』と、検察公文を写真に撮り、カカオトークに送っていた。
検察は今月7日、イ容疑者を召喚調査する過程で、チェ捜査官が介入した事実を確認した。釜山地検関係者は「当該捜査官は、先月24日、1回目の家宅捜索に参加したが、これらが交わした情報に重要な捜査状況がある事から、これらの拘束捜査が必要」「情報提供の過程で、金品・接待が行われたのかについても徹底的に調査する」と明かした。
韓国船級の組織的な妨害で、捜査がもたつく中、職員の犯罪容疑が明らかになり検察は困惑を隠せずにいる。最高検察庁が、海運業界の不正捜査を指示したのは先月22日。釜山地検は、これまで韓国船級本社や役職員の自宅など17ヵ所を家宅捜索したが、不正容疑を明確にする決定的な証拠物を確保する事は出来なかった事が分かった。
一方、検察は同日、釜山旅客船運営会社、A社を家宅捜索し、船舶購入に関連する書類・会計帳簿を分析している。検察は、A社が旅客船運航の承認を得る過程に問題が無かったか、運航時貨物・過積載は無かったかなどを調べている。検察は、韓国船級と釜山の某船舶設計業者を捜査する過程で、A社の関連容疑を掴んだ事が分かった。
http://news.hankooki.com/lpage/society/201405/h2014050920565121950.htm
釜山地検と海洋警察によると、先月24日、釜山海経のイ警査は知り合いの韓国船級法務チーム長に携帯電話メッセージを送った。「1時間後に家宅捜索に行く」という内容だった。
釜山地検の関係者は「家宅捜索に行ってみると一部の資料がないなど、事前に備えた印象を受けた」とし「このため捜査に支障が生じている」と述べた。また「家宅捜索1時間前でなく1日前に情報が漏れたという話もある」と付け加えた。
海洋警察は情報を流したイ警査を監察する方針だ。さらに捜査に参加しなかったイ警査が家宅捜索の情報を知ったことに関し、別の情報流出者がいるとみて追跡することにした。
「古い旅客船が国際航路に多いのは、国際条約に船齢制限が事実上ないからだ。」と書いてある。
船齢制限がなくとも旗国(主管庁)又は主管庁から承認された検査会社による検査を合格しなければ船は運航できない。検査に合格するための修理や維持管理は発生する。規則上老齢船の検査は新しい船と比べると厳しくなる。検査に合格するための修理や維持管理のコストと新造船建造のコストを比べ、新造船に替えることによる修理や維持管理コストの削減が大きい場合、乗客が新造船を望み、料金の安さよりも安全や快適さを求める場合、また新造船建造でも採算性が取れると船会社が判断すれば新造船建造となるだろう。
旗国(主管庁)又は主管庁から承認された検査会社が厳しく、適切に検査を行えば老齢船でも問題はない。例えば、ポンプが故障していたり、発電機を駆動するエンジンが耐久年数をかなり超えていたり、問題があれば交換すれば良い。外板やバラストタンク内部の腐食が酷ければ切り替えを要求すれば良い。検査レポートにコメントし、期間を与え、適切な対応をしなければ証書をキャンセルしたり、裏書きをしなければ良い。そうなれば船を運航する事は出来ない。定期的に船をドックに入れて、塗装したり維持管理していれば、良い船は長く使用できる。
海洋水産部が本当にこのような理解であれば、運が悪ければフェリー事故は起こるであろう。日本のPSC(外国船舶監督官)の検査は厳しくない。まあ、海洋水産部がこのありさまだから、今回の海難が最悪の結果となったのであろう!





2009年の冬に撮影。
サンプル 2
下記の写真もサブスタンダード船の写真である。
日本のPSC(外国船舶監督官)
は下記の船を検査したが下記の不備を見逃した






2010年の夏に撮影。






日本のPSCによる検査が2003年7月に行われた。不備としての指摘なし。
船倉がこんなに腐食していても日本のPSCは指摘しない!
もし座礁して、しばらく放置されると船体は真っ二つかも!
10時間漂流した船舶も
業界「交換する余裕ない」、海洋水産部「大きな問題ない」
旅客船「セウォル号」沈没事故を受け、韓国沿岸を航行する国内旅客船が老朽化しているという指摘が相次いでいる中、年間270万人以上が利用する国際フェリーも老朽化が深刻な状況にあることが分かった。
本紙が7日、韓国国内の6港と中国・日本・ロシアを結ぶ国際フェリー29隻(21航路)を全数調査した結果、平均船齢は22年に達することが分かった。
全29隻のうち、1994年建造で今年が20年目だったセウォル号より古い船は半数以上の17隻に達した。沿岸旅客船のうち船齢20年を超える船舶が24%(173隻中42隻)であることを考えると、国際フェリーの方が老朽化が深刻な状況だ。
全29隻中、韓中航路で就航する15隻(平均船齢22.3年)は全て建造から18年以上の老朽船だった。最近に作られたのは1996年10月に進水したニュー・ゴールデン・ブリッジ5号(仁川-青島)くらいで、80年代に建造され25年以上たった船も15隻中6隻に上る。中国との間を往復する15隻は全てセウォル号同様、貨物と乗客を一緒に載せるカーフェリーであるため、過積載によるリスクを常に抱えている。
韓日航路の12隻も平均船齢は21.5年に達する。そのうち高速船コビー3号(釜山-博多)とコビー5号(釜山-対馬)は77年に建造された船齢37年という国内最高齢の旅客船だ。東海岸の束草からロシアに向かうカーフェリー2隻も共に船齢20年を越えている。
古い旅客船が国際航路に多いのは、国際条約に船齢制限が事実上ないからだ。沿岸旅客船は30年という船齢制限があるが、国際フェリーは社団法人「韓国船級協会」が検査後に安全証明書を発行すれば30年以上運航できる。しかし「韓国船級協会は旅客船を所有する会社の便宜を図って安全証明書を乱発しており、海洋水産部(省に相当)もこうした状況を放置しているのではないか」という指摘もある。建造37年のコビー3号は、2010年に主要部品が外れた状態で出港して10時間漂流するなど、数回トラブルを起こしている。
国際フェリー業界では「新しい船舶と交換するだけの余力がないため、老朽船を投入するしかない」と説明する。韓中航路の15隻中、最も小さい旅客船(1万2304トン)はセウォル号(6825トン)の約2倍で、1隻当たりの交換費用は1000億ウォン(約100億円)以上と推算される。
海洋水産部は「国際フェリーは救命ボートを定員の125%(沿岸旅客船は100%)が乗れるよう備えなければならないなど、厳しい安全基準をクリアしているだけでなく、相手国の港湾当局から国際的な安全規則を遵守しているか監視・指導を受けているため、大きな問題はない」との見解を示している。
孫振碩(ソン・ジンソク)記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/05/08/2014050801220.html
海運・造船市況分析機関の英クラークソンによると、韓国造船会社の4月の船舶受注量は29万4167CGT(標準貨物船換算トン数)で、前年同月比84.8%減少した。
先月の世界の船舶発注量(226万1911CGT)が同48.1%減少した影響もあるが、競争国の造船会社と比べても業績悪化が著しい。
先月は受注量が中国だけでなく日本の企業にも抜かれた。中国は110万3857CGTを、日本の造船会社は60万4664CGTを受注し、シェアはそれぞれ48.8%、26.7%を占めた。これまで韓国は中国と首位争いを続けてきたが、先月のシェアは13.0%と日本をも下回り、順位を先月の2位から3位に下げた。月間受注量が日本を下回ったのは昨年1月以来となる。
昨年2月に中国を抑え月間受注量トップを記録した韓国は今年3月から受注業績が再び急激に悪化している。
1~4月の累計受注量は444万1372CGTで、前年同期比17.0%減少した。一方、中国は同10.8%増の603万4231CGTで首位を維持している。日本の受注量は219万4842CGT。
韓国造船会社の受注不振は、得意とする船種の受注減少や海洋プラント開発事業の遅延などが原因となっている。昨年は韓国が技術的優位を占める高効率・超大型商船の発注量が多かったが今年に入り低迷している。
業界関係者は受注量急減について、昨年の業績好調の反動が影響している面もあるとして、「今年の業績を悲観的にみるのはまだ早い」との見方を示した。
旅客船「ドルフィン号」(310トン)は2日午後2時40分、乗客390人と乗務員6人を乗せて鬱陵島(ウルルンド)を出発した。1時間40分後の午後4時20分ごろ、独島まで16キロを残したところで、機関室で故障警報が鳴った。エンジンの音も普段とは違った。機関長と機関士が直ちにエンジンを止めて調べた結果、2つのエンジンのうち右側エンジンの部品に問題があることを確認した。
報告を受けたキム・ボクマン船長(67)はひとまず、「エンジンに異常兆候があり、船を止めて点検します。しばらくお待ちください」と船内放送をした。
船長と機関長は修理は難しいと判断し、鬱陵島に戻ることを決めた。「近い独島には修理施設がないため、鬱陵島に戻るしかなかった」とキム船長は説明した。
エンジン一つで回航しながら、「安全だ。転覆することはない」と10回ほど放送を繰り返した。しかし不安感のため頭痛を訴えたり、嘔吐する乗客が少なくなかった。波が高くなるにつれ、船酔いする乗客も増えた。
ドルフィン号は鬱陵島に引き返すことを決めると、すぐに運航統制業務を担当する韓国海運組合の鬱陵運航管理室にこれを知らせた。運航管理室は東海海洋警察庁に伝え、30分後、警備艦2隻が来てドルフィン号を護送した。
旅客船はこの日午後8時ごろ、鬱陵島に到着した。多くの乗客は下船して安堵する姿だったと、海洋警察は伝えた。一部の乗客は「セウォル号の事故を知らないのか。どういう安全点検をしているのか」と大声を上げながら怒りを表した。
乗客のうち約50人は港の待合室に出ていたドルフィン海運の職員に抗議した。7人は船酔いがひどく、鬱陵郡医療院に入院した。医療院側は「かなり驚いたためか、心臓が痛いという患者もいる」と明らかにした。
ドルフィン号のエンジン故障に関し、安全点検が徹底的に行われていなかったという指摘も出ている。船舶検査機関の韓国船級から3月18日に検査を受けた際、異常なしという結果が出たからだ。セウォル号事故直後の先月末に東海海洋警察庁が実施した緊急点検でも、一部の船員が消火装備をきちんと操作できなかった点、機関室に非常操舵装置がないという点が指摘されただけで、エンジンの異常は確認されなかった。
ドルフィン号は1996年8月にシンガポールで建造された。長さ45メートル、幅10.1メートルで、香港の船会社が運営していた。これをドルフィン海運が買収し、2012年6月から鬱陵島-独島路線を運航している。
一方、この日午後6時28分、慶尚南道巨済市一運面の船着き場から180メートル離れた海上で、乗客141人(子ども26人)を乗せた38トン級の遊覧船1隻がエンジンの故障で止まった。乗客は事故発生から15分後に現場に到着した他の遊覧船2隻に分かれて乗り、長承浦港に戻った。乗客は巨済海金剛などを観光し、長承浦港に戻る途中だった。この遊覧船の定員は成人136人。海洋警察は「子ども2人を成人1人と計算するため、定員は超過していない」と話した。人命被害はなかった。
旅客船「ドルフィン号」(310トン)は2日午後2時40分、乗客390人と乗務員6人を乗せて鬱陵島(ウルルンド)を出発した。1時間40分後の午後4時20分ごろ、独島まで16キロを残したところで、機関室で故障警報が鳴った。エンジンの音も普段とは違った。機関長と機関士が直ちにエンジンを止めて調べた結果、2つのエンジンのうち右側エンジンの部品に問題があることを確認した。
報告を受けたキム・ボクマン船長(67)はひとまず、「エンジンに異常兆候があり、船を止めて点検します。しばらくお待ちください」と船内放送をした。
船長と機関長は修理は難しいと判断し、鬱陵島に戻ることを決めた。「近い独島には修理施設がないため、鬱陵島に戻るしかなかった」とキム船長は説明した。
エンジン一つで回航しながら、「安全だ。転覆することはない」と10回ほど放送を繰り返した。しかし不安感のため頭痛を訴えたり、嘔吐する乗客が少なくなかった。波が高くなるにつれ、船酔いする乗客も増えた。
ドルフィン号は鬱陵島に引き返すことを決めると、すぐに運航統制業務を担当する韓国海運組合の鬱陵運航管理室にこれを知らせた。運航管理室は東海海洋警察庁に伝え、30分後、警備艦2隻が来てドルフィン号を護送した。
旅客船はこの日午後8時ごろ、鬱陵島に到着した。多くの乗客は下船して安堵する姿だったと、海洋警察は伝えた。一部の乗客は「セウォル号の事故を知らないのか。どういう安全点検をしているのか」と大声を上げながら怒りを表した。
乗客のうち約50人は港の待合室に出ていたドルフィン海運の職員に抗議した。7人は船酔いがひどく、鬱陵郡医療院に入院した。医療院側は「かなり驚いたためか、心臓が痛いという患者もいる」と明らかにした。
ドルフィン号のエンジン故障に関し、安全点検が徹底的に行われていなかったという指摘も出ている。船舶検査機関の韓国船級から3月18日に検査を受けた際、異常なしという結果が出たからだ。セウォル号事故直後の先月末に東海海洋警察庁が実施した緊急点検でも、一部の船員が消火装備をきちんと操作できなかった点、機関室に非常操舵装置がないという点が指摘されただけで、エンジンの異常は確認されなかった。
ドルフィン号は1996年8月にシンガポールで建造された。長さ45メートル、幅10.1メートルで、香港の船会社が運営していた。これをドルフィン海運が買収し、2012年6月から鬱陵島-独島路線を運航している。
一方、この日午後6時28分、慶尚南道巨済市一運面の船着き場から180メートル離れた海上で、乗客141人(子ども26人)を乗せた38トン級の遊覧船1隻がエンジンの故障で止まった。乗客は事故発生から15分後に現場に到着した他の遊覧船2隻に分かれて乗り、長承浦港に戻った。乗客は巨済海金剛などを観光し、長承浦港に戻る途中だった。この遊覧船の定員は成人136人。海洋警察は「子ども2人を成人1人と計算するため、定員は超過していない」と話した。人命被害はなかった。
ニューヨーク州ベッドフォード・ヒルズ在住だというこの請願者は、先月25日、ホワイトハウスの請願サイト「We the People」に、キリスト教「救援派」と清海鎮海運の株主に対する捜査を非難する請願をそれぞれ登録した。
この人物は、二つの請願で「船の欠陥や不適切な運航、船長はじめ船員が乗客の避難に失敗したために人命被害が発生したが、韓国政府やメディアは、直接関係もない教会組織ばかりに不当に焦点を合わせている」「韓国政府が、海洋警察や国家的災害救助システム、政府に対する国民的な怒りをよそに向けるため、教会に対する攻撃を含め前例のない調査を始めた」と主張した。
5日現在、この二つの請願に署名した人物はそれぞれ約1700人(宗教の自由)、約600人(株主の弾圧)程度にとどまる。請願者や署名者の身元は、具体的に公開はされなかった。しかし、米国内に住所がある署名者は多くないという点から考えると、救援派の信徒が請願に参加しているものと推定される。なお、署名者が10万人を越えた場合、ホワイトハウスは公式の答弁を行うことになっている。
ワシントン=ユン・ジョンホ特派員
1918年(大正7年)に創業の同社は、大中型まき網漁業を主力に事業を展開し、日本近海を漁場にアジ・カツオ・マグロ・イワシ・サバなどを漁獲していました。
しかし、漁獲高の減少や魚価の下落で業績が悪化すると、燃料費の高騰も重なり資金繰りが逼迫したため、これ以上の事業継続は困難と判断し今回の措置に至ったようです。
帝国データバンクによると、負債総額は約30億円の見通しです。
Concern is growing within South Korean shipping circles that the strength of public outrage over the loss of the ferry Sewol — which has left 302 people, mostly schoolchildren, dead or missing, is encouraging police to find scapegoats among maritime officials.
Amid the anger over the loss, Korean Register (KR) chairman Chon Young-kee resigned as his organisation was investigated over the safety certification of the vessel and approval for earlier modifications to increase its cargo and passenger capacity.
His resignation comes even though no official investigation into the loss has been concluded and no charges or allegations have been made against KR. Chon said he was stepping down to ease the “pain and suffering” of the Korean people and families of the victims. But he insisted that KR had carried out its duties “diligently” and his resignation does not suggest “wrongdoing or negligence”.
As TradeWinds reported last week, a loss of stability because of modifications is being investigated as a possible cause. KR approved the modifications but only as long as certain operational conditions were met, mostly involving the ballast condition of the ship.
class allegations
KR’s Charles Choi says that with emotions running high in the country, there have been widespread speculation and allegations made without proper understanding of the work of a classification society.
“The classification society business is not well known. We carry out the survey and we verify and make sure all the hardware is within the rules but from that time until the next survey, it is the responsibility of the owner,” he said.
“Before we know what happened to the vessel, we have to look at the whole picture.”
Three officials from the Korea Shipping Association (KSA)’s Inchon office, which is tasked with ensuring safety in the domestic ferry industry, have been arrested under suspicion of destroying evidence.
The KSA president said he would step down from his position over his association’s involvement.
Police have also launched an investigation into the role of the Mokpo emergency services, the coastguard and regional vessel traffic services as it seeks to identify the cause of the delay in responding to the casualty. The arrest of the master, Joon-Seouk Lee, and officers of the Sewol has now been extended to all 15 surviving crew suspended for negligence and breaking maritime law.
Operator investigated
Yoo Byung-eun — the owner of the vessel’s operator, Chonghaejin Marine — has also been held in the country while his company is investigated.
Reports suggest that the Sewol, which can carry ro-ro cargo as well as containers, may have been loaded by as much as three times over its limit. The vessel’s maximum cargo capacity was recalculated to 1,000 tonnes after its modification but it is reported to have had more than 3,000 tonnes onboard at the time of the sinking.
The hard line of the police investigation comes not only in response to the strength of public feeling to locate responsibility but also against the background of an upcoming election.
Korean prime minister Chung Hong-won announced his resignation over the tragedy on Sunday. Local elections are to be held in June.
In a separate development, International Maritime Organisation (IMO) head Koji Sekimizu says he is willing to step up his ferry-safety initiative in response to the Sewol accident and urged Korea to pass on the findings of its safety investigation.
“I have the opinion that the time has now come for IMO to step forward to take action to improve the safety of passengerships carrying hundreds of the general public, regardless of the nature of their voyage, whether domestic or international. Only IMO can take such action,” he said.
By Adam Corbett London
「海運組合の代わりに安全管理引き受ける専門機関設立」
法案発議されたが政府・与党・ハッピーが反対
船会社の利益団体である海運組合の代わりに海洋安全専門機関を設立して船舶運航安全管理を任せる方案が3年前に推進されたが政府と与党が反対して立法が失敗に終わった事実が確認された。当時専門機関が新設されたとすれば体系的な安全管理でセウォル号沈没惨事を防げたことという指摘が出ている。業界では当時海運業体と『ハッピー(海水部+マフィア)』のロビーのために法案が廃棄された可能性が高いと見ている。
30日、韓国日報の取材の結果、2011年8月チェ・キュソン議員(当時民主党)等は独立機関である海洋安全交通公団を新設して運航管理業務を任せる内容の海事安全法一部改正案を発議した。だが、2011年11月、国土海洋委員会法案審査小委で廃棄されて常任委さえ上程されることができないと発表された。
当時法改正案はセウォル号沈没惨事であらわれた問題をそのまま反映している。貨物過剰積載とバラスト水不足が沈没原因として指定されているが監督を委任された海運組合運航管理者はこれを全く把握できなかったし、海上警察は海運組合を制裁する手段がなかった。すなわち利益団体が運航を管理する矛盾を解決して専門性を高めるために、独立機関である海洋交通安全公団が運航管理者を選任して管理監督を海上警察で一元化しようということが法改正の趣旨であった。
だが、当時国土海洋部が海運組合を積極的に擁護して専門担当機関設置は失敗に終わった。キム・ヒグク当時の国土部2次官は2011年11月、国会国土海洋委に出席して「海運組合で(安全管理業務を)よくしているのにあえて法制サイドに渡す実益がない」と明らかにした。
国土海洋部は法案審査を控えて■船舶安全管理は国土部の固有業務で■海運組合の運航管理体制は検証された制度であり■追加費用が発生して船会社の反発が憂慮されるとして法律改正反対の立場に立った。海上警察と業務管轄の戦いが推察できるだけでなく船会社と癒着の可能性を示唆する大きな課題だ。歴代海運組合理事長12人中10人が海水部(国土部)出身である点を勘案すればハッピーが法案通過を邪魔した可能性が高いというのが政界の観測だ。
法案廃棄には与党議員も積極的に加勢した。当時セヌリ党ヒョン・ギファン議員は法案を「殺さなければならない」として廃棄を主張し、他の議員も概して同調した。
3年前に海運組合を擁護した海水部はセウォル号惨事以後に手遅れになって騒ぐ対策を出して「海運組合を船舶安全管理業務から排除する」と明らかにした。パク・クネ大統領が29日注文した国家安全処設立もやはり安全管理専門担当機関の必要性を示唆している。
政界のある関係者は「国民の生命と直結する安全管理業務が利益団体の影響に左右されて駆け引きの対象に転落したという点で自己恥辱感を感じる」と話した。
韓国日報(韓国語)
http://news.hankooki.com/lpage/society/201405/h2014050103333021950.htm
船舶が無理な構造変更の影響で沈没した場合、保険会社が船舶運航社に保険金を支給しなくても良いという裁判所判決が下されてきた。
ソウル中央地方法院民事合議31部(オ・ヨンジュン部長判事)は東部火災が石井建設を相手に出した訴訟で「東部火災に保険金支給義務がないということを確認する」として原告勝訴で判決したと1日明らかにした。
石井建設が保有した船舶『石井36号』という1984年に日本で建造されて2007年に輸入された老後作業船だった。この船は2012年12月、蔚山(ウルサン)新港3工区工事現場で作業途中に片側に傾いて沈没した。
事故原因は無理な構造変更と明らかになった。会社側は工事期間を短縮するために専門家の安全診断なしに任意に作業設備を建て増しした。その結果重さが500t以上伸びた。
船舶安全技術公団釜山(プサン)支部はこれと関連して「増設された設備の重さと位置を勘案すれば顕著に錘の重心が上昇して船舶の復原力が減少したと推定される」という所見書を作成した。
東部火災は船舶保有会社が保険金を請求するとすぐに訴訟を起こした。裁判所は約款上保険金支給義務がないという保険会社の主張を受け入れた。
裁判所は「保険約款に規定された『海上固有の危険(Perils of the seas)』がこの事件沈没事故の支配的で直接的な原因だと断定し難い」として「かえって大々的な構造変更が影響を及ぼした」と指摘した。
裁判所は引き続き「被保険者側が船舶の構造上の欠点や事故発生の可能性に関し非常に注意を欠如したと見られる」として「約款上保険金支給義務を認めることはできない」と判示した。
韓国日報(韓国語)
http://news.hankooki.com/lpage/society/201405/h2014050106102922000.htm
同市は「現地で開封すると、安全を担保できない」として、同社に即時引き取りを求めていたが、「小包を鉛シートで覆うなど安全対策が示された」として了承した。
コンテナの中身は、全国から川崎東郵便局に集配された台湾行きの小包約250個。4月11日、本牧ふ頭入り口に設置された検知装置で、国の基準値(1時間あたり5マイクロ・シーベルト)に近い放射線量が検出された。14日に原子力規制庁が測ったところ、一部で基準値を超す最大15マイクロ・シーベルトの放射線量を検出。「原因特定後でなければ移送できない」と現地開封を求める同社に、「安全が担保できない」と市が反論し、コンテナの取り扱いは3週間近く、宙に浮いていた。
同社などによると、1日午前9時半にコンテナを開封後、周辺の空間線量を計測しながら作業員が線量計を使って原因の小包を特定し、鉛シートなどで覆って放射線量を抑制する。その後、移送先が決まるまでは、コンテナ内で保管するという。市は引き続き、速やかな移送を求めていく。
また、線量に問題のない小包については、コンテナから搬出後、川崎東郵便局に搬入した上で、送り主の要望に従い、再送や廃棄などを行う。
During his opening address to the Legal Committee (the first IMO Committee to meet since the Sewol tragedy) IMO Secretary-General Koji Sekimizu expressed his hope that IMO would be informed of the outcome of the casualty investigation to find the causes of the Sewol incident, and, in particular, any findings to suggest the need for improvements in safety standards and recommendations already established by IMO, if the casualty investigation were to reveal the need for such action at the international level.
Referring to the fact that there had been a number of accidents involving domestic ferries in developing countries in recent years and, under the Technical Cooperation Programme, IMO has a specific project on domestic ferry safety, Mr. Sekimizu further stated, “I have the opinion that the time has now come for IMO to step forward to take action to improve the safety of passenger ships carrying hundreds of the general public, regardless of the nature of their voyage, whether domestic or international. Only IMO can take such action.”
His words came in the wake of the Sewol tragedy, which took place in the Republic of Korea nearly two weeks ago, with considerable loss of life. In the immediate aftermath of the accident, Mr. Sekimizu wrote to the Ambassador of the Republic of Korea to convey the profound sympathy and compassion of the Organization to the families, friends and colleagues of victims. Now he has called for the membership to unite behind a new policy direction to help prevent a recurrence of such incidents in the future.
___
IMO – the International Maritime Organization – is the United Nations specialized agency with responsibility for the safety and security of shipping and the prevention of marine pollution by ships.
The Korean Register and the Korean Shipping Association have both fallen under the spotlight in the aftermath of last week’s Sewol casualty. Offices of both KR and the KSA were raided by police on Thursday as part of the ongoing investigation into the sinking. The offices and home of the owner of the vessel, Chonghaejin Marine head Yoo Byung-un, were also raided.
An official at KR said that KR had carried out an intermediary survey on Sewol in February and that the survey established that the ship was “in accordance with regulations”. KR had also conducted a check on Sewol’s stability when the vessel underwent modification to add space for 117 additional passengers. The registry found that the modification complied with regulations. South Korea’s Yonhap news agency said investigations would look at the possibility of corruption in testing ships and whether bribes were paid.
Chonghaejin Marine has come under close scrutiny in the days since the sinking. Mr Yoo was jailed for fraud for four years in the early 1990s.
Ten days after the sinking, 187 bodies have been recovered and 115 people are believed to be missing, though the government-wide emergency task force has said the ship’s passengers list could be inaccurate. Only 174 people survived, including 22 of the 29 crew members.
1つ言える事は形だけの検査は検査を行ってもあまり意味が無い。どれだけ適切に検査を行えるかが、PSCから出港停止命令を受ける船の隻数に影響する。
監査院、海洋水産部への特別監査を検討
欠陥などの理由により外国の港湾当局から出港停止の処分を受けた船舶に対し、海洋水産部(省に相当)が特別点検を行わないなど、
船舶の安全管理が不十分な実態が、昨年の監査院の監査で指摘されていたことが、23日までに分かった。
2009年から昨年にかけ、外国の港湾当局の安全点検で欠陥が見つかり、出港停止の処分を受けた韓国の船舶115隻のうち、
処分を受けた日から3年が経過した59隻について監査院が調査した結果、このうち15隻(25.4%)が特別点検を受けていなかったことが分かった。
船舶安全法では、過去3年以内に外国の港湾当局から出港停止の処分を受けた船舶に対し、海洋水産部が救助設備などの欠陥の有無について特別点検を行うよう定めている。
だが、重さ2654トンのある船舶の場合、中国の港湾で通信・消防設備の欠陥が見つかり出港停止処分を受けた後、韓国の港に39回も入港したにもかかわらず、
海洋水産部による点検は1度も行われなかった。
昨年12月に調査結果が発表された今回の監査院の監査は、船舶の安全性や船舶関係者の安全運航に関する力量の強化を目的として
2012年に策定された「国家海事安全基本計画(2012-16年)」がきちんと履行されているかを点検するために行われた。ところが、
政府が計画を策定してもその通りに実践されていないということが監査院の調査で明らかになった。
監査院はまた、済州・釜山・仁川・木浦・浦項など全国の港の沖合で沈没し、2次災害を引き起こしかねない船舶のうち、
324隻が海洋水産部の管理対象から抜け落ちている事実も突き止めた。
海洋水産部は「沈没船舶管理規定」に従い、沈没した船舶の危険性を評価し、関連する情報を管理しなければならない。同部は2012年12月
「沈没船舶の管理を体系化する」として、海洋環境管理法に沈没船舶の管理に関する規定も追加した。ところが、各地方の海洋警察や
海洋安全審判院が過去7年間(2006-12年)の海難事故の調査を行い確認した沈没船舶551隻のうち、324隻が管理対象から抜け落ちていたことが分かった。
一方、監査院は、旅客船「セウォル号」沈没事故の収拾が済み次第、海洋水産部をはじめとする海洋安全関連当局に対し、特別監査を行う案を検討していることが分かった。
商船三井側は供託金を支払った。同社は「具体的な金額は明らかにできない」としているが、約40億円とみられる。
中国側に供託金の支払い理由について、同社は「差し押さえが長引くと顧客にご迷惑をおかけすること、またその結果、当社の中国での事業活動に悪影響を生じかねないことを勘案した」と説明している。
3年前の判決確定時点で会計上の手当ては済んでおり、供託金の支払いによる平成27年3月期の業績への影響は軽微としている。
これは上海海事法院が19日付けで発表したものです。
この裁判は、上海の船会社の親族が、1937年に始まった日中戦争の前後に日本の船会社に貸した2隻の貨物船の賃貸料などが未払いだとして、1988年に日本側の会社を相手取って賠償を求めていたものです。
この裁判を巡っては、2007年、上海海事法院が原告側の訴えを認め、日本側の会社をその後吸収合併していた「商船三井」に対し、日本円で29億円余りの賠償を支払うよう命じる判決を出しました。
商船三井側は判決を不服として申し立てていましたが、2010年12月、中国の最高裁判所に当たる最高人民法院が、これを却下しました。
そして、その後、商船三井側が賠償の支払いに応じなかったとして、上海海事法院が19日、浙江省の港に停泊している商船三井の鉄鉱石運搬船「BAOSTEEL EMOTION(バオスティール・エモーション)」を差し押さえたとしています。
中国では、戦時中に日本に強制連行され過酷な労働をさせられたとして、中国人の元労働者や遺族が日本企業を相手に損害賠償を求める訴訟が相次いでいます。
今回の差し押さえによって、中国での戦後賠償に関連する裁判で、今後、原告側が勝訴した場合、日本企業の中国国内にある資産が差し押さえられる可能性も出てきたとして、議論を呼ぶことになりそうです。
商船三井「事実関係を確認中」
今回の船の差し押さえについて、「商船三井」は、「現地から情報はあったが、事実関係を現在確認中で、今後の対応は検討中だ」と話しています。
商船三井によりますと、差し押さえられた鉄鉱石運搬船の「BAOSTEEL EMOTION」は、総トン数11万9000トン、全長およそ320メートルある大型船で、22万6000トンの鉄鉱石を一度に運ぶことができます。
商船三井では、この船の建造費用は明らかにしていませんが、平成23年9月に日本の造船所でしゅんこうしました。
この船は、商船三井と中国の鉄鋼メーカーが、専用船として長期の契約を結んで、中国とオーストラリアなどとの間を往復し、鉄鉱石の運搬に使われていました。
また、上海の日本総領事館は、「きのう、海事裁判所の担当者が船舶まで来たと聞いているが、そのほかの状況については情報を収集しているところだ」と話しています。
「団塊の世代が現場を支えてきたが、中小企業に若手を育てる体力がなかった」。約3千社でつくる日本内航海運組合総連合会(東京)の上窪(かみくぼ)良和・船員対策委員長(66)は漏らす。中には交代要員の手が足りず長時間労働につながるケースも出てきているという。
1990~2000年代始め、海外輸送の「外航船」や遠洋漁船からの転職者を“即戦力”として採用し、新卒採用を控える傾向が強まった。若年層も海上で閉じられた空間という特殊な職場環境を敬遠したことで、高齢化が加速。国交省の12年の統計では、船員約2万7千人のうち50歳以上が半数を占めた。
1年前ごろから業界を支えたベテラン層がごっそりと引退し、今年1月の全国の有効求人倍率は1年前から0・55ポイント伸びて1・71倍。神戸も1・59倍。同時期、職業全般で見た場合、全国では1・04倍、兵庫県内では0・83倍で、船員の不足が際立つ。
将来の船員を養成する独立行政法人「海技教育機構」は100%近い就職率が再評価され、13年度の入学倍率は3・0倍だが、定員が計350人と少なく、船員不足の解消には至らない。上窪さんは「定員をもっと増やせないか」と期待する。
船員確保の施策を展開する神戸運輸監理部は13日、県内外の海運29社を集めた説明会を市内で開催。船員資格者ら約130人が各ブースを巡り、人事担当者の説明に耳を傾けた。
▽内航船 貨物を海外輸送する「外航船」に対し、国内の港を結び、生活必需品や工業製品を運ぶ。国内貨物の輸送は、輸送量×距離でみると、トラックに続く約40%を占める。1980年には約1万1200隻あったが、昨年3月には約5300隻。長距離や大型荷物の輸送に適し、鉄鋼やセメントなど産業資材の国内輸送では80%を占めるという。
北朝鮮乗組員16人乗った貨物船(モンゴル籍) 韓国南部で沈没
韓国の海洋警察は救助活動を行って5人を救助したが、2人は死亡し、追加捜索を行って1人の遺体を引き揚げた。救助された3人と遺体3体は板門店(パンムンジョム)を経由して北朝鮮に送った。海洋警察や麗水警察署などによれば、沈没した船は北朝鮮の清津(チョンジン)港から出発して中国揚州市近隣の江都港へ向けて航海中だった。重油50トンや鉄鉱石などが載っていた。韓国政府は14日、最後の遺体1体を北朝鮮に引き渡した。
グランドフォーチュン1号は海がない内陸国、モンゴル国籍の船だった。船主は香港にある会社だった。海洋水産部などは船主が「便宜置籍」の一環としてモンゴルに船を登録して賃金が安い北朝鮮船員を雇用し、貨物事業を展開していたと推測した。
便宜置籍は、自国船員の義務雇用比率を避けて税金節約のために他国に船を登録することをいう。それ自体は違法ではない。パナマやリベリア国籍の船が多いのは便宜置籍が多い国だからだ。
モンゴルは内陸国だが2003年から船舶登録局を開設して他国の船の登録を受けている。船舶登録を受けて税金を集めて海運産業を育成するためだ。ウィキリークスが2007年に公開した米国大使館の資料によれば、モンゴルには283隻が登録されている。船の主人の国籍はシンガポール(91隻)、パナマ(22隻)、マレーシア(22隻)、香港(12隻)などだった。船主が国籍不明な船も39隻あった。
北朝鮮が香港会社を代理船主として前面に出し、モンゴルに船を登録した可能性を見せている部分だ。外交部関係者は「今回のグランドフォーチュン号は、韓国領海ではない公海上で発見されたので対北朝鮮制裁決議にともなう船舶の捜索や調査を行えなかった」として「すぐに目についた重油や鉄鉱石のほかに、どんな物があったのかは確認できなかった」と話した。
先月出てきた国連安保理の対北朝鮮制裁の専門家パネル報告書によれば、国籍は北朝鮮ではないが実際は北朝鮮の船と疑われるものが最低8隻以上だった。このうちスンリ2号、グンザリ号、クァンミョン号の3隻は、今回発見されたグランドフォーチュン1号のようにモンゴルに登録されている。他国の国籍を持っており、船主は香港人である船も1隻あった。
国連対北朝鮮制裁の専門家パネルは報告書を通じて「安保理の対北朝鮮制裁決議2094号(2013年)が発効された後、北朝鮮は船舶を再登録したり国籍を変更したりして制裁を避けようとする可能性が高い」と指摘した。実際に北朝鮮は昨年だけで4隻の船をカンボジア・トーゴなどに国籍を変更した。
このような前例もある。2011年5月、北朝鮮の南浦港(ナムポハン)からミサイル武器などと推定される部品を載せてミャンマーへ向かった「ライト」号は、米国海軍の追撃を受けると公海上にとどまって回航した。ライト号は2006年まで「ブヨン1号」という名前を使う北朝鮮国籍の船舶だったが、北朝鮮核実験後に対北制裁が激しくなると名前を「ライト」に変えて国籍も中米のベリーズに変更して運行した。「ライト」号は米国の取り締まりがあってから2カ月後、アフリカのシエラレオネで国籍を変えて船の名前も「ビクトリー3号」に変更した。国連の対北朝鮮制裁の専門家パネルは、国籍を「洗浄」した北朝鮮の船が19隻以上に上ると推定している。
1971年に「新栄工業」として創業の同社は、プラント機械や工業炉などの大型製缶や重量鋼構造物の製造、船舶の建造や海上輸送を主力に事業を展開し、工場用地は9万平方メートルを誇るほか、大手重機メーカーや大手船舶メーカーを取引先として事業を拡大していました。
しかし、景気低迷に伴う海運市況の悪化で受注が大幅に減少すると、その後も取引先における設備投資の抑制が長引いたことで業績は低調に推移したため、これ以上の事業継続は困難と判断し今回の措置に至ったようです。
毎日新聞(電子版)などが伝えたところによると、負債総額は約9億円の見通しです。
13日午後4時半ごろ、横浜市の本牧ふ頭で、「コンテナから10マイクロシーベルトの放射線漏れがある」と日本郵政の社員から通報がありました。消防が調べたところ、コンテナから最大6マイクロシーベルトの放射線量を検出しました。日本郵政によりますと、このコンテナは台湾宛ての郵便物を積んだもので、11日、船に載せる前に測定したところ、4.5マイクロシーベルトを検出しました。13日午後に再度、測定すると、国の基準の5マイクロシーベルトを上回ったということです。消防は、コンテナに近付かないよう呼び掛けるとともに、コンテナの中を調べることにしています。
ケッペル・オフショア・アンド・マリン(O&M)は完全子会社のFELSオフショアを通じ、石油化学製品の物流サービスを提供する泰山石化集団、その子会社である泰山泉州船廠との間で、造船所の運営サービス契約を結んだ。同社は株式投資ではなく、造船所を運営する契約を結ぶことで、最小限の資本投下で中国の顧客基盤を狙う。
ケッペルO&Mは福建省泉州市の造船所を改造し、海上石油掘削装置(リグ)を修繕し建設する技術とノウハウを導入する見通しだ。
泰山石化集団は、新たに株主となった国有石油商社の下で経営再建中だ。同社はリストラ戦略の一環として、造船業の低迷にもかかわらず需要が大きい種類の船舶に特化するため、海上リグ建設事業に参入する。
ケッペルO&Mはケッペルが独占所有権を持つ設計技法を使い、「泰山ブランド」でリグの修繕や建造などを手掛け、プロジェクトごとの手数料の他に造船所運営費を受け取る見通しだ。110ヘクタールの面積を占める造船所が完成すれば、4つの巨大な乾ドック(ドライドック)を有することになる。契約期間は30年間でその後更新が可能だ。(シンガポール=谷繭子)
Why so? Well it’s easy to cheat when delivering bunkers from small bunker ships and barges to oceangoing vessels at Singapore and even easier when delivery is to what what is commonly known as the OPL (outer port limits) area. Bunkers are usually sold on weight but delivered by measuring volume which can be deliberately manipulated by increasing bunker temperature (so it expands and then lying about the temperature) as well as by introducing compressed air into the bunker line while loading (known as the Cappuccino effect) or simply by tank measurement falsification or even the addition of toxic waste to bulk up the bunker delivery quantity.
It’s all been done in Singapore and numerous people have been caught and have lost their bunkering licenses and have been heavily fined as well.
Crazy? Yes, but due to high bunker prices, so is the big money which can be made from cheating. Worse, the ship’s crew can often part of the fraud because it is not unusual for Chief Engineers to fiddle their daily main engine fuel burn figures and put the balance aside into a secret on board tank for later cash sale to a so called ‘oily bilge slop’ buyer.
So who’s being cheated? Well ship owners of course as well as time charterers who are required to pay for a ship’s fuel during the C/P term as well as owner’s claims for engine damage if the bunkers are contaminated.
It’s all a nasty business but Singapore’s MPA has fought back with the implementation of comprehensive controls which include the enactment into law of the “Singapore Standard Code of Practice for Bunkering – SS 600”. The Code includes the procedures for pre-delivery, delivery and post delivery activities. The formal licensing of Singapore bunkering companies and the training and assessment of bunker surveyors is also a key feature of the MPA’s quality and regulatory control plan.
Singapore’s latest ‘no cheating’ tool is to legislate the mandatory use of approved and sealed (tamper proof) “mass flow meters” on board all bunker ships and barges which operate out of Singapore. Full details of the mass flow meter approval and implementation date, widely expected to occur before the end of 2014, will be announced by the MPA during this month’s Maritime Week in Singapore.
But here’s the big question: what is the proven efficiency and reliability of such equipment and will it provide the deterrent effect necessary to stop the cheating? Part of the answer lies in the name “mass flow meter” (also know as “Coriolis flow meters”) where the word “mass” refers to this type of meter’s ability to measure weight as well as volume (unlike “volumetric flow meters” which have been around for decades).
OK, so “mass flow meter” accuracy will be much better but will these units be able to deal with the detection of Cappuccino bunkers? Some manufacturers claim it will but there are views to the contrary which relate to the noise level created by Cappuccino bunkers being loaded on board and its interference with a mass flow meter’s signal processing system. Time will tell.
So will mass flow meters put a permanent lid on all bunker fraud in the Lion State? Sorry, but they probably won’t because bad behaviour and greed are still out there as evidenced by the recent spate of bunker license offences and MPA cancellations. These ‘bad apples’ (as detailed on the MPA’s website) included Excel Petroleum Enterprises, Lian Hoe Leong & Bros. in January of this year followed Coteam Petroleum Trading in the past few days. Their offence? They allowed other unlicensed bunkering companies to use their Bunker Delivery Notes (which included their letter head and bunker license details) for the purpose of delivering bunkers and facilitating illegal transactions.
In summary, ‘bunker monkeys’ are still afoot in Singapore and will no doubt continue their fraudulent activities even in a highly regulated market and despite the installation of mass flow meters. The answer? Utmost vigilance which includes the appointment of reliable and licensed bunker suppliers and even more reliable and certificated bunker surveyors to protect the interests of both ship owners, time charterers and their long suffering insurers.
Not sure how to avoid being ripped off? Give SEAsia a call and we will be pleased to provide practical advice and assistance.
Chinese banks are stuck in a lose-lose legal battle between domestic shipyards and foreign buyers over billions of dollars in refund guarantees that are supposed to be paid out if shipbuilders fail to deliver on time.
One in three ships ordered from Chinese builders was behind schedule in 2013, according to data from Clarksons Research, a UK-based shipping intelligence firm. Although that was an improvement from 36 percent a year earlier, it was well behind rival South Korea, where shipyards routinely delivered ahead of schedule the same year.
That means Chinese banks may be on the hook to pay large sums to buyers if the yards can't come through per contract, with little hope of recouping the cash from the yards. China is the world's biggest shipbuilder, with $37 billion (22 billion pounds) in new orders received last year alone. Buyers pay as much as 80 percent of the purchase price upfront.
Chinese bankers rushed to finance shipbuilding after the 2008 global financial crisis as Beijing pushed easy credit and tax incentives to lift the industry and sustain industrial employment levels in the face of collapsing exports.
Fees generated by offering such guarantees looked like easy money until massive oversupply and falling demand started taking a toll on the yards around 2010. Shipyards fell behind schedule and buyers demanded their money back. But behind or not, the builders, keen to keep orders on the books and prepaid money in their pockets, have submitted injunctions against banks in Chinese courts to prevent them from paying out.
"China's ambitions to take over South Korea as the top major shipbuilder meant that all the banks were encouraged to open up their wallets and lend money to the shipbuilders without making thorough due diligence," said AKM Ismail, former finance director for Dongfang Shipyard, the first Chinese shipyard to be listed on London's AIM Stock Exchange in 2011.
Since ships cost millions of dollars and can take years to deliver, a shipbuilder generally asks for part of the purchase price upfront to cover material and labour costs. Buyers normally obtain a refund guarantee from a bank to assure their money is returned if the yard defaults, and the yard pays the bank's fee for the service.
Lawyers say that in many cases, banks did not require shipyards to pledge any specific collateral, partly because these guarantees are like a form of insurance rather than a loan. That leaves banks stuck with the default bill.
If banks obey local court injunctions and hold off from issuing refunds, they risk being taken to court by ship buyers in foreign jurisdictions. But if they pay out under the refund guarantee or seek compensation from the shipyard for the loss, bankers say they risk alienating local governments, which can damage the banks' business interests in the region.
"The whole issue of refund guarantees has been a big headache," said a finance executive at China Minsheng Bank.
"On the one hand, we know that our clients, the shipyards, will be saddled with huge debt that they will struggle to repay to us, if they can even pay back at all. But at the same time, our credibility is at risk, so we have to pay them out."
He and other bankers interviewed for this article all spoke on condition of anonymity because of the legal sensitivities of the issue.
Minsheng Bank did not respond to a request for comment.
In one case, UK court records show that in November 2012, subsidiaries of German ship owner First Class Ship Invest GmbH took China Construction Bank Corp to court in London to enforce payment of more than $10 million under a refund guarantee after Zhejiang Zhenghe Shipbuilding Co Ltd allegedly failed to deliver on an order.
CCB lawyers argued that an injunction served on it by Zhejiang Zhenghe in China would open up the bank to fines and the responsible banker could be arrested in China were it to pay out, but the judge rejected the argument.
None of the parties in the suit responded to requests for comment from Reuters.
Reuters was unable to find a single public example of a Chinese bank successfully fighting off a refund guarantee claimant in an overseas court; nearly all refund guarantee contracts stipulate litigation must be conducted in a foreign court.
Jim James, a partner at Norton Rose Fulbright in Hong Kong, said that he has been involved in several cases in which yards repeatedly obtained injunctions from different Chinese courts to drag out the refund process.
James, who has represented buyers, shipyards and banks in different cases, said the problem had become so serious that China's supreme court planned to issue guidance to lower courts on the handling of injunction applications.
LOBBYING WAR
Most customer suits are settled in arbitration and domestic court records are usually not published, so there is little hard data on the number or value of contracts under dispute.
But loan officers at China Export Import Bank, Bank of Communications, Bank of China and Shanghai Pudong Development Bank told Reuters that they had seen refund claims rising rapidly in 2012 and 2013.
The problem was widespread enough for the China Behavior Law Association Training Cooperative Center, an organisation registered with the Ministry of Civil Affairs, to hold a three-day conference for Chinese banks last July on the risks of refund guarantees.
On the other side, the Shanghai Shipbrokers' Association published advice for shipyards on how to keep banks from paying out refund guarantees on its website, saying Chinese banks should be more cooperative.
Shanghai Pudong Development Bank said it largely disbanded its shipping finance team in 2012, due to the sudden rise in refund guarantee claims and worsening market conditions.
An executive at another Chinese municipal bank told Reuters his company was interested in getting into the refund guarantee business "but we've been warned by regulators to be careful."
Jonathan Silver, shipping finance partner at Howse Williams Bowers, said banks have been taking steps to reduce their exposure, including asking shipyards to put up the partially built vessel as collateral for the guarantee.
SHARING BLAME
But lawyers also said that the Chinese shipyards are not always to blame, nor are their injunctions always frivolous.
Ismail of Dongfang Shipyard said his experience at the yard showed many foreign investors had exploited the weakness of Chinese shipyards - and inexperience of Chinese banks - to drive very hard bargains vis a vis refund guarantees.
Some buyers would gamble that prices would rise by the time the ship was completed and they could sell for an immediate profit. If prices didn't rise, they would reject the ship and cash in the guarantee.
In one instance, he said Dongfang had an agreement to deliver two or three ships that were behind schedule but 90 percent completed. The buyers pulled the plug and sought a refund, even though Dongfang was willing to renegotiate and sell the ship at a lower price, he said.
BIG FISH
Clarkson Research data shows that the Chinese shipbuilding industry won $37 billion in new ship orders in 2013, up 92 percent year-on-year.
But this rising tide is not lifting all boats: Chinese state media reported that 80 percent of new ship orders went to just 20 yards. Investors are concerned that the debt-sodden Chinese shipping industry is set for a wave of defaults if Beijing doesn't bail it out.
China Rongsheng, the country's largest private shipyard, reported a $1.4 billion loss for 2013 and and some customers are worried about Rongsheng's $4.6 billion worth outstanding orders.
Greek ship operator Dryships Inc has already put down a $11.56 million downpayment, 8.5 percent of the total cost, toward four cargo ships scheduled to be delivered in 2014, but Dryships executives said they aren't sure Rongsheng has even started cutting steel.
"We don't want to make any more payments to Rongsheng," Dryships CFO Ziad Nakhleh told Reuters in February. "Things are getting worse not better."
Rongsheng said in an emailed statement to Reuters that thanks to recent refinancing, it is optimistic it can make delivery, but would not otherwise comment on other refund guarantee cases.
Regardless, Dryships executives also said they expect Bank of China, the guarantor, to refund their money plus 8 percent interest if Rongsheng fails.
Bank of China did not respond to a request for comment.
By paying up, Chinese banks can reassure foreign customers doing business in China, protect their overseas assets and preserve their reputations. And the amounts, while large, are manageable, said Silver of Howse Williams Bowers.
"If there is any collection of banks anywhere in the world able to disperse those sums of money... it's going to be Chinese banks."
(Additional reporting by the Shanghai Newsroom, Fayen Wong, and Keith Wallis in SINGAPORE; Editing by Emily Kaiser)
2隻の大型客船は11年11月に米カーニバル社の欧州法人コスタ・グループ傘下のアイーダ・クルーズから受注した。12万4500総トンの3300人乗りで、1番船の建造に着手済み。だがホテル客室の仕様変更などで作業が大幅に遅延。設計費だけでなく、資材調達の費用が膨らんだ。鯨井洋一取締役常務執行役員は記者会見で「契約上、顧客に請求できる部分は請求していく」と語ったが、将来発生する損失見込み額も含めて引当金に一括計上する。
14年3月期の業績予想は据え置いた。連結純利益は前期比54%増の1500億円を予想している。為替相場の円安に加え、三菱重工が65%を出資する「三菱日立パワーシステムズ」の好調が業績を下支えする。野島龍彦取締役常務執行役員は「純利益で1400億~1500億円は達成しうる」と述べた。
三菱重工は02年に建造中の大型客船「ダイヤモンド・プリンセス」で火災事故を起こし、客船受注を一時停止した経緯がある。10年ぶりの大型受注を軌道に乗せ、客船事業を収益の柱に育てる方針だったが、建造する2隻以降の受注計画についてはいったん白紙になる可能性もある。
内航海運(日本国内での海運業)業界の船員不足が半端ではないからだ。
日本国内の船員のうち海運業に携わる者の数(船舶所有者に雇用されている船員)は、1980年の101,633人から減少し続け2012年現在では29,427人。3割程度に減ってしまった。この数に外国人船員は含んでいない。
日本の産業界における海運業は、重要な位置を占めている。2012年の貿易量は、トン数ベースで9億6,300万トン。その99.7%を海上貿易が占める。内航海運(日本国内での海運)についてはトン数ベースで3.6億トンと、全体貨物輸送量の7.3%を占めるに留まるが、輸送量に輸送距離を乗じた輸送活動量ベースで見ると1,749億トンキロと、全体の40.7%を占めるようになる。
これは内航海運が、鉄鋼、石油、セメントなどの産業基礎資材の長距離・大量輸送を多く担っているためである。
「海運業は日本経済を支える大きな産業。衰退していけば、国民が困る。何としても後継者を育てたい。進水式に子どもを招待するなどして海運業のイメージアップを図り、船員に憧れる若者を育てたい」とA社長。
このように海運業の船主たちは、切実な課題に取り組もうとしている。その一方で、福岡市では港湾局で不祥事が発生し、船を迎える港のイメージを低下させている。これでは船主たちの苦労も台無しだ。観光船の受け入れを望む福岡市にとって海運業は関係ないと言いたいかもしれないが、同じ海に携わる業界のものとして、足を引っ張ることだけは止めて欲しい。
【黒岩 理恵子】
The story of ‘Flag of Convenience’ (FOC) ships is well known. Merchant ships engaged in international trade are registered by their owners in countries that exercise minimal or no regulation over them, resulting in substandard pay and working conditions for crews, poor safety standards, involvement in arms, people and drugs smuggling, and disastrous environmental impacts. Recent changes in Australian shipping law may go some way to mitigating the FOC problem.
The Shipping Registration Amendment (Australian International Shipping Register) Act 2012 (Cth) amended the Shipping Registration Act 1981 (Cth) to provide for the establishment of a new Australian International Shipping Register. Stated objects of the reform included:
• providing an alternative to offshore registration of Australian-owned ships involved in international trade;
• promoting Australian shipping growth and involvement in international trade; and
• ensuring the viability of the Australian shipping industry, including by strengthened regulation and enforcement of seafarer employment conditions, and safety and environmental standards.
The Australian Maritime Safety Authority is the regulatory authority, including in relation to labour standards.
Section 12(1) of the Shipping Registration Act 1981 (Cth) requires that all Australian-owned ships are registered under the Act. As well as the international register, there is also the Australian General Shipping Register (but a ship cannot be registered in both registers). The owner/s of Australian ships are guilty of an offence if their ship is not registered and the ship is liable to detention until registration is effected.
The establishment of the Australian International Shipping Register was made against the background of globalisation and an expansion of Australian ship-borne commodity trade. This context has both encouraged and facilitated the growth of the FOC phenomenon. Under the pressures of heightened international competition and with the facility provided by a more open global economy, shipowners have increasingly sought registration for their ships in FOC countries – Panama and Liberia being two of the more notorious FOC states.
The advantages of registration in an FOC state – for shipowners – include low registration fees, non-existent or little taxation, and the ability to employ labour cheaply. The lack of effective control by the registering state has also meant that FOC ships have not met acceptable standards. For example, they have been responsible for a number of high-profile oil spills. Legal anonymity for the shipowners and therefore their avoidance of criminal and civil liability is another FOC outcome.
With regards to the protection of the labour conditions and rights of seafarers, it is noted that a ship is not allowed to be registered on the Australian International Shipping Register if a collective agreement has not been concluded between the shipowner concerned and the crew’s bargaining unit (Shipping Registration Act 1981, s 15F(3).)
Registration is one of the topics examined in the updated The Laws of Australia Subtitle 34.3 “Shipping” .
The latest order comes from a Taiwanese shipowner Wisdom Marine and is for two 81,700 dwt bulkers.
According to Wisdom Marine, the total contract price for the two vessels is not to exceed $70 million.
Other details of the contract like the delivery date and vessel particulars were not disclosed.
SBT Staff, February 28, 2014
A team of prosecutors and investigators obtained computer hard drives and confidential documents such as accounting books from the offices, including the group's headquarters in central Seoul, to corroborate the charges, prosecutors said.
"The raid was conducted after the company requested the investigation regarding inside corruption," said an investigator of Seoul Central District Prosecutors Office.
STX Group, once the country's 13th-biggest conglomerate with a total of 10 affiliates under its wing, has seen its major affiliates struggling from liquidity shortages and mounting debt due to the downturn in the shipbuilding and shipping sectors.
Kang Duck-soo, the chairman of the group, resigned from the top posts of STX Offshore & Shipbuilding Co., the group's shipbuilding arm, and STX Pan Ocean Co., the country's leading bulk carrier, last year.
(END)
同社は、1970年5月に設立された内航船舶貸渡業者。旭丸(499トン、貨物船)1隻を所有、大手海運会社のチャーターで運航し、鋼材やスクラップなどを輸送、ピーク時には売上高2億円を売り上げていた。
しかし、船舶が老朽化し用船料の値下げが続いたため06年に売却し、所有船舶のない状態となった。その後、同社に在籍する船員を関係会社に派遣し、手数料によって借入金利の返済を続けてきたが、先行きの見通しが立たないことから、債権者、金融機関と協議のうえ、今回の事態に至った。負債は2億3000万円、うち金融債務は9000万円。
KDB losses may surpass W1 tril.
By Kim Rahn
The Korea Development Bank (KDB) may see more than 1 trillion won ($933 million) in losses for 2013, largely due to huge loan-loss reserves for financially troubled conglomerates, the chief of the bank said.
Hong Kyttack, CEO of the bank and chairman of the bank’s parent company, KDB Financial Group, said Tuesday the policy lender’s net losses for last year may surpass 1 trillion won, although the exact amount will come out in March.
“We had to set aside larger-than-expected loan-loss reserves as many large companies fell into financial troubles last year, including STX Group,” he said at a media briefing at the bank’s building in Seoul.
The chairman added that the bank also had losses from its stake in Daewoo Engineering & Construction (E&C).
“We acquired Daewoo E&C in 2010, and the firm’s stock price kept falling amid a slump in the construction industry. We have to write it off as losses, and the amount is huge,” Hong said, not elaborating on the amount.
KDB bought the builder’s stocks at around 15,000 won per share at that time, but it is now 7,400 won.
However, he expected some 600 billion won in net earnings this year from reduced loan-loss reserves, more interest income and stronger risk management.
Hong also denied the allegation that Daewoo E&C attempted accounting fraud to cover huge losses and KDB was aware of it.
It was alleged that Daewoo E&C has hidden some 1.4 trillion won of losses and planned to write it off by cooking accounting books for five years through 2017. The Financial Supervisory Service has been investigating the suspicion following a tip.
“It was not confirmed losses, but an estimate of possible losses the builder may see if problems occur with its future or ongoing construction projects. The KDB examined the report as well and discussed with the builder how to minimize the potential losses,” he said. “It is a scenario drawn up for risk management.”
For affiliates of STX Group, of which the KDB is the major creditor, Hong said STX Pan Ocean’s court receivership programs are well carried out, while four other subsidiaries are under debt rescheduling.
“In case of STX Offshore and Shipbuilding, the company’s executives provided insufficient and distorted information about its financial condition. So we had to re-inspect the condition and found the actual debts were larger than first known. We are redrawing new workout plans with other creditor banks,” he said.
The lender is also supporting major conglomerates’ self-help schemes to resolve liquidity shortages, including Dongbu, Hyundai and Hanjin groups.
Hong said the bank is preparing the planned re-merger with the Korea Finance Corp., which was spun off from the KDB in 2009, although the passage of the revision bill is being delayed in the National Assembly.
1973年に設立の同社は、外航海運不定期航路事業を手掛け、中国・韓国・東南アジア向け建設機械や重機・自動車の運搬を主力に事業を展開し、福岡のほか東京・大阪に拠点を開設するなど事業を拡大していました。
しかし、景気低迷による荷動きの落ち込みや東日本大震災の影響で業績が悪化すると、多額の借入金が資金繰りを逼迫したため、これ以上の事業継続は困難と判断し今回の措置に至ったようです。
信用調査会社の東京経済などによると、負債総額は約21億円の見通しです。
同社は、1973年(昭和48年)3月に関係会社が所有する船舶の運営・管理事業を目的に設立。その後、一時休眠期間を経て、99年8月に有村産業(沖縄県那覇市、99年6月会社更生法)の外航貨物海運事業を引き継いだ。自動車やトラック、建設機械などの車両運搬を主体に、工業製品や原材料、穀物、大型プラントなどの海上輸送サービスも展開。
台湾、香港のほか、ベトナム、中国、タイ、シンガポール、マレーシア、フィリピンなど東南アジアへの航路を増加させ、ピーク時にはRORO船など5隻を稼働し、08年9月期は年売上高34億8900万円を計上した。
しかし、リーマン・ショック後の世界的な景気低迷に加え、11年3月に発生した東日本大震災の発生に伴う荷動きの停滞から、12年9月期の年売上高は18億円までダウン。この間、稼働する船舶を3隻まで減らすなどでコスト削減を図っていたが、海外資本の海運業者との競合や、燃料費高騰、為替変動などの影響もあって欠損計上を余儀なくされていた。
こうしたなか、管理船舶への投資資金など多額の有利子負債が重荷となり、資金繰りがひっ迫。返済条件緩和などの金融支援を受ける一方、海外新市場の開拓や内航航路への進出も模索していたが、奏功せず、今回の事態となった。帝国データバンクでは「負債は債権者73人に対し、21億円が見込まれる」としている。
Japan oil buyers were the hardest hit by the shipping insurance limits in Western sanctions because they chose to continue to use Japanese tankers for deliveries.
India, South Korea, and China, at least partially, all began relying on Iranian shippers and insurance providers for their oil deliveries from Tehran.
The international P&I club, of which JPI is a member, resumed normal coverage of $7.6 billion per ship, including $1 billion for oil spills, on Monday as European Union reinsurance became available again for the first time since mid-2012, a JPI official said.
That means Japanese buyers of Iranian oil will not have to rely on Tokyo's sovereign scheme to provide the same level of liability coverage for tankers carrying the crude.
"The resumption of cover is very much restricted to that which is expressly permitted under the implementing EU and U.S. measures," Andrew Bardot, executive officer of the International Group of P&I clubs, said separately.
"It does not fully open up the trade or the insurance of the trade. It is restricted to current importers based on their import quotas and it is for six months only."
Specialist Protection & Indemnity insurers, mutually owned by shipping lines, dominate the market for insuring ocean-going vessels against pollution and injury claims, the biggest costs when a tanker sinks.
Japan temporarily halted its Iranian imports in July 2012 to avoid running afoul of the shipping and insurance sanctions, waiting for the government's $7.6 billion sovereign liability guarantee per tanker to keep oil trade with Tehran going.
Buyers in India and South Korea said they are still waiting for further information from insurers and their governments before making any changes to how they have been receiving Iranian oil under the sanctions regime.
SOVEREIGN SCHEME TO STAY FOR NOW
Japan's sovereign scheme will stay in place for the time being, but will no longer be liable for insurance payments now that buyers can obtain JPI coverage, a government official said.
The government is not ready to scrap the sovereign scheme just yet, as the sanctions relief is regarded as temporary, the official said.
Japan's parliament would have to authorize any extension of the scheme past the fiscal year ending March 31.
The easing in U.S. sanctions will allow Iran's six current customers - China, India, Japan, South Korea, Taiwan and Turkey - to maintain their purchases at the current reduced levels for the six-month duration of the interim nuclear deal between Iran and world powers, the U.S. Treasury Department said.
Japan's Iran crude imports will likely stay steady in the short term following the easing of sanctions and the switch in insurance providers, Yasushi Kimura, president of the Petroleum Association of Japan told reporters on Monday.
Japan's imports of Iranian oil in January-November 2013 fell by 4.6 percent from a year earlier to 178,539 barrels per day (bpd), trade ministry data showed last month.
Japan's Iranian crude imports in 2011, before the tough sanctions were put in place were 313,480 bpd. Japan cut its Iran imports by nearly 40 percent in 2012.
帝国データバンクによると長栄海運は、笠岡市の旅客海運業者が事業多角化の一環として、1964年9月に設立された内航貨物運送業者を88年10月に買収し、事業を本格化した経緯がある。
90年代に入って船舶の購入・建造を積極的に進め、ピーク時にはLPG船1隻を含む7隻を運航、95年10月期には売上高8億円を計上していた。
しかし、景気の低迷を反映して荷扱い量の減少、用船料の引き下げなどで業績が低迷し、02年10月期の売上高は6000万円までダウン、船舶の購入・建造資金の借入金が重荷となって厳しい資金繰りを余儀なくされていた。
この間、船舶の売却や人員削減などによる合理化を進めていたものの収益性は改善せず、02年11月に海運事業を停止の後、社有不動産の賃貸・管理業務に事業転換して賃貸収入で借入金を返済していたが、前代表がことし7月に逝去したため、今回の措置となった。
笠興海運は、71年設立の海運業者を笠岡市の同旅客海運業者が88年頃に買収したもので、長栄海運のグループ会社として貨物船2隻を運航していたが、同社の業績低迷に連動して事業の継続が困難な状況に陥っていた。
負債は、長栄海運が33億7100万円、笠興海運が9800万円、2社合わせて34億6900万円。
経済危機直撃で中小造船所の連鎖倒産...政府は無対策で一貫
ユン・ジヨン記者 2012.04.27 16:05
世界1位の韓国造船業が没落の道を辿っている。
統営地域を中心とする中小零細造船所の連鎖倒産が予告されており、数万人の 造船業労働者が路上に追い出されている。
ヨーロッパ発の経済危機と中国との低価格受注競争で、すでに2010年から造船 産業には赤信号が灯っていたが、政府は今まで明確な対策を出さずにいる。 昨年は韓進重工業の整理解雇事態を味わい、造船業全般の危機が表面化したが、 結局、中小零細造船所の連鎖倒産が現実になり、造船業労働者の悪夢は本格化 している様相だ。
中小零細造船所、連鎖倒産の危機
2月、統営の中小造船会社、サモ造船が清算手続きに入った。全般的な造船景気 の沈滞で、昨年4月、法定管理を申請したが、結局一か月で不渡りになり工場の 門を閉じることになった。
サモ造船は1~2万トン級タンカーを建造する会社で、2000年代中盤までは500人 ほどの職員が働き、受注残高基準世界100大造船所として好況を享受してきた。 だが最終的に不渡りになった2月、サモ造船で働く労働者は80人だけだった。
サモ造船の不渡りは、統営地域の中小造船所の連鎖倒産を警告する信号弾だっ た。統営地域の別の中小造船所である21世紀造船とシナSB、ソンドン造船など も連鎖倒産を控えてきわどい綱渡りをしている。
21世紀造船は6月で建造物量が枯渇し、清算型法定管理を目前にしている。統営 最大の造船所であるソンドン造船海洋は、構造調整を前提に債権団が資金支援 を検討している。セッコ重工業などは結局作業場を暫定的に閉鎖した。
シナSBも、すでに多くの労働者が現場を離れ、残る労働者も一部仕事を止めた。 シナSBは2008年から4年間、一隻の船も受注できなかった。現在建造作業をして いる船舶4隻も、9月には作業が終わる。12月はウォークアウトが終了する時点 で、破産が目前の状況だ。
シナSB支会のチョン・ギョングク副支会長は「物量が少なくなり、4000人近い 労働者の半分以上が現場を離れ、現場に残っていても仕事がないパートが続出 しており、現在150人ほどの労働者が仕事を止めて待機している」と説明した。
賃金未払いも本格化した。チョン・ギョングク副支会長は「4月25日、管理職の 給与中断を始め、現場職の給与と賞与金中断が行われる見込み」と明らかにした。
シナSBは産業銀行と貿易公社が持分の70%以上を確保している。だから労働者 は産業銀行でのウォークアウト期間延長により、2014年上半期まで支援を続け れば、2014年から受注により負債を返せると期待している。今年末にウォーク アウト期間が終了するので、ウォークアウト期間延長のために早期に話しあわ なければならない状況に置かれたわけだ。
世界1位造船業没落か...政府無対策一貫
現在、造船景気沈滞に直撃されている造船業体は、船舶完成工程で事業を拡張 した中小企業だ。
彼らは既に韓国のビッグ3造船所の周辺にブロックを形成し、部品工程を担当し てきたが、造船産業の好況期に完成工程に事業を拡張した。
だからまだビッグ 3を中心としてブロックを形成する部品企業は、酸素呼吸器で延命しているが、 事業を拡張した中小零細完成企業はヨーロッパ経済不況と中国との低価格受注 競争などで工場の門を閉じる状況に置かれた。
中小零細造船所は連鎖倒産の危機に苦しんでいるが、韓国のビッグ3造船所は、 まだ健在だ。サモ造船が清算手続きに入った2月14日、現代重工業とSTX造船海洋 は、大規模液化天然ガス(LNG)船の受注を勝ち取った。
大宇造船労働組合のソン・マノ委員長は、「ビッグ3は中国が作れない海洋プロ ジェクト事業などの技術力を確保している」とし「だが中小事業場はこうした 技術力がなく、中小型船舶で競争をしているので、ヨーロッパの経済危機で物量 の削減と中国との低価格受注競争に押され、破産が続く状況」と診断した。
こうした状況でも政府の対策は何もない。ソン・マノ委員長は「中国は、国家 で造船業を戦略事業として育成し、技術力と財政など多くの支援をしているが、 世界1位をかろうじて守っている韓国政府は造船業の危機の中でも、何の対策も 用意していない」と指摘した。
そのため金属労組造船分科委員会は、3月22日、国務総理室に2012年対政府3大 共同要求とし、△総雇用(非正規職含む)保障、△造船産業発展戦略委員会(労使政 対話機構)、△中小造船所支援対策作りを伝えた。
続いて関連政府部署の知識経済部に面談を要請して、4月12日に果川政府庁舎で 自動車造船課長と金属労組造船分科代表者の参加で面談を開いた。だが政府側 からはまだ公式の回答はない。
ソン・マノ委員長は「韓進重工業のスービック造船所移転により打撃を受けた 労働者とシナSB、サモ造船、ソンドン造船、21世紀造船などの労働者まで数万 の労働者が路上に追い出されている」とし「2010年には予想されていた造船 不況に政府は無対策で一貫してきたので、今は政府と企業が労働者の雇用と 造船危機を打開するための三大要求を即刻施行しろ」と強調した。
検察捜査で確認された納品業者の上納額が現在まで50億ウォンに達する。
起訴された造船業者と納品業者役職員数も40人余りもなる。 検察は大型造船業者職員の金品授受が組織的·慣行的になされたと見て捜査を拡大している。協力業者に対する押収捜索と取り引き口座追跡を通じて過去取り引きまでも隅々まで見回している。この過程で検察に起訴される大型造船業者および納品業者職員もまた継続して増えていて捜査結果が注目されている。
造船業界の納品不正が初めて捉えられたことは去る5月だ。 蔚山(ウルサン)地方検察庁特捜部は大宇造船海洋役職員が部品納品や協力業者選定代価で巨額を上納受けているという機密情報を入手した。 以後5ヶ月の間に強力な捜査を行った。 200人余りの口座を追跡した。 大宇造船海洋と納品業者事務室を押収捜索した回数だけ18回に達する。 チェ・チャンホ蔚山(ウルサン)地検特捜部長は“捜査中にも大宇造船海洋と協力業者内部職員の情報提供が続いた”と話した。
結果は検察さえ舌を巻くほどであった。ある役員は“息子が修能を見る”として純金で出来た50万ウォン相当の鍵を要求した。 試験が終わった後には家族の海外旅行経費一切を提供させた。 ある次長級職員は12億ウォン相当の借名口座4個が検察に摘発された。 この中一個が実母名義だったが、捜査官が関係を促すとすぐにこの職員は母子関係を否定したと分かった。
ある役員は協力業者資金の一部を受けて住宅を買いとった後、会社に再賃貸する方法で暴利を取った。 ある職員は1億ウォンの現金を5万ウォン札束で家に保管して検察に摘発されることもした。 検察は10月15日前·現職大宇造船海洋役職員と協力業者幹部30人を起訴した。
大宇造船海洋で始まった納品不正捜査は現代重工業と三星重工業で拡大した。 検察捜査を受けた納品企業等が二つの会社にも巨額を伝達した事実が追加であらわれた。 検察は納品業者選定代価で2億3000万ウォンを受けた疑惑(背任収賄)で三星重工業幹部カク某氏を最近拘束起訴した。
納品請託や納品期間延長代価で協力業者に少ないのは4000万ウォンから、多くて5億ウォンを受けた現代重工業幹部3人も拘束した。
合わせて大型造船業者に巨額の金品を提供した疑惑(背任受財)でH社とL社代表パク某氏とイ某氏も拘束起訴した。
監査機関のある関係者は“わいろで受けた金額が大きい点を考慮する時組織的に関与した可能性がある”として“上納の輪がどこまで連結されるのか捜査していると知っている”と話した。
大宇造船からサムスン·現代重工業へも‘飛び火’
検察に名前が上がってはこれらの企業らは一様に“全く知らないことだ。問題があるならば職員個人のこと”と否認した。三星重工業関係者は“検察調査は私たちも知らないことだ。(検察で)どんな通知も受けた事実がない”と話した。事実関係を確認した後、再び返事をすることにしたがまだ連絡がこないでいる。 現代重工業関係者は“会社ではその間、倫理経営を制度的に定着させるためにグループ次元の努力を広げてきた”として“今回検察に不正が摘発された職員は3~4年前に内部監査で不正が摘発されて懲戒を受けた”と説明した。
一部職員は検察捜査渦中にも協力業者で金品を受けたことが明らかになって衝撃を加えている。 検察によれば現代重工業・パク某次長は今年2月まで配電盤部品納品請託と共に協力業者代表から1億2000万ウォンを受けた。 パク某次長の場合、大宇造船海洋の納品不正捜査が真っ最中だった今年10月までにも合計5億ウォンを受けた疑惑を受けている。
財界では“造船業界のモラルハザードが深刻な水準”と指摘した。一例としてサムスングループはその間内部規律確立を強調してきた。サムスンは大小の問題がふくらむたびに再発防止とともに内部規律確立方針を発表した。サムスン電子、華城(ファソン)工場のフッ酸漏出事故が起こった今年のはじめには系列会社代表理事および役員評価に遵法経営結果を反映すると明らかにした。
だが、今回三星重工業職員不正が検察に摘発されながら遵法経営意志が見るべきものがなかった。三星重工業は去る3分期に売り上げ3兆5757億ウォン、営業利益2085億ウォンを記録した。
売り上げは昨年同期より12%減ったし、営業利益は40%近く急減した。このような理由で年末要人を控えて‘パク・テヨン社長更迭説’が出回ることもした。 12月2日発表された社長団人事でパク社長の留任が決定されたが内部職員が納品不正にかかわりながらパク社長の位置づけも狭くて入るものと見られる。
倫理経営明らかにしたが‘空念仏’
現代重工業でも今年の初めから役職員不正が絶えなかった。 去る5月電機電子システム事業本部役職員25人が下請け業者7ヶ所から10年の間25億ウォンを受けた疑惑で司法処理された。 7月には原子力発電所納品不正と関連して10億ウォン台の資金を韓国水力原子力幹部に伝達して役職員3人が拘束された。
現代重工業は11月末グループ法務監査室長を受け持っているイゴンジョン副社長を社長に昇進させた。 倫理経営強化のための布石と解説される。 イ・ジェソン現代重工業社長も11月21日社長団人事で副会長職を経ないですぐに会長に昇進した。 同じように財界では責任経営と遵法経営を強化しようとする意図で見ている。 イ・ジェソン会長は就任辞で“透明な経営に対する社会の要求が高まっている”として“国際的基準に合う倫理経営のための努力を強化する”と明らかにした。だが、原子力発電所不正に続き協力業者納品不正までさく烈しながらグループ イメージに少なくない打撃を受けることになった。 造船業界関係者は“国内ビッグ3朝鮮3社中で今年売り上げ減少が予想される所は現代重工業が唯一だ”として“実績悪化に続き納品不正までさく烈しながらイ・ジェソン会長のリーダーシップがいつの時より重要になった”と話した。
造船株、‘みにくいアヒル’から‘白鳥’に変身
造船業界一角ではせっかく生き返った造船景気が”検風”の影響を受けないだろうか憂慮している。国内造船業界は2008年近づいたグローバル金融危機の直撃弾を受けて最近難しく復活に成功した。2013年9月末を基準として発注量は8000万DWT(財貨重量トン数)を記録した。 2012年全体発注量(5400万DWT)をふわりと越えた。 造船業界状況を計ることができる新造船価指数も反騰に成功した。 チェ・グァンシクLIG投資証券責任研究員は“世界経済回復期待感で2013年多くの船舶発注と新造船がターンアラウンドに成功した”として“来年にもヨーロッパと中国の景気回復が予想されて展望が良い方”と話した。
その間‘みにくいアヒル’の取り扱いを受けてきた証券市場でも造船株は‘大事な’接待を受けている。
12月6日基準としてコスピ指数の最近1年間上昇率は1.84%に終わった。だが、三星重工業(-0.27%)を除いて大宇造船海洋と現代重工業はそれぞれ41.27%と19.3%上昇した。 去る10月中旬以後造船株が市場で調整を受けている。 以前までだけでも三星重工業やはり20%台の高い株価上昇率を見せた。 外国人と機関は低評価されていた造船株を買い物かごに掻き集めるのに忙しかった。 イ・ドングン投資諮問本部長は“造船株中心の景気を敏感な大型株でポートフォリオを構成している”として“来年まで造船株比重を20~30%台で維持するだろう”と話した。
去る9月さく烈した不良事態で苦労したSTXグループもやはり経営正常化手順を踏んでいる。債権団方針により造船グループ(STX造船海洋·STXエンジン·STX重工業·ポステック)だけ残して残りは空中分解される状況だが会社は新規資金を支援されて正常化踏み台を用意できると展望される。 造船グループの核心であるSTX造船海洋はすでに主債権銀行である産業銀行が最大株主(17.16%)にのぼった状態だ。 産業銀行は最近チョン・ソンニプ前大宇造船海洋社長を新任代表で内定して新たな編成に出た。 残りの会社やはり債権団の出資転換や有償増資等を通して経営正常化手続きに突入した。 近い将来STXグループまで正常化すれば国内造船産業はより一層活気を帯びると予想される。
だが、大宇造船海洋に続き現代重工業、三星重工業などで検察捜査が拡大しながら不安感が大きくなっている。 検察は現在の捜査内容に対する公式的な言及を敬遠しているけれど金品授受疑惑で起訴される造船業者役職員数は継続して増えている。 ある造船業者関係者は“造船業界のリベート慣行に対する検察捜査はかなり以前から予想されてきた”としながら“今後海外競争会社との入札で不利益を受けないだろうか心配”と憂慮した。
(翻訳:みそっち)

佐々木造船(広島県大崎上島町)が、液化石油ガス(LPG)の運搬船の受注を急増させている。2012年末まで4年余り受注がなかったが、今春以降は内定を含め7隻。米国の「シ...
立石海運は、1958年創業、68年12月に法人改組した内航海運業者。北九州市の海運会社の専属下請けで2隻の船舶を運航、建材などを運搬し、90年12月期には2億5000万円の年収入高を計上していた。
泰洋汽船は、83年3月に立石海運の関連会社として設立した内航海運業者で船舶を1隻保有し、運航していた。
しかし、近年は不況による荷動き低下や原油価格の高騰により両社とも収益が悪化していたうえ、両社の経営を支えていた前代表が12年4月に死去したこともあり、同年末までに事業を停止し、今回の措置となった。
負債は、立石海運が7億3000万円、泰洋汽船が6億8000万円で、2社合わせて14億1000万円。

The 28,450-dwt Da Cui Yun has the capacity for 1,735 containers as well as general cargo.
Emails to Coscol, a Shanghai-listed unit of state giant China Ocean Shipping, and Incisive Law seeking comment did not receive replies, reports Lloyd's List.
It said the company is not known to have any cash issues, although Coscol has faced mounting losses in recent quarters due to weak freight rates.
The multipurpose vessel operator posted net losses totalling CNY42.8 million (US$7 million) for January-September, and losses of CNY49.7 million during the same period a year earlier.
Cash reserves stood at CNY1.7 billion as of September 30, significantly lower than CNY4.3 billion at the start of 2013.
In 2011, several bulk carriers linked to China Cosco Holdings, the flagship unit of Cosco Group, were arrested in disputes over charter payments with a number of Greek shipowners, including DryShips and the Angelicoussis Shipping Group. The issues were resolved within months, after the carrier reportedly resumed regular payments at reduced rates.

According the Polish government the financial aid was refused, because during the meetings was not presented updated business plan and effective restructure of the company. This means that the birthplace of the movement “Solidarity” may close its doors and go into the history. According to Polish medias, the owners are preparing to declare bankruptcy in the shipbuilding factory during the first month of the new year.
”Once again, the majority owner of the shipyard did not fulfilled its obligations, which further undermined the credibility and collaboration has become even more difficult. We appealed for monthsthe oner to create a realistic business plan for the shipbuilding yard, but now we are powerless. The fuure of the plant is in the hands of the Ukrainian owners”, said the deputy Financial Minister of Poland Rafal Banyak.
負債額は42~45億レで、フォーリャ紙によれば、社会開発銀行(BNDES)と連邦貯蓄銀行(カイシャ)に16億レ、スペイン系のAcciona社と、亜国、イタリアを拠点とする財閥のテチント・グループに10億レの負債があるという。
手続きを申請したのは国内にあるOSXグループ3社(OSXブラジル、OSX造船、OSXオペレーションサービス)。法的な保護が直ちに認められなければ、3社とも再建は不可能との見方が強い。会社更生手続きが適用されない場合のキャッシュフローは2014年4月にマイナス12億レに達するが、適用されればプラス3180万レとなる見込みだ。
従業員への給与の不払いはないというものの、既に100人が解雇され、一部の土地の返却も必要になる。
エスタード紙によればOSX社の会社更生手続きを行うチームは、BNDESが5億4800万レの繋ぎ融資を行う可能性を見込んでいる。これは2011年に同社が契約し、ヴォトランチン銀行が保証したものだ。
ただフォーリャ紙によればBNDESとカイシャからの10億レの融資の返済が2014年10月まで期限を延ばされ、それが民間のヴォトランチン銀行に保証されたという。
再編計画の戦略は、3つの海上プラットフォームを売却することだ。スイスの銀行クレディ・スイスが売却を交渉しているが、これが成功すれば国外向けの負債を完済でき、余剰金をOSX社ブラジルの再建に当てるという可能性も出てくる。関係者によれば、オランダやオーストリアにある国外の子会社については資産額が負債額を上回っているため、会社更生手続きの適用対象にはならないという。
また、リオのポルト・ド・アスー社(EBXグループ傘下)が建設中の造船所の一部を売却する交渉もある。
〃エイケ王国〃が事実上崩壊の一途をたどる中、エイケ氏はここ数カ月でグループ会社のMPX、LLX、MMXの一部を売却した。OGXとOSXに関しては、買い手がつかないために法的な措置に訴えた格好だ。両社あわせて160億レもの負債がある。
OSX社の株価は2010年の資本投入当時は32レだったのがそこから98%下落し、現在は0・5レとなっている。
これは同社が前週末に開いた取締役会で、破産法の適用申請を正式に決定したもので、早ければ11日にも裁判所に破産法の適用申請を行う。その後は28日に開く臨時株主総会で破産法の適用申請の決定について最終承認を得たいとしている。負債総額は23億ドル(約2300億円)で、国営や民間の銀行、サプライヤー(部品・資材供給業者)が主な債権者。
破産法の適用が申請されれば、同社は60日以内に会社再建計画を裁判所に提出しなければならない。しかし、その後、債権者全員が180日以内に再建計画を承認しなければ破産に向けた手続きに移行する。また、OSXはルイス・マルセロ・マイア・ゴメス社長の退任と、その後任にイーヴォ・デヴォルジャック・ソン氏が就任することも明らかにした。
提供:モーニングスター社
By Wu Yiyao in Shanghai (China Daily)
An executive director at China Cosco Holdings Ltd, Xu Minjie, is being investigated by the authorities, the company said on Friday.
The company's shares on the Hong Kong stock exchange declined 5.04 percent to HK$3.58 ($0.46) on Friday, while its shares on the Shanghai bourse were down 3.85 percent to 3 yuan ($0.49).
Cosco said on Friday that Xu is under investigation by "relevant departments" in China without disclosing any additional information about the investigation.
"The board believes that ... the investigation will not have a material adverse effect on the group, and the business and operations of the group remain normal," Cosco's statement said.
Xu, 54, joined Cosco in 1980 and became the vice-president of Cosco Group in 2011. He also served as vice-general manager of Cosco Holdings and general manager of Cosco Pacific.
Media reports said on Thursday that Wei Jiafu, the former chairman of Cosco, is also under investigation and is barred from leaving China as investigations into the group continue.
Wei, who was once the most powerful man in China's shipping industry, was removed from his post in July.
Cosco said in a separate statement on Friday that the rumors targeting Wei are "groundless".
"We firmly implement the Party and the country's anti-corruption rules, and sincerely accept supervision from the public," that statement said.
Cosco, which runs container shipping and port businesses, has suffered losses in the past two years. In the first three quarters of the year, the company recorded a loss of 2.03 billion yuan.
In July, the former general-manager of Cosco's Dalian branch, Meng Qinglin, was arrested for corruption, while in 2011, the former vice-general manager of Cosco's Qingdao branch, Song Jun, was also arrested under corruption charges.
China's latest anti-corruption drive has swept up a series of provincial leaders and corporate executives, including the mayor of Nanjing and officials at PetroChina Co Ltd, one of the country's largest oil groups.
【リオデジャネイロ】ブラジルの資産家エイケ・バチスタ氏が経営する同国の石油会社OGXペトロレオ・エ・ガス(以下OGX)は30日、リオデジャネイロの裁判所に破産法適用を申請した。資金繰りを改善して、直ちに会社整理に直面するのを避けるのが狙い。これは中南米で過去最大の破産となる可能性がある。
破産法申請書類を提出した同社の弁護士は電話取材に対し、OGXが資金繰り問題を解決できると信じていると述べ、「この会社には多くの資産があり、他社とパートナーシップを組むこともできる」と語った。
リオデジャネイロ州裁判所民事部は、OGXから法的会社再建の申請を受理したことを確認した。
同弁護士によると、申請が承認されれば、OGXは60日以内に資金繰り再編計画の提出が義務づけられる。その後、債権者は30日以内に再編計画の承認あるいは拒否を決断する。
OGXは、過去7年間にわたって主としてブラジルの資本市場から何十億ドルという資金を調達し、原油と天然ガスを掘削した。しかし掘削努力に見合う資源はほとんど産出されず、同社は債券について今月30日までにデフォルト(債務不履行)に陥る瀬戸際に立たされ、供給業者への借金返済にも四苦八苦している。
OGXの破産法適用申請に先立ち、バチスタ氏はいわば時間との競争で、自らの一部企業グループのテコ入れを急いでいた。
関係筋によれば、こうした試みの一つとして、バチスタ氏は北東部マラニョン州の天然ガス生産会社OGXマラニョンに新しい投資家を呼び込んだ。OGXはこのOGXマラニョン株式の66.7%を保有し、電力会社エネヴァが残りの株式33.3%を保有しているが、エネヴァの過半数株は、同氏がドイツのエネルギー大手エーオンとともに保有している。
関係筋は、この狙いはOGXマラニョンが天然ガス田への投資資金を供給し続けるか、あるいは一部の資金を債務にあえぐ親会社OGXに供給する、ないしその双方を可能にすることにあったと述べた。
今週初め、エネヴァはOGXが債券でデフォルトに陥った場合にはイタウBBA、モルガン・スタンレー、そしてサンタンデールという銀行3行に2億レアル(約9170万ドル、約90億円)支払うことで合意した。その見返りとして、エネヴァは、ガス田操業会社であるOGXマラニョンに対する親会社OGXの持ち株分(66.7%)を引き取るとされた。
OGXが30日申請した法的再建手続きでは、OGXに対し、直ちに会社整理するのではなく、資金繰りの再編が認められる。
OGXは2007年にバチスタ氏が創設した石油会社で、ブラジル沿岸沖合で石油・天然ガスの探査で何十億ドルもの資金を調達し、そしてそれを失った。昨年、同社の最初の油田が生産目標に到達できなかったためで、バチスタ氏の企業グループ全体が金融危機に陥った。
29日にOGXが公表したデータによると、同社は株式と債券を発行して80億ドル近くの資金を調達した後、現在、推定50億ドル強の債務を抱えている。一方、保有する資産はその半分程度だという。
OGXは供給業者への支払いに四苦八苦しており、ツバロン・マルテロという沖合油田鉱区で生産を開始するのに十分な資金があるかどうか不透明だ。同社が来月中に生産を開始したとしても、成功の保証は全くない。同社の最初の油田であるツバロン・アズール油田は生産開始の際、全く期待に沿えなかった。
OGXの債券価格は現在、1ドルにつきわずか数セントとなっている。同社株式も過去1年間で90%以上下落しており、破産法申請により、サンパウロ証券取引所で(ボベスパ)取引停止とされた。OGZ株は後日取引が再開される可能性もあるが、ボベスパの各指数には含まれない見通しだ。
バチスタ氏は他にも造船会社や港湾管理会社など数多くの企業を保有しており、その株価や債券相場も最近数カ月間に下落した。
実際、サンパウロのBNPパリバ銀行の債券市場ディレクター、ロドリゴ・フィッティパルディ氏は「OGXのケースはシステミック(連鎖)リスクではないので、他の企業にとって資金調達コストに影響はないと思う」と述べ、「これはバチスタ氏の企業グループに絡む極めて特殊な問題だ」と語った。
バチスタ氏の築いた企業帝国(企業グループ)の内部では、最大の影響は造船会社OSXブラジルが影響を受けるかもしれない。同社は親会社OGXが主要な顧客で、OSXブラジルが製造し、グループ傘下の姉妹会社にリースした石油プラットフォームの大口代金の支払いが滞っている。
バチスタ氏の主要な債権者の一つはアブダビ政府系投資会社ムバダラ・デベロップメント社だ。同社は2012年初めにバチスタ氏の企業グループ(EBXグループ)に20億ドル投資することで合意した。しかしOGXの生産が失望続きだったため、ムバダラは7月、投資額を15億ドルに削減し、EBX向け投資に対する追加保証を求めた。
海底油田の掘削現場=OGXサイトより破産法の適用を申請したのは、OGXペトロレオと傘下のOGXペトロレオ・ガス、OGXインターナショナル、OGXオーストラリアの中核3社。負債総額は51億ドル(約5000億円)で、主な内訳は、ブラジル国外で発行された社債が36億ドル(約3600億円)、下請け業者に対する債務は9億ドル(約900億円)、ブラジル金融大手イタウ・ウニバンコなど銀行に対する債務は3億ドル(約300億円)などとなっている。
OGXは自社のウェブサイトで、年末までの事業継続に必要な運転資金は確保されているが、来年3月まで債務返済には2億5000万ドル(約250億円)の新たな資金が必要になっている、と指摘している。
同社は今月1日に資金繰り難のため、債権者との間で債務の再構築をめぐって協議を進めている中、2022年償還の10億6000万ドル(約1040億円)の社債の利払い期日を迎えたが、予定された4500万ドル(約44億円)の利払いを拒否して以降、米スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)や米英フィッチ・レーティングスなど大手信用格付け会社が相次いで同社の格下げを決めるなど、破産は時間の問題と見られていた。
海底油田から船舶への原油積み出し=OGXサイトより破産法の適用申請を受けて、サンパウロ証券取引所(ボベスパ)は同社の株式の売買を停止した。同社の株価は2010年のピーク時の23.27レアル(約1050円)から30日時点でタダ同然の0.17レアル(約8円)まで99.3%も下落し、時価総額で747億レアル(約3.4兆円)も失っている。30日だけで26%も下落した。今後、OGXは60日以内に裁判所に対し、会社再建計画を提示することになるが、その後、債権者全員が180日以内に再建計画を承認しなければ破産に向けた手続きに移行する。
RIO DE JANEIRO (Reuters) - OGX Petróleo e Gas Participações SA (OGXP3.SA: Quote), the Brazilian oil company controlled by former billionaire Eike Batista, sought court protection from creditors on Wednesday in Latin America's largest-ever corporate bankruptcy filing.
The bankruptcy protection request, filed in a Rio de Janeiro court, came after OGX failed to reach an agreement with creditors to renegotiate part of its $5.1 billion debt load. The request marks another chapter in the unraveling of Batista's once high-flying industrial empire, which he has been dismantling in recent months after disappointing output from offshore OGX wells set off a crisis of investor confidence.
If the court approves the request, OGX will have 60 days to come up with a restructuring plan. OGX creditors, which include the California-based bond fund Pacific Investment Management Co (PIMCO), and U.S.-based investment fund BlackRock Inc (BLK.N: Quote), will then have 30 days to endorse or reject the plan.
It is too early to know how long a restructuring could take, but in Brazil's slow-moving judicial system, some bankruptcy proceedings take years. The company's fate could depend on whether OGX, even as it restructures, honors contractual obligations with the government in the oil fields it operates.
An OGX bankruptcy is unlikely to have a significant effect on Brazil's economy. The company is barely out of its start-up phase and produces almost no crude oil, and most of its debt is held by foreign bondholders.
Still, Batista's decline has become a symbol of Brazil's own economic woes. After a decade-long boom in which investors poured cash into Brazil and Batista's enterprises, Latin America's largest economy has been in a rut for three years.
And the fate of sister company OSX Brasil (OSXB3.SA: Quote) depends almost entirely on OGX, whose market value has plummeted by nearly $45 billion since October 2010. Batista created OSX, which had to scale back efforts to construct the largest shipyard in the Southern Hemisphere, to build and lease oil production and service vessels to OGX.
OGX's decision to seek protection from creditors came as no surprise. After missing a $44.5 million interest payment owed to bondholders on October 1, OGX scrambled to restructure its debt before the end of a 30-day grace period or be declared in default on $3.6 billion in bonds.
The process was rocky from the outset, and OGX called off the talks with creditors on Tuesday, leaving a bankruptcy filing as the only viable option to buy it more time.
"We knew it was coming. Even the shoeshine boy told us about this," said Dan Fuss, vice chairman and senior portfolio manager at Loomis Sayles, which oversees $193.5 billion in assets under management, including OGX bonds.
OGX declined to comment.
In its bankruptcy filing, OGX lawyers said the company's 10 billion real (US$4.6 billion) exploration campaign was a high-risk venture and that these risks were clear to investors from the start.
Lower output from its first field and the cancellation of two others was bad geological luck, the lawyers wrote.
"Once we restructure our debt and make our capital structure adequate, OGX will have a prosperous future, able to generate wealth for its shareholders, workers, creditors and for Brazilian society," the filing said.
A renowned dealmaker who once boasted he would become the world's richest man, 56-year-old Batista has seen his personal fortune reduced by over $30 billion in the last 18 months as investors punished the share price of his listed companies.
The downward spiral forced Batista to start breaking up his Grupo EBX conglomerate, which also included a port operator, mining and energy interests, and an entertainment company.
RACING TO PUMP OIL
Brazil's 8-year-old bankruptcy law is similar to U.S. Chapter 11 proceedings, and gives OGX a chance to reduce its liabilities and emerge as a going concern. Bondholders will play a key role in the process, though in recent cases - such as those of power companies Celpa SA and Grupo Rede Energia SA REDE3.SA - some creditors complained that judges privileged the claims of state-owned banks over theirs.
Indeed, bankruptcy cases have not always moved smoothly through Brazilian courts and some judges have been sympathetic to pressure from different stakeholder groups like employees, pensioners and shareholders, at times putting their interests above those of creditors, said Paulo Rabello de Castro, head of SR Rating, a Brazilian credit rating agency.
Investors worldwide will be watching as the OGX proceedings unfold. If bondholders feel they are not treated fairly in the restructuring process, foreign investors may think twice before investing in other Brazilian companies, analysts say.
PIMCO and Blackrock declined to comment. PIMCO held nearly $387 million worth of OGX bonds in registered funds at the end of June, according to the latest data provided to Lipper.
OGX is racing to start output at its offshore oil field Tubarão Martelo field by the end of November, its best hope for a source of revenue. Failure to get Tubarão Martelo producing will make it harder to find an investor to buy all or part of the field and could lead to the breaking of contractual obligations to Brazil's oil regulator, the ANP.
While the ANP has said a bankruptcy filing would not automatically cause OGX to lose its production leases and exploration rights, it stressed that any failure to meet the conditions of these contracts would result in their loss. That would strip OGX of any chance of generating future revenue.
The company needs about $250 million of debt or equity financing to keep operating through April 2014, it said in a recent presentation to bondholders. Without new financing, OGX said it would run out of cash in the last week of December.
During talks, OGX and the bondholders discussed a potential $150 million credit line aimed at funding the company's exploration campaign for a few more months. But there was disagreement over Batista's plan to have bondholders convert debt into equity as well as the terms of his potential departure from the company, sources told Reuters last week.
Bankruptcy judge Gilberto Faria Matos will have to decide if output from Tubarão Martelo and other offshore and onshore areas are sufficient to keep the company operational and allow for some repayment to creditors.
The main sources of revenue for a future OGX would be its share of $17.2 billion of offshore oil and natural gas revenue from its Tubarão Martelo field and BS-4 block, the company said in the bankruptcy filing.
"I think there is some value in OGX's offshore assets," said an oil executive who has seen geological data about OGX's prospects and fields. "If the price is right I think someone may well buy them and that they could produce pretty well."
FROM RECORD IPO TO BANKRUPTCY
OGX was founded in 2007 and raised $1.3 billion from private investors to buy oil concessions in November of the same year, a month after state-run Petroleo Brasileiro SA (PETR4.SA: Quote), or Petrobras, announced the discovery of a giant offshore oil province south of Rio de Janeiro.
Seven months later, Batista raised 6.7 billion reais ($4.1 billion) for OGX in an initial public offering in what was at the time the biggest IPO in Brazilian history.
A year after that he was drilling wells. A period of rapid success in finding oil led OGX to briefly outstrip Petrobras as the most successful explorer in Brazil by strikes registered.
OGX pumped its first oil in January 2012, but by mid-year it became clear that the field would not produce near expectations and the company's stock began a drawn-out decline.
In the last year alone, OGX's share price has plunged about 95 percent, making it the worst performer on the BM&FBovespa Stock Exchange's main index .BVSP.
The case is docket number 0377620-56.2013.8.19.0001, in the 4th Section of the Corporate Division of the Justice Tribunal of Rio de Janeiro State.
($1 = 2.19 reais)
(Additional reporting by Jennifer Ablan in New York; Writing by Todd Benson; Editing by Gerald E. McCormick and Richard Chang)
先進的な技術・運営ノウハウを提供して相互振興をはかる
三菱重工業株式会社、今治造船株式会社、株式会社名村造船所、株式会社大島造船所および三菱商事株式会社の5社は22日、ブラジルの大手造船会社エコビックス-エンジェビックス社(ECOVIX-Engevix Construções Oceânicas S.A.:エコビックス社)に資本参加することで合意し、株式購入契約を締結しました。ブラジルの海底油田開発のさらなる発展を目指す国内産業育成策に沿い、先進的な技術や運営ノウハウを提供することで日伯造船業の相互振興をはかっていくのが狙いで、同国の造船事業に日本の造船会社と商社が連合して出資する初めての案件となります。
日本連合は、三菱重工業をコンソーシアムリーダーとして、5社が現地に設立する特別目的会社(SPC:JB MINOVIX INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.)を通じてエコビックス社株式のうち30%の出資参画を果たし、エコビックス社の経営に参画します。日本連合のSPC内における出資比率は、三菱重工業が約半分で残りが他の4社による出資となり、ブラジルの独占禁止法管理当局からの許可が下り次第出資を完了する予定です。
契約調印は東京において、日本とブラジルの関係当局出席のもとで、エコビックス社および三菱重工業、ならびに今治造船、名村造船所、大島造船所、三菱商事の6社により行われました。
エコビックス社は、エンジニアリングや発電などを幅広く手掛けるジャクソン(JACKSON)グループの傘下にあります。同グループはエコビックス社のほか、ブラジルの大手エンジニアリング会社であるエンジェビックス社(ENGEVIX Engenharia)、クリーンエネルギー発電会社のデセンビックス社(DESENVIX)、インフラ関連の運営を手掛けるインフラビックス社(INFRAVIX)を統括する持株会社です。エコビックス社は2010年、ブラジル国営石油公社ペトロブラス社向けに、沖合のプレソルト層油田から石油を採掘する同国のプログラムをサポートするFPSO(洋上浮体式生産・貯蔵・積出施設)船体8隻を建造するために設立されました。2012年8月には、ブラジル政府向けにドリル船3隻を受注しています。
同社はラテンアメリカで3番目に大きな年金基金のFUNCEF(Fundação dos Economiários Federais)と共同で、南部のリオグランデ・ド・スル州(Rio Grande do Sul)にある造船所(持株会社名:RG ESTALEIROS)を運営。同造船所は従業員5,000人強で、2,000トンのガントリー・クレーンを備えた国内最大のドライドックを持っています。
プレソルト層に埋蔵されている石油はここ数十年で最大の発見で、埋蔵量確認とその採掘には技術的課題がありましたが、ペトロブラス社はこの課題の克服に成功しました。ブラジルは数年後にはこの石油を国内消費するだけでなく輸出することを計画しており、埋蔵量探査とその後の石油生産は、今後20年にわたる国家計画の重要な部分を占めています。
こうした背景からブラジルでは、新技術の導入および造船業を含めた地場産業の育成が進められる一方、沖合のプレソルト層の油田を開発・掘削するためのドリル船やFPSOをはじめとする各種船舶・海洋構造物の需要が増大しています。
日本連合5社は資本参加を通じて、沖合での安全な石油生産に不可欠な各種設備の品質向上や納期短縮などの技術でエコビックス社に協力することにより、ブラジルの国家戦略にも貢献。併せて、日本の優れた造船所経営手法や、船舶・海洋構造物に関する先進技術を幅広く提供することで、ブラジル第一位の造船会社を目指す同社を強力に支援していきます。
Privinvest, owned by Iskadar Safa, does not seem to want to yield and, according to sources, intends to allow the shipyard to fail, requesting through international arbitration compensation from the Greek government to the amount of 1.4 billion euro.
If the shipyard closed permanently, Greece would lose its largest shipbuilding company, which will seriously affect the entire economy, and perhaps its submarines (there is no alternative for building them in another shipyard) which are considered as key regarding the national defence. Moreover, the Greek side has so far paid 2.3 billion euro for the submarines and has not received anything in return, and 1,200 people will lose their jobs.
Both sides have financial differences in connection with the continuation of the construction of the six submarines, which have been left in the shipyard. Iskadar Safa requested more than 200 million euro to restart the construction works, assuring that he would be able to gradually resume other commercial activities beyond the Greek navy, based on the decision on the supply of military equipment issued in 2010.
In early summer, the Greek government was willing to pay 75 million euro but its proposal was not accepted. Over the past two months, it seemed that the development of the negotiations would be positive but, according to sources from the Ministry of Defence, more issues than initially agreed were posed literally at the last moment.
Since the shipyard seems ready to come to an end, the Greek government, which has seen major companies closing or moving their headquarters over the past two years, actually has two options. The first is to request the owners of the shipyard to pay a fine of over 550 million euro, since the condition for the company to avoid paying a fine was the fulfilment of all the terms set in the decision of 2010. In this case, the shipyard will go bankrupt, the state will claim its movable property and will endeavour to offer the company for privatization again.
However, the fact is that the completion of this procedure, if it succeeded, would take many years, which will actually destroy the shipbuilding industry of Greece.
The second option for the Greek government is to sell one or two submarines which will allow it to finance the construction of the rest and then subsequently to proceed to the establishment of a single body of the shipbuilding industry of Greece, bearing in mind the fact that all in the industry approve the idea of creating such a single body.
Clear position
The intentions of the shipyard’s owners to the Greek government are declared in a letter to the company's employees. "There are no clear signs that the issue will be addressed immediately but we continue to hope, and we are ready to examine exhaustively all options for finding a fair solution which will ensure the shipyard’s future and viability", states president and CEO of Privinvest Boulos Hankach, and adds, "As you know, our gradual isolation from any action on the one hand, and the fatal collapse of the workload due to deliberate non-payment by the contracting authority on the other, have brought us to financial collapse."
The employees
The employees in the shipyard, in turn, have started protests in order for them to receive answers from the Greek state. According to recent information, they had been asked to show patience for about another 15-20 days. However, the Ministry of Defence which has undertaken the negotiations has continuously been suggesting this in recent months.
1896(明治29)年、川崎造船所が修繕船の受注拡大を目指して着工。地盤が弱く、工事は難航したが、約1万本に及ぶ松の木のくいを打ち込んで基礎を固め、ふんだんに御影石を張った。完成当時の大きさは長さ130メートル、幅15・7メートル、深さ5・5メートル。船舶を大量に修繕し、同社発展の礎となった。
阪神・淡路大震災でクレーンが倒壊し使用を中止。歴史的価値が評価され、98年に登録有形文化財となり、2007年に近代化産業遺産に認定された。
川重が閉鎖を決めたのは、このままの状態では事業に活用できない上、「維持しておくのが困難になったため」としている。
埋め戻した後、跡地は駐車場や資材置き場、工場設置などの利用を検討する。川重は10月22日にOBら関係者を招き、式典を開く。(佐伯竜一)
【ドック】 船の修繕・建造施設。川重神戸工場の第一号ドックは「乾ドック」というスタイルで、出入り口が海に面しており、海水をポンプで入排水して船を出入りさせる仕組み。
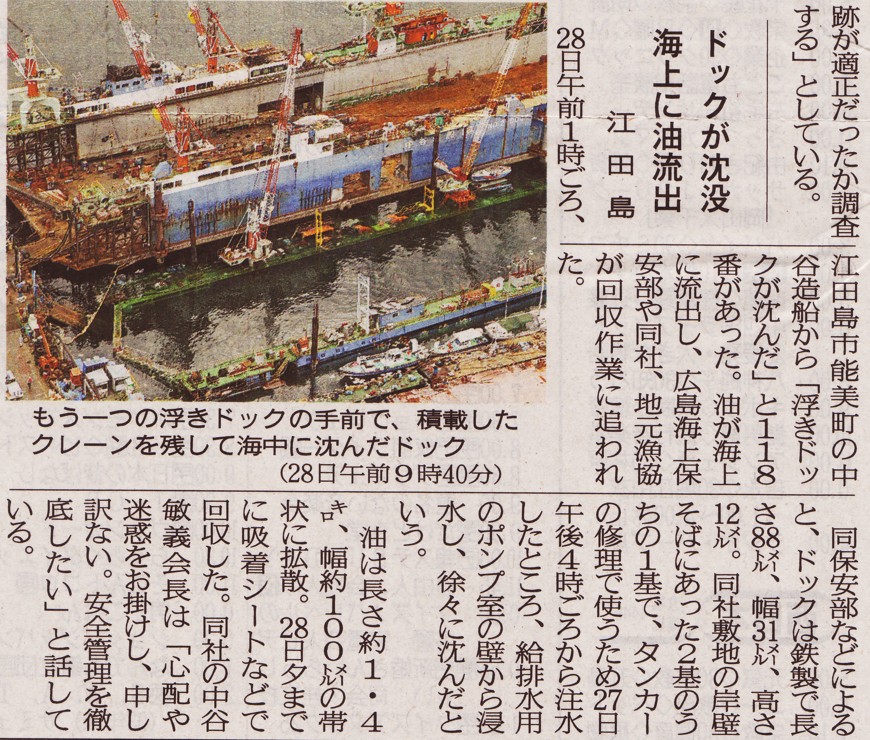
20日午後4時ごろ、江田島市の造船会社「中谷造船」で、およそ40トンある船体の一部をクレーンでつり上げて組み立てる作業をしていたところ、クレーンの角度を調節するワイヤーが突然切れ、およそ20センチの高さから落下しました。
この際、高所作業車に乗ってそばで作業していた40代の男性社員が飛び降りて逃げようとして、かかとの骨を折る大けがをしました。この労災事故を受けて、労働基準監督署は21日から、クレーンのワイヤーが切れた原因を詳しく調べています。
広島労働局によりますと、ことし1月から半年間に県内の製造業で起きた労災事故で2人が死亡し、462人がけがをしているということで、作業中の安全確保を徹底するよう呼びかけています。
水産庁によると、ブラジルの漁獲ルールに違反したことが原因だが、性能が良く漁獲量の多い日本船に対する不満が、今回の拿捕につながったという情報もある。
3隻はブラジルの200カイリ水域内で操業後、同国行政当局に漁船や漁具、漁獲物を差し押さえられた。約20人の乗組員は無事で、同国司法当局から出港許可が間もなく下りるとの情報もあるが、同社の従業員の1人は「こんなことは初めて。何事もなく操業再開できればいいが……」と不安げだ。
拘束は1か月以上続いており、3隻が所属する「日本かつお・まぐろ漁業協同組合」(日かつ漁協)は「長期間操業できなければ、経営はダメージを受ける。差し押さえられたマグロは売り物にならない」と嘆く。
水産庁によると、拿捕の理由は、海鳥を混獲しないようブラジルが定める国内法に違反したためだという。海鳥の混獲防止を巡っては〈1〉漁具におもりをつける〈2〉鳥よけのポールを装備する〈3〉夜間に漁具を海に入れる――の三つの方法から二つを選んで実施するというのが国際ルールだ。
加盟国はそれに従って国内法を整備するが、ブラジル政府は漁業者に対し、〈1〉と〈2〉を必須とする国内法を整備していた。一方、3隻は〈1〉の方法だと漁がやりにくく、おもりで船員がけがをする恐れがあるため、〈2〉と〈3〉の方法を取っていたという。
領海侵犯や禁漁区での漁が原因で拿捕されることはあるが、今回のようなケースは極めて珍しい。日かつ漁協が、現地法人のアトランティック・ツナ社と漁船賃貸契約を結び、マグロ船をブラジルに派遣し始めたのは11年から。同年に11隻、12年にも3隻が〈2〉と〈3〉の方法で同国の200カイリ水域内で操業していたが、拿捕されることはなかった。
水産庁の担当者は「日本船は性能が良く、現地の船より、多くのマグロを漁獲していた。それに現地の漁船員たちが不満を募らせ、日本船の不備を当局に通告したという情報もある」と明かす。
一方、遠洋マグロはえ縄漁船を保有する気仙沼市の別の水産会社の社長は「最近は資源管理や環境保全のための規制が厳しい。漁業者も漁場や国ごとに定められたルールに対応することが求められている」と語る。
拿捕されたのは、岩手県の「第108欣栄丸」、宮城県の「第7勝栄丸」、鹿児島県の「第58錦哉丸」の3隻で、ことし7月から8月にかけてブラジル沖で操業中に当局に拿捕されました。
ブラジルの環境省では、3隻は海鳥を誤って捕獲しないよう仕掛けがすぐに海に沈むようにおもりをつけることを義務づけた国内の環境保護規定に違反していたとして、「欣栄丸」の漁労長を一時、逮捕したほか、漁船や捕獲したマグロなどを差し押さえました。
ブラジルにある日本大使館などによりますと、漁船側は「国際ルールを守っていた」と主張し、違反はなかったとして裁判所に異議を申し立て、「勝栄丸」と「錦哉丸」については差し押さえの必要性はないと裁判所が判断し、出港が許可されました。
しかし「欣栄丸」については裁判が進まず、2か月近くにわたって、ブラジル南部の港に留め置かれ、この間に漁船の経費などで一日に数十万円かかっているということです。
また、漁労長の行動も制限されている状態が続いていることから、日本政府では早期の解決を求めて関係当局に働きかけています。
在ブラジル日本大使館が明らかにした。うち1隻は今も解放されていないという。
大使館によると、ブラジル当局に拿捕されたのは、第108欣栄丸(岩手県)と第7勝栄丸(宮城県)、第58錦哉丸(鹿児島県)の3隻。当局は、規定で定められた海鳥を傷つけないための網を使っていないとして、船などを差し押さえた。
欣栄丸は南部の港で停泊を命じられた状態。4、5人の日本人を含む乗組員20数人のうち日本人漁労長1人が船内に留め置かれている。日本の水産庁職員が現地入りし、ブラジル側と折衝に当たっている。他の2隻は供託金の支払いで合意して解放されたという。(共同)
負債総額はおよそ14億円とみられています。
東京商工リサーチ和歌山支店によりますと、起南造船所は昭和3年に創業し、昭和58年ごろまでは造船業を営み、最高で年商およそ12億円を計上していましたが、収益性が低下したため、近年は漁船などの修理業や船舶用設備の販売を行っていました。
しかし、取引銀行が相次いで倒産したことで規模を縮小しながら事業を続け、年商は一時2億円まで回復して黒字計上を続けていましたが、ことし(2013年)6月に修理していた船舶が破損し、これに伴う損害金が発生したこととこれまでの借入金の負担が重かったことも相まって先行きの見通しが難しくなったことから事業継続を断念したとみられています。
負債額は約2億5千万円。
受注不振。
China Ocean Shipbuilding Industry Group Ltd warned shareholders and prospective investors today:
Based on the preliminary review of the unaudited management accounts of the Group, the Group is expected to record significant decrease in revenue and increase in loss for the six months ended 30 June 2013 as compared to those for the corresponding period of last year. The decrease in revenue and increase in loss were mainly due to the downturn of shipbuilding market, decrease in the market selling price of ships, appreciation of Renminbi and the absence of a one-off gain on settlement of deferred consideration in 2013.
China Ocean Shipbuilding Industry Group Ltd. expects to finalize their first half results for the six months ended 30 June 2013 by the end of August.
A spokesman for Hamburg-based receiver Berthold Brinkmann told The Motorship on 6 August “talks are being held with interested parties both inside Germany and abroad, among them two interested parties from Russia”. He added “Mr Brinkmann aims to sign a contract between September and October”.
The spokesman said Mr Brinkmann did not want to name any of the potential investors at this stage, but German media reports named one of the two Russian parties as Vitaly Yusufov, owner of the Nordic Yards in Wismar and Rostock-Warnemuende.
That yard group, the former Wadan Yards and Aker Ostsee Werften, is doing well after switching production from traditional cargo ship newbuilding to the construction of giant offshore wind park transformer platforms and offshore service ships as well as specialised ice-breaking vessels.
It is a year since the P+S Yards, grouping Volkswerft and the smaller Peene-Werft in Wolgast, announced insolvency. Peene-Werft has since been sold to the Bremen-based Luerssen Group, but the sale of Volkswerft has not proved so easy.
That’s despite regular word of interest being shown in the yard, the former management of which was until just last year boasting of full order books and work for years to come. It still employs about 500 people and is delivering the first of two special 195.2m ro-ro transporters for Denmark’s DFDS later this year.
That order was renegotiated after insolvency but other orders were cancelled. Among them were the two largely completed 169.5m ro-pax ferries Berlin and Copenhagen cancelled by Scandlines because they were 200 tons overweight and also late. Interest in those ships from other buyers has however long been reported
The financing squeeze is set to hit less established yards, but could strengthen bigger players such as Yangzijiang Shipbuilding Holdings (YAZG.SI) and South Korean rivals.
Some banks have started asking for more prudent ship construction contracts before they grant loans and have withdrawn loan approval rights given previously to branches, industry and banking sources told Reuters.
They are asking the yards to get clients to put upfront payments of at least 15 percent now in order to get loans, said an executive at a large Chinese shipyard, who did not want to be identified as he was not authorized to speak to the media. Some yards had offered generous terms to shippers, requiring payments upfront of as low as 1 percent.
In some cases the banks are also cutting credit lines and moving to recover outstanding loans, said the China Association of the National Shipbuilding Industry.
"As the shipbuilding market remains depressed, banks and other financial institutions have listed shipbuilding as a key industry for credit control," the association said in a comment on its website posted on July 18. (www.cansi.org.cn)
An executive at a private shipyard in eastern China said banks had demanded yards charge as much as 30 percent in upfront payments from their clients. State-owned shipbuilders, though, could get easier credit terms, the executive added.
The bank measures come as China's cabinet said this month it would cut off credit to force consolidation in industries plagued with overcapacity. This was shortly after China Rongsheng Heavy Industries Group (1101.HK), the country's largest private shipbuilder, fell into financial turmoil.
Beijing did not specify then the industries it had in mind, though in 2009 it named nine, including shipbuilding. Industry sources said neither the banking regulator nor any central government agency had issued new rules on tightening lending to shipyards or other industries.
China rivals South Korea as the world's top shipbuilder, though the ships built in China are mostly of lower value and less complex technologically. This has forced Chinese yards to compete on price and financing terms for orders that have slowed to a trickle since the global financial crisis.
At the end of May, the orderbook of Chinese yards stood at $68.5 billion, second to South Korea's $102.5 billion, even though China's orderbook in tonnage terms exceeded South Korea's, data from Clarkson Research Services Limited showed.
"The goal is to gradually cut down the credit but not to kill all of them at one go," said a banking source, who did not want to be named due to the sensitivity of the matter. "As the economy is not doing well, banks aren't willing to lend as much anyway."
The size of outstanding loans at shipyards is unclear, but many banks are involved in handing out these loans, including top commercial banks such as Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) (601398.SS), China Construction Bank (601939.SS), Agricultural Bank of China (601288.SS), Bank of China Ltd (601988.SS) and Bank of Communications (601328.SS).
ICBC declined to comment on lending to shipyards when contacted by Reuters. Other banks could not be reached immediately.
DELAYED PAYMENTS TO STAFF, SUPPLIERS
Total profit from the 1,647 Chinese shipyards whose core business revenue exceeded 20 million yuan slumped 29.1 percent on the year to 28.8 billion yuan ($4.69 billion) in the first 11 months of 2012, according to industry association data.
"Affected by banks' restriction on loans, shipyards are facing tight working capital and difficulty in purchasing raw materials and equipment, which results in increasing phenomenon of delayed payment to suppliers and staff," the association said.
But the Export-Import Bank of China, a policy bank and an active player in shipping finance, said it had not changed its criteria for funding ship construction recently.
"We will continue to support qualified clients," said Chen Bin, deputy general manager of the bank's transport finance department.
Ex-Im Bank had about $13 billion in outstanding shipping loans in May, up 30 percent from the end of 2011, Chen said earlier this year.
Despite China Rongsheng's troubles, large and financially sound yards in China, as well as yards with a good track record outside China, are expected to benefit, analysts said.
"It depends on the conditions at your shipyard. Well-run companies don't have any problem," said Ren Yuanlin, chairman of Yangzijiang Shipbuilding, when asked if the company has facing tightening credit.
Singapore-listed Yangzijiang has won new orders worth $1 billion so far this year.
Source: Reuters

Officials from the Upper Great Lakes Group company that operated the Port Weller dry docks declined to comment Tuesday.
"We filed Monday, but beyond that I cannot say anything else," said Charlie Payne, Seaway Marine operations director.
The bankruptcy proceedings are being managed by the Toronto firm Ernst & Young.
According to bankruptcy documents posted online by Ernst & Young, Seaway Marine has around 208 creditors who are owed about $12 million. The largest is Upper Great Lakes Group, claiming $6.9 million.
Kyle Groulx, business representative for the International Brotherhood of Boilermakers Local 128 — the union representing the shipyard workers — said he was caught off guard by the news.
"We knew things were tight. In all our discussion with the company, we were told bidding was tight, everything was tight," Groulx said. "But we did not know the situation was so dire."
Groulx said major contracts continue to go either to Quebec or the west coast. Still, the ship yards have been busy enough recently to keep up to 130 people employed.
"Things were actually going pretty well for the last 30 months or so," he said. "It's one the longest good runs we've had in a long time."
Unless another company comes in to operate the ship yards, many of those workers will have to try and apply their skills elsewhere, he said.
Groulx said some of them have skills that can be transferred to other manufacturing industries, although that will likely mean leaving Niagara, or even Ontario, to find work.
"And even then, having to uproot your family and move for your job isn't easy," he said. "The bigger picture though is how much more can we loose? The steel mills are gone, GM, now the shipyards. You cannot run an economy on a commuter bus to Toronto and a casino in Niagara Falls. We need industry in Niagara."
The last federal budget earmarked $5 million to upgrade the docks, which recently completed a $6-million refit of the Canadian Coast Guard ship Amundsen.
The declaration of bankruptcy of Seaway Marine, which has run the docks since 2007, also came as a surprise to St. Catharines MP Rick Dykstra, who has helped lobby for federal dollars to support the ship yard.
Dykstra said Tuesday he had yet to speak to any of the parties involved. However, he did say the money allocated for a refit of the docks in the last budget hasn't been used yet.
"It's obviously disappointing but the last time this happened (in 2007) another company came in quickly." Dykstra said of Seaway Marine's takeover of the docks. "So in some ways, this filing for bankruptcy could make it easier for that to happen again."
He said although major ship building projects have been moved overseas to China, repairs and refits are done in Canada, so the potential for more work in Port Weller exists.
An Ernst & Young spokesman said more information is expected to be released Wednesday.
During the 2007 shipping boom, China’s shipyards charged down payments of as much as 60 percent of a vessel’s value. Now, shipbuilders are cutting those payments to as little as 2 percent, giving an advantage to state-owned companies that can tap the government’s cash.
With flagging demand pushing shipyards to compete by cutting down payments and China taking measures to rein in lending, the nation’s privately owned yards are getting squeezed by state-owned rivals that enjoy greater access to financing. China Rongsheng Heavy Industries Group Holdings Ltd. (1101), the largest shipbuilder outside state control by order book, said this month it’s seeking government support after failing to win any new vessel orders this year.“The payment terms mean shipyards have to burn their own money to build ships, which brings them extraordinary cash-flow pressure,” said Lawrence Li, a Shanghai-based analyst at UOB-Kay Hian Holdings Ltd. (UOBK) “Only state-owned yards that are able to secure funding can offer such aggressive down-payment terms.”
State-backed companies grabbed 74 percent of new vessel orders in China, the world’s biggest shipbuilding nation, in the first half of this year, according to data compiled by UOB-Kay Hian. That compares with 52 percent in all of 2012.
Dalian Shipbuilding Industry Co., a unit of state-owned China Shipbuilding Industry Corp., won an order this month to build seven ships that can carry 8,800 containers each. The buyer, a unit of state-run China International Marine Containers (Group) Co., agreed to pay 2 percent of the total amount of $595 million as a first installment and the rest upon delivery.
Fivefold Surge
New orders for commercial vessels at Dalian’s parent, which also built the nation’s first aircraft carrier, surged more than fivefold in the first half in terms of contract value, the company said in a statement posted last week on the website of China Association of the National Shipbuilding Industry.
China Shipbuilding Industry and China State Shipbuilding Corp., the two biggest yards owned by the government, didn’t reply to e-mailed and faxed questions from Bloomberg News.
The ability to get financing has become one of the most critical issues for yards to win orders, said Bao Zhangjing, deputy director of the China Shipbuilding Industry Economy Research Center.
“The market is going to be more dominated by fewer players given the current situation,” Bao said. “Those with competitiveness will have opportunities. State-owned companies and some local firms are doing relatively better.”
Of about 1,591 shipyards in China in 2011, 70 were state-owned, according to the latest available data from the shipbuilders group.
Vessel Glut
Rongsheng and other shipmakers are struggling as a global vessel glut makes orders more difficult to win and pushes down prices. A third of the shipyards in China, the world’s biggest shipbuilding nation, may be shut in about five years as they failed to win orders “for a very long period of time,” the shipbuilders group said July 4.
A clampdown on excessive short-term borrowing sent China’s overnight repurchase rate to a record 13.91 percent last month, forcing at least 22 companies including China Development Bank Corp., a backer of the shipping industry, to cancel or delay bond sales. Premier Li Keqiang said this month that China will seek to keep economic growth above an unspecified lower limit without indicating any immediate plans to boost credit even as the pace of expansion slows, while the State Council pledged to maintain its “prudent” monetary-policy stance.
Tight Liquidity
Shipyards generally have tight liquidity, and low down payments have worsened the situation, said Wang Jinlian, secretary general of the shipbuilding group. Yards received down payments averaging 40 percent in 2007, with 60 percent being the high mark, Wang said.
Buyers now pay about 5 percent to 10 percent on average, he said, characterizing 2 percent as “abnormally” low.
“We urge financial institutions to help key enterprises like Rongsheng,” Wang said.
Rongsheng has plunged 29 percent in Hong Kong trading since saying it was seeking government support on July 5. Trading of the shares was suspended July 4 after the Wall Street Journal said the company recently eliminated about 8,000 jobs. The shipyard, which has forecast a loss in the first half, said it’s restructuring its workforce and is in talks with financial institutions about renewing credit facilities.
Rongsheng’s down-payment requirements are “competitive” in the market, the company said in an e-mailed statement to Bloomberg News, declining to disclose the terms. While it hasn’t landed any new ship orders this year, it secured contracts to build offshore equipment, the company said.
Yangzijiang, Hyundai Heavy
Some private shipyards in China continue to win contracts. Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. (YZJ), the nation’s second-biggest private yard, said in a July 4 statement it has won $1.01 billion of shipbuilding orders in the first half.
Demand is picking up for South Korean yards as well, said Park Moo Hyun, an analyst at E*Trade Securities Korea in Seoul. Hyundai Heavy Industries Co., the world’s biggest shipbuilder, said this month it plans to raise prices in the second half.
“The big Korean shipyards have already achieved more than 60 percent of their order targets for this year,” Park said. “This is enabling them to get better payment terms.”
Global ship orders surged from about 2007 because of speculation fueled by China’s demand for raw materials. The government also provided low-cost financing for new vessels to help support shipyards, leading to a global increase in orders.
‘Sake of Workers’
Chinese yards had an order book of 218 million deadweight tons in 2008, overtaking South Korea as the world’s largest shipbuilding nation, according to Clarkson Plc, the world’s biggest shipbroker. China held an order book of 109 million deadweight tons at the end of June, 13.4 percent lower than a year earlier, according to the Ministry of Industry and Information Technology.
Lianyungang Wuzhou Shipbuilding Heavy Industry Co., based in eastern China’s Jiangsu province, has reduced the number of workers by half from last year to about 1,000, Chairman Ye Yunzhu said. The privately held yard is maintaining production by accepting orders to build vessels with a price tag of about 10 million yuan ($1.6 million), he said in a phone interview. It used to build vessels priced at more than 100 million yuan.
“We are only maintaining basic production for the sake of workers,” Ye said. “We can’t make money at the moment, therefore our focus is to avoid losing money.”
The yard's creditors will have two months to lodge claims with the appointed administrator.
Ryszard Glouch, president of the shipyard, said that bankruptcy would release Gdansk from economically unviable ship-building contracts.
中国の造船業界の今年5月の受注は前年同期比23%減となった。受注の減少は手付金受領額の減少にもつながっている。10年には総価格の20%を要求していた手付金は、現在は総価格の2.5%まで引き下げているケースもある。
また、受注単価や総額も下落している。今年4月には、コンテナ1万3500個の積載が可能な船舶を08年6月以降の最低価格1億600万ドルで受注した。新規受注総額も08年の1747億ドルから12年には847億ドルへと半減している。
一方、各企業の流動性資金の不足も顕著になっている。中国船舶工業行業協会の王錦蓮(ワン・ジンリエン)秘書長は「金融機関自身の流動性資金不足が問題になっている現段階では、造船業界に資金提供したがらない」と話した。
世界第2の造船国・韓国との競争激化も中国企業の苦境に大きく影響している。中国の造船業界は12年、造船所464カ所で受注額143億ドル、積載量1870万載貨重量トンを受注した。これに対し韓国は、造船所88カ所で受注額296億ドル、1460万載貨重量トンを受注している。
昨年12月末現在で、中国には年間500万元(約8250万円)以上の売上高のある造船所が1647カ所存在しているが、これらの造船所は現在、石油採掘取引の拡大によって新規受注額下落の影響とのバランスを保っている。
業界アナリストは「市場全体が不景気のため、造船業界は八方ふさがりの状態にある。今年は従来よりもさらに厳しい年になる」と予測している。(翻訳・編集/HA)
「銀行やその他金融機関が造船業に対して貸し渋りしている」と同社は開示しています。
このため同社は既に従業員の40%をレイオフし、出入りの下請け業者に対する支払も滞っているそうです。
これまで世界の他の国々の船主が造船の注文をキャンセルすると、中国の造船会社がそれを水面下で引き継ぎ、造りかけの船を完成させるということが横行していました。バルチック・ドライ指数が低迷して久しいにも関わらず、傭船料がなかなか改善しなかった理由は、この「キャンセルしても、キャンセルしても、どんどん船が完成する」という奇怪な現象が原因です。
折から中国政府はシャドー・バンキングを抑制するために引き締め政策を行っています。今回の中国熔盛重工集団の資金繰り困難は、そうした金融セクター全般の資金ひっ迫を背景にしたものだという風にも説明できます。
中国政府が同社に救済の手を差し伸べるかどうかが注目されます。また同社が破綻した場合、それがバルチック・ドライ指数底入れのきっかけになるかも知れません。
引き続き注目したいと思います。
熔盛重工が香港証券取引所に提出した報告によると、資金難から従業員への賃金支払いが滞り、江蘇省の造船所で今月2日、大規模なストライキが発生。8日まで生産停止することを決めた。
業績悪化への懸念から香港市場で同社の株価は急落。同社は資金難を乗り切るため、複数の金融機関と融資の交渉をしているほか、政府や株主に支援を求めていることを報告で明らかにした。同社は報告で「世界の造船市場の需要が下落している。中国の造船業はかつてない試練に直面している」と窮状を訴えた。
China, the world’s biggest shipbuilding nation, may see a third of its yards shut down in about five years as they struggle to win orders amid a global vessel glut, an industry group said.
The yards in peril of closure have failed to get any orders “for a very long period of time,” Wang Jinlian, secretary general of the China Association of National Shipbuilding Industry, said in an interview yesterday. They may end operations in three to five years if the “gloomy market persists.” The nation has more than 1,600 shipyards.
China Rongsheng Heavy Industries Group Holdings Ltd. (1101) fell the most in almost a year in Hong Kong trading today after saying it’s seeking financial support from the government and its largest shareholder amid a plunge in orders and prices. The stock of China’s biggest yard outside state control was halted yesterday after the Wall Street Journal reported it recently cut about 8,000 jobs.
“Because of the overall market, there’s no way out for the companies; so only the strongest will survive,” Sarah Wang, a Shanghai-based analyst at Masterlink Securities Corp. (2856), said. “Life for China’s shipyards will be tougher this year as any form of credit crunch is critical.”
Rongsheng Restructuring
More than half of the Rongsheng employees laid off were subcontractors and the rest full-time workers, the Journal reported July 3, citing Lei Dong, secretary to the Shanghai-based company’s president. William Li, a Rongsheng spokesman, declined to comment on the report.
The shipbuilder had a net loss in the first half, it said in today’s filing. Shareholder Zhang Zhirong agreed to provide an interest-free 200 million yuan ($33 million) loan to the Shanghai-based yard, it said.
Rongsheng is undergoing “workforce restructuring,” and is “gradually downsizing production” in some areas, it said in today’s statement without elaborating.
The shares fell as much as 16 percent to 89 Hong Kong cents, the most since July 30 last year, before trading at 93 Hong Kong cents as of 10:03 a.m. local time.
The order book at China’s shipbuilders fell 23 percent at the end of May from a year earlier, according to data from the shipbuilders’ group. Yards have reduced down-payment requirements, with some slashing their rates to as little as 2.5 percent of contract value compared with 20 percent before 2010, according to UOB-Kay Hian Holdings Ltd. (UOBK)
Tight Liquidity
The nation’s clampdown on excessive short-term borrowing sent the overnight repurchase rate to a record 13.91 percent last month, forcing at least 22 companies including China Development Bank Corp., a backer of the shipping industry, to cancel or delay bond sales. Economic growth in China has held below 8 percent for the past four quarters, the first time that has happened in at least 20 years.
“Currently financial institutions themselves may have tight liquidity, so they are reluctant to lend money to companies in this sector,” China Association’s Wang said. “If they can help some good companies, there would be no problems.”
“Rongsheng’s move reflects the bad market,” said Lawrence Li, an analyst at UOB-Kay Hian in Shanghai. “More small-to-medium sized shipyards, especially those that lack government support, may take the same actions or even close down.”
Order Targets
Rongsheng had as many as 38,000 workers including its own employees and contract staff at the peak of the industry boom a few years ago, UOB-Kay Hian’s Li said. Brazil and Greece accounted for more than half of Rongsheng’s 2012 revenue, according to data compiled by Bloomberg.
The company posted a loss of 572.6 million yuan ($93 million) last year, after three consecutive years of profits, according to data compiled by Bloomberg. It had short-term debt of 19.3 billion yuan as of the end of 2012, the data show.
The shipbuilder targets new ship and offshore orders worth more than $2.3 billion this year, Chen said in Hong Kong in March. The company pared about 3,000 employees last year as it aims to return to profit this year, he said at the time.
Rongsheng’s cash conversion cycle, a gauge of days required to convert resources into cash, more than doubled to 582 last year from 224 in 2011, the data show. Its shares have fallen 15 percent this year in Hong Kong, compared with a 9.7 percent decline for the benchmark Hang Seng Index.
Ship Prices
Ten of the 14 analysts tracked by Bloomberg recommend selling Rongsheng stock with the rest rating it hold. The company raised HK$14 billion ($1.8 billion) in its initial public offering in 2010.
Ship prices for a vessel that can carry as many as 13,500 boxes fell to $106 million in April, which was then the lowest since Clarkson Plc (CKN) started compiling the figures in June 2008. Contracts for new vessels halved to $84.7 billion in 2012, compared with $174.7 billion in 2008, according to Clarkson.
About 464 shipyards in China won 18.7 million deadweight tons of orders worth $14.3 billion last year, the lowest since 2004, according to Clarkson. That compares with contracts for 14.6 million tons worth $29.6 billion received by 88 yards in South Korea, the world’s second-biggest shipbuilding nation.
China had 1,647 shipyards with annual sales of more than 5 million yuan at the end of December, according to the China Association. The sector contributed an industrial output of 790.3 billion yuan last year.
Shipbuilders are trying to offset the plunge in new vessel prices and orders by expanding their oil-rig business. Rongsheng announced in October its first order to make a tender barge while rival Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. (YZJ) got its first rig contract in December.
China Rongsheng Heavy 1101.HK -16.04%Industries Group Holdings said Friday that it is struggling to pay its employees and is seeking financial help from the government to see the shipbuilder through a prolonged industry slump. Its Hong Kong-traded shares slumped 16% on Friday.
Rongsheng didn't mention the cash squeeze that gripped China's financial system last month in what was widely seen as a warning from Beijing over freewheeling lending. But in the company's statements, it said credit had become harder to come by because of industrywide woes in shipbuilding.
"Banks and other financial institutions have tightened credit facilities available to shipbuilders, and many shipowners have delayed, renegotiated or defaulted on payments to shipbuilders," Rongsheng said Friday in a filing with the Hong Kong Stock Exchange. The increased financial pressure had caused the company to delay "payment to its suppliers and workers" in recent months, it said.
In an interview earlier this week, a Rongsheng executive said the company had already laid off about 40% of its 20,000 employees.
Friday's disclosure came on the same day that Beijing warned it would take a tougher line against the overcapacity plaguing a range of Chinese industries, including steel, cement, cars and solar panels. China's State Council, or cabinet, vowed to thwart the financial risks arising from the excess production capacity and to help banks and firms deal with bad debt.
The test for Beijing is whether it will allow major employers to falter, creating the potential for restless unemployed workers and damage to local economies. Despite increased rhetoric about overcapacity in recent months, troubled Chinese companies have shown little sign of retrenchment.
China has seen a massive increase in credit in the five years since the global financial crisis struck. While the infusion helped the Chinese economy weather the crisis early on, it also fueled a massive expansion of industrial capacity as major manufacturers took advantage of easy credit. That expansion is being put to the test by the cooling of China's economy and demand for its exports.
China's shipbuilding sector in particular has struggled, as global overcapacity amid a slump in trade following the 2008 financial crisis has hit the industry. Shipbuilding completions in the January-May period fell nearly 24% from a year earlier to 17.2 million deadweight tons, a common industry measure, according to the China Association of National Shipbuilding Industry.
Without being more specific, Rongsheng said it expects to report a net loss for the six months ended June 30. The shipbuilder posted a loss attributable to equity holders of 573 million yuan ($93.4 million) for all of last year.
The State Council in its statement presented a hard line on financial risks arising from China's overcapacity problems.
"We will strictly prohibit providing new credit supply or direct financing in any form to illegal construction projects in sectors with overcapacity, so as to avoid reckless investment exacerbating the problem of excess production capacity," it said.
The council also said that it would give banks more power to write off and dispose of bad loans so that they can absorb risks "in an active and timely manner."
About 1% of all loans in China's banks system are delinquent, but analysts expect that figure to rise in coming years.
Rongsheng said Friday that it is in discussions with a number of banks about "renewing existing credit facilities." The company also said it has reached an accord with a company controlled by key shareholder Zhang Zhirong, the shipbuilder's founder and former chairman, for an interest-free and security-free loan of 200 million yuan ($32.4 million).
Mr. Zhang stepped down as chairman in November, weeks after an investment firm he controls, Well Advantage, paid $14.2 million to the U.S. Securities and Exchange Commission to settle allegations of insider trading after the firm amassed shares of Nexen Inc. ahead of an announcement that China's Cnooc Ltd. 0883.HK +2.19%would acquire the Canadian energy company. Rongsheng wasn't accused of wrongdoing. Well Advantage, listed in Hong Kong, settled the case without admitting wrongdoing.
Rongsheng is a vital part of the local economy in its home of Rugao, in China's eastern Jiangsu province, roughly a two-hour drive from Shanghai. In 2010 its parent company, Jiangsu Rongsheng Heavy Industries Group Co., paid more in local taxes than the next seven biggest firms combined, according to government data. In May, Jiangsu Rongsheng was Rugao's eighth biggest taxpayer, paying 25.54 million yuan—less than a quarter of what it paid in the same month last year when it was still the top corporate taxpayer.
Set up in 2005 and owned by private investors, Rongsheng has become one of China's biggest shipbuilders. Last year, it was China's third biggest shipbuilder in terms of output in deadweight tonnage, a measure of how much weight a ship can carry, according to Clarkson Research Services, the research arm of Clarkson shipbrokers. The two largest shipbuilders are state-owned.
Rongsheng's 2012 annual report said orders on hand had a contract value of $5 billion for 91 vessels, down from 111 at the end of 2011. Meanwhile, it has to repay more than 15 billion yuan in loans this year.
The company said laid-off workers blockaded its headquarters on Tuesday, but later dispersed. It said there has been no industrial action by current employees.
The company also said shipbuilding continues, although it asked some employees at the group's production base in Nantong city in east China's Jiangsu province to halt work for three days this week "due to the high temperature."
Late Tuesday, Lei Dong, secretary to Rongsheng's president, said in an interview that about 8,000 employees had been laid off in recent months. He said the layoffs weren't a sign of financial trouble and were the result of a restructuring that aims to shift the company's focus from bulk carriers to specialized vessels for the offshore oil-and-gas industry.
Lei Dong, secretary to Rongsheng's president, had said that the layoffs weren't a sign of financial trouble and were the result of a restructuring that aims to move the company's focus away from bulk carriers toward specialized vessels for the offshore oil-and-gas industry.
"Orders and prices of vessels decreased sharply as compared with the previous year," Rongsheng said in its statement. "The Chinese shipbuilding industry is still facing unprecedented challenges."
—Liyan Qi and Joanne Chiu contributed to this article.
* Govt says wants closure of firms plagued by overcapacity
* Does not mention specific industries or companies
* China Rongsheng shares drop 16 percent to record low
* Company says expects H1 net loss, delays payments to suppliers (Adds analysis, quotes)
By Clement Tan and Umesh Desai
HONG KONG, July 5 (Reuters) - China Rongsheng Heavy Industries Group, China's largest private shipbuilder, appealed for financial help from the Chinese government and big shareholders on Friday after cutting its workforce and delaying payments to suppliers.
Analysts said the company could be the biggest casualty of a local shipbuilding industry suffering from overcapacity and shrinking orders amid a global shipping downturn. New ship orders for Chinese builders fell by about half last year.
Hours after China Rongsheng made its appeal in a filing to the Hong Kong stock exchange, where the company is listed, Beijing vowed to bring about the orderly closure of some factories in industries plagued by overcapacity.
The statement by the State Council, or cabinet, laid out broad plans to ensure banks support the kind of economic rebalancing Beijing wants as it looks to focus more on high-end manufacturing. It did not mention any specific industries or companies and there was no suggestion it was referring to Rongsheng.
China Rongsheng said it was expecting a net loss for the six months that ended June 30 from a year earlier, according to the filing. It gave no figures.
The company reported a net loss of 572.6 million yuan ($93.47 million) in 2012, its worst-ever, despite getting government subsidies of 1.27 billion yuan in that year, its latest annual report shows.
Rongsheng shares plunged 16 percent to a record low in heavy turnover on Friday, leaving its market capitalisation at just under $1 billion. The Hang Seng Index climbed 1.9 percent. China Rongsheng is down 28.2 percent on the year.
"Obviously it's bad with the fact that you have a profit warning and there is a request to ease financial pressure through the government," said Nathan Snyder, a transport analyst at CLSA.
In its filing, China Rongsheng said some workers had been made redundant, although it gave no numbers or timeframe for the losses. The company did not immediately respond to requests for more information.
The Wall Street Journal said this week there had been 8,000 job cuts in recent months, representing about 40 percent of China Rongsheng's workforce.
TOO RELIANT ON BULK CARRIERS
Analysts said the company was suffering partly because of its reliance on building bulk carriers that ship iron ore from producer nations such as Brazil to China. The bulk market accounted for about 58 percent of its orderbook.
That segment was under pressure due to a slowdown in global steel production, relatively high iron ore port inventory levels and a wave of new ships hitting the market in 2011-12, Citigroup said.
China Rongsheng has said it won only two shipbuilding orders worth $55.6 million last year when its target was $1.8 billion worth of contracts. This year, it received orders to build two drilling rigs used in oil exploration, worth $360 million.
By contrast, another Chinese shipbuilder, Singapore-listed Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd, has secured total orders of $1 billion in the first half, Barclays said.
"Shipyards are a lot like banks, confidence matters ... Any yard anybody is worried about is going to find it very difficult to get new orders," said Jon Windham, Barclays head of Asia industrials equity research.
While the Chinese shipbuilding industry faced "unprecedented challenges", China Rongsheng's board was confident management could ease pressure on working capital in the near future and maintain normal operations, the company said in the filing.
It was coping with tightened cash flow by delaying payments to suppliers and workers, the filing added. The company denied claims suppliers had towed away machinery from its Nantong production base in eastern Jiangsu province, near Shanghai.
The company said it was in talks with banks and other financial institutions to renew existing credit lines.
According to its December 2012 annual report, issued on March 26, China Rongsheng's cash and cash equivalents fell to 2.1 billion yuan from 6.3 billion yuan a year ago.
It had borrowings of 16.26 billion yuan that were due in less than a year, said the report, the latest financial statistics available on the company's website. Total borrowings were 25.1 billion yuan as of the end of 2012.
"The group is ... actively seeking financial support from the government and the substantial shareholders of the company, and increasing its efforts in negotiations with its customers to maximise the collection of receivables," China Rongsheng said in the filing.
One shareholder, founder and former chairman Zhang Zhirong, gave an interest-free 200 million yuan loan on Wednesday, the company said.
NOT ALL SHIPYARDS IN SAME BOAT
A note from Macquarie Equities research said the statement highlighted the "severity" of China Rongsheng's liquidity problems, adding this was not necessarily representative of the wider sector.
It said other listed Chinese shipyards were not as leveraged as China Rongsheng. The loan from Zhang was a surprise, it said, showing how badly the company needed cash.
Barclays' Windham added: "The inference that a lot of investors, including myself, will take from that is that they couldn't get the bank borrowing to do it."
Receivables pending for more than six months rose to 83 percent from 21 percent a year ago, the annual report said. The industry slowdown was also taking its toll on sales, with inventory turnover at 136 days, up from 73 days.
"Rongsheng will need to address the problems immediately to reassure the market," said Martin Rowe, managing director of Clarkson Asia Limited, a global shipping services provider.
The Chinese government has been trying to support the domestic shipping industry since the 2008 financial crisis, and local media reports said this week Beijing was considering policies to revive the shipbuilding business.
The holding orders of Chinese shipyards dropped 23 percent in the first five months of this year compared with a year earlier, according to the China Association of the National Shipbuilding Industry. New orders dropped to a seven-year low in 2012. ($1=6.1258 yuan) (Additional reporting by Yimou Lee and Twinnie Siu in Hong Kong and Keith Wallis in Singapore; Editing by Dean Yates)
しかし足元数日では抗議活動も規模が小さくなり、生産に影響は出ていないとも述べた。
同社の総裁執行室主任、雷棟氏はウォール・ストリート・ジャーナルに対し、レイオフは同社の財務問題の前兆ではなく、ばら積み貨物船からオフショア船に焦点を移す動きに伴う、事業再編の結果だと説明した。
同社はその後の声明で、抗議している労働者は施設を離れるよう説得がなされたと述べた。
声明の中で主任は「ここ数日、(雇用の)申し出を得られなかった一部の労働者が、南通市の生産拠点の入り口を包囲して生産を混乱させる活動を計画している」と述べた。「しかし、説得チームを動員しグループの方針を説明した後にこの集団は解散した」と明らかにした。
主任は対立が近いうちに解決されるとの考えを示した。またレイオフされた従業員の半分以上は下請けで、残りが正規社員だったとも明らかにした。同社は今年初めに約2万人の従業員を採用していた。
The first bankruptcy motion was submitted to court two weeks ago, but was rejected on formal grounds. Biprostal's lawyers told Puls Biznesu that a new motion has already been prepared and filed.
Stocznia Gdańsk is majority-owned by the shareholders of Ukrainian industrial holding ISD. The Gdańsk shipyard was the home of the Solidarity opposition movement in communist-era Poland. The shipyard went bankrupt 17 years ago and its assets were transferred to the company which currently operates the shipyard.
The shipyard is owned by Ukrainian Gdańsk Shipyard Group (75 percent), and state-controlled Agencja Rozwoju Przemysłu (25 percent).
Although TMT did not immediately disclose its debt position, local media reported earlier this month that the shipper has debts of US$800 million.
According to the media reports, Taiwan's First Commercial Bank is the company's biggest creditor, with lending reaching US$120 million, while Mega International commercial Bank, another major bank in Taiwan, is the second-largest, with outstanding loans of US$96 million to the shipper.
The Financial Supervisory Commission, Taiwan's top financial watchdog, said in a statement released in late May that largely due to the loans extended to TMT, the total overdue loans of the local banking system as of the end of April had risen by NT$5.7 billion (US$188 million) from the previous month to NT$100 billion.
In a statement, TMT Chairman Nobu Su said the financial difficulties the company faces result from a slowdown in the global economy in recent years. He said the company had no choice but to seek restructuring with court assistance.
TMT said local creditor banks have already seized some of the vessels it had pledged as collateral, which has affected the company's operations, forcing it to seek bankruptcy protection in the U.S., which the company said has better governance over corporate reorganization.
Su said he assumes full responsibility for the problems TMT has encountered.
“I want my ships on the high seas earning money to pay off my loans, but bank actions have contributed to delaying a successful restructuring of the shipping side of the business,” Su said in the statement.
The shipper said that with the global economy showing signs of recovery, TMT has confidence that shipping demand will revive on expanding trade activity and that the shipper will be able to resolve its crisis.
TMT's chairman, Nobu Su, has been restructuring his shipping business for three months, and he said the Chapter 11 bankruptcy process is part of that plan.
The bankruptcy process puts the affected companies into temporary court administration, allowing them to delay the payment of some debts and avoid closing down.
The Chapter 11 process runs in parallel with mediation between TMT and Taiwanese authorities and banks.
“The critical factor being the maturity of our credit facilities with our major lenders
Nobu Su, Chairman, TMT "Over the last 10 years TMTs businesses have enjoyed considerable success, allowing us to invest in one of the most modern fleets of merchant ships in the World," Nubu Su said.
"However in the last three years, initiated by the economic downturn a combination of factors has required some of our companies to file for Chapter 11.
TMT compared its decision to moves by General Maritime Corporation (Genmar) and Overseas Shipholding Group (OSG), both of which used the Chapter 11 process to restructure.
TMT said in April that it was considering legal action against the Royal Bank of Scotland (RBS) over its role in the ship owner's loss of over $1 billion in 2008.
Global shipping company TMT Group sought bankruptcy protection after failing to restructure its $1.46 billion debt load out of court.
The company, which has a fleet of 17 vessels that transport everything from oil to vehicles around the world, filed for Chapter 11 protection on Thursday in Houston, the latest victim of an industry downturn that has left shipping businesses struggling with their balance sheets.
In the years leading up to the recession, TMT, like many of its peers, was building up its fleet, placing orders for new ships. But when work dried up and charter rates dropped, TMT had trouble servicing its debt and keeping up with operating expenses. Many of the Taiwanese company's ships, which contain names like Ladybug, Whale, Elephant and Duckling, have been detained at ports around the world, cutting the company off from its source of revenue.
"The arrested vessels are currently laid up in multiple ports, losing income and accruing crew fees, arrest fees and other expenses, rather than generating funds that would inure to the benefit of the debtors' estates, creditors, and defendants themselves," the company said in court papers.
The defendants—an array of international banking and shipping institutions—are targeted in a complaint TMT filed with the bankruptcy court, seeking to recover its vessels. The company wants a judge to issue a temporary restraining order protecting the ships.
Representatives for several of the banks weren't immediately available for comment on Friday.
TMT's name has its roots in a company known as Taiwan Marine Transport Co. Taiwan Marine Transport, which isn't included in the bankruptcy filing, was founded in 1958 as a banana-boat operator with routes in Asia.
"Since then, the TMT Group has grown into a provider of world-wide sea borne transportation services," Lisa Donahue, a restructuring professional with AlixPartners, said in court papers.
In 2007, the TMT acronym was changed from Taiwan Marine Transport to Today Makes Tomorrow to reflect the company's growing operations. A total of 23 entities filed Chapter 11 petitions Thursday.
TMT, which has $1.52 billion in assets to its $1.46 billion in liabilities, hired AlixPartners in March to negotiate a debt restructuring but a deal wasn't forthcoming. Instead, it has seen some of its lenders push for sales of the company's arrested vessels. The company said its bankruptcy filing was an attempt to "preserve its assets and maximize value for all stakeholders."
TMT is set to make its debut in bankruptcy court on Monday, where the judge will consider signing off on a variety of requests, including one in which TMT seeks access to cash securing its lenders' claims. The company said its prebankruptcy bank lenders—First Commercial Bank Co., Sinopac Bank, Mega International Commercial Bank, 2886.TW -2.19%Cathay United Bank and Shanghai Bank—have frozen a total of $54.31 million in cash collateral, an act that has "imperiled the survival of [TMT's] business."
TMT has tapped attorneys from Bracewell & Giuliani LLP to help guide the company through the Chapter 11 process.
Oct 15 (Reuters) - Taiwan shipowner Today Makes Tomorrow Group (TMT) has defaulted on payments for 12 bulk cargo ships with a total contract value of $650 million ordered from South Korea's Hyundai Group, as an industry downturn takes its toll.
Hyundai Heavy Industries Co Ltd and affiliates Hyundai Samho and Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd are building the ships, and the group is in talks to resell at least one of the vessels.
"The current market condition is very bad and we are adjusting our operation and forced to forfeit some of the ships we ordered," a TMT spokesman told Reuters on Monday.
TMT, which has cut its fleet by half to about 40 vessels since the financial crisis in 2008, is in talks with Hyundai on how to proceed with the orders, the TMT spokesman said.
"We did not make payments for the ships and the shipbuilder wants to resell them in the market," he said.
Hyundai was close to reselling a vessel of 263,000 deadweight tonnes (dwt), the TMT spokesman said, adding that the Taiwan company still hoped to take delivery of some ships.
Hyundai may suffer losses if the resale prices are lower than contract prices.
The 12 vessels, most of them ordered in 2010, include two 263,000 dwt ore carriers from Hyundai Heavy, two 263,000 dwt ore carriers and seven 84,062 bulk carriers from Samho and one 37,000 dwt bulker from Hyundai Mipo, with a total capacity of about 1.6 million dwt, shipping newspaper Lloyds List reported.
The TMT executive would not comment on payment details of the ships but said the company, which also operates oil tankers and LNG carriers, was at a breakeven level last year although it could make a loss this year.
This is not the first time that TMT, led by enigmatic tycoon Nobu Su, has seen its ordered ships auctioned off.
In May, its two very large crude carriers at Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering were auctioned off after TMT failed to meet payments, Lloyd's said.
Su, TMT's chief executive, is looking to diversify the firm's business by investing $2 billion to $4 billion in building a complete liquefied natural gas (LNG) supply chain that is expected to come on stream in 2015.
Its investment includes the re-design of one of its very large oil oilers (VLOOs) into a floating liquefied natural gas (FLNG) unit, which will help extract natural gas from the ocean and convert it into liquid, for shipping to customers in Asia.
When asked how the company could finance such an investment, the spokesman said: "We are going through a very hard time but we will use various means to fund the project, which will span into a number of years." (Additional reporting by Joyce Lee in Seoul, Editing by Clarence Fernandez)
Bloomberg News
The STX Group 011810.SE -10.42%building that houses the STX Pan Ocean Co. headquarters in Seoul.Kang Duk-soo, who built up STX Group into one of South Korea’s big conglomerates through M&As over 12 years, earned great respect for not being born into wealth like the heads of other conglomerates such as Samsung, Hyundai and LG.
But the 63-year-old’s shipping-to-shipbuilding empire is falling apart as a result of his restless appetite for expansion. STX Group, which has more than 10 trillion won ($9 billion) in total debt, is selling most of its assets, except for the shipbuilding business, to stay afloat.
Mr. Kang hasn’t spoken publicly since the bankruptcy filing by bulk carrier STX Pan Ocean on Friday, but has made it clear he’s on the ropes.
In an email to employees early last month, Mr. Kang said: “As chief executive, I will do whatever it takes and sacrifice all my personal interest to minimize the impact on jobs of employees and subcontractors taking.”
Mr. Kang began his career as a salaried worker at a cement company in 1973. In 2001 he bet all his wealth on a takeover of SsangYong Heavy Industries, the precursor of STX Group. Through 2007, STX Group spent more than two trillion won to buy four companies, including cruise-ship maker Aker Yards ASA from Norway.
“There’s no need to compete in this small domestic market only to be the biggest player or the second. Rather, we should be first to occupy the enormous overseas markets to survive,” Mr. Kang said early in 2008, according to STX.
But the global financial crisis that year saw international trade collapse, first slamming the shipping industry and then shipbuilding as orders for new vessels dried up. STX’s construction arm was hit hard, too.
STX Group
STX Group Chairman Kang Duk-soo“Even if a company ran one of the three businesses—shipping, shipbuilding and construction—it would be hard to survive today. STX has all of them,” noted a former STX executive who left the company late last year.
But Mr. Kang’s desire to diversify the group’s business portfolio never subsided even when its mainstay businesses entered a downturn. He expressed interests in Daewoo Engineering & Construction Co. 047040.SE -0.64%in 2010 and Hynix Semiconductor Inc. 000660.SE +0.15%in 2011 before dropping out of both bids.
STX Group shares suffered a free fall since late 2008 as the group earns about 90% of its total sales from the shipping and shipbuilding businesses. For example, STX Pan Ocean plunged to 2,565 won Tuesday from 10,900 won Dec. 15, 2008, and STX Offshore & Shipbuilding also 067250.SE -4.80%nosedived to 2,595 won from 14,500 won during the same period.
The fortune of the company started to wane largely due to the founder’s continued push for expansion. Few outside directors stood against the charismatic chairman’s investment decisions.
STX’s former and current officials said the main reason for current problems is that the group spent a great chunk of advance payments from clients in takeover deals without leaving some as operating capital.
“Mr. Kang should have put aside some money to continue to build ships during the downturn and adopted warnings raised by his aides and the market,” a current STX official said. “What stopped him was snowballed debts, after all.”
Mr. Kang has promised he will fully cooperate with the creditors for the group’s restructuring and entrust all his voting and disposal rights as a major shareholder to the creditors, said main creditor Korea Development Bank.
“We will draw up business plans only for survival scrapping the [expansion] strategy hired during the boom years,” he said in his recent email to staff.
漁船がマグロを誘引し、大量捕獲するために浮かすこの浮遊物は、魚群収集装置(FAD=Fish Aggregating Device)と呼ばれる。特別な材質・形があるわけではないが、時には位置追跡装置まで付着する先端FADもある。問題はFADを使用すれば同時に集まったイルカ・サメ・海亀まで網にかかるという点だ。
昨年12月にフィリピン・マニラで開催された中西部太平洋水産委員会(WCPFC)で、韓国など参加国がFAD使用禁止期間を年間3カ月から4カ月(7-10月)に増やすことで合意したのもこのためだ。
しかしFADをほとんど使用しない先進国の漁船とは違い、韓国漁船は禁止期間のみ自制するだけで、残りの期間にはFADを使用してマグロを乱獲するという批判が出ている。国際環境団体グリーンピースのソウル事務所は9日、報告書を出し、「東遠・思潮・オトゥギなど韓国のツナ缶製造会社にマグロを供給する遠洋漁船がFADを使用し、マグロ乱獲を続けている」と明らかにした。グリーンピース側はFADを使用すれば、10缶分量のマグロを漁獲する度に1缶分の他の海洋生物も犠牲になると説明した。FADは「死の罠」ということだ。
韓国の場合、2010年のマグロ漁獲量は31万1925トンで、世界3位。日本は49万7979トンで1位だった。にもかかわらずグリーンピースが韓国を批判するのはFADのためだ。匿名を求めた水産業界の関係者も「日本の場合、マグロ漁獲量は多いが、刺し身用のマグロを一本釣りするなど、FADを韓国漁船ほど使わない」と話した。
韓国遠洋漁船が漁獲したマグロのうち、年間およそ20万トンはタイなどを経て輸出される一方、残り10万トンは国内に搬入され、ツナ缶として消費される。ツナ缶の消費量に限れば韓国がアジアで最も多い。
グリーンピース活動家のハン・ジョンヒ氏は「英国・豪州・米国など先進国のツナ缶生産会社ではFADなしに生産したツナ缶を別に表示し、消費者が選択できるようにしている」と述べた。一方、韓国企業は、まだ需要がなく収益性が高くないという理由で「FADフリー(free)」ツナ缶を出していない。サジョ産業だけがFADフリーのツナ缶を検討中という。
こうしたグリーンピースの主張に対し、韓国企業は否定的な反応だ。匿名を求めた韓国ツナ缶製造会社の関係者は「国際的な規律に基づき、1年に4カ月はFADを使用していない」とし「FADを全面禁止すれば、漁獲量が40%ほど減り、ツナ缶の価格が暴騰するだろう」と話した。
これと関連し、韓国政府はマグロ違法漁業を防ぐため、4日、ハワイとニュージーランドを含む南・西太平洋上に西海漁業管理団所属の国家漁業指導船(ムクゲ31号、500トン級)を初めて派遣した。乱獲で国家イメージが低下するのを防ぐためだ。
キム・ドンウク西海漁業管理団長は「指導船は来月末まで韓国の遠洋漁船が国際的な操業基準を守っているかどうかを把握する予定」と述べた。この海域は韓国マグロ漁遠洋漁船の90%が操業をするところだ。
STXパンオーシャンは、STXグループが昨年末から売却を推進したものの失敗。今年初めからは主な債権銀行の韓国産業銀行による買収も検討されたが、資産査定の結果、不良債権が予想を上回っていることが判明し、買収が見送られた。結局は法定管理の申請が避けられなくなった。
STXパンオーシャンの負債は総額4兆5000億ウォン(約3830億円)に達する。内訳は金融機関による融資が3兆2000億ウォン(約2720億円)、社債が1兆1000億ウォン(約940億円)だ。法定管理に入ると、金融機関による融資だけでなく、社債などすべての債務がいったん凍結される。社債購入者の資金回収率は通常20%程度にとどまり、投資家には損失が生じる。
STXパンオーシャンの経営が結局破綻したことで、昨年9月には熊津グループが法定管理に入った当時と同様、社債市場が打撃を受ける可能性が高い。投資家が社債に投資しなくなれば、景気低迷で資金事情が悪化した企業が起債で資金調達を行うのが難しくなる。
金融委員会は、そうした事態を防ぐため、政府が信用保証基金を通じて支援を行うプライマリー債権担保付き証券(P-CBO)の発行を拡大する案などを検討している。信用度が低く、単独では社債発行が困難な企業が発行した債券をまとめ、信用保証基金による保証で信用度を高めた上で発行する方式だ。過去に実施例がある産業銀の「社債迅速買い取り制度」の採用も一部で検討されたが、資金難に陥った企業の社債を買い取るのは、産業銀にとって大きな負担となるため、見送られそうだ。金融当局関係者は「STXパンオーシャンをめぐるリスクは既に市場に反映されている。まだ影響は表れていないが、鋭意注視している」と述べた。
STXパンオーシャンが法定管理を申請しても、STXグループを造船分野に特化させる事業再編に特に影響はない見通しだ。産業銀のリュ・ヒギョン副銀行長は7日の記者懇談会で、「STXグループは他の企業グループとは異なり、系列会社間の債務が少ない。STXパンオーシャンが持ち株会社のSTXに燃料代金として1000億ウォン(約87億円)の債務がある程度だ」と説明した・
STXグループは現在、STX、STX造船海洋、STX重工業、STXエンジンの4社が債権団と自発的な協約を結び、造船分野に特化した企業へと事業再編を進めている。非造船分野の系列会社や海外法人は売却を目指している。リュ副銀行長は「STXパンオーシャンを除く他の系列会社は、比較的順調に作業が進んでいる。今月末までには全体像が明らかになるはずだ」と述べた。
しかし、STXグループが解体に向かうのではないかとの見方もある。STXグループはSTXを持ち株会社とする体制を取っているが、STXパンオーシャンが法定管理でグループを離脱するのに続き、他の系列会社も事業再編の過程で、実質的に債権団が株式を保有する形となり、出資関係が断絶するためだ。これについて、産業銀関係者は「人為的な系列分離は考えていない。現体制でできるだけ正常化を目指す」と説明した。
Tongyeong branch of Changwon District Court notified Korea Yanase on May 30 that the Changwon-based company had been chosen as the final successful tender for Samho’s new owner.
At the fourth court auction, Yanase suggested the highest value of all, KRW 25.1bn ($22.2m), and will be confirmed to become the new owner of Samho if there are no objections till June 7.
According to the Tongyeong branch, Samho’s price tendered was close to KRW 40bn at the first bid, however, each time the bid failed, the price fell by 20% that finally KRW 25.1bn was the final contract price.
Since established in June, 1991, in Changwon, South Gyeongsang Province, Korea Yanase has been involved in marine equipment business for Lashing Bridge, Hatch Cover, Car Deck System and etc. and newbuilding business as well for Jack-up Barge, AHTS, chemical tanker, Tug-boat and so on.
Published : June 3, 2013
今井さんは言う。
「彼の言ったことは日本と中国・アジアでの人々の意識の違いを語る上で象徴的だと思った。日本人は商品やサービスに完璧さ、レベルの高さを求め、それが今も世界標準と考えているところがあるが、海外、特に東南アジア向けの展開では“安くてこのレベルでいい”という発想が必要。そうでないと中国などには対抗できない。だれも日常の消耗品に完全なものを求めていない。日本の価値観は今やガラケー化(世界標準から外れ孤立化)している」
今井さんは日本人相手の商売が次第に行き詰まったため、店は中国人に任せて湖南料理に業態を替え、自身は平成18年、ベトナムに進出。ホーチミンに同様の日本料理店をオープンし、他のビジネスにも乗り出している。
「日本の細やかな商品やサービスは東南アジアでも望まれている。日本人は自分たちが持つそうしたDNAをうまく生かし、競争意識を持てば十分勝負できる」。今井さんは中国、ベトナムでの体験をもとに切実にこう訴える。
川崎重工と三井造船はともに造船部門が起源ですが、国内の造船は需要が落ち込んでいるほか世界市場では中国や韓国が大きなシェアを占めています。関係者などによりますと、このため両社は将来的な経営統合を視野に入れた交渉を始める方向で調整しているということです。
重工業では、成長が見込めるエネルギー関連のプラントや洋上開発など幅広い分野での開発力が必要となっていて、統合によってこうした分野の競争力を強化する狙いもあるとみられます。
両社の連結の売上高を合わせると2兆円規模となり、統合が実現すれば三菱重工業に次ぐ巨大企業が誕生することになります。(
The daily Turun Sanomat reported Wednesday that the South Korean-owned shipbuilder STX Corporation is teetering on the brink of bankruptcy. On Tuesday the shipbuilding unit STX Offshore and Shipbuilding voluntarily filed for debt restructuring with its creditors. According to Turun Sanomat, this year alone, the company will have to fork out over one billion euros to repay its debts.
The crisis appeared to be deepening, as STX revealed last weekend that it had failed to offload its bulk carrier shipbuilding affiliate STX Pan Ocean. On Tuesday shares in STX Offshore plummeted 15 percent. Shares in the parent company STX Group also shed 15 percent in value. The decline is the largest permitted on the Seoul stock exchange.
According to the Reuters news agency, financiers will be looking this week to stabilise the company. Meanwhile Korean analysts say one possible option would be for majority shareholder in STX, the state-owned Korean Development Bank to assemble an ownership cluster to take over the beleaguered shipbuilder.
STX has already sold off a considerable chunk of the business group. Late last year the Italian shipbuilder Fincantieri shelled out 455 million euros to purchase for a majority stake in the offshore shipbuilding business STX OSV.
STX also struggling in Finland
STX runs two shipyards in Finland in Rauma and Turku, both in southwest Finland.
Earlier this year the Finnish government drew up a programme of some 40 million euros in subsidies to help the company's Turku-based shipyard to secure two luxury liner orders that could help secure its future. The Turku operation had previously lost a lucrative luxury cruise liner offer to another STX shipyard in France.
The Turku shipyard also raised an additional 23 million euros in a buy and lease-back arrangement in which the government purchased the Turku property to lease it back to the shipyard.
負債額は約2億円。
受注減と構造的な落ち込み。
尾道海上保安部の発表によると、フェリーはこの日朝、造船工場の約600メートル沖にエンジンを止めて停泊。浜本さんは計器類の点検などのため、軸の上に座って作業をしていたという。同保安部は、別の作業員が浜本さんに気付かず、エンジンを始動させたとみている。
フェリーは青森県と北海道函館市を結ぶ航路で用いられるため、今月27日に納入予定だった。
建造費は26億円。事業主体は大間町で、県から5億円の支援と、鉄道建設・運輸施設整備支援機構から5億円の融資を受けて建造。運航は青森~函館フェリー航路などを有する津軽海峡フェリーが行う。
大函丸は2013年4月、老朽化した現行船・ばあゆ(1529トン)を置き換えるかたちでデビューする予定。この新造船の就航にあわせ、大間港に新ターミナルもオープンする。
《大野雅人》
多度津工場の従業員約260人は常石工場(広島県福山市)やグループ企業に配転する。一方、月内をめどに同業他社に多度津工場の売却を打診しており、交渉がまとまらなければ年内にも閉鎖する。地元の多度津町は「影響については現在調査中だが、閉鎖した場合は地元雇用だけでなく、税収に関しても億円単位の影響が出るとみている。具体的な対応策は会社の方針がまとまってから決めたい」と話している。
多度津工場は1977年に経営破綻した旧波止浜造船の工場が前身。ツネイシHDは76年に旧波止浜造船と提携、経営破綻後の80年に傘下に収め、2000年に吸収合併した。最盛期の06年3月期には13隻建造していたが、11年12月期は7隻にとどまっていた。70~80年代の造船不況を構造改革で生き延びた多度津工場も今回の荒波は乗り切れなかった格好だ。
同社はここ数年、円高が進む中で建造コストを抑えるため中国・舟山とフィリピン・セブ島の造船子会社に新造船の建造を振り向けている。12年12月期は新造船62隻のうち中国が20隻、フィリピンが19隻、国内が23隻(常石12隻、多度津11隻)だった。今後は常石工場と中国、フィリピンの3拠点で生産する。
造船大手の生産撤退は12年6月の三菱重工業の神戸造船所(神戸市)での商船生産の撤退に次ぐもの。
韓国と中国に押されて受注が激減するなか、常石造船は香川県多度津工場の閉鎖を検討していることが明らかになりました。
広島県に本社を置く常石造船は、詳しい時期は明らかにしていませんが、受注がほとんど無くなる2015年1月以降に多度津工場の撤退を検討しています。
他の会社への売却が出来なければ、閉鎖もあるということです。
常石造船多度津工場は、現在、従業員が260人、下請業者も35社ほどあり、閉鎖となると地域経済や地元自治体の税収減など大きな影響が出ます。
多度津町は今後影響額を試算することにしていますが、閉鎖となると、少なくとも億単位の税収減少につながる見通しです。
日本の造船業界は円高による価格競争力の低下を背景に韓国や中国に押されて受注が激減していて、作る船が無くなってしまう「2014年問題」として業界に暗雲が立ち込めています。
売却されたのは、ビナラインズ傘下のファルコン・シッピングが保有していた「スピーディ・ファルコン号」。2011年11月からクアンニン省ホンミエウ島に放置されていたが、昨年末に物資設備会社ベトシップに売り渡された。
ビナラインズは長年にわたって保有船を拡充してきたが、昨年経営難が明らかになって以来、保有船舶の外国港での抑留といった問題が次々に表面化している。昨年11月には、クアンニン省ハロン湾地域に数千トン級の貨物船が多数放置されている問題も報じられた。スピーディ・ファルコンもこの種の放置船の1つだ。
ベトナム登録検査局によれば、スピーディ・ファルコンは1981年に日本で建造され、載荷重量(DWT)は6万4,300トン近く。ファルコン・シッピングは08年に4,200億ドン(2,000万米ドル、18億円)で購入したが、ベトシップへの売却価格は6分の1の700億ドンだった。売却額を船の重さを示す排水量(1万1,408トン)で割ると、1トン当たり約600万ドンとなり、現在1トン当たり840万~890万ドンで取り引きされている鉄スクラップよりも安い。
ベトシップが買い取る前に、スピーディ・ファルコンは銀行融資の抵当に入っていたために差し押さえられていたもようだ。
北部ハイフォン市の中古船舶の売買専門業者によれば、海洋船舶は放置しておくと劣化が速く、1年間放置されただけで約20%値下がりすることがあるという。海運不況が追い打ちとなって、売値はさらに低下したが、業者は「それにしても6万トン級の船が700億ドンとは安すぎる」と話している。
同当局者は、「この数年間に北朝鮮に出入りした第3国の船舶は中国、カンボジア、ベトナム船籍の数百隻に達する。これら船舶が韓国と米国、日本、欧州連合(EU)の港に入ることを防ぐ入港規制案を関係国と積極的に検討している」と話した。この案が成立すれば国際社会は北朝鮮に事実上の海上封鎖を実施することになる。
同関係者は、「これまでの北朝鮮制裁は核と在来式兵器の封鎖に限定されてきたが、入港規制は北朝鮮の一般物資の輸出入に打撃を与え非常に実効性のある制裁になるだろう。入港規制案に中国は消極的な姿勢を見せる可能性は高いが、北朝鮮が毎年10億ドル以上稼いでいる石炭輸出も中国の船舶で行われているだけに中国の参加を積極的に要請する方針だ」と話した。
外交通商部関係者も「李明博(イ・ミョンバク)大統領が先月31日の緊急外交安保長官会議で下した指示により、北朝鮮の1度目と2度目の核実験直後に採択された安保理決議1718号、1874号、2087号より範囲が広く強度も高い追加の北朝鮮制裁案を日米中と議論している」と伝えた。韓国政府は1日から1カ月にわたり安保理議長国を務めることから、すでに米国とは北朝鮮制裁決議案の草案をまとめており、草案には入港規制と金融制裁など「実効性のある」制裁を含むことを検討しているという。
金融制裁案には▽北朝鮮指導層の海外資産凍結▽北朝鮮のマネーロンダリング窓口の疑いがある口座を凍結させるバンコ・デルタ・アジア(BDA)方式の制裁▽北朝鮮の金融機関と取り引きする第3国法人を制裁する「2次ボイコット」などが検討されているという。
韓国政府はすでに昨年12月12日に北朝鮮の長距離ミサイル発射直後に米国とこのような骨子の北朝鮮金融制裁案を検討しており、今回はこれら金融制裁のうち一部が必ず含まれるだろうと関係者は話している。
しかし北朝鮮外務省報道官は2日、「われわれの光明星3号2号機の打ち上げは不当に問題視し、南朝鮮(韓国)の羅老(ナロ)号打ち上げは庇護し肩を持つ米国の破廉恥な二重基準はわれわれの超強硬対応を免れられないだろう」とし核実験強行の方針を示している。
北朝鮮の対南窓口である祖国平和統一委員会もこの日、「南朝鮮が北朝鮮制裁に加担すれば報復は免れられないだろう」と威嚇した。
韓国政府高位関係者は北朝鮮が3度目の核実験でプルトニウム爆弾を使う可能性が高く、爆発力は1945年に広島に投下された15キロトン級から20キロトン級の間が目標になるとみられると話した。同関係者は、「北朝鮮の2006年の1度目の核実験当時の爆発力は1キロトン、2009年の2度目の核実験の爆発力は2~6キロトンにすぎず核兵器とは認めにくかった。したがって3度目の核実験では15キロトン級以上の爆発力を誇示し国際社会に核保有国であることを強弁しようとするのが北朝鮮の意図だ」と話している。(中央SUNDAY第308号) .
西南圏の最大産業団地であるデブル産業団地が崩壊危機を迎えている。 グローバル造船不況が長期化し、休・廃業または操業を中断する会社が続出している。 デブル産業団地は入居会社の74%の218社が造船関連業種。 このうち正常に操業している会社は半分にもならない。 枯死危機に直面している中小企業とは違い、現代三湖重工業や大韓造船は正常操業しているが、確保した受注量が減り、さらなる打撃が避けられない状況だ。 現代の場合、受注量が2011年末の178万CGT(標準貨物船換算トン数)から昨年末には88万CGTへと半減した。
デブル産業団地は現在、約40社が4大保険料を出すことができず、財産が差し押さえられた状態だ。 入居会社の2割が100万-300万ウォンの保険料を4カ月以上支払えないほど経営は悪化している。 デブル経営者協議会のコ・チャンヒ会長は「08年のグローバル危機後、造船関連会社の受注量が60%ほど減り、生存危機を迎えている」と語った。
受注難と経営悪化のため、企業は業種転換に活路を見いだそうとしている。 造船業種と似た海洋プラントや風力発電の方向に進出しようということだ。 すでに業種を転換または検討中の企業は50社を超える。 しかし投資費用が大きいうえ、技術障壁が高いのが悩みだ。 全南発展研究院のオ・ビョンギ経済社会研究室長は「デブル産業団地の産業多角化に向けた金融および技術支援が必要な状況」と述べた。
事情がこうであるため、雇用問題も深刻だ。 デブル産業団地の職員は現在1万1150人で、08年当時に比べてやや増えた。 しかし韓国人は減り、60-70%は相対的に賃金が低い外国人労働者で埋まっている。 職場を失った韓国人は全羅北道群山などに移っている。
◇デブル産業団地=全羅南道霊岩郡で89年10月に着工され、97年8月に完工した総面積1036万7000平方メートルの産業団地。 08年1月当時、李明博(イ・ミョンバク)次期大統領が指摘した「産業団地内の電柱問題」がイシューになるほど活況だったが、グローバル危機後は下降線をたどっている。
約100人が、ブラジルで造船所を立ち上げてドリルシップ(資源採掘船)を建造するための「指導員」の役割を担うが、じつに約2万キロの、南半球の異国への「転勤」になる。
ブラジルでの新規事業を立ち上げる、チャレンジ
同社はEEPと合弁会社を設立し、ブラジル・バイア州に約900億円を投じて敷地面積160万平方メートルの大型造船所を建設。ここに坂出工場に勤める約100人を、2015年までに送り込む考えだ。
具体的な異動の時期や条件はまだ決まっていない。同社は、「たしかに100人もの従業員が海外に移ることはめずらしいかもしれません。ただ、これは国内事業の縮小や現地での人手を手当てすることが目的ではありません。ブラジルでの新規事業を立ち上げる、チャレンジであり、現地での造船業を拡大し、発展させるためです」と説明する。
ブラジルではドリルシップを建造するノウハウが不足していて、「それを支援して、指導的な役割を果たしてもらいます」という。
川崎重工は、中国にも2か所(南通市、大連市)に造船所をもっている。しかし、中国は現地雇用でまかなっていて、日本人は幹部らがそれぞれ10人程度が派遣されているだけ。「生産工は(中国から)日本に来てもらい、1年ほど技術を学んでもらっています。その後、戻ってから現地指導にも当たっています。ブラジルは距離的なこともあり、そのようなことができない事情もあります」と話す。
同社では、コンテナ船や鉄鉱石や石炭を輸送するばら積み船などの汎用船の建造を中国で、またドリルシップはブラジルと、世界で船を造り分けていくことも考えているようだ。
中国、韓国が圧倒 しぼむ日本の造船業
一方、日本の造船業は縮小傾向にある。世界の造船需要は2008年のリーマン・ショック以降に縮小しており、少ない需要を中国と韓国、それに日本が奪い合っている。中国や韓国の造船会社との競争が激しくなり受注が激減。加えて、海運不況で船の価格が下落した。そこに1ドル75円~80円という「超円高」が、日本勢をますます劣勢に追い込んだ。
日本造船工業会によると、2011年の世界シェア(国別受注量)は中国が約1911万トン(33.6%)、韓国が約2513万トン(44.2%)、日本は約769万トン(13.5%)と、中国に約2.5倍、韓国には3倍超の差をつけられた。
川崎重工も例外ではない。同社の2011年の国内建造量は約84万トン。ピークの06年(約114万トン)から3割弱も縮小した。造船部門の13年3月期の営業損益は20億円の赤字(前期は39億円の黒字)に転落する見通しで、収益改善に向けて抜本的なテコ入れ策を加速させる必要が出てきたわけだ。
坂出工場は配置転換の対象となる180人のうち、100人をブラジルに、80人は2013年度内にタービン機器や航空機向け部品などを生産する神戸工場や名古屋工場などに移す。今後は付加価値の高い液化天然ガス(LNG)船の建造に特化する。

Vosco Sunrise, which is 190 metres long and 32.26 metres wide was designed by Japanese company IHI Marine United Inc and certified by the Japanese ship classification society NK and the Vietnam Vehicle Registration Agency.
The bulk carrier features five holds and four state-of-the-art cranes and is powered by an 8,890 kW main engine.

The ship, 190 meters in length and 32.26 meters in width, has a total capacity of 7,110kW. It is designed by IHI Marine United INC and under the supervision of Japan Register and Vietnam Register.
The modern cargo ship was built by Vietnam to bring its trademark to the world. The Ministry of Transport asked Nam Trieu Shipbuilding Industry Corporation to closely coordinate with the ship owner and registration agency to complete all procedures and put the ship into operation in the first quarter of 2013.
造船関連の配管工事を主体とする(株)大西組[広島県尾道市因島田熊町4331-3,大西謙治郎代表,資本金1,000万円]が、(株)共栄造船の本社地を整理回収機構から購入し、平成16年11月より造船業に進出。その後の平成17年3月に、法人成した経緯にある。ケミカル船などの建造を主力に、造船業界の活況を背景として 業績は伸長傾向を辿っていた。
しかし、急速な事業拡大に伴い資金面は多忙化。加えて、平成20年以降は、 世界的な景気後退が進み、受注面が急速に悪化。取引先に対して支払延期を要請 する他、手形決済への支払条件変更も打診するなど逼迫した資金運営が続いて いた。しかし、資金面は好転せず、21年6月に民事再生法を申請した。
その後、法的措置による再建に取り組んでいたが、造船業界は益々厳しさを増し、売上規模は大幅に縮小、直近24年3月期には2億円内外まで減収が進んでいた。業況改善に至らず、24年6月頃には全従業員が当社を退職する流れとなり、民事再生法による再建を断念、破産申請へと切り替えるに至った。
破産開始の決定を受けていたのは、「MERIDIAN BULKSHIP」「MELODY BULKSHIP」「CENTURY BULKSHIP」「CONCORD BULKSHIP」「COURAGE BULKSHIP」「VENUS BULKSHIP」の6社。 6社とも三光汽船の関係会社。リベリア事業会社法に基づいて設立され、船舶所有を目的としていた。申立時点で確定している債権者に対する負債は6社で合計46億2000万円。これ以外に金額の未確定分があり、総額はさらに膨らむ見込み。
三光汽船は7月2日、東京地裁に会社更生法の適用を申請し経営破綻。その時点では、上記6社はまだ船舶を所有しておらず、国内造船会社から船舶を買い取る予定となっていた。また、三光汽船の会社更生手続が行われている中で6社の船舶の必要性が薄れ、6社は10月10日に三光汽船の本社同所に営業所を設置したうえ、総合的な判断として今回の措置となった。
同様の措置となったリベリア事業会社法に基づき設立された三光汽船の関連会社は、10月25日に破産開始決定を受けた「PEARL BULKSHIP」(負債総額23億3056万円)に続き、累計7社となった。
MELODY BULKSHIP LIMITED(同、日本事務所:同、代表:同)
CENTURY BULKSHIP LIMITED(同、日本事務所:同、代表:同)
CONCORD BULKSHIP LIMITED(同、日本事務所:同、代表:同)
COURAGE BULKSHIP LIMITED(同、日本事務所:同、代表:同)
VENUS BULKSHIP LIMITED(同、日本事務所:同、代表:同)
の6社は11月21日、東京地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には、坂口昌子弁護士(電話03-3212-1451)が選任されている。
負債額は、MERIDIAN社が約6億円、MELODY社が約6億円、CENTURY社が約7億円、CONCORD社が約7億3千万円、COURAGE社が約7億3千万円、VENUS社が約12億6千万円の合計額は約46億円。
上記6社は、約1558億円の負債を抱え、7月2日会社更生法を申請して経営破綻した三光汽船(株)の関係会社であり、船舶は所有していない。三光汽船の破綻で同様な措置が取られたのは、10月25日に負債額約23億円を抱え、破産開始決定を受けたPEARL BULKSHIP LIMITEDがあり、関連7社が破産した。
河本さんも泣いていることだろう。
同署などによると、男性は高さ40メートルのクレーンのそばで鉄板をつり上げて移動させる作業を行っていたという。鉄板の一部が地面についた状態でクレーンから外れて男性の方に倒れたとの目撃情報もあり、同署などが詳しい事故原因を調べている。
川重の造船部隊は今年6月末、6年ぶりにLNG(液化天然ガス)運搬船の受注を獲得した。関西電力が輸入するLNGを運ぶための船で、関電と長期運行契約を交わした商船三井からの発注だ。LNG船は商船の中でも工事規模が大きく、金額は1隻で150億円を下らない。川重にとってうれしい受注のはずだが、神林常務の表情は険しい。
1年前、川重はLNG船を複数受注する絶好のチャンスを得た。大阪ガスが2隻のLNG船新設を決め、発注先の選定を進めていたからだ。LNG船建造は韓国が主役になって久しいものの、日本のユーザーに限れば、長年の信頼関係がある国内造船所への発注が今も常識だ。しかも、関西発祥の川重は大ガスと取引関係が深く、大ガスのLNG船は主に川重が手掛けてきた。
ところが、川重の期待に反し、実際に仕事を請け負ったのは三菱重工業だった。しかも、2隻ともだ。大ガスからの受注に際して、三菱重工は新設計のLNG船を投入。球状のタンクを丸ごと覆った新構造で走行時の空気抵抗を減らしたほか、内燃機関なども全面的に見直し、同社の従来型船より燃費性能を2割以上改善させた。そして、この最新鋭のLNG運搬船を、川重より安い価格でぶつけてきたのだ。
三菱重工の造船事業は1000人以上もの開発技術者を抱え、平均給与水準も高い。固定費負担が大きい分、本来なら、造る船の値段は他社より高くなる。「三菱の出してくる見積額がいちばん高い」(国内の大手海運役員)。それは海運・造船業界における長年の常識だった。
大ガスで失注した川重は、「今回は何としてもうちが全部取る」と決死の覚悟で関電向けLNG船の受注交渉に臨んだ。発注されるLNG船は2隻で、競合相手は再び三菱重工。お互い一歩も引かず、価格競争は熾烈化。最終的に関電案件は川重、三菱重工が1隻ずつ受注する形で決着したが、両社とも採算割れの赤字受注だったと見られている。
日本を代表する重工2社による、身を削るかのような受注争奪戦。その背景にあるのは、迫り来る「2014年問題」への強い危機感だ。
■ 船腹過剰で受注激減 仕事払底の危機が迫る
近年、世界の造船業は空前の好景気に沸いた。中国爆食などを背景に2000年代半ばから海運市況が高騰し、世界中の海運会社、船主が競って新船の仕込みに走ったからだ。海運バブルが造船バブルを呼び込み、それまで年間3000万総トン(総トンは船の容積を表す単位)前後だった新船需要は激増、ピークの07年には1・7億総トンにまで膨れ上がった(下グラフ参照)。
当時、韓国勢の追い上げで劣勢に立たされていた日本の造船業界は、この“神風”でにわかに活気を取り戻す。国内外から次々に舞い込む新船建造の依頼。各社とも受注残(=手持ち工事)は建造能力の数年分にまで積み上がり、たちまち国内の造船所はどこもフル操業に。10年には初めて日本の竣工量が2000万総トンの大台を超え、12年も国内造船所の稼働率は依然高い。
にもかかわらず、日本の造船業界は今、暗いムードに包まれている。なぜか。将来の飯の種となる新規の受注が激減しているからだ。リーマンショック前に発注された大量の新船がこの2~3年で続々と竣工した結果、海運業界はたちまち船腹過剰に陥り、運賃市況が暴落。その余波が造船業界にも及び始めたのである。
日本造船工業会によると、国内の主要造船会社による11年の新船受注量は770万総トンと前年から4割近く減少。リーマンショック直後の09年実績(850万総トン)をも下回り、過去15年間で最低水準にとどまった。12年に入っても同様の状況が続いているため、手持ち工事量は目に見えて減っている。6月末時点の受注残は約3000万総トンとピークだった07~08年当時の半分弱で、しかも、その大半が13年末までに竣工・引き渡しを迎える。
つまり、このまま新規の仕事が取れずに受注残の取り崩しが進めば、「国内造船会社の多くで14年途中に仕事が底を突いてしまう」(国土交通省の今出秀則・海事局船舶産業課長)のだ。これが日本の造船業界に迫る“危機”の正体、いわゆる「2014年問題」だ。
■ 船価はピークの半値 日本勢は円高も打撃
すでに一部の造船所では、危機が現実のものになりつつある。
住友重機械工業の造船子会社、住友重機械マリンエンジニアリング。石油タンカーを専門とする同社は、2年近くにわたり新規受注が途絶えている(10月末現在)。契約どおりに今年度5隻を引き渡すと、残る手持ち案件はわずか1隻のみ。来年度以降の大幅な操業縮小は避けられず、横須賀造船所の正社員約500人の大半をグループ他事業へ配置転換するなどの対応策を検討中だ。
何しろ、業界の受注環境は悲惨な状況だ。量の減少に加え、船価は数年前の半値近くにまで下落(下グラフ参照)。金額だけを見るとバブル前の水準に戻っただけのようにも見えるが、製造原価の過半を占める鋼材価格は当時の倍近い。今の船価は、コストの安い中国、韓国勢でさえ赤字になる水準だ。
さらに日本勢を苦しめるのが昨今の円高だ。造船所の品質と生産性は現場作業員の技能・熟練度に左右されるため、造船業界は他の製造業のような海外生産移管が進んでいない。一方、海運会社や船主からの建造発注は米ドル建てなので、円高進行はまさに死活問題である。
「こんな相場では、(受注を)取れば取ったで大きな赤字が出る。仕事欲しさに無理して取れば、自分で自分の首を絞めることにもなりかねない」。大手造船の幹部はこうこぼす。将来の操業対策と受注採算の板挟みで、各社は頭を悩ませている。
振り返れば、日本の造船業界は、1970年代、80年代と2度にわたる「造船大不況」期を乗り越えた。しかし、当時と今では、競争環境がまるで違う。当時の日本は新船竣工量で5割以上のシェアを誇り、世界最大かつ最強の造船国だった。その後、90年代に韓国、さらに00年代半ば以降は中国も急激に台頭。すでに日本は竣工量で両国に抜かれ、シェアも2割程度にまで下がっている。
■ 需給ギャップは深刻 韓・中との競争熾烈に
こうしたアジア勢の設備新設・拡張によって、業界の供給能力(=建造能力)は一挙に膨れ上がった。その規模たるや、年間1・1億総トン超。一方、12年の新船発注量はせいぜい三千数百万総トンと見られており、供給能力は足元の需要の3倍にも及ぶ計算だ。「異常としか言いようがない。再び造船バブルでも起こらないかぎり、この需給ギャップは到底埋まらない」(日本造船工業会の桐明公男・常務理事)。
新規の需要が細る中、すでに設備を持て余した中国、韓国勢は、採算度外視の受注に走っている。日本の造る船は品質や省エネ性能で勝るため、必ずしも同じ価格にまで下げる必要はないが、「限られた仕事に日、韓、中の造船所が殺到しているので、発注側から容赦なく値切られる」(三井造船の岡田正文・常務取締役)。ライバルの数は、過去の第1次、第2次不況時の比ではない。
にわかに業界の危機感は高まり、生き残りに向けた新たな動きも出始めている。
「ある程度の規模なしには、韓国、中国勢と戦えない。規模の効果で資材調達費を削減する一方、省エネ船の開発により多くの技術者を投入する」。今年12月に合併する、IHIマリンユナイテッドとJFE系のユニバーサル造船。新会社の社長に就くユニバの三島愼次郎社長は、合併会見で危機を強くにじませた。
■ ユニバ、IHIマが合併 三菱重は客船を柱に
両社は08年春に合併の検討開始を表明。狙いは需給逼迫下での建造能力拡大にあったが、思惑の違いなどからやがて実務協議は途絶え、合併構想は立ち消えに。その後、海運バブル崩壊で事業環境は激変、11年秋に協議を再開して合意に至った。当初の合併検討表明から4年の間に、再編の目的は「成長・拡大」から「生き残り」へと様変わりした。
一方、独自の戦略を打ち出したのが三菱重工だ。コンテナ船など汎用領域の一般商船から撤退し、今後は技術的な強みが生かせる領域に経営資源を集中させるというのだ。その柱に位置づけるのが、冒頭にも登場したLNG船、そして国内では異例とも言える大型客船である。
同社は昨年秋、クルーズ客船の世界大手、米カーニバル・グループから客船2隻の受注を獲得。定員3000人以上の超大型客船で、2隻合わせた受注金額は推計で1000億円前後に上る。三菱重工では02年に建造中の大型客船が炎上、造船事業は巨額の赤字を出し、以降は受注も途絶えていた。約10年ぶりとなる今回の受注。尊田雅弘・客船プロジェクト室長は、「客船をコア事業にするという明確な意思決定の下、会社として総力を挙げて取りに行ったからこそ受注できた」と語る。
大型客船は部品総数が1000万点と膨大で、ピーク時には3000人規模の作業員を要する。工事が大掛かりで工程管理などが非常に難しいため、一般商船と違ってアジア勢の姿はなく、独マイヤー、伊フィンカンチェリなど客船を専門に手掛ける特定の欧州企業が一手に建造を担っている。こうした欧州勢の中に割り込み、独自の柱に育てようというわけだ。
その三菱重工の造船部隊を率いる原壽・常務執行役員(船舶・海洋事業本部長)は静かに、そしてはっきりとこう言い切る。「これから先は、われわれ日本の造船業にとって過去最大の試練になる。何も手を打たなければ死ぬ。それは当社の造船だって例外じゃない」。
国内勢には平均1・5年分の仕事(=受注残)がまだあるが、それはあくまで“量”の話。造船バブル時に受注した好採算の船はほぼ一巡し、今後は船価暴落後の受注案件が工事の大半を占める。目先の操業は維持できても、大幅な採算悪化は避けられず、来13年度には赤字転落組が続出する見通しだ。大氷河期は目前に迫っている。
(週刊東洋経済11月17日号)
同社のイ・ジョンファン企画文化室チーム長は「道路、工場が部品を運ぶトラックやフォークリフトなどで混み合い、クレーンの音が耳に響くのが通常の状態だ」と話した。
影島造船所では従業員約700人のうち約290人が特殊船舶の建造作業に当たり、残る約410人は休業中だ。こうした中、同社は今月9日、1年9カ月前に整理解雇した従業員92人を復職させた。昨年の労働団体やリベラル系政治団体などがバスを動員して実施したデモ、クレーンにろう城しての会社側への圧力、国会環境労働委員会の勧告などに従い、趙南鎬(チョ・ナムホ)会長が92人を1年以内に再雇用することを約束していた。
復職した92人は、12日午前9時から午後1時まで釜山市南区の同社技術研究院で会社側の説明を受けた。しかし、92人は13日から予定にない休業に入ることになった。
会社側によると、受注減で従業員を休業させる場合、通常の賃金の全額に当たる月200万-250万ウォン(約14万6000-18万2000円)を支払わなくてはならない。子女の学費、医療費、保険など福利厚生費まで含めると、1人当たり400万ウォン(約29万円)かかる。会社は売り上げがなくても、毎月約20億ウォン(約1億4600万円)の人件費負担を強いられる計算だ。
商船作業ゾーンの2番岸壁には中国や日本の旅客船3隻が接岸しており、作業場の片隅ではSK建設がコンクリート構造物を建造していた。イ・チーム長は「船舶受注がないため、旅客船の修理作業、港湾用防波堤に使うコンクリート構造物の建造に必要なスペースを船会社、建設会社に貸している」と説明した。本来造船に使うべきスペースを貸して、収入を得ている形だ。造船所は船を作らずに「不動産リース業」に転落してしまっていた。
同社のイ・ジェヨン社長は「昨年6月にある船会社と船舶の建造意向書を結んだが、ストライキの長期化、労働団体や政界による介入で契約には至らなかった。欧州財政危機の前だったため、会社経営を正常化するチャンスだったが、外部の介入で機を逸した」と話した。イ社長は「会社の正常化が遅れ、下請け企業の従業員約3000人が職を失った」とも語った。
2008年9月以降、船舶の新規受注がない韓進重工業は、今年の売上高が好況期の8分の1の2000億ウォン(約146億円)程度にとどまる見通しだ。同社関係者は「政府系企業でも慈善事業でもない民間企業が経営上の判断でリストラを実施したにもかかわらず、政治的な論理で外部から振り回されてもよいのか。昨年政界が調停案を勧告した際『会社の正常化を支援する』と言っていたが、全く支援など得られていない」と不満を漏らした。
復職した従業員も喜んでばかりいるわけではない。ある従業員は「復職できたうれしさもあるが、受注がないことが心配だ。このままでは共倒れになるのではないか」と話した。復職した従業員の一部は会社側の説明会後にアルバイト先へと向かった。
慶尚南道(キョンサンナムド)統営には中小造船会社が集まっている。三湖(サムホ)造船所はすでに廃業し、21世紀造船も近く閉鎖する。長びく不況のせいだ。新亜(シンア)SB造船など残った会社も厳しい状況だ。新亜SB生存汎市民対策委員会のキム・ミンジェ委員長は、「月給もまともに受け取れずにいるのに会社と債権団は何の対策もなく時間なかり引き延ばしている。造船業は基幹産業といいながら政府は生かす意志を持っているのか疑わしい」と声を高めた。浦項にも不況の余波が広がっている。浦項商工会議所が地域の製造業者82社を対象に第4四半期の景気見通しを調査した結果、企業景況指数(BSI)は66となった。2009年第2四半期以後で最も低い。企業がそれだけ不況を体感しているということだ。
浦項の鉄鋼産業は造船・建設分野の不況のため3年ぶりのマイナス成長が予想される。浦項税関の通関量を基準として9月の輸出は8億1000万ドルと前年同期より23%減った。浦項商工会議所対外協力チームのペ・ヨンジョ次長は「1998年の通過危機、2008年のリーマンショックでも浦項はよく耐えたが、最近はとても厳しい」と話した。問題は解決策が見られないということだ。
世界トップの造船会社である現代重工業は先月22日から希望退職の申し込みを受け付けている。9日までだ。対象は50歳以上、課長級以上の事務・技術職だ。予想規模は2000人余り。だが、1日現在で50~60人しか申請していないという。退職金だけでなく慰労金として1人当たり3億~4億ウォン(基本給の60カ月分)を追加で支払う条件なのにだ。ある従業員は、「会社を出てもこのような不況ではやることがないためだ」と話した。会社は「人材構造調整ではない」と強調する。課長・部長級がとても多いゆがんだ人材構造を変えようとするものという説明だ。だが、従業員は額面通りには信じていない。
現代重工業の希望退職は創立40年で初めてだ。定年をこれまでの58歳から60歳に延長してから1年も経っていない。しかし造船業況が最悪水準に落ち込み状況はすべて変わった。同社の受注量は10月末までで年間目標の半分をようやく超えた。受注残高も過去最高を記録した2008年の3分の1にも満たない。労組関係者は、「口に出さないだけで希望退職がさらに大幅な構造調整につながらないか不安に思う」と話した。市内の食堂の店主は、「現代重工業の会食は月に2~3回あったが、今月に入って急になくなった。希望退職で雰囲気が沈んだためのようだ」と伝えた。
By Jemma Castle, Lloyd's List Australia
(This article first appeared on Lloyd's List Australia on Nov 13, 2012)
Federal government should carry out an inquiry into the three deaths on board the Japanese owned and operated bulk carrier Sage Sagittarius (IMO 9233545), according to the International Transport Workers’ Federation (ITF).
“I haven’t seen in all my years at sea, anything that resembles this. I haven’t seen two [deaths], let alone three, so closely together,” said ITF coordinator Dean Summers [pictured in thumb image].
Currently, the incidents aboard the Panama-flagged Sage Sagittarius are subject to three separate investigations – by the Australian Federal Police, by the New South Wales Police and by Japanese authorities.
As the flag state, Panama has a responsibility to investigate the deaths.
However, the ITF says the Panamanian authorities have not done anything yet.
Although Lloyd’s List Australia has made inquiries, we have been unable either to verify or refute this statement, at the point of publication.
“We’re calling for a coordinated response that sees across these jurisdictions.
"It’s difficult to work in those four jurisdictions but our Federal government has got a responsibility to do that.”
The office of the minister for justice Jason Clare received the ITF’s call for an inquiry about a week ago.
A spokesman for Mr Clare said that it is still under consideration.
The ITF is currently undertaking a "week of action" at Newcastle's port to inspect ships sailing under what the ITF describes as “flags of convenience”, a union-term for ships flying the flags of open registries.
Panama-flagged ships are on the White List of the Paris MoU – a port state control safety reporting body.
In the period 2009 to 2011, Panama-flagged ships were inspected 7611 times by port state control inspectors resulting in 345 detentions.
Sage Sagittarius (IMO 9233545) is a 105,708 dwt, 2001-built, dry bulk carrier, according to Equasis and Lloyd’s List Intelligence.
It is owned and operated by Hachiuma Steamship of Japan, which is a subsidiary of shippingcompany NYK.
It is supposed that the victim had been crushed in a conveyor belt.
Why is this suspicious? Investigations will answer this question.
The first victim was a Filipino chief cook who disappeared off the Queensland coast 2 months ago. 2 weeks after the first tragic incident ship's chief engineer, Hector Collado, 55, died in Newcastle.
All people part of the crew were deeply shocked and they were sent home by the shipping company.
Nippon Yusen Kaisha will investigate the incident with closer cooperation with Newcastle and Sydney staff.
9月15日付で、パナマ船籍、日本郵船所属、八馬汽船運営の「セージ・サジタリウス」で船員が海に転落して行方不明になり、他の船員が何者かを怖れて船室に立てこもっているという報道があったが、その後、さらに1人が階段から転落して死亡し、NSW州警察がその捜査を続けているが、10月6日にも、日本で荷揚げ中にさらに船員1人が死亡していたことが明らかになり、ABC放送が3件の死亡事件を取り上げている。
以下は、ABC放送の報道内容。最初の事件が起きたのは、8月末で、同船が、ケアンズの北東450カイリ(約830km)のチモール海公海上を航行中に船員一人が行方不明になった。海員労組では、「行方不明の船員は、労働条件で苦情を訴えようとしていた」との情報を発表している。この事故の捜査のため、同船はポート・ケンブラに停泊するよう命令を受けた。しかし、その後何日かして、同船がニューカッスルに入港する直前にさらに船員1人が階段から転落し、死亡した。この船員の死亡事故は、現在もNSW州警察が捜査を続けている。また、ポート・ケンブラでも最初の船員行方不明事故についてNSW州警察の捜査が続けられている。ところが、10月6日、同船が日本で積み荷の石炭を荷揚げ中に、八馬汽船に雇われていた社員がコンベヤー・ベルトに挟まれ死亡するという事故が起きていた。同船が、日本に向けてニューカッスル港を出港する前に、船員の安全を監督するため、その社員が同船に乗り込んでいたとされている。
国際運輸労連(ITF)のディーン・サマーズ氏は、「この3人目の死者は、何週間も報告がなかっただけに非常に怪しい。この事件は、オーストラリアの捜査員が同船のログブックに添えられたメモを見て初めて明らかになった。その監督は、船員の福祉と安全を守るために船に乗っていたのだが、10月6日に死亡したのがその監督だ。今日は10月29日だ。その事故が業務上の事故であれば、しっかりした当局なら、この事故に胡散臭さを感じてとっくに立件しているものと期待して当然だと思う。しかし、私たちの知る限り、そうはなっておらず、未だに捜査中ということだ。過去にも2件の疑わしい事件が起きていることを考えれば、すぐに結論を出すわけにはいかない。政府がタスクフォースを編成し、豪連邦警察、NSW州警察、日本の警察合同で直ちに3件の海員死亡事件を捜査すべきだ。」と要求している。
オーストラリアの警察は、なぜその船で3件も立て続けに死亡事故が起きたのかを今も捜査中だが、20年前に国際海運業界を変えた報告書を作成した人物は、「海運業界全体を再度捜査すべき時期だ」と語っている。「Ships Of Shame」と名付けられたその報告書は、老朽船が海員の安全衛生問題を引き起こしていたことと、海員の待遇問題について切り込んだもので、ピーター・モリス元連邦運輸大臣が、指揮して調査した。モリス氏は、「この報告書の後、国際海運業界はかなり改善された。しかし、セージ・サジタリウスで起きている事件は非常に問題だ。船員達は死亡事件について口外しないよう圧力をかけられているのではないか。1992年の調査時にも同じようなことがあった。船員達は脅されていたし、食事もろくに与えられなかった。外との連絡もできず、起きていることを外部に伝えることもできなかった。この船の状況を考えると、直ちに司直の手でこの船を捜査すべきだし、この船で起きていることは他の船でも起きている可能性があると考えるべきだ」と述べている。連邦警察とNSW州警察は今も最初の2件について捜査を進めている。(NP)
貨物船SAGE SAGITTARIUSは、徳山下松港の下松石炭中継基地で船倉の石炭をアンローダーによって揚げ荷役中、平成24年10月6日07時25分ごろ、自動荷役装置に関する保守、指導等のために乗船していた工務監督(Superintendent)がアンローダーのフィーダーコンベアローラーに巻き込まれているところを発見され、死亡が確認された。
本事故は、本船が、徳山下松港の下松石炭中継基地で船倉の石炭を1号機によって揚げ荷役中、フィーダーコンベアで異音が発生し、SIが、1号機が運転されている状態で本件ローラーへ注油して異音を止め、3時間ごとに注油することとしていたところ、本件ローラーで異音が発生しているとの連絡を受け、フィーダーコンベア通路で本件ローラーの注油作業を行っていた際、本件ローラーに巻き込まれたため、発生したものと考えられる。
下松署によると、門司さんはオーストラリアから船で運んできた石炭を陸揚げする
作業をしていた。同署は業務上過失致死の疑いがあるとみて、徳山海上保安部と合同で
詳しい状況を調べる
22日の現代重工業によると、この日から3週間、満50歳以上で課長級以上の事務・技術職を対象に希望退職申請を受け付けるという。 退職慰労金として、基本給に職責・地域福祉手当などを加えた基準賃金の最大60カ月分が支払われる。
現代重工業の関係者は「50歳から第2の人生を歩む準備をする期間を与えようという意味で行った」とし「希望退職制度を常時運営するのか、短期で終えるかはまだ決まっていない」と述べた。
しかし業界では、造船業界の不況が長期化する中、これに対応するために先手を打ったとみている。 現代重工業の今年の受注額(1-9月)は131億1600万ドルで、前年同期(220億1800万ドル)に比べ40%ほど減った。 同社は「財務健全性を向上させる」として7月に現代自動車株320万株を売却し、7047億ウォン(約500億円)の現金を確保した。
造船業界の関係者は「現代重工業は今年7月の賃金・団体協約で定年を満58歳から60歳に延長したが、高齢の職員が多く賃金の負担が大きいため、希望退職制度を導入したようだ」とし「商船の発注が急減した状況で従来の人材を維持するのは難しくなるため、リストラは加速するだろう」と述べた。
造船所の最も大きな競争力が人であるために可能なことだった。 韓国造船産業が船舶輸出分野で世界シェア1位である最近も、現場で船舶を建造するのはほとんど手作業で行われる。 船会社の要求通りに作るためだ。 数十年の経歴を持つ現場勤労者を「名匠」と呼んで待遇する理由もここにある。 後輩を育成し、世界市場で競争力を持つ船の建造を可能にする、造船所の財産だからだ。
しかし最近の造船産業の危機で、40年以上育成されてきた造船人材プールが崩壊している。 グローバル景気沈滞で船舶受注量が減り、ほとんどの中小造船会社がリストラに入った。 大韓民国の造船メッカとされる「南海岸造船ベルト」は倒産危機を迎えている。 統営の造船会社の新亜sbで会った職員は「食べていけないので、ベテランの船舶溶接工が田舎でビニールハウスの溶接をしている」と話した。
20年前の日本の状況も似ていた。 90年代の造船業界の不況で日本の造船分野の人材は各方面に散らばった。 危機を迎えた日本造船業界は主力業種を重工業に変更した。 大学からは造船関連学科が消え、現場では人材供給が途切れた。 その結果、また造船好況期を迎えた時には韓国に世界1位を明け渡した。 量的な側面でも造船産業の雇用効果は大きい。 工学翰林院によると、10億ウォン(約7000万円)を投資する場合、半導体産業は4.4人を、造船は12人を雇用する。 すなわち造船所一つが閉鎖される場合、地域経済も同時に揺れることになる。 統営市の場合、主要造船所の破産が続く中、人口が大きく減り、商店街も衰退している。 固城・金海・梁山などの造船所に部品を供給する機資材業者が集まる地域も危機を迎えている。
このように造船産業とその関連産業が形成するネットワークはぼう大でありながら目は細かい。 造船産業は、造船所の職員、納品会社の職員、地方自治体の住民をはじめとする数多くの人が当事者としてつながっている。 造船所一つが整理されて危機が終わるわけではない。 日本の前轍を踏んで世界トップの座を奪われないか心配だ。

中小造船所が密集している南海岸造船ベルトが崩れている。 10日の金融監督院(金監院)によると、国内中小造船会社23社のうち1社(シンアン重工業)を除いた22社がリストラ中だ。 この中には回生の可能性が見えず、破産が決まったところもある。 全羅南道木浦(モクポ)にある一興造船は企業再建手続きを中断し、近く売却手続きを踏む予定だ。 統営にある三湖造船は今年破産し、21世紀造船はまもなく廃業する。
こうした状況であるため、業種転換をした造船所もある。 釜山のオリエント造船は新規船舶の受注がなくなった中、船を修理する修理造船所として生き残りを図っている。 造船業界の関係者は「最近、船舶の発注が出てきても、金融業界が前受金払い戻し保証(RG)を発給しないため、受注できない中小造船会社が多く、不満が高まっている」とし「金融業界は中小造船会社を支援するより、整理する方向に決めたようだ」と述べた。
08年の世界金融危機以降、中小造船会社の危機は加速した。 欧州財政危機まで重なり、船舶の発注が途絶えた。 英国の造船・海運調査機関クラークソンリポートによると、07年の船舶発注量は9329万CGT(標準貨物船換算トン数)だったが、今年1-9月は1430万CGTにすぎない。 中小造船会社が直撃弾を受け、ともに造船ベルトを形成している機資材企業も危機を迎えている。 金海市ノクサン工業団地には機資材100社ほどが密集している。10年前から会社を経営してきたキム社長(50)は「主要取引先がリストラに入り、納品量が減っている。一日一日が厳しい」とため息をついた。
造船ベルトの崩壊は南海岸一帯に大きな影響を与えている。 造船5社がある統営の場合、1年間に人口が800人も減った。 統営商工会議所のパク・サンジェ副会長は「住民登録を移転していない造船所の職員まで合わせれば、もっと多くの人口が流出している」と述べた。
解体作業中だった台船上の港湾荷役用クレーン(高さ約50メートル)の垂直アーム装置が全焼し、約6時間半後に鎮火した。けが人はいなかった。
同社や同市消防局などによると、出火したのはアームの頂部に近いコントロール室付近。クレーンはベルトコンベヤーで石炭を上下に運ぶ装置で、当時は作業員約10人が解体作業に当たっていた。広署はバーナーの火花がアーム装置に残った石炭くずなどに燃え移った可能性があるとみて、原因を調べている。
出火場所が高所にあるため、消火作業には広島市消防局のヘリコプターや海上保安庁の巡視艇5隻が出動。陸海空から放水して消火に当たった。
中国船舶工業協会が8月28日に発表した船舶工業経済運行統計データによると、今年1~7月までの中国の主要造船指標が前年同期比で大幅に下落している。同統計データによると、1~7月までの中国造船竣工総量は3549万積載重量トンで、前年同期比77%減少した。1~7月までの新規造船受注総量は1164万積載重量トンで、同50.7%減少。さらに7月末現在の手持ち受注量は1億2348万積載重量トンで、同29.9%減となり、2011年末と比べて17.6%減少した。
イギリス造船・海運調査会社の「クラークソン・リサーチ」によると、1~6月まで中国造船業が獲得した造船受注件数は182隻で、昨年同期の561隻と比べて67.5%と激減した。さらに中国造船業ピーク時の2007年の2036隻と比べて、約91%と激減した。
受注が激減した影響で、過去1年間で生産停止に追い込まれた造船企業が多くある。民営中小造船企業が集中する浙江省楽清市経済および情報化局の統計によると、同市には約23社の造船企業があり、昨年下半期に正常生産をしていた企業の数がまだ13社あったが、現在7社にとどまっており、約3分の2の企業が生産停止をしたという。
また、民営中小規模を中心に倒産せざるを得ない企業も多くある。昨年10月浙江省寧波市では優良企業の藍天造船集団と恒富船業有限公司の2社が倒産した。今年に入ってから、2月に四川省重慶市金龍船業有限公司、3月に江蘇省南通市の南通恵港造船公司、5月に浙江省台州市の金港船業有限公司、さらに6月に中国と韓国の合資会社である遼寧省大連市の東方精工船舶有限公司が相次いで倒産した。
一方、造船大手企業も収益減で難局に直面している。2010年に香港株式市場に上場を果たした中国民営造船最大手の熔盛重工集団(江蘇省)が8月21日発表した『2012年中期業績報告』によると、今年上半期の同社の営業利益は54億6000万元で、前年同期比で37.2%減少した。また、同期の純利益が2億2000万元で、同82%減少。国内報道によると、同社が上半期での業績が純利益を出せたのは、政府当局から6億7000万元の補助金を受給したからだという。このような非経常的収益を除けば、同社の上半期の業績は赤字に転じる可能性が高かった。
また、国有企業で香港と上海両株式市場に上場している広船国際股份有限公司(広東省広州市)は政府からの軍需工事受注があったにもかかわらず、同社が8月24日発表した『2012年中期業績報告』によると、上半期の営業利益が34億3300万元で、前年同期比で約14%減少。また純利益が約8799万元にとどまり、同67%減少した。
さらに、昨年8月18日に英ロンドン証券取引所に新規株式公開(IPO)を実現した浙江省温州市にある民営造船大手の東方造船集団は、国内外景気の急速な冷え込みで負債総額が11億元に達したことで、同社の陳通考・会長が今年2月に行方をくらましたことを受けて、今年6月8日にロンドン市場から上場を廃止された。現在、中国農業銀行や中国建設銀行および上海浦東発展銀行が、東方造船を「船舶運営融資契約違反」「融資契約違反」などの理由で起訴し、浙江省寧波市海事裁判所にて審理中だ。
2006年、中国政府が造船業を国家重要戦略産業と位置付け、「船舶工業中長期発展計画」を発表した。このように政府からの強い後押しを受けて、安価な製造コストと人件費を武器に、中国の造船業が急速に発展し、韓国や日本に次ぎ世界3位になった。しかし、2008年世界金融危機発生で造船受注が大幅に低迷したことで、2009年中国政府当局が造船業を含む「十大産業振興計画」を打ち出し、国内船舶市場の需要拡大、金融機関の造船企業への融資枠拡大などを促した。その結果、2010年は上半期中国造船業が受注量、手持ち工事量、竣工量の主要指標で韓国を抜き、世界1位となった。国営大手や民営中小造船企業の数もピーク時には3400社に達し、一定規模以上の船舶工業関連企業が1630社あったという。
しかし、欧州債務危機の長期化や米国景気回復の遅れなどで受注が激減したことにより、中国造船業界の過剰生産能力問題が浮き彫りとなった。また、造船企業間の激しい競争により、新造船の価格が8年ぶりに最低水準に下落したため、受注があっても利益にならない状況がよくあるという。
このような状況を受けて、国内専門家や業界関係者は造船会社の大規模な淘汰が始まったとの見方をしている。中国船舶工業経済研究センターの首席研究員である張静氏は「北京商報」(7月31日付)の取材に対して、造船業界における倒産ブームはまだ始まったばかりだと示した。7月2日付国内紙「証券日報」によると、国営造船大手中国船舶工業集団公司の譚作鈞社長は将来2~3年間で約50%の造船会社が倒産に見舞われるだろうと話した。さらに9月4日付「中国経済週刊」誌は、資金調達難や受注激減などが中国造船業に深刻な打撃を与えており、最も悲観的な予測をするならば、打撃を受けた造船企業の数はピーク時の3400社から300社に激減するだろうと考えられるとの見方を示した。
11年の受注シェアで、中国は韓国の47.2%を大きく下回る29.0%と2位に後退。中国の造船業界団体の調べでは、今年1~6月の受注量は1074万載貨重量トン(DWT)で、前年同期比50.3%と半減した。
今年通年では日本を下回って中国が3位に順位を下げる可能性が指摘されているほか、「中国に約1600社ある中堅以上の造船会社の約3分の1が経営破綻に追い込まれ、業界再編が進む」と話す関係者もいる。
日韓に比べ安価な人件費を武器に、安値受注競争を繰り広げた結果、10年にはその反動で船舶が供給過剰となっていたところに、欧州債務危機のあおりで新造船の発注量が急速に落ち込んだ。景気変動への機動的な対応や、受注量の適切な調整といった長年の経験則に基づく経営判断ができなかった中国の造船業界の脆弱性が、露呈した。コンテナ船やばら積み船の世界的な運賃の値崩れで、発注元である海運会社が発注済みの船舶の引き渡し時期の延期や発注そのもののキャンセル、支払い停止が相次いだことも、受注残の多い中国を直撃した形だ。500社前後の造船所が操業停止に追い込まれる懸念があるという。
地元紙によると、大手造船では民間企業の重慶金竜船業が過去1年間に1件の受注もなかったとして今年2月から操業を停止。また国有の重慶長航東風造船も海外からの受注が1年以上もゼロとなり、経営が行き詰まっている。遼寧省大連の大連東方船舶重工も4月に操業を停止して、経営破綻状態にある。 上海船舶研究設計院の専門家は、中国の造船業界が「冬の時代」を迎えており、来年から16年にかけて一段と下降を続けるとの厳しい見方をしている。 日韓をライバル視した中国の造船業界は1990年代からコンテナ船や、LNG(液化天然ガス)船、タンカーなど大型の造船技術を急いで身につけ、2000年代に入り、ともかく安値で受注量を求め日韓を追い落とそうとした。だが過当競争が逆に、作れど作れど収益の上がらない「利益なき繁忙」を生み、中国造船業界にあっという間に「冬」が来たといえる。
身の丈を超えた受注競争を象徴する“事件”もあった。オーストラリアの資産家が4月、100年前に沈没した豪華客船タイタニックの仕様に近い豪華客船「タイタニック2号」を中国企業に発注したと公表した。だがその後、業界団体の調査で、受注したはずの江蘇省の中国外運長航集団船舶重工金陵造船所には、客室840室を備える豪華客船など建造する技術も能力もないことが判明した。
4年後の処女航海を予定していた「タイタニック2号」の建造計画は漂流中だが、その前に、中国の造船業界そのものが危険水域に近づいている。(産経新聞上海支局長 河崎真澄)
YUEQING, China — A shipbuilding boom raised the fortunes of this hardscrabble industrial port. Five-star hotels sprouted along with machinery depots and metal shops. European luxury cars darted past heavy trucks on the bustling streets.
But in another sign ofChina'seconomic slowdown, shipyards are now closing and half-finished vessels lie rusting in the humid haze. Prosperity is receding like the tide.
Thousands of laborers have lost their jobs. Liu Danyin, a compact man with bulging forearms, found so much work in the region's shipyards over the last decade that he built a new home for his family hundreds of miles away in the countryside. Then he was laid off suddenly last year.
"Many companies collapsed," said Liu, 48, who recently took a lower-paying job building a sea bridge. "There used to be so much energy and life here. Now they don't build ships anymore."
The hard times that have befallen Yueqing, a county in the eastern province of Zhejiang, are playing out at shipbuilding bases across China, from the northern port of Qingdao to the silt-filled Yangtze River in the central heartlands.
The bellwether industry's troubles have their roots in a shipping boom that started a decade ago. Global investors rushed to finance new vessels needed to haul coal and copper toChina'shumming factories and to transport finished electronics, toys and other exports out. China went from producing just over 100 vessels in 2002 to more than 1,000 in 2010, according to Worldyards, a Singaporean-based shipping industry research firm.
That over-exuberance resulted in a glut of ships. It's a problem that has worsened as China'seconomy has decelerated along with that of its major trading partners — Europe and the United States. Fewer customers for Chinese exports and a shrinking appetite at home for raw materials mean fewer vessels needed to carry that cargo.
Ship values have plummeted and many owners now owe more on their loans than their boats are worth. And all that capacity is putting downward pressure on shipping rates as Chinese transport companies seek new markets abroad to keep their vessels working.
"The building binge was overwhelming," said Ralph Leszczynski, the Beijing-based head of research at ship broker Banchero Costa & Co. "People earned so much money they didn't know what to do with it. The Chinese started opening shipyards every day. But it created a bubble. Now everyone is paying for the hangover."
Shipbuilding is typically a cyclical industry nagged by overcapacity every few years. But experts say this trough is being prolonged by the scope ofChina'sseafaring expansion.
Under central government guidance, China poured money into developing its shipbuilding and maritime logistics sectors, deeming them crucial for the nation's development.
China is home to six of the world's 10 busiest ports, including Shanghai, which is No. 1. The state-owned China Ocean Shipping Co. operates the globe's largest fleet of bulk carriers and fifth-largest fleet of container ships. China also dominates the manufacturing of cargo containers.
今井さんは言う。
「彼の言ったことは日本と中国・アジアでの人々の意識の違いを語る上で象徴的だと思った。日本人は商品やサービスに完璧さ、レベルの高さを求め、それが今も世界標準と考えているところがあるが、海外、特に東南アジア向けの展開では“安くてこのレベルでいい”という発想が必要。そうでないと中国などには対抗できない。だれも日常の消耗品に完全なものを求めていない。日本の価値観は今やガラケー化(世界標準から外れ孤立化)している」
今井さんは日本人相手の商売が次第に行き詰まったため、店は中国人に任せて湖南料理に業態を替え、自身は平成18年、ベトナムに進出。ホーチミンに同様の日本料理店をオープンし、他のビジネスにも乗り出している。
「日本の細やかな商品やサービスは東南アジアでも望まれている。日本人は自分たちが持つそうしたDNAをうまく生かし、競争意識を持てば十分勝負できる」。今井さんは中国、ベトナムでの体験をもとに切実にこう訴える。
海運業界では、大型船が大量に供給されたことで運賃が低迷。同社は2011年3月期の最終損益が約157億円の赤字となるなど資金繰りが悪化し、今年3月15日に事業再生ADRを申請。同月下旬には債権者会議を開き、借入金返済の一時停止について承認されたものの、所有する船を海外の船主に差し押さえられるなどのトラブルが発生。その結果、資金繰りが厳しさを増したこともあり、私的整理による再建を断念した。
"The company filed for bankruptcy in mid-June as it is unable to meet its debt obligations of over 300 million yuan ($47.1 million)," reportedly said Yu Shengyue, director of No. 2 Civil Tribunal of the People's Court of Wenling county, where the company is based.
The major creditors include the local branches of Construction Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China and Zhejiang Materials Industry Group Corp, a State-owned logistics company, according to Yu.
"The debtor and the creditors are considering reorganization, because the shipbuilding industry is not in good shape and the outlook is not optimistic, either. The company still has a ship order to be delivered," he said.
Zhejiang Jingang Shipbuilding Co Ltd, headquartered in the Taizhou city of East China's Zhejiang province, recently filed a bankruptcy petition to the Taizhou Municipal Intermediate People's Court due to its significant loans and lack of new orders, said a public relations officer of the court, without elaborating.
Founded in 2004, the company has the ability to build four vessels with a tonnage of over 16,000 tons per year, making it the biggest export shipbuilding enterprise in Taizhou, its website says.
In February, the company had not received any orders since last year, Liu Min, a senior director at Jingang said at the time.
Most banks regard the export-led shipbuilding industry as "high risk", refusing to underwrite or extend loans to related companies.
The Jingang shipyard is only one among many similar Zhejiang-based shipyards that have suspended business and dismissed employees due to the difficult market conditions. In June, Ningbo Hengfu Shipping Trade (Group) Co Ltd and Ningbo Beilun Sky Shipbuilding Co Ltd both filed motions to sell off assets.
Industry losses are widespread, as the volume of new orders in 2011 fell 52 percent, according to the China Association of the National Shipbuilding Industry.
In the first five months of 2012, China built ships amounting to 22.5 million deadweight tons, down 10.1 from the previous year.
New orders totaled 9.45 million deadweight tons, a drop of 47.3 percent from a year earlier. Combined outstanding orders were 134.4 million deadweight tons, down 10.4 percent from the end of 2011.
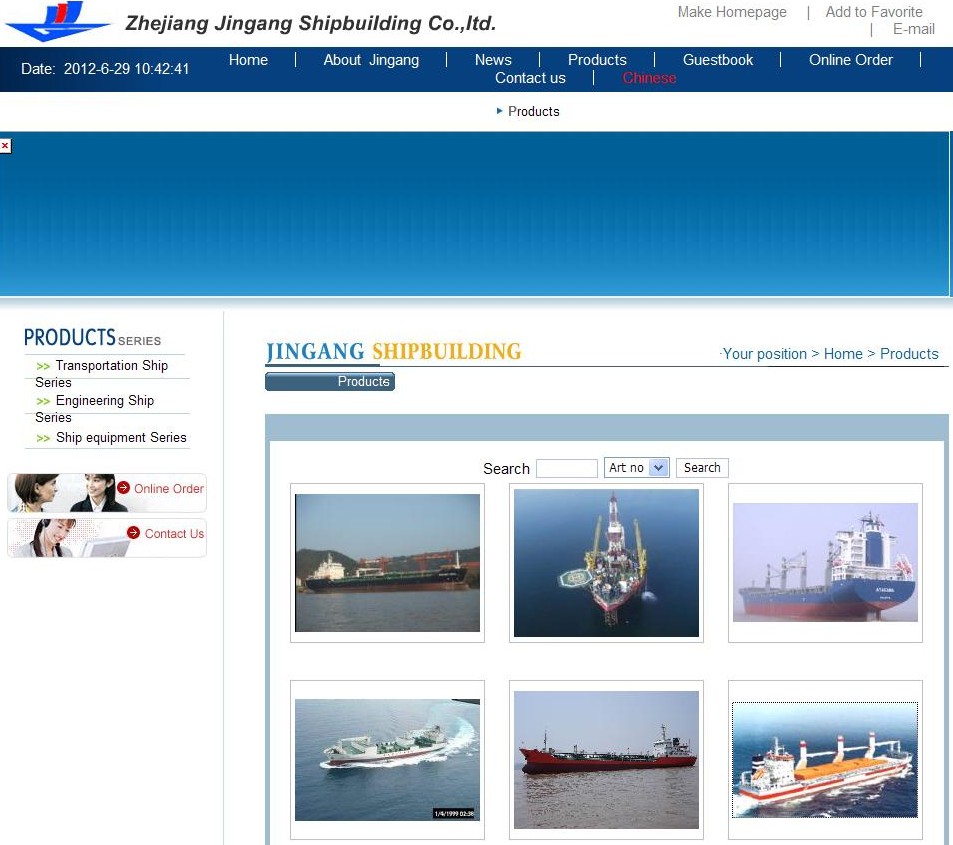
3日付の中国紙・毎日経済新聞によると、造船業界団体、中国船舶工業協会の張広欽会長はこのほど、「豪華客船建造に求められる技術はとても高く、わが国にはまだ能力がない。大手企業でも技術を蓄積している段階だ」と明言した。(
男性は鉱業などに携わる実業家クライブ・パーマー氏で、既に中国国営の造船業者と覚書を交わし「あらゆる点で初代と同じぐらい豪華で、なおかつ最新の安全システムを備える」と強調。初代タイタニック号に関わった人々への敬意を示すとしている。
建造費用は不明。ディーゼル燃料を使用するが、石炭を燃料とした初代をまねるため、4つの大きな煙突も装飾として設置する予定だ。(共同)
中国船舶業が2011年下半期に低迷傾向に転じ、今年1-2月には、受注不足の圧力がより顕著になり、三大造船指標が軒並み低下する現象が発生した。1-2月、全国の造船竣工量は前年同期比15.1%減の719万積載重量トン(DWT)、新規受注量は同40.1%減の494万積載重量トン、手持ち工事量は同24.7%減の1億4694万積載重量トンだった。
1-2月、中国船舶工業業界協会が重点的にモニタリングを行なっている57社の船舶企業の主要営業収入は前年同期比7.3%減の336億元、利益総額は同26.2%減の18億8000万元だった。うち37社の利益が減少し、16社が赤字となった。
船舶市場の不景気が続いたことにより、新規造船起工量が不足する現象が一般的となり、多くの造船企業が赤字或いは業績下降の「泥沼」状態に陥っており、業界全体の工業生産額の増加幅の減速を招いた。今年1-2月、一定規模以上(国有企業と年商500万元以上の国有企業)船舶工業企業は1618社、工業生産額は前年同期比9.7%増の1101億元で、増加幅は10ポイント以上の減速となった。
注目に値するのは、船舶製造、船舶修理などの分野が低迷しているものの、政策支援を受けている海洋工学設備製造分野は好調な発展傾向が表れていることだ。今年1-2月、海洋工学設備製造分野の生産総額は前年同期比13.5%増の29億6000万元、輸出納品額は同76.8%増の5億1000万元だった。(編集担当:陳建民)
2日午後4時15分ごろ、宮城県塩釜市北浜、造船会社「東北ドック鉄工」のドックのタンカー付近でガス爆発があった。地元消防によると、作業をしていた男性ら4人が負傷した。
塩釜署によると、タンカーは検査や塗装のために入庫中で、作業員が船底を溶接しようと点火したところ、ガソリンに引火したとみられる。
現場はJR東塩釜駅の南東200メートルで、工場や倉庫などが並ぶ工業地帯。(共同)
出港前日に…韓国船員はねられ死亡 秋田の港湾道路 04/01/12(産経新聞)
秋田市土崎港相染町の港湾道路で3月31日午後7時55分ごろ、秋田県男鹿市船川港比詰の美容師、竹谷裕子さん(28)の乗用車が、韓国人の船員、朴慶圭さん(46)をはねた。朴さんは1日午後2時35分ごろ、搬送先の病院で死亡した。
秋田臨港署によると、朴さんが乗った貨物船は3月23日、秋田港に入港。1日未明に出港する予定だった。朴さんは1人で買い物に出掛けており、船に戻る途中に事故に遭ったとみられる。
現場は秋田港に近い片側2車線の直線道路。
造船所のタンカー内で爆発 作業中の30歳男性重傷 04/02/12(テレビ朝日系(ANN))
2日夕方、宮城県塩釜市の造船所で爆発があり、タンカーの中で作業していた男性1人が顔などにやけどを負って重傷です。
警察によりますと、午後4時15分ごろ、塩釜市の「東北ドック鉄工」で、ガソリンや軽油などを運ぶオイルタンカーの内部で爆発が起きました。
現場責任者:「一瞬にして火ではなく、熱風が立ち上ったという感じ」
当時、船内では作業員4人が配管の溶接作業を行っていて、この事故で、平山雅之さん(30)が顔や首にやけどを負って重傷です。警察では、ガスバーナーの火が配管に残っていた油に引火し、爆発したとみて調べています。
めざす航路は「燃費向上」 造船各社、技術競う 03/27/12(日本経済新聞)
中国や韓国など海外勢との受注獲得競争が激化する中でJFEホールディングスとIHIが造船子会社を10月に経営統合する。常石造船(広島県福山市)など
中国地方の造船各社も生き残りに向けて懸命に技術開発に取り組んでいる。キーワードは「燃費向上」。原油高や地球温暖化問題に対応しながら差異化を図る狙いがある。
JR宇野線宇野駅からタクシーで10分弱。三井造船玉野事業所(岡山県玉野市)の工場に足を踏み入れると、巨大な設
備に目を奪われる。船に搭載する「次世代型ディーゼルエンジン」の実験設備だ。
排ガス中の窒素酸化物(NOx)を化学反応で窒素にして無害化する装置や、排ガスを再びエンジンに送り込みNOx
の発生を抑える装置を備えている。エンジンでプロペラの回転軸を回す力として排ガスを活用する装置もあり、従来比
3%程度の燃費向上を目指す。
■営業も厳しく
同事業所は2012年度を「総仕上げの年」(同事業所)と位置付け、この実験設備で培った技術を船に導入し、海上で効
果を確認する計画。
「最近では、ランニングコストも含めトータルで船価はいくらになるかと船主が聞いてくる。他社と比べて燃費が悪い
と話にならない」。内海造船の川路道博取締役は、営業での厳しさをこのように表現する。
燃費向上に関連する同社の一押しの技術が、独立行政法人海上技術安全研究所の支援を受けて開発した「ステップ(突
起)」だ。荒天時のコンテナ船などに対する波の抵抗を軽減する技術で、船首に薄い鋼製の突起を取り付けて、波が船体
にまとわりつきにくいようにする。波の抵抗を10%減らし、燃料使用量を2%程度抑える。すでに突起を取り付けた船を
使って海上での実証実験を始めており、「何とか燃費削減などの目標はクリアできる見通し」(同社)。
ツネイシホールディングス(広島県福山市)の伏見泰治会長兼社長は、「船の発注元はこれまで以上にエネルギー効率
に敏感になっている」と指摘する。子会社の常石造船は、甲板上に設ける「居住区」の形状を改良して風の抵抗を減らす
技術を、広島大学と共同開発した。
■プラスα必要
中国地方の造船各社が燃費向上の技術開発に力を入れる背景には、国内他社や中国・韓国などの海外勢との受注競争の
激化がある。
Sekwang Heavy Industriesが清算するらしい。
A series of warnings from senior industry leaders against more new building orders, it seems that a lot of ship owners are still looking for more deals with shipyards, oblivious of the concequences on the general market balance of demand and supply. Already plagued with oversupply issues, most shipping markets are having to sustain heavy pressures in terms of low rates, as a result of too many ships competing for too few cargoes. Still, as it turned out last week, there was a resurgence in activity in the new building market with report of new business being concluded across a variety of sectors. In its latest weekly report, Clarkson Hellas mentioned that “whilst new enquiry in the beginning parts of the year was somewhat tentative, these latest orders do help to highlight that interest is beginning to grow again as we proceed further into 2012. Newbuilding pricing has continued to soften and with the charter market continuing to look like it will remain somewhat challenging in the short term, owners are increasingly looking towards the future. As was witnessed throughout 2011 and in the early stages of 2012, many of the shipyards have focused their efforts in improving the efficiency of their designs and have made significant inroads to improving on their fuel oil consumption figures.
Bunker pricing has historically been closely correlated to that of Crude Oil and with the potential for this to rise further on the back of any further growth in oil demand, or with simple price shocks in the market, the importance of these design improvements and the subsequent savings over current design on the water, cannot be understated. It will be interesting to see which owners over the coming months look to take advantage of the perceived oversupply of capacity in the market, to place orders and therefore take advantage of these potential future savings on fuel” concluded Clarkson Hellas.
In a separate report, shipbroker Golden Destiny said that “the newbuilding business keeps its downward pace with shipyards feeling the pain from the slump of the freight markets. South Korean Shipyards, Sekwang Heavy Industries and Samho Shipbuilding, are set to finally close after failing to find a buyer, while 21st Century Shipbuilding is running out of work with not receiving new orders for several months now. Ship-owners are not in hurry to sign new deals either for dry or wet units waiting to see the performance of the freight market and the new trends in newbuilding prices.
Overall, the week closed with 18 fresh orders reported worldwide at a total deadweight of 1,402,240 tons, posting a 5% week-onweek decline with 4 transactions reported for bulk carriers, 6 for tankers and for gas tankers. This week’s total newbuilding business is up by 20% from similar week’s closing in 2011, when 15 fresh orders had been reported with bulk carriers and containers grasping 53% share respectively of the total ordering activity. In terms of invested capital, the total amount of money invested is estimated at region $1,32 billion with 1 transaction reported at an undisclosed contract price. The most overweight segment appears to be the LNG segment by attracting 61% of the total invested capital” said the Piraeus-based shipbroker in its report.
It carried on by mentioning that “in the bulk carrier segment, U-Ming Marine Transport Corp, a member of the Far Eastern Group, placed an order with Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co to build up to 10 capesize vessels at a price of region $49,8mil each with delivery in 2014.
Oceanfreight of Greece is said to have received a $120 million loan from China Development Bank ($108mil) and Bank of China ($12mil) for covering the construction of three bulk carriers from Jiangnan Shipyard Group Ltd. for delivery in 2013. The size has not been yet specified, but sources suggest that the units will be kamsarmaxes or mini capesizes.
In the tanker segment, Norwegian shipwoner John Fredriksen has placed an order for four 51,000dwt product tankers, with an option for two more units, for delivery in 2013 at STX Offshore & Shibuilding at a total cost of $209 mil. Furthermore, the owner in an interview in Financial Times unveiled its plans for ordering VLCC units for his newly founded Frontline 2012 defying vessels’ market glut.
In the gas tanker segment, the LNG newbuilding interest is very strong as the demand outlook from the two world’s largest consumers, Japan and South Korea, seems strong and owners are scheduling their investment plans. Sovcomflot of Russia has boosted its LNG orderbook at South Korean shipbuilder STX by declaring an option for two more units from its original contract placed at the end of May last year. Sovcomflot originally contracted two of the 170,200 cu.m LNG units at a price of region $205mil per vessel and now exercised its option for two more similar units with delivery in 4q 2014 and 1q 2015.
Furthermore, Golar LNG has entered into two newbuilding contracts for 162,000 cu.m new buildings with fixed priced options for a further two with the Korean shipbuilder Hyundai Samho Heavy Industries Co., Ltd. ("Hyundai") for delivery during the third quarter of 2014 and the other will deliver during the fourth quarter of 2014. The total cost of the two vessels is slightly above $400 million. Also, Greek player Dynagas is rumoured to be behind the order for an additional LNG pair, of 162,000 cbm, in South Korean Shipbuilder Hyundai Heavy Industries that are scheduled for delivery in the following year, after confirming four LNG carrier newbuildings of 155,000 cbm last year. In last, Chinese shipbuilders is said to have been asked an indication for their availability to construct two 170,000 cbm LNG carriers that are expected to be owned jointly by UK-listed BG, CNOOC Energy Technology & Services and the Cosco China Mechants joint venture China LNG Shipping (Holdings) Co (CLNG)” concluded Golden Destiny.
Shockingly, Sekwang Heavy Industries (SHI) based in Ulsan is said to have lately filed for court receivership.
According to the sources dated Apr. 28, SHI filed with Ulsan District Court for the court receivership on Apr. 20. The shipbuilder has been classified as a C-grade firm with insolvency for a year from Jun. last year.
The filing for the court protection by SHI is analyzed mainly attributable to its capital completely impaired with a rapid increase in its total debt including account payables and short-term debts that have increased from the first half of 2008.
Since SHI has been listed as a firm under the work-out program in Dec. 2009, it has been struggling with short liquidity, unable to cope with cash crisis despite shipbuilding funds provided from its bankers, so it is said to have filed for the court receivership.
According to SHI’s audited report, the shipbuilder’s total liabilities actually stood at KW 375.5 billion (bil.) as at the end of June, 2008. At the time, SHI’s capital stock stood at KW 31.5 bil. same as a year ago (the end of June, 2007) while its total capital stock was computed completely impaired.
As at the end of June, 2009, SHI’s Financial Statement described its completely impaired capital as sustained. At the time, though its capital stock remained unchanged at KW 31.5 bil., its total liabilities rose to KW 59.2 bil. below zero amid the complete impairment of its capital going on. Apart from this, SHI’s total liabilities snowballed to KW 59.1 bil. in excess of its total asset as a result of its accumulated deficit.
One year later (at the end of June last year) the impairment of capital got worse. With its capital stock unchanged at KW 31.5 bil., its stockholders’ equity fell to minus KW 537.6 bil. while its total liabilities soared to KW 349.8 bil. As at the end of Dec., 2010, SHI’s capital stock stayed unchanged at the same level as before while its total liabilities rapidly rose to KW 349.8 bil. from a year earlier. As at the end of Dec. 2010, SHI’s capital stock remained the same while its total shareholders’ equity deteriorated to minus KW 675 bil. with its impaired capital status worsening as shown by its audited report.
Since its inception in 1939 as a shipyard in Bangeojin in Ulsan, the shipbuilder who was renamed “Chung-gu Shipyard” in 1960, continued to grow awarded with Export Tower for US$ 5 mil. from the government in Nov. 1994, and it was placed under court receivership in 1997 to solve its insolvency caused by its expansion during the foreign currency crisis that Korea experienced to be rescued by IMF in the same year.
The shipyard was renamed “INP Heavy Industries” in 1999, and thereafter it was sold to Sekwang Shipping in 2007 and renamed “SHI.” It made a fresh start, demonstrating its outstanding capabilities and workmanship in construction of stainless steel chemical tankers and anchor handling tug supply (AHTS) vessels as distinguished among small and medium size (SM) shipbuilders in Korea.
SHI was the first among SM Korean shipbuilders to receive an order for ethylene carrier. The shipyard, nevertheless, was faced with the cancellations of some orders due to the sustained delays in delivery of vessels over the last two years. SHI filed with Korea Trade Insurance Corp. (K-sure) for export credit guarantee for cash settlement (ECGCS) limited to KW 290 bil. in 2009 and just obtained it from K-sure though the guarantee was only available to an exporter with its annual export record of more than KW 1 trillion. K-sure had to bear the financial burden of KW 264.5 bil. owing to SHI’s insolvency in Dec., 2009 when the shipbuilder was listed as one of the firms under the government-led workout program due to its insolvency.
ベン・ライン・エージェンシーズ・ジャパン 海外送金問題で不起訴決定 03/29/13 (日刊CARGO)
ベン・ライン・エージェンシーズ・ジャパン(飯垣隆三社長)は29日、海外送金に関する同社への捜査に関連して声明を出し、「最終的な捜査の結果、容疑が晴れ、3月28日に正式な不起訴決定がなされた」と発表した。職員1人が海外送金処理...
三光汽船が私的整理へ 昭和60年に戦後最大の破綻…再び苦境 03/10/12 (SankeiBiz(サンケイビズ))
中堅海運会社の三光汽船(東京都千代田区)が、第三者機関の「事業再生ADR」を活用し、金融機関による支援で再建を目指す私的整理に入る方針を固めたことが9日、分かった。週明け12日にも発表する。
世界的な海運不況に加え、円高や原油高騰の影響で資金繰りが悪化した。同社は昭和60年に会社更生法の適用を申請し、負債総額5200億円と当時としては戦後最大の経営破綻となった。
同社は平成10年に更生手続きを完了し、事業を縮小して業務を続けてきた。しかし、再び苦境に陥り、平成23年3月期決算では、141億円の最終赤字を計上していた。海運業界では、コンテナ船の供給過剰で運賃が大幅に下落し、大手海運会社も軒並み最終赤字となっている。
ADRは経営不振に陥った企業が、事業を継続しながら再建を目指す私的整理の手法の一つ。法的整理に比べて手続きの期間が短く、早期の再生が可能。ただ、すべての取引先の金融機関の同意が必要で、調整が難航する可能性もある。
受注残ゼロ「造船2014年問題」 再編&エコシップで復活なるか (1/3ページ) (2/3ページ) (3/3ページ) (産経新聞)
かつて世界を席巻した日本の造船業界が、2年後に造る船がなくなる「2014年問題」の危機に直面している。韓国や中国のライバルの後塵(こうじん)を拝し受注が激減しているためだ。危機感を募らせたJFEホールディングスとIHIが今年10月に造船子会社の統合に踏み切るほか、世界をリードする環境技術を生かした「エコシップ」の受注にも力を入れている。“造船ニッポン”は復活するのか。
◆韓国の5分の1
「韓国勢に大差を付けられてしまった」。日本造船工業会の釜和明会長(IHI社長)は2月21日の定例会見で唇をかんだ。同工業会によると、昨年1~6月の新造船受注量は385万トンと、前年同期から57%も激減。通貨ウォン安を武器に60%増と受注を急伸させた韓国の1805万トンの約5分の1にとどまった。中国も60%減の714万トンに落ち込んだが、日本のほぼ倍を獲得した。
船舶の建造はほとんどがドル建て契約。歴史的な円高によって、「無理に受注しても赤字を垂れ流すだけ」(業界関係者)という状況では、とても中韓勢に太刀打ちできない。価格競争が激しい中型タンカーに特化する住友重機械工業は11年度に一件も新規受注を獲得できない可能性があり、このままでは受注残が13年6月末でなくなる。JFEホールディングス傘下のユニバーサル造船やIHI傘下のIHIマリンユナイテッド(MU)、川崎重工業も、今後2年で受注残が底を突く。
◆技術力は世界一
「受注残ゼロ」の悪夢が現実味を帯びるなか、JFEとIHIが動いた。両社は08年4月に子会社のユニバーサルとMUの統合交渉に入ったが、その直後のリーマン・ショックでそれどころではなくなり頓挫していた。だが、昨秋にひそかに交渉を再開し、4年間も停滞していた交渉を数カ月でまとめ、今年1月30日に合意を発表した。合併後の売上高は約4千億円となり、国内トップの今治造船に迫る。両社は規模のメリットで造船コストの65%を占める材料費を削減し、年100億円規模の効率化効果を目指す。
狙いは、コスト削減だけではない。ユニバーサルの三島慎次郎社長は「開発陣を手厚くし、得意の省エネ船の開発を強化すれば韓国メーカーとも戦えるようになる」と意気込む。両社合わせた開発部門の人員は、計約1500人となり、国内で最も技術力が高いといわれる三菱重工業を上回る。
波や風の抵抗を受けにくい形状で、燃焼効率に優れたエンジンを搭載し、太陽光発電なども活用するエコシップには、釜・造船工業会会長が「世界トップ」と胸を張る技術力のアドバンテージがある。国際海事機関(IMO)が、14年1月以降に建造契約が結ばれる400トン以上の国際運航船舶に対し、二酸化炭素(CO2)排出量の最大30%削減を義務づける環境規制の導入を決めたことも追い風だ。MUは従来船より燃費性能を30%高めたコンテナ船、ユニバーサルは25%改善した鉄鉱石や石炭を運ぶバルク船の設計を完了。受注残ゼロ回避の切り札と位置付け、売り込んでいる。
◆ノウハウを売却
一方で、“門外不出”の技術やノウハウを海外メーカーに売り渡すというタブーをあえて犯す策に打って出たのが、三菱重工業だ。昨年12月にインドの建設機械大手ラーセン・アンド・トウブロと提携し、設計図などの技術を供与することで合意した。ライセンス収入を得るだけにとどまらず、将来的には合弁事業に発展させ、共同受注によって低コストの海外生産への道を開こうという深謀遠慮だ。
だが、経営統合やエコシップ、技術売却も生き残りの決め手にはならない。中韓勢が大量建造のため、造船所を増やし続けてきた一方、海運会社はリーマン前の世界的な好景気に浮かれて大量発注した結果、船舶が有り余っている。供給過剰が一段と強まるのは確実で、「中国勢の投げ売り受注で船価の下落がさらに加速する」(業界関係者)と懸念されている。
価格競争力で大きく劣る日本勢は、さらに厳しい戦いを強いられる。国土交通省が昨年7月にまとめた報告書は造船業の国際競争力強化に向け、「連携や統合が必要」と指摘した。
「われわれの統合に加わろうという会社が増えれば、喜んで受け入れる」。ユニバーサル造船の三島社長は、統合合意会見でこう呼びかけた。さらなる合従連衡によって、「日の丸造船」を誕生させ、総力を結集できるかが、復活のカギとなる。(今井裕治)
(朝鮮日報日本語版) 韓国の中小造船会社、相次ぐ経営危機 02/15/12 (朝鮮日報日本語版)
韓国の造船業界で、2006-07年の好況期に経営規模を拡大した中小造船会社が連鎖的に経営危機に直面している。慶尚南道統営市にある中堅造船会社、サムホ造船が業績不振から清算手続きに入った。世界8位の造船会社、城東造船海洋は先月末、債権団とコスト削減、経営効率化などの構造調整を進めることで合意した。大韓造船は3年間にわたり大宇造船海洋に経営を委託し、再建を図ることを決めた。
昌原地裁は14日、サムホ造船の企業再生手続きの停止を決定したと発表した。受注減少、資金事情の悪化で、同社は清算手続きに入ることになった。同社はアデン湾で海賊に襲撃され、劇的な救出作戦の舞台となった「サムホジュエリー号」を保有するサムホ海運の系列企業。2008年には売上高4394億ウォン(約306億円)、営業利益483億ウォン(約34億円)を達成するなど、一時は世界の造船所上位100社にも浮上したが、景気低迷を受け、昨年5月に倒産していた。
危機に直面した中小造船会社には、約5年前に船舶の発注が相次いだ好況期に造船市場に参入した社も多い。しかし、08年のリーマンショックで世界的な不況が始まり、技術力で劣る企業が経営に行き詰まった形だ。
造船業界の関係者は「金融機関からの資金調達ができなくなった上、今後の景気見通しも暗く、低い技術力では生き残ることが難しい。(中小造船会社が手掛けていた)ばら積み貨物船、タンカーなどの事業にも大企業が参入しており、太刀打ちできない」と指摘した。
韓国の大手造船会社は、それほど深刻な状況ではない。昨年から掘削船、洋上浮体式生産・貯蔵・積出設備(FPSO)などの海洋プラントや液化天然ガス(LNG)タンカーなど付加価値が高い船舶の受注が伸びているためだ。現代重工業は13日、ノルウェーのホーグLNGから海洋プラント1基を受注するなど、年初来5件、11億ドル(約863億円)の受注を獲得した。STX造船海洋も今月10日、ロシア国営の海運会社、ソブコムフロートからLNGタンカー2隻を受注した。
韓国と中国の言い分に食い違い…中国漁船員暴行事件 02/07/12 (サーチナ)
在中韓国大使館は3日、中国漁船の乗組員が1月17日に韓国の排他的経済水域(EEZ)で韓国海洋警察に暴行を受けた事件について、「報道に誤りがある」との声明を発表した。これを受け、中国の台州市渉外漁業協会の膨虎林秘書長は、「韓国政府の説明は、事実ではない」と反論した。中国新聞社が6日付で報じた。
中国の漁船乗組員が1月17日に韓国の排他的経済水域(EEZ)で韓国海洋警察の取り調べを受けた際、暴行を受けたとされることで、中国国内では、韓国政府に対する批判が高まった。
在中韓国大使館は3日、同件について「報道に誤りがある」との声明を発表した。
韓国政府は、海洋警察が殴打に至った原因を、「中国漁船乗組員が銃を奪うなど、激しく抵抗したため」と主張。韓国海洋警察は2人が負傷、中国漁船乗組員は3人が負傷したと説明した。
これに対し、同事件の調書収集や対外交渉などを行っている台州市渉外漁業協会の膨虎林秘書長は、「韓国政府の説明は、事実ではない」と反論。韓国海洋警察の負傷に関する証拠がないとした上で、「もし本当に負傷したのであれば、医療費の負担も惜しまない」と述べた。
さらに「真実は、韓国海洋警察が保有する映像資料にある」とし、同件を撮影した映像の公開を強く求めた。(編集担当:立花亜美)
海運:BDI、金融危機時下回る 01/31/12 (Yahoo!ニュース )
代表的な景気先行指標で、海運業界の業況を占うバルチック海運指数(BDI)が年初来、2008年の金融危機を下回る水準まで低下している。
海運業界によると、2月3日のBDIは647ポイントとなり、金融危機直後の08年12月5日(663ポイント)を下回った。BDIは造船・海運業界の好況期だった08年6月には一時1万1000ポイントを超えた。現在の運賃がピーク時に比べ15分の1以下に下落したことを示している。
BDIはロンドンのバルチック海運取引所が世界の主要26航路のばら積み貨物船の運賃を集計し、毎日発表している。BDIの急落は、鉄鉱石、穀物などの原材料に対する需要が減り、今後の世界経済が悪化するとみられることを意味する。
海運業界は、予想外のBDI急落に戸惑っている。韓国海洋水産開発院は昨年末、今年のBDIは1600-1800ポイントで推移すると予測した。BDIの低下が進めば、海運景気の回復が当初見込まれた来年よりもずれ込む懸念が浮上する。
一部には、世界景気とは特に関係なく、ばら積み貨物船の供給が過剰となったため、運賃が急落したとの分析もある。07-08年の好況時に発注されたばら積み貨物船が昨年から市場に投入され、船舶の供給が需要をはるかに上回っている点を指摘する見方だ。海運専門の調査会社、クラックソンは、ばら積み貨物船が今年は12%増加するが、鉄鉱石などの海運貨物が5%増えるにとどまると予想している。
ばら積み貨物船とは異なり、テレビ、冷蔵庫など工業製品を運ぶコンテナ貨物船の運賃は反発の兆しを見せている。中国コンテナ運賃指数(CCFI)は年初来上昇を続け、昨年末の800ポイント台から900ポイント台へと反発した。韓国海洋水産開発院のキム・ウホ海運市場分析センター長は「工業製品を運ぶコンテナ船指数は少しずつ回復しているため、海運業と世界経済の先行きを悲観的に見過ぎる必要はない」と指摘した。
中国造船各社の新規受注が半減、事業環境がさらに悪化の危険も 01/31/12 (サーチナ)
<中国証券報>中国船舶工業行業協会(CANSI)のまとめによれば、2011年の全国の造船受注量(重量トンベース)は3622万トンで、前年同期比51.9%まで落ち込んだ。2日付中国証券報が伝えた。
データによると、11年の全国の造船竣工量は同16.9%増の7665万トン、新規造船受注量は同51.9%元の3622万トン、年末時点での手持工事量は同23.5%減の1億4991万トンだった。
新規受注量の半減は造船業界の将来に暗い影を落としており、手持ち工事量も2割減少していることから、閉鎖の危機に陥る造船会社も増えている。CANSIによれば、竣工量は連続12カ月に渡って受注量を上回っており、調査対象企業のうち3分の1が全く受注のない状況だという。08年の金融危機以降、造船業は急速に落ち込みが目立つようになり、11年下半期(7―12月)からは生産量や利益率が軒並み前年比割れしている。
業界の専門家は、12年の世界の新規造船受注量を7000―8000万トン、竣工量を約1.5億トンと見込んでいるが、需給バランスの乱れは今後更に悪化し、船舶の価格も引き続き下落すると予想する。12年に納入予定の船舶のうち、特に高価な船舶の割合が大幅に減少している上、製造コストの上昇も続いていることから、造船業の利益低下が更に深刻化すると懸念を示している。(編集担当:浅野和孝)
韓国が拿捕した中国漁船、船団に奪取されていた 01/31/12(読売新聞)
【ソウル=門間順平】韓国紙・朝鮮日報は1月31日、韓国海洋警察が昨年11月、不法操業で拿捕(だほ)した中国漁船を連行する際、仲間の中国漁船団に襲われ、船を奪い取られていたと報じた。
同紙によると、海洋警察の警備艦が昨年11月19日、済州島(チェジュド)北方沖の韓国領海内で不法操業をしていた約40隻の中国漁船団を発見。海洋警察官10人が、このうちの1隻に乗り込んだが、他の漁船3隻から手おのや鉄パイプを持った船員が乗り込んできて、警察官に暴行を加えた。警察官5人が重軽傷を負い、漁船は奪い返された。さらに中国漁船団は逮捕された船員の釈放を求め、逆に警備艦を追跡。海洋警察は最終的に3隻を拿捕したが、残りは中国領海内に逃走した。
イラン不正送金、社員を略式起訴 役員らは処分保留 02/14/13 (日本経済新聞)
国の許可を得ずにイランの企業に送金したとして、東京地検は14日までに、海運代理店、アトラス・シッピング(東京・品川)の送金業務を担っていた関連会社の三宅由紀社員(41)と法人としてのアトラス社を外為法違反(支払い等の制限)の罪で略式起訴した。東京簡裁は同日までに、三宅社員に罰金50万円、同社に罰金100万円の略式命令を出した。
アトラス社を設立した海運代理店の男性役員(64)と男性の経理統括部長(58)も同法違反容疑で逮捕されたが、いずれも処分保留で釈放した。
これまでの調べによると、三宅社員は2011年11月~12年2月、国の許可を得ずに、イランの船会社向けにアトラス社名義の口座から総額約1400万円を送金したとされる。
イラン不正送金事件 イラン包囲網に危機感? ダミー会社で資金の流れ複雑化 01/28/13 (SankeiBiz)
イラン制裁安保理決議に基づく経済制裁に違反し、核関連物資を運搬しているとされるイラン国営の船舶会社IRISLは世界中に点在するダミー会社を隠れみのに、制裁逃れを続けてきた。国際社会がイランに厳しい姿勢を示す中で、公安部は日本でも水面下で行われていたイランの資金獲得工作の全容解明を進めている。
IRISLはイラン商務省の傘下で、同国防軍需省が扱う軍事物資を輸送している疑惑が持たれており、米国が平成20年9月に初めて経済制裁の対象に加え、国連安保理が22年6月、EUが同7月、日本も同9月に追随した。
捜査関係者によると、IRISLは、イラン以外にも欧米、東南アジアなどにダミー会社を設立。経済制裁で禁じられた金融取引を続けているほか、貨物船の塗装を塗り替え、船名を変更するなどして、輸送活動を継続してきたとされる。
公安部が摘発した海運代理店「ベン・ライン・エージェンシーズ・ジャパン」が不正送金していたIRISLの関連会社「ハーフィゼ・ダルヤー・シッピング・ラインズ(HDSL)」も、IRISLのコンテナ部門を独立させる形で設立されたダミー会社だ。
公安部幹部は「制裁逃れが目的なのに、ダミー会社の住所がIRISLと同じであるなど、手口はずさん。IRISLとの関係が確認されれば制裁が強化される。いたちごっこが続いている」と語る。
23年6月には、米金融機関を通じて偽造書類で約6千万ドルの取引をしていたとして、米司法当局がIRISLとダミー会社を摘発。ベン社は国際社会がイラン包囲網を狭める中で、焦燥感を募らせたとみられる。
制裁後、金融機関からベン社経理統括部長、野武俊明容疑者(58)にIRISL側との取引禁止が伝えられたが、ベン社がIRISL側に支払わなければならない貨物運賃は数億円も残されていたという。
ベン社は日本でのIRISLの業務を独占的に請け負っており、「両社の関係は周知の事実。制裁後も取引を続ければ、ベン社自身も制裁対象になりかねないとの焦りが生じたのではないか」(捜査関係者)。これが、複雑な送金の流れを構築した動機とみられる。
ベン社は23年1月、「アトラス・シッピング」を設立。HDSLと代理店契約を結ぶ一方、IRISLとの契約を解除した。だが、水面下では、ベン社がアトラス社の経理業務を請け負う形で、IRISL側への不正送金を続けていた。
捜査関係者は「ベン社社員がアトラス社にまとめて移るなど、両社は一体」と指摘。HDSLからの送金指示は、ベン社社員に直接メールされ、アトラス社の資本金1千万円もベン社側が出していたという。
一連の偽装工作はベン社役員、水島邦明容疑者(64)の指示とみられる。捜査幹部は「会社の利益を優先し、結果的にイランの核開発を支えていることへの罪の意識が希薄だ。テロ支援国家に対する経済支援は厳しく取り締まっていく」と強調している。(伊藤真呂武)
「建設中の高架橋が崩落 『破壊実験だ』と当局=安徽省」今回は船が沈没するか、大規模な実験をおこなっただけだろう。




「92億円で建造のタンカーが試験航行で沈没」と社員がネットで暴露―中国 01/18/12(Record China)
2012年1月16日、中国の造船大手・武昌船舶重工有限責任公司(湖北省武漢市)の社員がインターネット上の掲示板で、同社が7億6000万元(約92億4750万円)かけて建造したタンカーが試験航行中に沈没したことを暴露した。17日付で新京報が伝えた。
沈没が暴露されたのは「海洋石油682UT778CD」。上海市打撈局(海難救助局)の関係者が明かしたところによれば、14日午後4時(現地時間)頃、船舶のサルベージ要請を受けた時にはすでに沈没していた。船主は中海油田服務股フェン公司(チャイナオイルフィールドサービス)。
これに対し、中海油田服務IR部門の担当者は「タンカーはまだ建造中で、引き渡しも済んでいない。その他のことは分からない」と反論。武昌船舶重工側もウェブサイトに公開されている電話番号に同紙記者が取材を試みたが、誰も出ない状態が続いている。
なお、武昌船舶重工の親会社である中国重工集団公司の株式は16日にA股(株)市場全体が高騰した影響で9.02%上昇、終値は1株5.56元となり、上海市場は4.18%上昇している。
中信建設のアナリストは「建造費は船型によって大きく異なる」とし、武昌船舶重工は中国重工の上場資産に組み込まれていないことから市場への影響は出ないだろうと指摘している。(翻訳・編集/岡田)
新造船が試験航海中に沈没…「低級な操作ミス」で折れる=中国 01/18/12(サーチナ)
武昌船舶重工有限責任公司が製造した「海洋石油682UT778CD」が、長江で試験航海中に沈んだことが分かった。同公司の職員とみられる人物が16日、インターネットで暴露した。「低級な操作ミスで、船体が折れて沈んだ」という。中国新聞社などが報じた。
沈没したのは14日とされる。インターネットでの「暴露」によると、同船は長江(揚子江)で試験航海をしていた。江蘇省南通市で接岸を試みた際、「低級な操作ミスで、船体が折れて沈んだ」という。
暴露した人物は、「わが社が造った船の中で最も高価で、最高の技術を込めた船だった」と嘆いた。同船の価格は「7億8000万ドル(約598億日本円)」と報じられた。ただし、価格については異なる説もある。
現場で救助や事故船の引き上げなどを行う上海市打撈局の関係者も「14日午後4時に、救助要請を受けた」、「同船はすでに沈没した」と認めた。ただし、事故の詳細については「彼ら(武昌船舶重工)の方が、よく知っている」と述べ、回答を避けた。武昌船舶重工は、事故について発表していない。
沈没した船は、海洋における石油や天然ガスの採掘などを行う中海油田服務が引き取る予定だった。同社関係者は「海洋石油682UT778CD」について「まだ造船中で受け取っていない」と述べた。
沈没による死傷者の情報などは、伝えられていない。(編集担当:如月隼人)
(Reporter Jenny Chung) January 16, there Wuchang Shipbuilding Industry Co., Ltd. (hereinafter referred to as military vessels) in the forum staff broke the news that the construction of a military ship worth 760 million yuan of the “Offshore Oil 682UT778CD “recently sank. According to financial reports, the Shanghai Salvage Bureau, said the person in at 4:00 p.m. on January 14 received salvage distress, confirmed the vessel had sunk, the owner is COSL.
yesterday afternoon, this reporter called salvage at the Shanghai Salvage Bureau, who is not related to direct statement on the matter, saying only that the shipyard should ask, “what should be their own more clearly.” But as of press , arms ship released its official website the phone has been in no one answered.
COSL investor relations department official told reporters yesterday, now only know the boat is still under construction, has not yet been delivered, the message is unclear for the other, if messages are timely and of foreign disclosure.
It is understood that Wuchang Shipbuilding Industry Co., Ltd., a subsidiary of China Shipbuilding Industry Corporation, a listed company held by the Group’s 97% stake in China’s heavy industry, Heavy Industries and China (601,989) in 2009 in A-share the market.
high Xiaochun CSC analyst, told reporters yesterday that the cost varies greatly in different ship types, if the cost of 7.6 billion, in fact, is not high. High Xiaochun said, due to the current military ship has not yet entered China Shipbuilding Industry Corporation listed assets, it will not impact on listed companies.
subsequent inquiries from reporters learned that China’s heavy industry (601989) rose 9.02% yesterday, closing at 5.56 yuan/share. And yesterday’s rally apparently by the A-share market rose, driven, data showed yesterday stock index rose 4.18%.
建設中の高架橋が崩落 「破壊実験だ」と当局=安徽省 12/07/11(Epoch Times.jp)
【大紀元日本12月7日】安徽省合肥市で5日、建設中の高架橋が崩れて落下した事故が起き、6人の作業員が負傷した。だが当局は事後、「事故」ではなく、計画通りに行った「破壊実験」だと発表し、現場を通った作業員1人が軽い擦り傷をしただけと話している。河南商報が報じた。
崩落が起きたのは合肥市内にある包河大道の高架橋建設現場。5日朝7時半ごろ、「(高架橋の)下で作業していたら、上が揺れはじめ、そのうち全部崩れ落ちた」と作業員の1人は証言する。崩落した部分は900平方メートルに及ぶという。
事故後、包河大道プロジェクトの責任者・江浩氏は、これは「事前に計画した破壊実験だ」とメディアに話した。「実験を行わないと必要なデータが得られない」と説明している。
合肥市の重要インフラ管理局の張家祥・副局長も「仮設梁の超過荷重実験を行っていた」と話し、事前に作業員に通知していたという。
これに対して、作業員らは何の知らせも受けていないと反論した。
さらに、負傷者について、張副局長は、現場を通った作業員1人が「軽い擦り傷」を負っただけと話したのに対し、河南商報は、現場作業員の話として、6、7人が負傷したと伝えている。「その場で気を失った人もいる」という。けが人の手当にあたった合肥市友好病院の医師も、負傷した人は6人だと証言し、うち3人は入院治療を受けているという。
これらの証言について、張副局長は「今のメディアはそんなもんだろう。記者は詳細に調べていない」と反発している。
(翻訳編集・張凛音)
ド中国海運業は経営状態が悪化の一途、過剰輸送力の解消に5年 12/19/11(サーチナ)
<中国証券報>14日のバルチック海運指数(BDI)は1912で、2011年2月の1048から約2倍の水準まで回復した。しかし中国の海運会社の経営状況は依然悪化の一途をたどっており、最大の原因である過剰な輸送力を消化するには少なくとも5年かかる見通しだ。16日付中国証券報が伝えた。
同花順によれば、海運上場企業14社の今年1―9月の親会社に帰属する純利益は60.9億元のマイナスで、前年同期の14社113.07億元の黒字から大幅な悪化となった。小規模な海運会社を中心に倒産や買収が相次いでおり、多くの企業がコスト削減のため80年代から90年代初頭に製造した貨物船を廃棄したり、元々収益性の高かった欧米路線からの撤退を進めている。
交通運輸部水運科学研究所水運発展研究センターの賈大山主任は「海運業の低迷は、世界レベルでの輸送力過剰が原因だ」と指摘する。09年から10年の好調期に多くの企業が輸送能力を大幅に引き上げたが、貨物量や輸送需要の減少で今年はバラ積み乾貨物、石油、コンテナ貨物が赤字に転落。来年また新たな貨物船が投入されれば需給バランスはさらに悪化することになる。
交通運輸部は企業間の協力強化や、共同運行によるコスト削減などを呼びかけているが、賈主任は「海運需要が年5%増加し、大型貨物船が投入されないと仮定しても、過剰な輸送力の消化には5年ほどかかる」と指摘する。
賈主任は「この厳冬期を乗り切るには、抜本的な運行効率の改善と経営モデルの刷新が必要だ」と述べ、海運世界最大手のA.P. モラー・マースクは様々な工夫で今年9月までに前年同期比9%の成長に成功したことを挙げ、「中国の海運企業も見習うべきだ」との考えを強調した。(編集担当:浅野和孝)
ドーヴァル海運(化学薬品のケミカル船運航、東京都)民事再生法の適用を申請 12/02/11(帝国データバンク)
ドーヴァル海運(株)(TDB企業コード:982820181、資本金4800万円、東京都中央区新川1-16-3、代表柳智啓氏、従業員50名)は、12月2日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請、同日保全命令を受けた。
申請代理人は吉田広明弁護士(東京都千代田区丸の内1-7-12 、電話03-5219-5151)。監督委員には加々美博久弁護士(東京都港区西新橋1-4-9 、電話03-6203-2211)が選任されている。
当社は、1973年(昭和48年)8月に設立された化学薬品中心のケミカル船運航業者。ケミカルタンカーなどの海上運送オペレーター業務を柱に、主要海上輸送地域は、JANZ(=日本、オーストラリア、ニュージーランド)航路と世界航路に大別され、特に同業他社より先駆けて切り開いたJANZ航路に強みを持っていた。荷主は海外では米国の石油メジャー、大手ケミカル会社を中心に、国内では大手商社が取引上位を占めていた。積荷は、ベンゼン、パーム油、アンモニアなど石油基礎製品や石油2次製品のほか、近年はバイオディーゼルやバイオエタノールなども扱い、2008年9月期には年収入高約235億8000万円を計上、業界中堅クラスに位置づけられていた。
その後は米国経済の低迷が続くなか同国向け太平洋航路が改善に至らず、新造船の投入で扱い量の大きな落ち込みは免れたものの、為替による減収要因もあり、2010年9月期は年収入高約219億8400万円にとどまっていた。さらに、原油価格高騰に伴う船舶燃料費のコスト増や、用船費用の上昇により赤字決算を余儀なくされていた。このためピーク時36隻あった船舶を20隻まで縮小、効率を高めた運航体制で立て直しに努めていたが、円高傾向が続くなか得意先である海外企業からの回収の大半がドル建てとなるなど厳しい状況に陥り、自主再建を断念した。
負債は子会社に対する保証債務を含めて約150億円。
内海造船が修繕船工事の田熊工場を12年3月末で閉鎖 10/17/11(不景気.com)
東証2部・大証2部上場の造船業「内海造船」は、2012年3月31日をめどに修繕船工事を手掛ける「田熊工場」(広島県尾道市)を閉鎖すると発表しました。
修繕船市場の競争激化で厳しい環境が続いていることから、同工場を閉鎖し主力工場の「瀬戸田工場」へ事業を集約することで競争力の強化を目指す方針です。
なお、従業員については全て瀬戸田工場へ異動する予定で、工場閉鎖後の跡地利用については今後検討していくとのことです。
By Dawn McCarty
(Updates with assets and debt in second paragraph.)
July 8 (Bloomberg) -- Omega Navigation Enterprises Inc., an Athens-based shipper of refined fuels such as gasoline and heating oil, filed for bankruptcy in the U.S. after failing to reach an agreement with lenders to restructure debt.
The company listed assets of $527.4 million and debt of $359.5 million as of Dec. 31 in Chapter 11 papers filed today in U.S. Bankruptcy Court in Houston. Several affiliates also sought protection.
“The company is disappointed in the senior lenders’ intransigence and has commenced litigation against them in Greece,” Omega said today in a statement. It plans to use Chapter 11 to “restore the company to long-term financial health.”
The Chapter 11 filings don’t include Omega Management Inc., Omnicrom Holdings Ltd. or Omega Investments Inc., according to the statement.
The company’s legal adviser for the restructuring and Chapter 11 case is Bracewell & Giuliani LLP. Jefferies & Co. is its financial adviser.
The case is In re Omega Navigation Enterprises Inc., 11- 35927, U.S. Bankruptcy Court, Southern District of Texas (Houston).
--Editors: Stephen Farr, Alaric Nightingale
A HREF="http://www.maritime-connector.com/NewsDetails/12943/lang/English/The-end-of-Samho-Shipbuilding.wshtml" target="_blank">
Samho Shipbuilding
officially went bankrupt at the end of last week. According to Samho's creditors on 13 May, Samho was meant to honour a promissory note of KRW2.1bn ($1.93m) but went bankrupt on 11 May and went bankrupt officially on 12 May by failing to pay back the loan on the following business day.
There have been reports that the yard has failed to pay its staff for the past couple of months. Sister firm Samho Shipping applied for court receivership on 21 April.
Haedong Shipbuilding Corporation was set up in June, 1994 and was renamed to the current name of the company, Samho Shipbuilding Corporation in 2001.
Source: seatrade-asia.com
Samho Shipping files for court receivership 04/28/11(Maritime Press)
Korea shipping industries are shocked again that
Samho Shipping Co., Ltd. (Samho)
, medium-sized (MS) ship owners, filed with Busan District Court for court protection on Apr. 21. The shock to Korea shipping industries is intensified that merely three months after Korea Line’s filing on Jan. 25 this year for court receivership Samho known as MS tanker player for its relatively solid operation has filed for the court protection.
Samho filed for company rehabilitation procedures together with application for relief restraining order and for company asset protection and disposal. The rehabilitation procedure commencement has yet to be ruled by the court at this coming weekend, normally taking a week for the court to judge whether going ahead with it or not.
Samho was said to have experienced considerable difficulties in business last year, ranked 20th among Korean shipping firms, posting KW 196.7 billion (bil.) in annual sales, KW 43.2 bil. in operation loss and KW 65.2 bil. in net loss for last year. Notably, Samho had tried its best to normalize its operation relying on the sales and lease-back of its two chemical tankers under Korea Development Bank’s “Lets Together Shipping Fund.” Yet the shipping firm was unable to overcome difficulties and opted for the court protection, the Maritime Press was told.
Among the major factors that contributed to Samho’s option taken to file for the court receivership, the first one is that the tanker market for its main business has recorded the worst slowdown last year and that it is still going on without any improvement this year. As of the end of last year, Samho owned a fleet of 21 product carriers amounting to 257,419-dwt, excluding one bulker and two VLCCs. Under the on-going poor tanker market situation carried over from last year, Korean flag carriers like SK Shipping, Daelim Corp, Heung-A Shipping and others have suffered considerable difficulties in tanker business thus far.
Samho Shipping’s liquidity problem has got worse with its financial commitment to Samho Shipbuilding, its associate, overburdened due to its payment guarantees issued beyond its capacity together with its large amount of newbuilding orders placed at its associated shipyard. Samho Shipping has underwritten Samho Shipbuilding’s debt of KW 337.912 bil. representing 53.5% of its total asset, while recording KW 65.2 bil. in net deficit for last year.
To make the matter worse, the hijacked M/V Samho Dream and M/V Samho Jewelry by the pirates last year on top of the on-going market slump hit the company hard leading to big loss unexpectedly and to the last decision for the court receivership.
The court receivership just filed by Samho Shipping adds up to a total of seven Korean shipping lines that have filed for court protection so far since the start of shipping crisis in 2008, including Samsun Logistics, Daewoo Logistics, TPC Korea, Serim Ocean Shipping, Bongshin Co., and Korea Line.
13日午後、三原市の造船所で岸壁に係留して改造中のコンテナ船の中で爆発事故があり、作業をしていた中国人の22歳の男性が全身を強く打つなどして死亡しました。
13日午後1時10分ころ、三原市須波西1丁目の「大西組造船所」で、岸壁に係留して改造作業を行っていたコンテナ船の中で爆発事故が起きたと消防に通報がありました。
この事故で、船首部分の甲板の上で作業をしていた中国国籍のイン・長利さん(22)が爆風で吹き飛ばされ全身を強く打つなどしてまもなく死亡が確認されました。警察や消防によりますとこのコンテナ船は幅18メートル長さ90メートルの約3000トンの船で、インさんは船内にある電気ケーブルを引き上げる作業を行っていましたがブリッジから8メートル下の鉄製の船底部分に転落したということです。
警察などによりますとこの船は砂利運搬船からコンテナ船への改造作業中で、数日前までは船の塗装作業が行われていたということで、塗料によって船内に充満していた可燃性のガスに、作業中に発生した火花が引火するなどして爆発した可能性もあるとみて、警察では爆発が起きた状況や原因を調べています。
造船所で爆発、中国人作業員死亡 三原 05/13/11(中国新聞)
13日午後1時10分ごろ、三原市須波西1丁目の大西組造船所で爆発があり、作業員の中国人男性1人が吹き飛ばされ死亡した。三原署などによると、男性が建造中の船内で作業中に爆発したという。
South Korean chemical-tanker owner Samho Shipping
has filed for court protection after suffering liquidity problems.
The company’s predicament is being blamed on the collapse of the shipping markets together with expensive vessel investments.
But Samho has also had its trading activites disrupted by the seizure of two of its ships by pirates.
An executive at Busan-based Samho confirms it has filed for court receivership. “We [Samho] have no money to manage the company,” he said. “We will know the court’s decision in one month’s time.”
A source told TradeWinds: “[Samho] has filed for court protection so that it can continue with its operation. It hopes the court protection will help it tide over this difficult period.”
Samho is said to taken bank loans worth $245m to buy two VLCCs and a panamax bulker between 2006 and early 2008 when the shipping market was at its peak.
It thought to have paid $137.5m for the 320,000-dwt Samho Dream (built 2002) from Dynacom, $93m for the 300,000-dwt Samho Crown (built 1996) from OSG, with the seller chartering back the tanker for seven years at $35,000 per day with an equal profit share between the two parties, and $106m on the 77,000-dwt panamax bulker S Nicole (built 2007).
The latter is said to be a one-year charter to U-Sea Bulk at $15,500 per day, which would be a loss-making level given the amount Samho paid for the ship.
Among Korean banks with exposure to Samho are Busan Bank, which is said to have provided loans of $107m, Kyongnam Bank on $54m, Nyonghup Bank on $44m and Korea Development Bank on $15m.
Samho has also been a victim of piracy with two of its tankers hijacked.
In January, the 19,900-dwt Samho Jewelry (built 2001) together with its 21 crew was seized in the north-eastern part of the Arabian Sea close to India. However, it was rescued by Korean navy commandos after five days.
The Samho Dream was hijacked and held for seven months last year and only released after the payment of a $9m ransom.
Sources say the ship has still not returned to trading.
Meanwhile, OSG redelivered the Samho Crown early because of technical problems
Market players familiar with Samho say it has sold a number of chemical tankers to raise cash and is looking to sell a piece of real estate it owns in Gosung county in Gyeongnam province.
Samho bought the land a few years ago with the intention of building a mammoth yard on the scale of Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering when the shipbuilding market was booming.
However, it dropped the idea when the markets dived in the wake of global financial downturn.
Meanwhile, others say some of Samho’s chemical tankers are anchored at ports as the owner cannot afford to pay for bunkers.
Observers familiar with Samho say that before its rapid expansion into the VLCC and dry-bulk trades, the company was doing well.
“Samho’s chemical tankers were both time chartered out and trading spot. Its vessels were sailing in Asia and as far as the Arabian Gulf,” added one.
Samho is one of the 13 companies in Samho Group. Other business include Samho Shipbuilding, real estate, metal and steel manufacturing and the operation of floating cranes and tugs.
IMO Secretary Generalで検索したら下記のサイトを見つけた。候補者について調べたわけではないが個人的な意見では 韓国:もっとPSCの検査を厳しくするべき。内航船のような装備で韓国船籍船を日本に来させないでほしい。国際航海のはずだ。 フィリピン:公務員の賄賂問題やお金に絡む不公平な対応は改善が必要。 アメリカ:PSC検査の基準の統一化が必要。厳しい検査は国の方針だと思うので仕方がないが、担当者によって基準に大きく違うのは問題。 もしコメントを見る機会があれば改善してほしい。
IMO Secretary General Korea's candidate visits The Bahamas 05/03/11(thebahamasweekly.com ) Filipino Diplomat Nominated for IMO Secretary General Position U.S. Coast Guard Employee IMO Secretary General Candidate Six candidates for position of IMO Secretary-General 04/04/11(Hellenic Shipping News Worldwide)
By the deadline of 31 March 2011, six candidates had been nominated by their Governments for the position of Secretary-General of the International Maritime Organization (IMO).
The election for the post will be held at the 106th session of the 40-Member strong IMO Council, which meets from 27 June to 1 July 2011. The decision of the Council will be submitted to the IMO Assembly, which meets for its 27th session from 21 to 30 November 2011, for its approval.
The nominations received are listed below in alphabetical order by candidates’ name.
Candidate Government
Mr. Lee Sik Chai Republic of Korea
Mr. Andreas Chrysostomou Republic of Cyprus
Mr. Neil Frank Ferrer Republic of the Philippines
Mr. Jeffrey Lantz United States of America
Mr. Esteban Pacha Vicente Kingdom of Spain
Mr. Koji Sekimizu Japan
The present incumbent, Mr. Efthimios E. Mitropoulos, ends his second four-year term as Secretary-General on 31 December 2011.
Source: IMO
あるコンテナ船では代わりの船員が原発事故による放射能を恐れて来ないと騒いでいた。多くの船員が 早く帰りたいと言いながら「日本は大丈夫なのか。」と聞いてくる。個人的に日本政府が言っていることは信用しないが 船員が騒ぐほど酷くないと答えた。ある船員は技術立国の日本なのになぜ事故が起こったと聞くから、 「政府の原子力安全委員会の班目(まだらめ)春樹委員長は割り切った考えに基づくと安全な原発の 設計は無理だと言った。」と説明した。日本の技術の問題ではなく、東京電力や政府の原子力安全委員会がお金を ケチった人災だと答えた。お金がたくさんある日本なのになぜと理解できないようだった。
コンテナ船日本へ引き返す 足止めの中国福建省から 03/28/11(産経プレス)
27日の新華社電によると、高レベルの放射線量が計測されたとして、中国福建省のアモイ港沖合で足止め状態となっていた商船三井のコンテナ船が自ら日本に引き返した。
新華社は計測された放射線量の数値については伝えていない。(共同)
INDO NEWZ – Yesterday, investors meeting in Hamburg. Investor Oaktree (holding 49.5% shares of the company) will next Monday to file for bankruptcy if the creditors do not give much of their claims against the troubled company. The approximately 500 employees in Bremen (worldwide 1900) fear for their jobs. An employee: “There is total uncertainty. No one knows how it goes. I expect it every day that I will be terminated. ”
Meanwhile the new head of Oaktree stop all projects that do not belong to the core business of Beluga. So from, the construction work for the ex-chief Niels Stolberg sponsored Handball boarding school in Oldenburg-Wechloy and the training center “Maritime Campus Elsfleth” first set.
Also on the site for Stolberg’s private home in Bad Zwischenahn to go any more. Stolberg himself seems to the preservation of his life’s work to believe. The owner of Northwest newspaper: “beluga has a real chance of survival.”
東北地方の造船所に甚大被害、地震・津波で設備が損壊 03/15/11(海事プレス)
東北地方の造船所に甚大被害
地震・津波で設備が損壊
東日本巨大地震で、東北地方の造船所には地震と津波による甚大な被害が出ている。とりわけ宮城県の気仙沼市と石巻市での被害が深刻とみられるが、現地の被害状況の全貌はなお明らかになっていない。
国土交通省が取りまとめた14日午前11時時点での東北地方の造船所施設の被害状況は次のとおり。
■北日本造船
八戸工場(青森県八戸市)は人的被害の報告はなし。建造中の船舶3隻は係留済みで、外板などが損傷。一方、久慈工場(岩手県久慈市)は施設が半壊したものの、人的被害はなかった。
■気仙沼市の造船所
吉田造船鉄工所、木戸浦造船が火災により施設の大半が焼失との目撃情報。
■ヤマニシ
人的被害不明。造船施設の大半が損壊。
■鈴木造船所(石巻市)
施設全壊(目視確認)。
■東北ドック鉄工(塩釜市)
人的被害なし。入渠中の漁船2隻が流されたが、ドック前で錨泊中。変電所は使用不可。ドック作業船が沈没。
■宮城造船鉄工(塩釜市)
人的被害なし。事務所が一部破損。
■函館どつく
本紙調べによると、函館どつくでは函館造船所が津波により一部構内が浸水したが、物的・人的に大きな被害はなかった。週末にクレーンや電気系統のチェックを行い、月曜日から操業を開始している。また、室蘭製作所は被害がなかった。
兼松1億5千万円所得隠し ベトナム側に不透明支出 大阪国税局指摘 (1/2ページ) (2/2ページ)02/09/11(産経新聞)
東証1部上場の総合商社「兼松」(本店・神戸市中央区)が大阪国税局の税務調査を受け、平成21年3月期までの5年間で、約2億5千万円の申告漏れを指摘されていたことが8日、分かった。ベトナムの国営企業グループに対する造船技術供与などの受注工作に絡み、ベトナム側へ1億円以上の不透明な支出があったことも判明。申告漏れのうち、不透明な支出を含む1億5千万円前後が悪質な所得隠しと判断されたもようだ。
追徴税額は本来、重加算税を含め1億円近くになるが、累積した過去の赤字と相殺されたため約1700万円にとどまった。兼松はすでに修正申告や納税を済ませたとしている。
関係者によると、兼松では15年以降、国営ベトナム造船グループ(ビナシン)に対し、多数の日本向け新造貨物船を発注。新造船を建造する際は、兼松側からビナシン傘下の造船所に機材や船舶設計、造船技術などを一括して供給してきた。
ただ、ビナシン側に一括供給を受け入れてもらうため、兼松から現地のエージェント(代理人)に対し、新造船を建造するたびに多額の支払いが発生したという。兼松ではエージェントへの支払いは仲介手数料に当たると判断し、税務上の経費に当たる「損金」として処理していた。
これに対し国税局は、エージェントへの支払いが受注工作を目的としたビナシン側への不透明な支出であり、損金に算入できない「交際費」に当たると指摘。さらに悪質な仮装・隠蔽(いんぺい)行為もあったとして、所得隠しと認定したとみられる。
兼松は産経新聞の取材に対し、「受注に絡む正当な支払いだったと認識しているが、国税当局から指摘があったので内部調査をしたうえで修正申告した」とコメントしている。
◇
【用語解説】兼松
明治22年、兼松房治郎が神戸で創業。昭和42年に繊維商社「江商」と合併し、平成2年に現在の商号となった。近年は三菱東京UFJ銀行の支援を受け、IT(情報技術)や食料など4本柱に集中する「脱総合商社路線」を進めている。資本金277億円8100万円。22年3月期の連結売上高は8612億円。
Bulk ship operator Korea Line has filed for court receivership to avoid bankruptcy, it said Thursday. Bulk ships transport timber, iron ore, grains and other large-volume cargo.
The company had been in financial difficulties due to dwindling vessel charter rates. During the bulk shipping boom in 2007-2008,
Korea Line drastically expanded charter services by borrowing ships from other companies. But charter rates, which were around US$100,000 a day,
dropped to around $20,000 after the 2008 financial crisis, said a shipping industry source. "Korea Line signed long-term contracts for the borrowed vessels,
and 80 percent of its revenues go to paying for charter fees," the source added.
Chung Seo-hyun, a researcher at E*Trade Securities, said, "Korea Line appears to have filed for court receivership not under pressure from creditors but
because it did not see any chance of improvement in its financial condition as operating funds ran out."
With W2.28 trillion (US$1=W1,118) in sales in 2009, Korea Line is the country's fourth-largest shipping company after Hanjin Shipping, Hyundai Merchant Marine and STX Pan Ocean
On Tuesday, ocean shipping firm Korea Line announced that it will file for bankruptcy protection due to decreased dry-bulk freight rates that drove operating losses
and a resulting inability to service its debt. Several of the dry-bulk shipping firms we cover rented vessels to Korea Line; Eagle Bulk EGLE is the most-directly affected,
although Navios NM and Genco GNK also are impacted. Eagle currently operates 39 ships, of which it rents 13 to Korea Line. That said, we're encouraged that the attached fixed rates are currently near market levels,
mitigating Eagle's risk should Korea Line break the contracts. Similarly, although Navios' partially-owned subsidiary Navios Maritime Partners NMM garners about 15% of its revenue from Korea Line,
Navios' charter insurance policies should stand to reimburse the company for any losses that arise from the situation. Finally, Genco rents only one of its 50 ships to Korea Line, and the contract is currently slated to expire in February.
Still, we think Korea Line's failure is testament to how bad freight rates have gotten for the industry's largest ships. We believe that much of this weakness stems from floods in Australia which has led to a glut of ships moving from this geography into others,
and we still think that the eventual recovery of this region will lead to better global vessel utilization. However, the magnitude of the recent decline for the largest vessel classes has led us to trim our fair value estimate for Genco and Navios,
which are most exposed to near-term headwinds for these ships. We're maintaining our valuations for Eagle, Diana Shipping DSX, and Excel Maritime EXM due to their limited exposure to both Korea Line and near-term Capesize rates. However,
we caution that a prolonged slump in the dry-bulk industry, stemming from continued weather issues, increased ship supply, or weakened Chinese commodity demand, could lead us to further reduce our discounted cash-flow modeling assumptions.
We reiterate the very high uncertainty that surrounds our fair value estimates.
中国の軍事力向上に貢献/商船三井、新造4隻の建造造船所に滬東中華造船有限公司を選定 01/18/11(JC-NET(ジェイシーネット))
商船三井とExxonMobil社は、パプアニューギニアLNGプロジェクトおよび豪州ゴーゴンLNGプロジェクトの中国向け輸送に必要となる新造LNG船4隻の建造造船所に、中国船舶工業集団公司グループの滬東中華造船(集団)有限公司(Hudong社) を選定した。
商船三井とHudong社との間で造船契約基本協定書を、同時にExxonMobil社を加えた3社間でプロジェクト開発協定書をそれぞれ締結し、1月15日に、協定書の締結を祝う記念式典が北京で開催され、中華人民共和国 張国宝国家発展改革委員会副主任兼国家能源局局長、ExxonMobil社 Mark Albers上級副社長、中国海運(集団)総公司 張国発副総裁、中国船舶工業集団公司のTan Zuojun会長、滬東中華造船(集団)有限公司 王勇社長、及び商船三井の芦田会長が出席した。
今回対象となる新造LNG船4隻は、2015年から2016年にかけて竣工し、中国大手国営船社である中国海運(集団)総公司を共有船主として、長期に亘るプロジェクトへの貸船契約に投入される。
海外船社として初めての中国造船所へのLNG船発注であり、造船所の建造品質と安全基準の引き上げを目指して指導・監督すべく、当社は2011年1月より技術者を5名派遣する。今後、これら4隻の建造が並行して進むピーク時には50名規模まで派遣員を増やす予定で、過去に例がない規模の海外LNG船建造プロジェクトといえる。
商船三井は、本プロジェクトは中国の大手エネルギー会社向けLNG輸送であり、中国の造船所起用、および中国の大手船主である中国海運(集団)総公司とのパートナーシップと、多方面で中国に深く根ざしている。この長期に亘るビジネスを通して、中国関係者との連携を深め、今後の中国ビジネスの発展につなげるとしている。
しかし、4隻とも中国というのは、中国と現政権与党からの圧力でもあったのか?
これでは、新幹線技術流失の二の舞になることは確実。
どちらにしろこれで日本造船技術が中国の軍事技術向上に大きく役立つことだろう。こわっ。
中国の造船業が不況、海外の船主が底値待ちで買い控え―中国メディア 05/22/10(Record China)
2010年5月20日、中国新聞社によると、中国の造船企業が新たな不況に直面している。その影響は金融危機以上のものになるかもしれず、大規模な業界再編にもつながる可能性もある。
これは、19日に江蘇省南京市で開催された中国国際船舶工業博覧会において多くの業界関係者に共通する認識だという。現在、中国の造船業は受注高で韓国に次いで2位だが、原材料価格や船主の売却価格の上昇などにより、利潤は以前より低い状態となっている。
中国造船業のメッカは江蘇省で、中国の新規受注高の36.4%、世界全体でも14%を占めているが、2009年には受注が1件もない月が3カ月あった。そして今年も受注が1件もない企業が多く出ている。
その背景には海外の船主が底値を待ち、買い控えていることがある。発注があっても単発的なもので、この状況が続けば2年以内に2度目の業界再編を迎える可能性が高いとみられている。(翻訳・編集/岡田)
A former South Korean shipyard employee has been arrested amid accusations he attempted to steal vessel designs worth over $100m and hand them to rival Chinese yards.
The 30-year-old lifted the blue-prints for 50 ships over 50,000 tonnes during an eighteen month period before passing them on to shipbuilders in China, South Korean authorities say.
"[He] appears to have aimed at bargaining for a higher salary at another firm with the designs he stole," police said, according to a report by the Yonhap News Agency.
Authorities value the designs at KRW 2.5bn per ship, meaning KRW 120bn ($103m) worth of designs were handed over to the Chinese firms, police claim.
Investigators are looking into whether the designs were given to a Chinese yard where the man, named only as Kim, has recently started work.
Police did not identify the South Korean yard from which the designs were allegedly stolen, but say it is based in Busan and ranks among the world’s 10 largest shipbuilders.
By Andy Pierce in London
消えた新規受注、盟主韓国の焦り>設備過剰でしょ 2009/10/19 (こりあうぉっちんぐ)
機密費・横領疑惑のSLS造船を捜索 09/16/09(中央日報)
検察が中堅造船グループであるSLS造船とその系列社に対する捜査に着手した。
昌原地検特捜部は15日、慶南統営(キョンナム・トンヨン)市のSLS造船本社と同社イ・ククチョル会長(47)の事務室などを家宅捜索した。検察関係者は「機密費造成及び横領疑惑があり、確認作業をしている」と述べた。検察はまた同社が官給工事を受注し、政・官界関係者を相手にロビーをしたのかについても調査する計画だ。検察はイ会長を出国禁止とした。最高検察庁中央捜査部も会計分析チーム捜査官を現地に派遣した。今回の捜査はキム・ジュンギュ検察総長が就任後、不正捜査の信号弾になるものとみられる。
イ会長は鉄道庁公務員で10年間働いた後、造船グループを育て、サラリーマン成功神話の主人公として知られている。1990年代初め、鉄道車両製作会社であるデザインリミットを設立した後、SLS重工業に確張した。以後、シンア造船を買収し、SLS造船に名前を変えて中堅グループとして定着した。以後、SLSキャピタルなど金融系列会社を置くほか、慶南慶山(キョンサン)で産業・造船機資材と鉄道車両部品などを生産するSPロジテックという会社も系列社だ。昨年、SLS造船と10系列社の売上は9800億ウォン台に造船業界7位だ。
検察関係者は「会社の会計帳簿を分析して会社が急速に成長した過程を分析する計画」だとし「会社と地域有志の結託も捜査の対象だ」と述べた。これに対して会社側は「造船業界の不況により、会社の資金事情が良くない状況で検察が捜査を始めた理由が分からない」と話している。
破産手続き中の讃岐造船/中国人研修生ら足止め 09/05/09(四国新聞)
破産手続き中の讃岐造船鉄工所(香川県三豊市詫間町)と関連会社5社が受け入れていた中国人研修生・実習生が、破たん後の約1カ月間、未払い賃金などの支払いを求め、同町内の社員寮で待機する状態が続いている。4日には研修先を仲介した組合の代表理事が寮を訪問、今後について説明したが折り合いが付かず問題解決には至らなかった。
待機しているのは、異業種協同組合「徳島テクノフォーラム協同組合」(徳島市)の仲介で研修していた20代~40代の中国人男性50人。破たん以降、同鉄工所側から身分保障や未払い賃金などについて説明がなかったため、同組合と協議を重ねていた。
この日は、同組合の代表理事が未払い賃金について「将来的には受け取れる」と説明したが、研修生らは「賃金がもらえるまでここを離れない」と主張、一斉に退席するなど一時騒然となる一幕もあった。
同組合はこれまでに11人を帰国させ、新たな研修先の斡旋(あっせん)を模索。研修生の一人(27)は「今は少ない貯金を切り詰めて生活しており、早く解決してほしい」と話し、代表理事は「制度上、解決が困難な事案もあるが、何とかできるよう頑張っている」としている。
村瀬海運:倒産 負債額約25億円 /熊本 08/26/09(毎日新聞)
沿海貨物海運業「村瀬海運」(熊本市安政町)が民事再生法の適用を熊本地裁に申請していたことが分かった。負債額は約25億円に上るという。
民間信用調査会社によると、同社は1961年2月創業。01年12月期には売上高12億2900万円を計上していた。景気後退による輸送需要の減少で業績は急激に悪化し、08年12月期の売上高は8億5000万円程度になっていたという。船舶建造費用の設備投資や不動産取得費用負担なども響いた。
South Korean insurers that had offered bank guarantees on behalf of the recently defunct Jinse Shipbuilding are struggling to pay up.
The need to build up reserves to cover losses from bank guarantees called in by shipowners or their banks has hit at least three of South Korea's non-life insurers.
Heungkuk Fire & Marine Insurance has had to raise Won30bn ($24.4m) after the company saw its solvency margin ratio fall well below the 150% recommended by the country's Financial Supervisory Service.
Taekwang Industrial, Heungkuk's largest shareholder has taken Won7.6bn of new shares issued by the insurer and provided a loan of a further Won20bn.
Heungkuk Life Insurance also purchased Won2.4bn of the non-life insurer's new rights issue.
"Our solvency margin ratio fell [to 118%] as we piled up reserves to prepare against a possible loss from refund guarantee insurance," a spokesperson for the company told local reporters.
"The loss from RG insurance is not realised yet. We just amassed the reserves as there is a possibility we will incur the loss," a spokesperson said.
Jinse Shipbuilding had as many as 40 vessels on order after it upgraded from a block manufacturer to a shipbuilder in 2007, and before owners started to cancel vessels due to late or non-delivery.
Greek shipowner Metrostar ditched deals for 10 handysize bulkers from its order of 16 ships.
Turkish operator Aktif Denizcilik scrapped seven similar vessels from an original order for 10, and sold on the balance to US shipowner Genco. Genco subsequently abandoned the three vessels from Aktif.
Other South Korean insurers involved in offering refund guarantees include Meritz Fire & Marine Insurance and Hanwha Non-Life Insurance.
All three insurers had pushed for providing Jinse Shipbuilding with additional cash of up to Won77.8bn, following a credit evaluation of the yard in March 2009. But the leading creditor banks rejected the proposal of a financial work out plan and the shipyard was abandoned as a working concern.
オデンセ造船所(デンマーク)は撤退。造船をやめる。
* Maersk to end shipbuilding at Odense Steel Shipyard
* To put Baltija Shipyard in Lithuania up for sale
* Shares down 2 pct, underperforming local bourse
(Adds CEO quotes, details, share price)
By Teis Jensen
COPENHAGEN, Aug 10 (Reuters) - Danish shipping and oil group A.P. Moller-Maersk (MAERSKb.CO) will end shipbuilding at the loss-making Odense Steel Shipyard in Denmark and put its Baltija Shipyard in Lithuania up for sale, the company said on Monday.
Maersk said in spite of major efforts to improve competitiveness at Odense through new technology and more efficient production processes, it had run up "very considerable" annual deficits and was unable to attract "commercially sound" orders.
The shutdown of the Odense yard marks the end of a 900-year-old tradition of building big ships in Denmark.
Maersk shares fell 2 percent to 34,000 crowns by 1342 GMT, underperforming a 0.9 percent fall in the Copenhagen bourse blue-chip index .
A.P. Moller-Maersk Chief Executive Nils Smedegaard Andersen said Odense Steel Shipyard had played a key role as Maersk became a global player in the shipping industry.
"But times have changed. Overcapacity in the market and tough competition have made the situation increasingly difficult in spite of initiatives taken to meet these challenges," Andersen said in the statement.
Odense Steel Shipyard posted a 562.3 million Danish crowns ($107.2 million) pretax loss in 2008, a 156.7 million crowns pretax loss in 2007 and a 1.07 billion crowns pretax loss in 2006.
In March, the A.P. Moller-Maersk group posted a net profit of $3.5 billion for 2008, up from $3.4 billion in 2007.
The yard, which currently has 2,700 employees, will fulfill existing orders and continuously downsize the workforce, the company said.
The first redundancies of about 175 employees are expected to take place from the end-August, and the last new vessel on order is expected to be delivered in February 2012, it said.
"With the discontinuation of the shipbuilding activities at Odense Steel Shipyard there is no longer a need for ownership of the Lithuanian shipyard, Baltija Shipyard. The company is therefore put up for sale," Maersk said.
Design and engineering company UAB Baltic Engineering Centre in Lithuania is also up for sale, it said.
Sydbank analyst Jacob Pedersen said Maersk could not avoid closing Odense Steel Shipyard.
"They are looking closely at all parts of the company to find places to cut costs," Pedersen told Reuters, adding there was no prospect of a rebound in shipbuilding orders in the short term. ($1=5.247 Danish Crown) (Editing by Simon Jessop)
Facing sparse orders, iconic yard also will delay ship deliveries
A.P. Moller-Maersk is considering an additional 175 layoffs at its iconic Danish shipyard because of a lack of orders.
The Copenhagen-based shipping and energy group also said the loss-making Odense Steel shipyard, which has built the world’s biggest container ships, has agreed to delay the delivery of three ships.
“We have not obtained new orders for ships since the first quarter of 2008, and during the (current) financial crisis, the prospect of forthcoming orders is poor,” said Finn Buus Nielsen, managing director of the shipyard.
The Odense shipyard has built the world’s biggest container ships for A.P. Moller-Maerk’s ocean container carrier Maersk Line. Maersk says the ships have an 11,000-TEU capacity, but industry analysts put the figure closer to 14,000 TEUs.
The yard has struggled to compete on price with Asian yard,s prompting several hundred layoffs last year aimed at boosting productivity.
Last year, Maersk Line placed an order for 16 7,450-TEU ships at South Korea’s Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering and 18 4,500-TEU vessels at Hyundai Heavy Industries, also in Korea.
A.P. Moller-Maersk quit shipbuilding in Germany and put its Estonia shipyard up for sale last year.
The Odense yard has orders for six bulk carriers, seven roll-on, roll-off vessels and three frigates. This requires around 2,000 workers until the summer of 2010, but this will drop to just 500 if there are no new orders.
The yard said it agreed to delay delivery of three ro-ro ships for Pacific Basin because “charters are difficult to find . . . in a particularly difficult market.”
佐文工業が破産申請へ/讃岐造船破たんで 08/04/09(四国新聞)
帝国データバンク高松支店によると、船舶ブロック製造、鉄板切断加工の佐文工業(香川県丸亀市、佐文日出夫社長)は3日までに事業を停止、自己破産申請の準備に入った。実質的な子会社だった讃岐造船鉄工所(三豊市)の破たんにより多額の不良債権が発生し、事業継続を断念した。負債は約20億9700万円。
東京商工リサーチ高松支社によると、佐文工業の関連会社の万達工業、進工業(ともに丸亀市)も破産手続き開始申し立ての準備に入っている。負債総額は3社合わせて約23億2000万円。
佐文工業は1988年に設立。大手造船業者を得意先とし、2000年に民事再生法を申請した讃岐造船鉄工所の株式を佐文社長が04年9月に取得、筆頭株主となり受注を拡大した。
好況もあって増収基調で推移していたが、7月29日に讃岐造船鉄工所が2回目の民事再生法の適用を申請(同31日に自己破産申請に切り替え)し、貸付金などが不良債権化した。
讃岐造船が破産申請/民事再生取り下げ 08/01/09(四国新聞)
帝国データバンク高松支店によると、7月29日に民事再生法の適用を高松地裁に申請していた小型鋼船、アルミ船製造・修理の讃岐造船鉄工所(香川県三豊市、佐文日出夫社長)は、申請を取り下げ、31日に自己破産を申請した。負債は約90億円の見込み。
同社は1942年設立。2000年9月に民事再生法適用を申請、04年11月に再生手続きが終結したが、余裕の乏しい資金繰りが続いていた上に事業外への資金流出もあり支払い不能となり、29日に2回目の民事再生法の適用を申請した。しかし、申請が認められなかったことから、事業継続を断念した。
2回目の民事再生法の適用申請/讃岐造船 07/31/09(四国新聞)
帝国データバンク高松支店によると、小型鋼船、アルミ船製造・修理の讃岐造船鉄工所(香川県三豊市、佐文日出夫社長)は29日、2回目となる民事再生法の適用を高松地裁に申請した。負債額は約90億円。同じ企業が民事再生法適用を2回申請するのは異例という。
【→参照記事】
同社は1942年設立。内航タンカー、フェリー、砂利採取船などを建造し、県内トップ級の造船業者に成長した。景気低迷などで2000年9月に民事再生法を申請したが、04年11月には再生手続きが終結。07年10月に2号ドックが完成し、造船業界の好況もあり08年11月期に売上高約64億5900万円を計上した。
東京商工リサーチ高松支社によると、今年6月に不透明な資金操作が発覚し、銀行の支援が困難となったことから、7月末の決済の見通しが立たなくなった。
株式会社讃岐造船鉄工所
自己破産を申請
負債90億円
7月29日に高松地裁へ民事再生法の適用を申請していた(株)讃岐造船鉄工所(資本金1億9587万円、香川県三豊市詫間町詫間2112-17、代表佐文日出夫氏、従業員67名)は、民事再生手続きを取り下げ、7月31日に高松地裁へ自己破産を申請した。
申請代理人は馬場俊夫弁護士(香川県丸亀市本町3-25、電話0877-25-1005)ほか1名。
当社は、1942年(昭和17年)2月に戦時中の企業整備令により個人船舶業者が集まり設立された。当初は遠洋漁船の建造を中心としていたが、62年7月にドック設備が整えられ、アルミ合金製旅客船や内航タンカー、フェリー、砂利採取船など幅広く建造し業容を拡大。県下トップクラスの造船業者へと成長。90年11月期には年売上高約51億6500万円をあげていた。
しかし、景気低迷による受注減、競争激化に伴う収益の低下、受注のキャンセルなどから2000年9月に高松地裁観音寺支部へ民事再生法の適用を申請。翌2001年8月には同地裁より2002年~2009年の8回(年1回)弁済などを骨子とする再生計画案の認可決定を受け、2004年9月には現代表の佐文日出夫氏が出資し筆頭株主となったことで、同氏が代表を兼務する佐文工業(株)(香川県丸亀市)の実質的な子会社として再スタート。同年11月には再生手続きが終結していた。
その後は、佐文工業(株)の支援のもと、2007年10月には2号ドックの完成により最大建造能力が1万トン級となるなど大型化へ対応。造船業界の好況もあって2008年11月期には年売上高約64億5900万円を計上していた。
しかし、昨秋以降は世界的な景気悪化が急速に進んだことで、用船料の低下や発注のキャンセルなど業界環境の厳しさが増すなか、当社においては受注残12~13隻を抱えるなど業況を維持してきたものの、再生債務を残し、債務超過状態にあったことで資金繰りが限界となっていた。加えて、事業外への資金流出もあったもようで、資金調達の限界から支払い不能に陥り、7月29日に高松地裁へ民事再生法の適用を申請していたが認められず、事業の継続を断念して今回の措置となった。
負債は、前受け金を含め約90億円となる見込み。
(株)讃岐造船鉄工所 07/30/09(株式会社東京商工リサーチ)
民事再生開始申立 [香川] 造船業
負債総額 約 94億 円
~2度目の民事再生申立て~
TSR企業コード:80-002437-0
(株)讃岐造船鉄工所(香川県三豊市詫間町詫間2112-17、昭和17年2月、資本金1億9587万円、佐文日出夫社長、従業員67名)は7月29日、高松地裁観音寺支部に民事再生手続開始を申し立てた。
申立代理人は、馬場俊夫弁護士(香川県丸亀市本町3-25、電話0877-25-1005)。
負債は約94億円(平成20年11月期ベース)。
明治20年4月創業の老舗の造船建造業者。第二次世界大戦のさなか、昭和17年2月に海務院長官から企業合同の司令を受け、船舶業者が集合し設立されたもの。以降、フェリー旅客船、小型タンカー、砂利採取船など内航船を主力とし、昭和57年11月期には59億1500万円の年商を上げ、地区中堅に成長した。
しかしその後の造船不況、海外の業者との競合などで単価も低迷し、苦戦を強いられた。平成9年、10年と韓国の経済危機などでやや需要が回復したが、11年以降は需要低迷から状況が悪化。11年11月期には年商が24億4200万円まで落ち込んだことで、過去からのドックなど工場設備投資による負担が重く圧し掛かる格好となり、負債総額約36億円を抱え、12年9月に高松地裁観音寺支部に民事再生手続開始を申し立てた。
その後13年7月再生計画認可、16年9月には佐文工業(株)(丸亀市)の代表者である佐文社長が第三者割当増資を実施して筆頭株主となり、同社主導で再生に乗り出していた。以後は造船業界の活況もあり、近海船、内航船の新造受注が好調に推移、平成20年11月期には近海船4隻の新造が寄与し、年商64億5936万円を計上していた。しかしながら、21年6月不透明な資金操作が発覚、これにより銀行の支援が困難となり、7月末の決済の見通しが立たなくなったことから、今回の事態に至った。
開成通商株式会社 民事再生法の適用を申請 06/30/09(帝国データバンク)
「東京」 開成通商(株)(資本金2000万円、港区新橋4-25-6、登記面=江東区大島4-5-11、代表深堀正夫氏)は、6月29日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。
申請代理人は南裕史弁護士(千代田区永田町2-12-4、電話03-5156-8883)。
当社は、1989年(平成元年)12月に設立された海運業者。内外航傭船業者として国内および中国や韓国、東南アジア向けの輸出入業者を得意先に石油化学製品などの運送を手がけ、2000年10月期には年収入高約39億2500万円を計上していた。2003年から2004年にかけて受注が大きく落ち込み、一時は20億円を割り込むまで減少していたが、その後は好景気の影響受けて荷動きが活発となり収入は年々増加、2008年10月期には年収入高約41億5800万円と4期連続の増収決算を計上していた。
しかし、船舶購入資金などの借入金が財務面を圧迫。こうしたなか、取引先でケミカルタンカー等の造船を手がける(株)大西組造船所(広島県三原市)が資金繰り難から民事再生法の適用を申請する事態となり、手形決済のメドが立たず連鎖する形となった。
負債は2008年10月期末時点で約35億8100万円。(帝国データバンクより)
開成通商(株)~民事再生手続開始申立 07/01/09(TOKEI NEWS)
業種 海運
所在地 東京都港区新橋4-25-6
登記上 東京都江東区大島4-5-11
設立 平成元年12月
代表者 深堀 正夫
資本金 2,000万円
年商 (H20/10)41億5,800万円内外
負債総額 (平成20年10月期末時点)35億8,100万円内外
6月29日、東京地裁に民事再生手続開始の申立を行った。
当社は石油化学製品等を運送する海運業者で、平成20年10月期の売上高は41億円を計上していた。 しかし、船舶購入に係る借入金の増加で資金繰りが多忙化する中、取引先であった造船業者の(株)大西組造船所(広島県三原市)が6月29日に民事再生手続開始を申し立てた。これにより、連鎖する形で今回の事態となった。
申立代理人は南 裕史弁護士(東京都千代田区永田町2-12-4、TEL 03-5156-8883)、負債総額は平成20年10月末時点で35億8,100万円内外との事。
(株)大西組造船所~民事再生手続開始申立 06/30/09(TOKEI NEWS)
業種 造船
所在地 広島県三原市須波西町2423-1
設立 平成17年3月
従業員 76名
代表者 大西 謙治郎
資本金 5,500万円
年商 (21/3)87億9,363万円
負債総額 71億円内外
US情報 広島版(H20.12.31)、特別情報 福山版(H21.1.13)ほかで経営難を既報の当社は、6月29日、東京地裁に民事再生手続開始を申し立て、同日開始決定および保全命令を受けた。申立代理人は、新明 一郎弁護士(トラスト綜合法律事務所、東京都中央区日本橋3-3-3、TEL 03-3246-7766)。
なお第1回債権者集会は、7月3日 午後1時より当社会議室で開催予定。現時点で判明している負債総額は71億円内外。
親会社的な存在である(株)大西組(広島県尾道市)が、造船関連の配管工事を行っていた関係で、元・(株)共栄造船(平成11年4月和議申立のち取り下げ)本社地を整理回収機構から購入、平成16年11月から営業を開始し、最初の受注確保に成功。同17年3月に別途新設法人として当社を設立した。
ケミカルタンカーを中心とした船舶の製造および修理を主業務とし、現在 広島県三原市を本社に、東京都港区に支店を配しての事業を展開、元・(株)共栄造船の従業員を雇用し建造体制を構築。折からの造船業界活況の勢いに乗り、売上高は1期目・同18年3月期13億円、同19年3月期36億円、同20年3月期62億円、同21年3月期88億円(この期より進行基準導入)と非常に順調な推移をたどってきた。
当社の特徴は、5,000トン内外のケミカル船の建造であり、同業他社の倒産などにより世界唯一のメーカーとなったため、受注が集中。手持ち受注は合計272億円に到達し、3年分仕事のうち今後2年間は年商100億円以上を確保できる見通しとなった。
一方、設立日が浅く信用希薄なため「支払いはオール現金でしか取引してもらえない」「内燃機関係は前払いでしか納入してもらえない」「急速な事業拡大に資金調達が追い付けない」などを要因から、資金状況は極めて多忙化。平成20年12月ごろから特に厳しさが増し、一部取引先に対して支払いを延期、その金額は総額で3億円内外にまで膨張。加えて、昨年12月に消費税7,500万円の追徴を受けたことも、資金繰りに大きく影響を及ぼした。
平成21年2月には取引先に手形決済への支払い条件変更を打診。直近決算(残高試算表)では、上記通り売り上げ急増を果たしたが、反面で採算割れを誘発し、▲17億7,873万円の当期損失にて終止した。
そのような中、今月末の手形決済資金1億7,000万円のメドが立たず今回の事態となった。なお、会社側の説明によると、既にスポンサーは決定しているとのこと。
資金難の海運会社には朗報だろう!しかし将来への期待から高い船価での中古船購入や高い船価での購入した場合、
かなり良い値で買ってくれないと船会社は困る!傭船料も低迷している!船を買取した後、どのようにするのだろうか??
船会社の損を韓国国民が税金で支えるのか??
新規の造船所建設で世界の建造能力は増えた。加えて既存の造船所の設備投資による建造能力アップした。
今後、低価格で船は建造されるだろう。船舶建造の技術、コスト、品質、設計、耐久性及び営業能力と船主のニーズのさまざまな要素により造船所も
淘汰されるだろう。経営判断を誤った全ての海運会社を一時的に助けても、将来にはつながらないと思う。
政府が海運を守る方針を出したのなら国民が支えるのだろう!日本のお金は当てにしないでね!
船舶ファンド造成、資金難の企業から船買い取りへ 04/15/09(朝鮮日報)
政府系機関と民間が共同で
政府系機関と民間が共同で出資し、4兆ウォン(約2900億円)規模の船舶ファンドが造成される。このファンドは海運業界の構造改革を後押しするために、資金難に陥っている海運会社の船舶を買い取る計画だ。
大統領府で23日、李明博(イ・ミョンバク)大統領主宰の非常経済対策会議が行われ、政府はこれらの内容を中心とする「海運産業の競争力強化方策」を確定し、発表した。
政府はまず、メーンバンクが500億ウォン(約36億円)以上の信用供与を行っている大手海運会社38社に対する信用リスク評価を今月末までに終了し、残り170社の中小海運会社に対する評価も6月末までに終わらせることにした。
また円滑な構造改革を支援するため、政府系機関が1兆ウォン(約730億円)前後、民間の投資家や債権を保有する金融機関などが残りを出資し、共同で総額4兆ウォンの船舶ファンドを造成することも決めた。このファンドは構造改革の対象となった企業や精算が決まった企業が保有する船舶を時価で買い取る計画だという。国土海洋部の関係者は「4兆ウォンあれば100隻以上の船を買い取ることができる」「実際の買い取りは、早ければ6月ごろから可能になるだろう」と述べた。
建造中の船舶については、輸出入銀行による製作金融や船舶金融による支援を行うことにした。今年、造船業界向け船舶金融により融資が策定された額は3兆7000億ウォン(約2700億円)に上り、海運業界向けの船舶金融もおよそ1兆ウォンに達する。これに今回の船舶ファンドを合わせると、総額で8兆7000億ウォン(約6300億円)が海運業界への支援や構造改革に投入されることになる。
また、構造改革の過程で船舶が不当に安値で海外に売却されることを防ぐために、韓国国内で船舶に投資する際の複数の規制が緩和される。大手企業や金融機関による船舶金融業への参入を後押しするため、船舶運用会社に対する出資制限(30%)が廃止され、船舶投資会社に義務づけられている項目の中で、3年以上の存立などを定めた規制も2015年までに緩和される。政府は構造改革と支援を並行して行うことで海運業の競争力を高め、世界の5大海運大国に飛躍する、という目標を定めている。
羅志弘(ナ・ジホン)記者
佐々木造船、アイツェンの解約「合意前」ケミカル船5隻建造中、今週引き渡しも 04/13/09(マリタイム ニューズ 《海事業界専門通信社提供》)
ケミカルタンカー(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
カナサシ重工破綻 金融機関と認識に差 04/15/09(読売新聞)
背景に“見通し甘い経営陣”“赤字に追加”
会社更生法の適用を静岡地裁に申請した静岡市清水区三保の造船会社「カナサシ重工」は、1日から停止していた操業を13日に再開した。同社は今後、操業を続けながら会社の再建を目指す。運転資金を確保できなくなったとして操業の一時停止を自ら発表し、金融機関からの融資を引き出そうとしたものの結局経営破綻(はたん)に至った背景には、経営陣と金融機関との認識の違いがあった。(出口太)
同社は3月31日、「3月末の所要資金の融資を実行してもらっていない。きょう以降の支払いのめどが立たない」などと発表。4月1日から操業を一時停止するとともに、2009年度の新規採用予定者19人の内定取り消しを決めた。
だが、この時点で同社は、「法的整理手続きの準備はしていない。09年3月期も資材暴騰などの要因から23億円の赤字を見込むが、受注残が722億円あり、相当額の利益も見込める」と強気の姿勢だった。
同社は08年3月期決算では年商約102億円を計上したが、鋼材価格の高騰で資金繰りに余裕はなく、収支は7900万円の赤字。09年3月期も年商191億円を目指したが、赤字は23億円に膨らむ見通しで、3月末に金融機関の追加融資を受けられなくなった。
帝国データバンク静岡支店は「いくら受注残を強調しても、赤字が膨らんでいたのは事実。長期的な損益見通しに基づいて融資を実行する金融機関は、昨年来の世界的な金融危機も重なり、姿勢が硬化したのでは」と指摘する。片上久志・元社長も、更生法の適用申請を発表した10日の記者会見で、23億円の赤字見込みへの評価について「金融機関との間に認識のずれがあった。自分たちは(業績は)V字回復すると思っていた」と述べ、悔しそうな表情を浮かべた。
同支店によると、同社は遠洋漁業の不振で事業の軸を漁船から貨物船の建造に移した。近年は、貨物船建造と船舶修繕を中心に、実習船の建造や耐震貯水槽の製造なども手がけていた。貨物船の建造で年商は拡大したが、貨物船は漁船より工期が長く、その間に受注時より鋼材価格が高騰したりアクシデントに見舞われたりといったリスクを抱え込みやすい。実際、同社のドックで3月28日、新造中の貨物船から出火した。修繕には多額の費用がかかるとみられている。
同支店は「金融機関の融資を受け続けるには、より厳格な経営見通しが必要だった」と、同社の見通しの甘さを指摘している。
支援企業選びが焦点 更生法適用のカナサシ重工 04/15/09(静岡新聞)
総額201億2000万円の負債を抱え、会社更生法の適用を申請した造船会社のカナサシ重工(静岡市清水区)が、今週から操業を再開した。次の焦点となる支援企業選びは同業他社を軸に進むとみられ、保全管理人の下で法的手続きが本格化する。ただ、比較的手続きが簡易な民事再生法ではなく会社更生法を適用したことで、再建への道のりは長期化も予想される。
大企業の経営破綻(はたん)で利用されることが多い会社更生法は事業の継続に支障が少ない一方、手続きが厳格で、開始決定から終結まで10年以上かかる例もある。同社は民事再生法ではなく会社更生法を選んだ理由を「より強力な手続きだから」と説明する。担保を設定した債権者の権利行使を凍結できることなどを考慮したという。
支援企業についてカナサシ重工側は10日の会見で、「発表する段階にはないが、支援してもらう方向で進んでいる話がある」と打ち明けた。造船会社の経営破綻の場合、同業他社がスポンサーに乗り出す例が多く、「手持ち資金が豊富で事業に精通した大手造船会社が候補の中心になる」との見方がある。
今後は支援企業とともに1年以内をめどに更生計画案を策定し、債権者らに諮ることになる。信用調査会社の関係者は「カナサシ重工は700億円以上の受注残があるとされ、利益が出る体質に変えることができれば魅力はある」と分析。一方で、「会社更生法は手続きが長期化する傾向にあり、その間に経済情勢が急変すれば、計画案の再考などでさらに再建が長引く可能性もある」と指摘する。
カナサシ重工は、1988年9月に会社更生法の適用を申請した金指造船所が前身。当時も更生計画を変更して清水工場を分社化するなどし、手続きの終結までに15年を要した。
カナサシ重工 更生法申請 負債総額201億円 04/11/09(中日新聞)
資金繰りに行き詰まり操業停止していた造船会社「カナサシ重工」(静岡市清水区)が10日、静岡地裁に会社更生法の適用を申請し、保全命令を受けた。負債総額は201億2000万円。信用調査会社の帝国データバンク静岡支店によると、静岡県内では過去16番目の超大型倒産。
カナサシ重工によると、2009年3月期で23億円の赤字となる見通しで、金融機関からの資金調達がまとまらず、自力再建を断念した。同社は法的整理について今月1日の操業停止直後から検討。最終的に同法の適用申請に踏み切った理由としては「納期の迫った貨物船があり早期に操業を再開する必要があった」としている。
新規の造船受注額が722億円あり、今後3年間で100億円を超す黒字が見込まれるとして、13日に操業再開し、140人の社員全員の雇用を継続する。入社前日の3月31日に内定を取り消した大卒、高卒の19人については当面、白紙の状態としている。
静岡県庁で記者会見した片上久志社長は「V字回復できると思っていたが、赤字について金融機関の受け止め方は違っていた。ご迷惑を掛け申し訳ありませんでした」と謝罪した。
保全管理人は、会社更生手続きの条件となるスポンサー企業について「ある程度の見通しはあるが、発表する段階にない」とした。
同支店によると、カナサシ重工は海運業界の活況で、08年3月期に過去最高の売上高102億円余を計上する一方、鋼材価格の高騰で7900万円の赤字に転落。4月1日から操業を停止し、静岡市や清水商工会議所が支援策を発表していた。
カナサシ重工 1903年に大阪で創業した金指造船所が前身。遠洋漁業の不振で88年に会社更生法の適用を受け、再建を果たした。91年にカナサシに社名変更。清水工場を分社化する形で99年、カナサシ重工が設立された。現在は商船建造が中心。資本金3億円。愛知県豊川市に営業所がある。
入社式前日の内定取り消しに、融資を受けるめどが立たない中での操業再開表明……。1日の操業停止以来揺れ続けていた静岡市清水区の造船会社「カナサシ重工」が10日、静岡地裁に会社更生法の適用を申請し、受理された。9日には、同社は13日からの操業再開を明らかにしたばかり。いったんは改めて入社を要請するとしていた内定取り消し者については、「全くの白紙」と繰り返した。
「多くの関係者に迷惑をかけ、申し訳ありません」。10日午後、県庁で記者会見をした同社の片上久志・元社長は深々と頭を下げた。
同社によると、1日の操業停止後も金融機関と融資継続の協議を続けてきたが、時間がかかると判断。建造途中の船が3隻あることから、会社更生の手続きのもとで一刻も早い操業再開を図る道を選んだという。今後、支援企業を探す方針だが、めどは立っていないとしている。
13日の操業再開後は、建造途中の船を完成させ、その売上金を運転資金にまわす計画。一時帰休にしていた正社員と下請け会社の従業員計500人については、一時帰休を解くとしている。
一方、入社式前日の3月31日に採用内定を取り消した新卒者19人に対して、保全管理人に選任された弁護士は「会社の実情などを調査したうえで決めるが、今のところは全くの白紙」と繰り返した。同社幹部は9日、操業再開後に内定取り消し者には改めて採用したい旨を申し入れるとしていたが、弁護士は10日、そのような考えはないことを強調した。
同社の会社更生法申請を受け、金融機関に同社への融資継続を要望している静岡市の小嶋善吉市長は「どのような形であれ、事業が継続されるよう願っている。市として支援できることを引き続き検討していく」とのコメントを出した。
【韓国】一極集中に限界露呈、現代重の造船事業 04/10/09(NNA)
韓国造船トップ、現代重工業の主力事業である造船・海洋プラント事業が低迷していることが9日までに分かった。世界的な景気低迷で、発注量が大幅に減ったことが影響しているという。手持ち工事量が減り始める2~3年後にも経営環境が大幅に悪化するともいわれており、その対策として事業の多角化にも着手。同社の事業低迷は造船好況で潤ってきた造船大国・韓国の象徴といえそうだ。【東アジア編集部・安藤久史】
■2月は受注85%減
現代重工業の今年2月の全受注額は、前年同月比85%減の12億5,000万米ドル(約1,250億円)と低迷した。これまで全体の約7割を占めていた造船・海洋プラント受注が大幅に悪化したことが大きく響いた。
事業別にみると、造船は昨年2月の44億1,900万米ドルからゼロ。海洋プラントは93.7%減の1億100万米ドルと急減した。
これまで付帯産業として位置づけられていたエンジン機械は75.2%減の3億4,800万米ドル、建設設備は59.3%減の1億5,400万米ドルといずれも低迷した。
事業で増加したのは19.3%増の5億9,300万米ドルを記録した電気電子事業だけだった。
■比率低下43%に
これまで主力としてきた造船事業の比率は、今年2月には昨年末の45.5%から43.0%に下落。今年は世界的な景気低迷で、発注量が大幅に減少していることから、今後も、現代重の造船比率は下落するとみられている。
さらに、海洋プラント事業では、液化天然ガス(LNG)を生産できる浮遊式石油・ガス生産貯蔵積出システム(LNG-FPSO)などの発注量は増えているものの、技術競争力がないため、受注に至っていない状況だという。
受注額の減少により、現金保有額も大きく悪化している。昨年末は2兆4,466億ウォンと、前年に比べ32%減った。さらに、今年第1四半期(1~3月)には1兆5,000億ウォン台にまで下落するとも推算されている。
グッドモーニング新韓証券のアナリストは、「造船業界が好転しない限り、現代重の造船・海洋プラント比率は下落し続ける」と予測。今後、事業の多角化を進めない限り、手持ち工事量が減り始める2~3年後には業績が大幅に悪化することになるとも指摘する。
■カギは経営多角化
これまで無借金経営を行ってきた現代重だが、今後も造船不況が続く可能性があることから、今月3日、太陽光・風力発電事業のために3,000億ウォンの社債を発行した。
同社はメーン事業の悪化から、成長が見込まれているエコ事業で業績を好転させる方針だ。来年には、同事業の売上高を昨年実績(1,100億ウォン)の約9倍に当たる1兆ウォン規模にまで引き上げる計画という。
新・再生エネルギー部の関係者は「太陽光事業でも金融危機の影響を受けているが、目標達成には自信がある」と強気の姿勢を示している。
自信の裏には、同社の積極投資がある。忠清北道・陰城で、昨年6月に稼働した30メガワット(MW)級の太陽電池工場、70MW級の太陽光モジュール工場に加え、今年10月には300メガワット(MW)級の太陽光モジュール第2工場が稼働する予定。さらに、第3工場の設置を含め、2012年には計1ギガワット(GM)規模にまで工場を拡張する計画だ。
また、風力発電事業でも、今年9月には、全羅北道の群長国家産業団地内に風力発電所(年産60万キロワット=kW)が完成する予定となっている。
■「日本の跡」追えるか
ある業界関係者は、「今後、どこまで造船の事業比率が下がるかが焦点」と指摘する。
かつて造船大国といわれた日本も、1970年代の造船不況の影響で、事業の多角化に乗り出した。現在では造船比率が10%を切る造船メーカーも多い。
現代重の低迷は今後、造船比率が8割を超える大宇造船海洋やサムスン重工業にも大きな影響を与えるのは必至。造船産業は、これまで韓国経済をけん引してきただけに、今後の造船事業の行方は韓国全体の景気にも影響を与えそうだ。
真面目な話 04/03/09(Re:Re: Ver.みんカラより)
以前も船の機関室で事故を起こしていたようだ。過去の教訓を生かせなかったのだろう。
タンカー爆発10人けが 清水市の造船所 09/08/99(Yellow Hiro の 独り言のHPより)
8日午後3時50分ごろ、静岡県清水市三保の造船会社「カナサシ重工」清水工場(行徳威夫社長)のドック内で、名古屋市港区の東海タンカー所有のオイルタンカー八葉丸(699トン)の機関室付近が爆発。乗組員の東海タンカー社員村田成秋さん(49)=三重県南勢町=が意識不明の重体となったほか、同社員や作業員ら4人が全身やけどの重傷を負うなど、計10人がけがをした。八葉丸の船内の石油タンクは空で、建物などへの延焼はなかった。
村田さんのほかに全身やけどの重傷を負ったのは、東海タンカー社員の田岡靖史さん(52)=三重県南勢町▽同、浜口道夫さん(49)=同県浜島町▽カナサシポートサービス社員の内田忠良さん(52)=静岡県清水市▽清水船舶機械工業所社員の増田政治さん(50)=同。
静岡県警清水署などの調べでは、八葉丸は4年に1度の定期検査のため、7日から14日までの予定でドック入りしていた。8日は午前8時からエンジンの分解作業中で、負傷した10人はいずれも機関室内にいた。事故当時はエンジンから油を抜き取る作業をしていたという。
静岡の造船会社、入社式前日に19人内定取り消し 04/02/09(読売新聞)
静岡市清水区三保の造船会社「カナサシ重工」(非上場、片上久志社長)が、1日に採用を予定していた19人の内定を3月31日に取り消したことがわかり、静岡労働局が事実関係の調査を始めた。
同社は「運転資金の融資が受けられない」として、1日から操業を一時停止した。同社によると、内定を取り消したのは大卒7人、高卒12人で、1日に入社式を行う予定だった。しかし、08年3月期決算で7900万円の赤字を計上。09年3月期も資材価格高騰などで23億円の赤字が見込まれ、融資が受けられない状況に陥り、31日に操業の一時停止と内定取り消しを決めた。
静岡市清水区の造船会社、操業を一時停止 04/01/09(SBS TV)
清水区の造船メーカー操業一時停止 融資受けられず 04/01/09(静岡新聞)
静岡市清水区三保の造船メーカー・カナサシ重工(片上久志社長)は31日、メーン銀行から年度末に必要な資金の融資を受けられず、取引先への支払いのめどが立たないことを理由に、4月1日から操業を一時停止することを決めた。現時点では法的整理手続きの準備はしていない。新造船の受注は好調で、今後は黒字化も見込めるため、操業の再開を目指して金融機関との折衝を続けていく。
同社によると、平成20年3月期は7900万円の赤字(経常利益は8900万円)、21年3月期も鋼材など資材暴騰などが要因で23億円の赤字決算を見込んでいる。その一方、新造船受注残は約722億円ある上、いずれも利益が見込める優良な受注だとして、今後3年間で100億円強の黒字を出すとしていた。
こうした状況を踏まえて金融機関には融資を依頼してきたが、「ご理解いただけない状況にある」(同社)としている。
同社は融資が受けられるよう引き続き金融機関と折衝を続けていくが、「不可能な場合は、法的整理手続きを行わざるを得ない事態も考えられる」という。操業停止は31日夕方ごろから債権者などの関係者に伝えたとみられる。
同社の前身の金指造船所は明治36年に大阪で創業し、その後、旧清水市内に工場を移転した。昭和38年には鋼製漁船建造量で日本一となったが、その後の造船不況などによって経営は悪化し、同63年には静岡地裁に会社更生法の適用を申請した。平成3年からは更生計画に基づいて会社の再建を進め、同11年には更生計画を変更して清水工場を分社化し、新たに子会社「カナサシ重工」を設立、漁船や貨物船の建造、修理などを続けてきた。
同社は資本金3億円。従業員は約150人。20年3月の売り上げは約100億円。
28日午前8時15分頃、静岡市清水区三保の造船会社「カナサシ重工」のドックで、新造中の貨物船(約1万8600トン)から出火し、機関室を焼いた。船内にいた作業員約50人のうち、2人が煙を吸って病院に運ばれたが軽症という。
清水署と同社の発表によると、この日は午前8時頃から作業を始めたが、船体後部の機関室で溶接中、出火したとみられる。
現場は造船所や火力発電所などがある清水港の工業地帯。消防車15台やヘリコプターが出動した。
近くに住む男性会社員(50)は「機関室の排気口付近から黒い煙が上がっていた。消防車のサイレンもしばらく鳴っていた」と話していた。
建造中の大型貨物船で出火、一部焼ける 静岡市 03/29/09(産経新聞)
28日午前8時15分ごろ、静岡市清水区三保の造船会社「カナサシ重工」前のドックで、建造中の大型貨物船(1万8600トン)内から出火。火は約2時間後に消し止められたが、船内後部機関室の一部などが焼けた。煙を吸った男性作業員2人が病院へ運ばれたが、命に別条はないという。
当時、機関室周辺で溶接作業が行われていたといい、清水署は火花が船内の重油に引火した可能性があるとみて原因を調べている。船内では作業員約50人が造船や点検作業に当たっており、貨物船は完成間近だったという。
建造中の貨物船一部燃える 静岡、作業員2人搬送 03/28/09(産経新聞)
28日午前8時半ごろ、静岡市清水区の造船会社「カナサシ重工」のドックで、建造中の貨物船(18600トン)から出火、船の後部機関室の重油などが燃えた。煙を吸って気分が悪くなった作業員2人が近くの病院に運ばれた。
機関室周辺では溶接作業が行われており、清水署は火花が重油に引火した可能性があるとみている。
同署によると、当時、船内では作業員約50人がいて、溶接作業のほか機関室の重油が循環するパイプの掃除などをしていた。貨物船はほぼ完成していた。
新造貨物船の機関室焼く、2人が煙吸う…静岡・清水港 03/28/09(読売新聞)

28日午前8時15分頃、静岡市清水区三保の造船会社「カナサシ重工」のドックで、新造中の貨物船(約1万8600トン)から出火し、機関室を焼いた。
船内にいた作業員約50人のうち、2人が煙を吸って病院に運ばれたが軽症という。
清水署と同社の発表によると、この日は午前8時頃から作業を開始したが、船体後部の機関室で溶接中、出火したとみられる。現場は、造船所や火力発電所などがある清水港の工業地帯。消防車15台やヘリコプターが出動し、午前10時28分に鎮火した。
【韓国】韓国造船ピンチ、今年の受注はまだ1隻 03/10/09(NNA)
韓国の輸出産業を支える造船各社の受注が急減している。世界的な景気悪化の影響で昨年下半期(7~12月)から減少しはじめた世界の船舶発注量は1けた台まで落ち込み、大手造船会社の今年に入ってからの新規受注は1件にとどまっている。さらに、発注の取り消しを要求されるケースも相次いでいる。
業界筋によると、韓国造船大手4社(現代重工業、大宇造船海洋、サムスン重工業、STX造船)の受注は、1月はサムスン重工業が受注したLNG-FPSO(浮遊式石油・ガス生産貯蔵積出システム)1隻、先月はゼロだった。昨年、引き渡し量で世界トップとなった現代重工業は、ここ5カ月間、防衛事業庁が発注した戦闘艦を除くと新規受注が1隻もない状況だ。
背景には、世界的な不況で物流量が減少し、船舶の発注が急減していることがある。造船・海運専門の調査会社の英クラークソンによると、世界の船舶発注数は昨年7月(322隻)以降減少しており、今年1月は9隻にすぎなかった。2月も前月と同水準とみられている。今年は世界の船舶受注量が昨年比60%減少するという見方もでているほどだ。
さらに、船主が受注の取り消しや変更を求めるケースも増えている。現代重工業はギリシャの船主から受注していたバルク(ばら積み)船2隻の発注が取り消しとなった。また、イスラエル海運大手のジムが、発注済みの船舶41隻の契約取り消し・変更を表明していることから、サムスン重工業や現代三湖重工業の受注分が白紙化もしくは引き渡し延期となる可能性も出ている。
中小の造船業者はさらに深刻だ。主な取引先である国内の中小海運業者が資金難に陥り、代金支払いが滞ったり契約取り消しを求めているためだ。ワークアウト(債権銀行による企業再生プログラム)を行っている大韓造船、進世造船、ノクボン造船の3社は、注文の大部分が取り消される可能性もあるという。進世造船は6億米ドル規模の受注が白紙化となり、契約金の返済を要求されている。
■大手3社も資金確保へ
こうした受注不振の中、現代重、サムスン重、大宇造船の大手3社は資金不足を補うため、社債やコマーシャルペーパー(CP)の発行を推進している。
3社の現金もしくは現金化できる資産は、昨年下半期以降の受注不振により、ここ6カ月で半減したとみられている。各社は現在の手持ち資金では上半期(1~6月)を乗り切るのも困難と判断し、短期的な資金確保のため、社債やCP発行を急いでいるもようだ。
2002年の社債発行以降、現在まで無借金経営を行ってきた現代重工業は、近く最大1兆ウォンの社債を発行する見通し。同社関係者は「具体的なことは決まっていないが、どのような形であれ資金調達が不可欠」と話している。
大宇証券のアナリストは「大手は3~4年分の手持ち工事量を確保しているため中・長期的には問題ないが、新規受注がないため短期的な現金の流れは極めて不安定な状態」と話している。毎日経済新聞などが伝えた。
ウォン暴落 造船キャンセルへの動きを直撃 02/24/09(Lloyd's List)
船主達と韓国造船業者の間で進められている何億ドルもの新船建造の契約キャンセル交渉は、ウォンの下落に伴う造船所の保有外貨の莫大な損失の脅威によって妨げられている。
造船業者の問題は、新規建造注文によって今後2~3年に渡って支払われる予定の、先物ドル売り予約に起因する ─ これらの契約がキャンセルとなれば、船主は支払いをしないこととなり、造船所は外為決済のために高価なドルを買い付けねばならない。
造船所によるドル買い要求は韓国通貨へのさらなる値下げ圧力となり、国の貿易地位悪化への負のスパイラルを大手貿易業者の上に築き上げる。
ある船主は「現実的に韓国企業は船の注文がもたらすドルを切実に必要とするため、キャンセルや(引渡し)延期を了承できないということだ」と語る。
大宇証券の分析によると、ウォンの急落の要因には、東欧経済危機の『飛び火の可能性』を含む銀行の外貨建て負債に対する信用不安と、造船注文のキャンセルなどのいくつかが挙げられている。
大多数の韓国造船企業は予定されているドル収益を、国内銀行と先物取引を通じて交換していたと思われ、先に挙げた二つの要因は関連があるといえる。
次に(韓国の)銀行は、国際市場において類似の行動を取った。
韓国の造船業は約2千億ドル相当の各種注文を受けているが、殆ど建造の進んでいない2008年に結ばれた契約の殆どが、キャンセルの危機に曝されている。
大宇証券は、韓国造船業が昨年合計595億ドルに達する新規建造注文を確保でき、そこから30%を原料と設備を輸入することに費やしていると見積もる。
証券会社は、造船業のもつ注文価格の残り70%中、約90%がヘッジされると指摘する ─ このように、先物ドル売り予約による純益は、注文価格の約63%と見積もられる。
2008年に595億ドルの契約が利益を上げたと仮定すると、外為取引を通じた375億ドルがヘッジされると推定される。
ウォンの対ドル価格が2008年前半の数値から60%減少した今、新規造船契約がキャンセルされるなら、先物ドル売り予約は実質的に『アウトオブマネー(利益が得られない状態)』に陥ると言える。
「造船キャンセルに伴うドル需要は、世界中の金融市場の市況で観測されている」と大宇証券は語る。
世界的金融危機に伴う混乱のために、2008年第4四半期に危機に陥った韓国の[外国為替]市場は、2月にも類似した苦境に直面している。
「東欧の金融危機と造船キャンセルにある程度の見通しが立たない限り、金融不安は消えそうにない」
当然ながら多くの海運会社は、財政圧力と鉄鋼価格下落による譲歩を造船業者に期待するかもしれない。
「しかし、韓国が絶望的状況にあるのを、彼らは見ようとしない」と、ある船主は語る。
「私の個人的な推測だが、韓国の造船業者はキャンセルや引渡し延期の、いかなる交渉も承諾も受け入れないよう、中央銀行(韓銀)からの圧力を受けているように思える」
大宇証券は、韓国金融当局が輸入と借り入れを減少させることによってドル準備高を維持し、対外投資を回収することによりドル需要を減らす方針だと語る。「供給拡大してからの輸出・対外投資を通じてのドル需要は、さらに大きくなった」
非常事態の海運業界「先が見えない」 01/06/09(東亜日報)
韓国内海運業界10位、TPCコリアのイム・ドンピョ企画取締役は最近、韓国船主協会や金融圏を頻繁に訪れ、世界的な信用危機で厳しくなっている資金調達に余念がない。
同社が現在造船会社に発注した量は計10隻余り。中途金(契約金と残金の中間に払う代金)を支払うことができなければ、契約は破棄され、契約金の30%に上る手付金を失う羽目になる。
最近の景気低迷で、中国の鉄鉱石の輸入が激減するなど、海運需要すら激減し、各海運会社とも経営が目立って悪化している。実際、海運業のバルク船収益性指標であるバルチック海運指数(BDI)は最近、700~800台で、昨年のピーク時(11793)の10分の1以下へ急落した。
一部の中小海運会社では、今年1月から3月までの3ヵ月間の社員給料を繰り上げ、昨年12月にまとめて支払った。帳簿上の費用項目を最大限増やし、法人税を削減するための苦肉の策だ。
危機に見舞われている各海運会社の非常事態は、財務や組織、経営など各部門で本格化している。
●中小造船メーカーが一番打撃
世界的な金融危機は海運会社のみならず、中小造船会社にまで飛び火し、海運や造船業界が軒並み非常事態になる可能性もありうる。海運会社への中途金の貸出に行き詰まり、造船契約が相次いで破棄されているためだ。運賃料の下落で船舶価格が下がったことも、大きな影響を及ぼしている。
韓国船主協会と海運業界によると、手付金の還付保証(RG)を受けていない韓国内海運会社による発注船舶は現在、50隻余りに上り、近いうちにこれらの造船契約は破棄されるものと見られる。昨年末基準で、韓国内造船会社の受注残高(334隻)の56%(188隻)は、韓国内の各海運会社が発注したもの。
これを受け、韓国船主協会はNH投資証券と連携し、船舶管理会社(SAMCO)設立を推進している。流動性危機に見舞われている各海運会社は、船舶をSAMCOに売却し、現金を確保した後、一定期間(3年)該当船舶を借り、使用する方式だ。
海運会社では、全額借金を返済し、約定した賃貸期間が過ぎれば、SAMCOから再び船舶を買い戻すことができる。
●海運会社は船舶減らし、組織改革も
各海運会社では需給調整のため、従来のバルク船の廃船にも積極的に乗り出している。
韓国海洋水産開発院(KMI)は、今年末までに全世界で約70隻以上のバルク船が解体されるものと予測している。これは海運物量の減少で船舶需要が減っている上、老朽化した船舶へのメンテナンス・コストを節約するための対策である。
昨年上半期までは、各海運会社とも我先にバルク船を注文したのとは対照的な状況である。
割合余裕のある大手海運会社でも今年、新たに船舶を契約するよりは、チャーターをし、使用する方針だ。韓進(ハンジン)海運と現代(ヒョンデ)商船は今年、造船契約の発注を行わない計画だ。
現代商船の関係者は、「3~4年前までは、船を新たに発注するコストが安くて発注したが、昨年と今年は船が余っており、借りても十分間に合うものと思う」と語った。
【韓国】危機の海運業、政府が再編主導か 12/16/08(NNA)
海運景気の悪化が深刻化している。昨年初めの海運好況で、銀行から融資を受けて船舶を大量に借り入れた業者が、世界的な景気悪化による物流量の減少や運賃の大幅下落により資金難に陥っているためだ。韓国政府は最近、業界の実態調査を行っており、造船および建設業に続き、海運業も政府主導で事業再編を行う見通しだ。
毎日経済新聞などによると、破産申請はしていないものの、用船をすべて返還して事実上、事業を行っていない中小企業が10社はあるとみられている。船の価格が大幅に下落しているため船舶を処分することもできず、金融機関側も融資の返済を延長することができないのが現状だ。船を処分せずにいる業者の中でも貨物量の急減や運賃の下落で、赤字が膨らむとの理由で運航を中止した企業も多い。
海運景気の指標となるバルチック運賃指数(BDI)は年初から上昇を続け2,000ポイントまで回復したが、ここ数日は下落が続き1,800ポイント台にとどまっている。
中小の業者だけでなく、韓国の海運ビッグ4(現代商船、韓進海運、STXパン・オーシャン、大韓海運)も事情は同じだ。
STXパンは、昨年第4四半期(10~12月)に1,306億ウォン(約82億円)と4社中で最多の営業利益を計上したが、これは年間営業利益の17%に過ぎなかった。現代商船は第3四半期(7~9月)までに5,478億ウォンの営業利益を記録したが、第4四半期には398億ウォンと急減した。今年第1四半期(1~3月)について業界関係者は、「これまでに経験したことのない最悪の実績も避けられない」と話している。
大韓海運は166隻の用船を保有しているが、大部分は長期契約のため用船料の負担が重くのしかかっている。
■実態調査はすでに完了
これを受け、国土海洋部などは海運各社の実態調査を実施。企業側に、昨年の実績や1年以上の長期契約の有無、海外での雇用概況など詳細な資料を要請したとみられている。
政府は再編の有無について明言はしておらず、「海運業の経営環境が悪化しており、対策を立てるため」しているが、業界再編を念頭に置いたものとの見方が支配的だ。
昨年はパークロードとC&ラインが債務不履行を宣言。今月には業界7位の三善ロジックスが法定管理(会社更生法に相当)を申請しており、業界では連鎖的な倒産が懸念されている。
THE latest victim of insolvent South Korean shipping company Samsun Logix is Nippon Yusen Kaiun affiliate Taiheiyo Kaiun Co.
The Japanese bulk specialist told Lloyd’s List that it had sub-chartered two handymax vessels to Samsun Logix.
A source at Taiheiyo Kaiun said: “In addition to outstanding charter fees of two years at around $46,800 per day and two and a half years at $27,600 per day, Samsun Logix also owes this company \181.28m ($1.4m) for shipping service fees.”
The source was not prepared to divulge which operator it had chartered the two vessels from.
As yet the vessels have not been returned and Taiheiyo is undecided whether it will attempt to operate the ships in the greatly depressed spot market, as the company had chartered the vessels for similar periods from the original owner.
“We are still considering our approach to this problem but bringing an action against Samsun Logix would seem inevitable,” the source said.
Taiheiyo continues to negotiate with another foreign sub-charterer that announced it wanted to prematurely dissolve contracts on four panamax and handymax vessels that the company has chartered. So far Taiheiyo has refused to accept the intended breach of contract.
In recent months Taiheiyo has sought to mitigate the likely losses incurred in a depressed market through the sale of some of its tankers.
It successfully sold three very large crude carriers to parent company NYK and accrued a profit of \2.9bn.
In January, however, it was less successful when attempting to sell a fourth VLCC to Malaysia’s Eraru (L) Ltd, when the buyer failed to come up with the funds within the contracted period.
The source said it had so far failed to raise any interest for the VLCC from other parties but was hopeful of making a sale before the end of fiscal 2008.
Samsun Logix filed for court receivership at Seoul central district court on February 6.
The Dry-Bulk Domino Effect Ruthie Ackerman, 02.10.09, 06:40 PM EST (Forbes)
Bankruptcies disrupt charter deals for Samsun Logix, which files for protection and puts rivals under the gun.
Logix is the latest domino to fall in they dry-bulk shipping market, bringing pressure on those companies that might be next in line. The South Korean shipping company has filed for the equivalent of bankruptcy protection, raising questions about a number of publicly traded dry bulk ship owners that had chartered their vessels to the firm.
Those at risk: DryShips (nasdaq: DRYS - news - people ), Genco Shipping & Trading (nyse: GNK - news - people ), and Navios Maritime Holdings (nyse: NM - news - people ), which all have ships chartered to Samsun Logix.
DryShips shares tumbled 11.1%, or 72 cents, to $5.78, on Tuesday, while Genco slid 10.8%, or $2.27, to $18.69. Navios sank 10.0%, or 47 cents, to $4.21.
Reports began circulating on Monday that Samsun Logix filed for court receivership, which is similar to bankruptcy protection, on Friday, according to a senior official from creditor Shinhan Bank. Samsun Logix got slammed by the cancellation of a number of contracts by companies to which it had subchartered vessels, causing it to run short of cash. Shipping companies sometimes have some vessels chartered to competitors while other craft are chartered from them.
Three other dry-bulk shipping companies – U.K.-based Britannia Bulk Holdings, Singapore-based Armada, and Ukraine-based Industrial Carriers – all filed for bankruptcy protection in the last several months and returned ships they chartered from Samsun earlier than expected, sticking the Korean company with massive losses, according to the shipping publication Lloyd's List. (See “Britannia Battered By Drop In Demand,” “Dry Bulk Shipping Slips Underwater” and “Atlas Leaves Lessors At Sea.”) Armada filed for bankruptcy protection after Australian miner Fortescue Metals Group defaulted on a contract said to be worth $200.0 million.
As freight rates plunged over 90.0% from their summer highs, the number of companies filing for bankruptcy protection kept piling up. The pain isn’t just felt by the companies that go under, but also by those from which they charter vessles. .
On Friday, DryShips announced it agreed to sell the 1995-built M/V Toro for $36.0 million, a 43.0% discount to the $63.4 million agreed upon with buyer Samsun Logix in July. (See “Desperate DryShips Makes A Deal.”) At the time the news looked like a good deal since DryShips had announced in January in a filing with the Securities and Exchange Commission that Samsun Logix had backed out of the deal completely. The news that Samsun Logix is filing for bankruptcy protection calls into question whether the sale of the Toro will go through at all.
■行政・金融機関/連絡会議開く
佐世保市の船舶荷役機械大手、辻産業(辻恒充社長)が12日に会社更生法適用を申請したことを受け、週明けの15日、県や市、金融機関などは、連鎖倒産の防止や雇用を確保する取り組みを本格的に始めた。同社ではいつも通りに従業員が出社して作業に臨む姿が見られたが、「本当に仕事が続けられるのか」と不安を漏らす従業員もいた。
▼「仕事は」従業員不安
午前8時すぎ。同市光町の辻産業相浦工場から工作機械の音が響き始めた。構内ではトラックやフォークリフトが慌ただしく行き交っていた。
従業員が申請を知らされたのは週末を控えた12日午後だった。構内で開かれた緊急集会で東京地裁からの保全命令や、全従業員の雇用確保について伝えられたという。
子会社4社と合わせて負債総額は758億円に上り、従業員らは不安を隠せない。
ある男性従業員は「本当にいまの仕事を続けられるのか。今後の給料や、受け取っていない冬のボーナスはどうなるのか何も分からない」。別の男性は「危ないという話は聞いていたが、創業120年のネームバリューと高い技術力で乗り切れると思っていた」と、いまだに信じられない様子だった。
辻産業労組は15日、始業前から工場正門でビラを配った。今後の雇用や賃金について保全管理人の弁護士と交渉し、従業員に情報公開するという内容だ。
労組は11月中旬、「取引先への支払いが滞り、資材が納入されない」などという経営危機をうかがわせる情報を入手。辻昌宏会長らに確認を求めたものの、返答がないまま更生法申請の日を迎えた。宮崎博委員長は「経営監視の役割を十分に果たせなかった。雇用や待遇を守るため、できる限りのことをする」。
同市天満町の県北振興局分庁舎では15日午後、行政や金融機関などが連絡会議を開いた。県や市、政府系金融機関が扱っている緊急融資制度や、主取引行の親和銀行などが実施している関連企業への支援策の情報を交換した。
だが、どの参加者とも、関連企業に与える影響を測る情報が十分でなく、17日に市内で開かれる債権者集会の後に改めて支援策や雇用対策を緊密に協議することにした。
Tsuji Heavy Industries, the leading Japanese deck manufacturer which recently broke into the shipbuilding market, has filed for bankruptcy.
The Sasebo-based company filed for court protection with Tokyo District Court last Friday.
According to local press, Tsuji and its four subsidiary companies – Tesco Co, Tsuji Marine Services Co, Sky Arc Ltd and Ace Industries Ltd are estimated to have a combined liability of around JPY 75.8bn ($835m).
Market players say they are surprised to hear the news of Tsuji’s collapsed.
“Tsuji has been a very strong company. We did not see any sign of the company struggling”, said a newbuilding broker.
“It recently delivered its first newbuilding and we thought the company was doing well”.
They believe the global credit squeeze combined with the high steel price have caused Tsuji to run into financial difficulty.
Sources say Tsuji’s venture into the shipbuilding arena has drained up the company’s cash.
”If it has stayed with the production of ships’ equipment, it probably will not meet such problem”, commented a Japanese shipbuilding player.
Tsuji made its name as a deck and hatch cover maker but entered the shipbuilding business in 2006 by converting a portion of it 100% owned shipyard in Zhangjiagang in China - Tsuji Heavy Industries Jiangsu, to construct newbuildings.
It first planned to establish the Chinese yard six years ago was to expand its hatch covers and ships’ equipments production.
In addition to committing to shipbuilding at its Zhangjiagang-based shipyard, Tsuji is building a second shipyard in Zhejiang province.
The new yard which was reported to costs CNY 50bn ($472m) is five to six times bigger than its first yard and is already 65% complete. The yard is to be named as Tsuji Heavy Industries Zhejiang.
Tsuji concentrates in building handysize bulk carriers of 30,000-dwt and 37,000-dwt.
The company is building only building ships for Clipper Group of Denmark, Yasa Shipping of Turkey and Bahama-based Campbell Shipping. The three owners have placed a total of 48 firm vessels and 17 option units.
Tsuji recently delivered its first bulker newbuilding – the 30,000-dwt Clipper Tsuji (built 2008) to the Danish owner some six months late.
By Irene Ang in Singapore
◆会見/解雇の考えない
会社更生法適用を12日に申請した佐世保市の船舶荷役機械大手、辻産業。帝国データバンク佐世保支店によると、負債は子会社4社と合わせて758億円と、九州で今年最大、戦後8番目の規模となる。辻産業は緊急の記者会見を開くなど対応に追われた。
辻昌宏会長は辻恒充社長と共に同日夜、佐世保商工会議所で会見。「新しい感覚で経営を伸ばしていただける受け皿会社に引き継いで、私どもは退任し、皆様方におわび申し上げたい」と、会長、社長共に経営責任を取ることを明らかにした。
債務については「県内の金融機関には145億円の借り入れだ。会社更生法の申請手続き上、保証債務を計上して741億円に膨らんだ」と説明した。
会社の再建については、最大の取引先である大島造船所(西海市)から支援検討の申し出を受けていると明かした。従業員の処遇については、解雇する考えはないと強調した。
地元経済への影響については「大型の債権者は関東、関西、四国、瀬戸内海方面。50万円以下の債権についてはお支払いをする」とした。
一方、中国進出が失敗だったのではと問われ、「第一工場までは成功したと思っている。(次いで建造中の工場がある)舟山は中国の最後の造船適地であり、最後の外資に対する造船許可だったので、先行者メリットが受けられると読んでいたが、結果として読み違いがあった」とした。
その上で、中国の造船所については、現在受注が残る船については造船を続けるとの方針を明かしたが、29隻は契約が流れたと説明した。
▼労組「すぐ雇用不安出ない」/地元の反応 親和銀・県が相談窓口
辻産業労組の宮崎博委員長は「受注量はかつてないほど。人手が足りないぐらいで、すぐに雇用の不安が出るわけではないだろう。ただ、労働条件を落とすわけにはいかない。不安にならずに再出発できるよう、非組合員を含めた従業員に呼びかけていく」と話した。
佐世保市は辻産業の取引先や下請け企業などを対象にした金融相談窓口を設ける予定という。朝長則男市長は「業績も回復し、自力での再建が可能と思っていた矢先のニュースに大変驚いている。社員の雇用継続と協力企業への仕事量が確保され、一日も早く再建されることを願う」とコメントした。
辻産業の辻昌宏会長は佐世保商工会議所会頭も務めている。田平敏昭専務理事は夕方に出張から戻って、会社更生法適用申請を聴いた。「会頭から話を聞いておらず、佐世保経済界に具体的にどんな影響があるかわからない。私からコメントを出すわけにもいかない」と話した。
辻産業のメーンバンク親和銀行の親会社、ふくおかフィナンシャルグループは12日、辻産業グループの取引先に対する「相談窓口」を県内の全営業店に設けると発表した。親和銀行本部には「支援対策室」を設置するという。
県は、辻産業に関係する雇用相談窓口を県北振興局(佐世保市木場田町)に設置。午前9時~午後5時45分、窓口と電話(0956・24・5287)で週末も受け付ける。また、県連鎖倒産防止資金(5億円枠)で、同社と取引がある中小企業向けの特別枠をつくる方針という。
荷役運搬設備製造 辻産業株式会社など5社 会社更生法の適用を申請
負債758億300万円 12/12/08(帝国データバンク)
「長崎」 辻産業(株)(資本金3億円、佐世保市光町177-2、代表辻恒充氏ほか1名、従業員428名)と(株)テスコ(資本金1000万円、同所、代表辻昌宏氏ほか1名)、辻マリンサービス(株)(資本金1000万円、同所、代表辻恒充氏)、(有)スカイアーク(資本金300万円、同所、代表辻昌宏氏ほか1名)、(有)エース工業(資本金300万円、同所、代表辻昌宏氏ほか1名)の子会社4社は、12月12日に東京地裁へ会社更生法の適用を申請、同日保全管理命令を受けた。
申請代理人は松嶋英機弁護士(東京都港区赤坂1-12-32、電話03-5562-8500)ほかで、保全管理人には小杉丈夫弁護士(東京都千代田区内幸町2-2-2、電話03-3500-0331)が選任されている。
当社は、1939年(昭和14年)5月設立、45年10月に現商号に変更した。デッキクレーンやチップアンローダ(荷役装置)、ガントリークレーン、ハッチカバーなどの船舶用機械を主力に、産業用機械の製作や橋梁・鉄骨・土木建築工事などを手がけていた。
近年は、造船業界の好況を受けて積極的に事業を拡大、2002年には、中国現地法人の辻産業重機(江蘇)有限公司(中国江蘇省張家港市)を設立、造船事業に進出。2007年には、中国浙江省舟山市に辻産業船務工程(舟山)有限公司(船体ブロック製造、辻産業100%出資)と辻産業重工(舟山)有限公司(造船事業、当社49%出資、中国資本51%出資)を設立し、造船事業を拡充した。中国現地法人では、2009年夏ごろの完成を目指し、造船所の新築も進めていた。
なお、造船事業については、中国現地法人(辻産業重機(江蘇)有限公司と辻産業重工(舟山)有限公司)が受注し、当社からは造船に必要な鋼材ほか材料やクレーンなど機械全般を納入する形態を採っていた。
造船業界の好況を受けて本業の船舶用機械の受注が伸びるとともに、中国現地法人での造船事業開始もあって、2008年5月期の年売上高は、過去最高の約253億1200万円を計上したが、過去の積極的な投資などから多額の金融債務を抱え財務面は脆弱な状態が続いていた。また、最近の金融事情の変化に加えて、鋼材価格の高騰、円高ドル安や、風評悪化による取引条件の変化などから、資金繰りが悪化。先行きの見通しが立たなくなったため、今回の措置となった。
負債は辻産業が約741億円で、テスコが約2億6200万円、辻マリンサービスが約3億2000万円、スカイアークが約1億6900万円、エース工業が約9億5200万円で、5社合計で約758億300万円。
佐世保の辻産業が更生法申請 負債741億円 九州沖縄で今年最大 12/12/08(西日本新聞)
造船・舶用機器関連メーカーの辻産業(長崎県佐世保市)は12日、東京地裁に会社更生法の適用を申請し、同日付で保全管理命令を受けた。負債額は約741億円。東京商工リサーチによると、九州・沖縄地区の倒産としては今年最大。
辻マリンサービスやエース工業など子会社4社も同時に同法適用を申請した。4社を含めた負債額は約758億円。
辻産業は1888年創業。船舶用クレーンの製造などを手掛けてきた。2002年3月、中国江蘇省張家港市に現地法人を設立し、03年から船体ブロックなどを製造。06年8月に造船事業に進出、07年3月には浙江省舟山市での大型造船所建設に着手し、来春にも操業開始予定だった。
08年5月期には過去最高となる約253億円の売上高を計上。造船業の好況で3万トン級のばら積み船など2000億円以上の受注を確保していたが、鋼材の高騰で製造コストが上昇した上、世界的な金融危機のあおりを受け、中国の新工場建設事業への投資などの資金繰りが悪化した。私的再建も検討したが金融機関との協議が不調に終わったという。
今後、辻産業は同県西海市の大島造船所の支援を受けて、会社再建を目指す。従業員の雇用や給与は確保するという。中国の子会社は自力で再建を図る方針。
佐世保市で会見した辻昌宏会長は「全く予想しなかった米国発の金融危機で大きなダメージを受けた。債権者ら関連企業に心からおわびしたい」と話した。辻会長は辻産業会長のほか、佐世保商工会議所会頭や松浦鉄道社長などの役職も辞職する意向を示した。
長崎の経済をリードする造船業が活況を呈している。03年から始まった海運好況を受けて、3~5年先まで注文で埋まる。だが、鋼材の値上げや中国、韓国の造船業の台頭、熟練工の大量退職と不安要素もある。「いまが好機」とにらんで、中国で初めて造船に挑戦する船舶機械メーカーも現れた。各社は今後の生き残りをどう図ろうとしているのか。県内の造船所を訪ねてみた。(吉田啓)
《中韓が受注シェア拡大》
△量・価格ではなく技術で対抗
高所作業車に乗った作業員がバーナーの火花を散らし、高さ数十メートルの船首部分の溶接を進めた。その奥では船橋や船尾部分の組み立てが続く。
長崎市香焼町の三菱重工業長崎造船所香焼工場にある長さ990メートル、幅100メートルのドックでは、全長約300メートルの液化天然ガス(LNG)船の建造が進められていた。隣のドックでも大型LNG船が建造中だ。
中国の経済成長に伴う世界的な物流量増加により03年夏から始まった海運好況は、長年冷え込みが続いていた造船業界にも恩恵をもたらした。01年に約3650万総トンだった世界の新造船の受注量は、07年には約1億6480万総トンと4・5倍に増えた。
同造船所では3年先まで、佐世保重工業佐世保造船所(佐世保市立神町)も5年先まで受注で埋まる。
だが、佐世保重工業の小林勉経営企画部長は「この春先から潮目が変わってきた」と気を引き締める。主原料となる鋼材が1トンあたり3万円近く値上げされそうだからだ。
船の価格は建造契約が結ばれた時点で決まる。契約から実際の造船には数年かかることもあり、その間の部材の値上がりによるコスト増は造船所が負担するしかない。値上げされれば、鋼材を1万トン使う船では3億円の負担増だ。小林部長は「ほかのコストを削減しても追いつかない。利益が吹き飛ばされる」と警戒する。
造船所への大規模設備投資を続ける韓国や中国との受注競争も激しくなっている。日本の新造船の受注シェアは01年に39・9%で世界一だったが、07年には12・5%にとどまった。一方、01年11・3%だった中国の受注シェアが07年には35・2%に伸びた。韓国は03年、シェア世界一の座を日本から奪い、07年には41・2%まで伸ばした。
だが、三菱重工業長崎造船所の橋本州史・船舶業務グループ長は「中韓の造船所とは、大規模設備投資による受注量の増加や価格での競争はしない」と冷静だ。
同社は約1100人の設計技術者を抱える。軽くて耐久性に優れた鋼材や、パイプ類や鋼材の配置関係や取り付けの仕方が一目で分かる3次元設計ソフトといった独自技術を開発してきた。今後は、1隻300億円以上の大型LNG船や、さらに高価な大型客船など、優れた技術が求められる船造りに重点を移す。
佐世保重工業も、これまであまり受注実績がない液化石油ガス(LPG)船の建造に力を入れる。「質で生き残りをはかる」戦略は一致する。
《熟練工の大量退職迫る》
△教育施設で若手に基礎
高い技術力を支えてきた熟練工には、大量退職が迫っている。
全社員約1100人の佐世保重工業では07年から4年間で毎年百数十人、計約500人の熟練工が定年を迎える。三菱重工業長崎造船所も造船技術者の3分の2ほどが50代だという。不況時に採用を抑えた結果、30代後半~40代の技術者が極端に少ない。若手の育成が急務となっている。
佐世保重工業が04年、佐世保造船所内に開設した技能教育センターでは今春、入社した技術者の卵たちが、バーナーの散らす火花の色や音に注意を凝らし、二つの鉄材を垂直に溶接する練習に取り組んだ。その様子を見守っていた青木秀夫センター長は、「ここで基礎を教え、即戦力に育てる。現場では職人技を学んでもらう」と話した。
三菱重工業長崎造船所も07年に国や長崎市などと協力して、関連、下請け会社の新入社員らへ初期技術や資格取得の教育をする技術習得センターを開所した。幅や長さ十数メートルの鉄板をバーナーの熱と水の冷気で精妙に曲げ、設計図通りの複雑な曲線を作り上げる。作業のマニュアル化、機械化を進めても職人技に頼る部分は残る。
両社は定年延長や子会社への再雇用で熟練工を引き留めながら、技術の伝承を急ぐ。入社39年目の青木センター長は船や橋梁(きょうりょう)を造ってきたが、「熟練工がいなくなる前に、何とか育ってくれそうです」と若手の成長に期待を込める。
《低コスト+広大な土地》
△好条件求め中国進出
一方、「人件費などコストの安さと、大規模な生産設備を造れる土地の広さ」を求めて、中国で造船に新規参入した業者もある。
佐世保市の船舶クレーンメーカー、辻産業は07年、上海近郊の江蘇省張家港市にある約33万平方メートルの自社工場の一部で造船所の稼働を始めた。
鉄鉱石などを積む「ばら積み船」を手がける。3万トンクラスの船を3隻同時に建造でき、当初12隻だった受注を1年間で48隻にまで増やした。
上海沖の浙江省舟山市にも160万平方メートルの造船所用地を造成中だ。来夏には船を建造する船台2基とドック2本を稼働させ、6万~10万トンクラスの造船も始める予定だ。
三菱重工や佐世保重工を退職した日本人造船技術者35人を指導役に、中国人技術者を育成した。同社の辻昌宏会長は「正直、技術力が低いのではと心配だった。だが手先の器用な人が多く、ハングリー精神も旺盛だ。技術を貪欲(どんよく)に吸収し、あっという間に成長した」と目を見張る。
人件費の安さに加え、広大な工場敷地の確保により、素早く効率の良い船の組み立てが可能になった。
辻会長は「大手海運各社があと10年は海運好況が続くと予測して新造船を発注し続ける」とみている。「中韓の造船所も5年先まで受注で埋まる。わが社にはまだ50%の生産余力があり、貨物船には欠かせないクレーンの製作という『得意技』もある。質でも量でも勝負していきたい」と強気に構える。
【キーワード】
長崎県と造船
1857年、現在の長崎市に日本で初めての艦船修理工場「徳川幕府 長崎鎔鉄所」(後の三菱重工長崎造船所)が設けられ、その33年後、現在の佐世保市に旧日本海軍佐世保鎮守府造船部(後の佐世保重工佐世保造船所)が造られた。1973年には炭坑閉山後の産業誘致で大島町に大島造船が設立された。
県統計課の調べでは、06年の県内の工業に占める「船舶製造・修理業、舶用機関製造業」の割合は、事業所数(122カ所)で5・35%、従業員数(6273人)で10・69%、製造品出荷額(3536億1751万円)で23・34%となっている。
※ ※ ※ ※ ※
4月に佐世保支局に赴任した。県内の地図を眺めるうち、佐世保市や長崎市で大きな存在感を放つ造船所が気になった。外洋に面し、天然の良港に恵まれる長崎は「造船の街」でもある。
だが、活況を呈していると聞き訪ねてみた県内の造船所は、厳しい経営環境の中で生き残りを模索していた。「壮大で緻密(ちみつ)なものづくり」と造船の魅力を語り、「長崎の若者が夢を持って飛び込める仕事であり続けるため、踏ん張りたい」と話す造船マンの思いに胸を打たれた。
来年も貨物の増加量に比べ、世界の船舶供給が過剰状態になるとの見通しが相次いで出ている。
韓国海洋水産開発院が6日明らかにした「世界の主要海運専門機関の来年見通し」によると、造船・海運専門調査機関のクラクソン社が来年の船舶の供給過剰はさらに深刻化すると予測したという。同社は、来年に引き渡されるバルク船の供給量が6650万トンに達し、今年に比べ16.2%増加すると予想した。一方、貨物の取扱量は、世界の景気停滞で2.7%増にすぎないと予測した。韓国海洋水産開発院は「来年の船舶過剰率は13.9%程度と予測される。バルク船市況の不調が継続した場合、相当数の船会社の倒産が見込まれる」との見方を示した。
キム・スンボム記者
STX Europe has signed contracts for delivery of design and ship equipment to four platform supply vessels of STX Europe's own design PSV 09 CD. The total value of the four contracts amounts to approximately NOK 400 million.
The vessels will be built by the Japanese shipbuilding group Universal Shipbuilding Corporation (formerly NKK Corporation and Hitachi Zosen Corporation) for delivery to the Japanese ship-owner Sanko Steamship Company (Sanko Line) between 2010 and 2012.
"With these new contracts we have established a very good relationship to two of the largest and most important Japanese ship-owners," said Roy Reite, President for STX Europe's business area Offshore & Specialized Vessels.
The vessels, which will have a deadweight capacity of 4 800 dwt and a length of 86.6 meters, are designed by STX Europe's design company in Alesund where the PSV 09 is one of the most popular designs. Two ships have already been delivered of this type and, including the four new contracts in Japan, there are a total of 13 vessels delivered or in order.
The PSV 09 CD is a diesel-electrical driven vessel known for its large and competitive cargo-capacity, excellent manoeuvring- and sea keeping performance and low bunker consumption. The design has an environmental profile and comes with high comfort level for the crew.
Important contributors in the process leading to these contracts, in addition to the design company and the trading department, have been STX Europe's newly opened office in Singapore.
There will be both Norwegian and foreign suppliers of ship-equipment to these contracts. Electrical and electronically equipment such as switchboards, consoles and integrated alarm- and control system and power management system will be manufactured by STX Europe's electro company. They will also supply complete drives for the electrical propulsion systems.
STX Norway Offshore Design (former Aker Yards Project) has now delivered design for more than 60 vessels, of which eleven are already delivered and 50 are under construction or in order. Approximately 20 percent of the vessels designed by STX Europe are to be built by external yards. STX Europe has already contract with another Japanese ship-owner, K-Line, for delivery of four vessels of PSV 06 CD design and two ultra-large anchor handling tug supply vessels of type AH 12.
DESEC、日本からバルク船6隻を受注 11/26/08(中央日報)
大宇(デウ)造船海洋の子会社DESECは、日本の佐世保重工業(SSK)と計260万ドル(約2億5000万円)で、バルク船(3万8000トン級)6隻の設計供給契約を締結した。同社は、世界造船市場で技術力を認められている日本の造船所に、船舶設計の技術を供給することによって、韓国の造船技術の優秀性を立証付けることになった。
‘造船ビッグ3’、2カ月間の受注はわずか4隻(1) 11/19/08(中央日報)
三星(サムスン)重工業は20日午前、「ドリル船2隻を総額14億4000万ドルで受注した」と株式市場に公示した。 ブラジルの船会社と原油を採掘するドリル船を建造する契約をしたという内容だった。
造船業界は「受注不足の中の恵みの雨」と言って喜んだが、暗い表情を隠すことはできなかった。 現代(ヒョンデ)重工業と大宇(デウ)造船海洋を含むビッグ3(大型造船3社)にとって、今回が10-12月期の2件目の受注だったからだ。 世界1-3位会社を保有する国内造船業界では、2カ月前まで10億ドル台の受注はニュースにもならないほどだった。
◇2カ月間受注なし=世界最大造船会社の現代(ヒョンデ)重工業は9月中旬以降、一隻も受注がない。 大宇(デウ)造船も10月以降、受注実績がない。 三星重工業が10月15日にタンカー2隻を受注したのが最後だった。
韓国造船協会のク・ボンソン課長は「10月以降、国内造船業界の受注船件数は1けた」とし「それどころか、受注の取り消し、建造費を引き下げてほしいという発注社の要求に苦しんでいる」と話した。
南海岸の中小型造船企業からなる韓国中小型造船協会のチェ・ヨンイル事務局長は「銀行がリファンド保証書(RG)の発行を避けていて、新規受注は考えられない」と述べた。 こうした状況は韓国だけの問題ではなく世界的な現象だ。
日本船舶輸出組合によると、10月の受注量は29万CGT(標準貨物船換算トン数)と、前年同月の161万CGTに比べて80%減少した。 コンテナ運搬船を主に建造している中国造船所も大量の発注取消に頭を悩ませている。
‘造船ビッグ3’、2カ月間の受注はわずか4隻(2) 11/19/08(中央日報)
◆金融危機の直撃弾=船の注文が急減したのは世界的に物流量が急減したからだ。 米国発の金融危機が世界各国の経済を強打し、海上物流量が大きく減ったのだ。
海運業界の関係者は「夏まで物流量は多かったが、それがどこへ消えてしまったのか…」と話した。 中国景気の失速で原資材の需要が減少し、各国の実体経済が冷え込みながら輸出入量が減った、という分析だ。 穀物や石炭などを運搬するバルク船の運賃指数(BDI)は7月末の8859から19日には859と、10分の1水準に落ちた。
コンテナ船総合用船指数も今月第1週が709と、前年平均の1343の半分になった。 物流量の減少は新規船舶発注の減少につながる。 LNG船や超大型タンカー(VLCC)は建造費が数億ドルにのぼる。 こうした船は普通、発注会社が金融市場で投資家から集めた資金(PF)で発注するが、金融危機の影響で投資家が集まらないのだ。
◆高付加価値船に注力すべき=東部(トンブ)証券のチョン・ヨンボム研究委員は「船発注市場が金融危機で深刻に冷え込んでいるうえ、実体経済も良くないため、造船市況はいつ改善するのか予想するのは難しい」と述べた。 世界景気が回復するまで少なくとも2-3年の沈滞期を乗り越えなければならない、ということだ。
韓国造船協会のカン・サジュン経営支援部長は「大型造船3社は今後3年間の受注分があるため今回の不況は乗り越えるだろうが、70余りの中小型造船所は深刻な時期を迎えるだろう」と話した。
教保(キョボ)証券のチェ・クァンシク研究員は「大型造船会社は景気の影響が少ない石油メジャーを狙って高付加価値船のドリル船や海上プラントに力を注ぐべきだろう」と述べた。
現代経済研究院のイ・ジュリャン研究委員は「南海岸に集まった中小型造船会社は超大型タンカーやコンテナ船などの分野で競争力のある会社を中心に再編される必要がある」と診断した。
運航中断に経営破たん説、海運業界に危機拡大 11/19/08(朝鮮日報)
世界的な景気低迷で海運需要が大幅に減り、海運各社も資金難や経営危機に直面している。
業界関係者によると、C&グループ系列のC&ラインは業績悪化を理由に、先月から船舶の運航を中断した。また、10隻の船舶を保有するある海運会社には最近、経営破たん説が浮上している。
韓国海運業界は国内外の造船所に334隻(29兆ウォン=約1兆2000万円)の船舶を発注している。船舶発注のために国内外から借り入れた資金だけで25兆ウォン(約1兆7000万円)に達する。こうした状況で需要減と運賃急落に伴う経営環境悪化により、多くの海運会社が資金難に苦しんでおり、発注済みの船舶に対する中途代金の支払いが滞る業者も出ている。
一部の中小海運会社は、船舶を借り受けるために支払う傭船(ようせん)料の支払いに負担を感じ、違約金を支払って契約満了を待たずに船舶を船主に返却している状況だ。
韓国の海運会社164社で構成する韓国船主協会は「金融機関から支援が受けられない場合、海運業界では連鎖倒産が懸念される」と話している。
今年上期まで海運業界は好況に沸いた。しかし、下期に入り世界的な金融危機が本格的に広がり、景気に敏感な海運業は打撃を受けた。中国の成長が鈍化し、中国特需が消えたことも大きかった。17万トン級のバルク船の傭船料は現在1日当たり1万8000ドル(約170万円)で、6月時点の18万6500ドル(約1780万円)の10分の1まで下落している。
金承範(キム・スンボム)記者
受注減と資金難、中小造船所を直撃(上) 11/19/08(朝鮮日報)
過去3-4年間の造船好況を乗り、韓国南海岸一帯に雨後のタケノコのようにできた中小造船所が国内外の景気低迷で直撃を受けている。船を建造するのに使う鉄鋼が急騰したことで上期に困難に直面した中小造船所は、最近は船舶受注の減少と資金難に苦しんでいる。韓国政府が18日、債権銀行団との協約などを通じ、造船業界に対する構造調整を進める方針を示したことについて、専門家らは「想定の範囲内」だと指摘した。現代重工業など大企業は流動性に大きな問題はないが、中小造船業者の中には資金難で操業を中断したり、操業に影響が出るケースが続出している。
◆資金難と世界的な造船景気低迷
C&グループ傘下のC&重工業は約60隻の船舶を受注したが、金融機関から1700億ウォン(約110億円)の必要資金を借り入れることができず、8月から操業を中断している。同社は下請け業者にも780億ウォン(約52億円)を支払えずにおり、従業員にはグループ支援で9月分の給与が最近やっと支給されたほど資金難にあえいでいる。大韓造船も4500億ウォン(約300億円)の資金を調達できず、先月完成予定だった船舶用ドックの建設工事を中断した。
船主から船舶建造のために前払い金を受け取る場合には、銀行による払い戻し保証が必要だが、銀行が最近中小造船所に対するリスク管理を強化し、保証を制限したため、一部の中小造船所は前払い金も受け取れずにいる。現代重工業、サムスン重工業、大宇造船海洋など造船大手は3-4年分の受注を確保し、超大型タンカーなど高付加価値の船舶を建造することで収益性を維持している。これに対し、中小造船所はバルク船など相対的に安価な船舶を主に受注しており、景気低迷の直撃を受けている。
バルク船の市況を示すバルク船運賃指数(BDI)は17日、856ポイントを記録し、5月のピーク時(1万1793ポイント)に比べ92.7%も下落した。造船業界によると、全世界の貨物船受注量は1-9月に950万CGT(標準貨物船換算トン数)にとどまり、前年同期に比べ34.5%減少した。
信栄証券リサーチセンター長のチョ・ヨンジュン氏は「10月末以降、3日に1社の割合で海外の海運業者が破綻しており、海外の中小海運会社との取引が多い韓国の中小造船所も打撃を受ける可能性がある」と分析した。既に受注済みの船舶についても船会社が資金負担への懸念から発注をキャンセルする動きを見せている。さらに大きな問題は造船市況に当面改善の兆しが見られないことだ。専門家は「設備の過剰に対するある程度の構造調整は避けられない」と話している。
受注減と資金難、中小造船所を直撃(中) 11/19/08(朝鮮日報)
◆過剰投資で状況悪化
造船業の好況を追い風に2004年以降、南海岸一帯には中小造船所が20カ所余り建設され、過剰投資ではないかとの指摘を受けてきた。造船工業協会関係者は「新しい中小造船所が建造する船が韓国全体の船舶建造量に占める比率はこれまでの10%から今年は15%以上に上昇する見通しだ」と語った。しかし、増加分に対し質的レベルは劣る。大型造船所が二けたに迫る営業利益率を記録している半面、中小造船所は何とか黒字を維持しているというところも多い。
中小造船所の資金難は過剰投資に加え、建造能力を考慮しない無差別受注戦によるものだとの指摘もある。慶尚南道の造船所役員は「今年引き渡し予定の船を半分も引き渡せない造船所がある。とりあえず受注を確保しておこうという考えから、建造能力を上回る注文を受けた結果、納期を守れないケースが多い」と状況を語った。一部の中小造船所が納期を守れなければ、韓国の造船業に対する信頼度が落ちるため、構造調整は避けられないとの主張が強まっている。
金承範(キム・スンボム)記者
受注減と資金難、中小造船所を直撃(下) 11/19/08(朝鮮日報)
◆中小造船業者「銀行が責任転嫁」
金融機関が造船業の構造調整に乗り出す姿勢を見せていることについて、中小造船会社は「今の苦境は金融機関が融資を中断したために生じたものなのに、まるで中小造船会社による行き過ぎた設備拡張と無理な受注のせいだというように責任を転嫁している」と反発している。
C&重工業、21世紀造船、YS重工業など中小造船所10社で構成する韓国中小型造船協会は「2-3年分の受注を確保し、建造能力があるにもかかわらず、銀行が融資に応じず操業ができない。その上、払い戻し保証も拒否され、受注契約を結ぶことのできない企業が多い」と主張した。
同協会は「売れ残りマンションで危機に陥った建設会社と、受注を確保しながら金融機関の支援を受けられずに一時的な資金難に直面する中小造船所を同じように扱ってはならない」と訴えている。
C&重工業関係者は「支援さえあれば今すぐにでも船を作れる」と述べた。大韓造船の金浩忠(キム・ホチュン)社長は「造船産業は地域経済に対する寄与度が高いため、中小造船所に対する金融支援策を取りまとめるべきだ」と話した。
金承範(キム・スンボム)記者
建設・造船危機、「救済」か「破たん」か(上) 11/19/08(朝鮮日報)
政府・債権団、事業再構築プログラムに着手
18日、ソウル市内の2カ所で建設会社・造船会社を対象とした債権団の金融支援プログラム説明会が開かれた。同日午後3時ごろ、同市乙支路2街の韓国外換銀行本店4階にある大講堂。銀行連合会の主催で行われた「建設会社貸主団(債権金融機関の集まり)協約説明会」には、全国各地から建設会社役員500人余りが集まった。300ほど用意された席は早々に埋まり、座ることさえできずに、会場の隅に立ったまま説明を聞く人たちも多く見られた。「資金事情はどうなっているのか」「事業再構築プログラムに参加するつもりなのか」という報道陣の質問に、建設会社役員らは緊張した面持ちで即答を避けた。続いて午後5時からは近くの銀行連合会ビルで「造船会社金融支援プログラム説明会」が行われた。同説明会にも中小の造船会社関係者100人余りが集まった。
景気低迷が深刻になる中、建設・造船・貯蓄銀行などでは業種ごとに「再生させる会社」と「破たんさせる会社」を選別するため、政府や債権団の事業再構築プログラムが動き出した。しかし、この日の説明会に出席した建設会社や造船会社のうち、事業再構築プログラムに参加するところは1社もないという。「下手をすれば、参加企業名簿に載ることにより、不良債権を抱える企業というレッテルを張られたり、強制的に事業再構築を迫られたりするのでは」と各社とも神経をとがらせているのだ。
(1)建設業界
建設会社の事業再構築案の骨子は「貸主団協約」だ。貸主団には合計184の金融会社が加入している。当初、銀行業界は23日までに建設会社の上位100社を対象に貸主団協約加入を取り付けることにしていたが、加入期限や建設会社の規模は制限しないことにした。上位100社以外の建設会社も個別に協約に加入すれば、受け入れる。「(上位100社に限れば、貸主団協約に)加入する企業と加入できない企業を分ける“死に神のリスト”を作るのと同じ」と建設業界が強く反発しているためだ。
銀行連合会側は「貸主団協約に加入すれば、債権満期を一括して猶予してもらえるので、それぞれの銀行と接触して満期を延ばすよりははるかに便利」との利点をうたい、建設会社に加入を勧めている。だが、各建設会社はかなり強い拒否感を示している。18日の説明会で、釜山市内のある建設会社役員は「貸主団協約に加入すれば、“金融業界から支援してもらわなければ生き残れない不良企業”と見られ、再建が難しくなるのでは」と懸念を示した。
姜京希(カン・ギョンヒ)記者
チョン・チョルファン記者
建設・造船危機、「救済」か「破たん」か(下) 11/19/08(朝鮮日報)
政府・債権団、事業再構築プログラムに着手
(2)造船業界
海運業界の好況に乗り、この3-4年間で「雨後の竹の子」のように増え続けた中小の造船会社だが、そのうちの一部は破たんが避けられない見通しだ。世界の造船景気が低迷し受注量が減ると、今年下半期から銀行は、事業性の先行きが不透明だと思われる中小造船会社に対して資金支援を中止した。危機の真っただ中にいる中小造船会社に対しては、迅速な支援プログラム「ファースト・トラック方式」を通じ事業再構築が行われる。例えば、危機に陥っている中小造船会社が、主債権銀行に流動性支援を申し入れると、主債権銀行は中小造船会社をA等級(正常な企業)、B等級(一時的に経営難に陥っている企業)、C等級(不良債権化の兆候が深刻な企業)、D等級(再建不可能な企業)に分類する。A・B等級には銀行が新規資金を支援する一方、C等級の企業はワークアウト(企業改善作業)手続きを踏むことになる。D等級は支援が中止され、事実上破たんすることになる。
(3)貯蓄銀行業界
不動産プロジェクト・ファイナンシング(PF、不動産事業の推進費用として供給された融資)が不良債権化していることから、金融業界では貯蓄銀行業界に真っ先に事業再構築の火の粉が降りかかっている。貯蓄銀行のPF融資残高は6月末現在で12兆2千億ウォン(約8160億円)。不動産の実体経済が低迷する中、建設会社に融資した資金の回収がままならず、不良債権化している。延滞率は14.3%と、銀行のPF融資延滞率の21倍に達する。
貯蓄銀行では静かながらも事業再構築が進みつつある。106ある貯蓄銀行の国際決済銀行(BIS)基準自己資本比率は平均9.1%だが、8%を下回る貯蓄銀行は約20行に達する。先日、このうち破たんした貯蓄銀行4行が別の大手・優良貯蓄銀行に合併された。また、政府は別の4行に対し、具体的な経営改善計画を立てるよう勧告している。
姜京希(カン・ギョンヒ)記者
チョン・チョルファン記者
海運会社のパークロード、事実上の破産を宣言
船主側に船の権利移譲の覚書...海運業崩壊'シグナル'の懸念 11/19/08
業界を中心に、破産説が飛び交った中堅海運会社のパークロードが債務不履行を宣言した。事実上の破産である。売上高3000億ウォン以上の中堅海運会社が崩れたのは今回が初めてで、市場は、連鎖的な海運業界の崩壊の第一歩になるのか注目している。
パークロードには、過去1996年に設立された中堅海運会社。昨年の3039億ウォンの売り上げを記録した。計10隻(放浪者7隻、定期船3隻)の船を保有しており、最近の攻撃的なバルク船傭船を使って営業を拡大してきた。
債務不履行宣言の原因は、景気低迷による取扱量の減少。パークロードには、昨年7月にシンガポール現地法人を通じて、 40余隻に達する大型バルク船を傭船した。しかし、その後BDI(バルチック海運指数)90 %以上急落するなど、市場の状況が急速に悪化し、流動性危機を迎えることになった。
結局、先月末ソン主事(船を貸した会社)の側面に'傭船船舶に対するすべての権利を移譲する'は、覚書を書いた。借金を返済する能力がないため、契約期間に関係なく貸してくれた船の両方を持っていけは、事実上の債務不履行)宣言だった。市場関係者は"公式に破産を認めたわけではないが、権利の移譲への署名は、すぐに破産を意味する"と説明した。
パークロードのデフォルト宣言で、これまでのパークロードと取り引きしてきた関連船会社,零細企業等の大規模な被害も懸念される。市場では、これらが数百億ウォン規模の被害を見ることを期待している。
海運業界の関係者は"国内外のお届けは、デフォルトを宣言した業者とは絶対に取引をしない。今後、パークロードという社名では営業が不可能だ"とし、 "パークロードと似た規模の海運会社らも最近の不況から自由でないから連鎖的な破産が憂慮される"と明らかにした。
輸出不振で空コンテナが山積み /蔚山(上) 11/16/08(朝鮮日報)
米国発の金融危機に端を発する世界的な景気低迷は、韓国最大の産業基地であり韓国の輸出品の17%以上を送り出す蔚山を襲っている。蔚山の主力である石油化学や造船産業は1カ月以上も輸出・受注不振に陥り苦戦、輸出埠頭(ふとう)には空のコンテナだけがうず高く積まれたままになっている。
7日午後2時ごろ、蔚山市南区梅岩洞の蔚山コンテナターミナル(UCTC)のコンテナ野積場。広さ6万3000平方メートルの土地にコンテナがすき間なく積み上げられていた。積載限度は1万TEU(1TEU=20フィートのコンテナ1基)だが、現在積み上げられているコンテナは9930TEU(蔵置率99.3%)に達している。このうち約60%は空のコンテナだ。UCTCのパク・ジェソク次長は「適性蔵置率は約60%だが、先月初めから100%前後で飽和状態が続いている」とため息をついた。
別のコンテナ埠頭も同様だ。蔚州郡温山邑のチョンイル・コンテナターミナルもこのところ蔵置率が最大130%まで上がるなど、飽和状態が1カ月以上続いている。
蔚山港のコンテナ埠頭が飽和状態になっているのは、輸出が振るわないためだ。世界的な景気低迷は原油高や不利なレートで、石油化学業種を中心に製品輸出価格が原料価格にもならないという逆転現象が起き、これが蔚山の輸出に悪影響を及ぼしている。蔚山商工会議所は「10月以降、全般的な輸出量は約30%減少しているものと推定される」と話す。
このため、UTCTもチョンイル・コンテナターミナルも空の「エンプティコンテナ」蔵置率が適性範囲をはるかに上回る120-150%に達している。チョンイル・コンテナターミナルのパク・イルリュン係長は「輸出が振るわないため、空のコンテナをコンテナヤード(コンテナを一時的に保管するエリア)に山のように積んでもスペースが足りず、近くの荷役会社の野積場まで借りて使っている」と語った。
蔚山=金学賛(キム・ハクチャン)記者
輸出不振で空コンテナが山積み /蔚山(下) 11/16/08(朝鮮日報)
その一方で、貨物が入っている「フルコンテナ」も船積み期日が決まらず、長期間野積みされている。蔚山港で船積みされ、ロシアに輸出されるはずの自動車部品は、ロシアの景気悪化により7日現在で2500TEU以上も野積みされたままだ。同じく、中国・東南アジア向けの石油化学製品輸出コンテナ約1000TEUも船積み時期が決まらず、埠頭に積み上げられている。
こうしたことから、生産工場では輸出不振や在庫累積により、減産・一時稼働中止が相次いでいる。特に、輸出入景気に影響されやすい石油化学産業は深刻だ。
SKエネルギー蔚山コンプレックス(CLX)のナフサ分解工場第1工場は、先月27日から稼動を一時中止(シャットダウン)している。1962年の創業以来、46年間で初めての事態だ。同社は「在庫が増えているため」と説明、「シャットダウン期間は当初、17日までの20日間を考えていたが、中国や東南アジアの景気に好転の兆しが全くないため、延長は避けられないだろう」と話している。
蔚山CLXのポリプロピレン生産工場も稼働率を通常の8割程度に抑え、原油精製施設5基のうち、規模が小さい1基(1日6万バレル)と2基(同11万バレル)を減産または当分稼働を中止する方向で検討している。
蔚山石油化学団地にある泰光産業も、5日から蔚山の3工場で稼動を中止した。やはり需要減や在庫累積が理由だ。同団地内のほとんどの企業は、通常の6-8割程度に稼働率を抑えており、中には各工程で稼動を中止する企業もある。
一方、造船業界にも不況の波が迫っている。現代重工業と現代尾浦造船は10月以降、受注実績が1件もない。現代重工業が月別実績で1隻も受注できないのは3年10カ月ぶりだ。ただ、両社はこれまでの受注が3年分以上残っており、それが唯一の救いになっている。
現代自動車も内需不振を懸念している。7-9月期の内需販売合計台数は昨年同時期を3.4%下回った。それも、7月から9月にかけて行われたストで滞っていた輸出が再開され、内需不振を補っているのが実情だ。
蔚山=金学賛(キム・ハクチャン)記者
海運:バルク船の市況指数89%下落(下) 10/26/08(朝鮮日報)
◆世界的金融不安の影響で先が見えない状況に
一部では最近の海運業界の不況について、金融危機の影響が世界の実体経済の不振へとつながる兆候を示す可能性があるとの指摘もある。原材料を運搬するバルク船は中国やインドなどの製造・生産基地の景気と直結し、完成品を大量に運搬するコンテナ船の状況は欧米など先進国の景気を反映しているからだ。
ハンファ証券アナリストのイ・ウォンジョン氏は「中国の7‐9月期の国内総生産(GDP)が1ケタの成長に止まるなど、成長の勢いが徐々に失われていることから、世界の海運需要の減少も長期化する見込みだ」と述べた。
最近の海運業界における複数の指標の落ち込みは、世界経済の不振の影響だけではないとの見方もある。昨年船舶の発注が急激に増加したことで、来年から2年間に総1億7400万トン規模の船舶が市場に新たに出回る予定だ。これは04年から昨年までの4年間の供給量である1億200万トンをも上回っている。来年以降は供給が需要を上回る可能性が高いということだ。
海運業況の悪化は造船分野にも影響を及ぼしている。18万トンクラスのバルク船を新しく製造する際の契約価格は、先月9600万ドル(約96億円)だったのが、今月は9350万ドル(約93億5000万円)にまで落ち込んだ。また6500TEU(1TEUは20フィート・コンテナ1個)クラスのコンテナ船建造の際の契約価格も、ここ1カ月で200万ドル(約2億円)も落ち込んだ。産業研究院のホン・ソンイン研究員は、「景気不振の影響で海運需要そのものが減少しており、さらに船舶発注の減少へとつながっていくだろう」と予想した。
◆対策に追われる業界
C&グループ子会社のC&ラインは今月中旬、業績悪化のため船舶の運航を中断し、このニュースに衝撃を受けた海運業界では危機感が高まっている。C&ラインでは現在、企業そのものの売却も進められているという。業界ではバルク船の比重が高い中小の海運会社の状況が特にひどいと予測しているが、影響が比較的少ないとみられていた大手も航路の調整に乗り出すなど、対策に乗り出している。
韓進海運や中国コスコなど4社で構成されている「CKYアライアンス」は最近、アジア-地中海航路の運航を中断することを決定した。さらにアジア-トルコ航路の貨物積載能力も調整する計画だ。現代商船やシンガポールAPLなどが参加する「ザ・ニュー・ワールド・アライアンス」も今月下旬から、アジア-欧州航路の運航を調整する方針だ。
■バルク船運賃指数(BDI)
鉄鉱石や石炭などの原材料や穀物を運搬するバルク船の市況を示す指数。世界26の主要な航路を運航する船舶の類型ごとの貨物運賃や用船料などを総合して算出される。1985年1月4日を基準時点(指数=1000)として1999年から発表が行われている。
金承範(キム・スンボム)記者
海運:バルク船の市況指数89%下落(上) 10/26/08(朝鮮日報)
用船料も1カ月に75%以上下落
一部海運会社は運航を中断、中小の海運会社も大きく動揺
ここ4年にわたり好況を謳歌(おうか)してきた海運業界に危機感が高まっている。バルク船(穀物や鉱物などを運搬する一般の貨物船)の場合、運賃がここ5カ月で90%近く急落し、船を貸す際に受け取る用船料も1カ月で4分の1にまで落ち込んでしまった。
このため、韓国の中小の船会社の中には船舶の運航を中断したケースもある。米国発の金融不安に伴う世界的な景気不振の影響を直接受けているのだ。海洋水産開発院のファン・ジンフェ博士は「海運業は世界の景気に大きく作用される業種だ。その上、昨年は船舶の受注量が急増し、船が市場に数多く出回っていることから、海運会社は困難に直面している。こうした状況は今後もしばらく続くだろう」と述べた。
◆バルク船運賃指数は底なしの下落
バルク船の市況を示すバルチック海運指数(BDI)は20日に1355ポイントにまで落ち込んだ。今年5月に記録した最高点1793ポイントに比べると、89%も下がったことになる。これは2002年10月以来6年ぶりの最低水準だ。
用船料も急激に落ち込んでいる。業界関係者によると、17万トンクラスのバルク船を6カ月間借りた場合にかかる用船料は1日に2万8500ドル(約285万円)で、1カ月前の11万8500ドル(約1185万円)に比べるとわずか25%だ。コンテナ船によるアジア-欧州航路の運賃も、昨年の同じ時期に比べて40%以上も落ち込んでしまった。
大手海運会社の関係者は「この時期になると冬の石炭需要に備えるための運航が増加し、ハロウィンやクリスマス商戦に向けた商品も増加するのだが、今年は例年とは様子が異なる」と述べた。アジア-米州航路に就航している海運会社の業界団体である太平洋航路安定化協定(TSA)の最近の市場分析によると、今年上半期のアジア-米州間の物量は昨年に比べると6.9%落ち込み、今年全体ではおよそ8%下落する見込みだという。
金承範(キム・スンボム)記者
韓国の中小造船所、資金難でSOS 10/26/08(朝鮮日報)
韓国の中小造船所が資金難にあえいでおり、船舶建造に支障が出ている。一部造船所では資金確保のため、会社役員が月給を返納したケースも出ている。過去3‐4年間の造船景気で韓国の南海岸地域には中小造船所が雨後のタケノコのように建設されたが、一方で過剰投資の懸念が指摘されていた。
造船業界によると、全羅南道木浦市のC&重工業は船舶約60隻、約3兆ウォン(約2800億円)相当を受注した状況で資金調達に行き詰まり、造船所建設と船舶建造が遅れている。同社関係者は「ドックをはじめ造船設備の建設に必要な3800億ウォン(約360億円)のうち1700億ウォン(約160億円)が不足しており、金融機関に融資を申し込んだがまだ資金を確保できていない。年末に最初の船舶を引き渡す予定だったが、スケジュールが遅れ、来年初めにずれ込む見通しだ」と話した。同社役員は最近、資金確保のため月給を返納したという。
全羅南道海南市の大韓造船でも状況は同様だ。4000億ウォン(約380億円)を投じる第2ドックの建設に向け、金融機関に支援を要請したが、融資が受けられず建設に遅れが出ているという。同社関係者は「ドック建設が遅れている上、船主から前受け金の支払いを受けるのに必要な払い戻し保証を銀行から受けられず、船舶の建造スケジュールに支障が出ている」と語った。同社は現在、バルク船43隻(うち1隻は引き渡し済み)、総額3兆3000億ウォン(約3100億円)相当を受注している。
中小造船所が資金難に直面しているのは、金融機関が金融不安、造船業の景気後退に対する懸念から新興造船所に対する融資審査を厳しくしているためだ。信栄証券リサーチセンター長のチョ・ヨンジュン氏は「原材料価格の急騰が中小造船所の収益悪化を招いている。そこに人材難までが重なり、技術力と資金力を持たない中小造船所は困難な状況に追い込まれそうだ」と分析した。
しかし、C&グループのキム・チョルホ理事は「中小造船所も大型造船所が取り扱わない船舶を中心にすき間市場を攻略し、競争力を確保できる。韓国の造船業の足元を固めるため、中小造船所に対する政府レベルでの支援策が求められる」と指摘した。
金承範(キム・スンボム)記者
造船・鉄鋼の好景気は終わったのか(上) 10/04/08(朝鮮日報)
米国発の金融危機と世界的な景気低迷の中でこれまで好況に沸いてきた造船、鉄鋼業界が揺れている。造船業界では世界の船舶発注量が前年同期に比べ30%以上減少し、先行指標といえる海運業況も急速に悪化している。鉄鋼業界では下期から中国で需要が急減し、主要製品の国際価格が軒並み下落している。さらにウォン安による原材料輸入コストの増大で韓国の鉄鋼業界は苦しんでいる。造船、鉄鋼業界は2002年から「チャイナ効果」で7年連続の伸びを示す「スーパーサイクル」の中で、韓国経済を支える役割を果たしてきた。
◆造船業界の「祭り」は終わった?
世界の造船景気は昨年をピークに後退局面に入ったとの分析が今年初めからささやかれ始めた。年初から世界景気が低迷の兆しを見せたことや船舶建造の主要材料である厚板の価格が上昇したことが理由だ。世界の船舶発注量は02年から毎年増加を続けてきたが、今年に入って頭打ちになった。信栄証券リサーチセンター長のチョ・ヨンジュン氏は「本格的な低迷期に入ったとは言いにくいが、米国のサブプライム問題の余波で世界金融市場が収縮し、船主の資金調達が困難になったことで、発注減少の懸念が生じている」と述べた。韓国造船業界は今のところ善戦している。現代重工業、サムスン重工業などの造船大手が高付加価値船舶の受注を増やし、8月現在で世界の船舶発注量に占める韓国のシェアは昨年通年の37.5%から42.4%へと上昇した。
しかし、一部の中小造船所は資金難にあえいでいる。C&グループ傘下のC&重工業が造船所の建設に必要な資金1700億ウォン(約147億円)を金融機関から借り入れることができず、今年末に予定していた船舶引き渡しを来年初めに延期した状況だ。
造船景気に先行する海運業況も急速に悪化している。バルク船市況を示すバルチック運賃指数(BDI)は1日、3025ポイントを記録した。これは5月のピーク時(1万1793ポイント)に比べ74.3%も下落した。産業研究院の洪性仁(ホン・ソンイン)研究委員は「景気低迷に伴う需要減少で海運物流が減り、船舶の発注減少につながる」と分析した。
崔有植(チェ・ユシク)記者
金承範(キム・スンボム)記者
造船・鉄鋼の好景気は終わったのか(下) 10/04/08(朝鮮日報)
◆危機感が漂う鉄鋼業界
鉄鋼不況の震源地は中国だ。中国では北京五輪直前の7-8月に主要鉄鋼製品の価格が一斉に10-15%下落した。世界的な景気停滞に伴う輸出不振と不動産価格の急落で建設、自動車、機械、家電など主要業種の鉄鋼需要が大きく減少したためだ。欧米市場の主要鉄鋼製品価格も過去2カ月で10-15%下落した。
世界の鉄鋼メーカーは相次いで減産に乗り出している。鉄鋼世界最大手のアルセロール・ミッタルが10-12月期に15%減産計画を明らかにしたほか、日本の主要鉄鋼メーカーもそれぞれ10-20%の減産を計画中だ。中国鉄鋼最大手の宝鋼集団も8月と9月に値下げに踏み切ったのに続き、減産を検討中だ。
韓国の鉄鋼メーカーにも危機感が漂っている。サムスン証券によると、韓国に輸入される中国製ホットコイルの輸入価格は7月の1トン当たり1063ドル(約11万1900円)をピークに下落し、今月に入ってからは800ドル(約8万4200円)にまで落ち込んだ。
現代製鉄の関係者は「中国の内需減少で安価な中国製品が大量に韓国に流入すれば、ただでさえウォン安で原料価格が上昇する中で、鉄鋼業界は大きな困難に直面しかねない」と懸念を示した。
宝鋼集団の徐楽江董事長は最近、世界の鉄鋼業界の状況と関連し、「鉄鋼業の高速成長時代は既に過ぎ去った」と述べた。一方、サムスン証券アナリストのキム・ギョンジュン氏は「欧米の景気低迷で当面は困難な状況だが、新興開発途上国の需要は今後も存在する。1-2年間の一時的な調整を経て、再び好転するのではないか」と話した。
崔有植(チェ・ユシク)記者
金承範(キム・スンボム)記者
債権の取立不能又は取立遅延のおそれ 兵機海運(株)(9362) 09/10/08(DATA MAX)
兵機海運(株)は、取引先である(有)福島海運が、9月1日付で徳島地方裁判所に破産申し立てを行なったことに伴い、同社に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じたと発表した。 取立不能が生じた経緯として、兵機海運は福島海運の金融機関からの船舶建造資金借入に対して、3件450百万円の債務保証を行なっていた。今般、福島海運が財政状態の悪化等から、破産申し立てを行ったことから、金融機関は兵機海運に債務保証の履行を請求していた。 今般、上記に伴い福島海運に対する債権について、取立不能又は取立遅延のおそれが生じたものである。 (有)福島海運に対する債権の種類及び金額 1、債務保証の代位弁済による求償債権 365百万円 2、当社貸付金 2百万円 今後の見通しについては、当該債務保証・貸付金については全額引当済であり、2008年8月4日に発表した2009年3月期第2四半期累計期間及び2009年3月期通期の連結業績予想に変更はないとしている。 韓国でABS検査官がスパイ容疑で捜査されているようだ!
Korea's Joon Ang Daily reports Busan prosecutors as saying that a "Chinese industrial spy" was indicted yesterday on charges of stealing shipbuilding technologies from a prominent Korean company.
The Busan District Prosecutors Office said yesterday that its special investigation unit has charged a 35-year-old Chinese ship classification surveyor affiliated with the American Bureau of Shipping with stealing key shipbuilding technology while working at a local shipyard, says the newspaper.
While the Chinese suspect is affiliated with the American Bureau of Shipping, he was dispatched to Korea at the special request of a state-run Chinese maritime corporation, Joon Ang Daily reports the prosecution as saying.
ABS says it is cooperating fully with the Korean authorities but cannot comment further at this time because of the lack of factual information and the pending court case.
According to prosecutors, the suspect was dispatched to the Korean shipbuilding firm in September last year. He is suspected of downloading about 1,500 files from the companyÕs server onto his laptop. The data included drill ship design plans and technologies related to LNG vessels.
ONE of a gantry crane's flexible legs broke, triggering a collapse that killed three operators and injured two security guards at Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group in Pudong this morning, Xinhua news agency reported, citing a preliminary investigation of the accident.

Two gantry cranes, weighing 600 ton each, toppled together about 12:20am when lifting 900 tons of materials. Three crane operators fell from 60 meters and died immediately, the report said.
Two security guards patrolling the area were crushed by debris. One guard was seriously injured. Both were being treated at nearby East Hospital, the report added.
The cranes were operating normally and the lighting was standard, a Xinmin Evening News report said, citing a senior official of Hudong-Zhonghua.
The noise from the collapse was so loud that nearby residents thought it was an earthquake, one person living in the area told Xinmin.

Police set up a restricted area around the site.
The report added that there was a possibility that another crane might collapse.
Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group at No. 2851 Pudong Avenue is a subsidiary of China State Shipbuilding Corporation, the country's main ship manufacturer.
On July 17, 2001, a 4,000-ton gantry crane carrying a crowd of workers toppled at the same site, killing 36 people, including nine supervisors or professors from Tongji University's Engineering School, the report said.
DRYDOCKS at China’s Hudong-Zhonghua Shipbuilding could be out of action for at least six months, possibly delaying delivery of up to 103 vessels on order at the Shanghai-based yard.
The collapse of two 600-tonne gantry cranes, which killed three shipyard workers, was a tragegy that underlined uncertainity in future delivery schedules, said DNB Nor Bank today.
Analyst Henrik With reported speculation of a six-month closure of drydocks, and the possible impact on the orderbook, which included container, bulk carriers, and LNG tonnage.
He said there were 103 vessels contracted, including six, 8,600 teu container ships for Orient Overseas International, and a series of panamax bulk carriers and tankers for Italian-based Rizzo Bottiglieri.
Cardiff Marine, Iolcos Hellenic and Irika Shipping are some of the Greek-based companies with panamax bulk carriers on order at the yard.
More than one fifth of the orderbook includes panamax bulk carriers scheduled for delivery from 2008 until 2012.
The dry bulk market, which faces a deluge of new tonnage from 2009, is actutely sensitive to news about bulk carrier delays. There are fears that over-ordering may see spot rates plummet amid a glut of bulk carriers coming into the market.
Shipowners have said only delays or cancellations could prevent rates from falling from their historically high levels.
An investigation meanwhile has been launched following the gantry crane collapse.
The three workers that died were in the cabs of the two cranes which fell about 10m to the ground.
Sources said columns on the cranes buckled and collapsed at about 0025 hours on today. Two security guards were injured, one critically, and both were taken to a local hospital.
While the accident prompted concern that one of the dry docks at the yard could be out of action for up to six months, industry insiders have already suggested that the shipbuilder would try to spread work among its other facilities to mitigate delays.
The Hudong-Zhonghua group has four shipbuilding facilities including Shanghai Edward Shipbuilding, at Pudong, Punan and Fuxing.
They include a dry dock capable of building very large crude carriers, a 120,000 dwt floating dry dock and five shipbuilding berths for vessels up to 20,000 dwt, 70,000 dwt and 120,000 dwt. The shipbuilder has eight 100 tonnes capacity cranes working at its shipbuilding facilities.
One source said: “The accident is potentially crippling for the shipbuilder. But until a proper assessment can be carried out and executives can review how much work can be carried out by other facilities it is difficult to comment on how much impact the accident will have on production.”
Captain Doug Brown, general manager of China LNG Shipping (International), told Lloyd’s List that none of the five 147,000 cu m LNG carriers being built by Hudong-Zhonghua were affected by the accident.
The Dapeng Sun has already been delivered, and the next vessel in the series, Dapeng Moon, is due for delivery by July.
朝日新聞(2008年1月12日)より
国内首位へ交渉 中韓勢に対抗
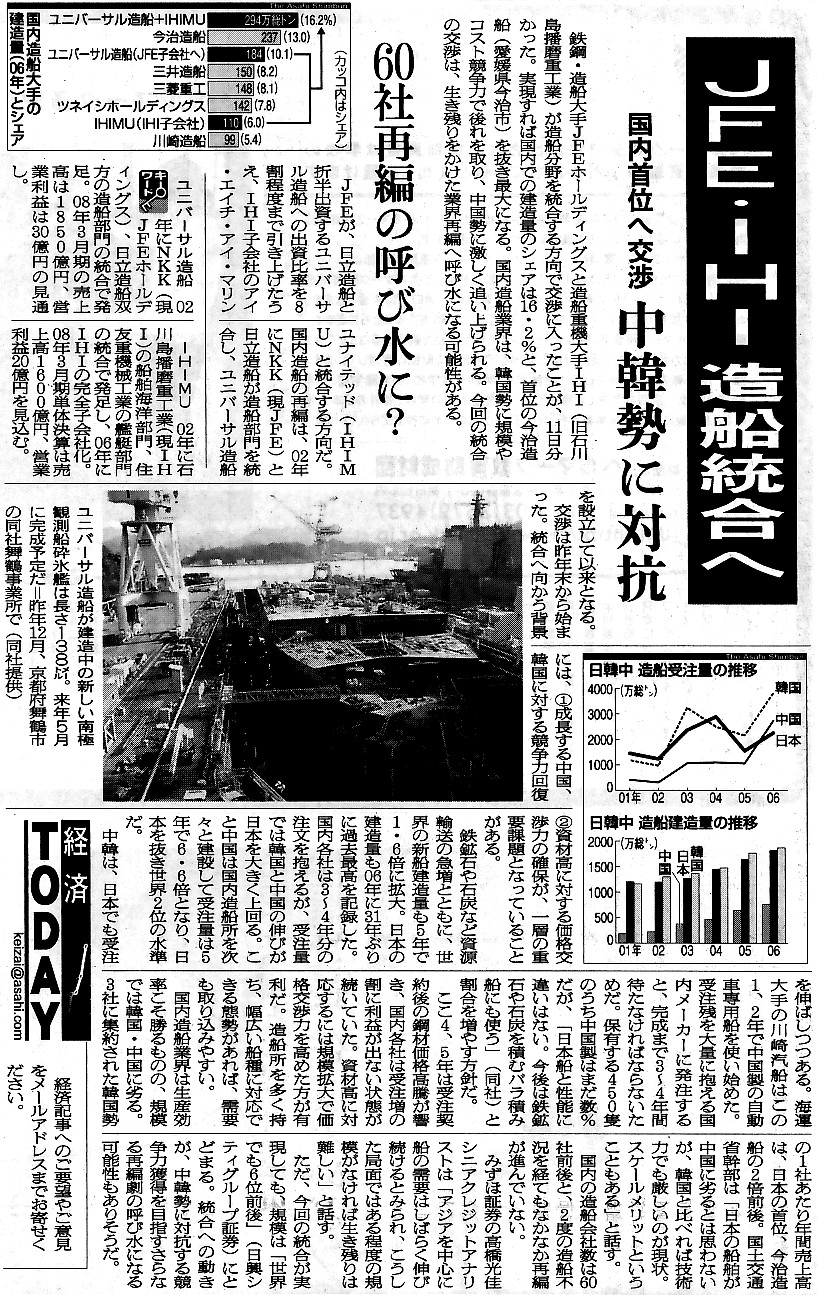
2950トン貨物船建造/いちき串木野・寿工業 1000トン超、鹿県内30年ぶり 01/26/08(南日本新聞)
船舶造修業の寿工業(いちき串木野市新生町、伊高和夫社長)が建造したパナマ船籍の貨物船「YUSHO EIGHT」(2950トン)が25日完成し、同市の串木野漁港で命名・引き渡し式があった。九州運輸局鹿児島運輸支局によると、県内で総トン数1000トン以上の船が建造されたのは30年ぶり。
 完成し引き渡された貨物船「YUSHO EIGHT」=25日、いちき串木野市の串木野漁港
完成し引き渡された貨物船「YUSHO EIGHT」=25日、いちき串木野市の串木野漁港
同社によると、大東海運産業(鹿児島市城南町、東文夫社長)のパナマの子会社に引き渡された貨物船は、全長84.86メートル、幅14.8メートル。積載重量3800トンで航海速力12ノット。昨年5月に着工し、建造費は約10億円。主に日本-台湾間の国際航路で鋼材や一般雑貨などを運ぶ。
船舶、行政関係者ら約140人が出席した式では、綱の切断や社旗交換などがあり、花火やくす玉を割って完成を祝った。伊高社長は「無事に船が引き渡されたのは大きな喜び。航海の安全を願う」と話した。貨物船は25日午後に串木野漁港を出港。横浜を経て30日に韓国へ向かう予定。
寿工業では年間1、2隻の船を建造しており、今年は貨物船2隻、タグボート1隻の計3隻の引き渡しを計画している。
中国新聞(2008年1月12日)より
建造量で国内トップへ
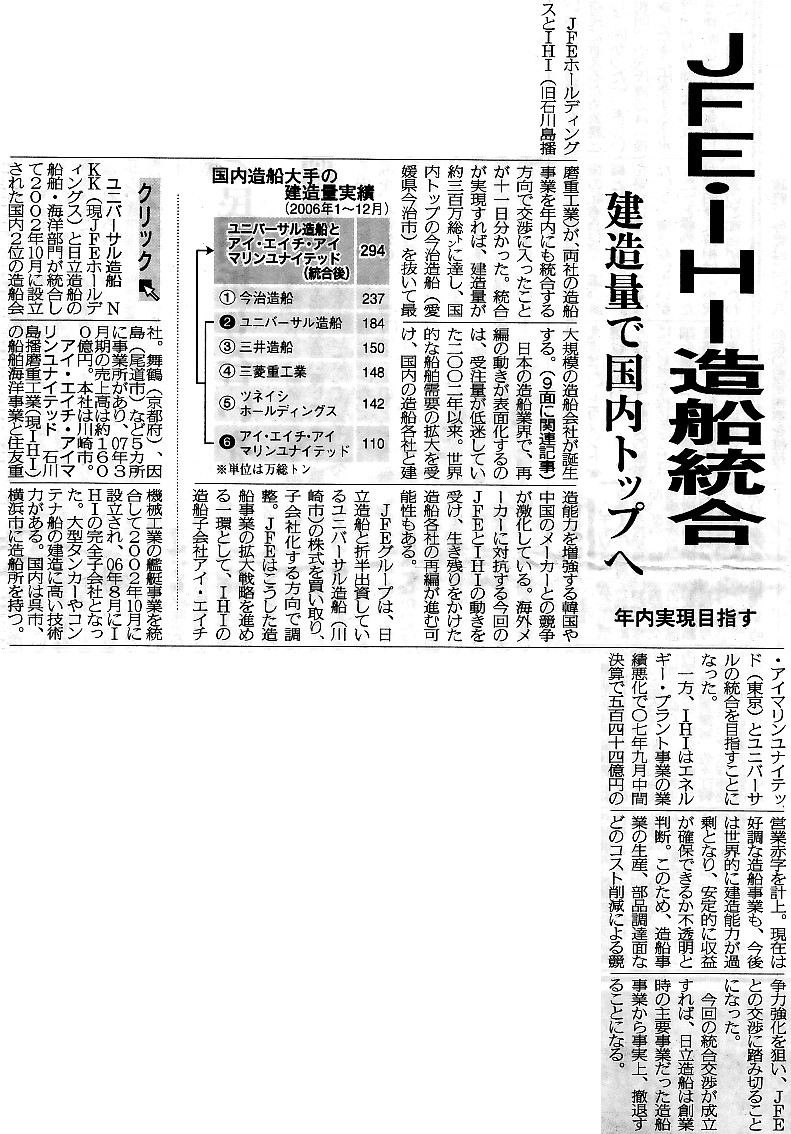

韓国造船業の強さの秘密? 世界中を飛び回るCEOたち 07/04/06(朝鮮日報)
「1月、マレーシア修理造船業共同進出交渉、ギリシャ、トルコタンカー船契約」「2月、カナダタンカー船契約、フランス旅客船命名式…」
サムスン重工業金澄完(キム・ジンワン/60)社長の今年下半期の海外出張スケジュールの一部だ。金社長は6月まで10回余に渡り2カ月以上海外出張に行った。下半期にも2カ月の海外出張の日程が組まれている。1年の3分の1にあたる4カ月を海外で過ごしている計算になる。出張地域も欧州、東南アジア、米国など一カ所にとどまらない。顧客がおり、市場のあるところならどこにでも出かけていく。
世界最高の競争力を誇る韓国の造船会社の社長が世界を股にかけて活躍している。2位の日本を引き離し、追撃してくる中国との差をさらに広げるため、海外マーケティングを強化しているからだ。特に、造船会社の契約は一度に10億ドル(約1160億円)を超えるケースも多々あることから最高経営者が直接契約をするケースが多く、世界最高の幹部らが船主を直接訪問して管理しなければならないというのが造船業界関係者の説明だ。
大宇造船海洋の南相兌(ナム・サンテ/56)社長も、海外営業に力を入れている。今年3月に就任した南社長は、4月以降3カ月間に8カ国を回った。4月に中国、5月に英国、ノルウェー、ドイツ、カタールの船主と会い、6月にはギリシャとスイスを回った。チョン・グァンソクSTX造船社長(53)も、通常1年の4分の1を海外で過ごす。上半期にマレーシア、イタリア、英国、ギリシャを回り、7月以降は中東、東南アジア、ヨーロッパを訪問する予定だ。
韓進重工業洪淳翊(ホン・スニク/60)社長は、ドイツ、ギリシャ、トルコ、ドバイ、フィリピンを回る25日間の海外出張に行ってきた。韓進重工業はフィリピンのスービック湾に70万坪規模の造船所設立を推進しており、フィリピンへの出張がさらに増える見通しだ。現代重工業の崔吉善(チェ・ギルソン/60)社長もアフリカのナイジェリアなどに2週間出張している。営業担当本部長が主に海外出張に行く普通の会社に比べ、造船業界ならではの慣行だと現代重工業関係者は説明した。
韓国造船業ピンチ! 技術・人材が中国に流出 11/03/06(朝鮮日報)
「設計技術と熟練工の中国流出を阻止せよ」
中国が、造船業で世界第1位(シェア40%)を誇る韓国の足を引っ張り、技術を盗もうと躍起になっている。
中国は現在、「2010年には世界造船の第1位」を目標に、大々的な設備増設に乗り出している。このため、中国側が韓国の船舶設計者や熟練工らに接近しようとするケースが増えている。造船の中核をなすのはやはり設計技術だ。韓国国家情報院もこのところ、慶尚南道蔚山・昌原・鎮海・巨済、釜山一帯で造船関連技術の中国流出の実態について、情報収集や現場調査を行っている。
◆設計ノウハウや熟練工がターゲット
釜山にあるC社は造船業界では比較的よく知られている船舶設計専門会社だ。C社はかつて韓国内の大手造船企業から発注を受け、タンカーやばら積み船(バルクキャリア)の設計を行なっていた。しかし最近では、中国有数の造船会社から発注を受けた船のみを設計している。理由は中国側の提示する単価の方が高いためだ。それ自体、不法なことではないにしても、中国と競争している韓国の中堅造船会社に与える打撃は少なくない。韓国の進んだ設計技術のおかげで、中国の造船会社が納期を縮め、設計ノウハウを自然に習得し、競争力を高めることにつながるからだ。
ところで韓国屈指の造船会社に勤める熟練工のKさん(56)は現在中国に行く準備をしている。先に中国の造船会社へ行った先輩たちから「熟練工の待遇がいい」と聞き、同僚と一緒に団体で中国行きの話を進めているのだ。
中国は主に付加価値の高い船舶の図面を手に入れたり、熟練工をスカウトしたりして技術を移転している。今年、造船各社が定年を延長した背景には、造船業界の好況による人材不足に加え、熟練工の海外流出に対する懸念も作用したと言われている。
◆海運会社通じ入手も
技術・人材流出に関し、韓国企業の警戒が強くなると、中国は海運会社を通じた接近を試みている。韓国企業が中国企業からの度重なる技術提供の申し入れを断っていることから、今度は船舶を発注する中国の海運会社を通じ、高度な図面を入手しようとしているのだ。通常、船舶を発注した会社は自社の社員を派遣し、2年近く常駐させて船舶の建造過程を細かくチェックする。この際に、船舶設計図を要求したり、閲覧したりする機会が多い。
◆設計者・熟練工が競争力の中核
韓国が世界の造船業界のトップに立ち、LNG(液化天然ガス)船のような付加価値の高い船舶の受注を一手に引き受けている背景には、高度な設計技術や熟練工の技、優れた施設運営能力がある。特に現代重工業で働く設計者は1300人、研究開発人材は3000人にも及ぶ。同様にサムスン重工業・大宇重工業にも1500人前後の設計者たちがいる。
1隻当たり2億‐3億ドル(約230億‐350億円)に達する船舶の設計には、船主たちの細かい要求に答えるのはもちろん、頻繁な設計変更にも柔軟に応じられる技術力が求められる。
方聖秀(パン・ソンス)記者
【インドシナ】兼松受注の船が進水式で事故 06/20/06(NNA)
ベトナム造船総公社(ビナシン)が兼松(本社・東京都港区)から受注した野間海運(本社・愛媛県今治市)向けの貨物船(積載量1万500トン)が、17日北部ハイフォン市のバクダン造船所で行われた進水式の最中に立ち往生するトラブルが発生した。
貨物船は野間海運が受領予定の3隻の船の2隻目で、全長110メートル、幅18.8メートル、自重2,700トン。同日午後7時ごろ、船台から水面まで250メートルの誘導レールを自走している途中100メートルの場所で停止し、船体の一部が水に浸かった状態になっている。
バクダン造船所のチュー・テー・フン所長によると、気温が40度に上昇して、潤滑作用のあるパラフィンワックス(グリース)が固まったことが、船体が停止した原因だ。同日午後9時に進水救援のためのエットキエウ号(ハイフォン港所属、3,200馬力)が到着したが、進水させることはできなかった。
フン所長によると、今月27日の大潮(水深3.7メートル)まで待つ方針だ。進水式の時には3.4メートルだった。
兼松本社はNNAに対し、事故はおおむね現地報道の通りだとしている。一方、グリースが固まったのは暑さだけでなく調合ミスの可能性もあることを指摘している。また水位(潮位)の低さは関係ないという。
■船体への影響は?
19日付ラオドン電子版は、「船体には問題ない」と報じているが、タインニエン電子版は、「船底のシステムにダメージがあり、直ちに措置をとらないとさらに深刻な事態になる」と伝えている。
これについて兼松は、「船が斜めになっている状態だが、船体への影響はほとんどない」とコメントしている。
ベトナムでの進水は、船台で造船し、水面にすべり台(レールなど)で落とす方式で、関係者が最も細心の注意を払う場面だ。今回と同様のケースは、日本でも以前は起きていたが、現在は造船後にドック内で注水する「ドライドック方式」が主流。このため、注目されつつあるベトナムでの造船事業が、今回の事故で直ちに縮小することはなさそうだ。
兼松は今回の造船で機材納入契約を交わしてパッケージング供給を行い、船舶設計も日本から供給した。日系商社の中ではベトナムでの造船業の関わりが最も深い。
■ハロンでも進水事故
進水式での事故としては、英グレイグ・インベスツメンツが受注した、ビナシンのハロン造船所で4月6日に起きた事故が記憶に新しい。国内建造船として最大の貨物船(5万3,000トン)が進水した直後に障害物に接触、浸水した事故で、船底の裂け目は1.2メートルに及んだ。喫水の浅いハロン・ハイフォン地区は大型船建造に不向き、との日本の関係者の指摘もある。
韓国造船の‘奇跡’に世界が驚く 04/19/06(中央日報)
18日午後2時、釜山影島区(プサン・ヨンドグ)にある韓進(ハンジン)重工業影島造船所。 300メートルのドックの端に横3.1メートル・縦15.1メートル・高さ7.7メートルのV字型構造物が設置されていた。 韓進重工業は水中で船体を溶接する作業を行うために「ダム」と呼ばれるこの構造物を考案した。 配水および放水処理されていて、ドックの水門を開いて海水を満たしても水は入らない。
同社のウ・ゴンゴン部長は「ドックの長さがもっと長い船を最終的に組み立てる際、船体に密着させて使用する装備」とし、「水中でも5、6人が地上と同じ条件で作業できる」と説明した。 「船はドライドックで作る」という造船業界の長い間の固定観念を韓国業界が打ち破っている。 押し寄せる注文を消化するため陸上建造、海上建造、水中建造など新しい技術を次々と開発しているのだ。

三星(サムスン)重工業は先月、慶尚南道巨済(キョンサンナムド・コジェ)造船所に長さ320メートル・幅55メートルの「フローティングドック」2号機を設置した。 01年に同社が世界初めて設置した1号機に比べて50メートルほど長い。 水上に浮かぶ「フローティングドック」は、海上クレーンを使って最大25万トン級の船を年間8隻も建造できる。 大宇(デウ)造船海洋も今月15日、横271メートル・縦51.5メートルのフローティングドックと、3600トンをつり上げられる超大型海上クレーンを巨済島の玉浦(オクポ)造船所に建設した。
現代(ヒョンデ)重工業は昨年、世界で初めて陸上建造工法を導入した。 この工法はドックではなく海岸で船を完成し、バージ船に積んで海上に出して進水させる方法だ。 昨年1月、ロシアの海運会社に10万5000トン級の原油運搬船を初めて引き渡して以来、これまでこの工法で6隻を引き渡し、現在21隻を建造または建造予定中という。STX造船は今年から船体ブロックをクレーンでつり上げて移動させる代わりに、潤滑剤を使って押して移す工法を適用し、生産性を大きく高めている。
このような努力は国内造船会社の建造量を大きく増やす結果をもたらした。 現代重工業は10年前、蔚山(ウルサン)造船所で年間40隻を建造したが、昨年は70隻に増えた。 三星重工業も同じ期間、20隻から50隻に生産量を増やした。
造船会社はこのほかにも生産性や品質の向上のため、さまざまな努力をしている。 三星重工業は、鉄板の加工段階から最終組み立てまでの全工程で作業者の名前を明確にする作業実名制を導入している。 欠陥がない状態で船主に船を届ける‘無欠点引き渡し制度’も実施している。
大宇造船は午前7時から社長ら全役職員が造船所を清掃し、一日を開始する。 同社の役員の車にはゴルフバッグではなく、ほうきと塵取りが積まれている。 韓進重工業は毎朝、班長が職員の飲酒量や手の震えなどを確認する。 STX造船は降雨が予想されると、野外作業を室内作業に回して生産性を高めている。
造船工業協会のハン・ジョンヒョプ常務は「限られた敷地と厳しい建造環境でも絶えず新技術を開発し、効率と品質を高めているのが底力」と語った。
ベトナム最大の貨物船、進水直後に浸水 04/08/06(ベトナム ネット)
ベトナムで建造された船舶としては最大の5万3000トン級貨物船・HL01-フローレンス号の進水式が先日6日行われたが、1時間後、船倉の一部が浸水しているのが発見された。進水時に何らかの理由で船体に傷が入ったか、もしくは船員によるバルブの閉め忘れが原因と見られているが、依然原因ははっきり分かっていない。
HL01-フローレンス号は、全長:190メートル、幅:32.26メートル、高さ:17.5メートル、載貨容積6万4000立方メートルの大型貨物船で、リモートコントロールシステムや安全警報システムなど、最新の設備が整っている。
同船舶を建造したハロン造船は、このような事故は初めてだ、と語っている。
|
◆サブスタンダード船
◆サブ・スタンダード船と旗国の関係 ◆なぜ、サブ・スタンダード船? ◆サブスタンダード船の見つけ方 ◆サブスタンダード船の写真 ◆検査会社の問題 |
 ★HOME |
◆海運関連業界
◆なぜ、サブ・スタンダード船? ◆BLUE OCEAN(ブルーオーシャン)の事故 ◆座礁船及び放置船 ◆PSCによる検査の現状 ◆船舶油濁損害賠償保障法 |
|---|